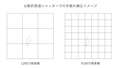���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S1840�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2025�N9��3�� 15:29 | |
| 14 | 10 | 2025�N8��24�� 20:23 | |
| 33 | 6 | 2025�N8��9�� 18:14 | |
| 48 | 52 | 2025�N5��27�� 19:22 | |
| 51 | 8 | 2025�N5��3�� 14:20 | |
| 28 | 9 | 2025�N4��15�� 13:09 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DC-GH7 �{�f�B
�ċx�݂�����ă_�i���ɍs���Ă��܂����B
�\���`�����R�ی��ŎB�e������Ŋ뜜��̃A�J�A�V�h�D�N�����O�[������ł��B
GH7�ɂP�O�O�|�R�O�O�����Y�[�������Y�Ŏ莝���B�e�ł��B
�K�C�h����̉^�]����o�C�N�̌��ɏ���ĒT���Ȃ���s���c�A�[�ł��̂ʼnו��͍ŏ������������Ă����Ȃ��̂Ń}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ə��^�Y�[�������Y�ōs���܂����B
![]() 11�_
11�_
�f���炵���ʐ^�ł��ˁB
���̎ʐ^�́A�I�[�g�t�H�[�J�X�݂̂ŎB��ꂽ�̂ł��傤���H
����3���ځA4���ڂ́A�s���g�������ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����̂ŁB
�����ԍ��F26280362
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��������܂��B
�}�j���A���t�H�[�J�X�ŎB�e���Ă܂��B
�����ԍ��F26280393
![]() 0�_
0�_
��ken-san����
���������肪�Ƃ��������܂��B����ς�A�}�j���A���t�H�[�J�X�Ȃ�ł��ˁB
���́AG9M2���g���Ă��܂��āA���҂��Ă����قǃI�[�g�t�H�[�J�X������Ȃ��ȂƎv���Ă����̂ŁB
GH7�͂����Ɛi�������̂��Ǝv�����Ⴂ�܂����B
�Z���Ԃł�������}�j���A���ō��킹����Z�p�͑f���炵���ł��ˁB
���̓I�[�g�t�H�[�J�X����Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F26280505
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DC-S9K �W���Y�[�������Y�L�b�g
�Ȃ�łڂ��͍��܂ŋC�Â��Ȃ��������낤�B�݂Ȃ���́A����Ă܂������H
�n�C�u���b�h�Y�[��+�莝���n�C���]�ŕ��i��悪�߂��Ⴍ����L����܂��ˁB���������𑝂₷�Ƃ��������B���[�J�[�͂��܂肱�̂����͒�Ă��ĂȂ��ł��ˁB
�����ԍ��F26270951�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�n�C�u���b�h�Y�[�����ĂȂ��Ȃ��Ďv������A������f�W�^���Y�[���ƌ��w�Y�[����A��������@�\�̂悤�ł��ˁB
���I�Ƀf�W�^���Y�[�����Ă������_�Ŗ����ł����ˁB���ʂɌ��w�Y�[���ŎB���āA�摜�ҏW�����ق����܂�������Ȃ��ł����ˁH
�n�C���]�͕ҏW�ł��̂͑�ςł��傤����A����͂���ł������Ǝv���܂����ǁA����ς�莝���ł͂Ȃ��O�r�Ȃǂ��g�����������Ƃ͎v���܂����ǂˁB
�œ_�����̕ύX������{�I�ɏo���Ȃ��R���f�W��X�}�z�Ȃ�܂������A�����Y�������J�����ł͂ǂ��ł����ˁB�����Y�������P�{���ʓ|�Ȃ�e���R���������ł�����Ȃ����Ǝv���܂����ǂˁB
�����ԍ��F26271056
![]() 1�_
1�_
��KIMONOSTEREO����
���f�W�^���Y�[���ƌ��w�Y�[����A��������@�\
�Ƃ͈Ⴂ�܂���A�n�C�u���b�h�Y�[���͌��w�Y�[���̏œ_�����ƃZ���T�[�N���b�v�{���̌v�Z���ʂł��̂ŁA�ő�ɂ���Ɖ�f����2.5M���炢�ɂȂ��Ďg�����ɂȂ�Ȃ�����n�C���]�ʼn�f�����₷�Ƃ����b���ł��B
�N���b�v�Y�[���ƌ��w�Y�[���̃Y�[�������O����𗼕��g������n�C�u���b�h�Y�[���ŁA�Y�[�������Y�g�p���݂̂̋@�\�ł��B
�����ԍ��F26271441
![]() 3�_
3�_
���ڂ�Ă�ڂ�
3�{��XS�ɂ������Ŗ�2.5M�ȉ��Ȃ�ł���ˁB�L�b�g�����Y��28-200mm�g���Ă���600mm�̉�p��SNS�ɏグ��Ȃ�A�掿���������ɒ��x�����T�C�Y�ł����A�v�����g�p�Ńn�C���]�ɏグ�Ă���10M�ł��̂łǂ��ł����ˁB
������2�{�܂ł����g���܂���A3�{�͋L�^�p�Ƃ��Ċ�����Ă܂�
�����ԍ��F26271452
![]() 1�_
1�_
�n�C�u���b�h�Y�[���́ARAW��n�C���]�͎g�p�o���܂���B
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S9jp/html/DC-S9_DVQP3137_jpn/0045.html
�莝���n�C���]���g�����炢�ł�����A����ŎB�e����Č�X�g���~���O�ł��ǂ��C�����܂��B
���i�ŗL���RAW�����͕K�{�ł���Ǝv���܂��B
�l�I�ɂ̓n�C�u���b�h�Y�[���͓���B�e�ɗL���ȋ@�\�ł���Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F26271701�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ���A���낢��ƎQ�l�ɂȂ邲�ӌ������肪�Ƃ��������܂��B
���́A�ŋ߂͂����Ɍ㏈�������炷���Ƃ������Ƃ��l����悤�ɂȂ�A�ERAW�͂������A��p����{�I�Ɍ��n�Ō��߂āA�ォ��̃g���~���O�����Ȃ��Ȃ�܂����B�ォ����̂̓g�[���J�[�u���x�ł��B�Ȃ̂ŁA�n�C�u���b�h�Y�[�����n�C���]�B�e���ƂĂ��j�[�Y�ɍ����Ă��܂��B
��i�̃A�E�g�v�b�g�ɂ��Ă��A�Î~���4K����ɂ܂Ƃ߂�70-100�^���x�̉t���p�l���ōĐ�����`����ƂȂ�A�唻�v�����g�����Ă������قǂ̉�f�����K�v�Ȃ��Ȃ�܂����B
���낢��ȃN�`�R�~�����Ă�ƁA�g���~���O������Ɖ掿��������ƌ�����Ă���������\���܂����A�掿��������̂ł͂Ȃ��A�摜�T�C�Y���������Ȃ邾���ŁA���̃T�C�Y���A�E�g�v�b�g�T�C�Y�ɂ����܂��Ă���̂ł���A�ϋɓI�Ƀg���~���O���ėǂ��Ǝv�����A���̏�A��f�⊮�Ńn�C���]������A���Ȃ�̖��͉����ł���Ǝv���Ă��܂��B
�����A�g���~���O�ʼn掿�������邱�Ƃ͂���܂��A��f�⊮�ł̓T�C�Y�͒S�ۂ���Ă��掿�͕⊮�ɂ���Ă킸���Ȃ��痎���܂����ǁB����ł��A�C�ɂ��郌�x���ł͂Ȃ����ƁB
�����ԍ��F26272016�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ƁA�Y�[���̍L�p���Ńn�C�u���b�h�Y�[�����������Ȃ��ݒ��ON�ɂ��Ă��Ȃ��l�����\����݂����ł��B�掿�ێ��̂��߂ɂ́A�����ON�ɂ��ׂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26272022�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���ڂ�Ă�ڂ�
����ɂ���
�� �g���~���O������Ɖ掿��������ƌ�����Ă���������\���܂����A�掿��������̂ł͂Ȃ��A
�� �摜�T�C�Y���������Ȃ邾��
���̂Ƃ���Ȃ�ł����ǁA
�T�C�Y���������Ȃ���������A�摜�T�C�Y�𑵂��Ĕ�r(�Ⴆ�Γ����T�C�Y�Ńv�����g�A�����T�C�Y�ʼn�ʕ\��)������A�掿(SNR, DR)�������Ă܂��A�Ƃ������ƂŌ���ł͂Ȃ��Ǝv���܂�
�N���b�v�����菬���ȃt�H�[�}�b�g�ŎB�����肵������ƁA�����Ȏʐ^�ł���ƍl�����ɁA�T�C�Y�𑵂��Ĕ�r����̂͏K�����Ǝv���܂��̂�
�N���b�v���ď������A��𑜓x�ɂȂ������̂Ƀn�C���]��K�p����̂͂ƂĂ����ɂ��Ȃ��Ă�Ǝv���܂��A�n�C���]�����ɂ̓m�C�Y��ጸ���ĉ掿�����コ������ʂ����҂ł���̂�
2400����f�̒��x�̃t���T�C�Y�@�ɁAAPS-C�N���b�v�̎������n�C���]��������2400����f�ɂ��Ă����@�\������ƂƂĂ����͓I���ȂƎv���Ă܂�
�����ԍ��F26272064�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����o������
�ԐM�����肪�Ƃ��������܂��B
�����ł��ˁA�t�H�[�}�b�g�𑵂��Ĕ�r����A���]�����[�V�������ቺ�����Ƒ������܂��ˁB�����A���{��r�ƂȂ�g���~���O�ɂ���ĉ掿�ɕω����Ȃ����Ƃɂ��Ȃ�̂ŁA����ǂ��ɂ������ŕ]�����ς�邱�Ƃł��ˁB
������ɂ��Ă��A��f���ێ����C�ɂ��߂��ĎB�e���@�𐧌����Ă��܂��̂́A���������Ȃ����Ƃł��ˁB�����̃A�E�g�v�b�g�`���ɑ��ĕK�v�ȉ�f���͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂������ʂ��Ȃ���I�����邱�ƂŎB�e�̕����L����Ǝv���܂��B����́A�����ō���f���ł���K�v�͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����邩�ȁ[�Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F26272105�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���̃X���̒�Ắu�n�C�u���b�h�Y�[��+�莝���n�C���]�v�ŗ��p���邱�Ƃ��Ǝv���܂������A�����̋@�\�͓������p���o���Ȃ��Ǝv���܂��B
�O��̃R�����g�ł�RAW�Ƃ������t���o���Ă��܂��܂������AJPEG�̂ݗ��p�ł����l�ł��B
�܂��掿�̔�r�͓��R���T�C�Y�Ŕ�r���ĕ]���ł��B
�Ⴆ�X�}�z�̏����ȉ�ʂŊς�̂ŗL��A�O���b�v�Y�[���ɂ��𑜓x�ቺ�͏\���ɋ��e�o����ꍇ�������̂ł��傤�B
��^TV���j�^�[�⍂���ׂ�PC���j�^�[�A�傫�ȃT�C�Y�Ńv�����g����Ȃ��f����������x�͑��������ł���ˁB
�����ԍ��F26272172�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��longing����
�������p�A�����H�Ǝv���AS5ii��S9�Ńe�X�g���Ă݂܂����B
���ʁA�A���̒ʂ�ł��ˁB
���̕��@�̓i�V�ł��ˁA�A
�����������܂����A�A
�J���җl�A���Ђł���悤�ɂ��ė~�����ł��I
�����ԍ��F26272181�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DC-G9M2 �{�f�B
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/download/fts/dl/g9m2.html
�o�[�W�����A�b�v�A���܂����B���@�p�i�\�j�b�N�I
�����ԍ��F26047349�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 17�_
17�_
EX�e���R���������Ȃ�A�N���b�v�Y�[���Ƃ������̂ɕς�����悤�ł����AEX�e���R���ƃN���b�v�Y�[���̈Ⴂ�͂Ȃ�Ȃ�ł��傤���H�f�l�̎���ŃX�~�}�Z���B
�����ԍ��F26049442�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���̋@��AAFS,AFC�����o�[�őf������ւ��o����̂͗ǂ��̂ł����A
AF���[�h���Ƃ�AF�_���ʂɋL���ł���悤�ɂ��ė~���������ł��B
�����͕��i�╨��AFS�Œ�����_�A�������q����AFC�Ńt���G���A�i�l���F���j��
�g�p�������̂ł����AAF�_���ւ���̂��ʓ|�ł��B
���ƁA�N���[�j���O�������s�������u�d������꒼���Ă��������v�Əo�܂����A����ɍċN�����Ă�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26049471
![]() 3�_
3�_
��hide4740����
����Ă邱�Ƃ͓����ł���
�X���[�Y�ɕω����Č��w�Y�[���Ƃ��V�[�����X�Ɏg���₷���Ȃ��āA���O���ς��܂���
https://asobinet.com/review-lumix-s9-hybrid-zoom/
�����ԍ��F26049534�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�d���I������N���܂ł������Ȃ��Ă��܂��I�H������ G9M2 �͖��炩�ɉ������ǂ��Ȃ����Ɗ����܂��BISO �{�^���������Ă��� ISO ���x�ύX���[�h�Ɉڂ�����ɁA�ēx ISO �{�^�����������ۂ̓�����ς���Ă��܂��H�ȑO�� ISO ���x�̐ݒ�l���E�ɏ�����ɂȂ��Ă������A����� ISO ���[�h�̏I���ƂȂ�A�����ɂ͎g���Ղ��Ȃ�܂����B
�����ԍ��F26051653
![]() 6�_
6�_
���o���^���ꐢ����
�����o�[�W�����A�b�v���܂����B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F26085069
![]() 0�_
0�_
7��29���t�łɐV�����o�[�W�������o�Ă��܂����B�����C�Ȃ̂��ύX�����Ƃ��낪���ɂ͕�����܂���ł����B
���[�J�̕������Ă邩������Ȃ��̂ŁA����̃o�[�W�����A�b�v�Œ����ė~�����Ƃ���������Ă����܂��B
����B�e����AF�����̌��ł��B
AF�A������OFF�ł����o�[��AFC�̏ꍇ�AAF�{�^���������Ă���Ԃ͐Î~��̂悤�ɍ��킹�����ė~�����ł��B
�l���ł������ł��\��O�ɑO��ɓ�������Ă��鎞�A��ނ��`�e�{�^����A�ł��Ă���܂��B
�����ԍ��F26259172
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DC-S1M2ES �{�f�B
S5II�Ɖ����Ⴄ�낤�Ǝv���āA�ȒP�ɒ��ׂ����ʁA���Ȃ�Ⴄ�悤�ł��B
�E��荂���ȃv���Z�b�T�[���̗p���Ă���AAF���\��^��@�\������
�E���S�Ȗh�o�E�h�H���\������A-10���܂ł̑ϊ����\
�E576���h�b�g��OLED EVF�𓋍ڂ��A���t���b�V�����[�g�͍ő�120fps�A�x����0.005�b�����Ɣ��Ɋ��炩�ȕ\�����\
�ES5II�͎�U���͍ő�6.5�i�������AS1IIE�ł͍ő�8�i���Ɍ���
�ES5II�͘A�ʂ�AFC���J�V���b�^�[����7�R�}/�b���������AS1IIE�͑��x�D�惂�[�h�i12bit�j�� 10�R�}/�b���\�ɂȂ����B
�EUHS-II SD�J�[�h�X���b�g��XQD/CFexpress�X���b�g���e1���
![]() 9�_
9�_
��{�I�ɂ͒���f������f���Z���T�[�T�C�Y�������Ȃ�����͓����ł��B
�s���{�P���A��ʑ̃u���������ł��B
�u�������{�P��������ł��B
�����ς��܂���B
�ł��̂ŋC�ɂ���K�v�͂���܂���B
�ς��悤�ɔ�������Ă���������܂����A���v�ł���?
���ۂɎB���Č���ׂĂ݂��ق����ǂ��ł���B
����f�@���Â��ʂ�A�͈ȑO�����Ă����b����
���̍l���ł͂���܂���B
��f�s�b�`�����������炾�����ł��B
���̍l���ł͂���܂���B
�����čŋ߂̓Z���T�[�̐��\���ǂ��Ȃ����̂ŁA���͖����Ȃ����A
���̂��ߊg�嗦���̔�ʑ̃u�����̂ɗ��R���ύX�ɂȂ����悤�ł��B
���ꂪ��t���ł��B
����[���Ȃ��b�ł���B
�����ԍ��F26184512�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>���x���\���グ�܂����A�g�嗦�ɂ��
���ꂪ�ڗ����ǂ����A�Ƃ����b�ł��B
�g�傷��ׂ������������Ă���̂�
������O�̘b�ł���B
�ŏI�m�F���Ⴆ�g���~���O�Ȃ��ŁA
�����Î~��̃��j�^�[�ł�
�t���X�N���[���ӏܓ������
���R�ς��܂���B
�܂��B�e��������Ƃ��@��ɂ���āA�܂���ς�����b�ł͂��邯��ǂ��g�嗦�̈Ⴂ�Ő�������͔̂@���Ȃ��̂��ƁB
�Ƃ����̂́A2400����f�̃J�����̏ꍇ�͌��X�̕`�ʌ��E�ɉ����ă��[�p�X�t�B���^�[�̃}�C�i�X�e��������AJPEG�G���W���ɂ���Ă��ꂪ(�����ڏ�)�قڏ���������x�ɂ̓V���[�v�l�X�▾�Č��ʂ��������Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA�g�債�Ă���ƕ�������x�̔��u���ł�����̃V���[�v�����͈̔͂Ŗ�����Ă��܂��ꍇ�������ƍl�����܂��B
������4500��6000���̃��[�p�X���X�@��̓V���[�v�̐ݒ肪���������Ⴂ�܂����A�V���[�v��������O�̉摜�������Ⴂ�܂��BRAW�ŃV���[�v�ݒ�̐��l��S�������ɂ�������Ȃ���r�ł���Ƃ��������Ȃ��ł��傤�B
�Ȃ̂Ŋg�傷��ׂ�������e���ڗ����Ղ��Ȃ�A�Ƃ����Ă��A���܂�q�ϐ����Ȃ��Ď����Ƃ��ꗂ�����悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F26186470�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��longing����
����u���������J�����ɂ����āA�u���Ղ��͉�f���ɉe�����Ȃ��Ǝv���܂��B
��hunayan����
����{�I�ɂ͒���f������f���Z���T�[�T�C�Y�������Ȃ�����͓����ł��B
���J����SP����
���܂���ς�����b�ł͂��邯��ǂ��g�嗦�̈Ⴂ�Ő�������͔̂@���Ȃ��̂��ƁB
������̎�U�����J�Ő��\�������ꍇ�A
�u�Z���T�[��ŕ�ł����U��̐�Ηʁv��
�����ł���ˁH
�i��F��7CII�ƃ�7CR�Ƃ��AR6��R5�Ƃ��j
��U���̓Z���T�[��̂Ƃ����f��
���B���ׂ��������ꂽ���̂�{���̈ʒu��
�߂���Ƃɑ��Ȃ�܂���B�iIBIS�AOIS�A
�O�r�g�p�A��������\����A���ړI�͓����ł��j
���S�ɂ���ׂ��N�_���炸���ꍇ�A���̂����
���m���Ė{���̈ʒu�ɖ߂����Ƃ���킯�ł����A
2400����f�ł͂��͈̔͂Ɏ��܂�u���ł����Ă�
6100����f�ł́u�ƂȂ�̉�f���ł��Ȃ��ق�
�I�����Ă��܂��܂ł̃u���v�ɂȂ�܂���ł��傤���B
�i�}1�A�}2�j
�אډ�f�ɓ���͂��̌����{���̉�f�i���S���j
�ɂ�����ł��傤����A�I�o�s���͂Ȃ��ł��傤���A
�e�F�̐F�����͖��炩�Ɉ����Ȃ�܂��B
�i���m�N���ł��P�F�Ƃ��������ŕ������킭��Ȃ�܂��j
�摜�����ő����̂��܂����͂ł���Ǝv���܂����A
�אډ�f�̘I�����ڗ��A���邢�͂�葽���Ȃ�
�قǂ̋O�ՂɂȂ�Ɖ摜��̓u���A�Ƃ��Ďc��܂��B
�i��ςł���t���ł�����܂���j
�|�[�g���[�g��SK����̂悤�ɐ�ΓI�ȉ𑜓x��
�����܂ŏd�v������Ȃ��A�܂��̓e���r�ȂǂŁA
�ӏ܃T�C�Y�����܂��Ă���ꍇ�͍���f��
���f��������قǕς��͂Ȃ��A�Ƃ���
���ӌ�������������������Ƃ͎v���܂��B
��������f�@���[�U�[�Ȃ�2400����f�ł�
������Ȃ����i�̑�L���≓���̒���
�����Ȃǂ̃g���~���O���������������ʂ�
����������Ǝv���܂��B
�i2400����f�Ŏg���ӏ܃T�C�Y�ȏ�Ɂj
�g�傷��̂̓i���Z���X�A�Ƃ����̂�
�ĉf�ʂ̍D�݂̃t���t���[���ł̎B�e��
��r�I�e�ՂȎB�e�W�������i�|�[�g���[�g��
�X�i�b�v�Ȃǁj�ł̘b���ȂƊ����Ă��܂��܂��B
���j�}�̐����ŁA�{����2400����6100����f��
��f�s�b�`�͖{��1.59�{�̈Ⴂ�Ȃ̂ł����A
��}���ʓ|�Ȃ���3vs5�}�X�ő�p�i1.67�{�j
���Ă��܂��B
�����ԍ��F26188927
![]() 0�_
0�_
��hunayan����
������f�@�͈Â��ʂ�̂ŁA���f�@���V���b�^�[�X�s�[�h��������K�v���o�Ă���̂�
����f�͒ኴ�x�ŁA�Ƃ����b���Ȃ�̂��Ƃ�
�ǂ�������Ȃ������̂ł����A�������
�t�W���J��������̐����̂��Ƃł��傤���B
�E����f�J�����ŎB�e���郁���b�g�E�f�����b�g
�u�f�����b�g
��u���Ɏア
��f���̑����J�����ŎB�e����Ƃ������Ƃ́A��f1������̎���ʂ����Ȃ��Ȃ�܂��B
�Â��Ƃ���Ńm�C�Y�����₷���̂Ɠ������V���b�^�[���x�������Ȃ�A
��u�����N���₷���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�������A�ߔN�̍���f�J�����͉摜�����G���W���̑啝�Ȑi����
�{�f�B����u������ڂ̐��i�������Ă��Ă���A���P����Ă��܂��B�v
�E�ʐ^�E����̎B����E�n�E�c�[�i2025.01.05�j
�J�����̉�f���͑������������H�掿�Ƃ̊W�ƍ���f�̃����b�g�E�f�����b�g�����
https://www.fujiya-camera.co.jp/blog/detail/info/20200820/
����f�@�̍����x�h�r�n�m�C�Y������邽�߂�
�V���b�^�[���x��������A�Ƃ����B�e�@��
�u���₷���Ȃ�̂͂܂��A����͓��R�ł����A
������͒��f�@�ƍ���f�@���g���ۂ�
�u�^�p��ł̃u���₷���v�̈Ⴂ�̐����ł��B
���F�X�A�����ƒ��ׂĂ���̂ق����ǂ��ł��傤�B
�����̏ꍇ�ł����A��������̓L�^������
�u����͂��������ʁv�̂��߁A
���h�o�V��}�b�v�A�t�W���������
�ɂ����邩�Ŕ��f���Ă��܂��B
�����قǂ�S1RII�̂`�e�̘b�������܂������A
�����A�ʂł��Ă����[�����O���傫�����Ƃ�A
���ڂ��ꂽ����@�\�����̘^��\���Ԃ�
�t�@���A�t�B���t���Ȃ̂ɂ����̂Ȃ�
��1II�9III�������͒Z���A�Ƃ����_����
��ÂɎs��ɔ��f����Ă���̂��Ǝv���܂��B
�����Ȃ�ɒ��ׂĂ͂������Ȃ̂ł����E�E�B
�����ԍ��F26188948
![]() 0�_
0�_
>���S�ɂ���ׂ��N�_���炸���ꍇ�A���̂����
���m���Ė{���̈ʒu�ɖ߂����Ƃ���킯�ł����A
2400����f�ł͂��͈̔͂Ɏ��܂�u���ł����Ă�
6100����f�ł́u�ƂȂ�̉�f���ł��Ȃ��ق�
�I�����Ă��܂��܂ł̃u���v�ɂȂ�܂���ł��傤���B
�i�}1�A�}2�j
�}���̂��͕̂�����Ղ��̂ł����A����͎�Ԃ�Ƃ�����胁�J�V���b�^�[�Ȃǂ���̔��U���ɂ��u���Ɏv���܂��B
���ۂ�6000����4500����f�́A�u���s�ʐ^�Ƃ����قǂł͂Ȃ��͂��ȃu���v�̓��{�摜���茳�ɉ���������܂����H���̉摜�́A2����3�s�N�Z���̒P�ʂŃu���Ă��܂��ł��傤���H
�����z�肵�Ă���͂��Ȏ�Ԃ�́A�Ⴆ�ΘI�����Ԃ̂���9���ʂ͂قڕ����Ă���A�c���1�����Y���Ă���(���ʁA�֊s�̃R���g���X�g�ቺ)�悤�ȃC���[�W�ł��B���Ȃ��G�c�ł����B
>�אډ�f�ɓ���͂��̌����{���̉�f�i���S���j
�ɂ�����ł��傤����A�I�o�s���͂Ȃ��ł��傤���A
�e�F�̐F�����͖��炩�Ɉ����Ȃ�܂��B
�i���m�N���ł��P�F�Ƃ��������ŕ������킭��Ȃ�܂��j
���ɂ������Ƃ��Ă��A
���[�p�X�t�B���^�[�ɂ��(��Ԃ�ȑO��)�F�����̈������}�C�i�X30�_�A�}�Ɏ����ꂽ�悤�ȃu���ɂ��(���[�p�X���X����f�@)�̃}�C�i�X������20�_�Ȃ�A����f�@�̂ق�����Ԃ�Ɏア�Ƃ͒f��ł��Ȃ��C�����܂��B
����f�ł�����[�p�X���X�ł͂Ȃ��Ă��A�����ʂ̔������[�p�X�ɏo����킯�Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F26189334�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
���}���̂��͕̂�����Ղ��̂ł����A����͎�Ԃ�Ƃ�����胁�J�V���b�^�[�Ȃǂ���̔��U���ɂ��u���Ɏv���܂��B
���������悤�Ƀu���̓~���[�A�b�v��
�V���b�^�[�斋�̓��B�Ռ��ł��N���܂��B
�������A�~���[���X���d�q�V���b�^�[�Ɠ���
����B�e�ł���U��͋N����̂ł��B
�����Â��_���ł����A�X�`���Ɠ����
��U��v���Ɋւ���_���ł��B
�E���w����U���͂ǂ��܂ʼn\���H
��U��v���ƎB�e�摜�̍��𑜓x���B
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/62/4/62_4_500/_pdf
�������z�肵�Ă���͂��Ȏ�Ԃ�́A�Ⴆ�ΘI�����Ԃ̂���9���ʂ͂قڕ����Ă���A�c���1�����Y���Ă���
9�������̉�f�́i���[�p�X�܂މ摜������
���܂�����j��͈͂ɓ����Ă���A�ł��ˁB
���̂킸���Ǝv����U�ꂪ�A���b���̎�U���
���]���̂悤�ȕ����p�x�̏����������Y�ł�
���ɂȂ�Ȃ��ł��傤���B���̎�U����
���E�l�ɋ߂��悤�ȏ����ł͕�����Ղ�����
�v���̂ł����B
�����W���Ȃ��Ȃ�A���b���ł������]���ł�
�Î~�̔�ʑ̂ɂ�����AF�����܂��Ă����
��U��i�Ǝv�����掿�ቺ�j�͋N���Ȃ������ł����A
�����g�̃J�����ł͂������ł��傤���B
�Z�Z�b�莝���B�e�\�I�Ƃ��������݂Ă�
���ƂȂ��Â��i�莝�����͂������ǂ��ł����j�A
�摜���g�傷��ƒ��S�����炫����Ƃ�
�𑜂��Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂����ƌ������܂��B
�����[�p�X�t�B���^�[�ɂ��(��Ԃ�ȑO��)�F�����̈������}�C�i�X30�_
���_�ʐ^�p�Ƀ��[�p�X����苎�����J������
���[�p�X�̂Ȃ��j�R��D800E��D800�����A
�i�i�Ƀu���₷���Ȃǂ̎��Ⴊ����̂ł��傤���B
�i�����͕��������Ƃ�����܂��j
�����ԍ��F26189374
![]() 0�_
0�_
�Ƃт��Ⴑ����
���Ԃ̓s��������_���͓ǂ߂Ȃ��ł��B
�����̂킸���Ǝv����U�ꂪ�A���b���̎�U���
���]���̂悤�ȕ����p�x�̏����������Y�ł�
���ɂȂ�Ȃ��ł��傤���B���̎�U����
���E�l�ɋ߂��悤�ȏ����ł͕�����Ղ�����
�v���̂ł����B
�����W���Ȃ��Ȃ�A���b���ł������]���ł�
�Î~�̔�ʑ̂ɂ�����AF�����܂��Ă����
��U��i�Ǝv�����掿�ቺ�j�͋N���Ȃ������ł����A
�����g�̃J�����ł͂������ł��傤���B
������ƕԐM�̈Ӗ���������Ȃ��ł��B
���́A�u���ɂȂ�Ȃ��v�u�W���Ȃ��v�Ƃ����Ӑ}��
�u�I�����Ԃ̂���9���ʂ͂قڕ����Ă���A�c���1�����Y���Ă���v�Ƃ��������������킯�ł͂Ȃ��B
�ǂ��炩�ƌ����ƁA���肬��NG(�\�Ȃ�B�蒼������)�̏ꍇ���C���[�W���Ă��܂��B
>�Z�Z�b�莝���B�e�\�I�Ƃ��������݂Ă�
���ƂȂ��Â��i�莝�����͂������ǂ��ł����j�A
�摜���g�傷��ƒ��S�����炫����Ƃ�
�𑜂��Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂����ƌ������܂��B
���͎莝�����b�A�̂悤�ȎB�e�͂��Ȃ��h�ł��B
�����_�ʐ^�p�Ƀ��[�p�X����苎�����J������
���[�p�X�̂Ȃ��j�R��D800E��D800�����A
�i�i�Ƀu���₷���Ȃǂ̎��Ⴊ����̂ł��傤���B
�i�����͕��������Ƃ�����܂��j
���[��B������Ӗ���������Ȃ��B
���́A�ǂ��炪�i�i�ɂԂ�₷���A�Ƃ����悤�Șb�͑S�����Ă��܂���B
���[�p�X�t�B���^�[��K�v�Ƃ�����f�̃J�����́A��Ԃꂷ�邵�Ȃ��ȑO(����\�ɂ�炸)�ɑS�Ă̎ʐ^���ڂ₯�܂��B(A)
��ɂƂт��Ⴑ���}�Ŏ����ꂽ���u��(���f�@�ł͎��F������Ȃ�u��)��z�肷��Ȃ�A����f�̃J�����͎�Ԃ���E�t�߂ł��F�����������Ȃ�ڂ₯��Ƃ��܂��B(B)
B��90�_�̎���70�_�̎��ł炯�闦�͒��f�@��菭�������ł��傤�B����������������āA����f�̃J�������u���₷���Ƃ͌����Ȃ����A���̋t���R��Ƃ����b�ł��B
�u�����L�^���Ă��܂����A��ʑ̂������ɋL�^�ł���킯�ŁA���̑��E���镔����������Ă��܂��B�ܘ_�A���炩�Ƀu�����ڗ��ꍇ�̘b�ł͂���܂���B
�����ԍ��F26189428�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
���ǂ��炩�ƌ����ƁA���肬��NG(�\�Ȃ�B�蒼������)�̏ꍇ���C���[�W���Ă��܂��B
����B�e�����Ńu�����A�Ǝv������B�蒼���킯�ł���ˁH
���̃_�����A�Ƃ��锻�f�������f�@�ł͏オ��킯�ł����B
�����͎莝�����b�A�̂悤�ȎB�e�͂��Ȃ��h�ł��B
�|�[�g���[�g�����B�e����Ȃ��Ȃ��
���R���b�I�������@����܂��Ȃ��ł��傤���A
�����獂��f�����f����U��ɂ͊W�Ȃ�
�Ƃ�����̂ł��傤���B
�����g�̂�������ꂽ�B�e�͈́A�ΏہA
�ӏܖ@�ł̂����f�ɂȂ�܂���ł��傤���B
�����[�p�X�t�B���^�[��K�v�Ƃ�����f�̃J�����́A
����Ԃꂷ�邵�Ȃ��ȑO(����\�ɂ�炸)�ɑS�Ă̎ʐ^���ڂ₯�܂��B(A)
���[�p�X�@�ł͂����������ׂĎʐ^���ڂ₯�邩��A
���f�@�̓u���Ɋ��e�A����f�@�̓��[�p�X����������
��U��ɃV�r�A�A�Ƃ������l���ł��傤���B
�������܂��ƁA���f�@�ɂ͎�U����
�ʂɗL���Ă��Ȃ��Ă��ǂ���ł����ˁH
�����[��B������Ӗ���������Ȃ��B
���[�p�X�̗L���Ńu���̔��f���ς��A�Ƃ�������ׁ̈A
�������[�J�[�A����f�A�����\�����[�p�X�t�B���^�[��
�L�������m�ȋ@����Ƃ��ďグ���̂ł����A
���̈Ⴂ�͂킩��Ȃ��̂ł��傤���B
�������܂��ƁA���[�p�X�̗L����
���܂�W���Ȃ���������܂���ˁB
���u�����L�^���Ă��܂����A��ʑ̂������ɋL�^�ł���킯�ŁA���̑��E���镔����������Ă��܂��B
�u�����L�^���Ă��܂�����A�����Ɏʂ邱�Ƃ͂���܂���B
����Ƃ�����f�@�̓u�����L�^���₷�����ǂ��A
���ӂ��ĎB�e����A�����Ɏʂ����Ƃ��o����A
�Ƃ����Ӗ��ł��傤���B
��������������Ղ���Ƃ���1200����f��6100����f
�i��f�s�b�`����2.25�{�j�ł͂������ł��傤���B
�i�}3�C4�j
��U���\�͂������ꍇ�A���[�p�X�]�X�ȑO��
����f�@�̕����ǂ����Ă��u���ɃV�r�A�ɂȂ肻���ł����B
���F��}��3�F7�i2.33�{�j�̂��ߎ��ۂƂ͈قȂ�A
�u���̋O�Ղ�������������K���ȃC���[�W�ł��B
�����ԍ��F26189522
![]() 0�_
0�_
>����B�e�����Ńu�����A�Ǝv������B�蒼���킯�ł���ˁH
���̃_�����A�Ƃ��锻�f�������f�@�ł͏オ��킯�ł����B
6000���M���M���̃f�B�e�[���ŁA�Ƃ������͐T�d�ɎB�e���܂��B2400���ł����l�ł��B
���|�[�g���[�g�����B�e����Ȃ��Ȃ��
���R���b�I�������@����܂��Ȃ��ł��傤���A
�����獂��f�����f����U��ɂ͊W�Ȃ�
�Ƃ�����̂ł��傤���B
�����g�̂�������ꂽ�B�e�͈́A�ΏہA
�ӏܖ@�ł̂����f�ɂȂ�܂���ł��傤���B
�|�[�g���[�g���A���̎B�e�W�������̕��������ł��B�������i�ł͂����ďڂ������M���Ă��܂���B
��Ԃ�����̎B�e���p�ɂɂ��Ă��܂��B
�����[�p�X�t�B���^�[��K�v�Ƃ�����f�̃J�����́A
����Ԃꂷ�邵�Ȃ��ȑO(����\�ɂ�炸)�ɑS�Ă̎ʐ^���ڂ₯�܂��B(A)
���[�p�X�@�ł͂����������ׂĎʐ^���ڂ₯�邩��A
���f�@�̓u���Ɋ��e�A����f�@�̓��[�p�X����������
��U��ɃV�r�A�A�Ƃ������l���ł��傤���B
�������܂��ƁA���f�@�ɂ͎�U����
�ʂɗL���Ă��Ȃ��Ă��ǂ���ł����ˁH
�Ⴂ�܂��B�ǂ��炪�V�r�A�ƒf�肷��Ӗ��������A�Ƃ����b�����Ă��܂��B
��Ԃ��͕K�v�ł��B��ɐ}�ł��߂��ꂽ�A�u2400���ł͂قږ����ł��邪����f�ł͎��F�ł�������ȃu���v�ɑ��錩���́A��Ԃ�������Ȃ�ɗL���ɍ�p������(�������́A�œ_������2�{�ʂ�SS�͊m��)�ł̘b�Ȃ̂ŁB
���u�����L�^���Ă��܂����A��ʑ̂������ɋL�^�ł���킯�ŁA���̑��E���镔����������Ă��܂��B
�u�����L�^���Ă��܂�����A�����Ɏʂ邱�Ƃ͂���܂���B
����Ƃ�����f�@�̓u�����L�^���₷�����ǂ��A
���ӂ��ĎB�e����A�����Ɏʂ����Ƃ��o����A
�Ƃ����Ӗ��ł��傤���B
���ׂȃu���A�ł���A���Ȃ�̒��x�����Ɏʂ��Ă��܂��B�v�́A��������2400���@�̃��[�p�X�L�摜�����V���[�v������K�ɂ��Ă���荂���_�̎ʐ^�ɂȂ�ƁB
2400���Ŋg�債�Ăقڎ��F�ł��Ȃ����x���̔��u���A��Ԃ������������������Ŋ��S�ɂ͕������Ă��Ȃ��̈�̉摜�ł��B
�������A��ɒ��f�@���L���Ƃ͂���������͏o��ł��傤�B
>��������������Ղ���Ƃ���1200����f��6100����f
�i��f�s�b�`����2.25�{�j�ł͂������ł��傤���B
�i�}3�C4�j
��U���\�͂������ꍇ�A���[�p�X�]�X�ȑO��
����f�@�̕����ǂ����Ă��u���ɃV�r�A�ɂȂ肻���ł����B
1200���A500���A�Ƃǂ�ǂ炵�Ă�����
��Ԃ�����������Ŏc��悤�Ȕ��u���A�͈̔͊O�ɂȂ�Ǝv���܂��B���͂��Ԃ�����v��Ȃ��ƁB
�����������u������x�ȏ�ɃV���[�v�Ȏʐ^���B��K�v������(�V���[�v�ł���قǍ����_)�v�Ƃ����O��Ŏ��͘_���Ă���̂ŁA500����f�@�͎�Ԃ�ɋ������H�A�͎�|���̂��̂�����Ă��܂��B
D800��D800E�Ɋւ��ẮA��҂�I�т܂��B���ɎB���ďo��JPEG���g�債�Ĕ��u�������F�ł��Ă��A�œK�ȃV���[�v������D800��(�S��������Ԃꂾ����)�摜��菭�������_�ɂȂ�₷���Ƃ����l���ł��B�������A���B�蒼���ΎB���ďo����90�_�ɂ��o���܂��B
�����ԍ��F26189631�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
����f�Ńu�����ڗ����₷���A�ڗ����ɂ�����
���RAW�����V���[�v�l�X�����ł��܂�������悢�A
�͂��ꂱ���ʌ��ɂȂ�܂���B
�����ԍ��F26189831
![]() 0�_
0�_
>����f�Ńu�����ڗ����₷���A�ڗ����ɂ�����
���RAW�����V���[�v�l�X�����ł��܂�������悢�A
���̏ꍇ�A2400���@�ł��\���Ɋg�債�Ă悭����A�܂��������ׂ̍��Ȕ�ʑ̂ł���Δ��u���͊m�F�ł���i�֊s���̋͂��ȃR���g���X�g�̒ቺ�j�Ƃ����z��ł��B
������u�X��C�ɂ��Ȃ��i�������Ȃ��j�v�Ƃ����̂́A�����܂Ŏ�ςƗp�r�̖��ł���A�u���RAW�����V���[�v�l�X�����ŌӖ������v�Ӗ����Ȃ��i�S�����P����Ȃ��j�킯�ł͂���܂���B
���炽�߂Đ�������ƁA���Ƀ��[�p�X�L��2400���@�̍ō��掿����2100���Ɖ��肵��
�@�ǂ�ȂɁi�莝���Łj�撣���Ă����2100���̉掿���������Ȃ���U��ɃV�r�A�ȏ����Ŗ����̂悤�ɎB�e���鎖���m�肵�Ă���B
�A�ǂ�ȂɎ�U��ɃV�r�A�ȏ����ł����Ă��A��ɖ�5600�������̉掿�ŎB��Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�B�肽���j�Ɗm�肵�Ă���B
�@�̃P�[�X�ł́A���R2400���̒��f�@���ł��傤�B
�A�̃P�[�X�ł́A��͂�掿�̍Œ�l�������̂�6000����f�@�킴��܂���B
����f�@�̕�����U��Ɏア�A�Ƃ����������Ȋw�I�ɊԈႢ���Ƃ����b�ł͂Ȃ��A�@�ޑI��������ł��́u�̕�����U��Ɏア�v��������قڈӖ����Ȃ��Ȃ��Ƃ������ł��B
�Ƃ����̂́A���ɇ@�̂悤�ȎB�e�����ɔN�ɋ����I�ɉ��x������Ƃ��Ă��A6000���@�ŎB����2400���@��茋�ʂ������Ȃ�킯�ł͂���܂���B�����āA�@�̏������T�T�ł���ƕ������Ă���i���Ɩ��B�e�̃��C���j�Ȃ�A��͂�命���̐l�͖��킸2400���@��I�Ԃł��傤�B
���������A2400���ł͎��F������ō���f�ɂȂ�Ɩڗ��悤�ȃu���A���ĕp�ɂɔ�������悤�Ɋ����܂���B������͎�ςł�
�����ԍ��F26190056
![]() 0�_
0�_
�NjL�B
���f�@�ɂ����āA�ŏ����烍�[�p�X�t�B���^�[�ɂ��u�S�Ẳ摜���ڂ₯��v�O��ōœK��(�ƃ��[�J�[���l����)�V���[�v���������Ă���Ȃ�A
����f�@�ɂ����Ď�Ԃ�ɃV�r�A�ȏ�ʂł̎B�e�ōŏ�����u�S�Ẳ摜���͂��ɔ��u�����邩���m��Ȃ��v�O��̃V���[�v�ݒ��^���鎖�͓��ʃA���t�F�A�ł͂Ȃ��Ƃ̔��z�ł��B
����Ă鎖�̈Ӑ}�͓����Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F26190080�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
������f�@�̕�����U��Ɏア�A�Ƃ����������Ȋw�I�ɊԈႢ���Ƃ����b�ł͂Ȃ��A
�אڂ����f���u���ɂ��I������₷���A
�Ƃ������Ƃ͂����������������Ƃ������Ƃł��ˁB
���̗אڕ��̉�f�̘I�������C������Ȃ�
�i������ɂ��������u����Ȃ�j�{������ׂ���f��
�I���ʂ���ł��傤����A�摜�����������
���Ă��A�u�������ׂ���f������ς���āv
���܂��܂�����ˁB���u���ǂ��납�A���S��
�u���摜�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���@�ޑI��������ł��́u�̕�����U��Ɏア�v��������قڈӖ����Ȃ��Ȃ��Ƃ������ł��B
�����͂Ԃ�₷�����獂��f�@��I�Ȃ��悤�ɁA
���Ƃ͈ꌾ�������Ă��܂����B
�������hunayan����̌�咣�Ȃ̂ŁA
�����Ⴂ�Ȃ���Ȃ��悤���肢���܂��B
�����̋@�ނ����C���͍���f�@�ł��B
�p���������b�ł��������͎�U�ꂵ�₷���A
�~���[���X�ɂȂ��ă~���[�V���b�N���Ȃ��Ȃ�
�d�q�V���b�^�[�ɂȂ�A�����Y���\���オ��
�t�B��������͂������A���t�������
����f�@�ō��掿���������
�����Ă��Ă�����̂́A�����B���
�\���ɐ��\�������o���Ȃ��Ȃ�
�����Ȃ���B�e���Ă��܂��B
������Jpeg�B�e�h�Ȃ̂ŁA���s�ʐ^��
���̌��RAW�����ŃV���[�v�l�X��
������Ƃ�����Α��v�A�Ƃ���
���z�͂Ȃ���ł���ˁB
�����ԍ��F26190167
![]() 0�_
0�_
>���̗אڕ��̉�f�̘I�������C������Ȃ�
�i������ɂ��������u����Ȃ�j�{������ׂ���f��
�I���ʂ���ł��傤����A�摜�����������
���Ă��A�u�������ׂ���f������ς���āv
���܂��܂�����ˁB���u���ǂ��납�A���S��
�u���摜�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���̘_�|�����߂Ċ��ݍӂ��ƁA
�܂���Ԃ��@�\�̔\�͂ƃ����Y���\(�����̉𑜗�)��ISO�̑ϐ����Ɖ��肵�āA
�����2000����f�̉𑜓x����������x�̎�u��
������4000�������̃u��
6000�������̃u��
����Ɉꉭ�����̃u��
�����邾���ŁA�J��������f���ɂ��u��Ԃ�ɋ������ǂ����v��_����K�v�͂Ȃ��Ƃ����b�B(��Ԃ��@�\�̐��\���������ǂ����́A������Ӗ�������)
���̂Ȃ�A�P���Ɂ��̂悤��(��f�̘I���Ɋւ���)�����ɏI�n����Ȃ�A����́u���掿�Ȏʐ^���B�e����̂͒�掿�Ȏʐ^���B�������v�Ƃ�����ʘ_�������Ă���̂Ƒ卷���Ȃ��Ȃ邩��ł��B
�����ĉ��Ɉꉭ��f�̃J�����œx�X5000���̎ʐ^�����B��Ȃ��̂��u�ܑ̖����v�ƍl���邩�ǂ����́A�����܂Ŗ{�l�̎�ς�p�r�̖��B
����f�ȃJ��������Ԃ�Ɏア�A���邢�̓u���₷���킯�ł͂Ȃ��B
��{�I�ɂ͂ǂ�ȏ����ł��A����f�ł���قǍ��掿�ɂȂ�\��������(��ɏq�ׂ��悤�����Y���\��ISO���ł���Ȃ�)�ƍl����̂��K�Ɏv���܂��B
���Ƃ́A�����Ɏg�p���郌���Y��ISO���Ԃ����\�Ƃ̌��ˍ����ł��ˁB
��₱�����̂ł��̕ӂŁB
�����ԍ��F26190402�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
S1R2�̓}�b�v�J�����ƃt�W���J�����͍��������ł��ˁB
�Ӗ��s���Ȑ}�����������Ă��A
�u���̍��͔������܂���A���ꂾ���ł��B
��u����̐��\���ς��܂���B
���[�J�[�̎d�l�����S�Ăł��B
�떂�����Ă����ʂł���B
�����ԍ��F26190434�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
�������2000����f�̉𑜓x����������x�̎�u��
��������4000�������̃u��
��6000�������̃u��
������Ɉꉭ�����̃u��
�������邾���ŁA
������e�i300dpi)�̎w�E�T�C�Y��
500����f��A5�A200����f��A3�A
4000����f��A2���x�ł��ˁB
�E�f�W�J���̉�f���ƈ���\�ȃT�C�Y��K�ȉ𑜓x���ڂ������
https://www.photografan.com/basic-knowledge/print-degital-camera-resolution/
��f���ɂ�苖�e�ł���g�嗦�i���ł���̈����������j��
��������AA2���x�̑傫���i594×420mm�j���x�Ȃ��
�u���ʂ́iA4�ƕς��Ȃ��j�����Ŋg��ӏ܁v
���邱�ƂɂȂ�܂���B
�𑜓x�𗎂Ƃ���4000����f�N���X��A0����ł��āA
�����܂łȂ�Ə�������Ă݂���͂���ł��傤���ǁB
�����g���G���AA4���x�܂ł����L���Ȃ�����
�ς��Ȃ��i�킩��Ȃ��j�͕ʂƂ��Ăł���
�i��ς̖��j�B
��hunayan����
���Ӗ��s���Ȑ}�����������Ă��A
���������i�ނƂ悢�ł����B
��S1R2�̓}�b�v�J�����ƃt�W���J�����͍��������ł��ˁB
�������R�����g�������͂ǂ��炩��
�{�f�B�݂̂����������̂ł����A
�����Ă݂܂��ƁA
�}�b�v�ł̓����Y�L�b�g�ɂ���A�{�f�B�ɂȂ��A
�t�W���J�����ł̓����Y�L�b�g�ɂ���A�{�f�B�Ɏc��͂�
�ł��ˁB
�l�o�̑������j���ɍɂ����������āA
���j�������Ƀ��[�J�[�����[���ꂽ�̂ł��傤���B
���Ƃ���ƁA�����܂ł͕i�s���ł��Ȃ��悤�ȁH
�C�����܂��ˁB
������x����Ă���Ȃ�A����͂���ł��ꂵ���ł��B
�p�iHD��1���l���X�g����s�̎Z����̌����������邻���ŁA
�G���^�[�e�C�������g���R�~���j�P�[�V�������ɂ�
�撣���Ē����Ȃ��ƁAOMDS�̈�{���Ŗ@�ł�
M4/3�V�X�e���i���[�U�[�ł��j���S���Ƃ���܂���̂ŁB
�����ԍ��F26191590
![]() 0�_
0�_
�Ȃ�����̘b�ɁH���ۂɁA2400���Ŋg�債�ĕ�����Ȃ��͂��ȃu���A������5000���Ŋg�債�Ĕ��ʂł���ʐ^���L��������������Ȕ�r�摜�Ȃ�܂�������܂��B
>�����2000����f�̉𑜓x����������x�̎�u��
������4000�������̃u��
6000�������̃u��
����Ɉꉭ�����̃u��
1����f�@�̂ق���(�𑜓x���t���ɔ����������Ȃ�)��Ԃ�Ɍ������A���ꂾ���Ȃ�N�ł��ŏ�����m���Ă��鎖�ł��B1000���̎ʐ^������Ɍ��܂��Ă܂��B
�����A���������Ă��@�ޑI��ɂ͂قږ��ɗ����Ȃ��Ƃ����b�����Ă��܂��B���̓_�͉��x�������Ă܂���ˁB
�Ⴆ��3000����2400���@�Ŏ�Ԃꂪ�������č���A�Ȃ�ă��r���[��(���ʂ̗p�r�̃��[�U�[�Ȃ�)���i�ł��قƂ�nj������܂���B
5000��6000���Ŕ��u�����C�ɂȂ�Ȃ�AISO����i�グ�邩�i�����i�J���邩�A�����i���ς��邩�A�ł��������̏�ʂ͑Ή��ł��܂��B��7R�X�̉��i���r���[�ł���Ԃ��@�\�̐��\UP�͕]������Ă��邵�A�m�C�Y�������\�t�g�̐i������Ώ��̗]�n������ł��傤�B
�܂�����f�@�͉��i������Ȃ�ł�����A�ǂ̃��[�J�[�������@��萫�\���ǂ���Ԃ��𓋍ڂ���X��������܂��B
�Ƃт��Ⴑ������f�@�̎�Ԃ�ō���@������Ȃ�A����͋�̓I�ɂǂ̂悤�Ȕ�ʑ̂Ɨp�r�Ȃ̂ł��傤���H���_�I�ɗאڂ����f���ǂ��̂����̂́A�ŏ����玄���f�l�Ȃ�ɔc�����Ă��܂��B
���̏ꍇ�́A�Â������̐Õ������肵��(�֎q�ɍ����ǂɊ�肩���铙)�\����50����100mm�ŎB�e�������莝��1/10�ȉ���F5.6�Ő���B���(�Œ�1��OK�J�b�g���m��)���ɖ��͂���܂���BISO��3���Ŏ��܂�܂��B���̎�̔�ʑ͎̂B�蒼�����\�Ȏ����������A4���Ă����b�ł��B
�|�[�g���[�g�ł͔�ʑ̃u�����C�ɂ���SS�����߂܂������Ԃ�͂��܂�W�Ȃ��ł��B�X�|�[�c�⓮���������ł���ˁB���i�����̉e��������܂��B
���Ȃ�Â���i��A�A�A���������O�r�Ȃ��ŗǂ��ʐ^�B��܂����ˁH����f�@�̂ق�����Ԃ��̐��\�͗ǂ������肷�邪�A�A�A����͂ނ��덂���x�ϐ��̖�肩�ƁB
��ʘ_�Ƃ��āA2400���J�����̂ق������t�ɎB��镔���͂���ł��傤��
�u����f�̎�Ԃ���C�ɂ��Ă���v���[�U�[�́A������������f�ɂ��掿�ʂ̉��b�ɊS�������čw�����ɓ���Ă���킯�ŁA�uISO��SS�グ��ʂȂ狻���Ȃ��v�Ƃ͊ȒP�ɂȂ�Ȃ��ł���B
��̓I�ɂǂ�ȎB�e�����łȂɂ��B��̂��A����Łu��Ԃ�ɍ���v�x�����͑S�R�ς���Ă��܂�����A���̓_���������������B
�����ԍ��F26191755�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�NjL�B
>���̏ꍇ�́A�Â������̐Õ������肵��(�֎q�ɍ����ǂɊ�肩���铙)�\����50����100mm�ŎB�e�������莝��1/10�ȉ���F5.6�Ő���B���(�Œ�1��OK�J�b�g���m��)���ɖ��͂���܂���BISO��3���Ŏ��܂�܂��B
���Ȃ݂ɂ��̏�����NG�J�b�g�́A�u2400����3300���ŎB�e���Ă��Ă��Ԃꂪ���ʂł����ł��낤�v�ʐ^�̕�����⑽���̂ł��B
�ƂȂ�ƁA�ᑬSS���Ƀ�7R�X��(�Ⴆ��7�W�ɔ�ׂ�)��Ԃ�Ɏア�A�ƒf��ł��Ȃ��C�����܂��B
�����ԍ��F26191786�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ȒP�Ƀe�X�g���Ă݂����ǁA
������SS1/3�AISO800�A135mm�Ń�7R5��6100����M�T�C�Y2600���̔�r����A�҂�����~�܂�̂�5����1�����x�łǂ�����ς��Ȃ��B
�̐�������1/6�b�ł��A�قƂ�Ǔ���(5����)�ł��B
�ŏ�����2600���̃Z���T�[���Ƒ����Ⴄ�̂����B
�����ԍ��F26191836�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
���Ȃ�����̘b�ɁH
35�~���i�t���T�C�Y�j���ł����
�g�嗦���ς���r�I�g�߂�
�Ꭶ�Ƃ��Ăł��B
�ӏ܁i���邢�͓��e�j�t�H�[�}�b�g��
���܂��Ă�����X�ɂ͊W�Ȃ��b�ł��傤���B
���Ƃт��Ⴑ������f�@�̎�Ԃ�ō���@������Ȃ�A
���݂͂��قǍ����Ă��Ȃ��̂ł����A
���C���@����7RIII�ɂ������Ƀs���g��
�u���i��ʑ̃u���A��u���j��
�V�r�A���ȁA�Ɗ���������ł��B
�����ԍ��F26192261
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DC-S1RM2 �{�f�B
�A�b�v���[�h�̂���4200����f�ɏk���ς� |
�A�b�v���[�h�̂���4200����f�ɏk���ς� |
�A�b�v���[�h�̂���4200����f�ɏk���ς� |
���܂��̃K���_���i����͒ʏ�B�e�j |
����K�ꂽ�����Ŕ��p�i���B��@��������̂ł���
Lumix�̋��͂Ȏ�U����������
�莝���n�C���]�V���b�g���g���Ă݂܂����B
���ʁA���p�i�ׂ̍₩�ȃf�B�e�[������������L�^����
���Ƃ��炶������ώ@�ł���̂ŁA��͂茋�\�g����@�\���Ɗ����܂����B
�����n�C���]�����ɂ͎��Ԃ�������e���|�ǂ��͎B�e�͏o���Ȃ�����
����ł��Č��ɐl�̑҂�������ꍇ�͌����Ȃ��ł��ˁB
���炽�߂�S1Rii�{20-60mm�̃R���r�͋@���͍����ėǂ��ł��ˁB
![]() 14�_
14�_
��kagura03374����
�莝���ł́A�Y������u���܂��H
�����ԍ��F26163292
![]() 2�_
2�_
��kagura03374����
����ɂ��́B
���莝���n�C���]�V���b�g���g���Ă݂܂����B
�m���ɍׂ����`�ʂŃm�C�Y�����Ȃ����ł����A
�摜�����Â߂Ɋ�����̂́A�掿�ݒ艻
�n�C���]�̍����v���Z�X�A���邢�̓����Y��
�i��J�����\�ɂ����̂Ȃ̂ł��傤���B
�i�C�̂�����������܂��j
�����ԍ��F26163330
![]() 2�_
2�_
��From Photo����
�ݒ�Ɏ莝���n�C���]���[�h������A�����g��������ł͎莝���ł��Ԃ�܂���ł����B(�B�e���ɃJ�������������莝���ău���ɋC���g���Ă��܂���)
�����ԍ��F26163412�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���Ƃт��Ⴑ����
���icom�̎d�l��APC�̃f�B�X�v���C�ݒ��100%�ȏ�̐ݒ�ŕ\�����Ă���Ƃ��̕��摜���g��⊮����Ď��ۂ��Â������܂��B(�����̏ꍇ4k���j�^�[��200%�\�����Ă�̂œ��{�\���͑啪�Â��Ȃ�܂�)
���j�^�[�ݒ肪100%�ł�������������Ȃ烌���Y�̊J���`�ʂ�s���g�̂�����������܂���B(�����ȊO�͊Â��Ȃ肪���ł���)
�����ԍ��F26163435�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�̉摜������ɂ��Ă��A�������܂艶�b�͊����Ȃ��ł��ˁB�������̕��i�ł���ΈႢ���o��̂�������Ȃ����ǁA�O�Ȃ疳���łȂ��ƃ������o��ł��傤���B�l���ł��A����X�J�[�g���Ȃт�����͂��܂�����B
4200���̒ʏ�B�e�ŁA�������̃V���[�v�̂������Ƃ�AI�ł̃A�b�v�X�P�[�����őΏ����������قƂ�ǂ̏ꍇ�͗L�����������悤�Ɋ����܂��B
�����ԍ��F26166585
![]() 2�_
2�_
���J����SP����
�擾�ł�����ʂ͊m���ɏオ��̂ŁA�����ĂȂ����̋L�^�p�ł��ˁB
�����͍���g����@�\���Ɗ��������߁A�Ƃ肠����1�V���b�g�͎B��悤�ɂ��Ă܂��B(���i��Õ��Ɍ���܂���)
��������AI��̕��������ڂ̉𑜊��͏オ�邩������܂���ˁB
�����ԍ��F26166807�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��4200���̒ʏ�B�e�ŁA�������̃V���[�v�̂������Ƃ�AI�ł̃A�b�v�X�P�[�����őΏ����������قƂ�ǂ̏ꍇ�͗L�����������悤�Ɋ����܂��B
�����������Ɖ��肵�Ă��A�莝���n�C���]�œ���ꂽ���𑜂ȉ摜�Ɂu�������̃V���[�v�̂������Ƃ�AI�ł̃A�b�v�X�P�[���v�Ƃ��̏������{���A����ɗǂ����ʂɂȂ���Ď��ł��ˁB
�������C�ɓ���Ȃ�������āA���������������������肵�Ĕے�����肷��l���Ă��܂���ˁB�i�قږ����l�ł����j
�ق�̐��N�O�́u�~���[���X�v�A�u�d�q�r���[�t�@�C���_�[�v�ɂ��ے���肵�Ă��l�����͍��͂قڐ�ŁA���̐l�������~���[���X��EVF�����������g���Ă��肵�܂��B
�@��͈Ⴂ�܂����A�����莝���n�C���]�͑f���炵���Z�p���Ǝ������Ă���A�ϋɓI�Ɏg���Ă܂��B
�����ԍ��F26166909
![]() 19�_
19�_
�莝���n�C���]�V���b�g�́A�Ƃ肠�����P���Ƃ��Ƃ����i�p�V���j
���Ă��������ŎB�e���Ă���B
�E��U����C�ɂ��Ȃ���1�V���b�g�����i�����Ɏ��Ԃ������邩��j�B�e����B
�E�����ɐ���������掿�̎ʐ^����ɓ���B
�Ƃ����B�e�X�^�C�����ʔ��������Ă��܂��B
�_�C�A�������킹��ڂ������܃n�C���]�B�e���[�h�ɂȂ�̂��ǂ��ł��ˁB
�ȑO�̓��e�ƈꕔ���Ԃ�܂�������������ʑ̂Ŏg���Ă��܂��B
�i�k�����Ă܂��j
�����ԍ��F26167941
![]() 5�_
5�_
�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DC-S1RM2 �{�f�B
���낻��܂����O���ƌ���ꂻ���ł����B
Lumix Spro 70-200mm F4.0���}�X�^�[�����Y�Ƃ���
1.4�{�e���R���{�n�C�u���b�h�Y�[���iM�j�{40�R�}�A�ˁ{�v���L���v�`���[�{�������o�i���j
�Œ��������B�肵�Ă��܂����B
����B�e���Č���I�Ȑ��\�s�������������̂ł����B
����͎B�e�҂̔��ł��钹���t�@�C���_�[���Ɏ��߂�X�L���ł��B
���₷���t�@�C���_�[�A�����\��AF���ʑ̌��o�@�\�A�A�ˋ@�\�������Ă�
�̐S�̔�ʑ̂𑨂���\�͂��Ȃ���Ε�̎�������Ƃ������Ƃ�����܂����B
�Ȃ̂ō����œ�������ʑ̂��B��Ƃ��̓n�C�u���b�h�Y�[���g�킸
�t�@�C���_�[�����L���Ƃ邽�߂ɕ��ʂɎB�e���������ǂ���������܂���B
�i���Ȃ݂�RAW�{Jpeg����RAW�ɂ̓N���b�v�O�̃t����f�̉摜���ۑ�����܂��B�j
�A�ˋ@�\�ł����A�b��40�R�}�{�v���L���v�`���[�A�˂͑f�l�̎��ł��ʔ����ʐ^�i����I�u�ԁj���B���
�f���炵���@�\���Ɗ����܂����B
�����o�b�t�@��70�R�}���ł��肱�̃o�b�t�@��1�b������Ƃŏ���Ă��܂����߁A���f�B�A�ւ̏������݂���������܂�
���̎B�e�J�n�܂Ō��\�҂�����܂����B�i�����ƍ����ȃ��f�B�A���g�p����Ή��P���ꂻ���ł͂���܂����B�j
1.4�{�e���R���{�n�C�u���b�h�Y�[���iM�j�̉掿�ł����{�̂�����f�@�ł���
���̃����Y�̉𑜓x�������������\�����p�ɂȂ�掿���Ɗ����܂����B
���������Ȃ̂ō����ڂ��Ă����܂��B
���肸�ɂ��t������������K���ł��B
![]() 11�_
11�_
���Ȃ݂ɂ��̐ݒ�̏ꍇ�e���[��392�����ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F26137277
![]() 1�_
1�_
35mm���ZiA�Y�[��800mm�ŎB�e |
35mm���ZiA�Y�[��800mm�ŎB�e |
35mm���ZiA�Y�[��800mm�ŎB�e |
35mm���ZiA�Y�[��800mm�ŎB�e |
kagura03374����A�����́B
�A�b�v���ꂽ�쒹�̍���q�����܂������Akagura03374����
S1RM2���g���āA�B�e���y���܂�Ă���l�q���ǂ�������܂��B
���̓����Y�P�̌^���{���Y�[���@���g����
���ɃA�b�v�����悤�ȁA�쒹�̔��ăV�[�����B�e���Ă��܂��B
�u���ł��钹���t�@�C���_�[���Ɏ��߂�X�L���v����
�쒹�Ɍ��炸�A���낢��ȓ����̑�����ʑ̂��B�e����Ƃ�
�����̎B�肽���ʐ^���B���m�����傫���A�b�v���܂�����
���ЎB�e���y���݂Ȃ���A���̃X�L�����Ă��������B
�܂��A�f���炵����Ⴊ�A�b�v�����̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F26137414
![]() 5�_
5�_
��isiura����
�R�����g�Ƒf�G�Ȃ��ʐ^���肪�Ƃ��������܂��B
���̓J�����̐��\�ɂ���Ԃɂ������ȏ�ԂȂ̂ŁA���ɂ������ݒ���o������B�e����X�L�����Ă�Œ��ł��B
���������̂͂�͂�o�����Ǝv���܂��̂ō���������ȏꏊ�Ə����ŎB�e���A�ʐ^���y����ōs�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26137484�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
>����B�e���Č���I�Ȑ��\�s�������������̂ł����B
����͎B�e�҂̔��ł��钹���t�@�C���_�[���Ɏ��߂�X�L���ł��B
���͂́[�B�{���ɂ����Ȃ�ł���ˁB�l���S���l�̂��Ƃ͌����܂����
�J�����Ɏ������a�̂����ڂ�҂��̃g�r�͌��\�̂�т�߂ɔ�Ԃ��ǃJ�������Č��\�r�����r������щ���āA�����Y�U��Ȃ��Ƃ��Ă����Ȃ��ł����
S Pro 70-200/4�͊��Ƒ傫�߂����ǂ��̕��悳�����ł��ˁBS1RII�͂�͂�o�b�t�@��������ƃl�b�N�H
�����ԍ��F26137614�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��seaflanker����
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
400mm�߂��]�����Ǝ��̃X�L���s���������ɏo�܂����B����Ȃɓ���Ƃ́B
�h�b�g�T�C�g�ƌ����@�킪�Ȃ�����̂��킩�����C�����܂��B
SPRO 70-200 F4.0�͎ʂ���ǂ��C�ɓ����Ă��܂���F2.8���͌y���Ƃ͂����傫�߂̃����Y�ł��̂Ŏ莝���ň�����B�e���Ă���Ɨ����ؓ��ɂɂȂ�܂��B(�B�e���Ă鎞�͊y�����Ă��܂�C�ɂȂ�Ȃ��̂ł���)
�����ԍ��F26137652�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��kagura03374����
S Pro 70-200mm F4��985g�ƃ��t�@�����70-200/4����������Əd���ł��ˁB�ł����̕��A�p�i�\�j�b�N�͌��a�H�̏������ɍS���Ă�悤�Ȃ̂ŁA�ʃ{�P�Ƃ��ǂ�Ȋ����Ȃ̂��C�ɂȂ�܂��ˁB
�l�l�I�ɂ�Otus 1.4/28��28mm F1.4�Ȃ̂�1.3kg�Ȃ̂ŁA1kg�����Y���ƌy��~�ɂȂ��Ă��܂����炢���o���Y��������Ă܂���
�����ԍ��F26147343�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z�T�[�o�[�p����PC �\����
-
�y�~�������̃��X�g�z10��7��
-
�y�~�������̃��X�g�z�����Y
-
�y����E�A�h�o�C�X�z����PC���ւ�����
-
�y�~�������̃��X�g�z����p�\�R��2025
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h
- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j