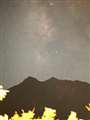���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S234202�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2025�N10��20�� 18:40 | |
| 4 | 5 | 2025�N10��20�� 16:32 | |
| 33 | 4 | 2025�N10��27�� 17:04 | |
| 12 | 6 | 2025�N10��27�� 20:55 | |
| 24 | 28 | 2025�N10��24�� 19:54 | |
| 8 | 15 | 2025�N11��1�� 14:26 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > SONY > ��7C ILCE-7C �{�f�B
�����b�ɂȂ�܂��B
�薼�̂Ƃ���A���݂�ZV-E10�𗘗p���Ă��܂��B
���܂Ńt�@�C���_�[�t���̑��А��i�𗘗p���Ă������߁AEVF�t���̐��i�ɐ�ւ������Ǝv���Ă��܂��B
���݂�SIGMA��CONTEMPORARY16mm F1.4 DC DN��^��������Model B061 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD�𗘗p���Ă��܂��B
���̂��߁A�t���T�C�Y�����Y�̔��������͓��ʂȂ����Ǝv���܂��B
���͓���i4K�͂��܂藘�p���܂���j���B������A�H�ו���ԂȂǂ̎ʐ^���B������Ɗ��Ă��܂����B
7C��6700�A���z�I�ɋ߂��Q���Ǝv���܂��B
�ǂ��炪�������߂ł��傤���B
�܂��A�������̑��̋@��ł��������߂�����Ε����Ă����������������܂��ƍK���ł��B
�����A�������̂قǁA��낵�����肢���܂��B
![]() 1�_
1�_
���͂�ǂ那����
>> �t���T�C�Y�����Y�̔��������͓��ʂȂ�
APS-C�����Y�ł��ƁA
�t���T�C�Y�@�̉��b���Ȃ��̂ŁA
�t���T�C�Y�����Y���邱�Ƃ��������߂��܂��B
APS-C�̃�6700�ł����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26320630
![]() 2�_
2�_
���͂�ǂ那����
�@���̏����Ȃ�A��6700�����Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F26320649
![]() 0�_
0�_
���͂�ǂ那����
�t���T�C�Y�����Y�̔��������͓��ʂȂ����Ǝv���܂��B
��ʑ̂ɂ����܂����AAF���i��������7C�U�Ȃ�I�X�X���ł����A�\�Z�̓s����7C��I�����Ă�APS�p�����Y�ʼn^�p����Ȃ烿6700���w�����������ǂ��Ǝv���܂��B
�܂��A��7C�U�ɂ��Ă�APS�����Y�ł����6700���ǂ����Ă͕̂ς��܂��B
�t���T�C�Y��APS�����Y���ƃN���b�v�^�p�Ȃ̂ʼn�f��������܂��B
�ӏܕ��@�ŃN���b�v������f���ł����Ȃ��Ȃ�Ƃ͎v���܂����AAIAF�ł�����V�X�e���Ƃ��Ă̓�7C�U��APS�łƍl���ėǂ��̂��ȂƎv���܂��B
�ǂ����Ă��t���T�C�Y�Ȃ烿7C�U�ƃ����Y��������܂ő҂��������ǂ��Ǝv���܂����A����Ń{�f�B���ւ���A�lj�����Ȃ烿6700���x�^�[���Ǝv���܂��ˁB
�����ԍ��F26320678�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��with Photo����
���G���~�l�A����
��������@������������
�݂Ȃ��܁A�����̂����肪�Ƃ��������܂��B
�����O�̂Ƃ���A���p�p�r�����ӂ݂Ă��t���T�C�Y�����Y���w������\�������Ȃ�Ⴂ�̂ŁA6700�Ō�����i�߂����Ă��������܂��B
�����͒l�i��������6600��6400�Ƃ��v���Ă��܂�����ZE-V10����̏�芷�����ƒ��r���[���Ǝv���V�b�����ɋ����Ă���܂����B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F26320846
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > SONY > ��7 III ILCE-7M3 �{�f�B
�C�O�d�l�̕��͓��{��\���������ƕ����܂����A�{�̋@�\�Ńt���b�J�[���X�Ȃǂ͓��{�łƓ��l�ɓ��{�Ŏg����̂ł��傤���H
�����ԍ��F26320408�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ÂŊ撣���Ă܂�����
�g���܂���B
�����ԍ��F26320416
![]() 1�_
1�_
�����ÂŊ撣���Ă܂�����
���߂܂��āB
���ꃁ�j���[�œ��{�ꂪ�I�ׂȂ����Ƃ�PAL�ENTSC�̐�ւ������邱�Ƃ����{�s��d�l�Ƃ͈قȂ邾���ŁA���̒m����葼�͓����ł��B
�����ԍ��F26320486
![]() 1�_
1�_
�����ÂŊ撣���Ă܂�����
�C�O�ł��t���b�J�[���X���܂ދ@�\�͓��{�ƕς��Ȃ��ł��傤�ˁB
calamari�������Ă�PAL�����ANTSC�����̐�ւ������{�d�l�������Ă̂͏��߂Ēm��܂������B
�A�����J������NTSC�����A���[���b�p�⒆��������PAL�����Ƃ��A�o��ňႤ�̂��ȁH
�����ԍ��F26320531�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����̌��͗������Ă�̂ł�����A�w���悪�C�O�̏ꍇ�m�������ł̕ۏ������Ȃ��Ȃ�̂ŁA�����s�ǂł��̏ስ���ɂȂ邾�������ƁA���̕ӂ�����邩�ł���
�����ԍ��F26320547
![]() 1�_
1�_
��with Photo����
��calamari�������Ă�PAL�����ANTSC�����̐�ւ������{�d�l�������Ă̂͏��߂Ēm��܂������B
���A�����J������NTSC�����A���[���b�p�⒆��������PAL�����Ƃ��A�o��ňႤ�̂��ȁH
[calamari]>> ���ꃁ�j���[�œ��{�ꂪ�I�ׂȂ����Ƃ�PAL�ENTSC�̐�ւ������邱�Ƃ����{�s��d�l�Ƃ͈قȂ邾����
�܂�A
���{�s��d�l�FPAL�ENTSC�̐�ւ����j���[���Ȃ��iNTSC���ɌŒ�j
�C�O�s��d�l�FPAL�ENTSC�̐�ւ����j���[������i���E�n��ɂ�蓮��L�^�ő����������Ⴄ���߁j
�ł��B
���{�ꃁ�j���[�Œ肪�A�ב֑���ʼn~�����̂Ƃ����{�s�ꐻ�i�̓]���h�~�ɂ�����Ă��܂��B
�����ԍ��F26320755
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B
OM-1MK2�iOM-1/OM-3/OM-5MK2�j�ł͎莝���B�e�A�V�X�g�@�\���g���ĊȒP�Ɏ莝���Ő��i�B�e���ł��܂��B
�莝���B�e�A�V�X�g�ɂ��Ă͈ȉ��̌���������Q�Ƃ��������B
OM-1�́u�莝���B�e�A�V�X�g�v�Ƃ͂ǂ̂悤�ȋ@�\�ł����H�sOM SYSTEM PLAZA�t
https://www.youtube.com/watch?v=Fk9EVxDe4S4
�莝���B�e�A�V�X�g�̋����͈ȉ��̓�����Q�Ƃ��������B
OM-3�Ŏ莝������B�e�͂����ɁH�G�kLIVE�@�iAkiraxe_Lab�j�@32�����炢����
https://www.youtube.com/watch?v=X65p8iapKe0&t=2184s
�B�e���A�h����̃o���R�j�[����V�̐삪�B���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����̂ł����A���ۂ͖��������]�I�ȏɂ������肵�܂����B
�������Ȃ���A�h����̂����ӂŕ~�n���̍���ɂ���L���21���܂ʼn�����Ē�����Ƃ̂��Ƃ�
�Ȃ�Ƃ����L�p�ɂ��Y��ȓV�̐���B�e���邱�Ƃ��ł��܂����B
�������Ȃ���A42.5mm�i35mm��85mm�����j���g�p�����c�C���s�[�N�Ɋ|�������V�̐���B�e����ɂ�23����㔼�łȂ��ƎB�e�ł��Ȃ��ł����B
�o���R�j�[����̎B�e������ɂ�����A�O�r�g�p�ł͍��������肸�����̌������������X���ۂ��Ԃ�ɂȂ�̂ŁA�~�ϑ[�u�Ƃ��Ď莝���B�e�ɗ��������ʁA�Ȃ�Ƃ��B�e���邱�Ƃ��ł��ĂƂĂ������ł��B
��������35mm��85mm�����̒��]���ł̎莝���B�e�͖��d���Ƃ��v���܂�����
��U��B�e�A�V�X�g�̂������Ő�����1/2��1/3���炢�ł͌��ʂ��c�����Ƃ��ł��܂����B
�����������Y�̓p�i�\�j�b�N���Ȃ̂Ŏ�U���͖{�̑��݂̂ɗ������ł��B
�B�e�̐��Ƃ��Ă͎肷��̕⏕�͂�������A�����Y��������ɂ���̂Ře�����߂�Ȃ���Ԃł����B
����Ȃ�L�p�����Y�⒴�L�p�����Y�ł͊y�����낤�ȂƎv��������ł��B
�����͐��i�K�`���Ȃ̂ŕ��i�͎O�r�K�{�ł����AOM�V�X�e�����[�U�[�݂̂Ȃ���A�O�֏o�ċC�y�ɐ�����B��܂��傤�B
�s���g���킹�͂������AF�ł��B
![]() 24�_
24�_
M.Zuiko 7-14mm f2.8�Ƀt�B���^�[�Ȃ� |
PureRaw��Lightroom�����O�ł� |
M.Zuiko12-40mm f2.8 ������B�v���\�t�g���t�B���^�[���g���Ă��܂� |
��Seagulls����
10���ɓV�̐�ʐ^�H�Ǝv���Ĕq��������A7��20���ɎB�e����Ă����ʐ^�ł����ˁB
�莝���ł�������̂ł��ˁB�S���܂����B
���͂ƌ����ƁA���j�^�[���L������A����ŌŒ肵����Ƃ���Ă���܂����B
���N�A�l���łقڏ��̓V�̐�ʐ^���B��܂����B���͎O�r�𗘗p���܂����B
7���ɏ��w���̑��q�B�Ɩk�ĂŃe���g�����s�������̒���ł��B
�i���\�N�O�̏��w������A�I���W�i����OM-1�Œ��킵�܂������A�U�X�ł���...�j
��[���݂�ƁA�J��13�b�Ő������ꂿ����Ă܂����i�����Y�O���Ȃ̂��A�����h�炵���̂��j�܂��������Ƃ��������ł��B
�F�B�E�G�ƃX�}�z�֑����Ă��A���q�����Ɖ�ʂŒ��߂Ă����ł��炦�郌�x���ł��B
����AF�͊y����ł��ˁB�V�̐삾������A24mm����50mm���炢�ł������܂����A
�o�R��L�����v�����Ă���ƁA�����������ߖ�x���܂ŋN���Ă���̂͂���ǂ��̂ł����A����ł��A����AF�͓r���ŋN���Đ��J�b�g�B���Ă݂悤�Ƃ������@�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F26320477
![]() 8�_
8�_
��R232����
�j�t���i�H�j�ƓV�̐�A������C���̍\�}�ō��ł��ˁB����ς�V�o�ǂ��Ȃ��Ǝv���܂����B�i�����ĂȂ��̂Łj
���ӕ��̐��̗���͒��L�p�Ȃ̂Œv�����Ȃ��Ǝv���܂��B�ςȃR�}�t���A�������̂ŗD�G�ȃ����Y�ł��ˁB
����AF�͂ق�ƕ֗��ł��ˁB
�����͐��B�e�̃��C����LUMIX�@S5�Ȃ̂ł����A�}�j���A���ō��킹�Ă���̂ŁA�ƂɋA���Ă���u�Ȃs���g�C�}�C�`�����v�݂����Ȃ��Ƃ������ɂ悭����܂��B
�莝�����i�B�e�̎��́u���x�D��v�ɐݒ肵�܂������A���ɖ�肠��܂���ł����B
�����ԍ��F26321468
![]() 1�_
1�_
��Seagulls����
���V���őQ���P�O/�Q�R�Ƀ������a�����B�邼�I�Ƒ�͂̉͐�~��
�s�������̂́A�T�b�J�[�̖�ԗ��K�ŕӂ�͋���ȃ��C�g�Ő^���ԏ�ԁB
�ڕW�T���̐����������Ȃ��̂ŁA�����ꏊ�ړ��������̂̍�N�̂悤��
�n�b�L�����������̂悤�ȖڕW�����炸�A����グ��Ԃł����B
�V�C����ł��������܂ŏꏊ��ς��čă`�������W�������ł��B
�����ԍ��F26325123
![]() 0�_
0�_
���⋛����
����ɂ��́B
�������a���B�ꂽ�炠����̃X���ɂ��ז����悤�Ǝv���Ă���܂����B
���ʓI�ɂ͂P�O���P�W���E�P�X���̓y�����V��A�Q�T���E�Q�U���̓y�����V��A
���̂P�P���P������R���̏T���͏��p�ŎB�e�ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃō���͒��߂邱�Ƃɂ��܂����B
����͎�����Â炢�悤�ł��ˁB���삪�L�߂̑o�ዾ�K�{���Ǝv���܂��B
�Ⴂ�ʒu�̂悤�ł��̂ŁA�������C�Ƃ������P�[�V���������߂��ɖ����悤�ł�����
����ɏオ��̂��肩������܂���B���䂩��X�̓���������ɂ��Ă��ڂ̑O�����X�Ɩ��邢�͔̂�������Ǝv���܂��B
�B�e�ł��邱�Ƃ����F�肢�����܂��B
�����ԍ��F26326145
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-3 �{�f�B
�ǂ��炪�ǂ����������͖Y��܂������B
�Е���OM SYSTEM�̌����T�C�g�ōw�������J�����{�̕t���̃o�b�e���[�B�����Е��͓�����OM SYSTEM�̌����T�C�g�ōw�������P�i�o�b�e���[�B
�قړ������ɍw�������̂ł����A�����i�ł������������Ƃ�����Ƃ������ƂŁB
�Q�l�܂łɁB
![]() 4�_
4�_
���������܂��͐����ꏊ���قȂ�̂ł��傤���ˁH
���ʂ��قȂ��Ă���̂ł��傤���H
�����ԍ��F26320180
![]() 1�_
1�_
���ʁA�m���ɈقȂ��Ă܂����B
������23�N3�������B���ʂ͉p��Ɠ��{��B
�E����24�N11�������ŗ��ʂ͓��{��Ȃ��B�����ꑼ��ɃA�W�A�����ȕ����B�p��\�L���Ȃ��B
�����͂ǂ���������B
�ȑO�b��ɂȂ��Ă܂������A���b�g�ɂ���ē��{��Ȃ��ɂȂ�̂��ȁB����Ƃ�������ɓ��ꂳ�ꂽ���B
�����Ƒ����Ɋm���߂�ׂ��ł����B
�������Ɍ����X�g�A�Ńp�`�����͔̔����Ȃ��͂��Ȃ̂ŁB�������F������������@������
�����ԍ��F26320207
![]() 2�_
2�_
���L�q�l������
�����[����肪�Ƃ��������܂��B
������Ɗm�F�����Ă���������Ǝv���Ă���̂ł����A�V�[���̕���
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001674966/SortRule=2/ResView=all/Page=2/#26293597
�̏������݂�
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001674967/SortID=26293597/ImageID=4072603/
�̉摜�Ɠ����悤�ɉp��ƃ^�C��ƒ����ꂪ�������Ă���̂ł��傤���B
�����i�Ƀ^�C��̕\�L�ƃ^�C�̃I�����p�X�̃T�C�g�ւ�QR�R�[�h�ɂ�郊���N���\�L����Ă���悤�ł�����A�^�₪�킢�Ă��܂��B
�����N���www.olympusimaging-th.com�͑��݂���
https://explore.omsystem.com/th/th/
���{���̃T�C�g�̂悤�ł����AOM System�̓^�C�ɃJ�����̐��Y�H��͎����Ă��Ȃ��͂��ł��̂ŁA�^�C�����p�̃o�b�e���[��OM SYSTEM�̌����T�C�g�Ŕ����Ă���Ƃ������ł��B
�H����ޓ������������Ń~�X�~�̔��i���̋@������@�u������v�ŏ]�ƈ��Ǘ��@�����o�r�W�l�X
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00304/102300216/?n_cid=nbpnb_mled_g
�ɂ��A���グ���Ă���̂ł����A�����ɂ�����{��Ƃ̍H��ł͕��i�������̐l���ɂ��ޓ��������A�����ċz��nj�Q�iMERS�j�����s�邿����ƑO�̍��A���̒m�l���߂Ă��������ɂ���o�C�N�H��ł����i�̍ɐ�������Ȃ��Ȃ������Ƃ������������ł��B
�ŁA�قړ������ɂ��̃o�C�N�̃p�N���Ǝv����V����Ƃ̃o�C�N���s��ɏo���A�������[�J�[�Ƃ͎v���Ȃ����\�ŕ]���ɂȂ��Ă����̂ŁA�w�����ăo�������Ƃ��떳���Ȃ������i���g���Ă��������ł��B
�o�b�e���[�̃v���X�`�b�N�O�������܂�A�͑��i���o����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��̂ŁA�C�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F26326115
![]() 0�_
0�_
���L�q�l������
>�ȑO�b��ɂȂ��Ă܂������A���b�g�ɂ���ē��{��Ȃ��ɂȂ�̂��ȁB����Ƃ�������ɓ��ꂳ�ꂽ���B
>�������Ɍ����X�g�A�Ńp�`�����͔̔����Ȃ��͂��Ȃ̂ŁB
����̂i����̏������݂ł��B
>OM SYSTEM���������܂����B
>BLX-1�́A���Y�r������o�b�e���[�̈�����e����ւ���āA����̂悤�ȑ�����ŋL�ڂ��Ă���A�摜���������ł͖͑��i���Ɣ��肷��悤�ȗv�f�͂Ȃ��Ƃ̂��ƁB
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001674966/SortRule=2/ResView=all/Page=2/#26293597
�����ԍ��F26300920
�����ԍ��F26326155
![]() 1�_
1�_
�F�l�A���肪�Ƃ��������܂��B
���߂Ċm�F���܂����B
���̉E���Ɏʂ��Ă�����̃o�b�e���[�ɂ��A
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001674967/SortID=26293597/ImageID=4072603/
�̏������݂Ɠ������̂��������Ă��܂����B
���ʂ������Ƃ��Ă��܂����B
���̃o�b�e���[��2024-11-23-WCB�ƍ���Ă��܂����B
����̂i����̃o�b�e���[�Ƃ͂Q���Ⴂ�ł��ˁB
QR�R�[�h��ǂݎ��A�����N�悪���L�y�[�W�ƂȂ�܂��B
https://appdb.tisi.go.th/Q/i.php?d=872471550
����ŁA�����Ɏʂ��Ă�����̗̂��ʂ��A�b�v���[�h�������̂���̉摜�ł��B
������̓����N��̂��̂ƈقȂ�A���ʂɂ͉����������Ă��܂���B
����̒ʂ�A������̐������̕����Â��ł��B
���߂ĂQ���ׂĂ݂�ƁA���ʏ㑤�͐������̍������قȂ�܂��B���͓����ł��B
�o�b�e���[�Z���͓��{�����ŁA�g�ݗ��Ă������̂悤�ł��B�u�����h�I�[�i�[��OM-SYSTEM�ł��ˁB
����̂i����̏������݂̎��Ɏ������m�F����Ηǂ������ł��B
�����ԍ��F26326275
![]() 2�_
2�_
���L�q�l������
�V������肪�Ƃ��������܂��B
https://appdb.tisi.go.th/Q/i.php?d=872471550
�̓^�C���{�̃T�C�g�ł��ˁB
OM SYSTEM�̌����m������n���p��ƒ�����ƃ^�C�ꂾ�Ƃ���ƁA�Ȃ���킵���ł��ˁB
�o�b�e���[�̕\�ʂ̃t�����X��\�L�̓I�����s�b�N�̃A�i�E���X���ۂ����Ă���Ȃ�ɗ����ł��܂����c
�����J�����ɕt�����Ă�������2023�N3���������Ǝv���܂��B
����OM-1�ƈꏏ�ɍw�������o�b�e���[���m�Q�n��OM-1mkII���o��O�ɍw�������̂��m�U�n��OM-1mkII�ɓ�������Ă����̂��m�V�n�ł��B
�ǂ����J�����ɓ�������Ă���o�b�e���[�̕����P�N�߂��Â��̂���ʓI�̂悤�ł��̂ŁA���������Ⴂ�����ł��ˁB
�����ԍ��F26326307
![]() 2�_
2�_
�f�W�^�����J���� > �j�R�� > Z fc �{�f�B
Zfc�œS���̓�����B�e���悤�Ǝv������ǂꂭ�炢AF���ǂ������Ă���܂����H
��ʑ̌��o������Z8�ȂǂƔ�ׂĂǂꂭ�炢�Ⴄ���������ĉ�����Ə�����܂��B
�B�e�����ʂ�S���J�[�u��X�g���[�g�Ȃǐ��ʂŎB�e���邱�Ƃ������Ǝv���܂��B
�B�e�����͋ߋ�������]���ŗl�X�ł��B
���܂ɉ��߂̓�����B�e���܂���
�����ԍ��F26320058�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��l
�����́A�@YAZAWA_CAROL�@�ł��B
�����܂ŗv���ł�����A
�f�W�C�`���悢�ł��B
�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26320067
![]() 0�_
0�_
�����111����
�����܂ŗv���ł�����A
Z8���ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26320070
![]() 4�_
4�_
�����111����
Z8�̃T�u��Z50 II �����g���̕��������̂ŁAZ50 II���������ǂ��ł��傤�ˁB
���t�@��D500����Z50 II �ɔ������������������ł���B
Zfc�́AZ5�iII�ł͂Ȃ����j��AF���x��Ï����\���������炢�������ł��B
�����ԍ��F26320091
![]() 4�_
4�_
�����111����
�S���̃X�s�[�h���ǂꂭ�炢���킩��܂��AZ50II����낵�����Ǝv���܂��B
Z fc�ł��ƃR���s���[�^�̃X�s�[�h��Z 50II���x���̂�Z fc�͂����߂������܂���B
�����ɂȂ̂ŕa��̋�������Z fc�ŎB���Ă��܂��傤���H
����Ȃɉ����ł͂���܂���B
3�����炢�ōs���܂��B
�w���ɑ��k���ċ����܂����瓮��𓊍e�������܂��B
�����ԍ��F26320328
![]() 3�_
3�_
�����111����
��ʑ̌��o�̓I���ɂ��Ȃ��Ƃ��߂ł����H
���s�������ȋC�����܂��B
�����ԍ��F26320353
![]() 2�_
2�_
��ʑ̌��o�͂���܂���ł����B
���݂܂���B
�����ԍ��F26320381
![]() 0�_
0�_
�����111����
�g�p���郌���Y�������Ă��Ȃ��ȁB
�����ԍ��F26320397
![]() 0�_
0�_
���̒��S�Ȃ�AZ50�U���I�X�X���ł��B
�����ԍ��F26320446
![]() 5�_
5�_
�����͉J���~���Ă���̂ŎB�e�͂�߂܂��B
���邢�V�C�̗ǂ��Ƃ��ɂ��܂��B
�����ԍ��F26320515
![]() 0�_
0�_
�F�����J�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B
�������Ă͂��܂�������͂�Z50�U�������ł���ˁc
�X�i�b�v�B�e�◷��Ɏ����o���Ƃ��ɂ��̌����ڂ̂ق����ǂ��Ǝv�����̂ŏ�
�ꉞZf���l���Ă܂��B
�����ԍ��F26320663
![]() 1�_
1�_
����Ȃ̔����ĎB���Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��B
�S������ł���Ȃ̂�~�ƌ��������āA�V�`���G�[�V�����Ȃ�ėl�X������A�����Y��B�e�҂̃X�L����B����ɂ���Ă��A����Ȃ͕̂ς��͓̂�����O������B
����(�@��)�̂ق����ǂ����낤�Ƃ��A����̋�_(�S��������B���Ă����Ȃ��l��)�Ă��X�ɃA�e�ɂȂ�ĂȂ�Ȃ��B
�]���ŎB��ጩ�����̑��x�͒x���Ȃ邵�A�L�p�ōi���ĎB���AF�Ȃ�Ă����܂ŋC�ɂ��Ȃ��čςނ�...
Zfc�Ȃ�A���g����������Z50��肩�͐l�C�������Ĕ��p���ɂ��L���Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�����͈�ԋC�ɂȂ�Zfc��������Ď����Ă݂�̂��ǂ��Ǝv����B
���Ƃ̓��m�͎g���悤�B
���\�̌��E�ŏ�肭�s���Ȃ���A��肭�s���悤�ȎB���(�앗)���l����B
Z50�U�ɃC�L�i���������Ƃ���Ŗ�������Ƃ��v���Ȃ��B
��������ς�ō���Z9���A���惁�C���@Z6�V���ō�����Ȃ�čl�����Ⴄ�̂��I�`����B
�����ԍ��F26321095�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����111����
���݁AZ fc�̍Œቿ�i���E��������ł��B
�������Ⴆ���V���i���o�遨���܂��
�͔��������Ƃ���ł��B
�����������N���N���đ҂��Ă����ق����y������������܂����B
�����܂ł킽�����̖ϑz�Ȃ̂Ŕᔻ�̂�����͂��߂�Ȃ����B
���Ȃ݂ɓ���B�e���́A���N���͊o���Ă��܂���8mm�t�B��������ł��B
�����ԍ��F26321137
![]() 1�_
1�_
����
�t�B�����ł͂���܂���ł����B
�t�C�����ƌ����Ă��܂����B
�����ԍ��F26321138
![]() 0�_
0�_
�l�i���́A���_���A�������A�ё����A�v���C�o�V�[���� ���āA����ɂ����Ė@����̕ی���Ă���B
�����ԍ��F26321143
![]() 0�_
0�_
�Ȃ�̎��ł��傤���H
�����ԍ��F26321316
![]() 0�_
0�_
���t�@�[�X�g�T�}�[����
������N�Q���Ă������Ȏʐ^���A�b�v���[�h���Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B
���p����邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃł��B
����Ȃǂ��f�ڂ���킯�ɂ͂����܂���B
������f�ڂ��������Ă݂悤�Ƃ���l������邱�Ƃ�����̂ŁB
�����ԍ��F26321361
![]() 0�_
0�_
�����111����
���������V�C����������Ȃ��A�B�e�͂�߂܂����B
���߂�ˁB
�����ԍ��F26321499
![]() 0�_
0�_
�F���u�H�H�H�v�Ǝv���A����...��
�����ԍ��F26321708�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��Happy0001����
������N�Q���Ă������Ȏʐ^���A�b�v���[�h���Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B���p����邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃł��B
�ǂ��̒N�����p�����́H�����N��\���ĉ������ˁB
����Ƃ��ϑz�H���C�ł����H
�H�H�H
�����ԍ��F26321759
![]() 0�_
0�_
���t�@�[�X�g�T�}�[����
������N�Q���Ă���ʐ^�ł��B
���p���Ă���ʐ^�ł͂���܂���B
�����ԍ��F26321766
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > �V�O�} > SIGMA fp L ELECTRONIC VIEWFINDER EVF-11 �L�b�g
�������炭�d�����Z�����āA��̎��Ԃ��[���������̂Œm��܂���ł������A���̃J���������I�����Ă�����ł��ˁB
�u���ł���ɓ��邩�炢����B�v�ƁA�w���͐摗��ɂ��Ă����̂ł����A�o�ꂵ�Ă��炷�ł�4�N�H
�m���ɁA�������I�����Ă��Ă����������Ȃ��B
���h�o�V��r�b�N�J���������ăA�}�]���ł͍ɕ���B
�V�O�}�̃T�C�g�ł��Ɍ���B
�Ƃ�����ōQ�Ăă{�f�B��EVF����肵�܂����B
����͂��ď[�d���āA�u���āA�����Y�ǂ����悤�H�v�ƁA���l���Ă���Ƃ���ł��B
�u���̃J�����������郌���Y�̓R���p�N�g��35mm���낤�B�v�Ɨ������Ă���̂ł����A�莝���ɂ���35mm�͖����B
35mm�݂͂�ȏ������Ă��܂����̂ŁB
���̃J�����ɁA�莝����Sigma40mm F1.4��t����͖̂��B
���Ԃ�R�V�i�̃J���[�X�R�p�[���E���g���������肪���������ȁH�ƁB
���邢�́A�R�V�i�̃r�I�S���H
���̃J�����̗p�r�́A�V�̎ʐ^�B
ASCOM�h���C�o�[���t�����X�̃v���C�x�[�^�[�������Ă��ꂽ�̂ŁA������g���Ď����B�e������̂��{���̖ړI�B
��������ƁA�d�����펞�������Ȃ��ƂȂ�Ȃ��̂ŁA�d���A�_�v�^�[���K�v�B
L-EF�ϊ������O���K�v�B
�����EF�����Y�p�̃��V�A��AF���u���悤�₭��������B
Sigma135mmF1.8�p�̃����Y�T�|�[�g������ɕ����ē���o�����̂ŁA�J�����ɕ��ׂ������炸�V�̎ʐ^��AF�B�e���o����B
�ƁA�d�����Z�������Q�ĂĎ�葵���܂����B
���̓A�}�]���łقƂ�ǂ̂��̂���������̂Ŗ{���ɕ֗��B
�J�����������o���ĎB�e�ł���̂́A�������悩�ȁH
�ƁA�Ƃ肠�����̕ł����B
![]() 2�_
2�_
�V�O�}�����������{�f�B���o���悤�ɂȂ����̂ɍ�����܂�����BF�݂̂Ƃ����̂������ł���w
Biogon���l���Ă�Ƃ̂��Ƃł����A������fp���Ƃ������߂ł��܂���Bfp���[�U�[����F�X�����܂������A�����J�o�[�K���X�������A�e���Z���g���b�N���X�����Ȃ������Y���ƐF��肷��N���邻���ł��B
�J�o�[�K���X�������j�R��Z�ł���Biogon�͐F���͂Ȃ��Ƃ��l���͗���Ă��܂��̂�(�f�W�^��M���C�J�ł͋N���Ȃ�)�̂ŁA��ʂ���������łČ�������r�I�ɐ^���������郌���Y��I�ԂƂ������Ǝv���܂��B
COLOR-SKOPAR 35mm F2.5�Ɠ������w�n��SC SKOPAR 35mm F2.5��Nikon Z6�Ŏg�������Ƃ���܂����A�������͗y���ɋx�݂��Y��Ɏʂ��Ă���邵�������̕����ǂ������ȋC�����܂��B
�������{�f�B�Ƀf�J�������Y������̂͌l�I�ɂ͎^���ł�w
�����ԍ��F26320079�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��seaflanker����
���́A�Ă�����FP���A�b�v�f�[�g�����@��ɂ���̂��ȁH�Ǝv���Ă����炠������������߂Ă��܂��܂����ˁB
BF�́A���������Ⴄ�ʕ��Ƃ�����ۂł��B
�����ł����ˁB
�Ώ̍\���̃����Y�́A�Z���T�[���͂̓��ˊp���Q�Ă��܂��̂ŁA���^�ԊO���J�b�g�t�B���^�[�̔g�����ς���Ă��܂��܂���ˁB
�ȑO�A
8���ʃY�~�N�������L���m��M�Ɏ��t�����ۏ������͂��F��肵���̂��v���o���܂����B
���̃��C���Ɏg���Ă���Capture one�ɂ́A�J���[�L���X�g�̕�@�\�͂���̂ł����A�t���b�g�f�[�^���B�e���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂������ł����B���s�̃��C�J�����Y�ł̓��[�J�[�����Ă���悤�ł����B
���̓_�A�J���[�X�R�p�[35mmF3.5�́A���ʂ�傫�����ɋ߂Â��đĂ���悤�ł��ˁB
����ł��̃����Y�ɂ��邩�A
�����ʃY�~�N����F2�ɂ�������ȃ����Y�\���̃E���g����35mmF1.4�Ƃ��邩�Ɍ��߂������Ă��܂��B
�i��J�����Ƌ��ʎ����Ńz���z���ȂƂ���܂Ő^�����悤�Ɍ����܂�(�B
�莝���̃����Y�͂ǂ���\���V���[�v�Ȃ̂ŁA�v�X�ɃN���V�J���ȃ����Y���ǂ����H
�Ǝv���ł��ˁB
�Ƃ肠�����AEVF�����t���āA�A���J�X�C�X�}�E���g�p�̃t���[���ň͂��܂����B
�W���X�g�śƂ�A�т�����B
�X�g���[�g�V���[�e�B���O�ł́A����ɃR�V�i�̂ǂꂩ�ɂȂ�̂��ȁH
�����ԍ��F26320161
![]() 1�_
1�_
�J���[�L���X�g�������Ȃ�ł����A�J�o�[�K���X�Ō������܂��Ă��܂��A���݂ɂ���Ă͑��ʘp�Ȃ��N�����Ă��܂��P�[�X�������ł���B�J���[�L���X�g�͂܂���ł����ł����Ǒ��ʘp�ȂȂ̂Ńs���g�ʒu���ꂿ����Ă܂�����A�����ǂ��ɂ��Ȃ�܂���...��
COLOR-SCOPAR 35�Ƃ��APlanar 2/50�Ƃ����̕ӂ�͗ǂ����������B
�l�̃t���t�����Ă鎞�̂�����Leica M��Summaron-M28/5.6�ł��B�����Œ�݂����Ȃ̂��y�����ł���
�����ԍ��F26320939�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��seaflanker����
�Y�}����28�~�������Ă��܂������B�������Ȃ��A������D���Ȃ�ł���B
�u���C�J�̃����Y�łǂꂩ��ɍi��B�v�ƌ���ꂽ�玄�͂��̃����Y�ł��ˁB
���������ʁA�����čŌオ�ԃG���}�[5�p�B
���̎O�@��A�����N��1958�N������ŁA�`�ʂ��������Ă����ł���ˁB
�Ɠ��̗��̊��Ɛ��ׂ̍����B
1970�N�ォ�烉�C�J�����Y�̐v�͓��{������Ă����悤�Ȃ̂ŁA
�`�ʂ͍��Y�ƂقƂ�Ǔ����ɂȂ��Ă������肵�����̂ł��B
���ʂ̓V�O�}�̐v�����������悤�ł��ˁB
�~�m���^��40�~���́A��������C�J�Ƃ�������ȕ`�ʂɂȂ�܂����A�O���ƑS�R����āA
���Ȃ�o���������������ł��ˁB
�L���m����35�~��F2.8�͂����Ɣ�בS�����F�Ȃ��ǂ��`�ʂ̃����Y�Ȃ̂ŁA���ɂ͓���Ă��܂��B
�ł��A��������������R�V�i�̐V�����̂ɂ��悤���ȁH�ƍl���Ă��܂��B
�m���ɁAFPL�̃��[�o�X�t�B���^�[�A�Ɍ��ł��ˁB
�R�X�g�̊W�ŁAEOS-1�̂悤�Ƀj�I�u�_���`�E���̔����t�B���^�[���g���Ȃ������̂ł��傤�B
�����Y��ʂɓ���Ɍ��K���X�́A�̃L���m��25�~�������Y�ŁA�������x�R���̏œ_�����̃o����������̂Ɏg���Ă��܂����B
�g�|�S���^�C�v�Ȃ̂œ��{�ł͐��������Ȃ��ς������悤�ł��ˁB
�L���m���̃����Y�v�҂̍��삳����u����Ȃ��Ƃ�����Ɣ�_�����������Ă��܂��Đ��\�͗��Ă��܂��B�v�ƌ����Ă��܂����B
���\���́A���̕��R����D�悵���Ƃ̂��Ƃł��B
���邳���ڂŌ���ƁA�f�W�J���̋Ɍ����[�o�X�t�B���^�[�ɂ͂���ȕ��Q������ł��傤�ˁB
��_���������ōl����ƁA���g���t�H�[�J�X�̂ق����ނ���ǂ���������܂���ˁB�V�O�}40�~����L���m����TSE24�~���̂悤�ɁB
�킽���̎����Ă���Y�}����28�~��F5.6�����R�g���\��ɂ͓����Ă��܂��B
����ƁA���V�A���̃I���I��28�~���B
�́A�g�|�S���t�@�~���[�̃����Y���Ƃ������Ђ������A�{�ƃc�@�C�X�A�j�b�R�[����25�~������A�L���m����25�~���A�����������������e�X�g���āA�Ō�̎c�����̂�����ł����B
�`�ʂ���ԗǂ������B(��
���̃����Y�́A��_�����̃o�����������ĕ��������̂ł��B
���V�A�ɂ�����͂��邯��ǁA���ϓI�ɗǂ��āA����ɃL�[�v�����͈̂�ԗǂ������̂ł��B
�݂����̓|�����̂ŁA�`�[�v�Ɍ����܂����A�`�ʂ́A��ꋉ�B
�A���~�o�����Ōy���̂ŁA�Y�}�����̂悤�ɃJ�������O�����݂ɂȂ�ɂ����̂��D���ł��ˁB
�o���i�b�N�ɃY�}����28���Ƃ߂�����d�����B
���͂�t�B�����͒������i�Ō������v�����g�������Ȃ̂ŁA��������ȎB�e�͏o���Ȃ��ł��ˁB
������ɂ��Ă��AFPL���ǂ�ȕ`�ʂ����Ă����̂��y���݂ł͂���܂��B
�����ԍ��F26321139
![]() 0�_
0�_
��gonigoni����
Summaron-M 28mm f/5.6��Otus 1.4/28��Leica��ZEISS�̗��ɒ[��28mm�g���Ă܂��B�����̕�����₳�Ȃ�Ƃ��ŁA�Y�}����28�͕����ł�V�i�Ŕ����܂����B
�Y�}����28����MTF��������ƃW�F�b�g�R�[�X�^�[�݂����ȋȐ��Ȃ��ǁA���ۂ͎l���ȊO�̓R���g���X�g�����̉𑜂������Ă�悤�Ɍ����Ȃ����A����肠�̋���ȃR���g���X�g�̍����Ǝ��ӌ����͕ȂɂȂ�܂���ˁB
���Ƃ�Summicron-M 50mm f/2 4�����Elmarit-M 90mm f/2.8 E46�ł�����~
�Y�~�N����50 4����A������w�I��70�N��v���˂ǂ���Ȃ�����I�[�p�[�c�ł����
�~�m���^��40mm��M-ROKKOR�ł��������A���{�ȊO�ł�Summicron-C�́B�R���̊W�Ń��C�J�p�Ƃ��Ă͎肪�o�܂���B
���t�p�����Y�͌��X�o�b�N�t�H�[�J�X�������̂œ��ˊp�͂���قǃL�c���Ȃ������̂ŁA���܂���ɂȂ�ɂ��������낤�Ǝv���܂��B�����W�t�@�C���_�[�͘I�o�v�A�[���̊��Ƃ��������A����̃~���[���X�p�����Y�̂悤�ɃV���[�g�o�b�N�t�H�[�J�X�Ȑv���ł��āA�����Z���T�[�J�o�[�K���X�Ȃ�Ă��̂��O��ɂȂ�����̐v�ł�����A����Ⴀ�f�W�^���J�����Ŏg���ɂ͌������낤�ƁB
�z���S���Ȃ��f�W�^���Ŏg������������Ƃ͂���܂������A���X�ߎS�ł�����
�t�ɁA���t�p�̈����艿2���~���x�̍L�p��AF�j�b�R�[�������C�J�{�f�B�Ɏh���Ă݂���J���[�L���X�g���Ȃ������̂ŁA��͂背���W�t�@�C���_�[�≖�p�����Y�Ƃ������̂̓��C�JM�{�f�B�ł͌������낤�ƁB
EOS-1D�n���̃j�I�u�_���`�E������GD���[�p�X�t�B���^�[�ł��������B�m��1D�n���݂̂ŁAEOS R3�ɂ����ڂ���ĂȂ������͂��ł��ˁBR�n����R1���ŏ��ł����ˁB
�m��CONTAX N DIGITAL�Ȃł��̗p����Ă��C�����܂����A�Z���T�[�Ǝ���ŃR�X�g�̂قƂ�ǂ��Č����Ă܂����ˏ�
�Ȃ��A���[�p�X�t�B���^�[�������ł����A�Z���T�[��O�̃J�o�[�K���X���܂߂��A�Z���T�[��O�̏��X�ł��ˁB
���[�p�X���X�̃��f���ł��J�o�[�K���X�͂��ĂāA���[�p�X�L���̓��f���ɂ���ĈقȂ�܂����A�����������Ȃ�悤�Ƀg�[�^���̌��݂��P�ꃁ�[�J�[���œ������x���ɂȂ�悤�ɂ��Ă�Ǝv���܂��B
L�}�E���g�̓{�f�B��4�Ђ��炢����o�Ă�킯�ł����A�ȑO���C�J�J�����ւ̃C���^�r���[�ŁALeica SL�n���̃J�o�[�K���X�͑���L�}�E���g�J������蔖���Ɣ������Ă܂���
�p�i�\�j�b�N���w���Ă���V�O�}���w���Ă��͏�����Ă��܂���ł������AM�^���C�J�̎���SL�{�f�B��M�����Y�Ɍ����Ă���Ɣ������������̂ŁA�l�̓V�O�}�A�p�i�\�j�b�N�̂�����������C�J�������Ɖ��߂��܂����B
����K�i���̈ك��[�J�[�ԂŃJ�o�[�K���X���قȂ����...�قȂ郁�[�J�[�ԂŃ����Y�̐��\��{���Ɋ���������ł��傤����...
�����ԍ��F26321276�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����A���h�o�V�ɍs���ă��C�J���̏����}�E���g�A�_�v�^�[���肵�܂����B
�������ɍ����ł��ˁB
�T�[�h�p�[�e�B������܂������A
���x�̓_�A�����l���Ȃ��Ă��ςނ̂ŁA�]�v�ȐS�z���v��Ȃ�����D�悵�܂����B
�X�ɁAM-L39�����ϊ��A�_�v�^�[���L�^�����Œ��B���A�I���I��28mm��t���܂����B
�����Y���˂����݂Ȃ���A�u���������A�X�N�����[�̎��萸�x�������ďa��������ȁB�v
�Ƃ����̂��v���o���A
�u�t�H�[�J�X������l�W���ɂނ�Ȃ����H�v�Ƃ������炢�L�c�L�c�̃t�H�[�J�X�����O�̊��G���v���o���܂����B
�g��Ȃ��Ȃ���20�N�͉߂��Ă��܂��܂�������B
�r���[�t�@�C���_�[��`���Ă݂�ƁA�I���I��28�~���̒��ڏœ_���������܂��B
���܂ł́A�B�e���Ȃ���Ε�����Ȃ������������̃S�[�X�g���������蕪����܂��B
��������A�摜��������ƌ�����̂��������B
���܂ł̓r���[�t�@�C���_�[�̘c�Ȏ����ŒM�^�ɘc�������Ȃ���R���Ńt���[�������߂Ă����̂��A
���t�̂悤�ɗ��������ďo���܂��B
�Ƃ���ŁA�t�@�C���_�[�̋P�x�����A�ǂ��ɂ���̂�������܂���ł����B
���x�����͕��������̂ł����B
���ƂŃ}�j���A�����܂��B
�t�H�[�J�X�ʒu�̊g��\��������̂͗ǂ��̂ł����A�t�H�[�J�X�t���[���̈ړ����r���[�t�@�C���_�[�����Ȃ���ł��܂���B
AEL�{�^���������āA���邭�郊���O���Ă��ړ����Ȃ���ł���ˁB
�r���[�t�@�C���_�[����w�ʃ��j�^�[�ɐ�ւ���ƃ^�b�`�ŏo����̂ł����A
���Ȃ���o���Ȃ��̂͒v���I�ł��ˁB
���t�Ȃ�t�@�C���_�[����ڂ𗣂��Ȃ��ŏo���܂���ˁH
�s���g�ʒu���Đ^�����ł͖����Ǝv���̂ł����B
�u�u���s������B�v�Ƃ������ƁH
�����͂���ȏ�̎������鎞�Ԃ��Ƃ�܂���ł����B
�����ԍ��F26325523
![]() 0�_
0�_
��seaflanker����
Otus 1.4/28�������ł����B
����͍����\�ł��ˁB���Ԃ�V�O�}�̓��X�y�b�N��art�����Y���B
���͎������Ă��܂��B�ǂ���ɂ���̂��B
�g���p�x���l����ƁA�Y�[�������Y��28�����ł��p�͑���Ă��܂��̂ł����A�V�̎ʐ^���Ɩ��邢�̂͗L���Ȃ̂ŁB
�Y�}����28����F2.8�́A�e�l���Â��̂ł݂Ȃ����т菟���ł����A
�����Y���\�͍��ł��g�b�v�����N����Ȃ����Ǝv���܂��B
���ʂ��ٗl�ɕ��R�ŁA���ӂŏ����T�W�b�^���ƃ����I�f�B�i�����������x�ł��B
�����Y�\�����I���g���^�[�^�ŁA�V���i�C�_�[�Ō����ƃW���}�[�ƈꏏ�B��_�������قƂ�ǖ��������Y�ł��ˁB
�A�|�����Y�ł͂Ȃ��̂ŁA�F�̃t�����W���o�܂����A�ӏ܃T�C�Y���ƋC�ɂȂ�Ȃ��͂��ł��B
�A�|�W���}�[�����̌�o���悤�ɁA����̃��o�C�o���ł��A�|�Y�}�����ɂ��ė~���������ƌl�I�ɂ͎v���܂����B
����ł��A�����k���ȕ`�ʂ́A�Ɠ��ł��ˁB
GD���[�p�X�t�B���^�[�́A�m������45�x�����ɂ����[�o�X���\�������t�B���^�[���Ǝv���܂��B
EOS-1D�W���������܂ł́A�c�����Ɖ������̓����ł��B
�j�I�u�_���`�E���́A��������̂ŒP�i�Ńt�B���^�[���\���ł����A1/4�g���t�B���^�[�̗��ʂɁA
EOS-1D�ł̓j�I�u�_���`�E���w����������`�ō\�������t�B���^�[�ɂȂ��Ă��܂����B
���i�̈��������t�B���^�[�́A1/4�g���t�B���^�[�����X�Ɍ���1/2�g���t�B���^�[���g���͂��������ƋL�����Ă���̂ŁA
5�{�����t�B���^�[�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���̕��A��_������������̂ŁA���邳�������C�ɂ���l�ɂ́A���܂芽�}����Ȃ��t�B���^�[��������܂���B
�����A�����Ń{�P�Ă��ꂽ�ق����A���A���͌���̂Ńf�W�^���̐��E�ł͊��}����邩������܂���ˁB
�g���Ƃ������t���o�邭�炢�Ȃ̂ŁA���@���x�͏��Ȃ��Ƃ�1/16�g�����炢�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
����CCD�̉��i���Ђ���Ƃ����獂�������H�Ǝv����������Ă��܂��B
�V�̖]�����̃g�[�^���̕K�v���x�́A��ʓI��1/6�g�����O�B�����\�o�[�W������1/32�g�����炢�ł��B
�J���������Y�͂�����ɂ��Ƃ������Ƃł��ˁB1/4����1/2���炢���Ǝv���܂��B
���ۂɓV�̎ʐ^���ʂ��Ă݂�ƁA�]�������Y�Ɩ]�����̐����͈��|�I�ɈႢ�܂��B
�]�������Y�́A�ڂ���Ƃ��Ă��܂���ł��ˁB�ŋ߂̃V�O�}�͂��Ȃ�ǂ��ł����B
����ƃL���m����EF100-400��L�����Y���X�g���[����0.8�ȏ�͍s���悤�ł��B
�����A���ꂩ�烉�C�J�����Y�𑵂���Ƃ�����A�A�|�Ɩ��̕t�����̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�V�O�}��EF�}�E���gart������̂��̂́A�قƂ�ǃA�|�N���}�[�g�ɂȂ��Ă��܂����B
�L���m����EF������A�|�N���}�[�g������Ă��܂������ARF�̓����Y�ɂȂ��ċt�Ɍ��ɖ߂��������Y�������Ăт����肵�܂����B
����ł�RF��50mm��85�����A���ꂩ��135mm�̒P�œ_�����Y�̓A�|�N���}�[�g�ł��ˁB
�����ԍ��F26325552
![]() 0�_
0�_
��gonigoni����
�Y�}����28mm�͕����łł����A�������g���Ă�͈͂ł̓t�����W�͊����܂���B�����Â��v�ł���(������ł͊撣���Ė��邭������ł��傤��)
�v���MTF�ł͑���15mm�ӂ肩���C�ɗ���������Ƃ������ƂɂȂ��Ă܂����A���ʏ�ł͑���19mm���炢�܂ł̓R���g���X�g�A�𑜂����S�Ɉێ����Ă���悤�Ɍ����܂��B
���̃m�N�`���b�N�X��^���o�[�����l�A�����܂ŕ����ł����炻���������ƂȂ�ł��傤�B����ł��R�[�e�B���O�͐V�����ł�����t�����\���\���ŁA����ł��Ă��̎ʂ�Ȃ̂ł��邢�ł��B�Y�}����28mm���^��L39�}�E���g�̎B�e����݂����Ƃ�����܂����A�R�[�e�B���O���������A
�S�̂��t���A��ɂȂ��Ă�����̂��قƂ�ǂł����B
���C�J��M�����Y�̓Y�}����M28�ƃY�~�N����M50 4th�ł������������ς��ɂȂ�܂����B�Y�~�N����M50/2 4th���v70�N���
���̎ʂ�́A����Ȃ̂����I�[�p�[�c�ł���B
Otus 1.4/28�́A�ґ�Ȃ��ƂɈꎞ��AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED�ƈꏏ�Ɏ����Ă�������������܂����B���ʃj�b�R�[����������܂����B
�j�b�R�[���̂ق����ߐڂŎg�����Ƃ��͌�{�P�͏_�炩�������ł����A�����ꏊ����j�b�R�[����Otus�Ŗ������Ŏ������Ƃ���...���܂�ɂ��������Ⴂ������...�l�i���Ⴂ�������ł����B�Ƃɂ����R���g���X�g�����܂őS�R�����Ă����Ȃ���ł���ˁB
�����ԍ��F26326424
![]() 1�_
1�_
��seaflanker����
�����ŁA�R�[�e�B���O���ŐV�̂��̂ŁA���������N���A�[�Ŏʂ肪�ǂ����낤�Ǝv���܂��B
�����60�N�ȏ�O�̎��_�ł��f���炵���ʂ肾�����̂ŁA�����낤�͂��������ƍl���Ă܂����B
���̃Y�}�����́A������30�N�ȏ�O�ɔ��������̂ł��B
������Âł������A���̍��ł�F�l���Â��قƂ�ǘb��ɂȂ��Ă��Ȃ�������Ȃ����ƋL�����Ă��܂��B
�����̓��{�̃J�������D�҂́AF�l��1.4�N���X�̃����Y���n�C�G���h�ŁA1.8��2�͕��y�i�B
�u�����Y�̃f�J�����̂قǍ����\�v�Ƃ���������F�����܂���ʂ��Ă��܂�������A�����̂悤�ȃ����Y���g���l�́A
���g�̋����v�������Ă����Ǝv���܂��B
����ȕK�v�͖����̂ɂˁB
F1.2�̃����Y�̐��\���{���ɗǂ��Ȃ����̂́A�L���m������RF��50mmF1.2���ŏ��ł��傤�ˁB
���̑O�̃I�[�^�X55mmF1.2������ł悤�₭�n���̖��������Y���o���č������[�J�[���S�����ւ����悤�ł��B
����EOS-1Ds3���w�������Ƃ��́A�d���Ȃ����琔�{�����L���m�����������Y���āA���C�������Y�̓R���^�b�N�X�̃f�B�X�^�S��21mmF2.8�Ƃ��Ă��܂����B���̃����Y�́A���Ԃ���t�p�̍L�p�ŏ��̃A�|�N���}�[�g�������Ǝv���܂��B
������{�����F�������Ȃ������̂ŁB
�L���m�������߂Ă���ɒǂ������̂��ATSE-24mm��F3.5�B�L���m�����̍L�p�̃A�|�N���}�[�g���낤�Ǝv���܂��B
���A��{�I�ɍi���Ďg���l�Ȃ̂ŁAF1.4�̃{�P���Ă��܂胂�`�[�t�ɏオ��Ȃ���ł���ˁB
�Y�}�����̘b�ɖ߂�܂����A���������Ƃ���ɁA���̎����̃��C�c�̃R�[�e�B���O�͗�����܂��B
8���ʂ��ԃY�}�����ɂ��ԃG���}�[�ɂ�������ޗ�����܂��B
�ł��A�N���[�j���O���Ă̓_���ŁA���������ƁA���\����Ό��ɖ߂�Ȃ��ł��B
�������C�c�̓��{�㗝�X�̏C�����Ƃ��낢�둊�k�����̂ł����A���������ɗ��������܂����B
�u�N���[�j���O���Đ��\���Č��ł���ۏ��Ƃ�Ȃ��B�v�ƁB
�莝���̃����Y�ɗ��������܂ŁA���ꂼ��3�炢���������̃����Y���ւ��Ă��܂��B
���C�c�̃����Y�ɂ́A�o�����̃r�X�ɐ��F�̃j�X���h���Ă����āA���ݎ~�߂����Ă��܂��B
���ꂪ���������Y�́A�ԈႢ�Ȃ��ߋ��ɕ��𐴑|����Ă��܂��B
�����Y���Y��ł��R���g���X�g���������s���g���Ȃ�ƂȂ������Ȃ��Ă����ł��ˁB
�R�[�e�B���O�́A���m�Ɍ����ƁA�����A�����Y�i��Ȃǂ̃I�C���������������̂̕t���Ƃ����������̂ق����������ł��B
���̃Y�}����F5.6�́A�s���g�͍��Y�����Y���t�������Ă�����Ȃ����炢�V���[�v�ł����A�R�[�e�B���O�̗ŁA
�R���g���X�g�����������܂��B
8���ʃY�~�N������5�炢�����ւ��āA�悤�₭��������Ă��Ȃ��̂������܂����B
����͂قƂ�ǂ̂��̂������N���[�j���O����Ă��āA�s���g������������A
�s���g�ʒu���Y���Ă�����ƁA���\�����Ă�����̂��啔���ł��B
������Ƃ����v����������Ă���C��������Ȃ��Ɛ��\���Č��o���Ȃ��ł��B
���C�c��L39�}�E���g��35mm�Y�}����F3.5�͕`�ʂ��ƂĂ��f���ōD���ȃ����Y�ł��B
���ʘp�Ȃ�����̂ŁA���ӂ̓s���g���Â��Ȃ�܂����A�Ȃ������̂łƂĂ��ǂ����͋C�̎ʐ^�ɂȂ�܂��B
�I���W�i���̃r�I�S��21mmF4.5��35mmF2.8���`�ʂ̗ǂ������Y�ł����ˁB
�{�Ƃ̃g�|�S��25mm��j�b�R�[���̃g�|�S���R�s�[��25mm�͉��x���g���C���Ă݂܂������A
���𐴑|���ꂽ���A�j�b�R�[���͂��Ƃ��Ƃ̐v�������������ŁA�S�邽��`�ʂƂ�����ۂł����B
�c�Ȏ����̖ʂł́A���g���t�H�[�J�X�����Y�Ō������c�܂Ȃ������Y�͂͑��݂��Ȃ��ł����A
���̓f�W�^���ŕ�ł���̂ŁA�~���Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F26327120
![]() 0�_
0�_
����������Ă݂���AEVF���̃t�H�[�J�X�|�C���g�ݒ�́A
�^������LCD���j�^�[��ʂ��w�Œ@����EVF�̉摜�Ƀ|�C���g������Ă����ňړ��ł��邱�Ƃ�������܂����B
���邭��{�^���Ɋ��蓖�Ă���ǂ��̂ɁA�Ǝv���܂����B
���܂�g���₷���Ȃ����ȁH
�����ԍ��F26327123
![]() 0�_
0�_
USSR Orion28mm F6.0�ŎB�e���Ă݂܂����B
�ӊO�Ȏ��ɃJ���[�L���X�g�͖w�NjC�ɂȂ�܂���ł����B
���̑�����ӌ����͋���ŁA���܂ǂ��̃����Y�ɂ͖����`�ʂ��Â������������܂���ˁB
���̃����Y�A�\�A��1966�����������q�^�[�v�̃g�|�S���̃t�@�~���[�B
���\�A�̓c�@�C�X�̐v�҂����X�N����E�N���C�i�ɋ����h�������Ă����̂ŁA
�v�̓c�@�C�X���̂��̂��Ǝv���܂��B
�����Y�f�[�^�́A�펞���Ƀj�R���ɂ��n���Ă��܂����̂ŁA�j�R���ł����l�ȃ����Y�����Ă��܂����B
���~�ɋ߂��ɒ[�ȃ��j�X�J�X�ʃ����Y�̓����ɂ�͂蓯�l�Ȓf�ʂ̉������Y�Ƃ����Ƃ��Ă�����������ȃ����Y�B
�\�A�̃����Y�́A�����̍��͂߂��Ⴍ����Ȃ̂ɁA�����Y���̂��͓̂��{�������ǂ��ł��B
�����Z�p�����{��A�����J����ŁA
�C���^�[�t�F�����[�^�[�̓�����������肸���Ƒ��������̂��A�\�A����㖾�炩�ɂȂ������炢�ł��B
���ʂ͓Y�t�̎ʐ^�̂Ƃ���ŁA
�����n�����c��̂������ŁA���ꂪ�摜���_�炩�����Ă��錴���ł��B
����ǁA�ƂĂ��𑜗͂������Ęc�Ȏ����Ɣ{���F�����͊F���ł��B
��ʂ̒[�ł��F���Y���Ȃ��ł��B
���̂�����́A�ԃY�}����28�����Ƒo���ł����A�R�T�C��4�摥�̌����������i�������̂�
���Ƀh���}�`�b�N�ȕ`�ʂɂȂ�܂���ˁB
�����ԍ��F26328076
![]() 0�_
0�_
����̐�̎ʐ^�B
�����ɂ͒O���߂�����Ƃ̂��Ƃł��B
���A���̍s�������ɂ͋��܂���ł����B
����ɂ��Ă��Ȃ�ăh���}�`�b�N�Ȏ��ӌ����Ȃ̂ł��傤�B
�܂�ŋ≖�ʐ^�ŎB�e�������̂悤�ȃg�[��������܂��ˁB
�ߔN�A�L�p�Ƃ����ƁA16������14���������ʂɂȂ�����������܂��A
28���������ێg���Ă݂�ƁA���\�L�p�ł��ˁB
�l�Ԃ̎���Ƃ͈قȂ������͋C�ɂȂ�܂��B
�v�X�Ɏg���ĐV�N�Ȉ�ۂ�����܂����B
�����ԍ��F26328085
![]() 0�_
0�_
�l�Ԃ̋���Ƃ���̕��i�͂���Ȏʂ�ɂȂ�܂����B
�Ɍ��̃��[�o�X�t�B���^�[�������Ă��܂����A�����Y�̓������o�����Ă���悤�Ɍ����܂��B
���Ȃ���ׂ̍��`�ʂ̃����Y�ł����A���ꂪ���̂܂܍Č�����Ă���悤�Ɋ����܂����B
����������ƁA�c�Ȏ����̋��A�{���̐F�����̋��������܂����A
���̃����Y����͑S�������Ȃ����낤�Ǝv���܂��B
���w�i�ɂ��������ł́A�n�������������܂��B
����ǁA�덷�͈̔͂ł��ˁB
���낢��ȊŔ̕��������Ă��@�ׂɂ�����ƍČ�����Ă��܂��B
���F���\���ɗǂ��ƌl�I�ɂ͎v���܂����B
�Ȃɂ��n�C���C�g����V���h�E�܂ŊK���Č����f���炵���ǂ��ł��B
���ɃJ�����̋@�\�ł����A
EVF���g���Ă��Ă�LCD���j�^�[�͐����Ă���̂ŁA�������G���Ə���Ƀ��[�h��ݒ肪�ς���Ă��ĕ����܂����B
���̏ꍇ�́A�d������Ȃ����Ă��Ƃɖ߂��܂����A�v�͈����ł��ˁB
��͂肭�邭��{�^���Ɋ��蓖�Ă�ׂ��ł����B
EVF�̎g������͑f���炵���B
�����W�t�@�C���_�[���C�J�̃t�@�C���_�[��100�{�ǂ��ł��B
�����Y�Ɏʂ��Ă�����̂������������܂�����B
�o�����肪�����̂ŁA�����^�т͕s�ցB
�w��̐G���Ƃ��낪�������āA�t�@�C���_�[�`���Ă���Ƃ��ɑ���͂��ɂ����B
���ׂ��X�y�[�X�������ł���ˁB
���j���[�̊K�w�\����g��������L���m���Ɣ�ׂ�Ɩ������B
�J�����Ɏg���Ă��銴���B
BF�Ȃo���Ȃ��ŁA�����Ƃ��̃J���������ǂ����@��ɂ��ė~���������ł��ˁB
�ƁA
�l�I�Ȉ�ۂł����B
�����ԍ��F26328117
![]() 0�_
0�_
�o�悩�玩��ɖ߂�ACapture One �Ńr�l�b�g���������DNG����JPG�ɕϊ�����Orion�̉摜���Ċm�F���܂����B
���������ƁA�������ӌ����͂قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂����B����������肭����Ă����悤�ł��B
��ɃA�b�v���[�h�����̂́A�E�B���h�E�Y�ɕt�����Ă���y�C���g�Ƃ����A�v����DNG����ϊ��������̂ł����A
����̓N�H���e�B���܂�ňႢ�܂����B
�m���Ă͂�������ǁA���߂ĉ摜�ϊ��\�t�g�̗D��͂�����̂ł��ˁB
�V�O�}FPL��DNG�̕ϊ��͂�͂�Capure One���ǂ������ł��B�K������芊�炩�ŁA�ׂ����Ƃ���̐������ׂ��@�ׂł����B
�S�̓I�ɏ_�炩���摜�ɂȂ�܂��ˁB
���̍D���ȉ摜�ł��B
�J����������jpg�ϊ��\�t�g�́A�ǂ��̃��[�J�[���X�s�[�h�ŗD��Ȃ̂ŁA�ϊ��̔������e���掿�������ł��B
���̓J�����̎B���ďo���̉摜�����ăJ�����̐��\�����߂���̂́A���܂茫�����Ƃł͂Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
DNG�́A�E�B���h�E�Y�̕t�^�A�v���ł��v���r���[���o����̂ŁAjpg�ŎB�e����K�v�����������Ǝ��͊����܂����B
Orion�̃J���[�L���X�g�ł����A���ӂɍs���قǐ��Ȃ�X��������悤�ł��B
��ʒ������ɂ͐Ԃ��c���Ă���̂�������܂��B
�C���t���l�͂���Ǝv���܂��B
����p�̑傫�ȍL�p�����Y�ł����ӂ̕`�ʂɂ͖��͖����悤�ł��ˁB
�����ԍ��F26329919
![]() 0�_
0�_
�X�g���[�g�̎ʐ^�ɂ�Capture One�Ńr�l�b�g��������Ă݂܂����B
��͂�A�ӂ��̎ʐ^�͎��ӂ܂ŋψ�Ȗ��x�̂ق������₷���ł���ˁB
����ɂ��Ă��A�I���I���̉摜�̗ǂ��ɂ͉��߂Ċ��S���Ă��܂��܂��B
�ƂĂ�60�N�O�̃����Y�Ƃ͎v���Ȃ��ł��B
FPL�ŎB�e���Ă��鎞�̃f�[�^�����̑����́A�l�I�ɂ͑S����肠��܂���ł����B
�B�e�̃e���|��j�Q����悤�Ȓx�����A�قƂ�NJ����܂���ł����B
����Ŏw���m��Ȃ��ԂɐG��Đݒ肪�ς��̂����Ȃ���A�X�g���[�g�V���[�e�B���O�ɂ������Ǝv���܂��B
EVF�̉掿�́A�\�j�[�̃R���f�W��菭�������n�C���C�g����т����ł��B
����ǁA������̎���{�����S�R�傫���̂ŁA���₷����������������ł��B
����ƁA
�Ȃɂ��֗��Ȃ̂́A�t�H�[�J�X�{�^���������ƃt�H�[�J�X�t���[�����g��\�����Ă����̂ŁA
�}�j���A�������Y�ł��s���g���ƂĂ����킹�₷���B
�\�j�[�̃R���f�W�ɂ��g��@�\�͂���̂ł����A
�s���g�̃s�[�N�J��������ɂ�������������ł��B
�g��̃g���K�[�̓t�H�[�J�X�����O��������Ǝ����I�ɋN�����܂��B
�ł��A�s���g����Ɏg�p�҂̈ӎu�����f����Ȃ��̂́A�D�܂����Ȃ��ł��ˁB
�t�Ƀt�H�[�J�X�t���[���̈ړ��́A�\�j�[�̂ق������₷���B
���邭��{�^���ɂ��̋@�\������̂ŁA�m���Ɉړ��ł���B
�V�O�}FPL�́ALCD�t�����^�b�v����K�v������̂ƁA����Ɋm�����������B
���̃J�����̑��쐫���l�����l�́A���܂�J�������g��Ȃ��l�Ȃ�Ȃ����ȁH
�����ԍ��F26329948
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
-
�yMy�R���N�V�����z����\��
-
�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j