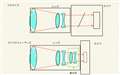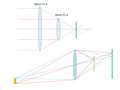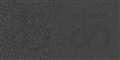���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S3107�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2021�N10��8�� 14:12 | |
| 117 | 132 | 2021�N10��7�� 00:51 | |
| 31 | 15 | 2021�N10��6�� 04:59 | |
| 76 | 51 | 2021�N10��1�� 02:21 | |
| 133 | 61 | 2021�N9��25�� 22:06 | |
| 69 | 16 | 2021�N9��25�� 20:37 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
https://www.phileweb.com/news/d-camera/202110/06/999.html
���`�F�L�ł̓L�����N�^�[���`�F�L�v�����g����V�����y���ݕ����Ă���B�C�V���X�C�b�`�̃A���o���ɕۑ������Q�[���摜���ȒP�Ƀ`�F�L�v�����g�����肷�邱�Ƃ��\�ɂȂ����B�u���ƂŃQ�[�������鎞�Ԃ�������Ȃ��A�`�F�L�Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA�Q�[�����̂̊y����������ɃA�b�v����V�������l�������ł��݂��Ă��������B
������
�ߋ��ɂ��f�W�J���̉摜���`�F�L�̗p���ɏo�͂���v�����^�[�o���Ă����ǂ�
��u�ŏ��ł�����Ȃ������c
�`�F�L�̗p�����ƃN�\��������Ȃ���
�q�����l�i���킩�炸�ɒ��q�ɏ���ăo�J�X�J�v�����g����
��Őe�����߂�V�[�����ڂɕ�����
����ʐ^�p���Ƀ`�F�L���Ƀv�����g���Ă����v�����^�[�̕����ǂ�������
![]() 2�_
2�_
���ꂪ������ƌ����̂Ȃ�A�ԈႢ���ȁA��یN(�M�E�ցE´)�U
�����ԍ��F24385083
![]() 2�_
2�_
���������F��ɁR°��
�������ɂ�������������ȁB
�����ԍ��F24385273
![]() 1�_
1�_
�����̓��e�́A�t���T�C�Y�J�����̉掿��ے肷����̂ł͂���܂���B
����f�̃t���T�C�Y�ł���A���i�ʐ^�ɂ����āA�}�C�N�t�H�[�T�[�Y��薾�炩�Ƀm�C�Y�����Ȃ��v���́H(�B���f�q���傫����A�͖{�����H)
�悸�A�O��Ƃ��āA�uSN ��͈��f������̎���ʐςŊT�ˌ��܂�v�ƍl�����܂��B�܂��A���𑜓x�^�C�v�́A�m�C�Y���̂������ڂɏ��������Ƃ���A�ʐ^�Ƃ��ăm�C�Y���͏��Ȃ��Ȃ�܂��B
�����N��̉摜��r�́A���ϓI�𑜓x�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ƁA���𑜓x�̃t���T�C�Y��RAW�Ŕ�r�������̂ł��B���f������̎���ʐς̎����@���I�����邱�ƂŁASN ����߂Â��Ă��܂��B�摜������ׂ�ƁA�m�C�Y�ʂ͓��������ł����A�t���T�C�Y�̕����m�C�Y�̂��ߍׂ�������m�C�Y���͏��Ȃ����Ƃ������ł��܂��B�������A�ɒ[�ȊJ��������Ƃ͎v���܂���B
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=olympus_em1iii&attr13_1=sony_a1&attr13_2=nikon_z7ii&attr13_3=canon_eosr5&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&attr126_0=1&attr126_1=1&attr126_3=1&normalization=compare&widget=1&x=0.8739070738091508&y=0.20370175828554332
�Ƃ��낪���i�ʐ^�o���҂́A���i�ʐ^�ɂ����ăt���T�C�Y�́A����𑜓x�^�C�v�ł���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɔ�ׂĖ��炩�Ƀm�C�Y�����Ȃ��ƌ����܂��B
�����ŁA�f�p�ȋ^��́A���́A���i�ʐ^�ȂǂŁA�t���T�C�Y�ƃ}�C�N�t�H�[�T�[�Y�ɂ�����̍����o��̂��H�ł��B��L�摜��r���x�̍��Ȃ�Ƃ������A���炩�ȍ��̏o��v���͉��ł��傤���H
���́A�B���f�q�̐��\�ȏ�ɁA�����Y�L�����a�̗v�����傫���̂ł͂Ȃ����H�ƍl���Ă��܂��B�V�̊ϑ��ɂ����āA�Ε������Y�̌��a�́A���邳�A���ēx�����߂錈��I�v���ł��B������A�傫�Ȗ]������K�v�Ƃ��Ă���̂ł��B���i�ʐ^�ł����l�̂��Ƃ�������͂��ł��B
�B���f�q�P�̂̐��\���r����Ȃ�A�����L�����a�̃����Y�Ŕ�r����K�v������ł��傤�B�Ⴆ�A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y12mm(24mm�����̉�p) f2.0�̗L�����a��6mm�ł��B���L�����a�̃t���T�C�Y24mm�����Y�̖��邳��f4.0�ƂȂ�܂��B�܂�B���f�q�P�̂̐��\��r�́Af2.0��f4.0�ł��Ȃ��Ƃł��܂���Bf2.0���m�Ŕ�r���Ă��܂��ƁA��������ʂ�4�{�������A�������قȂ邱�Ƃ���A��������_�ɂȂ�܂��B
���i�ʐ^�ɂ����č���𑜓x�̃t���T�C�Y�ł���m�C�Y�̏��Ȃ���v���́A�B���f�q���傫������ł͂Ȃ��A�u�t���T�C�Y�̃����Y�̗L�����a���T���đ傫������v�Ƃ����̂����̌����_�ł̌����ł��B
�����̓��e�́A�t���T�C�Y�J�����̉掿��ے肷����̂ł͂���܂���B
![]() 2�_
2�_
���Ԕ�r�ɂȂ�ƁA�i��J���ł̎������̗v�����ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���̂�����͉��炩�́y�O������z�����߂Ă����ׂ�����(^^;
�����ԍ��F24361848�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
2021/09/25 15:23�i1�N�ȏ�O�j
���B���f�q�P�̂̐��\���r����Ȃ�A�����L�����a�̃����Y�Ŕ�r����K�v������ł��傤�B�Ⴆ�A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y12mm(24mm�����̉�p) f2.0�̗L�����a��6mm�ł��B���L�����a�̃t���T�C�Y24mm�����Y�̖��邳��f4.0�ƂȂ�܂��B�܂�B���f�q�P�̂̐��\��r�́Af2.0��f4.0�ł��Ȃ��Ƃł��܂���Bf2.0���m�Ŕ�r���Ă��܂��ƁA��������ʂ�4�{�������A�������قȂ邱�Ƃ���A��������_�ɂȂ�܂��B
����������r�ɂ��Ӗ��͂��邯�ǂ�
��������ʂ�4�{�̍�������̂��t���T�C�Y��MFT�̈Ⴂ
�ł��邱�Ƃ���O�Ƃ��Ĕ�r���������ʓI�ł���Ӗ��͑傫����
���Ɛ����B��̂Ƀt���T�C�Y�ł�20/1.8���ă����Y�͕��ʂɂ��邯�ǂ�
MFT�p��10/0.9�Ȃ�ă����Y�����������H
�ƂȂ�A�P�ʖʐϓ�����̌���4�{�ɂ���Ȃ�Ăł��Ȃ���ʂ����X����
�����ԍ��F24361889
![]() 3�_
3�_
���肪�Ƃ��A���E����
�m���ɁI
��r�e�X�g���A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y�̊J���ƃt���t���[���̍i�荞�݂łł��邩���ƍl���Ă܂������A�ȒP�ł͂Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F24361898
![]() 0�_
0�_
�j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
���w�E�̒ʂ�ł��B
�u�V�X�e���v�Ƃ��Ă̏o����ō����\�̔�r�͕ʂł��B
�����ԍ��F24361913
![]() 0�_
0�_
2021/09/25 15:39�i1�N�ȏ�O�j
����t���T�C�Y�@��
�\�j�[��7
8�N�O�̋@���
ISO25600�ŎB��܂���
JPEG�B���ďo���ł�
�ǂ��v���܂��H
�C�\�@�ɂ���Ȃ���
�C�\�@�ɂ܂���
�����ԍ��F24361916�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�A�[�g�t�H�g�O���t�@�[53����
�������ˁB
�����ԍ��F24361949
![]() 0�_
0�_
���A�[�g�t�H�g�O���t�@�[53
��7S �̂悤�����ǁB
�W�N�O�ɂ͔����ĂȂ��J�����̂悤�����ǁB
iso20000 �̂悤�����ǁB
�����ȃA�J�E���g�œ����̓\���Ă��ˁB
�����āA��7S ��iso20000�Ƃ͎v���Ȃ����炢�A�m�C�W�[�Ȃ��ǁB
�����ԍ��F24361974�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 12�_
12�_
�X���傳��Ƃ��ẮuE-M5MarkIII�Ńt���T�C�Y���݂̐��i�ʐ^���B���v�Ǝ咣�����������悤�Ȃ���ǂ�
�I�����p�X��4/3��APS-C�A�t���T�C�Y�Ƃ̍����x���\�������������A���i�ʐ^�҂��̉����̃��P������Ȃ��������˂���4/3�̍����������������ŁA��̉����ړI�Ȃ̂�������Ȃ��Ȃ����̂Ŗ��ʂȃX�����Ă�̂͂�߂�����������Ȃ��ł��傤���H
��12mm(24mm�����̉�p) f2.0�̗L�����a��6mm�ł�
���ۂɂ̓C���[�W�T�[�N�����ӕ��̉掿�ቺ�E�P���������A��u����̂��߂̗]�T����������K�v�����邽�߁A�����Y�̂ЂƂa��6�o�������Ȃ�傫���͂��ł��B�Ⴆ��APS-C�p�Ə̂��Ă郌���Y�̒��ɂ̓t���T�C�Y�Ɏg�p���Ă����܂Ŏʂ���̂��������݂��܂��B
���̌��܂�����ŁA
���A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y12mm(24mm�����̉�p) f2.0�̗L�����a��6mm�ł��B���L�����a�̃t���T�C�Y24mm�����Y�̖��邳��f4.0�ƂȂ�܂��B�܂�B���f�q�P�̂̐��\��r�́Af2.0��f4.0�ł��Ȃ��Ƃł��܂���Bf2.0���m�Ŕ�r���Ă��܂��ƁA��������ʂ�4�{�������A�������قȂ邱�Ƃ���A��������_�ɂȂ�܂��B
������ԈႢ�ł��ˁB4/3�ƃt���T�C�Y�̉掿���r�������Ȃ瓯��ISO���x�A�����V���b�^�[���x�A�����i��l�Ŕ�r���Ȃ��ƈӖ����Ȃ��ł��B4/3��f2.0�Ȃ̂Ƀt���T�C�Y��f4.0����ISO���x�������Ȃ�t���T�C�Y���̃V���b�^�[���x��1/2�A���̏ꍇ�o�u���J�����Ԃ�2�{�K�v�ɂȂ�܂��B���b�m�C�Y�̊W�őΓ��Ȕ�r�ɂ͂Ȃ�܂���B
�����i�ʐ^�ɂ����č���𑜓x�̃t���T�C�Y�ł���m�C�Y�̏��Ȃ���v���́A�B���f�q���傫������ł͂Ȃ��A�u�t���T�C�Y�̃����Y�̗L�����a���T���đ傫������v�Ƃ����̂����̌����_�ł̌����ł��B
������������ŁA�m���ɂЂƂa���傫�������Y�̕����W���͂ƕ���\�͏オ��͂��ł����A�w�B���f�q��������������A1��f�̖ʐς��������ƌ��q�𑨂���������������ăZ���T�[�̊��x��������A�X�ɓd�q�̃g���l���d���ɂ��Ód���m�C�Y�̊��������ΓI�ɑ傫���Ȃ��Ė����ł��Ȃ��Ȃ�m�C�Y����������x�ƌ������͂��ł��B
�Ȃ��A���̎ʐ^�p�r�ɂ͍����x���ア����f�@�����W���`���f�@�������߂��܂��B
���w�����Y�ɂ̓U�C�f����5�����ƌĂ����������݂��A���̌���1�_�ɂ͎�������������x�L������������`��Ɏʂ�̂ō���f�ɂ������K�v������܂���B�����x�Ńm�C�Y�����Ȃ��������x�������Əo�邱�Ƃ���ԏd�v�ł��B
�����ԍ��F24362053
![]() 4�_
4�_
EOS 6D�U���[�U�[����
> �uE-M5MarkIII�Ńt���T�C�Y���݂̐��i�ʐ^���B���v�Ǝ咣�����������悤�Ȃ�
���̗l�ȈӐ}�͂���܂���B����ȉ����͂�߂܂��傤�B
> ���ۂɂ́A��U���������Y�̂ЂƂa��6�o�������Ȃ�傫���͂�
�ЂƂa�͎B���f�q���A�L�����a�͑Ε������Y���ł́H�@f�l�̒�`(�v�Z��)������x�m�F���Ă��������B
>4/3��f2.0�Ȃ̂Ƀt���T�C�Y��f4.0����ISO���x�������Ȃ�t���T�C�Y���̃V���b�^�[���x��1/2�A���̏ꍇ�o�u���J�����Ԃ�2�{�K�v�ɂȂ�܂��B���b�m�C�Y�̊W�őΓ��Ȕ�r�ɂ͂Ȃ�܂���B
���̓_��V���ɖ���N���܂����B�u���������ʁv�𑵂���ׂ��ł͂���܂��H�����̎咣����Ƃ���ł��B
> 1��f�̖ʐς��������ƌ��q�𑨂���������������ăZ���T�[�̊��x��������A�X�ɓd�q�̃g���l���d���ɂ��Ód���m�C�Y�̊��������ΓI�ɑ傫���Ȃ��Ė����ł��Ȃ��Ȃ�m�C�Y����������x�ƌ������͂��ł��B
�`���̑O��ɂ����Ă��w�E�̈Ӑ}���܂��Ă��܂��B���̏�ŁA���w�E�̓_�́A1�v���ł�����̂́u��v�v���ł͂Ȃ��ƍl���܂����B
�����ԍ��F24362163
![]() 3�_
3�_
2021/09/25 18:48�i1�N�ȏ�O�j
���ƃZ���T�[��4�{�̌��Ă�Ƃ������Ƃ�
�t���T�C�Y�ɑ���MFT��2�i�Ⴂ���x�ɂł��Ȃ��Ƃ����Ȃ�
�܂����i�ʐ^�ł͂�����x�����x�g������ł���킯�����ǂ�
����x�ł͖��������
�ނ���Z���T�[���傫����������x���Ⴍ���₷���킯��
���ǁAMFT�Ƀt���T�C�Y�ɑ��ĊJ��F�l��2�i���邢�����Y�������
�����x�掿�Ƃ��A�{�P�Ƃ��t���T�C�Y�Ɠ����ɂł���Ă̂͌�����ʂ͑����̂����ǂ�
���ǂ���̓����Y�̑傫���͂قړ������炢�ɂȂ�
�����Ă��߂�Ή𑜓x�̓t���T�C�Y��1/2�i��f���ł�1/4�j�Ȃ̂�MFT
�f���ɍŏ�����t���T�C�Y�g�������ǂ���
MFT�͂��������p�r�Ŗ������g���J�����ł͂Ȃ�
�����ԍ��F24362255
![]() 6�_
6�_
�j���[���ӂ�U�܂����偙�c��
>�f���ɍŏ�����t���T�C�Y�g�������ǂ���
�Ɋւ��A�٘_�͂���܂����A�E������̂ŃX���[���܂��B
�����ԍ��F24362381
![]() 1�_
1�_
2021/09/25 20:11�i1�N�ȏ�O�j
��KazuKat����
�E���˂���
�j�S���Ǝv�����ǂȂ���
���Z�œ_�����������ŗL�����a�̓��������Y���g����
�t���T�C�Y��MFT�ʼn掿�ɂ���Ȃɍ����o�Ȃ��Ȃ�ē�����O�̘b�Ȃ킯��
�i���F������f���Ȃ�j
������x�������Ă�l�ɂ͏펯
�����ǂ���������Ӗ������邩�Ȃ����̕����d�v���Ǝv����
�Ƃ肠�����l�ɂ͂��Ӗ����S������
MFT�͑�D�������ǂ�����Ȃ��Ƃ�邽�߂ɏ��L���Ă���̂ł͂Ȃ�
�����ԍ��F24362424
![]() 3�_
3�_
��KazuKat����
�f��̘b�͌������I
�펯�̂������₩��A�X���Řb�������ĉ��߂Ă܂Ƃ߂�K�v�������B�b�������Ă��A������펯�͋Ȃ����w
�X���傪�킩�������F�����Ă���Ă�₯��
�����������ԓx�����i�j
�܂��A�ʃX���D���₯�ǁB
���A�[�g�t�H�g�O���t�@�[53����
����傤�}�[�`����
���̃w���Ȃ��ށ`〜�~�����
�����ԍ��F24362523�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��KazuKat����
�o���_�͂����ł���H
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24344116/#tab
�������̎ʐ^���o���ꂽ�̂Ɏ����i��������j�u���ꌩ�����ł͎��I�ɂ͐��i�Ɏg�����ɂȂ�Ȃ��v���ď���������A�ӌŒn�ɂȂ��Ă�̂ł́H
���̓_�͂��l�т��܂��B�ʂɃX�}�z�Ō���Ԃ�ɂ͖��Ȃ��Ǝv���܂��E�E�E�ŋ߂̃X�}�z�ɂ͐��B���̂����邻���ł��ˁB
���̕��̏������݂ɂ�����܂������A�R���f�B�V������g�����ł̓ʂS�^�R�ł��Ȃ�Ƃ��Ȃ�̂ł��傤���ǁA������������APS-C��t���T�C�Y�i�œ��������̃����Y�j������A�������̕�����Ԃ͗ǂ��Ȃ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24362997
![]() 2�_
2�_
��KazuKat����
�L�����a�̗v�f�͗L��܂����A���ۂ͂ƌ������A
�����ȂƂ��듯��p�A��F�l��MFT���t���T�C�Y�A
�ǂ��炪�Y��Ȑ��̎ʐ^���B��邩�ȁ[���čl��
��������킯�ł�����B
����Ȃ�傳��ȊO�Ōy�ʉ��������l���AMFT��
�t���T�C�Y�ς��Ȃ��Ȃ�[�[���ă~�X���[�h��
�q����Ȃ��ׂɂ��A���܂藝�������˂ĈӖ��������
��r�����Ȃ������ǂ����ȂƎv���܂��B
���͖��邢������Â����������ɗL��܂��B
�m�C�Y�Ȃ̂����Ȃ̂��P�ʂ��Ɣ��f�����炢��
�o�Ă��܂��B
������NR�͂��������ł����Ƃ̓m�C�Y�Ƃ�������
�������ď����Ă�����ł͗L��܂���B
NR�������遁�\�j�[���ł͖����ɂ��Ă�(�\�j�[
���[�U�[����w)NR�̊|����ɂ���đ����Ȃ�Ƃ�
���H���̔����Ɍq�������肵�܂����A�����g��������
���l�ɔ{�̕b���ɂȂ��NR�x�����A�͂��܂��قȂ�
���[�J�[�ł����炻���������A���S���Y����MTF�ƃt��
�T�C�Y�Ŕ�ׂ悤�������ł��B
����Ė`���ŏ������ʂ�����͒P���ɓ���p�A��F�l��
�B�������̔�r�ł̈Ⴂ�̓Z���T�[�T�C�Y�ʂ̈Ⴂ�ɂȂ���
���܂����N�̖ڂɂ��������₷���Z���T�[�T�C�Y���ƌ�������
�Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�X���傳�{�f�B�I�тɃt���T�C�Y��apsc�Ɩ����Ă���
���܂����A��������b�Ƃ��Ă̓����Y�̗L�����a�܂߂Ă�
���Ȃ̂ł��傤���H
�����ԍ��F24363230
![]() 2�_
2�_
���ʂ䂸����
���u���ꌩ�����ł͎��I�ɂ͐��i�Ɏg�����ɂȂ�Ȃ��v���ď���������A�ӌŒn�ɂȂ��Ă�̂ł́H
�������A�������܂��B���w�E�̓_�́A�����Ƃ��Ď~�߂Ă��܂��B�ӂ��Ē����K�v���L��܂���B�ނ���C�Â����Ē��������ƂɊ��ӂ��Ă��܂��B
���́A�����ɑ��Ă��A�Ȋw�I�Ș_���w�i��m�邱�ƂŁA���ǂ��A�E�g�v�b�g���o����ƍl���Ă��܂��B�掿�����߂�v���ɂ��Ă��A�u�Ȋw�I�Ș_���w�i�v��m�肽���̂ł��B�������A�Ȋw�I�Ș_���w�i���𖾂���菇�͂ƂĂ��ʓ|�ł���A�����̒����ɏ]���A�u�펯���^���v���Ƃ���n�߂�K�v������܂��B�u�펯���^���v�ߒ��ɂ����āA�����̕��Ɍ������Ă���Ɗ����܂��B�F�́u�t���t���[���͉掿�͗ǂ��v�ƌ����Ă��邱�Ƃɑ��A���_��������ł͂���܂���A�𖾂������̂ł��B
�����ԍ��F24363475
![]() 1�_
1�_
���́A�����ɑ��Ă��A�u�Ȋw�I�Ș_���w�i�v��m�邱�ƂŁA���ǂ��A�E�g�v�b�g���o����ƍl���Ă��܂��B�掿�����߂�v���ɂ��Ă��A�u�Ȋw�I�Ș_���w�i�v��m�肽���̂ł��B�������A�Ȋw�I�Ș_���w�i���𖾂���菇�͖ʓ|�ł���A�����̒����ɏ]���A�u�펯���^���v���Ƃ���n�߂�K�v������܂��B�u�펯���^���v�ߒ��ɂ����āA�����̕��Ɍ������Ă���Ɗ����܂��B�F�́u�t���t���[���͉掿�͗ǂ��v�ƌ����Ă��邱�Ƃɑ��A���_��������ł͂���܂���A�𖾂������̂ł��B
�����ԍ��F24363482
![]() 1�_
1�_
hattin89����
���w�E�̓_�Ɋւ��A���̈٘_������܂���B���Ƀ~�X���[�h�̂Ȃ���Ƃ�����A�ǂ��Ȃ��ł��ˁB
���́A�掿�̗ǂ��Ȃ闝���𗝉��������̂ł��B
>�X���傳�{�f�B�I�тɃt���T�C�Y��apsc�Ɩ����Ă��肵�܂����A��������b�Ƃ��Ă̓����Y�̗L�����a�܂߂Ă̎��Ȃ̂ł��傤���H
���́A�����_�Ń{�f�B�[�I�тɖ����Ă��܂���B���ʂ�M43�ōs�����Ƃ����߂Ă��܂��BM43�ł��掿�̗ǂ��ʐ^���B�邽�߂ɁA�����̉𖾂�ڎw���Ă��܂��B�L�����a���v�ł���Ȃ�A�L�����a�̑傫���u�����Y��T���v���ƂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F24363505
![]() 1�_
1�_
���Ă�HN�u�ʎq�̕��v��������悤�Ȋ뜜���E�E�E(^^;
���Ȋw�I�Ș_���w�i���𖾂���菇�͖ʓ|�ł���A�����̒����ɏ]���A�u�펯���^���v���Ƃ���n�߂�K�v������܂��B
��
����́A�u��背�x���̌����v�Ɏ����āA���߂ĉ\�ɂȂ�܂��B
�����łȂ��ƁA�ے�\�ȂƂ���Ɣے�s�\�ȂƂ���̌��������t���Ȃ��ł��̂�(^^;
���m�[�x����҃��x���̌����Ƃ���́u�ے�v�́A���Ԉ�ʃ��x���ł͂܂����B�ł��܂���̂ŁA�^�ɎĂ��_���ł��B
��i�̍���̕��������҂���u���b�v�T�[�r�X�v���炢�Ɏ��ׂ��ł��傤�B
(�m�[�x����҃��x���A�ƌ����Ă��A���R�̍K�^���������߉߂���ꍇ�͏��O)
���Ă�HN�u�ʎq�̕��v�́A�u��背�x���̌����v�Ɏ���O�Ɂy�ȉ����\���z���A���Ȃ��Ƃ��Q�x�߂̃A�N�ւɂȂ��Ă�������܂����B
(�����K���a�ق��̈����ŁA�����I�ɑ��݂��Ȃ��Ȃ����\����������H)
�����ԍ��F24363531�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���L�����a���v�ł���Ȃ�A�L�����a�̑傫���u�����Y��T���v���ƂɂȂ�܂��B
��
�u�]���v�ɂȂ�قǗL��(��)�a���d�v�ǂ��납�K�{�v���ɂȂ�܂����A
�u�L�p�v�ɂȂ�قǗL��(��)�a�̏d�v���͒ቺ���܂��B
����́A�L��(��)�a�ƕ���\�̊W���u�����̃����Y�𑜓x�v�������肩��ɂȂ�A�����̃����Y�𑜓x�ɑ��ĂQ�{�R�{�̕���\�ɂȂ��Ă���ƁA��������Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B
�܂��A��C���̃����Y�ɂ����ẮuF0.5�v�����_����ɂȂ�܂����A�Ȃ��u0.5�v�ɂȂ�̂��ׂĂ����ߒ��ŁA���낢�듾��Ƃ��낪�o�Ă���ł��傤�B
��������ƁA�L�p�ɂ����čD������ɗL��(��)�a��ݒ肷�邱�Ƃ����ِ��E����I�Ȉʒu�Â��ɂȂ邱�Ƃ��m�邩���m��܂���(^^;
���ƁA�Ȋw�����ɂ�����u�����𑵂���v�Ɓy�������z�Ƃ͈Ӗ����قȂ�܂��B
���������u�����𑵂���v�̑O�ɁA���������܂��͌��������̐ݒ肪����܂����A
���̎��������܂��͌��������̐ݒ肪�s�K�ł���A
�s�K�Ȑݒ�����ɂ��āu�����𑵂��v�Ă��A�Ӗ�������܂���B
����́u�`���I�ɏ����𑵂����v�����ł����āA
�u�K�ȏ����͑����Ă��Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F24363574�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���肪�Ƃ��A���E����
���w�E�̓_�͗������܂��B
�������A���̊�{�I�ȍl�����́A�f�l�Ńo�J�ł���u�����ōl���邱�Ƃ͑�ł���v�ł��B
���ێ��́A���̃X���b�h�𗧂��グ�����ƂŁA���[���l����Ɏ���A�����̃q���g�邱�Ƃ��ł��܂����B���̃q���g�́A�u�t���t���[���̓m�C�Y�����Ȃ��v�������l��������āA�t���t���[����ӖړI�ɔ����Ă�����A���邱�Ƃ̖����������Ƃł��B
�����ԍ��F24363596
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
�d�ˏd�ˁA���肪�Ƃ��������܂��B
���L��(��)�a�ƕ���\�̊W���u�����̃����Y�𑜓x�v�������肩��ɂȂ�A�����̃����Y�𑜓x�ɑ��ĂQ�{�R�{�̕���\�ɂȂ��Ă���ƁA��������Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B
����C���̃����Y�ɂ����ẮuF0.5�v�����_����ɂȂ�܂�
�������肵�Ă���ƁA�����Ƃ��Ă܂��Ă��܂������ł��B
���u�K�ȏ����͑����Ă��Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���ނ��ł��B
�����ԍ��F24363624
![]() 0�_
0�_
�u�����ōl���邱�Ƃ͑�ł���v
��
����͋C�����̖��Ƃ��Ă͐������̂ł����A�y�ȉ�������䖳���z�ɂȂ�܂��B
���̈Ӗ��ł���l���Â��͐���N�A�ߑ�ȍ~�ł����\�N�ȏ�́y�m�̒~�ρz�����p���邱�Ƃ́A���ɗD�揇�ʂ������Ȃ�܂��B
�������A�t���T�C�Y�u������v�����x�Ƃ����P���v�l�͕��ʂɔے肵�܂����A
�u�B���ʑS�́v�̎���u�����v�Ŋ��x�ƒ���������ȉ������ʂɔے肵�܂���(^^;
�����ԍ��F24363636�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���肪�Ƃ��A���E����
���y�ȉ�������䖳���z�ɂȂ�܂��B���̈Ӗ��ł���l���Â��͐���N�A�ߑ�ȍ~�ł����\�N�ȏ�́y�m�̒~�ρz�����p���邱�Ƃ́A���ɗD�揇�ʂ������Ȃ�܂��B
�ܘ_�S���Ă��܂��B
�����ԍ��F24363647
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
�܂��܂��A�����������肢���܂��B
���́A�����ܗ��̃����Y�ɂ����ĐF�x�����W�������邱�Ƃ͍���낤�ƍl���Ă��邱�Ƃ���A���L�p�����Y�ɂ����Č��a��傫�����邱�Ɠ���̂��낤�Ǝv���Ă܂��B���������ł���Ȃ�A24mm�����̍L�p�����Y�́A����ܗ��Ŏ����\�ȃt���t���[���̕����A�����ܗ���K�v�Ƃ���}�C�N�t�H�[�T�[�Y���A���w�ʂ�����L���ƂȂ�܂��B���̍l�����͐������ƌ�����ł��傤���H
(����Ƃ��A�Z�p�I�ɂ́A�������Y�����ɑg�ݍ��킹��A���L�p�����Y�ł�����a���ȒP�Ɏ����ł���̂ł��傤���H)
�����ԍ��F24363742
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
�Ȃ�u�t���T�C�Y�̕����ʂS�^�R�����m�C�Y�����Ȃ��Đ��i�ʐ^�Ɍ����Ă�����Ă̂̓z���}�ł����H�v�Ƃ������̃X���̐ݖ�ɂȂ�Ȃ��Ǝv���̂ł����B
�����ԍ��F24363759
![]() 1�_
1�_
���ʂ䂸����
�{���ł����H�Ɩ₤���Ƃɂ���āA�Ȋw�I���_�ւ̗������[�܂�ƍl���Ă��܂��B�Ȋw�I���_�ւ̗������[�܂�A���ǂ��ʐ^���B���ƍl���܂��B
�����ԍ��F24363788
![]() 1�_
1�_
�������ܗ��̃����Y�ɂ����ĐF�x�����W�������邱�Ƃ͍���낤�ƍl���Ă��邱�Ƃ���A
��
�����L�p�����Y�ɂ����Č��a��傫�����邱�Ɠ���̂��낤�Ǝv���Ă܂��B
��ɁA��C���̃����Y�ɂ����āuF0.5�v�����_����ɂȂ闝�R�ׂẮH
���̉ߒ��ŁA�K�v�Ȏ����Ɍq�����Ă������ƁB
��24mm�����̍L�p�����Y�́A����ܗ��Ŏ����\�ȃt���t���[���̕����A�����ܗ���K�v�Ƃ���}�C�N�t�H�[�T�[�Y���A���w�ʂ�����L���ƂȂ�܂��B
��
�t���T�C�Y��4/3�^���x�Ȃ�A�u�ʏ�̎B�e�@��v�Ƃ��Č덷�͈͂����H
���������A�������̎������l������ƁA�B�e�ʂ̒��������ʒ[�̋����������Ȃ���ǂ��Ȃ�̂��A���̂����肩�璲�ׂĂ݂Ă͂ǂ��ł��傤���H
����������b�I�ȂƂ���ƁA���w�I�ɕ�\�ȂƂ���ւ�(����J�����R����)���ۂ̃����Y�Ɋւ���Z�p�ȂǁA���낢�날��܂���(^^;
�����ԍ��F24363789�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���Ȋw�I���_�ւ̗������[�܂�A���ǂ��ʐ^���B���ƍl���܂��B
�K�{�����ł͖����A�Ǝv���܂��B
�L�͂ȃJ�����}���͂ǂ��ł��傤���H
�Ⴆ�A�L���Ȃق��̃J�����}���Ƃ��Ĕ�r�I�ɍ��w���ȋ{���Ύ���
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B6%8B%E8%8C%82%E6%A8%B9
�����ԍ��F24363808�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
���uF0.5�v�����_���
�������w�I�Ș_���w�i�𗝉�����Ɏ����Ă܂���B���������_�̗����Ƃ������A�l���Ă݂���A���������e���[�J�[���ʎY�\�Ȍ��Ef�l(�L�����a)�̃����Y����Ă���(�Ⴆ��f1.4)�Ȃ�A�t���T�C�Y�ƃ}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃m�C�Y����p�Ɖ�f���Ŕ�r����ƁA�t���T�C�Y�́A�����Y�ɂ����ėL�����a2�i�������W�����A1��f�ɂ�����2�i��SN�䂪�傫�����Ƃ���A�V�X�e���S�̂ł�4�i�������������ƂɂȂ�܂��B�܂�A���������u���|�I�Ɂv�t���t���[���̕����m�C�Y�����Ȃ��A�ƌ��������ł��B��������ȏ�A�H�w�ʂōl���铮�@������Ă��܂����B�B�B
�����ԍ��F24363877
![]() 0�_
0�_
2021/09/26 15:08�i1�N�ȏ�O�j
��24mm�����̍L�p�����Y�́A����ܗ��Ŏ����\�ȃt���t���[���̕����A�����ܗ���K�v�Ƃ���}�C�N�t�H�[�T�[�Y���A���w�ʂ�����L���ƂȂ�܂��B
����͗Ⴆ�t���T�C�Y��24/1.4�ɑ���MFT��12/0.7�����ꍇ�ł������ȁH
�ׂ������ƌ������̏ꍇ�t���t���[���Ƃ������t���g���͕̂s�K��
�t���t���[�����ƃt�H�[�}�b�g�T�C�Y�����܂�܂���
35mm�t���t���[���Ƃ�645�t���t���[���Ƃ�����Ȃ��Ƃ����Ȃ�
����ɑ��ăt���T�C�Y�̓��C�J���ł����g��Ȃ����t������
�t���T�C�Y�ƌ��������ł�OK
�����ԍ��F24363961
![]() 1�_
1�_
���肪�Ƃ��A���E����
��Ƃ��痿�̐����m���ɊW�Ȃ����ȊG���������Ƃ��ł���̂Ɠ��l�A�ʐ^�Ƃ͍H�w�m���ɊW�Ȃ����Ȏʐ^���Ƃ邱���ł���ł��傤�B�����K�{�Ƃ͍l���Ă܂���B
�����ԍ��F24364410
![]() 0�_
0�_
�j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
������͗Ⴆ�t���T�C�Y��24/1.4�ɑ���MFT��12/0.7�����ꍇ�ł������ȁH
��Ⴂ�܂��Bf�l�̌��w�_����̏����0.5�ł���Ȃ�A�s�̂���Ă���f1.4�́A�t���T�C�Y�ł���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł���A�ʎY���̎������E�ɓ��B���Ă�����̂Ɖ���ł��܂��B�����ł���A�t���T�C�Y��24/1.4�ɑ��AMFT�ł�12/0.7�������ł���12/1.4�܂ł����ʎY���ł��Ȃ��ƍl�����܂��B
�����ԍ��F24364438
![]() 0�_
0�_
2021/09/26 20:11�i1�N�ȏ�O�j
��KazuKat����
�������Ă���̂ł͂Ȃ�
�t���T�C�Y��24/1.4��MFT��12/1.4�Ȃ���ܗ�����
�����ԍ��F24364606
![]() 1�_
1�_
�j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
���t���T�C�Y��24/1.4��MFT��12/1.4�Ȃ���ܗ�����
���ܗ��́A�����ł����H�@�œ_�����̒Z�������A�傫���̂ł́H
�����ԍ��F24364618
![]() 2�_
2�_
���t���T�C�Y�́A�����Y�ɂ����ėL�����a2�i�������W��
�u�W���v�̌�A�B���f�q�T�C�Y(�̃C���[�W�T�[�N��)�Ɂu�z���v���܂���ˁH
���ʂƂ���F�l�̂܂܂ň��������킯�ł��B
�E�E�E�������������R�����g���Ă����ׂ������������E�E�E(^^;
�����ԍ��F24364622�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
> �t���T�C�Y�ƃ}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃m�C�Y����p�Ɖ�f���Ŕ�r����ƁA�t���T�C�Y�́A�����Y�ɂ����ėL�����a2�i�������W�����A1��f�ɂ�����2�i��SN�䂪�傫�����Ƃ���A�V�X�e���S�̂ł�4�i�������������ƂɂȂ�܂��B
����͌��ł��B
�܂��̓J�����̘I�o�ɂ��Ċw��ł݂Ă͂������ł��傤�B
���i�ʐ^�ɂ͕K�{�̒m���ł��B
�����ԍ��F24364624
![]() 4�_
4�_
2021/09/26 20:28�i1�N�ȏ�O�j
��KazuKat����
�P���Ƀt���T�C�Y��24/1.4�̌��w�n��1/2�ɏk�������
MFT��12/1.4�̌��w�n�Ƃ��Đ��藧�̂�
���̏ꍇ���ܗ��͓����ł�
�����ԍ��F24364646
![]() 1�_
1�_
���肪�Ƃ��A���E����
���u�W���v�̌�A�B���f�q�T�C�Y(�̃C���[�W�T�[�N��)�Ɂu�z���v���܂���ˁH
�����ł���Af�l�������ł���ΎB���f�q�ɂ�����P�ʖʐς�����̏W���ʂ͓����ł���A���̈Ӑ}�����Ε������Y�L�����a�̃n���f�B�[�����͊Ԉ���Ă������ƂɂȂ�܂��B
�����Ȃ�ƁA����f�^�C�v�t���T�C�Y�ł���u���炩�ȍ��v�Ńm�C�Y�����Ȃ��A�Ƃ����v����������Ȃ��Ȃ�܂��B��͂�A����f�Ƃ͌���1��f�̎���ʐς͈ˑR�Ƃ��Ĕ{�����邱�ƁA����Ȃ�ł͂̃m�C�Y�̂��ߍׂ����A��2�_����ł����ˁH
�����ԍ��F24364694
![]() 0�_
0�_
�j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
�t���T�C�Y��24/1.4�����Y�̑Ε������Y�L�����a17.1mm������悤�A�u���ܗ��ύX�v�ɂ���ďœ_����12mm�ɒZ�k���C���i�[�T�[�N�����}�C�N�t�H�[�T�[�Y�a�Ɉ��k�ł���Af�l��0.7�ɏオ�邩�Ȃƍl�������̂́A���w���_�I�ɂ��H�w�I�ɂ����������ƌ������Ƃł��ˁB
�����ԍ��F24364755
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
(�����Y���̓��ߗ����������)
����F�l�ł���A�P��f������̖ʐύ����u����v�ʂ̍��ɒ������܂��B
�����āu����v�ȍ~�́A�X�̎B���f�q�̐��\���ɂ��܂��B
(�����Z�p���x���ł́u���d�ϊ��v�ɑ卷�����̂ŁA���ʓI�ɂP��f������̖ʐύ� �� ����ʂ̍��̊ւ�肪�[���Ȃ�킯�ł�)
�������ŁA�P��f������̖ʐςƎ���ʂɂ��čČf�B
�ȑO�ɃA�b�v�����Ƃ��Ɓu���Ă��鐔�l�̈�ۂ��ς�����v�̂ł���A�ȑO�̃A�b�v���_����X���傳��͐i�����Ă��邩���H
��
�m�C�Y���C�ɂȂ郌�x���́A(��ʂ�)�̋@��̍ō����x�̉����̂P�Ƃ����Ƃ���ł��̂ŁA���̂悤�ȑ������������ƑO�X���݂����ɂȂ�܂�(^^;
�����̈Ӑ}�����Ε������Y�L�����a�̃n���f�B�[�����͊Ԉ���Ă������ƂɂȂ�܂��B
��
�����͋L�ڃ~�X���Ǝv���܂������A���{�I�Ɋ��Ⴂ���Ă���悤�̂ŁA��̂悤�ȃ��X�����܂����B
(�u�ӌ��v�Ƃ͊W�����P�Ȃ�ԈႢ�Ȃ̂ŁA�x���ꑁ����C�Â��ł��傤����A���������̂ق����ǂ�����)
�����ԍ��F24364766�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
���Ƃ�̑O�����Ɉ���Ă���l�Ɏv���܂��B����f�l�ł����1��f������̎���ʐς����ʂ̍��ɂȂ邱�Ƃ𗝉����Ă��邩�炱���A�����A����L�����a��r(�n���f�B�[������r)����܂����B
�Ⴆ�A�t���T�C�Y��24/1.4�����Y��(�Ε������Y�L�����a17.1mm)���A�u���ܗ��ύX�v�ɂ���ďœ_����12mm�ɒZ�k���C���i�[�T�[�N�����}�C�N�t�H�[�T�[�Y�a�ɏW���ł���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A�Ε������Y�L�����a17.1mm�������ƂŃn���f�B�[�������ł��Af�l0.7�̃����Y�邱�Ƃ��ł���ƍl���܂����B
�������A���ԂƂ��Ă͌��Ef�l�̖�肩��A���w�I�ɂ��H�w�I�ɂ�����������Ƃ������Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24364834
![]() 0�_
0�_
��
���AISO���x�Ǝ���ʂ̊W���L�ڂ��Ă����܂��B
ISO�@�@���ʏƓx(���j���[�g�����O���[�����ŕW���I�ȘI�o�ɂȂ郌�x��)
100�@�@0.1 lx�E�b
�@ �� 1/60�b�Ȃ� 6 lx(ٸ�) �� �B�e(��ʑ�)�Ɠx�Ƃ��Ė�600 lx(ٸ�)
1000 �@ 0.01 lx�E�b
�@ �� 1/60�b�Ȃ� 0.6 lx(ٸ�) �� �B�e(��ʑ�)�Ɠx�Ƃ��Ė�60 lx(ٸ�)
10000�@0.001 lx�E�b
�@ �� 1/60�b�Ȃ� 0.06 lx(ٸ�) �� �B�e(��ʑ�)�Ɠx�Ƃ��Ė�6 lx(ٸ�)
�����ʏƓx�́AISO100�Łu0.1 lx�E�b�v�܂��́u0.1 lx�Es�v
�B�e(��ʑ�)�Ɠx�ɑ��āA���ʏƓx�͕��������Ȃ��Ȃ�܂��B
��ʑ̂̔��ˌ��Ƃ��Ă܂��������A�����Y��ʂ��Č�������̂ŁB
���ڂ������Ƃ͌������Ē��ׂĂ݂Ă��������B
�������A���Ԉ�ʃ��x���̌������ʂ̃C���[�W�ƈ���āA�Ȃ�����I�ȓ��e����������Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F24364875�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
�����܂���A���Ƃ�̑O�����Ɉ���Ă��܂������́A���������������̈Ӑ}��\�����Ă��Ȃ�����ł��ˁB�������܂����B
����f�l�ł����1��f������̎���ʐς����ʂ̍��ɂȂ邱�Ƃ𗝉����Ă��邩�炱���A�����A����L�����a��r(�n���f�B�[������r)����܂����B
�Ⴆ�A�t���T�C�Y��24/1.4�����Y(�Ε������Y�L�����a17.1mm)�̌��w�n���ꕔ�������A�œ_����12mm�ɒZ�k���A�C���i�[�T�[�N�����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�a�ɏW���ł���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A24mm������p�ɂ����Ă��A�Ε������Y�L�����a17.1mm�̃����Y(f�l0.7�̖��邳)�邱�Ƃ��ł��A�n���f�B�[�������ł���ƍl���܂����B
�������A���ԂƂ��Ă͌��Ef�l�̖�肩����w�I�ɂ��H�w�I�ɂ�����������A�Ƃ������Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24364891
![]() 0�_
0�_
���n���f�B�[����
Handicap�̃n���f�B�ł����H
(^^;
�u�����v�������A���̃����Y���w�������p�̍��z���l������ƁA�t���T�C�Y�����ق��������A�Ƃ��A(��)����a�����Y�ɂȂ�Ƌ���Ńw�r�[���Ȃ�A�t���T�C�Y�p�̂ق����}�V���A�Ƃ����{���]�|�p�^�[���ɂȂ�܂��H
���������A��ɉ������K�v�ł͂���܂����ˁH
�����ƈÎ��1/2.3�^�ł����i���l������A4/3�^�����n�Y�̂P�^�ł����������̈ʒu�Â��ɂȂ��Ă��܂��B
kakaku�̎���X���̃��x���ł́A�u�����Z�̈Â��̈�ٓ��ł̃X�|�[�c�B�e�v�́A�t���T�C�Y�̍����x���\����Ɋ�ɂȂ�A4/3�^�ǂ��납APS-C�ł��h���Ƃ���ł��B
����ȊO�ł́A�i�C�^�[����ł����A����́u�����Z�̈Â��̈�ٓ��ł̃X�|�[�c�B�e�v�������{���邢�̂ŁA�ނ���4/3�^�̖]�������b�g���o��n�Y�Ȃ���A���Ԉ�ʌ������i�̍��{���Y�[��(�]���[�̎�f=400mm�A���Zf=800mm)�������ɓ������ł���(^^;
�����ԍ��F24364913�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2021/09/26 23:00�i1�N�ȏ�O�j
���ǁA���_�I��MFT�p��2�i���邢�����Y����ꂽ�Ƃ��Ă�
�����I�ɂ̓����b�g���قƂ�ǂȂ�����Ȃ����c
�f�����b�g�͖��m�ɂ��邯�ǂ�
�t����24/1.4��MFT��12/0.7
�������Ƃ��Ăǂ��������i�������Ǝv���܂��H
���Ă����܂܂ł�FT�����MFT�̗���I��
12/0.7�̕��������Ǝv��
�����đ傫���d�����������炢�ɂȂ��Ă��i���ɕ����I�ɉ𑜓x��1/2�̐�����
�������MFT�ŎB�e����Ӗ�����̂��ȁH
���Ȃ��Ƃ��l�ɂ͊F������
�����ԍ��F24364988
![]() 2�_
2�_
���肪�Ƃ��A���E����
���{���]�|�p�^�[���ɂȂ�܂��H
�{���]�|�̉\���́A�傢�ɂ���܂��B���F�A���̎v�������x���ł�����B�B���f�q���ɏW���n��lj����邾���Ȃ�A�t���T�C�Y�J���������������͈�����������܂���B�������A����ȊȒP�Ɏ����ł��邱�ƂȂ̂��A�����̑f�l�Ȃ̂őS��������܂���B
�����ԂƂ��āA�X�|�[�c�B�e���Ӑ}�����t���T�C�Y������L�����a�̒��]�������Y���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ɏ��݂��ĂȂ��B
���̒ʂ�ł��ˁB���^�y�ʂ��Z�[���X�g�[�N�ɂ��Ă��邱�Ƃ���A�t���T�C�Y�Ɠ�������L�����a�����Y���o���Ȃ��̂�������܂���B
�����ԍ��F24364994
![]() 0�_
0�_
�j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
��(�����܂ł���)�A�������MFT�ŎB�e����Ӗ�����̂��ȁH
�����A�Ӗ��Ȃ��\���͍����Ǝv���Ă��܂��B
�������A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł������̓t���T�C�Y�ɋ߂����]�n�̂��邱�Ƃ��A�m�F�ł����Ӌ`�͑傫���Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F24365012
![]() 0�_
0�_
2021/09/26 23:21�i1�N�ȏ�O�j
���������A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł������̓t���T�C�Y�ɋ߂����]�n�̂��邱�Ƃ��A�m�F�ł����Ӌ`�͑傫���Ǝv���Ă��܂��B
�܂��A����̂���̏펯�Ȃ�ł�
�������i�ł��U�X����Ă������ƂȂ�ł���
�X���傳��ɂƂ��Ă͐V�������Ȃ̂Ŋw�ׂĂ悩�����ł��ˁ�
�����ԍ��F24365026
![]() 2�_
2�_
���B���f�q���ɏW���n��lj����邾���Ȃ�A
�u�����v�H
���߂āu��}�v���Ȃ���l���Ă�������(^^;
�L�[���[�h�Ƃ��āu�W���n�v�ƌ����Ă���u�����v�ł���A���S�ɔے肳��܂��B
�ߋ��S�N�ȏ�̃����Y�֘A�̋Z�p�҂⌤���҂��l�����Ȃ������悤�Ȉ̑�Ȕ���~�����ł���Εʂł���(^^;
�Ȃ��A(����)�W���n�̗L���Ɋւ�炸�AF�l = �œ_���� / �L��(��)�a �̎��͈̔͂ɓ���̂ł���A����͏]���͈̔͂Ɖ����ς��܂���B
�����ԍ��F24365033�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ԂƂ��āA�X�|�[�c�B�e���Ӑ}�����t���T�C�Y������L�����a�̒��]�������Y���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ɏ��݂��ĂȂ��B
��
���́A���̂悤�ɋL�ڂ��Ă��܂����B
���p���u���v������Ȃ�A�R�s�y���Ă��������B
��
���L���I���W�i���B
�����Ԉ�ʌ������i�̍��{���Y�[��(�]���[�̎�f=400mm�A���Zf=800mm)�������ɓ������ł���(^^;
��
���������O����Čf���܂����A
���i�C�^�[����ł����A����́u�����Z�̈Â��̈�ٓ��ł̃X�|�[�c�B�e�v�������{���邢�̂ŁA�ނ���4/3�^�̖]�������b�g���o��n�Y�Ȃ���A���Ԉ�ʌ������i�̍��{���Y�[��(�]���[�̎�f=400mm�A���Zf=800mm)�������ɓ������ł���(^^;
��
���Ԉ�ʌ������i�Ȃ�A�]���[�͓��R�Ȃ��� F5.6~6.3�B�i�C�^�[�ł� 1000 lx�O�゠��̂ŁA
�B�e(��ʑ�)�Ɠx1000 lx�� 1/500�b�B�e�̏ꍇ�A
F5.6�Ȃ� ISO 4000���x�A
F6.3�Ȃ� ISO 5000���x�ƁA�ꉞ4/3�^�ł��u���̃{�P(��ʑ̃u��)������}�V�v�Ȋ��x�͈̔͂ł́H
�����ԍ��F24365066�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�E����ʐ^�ɂ���
��(�P��)�͂ƂĂ������ɂ���̂ŁA���ʂ̃f�W�^���J�����E�����Y�ł�1��f�ɂ������Ȃ��ɂ߂ď����ȓ_�Ƃ��Ďʂ�܂��B
��Ƃ��Ă킩��₷���u35mm�Ńt���T�C�Y��50mm/F2.0�v�Ɓu�}�C�N���t�H�[�T�[�Y25mm/F2.0�v�Ƃ���ƁA
�����Y�L���n�́u25mm�v�Ɓu12.5mm�v�A
�O�҂�4�{�̌�����荞�݂܂��B
1��f�ɖ����Ȃ��_�ƌ����Ă��A����������̂͂ǂ����1��f�ł�����
�O�҂�1��f��4�{�̌����܂��A�����4�{���邭�ʂ�܂��B
�u������H�@����F�l�Ȃ̂ɖ��邭�ʂ�Ƃ́E�E�E�v�B
�����͎����ōl���Ă��������B
�ߋ��̏������݂��Ɛ������k�J�ɏI��邱�Ƃ�����悤�Ȃ̂ŁB
<�]�k>
�J�����j��ł����邢�����Y
http://a-graph.jp/2017/08/26/29010
�N�����R�������̂��A�m��Ȃ��B
�����ԍ��F24365104
![]() 0�_
0�_
�X���傳��̌����Ă邱�Ƃ͂قƂ�ǃt�H�[�J�����f���[�T�[�łȂ��ł����ˁH
����͏œ_������Z������F�l�����������郊�A�R���o�[�^�[�ł��B
�����̏��i���o�Ă܂������Ƃ��ẮAMetabone Speed Booster XL0.64���g���A
�������Y�Ƃ���35mm�pF1.2��t����ƃt�H�[�T�[�Y���F0.74���x�������܂��B
���B�e�p�r�ł͊�]����𑜗͂��Ȃ��\���������Ǝv���܂����A
FHD�̈�ʎB�e���x�Ȃ�g���邱�Ƃ������悤�œ���p�r�ł͊��Ƃ悭�g���Ă��܂��B
�T���Ύ��ۂ�F1�����̍���������Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɃA�b�x�̐�������(F0.5����̘b)�̓R�}�������Ȃ��ꍇ�̏����Ȃ̂�
���B�e�p�����Y�̘b�Ƃ��Ă͏\���L�����Ǝv���܂����A�Ë��_�����낢�날��
�ʐ^�����Y�̈�ʓI������̂悤�ɑ�����̂͂ǂ����ȂƎv���܂����B
�����ԍ��F24365109
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
�X�s�[�h�u�[�X�^�[���m����Ԃ���w
�����ɃX����̏��ʖ�����������B�ǂ̎��ォ�痈�����i�j
������A�܂��A�����̌�F��f���ɔF�߂�Ƃ��X�^�[�g��Ǝv���B�����Ă���Ă�ЂƋ�����B
�ŁA�f��͉�������H
�����ԍ��F24365128�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���J�����j��ł����邢�����Y
��http://a-graph.jp/2017/08/26/29010
�@��
���Z�����Y�ł���H�Ƃ��v���Ȃ�����A�ڂ����d�l����̂悤�ł��B
(�}�ʂ��m��)
����(�����͓��R�A�≖�t�B����)�������炵���H
�����B�e�p�����Y�̘b�Ƃ��Ă͏\���L�����Ǝv���܂����A�Ë��_�����낢�날��
���ʐ^�����Y�̈�ʓI������̂悤�ɑ�����̂͂ǂ����ȂƎv���܂����B
��
����́uF0.5�v�͒��߂̂悤�Ɂu��C���v���O��ŁA����̃����Y�̋Z�p����{(���S�Ҍ��ł͖����Ǝv����)�ɂ����߂���Ă��܂������A
����A�K�v������Ώ��Ȃ��Ƃ��\���͕ς���悤�ɂ��邩���m��܂���B
�Ȃ��A�B�e�����̌v�Z������ F0.5����ɂȂ��Ă���Ǝv���镔��������܂����A����͓��ʌ���ێ��ɂ��悤�Ǝv���܂��B
(�c�O�Ȃ���A�m���ȉ�������͖������ł����A���Ȃ��Ƃ��W���Ƃ��Ĕ����Ȃ��̂�)
�����ԍ��F24365131�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
lssrt����
���ɂ���ł��I
���i�ʐ^�ł̎g�p�̌��L�ȂǁA�����m����܂��H
�����ԍ��F24365138
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
�u�Ɩ��p�v�Ƃ��𑜗͂��ł��ꉽ�ł��L�肩�Ǝv���܂���(^^;
lssrt����ɐq�˂ẮH
�����B�e�p�r�ł͊�]����𑜗͂��Ȃ��\���������Ǝv���܂����A
��
����Ȋ����ɂȂ肻���H
�ȑO�̋≖�p�t���T�C�Y(35mm���t�B����)�p�̃����Y���AAPS-C�T�C�Y�̎B���f�q�ł�35mm���t�B�����p�����Y�̉�p�Ƃقړ��l�Ŏg�����߂ɁA�ꎞ���͏k�����w�n�̃����Y�A�_�v�^�[(�}�E���g�A�_�v�^�[)������o�Ă����悤�ł����A
�����炭�����ɂȂ�قǎg���Ȃ��d�l�������낤�Ǝv���܂��B
�\���Ɏʐ^�p�����Y�Ƃ��āy��p���킸�z���p�\�ł���A���W���[�ɂȂ��Ă������낤�Ǝv���܂����B
�E�E�E���L�p�ɂȂ�قǁA���̃����Y�̒i�K�ł��������̌��������x���ł�����A�����Ȃ邱�Ƃ͂����Ă��ǂ��͂Ȃ�Ȃ��悤�ȁH
�����ԍ��F24365150�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���X�b�]�R����������
>�ߋ��̏������݂��Ɛ������k�J�ɏI��邱�Ƃ�����悤�Ȃ̂ŁB
����܂ł̗�������Ă���ƁA
�X�b�]�R���������� �̂��w�E�ɋC�Â��l�͂��Ȃ���������܂���B
�����ԍ��F24365170
![]() 0�_
0�_
<�]�k�̂���>
[�����ԍ��F24365104]�̕��͖��ŐG�ꂽ�u�J�����j��ł����邢�����Y�v�B
�u���E�ꖾ�邢�����Y�v���������AWeb�������猩���������N�B
���̌�A���̃����Y���ł����Web�����B
�O�����Web�y�[�W��Web�|���Ƃ���A
���̕ӂɓ]�����Ă���(���Ԃ���L�@�̌����W���p�̃R���f���T�[�����Y����Ȃ����Ǝv��)�����Y��ȂŁA�X�y�b�N���K���ɂ�����ۂ�������g�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��t�F�C�N�i�炵�������B
�G�C�v�����t�[���̃l�^�Ƃ����������݂͌������Ȃ��������ǁA����Ȋ��������B
�m�������Ԃ�Ől�ɘb���ƁA�p�����������B
�E�E�E���Ă��߉�B
Tranquility����A�����ˁB
�����ԍ��F24365203
![]() 0�_
0�_
���X�b�]�R����������
��Tranquility����A�����ˁB
���[�����̍��݂ŃX�����y���݂܂��傤w
�����ԍ��F24365491�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��
�����炭�����ɂȂ�قǎg���Ȃ��d�l�������낤�Ǝv���܂��B
��
�����炭�L�p�ɂȂ�قǎg���Ȃ��d�l�������낤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24365575�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�X�b�]�R����������
���u35mm�Ńt���T�C�Y��50mm/F2.0�v�Ɓu�}�C�N���t�H�[�T�[�Y25mm/F2.0�v�Ƃ���ƁA�����Y�L���n�́u25mm�v�Ɓu12.5mm�v�A�O�҂�4�{�̌�����荞�݂܂��B
�f����������́A���̖`���ɂ����Ė���N�����uf2.0���m�Ŕ�r���Ă��܂��ƁA��������ʂ�4�{�������Ă��܂��v���Ċm�F������̂ł��ˁH
�����ԍ��F24365771
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
���i�ʐ^�ɂ�����MFT�ƃt���T�C�Y�̍��ɂ��ē˂��l�߂悤�Ƃ��Ă���X���傳��ɋt�ɂ��肢������̂ł����A
�����ꏊ�E�������ԁE�������E�����i�����j��p��MFT�ƃt���T�C�Y�i�����^���j���B���ׂė~�����̂ł��B
F�l�Ɛݒ�ISO���x�ɂ��ẮA�����ݒ�ł����ꂼ��̃x�X�g�ݒ�ł������ł��B
�����̋����̓m�C�Y�Ƃ������u�����ʂ�ʂ̍��v�ł��B
�����ł͂߂�ǂ������ĂƂĂ��o���܂����ʂɂ͂ƂĂ�����������܂��B
������o���Ă�����Ō��\�ł��B
�i���i�ʐ^�͂ق�̏����̌�������p���ɓ��邩�ǂ����ł��ʂ�ɍ����o��̂łł���ΎO�r��{�Łj
�������Y�t�����̂́A���i�ʐ^�i�Ï��j�ɉ�����MFT�̋ߌi�摜��MAX����Ďʂ�ƕ����݂�ׂ̃T���v���ł��B
�V���h�E��MAX�ɏグ�Ă���ׁA��̓m�C�W�[�ł����A�ߌi�̎ʂ�́i�����I�ɂ́jMFT�ł��[�����i�_�ł��B
���Ȃ݂ɎB�e�n�͐^���ÂŎ茳�����������Ȃ��ꏊ�ł��B�Ƃ͂����C�Ȃ̂ʼn����Ί݂̌��E5km����̌����̖�����E��������ł��B
�R���̐^���Â��͏����}�V�ł��B��������͖����i�����o��O�j�A�v���\�t�g���N���A�����Ă��܂��B
�~�`�O���f�[�V�����E���`�O���f�[�V�����ɂ�镔����͍s�Ȃ��Ă��܂���B
�ߌi�𖾂邭������ł����ƌ����ʐ^�ɂ���ɂ͕�������K�v��������܂���B
������ɂ��Ă��AMFT���i�ʐ^�������ł��邱�Ƃ͈ȉ����炢�ł��傤�B
�E�Ȃ�ׂ��V�����N���̃J�����{�f�B��I������B
�EF�l�͂��ꂼ��̉�p�ň�Ԗ��邢�����Y����������B�i�A�������̏��Ȃ����́j
�E�I�o�I�[�o�[�ŎB��i���̎ʂ�ʂ��ς���Ă��܂��j
�EISO�͏�����P�U�O�O���x�ɂ���i����͌���l�ƎB�e���ɂ��ς��܂��j
�����ԍ��F24365842
![]() 0�_
0�_
�����I�Ȑ���͕ς��Ȃ�����A���낢��ݒ芷���ď����ł����������ݒ�l��T���Ƃ��A�ԓ��V�g���ĘI�����Ԃ�������ISO�l������Ƃ��O�����Ȏ��Ɏ��Ԃ��g��������̂ɁB
�����ԍ��F24366181
![]() 1�_
1�_
��H�Ō�Ɏ���킹��
�^��`�Ń��X����̂��āc( ߁[�)
�ʎq�̕�����A�]�������́H( ߁[�)
�����ԍ��F24366323�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
Seagulls����
���́A��r���邱�Ƃ����Ɍ����n�߂܂����B�t���T�C�Y�̓����^������ƁA���Ȃ��Ă��{�f�B�[5��~�����Y�R��~�͂����肻���ł��B�O�r���K�v�ł��B�ł��邱�ƂȂ�P��f�̑傫�������������Ƃ���ł��B�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃����Y�����ʂ����킹�����Ƃ���ł��B���낢��l����Əo����������݂����ł��邩��A�S�O���Ă܂��B���������ɂƂ��čł���ςȂ��Ƃ́A���̌����ꏊ�ɍs�����Ƃł��B�����Ԃ������ĎB�e�n�ɍs������܂肾�����A�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�����g���W������܂���B���s�ɂ͎����Ȍv�悪�K�v�Ȃ̂ł��B
�Ƃ���ŁA�T���v���œ��e����������12/F1.4�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̍L�p�n�̒��ōł����邢���Ƃ���A�w�����Ƃ��Č������Ă���܂����B�������A���ʂ��t���T�C�Y��1/4�ł��邱�ƂɋC�Â��A�l�������Ă��܂��B
�����ԍ��F24366339
![]() 0�_
0�_
���ł��邱�ƂȂ�P��f�̑傫�������������Ƃ���ł��B
��
���H
����͗D�揇�ʓI�ɖ��ʂ���(^^;
���B���f�q�̐����N�㍷���L���� �� �Z�p���x�������傫���Ȃ� �� �u���d�ϊ��v�̌��������傫���Ȃ�B
�����ԍ��F24366579�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
�������Ԃ������ĎB�e�n�ɍs������܂肾�����A�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�����g���W������܂���B
���ꂪ�܂��ɓY�t�����摜�̏�Ԃł��E�E�E
�ړI�͓V�̐�ł������B��܂���ł����B�ł����i�B�e�Ȃ�Ă���Ȃ���ł��B
���s�A�O�������s���ł̎B�e�ƈʒu�t���V���b�N���y������̂ł��B
���T���v���œ��e����������12/F1.4�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̍L�p�n�̒��ōł����邢���Ƃ���A�w�����Ƃ��Č������Ă���܂����B�������A���ʂ��t���T�C�Y��1/4�ł��邱�ƂɋC�Â��A�l�������Ă��܂��B
���ɂ��t�H�N�g�����_�[ NOKTON 10.5mm F0.95���L��܂��ˁB
�ł�F1.4���_���Ƃ��Ȃ�����g����@�ނ��قƂ�ǖ����Ȃ�̂�
����������r����������Ӗ��������悭�킩��Ȃ��Ȃ�܂��ˁB
�O�r�͑��̌p���ڂ�G���x�[�^�[�@�\�ɃK�^�t���̖����������肵������I�т܂��傤�B
�ꖜ�~��̂��̂͂������߂��܂���B
�����ԍ��F24366651
![]() 1�_
1�_
���������A���ʂ��t���T�C�Y��1/4�ł��邱�ƂɋC�Â��A�l�������Ă��܂��B
�t���T�C�Y�g�p�҂̑�����~���邢�͑S����F1.4�̃����Y���g���Ƃ����z��ł����H
�E�P�œ_�����Y���Ďg���l���̂����Ȃ��B
�E�P�œ_�����Y��F1.4�ƂȂ�ƁA����ɏ��Ȃ��B
���������Ӗ��ł́A�P�œ_�����Y�ł� F2.8�����肪�V��̂P�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂�����A����Ɣ�ׂĂ݂��肷��ǂ��ł��傤���H
����Ƃ��A�Ƃ���(�v�`)�����J�������p�̓��ُ�A�̂悤�ɁA�u~ �łȂ���A�B�e���Ȃ��ق����}�V!!�v�Ƃ����^�C�v(����)�ł��傤���H
�����ԍ��F24366673�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
���P�œ_�����Y�ł� F2.8�����肪�V��̂P�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂�
�m���ɁB
�����l����ƁA�����Y�́AM43��12/1.4(�p�i) �ƃt����24/2.8(�^���������\�j�[)�Ŕ�r����A�C�[�u���ŗǂ��ł��ˁB
�J�����́A�I��EM5�V(22Mpix)�ƃ\�j�[7R�W(61Mpix)�B�t���́A1��f���_���ʐ�4/3��+���ʏƎˁA�m�C�Y�T�C�Y��1/3�Ƃ��Ȃ�L���B
�����ԍ��F24366752
![]() 1�_
1�_
���t���́A1��f���_���ʐ�4/3��+���ʏƎˁA�m�C�Y�T�C�Y��1/3�Ƃ��Ȃ�L���B
��
�m�C�Y�T�C�Y���āA�ǂ������Ӗ��ł����H
�܂��A���̎Z�o�́H
�����ԍ��F24366768�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
���m�C�Y�T�C�Y���āA�ǂ������Ӗ��ł����H�܂��A���̎Z�o�́H
�m�C�Y�T�C�Y�́A�B���f�q�̉𑜓x�̈Ⴂ���痈��m�C�Y�̂��ߍׂ����B�Z�o�́A�P���ɉ𑜓x��ŋ��߂܂����B22Mpix : 61Mpix
�������AJPEG(1920×1080)�ɏĂ�����ǂ��Ȃ邩������܂���B
�����ԍ��F24366808
![]() 1�_
1�_
�E�E�E(^^;
���Ԃ�u���ʔF���v�̘g�O�ɂȂ邩�ƁB
���ƁA
���������AJPEG(1920×1080)�ɏĂ�����ǂ��Ȃ邩������܂���B
��
����́u�ʖ��v�ł��傤�H
�u�����v�Ɓu�ꏏ�N�^�v�͎��ĈقȂ�܂���(^^;
�����ԍ��F24366830�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
�m�C�Y�́A�����傫���̎d�オ��ɂ����āA���𑜓x�ɂȂ���ߍׂ����Ȃ�m�C�Y��������A�ƌ����̂����ʔF���������Ǝv���Ă܂��B���̎����m�C�Y�T�C�Y�ƒ[�܂��ĕ\�����܂����B
�����ԍ��F24366859
![]() 1�_
1�_
�����𑜓x�ɂȂ���ߍׂ����Ȃ�m�C�Y��������A�ƌ����̂����ʔF��
��
����͑��Ώ����Ȃ̂ŁA�^�����邩�ۂ��͌l���悩�ƁB
�܂��A����̌v�Z���Ƃ������ʔF���͖����̂ł́H
�����ԍ��F24366873�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
������͑��Ώ����Ȃ̂ŁA�^�����邩�ۂ��͌l���悩�ƁB
���������Ӑ}�Ȃ�A�����ł��ˁB
���܂��A����̌v�Z���Ƃ������ʔF���͖����̂ł́H
�m���ɗL��܂���B
�����ԍ��F24366877
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
> �m�C�Y�́A�����傫���̎d�オ��ɂ����āA���𑜓x�ɂȂ���ߍׂ����Ȃ�m�C�Y��������A�ƌ����̂����ʔF���������Ǝv���Ă܂��B
���̔F���ō����Ă��܂��B
�J�����̉摜�̕i���̕]���ł͉𑜓x���l�������w�W���g���܂��B
DXOMARK�ł�800����f�ɐ��K�������w�W��p���ăZ���T�[�X�R�A���Z�o���Ă��܂��B
DPREVIEW��Image comparison tool��PRINT(8MP)�������ł��B
���ہA�O�̃X����cbr_600f�����̌��ʂ��摜�Ŏ�����Ă��܂��B
DXOMARK camera sensor testing protocol and scores
https://www.dxomark.com/dxomark-camera-sensor-testing-protocol-and-scores/
> The Sensor Overall Score is normalized for a defined printing scenario of 8 Megapixels printed on a 8×12-inch (20cm x 30cm) size at 300 dpi resolution. Any other normalization, even at a higher resolution, would lead to the same ranking, given that any camera that cannot deliver the chosen resolution is eliminated from the comparison.
�����ԍ��F24366968
![]() 1�_
1�_
����݂�����
�ʂ͏��Ȃ����Ǒe���m�C�Y�ƁA�ʂ͑������Ǎׂ����m�C�Y�����������A���҂��q�ϓI�ɔ�r�]�����邽�߂̌v�Z���͂Ȃ���ˁA�ƌ����Ӗ��ł��B
�����ԍ��F24368410
![]() 0�_
0�_
>���ʂ��t���T�C�Y��1/4
�ʂ�͈͂�1/4�B�u���ʁv���Č����������炵���B
�����ԍ��F24368423
![]() 2�_
2�_
��KazuKat����
�u�����ԍ��F24365104�v�� �X�b�]�R���������� �̂��w�E�ɂ��čl�@�͂��ꂽ�ł��傤���H
�m�C�Y�Ƃ͒��ڊW������܂��A���̎ʐ^�ɂ��čl�@����ۂɏd�v�Ȃ��Ƃł��B
>�B���f�q�P�̂̐��\���r����Ȃ�A�����L�����a�̃����Y�Ŕ�r����K�v������ł��傤�B
�Ȃ��ł����H
>f2.0���m�Ŕ�r���Ă��܂��ƁA��������ʂ�4�{�������A�������قȂ邱�Ƃ���A��������_�ɂȂ�܂��B
�u��������ʁv�Ƃ͉��̂��ƁH�@�N���ǂ��œ�����ʁH
����ƁA���a��������L���͑啶���ŁuF�v�ŁB
���̎B�e�ł́A���̎ʂ�ɂ����āu�L�����a�v�u���a��iF�j�v�̈Ӗ����������ʏ�̎ʐ^�ƕς���Ă��܂��B
����������Ă���ł��傤���H�@�c�_�ɎQ���̊F����͂������ł��傤�H
�����ԍ��F24368543
![]() 2�_
2�_
�u�L�����a�v�Ƃ��i�j�ǂ���DPReview�̉摜�����o�ė��Ȃ�����ǂ��ł��ǂ������
�����ԍ��F24368639
![]() 0�_
0�_
Seagulls����
��MFT���i�ʐ^�������ł��邱�Ƃ͈ȉ����炢�ł��傤�B
���Ȃ�ׂ��V�����N���̃J�����{�f�B��I������B
MFT�̎B���f�q��2016�N����قƂ�ǐi�����Ă܂���B�ł�����AM1�U �ȍ~(M5�V�AM1�V�AM1�])�́A�ǂ���قƂ�Ǔ������Ǝv���܂��B�\�j�[�����\�������ʏƎˌ^�̎B���f�q�Ɋ��҂ł��B
��F�l�͂��ꂼ��̉�p�ň�Ԗ��邢�����Y����������B�i�A�������̏��Ȃ����́j
�����ł��ˁB
���I�o�I�[�o�[�ŎB��i���̎ʂ�ʂ��ς���Ă��܂��j
��ISO�͏�����P�U�O�O���x�ɂ���i����͌���l�ƎB�e���ɂ��ς��܂��j
���i�ʐ^�ɂ����āAISO��SN��ƊW�Ȃ������ł��B����т��Ȃ�����3200��4000�Ȃǂɏグ�Ă���(�ꍇ�ɂ���Ă͂�����)�A�������_��ISO��������������₷���Ǝv���܂��B�ނ���I�����Ԃ�500���[���܂ł�������m�ۂ��邱�Ƃ��̗v�ƍl���܂��B�I�����Ԃ���������m�ۂ��邱�ƂŁA���i�F������т���̂Ȃ�A�B�e�ꏊ�������Ǝv���܂��B
��邱�Ƃ́A�܂�����Ǝv���܂��B
�m�C�Y�͖���ׂɔ������邱�Ƃ���A�ނ���ȒP�ɏ����ł���̂ł́H�Ɗy�ώ����Ă��܂��B(�ƌ������A���������o���Ă܂���)
�ł��̐S�Ȃ��Ƃ́A���Q�̂Ȃ����̂悭������ꏊ�ŎB�e���邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
�ԓ��V�Ɩ]�����g���Ȃ�A�ނ��돬�^�y�ʂ�MFT�̕����t���T�C�Y��舵���Ղ��L���Ƃ��l���Ă��܂��B
�����ԍ��F24368641
![]() 0�_
0�_
�E�E�E(^^;
�c�b�R�~�ӏ����R�������Ėʓ|�ɂȂ����̂ŁA�Ƃ肠�����Êς��܂�(^^;
�����ԍ��F24368662�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
Tranquility����
���u�����ԍ��F24365104�v�� �X�b�]�R���������� �̂��w�E�ɂ��čl�@�͂��ꂽ�ł��傤���H
���m�C�Y�Ƃ͒��ڊW������܂��A���̎ʐ^�ɂ��čl�@����ۂɏd�v�Ȃ��Ƃł��B
�w�E�ł͖������̖`���R�����g�̌J��Ԃ��A�Ǝ~�߂��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă܂���B
�����B���f�q�P�̂̐��\���r����Ȃ�A�����L�����a�̃����Y�Ŕ�r����K�v������ł��傤�B
���Ȃ��ł����H
�������ʂŔ�r���邽�߂ł��B���ʂ��S�{���قȂ�A�B�e���ʂ����R�قȂ�ƍl���Ă��܂��B
���u��������ʁv�Ƃ͉��̂��ƁH�@�N���ǂ��œ�����ʁH
�J�����̑Ε������Y�̑�����A�V�̂���̌��̗ʂ��w���Ă��܂��B�V�̖]�����̑Ε������Y�̃����Y�a���C���[�W���Ă��������B
�����ԍ��F24368683
![]() 2�_
2�_
�� KazuKat����
>���̖`���R�����g�̌J��Ԃ�
�Ⴂ�܂���B
>�������ʂŔ�r���邽�߂ł��B���ʂ��S�{���قȂ�A�B�e���ʂ����R�قȂ�ƍl���Ă��܂��B
���̌��ʂ��ɂ���̂ł����H
>�J�����̑Ε������Y�̑�����A�V�̂���̌��̗ʂ��w���Ă��܂��B
����������Ȃ�A�X�b�]�R���������� �̂��w�E��������x�l���Ă݂Ă��������B
�����Y�ɓ��˂������̌��ʂ��A�ǂ��łǂ��Ȃ��Ă��܂����H
���̑��ƁA�w�i�̖��E�V�̐�E���_�E�_�E�n�㕗�i�̑��ł́A�����Y�ɓ��˂�����ʂ̊ւ������Ⴄ�̂ł����A����������Ă��܂����H
�����肪�Ƃ��A���E����
�M�S�ɃR�����g����Ă��܂����A���l���͂������ł����H
�����ԍ��F24368724
![]() 2�_
2�_
��KazuKat����
���[���Ɖ����珑���n�߂܂��傤���ˁB
��MFT�̎B���f�q��2016�N����قƂ�ǐi�����Ă܂���B
�ȉ��̋L����ǂ�ł݂Ă��������B�l��f�l�ɂ͕�����p���Ȃ��V���ȃA���S���Y�����V�����@��قǓ��ڂ���Ă���\���������̂ł��B
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/1105281.html
����F�l�͂��ꂼ��̉�p�ň�Ԗ��邢�����Y����������B�i�A�������̏��Ȃ����́j
�������ł��ˁB
�Ȃ���������������H�����烌���Y�̗L�����a�����������Ō��ǂ̏��A��Ԗ��邢�����Y���������邵���Ȃ���ł��B
�t���T�C�Y�̐l������F2.8��F4�ł��B���ꍇ������܂����B
�����i�ʐ^�ɂ����āAISO��SN��ƊW�Ȃ������ł��B
�`���Ɠ��ōl���Ă��邾�����ƁA������������܂��A����ISO���グ��Ɛ��i�ʐ^�ł͈�w�摜�͔j�]���܂��B
������т��Ȃ�����3200��4000�Ȃǂɏグ�Ă���(�ꍇ�ɂ���Ă͂�����)�A�������_��ISO��������������₷���Ǝv���܂��B
������ISO��������Ƃ��̂͏��߂ĕ����̂ł悭�킩��܂���B�u������SS������v�Ƃ��u������F�l�ς���v�݂����Ȃ̂ł����H
�X���傳�B����ISO4000�̉摜�̗l�ɈÂ��B����ISO3200�ȏ�̉摜�𖾂邭����ƕK���j�]���܂��B(MFT�̏ꍇ)
�����Ă��̉摜�͒�������O����j�]���Ă��܂����B
�A��������A�R����̘b�Ȃ̂ŁuISO4000��������v�Ǝv���Ă�����ɂ���ȏ�͈Ӗ����Ȃ���������܂���B
���m�C�Y�͖���ׂɔ������邱�Ƃ���A�ނ���ȒP�ɏ����ł���̂ł́H�Ɗy�ώ����Ă��܂��B
�ŋ߂�DXO pureraw�Ƃ��D�G�Ȃ̂��L��݂����ł����A�m�C�Y�����Ƃ͏��F�{�c��f��h��G���Ă���ɉ߂��܂���B
�D�G�ȃm�C�Y�����Ƃ́A�uAi���Y��ɍ�悵�Ă���Ă���v���Ƃ��ƌl�I�ɂ͎v���Ă��܂��B
����͉ʂ����āu�Y��ɎB�����v�ƌ�����̂��H�Ƃ����b�ł��B
���܂�����������b�͌��Ȃ̂ł����A�X���傳��͌o�������Ȃ����钆�ő�������낤�Ƃ��߂��ł��B
�܂���������B��܂��傤�B�܂������������܂��傤�B
�b�͂��ꂩ��ł��B
�����ԍ��F24368790
![]() 2�_
2�_
��KazuKat����
> �ʂ͏��Ȃ����Ǒe���m�C�Y�ƁA�ʂ͑������Ǎׂ����m�C�Y�����������A���҂��q�ϓI�ɔ�r�]�����邽�߂̌v�Z���͂Ȃ���ˁA�ƌ����Ӗ��ł��B
��f���̈Ⴄ�Z���T�[���ʓI�ɔ�r����v�Z���͂���܂��B
2�̃Z���T�[�̉�f�������ꂼ��n1, n2�̂Ƃ��ASNR�̈Ⴂ��
��(n1/n2)
�ŕ\����܂��B
DXOMARK���̕]���T�C�g�ł͂��̎��ʼn�f���𐳋K�����āASNR�̒l���Z�o���Ă��܂��B
�����ԍ��F24368883
![]() 0�_
0�_
Seagulls����
����MFT�̎B���f�q��2016�N����قƂ�ǐi�����Ă܂���B
���ȉ��̋L����ǂ�ł݂Ă��������B�l��f�l�ɂ͕�����p���Ȃ��V���ȃA���S���Y�����V�����@��قǓ��ڂ���Ă���\���������̂ł��B
�㏈���ɐV�����A���S���Y�������ڂ���Ă��ARAW�f�[�^�̃m�C�Y�ɉe�����Ȃ��ł��傤�B
���ہA�摜��r�T�C�g�Ŕ�r���Ă݂�ƕ�����܂��B���ォ��E���Ɍ������ăJ�����͐V�����Ȃ�܂��B�������m�C�Y�͉��P����Ă܂���B
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=oly_em10ii&attr13_1=olympus_em1ii&attr13_2=olympus_em1iii&attr13_3=panasonic_dcgh5m2&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&attr126_0=1&attr126_1=1&attr126_2=1&attr126_3=1&attr171_0=1&attr171_2=1&attr171_3=1&normalization=compare&widget=1&x=0.8739070738091508&y=0.20370175828554332
���L�����a�����������Ō��ǂ̏��A��Ԗ��邢�����Y���������邵���Ȃ�
���̒ʂ�ł��B�Ȃ��A�X���b�h�̎���SN������߂�v���̊m�F�ł��B
������ISO���グ��Ɛ��i�ʐ^�ł͈�w�摜�͔j�]���܂��B
ISO���グ�Ă��A�M���ƃm�C�Y��������ő������Ă���ASN��͓����Ȃ̂ł��B
��������ISO��������Ƃ��̂͏��߂ĕ���
�����\�t�g�̍��ڂ��悭�m�F���Ă��Ă��������B�uISO�����v�Ɓu���邳�����v���ʂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�uISO�����v�̓J�������ł��p�\�R�����ł�RAW������Β����ł���̂ł��B
�����m�C�Y�͖���ׂɔ������邱�Ƃ���A�ނ���ȒP�ɏ����ł���̂ł́H�Ɗy�ώ����Ă��܂��B
���ŋ߂�DXO pureraw�Ƃ��D�G�Ȃ̂��L��݂����ł����A〜
����A�����̎ʐ^���X�^�b�N����i�d�˂�j���ƂŁA���m�C�Y�y���łł���̂ł́H�ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F24369991
![]() 0�_
0�_
Tranquility����
���Ⴂ�܂���B
�������A�������Ƃ��J��Ԃ��Ă܂��B
�ȉ��̂Q�̃R�����g��ǂ��ǂ�Ŕ�r���A�Ӑ}�𗝉����Ă��������B�������Ƃ������Ă܂�����B�Ⴂ������Ǝ咣�����Ȃ�A��̓I�ɂǂ��́A�Ȃɂ��Ⴄ�̂��A������悤�ɃR�����g���������B
���̖`���̃R�����g
���}�C�N�t�H�[�T�[�Y12mm(24mm�����̉�p) f2.0�̗L�����a��6mm�ł��B���L�����a�̃t���T�C�Y24mm�����Y�̖��邳��f4.0�ƂȂ�܂��Bf2.0���m�Ŕ�r���Ă��܂��ƁA��������ʂ�4�{��������
�X�b�]�R����������̃R�����g
���u35mm�Ńt���T�C�Y��50mm/F2.0�v�Ɓu�}�C�N���t�H�[�T�[�Y25mm/F2.0�v�Ƃ���ƁA�����Y�L���n�́u25mm�v�Ɓu12.5mm�v�A�O�҂�4�{�̌�����荞�݂܂��B
�����ԍ��F24370353
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
�O��̃R�����g�ł͏����]�v�Ȃ��Ƃ������߂��܂����B���Ȃ��Ă���܂��B
�܂��A�X���̎�肪�u�m�C�Y�v�Ȃ̂͗������Ă��܂����A�����̓m�C�Y���܂߂��掿�̘b�����Ă���̂�
����ȏ㎩�����R�����g����͎̂~�߂悤�Ǝv���܂��B
�Ō�Ɉ�_�����A�X�^�b�N�Ɋւ��ăm�C�Y�����炷���@�Ƃ��ėL���Ȃ̂͒m��ꂽ���ł���
���ɓV�̎ʐ^(����ʐ^)�Ƃ��Ă͈�ʓI�Ȏ�@�Ȃ̂ł����A���Ɛ��i�ʐ^�Ɏ����Ă͐����ړ�����̂�
������n��E����ʎB��ɋ߂���@���ƌl�I�ɂ͎v���Ă��܂��B(������Ȃ牽�ł��L�肶��Ȃ�����)
�����A����Ȏ�������r�������͂��̂ŁA�������e���邩�ǂ����̐������́A�܂��l�Ɉ˂�܂���ˁE�E�E
�����ԍ��F24370362
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
�܂��A��{�I�ȂƂ��납�玿��B
KazuKat���� �́A�ʂ鐯�̖��邳��_���Ă���̂ł����H
���i�ʐ^�̃m�C�Y�ɂ��Ę_���Ă���̂ł����H
�����ԍ��F24370376
![]() 1�_
1�_
Tranquility����
���ʂ鐯�̖��邳��_���Ă���̂ł����H���i�ʐ^�̃m�C�Y�ɂ��Ę_���Ă���̂ł����H
SN��i�ʂ鐯�̖��邳�Ɛ��i�ʐ^�̃m�C�Y�̔�j�ł��B
�����ԍ��F24370458
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
>�����̎ʐ^���X�^�b�N����i�d�˂�j���ƂŁA���m�C�Y�y���łł���̂ł́H�ƍl���Ă��܂��B
Seagulls���� ���G��Ă����܂����A�u�X�^�b�N�v�Ƃ������Ƃ́A�V�̎ʐ^�̐���B�e�i���i�Ƃ͈Ⴄ�j�ɂ��Ă��l���Ȃ̂ł����H
�����ԍ��F24370474
![]() 1�_
1�_
Seagulls����
���X�^�b�N�Ɋւ��ăm�C�Y�����炷���@�Ƃ��ėL���Ȃ̂͒m��ꂽ���ł����A���Ɛ��i�ʐ^�Ɏ����Ă͐����ړ�����̂ł�����n��E����ʎB��ɋ߂���@���ƌl�I�ɂ͎v���Ă��܂��B
���w�E�̒ʂ�ł��B�٘_����܂���B�����炱�����������������Ă��Ȃ��̂ł��B�������A�m�C�Y������ׂł��邱�Ƃɑ��āA���̓����͋K��������A�n��̌i�F�͒�ʒu�ł��邩��A�s�\�ł͂Ȃ��͂��ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F24370476
![]() 0�_
0�_
���n��̌i�F�͒�ʒu�ł��邩��A�s�\�ł͂Ȃ��͂��ƍl���Ă��܂��B
�g�A���ɑ��E�E�E
���i�Ȃ�E�E�E�ώZ���Ԃɂ���Ắu�_�v��(^^;
���LURL
https://gigazine.net/news/20100823_russia_in_color/
�ɂ́A�S�N�قǑO�̃J���[�ʐ^�t�����ɓ����̃��V�A�鍑�ŎB��ꂽ�J���[�摜(��)������܂����A���ʂ����ׂȓ��̂悤�ɐF���t�����摜������܂��B
���̂�������܂����H
���I���W�i���摜���ǂ�����HP�ɂ���܂��B
�����ԍ��F24370498�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����݂�����
��DXOMARK�ł�800����f�ɐ��K�������w�W��p���ăZ���T�[�X�R�A���Z�o���Ă��܂��B
����f���̈Ⴄ�Z���T�[���ʓI�ɔ�r����v�Z���͂���܂��B2�̃Z���T�[�̉�f�������ꂼ��n1, n2�̂Ƃ��ASNR�̈Ⴂ�́�(n1/n2)
�ƂĂ������[�����w�E���肪�Ƃ��������܂��B
�m���ɁADXOMARK�ł́A��f���̈Ⴂ���痈������A��f���������������ƂŔ�r���Ă��܂��B���������ڍׂɋ����Ă��������܂��ł��傤���H
�J�����P�̃m�C�Y�P�ɑ��āA�W���Ƃ��� ��(800��/�J����1�̉𑜓x) ����Z���Ă���ƌ������Ƃł��傤���H��̓I�Ȏ����������ł��傤���H�T�C�g�����Ă���������܂���B
�����ԍ��F24370508
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
���g�A���ɑ��E�E�E���i�Ȃ�E�E�E�ώZ���Ԃɂ���Ắu�_�v��(^^;
���R�A�����ȃP�[�X������܂��B
�����ԍ��F24370510
![]() 1�_
1�_
����f���̈Ⴄ�Z���T�[���ʓI�ɔ�r����v�Z���͂���܂��B
��
����́A��ʂƂ��������u���Ε]���v�B
(���v�Z�l���o��u�����v�ł͒�ʂƌ����(^^;)
��r�����͓��Łu��ʁv�ƌ�����̂́A��r�Ώۂ̕����Ȃǂ����炩�ȏꍇ�A�Ⴆ�Ύ���Ȃǂ̏o���̕��͒l(���邢�͌v���l)�����炩�ȏꍇ(�Z�x���̐��я����Y�t����Ă���)�Ɍ����邩��(^^;
�����ԍ��F24370552�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����܂���A�����ɔ��Ԃ������邾����������܂��c�B
���}�C�N�t�H�[�T�[�Y12mm(24mm�����̉�p) f2.0�̗L�����a��6mm�ł��B���L�����a�̃t���T�C�Y24mm�����Y�̖��邳��f4.0�ƂȂ�܂��B�܂�B���f�q�P�̂̐��\��r�́Af2.0��f4.0�ł��Ȃ��Ƃł��܂���Bf2.0���m�Ŕ�r���Ă��܂��ƁA��������ʂ�4�{������
�u���{���v�̍l�����������Ă���Ǝv���̂ł����c�B
�w�i�̃{�P���Ƃ��A�����ɂ�����̂̉𑜌��E�̘b������Ȃ�L���a���x�z�I�ł����Ǝv���̂ł����A�߂��ɂ�����̂�傫�Ȃ��̂��ʂ��Ƃ��́A�߂Â�������L���͈͂̌�����荞�ނ��Ƃ��ł���̂ŁA������Ƙb���ς���Ă��܂��B
���̏��A4��A3�̎���u���Ă݂Ă��������BA3�̎��̕�����葽���̌��˂��Ă���̂ł����A�傫�����Ⴄ�����ŖڂɌ����閾�邳�͂ǂ���������ł���ˁB
�����_�ɒ��ڂ���ƁA�m���ɗL���a���傫���������L���͈͂̌����W�߂�̂Ŗ��邭�Ȃ�悤�Ɋ����܂��B�����������L���a�Ȃ�A�œ_�����������������傫���ʂ�(�����������͂��L���͈͂ɕ`�����)�̂ŁA�P�ʖʐϓ�����̌��ʂ͒Ⴍ�Ȃ�܂��B
���ʓI�ɁuF�l�������Ȃ瓯�����邳�v�ɂȂ�܂��B����A���̂悤�ɂ��܂�ɉ����ɂ�����̂́A�œ_���������������Y���g�����Ƃ����1��f���đ傫���Ȃ�܂���B(�������܂ōL����܂�������͕ʂ̘b�Ȃ̂�) �߂����̂�傫�Ȃ��̂́A���{�����オ��Ƒ傫���Ȃ�(�����ڂ�����f�̎��ӂ̉�f�ɍs���Ă��܂�)�̂ł����A���ꂪ�N����Ȃ��̂ŗL���a���傫���قǖ��邭�Ȃ�܂��B
�l�Ԃ̖ڂ������ŁA������x�߂��đ傫�Ȃ��̂́A������傫����ς��Ă��u���邳�͓����v�Ƃ��ĔF���ł���̂ł����A�ǂ�ǂ������Ă����ƍŌ�͑傫���̈Ⴂ�ł͂Ȃ��u���邳�̈Ⴂ�v�Ƃ��Ċ����܂��B
���̐����͒f�ГI�ŕ\�����@���˂����݂ǂ��떞�ڂł����A�b�̗v�f�������Ƃ��ɃN�C�Y�`���ŋC�Â��𑣂��Ƃ����̂͂��܂�ɔ�������ȂƊ����Ă�����ď����Ă݂܂����B
�����ԍ��F24370571
![]() 2�_
2�_
cbr_600f����
�����A���肪�Ƃ��������܂��B
���́A���w�E�̓_�܂��O��ɁA���̃X���b�h�i�ʐ^�A���ɐ��Ɋւ��Đi�߂Ă��܂����B
�F����������Ă���l�q����A�����͑�Ϗ�����܂����B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24371068
![]() 1�_
1�_
���F�������������l�q����A
�@��
���H
�����ԍ��F24371226�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����
cbr_600f����
���́A���w�E�̓_�܂��O��ɁA���̃X���b�h�i�ʐ^�A���ɐ��Ɋւ��Đi�߂Ă��܂����B
�F����ɂ��̑O��i���i���������X���b�h�ł���_�j����₷���`���Ă��炸�A�����̕��������������l�ł��B
�����͑�Ϗ�����܂����B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24371270
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
�������Ă���̂́A�����g������_���Ă���̂��s��������ł��B
�܂��A�����g���炵�č����i�Ƃ������A�����j���Ă���Ǝv���܂��B
>�}�C�N�t�H�[�T�[�Y12mm(24mm�����̉�p) f2.0�̗L�����a��6mm�ł��B���L�����a�̃t���T�C�Y24mm�����Y�̖��邳��f4.0�ƂȂ�܂��Bf2.0���m�Ŕ�r���Ă��܂��ƁA��������ʂ�4�{��������
���́u��������ʁv�����̂��Ƃ����m�ł͂���܂���B
����Ŏ��͉��x���₢�������̂ł����B
�Z���T�[����������ʂ́A�u���̖��邳�i�œ_���̒P�ʖʐς�����̌��ʁj�v�Ɓu�I�����ԁv�̐ςɂȂ�܂��B���ꂪ�m�C�Y�̏o����������Â��܂��B�����Y�̌��a��F�������ōl���Ă��d������܂���B
>>�ʂ鐯�̖��邳��_���Ă���̂ł����H���i�ʐ^�̃m�C�Y�ɂ��Ę_���Ă���̂ł����H
>SN��i�ʂ鐯�̖��邳�Ɛ��i�ʐ^�̃m�C�Y�̔�j�ł��B
����́u�o�b�N�O���E���h�̃m�C�Y�ɖ�����Ȃ��ňÂ����̑������ʂł��邩�ǂ����v�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����A����͒P���Ƀ����Y�̏œ_���������������L���ł��B���́A���a�Ƃ�F���Ƃ��W�Ȃ��̂ł��B
�����Ő��̓����^���ɂ�鑜�̈ړ������ɂȂ��Ă��܂��B
�Â����܂Ńn�b�L���Ǝʂ��o���ɂ́A�œ_�����̒��������Y��p���Ēǔ��B�e�����邱�Ƃł��B
�����ԍ��F24371346
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
> ��̓I�Ȏ����������ł��傤���H�T�C�g�����Ă���������܂���B
�ȑO��DXOMARK��normalization�ɂ��ĉ�������y�[�W���������̂ł������͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�T�����Ƃ���AWeb archive�Ɏc���Ă��܂����B
������ɐ����Ƌ�̓I�Ȏ�������܂��B
Detailed computation of DxOMark Sensor normalization - DxOMark
https://web.archive.org/web/20160720063810/http://www.dxomark.com:80/Reviews/Detailed-computation-of-DxOMark-Sensor-normalization
�����肪�Ƃ��A���E����
> ����́A��ʂƂ��������u���Ε]���v�B
> (���v�Z�l���o��u�����v�ł͒�ʂƌ����(^^;)
�u��ʓI�v�̈Ӗ��A�킩���Ă܂����H
���l�Ƃ��Ĉ����邾���ŁA��ʓI�̗v���͖������Ă��܂��B
��ʓI(�Ă���傤�Ă�)�Ƃ͉��H Weblio����
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9A%E9%87%8F%E7%9A%84
> �����̗l�q�܂��͕ω��Ȃǂ𐔎��ɒ����ĕ��͂��邳�܂��Ӗ������B�`��Ƃ��Ắu�萫�I�v���������A�����̐����ł͕\���Ȃ������ɒ��ڂ��ĕ��͂��邳�܂��Ӗ�����B
�����肪�Ƃ��A���E����
> ��r�����͓��Łu��ʁv�ƌ�����̂́A��r�Ώۂ̕����Ȃǂ����炩�ȏꍇ�A�Ⴆ�Ύ���Ȃǂ̏o���̕��͒l(���邢�͌v���l)�����炩�ȏꍇ(�Z�x���̐��я����Y�t����Ă���)�Ɍ����邩��(^^;
�Ȃ��W�̂Ȃ����w�̘b�������o���̂ł��傤�H���w���͂́u��ʕ��́v�̐����ł����B
���������āu��ʕ��́v�́u��ʁv�Ɂu�I�v���t�����ƌ��t���Ɖ��߂����̂ł��傤���B
�����ł���A�u��ʂ͑���Ő����ʂ����߂邱�Ɓv���u�����ʂ͐�Βl�v���u���Ε]���̓_���v�ƌ�������̂��[���ł��܂��B
��ʕ��� - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E9%87%8F%E5%88%86%E6%9E%90
> ��ʕ��́i�Ă���傤�Ԃ��Aquantitative analysis�j�Ƃ́A�������ɂ��鐬���ʂ����肷�邽�߂Ɏ��{���鉻�w���͂ł���B�������̐��������m�ł���ꍇ�́A��ʕ��͂ɐ旧���Ē萫���͂����{����B
�����ԍ��F24371836
![]() 2�_
2�_
���w�̕��͗�͕����ʂ�y�Ꭶ�z�ł����A
��{�I��(������)��Ηʂ�������ł��B
����f���̈Ⴄ�Z���T�[���ʓI�ɔ�r����v�Z���͂���܂��B
��2�̃Z���T�[�̉�f�������ꂼ��n1, n2�̂Ƃ��ASNR�̈Ⴂ��
����(n1/n2)
��
����́u���Ε]���v�ł�����A
�uA��B���A2Ev�v�����Ƃ� �ǂ��Ƃ��͌�����킯�ł����A��r�ΏۂɌv���W����������A(������)��Ηʂ͕s���ł��B
��ʌ����̗�ɂ���ƁA
�u�̉����オ������������������������Ȃ��̉��v�v�݂����ȃ��m�ŁA
A������B����͑̉��� 2�x�����Ƃ��Ⴂ�Ƃ��A����ȁu���Ε]���v�����o���Ȃ��킯�ŁA����͒�ʂƌ����Β�ʂɂȂ邩���m��܂��A�u�����H�v�����ł�(^^;
����݂����������₷���W�������Śg�������Ǝv���̂ŁA
�E��w���̐�U
�E�E�Ƃł̐��Z�p
�����ꂩ�܂��͗����������Ă���܂��H
�����ԍ��F24372019�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E���� �A����݂�����
�����҂Ƃ��{���ɂ����ď\����������Ă��邱�Ƃ͖����ł��B
�����ł́A���܂茾�t�̒�`�i�s���Ⴂ�j���c�_���ė~�����Ȃ��l���ł��B��U�́A�萫�I�ɑ��Ē�ʓI�A���ΓI�ɑ���ΓI���`��ŗǂ��Ƃ��܂��B
�Ȃ��A���̈Ӑ}������́A�t���T�C�Y�ƃ}�C�N���t�H�T�[�Y�Ƃɂ�����ASN���d�オ��Ɋւ����r�ł��邱�Ƃ���A�@����݂�����@�̎�����DXO�̕]����́A���ΓI�Ȕ�r��]���w���ł���_�łƂĂ������[���Ǝv���܂��B�������ADXO��dpreview������ׂ�ƁADXO�̃m�C�Y�]���w���iSports (Low-Light ISO)�j�ł͐V�����J�����قǗǂ��ɂ��ւ�炸�Adpreview�̔�r�摜������ƌÂ��J�����̕����m�C�X�̏��Ȃ��l�ɂ������܂��B�]���w���͋����[���Ǝv�����A���o�ƈ�v���Ȃ��P�[�X�����肻���ŁA�@���肪�Ƃ��A���E����@�̂��w�E���������l�Ɍ����܂��B
dxomark
https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Olympus-OM-D-E-M10-Mark-II-versus-Olympus-OM-D-E-M1-Mark-II-versus-Panasonic-Lumix-DC-GH5-II___1046_1136_1366
dpreview
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=oly_em10ii&attr13_1=olympus_em1ii&attr13_2=olympus_em1iii&attr13_3=panasonic_dcgh5m2&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&attr126_0=1&attr126_1=1&attr126_2=1&attr126_3=1&attr171_0=1&attr171_2=1&attr171_3=1&normalization=compare&widget=1&x=0.8739070738091508&y=0.20370175828554332
�����ԍ��F24372217
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
�u���ł��J���ł�800����f(����)�v�ɂ��Ă��܂��āA���̃f�����b�g�������A�Ƃ����킯�ł͂���܂���(^^;
�܂��A���L�̂����ꂩ�ɊY������悤�ł���A�܂�����Ȃ�̗����ʒu�������悤�Ƃ͎v���܂����A����ł́u�]����@�̂P�v���炢�Ɏv���Ă���ق���������m��܂����(^^;
�u���ł��J���ł�800����f(����)�v�ɂ���]����@���A
�EJIS�K�i�Ȃ�ISO�K�i�Ȃǂ̍H��(�Y��)�K�i�̂P�ɂȂ��Ă��郌�x���ł���B
�E���̕]����@�ŗL���̕]���������s���Ă��鎎����Ђ⎎���@�ւȂǂ�(�S���E��)���Ȃ��Ƃ��\���Јȏ゠��B
�E���̕]����@���A���Ȃ��Ƃ����Јȏ�̃J�������[�J�[�Ŋ��p����Ă���B
�E���̕]����@���A���Ȃ��Ƃ��\���ӏ��ȏ�̃J�����Z�p�֘A�̌����@��(��w���܂�)�Ŋ��p����Ă���B
�E���̕]����@���A���Ȃ��Ƃ����\�̓���������̎��{��Ȃǂ̉ӏ��ŋL�ڂ���Ă���(���p����Ă���)�B
���B���f�q�֘A�̓����o��́A�S���E�Ő������琔�\�����قǂ̏o�茏��������Ǝv����̂ŁA�����������\���x�̌���ւ̋L�ڂł͓����̔��e�����m��܂���(^^;
��
����Ȋ����ŎY�Ə�̊��p���т�����A�u���ł��J���ł�800����f(����)�v�̍l�������ꉞ�u�Y�Ə�~�w�p��ɂ����Ă��v�������Ă���A�ƌ����邩���m��܂����(^^;
����L�̂悤�ȎY�Ə�~�w�p��̊��p��������� URL����������������ꂽ��A���������肢���܂�(^^)
�����ԍ��F24372272�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������������̎��{��Ȃǂ̉ӏ��ŋL�ڂ���Ă���(���p����Ă���)�B
��
���{��̉ӏ��Ɍ��肵�܂���B
�v�́A����(�܂��͎��p�V�Ă�)������̋L�ڂɂ���āA���p����Ă��鎖�����m�F�ł���悢�A�Ƃ������Ƃł��B
(�������A�����O�Ő��\�ȏ�)
�����ԍ��F24372301�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�܂�SN���Signal��Noise�̑��Δ�ł����A�摜�̉𑜓x���u�{��/�摜�̍����v���Ă������Βl�������肵�܂����c�B
�ʐ^�͐l��������̂Ȃ̂ŁA�掿���l�����Łu��p�Ɗӏ܃T�C�Y�𑵂���v���Ă����̂͂���Ȃ�̑Ó����������āA�t�B�������ォ��قȂ�t�H�[�}�b�g���r����Ƃ��͓�����掆�ɏĂ��āA�ŏI�I�Ȕ{���𑵂��Ă�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
��f���������J�����͂�萸�ׂɎB����ł����A�����I�ɉσs�b�`�̃��j�^�Ƃ����̂͑��݂��Ȃ��̂ŁA�����T�C�Y�Ɉ������Ƃ������@�̎�y�ȑ�֎�i�Ƃ��āA�m�C�Y��_�C�i�~�b�N�����W�𑪂�Ƃ��Ƀ��T�C�Y����Ƃ������@����Ă��ꂽ�����ł��傤�B�ʂ�8M�ɏk������Ȃ��Ă��A���o�̋�Ԏ��g���������l������Ă���ΑS�Ă�1����f�Ɋg�債����Œ�ʉ����Ă�������ł��B
�Ƃ͂�������͂�����x�߂�������傫�������肷����̘̂b�ŁA���ɏ������ĉ������̂������ł����掿�ŎB�肽���Ƃ������E�ɂ����ẮA��p�𑵂��邱�Ƃɂ��܂艿�l���Ȃ��̂ŁA�����Ó��ȕ]�����@���Ƃ����b���ς���Ă�����̂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24372455
![]() 0�_
0�_
2021/10/01 06:26�i1�N�ȏ�O�j
��dpreview�̔�r�摜������ƌÂ��J�����̕����m�C�X�̏��Ȃ��l�ɂ������܂�
�m�C�Y�Ɖ𑜊��̓g���[�h�I�t�Ȃ̂Łc
E-M10�U����ԉ掿���悭�Ȃ��Ǝv������
�����ԍ��F24372544
![]() 0�_
0�_
dpreview �� studio test ������Ƃ��͎B�e�������悭�`�F�b�N���Ȃ��ƃ_���ł��B
M10II��M1II�̔�r�Ō����AJPEG ISO6400�ɂ����SS���O�҂�1/3200�A
��҂�1/2000�ƂȂ��Ă��蓯��ISO�ł��J�����f�t�H���g�̎������x��
�Ⴄ���Ƃ�������܂��B
�����raw�ɂ���Ɨ����Ƃ�1/2500�ɑ����܂��̂ŁAM10II���̓I�[�o�[�I�o�ɁA
M1II���̓A���_�[�I�o�ŎB�e���A�ui�v�A�C�R���̒��߂ɂ���Ƃ���exposure corrected�A
�܂�g�[������Ȃ���܂��B�]���ĈÕ��𑽂��܂ޓ��Y�ӏ��̌����Ƃ��Ă�
M10II�����悭�����ē�����O�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���Ƃ��� Lighting��Low light �ɂ���ƁASS�͂�͂�1/20�ő����Ă���̂ł����A
���Y�ӏ����I�[�o�[�C���Ȃ̂ňقȂ錋�ʂɌ�����͂��ł��B
dpreview��raw�e�X�g�͂����������̂ŁA�ǂ������I�o�C���[�W�����Ă���
�̂��͂悭�悭���ӂ���K�v������܂��B
����DxO�̕��́A�����Signal�Ƃ��ĉ��𑪂��Ă���̂��͖��Ȃ̂ł����A
�����炭�\�����邢�K�ؘI�o�̉����𑪒肵�Ă���͂��ł��B
DxO�͎������x�����߂���ł���(S/N)���v�Z���Ă܂��B
�Ƃ����킯�ł����炭�̓Z���T���AD�����łȂ��\�t�g�E�F�A�̑�����
���Ă��܂��Ă邱�Ƃ��]���ɈႢ���������Ԃ̌����łȂ����Ǝv���܂��B
�������̍��≷�x���A���ɂ������o��v���͍l�����܂����A
�ЂƂ܂��ǂ�������͂̈ꑤ�ʂł͂���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24372652
![]() 1�_
1�_
���Ȃ݂�
DXO�͂���Ȋ����̂悤�ł�
https://www.dxomark.com/dxomark-camera-sensor-testing-protocol-and-scores/
�����ԍ��F24372685�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���肪�Ƃ��A���E����
���u���ł��J���ł�800����f(����)�v�ɂ��Ă��܂��āA���̃f�����b�g�������A�Ƃ����킯�ł͂���܂���
������ł́u�]����@�̂P�v���炢�Ɏv���Ă���ق���������m��܂����(^^;
����Ⴛ���ł��傤�ˁB
���u���ł��J���ł�800����f(����)�v�ɂ���]����@���A
��JIS�K�i�Ȃ�ISO�K�i�Ȃǂ̍H��(�Y��)�K�i�̂P�ɂȂ��Ă��郌�x���ł���B
�����̕]����@�ŗL���̕]���������s���Ă��鎎����Ђ⎎���@�ւȂǂ�(�S���E��)���Ȃ��Ƃ��\���Јȏ゠��B
�ӊO�ƃX�^���_�[�h�Ȃ�ł��ˁB�����肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24373750
![]() 0�_
0�_
cbr_600f����
�������ł����掿�ŎB�肽���Ƃ������E�ɂ����ẮA��p�𑵂��邱�Ƃɂ��܂艿�l���Ȃ��̂ŁA�����Ó��ȕ]�����@���Ƃ����b���ς���Ă�����̂Ǝv���܂��B
���ނ��ł��B�����A�l�ɂ���đÓ��ȕ]���͈قȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24373771
![]() 0�_
0�_
�j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
���m�C�Y�Ɖ𑜊��̓g���[�h�I�t�Ȃ̂Łc
�Ȃ�قǂł�
�����ԍ��F24373773
![]() 0�_
0�_
���ӊO�ƃX�^���_�[�h�Ȃ�ł��ˁB�����肪�Ƃ��������܂����B
�Ⴂ�܂���(^^;
���L�̂����ꂩ�Ɂu�Y������̂ł���v����Ȃ�̗����ʒu��������̂ł́H
�Ƃ�����|�ł�(^^;
�EJIS�K�i�Ȃ�ISO�K�i�Ȃǂ̍H��(�Y��)�K�i�̂P�ɂȂ��Ă��郌�x���ł���B
�E���̕]����@�ŗL���̕]���������s���Ă��鎎����Ђ⎎���@�ւȂǂ�(�S���E��)���Ȃ��Ƃ��\���Јȏ゠��B
�E���̕]����@���A���Ȃ��Ƃ����Јȏ�̃J�������[�J�[�Ŋ��p����Ă���B
�E���̕]����@���A���Ȃ��Ƃ��\���ӏ��ȏ�̃J�����Z�p�֘A�̌����@��(��w���܂�)�Ŋ��p����Ă���B
�E���̕]����@���A���Ȃ��Ƃ����\�̓���������̎��{��u�Ȃǁv�ǂ����̉ӏ��ŋL�ڂ���Ă���(���p����Ă���)�B
��
�J��Ԃ��܂����A
��L�̂����ꂩ�Ɂu�Y������̂ł���v����Ȃ�̗����ʒu��������̂ł́H
�Ƃ�����|�ł�(^^;
������A���������Y�����鎖��������HP�Ȃǂ��u����v�A����URL���������ė~�����Ȃ��A�Ə����Ă���킯�ł�(^^;
�����ԍ��F24373792�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
lssrt����
���ui�v�A�C�R���̒��߂ɂ���Ƃ���exposure corrected�A�܂�g�[������Ȃ���܂��B
�m����exposure corrected�Ƃ̒��߂�����܂��B�ǂ������ɂȂ��Ă܂��ˁI
�m�F�ł����Aexposure corrected�́A��������ISO����(�摜�S�̒���)�̂��Ƃ��w���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�g�[����͕��������̗l�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F24373887
![]() 0�_
0�_
�w���̍����猻���t���V�[�g�ɗ��߂�1��T�C�Y�ɑ�L������Ƃ�����Ă����̂ŁA���I�ɂ͍ŏI�I�Ȏd�オ��T�C�Y���N�_�Ƃ��ăm�C�Y��𑜓x���l����Ƃ������Ƃ͎��ɓ��R�Ŋ�{�I�ȕ]�����@���Ǝv���Ă܂��B(��ɏq�ׂ��悤�Ɍ���쒹���B�邽�߂̒��]���̐��E�͈قȂ�܂�)
�ł��f�W�^������������l�ɂƂ��Ă̓s�N�Z�����{�\���������ȕ]���ł���A�摜�S�̂̊ӏ܃T�C�Y�Ƃ����T�O�͂��܂艏���Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�uAPS-C�ɃN���b�v���Ă��t���T�C�Y�掿�ł��v�Ȃ�Č����l�����Ȃ��Ȃ��ł����ˁB
�܂��A�掿�Ɋւ��Ă͍L�܂��Ă���]�����@�Ƃ����̂́A�������Ă����H�ł���A�u�ȒP������v�Ƃ����̂��ł��傫�ȗ��R���Ǝv���Ă��܂��B���o����(�����ڂ̈��)�Ƙ���������ȒP�ȕ]�����@�ƁA���o�����ɋ߂Â��悤�Ƃ��ĕ��G�����A��Փx���������߂Ɏ嗬�ɂȂ�Ă��Ȃ��]�����@�̂ǂ��炪�D��Ă���̂��c�Ƃ����b�ł͂Ȃ����ƁB
�܂��A�ڋʏĂ��ɉ���������̂��嗬���H���ă}�E���g����荇���̂Ɠ����l�ȁA��ΓI�Ȑ����̂Ȃ��b�ł��ˁB
�����ԍ��F24374070
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
�����ӊO�ƃX�^���_�[�h�Ȃ�ł��ˁB
���Ⴂ�܂���(^^;
�������t�ɑ����Ă��܂��Ă܂����B�X�^���_�[�h�ł͂Ȃ��̂ł��ˁB�������܂����B
�����ԍ��F24374120
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
> ����́u���Ε]���v�ł�����A
> �uA��B���A2Ev�v�����Ƃ� �ǂ��Ƃ��͌�����킯�ł����A��r�ΏۂɌv���W����������A(������)��Ηʂ͕s���ł��B
������@�͒�߂��Ă��܂��B������ɐ���������܂��B
DXOMARK camera sensor testing protocol and scores
https://www.dxomark.com/dxomark-camera-sensor-testing-protocol-and-scores/
����������@�ő��肵�āA���茋�ʂ���f���Ő��K�����܂��B
���K���̉ߒ��ŃZ���T�[�T�C�Y�����f����܂�����A����͐��ʂ̔�r�ɂȂ�܂��B
�V���b�g�G����SNR�̎��̌`���炱��͖��炩�ł��傤
(N�͌��q��)
SNR = N/��N = ��N
����SNR��1��f�̒l�ŁA��f����n��f���Ƃ��܂��Bn0��f�ɐ��K�������
��N * ��(n/n0) = ��(N * n) / ��n0
�����(N * n)�̓Z���T�[�S�̂ɓ��˂������q���ɂȂ�A����́�n0�͒萔�ł��B
�܂�S�̂Ƃ��ăZ���T�[�̖ʐςf������Ηʂɔ�Ⴕ���l�ɂȂ�܂��B
n0���l�ɌŒ肷��ΐ�Ηʂ��r���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�V���b�g�G�� - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%E9%9B%91%E9%9F%B3
> ����݂����������₷���W�������Śg�������Ǝv���̂ŁA
�ł͐��w�ł��肢���܂��B
�����g�̍l���𐔎��ŕ\�����āA�Ȍ��ɐ������ĉ������B
�����ԍ��F24374140
![]() 3�_
3�_
�R���f�W�̋�����f���ɔ����u��f������̗̗��j�v���ӂ݂�ƁA
�]���̕]�����@�ł́AAPS-C�ł��낤���t���T�C�Y�ł��낤���A
������f�����i�W����A�܂��u��f������̗̗��j�͌J��Ԃ����v���Ƃ��y���d�ϊ��̊�{�z�ɂ����Ă��K�R�ł��B
�����ŁA�u���ł��J���ł�800����f(����)�v�B
�u���ł��J���ł�800����f(����)�v�ɂ��Ă��܂��A�u��f������̗̗��j�v�͌��Ȃ��t�����o���܂��B
�u���ł��J���ł�800����f(����)�v�̃����b�g�̂P�Ƃ������邩��(^^;
������1.0�ŁA���Zf=35mm�̉�p�� 800����f(����)�ɋ߂��Ȃ�̂ŁA���̈Ӗ��ł͎^���ł���̂ŁA
�u���ł��J���ł�800����f(����)�v��S�ے肵����͂��܂���B
(�t�ɁA�S�m�肷�邱�Ƃ�����܂���(^^;)
�����ԍ��F24374145�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2021/10/02 05:21�i1�N�ȏ�O�j
���̎���Ȃ�c�Ƃ����Ă��\���N�O����H
1200����f���炢�Ŕ�r����̂��Ó��Ǝv���Ă邩��
���̍Œ��f����������1200����f�Ƃ����������Ă�
�����ԍ��F24374402
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
> exposure corrected�́A��������ISO����(�摜�S�̒���)�̂��Ƃ��w���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
> �g�[����͕��������̗l�Ɏv���܂��B
���̗p��̎g�������̓X���傳�g���Ă錻���\�t�g�̓Ǝ��p�@�ł��B
�����܂ł̂��Ƃ�ő��̕����������Ă����̂͂����������R�ƌ����܂����A
���̂��Ƃ������Ă����̂�����Ə���������܂���(^^;
�����ԍ��F24374419
![]() 0�_
0�_
���ł͐��w�ł��肢���܂��B
�������g�̍l���𐔎��ŕ\�����āA�Ȍ��ɐ������ĉ������B
��
(^^;
���ł͐��w�ł��肢���܂��B
�������g�̍l���𐔎��ŕ\�����āA�Ȍ��ɐ������ĉ������B
��
���Ƃ��āA���́u�����v�𐔎��ŕ\�����Ă��������B
�\�ł����(^^;
�����ԍ��F24374450�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�́A�m�C�Y�ɂ܂݂�Đ��������Ȃ��Ȃ�܂����B�B�B
�����ԍ��F24374836
![]() 4�_
4�_
��lssrt����
> ����DxO�̕��́A�����Signal�Ƃ��ĉ��𑪂��Ă���̂��͖��Ȃ̂ł����A
> �����炭�\�����邢�K�ؘI�o�̉����𑪒肵�Ă���͂��ł��B
> DxO�͎������x�����߂���ł���(S/N)���v�Z���Ă܂��B
��̓I�ɂ͈ȉ��̎菇�ő��肵�Ă���悤�ł��B
DXOMARK��SNR�̑���ł́A�͂��߂ɃZ���T�[���O�a����I���ʂ𑪒肵�܂��B
�����Hsat�Ƃ����Hsat��18%�̘I���ʂ�SNR�̑�������܂��B���ꂪSNR18%�ɂȂ�܂��B
�����Hsat����ISO12232�̌v�Z����ISO�����߂Ă��܂��B
���ꂪMeasured ISO�ɂȂ�܂��B
Measured ISO = 78 / Hsat
ISO speed - DXOMARK
https://www.dxomark.com/glossary/iso-speed/
��Tranquility����
> ���̃X���b�h�́A�m�C�Y�ɂ܂݂�Đ��������Ȃ��Ȃ�܂����B�B�B
���̏������݂������ŃX���̖{��(��)��������ł��܂����悤�ł��B
�\�������܂���B
�����ԍ��F24377706
![]() 3�_
3�_
������݂�����
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
����ISO���O�a���ʂɑ���18%�Ōv�����v�Z�͂��������ʂ肩�Ǝv���܂��B
�������̖O�a����̓I�ɉ����Ƃ����̂��l�ɂ͂��܂����B���Ɋ������Ă܂��āA
https://www.dxomark.com/dxomark-camera-sensor-testing-protocol-and-scores/
We compute the mean gray level and noise values for each patch and for all images
shot at different ISO settings, and finally interpolate these numerical values
for all gray levels to calculate and plot signal-to-noise ratio (SNR) curves,
from which DxO Analyzer extracts the SNR 18%, the dynamic range, and the tonal range.
���̂�����ł��傤���B
�uNoise and dynamic range�v�̃Z�b�g�A�b�v�̃V���b�g��13.3f-stop�Ƃ�1/10000 ratio
�̌����p�b�`���B�e����̂͊ԈႢ�Ȃ������Ȃ̂ł����A�h���b�v����܂�SNR�ő�ӏ���
����̂��ʂ̌���������̂��A���̃f�[�^�����̂܂ܕʃZ�b�g�A�b�v��Measured ISO�ł�
�g���Ă���̂��Ⴄ�̂��A�Ƃ����������肪���܂莩���łȂ��悤�ȋC�����Ă��܂��B
�Z���T�����ƒl�̂Ƃ�������SN�̗D���Ȃ�ς���Ă��܂��C�������ł����A
���̂Ƃ��낪����DxO Analyzer�ɂ܂�����Ă���悤�Ɏv����̂ł��B
�ł����߂�DxO��ǂݒ����������������ɂȂ�܂����B
�R�����g�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24379811
![]() 0�_
0�_
��lssrt����
> �������̖O�a����̓I�ɉ����Ƃ����̂��l�ɂ͂��܂����B���Ɋ������Ă܂��āA
�O�a�Ƃ����̂̓Z���T�[�̏o�͒l������ɒB���邱�Ƃł��B
12bit RAW�ł͉�f�̒l��4095�ɂȂ邱�Ƃł��B
�Z���T�[�̎d�l�ł�Full Well Capacity�ƌĂ�܂��B
��̓I��SNR�̌v�Z���͈ȉ��̃y�[�W�ɂ���܂��B
Noise - DXOMARK
https://www.dxomark.com/glossary/noise/
�����ԍ��F24381204
![]() 1�_
1�_
�Ȃ����^���̖A���ڂ��ڂ������Ă��Ȃ��������Ă�悤����E�E�E�B
���邢�́u�o���ɂ͌����������Ă�v���Ă킩����Ă���H��K���ɕ����Ă�悤�ȁE�E�E�B
�����ԍ��F24381864
![]() 0�_
0�_
������݂�����
> 12bit RAW�ł͉�f�̒l��4095�ɂȂ邱�Ƃł��B
> �Z���T�[�̎d�l�ł�Full Well Capacity�ƌĂ�܂��B
�j�s�ڂƈ�s�ڂ͓����悤�ňقȂ邱�Ƃ������Ă���Ǝv���܂��B
������DxO Analyzer���ǂ̂悤�ɔ��f���Ă��邩�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����ԍ��F24381914
![]() 0�_
0�_
��lssrt����
> ������DxO Analyzer���ǂ̂悤�ɔ��f���Ă��邩�Ƃ������Ƃł��ˁB
DxO Analyzer�̏����ɂ��Ă�DXOMARK�ɂ����킩��Ȃ��Ǝv���܂��B
���ISO12232�ɂ͋K�i�ɕK�v�Ȕ͈͂ŁA�Z���T�[�̖O�a�̑�����@��������Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24383007
![]() 0�_
0�_
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/comic/clinic/1353953.html
���܂Ɍ������Ă�����Ă���WEB����ł��B
�ʔ����e�[�}���Ǝv�����̂ŁA�Љ�܂����B
�V�܃J�����G���������ݔp�����Ă��܂������ł́A
SNS��UP���������L���ɂȂ�鎞��Ȃ̂ł��ˁB
�����ԍ��F24373940�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��҂���̃R�����g��ǂ�łт����肵���̂ł����A
���܂�ɂ����^�b�`���ꂽ�G���×����Ă��܂������߁A
���݂́A�B���ďo���̊G���t�ɕ]������Ă���Ƃ̎��B
�����ԍ��F24373949�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���|�|�[�m�L����
�B���ďo���ƌ����Ă��{���ł͂ł̓A�v�����g�킸�ɃX�}�z�ŎB������i���u�f�������g��Ȃ��Ă����͂���ȂɃL���C�Ȃv�ƌ����Ă邾���ł���ˁB
�X�}�z�ʼnf��Ƃ�CM���B��鎞��ł����A����ȃJ�������A�X�}�z�̃J�����͌��h���悭�B���悤�ɂ��Ă邩��A�m���ɃL���C�Ȍ��h���̂����ʐ^�ł����ǁE�E�E�@�R���f�W���܂��܂�����Ȃ��Ȃ�낤��
�����ԍ��F24374023
![]() 1�_
1�_
2021/10/01 23:03�i1�N�ȏ�O�j
�Ⴓ�ƌ������
���S �Y���ׂ��炸
���Ǝv���܂�
���S���o���Ă��邩�炱��
����܂łƈႤ
�ʐ^���B���̂��Ǝv���܂�
�����ԍ��F24374037�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
������89����
�����A�X�}�z�̊G���͂ǂ��ɂ��D���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��ˁB
�O�[�O��Pixel�́A��r�I�i�`�������Ƃ͕����Ă��܂��B
�����ԍ��F24374045�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���A�[�g�t�H�g�O���t�@�[53����
�������A���i�R���d���̃A�[�g�t�H�g�O���t�@�[����
�Ȃ�ł͂̂��ӌ��ł��ˁB�J�����������n�߂�����
�p�b�V�����́A���������Ȃ����̂ł��B
�����ԍ��F24374050�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���B���ďo���̊G���t�ɕ]������Ă���Ƃ̎��B
�������́u�B���ďo���v���̂����Ɂu�����Ă�v
�ƌ����B
�I�[�f�B�I�ł����������~�j�R���|����̂ɂȂ��ė�����
���烌�R�[�f�B���O���_�Ńi�`�������ȃo�����X�ł͖���
�����a�X�s�[�J�[�ł��Տꊴ���o��l�ɒቹ���u�[�X�g����
�����������B
�����ԍ��F24374133
![]() 6�_
6�_
�������V�傳��
���Ɍ����h���V�����ł��ˁB�Ƃ͌������̂́A
�{���Ƀt���b�g�ȉ����ƒ����Ă��Ă܂�Ȃ��炵���A
�ǂ̃��[�J�[�������̃`���[�j���O�͂��Ă��邻���ł��B�����炭�A�f�W�^���J�����̊G���������Ȃ̂ł��傤�B
�����ԍ��F24374178�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���|�|�[�m�L����
�킩���Ė����ł��A�X�}�z�̃J�����̊G�삪�ł��B
�����ԍ��F24374204
![]() 4�_
4�_
�@���[��A���̖���̎�|�ɌX�̕����͗ǂ����ǑS�̂Ƃ��Ă͔����Ɏ^���ł��Ȃ������B�ȉ��^���ł��Ȃ����������������܂��B
�@�u�ʐ^�ɂ͎Ⴂ�������K�v�v�͗ǂ��Ǝv�����ǁA�N�z�̐l�̊����ŎB�����ʐ^���ǂ���Ȃ��A�Ƃ��v���܂��B�v�͎ʐ^�����Ă���l�̐S�ɓ͂A�ǂ���ł��ǂ��悤�ȁB���^�b�`�]�X�����l�ŁA���^�b�`���������悤���A�����łȂ��Ă��A���ʂƂ��āA�ʐ^�����Ă���l�̐S�ɓ͂������Ηǂ��ʐ^�Ǝv�����ǁB
�@�J�b�R���ď����ƁA�ʐ^�͂����łȂ��ƌ��߂���̂ł͂Ȃ��A�ʐ^���B��l����l�̑��l�����d�ĐF�X�����ėǂ���ˁA�Ǝv����ł��B
�����ԍ��F24374660
![]() 6�_
6�_
���̖���ł́A
���҂���҂̊����Ɏ��i���������̂悤�ȁB
�������������Ă��C�̗͍͑��͂��Ȃ���
�ʐ^�ɂȂ炸�Ӗ����Ȃ��̂ŁA
��Ҍ������낤�����W���������낤���A
�̊��A�`�������W�ł���]�T���m�ۂ��܂��m�ۂ��Ȃ��ƁB
�����̏ꍇ�́A�ݑ�Ζ��ŗ������ؓ��D��B
�����ԍ��F24374784�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�|�W�̍��́c�[���`���Ƃ��̃t�B���^�[���[�N�Ƃ����Đ����Ă����ǁc�B
�X�}�z�ł��I���z�͍I�����B
�y���ނ̂���Ԃ���Ȃ��H
�����ԍ��F24375365�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
����삳��
�m���ɁA�Ⴂ���������������������Ƃ����킯�ł�
����܂���ˁB�ʐ^�����鑤������͐i��ł��܂����B
�����ԍ��F24375776�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��kooth����
���i���n��̃G�l���M�[���Ƃ������A�Ƃ肠��������̃l�^�ɂ͂Ȃ��Ă��܂��ˁB^^;
�����ԍ��F24375780�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����i�e������
�f�W�^���ɂȂ��āA�t�B���^�[�ނ̎��v�͌�����������
����܂���ˁB���̑���A�������c�����i�������Y�A
���������Y�̎��v�������Ă���悤�ł��B
�����ԍ��F24375788�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���|�|�[�m�L����
���͍�҂���̉��L�̃R�����g�ɓ����ł��B
�u�Ⴂ�l�����̊Ԃŗ��s���Ă���i�Ƃ����j���̂ŁA��l�����Ă͂₵�Ă�����̂́A����������������������ł����Ȃ̂Ő^����ɉ������������܂���ˁB�v
�N����Ă���Ƃ��������������������g�ɂ��Ă���̂ŁA����m��Ȃ��E�C�ɂ��Ȃ��Ⴉ�������̂悤�ɐF��Ȃ��Ƃɒ���͂ł��Ȃ��Ȃ�̂����ł��i�j
�����ԍ��F24381402
![]() 0�_
0�_
https://digicame-info.com/2021/09/post-1469.html
�X�}�z�ɋ쒀����A�s�[�N����1/10�ɂ܂�
�o�ב䐔���������钆�A�����̃��[�J�[��
�����̎�i�͂���ƌ�����ł���̂��S�����ł��B
�����ԍ��F24346079�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���̒��ŃL���m����
�ʐ^�̎B�e�����͔���I�ɑ����Ă���
���̉��y�ƊE�ɂ����Ă�
�p�b�P�[�W���f�B�A���̂Ŗ���
�T�u�X�N�ʼn��y��������A�݂̂�����CD���ꖇ�����J�ɒ����Ă�
������y���ɑ����̊y�ȁA�A�[�`�X�g��m�鎖���o����B
�ł��A�����̂̓X�}�z�o�R�B
�A�[�`�X�g�̎����͐̂�CD�S�������范�����Ă�B
�ʐ^������I�ɖ����͑����Ă邪�A�w�ǂ��X�}�z�ł̎B�e�B
�ƌ������X�}�z�ŎB�邩�獟���܂ŎB�e�������������B
�����ԍ��F24346118
![]() 3�_
3�_
�����́A
10�N��1/10�Ȃ�Đ��ދƎ�͂ق��ɂ���܂����ˁB
���ނ�����ɂǂ̂悤�ɐi�ނ̂��������[���ƊE�ł��B
����J�����}����ʐ^�قł͂͂�����̂����@�ނ͕K�v�ł��傤��
�v���������}�j�A�b�N�Ȑl�����̗V�ѓ���ƂȂ������B
5�N������X�}�z�Ńv���i�[T��85mmF1.8�e�C�X�g�̃{�P�I��
�Ȃǂ��ł���悤�ɂȂ�Ɗ��҂��Ă���B
���ꂩ��̓X�}�z�J�����̎��ゾ�B
���������Ă邩��`�����X�������Ă���̂��B
�����Y�����甲���o�����߂ɗǂ��X�}�z�����Ƃ��B
�����ԍ��F24346156
![]() 2�_
2�_
F1.8 �� F1.4
�����ԍ��F24346169
![]() 1�_
1�_
��40�N�O�A�a���^�C�v���C�^�����[�v����p�@�ɋ쒀����A���[�v����PC��WORD�ɋ쒀���ꂽ�̂Ɠ��l�ɁA
�t�B�����J�����̓f�W�J���ɂقڋ쒀����A�f�W�J���̓X�}�z�̑O�ɒ��̑��B
�c���m�ɂ�(��)���z���i�Ƃ��ăf�W�^�������~���[���X������͎c��Ƃ͎v���܂��B
���]����}�N���B�e�A���̑����ꃌ���Y�n����y�ɍ��i�ʂɒ������Ɏ����ł���X�}�z�Ŗ��Ȃ���ŁA
���̓����Ƃ��Ȃ��Ȃ����A�Ɗy�ς��Ă܂��B
�����ԍ��F24346239
![]() 4�_
4�_
�����́B
�u�����v�͓���Ǝv���܂����A��Ƃ��Ďc���Ă����Ǝv���܂��B
�������A�ʐ^���B�鐞����L�����Ƃ��Ă��A���ꂾ���X�}�z�̃J�������i�����Ă���ƁA��p�@�ɂ܂Ŏ���o�������͗����Ă���ł��傤���A��҂̏����������Ȃ��ƁA�J�����Ȃ�ėT���ȔN���̓��y�ł����Ȃ��Ȃ邩���B
�����O�܂ŎB��Ȃ��������L�p�����ځA�w�i�{�P���p�b�ƌ��͕�����Ȃ����x���A�������h���c�ƂȂ�ƁA��p�@�Ȃ�ł͂Ǝv�킹��v�f�͖]���悮�炢�����c��Ȃ��悤�ȁc�B
����ł��A�����Ă��قƂ�ǃX�}�z�ōς܂���l�������ł����c�B
�X�y�b�N�̍������łȂ��āA�X�}�z�Ƃ͕ʂɂ킴�킴���������Ȃ�悤�ȁA�g������C�t�X�^�C�����܂߂���Ă݂����Ȃ��̂�����Ƃ����̂ł����B
�����ԍ��F24346263�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���|�|�[�m�L����
�܂��A�ԂŌ����ƃX�|�[�c�J�[�݂����Ȋ����ōׁX�Ƃł͂��邯��
�c���Ă����Ǝv���܂��ˁB
�X�}�z�̃J�����̋Z�p�Ɋւ��Ă����t��~���[���X����̋Z�p��
�����g���Ă�Ǝv���̂ŋt�ɃX�}�z�����ɂȂ��Ă��܂��ƃX�}�z��
�J�����Z�p�����ł��ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���z�͂ǂ�����ǂ��W�Ŏc���Ă����̂��ǂ���ł����ǂˁB
�����ԍ��F24346277
![]() 2�_
2�_
2021/09/17 02:30�i1�N�ȏ�O�j
�̂��猾���Ă邯��
���̓X�}�z�̏�ʋ@��ƃ��[�J�[�͂�����ƔF�����Ȃ��ƃ_�����Ǝv��
���ʋ@��ŏo���邱�Ƃ͏�ʋ@��Ȃ�ł��ē�����O�ɂ��Ȃ���
���̑Ή������܂�Ɍ����ɂȂ��Ă���
�^�b�`�p�l��������USB���d������
�����ԍ��F24346289�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���|�|�[�m�L����
�X�}�zor���i�����R���f�W�܂ށj�ɓ�ɉ��������ʁA
���r���[�ȃR���f�W�͔���Ȃ��Ȃ�������ǁA���z��
�@��͔����̂Ŕߊς���K�v�͂Ȃ��ł��傤�B
�ɒ[�Șb�A�����ɒ��͂���Ηǂ��̂ł��B
�X�}�[�g�t�H�����[�J�[�͈��w���w��_������
�m��܂��A�J�������[�J�[�͑R����̂ł͂Ȃ��A
�A�g���A�ǂ�ǂ݂��o���čs�����Ƃ�_���͂��B
�����ԍ��F24346290�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
2021/09/17 02:59�i1�N�ȏ�O�j
�����[�v����PC��WORD�ɋ쒀���ꂽ�̂Ɠ��l��
���{����WORD�ȑO�Ɉꑾ�Y�ɋ쒀����Ă邩��
�����Ĉꑾ�Y��WORD�ɋ쒀���ꂽ
�l�����_�������Ƃ��̓��[�v����������
�������ɂ̓}�b�N�������ă��[�N�t���[���߂�ǂ���������
�ߓn�����Ă���ȁi�j
�����ԍ��F24346305
![]() 3�_
3�_
���|�|�[�m�L����
�X�}�z�͊m���ɍ����\�ɂȂ��Ă܂����A���̑��艿�i���ǂ�ǂ�オ���ă��[�U�[����s���̐����o�Ă��܂��B
���\���ꂽiPhone13�͂���10���~�E�E�E
������iPhone13���������Ńo�����X�悭�@�\�������Ă�V�^iPad mini�ɒ��ڂ��W�܂����悤�ł��B
�Ƃ肠����iPhone SE�̂悤�ȓd�b�ASNS�A���[�����ł���悢�����X�}�z���āA�f�W�^���J�����ɖ߂��Ă��郆�[�U�[�����邩������܂���ˁB���������Ӗ��ł́ASONY�̂悤�ɐÎ~�悾���łȂ�Vlog�@�\�����������f�W�J�������A�X�}�z���[�U�[����荞�ނ̂͗ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24346341
![]() 1�_
1�_
50�N�ȏ�O�A�V���̋ǂ�N.C.�ɂ͎ʐA�X�[�p�[�ɑ��郏�[�v���̑��肪�����I�ɓ����Ă����B
�I���\�z��IBM �V�X�e��360���g��ꂽ����B
�X�^�W�I�̕Ћ��Ƀe�X�g�p�炵��Sony�̌̉�TV�J�������������B
�����嗬�̓v�����r�R����16mm�BVTR��Ampex�B
�����I�ŕς�����Ƃ����Ες�������B
�����ԍ��F24346400
![]() 1�_
1�_
���X�}�z�͊m���ɍ����\�ɂȂ��Ă܂����A���̑��艿�i���ǂ�ǂ�オ���ă��[�U�[����s���̐����o�Ă��܂��B
�����\���ꂽiPhone13�͂���10���~�E�E�E
�X�}�z �Ƃ����Ă��A����Android�X�}�z������܂�����AiPhone��I�i�K�Ŏ����I�ɕ��S���z������������܂���(^^;
(���̂Ƃ���A���܂荂�� iPhone�킹�Ȃ��悤�ɂ͂��Ă��܂���)
�������� iPhone�䗦�ُ͈�Ȃ��炢�ł��̂ŁA�ی�҂Ƃ��Ă͕��S���E�E�E(^^;
�E�E�E���̑���A�R���i�Ђ̍�N�̃I�����C�����Ƃ̍ۂɂ́A���܂舵���ɏڂ����Ȃ��Ă��F�l�⓯�����ɋ����Ă�����ĉ��Ƃ��Ȃ����A�Ƃ��������b�g������܂�������(^^;
�����ԍ��F24346463�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����{����WORD�ȑO�Ɉꑾ�Y�ɋ쒀����Ă邩��
�������Ĉꑾ�Y��WORD�ɋ쒀���ꂽ
��������PC�ɂ́u���v��(^^;
�A�E��̌����J������ł́u�ꑾ�Y�v�A���������Ƃł����l��PC�P��̎��ゾ�����̂Łu�҂��c�Ɓv����̂��߂Ƀ��[�v����p�@���w���E�E�E��(^^;
�����ԍ��F24346478�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�X���^�C����O�ꂽ���X�t���Ă��� --- ���ȁB
���X�L���������ŁA
�摜�E�f�����Ƃ��ẮA���w�E�d�C�@��̎��v�͉v�X�����ł��傤����A
�ƊE�Ƃ��Ă͒m���E�Z�p���������邱�Ƃŗ��v�m�ہA�����c���ł��傤�ˁB
���s�J�������̂��̂́A�嗬����O��邩���m��܂��B
�����ԍ��F24346496
![]() 1�_
1�_
�X�}�z�B�e���ߋ��̂��̂ɂȂ邩������܂���ˁA
https://www.businessinsider.jp/post-242045
���ꂪ�i������ΎB�e���Ȃ��Ă��A��ۂɎc��V�[���������ۑ����Ă����悤�ɂȂ邩������܂���A
�u�B��v�Ƃ����s�ׂ̂��߁A�J�������c��\���͂���A�Ǝv�������ł��B
�����ԍ��F24346544
![]() 1�_
1�_
���i�R���ł��ߑa���Ă�͂���������܂�����J�����������̂����͑��v�ł��傤�B
���X���t���Ȃ��ł���X�������\����݂����ł��B
�����ԍ��F24346658
![]() 1�_
1�_
2021/09/17 10:34�i1�N�ȏ�O�j
�������\�t�g�Ƃ�����
���[�^�X123�͏Ռ��������Ȃ�
�p�\�R����������ŏ�������Ă���\�t�g�Ƃ��Ē�Ԓ��̒�Ԃ������̂�
�����ԍ��F24346718�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�}�C�N���v���H�̃��[�h�X�^�[�A���[�h�}�X�^�[�A�Ǘ��H���̏��A�����̃W���X�g�V�X�e���̈ꑾ�Y�A�A���_�X�̃y�[�W���[�J�[�ALotus1/2/3�A�c�F�X�����b�ɂȂ����^��J������ꂽ�\�t�g���ߋ����\�N�Ƀ]���]������܂����ȁB
����قڂق�MS��Word/Excel, Adobe�̃\�t�g�ɏW��܂������A����w�����������x�f�[�^�݊����ێ����ʌ��Ē������ȃT�[�h�p�[�e�B���I�t�B�X�\�t�g������Ȃ�ɑ��݂͂��܂��B
�J�����������悤�Ȃ���Ȃ��ł��傤���ˁB
���a40�N�㍠�܂łȂ�A�y�g�����[���U�u���j�J��烄�V�J���A���\�ƌ�����Ƃ��܂��撣���Ă����悤�ȁB
�܂����̃f�W�J��������[�J�[�������Ȃ����Ƃ��Ă��A�b���͎B�e�����f�[�^�͎c��ł��傤����w�b���x�͈��ׂ��ȁB
���������Ă�MO�f�B�X�N��X�[�p�[�t���b�s�B�݂�����R/W�\�ȑ��u�����ł����悤�ɁA�Đ��\�h���C�o������^�T�|�[�g�ł���\�t�g�������̐�����[���Ǝc��Ƃ͌���Ȃ��̂ŁA�Ǝ��`���̉ߋ���f�[�^�����l�́A�ėp�f�[�^�ւ̃R���o�[�g������Ɍ��������͂��Ƃ��������ǂ��悤�Ɏv���܂��B
�����܂ł��@����Ǝv���ȁ@�K�i�ƃf�[�^
�����ԍ��F24346730
![]() 1�_
1�_
�����[�^�X123
���w���Ƃ��ẮA���w�����̌v�Z�����Ƀ��N�ɂȂ�܂���(^^;
�����ԍ��F24346773�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�f�W�^���̃t�H�[�}�b�g�̎����ɑ��A
���Ȃ�����I�ɐV���i�����Y���o�ꂷ��
���C�JM�}�E���g�̎����͋��ٓI�ł��ˁB
�����ԍ��F24346782�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�����10�N�����Ƃ��̎���͂悩�����A���̃J�����͂����������̂������Ƃ�����ڃX���b�h���ڗ��悤�ɂȂ�B
�@
�����ԍ��F24346789
![]() 1�_
1�_
�X���b�h�^�C�g���Ƃ͊W�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂�����...
> ���[�^�X123
> �y�[�W���[�J�[
�ȂA���������ł��ˁB
�����Ă��������́B���e�[�v�A�p���`�J�[�h�A�J�[�g���b�W�f�B�X�N�A�^�C�v���C�^�[�A�L�����N�^�f�B�X�v���C�A���[�N�X�e�[�V����...
���[�J�[���BDEC�ASun Microsystems...
�����ԍ��F24346796
![]() 1�_
1�_
2021/09/17 12:05�i1�N�ȏ�O�j
Sun Microsystems���Ă��̂܂ɂ������Ȃ��Ă��̂�
�Z�����������w�̌�������
SPARC�ς��[�N�X�e�[�V���������������Ɗ��ł����̂��v���o���i�j
�����ԍ��F24346848
![]() 1�_
1�_
�������Ă��������́B���e�[�v�A�p���`�J�[�h�A�J�[�g���b�W�f�B�X�N�A�^�C�v���C�^�[�A�L�����N�^�f�B�X�v���C�A���[�N�X�e�[�V����...
�����炷��W�r�b�g�̃Q�[���@���n��ȃf�o�C�X�Ō��܂ŗL�l�����ł�������A�債������ł��B
�ŐV�̎������͂�R3�������Ă���A���z�n�̉ʂĂ܂ʼn����ł������ȁc��͂Ȃ����B
���^���̑s��Ȗ���ڕW�ɂ����A���܂��܂ƃR�X�p��o�ώw�W��ǂ������A���C�o���@�Ƃ̋����ɖ������Ă���ƁA
����̑����Ə����Ă�����Ȃ��ł����ˁA�f�W�J�����B
�����x�@�̃}�V��RS�̏���Ȃɏ�������Ă��g�[�V�o��PASOPIA�AOKI��IF800�AFACOM��9450�ANEC��N5200�A�q�^�`�̃x�[�V�b�N�}�X�^�[������Ɉ��ݍ��܂�Ă��������i�͐��m�ꂸ�B
�f�W�J�����R��B���ҕK���̗��͍��������B
�����C�JM�}�E���g�̎����͋��ٓI�ł��ˁB
�x�[�V�b�N�ŃV���v���ȓz�������c��A�ƌ������Ƃł��傤�ȁB
�����ԍ��F24346878
![]() 1�_
1�_
�����肪�Ƃ��A���E����
�m����Android�X�}�z�̓s���L���ł��ˁB�����AAndroid�X�}�z���J�������\���ǂ��͍̂����ł͂Ȃ��ł��傤���B
�l�I�ɂ�Android�X�}�z�͌l���R�k���C�ɂȂ��Ă��܂��B���Ɉ����Ȓ��X�}�z�E�E�E
�����ԍ��F24346884�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
2021/09/17 12:33�i1�N�ȏ�O�j
���x�[�V�b�N�ŃV���v���ȓz�������c��A�ƌ������Ƃł��傤�ȁB
�܂�����قǍ��x�ɐi�������^�������̃����Y�}�E���g�����V�X�e����
���Lj�ԍŏ��ɏo���ł��V���v����T�}�E���g������
���܂��ɋƊE�X�^���_�[�h�Ƃ��Đ����c���Ă��ˁi�j
�����ԍ��F24346891
![]() 1�_
1�_
���x�[�V�b�N�ŃV���v���ȓz�������c��A�ƌ������Ƃł��傤�ȁB
�x�m�t�C�����̃`�F�L�͖����ɔ���Ă�݂����ł��ˁB
�����ԍ��F24346915�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���[�J�[�e�ЂƂ��A�t���T�C�Y�E�~���[���X�̊J���Ŏ��t�Ȃ͕̂�����܂����ǁA���{�������Y��̌^�J�����̐V�@�킪�~�����B
�����~�����J�����̏����B
�E�Y�[���悪�A24mm�`1200mm�ȏ�B
�EEVF�̌��₷�����ASX70 HS�Ɠ����ȏ�B
�E��u������ASX70 HS�Ɠ����ȏ�B
�E�d��700g�ȉ��B
�EAF��SX70 HS��傫�����郌�x���B�ł���Β���AF���~�����B
�u���O�����ɍ쐬�����}�u���{���Y�[���i�]���[1000mm�ȏ�j�����Y��̌^�J�����̔����v��Y�t���܂��B
�i�u���O�̃����N�͍T���܂��B�j
�\�j�[�A�p�i�\�j�b�N�A�x�m�t�C�����́A�������{�������Y��̌^�J�����̊J���͂��Ă��Ȃ��Ǝv����B
�\�����c��̂́A�L���m���A�j�R���BSX80 HS���AP900�̒핪�iP800/P700 �H�j�����҂������B
���ꂪ�ʖڂȂ�A1�^�̃\�j�[G3 X Mark II�i24mm�`600mm�j�ł������B
�����ԍ��F24346968
![]() 2�_
2�_
���������邩��ˁA�A�A�ߊς��Ă�Ȃ�Č����Ȃ��B
�����ԍ��F24347062�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���A�ʐ^�ŗǂ����ʂ��o���ĊF�Ɏ]������ɂ́A���\�̗ǂ����z�ȋ@�ނ�����͂��L��A���A�J���Z�~�r�퓬�@�����ł��n�ɕ����A�x�����炸�����ʂ���ɐl�ŗL��K�v���L��B
����A�J�������[�J�[�͂��������l�X��ɏ��������čs�����낤�B
��1�AR3�AZ9�̓J�������[�J�[�̍s����������\�I��݂����ȃJ�������B
�����ԍ��F24347327�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����Ⴀ�����̃J�������[�J�[���J�����͂����I���R�����Ƃ������������o�����炶�Ⴀ�����P�ނ����ƃc�b�R�܂�邾���Ȃ̂Łc
�ߊς��Ă����͓̂P�ނ������[�J�[�����ł�
�����ԍ��F24347492
![]() 2�_
2�_
 |
 |
 |
|---|---|---|
CIPA���v�y�o�א��z'20�N10��~ '21�N 7�� |
CIPA���v�y�o���z�z'20�N10��~ '21�N 7�� |
CIPA���v���y���ϒP���z'20�N10��~ '21�N 7�� |
��2ndart����
���o��(�S���E���Y�t�摜�̍���)�Ƃ��āA�����Y��̌^(�R���f�W)�́A
�E�u�䐔�v�ŁA�~���[���X�ɓ�������قǂňӊO�Ƒ���(�Y�t�摜��1���ڂ̃O���[����)
�E�u���z�v�ł́A�O���t���̍ŏ��z����(�Y�t�摜��1���ڂ̃O���[����)
�E�E�E���ʂ́A�~���[���X�ƃt���T�C�Y�p�����Y�Ɂu���͂��邵���Ȃ��v�̂��J�������[�J�[�̌��������H
�����ԍ��F24348006�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���|�|�[�m�L����
���~�b�R�����]����l��
���̌����\���āA�����
�L��o���҂̎�i�߂�Ȃ�A�����Ǝv���܂�
2009�����ُ�Ȃ�ł���
D40 vs Kiss �Ƃ�
D700 vs 5D vs ��900�Ƃ�
���������牽���i�����ĉ����ǂ��Ȃ������H
2021���݂ɗ�ÂɐU��ւ���ƁA�����̋@�\��
���\����͗L���Ă��A�����Y�������J������
�@�ނƂ��Ă̖��͂𑝂₵�Ă͂��Ȃ�
�w���w���x����Ȃ����A�H���t���Ȃ�
Nikkor�Ƃ�Canon��L SONY��GM PENTAX��Zuiko
��ďC������Y��Jpeg�𓋍ڂ����X�}�z�Ƃ�
������o����͂��邩�ȁH�Ƃ͎v���܂���
Leica��Carl Zeiss�̎�����l�����
�����܂Ńu�����h���l���L�邩�́c( ߁[�)
�����ԍ��F24348385�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����肪�Ƃ��A���E����
�J�����ƊE�̏��炷��Ύd���Ȃ���������܂��A�X�}�z�ł͑��������ł��ȂƎv����œ_����1000mm�ȏ�̃J�����̎��v�͎c��͂��Ȃ̂ŁA�L���m���A�j�R���ɂ͑����ė~�����ł��B
SX80 HS�͍��N�͖����ł����N�ɂ͏o���ė~�����B
�j�R���͌��s�@��P1000�AP950�̏d�ʋ@�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���̂ŁA700g���x��P610/B700��p�@���o���ė~�����ł��B
�����ԍ��F24348408
![]() 1�_
1�_
2021/09/18 09:06�i1�N�ȏ�O�j
�X�}�z�̋��܌��w�n�]�������Y���ǂ��]������邩���d�v���Ȃ���
�]���͒��]���悾�������R���f�W���v�͖����Ȃ邩�������
�����ԍ��F24348411
![]() 1�_
1�_
����A���{�A���v�X�����̓W�]�䏸������
�ݒu���Ă���100�~�o�ዾ��
Nikon×1 KOWA×2�ŃR�[���̏���( ߄D�)�
�����A��������Ȃ�Nikon�c( ߁[�)
�\�R�ł�KOWA��1��͓d�q�o�ዾ�����
�S�R�y�����Ȃ��c( ; ߄D�)
�����ԍ��F24348442�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́A
�Q�������F�B��͊댯�����A�r�̂قƂ�̖쒹�J�����}���͑�������ł��傤�B
�ł��A�����ł͑傫�Ȉ֎q�̎������݂͂�߂܂��傤�ˁB
�O�r���̂����łɎז��Ȃ�ł�����B
�����ԍ��F24348601
![]() 1�_
1�_
> �O�r���̂����łɎז�
�Ȃ̂ŁASX70 HS �̂悤�Ȏ�u�������̏d��700g���x�̃����Y��̌^���{���Y�[���J�������K�v�Ȃ�ł���ˁB
�����ԍ��F24348670
![]() 1�_
1�_
��2ndart����
�X�}�z�Ɏ�t������A��u�������̍��{���Y�[�������Y���o���Ƃ�����E�E�E
�����ԍ��F24348723�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���K�^�L���o�R���{����
> �X�}�z�Ɏ�t������A��u�������̍��{���Y�[�������Y
�X�}�z�̃Z���T�[�ƃ����Y�ɕt�������Ƃ������Ƃł���ˁB
�X�}�z���ƁA�y���X�R�[�v���g���Ă��œ_����200mm���x�����E���ƁB�y���X�R�[�v���ƃZ���T�[�T�C�Y��1/2�C���`���x�����E���ƁB����ŗႦ�Ό��w1200mm�ɂ��悤�Ƃ����6�{�̃����Y�ł���ˁB
�Z���T�[�T�C�Y�I�ɂ��A�����Y�I�ɂ��掿�ł͂��Ȃ薳��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����ƁA�쒹�B�e�ł�EVF�Ȃǂ̃t�@�C���_�[���Ȃ��ƎB�e��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24348795
![]() 2�_
2�_
> �Z���T�[�T�C�Y�I�ɂ��A�����Y�I�ɂ��掿�ł͂��Ȃ薳����
���݂܂���B�Z���T�[�T�C�Y��1/2�C���`���x�Ȃ�A1/2.3�^�J�����ɔ�ׂđ��F�Ȃ����ƂɂȂ�܂��ˁB
�������A�X�}�z�̌����ŁA�y���X�R�[�v�ŃZ���T�[�T�C�Y��1/2�C���`���āA�ǂ�����ē����Ă���̂��s�v�c�B
�����ԍ��F24348829
![]() 1�_
1�_
���Ȃ݂ɁA���̒m���Ă������ł́A���{���X�}�z�͈ȉ��ł��ˁB
��Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
- 240mm (�y���X�R�[�v) 1/3.24�C���`
��Xiaomi Mi 11 Ultra
- 120mm (�y���X�R�[�v) 1/2.0�C���`
�����ԍ��F24348849
![]() 1�_
1�_
1/2�^ �� �Ίp����=8mm ���u���v��16mm�
1/2.3�^ �� �Ίp������7.7~7.8mm ���u���v��18mm��ŁA�����@�̎d�l��������(^^;
��
���@��� 3%���x�A
�ʐϔ�ł� 6~7%���x�Ȃ̂ŁA�u1/2�^�v�Ɓu1/2.3�^�v�́y�\�L���̃C���p�N�g�_���z���Ǝv���܂�(^^;
�����̐́A�Ίp����=6mm(�{���� 1/2.67�^)�Ȃ̂Ɂu1/3�^�v�Ɖ����ʂ����܂�����Ă��܂��A���Ȃ��Ƃ��ƊE���K�Ƃ��āA(�����炭)
�Ίp����8mm�y�ȏ�z�� 16mm��A
�Ίp����8mm�y�����z�� 18mm��ɂȂ��Ă��܂����悤�Ɏv���܂�(^^;
�����ԍ��F24348879�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�ʐ^����i�d���j�ɂ��Ă���l�ɂƂ���i13���낤��mi11u���낤�����C���@�ނƂ��Ă͑I��Ȃ��B
���ɂ̓I�����s�b�N�̃v���J�����}���S�����X�}�z���\���Ă���p�͑z���ł��܂���B�܂�����͂���Ŏ���Ȃ̂��낤����ǁB
�����ԍ��F24360540�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������A���C���̋@�ނɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤���ǁA���������p�r�Ńv�����g�p���邱�Ƃ�����̂������ł��B
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2109/17/news098_2.html
�ǂ�ȂɊ撣���Ă��A���ł͂Q�`�S���J������������X�}�z�ɂ͓G��Ȃ������͂���i�Ƃ�����菬���������Y�ƃZ���T�[�����l�߂Ȃ��X�}�z�Ŕ@���ɂ��ĉ掿�����コ���邩�Ƃ����i���������̂ł����j�̂ŁA�ʐ^�B�e�ɑ���A�v���[�`�͕ς���Ă���ł��傤�ˁB
�X�}�z�ŒN�ł��ȒP�ɃL���C�Ȏʐ^���B���E�E�E�E�E�ړI�n�ɂ��������悢�����^�]�̃N���}
���Ń_�C�����𑀂��ăV���b�^�[�̗]�C�ɐZ��Ȃ���B��E�E�E�E�E�h���C�r���O���y���߂�MT�̃X�|�[�c��
�����Ă݂R�������炢��������̂ŁA���I�ɂǂ�ǂ��Ă����͎̂d���Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F24360618
![]() 1�_
1�_
2021/09/30 03:01�i1�N�ȏ�O�j
�Z���T�[�T�C�Y���ē���Ȋ��Ⴞ����Ȃ�
1/2�C���`�͂����炭1/2.3�C���`�̂��ƂƂ���
1/2.3�C���`��11mm������Ίp������11mm�Ȃƌ������₷�����ǂ�
�Ƃ����ɐ�ł��Ă���1/2.3�C���`�a�̎B���ǂ̎B���ʂ̃T�C�Y�Ƃ����Ӗ���
11mm���߂���Z���c
�Ă�8mm�サ���Ȃ�
6.2×4.6mm���炢�̃T�C�Y��
���̂�����u���E���ǂ���t���ɂȂ���TV��j�^�Ƃ͈Ⴄ���
�u���E���ǂ��u���E���ǎ��̂̊O���̑Ίp������������17�C���`�Ƃ������Ă��̂�
�摜�͂����肩�Ȃ菬�����������ǂ�
�t���ɂȂ����Ƃ��t�����̂̑Ίp�����ŌĂԂ悤�ɕς��Ă�
�䂦�Ƀu���E���ǂ�17�C���`�����t����17�C���`�̕������Ȃ�ł����i�j
�����ԍ��F24370660
![]() 0�_
0�_
����������ژ^�̔���������悤�Ȃ̂ŁB
���͕x�m��OASYS�̋Ɩ��@���ȁB����FACOM�Œ[������COBOL�v���O���~���O�g��ł����ǁA���[�v���Ŏ������ɂ͐�p�[����OASYS�ŕ��͍���Ă��B���̌�AFM-R��TOWNS����OASYS�{�e�w�V�t�g�L�[�{�[�h�g������B
�ꑾ�Y��NEC��98�ő�q�b�g���܂����ˁB���͎g���ĂȂ��������ǁB
���[�N������ȂƎv���܂���B
�����ԍ��F24370673
![]() 1�_
1�_
������������ژ^�̔���������悤�Ȃ̂ŁB
�����A���������ȁA�����A��������B
���x�m�ʂ�FACOM�Œ[������COBOL�v���O���~���O�g��ł����ǁA
������_���[�������ˁB
���V��FACOM380�H780��������Ȏg���Ă���B
���Ɠ����̃n�C�^�b�N���g���Ă���B
�x�m�ʂ��������G�f�B�^�[�͂܂����������������炢���Ă���B���j���[�������P�����A�Ђ�A���t�@�x�b�g�P���������Ⴂ�B�G�f�B�^�[���u3�v�ɑ��ĕЂ�ue�v�Ăȋ�B���Ƃ͑����R�}���h���Ⴄ���炢������B
���[�v���Ŏ������̓��V��OASYS�ō���Ă��B
FMR�ˁA����������B�����ۊǂ̓t���b�s�[�f�B�X�N�������B���₠�A����������z���}�B
�ꑾ�Y���OASYS�̕����f�R�g���₷��������B���{��ϊ�����Ԃ܂Ƃ�������B
�����ԍ��F24372343�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���|�|�[�m�L����
�������̃��[�J�[�� �����̎�i�͂���ƌ�����ł���̂��S�����ł��B
�����ł�ȁ[�A�ق�ܗ��������v���B
�����ԍ��F24372350�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
https://blog-imgs-130.fc2.com/t/b/s/tbsshi9094/blog_import_5d3f22863f530.jpeg
��
�B���u�ǁv�́u�O�a�v�Ɓu�B���ʁv���悭�킩��摜
��
(��) �ŊO���̍��������́A�O�����x�����ނȂ̂ŁA�����ЂƉ������ɒ��ڂ��Ă�������(^^;
����URL
https://tbsshi9094.blog.fc2.com/blog-entry-704.html
�Ƃ���ŁA
���u���E���ǂ��u���E���ǎ��̂̊O���̑Ίp������������17�C���`�Ƃ������Ă��̂�
���摜�͂����肩�Ȃ菬�����������ǂ�
��
����́A���{�Ȃǂ̍H�ƋK�i�ɂ����̂ŁA
���B�p��(������)�t�B���b�v�X���u���E���ǃe���r�ł́A�t���Ɠ������u�L���ʃT�C�Y�v�ŕ\�����Ă���A�����u�^�v�ł����{���̌^�����P����傫�����̂ł����B
��
�펞�̔�����Ă��炸�ꎞ�������ł������A�����A�u�����^�ł��傫���v�̂Ńr�W���A���@��֘A�̎G���ł�����Ƙb��ɂȂ�A�_�ˎO�{�̃W���[�V���ł���r�I�ɖڗ��悤�ȓW�������Ă��܂����B
(���̂��߂��A���܂��O�\���N�O�̋L���ł��v���o����(^^;)
�����ԍ��F24372399�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���A�ԓ�����
�����[�v���Ŏ������̓��V��OASYS�ō���Ă��B
��FMR�ˁA����������B�����ۊǂ̓t���b�s�[�f�B�X�N�������B���₠�A����������z���}�B
�������E�E�B�킩��l�ɂ͂킩��B�������ł��B
98�̈ꑾ�Y�͎g���ĂȂ��������ǁA�ꑾ�Y�̊����ϊ���ATOK�i�ł��������H�j�͂�����Ƃ��������b�ɂȂ����L���͂���܂��B
�����ԍ��F24372474
![]() 1�_
1�_
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃J�����Ŏʐ^���B���Ă��܂��B����A���܂�ď��߂Đ�����B�e������A�V�̐삪�v���̂ق��ʂ��Ă����̂ŁA�����̎����Ă���J�����̃|�e���V�����Ƀr�b�N�����Ă��܂��B
��r�T�C�g�Ń}�C�N���t�H�[�T�[�Y��35mm�t���T�C�Y�̃e�X�g�B�e������ׂ�ƁA�m�C�Y�͓����x�Ɍ����܂��B
�ǂ����A�u35mm�t���T�C�Y�̓m�C�Y�����Ȃ��v�̕\���͐������Ȃ��l�ł��B�������́A�u�m�C�Y�́A�B���j�~���傫���A�𑜓x���Ⴍ�A�Z�p���V�����قǏ��Ȃ��v���������l�ł��B�i�܂�B���f�q�ɂ�����P�s�N�Z��������̎���ʐς��傫���قǁA�m�C�Y�͏��Ȃ��B�j
���Q�l�@��r�e�X�g
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr144_0=olympus_em1iii&attr144_1=nikon_z7ii&attr144_2=canon_eosr5&attr144_3=sony_a1&attr146_0=200_4&attr146_1=100_6&attr146_2=100_6&attr146_3=100_6&attr177_2=efc&attr177_3=efc&attr404_0=1&attr404_1=1&attr404_2=1&attr404_3=1&normalization=full&widget=675&x=0.8948217967599412&y=0.18564391273750877
![]() 5�_
5�_
��KazuKat����
�f�o�C�X�T�C�Y�i�t���T�C�Y�^APS-C�^MFT�ȂǂȂǁj�ƌ������́A�����͌��d�ϊ����ɂǂꂾ���������ʂ�
�����Ƀf�W�^�����ɒu���������邩�A�ϊ��A���v�̃��j�A���e�B�^�m�C�Y�t�B���^�����O�A�L�����Z�����O���c
�Ȃ�Ă����v�f�̕����d�v���ȁH�Ǝv���Ă܂��B
�ȉ��̂悤�Ȑ����͐����͂�����ł��傤���ˁH
�w���w�I�Ȋ����f�o�C�X������Ƃ��܂��B
�ő�100�܂ł̌��𒉎��ɓd�C�M���Ɋ����܂��B
������10�ȉ��̌��́A���̃f�o�C�X�ł͈Â����邽�߁A���Ƃ��撣���ēd�C�M���Ɋ������Ƃ��Ă��A
�P�`�P�O�̌��͂��������R�`�P�Q���x�Ƀo�����ēd�C�M���ɕϊ�����܂��B
���܁`�ɂP�`�W���x�Ɏ��܂����肵�܂��B
���̎��Ȍ����������Ƃ��ɁA��肭���̋��x���ϊ����ꂸ�ɏo�͂���Ă��܂����A���m�C�Y�ł������肵�܂��B
�����́A�R�̌������������ɁA�ǂ����炩��э���ł����G�l���M�[�Ȃ�{���̓d���G�����f�o�C�X�ɔ�э����
�ϊ���Ƃ��g�`���킹�Ă��܂��R���ᖳ���W�Ƃ�20�Ƃ��Ɍ�ϊ�����A�Ȃ�Ă��Ƃ�����ł��傤�B
�����������������ϊ�����Ȃ������A�m�C�Y���L��ƕ\������Ă܂��x
�c�Ȃ̂Ō���20�`80�Ɏ��܂�悤�Ƀ����Y�߂���Ȃ胍�P�����I�ԁA
����������f�o�C�X�ɑ��Č��ʏ\������������A�܂��͒���ʎ��̕ϊ����x���グ��d�|����c
�i�P��s�N�Z�����ɐ�p�ϊ���H��p�ӂ���̂͐�]�I�ɑ�ς��Ƃ͎v���܂����j
����Łw�m�C�Y�����ɏ��Ȃ��x��Ԃ���������A�̂��X�}�[�g�Ȃ̂��ȁH�H
�v�͌��d�ϊ���H�̐v�Ǝ����̗ǂ��������ŏI�I�ȕi���E���\�����߂Ă��܂��c�ƌ������Ƃ��Ɨ������Ă܂��B
�����ԍ��F24355947
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
�Y�t�摜�́AISO���x�ʂ�
��\:�u�P��f������v�̌��q�̎����
���\:�u�P��f������v�̌��V���b�g�m�C�Y��S/N��
�̒P���v�Z�l�ł��B
(��������P�g��555nm�Ƃ��Čv�Z)
���Q�l�܂�(^^;
�����ԍ��F24355987�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����͂�����
���w�E�̓_�̕ϊ��~�X�ɂ��Ă����ނ����Ǝv���܂��B
���͑S���̑f�l�ł����A���̍l���������`�����܂��B
�����ۂɃe�X�g���邱�ƂŁA�m�C�Y�͂��������Ŕ������Ă��邱�Ƃ��A�m�F�ł��܂��B
�m�C�Y�e�X�g�P
�P�O�O���^���Âȏ�ԁi�����Y�L���b�v���A����Ɏ�����^�I���ȂNJ����āj��ISO�A�����ԁi20�b���j�ŎB�e�B�^���Â̎ʐ^���B���͂��̂Ƃ���A�����_���ȃm�C�Y���B�e�ł��܂��B
�m�C�Y�e�X�g�Q
�����P�O�O���^���Âȏ�ԂŁA�ō����̃V���b�^�[�ŎB�e�B����܂��A�킸���Ȃ��烉���_���ȃm�C�Y���B�e�ł��܂��B
�����̍l����
�m�C�Y�e�X�g�P�ɂ��ẮA�����_���m�C�Y�ł��邱�Ƃ���A���̘R��ł͂Ȃ��B���炭�����������Ńm�C�Y���������Ă���B
�m�C�Y�e�X�g�P�ɂ��ẮA�����_���m�C�Y�ł��邱�Ƃ���A������ȍ~�̉�H�Ńm�C�Y���������Ă���B��H�p�^�[���̔������⓱���̒����i�t���T�C�Y�͕s���H�j��M���e�����Ă���B
��L�m�C�Y�̗ʂ́A����ʂɑS���W�Ȃ����B����āA����ʂ͎���ʐςɔ�Ⴗ��O��A����ʂƃm�C�Y�̔�iSN��j�̓s�N�Z��������̎���ʐςɑ傫���e������B������A���𑜓x�̓m�C�Y��������B
�ȏ�ł��B
�����ԍ��F24356018
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
�����ł��ˁB
SN��̎Z�o�́A�ǂ̂悤�ȍl�����A�Ƃ̗l�Ȏ��ł��傤���H
�v�Z���ʂ́A���ۂ̑��茋�ʂƋߎ�����̂ł��傤���H
�����ԍ��F24356083
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
�m�C�Y�ɂ��Ă̂��l�� �����悻�����Ă���Ǝv���܂�
���Ƃ́A���肪�Ƃ��A���E���� ��������ꂽ�V���b�g�m�C�Y�ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƂƂĂ������[���Ǝv���܂�
���i�̐������ĂČ������q�Ƃ��ĐU�镑�����ۂ�ڂ̓�����ɂ�����A���q���傫�����č��邱�Ƃɑ������邱�Ƃ��ĂȂ��Ȃ������ł�����
�����ԍ��F24356213�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
�ڂ������_�I�Ȏ��͂悭������܂���
�t���T�C�Y�Ƃ̌���I�ȈႢ�́u�m�C�Y�v�Ƃ������u�_�C�i�~�b�N�����W�̈Ⴂ�ɂ�郌�^�b�`�ϐ��̍��v
���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�Y�t�f�[�^�͂قژI���ʂ������Q��ނ̃f�[�^���p�����[�^�Ń��^�b�`�������̂ł��B
�@��̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł����A�����I�ɂ�ISO3200�̉摜�͋��e�ł��܂���B�iISO1600�ŃM���M���j
�t���T�C�Y�͎����Ă��Ȃ��̂ʼn��Ƃ������܂��A�@��ɂ���Ă�ISO6400���x�܂ł͎g����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
���������傢���傢���r���[��N�`�R�~�Ń}�C�N���t�H�[�T�[�Y�@�ł̓V�̐�̉摜���A�b�v���Ă��܂���
�Ӗ������Ƃ��Ắu����ȂɎʂ�܂��v�ł͂Ȃ��u����ŗǂ��Ƃ���l�ɂ͎g�p�ɑς��܂��v�Ƃ��������ł��B
�����ԍ��F24356241
![]() 5�_
5�_
��KazuKat����
�ǂ���(^^)
���V���b�g�m�C�Y�̏ꍇ�AEXCEL(�܂���google�X�v���b�h�V�[�g)�Ȃǂ̊��́A
�u=6*log(�y���q���z^0.5,2)�v�ŒP���v�Z���Ă��܂��B
(�P�ʂ́udB�v����)
���y���q���z^0.5�ɂȂ�Ӗ��́u���V���b�g�m�C�Y S/N�v�Ō������Ă݂Ă�������(^^;
���Ԃł́A���ɔM�m�C�Y�Ȃlj����܂��̂ŁA���R�Ȃ���C�R�[���ł͂���܂��A
�u�B���f�q�ւ̎���ȑO�ɔ������Ă�����V���b�g�m�C�Y�����ł��A���ꂮ�炢�ɂȂ��Ă��܂��v�Ƃ��������ŎƂ��Ă�������悢���Ǝv���܂�(^^;
�����ԍ��F24356259�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
2021/09/22 16:05�i1�N�ȏ�O�j
�ȒP�Ȏ������ł��܂�
�����J������
���S���
���g���~���O�������
�Ŕ�ׂČ��ĉ�����
�����J��������������͓����ł����
�t���ʐς��H
�����ʐς��H
�ǂ��炪�����x�̃m�C�Y�����Ȃ����H
����܂���
�����ԍ��F24356276�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
Seagulls����
����A���܂�ď��߂Đ�����B�e���Ă݂܂����B���́A���i�ʐ^�Ɋւ��ẮA�ʐ^���P���́A���S�҂̒��ł��Ō���̒����S�҂ł��B����ł��AEM5 mark3�ŎB�e����RAW�t�@�C�����p�\�R���Ńm�C�Y������RAW����������A���܂�ď��߂Ắu�P�V���b�g�ځv����Y�t�̎ʐ^����яo���Ă��܂����B�����g�A�I�����p�X�̃J�����̎��|�e���V�����ɋ����A�������܂����B����̌������邮���鈫�������ł̎B�e�ł��B�i���ʁA�����͗ǂ��Ƃ炳��āA�݉c��ו��ɍ��邱�Ƃ͂���܂���ł������ǁB�j
�摜���́A�ڂɂ͌����Ȃ��Õ��ɂ��Ȃ�c���Ă���l�ł��B�u�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̓��^�b�`�ϐ����������v���{���ł��傤���H���̎ʐ^���������A�ϐ��͋��낵�������l�ɂ������܂��B
�����ԍ��F24356287
![]() 6�_
6�_
���肪�Ƃ��A���E����
���肪�Ƃ��������܂��B
�Ȃ�قǁA���d���ʂɂ��m�C�Y���L��̂ł��ˁB�V���b�g�m�C�Y�̃m�C�Y�ʂ́A���̃e�X�g�Ō������P�O�O���^���Âȏ�Ԃł���������m�C�Y�Ɣ�r���āA�����̂ł��傤���H
�����ԍ��F24356298
![]() 0�_
0�_
�A�[�g�t�H�g�O���t�@�[53����
�����������̂��A���Q�l�@��r�e�X�g�@�̃����N��Ǝv���Ă܂��B
�Ⴄ�̂Ȃ�A�M�����G�r�f���X���o���Ă��������B
�����ԍ��F24356303
![]() 9�_
9�_
��KazuKat����
���V���b�g�m�C�Y�́A
���u�B���f�q�ւ̎���ȑO�ɔ������Ă���
��ł�(^^;
�����Y��Ԃ܂ł��A�z�[�X�ɂ��U�����C���[�W���Ă݂Ă��������B
�U���̎嗬�ɑ��āA���͂ɎU��鐅�H�����V���b�g�m�C�Y�Ƃ��Ěg�����肵�܂�(^^;
�����ԍ��F24356335�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�_�C�i�~�b�N�����W�A�Ï��ϐ��Ńt���T�C�Y�̕����D��Ă�Ǝv���܂��B
�m�C�Y�͔�ʑ̂ɂ���ďo�����Ⴄ�B
�J���Z�~���ԂŃI����EM1X�g���Ă�l�����邪�A�܂��Ă���ƒׂ�ĉ𑜂��Ă���Ȃ��ƒQ���Ă����B
�t���T�C�Y���~�����ƌ����Ă����B
�t���T�C�Y���t�H�[�T�[�Y���ǂ��̂Ȃ�A���U���U�d���ăf�J���č��z�ȃt���T�C�Y�Ȃ�ĒN������Ȃ���B
�����ԍ��F24356354�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�m���^�[�{����
�m�C�Y�ʂ��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ɠ����ł���t���T�C�Y�̎B���f�q�̏ꍇ�A�{���ɁA�_�C�i�~�b�N�����W��Ï��ϐ��܂ł����}�C�N���t�H�[�T�[�Y���ǂ��̂ł����ˁH�@�������悭������܂���B�i�m�C�Y�ʂ̏��Ȃ��B���f�q���_�C�i�~�b�N�����W��Ï��ϐ����ǂ��A�ƌ����Ȃ番����܂��B�j
�����ԍ��F24356424
![]() 2�_
2�_
�����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����C���ɗ��p���Ă��܂����A�t���T�C�Y���g���Ă��܂��B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł��\���ɗǂ��ʐ^���B�e�o���܂����A�S������܂���B
����ł��A�t���T�C�Y�Ȃ�ł̗͂ǂ�������܂��B
������p�A����F�l�œ��l�ɍ����\�ȃ����Y�����T�C�Y�A�����i�Ŕ̔�����Ă���̂ł���Ζ��킸�t���T�C�Y�̈���ł����A���ۂɂ͂����ł͖����̂ŁA���̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y��I�����Ă��܂��B
�l����r�������ʂ�M����̂��ǂ��ł����A�ǂ��炪�����ɍ����Ă���̂����f����̂ł���A���ۂɗ����g���Ă݂đ̌����Ƃł��B
�����ԍ��F24356433�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
longing����
���ނ��ł��B�٘_����܂���B
��r�T�C�g�̌��ʂ���A�u�t���t���[���̓m�C�Y�����Ȃ��v�ƌ����Ă��邱�Ƃɑ��āA�f�p�ɋ^��������Ă邾���̂��Ƃł��B
�����ԍ��F24356442
![]() 3�_
3�_
��KazuKat����
�ʃX���ŕ�O�̉摜���q�����Ă��܂��B�}�C�N���t�H�[�T�[�Y��ISO4000�炵������������Ǝv���܂��B
�i���ꂾ�������Ă��t���T�C�Y�Ɠ����Ƃ͌�����ł��j
����Ƃ��܂�m�C�Y������������Ɠh��G���ۂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���̕ӂ�̍�����������A�u���^�b�`�ϐ����L��v�Ƃ����͓̂h��G�݂����ɂ��Ȃ��͈͂Ō����摜�Ɏd�グ�鎖���Ǝv���܂��B
�u���̎ʐ^���������A�ϐ��͋��낵�������l�ɂ������܂��v����ɂ��Ă͋t�̊��z�������܂����B
�������̃J������摜���C�ɓ��鎖�͑�Ȏ����Ǝv���܂���
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̈ꖇ�����Łu�t���T�C�Y�Ɠ����v�Ɣ��f�����̂͂�����ƈႤ���ȂƎv���܂��B
�����ԍ��F24356459
![]() 6�_
6�_
Seagulls����
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̈ꖇ�����Łu�t���T�C�Y�Ɠ����v�ƁA���f���Ă܂��A�f�肵���R�����g����������łȂ��Ǝv���܂��B�����A��r�T�C�g���������A�m�C�Y�͓����x�ł��邩��A�u�t���T�C�Y�̓t�H�[�T�[�Y���m�C�Y�����Ȃ��v�Ƃ����u�P���Ȑ����v�ɁA�^��������Ă��邵�����ł��B
�^��������邱�ƂɁA������肠��̂ł��傤���H
�����ԍ��F24356477
![]() 3�_
3�_
��KazuKat����
�F�l�̈ӌ��Ɏ��X���Ȃ��ƁA�ʃX���ɂȂI
�܂��A�ʃX���D���₯�ǁB
�ǂ������Η������Ă��炦�����A�F�撣���Ă���B
�h���X�}�����A�����������猩�����Ă�B
�����ԍ��F24356515�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 10�_
10�_
��KazuKat����
�Y�t�摜�̕\�́A�B���f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W�̊ւ���������ނ��t�^���ꂽ�����o��~�����o�^�ɂ��āA�ȑO���ׂĔ����������̂ł��B
�v����Ɍ��d�ϊ���́u�d�ׂ̒~�ϗe�ʁv���d�v�ŁA
�E��{�I�ɉ�f�� �ˁu����f�q�v�P��
�E���ݕ����͎��R���݂Ɍ����ł��Ȃ��̂ŁA���ۂɂ͂P��f������̖ʐς��d�v�ɂȂ�
�Ƃ��������ł��B
�����ԍ��F24356602�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
����������������B
��r�摜�ł����A����m43��+4EV�Ńt���T�C�Y��+6EV�Ȃ̂ł��傤���H
Iso���x�̈Ⴂ���l�������ꍇ�A�t���T�C�Y�̕���+5EV�ł͂Ȃ��ł��傤���H
���ɔ�r�摜�̉E���imagesaize��full�Ŕ�r���Ă��܂��B
�ŏI�o�͂����ɂ��邩�ŁA�ݒ��ς���ׂ����Ǝv���܂��B
�Ⴆ�Am43 2000����f�ƃt���T�C�Y2000����f�̔�r�̏ꍇ�ɂ́A�s�N�Z�����{�Ŕ�r����ƁA
�o���オ��̑傫���͓����B
�Ⴂ�́A�B���f�q�̑傫���ɂ��Ⴂ�ɂ��m�C�Y�̍��ɂȂ�܂��B
m43 2000����f�ƃt���T�C�Y8000���摜�̔�r�̏ꍇ�ɂ́A�s�N�Z�����{�ɂ����
�B���f�q�̑傫���͂قړ����Ȃ̂ŁA���������̃m�C�Y�̍��͓����x�A�����Ǐo���オ��̑傫���͈قȂ�
�o���オ��̑傫���ꂷ��ƁA�t���T�C�Y�̕����g�嗦���������Ȃ邽�߃m�C�Y�̑傫�����������Ȃ�̂ŁA
�m�C�Y�����Ȃ�������(�����傫���̃m�C�Y�ł��A�g�嗦�̈Ⴂ�ŁAm43�̕���4�{�傫���Ȃ�)
�m�C�Y�ɂ��ẮA�B���f�q�̑傫���ƁA�Z���T�[�̑傫���ɂ��g�嗦�̈Ⴂ�A�̂Q�̗v�f������ł���̂�
���G���Ǝv���܂��B
�Ȃ̂�6EV��5EV�ɂ��Ċ��o���オ��̑傫���𑵂���ƁA�ȉ��̈Ⴂ�ɂȂ�̂ł͂Ǝv���܂��B
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr144_0=olympus_em1iii&attr144_1=sony_a1&attr144_2=nikon_z7ii&attr144_3=canon_eosr5&attr146_0=200_5&attr146_1=100_6&attr146_2=100_6&attr146_3=100_6&attr177_1=efc&attr177_3=efc&attr404_0=1&normalization=print&widget=327&x=0.902762555363506&y=0.2046732807799696
���Ƃ́A�m�C�Y�͖��邢�Ƃ��ƈÂ��Ƃ���ō�������Ǝv���܂��̂ŁA��r���Ĉ���J�������
�����̋@�ނ��g���Ď����̎B���ʑ̂��B��ꍇ�A���������̂����厖���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24356654
![]() 4�_
4�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
��77(2011�N���AISO4000) |
EOS6D�U(2017�N���t���T�C�Y)��ISO4000��1/2500�b�V���b�^�[ |
EOS6D�U(2017�N���t���T�C�Y)��ISO12800 |
EOS6D�U(2017�N���t���T�C�Y)��ISO51200 |
E-M5MarkIII ��10�N�O��APS-C�̃�77���ق�̂�����ƃm�C�Y���������x��
���܂��Ă�Ǝv���܂��B
�ł����̌o����͍����x�ō����V���b�^�[������o���u�����ɂ߂ăJ������
�������������Ǝv�����E-M5MarkIII��ISO4000�Ƃ�ISO6400�ō����V���b�^�[���Ă݂Ă��炦�܂����H
�ŋ߂̃t���T�C�Y��ISO12800�͓���I�Ɏg�p�\�A�����K��������ĉ𑜗͂������Ă������Ȃ�
ISO51200���炢�܂Ŏg���܂��B
�����ԍ��F24356663
![]() 3�_
3�_
��KazuKat����
> 35mm�t���T�C�Y�̓m�C�Y�����Ȃ��A�͖{���ł����H
�{���ł��B�����ł̃m�C�Y�Ƃ͌��V���b�g�m�C�Y(�V���b�g�G��)�̂��Ƃł��B
���̃m�C�Y�͌��̕����I�������琶������̂ŁA�Z�p�I�Ɏ�菜�����Ƃ͏o���܂���B
> ��r�T�C�g�Ń}�C�N���t�H�[�T�[�Y��35mm�t���T�C�Y�̃e�X�g�B�e������ׂ�ƁA�m�C�Y�͓����x�Ɍ����܂��B
���ꂽ��r�ł͂����Ȃ�܂��B
> ���Q�l�@��r�e�X�g
���̃t���T�C�Y��SS 1/320s�ł����AE-M1����1/160s�ŘI�o��1�i���L���ɂȂ��Ă��܂��B
FULL(���{)�ł̔�r�ł��̂ʼn�f�̃T�C�Y���e�����܂����A��1�Ƃ̔�r�ł̓�1�̕�����f��1.5�{�傫���̂�0.6�i���L���ł��B
����Ă��̔�r�ł͍�������0.4�i��E-M1���L���Ȃ̂ŁAE-M1�̃m�C�Y�����̃t���T�C�Y�Ɠ����x�Ɍ����Ă��s�v�c�ł͂���܂���B
��ʂɃt���T�C�Y���m�C�Y�ŗL���Ƃ����̂́A�Z���T�[�T�C�Y�̈Ⴂ(4�{)���܂߂Ă̘b�ł��B
�V���b�g�G�� - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%E9%9B%91%E9%9F%B3
�����ԍ��F24356710
![]() 5�_
5�_
��KazuKat����
���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̈ꖇ�����Łu�t���T�C�Y�Ɠ����v�ƁA���f���Ă܂��A�f�肵���R�����g����������łȂ��Ǝv���܂��B
�m���ɂ����ł��ˁB�ł��ȉ��̈��p�ɂ��A�V�̐�̎B�e��O��Ƃ��āA�X����́u�t���T�C�Y�ɂ͕����ĂȂ��Ǝv���Ă���v�Ɣ��f����
������(�u�t���T�C�Y�Ɠ����v�Ɣ��f�����̂͂�����ƈႤ���ȂƎv���܂��B)�Ƃ����\���ɂȂ�܂����B
����r�T�C�g�Ń}�C�N���t�H�[�T�[�Y��35mm�t���T�C�Y�̃e�X�g�B�e������ׂ�ƁA�m�C�Y�͓����x�Ɍ����܂��B
�����܂�ď��߂Đ�����B�e������A�V�̐삪�v���̂ق��ʂ��Ă����̂ŁA�����̎����Ă���J�����̃|�e���V�����Ƀr�b�N�����Ă��܂��B
�����i�ʐ^�ŋC�ɂ��ׂ��m�C�Y�ʂ́A�Z���T�[�T�C�Y�̑傫�������ł͐����ł��Ȃ��l�ł��B(�ʃX�����)
���m�C�Y���\�ł�35mm�t���T�C�Y�S���������Ƃ�Ȃ��悤�Ɍ����܂��B�����ł��ˁB(�ʃX�����)
�����āA�ȉ��ɂ���
���u�t���T�C�Y�̓t�H�[�T�[�Y���m�C�Y�����Ȃ��v�Ƃ����u�P���Ȑ����v�ɁA�^��������Ă��邵�����ł��B
���^��������邱�ƂɁA������肠��̂ł��傤���H
���͗L��܂��A�X���𗧂ĂĖ���N������Ă��邱�Ƃɑ���
�X���̎�|�Ɋ�Â��āA�X����̘_���ɋ^�`��悵�Ă��邾���̂��Ƃł��B
�X���傳�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA���̃��X�����Ԏ��̍Ō�ɂ��܂���
�����̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y���[�U�[�ŁA�B�e�҂̋Z�ʎ���ł̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y���t���T�C�Y�ɕ����Ȃ���͎B���Ǝv���Ă��܂��B
�ł��Ï��B�e�͈Ⴂ�܂��B�����܂��B�F��Ȑl�̍��(�B�e�f�[�^)�����Ă����番����܂��B
���܂肱���������Ƃ͌������������̂ł����A�X���傳��̓V�̐�摜�͏��߂ĎB�����ɂ������肢�Ǝv���܂���
�撣��������Y��ɎB��܂����A�㏈���������ď�肢�Ǝv���܂���B(�l�̊��z�ł�)
�����ԍ��F24356819
![]() 8�_
8�_
KazuKat����́A
���B���f�q�ɂ�����P�s�N�Z��������̎���ʐ�
��
�ƍŏ��̃X���ɖ������Ă���̂ɁA
�Ȃ����u�B���ʃT�C�Y�v��ӓ|�ʼn����낤�Ƃ����������̂����ɋC�ɂȂ�܂��B
����́A�u��Ђ̏]�ƈ��������قǁA�Ј���l�̋����������v�Ƃ������炢�Ƀn�i�V�ɂȂ�܂���(^^;
���Ƃ̂����]�ƈ��\���l����K�͂ŁA
�]�ƈ�6600�l�قǂ́u�L�[�G���X�v�̕��ϋ��^����悤�Ȋ�Ƃ͂ǂꂮ�炢����ł��傤���H
��(�R���i�ЈȑO�̃L�[�G���X�ɂ�����)�ߋ��T�N�Ԃ̕��ϋ��^��1930���~�Ƃ�(^^;
�����ԍ��F24356972�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
���x�ǂ����B
�m���ɁB
�s�N�Z�����A�P��f�̖ʐς��傫�����A���łɃA���v�̐��\���ǂ���Ύア�����m�C�Y�̊C����E���܂���ȁB
�^�C�g���w35mm�t���T�C�Y�̓m�C�Y�����Ȃ��A�͖{���ł����H�x�ɑ���
�����w�܂�B���f�q�ɂ�����P�s�N�Z��������̎���ʐς��傫���قǁA�m�C�Y�͏��Ȃ��B�x
�́A�������Ǝv���܂��B�����E�E�E
�^�C�g���Ɂw�t���T�C�Y�x�ƗL��̂ŁA�����ɗU���ăf�o�C�X�T�C�Y�̂��b���ɗU������Ă��܂����A
�ƌ����̂������������܂���B
�K�������́w�f�o�C�X�T�C�Y�i�t���T�C�Y�^APS-C�^MFT�ȂǂȂǁj�ƌ������́x�ƒf�����Ă܂����A
�s�N�Z���P�ʂƌ�����ɂ́A����܂�l�����y��ł܂���ł����B
�m�C�Y���o��v���ƁA�ǁ[�����ǂ����H�����l���Ă܂����B
�b���X���^�C���炸��Ă��܂��̂ōׁX�Ƃ͌����܂��A���̎�̂��b����������錴���̈�Ƃ��āA
���[�U����́A�J�����@�ނɑ���v���d�l���~�X�}�b�`�Ȃ��߁w�`�Ђ̃J�����̓_���ła�Ђ��D�G�x���Ƃ��A
�w�t���T�C�Y�����ゾ���x�Ƃ��ςȕ����Ɍ������̂��Ȃ��A�Ǝv�����肵�܂��B����͒u���Ƃ��܂��傤�B
���݂ɓ��{�̃V���`���[�T���́A�Ј��̂P�V�S�{�A�č��Ɏ����Ă͍ő�T�Q�X�S�{����V��������Ƃ��B
���₩�肽��E�E�E
�����ԍ��F24357009
![]() 0�_
0�_
Seagulls����
�_�_������Ă��܂����悤�ł��B
1.�悸�́A�ǂ���̕\�������K�ł��傤���H
�A.�u35mm�t���T�C�Y�́A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y���m�C�Y�����Ȃ��v
�C.�u�m�C�Y�́A�B���f�q���傫���A�𑜓x���Ⴍ�A�Z�p���V�����قǏ��Ȃ��v�i�܂�B���f�q�ɂ�����P�s�N�Z��������̎���ʐς��傫���قǁA�m�C�Y�͏��Ȃ��B�P�s�N�Z��������̎���ʐς��傫���Ȃ�A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y�̕����t���T�C�Y���m�C�Y�̏��Ȃ����Ƃ����蓾��B)
���́A�����N��̉摜��r����A�A.�ł͂Ȃ����ƍl���܂����B�f���ł��܂��B
2.���̏�ŁA���i�ʐ^�ȂǂɕK�v�ȈÏ��ϐ��́A�������ł��傤���H
�E.�t���T�C�Y�̕����A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y���D��Ă�
�G.�P�s�N�Z��������̎���ʐς��傫�������D��Ă���(�P�s�N�Z��������̎���ʐς��傫���Ȃ�A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y�̕����D��邱�Ƃ����蓾��B)
������Ɋւ��Ď��́A���̏��������Ă��Ȃ��ɂ̂ŁA������܂���B�������A�C�ƃE�̑g�ݍ��킹�́A��ѐ����������Ƃ���A�������Â炢�l�Ɏv���܂��B
Seagulls����̂��l������̌��́A�ǂ̗l�ȑg�ݍ��킹�ł��傤���H
�����ԍ��F24357011
![]() 0�_
0�_
������͂�����
�Ȃ�ق�(^^)
��
���^�C�g���Ɂw�t���T�C�Y�x�ƗL��̂ŁA�����ɗU���ăf�o�C�X�T�C�Y�̂��b���ɗU������Ă��܂����A
���ƌ����̂������������܂���B
�����ԍ��F24357021�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̈ꖇ�����Łu�t���T�C�Y�Ɠ����v�ƁA���f���Ă܂��A
�f�肵���R�����g����������łȂ��Ǝv���܂�
�ł��A���i���r���[�ł�
�u��Ԃ���ʂ̏��Ȃ��ɂ����Ă�35mm�ɔ�掿�̗ǂ����Ƃ����͂ł��B�v
���ď����Ă邵�Ȃ��B
�������������̂��A���Q�l�@��r�e�X�g�@�̃����N��Ǝv���Ă܂��B
�Ⴄ�̂Ȃ�A�M�����G�r�f���X���o���Ă��������B
���l�ɃG�r�f���X�����߂�̂Ȃ�A���g���t���T�C�Y�ƃ}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����B�e������
�B�����摜����ׂ����Ǝv���B
�����t���T�C�Y���Ƃ��Ɋ�ɂ����̂͂����܂ł������ŎB���������B��̔�r�B
�N���}�������Ɂu�����ԎG���̃e�X�g�̌��ʂ��ǂ������v���ė��R�Ŏ���������ɔ����l�͋��Ȃ��̂Ɠ���
�����ԍ��F24357026
![]() 3�_
3�_
���肪�Ƃ��A���E����
���肪�Ƃ��������܂��B
��͂�A�P��f������̖ʐς��d�v�ɂȂ�A�̂ł��ˁB�ƂĂ�������₷���l�������Ǝv���܂��B
�ƌ������Ƃ́A�P��f������̖ʐς��傫�ȃ}�C�N���t�H�[�T�[�Y���������Ƃ�����A�P��f������̖ʐς������ȃt���T�C�Y���A�m�C�Y�Ȃǂ��ǂ��ꍇ�����蓾��Ƃ��������ł�낵���ł��傤���H
�m�C�Y�ɂ��ẮA���̎����A�����N��̉摜��r����������܂����B
�������A��������̘_�_�Ƃ��ďオ���Ă��邱�Ƃ́A�_�C�i�~�b�N�����W��Ï��ϐ��ł��B�_�C�i�~�b�N�����W��Ï��ϐ����A�P��f������̖ʐς��d�v�ɂȂ�̂ł��傤���H�܂�A�P��f������̖ʐς������ł́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̕����t���T�C�Y���A�_�C�i�~�b�N�����W��Ï��ϐ����D���ꍇ�����蓾��̂ł��傤���H����Ƃ��A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A�t���T�C�Y�̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y���D��Ă���ƌ������ėǂ��̂ł��傤���H
�����ԍ��F24357047
![]() 2�_
2�_
���P�s�N�Z��������̎���ʐς��傫���Ȃ�A�}�C�N�t�H�[�T�[�Y�̕����t���T�C�Y���m�C�Y�̏��Ȃ����Ƃ����蓾��B
�����u�����v�ł͂����ł����A4/3�^�ɑ��ăt���T�C�Y�͎B���ʂłS�{�قLjႢ�܂��B
4/3�^�ŗL��2000����f�Ƃ���u����̎���f�q�T�C�Y�v�Ńt���T�C�Y�Ȃ�ΗL��8000����f���炢�ɂȂ�킯�ł��B
�y����f�q�̕����I�T�C�Y�����b�g�z�������Ă��� 4/3�^�̗L��2000����f���L���ɂȂ蓾��̂́A
�t���T�C�Y�ŏ��Ȃ��Ƃ��P����f�A(�Z�p�i���Ȃ�)�ꍇ�ɂ���Ă͂P���T�疜��f�ȏ�ɂȂ邩���m��܂���(^^;
��7R4�ŗL����6100���ł�����A���̂Ƃ���(���Ȃ��Ƃ���ʌ����ł�)4/3�^�̗L��2000����f�������u�P��f������̃T�C�Y�v�������ȃt���n�C�r�W�����@�͑��݂��Ă��Ȃ��悤�ȁH
�����ԍ��F24357073�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�˂��܂��̂Q�O�P�R����
����r�摜�ł����A����m43��+4EV�Ńt���T�C�Y��+6EV�Ȃ̂ł��傤���H
��Iso���x�̈Ⴂ���l�������ꍇ�A�t���T�C�Y�̕���+5EV�ł͂Ȃ��ł��傤���H
�u���ʁv�𑵂��邽�߁A�I�o�𑵂��܂����B
�t���T�C�Y�Fiso100�A�V���b�^�[�X�s�[�h1/320
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Fiso200�A�V���b�^�[�X�s�[�h1/160�@���}�C�N���t�H�[�T�[�Y��iso100���Ȃ�
���m�C�Y�̑傫���͎B���f�q�̑傫���̍��ɂȂ�
�Ȃ�قǁI�@���ꂪ�A�����ł���A���𑜓x�̕����m�C�Y���������Ȃ�̂ŁA�d�オ����T�C�Y�Ŕ�r�����
���𑜓x�̕����m�C�Y���ڗ����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�ł������Ƃ��ẮA�m�C�Y���W������Ζڗ��l�ɂ��v���܂��B
�����N��̔�r�摜�́A�t���T�C�Y�̕������𑜓x�̑f�q���g���Ă��钆�ŁA�d�オ�肪�قړ����傫���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A
���̗������ƁA�t���T�C�Y�̕������ۂ͂���Ƀm�C�Y���������ƂɂȂ�܂��B�i���̂܂Ƃ߂ɊԈႢ��������w�E�����肢���܂��B�j
�������A��r�́A�����ڂ��厖�ł��邱�Ƃ���A�d�オ����T�C�Y�ɂ��邱�Ƃ��ǂ��ƍl���܂��B�i�܂��r�T�C�g�̃T�C�Y�̂܂܂ŗǂ��j
�����Ƃ́A�m�C�Y�͖��邢�Ƃ��ƈÂ��Ƃ���ō�������Ǝv���܂��̂ŁA��r���Ĉ���J�������
�������̋@�ނ��g���Ď����̎B���ʑ̂��B��ꍇ�A���������̂����厖���Ǝv���܂��B
���ނ��Ȃ��w�E�ł��B���̃X���b�h�͎��̍D��S���炭��f�p�ȋ^��ɂ����̂ł��B
�����������N��́A�t�H�[�T�[�Y�����Â����Ă���A�I�o�������Ă��Ȃ����Ƃ���A��r�Ƃ��ĕs�K���Ǝv���܂��B
�i��肪������w�E�����肢���܂��j
�����ԍ��F24357104
![]() 1�_
1�_
EOS 6D�U���[�U�[����
�\����܂���B���̉����Ƙ_�_������������ł̂��w�E�Ȃ̂��A�܂��A��������Ă��Ȃ��܂܂ł̂��w�E�Ȃ̂��A���ʂ���͓ǂݎ��Ȃ��̂ŁA��U�A�X���[�������܂��B�����܂���A���ӂ͂���܂���B
�����ԍ��F24357108
![]() 1�_
1�_
�����V�傳��
�_�_���g�U����̂ŁA��U�A�X���[���܂��B
�����ԍ��F24357133
![]() 6�_
6�_
���_�C�i�~�b�N�����W��Ï��ϐ��ł��B
���_�C�i�~�b�N�����W��Ï��ϐ����A�P��f������̖ʐς��d�v�ɂȂ�̂ł��傤���H
�_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��ẮA�������甲����������������(^^;
�܂��A�Ï��ϐ��Ƃ́A��̓I�ɉ��������Ă��܂����H
��́A���x�ʂ̌��q���Ɓu��p���x�v����сu�ő労�x�v�̂Ƃ���̖ڈq���g�ɂȂ�܂��H
���܂�A�P��f������̖ʐς������ł́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̕����t���T�C�Y���A�_�C�i�~�b�N�����W��Ï��ϐ����D���ꍇ�����蓾��̂ł��傤���H
(��̃��X�̒ʂ�)
�����̏�ł͗L�蓾�܂����A4/3�^�ŗL��2000����f�����X�^���_�[�h�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂�����A���Ԃ͓���ł���(^^;
������Ƃ��A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A�t���T�C�Y�̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y���D��Ă���ƌ������ėǂ��̂ł��傤���H
����ł́y���x���z�͈̔͂��傫���̂ł́H
�ő労�x��r�ł́A���q���̌v�Z�\�̒ʂ�(������)�t���T�C�Y�@�ɑ卷��t�����Ă���̂������ł����A
�O������Ƃ��āy���̌���ISO���x����p���Ȃ��̂ł���z�A�B�e���ɂ����Ă͎B�e�̎d���ŁA
�J�����{�̂ɂ����Ă�(���@�_�Ƃ��Ă�)�V�[���ʂ̃m�C�Y���_�N�V�����������I�ɂ���Ƃ�����A��{���\�����m�C�Y���_�N�V�����Ɋւ��V�[������A���S���Y���̗D��̂ق����e�����傫�������m��܂���B
�Ȋw�I�ɔ�r����̂ł���A
��r�ɂ�������������̓���͓��R�Ƃ��āA
���������͈̔͂��d�v�ł��B
�Ⴆ�A��p�̍Œኴ�x��r�ł̃m�C�Y�̗D��́A���{�I�ȃm�C�Y�̗D��Ƃ͌����������ł��傤�B
�ɒ[�ȗ�Ƃ��āE�E�E�m�C�Y���_�N�V�����ɔ����K���̗ƁA�����ɂ�����̑f�l��_�����ߏ�ȃm�C�Y���_�N�V�����́A���[�J�[�̍������͈̗̔͂v�����傫���A�Z�p�͂Ƃ͏����Ⴄ�킯�ł��B
�������A�����x�ɂȂ��Ă����ƁA�܂��Ⴄ�X���������Ă��邩���m��܂���B
���v�I�ɔ��f����Ƃ��āA
ISO���x�����ł��Œᐔ�����A
�B�e���̖��邳�̑g�ݍ��킹�ł��Œᐔ�����A
�����Đ��@�킩��\���@��̑g�ݍ��킹�B
���ɁA7*7*15�̑g�ݍ��킹�ł� 700���܂��B
�܂��y�Č����z���l������A�Œ�ł�2000�ȏ�ɂȂ�킯�ł��B
�u������v�悤�Ȃ��Ƃ͐������x�ł́A(�Ȋw�̎����Ƃ��Ă�)�s�K���Ǝv���܂�(^^;
�����ԍ��F24357143�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
1.�ɂ���
�ŏ��ɂ������܂������A�F����̗l�ɍׂ������͂킩��܂��A���w�ɂ͂��܂苻��������܂���B
�������l�X�ȏꏊ�E�����ŎB�����ʐ^�ƁA�摜���e�T�C�g�Ō������̐l�̎ʐ^(�@��E�����Y�EExif�f�[�^)�����f�ޗ��̑S�Ăł��B
����ɂ��Ă͖]�܂�Ă���悤�ȓ������ł����\����Ȃ��ł��B
���̏�ŁA2.�ɂ���
���i�ʐ^�ɂ��Ă̓t���T�C�Y���D��Ă���͉̂�����������炩�ł��B
��������B���āA�����������ŗ�O�͂قڗL��܂���BEOS R5 �N���X�̍���f�@�ł������ł��B
�����t���T�C�Y�@�̎ʐ^�ʼn掿�ʂʼn���Ȑ��i�ʐ^������Ȃ�A����͎B��肪����Ȃ����ł��B
���܂ɒ����肢�ʐ^�Ő���E�n��ʎB�荇���̐l�����܂����A�������Ă���Α�̂킩��܂��B
�����ԍ��F24357149
![]() 2�_
2�_
���肪�Ƃ��A���E����
���B���f�q�̖ʐϔ�͂S�{������A���̂Ƃ�����݂��Ȃ��B
�m���ɁI
1200����f�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ȃ�A5000����f�̃t���T�C�Y�Ɠ��������A�ƌ������Ƃ���ł��ˁB
��������m�C�Y���C�ɂ���悤�ȔM�S�ȃJ�����}���́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł����Ă�2000����f�ȏ��
���߂Ă��邱�Ƃ���A�u1�s�N�Z���̖ʐρv�Řb�����邱�Ǝ��̂����肭�ǂ��ł��ˁB
ASP-C�Ƃ̔�r�ɂ����Ắu1�s�N�Z���̖ʐρv�Ō��ׂ��p�^�[�������邩������܂��A����͕ʂ̘b�B
�܂�A�u�t���T�C�Y�̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y���m�C�Y�͒Ⴂ�v�́A���̉������������Ƃ��Ă��A
���ԂƂ��Ă͐������ƌ����܂��ˁB
���肪�Ƃ��������܂����B
�������A�����Ȃ�ƁA��r��ʂ��C�ɂȂ�܂��B������́A���w�E�������ʂ̕���
�����ԍ��F24357151
![]() 1�_
1�_
���肪�Ƃ��A���E����
�����v�I�ɔ��f����Ƃ��āA7*7*15�̑g�ݍ��킹�ł� 700���܂��B
���܂��y�Č����z���l������A�Œ�ł�2000�ȏ�ɂȂ�킯�ł��B
���u������v�悤�Ȃ��Ƃ͐������x�ł́A(�Ȋw�̎����Ƃ��Ă�)�s�K���Ǝv���܂�(^^;
���ނ��ł��B
�_���I�ɕ�����₷�������A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24357154
![]() 0�_
0�_
Seagulls����
�����i�ʐ^�ɂ��Ă̓t���T�C�Y���D��Ă���͉̂�����������炩�ł��B
����ς肻���ł����B�����łȂ��ƁA�F������قǎw�E���锤���Ȃ��ł��ˁB
���X�Ƃ��肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24357158
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
���������ʂ�A1��f���t���T�C�Y���傫���t�H�[�T�[�Y������A�u�s�N�Z�����{�Ō����ꍇ�̃m�C�Y�v�͒Ⴍ�Ȃ�܂��ˁB����͐������Ǝv���܂��B
���̕���1��f�����łȂ��B���f�q�S�̘̂b�������̂́A�S��ʂŕ\�������ꍇ��A��������ꍇ�Ɍ��������ς�邩��Ȃ�ł��B
�Y�t�̉摜�̍����́A�����u���v�Ƃ��������̉摜�Ƀm�C�Y��t���������̂ł��B
�E���́A�c��2�{�T�C�Y�̑傫�ȉ摜�ɓ��������̃m�C�Y��t�����āA�c��1/2�ɏk���������̂ł��B
�����m�C�Y�ʂ�������A��f�������������k���ɔ����ĕ��ω�����ăm�C�Y������̂ł��B
�v�����g����ꍇ�̓m�C�Y�̗����ׂ����Ȃ��Č����ɂ����Ȃ�����A�ׂ�ď�����̂ŁA��͂�m�C�Y������܂��B
�Z���T�[�T�C�Y���傫�������m�C�Y�����Ȃ��Ƃ��_�C�i�~�b�N�����W���L���Ƃ������b�́A1��f�T�C�Y�ƃs�N�Z�����{�ӏ܂����ł̔�r�ł͂Ȃ��A�S�̕\�����������ꍇ�̂��Ƃ��܂ޕ\���Ȃ�ł��B
�����ԍ��F24357392
![]() 3�_
3�_
��KazuKat����
�E�P��f�P��(����f�q�P��)��
�E�B���f�q�Ƃ��Ă̑���
�́A���ʍ�������ΕʂɂȂ邱�Ƃ����邾���ŁA
�ꏏ�N�^�ɂ���ƒʗp���Ȃ��ꍇ������킯�ł�(^^;
�Ȃ��A�g���~���O�Ȃǂ��l�����āu���{�]���v���d������ꍇ�́A�P��f�P��(����f�q�P��)�̕]�����d�v�ɂȂ��Ă��܂����A
����f �� ������f���������W�𑜓x����ƁA�R���f�W�̂悤�Ɂu��f���̉𑜂Ƃ͒������v�悤�ɂȂ��Ă����܂��B
���J���[�B���f�q�̃x�C���[�z�ɂ�鐧���O��Ƃ��Ă�
�����i����EF�l�̖�������܂��B4/3�^�̗L��2000����f���� F9.9�ł����B
�����ԍ��F24357413�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
���u���ʁv�𑵂��邽�߁A�I�o�𑵂��܂����B
���t���T�C�Y�Fiso100�A�V���b�^�[�X�s�[�h1/320
���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Fiso200�A�V���b�^�[�X�s�[�h1/160�@���}�C�N���t�H�[�T�[�Y��iso100���Ȃ�
�����F���Ɍ�肪����Ǝv���܂��B
�t���T�C�Y�@iso100 1/320 +6EV
M43. Isi200 1/160 +4EV
�M�a��EV�̃v���X��̂��Ƃ�S���l������Ă��܂���
��̗�Ō����ƁAISO100 1/320 +6EV �Ȃ̂� 1/320�ŎB�e���Ăł����摜�����炩�̕��@��6EV���邭���Ă����
�������B�R���̓f�W�J���Ŋ��x�ݒ肷��菇�Ɠ����ł��B
�܂�A��̋M�a�̔�r�̏ꍇ�ɂ�
�t���T�C�Y 1/320�ŎB�e���� iso100��+6ev���Ă�̂ŁA����ISO6400�ŎB�e�����̂Ɠ���
M43 1/160�ŎB�e����ISO200��+4ev���Ă�̂ŁA����ISO3200�ŎB�e�����̂Ɠ���
�܂�M�a�̓t���T�C�Y��ISO6400��M43��ISO3200���r���Ă��܂��B
���Ď��̏�Œ�����ł���
�t���T�C�Y�@1�^320�ŎB�e���ā@iso100��+6EV���Ă���̂ŁA����ISO6400�ŎB�e�����̂Ɠ���
M43 1/320�ŎB�e����ISO200��+5EV���Ă���̂ŁA����ISO6400�ŎB�e�����̂Ɠ���
�ɂȂ�ISO6400���m�ł̔�r�ɂȂ�܂��B
���������ł���1/160��1/320�͓������ʂł͂Ȃ��ł��ˁB�i��ƈႢiso���x�������Ă����ʂ͕ς��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F24357594
![]() 3�_
3�_
cbr_600f����
�ƂĂ�������₷�����Ⴀ�肪�Ƃ��������܂��B
�m���Ɍ����ڂ́A�E���̕������߂��ׂ����Ȃ�A�m�C�Y���͔���Ă܂��B�Z���T�[�T�C�Y���傫�������A�����ڂŃm�C�Y�y������邱�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24357796
![]() 1�_
1�_
���肪�Ƃ��A���E����
���ǂ́A�F������w�E����Ƃ���A�B���f�q�Ƃ��Ă̑����]���ɂ����Ă�1�f�q�����ł͌��Ȃ��ł��ˁB
ps���i����EF�l�̖��ɂ��āA�q���g���肪�Ƃ��������܂����B�����Ƃ��Ă܂����B��͂�ND�t�B���^�[��ϋɓI�Ɏg�����Ƃɂ��܂��B
�����ԍ��F24357829
![]() 0�_
0�_
�˂��܂��̂Q�O�P�R����
1/160��1/320�̌��ʂ́A�B�e���̔�ʑ̖̂��邳�������ł���A���w�E�̂Ƃ��蓯���ł͂Ȃ��ł��傤�B�������A1/160�B�e���̔�ʑ̖̂��邳�������ł���A�����ł͂���܂��H
��r�摜���A�قȂ�d�u�ɂ����āA���邭�Ȃ����蔒��т��Ă��Ȃ����Ƃ���A�e�X�g�͂��ꂼ��̂d�u�ɂ����Ĕ�ʑ̖̂��邳���قȂ��Ă���Ɖ��߂��܂����B
�����ԍ��F24357862
![]() 1�_
1�_
��KazuKat����
�t���T�C�Y 1/320�ŎB�e���� iso100��+6ev���Ă�̂ŁA����ISO6400�ŎB�e�����̂Ɠ���
M43 1/160�ŎB�e����ISO200��+4ev���Ă�̂ŁA����ISO3200�ŎB�e�����̂Ɠ���
�Ƃ����̂��e�X�g�̊��ł���ˁB
���ꂼ��̏����ŎB�e���āA�ǂ�����������邳�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ́A�������邳�Ńe�X�g��
���Ă���ƔF���ł��܂��B
��L���������邳�Ńe�X�g�����Ă���Ƃ����G�r�f���X�ł��B
��1/160�B�e���̔�ʑ̖̂��邳�������ł���A�����ł͂���܂��H
���̃e�X�g��1/160�B�e���ɖ��邳�������ł���Ƃ����̂Ȃ�A�M�����G�r�f���X���o���Ă��������B
������ɂ��Ă�ISO6400��ISO3200�̔�r�����Ă���Ƃ������_�ł������Ȕ�r�ł���B
�����ԍ��F24357976
![]() 4�_
4�_
��KazuKat����
�ʂɂ�����ł���B���̋��������v��1�~���������Ȃ���ŁB
�����A�t���T�C�Y�ł�ISO12800�̏�Ԃō����V���b�^�[����ƃU���U���U���U���A
�f�B�e�B�[���ׂ̒�ʼn掿���������Ȃ��Ă���݂����ł��B
�f�W�^���J�����ʼn摜���L�^�����͎̂B���f�q�Ɍ��q����э��ۂ̌��d���ʂ�
���p���Ă��āA�B���f�q���������������f�������������肷��Ɖ�f�ɔ�э���ł���
���q�̐����������Č��d���ʂ�������(=���x��������)�̂ɁA��f���������Ȃ邱�Ƃ�
�d�q�̃g���l�����ʂɂ��Ód���m�C�Y�������ł��Ȃ��Ȃ�m�C�Y�͑����邱�ƂɂȂ�B
�ǂ��t�����������Đ_�l�����̉F����n���������ɒ�܂��������@����ʎq���ʂ���
������Ȃ����Ă��Ƃł��B
�����ԍ��F24358303
![]() 1�_
1�_
�˂��܂��̂Q�O�P�R����A����݂�����
���w�E�̓_�A�U�����Ă�����A���̊��Ⴂ�ł��邱�ƂɋC�Â��܂����B
���������A�����N��̉摜��r�́AISO100�A1/5�Af5.6 ��K���I�o�Ƃ��A�i�K�I�ɃV���b�^�[�X�s�[�h���グ�邱�ƂŘI�o�A���_�[�������AISO���グ�邱�Ƃōēx�K���I�o�ɖ߂����Ƃ������e�X�g�ł��ˁB�����łȂ��ƃe�X�g�ɂȂ�܂���B�l���Ă݂��玩���ł����B
�܂�A�K���Ȕ�r�摜�́A�˂��܂��̂Q�O�P�R���� �̃����N��ɂȂ�܂��B�˂��܂��̂Q�O�P�R����̃����N�������Ε�����Ƃ���A�u�t���T�C�Y�̓m�C�Y���������v�i�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̓m�C�Y�������j���Ƃ��m�F�ł��܂��B���̋^��������Ɏ������o���_�ɂ��������̌�肪�������悤�ł��B
�̐t�v�̂��w�E���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24358455
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ��܂�
SN��̖{���́A�u���肪�Ƃ��A���E����v�̌v�Z��������Ⴉ����A�u1��f������̎���ʐρv�ɂ���ĊT�ˌ��܂�Ƃ̍l�����ŗǂ��ƍl�����܂��B
�������A�t���T�C�Y�̑f�q�Ƃ��Ẵm�C�Y��m�C�Y���́A���𑜓x�^�C�v�ł���u1��f������̎���ʐρv���傫����ɁA���𑜓x�ɂȂ�Ό����߂̃m�C�Y���������Ȃ�m�C�Y�����y������邱�ƂƑ��܂��āA�������ƌ����܂��B
���ۂɁASeagulls����⑼�̕������w�E�����悤�ɁA�t���T�C�Y�́A��pISO�͂Ƃ������A���i�ʐ^�⒴�����V���b�^�[��v����悤�ȋɌ��ɂ����ẮA����f�^�C�v�ł����Ă����炩�ɗL�����ƌ������Ƃł��B
���̌��w�ɒ��X�Ƃ��t�����������A���肪�Ƃ��������܂����B�܂��A�F�X�ƎB�e�Ɋւ���q���g�����킹�Ē����A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24358493
![]() 3�_
3�_
EOS 6D�U���[�U�[����
�H�w����ɂ����ڂ����ł��ˁB���w�E�̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24358496
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
�����J�ȕԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�����������������悤�ł悩�����ł��B
������⑫�ł����A�����܂Ŕ�r�̂����̔F���Ⴂ�ɂ��Ĉӌ������Ē������̂ł����āA
m43���t���T�C�Y������Ă���ƌ��������킯�ł͂Ȃ����Ƃ�F���肢�܂��B
����m43�g�p���Ă��܂����A�ǂ��Ƃ���R����Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F24359205
![]() 1�_
1�_
������ꂽ�e�X�g�摜�͑��������݂����Ȃ���
�ł�����A��r���̂������ɃY���Ă܂��ˁH
�����N�͒P���ɓ����x(6400�ݒ�)�A���I�o(SS
1/2500�AF5.6)�A�����傫���ŕ\��(�N���b�v��
�v�����g���ǂ��Ǝv��)�ŁANR������RAW�̑f��
��Ԃł����X���傳��I�ɂ͂���͔�r�Ƃ��ĊԈႢ
�������肷��̂�����H
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=olympus_em1iii&attr13_1=nikon_z7ii&attr13_2=canon_eosr5&attr13_3=sony_a7iii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&attr126_0=1&attr126_3=1&normalization=compare&widget=1&x=-0.25613706231431305&y=0.19122566245159064
�����ԍ��F24359219
![]() 4�_
4�_
hattin89����
���肪�Ƃ��������܂��B
���w�E�̒ʂ�ł��B�P����raw�f�[�^�̕����A��r���₷���ł��B
������r�T�C�g�̒��e��ǂ��������Ă܂���ł����B
�����������N�������ƁA�m�C�Y�ʂ͓������ۂ�������������̂́A�m�C�Y�ׂ̍�������t���t���[���̕����m�C�Y���̏��Ȃ���ۂł��B���_�Ƃ��Ă܂Ƃ߂����ƂƎ������ǂ��t�����܂��B
�����ԍ��F24360629
![]() 0�_
0�_
��KazuKat����
ISO���x���グ�Ă����ƍ����L�����Ă����܂��B
�����ԍ��F24361372
![]() 1�_
1�_
���Ƀ��������̂�������
�m���ɁI�@�����[�����w�E���肪�Ƃ��������܂��B
�����Ȃ闝�����������ł���A�������肢�܂��B
���́A1��f������̎���ʐς��قȂ邩��A�ƍl���܂��B
�����ԍ��F24361781
![]() 0�_
0�_
 |
 |
 |
|---|---|---|
Lightroom�C�V���[�v�E�V���h�[�m�C�Y�E�J���[�m�C�Y�S�ă[���ݒ� |
Lightroom�D�S�̕�̂ݎg�p |
Lightroom����DeNoiseAI�Ăяo���ł�������NR |
�w�ł����̌o����͍����x�ō����V���b�^�[������o���u�����ɂ߂ăJ������
�������������Ǝv�����E-M5MarkIII��ISO4000�Ƃ�ISO6400�ō����V���b�^�[���Ă݂Ă��炦�܂����H�x
�X���傳��ւ̃��N�G�X�g�ł����A�����Z���T�[��E-M1�U��E-M1X�ł܂��ɂ��������B�e�����Ă��܂��̂ŎQ�l�܂łɉ摜���e�����Ă��������܂��B
�v���L���v�`���[H���[�h�i�v���L���v�`���[�E�d�q�V���b�^�[60�R�}�^�b�F���̊��ł͖�45�R�}�^�b�j�ŎB�e�B
�d�q�V���b�^�[�����A�ʂȂ̂Ń��J�V���b�^�[�ł̒ᑬ�A��12�R�}�^�b���炢�Ɣ�׃m�C�Y�̖ʂŕs���ł��B
���I�����p�X�@�Ɍ��炸�d�q�V���b�^�[�ł̍����A�ʂł́A���Z�b�g�����Ȃ��c���d�ׂƔ��M�̂��߃��J�V���b�^�[�g�p���ɔ�掿������ƔF�����Ă��܂��B
dpreview�̔�r�͎Q�l�ɂ͂Ȃ�܂����ARAW�t�@�C���������i�����O�j�ɂ����炩NR�������Ă���@�킪����܂��̂ŁA�t�@�C�����_�E�����[�h���Ď��g�Ō������Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B
�����i�ƌ��T�C�g�Q�l�j�ł����AE-M1�U�͂��̔������̃t���T�C�Y�@�ɔ��1�i�`1.5�i���x�A�ŐV�t���T�C�Y�@�Ɣ��2�i���������������Ɗ����܂��B
��E-M1�U�̃Z���T�[�́AISO6400����Ƃ����b�Ɨ������ނ悤�Ȃ̂ŁA��L��r��E-M1�U��ISO6400�܂łł̘b�ł��B
�Ȃ��A�Q�l�摜�̂悤�ȎB�e�ł͔�ʊE�[�x��������x�~�������߃}�C�N���t�H�[�T�[�Y��2�i����Ă��Ă���ʊE�[�x�𑵂���O��Ȃ�A���̍����z������܂��B
�����ԍ��F24362089
![]() 3�_
3�_
��KazuKat����
�グ��ꂽ�摜�̌��X������z�����܂��ƁA�u�ʂS�^�R�ł��\���A����A�t���T�C�Y�ȏ�̐��i�摜���B�ꂽ���A�h���I�v���Ď��ł���ˁB
���͂��̉摜��q�����āu����͐��i�B�e�ɂ͖����v�Ɗ����܂����B
�ł����̓ʂS�^�R�i�͂��납�g�������Ƃ���Ȃ��̂ŁA���������Ŕ�r���Ă݂���Ⴄ���z�ɂȂ邩������܂���E�E�E�܂��S�Ȃ��̂ł��������@��͖����Ǝv���܂����ǁB
�������őI�ꂽ�@��E�t�H�[�}�b�g�ł��̂ŁA���M���������ɂȂ��Ăǂ�ǂi�B�e�Ɏg��������Ǝv���܂���A�t���T�C�Y�Ɣ�r����K�v�Ȃ��ł��傤�E�E�E��r���Ă��������ǂ��Ǝv�������芷����������Ƃł��B
�����ԍ��F24362182
![]() 1�_
1�_
mosyupa��
�ʐ^�̓��e���肪�Ƃ��������܂��B
�b�̗���𗝉��ł��Ă��Ȃ��܂܂ł̎��̉����ƂȂ�܂����A������f���ł���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�Ɣ�r���āA1��f�̎���ʐς�4����1�ł���ƍl�����邱�Ƃ���A�����ϐ���2�i����シ��ƍl�����܂��B
�����ԍ��F24362186
![]() 0�_
0�_
���ʂ䂸����
���u�ʂS�^�R�ł��\���A����A�t���T�C�Y�ȏ�̐��i�摜���B�ꂽ���A�h���I�v���Ď��ł���ˁB
�������B
�����ԍ��F24362603
![]() 2�_
2�_
��KazuKat����
�����ł��ˁB���������Ǝv���܂��B
���̑��ɕ����I�Ȍ��̗ʂɍ������鎖���W���Ă���Ǝv���܂��B
�����x�ŎB��ꍇ�ł��A�ʐ^�̖��邳�͒ኴ�x�ŎB�e�������̂Ɠ������炢�̃T���v�������Ă܂���ˁB
�Ƃ������́A�����Y��������Ă��镨���I�Ȍ��̗ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������ł��B
��f�Ɖ�f�̋��ڂɂ́A��������܂���ˁB�I�̑��̂悤�ȃC���[�W�B�i�I�̑��͎l�p�ł͖������ǁj
��f����������Ƃ��̒��̐��������܂��B
�Z���T�[���͓̂����ʐςȂ̂ŁA���̐��������ƕ����I�Ȍ�����荞�߂�ʐς�����܂��B
�����Y���a���傫���ƕ����I�Ɏ�荞�߂���̗ʂ������Ȃ�܂��B
�t���T�C�Y�̕����傫���̂ł��̍�������Ǝv���܂��B
�\���Ȍ����Ȃ��ƃm�C�Y�ɂȂ�̂ŁA�����I�Ȍ��̗ʂ��W���Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24362658
![]() 1�_
1�_
���Ƀ��������̂�������
�R�����g�A���肪�Ƃ������܂��B
�������Y���a���傫���ƕ����I�Ɏ�荞�߂���̗ʂ������Ȃ�܂��B
�܂��ɂ��w�E�̓_�ɋC�Â��A����������グ���X���b�h��������ɂȂ�܂��B
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24361808/#tab
�����ԍ��F24362683
![]() 0�_
0�_
��N�ň�ԍD���ȋG�߂ł��B
�H�̑�̓n�肪�n�܂�܂����B
�悸�̓n�`�N�}���n���Ă����܂����A�t�ƈ���ďH�͐����Ɨc�����n��܂��B
��ꂩ�����A�y���݂Ŏd��������܂���B
![]() 9�_
9�_
��jycm����
���v���Ԃ�ł��B
���̑O�A�R�̓W�]��ɍs������428�����������������̂Łu�����B���Ă��ł����H�v�ƕ��������̓n�肾�ƁB
����ȕ������鎖����m��܂���ł������A�ҋD���̕��ɂƂ��Ă̓��N���N�̃V�[�Y����������ł��˂��B
���炭�����琔�\�H�̑邪���ɕ����čs���܂����B
���͕W���Y�[�����������ĂȂ������̂œ����̗l�ɂ����B��܂���ł����B�i�j
�f���炵���ʐ^�����肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F24354134�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�S���́u���v���u�錩�v�ƕʏ̂����R��n�於�Ő̂���G�߂̕������������悤�ł��ˁB
���ł����݂ȏꏊ�ł́A���i�������Ȃ��悤�Ȓ��]�������Y�����鎖���ł��܂��B
500�`600�̓q���b�q�ŁA1000mm1200mm��2000mm�Ȃ�Ď��͂ނ��낱������������y���݂������肵��www
��̕����S���Ă��āA�ꏊ�ɂ���Ă͎R�̎Ζʂ��삯�オ��悤�ɕ����オ��
�㏸�C���ɏ��V�[���������Ă���܂��B
�����Ȉ���A��҂����Ȃ���錩�̌����A�C�i���V�тł���www
�����ԍ��F24354182
![]() 2�_
2�_
��jycm����
�����l�ł���
�܂����������y���߂����Ȃ̂ŗ��T�����҂��Ă܂��B
���ډ����ł������͋C�����Q�����܂��I
�����ԍ��F24354413
![]() 5�_
5�_
���i�DCOM�̃��[�L���X���ő�̓n��������Ē����A���N�łV�V�[�Y�����}���܂����B
�����܂Ńn�}��Ƃ͎v���Ă����܂���ł������A���͒n���̒m�荇���������y����ł��܂��B
���Ɏq�̒��N����
��ς����������Ă���܂��B
�Ȃ��Ȃ�����ł��܂��A�R���i�������������烌�[�X�i���o�����j�̎B�e�ɍs�������ł��B
��masterm����
��̓n��̊y���ݕ��͐l���ꂼ�ꂠ��܂��B
�{���Ɍ��邾���̐l��A�J�E���g���������A�ʐ^���B��������l�X�ł��B
���̓q���R�̃����Y�ŎB�e���Ă��܂��B
����ł��^���ǂ���߂�����ł���܂��B
�����ω� �G���q������
�E�E�E
��mirurun.com����
�i�C�X�ȑ钌�ł��B
������͍��T���Ƀn�`�N�}�ƃT�V�o�̃s�[�N���}����Ǝv���܂��B
�{���̎ʐ^�́A�n��̒��ł��������������ł��B
�����ԍ��F24354614
![]() 5�_
5�_
��jycm����
��͎B�������ƂȂ��ł����A���ꂩ��̋G�߂͍g�t���n�܂�̂Ŏ������D���ł��B
���ӂ����E�E�E
����ᖟ�悾�ˁB
��̎ʐ^�͓����炾���ǁA����̎�l��2�l�͎��ĂȂ����ǂˁB
�����ԍ��F24354688�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��jycm����
���Ƃ͖{���ɂ��V�C���������ˁ�
���������Ȃ̂œ��摜�œ��₩���Ă����܂��i�j
�S�����ł��߂�Ȃ����c
�����ԍ��F24355403�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�Q���ł���ʐ^���Ȃ��A�A�A(T . T)
�����ԍ��F24355431�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
��jycm����
�����́A
�i���}�痠�R�ł��B
����߂��̌����ŏt����Ăɉc�����Ă����n�C�^�J�t�@�~���[�������ɑ������]���ς݂ł��A
���ꂩ��͘h�̃V�[�Y���ł����܂��n���ė��Ă��܂���A�����ҋ͂��Ԃł��B
���ʐ^�y���݂ɂ��Ă���܂��Bm(__)m(*- -)(*_ _)�y�R��
����߂��̌����ɋ����n�C�^�J�̏؋��ʐ^��\�点�Ē����܂��B
�����ԍ��F24355473
![]() 4�_
4�_
�R�����g���܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B
��with Photo����
�@�����܂������̓n��Ă݂Ă��������B
���͍g�t�̎B�e�����܂肵�����Ƃ�����܂���B
��mirurun.com����
�{���̂��V�C�͂��܂�悭����܂��A�����͊��҂����Ă����ł��B
��������T���܂ʼn����ł��肢�������ł�(��)
���ʐ^���肪�Ƃ��������܂��B
����-RYO�̕コ��
�����Ȃ��ŎB���Ă����B
���≖���_���X�g����
�����l�ł��B
���ʐ^�ƃR�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�n�C�^�J�f���炵���ł��B
�������10���ɓ���n�C�^�J�̃V�[�Y���ɂȂ�܂��B
�S�̕��͂��x�݂��Ă��Đ\����܂���B
�܂��܂��V�[�Y���ɓ���������Ȃ̂Ŏʐ^�̍ɂ�����܂���B
�����牽��\�낤�E�E�E
�����ԍ��F24355655
![]() 4�_
4�_
��jycm����
�V�����n�`�R�o���o���B���Ƃ����ł��ˁ�
����-RYO�̕コ��
�B������(�P�[�P)
�����ԍ��F24356724�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�B������������(�P���P)�I�I
�E�E�E�E�E�J���X���ł����E�E�E�E�E�n��Ȃ��ҋׂł����E�E�E�E�E
�Ȃ����Ȃ��E�E�E�Q|�P|��
�����ԍ��F24357607
![]() 5�_
5�_
�{�����n����B�e���Ă��܂����B
�{���̓T�V�o�̓��ƂȂ�܂����B
��mirurun.com����
�n�`�q�����H���B�e���܂������A�w�Nj߂Â��Ă���܂���ł����B
�����q�͋߂��̂��B��Ă܂��B
�T�����y���݂ł��B
����-RYO�̕コ��
�ӂ����ĂȂ��ŎB���Ă����B
�����ԍ��F24358317
![]() 4�_
4�_
jycm�����Ȃ�O�Ɍ��������掿�ȃL���m��APS-C�ŋ��k�ł����Q�������Ă��������܂���^ ^
���A��-RYO�̕コ�� �n�X���̊F���� ����ɂ��́B
�����ԍ��F24359791�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���݂܂���...EXIF�S����...���炵�܂����B
�����ԍ��F24360495
![]() 4�_
4�_
������ a.k.a. ...����
�R�����g�Ƒf���炵���ʐ^�����肪�Ƃ��������܂��B
7�c2�͎��̘r�ł��Y��ɎB��܂���ł����B
���������� a.k.a. ...����ł��A���ɂ͂ƂĂ������ł��B
�{����54���ŋ߂����_���ł������S�s���Ă��܂����B
�����ԍ��F24362478
![]() 3�_
3�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
-
�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j