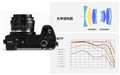���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S2102�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2022�N4��27�� 16:55 | |
| 4 | 0 | 2022�N4��21�� 23:19 | |
| 5 | 0 | 2022�N4��21�� 23:02 | |
| 7 | 8 | 2022�N4��15�� 08:33 | |
| 7 | 2 | 2022�N4��7�� 03:14 | |
| 48 | 55 | 2022�N4��7�� 00:37 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�y�V���b�v���zAmazon�FMICPhoto
�y���i�z�����F14315�@2000�~�N�[�|��������
�y�m�F�����z2022.04.27
�y���̑��E�R�����g�z�@
���i�����N�Fhttp://www.amazon.co.jp/dp/B09NCYWWLD?ref=myi_title_dp
�������w�i�߂����傤���������jTTArtisan 23mm f/1.4 C �́A35mm�����Z35mm�����iAPS-C�j�̑���a���L�p�����Y�ł��B�J�����̃I�[���h�����Y���v�킹�閡�̂���ʂ��A�����̂���O���f�U�C���A�����̍������������ɂ��S�n�悢���슴�ȂǁA�N���V�J���ȕ��͋C���y���ނ��Ƃ��ł��܂��B����a���ŒZ�B�e����0.2m�Ƃ�����{���\�������Ȃ�����A�S����}�����R���p�N�g�ȃT�C�Y�ŁA���^�̃J�����ɂ����������܂܋C�y�Ɍg�s�ł��郌���Y�ł��B
![]() 0�_
0�_
https://ganref.jp/m/turedure-drummer_picture/reviews_and_diaries/review/43897
�t���T�C�Y�~���[���X�J�����p70-300�~�������Y�̓�����Nikon����\�����ꂽ�l�ł��ˁB
�����̈Â��͂���܂��̂�S���C���ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�y�ʂŐU��₷�����������b�g�̂��̃N���X�̃����Y�B�y���݂ł��I
�����ԍ��F24711419�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
 |
 |
 |
|---|---|---|
�T�C�Y�k�� ������̑��痢 |
�T�C�Y�k���@���쉷�C�g�A�b�v�@�O�r�g�p�@30�b |
�����Â߂̕`�ʂȂ���ѕ��݂������ƍČ�����Ă܂� |
GFX50s�U�ɃA�_�v�^���܂���smcPENTAX FA645 80-160/4.5���g���Ă݂܂���
���s�i�̂ЂƂO�̃��f���H�̂悤�ł���F8�܂ł͊Â߁AF11����16�ӂ�ł͂Ȃ�Ƃ�5000����f�ɐH�炢�t���Ă��܂�
�A�_�v�^���݂�1.3kg���ƃt���}�j���A������̃����Y�Ƃ��Ă͑傫���d���ł����A�Ə����Ŕ��������Ƃ��l����Ɨǂ��̂�������܂���
![]() 5�_
5�_
����ɂ��́B
�Y�t�̉摜��Loxia 2/50�Ƃ��������Y��f2.8�ŎB�������̂ł��B��䊂��L�`���Əo�Ă��܂��B
���܂Ō�䊂��či������Ȃ�i��Əo����̂��Ǝv���Ă����̂ł���
�����Y�Ɉ˂��ĈႤ�̂ł��傤���H�@����Ƃ��i��ȊO�ɏo�₷���Ȃ����������̂ł��傤���H
![]() 0�_
0�_
���̃����Y�͎����Ă��܂��A����������Ɖ~�`�i��ł͖�����Ȃ��ł��傤���H
�~�`�i�肾�Ɗp����������䊂��łɂ����ƕ��������Ƃ�����܂��B
�����ԍ��F24698022
![]()
![]() 0�_
0�_
���i�^�[�V���V����
�~�`�i��̃����Y�ł��ƁA���\�i��Ȃ��ƌ�䊂͏o�Â炢�ł����A
�~�`�i��łȂ������Y�ł́A�����i��ƌ�䊂��o�₷���Ȃ�܂��B
���ƁA�������͂��̖����ɂȂ�A����͂��̂Q�{�̌�䊂ɂȂ�܂��B
�L���m��EF�͋������������ł����A�I�����p�XOM���������������ł��B
�����ԍ��F24698040
![]()
![]() 1�_
1�_
����̃����Y�͍i��H���ɃJ�[�u���L��
���Ȃ�i��Ȃ��ƌ�䊂͏o�܂���
�̂̃����Y�͍i��H���������ɋ߂��̂�
�i��������p�`
���p�`�̊p�����ٌ�䊂�����܂�
����1985�N������
�~�m���^70-210mmF4
������2�i�i����F8�ł��ꂾ����䊂��L�т܂�
�����ԍ��F24698074�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�i�^�[�V���V����@����ɂ���
https://www.youtube.com/watch?v=wU_ZywfEB6U
���YouTube��5������Ɂ@F2��F2.8�̔�r���L��܂����@F2.8�ł��Y��ɏo��̂Ł@�����Y�̎d�l���Ǝv���܂��B
��@���̃����Y�@�i��H10���̂悤�ł��̂Ł@��䊂̖{��10�{�o��悤�ł��B
�����ԍ��F24698141
![]()
![]() 1�_
1�_
�F���肪�Ƃ��������܂��B
�܂Ƃ߂ẴR�����g�Ŏ��炵�܂��B
>����|����
>������@������������
�����ă����Y�̍i���ڎ����Č��܂����B
�i�肪�J�����ɉ~�`�Ȃ̂�f2.8�ɍi���
�n�b�L��10�p�`�ɂȂ�܂��B���̃����Y��
f2.8���x���ƃn�b�L���������p�`�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂�
���ꂪ���R�Ȃ̂ł��傤�B
�ǂ������肪�Ƃ��������܂��B
>��̌|�p�Ƃ���
�i��H�ɃJ�[�u�ł����A�{�P���Y��ɂ��邽�߂̍H�ł����ˁB
�������肪�Ƃ��������܂��B
>���ƃ��{�}�� �Q����
������₷������̏Љ�肪�Ƃ��������܂��B
�ȂX�b�L�����܂����B
����Loxia 2/50�͕��}���Ȃ��Ǝv���Ă����̂ł���
��R��i���B��y���݂��o���܂����B
�����ԍ��F24698333
![]() 0�_
0�_
�i�^�[�V���V����@�ԐM���肪�Ƃ��������܂�
���̃����Y�̌�䊁@�{�����o�����X�悭�@�Y��Ȍ�䊂ł��ˁB
�����ԍ��F24698345
![]() 1�_
1�_
����ɂ���
���p�`�́u�p�v�Ō�䊂��o���Ă���̂ł͂Ȃ��̂ŁA�����ӂ��B
�����ԍ��F24699109�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����傤�}�[�`����
�Ԏ����x���Ȃ�܂����B
�����ɂ��Ă͂����������Ȃ̂ł����F�X����P����o�Ă��Ă߂��Ă��Ă��܂��i�j
��肠�����̑f�p�ȋ^��ɂ��Ă͊F����̃R�����g�ň�藝���͏o���܂����B
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F24700304
![]() 0�_
0�_
�\�ʂ�ɖ{�����\���܂����B
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/nikkor_z_800mm_f63_vr_s/
4��22�������\��
973,500�~�Ƒz��������Ȃ肨���߂ł��B
���B��̕��ɂ͖��͓I�����ł��B
���͂����܂ł̏œ_�����͂���Ȃ��̂�Z428���w�������̂Ńp�X�ł��B
![]() 3�_
3�_
�����A�k�Ă̓X�����i��$6,500�i4/6�בփ��[�g�F124�~�ŏ����10%���悹�Ă�90���ȉ��j�ł�����A
�����̎������i�����l90���ʂł��傤���H�H
�\����Ă���$6,000��菭����������ł��ˁc�B�i���傹��͉\�ł����j
�܂��܂��A�w�z������ϑ����̂��\������������āc�x���o���ł��傤�ˁc�B
�����ԍ��F24687726
![]() 4�_
4�_
����s�J�[�h����
���܂��܂��A�w�z������ϑ����̂��\������������āc�x���o���ł��傤�ˁc�B
����͖{���ɗ\����E�����邩����(��)�B
F6.3�Ƃ͌���800mm�̒P�œ_�����̒l�i�ł������A�d�ʂ����ꂾ���y�ʉ�
���ꂽ�̂͑傫���ł��傤�ˁB
�A�}�`���A�ł��̎�̉��i�т̃����Y����̂͂���Ȃ�ɔN�z�̐l��
�Ȃ��Ă��܂��̂ŁA���̏d�ʂȂ炢����Ǝv���l���o�Ă���̂ł́B
�l�I�ɒl�i�Əd�ʂ̃C���p�N�g��200-500mmF5.6�����\���ꂽ���ɑ������܂��B
�܂��A�܂�F�}�E���g�Ŋ撣���Ă鎩���ɂ͓����肪�o�Ȃ������Y�ł�����
�����g���Ă݂����Ǝv�킹�Ă���郌���Y���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24688197
![]() 0�_
0�_
�t���T�C�Y��Ⴊ�S�������}���Ă��܂��ˁB
�I�[���h�����Y��C�J�ł́A�F�������Ɍ��܂ŗ}�����A�|�N���}�[�g�����Y���悭�������܂��B�𑜂��ǂ��X�b�L���Ƃ��ꂢ�Ȏʐ^���B���悤�ł��B�j�R���A�L���m���A�\�j�[�Ȃǂ̍��Y���[�J�[�̃����Y�́A�A�|�N���}�[�g�ƌĂȂ������Ŏ��ۂɓ����̃����Y�͂���̂ł��傤���H
![]() 1�_
1�_
2022/03/31 21:55�i1�N�ȏ�O�j
���O���}���X�ȃN�}����
������
APO�����Y�Ƃ����A���~�m���^��V�O�}�ł��L��܂����ˁB
���̃V�O�}�ł�APO�����Y�̒�`�́A
https://www.sigma-global.com/jp/glossary/apo/
����ᕪ�U�K���X�ȂǂQ���ȏ㕡�����āA�F�������Ɍ��܂ŕ�����]�������Y
�Ƃ���܂����A�L���m���ł�UD�����Y�A�j�R���E�\�j�[��ED�����Y�Ƃ����������Y��
�Q���ȏ�g�p���Ă��郌���Y�́A���ǂ�������O�̗l�ɑ��݂��Ă���Ǝv���܂���B
�L���m���̌u��j�R����FL�����Y�P���́A�X�[�p�[UD�EED�����Y�P���܂���
UD�EED�����Y�Q���g�p�����̂Ɠ����̐F��������ʂ������搂��Ă��܂����A
�����������ꃌ���Y���g�p�����]�������Y�͑��A�����Ɠ��ꃌ���Y���g���Ă��āA
APO�����Y�ȏ�̌��ʂ������̂͑����Ȃ��Ă��Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24678494
![]()
![]() 3�_
3�_
���݂́A���ɃA�|�N���}�[�g�������������������g���Ă��܂��B
�\�����������������̓��ߗ��ቺ�́A
���w�疌���� �i�}���`�R�[�g�j �Z�p�̐i���ő����ɉ��P����Ă���܂��B
�t�B���^�ɂ��Ă����\�N�O�܂ł͒P�w�疌�ł��� --- ���ł��i�D�����z�͋C�ɂ��Ȃ��Ŏg���Ă܂����B
�����ԍ��F24678506
![]()
![]() 1�_
1�_
�R�V�i�̃A�|�����^�[�A�A�|�X�R�p�[��HP�ł��A�|�N���}�[�g�v�ƌ����Ă��܂��B
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001203812_K0000983403_K0001332659_K0001392168_K0001064923&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3
���ЂŌu�A�d�c�����Y�A�t�c�����Y�ASD�����Y�ASLD�����Y�AFLD�����Y�ق��A���낢��ȌĂі��͂���܂����A�܂�ُ핔�����U�̂��郌���Y���g���������Y�́A�A�|�N���}�[�g�v�Ƃ͌����Ă��܂��A�A�|�N���}�[�g�Ȃ̂�������܂���B
�A�|�N���}�[�g�����Ƃ́A�X�[�p�[�A�|�N���}�[�g�Ƃ��̂��Ƃ�������܂��A����������ƃj�R����NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S��SR�����Y��A�L���m����RF85mm F1.2 L USM�Ȃǂ�BR�����Y�͂���ɋ߂����̂�������܂���B
�����ԍ��F24678552
![]()
![]() 2�_
2�_
�A�|�N���}�[�g�͌��͓V�̖]�����p��ł�
�Â���`�ł�
�F������2�F������̂��A�N���}�[�g
�P���R�[�̃N���[�Y�A�b�v�����Y��
�A�N���}�[�g�d�l���L��܂�
�F������3�F������̂��A�|�N���}�[�g
�ȑO�A�~�m���^��V�O�}���F������ׂ̈�
�����ȓ���蕪�U�����Y�g���������Y�ɃA�|��
�����Y���ɂ��Ă܂���
�~�m���^100-300mmF4.5-5.6��
�V�O�}70-300mmF4-5.6 DG�Ȃ�
1�`2���~�Ⴂ��
�m�[�}����APO�Ɨ��^�C�v�L��܂���
�ǂ̃��[�J�[���]�����ɓ���蕪�U�����Y���g��APO�d�l�Ȃ�ł���
�ǂ̃��[�J�[���A�|�����i���ɂ��Ă܂���
�W���Y�[��������蕪�U�����Y��
�g���Ă܂���
����̓V�O�}�̓A�|�Ƃ͌Ă�ł܂���
�t�B�������ڗ��{���F����
�f�W�^���Ή����W���Y�[���̓���蕪�U�����Y�ł�
����蕪�U�����Y�̓t�B��������̕W���Y�[���ɂ͎g��ꂸ
�]�������Y�݂̂Ɏg���
APO����ED�j�b�R�[������
���i���ɂ��Ă܂���
�����ԍ��F24678587�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�F����A���肪�Ƃ��������܂��B
�R�V�i�����C�J���u�A�|�v�Ƃ�������t�������i������܂����A�u�A�|�v���t���Ă��Ȃ��Ă��u���w�n���\�����郌���Y�͑S����11���B���̂���2���ɂ͔ʃ����Y���A4���ɂُ͈핔�����U�K���X��p���A�F������ǍD�ɕ���Ă��܂��B�v�Ƃ������i(���C�J �Y�~���b�N�X SL f1.4/50mm ASPH) ������܂��B
����œ������C�J�ɃA�|�Y�~�N�����Ƃ������i������܂��B���̐��i�̐����ɂ́u���w�n���\�����郌���Y��11���ł����A���̑啔���Ɉُ핔�����U�����������������x�ō��i���ȓ���K���X��p���Ă��܂��B�v�Ƃ���܂��B
���C�J�ł́A11����4���ł̓A�|�ƌĂȂ��悤�ł��B
�F�l����̏��Ɠ�������ƁA�A�|�ɂ��Ă̖��m�Ȓ�`�͂Ȃ��A������2���ȏ�̓���ᕪ�U�K���X���g�����Ƃ��Œ���̗v���̂悤�ł��ˁB
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24678831
![]() 0�_
0�_
���O���}���X�ȃN�}����
>�A�|�ɂ��Ă̖��m�Ȓ�`�͂Ȃ��A������2���ȏ�̓���ᕪ�U�K���X���g�����Ƃ��Œ���̗v���̂悤�ł��ˁB
�u�A�|�N���}�[�g�v�̒�`�͖��m�ł��B�u3�̔g���ɂ��ĐF�����������Ă��郌���Y�v�ł��B
�������A�u�ԁE�E�v�Ƃ��u�ԁE�E���v�Ƃ������āA3�̔g���͌��܂��Ă��܂��A��̒��x�����܂��Ă��Ȃ��̂ŁA�A�|�N���}�[�g�𖼏�邩�ǂ����͐����҂ɂ�肻���ł��B
�܂��A����ɍރ����Y�������g����̂̓A�|�N���}�[�g��B�����邽�߂ŁA�g��ꂽ���ǂ����̓A�|�N���}�[�g�̒�`�Ƃ͊W�Ȃ��ł��B
���Ȃ݂Ɂu2�̔g���ɂ��ĐF�����������Ă��郌���Y�v���u�A�N���}�[�g�v�ł��B
��������V�̖]�������̗p��Ƃ����킯�ł͂���܂��A��`�̌Â��V����������܂���B
��������Ń����Y�Ȃǂł��d������邱�Ƃł����A�J���������Y���������A�|�N���}�[�g�ł��傤�B
�J���������Y�ŁuAPO�v�𖼏�鐻�i�́A���[�J�[�����ɐF�����̏��Ȃ��������������Ƃ����Ӑ}������̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F24679102
![]() 5�_
5�_
���O���}���X�ȃN�}����
���ג������炿����ƌ�肪����܂����̂Œ������܂��B
�y�A�|�N���}�[�g�z
�w3�F�i���Ȃ�g���̈قȂ����F�Łj�ȏ�ɑ��ĐF�����ɂȂ��Ă��āA���̂�����2�F�ɂ��Ă̓A�v���i�[�g�ɂȂ��Ă��郌���Y�B�G�����X�g�E�A�b�x����`�x
�i�V���A�}�`���A�̂��߂̖]�������w�E�g�c�͑��Y���E1978 �ɂ��j
�y�A�N���}�[�g�z
�w2�F�i���Ȃ�g���̈قȂ����F�Łj�ȏ�ɑ��ĐF�����ɂȂ��Ă��āA���̂�����1�F�ɂ��Ă̓A�v���i�[�g�ɂȂ��Ă�����w�n�x�i����j
�y�A�v���i�[�g�z
�w���ʎ����ƃR�}�������ɏ����������w�n�x�i����j
�y�G�����X�g�E�A�b�x�z
Ernst Karl Abbe�B�h�C�c�̕����E���w�ҁB1840 - 1905�B
�����ԍ��F24679324
![]() 3�_
3�_
�Ē����ł��B���݂܂���B
�y�A�N���}�[�g�z
�w2�F�i���Ȃ�g���̈قȂ����F�Łj�ȏ�ɑ��ĐF�����ɂȂ��Ă��āA���̂�����1�F�ɂ��Ă̓A�v���i�[�g�ɂȂ��Ă��郌���Y�x�i����j
�����ԍ��F24679396
![]() 2�_
2�_
>���̂�����2�F�ɂ��Ă̓A�v���i�[�g
>���̂�����1�F�ɂ��Ă̓A�v���i�[�g
�@2�܂���3�S�Ă���ςƎv���Ă����̂�
�@���ƈႢ�܂�����
�@�A�v���i�[�g�͋��ʎ����ƃR�}���������Ă���
�@�����Y������1�͕����Ă��Ȃ��ėǂ��킯�ł���
�@�F�̎���s���g�͓����ł����ʎ������Ⴄ�Ƃǂ��Ȃ�
�@���ƋC�ɂȂ�܂���
�@�b��͕ς�邯��
�@�R�[�e�B���O���Ĕ��˂��ʑ��̈قȂ锽�˂�
�@���ŏ������Ƃ�����K���X��
�@���ߗ��ɂ͍v�����Ȃ��Ǝv���Ă�������
�@�Ⴄ�̂��낤��
�@��͂�C�ɂȂ�܂���
�@�i�m�R�[�g�̓K���X�̑O�ɃK���X�ʂ�
�@����߂ċ}���ȋ��ܗ������łȂ��悤��
�@���Ĕ��˂�}���镨�ł���
�@������K���X���̂̓��ߗ��ɂ�
�@�v�����Ȃ�
�@�����Y�̓��ߗ��̎��Ȃ̂��낤��
�@�C�ɂȂ�܂�
�����ԍ��F24679794
![]() 0�_
0�_
���f���[�U����
>�F�̎���s���g�͓����ł����ʎ������Ⴄ�Ƃǂ��Ȃ�
�c�������̑��{�P���o�邾���ł��傤�B
>�R�[�e�B���O���Ĕ��˂��ʑ��̈قȂ锽�˂̊��ŏ������Ƃ�����K���X�̓��ߗ��ɂ͍v�����Ȃ��Ǝv���Ă������LjႤ�̂��낤��
�R�[�e�B���O�Ō����������ˌ��̕��A���ߌ��������܂��B
�����ԍ��F24680070
![]() 3�_
3�_
���f���[�U����
https://coating.nidek.co.jp/article/information/type/a37?mode=amp
��
������̓����Y�R�[�e�B���O���̂��̂ł͂���܂��A��r�I�ɂ킩��₷�����ƁB
�����ԍ��F24680092�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����́B
�u�A�|�N���}�[�g�v��[������]�ɂȂ����悤�Ȃ̂ł��ז������Ă��������B
�����Y�̔��˖h�~��(�R�[�e�B���O)�̂��Ƃł��B
���˂�����̂́u�g���ł����������v�Ŕ[�������C�ɂȂ��̂ł����A
�u���ߗ��v�A�b�v�̗������A�����ł��܂���B
�����N���
�u�ł��������������̍s���v�̒i����
�u���̕�(���˂���g���ł�������������)�傫���Ȃ�܂��v�Ƃ���܂��B
�����f���ɍl����ƁA
�u���˂���g���ł��������������v�ߌ��ɗ^���ē��ߌ���������B
���ˌ��́A��������������u�^���v��m���Ă��āA���́u���v�����炩���ߓ��ߌ��ɕ����^�������̂悤�B
���ˌ����ł����������ď�����͔̂��˂�����A
�������˂Ɠ��߂ɕ������u�Ԃ͂�����O�ł�����A
���Ԍo�߂��t�]�B
�݂����ȗ����ɂȂ�܂��A�[�l�����Ă܂����B
Web��������Ɓu�G�l���M�[�ۑ����v�ɗ��߂�����������܂��B
���̑��ʁ����ߌ��{���ˌ�
������A���ˌ������������A���ߌ���������A���ʂ͓���������B
�Ƃ��B
�f���ɔ[���ł���l�������܂������v���Ă܂����A�����ƁB
�܂��A���̕��́A�����ł�����s�\���A�l�ɓ`�����̂��Ɗ����E�E�E�B
�����ԍ��F24680119
![]() 0�_
0�_
��̌|�p�Ƃ���
>�����ȓ���蕪�U�����Y�g���������Y�ɃA�|��
>�ǂ̃��[�J�[���]�����ɓ���蕪�U�����Y���g��APO�d�l�Ȃ�ł���
>�W���Y�[��������蕪�U�����Y��
>�f�W�^���Ή����W���Y�[���̓���蕪�U�����Y�ł�
>����蕪�U�����Y�̓t�B��������̕W���Y�[���ɂ͎g��ꂸ
����u��v���U.... �ł͂Ȃ���
����u��v���U....�ł���
�����ԍ��F24680163
![]() 2�_
2�_
��?
�Ƃ������Ƃ́A���C�J��R�V�i��APO���Ă͉̂��l�������ł��傤���H
�m���ɁA��������ƍ��Ŗʂ̃V���[�v���͑f���炵���̂ł����A�A�A�v�����݂̂悤�ɂ������܂��B�ŋ߂̓f�W�^���ŕ�ł��邱�Ƃ̓{�f�B���ɔC���A�����ł͂Ȃ����Ƃ������Y�œO��I�ɑΏ�����̂��g�����h�ŁA���̌��ʁA�����Y�ƃ{�f�B�̑g�ݍ��킹�őf���炵���A�E�g�v�b�g�������܂���ˁB
EVF�����炱�����������@�ł����A�����Y�̏��^���ɂ��v���ł���̂ŁA�嗬�ɂȂ�̂��ȁH�Ƃ��������̒��ŁAAPO�̉��l�͂������Ȃ�ł��傤�ˁH
�����ԍ��F24680183
![]() 0�_
0�_
���O���}���X�ȃN�}����
���F�l����̏��Ɠ�������ƁA�A�|�ɂ��Ă̖��m�Ȓ�`�͂Ȃ��A������2���ȏ�̓���ᕪ�U�K���X���g�����Ƃ��Œ���̗v���̂悤�ł��ˁB
�ُ핔�����U�K���X���̃����Y���Q���g�����Ƃ͕K�{�ł͂���܂���B�ُ핔�����U�K���X�i�������͌u�j�̃����Y�ƍ����ܗ������U�K���X�̃����Y�e�P���i�Q�Q�Q���j�ō\�����邱�Ƃ͉\�ł��B�{�[�O�̖]�����͂����������\���ł��B�������Q�Q�Q���ł́A�C���[�W�T�[�N���̑傫�����Ɍ��E���o�܂��B
https://www.tomytec.co.jp/borg/products/detail/arguments/699/7
���Ƃ������Ƃ́A���C�J��R�V�i��APO���Ă͉̂��l�������ł��傤���H
�A�|�N���}�[�g��搂��Ă��Ȃ����̂́A�{���ɃA�|�N���}�[�g���ǂ����͂킩��܂���B�܂������Y�����́i����j�F���������ł͂Ȃ��̂ŁA�g�[�^���̕�����ɂȂ�܂��B
���ŋ߂̓f�W�^���ŕ�ł��邱�Ƃ̓{�f�B���ɔC���A
���̂Ƃ���A�{���F�����̓f�W�^������\�ł����A����F�����͌��w�n�ŕ����ׂ������̂��̂ƂȂ��Ă��܂��B�A�N���}�[�g�A�A�|�N���}�[�g�͎���F�����̕�Ɋւ�����̂ł��B
����̌|�p�Ƃ���
���A�|�N���}�[�g�͌��͓V�̖]�����p��ł�
�A�|�N���}�[�g�̋N���͌������̑Ε������Y�ł͂Ȃ��ł��傤���B�ُ͈̂핔�����U�K���X�͂Ȃ��A�u���V�R�̂��̂����Ȃ������̂ŁA�]�����Ɏg���悤�ȑ���a�̃����Y�͍��܂���ł����BWikipedia�ɂ��ƃA�b�x���A�|�N���}�[�g�����������Y�������̂�1886�N�炵���ł��B
�����ԍ��F24680423
![]() 3�_
3�_
���X�b�]�R����������
�u����Ȋ����̌��ہv�Ƃ��Ĉ����ȏ�̂��Ƃ����߂�̂ł���A
�u���˖h�~ ���p�����v�Ȃǂł̌������ʂŏo�Ă���悤�ȁA�w�p���x���̒T��������ẮH
�����܂ł̃��x�������߂�O�ɁA��̃����N
https://coating.nidek.co.jp/article/information/type/a37?mode=amp
��
��������āA���g������(�g������)������̂ł́H
�ƋC�t�����C�t���Ȃ����ŁA�w�p���x�������߂������ɂ��ׂ����Ƃ����邩������܂���B
�����g������(�g������)���C�ɂȂ�����A�Ⴆ�Ή��L�́u�P�w���˖h�~���v�Ɓu���w���˖h�~���v�Ƃ��r���Ă݂܂��傤�B
https://jp.optosigma.com/ja_jp/category__opt_d__opt_d03
��
�O���t�̋Ȑ������ɒ��ڂ����A�O���t�̔g���͈̔�(���g���͈̔�)�ɒ��ڂ��܂��傤(^^)
�����ԍ��F24680441�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
wiki.�u�G�����X�g�E�A�b�x�v
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%99
��
�@(�Ɛ�)
��1866�N�ɂ̓c�@�C�X���w�H��i�� �J�[���E�c�@�C�X�Ёj�̌��������ƂȂ�A1886�N�ɂ͌��F�Ɠ�F�̗����̘c�݂��������������������Y�u�A�|�N���}�[�g�v������[5]�B
�����ԍ��F24680466�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
> ���C�J��R�V�i��APO���Ă͉̂��l�������ł��傤���H
�����̃��[�J�[�̏ꍇ�́A��APO�ɑ���APO�͂��z�����Ă���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�ǂ̃��[�J�[�ł����Ă�����F�������l�����Ă��Ȃ������Y�͂Ȃ��̂ŁA
���̕\�L�����Ă��鎖���̂��ÏL���u�����h�Ƃ�����ۂ͂��邩������܂���B
�܂����̂���Y�\�����ǂ��ł���A�e�탌���Y���r���[�Ŏ���F�����̒��x��
�m�F�ł��܂�����A�������������̂����Ă����Ύ��͂͂�������������܂��B
�قƂ�ǂ͉p��̃��r���[�ł��� longitudinal chromatic aberration ���
LoCA �ȂǂƏ����Ă�����̂�����ł��B
�����ԍ��F24680497
![]() 1�_
1�_
���X�b�]�R����������
>���˂�����̂́u�g���ł����������v�Ŕ[�������C�ɂȂ��̂ł����A
>�u���ߗ��v�A�b�v�̗������A�����ł��܂���B
���w�����Ŕ��˂��ጸ���邱�Ƃ��A���̔g�̐����ł��̂悤�ɉ��߁i�����j�ł���Ƃ������Ƃł��傤�B
�u�K���X�\�ʂƔ����Ŕ��˂��������ł����������Ĕ��ˌ�����������v�ƍl����ƁA�����������Ȃ����߂�����ɂȂ�̂��H�Ƃ�����Ȋ����ɂȂ�܂���ˁB
�����ł�����Ǝ��_��ς��āA�u����������ƃK���X���Ɍ�������₷���Ȃ�v�ƍl����ƁA���ߌ��������Ď����I�ɔ��ˌ�������Ƃ����̂�����₷���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��{�I�ɁA���������ɓ���₷�������͓����ŁA��������Ȃ������͕s�����ł��B
�K���X�͌��������ɓ���₷�������ł����A����ł��E�ʂ�4 ~ 5%�͔��˂��܂��B���ꂪ�����������{�����Ƃɂ���Č��������ɓ���₷���Ȃ��āA���ː�����1%�Ƃ�0.2%�Ƃ��Ɍ�������ƁB
������ɂ���A�����������̐������ƍl���邵���Ȃ��Ǝv���܂��B�s�v�c�Ȃ��̂ł��ˁB
�����肪�Ƃ��A���E����
>�����g������(�g������)���C�ɂȂ�����A
���������b�ł͂Ȃ��āA�����ƍ����I�ȋ^��ł��ˁB
�����ԍ��F24680751
![]() 1�_
1�_
���O���}���X�ȃN�}����
>���C�J��R�V�i��APO���Ă͉̂��l�������ł��傤���H
�uAPO�v��搂������Y�ƁA�����łȂ������Y���r���Ă݂�킩��܂���ˁB
�yVoigtlander Apo Lanthar 50 mm f/2 Aspherical�z
��REVIEW�iSony A7R II or the Sony A7R III�j
https://www.lenstip.com/613.1-Lens_review-Voigtlander_Apo_Lanthar_50_mm_f_2_Aspherical.html
���摜�𑜓x
https://www.lenstip.com/613.4-Lens_review-Voigtlander_Apo_Lanthar_50_mm_f_2_Aspherical_Image_resolution.html
���F����
https://www.lenstip.com/613.5-Lens_review-Voigtlander_Apo_Lanthar_50_mm_f_2_Aspherical_Chromatic_and_spherical_aberration.html
�ySony FE 50 mm f/2.5 G�z
��REVIEW�iSony A7R II or the Sony A7R III�j
https://www.lenstip.com/605.1-Lens_review-Sony_FE_50_mm_f_2.5_G_Introduction.html
���摜�𑜓x
https://www.lenstip.com/605.4-Lens_review-Sony_FE_50_mm_f_2.5_G_Image_resolution.html
���F����
https://www.lenstip.com/605.5-Lens_review-Sony_FE_50_mm_f_2.5_G_Chromatic_and_spherical_aberration.html
���摜�𑜓x�̃O���t�͓����J�����Ńe�X�g���Ă���̂Œ�����r�ł��܂��B
���F�����̃O���t�͔{���i���j�F�����ł�����uAPO�v�Ƃ͊W����܂���B
>�f�W�^���ŕ�ł��邱�Ƃ̓{�f�B���ɔC���A�����ł͂Ȃ����Ƃ������Y�œO��I�ɑΏ�����
�A�|�N���}�[�g���ǂ����Ɋւ�鎲��i�c�j�F�����E���ʎ����E�R�}�����́A�f�W�^����͂ł��܂���B
����f�W�^������Ă���̂́A�c�Ȏ����Ɣ{���i���j�F�����ł��B
�����ԍ��F24680753
![]() 2�_
2�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�����Y]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�ǂꂪ�������߁H�z�d�����Ȃ�ǂ�H���F����2����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
-
�yMy�R���N�V�����z����\��
-
�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�����Y
�i�ŋ�10�N�ȓ��̔����E�o�^�j