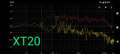このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2024年10月4日 15:02 | |
| 43 | 13 | 2024年9月3日 17:33 | |
| 7 | 3 | 2024年6月3日 00:18 | |
| 14 | 4 | 2024年5月23日 09:31 | |
| 96 | 36 | 2024年5月5日 21:29 | |
| 81 | 22 | 2024年4月24日 19:01 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
スピーカー > KEF > LS50 Meta [カーボン・ブラック ペア]
LS 50 Metaで迷っています。オーディオ専門店で質問したところ10万20万のアンプ程度ではWireless IIと大差はつかないと言っていました。
そこではアキュの40万位のアンプで鳴らしていました。KEFの店でWireless IIも聴かせてもらったのですが、環境の違いかMetaの方が良く感じました。マルチアンプで直接ドライブしているのでWireless IIの方が良かったりしないのかなとも思ったのですが...
質問なのですが、0から構築するとして、みなさんだったらどっちにしますか?また同じ環境で聴かれたことのある方の感想も伺いたいです。
アンプの第一候補はMarantz model 60n、システムのアップグレードは将来KC62を入れようかな程度です。
![]() 1点
1点
>kenken.u_uさん
こんにちは。
スピーカーとアンプでは、スピーカーの方は機種による音の差があからさまに出ますが、アンプの方は機種を変えても大差と言うほどの差はつきません。
LS50 MetaとLS50 wirelessIIはどちらもスピーカー自体は同じですからアンプによる音の差の少なさを考慮すると店員の言うことにも一理あるとは思います。
ただwirelessIIは有線接続もできますが、スピーカー背面がごちゃごちゃして個人的にはイマイチに感じます。またアンプによる差は少ないとはいえそれはそれでありますし、駆動力の高いアンプでドライブしてみるような発展性がないですよね。
なので個人的にはLS50meta + 外部アンプですね。
両者の差は15万円なので、例えばあと10万積んで、駆動力が極めて高いマランツのPM12 OSEなどを奢れば、LS50metaは実力を100%発揮するかと思います。アキュも良いですがコスパならこちらでしょう。世界的に有名で評価も定まっているHypex社のnCoreモジュールを使用しているので駆動力や音質は間違いありません。model60よりこちらをお勧めします。
書込番号:25912724
![]()
![]() 2点
2点
>プローヴァさん
ありがとうございます!
PM-12 OSE少しレビュー等見てみましたが、かなりお買い得なアンプみたいですね。
これにネットワークプレイヤーを足すとしたらどんな物があるでしょうか?
マランツのものはもう売ってないみたいです。
できれば、HDMI入力があると良いのですが...
書込番号:25912796
![]() 1点
1点
>kenken.u_uさん
HDMI入力が欲しい理由はTVの音を聞きたいからですか?
であればHDMI ARC付きのネットワークプレーヤーになりますが、高いんですよねー。DNP-2000NEとかね。
HDMIなしならWiim Proとかでいいんじゃないですか?
正直TVのARCから流れてくる音ってロッシーなマルチ音声までですし、アンプが2chだと例えばModel60n等でもTVからは2chで出力することになりますので、そのためだけにHDMI ARC付きの高価なネットワークプレーヤーを選ばなくても良いとは思います。
例えばこの手のものでRCA出力を取り出したのでも十分という気はします。
https://amzn.asia/d/aQkfjJn
まあModel60nだとオールインワンですっきりはしますよね。
DAC内蔵でデジタル入力も受けてHDMIも付くようなアンプはまあ言ってしまえば手軽さ優先で、質を追い求めてはないです。とても高いものを除いて。
書込番号:25912949
![]()
![]() 1点
1点
>プローヴァさん
ありがとうございます。
HDMIが欲しいのはお察しの通りテレビの音声を流せてテレビリモコンで音量調節できるからです。
高いものしかないということになると光デジタル入力があればよいのかなと思っております。
Wiim Proですねー候補に入れてみます。
HDMI付のアンプですが、内部構造からして半額以下のピュアなプリメインと同等なのかなーとは思っておりました。
どうもありがとうございました。もう少し悩んでみます。
書込番号:25914247
![]() 0点
0点
スピーカー > KEF > KC62 [ミネラル・ホワイト 単品]
この度,KC62白を購入しました.筐体が小さい事が決めてです.電気機器に詳しくないので,説明書を読んで分からない事があります.どなたか有識者の方ご教示ください.
1)LFE入力,ライン入力,スピーカー端子入力
どれを選択しても同じなのでしょうか?LFEとレシーバのsuboutが同じだとすれば私の環境では3つとも選択できます.どれが良いとかマニュアルには載っていないので,ケーブル一本ですむのが良いのかなとか,ステレオなんだから二本を選択するのかなとか,サブウーファだってスピーカなんだからスピーカ端子からを選択するのが良いのだろうかなとか,想像しますが...
2)80Hz当たりでクロスオーバー周波数を設定
どうやって「自然に繋がる」と判断するのでしょうか.自分の耳で「自然だな」って思えば良いのかもしれませんがとても主観的で正直,なんだかわかりません.マイクで聞きとってとか,スマホで録音してとかデータを作成して何かでグラフにでも表示するのでしょうか...
せっかくなので出来る範囲で設定してみたいと考えています.何かプラスアルファとなる情報もお教えいただければ,大変ありがたいです.
![]() 2点
2点
アンプ側でクロスオーバー設定が出来るならLFEにすべき。
アンプでそれが出来ないならばサブウーファー側でハイカットをするだけになる。フロントスピーカーのローカットは出来ないのでフロントスピーカーの出せない領域あたりに設定するのが理想じゃないかな。
スピーカー入力はできれば使いたくないところ。
書込番号:25874458 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 10点
10点
>XJSさん
ご教示ありがとうございます.余分な電気信号を送らない様に設定する.LFEがそれが可能ということですね.とても納得できます.
書込番号:25874811
![]() 0点
0点
んんん、LFEはサブウーファー側では何も制限せずにアンプ側に任せる場合です。
アンプ側でクロスオーバー設定出来ないならばサブウーファー側でマニュアルでローパスを制限しなくてはならない。
書込番号:25874849 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 8点
8点
>XJSさん
何度もありがとうございます.つまりこういうことだと理解させていただきました.
1)LFEを使うと一本のケーブルで済み,アンプ側にあるクロスオーバ周波数を何かしらの値(80Hzとか)に設定する.スピーカ側のクロスオーバ周波数をアンプ側より大きい値にする.「自然な良い感じ」に聞こえる様にこのアンプの値を調節し.スピーカ側の値は干渉しない様な値にする.
2)ステレオケーブルを使うと二本になり,スピーカ側のみでクロスオーバ周波数を何かしらの値(80Hzとか)に設定する,「自然な良い感じ」に聞こえる様にこのスピーカ側の値を調節する.
3)方法1のほうが入力信号がアンプから各スピーカに周波数を最適化した信号で送ってくれるからより良い設定である.方法2だと最適化されていない信号が送られるから,音がかぶってしまうとか起きる.
週末にリビングルームのセットで1)の方法で設定してみました.Onkyoの10年程前に家族が購入していたレシーバにLFEという設定項目がありましたので有効にしてデフォルト値80Hz(THX)のママとし,suboutからamazonベーシックスピーカケーブルを繋げました.3.1チャンネルという構成だと思います.
低音が聞こえ,中低音も違って聞こえ,第一段階は達成し満足ました.ただ,曲によっては特定の低音,ベースやコントラバスが極端に大きくかぶって鳴ってしまいます(共鳴でしょうか).恐らくこれがグラフの「凸」で後はクロスオーバ周波数を調整して「自然な良い感じ」に聞こえる様にすれば良いのでしょうね.
誤りや何かしらおかしな点があればコメントいただければと思います.ありがとうございました.
書込番号:25875119
![]() 1点
1点
ちょっと違いますね
アンプは何をお使いですか?AVアンプ?
書込番号:25875148 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 8点
8点
>すなおなさん
こんにちは。
・LFEは、KC62側でフィルタリングせず入力をそのまま出すモードです。およそ200Hzまでの音が出ます。
・MANUALはKC62側でフィルタリングするモードです。
AVアンプと組み合わせてキャリブレーションするような場合は、LFEに設定しておいてキャリすればOKです。
ステレオアンプなどと組み合わせるような場合は、MANUALに設定してレベルやクロスオーバーを自力で調整します。
自力調整の場合ですが、きちんとやるには測定器がないとできません。聴感でやるならテキトーですね。スマホなどの測定アプリは測定器ではないのであまりあてにならないです。
測定器無しでやる場合でも、フロントLRの機種や周波数特性がわかればクロスオーバーをこのあたり、とあらかじめ決めることはできます。その上でレベル調整は聴感でやればよいと思います。クロスはスピーカーに応じて決めるものです。
>>曲によっては特定の低音,ベースやコントラバスが極端に大きくかぶって鳴ってしまいます
これはサブウーファーのレベルが高すぎるのだと思います。まずはレベルを下げることですね。
本来KC62は小さいわりに結構ちゃんと低域が出せるサブウーファーなので、3.1などAV対応を目指すなら、少なくともキャリブレーション機能があるAVアンプと組み合わせて、リスニングポイントに付属マイクを置いてキャリブレーションをお勧めします。低域もレベルやアライメントが自動調整されます。
書込番号:25875151
![]() 0点
0点
御両名とも返信,投稿ありがとうございます.
>XJSさん
OnkyoのTX -NR609というモデルです.家族が10年以上前購入し,3つのスピーカー(左右と中央)がついています.
>プローヴァさん
Onkyoとスピーカーには銘打ってありますが,機種はどこに描いているのだろう...というもので,買った当人に聞いた所,アンプを買ったら貰ったと言っています.さらにKEFのスピーカを買うとスマホで上手く調整できるように説明書にあるのですが,さすがにそれはしたくないです.どこの業界も一緒だな,と思いますが :-)
一日ほど経ち,私は3.1chで音楽とテレビ,Youtubeを楽しむのですが.たまにビックリする低音が出て家族からの評判が芳しくありません.自室にあるステレオセット(+コンピュータ)に移動して,クロスオーバーの調整を練習?し,しばらくそちらで使うかもしれません.その場合はJVCのEX-A1(これも家族が10年以上前購入した物)と私が貰ったあとコンピュータ,スマホとBuetoothで繋げるためにamazonで買った無名のデバイスがあり,そのAUX outとラベルされたステレオ端子があるのでそれを使うかなと考えています.
双方とも検索すると当サイトがヒットしますね.リンクをしておきます
https://kakaku.com/item/K0000232734/
https://kakaku.com/item/20708010178/
良いアドバイスがあればよろしくお願いいたします.
書込番号:25876241
![]() 0点
0点
ひとつ訂正です
正しくは,Onkyo TX-NA609です.(検索するとTX-NR609という機種名でヒットし,コピペ間違いをしてしまいました)
書込番号:25876254
![]() 0点
0点
AVアンプですね、自動音場補正はしないのですか?
普通はスイッチをLFEにしてサブウーファーでは何も制限しない状態にしといて、アンプの自動音場補正を実行すればクロスオーバーなど自動的に設定されます。
書込番号:25876274 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
![]() 7点
7点
>すなおなさん
既に書いたように、付属マイクを立ててキャリブレーションすれば低音の過剰は抑えられると思います。
ただ貰い物でありがちですが付属品のマイクがないならキャリブレーションはできませんね。
探して無ければ、ネットオークションでも探せばマイクの出品があるかも知れません。
スピーカーの型番は背面に書いてあることが多いです。
ただオンキョーはすでに一度倒産したので、倒産前の機種情報が散逸していて、取説などもネットで見つからないことも多いですね。
AVアンプも13年前の商品なので、この機会に刷新しても良いとは思います。
書込番号:25876420
![]()
![]() 0点
0点
>XJSさん
>プローヴァさん
返信ありがとうございます.前回投稿いただいた内容,分からない部分はすっ飛ばしていたのがばれてしまった様なご返事でした.サブウーファーの設定ではなく,レシーバの取り扱い説明書を読んで設定をする方法を理解する必要があるということですか.ウェブでレシーバの取り扱い説明書を見つけて,キャリブレーションとか自動で設定とか,マイクが必要とか理解できました.メルカリ・ヤフオクで漏斗型のマイクを探してみたいと思います.
サブウーファーの質問でしたので,結論はサブウーファをちゃんと設定したければアンプの説明書を読む,という理解?で解決したと思います.ありがとうございました.
書込番号:25876631
![]() 0点
0点
すごくいいサブを入手されたんで、適切にセッティングしてほしいですね
書込番号:25876654 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 7点
7点
>すなおなさん
ですね。
AVアンプはつなげば終わりの商品ではありません。設定やキャリブレーションをしないと本来の音が出ません。
ユニット対抗配置のサブウーファーは筐体振動が最小限で、サイズの割に良質な低音を出せます。
TX-NA609はいささか古すぎですので、良質な最新AVアンプへのグレードアップとスピーカーを追加してのサラウンドシステム化をご検討ください。サブウーファーの価格からすればデノンAVR-X3800Hあたりが妥当かと。
書込番号:25876896
![]() 0点
0点
スピーカー > KEF > LS50 Meta [カーボン・ブラック ペア]
お金と部屋のスペースに若干余裕が出来たことから、スピーカースタンドを購入してLS50metaを今の卓上(インシュレーターAT6900BRのみ使用)から独立させたいです。
LS50metaを購入してスピーカースタンドと共に運用されてる方はどのスピーカースタンドを使用していますか?
専用モデルのS2 Floor Stand一択なのでしょうか?
どうにもスタンドに6万は余裕があれど即決できる値段でもないので悩んでます。
他にオススメなどあれば併せて教えて頂きたいです。
書込番号:25018792 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 2点
2点
>うわああああああああああ!!さん
>専用モデルのS2 Floor Stand一択なのでしょうか?
LS50ユーザーではありません。
デザイン的には専用が一番だと思いますが、重量が4.8kgと軽く支柱の中が空だと思われます。
よってある程度中に砂など充填剤を入れないと、音的にはイマイチではないかと。
充填剤については、検索すれば色々出てきます。
デザインにこだわらなければ、TAOC WST-C60HB、BST-60L等の重量10kgクラス以上をお奨めします。
WST-C60HBのほうが安いですが、スパイク受けが付いていません。PTS-G、PTS-Aあたりを使用しましょう。
スタンド下にオーディオボードを敷けば、さらに良くなります。
書込番号:25019799
![]() 4点
4点
なるほど、軽さが気になる感じですね…。
オススメ頂いた商品も参考にさせていただきます。
もう1~2日様子を見て他にアンサーが無いようでしたらBAさせていただきます。
書込番号:25020026 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
ずいぶん前のスレですが回答します。
昨日、表参道のショールームに行ってきました。フロアで一番年配の支配人的な人とゆっくりKEF製品を全フロア解説していただきました。その中で当スタンドの話もありました。専用スタンドはネジ固定が可能で、スピーカー側も音響的に問題ない位置に鬼目ナットを最初から設計してるので、ぜひ専用スピーカーで鳴らしてほしいとのことでした。
個人的にはスレ主さん同様、価格のバランスが悪いくスタンドが割高に感じますが、本体が気に入ってるのでしたら、思い切って買ってしまえば何年もモヤモヤせずに精神的に安定するのではないでしょうか?
書込番号:25758390
![]() 1点
1点
スピーカー > KEF > Q950 [ヨーロピアンウォールナット ペア]
この度スピーカーを追加で購入予定なのですが
先日アキバへ行って聞き倒した結果
このQ950がかなり気に入りました
DALIやB&W等もかなり聞いたのですが
何故かこの機種がしっくり来ました
ただ帰って来てから再度ネットなどで
調べておりましたら新たにR900とQ750が
気になってしまい、、、なかなか決められずにいます
このどちらもアキバでは聞いていません
どなたか実際に試聴されて
その差がどうだったのかお分かりでしたら
お聞かせ願えないでしょうか
聞くジャンルとしては
JAZZ、女性ボーカル、J-POPです
クラッシックは全く聞きません
またアンプ等はスピーカーに合わせて
買い足すつもりでおりますので
スピーカーの音質差を教えて頂けると
大変助かります
よろしくお願いいたします
書込番号:25743788 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 2点
2点
>kiro2011さん
こんにちは。
KEFの同軸は過去12回以上変更されて熟成が進んでいますので、同軸の中ではかなり良いユニットで、定位感の自然な再現性と高域をいたずらに強調しない点が美点ですね。
Q750はユニットが16.5cm、Q950は20cmの差ですね。
低域限界は-6dB表示で42Hzと38Hzで4Hzしか差はありませんが、実際に聴くとQ950の方がよりリッチな低域や艶感みたいのが再現されます。
>>DALIやB&W等もかなり聞いたのですが
DALIやB&Wは何と比べましたか?
DALIもB&WもKEFも、高いラインと安いラインでは音質は全然違ってきます。
また、Q750とQ950でも予算がそこそこ変わってくるので、まずは予算を明確にした方がいいですよ。
下剋上ってなかなかないし、高いものを見出すときりがありませんので。
どちらも予算内ならQ750に目移りする必要はないかと思います。
ところでR900って何?話の流れ的にはこれじゃないですよね?
https://jp.polkaudio.com/shop/polkaudio-bookshelfspeakers/r900_jp
書込番号:25743826
![]()
![]() 1点
1点
kiro2011さん
>Q950がかなり気に入りました
DALIやB&W等もかなり聞いたのですが
何故かこの機種がしっくり
B&Wは高解像で定評あり、
でもkiro2011さんではQ950に軍配
人の話しとはそんなもの
kiro2011さんの感性で
現物を聞かれた方がよいと思います。
書込番号:25743997 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
![]() 7点
7点
>プローヴァさん
ご意見いただきありがとうございます
正直予算はペアで50万程度にしてましたが
何となく少しお安くなりますが
この価格帯のスピーカーが気になりました
やはり750よりは950の様ですね
低域はとても気にしてます
R900は既に販売停止されてまして
https://s.kakaku.com/item/K0000320681/
になります
今丁度中古で出てましたので
気になってしまいました
もう少し悩んで決めたいと思います
書込番号:25744901 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
>あいによしさん
ご意見ありがとうございます
そうなんですよね
人の意見はあくまで参考程度
私もそう思っていたので九州から
アキバまで試聴しに行ってきましたが
結果試聴してない機種も気になりだして
この始末です
もう少し考えて決めたいと思います
書込番号:25744903 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 4点
4点
スピーカー > KEF > R3 Meta [ホワイトグロス ペア]
振動板の素材についての質問です。
このスピーカーの振動板は、ツイーター、ウーファーともにアルミニュウムです。
振動板の素材が統一されているので、音色が整っている印象です。
ただし、アルミニュウムのウーファーの音については、他のメーカーがあまり、ウーファにアルミニュウムを採用していないので、その音色に馴染みがありません。私は、このスピーカーに限らず、KEFのスピーカーの音が不思議に感じてしまいます。個人差なのかもしれません。このスピーカーの音を楽しむに当たってアドバイス頂ければ幸いです。
![]() 2点
2点
暇つぶしに試聴比較してきましたので、参考までに(笑
測定アプリでザックリ計測。
R3 METAは実機が無かったので、同素材のQシリーズで。
システム
プレイヤー
DENON/1700NE
アンプ
DENON/SX11
スピーカー
KEF/Q350
POLK/XT20
BW/706S3
DALI/OPTICON2/MK2
試聴距離/1m
音源/女性JAZZボーカル
KEF/Qは、同軸/アルミ効果なのか中域のボーカルのクリア感ナチュラル感はありましたが、他スピーカーよりもフラットではなかったですね。
POLK/XT20は、この値段で一番フラットな感じでしたが、低域に物足りない感じ。
コスパ的にはハイレベル。
BW/706S3は、解像度はピカイチで高域/10KHZの解像度が高く演出気味ですが、全体的にバランスが良い感じ。
環境が悪いのか低域がブーミーだった。
DALI/OPTICON2/MK2は、全体のバランスが高くナチュラルフラットで違和感なしだが、何か物足りない感じ。
同軸/アルミが、スペック上は一番フラット特性になるかと思ったんですが、環境に左右されやすいのか。。。
微妙な結果に終わりました。
書込番号:25712829 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
KEF/Q150
KEF/Q350
の比較バージョン
同じ同軸ユニットなので、特性はほぼ同じ。
100hz-200hz付近と1000hz付近に、同じディップが発生した。
書込番号:25712841 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
>エラーゴンさん
様々なデータを提供していただいていますが、各スピーカーの周波数特性のグラフの読み方についてコメントしてください。
赤線のグラフと黄線のグラフがありますが、それぞれ何を意味するグラフなのでしょうか。
また、100ヘルツ以下について、定在波の影響が見受けられませんが、マイクとスピーカーの測定距離は1メートル程度でしょうか。
よろしくお願いします。
書込番号:25713156
![]() 0点
0点
>Mr.IGAさん
変わった視点からのご意見有難うございます。
スピーカーの良し悪しは、聴く人によって大きく異なってくるのではないかという視点について、私も常々感じているところです。
特に低音については、人による感じ方の差が大きいと思っています。
これが、耳たぶの影響によるものだとは知りませんでした。
私の耳たぶの大きさを鏡で見てみました。大きくはありませんが、左右の比較では、右側が少し大きいようです。
私は、さほど低音を感じるタイプではないので、耳たぶの大きさによる影響について、「ガツテン」という感じです。
大阪の日本橋にあるオーディオ専門店でスピーカーを見ていたところ、店員さんから、話しかけられて、私に対して、このスピーカーの音をどう感じるか、別のスピーカーと比較してどうか、どちらのスピーカーの音が心地よいと感じるか、などなど、質問された(テストされた)ことがありました。この店員さんは、客によってスピーカの音の好みが分かれるということを前提として、客の好みに合うスピーカーを紹介しようとする態度が明確でした。この店員の質問を受けて、自分自身、どのような音を求めているのか、返答に困ってしまい、それ以降、自問自答するようになった経験があります。聴き手側の問題もあり、オーディオは意見が分かれて、奥が深いということを感じてしまいます。
さて、スピーカーの音は、聴き手により大きく左右されるということを前提として、このR3 metaは、濁りがなく、嫌な音が出ないという点では、優秀なスピーカーだと感じています。
Mr.IGAさん のご意見について、何か参考になるホームページなどがあれば、紹介していただければ幸いです。
書込番号:25713168
![]() 0点
0点
>ねるとん2さん
>周波数特性のグラフの読み方
赤が最大値
黄がリアルタイム/暗騒音
>測定距離
約1m
まあ、ザックリ測定なので参考程度ですが、Qシリーズは同じ同軸/アルミ素材なので、同じ特性なのが把握できるでしょう。
店の環境なので、後ろスペースが広大なので、定在波の影響は少なかったのでしょう。
実際の自宅環境で計測すれば、また違った結果になるでしょうが、スピーカー自体の特性はそんなに変わらないでしょう。
詳しくは、石井式音響学に書いてありますが、
ここも参考になるでしょう。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1405932.html
例えば、一般的な6畳間の場合は……
・長辺 :3.6m 47Hz
・短辺 :2.7m 63Hz
・天井高:2.4m 71Hz
といった具合で、部屋の中では、3つの周波数付近で定在波が確認できる。
実際には、壁面、天井、床の反射率(材質や強度)が影響し、厳密には音速も室温で変化(室温20度時の音速は343.5m/s)するため、計算通りには行かないが、ここでは、上下、左右、前後で定在波の“素”が発生すること。そして、その周波数がちょうどサブウーファーの美味しい帯域で発生することを理解できればOKだ。
なお、定在波は、基本となる最小周波数の2倍、3倍……も発生する。300Hzくらいまでは音質に顕著な影響が表れるため注意が必要だ。また、定在波の影響は、低音の周波数特性の乱れだけでなく、中高域の伝送特性にも大きく影響する。端的には音質が悪い方向に変質する。
では、劇場映画館の場合はどうなのか。御存知の通り映画館はホームシアターと違って空間が広いため、定在波が生じる周波数も数Hzと非常に低い。つまり、音の定在波は、ホームシアター特有の課題と言っていいわけだ。
書込番号:25713295 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
ねるとん2さん
>濁りがなく、嫌な音が出ないという点では、優秀なスピーカーだと
ペア80万円のスピーカーを聞きました
クラシックはとてもよかった
シネマになり、アクションシ―ンになったら
銃撃、衝突、破壊、全て鈍って、ぜんぜん楽しめない
マエストロのような人が特定ジャンルで音作りすると
元の音からかけ離れたようにも出来るのかと驚きました。
メーカ―側は音で他と大きく差別化出来ないと
客を引き付けられないし
値段が付けられないのかもしれませんが
シネマは痛い音、嫌な音、混濁したような、
複雑不協和音も表現として使います
クラシックだけで飛び着かず
いろんなジャンルを聞いて、得手不得手なく再生
させてみないとわからない。
結局、入っている音は、素直に出せるのが
よいスピーカーでしょう
音色を変えたければAVアンプ側
変えた音色を素直に出してくると思います。
上記は腹芸で音を変えてしまう例
他にも、細かい音、痛い音はバッサリ消して
ツィ―タ―で細かな音を独自付与
ちょっと聞きでは情報量があるように聞こえる
何を聞いても、いい音のスピーカーもありました
アンプの試聴会に行って聞きましたが
さっぱり音の違いがわからない、不思議な音でした。
書込番号:25713398 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
>ねるとん2さん
>>自分自身、どのような音を求めているのか、返答に困ってしまい、それ以降、自問自答するようになった経験があります。
好みは確かにありますね。昔のスピーカーは解析技術が今ほど発達してなかったので、特性をフラットに作るのが難しかったので、聞く方も好みの見極めが大事でしたが、今は良いとされるスピーカーの多くはフラット指向で設計されています。作る側も誰の好みを基準に作ればよいかなんてやってたら、ギャンブルになっちゃいますからね。
もうだいぶ前になりますが、地元のオーディオショップで、31バンドのグライコを使って徹底的に周波数特性をそろえた実験をやったことがあります。3つのスピーカーをスペアナを使いながらフラットになる様調整するわけです。
これはこれで結構手間がかかる作業ですが、それを行ったあとでグライコをオンオフできるようにして比較視聴します。
これをやると、どのスピーカーもとても似た様な音になりますので、スピーカーのキャラって周波数特性のばらつき要因が大きいということが当時わかりました。
調整した音は音の鮮度と言う点では若干劣るかもだけど、クラシックもジャズもポップスも何を聴いてもそつなくこなし、コンテンツによる相性が殆どなくなります。
このあたりが個人的には原点の体験であって、それ以降はパッと聴きの好みではなく、フラットであることを指標に製品の見極めを考えるようになりました。ジャスにだけ向くような演出やクラシックにだけ向くような脚色は不要と言うことです。
実際に最近の高級スピーカーって何を聴いてもいい、という感じに聞こえる場合が多いですね。
>>さて、スピーカーの音は、聴き手により大きく左右されるということを前提として、このR3 metaは、濁りがなく、嫌な音が出ないという点では、優秀なスピーカーだと感じています。
R metaはフラットさと指向性の広さを科学的に突き詰めていますので、さもありなんです。spinoramaなどでもQシリーズとは隔絶した特性になっていますし、一聴して違いが判ります。中身は値段なりと言うことです。
書込番号:25713404
![]()
![]() 1点
1点
>プローヴァさん
貴重な体験に基づくご意見有難うございました。
「スピーカーのキャラって周波数特性のばらつき要因が大きいということが当時わかりました。」ということですが、非常に参考になります。「フラットであることを指標に製品の見極めを考えるようになりました」ということですが、ご自身の基準がしっかりしているので、自信を持ってご意見を発言されているのだと思います。私は、なかなか自分の考えに自信を持てないものですから、様々な質問を繰り返しています。
書込番号:25714056
![]() 1点
1点
ねるとん2さん
>フラットであることを指標に製品の見極め
フラットであっても設置したら、
何らかの部屋の影響を受けてしまいます
部屋に置いて、その環境に合わせフラットに
することが必要です
スピーカーは解像度の高いもの、
情報量の多いものを選びます
活きがよく音数が多く楽しいもの
それを部屋に入れて、フラットに調整します
ドレミが滑らかにならないピアノでは
名演奏は聞けません
反対に情報量が少ないものは音数が少なく
寂しく聞こえます。
フラット調整すると、余計に元気がなくなり
やらない方がマシな場合があったりします。
書込番号:25714229 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
>ねるとん2さん
>私は、なかなか自分の考えに自信を持てないものですから、様々な質問を繰り返しています。
参考までに、オーディオの基本は、、、
「オーディオ機器」30%
「セッティング」30%
「部屋の環境」40%
と言われていますので、
「機器」と同等以上に「セッティング」、そして「部屋の環境」が重要になります。
機材だけアップグレードして、音が良くなると思わない方がいいですね。
それと、、、
良い音を求めてスピーカー/フラット特性にこだわりすぎるというのは、音楽を楽しむという本来の目的からどんどん離れて行くことを意味します。
そういう人は、たいていKEFとフルスペックAVアンプを好みます。人によってその組み合わせは違いますが。
理由は簡単です。
はるか何十年も前から評論家が評価し、良いものとされている上に、見た目の高級感があるからです。
ようは、権威に負けているだけ。
耳は肥えてないのです。
単純にサウンドで選んだら、5分の1の価格のアンプやフルレンジスピーカーの方が出音素晴らしかったりします(笑
これも、オーディオマニアや評論家が良いと言っているから。
全部、他力本願。
お金で安心を買っているだけです。
AV鑑賞はキャリブレーションが前提なので、なおさらです。
書込番号:25714248 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
エラーゴンさん
「オーディオ機器」30%
「セッティング」30%
「部屋の環境」40%
スタジオ関連雑誌で音への影響
部屋70%機器30%の記載あり
一致してますね。
機器のうち90%がスピーカーと言ってました。
アンプやDACの性能差に比べ
電気を音に変換する部分は、性能、能力、千差万別
書込番号:25714459 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
書いてる途中で飛んでしまいました、すみません
部屋とセッティングで70%なので
チュ―ニングで効果が大きいのは説明がつきますね
書込番号:25714463 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
>ねるとん2さん
ありがとうございます。でもそんな大した話でもないです。
理系と言うのは元々物理的な原理原則に従って理解しようとする癖がついていますが、それとは別に経験年数というか経験値が高くなると、過去の類似体験に当てはめて理解しようとする要素も出てきて、本人的には原理原則と合わせて理解が深まった気になっちゃったりします。一家言あり状態になるわけですね(笑)。
オーディオも今や、各社生き残りをかけて玉石混交状態になっているので、昔のようにやれJBLだタンノイだといったように、ブランドで商品を選んでいる場合ではありません。新進メーカーでもいいスピーカーは出てきてますね。
でも当然ながら物理原則の上に成り立っていて、その原理原則をどう利用するかで設計方針が変わっている感じです。だから物理原則の理解があるとないとでは理解の深さは違ってくるとは思います。
例えば、感度の高いシステムは歪率の低減や指向性が課題だし、感度が控えめのシステムはアンプの駆動力を要求する、どっちがいいかなんて永遠に結論は出ないと思います。でもどちらも追及すると金がかかるのは間違いないですね。今は低能率・低歪方向の設計勢力シェアが大きい気はなんとなくしますが、高能率方向だとやはり本筋のコンプレッションドライバーが気になります。これもがっつり高価ですからね。
私も今回老舗のKEFを買ってみたけど、人生初のKEF購入だったのでブランドに対して特段の思い入れはありません。でも試聴して、買ってみて、聞いてみて良かったので、質問されれば体験についてはこってりお話できます(笑)。
スピーカーの特性がフラットでも意味がない、みたいな意見もあるようですが、個人的にはその様に思っていません。
余程変な部屋でない限り、スピーカーの周囲をそこそこあけて壁からの距離をとって適正に設置すれば、中高域はほぼほぼスピーカーの特性通りの音が出ます。低域は定在波があるんでどうしてもピークディップができますが、これは仕方ないですね。
AVアンプでキャリブレーションしても補正量が多くなると歪も大きくなるので、なるべく中高域は低補償でいけるのが望ましいかと思います。
また、フラットな特性のスピーカーは無味乾燥だの、味気ないだのとイメージで言う人もたまにいらっしゃいますが、全然そんなことないですよ。
フラットになるように高度に設計されたスピーカーは世の中多くありますが、その中でも、やはり聴感上の差は少ないながらしっかりあり、そういう微妙な差を楽しむような時代なのかなとも思います。
書込番号:25714534
![]() 2点
2点
>あいによしさん
>スタジオ関連雑誌で音への影響
部屋70%機器30%の記載あり
一致してますね。
スタジオ系は、セッティングに一番うるさいでしょうし、石井式でも徹底的に検証されてますからね。
突き詰めるとそうなるんでしょうね。
>フラット
スピーカー自体のフラット性って、別にKEFだけじゃなくてYAMAHAとかもその方向ですから、KEF=フラットとイメージはないですね。
同軸型/Uni-Qドライバーだってもう昔からやってる訳ですし、目新しさはないですね。
それに、技術的とかコンピューター解析だって今じゃどのメーカーも当たり前ですから、メーカーとしては、差別化する為のブランディングワードとして、活用してるに過ぎないでしょう。
ある意味、、、
SONYの、ハイレゾ/360SSMみたいなもんですね(笑
それと、KEFショップは、今まで以上にブランドイメージ戦略に力を入れてく方針みたいですから、青山にショップ移転しましたしね。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1553619.html
昔からのオーディオマニアよりも若者ターゲットカモ。
技術で訴求しても、今どきの若者は分からないでしょうし(笑
私も含めてですが。。。。
最終的には、ラーメンのトッピングみたいに、マニュアルEQとかで自分好みの音に調整してしまうので。。。
書込番号:25714737 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
ベテランの皆様がお書きですが、当方からも考えを書きたいと思います。
理論的に上手くいい音が出るよう設計され、各種測定値が良くなるよう改良を加えて作られた製品〜これはややもすれば国内製品に思い当たるフシがあると思います。
もう一つは、試作品の試聴を繰り返し、希望する音へ改良を加えた製品〜ブリテッシュオーデオと世界中から評価されるイギリスを中心としたヨーロッパ製品
What Hi-FI誌はイギリスの雑誌であることもあり、自国製品へ評価が高いかも知れませんが、それを差し引いても日本製スピーカー
には厳しいみたいです。(再出発したテクニクスには「これがテクニクス?」と書かれていましたし、日本国内でも売れていないみたいです、ヤマハもヨーロッパへ進出してますが、余り売れてるとは見かけません、他方、ブリテッシュからだけで10社程度日本で売られています)。
それからリスニングルーム環境が大きく音に影響を与えるとのプロのお話のようですが、一般住宅での具体的にどうすれば良くなるのか改造など困難であり、その置かれた環境でリスナーの望む音が出せる製品選びとセッテングをするのがいいと思います。
書込番号:25714945
![]() 0点
0点
>里いもさん
こんばんは。
>リスニングルーム環境が大きく音に影響を与えるとのプロのお話
石井式は、プロの現場でも採用されてますが、基本的には観賞目的のものですね。
>ブリテッシュオーデオと世界中から評価されるイギリスを中心としたヨーロッパ製品
スピーカーはやはりブリティッシュが世界をリードタイムしてる感じですよね。
KEF自体は、スピーカー買う時に購入しようかと思ってぐらいなので、好きでも嫌いでもないんですが、、、
結局、BW買っちゃいましたね(笑
で、そのあとトールボーイ系を買う際も、色々、比較試聴した結果、KEF買おうかなと最後まで思ってたんですが、KLIPSH買っちゃいましたね。
同じアルミですが、ホーン型でクリア感が高かったので。
また次に同じ30万クラスで買うなら、私はLINTON 85TH/が欲しいですね。
ヴィンテージ感が好みなんで。
なんだかんだ言って、KEFはフラットとか関係なく決め手にかけるというか、なんか最終的に購入に至っていません。
ワイヤレスのLSX II LTなんかは、デスクトップ用には買ってもいいかなと思ってますが、自作フルレンジを製作予定なので、それ作ったら置く場所ないし厳しそうです。。。
書込番号:25715144 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
ちなみに、
>里いもさん
的には、ブリティッシュスピーカーの評価/KEF含めてどんな感じなんですかね?
書込番号:25715160 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
言われてるように部屋環境次第は正解。
住宅は、軸組工法よりツーバイフォー、ツーバイシックス、モノコック構造の住宅にした方が音が良いとされてます。また寒冷住宅使用の密度の高い部屋が理想ちゃ理想です。
KEFの流れで!
このメーカーはシアターシリーズのスピーカーが1番良いかも知れない。LSを知人宅でロック、ジャズ、アニソンを聴いたけど、特にはって印象だった。
やはりピュアは、アンプはオーディオラックに
スピーカーセットアップは重要でして!
スピーカー振動板の材質の事を語るには、それなりの準備をしてからですね。
書込番号:25715534 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 3点
3点
>ねるとん2さん
すいません資料がありません。
医師の言うことをそのまま書いたのと、海外こ会社に在籍していたときに、Customer ネゴシエーション skillsと言うTrainingで、顧客を知る前に論理を知ろうとの中で、ボストンコンサルの人からの受売りを書かせて頂きました。因みに、耳たぶの影響もあるとので、スピーカに正対して、耳の後で手を開くと聴こえる音も変わります。
私もオーディオ店でどのような音が好みですかとよく言われました。最近は言われる前から、???のような音が好きですと言うのですが、そんなことを言うと、ハイエンド製品を勧められ、まんまと、ショプの罠のに捕まります。
書込番号:25722538 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
>Mr.IGAさん
回答があったのに気付くのが遅れてしまいました。
>>スピーカに正対して、耳の後で手を開くと聴こえる音も変わります。
ということですが、簡単に試すことができるので、やってみました。
低音の聴こえ方が大きく変わるのかと思っていましたが、そうではありませんでした。
自分の両耳のすぐ後ろにそれぞれ掌(てのひら)を開いた状態で当ててみたところ、音がくっきりとしました。
低音が増強されるとか、低音がよく聞こえるとかではなく、ごく簡単に、自分の後方からの反射音が掌で遮られることによって、前方から来る直接音がより、はっきりと聞こえました。さらに、自分の耳の後方だけではなく、横方向からの音を遮るように掌で耳を覆うようにすると、より一層、前方からの音がくっきりと聞こえてきました。
こんなに簡単に聴こえ方が変わるのであれば、ルームアコースティックを工夫するよりは、自分の耳の周辺に工夫を凝らす方が安上がりで効果的であるということを認識しました。
書込番号:25725296
![]() 1点
1点
スピーカー > KEF > R3 Meta [ホワイトグロス ペア]
このスピーカーの仕様を見ていたところ、インピーダンスが4Ωでした。アンプとの相性問題を含めて、アンプに何らかの影響があるのでしょうか。
また、スピーカーの能率についてですが、仕様では、「感度 (2.83V/1m):87dB」と記載がありました。これは、能率とイコールでしょうか。それとも、スピーカーのインピーダンスが低いと、音が出やすいということを考慮すると、8Ωのスピーカーと比較して、能率は、87デシベルよりも高くなるのでしょうか。なお、インピーダンス8ΩのB&W 705 S3 では、「感度 88dB spl (2.83Vrms, 1m)」とありますので、能率としては、87デシベルであるという理解でよろしいでしょうか。
KEFがこのように低インピーダンスのものを製品化している理由は何なのでしょうか。参考になることがあれば教えてください。
![]() 2点
2点
>ねるとん2さん
good questionですね。
能率の指標は昔はdB/W/mでしたが最近はdB/2.83V/mが使われますね。
ざっくりいうとどちらも同じアンプで音を出した時の音の大きさの指標になりますが細かい差はあります。
例えば8Ωスピーカーに2.83Vを加えると、
P=I・V=V/R・V=V・V/R=2.83x2.83/8=1Wになります。この場合dB/W/mと同じですね。
4Ωスピーカーに2.83Vを加えると、
P=2.83x2.83/4=2Wになります。
つまり、4ΩのスピーカーはdB/2.83V/m指標だと実際は2W食わした時の音の音の大きさを示すことになるので、dB/W/mではなくdB/2W/m相当になるってことになりますからdB/W/mで表現するより能率数値は高く見えるってことにはなります。
でも、実際に同じアンプで駆動したときの音の大きさを正確に示すという点では、インピーダンス影響も加味したdB/2.83V/mの方が聞こえる音の大きさ指標として正確という言い方はできると思いますね。
一方で、インピーダンスはアンプの最大出力に影響を与えます。
電源部に十分余裕のあるアンプなら8Ωで最大出力100W出るアンプなら4Ωで最大出力200W出ますが、非力なアンプなら4Ωでも150Wしか出ないかも知れません。
でもこれはあくまで最大出力の話であって、普通の音量(電源の余裕範囲内)で聞いているなら、スピーカーの能率dB/2.83V/m通りの音の大きさの差が出るということになります。
最近dB/2.83V/mの指標が用いられるのは、インピーダンスに関係なく同じアンプでの音の大きさの指標になるからですね。
またメーカーや機種によってインピーダンス値が異なるのは完全に設計都合です。インピーダンスの大小で変わってくるのはアンプの最大出力だけであって、実際に聞く音量では音質に影響は与えませんから。
昔フォステクスなどは同じユニットでインピーダンス違いのものを何種類かだしていましたが、これは複数ユニットを並列接続や直列接続などする際の自作派の都合に合わせてのラインナップでした。音質はインピーダンスが違っても同じでした。
スピーカーのスペックは、技術に明るい人が見れば、スピーカーの成り立ちを想像する手掛かりになる場合はあります。±3dBの周波数範囲の広さは周波数特性のフラットさの指標、最大入力と能率は音の大きさの指標にはなります。でも数値を見たところで実際の音は想像できません。スレ主さんの場合小型フルレンジでの音の小ささが悩みなので能率と最大入力は良くチェックすべきですね。
書込番号:25708452
![]()
![]() 4点
4点
>ねるとん2さん
こんにちは、詳しくはないので誤っていたら済みませんが、
アンプの仕様の一例で最大出力は4Ωで100w、8Ωで50wとなっていますので、スピーカーのインピーダンスが低いと多くの電流を流すのでアンプ側は負担がおおきくなるという関係と思います。オームの法則
能率が良い(高い)と小出力アンプでも大きな音が出せます。今の能率が低いスピーカーは半導体アンプの進歩に合わせて、スピーカー製作側でも構造や素材も融通が利くようになったと思います。(複数のユニットの場合は能率は計算値らしいです)
スピーカーのインピーダンス(抵抗値)は周波数で違いますので、フルレンジスピーカーユニットの特性を見ると感じとれます。この例では最低値が4Ωというでしょう。複数ユニットの場合はネットワークを介して組み合わせています。
現在のスピーカーはコンピュータで動的解析されて箱を含めて製作されていますので、購入する人はご予算内で好みの聴感やデザインで選べば良いと思います。音の大きさではアンプも半導体アンプなら問題は無くて、真空管アンプはきつい場合があると思います。
書込番号:25708532
![]() 6点
6点
>ねるとん2さん
シンプルに言うとこんな感じですね。
4Ωのスピーカーを使用する場合、アンプにいくつかの影響があります。
1. 電力供給: 4Ωのスピーカーは電気的に負荷が低いため、アンプはより多くの電力を供給する必要があります。これにより、アンプがより高い電力を消費し、熱を発生させる可能性があります。
2. 安定性: 一部のアンプは4Ωの負荷に対して安定性が低い場合があります。特に低品質なアンプでは、4Ωの負荷に対応できないことがあります。これにより、歪みや不安定な動作が引き起こされる可能性があります。
3. インピーダンスマッチング: アンプとスピーカーのインピーダンスが一致しない場合、信号伝達の効率が低下し、電力損失が発生する可能性があります。これにより、音質が劣化する場合があります。
総じて、4Ωのスピーカーを使用する場合、アンプにはより多くの電力供給が必要であり、安定性やインピーダンスマッチングに注意する必要があります。
スピーカーメーカーが4Ωのスピーカーしか提供していない理由はいくつか考えられます。
1. 効率と出力: 一部のスピーカーメーカーは、4Ωのスピーカーを提供することで、より効率的な電力の利用や高い出力を実現することを重視している場合があります。これは、4Ωのスピーカーが電気的に負荷が低く、より多くの電力を吸収できるためです。
2. マーケティング戦略: スピーカーメーカーは、特定のニッチ市場や需要に焦点を当てている場合があります。そのため、4Ωのスピーカーの提供により、特定の需要に対応することができる可能性があります。
3. テクノロジーの選択: メーカーが特定の技術や設計アプローチを採用している場合、それに適合するインピーダンスが4Ωである可能性があります。この場合、メーカーはその技術を最大限に活用するために、4Ωのスピーカーを提供することがあります。
総じて、スピーカーメーカーが4Ωのスピーカーしか提供していない理由は、様々な要因によるものですが、効率や出力、マーケティング戦略、テクノロジーの選択などが関与している可能性があります。
また、スピーカーメーカーが4Ωと8Ωのスピーカーを提供する理由はいくつかあります。
1. 選択肢の提供: 異なるインピーダンスのスピーカーを提供することで、顧客に選択肢を与えます。一部のアンプやシステムは特定のインピーダンスに最適化されているため、顧客が最適なスピーカーを選択できるようになります。
2. アンプとのマッチング: 一部のアンプは4Ωの負荷を扱いやすい場合があります。そのため、4Ωのスピーカーを使用することで、アンプとのマッチングを最適化できます。一方、他のアンプは8Ωの負荷により適している場合があります。
3. 効率の最適化: 一部のシステムでは、4Ωのスピーカーの方がより効率的に電力を利用できる場合があります。特に、大きな音量や低い周波数での再生を必要とする場合、4Ωのスピーカーが好まれることがあります。
総じて、異なるインピーダンスのスピーカーを提供することで、顧客がそのシステムや環境に最適な選択をすることができるようになります。
能率はそのまんま87dbでしょう。
鳴りやすさでは、イクリプスよりも高いでしょう。
まあ、自宅の視聴距離含めて、アコースティックデザインすると良いでしょう。
書込番号:25708617 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
![]() 7点
7点
>ねるとん2さん
>インピーダンス4Ωは、アンプにどのような影響がありますか。
8オームのスピーカーに比べてアンプの必要な電圧は低くなる代わりにたくさんの電流を流せる必要がある、となりますね。
アンプの個別回路の電流負荷が大きくなるということです。
あと、アンプに2組のスピーカーを並列接続する場合(出力AとBと2系統ある場合でも中はつながっているので同じです)、4オームのスピーカーを2組繋ぐと合成抵抗が2オームになり、抵抗が低すぎてアンプが対応しきれないという場合もあります。
4オームのスピーカーが増えた理由は私は知りません。
専門的なことは分かりませんが、能率と感度については私はどっちも一緒じゃんと思ってます。
ただし、
87dBとかだけ言った場合は単位がないので意味がない数字です。
感度 (2.83V/1m):87dB
というのは他の人も書かれているように、
昔は 8オームのスピーカーで 1Wで鳴らした場合の1mの距離での音量をデシベルで表すことが多かったのですが、
最近は4オームのスピーカーとかも増えてきたため、昔の基準と同じ電圧をかけた場合の音量で表すようにしたものです。
2.83Vというのは 8オームだと1Wになりますが、4オームだと2Wです。
逆に8オームで1Wの時の電流は 0.35アンペアですが、その電流で4オームで鳴らすと1.41Vになり、0.5Wの出力となります。
V = IR,
P [W] = IV = I x I x R
1 [W] = I x I x 8,
I = (1/8)^(1/2) = 0.3536 [A] 8オームで1Wで鳴らした時の電流
V = IR = 0.3536 x 8 = 2.83 [V] 8オームで1Wで鳴らした時の電圧
V = IR = 0.3536 x 4 = 1.41 [V] 4オームで1Wで鳴らした時の電圧
P [W] = IV = I x I x R
= 0.3536^2 x 4 = 0.5 [W] 8オーム1Wの時と同じ電流で4オームのスピーカーを鳴らした時の出力
ちなみに4オームのスピーカーを1Wで鳴らした場合は 3dB小さい数字になります。
感度 (2.83V/1m):87dB (4オーム) は
感度 (1.41V/1m):84dB (4オーム)と同じであり、
84dB/W, mと同じ意味です。
ワット数で考えるか、電圧で考えるかの違いですね。
電圧で考えた方がおそらくアンプのボリューム位置が同じで比較できるから分かりやすいのだと思います。
ただし、スピーカーによっては周波数によって抵抗がかなり変わる場合もあるので実際はそう単純でもなかったりします。
同じでdB/Wmの 8オームのスピーカーに比べて4オームのスピーカーだとボリューム位置は低くて済みますが(=電圧は低くていい)、その代わりに電流がたくさん必要でむしろアンプには負担が大きいと考えるのが普通だと思います。
ポータブル機器などでインピーダンスが低い方が鳴らしやすいと言ったりするのは電池駆動だったりで電圧が上げにくいポータブル機器ではインピーダンスが高いと電圧が足りなくなりがちだからですね。ただしヘッドホンなんかでも高級機の能率低めの低インピーダンスの平面磁界ヘッドホン(13オームとか)はむしろ電流が足りなくなって鳴らしにくいことの方が多いですね。
100V駆動の家庭用機器(ブレーカー付近含む)と比べて12V駆動の自動車だとバッテリーにつながっている電源ケーブルが異様に太いのは電圧が低いため電流をたくさん流してワット数を稼いでいるためです。
アンプでも同様にスピーカーの抵抗が低いと低い電圧で電流がガンガン流れちゃうのでその電流に耐えられる設計にする必要が出てきます。
アンプの場合、8オームでの出力に対して4オームの出力が2倍になっているものはアンプの回路の最大許容電流の制限がかからずに理論値通り2倍になっているので余裕がある設計ということになりますね。Accuphaseの上位機なんかは電源がしっかりしていて2オームまでリニアパワーで倍々になるって売りにもしていますね。
比較的鳴らしにくい平面磁界スピーカーのマグネパンなんかは4オームの時に8オームの2倍の最大出力になるアンプを推奨したりしています。
書込番号:25708710
![]()
![]() 8点
8点
済みません、誤記があったので訂正と追記です:
誤:
> V = IR = 0.3536 x 4 = 1.41 [V] 4オームで1Wで鳴らした時の電圧
正:
> V = IR = 0.3536 x 4 = 1.41 [V] 8オームで1Wで鳴らした時の電流を4オームのスピーカーで流す時の電圧
追記:
ちなみに
8オームのスピーカーでは2.83Vで1Wですが、
4オームのスピーカーでは2.83Vでは2Wで、2.00V で1Wになります。
V=IR
2 = I x 4
I = 2/4 = 0.5 [A]
P [W] = IV = I x I x R = 0.5 x 0.5 x 4 = 1.0 [W]
同じ1Wの出力でも8オームの0.35A に比べて4オームのスピーカーでは 0.5A とより多くの電流が流れます。
8オーム1Wのときと同じ電流だと4オームのスピーカーでは0.5Wにしかなりません。
書込番号:25709257
![]() 4点
4点
>エラーゴンさん
>プローヴァさん
>core starさん
非常に詳しい解説ありがとうございます。
単純な質問について、このように様々な方から解説していただき恐縮します。
書込番号:25709370
![]() 0点
0点
なんか うまくまとまらないので雑談的に書きます。
◎スピーカーのインピーダンスはいいかげん
スピーカーのインピーダンスって周波数によって変動していて 一般的にいちばん低いところを示すんですが、かなりいいかげんです。
https://soundfort.hatenablog.com/entry/2021/12/speaker-impedance
本当は、周波数/インピーダンス特性グラフをカタログに載せて開示するべきですが、周波数特性はともかくインピーダンス特性まで開示している例はあんまり見たことがないです。
インピーダンス実測値とスピーカメーカーの仕様値は メーカーによって違うでしょうけどかなりいいかげんなんで あまり気にしてもしょうないです。
◎4Ωのスピーカーが増えてきたのは、アンプの電源電圧がだんだん下がってきたせいではないかと邪推します。
例えば、カーオーディオの12Vバッテリーを使う場合、インピーダンスが低いほうが出力が稼げます。
昔は、トランス電源で巻線比変えて電源電圧を作れたのでアンプ回路の電源電圧が50〜80Vってよくありましたが、ACアダプタ駆動のアンプも増えてきたこと、パワーICを使う場合、上限電圧が36Vくらいのが多いこと、D級ICはもっと低いのが多かったりします。
アナログアンプだと電源電圧に対して出力電圧が低くなるんで出力下がりますが、D級アンプだと 電源電圧=出力電圧にできるので低電圧でも出力が稼げるんで電源電圧が下がってきたのでしょう。
◎アナログアンプは限界に達しなければOK
アナログ出力のアンプに関しては 出力素子(トランジスタ、FET)で損失する電力の設計上の上限や出力電流の上限があって それを守れば動作します。
また、電源の設計と出力素子の設計によって来まる出力電流の上限があります。
これは設計上の熱損(A〜B級など)、電源電圧、放熱設計、周囲温度等があって個々のアンプによって どれが先に限界に達するかによって違います。
市販のアンプはやばい状況になると動作する保護回路があるんで 過剰に心配する必要はなくて 保護回路動作しなければOKと思っていてよいです。
◎D級アンプは スピーカーのインピーダンスによって設計が違う
アナログアンプは 極論すれば限界に達しなければどんなインピーダンスのスピーカーに接続しても動作は変わらないんですが、D級アンプは事情が違います。
D級アンプは300KHz以上でスイッチング動作しているので そのままスピーカーに垂れ流すと 無音でも一発でツィータが焼損するんで 可聴周波数だけ通すローパスフィルタ(ポストフィルター)をアンプICとスピーカーの間に入れます。
このローパスフィルタの定数が、スピーカのインピーダンスによって定数が違います。
添付の図は YAMAHAのD級アンプIC YDA138のデータシートの抜粋ですが、パワーICの製造メーカーによって明確にスピーカーインピーダンスとフィルターのLとCの値の対応が規定されています。
実際に、フィルターの定数とスピーカーのインピーダンスがミスマッチした時に不具合が起こるか? 音質の低下はあるか?と言うと よく使う TDA7498EとYDA138に関しては、はっきりした差がないというのが僕の印象ですが 他のICはいじったことが無いのでわかりません。
余談ですが、D級アンプのポストフィルターに使いL,Cの素子の質は ものすごく音質に効くキーパーツで D級アンプ改造する時に真っ先にいじります。
この素子の選定が スピーカーのインピーダンスによって違うので 設計時に終わってますが、スピーカーのインピーダンスに影響があることになりますかね。
書込番号:25709380
![]() 5点
5点
>ねるとん2さん
>>非常に詳しい解説ありがとうございます
chatGPTのコピペ回答よりもわかりやすければ良かったのですが、どうでしょうね(笑)。
書込番号:25709482 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
>ねるとん2さん
当方は、プロの開発者じゃないので、ただの素人解説です(笑
詳しくは、KEF/プロショップか、オーディオショーなどで、メーカー開発者に聞くと良いでしょう。
KEF/素人よりも、詳しく教えてくれると思います。
書込番号:25709993 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 4点
4点
締め切ったのでどうでもいいですが。
ダンピングファクターに触れていませんので
一般的に100(インピーダンス8オーム)あれば問題ないって事ですが駆動力のないアンプつまり
電源トランスや電源回路や増幅回路が貧弱なら計算上、インピーダンス4オームなら50になってしまいます。
ダンピングファクターの計算式。100=インピーダンス8オーム/出力回路の内部抵抗0.08オームです。
ダンピングファクターは電気ブレーキようなものです。ウーハァーから発生した逆起電力を熱などに変えます。
ウーハァーの不要な動きをセーブします。
低インピーダンスの場合、
一般的によく言われる事はボイスコイルが軽くなります。レスポンスがよくなるのですがその分アンプの
駆動力、制動力が必要になります。アンプを選ぶことになります。
音圧デシベル計算では音声出力が2倍になってもデシベルでは約3dbほどしかかわりません。
書込番号:25710927
![]() 4点
4点
>次世代スーパーハイビジョンさん
それを言うなら。
一般的なリニアアンプは、定格出力付近までは、出力を上げれば上げるほど歪率が下がっていく、という特性を持ちますので、アンプの電源余裕範囲内で使うなら、低インピーダンス負荷で動作点を上に持ってきた方が歪率の小さい領域を使えるということになろうかと思います。
書込番号:25711119
![]() 1点
1点
>低インピーダンス負荷で動作点を上に持ってきた方が歪率の小さい領域を使えるということになろうかと思います。
?
論点がずれていると思いますが。そもそも電子回路の内部抵抗を低くするには限界がある。
低インピーダンスやダンピングファクターをあまり理解されていないようですね。
書込番号:25711131
![]() 6点
6点
>次世代スーパーハイビジョンさん
ダンピングファクターの話はおっしゃる通りですが、歪率の観点からは別の話になるでしょう、とお伝えしたかっただけですが、ダンピングファクターの話しか理解されていないようなので話にならないようです。もう結構ですよ。
書込番号:25711148
![]() 2点
2点
そもそも電子回路の内部抵抗を低くするには限界がある。
だから最終段をパラレル構成やバランス構成にする。
書込番号:25711150
![]() 3点
3点
もう結構ですよ。
ひずみ率の話は最初からしていませんから。
低インピーダンスは電流を多く流す必要があるんでデバイスを選ぶという事を述べているんで。
書込番号:25711163
![]() 7点
7点
締め切りしているのでアレですが。
カーオーディオとピュアオーディオを混同といいますか。ごちゃ混ぜにしているようで。
カーオーディオはカーバッテリーが電源で低電圧で内部抵抗が低く大電流が供給できる。
一方、ピュアオーディオには必ず電源トランスがあり大電流を取り出すにはコイル線を太く
する必要があり必然的に鉄心が大きくなり大型で重量が重くなる。洩れ磁束も配慮する
必要がある。
書込番号:25711298
![]() 3点
3点
>次世代スーパーハイビジョンさん
何をお怒りなのか理解できませんが、当方はダンピングファクターの話について否定も肯定もしておりませんし、その話題に触れてすらおりません。
書込番号:25711328
![]() 1点
1点
既に同様の事、書いておられて重複しますが。
各メーカーの定格出力とひずみ率の計測条件。スペックを見ればおわかりになりますが。
PMA-2500NE
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-amplifiers_ap/pma2500ne_ap
アキュフェーズE-700
https://www.accuphase.co.jp/cat/e-700.pdf
ヤマハA-S2200
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/a-s2200/specs.html#product-tabs
ヤマハA-S3200
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/a-s3200/specs.html#product-tabs
価格が一番高いから当たり前でしょうか。アキュフェーズE-700は他社を圧倒している。
20hzから20khzにおいて定格出力。
定格出力。
8オーム35ワット
4オーム70ワット
2オーム140ワット
定格出力時のひずみ率。
2オームから4オーム負荷でひずみ率0.05パーセント。
8オームから16オーム負荷でひずみ率0.03パーセント。
アンプを選ぶ際、このあたりのスペックを参考にされたらよいかと。
DENONさんはお茶を濁したような感じですが。ヤマハさんは正直ですね。
書込番号:25712185
![]() 1点
1点
表示されているスピーカーインピーダンスは1KHzでの値です。
スピーカーの形態(バスレフ、BH、,密閉型)によって対周波数インピーダンスは変化します。
ソースはシングルトーンじゃなく、例えばバイオリンは多くの倍音が含まれてます。
書込番号:25712660
![]() 1点
1点
参考までに、、、、
LUXMAN/507Z
110W/8Ω
220W/4Ω
MARANTS/MKDEL30
100W/8Ω
200W/4Ω
で、2倍
LUXMAN/505Z
100W/8Ω
150W/4Ω
MARANTS/MKDEL50
70W/8Ω
100W/4Ω
で、約1.5倍
MODEL30は7月から値上がりして、505Zよりも高くなるので、今がお買い得かも(笑
書込番号:25712786 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
スピーカー
(最近5年以内の発売・登録)