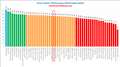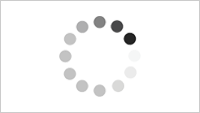���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S425�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2024�N8��30�� 13:26 | |
| 10 | 7 | 2024�N8��21�� 07:52 | |
| 11 | 199 | 2024�N10��3�� 23:02 | |
| 73 | 13 | 2024�N8��2�� 16:35 | |
| 420 | 180 | 2025�N11��4�� 07:20 | |
| 2 | 0 | 2024�N7��16�� 11:36 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�I�[�f�B�I�r�W���A�����[�J�[�̃T�|�Z��/�T�[�r�X�̃N�I���e�B�ɂ���
����܂ł������̃I�[�f�B�I���i���g���Ă��܂������A�T�|�Z��/�c��/�L��܂߂ĕi�����Ⴂ�ƁA�w���O��̖����x�ɂ��e�����܂��̂ŁA�T�|�Z��/�T�[�r�X�̃N�I���e�B�͈ӊO�Əd�v�ł��ˁB
YAMAHA/����������
���X���������m�Œ��J
�A�v���s������������J����
�ܔN�ۏؐ��i���������[�U�[�����x�͍�������
SONY/������
���X�������J�����s����Ȃ��Ȃ��F�߂Ȃ�
�Â��@��ł��}�j���A�������著�t���Ă����
�A�v���X�V�x��
ARCAMA.JBL.HARMAN/������
���X�������J�����C�O���[�J�[�Ȃ̂ŋZ�p���s��
�d�l�m�F�Ɏ��Ԃ�����ꍇ����
�A�v���X�V�x��
BlueSound/����������
���X�������J�����C�O���[�J�[�Ȃ̂ŋZ�p���s��
�d�l�m�F�Ɏ��Ԃ�����ꍇ����
�A�v���X�V����
DELA.�����R/����������
���X�����c�ƃ}���̑Ή����_�Ή�
DENON.MARANTZ.POLK.B&W/����
���X�x�����G�ł��܂ɊԈ���Ă���
���m�ȏ����J�����Ȃ�
�c��/�T�|�Z�������������ʼn����ƌ떂�����Ă���
�A�v���X�V����
�ܔN�ۏؐ��i�͂��邪�l�i�̊��Ɏ����Ⴂ
EVERESOLO.�u���C�g�[��/��
���X�������n��ŋZ�p���s��
�X�^�b�t1�l�������Ȃ�����
TEAC.ONKYO.PIONEER.KLIPSH/��������
���X�������J
�d�l�m�F�����m
�Â��@��̓T�|�[�g�s��
�A�v���X�V�x��
LG/������
���X�͑������T�|�[�g�V�X�e�����g���Â炢
�A�v���X�V�͑������C�O���[�J�[�Ȃ̂ŋZ�p���s��
APPLE.apple Music/��������
���X�������J�������₷��
�T�|�[�g��p������
�A�v���X�V����
�ꕔ�n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή����ĂȂ�
android.google/��������
���X�������J�����o�O������
�A�v���X�V����
fireTV.AMAZON MUSIC/������
���X�������J�����@�B�I
�A�v���X�V�����R�X�p����
�n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή����Ă�
cerative/����
���X���x��
�C�O���[�J�[�Ȃ̂ŋZ�p���s��
�A�v���X�V�x��
SHARAP/��
���X�x���������_������
���̑�.�����[�J�[/����������
���X�������T�|�Z�����_�Ή�
�s�����Ƃ����ɕԋ����Ă����
�T�|�Z���i���ł����ɓ��{���[�J�[�T�C�g�����Ă邩��
�����ԍ��F25868260�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�̔��X��HP
�@�̔��i�ɑ���Q��A
�A�f���i���q�l�Ɣ̔��X�܂��́A���q�l���m�̃R�~���j�e�B�j
�A�̌f���ɉ��y�̘b����R�����g������A�����̓I�[�f�B�I�̔��X�ł���
���y�̘b��͂悻�ł���Ă���Ƌ����ꂽ
���̔̔��X�͉��y�͋��Ɣ��f�����p��������߂�
�����ԍ��F25868940
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
YAMAHA�F�l�����͂��܂��i�j�A�T�|�[�g�̎��͍����ł��ˁB
���m�ȏ���`���Ă����̂ŏ�����܂��B
DELA�F�����炪�\����Ȃ��Ǝv���ʂ̐_�Ή��ł��ˁB����fidata��
�E�E�E�Ȃ�Ďv���Ă܂������A�����܂ł̑Ή��͂Ȃ��ł��傤���A������
DELA���g�����������ł��B
DENON�AMARANTZ�F�������ʂ̌f���ɏ����܂������S���҂ɂ����
���������ŁA�������ԈႦ�Ă��邱�Ƃ������ł��B
���i�̐��ɑ��ăX�^�b�t�̗͗ʂ��ǂ��t���Ă��Ȃ����������܂��B
�u���C�g�[���F���̏�Ȃ�����Ȃ��B�݂�� eversolo�Ƃ��悭������Ȃ�
�v���܂��B���ȐӔC�Ŏg����l�����ł��ˁB
TEAC�F�������Ή��������A���J�ł��ˁB
�T�|�[�g�̐����_���ȂƂ���́A�ŏ�����w�������̑ΏۊO�ł��B
�����ԍ��F25870511
![]() 0�_
0�_
��������K����
���ڂ����ł���(��
��YAMAHA
�T�|�[�g���ǂ��̂Ŕ����Ă���������ł����A�l�i��������Ȃ��ł��ˁB�B�B
���f�m�}��
���x�A�~�����@�킪�f�m�}���ɂ����Ďd�l�m�F���܂������A���̃��[�J�[����2.3��Ŋm�F�ł���Ƃ���A10��ȏォ����܂����B
�����l���Ή����Ă��Ăق�ƂɃT�|�[�g�̎����Ⴂ�ł����A�@�\/�R�X�p�͍��߂Ȃ̂ŃW�����}�ł��ˁB
���u���C�g�[��
������́AEVERSOLO�̃y���y���̃}�j���A���������Ă��ďI���܂����ˁB
�܂��A����������Ă����T�|�[�g���������肵�Ă���̔��X����w���\��Ȃ̂ŁA���ȐӔC�ł����ˁB
��TEAC
�����͈ӊO�Ƃ������肵�Ă�̂ŁA������������S�����߂ł����AONKYO/PIONEER��AV�A���v�̓��C���i�b�v�����Ȃ��̂��l�b�N�ł��ˁB
���i�̃R���Z�v�g/�R�X�p�͍��߂Ȃ̂ŁA�����Ɣ���Ă��������������܂����B
�f�m�}���ɒǂ�������Ă��܂������͔ۂ߂܂���B
�T�|�[�g/���i/�R�X�p�A�S�Ẵo�����X�������̂����z�ł����A�A�A
���̂Ƃ���A�~�j�R���|/�l�b�g���[�N�v���C���[/AV�A���v/�X�s�[�J�[�n�̃V�F�A���ƃf�m�}���D�ʂŁA�f�m�}���̐��i�J��/�����������Ă銴���ł��ˁB
�f�m�}���̈�l���o�ɑR�ł��郁�[�J�[���o�Ă��ė~�����Ƃ���ł����B�B�B
�܂��A���[�U�[�Ƃ��ẮA�����Ƃ���肵�čœK�ȃV�X�e���\����g�߂�x�X�g�ł��ˁB
�����ԍ��F25870603�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2024/08/30 09:21�i1�N�ȏ�O�j
���o���J�^�t�������W����
����ɂ��́B
��ϋ����[�����i�X���b�h�j�ł��ˁB�����̐��i�ɂ͋����͂���܂��Q�l�ɂȂ�܂��B
���āA�������\�ł�����̘b�Ȃ̂ł�����ǂ��A�X�����I�T�E���h���ɂł��ł��ƍL�����o���Ă���C�O���i�̓��{�����A�����̃T�|�[�g�Ɋւ��Ă����̃T�[�r�X�̎��ȂǂɌ��y���ĉ������܂��Ƃ���ɎQ�l�ɂȂ�̂ł����A�������ł��傤���B
�����ԍ��F25870626
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
TEAC��ONKYO�ƃp�C�I�j�A���P���Ɏ��߂��̂ɁA�����ς�ł��ˁB
������AV���ʂɂ��͂�������肩�Ǝv���Ă����̂ł����A���@�픭������
�ȗ��A�����������B
���������悤��D&M�̑R�n�ɂȂ肤��̂�TEAC�����Ȃ�ł���ˁB
����������Ɗ撣���Ăق����ł��B
��ListenFirstMeasureAfterwards����
�����ւ̎���ł͂Ȃ��̂ŋ��k�ł����E�E�E
�ELINN JAPAN�F�d�b�A���[���Ƃ��Ή������J�ł��B�ڋq����������ƊǗ����Ă���悤�ł��B
�E���z�C���^�[�i�V���i���FdCS���D���Ȃ̂ŁA���x������肵�����Ƃ�����܂����Z�p�I��
�@�����ȂǏڂ����b���Ă�������A��ϊ����̗ǂ���ۂ��܂����B
�E�i�X�y�b�N�F���Ј����̃u�����h�ɑ��ĐӔC�����������莝���Ă����ۂł��B�����Ŕ̔�
�@����Ă��Ȃ����f�����ꕔ��舵���Ă��ꂽ��A�Z�ʂ������܂��B
�E�����d�C�F������Ɠa�l�����̂悤�Ȋ����������͍D���ł͂���܂���B
�E���L���F�ǂ����̂������Ă���̂ɁA���܂蔄�낤�Ƃ����p�����������܂���BELAC�͑㗝
�@�X��ς�������������Ȃ����Ǝv���܂��B
�EKEF�F�d�b���A���[���Ƃ��ɒ��J�ł��B�T�|�[�g���e�����m�ł��B
�E�t���[�����R�[�f�B�l�C�g�F�������ǂ��Ǝv���܂��B�����A�����Ɣ���C���o���Ȃ��ƕ�̎�������
�@�ł��B
�������m���Ă���Ƃ���ł͂���Ȋ����ł��傤���B�����ɗ��ĂȂ������炷���܂���B
�����ԍ��F25870744
![]() 0�_
0�_
��ListenFirstMeasureAfterwards����
����ϋ����[�����i�X���b�h�j�ł��ˁB
���肪�Ƃ��������܂�(��
���X�����I�T�E���h���ɂł��ł��ƍL�����o���Ă���C�O���i�̓��{�����A�����̃T�|�[�g
��MONITOR AUDIO/�i�X�y�b�N
�Ή��������e�ł����A�ŏI�I�ɂ͔̔��X�ɐU���܂��B
���N�܂ŃT�C�g���Â��Č��ɂ��������ł����B���j���[�A������ď����ǂ��Ȃ�܂����B
�I�[�f�B�I�V���[�ɂ����c�ƐӔC�҂͓Ɨ����āA�M���V���n�̃A���v�A��/�x�T�w�����n�߂������ł��B
�ǂ������̐l�ł����B
��LINN/�T�E���h�N���G�C�g
LINN�ɒ��ږ₢���킹�����͂Ȃ��ł����A�㗝�X�̃T�E���h�N���G�C�g�͐ڋq/�T�|�[�g�Ή����ꗬ�ł��ˁB
���̃V���b�v���ƁA�l�b�g���[�N�����܂Ƃ��ɐ������炳��Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����AROON�o�R�Ŏ�������ł��Ȃ��ꍇ�������ł����A������͓X�̕��͋C/�ݔ�����������Ă���̂ŁA���������₷���ł��B
�����炪�ӏ܂��Ă��鎞�́A�X�^�b�t�͗����Ă��܂��B
�l�b�g���[�N���i���C���ň����Ă�̂ŒʐM�����肵�Ă��܂��B
��KEF
�����̉c��/�}�[�P�e�B���O�S���҂͂�����݂����ł����A�V���b�v/�T�|�[�g�͂܂��܂����������ł����A�����\�Ă��ԐM�Ȃ������肵����������A�s����Ȃ̂ōw�����܂���ł����B
�Z�p�I�ɍ������ɖ����Ă܂����A���͂����܂ō����Ȃ������ł��ˁB
�ЎR�E��������L�����Ɏg������A�u�����h�u���Ȃ̂ł��������̂��D���Ȑl�����ł��傤�B���i�헪���C�}�C�`�Ȋ����ŐL�єY��ł��ۂł��B
�����̃X�^�b�t�����������Ă܂����B
�������d�C
���h�o�V�ɂ���X�^�b�t�͐e�ؒ��J�ŁA�Z�p�m���L�x�ł��B
���ɃA�L�o�̃X�^�b�t�͌��f�m�}���Ȃ̂ŁA�ƊE������ɂ����ʂ��Ă��ĎQ�l�ɂȂ�܂����B
�f�m�}���̑̎������킸�Ɋ����ɈڐЂ��������ł����A�����������݂����ł��B
��������́A�d���^�b�v�������������ƂȂ��ł����A���i�N�I���e�B�͍��߂ł��ˁB
��ifi/�g�b�v�E�B���O
�Z�p�m���I�ɂ͈�Ԑ��m�ł��ˁB
�Z�p�҂��T�|�[�g���Ă銴��������̂ŁA�T�|�Z���̃N�I���e�B�ł͈�Ԃ�������܂��ADAC/�o�[�u���E������E�p���Ăق����Ƃ���ł��B
SFP�Ή����i�Ƃ��Z�p����X���Ȃ̂ō���Ɋ��҂ł��B
��JVC/�P���E�b�h
�v���W�F�N�^�[�c�ƒS���҂͋Z�p�m���L�x�ŁA�e�ł����AV900R�Ȃǃt���b�O�V�b�v��200���~�ȏシ��̂ŁA���X�肪�o���܂���B
�f���ł����ۂɂ͐G�ꂽ��ł��Ȃ��̂ŁA���z�Ȋ��ɕs���͎c��܂��B
�i��/�T�|�[�g�̓g�b�v�N���X���Ǝv���܂����A���ɂ̓I�[�o�[�X�y�b�N�ł����B
��AVAC
���l�X�ɉ��x���������ɂ����܂������A�X�^�b�t�͋Z�p�m���L�x�ŏڂ����ł����A�a�l�������Ă��Đڋq�ԓx�������̂ł��̓X����̍w���͌�����܂����B
�V�h�X�͒��J�ŕ����_�炩���̂ōD��ۂł����B
��SENNHEISER
�C�x���g�ł̃X�^�b�t�͋Z�p�m���L�x�Őe�ؒ��J�ł��B
�C�O���[�J�[�̒��ł́A���i/�R�X�p/�T�|�[�g�̃o�����X���������[�J�[�̈�ۂł��B
��FIDATA/IO�f�[�^
���X�������Z�p���s���ŃC�}�C�`�ł����B
���I���I�X�y�b�N
�A�L�o�ɂЂ�����Ƃ���PC�p�[�c���ł����A��\�̃l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�֘A�̋Z�p���͍����ł��B
ROON�n�̃C�x���g����Ă���A���S�}�j�A�����̃C���f�B�[�Y�݂����Ȋ����ł��ˁB
�l�b�g���[�N���[�N�I�[�f�B�I������Ă���10���N�o���Ă�݂����ł����A���{�����ł͂��̓y�낪�܂��܂��n��ŁAAMAZON MUSIC/�r�b�g�p�[�t�F�N�g�������ғ��ł��Ȃ���Ԃł����B
�悤�₭�f�m�}�����i��ROON REDAY�Ή����āA��ʑw�ɂ��{���̈Ӗ��ł̃l�b�g���[�N�I�[�f�B�I���������闬�ꂪ�o�������ł����A�f�m�}���̃T�|�Z���N�I���e�B���Ⴂ�̂ŁA�ʂ����Ăǂ��܂ň���/���y���邩�B�B�B
�������C������ł����A�A�A
���Ȃ݂ɁAHARMAN��ROON�������̂́AARCAM�Ȃǂ�ROON�Ή����s���肾�������炾�����ł��B
������������x�X�g�ł����A�\�t�g�J���͂��ア�̂Ŋ��҂ł��܂���B
�ł����A�l�I�ɂ�ARCAM�̐��i/�R���Z�v�g
/�R�X�p/�T�|�[�g�i���͍��߂Ȃ̂ŁA���̂܂g��������ł��傤�B
�܂��A���̂Ƃ��낱��Ȋ����ł��ˁB
�����ԍ��F25870918�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��������K����
��TEAC��ONKYO�ƃp�C�I�j�A���P���Ɏ��߂��̂ɁA�����ς�ł��ˁB
������AV���ʂɂ��͂�������肩�Ǝv���Ă����̂ł����A���@�픭�����Ĉȗ��A�����������B
�����ł��ˁB
�C�O���C���i�b�v�͑����悤�ł����ATEAC�͓��{�̑㗝�X/�T�|�[�g�Ɩ������݂����Ȃ̂ŁA�̔��헪��PAC�哱�ł����A�C�}�C�`���C�������ł��ˁB
ONKYO��KLIPSH�ƃR���{���āAAV�A���v������d�l�̃T�E���h�o�[�J��/�������Ă�̂ŁA������̕���/�C�O�s�ꃁ�C���ɐi��ł�݂����ł�(��
https://onkyo.com/intl/receivers/klipsch-flexus-sound-system
�����A�H���ɂ�AV�A���v�́AAMAZON MUSIC/�n�C���]/�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή�����炵���ł����B
PIONEER/LX805�Ƃ��́A�f�m�}���������ROON REDAY�Ή����Ă���̂ŁA�Z�p�I�ɂ͐�s���Ă��ł����A��`/�v�����[�V�������n�������ĒN���C�Â��Ă��Ȃ���������܂���ˁB
���N��ɂ͂��������������邩������܂��A���C���i�b�v���₵��➑̂������ƃR���p�N�g�ɂ��Ăق����ł��ˁB
�S�̓I�Ƀf�J������̂ŁA�A�A
�����ԍ��F25871020�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����ɂ���
�ŋߐ^���Ƀf�W�^������i�߂Ă���A���v�ł܂��ʔ������̂��̂��o�Ă����̂ŗ\�܂����B
��x�s�Ǖi��͂܂��ꂽFOSI�����m�A���v�B
11���ʂɗ���݂����B
�Ȃ��Ȃ��������v�Ń{�����[����r���ASN��120�ȏ�ɂȂ��Ă����Ƃ��ɒ��ځB
�p���[��100�ł�300�ł��ǂ��̂ł����A�C���s�[�ω��ɂ��Ή������炵���h���C�u�i���ǂ�Ȋ������B
�ǂȂ����\�ꂽ�������Ȃ��ł��傤���B
YouTube�ł͂������Љ�n�܂����݂����ŁB
���ŎO���~���傢�ŁA�g�̉�萮���̎����J�ōw���B
DAC�v������XLR�Ō��сA�p���[���X�s�[�J�[�ɂقڒ����ʋ߂Â��Ă���Ă݂悤�Ƃ����V�тł��B
�\�Ȃ����݂̂ŁA�m���P�[�u���B
��w�_���s���N���オ��͂��Ȃ̂ŁA�L���L���̏o���ɂȂ��Ȃ����Ɗ��ҁB
�������Ȃ����ȁB
�����ԍ��F25849787�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�N���t�@���Ŏ��������Ă����z�ł��ˁB
tpa3255�����m�����Ŏg���ăR���p�N�g�Ŗ{�i�I�ȃn�C�p���[�p���[�A���v�����܂������Ċ����̐��i�ŁA�ǂ����ŋ߂�tpa3255���ڃA���v�̃g�����h�́A��Ղ̗��Ƀ`�b�v�����t���Ē�ʂ���M�����v�ŁA���̃A���v�����̗�ɘR��Ȃ������ł��B
���[�J�[��HP�ł̓N���t�@���Ƃ̍��z���o���ƍw���ł��܂�����Ċ����ł����AAliExpress�ł�8/31�����ŁA���݂́u�\��t���v�S���Ă��܂��B�����͂��ɂȂ�̂��킩��Ȃ��ł����E�E�E�E�E�E�E
�����ʐ^�����J����Ă��āAYouTube�ł����l�������r���[���Ă��܂����Atpa3255��������ƍ��n�Y���͖����Ǝv���܂����A�g��������ǂ������Ȃ̂ŁA�㗬�Ƀo�����X�o�͂Ƃ���Ȃ�̃{�����[���R���g���[��������DAC������V���v���ɗǎ��ȃV�X�e�����g�߂����ł��ˁB
���a���Ȗl�́A���i���ł͂��߂āA�]����������x�ł�������x�[�X�ɍw�����Ă݂悤���Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F25857079
![]() 0�_
0�_
����ɂ���
�ԐM�������肪�Ƃ��������܂�
�t�@�E���f�B���O�֘A�͂悭�킩��܂��A3255�Ȃ̂ŁA���̂��������i�ɂȂ��Ă邩�ǂ������킩��܂��A�������������o�����Ɋ��ӂ��܂��B
�������[�J�[�͉�����Ă�̂ł��傤�ˁB
�}�[�P�b�g���Ȃ��Ƃ͂����A�C�O�̈������[�J�[�ɖʔ����Ƃ���������Ă�����āB
���������y�A�O�����傢�ŐV�����h���C�u�����y���߂�������V�сB�ǂ��v����DAC�����킹�Ă�������A�莝���̃X�s�[�J�[�ނ̐V�����������݂Ă������܂��B
���Ƃ�����YOUTUBER�͂��������̎����m�F���Ȃ���A�債�����e�Љ���V���������ɂ��G�ꂸ�A4343�ɂ͑���Ȃ������Ƃ��A��͂蔖���R�����g�B
���i�̊��ɂ͊撣���Ă�Ƃ��B����Ȓ��x�B
�����_�ŊS����̂́A�A���~�{�f�B�[�ɑϔM���������Ȃ肵�Ă���_�ŁA�f�W�^���͉ߋ�10�@��ʁA����2��g���Ă܂����A����قǔM�������Ȃ��B
����͂͂��߂���48V���͂ŁA���o�͌^�ɂ��Ă�̂ŔM���o��̂��ȁA�ƁB
����e�N�j�N�X�A�}�����c���f�W�^���ɒ��͂��Ă܂����AONKYO��VL�V���[�Y�Ŋ撣���Ă��āA�������[�J�[�ɂ܂��܂��s���A�I�[�f�B�I�撣���ė~�����ł��B
�}�����c�͉ߋ������ȃ��m�p���[����Ă���A���C�Ȏ�������܂����B
���̓v�����C�������A�e�ЃG���g���[�@�͏��Ȃ��A�l�X��т��č���Ă�̂̓��}�n�ʁB
��������L���ď��߂ăX�^�[�g�������A������������������悤�ȁA�����ȋ@�B�ł��F�X�y���߂��A�Ƃ������i�J�������肢�������ł��B
�I�[�f�B�I�V���[�Ȃ��A��ʋ@�B����̂ɂȂ肷���āA����������w����Ă��Ă��܂��B
������ƈႤ�̂ł͂Ǝv���܂��ˁB
�����ԍ��F25857194�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���m����D���A���v���ā@�Ȃ��Ȃ��������낢�\���ł��ˁB
�ȑO�@�X�e���ID���A���v�I�V���X�R�[�v�œd���̔g�`�ώ@�������ǁ@L/R�Ńo���o���̃^�C�~���O�œd����v������̂�L/R�ő��݊����ēd���g�`������Ă܂����B
�Ȃ�Ł@���m�����d�l�ō��E�̓d��������ق����x�^�[�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��B
�d�l���Ă݂�Ɓ@�d���ʔ���ł��ˁB
https://fosiaudio.com/products/power-supply-adapter-48v-5a-10a?variant=4436780767664
48V 5A�Ł@59.99USD 48V 10A ��109.97USD �ł��ˁB�i�Q��K�v�j
�����l������Ɓ@10A�̕����x�^�[�����ǁA�A���v�{�̂�荂�����܂��ˁB
�ȑO�@Fosi Audio BTA10���ăA���v�g���Ă������ǁA�莝���̃��j�A�d���Ȃ����Ƃ������ǁ@DC�̃R�l�N�^�������Ɉ���Ă��ā@�s�̂�2.5mm���̃R�l�N�^�����@�I�ɍ������ǁ@�ނ��Ⴍ����ł��Ďh����ɂ���������Ł@AC�A�_�v�^�̋��d�����Ԃ������Ďg�����o��������܂��B
�����ȊO�̓d���g���Ƃ��͐ڑ��ɋC�����Ďg�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B�i���P����Ă��邩������܂��j
���Ɓ@�V�k�S�Ȃ���@�u�f�W�^���A���v�v���Ē�`�������������܂��ł��B
�f�W�^�����͂������ā@�A���v���̂��A�i���O�Ȃ���@�f�W�^���A���v���Č����l������B
�Ȃ�Ł@D���A���v���Č������ق����@�������`���܂��B
�����ԍ��F25857221
![]() 0�_
0�_
���łɁ@Fosi Aduio�Ł@�F�l���Q��A���v��������ł����A���g���m�F����Ɓ@���i���ς���Ă�����A�z���ނ��ς���Ă����肵����Ł@�o�C�A���v��}���`�`�����l���������́A�Q��ɕ����Ĕ��킸�Ɂ@��C�ɑS�������������ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25857229
![]() 1�_
1�_
�ǂ����AFosi Aduio��HP���݂�ƁA���̃A���v�́u�Q�����X�e���I�v�ɂ�������Ė����āAAV�̃}���`������A�`�����l���f�o�C�_�[���g�����}���`�h���C�u���Ɂu�C�y�v�Ɏg����A���v���ė����ʒu�݂����ŁA�d����48V5A���ƂP��A48V10A���ƂQ��܂Ōq���܂�����Ďd�l�ł��ˁB
���ۂɂ͂����܂ő傫�ȓd����p�ӂ��Ȃ��Ă������Ƃ͎v���̂ł����E�E�E�E�E�E�E�d���̐v�ɂ����܂��ˁB
�l�́A������Ǝ����ăC�P�����Ȃ�A�Ȃ���ȓd������肻���ł����E�E�E�E�E�ȂˁA�ߋ��Ƀg�����X��������āA�p���G���p�̂ł������R���f���T�Ƃ��A�e�t�����R���f���T���Ƃ���ςݍ��d�������E�Ɨ��悹�Ă��l�B�������ł���B
��Fosi Aduio�Ł@�F�l���Q��A���v��������ł����A���g���m�F����Ɓ@���i���ς���Ă�����A�z���ނ��ς���Ă����肵�����
���ؐ��i���邠��ł��E�E�E�E�E������Ղ��g���܂킵�āA���낢��ȂƂ���őg�ݗ��ĂĂ܂�����ˁB
�t�@�[�X�g���b�g�͗��ɁA�p�[�c�ς����Ⴄ���Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
���̎�̒��ؐ�D���A���v�́A�v���`�b�v�̃��t�@�����X�f�U�C�����قڂ��̂܂܂ɂ��āA��ʐ��Y�����A��Ղ��������ɗ����܂���̂ň������Ă��܂��B���{���[�J�[��������Ɛv���āA�����Ƃ���Ƃ��̉��i�тł͐��i���͖����Ȃ̂ŁA�����ɂ��̒l�i�тł͑���Ȃ��̂��낤�Ǝv���܂��B
�܂��AAV�A���v�̕������v�������̂ŁA�G���g���[�N���X�̃I�[�f�B�I�͂ǂ�ǂ�Ȃ��Ȃ��Ă����悤�ȋC�����܂��B
���������l���A���݂̓I�[�f�B�I�@��͎g���Ă܂���B
PC��RME�̃T�E���h�f�o�C�X���Ȃ��ŁAGENELEC��DYNAUDIO�̃A�N�e�B�u���j�^�[���g���Ă��܂��B
RME���̃T�E���h�f�o�C�X�{GENELEC�ŁAGENELEC�̃t���[�\�t�g�ŕ�����Ă��܂��Ɓu������ӂ̃I�[�f�B�I�v������قǃ��A���e�B�������̂łǂ����悤���Ȃ���ł���ˁA�T�C�Y�����������E�E�E�E�E
�����ԍ��F25857678
![]() 2�_
2�_
����ɂ���
���̋@��ł̓��͂�48V 5A�ōő�o�͂̂悤�ŁA����3255�n���̂悤10A�Ȃ�300w�Ƃ����悤�Ȑݒ�ł͂Ȃ��悤�ł��B
���i���o�͂͋��߂܂��A���m�A�m���{�����[���ŃV���v���A��SN�Ƃ��ꂽ�̂����͂ł��ˁB
�A�_�v�^�[���g���d���͌��Ȃ̂ŁA�ȍ~100��240v�ʏ���͂ɂ��ė~�������́B
�ߋ��Ɏg���Ă�����^�A�i���O�A���v�ނƂǂ�Ȋ����Ƀh���C�u���Ă���邩����̂��y���݂ł��B
�X�s�[�J�[�[�q�������ɒu�����߂ɃX�y�[�X�����͂��߁A�W�����p�[�܂��͒Z���P�[�u���^�Ō��Ԃ����y���݂ł���܂��B
�����ԍ��F25858306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
TAD�ɂ�m2500�Ƃ��{�iD������A�����������D���ǂ̈ʉ\�����邩���y���݂ł��B
�܂��Ƀ��V�v���G���W����EV�̐}���ƑI�B
���̋@�B��BYD��EV�݂����ȂƂ��ł��傤���B
���Ȃ��Ƃ��Â����ꂽ�X�s�[�J�[��V�N�ɐV���ɖ炵�Ă����D�o�͂͂���Ă��Ċy�����ł��B
ONKYO��VL1�Ȃ͂Ȃ��Ȃ��Â��̂Ƀv���~�A�I�Ȓ��É��i�Ɏ����Ă܂��ˁB
�����ԍ��F25859070�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����
�œK�ȃX�s�[�J�[�\���ɂ��āA�������}�^�[���ǂ���
�قځA�u���O�A�����r���[�ƂȂ����܂����A�A�A��
�����ԍ��F25849338�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�ŐV�^��LG���^4K���[�U�[�v���W�F�N�^�[���������Ă��܂����B
���S�Î�����Ȃ���Ԃł������A���邳�I�ɂ͂����������邭�f���Ă��܂����B
�ڍ׃��r���[�͌���B
�����ԍ��F25854461�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��HU710PB�ɂ���
�C�O�̃��r���[�T�C�g�ŋ�܂���܂�����������A��͂�掿�͗ǂ������ł��B
���S�Î�����Ȃ��Ǔ��ʂł������A�𑜓x�I�ɂ�4k/HDR�܂ŏo�͉\�ŁA����������4K���͊������܂����B
�F���͍��g���Ă���i��2K�����m���ɐ��\����ŁA�����LG�L�@TV�ɋ߂���ۂ�4K�g���v�����[�U�[�̔��F�̗ǂ��������܂����B
���邳�́A�X�y�b�N/500ANSI���[�����ł����A70�C���`���炢�̓��e�ŗ]�T���������̂ŁA����Î��ł�100�C���`���e�ł��g�������ł��B
�T�C�Y�͗\�z�ȏ�ɏ����������ł����A���\/�R�X�p�I�ɂ͂��Ȃ荂�����ł��B
�����ԍ��F25854654�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�͂܂��Ȃ�������������Ȃ̂ŁA�قڒ艿�B
�v���W�F�N�^�[�͂��܂�����Ȃ�Ȃ��ł��傤����A�N���t�@���̎���10���Ŕ����Ƃ��A�A�A
������ƌ���B
�܂��AV900R�N���X�̃l�C�e�B�u4K�ɔ�ׂ���A��1/20���i�Ȃ�ň��|�I�����ł����B
���i���ȏ�ɐ��\�͗���ĂȂ����������܂����B
�����ԍ��F25854666�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���o���J�^�t�������W����
���r���[���肪�Ƃ��������܂��B
�䂪�Ƃ͊��S�Î���90�C���`�A2000ANSI ���[�����ł����������邷����̂ŏȃG�l���[�h�ɂ��ċP�x�𗎂Ƃ��Ă��܂��B���̃��[�h�ł͌���������1.5�{�ɐL�т܂��B
�����ԍ��F25854711
![]() 2�_
2�_
��AV�A���v�V�X�e��/AV�v���A���v�ɂ���
��/100�C���`�X�N���[���Ƀv�����C���A���v/SA30�����Ă���A��ꃖ���o�߂��܂����B
���݂͂܂��A2CH����Stereo���y�ӏ܂Ȃǂ͂��������������Ă܂����A�A�}�v��/5.1�h���r�[�n�ƃA�g���X�f��A�A�g���X���y���f�R�[�h�������Ȃ��Ă����̂ŁA���낻��AV�A���v�����̏��������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�ʕ�����TV�pAV�A���v�͂��̂܂܂̗\��B
������̃X���ł��A�h�o�C�X���炢�܂������AAV�A���v��̌^��AV�v���A���v/SA30/�f�W�A���̃Z�p���[�g�^���̂ǂ��炪�œK�ȑg�ݍ��킹�ɂȂ肻�������ӌ�������肢���܂��B
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25849748/#25858261
�������V�X�e��
����̌^�V�X�e��/4.1.4
AV�A���v/X6800H/X8500H
�t�����g�A���v/SA30
�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500
���Z�p���[�g�V�X�e��/4.1.4
AV�v���A���v/AV8805A/\385000
�t�����g�A���v/SA30
�T���E���h�A���v/Fosi Audio V3/\13500
4ch�X�s�[�J�[��BW700�V���[�Y/�u�b�N�V�F���t
�p�r
���y�ӏ�6/�f��ӏ�4���炢
AV8805A/\380000�́A�܂��V�i����ł���悤�Ȃ̂ŁA���̂������ł̓R�X�p���������ł����A�C�O���r���[�T�C�g�ł̓C�}�C�`�ȕ]���ŁA��̌^��X8500H/\300000�̕����ASINAD/���\�͍����悤�ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/marantz-av8805a-review-av-processor.25971/
�������AX8500H�͂��łɐV�i����͂ł��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���_��A���Č�p�@��X6800H/\430000�����ɖ߂��܂����B
AV8805A�̎��ۂ̃��[�U�[�]���ł́A���y�ӏ܌����Ƃ̎��ł����A��������悤�Ȃ̂ōw�����悤�������Ă܂��B
https://s.kakaku.com/bbs/K0001037015/SortID=23870850/
�܂��AYAMAHA/CX-A5200�����Y�I���ŁAAV�v���A���v�̑I�����͂قږ����Ȃ����悤�ł��B
YAMAHA�̕��j�Ƃ��ẮARX-A8A�̈�̌^����p�@�̂悤�ŁA����AV�v���A���v�͂����o���Ȃ��݂����ł����A��̌^�̐��\�������I�ɗ��킵�Ă���Ȃ�A�킴�킴�Z�p���[�g���Ȃ��Ă��ǂ������ȋC�����Ă��܂����̂ŁARX-A8A/\420000�����ɓ��ꂽ���Ǝv���܂��B
DAC��ES9026PRO�Ȃ̂ʼn����I�ɂ͍������ł��B
https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/yokohama/202200718
����̌^�V�X�e��/4.1.4
AV�A���v/RX-A8A/\420000
�t�����g�A���v/SA30
�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500
�����ԍ��F25858686�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
DAC�����Ȃ̂ł�������lj�
����̌^�V�X�e��/4.1.4
AV�A���v/VSA-LX805/\420000
�t�����g�A���v/SA30
�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500
�����ԍ��F25858700�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
HiVi���č���194�y�[�W�̋L����ǂ�ŁAX6800H�𒆐S�ɑg�ނ̂��ǂ��悤�Ɏv���Ă��܂����B
�t�����g��SA30,�T���E���h�͓����A���v�ŁB
�����ԍ��F25858758
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��194�y�[�W�̋L��
�ȃG�l/�R���p�N�g/������
�Ŏ��߂�Ȃ�X6800H�����z�I�ł���(��
����ɂ��Ă��A�]�_�Ƃ̓t�����g�v���A�E�g/�}�[�N���r���\�������ł��ˁB
X8500H�̖������i��30���~�����Ă܂�������AX6800H/35�����炢�Ȃ甃�������ȁB
DENON�̔����Ɍ����Ă݂܂��B�B�B
�����ԍ��F25859937�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���r���[�T�C�g�ōׂ�����r������Ă�悤�Ȃ̂œ\���Ă����܂��B
https://youtu.be/suaygCG03QM?si=3rszPFzwxC1mlA_i
�����ԍ��F25859939�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��SINAD�X�R�A��r
X8500H/103
X6700H/100
LX505/98
RZ50/97
X4700H/97
X4800H/95
X3800H/87
X6800H�͌��܂��̂悤�ł����AX6700H�Ɠ����x���̃n�C�X�R�A���o�����ł��B
���^��X4700H���V�^�����n�C�X�R�A�̂悤�ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/denon-avr-x4700-avr-review-updated.14493/
�e�A���v�ɂ����܂ő傫��SINAD/���\���͖����̂ŁA�K�v�ȃ`�����l�����������āA���i�����������n�C�R�X�p�ɂȂ銴���ł��ˁB
AV�v���A���v/�Z�p���[�g�̓R�X�p�������ł��B
���[����́ADIRAC LIVE������RZ50���D�ʂł����AAudacy MultEQ�������\�����Ă�̂ł������������x���ł��傤�B
�\�t�g�ʂ́AHEOS/�X�g���[�~���O/�r�b�g�p�[�t�F�N�g�ň��萫�����D�ʂȂ̂ŁA�����͂ł���͂�DENON�D�ʂȊ����ł��ˁB
�����ԍ��F25860196�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
X6800H���r���[/AVAC��
https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/yokohama/20240407
����Ȃ�ɐi�����Ă�悤�ł����A�T�u�E�[�t�@�[4ch������Ȃ���ȁB
RZ50���r���[
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/onkyo-tx-rz50-review-home-theater-avr.30842/
RZ50��DIRAC�����ŃR�X�p���߂ł����A�T���v�����O�����Ɠd�͐����ɖ�肪����̂ł�͂肱������肪�o���Ȃ����ȁB�B
�����҃��x���Ȃ�AX4700H/X6700H������̐V�i���g�p������A�\���ȋC�����Ă��܂����B
�܂��A�t�����g�v���A�E�g���Ďg�������Ȃ�A�}�����c/NR1710/����1���~���x�ł���������(��
�����ԍ��F25860860�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̓�����݂�Ƃ܂��܂��A�l�グ�����������āZ800�ԑ�͔����Ȋ��������Ă��܂����B
https://youtu.be/GoiFKbLDGFs?si=-6Wwq02H_I_dDqKq
���i�I�ɂ́AA6A/X4800�͓����i�ɂȂ�܂����ADAC�`�b�v�Ȃǂ̊�{���\��A6A�̕����O���[�h��Ȃ̂ŁAYAMAHA/A6A���̂Ă������B
������5�N�ۏ�
����̌^�V�X�e��/4.1.4
AV�A���v/RX-A6A/\260000
�t�����g�A���v/SA30
�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500
���Ȃ݂ɁAMUSIC CAST/AMAZON MUSIC�́A�n�C���]/�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή��ς݂Ƃ̎��B
�����ԍ��F25861346�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
A6A��A8A�̉����ɂ͑傫�ȍ�������悤�ł��B
A6A�̉����ɖ����ł���A8A�ɔ����������������܂��B
�����ԍ��F25861469
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
A8A/\420000
X6800H/\430000
A8A�́AX8500H�̃A�b�v�f�[�g��/AVC-A110�𗽉킷��Ƃ̕]��������܂��ˁB
DENON�̃t���b�O�V�b�v/A1H/��\850000�ɒl�オ�肵�����AYAMAHA�̃t���b�O�V�b�v/A8A/\420000���n�C�R�X�p�Ɍ����܂��ˁB
�T�C�Y�I�ɂ͂قړ����ł����A�d�ʂ͌y�߁B
A8A
��x����x���s��435x192x477 mm
�d��21.4 kg
A110
��x����x���s��434x195x482 mm
�d��25.4 kg
A1H
��x����x���s��434x195x498 mm
�d��32 kg
DAC���́A�uES9026PRO�v��2��ڂ��A�S�`�����l���̉��F����B
���̓_�͒P�ɍŏ�ʋ@��ƌ��������łȂ��A�����\�����̗p����Ă���̂�CX-A5200�����ARX-A6A�⋌�@��̍ŏ�ʋ@�ł���RX-A3080A�́uES9026PRO�{ES9007�v�̑g�ݍ��킹�ƂȂ��Ă���ARX-A8A���������������N�����Ă���܂��B
�p���[�����ł����������܂�A6A�Ƃ͖��m�ɋ�ʂ���Ă���܂��B
�d�����́A�d���������Ɠd���������̓d�������������J�X�^�����C�h�̃g�����X�𓋍ڂ��Ă��܂��B
�����āA�p���[�A���v���d���ƃO�����h�z���ɂ̓��}�n �Z�p���[�g �p���[�A���v�uMX-A5200�v�Ɠ��������̔z�����̗p���Ă���A����Ȃ郍�[�C���s�[�_���X�����������܂����B
���ɂ��h�C�cWIMA�А��̃t�B�����R���f���T��J�X�^�����C�h�̑�e�ʃu���b�N�P�~�R�����̗p�������ŏ]�����f����Ŗ�2�{�̃n�C�X���[���[�g���������A�M���̒Ǐ]���ƈ��萫���i�i�ɍ��߁A�n�C���]�����ȂǍ����g���܂މ����M���̍Č��������サ�Ă��܂��B
�`�����l�����Ɋւ��ẮA���݂̏Z���ł̓z�[���V�A�^�[�̍\�z�ɂ��Ă�قǂ̎��̖������葽���Ă�13ch������Ώ\�����Ǝv���܂����AStrom Audio�Ȃǁu����ȏ�v�̃��f���́A�@�ލ\���I�ɂ��u��p���v����鎖���O��ɂȂ�܂��B
�Ȃ��A���ݍő��13Ch�𓋍ڂ���DENON�@AVC-X8500HA�Ȃǂ̓t�����gBi-Amp�ȂǁA�J�X�^�����[�h�Ȃǂ̓���Ȏ����������11ch�V�X�e���̐��\������Ɍ��コ��������Ŏg�p����邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B
�܂��u���[���h���C�h�v�́A�����āu���f���\���v����l���Ă݂��ꍇ�A���̃��[�J�[�����`�����l���������{�f�B�ɑg�ݍ���ł��錻��ł́A�@�ނ̒u���ꂪ��{�ɂȂ鎖�́u�����ړI�ȁv�X�e�[�^�X�ɂ͂Ȃ�܂����A�s���A�I�[�f�B�I�N���X�̃p���[�A���v���Ɏ������킹�Ă��Ȃ�����A11ch�̃p���[�A���v�Ƒg�ݍ��킹�Ă����݂̃}���`�`�����l���A���v�Ɣ�r���đ傫�ȃA�h�o���e�[�W�ƌ�����ɂ͍s���܂���B
https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/yokohama/202200718
�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA11.2ch�Œ��g�͂������肵�Ă���DAC���\�I�ɂ�DENON������Ȋ���������̂ŁA40���~��Ȃ甃�����ł�����?
����̌^�V�X�e��/4.1.4
AV�A���v/RX-A8A/\420000
�t�����g�A���v/SA30
�T���E���h�A���v/������������Fosi Audio V3/\13500
�����ԍ��F25861683�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��YAMAHA/AMAZON MUSIC�d�l�ɂ���
YAMAHA����ԓ����͂����̂ŁA�\���Ă����܂��B
��AMAZON/�r�b�g�p�[�t�F�N�g
Amazon Music�̊y�Ȃ̕i��(�T���v�����O���g���A�r�b�g���[�g)��ϊ��Ȃ��Đ�����Ƃ������Ƃł���ΑΉ����Ă���܂��B
MusicCast CONTROLLER�ɂāAAmazon Music���F���c�q�J��/SCIENCE FICTION�@24bit/96kHz�̉��������ۂɍĐ������ꍇ�A�Đ���ʂ̃W���P�b�g��ʉ��ɃT���v�����O���[�g�\��������܂��B
���Y�t�摜�i�T���v�����O���[�g�\���j�����Q�Ƃ��������B
�T���v�����O���[�g���\������Ȃ��ꍇ�́AMusicCast CONTROLLER�̍Đ���ʂ̉E���ɂ���T�E���h�ݒ�̃A�C�R�����^�b�v���A��������̃g�O�����I���ɂ��Ă��������B
���v���A���v���[�h
4.1.4ch�Ńt�����g�v���A�E�g���Ďg���ꍇ�A
�X�s�[�J�[�ݒ�ɂāA�Z���^�[�ȂǕK�v�Ȃ��X�s�[�J�[���u�g�p���Ȃ��v�ɐݒ肷�邱�ƂŁA�Y���̃`�����l���o�͂��I�t�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
(�X�s�[�J�[�[�q�APRE OUT�[�q�̂ǂ��炩����M�����o�͂���Ȃ��Ȃ�܂��B)
���A�v���s�
Amazon Music�ւ̃A�N�Z�X�G���[�Ɋւ��ẮA�����O���܂߂ă��[�U�[�l���ގ�����Ǘ�̔����������������Ă���A���Г��ɂĂ��Ǘ���m�F���Ă���܂��B
���L�̃y�[�W�ɂāA�s��̏ڍׂ�ꎞ�����ɂ��Ă��ē������Ă��������Ă���܂��B���Q�Ƃ��������B
MusicCast�A�v���ɂ�����AmazonMusic���̃X�g���[�~���O�T�[�r�X�Đ��̕s��ɂ��āi2024�N8��9���j
https://jp.yamaha.com/news_events/2024/audio_visual/mcc2024.html
��8/23�����݁A���������L�̋@��ł̊m�F�ł̓A�N�Z�X�G���[�͔������Ă���܂���B
���M���b�v���X��
���ɃM���b�v���X�Đ��Ɋւ��Ăł����AAmazon Music���܂ރX�g���[�~���O�T�[�r�X�͎c�O�Ȃ���Ή����Ă���܂���B
���q�l�̂��v�]�ɂ������ł����\�������܂���B
�Ƃ̎��Ȃ̂ŁAARACAM/MISIC LIFE�Ɍ��炸�A���А��A�v���ł�AMAZON MUSIC�Đ��͕s����݂����ł��B
�{���AHEOS/AMAZON MUSIC�ł����O�C���G���[�����������̂ŁAAMAZON MUSIC�T�[�o�[���ɂȂ�炩�̖�肪���肻���ł��ˁB
�����ԍ��F25862607�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
AI��
��,�X�g���[�~���O�A�v������AMAZON Music�Đ�����ƃ��O�C���G���[�Ȃǂ���������
������AMAZON�T�[�o�[��API�F�ؖ��Ȃ̂�
A,Amazon Music�Đ����̃��O�C���G���[���������錴���Ƃ��āA�������̉\�����l�����܂����AAPI�F�ؖ�肪���̈�ł���\��������܂��B�ȉ��̗v�����l�����܂��F
1. **API�F�G���[**: Amazon�̃T�[�o�[���ŁA�X�g���[�~���O�A�v���ƘA�g���邽�߂�API�F�ɖ�肪�������Ă���ꍇ�A���O�C���G���[��Đ��G���[����������\��������܂��B����͓��ɁA�T�[�o�[�̃����e�i���X���Q���ɋN����₷���ł��B
2. **�A�v���̃o�O��݊����̖��**: �X�g���[�~���O�A�v�����̂Ƀo�O������ꍇ��AAmazon Music�̔F�ؕ������ύX���ꂽ�ꍇ�ɁA�A�v�����ŐV�̎d�l�ɑΉ��ł��Ă��Ȃ��ƃ��O�C���G���[���������邱�Ƃ�����܂��B
3. **�l�b�g���[�N�ڑ��̖��**: Amazon Music�̔F�ɂ͈��肵���l�b�g���[�N�ڑ����K�v�ł��B�l�b�g���[�N�̈ꎞ�I�ȕs�����ڑ��̒x�����A���O�C���G���[�̌����ƂȂ�ꍇ������܂��B
4. **�L���b�V����N�b�L�[�̖��**: �X�g���[�~���O�A�v���̃L���b�V����N�b�L�[���j�����Ă���ꍇ�A�������F���s��ꂸ�A�G���[���������邱�Ƃ�����܂��B
��Ƃ��ẮA�A�v���̍X�V��ăC���X�g�[���A�l�b�g���[�N�̊m�F�A�L���b�V���̃N���A�Ȃǂ������Ă݂�Ɨǂ��ł��傤�B����ł��������Ȃ��ꍇ�́AAmazon���̖�肪�l�����邽�߁A�����̏�Q����T�|�[�g�ɖ₢���킹�邱�Ƃ������߂��܂��B
�����ԍ��F25862608�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��AV�A���v��r
����ACINEMA50/CINEMA40/CINEMA70/X6800H/X4800H/X3800H��������r���Ă��܂����B
A4A/A6A/A8A�͎��@�m�F�̂݁B
�S�̓I�ȑ��슴/�f�U�C��/������CINEMA�n�̕����D�݂ł����B
YAMAHA�́AA4A�̎��_�Ńf�J������̂ŋp���B
X6800H�n��CINEMA�n�����R�X�p���߂ł����A����DENON�g���Ă�̂œ��n���̓C�}�C�`�������킩���A��͂�CINEMA�n���D�ʁB
�T�C�Y/�o�����X�I�ɂ́ACINEMA50���炢�����x�悢�����ł������A�l�i�����߂Ȃ̂�CINEMA70�ł��ǂ����������܂����AHDMI�o�͂���n�������Ȃ��̂��l�b�N�B
���̒��ԃ��f�����Ȃ��̂��Ǝv������A�C�O�ɂ�CINEMA60������悤�ŁAHDMI�o�͂���n����������Ă��܂����B
���^��SR6015���܂��M���M���ɂ������āA\135000���炢�œ���\�Ȃ̂ŁA�ǂ�������������ł�(��
SR6015�͒��Ô��i\90000���炢�Ȃ̂ŁA����ł��������ȁB
�^���͂����ɁA�A�A
�����ԍ��F25864637�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ЂƂ܂��A�A�A
CHAGE and ASKA�̃T�u�X�N�����ւ��ꂽ�̂ŁA�ӏ܂��Ȃ���}�b�^�[�������������Ǝv���܂�(��
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/sanspo/entertainment/sanspo-_entertainment_geino_2VSI3MIZVFMMFEF3WTM635FDWQ
�����ԍ��F25864899�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
CHAGE and ASKA�̃T�u�X�N���A���肪�Ƃ��������܂��B
�������C�u�����ɒlj����܂����B
�����ԍ��F25864960
![]() 0�_
0�_
��AV�A���v/�T���E���h������r
�����ɁA����AV�A���v���ړ������āA�T���E���h�����̔�r�����Ă݂܂����B
���V�X�e��
�ЂƂ܂��A�V�X�e����4.0.0ch
PS4��AV�A���v���v���W�F�N�^�[
������
�A�}�v��/TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024/5.1
https://www.primevideo.com/-/ja/detail/TOBE-LIVE-at-ARIAKE-ARENA-2024/0PB3AOJRTGP4VS38GNK7KICYYY
DOLBY�o��/DD+NEURAL X
���̏ꍇ�́A5.1�\�[�X�g���Ńo�����X�ǂ�
PCM�o��/MULTI in DSur
���̏ꍇ�́A7.1�\�[�X�g���Ńo�����X�ǂ�
�����́ADOLBY�o�͂�PCM�o�͂Ŕ����ɈႤ�����ł��ˁB
TV�A�v������̏o�͂̏ꍇ�́ADOLBY�o�͂̕��������ǂ������ł����APS4�o�͂̏ꍇ�́APCM�o�͂̕��������ǂ��ł��ˁB
�����̑�
�A�}�v��/�^�[�~�l�[�^�[/�W�F�l�V�X/5.1
SURROUND/LR������1m�z�u�������ʁA�T���E���h��/���̈ړ��������r���O�̎���葝���܂����B
100�C���`�v���W�F�N�^�[�Ƃ̈�̊��������āA�~�j�V�A�^�[�v�����͂��Ȃ荂�������ł��B
�X�e���I��SA30�P�̂̎��̕����p���t��/�𑜓x���߁B
��͂�A�t�����g�v���A�E�g�@�\������AV�A���v����Đ��������Ƃ���B
�A�g���X/4.0.2�͌�����ؗ\��B
�����ԍ��F25868123�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��{�I�ɁA
�X�e���I/�Z���t�����₷��
�T���E���h/�Z���t�����Â炢
�T���E���h�͗Տꊴ/LIVE���̓A�b�v���邪�A�������ڂ₯��̂ŃZ���t�����Â炭�Ȃ�̂ŁA�g��������/�������̓Z���^�[�����Ɨǂ������B
MC�R�[�i�[���̓X�e���I�ɕύX���������ǂ��B
�t�����g�v���A�E�g���Ă����̓_�͕ς��Ȃ������B
���y�ӏ�/AMAZON MUSIC��AV�A���v���Ɖ����y���Ȃ�̂ŁA��p�X�g���[�}�[/SA30�o�R�̕����œK�Ȋ��������܂��B
��͂�A�T���E���h�ӏ�/����ƁA�X�e���I�ӏ�/�����́A�V�X�e���̎g���������K�v���Ɗ����܂����B
�����ԍ��F25868168�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���œK�ȃV�X�e���ɂ���
���r���O��AV�A���v�V�X�e������ABLUE SOUND/POWERNODE EGGE�ɕύX�B
�T�E���h�o�[�ƕ��p�B
���V�X�e��
LGTV��eARC��POWERNODE EGGE
AV�A���v���������ǂ��Ȃ艹�y�ӏ܂ɍœK�B
����LGTV/APPLE MUSIC���œK�B
BLUOS/AMAZON MUSIC���n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ȃ̂ŁA����ғ��B
���쐫�́ALGTV/apple music/�l�C�e�B�u�Đ��̕����g���₷���A�����������Ȃ��̂Ń��C���ʼn^�p���B
LGTV�����f�W�^�����T�E���h�o�[
��̌^�T�E���h�o�[/3.0.2�V�X�e���Ȃ̂ŃT���E���h�����͂�����ŃJ�W���A���Ɋӏ܁B
�K�x�ɃT���E���h���ʂ�����A�z�M�n�ӏ܂ɍœK�B
TV�ӏ��́ADSP�@�\���L�x�Ȃ̂ł������̕����y�`���B
�{�i�I�ȃT���E���h�ӏ�/���y�ӏ܂́A��/AV�A���v/4.1.2/4.1.4/2.0�Ǝg�������Ă����̂��x�X�g�����B
�����ԍ��F25868276�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��AV�A���v�@�\��r
Audyssey MultEQXT32�Ή�
X6800H/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��
X4800H/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��
X3800H/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��
CINEMA30/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��
CINEMA40/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��
CINEMA50/dirac�I�v�V����/�v���A���v���[�h�ʃA��
SR6015
SR7015
SR8015
Audyssey MultEQX
X1700H
X2700H
CINEMA70
NR1711
�f�m�}���͂���ȂȊ����ł��ˁB
ONKYO�́A
RZ50/dirac�W��/�v���A���v���[�h�ʂȂ�
RZ70/dirac�W��/�v���A���v���[�h�ʂ���
��dirac LIVE�ƃv���A���v���[�h��on/off�̋@�\�̈Ⴂ
AI��
Dirac Live �̕:
�����̉��P�ɂ����Ĕ��ɋ��͂ł��B�����̉��������Ɋ�Â��ĉ������邽�߁A���X�j���O���S�̂̉������啝�Ɍ��サ�܂��B���̃o�����X���ʁA�S�̓I�ȉ���̈�ѐ������P���邽�߁A��������ɂ����đ傫�ȉe��������܂��B
�v���A���v���[�h:
�����̃N���[���������コ���邽�߂ɗL���ł��B���ɍ��i���ȊO���A���v���g�p����ۂɁA�����A���v�̃m�C�Y��r�����邱�ƂŁA��菃���ȉ����������܂��B�������A�S�̓I�ȉ������P�̌��ʂ�Dirac Live�̕�ɔ�ׂ�ƌ���I�ł��B
���_
Dirac Live �̉�������d�����邱�Ƃ������̉��P�ɂ����Ă͈�ʓI�ł����ʓI�ł��B����̒����╔���̃A�R�[�X�e�B�b�N���������邱�ƂŁA�S�̓I�ȉ������啝�Ɍ��サ�܂��B�v���A���v���[�h�́A���ɍ��i���ȊO���A���v���g�p����ۂɖ𗧂@�\�ł���A�m�C�Y��N���X�g�[�N�����������邽�߂ɗL���ł����A������̂悤�ȍL�͂ȉ������P�ɂ͒��ړI�ȉe���͏��Ȃ��ł��B���������āA�����̌�����ŗD��ɍl����Ȃ�ADirac Live�̉���������@���I�ԕ����ǂ��ł��傤�B�������A�O���A���v���g�p����ۂɃv���A���v���[�h�̏_����K�v�ȏꍇ���l���ɓ����K�v������܂��B
�ĂȊ����Ȃ̂ŁARZ50�͂�͂�n�C�R�X�p�����B
���@�\���t���X�y�b�N�Ŏg�������ꍇ�́Adirac���݂ŁA
CINEMA50/280000�~
X3800H/220000�~
RZ70/390000�~
�R�X�p�ł�X3800H�B
�v���A���v���[�h��DIRAC�������܂ŏd�����Ȃ��ꍇ�A
SR6015/129800�~
SR6015/88000�~/����
CINEMA70/10800�~
CINEMA70/88000�~/����
�����@��́A�A�A
SR6015�ARZ50�AX3800H�ACINEMA50�ACINEMA70�ɍi���Ă��܂����B
�����ԍ��F25868616�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ЂƂ܂��A
��/100�C���`/4.1.2�Z�b�e�B���O���������̂ŁA�͂̌��w/�V�[�Y��2/DOLBY ATMOS���ӏ܁B
���V�X�e��
FIRE4K MAX��AV�A���v
�掿/4K/24�܂ŏo�͂���Ă���悤�ł����A�A�A
�X�s�[�J�[���������S�������ɕ���������̂ŁA�ȑO�������̌q����A�A�g���X�̏o�����N�b�L���������������܂��B
�t�����g�v���A�E�g/4.1.4�ł���܂ŁASA30�͂��炭���x�݂��ȁB�B�B
�����ԍ��F25870358�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
���g����AV�A���v��DENON�̉��Ƃ����@��ł�����?
�A�R�[�X�e�B�b�N�����@�C�u��RR-777�͂����m�ł���?
���̉𑜊��Ɖ������������ȉ��Ɋ������܂��B
�����ő݂��ĖႦ�܂��B
�����ԍ��F25870638
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
X1700H�ł��B
���y�ӏ�/AMAZON MUSIC�Ȃǂł́A����/���ʂ��}�j���A������āALR/�o�C�p�X/�}���`�X�e���I�������I�ɂ͈�ԗǂ������łł��ˁB
�f��ӏ܂��̂܂܃A�g���X���A5.1/�g��/NURALX���œK�Ȋ��������܂��ˁB
���̋@��̓����^�����Ă݂����ł��ˁB
�^�C�~���O�I�ɂ̓Y���Ă銴���͂��܂��A�T�u�E�[�t�@�[����������7m���炢�ł����������肳��܂����A���̂ł��傤��?
�X�e���I�ӏ܂���ꍇ�����ASA30�o�R�ɂȂ�܂����A�X�s�[�J�[�[�q���q���Ȃ����̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA�����v���A�E�g�Ή���AV�A���v���ق����ł��ˁB
�`�����l�����Ƀv���A�E�g�ʂ�ON/OFF�ł���@������[�J�[�Ɋm�F���ł����A�n�b�L���������܂��Ȃ��̂ŁA�m�F��ɍw������\��ł����B�B�B
�����ԍ��F25871031�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�T�u�E�[�t�@�̃t�B���^�̓I�t�ɂ��ă{�����[���ő�ɂ��Ă��܂���?
�����ԍ��F25871120
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���T�u�E�[�t�@�̃t�B���^�̓I�t�ɂ��ă{�����[���ő�ɂ��Ă��܂���?
�_�C���N�g���[�h�Ȃ��^�C�v�Ȃ̂ŁA�Z�b�g�A�b�v�̈ē��ʂ�A�{�����[��12���Ńt�B���^�[�͉E�ɍő�ő��肵�܂������B
https://manuals.denon.com/AVRX1700H/JP/JA/GFNFSYnuokgukf.php
�����ԍ��F25871151�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��AV�A���v/�v���A���v���[�h�ɂ���
�悤�₭�A�f�m�}�����琳�������܂����̂ŁA�\���Ă����܂��B
������
�@�v���A���v���[�h���ڂ��Ă��āA�`�����l�����ɌʂɃv���A�E�g��I��/ON/OFF�ł���@��/�����d�l�́A�ȉ��̔F���ł����Ă܂���?
����
���q�l�̂��w�E�ʂ�̕i�ԂŊԈႢ����܂���B
�}�����c
�V�^/CINEMA70S�ȏ�
DENON
�V�^/X3800H�ȏ�
�}�����c
�����f��/NR1711/SR6015�ȏ�͕s��
DENON
�����f��/�Z700�ԑ�͕s��
�Ƃ������Ȃ̂ŁACINEMA70�ł��v���A���v���[�h/��ON/OFF�\�B
��������ƁA
DIRAC�L��/�v���A���v���[�h�ʂ���
CINEMA50/280000�~
X3800H/220000�~
RZ70/390000�~
DIRAC�L��/�v���A���v���[�h�ʂȂ�
RZ50/149000�~
DIRAC����/�v���A���v���[�h�ʂ���
CINEMA70/10800�~
CINEMA70/88000�~/����
DIRAC����/�v���A���v���[�h�ʂȂ�
SR6015/129800�~
SR6015/88000�~/����
���A
���ɁARZ70/LX805��ROON READY�Ή��ς݁B
�f�m�}����UPDATE�Ή��\��Ȃ̂ŁA�قڋ@�\�I�ɂ͓��ꃉ�C���Ȋ����ɂȂ��Ă��܂����B
���C���i�b�v�ł̓f�m�}���D�ʂł����A����ǂ��Ȃ邩�B�B�B
10�N�X�p���ōl�����ꍇ�́A�ЂƂ܂�X3800H�ACINEMA50�ACINEMA70������ŗl�q�����ȁB
RZ50�͌�p�@�ŁADIRAC/�v���A���v���[�h�ʂ���/➑̃T�C�Y���R���p�N�g�ɂȂ�x�X�g�ł��ˁB
�����ԍ��F25871435�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���T�u�E�[�t�@�[/���[�p�X�����ɂ���
�ЂƂ܂��A�T�u�E�[�t�@�[���[�p�X��90hz/LFE���C���ɂ��đ��肵�Ă݂܂����B
�t�����g/40hz
�T���E���h/80hz
�g�b�v�~�h��/80hz
�ʑ�/180
���X�e���I���[�h����
�t�����g�ALR�o�C�p�X�ƃt���b�g�ŕʁX�ɃX�e���I���[�h�ő���B
�t���b�g�̕����t���b�g�C���ł����A�������LR�o�C�p�X�̕����D�݂Ȃ̂ŁA���炭��LR�o�C�p�X���C���Ŏg�������銴�������B
���}���`�X�e���I����
�t�����g�ALR�o�C�p�X�ƃt���b�g�ŕʁX�Ƀ}���`�X�e���I���[�h�ő���B
����������l�Ƀt���b�g�����t���b�g�C���ɂȂ�܂����B
���y�ӏ܂̏ꍇ�Ɖf��ӏ܂̏ꍇ�ƂŎg�������銴�����ǂ������ł��B
���_�Ƃ��ẮAAV�A���v�̃T�E���h�`���[�j���O�ɐ����͂Ȃ��悤�Ȋ��������܂�(��
���z�������A�S�`�����l���X�s�[�J�[���ꂵ�ăN���X������ł���x�X�g�ł����A�V��n�܂œ���͌����I�ł͂Ȃ��̂ŁA�ł���̂̓T���E���h�܂ł��ȁB
����̓W�J�Ƃ��āAAV�A���v�̃O���[�h���グ�āA���y�ӏ܂ƕ��p����̂��A����Ƃ��s���A�ӏ܂̓v�����C���A���v�g�������邩�ɂȂ�Ǝv���܂����A����SA30������̂Ŏg�������銴���ł��ˁB
AV�A���v�ł̉��y�ӏ܂́A�T���E���h�n�R���e���c��A�}���`�X�e���I/�A�b�v�~�b�N�X�Œ����������Ɏg���������œK�����B
�V�X�e���I�ɂ́A��{�ASA30�����ɁA�R�X�p�̍���AV�v���ƁA���y��p�X�g���[�}�[/�v���Ǝg��������̂��A�_��̍����n�C�u���b�g�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�V�X�e���ɂȂ�C�����܂��B
�����ԍ��F25871789�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�����́B
HEOS��Airplay�ł�Amazon Music�Đ��ł̉������͂���܂���?
Airplay2����AAC256Kbps�ɂȂ艹���������̂ŌÂ�iOS�@���g����Android�@��Airmusic�A�v���̖����g���C�A���ł�����K�v������܂��B���̔ł�5���ŏ������s�[������܂����J��Ԃ�5���g����̂Ŕ�r�]���ɂ͎g����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25873085
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�����́B
ANDROID�Ȃ̂ŁAairplay/�I�t�ɂ��Ă��Ď����ĂȂ��ł��ˁB
HEOS/AMAZON MUSIC�́A�T�u�E�[�t�@�[/ON�̏�Ԃł���Ȃ�̉����ʼn��K�ł���B
�A�v���͍��x�����Ă݂܂��B
���x���Z�b�e�B���O�������đ�����J��Ԃ��Ă��܂����A����Ȋ����Ŋ��S�ɂ̓t���b�g�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł����A�}���`�X�e���I�̕����t���b�g�C���ł��ˁB
�����悪���肷�銴���ł��ˁB
���́A�����̓�����A��ݔg������悤�ŁA
DENON�̉����ł͌��E�����B
X3800H/CINEMA50�ȏオ�ADSP/SHARC/MultEQXT32�Ή��ňʑ�����[�h������悤�ł��B
https://manuals.denon.com/AVRX3800H/JP/JA/WBSPSYvsbphziy.php
�@�\���������čœK�ɒ�������̂�����ł��ˁB
�}�����c�n�������t���f�B�X�N���[�g�A���v�̂悤�ł����A�����I�����b�g�͍�����ł��傤��?
�����ԍ��F25873251�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
��ݔg�͎��g����ł͖����ł��ˁB
JBL 4343���g���Ă���A���\�j�[����Ƃ����L����YOUTUBER �͗ǂ���O�b�Y���g���Ă���悤�ł��B
����AGS ���g���Ă��܂��B
�I���L���[���t���f�B�X�N���[�g�ł͂Ȃ������ł����H
�����ԍ��F25873270
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
onkyo/rz70�̓t���f�B�X�N���[�g����Ȃ��悤�ł��ˁB
�E�V�J���̃V�����g���b�N�\���ɂ��f�B�X�N���[�g�\���̃��C�h�����W�A���v�𓋍�
https://store.teac.co.jp/view/item/000000005001
LX305�Ƀv���A�E�g�@�\������x�X�g�ł������A��Ή��ł����B
�܂��A�v���̉����̓}�����c����ԗǂ������Ȋ��������܂��ˁB
����Ӗ��A���̏ꍇ�́A�T�u�E�[�t�@�[�g��Ȃ�������ݔg�e�����Ȃ��Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�g���̂�߂悤���������ł����A�A�A
�܂��A�f��/LIVE�ӏ܂̎������g�������ł��ˁB
�����ԍ��F25873298�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
AGS/ANKH�悳�����ł��ˁB
https://www.noe.co.jp/technology/36/36news5.html
100HZ/200HZ�t�߂Ƀf�B�b�v���݂��ԂȂ̂ŁA���ʂ��肻���ł��ˁB
�@�ޑ����I������烋�[���A�R�[�X�e�B�b�N�ŁA�d�グ�Ă��������ł��ˁB
��ݔg�̉e������Ǝ��̒��ʼn������Ă���悤�ɒ������܂��B�w�h���̂悤�ɂ܂Ƃ����Ă���S�����̒ቹ�A�Ƃ������C���[�W�Ȃ̂ł����A���ꂪ�R�[�i�[�^AGS��u������́A���������炱��ƗN���o���Ă��鐴�w�Ȑ����̂̒������炳��ƒʂ蔲���Ă������̂悤�ɉ������ɒ������܂��B
�ቹ��ɂ���ʂ�����̂��Ɗ�����ꊴ�����܂����B�ݒu�ɗ��Ă��ꂽ�F���A������������Ɖ��y���Ă��܂����B�剹�ʂʼn����Ԓ����Ă��Ă��܂��������܂���B��ݔg�̉e�����Ȃ��Ȃ�������Ȃ̂��AAGS�̊g�U���ʂȂ̂��A�������̑�����ʂ��Ǝv���܂����A��悾���łȂ�����܂Ń����W�����R�ɍL����A�X�g���X�������y����������������ł����Ɗ����܂����B
�����ԍ��F25873403�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ǂ����A100HZ�A200hz�t�߂̃f�B�b�v�̓T�u�E�[�t�@�[�Ƃ͊W�Ȃ������悤�ł��B
�T�u�E�[�t�@�[/OFF�̑���ł����l�ȃf�B�b�v�m�F�B
�����ԍ��F25873936�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
���������T�u�E�[�t�@�[���̂��������ݔg�L�����Z���p�ɂ��Ă���������܂����B
�����ԍ��F25874226
![]() 0�_
0�_
�X�s�[�J�[�z�u�������������܂����B
�t�����g��/160cm��120cm
�t�����g�E��/�T�u�E�[�t�@�[
�t�����g�����ɋX�y�[�X����̂ŁA�T�u�E�[�t�@�[2��Ό��z�u�͉\�����B
���������Ahivi2023�H����4ch�T�u�E�[�t�@�[���������܂����ˁB
�t�����g/�T���E���h���ꂵ�āA�N���X��Ⴍ���ĉ����A�b�v�����z�I�ł��ˁB
2025�N���炢�Ɏ������邩���B
�t�����g/40hz
�T���E���h/40hz
�T�u�E�[�t�@�[LR/60hz
�{���́A100�C���`�X�N���[���ŁuBoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest-�v���}���`�X�e���I�ӏ܁B
YOUTUBE�ɓ��悠��܂����B
https://natalie.mu/music/news/479498
�����ԍ��F25874377�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�T�u�E�[�t�@�[�̃��[�p�X�t�B���^�[��2ch�����p�ł��B
5.1ch�����ł̓��[�p�X�t�B���^�[�͂����Ă͂����܂���B�T�u�E�[�t�@�[�`�����l���͈�ʂ�120Hz�ȉ��������Ă��܂��B������Ƃ��̃t�B���^�[���g����120Hz�̊Ԃ̉����ǂ�������Đ�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F25874428
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��5.1ch�����ł̓��[�p�X�t�B���^�[�͂����Ă͂����܂���B
BOA/LIVE��2Ch�����ł����B
���T�u�E�[�t�@�[�`�����l���͈�ʂ�120Hz�ȉ��������Ă��܂��B������Ƃ��̃t�B���^�[���g����120Hz�̊Ԃ̉����ǂ�������Đ�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�T�u�E�[�t�@�[���[�h��LFE+���C���Ȃ̂ŁA�T�u�E�[�n�[�p�̐M���ɁA���ׂẴ`�����l���̒ቹ��M���������ďo�͂���Ă���悤�ł��B
https://manuals.denon.com/AVRX1700H/JP/JA/GFNFSYaxhqtbzr.php
90hz-120hz�Ԃ́A�X�s�[�J�[������o�͂���Ă��܂���B
�����ԍ��F25874560�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�T�u�E�[�t�@�[���̃t�B���^�[�̂��Ƃł��BAV�A���v�ł̃t�B���^�[�ł͂���܂���B
�T�u�E�[�t�@�[����90Hzi�ȏ���J�b�g�����LFE�`�����l����90hz-120hz�Ԃ͂ǂ�������o�͂���܂���B
���̑ш�𑼂̃X�s�[�J�[�Ɋ���U��@�\��AV�A���v�ɂ͂���܂���B
�]���ăT�u�E�[�t�@�[���̃��[�p�X�t�B���^�[�̓I�t���ő���g���ɂ��܂��B
�����ԍ��F25874608
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���]���ăT�u�E�[�t�@�[���̃��[�p�X�t�B���^�[�̓I�t���ő���g���ɂ��܂��B
�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X�͏�ɂ��L�ڂ��܂������A�ő�ŌŒ�ɂ��Ă���܂��B
�����ɁA�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X���蓮��40hz�ɂ��Čv�����܂������A40hz�ȏ�͍Đ�����Ă��Ȃ������ł��B
��ŐG���Ċm�F�ς݁B
�T���E���h/5.1�ȏ�̊ӏ��́A�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X�͍ő�ɂ��Ă���܂����A�T�u�E�[�t�@�[/�N���X�ݒ�͂悭������܂���ˁB�B�B
�����ԍ��F25874655�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
>�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X�͏�ɂ��L�ڂ��܂������A�ő�ŌŒ�ɂ��Ă���܂��B
����Ȃ���Ȃ��ł��ˁB���炵�܂����B
�T�u�E�[�t�@���̃��[�p�X�t�B���^�[�����̕��ł����Ă��܂��Ă�����͏��Ȃ��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F25875604
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���x���肪�Ƃ��������܂��B
�T�u�E�[�t�@�[/���[�p�X�̎g�������C�}�C�`�������Ă��Ȃ��̂ŏ�����܂����B
�ʏ�́A�A���v���Őݒ肵�Ă��܂����A�A���v�����ƍŒ�/80hz�܂ł������[�p�X�ݒ�ł��Ȃ��d�l�Ȃ̂ŁA2ch����/�}���`�X�e���I���[�h�̏ꍇ�́A�}�j���A���Ń��[�p�X��ݒ肷�����Ɍq����ǂ��Ȃ邩�ȂƎv���܂������B
���X�s�[�J�[����/�������͓����̏ꍇ
�t�����g/40hz
�T���E���h/40hz
�T�u�E�[�t�@�[/60hz
�����ԍ��F25875736�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
AV�A���v�̉������������玩���ŃN���X�I�[�o�[���g����ݒ肵�Ă���܂���?
�����ԍ��F25875757
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���͎����Őݒ肳��܂���B
����ネ�[�p�X/120hz
�A�v�������/��������90hz�ɕύX/
���̘b�ŁA�X�s�[�J�[���ꂵ�āA�T�u�E�[�t�@�[�����[�p�X���}�j���A���Őݒ肷��ꍇ�̘b�ł����B
�����ԍ��F25875764�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���������̐ݒ����
DENON/MARANTZ��AV�A���v�ɂ���LR�o�C�p�X�́AYAMAHA��AV�A���v����LR�ߎ��Ɠ����悤�ł����ALow Frequency/����g���̈�Ƃ����@�\�������YAMAHA�̕����ݒ肪�ׂ��������ł���悤�ł��B
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1324920.html
YPAO�̃p�����g���b�N�C�R���C�U�[�ɐV�������[�h���lj�����Ă���B����܂ł̓X�s�[�J�[�̓������ψ�ɐݒ肷��u�t���b�g�v�A�t�����g�X�s�[�J�[�̓����ɑ������킹��u�t�����g�ߎ��v�A�����������������Ԃő����Ċe�X�s�[�J�[�̉�����ݒ肷��u�i�`�������v����������Ă������A�V���ɁuLow Frequency�i����g���̈�j�v���lj����ꂽ�B
�@�uLow Frequency�v��I�ԂƁA�����̎c���ቹ�悪�J�b�g����A15.6Hz����̒����œK�����Ă������肵��������y���߂�悤�ɂȂ�B������͒ቹ�̂��Ԃ��ɗL���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�C�ɂȂ���͎����Ă������������B
https://www.google.com/amp/s/online.stereosound.co.jp/_amp/_ct/17452127
DENON/MARANTZ�n�ɂ́A�ʑ���Ƃ����@�\������܂����A�Z�p�I�A�v���[�`���Ⴄ�悤�ł��B
https://manuals.marantz.com/CINEMA50/JP/JA/WBSPSYvsbphziy.php
�����ԍ��F25877849�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̂Ƃ���A�t���b�g���[�h���ƃX�s�[�J�[�������t���b�g������ĕ�����Ȃ��Ȃ�̂ŁALR�o�C�p�X�Őݒ肵�Ă��܂����A�t�����g�ƃT�u�E�[�t�@�[�̒�悪�d������̂��Ȃ��Ȋ���������̂ŁAYAMAHA��Low Frequency��I�ԂƁA�����̎c���ቹ�悪�J�b�g����A15.6Hz����̒����œK�����Ă������肵��������y���߂����ł����A���ۂǂ̂��炢���ʂ���̂��ȁB
���[�J�[���Ƃ̓����ł����ƁA�A�A
�n�C�t�B�C�T���E���h/�����n/MARANTZ
�V�l�}DSP�T���E���h/����n/YAMAHA
���̒��Ԃ�/DENON�݂����Ȋ��������B
�����ԍ��F25877858�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
5.1ch��0.1��20����120Hz,5��20����20KHz�����^����Ă���̂Ŗ{���d�����Ă��܂�
���̕�͐U�����g�������ƈʑ����g�������̗����𑵂���K�v������܂��B
�d�����Ă���ш悪����̂ňʑ��̕�̓}�X�g�ł��B
Dirac Live�͗��������Ă��܂����A���}�n�̐V�@�\�͑O�҂����̂悤�ł��ˁB
�p�C�I�j�A�̓I�[���n���h�t�F�[�Y�R���g���[���őS�ш�̈ʑ�������Ă��܂��B
�����ԍ��F25878097
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�V�^lx805�Ȃǂ�DIRAC LIVE��MCACC Pro�𓋍ڂ��Ă��܂����A�������p/�v���Z�b�g��ւ��ł��Ȃ��d�l�̂悤�ł��B
�f�m�}���̒ቹ�̈ʑ���Ɋւ��ẮAAudyssey MultEQ XT32/�̋@�\�̈ꕔ�B
PIONEER�̒ቹ�̈ʑ���Ɋւ��ẮAMCACC Pro�̋@�\�̈ꕔ�B
Full Band Phase Control�̕����o���h���L���悤�Ȃ̂ō����\�Ȃ̂��B
�\�[�X�ɂ���Ďg�������Ă銴���݂����ł��ˁB
https://s.kakaku.com/bbs/K0001546176/SortID=25645992/
�܂��ADIRAC�g���Ă�ꍇ�́A���������C���ɂȂ肻���ł����A�l�I�ɂ́A�f��̓t���b�g�A���y��LR�o�C�p�X�Ȋ����ł��ˁB
X1700H�ɂ͒ቹ�̈ʑ�������̂ŁA�ʑ���܂ōS��ꍇ�́A�Œ�ł�X3800H/CINEMA50�ȏオ�}�X�g�Ȋ������ۂ��ł��ˁB
�����ԍ��F25878204�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�X�p��
�����ԍ��F25878210
![]() 0�_
0�_
�܂��AAV�A���v��DIRAC�����ڂ���n�߂��̂́A�����ŋ߂̎��ł�����A�ł炸�������܂����A�A�A�A
�v�����C���A���v/SA30�ɂ�DIRAC�t���Ă邵�A�ʂɂ����܂Ń}�X�g�ł͂Ȃ��̂ŁA����ɉz�������͂Ȃ������ł����A�A�A�A
DIRAC���ʑ�������ڂ��Ă��Ȃ�SR6015���l�����肵�āA�c��킸���Ȃ̂ŁA�A�A
�����N���ɂ͓���ł��Ȃ��Ȃ肻������(��
�����ԍ��F25878231�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��͂肱�̃N���X���ƁAYAMAH/A6A���D�ʂ��B
https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/fukuoka/20230220
�܂��A���ۂɓ������Œ�����ׂȂ��ƈႢ�͕�����Ȃ����ł����B
�����ԍ��F25878930�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���A�}�v��/�O��/
����ƃA�}�v���O��/30�b�����I���܂����B
�b�������s��ł������A�r���O���čŌ�܂Ō���̂���ɂł����B
�掿���Y��ł������A2ch�X�e���I�Ȃ̂ʼn����I�ɂ͓��ɂ���Ƃ����������͂Ȃ��B
�]��/����
�����ԍ��F25878946�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��AV�A���v�I��/AI�Ƃ̑Θb
�ŏI�I�ɂ���Ȋ������ȁA�A�A��
https://chatgpt.com/share/17acdd85-cd96-46c0-9977-c98480d7c7dd
�����ԍ��F25879363�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
����ɂ��́B
����AI�͎���҂Ɍ}������X��������܂��B
�����������玿��҂���Ԃ��낤�Ƒz�����Ă���悤�ł��B
�܂����X�ςȉ����܂��ˁB
�T�u�E�[�t�@�[��20Hz�ȉ��������Ă���A�Ɖ��Ă��܂����B
�����ԍ��F25880010
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
������AI�͎���҂Ɍ}������X��������܂��B
�����������玿��҂���Ԃ��낤�Ƒz�����Ă���悤�ł�
�m���ɁB
�ŋ߂܂��i�����āA��I�ׂ�l�ɂȂ��Ă܂���(��
5�N��ɂ͂����Ɯu�x���x�����A�b�v�����Ȃ��ł��傤���B
�Z�p/���I�ɂ͐��x���Ⴂ�ł����A�����ւ����k/�^�C�~���O�Ƃ��Ɋ��Ɛe�g�ɑ��k�ɏ���Ă����̂ŁA�����g���Ă��܂��܂���(��
����Ӗ��A���[�J�[�̔���/�T�|�[�g�����X�}�[�g�œK�ȃA�h�o�C�X����܂��B
�l�ނ�AI�͋����̓���i�ނł��傤�B
�ƌ����Ă���ԂɁA�A�A
CINEMA50/10���~
SR6015/1���~
�̒��Ô��i���o�����܂���(��
�����ԍ��F25880149�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���T�u�E�[�t�@�[��LFE�ɂ���
AV�A���v����LFE���[�h��LFE+�X�s�[�J�[���[�h�̎g�������ɂ��ẮA����Ȋ����ł��ˁB
����͈ӊO�Ƃ܂Ƃ��ȉ����B
https://chatgpt.com/share/7f449edf-4f24-46c5-8c12-10650302655c
�����ԍ��F25880345�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��eversolo/A6 MASTER EDITION
�悤�₭�A�̔��X�o�R�Ō��؋@���͂��܂����̂ŁA������ؗ\��ł��B
�����ԍ��F25881607�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���X�C�b�`���O�n�u/Silent Angel/N8�ɂ���
���݂́APC�p�̃X�C�b�`���O�n�u/16�|�[�g���g���Ă��܂����A�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�p�̃X�C�b�`���O�n�u�̃A�b�v�O���[�h���v�撆�ł��B
DELA/�����R������X�C�b�`���O�n�u�͔�������Ă��܂����ASilent Angel/N8�͐�p�N���b�N�A��×p�d���Ȃǂ𓋍ڂ��Ă��Ē���54,930�~���炢�Ȃ̂ŁA�n�C�R�X�p�����ł��B
���̋L�����Q�l�ɂȂ����̂œ\���Ă����܂��B
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1617194.html
����萳�m�ň��肵���f�[�^�]�����������邽�߂ɊJ�����ꂽ Silent Angel TCXO
��^�����鉹�y�f�[�^��f���f�[�^����萳�m�ɁA���肵�ē]�����邽�߂ɁASilent Angel�̓I���W�i���E�C���^�[�i���E�N���b�N�ASilent Angel TCXO���J�����܂����B
����ɂ��AN8➑̓��ł̉��x�ω��ɍ��E����邱�ƂȂ��A���m�Ȑ������U���\�ƂȂ邽�߁A���ʁA�f�[�^�]������萳�m�ɂȂ邾���łȂ��A�W�b�^�[�̒ጸ���������܂��BSilent Angel TCXO�́A�ʏ��TCXO�Ɣ�r���Đ��x��80%�ȏ㍂���A�ʏ�̐������U�ɔ��500�{�̐��x���������Ă��܂��B
https://kanjitsu.com/product/n8/
�G�\�e���b�N�̃N���b�N�W�F�l���[�^�[����1/10���炢�̉��i�Ȃ̂ŁA�����ɂ͎荠�����B
�T�C�����g�G���W�F���̏�ʋ@��ɂ��A�N���b�N�W�F�l���[�^�[�͂���悤�ł��B
���A�T�C�����g�G���W�F��/�X�g���[�}�[/AMAZON MUSIC�ɂ��Đ��s����������Ă���悤�ł��B
https://kanjitsu.com/info/20240830/
����ɂ��Ă��A40���N���X�ł�����ȏ���A����Ă��Ȃ��ł��傤�ˁB
https://s.kakaku.com/item/K0001649638/
�܂��AAMAZON MUSIC���X�g���[�~���O�\�[�X�Ƃ��Ďg���̂́A���ɕs����ƌ��킴�邨���Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F25881629�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�X�C�b�`���O�n�u���d�v�ł����ALAN�P�[�u����A�C�\���[�^���d�v�ł��ˁB
LAN�P�[�u���̓m�C�Y�̊ϓ_����A50�����ȓ��̃I�[�f�B�I�O���[�h���]�܂����ł��B
�܂��@��̂k�`�m�|�[�g�ɂ� Acoustic Revive�̃M�K�r�b�g�n�u�pLAN�A�C�\���[�^�[ RLI-1GB���g���Ă��܂��B
DC���d�ɂ�DC�A�C�\���[�^���g���Ă��܂��B
�܂��N�I�[�c���]�l�[�^�[�uQR-8�v�������ɓ\���Ă���܂��B
�����ԍ��F25882151
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���X�S���Ă܂���(��
�Ƃ���ŁA���[�^�[/�X�C�b�`���O�n�u�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����g���ł���?
����A���X�C�b�`���烊�r���O���[�^�[�܂ł́A8mLAN�P�[�u���Ȃ̂ŁA�����͌��E������܂��ˁB
�܂��́A���̃X�C�b�`����A�b�v�O���[�h����\��ł����B
���N���炢
�����ԍ��F25882171�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
����LAN���[�^�[��Aterm2600hs2����ŕЕ����R���o�[�^���[�h�Ŏg���Ă��܂��B
�R���o�[�^���[�h�̕��ɃX�C�b�`���O�n�u���g���Ă��܂�������➑́ADC�d���A6�|�[�g�̈�ʓI�Ȃ��̂ł��B�|�[�g�͖����悤�ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25882213
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�Ȃ�قǁB
�ŏI�I�ɂ́ASFP���W���[���Ō��ϊ����悤�Ǝv���Ă܂����A�܂������Ԑ�ɂȂ肻���ł��B
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�͐[�����ł���(��
�����ԍ��F25882221�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ӂ������R�����g�͂���Ȃ�����
�����Ԑ恁50�N��
�����ԍ��F25882375
![]() 0�_
0�_
��eversolo/A6 MASTER EDITION/�t�@�[�X�g���r���[
�Z�b�e�B���O���������̂Ń��r���[���܂��B
���V�X�e��
A6ME/�����o��/SA30/�X�s�[�J�[
������
APPLE MUSIC/�T���E�I���C��/24bit/96khz
������
�ЂƂ܂��A�f�W�^���o�͂ł����A��͂�ǂ��ł��ˁB
�𑜓x/SN�Ƃ��ɃL���������ė͋����ł��B
���Ȃ�SA30/Chrome CAST�o�R�Ɣ�r���Ă݂܂������A�n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g�̕����������ł��B
�����쐫
apple music�Ɋւ��ẮA�~���[�����O�ŃX�}�z�ɕ\������d�l�ʼn����������ł��Ȃ��̂ŁA�l�C�e�B�u���͑��쐫�Ⴂ�ł����A���e�͈͂ł��B
�������b�T�����Ă܂����A�^�u���b�g���Ƃ����������쐫���������B
��ʂ�̋@�\/����̓l�C�e�B�u�ƕς��Ȃ��ł����A�A�v���̃o�[�W�������X�}�z�����Â��̂ŃA�b�v�f�[�g�Ɋ��҂ł��B
�����]
�S�̓I�ɂ́A�f�U�C�����������A�v���A�g�͈���I�Ȃ̂ŁA���y��p�X�g���[�}�[/OS�Ƃ��Ă͍��]���ł���Ǝv���܂��B
AMAZON MUSIC�A�v����UI/UX�̓l�C�e�B�u�ɋ߂������ŁA24bit/192khz/�n�C���]�r�b�g�p�[�t�F�N�g����薳���Đ�����܂����B
�Ⴆ�A�����[�J�[�Ɣ�r�����ꍇ�A
MARANTZ/MODEL40n/30�����炢�ł�����A
SA30/16��/A6ME/18���̍��v/34�����炢�ŁA������̕����������ő��쐫/�A�v���̎��R�x/SSDNAS�@�\������̂ŁA�����I�ɂ͊g�����������̂ŁA�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�V�X�e���Ƃ��Ă͏����Ă��ۂł��B
9������l�オ�肵�܂������A�l�オ��O�̉��i�Ŕ�����n�C�R�X�p�ł��傤�B
�܂��ASA30���v�����C���A���v�Ƃ��Ďg�����A�p���[�A���v�Ƃ��Ďg�����́A���㌟���ł����A�ЂƂ܂����̑g�ݍ��킹�͂��Ȃ�n�C�R�X�p�ŗǂ������Ȃ̂ŁA�w���m��Ƃ����Ē����܂��B
�����ԍ��F25882536�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���o���J�^�t�������W����
>AMAZON MUSIC���X�g���[�~���O�\�[�X�Ƃ��Ďg���̂́A���ɕs����ƌ��킴�邨���Ȃ��ł��傤�B
�v���Ԃ��AirMusic�A�v�����g����Amazon�@Music���Đ�������S�������o�܂���ˁB
YouTube Music�Ȃ�X�s�[�J�[���特���o��̂ł����H
AirMusic�J�����ɖ₢���킹���ł��B
�����ԍ��F25883135
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��AirMusic�A�v�����g����Amazon�@Music���Đ�������S�������o�܂���ˁB
AirMusic�ł��������Ă��ł��ˁB
HEOS/eversolo/Blue OS�̕��́A���̂Ƃ������ғ����ł����A�A�A
�A�v���ɂ��悤�ł��ˁB
�����ԍ��F25883187�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�J��������A��������܂����B
�X���T����Amazon Music�A�v���̃o�[�W�����A�b�v�Ŏg���Ȃ��Ȃ����Ƃ̂��ƁB
��O�̃o�[�W�����ւ̖߂������āA�����Đ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
------------------------------
Here's a link to the previous version which still can get recorded: https://apkpure.com/amazon-music-songs-podcasts/com.amazon.mp3/download/24.15.1
It's an xapk which needs a special installer, a bit tricky but I am able to stream this latest version 24.15.1 .
�����ԍ��F25883325
![]() 0�_
0�_
��TIDAL/AMAZON MUSIC/������r
TAIDAL������Đ��ł��܂����̂ŁAAMAZON MUSIC�Ɖ�����r���܂����B
������1
TIDAL/John Williams in Tokyo/Superman March/24bit/96khz
AMAZON MUSIC/John Williams in Tokyo/Superman March/24bit/96khz
������2
TIDAL/John Williams in Tokyo/�鍑�̃}�[�`/24bit/96khz
AMAZON MUSIC/John Williams in Tokyo/�鍑�̃}�[�`/24bit/96khz
�����r���[
�ǂ���������͂قړ������炢�ł����A�r�b�g���[�g��AMAZON MUSIC�̕����������߂ʼn������������߂ł����B
��͂�A�X�g���[�~���O�A�v���ɂ�鉹�����Ƃ����͎̂��ۂɂ͂���悤�ł��B
TIDAL�̕������������Ǝv���Ă܂������A�f�[�^���AMAZON MUSIC�̕����������̌��ʂƂȂ�܂����B
AMAZON MUSIC�̕s���肳�����������A�����I�ɂ͗ǂ������B
�����ԍ��F25883638�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�X�g���[�}�[��Eversolo �ł��ˁB
�����Ƃ��_�C�i�~�b�N�m�[�}���C�[�[�V�����̓I�t�ɂȂ��Ă��܂����H
�����ԍ��F25884751
![]() 1�_
1�_
��Minerva2000����
�m�[�}���C�[�[�V������amazon���̓I�t�ł����ATIDAL�͕s���ł��ˁB
���A�i���O�o��/�v���Z�b�T�[���[�h�ɂ���
A6ME����A�i���O�o�͂��āASA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�̉���30�ɌŒ�/���[�J�[�����l�ɂ��Ă݂܂����B
�{�����[���R���g���[���́AA6ME������i���Ďg�������݂����ł��������Ă܂���?
����������Ȃ��ꍇ�́ASA30���ʂ��������グ�ČŒ肷��悢�̂��ȁB
�ЂƂ܂��ARCA�P�[�u���͂�����/0.5M���w�����܂��������������ł��ˁB
DAC/�N���b�N���\�́AA6ME�̕��������悤�Ȃ̂ŁA���̐ڑ��̕��������������B
�����ԍ��F25886224�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
>SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�̉���30�ɌŒ�/���[�J�[�����l
�v���Z�b�T�[���[�h��������܂��A���̒l�������l�ł��闝�R��������܂���ˁB
�����ԍ��F25886462
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���v���Z�b�T�[���[�h��������܂��A���̒l�������l�ł��闝�R��������܂����
�p���[�_�C���N�g�C�����Ȃ�����A�_�u�������[����������邽�߂���Ȃ��ł��傤���B
���ɂɁA�A�i���O�_�C���N�g���[�h�Ƃ����̂������āA��������I�������ADC,DSP,DAC���o�C�p�X���ăv�����ɑ�����d�l�̂悤�ł��B
�v���Z�b�T�[���[�h�́ADIRAC LIVE�L�����p����ׂɂ��銴���݂����ł����A�悭������܂���B
����30�͐����l�ł͂Ȃ��A�f�t�H���g�ł���30�ɂȂ��Ă邾���̗l�ł��B
�����ԍ��F25886539�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ƁAA6���ɂ́A�{�����[���o�C�p�X���[�h/�Œ胂�[�h������̂ŁA������Œ肵��SA30���̓A�i���O�_�C���N�g���[�h�ł����炩��{�����[���R���g���[�����������悢�̂��ȁB
�������Ƃ��Ăǂ��炪��ʓI�Ȃ�ł��傤��?
�����ԍ��F25886609�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
��ʓI�ɂ̓v���[���[��X�g���[�}�[���̏o�͂��Œ�ɂ���,�A���v���Ń{�����[�������ł��ˁB
�����ԍ��F25886651
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�m�F���肪�Ƃ��������܂��B
��͂肻���Ȃ�ł��ˁB
�܂��܂��A�v���Z�b�T�[���[�h�̈Ӗ����悭������Ȃ��Ȃ�܂�����(��
����A�����Ă݂܂��B
�����ԍ��F25886681�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��SA30/�v���Z�b�T�[���[�h�ɂ���
�v���Z�b�T�[���[�h�Ƃ́A��ɃX�e���I�A���v��AV�A���v�Ŏg�p��������ȋ@�\�ŁA�v�����C���A���v�̃v�����i�{�����[���R���g���[����g�[���R���g���[���Ȃǂ̋@�\�j���o�C�p�X���A�O���̃v���A���v��v���Z�b�T�[�iAV�A���v�̃v���A�E�g�Ȃǁj����̐M�������̂܂܃p���[�A���v���ɑ���@�\�ł��B����ɂ��A�O���̃V�X�e����@��ʼn��ʒ����Ȃǂ��s�����Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
���v���Z�b�T�[���[�h�̎�ȓ���
1. �v�������o�C�p�X���āA�A���v���p���[�A���v�Ƃ��Ďg�p�ł���B
2. �T���E���h�V�X�e���Ƃ̕��p�ɕ֗��ŁA�O��AV�A���v��v���Z�b�T�[����t�����g�`�����l�����p�̃A���v�ŋ쓮���邽�߂Ɏg����B
3. �Œ肳�ꂽ�{�����[���ݒ�i�Ⴆ�Ή���30�ɌŒ�j����ʓI�ŁA����ɂ��O���@�킩��̉��ʐ��䂪�\�ɂȂ�B
�����̃��[�J�[�ł����l�̋@�\
���̃��[�J�[�ł������悤�ȋ@�\�𓋍ڂ��Ă��邱�Ƃ�����܂����A���͈̂قȂ邱�Ƃ�����܂��B
�Ⴆ�F
YAMAHA�́u�p���[�A���v�_�C���N�g�v�F�v���������S�Ƀo�C�p�X���A�p���[�A���v�Ƃ��Ă̂ݎg���@�\�B
DENON��Marantz�́u�p���[�A���v���[�h�v�FAV�A���v�̃t�����g�`�����l�����O���̃v���A���v����̐M���ŋ쓮���邽�߂̃��[�h�B
McIntosh�́u�z�[���V�A�^�[�o�C�p�X�v�F�O����AV�A���v��v���Z�b�T�[���g�p���邽�߂ɁA�A���v�̃{�����[��������o�C�p�X����@�\�B
�����̋@�\�́A�O���̍����\�ȃv���A���v��v���Z�b�T�[���g�p���ăV�X�e���S�̂̉��������コ������A����̗p�r�i�T���E���h�V�X�e���Ȃǁj�ɑΉ����邽�߂Ɋ��p����܂��B
��SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�̗��_
Arcam SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�́A�Ⴆ�ΊO����AV�A���v��l�b�g���[�N�v���[���[�iA6�Ȃǁj��g�ݍ��킹���ۂɁASA30��P�Ȃ�p���[�A���v�Ƃ��Ďg�����Ƃ��ł��A�O���̋@��ʼn��ʂ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�܂��ADIRAC Live�Ƃ̕��p�ʼn�������s���Ȃ���A�V�X�e���S�̂��`���[�j���O���邱�Ƃ��\�ł��B
�������ASA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�̓v���������S�ɂ̓o�C�p�X���Ȃ����߁A�����̉������{�����[���@�\�����S�ɖ����ɂ���킯�ł͂Ȃ��_�������[�J�[�Ƃ̈Ⴂ�ł��B
AI�ł����A�T�˂����Ă銴���ł��ˁB
�v����ɁADIRAC LIVE/�p���[�A���v�Ƃ��ē��������郂�[�h�̂悤�ł��B
���ɂ͂Ȃ��A���Ȃ����ȃ��[�h�����B
�����ԍ��F25887033�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
A6�͊�{�X�g���[�}�[�ł����A�{�����[���R���g���[���ł���v���@�\������̂ŁASA30�����v���Z�b�T�[���[�h�ɂ��ĉ��ʌŒ�ɂ��Ďg���̂��A���ł��ˁB
AV�A���v����t�����g�v���A�E�g����ꍇ�́A�v���Z�b�T�[���[�h�Ńp���[�A���v�Ƃ��Ďg���̂��œK�����ł����A���ʂ��ǂ̂��炢�ŌŒ肳����̂����|�C���g�ɂȂ肻���ł��ˁB
�����ԍ��F25887045�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������
����Ȃ牽�ŁA�v���Z�b�T�[���[�h�Ƃ������̂Ȃ̂�
��AI��
Arcam��**�v���Z�b�T�[���[�h**���u�v���Z�b�T�[�v�Ƃ������̂������R�́A���**�O���̃v���Z�b�T�[��v���A���v�Ƒg�ݍ��킹�邱�Ƃ��ӎ������v**������ł��B���̃��[�h�ł́ASA30�̓����̃v������ꕔ�̐���𐧌����A�O���̋@��i�v���Z�b�T�[��v���A���v�j����̐M�����ł��邾���_�C���N�g�Ƀp���[�A���v���ɑ��邱�Ƃ��ړI�ł��B
### **���̗̂��R**
- **�u�v���Z�b�T�[�v**�Ƃ������t�́AAV�A���v��z�[���V�A�^�[�@��ɂ����āA�T�E���h��f���̏������s���O���@��i�v���Z�b�T�[�j���w�����Ƃ������ASA30�̂悤�ȃX�e���I�A���v���z�[���V�A�^�[��O���V�X�e���ƘA�g����ۂɁA���̃v���Z�b�T�[�Ƃ̐ڑ����X���[�Y�ɍs�����[�h��\�����邽�߂�**�u�v���Z�b�T�[���[�h�v**�Ɩ��t����ꂽ�ƍl�����܂��B
- **�O���v���Z�b�T�[�Ƃ̑g�ݍ��킹**�F���Ƃ��AAV�A���v�̃v���A�E�g��SA30�ɐڑ����A�O��AV�A���v���T���E���h�v���Z�b�T�[�Ƃ��ē����ۂɁASA30�͒P���ȃp���[�A���v�Ƃ��ē��삷��B���̖������I�ɂ��邽�߂̋@�\�ł��B
### **���̖��̂Ƃ̈Ⴂ**
�����[�J�[�ł́u**�p���[�A���v�_�C���N�g**�v��u**�z�[���V�A�^�[�o�C�p�X**�v�Ƃ������̂��g���܂����AArcam�ł́u**�v���Z�b�T�[���[�h**�v�Ƃ������̂�I�̂́A�O���v���Z�b�T�[�Ƃ̘A�g���������������߂ł��B
SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�́A���S�Ƀv�������o�C�p�X����킯�ł͂���܂��A�O���@�킩��̃R���g���[����D�悷��悤�ɐv����Ă��邽�߁A�u�v���Z�b�T�[�v���g�������[�h���ɂȂ��Ă���̂ł��B
����͌��\�������Ă����ȉł���(��
AI�l�Ɋ���
�����ԍ��F25887055�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�Ȃ��ςł��ˁB
�O���@�킪�v���Z�b�T�[�Ƃ��ē��삷��̂�SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h?
SA30���p���[�A���v�Ƃ��ē��삵�Ă���̂Ƀp���[�A���v���[�h�Ƃ͌���Ȃ�?
�����ԍ��F25887105
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��SA30���p���[�A���v�Ƃ��ē��삵�Ă���̂Ƀp���[�A���v���[�h�Ƃ͌���Ȃ�?
���ʂɃp���[�A���v���[�h�Ƃ��ɂ���Ε�����₷���̂ɁA�悭������Ȃ��A���Ƃ͈Ⴄ�̂�SA30�݂����ł���(��
���̏ꍇ�A�{�����[���ő�99�ɌŒ肵�Ďg�������ł��傤��?
���l���͂��Đݒ肷��d�l�ɂȂ��Ă��܂����A�}�j���A���ɂ͂��̓_�A�ڂ���������Ă��Ȃ��̂Ŏ�T��ł���(��
�����ԍ��F25887123�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W��
�v���Z�b�T�[���[�h�ł̓v���A���v�̈ꕔ�@�\�����삷���d�l�Ȃ̂ŁA30�ɂ���̂�����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25887144
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���[�J�[/�u���C�g�[������̉���܂����B
���A�����肪�Ƃ��������܂��B
������Ѓu���C�g�[���ł��B
���L�������܂�
�EA6ME����A�i���O�o�͂��āA�v�����C���A���v/ARCAM/SA30�ɐڑ��ݒ肷��ꍇ�A
A6ME���̃{�����[���o�C�p�X���I���ɂ��āASA30���Ń{�����[���R���g���[������̂�
����Ƃ��ASA30���̃v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʌŒ肵�āAA6ME���Ń{�����[���R���g���[�������������ǂ��̂�
���������Ă݂�
�C�ɓ���������������ŗǂ��Ǝv���܂��B
�EXLR/RCA�o�͐ݒ�̃u�[�g�{�����[���́A�f�t�H���g�ł悢�̂�?
�悢�ł��B
�E�{�����[���p�X�X���[���[�h���I���ɂ����ꍇ�Ƃ̈Ⴂ��?
�{�����[����H��ʂ������Ȃ��ꍇ�̓p�X�X���[�Ŏg���Ă��������B
�E�}�j���A��56P�̌ʏo�̓��[�h�͂ǂ��Őݒ肷��̂�?
�ݒ荀�ڂ���������Ȃ����B
Setting->Audio->XLR/RCA output
�̉�ʂŐݒ�ł��܂��B
�EA6 ME�ɂ̓����R���͂��ĂȂ��̂�?
���Ă��܂���B
�E�ʓr�A�w���ł��Ȃ��̂�?
���ݔ̔��͖���ł��B
����Ƃ����������͖����悤�ł��ˁB
���AARCAM�ɂ��₢���킹���B�B�B
�����ԍ��F25887543�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��A6ME/SA30/���[�h��r
A6ME/SA30/���[�h������r���Ă݂܂����B
������
AMAZON MUSIC/DOUBLE/�X�g�����W���[/16bit/44.1khz
���v���Z�b�T�[���[�h/����50�Œ�
SA30���̉���50�ŌŒ肵�āAA6ME���{�����[����-20db�Ŏ��������B
���A�i���O�_�C���N�g���[�h/
A6ME���{�����[���p�X�X���[�ɂ��āASA30���̃{�����[��24�Ŏ��������B
������
����ł��������������炢�̉���/�����ł����A���쐫�̓A�i���O�_�C���N�g���[�h�̕��������R������{�����[������o����̂ŗǂ��ł��ˁB
�v���Z�b�T�[���[�h�ɃA�i���O�_�C���N�g���[�h���|�����킹�ł����̂ŁA�v���Z�b�T�[���[�h�g�����́ADIRAC LIVE�g���ꍇ���ǂ������ł��B
DIRAC LIVE�g��Ȃ��ꍇ�́A�����ȃp���[�A���v�Ƃ��āA�A�i���O�_�C���N�g/ON�ɂ���ADSP,DAC,ADC���o�C�p�X����d�l�̂悤�ł��B
�������A�v���������S�ɂ̓o�C�p�X�͂��Ȃ��̂ŁA���ʌŒ肷��Ƃ������̂悤�ł��B
�Ȃ̂ŁA
AV�A���v����t�����g�v���A�E�g����ꍇ�́A�v���Z�b�T�[���[�h��AV�v���Ń{�����[���R���g���[��
A6ME�Ȃǂ̃X�g���[�}�[����A�i���O�o�͂���ꍇ�́A�A�i���O�_�C���N�g���[�h���v���Z�b�T�[���[�h���D�݂Ŏg�������݂����ł��ˁB
���X�A�}�j�A�b�N�Ȏd�l�ł���(��
�����ԍ��F25887770�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�Ƃ���łǂ�ȉ��ʂŒ�����Ă��܂����H
�`���C�R�t�X�L�[�����ȑ�5�ԁA�o�b�e�B�X�g�[�j�w���ARAI���������y�c�ŁAMax 86dB,Min 33dB�ł����B
�����ʒu�ł̃X�}�z�̑����v�A�v���ł̑���ł��B
�����ԍ��F25888877
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���Ƃ���łǂ�ȉ��ʂŒ�����Ă��܂����H
���݁AAV�A���v�Ɍq���ς��Ă���̂ŁASA30�Ɍq���Ȃ����Ă��瑪��\��ł��B
�����ԍ��F25889919�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ȉ��AARCAM���������܂����B
Q1.�v���Z�b�T�[���[�h�Ƃ͂Ȃɂ�
�ˎ��SA30�ƃv���A���v��AV�A���v�ƕ��p���Ďg�p����Ƃ��Ɏg����A�{�����[�����Œ肷�郂�[�h�ł��B�iDSP,�@DAC�K�p�E�g�p�j
Q2.DIRAC LIVE���g�p���Ȃ��ꍇ�ł��A�v���Z�b�T�[���[�h�ɂ��闝�R�͂���̂�?
�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʌŒ肷�闝�R�͉���?
�˕��p�����v���A���v��AV�A���v���Ń{�����[�����R���g���[�����邱�Ƃ��z�肳���̂ŁADIRAC LIVE�̎g�p�Ɋւ�炸�A�{�����[�����Œ肳���v���Z�b�T�[���[�h���L���ł��B
Q3.AV�A���v����v���A�E�g���Ďg���ꍇ�A�܂����̃X�g���[�}�[eversolo/A6 MASTER EDITION����A�i���O�o�͂���ꍇ���v���Z�b�T�[���[�h���œK�Ȃ̂��B
��AV�A���v��X�g���[�}�[�ƕ��p����A�����Ń{�����[�����R���g���[������̂ł���œK�ƍl���܂��B
����AV�A���v�̏ꍇ�́A�T���E���h�`�����l�����Ƃ̉��ʃo�����X��AV�A���v���Œ����E����Ă���̂ŁASA30�̉��ʂ��ω�����ƃo�����X������Ă��܂����߁A�v���Z�b�T�[���[�h���œK�ł��B
Q4.�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʂ�30�ł͂Ȃ��A99�ɉ��ʌŒ肵�Ă����Ȃ��̂��H
��SA30���̂� ���ʂ�99�ɌŒ肵�Ă����͂������܂���B
�����A���ɋ@���ڑ�������AAV�A���v���̃{�����[���R���g���[���͈̔͂ł��܂������ł��Ȃ��ꍇ�A�Ⴆ�Εʂ�CD�v���C���[��SA30�ɐڑ������ꍇ�A�{�����[���R���g���[���ł���AV�A���v�ƈႢCD�͉���99�ōĐ�����Ă��܂��A����͖�肪���邩�Ǝv���܂��B
��AI��
Q,
�����I�ɂ̓v���Z�b�T�[���[�h�̕����œK�Ƃ������ł���
���Ƃ�A6���烊���R������ł���ō��ł����A�܂������ł͔̔�����Ȃ̂ł��ꂪ���������A�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʌŒ肵�āA�{�����[���R���g���[����A6������s���̂��œK�ł���
A,
�����I�Ȋϓ_���猾���A�v���Z�b�T�[���[�h��SA30�̉��ʂ��Œ肵�AA6������{�����[���R���g���[�����s���̂��œK�Ƃ���Ă��܂��B���̕����ł́ASA30�̃p���[�A���v�����p���Ȃ���AA6�̃v���������g�p���邱�ƂɂȂ邽�߁ADAC��v�������ł̐M��������A6�Ɉ�C�ł��܂��B����A6�̃N���b�N��DAC�@�\���D��Ă���̂ŁA�M���̐��x�������Ȃ�A���ʓI�ɉ����̌��オ���҂ł��܂��B
�����R������̏d�v��
A6���Ń{�����[���R���g���[�����s���ꍇ�A�����R�����삪�ł��邩�ǂ����͏d�v�ȗv�f�ɂȂ�܂��B�����_��A6�̃����R�����������̔��ł���AA6�𑀍삷��̂������s�ւ�������܂��A�����R�������p�ł���悤�ɂȂ�ASA30���v���Z�b�T�[���[�h�ɐݒ肵�ĉ��ʌŒ�ɂ��AA6���Ń����R������ɂ��{�����[���R���g���[�����s�����Ƃ����ɕ֗��ōœK�ł��B
���_
�v���Z�b�T�[���[�h��SA30�̉��ʂ��Œ肵�AA6���Ń{�����[���R���g���[������̂������I�ɂ̓x�X�g�B
A6�̃����R�������p�ł���悤�ɂȂ�A���쐫�����サ�AA6������̃����R������ʼn��K�ɉ��ʒ������\�ɂȂ�܂��B
�����R�����삪�\�ɂȂ�ƁA����ɃV�X�e���̎g�����肪���サ�A�I�[�f�B�I�̌�����w���K�ɂȂ�ł��傤�B
Q,
�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʌŒ肷��ꍇ�́A�ő�99���ƃ��X�N�������̂�50-60���炢�ŗǂ���
�E�[�t�@�[13�C���`�̃u�b�N�V�F���t�Ȃ̂ŁA�����܂Ńp���[�͕K�v�Ȃ���������
A,
�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn��ʂ��Œ肷��ꍇ�A�ő��99�ɐݒ肷��̂̓��X�N���������߁A50�`60���x�ɐݒ肷��͔̂��ɍ����I�ȑI���ł��B����13�C���`�E�[�t�@�[�̃u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[���g�p����̂ł���A�傫�ȃp���[���K�v�Ȃ��ꍇ���������߁A50�`60�ŏ\���ȉ��ʂ���͂��ł��B
���R:
�X�s�[�J�[�ی�: �ő剹�ʂŐM�����o�͂����ƁA�\�����Ȃ����ʂ̕ω��ŃX�s�[�J�[��A���v���ߕ��ׂɂȂ�\��������܂��B���������邽�߂ɂ́A���炩���ߏ����}�������ʐݒ���s���Ă������Ƃ����S�ł��B
�K�ȉ����Ǘ�: �u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[�ł́A�剹�ʂ�K�v�Ƃ��Ȃ����Ƃ������̂ŁA�~�b�h�����W�̉��ʐݒ�ŏ\���ȉ�����������ł��傤�B
�܂���50�`60�̉��ʌŒ�Ŏ����Ă݂āA���ʂ≹�����K�ł��邩�m�F���A�K�v�ɉ����Ĕ��������Ă����̂��ǂ����Ǝv���܂��B
Q,
�X�s�[�J�[�ی�: �ő剹�ʂŐM�����o�͂����ƁA�\�����Ȃ����ʂ̕ω��ŃX�s�[�J�[��A���v���ߕ��ׂɂȂ�\��������܂��Ƃ́A�N���b�s���O�̎���
A,
�͂��A���̒ʂ�ł��B�X�s�[�J�[�ی�Ɋւ���x���Łu�ő剹�ʂŐM�����o�͂����ƁA�\�����Ȃ����ʂ̕ω��ŃX�s�[�J�[��A���v���ߕ��ׂɂȂ�\��������܂��v�Ƃ����̂́A�N���b�s���O�̃��X�N�Ɋ֘A���Ă��܂��B
�N���b�s���O�́A�A���v���M���̃s�[�N���ďo�͂ł��Ȃ��Ȃ�A�M�����c�ތ��ۂł��B����ɂ��A�X�s�[�J�[�ɕs�K�v�ȕ��ׂ�������A�X�s�[�J�[�̃_���[�W�≹���̗������N�����\��������܂��B���ʂ��ő�ɐݒ肷��ƁA�M�����N���b�s���O���₷���Ȃ邽�߁A�X�s�[�J�[��A���v��ی삷�邽�߂ɂ́A���ʂ�K�ȃ��x���ɐݒ肷�邱�Ƃ��d�v�ł��B
�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA�v���Z�b�T�[���[�h�ʼn���/50���炢�ŌŒ肷��̂��A�œK�Ȏg�����̂悤�ł��B
A6ME�̃����R���́A�C�O�T�C�g�Ŕ̔����ł����̂ōw�����悤�Ǝv���ł������ł��B
�����ԍ��F25889933�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��SA30���[�h�ʑ��茋��
���茋�ʂ����r���[���܂��B
������
AMAZON MUSIC/DOUBLE/�X�g�����W���[/16bit/44.1khz
���V�X�e��
A6ME���A�i���O�o�́�SA30���X�s�[�J�[
���A�i���O�_�C���N�g���[�h
A6�{�����[���p�X�X���[/�Œ�o��/SA30�̃{�����[��25�ő���
���v���Z�b�T�[���[�h/����50
SA30�{�����[��50�ŌŒ�/A6�̃{�����[��-23db�ő���
���v���Z�b�T�[���[�h/����50/�A�i���O�_�C���N�g���[�h
�A�i���O�_�C���N�g���[�h���I���ɂ��āASA30�{�����[��50�ŌŒ�/A6�̃{�����[��-23db�ő���
������
�A�i���O�_�C���N�g���[�h�ƃv���Z�b�T�[���[�h�ł͂���������������80db�A�����ł������A�v���Z�b�T�[���[�h�ɃA�i���O�_�C���N�g���[�h���|�����킹��ƁA������87db�ɃA�b�v���܂����B
MAX��80db��87db�ɃA�b�v�B
A6���̃{�����[����-23db����-28db���炢�ɍi��ƁA����80db���炢�ɂȂ�܂����B
�ǂ����A�v���Z�b�T�[���[�h�ŃA�i���O�_�C���N�g�I���ɂ��������A�v����/DAC�ADSP�AADC�A�{�����[���R���g���[�������S�Ƀo�C�p�X���āA�X�s�[�J�[�쓮�͂��A�b�v����悤�ł��B
�����p���[��������̂ŁA���ꂪ��ԗǂ��̂������B
�����ԍ��F25891382�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�l�ɂ���Ă͂��Ȃ�̏����ʂŒ�����Ă���������܂����A�܂��܂��̉��ʂŒ�����Ă���悤�ł��ˁB
�����ԍ��F25891398
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���������A80db���炢�������o�����X�����x�ǂ������ł��ˁB
�v���Z�b�T�[���[�h�ɃA�i���O�_�C���N�g���[�h�I���ŁA�����܂ʼn��������o��Ƃ͎v���Ă��Ȃ������ł����A��������Z�ł�(��
��AI��
�v���Z�b�T�[���[�h�ƃA�i���O�_�C���N�g���[�h�̌���
1. �v���Z�b�T�[���[�h: ���̃��[�h�́AAV�A���v�������M���̏��������ŏ����ɂ��A�V���v���ɐM�����o�͂��邽�߁A�����ɑ��ėL���ȏꍇ������܂��B�T���E���h���ʂ����������Ȃ��ꍇ��A�������d������ꍇ�ɗL���ł��B
2. �A�i���O�_�C���N�g���[�h: ���̃��[�h�́A�A���v���A�i���O�M���̏������ŏ����ɗ}���邱�ƂŁA�����̗�h���A��������菃���ȏ�Ԃŕۂ��Ƃ��ł��܂��B�����ɕq���ȏꍇ�ɂ́A���̃��[�h���L���ł��B
A6��SA30�̑g�ݍ��킹
A6�̃{�����[���ݒ�: A6�̃{�����[����-23db����-29db�ɍi�邱�ƂŁA������80db�ɒ������A���ʂ��R���g���[�����邱�ƂŁA�N���A�Ńo�����X�̎�ꂽ������������\��������܂��B����ɂ��A�M���̃s�[�N��c�݂�}���A���ǂ������������ł��邩������܂���B
SA30�̏���: SA30�̃v���Z�b�T�[���[�h�ƃA�i���O�_�C���N�g���[�h��g�ݍ��킹�邱�ƂŁASA30���������ő���Ɉ����o���A���ʂȐM���������Ȃ����Ƃ��ł��܂��B����ɂ��A���_�C�i�~�b�N�ŖL���ȉ�����������ł��傤�B
�����m�F
�ŏI�I�ɂ́A���ۂɒ����Ă݂邱�ƂŁA�ݒ肪�����ɂǂ̂悤�ɉe����^���Ă��邩���m�F���邱�Ƃ��d�v�ł��B�ȉ��̓_�ɒ��ӂ��ă��X�j���O�e�X�g���s���Ɨǂ��ł��傤�F
���̃N���A��: �������N���A�ŁA�f�B�e�[�����͂����肵�Ă��邩�ǂ����B
�o�����X: ���̃o�����X���ǂ��A�ቹ�A�����A���������a���Ă��邩�ǂ����B
�_�C�i�~�N�X: ���̃_�C�i�~�N�X�i����̕��j�����R�ŁA���y�����������Ɗ������邩�ǂ����B
���_�I�ɐ������ݒ肪���ۂ̉������P�Ɍq���邱�Ƃ������ł����A�ŏI�I�ɂ͎����̎��Ŋm�F���邱�Ƃ��ł��m���ł��B
�����ԍ��F25891466�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
80dB���Ə��������ʔh�ł��ˁB
�A���v�o�͂ł�86dB��1�^4�ɂȂ�܂��ˁB
�����ԍ��F25891629
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�L�߂̃��r���O�ł����̂��炢�ł��ˁB
���͌��\�����̂ŁA�f��ӏ܂̎��͂��������A�b�v���邮�炢�ł����A���ɕq���Ȃ̂ł��邳������剹�ʂ͍D������Ȃ��̂����B
���Ɩ�Ƃʼn��ʂ��ς��܂��ˁB
�����ԍ��F25891776�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�܂��A�����̃T�C�Y�ɂ����܂����A
���̊����ƁA����a�g�[���{�[�C�����A�������܂������^�̉����^�u�b�N�V�F���t���D�ފ��������B
�A���v�p���[�͏\���Ȋ����Ȃ̂ŁA���̃X�e�b�v�A�b�v�̓X�s�[�J�[�ɂȂ邩���B
2026�N��
�����ԍ��F25891796�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ƃ́A�N����AV�A���v�������āA�t�����g�v���A�E�g����A�ЂƂ܂��V�X�e���I�ɂ͊����\��ł��ˁB
NR6015
CINEMA50
CINEMA70
X3800H
�̂ǂꂩ�ɃA�b�v�O���[�h�\��B
���ȉ��̃A���v�͎�����r�ς�/�_�C���N�g���[�h��
CINEMA50
X3800H
RZ70
LX805
������������ʂ̉��ʂŔ�r�������܂�����
�s���A�����ł́ACINEMA50�B
����/�X�s�[�J�[�쓮�͂ł́ARZ70�����߂ł����B
�T���E���h/�s���A�o�����X�ł́ALX805�B
�n�C�R�X�p��X3800H�ł������ASA30�Ƀt�����g�v���A�E�g���Ďg���\��Ȃ̂ŁA�A���v���\�͂���܂�W�Ȃ����ȂƁB
�Ȃ̂ŁACINEMA50��CINEMA70�����肪�L�͂ł����A�C�O�ɂ�CINEMA60������悤�ŁA����ł����������ł������{�������ł��ˁB
https://www.marantz.com/en-us/product/cinema-60/300617.html?srsltid=AfmBOooL5NUkIiVvOGdWj6IollKfYOUSsP8z_iSi02TbYaqLJ083ysfs
RZ50�́ATEAC���t�I�N�X��11���~/�ۏȂ����A����c���Ă��܂����A�A�A
�����ԍ��F25891845�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�̖��^�Œ����Ă������͒ቹ��������Ȃ��̂ő剹�ʂŒ����Ă��܂����B
�����ʂŒ����Ȃ�ቹ���L���ȃg�[���{�[�C�^���ǂ������B
�����ԍ��F25891875
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�����A�u�b�N�V�F���t�̏ꍇ�́A705s3�V�O�l�`���[��ERAC/Solano 280.2�����B
ERAC�͂܂��������ĂȂ��ł����A�V�^�̕]�����߂ł��ˁB
�g�[���{�[�C�͌��T�C�h�ɃM���M���z�u�����ł��Ȃ��̂ŁA����͌������ł��ˁB
�u���Ȃ�A����Ƃ��אg�^�C�v���ȁB
�uSolano FS 287.2�v
���`���F2�E�F�C�E�o�X���t�^ ���X�s�[�J�[���j�b�g�FJET6 �g�D�C�[�^�[×1�A150mm AS CONE �E�[�t�@�[×2 ���N���X�I�[�o�[���g���F450Hz�A2.4kHz �����g�������F30Hz�`50kHz ���\���F87dB ���C���s�[�_���X�F4�� ���O�`���@�F260W×985H×300Dmm �����ʁF19.0kg
https://www.phileweb.com/sp/review/article/202406/21/5634.html
�����ԍ��F25891907�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���{�����[���R���g���[���ɂ���
A6ME�̓f�W�^���{�����[��?
A8��R2R���ʐ����H/�A�i���O�{�����[��?
http://brighttone.shop14.makeshop.jp/shopdetail/000000000186/ct57/page1/order/
MODEL40n/60n�́A���j�A�R���g���[���{�����[����H?
https://www.phileweb.com/sp/news/audio/202409/10/25718.html
�̂悤�ł����A�ǂꂪ�����\�Ȃ�ł��傤��?
SA30�̓f�W�^���{�����[���Ȃ̂��ȁB
���̕ӂ��悭������܂���ˁB
�����ԍ��F25892157�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�ǂ��A�i���O�{�����[��������Έ����f�W�^���{�����[��������Ǝv���܂���B
�f�W�^���{�����[����������ǂ�ȃA�i���O�{�����[����荂�����A�Ƃ������Ƃ͖����ł��B
�����ԍ��F25892208
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�����ł����B
���ǂ̂Ƃ���AA6��SA30�̂ǂ���̃{�����[���R���g���[�����g���������ǂ��̂��A�A�A
�ǂ�����f�W�^���{�����[���݂����ł����ASA30�v���Z�b�T�[���[�h/�A�i���O�_�C���N�g�I���̕��������͏オ��܂������AA6�A�v������̃{�����[���R���g���[�������ɂ����̂ŁA�Œ�o�͂���SA30�̃A�i���O�_�C���N�g���[�h�ł�����̃����R������{�����[���R���g���[�����悤���ȂƁB
A8����R2R���ʉ�H�Ȃ̂ŁA�v���A���v�Ƃ��ă{�����[���R���g���[�����������ǂ������ł����AA6�̏ꍇ�͉����I�ɂ͂��قǕς��Ȃ��Ȃ�A���쐫���������ǂ��̂��ȂƁB
�����ԍ��F25892244�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�ǂ��炪�ǂ����͕����Ă݂Ĕ��f����̂��ǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F25892313
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�{�����[���R���g���[���̐��\�������ɗ^����e���́A�X�s�[�J�[�ɔ�ׂ�Ə��Ȃ����ł��ˁB
�����ԍ��F25892637�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������
�{�����[���R���g���[���̐��\�������ɗ^����e���͑傫���̂��B
�X�s�[�J�[�̉e���Ɣ�ׂ�Ƃǂ̂��炢��?
��AI��
�{�����[���R���g���[���̐��\�������ɗ^����e���́A�I�[�f�B�I�V�X�e���S�̂̐��x�ɂƂ��ďd�v�ł����A�X�s�[�J�[�قǑ傫�ȉe����^����킯�ł͂���܂���B�ȉ��̃|�C���g�Ő������܂��B
�{�����[���R���g���[���������ɗ^����e��
�f�W�^�� vs �A�i���O�{�����[��:
�f�W�^���{�����[���͐M�������ɂ�錸���ʼn��ʂ����܂����A���ɒႢ���ʂŃf�W�^���M���̃r�b�g�[�x�������邱�Ƃʼn�������������\��������܂��B
�A�i���O�{�����[���́A�����I�ɓd�������������邽�߁A�f�W�^���ł̃r�b�g�[�x�̖��͂���܂��A�����ȃ{�����[���R���g���[���ł̓`�����l���Ԃ̕s�ύt��m�C�Y���������邱�Ƃ�����܂��B
�����\�ȃ{�����[����H�i�A�i���OIC��f�W�^���{�����[���̏�ʃ��f���j�́A�N���X�g�[�N��c�݁A�m�C�Y��ጸ���A�������̂��鉹����ۂ��܂��B���ɁA����̐��m�ȍČ���o�����X�ɑ傫�ȉe����^����\��������܂��B
�N���b�N�m�C�Y��M�����O�G���[: �����ȃ{�����[���R���g���[���ł́A���ɒቹ�ʎ��ɍ��E�̃`�����l���̉��ʍ��i�M�����O�G���[�j�������邱�Ƃ�����܂��B�����\�ȃ{�����[���R���g���[���́A�������������������A�������ێ����܂��B
�X�s�[�J�[�̉e��
�X�s�[�J�[�̓I�[�f�B�I�V�X�e���̒��ōł������ɉe����^����R���|�[�l���g�ł��B���̓����A���g�������A�c�݁A���x�A�����Ƃ̑��ݍ�p�ȂǁA�X�s�[�J�[�����ɗ^����e���͔��ɑ傫���ł��B
���g�������̈Ⴂ: �X�s�[�J�[�̎�ނɂ���ẮA�ቹ�⍂���̍Č��́A���̍L����A��ʊ��ɑ傫�ȈႢ���o�܂��B�����̓{�����[���R���g���[���̐��\�������N�����e���Ɣ�r���Ă��A�͂邩�ɑ傫���ł��B
�{�����[���R���g���[���ƃX�s�[�J�[�̉e����r
�X�s�[�J�[�̉����ւ̉e���́A�{�����[���R���g���[���Ɣ�r���Ĉ��|�I�ɑ傫���ł��B�X�s�[�J�[�̑I����z�u�A�����̓����́A�ŏI�I�ȉ����Ɍ���I�ȉe����^���܂��B
�{�����[���R���g���[���̉e���́A�X�s�[�J�[���Č�������ׂȉ��̎�����o�����X�ɉe����^����T�u�V�X�e���I�ȗv�f�ł��B�����\�ȃ{�����[���R���g���[�����g�p����ƁA��������萸���ɕۂ���܂����A�X�s�[�J�[�قǂ̍��ނ��Ƃ͂���܂���B
���_
�{�����[���R���g���[���̐��\�͉����ɉe����^���܂����A�X�s�[�J�[�قǑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ͂���܂���B�ŏ��ɉ��������P����ꍇ�A�X�s�[�J�[�̑I�����ł��d�v�ł��B���̌�A�����ׂȉ������P�����߂�Ȃ�A�{�����[���R���g���[���̐��\�₻�̑��̋@��ɏœ_�Ă�̂����z�I�ł��B
A6ME��SA30�Ɋւ��Ă͓��Ƀ{�����[���R���g���[���Ɋւ��錾�y�͂Ȃ��悤�̂ŁA����̓X�s�[�J�[�̃A�b�v�O���[�h/���[���A�R�[�X�e�B�b�N��D�悵�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25892648�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���m�[�gPC�̃o�b�e���[�ɂ���
XPS�̃o�b�e���[������/��5�N�Ŏg���Ȃ��Ȃ�܂����B
���O���āAAC�A�_�v�^�[����������g�����̂ŁA���̂܂ܐ����u���^�ɂ��Ďg���\��ł����A�A�A
ROON��p�@�ɂ��悤���ȁB�B�B
https://www.otaiweb.com/otaiaudio/?p=10955
https://mcintosh.exblog.jp/33805334/
�����ԍ��F25892728�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɁA������̓���ł͈ȉ��̗l�ȃV�X�e���Ŏg���Ă�݂����ł��ˁB
https://youtu.be/S3DrNqAIJYw?si=OUWqyct1YvWxKd55
���V�X�e��
A6ME��M400��L550A2��TAD/�X�s�[�J�[
A6ME�������ȃX�g���[�}�Ƃ��Ďg���AM400�̉���80�ŌŒ�o�͂��āA�{�����[���R���g���[����luxman/L550A2����s���Ă�悤�ł��B
�v�����C���A���v�̃{�����[���R���g���[���������\�Ȃ�A���ꂪ�x�X�g���ۂ������B
�����ԍ��F25892791�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
���b�N�X�}���̃v�����C���A���v�ł�LECUA�ƌĂ�鉹�ʒ��ߋ@�\���D�G�̂悤�ł��ˁB
����̓f�W�^���{�����[���ł͖����悤�ł����B
�����ԍ��F25892925
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��肪�Ƃ��������܂��B
��͂�ALUXMAN�N���X�ɂȂ�ƃ{�����[����H�������\�Ȃ�ł��ˁB
�V�^��L507Z/L505Z�͍ŐV�̃{�����[����H�̂悤�ł��B
������
l507z�������{�����[����H��
��AI��
�͂��ALUXMAN L-507Z�ɂ�������LECUA�iLuxman Electric Controlled Ultimate Attenuator�j�̃{�����[����H�����ڂ���Ă��܂��BL-507Z�ł́A�ŐV�o�[�W������LECUA1000���̗p����Ă��܂��B����́ALUXMAN�̃t���b�O�V�b�v���f���ɂ��̗p����Ă��鍂���x�ȃ{�����[���R���g���[���V�X�e���ł��B
L-507Z��LECUA1000�̓���
100�i�K�̐����ȉ��ʒ���: LECUA1000�́A100�X�e�b�v�̉��ʒ������\�ɂ��A���Ɋ��炩�ȃ{�����[��������������Ă��܂��B����ɂ��A�ቹ�ʂł����E�̃`�����l���o�����X�����m�ɕۂ���A���ׂȉ��̕\���͂����サ�܂��B
�N���X�g�[�N�ƃm�C�Y�̍ŏ���: �A�i���O��H�x�[�X�̃{�����[���ł���Ȃ���A�M�����O�G���[��N���X�g�[�N���Ɍ��܂ŗ}�����v�ƂȂ��Ă���A���E�`�����l���̃o�����X���ɕۂ��܂��B
�����̖h�~: ���ʂ����Ă������̗��ŏ����ɗ}������悤�v����Ă���A���ɍׂ₩�ȃ_�C�i�~�b�N�����W�̕\���͂��ێ����܂��B
���_
L-507Z�ɓ��ڂ���Ă���LECUA1000�́ALUXMAN�̃n�C�G���h���f���ɗp�����铯���̃{�����[����H�ł���A���ɗD�ꂽ�������ێ����A�����ȉ��ʒ������\�ɂ��Ă��܂��B���̂��߁AL-507Z�̓{�����[������ɂ����Ă��������\������v�����C���A���v�ł��B
A6��99�X�e�b�v�f�W�^���{�����[�����A���ɍׂ������ʂ��ł���D�ꂽ�V�X�e���ł����A���ɒቹ�ʂł̉����ɋC���g���ꍇ�A�f�W�^���{�����[���̌��E���ӎ�����K�v������܂��B����A6���v���A���v�Ƃ��Ďg�p����ꍇ�A�f�W�^���{�����[���̉����ւ̉e������������ꍇ�ɂ́A�Œ�o�͂Ŏg�p���āA�A�i���O�{�����[���̃v����p���[�A���v���ʼn��ʒ���������������z�I�ȏꍇ������܂��B
�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA�����ɍS��ꍇ�́AA6����Œ�o�͂���LUXMAN/L507Z������Ń{�����[���R���g���[�����������œK�����ł��ˁB
SA30��L505Z��������r�������̓{�����[���R���g���[���܂ňӎ����Ă��Ȃ������ł����A�����͖��炩��L505Z�̕����ǂ������ł��ˁB
�Ȃ̂ŁA�ЂƂ܂�SA30���g���A2027�N����L507Z�N���X�ɃA�b�v�O���[�h���邩���B
�I�[�f�B�I���ł���(��
�����ԍ��F25893175�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��LUXMAN/L507Z�ɂ���
�ȉ��ɁA�v����2�d�ɂ��ċL�ڂ�����܂����̂ŁA�\���Ă����܂��B
https://s.kakaku.com/review/K0001395238/ReviewCD=1778423/
LUXMAN����A�h�o�C�X�����́A�f�t�H���g�ݒ肾��UD701N ���̃v���i��L507Z�̃v���i��2�d�̃v���i�������ɉe���^����̂ŁAUD701N����fixed�o�͂ɂ��ĉ������ƁB�킴�킴TEAC����ɋZ�p���⍇���ăA�h�o�C�X���ꂽLUXMAN�̃T�[�r�X�Z���^�[�̕��A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25893632�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���f��ӏ܃��r���[
�ŋߌ����f��/�u���[���C�����r���[���܂��B
�����̘f��/�n���L/DTS HD7.1
���̘f��/�V���L
���r���[
���̘f���V���[�Y��100�C���`�X�N���[���ōĊӏ܁B
���ɐV���I�̃N�I���e�B����������������B
�ŐV��̓h���r�[�V�l�}�Ŋӏ܂������A�����^���łŊӏܗ\��B
�����͕��ʂɗǂ������B
���X�^�[�E�H�[�Y1/DTS HD6.1
�X�^�[�E�H�[�Y2
�X�^�[�E�H�[�Y3
�X�^�[�E�H�[�Y7
�X�^�[�E�H�[�Y8
�X�^�[�E�H�[�Y9
���r���[
���V���[�Y��100�C���`�X�N���[����OLED65�C���`TV�Ń����_���ӏ܁B
�掿�͗L�@�����|�I�����A���͂�100�C���`�������B
�����̈ړ���/���͂́A�V���[�Y1.2.3�̕����h��Ŗʔ��������B
2ch�X�e���I�ł��\���y���߂�B
�����̒J�̃i�E�V�J/LPCM2
���r���[
100�C���`�X�N���[���ŏ��ӏ܁B
�掿�̓m�C�Y���߂��������A���ł��ӏ܂ł��閼��B
������2ch�X�e���I�����Ȃ��̂ŃV���{�����A�}���`�X�e���I�Ɋg������Δ��͑����Ċy���߂�ł��傤�B
��DUNE2/�h���r�[�A�g���X
�b�͑��ς�炸�P���ł܂�Ȃ������B
�������h���r�[�A�g���X���͓��Ɋ������Ȃ������B
���̃V���[�Y�͓��Ɍ��������Ȃ��̂ŁA���ҊO�ꊴ�������B
����A�A�A
�}�b�h�}�b�N�X�E�t�����I�T/�u���[���C
SHOGUN/�f�W�^���z�M�ӏܗ\��
���̘f��/�f�W�^���z�M�ӏܗ\��
�����ԍ��F25894332�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��SA30/�{�����[���R���g���[��
���[�J�[�T�C�g��������܂����B
��SA30�́A�A�i���O�{�����[���A�f�W�^���{�����[���ǂ��炩?
�˃A�i���O�{�����[���ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F25894534�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��everaolo/v1.3.20����
�ǂ����Av1.3.20�ɃA�b�v�O���[�h�����悤�ł��B
�A�b�v�f�[�g���e�͈ȉ�����m�F�ł��܂������A�f�W�^���o�͉��ʒ�����EVC�G���W���ɃA�b�v�O���[�h���ꂽ�悤�ł��B
EVC �G���W���� Eversolo Volume Control �̗��ł��B�Ǝ��̉��ʒ����A���S���Y�����g�p���āA���܂��܂ȃQ�C�� ���x���ł̃G���[�𐳊m�ɔr�����A���ʂ����Ȃ���M���̌`�ύX����Ȃ��悤�ɂ��āA�o�b�N�G���h DAC �ɂ�芮�S�ȃI�[�f�B�I������܂��B
����: �f�W�^���o�� EVC �G���W���́A-100 �` 0 �͈̔͂̉��ʒ������T�|�[�g���Ă��܂�
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/new-version-v1-3-20-for-dmp-a6-dmp-a8-release.98955/
�����ԍ��F25894743�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ɉ���I�Ȃ̂��AApple Music�����y�T�[�r�X�ꗗ�ɒlj�����Ă��܂��ˁB
�����T�[�r�X�̕������슴/UI�̓l�C�e�B�u�ɋ߂��ėǂ��ł����A�ō�������44.1Khz�~�܂�ł��B
��荂������/�r�b�g�p�[�t�F�N�g���K�v�ȏꍇ�́AApple Music�l�C�e�B�u�A�v���������p���������Ƃ̎��ł����A�����܂łł���Ȃ炳�����ƃr�b�g�p�[�t�F�N�g�Ή����ė~�����ł��ˁB
�܂��Aapple���̖��ł����ǁA���쐫�̓o�c�O���ł��B
�����ԍ��F25894767�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��SA30���[�h�ʑ��茋��
A6ME�̃o�[�W������V1.3.20�ɂ����̂ŁA�đ��茋�ʂ����r���[���܂��B
������
APPLE MUSIC/�F���c�q�J��/Addicted To You/24bit/96khz
���V�X�e��
A6ME���A�i���O�o�́�SA30���X�s�[�J�[
���m�[�}�����[�h
A6�{�����[���p�X�X���[/�Œ�o��/SA30�̃{�����[��26�ő���
���A�i���O�_�C���N�g���[�h�I��
A6�{�����[���p�X�X���[/�Œ�o��/SA30�̃{�����[��26�ő���
������
�m�[�}�����[�h����80db
�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I���ŁA������86db
MAX��80db��86db�ɃA�b�v�B
A6ME/�Œ�o��/�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I���ł��A���ʂ���悤�Ȃ̂ł��ꂪ�œK�Ȋ����ł��ˁB
���ǂ̂Ƃ���A�A�A
A6ME����Ϗo�͂��āASA30�v���Z�b�T�[���[�h���ʌŒ肵�āA�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I���ł��������炢�����オ���Ă��̂ŁASA30�̃A�i���O�{�����[�����AA6ME�̃f�W�^���{�����[��/EVC�G���W���̂ǂ��炪�x�X�g���́A�����ȂƂ��땪��܂���B
���쐫���l����ƍ��̂Ƃ���A�����炪�œK�ȂȊ����Ȃ̂ł��炭����ʼn^�p���Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25894797�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��A6ME/SA30/���茋��
�����Ƀ��[�h�ʂő��肵�Ă݂܂����B
������
AMAZON MUSIC/�F���c�q�J��/Addicted To You/24bit/96khz
APPLE MUSIC/�F���c�q�J��/Addicted To You/24bit/96khz
���V�X�e��
A6ME���A�i���O�o�́�SA30���X�s�[�J�[
�����胂�[�h1
A6ME���Œ�o�́�SA30/�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I�����{�����[��26���X�s�[�J�[
�����胂�[�h2
A6ME���Ϗo�́��{�����[��-23db��SA30/�v���Z�b�T�[���[�h����50/�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I�����X�s�[�J�[
������
�ǂ���̃��[�h�ł�����/80db�ɂȂ�l�ɒ����B
���Ȃ�AMAZON MUSIC��APPLE MUSIC����A���ꂼ�ꑪ�肵�����ʁA����/80db�œ����ł����B
�ǂ���̃��[�h/�{�����[���R���g���[������Đ����Ă��A�傫�ȉ������͂قڂȂ���Ԃł����B
�����_
�Ϗo��/�Œ�o�́A
�f�W�^���{�����[��/�A�i���O�{�����[���̍��͂��̐��i�ł͂��܂�Ȃ��̂����B
�����ԍ��F25895513�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��A6ME/SA30/���茋��
������
�ǂ����ASA30�̎d�l�ŃA�i���O�_�C���N�g���[�h�����̂܂܂ɂ��ēd�����꒼���ƁA�I���̕\���͂��ꂽ�܂܂ł�������ɃI�t�ɂȂ��Ă��܂��悤�ł��B
�Ȃ̂ŁA�{�����[��26�ő��肵�Ă�����/80db�̂܂܂ł����B
�Ȃ̂ŁA�ēx�A�i���O�_�C���N�g���[�h���I���ɂ������đ��肵���Ƃ���A����/86db�ɂȂ�܂����B
������
AMAZON MUSIC/�����ގq/�Z�����A���u���[�̗�/16bit/44.1khz
���V�X�e��
A6ME���A�i���O�o�́�SA30���X�s�[�J�[
�����胂�[�h1
A6ME���Œ�o�́�SA30/�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I�����{�����[��26���X�s�[�J�[
�����胂�[�h2
A6ME���Ϗo�́��{�����[��-23db��SA30/�v���Z�b�T�[���[�h����50/�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I�����X�s�[�J�[
������
�ǂ���̃��[�h�ł�����/86db�ɂȂ�l�ɒ����B
���Ȃ�AMAZON MUSIC���炻�ꂼ�ꑪ�肵�����ʁA����/MAX86db�œ����ł����B
�������ɂ���
��[��������r����ƁA�����̉����͂قڕς��܂��A�Ϗo��/�f�W�^���{�����[���̕����A�Œ�o��/�A�i���O�{�����[�������𑜓x�����������d�߂Ńp�L�p�L���Ă܂��B
�Œ�o��/�A�i���O�{�����[���͏����}�C���h�Ȋ����ł��B
�ق�ƁA���̕ӂ͍D�ݔ��e���ȂƎv���܂��̂ŁA�D���ȕ��Ŋӏ܂���̂��œK���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25895623�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��A6ME/SA30/���茋��
�v�X��DELA����l�b�g���[�N�Đ����Ă݂܂����B
������
DSD/�x�X�g�E�I�u�E�T�E���h�g���b�N/�p�C���[�c�E�I�u�E�J���r�A��/1bit/5.64MHZ
FLAC/JAZZ ONE HD/TAKE FIVE/24bit/96khz
���V�X�e��
N1/A6ME���A�i���O�o�́�SA30���X�s�[�J�[
�����胂�[�h
A6ME���Ϗo�́��{�����[��-23db��SA30/�v���Z�b�T�[���[�h����50/�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I�����X�s�[�J�[
������
�Ȃɂ���āA�ő剹��/87db�[80�t�߂ɂȂ�B
���ł��p�C���[�c�E�I�u�E�J���r�A�����A�ő剹��/87db�ň�ԍ��������B
�������ɂ���
DSD/DSF�����́A5.6MHz/1bit�Ńr�b�g���[�g/11.29Mbps�ŁA�_�C�i�~�b�N�����W���L�����ʂ����������B
�_�C�i�~�b�N�ȃT�E���h�g���b�N�Ȃǂ́A���X���������ŃN�Z�ɂȂ�܂��B
FLAC�����́A96Khz/24bit/�Ńr�b�g���[�g/4.62Mbps�ŁA�X�g���[�~���O�̖�1.8�{�ł����AJAZZ�n�̏a���ቹ�������Ă��肱����܂����X���������Œ�����������܂����B
�n�C���]�n�̃X�g���[�~���O�n��NAS�l�b�g���[�N�n���ƁA���Ȃł������̉�����������̂�������܂��A���̃V�X�e���ł͂ǂ��炩����ӏ܂ł���̂��m�F�ł����̂łЂƂ܂�����S�ł��B
���Ԃ́A�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I���ŁA�����ő�/86db���炢�Ŋӏ܂���ƋC���������ł���(��
�}���`�Œ��������ꍇ�́A
DELA/AV�A���v/�}���`�X�e���I/SA30/�X�s�[�J�[�������ł��ˁB
�����Ɖ��ꂾ�ƁA�̌��I�ɂ͉��ꂪ�����܂����A�����I�ɂ͍��̂Ƃ��낱��2ch�V�X�e�����n�C�R�X�p�Ńx�X�g�ł��ˁB
�����ԍ��F25896383�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
2CH�X�e���I�Đ��ł��X�s�[�J�[�̈ʑ��������Ă���ƁA���������̕\�����\�ɂȂ�܂��B
Sophie Milman�̃A���o���ATake Love Easy�̓�Ȗڈȍ~�ł́A�{�[�J���ʒu������ɒ�ʂ��܂����H
Nordost��System Tuning & Set-Up Disk�ɂ́A����������Ɉړ�������A�傫�ȃA�[�`��`���ĉ������ړ�����g���b�N������܂��B
�����ԍ��F25896449
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��Sophie Milman�̃A���o���ATake Love Easy�̓�Ȗڈȍ~�ł́A�{�[�J���ʒu������ɒ�ʂ��܂����H
��Ō����Ă݂܂��B
���Ȃ݂ɁA
�ŋߊς�YouTube�n�̂���Ƃ��ʔ��������ł���(��
https://youtu.be/CPSJdJ5aqLc?si=ooB1XdusmOg4rStd
���ƁA
JAZZ ONE HD�̉��Ȃ��́A�{�[�J��/L�A/�y��/R�����Ƃ����m�����^���ł����ˁB
�X�^�[�E�H�[�Y/�u���[���C�́A���r���O��POLK/MXT15�ŃX�e���I�ӏ܂��܂������A�㉺���E�ɉ�����ʈړ����āA�K�x�ɃT���E���h������܂����B
���r���O����AV�A���v�ړ����āA�X�b�L��2CH�X�e���I�V�X�e���ɕύX�B
��������POLK�n�̕���BW�����A�a���ĖL���ʼnf��������ȂƎv���܂����B
�f��T�E���h�g���b�N�Ȃǂ́A�ő剹��87db���炢���ƁA13���a�u�b�N�V�F���t�ł͒ቹ�Đ��Ɍ��E������܂��ˁB
�������炳��ɉ��܂Ŗ炷�ꍇ�́A�T�u�E�[�t�@�[���g�[���{�[�C�lj��ɂȂ�܂����A���̂Ƃ���͂��̂܂܊y���݂����Ǝv���܂�(��
���Ȃ݂ɁA�g�[���{�[�C�̃T�C�Y�I�ɂ́A704S3�����ƃX�����Ȃ̂Ō��ɂ͗ǂ������ȋC�͂��Ă��܂����B�B�B
https://s.kakaku.com/item/K0001473304/
���ꂩ�A�A���͉f��ӏܗp�ɂ��g���鍂���\�ȃT�u�E�[�t�@�[1�{�ɔC���邩�A�ǂ��炩�̃p�^�[���ɂȂ邩���B
https://s.kakaku.com/item/K0001140593/
���ƁAA6AE��HDMI DSD�}���`�`�����l���pDOH�`�b�v�𓋍ڂ��Ă���̂ŁA�}���`�o�͂��\�̂悤�ł����ADSD�}���`�����������Ă��Ȃ��̂Ŏ����܂���ł����B�B�B
�����ԍ��F25896719�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
���g����13���a�u�b�N�V�F���t�̍ő�o�͉����͉�dB�ł���?
���̎g���Ă���X�s�[�J�[��110dB�Ȃ̂Ń��X�j���O�|�C���g��100dB�͗]�T�ŏo���܂��B
SACD���Đ��ł���BD�v���[���[��5.1chDSD���o�͂��Ă��܂��B
�����ԍ��F25896782
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�����g����13���a�u�b�N�V�F���t�̍ő�o�͉����͉�dB�ł���?
�ő�o�͕͂s���ł��ˁB
�\����84db�ł����A���������������炢�ɂȂ��ł���?
�����Ƃ������A���Đ��\�̘͂b�ł����A100db�̔����Ŗ炵����ߏ��A�Ƒ������N���[�������܂���(��
86db���炢�ł��A�Ƒ�����͂��邳���ƌ����Ă��܂��̂ŁA�A�A
�Ă��A100db�Ŗ点����Ȃ�ł���?
�����ԍ��F25896805�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
>�\����84db�ł����A���������������炢�ɂȂ��ł���?
���e����100W�Ȃ�104dB�ł��ˁB
�^�钆��100dB�Ŗ炵�Ă��ߏ���Ƒ�����N���[���͍K�����܂���B
�����ԍ��F25896836
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���������h�ł���(��
�u���[���C�I�[�f�B�I�͎����Ă܂����ASACD�v���C���[�͎����ĂȂ��ł��ˁB
e-onkyo���ƁAFLAC/5.1ch�͂���悤�ł����A�}���`DSD�����̃_�E�����[�h�͂Ȃ��悤�ł��ˁB
https://www.e-onkyo.com/sp/search/search.aspx?ch=30&ext=4
A6AE����́APCM�}���`�o�͂��ł���݂����Ȃ̂ŁAFLAC/5.1�����ł�������̂��ȁB
�CHDMI DSD�}���`�`�����l���pDOH�`�b�v
�}���`�`�����l���X�g���[�}�[�Ƃ��āA
DMP-A6 Master Edition �́A
DSD�~���[�W�b�N�̍Đ��Əo�͂ɓ�������
HDMI�I�[�f�B�I�pDOH�����`�b�v���̗p���Ă��܂�
DSD�l�C�e�B�u �}���`�`�����l��RAW�o�͂�
D2P�o�� (PCM �}���`�`�����l���o��)�f�R�[�h�ɉ����AHDMI�p�Ƀ��W�F�l���[�g���ꂽ
�����x�̓Ɨ��N���b�N�������Ă��܂��B
�����ԍ��F25896883�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
e�|onkyo�ɂ�wav5,1�����͂���܂��ˁB
�����ԍ��F25896943
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
wav�����͊��ɔ̔��I���ɂȂ��Ă�悤�ł��B
https://www.e-onkyo.com/sp/support/guide4.aspx
���}���`����/��ԃI�[�f�B�I�ɂ���
�ЂƂ܂��AFLAC/5.1ch���_�E�����[�h���܂����̂ŁA������r���[���܂��B
�܂��A�u���[���C�I�[�f�B�I/5.1ch�̎��������ł������A5.1ch������������ɐ����Ƃ����̂͂Ȃ������B
�V��̈ړ����Ƃ��͂���܂������B
��������A2ch�������}���`�X�e���I�ɂ��āA�T���E���h�����ʒ������āA���̊��o������������̌��Ƃ��Ă͏����Ă銴���ł��ˁB
2ch�X�e���I�͊�{�I�ɑO������݂̂Ȃ̂ŁA�����グ�Ȃ��Ɣ��͂łȂ��̂ƁA�}���`�Œ�������ɒ����Ɣ��������܂��ˁB
�Ȃ̂ŁA�l�I�ɂ�2ch�X�e���I�͒����ʂŃ{�[�J���n�������蒮���̂ɍœK���ȁB
DOLBY ATMOS����/APPLE MUSIC/AMAZON MUSIC���ɁA��{�I�ɉ�����������d�l�Ȃ̂ł܂��܂�MIX�o�����X�����ł��ˁB
2ch�X�e���I�̕���MIX�o�����X/�����͗ǂ��ł��B
�I�[�f�B�I�n��5.1ch�����͂����������Ȃ����A�W�����������Ă��Ċ��Ɍ����X���ł��ˁB
���炭�ADOLBY ATMOS�z�M�Ɏ���đ�����̂ŁA������̐i����҂������Ǝv���܂��B
���̂Ƃ���AONKYO/PIONEER�̏�ʋ@��A�v�������AAMAZON MUSIC/DOLBY ATMOS�Ή����Ă��܂����B
APPLE MUSIC/AIR PLAY�͋�ԃI�[�f�B�I�Ή������悤�ł����A�܂������Ă��܂���B
���Â�AA6ME�A�v��/HEOS�Ȃǂ�����Ή�����Ƃ͎v�܂����B
https://www.google.com/amp/s/iphone-mania.jp/homepod-587059/amp/
�����ԍ��F25897268�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
AirPlay����ԃI�[�f�B�I�ɑΉ����Ă��܂����H
>��������A2ch�������}���`�X�e���I�ɂ��āA�T���E���h�����ʒ������āA���̊��o������������̌��Ƃ��Ă͏����Ă銴���ł��ˁB
Amazon Music�ɂ���ABob And Ray Throw A Stereo Spectacular���}���`�`�����l���X�e���I�Œ����A���������E�O������։������ړ�����ȂǁA�������ƂɂȂ�܂���B
�����ԍ��F25897344
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��AirPlay����ԃI�[�f�B�I�ɑΉ����Ă��܂����H
�Ή������悤�ł��ˁB
���ɂ��AAirPlay����ԃI�[�f�B�I�ɑΉ����Ă���AAirPlay���g����iPhone��iPad����HomePod�ɃI�[�f�B�I���X�g���[�~���O����ۂɁADolby Atmos�ɂ��Տꊴ���ӂ��I�[�f�B�I�̌����y���߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B
������A���W�J���Ă����ł��傤�B
�����ԍ��F25897567�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�Ή������̂ł����H�@���߂ĕ����܂����B
�Ƃ���œd���P�[�u���͉������g���ł����H
���̓A�R�[�X�e�B�b�N�E�����@�C�u�APS�@Audio,�I���C�f���g���Ă��܂��B
�����ԍ��F25897756
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
Apple TV��TVOS18�ɃA�b�v�f�[�g���ꂽ�̂ŁA���̕���̃��C�����X/��ԃI�[�f�B�I�A�g���������Ă����헪�݂����ł��ˁB
https://www.google.com/amp/s/www.itmedia.co.jp/pcuser/amp/2409/17/news138.html
���炭�A�ߓ����ɁALGTV��APPLE MUSIC/DOLBY ATMOS��AIR PLAY����Đ��\�ɂȂ�Ǝv���܂���(��
���r���O�V�X�e�ł́A���̂Ƃ��낱�ꂪ�œK�ł��ˁB
LGTV��APPLE MUSIC��HDMI�o�́�powernode egge���X�s�[�J�[
���͂��܂�m���Ă��܂��APOWERNODE�̓A���v�lj�����A���C�����X���A�X�s�[�J�[��4ch�܂Ŋg���\�ł��B
���r���O�Ȃ�ׂ��X�b�L�����������̂ŁA���C�����X�����Ă��������ł��ˁB
https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/yokohama/20220213
��Sophie Milman�̃A���o���ATake Love Easy�̓�Ȗڈȍ~�ł́A�{�[�J���ʒu������ɒ�ʂ��܂����H
���ɏ�X�ɂ͒�ʂ��Ȃ������ł��B
���ʂɂǐ^�Ƀs�^�b���ƒ�ʂ��Ă��܂��ˁB
��Nordost��System Tuning & Set-Up Disk�ɂ́A����������Ɉړ�������A�傫�ȃA�[�`��`���ĉ������ړ�����g���b�N������܂��B
���̃f�B�X�N�͋����[���ł��ˁB
���������A�̔���������DVD�N���[�j���O�f�B�X�N�Ɏ����悤�Ȓ����f�f���[�h������܂����ˁB
���Ƃ���œd���P�[�u���͉������g���ł����H
�d���P�[�u��/KOJO�APRO CABLE
�d���^�b�v/BELDEN�ACLASSIC PRO�AFURMAN
������d���^�b�v�Ńm�C�Y�Ă��܂����A
���T���炢�ɁA���[�^�[�ƃn�u��AC�A�_�v�^�[�ɁANFJ�m�C�Y�N���[�i�[��lj�����\��ł�(��
�����ԍ��F25897789�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
����ɒ�ʂ��Ȃ��͈̂ʑ��ɗ��ꂪ����܂��ˁB
Nordost�̃`�F�b�NCD�ł������ړ������ꂢ�ȃA�[�`��`���Ȃ��Ǝv���܂��B
Procable�͓d���^�b�v��3000W�_�E���g�����X���g���Ă��܂��B
�����ԍ��F25897801
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
������ɒ�ʂ��Ȃ��͈̂ʑ��ɗ��ꂪ����܂��ˁB
���r���O��POLK/MXT15�ł����A������͂���܂���?
������TV�u���Ă�̂łǂ����܂��B
�����ԍ��F25897821�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�̃\�j�[�̂��Ȃ��܂邳��̏����ʂ̃f���ɎQ���������Ƃ�����܂��B
�ʂ̔ނ��ďC�����A���o���ł������A�����ɏ����ʂ��Ă��܂����B
�Ƃ��낪���̃u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[���X�^���h����1cm���Ɉړ����A�X�^���h�̏o�������������Ƃ���S�������ʂ��Ȃ��Ȃ�܂����B
���̏o�����蕔���ʼn������˂��Ĉʑ�������Ă����̂ł��ˁB
Sophie Milman�̂��̃A���o���͂��Ȃ��܂邳�����ʂ���A���o���Ƃ��ďЉ��Ă������̂ł��B
�����ԍ��F25897847
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���Ƃ��낪���̃u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[���X�^���h����1cm���Ɉړ����A�X�^���h�̏o�������������Ƃ���S�������ʂ��Ȃ��Ȃ�܂����B
�Ȃ�قǁB
�����̏�ԂȂ̂ŁA�X�^���h�̏o������ɔ��˂��Ă����ł���(��
���ƁA��A���E�̐��x���Ⴂ�Ɗ����Ă��܂����̂ŁA���낻��{�i�I�ɃZ�b�e�B���O���悤�Ǝv���Ă����Ƃ���ł��B
����A�������Ă݂܂��B
�����ԍ��F25897880�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��LG4K�v���W�F�N�^�[ /HU710PB
����ALG���烁�[�����͂��܂����B
���4K���[�U�[���L�����y�[���ŁA�N���t�@�����i�܂Œl�������Ă�悤�ł��B
���̃^�C�~���O�ōw�����邵���Ȃ������ł��ˁB
�����ԍ��F25898111�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
HU710PB�͐F�悪�L���̂��ǂ��ł��ˁB
�m���Y�[���ƃ����Y�V�t�g�͕t���Ă��Ȃ������ł��ˁB
�ݒu�ʒu�����܂���������K�v�����肻���ł��B
�����ԍ��F25898455
![]() 0�_
0�_
���ʑ������ɂ���
���Ƃ��낪���̃u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[���X�^���h����1cm���Ɉړ����A�X�^���h�̏o�������������Ƃ���S�������ʂ��Ȃ��Ȃ�܂����B
�X�s�[�J�[�ʒu���X�^���h�O���Ƀs�b�^���ړ������āASophie Milman�̃A���o�����Ď������܂������A���ɏ����ʂ͂��܂���ł����B
���ʂɁA���ʒu���������ɒ�ʂ��Ă��܂��ˁB
�O�ׁ̈A������ňʑ��`�F�b�N�����܂���������ł����B
https://youtu.be/cJLI_2bthxU?si=TvpAxiqwYIv3bdnq
�����ԍ��F25898497�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
����youtube�͍��E�̃X�s�[�J�[�̈ʑ����������t�������`�F�b�N������̂ł��ˁB
�P�̂̃X�s�[�J�[�̈ʑ����g���������t���b�g���ǂ��������ŁADirac Live�ŕ�\���Ǝv���܂��B
�X�s�[�J�[�ɂ���ẮA�Ⴆ�ΐ̂�JBL�X�s�[�J�[�̓X�R�[�J�[���t���ڑ��ɂȂ��Ă�����̂��L��܂����B
���̃X�s�[�J�[�ł�����youtube�ł͖�薳���̔���ɂȂ�܂��B
2�E�G�C�ƂR�E�G�C�̃X�s�[�J�[�����݂����ăT���E���h��g�ނƁA�ʑ��������d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ʂ��Ȃ��͕̂ʂ̖�肪���肻���ł��ˁB
�����������ʂł���ƁA�Q�b�g�ł�����y�ȂǓV�䂩�特���~���Ă��܂��B
�����ԍ��F25898519
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���P�̂̃X�s�[�J�[�̈ʑ����g���������t���b�g���ǂ��������ŁADirac Live�ŕ�\���Ǝv���܂��B
����̎��ł����ˁB
https://aeoliand.hatenablog.com/entry/2021/05/26/131353
DIRAC LIVE�́A���̂Ƃ���SA30�̌��ł����g���Ȃ��ł��ˁB
MINI DSP�Ƃ����̂��ADIRAC�Ɠ����̈ʑ��t���b�g����ł���悤�ł����A�A�A
http://salogic.cocolog-nifty.com/blog/2017/09/post-0347.html
�ڑ��p�^�[���Ƃ��ẮA�ȉ������ł��Ȃ������ł��ˁB
LGTV�����f�W�^���o�́�MINI DSP���A�i���O�o�́�POWERNODE EGGE���X�s�[�J�[
https://minidsp.jtesori.com/products/minidsp-2x4-hd/
�����ԍ��F25898601�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ƃ́A�A
�V�^NODE�����{�������ꂽ��ADIRAC�I�v�V�����lj��Ŏg����悤�ł����A�R�X�p�������ł��ˁB
���s��POWERNODE EGGE�ɂ��A�b�v�f�[�g��DIRAC LIVE�Ή����Ă���̂��A���̂ւ�ł���(��
�����ԍ��F25898640�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�p�C�I�j�A��LX805�Ȃ�Dirac Live�ł�MCACC pro�ł��ʑ�����\�ł��ˁB
�����ԍ��F25898831
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��LX805
�����ł��ˁB
���r���O�ł͊�{2ch�����g��Ȃ��̂ŁALX805/42���̓I�[�o�[�X�y�b�N�ł��ˁB
SA30/16��/���A2�䔃���܂���(��
DIRAC LIVE/�ʑ�����ǂ��܂Ō��ʓI�Ȃ̂��́A������ؗ\��ł����A
���r���O�ł��ADIRAC LIVE���g����n�C�R�X�p�p�^�[���͂���Ȋ������ȁB
LGTV��SA30���X�s�[�J�[/16��
LGTV���V�^NODE�����p���[�A���v���X�s�[�J�[/12��
LGTV��miniDSP�����p���[�A���v���X�s�[�J�[/12��
LGTV��RZ50�A�E�g���b�g���X�s�[�J�[/11���~
������������ARZ50�A�E�g���b�g����ԃn�C�R�X�p����(��
�����ԍ��F25899023�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
Dirac Live�̈ʑ���ŏ����ʂ�����������A����͖{���ł��ˁB
�������Ȃ�������,�ǂ��܂ňʑ���o���Ă���̂��������ł��B
�䂪�Ƃł�MCACC Pro�̈ʑ�������Ă����Ȃ��Ă������ʂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25899036
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��Dirac Live�̈ʑ���ŏ����ʂ�����������A����͖{���ł��ˁB
�ȑO�ALX805��Dirac Live��ON/OFF�ŁA(3)���j�APCM�@96kHz/24bit(2ch �X�e���I)/�u���[���C�I�[�f�B�I������������������܂����A�����ʂ��Ă��܂���ł����ˁB
(1)���j�APCM�@96kHz/24bit(5.1ch �T���E���h)
(2)Dolby TrueHD�@96kHz/24bit(5.1ch �T���E���h)
(3)���j�APCM�@96kHz/24bit(2ch �X�e���I)
(1)(2)��5.1ch�T���E���h�����́A������/�A�g���X�A�b�v�~�b�N�X�œV��ړ����Ă��܂������B
�����ԍ��F25899412�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���������A2ch�X�e���I�ŏ����ʂ��Ă����̂́Agenelec�X�s�[�J�[�����������������ł��ˁB
���̎��́A�ʑ���Ƃ����Ɉӎ����Ă��Ȃ������ł����A��ʂ�������ɂ���܂����ˁB
���ƁA�ȑO�A���Ŏg���Ă��T�E���h�o�[�������ʂ��Ă��āA�K�x�ɓV�䂩�特���~���Ă��Ă܂����ˁB
�����ԍ��F25899422�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������Ă����߂ł��搢�E���o���^�J�̃R�����g�����Ă�
�ǂ����čœK���P�ł͂Ȃ�350�ȏ������̂ł���
�œK������350�ł͂Ȃ�1�ł��傤
��������Ȃ�
�����ԍ��F25900619
![]() 0�_
0�_
�o���J�^��
���������g�̃u���O�ł��
���E�����Ă邼
�����ԍ��F25900625
![]() 0�_
0�_
���ƁA�ʑ��/�����t���X�s�[�J�[���ƁA���ꂪ�n�C�R�X�p�ł��ˁB
�V�^�́AARC/�������Z�b�g�ɂȂ��Ĕ��ɂ��������ł��ˁB
�����ʂ��邩�͕���܂��A�����w�����Ă݂�����i�ł��B
https://www.ikebe-gakki-pb.com/new_product/?p=158620
�����ԍ��F25901293�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������Ɖ����̍l�@
������
�ʑ��������������Ă���ǂ�ȃX�s�[�J�[�ł������ʂ���̂�
AI��
�ʑ��������������Ă��邱�Ƃ́A���̒�ʂ≹��ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ȗv�f�ł����A���ꂾ���łǂ�ȃX�s�[�J�[�ł������ʂ��K���N����킯�ł͂���܂���B�������̗v�f�����ݍ����ĉ�����ʂ����܂邽�߁A�ʑ��������Ă��邱�Ƃɉ����āA�X�s�[�J�[���̂̐v��z�u�A���X�j���O�����傫�ȉe����^���܂��B
1. �X�s�[�J�[�̓���
�X�s�[�J�[�̐v�i�c�C�[�^�[�̎�ށA�h���C�o�[�̔z�u�A�w�����Ȃǁj�́A���̍L������ʂɋ����e�����܂��B�L���w���������c�C�[�^�[�𓋍ڂ����X�s�[�J�[��A����̐v�̃X�s�[�J�[�i��: �����X�s�[�J�[�j�́A�ʑ��������Ă���ꍇ�A���̓I�ȉ�������₷���X���ɂ���܂��B
����A�O����ʂ����������X�s�[�J�[�i��: �w�����������X�s�[�J�[�j�́A�ʑ��������Ă��Ă��A���ꂪ�O�ɏW�����₷���A�����ʂ�����ꍇ������܂��B
2. ���X�j���O��
�����̔�������z����Ԃ��A�����ʂɑ傫���e�����܂��B�ʑ��������Ă��Ă��A�V���ǂ���̔��ˉ������܂��g���Ȃ��ꍇ�A����������ɍL����Ȃ����Ƃ�����܂��B
���ˉ��̃R���g���[������肭�s����ƁA������藧�̓I�Ɋ������A�����ʂ����₷���Ȃ�܂��B���̂��߁A�����̌`���z���ށA�f�B�t���[�U�[�Ȃǂ����p���邱�Ƃ��d�v�ł��B
3. �X�s�[�J�[�̔z�u�Ɗp�x
�X�s�[�J�[�̐ݒu�p�x��z�u���A����̍L����ɒ��ډe����^���܂��B�������z�u�Ɗp�x���ێ�����Ă��Ȃ��ꍇ�A��������ɍL����ɂ����A�ʑ��������Ă��Ă���ʂ����Ғʂ�ɓ����Ȃ����Ƃ�����܂��B
4. ���g�������ƃN���X�I�[�o�[
������ʂɉe����^����͎̂��g��������N���X�I�[�o�[�̐ݒ���d�v�ł��B�Ⴆ�A��������̍Č��͂������A�X���[�Y�ɉ����Ȃ���X�s�[�J�[�́A�ʑ��������Ă���ꍇ�ł����R�ɉ�����ɍL����₷���ł��B
5. �ʑ���Z�p
**�ʑ���Z�p�i��: DIRAC LIVE�j**�́A���ɕ����̉e���ŗ��ꂽ���g�𐮂��A����̒�ʂ�L��������P������ʂ�����܂����A�X�s�[�J�[���̂̕����I�ȓ����i�w�����A�v�Ȃǁj����������Ă���ꍇ�A���̌��ʂɂ����E������܂��B
�ʑ������m�ɑ����Ă��Ă��A�X�s�[�J�[���̂����Ƃ��Ə����ʂɓK���Ă��Ȃ��ꍇ�́A��Z�p�݂̂ł��̌��ʂ�͓̂���ł��B
���_
�ʑ��������������Ă��邱�Ƃ́A�����ʂ◧�̓I�ȉ���邽�߂ɏd�v�ȗv�f�ł����A�X�s�[�J�[�̓�����ݒu���A���X�j���O���[���̉��������l�ɏd�v�ł��B�ǂ�ȃX�s�[�J�[�ł��A�ʑ��������Ă���ΕK�������ʂ���킯�ł͂Ȃ��A�X�s�[�J�[�̐v�i���Ƀc�C�[�^�[��h���C�o�[�z�u�j��A�����̉����������傫���e�����܂��B
���̂��߁A�����ʂ����ꍇ�́A�ʑ�������łȂ��A�X�s�[�J�[�̑I���ݒu�A�����̉����������T�d�ɍs���K�v������܂��B
�����ԍ��F25901326�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������
b&w/elac/polk����
AI��
Bowers & Wilkins (B&W)�X�s�[�J�[
1. �h���C�o�[�Z�p�Ɖ��̉𑜓x
B&W�̃X�s�[�J�[�́A�R���e�B�j���A���E�R�[����_�C�������h�E�c�C�[�^�[�Ȃǂ̓Ǝ��Z�p�𓋍ڂ��Ă���A�������̉𑜓x�ƗD�ꂽ�f�B�e�[���Č��͂������ł��B���ɍ�����̐L�т��ǂ��A�������N���A�ŃV���[�v�Ȓ�ʂ��������܂��B
�������A����Ɋւ��Ă͍L������d�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���W�������������Č�����X��������܂��B
2. ���m�ȉ����ƑO�����
B&W�̃X�s�[�J�[�́A���X�j���O�|�W�V�����ł̑O����ʂ����m�ł��B����͂��O���ɏW�����₷���v�ɂȂ��Ă��邽�߁A�����ʂ���ʏd�������v�ł͂Ȃ���������܂���B
�������AB&W�������x�ȃh���C�o�[�v�ɂ��A���m�ȉ������Č��ł��邽�߁A���X�j���O����z�u����ł͏㉺�����̉�����Č��\�ł��B
3. �G���[�V���i���ȃT�E���h
B&W�́A���ɉ��y�ӏ܂Ŋ����h���Ԃ�悤�ȖL���ȉ���ڎw���Ă���A���ቹ�悪�L���Ńp���t���ł��B���̂��߁A���X�i�[�ɑ��Ĕ��ɔ��͂̂���T�E���h�X�e�[�W����܂��B
ELAC�̓���
1. �����I�Ńo�����X�̗ǂ��T�E���h
ELAC�̃X�s�[�J�[�́A���ɍ�������ቹ�܂Ńo�����X���ǂ��A�����I�ȃT�E���h�������ł��B����ɂ��A�y�Ȃ̃f�B�e�[���������ɍČ�����A��ʂ̐��m���≹��̍L���肪���R�Ɋ������܂��B
�����ʂɊւ��ẮA�X�s�[�J�[�̔z�u��X�j���O���Ɉˑ����镔��������܂����AELAC�͑S�̓I�Ƀt���b�g�ŗ��̊��̂��鉹���Č����邽�߁A����̍L���肪��r�I�L���ł��B
2. JET�c�C�[�^�[�Z�p
�ꕔ�̏�ʃ��f���ł́AJET�c�C�[�^�[�Ƃ����Z�p���̗p���Ă���A����ɂ����ɐ��ׂȍ�������Č����܂��B�c�C�[�^�[�̎w�������L�����߁A���X�j���O�|�W�V�����ɊW�Ȃ��A�L�����ꂪ�������₷���ł��B���ꂪ�����ʂɂ��v�����܂��B
3. �L����̂��鉹��
ELAC�̃X�s�[�J�[�́A�L����̂��鉹�������Ƃ��Ă���A�����S�̂Ɏ��R�ɉ����L����܂��B���ɒ�〜������ł̍Č����������A���̒�ʂ����ɐ��m�ł��B���̂��߁A�����ʂ≹�̍����������邱�Ƃ��ł����ʂ������ł��傤�B
Polk Audio�̓���
1. �E�H�[���Ń��b�`�ȃT�E���h
Polk Audio�̃X�s�[�J�[�́A��r�I�E�H�[���Ń��b�`�ȃT�E���h��ڎw���Ă���A�ቹ�悪�L���Ŕ��͂̂���T�E���h�������ł��B���̂��߁A�ቹ���������ꂽ���y��f��ł̎g�p�Ɍ����Ă��܂����A�����ʂƂ����ϓ_�ł́AELAC�قǂ̐������≹��̍L����͏����}�����邱�Ƃ�����܂��B
2. Dynamic Balance�Z�p
Polk Audio�́ADynamic Balance�Z�p���̗p���Ă���A�S�̓I�ȉ��̃o�����X���d�����Ă��܂��B������⍂������N���A�ɍČ�����܂����AELAC�ɔ�ׂĂ��t�H�[�J�X���O���⒆���ɏW�܂�X��������A�L����Ƃ����ʂł͂��قȂ�̌��ɂȂ邩������܂���B
3. �ቿ�i�тł��D�ꂽ�p�t�H�[�}���X
Polk Audio�́A���ɒቿ�i�т̃��f���ł��R�X�g�p�t�H�[�}���X�ɗD�ꂽ��������܂��B����ɂ��A�荠�ȉ��i�ł��\���ȉ�����ʂ��y���ނ��Ƃ��ł��܂����A�����ʂ◧�̓I�ȉ�����d������ꍇ�A�X�s�[�J�[�̑I�ѕ���z�u�ɒ��ӂ��K�v�ł��B
ELAC��Polk�̔�r�F�����ʂƉ���
�����ʂɊւ���
ELAC�̃X�s�[�J�[�́A�����I�Ńo�����X�̎�ꂽ�T�E���h�ɂ��A�����ʂ������₷���v�������ł��B���ɁAJET�c�C�[�^�[�Z�p�𓋍ڂ������f���ł́A�L���w�����ɂ�胊�X�j���O�G���A�S�̂ɋϓ��ȉ�������A�㉺���E�ɉ����L����₷���ł��B
Polk Audio�́A���b�`�ŃE�H�[���ȃT�E���h������Ƃ��Ă��܂����A�����ʂ�ELAC�قǖ��m�Ɋ����Ȃ��ꍇ�������ł��B���̒�ʂ͔�r�I�O���ɏW���������ŁA���ɒቹ����������鉹�y��f��ł��̌X�������܂邱�Ƃ�����܂��B
����̍L����
ELAC�̃X�s�[�J�[�́A�L����������o�����Ƃ����ӂŁA���ɒ����悩�獂����ɂ����Ď��R�ȍL����������Ă��܂��B���ꂪ���̓I�ŁA���X�i�[�ɕ�ݍ��ނ悤�ȉ����̌�����܂��B
Polk Audio�̃X�s�[�J�[�́A����̍L����Ƃ��������A���͂̂���ቹ�ƃN���A�Ȓ������O�ʂɉ����o���v�������ł��B���ɉf���z�[���V�A�^�[�p�r�ł͂��̌��ʂ������ł����A���y���X�j���O���ɂ͑O���W���^�̉��ꂪ�������ꂪ���ł��B
���_
ELAC�́A�L����̂��鉹��Ɛ��m�ȉ�����ʂɗD��A�����ʂ������₷���X�s�[�J�[�ł��B����JET�c�C�[�^�[�𓋍ڂ������f���ł́A���̍L����⍂�����̊����₷���ł��傤�B
Polk Audio�́A�ቹ��̔��͂Ɖ��y��f��̃��b�`�ȑ̌��ɋ��݂�����܂����A�����ʂ≹��̍L����Ɋւ��Ă�ELAC�Ɉ�����邱�Ƃ�����܂��B
�����ʂ�L����������߂�ꍇ�AELAC���K���Ă��邩������܂��APolk Audio���p�r�ɂ���Ă͗D�ꂽ�I�����ƂȂ�܂��B
�Ƃ������Ȃ̂ŁA�ǂ��炩�Ƃ����A
polk/B&w/�O�ʒ�ʌ^/����
ELAC/�����ʌ^/����
��������܂���B
polk/B&w�͎��ۂɎg���Ă��āA�������������Ȃ̂ŁA���ꂼ��A�O�ʒ��/�����{�[�J���n���y�ӏ܁A���ቹ/�Z���t�O�ʒ��/�f��ӏ܂ɂ͍œK�Ȋ����ł��ˁB
2ch�����������ʂ����ċ�ԃI�[�f�B�I���ۂ����������ꍇ�́A4.1.2/�}���`�X�e���I�ɂ���A������/360���̊������炩�ɑ����̂ŁA������������ŏ\���y���߂銴���ł���(��
DIRAC LIVE�́A���x�Ȏ��g��/�ʑ���ʼn���Ɖ������X�b�L���N�b�L��������̂ɂ͌��ʓI�ł����A�ʑ��/DIRAC LIVE���A�K���Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł��Ȃ����ȂƎv���܂��B
DENON�̉������t���b�g�ɂ���ƁA���ቹ���������Ă��܂��̂ŁALR�o�C�p�X�ɂ��������_�C�i�~�b�N�ŐL�ѐL�т��Ă���̂ł��̕ӂ͂��D�݂ł��傤��(��
�����ԍ��F25901344�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�䂪�Ƃ�MCACC�̈ʑ�����I�����Ă��I�t���Ă������ʂ���̂́A��J�[�u���قڃt���b�g�Ŏ�����A�I���ł������Ă��Ȃ�����ł��ˁB
����̓X�s�[�J�[�̖{���̓����ɂ����̂ł��傤�B
�̃I�[�f�B�I�t�F�A�̊e�u�[�X��CD�������ĖႢ�����ʂ��m�F�������Ƃ�����܂����A3���͑S�������ʂ��Ă��܂���ł����B
�����ԍ��F25901468
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
������̓X�s�[�J�[�̖{���̓����ɂ����̂ł��傤�B
�̃I�[�f�B�I�t�F�A�̊e�u�[�X��CD�������ĖႢ�����ʂ��m�F�������Ƃ�����܂����A3���͑S�������ʂ��Ă��܂���ł����B
��͂�A�X�s�[�J�[�̓����ɂ�銴���Ȃ�ł��ˁB
���̕��́A���E�Ώ̂ŃX�s�[�J�[�Z�b�e�B���O�͊������Ă���̂ŁA���Ƃ̓��[���`���[�j���O�Ŕ��˃o�����X�����ł��B
�X�s�[�J�[�X�^���h/40cm�Œ�߂̂��g���Ă���̂ƁA�X�s�[�J�[�̓�����A�����ʂ͂��Ȃ������ł����ADIRAC LIVE�̃I��/�I�t�łǂ��܂ŕω�����̂��y���݂ł����A���܂���҂͂��Ă��܂���(��
A6ME/SA30�̃A�i���O�_�C���N�g���[�h���v���̊O�A�������Ȃ̂ŁA2ch�X�e���I�͂��Ȃ薞���x���߂ł��B
�����ԍ��F25901491�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��SA30/�{�����[����H�ɂ���
�ȑO�ASA30�̃{�����[����H�ɂ��āA���[�J�[�T�C�g��������܂������A�A
��SA30�́A�A�i���O�{�����[���A�f�W�^���{�����[���ǂ��炩?
�˃A�i���O�{�����[���ƂȂ�܂��B
�ēx�AAI�ɂ��m�F���Ă݂܂������ʁA
������
SA30�̃A�i���O�{�����[����LUXMAN/LECUA1000�A�i���O�{�����[���͂ǂ��炪�����\��
����83db�̏ꍇ
��AI��
Arcam SA30�̃{�����[���R���g���[���́A�f�W�^���{�����[���Ɋ�Â��Ă��܂��B���̂��߁ASA30�̃{�����[���R���g���[����Luxman L-507Z��LECUA1000�A�i���O�{�����[�����r�����ꍇ�A�ȉ��̓_�ňႢ���o��\��������܂��B
1. SA30�̃f�W�^���{�����[��
SA30�̓f�W�^���{�����[���R���g���[�����̗p���Ă���A���ʂ�������Ƃ��Ƀf�W�^���M���̃r�b�g�[�x������������\��������܂��B����ɂ��A���ɒቹ�ʂł̉������������邱�Ƃ�����܂��B
�������ASA30�̃f�W�^���{�����[���͍����\�ł���A���ʂ������x�i83dB�j�ł͉����͂���قnj����ł͂Ȃ��\��������܂��B
2. L-507Z�̃A�i���O�{�����[���iLECUA1000�j�Ƃ̔�r
L-507Z��LECUA1000�̓A�i���O�{�����[���R���g���[�����̗p���Ă���A���ʂ����������Ă����������邱�ƂȂ��A���̃f�B�e�[���⎿������������ƈێ�����܂��B���ɁA�ቹ�ʂ�@�ׂȉ��̕\���ł́A�A�i���O�{�����[���̕����D�ʐ�������܂��B
3. 83dB�ł̉����̔�r
83dB���x�̒����ʂł́ASA30�̃f�W�^���{�����[�����ǍD�ȃp�t�H�[�}���X�����A�����͂킸���ɂȂ�ƍl�����܂��B�������AL-507Z�̃A�i���O�{�����[���́A���ɍ����ׂȉ�����@�ׂȉ��y�\���ɂ����āA��莩�R�ŖL���ȉ��������ł��傤�B
4. ���_
�����d���̏ꍇ�A���Ƀs���A�I�[�f�B�I�I�ȃ��X�j���O���ł́AL-507Z�̃A�i���O�{�����[���iLECUA1000�j�̕����A���R�ȉ������ێ��ł��邽�ߗD��Ă��܂��B
������V�X�e���S�̂̓������d������ꍇ�́ASA30�̃f�W�^���{�����[���ł��\���ȉ�������܂����A�A�i���O�{�����[���قǂ̔��ׂȉ����Č��ɂ͋y�Ȃ����Ƃ�����܂��B
������83dB���x�̏ꍇ�ASA30�̃f�W�^���{�����[���ł��\���ɍ��i���ȉ������y���߂܂����A��莩�R�ȉ��������߂�ꍇ�́AL-507Z�̃A�i���O�{�����[���̕����킸���ɗD��Ă���\��������܂��B
�����ԍ��F25902773�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������
sa30���f�W�^���{�����[���ƌ����鍪����
��AI��
Arcam SA30�̃{�����[�����f�W�^���{�����[���Ƃ���鍪���́A���̂悤�ȋZ�p�I�ȓ����Ɋ�Â��Ă��܂��B
1. DSP�i�f�W�^���M�������j�̎g�p
Arcam SA30�ɂ́A**DSP�i�f�W�^���M���v���Z�b�T�j**�����ڂ���Ă��܂��B����DSP�́A���ʒ������܂ޑ����̐M���������f�W�^���̈�ōs���܂��B���ʂ�ύX����ۂɁA�M�����f�W�^���I�ɑ��삷�邱�Ƃʼn��ʒ������������Ă��邽�߁A�f�W�^���{�����[���Ƃ����܂��B
2. Class G�A���v�̐v
SA30��Class G�A���v���̗p���Ă���A�����I�ȃp���[�����Ɣ��M�Ǘ����s�����߂ɁA�f�W�^���R���g���[�����d�v�Ȗ������ʂ����܂��BClass G�̐v���͉̂��ʐ���ɒ��ڊ֗^���܂��A�V�X�e���S�̂��f�W�^������œ�������Ă��邱�Ƃ��A�f�W�^���{�����[���̈�ƍl�����܂��B
3. �f�W�^���������s��DAC�`�b�v
SA30�ɂ́AESS Sabre DAC�����ڂ���Ă���A�f�W�^���M�����A�i���O�M���ɕϊ����Ă��܂��B�����̏ꍇ�A���̎�̃f�W�^���{�����[���́ADAC�̓����ŐM���������s���A�M���̉��ʂ𐧌䂵�܂��B����ɂ��A���ʒ������A�i���O�̈�Ɉڂ�O�Ƀf�W�^���I�ɍs���邽�߁A�f�W�^���{�����[���̓��������Ƃ����܂��B
4. SA30�̃C���^�[�t�F�[�X�Ƌ@�\
SA30�́A�C���^�[�l�b�g�X�g���[�~���O��e��f�W�^�����͂��T�|�[�g���Ă���A�����̃f�W�^���M���̉��ʂ�DSP�Œ������邽�߁A�A�i���O�I�Ȍ�������g�킸�Ƀf�W�^���̈�ʼn��ʃR���g���[�����s���Ă���\���������ł��B
�����̗v�f����AArcam SA30�̃{�����[���R���g���[���̓f�W�^���̈�ōs���Ă���ƍl�����܂��B
�Ƃ̎��Ȃ̂ŁAARCAM/���[�J�[�T�|�[�g�̉�/�A�i���O�{�����[���́A���Ȃ�������ł��ˁB
A6ME���Ϗo�́��v���Z�b�T�[���[�h����50/�A�i���O�_�C���N�g���[�h�I���ŁA������80db��86db�ɏオ��̂��A�C�}�C�`�ςȎd�l�Ȃ̂ŁA��̂ǂ������M���������Ȃ���Ă���̂��B�B�B
�A�i���O�_�C���N�g���[�h�ł́AADC/DSP/DAC�o�C�p�X����d�l�Ȃ̂ŁA�ʏ�͉������オ����̂Ȃ̂��͓�ł��ˁB
���[�J�[�m�F���ŁA�ǂ��܂Ő��m�ȉ������邩�͕s���ł����B�B�B
�^���𖾗\��ł��B
�����ԍ��F25902787�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��A6ME/LUXMAN505Z/������r
�I�[�f�B�I�V���b�v�ŁAA6ME/LUXMAN505Z/�̉�����r���܂����̂Ń��r���[���܂��B
������
USB�o�R
FLAC/24bit/96khz
���V�X�e��
A6ME/�Œ�o��/LUXMAN505Z/����40/�X�s�[�J�[
A6ME/�Ϗo��-25db/LUXMAN505Z/�p���[�_�C���N�g���[�h/�X�s�[�J�[
������������83���炢�œ����ɂ��Ċӏ܁B
������
A6ME/�Œ�o��/LUXMAN505Z/����40/�X�s�[�J�[
�̕����A������̃N���A���������������ł����B
�{�����[���R���g���[���̉e�������B
�������ɂ���
�v���A���v�ƃp���[�A���v�̑g�ݍ��킹�ɂ���ẮA2.3db���炢�オ�����肷��P�[�X�͂���悤�ł����A6db�オ��P�[�X�͂��܂�Ȃ������ł��B
�����A������A�p���[�A���v�_�C���N�g�̕����A�M�����_�C���N�g�ɑ�������̂ŁA�������オ�錻�ۂ͂��肦��Ƃ̎��B
���[�h�̈Ⴂ�ɂ�鉹�����͔�r�ł��Ȃ������̂ŁASA30/�A�i���O�_�C���N�g���[�h�̉������オ�錴���͕ʓr�A���ؗ\��ł��B
���̌��ۂ́ASA30�̎d�l���ۂ��ł����A�ʂ����Ăǂ��������ʂɂȂ�̂��B�B�B
���A�A�A
�����ԍ��F25904993�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
LUXMAN��������܂����̂œ\���Ă����܂��B
���Ѓv�����C���A���v���w�����������Ƃ̎��A���肪�Ƃ��������܂��B
���L���ԐM�\���グ�܂��B
> �El505z/l507z/l509z�̃{�����[���R���g���[��/lecua�́A�A�i���O�{�����[����?
��
LECUA�͓d�q����A�b�e�l�[�^�[�̈Ӗ��ŁA�A�i���O�{�����[���ƂȂ�܂��B
> �E�����[�J/�X�g���[�}�[/EVERSOLO/A6ME�Ȃǂ���A�i���O�o�͂���ꍇ�A�ǂ��炪�œK��?
>
> LUXMAN���Ń{�����[���R���g���[��
> A6ME���Œ�o�́�l505z/l507z/l509���Ń{�����[���R���g���[��
>
> A6ME���Ń{�����[���R���g���[��
> A6ME���Ϗo�́��Z�p���[�gl505z/l507z/l509��
��
�{�����[���@�\���܂ރv����H�̕��ʓ����̔�r�ōl���܂��ƁA�v�����C�����Ń{�����[���R���g���[���̕����ǂ����ʂ�������ƍl�����܂��B
> �E��{�I�Ƀv�����̉��ʂ������������ꍇ�A�Z�p���[�g������������/�������オ��̂��̂Ȃ�?
�Z�p���[�g��➑̂�d����ʉ�H�ɂ��邱�Ƃɂ�艹���̌����}��܂��A
����ŐM���̓`�B�����������Ȃ�Ȃǂ̃f�����b�g������܂��B
������ɂ��Ă������ŗD���܂�킯�ł͂Ȃ��A�@�킻�ꂼ��̃N�H���e�B�̖�肩�Ƒ����܂��B
�����ɘ_�ɂȂ�܂����A�l�b�g���[�N�v���[���[�n���i�́A�Ⴆ�R���g���[���A�v���̊J���A���y�T�[�r�X�Ƃ̑Ή��ȂǁA���y���̏����ɊJ���Ɛ����R�X�g�������ɂ������Ă���A���̕��A�i���O�I�ȍĐ������͂�����x�����I�Ȑv�ɂȂ��Ă���ƍl�����܂��B
�Ƃ̎��Ȃ̂Ő�������ƁA
���{�����[����H
LUXMAN/LECUA/�A�i���O�{�����[��
ARCAMA/SA30/�A�i���O�{�����[��
A6ME/�f�W�^���{�����[��
���œK�ȏo�͕���
����̎�����r�ł��������ʂ�ALUXMAN�̃v�����C���A���v���Ń{�����[���R���g���[���������������ʂł͗D��
���Z�p���[�g
�@��̃N�I���e�B�ɂ��̂ŁA�Z�p���[�g���œK�Ƃ͌�������Ȃ��B
�A�i���O�{�����[���ł�LUXMAN�D�ʂȂ̂ŁA��������������V�X�e���\�����œK�����B
�I�[�f�B�I�V���b�v�̏��ł́ALUXMAN/LECUA�̓f�W�^���{�����[���Ƃ̎��ł������A�ԈႢ�������悤�ł��B
���̕ӂ𐳂����������Ă���l�͏��Ȃ����Ȃ̂ŁA�Ȃ�ƌ����܂��A�A�A�A
LUXMAN�̃T�|�[�g�͑����Đ��m�Ȋ��������܂����B
����AARCAMA�̃T�|�[�g�͖����ɉ�����܂���̂ŁA���ЊJ�����Ă���LUXMAN�Ȃǂɔ�ׂāA�Z�p���x��/�d�l�������Ⴂ�ƌ��킴��I���܂���B
���X�����Ă��x���ł����A�܂Ƃ��ȃI�[�f�B�I�V�X�e�����\�z����ꍇ�́A���ЊJ�����Ă��ăT�|�[�g���������肵�Ă���I�[�f�B�I���[�J�[��I�ق�������ł��ˁB
�����őS�Ď��ȉ����ł���Ȃ牽�ł��ǂ��̂ł��傤��(��
�����AARCAMA/SA30�̉������͂��ꂩ��Č����܂��̂ŁA���̌��ʎ���ł͕]���͂܂��ς�邩������܂���B
�ŏI�I�ɂ́A���i�i��/�R�X�p/�T�|�[�g�ȂǁA�����I�Ȕ��f�ɂȂ�܂��̂ŁA��������ƌ���߂čs�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25906130�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���X�s�[�J�[/����Ɖ����̍l�@
https://www.phileweb.com/sp/interview/article/202409/27/1007.html
POLK�̃��r���[�ɂ��L�ڂ�����܂������A��͂�A�����J���˂̃X�s�[�J�[�͌���^�ʼn����^/�O�ʒ�ʂ̂悤�ł��B
�X�s�[�J�[�̗p�r���炵�Ă��A���[���b�p�͕����p�ɔ��W���Ă�������ŁA�A�����J�̃X�s�[�J�[�͌���炿�Ƃ����̂�����킯�ł��B�f��ق̂ǂ��ɍ����Ă��Ă��������ł���A���������X�s�[�J�[���A�����J�ł͎嗬�ł����B
�܂��A�A�����J�̕ꍑ���y�̓`�����e�����Ă���͂��ł��B�J���g���[�A�W���Y�A�u���[�X�Ȃǂ́A�����ꏊ�Ŗڂ̑O�ɂ��鉉�t�҂̉����܂��B1970�N���PA���g�������ƃ��b�N�̎���ɂȂ��Ă��A�ԋ߂Œ������y���g�債���悤�ȉ��̍����ł��B�t�Ƀ��[���b�p�ł́A�����I�y���n�E�X�A�ߑ�ł̓z�[���ȂǍL���Ԑډ������̑�����Ԃł��B
�����������������A���[���b�p�̃X�s�[�J�[�͉���Ɖ����̃o�����X�Ő��藧���Ă��܂��B�A�����J�͈��|�I�ɉ����d���ŁA�����O�ɗ��Ăق����Ƃ����v�B���̗��R���A�A�����J�̕ꍑ���y�̓`���ƌ���炿��2���痈�Ă���Ƃ����킯�ł��B
KEF�́A�p�V���[�Y/MAT���ڂ̐V�^�����\����܂����B
�q�V���[�Y�����n�C�R�X�p�ɂȂ����̂Ŗ��͓I�ł��ˁB
https://www.phileweb.com/sp/news/audio/202409/26/25754.html
���̕ӃN���X�����������Ȋ����ł��ˁB
�E�u�b�N�V�F���t�^�X�s�[�J�[�uQ Concerto Meta�v192,500�~�i�ō��^�y�A�j
�E�t���A�^�X�s�[�J�[�uQ7 Meta�v264,000�~�i�ō��^�y�A�j
�t���A�^�́A�p�b�V�u���W�G�[�^�[�ڂŁA�ቹ���X�b�L�����Ă����ł��ˁB
���r���O��POLK
����KEF���n�C�R�X�p�ł�������(��
�����ԍ��F25906270�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
>KEF�́A�p�V���[�Y/MAT���ڂ̐V�^�����\����܂����B
���̃V���[�Y�͂Ȃ��Ȃ��ǂ������ł��ˁB
�ł����̊�]�X�y�b�N�ɂ͍����Ă��Ȃ��悤�ł��B
�P�D�t���A�^
�Q�D�������W�T�������x
�R�D�C���s�[�_���X���W��
�S�D�\����90dB�ȏ�
�|�[�N�I�[�f�B�I��N���v�b�V���ɂ͂���̂��ȁH
�i�a�k�͕č��ł̓z�[���I�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ͔F�m����Ă��炸�A�����ȃJ�[�I�[�f�B�I���[�J�[�Ǝv���Ă��܂��ˁB
�X�^�W�I���j�^�[�V���[�Y�̃X�s�[�J�[�������Ă���͓̂��A�W�A�����̂悤�ł��B�؍��A���{�A���`�A��p�B
�����ԍ��F25906394
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���i�a�k�͕č��ł̓z�[���I�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ͔F�m����Ă��炸�A�����ȃJ�[�I�[�f�B�I���[�J�[�Ǝv���Ă��܂��ˁB
AI�ł͂����ł͂Ȃ��悤�ł��ˁB
JBL�͕č��ł̓J�[�I�[�f�B�I�̕���ł��L���F�m����Ă������ŁA�z�[���I�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ��Ă��������݊��������Ă��܂��B����JBL�͒������j�����u�����h�ł���A�v���t�F�b�V���i�������̃X�^�W�I���j�^�[��R���T�[�g�p�X�s�[�J�[�ł������]���Ă��܂��B���̂��߁A�K�������u�����ȃJ�[�I�[�f�B�I���[�J�[�v�Ƃ��Ă̂ݔF�m����Ă���킯�ł͂���܂���B
�������AJBL�͕��L�����i�т̐��i��W�J���Ă���A�z�[���I�[�f�B�I��n�C�G���h�̃X�s�[�J�[�ɏڂ����Ȃ��w�ɂƂ��ẮA�荠�ȉ��i�т̃J�[�I�[�f�B�I���i��Bluetooth�X�s�[�J�[�̃C���[�W��������������܂���B�������A�I�[�f�B�I���D�Ƃ�v���t�F�b�V���i���̊Ԃł́AJBL�͈ˑR�Ƃ��č��i���ȃz�[���I�[�f�B�I���i�����u�����h�Ƃ��Ă̔F�����������ł��B
���X�^�W�I���j�^�[�V���[�Y�̃X�s�[�J�[�������Ă���͓̂��A�W�A�����̂悤�ł��B�؍��A���{�A���`�A��p�B
JBL�̃X�^�W�I���j�^�[�V���[�Y�́A���A�W�A�����łȂ��A���E���Ŕ̔�����Ă��܂��B���Ƀv���t�F�b�V���i�������̃X�^�W�I���j�^�[�́A�č���[���b�p�Ȃǂł��L���g�p����Ă���A���y�����f�搧��̌���Œ�]������܂��B�Ⴆ�AJBL 3�V���[�Y��JBL 7�V���[�Y�̃X�^�W�I���j�^�[�́A�v���̃G���W�j�A��N���G�C�^�[�ɍD�܂�Ă���A�O���[�o���ɗ��ʂ��Ă��܂��B
�܂��A�z�[���I�[�f�B�I�����̃��f�����W�J����Ă���A�n�C�t�@�C�I�[�f�B�I���D�ƌ����ɐv���ꂽ���i���A�k�Ă�[���b�p���܂ނ��܂��܂Ȓn��Ŕ̔�����Ă��܂��B���̂��߁AJBL�̃X�^�W�I���j�^�[�V���[�Y�����A�W�A����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�O���[�o���ɃA�N�Z�X�\�ł���B
https://www.jbl.com/floor-standing-speakers/
�����ԍ��F25906430�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���č��̃X�s�[�J�[�V�F�A���ɂ���
����
�A�����J�̃X�s�[�J�[���[�J�[�V�F�A��
AI��
2024�N���݁A�A�����J�̃X�s�[�J�[�}�[�P�b�g�͔��ɋ������������A��ɃX�}�[�g�X�s�[�J�[�A�|�[�^�u���X�s�[�J�[�A�����ď]���̃z�[���I�[�f�B�I�V�X�e�����s����߂Ă��܂��B�A�����J�̎�v���[�J�[�Ƃ��ẮABose�AHarman International (JBL)�A�����Sonos�����ɋ����A���ɃX�}�[�g�X�s�[�J�[��C�����X�I�[�f�B�I�Z�p�ɂ����ėD�ꂽ�u�����h�F�m�x���ւ��Ă��܂��B�����̃u�����h�́A�X�}�[�g�z�[���Ƃ̓�����C�����X�I�[�f�B�I�̃g�����h�ɏ��A�s��V�F�A���g�債�Ă��܂��B
����
polk,klipsh,JBL�ł�
AI��
2024�N���݁APolk Audio�AKlipsh�A�����JBL�̓A�����J�̃X�s�[�J�[���[�J�[�s��ɂ����Ă����ꂼ��m�ł��鑶�݊��������Ă��܂��B
Polk Audio �͎�Ƀz�[���V�A�^�[��I�[�f�B�I�V�X�e�������ɃX�s�[�J�[��W�J���Ă���A���ɉ��i�т��l�������o�����[�I�[�f�B�I�ŕ]������Ă��܂��B�X�}�[�g�X�s�[�J�[�s��ł͂��܂�ڗ����܂��A�ƒ�����̃X�s�[�J�[�s��ł̃V�F�A�͌����ł��B
Klipsh �́A���Ƀz�[���V�A�^�[��v���p�I�[�f�B�I�V�X�e�������̍��\���X�s�[�J�[�Œm���Ă��܂��B���ɓƎ��̃z�[���Z�p���̗p�����X�s�[�J�[�ŁA��������������鐻�i�������A�G���^�[�e�C�����g�I�[�f�B�I�s��ł̃V�F�A���ڗ����܂��B
JBL �́A�z�[���I�[�f�B�I�����łȂ��A�X�}�[�g�X�s�[�J�[��|�[�^�u���X�s�[�J�[�̕���ł����͂ȑ��݂ł��B����Harman International�P���ŁAJBL�u�����h�̓J�[�I�[�f�B�I��|�[�^�u�����i�ł����ɍ����V�F�A���ւ�܂��B�܂��A�X�}�[�g�X�s�[�J�[�̕���ł�Amazon��Google�Ƃ̒�g�ŏd�v�Ȏs��v���C���[�ƂȂ��Ă��܂��B
�����̃��[�J�[�́A�e�Z�O�����g�ɂ����ċ����͂��ێ����A�A�����J�s��ł̃V�F�A���g�債�Ă��܂��B
�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA�ǂ������^/�����^�̃X�s�[�J�[���[�J�[�Ƃ��ĔF�m����Ă���悤�ł����A�ŋ߂ł͎�Ғ��S�ɃT�E���h�o�[�A���C�����X�A�X�}�[�g�X�s�[�J�[�V�F�A���̕����L�тĂ���悤�ł��B
���{����KLIPSH�̓}�C�i�[�ł����A�z�[���^�ʼn������N���A�Œ����₷���ł��ˁB
�A�����J���̃t���A�^�́A�����[�J�[�����ł����̂��f�����b�g�ł���(��
�����ԍ��F25906470�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
https://www.jbl.com/floor-standing-speakers/
��L�ɂ̓X�^�W�I���j�^�[�V���[�Y�͌�������܂���ˁB
�́A�����̕č��̗F�l��JBL��m���Ă��邩�������Ƃ���,�S���J�[�I�[�f�B�I���[�J�[���Ɠ����Ă��܂����B
�����ԍ��F25906485
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�����ɂ���܂���B
https://www.jbl.com/studio-monitors/305PMKII-.html
�����ԍ��F25906499�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���́A�����̕č��̗F�l��JBL��m���Ă��邩�������Ƃ���,�S���J�[�I�[�f�B�I���[�J�[���Ɠ����Ă��܂����B
���̏��ł���?
JBL�͍ŋ߁AAV�A���v���������ăz�[���I�[�f�B�I�ɐϋɓI�ł���B
https://www.jbl.com/home-electronics/MA710.html
https://m.youtube.com/watch?v=UGnIBzMkAAk
�����ԍ��F25906519�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�\���N�O�̏��ł��B
���̃X�s�[�J�[�͓��{���܂ޓ��A�W�A�ŃX�^�W�I���j�^�[�V���[�Y�Ƃ��Ĕ����Ă���X�s�[�J�[�ł͖����ł��ˁB
�����ԍ��F25906526
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
4312G�Ƃ��̎����ȁB
����
�A�����J�ł��܂蔄���Ă��Ȃ����R��
AI��
JBL 4312G���A�����J�ł��܂蔄���Ă��Ȃ����R�͂������l�����܂��B
1. �^�[�Q�b�g�s��̈Ⴂ: 4312G�͎�Ƀv���t�F�b�V���i���ȉ����p�r���ӎ����Đv����Ă���A�X�^�W�I���j�^�[�Ƃ��Ă̎g�p���O��Ƃ���Ă��܂��B�A�����J�ł́A�ƒ�����̃I�[�f�B�I�V�X�e����G���^�[�e�C�������g�����̃X�s�[�J�[����葽�����v����Ă��邽�߁A����̃v���������f���͗��ʂ������܂��B
2. �̔��헪: JBL�̓A�����J�s��ɂ����đ��̃��f����u�����h�Ƌ������邽�߂ɁA��ʏ���Ҍ����̐��i�𒆐S�ɓW�J���Ă��邽�߁A4312G�̂悤�ȃj�b�`�Ȑ��i�����܂�ڗ����Ȃ��\��������܂��B�܂��A���̃X�s�[�J�[�ɔ�ׂĉ��i�����߂ł��邱�Ƃ��v���̈�ł��B
3. �n��I�Ȏ��v�̈Ⴂ: ���{�Ⓦ�A�W�A�ł́A4312G�̂悤�ȃv���t�F�b�V���i���������j�^�[�X�s�[�J�[�ɑ�����v�������A���ɉ�����v�ɂ������I�[�f�B�I�t�@�����������߁A�����̒n��ł͂�葽���̗��ʂ�����ƍl�����܂��B
�����̗v�����d�Ȃ�A4312G�̓A�����J�ł͂��܂蕁�y���Ă��Ȃ��̂�������܂���B�ڂ������́AJBL�̌����T�C�g��I�[�f�B�I���̔̔��X���Q�Ƃ��Ă��������B
�A�����J�̃z�[���I�[�f�B�I�́APOLK,KLIPSH�̕����A�n�C�R�X�p�ŃV�F�A��������AJBL�̓V�F�A�Ⴂ�悤�ł��B
���ɔ����\��͂Ȃ��ł���(��
�����ԍ��F25906568�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
4312G�ȊO��
https://jp.jbl.com/studio-monitor-speakers
�Ɍf�ڂ���Ă���X�s�[�J�[�����ł��B
�����O�ɂ�4429,4318,4365�Ȃǂ�����܂����B
�����ԍ��F25906585
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���̃V���[�Y�̓A�W�A�̈ꕔ�̃I�[�f�B�I�}�j�A�ɐl�C����悤�ł��ˁB
�A�����J�l�B�͂����ᒆ�ɂȂ���ł��傤��(��
�܂��A�X�s�[�J�[���̂Ń��[�J�[�ɂ����b�ɂȂ邱�Ƃ͂قڂȂ��ł��傤���A�n�[�}���O���[�v/ARCAM,JBL�̃T�|�[�g�́A���Ȃ背�x���Ⴂ�̂����������̂ŁA����ߊ��Ȃ������ł���(��
�K���A�w�������I�[�f�B�I�V���b�v�̃T�|�[�g/�n�[�}���c�ƃ}�����A�ǐS�I�������̂��B��̋~���ł���(��
����w������X�s�[�J�[�Ɋւ��ẮA�����^��BW/KLIPSH/POLK�͊��ɍw���ς݂Ȃ̂ŁA����^�̐V�^KEF/ELAC�Ȃǂ��w�����邩������܂���B
AV�A���v�Ɋւ��ẮAMARANTZ/CINEMA50/70�����肪�L�͂ł����A�A�A
���LG4K���[�U�[�v���W�F�N�^�[���w�����܂����̂ŁA���N�܂Ő摗��ɂȂ肻���ł��B
�l�C�e�B�u4K�v���W�F�N�^�[�́AZ7
/Z5����������܂������A����炪10���~���炢�Ŕ�����悤�ɂȂ����甃���ւ��邩������܂��A10�N�ギ�炢�ł��傤��(��
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0088/id=143809/
�����ԍ��F25906605�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɁABS4KWOWOW�̓j�[�Y����ŁA�I���̂悤�ł��B
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1626970.html
NHK/BS4K���ĕ�������ŃI���R�����̗�����ۂ��ł��ˁB
�t�ɁA�A�}�v���Ȃǂ�HD�f�����A4K���݂ɍ��掿�����Ă��Ă��܂��ˁB
https://m.youtube.com/watch?v=uOWVc2eCkHc
�����ԍ��F25906612�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
FHD�f���ł��\���Y��ł��ˁB
NHK��BS4K�ł̓N���V�b�N�ԑg�A��̓h���}�A100���R�A�O���[�g�l�[�`���[�����Ă��܂��B
�n�[�}���̐e��Ђ͊؍���SAMSUNG�ł�?
�����ԍ��F25906662
![]() 1�_
1�_
��Minerva2000����
BS4K�łقƂ��4K�f����Ȃ��Ȃ�܂����ˁB
NHK�͑��o�݂邮�炢�ł���(��
���N�̑�͓͂r���ŖO���Ă��܂��܂����ˁB
�n�[�}���̐e��Ђ́A���C�Z���X�ړI�ŁA�I�[�f�B�I�n�̊J��/�c�Ƃɂ͓��Ɍ��o�����Ă��Ȃ������ł��B
�Ƃ肠�����ALG4K���[�U�[��YOUTUBE/�A�}�v��/�f�B�Y�j�[�v���X�̉f��h���}���i���܂�(��
�����ԍ��F25906683�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɁA�n�[�}���O���[�v�̔̔��헪�͏�肭�����Ă���悤�ł��B
�n�[�}���O���[�v�̃I�[�f�B�I����́A�ŋ߂̋ƐтŐ����������Ă��܂��B2024�N�x�̑��l�����ɂ́A�O�N�������22%�̔��㑝���L�^���A���㍂��8��9700���h���ɒB���܂����B�܂��A2023�N�x�̑S�̂ł́A�n�[�}���̔���͑O�N������8%�������܂����B
�n�[�}���́A�I�[�f�B�I���i�⎩���Ԍ����C���t�H�e�C�������g�V�X�e���𒆐S�Ɏ��Ƃ�W�J���Ă���A���Ƀ��C�t�X�^�C�����i��v���~�A���I�[�f�B�I���i�̎��v�����܂��Ă��܂��B�ŋ߂̔��\�ł́A�u�����h�̒m���x����ƐV���i�̓������A����Ȃ鐬���Ɋ�^���Ă���Ƃ���Ă��܂��B
�n�[�}���̃I�[�f�B�I���i�Ɋւ���ڍׂȏ���ŐV�̋Ɛтɂ��ẮA�����T�C�g������Q�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B
���Ƀ��C�����X�C���z���A�X�}�[�g�X�s�[�J�[�̔���グ�D���ŁA�����ȃI�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ��������C���[�W�Ƃ��ẮASONY�ɋ߂��ł��ˁB
�����A�n�C�G���h/�}�[�N���r���\���Ȃǂ������Ă���̂ŁA���͍L���ł��ˁB
�J�[�I�[�f�B�I�̕���ł̓C���h�ɐi�o���Ďs��g�債�Ă�悤�ł��B
https://s.response.jp/article/2024/08/12/385136.html
�n�[�}���O���[�v���ꌾ�Ō����ƁA�u���l�ȃI�[�f�B�I�̌������A�v�V�ƕi���̃��[�_�[�v�ł��B�n�[�}���O���[�v�́A�ƒ�p�I�[�f�B�I�A�v���t�F�b�V���i���I�[�f�B�I�A�ԍڃC���t�H�e�C�������g�V�X�e���ȂǁA���܂��܂ȕ���ō��i���ȉ������i��W�J���Ă��܂��B�܂��AJBL��AKG�Ȃǂ̃u�����h��ʂ��āA��ʏ���҂���v���t�F�b�V���i���܂ŕ��L���j�[�Y�ɉ����鐻�i����Ă��܂��ˁB
�T�|�[�g�̕i����SONY���x���ł����A�Ή����ǂ����Ă��Ȃ��悤�ł�(��
�����ԍ��F25906692�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���N���V�b�N�R���T�[�g/����Ɖ����̍l�@
�v�X�ɃN���V�b�N�R���T�[�g�ӏ܂����̂Ń��r���[���܂��B
���R���T�[�g���/�y�c
�n���̉��y�z�[��/���Ґ��I�[�P�X�g��26�l
���y��
W.A.���[�c�@���g/�������o�b�n������
L.���[�c�@���g/�V�����o�b�n������
F.J.�n�C�h��/������ ��26�ԁu���́v
W.A.���[�c�@���g/���@�C�I�������t�� ��5�� �u�g���R���v
���@�C�I�����Ƒt/���������
�����z
���͒��K�̓z�[���ŁA����8���/�E��3���/���Ŋӏ܁B
�����͂����������̂��炢�ł����B
����8���/�ő剹��83
����3���/�ő剹��87
�����͂��������Ƃ̌��Ɠ������炢�ł������A�z�[���̕������ꂪ�L���̂őO�����ԓ��Œ����Ă��銴���ł��ˁB
���g���I�ɂ́A���60hz/����3000hz���炢���{�����[���]�[���ŁA�\�z�ȏ�ɋ��������ł��ˁB
���悪�����Ԍ������Ă���悤�ł��B
�o�C�I�����Ƒt�͂���ɋ����������������Ȃ�̂ŁA�����I�ɂ͎���I�[�f�B�I�̕����ǂ��ꍇ����B
�R���T�[�g�͐���LIVE�Ȃ̂ŁA�ӏ܈ʒu���܂߁A�v���C���[�̃v���C/�f��/��̕��͋C�Ȃǂ��ӏܗv�f�Ȃ̂ŁA�I�[�f�B�I�Ƃ͂܂��Ⴄ�̌��Ƃ��Ċy���߂܂����B
���͔N�����ȁA�A�A
�����ԍ��F25907339�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�̂т�z�[���̑�z�[���Ƀ��V�A�̃I�[�P�X�g�����������A���K�̑����v�ʼn����𑪂������Ƃ�����܂��B
���Ȉʒu�͑O����15��ڂ̒����ł��B
�P�D�u�W����̊G�v�L�G�t�̑��ŁA�s�[�N103dB
�Q�D�`���C�R�t�X�L�[�@�o�C�I�������t�ȂŁA�@�s�[�N96dB
�ł����B
�����ԍ��F25907404
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
����ł�����(��
https://www.biwako-hall.or.jp/performance/_2015-2016
�́A���b�N�n��LIVE��EDM�t�F�X�ɍs�������́A�̊���120db���炢����܂����ˁB
�����ԍ��F25907554�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
���E�t�H���E�W�����l�т�ł����B
1980�N��Ƀf�g���C�g�Ń|���[�X��������120dB�͂���܂����ˁB
�����ԍ��F25907573
![]() 0�_
0�_
��BS4K/�̂���JPOP/������r
�Ƃ̃��r���O�ł�80db���炢�ŏ\���ŁA�����ʂł��t���b�g�C���ł��������ł��ˁB
���y��
����������/����@�q
�~���N���E�K�[��/�i��^���q
���V�X�e��
TV��POWERNODE.EGGE��MXT15
�����ԍ��F25907610�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������Ɖ����̔�r�܂Ƃ�
1. ����iSound Stage�j:
�R���T�[�g�z�[��: �L��ȋ�Ԃ�������������̍L���������ŁA�I�[�P�X�g����o���h�̑S�̑�����������̂����͂ł��B���̔������Ԃ̍L����ɂ���āA���t�҂̈ʒu��y��̔z�u�����A���Ɋ������܂��B
����r���O: ����̓R���T�[�g�z�[���ɔ�ׂċ����Ȃ邱�Ƃ������ł����A�X�s�[�J�[�̔z�u�╔���̉��������ɂ���āA������x�̉���̍L����������邱�Ƃ��ł��܂��B
2. �����iImage�j:
����r���O: ����̃I�[�f�B�I�V�X�e���ł́A�X�s�[�J�[��X�j���O�|�C���g���œK�����邱�ƂŁA�������ʁA�N���A�������サ�܂��B���ɁA�ׂ������̃j���A���X��y��̈ʒu�m�Ɋ�����邱�Ƃ��ł���̂����_�ł��B
�R���T�[�g�z�[��: �����͍L���肪�������ŁA�����̒�ʂ����m�Ɋ����ɂ������Ƃ�����܂��B�����t�̔��͂͂�����̂́A�����̍ו��Ɋւ��Ă͎���̍��i���ȃV�X�e���ɂ͋y�Ȃ����Ƃ�����܂��B
�܂Ƃ�
���ꂼ��̊����������𗝉����A�����̗ǂ����y���ނ��Ƃ́A���y�ӏ܂�����ɖL���ɂ�����@�ł��B�R���T�[�g�z�[���ł̐����t�̗Տꊴ��L������y���݂A����ł͎����D�݂̉������ʂ�Nj����邱�ƂŁA���y�̌��̕����L����܂��B
���y�̊y���ݕ��𑽗l�Ɏ�����邱�ƂŁA���X�j���O�̌������[���������̂ɂȂ�ł��傤�B
���X�s�[�J�[�̃^�C�v�̎g������
1. ����^�X�s�[�J�[:
����: ���̍L������d�����A�����S�̂ɉ����s���n�点��v�B���ɁA�T���E���h���ʂ��K�͂ȃI�[�P�X�g���̍Đ��ɓK���Ă��܂��B
�g�p��:
��Ґ��̃I�[�P�X�g����f��̃T�E���h�g���b�N���y���ލۂɁA������L���đS�̂̉����������邱�Ƃ��ł���B
���r���O�Ńp�[�e�B�[��W�܂肪����Ƃ��ɁA�F�����y���y���߂�悤�ɔz�u�B
2. �����^�X�s�[�J�[:
����: ���̒�ʂ�N���A�����d�����A���X�j���O�|�C���g�ł̖��Ă���Nj��B�X�̊y���̃f�B�e�[�����������܂��B
�g�p��:
�N���V�b�N��W���Y�ȂǁA�ׂ����j���A���X���d�����鉹�y���ۂɁA�����̈ʒu�m�Ɋ����邱�Ƃ��ł���B
�A�R�[�X�e�B�b�N���C�u��{�[�J�����d���������y���y���ލۂɍœK�B
�g�������̃|�C���g
�����̃W������: ���y�̃W��������Ȃ̍\���ɂ���āA�ǂ���̃X�s�[�J�[�^�C�v���K���Ă��邩���l�����܂��B���Ƃ��A�I�[�P�X�g���̋Ȃ��K�͂ȃo���h�̉��y�ɂ͉���^�A�A�R�[�X�e�B�b�N�ȋȂ�\���p�t�H�[�}���X�ɂ͉����^���ǂ��ł��傤�B
���X�j���O��: ����̃��r���O�̍L����`��A�Ƌ�̔z�u�ɂ���Ă����̓`�������ς�邽�߁A���X�j���O���ɉ����ăX�s�[�J�[�̃^�C�v��z�u�����邱�Ƃ��d�v�ł��B
���_
�����ɂ���ĉ���^�Ɖ����^�̃X�s�[�J�[���g�������邱�ƂŁA���y�̑̌������[�߂邱�Ƃ��ł��܂��B���X�j���O����D�݂ɉ����āA�_��ɃA�v���[�`��ς��邱�ƂŁA���[���������y�ӏ܂��\�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25907650�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�^���̒i�K�ʼn���^�������^�������܂��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�܂�A�y��ɋߐڂ��Ẵ}���`�}�C�N�^���͉����^�A�y�킩�痣���3�{���炢�Ř^������̂�����^�B
�Đ����u�́A���̘^���ɉ����ĉ���^�ɂ������^�ɂ��Ή��ł���̂����z�����B
�����ԍ��F25909373
![]() 0�_
0�_
��LG4K���[�U�[�v���W�F�N�^�[/HU710PB/�t�@�[�X�g���r���[
���@���͂����̂Ńt�@�[�X�g���r���[���܂��B
���V�X�e��
HU710PB��X1700H��100�C���`�X�N���[��
��WEBOS
�܂��͓���WEBOS���ŐV�ɃA�b�v�f�[�g���āA�f��/������ݒ�B
���ƃT�N�T�N���Ă��āATV�ł�WEBOS�Ƃقړ����ݒ�A���쐫�ł��B
APPLE MUSIC���_�E�����[�h�ł��܂����B
���掿/���邳
������ł������Ԃ鍂�掿�ł��B
�S�z���Ă������邳500ANSI���[�����́A�S�����Ȃ����x���ŕK�v�\���Ȗ��邳������܂��B
�i��2K�v���W�F�N�^�[�ł��������炢�ł����̂ŁA���Î�/100�C���`�ł͒ʏ�g�p�ł���ł��傤�B
���掿/�𑜓x
YOUTUBE��4K/HDR�͗\�z�ȏ���Y���4K�����������܂��B
�A�}�v��HD�R���e���c/���̕v�ƌ�������
LG�L�@TV�Ō��Ă�̂Ƃقړ����x���̍��掿�ł��B
�A�}�v��UHD�R���e���c/�͂̎w��
�������LG�L�@TV�Ō��Ă�̂Ƃقړ����x���̍��掿�ł��B
���掿/�F��
�����������ł����A���e�͈͂ł��B
���ƂŃL�����u���[�V�����������Ƀo�����X�A�b�v���邩���B
���掿/�R���g���X�g
��̃��r���[�T�C�g�ʂ�A�������܂��Ă��Ė��Â��n�b�L�����Ă��܂��B
�������R��/���쐫
WEBOS����g���ꍇ�́A��M�@�������Ȃ̂Ŏ�A�M���̂���肪���ɂ����ł��B
FIRE4K MAX�Ƃ�����s���Ζ��Ȃ��ł��傤�B
������/eARC
���Ȃ��A���v�ɉ����o�͂ł��܂����B
�A�}�v���A�g���X�R���e���c/�͂̎w�ւ��h���r�[�A�g���X�o�͂ł��܂����B
������
�i���v���W�F�N�^�[�ɔ�ׂĔ��ɐÂ��ł��B
�����ʒu���瑪�肵��42db���x�ł��B
�����z
�Ƃɂ����A10���~�ł��̃N�I���e�B�Ȃ當�傠��܂���B
�l�C�e�B�u4K���̍��掿�ň�ʎg�p�ł���Ώ\���ȃN�I���e�B�ł��B
JVC�l�C�e�B�u4K�̍����@���������Ă��܂��̂ŁA�Ƃɂ����n�C�R�X�p�ł��B
�n�C�G���h�}�j�A���̍S�肪�Ȃ���A����łقڃz�[���V�A�^�[�V�X�e���͊����ł��܂��ˁB
���⑫
�v���W�F�N�^�[�A�b�v�摜�͎��ۂ̐F���Ƃ͂��ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F25910659�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�Ȃ��Ȃ��f���炵�����\�̂悤�ł��ˁB
�Ƃ���ʼn掿���[�h�͉��ɂ���Ă��܂���?
�����ԍ��F25910735
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���Ƃ���ʼn掿���[�h�͉��ɂ���Ă��܂���?
�W���ł��B
���̃��f���ɂ́A�ȃG�l���Ȃ��ł��ˁB
https://www.phileweb.com/sp/news/d-av/202405/23/60407.html
�����ԍ��F25910746�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�����F�X�ȃ��[�h�������܂������W�����[�h����ԗǂ��ł��ˁB
�ȃG�l���[�h�͉掿���j���[�ł͂Ȃ�,�ݒu���j���[�ɂ���܂���?
�����ԍ��F25910760
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���ȃG�l���[�h�͉掿���j���[�ł͂Ȃ�,�ݒu���j���[�ɂ���܂���?
���ꂩ�ȁB
�ŏ��ɂȂ��Ă܂��ˁB
�����ԍ��F25911079�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�ŏ��Ƃ������Ƃ͈�ԏȃG�l�ɂȂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����ԍ��F25911086�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������ő�ɂ���ƍł��ȃG�l�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25911094
![]() 0�_
0�_
��710PB/�掿��r
���̑��̃f�o�C�X������掿��r���Ă݂܂����B
���V�X�e��
PS4/X1700H/SA30/710PB/
�u���[���C/�O���f�B�G�[�^�[
���𑜓x
������������Ԃ鍂�掿�ł��B
��C���������܂��ˁB
�L�@TV�̃M���M�����掿�����i�`���������掿�ł��B
4K���[�U�[�f��كN�I���e�B�ł�(��
�����邳/�f���ȃG�l
���ʃ��[�h�ōő�ɂ���Ƃ����ԈÂ��Ȃ�̂ŁA�����ŏ����ǂ������ł��B
500ANSI/100�C���`�Î����ƁA���ł��\���Ȋ����Ŏ��R�Ȋ����ɂȂ�܂��ˁB
���R���g���X�g
�t�B�����������A���Ɋ������ĉf�敵�͋C���A�b�v���܂��B
���F��
���F�͗L�@TV�����ǂ������B
3�F���[�U�[�̊e�F����������ƗZ�����Ă��銴�������܂��B
����ɂ��P�x����������ł��܂��B
�������R��
�Ȃg����������ȂƎv������ALG�T�E���h�o�[�̐F�Ⴂ�Ō`���ꏏ�ł���(��
��CEC
PS4�d���I���őS�������I���ɂȂ�܂��B
�i���v���W�F�N�^�[��CEC������������Ȃ�������ł����B
���܂Ƃ�
100�C���`/4K���[�U�[/�z�[���V�A�^�[�Ƃ��ẮA�𑜓x/���邳/�R���g���X�g/�F��/�̑����I�ȃo�����X�ł́A����4K���[�U�[�f��ٕ��̃N�I���e�B�ł��ˁB
����ӏ܂��ƃx�X�|�W/2m���炢�̎����Ȃ̂ŁA�̊��Ƃ��Ă͉f��يӏ܂������Ă��܂��B
����/�T���E���h���܂߂�A����ɃJ�X�^�}�C�Y���ł��܂�����A�����x�͍��߂ł��ˁB
���Ƃ́A�z�M4K�������Ɋς�鎞��Ȃ̂ŁA�����s������ł��B
�R�X�p�I�ɂ́A
�L�@TV100�C���`��400���~
�l�C�e�B�u4K���[�U�[��/260���~
�Ɣ�ׂāA
LG4K���[�U�[��/10���~/���
�����x����Mars Pro 2/22���~/���
�Ȃ̂ŁA�n�C�R�X�p�����Ċ��ӊ����Ƃ��������悤������܂���(��
LG�͐_�u�����h�ł��ˁB
����̉ۑ�́AAV�A���v/�X�s�[�J�[�������A�b�v�O���[�h���邮�炢�ł��ˁB
�����ԍ��F25911240�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�s�N�Z���V�t�g�̋[��4K�v���W�F�N�^�[�ł�4K�𑜓x���y���܂�Ă���悤�ʼn����ł��B
�����ԍ��F25911342
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
LG�v���W�F�N�^�[�̐�y�ɁA�����܂ŐF�X�A�h�o�C�X�����Ċ��ӂ��܂��B
�v���W�F�N�^�[/�X�N���[�����o���������̂Ŕ��ɏ�����܂����B
���ƁA�t�H�[�J�X�Ɋւ��ẮA��ʎl���܂ł�������ƃs���g�������Ă��āA�{�P�Ė����ł��ˁB
�����Y���x�����߂����B
���Ȃ݂ɁA���̃X�s�[�J�[�́A����Ɖ����o�����X���������ł��B
��C�^���ł��������ł��B
https://youtu.be/h7QNs-4iynk?si=6N0DDZLsEw8FLBKN
�����ԍ��F25911360�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�ǂ��X�s�[�J�[�͉���^�\���������^�\�����ł��܂��ˁB
�����ԍ��F25911543
![]() 0�_
0�_
���v���W�F�N�^�[����̃A�g���X�Đ��ɂ���
710PB�ɂ��ẮA���[�J�[�T�C�g�̃X�y�b�N�ł��h���r�[�A�g���X�Đ��Ή���搂��Ă��܂���ł������A���ʂ�WEBOS���̃A�v������h���r�[�A�g���X�Đ��ł��܂����B
LG���炸�A�v���W�F�N�^�[����A�g���X�Đ��ł���ł��Ȃ��̓A�v�����̖��ł����A�����Ɋ��Ⴂ���Ă���P�[�X������悤�ł�(��
https://s.kakaku.com/bbs/K0001356307/SortID=25894291/
https://s.kakaku.com/review/K0001356307/ReviewCD=1885501/
�����ԍ��F25911760�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��710PB/���\�̍l�@
������
�l�C�e�B�u�R���g���X�g/1200:1�ō��߂����A�����I�ȗ��R��
��AI��
LG HU710PB�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g�䂪1200:1�Ɣ�r�I�������R�ɂ́A�������̋Z�p�I�ȗv�����e�����Ă��܂��B
1. ���[�U�[�����̓���
HU710PB�̓��[�U�[�������g�p���Ă���A���[�U�[�����͏]���̃����v�^�����ɔ�ׂāA��萳�m�Ɍ��𐧌�ł��܂��B��̓I�ɂ́A���[�U�[�̓X�C�b�`�̃I���E�I�t�������A����\������ۂɌ����̏o�͂��u���ɒጸ���邱�Ƃ��\�ł��B����ɂ��A�Õ������Â��Č�����A�R���g���X�g�����サ�܂��B
���̏o�͒������e�ՂȂ��߁A�Â��V�[���ł̍����x�������サ�A���ʓI�ɃR���g���X�g�䂪�����Ȃ�܂��B
2. 3ch RGB���[�U�[�̍����x�ȐF�Č�
HU710PB�ł́A3ch��RGB���[�U�[�������g���Ă���A����ɂ��ԁA�A���ꂼ��̐F���������x�Ő��䂳��܂��B���̐F�̕��������������Ƃ́A���ɐF�̈Ⴂ�������ł��邽�߁A���邢�����ƈÂ������̃R���g���X�g����������₷���Ȃ�܂��B
RGB���[�U�[�����́A��ʓI�ȃv���W�F�N�^�[�Ŏg����z���C�gLED����v���������F�̃s���A�����������߁A���Â̋��E����肭������\������܂��B
3. �_�C�i�~�b�N�g�[���}�b�s���O�Z�p
HU710PB�́A�_�C�i�~�b�N�g�[���}�b�s���O�𓋍ڂ��Ă���A����͉f���̊e�t���[�����Ƃɖ��Â��œK������Z�p�ł��B����ɂ��A�f���S�̂̃R���g���X�g�����A���^�C���Œ������A���邢��������т�������A�Â��������Ԃꂽ�肷�邱�Ƃ�h���܂��B
�_�C�i�~�b�N�R���g���X�g�@�\������ƁA���邳�ƈÂ������o�����X�悭�\������A�����ڏ�̃R���g���X�g�����サ�܂��B
4. �����Ȍ��w�v�ƃ����Y���\
HU710PB�́A���w�n�̐v�������ŁA�����Y�̉𑜗͂���̎��������������Ƃ��A�f���̍ו�����������\�����邽�߂̑傫�ȗv���ł��B�����Y�̐��x�������قǁA���̎U�������Ȃ��A���Â̋��E���ڂ₯���A�R���g���X�g���ێ�����܂��B
�����x�̃����Y�ɂ���āA���̎U�����}�����A�Õ������Â��\���ł��邽�߁A�l�C�e�B�u�R���g���X�g�����サ�܂��B
5. �Î��ł̌��ʓI�Ȏg�p
�l�C�e�B�u�R���g���X�g�䂪1200:1�Ƃ������l�́A���Î��ł̎g�p���ɍł����ʓI�ɔ�������܂��B�Î��ł͊O�����̉e�������Ȃ��A�v���W�F�N�^�[�{���̃R���g���X�g���\���t���Ɉ����o�����Ƃ��\�ł��BHU710PB�̂悤�Ƀ��[�U�[������p�����v���W�F�N�^�[�́A�Õ��̕\�������݂ŁA���������S�ɈÂ����邱�Ƃł��̔\�͂��ő���ɔ������܂��B
---
�܂Ƃ�
LG HU710PB�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g��1200:1�ƍ����̂́A���[�U�[�����̐����Ȍ�����ARGB���[�U�[�ɂ��F�̃s���A�ȍČ��A�_�C�i�~�b�N�g�[���}�b�s���O�ɂ�郊�A���^�C���̖��Ò����A���w�n�̐v����ȗv���ł��B�����̋Z�p���g�ݍ��킳��A���Â̕\���͂��D��Ă��邽�߁A�l�C�e�B�u�R���g���X�g�䂪�����Ȃ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25913285�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������
65�C���`�L�@TV�Ɣ�ׂđ��F�Ȃ����A�l�Ԃ̎��o�\�͓I�Ƀl�C�e�B�u�R���g���X�g�͂ǂ��܂Ŏ��ʂł���̂�
��AI��
�l�Ԃ̎��o�\�͂ɂ����āA�R���g���X�g�̎��ʂ͈��̌��E������܂��B���Ƀl�C�e�B�u�R���g���X�g�Ɋւ��ẮA�v���W�F�N�^�[��e���r�Ȃǂ̉f���@��Ŏ�����鐔�l�ƁA�l�Ԃ����ۂɊ������鍷�ɂ̓M���b�v������܂��B
1. �l�Ԃ̎��o�ɂ�����R���g���X�g�F��
�ʏ�A�Â��ꏊ�ł̎��o�R���g���X�g�́A�l�Ԃ̊Ⴊ���ɕq���ɔ������܂��B�ł����A1,000:1�ȏ�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g�Ɋւ��ẮA���o�I�ɂ���قǖ��m�ȍ��������邱�Ƃ͓���Ȃ�܂��B�����̐l��3,000:1-5,000:1�̃R���g���X�g�����ƁA����ȏ�̍������o�I�Ɏ��ʂ���͓̂���Ƃ���Ă��܂��B
�f���R���e���c�̍Đ����ɂ����āA�Î��̂悤�Ȋ����ɈÂ����ł͍����R���g���X�g�䂪���ʓI�ɔ�������܂����A�����̌��┽�˂ɂ���Ď��ۂɌ�����R���g���X�g�͒ቺ���܂��B
2. �l�C�e�B�u�R���g���X�g vs. �_�C�i�~�b�N�R���g���X�g
�l�C�e�B�u�R���g���X�g�́A�@�킪��ʏ�œ����ɍł����邢���ƍł��Â������ǂꂾ���Č��ł��邩�������w�W�ł��B����ɑ��ă_�C�i�~�b�N�R���g���X�g�́A�f�����ƂɃo�b�N���C�g������𐧌䂵�A�R���g���X�g�����コ����Z�p�ł��B�l�Ԃ̎��o�́u�u�ԓI�Ȗ��Â̐�ւ��v��u�V�[�����Ƃ̃R���g���X�g�v�ɕq���ɔ������邽�߁A�_�C�i�~�b�N�R���g���X�g�̌��ʂ̕������o�I�ɂ͑傫���Ɗ������邱�Ƃ������ł��B
�Ⴆ�A�L�@EL�e���r�ł͖�����̃R���g���X�g�i�^�̍���\���ł���j�ƌ����܂����A���o�I�ɏd�v�Ȃ͉̂f���S�̂ł̃R���g���X�g�̃o�����X�ł��B
3. 65�C���`�L�@EL�e���r�ƃv���W�F�N�^�[�̈Ⴂ
65�C���`�̗L�@EL�e���r�́A�������^�̉�ʂȂ̂ŁA�s�N�Z���P�ʂŃo�b�N���C�g�𐧌䂵�A�^�̍��������ł��܂��B���̂��߁A���ɈÂ��V�[���ł̃R���g���X�g�Č��͔��ɗD��Ă��܂��B
���āA�v���W�F�N�^�[�i�Ⴆ��LG HU710PB�j�͊O�������˂�����^�C�v�Ȃ̂ŁA���S�ȍ����Č����邱�Ƃ͓���ł��B�������A�v���W�F�N�^�[���D��Ă���_�́A�Î��Ȃǂ̓K�Ȋ��ł͉f�����傫���Ȃ邱�ƂŁA���o�I�ȃC���p�N�g�������A��r�I�Ⴂ�R���g���X�g��ł����o�I�ɖ����ł��郌�x���ɒB���܂��B
4. �R���g���X�g���ʂ̌��E
�l�Ԃ̎��o�́A���邢�����ƈÂ������̍��ɑ��ĕq���ł����A�������ɏ��Ȃ������i�Õ��j����ɖ��邢�����i�n�C���C�g�j�ł́A������x�͈̔͂���ƍׂ����ω������ʂ��ɂ����Ȃ�܂��B
��ʓI�ɂ́A10,000:1�ȏ�̃R���g���X�g��́A�����̐l�ɂƂ��Ď��o�I�ɂقڋ�ʂ����Ȃ��ƌ����Ă��܂��B�]���āA�Ⴆ��1200:1�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g��3000:1�̃R���g���X�g��̈Ⴂ�́A�����ȃV�[���ł͎��ʂł���ꍇ������܂����A���I�ȍ��������邱�Ƃ͏��Ȃ��ł��B
---
���_
LG HU710PB��1200:1�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g�́A�Î��ł̎����ɂ����Ă͔��ɗD�ꂽ�p�t�H�[�}���X�����A65�C���`�L�@EL�e���r�ɕC�G����N�I���e�B����܂��B�������A�l�Ԃ̎��o�I�Ȏ��ʔ\�͂̌��E���l����ƁA�R���g���X�g�䂪���I�ɍ����Ȃ��Ă��A�K�ȉf�����ł���Ώ\���ɔ������f�����y���ނ��Ƃ��ł��܂��B
�����ԍ��F25913289�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
1,��3,�̓_�C�i�~�b�N�R���g���X�g�̂��Ƃ������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F25913294
![]() 0�_
0�_
������
�l�C�e�B�u�R���g���X�g�̎��_�ɍi���Ă��肢���܂�
��AI��
�l�C�e�B�u�R���g���X�g�ɏœ_���i��ALG 710PB�A�l�C�e�B�u4K�v���W�F�N�^�[�A�L�@EL�e���r�Ƃ̔�r���s���܂��B
1. �l�C�e�B�u�R���g���X�g�̔�r
LG 710PB: �l�C�e�B�u�R���g���X�g 1200:1
710PB�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g���1200:1�ł��B����̓v���W�F�N�^�[�Ƃ��Ă͒����x�̃R���g���X�g�ŁA�Î��ł�����������̍����x�����Č��ł��܂����A���̕\���͂͂�������邱�Ƃ�����܂��B���ɈÂ��V�[���ł́A�������O���[�Ɍ�����\��������܂��B
JVC DLA-V900R: �l�C�e�B�u�R���g���X�g 100,000:1
JVC��DLA-V900R�́AD-ILA�Z�p���̗p���Ă���A���ɍ����l�C�e�B�u�R���g���X�g���ւ�܂��B�Î��ł́A���ɐ[�����ƍ����_�C�i�~�b�N�����W���������A�Â��V�[���ł̃f�B�e�[���≜�s�������|�I�ɕ\�����邱�Ƃ��ł��܂��B���̃N���X�̃R���g���X�g��́A�v���W�F�N�^�[�̒��ł��ŏ�ʃ��x���ł��B
JVC DLA-Z7: �l�C�e�B�u�R���g���X�g 50,000:1
DLA-Z7��D-ILA�Z�p���g�p���Ă���AV900R�ɂ͋y�Ȃ����̂́A�l�C�e�B�u�R���g���X�g��50,000:1�Ɣ��ɍ����ł��B���̕\���͂��D��Ă���A�Î��ł̉f��ӏ܂ɂ͏\���Ȑ��\�������Ă��܂��B
JVC DLA-Z5: �l�C�e�B�u�R���g���X�g 30,000:1
Z5��DLA�V���[�Y�̒��ŃG���g���[���f���ł����A30,000:1�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g���ւ�܂��B�Î��ł̎g�p��O��Ƃ���A�\���ɐ[�������Č��ł��邽�߁A�f���̃f�B�e�[����Â��V�[���ł̕\���͂������ł��B
�L�@EL�e���r: ���_��̃l�C�e�B�u�R���g���X�g�͖�����
�L�@EL�f�B�X�v���C�́A�s�N�Z�����ƂɓƗ����Ĕ����E�������\�Ȃ��߁A���S�ȍ���\���ł��A���_�㖳����̃R���g���X�g����������܂��B�Â��V�[���ł̍��̍Č����͑�z���Ă���A���̋Z�p�ł͒ǐ��ł��Ȃ����x���̃R���g���X�g����܂��B
2. �l�Ԃ̎��o�ƃl�C�e�B�u�R���g���X�g�̎��ʔ\��
�l�Ԃ̖ڂ����m�Ɏ��ʂł���R���g���X�g�̏���͂����悻3000:1���x�ƌ����Ă���A�������ƃR���g���X�g��̍���������͍̂���ɂȂ�܂��B�������A���ɈÂ������Ō���ꍇ�A���ɈÂ��V�[���ł̍��̐[����O���f�[�V�������A�R���g���X�g�䂪�����قǐ����ɕ\������܂��B���̂��߁ADLA-V900R��L�@EL�e���r�̂悤��10��:1�ȏ�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g�����f�o�C�X�ł́A�Â��V�[���ł̔��ׂȃf�B�e�[���⍕�̉��s�����ۗ����܂��B
3. ���_
LG 710PB: �l�C�e�B�u�R���g���X�g1200:1�́A�v���W�F�N�^�[�Ƃ��Ă͒����x�ŁA�Î��ł��������x�����ł��鍕�̍Č��͂���܂��B�������A�L�@EL�⍂���l�C�e�B�u4K�v���W�F�N�^�[�Ɣ�r����ƁA�Â��V�[���ł͍������Ȃ�܂��B
JVC DLA�V���[�Y: ����DLA-V900R��100,000:1�͈��|�I�ȃR���g���X�g��ŁA�Î��ł̎����ɂ����Ĕ��ɍ������̍Č��͂ƈÂ��V�[���ł̕\���͂���܂��B���i���������߁A���ɂ̃z�[���V�A�^�[��Nj����郆�[�U�[�����ł��B
�L�@EL�e���r: ������̃l�C�e�B�u�R���g���X�g�ɂ��A���̕\���͂ɂ����Ă͑��̋Z�p�����|���܂��B�������T�C�Y�ł̎����ł͓��ɈÂ��V�[���ł̉��s����f�B�e�[�����ۗ����܂��B
���̂悤�ɁA�l�C�e�B�u�R���g���X�g�̊ϓ_�Ŕ�r����ƁA�L�@EL�e���r��n�C�G���h�v���W�F�N�^�[�iDLA-V900R�Ȃǁj�̕������̍Č��͂ł͗D��Ă��܂����A710PB�����i�ɑ��Ă͏\���Ȑ��\�������A���ɈÎ��ł̎g�p�ɂ͓K���Ă��܂��B
�����ԍ��F25913304�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���ۂɂ́A������Ŕ�r���Ȃ��ƁA�n�b�L���Ƃ����Ⴂ�͕�����Ȃ��ł����A����ȏ�̐��\�͂���Ȃ����ł�(��
�����ԍ��F25913336�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
JVC�̃l�C�e�B�u�R���g���X�g����̃��r���[�T�C�g�ł̓J�^���O�l��1/5���炢�̂悤�ł��ˁB
�V�l�X�R�̉f��𓊉e���āA�㉺�̍��тƁA����̃X�N���[���̃u���b�N�}�X�N�Ƃ̍����C�ɂȂ�Ȃ����x���Ȃ���Ȃ��ł��傤�B
���т��O���[�Ɍ����Ă��܂��Ƃ�����Ɩ��ł����B
�����ԍ��F25913383
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���тƂ̍��́A�����ɔ�r����ƍ��͂���܂����A���ɋC�ɂȂ�Ȃ����x���ł��ˁB
�Q�l
�g�b�v�K��
�����ԍ��F25913428�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Q�l
���̕v�ƌ�������
�F��/�R���g���X�g�͂���ɋ߂��ł��ˁB
�X�N���[���̏㑤�͎��[�������̂ŁA�����ɔ��˂��ď������邭�Ȃ�̂���_�ł��ˁB
�����ԍ��F25913485�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���o���J�^�t�������W����
�R���g���X�g���\���ǂ������ł���
�����ԍ��F25913491
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���肪�Ƃ��������܂��B
�ЂƂ܂�����Ŋy���݂܂��B
�����ԍ��F25913515�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�܂����������A�A�A
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25913598/
�����ԍ��F25913601�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ԐM����200������ƁA���̃X���b�h�ɂ͕ԐM�ł��Ȃ��Ȃ�܂�
�ȑO����A�X�s�[�J�[�̑傫���i��ɒ��̖��j�ƕ����̍L���i�e�ρj�̊W�ɂ��čl���鎖������܂����B�������A��̓I�Ȑ��l�Ɋ�Â��\�L�̓l�b�g��I�[�f�B�I�G���ɂ��w�ǖ����A�l�̊��z���x���ł����l�@���܂����B
��ƂȂ鐔�l�Ɨv�f�i�����j�ł��B
1.���̍L��
���ԁi�{�ԁj�ƒc�n�T�C�Y
2.�e��
�V�䍂�ɂ��Ⴂ
3.�h��
�h�������ƗL��
4.�E�[�n�[�̐�
�V���O�����_�u���E�[�n�[���g���v���E�[�n�[��
5.�X�s�[�J�[�̌`���ƌ`��
�o�X���t������
�u�b�N�V�F���t���g�[���{�[�C���t���A�^��
��L1�`5�͌����ɍl�����A�V���O���E�[�n�[�̃u�b�N�V�F���t����Ƃ��܂��B
���̃��X�j���O���[���i��3.7��×���s��4.7��×�V�䍂2.6���E�h���j�ŁA���̓_����ZENSOR1(�E�[�n�[12����)������JBL�@S-4700�i�E�[�n�[38�����j�܂Ő��@�풮�����o�����猾���܂��ƁA�X�s�[�J�[�̐��\���t���Ɉ����o���ɂ́A���z�I�ɂ̓E�[�n�[���a�̐��l�Ɠ����L���A�Œ�ł��������K�v�ƂȂ�܂��B
��Ƃ��āA16.5�����̏ꍇ�A���z�I�ɂ�16��A�Œ�ł�8��ƂȂ�܂��B
���݂ɁA���̕����͒c�n�T�C�Y�ł͖�12��ɂȂ�܂����A�E�B�[���A�R�[�X�e�B�b�N ��haydn se signature�i�E�[�n�[15.2�����j�̓W���X�g�t�B�b�g�A�������̃��o�C�o���I�[�f�B�I��ATALANTE 3�i������18�����j�͏����ቹ���o�����̌X���ł��B
�݂Ȃ���̑̌��Ɋ�Â����ӌ������҂����Ă��܂��B
![]() 2�_
2�_
gjki����@����ɂ���
�O�X����A�����ƒ��Đ��ɂ��ď����Ă���̂ł����A�̊����܂߂Ėl�������悤�ȍl�����ł��B
�E�[�n�[���a�ƒ��Đ��̓j�A�ł͂Ȃ��̂ł����A���{�̃}���V�����K�i���炷��ƊC�O���̃t���A�X�^���h�X�s�[�J�[�͑傫�������ł���ˁB
B&W���͂��߁A�C�O�̃��[�J�[�́A�i���E���\�Ɋւ��Ắu�V���[�Y�v�ŏ㉺��t���Ă��āA�����V���[�Y���́u�����̗e�ςőI��łˁv���Ċ����ɂȂ��Ă��܂��B���ɂ�����Ə����Ă���̂�B&W�̖{���T�C�g���ȁB
���ɁA�ŏ�ʃV���[�Y�̂W�V���[�Y�́A��ԏ����ȂW�O�T���u�W�V���[�Y�̃G���g���[���f���v���Ă��������������Ă��āA��ԑ傫�ȂW�O�P���u�ŏ�ʋ@��v���Ǝv���Ă���l������̂ł����A�傫�ȊԈႢ�ł��ˁB�Z�p�I�ɂ͂W�O�T�ƂW�O�P����ԋ߂���ł����ǂˁB
�W�V���[�Y�̑I�ѕ��͐���gjki����̏����Ă���P�`3�̏����ɂ��킹�đI�Ԃ̂������B
�X�^�W�I���j�^�[�́A��͂�gjki����̏����P�`�R�ɍ��킹�đI�Ԃ̂����ʂł��B
���i�����ꏊ�Ńj�A�ŕ����j�̂��A�Z�~�t���A�Ȃ̂��A���[�W���j�^�[�Ȃ̂����Ă�ł��ˁB
�̌��k�������Ƃ̂��Ƃł����A�l�̏ꍇ�́A������PC�T�C�h�ɂ����Ă�̂́AGeneLec��8010�ł��B
�����͕n�R�Ȃ̂�5.5���Ȃ��ł����APC�e�[�u���̏�͋������A���X�j���O�̓X�s�[�J�[�ɋߐڂ��Ă���̂ł���ŏ[���ł��B
���Ԃ́A��͂�A�N�e�B�u�Ȃ̂ł����ADYNAUDIO��BM5���g���Ă��܂��B������̓p�[�e�[�V�������g��Ȃ����14��ł����A�W���Z��ł��܂�傫�ȉ��͏o���Ȃ����A�����l�͂��܂肱����肪�Ȃ��̂ł���ŏ[���B�Ƃ����Ă��A���ۂɕ��ʂɉ��y���̂ł���Αш�I�ɂ����ʓI�ɂ����s���R�͂Ȃ��A�ނ���A��������傫��������ז����Ȃ��ƁE�E�E�E����ł��Ƒ�����͎ז������B
�t�ɁA���Ƃ�30��ȏ゠�郊�r���O�i�Ƃ����Ƃ������������ǁA�N��������e��2�l��炵�Ȃ̂ŕǂ����Ȃ��ŁA�u�Q���v�Ɓu���r���O�v��2�����ɂ��Ă���B�j�Ȃ̂ŁA�u���Ă���X�s�[�J�[��JBL4343�ł��B
�����ԍ��F25831107
![]() 11�_
11�_
gjki����
38cm�Ȃ�38��ƌ������͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�X�y�[�X�Ƃ���
�c�B�[�^�[�ƃE�[�t�@�[�i�_�N�g���܂߁j
�Ԋu�ɑ�����������5�{�ȏ�
���ꂾ�ƌ��J��10�x�ȉ��ɂȂ�̂�
���������A�o���o���������Ȃ��Ȃ�ł��傤
���̋����Ő��O�p�`�̌�ɂȂ�
�X�s�[�J�[���E�Ԋu
������t�������W�A
�����a�͎��߂ɋ����ł��B
�����ԍ��F25831149�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 12�_
12�_
��gjki����
����ɂ��́B
��|�Ƃ̓Y���邩������܂��B�B�B
�����̓X�s�[�J�[�ɑ��郊�X�j���O�|�C���g���d�v�Ǝv���Ă��܂��B
�X�s�[�J�[�Ԋu����ӂƂ��鐳�O�p�`�̒��_�������ڂ�LP���Ƃ�Ȃ��ƃX�s�[�J�[���{���������\���ɍČ��ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
������X�s�[�J�[�̏o������X�P�[����傫���L����������A�X�s�[�J�[�Ԋu���L�߂ɁALP�����̕����ڂɎ����Ă���X�e�[�W�͑傫���Ȃ�܂����A���ȏ�L�����Ă����ƍ��x�͏������X�s�[�J�[�ł͉���̖��x���o���Ȃ��A���̐Z���͂��Ȃ������ɂȂ�܂��ˁB�����ő�^�X�s�[�J�[�̓o�ꂩ�ȂƎv���܂��B��������Ăǂ�ǂ��̍L�����傫���Ȃ��Ă���C���[�W�ł��B
�X�s�[�J�[�̎��́i���E�Ɖ��s���j�ɂ���Ԃ����K�v������̂ŁA�����̉����͏d�v�ł��ˁB
���j�b�g�a�ƕ����̍L���ڊ֘A�t����悤�Ȋ��o�͂��܂肠��܂���B
Foolish-Heart�����4343�͈ȑO����F�l��ʼn��x�������@�����A�ƂĂ��ƂĂ������܂����@�ނł����A���������悤�Ƀ��j�b�g���o�b�t�����傫���̂ŕ����̕��Ɖ��s�����K�v�ŁA���ꂱ��30��Ƃ��L���Ȃ��ƁA�����ڂ̎��o���ɑ��ĉ��ꂪ���ꂵ�������܂��ˁB���j�b�g�T�C�Y���o�b�t���ʂ̖ʐςƂ������������܂��B�����������ĕ��������X�s�[�J�[���Ƌ��߂̕����ł��ӊO�ƈ�a���Ȃ���ۂȂ̂ŁB
�����ԍ��F25831151
![]() 2�_
2�_
��Foolish-Heart����A�����́B
�����Ƃ�30��ȏ゠�郊�r���O�`�u���Ă���X�s�[�J�[��JBL4343�ł��B
�L�������ɑ傫���X�s�[�J�[�A�����ł��˂��B
��̎؉ƏZ�܂��̎��A�_�C���g�[����DS-1000HR�����Ƃ̍��~�i�{��16��j�ɒu������A���ꂪ�����X�s�[�J�[���ƌ��ԈႤ�i�����ԈႤ�j�قlj����ς��܂����B
�L���͐��`�ł��B
�����ԍ��F25831480
![]() 4�_
4�_
�������ɂ悵����A�����́B
��38cm�Ȃ�38��ƌ������͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�剹�ʂŖ炷�ꍇ�̗��z�I�ȍL���ł�����B
�����Ƃ��A38��̐�p���X�j���O���[���������Ă���}�j�A�́A������100�l�����Ȃ��Ɛ������܂��B
�����ԍ��F25831486
![]() 4�_
4�_
���v���[���@����A�����́B
���X�s�[�J�[�Ԋu����ӂƂ��鐳�O�p�`�̒��_�������ڂ�LP���Ƃ�Ȃ��ƃX�s�[�J�[���{���������\���ɍČ��ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
���ӌ��ł��B
���O�p�`�̒��_�Œ����ƒ�ʂ̓r�V�b�ƌ��܂�̂ł����A������u���Ԃ���v�̏�ԂŔ��܂��B���̏ꍇ�A���X�j���O�|�C���g�͐��O�p�`�̒��_���1���قnj��ł��B���̂ق�����Ԃ̍L���肪���R�ōD�݂ł��B
�����ԍ��F25831499
![]() 0�_
0�_
gjki����
�������܂�
����38cm�Ȃ�38��ƌ������͂Ȃ�
���a�ŃX�y�[�X�͈�T�Ɍ��܂�Ȃ��̈Ӗ��ł�
�����X�y�[�X�Ƃ���
�����c�B�[�^�[�ƃE�[�t�@�[�i�_�N�g���܂߁j
�����Ԋu�ɑ�����������5�{�ȏ�
�������ꂾ�ƌ��J��10�x�ȉ��ɂȂ�̂�
�������������A�o���o���������Ȃ��Ȃ�ł��傤
�����͉����̑傫�Ō��܂�Ӗ��ł�
�����ቹ�������邽�߂�
�������K�v
JBL4343��z��
�_�N�g�̔����U��25Hz�O��łƂĂ��Ⴍ���O
�c�B�[�^�[�ƃE�[�t�@�[�̎���73cm
5�{�Ȃ�
���E�̃X�s�[�J�[���S���玎������3.5m�͂ق���
�����ʒu�����̕ǂ܂�2m
�X�s�[�J�[���s��0.5m���1m�i�t�����g�_�N�g�j
�����̑O�������7m
�������̋����Ő��O�p�`�̌�ɂȂ�
�����X�s�[�J�[���E�Ԋu
�X�s�[�J�[���E�Ԋu3m
�O�����E��1.5m�ÂƂ���6m
42���āA23��ƂȂ�܂��B
���������܂��A��O�Ȃ甲���Ă��܂��̂�
�����悭����܂���
93dB/W/m�A�ϓ���100W�i2231A�j
SPL113dB�A���y��������ɂ�100dB�ق���
�X�s�[�J�[�Ƃ̎�������10m�܂�
��������110��
�i�ǂ̋z�����ɂ����E���ꂻ���j
�V�䍂���͒�ݔg�̊ϓ_��
�V�䍂��2.6m�Ȃ�E�[�t�@�[��65cm���炢��
�グ�����Ƃ���
��ݔg�ɗL���Ȃ悤�ɁA�Έ䎮�͂��Ȃ荂�����Ă���
�������𐁂������ɂ��Ă��邲�ƒ����������ł��B
gjki������
���X�s�[�J�[�̑傫���ƕ����̍L���̊W�ɂ��āA
����̓I�Ȑ��l�̓l�b�g��I�[�f�B�I�G���ɂ��w�ǖ���
JBL4343����^�Ȃ̂�23�炢�́A
�ق����ɂȂ�܂�����
���ʃT�C�Y�̃X�s�[�J�[�Ȃ�
��ʓI�ȕ����L���ɂ����܂肻���ł�
���ꂪ�w�ǖ������R�ł�
�����ԍ��F25831894�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
��gjki����
����ɂ���
���̍D�݂́@�l���ꂼ��ł�����A���̖��́@����ł��˂��B
���̐������@�Ƃ���ł̃I�[�f�B�I�Đ��́A�������͂���̂�������܂��A
���ꂪ�D�݂ƈ�v����̂Ƃ͕ʖ�肾�Ǝv���܂��B
�܂����݂����ɁA�q�ɕ��u�̂悤�ȕ����ɐݒu���āA����₱���ƍH�v���Ȃ���
�����̗��z�̉��Ɏ����čs���̂�
��̑�햡���Ǝv���Ă��܂����ˁB
�����ԍ��F25832045
![]() 8�_
8�_
�����ɂ悵����A�ڂ����Z�p�I�ɐ������Ă��������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B
�V�䍂���厖���Ƃ͑O����v���Ă��܂����B�}�j�A��K��ŁA�ǂ����������Ă��������͗�O�����V�䍂3���ȏ�ł��B�L�����V�䍂�̂ق����e���傩������܂���B
�����ԍ��F25834605
![]() 4�_
4�_
���I���t�F�[�u���^�[�{����A���͂悤�������܂��B
���o�C�o���I�[�f�B�I��ATALANTE 3�����ɁA�B��C�ɂȂ����̂�18�����E�[�n�[�ł��B�u������Ƒ傫���Ȃ��B�Z�b�e�B���O�ʼn��Ƃ��Ȃ邩�B�v�Ǝv�����̂ł����A��������Ƃ����Ƃ���ł��B���̕����ł͘Z���܂łƔ������܂����B
�l�I�ȍD�݂�l�����͕ʂɂ��āA�u�[���Ȓቹ��������Ȃ�A�X�s�[�J�[�̑傫���i�E�[�n�[�ƃL���r�l�b�g�j�͏������قǗǂ��B�v�����_�ł��B
�����ԍ��F25834623
![]() 3�_
3�_
��gjki����
����ɂ���
REVIVAL AUDIO �@
ATALANTE 3
�����炵�Ă܂��ˁB���̂Ȃ��肪�ǂ���A�ō��ł��ˁB
�m���ɃZ�b�e�B���O�́A�Ă����肻���ł��ˁB
����o�X���t�́A�ĊO�|�C���g���o���̂��A������ł��B
���̕��U�߂������A���肻���ł��ˁB
���̂Ƃ���͎����S�����͈̔͂ŁASP�Ԋu2.5���@��������~�����Ƃ���ł��B
�����ԍ��F25834644
![]() 5�_
5�_
�L���̊��o��ʐςł͂Ȃ��A�e�ςōl����̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�V�䍂���͊m���ɏd�v�ł��B
�悭�A��ݔg���Č��t���łĂ����ł����A���R�ɖʐϓI�ȍL�������ł͂Ȃ��āA���ƓV����W���Ă��܂��B
�ǂ����A�I�[�f�B�I���ĕ���͋@�ނ̂��Ƃɂ��Ă͐F�X�������̂ł����A�����Ƃ��ǍށE���ށE�V��ɂ��Ă͂��܂茾�y���Ȃ��ł���ˁB�W�O�`�X�O�N��Ɋ��Ă����u�I�[�f�B�I�]�_�Ɓv�B�͂��̂������������Ə����Ă���Ă��̂ł����E�E�E�E
�������ڂ̎��o���ɑ��ĉ��ꂪ���ꂵ�������܂��ˁB���j�b�g�T�C�Y���o�b�t���ʂ̖ʐςƂ������������܂��B
���͖{���ɂ������Ǝv���܂��B
4343�͌Â��v�Ȃ̂Œ��̓o�b�t�����ʂŕ⊮����悤�ɂł��Ă��܂��B
���̃X�s�[�J�[�́A�X�^���h�A���[���Ŏg���̂ł͂Ȃ��Ė{���́u�X�^�W�I�̕ǂɖ��ߍ��ށv�̂��������g�����ł��B
�Ȃ̂ʼn��s���͂��̐}�̂̊��ɂ͂��������A�����e�̓t�����g����s���܂��B
�o�b�t�����Q�����ɂȂ��Ă��āA�E�[�n�[�Ə�R����������Ă��ă����e�̍ۂ̓o�b�t�������j�b�g���Ǝ��O����ł���B
���������Ă��܂����AJBL���ăA�����J�����Ȃ��Ƃ��������œ��{���̐������͊F���ł���
���L���͐��`
������A�l�͂��̒ʂ肾�Ǝv���Ă��܂��B
DIATONE��SONY�̂R�O�Z���`�N���X�̃E�[�n�[�𓋍ڂ����X�s�[�J�[���w�̎��ɐH����`���y���Ɏ�������Ŏv������炵�����Ƃ�����̂ł����A�u������̎��͂͂����������v�Ǝv���܂����B
���̌�A���E���z�[������ăI�[�f�B�I�R���T�[�g�Ƃ��o�����Ă��܂����A�ƒ�ŕ����̂Ƃ͒i�Ⴂ�̗ǂ�������܂��ˁB
�o�u���̈�Y�I�Ȏ{�݂����{�S���ɂ���Ǝv���̂ł����A�X�P�W���[�����Ă���Δ�r�I�����Ɏ����̂łR�D�S�O�l�W�߂����Ȃɔ�p���S�����u�I�[�f�B�I�R���T�[�g�v�͂ł���̂ł���Ă݂�Ɩʔ����Ǝv���܂��B
�ȉ��G�k��
�����I�ɖʔ����̂́A�p�C�v�I���K�����ݒu����Ă���L���X�g������B
���������A�p�C�v�I���K���Ȃ�ĂȂ��Ȃ������Ȃ��l�������Ǝv���̂ł����A��悪�����������ǂ��̂Ƃ��̌��ł���̂ʼn����I�ȋ����������Ă���l�͍s���Ă݂邱�Ƃ��������߂��܂����A���m���y�̊�{�̓L���X�g���̗�q�ł�����N���V�b�N���D���ȕ��͗�q�̌o��������͉̂��y�̑��w��[�߂�ɂ��ǂ��Ǝv���܂��B
���݂̓��{�̃J�\���b�N�A������A�v���e�X�^���g�A���������͎����Ƃ��̂����ʉ����ĂĂ���݂����Ȃ�ł����A�@�h�̈Ⴂ�Ŏ�Ⴂ�܂��A�����ɍL�������́u�n��I�v�Ȃ�������̈Ⴂ���łĂ��āA�����̌����āu���D���Ȉꖇ�v���ƂȂɂ�������Ǝv���܂��B�@���Ƃ��ẴL���X�g�������A�����Ƃ��ẴL���X�g���̈�ʂ����w���Ċ����ł��ˁB
�������ƁA�J�\���b�N����q��w�A���{�����������w�A�v���e�X�^���g���R�w�@��w�������āA���ꂼ��̑�w�̓R���T�[�g���q�̓I�[�v�����Ǝv���܂����A�u��q�̋V���v�Ƃ��Ă͂����́u��w�`���y���v�̓A�����W�����Ȃ��̂ł������߂ł����A�{�݂��[�����Ă��܂����A�ςȊ��U���Ȃ��̂ŃI�X�X���ł��B�i���⑼�n���̂��Ƃ͂悭�킩��܂���A���߂�Ȃ����j
AV�A���v�̃G�t�F�N�g�v���Z�b�g�ɁuChurch�v���Ă̂��悭����Ǝv���̂ł����A���o�[�u��G�R�[�A�f�B���C���̋�Ԍn�G�t�F�N�g��������ɂ��Ă���̂��������邩���B
�ґs��搶�A�F��B�v�搶�̖{��ǂ�ŁA�`���y���ɍs���Ă݂�E�E�E�E�E�Ȃ�Ă��������E�����̌���I�I
�����ԍ��F25835110
![]() 6�_
6�_
Foolish-Heart����
���V�䍂���͊m���ɏd�v
2ch�̏ꍇ�͑O��A���A���E�̕ǂ��d�v��
�X�s�[�J�[���牓�����˂����炷�V���
�e�����傫���Ȃ����o�ł�
�V��������ۂ�����̂�
�����ł͂���܂���
AV�ƈ���č���������悤��
��4343�͌Â��v
���o�b�t�����Q����
���A�����J�����Ȃ��Ƃ�������
�@�\�I�Ŏa�V�ȃf�U�C���A�Ռ��I�ł���
�ꌾ�ł����ăJ�b�R����
���ł�������ł���
�����ԍ��F25835159�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
part 70�ɓ˓����܂��B
�@����A�G�k�@���ł�����ł��B
�@�������p�~�����݂����Ȃ�Ł@������̕�������܂��̂Ł@�C�y�ɉ��ł������ėǂ��ł����A������A���u�̒��g���A�������ǂ��q�͎���o���Ȃ��悤�ȃl�^�ɏd�_��u�����������ȃX���ɂȂ�܂��B
�@�ڂ��ڂ��s���܂��傤�B
![]() 5�_
5�_
��BOWS����
����
�X�����Ă��肪�Ƃ��������܂�
��matu85 ����
�ǂ������ł����@���S���܂���
�O�b�h�}��301
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22104899/ImageID=3072226/
�����猩��A�����ʒu�ɒu����
���g���ł�����
�A�L�V�I�����g����
matu85 ������X�s�[�J�[�̜f�r���Ɍ�����
�����낷�����̏���I�Ȃ�@(�l�̍D��)
���j�b�g�������Ă݂���H�@�Ƃ́A�v������ł���
�G�b�W���X�̌��Ԃ͂Q����������܂���
�����f���P�[�g�ł��@�ʐ^�̓R�C����
�Ȃ̂ŁA�Nj��A���v�̂R�v���x��
�]�����߂��������Ǝv���Ă���܂�
�Đ��́A�\�j�[�r�r�c���v���[���[
�m���E�I�[�o�[�E�T���v�����ODAC
�c�`�b���g�����X�h/�u�ϊ� �� �`�s�s
�Nj��A���v���Ŏ��Ԃ��߂����܂�
���}�n�ŐV������������艺����
�R���i�ɂ����Ӂ@�䕗�ɂ�
�Ԋ�n��
���肪�Ƃ��������܂����@�q��
�����ԍ��F25819110
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
�X�����Ă��肪�Ƃ��������܂��B
YAMAHA�̕��́A�G���N���[�W���p�̔�F�X�H���Ă��܂����B
�܂��g�ݗ��ĂĂ͂��܂���B
�H���������̂ŁA�����������ƍS�������ƁA�����Ɏ��Ԃ��o���Ă��܂��܂��B
�����A�~�X����炩���܂����B�܂��A�v���I�ł͂Ȃ������̂ŁAUse as is�ł��B
18mm�ɂ���Ɛ����d���Ȃ�܂��ˁB�d������ʂ̍H���l���Ă��܂������A
���ꂾ�Əd�ʃI�[�o�[������(��)�Ȃ̂ŁA�������Ȃ������ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25819118
![]() 1�_
1�_
��BOWS����
�V�X�����ā@���߂łƂ��������܂��B
�f�W�A���Ɋւ��āA�F�X�ƍ���͂����b�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
���̎��͂�낵�����肢���܂��B
������A�ł�������ƁA���������Ă��������܂��B
�����ԍ��F25819219
![]() 2�_
2�_
�X�����Ă���ꂿ���ł��B
�ʔ������A�Ƒn�I�ȂƂ����X�s�[�J�[���҂��Ă܂��A�R���e�X�g���ʑ҂��Ă܂��B
�V��Ɍ����ă��V�̃I�[�f�B�I�͂قڒf�̗��V�������N���I���܂����B
�����ԍ��F25819318�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�@�G�[�W���O���i�������A�����Ԃ�ǂ��Ȃ��Ă��܂����B
�@�ׂ��������łĂ����Ł@������u��C���v���\���ł��Ă��Ă���Ǝv���܂��B
Arch����
�@OMP600�͉����ǂ���ł����A����͂ł����ɔj�]���܂��ˁB
�@�U�����傫���Ȃ�Ɣj�]����T�^�ł����B
�@�����荢��̂��@Alpair 5V3��MAOP5�̂悤�ȁ@�_���p�[���X�̃��m�T�X�̃X�s�[�J�[�ł��B
�@�_���p�[���Ȃ����߁A�S���͂��キ�ā@�����ʎ��̔��������Q�ɗǂ���ł����A�����Ȃ�@��U�����ɐU�����{�C�X�R�C�������C��H���Ԃ��������Ĕj�����܂��BMAOP�͐U�����@�ׂŔj�������Ńq���q�����̂ł��B
�@�_���p�[������ƍS���͂������Ł@�j�]����O�ɘc��Ł@���낻���ׁ[�ȁ`�@�ƒ��ӂ����ł����A���m�T�X�́@�ق�Ɠ��˂ɔj�]����̂ŕ|���ł��B
�@���ɁA����i�������i�̃X�s�[�J�[���j�b�g���@������̂Ł@�}�E���g�s�\���łɓ݂�����������A��U�����ɋю������^�b�`�����m�C�Y���A�_���p�[��G�b�W�̕s�ψ�Ń{�C�X�R�C�����߂ɂȂ��ă^�b�`�m�C�Y�A�G�b�W�ƐU���̐ڒ����s�\���ő�U�����Ƀo�^���ăm�C�Y���o���肵�������o�����Ă��܂��B
�@�G�[�W���O�ł����A�s�v���Ƃ��A100���Ԃ�����Ƃ����ԓ`�������낢�날��܂����A�C���s�[�_���X�����v��������@fs�̎��g���ƃs�[�N���ς���Ő��l�ł킩��܂��B
�@���J�j�J���I�ȃX�g���X���ɘa�����Ł@���������ʼn��\���ԃG�[�W���O���Ă����܂�Ӗ��͂Ȃ��đ剹�ʂŖ炳�Ȃ��Ƃ��߂ł��ˁB
�@�����ȉ��̎��g���̃T�C���g��剹�ʂłԂ�����ł��ƐU���͐���Ƀu���Ă��邯�lj��͕������Ȃ��̂Ł@�ŋ߂͂������Ă��܂��B
�@�c�B�[�^�[�́A����������Ă���悤�ł����A���Ȃ�30KHz�Ƃ��˂�����Ŗ炷�ƃG�[�W���O���Ă��@�������Ȃ���ŗǂ������ł����A�����Ȃ�ł�肷����ƋC�Â����Ƀ{�C�X�R�C���đ������ŗv���ӂł��B
Foo����
>���ɁA�����Ă��Ȃ��h�b�J���|�[�g�͋��U�������łȂ����ۂɂ͎��ɕt��������R��Ă��܂����A���a�艹���C�ɂȂ肾���Ɗ����܂���ˁB
�@�R�ꒆ�����͋C�ɂȂ�܂��ˁA������x��ł��܂����A���S�ɖh���悤���Ȃ����A�X���b�g�`������Ƀt�F���g�\��Ɓ@�o�X���t�̓���_�������B
�@�Ȃ�ŃJ�b�g�A���h�g���C�����Ȃ��B
�@���艹�́A�|�[�g���̉������v�Z�ł����Ł@�v�ł�����x�J�o�[�ł����ł����ǁA���ʂ��ő剻����Ɖ������オ��܂��ˁB
�@���ɂ���Ə���肪�N���A�ł����ł����ǁAQts���߂̃��j�b�g�Ȃ�Ō����Ȃ����A�����炭�R���y�e�B�^�[�́A�o�X���t���Œ���Ł@�_�u���o�X���t�ABHBS�A�g�����X�~�b�V�������C���A�o�b�N���[�h�Ƃ��ቹ�⋭�����Ă���̂Ł@�R���邽�߂ɍŒ�o�X���t�͕K�{�Ȃ�ŔY�݂ǂ���ł��B
�@�ŁA���씠�ł��낢��������ā@�{�Ԃ̔�����܂��B
��x�݂���
�@AXIOM80�́A���W�I�Z�p�ŃA���v�ŗL���Ȏ��Ƃ����Ȃ�Z���ȉ�������Ă�����Ł@���̈�ۂ�����Ɏc���Ă��܂��B
�@���Ƃ���͎g�����Ȃ����Ƃ������A���ǃl�K�ȓ_�����@�����ꂸ�@���Ԃ�Ői���n�̃��j�b�g���Ă��܂����B
�@���L���͍s���s���ł����A�@��͋Z���@�X�s�[�J�[�@�Ō�������Ɖ������q�b�g���܂��B
�@�G�b�W���X�A�x�[�N�_���p�A�y�ʃR�[���A���S���C��H�̃t�B�[���h�^�Ł@�y�ʃR�[���ŋ��͂����鎥�C��H�Ȃ�Ł@���g�����オ��Ƙ_���ʂ�@�\����6dB/oct�ŏオ���Ă������߁A�n�C�オ��̂��߁A�O�i�Ńn�C�����ɂ��Ȃ��Ǝg���Ȃ��A20cm(�t�������W)�ɂ�������炸�A200L�ȏ�̖��𐄏��Ƃ�������ł����A�������㕨�̂悤�ł��B
�@(30cm�̃E�[�t�@�[������܂��B�����̉��i 40���~)
matu85 ����
�@�O�b�h�}���̂悤�ȌÓT���j�b�g�͎g���Ă݂����Ǝv���A�]�T���Ȃ��Ď����Ă��܂���B
�@���̂����A���_��A�Ŏg���Ă݂����ł��B
�@�̎g���Ă����@�p�C�I�j�A��PIM-16�͓��肵�ā@���܂ɕ��ʃo�b�t���ŕ����Ă܂��B
�I���t�F�[�u���^�[�{����
�@�Z�����ď������ݕp�x���ቺ���Ă܂����A��낵�����˂������܂��B
�
�@�f�̗������ł����@���炢�ł��B
�@�ϔY���Q�����Ă��Ł@���낢�둝�������Ł@���f�����i���W�e���݂����ɂȂ��Ă܂�(��)
�����ԍ��F25819538
![]() 2�_
2�_
YAMAHA�̐i���ł��B
��Ƃ͏T�������C���ɂȂ�̂ŁA��C�ɍs���܂�(��)
�����͔ނْ̍f���H�����Ă��܂����B
��{�̓V�i����9mm�ł����A2���\�荇�킹��18mm�ɂ�����̂ł��B
���R�͐F�X����̂ł����A��{�͈����Đ��x���o���₷�������������Ƃł��B
100�ςɍs���ď������������Ă��܂����B
100�ςɂ͂��܂�s���Ȃ��̂ł����A�֗��ł��ˁB
�_�{�ƒ��Ԃ���������ȁA�Ǝv���čs�����炠��܂����B
�l�b�g�ł��ǂ��̂ł����A���������邵��{�\���Ɏg��Ȃ��̂ʼn��ł�OK�Ȃ̂ŁB
���Ƃ̓X�N���[�p�[�Ƃ�������C�p�w���Ƃ������A�ڒ��܂�L����ł��B
8���ɓ�������g�ݗ��Ăɓ��ꂻ���ł��B
��BOWS����
> �G�[�W���O�ł����A�s�v���Ƃ��A100���Ԃ�����Ƃ����ԓ`�������낢�날��܂����A
�l���g�͂���قǃG�[�W���O����������Ƃ��Ȃ��̂łȂ�Ƃ������Ȃ��̂ł����A
�炵�Ă��邤���ɏ������ǂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ͌o�����Ă��܂��B
�����ԍ��F25820099
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
����ɂ���
���̃R���e�X�g
�ǂ����ȒP�ɖ�Ȃ��Ƃ���Ƀ~�\������悤�ŁA
���U�@�ł́A��Ȃ��̂�������Ȃ��ł��ˁB
���U�@�ł��߂Ȃ�E�E�E�E
�����ԍ��F25820111
![]() 3�_
3�_
Arch����
�@�̃J�b�g�܂ł������ł��ˁB
�@�g��ʼn��o������̂��y���݂ł��ˁB
�@�Ƃ���Ł@���j�b�g�̃V���A���ԍ��͉��Ԃł������H
�@�l�̂́@100,101�Ԃ������̂Ł@50�g�͏o�ׂ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�Ƃ������Ƃ́@MJ�t�F�A�o�i�ς�5�g�������@45�g....���`��@�{���������ł��B
�I���t�F�[�u���^�[�{����
�@�m�荇�����Q�����Ă���̂ŕ������Ƃ���A���Ȃ�ǂ��Ƃ����]���ł��B
�@�l�̂������ł����A�G�[�W���O�Ɏ��Ԃ�������̂Ł@�����Ă���ƕ]���ς���Ă���悤�ł��B
�@���j�b�g���ǂ���Ηǂ��Ł@����ۂǏ�肢�g�����Ȃ������Ȃ��Ǝ����]���ł͌��������ʂɂȂ�ł��傤�ˁB
�@
�����ԍ��F25822135
![]() 1�_
1�_
��BOWS����
> �g��ʼn��o������̂��y���݂ł��ˁB
�����ł��ˁA�Ƃ���������̂��߂ɐv���Đ��삵�Ă���悤�Ȃ���ł�(��)
�ŋ߂́A���ꂱ��ϑz���Ȃ��������Ă����ߒ����ʔ����ł����A
���n�߂��獡�x�͈�[�́u���v�ɂȂ����C���ɐ�������܂�(��)
> ���j�b�g�̃V���A���ԍ��͉��Ԃł������H
���o��Ȃ̂Ŗ߂�����m�F���܂��B
���Ȃ��Ƃ��S�D�T�{�̔{���Ȃ�ł��ˁA���m���܂����B
�����ԍ��F25822456
![]() 2�_
2�_
���X�v�[�j�[�V���b�v����
��A�����������Ă���܂��B
> �V��Ɍ����ă��V�̃I�[�f�B�I�͂قڒf�̗��V�������N���I���܂����B
BOWS����ɓ������A���̔ɎQ�����Ă���₽�烂�m�������܂����B
�X�s�[�J�[�V�X�e����7�`8�g���܂������A���j�b�g�͓������炢�c���Ă��܂��B�i���_�̓T�^�j
�Ƃ���m�l���A�f�̗���I����ے肵�Ă��܂����B
���̐l�̌������́u����m�����Ⴑ������Ȃ��B����܂ł͎������y���ށv
�Ƃ������Ƃł����B�܂��A�l���ꂼ��ł���ˁB
�����ԍ��F25822465
![]() 4�_
4�_
��Architect1703����
����ꂿ���ł��B
���_�ȃ��m�����ă��_�Ȃ��Ƃ��Ă��鎞����Ԋy�����ˁA
�ŋ�����M����Ă������Ƃ��y�����Ȃ��ŁB
�����ԍ��F25822619�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��BOWS����
��Architect1703����
�P�O�N�ʑO�A���}�n�̃L�B�[�{�[�h�A�V���Z�T�C�U�[�Ȃ̂�������܂��A
����قǑ傫���Ȃ�1,000X400x200�ʂ̋�̂���o�Ă��鉹�A���\�C���p�N�g�L��܂����B
���̋�̂���z���ł���X�s�[�J�[�X�y�[�X�A����Ȃɑ傫���Ȃ��Ǝv�����A���̍ޗ�����������z�����܂��B
�X�s�[�J�[�A�d�q��H�A���A�S�ĂŊy����\�����Ă��銴���B
����x�݂���
�M�d�ȃA�h�o�C�X�L�������܂��A�@�X�s�[�J�[�̍����A�֎q�ɍ����Ē��x�����炢�ł��A
����̏㉺�A���݂́A�s�\�ɋ߂���Ԃł��B�i�n���̕ǂɃR���N���[�g�{�P�~�J���A���J�[�ŌŒ肳��Ă��܂��j
���}�n�͒��킵�Ă��܂���B
�^��ǁA���w�A���Z�̎v���o�ŏI���ł��B
�ǂ��������]���A�y���܂�ĉ������B
���挩��Ȃ������ł��A�����̃X���Ď��������l�ł��B
�@
�����ԍ��F25822634
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
��[������������@���Y�p�C�ɋ����������o���A������DAC�̌^�ԓ��m�肽���l�ŁA�o�g���^�b�`���肢���܂��B
�X�������肢���܂��B
�����ԍ��F25824959
![]() 2�_
2�_
������
��matu85����
�@���X�s�[�J�[�̍����A�֎q�ɍ����Ē��x�����炢�ł��A
�@�@����̏㉺�A���݂́A�s�\�ɋ߂���Ԃł��B
�����܂Ŏ��̎����ł���܂��ā@���݂܂���
���D�݂̃z�[���������낷�l�ȉ����ɂ�
�ڐ��������ɉ���������A���߂�l�ȉ����ɂ�������������ł�
�Δ̃o�b�t���ʂ��������X�s�[�J�ŁA���I�ɂ͈���Ƃ�����
�v���ł�
DAC�́A30�N�O�̃}���`�r�b�gIC
�莝����ŁA�m���E�I�[�o�[�E�T���v�����O���o���܂���
(���N���b�N��H�͕t���܂���)
DAC�̏o�͂���_�C���N�g�Ƀg�����X�ŁAI/V�ϊ� �� �A�b�e�l�[�^�[
������ŏK�����Ԋ�� (�P���Ń��m)
��������(�o�����X����)�� �o�͂ɂ́A�p�[�}���C�R�A�� 1�F1
�g�����X�Ō��݂ɍ݂�܂�
���ւ̔M���͗ǂ��ł���
�ُ�C�ۂ̗l�ȔM���ǂɂ� ���݂��ɋC��t���܂��傤
�����⋋���\����
�������܂����n�C�h�����o��Ηǂ��ł���
���ז����܂����@�@�q��
�����ԍ��F25826200
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
���j�b�g�̃V���A���ԍ��ł����A400�̌�̉�3���ł���ˁH
478��479�ł����B239�g�ڂł����B�������{��(��)
��g2���~������A500���~�߂�����ł��B
���H�ł����A�������Ă݂�ƑS�R���x�o�ĂȂ��āA�p�e�̏o�Ԃ̂悤�ł��B
���̂��肪�p�e�S�J�ł�(��)�@�{���B���ɉ����l���Ă����Ȃ��ƁB
�ّf�ނ̑g�ݍ��킹�ŋ��U�����U����āA�C�C���ɂȂ邱�Ƃ��F��܂��B
�����ԍ��F25826470
![]() 2�_
2�_
�@����@40�炢����^���ő剹�ʂŖ炵�܂����B
�@���Ԃ��Ă����ȉ����ł������A�����Ɩ�܂����B
�@�������������ꂪ�ǂ��ā@�Ȃ��Ȃ��ǂ������ł����B
�@�������A���������}�n�̃��j�b�g�C�̃o�X���t�����ɓ��ꂽ�V�X�e�����炵����ł����A����̃��x��������Ċ��s�ł����B���炵���\���ɂ��Ȃ������̂ł����B
�@�����炭�@���̃R���e�X�g�H�@���̂��������x���������Ȃ肻���ł��B
Archi����
>���n�߂��獡�x�͈�[�́u���v�ɂȂ����C���ɐ�������܂�(��)
�@�d�オ������҂��ā@�o���オ��܂ł�������y�����ł��ˁB
>478��479�ł����B239�g�ڂł����B�������{��(��)
>��g2���~������A500���~�߂�����ł��B
�@�ő�ł��ˁB
�@�Q�T�O�g�߂��ł����`
�@�����@�ǂ��������@�ǂ��v���[���������r��������܂��ˁB
>���H�ł����A�������Ă݂�ƑS�R���x�o�ĂȂ��āA�p�e�̏o�Ԃ̂悤�ł��B
>���̂��肪�p�e�S�J�ł�(��)�@�{���B���ɉ����l���Ă����Ȃ��ƁB
>�ّf�ނ̑g�ݍ��킹�ŋ��U�����U����āA
�܂��@�悭���邱�Ƃł��B
�p�e�͌����Ȃ��Ȃ�悤�ɐ���r������܂��ˁB
�X�v�[�j�[�V���b�v����
>���_�ȃ��m�����ă��_�Ȃ��Ƃ��Ă��鎞����Ԋy�����ˁA
�@����͊j�S�I�Ȃ��Ƃ�
�@�g�̂Ɉ������̂قǔ��������ł�����˂�
matu85����
>���̋�̂���z���ł���X�s�[�J�[�X�y�[�X�A����Ȃɑ傫���Ȃ��Ǝv�����A���̍ޗ�����������z�����܂��B
Q0���傫�����Ƃ���@�����炭��ʊJ���̃G���N���[�W���ł�����Ȃ�ɓ������Ƃ�O���ɊJ������Ă����ł��傤�ˁB
�@
>��[������������@���Y�p�C�ɋ����������o���A������DAC�̌^�ԓ��m�肽���l�ŁA�o�g���^�b�`���肢���܂��B
�T�{���Ă��Ă��݂܂���B��قǁ@�����Ă����܂����B
��x�݂���
>DAC�́A30�N�O�̃}���`�r�b�gIC
>�莝����ŁA�m���E�I�[�o�[�E�T���v�����O���o���܂���
>(���N���b�N��H�͕t���܂���)
>DAC�̏o�͂���_�C���N�g�Ƀg�����X�ŁAI/V�ϊ� �� �A�b�e�l�[�^�[
>������ŏK�����Ԋ�� (�P���Ń��m)
>��������(�o�����X����)�� �o�͂ɂ́A�p�[�}���C�R�A�� 1�F1
>�g�����X�Ō��݂ɍ݂�܂�
�@����σ}���`�r�b�gDAC�͉��������Ă��Đ����ۂ��Ƃ��������S��������܂��ˁB
�����ԍ��F25828268
![]() 2�_
2�_
YAMAHA�̐i���ł��B
���T�͍\������̉��H�����C���ł����B
�ʐ^�̓o�b�t���̃��j�b�g���t�����ƁA�w�ʔ̃^�[�~�i�����t�����ł��B
��������W�O�\�[�ŊJ���܂����B�z�[���\�[�Ƃ������T�[�N���J�b�^�[������܂����A
����̓W�O�\�[�̗p�ł��B
�J�b�g���Ă���Œ��ɐn���܂�Ă��܂��A�ߏ��̃z�[���Z���^�[�Œ��B���܂����B
���߂Ĕ����̂Œl�i��m��܂���ł������A2����415�~�ł����B�����ď�����܂���(��)
��BOWS����
> 40�炢����^���ő剹�ʂŖ炵�܂����B
> ���Ԃ��Ă����ȉ����ł������A�����Ɩ�܂����B
> �������������ꂪ�ǂ��ā@�Ȃ��Ȃ��ǂ������ł����B
>
> �������A���������}�n�̃��j�b�g�C�̃o�X���t�����ɓ��ꂽ�V�X�e�����炵����ł����A
> ����̃��x��������Ċ��s�ł����B���炵���\���ɂ��Ȃ������̂ł����B
�܂��炵�Ă��Ȃ��̂Łu�Ӂ[��v�A�Ƃ������u�ւ��[�v�Ƃ��������܂���B
FOSTEX��FE�̋��͔ł��o�b�N���[�h�ȊO�ł͑S�R���������Ȃ��i��ɂ����j�݂����Ȃ���ł����ˁB
���C���ď�I�łȂ������������ł����A���̕������x�����x���o�܂��B
���ނƂ��Ă����܂��낵���Ȃ��悤�ŁA�����I�ɂ͍��`���C�X�ł��傤�B���^�V������̓V�i���ł��B
���C��SPF��1×4���炢�����g�������Ƃ�����܂���B
SPF���Z���g�����Ȃ�䖝�o����̂ł����A���x���o�ɂ����i�Ȃ���┽�肪����j�̂ŁA
���������ɂ͎g���܂���B
�����ԍ��F25828730
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
������
�f�W�A���̐Ԋ�Ɠ���DAC�̐Ԋ��
�}���`�r�b�g���ĔR����HDD(SSD��)�v���[���[��
�G���t�@�V�X��������o���Đ̖̂��������܂���
(�����Youtube)
https://youtu.be/s480XNHibeM&t=130
�����āA����ȏ��
�I�[�o�[�T���v�����O�̌��߂�m�鎖�ɐ���܂���
TDA1541A�@DAC �S�{�I�[�o�[�T���v�����O
Digital Filter: SAA7220 ���X
https://youtu.be/kac_Fzyf6qM
NOS�i�m���E�I�[�o�[�E�T���v�����O�j
���́ADAC�̓d�����@MC�g�����X�Ɠ����g�����ŁA
�܂��ɃA�i���O���o
����ŁADAC���X�s�[�J�[������ł�
����ł�
�����ԍ��F25829215
![]() 2�_
2�_
Architect1703����
����{�̓V�i����9mm�ł����A2���\�荇�킹��18mm�ɂ�����̂ł�
�ȑO�A�l�������Ă��܂����A�ǂ������x�I�ɂ������I�ɂ����荇�킹��̂͌��ʂ�����悤�Ɏv���܂��B
�����A���x�o���̂͌��\����Ƃ������Ă��āA�F�l�ƍl�����̂́A��{�͂P�Q�~���`�P�T�~�����ł����āA�˔��o�Ŗ؍ނ��P�ӂ��͂���ēd���g���}�[�Ő��Ċp�����킹�Ă������@�ł��B
���ꂾ�ƁA�p�e�ʼn��H���Ă��Ă��B���܂���B
���łɁA�p��ʎ����ł��܂��B
�����A������Ă��A�ǂ����������Ƃ肫��Ȃ��̂ŁA�\�ʂ������Ȃ�Ƃ����āA�w�ʂŘc�݂��銴���ɂ�����A��ʂ������H�v����K�v���łĂ����肵�܂��B
���̍�Ƃ����Ă��ꂽ�F�l�͖{�Ƃ�����҂Ȃ̂Ŋ�p�ł����A���̎�̍�Ƃɒ����Ă����̂łQ�l�ʼnƋ�Ƃ��h�A�Ƃ��X�s�[�J�[�Ƃ��F�X����܂����E�E�E�E�E�E���̃X�s�[�J�[�́A�����̐E��p�̃X�s�[�J�[�ŁA�R���p�l�ʼn���������ėe�ς��q�������O�Ŋm���߂āA�݂艺���p�ɍ�����̂ł����A�傫�߂̔��������āA���A���r�X�ł����Ȃ���e�ς����߂��̂Ŏ��e�ʂ͂킩��܂���
�ŏ��̓o�X���t�ɂ�����肾�����̂ł����A���̃T�C�Y�ɂ��Ă݂���A�u���̕����i�`�������ł������v�ƂȂ�A���ł��B
PARC�̃E�b�h�R�[���P�O�Z���`�Ŗ����Č��\������������
�]�k�ł����A���̃X�s�[�J�[�̑O��BOSE�P�O�P���ǂ��̃}�����c���Ȃ̃X�s�[�J�[�ł������APARC�ɕς����犳�҂���u���y�������₷���Ȃ����ˁv�ƌ���ꂽ�����ł��A�������A�P�l�����łȂ��A�����̊��҂��炢���āu�ӊO�ɂ݂�ȁA���Ò��̉��y�������Ă�ˁv�ƁE�E�E�E�E�E�E
�����{�����̉�����ƁA�Ƌ�Ƃ��X�s�[�J�[�Ƃ��X�s�[�J�[�X�^���h�Ƃ��A���v�Ƃ��F�X���܂����E�E�E�E�E�E�E
�����ԍ��F25830071
![]() 4�_
4�_
��Foolish-Heart����
> ���x�I�ɂ������I�ɂ����荇�킹��̂͌��ʂ�����悤�Ɏv���܂��B
��I�ɂ������I�ɂ������v���܂��B
���́A�o�b�t���ʂ����͐ڒ��܂ɃX�[�p�[X���g���\�肾�����̂ł����A�~�X�Ŗ؍H�p�{���h�ɂ��Ă��܂��܂����B
��芸�������̂܂܍s���܂���(��)
����̃V�i���́A������[�ނ̗ނł��������肳��Ĉ��������̂ō̗p���܂����B
����̃V�X�e�������̂ɂ��傤�Ǘǂ��ʂŔ����Ă���1,200�~�ł���(��)
���R�~�ł��قǂقǐ��x���o�Ă���悤�������̂Ŕ����܂������A���Ғʂ�ł��B
�\�ʂɏ������������Ă����肷��̂Ő��K�i�Ƃ��Ă͔���Ȃ����̂Ȃ̂ŁA
�\�荇�킹��̂��{���B���̖ʂ�����܂��B
> ���x�o���̂͌��\���
�؍H��Ƃ���ł�鎞�_�œ���ł��ˁB���낢��H�v��������ł����A�������̏����ŁE�E�E(��)
�����ƍ�Ƃ̎茳���������A�����ޗ��ɗ������肵�ē�s��s�ł��B
> ���̍�Ƃ����Ă��ꂽ�F�l�͖{�Ƃ�����҂Ȃ̂Ŋ�p�ł�
����҂���͊�p�ł���ˁB��p�łȂ��Ɩ��܂�Ȃ��ł����A�s���x�Ɋ������܂��B
�����ԍ��F25831157
![]() 2�_
2�_
Arch����
�@���X�Ɛi��ł���悤�ł��ˁB
�@���T�����炢�ʼn��o���ł������ł��ˁB
>FOSTEX��FE�̋��͔ł��o�b�N���[�h�ȊO�ł͑S�R���������Ȃ��i��ɂ����j�݂����Ȃ���ł����ˁB
�@�����܂ŃN�Z������Ȃ��ł����AQ0���߂Ȃ�Ł@�����߂̃o�X���t���A���ǂ��Ŗ炵�ɂ��������Ǝv���Ă܂��B
�@�l�́A�傫�߂̃o�X���t�ɂ��܂��B
>���C���ď�I�łȂ������������ł����A���̕������x�����x���o�܂��B
�@�g���Ɋւ��ẮA�S�����ӂł��B
�@���C�ނ́@�Z�~�i�[�ŕ�������A�F�l��ŕ������@�t�B�f�B���e�B���̖��C�ރX�s�[�J�[���ǂ��̂Ł@�����Ƃ��Ă̓x�^�[���Ȃ��Ǝv���܂��B�E�H���i�b�g�A�n�[�h���[�v���A�}�z�K�j�[�ʼn��������ԈႢ�܂��B
�@���̓_�AMDF�͉����ς��Ȃ���ł����@�Ƃ��Ă��܂�ŁA���̕�����ŁA�ŏ�ʂ����C��
�@�ޖ؎s��Ŗ��C�ނ̔������������Ă܂����A�Q�`�R�N���u���Ă���Ɓ@�����Ă��܂��B��蒼���āA�ɐ��`����K�v�������ā@���̂������ʓ|�A�t�B�f�B���e�B���̔��́@���̖ʓ|������Ă���Ă���̂ō����̂����傤�Ȃ��ł��B
�@����ƁA���C�ނ͍���ă��b�N�X���I�C�������Ŏd�グ�ł���̂Ŋy�ł��B�����������@����܂�l���Ȃ��ėǂ��B
�@�W���ނ������悤�Ȃ���Ł@�P���ł悭�g���܂��B
�@�O�́A���ō���Ē��F�{�j�X�h�����Ă�����ł����A�h�������ʓ|�Ŏ��Ԃ��������ā@�����������ēh���ʂ�������Ł@����A���Ȃ��Ȃ�܂����B
�@�t�@�C�i���X�g�ɂȂ�ɂ͌��h�����d�v���Ă��ƂŁ@������@�{�Ԕ��͏W���ނł��B
�@���̓\�荇�킹�͂�������Ƃ�����܂���B�ʐς̑傫�ȓ\�荇�킹�͓�������Ȃ��Ǝv���ā@����Ă܂���B
�@�����ƍH�삪����ǂ��ł��ˁB
�@������ɂ����ς��h�����(��)
�@����̍H��́A���씠�{�{�Ԕ��A�g���}�[�r�b�g�A�z�[���\�[���@���낢�듹�������ł��������g�[�^���Œl�������Ă܂�.�B�i���j�b�g��͌y���������j.
�����ԍ��F25831664
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
> �T�����炢�ʼn��o���ł������ł��ˁB
���₢��A����͓���ł��B
������ƃw���ȃV�X�e�������ł���̂ŁA�������炪��ςȂ�ł��B
���̂Ƃ���A�̓\�荇�킹���I����āA���j�b�g�ƃ^�[�~�i���p�̌����J���������ł��B
> Q0���߂Ȃ�Ł@�����߂̃o�X���t���A���ǂ��Ŗ炵�ɂ��������Ǝv���Ă܂��B
> �l�́A�傫�߂̃o�X���t�ɂ��܂��B
�����ł����B���̓��^�V���傫�ڂ̃o�X���t��\�肵�Ă��܂��B
�����A������YAMAHA���u�X�s�[�J�V�X�e������v�ƌ����Ă����ꍇ�ɔ����āA�l�������傫���ɂȂ��Ă��܂��B
�d������������̂ŁA�o�b�N���[�h�Ƃ����ǂƂ��A�ł�����͍��Ȃ��ł��ˁB
���C�ނɊւ��Ă͂����Ȃ�ł��ˁB�m���ɓh���̃����b�g�͂���̂ŁA���^�V�X�e���ɂ͗ǂ������Ȋ����ł��B
> �����ƍH�삪����ǂ��ł��ˁB
����̈�Ԃ̃n�[�h���������ł�(��)�@��ԏ��������ɍ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁB
��Əꂪ��[�������Ă���悤�ȃ��b�`�Ȋ��ł͂Ȃ��āA��ǎd���ł�����(��)
> ����̍H��́A���씠�{�{�Ԕ��A�g���}�[�r�b�g�A�z�[���\�[���@���낢�듹��������
> ���������g�[�^���Œl�������Ă܂�.�B�i���j�b�g��͌y���������j.
����܂��A�����ł����B
������͍��̂Ƃ���5�`6��~�ōς�ł��܂��B
�r�b�g�ނ�ؒf�H��ނ͂��Ƃ��Ǝ����Ă������A�����z�肵����ł͂Ȃ��̂ł����A
�R���N���[�g�p�̉��H�H��Ȃ���ʂ葵���Ă����̂ŁB
�\���ɖ{�ԗp�̔����Ă��������ȁB���₢��A�ꔭ�����ł�(��)
�����ԍ��F25831835
![]() 2�_
2�_
��x�݂���
�@SAA7220�L����DAC���ׂ���ł��ˁB
�@���̓���́A���V�A��H�Ȃ�Ł@�悭�킩������ł���
TDA1541���@����A�V���O���N���E���A�_�u���N���E���Ł@�Ⴄ�ƌ�������
�@SAA7220�� PA��PB�@�ňႤ�Ƃ�����������܂���
�@TDA1541��@TDA1540��DEM�����̃}���`�r�b�gDAC�́@��͂�Ȃɂ��ЂƖ���������ł���˂�
Foo����
>�����A������Ă��A�ǂ����������Ƃ肫��Ȃ��̂ŁA�\�ʂ������Ȃ�Ƃ����āA�w�ʂŘc�݂��銴���ɂ�����A��ʂ������H�v����K�v���łĂ����肵�܂��B
�@������S�ۂ���͓̂���ł���ˁB
�@���J�����ȈՓI�ȃ{�[���Վg���Ă܂����A�����[����͐����~���邵�ꏊ�H����
�@�ۃR�m�Ղ��@���[�^�e�[�u���Ƃ����L��ƍH�삪����܂����A�l�i�͂Ƃ������u���ꏊ��....
�@�Γc����̂Ƃ���̍H�쎺�ɂ͋z����t���őS�đ����Ă��āi�؍H���N�����j�@�������A�g�b�v�N���t�^�[���Ȃ��Ɗ��S���܂����B
>�ŏ��̓o�X���t�ɂ�����肾�����̂ł����A���̃T�C�Y�ɂ��Ă݂���A�u���̕����i�`�������ł������v�ƂȂ�A���ł��B
>PARC�̃E�b�h�R�[���P�O�Z���`�Ŗ����Č��\������������
�@�ቹ���ɒ[�ɋ��߂Ȃ���Ζ��ŏ\���Ƃ����P�[�X���������ł�����ˁB
Arch����
>���₢��A����͓���ł��B
>������ƃw���ȃV�X�e�������ł���̂ŁA�������炪��ςȂ�ł��B
�@�ǂ�ȕςȍH�v�Ȃ�������܂����A�����͏o���Ă���̂��y���݂��Ă��Ƃ�
�@�l���A���̎���d���ނ̂ɋ�J���Ă��܂��B
>�����A������YAMAHA���u�X�s�[�J�V�X�e������v�ƌ����Ă����ꍇ�ɔ����āA�l�������傫���ɂȂ��Ă��܂��B
>�d������������̂ŁA�o�b�N���[�h�Ƃ����ǂƂ��A�ł�����͍��Ȃ��ł��ˁB
�@���h�`�@���邱�ƑS�R�l���ĂȂ������B
�@�܂��A����܂�����
>�\���ɖ{�ԗp�̔����Ă��������ȁB���₢��A�ꔭ�����ł�(��)
�@�������`�@����́A���m�̍H�삪�����ňꔭ�{�Ԃ͖����Ł@�����ł��낢�뎎���Ă���{�Ԕ�����܂��B
�@���Ă��@����1�����ł�����@�X�p�[�g�����Ȃ��Ƃ܂����ł��B
�@�ł��AYAMAHA�̃u�����h�͔w�����Ă�����̂́A�悤�킩���X�s�[�J�[���j�b�g��2���~�Ń|���Ɣ�������N���t�^�[���Q�O�O�l�ȏ㋏����Ă̂��т�����ł��ˁB
�@�܂��`�@AKB��CD����Ȃ��ł����A�Q�����t���Ȃ�Ł@�Q������C�������ł��傤����
�@�l�Ȃ@MJ�t�F�A�ɍs���Ă����F�l����u�Q���~�o�����l����v�Ƃ����m�Ă���\�����݂܂�����
�@�\�I�ł́@���̏o�Ȃ��v���[�������̊����x�Ɩ��͓x���L�[�|�C���g�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25832907
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
> �ǂ�ȕςȍH�v�Ȃ�������܂����A�����͏o���Ă���̂��y���݂��Ă��Ƃ�
> �l���A���̎���d���ނ̂ɋ�J���Ă��܂��B�E�E�E�E
> ����́A���m�̍H�삪�����ňꔭ�{�Ԃ͖����Ł@�����ł��낢�뎎���Ă���{�Ԕ�����܂��B
���m�̍H��A����܂��ˁB9mm�\�荇�킹��18m��S�ʂɍ̗p����̂����߂Ăł����A
3��4�͏��߂Ă̗v�f������܂��B�ł��A������낤�Ǝv���Ēg�߂Ă������m���قƂ�ǂȂ̂ŁA
���N�����ăA�^�}�̒��ōH����@���o���オ���Ă��܂����B
�ЂƂ����g���C�A���h�G���[�����Ȃ��ƕ�����Ȃ��Ƃ��낪����̂ŁA�����Ɏ��Ԃ����ꂻ���ł��B
> ����1�����ł�����@�X�p�[�g�����Ȃ��Ƃ܂����ł��B
���^�V�͉ċx�݂��H��ɓ��Ă�\��ŁA8�����{�ɂ͉��o��������X�P�W���[���ł��B
8�����{�܂łɍׂ����Ƃ���̒����������������ł��B
�X�C�[�v�M���Ŏ��g����������̐^������������Ȃ��(��)
�����ԍ��F25833121
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
����ɂ���
Non-Over Sampling DAC
http://sparkler-audio.com/pdf/Note05.pdf
�@�@�@
��l�̋x��
�gTDA1541A Non-Over Sampling DAC�����h
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0428/nishikawa.htm
���������A����non-oversampling DAC�Ɍ����Ă̓��C���g�����X���g�����Ƃ���O��
���}�n�̃��j�b�g��
������܂�����
1541(A)�������ł�����
CD-34�n�̃}���`�r�b�g
7220���g��Ȃ��@NOS�̍ĔR�ł�
����ł́@�q��
�����ԍ��F25833490
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
> YAMAHA�̃u�����h�͔w�����Ă�����̂́A�悤�킩���X�s�[�J�[���j�b�g�E�E�E�E
> �l�Ȃ@MJ�t�F�A�ɍs���Ă����F�l����u�Q���~�o�����l����v�Ƃ����m�Ă���\�����݂܂�����
�����ł��ˁA�ǂ��Ȃ�ł��傤�B
YAMAHA�̓d�q�s�A�m�₻�̑��̓d�q�y���YAMAHA���̃��j�b�g���g���Ă���̂�������܂��A
����YAMAHA���̃��j�b�g���o�����Ƃ����������ƕ|�����̌��������������Ă���悤�ȋC�����܂��B
���^�V��BOWS����̏��ł��̃R���e�X�g��m���ĉ��債����ł����A���肷�邾���̐l������̂ł́H
���肷�邽�߂ɂ͌�����i����̃R���Z�v�g�j���l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA���肵�Ă���C���ς�邩������܂��B
BOWS����قǂ̒m����o���������Ă��i���^�V�̂悤�ȁj�r�����Ƀg���C����ɐl�͐��S�l�ȏア��̂���(��)
���^�V�̏ꍇ�́A�ʔ�����������`�������W����Ƃ��������ł��ˁB
> �\�I�ł́@���̏o�Ȃ��v���[�������̊����x�Ɩ��͓x���L�[�|�C���g�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�d���ł��Ȃ�ł������ł����A�K�v�ȃX�L�����Ǝv���܂��ˁB
�����̂�邱�ƁA��������ƁA�v�������Ƃ�ɉߕs���Ȃ��`����Ƃ����R�~���j�P�[�V�����\�͂��Ǝv���܂��B
�����̔���foo�������Ă����ł���(��)
�����ԍ��F25833868
![]() 2�_
2�_
�������̔���foo�������Ă����ł���(��)
�����H��
�R���e�X�g���Ė����̐l���Ȃ̂ł悭�킩��Ȃ��̂ł����A��������t����Ƃ�����u�����̎v���v�Ƃ��u�_���v���Ƃ�����o���Ēu�����Ȃ����Ċ����ł��ˁB
����̏ꍇ�Ȃ�A�S���b�g�����x�̉����ɓ���ĕ����Ă݂���Ƃ���E�E�E���̃��j�b�g�͉]�X����́A���̃��j�b�g�̎������̗ǂ������������߂ɂ́E�E�E�E�]�X�Ƃ������̂��ȁB
�v�Z�ʂ�̒�悪�o�Ȃ�������u�����āA�����ɒ����o�����Ƃ��������ɁA�y��p�̃��j�^�[�炵������A�����钆��̃��A���e�B���o���`���[���ɂ��܂����v���炢�̂��܂����͓���邩���E�E�E�E�E
�����ԍ��F25834503
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
����ɂ���
�ڑ��[�����@�ɂ�
�����ƈ��ڂƁA�n���_���@����܂����A
���ϒl���Ƃ�Ƃ���A�ǂꂪ�����������Ǝv���Ă܂��H
�������̂Ƃ��ɂł��A�Ԏ�����������B�B�Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F25834505
![]() 2�_
2�_
Arch����
>���m�̍H��A����܂��ˁB9mm�\�荇�킹��18m��S�ʂɍ̗p����̂����߂Ăł����A
>3��4�͏��߂Ă̗v�f������܂��B�ł��A������낤�Ǝv���Ēg�߂Ă������m���قƂ�ǂȂ̂ŁA
>���N�����ăA�^�}�̒��ōH����@���o���オ���Ă��܂����B
�@���߂Ă����A�C�f�A�����H������g������ɂȂ�Ƃ����X����܂�(��)
�@�������Ȃ��������̂Ŏ��씠�Ŏ����܂����B
>�ЂƂ����g���C�A���h�G���[�����Ȃ��ƕ�����Ȃ��Ƃ��낪����̂ŁA�����Ɏ��Ԃ����ꂻ���ł��B
�@���s���Ă����X�L�����x�����オ��܂��ˁB
>�X�C�[�v�M���Ŏ��g����������̐^������������Ȃ��(��)
�@�����̉e���Ƃ������ā@������X�L�����v��܂��ˁB
>����YAMAHA���̃��j�b�g���o�����Ƃ����������ƕ|�����̌��������������Ă���悤�ȋC�����܂��B
�@�s�̂��Ȃ��̂Ŋ��͂���܂��ˁB
>�d���ł��Ȃ�ł������ł����A�K�v�ȃX�L�����Ǝv���܂��ˁB
>�����̂�邱�ƁA��������ƁA�v�������Ƃ�ɉߕs���Ȃ��`����Ƃ����R�~���j�P�[�V�����\�͂��Ǝv���܂��B
�@���`����ł͒ʂ�܂���ˁB
���������L�[�v������ɐ����ăv���[������ā@������}���Ő�������������������w�͂�����B���ꂪ���Д�ł�(��)
��x�݂���
>���}�n�̃��j�b�g��
>������܂�����
>1541(A)�������ł�����
>CD-34�n�̃}���`�r�b�g
>7220���g��Ȃ��@NOS�̍ĔR�ł�
�@�����������Ƃ���ł����A�����ς���邱�ƃ��X�g���ςݏオ���Ă܂��B
�@�����Ԑ�ɂȂ肻���ł��B
Foo����
>�R���e�X�g���Ė����̐l���Ȃ̂ł悭�킩��Ȃ��̂ł����A��������t����Ƃ�����u�����̎v���v�Ƃ��u�_���v���Ƃ�����o���Ēu�����Ȃ����Ċ����ł��ˁB
>����̏ꍇ�Ȃ�A�S���b�g�����x�̉����ɓ���ĕ����Ă݂���Ƃ���E�E�E���̃��j�b�g�͉]�X����́A���̃��j�b�g�̎������̗ǂ������������߂ɂ́E�E�E�E�]�X�Ƃ������̂��ȁB
�@STEREO���̃R���e�X�g��A�̕��X�ɂ��ƁA�R�����̂��ꂼ��̐搶�̋����������|�C���g��D�������Ȃ��������������ā@��������c�{��˂��悤�ɃR���Z�v�g�Ɏd���ނ����ł��B
�@�n�C�����J�[�́A��邱�Ƃ���l���x���ƈႢ�܂��ˁB
�@�����A����́@���̃R���e�X�g�Ȃ�Ŋ���킩���̂ŏ�A���L���ɂȂ�ɂ������ł����A��o�p�̃��W���������̊����x�͋��߂�ꂻ���ł��B
>�v�Z�ʂ�̒�悪�o�Ȃ�������u�����āA�����ɒ����o�����Ƃ��������ɁA�y��p�̃��j�^�[�炵������A�����钆��̃��A���e�B���o���`���[���ɂ��܂����v���炢�̂��܂����͓���邩���E�E�E�E�E
�@��������āA���܂����ƗU�������r������܂��ˁB
�I���t�F�[�u���^�[�{����
>�ڑ��[�����@�ɂ�
>�����ƈ��ڂƁA�n���_���@����܂����A
>���ϒl���Ƃ�Ƃ���A�ǂꂪ�����������Ǝv���Ă܂��H
���[���Ɓ@���R�Ƃ��Ă��ď��s���Ȃ��߉�����悢�̂��킩��܂���B
�ڑ��[�����@�@���Ăǂ��̕��ʁH�@�X�s�[�J�[�P�[�u���̂���
�����͈����[�q�̂��Ƃ��Ǝv���܂����A���ڂ��ā@���{���P�[�u���Ƃ���n�̓˂����R�l�N�^�ɃO�T��Ǝh���C���[�W�������Ԃ�ł����A�ǂ��������Ƃ��Ӗ����Ă��܂����H
�@����ł����ā@�����ƌ����ƁA��ƌ����̂��Ƃ��Ǝv���܂����A�@����g��Ȃ��@���ڂ��P�ԂŁ@�������Q�ԁ@���c���ʼn��ʂł��傤�ˁB
�@���������������Ƃ́@��ƌ�������Ȃ��悤�ȋC�����܂���....
�����ԍ��F25835460
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
����ɂ���
���݂܂���@���S�Ɏ�ꂪ�����Ă܂����B
RCA�R�l�N�^�̎���̘b���o�Ă��܂��āA
���S���̂́A�[�����@�ʼn����ɂǂꂾ�������o����̂Ȃ̂���
���q�˂�������������ł��B�n���_���ƁA�l�W���ߕt�����́A�����Ɍ��������̂ł����A
�����^�C�v�́A�����̂ł��傤���ˁB�ŁA�����ɂ�鉹�̍��́A���Ȃ肠����̂��ǂ����A�Ƃ�������ł����B
���͂��Z�����ł��傤����A�܂���i���o���オ���Ă���A�����߂Ȃǂ���A
�����Ă������������Ǝv���܂��B
�����AQED�Ƃ������[�J�[�ɁA�͂܂��Ă���܂��B
�ł́@���������F��\���グ�܂��B
�����ԍ��F25835670
![]() 2�_
2�_
BOWS����
�����̃R���e�X�g�Ȃ�Ŋ���킩���̂ŏ�A���L���ɂȂ�ɂ������ł����A��o�p�̃��W���������̊����x�͋��߂�ꂻ���ł��B
���[�A����͂����ł���ˁE�E�E�E�E�E�E
�I���t�F�[�u���^�[�{����
QED�������̂Ȃ�A�ʂɂ����Ȃ��Ă��悢�̂ł́H
����ɁA�l�ɕ����Ă��킩��Ȃ��������Ƃ������̂ŁAQED�̃P�[�u���������y���Ɉ����Ɏ����͂ł���̂ŁA�K���ȃ}�C�N�P�[�u�����g����RCA�P�[�u���̊����i�i���c�j�ƁA�����P�[�u���ƃl�W���ߎ��̃v���O���w�����Ē�����ׂ�Ηǂ��Ǝv���܂��B
�I�[�f�B�I�̖ʔ����̂P�́A���Ɂu���z�I�v�Ȑڍ����������Ƃ��Ă��A���́u���z�I�ڍ��v�łȂ������u���I�ɍD�܂����v��������Ƃ��낾�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25836821
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
��Foolish-Heart����
����ɂ���
����i�Ł@�ǂ̒��x�̉������o����̂���
�����������Ă�������������ł��B
�܂��܂���̘b�Ȃ̂ŁA�����߃T�C�g�Ȃǂ���A�����Ă����������
������܂��B�P�[�u���̓}�C�N�P�[�u���ŁA�����^�łȂ��Ă悢��ł��傤���ˁH
�̂͌��\���������Ŕ����Ă����炵���̂ł����A�����߂�����Ǝv���܂���
���q�˂�������ł��B
�����ԍ��F25836891
![]() 2�_
2�_
�I���t�F�[�u���^�[�{����
���P�[�u���̓}�C�N�P�[�u���ŁA�����^�łȂ��Ă悢��ł��傤���ˁH
�������悢�̂Ȃ�A�����P�[�u���ł����Ă݂�悢�̂ł͂Ȃ��ł����H
����1�c�̃P�[�u���̊����i�ƁA�����P�[�u���Ńl�W�~�ߎ��̃v���O�ł����Ă݂邾���ł��B
�}�C�N�P�[�u�����I�[�f�B�I�������C���Ɏg���̂́A�u�����p�P�[�u���v�Ƃ��č���Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B
�l�̏ꍇ�ɂ́A�V�X�e�����̂��̂�RCA��r�����Ă���̂ŕ��ʂ�XLR�[�q�̃}�C�N�P�[�u�����A�t�H�[���[�q�̃}�C�N�P�[�u�����������C���Ɏg���Ă��܂��B
�}�C�N�P�[�u���́A�Q�c�����ƂS�c����������̂ł����A���̐ڍ����ǂ�����̂��͗l�X�ȃp�^�[��������A���̂�����������l�^�Ƃ��Ă͖ʔ����Ǝv���܂��B�����̂܂܁������Ō������Ă��u�v�I�ȂƂ��낪�o�Ă��܂���B�l��ɕ����Ȃ��Ă�������x�͎����Ō����ł���͂��ł��B
�������߃T�C�g�Ȃǂ���A�����Ă����������
����̓P�[�u���́u�̔��T�C�g�v�Ȃ̂��A����Ƃ��u�쐻�T�C�g�v�Ȃ̂ł��傤���H
�����̏��������̂Ȃ�u�I���C�f�v���u�T�E���h�n�E�X�v���Ǝv���܂��B
��������A�u����I�[�f�B�I�P�[�u���v���Ō������������ł��o�Ă��܂��B���i�̊Y������ł��낤�X�����݂Ă��̔��X���A�쐻�T�C�g�����łɑ����o�Ă��Ă��܂��̂ŁA�l�ɕ��������ł͂Ȃ��Ď����Ō������Ă݂邱�Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B
���̂͌��\���������Ŕ����Ă����炵���̂ł����A�����߂�����Ǝv���܂���
�����̂��ƂȂ���A�u�ȂɁv���̂͌��\���������Ȃ̂��킩��ɂ����ł��B
�����Ƃ��Ắu�����Ă邨�X�v�ł��Ƃ�܂����A�u�����P�[�u���v�Ƃ��Ƃ�܂��B
�l�̏ꍇ�ɂ́A�H�t���܂Ŏ��]�ԂłP�T���Ƃ������n�ɏZ��ł���̂ŁA��J�������Ƃ͑S��������ł���ˁB
����ł��A�ʓ|�������Ƃ��A�P�[�u������ʂɔ����Əd���̂ł�����x�̗ʂ��Ƃ��ɂ͒ʔ̂��g���Ă��܂��B
�g���ʔ̂́A���̎��X�ŁA�g���J�Ǝg���Ƃ�������A�I���C�f���g���Ƃ������邵�A�T�E���h�n�E�X��������A���h�o�V�������肵�܂��B
�����Ă�|�C���g��������A�[����������A������ňႤ�l�i��A�I���C�f���݂�Ɓu�P�O���ȏゾ�Ɓ����~�������������v�Ƃ����m�ɏ�����Ă���ꍇ������̂ŁA���̎��X�ł��B
�����R�~�f���Ȃ̂ŁA���̎�̘b��͖L�x�ł��傤�B
�{���Ă���킯�ł��A�C���c�C�Ă�킯�ł��Ȃ��̂ł����A�N���҂ɂȂɂ��\���グ��̂͑�ϐS�ꂵ���̂ł����A�l�b�g�ł�
�u�N���N���v�Ƃ����ԓx�́u�l�`�P�b�g�ɔ�����v�ƌ�����s�ׂł����A���������j�b�`�Șb��͂��u���ȐӔC�v�̋����l�^�ł��̂ŁA�l�ɕ����O�Ɏ����Œ��ׂāA���ׂĂ��킩��Ȃ��A���̃T�C�g�̐^�U���킩��Ȃ��Ƃ������Ɂu��̓I�v�ɘb�������Ă��ꂽ�ق���������܂����A���̕�����x��������̂ŁA�����g�ɂƂ��Ă��L�v���Ƒ����܂��B
����ɐ\���܂���A�P�[�u���ɂ��Ă̘b���͖l�Ƃ����ɂ悵����́A�I���t�F����̗��Ă��X���ł����y���Ă��܂���ˁB
��̂̐l���I�[�f�B�I����ɂ���Ɓu�P�[�u�����v�ɂ͂܂��Ă����̂ł����A������x�n�}��ƁA�u���ʂ̓����v������ς�ǂ��ɂȂ��Ă�����ł����A�����ɂ��ď����Ă��āA�����ɂ悵����R���Z���T�X�Ă��܂��B
���ǂ́A�����₷���A�N�Z�̖������m���ǂ����ĂƂ���ɍs�������Ƃ������A���ɂ��ׂ����Ƃ��������ƂɋC�����Ă��������ł��ˁB
���̂�����́A���������R�Ȃ��͂Ȃ��̂ł����A�̌��E�̊��̕����������āA��������u���ꉻ�v�����S�ɂł��Ȃ��ꍇ������܂��B
�Ȃ̂ŁA�j���A���X���ǂ��`����̂������Ȃ�H�v���Ă��āA���̂��߂ɕ��͂������Ȃ邱�Ƃ͂����āA�u���[��v�Ǝ����ł��v�����Ƃ͂���̂ł����A�����������Ƃ��Ắu���̃t�B���^�[�v�Ƃ��č�p�����Ă���������܂��B
������Ɠǂ�ł���Ă���̂��A�����Ŏ����Ă݂�l�Ȃ̂��A������ɂ��t�B�[�h�o�b�N�������l�Ȃ̂��E�E�E�E�E�E�E������ƒm���I�ȕ⊮�����Ă����l�Ȃ̂���
�I�[�f�B�I��Ȃ�āA���͂������j�b�`�ȕ���ł�����A�ł��邾�����D�̐l�Ƃ͏�肭����Ă��������Ǝv���܂����A��肭�s���ė~�����Ǝv���Ă���̂ŁA�����g�̂��߂ɂ��A��������
����x
�������Ă���������Ə�����Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F25837969
![]() 4�_
4�_
�I���t�F�[�u���^�[�{����
�@�ȉ��͂����܂Ŏ����ň�ʓI�ɓK���ł���b�ł͂Ȃ��Ƃ��f�肵��������
�@�l�W�~�߂̃P�[�u���́A�o�ߎ��ԂƂƂ��Ɋɂ�A�\�ʎ_������̂Ł@������肵�܂���A�͂t���P�[�u���͐ڍ���Ԃ��l�W�~�߂����肵�܂��B
�@�ł��A�n���_�̕��������ǂ����͉��L�̗��R�ʼn��Ƃ������܂���B
>����i�Ł@�ǂ̒��x�̉������o����̂���
>�����������Ă�������������ł��B
�@�����́A��Փx�����ł���B
�@�������̂́A�͂t�����邾���Ȃ�ŗe�Ղł����A�]���ƂȂ�Ɠ���ł��B
�@���̂��Ƃ����Ɓ@�ǂ̃��[�J�[�̂ǂ̌^�Ԃ̂ǂ�ȍ\���̃P�[�u�����g�����Ƃ����ގ��I�Ȗ����A�N����邩�Ƃ������l���̕����傫������ł��B
�@�ȑO�A�����P�[�u���A�����R�l�N�^���g���ā@4�l�œ����P�[�u�����͂t�����đ����Ē�����ׂ���ł����A�����ɑS�������Ⴂ�܂����B
�@��肢�l���͂t������Ɓ@�������Ȃ��悤�ȃf�B�e�B�[�����o�Ă��ā@�������C���̕\�����Z���Ȃ�܂��B�������@���{�����Ă������悤�ȉ�
�@����Ȑl���͂t������Ɓ@�f�B�e�B�[�����������x�^�b�ƕ��ʓI�ȉ��������ɁA���x�ɉ����ς��܂��B
�@�������A�R�l�N�^�ɑ��ăP�[�u�����͂t�����邾���ł����A�ǂ�����M�`�����̍������̉�Ȃ�Ł@�����ƒ[�q���ɑ���\�M�̗^�����A�ڍ��̃^�C�~���O�A���c�̏悹���ƗʂƗ����^�C�~���O�A��p�̂����Ł@�~�N���Ȉَ�����̊E�ʂ̐ڍ���Ԃ��ς��̂Ł@���ꂪ���Ɍ���܂��B
�@���̗ǍD�Ȑڍ���Ԃ����̃��x���ȏ�ɏ�ɕۂ̂͘r���v��܂��B
�@�Ȃ̂Ł@�ǂ��̒N���͂t�������킩���P�[�u���́A�����ǂ������Ƃ��Ă��@���ɔ������Ƃ��̍Č�������܂���̂Ł@�]���ɒl���܂���B
�@�����ȃP�[�u���͗ʎY�H�ƓI�Ȏ�@�ō��ꂽ�P�[�u���Ǝv���܂��B
�@�����i�P�[�u���́A�����͂t���̃X�L��������������̃G���W�j�A���͂t������̂Ł@�N�I���e�B���S�ۂ���Ă���Ǝא����Ă��܂��B
�����ԍ��F25838045
![]() 5�_
5�_
��BOWS����
����ɂ���
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
��͂�A�{�H����l�Ł@�����ɍ��������邭�炢�ɏo�܂����B�B
�m���ɐ���~�̃P�[�u���Ɋւ��ẮA�����ɂ��������̂�������Ȃ��ł����A
���������܂Œ��ӂ��Ē������Ƃ��P�[�u����ς��Ď��������Ƃ��Ȃ������̂ŁA
�Ⴂ���킩��Ȃ������̂ł����A
��͂�A����̏ꍇ�́A�ɒ��Z�g�����̓����[���Ɏ������ʂ��ł�悤�ł��ˁB
���ׂĂ��邤���ɁALAN�P�[�u�����A�S�c���ɕ����āARCA�v���O���쐻�����肵�Ă���l��
���܂����̂ŁA��������Ƃ����̂́A���������ł����B�B
�R�l�N�^�͑����̔����Ă���T�C�g�������܂����̂ŁA��̓P�[�u���̑I��ł����A
�������������W�߂āA���߂Ă݂����Ǝv���܂��BLAN�P�[�u���g�p�������́A���悪������L�ѐ�Ȃ���
����������Ă܂����B
���Z�������@�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B
BOWS������@���}�n�̕��A�撣���Ă��������B
�X���ł�����ˁB��ЂƓ���ł��ˁB
�����ԍ��F25838208
![]() 2�_
2�_
�@���}�n�̃t�������W�̉����i���씠�j��i�߂ā@�X�e���I�ŕ�����悤�ɂȂ�܂����B
�@����������������ȓ����\���Ȃ�ŋ�C�R��}�~�̂��߂ɗ{���e�[�v�x�^�x�^�\���Ă��ā@�J�b�R�����ł�(��)
�@�ł��A���͂����������͂Ȃ��ł��B
�@����YAMAHA�̃��j�b�g�@�������͋�FE�V���[�Y�݂����Ȃ�ł����A����ȑe�����ł͂Ȃ��A�f�B�e�B�[���\�����ǂ��ā@�������C�����������i�n�C�G���h�L�H�j�������܂��B
�@���܂܂Ł@�_���p�[���X�Ŕ��������ˏo����Alpair 5V3���x�X�g�Ƌ^��Ȃ�������ł����A�����Ă��܂����B
�@���܂ō���Ă��������a�t�������W�X�s�[�J�[�̒��Ńg�b�v�N���X�̉����o�Ă܂��BYAMAHA����ׂ�
�@�{�ԗp�̃A�J�V�A�W���ނ̔��̍쐻�ɂƂ肩�����Ă��Ďd�グ���ĂȂ�Ƃ��Ԃɍ������ȁ`�@���ĂƂ��ł��B
�����ԍ��F25854795
![]() 5�_
5�_
��BOWS����
����ɂ���
���X����J�l�ł��B
���Ȃ芮���ɋ߂Â��Ă��܂����ˁB
��������A���T�����肩�瓮���n�߂�\��ł��B
RCA�A
SP
�P�[�u�������Ɋւ��ẮA��]�̂�����̂������̂ł����A
����Ɋւ��ẮA���܂�o�Ă��Ȃ��ł��ˁB
YAMAHA�̃��j�b�g���A�{�̔������n�߂��悤�ŁA�Ȃɂ��ł��B
�����@���삵�Ă���l�������悤�ŁA�l�b�g���[�N�Ɏg�p����
�R���f���T��R�C�������Ȃ�g�p���āA�����Ă��܂������A
�قڑ�����Ԃł��B�������R���ɂȂ邩������܂��A�Ȃ�Ƃ��ʉ߂��Ă���������悤
�F���Ă���܂��B
�܂������̂ŁA�̒��Ǘ����C��t���Ă��������B
�����ԍ��F25854946
![]() 2�_
2�_
YAMAHA�̃��j�b�g�A���̂������E�E�E�E�E�E
�ǂ����A���낢��ȂƂ���ł��̃��j�b�g�̘b��ɂȂ�ƁA�|�C���g�̓��j�b�g�̌Œ�̏��A�e�ς͂V�`�P�Q���b�g���B
�y��̉���\���������E�E�E�E�E�g���؍ނ͕����ނŁA�A�J�V�A�A�o�[�`�����g��������B���ƍd���Ȗ؍ނ��ǂ������B
�ǂ����A�M���ւ̔��������Ȃ�ǂ������ł��ˁB
�o�X���t�n�́A�|�[�g�̎G���������Ă�����H�v������B������R���h���A���؉����Ȃ�ׂ��o���Ȃ��悤�ɍH�v����B�Ȃ��ɂ́A�G���W���̏W���ǂ݂����ȃ|�[�g������l�����܂��˂���
���́A��^�\�t�g�ŃX�s�[�J�[��pCAD������̂ŁA�v�����ƊȒP�Ȃ�ł����A���ꂾ����PC���g�����v�V�~�����[�V�����𗘗p���ăX�s�[�J�[�����ƁA�A�i���O�I�ȁu���U�v�̍����o�Ă��܂��ˁB
�X�s�[�J�[�H��̖ʔ����́A������Ƃ����A�C�f�A�Ƃ��A������Ƃ����H�v�����ł��Ȃ艹���ς�邱�ƂŁA���ɋ��x�E�����͐ڍ��ʂ̍H�v�ő傫���ς��̂Łu�������́v�I�ȍH�삪�ł���z���߂��ɂ���Ƃ�����ł���˂�
��肢�l���āA�S�T�x���킹�ŁA�p�Y���݂����Ȑ���ɂ��č��킹���Ⴄ��ł���ˁB���炩�ɒ�悪�Ⴄ�E�E�E�E�E�E
�����⋭���}�g���N�X�\���قǂł͂Ȃ����ǁA�y��̍����̂悤�ȍH�v������l�����āA�u�����̊��o�v������l�����ƃn�}��܂��ˁE�E�E�E�����\�����A�������g���ĕ��ʂ������Ă���E�E�E�E�E�E
���j�b�g�ɁA�j�b�g�X�q�����Ԃ��ċz���Ȃ�Ă̂�������Ȃ��E�E�E�E�E�E�E
�����ԍ��F25857037
![]() 3�_
3�_
YAMAHA�̃��j�b�g�́@�Ȃ��Ȃ��̈�i���Ǝv���܂��B�����炭�������ā@���C�ɂȂ��Ă���Q���҂��������ł��B
>�ǂ����A���낢��ȂƂ���ł��̃��j�b�g�̘b��ɂȂ�ƁA�|�C���g�̓��j�b�g�̌Œ�̏��A�e�ς͂V�`�P�Q���b�g���B
>�y��̉���\���������E�E�E�E�E�g���؍ނ͕����ނŁA�A�J�V�A�A�o�[�`�����g��������B���ƍd���Ȗ؍ނ��ǂ������B
>�ǂ����A�M���ւ̔��������Ȃ�ǂ������ł��ˁB
�@���H���A���x�A�����A�b�v�A�����̗ǂ��A�d�グ�̊y���̂��߂Ɂ@20mm�A�J�V�A�W���ގg���܂������A������15mm�����������o�[�ɔ�ׂ�Ɓ@�i�Ⴂ�̏d���ł��B
>�o�X���t�n�́A�|�[�g�̎G���������Ă�����H�v������B������R���h���A���؉����Ȃ�ׂ��o���Ȃ��悤�ɍH�v����B�Ȃ���
>�́A�G���W���̏W���ǂ݂����ȃ|�[�g������l�����܂��˂���
�@�ǂ�ȃ|�[�g��H
�@�o�X���t�̌��́@�g���}�[�Ŋ��炩�ɍ��܂��B
�@����A�lj��w�������g���}�[�r�b�g�����Ł@�@�g�P�������Ă܂�(��)
>���́A��^�\�t�g�ŃX�s�[�J�[��pCAD������̂ŁA�v�����ƊȒP�Ȃ�ł����A���ꂾ����PC���g�����v�V�~�����[�V�����𗘗p���ăX�s�[�J�[�����ƁA�A�i���O�I�ȁu���U�v�̍����o�Ă��܂��ˁB
�@�o�X���t�́A�R��ɂ���ā@�����Ԃ�_�ς���Ł@���^�ȏ�ɖ��x���v��������Ō��Ԃ��ǂ��l�߂邩�Ƃ����H�Z�p��R��Ȃ��v�Ńm�E�n�E�̍����o�܂��ˁB
�@���炭�́A���H�ƕ\�ʎd��Ł@���o���͂����Ԃ��ɂȂ�܂��B
�@����́A���h���̃t�@�N�^�[�͂��Ȃ�傫�����Ȃ�Ł@���ꂢ�Ɏd�グ�ɂ�Ȃ�܂���B
�����ԍ��F25857559
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
����ɂ���
Signature Audio 40���͂����̂ŎQ�l��
����܂��B���Ԃ̂���Ƃ��ɂł��@���f���Ă݂Ă��������B����������S���ł��B
�����́@�����x���@���ɍ����ł��B
�����ԍ��F25872853
![]() 3�_
3�_
�I���t�F�[�u���^�[�{����
�@���܂����B
�@�d�オ��͔������͂Ȃ���ł����A�����ƔM�����Ĕ��c�������m���Ȃ͂t���ł��ˁB
�@�\�ʂ������ۂ��̂́@���c�̓������Ǝv���܂��B
�@���̃P�[�u���@�≏�����d���@���K�~��2497�݂����Ȕ����f�ނł��ˁB
�@�������̃P�[�u�����ā@USB�ł�RCA�ł��≏�w���d���̂������C�����܂��B
�@����ƁA�O�����h���������Ȃ��Ă���ς�����R�l�N�^���g���Ă܂��ˁB
�����ԍ��F25876932
![]() 1�_
1�_
9/21�`22 ���Ŏ���X�s�[�J�[�̃C�x���g���J�Â���܂��B
�P�DFOSTEX�EWonderPure�@2�u�����h���ÃN���t�g�I�[�f�B�I�C�x���g
https://silicon.kyohritsu.com/FOSwp-2024/index.php
https://www.fostex.jp/20240905/19766/
�e��@14���@�v�\�����݁@�撅��
2024�N9��21��(�y)�@10:30�`12:00 (1���)
2024�N9��21��(�y)�@13:00�`14:30 (2���)
2024�N9��21��(�y)�@15:30�`17:00 (3���)
2024�N9��22��(��)�@10:30�`12:00 (1���)
2024�N9��22��(��)�@13:00�`14:30 (2���)
���E���{�� �����d�q�Y�Ɗ������ 1F �Z�~�i�[���[��
�i���s�Q������{����2-5-1�j
�Q�DDIY Loudspeaker Builder�fs Meeting 2024
https://diy-audiospeaker.sub.jp/2024/04/03/diy-loudspeaker-builders-meeting-2024/
https://diy-audiospeaker.sub.jp/2024/09/03/diy-loudspeaker-builders-meeting-2024_02/
2024�N9��22���i���j12:50�`17:30
YOSHU�z�[���i���s�������D��1-4-11�@�����r��2F�j
�Q����@��500
�@�l�́@9/22�@�̌ߑO/�ߌ�̃_�u���w�b�_�ŕ����ɍs���\��ł��B
�@����Ɓ@�u���}�n�Ƒn��X�s�[�J�[���쁕�����C�x���g�v
�@https://member.jp.yamaha.com/event/2955
�@�ɏo�i��̎����𑗂�܂����B
�@���������ς���10/6���ۉ�قŎ��{����C�x���g�ւ̑I�o���ʁi�t�@�C�i���X�g�P�O���j������\��ł��B
�@�i�\�ł́@�Q�O�{�ȏ�̋�����炵���j
�@���̏T���ɁA���̃C�x���g�ւ̏o�i��i�R�Z�b�g���W�߂ā@������Music Cafe�Ŗ����킹�����܂����B
�@�������j�b�g�g���Ĕ��������Ⴄ�X�s�[�J�[�ł����A���Ȃ艹�F������Ėʔ��������ł��B
�@�^�������̂Ł@�t�@�C�i���X�g�I�o���ۂɂ�����炸�A���J����\��ł��B
�@10/6�ɑ��ۉ�قɍs����l�́A�Q�����Ă͂������ł��傤�B
�����ԍ��F25885219
![]() 2�_
2�_
�@���}�n�̎����ǂ��烁�[�������ā@�t�@�C�i���X�g�ɑI�o���ꂽ���Ƃ��킩��܂����B
�@�������X�s�[�J�[��10/6 ���ۉ�قŌ��J����I�ڂɂȂ�܂��B
�@MJ�I�[�f�B�I���{�@���ăC�x���g�̂P�u�[�X�g���Ă��݂����ł��B
https://www.seibundo-shinkosha.net/magazine/hobby/90260/
�@���ꗿ�@\2,000�炵���̂Ł@���̂����
�@Music Cafe�� �R��炵�����ǁ@���̂����Q�䂪�I�o����Ă܂��B
�@BOWS�̂��Q�i�d�˂̉��̕��AA����̂����̂P�Q�ʑG���N���[�W���ł��B
�@�ڂ��ڂ�����ҏW���Č��J�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25887140
![]() 5�_
5�_
��BOWS����
����ɂ���
���߂łƂ��������܂��B
�I�o�P�O�g�̂����@�Q�g�ʉ߂����Ƃ������Ƃł��傤���H
�������ł��ˁE�E�����Ă݂����ł��˂��E�E
���̕��́A�P�[�u���̏��ɛƂ��Ă��܂��BQED�́A�܂����肵�܂��A
���������Ɍ������Ă��܂��̂ŁANC7v2_WN�Ƃ������悳�����ł��B
�����ԍ��F25887226
![]() 2�_
2�_
BOWS����
���A���܂����ˁB
���ۉ�ق��Ĕ����ɍs���ɂ����E�E�E�E�E�E�Ŋ���JR�����E�������̌䒃�m���A�������g�����c���̐V�䒃�m���ŁA���̗��w���炾�ƍ�����邾���Ȃ̂ł����A�A��͍��o��Ȃ��ƂȂ�Ȃ����܂��A�H�t���d�C�X���U��ł���ƃ|�W�e�B�u�ɂ�
YAMAHA�̃R���e�X�̎��Ԃ͂܂����܂��Ă��Ȃ��݂����ł����A�\�Ȍ���\�����悤�ɂ��܂��B
����R�[�i�[�Ƃ���������A�߂������ς��Ӓn���Ȏ�����������ł��˂��E�E�E
�����ԍ��F25887273
![]() 2�_
2�_
�I���t�F�[�u���^�[�{����
Foo����
�@���肪�Ƃ��������܂��B
�@����A���Ȃ�C�������č������Łi�ޗ���/���H����X �g�[�^���@�U�`�V���~���炢�j��J������܂����B
�@���Ƀf�b�h�}�X�d����ł��Ĕ��ɐU�����`���Ȃ��悤�ɍ���Ă����Ł@���������F���̂ƂĂ��h�܂�ˁ[���h�Ɏd�オ���Ă܂��B
�@�C�x���g�̓��e�͒ǁX�����ǂ��瓾����Ǝv���܂��B
�@����Ɓ@�C�x���g�I����Ď茳�ɖ߂��Ă�����@���炭�́AMuisc Cafe�ɒu���Ƃ��ā@��]�҂ɂ͕�����悤�ɂ������ł��B
>���̕��́A�P�[�u���̏��ɛƂ��Ă��܂��B
�@�̂́A�h�d�������h���Č����Ă܂����B�x�鈢���ɁA��������....(��)
�����ԍ��F25887789
![]() 1�_
1�_
��BOWS����
�t�@�C�i���X�g�I�o���߂łƂ��������܂��B
�c�O�Ȃ��烏�^�V���t�@�C�i���X�g�ɑI�o����܂����B
���ۉ�قʼn�܂��傤�B
���^�V�̂��f�b�h�}�X����Ă��܂��B
���߂Ă̗̍p�Ȃ̂Ń��j�b�g�N���Ȃ̂��f�b�h�}�X���ʂȂ̂�������܂��A
���ɗ����オ��̗ǂ��N���A�ȉ��ɂȂ��Ă��܂��B
�����ڂ͂܂�����I�N���݂����ȓz�ɂȂ�܂����B����͎��p���ł��B
�����ԍ��F25888325
![]() 6�_
6�_
Arch����
�@�I�o���߂łƂ��������܂��B
�@�I�N���� Ver3�ɃA�b�v�f�[�g���܂������I�H
�@�V�p�����Ă���̑�ς����ł��ˁB
�@���ۉ�قŖ����킹���y���݂ł��B
�����ԍ��F25888413
![]() 1�_
1�_
architect������ʉ߂ł����B
���@��@��
BOWS����A�X�s�[�J�[�����ł̓I�[�f�B�I�V�X�e���Ƃ��Ďg���܂���Ȃ��A�ĂуA���v�̊J���ł��ȁB
����g���܂��傤�A�ق��X���Řb��ɂȂ������m�A���v�B
�����ԍ��F25888658�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���}�n�C�x���g�p�ɔ��������X�s�[�J���A���}�n�ɓ��������悤�ł��B
�`�[���͂��Ă��炠���������肪���ŗV�ѕ����Ă����̂Œx�߂̔����ɂȂ�܂������A
����ł����ł��B
��BOWS����
> �I�N���� Ver3�ɃA�b�v�f�[�g���܂������I�H
�I�N��1����FE83sol�p�Ƃ���18mm���������ō��܂����B
�I�N��2����OMP600��OM-MF4��OM-MF4mica�ɕϑJ���܂������ASPF�� 1x4(�����o�C�t�H�[��)�ō��܂����B
�����č���̃I�N���R���ɂȂ�܂��B
�P���A�Q���͌܊p���ł������A����͎��p���ł��B
> �V�p�����Ă���̑�ς����ł��ˁB
���@�v�Z���ʓ|�������̂ŁA������̃T�C�g�����p���܂����B
https://keisan.casio.jp/exec/system/1258348324
�ؒf�͎��O�ŁA�ۋ��Ɋp�x��t���Ă��܂����B
�Ȃ̂ŁA���͏��ł��u�p�e���߂̏��v�ɂȂ�܂���(��)
�����ԍ��F25893955
![]() 2�_
2�_
��Architect1703����
��BOWS����
����ɂ���
������@�I�l���ɓ��܂��߂łƂ��������܂��B
Architect1703����̂́A�ǂ�ȉ�������̂��z�������܂��A�d�グ��̂�
��ς����ɂ��������܂��B
BOWS����Ǝ��̉����֘A�́@�����Ƃ��낪����Ɓ@���͏���Ɏv������ł���̂ł���
������̂�NC7v2_WN�ƒ�����ׂ����݂����ł��˂��E�E
�x���Ȃ�܂������A���܂��߂łƂ��������܂��B���ꂩ����撣���Ă��������B
�����ԍ��F25893998
![]() 2�_
2�_
���I���t�F�[�u���^�[�{����
> �I�l���ɓ��܂��߂łƂ��������܂��B
���肪�Ƃ��������܂��B
�����Ȍ������́A���}�n����͂������[���̕������g����
�u�I�l�ʉ߁v
�Ƃ����݂����ł��B���Ȃ݂�
�u�u��1��MJ�I�[�f�B�I���{�v�̊��̂P�Ƃ��āA�I�o���ꂽ10��i�̎���������{�������܂��B�v
�Ƃ������ƂȂ̂ŁA10��i�̂Ȃ��̈�̂悤�ł��B
> �ǂ�ȉ�������̂��z�������܂��A�d�グ��̂ɑ�ς����ɂ��������܂��B
BOWS�����������������܂��A�G���N���[�W���̒��̋�Ԃ̎�荇����z�u�Ƃ�
�H���̏��ԂƂ����l���Ȃ�����K�v������̂ŁA��Ԃ��������܂��ˁB
�d�グ���̂͂��܂�l����Ƃ��낪�Ȃ��̂ŁA��͂��܂���B
�ǂ����邩�i�h���A�˔A�J�b�e�B���O�V�[�g�j��Y�ނ����ł��B
�����ԍ��F25894156
![]() 2�_
2�_
�����������ƃ��}�n�̃��[����ǂݕԂ��Ă݂��̂ł����A
����́u�I�l�ʉ߁v�Ɓu�I�o���ꂽ10��i�v�́A�C�R�[���ł͂Ȃ���������܂���B
���}�n�̒��ł���ɐR�����āA�ǂ����̂�I�Ԃ̂ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B
�����ԍ��F25894167
![]() 2�_
2�_
���}�n�t�������W���j�b�g�𓋍ڂ����X�s�[�J�[�R��̔�r����������A�b�v���܂����B
Encloseure Sound Comprisonfor YAMAHA 9cm Full Range Speaker Unit
https://www.youtube.com/watch?v=dd_EaHUgyTA
�@�������j�b�g�Ȃ�Ł@���F�̈Ⴂ�͏������ł����A�ׂ��������Ɓ@���낢��Ⴂ�������ē������o�Ă��܂��B
�����ԍ��F25898249
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
����ɂ���
YouTube�pDAC�������̂ŁA����̓w�b�h�t�H���łȂ��A�I�[�f�B�I�ŁA��r���Ă݂܂����B
��Ԗڂ̃X�s�[�J�[�́A�S�̓I�Ƀo�����X���悭�A�Ȃ��Ȃ��A�����₷���^�C�v�Ɏd�オ���Ă���Ǝv���܂��B
��Ԗڂ̃X�s�[�J�[�́A��⒆���ɒ��S�������������ŁA�Ȃ͖����ł����A�D�������̕������Ƃ��낾�Ǝv���܂��B
��Ԗڂ�菬�����̂ɁA�T�u�E�[�t�@�[�����Ă����̂́A���̃X�s�[�J�[�����ł����B���͂���Ɉ�ԋ����������܂����B
�O�Ԗڂ́A������ɒ��S�������Ă���̂ł����A���f�b�v������̂��A����̂Ȃ���Ɉ�a���������܂����B����
���̓��Ɣ�ׂ�Ɓ@��������Ȃ��C�����܂��ˁB
�Ȃ̂Ŏ��̍D�݂Ƃ��Ă͓�Ԗڂ�~�����Ǝv���܂��̂ŁA�v���[���g���҂����Ă���܂��B
�܂�����͂��Ă����A�ǂ�������������Ă����ʂ��悭�o�Ă���Ǝv���܂��B
���ꂾ���̊����x���d�グ��ɂ͑����J�͂��₵�����Ƃ��Ǝv���܂��B
����ꂳ�܂ł����B
�����ԍ��F25898262
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
> ���}�n�t�������W���j�b�g�𓋍ڂ����X�s�[�J�[�R��̔�r����������A�b�v���܂����B
�����Ă݂܂����B�����ȂƂ���u���C���h�����ƕ�����Ȃ����ł��B
�Ƃ������AYouTube���̌��E���A�����V�X�e���̌��E���A���~�b�^�[�̂����銴����
���ܕ�������X�N���b�`�m�C�Y���C�ɂȂ��Ă��܂��āB
�R���g���o�X�ƃs�A�m�\���̔�r�ō���������܂������A��������X������̂ł����B
���̒��ŁA�X�s�[�J�̑��݂���Ԋ����Ȃ������̂���ԖڂŁA���Ƀs�A�m�̃n���}�[�������X�����Ƃ��������B
���͂���قǍ��������܂���ł����B
���j�b�g���������Ƃ�����������̂ł����ˁB
�����ԍ��F25898944
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
�F����
���������ł�
��V����I5�@win11�@21h2�@�I���L���E�r�d�|�t�R�R�f�w�@�P���E�b�h�@�J�i���^�C���z�[���ɂāB�i���ׂĉߋ��̋@��j
�f�b�h�}�X�e�����A�a�n�v�r����̂����ݐ������ɕ������܂����B
�P�O/�U�@�J���Ă������Ǝv���Ă��܂��B
�ŏI���ʊy���݂ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25899119
![]() 2�_
2�_
BOWS����
����q�����܂����B
����͎��O�ɊF���u����v�ƌ����Ă����̂ŁA�����@�ށA�������������킯�Ă݂܂����B
�P�@���C��PC��RME/Adi2pro��YAMAHA�@HPH-MT8
�Q�@���C��PC��RME/Adi2pro�����w�b�h�z��
�R�@���C��PC��RME/Adi2pro��Sennheiser�@MX 375
�R�̃w�b�h�z���̓��ӕ��삪�Ⴄ�̂ŁA�����ȍ����ǂꂪ�E���Ă���邩�Ȃ��Ƃ�
����ɁA�摜�����Ȃ��悤��YouTube�̓����DL���āA���������ĕ����Ă��܂��B
�R�̃w�b�h�z���̓��ӕ��삪�Ⴄ�̂ŁA���ꂼ��ō����������Ă������̂ł����A�P�Ԃ̃X�s�[�J�[�ƂQ�Ԃ͎��Ă��ł����A�R�Ԃ̂������������Ƃ������F���Ⴄ�B
�P�Ԃ̃X�s�[�J�[�������ہ[��Ȋ����̋����Ȃ̂ɂ������āA�Q�Ԃ͂ۂ�I�ŁA�R�Ԃ̓p�[���Ȋ����B
�P�Ԃ͉��̎��������߂Ȃ�ł����A�}�����o�Ƃ��p�[�J�X�̏��ʼn���������A���̑Ō������o��Ƃ����Ƃ���ł�����Ƃ����u���Ԃ�A���A���y��ł͂����͂Ȃ�Ȃ����낤�v���̍�����������Ă���̂ɂ������āA�Q�Ԃ́u���A���e�B�������v�A�R�Ԃ͂�邢�B
�P�ԂƂQ�Ԃ̍��͂��̂��������������ǁA�R�Ԃ����͂�����ƈႤ���Ȃ���
�P�Ԃ̃X�s�[�J�[�́A�������͓���̂ł����u�W�O�N����{�̃��[�J�[���X�s�[�J�[�v�I�ŁADIATONE��Victor�̃e�C�X�g���������ł���ˁA�Q�Ԃ́u���Ԃ�A�����܂ł��Ȃ��v���Ċ����ŁA�s�̃X�s�[�J�[�Ƃ��Ă͐������Ȃ����ŁA�R�Ԃ͂X�O�N��̃v���V���}�[���j�^�[�I�Ȋ��������܂����BPMC��������Ƃ�邭���������A��������THIEL�̃X�s�[�J�[�݂����Ȋ��o�B
���Ȃ݂ɁA���ʂ͂��Ȃ�グ�Ă��āA�����ɂ��Ȃ郌�x���ŁA�����傫�����͖������āA���̏����ۂƂ��A������X���C�_�[��߂��ăA�^�b�N�����o�邹�Ȃ�_���Ē�����ׂĂ��܂��B���̃T���v���͐��N�O�ɂ߂��Ⴍ���ᕷ���Ă�̂Ń|�C���g�͎����̒��ɂł��Ă�z�Ȃ̂ł�
������Ă݂āA�l����ԁu���A���������v�Ƃ��������̂̓��C�u�ŃM�^�[�̂�ƁA�}�����o�ƃR���g���o�X�̂�ł��ˁB
����A���̃T���v���~���[�W�b�N���g���������œ������������Ă���悤�ȋC������̂ł����A 10:46 Guitar Live �̍ŏ��̔��肪�I����ăM�^�[�̌��Ƀs�b�N��������܂łƁA�ϋq�̊����̋������A��������ԍ����ł܂��ˁB�i�������M�^�[����Ă��̂ł킩��₷���̂�����j
�����ŁA�u���[�A�Ⴄ�ȁv���o���đ��̃T���v�����Ă݂�Ƃ�����Ƃ킩��܂��ˁB
��ŁA���q�ɗ���ŁA�����DL���ĉ�����������ɁA�א�ɂ��āA�P�C�Q�A�R�̏��Ԃł͂Ȃ��A�V���b�t�����Ă݂���A�R�Ԃ����͊m���ɂ킩��܂����B���Ԃ�A�l�����łȂ��āA�u�����ӏ��v��������ꂽ��N�ł��킩��Ǝv���܂��B
�P�ԂƂQ�Ԃ̍����āADAC�̃��b�N�A�����W�W���X�g���������Ă�悤�Ȋ����ł��˂�
�Ƃ����Ă��ł��ˁA�Q�Ԃ�BOWS��͂��������\���Ƃ��A���R����m��������Ă邵�A�R�Ԃ��u�l�b�F�v�Ȃ�ʼn����Ă�̂ł��̃o�C�A�X������̂Ő��m�Ȓ�����ׂɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��ł��B
���̍����A���ۂɍL�������Ŗ炵�����ɁA�ǂ̒��x��������̂��͂킩��܂���B
���Ԃ�A���̃X���ł͂Q�Ԃ̕]���������̂ł����A�l�́u�L�������v�Łu���ʂ��傫���v�ƂR�Ԃ̕]���������A��ʓI�ȉƒ�Łu������ƃI�[�f�B�I�������Ă�v���炢�̐l���A�n���~�̃X�^���h�łP�O���O��̃v�����C���A���v�Ŗ炵�����Ԏg���₷�����������܂��B
�Q�Ԃ̃X�s�[�J�[������ł���̂́A�ӊO�ɂ��T�{�����AV�A���v�Ń}���`�������Ƃ������Ƃ��v�����肵�Ă��܂��B
�R�l�̐���҂��u���Ⴀ�A�N�͂ǂ��I�Ԃ̂��H�D���Ȃ̂������ċA���Ă������v�Ƃ���ꂽ��A�l�͂P�Ԃ̃X�s�[�J�[�������A���āA������Ǝv���Ƃ��낪����̂Ŏ����ōă`���[�����܂��B
�����ԍ��F25899388
![]() 3�_
3�_
�I���t�F�[�u���^�[�{����
>��Ԗڂ̃X�s�[�J�[�́A�S�̓I�Ƀo�����X���悭�A�Ȃ��Ȃ��A�����₷���^�C�v�Ɏd�オ���Ă���Ǝv���܂��B
>��Ԗڂ̃X�s�[�J�[�́A��⒆���ɒ��S�������������ŁA�Ȃ͖����ł����A�D�������̕������Ƃ��낾�Ǝv���܂��B
>��Ԗڂ�菬�����̂ɁA�T�u�E�[�t�@�[�����Ă����̂́A���̃X�s�[�J�[�����ł����B���͂���Ɉ�ԋ����������܂����B
>�O�Ԗڂ́A������ɒ��S�������Ă���̂ł����A���f�b�v������̂��A����̂Ȃ���Ɉ�a���������܂����B����
>���̓��Ɣ�ׂ�Ɓ@��������Ȃ��C�����܂��ˁB
�@���z���肪�Ƃ��������܂��B
�@Youtube�͎����@��Ŏ�����Ⴄ�̂Ł@�ቹ�̗ʊ��Ɋւ��Ă͐l���ꂼ��ŃI���t�F�[�u���^�[�{����̊����ł̌��ʂ͂����Ȃ�ł��傤�B
>�Ȃ̂Ŏ��̍D�݂Ƃ��Ă͓�Ԗڂ�~�����Ǝv���܂��̂ŁA�v���[���g���҂����Ă���܂��B
�@���Ԃ�AMusic Cafe�ɒu���Ă����̂Œ�������������ł₷�B
>���ꂾ���̊����x���d�グ��ɂ͑����J�͂��₵�����Ƃ��Ǝv���܂��B
�@����҂݂̂Ȃ���A�����Ԃ��J���ꂽ�Ǝv���܂��B
Archi����
>�����Ă݂܂����B�����ȂƂ���u���C���h�����ƕ�����Ȃ����ł��B
>�Ƃ������AYouTube���̌��E���A�����V�X�e���̌��E���A���~�b�^�[�̂����銴����
>���ܕ�������X�N���b�`�m�C�Y���C�ɂȂ��Ă��܂��āB
>�R���g���o�X�ƃs�A�m�\���̔�r�ō���������܂������A��������X������̂ł����B
����������Ȋ��z�ł��肪�Ƃ��������܂��B
�X�N���b�`�m�C�Y�͎��s�ł����B�^���J�n�O�ł���A�o�b�t�@�T�C�Y�ύX�őΏ�������ł���
>���̒��ŁA�X�s�[�J�̑��݂���Ԋ����Ȃ������̂���ԖڂŁA���Ƀs�A�m�̃n���}�[�������X�����Ƃ��������B
>���͂���قǍ��������܂���ł����B
>���j�b�g���������Ƃ�����������̂ł����ˁB
�@�ǂ�̔w��ׂ݂����ȂƂ���͂���܂��ˁB
�@Foo���w�E���Ă���悤�ɁA�P���ƌ������A����������Ă���Ɓ@���������\�͂��オ���ė��܂��B
matu85����
>�f�b�h�}�X�e�����A�a�n�v�r����̂����ݐ������ɕ������܂����B
�@���肪�Ƃ��������܂��B
�@�]�v�ȉ����o�Ȃ��̂Łu���ݐ����v�́A�������ȂƎv���܂��B
�@�����A���̂��D�����H�͐l�Ɉ˂�܂��ˁB
>�P�O/�U�@�J���Ă������Ǝv���Ă��܂��B
�@����ł���Ί������ł��B
�����ԍ��F25900699
![]() 1�_
1�_
�������Ă݂܂���
1�Ԃ�2�Ԃ͂���܂��ʂ����Ȃ��ł����A2�Ԃ̂ق����������������Ă���悤�ɏ��X�����܂���
3�Ԃ͈Ⴂ�܂��ˁB�I���t�F�����������ʂ�A�d�S�������悭�Ƃ��鉹�Ɏv���܂�
����⎎����ȊO�Œ����Ƃ��ꂪ��ԗǂ������ɒ�������悤�Ɏv���܂����A�t�Ɏ���ƒ��s���ɒ����������ł�
�Ȃ�1,2,3�ō����������̂̓R���g���o�X�}�����o�ł����B����1��2��3�Ȋ���
����MJ�Ő��Œ������̂Ɣ�ׂ�ƁAyoutube�̌��E�̕�����ɗ��Ă��āA������̉e���̕����傫�������ł���
�����ԍ��F25900731
![]() 3�_
3�_
Foo����
>����͎��O�ɊF���u����v�ƌ����Ă����̂ŁA�����@�ށA�������������킯�Ă݂܂����B
�@�������̒Nj��ł��ˁB
>����ɁA�摜�����Ȃ��悤��YouTube�̓����DL���āA���������ĕ����Ă��܂��B
�@�o�C�A�X��r�������i�ł��ˁB
>�P�Ԃ̃X�s�[�J�[�������ہ[��Ȋ����̋����Ȃ̂ɂ������āA�Q�Ԃ͂ۂ�I�ŁA�R�Ԃ̓p�[���Ȋ����B
�@�����A���ɓI�m�ȕ\���@���ԂƂ�T���I
>�P�Ԃ͉��̎��������߂Ȃ�ł����A�}�����o�Ƃ��p�[�J�X�̏��ʼn���������A���̑Ō������o��Ƃ����Ƃ���ł�����Ƃ����u���Ԃ�A���A���y��ł͂����͂Ȃ�Ȃ����낤�v���̍�����������Ă���̂ɂ������āA�Q�Ԃ́u���A���e�B�������v�A�R�Ԃ͂�邢�B
�P�ԂƂQ�Ԃ̍��͂��̂��������������ǁA�R�Ԃ����͂�����ƈႤ���Ȃ���
�@����̓X�s�[�J�[��SN�̈Ⴂ�Ł@N���������̂ŁA����������|�C���g���Ⴂ���Ă��ƂɂȂ�܂��B
>�P�Ԃ̃X�s�[�J�[�́A�������͓���̂ł����u�W�O�N����{�̃��[�J�[���X�s�[�J�[�v�I�ŁADIATONE��Victor�̃e�C�X�g���������ł���ˁA�Q�Ԃ́u���Ԃ�A�����܂ł��Ȃ��v���Ċ����ŁA�s�̃X�s�[�J�[�Ƃ��Ă͐������Ȃ����ŁA�R�Ԃ͂X�O�N��̃v���V���}�[���j�^�[�I�Ȋ��������܂����BPMC��������Ƃ�邭���������A��������THIEL�̃X�s�[�J�[�݂����Ȋ��o�B
�@���̕\�����u��������Ȃ�v���Ċ����ł���B
�@���܂����Ƃ������Ȃ�
>���Ȃ݂ɁA���ʂ͂��Ȃ�グ�Ă��āA�����ɂ��Ȃ郌�x���ŁA�����傫�����͖������āA���̏����ۂƂ��A������X���C�_�[��߂��ăA�^�b�N�����o�邹�Ȃ�_���Ē�����ׂĂ��܂��B���̃T���v���͐��N�O�ɂ߂��Ⴍ���ᕷ���Ă�̂Ń|�C���g�͎����̒��ɂł��Ă�z�Ȃ̂ł�
�����炭�l��Foo����́@���̊y�Ȃɋ��낵���b�����Ă���̂ʼn�������ׂ��|�C���g�����m�Ȃ�Ŕ��ʔ\�͂������ł��B
�Ȃ̂Ł@���A���^�C���ɓ�������Œ�����ׂĂ��Ă��u����H���̈Ⴂ�ɋC�Â��Ȃ��H�v���Ă��Ƃ��p�o���܂��B
Music Cafe�ŕ����Ă����A��100��ȏ㕷���Ă���̂ŁA�������������Ă���Ǝv���܂���
>������Ă݂āA�l����ԁu���A���������v�Ƃ��������̂̓��C�u�ŃM�^�[�̂�ƁA�}�����o�ƃR���g���o�X�̂�ł��ˁB
�@�T�^�I�Ȃ̂������ł��ˁB
>�P�ԂƂQ�Ԃ̍����āADAC�̃��b�N�A�����W�W���X�g���������Ă�悤�Ȋ����ł��˂�
�@�����[�����Ă邱�Ƃ킩���ł����A�قƂ�ǂ̐l�����̂�������H�@�ł��ˁB
>���̍����A���ۂɍL�������Ŗ炵�����ɁA�ǂ̒��x��������̂��͂킩��܂���B
>���Ԃ�A���̃X���ł͂Q�Ԃ̕]���������̂ł����A�l�́u�L�������v�Łu���ʂ��傫���v�ƂR�Ԃ̕]���������A��ʓI�ȉƒ�Łu������ƃI�[�f�B�I�������Ă�v���炢�̐l���A�n���~�̃X�^���h�łP�O���O��̃v�����C���A���v�Ŗ炵�����Ԏg���₷�����������܂��B
>�Q�Ԃ̃X�s�[�J�[������ł���̂́A�ӊO�ɂ��T�{�����AV�A���v�Ń}���`�������Ƃ������Ƃ��v�����肵�Ă��܂��B
3�Ԗڂ̃X�s�[�J�[�́A�ӂ��̃X�s�[�J�[�ɋ߂����̂Ŏ͗ǂ������ł��B
2�Ԃ߂́A�Ƃɂ����]�v�ȉ����o�Ȃ��ā@�s���|�C���g��ʂ����Ń}���`CH�ɂ���Ɵ��݂����Ȃ��ėǂ��Ǝv���܂��B
>�R�l�̐���҂��u���Ⴀ�A�N�͂ǂ��I�Ԃ̂��H�D���Ȃ̂������ċA���Ă������v�Ƃ���ꂽ��A�l�͂P�Ԃ̃X�s�[�J�[�������A���āA������Ǝv���Ƃ��낪����̂Ŏ����ōă`���[�����܂��B
�@��͂́A�炵���ł��ˁB
�����ԍ��F25902100
![]() 1�_
1�_
�@9/22�Ɏ���X�s�[�J�[�֘A�̃C�x���g�ɍs���Ă��܂����B
FOSTEX�EWonderPure
2�u�����h���ÃN���t�g�I�[�f�B�I�C�x���g
https://silicon.kyohritsu.com/FOSwp-2024/index.php
��
DIY Loudspeaker Builder�fs Meeting 2024
�@https://diy-audiospeaker.sub.jp/2024/04/03/diy-loudspeaker-builders-meeting-2024/
�@���ʂ��猾���ƁAFOSTEX�́@�z�����Ă����̂Ƃ������ĕς��Ȃ������ł��B
�@DIY Loudspeaker Builder�fs Meeting�́A�ŋ߂̎���X�s�[�J�[�֘A�ł̓g�b�v�N���X�ɖʔ��������ł��B
�@�܂��@FOSTEX�@�ł����A���ɂ͏\���l���x
FE-108 sol���v���~�A���i�œ]������Ă���̂ŋ��߂Ă���l�̂��߂�1���b�g�lj��ő����������ł��B
��p�̃o�b�N���[�h�z�[���G���N���[�W���ɓ��ꂽ�̂��܂������A���C�����ǃo�b�N���[�h�z�[�����ۂ��đe���Ȃ�
���ɁAFE-203�� RE ���āA����FE203���@�̕������f���ł��B
�S�`���t���[���ŃR�[���������炵�F�Ō����ڂ͕����Ȃ�ł����A�����Ԏ肪�������Ă��Đ̂̋���Ɏ��L������FE203���ƈ���āA�����ȃ\�[�X�����Ȃ��悤�`���[�j���O����Ă܂����B
�Y�R�A�L���搶�̐V���^�o�b�N���[�h�z�[���u�I�E�T�}�y���M���v�ɓ��ڂ���Ė炵�n�߂�ƁA���̕��͖����������ď[�����Ă�����ǁA���悪���̂������e���ăU���U�����Ă��Ă�����ƂȂ�....�ǂ����p�[�e�B�N���{�[�h�ő������炵����ł����A���ꂪ�������Ǝv���܂��B
���̌�A�W���o�b�N���[�h�z�[�������@�V�i����/MDF/���W�A�^�p�C���W���ށ@��3��ނō���Ă��ā@������ׂ��܂����B
�������̕����u�I�E�T�}�y���M���v��艺�̕��������Ă܂����A��ʓI�Ȃ��ŗǂ��ł��B
MDF�́@�����̉����ǂ��肵�Ă��ē݂��y�����Ȃ���/���W�A�^�p�C���W���ށ@�́@�C�ɂȂ�قǑ傫�������Ă��傢�Ǝ������A�o�b�N���[�h�z�[���炵���y�������ł͂��邪���߂��A�V�i���͂��̒��Ԃ��炢�B
���Ł@�ǂꂪ�D�����H���Ď��������������@�V�i/MDF/�p�C���@�Ł@4/0/6 ���炢�̐l�C�ł����B
�@
�@�}�[�N�I�[�f�B�I��}�n���̃��j�b�g���g���Ă���Ɓ@FOSTEX��FE�V���[�Y�͂�������Ȃ��Ǝv���܂����B
�@���������Ȃ̂ƒ����悪�e���̂��C�ɓ���܂���B
�@�����S�j�搶�͈̑�Ȑ��҂Ȃ̂͊ԈႢ���Ȃ���ł����A�㔼�̍����̋Z�p�������ꂽ�X�s�[�J�[�v��m���Ă��܂��Ɓ@���[�J�[�����[�U�[���i�����r�₦�ā@�����Ԃォ����c����Ă���悤�Ȉ�ۂ��܂����B
�@�S�j�̖S�삩��E�p������Ă��Ȃ��H
�@�㔼�ɑ���
�����ԍ��F25902119
![]() 3�_
3�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
�O���@������P�C�Q�C�R�C�S |
���S����@�R���f���T�X�s�[�J�[ |
���C�b�g�������@�I�[�v���o�b�t���X�s�[�J�[ |
�N�����O�t�B�����@�I�}�[�W�� |
Speaker Bulders Meeting 2024
�@����I�Ȑv��@���g���������I��2way�X�s�[�J�[����ׂ悤�Ƃ����C�x���g
https://diy-audiospeaker.sub.jp/2024/09/03/diy-loudspeaker-builders-meeting-2024_02/
�O���@�����S��
�P�DMJ�ɗ����̋L�����ڂ��Ă��� Dayton Audio��2way �X�s�[�J�[
�@����I�ȃA�v���[�`�ł����������Ă��ā@�����ȃ��j�b�g�ɂ�������炸�A�ǂ����������Ă���܂����B
�@FL�Q���l�b�g���[�N�A�o�b�t���X�e�b�v��A�m�b�`�t�B���^�[�Ɠd�C��������ł��B
�@�����ȃj�b�g�����ǁA�R���f���T�̂��l�i�����j�b�g�̂Q�{�������Ƃ�(��)
�@���́A�㎿�Ȏs�̕i�̂悤�Ȑ^�ʖڂȉ�
�Q�D�T�C�h�h�����R�[���@�X�s�[�J�[
�@������ɂ߂Č���I�ȃA�v���[�`�Őv���ꂽ�X�s�[�J�[�@�h�����R�[���̐v��@�������ėǂ������ł��B
�@���́A��悾���c����������܂����B
�R�D�f�X�N�g�b�v���� 15cm 2way
�@�f�X�N�g�b�v�ɒu����ő�T�C�Y�ɍ����悤��15cm�E�[�t�@�[�̃��j�b�g��I�����������ł��B
�@��������������荞�݂���Ă��ā@�[���ȉ��ł����B
�S�D�t���A�^�@�X�^�K�[�h����
�@����́A�O���狤�ǂ��g�����X�s�[�J�[������Ă���MUKU����̃t���A�^�X�^�K�[�h���ǁi�����̈قȂ�Q�{�̋��ǁj���g�����X�s�[�J�[
�@����ONKYO��OM-OF101���g�����G���N���[�W�����AScanspeak��2way���j�b�g�ɕύX���Ēǂ�������
�@�t���A�^���������đO�R�@��ɔ�ׂĂ������Ƃ�������A���C���g���̂ŋ��������ꂢ�ł����B
�@�ȏ�A���Ȃ�D�����ȃX�s�[�J�[�Ł@�s�̂̍����i�тƃ^�����������̂ł����B
�@�㔼�́@���Ȃ胄���`���Ȃ��̂�����
�T�D����R���f���T�X�s�[�J�[�i2way����Ȃ��ł́H�j
�@�܂��A�R���f���T�X�s�[�J�[�����삵�悤�Ƃ����u�ɔ���
�@�g�����X�������邽�߂ɂP�Q�̃g�����X���g���Ă���i�т�����I�j
�@�o�C�A�X�d����4.8KV
�@�d�ɂ̓p���`���O���^������Ȃ��ā@�������(������)
�@�C���s�[�_���X�́@�Q���`�Ȃ�ŃA���v��I��
�@���́A�T�^�I�ȃR���f���T�X�s�[�J�[�Ŕ������x�͔��Q�A�R�[���^�X�s�[�J�[�͂ƂĂ����Ȃ��
�@��C�������Q
�@�ቹ�͂����ς�o�Ȃ�������͂���ʼn����I
�U�D�r���e�[�WSP���j�b�g�������̕��ʃo�b�t�����ǂ��@�c�B�[�^�t���Ă��邪�z������ĂȂ�(��)
�@30cm���̓��ꂵ���A�N�����Ƀ��j�b�g���}�E���g���Ă����A�l�W�Ŏ��t�����O�����邱�Ƃɂ��A���j�b�g���������邱�Ƃ��ł���B
�@���R�[�h���b�N����Ȃ��ā@SP���j�b�g���b�N�ŃX�g�b�N���Ă����A���̓��̋C���Ō����\
�@�������V�����E�h�Ł@���ʃo�b�t�����ቹ���x������オ��B
�@�C���e���A�Ƃ��Ėʔ���
�@���́A���j�b�g�ɂ����I�@�����s�������͂����蕪�����B
�@�d�ቹ�́A�S���o�Ȃ����A�������o�Ȃ��̂Ńo�����X�悭�Z��������������B
�@�I�[�v���o�b�t���Ȃ�ŁA�X�g���X�Ȃ������̑�������������B�R���f���T�^�ɋ߂�
�@����͋Ȃɂ���ā@���j�b�g�ς��Ċy���߂�ʔ����A�v���[�`
�@���j�b�g�ɂ�鉹��
�@�i�V���i���̃Q���R�c 20cm(���Ԃ�50�N�O�I��)�@���������W�ŔZ�����悪������B
�@�e���t���P���̃A���j�R�i���Ԃ�80�N�I��j�@���Ȃ葁�������ŃT�N�T�N�����{�[�J����������@����͗ǂ�
�@����ŋ��t�B���b�v�X�̃r���e�[�W���j�b�g���������Ȃ����B
�V�D�h�C�c�@�N�����O�t�B�����E�I�}�[�W���@�X�s�[�J�[�@�����\��(101dB/W/m)
�@�g�p���Ă���E�[�t�@�[���j�b�g���@���h�C�c�̉f��قŎg���Ă����悤��RFT�̃��j�b�g
�@�l�́A���̎�̒��ÓT�̃W�[�����X�̃I�C���_�C����N�����O�t�B�����������Ƃ�����܂����A�ш��AM���W�I�����d�b���Œቹ���������S���o�Ȃ��ā@�t�K�t�K�����������낵���������ł���悤�Ȓ����\�����j�b�g�Ł@�ꕔ�̃��B���e�[�W�}�j�A����_�i������Ă��邯�ǁ@98%�̐l���Ȃ�R���H�Ɣ�����悤�ȉ��ł��B
�@���̓�Ȃ̉�݂����ȃ��j�b�g����肵���@Lo-Fi Audio�̊Ǘ��l�@����̊i�����M������Ă��ā@���̂������ʔ��������ł��B
https://naseba.exblog.jp/
�@�����URL����Ƃ킩��܂����A�o���o���̌���v������Ă��āAFL�̂S���l�b�g���[�N���A�o�b�t���X�e�b�v��A�E�F�[�u�K�C�h���RD�v�����^�ō쐻���āA���肵�Ă͐v��ς���Ƃ���������I�ȃX�s�[�J�[�r���_�[�ł��B
�@����I��2�}���`�E�F�C�X�s�[�J�[�́A�R�[���^�{�h�[��/���{���c�B�[�^�̃}���`�E�F�C���V�~�����[�V�����Őv��ǂ����݁A����œd�C�I�A�@�B�I�ȕ�������ē�����ǂ����ނ̂��������Ǝ咣���܂��B
�@���̉����ɏ]���ƁA����I�Ȓ�\���œ����̗ǂ��D�������j�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���ꂽ���j�b�g���Ȃ�Ƃ��g�������Ƃ������ƂŁ@�N�����O�t�B�����̌ÓT�X�s�[�J�[��RFT�̃��j�b�g������I�ȃA�v���[�`�Ŏg���b������܂��B
�@�ȂA�����G���N���|�W���e�ʁ@�Œ�200L�Ƃ����㕨�Ȃ�Ł@��J���Č����I�ȃT�C�Y�̃G���N���[�W���Ɏ��߁A���킹��z�[���h���C�o�̓h�C�c���琔�����������Ď����A�l�b�g���[�N���I���W�i���̒���^�ŃR���f���T�����Ǝ���̂����ƋÂ��Ă܂��B
�@�������A�l�b�g���[�N�̒ǂ����݂́@���ゾ���łȂ��p�x�������ė��_�I�ɑ��肵�ā@�C���s�[�_���X����A�g�����W�F���g����A�\�Ȕ͈͂Ń^�C�����C�����Ɠ��X����I�ȃA�v���[�`�Œǂ������̂ł��B
�@�ŁA�o�Ă������́@�Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȃ��C�h�����W�ȌÓT�X�s�[�J�[�Ƃ������킢�[�����̂ł����B
�@���Ǝ���̂���ڂ�����������Ȃ�������ł����A���ς�炸���ƍ���͕s�����邯�ǁ@����͗ǂ��Ȃ��@
�@���N����邻���Ȃ�Ł@��������l�͐����܂��傤
�����ԍ��F25904366
![]() 4�_
4�_
���}�n��9cm�t�������W���g��������X�s�[�J�[�@�C�x���g��A�b�v�f�[�g����܂����B
���}�n�Ƒn��X�s�[�J�[���쁕�����C�x���g
https://member.jp.yamaha.com/event/2955
>�������X�P�W���[��
>
>11:00-12:20�@�y1st session�z�@3��i�����V���v���̍�i
>
>13:00-14:30�@�y2nd session�z�@4��i
>
>15:00-16:20�@�y3rd session�z�@3��i�����V���v���̍�i
>
>16:30-17:30�@�yHighlight session�z �S10��i�i�e1�ȁj
�@�ƂȂ��Ă܂��B
�@���V�搶���ۑ�ȂQ�Ȃ𗬂��ďЉ����Ł@�������ԂɂȂ�悤�ł��B
�@Youtube�łR�Ԃߍ�i���@1st session
�@Youtube�łQ�Ԃߍ�i���@2st session
�@�ƂȂ�܂��B
�@���ꗿ�@��2,000 �������Ł@�C�y�ɗ��Ă����������Č����Ȃ���ł����A�ʔ����C�x���g�Ȃ�Ł@�������������炨���ł��������B
��[��������������
�@�ԐM���x���Ȃ��Ă��݂܂���B
>�������Ă݂܂���
�@���肪�Ƃ��������܂��B
>1�Ԃ�2�Ԃ͂���܂��ʂ����Ȃ��ł����A2�Ԃ̂ق����������������Ă���悤�ɏ��X�����܂���
�����炭�@�]�v�ȐU�����Ȃ����߁A�Ñ��������Ȃ����炾�Ǝv���܂��B
>3�Ԃ͈Ⴂ�܂��ˁB�I���t�F�����������ʂ�A�d�S�������悭�Ƃ��鉹�Ɏv���܂�
>����⎎����ȊO�Œ����Ƃ��ꂪ��ԗǂ������ɒ�������悤�Ɏv���܂����A�t�Ɏ���ƒ��s���ɒ����������ł�
�@���ǂ��ۂ��z�[�����[�h���������Ă����Œቹ�̗ʊ��I�ɂ͂����ł����A���ǂ̓����Ńs�[�N�f�B�b�v�������Ł@�����s�������o�邱�Ƃ�����܂��B
>����MJ�Ő��Œ������̂Ɣ�ׂ�ƁAyoutube�̌��E�̕�����ɗ��Ă��āA������̉e���̕����傫�������ł���
�@Youtube�^���������́A���Ȃ�f�b�h�ȕ����Ȃ�Ł@���ʂ͏グ�Ă��邩�炩������܂���B
�@����Œ������@�Ƃ�ł��Ȃ��剹�ʏo�Ă܂��B
�@�剹�ʏo�������ɁA���낢��s������݉������Ł@���̏ꏊ�͏d���Ă����Ă��܂��B�@
�����ԍ��F25911789
![]() 1�_
1�_
�������傢�A�����i�K�ŏ������Ǝv���Ă����G�k��
YouTube���g������r�����ł����A���݂�YouTube�̉������k�͂��ƍ��i���ŁA���ɒ�[�g���́u�������v�Ƃ̍��͏��Ȃ����k���@������Ă��܂��B�Ȃ̂ŁAYouTube������_�����Ă����̂͂P�O�O�������Ȃ���Ԃł͂���̂ł����A㩂������������āB
UP�������ォ��Q�S�i����ł͂S�W�j���Ԃ͉�������[�g�ŁA��ō����[�g�ɍ����ւ����܂��B
����́AYouTube�����ʂ��E�N���b�N���āu�ڍד��v���v�̂Ƃ�����݂�ƁA���s�ڂɁuOpus(xxx)�v�Ƃ����̂������āA���ꂪ�������k�t�H�[�}�b�g�ƃr�b�g���[�g�������Ă��܂��B�������m�F����Opus�i251�j�ȏ�ɂȂ��Ă���̂������āA�������J�n����K�v������܂��B�܂��AOpus�̃T���v�����O���[�g��48�������Ȃ�ŁAWindows�̏ꍇ�ɂ̓T�E���h�̏��łS�W�������ɍ��킹�Ă�����Ƃ�����ƃ}�V�ɂȂ�܂��B
�Ȃ�ł����A���ǂ�Windows�̃A�z�ȋ@�\���������ƂɂȂ�̂ŁAYouTube���������������͂悭���Ă��AWindows���_���Ȃ�ł���˂�
��r������݂āA����Ȃ�ɕ����邱�Ƃ�����̂ł����A�\�ȏꍇ�ɂ͓�����raw data����Ă��炤���Ƃɂ��Ă��܂��B
���̃X���ł��A���l���̐l�͖^YouTuber����c���192/24�̃f�[�^�����Ă���Ǝv���̂ł����A�����ȍ��͂�͂�raw data����͂����ق����킩��܂��B
���ƁA�w�b�h�z����ς��Ď�������̂ł����A���ꂪ�ʔ����ł��B
�l�̎莝���̋@�ނ̒��ł́A��Ԉ�����Sennheiser�@MX 375�����͂������킩��₷���B
���ɐ��Y�I�����Ă��āAAmazon���ŗ��ʍɂ������͊C�O����̕��s�A���i�����Ȃ��̂ł����A����D�G�B
���͗ǂ��Ƃ͌����Ȃ��̂ł����AYouTube�ł̔�r�����ł͍����킩��₷���B
������Sennheiser���ȂƎv���܂���
���Ƃ��Ƃ́A�X�}�z�ɒ��h�����āA�O�ŕ������߂ɍw�������̂ł����A�Ƃ��鏊�Łu���������v�����Ă���l���u�����悢�̂��ǂ����ł͂Ȃ��A�ɏ��M����������̂�Sennheiser����ԓ��ӂŁA����Sennheiser���C���z�����g���Ă��܂��v�ƌ����Ă��̂ŁAYouTube���̔�r�����ɂ�Sennheiser�@MX 375���g���悤�ɂ��Ă��܂��B�Ȃ��A���̕������y�����ɂ͑��̃��[�J�[�̃w�b�h�z����AKG�ASONY���g���Ă��邻���ł��B
�����ԍ��F25911803
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
6�����ɕ�����A�ǂ�ȉ��������邩�A�����̎��A�ʗp����̂��A�y���݂��Ă��܂��B
�X�P�W���[���\���āA���͉����ŐH�ׂ�̂ƁA�y2nd session�z���̎��Ԗ��C�������������āB
����オ��ƍD���ł��˂��B�@
��Foolish-Heart����
�@�@�@�@�������
�@�@�@�@JBL�@4343�@����������A���ɂȂ�����ł��A�����́A�P�O���T���l���A�V�䍂2,1m�A�ꐡ�Ⴂ�A
�@�@�@�@�܂��́A�Ⴄ�ׂ����A�悵�Ƃ��Ȃ��A�@
�@�@�@�@�Ⴄ�Ƃ��āA�W�O���������̂r�o�������ł��A
�@�@�@�@���̃X���b�h�ŁA�o�b�t���Q�����ł��O�ʂ�����O���\�̗l���������݂���Ă����L��������@
�@�@�@�@���̕ӂ̃m�E�n�E�A���J���Ē�����Ɗ������ł��B
�@�@�@�@���x�͗ǍD�ȃZ�b�g�ł��A�@�@���w���X�������肢���܂��B
�����ԍ��F25913234
![]() 2�_
2�_
matu85����
���̂������ɁA4343�������ł����H
����͂�����Ă����܂��傤��
������ƁA���m�����ƂȂ̂Ŏʐ^�Ƃ��B��̂��ʓ|�Ȃ�ł����A�S�R�S�R�́u�ǂɖ��ߍ��ށv�Ƃ����̂����Ƃ��Ƃ̎g�����Ȃ̂ŁA�S�ʂ���S�Ẵ����e�i���X���o����悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�o�b�t�����A�E�[�n�[�̏��ƁA���̏�̂Q�ɊO�����Ƃ��o���܂��B
�ŁA�E�[�n�[�̕��͓��ɊȒP�ɊO����̂ŁA����͂͂����āA�E�[�n�[�{�E�[�n�[�o�b�t���ɐ藣���ĉ^�Ԃ̂͊ȒP�ł��B
2231A�͒P�̂łWkg���炢����̂ŁA���ꂾ���ŁA�P�Okg�͌y���o���܂��B������ł�69kg�Ȃ̂ŏd���B
�㑤��3�́A3�AATT�̂Ƃ��낪������ƊO���̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA���j�b�g���ƂɊO���Ă����̂���낵�����Ǝv���܂��B
MID-LO��2121��4kg���炢�ŁA�R���v���b�V�����h���C�o�[���z�[���́A������ƊO���̂��|���̂ł����A���ꂪ�͂�����A7kg���炢���ȁE�E�E�E�ŁA�}�C�i�X�P�Pk��
�o�b�t�������Ȃ�d���̂ł����A�O�o�̒ʂ�AATT����̔z�������c�t���Ȃ̂ŊO���āA�t�����ԂƁA���̂܂܂ɂ���̂��͔Y�ނƂ���ł����A���ɊO�����Ƃ��Ă��A�������łT�Okg���炢����킯�ł��B
�\�ł���A�Ƃ肠�����̗A���͉^��������ɗ��ނ̂���낵�����Ǝv���܂����A�Z�b�e�B���O���ǂ�����̂��ł��ˁE�E�E�E�E�E�E
�P�l�ł͐��������ł��B�l�͂P�l�łȂ�Ƃ����܂������A���A���Ŗl�ɉ�������Ƃ�����l�́u�܂��A���邩�ȁv�Ȑg�̂��Ă܂����A������̂͂P�U�N�O�A���̖l�ł͖����ł��B
�o����A�A���́A�s�A�m�A�������Ă���Ǝ҂ɗ��ނƁAJBL�S�R�S�R�Ȃ�ł����E�E�E�Ƃ����A��̂킩��Ǝv���܂���
���ʂ̉^������������l�i�͍����ł����A���J�����A�����܂ʼn^��ł���܂��B
�ŁA��ɒu���ꏊ�E�E�E�E�X�^���h��e�Ղ��Ă����Ɨǂ��Ǝv���܂��E�E�����߂Ă����A�����ɒu���Ă���܂��B
���ۂɁA�l�����É�����̗A���́A�s�A�m�^����Ђɗ��݂܂����E�E�E�Ƃ������A�I�[�f�B�I���j�I���Œ��Íw�������̂ł����A���j�I���͓����A�s�A�m�^����Ђƒ�g���Ă����̂ŁA���ʂɂ����Ȃ�܂����B
�Ȃ��A���ւ̃x�^�����͂������߂��܂��A�Ȃ��Ȃ��S�R�S�R��u����X�^���h���Ȃ��̂łǂ�����̂��͔Y�݂܂��ˁB
TAOC�̃X�s�[�J�[�x�[�X�������I�ɕW���X�^���h�������Ǝv���̂ł����A���ɔp�ՁB
���Â�T���Ă��A4343�`4348�����̃T�C�Y�͂Ȃ��Ȃ��o�Ă��Ȃ���ł���ˁB
�����ł́A�d���Ȃ��A��Ή�����ɐ���Ă��炢�܂�����
���ƁA�C���V�����[�^�[�͎~�߂Ă������ق����ǂ��ł��B
���Ȃ�傫�ȃT�C�Y�̃��m���g���Ă��A�d���̂�4�_�ł������݂܂��B
���Ƃ��ƁA����ȂɍL���Ȃ��X�^�W�I�Ŏg���Ă����X�s�[�J�[�Ȃ̂ŁA�ӊO�ɍL���͋��߂Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B
���������A�����̃E�[�n�[�A�傫������z������قǂ̒ቹ�͂łȂ��ł����炗
�����ԍ��F25913660
![]() 2�_
2�_
��matu85����
����ɂ���
�����������Ă܂�
4343 �ǂ��ł���
��X�ł��傤��11����
������4343�������l�ł�
http://audiosharing.com/blog/?p=41790
�Q����͕K�v�ȗl�ł���
�߂��Ȃ�s�������Ƃ���ł���
���̓A�L�V�I����
4343 �����ɔ����o������ǂ��ł���
���ז����܂���
�����ԍ��F25913763�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
4343�ǂ��ł��ˁ[
�傫���Əd������ɂȂ�Ȃ��Ȃ��������Ⴂ�܂���[�B
�����ԍ��F25914002�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��matu85����
���`�I�����W�p�[�N���܂������B�����ł��ˁB�����͂܂�����C�z������܂���B
4343��肱�������C�ɂȂ�܂�
�݂Ȃ���4343����ɔ�������Ă���̂łȂ�ƂȂ��I�����W�ɔ������Ă݂܂���
�����ԍ��F25914079
![]() 2�_
2�_
��Foolish-Heart����
���X���w���L�������܂��B
�@
�@�n���։���������ւłU�O�s�Ƃ��Ă��Y�݂܂��A�������v����������Ă݂܂��A�L�������܂����B
�������̃E�[�n�[�A�傫������z������قǂ̒ቹ�͂łȂ��ł����炗
�@������y���݂ɂ��ā@�����ڎw���܂��B
����x�݂���
�@�|���ݒu�o���܂����牡�l�֏��҂��܂��B
�@�����Œ���̐V�������Β��ɂ͐V���l�A��A��w�ʼn��ł��B
���X�v�[�j�[�V���b�v����
�@�f�̗��ς܂������͑A�܂����ł��A�@����ő啪��ނ�ł��B
�@�ł��A�l���y���܂Ȃ��Ƃ����܂���ˁA�@����V�[�Y���N���N�n�A�Q�����f�ʼn߂����\��ł��B
����[��������������
�����`�I�����W�p�[�N���܂������B�����ł��ˁB�����͂܂�����C�z������܂���B
�@�@���̏��́A9/19�ɘA������A�c�������ƁA�@�Q�U�������A�P�O/�P���z�ē��A3�A�茳�ɁA
�@�@ (��)�h���[���N���G�[�V�����ɔ����ł��B
�@�@�m��o���Ă��ăj���}�����Ă��܂��A���͏o���Ă��܂���B
�@�@�g�ݗ��ăX�s�[�J�[�@�@�ʐ^�A�폜����Ӗ��s���ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�@���@�����牽�Č���Ȃ��ʼn������B�@
�����ԍ��F25914646
![]() 1�_
1�_
https://www.seibundo-shinkosha.net/mj/?p=4260
���}�n�Ƒn��X�s�[�J�[���쁕�����C�x���g�A�s���Ă��܂����B
BOWS����AArchitect1703����Amatu85����A�����l�ł����B
�ʐ^��UP���悤�Ǝv�����̂ł����A�l���f�荞��ł��āA�}�X�N����̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA��ق�BOWS�������Ə�肢�ʐ^��UP���Ă����ł��傤����A�l�͏ȗ���
�ߑO�P�P������A�x�e�����݂Ȃ���P�W���܂ŃK�b�c���ƂP�O�{�̃X�s�[�J�[���܂����B
�����Č�����̂́A�����Ȃ��E�E�E�E�ł����B
�ǂ̃X�s�[�J�[���A�A�C�f�A�A�����ڂ��悭�A�쐬�R���Z�v�g��������Ɖ��ɔ��f����Ă��đf���炵�������B
�����āAYAMAHA�̃X�s�[�J�[���j�b�g�ɑ���m�E�n�E�̐[���������������܂����B
�����d�q�s�A�m�ɓ��ڂ��邩������Ȃ����j�b�g�炵���̂ł����A�����ڂ͐����`�[�v�Ȃ�ł����A������������ɓ]�����Ă����̂ŁA���ʂȂ狖����Ȃ����炢�G�点�Ă��������܂������A�����ڂ̃`�[�v���Ƃ͂������ꂽ���J�ȏo���ŁA�N�\�A���ꂪ���E��YAMAHA�̎��͂Ȃ̂��Ƃ�
�R�[���́A�x�[�X�����ԂȂ�ł����A��������ݍ��܂��Ă��銴���ŁA�ǂ����̃t�H�X�e�N�X�̃K�T���������͂܂������Ȃ��A�w�Œ@���Ė炵�Ă݂�ƁA��������Ƃ����u�R�c�v�Ƃ����������āA�u����͂������̂��`�[���v�����A�G�b�W�̐ڍ������J�ŁA���̐ڒ��܂��J�������̂��ƕ��������Ȃ����̂ł����A�����Ȃ�������
�G�b�W�́A���A�u�`���Ƃ̂��ƂŁA���A�����邱�Ƃŏd���u�`�������^���j�b�g�̃G�b�W�Ɏg����y���ɂ����ƁE�E�E�E�E
���̃G�b�W�A�����ō��ł��BBOWS������A�G�b�W����̂ł����������ǂ��ƌ����Ă��̂ł����A�����킩��܂��B
�t���[���͓S�Ń`�[�v�Ȃ�ł����A���݂͂�����Ƃ����āA�@���Ă��J�[���͂Ȃ��A�`��ƌ��݂�������ƍl���Ă���낤�Ȃ��Ǝv�����A�_���p�[�͂���قǏ_�炩���Ȃ����ǁE�E�EMark����̃��j�b�g���݂Ă���ƌł������邯�ǁA����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��E�E�E�E�X�g���[�N���[������܂����B
�����p�[�c�ɑg�ݍ��킹��p�ɂł��Ă���̂ŁA���̂܂܂��ƃo�b�t���ւ̎��t��������̂ŁA���̂܂s�̂͏o���Ȃ����낤���ǁA�Ȃ�Ƃ��s�̂���Ȃ����Ȃ��E�E�E�E�E�EYAMAHA�̐l�Ɂu����A����Ȃ��́H�v�ƕ�������u����Ȃ���ł��A����Ȃ����ǁA�F�X�Ȑl�ɒm���Ăق�������A�F�X�ȏ��Ő�`���ĉ�Ђ����ė~�����v�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�����ɂ����܂��B
YAMAHA����A���ЁA���̃��j�b�g�����Ă��������I�I
���ۂɁA�x�^�x�^������āA���ꂱ�ꂵ�āA����ɁA�P�O�{�̃X�s�[�J�[�ƂP���t�������āA���̑O�ɁA�^BOWS����u��������v�Ɠ���݂����āA�o�����������Ă��邵�A����̗ǂ��A�R�[���̐U���̎����Ƃ��킩���Ă�̂ŁA�������C���X�p�C������Ă��܂��܂����A���̐ӔC��YAMAHA�͎��ׂ��ł��B
�����ɂ����A�Q�O�Q�U�N�����̃N���r�m�[�o�ɓ��ڂ����Ƃ̂��ƂȂ̂ŁE�E�E�E�F�͈Ⴄ�����ł��B�ň��́u�̏Ⴕ�܂����v�ƕ��i����������̂��Ȃ��ƈ������Ƃ��l���Ă��܂��Ă���̂ł����A���̃��j�b�g�A���������P�O�N�����ĐU�����J�������̂ł�����A�K�K�������āA�K���K�������Ă���������
�Ȃ̂ł����A�����Ȃ���v�����̂́A����ς�PARC�̃E�b�h�R�[���ƁAFOSTEX�@GX-100Limited�͂���ς����Ȃł�����
�悭�킩��Ȃ��̂ł����A�Ō�́u�}���\�������v�ł܂Ƃ߂ĂP�O�{�̃X�s�[�J�[���Ă�����A�]���Ɂu��r�C���[�W�v�ŏo�Ă����̂͂��̂Q�B
�����ԍ��F25917247
![]() 6�_
6�_
��BOWS����
��Foolish-Heart����
��matu85����
����͂���ꂳ�܂ł����B
�����ȊO��9��i�i���V����������10��i�ł���w�j�́A�������������ꂽ�M�ӂƘJ�͂ƋZ�p
�i���łɃR�X�g���j�����[�Ȃ��A�����������ɋ��Ă����낤���Ǝ�����Ă��܂����B
�Ƃɂ����d�グ���������Y��B
�l�ɂ���Ă͐��쒆�̃G���N���[�W����YAMAHA�̃��j�b�g�ɓ]�p�������̂�����܂������A
���ꂼ��̃A�C�f�B�A���f���炵���A�C���X�p�C�A����ċA���Ă��܂����B
BOWS�����͉������痈���āA�̗͓I�ɂ���ς������Ǝv���܂��B�{���ɂ���ꂳ�܂ł����B
�����ԍ��F25917717
![]() 5�_
5�_
 |
 |
 |
|---|---|---|
���V�搶/��J�o�b�t��/12�ʑ�SP/�Γc�w��BHBS |
���r�ǁ{�RD�v�����^�z�[��/�ϑw�_�u���o�X���t/6.5Kg�f�b�h�}�X/�y��^�o�X���t |
�A���~����N���[�W��/��^7�p�`�o�X���t/�����\���t���t���A�o�X���t |
Arch����
Foo����
matu����
�@�����l�ł����B
�@����3�����قǁ@���̃C�x���g�ɒ��͂��Ă����̂Ł@����ƏI������`���Ă��ł��B
�@
�@���Œ���܂������A�����ڂ͖}�f�ȃ��j�b�g�ł����A�U���A�G�b�W�A�_���p�[�̍�荞�݂��ǂ��ā@���낵���ׂ������܂ŏo�Ă��܂��B
�@���V�搶���킹�ĂP�P�{�̍�Ⴊ���o�����܂������ǁ@���ꂼ����������Ėʔ��������ł��B
�@���Ɉ�ۂɎc�����̂��@
�P�ԁ@��J�o�b�t��/��ʊJ���^�@���j�b�g�̑f������������
�S�ԁ@���r�ǁ{�RD�v�����^�z�[���@�ςȋ��U���̏o�₷���l�K�Ȉ�ۂ̉��r�ǃX�s�[�J�[���`���[�j���O���čr���Ȃ���\�������A�y������̂͌���
�U�ԁ@�����̂ł����A�𑜕����ɐU�����SN�̍������́A���Ƃ��Ȃ�Ⴄ�悤�Ɏv���܂����B
�X�ԁ@Arch����V�p���@��e�ʃo�X���t�炵���@�X�g���X���Ȃ����������Ă���
�P�O�ԁ@�����\���t���̃g�[���{�[�C�o�X���t�@���̖�����A�L�ѕ������炵���B
�@
�����ԍ��F25918547
![]() 6�_
6�_
 |
 |
 |
|---|---|---|
�������̗l����ۂɎc���i |
�f���Ŕ��ɏo���̗ǂ��������đ��̗e�e�i���j�@���̉����{���ƕ������ė��܂��i�E�j |
�d�S�Ⴂ�S�n�悳 |
BOWS����
Architect1703����
��i����Ɣ��\�ْ̋��A�����l�ł����B
BOWS����
Architect1703����
Foolish-Heart����
��̌����钇�Ԃɂ��Ē����L��������܂��B
�悸�́A�����Đ�����ϔO�ƈႢ�A�������o���́A���ƊS�������ł����B
���A���j�b�g������l�ɂȂ�����A�S�{�w�����A���V�搶�̗��_���Ă݂����A�Ǝv�����B
�����ԍ��F25920370
![]() 3�_
3�_
matu85����
�@�����l�ł����B
�@�������j�b�g���g���Ă��@�v�҂̍l�����ɂ���Đ獷���ʂ̖�������Ėʔ��������ł��B
�@����ƁA�����̈����Ȃ��������莝���Ă���Ȃ��Ǝv�����B
�@�����͎G�H�Ȃ�Ł@�����ȋȂ��Ă܂���....�������Ɍ|�\�R��g�̂悤�ȕϑԋȁH���`���C�X�����l�͋��܂���ł����˂�
�@����Ɓ@11/16�Ɂ@���Œ������悤�Ɂ@���}�n���j�b�g��ςT��̃X�s�[�J�[���W�߂Ė����킹�����܂��B
�@
�����ԍ��F25922466
![]() 3�_
3�_
�X�s�[�J�[�́A���j�b�g�ƃG���N���[�W���[�������āu���v���ł�̂ł����A���j�b�g�Ɋւ��Ă̓X�y�b�N��������Ă��āA�G���N���[�W���[�̃X�y�b�N���Ď��ɂ����鎖������܂Ȃ���ł���ˁB
���ǂ̒���=�Đ��ł�����g���A���ɒ��A���U�ǂ̋��U���g���͏�����Ă��邱�Ƃ������ł����A���Ƃ́A�ގ������Ȃ̂��Ƃ������ǂꂮ�炢�Ȃ̂����炢�ŁA���j�b�g�X�y�b�N����A�g�ݗ��Ă��X�s�[�J�[�̃X�y�b�N����u���Ԃ�A�����Ȃ낤�ȁv������o�������Ȃ��̂ł����A����ȃf�[�^�������Ă��A����z�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�ǂ����A���̎����킩���Ă��Ȃ��l���Ă̂������悤�ȋC�����Ă��܂��B
�G���N���[�W���[�̍ގ��A���A�`��A�h���i�������j�A����͏d�v�ȉ������߂�v�f�ŁA�����v�ŁA�ގ���ς��������ʼn��͕ς�邵�A�h���ł�����邵�A�X�s�[�J�[�H��̓|�C���g����R����܂��ˁB
�z���ނ��A�������߂�d�v�ȗv�f�ŁA�z���ނ��āA�z�����邯�ǔ��˂�����̂ŁA���̔��ˉ����G���N���[�W���[�����ł�����Əo�Ă���̂ŁA�u�����̗ǂ��z���ނ��K�v�v�Ƃ����A�z���ނ炵����ʌ��t���o�Ă��܂��B
BOWS��X�s�[�J�[�����t�@�C������Ƃ�����A�h�����ȂƂ��l�͎v�����肷�邗
�R���e�X�g���O�ɁA�n���J�`�ŕ\�ʂ��ӂ��Ă��āu���b�N�X���͂���Ă�v��BOWS���{�\�����Ă����̂ł����A�d�グ�́u�Ԏ�v�������ĂȂ��A���b�N�X�̍��荞�݂������̂��႗�i�̂����Ɍ����Ă܂����A�������A�l���F�l�ɂ悭�����Ă����j
���ꂢ�Ȗؖڂ������Ă�ޗ����g�����ɂ́A���b�N�X�d�グ���u�l���D���v�Ȃ̂ł����A���̃��b�N�X�������g���̂�������ł��ˁB
�d�オ�肾�����l����̂ł͂Ȃ��A���܂ōl������ƁA�������������̂��킩��Ȃ��B
�^���m�C��JBL�̃��[�U�[�́u�V�R���X�v���g�������b�N�X���D�݂܂����A�o�����I�Ɂu���X�v��h��Ɖ����u�D�����Ȃ�v�Ƃ����Ă��܂����A�����V�R�f�ނ̃J���i�o�́A���X�������������d�߂ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B
���X�ɂ��Ă��J���i�o�ɂ��Ă��A�������i�Ȃ̂ŁA�����ȃ��m���g�����Ƃ͂܂��Ȃ��̂ŁA�Y������Ă��鑼�̍ޗ��ł����͕ς��̂ł��̕ӂ́u�s�s�`���v�ł͂���܂��B
���Ȃ݂ɁA�J���i�o�Ƃ����ƁA�J�[���b�N�X��z������l������Ǝv���܂����A����ł���
���̌n�̃��b�N�X����������蒅�����邽�߂ɁA���n�ނƂ����̂�����̂ł����A������V�R�I�C���n�ƍ����n�������āA��y�ł�����Ɛ��\���ł�͍̂����n�ŁA���������������B
�����āA�h�������Ă����ƁA�u�s�A�m�h���v�������ɂ������Ȃ��ƁE�E�E�E�s�A�m�h�����n�߂�l���łĂ���̂ł����A����͂���ς肢���݂����ł��ˁB
�ŋ߂ł́A�J�V���[+�E���^���h�����Ă̂��P�t�łł���炵���A�J�V���[+�E���^���̓h���Łu�^���I�v�Ƀs�A�m�d�グ�ɂ���̂����I�ɂ������Ƃ���āA�����X�s�[�J�[�ɂ����Ă�����A����ł���Ă�l���łĂ��Ă��܂��B
�Ƃ������ƂŁABOWS����́A���ɗǂ��h����T�����ɏo��ƁE�E�E�E�E�E
�����ԍ��F25923067
![]() 2�_
2�_
BOWS����
����́A�L��������܂����B
���߂Ă̕�����ׁA�������j�b�g�ł���Ȃɂ��Ⴂ���o��A���������̂P���ł����B
�y��̈ꕔ�ŗL�郆�j�b�g�A�`�F���o���ł��A�A�j�\���A�ǂ�ȉ��ł����Ȃ��D�ꕨ�A
�������̈����Ȃ��������莝���Ă���Ȃ��Ǝv�����B
�@�F�l�A���ׂĂ��S��̉�ł��ˁB
�@�m��s�������y�ȂŁA���ׂĂ̍�i�A�����Ă݂����C�����܂����B
��11/16�A �I�����W�p�[�N�ĎQ���������Ȃ��@�Ǝv���܂����A���Ԃ�����Ȃ��A
�@�`�b�g�A�����������B
Foolish-Heart����
�䂪�A�Q�O�ʑ́A �^���m�C��JBL�̒��Ԃ��A���X�A�`�Ӗ��A���b�N�X�̎d�グ�B
����͂���
�S�R�S�R�C����Ċm�F�A�S�R�S�R�a�ł����B
�����ԍ��F25930808
![]() 2�_
2�_
matu85����
4343B�ł��A�����ł��炦��̂Ȃ�A��������Ⴂ�܂��傤��
�S�R�S�R�����AB���D�ސl�����邮�炢�ŁA�e�C�X�g�͌��\�Ⴂ�܂����A�A�����J����JBL�𖡂키�ɂ͗ǂ��X�s�[�J�[�ł��B
�A���ɂ��ẮA�{�̂������Ȃ̂ŁA�R�����炢�����Ă��s�A�m�^��������Ă�Ǝ҂ɗ��ނ̂��悢�Ǝv���܂��B
�厖�Ȃ��ƂȂ̂ʼn���������܂���
�S�R�S�R�́A�SWAY�Ȃ�ł����A�l�����Ƃ��ẮAMID-LO��MID-Hi�̂QWAY�ɃX�[�p�[�c�C�[�^�[��t���āA����ɃX�[�p�[�E�[�n�[�����Ă�ƍl����̂��ǂ��ł��B
�w�ʂ̃^�[�~�i���ɃX�C�b�`������̂ł����A����̓o�C���C���[/�o�C�A���v�̂��߂̃X�C�b�`�ł͂Ȃ��āA�P���ɃE�[�n�[��藣���X�C�b�`�ł��B
�Ȃ̂ŁA�ŏ��́A�E�[�n�[��藣���ăZ�b�e�B���O�ƒ������ATT�Œ������āA�E�[�n�[���ォ��ON����Ɨǂ��ł��B
�Ȃ��A�E�[�n�[��藣�����ꍇ�A�E�[�n�[�p�̃R�C�����O��āA�E�[�n�[�͒[�q���璼������܂��B����𗝉����Ȃ��ŃE�[�n�[��4312�̂悤�Ƀt���������W�Ŗ炵�Ă郆�[�U�[����͌��\���܂��B
�`�����l���f�o�C�_�Ńo�C�A���v�����Ȃ��Ă��A�E�[�n�[�p�̃l�b�g���[�N���O�t���ɂ��Ď�����Ă̂�����ł��B
�S�R�S�R�́A���܂���������Ɓu���́v���ĉ����ł�̂ł����A�g�����Ȃ�������Ƃ���������āA���\����܂���
�ł�matu85����Ȃ�A������y����ŁA���������������ł��ˁB
�����ԍ��F25931087
![]() 1�_
1�_
Foo����
>�ǂ����A���̎����킩���Ă��Ȃ��l���Ă̂������悤�ȋC�����Ă��܂��B
�@�G���N���[�W�����p�����[�^�ς��Ē�����ׂ邩�A�߂��o�������Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��ł��ˁB
�@���}�n�����ɑ��������씠�́A15mm���@���h�������������o�[�ő���܂����B
�@�{����́@���e�ʂƓ������@�͑S������Ł@20mm�� ���b�N�X�d�グ�A�J�V�A�W���ނő���܂����B
�@�\�Ȍ���A����U�������Ȃ��悤�ȍ\���ɂ����̂Ł@�{���A�قƂ�Ǎ����Ȃ��͂��ł��B
�@�������ɁA��{�I�ȂƂ���͕ς��Ȃ��̂ł����A���F�̐����̂��ꂩ���A�������͑喡�Ȋ����ł����B
�@����́A�������Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��ł��B
�@�p�����[�^�͂R��
�@�E�؍ނ̎�ށ@�����������o�[/�A�J�V�A�W����
�@�E���@15mm/20mm
�@�E�\�ʎd��@�Ȃ�/(���X�n)���b�N�X�d�グ
�@�����ɂR��̃p�����[�^�ς����̂Ł@�e�X�̊�^�͂͂����肵�Ȃ��̂ł���
�@���܂ł̌o������A�\�ʎd�グ�@�e����/���@�e���@��/�؍ނ̎�ށ@���Ȃ��
�@�z���ނ́A��ݔg��ɂȂ��Ł@���A�ʂ����łȂ��A�ǂ��ɔz�u���邩�������܂��B
�@����A�f�b�h�}�X�x���̂��߂ɁA���J���d����Q�ӏ��Ɏ��t������ł����A�����ɋz���ނ����t���܂����B�G���N���[�W���̓��ʑ��ł͂Ȃ��A�ɕ������悤�Ȋ����ł��B
�@
>BOWS��X�s�[�J�[�����t�@�C������Ƃ�����A�h�����ȂƂ��l�͎v�����肷�邗
�@�h���͖��h���ɋ߂����́@�I�C���d�グ�A�`�a�d�グ�A���b�N�X�d�グ�Ȃǂ̃O���[�v�Ɓ@�d���h���̓h���O���[�v�ɕ��ނ���ā@���h���O���[�v�́@�ڂ�[���Ƃ��Ă�����̂̕ςȃN�Z�͂Ȃ��Ė؍ނ̑f�̉����o�Ă��ā@�h���O���[�v�́A�h���̍\���ɂ���ĐF�X�����ς����̂Ƃ����F���ł��B
�@����Ȃ���A�{���h���Ł@�ȑO�䎋�������Ƃ���{���h�������̂������d�߂ʼn𑜂̍������ł����B
https://www.youtube.com/watch?v=_x6TR82agQo&t=9s
�@����....����E�l���������Ȃ����ƂŁ@�E���g�������������[��
�@�h���́A�����ł�낤�Ǝv���Ɠ���A�I�C���X�e���R��{�j�X�R�炢����ā@�悤�₭�y��_���Ă��Ł@���܂�ɖʓ|�������̂ōŋ߂���Ă܂���B
>�R���e�X�g���O�ɁA�n���J�`�ŕ\�ʂ��ӂ��Ă��āu���b�N�X���͂���Ă�v��BOWS���{�\�����Ă����̂ł����A
���[����A�����ƃ��b�N�X���������Ă�����ł����A�������������������ĉ^��A�X�|���W�ŐڐG�����ӏ������������Ă��Ƃł��B
�@���}�n����߂��Ă�����A�����P�b�N�X�����܂��B
�@���b�N�X���ā@�y�ł����A�؍ނƂ��ā@MDF�⍇�ɂ͎g���ɂ����ā@���C��W���ނłȂ�Ǝg���ɂ����ł��B
>�ŋ߂ł́A�J�V���[+�E���^���h�����Ă̂��P�t�łł���炵���A�J�V���[+�E���^���̓h���Łu�^���I�v�Ƀs�A�m�d�グ�ɂ���̂����I�ɂ������Ƃ���āA�����X�s�[�J�[�ɂ����Ă�����A����ł���Ă�l���łĂ��Ă��܂��B
�@�J�V���[�͐e���������̎d�グ�ɂ悭�g���Ă�����ł����A�����̂����낵���x���i���̂Ԃ�\�ʂ̕��R�x�������j�̂Ł@�����������Ԃ̊ԁA���������ꏊ���m�ۂ���̂������ł���
���Ƃ������ƂŁABOWS����́A���ɗǂ��h����T�����ɏo��ƁE�E�E�E�E�E
�ǂ��h���͂��邱�Ƃ͔F�����Ă����ł����A�����̊��ƋZ�ʂ����Ă����Ă܂���(��)
matu85����
>���߂Ă̕�����ׁA�������j�b�g�ł���Ȃɂ��Ⴂ���o��A���������̂P���ł����B
�@����́@���ۂɕ����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��ł��ˁB
�@�M�d�ȑ̌��Ł@���Q�O�O�O�������l�͂���܂��ˁB
>>�����̈����Ȃ��������莝���Ă���Ȃ��Ǝv�����B
>�@�F�l�A���ׂĂ��S��̉�ł��ˁB
>�@�m��s�������y�ȂŁA���ׂĂ̍�i�A�����Ă݂����C�����܂����B
�@���������A��҂̌����Ă�������ƁA��������́A�o�Ă��鉹�y�ƁA���y�̂�����Ȃ��킩���Ėʔ����ł��B
�@�l�́A�G�H�Ȃ�Ł@���낢�땷�������肵�Ă܂��B
�@���ϑԋȂ̌|�\�R��g�́@�����g���Ă�낤�ƃX�g�b�N���Ă������̂ł��B
>> 11/16�A �I�����W�p�[�N�ĎQ���������Ȃ��@�Ǝv���܂����A���Ԃ�����Ȃ��A
>�@�`�b�g�A�����������B
�X�s�[�J�[���������Ă�����Ă������ł���
�ꏊ�́@���music & Cafe�ł��B
�i�s�͌�����
�����ԍ��F25931843
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
���Ƃ����܂肻���ł��B
������������ˁA���music & Cafe�֍s�������ł��B
�G�[�W���O�Ƃ��A�o���������Ȃ��ł����A�`�����͉��Ƃ����肻���A
�\��}�́A�����^�J�[�ő���\��ACafe�O�̋������ɂ��s���Ă݂������B
�ڍח\��X�����B
�����ԍ��F25948527
![]() 3�_
3�_
matu85����
�@�C�x���g�̏ڍׂ́@�ǁX�@�������Ɍf�ڂ����\��ł��B
https://www.facebook.com/events/1063907168161778
�@13:00�J�� / 13:30�X�^�[�g�̗\�� / �I�� 15:00���̌�����
�@�I�������A�����v�������܂��B
�@���̌�́A�e�L�g�[�ɍD���Ȃ���@�炷���ƂɂȂ肻���ł��B
�@Music & Cafe�ɓ���Ɓ@REALITY CRAFT SPEAKER����̒���~�j�X�s�[�J�[�R���N�V�����Ɉ��|����܂��B
�@���������X�s�[�J�[�ɐ�ւ��Ė炷���Ƃ��o���܂��B
https://www.facebook.com/photo/?fbid=515331144582227&set=pcb.515331184582223&locale=ja_JP
�@�������́@Cafe�̑O����Ȃ��ĉ��ł��B�������̒��ɁA�傫�ȃ^���m�C���AALTEC���������Ă܂��B���������i
�@Cafe�̓X��́A���Αł��̎��i�����Ă��Ă���q���悭���܂��B
�@�X���J���x�Ɏd����̋����̎Y�n��ς��Ă���̂Ł@�\�̏��������ɁA�@�u�����́Z�Z��XX�n���̋����v���ď����Ă܂��B
�@�Ԃ�Cafe�̉��ɓ˂�����ŃX�s�[�J�[�����낵����A���̔��Α��̑傫�Ȓ��ԏ�Ɉړ����Ē�߂Ă����悢�ł��B
�����ԍ��F25950812
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
�����b�ɂȂ�܂��B
�����̊y���݂��d�˂��A���s�r���ɂȂ�܂��B
���ɋ��������@�A�ꍇ�������s���܂��A�����f�|���܂��A�X�������肢���܂��B
�X�s�[�J�[�P�[�u���@�ʐ^�̈����[�q�ŏI����Ă��܂��A���̂܂܂ő��v�ł��傤���H�B
���݁A��1�`�Q���ԉ��o�������Ă��܂��B
�����ԍ��F25957066
![]() 1�_
1�_
matu85����
>�����̊y���݂��d�˂��A���s�r���ɂȂ�܂��B
�@�y�������ɂȂ肻���ł��ˁB
>���ɋ��������@�A�ꍇ�������s���܂��A�����f�|���܂��A�X�������肢���܂��B
�@���������A���Ă��������邾���ł��肪�����ł��B
>�X�s�[�J�[�P�[�u���@�ʐ^�̈����[�q�ŏI����Ă��܂��A���̂܂܂ő��v�ł��傤���H�B
�@O�`�͂����炭�ʖڂŁ@C�`���o�i�i�@�܂��͗����̕����x�^�[�ł��B
�@
�@��12�ʑ̃X�s�[�J�[�Ƃ̔�r���ʔ������ł��B
�����ԍ��F25957975
![]() 1�_
1�_
�@����@���}�n�o�i�� �R��i�Ɓ@�{ �Q��i�̖����킹����܂����B
�@�����݂�萷���Ł@�݂Ȃ���y����ł����������悤�Ȃ̂ŗǂ������ł��B
�@�������j�b�g���g���Ă���ɂ�������炸�A�T�l�̍�҂ɂ��@�n�ӍH�v���Â炵���X�s�[�J�[�́A���ꂼ��@���F�鉹�Ŋy���������ł��B
�@���ɁA�������y�ʋ��̃X�s�[�J�[�̖���Ղ肪�悭�ăA���R�[���������Ă܂����B
�@�ԊO�҂Ŗ炵���@matsu����́@�I�����WPARC �Q���ڂ�20�ʑ̃G���N���[�W���́@�ƂĂ��ǂ�����Ղ�Ł@PARC�ŐV���j�b�g�̉������\�ł��ėǂ������ł��B
�@������藈�Ă����������@Foo����Amatsu����@�����č�i�݂��Ă�������@Arch���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25964401
![]() 7�_
7�_
BOWS����Amatu85����
�����l�ł����B
�ʔ��������ł��ˁAMJ�̎��������u���v�������銴���ŗǂ������ł��B
�Ȃ�Ƃ������A�g�т��q����Ȃ��R�̒����Ƃ͎v��Ȃ��������ǂ�
��ł��A�v�������艹�������āA�D������o���銴�͍ō��ł��ˁI�I
�A���~�����ނō��ꂽ���^�E�y�ʃG���N���[�W���[�̓z�͖{���ɐ����Ǝv���܂����B��������̗��H���R�Ƃ��������ƁA��������Ȃ��炫����Ɨ��_�Ɋ�Â��č쐬����X�^�C���͖{���ɑf���炵���B���ꂪ���A�u���������������������v�̖{������˂�
�ނƘb�����ł��邾���ł��Q���Ӌ`�����邮�炢�Ɏv���܂����B
�����āAmatu85����̃A���A����͂����������őf���炵�������B
���̃��j�b�g���̂��̂��u���܂����Ɓv�`���[�����ꂽ���̂ŁA���������ш�������������o���Ă�B
���̃��j�b�g������y��͂���ς萦���ł��ˁB����A����͂���܂�o�ĂȂ��̂ł����i�ƌ����Ă�16�������܂ŏo�Ă邯�ǁj�A���b�`�ŃX�C�[�g�Ȓ��ቹ�ŁA�Ⴆ��̂Ȃ�S�����̌˓c�q�q�搶�̃A���g�{�C�X�̂悤�ȃ��j�b�g�ł��ˁB
������A���X�s�[�J�[�̂悤�Ȋ����Ń��b�`�ȃe�C�X�g�ɂ܂Ƃ߂�matu85����̃Z���X�̍����͒E�X�ł����B
���ʂ̃X�s�[�J�[�ł͍Č������炢�ABOWS����̕��䉹�������Ȃ�ǂ������ōĐ����Ă��āu���X�s�[�J�[�v�̂悤�Ȏg�������ł��邯�ǁA������ƒ��S�ɗ���ƒ�ʂ��A�N�e�B�u���j�^���݂ɗǂ����Ă̂͗ނ����܂�Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�r���ŁAmatu85���X�s�[�J�[�̌�����ς��ă��X�i�[�ɑ��ă��j�b�g��90�x�ɂȂ�悤�ɂ��Ă��A���̃X�s�[�J�[�͈�a���������Ȃ����炢�ɖʔ����̂ł����A���̎���matu����́u���Ă������v�̊炪�����[�悩������
Architect����̂����炿���́AMJ�̎��ɂ́u�����A���b�`�ŗǂ��X�s�[�J�[���ȁv�Ǝv�����̂ł����A������u���b�`�ŕ����₷���v�ƂĂ��f���炵���X�s�[�J�[�ł���Ƃ͎v�����̂ł����AMJ�̎��Ɋ����Ȃ�������_����������āA�����������ގ��A���Ɋy��̐������X�ɏ����Ă����悤�ȏ��ň�a������������A���b�`�ȋ����Ȃ��ǁA���o�I�ɂȂ����Ⴄ�̂ł����u�����v�Ȃ�ł���ˁB���b�`�Ŕ������āA����͂���łȂ��Ȃ��ǂ��̂ł����A�Ȃ낤�A�d������ׂ������҂��Ă���A���������C�Ăāu�����`�����悤�v�I�ȁA�����܂łЂǂ��Ȃ��̂ł����A�Ȃɂ�����������Ȃ��̂��A�ǂ�����U���Ă�̂��Ȃ��E�E�E�E�E�E�E�E�l�ɂ͂�����ƃA�C�f�A���o�Ȃ������̂ł����A�u�Ȃɂ��v�u�ǂ����v�ɂ����ƃ��t�@�C������]�n������悤�ȋC�����܂����B�Ȃ�ł��傤�ˁA�u�ǂ��������䂢�v�B
���Ȃ݂ɁA�l�̓C�x���g�̌�A��ˉ���ɔ��܂�܂����B
�����A��ˉ�����Ēm��Ȃ������A��˂Ƃ����Ε�ˉ̌��c�̃C���[�W�����Ȃ��A��ォ��25�����x�ōs����u�s�s���v���Ǝv���Ă����̂ł����A��������ƎR�̒��ŁA�������{�ɂ������ɂ������ŁA������߂��Ⴍ����ǂ������ł��ˁB
��ォ��킸��25���ŁA���ꂪ������āA��イ���܂�����
�[�тȂ��A���t���ŁA���̒����т����������āA������悩�������A���т������������A�i�F�����\�������A������O�c�I�[�f�B�I��ɍs�������ɂ͎g�������ȂƂ��v���܂����B
�����ԍ��F25965525
![]() 5�_
5�_
��BOWS����
�����킹����l�ł��B
BOWS����̃G�l���M�b�V���Ȋ����ɂ͌h�ӂ�\���܂��B
��Foolish-Heart����
> �Ȃɂ�����������Ȃ��̂��A�ǂ�����U���Ă�̂��Ȃ��E�E�E�E�E�E�E
���u�]���肪�Ƃ��������܂��BFoo����̊m���Ȏ��ł����Ȃ�ł��ˁB
�Ƃ������A�����ł͂܂����܂蕷������ł��Ȃ��̂ŁA�ǂ����ǂ���p���Ă���̂��悭�������Ă��܂���(��)
����̃V�X�e���́u���܂���肭�s�����v�I�ȂƂ�������������Ǝv���Ă��܂��B
�Ȃ̂ŁA�߂��Ă��Ă��炠�����������낤���ȁA�ł����̃o�����X������\��������̂łǂ��܂ł�邩�B
�܁A�������Ă���ł��ˁB
�����ԍ��F25965684
![]() 2�_
2�_
Architect1703����
�]��������Ȃ��̂́Aarchitect����̃��j�b�g�́u�قڐV�i�v�Ȃ̂ɑ��āABOWS����B�̃��j�b�g�́u����Ȃ�ɖ炵�Ă���v�̂ŁA�܂��d��������Ǝv���̂ŁA�������Ԗ炵�Ă��������ɂǂ��Ȃ�̂��ł���ˁB
�������A�O�c�̉��͂��Ȃ艹�ʂ��グ����A�O�Ń^�o�R���z���Ă��Ă����ʂȂ�����郌�x���ʼn����R��Ă��Ă����������l�����Ȃ��Ȃ̂ŁA�������ň�莞�Ԗ炵����ł����烆�j�b�g���G���N�������Ȃ�
�I�N�������́A�㉺�������ʂł����A�ォ�狐��ȃ|�[�g�������āA���ꂪ���j�b�g�̗�������o�鉹�U�����Ă���̂ƁA���ʂɕ��s�ʂ������̂Œ�ݔg���N���ɂ����B������ƃV�~���[�g�����킯�ł��A���肵���킯�ł��Ȃ��̂ŁA�{���Ȃ̂��͂킩��ǁA�݂��߂���Ȋ���������ˁB
�ŁA���̃��j�b�g�́A�ׂ�������������Əo�邯�ǁA�p���t���Ō��\�u��v���j�b�g�Ȃ̂ŃG���N���̗e�ʂ��X�Z���`���j�b�g�Ƃ��Ă͑傫�����Ă��u������v���������܂����A���ۂɂ�����Ɓu�e�ʂ��������ˁH�v���炢�̑傫���ł��A���ꂪ���b�`�����o���Ă���̂͊m���ł��B
��U��Ƃ��������̂́A�Ȃ�Ƃ������u�����鉹���v�Ɓu������Ȃ������v�������āA��{�C�����ǂ����Ȃ�ł����A�Ȃɂ��u���܂ɁA�ӂƗ͂������Ă�v�������܂����B
MJ������f�[�^������Ă���Ă���̂ł����A�s�^�ʖڂȖl�͂�������ĂȂ��̂ŁA���ۂɖl�̊��o������f�[�^�ƈ�v���Ă���̂��͂킩��Ȃ��̂ł����A������u�������v�Ƃ͈Ⴄ��ł���ˁB
MJ�̕i�]��́u���ʂ̕����v�ɁA�ꉞ�A�����p�̑�����Ă����̂Łu������ƁA�킩���Ă�l�̃I�[�f�B�I���[���v�Ȃ̂ɑ��āA�O�c�̉��͓V��������������A�V�䒣���ĂȂ����特�����������A������Ƃ���ɃX�s�[�J�[�������āA���ɔw�ʂɑ�ʂ̃X�s�[�J�[������̂ŁA�����̋������Ⴄ�̂ł��������Ǝv���܂��B
BOWS����A�������̕����̓����𑪒肵�Ăق��������Ƃ����������ǁA���́A�A���~�X�s�[�J�[�̐���҂����āA���肵�Ă��Ȃ��킯���Ȃ��̂ŁA�ǂ��Ȃ̂��Ȃ��Ƃ��v�����肵�Ă��܂��B���t�ɁA���̕����̓����ƁAmatu85����̍�i�̑��������͗ǂ����ĉ\��������킯�ł����B
�Ƃ������ƂŁABOWS��VSArchitect��VSmatu85��́A�R��i�ɍi�������X�j���O����������ł���āA�݂�ȂŒm�b�̗֓I�ɂ��ꂱ�ꂵ�Ă݂����ł��ˁB
�֓��g�Ɗ��g�̒��ԓ_�A���É�������łǂ��ł��傤�H��
����̎O�c�ł́A��r�Ƃ��āu��ʓI�Ȏ���X�s�[�J�[�v��p�ӂ��Ă��܂������AGENELEC��8030+RME ADI-2pro�̒�ԑg�ݍ��킹�Ƃ̔�r�������ق����킩��₷���Ƃ��v�����肵�܂��BADI-2�͖l�������Ă��������̂ŁAGENLEC���������^�����܂��傤�B
�����ԍ��F25966249
![]() 1�_
1�_
Foo����Amatu����AArch����
>�A���~�����ނō��ꂽ���^�E�y�ʃG���N���[�W���[�̓z�͖{���ɐ����Ǝv���܂����B��������̗��H���R�Ƃ��������ƁA��������Ȃ��炫����Ɨ��_�Ɋ�Â��č쐬����X�^�C���͖{���ɑf���炵���B���ꂪ���A�u���������������������v�̖{������˂�
�@�悭�b���Ă����ł����A���肵�ĉ��������������Ď咣�́@�P�ɁA������@�����n�ʼn����̍�������ĂȂ��������낤�Ɛ������Ă��܂��B
�@�X�s�[�J�[�ł��@�X�s�m���}�Ƃ��V���������w�W�����܂ꂽ�悤�ɁA�����Ƃ����@�悭�킩�����̂��𖾂��悤�Ƃ����w�͂��d�˂�@������𖾂ł���Ǝv���܂��B
�@�ނ��u�������̂͑n��v�̐��_�ő��葕�u�A���@�������ō���Ă܂�����ˁB���茋�ʂ��d�v�ł����A���̊J���ߒ��œ�������̂��傫���Ƃ������Ƃł��B
�@NHK�̃A�j���ł���Ă܂����A�V�̊ϑ��̐��x�Ɗϑ����ʂ��������Ȃ��Ă���A�V�����̖��������݉����Ă��邱�Ƃ�������A�n�����Ŗ����Ȃ����Ƃ��F�m����鎞��ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
�@�����Ɋւ��Ă��@�]�����@���i�ނɂ�ā@������������̋�_��D���V�����h��������s���l�܂��Ă���Ǝv���܂��B
�@�����X�s�[�J�[�́A�Ǝ��ɑ����������ā@�p�����[�^��ς���x�ɁA����Ǝ������J��Ԃ��A����G���N���[�W���𐔂��Ȃ��ā@�����̃p�����[�^�̗��Ƃ�����T���ĊJ�����Ă��������ʂȂ�Ŋ����x�������ł��ˁB
�@���ɁA�l�́@�u�U���ȊO��Ζ炳�Ȃ���`�v�̏d������X�s�[�J�[�Ɣ�ׂ�Ɓ@��������ɂȂ��Ă���̂��ǂ�������܂��B
�@����@���Ƀo�����X�悭�A�i�悭�@�K�x�Ɋy�����炷�����ɂ߂Ă���̂Ł@�y�����X�s�[�J�[�ɂȂ��Ă��܂��B����́A����炳�Ȃ��Ƃ����I�������@���{����Փx�������ł��ˁB
�@���łɂ����ƁAMDF�̔��͂܂Ƃ��ɖ�Ȃ��̂Ł@����ʖڂ��Ă̂́A�����ł����������Ă��ĒɊ����č���g�����Ƃ͖����Ǝv���܂��B
�@matu����́@20�ʑ̂ł����A��PARC�ł��������̗ǂ��_�A�����_���������Ă������ł������A��肢���ƈ����_��}���Ė��w�����Ƃ��Ă������ł����ˁB
�@�ቹ�͔����ł����A�ςɃu�[�X�g�����ĂȂ��̂ŕȂ������ėǂ������ł��B
�@�v�킸�@����Ђ�������Ă��܂��܂������A�ǂ������ł��ˁ`
�@�I�N���R���́A�D�����̖��C�E�H���i�b�g�@�Ɓ@����㓙�̃A���~�����ށ@�̊Ԃɋ��܂ꂽ���Ԃ������̂Ł@������ƈ�ۂ����܂��������ł����ˁB
�@�������Ɛ�����X�s�[�J�[�������̂Ł@������Ƃ�邢�������D���ł�����
�@�J�t�F�̃I�[�i�[�ɑ��k����A�݂��Ă��炦��̂Ł@�����ꎝ������Ė炷�@��͂���܂��傤�B
�����ԍ��F25966644
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
��Foolish-Heart����
���n�̊F���ܗL�������܂����B
���ɓ����čŏ��Ɋ������̂́A����̗L�鐰��₩�ȉ��F�A
���Y�p�C�A�Ԋ�ՁA�ς��Ȃ��̂ɍ��̈Ⴂ�A�ꐡ�l�����ށA
�R���f���T�[�Ⴂ�Ȃ̂��H�B
�F�l�A�^����Ȋ፷���Řb���Ē����A���ɑS�_�o���X���Ē����������܂����B
����Ђ�A�������l�Ȋ����ł����A���̑I�ȁB�i�A�ꍇ�����ړ��M���Ȃ����Ƃ��j
���́Asd�J�[�h�ɉ��������čs������ł��A�B
���̒��ɂ�Ǖ��A�ڔ��A�o�X�N���C�l�b�g�A�f�B�I�i���^�j�����L�����B
���C���Ő����ł����A�Ђ�A�{�l����łȂ���B
��ꂪ���ԕӂ�ł��ƁA�}�[�N8cm�A�f�b�g�}�X�L�薳���A���̈Ⴂ��r�o����l
�c�q�Z����h���ʼn^�ׂ邩���B
�I�����WPARC�@�g�[�^�� �T���Ԉʂ������o�����Ă��܂���A���A�{���̉��Ƃ́A
�ʂȉ����o�Ă��Ǝv���܂��B �P���ł͒����Ă��܂���ł����B
�����ԍ��F25967425
![]() 3�_
3�_
matu����
>���ɓ����čŏ��Ɋ������̂́A����̗L�鐰��₩�ȉ��F�A
>���Y�p�C�A�Ԋ�ՁA�ς��Ȃ��̂ɍ��̈Ⴂ�A�ꐡ�l�����ށA
>�R���f���T�[�Ⴂ�Ȃ̂��H�B
�@���ł���������Ȑ������܂������A���i���V�����炢�ς���Ă܂��ˁB
�@���c�̑ł��������悭�����܂��B
�@�������܂����ē����m�b���Ԃ�����ł܂��B
�@��x�@���É��Ń��C�u�����@�i�������Ă͖炵�ĊF�ŕ����j��������Ƃ������ŁA�܂��A�C�x���g�Ƃ��čl���Ă��悢�����ł��ˁB
>����Ђ�A�������l�Ȋ����ł����A���̑I�ȁB�i�A�ꍇ�����ړ��M���Ȃ����Ƃ��j
�@20�ʑ̃X�s�[�J�[�����ā@�ȁ`��PARC�̉������������ɋՐ����������ā@����͔���Ђ肾���Ǝv���܂����B
�@���悤�Ł@�ǂ������ł��B
�@�����@�}�C�N�����낢��]�����Ă��܂������A�^�������Ă܂��B
�@�C����������AYoutube�ɃA�b�v���܂��B
>��ꂪ���ԕӂ�ł��ƁA�}�[�N8cm�A�f�b�g�}�X�L�薳���A���̈Ⴂ��r�o����l
>�c�q�Z����h���ʼn^�ׂ邩���B
�@����������r���y�������ł��ˁB
�@��肽�����Ƃ͂��낢�날���Ł@�s�����������܂��傤�B
>�I�����WPARC�@�g�[�^�� �T���Ԉʂ������o�����Ă��܂���A���A�{���̉��Ƃ́A
>�ʂȉ����o�Ă��Ǝv���܂��B �P���ł͒����Ă��܂���ł����B
�@�G�[�W���O�ł���ɏn�����Ă����̂��y���݂ł��ˁB
�����ԍ��F25968250
![]() 2�_
2�_
��MDF�̔��͂܂Ƃ��ɖ�Ȃ��̂Ł@����ʖ�
�l�́A�H��̎�ۂ������̂�MDF�͎g��Ȃ��̂ł����A���[��A�����͂�����Ƌ^�₪�������肵�܂��B
MDF���āA�����Ă鏊�Œl�i���d�����A�������̊��G���Ⴄ�̂�MDF�S���������̂��Ȃ�
�A���~�����ނ̃X�s�[�J�[��������l���A���肷���MDF�͑S�R�ʖڂ������Ƃ���������Ă��āA���̐����͂������[���ł����̂ł����A����ł��A�u�ǂ��Ȃ낤�v�Ƃ����^��͎c��܂��B
MDF���āA�����Ōł߂��ؕ��ŁA������ƒi�{�[���ɋ߂����m���ƔF�����Ă���̂ł����A�������ĐF�X�Ȏ�ނ����邵�A�ؕ��̎����������悤�Ȃ��������ł���ˁB�r�o�z�[����MDF�ƃR�[�i���Ō��\�Ⴄ�̂Łu��H�v�Ȃ�ł��悗
�d����������ƈႤ���A�������̊��o�Ƃ��A��������ɊJ�������̖щH�̗������Ƃ��A���n�ނ̐��ݍ�������������A�@���Ă݂�Ƃ���Ȃɉ������Ȃ��悤�ŁA�Ȃ�Ƃ������A�w�Œ@���āA���̐U���̓`���͈͂�������ƈႤ��ł���ˁB
�l�i���Ⴄ�̂ŁA������������A�Ȃɂ�MDF�ɂ��K�i�������āA�u������MDF�v�Ƃ������Ȃ��̂��Ȃ��Ƃ��v�����肵�܂��B�����A�S���ڂ����Ȃ��̂ŁA�K���ł���B�i���ׂ���A�\���p�����xMDF���Ă̂������āA��ʂ�MDF�������x�������āA�h���@�\�������āA�Z��̍\���Ɏg����MDF���Ă̂��������̂ŁA����͂ǂ��Ȃ̂��ȁj
�܁A�l�́A�l�W�������Ȃ����A�h��������̂Ō���������g��Ȃ����ǂ˂�
MDF��������Ɛڒ�����̂��āA��ςȂ�ł���ˁA���̖؍ނ͖l�W�ł��߂Ĉ����ł��邯�ǁAMDF���g���ƁA�A���O���N�����v�Ƃ�����������Ȃ邵�A���ݍ��ݎ����Ǝア�̂Ńl�W���߂̃N�����v�łȂ��Ƃ����Ƃ��Ȃ����A�����⋭������̂�����B
���ƁA�l�i�������킯�ł͂Ȃ����Ă̂�����܂��ˁB
�l�ɘr�O�������āA���[�^�[�Ŋ�p�ɉ��H�ł�����܂��Ⴄ�̂����ł����E�E�E�E�E�E�E�E
���Ȃ݂ɁA���̎��Ɂu�p�[�e�B�N���{�[�h�́A�����ň��v�ƌ���ꂽ�̂ł����A�����JBL��FOSTEX���[�U�[�Ɉœ����H�炤���Ƃ��v������
�����ԍ��F25968890
![]() 2�_
2�_
��matu85����
�O�c�̖����킹���ꂳ�܂ł����B
PARC��20�ʑ̂悳�����ł��ˁB��x�����Ă݂����ł��B
��Foolish-Heart����
> MJ������f�[�^������Ă���Ă���̂ł����A�s�^�ʖڂȖl�͂�������ĂȂ��̂ŁA���ۂɖl�̊��o������f�[�^�ƈ�v���Ă���̂��͂킩��Ȃ��̂ł����A������u�������v�Ƃ͈Ⴄ��ł���ˁB
�I�N��3���́A���g�������I�ɂ͑f�����Ə���Ɏv���Ă��܂��B
BOWS����̂������Ă�������̂ł����A��悪�Ⴄ�̂͂������A����600�`1600Hz�������Ⴄ��ł��B
25cm���@�̒�ݔg��688Hz�Ȃ̂ŁABOWS����̃^�e���R���@������ɋ߂��e�����Ă���̂�������܂���B
�Ȃ̂Œ���̍�������܂��B
���j�b�g�̎��g�������́A�{�����R���قڐ^�����ł���(��)
��BOWS����
> ���肵�ĉ��������������Ď咣�́@�P�ɁA������@�����n�ʼn����̍�������ĂȂ�����
����A���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
�����ƂɊւ��ƁA�Ⴆ�Ό��ׂ��������蒼�𗦂����������肵���Ƃ��ɊĎ��f�[�^�⌟�����ʗނ����܂����A
�f�[�^�Ɍ���Ȃ����ׂ�ُ�́A�P�ɑ��肪����ɍ����Ă��Ȃ��Ƃ��������ŁA�V���ɒT���K�v�ɔ����܂��B
�m���Ă��鑪��A�����A�������u���āv�ɂƂ��āu�����ɍ��������v�ƌ����Ă���̂́A
�P�ɉȊw��Z�p��m��Ȃ������ł��B
�����ԍ��F25969002
![]() 3�_
3�_
Architect1703����
BOWS����
���m���Ă��鑪��A�����A�������u���āv�ɂƂ��āu�����ɍ��������v�ƌ����Ă���̂́A�P�ɉȊw��Z�p��m��Ȃ������ł��B
�Q�l�Ƃ������Ȃ��Ǝv���܂����B
���n���Ƃ��A�m��Ȃ��Ƃ��E�E�E�E�E�E�������������Y�o�b�ƌ����Ă��܂��̂͂悭����܂���B
�l�́A�l���^�����Ƃ�m��Ȃ��̂ŁA�ނ�̌�����M���Ă܂���B�����[�ȁA�悭�����Ă���ȁA�ł��ނ�́u���v�Ƃ͂����܂����u�����v�Ƃ͌����ĂȂ����ǁB
�ނ�̎咣�́A�u�����ς��Ȃ��v�Ƃ����A�����ɏo���Ă��āA���̗��t���炵�����̂������o���Ă邾���ŁA���̍����͒��Ă��Ȃ��̂ł��B����͉Ȋw�I�Ȓm�����Ȃ��Ă����������A���n�̐l�������n���ɂ���u���n�v�I�ȍl�@������킩��b���ł��B
������u�����͉R�����Ȃ����A�l�͐����ʼnR��t���v�̓T�^�ł��傤�B
�Ȃ̂ŁA���̃f�[�^���o���Ƃ����ƁA�������t�Łu����͖��Ӗ����v�ƈ�ۓI�Ȍ��t�ōU�����邱�ƂŔ��_�Ƃ��Ă��܂��B
���̎��_�ŁA���ꂱ���ނ�̌����u�S�����ʁv�ŁA��萔�̎x���������邪�A�t�ɁA��萔�̋^�f�݂܂��B
����ɑ��āA�^�f�����������ցA������Ƃ������_�I�A�������͘_���I�ȕ\�����g���Ắu�����v�͑S���Ȃ���Ă��܂���B
�l�́A��{�I�ɐl��M�p���Ă���̂ŁA����́u�o����v�̂����ǂ��A�S�����ʓI�Ɂu�Η��\���v�ɂȂ��Ă���̂ŁA��������Ɓu�I�ɉ��𑗂邱�ƂɂȂ�v�̂ŏo���Ȃ��̂��낤�ȂƎv���Ă��܂��B
�l���A�Ⴄ����Ń[�~�Ƃ��w����t�H�[�����Ő������鎞�ɁA�[�܂鎖�������̂ő��l�̂��Ƃ͌����Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă����肵�܂��B
�����A�ނ�́A������}�l�^�C�Y���Ă���̂ŁA�����͖��@�I�ȁu���Ӂv�����鏊���l�Ƃ͈Ⴄ���ȁB
���������b���Ȃ�ƁA�������̓���z�M�҂̓���������������N����l�B������̂ł����A����A���v������Ă�̂ŁA���ނƋ��K���������܂��B�����Ă��܂��A�����B�̔т̎�ɂ��Ă���̂ŁA�f���̗��p���@�Ƃ��Ă͋֎~�͂���ĂȂ��̂�������܂��A���܂�J�߂�ꂽ�s�ׂł͂Ȃ��Ƃ͎v���Ă��܂��B
�قƂ�ǂ̉��i�f�����[�U�[�͑P�ӂŁA�����ł���Ă�킯�ł����A���m�Ɏ��v�ړI�̐�`�ŃC���p�N�g�̂��鏑�����݂Ń����N�܂���̂͗ϗ��I�ɂǂ��Ȃ낤�˂��āA�v��������Ă��܂��B
���̓_�A�l�͌��\�C�����Ă��āA����v������̓����N��܂����A�����𖾂炩�ɂ��Ă���u���O���̓����N���ł����A���v�������A���܂�ɃA�t�F���G�C�g�������u���O��A���炩�Ɍl�̊��z�Ƃ����L�̂���ŏ����Ă���u���O���̓����N��\��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�܂Ƃ߂�ƁA����͉Ȋw�ł͂Ȃ��āA�A�t�F���G�C�g�ړI�̏����ł��낤�A�Ƃ����̂��l�̋A���ł��B
�����ԍ��F25969083
![]() 2�_
2�_
��Foolish-Heart����
> �S�����ʓI�Ɂu�Η��\���v�ɂȂ��Ă���̂ŁA��������Ɓu�G�ɉ��𑗂邱�ƂɂȂ�v�̂ŏo���Ȃ��̂��낤�ȂƎv���Ă��܂��B
���������c�_�ɂ��܂莞�Ԃ��₵�����Ȃ��̂ł����A�ΏۂƂ��Ă��邱�Ƃ�����Ă���Ǝv���̂ł��̓_�����B
���^�V�i�⑽��BOWS������j�����������̂̓V���v���ŁA
�u���̓f�[�^�⑪�茋�ʂŏؖ��o���Ȃ��Ă��A����Z�p�⑪��@�ނ̐i���ɂ���āA�f�[�^�ŏؖ��o����͂��v
�Ƃ������Ƃ����ł��B
BOWS����������Ă��܂����A���̂��Ƃ͗��j�I�ɂ��ؖ�����Ă��܂��B
�����ے肵���ꍇ�́A�c�O�Ȃ���u���n�v���Ƃ��u�Ȋw��Z�p��m��Ȃ��v�Ƃ������_�ɂȂ�܂��B
���ꂾ���ł��B
�����ԍ��F25969565
![]() 5�_
5�_
Architect1703����
���܂����A�l�^������������ł��B
�l�̌��_�́A�u�ނ�͗��n�Ƃ��Ȋw�̘b���ł͂Ȃ��āA�P�O�N�ȏ�����v�����ꂽ��������z�M�҂̓���������N���Ă��邩��A���̓���z�M�Җ{�l���A�߂����l�ŁA�ړI�̓A�t�F���G�C�g�҂����v�ł��B
�Ȋw�Ƃ����n�Ƃ��A����Ȃ̂́u��`����v�ł��傤��
�Ȃ̂ŁA�u�m��Ȃ��v�ł��u���n�v�ł��Ȃ��āA�u�W�Ȃ��v���Ă��Ƃ��A������Ɣނ炪���ȕ��̂Ńl�^�I�ɏ���������ł����B
�������Ȃ���A���������f���Ƃ��Ắu�ނ�̎咣�v�̂����A����́u��������ȁv�Ǝv�����Ƃ͂���̂ŁA��l�Ƃ��ċ��ʂ̘b���_����͍̂\��Ȃ����A���O�̌o�ϊ����ɂ͕t�����������Ȃ��Ƃ����̂��l�̃X�^���X�ł��B
�����ԍ��F25969998
![]() 1�_
1�_
�F�l�A�����A�e�X�^�[�ʂ��������Ȃ��g�Ƃ��āA����b�͔����ł��B
MDF���ׂČ��܂�����A�K�i�A�F�X�L��l�ł��A
https://www.daiken.jp/buildingmaterials/etc/columnrhc/015/
���̃��[�J�[
���t�H�[���Ȃǂŏo���̖ؐ��i�A�Y�Ɣp���������Ǝ҂Ɉ˗�����ƁA�`�b�v������A
�X�ɕ��ӂ���MDF�̌����Ɉׂ�Ƃ��B
�z�[���Z���^�[�Ŕ�����MDF�ǂ�ȋK�i�ł��傤�B
Architect1703����
��PARC��20�ʑ̂悳�����ł��ˁB��x�����Ă݂����ł��B
�L��������܂��B
�R�S�R�S��������A�@�����Ǝv���Ă��܂��B
�ʐ^�P�@�A�V�_�����A�\��㔼�@���̃X�s�[�J�[�\�荇�킹�A�^���ċz���Ȃ鐧��L����ǂݓ_�����̑��݂�m��B
�ʐ^�Q�A��\��O���A���i�ɐ������_�����A�����Ȃ�����
�@�@ �@�@�O�\��A�Z�ʑ̂U���j�b�g���A
�@�@�@�@
�@�@ �@�@���\��A��\�ʑ̂Q���j�b�g
�@�@�@�@�@���\��A�㔼�A��\�ʑ̂Q���j�b�g �f�b�g�}�X��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �I�����WPARC���ԓ���
�@�@�@�@�@���l�����Ďv�����Ɛ߂̂��鐙���Ŕ��͍��܂��A
�����ԍ��F25979055
![]() 2�_
2�_
�������g�͂قƂ�ǃI�[�f�B�I���瑫�����Ă�Ȃ̂ł����ABOWS�����
�u���܂��A������Ɗ�݂���v�Ƃ����āA����X�s�[�J�[�̃R���e�X�g�ɎQ�����Ă��܂����B
���\�A�^�ʖڂɎQ�����邩��A�}�W�Ń{���{���ɔ����˂��i�ł��y�����j
https://musenohakobune.hatenadiary.org/entry/2024/11/16/230525
Mark�����STEREO�t�^�X�s�[�J�[OM-MF4-MICA���g�����R���e�X�g�B
�Ȃ��A���̃��j�b�g�͂܂��ɂ�����݂����ł��B
�����͂V�{�̗͍���ė��܂����B
�ʐ^�́A�ߐڂŎB�������̂͌l���������Ă���̂�UP�ł��Ȃ����Ȃ��Ƃ������Ă���̂ŁA���BOWS����UP���Ă����Ǝv���̂ŁA1st���|�[�g�����B
�F�X�ȕ����̃X�s�[�J�[���������̂ł����A������������20�N�قǑO����l���l�I�Ƀ`�F�b�N���Ă��鎩��nHP�̐l�ŁA�������邱�ƂȂ���A���̃t�@���𗬉�̂悤�Ȋ����ł����B
�u�X�p�C�����|�[�g�v�ƁA�u���S�X�s�[�J�[�v�͂����ƌ��Ă����̂Łu���A���ꂪ�������I�I�v�Ƃ��������Ńo�C�A�X��������
���Ɂu���S�X�s�[�J�[�v�͗Ⴆ��̂Ȃ�A�A�C�h���̈����ɍs�����悤�Ȋ��o�B
���ꂾ���ŁA�Ȃs���Ă悩�����Ȃł͂���܂��B
1�{�ڂ́A�A�N�������g�����������ȃX�s�[�J�[�Ńh�����R�[�����g���Ē������Ă��܂����B�G���N���̑傫���A���j�b�g�̌��a����͑z���ł��Ȃ���悪�łĂ��āA�������N�Z���悢���ǁu�������v�ł����B
�܂�ŁABOSE��ADAM�̃X�s�[�J�[�̗p�Ȋ����ł��ˁB
2�{�߂͂悭����܂���ł����B�i���M����悤�ȉ��ł͂Ȃ������j
3�{�ڂ́A����̋S�����肵�Ȃ���A�X�s�[�J�[�̐v��NG�Ƃ����邱�Ƃ�S������Ă݂��I�I�Ƃ����l�D�݂̃q�l�^���ŁA�G���͂���̂ł����A���Ƃ��Ẵo���X�������ǂ��āAOM-MF4-MICA���ɂ������H�v�����Ă���O�����O���g���ĐU�����d�����Ă��܂����B�v����Ɂu�O�c�I�[�f�B�I��v�̃����o�[��i�ł��B
���̐l�̃X�s�[�J�[���_�̍u��������Ă��������炢�ʔ����I�I
1�����ɁA�ނ̍�i���Q�������킯�ł����A�ǂ�����ƂɎ����A���ėV�т������炢�ɋC�ɓ����Ă܂��B
�l�ɂ��Ă͒������ׂ��J�߂ł��B
4�{�ڂ́A����̃R���e�X�g�Łu��������v�ŗD�������X�s�[�J�[�ŁA1�Ԃ̃X�s�[�J�[��������l���l�Ă����u�X�p�C�����_�N�g�v���A�N�����ō���Ă��āA�`���[���ɂ́uFoq�v�u�^���O�X�e���V�[�g�v�u�V�R�E�[���v�ƂȂl���ǂ��g�����̂��ӂ�Ɏg���Ă��܂����B
�n�}�鉹�ɂ͐����n�}��X�s�[�J�[�ł����A���\�ł͂Ȃ��B���̂����肪�����㩂ȋC�����܂����B�ǂ��Ƃ��낪����ėǂ��̂��]�v�Ɂu���v�ȏ�������������Ă邩�Ȃ��E�E�E�E�E�E�E�i���j�b�g�ɂ���Ɏ������Ă�̂������Ȃ��ǁA���ꂪ�ǂ��Ȃ̂��ȁj
5�{�ڂ́A�Ƃɂ����H�삪�L���C�ȃo�b�N���[�h�ŁA�R���Z�v�g��BH�̎�_����������Ƃ������ƂŁA�����ǂ��ł���BH�ł������ABH�ł����ABH�̎�_�͊m���ɉ��P����Ă��镔���͂��邯�ǁA����ς�BH����˂Ƃ��������ŁA�����̃R���e�X�g�ł͂������]�������������̂ł����A�����Ȃ��Ă��l���I�ԉ��ł͂���܂���ł����B�l�̐��]�́u���߂�Ȃ����v�ł��B
6�{�ڂ̓��S�X�s�[�J�[�ŁA��������́A�Ȃ낤���ł͂Ȃ���
���l�����l�łȂ����Ƃ��A�̂����܂������肩�Ƃ��A���������̂ł͂Ȃ��āA�l�����ł�����y�����������Ă���̂Ɠ������o�ł��B
�Ō��7�{�ڂ́A�^�C�g�����u���ʂ̃_�u���o�X���t�v�ŁA�����ڂ��X���b�g�o�X���t�łȂɂ��ڐV�������Ƃ͂Ȃ������̂ł����A���ꂪ�ǂ�������
�Ȃ�Ƃ������A����Ă�킸�ɃI�[�\�h�b�N�X�ɂ�����Ƃ܂Ƃ߂��ǂ����ۗ����Ă������������܂����B
YAMAHA�̃��j�b�g�����炵���������ǁA���̃��j�b�g�̔����ȉ��̒l�i�ŁA�X�Ɍ��a��������Mark����̃��j�b�g�̒�͂̐������Ċm�F���A�V�^�̃v���g�������͕����܂����B
�U�����K���X�łł������j�b�g�E�E�E�E�E���炢���x���������āA����\���߂��Ⴍ���ፂ�����Ńr�r��܂����B
�t�������W�Ƃ��X�R�[�J�[�ł͂Ȃ��āA����܂ōĐ��ł���c�C�[�^�[���Ċ����ŁA�L�������j�b�g�ł��B�i�v���g��Fs120�Ȃ̂��A�ŏI���f���̓_���p�[�����ǂ���Fs100�����ɂ���Ƃ̂��Ƃł��B�j
��OM-MF4-MICA��Amazon���ōɂ��܂�����̂ł����A���M�����[���i�Ƃ���CHN40Pmica�Ƃ����^�ԂŔ����Ă��܂��B
���Q�@CHN40Pmica�Ɏg���Ă���U����CHP90mica�ɂ��g���Ă��܂��B���̃��j�b�g���������ǂ��ł��B
�����ԍ��F25982301
![]() 2�_
2�_
�����Foo�������������BOWS�ł��B
>�������g�͂قƂ�ǃI�[�f�B�I���瑫�����Ă�Ȃ̂ł����ABOWS�����
>�u���܂��A������Ɗ�݂���v�Ƃ����āA����X�s�[�J�[�̃R���e�X�g�ɎQ�����Ă��܂����B
�@���t���������������A���肪�Ƃ��������܂����B
�@�ł��A�ʔ��������ł��傤
�@���N�̏H�́A�T�ӏ�������X�s�[�J�[�C�x���g�ɎQ�����ā@�����Ă��Ă��낢�땪���������Ƃ�����܂����B
�@���̓_�Ɋւ��Ă͌�ق�
�@�~���[�Y�̉�̓��F�Ƃ��ẮA����ꂪ�����āu����Ă݂��̂ŏo���Ă݂܂����v�Ƃ����̂�����܂���B
�@�����悤�ȕ����������ƒNj����Ă��Ă���������������ł��B
�@�o�����d�˂邱�Ƃɂ��������̏�肳���ǂ������ɓ����v���X���L��A��{�I�ȕ����ɖ�肪����ꍇ�ł��A���܂ł���Ă����o�����̂Ă��Ȃ��ăl�K������Ȃ��Ƃ������Ƃ������܂����B
�Ȃ��A�ŋ߁@�U���ȊO���特���o�Ȃ��o���o�����j�^�[�����X�s�[�J�[������ĕ����Ă��鎨�ŕ����Ă����̂ł��Ȃ�Foo������h���ł��B
>1�{�ڂ́A�A�N�������g�����������ȃX�s�[�J�[�Ńh�����R�[�����g���Ē������Ă��܂����B�G���N���̑傫���A���j�b�g�̌��a����͑z���ł��Ȃ���悪�łĂ��āA�������N�Z���悢���ǁu�������v�ł����B
�@���b�N�X�̓_�ŃA�N�����g�p�A�z���ޖ����A�h�����R�[���͗]�v�Ȓ�����o���Ȃ����߂ɁA�[�q�Ԃ��H�v���Đ������Ă���Ƃ����m�b���l�܂����\���ł����A�����ɂ���ĉ����ς��悤�ȂƂ��낪�����ċl�߂��Â��Ȃ��Ǝv���܂����B
>2�{�߂͂悭����܂���ł����B�i���M����悤�ȉ��ł͂Ȃ������j
�@�����҂��M����ǂ��������o��䗝�_�ȍ\�������ɂ��낢��d���܂�Ă��āA�U���ȊO�̕t�щ����R����ȏ�ɁA���j�b�g�����܂��Ă��ā@���U�������ς��������Ă��鉹�ł����B
�@���U�_�𑪒肷��Ȃ肵�ā@�l�߂�Ηǂ��Ȃ�\��������܂����A���������ĂȂ����ł����B
>3�{�ڂ́A����̋S�����肵�Ȃ���A�X�s�[�J�[�̐v��NG�Ƃ����邱�Ƃ�S������Ă݂��I�I�Ƃ����l�D�݂̃q�l�^���ŁA�G���͂���̂ł����A���Ƃ��Ẵo���X�������ǂ��āAOM-MF4-MICA���ɂ������H�v�����Ă���O�����O���g���ĐU�����d�����Ă��܂����B�v����Ɂu�O�c�I�[�f�B�I��v�̃����o�[��i�ł��B
�@�l�̂悭�V��ł��邨�F�B�̍�i�Ł@���g�͂悭�m���Ă����ł����A������6mm�̃y���y���̃t�@���J�^���g���Đ���ɔ��肳���Ă܂��B
�@���̔���̓������v�����ā@�o�b�N���[�h�z�[���̎�_�ł���t�ʑ��̒J�ɍ��킹�đ��E����Ƃ����_�Ƃ���Ă܂��B
�@�������Ł@�I�[���}�C�e�B�ł͂Ȃ����A�������ǂ��̂��X�s�[�J�[�ɂȂ��Ă܂����B
>4�{�ڂ́A����̃R���e�X�g�Łu��������v�ŗD�������X�s�[�J�[�ŁA1�Ԃ̃X�s�[�J�[��������l���l�Ă����u�X�p�C�����_�N�g�v���A�N�����ō���Ă��āA�`���[���ɂ́uFoq�v�u�^���O�X�e���V�[�g�v�u�V�R�E�[���v�ƂȂl���ǂ��g�����̂��ӂ�Ɏg���Ă��܂����B
�@����A�l�̕]���͒Ⴉ�����ł��B
�@���낢��t�@�C���`���[�j���O���悭����Ă���l���A�H�v���č���Ă����ł����A���ꂼ��̕Ȃ����܂����Ɩڗ����Ȃ��悤�ɂ܂Ƃ߂ĉ������グ��̂�����̋Z�Ł@�撣���Ă�����Njl�߂�����Ȃ��̂������Ă��ĕ�����܂����B
>5�{�ڂ́A�Ƃɂ����H�삪�L���C�ȃo�b�N���[�h�ŁA�R���Z�v�g��BH�̎�_����������Ƃ������ƂŁA�����ǂ��ł���BH�ł������ABH�ł����ABH�̎�_�͊m���ɉ��P����Ă��镔���͂��邯�ǁA����ς�BH����˂Ƃ��������ŁA�����̃R���e�X�g�ł͂������]�������������̂ł����A�����Ȃ��Ă��l���I�ԉ��ł͂���܂���ł����B�l�̐��]�́u���߂�Ȃ����v�ł��B
�@���̐l�̍�i�́@����������Ă����ł����A�ǂ����������o�b�N���[�h�̕Ȃ������ł����A���̃l�K���y������Z��m���Ă���̂Ł@���܂����Ƃ܂Ƃ߂Ă���A�����]���ɂȂ�܂���B
�@�؍H��m��s�����Ă���̂Ł@�d�グ�͂����ւ�������H�|�i���x���őf���炵���ł��B
>6�{�ڂ̓��S�X�s�[�J�[�ŁA��������́A�Ȃ낤���ł͂Ȃ���
>���l�����l�łȂ����Ƃ��A�̂����܂������肩�Ƃ��A���������̂ł͂Ȃ��āA�l�����ł�����y�����������Ă���̂Ɠ������o�ł��B
�@�Ȃ낤�A�������������ʖڂł��B
�@����A���S�Ƃ����Бf�ނ̏W���̂Ƃ����U�������̈����ȂA���������̓����Ȃ͂킩��܂��A�����ɕȂ��t�������ā@�H�v���Ēǂ�����A���܂����Ƃ���������낤���H�Ǝ��P��Ȃ��畷���Ă܂����B
>�Ō��7�{�ڂ́A�^�C�g�����u���ʂ̃_�u���o�X���t�v�ŁA�����ڂ��X���b�g�o�X���t�łȂɂ��ڐV�������Ƃ͂Ȃ������̂ł����A���ꂪ�ǂ�������
�@����A���̕ϓN���Ȃ������Ȃ����h���̃V�i���Ȃ�ł����A�f���ŕȂ����Ȃ��A�I�[���}�C�e�B�ɂ��Ȃ��@���x���̍����ӂ��̉��̃X�s�[�J�[�ł����B
�@��ł��b��������ł����A���̂�������i����Ă�����ŁA���̍\����o�X���t�̃|�[�g�`��Ƃ���������쐬���ĕ����Ă�������Ȃ�Ł@���Ƃ����̐ݒ肪�▭�ł��B
�@����Ӗ��A�ڐV������ѓ���݂����ȋZ�p�Ȃg��Ȃ��Ă��@�������̃X�s�[�J�[�͍����@�ƌ�������ŏՌ����܂����B
�@�V��i���āA��҂̕��Ƃ��b���ā@���낢��Ɠ��邱�Ƃ̑��������R���e�X�g�ł������A�Ō�ɕ�����...
�@�}�[�N�I�[�f�B�I�̔������̃t�B�f���e�B���T�E���h�̒������A�Љ�Ă����@�K���X�U����8cm�t�������W�@Alpair 5G�Ђ̖��C���ɋl�ߍ��X�s�[�J�[������....�S��i���P�n�g�قLj��������f���炵���������߂܂����B
�@���̂������ǂ������ł��B
�@���`��A����͎莝����...Alpair 5V3�����v���[�X����Ƃ����Ȃ�...�ƔY�݂������܂����B
�@�}�[�N�I�[�f�B�I����A���������@������𓊂��Ă��܂�...�����Ȃ���悩����...
�����ԍ��F25984764
![]() 5�_
5�_
BOWS����
�߂��Ⴍ����y���������ł���
�l�Ƃ��Ă͒������ƌ������A�l�͎��앨�Ɋւ��Ắu�����i�v�ł͖����ƌ������o������̂ŁA��]�͔�r�I�}�C���h�ɂ��Ă��܂��B
���������͍�B���Ă��Ďv���̂́A����ł��b���܂������A���̉��i�т����A����������������Ă郁�[�J�[�̐��i�́A�ʔ����Ȃ���������Ȃ����NJ����x�͍�������������܂��B
FOSTEX�AKEF�AB&W�ADYNAUDIO���̂�����̃��[�J�[��A�Ȃ͋�������JBL�ATANNOY�AFOCAL���D�܂ꂽ��A�ቿ�i�тł�YAMAHA�ASONY�̐��i�B
��̑O�Ȃ�VICTOR���l�͕]�����Ă��܂��B
�}�C�i�[�ł����AVICTOR��SX-M3�Ƃ����}�O�l�V�E���U�����g�����X�s�[�J�[��FOSTEX�Ƃ͂�����ƈ�������F�ł����l�i���l������߂���ǂ������B
���̃_�u���o�X���t�̍�҂���́A�����a���j�b�g�{�_�u���o�X���t�������Ɠ˂��l�߂Ă銴���ł��ˁB�����A���[�^�[�o�C�N���Ȃ̂œG�ł���
�����ԍ��F25986538�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
2025/01/01 13:34�i10�����ȏ�O�j
��BOWS����
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�@�@
���N�̓}���`�`�����l���ɍs�����Ǝv���܂��B
�}���`�`�����l���ɂ́A��������܂����H
���z�̐��E�ł����A�������ł���@���ʂ͂n�j�ł��B
�r�o�������������́@�a�n�v�r����Ȃ�E�E���\�y���߂�Ǝv���܂����E�E�E�E
���N����낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F26020902
![]() 1�_
1�_
��BOWS����
�F����
�V�N�̈��A�x��܂����B
�{�N����낵�����w�����������B
���݁A�G�[�W���O���˂Ȃ���A���~��������肵�Ă��܂��B
�P�[�X�A�����������A�y�����Y��ł������ł��܂��A�ł��A�S��ŋÂ�ł܂��Ă��܂��B
�����ԍ��F26027126
![]() 3�_
3�_
�@�N�z���œ���ҏW�ɒǂ��Ă��ā@�ԐM���x���Ȃ��Ă��݂܂���B
�I���t�F�[�u���^�[�{����
>�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�@�@
���N����낵�����肢���܂��B
>�}���`�`�����l���ɂ́A��������܂����H
�@�I�t�~�ł��傢���傢�̌����Ă���̂Ł@�S�n�悢���Ƃ͒m���Ă��܂��B
�@2ch�ł��@�܂Ƃ��ȉ����o���̂ɋ�J���Ă����Ł@�}���`�͌������ł��B
�@���ɓ�_�͉��ʒ����ł��ˁB
�@�g�����X���A�b�e�l�[�^����p���Ă����Ł@���̕����ɖ߂�Ȃ��Ȃ��Ă����ł����A�}���`�`���l���̃g�����X���A�b�e�l�[�^���ā@�g�����X�̐��Ƒ���H���[�^���[�X�C�b�`�Ł@���삵�Ă��P�O���~���R�[�X�Ȃ�Ŏ肪�o�܂���B
�@����Ȃ�@����y��GENLEC�ő�����̂��ǂ��Ǝv��...���l�i�͂���y����Ȃ�����(��)
matu85����
>���U�����痣��A��z�A�⌴�Ŋ���܂���܂����B
�@���N�I�ŗǂ��ł��ˁB
�@�������ꂱ��@�X�L�[�͂Q�O�N�قǍs���ĂȂ��ł��ˁB
>���݁A�G�[�W���O���˂Ȃ���A���~��������肵�Ă��܂��B
>�P�[�X�A�����������A�y�����Y��ł������ł��܂��A�ł��A�S��ŋÂ�ł܂��Ă��܂��B
�܂��A�P�[�X���H�͌o���Ɠ���Ō��܂�܂�����A��B���y�����ł��ˁB
���N������@�U�����炵�������o�Ȃ����샄�}�n�X�s�[�J�[�Ł@�����Ȃ��̕��������Ă��܂����A�������Ȃ������������낢�땷�����ā@��������ׂ����Ƃ����낢�댩���Ă��܂����B
���N�́A�㗬�ƃA���v�Ɏ��������ĊJ������̂ƁA�܂Ƃ��ȑ�����A�^���������邩�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�@
�����ԍ��F26027779
![]() 2�_
2�_
��BOWS����A�F����A����ꂿ���ł��B
���N����낵�����肢�������܂��B
�I�[�f�B�I�̂ق��͂����ς�ɂȂ��Ă��܂��܂������A���������Ȃʼn��y�͊y����ł܂��B
�N���ɔ��ˑ�R�o���ė��܂����A���łɑ������p�قɂ�����Ă��܂����B
�����ԍ��F26032844�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�
�@�����C�����łȂɂ��ł��B
�@���N���@�����i�߂܂���Ł@��낵�����肢�܂��B
>�N���ɔ��ˑ�R�o���ė��܂����A���łɑ������p�قɂ�����Ă��܂����B
�@���N�I�ŗǂ��ł��ˁB
�@�~�R�͌������̂Ŗ����Ȃ�Ȃ�悤��
�@�������p�ق́@��i�F���ƒ낪���ꂢ�ł��傤�ˁB
�@
�����ԍ��F26034990
![]() 1�_
1�_
�x���Ȃ�܂������A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�l�I�ɂ́A�I�[�f�B�I�͂قƂ�lj������ĂȂ����A��������܂肢���邱�Ƃ͂Ȃ����Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł��B
���N�̌㔼�́A�[�����I�Ȏ���X�s�[�J�[�̃C�x���g�ɂR�Q�������Ă��������܂������A���ꂪ�~�߂ɂȂ������������܂��B
���������X�s�[�J�[�̑f���炵�����Ċm�F����Ɠ����ɁA�܂�Ȃ���������Ȃ����ǖ��\�ȃI�[�f�B�I���[�J�[�̍��u���Ր��v�̗ǂ����������ʂ�����A�����āA�ƂɋA����GENELEC���ƁA�܂�Ȃ����A�����ĉ��I�ɂ͗ǂ��Ȃ��A�N�e�B�u���j�^�[�̒�K�I�ȗǂ��A������u���݂₷���v���͂����Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂����B
�ׂ��ȃf�B�e�[���Ƃ��A�{���̈Ӗ��ł̗ǂ����ł͂Ȃ��̂ł����A������^�������\�[�X���I�[�f�B�I�@��ŕ����ƁA�u��ɐ����ɂȂ�Ȃ��v���A�K���f�t�H������������̂ł����A�u�ǂ����f�t�H�����v�Ȃ̂����A�N�e�B�u���j�^�́u�킩��₷���v�̂ŁA�]���⊮�����₷���B�l�I�ɂ́u����ł��������v�ɂȂ��Ă��܂��B
���Ԃ�A���̖l�́u�����������N���v�Ȃ̂ł��傤��
�d���̃X�g���X����J�����ꂽ�̂ŁA�S�ɏd�������Ȃ��Ȃ�A���y�ӏ܂ւ̗~�������Ȃ��Ȃ����̂��������낤�Ǝv���Ă��܂��B
���܂ł́A���Ȃ����ԂŁA������ƕ����������Ă̂������āA�����Ȃ�́u�������v�����߂Ă����̂ł����A���́A�u�����A���ꂢ���Ȃ��ˁv�u����A�r���E�G�o���X�͂���ς莊���̗̈悾�ˁv�Ƃ�����ȗ]�T���ł�����Ă��ł���ˁB
�Ƃ������ƂŁA�����ւ̓��e�͂��ԂȂ茸��܂����A�Ȃɂ��I�[�f�B�I�I�ɐV�������Ƃ͓����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F26039155
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
��Foolish-Heart����
�@�@�F����
�����́A������C�������A�S�R�S�R�������ɍs���@���Ƃ������o��l�ɐ���܂����B
�n���ւ̔����́A�K�i�O�������g�݁@�d�����ԂƂQ�l�Ł@�`�G���u���b�N�ʼn����܂����A
�v���Ă������@�y�������@�t�H�[�N���t�g���g�킸�@��l�ʼn��Ƃ��ב�ɏ悹�܂����B
�b���͊y���߂邩�@�Ɓ@�v���Ă��܂��B
Foolish-Heart����@��̂��w���X�������肢���܂��B
�����ԍ��F26040612
![]() 3�_
3�_
�@���݁A���N�H�ɊJ�Â��ꂽ����X�s�[�J�[�R���e�X�g�̘^�����ʂ�ҏW����Youtube�ɏグ�悤�Ƃ��Ă����Ⴒ���Ⴕ�Ă܂��B
�@�����悤�ȃ��j�b�g�g���Ă����ł�����҂̌����Ă������������o�Ă��ā@���̂������ʔ����ł��B
�@�A�b�v�����炨�m�点���܂��B
Foo����
>���N�̌㔼�́A�[�����I�Ȏ���X�s�[�J�[�̃C�x���g�ɂR�Q�������Ă��������܂������A���ꂪ�~�߂ɂȂ������������܂��B
���ꏏ���܂������A���ꂪ�~�߂ɂȂ�܂�����
>���������X�s�[�J�[�̑f���炵�����Ċm�F����Ɠ����ɁA�܂�Ȃ���������Ȃ����ǖ��\�ȃI�[�f�B�I���[�J�[�̍��u���Ր��v�̗ǂ����������ʂ�����A�����āA�ƂɋA����GENELEC���ƁA�܂�Ȃ����A�����ĉ��I�ɂ͗ǂ��Ȃ��A�N�e�B�u���j�^�[�̒�K�I�ȗǂ��A������u���݂₷���v���͂����Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂����B
>�ׂ��ȃf�B�e�[���Ƃ��A�{���̈Ӗ��ł̗ǂ����ł͂Ȃ��̂ł����A������^�������\�[�X���I�[�f�B�I�@��ŕ����ƁA�u��ɐ����ɂȂ�Ȃ��v���A�K���f�t�H������������̂ł����A�u�ǂ����f�t�H�����v�Ȃ̂����A�N�e�B�u���j�^�́u�킩��₷���v�̂ŁA�]���⊮�����₷���B�l�I�ɂ́u����ł��������v�ɂȂ��Ă��܂��B
�p�ɂɘ^������悤�ɂȂ��ā@���߂Đ����Ƙ^���������̕ҏW���ăp�b�P�[�W���O���������Ⴄ���̂�Ɋ����Ă��܂��B
GENELEC�̃A�N�e�B�u���j�^�[���ā@�����čō��ł͂Ȃ���ł����A���\�ŕ��ϓ_�����������������@�܂����ꂪ�������Ȃ�ł���
�ŋ߁AWAV�t�@�C���̕ҏW�A����ҏW�̂��߂ɁAYAMAHA�t�������W�g�����X�s�[�J�[�ɃT�u�E�[�t�@�����ā@�j�A�t�B�[���h�Ń��j�^�Ƃ��Ďg���Ă����ł����A�����������čׂ����f�B�e�B�[���܂ōČ������̂Ł@������Ƃ����ω������ݎ���悤�ɂȂ�܂����B
���j�^�X�s�[�J�[���ĉ��y�������@�����\�͂�����܂���
>�d���̃X�g���X����J�����ꂽ�̂ŁA�S�ɏd�������Ȃ��Ȃ�A���y�ӏ܂ւ̗~�������Ȃ��Ȃ����̂��������낤�Ǝv���Ă��܂��B
>���܂ł́A���Ȃ����ԂŁA������ƕ����������Ă̂������āA�����Ȃ�́u�������v�����߂Ă����̂ł����A���́A�u�����A���ꂢ���Ȃ��ˁv�u����A�r���E�G�o���X�͂���ς莊���̗̈悾�ˁv�Ƃ�����ȗ]�T���ł�����Ă��ł���ˁB
�@����S���͐l���ꂼ��Ł@��낵����Ȃ��ł��傤���H
�@�I�[�f�B�I�Ȃi�����x���x����Ł@�ق����Ă����Ă����������炷���ɒǂ����܂����B
�@���Ȃ݂ɁA�~���[�Y�̕��M�R���e�X�g�̎��ɕ������Ă�������@Mark Audio Alpair 5G�̋L�����o�Ă܂��B
AV watch �}�[�N�I�[�f�B�I�A����K���X��U���Ɏg�����X�s�[�J�[���j�b�g�u���ꂱ�����z�I�ȓ_�����v
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1654348.html?fbclid=IwY2xjawH32K1leHRuA2FlbQIxMAABHTsxwM-CtNlAUg418ru_CZIxgw7NIniPzv_eYyzg4-UM-t7EYkclEuJO0g_aem_ug2SjC8mNKVH5F5I3KZq6Q
�@����Ɣѓc����̃��r���[
https://www.youtube.com/watch?v=wHGsD4HxT6M
�t�B�f�B���e�B���T�E���h�E�����d�q�Y�ƁEstereo 3�Ћ��Î�����@2025�~2/8,9
https://silicon.kyohritsu.com/ONfdKYO-2025/index.php
�@�TG�͂��l�i�͍�����ł����A�_���p�[���X�ŃK���X�U�����Ă��ƂŁ@�s�[�L�[�ʼn𑜓x�����̂�����������Ł@�莝����Alpair 5V3�ƃ��v���[�X������@�ǂ�ȉ������邩�H�@�����炭YAMAHA�������Ȃ��@
�@�Ƃ��낢��ϑz���Ă��܂�(��)
�����ԍ��F26041319
![]() 2�_
2�_
matu85����
�@���[���ɓ��肳��܂������I�H
�@���߂łƂ��������܂��B
�@����Ȃ��ā@���t�F�[�X�Ȃ�ł��ˁB
�@�܂��W�������̎c�荁�����肻���ȘȂ܂��ł��ˁB
�@�ڂ���JBL�ɏڂ����Ȃ���Ł@��͂�Foo����Ɍ���Ă�����������ǂ������ł��ˁB
�����ԍ��F26041324
![]() 1�_
1�_
�������݂͏��Ȃ��Ȃ�܂���Ə������Ƃ���Ƀ��X�������̂��ǂ����Ǝv���܂������A�e�[�}�����炩�ɂȂ��Ă鏊�ɂ��Ă̓��X���悤�Ƃ�
matu85����
���ɂS�R�S�RB�����ł����A�����͂Ȃ��Ȃ����Ⴖ��n�ł��B
���������Ƃ������Ă��܂����A�S�R�S�R�͂SWAY�Ȃ�ł����A��{�͂QWAY+�T�u�E�[�n�[+�X�[�p�[�c�C�[�^�[�Ƃ��Ă���������A��R���RWAY�Ƃ��đ����āA�E�[�n�[�͂Ƃ�ܒu���Ƃ������Őڂ���̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�܂��A�`�F�b�N���ׂ��̓E�[�n�[��Mid-Lo�̃G�b�W�ł��B
�����ڂ����v�����ł����i��ł��鎖�������̂ŁA�u�ǂ���������́v�Ȃ̂Ń��j�b�g��^��������ʼn����Ă݂Ă��������B
�ŁA������ƃo�����X�悭�߂��Ă�����u���̂Ƃ�����v�v�A�Ȃ�ƂȂ��A���o�����X�ʼnE�̖߂肪�����Ƃ����������Ƃ�����u���ɗ��Ă���v�A�����ăG�b�W�̈ꕔ���j������Ȃ�u���ɉ����������n�܂��Ă���v�̂ŃG�b�W�̒��ւ������邱�ƂɂȂ�܂��B
���ł�harman�̃T�[�r�X�ΏۊO�Ȃ�ł����A�����p�[�c�͂�����������܂��ɂ��Ă邩������Ȃ��̂�harman�ɖ₢���킹�����Ă݂Ă��������B
�����Aharman�ɂȂ���Δėp�̃G�b�W�p�[�c���g�����A�T�E���h�f����P�����b�N�T�E���h�ɖ₢���킹�ł��B
�ǂ�����l�H�Z�[���v�̃G�b�W�ɂȂ�܂��B
���ꂪ�A�A���j�R�^�C�v�̃��j�b�g���ƁAharman�̏��������e���������߂Ȃ�ł����AB�̓t�F���C�g�}�O�l�b�g�Ȃ̂ŃT�[�h�p�[�e�B���g���Ă������Ǝv���Ă��܂��B
�]�k�P
�@�A���j�R���j�b�g�̏C���́A��x���͂��Ă��烆�j�b�g�̏C�������āA�Ď����������ē��������킹�Ă���܂��B�������A�A���j�R�}�O�l�b�g������Ă�ق����u�D�݂̉��v�̏ꍇ���悭����܂��B���ɁAJBL075�Ƃ����c�C�[�^�[�͍L�悪W�s�[�N���������c�C�[�^�[�Ȃ�ł����A���͂���킭�Ȃ��Ă����W�s�[�N���ׂ�ĂP�s�[�N�ɂȂ��Ă��āu����A�A���j�R�c�C�[�^�[�͗D�������ł����ˁv�Ȃ�Ďv���Ă�l�����������肵�܂��B
�l�b�g���[�N�́A�قƂ�ǃt�B�����R���f���T�Ȃ̂ł�قǏo�Ȃ�����́u�߂��Ⴍ������Ă���v���͋H���Ǝv���܂��B
�S�R�S�R�͎�z���ł����A�������S�R�S�RB����z���ň����ō���Ă���̂ł��̃p�[�c�����͕ی�t���[�����O���Ă�����Ƃ���Ȃɓ���Ȃ��ł��B�z�����������悤�Ƃ���ƌ��\���G�œ���ł����ǁE�E�E�E
�Ƃ肠�����A���̃X�s�[�J�[�^�[�~�i�����́u�E�[�n�[�藣���v�X�C�b�`���Ђ˂��āAMID-LO����ゾ���ŕ����Č��Ă��������B
�ŁA�Ȃ��������Ǝv������i�X�y�A�i������A���E�������Ă������Ǝv���܂��j�A�l�b�g���[�N�̑f�q�s�ǂ��^���Ƃ������ڂŃR���f���T��R�C���̌��������܂��傤��
�Ȃ��A�S�R�S�R�̃o�C�A���v��ւ��́A�u�E�[�n�[���l�b�g���[�N�t���[�ɂȂ�v�d�l�ł��B
�����𗝉����Ă��Ȃ��l�����\���܂��B
�]�k�Q
JBL�̃v�b�V�����̃^�[�~�i���͂Q�~�����炢�̐������͂���Ȃ����A�o�N�Ńo�l������Ă邱�Ƃ�����̂ŁA��������DIY�ŐV�����[�q�ɂ���̂�����ł��B�����^�[�~�i�����܂��ɂ����邩���ł����A�o�i�i��O���g����[�q�ɕς���̂͂��肾�Ǝv���܂��B
�R����AATT�͓��{���ł���͊m�����[�J�[�ɍɂ��܂��������悤�ȋC�����܂��B
�قڊԈႢ�Ȃ��u�K���v�͂���Ǝv���̂ŁA�O���O�����ĂȂ���Ȃ��悤�Ȃ�A���𐴑|�����邩�A�������̂���肵�Č����ɂȂ�܂��B
�������ˁA�A���v�X���ł��B
�S�R�S�R�̓����̂P�ł���MID-Hi�̉��������Y�͉ƒ�Ŏg�p����ꍇ�ɂ́u����v�Ɓu�����v����ׂĂ݂Ă��������B
�Ȃ��E�E�E�N�x�͂������Ȃ邯�ǁA�T�[�r�X�G���A�������Ȃ�B�����ɂ���Ă�MID�����W�̉���MID-Hi��MID-LO�̍��ɋC�����B
����E�E�E��v���X�`�b�N�̉�������đN�x�������邪�A���E�̃T�[�r�X�G���A�͍L����MID-Hi��MID-Lo�̍����킩��ɂ����B
�������̍L���A�����A���X�j���O�ʒu�A�悭�����\�[�X�ɂ���Ă����̓��[�U�[���I������Ƃ��ł��B
�S�R�S�R�́A�����ڂ̊��ɒቹ���ł܂���B���X�j���O�ɂ͏[���ȑш�܂łłĂ���̂ł����A��^�E�[�n�[�Ȃ̂���������ƒႢ�Ƃ���܂ŏo���ˁI�I�I�Ȋ��҂͂��Ă͂����܂���
�łȂ��������߂ď��Ƀn�}��̂ł͂Ȃ��āA���͂���Ȃ���A�����āA�E�[�n�[���\�ɑ��ăG���N���[�W���[�e�ϑ���ĂȂ�����I�I�Ɗ�����Ďg���̂��S�R�S�R�̎g�������Ǝv���Ă��܂��B
��������Ƃ�����A�z���ނ��Ǝv���܂��B�z���ނ͐̂Ȃ���̃O���X�E�[���Ȃ̂ł����A��������ނ̃T�[���E�[���Ȃɂ���Ƃ��Ȃ��i�ɂȂ�܂����A�z���ނ̗ʂ�ς��邱�ƂŃ`���[�j���O���ł��܂��B
�������́A�\�Ȃ�ʐ^�����������������グ���ق����ǂ��Ǝv���܂����B
�C���V�����[�^�[�͉���Ɏg���Əd�ʃo���X����邭�Ȃ��Ď��d�ʼn���̂ł������߂͂��܂���B
���Ȃ�傫�ȃ��m���g��Ȃ��ƁA�G���N���[�W���[������܂��B
�������߂́A�d���t�F���g�A�^���O�X�e���V�[�g�A�R���N�V�[�g��g�ݍ��킹�Ď���ł��B
�����́A�^���O�X�e���V�[�g���g���Ă��܂��B
�T�v�I�Ƀ|�C���g�����Ƃ�����Ă����܂����B
�����ԍ��F26043409
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
�@�@�F����
��Foolish-Heart����
�@�@�����b�ɂȂ��Ă��܂��B
���܂��A�`�F�b�N���ׂ��̓E�[�n�[��Mid-Lo�̃G�b�W�ł��B
�@�@���w�E�̔@���A�������ׂ���Ԃł��B
���������́A�\�Ȃ�ʐ^�����������������グ���ق����ǂ��Ǝv���܂����B
�@�@�Q���ڂ̎ʐ^90mm�p�A��Ԃƃ{�b�N�X�̊ԂɗL��܂����B
�@�@3���ڂ̎ʐ^�A�A�b�e�l�[�^�[�̏�Ԃł��A���I�ɂ́A�~�h�ȏ�̃��x�����Ⴂ�l�Ȋ����ł��B
�@�@�O�b�h�}���A�I�����W�p�b�R�@���̔�r�ŒႢ�����o�����A�ꂪ�����l�ȁA�i�f�h�}�X�Ƃ̔�r�͖����ł����j
�@�@�O�c�������@���}�������A���o���Ȃ��ł��܂��B
�����ԍ��F26046148
![]() 3�_
3�_
�ʔ���DAC�������܂���
80�N��̔M�������Ă���!
�`�b�v�Z�b�g�������P��DAC D-10VN �m16BIT VINTAGE�n
https://greenfunding.jp/lab/projects/8662?utm_medium=GREENFUNDING&utm_source=criteo&utm_source=criteo&utm_medium=display&utm_campaign=2303_CV20LAL_last2030days&utm_id=364472&cto_pld=-5DyACwxAQCJuEEmHVX9Bg
�@DAC�`�b�v���T�u�{�[�h�ɂ��č����ւ�����DAC�ł��B
�@DAC�`�b�v�͂R��ނ���I��
�E�o�[�E�u���E��PCM53JP-V�@(16bit�}���`�r�b�g)
�E�\�j�[CX20152 (�ϕ��^DAC)
�EPhilips TDA1541A (16bit DEM)
�@
�@���ɐϕ��^DAC �\�j�[CX20152���咍�ڂł��ˁB
�@�ꎞ��PCM���R�[�_�ɓ��ڂ���Ă����@���Ɏ��p��̂Ȃ��ϕ��^DAC�Ō����I�Ɂ@�ŋ߂�DAC�݂����ɃC���[�W�m�C�Y���o�Ȃ��̂Ł@���Е����Ă݂�����i�ł��ˁB
�@�ꎞ���ADAC�`�b�v������ւ��^�͎��삵����Ł@PCM53��TDA1541A�������Ă��܂������A�ϕ��^DAC�����͎g�������Ƃ������ł��B
�@�܂��@�~�������@PCM53����Ȃ��ā@PCM63���ǂ��Ȃ��Ǝv���܂���(16bit�ł͂Ȃ���)
�@�O�ς� NEC A-10���Ł@���U�[�u�d�����ăM�~�b�N�ς�ł܂����A�قƂ�ǃX���[�z�[�����i�Ȃ�ʼn������₷�����ł��B
�@�ŋ߁A�K�v�������ă}���`�r�b�g��CD�v���C���[�����ē���DAC�Ł@SPDIF�o�R��PC�Ƃ�WiiM�Ȃ��Ł@Amazon Music�łʼn��o�����Ă����ł����A��͂�}���`�r�b�gDAC�͐���ĂȂ����ǁA�������ȋ������ǂ��ł�....��...�@�n�C���]96KHz�����ɐ�ւ��ƁA���e�͈͊O�ŋ���ȃm�C�Y���o����̂��ʂ���ł��B
�@���̂ւΏ��ł��Ă���̂��Ȃ����Ă��Ƃ��C�ɂȂ�܂����A�Ȃ��Ȃ��}�j�A�̋Ր��ɐG���ʔ�����悾�Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F26046213
![]() 3�_
3�_
����ҏW�Ɏ��Ԃ��������Ă��܂��܂������@��N�P1��3���ɍL���ŊJ�Â��ꂽ
�u��R��@�I���K�̉�@����X�s�[�J�[�R���e�X�g�v�̓����Youtube�ɃA�b�v���܂����B
https://www.youtube.com/watch?v=F0J1oFoS0jE
�@����́@FOSTEX 8cm���j�b�g���g��������X�s�[�J�[
�@����̓��}�n�ɒ��͂�����ŏo�i���Ă܂��A�^���Ɠ����S�����܂����B
�@�������ꂽ FOSTEX 8cm���j�b�g�ł����A�V�����j�b�g�A�������j�b�g�A�`�����@�I�[�v���o�b�t�����璹�^�o�b�N���[�h�z�[���܂łƁ@�o�i�҂̃A�C�f�A�̋l�܂������l�ȃX�s�[�J�[�V�X�e���������Ċy���߂܂����B
�@���z�Ȃǁ@�ꌾ�R�����g���炦��Ƃ��肪�����ł��B
�����ԍ��F26048921
![]() 3�_
3�_
�� BOWS����
�@�@
Youtube�@�]���o����V�X�e�������̂�PC�ʼn摜�������܂����B
�����I�Ȕ��A�d�グ���ǂ������ȁA�܂˖��������A
PC�̉��ł������̈Ⴂ�L��悤�ł��A�]���͖����B
�S��̃K���X�r�o�A����ł����H�A�S�{�����ĂT���z���A��̎n���l���Ȃ��ƁA
�Y�ނ���ł��B
�����ԍ��F26053704
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
|---|---|---|
Micro]NC5(�E�H���i�b�g)�Ƀ}�E���g����Alpair 5G |
NC5H(�}�z�K�j�[)�Ƀ}�E���g����Alpair 5G |
Alpair 5G�̎��g�������ƃC���s�[�_���X���� |
�t�B�f�B���e�B���T�E���h�E�����d�q�Y�ƁEstereo
3�Ћ��Î�����@2025�~�ɍs���Ă��܂����B
https://silicon.kyohritsu.com/ONfdKYO-2025/index.php
�@�ړI�́A�����K���X�U����(UTAG)���g�p���� Mark Audio Alpair 5G�����߂ł��B
�@���N�A�~���[�Y�̕��M�@�X�s�[�J�[�R���e�X�g�̃I�}�P�Љ�Ƃ��� Alpair 5G������ł����A�������Ƃ���ɁA�S�ẴR���e�X�g�o�i��i���]�������������܂����B
�@�ł������Z������(2����)�ł������L�����z�[����8cm���j�b�g��炵����Ł@����A�����Ə����Ȏ������Ł@1���Ԃقǂ�������ƕ����܂����B
�@�t�B�f�B���e�B���T�E���h�@��������ɂ��Ɓ@�~���[�Y�̕��M�Ŗ炵���̂ɔ�ׂā@�_���p�[������f0�𗎂Ƃ��Ēǂ������̂������ł��B
�@�����K���X�f�ނ��J���������{�d�C�Ɏq�̐���������܂������A�܂肽���݃X�}�z�̉�ʂŎg���锖���K���X�����g�������̂Ł@�U���̏d�v�v�f�A�����A�����W���A��d�̃o�����X���ǂ��A�S���g���ŋ��U�̎����������̂��������Ƃ̂���
�@�����\���ăV�r�����̂��@���g�������Ł@�A���~�U�����Ɓ@2KHz�Ńf�B�b�v5KHz�����肩�番���U���⋤�U�ɂ�錃�����s�[�N�f�B�b�v���n�܂��ł����AAlpair5G��f0�`10KHz�܂Ł@�قڃt���b�g�A15KHz�����肩��K���X�U���̋��U���n�܂��ł�������O�Ȃ�Ł@�قډe���Ȃ��̈� �悭�o�����}���`�E�F�C�X�s�[�J�[�̂悤�ł��B
�@����ł����ā@�C���s�[�_���X����������Ɓ@�ӂ����Ǝ��g���ɉ����Ă��킶��オ���Ă����ł����A�オ��������Ȃ��B
�@���ۂɖ炵�Ē����ƁA�𑜓x�����낵�������A���L���A�|���L���A�����U���L�����F���Ł@�K���X�L���H��F�C��������悤�Ȃ���
�@���傹��8cm���j�b�g�Ȃ�Ł@���ɗ���ቹ�܂ł͏o�܂��A���`�ō���܂ł͂܂������j�]�������B
�@���낵�����j�b�g�ł��B
�@���^��MicroNC5�E�H���i�b�g�ɓ��ꂽ���̂Ɓ@���傫�� NC5H�@�}�z�K�j�[���C���ɓ��ꂽ���̂��܂������A��{�I�Ƀ|�e���V�������������̂� ��͂�@NC5H�̕����]�T�������ėǂ������B
�@�Ƃ������ƂŁ@Foo����̗\�z�ʂ�@�N���t�@���ōw���\�܂����B(��)
http://blog.fidelitatem-sound.jp/2025/01/15/%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%ef%bd%9ealpair-5g%ef%bd%9e/
�@���j�b�g���̂̔\�͂͐S�z���Ă��Ȃ��̂ł����A�s���Ȃ̂́@�������E�����ă����N�����݂ɏo�ׂ��҂�����Ȃ��̂��H�Ɨ�ɂ���ă}�[�N����Ȃ�Ł@�����Ƀ��m�T�X�d�l�� Alpair 5G V2���o���ˁ[���Ƃ��A10cm���a�� Alpair 7G���o�Ȃ����Ƃ����S�z(����?�j�͂���܂��B
�@��������́@����������Y��������Ł@�����͏o�Ȃ�����Č����Ă܂������A�}�[�N����̓������ā@�ǂ̂��炢�H�Ƌ^���]�n�͂���܂��B
�����ԍ��F26068713
![]() 8�_
8�_
BOWS����
���[����
���̃��j�b�g�ABOWS������Ȃ��킯�Ȃ��Ǝv���Ă܂����B
�Ƃ���Ƃ���ŁA�l���u�ǂ���BOWS����������v�ƌ�������u���₢��v�Ƌ��Ă܂������A����2���Ԃ̎����Ŋ��S��BOWS�����߂郆�j�b�g�Ȃ̂��킩���Ă܂��������
�l�́A���ɗ������ȃw�b�h�z���h���C�o�[�Ɋ��ҁB
���ƁA���}�n�̃��j�b�g�ł���
https://mjnetshop.thebase.in/items/95875128
����Ȍ`�ŏo�Ă܂��ˁB
������Ȃ�ł���������܂����B
�����ԍ��F26070136�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
2025/03/02 17:43�i8�����ȏ�O�j
��BOWS����
����ɂ���
���@���Ă܂��āA���炭�͂Ȃ�Ă���܂����B
�A�L���t�F�[�Y�̂c�`�b�`�b�v�́A�Ǝ��̕��̂悤�ł����A
�������z���������ł��傤���H
�ӂƂ������Ƃ���A�L���t�F�[�Y�̂c�`�b����ɓ���A���ɂ���Ƃ����������͖����̂ł����A
�����Ԏ������Ă����Ȃ��Ƃ���ɁA�f�m���ƍ�������Ǝv���̂ł����E�E
�v�X�ɃA���v�ɉ���ꂽ�Ƃ���A���̈����ɂт�����E�E�E
�܂��Â��A���v�ł�����ˁE�E�E�E
NC7v2_WN�@+�@T500A-MK3�@�̑g�ݍ��킹�@�c�{�ɛƂ�Ƃ��������܂���B
�ł͂܂�����������@�Ȃ̂ŁA�����C�ŁB
�����ԍ��F26095520
![]() 1�_
1�_
�I���t�F�[�u���^�[�{����
�����A�ŋߏ������݂����Ȃ��Ǝv��������@�ł����H
�@�a�@����ꎞ�A��Ȃ�ł��傤���H
�@�������{�������������B
>�A�L���t�F�[�Y�̂c�`�b�`�b�v�́A�Ǝ��̕��̂悤�ł����A
�����@�A�L���t�F�[�Y���f�m���̐��i���A���܂�S���Ȃ��̂Ő^�ʖڂɃE�H�b�`���Ă��܂���B
����ƃA�L����DAC�͐v�����ɂ���ăf�B�X�N���[�g��������A��ʓI��DAC�`�b�v�g�����肵�Ă����Ł@���i�����킩��Ȃ��Ɖ��Ƃ�
>�v�X�ɃA���v�ɉ���ꂽ�Ƃ���A���̈����ɂт�����E�E�E
>�܂��Â��A���v�ł�����ˁE�E�E�E
�@�R���f���T�����܂�����ˁB
�@���炭�炵�Ă���Ǝ��ȏC����p�ł悭�Ȃ��Ă��܂���B
�@�X�s�[�J�[���炳�Ȃ��ł����Ɠ݂�܂��B
�����ԍ��F26095581
![]() 1�_
1�_
BOWS����
�|�[�^�u���d���l�^�ł����A����l�͂����ăX���[���Ă��܂��B
�Ȃ�Ƃ������E�E�E�E�l�i�Ȃ�ŁA��y�ɍw���ł���z�͋�`�g���^�������g������Ă���x�Ȋ����ŁA�������g���M�����[�^�[���Č��\�Ȓl�i���܂���ˁB
��×p�Ɏg���鏃�����g���M�����[�^�[�́A���ꂾ���Ő����~����E�E�E�E�E�E�E
https://www.youtube.com/watch?v=cuj2y_ZooDA
https://www.youtube.com/watch?v=qn2XqrAAgD4
�ŋ߁A���̐l�̓�����悭�݂Ă܂���
���������A�o�b�e���[�쓮����̂Ȃ�A�P�O�OV�̌𗬂ɒ��������A�Ȃ��݂��������Ē����ڗ������ق����������Ƃ��������Ă��܂��B
�����ԍ��F26096668
![]() 1�_
1�_
���A�������݂P�폜���ꂿ������
Accuphase�̈������悭�Ȃ������̂��Ȃ�
�Ȃ̂ł�����x�����ƁAAccuphase�́A���i���̂��̂́u������Ɓv�u�܂��߁v�ɍ���Ă���̂����A�J�^���O�̐�`���傪���ɂ���ˁ[���Ęb���ŁA�A�L�����撣���������A�s�[������̂̓K���K������Ăق����Ƃ���ł����A�f�o�C�X���[�J�[���撣�����������Ђ��撣�����悤�ɏ����̂͂ǂ��Ȃ��H���Ęb���ł��B
D���A���v���o�������ɂ́AIR�̃`�b�v���g�����̂ł����A�u���ʂ̃f�W�^���A���v�ł̓t�B�[�h�o�b�N���g��Ȃ��̂��A�A�i���O�i�Ƀt�B�[�h�o�b�N��Accuphase�͂����邱�ƂŁE�E�E�v����́A�`�b�v�̎d�l�ł��I�I
�Ƃ�
�X�e���I�Đ��ɂ͂P�`�b�v�Q��������DAC������悢�̂����AAccuphase�͂Ȃ�ƂW��������DAC���E�E�E�E�����ESS�̃`�b�v�̎d�l�ł��B���ł��A�W��������DAC��������Ƃ����Ă���Ă�̂Ȃ�A����͂���ł�����˂Ƃ͎v�����B���ؐ��̐��i�͂Q���������������ĂȂ������肷�邩��˂�
�R�͂��Ă��Ȃ����ǁA�O���[�]�[���ȕ\�L�������̂��l�͂������C�ɓ���Ȃ��A���i���̂��͈̂����Ȃ��̂�����^�����������ė~�����Ȃ��Ǝv���Ă���E�E�E�E�E�I�ȏ������݂ł����B
�܁A���ꂩ���A�ꐶ�����폜�v�����Ă�낤�˂�
�����ԍ��F26096906
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
�@�@�F����
��Foolish-Heart����
����͗L��������܂����B
���̌�i�W���Ȃ��܂܁@�����Ɏ����Ă��܂��B
�C���o�[�^�[�@���@d���A���v�Ɂ@�T�O�w���c�����g�����AOUT�Ƀg�����X��ڑ��B�P�Z�b�g�@���ł����B
�����{��k�Ў��@�d�C�͎~�܂�@�K�X�@�����@�����Ă����@�G���R���A�t�@���q�[�^�[���������B
�K���d�C���g��Ȃ��K�X�X�g�[�u�ۑ����Ă����A�i��_���Y�f���ʼn\���̂������@��A�����������ɂ�����Ƃꂽ��j
�d�C���g��Ȃ��@�g�[���A�i�J�Z�b�g�R�����ɋ��Ă��̖ԓ��j�D�D�D
���������������F�����ł��B
�����ԍ��F26096917
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ���
��matu85����
���������@��x�݂ł�
�����́A�A�L�V�I��80�ň�x�ݒ�
���āAmatu85����@���߂����������Ă܂�
�}�L�^�̃o�b�e���B�\�ł̃f�W�A���쓮�ł�����
�d�r���g���������v��USB�[�d��͂���܂�����
�ŋ߂�
�}�L�^�̃o�b�e���B�\�ł̃|�b�g(�P�g��)�ȂǗL��̂�
�����m�ł����H
https://www.makita.co.jp/product/cate/?&type=2&move=catm&catl=16&catm=&volt=&title=%E4%BB%96%E5%85%85%E9%9B%BB%E8%A3%BD%E5%93%81
�P�g����
https://www.makita.co.jp/product/list/?type=3&move=catm&acce=&btry=&volt=&idst=&catl=16&catm=%E3%82%B1%E3%83%88%E3%83%AB&title=%E3%82%B1%E3%83%88%E3%83%AB
�\�[���[�p�l������[�d�Ƃ��o�����
�f�W�A��������ɏȃG�l�ł���
���m��ł���X���[��������
���ז����܂����@�@��x�݁@�q��
�����ԍ��F26097320
![]() 3�_
3�_
2025/03/04 07:37�i8�����ȏ�O�j
��BOWS����
����ɂ���
���̕���2���ԂقǂŖ߂�܂����B
�c�`�b�͈ȉ��̂��̂ɂȂ�܂��B
�o�b�l�h�Ȃ̂ŁA�c�r�c�͒����Ă��Ȃ��ł��B
https://www.accuphase.co.jp/model/dc-801.html
��������܂����@�ł��B��������ǂ��Ђǂ��A�M���Ȃ��Ȃ�������܂���B
BOWS��������C�����Ă��߂������������B�ł́B
�����ԍ��F26097351
![]() 1�_
1�_
Foo����
>�|�[�^�u���d���l�^�ł����A����l�͂����ăX���[���Ă��܂��B
>�Ȃ�Ƃ������E�E�E�E�l�i�Ȃ�ŁA��y�ɍw���ł���z�͋�`�g���^�������g������Ă���x�Ȋ����ŁA�������g���M�����[�^�[���Č��\�Ȓl�i���܂���ˁB
>��×p�Ɏg���鏃�����g���M�����[�^�[�́A���ꂾ���Ő����~����E�E�E�E�E�E�E
���Ƃ��ƃL�����v�Ɏg���悤�Ȃ���Ő����@���������Ȃ��ł���˂�
https://www.youtube.com/watch?v=cuj2y_ZooDA
https://www.youtube.com/watch?v=qn2XqrAAgD4
�@�C�`�P������̉���͂��傢���傢���܂����A���~��������̂łقǂقǂɂ��Ă܂��B
�@�����g�o�͂�D���A���v�ł���˂�
�@�������̂̓X�C�b�`���O�ł����...
�@�̂�,AC�P�O�OV�̃��[�^�[�Ł@AC100V�̔��d�@�@�͋Z�̃m�C�Y�J�b�g���Ă��������܂����B
�@�ǂ������Ȃ�A���ׂ̏d���ɂ�����炸�ɏo�͂����肷��A���A���v�ŃC���o�[�^�������̂ɁA�g�C���Ƀo�b�e���Ȃ��Ȃ邩�Ȃ�
>���������A�o�b�e���[�쓮����̂Ȃ�A�P�O�OV�̌𗬂ɒ��������A�Ȃ��݂��������Ē����ڗ������ق����������Ƃ��������Ă��܂��B
�@�܂��������̒ʂ�Ł@�o�b�e���[�@���@AC 100V �� �����d���@���ā@�M�����C���Ɂ@���ʂ�AD�ϊ���DA�ϊ����Ԃ����ނ��炢���ʂȂ��Ƃł��B
�@�g�����X�����H��������M�����[�V�������o�b�`���ł��B
�@���́A�s�̂̑��u�������Ƃ��������Ȃ�Ł@�����Ȃ�����������ł��B
>�A�L�����撣���������A�s�[������̂̓K���K������Ăق����Ƃ���ł����A�f�o�C�X���[�J�[���撣�����������Ђ��撣�����悤�ɏ����̂͂ǂ��Ȃ��H���Ęb���ł��B
�@�ق�܃R��
�@�����D������Ȃ����ǁA�������������C�ɓ���܂���B
�@�I���t�F�[�u���^�[�{�����DAC�ׂ悤�Ǝv�������ǁ@�Ǝ���
�uMDSD�́A8��H����쓮�́uMDS++�ϊ�����D/A�R���o�[�^�[�v�ɂ��ϊ��덷�̋ɏ����Ɠ����ɁA�����g�̈�̕s�v�m�C�Y��ጸ����n�C�J�b�g�E�t�B���^�[�@�\���������Ă���̂��傫�ȓ����ł��B�v
�@���������@�ǂ�DAC�`�b�v�g���Ă���̂������ς�킩���B
�@���N���������n�C�G���h�E�I�[�f�B�I�V���[�Ł@�A�L����CD�v���[���̊�݂����ǁ@�����ڂ��ꂢ�Ȃ���AIT�������̊�݂����ɁA�S�͂�DAC�`�b�v�̉����グ�邼�Ƃ����C�����S���Ȃ��B�Ȃ��F�ʎY�i���Ă��ł����B
�@
�����ԍ��F26099351
![]() 3�_
3�_
�I���t�F�[�u���^�[�{����
���\�d�ǂۂ��ł��ˁA�Ƃɂ������g�̂����͑厖�ɂƂ����Ă��A���łɂԂ����Ă�̂ŁA������Ǝ����Ă����������K���ȁB
�Ƃ������ƂŁA�A�L���̃l�^���E�E�E�E�EMultiple Double Speed DSD����������ƁA������ƌÂ�
https://www.jas-audio.or.jp/journal-pdf/2015/05/201505_006-009.pdf
����ȋL�����łĂ��܂��B
�ǂ�ł����ƁAESS��ES-9018���g���Ă��邱�ƁA������9018�̓�������ɂȂ�܂��B
�ȒP�ȓ��{��Ȃ̂ŒN�ł��ǂ߂�Ǝv���̂ł����A�A�L��������Ă邱�Ƃ́A����9018�ɓ��������W��DAC��S���g�����A�Ƃ������������ł��ˁB
���̐��i�́A���E�ɂP�`�b�v=�W��DAC����삳���Ă�̂ŁA�P�U��DAC�����Ɏg�����x�������Ă�����Ă��ƂɂȂ�܂��B
�������Ɂu����v�Ȃ�ł����A�����Accuphase��������킯�ł͂Ȃ��AESS����������m�ł��B
�������A���̃`�b�v�A8��DAC����o�͂�����킯�ŁA�S���g����I/V�ϊ�����ɂ́u�d���ʁv���傫����OP�A���v�ł͂܂��Ȃ��L���܂���A�Ȃ̂ŁAAccuphase���撣�����̂́A�����̕����Ȃ킯�ŁA����͎��ۂɂ́u�悭�撣��܂����v�ȏ��ł͂���܂��B
ESS�̃`�b�v���g���Ă��Ă���������Ă���DAC��S���g���v�͓���̂ň������،n�̋@��B�͂ł��ˁA��������Ă���DAC�̂����̂Q���炢�����g���Ă��܂���B
���g���̋@��́A�m���ɂǂ��̃`�b�v���g���Ă���̂��킩��Ȃ��̂ł����AAccuphase�̃J�^���O���݂���DAC�`�b�v��1�ɂȂ��Ă��āA�ŏ�L��pdf�Ɠ����悤�Ȏ��������Ă���̂ŁA�����9018�̌�p�@�ł���9038���g���Ă���낤�Ǝv���܂��B
9038�́A����16��DAC�������Ă���̂ŁA9018���Q�g���̂Ɠ��������P�`�b�v�łł���̂ŁA�����ăO���[�h�_�E���ł͂Ȃ��̂ł����E�E�E�E�E�E�܂��A����ȂƂ���ł��B
�����ԍ��F26099591
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
�@�@�F����
����x�݂���
�A�L�V�I��80���������܂�����
�@�����ɂ��܂����f�[�^�[�@�@���ׂ���܂������@�����Ȃ��̂��ꐡ�₵���ł��B
�o�b�e���[�P�g���A���ɂ͋����킩���A�W���b�P�b�g�~���������B
�������M���ɁA���z�̗l�ȁA�ł��AAC�d���L�鏊�ł킴�킴�o�b�e���[�ŕ����������b�g�́A�H
�D���Ȑl�������ł��傤���ǁB
�莝���̃C���o�[�^���d�@�A2.3KW�����g�ď����ėL��܂����A
�ł��A��펞�A�Z���ԂȂ�@�o�b�e���[�A�K�\�����@���ł��傤���� �ЊQ���@���̗͂l�ȋC�����܂��B
D���A���v�Q���@�P�[�X�Ɏ��߂ċ��鏊�ł��B
�P���@�o�b�e���[�R�{�ς�ŁA���E�O�i�ʓd���ƂP�{�őS�����ւ���l�ɂ��Đf���B
���ʂQ���@�𐧍쒆�A�O�o�̃I�����W�p�b�R���쒆�@�ԈႦ�t�ʑ��ɂȂ������@���̈ӊO�ȉ��ɋC�t���@
�����ăX�C�b�`��t���܂����B
���ׂ���������ǁ@�Ȃ��Ȃ��O�ɐi�܂ʍ������̍��ł��B�B
�����ԍ��F26102700
![]() 4�_
4�_
�@Foo�����Matu����͂����m�ł��傤���ǁ@�^����CD�v���[�������S���Ȃ�ɂȂ�����Ł@10�N�Ԃ肭�炢��CD�v���[�����������Ă܂��B
�@1bit�n���ėD�G�����ǁ@�ǂ���������̂Ȃ�y�������̓}���`�r�b�g����˂����Ă��ƂŁ@�O���I�̍����i����肵�ăV�R�V�R�������Ă܂��B
�@�{����14bitDAC�̃I�[���h�}�����c����D���Ȃ�ł����A�������Ƀs�b�N�A�b�v�����Ղ�����I�V�}�C�Ȃ�Ł@���낢��T������@�݊��i�̃s�b�N�A�b�v���V�i�œ���ł���}���`�r�b�g�@�����������2��قǒ��Ó��肵�܂����B
�@�S�_�n���_�ł������A�d���R���A�Z���R���S�Ƃ������A�lj��R���f���T���ł��AIV�ϊ���R���Ƃ������@�Ƃ��������̃��j���[�ł����A���Y�p�CDAC�݂����ȁ@�@���͂Ȃ����ǁ@�Ȃ����₷���ā@���������ǂ��Č������܂����B
�@�����ACD���f�B�A�̓��b�s���O�����㉟������ɂ��܂�����Ł@���@�������ւ�ŕ����I�ȉ������ĊǗ�����ς��Ȃ��Ɓ@�v���Ă��邱�̍��ł��B
�����ԍ��F26111420
![]() 5�_
5�_
matu85����
matu�閧��n�͒j�q�Ȃ�݂�ȓ�����Ԃł����I�I
�����f�łȂ���ABOWS������x�݂����f�v���ĐF�X�����������ł��˂�
�S�R�S�R�͂܂��A����Ȋ����ł��B
10���N�O�ɂǂ����̎G���Łu�S�R�S�R�̎�_�����ǂ���v�Ȃ�ċL���������ăG���N���[�W���[����蒼���AMID-Hi�̃z�[��������MID-Lo���O���Ƃ�����Ă��̂ŁA����͂���Ă݂����Ȃ��Ƃ��l���v���Ă����肵�܂��B
�ŏI�I�ɂ�Mid-hi�̃h���C�o�[��2�C���`�h���C�o�[�ɂ��邱�ƂɂȂ邩�Ȃ��Ƃ��v��������E�E�E�E�E�E
BOWS����
CD�v���[���[���g��Ȃ��Ȃ���20�N���炢�o�̂�CD�v���[���[�̉����ĖY��Ă��܂���
�����ADAC�Ɋւ��Ă͂�����ƑO�ɂ��������Ǝv���̂ł������A�u�}���`�r�b�gDAC�v�̉��͖l���D���ł��B
���܂�b��ɂȂ�Ȃ�Analog Devices��20bit�̓z��������
���Ƃ́A�X�O�N���SONY��DAC�̉����D���ł��˂�
����Ă邱�Ƃ�ESS��DAC�ɋ߂��̂ł����A�����ł����獡�قǂ̐��x�͂Ȃ������̂����ł����u�����SONY�t���b�g�͂����Ȃ��v�Ƃ��v���Ă��܂����B�P��DAC�͎����Ă��Ȃ������̂ł����ADCT-2000ES�Ƃ���DAT�������Ă��āA�����̃f�W�^�����͂�CD�v���[���[��T�E���h�J�[�h�̏o�͂����Ďg���Ă��܂����B
������DTM������Ă��āASONY�̃f�W�^���G�t�F�N�^�������������ĂāA�u����σf�W�^����SONY�v���Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂��B
�ȂA�����Ȃ�SONY���I�[�f�B�I�������Ă��[DAC�Ƃ��A���v�Ƃ�����Ă���Ȃ����Ȃ��Ƃ��W�����҂����Ă��܂��B
�����ԍ��F26112686
![]() 1�_
1�_
Foolish-Heart����
�ŋߎv���Ă��鎖�́A�Ԋ�S������ �悸�́A�l�b�g���[�N�����[�p�X�A�p���h�p�X�A�o���h�p�X�A�n�C�p�X�A���ꂼ��ɕ����@�A�b�e�l�[�^�[ ���O���A���v��VR�Œ���
���Ŕ������s����Ȃ�A�A���v�̑O�Ƀt�B���^�[���@�X�s�[�J�[�O�̃t�B���^�[���O���B�i�r�o�ɉߓ��͂������ׂ̃n�C�p�X�͕K�v�Ǝv���j
�r�o���e�ϔ{���A�f�b�g�}�X���AMid-hi�̃z�[���̉������X�A����`���B
���ɂ��A�l���̒n�a�яc�f�ΒȎR�o�A���̒n�a�ѐ��֓V���A�_��܂ŁA�s�Ċς悤���A
�����茩�āA�c��̐l���ǂ��܂ł��B
�����f�łȂ���ABOWS������x�݂����f�v���ĐF�X�����������ł��˂�
�����ǂ��v�������L��ΐ���A�s���Ɉڂ��܂��傤�B
�����ԍ��F26115435
![]() 2�_
2�_
�m�荇�����炨�m�点��...
�y�C�V�m���{�^�}�X�^�[�Y�@�X�E�Ɩ��I���̂��m�点�z
https://ishinolab.net/
>���f���C�V�m���{�^�}�X�^�[�Y�������ڂ��������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B
>�ˑR�̂��m�点�ƂȂ�܂����A�X����2025�N1���ɉi���������܂����B
>����܂ŊF�l�Ɏx�����Ȃ���A��D���ȃI�[�f�B�I�ƌ����������������X�́A�X���ɂƂ�
>�Ă��������̂Ȃ����Ԃł����B
>�S�����߂Đ��i�����͂����A���q�l�ƌ𗬂��d�˂����Ƃ��A�����ƌւ�Ɏv���Ă������ƂƎv���܂��B
>�Ɩ��͏I�����A�H�[��2�����������đދ��������܂��B
>�z�[���y�[�W��3���ɃN���[�Y�����Ă��������܂��B
�@���炭���ĂȂ��������ǁ@�ނ�����V���b�N�ł��B
�@�䖻�������F�肵�܂��B
�@�I�[�f�B�I�E�l�̉��ЂƂ����܂����ˁB
�@�펯�I�Ȃ��l�i�œ���\�ȃg�����X���A�b�e�l�[�^�����p�b�V�u�v�����₽�ꂽ....�c�O
�����ԍ��F26116528
![]() 4�_
4�_
��BOWS����
�Ȃ��
�ƒ�̎���Ŕ����������������Ǝv���Ă��̂ɁA�i���ɓ���s�\�ɂȂ��Ă��܂��܂���
���̎�̂��̂�������Ȃ̂͂킩���Ă����̂�
�䖻�������F�肵�܂�
�����ԍ��F26116757
![]() 1�_
1�_
��[��������������
�@�ŋ߂܂Ł@�t�@�C�����b�g�R�A�g�����g�����X���p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�̐V����J�����Ă����̂Ł@���Ɏc�O�ł��B
�@�A�L���t�F�[�Y�̂悤�Ȋ�Ƒ̂Ƃ��ė��h�ȉ�Ђ̐��i���@�t�B�f���b�N�X�A�S�V���A�o�N�[���v���_�N�c�̂悤�ȑn�Ǝ҂̑z�������������@�ǂ����������Z���Ȃ̂��鐻�i�D���Ƃ��Ắ@�M�d�ȑ��݂ł����B
�@�u���܂ł��@�݂�Ǝv���Ȑe�ƃK���[�W���[�J�[�v
�����ԍ��F26117724
![]() 4�_
4�_
�C�V�m���{�X���l�̌䖻�������F��\���グ�܂��B
�{���Ɏc�O�ł��ˁB
�I�[�f�B�I�ƊE���A���Ȃ艺�����A���̒S����̔N����オ���Ă��Ă��Ă��������������ꂩ�瑽���Ȃ��Ă��������ł��B
�I�[�f�B�I�W�̃C�x���g�ɍs���ƁA�Ⴂ�l������Ƃ߂������Ⴄ���炢�ŁA�l�ł���u�ŔN�����v�B
�T�O�߂����������ŔN���ł��悗
https://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/52/52251.html
���̖{��D���A���v�������������ɍw�������̂ł����A��/���҂̖{�c�����IR�i�C���t�F�j�I���j��D���A���v�̊J���̐l�炵���A���̕����ǂ������R���̏o�g�ŁA�R������̏�i���C�V�m���{�̓X������炵���Ƃ����b�����ċ������������̂��C�V�m���{�ł��B
�ŁA�݂Ă݂���AD���A���v�ł͂Ȃ��āA�R���̉�H���g�������i��A�o�b�e���[�쓮�̃A���v�A�g�����X���v���A���v�Ƃ��u�Y�L���[���v�Ȑ��i�Q������Ă��B
���ǁA�C�V�m���{����̐��i�����Ƃ͖��������̂ł����E�E�E�E�E�E�E�E�E
������ƁA�R���̃A���v��}���cLV�ɉ����ċv���Ԃ�ɕ��������ȁB
�����ԍ��F26118240
![]() 1�_
1�_
Foo����
>�I�[�f�B�I�ƊE���A���Ȃ艺�����A���̒S����̔N����オ���Ă��Ă��Ă��������������ꂩ�瑽���Ȃ��Ă��������ł��B
>�I�[�f�B�I�W�̃C�x���g�ɍs���ƁA�Ⴂ�l������Ƃ߂������Ⴄ���炢�ŁA�l�ł���u�ŔN�����v�B
>�T�O�߂����������ŔN���ł��悗
�@�����ȃI�[�f�B�I�C�x���g��R���e�X�g�Ɋ���o���܂������A�قƂ�ǔN��肪�唼�ł��ˁB
>���̖{��D���A���v�������������ɍw�������̂ł����A��/���҂̖{�c�����IR�i�C���t�F�j�I���j��D���A���v�̊J���̐l�炵���A����>�����ǂ������R���̏o�g�ŁA�R������̏�i���C�V�m���{�̓X������炵���Ƃ����b�����ċ������������̂��C�V�m���{�ł��B
�@���{�̃I�[�f�B�I�j�ɂ����ā@�T���X�C�̑��݂́A���i�������ł����A�Z�p�҂̈琬�A�y�o�̈Ӗ����傫�������ł��ˁB
>���ǁA�C�V�m���{����̐��i�����Ƃ͖��������̂ł����E�E�E�E�E�E�E�E�E
�l���A������p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�͔������肾������ł���...
>������ƁA�R���̃A���v��}���cLV�ɉ����ċv���Ԃ�ɕ��������ȁB
�@���ꂪ���{�ɂȂ邩���ł��ˁB
�����ԍ��F26121341
![]() 2�_
2�_
�@������ƃX�s�[�J�[�l�^�ł��B
�@����A�����̃��T�Ŗ����킹������Ă܂������A��^�g�[���{�[�C�X�s�[�J�[��炵�����ɁA�����Ɉ�a���������ā@�����̉�������ʂ�^�����܂����B
�@�y�Ȃ��Ă���Ɓ@����̊y��̓���̃t���[�Y�Ł@������ƕς����ǁA�C���t���Ȃ��l������悤�ȃ��x���ł����B
�@�X�C�[�v�M�������Ă�������Ƃ�������������ł����A���g����ς��Đ����g10�g�o�[�X�g�M���𗬂������Ł@����̉������ςŁA�^�������g�`������A����Ȃ�Ȃ��Ă܂����B
�@�g�[���{�[�C�̒��ӓ������A���傤�ǁ@���̂��炢�Ł@����ɒ�ݔg�o�Ă��悤�ł��B
�@�����A�o�Ȃ��悤�ɋz���ނƂ����˔Ԃ�����ő��ł����A����Ȓ�ݔg���o��Ɓ@�ǂ��������ɂȂ�̂����킩���ā@�����������Ȃ�܂����B
�@����@�g�[���{�[�C���ā@�ӂ��ɍl������ݔg�o�₷���`��Ȃ�ł��ˁB
�����ԍ��F26121350
![]() 3�_
3�_
���́A�����̃X�s�[�J�[�V�X�e�����Ă���ƁABOWS����̂�������
�u�����Ɉ�a���������ā@�v�������邱�Ƃ͑��X����܂��B
��r�I�A���́u��a���v�����Ȃ��̂�KEF�̐��i��AB&W�̂W�V���[�Y�������肵�܂��B
JBL�́A���������u��a�����y���ށv�X�s�[�J�[���Ǝv���Ă��܂��B
���́A����n�̃X�s�[�J�[���Ă���ƁA�u��a���v�̕������u���v�ƂƂ炦�Ă��āA����҂́u��ԕ����Ă���y��v�̉����u�\�ɏo���v�悤�Ȏd�l�ȋC�����Ă����肵�܂����i���ꂪ�ABOWS����ƈꏏ�ɍs�����C�x���g�S�ʂւ̃g�[�^���̊��z�j
���ʂƂ��āA�l��GENELEC������ς�ǂ��ȂɂȂ����悤�ȋC�����Ă��܂����A���Ԃ̕]������B&W�̂W�V���[�Y��]�����Ă�����A��̑���}�j�A�l�̍������`���N�`���]�����Ă���_�ł��������肵�܂��B
�܂��A���ʑ̃X�s�[�J�[�ɉ\���������Ă���̂����̂�����������܂���B
���ɁAmatu85����̍�i��]�����Ă���̂��A���ꂪ�N�����Ă��܂��B
�Ƃ����Ă��A���i���炻���܂ő@�ׂȕ����������Ă��Ȃ��̂ŁA�I�[�f�B�I�́u�Ɠd�v�ł���u�Ƌ�v���Ƃ��v���Ă���̂ŁA�X�^�C���b�V���ȃg�[���{�[�C��ے�͂��܂���B���X���ŏ������̂ł����A���\�����߂�̂��A�f�U�C���A�������Ƃ̒��a�����߂�̂����I�[�f�B�I���Ǝv���Ă��܂��B
�����I�ɃX�s�[�J�[�������鎖���d�v�ł����A���m�Ƃ��Ă̑��݊������R�ł��邱�Ƃ��X�s�[�J�[�ɋ��߂��鐫�\���낤�Ȃ��Ƃ��������Ă����肵�܂��B
�����ԍ��F26122997
![]() 2�_
2�_
��Foolish-Heart����
�Ԃ͎~�܁^�߂����
�I�[�f�B�I�͒��߂����
���Ă�ł���
�����ԍ��F26123673
![]() 1�_
1�_
������Ȓ�ݔg���o��Ɓ@�ǂ��������ɂȂ�̂����킩���ā@�����������Ȃ�܂����B
��JBL�́A���������u��a�����y���ށv�X�s�[�J�[���Ǝv���Ă��܂��B
���Ɂ@�ڂ���B
�A
����[��������������@�́@jazz���Ȃ�<=>JBL�͌����Ȃ�<=>JBL��jazz������������jazz�O��̉����@�B
����A������ׂ����Č��܂����A�@�n�C�@�R�O�P�ɖ������A�S�R�S�R�L���ł��A�����́A�[���o���܂����B
�����A��ւȂ���̕�����ׂ��Ȃ��ł��A�����́A���y�A�y���߂�Α���ōD���̂��Ɓh�C�t�܂����h�B
�A���o�������I�������o����K���ȂƁB
�ŋ߁A�����̘A�ꍇ���A�ɂ��L��A���̉B��ƁA��̂��ĂS�R�S�R�Ŋy����ł��܂��A
�����̑��q�U�ˁA�^�C�^�j�b�N��CD�AJBL�ŕ���������A�h����������h�������Ă��܂�����B
���N�ɂȂ���4��ʁ@���ɐڂ��܂����A
https://nozasaho.jimdofree.com/�@���̐搶�̉��t��2���ʂ̎��ߋ����ŕ��������o���܂����B
�M�y���ǂ����̂ł��B
���C�V�m���{�@
���݂��m��Ȃ������ł��ASEL�@�^���S�@�R���@���b�N�X�@�P�O��㔼���A����Ȋ����ŔF�����Ă��܂����B
���p�̃A���v�A�R���̃h���C�o�[�g�����X�g���ĂȂ��A�v�͂ʏ��Ōq���ċ���̂����ł��B
���܂�ς���ĐV�̐��E������Ă��������B
�����ԍ��F26124554
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
�@�@�F����
�o�b�e���[���t���Q���@�A�r��������F�X�L��܂����A
�������l�ߊ����A���߉������A���[�^�F���l�@�A ���a�F�u���b�t�u�b�@
�����|�R�F��� �I�X�J�[�s�[�^�[�\���g���I���A�S�g���b�N�e�[�v�@��
������芬�\���܂����B�i2005�NWAV���j
�X�V���ꂽ�A��@�ŋv���Ԃ�ɒ����B
�Q�O�`�R�O��Œ����ăe�[�v�A���������̂ƁA�����ݔ��̈Ⴂ�A�V�N�Ȏv���ł����B
���Ԃ͎~�܁^�߂����
�@�I�[�f�B�I�͒��߂����
�@���Ă����Ă͂܂��B
�A���v�̃c�}�~�A�R���̏�����TR�A���v�̕��A���ɎR���̃g�����X�Q�B
�뎚�A�E���C�����ǂݑ����̂����������������B�@�@�@�@����ɑz�������Ă����\�ł��B
�����́A�O�b�h�}�����a�ł����B
�����ԍ��F26127980
![]() 2�_
2�_
��Foolish-Heart����
�����������b�ɂȂ�܂��B
�S�R�S�R�@�����z�[���̒����A�S�R�R�R�̂ŗǂ��Ǝv���̂ł����A���ۂ̒����A�J���ʐϓ��A
�������ɐ}�ʂȂǑ��݂��܂����B
�G�b�W�̏C���A�����s���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B
�X�������肢���܂��B
�����ԍ��F26133756
![]() 1�_
1�_
matu85����
JBL4333��4343�́A�E�[�n�[�AMID-Hi�AHi�͓������j�b�g�ł��B
�Ⴄ�̂́AMI���̃z�[���̒����ƁAMI���|LO���j�b�g�̗L���ƃG���N���[�W���[�T�C�Y�ł��B
�S�R�R�R���݂�ƁA�E�[�n�[�ƁAMID��S������2402�i�R���v���b�V�����h���C�o�[�j+2312�i�z�[���j+���������Y�̃N���X��800�����ł��B
2312+1�C���`�h���C�o�[�ł̒���800�����܂Ŏg���邱�ƂɂȂ��Ă���̂ł����E�E�E�E�������ɑш�I�ɂ͌q����܂����A�ǂ��������܂������ĂƂ���ł��ˁB
�W�O�O�����̃N���X�ŁA�X���[�v���ǂ�����̂����Ęb�����łĂ��܂��ˁB
�f�W�^���`�����l���f�o�C�_���g���č�����MID����āA�E�[�n�[�����t�ɂQ���Ő��ăC�R���C�U�[�ƃ��x�������ł��܂����Ƃ����Ă̂��ǂ����ł͂����ł����E�E�E�E�E�E
�Ƃ�܂���Ă݂�̂Ȃ�A���ۂ�4333�̃z�[���ƃN���X�I�[�o�[���w������ƊȒP�ɂł��͂���̂Ŏ����Ă݂鎖�͂ł���Ǝv���܂��B
matu85����̑_���Ƃ��ẮA�O�b�h�}���Ɠ������E�[�n�[��ǂ��g���ċ���ȃf�b�h�}�X���\�z���A�E�[�n�[�ɓK�ȗe�ς̃G���N���[�W���[��^���āA���ʂ�MID-LO���r�����Ċ�{�QWAY�̃V�X�e����g�ނ��Ƃ��Ǝv���̂ł����A�z�[�����ƃz�[���`�������I�Ȉٌ^�z�[���ɂ���Ƃ������Ɨ~�����łĂ������ȗ\�������܂��B
�����ԍ��F26136269
![]() 1�_
1�_
2025/04/17 13:00�i6�����ȏ�O�j
��BOWS����
����ɂ���
�����������Ă���܂��B
BOWS����������炱����ŁA������̂悤�ŁA�����܂�������ł��B
���āA�ŋ߃}���`�X�e���I�ɂ͂܂��Ă���̂ł����A�T�C�h�Ƀ\�j�[ �u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[ SS-CS5
���g�p�����Ă����̂ł����A�Ȃɂ�璆����������₵�Ă��銴���Ȃ̂ŁA�t�������W�ɂ��āA
CHP90mica�Ɍ������Ă݂܂����B���\�������肵�����ɂȂ�܂����B
�܂����F�^���I�ȃT�E���h�Ȃ̂ŁA�P�̂ł̉����͂l�`�n�o�V�Ƃ͈Ⴄ��������܂��A
�l�`�n�o�ɂP�R�Z���`�͂���@��т��Ă����̂ł����A�c�O�Ȃ���@�����悤�ł����B
�����ԍ��F26149589
![]() 2�_
2�_
Foo����
>�����I�ɃX�s�[�J�[�������鎖���d�v�ł����A���m�Ƃ��Ă̑��݊������R�ł��邱�Ƃ��X�s�[�J�[�ɋ��߂��鐫�\���낤�Ȃ��Ƃ��������Ă����肵�܂��B
�@�S�~�݂����Ȍ��h���̎���X�s�[�J�[��ʎY���Ă����Ł@�����ɂ��ł�(��)
��[��������������
>�Ԃ͎~�܁^�߂����
>�I�[�f�B�I�͒��߂����
�@����ł������ԂƎ��Ԃ�������̂��P�[�X�̍쐬�ł��B
�@�f�U�C���Z���X�������̂ŋ�J���Ă����h����...�Ő��i�̃A���v�̒��g���|�C���đ������g�����Ă��Ƃ��悭���܂��B
matu85����
�@4343�̏n�����i��ł܂��ˁB
�@��Ȃ�Ł@���낢��y���߂�Ǝv���܂��B
�I���t�F�[�u���^�[�{����
>�Ȃɂ�璆����������₵�Ă��銴���Ȃ̂ŁA
�@���l�i�����l�i�Ȃ̂Ł@�l�b�g���[�N�Ɏg���Ă��镔�i���n��Ŕ����������Ǝv���܂����A�K�����ĉ��C������A�t�������W�Ԃ��������ǂ��Ǝv���܂��ˁB
�@�}�[�N�̃y�[�p�[�R�[�� �}�C�J�� 6cm�̂���g���Ă��܂������A���悪����オ����̂̂Ȃ��Ȃ��@���������ł����B
�@13cm���Ɓ@�d�S���������ėǂ���Ȃ��ł��傤���H
�@���͒l�i�Ȃ�Ȃ�ł��傤���Ȃ��ł����A�o�X���t�̃`���[��������������ǂ��Ȃ邩���ł��B
�����ԍ��F26150119
![]() 2�_
2�_
���I�[�f�B�I��I�ԂƂ��ɂ͐T�d�ȑԓx�ŗՂޕK�v������
����g�ɂ܂���܂��˂�
�����ԍ��F26150706
![]() 1�_
1�_
�����������Ă��炢��������ł��B
�������@�� �������s�@�� ����ς��s�@�� �q�瑜 �� �T�u�X��
�@���ĂȂ���(��)
�����ԍ��F26150735
![]() 1�_
1�_
2025/04/18 14:09�i6�����ȏ�O�j
��BOWS����
����ɂ���
�q�瑜
���̕������킩��܂���E�E�E
���@�@�@���������ā@�n�C���]�H�H�H�H�H
�����ԍ��F26150867
![]() 1�_
1�_
�h���R���p�N�s�Ƃ��o���ʓD���n���Ƃ��͕������݂����ȑJ�s���s��Ȃ̂ł���
�����ԍ��F26150884
![]() 1�_
1�_
BOWS����
���S�~�݂����Ȍ��h���̎���X�s�[�J�[��ʎY���Ă����Ł@�����ɂ��ł�(��)
����X�s�[�J�[��A�{���͋Ɩ��Ŏg�����j�^�[�X�s�[�J�[�͂��̌���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
���̌��Ƃ��āA�����������y��I�[�f�B�I�ɋ������Ȃ��u��w�v�ɂƂ��ăX�s�[�J�[�͓��Ɂu�ז��v�ȃ��m�ł����Ȃ��̂ŁA���߂Ă������̒��Łu���a�v���K�v���Ǝv���Ă��܂��B
�l�́A��������16�N�A�������������̃X�s�[�J�[���ꂽ���ƁE�E�E�E�E�E
���v���̍ő�́u�X�s�[�J�[�P�[�u���v�ł��ˁB�|���̎��ɃX�s�[�J�[�P�[�u����������ɑ|���@����������̂ŋC�����Ɛ��������Ă��ăA���v���V���[�g������A�Ȃ����X�C�b�`�ނ��j�ꏰ�ɗ����Ă�Ƃ��A�s�̃X�s�[�J�[�̕n��ȃ^�[�~�i���̓v���X�`�b�N�̑����������E�E�E�E�E�E�E
TAKET��BAT-1�́A�u�z�R���������v�Ƒ|���@�ŋz���ē����̃t�B������̐U���������Ȃ��Ă��Ƃ��A���C���X�s�[�J�[�̏�v��@���|������Ƃ��ɗ��Ƃ���ăP�[�X�����ꂽ�Ƃ��E�E�E�E���������̂���
�w�b�h�z����������Ă��܂��B���̂������ŁA�^�Ђ̃w�b�h�z���́u�����ڂ͗ǂ����A���͎G���ȁv�Ƃ��킩�����肵�܂�������
����ςˁASONY�AAKG�AYAMAHA�͍�肪�ǂ��ł��˂��@���ɂ��������łȂ��A���ɉ��Ă��C�����ł���B���i������ł��邵�A���[�J�[�ɑ���Ƃ������蒲�����Ă���܂��B���i�T�C�N�����������Ă̂��d�v�Ȑ��\���Ȃ��Ƃ��v�����肗
�����̏ꍇ�ɂ́A�q���B�����A�Ȃ��ő�̔j��҂ł����A���Ƃł͕ꂪ�����悤�ȃ^�C�v�Ȃ̂Łu�����������̂��v�Ǝv���Ă��܂��B
�܂���͎������I�[�f�B�I���g���̂ŃX�s�[�J�[�P�[�u���͔����đ|��������̂ŗǂ�������ł����E�E�E�E�E
�Ȃ̂ŁA�u�ǂ�ȃX�s�[�J�[���ǂ��̂��v�ƍl����ƁA�����l�ɉƑ�������ꍇ�ɂ́u�Ƒ����厖�ɂ��Ă��ꂻ���ȃf�U�C���v�A�u�������̒��ł�����ƒ��a����f�U�C���v�Ƃ����͔̂��ɏd�v���Ǝv���킯�ł����A�C���̂��Ƃ��l����Ɓu���W���[���[�J�[�v�������́u��������Ƃ����㗝�X�v�����Ă�A���i�T�C�N���������ăp�[�c��������ƕۑ����Ă��郂�m���Ď��ɂȂ�Ǝv���Ă����肵�܂��B
����Ɍ����A�g���u���̌��ł���X�s�[�J�[�P�[�u�������������ǂ��Ƃ���
�����ԍ��F26155418
![]() 4�_
4�_
�}�[�N�I�[�f�B�I�̃K���X�U���X�s�[�J�[�ł����A�R�C�Y�~�����Ɂu�����@�v���͂��A�X���ŕ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
����̓}�W�Ŗʔ������j�b�g�Ȃ�ň꒮�̉��l�͂���܂��B
�܂��A�}�[�N����̐V��Q�O�Z���`���a�̃��j�b�gMA200-M�������ɁE�E�E�E�E�E
https://shop.koizumi-musen.com/?pid=183824051
��������炸�A�C�P�C�P�m���m���ȃ}�[�N���Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F26160589
![]() 1�_
1�_
��BOWS����
�@�@�F����
�� �v�킸�̂��v���o���ď��Ă��܂��܂���
�U��Ԃ��Ă݂ā@�@���ĊO�ꂽ�������ł��܂����@���� �n�C
�� Foolish-Heart����
�������������y��I�[�f�B�I�ɋ������Ȃ��u��w�v�ɂƂ��ăX�s�[�J�[�͓��Ɂu�ז��v�ȃ��m
���x�@�t�E�[�����́A���ꂢ�D�� �ЂÂ��Ȃ��v�̎�@�����܂łƔY��ŔY���
���́A�ЂÂ�����ŁA�������O�t���������Ɂ@��������]���Ɂ@�}�[���[�A�V���X�^�[�R�[�r�`�A�u���b�N�i�[���@�Ă��t�����B
�����A�\�[�X���e�[�v�����ׁA���[�����b�N������ςȎ��ɓx�X�B
�����A�S�R�S�R�a�@�X�s�[�J�[���ɔ[�߁A�P�A���o�������A�u�[�~�[�Ȓቹ�����܂�@�s�A�m�̉��F�����P���ꂽ�l�ȁB
�G�b�W�@�ގ��S���A\15,000���Q�@13,000���Q�@�ł����B
�b�����̂܂܂Ŋy���݂܂��B
����[��������������
�����N�̍�����MJ6�Œ������Ƃ��Ɉꔭ�ŋC�ɓ�����
MAOP11�@�|�`���܂������A
�S�{�|�`�b����A���Ȃ�̋��z�A�����Ɏg���A����́A�ÊρA�K���X���݂�悤�ł����B
�T�����{ �����\�����f�w��:�ɉ����āA �������璷��ӂ�܂� �ړ������݂悤�ƁA
�ژ_��ł��܂��B
�����ԍ��F26161551
![]() 2�_
2�_
matu85����
�G�b�W�������Ƃ���ƁA���܂ł́u�����Ă��[���v�������R�[����������Ɩ߂��Ă���̂Œቹ�͒��܂�܂��ˁB
4343�͌Â��v�Ŕ�I�ł����A�~����Ȃ���Ίy�����X�s�[�J�[���Ǝv���܂��B
ATT��������Ɠ��삵�Ă��ꂽ�璲����������܂����ˁB
���N������AATT���O���O�����Ă̂��B��̉�����ł�����
���T�����{ �����\�����f�w��:�ɉ����āA �������璷��ӂ�܂� �ړ������݂悤��
�l���T���㔼�Ɂu�Ȃ���̏��F�v������ꂽ�牓���ɍs�������Ǝv���Ă��܂��B
�u���܂Ȃ݁{��߂��܁v���A��B���ʁA�ɓ��哇�̂ǂꂩ��
�����A������Ƌ��N�g���[�j���O���T�{���Ă����̂ŁE�E�E�E�E�E�E�܂��̏d���i���Ă܂��B
�X�Rkg���W�S�����܂ōi�����̂ŁA���ƂT�������炢�i�����牓�����Ȃ��ƁE�E�E�E�E�E�̏d���i��Ȃ��Ə��₪������
�����ԍ��F26167995
![]() 2�_
2�_
��matu85����
MAOP11�͗~���������Ń|�`��܂���B����sp��u���X�y�[�X������܂��A����蔠��p�ӂł��܂���B
����web�ŏE������H�}�����ɃA���v�̕����ł��B
�z���p�ɔ������P�[�u���Z�b�g��AWG24�������̂ōׂ��Ɉ���ꓬ���B
�P���ň����₷���Ƃ��������b�g�͂���܂����A�莝���H���T�C�Y���͂��Ȃ��B�X�g���b�p�����͑�}���Ŕ����܂����B
�i���������Ƃ�AWG18/20�����������ƂɋC�t���B�B�B�͓����j
�d���ʓI��24�ŏ\���������邵�A24�Ɋ��ꂽ�ق��������̂��Ȃ�
�������璷��ł����A�����ł��ˁB�y����ł��Ă��������܂�
�����ԍ��F26168195
![]() 1�_
1�_
Foo����
>���̌��Ƃ��āA�����������y��I�[�f�B�I�ɋ������Ȃ��u��w�v�ɂƂ��ăX�s�[�J�[�͓��Ɂu�ז��v�ȃ��m�ł����Ȃ��̂ŁA���߂Ă�����>�̒��Łu���a�v���K�v���Ǝv���Ă��܂��B
�ŋ�WAF�Ƃ����]���w�W���ꕔ�Œ��ڂ���܂��ˁB
>WAF (Wife Acceptance Factor) �A����Ɓu�Ȃ̏��F�W���v�B�܂�A�I�[�f�B�I������ۂɁA���l��p�[�g�i�[�Ɏ��₷���W���Ƃ����Ӗ�
https://stereo.jp/?p=6649
>���v���̍ő�́u�X�s�[�J�[�P�[�u���v�ł��ˁB
....
>����Ɍ����A�g���u���̌��ł���X�s�[�J�[�P�[�u�������������ǂ��Ƃ���
�@���D�����܂ł��B
���̓_�A�p���[�h�X�s�[�J�[�̓P�[�u����������̂��ǂ������ł��ˁB
XLR����Ȃ��ā@RCA�̕����ǂ��̂���
�@�����̓��r���O�ɒu���ĂȂ��̂ʼnꂽ�o���͂Ȃ��ł����A230L�̃o�[�`�J���c�C�������r���O�ɒu���Ă������ɂ͂��Q���Ă܂����B
>�}�[�N�I�[�f�B�I�̃K���X�U���X�s�[�J�[�ł����A�R�C�Y�~�����Ɂu�����@�v���͂��A�X���ŕ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
>����̓}�W�Ŗʔ������j�b�g�Ȃ�ň꒮�̉��l�͂���܂��B
�Q���܂������@�����v���܂��B
�@������������ɐF�C�̂���MAOP�ƈ���������ł����A����̐L�ъ��͓��M���m�ł��B
�\������Ă��܂��@�W���ɓ���ł��邩��
�Ƃ肠�����@Alpair 5V3�ƃ��v���[�X�\��ł����A�C�ɓ��������p������邩������܂���B
matu85����
>�G�b�W�@�ގ��S���A\15,000���Q�@13,000���Q�@�ł����B
>�b�����̂܂܂Ŋy���݂܂��B
�@���X�ƍĐ��v�悪�i�s���Ă����ł��ˁB
�@�d�オ�肪�y���݂ł��B
>�T�����{ �����\�����f�w��:�ɉ����āA �������璷��ӂ�܂� �ړ������݂悤�ƁA
>�ژ_��ł��܂��B
�@�������������Ȃ��V���ǂ��G�߂Ȃ�Ł@�A�܂����ł��B
��[��������������
>����web�ŏE������H�}�����ɃA���v�̕����ł��B
�@����͑f���炵���B
�@�A���v�̎�����n�߂�Ɓ@�A���v�ƃX�s�[�J�[�̑��ւ��킩���ė������[�܂�܂��B
>�d���ʓI��24�ŏ\���������邵�A24�Ɋ��ꂽ�ق��������̂��Ȃ�
�A���v��鎞�́A�M����p�ׂ̍����A�����d�������p�̑��߂̐��A100V�n�̐��Ɓ@����ނ��g�ݍ��킹��̂ł����ȑ����Ɋ���Ƃ��������ǂ��ł��B
�����ԍ��F26170937
![]() 1�_
1�_
��matu85����
GW���ɒW�H�����瓿���ɓ��茕�R���O��A�ΒȎR�ɓo���ē��㉷��ɐZ����A���ė��܂����B
�����\�����ɉ����č����𑖂��Ă鎞�͉��K�ł����B
�R�������쒬�ɂ͎�����É��\�������H�����Ă��ē��{�̋����ڂ�������̂ł����A���Ă����܂����ǂ�������Ȃ������ł��B
�����ԍ��F26170993�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����̓_�A�p���[�h�X�s�[�J�[�̓P�[�u����������̂��ǂ������ł��ˁBXLR����Ȃ��ā@RCA�̕����ǂ��̂���
�p���[�h���j�^�̏ꍇ�ɂ͒��݂łȂ���Εǂ��V�䂩��A�[����L���ăP�[�u����XLR�Ŗ��ߍ��݂����ˁI�I
����Ȃ��Ȃ����A�����I�ɂ��ǂ������ł��B
�܂��A���������Ȃ������A���Ƃ��ł��傤����A�S�R�S�R�����܂����Ə������ăA���v�ނƂ����N���ɔ�����ăV���v���ȃV�X�e����g�݂܂���
8361A�̌�p�@�ƁA�\�[�X�@��͓K���ȃX�^�W�I�pDAC��I��ł����������Ȃ���
�Ƃ������Ȃ���A���̎��ɂȂ�����S�R�S�R�����ÓT�I�ȃV�X�e����g�ނ�������܂���B
��[��������������
BOWS������������ł����A�d�q�H��̓����z���́u�K�ޓK���v�ł��B
����Ă������Ɂu�����́A���̃Q�[�W�̃P�[�u���v���Ă킩���Ă���Ǝv���܂����A���̎��ɂ͑����Ɋ����Ȃ�Ċ��o�͂��łɖ����Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA�l���悭�g�������z���ނ̓��K�~��2514�@2515�@2516�@�ł��B
�Ƃ肠�����A�������߂̃v���A���v�L�b�g�Ƃ��Ă�
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g106469/
�������ȁBMUSES72320���g�����d�q�{�����[���Ȃ�ł����A�������ĊȒP�B
OP�A���v�͂��D�݂ŕς����܂����A�P�[�V���O���y�B
�d���́A�����d���ł����A������ŏ��̓L�b�g�ō���Ă��܂������Ǝv���܂��B
https://eleshop.jp/shop/g/gD5E413/?srsltid=AfmBOoqozsGYzxsexB_OwvVoj1SBjAy5IE1TCNCANcR_XpU69Nh0mwBv
���ꂪ���₷�����ȁB�g�����X�������̃g���C�_���͊��Ɨǂ��̂Ńg���C�_���g�����X�ƃZ�b�g�Ŕ����Ă��܂��Α����������ƁB
�����ԍ��F26171024
![]() 2�_
2�_
�ʐ^���������̂ŁE�E�E�E�E�E�E
�O�o�̏H���f�W�^���{�����[���L�b�g�ƁA�}���c��LV�p���[�A���v���g�ݍ��킹�āA�]�����Ă����p�[�c�ނŃR���p�N�g�ȃA���v���������ł��B
�T�C�Y�I�ɂ�A5�T�C�Y�Ɏ��߂Ă��܂��B
�P�[�X�́A���Ɏg���Ă����̂��A�p�[�c�̑g�݊����Łu�͂���ˁ[�ȁv�ō�蒼�����]�蕨�ŁA��������炯�������̂ł��傤�ǂ悢�[�ނ��]�����Ă����̂ŁA�����Ɋ����g�ݕt���ă|�R���ƃP�[�X�ɂ͂߂�������
���łɁA�P�O�N�ȏ�O�̍H��ŁA���Ȃ�������Y��ɁA������ƍ�����Ȃ��I�ȓz�ł�����
�����ԍ��F26171045
![]() 3�_
3�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
�����Ⴎ����z���@4��X�s�[�J�[�ؑցA�A���v2��ؑւ� |
�����Ⴒ����z���@�����Ďd�����Ε�����Ȃ� |
���܂Ȃ݊C���@�`��������ō��ł��傤�@�@Foolish-Heart���� |
��O���_�� |
��BOWS����
�@�@�F����
��Foolish-Heart����
�S�R�S�R�@���a���C�ɓ����Ă�݂����Ł@��������Ƃ͖����Ǝv���܂��B
���X�Rkg���W�S�����܂ōi�����̂ŁA���ƂT�������炢�i�����牓�����Ȃ��ƁE�E�E�E�E�E�̏d���i��Ȃ��Ə��₪������
�R�O��� ���� �����x ���R�r���@�����Ȃ��Ȃ����A�ꍇ���Ƃ��̉ו��A�����̕����A
�S���Ő��S���[�g����������������܂��A����ɋ߂��̏d������������J����ł��B
�u���܂Ȃ݁{��߂��܁v���F�����Ċy���܂�Ă��������B
����[��������������
���悢�攼�c�t���n�܂�܂����A�@�@�o�b�ƈႢ�A�A���v����ɂ́A���c�A�t�����ł����B
���ށA�S�������Ɩ����ł��ˁA���ẴS�~�̎R�@��N�����āA�K���ł��B
��BOWS����
�e�q�ł��Ȃ����@�Z��ł��Ȃ��@���ʂ��قȂ�@�����ł̑Ë��_ �@�C���h�p�L�X�^������������A�l�����߂��̐S�Ƃ��H�H
�K���X�U���X�s�[�J�[�@���ʂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B
���X�v�[�j�[�V���b�v����
��GW���ɒW�H�����瓿���ɓ��茕�R���O��A�ΒȎR�ɓo���ē��㉷��ɐZ����A���ė��܂����B
�ǂ��ł��˂��A���Ŏ���10�N�L�т܂������A�f�v�́A�h������̂ŁA���̖����Ǝv���܂������A����R�����x�݂�19���� �ΒȎR����R���\�܂����A70��Ō�̔N�A���N�̌��āA�̂�т�ƍs���܂��B
�������\�����ɉ����č����𑖂��Ă鎞�͉��K�ł����B
�i�����F�����łȂ���������ł����H�B�j
���̂���ŋ��܂����AWAF�@�̖�肩�ˑR�A���䗅�Q����@�ƁA
�����ԍ��F26172099
![]() 3�_
3�_
�J�^�@���ł��Ӓ�c�@�����Ă�����A�u�X�^�[����Ӓ���v�Ł@�G�A�W���[�_���̃V���[�Y���A���b�h�E�c�F�b�y�����@�L���u���őS�����̃T�C���������ꂽ�A���o���Ƃ������z�Ӓ肳��Ă��čŏI�˗��l��
�@�u�S�R�s���炨���ł́@�������傳��ł��B�v
�@���������@�ǂ����Ŋ猩�����Ƃ��Ƃ����邼�{�l���H�H
�@����́A�@�f���[�N�E�G�����g���y�c/���C�E�A�[���X�g�����O/�r���E�G���@���X/�w�����E������/�W�����E�R���g���[���@���X�̓`�����̃W���Y�E�W���C�A���g�̐��ʐ^�ƃT�C�����������A���o���������B
�@�ǂ����@�u���̎��Ɋy���܂ʼn��������ĎB�e���ăT�C����������Ƃ�
�@�܂��A��������@���Ȃ��肩�˂��낤�Ȃ��Ǝv�����B
�@�Ӓ�z�@�P�T�O���~�@�����`���ǁ@���̂��炢�̉��l�͏\�������Ȃ�
�@�˗��l�̏Љ�͈�ؐ����͂Ȃ��������@�܂��_�C�A�g�[���̑b��ł����Ă��L���Z�p��������@���낢�뎝���Ă�˂�
�����ԍ��F26185361
![]() 4�_
4�_
����
�W���Y�~���[�W�V�����̃T�C����
https://www.tv-tokyo.co.jp/kantei/kaiun_db/otakara/20250520/08.html
�����ԍ��F26185395
![]() 3�_
3�_
�_�C�A�g�[���Ȃ����...�^���� ���E�ōł������ꂽ DS251 mk2
https://audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-251mkii.html
�̗ތ^�R��̒�����ׂ����܂����B
�E�I���W�i��
�E�����i�i�U���A�G���N���[�W���A�o�X���t���A�l�b�g���[�N)
�E�I���W�i���{�z�[�����[�h
�@�T�O�N�O�̃X�s�[�J�[�ł����A�G�b�W�Ƀu���[�L�t���[�h��h���ď_�炩�����������ɂ�������炸�A�ĊO�@�܂Ƃ��ȉ��ŕ����ċ����܂����B�ŋ߂̗D�����ȃX�s�[�J�[�ɔ�ׂā@���L���Ƃ���͂���Ȃ���A�𑜓x�����������ėǂ��ł��B
�@�����i�͌��c�����@�D�G�ɂȂ�������
�@�z�[�����[�h�t���́A�z�[���̌��ʂƂ��������@�I���W�i���i���j�������̂܂芴���������ɂ������킸�A�w���������ĉ����L�тĂ�����ۂ�����܂����B
�@25cm�̗��h�ȃA���j�R���C��H������25cm�E�[�t�@�[�t���� �Q�{�łT���~�ƈ��������B���Ȃ�10�`20�{���炢�̉��i�ɂȂ邩�Ɓ@���Âł��e���������̂œ��肵�ėV�ѓ|���̂��ǂ�����...
�@
�����ԍ��F26186445
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
���Ɩ����@�����N�߂Ă��܂����A
�������Ō��������L��l�ȁA
�Ⴕ�����āA�@�B��Ƃɍs���Ď��܂����B
�Q�T�P�́A�J���Ă��܂���A�����Ǝv���Ă���SP�傫����������A�X�ɁA�t�F���C�g�ł��B
����͂Q�O�N�ʑO�A���O���̂��ݏċp��A������͋L���Ȃ��A�@�@���āA�@���l�Ɏg�p���A�܂���鎖�����ς��B
�@�@�@�@�@�@�@�ł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���C�Ȃ��h
�����ԍ��F26199966
![]() 2�_
2�_
���X�v�[�j�[�V���b�v����
��Foolish-Heart����
�~�J����錾�̒��A�o�Ă����A�l����B�P�S�O�O�������蔲���ė��܂����A
�K���A�ΒȎR�A���������������������i��͗��Α�R�����j�J���~�炸�B
�N�̎��A�A�ӂŖڊo�߁A�p�𑫂��Ȃ��瑋�z����������Ɩ��V�̐���A
�J���������o���O�ցA�@�@�@�@�@�@�@�@���̌i�F�A�@�@�����A�@�@��Ԃł����B
�I�[�f�B�I�@�������������A�@�ǂ����̏�ABOSE�t���Ă��܂������H�H�H�ł����B
�����ԍ��F26200052
![]() 3�_
3�_
��BOWS����
�@�@�F���܁A
�_�C���g�[���A�P�O�N�Ԃ�ʂɓd���ʂ��Č��܂����B
�ŋ߁A�Ԃ̃{���l�b�g�J���Ă݂Ȃ����A�u���[�L���A�g�߂Ŗ����Ȃ�܂��āA�����ēh������ǂ�Ȃ���ł��傤�B
���݁A�ǂ������̂́A�G���t�^�̃}�[�N�I�[�f�B�I�@�i�A�N�e�B�u�f�b�g�}�X���j
�O�H�A������������Ō��悤�Ƃ��v���܂��B
�����ԍ��F26237651
![]() 0�_
0�_
matu85����
�@���@�@�����낤���܂ł��B
�@��{�@���a�̃n�C�t�@�C���Ȃ̂ŌÏL���͂����ł����A�g���đf�ނ��@���������1�{10���~���ᖳ������Ƃ����ґ�ȍ��Ȃ�Ł@������Ζʔ����V�ׂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26248329
![]() 0�_
0�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
������̑S�i |
�݂�����10cmx2+�c�B�[�^�[��2way |
�≏�g�����X�@�m�C�Y�t���A�̒ቺ�Ɍ��I�Ȍ��ʂ��� |
��r�Ɏg�����@BOWS�� YAMAHA�t�������W����SP |
�@�^���Ł@�\���X�s�[�J�[��PA�Ŗ����m��Ă��邪�A�I�[�f�B�I�X�s�[�J�[�Ƃ��ĔF�m����ĂȂ� TOA�̃v���t�F�b�V���i�����j�^�[�@ME-50FS���J���҂̉�����Ȃ��炶�����蕷���@�����܂����B
�@10cm�E�[�t�@�[���j�b�gx2 + �}�O�l�V�E���n�[�h�c�B�[�^�[��2way�\���Ł@�����ɊĔz�u����Ă���ς�������C�A�E�g�̑f���C�̂Ȃ��X�s�[�J�[�ł��B
�@�w�ʂ�hypex��nCore250�iD���A���v���j�b�g�j��������ALC�l�b�g���[�N�������ĊO���A���v�ł��쓮�\�Ƃ����ς�����\���̃p���[�h�X�s�[�J�[�ł��B
�@�l�b�g���[�N���C���s�[�_���X���H�ȂNjÂ�ɋÂ��Ă��Ă����Ȃ�ʕ��͋C�������o���Ă��܂����B
�@B&W805�Ƃ�TAD ME1�݂����ȉ����ȂƗ\�z���Ă�����ł����A���������R���V���}�[�����ʎY�����n�C�t�@�C�X�s�[�J�[�𐔔n�g���������قǂ̋��낵���܂ł̉𑜓x�Ńr�r���܂����B���̌�����
�@�Ɍ��܂Řc�݂����炵�A������ē����t���b�g�ɂ�����ŁA�A���v�̓m�C�Y�t���A�����������Ă���̂Ł@�\�[�X�Ɋ܂܂�Ă��鉹���}�X�N���ꂸ�ɑS���o�Ă��܂��B
�@���ɁA�������n���S�^�����������Đ������Ƃ��ɁA������X�s�[�J�[�������錻�ۂ��N���ā@���ꂪ�X�s�[�J�[�O�ɂ��L����A�ڂ��҂�ƌ�����n���S�ɋ���悤�ȍ��o�Ɋׂ�܂����B
�@���y�^���������Ɓ@�s�̂̃~�b�N�X�_�E����������������A�R���v���b�T�[�������Ă�@���ш悢�����Ă�����}�X�^�����O�H���ʼn�����Ă��邩�킩���Ă��܂��悤�ȉ������������G�O���B
�@�ق�ł����ā@10cm���j�b�gx2�ł���Ȃ���A�����̃X�s�[�J�[���������ɂ��Ă���R���g���o�X�}�����o�̍Œ���炵��Ƃ����̋Ƃ�����Ă܂��B
�@�Đ����Ă��鉹���w�b�h�z���Ń��j�^�����O���Ă������ɁA�w�b�h�z�����O���ăX�s�[�J�[�̍Đ��������Ă��@�قƂ�Ǖω��Ȃ�...�悭����@�w�b�h�z���ŕ����̂ƃX�s�[�J�[�ŕ����̂ƈႤ��ł���....���Ď���ɑ��āuME-50FS�g���Έꏏ�ɂȂ��v�Ɖ��ł������B
�@�������H���邽�߂ɃX�^�W�I�Ō����}�X�^�����O���j�^�[�Ɏg���ɂ͍ō��̃N�I���e�B
�@���y�ӏ܂���ɂ́A���x�ȉ���肵�Ă��Ȃ��ƃ}�X�^�����O�̉����̔炪������ē����Č����Ă��܂��Ƃ��������Ƃ낵���X�s�[�J�[
�@�J���o�܂��܂������A�����h�������[�J�[�Ƃ��ė��l�߂Ŗ����グ����ŁA�J���҂����y�D���Ő��^���Ď���b���Ă���̂����������܂����B
�@��ʂ莋��������Ł@�}�j�A�̍��������X�s�[�J�[���r���ĕ����܂������A�X�s�[�J�[�̘c�݂��悭�킩��܂����B�����A�������Ɠ����őf�ނ̖�����X�|�C�����Ȃ�����@�D�݂̖��ɕς���݂����Ȃ����݂��킩���Ėʔ��������ł��B
�����ԍ��F26248335
![]() 5�_
5�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
Mark audio MAOP7 �� ���Ѓc�B�[�^�[ ���g��������o�X���t |
MJ�ɋL���������Ă�������� 2way |
��^30cm�E�[�t�@�[�Ƒ�^�h�[���~�b�h�A���{���c�C�[�^�[ |
DIY Loudspeaker Builder�fs Meeting 2025�ɍs���Ă��܂����B
https://diy-audiospeaker.sub.jp/category/news/
�@���N���s���ā@����R���f���T�X�s�[�J�[���@����v��@�őg�I�C���_�C���Ƃ��ϑԃX�s�[�J�[�������Đ���オ������ł����A���N�́@�V�̗͍�̉����܂����B
�@���N�́@��N�̂悤�ȕϑԂ͂��炸�A�ӂ��̔��^�����������ł����A�}�X�^�[�u�b�N�h�̎�ÂȂ�Ł@�e�X�s�[�J�[�̉���Ł@�X�s�[�J�[�̐v�Ɋւ��@TS�p�����[�^�A�V�~�����[�V�����A�l�b�g���[�N�v�A����������̑��茋�ʁA�C���s�[�_���X�����A�X�s�m���}���̗p���O���t���o���o���o�ꂷ�郌�x���̍������e�Ł@�ǂ����́A�u�������j�b�g�g���Ă���Ȃ��������A����Ȃ������o�Ă���`�@�����[����v�Ƃ������Ȓ��������ƈ�����悷����̂Ł@��������������܂����B
�@�ʔ��������̂́@���N��YAMAHA������ɂ��o�ꂵ�Ă����@�g�[���{�[�C�^�o�X���t��Mark Audio MAOP7 �� �c�B�[�^��g�����ā@�ቹ����̂������́A������ƌ��ł́@12cm 3way�Ɍ�����@12cm�p�b�V�u���W�G�^�[ + �P�u���[8cm���j�b�g +�c�B�[�^�[�@�̈����j�b�g���g���Ă��邯�ǁA�ނ��Ⴍ����Â����G���N���[�W�����g�������́@MJ�ɋL������e���Ă�������� SB Acostic��2way�ɃE�F�[�u�K�C�h �����������̂Ł@����͊i���P��Ł@�������u�ԂɁ@�n�C�G���h�X�s�[�J�[�Ȃ݂ɘc���Ⴍ�A�ʑ������������Ă�����́i�l�b�g���[�N�� �o�b�t���X�e�b�v��C���s�[�_���X�����̂őf�q���������@�����~�͂������Ă���j�@����Ɓ@30cm�E�[�t�@�[+50mm�h�[���~�b�h+���{���̑�^3way ���̃X�s�[�J�[���@�n�ӍH�v���Ēቹ���i��o���Ă���̂ɂ���ׂā@����a�炵�����[�Œቹ�����Ă��ā@��������������肫������o�Ă�����̂Ł@��������Ă��܂����B�@
�@���N���͎Q���l�����Ȃ������ł����A�����͖k�C�����痈�Ă���������āA�Z��������ȂƎv���܂����B
�@���N�́@Youtube�ŃI�[�f�B�I�֘A�̘b�����舵���Ă���@�S�\�Ԃ̃I�[�f�B�I��M�`�����l���@����������Ă����̂Ł@���̂������J�����Ǝv���܂��B
�@���N�͂P�P���ɂ�邻���Ȃ�Ł@�����̂�����͐���s���Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F26314524
![]() 5�_
5�_
DIY Loudspeaker Builder's Meeting���������Ă�����AAudiFill���@���������̎����L�����Ă���Ă��܂����B
29. DIY Loudspeaker Builder's Meeting 2024�����L
https://www.audifill.com/essay/eng/0_29.html
33. DIY Loudspeaker Builder's Meeting 2025�����L
https://www.audifill.com/essay/eng/0_33.html
�@�悭�����Ă����ł���...�@�ᔻ�I�ȉӏ����Ȃ���œǂ�ł��邾���ł́@�D�킩��ɂ����ł��B�@
�@���N�̏Љ�͑O�̓��e�ł��Ă����Ł@���N�ł����A�ϑԃX�s�[�J�[�������ā@�g�b�v�R���������
ESL165
�@���Ǝ���R���f���T�X�s�[�J�[�ł��B
�@�I�����_�̃R���f���T�X�s�[�J�[�}�j�A�̏������L���ǂ�Ł@�Ɨ͂ł��������Ƃ������Ł@���ȑO�ɍ쐬���������̂���^�ł��B
�@���̔��̒��ɂ́@�ł����g�����X�����������Ă��ā@����V�̃o�C�A�X���������Ă��܂��B
�@��[���
�@�R���f���T�X�s�[�J�[�̑t�ł�@�y�ቹ�͂ނ�����D���ł��B
Open B
�@���j�b�g�������̃I�[�v���o�b�t���X�s�[�J�[
�@���̎�̌ÓT�X�s�[�J�[���č����i�݂����ȉƋ�̔��Ƀ}�E���g����Ă��邱�Ƃ�������ł����A�f�U�C�����o�g�̍�҂����Ƃ����_���ȕ��͋C�ɍ\�����Ă��Ėʔ����B
�@���́A���j�b�g�ɂ���ĈႤ���ǓT�^�I�ȃJ�}�{�R�����ŏ�������o�Ȃ����A���̂��钆���������S�n�ǂ�����
�@�\������x�Ƀc�B�[�^�[���t���Ă��܂����A�z������Ă܂���
�@�}���`�E�F�C�X�s�[�J�[���Q�����肾�����͂�....
Klangfilm Homage
�@�����ڂ͂�����ƃr���e�[�W���ۂ��ł����A�P�O�O�N�߂��O�̃g�[�L�[�����̃X�s�[�J�[���j�b�g���@�ŐV�̃V�~�����[�V����/������@����g���ā@���G�ȃl�b�g���[�N�g��Œǂ�����ł�B�X�s�m���}�܂Ōv������Ă��܂����B
�@���̎��Klangfilm EURODYN�n�́@�������Ă����ł����A�̂̍��d�b�݂����ȋ��ш�Ł@�R���g�[/�e�B�{�[/�J�U���X�݂����ȌÓT�̖����q������݂����ȂƂ��낪�����ā@�n�[�h���b�N�Ȃ�����ƍ��ӂ��ɂȂ��ł����A���̃X�s�[�J�[�́@���������܂Ƃ��ɕ����Ăт����肵�܂����B
�@����ρA�X�s�[�J�[���A���v�������l�̑z���Ƙr����Ŕ��������s�������Ȃ邾�Ȃ��Ɗ��S�����������ł��B
�����ԍ��F26317653
![]() 3�_
3�_
 |
 |
 |
|---|---|---|
JBL4343�����i�ƒlj��E�[�t�@�[�@�^���m�C�̏�Ɏ���`�����f�o |
����`�����f�o�� 130Hz��72Hz��12dB/oct |
JBL ��莿������TAD�̃E�[�t�@�[ |
�@���̏T���@�^����JBL4343�ŗV��ł܂����B
�@�J�^�M��4343����Ȃ��ā@�R�[�������������A�G�b�W�S���ւ��A�h���C�o�̐U�����H�A�I���W�i���̃l�b�g���[�N�͕���o���ăV���v�����Ƃ������N�U��4343�ł����A�~�b�h�E�[�t�@�[�̈�������V�� �܂Ƃ��ɖ�̂ɂ����Ԃ��Ԃ������Ă܂����B
�@�����܂ʼn������Ă��@�E�[�t�@�[�͏�肭�炸�A��ɒlj�38cm�E�[�t�@�[��������@�㉺�ŋ��U���N���đ��������ɁA�Ȃ����Ł@����̃`�����f�o�lj����ā@�J�b�g�I�t72Hz�łȂ��Ł@���Ƃ��s���R����Ȃ��ቹ���o�n�߂܂����B
�@�O����v���Ă������ǁ@4343���Ė炵�ɂ����ƌ������A��{�v�ǂ��Ȃ��Ǝv���B
�@�ŏI�I�ɁA����4343��肸���Ԃ�}�g���ɖ�Ƃ���܂ŏo��������...�E�[�t�@�[�Ɋւ��Ắ@TAD�̃E�[�t�@�[�̕����@�����Ԋi��Ŏ����̗ǂ��ቹ�ł����B
�@4343�̃E�[�t�@�[�̂Ăā@TAD�������Ă̂����s�������R���悭�킩��܂����Ƃ�
�����ԍ��F26321133
![]() 4�_
4�_
��BOWS����
4343���ăE�[�t�@�[���G���N���[�W���[���[�ɂ��Ă���̂ŁA�����痣���Ȃ��Ə�����̔��ˉ����������Ă܂Ƃ��ɖ�Ȃ��Ǝv���܂��B10-15cm�������������ɖ�Ǝv���܂����B
���[�U�[�ƌ����킯�ł͂Ȃ��A���������L�ґ�ł̎��̌��ł����B
�ȑO���l�̃P�[�X�ł��܂���Ȃ����Č����Ă��������A���������悤�A�h�o�C�X������A�p�ނŏ�����10cm���炢�����Ă����Ԃ���P�����Ƃ���������Ă܂����B
�����ԍ��F26321283
![]() 1�_
1�_
�v���[���@����
�@4343�́A�X�^�W�I�ŕǖ��ߍ��݂Ƃ��z�肵�Ă����Ł@������x�̍����グ�������ǂ������ł��ˁB
�@JBL�̑�^�X�s�[�J�[�� ����4343��S4600�������܂������A�ǂ������@����ł̓C�}�C�`�Ȃ�ŁA�V���H�[����ő啝�ɉ������Ă��܂��B�u���O�ɉ����L��������܂��B
https://ameblo.jp/youin-koubou/entrylist.html
�@����4343�̃E�[�t�@�[ 2231A�� �U���n���ʂ��d���� ���U���g�� f0=16Hz�Ƃ��̂������Ⴂ�̂Ł@�₽�甽���������ł��B
https://blog.goo.ne.jp/blowup2017/e/7da82f5d3896bff88655e7a80315b6a2
�@�������Ă��@�����̗ǂ� ALTEC 604-8G 38cm �i�������j�b�g�́j�E�[�t�@�[ �U���n��50g�ɑ��� 2231A��151g��3�{�d���̂� �p���X�̗����オ�肪�x���A�܂��U���̎������x���悤�ł��B
�����ԍ��F26321864
![]() 2�_
2�_
��BOWS����
�Ȃ�قǁB
���j�b�g�ɂ���肠��Ƃ������Ƃł��ˁB
�U����150g���Ċm���ɏd���ł��ˁB
38cm�E�[�t�@�[�������Œ��ׂĂ�150g�O��̂��̂͂��邯�ǃ}�O�l�b�g���o�J�ł����Ȃ��Ă��܂����B
�U�����d������͍̂����𑝂��ĕ����U����h���Af0��������̂��ړI���Ă��ƂȂ�ł����ˁB
�����ԍ��F26322053
![]() 0�_
0�_
�v���[���@����
�@�X�s�[�J�[����ŐU���n�ɏd���lj�����Ƃ����̂́@�悭�������ł��B
�@�d���lj�����ƃ��j�b�g�́@f0(�Œዤ�U���g��)��������A���e�ʃG���N���[�W���Œቹ��L���������ɂ��܂��B
�@����p�Ƃ��āA�\���̒ቺ�A�����̒x���A�U�������������Ȃ铙�̃��X�|���X�̗������Ł@�ǂ̕ӂŐ܂荇�������邩���̂Ń��j�b�g�@�p�����[�^��������Ȃ��痎�Ƃ�����T��܂��B
�@�o�X���t�̃`���[�j���O���ς���Ń|�[�g���Ƃ������邱�Ƃ�����܂��B
�@4343�́@25cm�̃~�b�h�o�X�lj��������Ƃɂ���ā@�E�[�t�@�[�͍Œ���L�����߂ɏd�����U���n��I�悤�ł����A�����̎��C��H�ł͎��ė]�����悤�Ȑv�ɂȂ��Ă܂��B
�@����ɔ�ׂā@TAD��38cm�E�[�t�@�[�͐U���n117g������܂����A������V�������Ƃ�����A�悭�o���Ă��ă��j�b�g�d�ʂ��I���W�i����2231A��7.5Kg�Ȃ̂ɑ��ā@TL-1601a��11Kg����܂��B
�@����Ɓ@�E�[�t�@�[�̓~�b�h�o�X�̃N���X���g����300Hz������Ƃ��̂������Ⴂ�̂Ł@�l�b�g���[�N�̃C���_�N�^���X�ƃR���f���T�̒l���傫���Ȃ��ā@�����̈����S�S����R�C���Ɠd���R���g���Ă܂��B
�@�I���W�i���̃l�b�g���[�N��������o���Č����Ƃ��Ɂu�ʖڂ������v�Ǝv���܂����B
�����ԍ��F26324406
![]() 0�_
0�_
��̕��Ł@������DIY Loudspeaker Builder�fs Meeting 2025
�̓��悪���J����܂����B
https://www.youtube.com/watch?v=-f7ChvA2snM
�@�쐻�҂̐v�v�z�A�V�~�����[�V�����⑪�����������ă��x���͍����ł��B
�@����Ŕ��ʂł��邩�킩��܂��A�l�I�ɂ����ȂƎv�����͈̂ȉ��@�S��i
�Q��i�ځA�ӂ�������uunknown�i2WAY+�p�b�V�u���W�G�[�^�[�j�v
�@�� ���j�b�g�P���͑S����1.5���~���炢�̃��[�R�X�g�Ȃ���A����ςȉ��ŃR�X�p�ō��@����������؍H���H�Z�p���K�v
�R��i�ځA�݂₳��u�p�b�V�u���W�G�[�^�[�^�R���p�N�g2WAY
�@���@�����I�ȃ��j�b�g�`���C�X�Ŏ茘������Ă���B
�T ��i�ځA��؍N������u�E�F�[�u�K�C�h�ƃA���~�U�����g���������\�QWAY�V�X�e���v
�@���@MJ���҂ɂ���@�c�݂�^�C���A���C�����g�����S�Ɋi��̐��m�ȉ�
�@�@�@���j�b�g�͂܂��܂��̃��m�g���Ă�����ǁ@�l�b�g���[�N�̕��i�̃N�I���e�B���ނ����ፂ���ā@���j�b�g���i�̂Q�`�R�{�͂������Ă�����Ȃ��Ǝv�����B�@
�V ��i�ځA�r�䂳��u30cm�E�[�n�[/�h�[���~�b�h/���{���c�C�[�^�[3WAY�V�X�e���v
�@���@����i�������a���j�b�g�ŕ������H�v���Ēቹ���i��o�����Ƃ��Ă���̂ɑ��ā@30cm���j�b�g�{��e�ʃo�X���t�̗]�T�ƗD�G�ȑ���a�h�[���~�b�h�����W�A���{���c�B�[�^�ɂ�郏�C�h�����W�Ȃ��́@���Ƀc�B�[�^�[���D��Ă���Ǝv�����B
�@�R�����g�́@�����ƌ��邭�N���b�N����Ɓ@�����Ŏ������o���Ł@�N���b�N����Ɣ�т܂��B
�����ԍ��F26324828
![]() 0�_
0�_
���T��(11/2)�ł����A�L���̎���X�s�[�J�[���D�Ƃ̏W�܂�u�I���K�̉�v�Ŏ���X�s�[�J�[�R���e�X�g�����{���܂��B
�J�×v���͂�����
https://tatuiti.in.coocan.jp/omega/ouboyoukou4.htm
���M�����[�V�����Ƃ��Ă�
�ESTEREO���Ŕ̔����ꂽ�@�X�s�[�J�[���j�b�g�𓋍ڂ��邱��
�E2�{��120�T�C�Y�Ɏ��܂邱��
�Ł@10��i���G���g���[���Ă��܂��B
�@�Γc��BHBS�ŗL���ȐΓc�����ASTERO���̎���X�s�[�J�[�R���e���X�g�̗D���҂��Q�����Ă��܂��B
�@���N�́ASTEREO�������ނ������Ł@STERO���ɂ��L�����ڂ�\��ł��B
�@�l�́A�X�^�b�t�Ƃ��ăp�V��������ŃG���g���[���Ă��܂��A�L���߂��ŋ����̂�����͉F�i�����قŊJ�Â���̂�
�����ł��������B
�@�J�×v�̂ɏ����ĂȂ����� �Q����T�O�O�~ ���������͂��ł����A���ނ肪����قǖʔ����C�x���g�ł��B
�@���N�ƈ��N�̃R���e�X�g�̓���
https://www.youtube.com/watch?v=SxfzMm6teYc&t=585s
https://www.youtube.com/watch?v=F0J1oFoS0jE&t=372s
�����ԍ��F26325991
![]() 1�_
1�_
11/15�`16�� �t�B�f�B���e�B���T�E���h�E�����d�q�Y�ƁEstereo 3�Ћ��Î�����@2025�H������܂��B
https://silicon.kyohritsu.com/ONfdKYO-202511/index.php
�@����̖ڋʂ́@�O���X�U���X�s�[�J�[ Alpair 5G ���G���N���[�W����ς��Ē�����ׂ�Ƃ������̂Ł@�s�̕i�ł͂܂����ڂɂ�����Ȃ��A�n�[�h���[�v��/�E�H���i�b�g/�}�z�K�j�[���C���G���N���[�W���ɂ������̂Ł@�̂���Ƃ�������MDF�Ƃ͂��Ȃ苿�����Ⴂ�܂��B
�@�ŋ߁A���������Ȃ�Stereo�����@�Ȃ��\�����肻���H
����Ō��ݐi�s�`�� Alpair 5G �g���Ă����ŕ����ɍs������ł��B
�@���Ȃ݂ɁA11/9�܂Ł@�����d�q��Alpair 5G 10%�����Ŕ̔����Ă܂��B
https://eleshop.jp/shop/g/gP4H311
�����ԍ��F26326690
![]() 0�_
0�_
��BOWS����
����ɂ���
�����J�Ï�肪�Ƃ��������܂��B
���������C�ɂȂ��Ă܂����ANC7v2_WN�ƁA���Ȃ�Ⴂ�͂���܂����ˁE�E
�܂��u���ꏊ���Ȃ��ł����E�E�z��ł��\���܂���̂ŁA���ӌ�����������A���肪�����ł��B
https://shop.koizumi-musen.com/?pid=187836398
�����ԍ��F26326736
![]() 0�_
0�_
�I���t�F�[�u���^�[�{����
�@�G���N���[�W���ȑO�Ƀ}�E���g���郆�j�b�g�̍����傫���ł��B
�@Mark Audio �� ���m�T�X(�_���p�[���X)��Alpair 5V3�g���Ă��܂����A�f�B�e�B�[�������X�^�[�ȂƂ��낪�����ā@���X�s�[�J�[�ł͕��������C���t���Ȃ������t�̋@�������̃��j�b�g�ŕ������邱�Ƃ������ł��B
�@�������@���m�T�X�͑傫�Ȍ��_�������āA�U���𒆉��ɕێ�(�S��)����͂��キ�ā@���R�ɐU���������܂��B
�@�S�����ア���߂ɔ��ׂȉ����Č������̂ŏ��n�̌��Ƃ������܂����A�㏞�Ƃ��đ剹�ʂŐU�����傫���Ȃ肷���ĐU���Ǝ��C��H���Ԃ����Ĕj�ʼn������܂��B�{�����[���グ���Ȃ��B
�@�Ώ��Ƃ��ẮA������܂��ł������a��傫�����ĐU���ʐς𑝂₵�ĐU����������̂����ʓI�Ł@MAOP 11 MS��14cm���a�������Ă��܂��B
�@�ȑO�AMAOP 11(���m�T�X�ɂȂ�O�̂��)�C�ނ̃G���N���[�W���ɓ��ꂽ�X�s�[�J�[���������蕷�������Ƃ�����܂����A�u����I��̃t�������W��Ȃ��v�Ǝv���܂����B
�@MAOP11�����m�T�X��������A�����炭�ŋ��̃t�������W�ɂȂ�܂��B
http://www.fidelitatem-sound.jp/a_detail%20MAOP11MS.html
�@�����Ɂ@�]�_�Ƃ̐搶�̘b���o�Ă܂����A�u������낤�ȁv�Ǝv���܂����B
�@���̃��j�b�g�ɑȉ~�o�X���t�|�[�g�̖��C�ނ̃G���N���[�W���Ȃ�Ł@�܂��ŋ��ł��傤�ˁB
�@MAOP7���A�G�l���M�[���ቹ���ɂȂ�ł��傤���A�D�G�ȃc�B�[�^�[�����Ă���^�[�{����Ȃ�A�R���f���T�̗e�ʕς��邭�炢�őΉ��ł���Ǝv���܂���B
�@�ł�����A�����̃C�x���g�ɍs���ā@�t�B�f�B���e�B���T�E���h�̒�������ɕ����Ă݂Ă͂������ł��傤�H
�����ԍ��F26326902
![]() 1�_
1�_
��BOWS����
����ɂ���
�����Ă����������肪�Ƃ��������܂��B
MarkAudio 16cm�t�������W MAOP11_MS�̑O�ɁA�_�u���T�X�y���V�����̂��Q�Ƃ����̂�
����悤�ł����A�]���́A�l�r�̕������|�I�ɗǂ��ł��ˁE�E�E�E
�܂������Ȃ��E�E�T�C�Y�I�ɂ͖��Ȃ������̂ł����A���łɎ��������E�������N�����Ă���̂ŁE�E�E
�Ƃ肠�����́A����̈��Ǝv���܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F26327024
![]() 0�_
0�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
No1�`5 �T��i |
No6~10�@�T��i |
�O�����v���̂RD�v�����^�ō쐬�����_�炩�X�s�[�J�[ |
�O�����v���̉��nj^�o�b�N���[�h�z�[��SP |
�@�I���K�̉� ��4��X�s�[�J�[�R���e�X�g�ɎQ�����Ă��܂����B
�@����́@STERO���̕t�^���j�b�g���g���Ƃ�������ł��B
�@�Q������10��́@�ӂ��̔��^�o�X���t�Ƃ������肫����ȋ@��͖����āA���Ȃ�Ƒn�I�ȃA�C�f�A�荞���I�Ȃ��̂Ō`�����o�b�N���[�h�z�[���A�o�b�N���[�h�o�X���t�A���ǁA�^���f���_�u���o�X���t���Â��Ă܂��B
�@�L�����ő剹�ʂŖ炷�̂Ł@�剹�ʂŕ���Ȃ��Ƃ����̂��v�_�ł��B
�@����A�P�Ȃ�����킹�ɉ����āA��r�Ώۂ̕W���X�s�[�J�[�Ƃ��ā@Oberon1�����t�O�ɖ炵�ĕW���Ɣ�r�����̂Ł@�ő�10cm���a�̊e�X�s�[�J�[�͋������Ă��܂������AOberon1�������Ղ�����������X�s�[�J�[�����Ȃ��Ȃ������ł��B
�@�e��i�̏ڍׂ�
https://tatuiti.in.coocan.jp/omega/omega150/reikai150.html
�@�Ō�ɁA�C�ɓ������X�s�[�J�[�ɋ��肵�ăO�����v�������߂܂������A������ʂŁ@���炩�X�s�[�J�[�ƕό`�o�b�N���[�h�z�[����2��ނ��I�o����܂����B
�@���N�@��5��R���e�X�g�����{�����̂Ł@�o�i�������͕����ɍs���Ă͂ǂ��ł��傤�B
�@�Ȃ��A���y�V�F�Ђ����ނ�����A����STERO���ɋL�����ڂ邻���ł��B
�@����ƁASTERO����ÂŁ@Alpair 5G ���g��������X�s�[�J�[�R���e�X�g���J�Â����悤�Ł@STEREO���ɗv�����f�ڂ���邻���ł��B
�����ԍ��F26331896
![]() 3�_
3�_
�����̃X�s�[�J�[���Ȃ��g�ݍ��킹�A�Ƃ������Ђ������Ƃ���������ƍD�݂̉��ɂȂ�܂����B�����I�ɑш��⊮���Ă���Ǝv���܂��B���̓t�������W�I�ɂ��Ȃ��Ƃ��߂��Ƃ������Ƃ��킩��܂����B
���ÃX�s�[�J�[�Ȃ̂ŁA���̂܂܂ł͂��߂Ȃ̂Ŏ�������Ă��܂����B
![]() 2�_
2�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�X�s�[�J�[]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�ǂꂪ�������߁H�z�d�����Ȃ�ǂ�H���F����3��
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
-
�yMy�R���N�V�����z����\��
-
�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�X�s�[�J�[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j