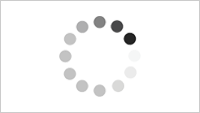���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S425�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2012�N3��22�� 10:28 | |
| 290 | 99 | 2012�N3��18�� 07:38 | |
| 1 | 0 | 2012�N2��7�� 22:08 | |
| 25 | 17 | 2011�N12��30�� 12:08 | |
| 15 | 6 | 2017�N10��6�� 12:50 | |
| 101 | 37 | 2011�N12��17�� 21:24 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�ߋ��X���ɂȂ��悤�Ȃ̂ŃX�����āB
�����O�����厏�̃E�F�u�T�C�g���ō��m����Ă��܂����A���k�I�[�f�B�I�t�F�A���J�Â���邱�ƂƂȂ�܂����B
�����F2012�N4��14��-15��
�ꏊ�F���T���t�F�X�^3�K�R���x���V�����z�[��
�Q����p�F���ꖳ��
�ڍׁFPDF�t�@�C���Q�� http://www.jas-audio.or.jp/pdf/20120319.pdf
�����̎�ẤA�₢���킹�悪Dynaudio Japan�̑O�c���ɂȂ��Ă���̂�Dynaudio Japan���Ǝv���܂��B
![]() 1�_
1�_
�����ł��˂��`�B�i�C�����Ă��̂悤�ȃC�x���g�͍ŋߎ��̒n���ł͕����Ȃ��Ȃ�܂����B
�������ς�@�ނ����Ă��炤�̂͂x�o�V����ł��B���肪�Ƃ��B�����B
���ł������āA������ׂ������Ȃ�Ƃ��o���A�ŐV�@�ނ����\�����Ă��܂����炷����
�������ł��B�n���V���b�v�ł͂��������ł����A�]�v�Șb���������̂ŁA�����ƍs����
�����A�A���Ă��܂��B
�t�F�A�ł͂�����蕷���܂��ˁB��N��̕��X�̃I�[�f�B�I��A����������悤�ł��̂�
����Ă���̂ł��傤���B�\�Z�̂�����͂��������ėǂ����̂��w�����Ă��������B
�����ԍ��F14327655
![]() 0�_
0�_
�d����P�[�u���ʼn��͕ς��܂���B
�d����P�[�u���ʼn����ς��Ȃ��̂͗�����Ă��܂��B
http://c.2ch.net/test/-/pav/1326059878/1-
���URL��2����甲�F���܂����B�Q�l�ɂǂ����I
�ƎҁA�I�J���g�A���r���[�ȃI�[�I�^���x����Ȃ��Ŏ������D���ȕ���I��Œ����܂��傤�I
![]() 10�_
10�_
���d����P�[�u���ʼn����ς��Ȃ��̂͗�����Ă��܂��B
������ĂȂ����炢�낢��A�����Ă��ł͂���܂��H
���ƎҁA�I�J���g�A���r���[�ȃI�[�I�^���x����Ȃ��Ŏ������D���ȕ���I��Œ����܂��傤�I
�������Ă܂��H�ς��Ȃ��Ȃ�I�ԕK�v�����Ȃ��̂ł́H
�����ԍ��F14252918
![]() 10�_
10�_
2012/03/07 11:15�i1�N�ȏ�O�j
2�����ł����c
����Ȃ̂��L��܂���
����q��
��݂̏d�ʊ��Ƥ�ǂ��܂ł��˂������钆���q�̓�������������D�݂��������
���
�˂��Ƃ�Ɨ��݂�C�d���̏d�����ɤ�����̌y�ʊ������X�����ނ����ʓI�Ȋ��o�
�����
�͋����e�z�������͂̒��Ɋ������顐��H��������Ʊ���Ȗ��킢�
�����
�ʏ�ͤ���敗�̐������������ʂ��グ��قǂɔj��͂𑝂��Ă������Я��ݼނ̍L�������͡
����z�d�r
�����I�Ȕ�����������S�̓I�ɍd���������ł͋��̂悤�Ȕ��˂����͂ƂȂ�
�d�͉�� ���� �Z�� �����ߓx
------------------------------------------------------------------
�����d�� ���ݽ ӯ�ؒx�� C
�����d�� ���ʊ� ��拭���� A+
���d�� ����ǹ �������� B
�����d�� ������ ��攖�� B+
�k���d�� ���Ăȉ� ��攖�� A-
���k�d�� ���x��SN ��攖�� A+
�l���d�� �F�ʊ��Ɖ��x ��攖�� A
��B�d�� ���ݽ ������ C
�k�C���d�� ���i�� ���ꋷ�� B-
����d�� �����扐 ӯ�ؒx�� A
�����ԍ��F14253319
![]() 4�_
4�_
����
���X����P�[�u���Ȃ����Ď���Ńe�X�g�Ȃ蕷���Ă݂�ᒼ���������o�܂��B
�ŋ߂͗ʔ̓X�ȊO �P�[�u���ނ�݂��Ă���ƃ��[�J�[�Ȃ�₢���킹�����߂Α݂��ĖႦ�邩�Ǝv�����A�^�����L��V���b�v�œd���P�[�u���̕ω����m���߂�B
���ꂪ�����葁����������������@����Ȃ����ȁI
���݂Ɏ��l��
���������ȋ@��̃Z�b�e�B���O����Ă���⌎�ɐ����Ԓ��x�u�Ȃ��畷���v������Ă���ɂ͓d���P�[�u���̌����̓I�X�X�����܂���B
�ܘ_�I�[�f�B�I�@����������ƂȂ��q�g�͘_�O(��)
�C���^�[�l�b�g�ŕς��ς��Ȃ��̂���肷����V���b�v�ɏo�����Ȃ肵�Ď��g���s�����܂��傤�ł��ˁc�X���傳��B
�����ԍ��F14253350
![]() 5�_
5�_
�\�[�X�̒�2ch�Ƃ��l�̃T�C�g�Ƃ��A���J�L�R���d���ŕς��Ȃ��X���Ƃ��A���ʂ��Ă���l����ł��ˁB
�����ƈႤ���l�ς����̒��ɂ͗L�ۖ��ۂɂ���̂ƁA�܊��ɂ�����s���肪����܂��B
�߂��e���Ȃ�Ƃ������A�܂������̑��l�͎����ƈႤ���E�ɐ����Ă�ƍl���܂��傤�B
���̒��ς��Ƃ����l������̂��Ƌ��e�ł�����̐[�����炢�͂����Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���Ȃ݂Ɏ��͕ς��Ƃ͎v���܂����A�ς��Ȃ��Ǝv���l�ɋ����������͈����܂���B
�����Ă��ς��Ȃ��Ɗ�����l������Ƃ͎v���܂��B
��Ȃ̂�����y���݂܂��傤�B
�����ԍ��F14253395
![]() 3�_
3�_
�@������u�P�[�u���ے�h�v��������u�P�[�u���Ȃʼn��͕ς��Ȃ��̂����I�v�ƌ���������Ƃ���ŁA���ۂɃP�[�u����t���ւ��Ă݂�Ɖ��̓R���R���ς��킯�ł��B
�@�P�[�u���i����ѓd�����Ӌ@��j�̓���ւ��ʼn����ς��Ƃ����A���́u�����v��O�ɂ��Ắu�P�[�u���ے�h�v�̕������͋����������ł��ˁB
�@�������A������P�[�u����t���ւ��悤���܂��������̕ω����������Ȃ��l�����̒��ɂ͑��݂��܂��B
�@�������A���������l�͂��Ȃ�̊m���Ŏ��ۂ̊y��̈Ⴂ���������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�X�^�C���E�F�C�ƈ����s�A�m�Ƃ̉��̈Ⴂ��������Ȃ�������A�X�g���f�B���@���E�X�̉��ƈ����ȗ��K�p���@�C�I�����̉��Ƃ������ɒ���������A�w�^����ƃ��@�C�I�����ƃ��B�I���̉��������������Ȃ������肷��̂ł��傤�B
�@�f���Ă����܂����u�����������Ȃ�����_�����v�ƌ�������͂���܂���B���ɑ��銴���͐l���ꂼ��ł��B�������A���������l�̓s���A�E�I�[�f�B�I�ɂ͌����Ă��܂���B�ʂ̎�������������ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F14253514
![]() 10�_
10�_
����ɂ��́B
CD�v���[���[�Ȃǂ̋@���50���~�A100���~����₷�̂Ȃ�A�d���P�[�u���A�X�s�[�J�[�P�[�u����RCA�P�[�u���Ȃǂ�3�`6���~�O�ォ���ăP�[�u����V���ȕ��ɑւ��������y���ɉ������ς��A�ق�ŁA�m���ɂ��ꂪ���シ��̂ł����`�I
���̕����A�������Ĉ��オ��ł���I(��)
����A�����o�̓d���P�[�u���ƃ^�b�v���܂����̂ŁA�A���v�A�u���[���C�v���[���[�ACDP�Ȃǂɕt���ւ���̂�A�y���݂��`�I�I(��)
�N�b�A�N�b�A�N�b�A�N�b�c�B(��)
�����ԍ��F14254369
![]() 1�_
1�_
>�d���A�P�[�u���Y�݁A�Q�l��
�E�E�E�Ȃ�܂���ł����B
�����ԍ��F14254442
![]() 6�_
6�_
������Ă���̂͂ނ���@�ׂł���Ȃ���v�A�ł�����l�Ԃ̊��o�̕��ł����ĕ��̑P�������⍷�ق̗L���ł͂Ȃ��B�N�I���e�B���C�t�Ɩ����Ȑl���ɂƂ��Ă͎��p��̖ړI�����B����������ł悢�̂��낤�B���_�I�A��p�I�ȗ]�T�̗L�������l�ςƂ��Č�����l�����ɔ��f����Ă���̂ł͂Ȃ����B�����ɂ̓P�[�u���Ȃɂ����̕ω��̗L���ȑO�ɑ喇���͂����Ď�ɋ�����l���ւ̂�����݂ɕ������ĂȂ�Ȃ��B
�g�쉮�A�����̋����Ƌ�������̋����B�����ŕ������Ƃ����ړI�ɍ��͂Ȃ�����ǂ����H�ׂĂ��ꏏ�Ɗ�����l���ɂ͖��o�Ƃ����t�@�N�^�[�͕s�v�ł���B�ړI�n�܂Ől���P���Ə��X�̉ו����^�Ԏ�i�Ƃ��ĂȂ�K�J�[�ƃ��N�T�X�ɂ���Ƃ��������͂Ȃ��B���������K���ǂ����͕ʂ̘b��ł���B���p��̖ړI���A���S�Ă̐l���ɂƂ��Ă͂���������������̋��������N�T�X���I������Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ��̂�������Ȃ����B
�ʓd�ł���Ύx�Ⴊ�Ȃ��ƍl����l���ƒʓd���̂��̂ɂ���N�I���e�B��]�ސl���Ɍ����Ȃ�ΐړ_�͑��݂��Ȃ��̂ł���B
�����ԍ��F14255645
![]() 7�_
7�_
�^���͂P�B
������Ες��܂��B���R�́A�������Ⴄ����ł��B
�������A�̊��x�����ɂ͊���l��������܂��B
���R�[�f�B���O�X�^�W�I�Ȃǂ̉��y����̌���ɂ��ϋɓI�ɓ�������Ă܂��B
�u�ς��Ȃ��v�h�́A�������o���݂��H�A�����������H�A�����C�������H�A���ꂩ�ł��B
�l�I��ςł����A�P�[�u���ނ́A�d�����ł��̊��o���܂��B
�`�d�s���E�߂��܂��B
�����ԍ��F14257069
![]() 2�_
2�_
�����܂ł̏������݂����Ăǂ������܂������H
�����܂ŃI�[�f�B�I�ƊE���I�J���g�ɐN�I����Ă��܂��B
�������@�ւł́A�u���͉��̈Ⴂ�ŃP�[�u���̈Ⴂ�f�ł���v�ƌ����Ă���荇���Ă���Ȃ��̂�����B
�u����Ō��̕ė���������v�Ƃ����Ă��A��荇���Ă���Ȃ����炢�̗^���b�����B
�x���f���iBelden)���u���C���h�e�X�g����Ɗ�悵�����Ƃ�����B
�������ǂ̎����ł����j��P�[�u���ʼn��̈Ⴂ����������͈�x���Ȃ��B
�i�������ɕς�����A�Ⴂ��������Ƃ����Ă���l�𐳎��ȃu���C���h�e�X�g�����100�������킯���ł��Ȃ��B�j
�I�[�f�B�I�̒B�l�����ɒʏ��SP�P�[�u����e��̍���SP�P�[�u���������A�@��̔w��ɉ���ăP�[�u�����������Ă͉��y�������B
�ǂ̍����P�[�u�����D�ނ��ɂ��Ă͈ӌ��������ꂽ���A�S�����ʏ��SP�P�[�u���̉��͂��b�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��ċp�������B
�������A���́A�ŏ�����Ō�܂œ����ʏ��SP �P�[�u�����Ȃ��ł����c�c�B
�Ƃ����b��Belden�Ђ̐l�����b�Ƃ��ďЉ�A�l�Ԃ͎����̊��҂Ɋ�Â��ĉ���m�o������́A�Ƃ܂Ƃ߂Ă���B
���I�ȃu���C���h�e�X�g���炢�����������Ȃ��ƁA�����҂��ʂ̐l�ɂ��M���Ă��炦�Ȃ����낤�ˁB
�����X�^�[�P�[�u��vs.�j���n���K�[�ł���u���C���h�e�X�g�Ŕ��ʕs�\�Ƃ����ʔ������b�̃e�X�g������A������I�[�f�B�I�ƊE�ł��L���Șb���B
�ȏ�A�d����P�[�u���Ȃǂʼn����ς��ȂǃI�J���g
���܂�C�ɂ����v���V�[�{���o�ł��y���݂��������B
���_������Ȃ烁�[�J�[�Ȃǂɒ��ڕ�������b�������ł��B
�ς��Ƃ��ς��Ȃ��Ƃ��B���ȉ��Ɋ����\���ʼn��Ԃ��Ă��܂��B
���[�J�[���ς��ƒf���ł��Ȃ��̂����́w�I�[�f�B�I�ƊE�x�Ȃ̂ł��B
�����ԍ��F14261479
![]() 8�_
8�_
�I�[�f�B�I�n������
�}�j�A�̊Ԃ̘b�ł͓d���P�[�u���𒈒݂�ɂ���Ɖ����ς��炵���ł��B
���Ă��Ƃ͉��y���Đ����ɓd���P�[�u�����O�j���O�j���ƋȂ����肵����
�����Ɖ����ς���Ē�������̂ł��傤�ˁB
�����̔M�S�ȃ}�j�A�̕��X���āA�ǂ������ʂȐ��������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F14261597
![]() 8�_
8�_
�M�S�Ȕے�h�i���������ʂł͂Ȃ������Ȃ��h�j�����ʂ̐����������Ă��Ă��Ȃ���܂���B
���l�̎��Ɍ����o�����A�����R�ɐj���n���K�[���g���Ă���H
�����Ŏ����Ȃ��̂͐��]����Ă鋰�ꂪ����t�ɐS�z�ł��B
�����ԍ��F14261651
![]() 3�_
3�_
�����M�S�Ȕے�h�i���������ʂł͂Ȃ������Ȃ��h�j�����ʂ̐����������Ă��Ă��Ȃ���܂���B
�ǂ����������ʂȐ����ł����H
��̓I�ɗ�������Ă��������B����������܂��B
�������l�̎��Ɍ����o�����A�����R�ɐj���n���K�[���g���Ă���H
�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B
���������̂悤�ȕs���R�ȃA�C�e���������Ďg���قljɂł͂���܂���B
���������Ŏ����Ȃ��̂͐��]����Ă鋰�ꂪ����t�ɐS�z�ł��B
�Ȃ������Ă��Ȃ��ƌ��ߕt����̂ł��傤���H
���������Ă��Ȃ��Ƃ��������������Ă��������B
�����ԍ��F14261674
![]() 5�_
5�_
2012/03/09 06:50�i1�N�ȏ�O�j
�ŁAValentine vs Valensia����́A
�@�S���ς��Ȃ�����
�A�ς�������ǂ���������Ȃ�����
�B����C������
�C���
�D�ς�����獢��
�E����������
�F��C������
������(��)
�����ĉ������B
���͋@�ށA�P�[�u���ɂ��A�C�ł����B
�����ԍ��F14261814
![]() 0�_
0�_
�@�I�[�f�B�I�n������Valentine��搶�́A�v����Ɏ����ł̓P�[�u������x���t���ւ������Ƃ��Ȃ������Ɂu�P�[�u���ł͉��͕ς��Ȃ��B�ς��Ȃ�������ς��Ȃ��B���[����Ⴑ���v�ƌ��������Ă���킯�ł����A���́u�����ł͂�������Ƃ��Ȃ������ɁA�����ւ����悤�ɑ匾�s�ꂷ��v�Ƃ����̂́A��ʐ��ԓI�ɂ͂ƂĂ��ɁX�����s�ׂł��B
�@���Ƃ��Č����Ȃ�A�^�]�Ƌ��������Ă��Ȃ������ɁA�e�Ԃ̃h���C�u�t�B�[�����̂����Ɍ��Ƃ������悤�Ȃ��̂ł��傤���B�܂��́A�����������ڂ�������������A����ior�����j�̂����ɐQ�Z�l�\����Ɋւ��ē��X�ƃE���`�N���I���Ă��钆�����Ɠ����x���ł��i���[���ƁA���̃A�[�e�B�N�����폜���肩�I ^^;�j�B������ɂ��Ă��A���͂̐l�Ԃ͎����邵������܂���B
Valentine��said
�����������Ă��Ȃ��Ƃ���
���������������������B
�@���́u�����ł͂Ȃ��Ƃ����؋���������v�Ƃ����̂́A�_���I�ɗL���ł͂���܂���B���ؐӔC�̓A�i�^�ɂ���܂��B�܂�u���̓P�[�u���Ɋւ��Ă��ꂱ�ꂱ���������n���������s�������ǁA�ω��͔F�߂��Ȃ������v�Ƃ������Ƃ��A��ɘ_�q����K�v������܂��B��������Ȃ��ƁA�A�i�^�̕������ɂ͐����͔͂��o������܂���B
�@���āA�ʃX���b�h�ł������܂������A����d���W�̃A�N�Z�T���[�̎�����ɏo�����Ă��܂����B�d���P�[�u���A�d���V�X�e���A�d���{�b�N�X�i�^�b�v�j�̊e�Ђ̐��i���W�߂Ắu������ב��v�ł������A�z���g�ʔ����悤�ɉ����ς��܂��ˁB�Ƃ͂����A��ԉ��̕ω����傫�������̂��d���P�[�u���ł��̎����d���V�X�e���A���ēd���^�b�v�͉��̕ω��ʂ����Ȃ��Ƃ������悤�ɁA�e�A�C�e�����ƂɃV�X�e���ɑ���e���ɍ������邱�Ƃ����߂ĔF���ł��܂����B
�@�������A���̃C�x���g�̐i�s���߂��]�_�ƁE���c����́u�I�[�f�B�I�O���[�h���\�I�v�Ƃ������X�^���X�ɂ́A�l�I�Ɏ�ً̈c�����������ł��ˁB���ꃁ�b�L���̂��낢��ȁu�H�v�����邱�Ƃ́A���ꂾ�����ɐF�t��������Ƃ������Ƃł�����A�V�X�e����\�[�X�ɑ��Č����s�������o�Ă��邱�Ƃ��\�z����܂��B
�����ԍ��F14262068
![]() 7�_
7�_
Belden�Ђ̐l�����b�Ƃ��ďЉ�c�A�\�[�X�v���[�Y�B
�����ԍ��F14262087�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�u�ς��Ȃ��h�E���������̂Ȃ��h�v�͂���͂���Ő��]����Ă����Ȃ��́B
���ɖ����ꎎ���Ă݂ĕς���Ă��u�ς��Ȃ��v�Ǝ咣��������ł��傤�B
�����ԍ��F14262124�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�\�[�X���́ABelden�Ђ̎Ј��Əؖ��ł��镨�����肢���܂��B
�Ȃ���Ă�Ȃ肷�܂�Belden�� �Ј��ł͐M�ߐ�0�ł�����ˁB
���ƁA�����X�^�[�P�[�u���Ђ̂����l�ɂ��肢���܂��B
���ЂƂ����Ɍ����ɂ��������Ă�Ȃ�z���y�[�W�ɂ��������L�ڂ���́H
�����ԍ��F14262182�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ĂȂ��������������āc�i�j
�܂�������ւǂ����i�j
�����g�̎������l�ɂ킩��Ƃ��������̂ł����ˁi�j
�ς��Ȃ��Ȃ�ʂɂ���ł�������Ȃ��ł����B
�ς��Ȃ��X�����Ă���A��������l�̃X���ɏ�荞��ł�̂��A���Ȃ�ł���B
�ς��X��������Ȃ�ς��Ȃ��X���������Ă������Ə�����Ă܂������A�ς��X���Ȃ�Ă��������ȂƋ^��ł��B
�Ⴆ��
�^�C�g�� �P�[�u���ʼn��͕ς��܂��I
�P�[�u���ʼn��͕ς��܂��I
�ς��Ȃ��̂̓v���V�[�{�ł��I
�Ȃ�Č����������ƂȂ��ł��B
����̂͂ǂ̃P�[�u�����炱�̃P�[�u���ɂ�����]�X�Ƃ��͂悭�������܂��B
�ς��Ƃ������̕�����̓I�ł��ˁB
���������ς��Ȃ��Ƃ������Ɉӌ��������Ă��ł͂Ȃ��A�ς��Ȃ��Ƃ��鍪�������g�̑̌��ɂ�闠�ł����Ȃ��̂ƁA�\�[�X���M���ł��镨���Ȃ�����A�₢�|�������Ă��邾���Ȃ̂ł��B
�ς�鑤�ɂ�����͌����܂����A�ς��Ƃ������́A�͂����莩�g�̑̌������܂����A�P�[�u�����[�J�[���i����搂��Ă��܂��B
�ς����Ƀv���V�[�{�ƌ����Ȃ�A�ς��Ȃ����Ƀv���V�[�{�ƌ����Ă��悢�̂ŁA�ς��Ȃ��̂̓v���V�[�{�Ǝ��o���Ă��������B
�����ԍ��F14262256
![]() 0�_
0�_
>�x���f��(Belden)����Ɗ��Ńu���C���h�e�X�g���������Ƃ�����B
�ƃX����͌������Ă܂�����˂��A�M���E�ؖ��ł���\�[�X�������Ȃ���ł����ˁH
�M���E�ؖ��ł���\�[�X�łȂ���X���傪�S�����i�T�C�ł����ł���(��)
�����ԍ��F14262314�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
2012�N�x�̃I�[�f�B�I�V���[�̓��������܂�܂����B�������ł͍��T����X�^�[�g���܂����A���W��@��w������������Ă�����́A�V�тɍs����Ă݂��炢�����ł��傤���B
�Q���P�O���i���j�`�P�Q���i���j
�I�[�f�B�I�t�F�X�^�E�C���E�i�S���@�Q�O�P�Q
http://www.audiofesta.jp/
���T�J�×\��ł����A������������̓��[�J�[�������낢���܂��B
ATOLL�̐V�^DAC�����{���Љ�邻���ł��B
2��25��
PORTABLE AUDIO FESTIVAL2012
e���C���z�������{���{�X�E�V�X��
�@�@�@�@
http://gigaplus.makeshop.jp/gcom1420/PAF/index.html
���ŁB�w�b�h�t�H���Ղƌ����ׂ��ł��傤���B�V�X�܂̂���I�ڂ����˂Ă���݂����ł����A�������ɏH�t���X���������邻���ł��B
�R���Q�R���i���j�`�Q�T���i���j
��B�n�C�G���h�t�F�A�i�����s�j
�������ۉ�c��S�e���݉��(�}�b�N�X�I�[�f�B�I��Áj
http://www.maxaudio.co.jp/
�S���ȍ~�\��I�[�f�B�I�V���[�B
�T��12��
�w�b�h�t�H����
�X�^�W�A���v���C�X�R
http://www.fujiya-avic.jp/
�T�����{�B
�n�C�G���h�V���E�g�E�L���E�Q�O�P�Q�X�v�����O
������ʉ�فi�L�y���j
http://www.hi-endshow.jp/
![]() 1�_
1�_
�l�I�Ɉ�ۂɎc���Ă���(������/��������킸)�X�s�[�J�[�ł��B
�l�I�ɂ̓T�C�Y��������W�Ԃ��Ă��܂��B
�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[��
ESI nEar05 Experience \27130
�쓮����:�A�N�e�B�u
���[�J�[:�؍�
�����o��:�O�؊y��TOOLS������AWEB�A�E�g���b�g�w��
���̉��i�ɂ��Ă͉����O�ɏo�Ă���B
�𑜓x�͍r�������j�^�[�Ƃ��Ă͂������艹�̋��(�����̈Ⴂ)�������ł���B
�c�B�[�^�[�������Ƃ������������Ȃ��j���[�g�����T�E���h�����A���y�I�Ȃ̂�̂悳�ɕs���͊����Ȃ��B
���p�X�^�W�I���j�^�[�AADAM S2X���w������ۂɏ����W�̂��ߌ������Ă���q�b�g�����̂�
����������̂��肪����Tom-H@ck���������B
�ނ̃T�C�g���v���Ԃ�Ɍ��Ă݂�Ƃ��̃X�s�[�J�[���Љ��Ă����B
�T�����R�ɂ����r���[����
http://port.rittor-music.co.jp/sound/productreview/monitor/050401_8356.php
ADAM A3X \59600
�쓮����:�A�N�e�B�u
���[�J�[:�ƍ�
�����o��:�O�؊y��TOOLS
ADAM Aduio GmbH.��ELAC��JET�c�B�[�^�[���J�������N���E�X�n�C���c�����������[�J�[�œ������h�C�c���Ђł���B
���̃X�s�[�J�[��50KHz�܂łقڃt���b�g�ȓ������ւ�X-ART�c�B�[�^�[�𓋍ڂ���ADAM�̃G���g���[�@�B
�n�C�g�����W�F���g�ȑ���̂Ȃ����Ə����a4.5�C���`�E�[�t�@�[�̏��C���ǂ��쓮�A�_�u���o�X���t�|�[�g�ɂ��x��̏��Ȃ��T�C�Y�����L�тƉߑ������Ȃ��ʊ��B
���j�^�[�ɂ͂������AiPod���Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ��\�������Ă���邾�낤�B
KRK VXT4 \59600
�쓮����:�A�N�e�B�u
���[�J�[:�č�
�����o��:�O�؊y��TOOLS
��ԏ��߂ɃT�C�Y���������������X�s�[�J�[�B
�č��炵�������r��������������p�^�L���r�l�b�g�B
4�C���`�P�u���[�E�[�t�@�[�̏��C���ǂ��T�E���h�Ȃ���A�X���b�g�o�X���t�̗p�ɂ��T�C�Y����͑z���o���Ȃ����̐L�тƗʊ���������B
���j�^�[�Ƃ��Ă̎����\�����Ȃ����Ȃ̂ŏ��߂ĕ������Ƃ��͉��̃X�s�[�J�[�����Ă�̂��Ɗ��Ⴂ�����قǂ��B
�c�B�[�^�[�������ǂ��A���ƍ���̈�ۂ̋���������h���V�����C���̈�ۂ�������邩������Ȃ����A�����Ă��ǂ��Ȃ��B
�������A���ʂɂ���ăo�X���t����̗ʊ����ω����₷���͎̂d���̂Ȃ����Ƃ��낤�B
�č��炵���A�^�b�N�̕������m���̗ǂ��T�E���h�͖O���邱�ƂȂ������Ă�����B
ADAM S2X \399600
�쓮����:�A�N�e�B�u
���[�J�[:�ƍ�
�����o��:�������p
ADAM�X�^�W�I���j�^�[�̂Ȃ��Ń��C�����C���A�b�v�ƂȂ�SX�V���[�Y�ň�ԏ�ʂ̃I�[�\�h�b�N�X��2Way2���j�b�g���j�^�[�B
�p�b�V�u�ł��n�C�G���h�@��ɍ̗p����Ă���A�h�C�cEATON(�J�[�I�[�f�B�I�����ŗL��)��HEXA�R�[���E�[�t�@�[18.6cm�𓋍ڂ��AX-ART��2.2KHz�̃N���X�I�[�o�[�łȂ��Ȃ���Ɉ�a���̂Ȃ��T�E���h���������Ă���B
35Hz-50KHz�܂Ńt���b�g�Ȏ��g���������������A�T�E���h�Ɋւ��Ă��c�B�[�^�[�������Ȃǃ��j�b�g�ɂ��J���[���[�V�����͊F�����낤�B
��ʉƒ�ł��^�C�g�Ȃ������������܂łȂ狿���L�т����
����y�퉹�d�q����킸�ɃI�[���}�C�e�B�ɂ��Ȃ��n�C�X�s�[�h�ȍ���́A�܂���X-ART�ɂ�鎒���B
����ȏ�̃R�X�g�p�t�H�[�}���X���ߎ����i�тł��ڂɂ����肽�����̂��B
�����Ă̓p�b�V�u�ł���B
![]() 1�_
1�_
KEF QX10 \117700
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:�p��
�����o��:���^�j���}���Z��
�ʔ̓X�̃I�[�f�B�I�R�[�i�[�Ɗy�퉮����ׂ����Ƃ��Ɉ�Ԉ�ۂɎc�����X�s�[�J�[�ł���B
�܂��������j�^�[�Ƃ�����悤�Ȋy�퉮�̃X�s�[�J�[�Ɠ��������̃x�N�g����ɑ��݂��鉹�ŁA
�_�����ɂ��Ȃ�̂悳�A�y���ȃT�E���h����ۓI�ł������B
���邢�L�����N�^�[�ŁA�����ďd���Ȃ炸�A�f�U�C���I�ɂ����h���܂߂ė��ɂ��Ȃ����`���낤�B
�^�����e�ϊg��Ȃǂɍv������Y�ɂ��z���ދZ�p�Ȃǒ��ړx�̍������[�J�[�ł�����B
���܂��܂Ƃ߂�ꂽ���̃X�s�[�J�[�̓T�C�Y���炭�鋇�����������Ȃ��B
�v���[���[/�A���v/�X�s�[�J�[�őO��2��10���A�X�s�[�J�[10���Ōv20���A�Ƃ��e10���Ōv30��
�Ƃ�����̖{�i�I�ɂ͂��߂����҂̗��z�I�ȗ\�Z�z�����낤�Ǝv�����A�X�s�[�J�[��10���O�㊄���Ȃ�A����҂ɂ�B&W CM1�Ȃǖڂɓ���̂ł͂Ȃ����낤���H
���ډ��������Ƃ͂Ȃ����A��ʋ@��̃g�[���{�[�C�̈�ۂ�M���̒u���郌�r���[�A�[��Red����̃��r���[��������菉�S�҂ނ��ł͂Ȃ���������Ȃ��B
���ꂩ����傳�����ɂ����m���Ă��炢�����X�s�[�J�[��������Ȃ��B
TAD TSM-2201-LR \157500
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:���{
�����o��:�r�� �p���[���b�N���Փ�
�y����������ۂ����A�X�^�W�I���j�^�[�R�Ƃ����X�^�W�I���j�^�[�B
�F�Â��͈�Ȃ������₷���B
�𑜊������R�̂��ƂȂ���X�^�W�I���j�^�[�N���X�ł���B
���y���ɂ��Ă��Ȃ�ɂ��Ă��I�[���}�C�e�B�ɂȂ��ߕs�����Ȃ����Ȃ��Ă��܂���������������B
�X�y�b�N�Ɋւ��Ă��\�����Ȃ��A�����40KHz�܂ŏo��̂ōŋ߂̃n�C���]�����ɂ��Ή��ł���B
�����ėʂ�ǂ����߂����m����Nj������^�C�g�Ȓ����A�L�тɃX�g���X�����������Ȃ�������ǂ����̒ʂ钆����A������TAD�Ƃ��������Ȃ郂�j�^�[�ł���B
TAD�̐��藧���ƃL�m�V�^���j�^�[http://pro.miroc.co.jp/2010/12/30/tadpro-tsm-2201-lr/
ELAC 310 INDIES BLACK HB \201600
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:�ƍ�
�����o��:���@������ʼn��x��
ADAM Audio GmbH.�n�ݎ҂�ART�c�B�[�^�[���J�������N���E�X�n�C���c���X�s�[�J�[���[�J�[�ݗ��̎����m�ۂ̂���ELAC��JET�Ƃ��ăc�B�[�^�[��̔����Ă����B(���z�C���^�[�i�V���i���L��)
���̂��߂��̃c�B�[�^�[���̗p�����X�s�[�J�[�����߂Đ��ɑ���o�����̂�ELAC���B
�V���L�[�ȍ���ƁA�T�C�Y�����ʊ���]�T�Ŗ炷���B
�C���e���A�f�U�C���Ƃ��Ă��D�ꂽ�L���r�l�b�g�͋��łȃG���N���W���[�ł�����A���j�b�g�̕s�v�U����O��I�ɔr������v�z��������B
Sonics Anima
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:�ƍ�
�����o��:�Ȃ�(�T�C�h�v���X�̔�FAPS�œW���f���Ɏg�p
������T�C�Y���������o���X�s�[�J�[�̖͗l�B
���Ƀj���[�g�����ȏo���Ɛ[���L�т������o���炵���B
�f�T�C�����ŋ߂̍�i�炵�����A����ȏ�Ƀe�N�m���W�[�Ɋւ��Ă��ŋ߂̐��i�炵�����荞�݂�����Ă����Ɍ�����B
�������������ɂ��Ȃ�����肱�݂ɂ�莩�R������̂Ȃ��T�C�Y���������o�����Ƃ��ł���̂��낤�B
�����ԍ��F13945244
![]() 1�_
1�_
Joseph Audio RM7XL \422500
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:�č�
�����o��:�Ȃ�(�T�C�h�v���X�̔�FAPS�œW���f���Ɏg�p
��������T�C�Y���������o���X�s�[�J�[�B
Sonics Anima�Ƌ���FAPS�C�`�I�V�̃X�s�[�J�[�ł���B(���PMC�Ƃ�
������I�[�\�h�b�N�X�ȊO�ρA2way�Ȃ���ŐV�e�N�m���W�[�ō\�z���ꂽ�X�s�[�J�[�̈�ŁA
�V�[�����X�ȂȂ���A�F���Ȗ���������Ă���Ƃ����B
�T�C�Y�����㉺�����̐L�т��������������Ă���B
Raidho Acoustics X Monitor \546000
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:����
�����o��:�Ȃ�
���{���c�B�[�^�[�ɂ��5KHz�Đ��Ƃ�����11cm�̃Z���~�b�N�R�[���E�[�t�@�[�ɂ��50KHz�Đ����������A����܂��T�C�Y�����������Ȃ��X�y�b�N��i���Ă���B
ADAM�̃X�s�[�J�[�ɋ߂�(MP1�̓Z���~�b�N�E�[�t�@�[)�A�V�i�C�s�̃u�����h�Ɏv����B
Elac�Ƃ��ʂÂ�A�N���X�^���u���b�N�ȊO�ς́A�V���v����sony���i�̂悤�ŁA��i�I�ł���Ȃ���}�b�V���Ȉ�ۂ��^���A���S���A���芴�����������Ă���܂��B
���j�b�g�}�E���g�����A�����X�^���h�Ƃ��O��I�ɉ��������ޕ����Ƃ͐^�t�̃X�^�C���ŁA�W�[�N���t�����̕��V�V���V�����[�^�[�̂悤�ȕ����Ɏv����B
���Ȃ݂ɁA�h�C�cAacuton�������ɃZ���~�b�N���j�b�g���o���Ă���A�n�C�G���h�X�s�[�J�[�ɂ��̗p����Ă���悤�ł��B
ReyAudio �L�m�V�^���j�^�[ KM1V \819000
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:���{
�����o��:�Ȃ�
�����ɗ��Ă悤�₭3���j�b�g2way�����̃o�[�`�J���c�C�����f���̓o��ł���B
�o�[�`�J���c�C���{�Ɩ{�����C�I�[�f�B�I�̃~�b�h�t�B�[���h���j�^�[�ŁA
���`�ؐ��G���N���[�W���[�̗̍p�A�T�C�h�X���b�g�o�X���t�|�[�g�̓��ڂȂ�
�L�m�V�^���j�^�[�̐v�͂̍������f����B
����Ɠ����ɃX�^�W�I���[�X�ŋ��߂��鍂�ϋv/�������v�ŐM�����̍�����i�ł�����B
Audio Machina CRM \898000
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:����
�����o��:�Ȃ�(�ԉ����L
�I�[�f�B�I�}�V�[�i�̓A���~�؍�H�Ƃ̎В�����������ЂʼnF���q��O���[�h�̃A���~�����u���b�N�����肾���ꂽ�������ȃG���N���[�W���[�ɂ��A���^���^�Őݒu�ꏊ��I�Ȃ��Ȃ����
���ɍL��������������o���A�������̂𖣗�����X�s�[�J�[�̂悤�ł��B
��ʋ@�����̐v�v�z�ɂ��A�����t���Ȃ��n�C���x���ȃT�E���h�����\�\�B
�����ԍ��F13945455
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
Audio Machina The Ultimate Monitor |
YG ACOUSTICS Anat Reference Main Module |
Audio Machina The Pure System |
Audio Machina Maestro |
Audio Machina The Ultimate Monitor \1820000
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:�č�
�����o��:�Ȃ�
��������3�P�^�I�[�o�[�̑��ցE�E�E�B
����܂��I�[�f�B�I�}�V�[�i�����ӂ̃K�b�`�K�`�����A���~�G���N���[�W���[�Ōł߂�ꂽ��i�B
REY AUDIO�����݂̃}�e���A���Ŋ�����������E�E�E�B
����ȃj�I�C�̂���X�s�[�J�[�ł���B
http://www.zephyrn.com/products/audio_mac/ultimate.html
YG ACOUSTICS Anat Reference Main Module
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:�ȐF��
�����o��:�Ȃ�
�T�����R�̋L���ɘa�c�������̃C���^�r���[������Ă���A���y�Ƃł��萻��T�C�h�̐l�Ԃł��鎁���u�^������Ȃ�}�X�^�����O�X�^�W�I�̉���^������v�Ƃ����Ă����̂���ې[���B
����Ȏ������C���X�s�[�J�[�Ƃ���̂����̃X�s�[�J�[�ɃT�u�E�[�t�@�[��t��������Anat Reference STUDIO�ł���B
������͓����A���~�ł��F���q��O���[�h��Audio Machina�ɑ��A�C�X���G���R���}�e���A���g�p�̃~���^���[�O���[�h�ł���B
�������K�b�`�K�`�Ɍł߂��A���~�����L���r�l�b�g�Ƀ��j�b�g���Œ肵�Ă���̂��Ⴂ�Ȃ��B
http://www.h3.dion.ne.jp/~yamaden7/ACCA.html
Audio Machina The Pure System
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:�č�
�����o��:�Ȃ�
��������̓g�[���{�[�C�̃X�s�[�J�[�ɂȂ��Ă���B
����FOSTEX�t�������W���j�b�g���g�����I�[�f�B�I�}�V�[�i�̃��C���R���|�[�l���g��
�t�������W�ɃX�[�p�[�c�B�[�^�[�ƃT�u�E�[�t�@�[��lj������g�p�ƂȂ��Ă���B
FOSTEX�̃��j�b�g�g�p�Ȃ�����M�����Ȃ������o���悤�ŁA
����������̂͂��͂ⓖ����O�A�L��ȉ�����o������ɁA�𑜊����\�����Ȃ��Ƃ����I�[�f�B�I�}�V�[�i�̃R���Z�v�g�Ɨ͗ʂ�m�炵�߂邱�ƂɂȂ����X�s�[�J�[�B
����܂����^�R���p�N�g�ŃZ�b�e�B���O�Ɉˑ����ɂ������̐[���͌��݁B
�����ɗ���FOSTEX�̋Z�p�҂��u�Ȃɂ��ǂ�������炱��ȉ����o��I�H�v�ƌ��킵�߂��قǁB
http://www.zephyrn.com/news/pdf/the_pure_system.pdf
Audio Machina Maestro ��6800000
�쓮����:�p�b�V��
���[�J�[:�č�
�����o��:�Ȃ�
����̓g�[���{�[�C�ł�����ɑ�^�X�s�[�J�[�ƂȂ�B
�����Ƃ���ɂ��A���Ђ�The Ultimate Monitor��The Pure System�������Ƃ���肵���悤�ȉ����Ƃ����B
�O�҂̐��m����ȃT�E���h�A��҂̍L��ȉ�������X�s�[�J�[�ŁA���{�������o�[�`�J���c�C���Ƀ_�u���T�u�E�[�t�@�[�Ƃ����\���Ɍ�����B
YG�� Anat Reference Professional�݂����ȍ\�����Z�p���[�g�ł͂Ȃ���̉������݂������B
�����ԍ��F13947108
![]() 1�_
1�_
���i�ɂ���
���t�̉��i�тōl����Ƃ킩��₷�����낤���B
10���ȉ��͓���̈ʒu�Â���10��20���N���X�͒����@�ŃA�}�`���A����30�`60���N���X�̓n�C�A�}�`���A�`�v������
�����l����ƃu�b�N�V�F���t��5�`60�����n�C�A�}�`���A�N���X��80���`100���N���X�͒����J�����Ƃ����낤���B
100���I�[�o�[�͂��͂�mamiya ZD�`�N���X�̃X�^�W�I�J�����N���X�ł���B
�E�E�E�����܂ł��A�J�����̉��i�тƔ�r�����ꍇ�����B
�����ʼn��i�ɑ��Ē��������Ă��������B
KRK VXT4 \64800
Sonics Anima \342000
YG ACOUSTICS Anat Reference Main Module \2300000Over
Audio Machina The Pure System\420000
�ł���B
���j�b�g�_�C�A�t�����}�e���A��(�U����)
���{���A�A���~�h/�J�[�{��/�Z���~�b�N�Ȃǂ̃}�e���A���A����`��̃E�[�t�@�[�A�o�[�`�J���c�C���ɂ��^���_�����_���⓯�����j�b�g�B
�܂��������z��Nj�����Ƃ���V�f�ނƋZ�p�̗Z���B
�����������ߔN�̃X�s�[�J�[�͂��Ă��ăn�C���x���ȏo�����m�ۂ��Ă��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���H
��ʉ��i�т̂��̂͂قƂ�ǃ}�e���A����Ƃ������A����ł���B
�O��I�Ƀ��W�b�h�Ɍł߂邩�A�d�q�@��̃A�[�V���O�̗v�̂Łu�U���̃A�[�V���O�v���s�����߃��j�b�g�}�E���g�t���[�e�B���O�����Ă��܂������B
�P��������҂̂ق������R�X�g�ɂȂ�₷����������Ȃ��B
��҂͒�R�X�g�����A�Z�b�e�B���O�̖�(�f�U�C����)������邩������Ȃ��B
���j�b�g���Œ肳����G���N���[�W���[�̐ݒu���@���d�v�Ȃ̂͂����܂ł��Ȃ��B
�v���C���[/�A���v�����l�B
Stillpoints
�Z��̖Ɛk�\���̂悤�ɁA�Z���~�b�N�{�[���x�A�����O�ɂ��_�x���𗘗p�����C���V�����[�^�[�B
�Z���~�b�N�{�[���x�A�����O�̓��[�h�@�ރ��^�N�����������Ƃ��Ă͂�����Ƃ������������(��
���m���������{�͍��̂Ƃ���ʎY�i�ł͍ō����G3�N���X�Ƃ����C�O�̍������y�i��10�`50�{�덷���x���ւ�Z���~�b�N�{�[���x�A�����O�����낲��ʎY�ł��鍑�ł���B
SURE-FLEX
������͑f�ނƍ\�����_����X���[�Y�ȐU���`�d�����������\���ł���B
�߂��߂悳���g���Œm�������i�ł���B
�@�킩�珰�ނւ̐U���A�[�V���O�Ɍ������Ȃ���i�̂悤���B
Wellfloat
������̓��[�W�����g���̕��V�C���V���B
�����TAD�������Ă��܂��̂͊F���������Ă�͗l�B
��i�قł���^����ĂāA�t���A�^��g�[���{�[�C�ȂǂɗL�p���낤�B
Side-Press RB
���ꂼ���ɂ̃X�^���h�B
�قڃm���J���[���[�V���������������A�X�s�[�J�[�̖{���̐��\��������X�^���h�B
�߂��߂悳��̂��i��������X�s�[�J�[�w����܂��Ȃ��������Ă݂����Ȍナ�t�@�����X�ȃX�^���h�ɂȂ����̂͊ԈႢ�Ȃ��A�ꐶ�t���������i�ł���B
������͏��`���^�̃u�b�N�V�F���t�ɂǂ����B
�����ԍ��F13947461
![]() 1�_
1�_
�g�����X�|�[�g
�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[���g�p���Ă���̂ŁA�A���v�ɂ͏ڂ����Ȃ����A
�g�����X�|�[�g�ɂ��Ă����ŏ����B
Aura neo CD PLAYER-���p
�O�m�̃��J�j�Y���Ɠ��ł̃h���C�u�`�b�v�Z�b�g���̗p����CD�v���[���[�BDAC�ɂ̓V�[���X���W�b�N�́uCS4398�v���̗p����BCD�̍Đ����@�������I�ŁA�f�B�X�N���Z�b�g���A�X�^�r���C�U�[�����Ă���8mm���̃O���X���b�h���X���C�h������ƃ��[�f�B���O���J�n����B
�f�W�^���I�[�f�B�I���V�[�o�ɂ͈������́uAK4117�v���A�܂��T���v�����[�g�R���o�[�^�ɂ�96/192kHz�Ή��́uAK4125�v�𓋍ځB���A��USB�[�q�𓋍ڂ��APC��USB�ڑ����\�BPC����̉�����f�W�^���I�[�f�B�I�@�킩��̐M������͂��A�A�b�v�T���v�����O���ďo�͂��邱�Ƃ��ł���B
XLR��RCA�̃A�i���O�o�͂��e1�n��������ق��A���f�W�^�����o�͂Ɠ����f�W�^�����o�͂��e1�n�������B�O�`���@��286×278×78mm(��×���s��×����)�B�����R�����t������B
Aura groove amplifier -���p
75W×2ch(8��)�o�͂̃v�����C���A���v�B�A�i���O���͂̂ق��AiPod�p��USB�[�q�����AiPod���̊y�Ȃ��Đ����\�BiPod�Ƃ̐ڑ��̓A�i���O�ƂȂ�B
�p���[�g�����W�X�^�ɓ�����MOS-FET�uJ162/K1058�v���̗p���A�p�������v�b�V���v�������ō\���B�{�����[���p�[�c�ɂ́A�V�[���X���W�b�N�́uCS3318�v�𓋍ڂ���B
�A�i���O���͂�XLR��1�n���ARCA��3�n���A�A�i���O�o�͂�PREOUT��RECOUT���e1�n��������BiPod�p��USB�[�q�̂ق��APC�ڑ��p��USB�[�q�����ڂ���B�O�`���@��286×300×75mm(��×���s��×����)�B�����R�����t������B
���p��http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20090820_309464.html
Nuforce CDP-8-���p
�߂��߂悳��ARed���������������A�����]����CDP
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000126744/SortID=12347663/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11002209/
Nuforce P-9
Nuforce�̃Z�p���[�g�v���A���v�B
����:http://www.nuforce.jp/highend/products.html
�����ԍ��F13950868
![]() 0�_
0�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
Cambridge Audio iD100 |
Cambridge Audio iD100 |
BDP-93 NuForce Xtreme Edition |
OPPO BDP-95 Belltech Custom |
Cambridge Audio iD100
iPad�ɂ��Ή������f�W�^���g�����X�|�[�g�B
�������ǂ������R���t���ŁA������S�n�悢�B
�Ȃ�Ƃ����Ă�AES/EBU�Ή��Ȃ̂����ꂵ���Ƃ���B
http://naspecaudio.com/cambridge-audio/id100/
BDP-93 NuForce Xtreme Edition
OPPO��Nuforce�̃R���{���f���B
BDP��SACDP�Ƃ��Ă����p�ł���B
http://www.nuforce.jp/highend/products/oppo_bdp_93nxe.html
OPPO BDP-95 Belltech Custom
�x���e�b�N�����AEMC�v�̔��̋��ɂ�BDP!!
���ׂĂɂ����ăO���[�h�A�b�v���Ă��܂��B
http://blog.emc-design.jp/2011/06/oppo_bdp95_3.html
�����ԍ��F13951013
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
BENCHMARK DAC1 |
LAVRY ENGINEERING DA11 |
Mytek Digital USA Stereo192-DSD DAC |
Antelope Audio Isochrone OCX |
DAC
������ł̓X�^�W�I�N�I���e�B�̃n�[�t���b�N�T�C�Y��DAC�������Љ��
BENCHMARK DAC1
���킸�Ƃ��ꂽHigh Quality LowPrice DAC�̑������I���݁B
�������炻��Ȃ�̌����������Ă��邪�A����ł��F�����Ȃ����݂����B
����pDAC�͂܂����ꂩ��B
LAVRY ENGINEERING DA11
DAC1�𗽉킷��V����DAC�B
�O���DA10�̃u���b�V���A�b�v���f���ł���B
���l�߂ō��ꂽDAC�Ȃ�����f�W�^�������������������Ȃ��N�I���e�B�͌����̈ꌾ�B
Mytek Digital USA Stereo192-DSD DAC
Mytek������DSD���S�Ή��̍ŐVDAC�B
OPPO BDP��J�v���[�X�ɍ̗p���ꂽDAC�Ɠ����`�b�v���[�J�[��DAC�AES9018���̗p���A
�L�x�ȓ��o�͒[�q�ƃn�C�N�I���e�B�ȉ����𗼗����Ă���B
�N���b�N���o�͂܂Ŋ����B
�N���b�N-�ԊO��
Antelope Audio Isochrone OCX
������̓}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[�ŁAWC�[�q��������e�f�W�^���@�ނɃ}�X�^�[�N���b�N������������̂ł���B
�N���b�N����ɂ��A�e�@��̓�����V���N�������A���萫�����}����̂����A���_�T�E���h�N�I���e�B�ɂ������Ă���B
��������̃f�W�^���@�ނɈ͂܂�Ă���̓���p�ɂ����߁B
�����ԍ��F13951068
![]() 1�_
1�_
PA/SR�p�A���v��
PA/SR�p�A���v�ł���B
�����ł��邪���͎҂��낢�B
CLASSIC PRO CP400 \15800
�T�E���h�n�E�X�I���W�i���u�����h�̃N���V�b�N�v���̓��僂�f���B
��x�w�����Ďg�p���Ă����������������A�����O���Ƃ͗����ɂ�������Əd�����̋l�܂�����������B
�������ɂ͂��傤�ǂ������i�т����A�ӊO�ƒ���������ϋv���ƃN�I���e�B�̏o���̂�����B
CLASSIC PRO DCP400 \19800
�������CP400�̃f�W�^���X�e���I�A���v�ŁB
����������z+\4000�����ς�炸����p�ɂ����߁B
�������X�s�R���R�l�N�^�d�l�Ȃ̂ł��̂�����͒��ӂ��K�v�ł���B
BEHRINGER EPQ304 \20800
������͂׃����K�[��1U 4Ch�p���[�A���v�Łu���y�ʁA����m�C�Y�A����d�͂̒Ⴂ�X�C�b�`���O�d���v��ATR�e�N�m���W�[(Accelerated Transient Response)�ɂ��y���Ńp���`�̂���T�E���h������B
BEHRINGER A500 \21800
�������2U�^�C�v�̃A���v�Ń��R�X�^/�|�X�v���Ȃǂ̎d�l���z�肳�ꂽ���f���ł���B
�p�b�V�u�^�C�v�̃X�^�W�I���j�^�[�ɂ��ǂ��������Ǝv����B
�����ԍ��F13951415
![]() 1�_
1�_
ALESIS RA150 \20800
�����Ȃ�����A�X�^�W�I���t�@�����X���j�^�����̃A���v�B
�T�E���h�n�E�X�ł̕]�������B
ART SLA1 \28900
��������R�X�p�ɗD�ꂽ�X�^�W�I���t�@�����X�A���v�B
VESTAX VDA-1000 MK2 \41200
������͂��R���p�N�g�ȃf�W�^���A���v�B
CROWN D-45 \59800
���킸�ƒm�ꂽProcable�Ő�^����m��n�����p���[�A���v�B
������������X�^�W�I�Ŏg���Ă���悤���B
���A���{�ł̔̔����́uamcron�v���B
�����ԍ��F13951458
![]() 1�_
1�_
PA/SR�pCDP-�ԊO��
DENON DN-C620 \39800
1U�^�C�v�̔��^�v���C���[�B
AES/EBU�܂œ��ڂ��Ă���A�t�����g�̃f�U�C�����Ɩ��p�@�ɂ��Ă͏G��B
�L�x�ȃv���C�o�b�N�@�\��A���Ƃіh�~�@�\���������[���B
1Bit Digital Sutudio Master Recorder-�ԊO��
KORG MR-2000S BK \178000
128fs�܂őΉ�����DSD�}�X�^�[���R�[�_�[�B
���Ód�H��N�X�g�Ƌ����J�����s���X�^�W�I�G���W�j�ASTRIP�̐Ԑ�V�ꎁ�������p�Ƃ̂��ƁB
Audio Interface-�ԊO��
RME Fireface UFX \209500
���킸�ƒm�ꂽ�ƍ��̃I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X���[�J�[RME�̊O�t���C���^�[�t�F�[�X�̍ŏ�ʔŁB
�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�Ƃ�A/DC-D/DC-D/AC����܂Ƃ߂ɂ܂Ƃ߂����̂ł���B
SR�p�A�N�e�B�u���E�h�X�s�[�J�[-�ԊO��
Mackie SRM350v2 \55800
���^�y�ʃn�C���X�|���X���������AHF���j�b�g�ALF���j�b�g�̓`�B�\�͂����낦��@�\�܂œ��ڂ���B
�����ԍ��F13951526
![]() 1�_
1�_
�u��������T�C�Y���������o���X�s�[�J�[�v�Ƃ�
�u�T�C�Y�����㉺�����̐L�т��������������Ă���v�Ƃ�
�����ŕ����Ă����Ȃ��̂ɁA�ǂ����̐�`�⑼�l�̈ӌ���������
�����̗~�������̓����̗���A��̉��i�̃X���b�h�ʼn����������̂��ȁH
�����̂g�o�Ɠ����悤�ɁA�����̌f�����g�p���č\��Ȃ��Ɗ��Ⴂ���Ă�H
�����ԍ��F13951875
![]() 7�_
7�_
�����̏��̗���ł��B
�c�O�Ȃ���z�[���y�[�W�͎����Ă��܂���B
���Ɋւ��܂��Ă̓l�b�g�ł�����A�����Ȃ���킩��Ȃ��킯�ł�����N���^�U�͂킩��܂���B
�l�ÂĂł����̔}�̂ɂ��Ă��A�ł��B
���̉{���҂��炷����̐l���������A�����ĂȂ����W�Ȃ��ł��B
�{���ɂ��������ǂ����Ƃ��A���̐l���g���Ċ�������ۂ͕��ʈȏ�ł����ʈȉ��ł�����܂���B
�f���͏���ǂ����Ă���������p����܂�����A�����ɂȂ����Ȃ�ǂ������ȂƂ����b�ł����A
�C�ɓ���Ȃ��Ȃ�X���[����������A�C�ɓ���Ύ����Œ��ׂ�����Ǝv���܂��B
�{���҂�������̑I������b�ł����Ȃ��ł��B
���Ƒ��̌��R�~�ň��p���邽�߂ł�����܂��B
�N����ᔻ������U�������苕�U�̏��𗬂�����͂���܂���ʒi���f�̂�������̂ł��Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E�B
����ɈӐ}���킩��Ȃ��A���X�̂��Ȃ����R�~�͗���Ă����܂�����A�ق��Ă����ꂽ�ق���������������܂���B
�����ԍ��F13951924
![]() 1�_
1�_
�폜�˗��o���Ă����܂����̂ł����S���������B
���̍������Ȃ��������ݎ��炢�����܂����B
�Ȍ�C�����܂��B
�����ԍ��F13952106
![]() 0�_
0�_
����0�^����A�����́B
>���̍������Ȃ��������ݎ��炢�����܂����B
�����̗L������������Ă�����e���l�I�ł���A�܂����̓��e���������Ƃ̕�����肾�Ǝ��͎v���܂����B
������́u�N�`�R�~�f���v�ł͂Ȃ��u�����v�ł������̌f�����쐬�����낵�����Ǝ��͎v���܂��B
�����ԍ��F13952339
![]() 5�_
5�_
�������Ă�܂ł��Ȃ��Ǝv���Ă���܂����B
��͂��������悤�ł��B
�X�l�̈ӎ��̈Ⴂ�Ƃ������̂��O���ɂ����ď������݂��ׂ��ł����B
�����ԍ��F13952487
![]() 1�_
1�_
����0�^����A�����́B
����͎����̂����ɂ�����0�^����̏������݂���肾�Ǝw�E�����Ă��������܂������A���͎����l�I�ȏ������݂�^�f���ɒ��X�Ə�������ł��܂������Ƃ�����܂��B
��������ł��炭���������ƁA����ς肱��͎����̃u���O������Ă����ɏ������ނׂ��������c�Ɣ��Ȃ��܂����B
�ł����玄�͍���0�^����ɑ��Ĉ̂����Ɍ�����l�Ԃł͂Ȃ��̂ł����A���Ɠ��l�̎��s�͂��Ăق����Ȃ��Ǝv������̂悤�ȏ������݂������Ă��������܂����B
�܂��A�����قǂ��玄�͍���0�^����̏������݂��u�l�I�v�ƌ����Ă��܂����A����͎��̎�ςɂ����̂ł��B
���̈ӌ����������Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ�����܂���B
����0�^����̏������݂��u�l�I�v�ł͂Ȃ��Ǝv����������������邩������܂���B
���������͍���0�^����̏������݂����̎��s�Ɏ��Ă���Ǝv�����̂ō���̂悤�ȏ������݂������Ă��������܂����c
�����ԍ��F13957434
![]() 0�_
0�_
���e�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B
�l�b�g�ł͋C�������傫���Ȃ�A���������ɂȂ����肵�����Ȃ͎̂����̔��ȓ_�ł��B
���ƁA�w�E����܂���Ƃ킩��܂���A���w�E�����������̂͂��肪�������Ƃ��Ǝv���܂��B
���R�~�Ǘ��l������폜�˗��R���܂����̂ŁA�ȍ~�����悤�����ł��肢���܂��B
�����ԍ��F13958540
![]() 1�_
1�_
�ȑO����C�ɂȂ��Ă���BELDEN��8470�X�s�[�J�[�P�[�u�����܂����B
�w�����ProCable�̃T�C�g�ł��B
���X�ǂ��ɖ�肪�����Ĕ�������ł͂���܂��A����y�ȉ��i���D��S��U�����̂��Ǝv���܂��B
����͓��T�C�g��LAN�P�[�u�������������āA���x����������Ƒ�����������̂ł��ōw����������ł��B
���̃T�C�g�ɂ��ĊF�l�ɂ͎^�ۗ��_����悤�ł����A�X�s�[�J�[�P�[�u���I�т�A�Z�b�e�B���O�ɂ��ďڂ��������Ă��莎���܂����B
�ŏ��Ɍq�����������ɂ���قǃC���p�N�g�̂�����ʂ͂Ȃ������̂Ŏ��s���������ȁ`�Ǝv���܂������A���ꂩ�特�̏œ_�ɂ���3�����炢�����Ē��킵�Ă݂܂����B
�����������̏œ_���Ȃ�Ȃ̂��T�C�g�̐�����ǂ�ł��悭�����ł��܂���ł������A�����ÂP�[�u����ؒf���ĉ��̕ω����m�F���Ă����܂����B
60�Z���`��������������ɕω�������ꂽ�̂ŁA����Ȃ�ɕω�������Ȃƌp�����Ă����܂����B
�����Ƃɒ��������Ă���̂ŁA���̕ω����_���_�������ł��܂������A�ǂ��Ɍ������Ă��邩�܂��悭�킩�炸��Ԃł��B
70�Z���`����������肩��}�ɕω����n�߂āA����ƈȑO�̉��ɖ�肪���邱�Ƃ𗝉��B
���܂ʼnߋ����������y���O���Ă��܂��ĕ����̂��~�߂Ă�����Ȃ��A���ɕ������Ă��鉹�̃t�H�[�J�X���������玩�R�Ɖ��������Ă����Ɨ������܂����B
�{���ɂ���ɋC�Â��Ă悩�����ł��B
�Ƃ���ŊF���A������SP�P�[�u�����炱��BELDEN��8470��8460�ɕύX���Ă��鏑�����݂����܂����A���̏œ_�ɂ��Ē����͂Ȃ���Ă���̂ł��傤���H
�f���̌����Ō������P�[�u���̕ύX�݂̂ʼn��̉��P������悤�ł��ˁB
�������̏œ_�ɂ��ċ^�₪����̂Ȃ�A���͂���Ă݂鉿�l�����邱�Ƃ�`�������ł��B
![]() 4�_
4�_
�g���l�[�h�Q����@
������B
�@�ςȌ������ł����A�S�傪�S��Ƃ����l������A�X���b�h?������A�Ȃ��Ȃ��R�����g���|���Ăł��Ȃ�����������܂��B
�@�œ_�ōK���ɂȂ��̂ł���Ύ�̐��E�A�v���V�[�{�̐��E�Ȃ̂ōK���ɂȂ����ꂪ��ԗǂ������Ǝv���܂��B
�@�����ő̊����ω���̓��ł���A���ꂪ��Ԃł��B�Y�N���Ŏx���ŗ�ł��݂܂���B
�@�[���Ӗ��͂Ȃ��H�ł��B
�����ԍ��F13894187
![]() 1�_
1�_
furuji����
�Y�N��̋A��ɗ�������Ă��������āA����X���b�h�ɃR�����g�����芴�ӂ��܂��I
�u���V�[�{���ʂȂ�ŏ����炱��ȏ������݂͂��Ȃ���ł���
�{���Ɍ��ʂ������Ǝ�����`�����������̂ł��B
�ł��A���̃P�[�u����Ⴆ�Ώ��S�҂Ɋ��߂��肷��ߒ��ŏœ_�̒����ɂ��ẮA�m�炳��Ă��܂���B
�{�������܂ł��Ȃ��ƁA�u���V�[�{���ʂŏI����Ă��܂��܂��B
����́A�V�т���Ȃ��I�[�f�B�I�̊�{��m���|����ɂȂ�܂��B
����Ȑ[��܂Ŏ����N���Ă���̂́A���܂Œ��߂Ă����Ȃ��ēx�ANAS�փR�s�[���������Ȗ�Ȋy����ł��邩��ł��B
�����Ă���́A�I�[�f�B�I�̏펯��ς��鎖���̔������Ǝv���܂��B
�l�I�Ȋ��z�Ǝ~�߂�Ă��\���܂���B
�����ԍ��F13894248
![]() 2�_
2�_
�g���l�[�h�Q����@
���̏œ_�Ƃ͉��ł����H�B��ʂ̎��ł��傤���H�B�Ⴆ�p�C�I�j�A��S-1EX�̃p�[�t�F�N�g�^�C��
�A���C�������g�f�U�C���̗l�ɁA�^�C���A���C�������g�̗l�Ȃ��̂ł��傤���H�B
http://pioneer.jp/components/ex/1ex/technology_3.html
�����ԍ��F13898405
![]() 1�_
1�_
130theater 2����@
���������Ȃ�̂��Ƃ�����Ă݂Ȃ��Ɨ����ł��Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B
���������ł����B
ProCable��Web�T�C�g�̐����ɂ��鉹���}�C���h�ɂȂ�Ƃ��V���[�v�߂���Ƃ�����܂��悤�ɁA���̕��������܂��B
�����}�C���h�ɂȂ�ƌ����Ă��A�X���Ƃ��Ắu�����v�ɋ߂Â��Ƃ����C���[�W�ł��B
���̐����ɋ߂Â��邱�ƂƂ́A�A���v��CD�v���C���[�y�уX�s�[�J�[�P�̂łǂ��ɂ��Ȃ���̂ł͂Ȃ��ł��B
���ꂪ�����ł��܂��B
�����ԍ��F13899620
![]() 4�_
4�_
AV�A���v���~���[�W�b�N�����Ɍ����Ȃ��Ƃ����̂͂��ׂē��Ă͂܂�Ȃ��̂ł��ˁB�i�����Ɗ��Ⴂ���Ă����j
BELDEL�P�[�u���ɕς��Ă���̉��͂܂Ƃ��ȉ��ɂȂ�܂����B
�Ƃ��Ă��U��������ɋC�Â��đ������C���ł����A��������肵�܂����B
���ЁA���̐l�͌�����Ȃ��ł��炢�����ł��B
�����ԍ��F13944677
![]() 1�_
1�_
���g���l�[�h�Q����@��
�������̏œ_���i�҂ł��B
�ŋ�RCA�P�[�u���ɂ����̏œ_���L��̂����āw�V���̏œ_�x�Ɩ��t���܂����B
�ڂ����͎��̃u���O Community.Phile.Web.com ID Tada-Min ���������������B
�v���P�[�u������ɂ��ς݂ł��B
�ŋ߂����ȃT�C�g�����Ă���Ɠd���P�[�u���ʼn����ς��Ƃ����L�����C�ɂȂ�܂��B
�܂������Ă��܂��A������ēd���P�[�u���ɂ����̏œ_���L��̂ł́H
�ȏ�@���̏œ_�@�ɜ߂��ꂽ�j�̙ꂫ�ł����B�N�������āI�I�I�I�I�I�I�I�I�I
�����ԍ��F21255744
![]() 2�_
2�_
���t�̖ʂł͂߂��߂悳��̉e���������B
�C���p�N�g����������̂��B
������SP�����O�ł܂��܂����܂�肳��ɖ��n���������߁A
���̌��t�̐��X�̉e���������ł��Ȃ����̂��������낤�B
��������Ƃ�����C�m�E�G�V�X�e�������g��������������͌������s�u���A�T�C�h�v���X�A�����̈Ӗ��̂Ȃ��A�t�������W�ꔭ�A�g�����W�F���g�Ƃ������t����ɂ����������B
���ɃT�C�h�v���X�A���s�u���A�g�����W�F���g�Ƃ�����Q�͈�ԉe�����Ă���B
��������t�������W�����g���̎��͂Ȃ������̃��j�b�g���K�v�Ȃ̂��A�Ƃ����₢�����ꂽ�B
�}���`�E�F�C�̌��p�����܂������ł��Ȃ��������A���ł��g�p���Ă���S2X�̃c�B�[�^�[���g�����߂̕K�v���Ƃ��ăE�[�t�@�[�����݂��Ă���Ƃ�������̐��������ł��Ȃ��B
���̉����⏑�����݂����Ă���Ɛ��m�ɂȂ点��g�����W�F���g�ƃ_���s���O(�����������A����������O�ɐZ������̕s�v�����[��)�ł���u�T�C�Y�������v�͉\�ł���A�Ƃ������Ƃ��킩��B
������悪�T�C�Y�����X�s�[�J�[�Ƃ����̂͂��������̂��̂Ȃ�o��������Ƃ�����B
���j�b�g����������ΐ������₷���A�����U����}���₷���B
�Ȃ�A����a�ꔭ�ł͂Ȃ������a���j�b�g���g���A�V���N�������Ė炷�A�^������a(�������j�b�g�ŐU���ʐς��҂�)���@���Ƃ��邱�Ƃ�����B
�z���]���^��(ADAM�ł悭��������)��o�[�`�J���c�C�������̕��ނɓ����邾�낤�B
�l�I�ɂ͌��a8�C���`(20cm)�܂łȂ�l�I���e�͈͓����Ǝv���B
�\����3wey���@�[�`�J���c�C����z���]���^��(S3X-H)������܂ł����e�͈͂ł���B
����a�ꔭ���������a���j�b�g2�����V�����g���b�N�ɖ炵���ق�����������ł���B
�l�I�ɂ͕K�������G�A�{�����[����K�v�Ƃ��Ȃ��B
�^�C�g�ŗǂ��L�ѐ[�����݂��ޒ��A���̌`��������(�����̍���炵������)���j�b�g�ł��邩�ǂ������B
���̎v�z���l���Ă݂�ǂ��炩�Ƃ����Ǝ��g�� de Main�ł͂Ȃ� Time de Main�Ȃ̂�������Ȃ��B
![]() 2�_
2�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
���̋������������Ă��ꂽKuro���S�Ҏ����p��LINN |
���̐l�������̂ł͂Ȃ��A�������������Ƃ������̂� |
�������q�l�N���e����(�e���̖ؐ��l�ۂ� |
�����A����ȏ�̃}���`Wey��g�[���{�[�C�A���{�Ɖ��̋�ԃT�C�Y�������悤�ȋ���X�s�[�J�[�͐����ł��Ȃ��B
�������g�I�[�f�B�I�͂���Ă��Ȃ����A�I�[�f�B�I�@�탆�[�U�[�ł͂Ȃ����炾�B
�o�[�`�J���c�C���܂ł̃g�[���{�[�C�͂܂����e�ł��邪�E�E�E�B
�����P�ɁA�����b�g����Ă��������Ȃ��A���̈�_�ɐs����B
���j�b�g���m�̂Ȃ���������Ń^�C���h���C����SP�ł������Ⴂ�����o��낤���ǁA
�o�[�`�J���c�C���ǂ���ł͂Ȃ����A�������Ă��͋��������ł̓o���o���ɕ�������̂ł́H
��ꂻ��Ȃł�����͓��{�Ɖ���z�肵�Đv���ĂȂ����낤�Ǝv���̂����E�E�E�B
�����ԍ��F13863784
![]() 2�_
2�_
�u�Ȃɂ������Ă悵�Ƃ���̂��v�͐l���ꂼ�ꂾ���A����������~�̉~�Ղ��Ƃ��ɂ����猇���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���̂��낤�B
���쌻��ł���X�^�W�I�̃v���C�o�b�N���z������u���ƃv�������������v
�R���V���[�}�[�I�[�f�B�I���X�^�W�I���j�^�����O�@�ފe�P���������͂���ȉ��ł��낦����Ȃ狳���Ăق����B
�����炢�����̂ł����Ă��g�����Ȃ��Ȃ���o�J�����e�傲�ݓ��R�ł���A�����܂ŋ�J���ăZ�b�e�B���O���āA�n�k�̂��эăZ�b�e�B���O�܂ł��˂Ȃ�Ȃ��悤�ȃV�r�A�Ȃ��̂͒����I�Ɍ��Ďg���ɑ���Ȃ��V�����m���Ǝv���B
���đ��t�������˂�ꂽ�Ƃ��u����͈ꐶ�g����X�s�[�J�[���H�v�ƕ����ꂽ�B
���t�ɋl�܂����͎̂����B
�����A�g������͎��ɃV���v���Œ����t���������o���������B
���ꂪ��Ƀ��[�U�[�̊Ǘ����ɂ����j�Ɏ���ʂ��悤�ȋ@�ޑI��/����/�Z�b�e�B���O�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Ȃ炢���炢���X�s�[�J�[�ł��ꐶ�t���������Ƃ͂܂܂Ȃ�Ȃ����낤�B
�X�s�[�h�ɂƂ��ꖽ�����ōō����A�^�b�N���J��Ԃ�������p�݂̈�����Z�⍕�������ł͂Ȃ����B
�����ԍ��F13863822
![]() 2�_
2�_
���j�^�[�̏ꍇ�A�S�̂̉��̂܂Ƃ܂�ȑO�ɌX�̉����m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����}���`WEY�Ƃ����̂͂킩��B
���V�������u�������͈ꐶ��������Z�ߏグ�悤�Ƃ��Ă���̂ɁA�Ȃ����I�[�f�B�I�}�j�A�͉�����������B�v
�݂����Ȃ�Ă��Ƃ������B
�������Ȃ��ق��������̂Ȃ�3WAY�ȏ�͂��܂�K���Ȃ��ꍇ��������Ȃ����낤���H
�������܂Ƃ܂�̂���SP���g�����Ȃ����̂Ȃ�b�͕ʂ����B
���ƁA�Ȃ₽��ƃN���V�b�N���蕷���͉̂��ł��낤�B
������CD�̉����o�͂ł���̂ł���ŐV�̃f�W�^���T�E���h�̂悤�ȗ����オ��̑����s���Ȃł��Đ��ł��邾�낤�ɁB
���̋@��̓��ӕ��삪�ǂ����炱������A�@�ނɂ��킹�ăW�������������Ƃ����̂Ȃ�
�u����i��Ŏg���Ă�̂��A�@�ނɎg���Ă�̂��v
�����������̂Ȃ�X�^�W�I���j�^�[�ŏ\�������A�X�^�W�I�ł͂ǂ�ȃW�������̊y�Ȃł����̃X�^�W�I�̃��j�^�[�Ń~�b�N�X������Ȃ�Ȃ��B
�X�^�W�I�ł͕ǂɖ��ߍ��܂ꂽ���[�W�ɃW��������g�������Ȃ�ĂȂ���B
�����ԍ��F13863899
![]() 2�_
2�_
�����̃��C���@�ނ͑��z60�������B
�@�ł�������郌�x�����낤�ˁB
�ł����y����̊�����̂��ċ��z����Ȃ��Ǝv���B(���܂ɂ͂������Ƃ�����
�������̃P�[�u���A�R�l�N�^�A�@����W�߂Ăǂ��������낤�B
�ǂ�Ȃ��̂ɂ����ꂼ���������B
�u���̊W�߂̓{�g���l�b�N�̊W�ߏo�����Ȃ��v
���̑����Z�̓}�C�i�X�������ݏo���Ȃ��B
����قnj��܂��Ȃ����̓��m�������炤�܂�������������Ȃ����낤���ǂˁB
�ł�����Ȑj�̌��Ɏ���ʂ��悤�Ȃ߂�ǂ��������Ƃ���K�v�Ȃ��Ǝv���B
������������ȊW�߂̉����X�s�[�J�[����o�Ė����ł���Ƃ͎v���Ȃ��B
���Ă������A����Ȗ炵�ɂ����X�s�[�J�[�Ȃ�Ȃ�Ń��[�J�[��100%�点��悤�ȃA���v���Ȃ��낤�B
����Ζׂ���̂ɁB
���߂ĊJ�����Ɏg�p�����@�햼��������点��B
�������Ȃ����ƂɂȂ��^��������Ȃ��悤�ł́A�g�����Ȃ��Ȃ�Ė������낤�B
���������Ӗ��ł��X�^�W�I���j�^�[�̓p���[�h���嗬�Ȃ낤�B
���������d������̂Ɂu�P�[�u�����v�Ƃ��u�A���v���v�Ƃ���炳��Ă�����������B
�n�܂������n�܂���B
�܂��A�������g�I�[�f�B�I�@��̂悳���킩��Ȃ��ʎ��Ȃ̂����m��Ȃ����ǁA
�I�[�f�B�I�R�[�i�[��I�[�f�B�I�V���b�v�A�Ɗy�퉮�ŃX�s�[�J�[����ׂ��Ƃ�
�ǂ��l���Ă��y�퉮�̂ق����C�����悭�Ȃ��Ă��B
�y���ɉ��y���Ȃ��Ă��͎̂����B
�����҂������ӌ����������B
����Ȏg�����Ȃ��̕K�v�ȃ��m���͓̂��{�l�������ĐX�������ȌX���Ɋׂ�₷�����Ă��Ƃ��낤�B
�����Ŕ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA�Z�p���[�g���ĕ������l����A���F����B
�X�s�[�J�[�������̂ł͂Ȃ��̂��A���{�̎���ɍ����ĂȂ��̂��B
�Ȃ�ΑI��҂̕i��߂Ǝg�����Ȃ����Ԉ���Ă���\��������B
���Ď��Ɍ���ꂽ���t���u�I�[�f�B�I�͂Ȃɂ�I�Ԃ����Ȃɂ�I�Ȃ������v�ł���
�����ԍ��F13863988
![]() 4�_
4�_
�����̕W�Ԃ��鉹�����������Ȃ��̂ɂׂ͊�Ȃ��͂����B
�݂�Ȑ悪�����Ȃ��̂ɂ������R�ƑO�ɐi��ł���A�����Ȃ���܂ł����Ă��I���̗��Ȃ��̉͌��ł���B
�X�^�W�I�G���W�j�A���ڎw���̂͂ǂ�Ȋ��ł����y�̈�ۂ������łȂ���Ȃ�Ȃ��A�܂�^�̖��l�ł��낤�B
�����������ꂽ�u�^�̖��ʐF�������A�^�̋ɍʐF�ł���v�Ƃ������t����킩��悤�ɁA
���ɉ��y�Ƃ��Đ��ݏo���ꂽ�u�A�[�e�B�X�g�̍�i�v�Ȃ�X�g���[�g��CD�̉������o�����
�G���W�j�A���Ӑ}�����Ƃ���̉����o�āA�ʐF�ȂǗv��ʂ̂ł���B
CD�ɂ͌����Ă��Ȃ����̓G���W�j�A�̈Ӑ}���Ă��Ȃ����ł���A
�z�[���̂悤�ȉ������Ƃ����Ƃ��������ACD�ɓ����Ă���Γ����Ă��镪�����̋�C���͏o�邾�낤���A�����Ă��Ȃ��̂ɏo�����Ƃ���Ƃ��A���S����������Ƃ��Ύ~�ł���B
�����������̂ɋ��������Ă�l�͂��Ƃ��ƃ{�b�^�N���㗝�X�̑������{�̔̔��X��[�J�[�̂����J���ł���A����Ȕ��f�͂�D���A�����z�������̂ł���B
�I�Z���̍����ق��݂����ɁB
�l�i�����ȋ�ԃT�C�Y�Ƃ������K��������������Ȃ�܂������ł��邪�B
���̓�����̂��Ƃ��낭�ɂ���Ȃ������ɉ��̏o�������������Ă�l�͂������Ȃ��̂��B
�����ԍ��F13864019
![]() 2�_
2�_
���͂��Ă��������ꂽ�B
�u�����ɈӖ��͂Ȃ��v�ƁB
���Ŏg���Ă�P�[�u���������킩��Ȃ�����A�Ƃ����|�̔����ł������B
����Ⴛ�����ACDP���Ⴄ�A���������炷�ꏊ���Ⴄ�B
�X�s�[�J�[�ȊO�y���[�̃s�A�m���b�X����ɉ����������Ⴄ�B
�����Ⴄ�ŃV��
http://www.youtube.com/watch?v=C0o1vAh2JR8
�������A�W�����}�ł���B
�����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��̂ɕ����Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ���
����ς�A�P�ꃁ�[�J�[�ł��낦�Ȃ�����[�J�[���Ӑ}�������ɂ͂Ȃ�Ȃ���
���������A�X���f�����Ƃ��Ő��i�̂悵�����Ȃǂ킩��͂����Ȃ��B
�{���̐��i��6�����̐��\���o�Ă��Ȃ���ł͂Ȃ����낤���H
�����̂悤�ȑʎ��ɂ͈Ⴂ���ǂ��킩��Ȃ��B
�X���̉��͉����d�����Ȃ��Ђ�������Ȃ̂Łu�T�E���h�j�[�g�X�s�[�J�[�v
�y�퉮�̉��̂ق����|���u���Ŋi���̊���Ɋy����������B
�u�X�s�[�J�[�͊y�킾�A������y�퉮�Ŕ������v
�������I�[�f�B�I���ɘA��čs���Ċ��ł���邾�낤���H
����͂��Ȃ�H�ł��낤�B
��������ł͕��͋C���������̊������^���Ă���Ȃ�����ł���B
��������a�����o����V�X�e���͂ǂ������������u���f�B�[�X�T�E���h�x���`�}�[�N�v
�����̊����͒j�̃\���Ƃ͎������Ⴄ�B
�I�[�f�B�I���i���l�͕K�������ڂ��Ƃ��f�U�C�����Ƃ������B
���͂�������ǁA�����ڂ��E�E�E�B
�Ȃɂ����ĂA���ʂɍl����I�[�f�B�I�X�s�[�J�[���Ċ�ȕςȌ`�̂��̂��������I�I
�Ȃ�ł���ȂɌ����ڂɂ������u���͌����Ȃ��v
�@�\�����Ă̋@�\���������u�f�U�C���v���A�����ڂ̉ؔ��������o������̂ł͂Ȃ��B
�f�U�C���Ƃ������t�̈Ӗ��𗚂��Ⴆ�Ă�l�������C������B
�T�C�h�v���X�������ɓ��������������ŃX�s�[�J�[��������A�X�s�[�J�[���ӎ����Ȃ��Ȃ�Ă��͂ⓖ����O�̂��Ƃ����A�u�b�N�V�F���t�łȂ��s���͂Ȃ��A�ނ���D�s�����B
�����ԍ��F13864058
![]() 5�_
5�_
�v���̂ق������Ȃ����ȁH�H(�V���d�l�ł�������
���y�Đ��Ɋւ��Ă�CD-R����̂�����Ƃ������܂�Procabre�ɂ��G�������Ƃ�����
�����Ă��܂��I�[�f�B�I�ے�_��������Ă�ˁB
�����̓��ł͂ς��Ƃłŕ��G����ȃI�[�f�B�I�̐��E�𗝉����邱�Ƃ͏o���Ȃ������B
���z�̓������Ă���ɃZ�b�e�B���O�Ə̂��čX�Ȃ铊���Ǝ��Ԃ̓����܂ōs��˂Ȃ�Ȃ��̂Ȃ�
jubee����ɂ��Č���ꂽ�u�R���T�[�g�s���Ȃ����A���̉��y�������Ȃ����v�ł���B
�I��Ŋy�����A�g���Ċy�����B
���܂ł͋@�ރ��^�N�ł���قڑO�҂������B
���ꂩ��͌�҂ł��肽���Ǝv�����A�\�t�g�������S���������B
�E�E�E�ǂ�ǂ�E������ȁB
���Ƃ͒P�ɑ�^�X�s�[�J�[�ƃ}���`way�̃����b�g����Ă����܂������ł��Ȃ��A�Ƃ����b���������ǁE�E�E�B
�I�[�f�B�I�t�@�C���̂��������͂ǂ����l���Ȃ낤�B
�����ԍ��F13864710
![]() 4�_
4�_
������
�܂��܂��A�J�L�R�~����v���܂��B
�Ȃ��A�}���`�E�G�C�Ȃ̂��H
���́A��^�ɂȂ�̂��H
�u�ቹ���~��������v�ł��傤�B
�I�[�f�B�I�̗��j��R�����ƁA�����ɂ��ėǎ��Ȓቹ�Đ��邩�H�̗��j�A�ƌ��邱�Ƃ��o����Ǝv���܂��B
���x�A�l���ɂ��z���̍ۂɂ́A�A�o���M�����h�̃t���b�O�V�b�v�i�g���I�{�U�o�X�z�[���j��炵�Ă���i���X�ɂ����܂��傤�B
��^�̃z�[���X�s�[�J�[����o�Ă���ቹ�𗁂т�A�������͂߂�Ǝv���܂��B
http://www.esoteric.jp/products/avantgarde/trioomegag2/index.html
http://tournezlapage.jp/tennai.html
�����āE�E�E�E�T�M�����ŁA���a11.5cm�́u�����U�����Ȃ��t�������WSP�v����o�Ă���ቹ�Ɣ�ׂĂ݂ĉ������B����ɁA�����Ȃ��Ƃ��A�����ė���E�E�E��������܂���B
�Ȃ�ĂˁB
�����ԍ��F13866385
![]() 5�_
5�_
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�}���`���ቹ���ق�������Ȃ�ł����H
��[�A��^���͒ቹ�ɊW����Ǝv���܂����A�}���`�͂ȂႤ�C���[�W�ł����B
��^��n���ɂ��Ă�̂ł͂Ȃ��A���[�W���@�̂悤�Ȑ�p�����ɓK�x�ȍL��������Α傫�ȃX�s�[�J�[����������Ǝv���܂��B
�ቹ���ق�������Ƃ����ă��[���L���p�V�e�B�ɍ���Ȃ��悤�ȃT�C�Y���P�ɂ����ɂ��o�����X�������Ɍ�����Ƃ����E�E�E�B
�ǂ�Ȃɑ傫���Ƃ��y�퉮�ŗǂ���������PA�T�C�Y��JBL�̒��^���j�^�[�����E����Ȃ��ł��傤���H
���ʃg�[���{�[�C�͓��{����̗��ɂ��Ȃ����^�C�v�ł���ˁB
����^�̃z�[���X�s�[�J�[����o�Ă���ቹ�𗁂т�A�������͂߂�Ǝv���܂��B
�ł܂����ˁA�A�o���M�����h(��
�����̎ʐ^�q�����܂������A�X�܉^�c�ł���قǂ̃Z�b�e�B���O�ƃ��[���L���p�V�e�B�Ȃ�j�]������͂��Ȃ��ł��傤�B
���ƁA�_�C�i�~�b�N���z�[����{���n�̂ق������낢��L���̂悤�ł����A
38cm�E�[�t�@�[�Ƃ��Ƃ͂܂���������G�Ȃ�Ȃ��ł��傤���˂��B
�܂��A����ł����{�Ɖ��ɂ͕s�ލ������낤�Ƃ͎v���܂����B
�����ԍ��F13866418
![]() 2�_
2�_
���������B
�t�������W�P���ŁA20Hz�`20kHz���L�b�`���Đ��ł���A�}���`�ɂ���K�v�͖����ł��傤�H
�`���́A�o�[�`�J���c�C�������ɂ��Ă��A�}���`�E�F�C�����������t�������W�̂悤�ɖ炵�����Ƃ����H�v�̌��ʂł��B
�`���̈�ԉE�ɂ���X�s�[�J�[�́A�o�[�`�J���c�C���̏��^�u�b�N�V�F���t�{�T�u�E�[�t�@�[�̍\���ł��B
�A�o���M�����h�̃o�X�z�[�����A����Ă邱�Ƃ͓����B
���y�̍\���ɌW��炸�A�X�s�[�J�[�̔\�͂̓s���ŁA���g���ш悲�ƂɒS���X�s�[�J�[��U�蕪����̂��}���`�E�F�C�ŁA20Hz�t�߂܂Œቹ���~�����ꍇ�́A�E�[�t�@�[�����A���ł��z�[���ł��A��^�ɂȂ�̂ł��B
���������ɑ�^�X�s�[�J�[������̂��A20Hz�t�߂̒�悪�~��������A�ƁA���^�N�V�͉��߂��Ă��܂��B
�d�ቹ�̃v�[���ɐZ��̂́A���y�̉����̏d�v�ȗv�f�Ȃ̂ŁA��^�X�s�[�J�[�Ɋ���Ă��܂��ƁA�����̏��^�u�b�N�V�F���t��g�[���{�[�CSP�̏d�ቹ�����������y�\���i���d�ቹ�͍ŏ����j�ł́A���̂���Ȃ��Ȃ�̂ł��傤�B
ADAM�ɂ��Ă��A�n�C���h���C�o�[�P����20Hz�܂ōĐ��ł���A�E�[�t�@�[�͗v��Ȃ��n�Y�Ȃ̂ł��B
�ł��A�n�C���h���C�o�[�P���ł́A��悪�o�Ȃ����R�[���`���̃E�[�t�@�[��lj����Ă��܂��ˁB
���ቹ���~��������Ȃ̂ł��B
�X�s�[�J�[�J���̗��j�̒��Łu�����U�������e����v�ƌ��߂Ă��܂����̂ŁA�i���̕������A�}���`�E�F�C�̕����ɍs���͕̂K�R���Ǝv���܂��B
�u�����U�����Ȃ��v�ƌ��߂Ă�����A�S���ʂ̐i�����l�X�ȃt�������W�X�s�[�J�[�ň��Ă����E�E�E��������܂���B
�Ƃ���ŁA�����A����0������ɃX�s�[�J�[�̊�{�v�̌��茠���������Ȃ�A
�u�����U�������e����v
�u�����U�����Ȃ��v
�������I�����܂����H
�����ԍ��F13866718
![]() 5�_
5�_
�Ȃ�قǁA���������ϓ_�ł���������Ă���ł��ˁB
�ł͒��ȏ�̑ш�ł͎��g���т��ו�������}���`way�͂ǂ̂悤�ȃ����b�g������̂ł��傤�B
�l�I�ɂ̓c�B�[�^�[�@�X�R�[�J�[ �E�[�t�@�[��3�\������������x�ł����A(�N���X�I�[�o�[��q����1�`3KHz�O���������Ƃ������Ӗ�������ł��傤��)
�����⓯��ш�������a�ŃV�����g���b�N�ɍĐ�������o�[�`�J���c�C���Ȃǂ͂܂������ł��܂��B
�������m���ɂ����X�[�p�[�E�[�t�@�[�ш�͂����Ƃ��āA����ȏ�̑ш悪���������ו������ꂽ�X�s�[�J�[������܂��B
wikipedeia�ł�
�X�[�p�[�E�[�t�@�[ - ���ቹ�p�i1Hz�`100Hz�j��ch�\�L����Ƃ���0.1ch�Ő�����
�E�[�t�@�[ - �ቹ�p�i20Hz�`5kHz�j
�~�b�h�o�X - ���ቹ�p
�X�R�[�J�[ - �����p�i500Hz�`5kHz�j���~�b�h�����W�Ƃ�����
�g�D�C�[�^�[ - �����p�i5kHz�`24kHz�j
�X�[�p�[�g�D�C�[�^�[ - �������p�i25kHz�`100kHz�j
�Ƃ������ނł��B
X-ART��1:4�̋�C���k����ւ�Ȃ���2.2KH���`50KHz�̑ш��S������̂���������������������܂��A
�~�b�h�o�X�̓E�[�t�@�[���X�R�[�J�[�̑ш���l�������Ȃ��ł��傤�B
�X�R�[�J�[���E�[�t�@�[�ƃg�D�C�[�^�[�őΉ��ł��܂��B
(2wey����X�R�[�J�[��lj�����3wey�ɂ���ꍇ�A
�E�[�t�@�[�̒S���������ш������������ɋ����E�[�t�@�[�����߂���A�Ƃ����l�����o���܂����B
����/�o�[�`�J���ȊO��2way�ȏ�Ɏ��g���ш�(20Hz�`20KHz)���ו������郁���b�g�͒������ւ̊g���A�l�̎����q����1~3KHz�̃N���X�I�[�o�[�������A
�ȊO�ɂ��܂�����܂��ł��傤���H
�����������ɑ�^�X�s�[�J�[������̂��A20Hz�t�߂̒�悪�~��������A�ƁA���^�N�V�͉��߂��Ă��܂��B
���̐L�т����Ȃ�܂������ʊ��܂ŋ��߂�Ɖ����j�]���Ȃ���ł��傤���H
�ʊ����o��Ƃ������Ƃ͂���Ȃ�̉��ʂŕ������ƂɂȂ�ł��傤����B
���Ƃ���ŁA�����A����0������ɃX�s�[�J�[�̊�{�v�̌��茠���������Ȃ�A
�u�����U�����Ȃ��v
�ł��ˁB
X-ART�͕����U���A�_�C�A�t�������߉��A�g�����W�F���g�̊ϓ_����͍\���㕪���U���Ȃ������ł����A
HEXA�R�[�����m�[���b�N�X�n�j�J���R�A���P�u���[�ŃT���h�C�b�`���Ă��܂����A
�[���Ƃ͍s���Ȃ��܂ł��������������������Ă��Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F13866932
![]() 3�_
3�_
��X-ART�͕����U���A�_�C�A�t�������߉��A�g�����W�F���g�̊ϓ_����͍\���㕪���U���Ȃ������ł����A
��HEXA�R�[�����m�[���b�N�X�n�j�J���R�A���P�u���[�ŃT���h�C�b�`���Ă��܂���
X-ART�����ŁA���ʂ̕����Œ������鉹�ʂŁA20Hz�܂ōĐ��ł���Ζ��Ȃ��ł��傤�B
�������AHEXA�R�[����20kH�܂ōĐ��ł���A���͉������܂��B
���t�������W�P���ŁA20Hz�`20kHz���Đ�����A�Ƃ������肪��������킯�ł��B
�������A�o���Ȃ��B
�Ȃ��o���Ȃ��̂ł��傤���H
�u�i���v�Ƃ������t�̈Ӗ��ɁA���̔閧������ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F13867033
![]() 4�_
4�_
�ǂ��A������
�Ԃł��ϑ������Œᑬ���獂���܂ł܂��Ȃ���G���W��������Ȃ�A���X��ϑ��V���b�N�������ė��z��������܂������������G���W�����J��������ϑ��@�\���g�����ق��������I�B
�X�s�[�J�[�Ń}���`Way���嗬�Ȃ̂������ł́H
�y�킾���Č��y��͂P�{�̌��Œ��`����܂ł܂��Ȃ����肹�������č���Ă܂��ˁB
�M�^�[�Ȃ�U�{�̃}���`Way�A���ꂪ�y��̃T�C�Y���猩�ė��ɂ��Ȃ��Ă��邩��ł��傤�B
�d���������Œቹ���A�ׂ��y�����ō�����t�ł������P�{�̌��őS�ďo�������������F���o����B
�X�s�[�J�[�����Ē��͌��a�̑傫�ȃE�[�t�@�[�A����͌y���ď������c�B�[�^�[�ɔC���������V���O���ŏ㉺���撣���ĐL����藝�ɂ��Ȃ��Ă���A�Ɣ��f���Ă���I�[�f�B�I���[�J�[���命�������獡�̏�ԂȂƎv���܂��B
�ł��ł��A�����V���O����20Hz�`20KHz�܂ł�������o����X�s�[�J�[������Ȃ�I�[�f�B�I��Y�Ƃ��Ă͗~�����ł��ˁA����B
�����ԍ��F13867484
![]() 5�_
5�_
��X-ART�����ŁA���ʂ̕����Œ������鉹�ʂŁA20Hz�܂ōĐ��ł���Ζ��Ȃ��ł��傤�B
���ł��ł��A�����V���O����20Hz�`20KHz�܂ł�������o����X�s�[�J�[������Ȃ�I�[�f�B�I��Y�Ƃ��Ă͗~�����ł��ˁA����B
��[ ART�~�b�h�����W��400-12K�̂悤�ł�����˂��B
�t���b�g�ȓ����Ń��j�A�Ɏ��g���������Č��ł���Ƃ������畽�ʌ^�Ȃ��]���肻���Ȃ�Ȃ��ł����˂��E�E�E�B(�ڂ����Ȃ��ł����ǁB
�����ԍ��F13867720
![]() 2�_
2�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
PAGANI ZONDA R |
Nur�k ���E�ő� 6:47.50 |
0�|100km/h����2.7�b �ō��� 350km/h 1070Kg�d |
�g�����X�~�b�V����:�p�h���V�t�g��6���V�[�P���V����AT |
���i�����_����
�ǂ����R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
���Ԃł��ϑ������Œᑬ���獂���܂ł܂��Ȃ���G���W��������Ȃ�A���X��ϑ��V���b�N�������ė��z��������܂������������G���W�����J��������ϑ��@�\���g�����ق��������I�B
�������I�A�ϑ��ł������I�I
����`�A���̔��z�͂���܂���ł����B
�������Ė��A�G��Ȃ��Ƃ��ł��˂��`�B
����ŁA�^�₪���ׂĖ��������ł��ˁI�I
�N���}�ł̖��i�K�ϑ���EV��(�z�[���C���e�O���[�e�b�h���[�^�[��)�Ŏ����\�ł����A�_�C�A�t�����ł̓w�b�h�z���ȊO�Ȃ��ł���˂��B
��ԗ��z�I��SP��Hexa�R�[��&X-ART�����ł��ˁB
�o�[�`�J���c�C������ADAM ���j�^�����O�s�[�X MP1�����z�n�Ȃ̂��Ȃ��B
Nur�k ���E�ő� 6:47.50 http://www.youtube.com/watch?v=YPd0ATqvoJM
(GTR2) �����Z�[�t�e�B�J�| vs �]���_R in �j�����k http://www.nicovideo.jp/watch/sm15542769
�����ԍ��F13867829
![]() 2�_
2�_
����ɂ���
���Ȃ��}���`�E�G�C�Ȃ̂��H
�͂��A�V���O���R�[���X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X������
���ƍ��悪�����Ȃ�܂��̂ŁA���ʂ̃A���v�i��d���^�C�v�j
�ŁA�炷�ƁA���g���тɋϓ��ɓd���������܂��̂ŁA
���ʁA�ቹ���������������Ȃ�܂��B
�V���O���R�[���X�s�[�J�[����t���b�g�������o�����Ƃ����
��d���A���v�ł̓����ŁA��d�̓A���v���K�v�ɂȂ�܂��B
������ɐ���������܂���
http://blog.goo.ne.jp/gokounosurikire_3/c/0c8f7ed1585f00226a692df4e59b5967
�܂Ƃ�
�I�[�f�B�I�͇@�ƇA�łق�100�����߂Ă��郏�P�ł��B
�@�}���`�E�G�C�X�s�[�J�[�{��d���A���v
�@�l�b�g���[�N�g�p�ŃC���s�[�_���X�������t���b�g�ɂ��āA
�@�e�ш�ɋϓ��ɓd����������̂ŁA�t���b�g���m�ۂ����
�A�V���O���R�[���X�s�[�J�i�����U������j�{��d���A���v
�@�o�Ă��Ȃ�������U���ŐL�т��悤�ɒ������A
�@�s��������͔��ōH�v���đ�������
�B�V���O���R�[���X�s�[�J�[�i�����U���Ȃ��j�{��d���A���v
�@�����U���̏������Ȃ��̂ŁA��d���A���v�̓��������̂܂o�遁����E��悪�o�Ȃ�
�C�V���O���R�[���X�s�[�J�[�i�����U���Ȃ��j�{��d�̓A���v�@
�@�����U���̏������肸�A���C�h�����W���m�ۂ���B�ꖳ��̎�i�����m�̉�
�����ԍ��F13868580
![]() 4�_
4�_
����0������
������ŁA�^�₪���ׂĖ��������ł��ˁI�I
���������A�悤�₭�A��ɏ�����Ƃ��낾�Ǝv���܂��B
�^��̖{���ɋ߂Â��������ŁA�����Ȃǂ��Ă��܂���B
���ՂɁA������m�肵���邽�Ƃ��b�◝����t���āA�������������C�ɂȂ邾���ł́A���������̋^�₪���������Ȃ��B
����[ ART�~�b�h�����W��400-12K�̂悤�ł�����˂��B
�S�R�A�ш悪����Ȃ��ł��ˁB
���ɁA�����B
����ԗ��z�I��SP��Hexa�R�[��&X-ART�����ł��ˁB
����́A�u�����U�������e����v�Ƃ������E�Ői�������X�s�[�J�[�̘b���Ǝv���܂��B
��HEXA�R�[����20kHz�ŋ쓮���Ă݂���ǂ��Ȃ邩�H
���Ԃ�A�����U�����܂����āA�}�g���ɖ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�u�����U�����Ȃ��v�t�������W�Ƃ����̂́A20Hz�`20kHz�͈͓̔��ŕ����U�����Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��B
�}���`�E�F�C�ɂ���̂́A���ꂼ��̃T�C�Y�̃X�s�[�J�[�����ӂȑш�i�������U�������Ȃ��ш�j�������g���āA���t������Ƃ����R���Z�v�g�Ȃ̂ł��B
�܂��AHEXA�R�[����20kHz�ŋ쓮�ł���A���v���A�u��d���A���v�v�̐��E�ɂ͑��݂��Ȃ��\���������Ǝv���܂��B
�u�����U�����Ȃ��v�ƌ��߂��Ƃ���ƁA�ł́A�����U�����Ȃ��t�������W�X�s�[�J�[���A�ǂ������20Hz�`20kHz�Ŏ��݂ɋ쓮���邩�H�Ƃ������ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�܂��B
���́A�A���v���p�ɍ��Ȃ��ƁA���������̃t�������W���g���Ȃ��̂ł��B
�����U�����Ȃ��t�������WSP���A�ʏ�́u��d���A���v�v�Ŏ��ۂɖ炵�Ă݂�A�����N���邩�����Ƃ��ł��܂��B
���悪�S���o�Ȃ��������쓮�ł��Ȃ��̂ł��B
�����I�ɍ���œd�͕s���ɂȂ�̂ŁA�ǂ�Ȃɋ��͂ȃA���v�ł��i�����́j�A�J�e�S���[����d���A���v�ł������A�������Ȃ������ł��B
�E�E�E���^�N�V�́A���̘b�����Ƃ��A�u�ł́A���ۂɒ����Ă݂悤�B�w�����āA�g���Ă݂悤�B�v�Ǝv���܂��āA���s�Ɉڂ��܂����B
�ŏ��ɁA�C�m�E�G10cmSP���܂����B10cm�Ƃ����Ă��A����7cm�̃t�������W�P���B
�쓮�͂ɒ�]�̂���f�W�^���A���v���͂��߁A�l�X�ȃA���v�Ŗ炵�Ă݂܂������A�����ɁA���悪�o�Ȃ��̂ł��B
���A�z���g���I
�g�I�[�f�B�I�E�h���āA�ʔ����Ȃ��`
�Ƃ����W�J�ł��B
���i�����_����
����ɂ���
���ł��ł��A�����V���O����20Hz�`20KHz�܂ł�������o����X�s�[�J�[������Ȃ�I�[�f�B�I��Y�Ƃ��Ă͗~�����ł��ˁA����B
���^�N�V�������~�������āE�E�E�T���o���āA�����܂��āA�����g���|���Ă��܂��B
����́A�u�����U���Ȃ��v�Ƃ������E�ɐ������Ă���A�i�����炭�B��́j�V�X�e���ł��B
�����ԍ��F13868590
![]() 3�_
3�_
���A�ڊo�߂悳�B
�������������܂��B
�����O������
���t���b�g�ȓ����Ń��j�A�Ɏ��g���������Č��ł���Ƃ������畽�ʌ^�Ȃ��]���肻���Ȃ�Ȃ��ł����˂��E�E�E�B(�ڂ����Ȃ��ł����ǁB
���������l���܂����ˁA���^�N�V�ƁB
�ŁA���^�N�V�́E�E�E��ɂ���āA�����ɂ����܂����B
http://www.fal.gr.jp/
���܂��܁A�ߏ��̘V�܃V���b�v��FAL���X�I�Ɏ�舵���Ă��܂��āA�W�b�N���Ǝ����ł�����Ȃ̂ł��B
�����̃X�s�[�J�[�Q�Ƃ͑S���قȂ鉹���E�����グ�Ă��āA�꒮�̉��l����ł���B
�����Ⴄ���āA������ʂ���ꏊ���Ⴄ�̂ƁA�w���������̌��]�[���ɓ˓����Ă��邱�Ƃł����B
�ł��A�t�������W�P���ł͍��恕��悪�o�Ȃ����ƂɊւ��ẮA��ʓI�ȃX�s�[�J�[�Ɠ����ł��B
���u�����U�������e����v���E�̎푰�ł��A���Ԃ�B
���C�m�E�G�̒�d�̓A���v�ŁAFAL Supreme S��炵�Ă݂����E�E�E�Ƃ����D��S�͂���܂��B
��������������A���������邩���m��܂���B
�����ԍ��F13868627
![]() 4�_
4�_
����ɂ���
�ӂƁA�v�������̂ł����A�u�n�C�X�s�[�h�J�����v�ŁA���y�Đ����̃X�s�[�J�[���B�e���āA�u�����U���v��u➑̂̐U���v��u���Ƃ̐ڐG�ʂ̐U���v�u�X�s�[�J�[�P�[�u���̐U���v�Ȃǂ��X�[�p�[�X���[����ł݂�A�I�[�f�B�I�ɂ܂��^��̐��X���A��ڗđR�ƂȂ�\���������Ǝv���܂����B
100���R�}/�b���炢�܂ł͎B�e�ł��邻���Ȃ̂ŁA20Hz�`20kHz�Ȃǂ́A���ёO�ł��ˁB
38cm�E�[�t�@�[���A�@���ɑ傫�ȕ����U�������Ă���̂��H�Ȃǂ��A�����邱�Ƃ͊m���ł��B
�����炭�A�u���[�I�I�I�v�Ƃ����������A�I�[�f�B�I�E�ɏՌ�����������H�H�J���ł��B
�X�s�[�J�[�̐V���i���o����A�܂��́A�����O�Ƀn�C�X�s�[�h�J�����B�e���s���āA�u�X�s�[�J�[�̓����v���摜�ŕ]�����Ă��܂��E�E�E�Ȃ�Ă����A�v���[�`�́A�ʔ������ł��B
����i�߂Ă����E�E�E���ɁA��胁�[�J�[�ł́A�R���s���[�^�[�̃V�~�����[�V�������x���ŁA����I�ȍ�ƂȂ̂ł��傤���E�E�E�������J���ė~�������̂ł��B
�����ԍ��F13872591
![]() 3�_
3�_
������
�������܂Ńt�B�[���h�X�R�[�v�ŊF�����H���Ă܂������ɂ��Ȃ��č~�Q�A�ł������Ŗڂ��o�߂܂����B
���E�T�M����
���X�s�[�J�[�̐V���i���o����A�܂��́A�����O�Ƀn�C�X�s�[�h�J�����B�e���s���āA�u�X�s�[�J�[�̓����v���摜�ŕ]�����Ă��܂��E�E�E�Ȃ�Ă����A�v���[�`�́A�ʔ������ł��B
�@70�`80�N��̃X�s�[�J�[�J�^���O��I�[�f�B�I�֘A�̖{�Ƃ��ŕ����U���p�^�[����F�Ŏ������摜��ǂ������L��������܂��B�\�t�g�h�[���c�B�[�^�[�����S�~����Y��ɕ����U�����Ă���l�q�Ƃ��B
�@���Ȃ݂Ɏ��������U�����݂ŋ���Ȉ�ۂ�����̂̓r�N�^�[��SX-7�Ƃ����X�s�[�J�[�B
http://audio-heritage.jp/VICTOR/Speaker/sx-7.html
�E�[�t�@�[�ɕ����U����}���邽�߂̃R�u���t�����f�U�C��������ł����B
���w���̍��A�G���ɍڂ��Ă�������x�X�g�e���Ō��\��ʂɂ������̂Ŗڂɗ��܂����̂��o���Ă��܂��B���cHR�R�[���݂����ł���(^^)
�@�C�m�E�GSP��20�`20kHz�܂Ń{�C�X�R�C�����ӂƃG�b�W�t�߂܂ŕ����U�������Ńs�X�g�����[�V�������Ă���f���ƁA�ߑ�̃}���gWay���j�b�g�̒S���ш�ʂ̉f������ׂČ��Ă݂����ł��ˁB����B&W�̃_�C�������h�c�B�[�^�[��30Khz�܂Ő��m�ɓ��삵�Ă���Ƃ����Ƃ�����n�C�X�s�[�h�B�e�ł̋Z�p�f��������w���ӗ~����w�N�������ł��B
�����^�N�V�������~�������āE�E�E�T���o���āA�����܂��āA�����g���|���Ă��܂��B
T-TOP�̃X���͂��������[�����Ă܂��B
�ł��A���v�͑f�q���Ԉ���Ĕz������Ă邱�Ƃ�����̂ł���������Œ������炢�̋Z�ʂ������ƃ_���݂����Ȃ��Ƃ�ǂƂ��Ɂu�����ɂ͖����v�ƒ��߂܂����B
�����ԍ��F13876288
![]() 4�_
4�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�X�s�[�J�[]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y���̑��z���_�p�H
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC
-
�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
-
�y�~�������̃��X�g�z�J�����{�����Y
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�X�s�[�J�[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j