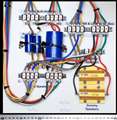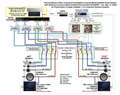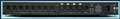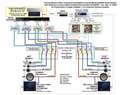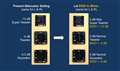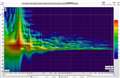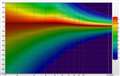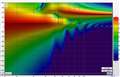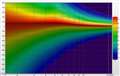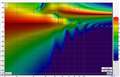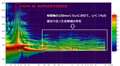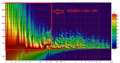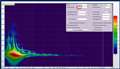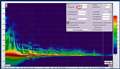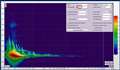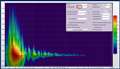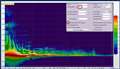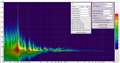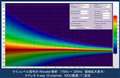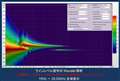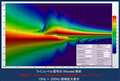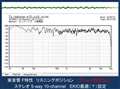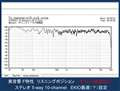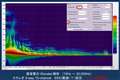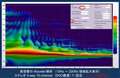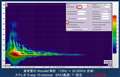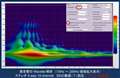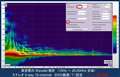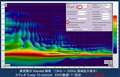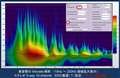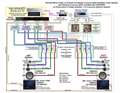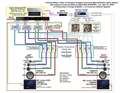このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 2020年11月4日 23:00 | |
| 252 | 190 | 2020年7月10日 09:14 | |
| 2 | 3 | 2020年6月19日 13:13 | |
| 239 | 149 | 2020年5月12日 11:06 | |
| 4 | 4 | 2020年5月2日 15:55 | |
| 9 | 4 | 2020年4月17日 21:38 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
OTOTEN ONLINE:日本オーディオ協会
https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/
CEATEC 2020 ONLINE
https://www.youtube.com/channel/UCqRDAW44Ow7J_ux8ddjaMVA
![]() 3点
3点
>サブスク万歳さん
こんにちは。情報ありがとうございます。
スピーカー比較は値段相応の感ですね。
書込番号:23759234 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
>サブスク万歳さん
スピーカー10機種比較動画ご紹介ありがとうございます。
部屋が響きすぎて録音があまり良くないようにも感じましたが、とても興味深く聴かせていただきました。
音質の格という意味では値段に比較的比例しているような感じですが、各社音色に個性があるのはもちろんですが、低音の質や低音の反応の速さとかは各社目指すところもだいぶ違うのかなと感じました。
そしてやはり独自路線のタンノイとかJBLはまた別の意味で "らしい" 個性がありますね。
個人的には、それぞれ個性がだいぶ違いますが試聴機の中では、JBL, Kripton, B&W が自分の好みでした。
でも人に勧めるなら予算と音色のお好みで、となるかなぁ。それぞれ美点はありますものね。
各社色々独自の個性があり、スピーカー選びはそこが難しくもあり楽しくもあり、ですね。
録音や写真はせめてもうちょっとマシにして欲しいですが、もっとこのような比較動画が見たいですね。
YouTubeで一つだけの機種での録画を見ても全く意味がないですが、同条件での複数機種比較は雰囲気を知るには参考になりますよね。
書込番号:23760135
![]() 1点
1点
サブスク万歳さん、こんにちは
10機種比較は面白いですね、スピーカーの音の差が大きく、同じ音源がこんなに違っていいのか?ですね。
低音の再生能力の差なのか価格なのか、やはり箱の大きい方がリアルな感じがします。
ボーカルだとJBLがマイクロフォンの音っぽくムードが出ていて、好きな人も多そう。
ホーンでなくコーンで出すから上手というか、喰えないメーカー。
オルガンだとB&Wの分離は頭抜けてますね。
鳴り分けずべったりみたいなのもあり、値段や見栄えで選ぶとジライですね、スピーカーは試聴がマストと再確認しました。
書込番号:23760790
![]() 0点
0点
2つの意味で興味深かったです。
一つはもちろん、同条件での他機種比較。とても参考になりました。
もう一つは、これを聴いた感想が他の方と自分とではだいぶ違うこと。
>スピーカー比較は値段相応の感ですね。
自分には高くても??の機種がありました。
>JBL, Kripton, B&W が自分の好みでした
今回の結果だけなら、自分だったら避けるかもという機種です。
ただし、密閉型は空気録音するとしょぼく聞こえるのでKRIPTONは別かなと。
>JBLがマイクロフォンの音っぽくムードが出ていて、好きな人も多そう。
高音が伸び切っていないので自分はダメです。
>オルガンだとB&Wの分離は頭抜けてますね。
むしろ不自然に感じました。ボーカル曲も。
あとは、全体を通して音が「固い」と感じました。
アキュフェーズのせいなのか、上流機器のせいなのか
録音のせいなのかはわかりませんが。
というように感じる方が他にいらっしゃらなければ
自分の耳がかなりおかしいことが証明される事になるので
これもまた興味深いですw。
書込番号:23761579
![]() 0点
0点
>なぜかSDさん
各本物のスピーカーで音を聴いたことありますか。
本物の音を聴いからではまた違う感想かもです。
空気録音は空気 イメージ感は伝わりますが、人により聴く環境も違い、思い込みも強く働きやすいと思います。音の感じ方は人により違うのが当たり前ではないでしょうか。証明などはできない物だとわたしは思います。
書込番号:23761928 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 2点
2点
後日、欧米の見本市とかあったらUPします。
5G、ローカル5Gはネッワークプレーヤ、AVアンプ板で
書込番号:23762121
![]() 0点
0点
なぜかSDさん、こんばんは
要約すると
JBL, Kripton, B&Wは好みではなかった。
KRIPTONは密閉型なので空気録音ではしょぼかった。
録音のせいなのかはわからないが
アキュフェーズは上流機器なので音が「固い」
ですね。
すると、なぜかSDさんの好みは
モニオとDenonとかでしょうか?
書込番号:23762196
![]() 0点
0点
>fmnonnoさん
聴いたことがあるものもありますが、このスレでは
あくまでYouTubeの音源についての感想です。
お書きになっている通り、
自分も音の感じ方って違うんだなぁという事を書いたつもりです。
>あいによしさん
こんばんは。
あの動画では(あくまでもあの動画ではですが)
一番安いモニターオーディオとフォーカルが心地よく聴けました。
という事は、自分は安く済むので幸せなのかもしれません。
デノンはPMA-60しか所有した事がないのですが
あんまり好きじゃありませんでした。
という事で、よく知りません。
書込番号:23762239
![]() 0点
0点
サブスク万歳さん
紹介ありがとうございます。
スピーカー10種類比較 面白く聞きました。
僕は、自分の装置を何種類か鳴らして比較試聴動画を公開しているので ちょっと違った視点で聞いてました。
・OTOTENの配信なので 装置1の解説 → 装置1で課題曲1 → 装置1で課題曲2 →装置2の解説
って流れになるのは分かりますが、途中でリセットされるので音の記憶の比較には向かない
解説抜きで 装置1で課題曲1→装置2で課題曲1→....
って同じ課題曲を比較機種分を5台連続で流す別バージョンもあれば もっと良い
・再生環境の説明はあったが、録音環境の説明も欲しい
EarthWorksの高そうなコンデンサマイク使って(良いな〜)遮音性が良く大音量鳴らせる環境なので良さそうですが、部屋がややライブ気味で スピーカーとマイク間の距離をある程度確保して録音しているので 直接音に対する(時間差のある)間接音の比率が高くて やや音が滲んだ録音だと思いました。録音が良くないという評価の一部は そのせいだと思います。
このため、箱鳴りを前提として間接音が多い音作りをしているスピーカーは、不利だと思いました。(特にJBLとTANNOY)
自分も間接音がが過多なプレーンバッフルを空気録音しているんですが、Youtubeでの評価は悪いです。
自分で聞いても よくねぇなぁと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=AYt3cDTHRZg
ところが、現物を聞いた人たちの評価は かなり高くて譲ってくれだの作ってくれだの よく言われます。
このスピーカーは 直接音が前から来て、間接音は部屋の壁や天井で反射して 左右上下や裏から聞こえてきます。
人間の耳では、聞こえてくる方向の音を脳内で処理して分離して聞いているので 直接音と間接音を分けて聴くことができ、間接音があると雰囲気が良く聞こえます。
ところが、マイクで録音すると直接音も間接音もフラットな電気信号に変換してしまうので ただの混濁音になってしまうんだろうなと思っています。
なので、録音時にスピーカーとマイクの間隔を近づけて 直/間比率を変えて録音したほうが良いのではと思いました。
個人的には Dynaudioが好みでした。
書込番号:23762934
![]() 2点
2点
なぜかSDさん、こんばんは
>モニターオーディオとフォーカルが心地よく
>デノンよく知りません。
返信ありがとうございます、半分当たりでしたね。
アンチB&W、アキュの常連さんがいて、
その方はモニオとDenonイチオシなので、
この音は対極なんだろうということと。
そのD&Mが、B&Wの代理店をやっている不思議。
2つの意味で興味深かったです。
書込番号:23763881 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
>あいによしさん
こんばんは。
>アンチB&W、アキュの常連さんがいて、
>その方はモニオとDenonイチオシなので、
そうだったんですね。誰?あの人?
まあ、それは置いておいて
モニターオーディオは、この動画では、という事でして、
実物を聴くとあんまり心に残っていなかったりします。
こういうスレでは
俺はAがいい、僕はBがいい、私はCだ、という感じで
色んな意見が聞けると楽しいなと思って参加したのですが
あんまり書き込みないですね。
YouTubeだし、それぞれの視聴環境も違うので
厳密な比較にはなり得ませんから
盛り上がらないのかな。
BOWSさんの素晴らしい書き込みがありましたけれど
このまま静かに収束しそうな雰囲気ですね。
書込番号:23764076
![]() 1点
1点
>BOWSさん
録音が悪いと書いたのは、おっしゃる通り響き過多というのも大きいですね。機器以外の部屋とかの要因も含めた"録音"について述べたつもりです。
ちゃんとしたリスニングルームとしてセットアップされた環境ではないのではないかなと、説明の声を聞いた瞬間に感じました。
自分がまともな録音やったことがないので簡単に言えるんですけどね。
でも、機器はいいのだからもうちょっといい部屋とか写真とかも含めてセッティングの手間かけてもいいのになと残念に感じました。
もしかしたらYouTube比較なんてと社内でも軽視されているのかもしれませんね。
> 個人的には Dynaudioが好みでした。
自分もあの中からどれかお勧めはと人に聞かれたら一般の音楽好きにはSpecial Forty ですね。
自分で使うならあの録音のままではちょっと低音の鳴り方が不満なのですが、もしあの中からの1台しか使えないと言われたら、セッティングやアクセサリなどで追い込める可能性もあり、自分でも選ぶ可能性があります。
また、古楽や近現代オケあるいは現代音楽が好きで分析的聴き方を好む人にはB&W、ジャズメインの人にはJBL、を提案すると思います。
あくまで提案であって、聴く人次第でどの機種でもあり、だとは思いますけどね。
自分は低音が遅れたり如何にもバスレフで単調で大きいとかは受け付けないタイプなので、けっこう好みが限られてしまいました。
ところで、BOWSさんの比較動画、いいですね。
平面バッフルは自分にはとても馴染みのある感じの鳴り方です。自分はメインシステムとリビングのシステム両方でマグネパンの平面磁界型を使っているのですが、同じダイポール型としてコーン型のスピーカーでも雰囲気は共通するものがありますね。
あと、Markaudioの OM-MF519、箱が大きくて立派なおかげもあると思いますが、むちゃくちゃ好みです。
箱自体を自作したことはないのですが、まずはユニットだけでもと後先考えず発注しちゃいました。
また、FOSTEXはやっぱり良くも悪くもFOSTEXらしい音だなと感じました。
書込番号:23764095
![]() 0点
0点
>こういうスレでは
雑談スレですから自身の所有機器、試聴体験紹介でも
SPは
ハーベス、HL-Compact7ES-3
ディナウディオ、Focus110
クアドラル、ロンド
とかありますがELAC BS312 買ったら別次元で他のSPは使わなくなった
書込番号:23764352
![]() 0点
0点
core starさん
スレ主さんから雑談スレの認定が出ましたので 雑談モードで
>でも、機器はいいのだからもうちょっといい部屋とか写真とかも含めてセッティングの手間かけてもいいのになと残念に感じました。
>もしかしたらYouTube比較なんてと社内でも軽視されているのかもしれませんね。
軽視というより...Youtubeで明確に機器の違いが判別できると 都合の悪いことになるとか....
>自分もあの中からどれかお勧めはと人に聞かれたら一般の音楽好きにはSpecial Forty ですね。
僕は、比較試聴やったりするので 美音より、良し悪しを素直に出してくれる機器が好きなのと Dynaudio使っているので慣れているからかもしれません。
>あくまで提案であって、聴く人次第でどの機種でもあり、だとは思いますけどね。
多様性が無いとつまらないので 人によって好みが違うのはありですし、複数のスピーカー買って使い分けるとかが良いですね。
>ところで、BOWSさんの比較動画、いいですね。
>平面バッフルは自分にはとても馴染みのある感じの鳴り方です。自分はメインシステムとリビングのシステム両方でマグネパンの平面磁界型を使っているのですが、同じダイポール型としてコーン型のスピーカーでも雰囲気は共通するものがありますね。
ありがとうございます。
マーチンローガン、アポジー、マグネパン、QUAD ESL等の箱が無い衝立型で振動板極薄で軽量、背面から音がじゃんじゃん出てくるタイプのスピーカーって初動が早くて、ディテール表現に優れるけど、大音量と低音がダメでセッティングでコロコロ変わるという特殊なスピーカー郡で OTOTENのような大会場では力が発揮出来ないタイプですね。
平面バッフルは、ダイナミックスピーカー使っているんで 衝立型と箱スピーカーの中間くらいで 雰囲気はある程度出ますね。
>あと、Markaudioの OM-MF519、箱が大きくて立派なおかげもあると思いますが、むちゃくちゃ好みです。
>箱自体を自作したことはないのですが、まずはユニットだけでもと後先考えず発注しちゃいました。
参考になってよかったです。
OM-MF519は本当にバーゲンプライスです。
おかげで ユニット単価が倍くらいするFOSTEX FE83solを売ってしまいました。
最初は音楽之友社の2Lのキット箱使っていたんですが、薄いMDFで響きが良くなくて、容量小さすぎて低音が出ないのでダメでした。
あの箱は、ヤフオクでMarkAudio 8cmユニット用のMDFじゃない ある程度大きな箱を探していてペア1万円以下で落札したので トータルで2万円切ってます。
自信持って勧められる箱の確証が無いんですが 5L以上の集成材か無垢材の箱が良いと思います。
良質な小口径フルレンジを一つ持っておくと、メインシステムで定位が決まらない、高音と低音のバランスがおかしい等の時に、参考として使えます。
書込番号:23766571
![]() 2点
2点
こんな感じなので
「大阪ハイエンドオーディオショウ2020」がオンライン開催に。11/6より公式サイトで配信
「秋のヘッドフォン祭 2020 ONLINE」、11/7 11時50分から配信
書込番号:23766762
![]() 0点
0点
>BOWSさん
> 軽視というより...Youtubeで明確に機器の違いが判別できると 都合の悪いことになるとか....
あはは、提灯記事専門の日本のメディアだとそれはあるかもですね。
スポンサー怒っちゃうかもしれませんものね。
> マーチンローガン、アポジー、マグネパン、QUAD ESL等の箱が無い衝立型で振動板極薄で軽量、背面から音がじゃんじゃん出てくるタイプのスピーカーって初動が早くて、ディテール表現に優れるけど、大音量と低音がダメでセッティングでコロコロ変わるという特殊なスピーカー郡で OTOTENのような大会場では力が発揮出来ないタイプですね。
その中では、QUAD ESLはフル静電型、アポジーはフルリボン、マーティンローガンは主力機種は静電型+コーン型ウーファーで、マグネパンは平面磁界型+むちゃくちゃ長いリボンツイーター(上位機のみ)ですね。
Magnepan は米国では部屋が広いこともあるかと思いますが1.7ですらサブウーファーを使う人が多いらしいですが、自分的には狭い部屋でMagnepan 1.7だと低音は40Hz未満のサブベースの沈み込みはともかくベース領域の量は充分すぎるほどですし、音量も耳が耐えられない爆音まで出すことも可能です。(その前にアンプが気絶しちゃいますが。)ただし、測定すると低音の歪率はひどいらしいですね。また、20畳以上あるLDKでMagnepanの通常タイプで一番小型のMMGだと低音は流石に物足りないと感じました。7畳だと不足には思わなかったんですけどね。そこは Tannoy Mercury 7.1(アッパーベースは盛り上げずにフラットですが、その代わりかサイズの割には意外にもサブベースがよく伸びています) にすら劣ったので、小さい機種は低音出ないと言えばそうなのかもとは思います。
> OM-MF519は本当にバーゲンプライスです。
> おかげで ユニット単価が倍くらいするFOSTEX FE83solを売ってしまいました。
BOWSさんの他の動画で SOLと比較して自分は MF519の方がずっと好みだと思いました。SOL は同じFOSTEXの紙コーンでもあり、自分が所有している FE108En や家族が以前作って持っていた大昔のスワンのドライバとかと大きくは変わらなそうに感じました。
> 自信持って勧められる箱の確証が無いんですが 5L以上の集成材か無垢材の箱が良いと思います。
無垢はちょっと歪みそうで怖いので個人的には集成材が一番良さげですが、あまりないのですよね。
今ちょうどヤフオクに出てる集成材の 4.6Lのをちょっと小さいけど繋ぎで買おうか迷っています。
第1候補として目を付けているのは現在在庫切れでいつ復活するか不明なのですが、QualityCreateさんというところの 14Lダブルバスレフの下記です。板は薄そうだしMDFに突き板なんですけどね。空気録音動画も悪くなさそうだし。
http://blog.livedoor.jp/qck_01/archives/6033088.html
https://www.youtube.com/watch?v=yd8F5mVpm18&t=122s
楽しい悩みですね。
書込番号:23768413
![]() 0点
0点
>サブスク万歳さん
>「大阪ハイエンドオーディオショウ2020」がオンライン開催に。11/6より公式サイトで配信
>「秋のヘッドフォン祭 2020 ONLINE」、11/7 11時50分から配信
またまた紹介ありがとうございます。
こちらは比較動画ではなくて通常の紹介動画っぽくなりそうですが、それはそれで新製品などがあると面白かったりしますよね。
書込番号:23768417
![]() 0点
0点
昨年末から、下記それぞれのスレッド;
【複数のプリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道か?】
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284
【続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776
【チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab
【ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
【続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/
にて貴重な情報交換をさせていただき、その結果として、
PCソフトウェアであるLUPISOFT社のチャンネルデバイダー(クロスオーバー)EKIO;
http://www.lupisoft.com/ekio/
http://downloads.lupisoft.com/ekio/EKIO_user_manual.pdf
と
ステレオ4-way 8-チャンネル DAC機である OKTO RESEARCH社の DAC8PRO;
https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf
を用いて、
1. Windows 10 Pro 64bit PC内部で、Roon や JRiver MC26 から 192 kHz 24bit のステレオデジタル信号をAD変換なしで EKIO に入力して 192kHz 24bit のままでステレオ4-way 8-チャンネルのデジタルチャンネルデバイダー処理=帯域分割(クロスオーバー処理)を行い、
2. デジタル8-チャンネルをUSBケーブル1本で同時に DAC8PROへ 出力して DAC変換させ、それぞれのアナログ音声信号をアンプ群(ステレオアンプ4台、またはモノラルアンプ8台)に導いて、ステレオ4-way 8-チャンネルのマルチアンプオーディオ環境を構築する、
ことを計画中です。
これに、左右1台ずつの独自アンプ内蔵サブウーハー(YAMAHA YST-SW1000 2台)が加わりますので、実質的には、ステレオ5-way
10-channel のマルチアンプ環境となる予定です。
書込番号:23398943
![]() 3点
3点
再録になりますが、今回のマルチアンプ化の対象であるスピーカー群について紹介します。
構成は、3-wayのメインスピーカー (ウーファーWO、スコーカーSQ、ツイーターTW)に加えて、左右にスーパーツイーターST、およびこれも左右にアンプ内蔵の強力なサブウーファーSWを使い、実質的には5-wayの構成です。
長年愛用しているメインスピーカーは、メンテナンスと改造を重ねて今でも絶好調な YAMAHA NS-1000 です。 NS-1000Mではありません。(NS-1000 の背面、側板、天板、定番は NS-1000M より 5mm 厚く、前面バッフル板は、何と 15 mm も厚く、総重量は 39 kg でNS-1000M より 8 kg も重くなっています。)
従って;
WO 30 cm コーン
SQ 8.8 cm ベリリウム ドーム
TW 3.0 cm ベリリウム ドーム
です。
https://sawyer.exblog.jp/12639976/
で報告されている方に全く同感で、SQおよびTWのアッテネーターは、-4 〜 -5 dB の設定で WO とのつながり、バランスが最高で、総合能力をフルに発揮してくれており、バリバリの現役です。
http://audio-summit.co.jp/2019/04/04/ns-1000m%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%B4%97%E6%B5%84%EF%BC%89/
http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/
あたりを参考にして、昨年夏にアッテネーターを完全分解&洗浄してオーバーホールし、さらに;
http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/
を参考にして、NS-1000は3端子化して各ユニットに直結し、内部のクロスオーバネットワークとアッテネーターは撤去し、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス化しております。
クロスオーバーは、NS-1000 オリジナルとほぼ同様の;
500Hz,両側 -12 dB/Oct
6000Hz, 両側 -12 dB/Oct
です。
STは、非常に高能率なホーン型 FOSTEX T925A で、アッテネーターは -15 dB あたりで鳴らしております。低域カットは、 1.5 μF コンデンサー一発のみですので、 約 8 kHz, -6 dB/Oct 傾斜で、NS-1000 のTW とかなり重なっていますが、 -15 dB アッテネーター設定で最適化しており、10 kHz 以上で本領を発揮させています。この ST は、NS-1000 のスピーカー架台の中に配置しており、WO と SQ を、TW と ST で上下から挟むという、ちょっと特殊な配置にしております。
左右の SW は、YAMAHA YST-SW1000 2台で、120W 5Ωの強力アンプ内蔵、歪0.01%、カットオフ周波数 30 Hz〜130 Hz 連続可変(-24dB/oct)、レベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過去2回のヤマハでのメンテナンスを経て、いまでも完動、現役です。
ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIOは、既にチャンネル数無制限の有償版を入手して試用を開始しており、その試用状況については、スレッド;
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
の最後のあたりから始まり、前スレッド;
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/
で、かなり詳細に情報交換させていただきましたで、そちらもご覧下さい。
次の応答欄から、引き続き、準備状況およびマルチアンプ構築状況について情報交換させていただきます。
なお、ご参考までに。。。。
ASR (Audio Science Review) Forum にて、すべて英語ですが;
【Multi-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC】
と題したスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
も主催しておりますので、ご興味がおありでしたら訪問いただき、またご参加下さい。
書込番号:23398985
![]() 3点
3点
マルチアンプへ移行前の、原状のシングルDAC+シングルアンプ環境の機器構成は、添付画像の通りで、マルチアンプ環境構築後も、この環境を維持するために、ご覧のSPケーブル接続切替ボードを制作済みです。
書込番号:23399022
![]() 3点
3点
少々慌てておりました。
自明ですが、最初の書込の訂正です。
誤) 先行スレッドが、かなり頂戴になりましたので、
正) 先行スレッドが、かなり長大になりましたので、
書込番号:23399118
![]() 2点
2点
さて、現在構築中のマルチチャンネル−マルチアンプシステムの概要図です。
基準音響システムとして残しておく 「シングルDAC−シングルアンプの環境」 も一緒に描いておりますので、少々複雑に見えますが、ご了解下さい。
書込番号:23399137
![]() 1点
1点
このマルチアンプ環境構築の中核となるのが、チェコ共和国の首都プラハにある OKTO RESEARCH社;
https://www.oktoresearch.com/index.htm
の8連装マルチチャンネルDAC 「DAC8PRO」 です;
https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf
DAC8PRO は、昨年の登場以来、その驚異的な高性能とコストパーフォーマンスが、世界的に大きな話題となっております。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
DACチップは ES9028PRO 一つですが、優れた XMOSコントローラー(と内蔵ソフトの設計と実装)によって、ES9028PROの性能を極限まで引き出していることが実証され、何よりも、その8チャンネル全てにおいて驚異的な音響性能が実現されており、今日現在でも世界最高クラスの10指(おそらく5指)に入る DACと見なされており、実際に利用を開始している Hi-Fiオーディファンからも多数の絶賛報告が各所に掲載されています。
私は、本年2月15日に DAC8PRO+リモコン(Apple Remoteです、DAC8PROとペアリングして出荷)を発注し、個人輸入(関税などは一切かからず)で5月9日に入手いたしました。恐らく、(確実に?!)、日本では最初の利用となります。 (もし、既に日本で使われておられる方がおられましたら、是非、ここでお知らせ下さい!)
「個人輸入」といっても、OKTO社のホームページで、クレジットカード決済で発注しただけで、発送は FedEx の国際航空貨物便で、プラハを出発してから5日目に私の自宅(千葉県)に配達されました。成田空港の通関手続きで、問い合わせが来るかも、とも予想しておりましたが、それも一切なく宅配されてまいりました。
なお、OKTO社は、代理店を一切使わない主義だそうで、ホームページからの発注が唯一の購入手段です。
書込番号:23399200
![]() 1点
1点
このマルチアンプ環境構築におけるもう一つの「主役」は、ソフトウエアクロスオーバー(チャンネルデバイダー) EKIO です。
http://www.lupisoft.com/ekio/
http://downloads.lupisoft.com/ekio/EKIO_user_manual.pdf
PC内で、JRiver MC, Roonなどから ASIOドライバー経由で、直接 192 kHz 24 bit のステレオ信号を受け取って帯域分割処理を行い、各分割帯域を ASIOドライバーで DAC8PRO へ出力できます。
私は、2月7日(米国滞在中)に DAC8PRO の情報を初めて入手し、その前週から調べていた EKIO と組み合わせることで、昨年末以降、ここで多くの議論と情報交換を進めていた、
「PC内部のフルデジタル処理による マルチチャンネル−マルチアンプシステム」
が、一挙に、リーズナブルな予算で、恐らく現在最高の音響品位で、構築できることを確信いたしました。その過程では、最初の書込で紹介した各前身スレッドで、多くの皆様から、非常に貴重かつ膨大なご支援を頂戴しましたので、ここでも、あらためて深く御礼申し上げます。
EKIO における「全ASIOドライバー」入出力の詳細については、
前スレッド;
【続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/
および ASR の私のスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
で詳しく報告しておりますので、ご参照下さい。
また、もし EKIOを利用され、I/Oなどで情報交換を望まれる際には、ご遠慮なく、このスレッドでお知らせ下さい。
書込番号:23399274
![]() 1点
1点
ソフトウェアクロスオーバー(チャンネルデバイダー)の利用に際しては、大きく分けて、次の4点が常に大きな課題となります;
1.ソフトウエアクロスオーバーへの/からの、ASIO入出力を、どのように構築するか?
2.帯域分割やSP配置に帰因するディレイ(遅延)問題(ディレイ、レイテンシー、同期 の問題)を、どのように処理・解決するか?
3.複雑で唯一の解決策がない「位相問題」を、どのように処理・解決するか?
4.マスターボリュームおよび各チャンネルの相対ゲイン調整(左右バランス調整を含む)を、どこで、どのように行うか?
これらについても、EKIOと DAC8PRO の利用を前提として、かなり徹底的に議論、検証、シミュレーションを完了し、ほぼ理想的な方向性が得られておりますので、各前身スレッドや ASR のスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
をご参照下さい。 また、個別に必要があれば、ここで、お問い合わせ下さい。
では、次の書込以降では、DAC8PRO 入手以降のプロジェクト進展について情報交換させていただきます。
書込番号:23399282
![]() 1点
1点
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
でも紹介済みですが、DAC8PRO は、本邦初演のようですので、まずは本体の内外の様子を写真画像でお知らせします。
なお、取説は、ここにあります;
https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf
書込番号:23399295
![]() 1点
1点
このマルチアンプ環境の構築には、この図の Amplifier-1 〜 Amplifier-4 の、4台のステレオアンプ、または8台のモノラルアンプ、が必要となりますが、これらのアンプ群については、現在、鋭意検討中で、機種決定には至っておりません。
前スレッド;
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/
の後半における Naim ND555 enthusiastsさんとの豊富な情報交換も踏まえつつ、現在では、Hypex社製ステレオデジタルアンプモジュールを4基搭載した自由構成アンプ製品;
NORD ONE MP NCXXX 4-8 122-500W Custom Configurable Channel Amplifier
https://www.nordacoustics.co.uk/product-page/nord-one-mp-ncxxx-4-8-122-500w-custom-configurable-channel-amplifier-black
および
Apollon Audio NCMP8200
https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/
に的を絞って、情報収集、検討中です。
その一方では、ステレオ 2-way 4-channel の DENTEC DP-NC400-4 (Hypex NC-400 を2基搭載)
http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html
を2台、XLRバランス入力仕様で、無償で試聴させていただけるお話が進んでおり、6月末頃には実現しそうですので、この試聴も経た上で、マルチチャンネルアンプ(8チャンネル必要)を決定したいと考えております。
そのため、しばらくは、現有の 「シングルDAC+シングルアンプ(E-460)+LC-ネットワーク」システムで、EKIO と DAC8PRO の検証を進めております。次の書き込み以降で、その様子をご紹介します。
書込番号:23399389
![]() 1点
1点
DAC8PRO の到着に先立って、Windows 10 環境下で DAC8PRO の全機能と連携できる ASIO ドライバー(おそらく、まだ評価版?);
DIYINHK_UsbAudio_v4.59.0_2019-02-28_setup.exe
が送られてきましたので、これをインストールしてから、USB 2.0 ケーブル1本で DAC8PRO を繋ぎ、電源を投入すると、Windows は、DAC8PRO をDIYMHK USB Audioデバイスとして認識すると共に、ASIOドライバーが利用可能となります。
柔軟な、完全ASIO環境によるEKIO利用の準備としては;
VB-Audio Virtual Cable;
VBCABLE_Driver_Pack43.zip (1.09 MB - OCT 2015), Donationware
https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm
VB-Audio Hi-Fi CABLE & ASIO Bridge;
HiFiCableAsioBridgeSetup_v1007.zip (3.82 MB - MAR 2014) , Donationware
https://www.vb-audio.com/Cable/#DownloadASIOBridge
ASIO4ALL 2.14;
ASIO4ALL_2_14_English.exe (452 KB - MAY 2017)
http://www.asio4all.org/
Ekio-1.0.6.0-install.exe (6.5MB, now Version 1.0.6.0, US$149 Net Price for one license)
http://www.lupisoft.com/ekio/
の各インストール(上記の順序をお勧めします)が必要です。詳細は、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-369800
をご覧下さい。
以下、JRiver MC26 による再生を例にして、DAC8PRO と EKIO の利用検証の原状を、お知らせします。
書込番号:23399425
![]() 1点
1点
DAC8PRO の8チャンネルの各チャンネルは、192 kHz 24 bit, 2xDSD (DSD128) までの DAC変換に対応しておりますので、まずは EKIOを使わずに、最高品位の 2xDSD (DSD128) における総合音響品位を OPPO SONICA DAC と比較しました。
添付図のように、ACCUPAHSE E-460 には、2系統のバランスXLR入力が可能で、同時に同じ信号を流しながら切り替えて比較試聴できるので、非常に便利です。
この場合は、EKIOは使わないので、右図のように、JRiver では DIYNHK ASIO Driver (ASIO) を出力デバイスとし、DAC8PRO の CH-1(L) および CH-2(R) へ ASIO入力して DAC変換させ、E-460 の BAL-2 へ入れています。
OPPO SONICA DAC のサウンドを聴く際には、もちろん、OPPO SONICA ASIO (ASIO) を選択して SONICA DAC へ入力してDAC変換させ、そこからE-460 の BAL-1 へ入れています。
両者の音響品位比較では、Super Audio Check CD
https://www.discogs.com/Various-Super-Audio-Check-CD/release/12859958
の基準レベル音源を再生して E-460 のVUメーターで再生レベルが同じになるようにボリューム位置を記憶し、「同じ音響レベル」で総合品位を比較しました。
比較試聴音楽トラックは、添付図の私のオーディオチェックプレイリストの通りです。ここでは、44.1 kHz, DSD64, DSD128 が混在していますが、JRiver で、2xDSD (DSD128) にリアルタイム変換して比較試聴しました。
もちろん、念のため、E-460 への BAL-1, BAL-2 入力を入れ替えたり、BAL-1 で両者を比較したり、も行って、比較結果を検証しました。
その結果、もちろん OPPO SONICA DAC ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/oppo-sonica-usb-dac-and-streamer-review.11845/
の音響も依然として非常に素晴らしいのですが;
1.自然な音響 (比較するとSONICA DACは、OPPOの色づけと臭いが強い=低音部と高音部の僅かな誇張?)
2.圧倒的な S/N 比
3. いわゆる「何枚かベールが剥がれた」晴明感、澄明感、ソノリティ
4. 3D音響定位 (3D sound perspective)
5. 圧倒的な音響解像度
などの全てにおいて、DAC8PRO が SONICA DAC に優っていることが、明確に確認できました。DAC8PRO の音響品位は、「まさに恐るべし!」 と実感しました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
で絶賛されていることが、よく理解できました。
どうやら、OKTO社が絶対の自信を表明している XMOSと実装ソフトの完成度が、圧倒的に高いのだと思われます。
まだ、エージングは終わっていないにもかかわらず。。。。
いや、発注から出荷まで数ヶ月かかっているので、OKTO社で十分なエージングを済ませているのかも知れません。
次の書き込みでは、いよいよ EKIOも使って 192 kHz 24 bit で DAC8PRO の全8チャンネルの総合音響品位を、同条件でSONICA DACと比較した結果をお知らせします。
少々お待ちください。 しばし、休憩します。
書込番号:23399499
![]() 2点
2点
dualazmakさん
ご無沙汰していて申し訳ありません。
OKUTO DAC8PRO ついに入手されましたね。
素晴らしい
キャノンコネクタが12個並んでいる背面は RCAとXLRがごちゃごちゃ並んでいる民生用と違ってシンプルかつプロ用というオーラが出ていていいですね。
それと基板写真ありがとうございます。
ものすご〜〜〜く参考になります。
背面のように、シンプルかつ機能的で無駄が無くて美しい構成ですね。
アナログとデジタルでトランス2個
ES9028PROから タコのように8本伸びていて 差動ローパスフィルタに配られている配線と それにフル差動OPAMP OPA1632が配置されていますね。
OPA1632の使用例はあまり見たことがありません。差動なため、左右対称レイアウトがきれいかつ機能的です。
シンプルなIV変換と1次のローパスフィルタ兼ねていて 大電流DACらしく 100Ωのチップ抵抗だけが2011サイズのようですね。2chだけ 無いのが気にかかりますが
最近のDACのらしくコンデンサはすべてセラミックですね。
それと、ES9028PROはSRC内蔵していてSONICA DACもそうなんですが、 50〜100MHzくらい一発でレートコンバートしているんですが、44.1KHzと48KHzの1024fsのクロックが載ってます。干渉低減なのでしょうか?入力によって切り替えるとは凝ってます。
出来ましたら、
・DAC基板のヘッドホン端子(黒四角)と電源基板への接続端子が並んだあたりの拡大写真がほしいです。
・ES9028PROの拡大写真のちょっと上の写真
いずれも電源ICが搭載されていて どんなレギュレータを使っているか知りたいです。
これからパワーアンプも導入して シンプルかつ機能的なマルチアンプの構築を楽しみにしています。
それと、以前 友人がSONICA DAC持ってきたので 聞いて10秒で「雑味いっぱいで駄目だこりゃ」と思いました。
民生用なんで いろいろ機能や端子を盛込んで雑音発生源が点在するのとアナログ段と電源段が弱点かなぁと思いました。
書込番号:23399824
![]() 2点
2点
>BOWSさん
お久しぶりです。ここまで来れたのも、皆様のおかげです!
ご希望の拡大写真、明日にでも接写撮影して、お目にかけます。
OPPO SONICA DAC と比較していますが、SONICA DAC についても、「なんで今頃?」ですが、ASR で例の amirm さんが評価して報告しています。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/oppo-sonica-usb-dac-and-streamer-review.11845/
まだ触り始めたばかりですが、DAC8PROは、本当に凄いです! 感動しています。
今日は、強制的な自宅待機日ですので、ちょっとまとめて、書き込んでいます。もう少し、23時あたりまで、かな? 続けてみます。
書込番号:23399915
![]() 2点
2点
さて、EKIO経由で試聴するために、JRiver の出力先を ASIO4ALL (ASIO) に設定し、 DSPで出力フォーマットを 192 kHz 24 bit に固定します。
DIYNHK ASIOでも EKIO に繋げますが、EKIO の出力先を複数DACに柔軟に振り分けるためにも、ここでは JRiver から ASIO4ALL (ASIO) に出力させることで、非常に安定した次の二つの I/O を、「同時並行で」 確立できます。
JRiver --> ASIO4ALL --> VB Audio Hi-Fi Cable ASIO --> EKIO --> ASIO4ALL --> DIYHNK ASIO --> each of 8-channels of DAC8PRO --> E-460 amp
および、
JRiver --> ASIO4ALL --> VB Audio Hi-Fi Cable ASIO --> EKIO --> ASIO4ALL --> OPPO ASIO --> OPPO SONICA DAC --> E-460 amp
です。
ASIO4ALL for JRiver および ASIO4ALL for EKIO のパネルを、添付画像のように適切に設定してから、EKIO の Settings で、一旦 None を選んでから、再度 ASIO4ALL を設定すると、添付画像のように、EKIO の I/O 画面の各チャンネル出力先としてDAC8PRO 1〜8 が選択できます。
L, Rの入力は、JRiver から ASIO4ALL が受け取ってルーティングしている VB Audio Hi-Fi Cable 1 (L) と VB Audio Hi-Fi Cable 2 (R) を指定して、JRiver からの 192 kHz 24 bit 信号を獲得しています。
この EKIO設定では、はやる心を抑えて(!)、添付の通り帯域分割機能は一切使わずに、L, Rの入力チャンネルを、単に分配するチャンネル分配器として EKIO を使っています。 こうすることで、ご覧のように、SONICA DAC と DAC8PRO の8チャンネルに、同時に、同期して、同じステレオ信号を流すことができます。
SONICA DAC の L と R から E-460 の BAL-1 へ、
DAC8PRO の CH-1(L) と CH-2(R) から E-460 の BAL-2へ、
同じ信号を完全に同期して流せますので、E-460 のリモコンで BAL-1, BAL-2 を瞬時に切り替えることで、両者を比較試聴できる、という設定です。
ご覧のように、EKIOから DAC8PRO の
CH-3(L) & CH-4(R)
CH-5(L) & CH-6(R)
CH-7(L) & CH-8(R)
へも同じ信号を流していますので、XLRバランスケーブルを差し換えることで、DAC8PROの全てのチャンネルの音響を SONICA DAC と比較することができます。
この厳密な 192 kHz 24 bit の比較試聴においても、先ほどの 2xDSD (DSD128) の場合と同様に、
1.自然な音響 (比較するとSONICA DACは、OPPOの色づけと臭いが強い=低音部と高音部の僅かな誇張?)
2.圧倒的な S/N 比
3. いわゆる「何枚かベールが剥がれた」晴明感、澄明感、ソノリティ
4. 3D音響定位 (3D sound perspective)
5. 圧倒的な音響解像度
などの全てにおいて、DAC8PRO の全てのチャンネルで、SONICA DAC に優っていることが、明確に確認できました。
書込番号:23400018
![]() 2点
2点
次に、DAC8PRO の、任意の2チャンネルペア同士の間で、音響品位の差がないこと(当たり前ですが!)を厳密に確認するために、添付画像のように、DAC8PRO の任意の出力ペアを、E-460 の BAL-1, BAL-2 へ繋いで、先ほどと同様の EKIO分配設定で、瞬時に切り替えながら比較試聴しました。
もちろん、チャンネルペアを変える際には、一旦ミュートしてから XLRバランスケーブルをペアで差し換えています。
この任意のペア間の比較試聴によって、当たり前ですが、DAC8PRO のチャンネル間で、出力ゲインや音響品位に全く差がないことも確認できました。
書込番号:23400038
![]() 1点
1点
DAC8PRO と EKIO を用いた、ここまでの検討、実証、試聴により、以下の5点が確認できました。
1.受け取った DAC8PROには、何らかの問題や初期不良は皆無で、期待したように完璧に動作している。
2.非常に慎重に設定した同一条件下の比較試聴により、2xDSD (DSD128) および 192 kHz 24 bit 再生の両方において、DAC8PRO の総合音響品位は、SINOCA DAC の音響品位を顕著に凌駕することが確認できた。
3.DAC8PRO の8チャンネル相互間で、ゲインや音響品位の差は全くないことが確認できた。(あたりまえであるが)
4.ASIO4ALL および VB AUDIO Hi-Fi CABLE による full ASIO I/O ルーティングにより、EKIO は、期待およびシミュレーションしていた通り、分割した任意のチャンネルを DAC8PRO 8チャンネルの任意のチャンネルへ、柔軟にASIO出力できることが確認できた。
5.ASR Forum における測定結果をベースとした非常に高い評価;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
および The Art of Sound Forum における、どちらかというと主観的な高評価;
https://theartofsound.net/forum/showthread.php?68601-Okto-Research-DAC8-Pro-multi-channel-DAC
は、いずれも非常に妥当な評価であることが、入手したDAC8PRO実機において再確認できた。
EKIO も、DAC8PRO も、期待通りの動作が可能なことが確認できると共に、DAC8PRO の高性能、高品位を目の当たりにして、「DAC8PRO 恐るべし!」 の感を深めております。
次は、再度、「いよいよ」ですが、 EKIO のクロスオーバー(チャンデバ)ステレオ5帯域分割と、ステレオ4-way 8-channel の DAC8PROへのASIOインプットと再生を検証します。
書込番号:23400115
![]() 1点
1点
これまでの、慎重な調査と検討、そしてシミュレーションの結果として、私の環境において、8チャンネルマルチアンプの導入後に、最初に試すべき EKIO のチャンデバ(クロスオーバー)設定は、添付画像の通りである、との結論を得ております。
5帯域の分割周波数帯は、まずは、現在のLC-ネットワーク回路の設定を踏襲して;
15 Hz 〜 50 Hz for SW (sub-woofer/サブウーファー)
45 Hz 〜 600 Hz for WO (woofer/ウーファー)
600 Hz 〜 6,000 Hz for SQ (squawker/スコーカー)
6,000 Hz 〜 for TW (tweeter/ツイーター)
9,000 Hz 〜 for ST (super tweeter/スーパーツイーター)
であり、
◆ 15 Hz low-cut を含む全ての low-cut, hi-cut EQフィルターは、LR (Linkwitz Riley)型で 12 dB/Oct 傾斜、
◆ 全て 12 dB/Oct 傾斜なので、理論上の帯域位相は、低周波側から順に;
(SL) reverse - (LO) normal - (MD) reverse - (HI) normal - (SH) reverse
となるので、EKIO帯域パネルでは、SL領域とMD領域で位相反転(Invert)をチェックして位相を合わせる
(TWとSTは、各SPユニットのケーブル端子接続で逆相接続されている; TWは YAMAHAオリジナルでも逆相接続)
◆ 各分割フィルターと帯域グループにおけるディレイ設定は一切なし、
◆ 分割帯域におけるゲイン設定も基本的になし、ただし TW領域とST領域は大きく重なるので、それぞれ -4, -5 dBゲイン設定
◆ 30 Hz 〜 20 kHz 全域で、ほぼフラットな出力周波数カーブ (SWは、独自のボリュームも持っているので調整可能)
◆ L, R インプットでは、クリッピングを厳に避けつつも、ビットロスを最小化するべく、なるべくハイゲインで処理させる、
◆ 各分割帯域も、なるべくフラットな周波数応答状態で、なるべくハイゲインで DAC へ入力してDA処理させる、
◆ 必要なマスターボリュームおよびチャンネル間相対ゲイン調整(左右バランス調整を兼ねる)は、DA変換後にDACチップ(またはDAC装置)のボリューム/ゲイン機能で行う、
との基本方針です。
ディレイ設定は、これまでにも数多くの最適化シミュレーションを実施しておりますが、以下の理由から、「一切ディレイなし」 の設定から検討を開始します。
● チャンデバソフトでディレイを設定すると、必ず「位相」の複雑化を招く、
● NS-1000 の WO, SQ, TW は、YAMAHA の厳密な設計で、相対位置が最適な位相関係に固定されている、
● SWは、独自の位相反転スイッチを有しており、リモコンで反転可能、
● SWは約 40 cm の範囲内で物理的に前後移動が可能、
● STも前後に移動可能であるが、原状が最適位置であることを聴覚でも、REW-Wavelet 解析でも確認済み
● 以上は、実音響の REW-Wavelet 解析でも、ほぼ検証済み
添付の EKIO 設定で、現有の OPPO SONICA DAC+E-460+LCネットワークでSP群を駆動し、位相とディレイを含めた総合音響が、EKIOなしの音響とほぼ完全に同一であることを、慎重な試聴比較と REW-Wavelet解析で確認済みです。
さて、DAC8PROも入手できましたが、マルチアンプは、当面、「おあずけ」状態ですので、まずは、添付画像3番目(右端の画像)のように、 Lチャンネル全てを DAC8PRO の CH-1 へ、Rチャンネル全てを CH-2 へ出力し、DA変換後に E-460 の BAL-2 へ入力しました。
つまり、現在のシングルアンプ+LC-ネットワーク経由で、EKIO分割後の全帯域の音響を試聴できる、という設定です。
EKIO の出力パネル(ここでは全10チャンネル)のそれぞれには、MUTE と SOLO のボタンがありますので、全10チャンネルの総合音響を聴くことができるのみならず、それぞれのチャンネル単独の音響(L,Rのどちらか一方のみでも)、さらには、任意の組み合わせの混合音響、を、簡単に選択して聴くことができます。 これにより、EKIOによる帯域分割後の、それぞれの帯域音響を個別に、また組み合わせて、確認できました。
また、EKIOからの出力を DAC8PRO の CH-3, CH-4 に導いて、XLRケーブルをそこに付け替えて E-460 の BAL-1または BAL-2へ入力することで、CH-3, CH-4 を用いて同じ試聴確認ができました。以下、 CH-5, CH-6、 CH-7, CH-8 についても、同様に試聴確認しました。
この確認実験により、マルチアンプ導入後のEKIOチャンデバ設定と DAC8PRO 8チャンネルによるマルチアンプ駆動を確実にシミュレーションでき、全帯域の同時試聴により、EKIOチャンデバを経由しても、位相やディレイを含めて、帯域分割を行わない設定と同様の非常に高品位な総合音響が得られることを確認することができました。
書込番号:23400396
![]() 1点
1点
>BOWSさん
> 出来ましたら、
>・DAC基板のヘッドホン端子(黒四角)と電源基板への接続端子が並んだあたりの拡大写真がほしいです。
>・ES9028PROの拡大写真のちょっと上の写真
> いずれも電源ICが搭載されていて どんなレギュレータを使っているか知りたいです。
再撮影するまでもなく、先日のオリジナル画像が十分に高解像度でしたので、拡大表示してトリミングしてみました。
他の部分の詳細もご希望でしたら、お知らせ下さい。
書込番号:23400916
![]() 1点
1点
BOWSさん
これで、影の部分でもチップの印字が読めますかね? 右のチップと同じ印字ですね。
書込番号:23400922
![]() 1点
1点
皆さん、
この資料;
http://linea-research.co.uk/wp-content/uploads/LR%20Download%20Assets/Tech%20Docs/CrossoverFilters%20White%20Paper%20-C.pdf
教科書的で基礎的ですが、私のような素人にとって、基本的な理解を得るのに最適なように感じております。
書込番号:23400959
![]() 1点
1点
dualazmakさん
写真ありがとうございます。
とっても参考になりました。
3.3V電源系は LTのローノイズレギュレータ使っていますね(けっこうお高い...)
要所、要所に配置していて 最近の潮流のpoint of load 配置に沿っていてクレバーだと思います。
ただ、OPAMPの電源が見当たりません。
おそらく基板裏の見えない位置にレギュレータが配置されていて スルーホール通して ±12V程度が8個の差動OPAMPに供給されるんだと思います。
書込番号:23401052
![]() 2点
2点
dualazmakさん
こんにちは。
毎日の御更新お疲れさまです。
再度(最初はARSにて)楽しく拝見させていただいております。
それにしましても、ASR は ASR の名称通り測定第一主義に徹しているように感じます。
測定ソフトウェアの一つである Acourate というのも大変強力そうに思えます。
https://www.audiovero.de/en/acourate.php
ASRメンバーの何人かはこのソフトについて良くご存知なのかも知れませんね。
それに対する手引書の一冊としましては
https://www.amazon.com/Accurate-Sound-Reproduction-Using-DSP-ebook/dp/B01FURPS40/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
また、それらの測定ソフトウェアの比較につきましては
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/mitch-barnetts-new-calibration-service.10212/
で言及されています。
最後に、以下のような測定サービスまで存在しているのですね。大変便利な時代になりました。
https://accuratesound.ca/
それでは、今後の御進展を楽しみにしております。
追伸: 当方、最近では Audiophiles 用の Network Switches (Switching Hub) にまで関心を持ち始めて、いろいろと調べています。Ethernet cables についてはほとんど調査は済んでいますが。
書込番号:23401459
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
こんばんは
ASRの何人かは、確かに「測定中毒」気味ですね。彼等は、音楽よりも音響に興味があるようです。
さて、例の Iddo Barshai のショパン マズルカ集が到着し、今、DAC8PROで聴きながら、これを書いています。
https://www.amazon.com/Chopin-Assorted-Mazurkas-Bar-Shai-Piano/dp/B001HBW31U
今晩は、CH-5, CH-6 で聴いています。
マズルカ集は、何枚かの名演を持っておりますが、Barshaiのアルバムも大いに気に入りました。録音品位も期待に違わず好感が持てます。全体を通してダイナミックレンジが広く、優れたピアノ録音だと思います。MIRAREレーベルのピアノ録音、気に入ってます。
Barshai は、弱音でのタッチ、演奏がとても綺麗ですね。その意味でも、このアルバムは、マルチアンプシステム完成後に、LC-ネットワークを通さないマルチチャンネルシステムで聴くことが楽しみです。マルチシステムの総合チェックにも好適なアルバムだと感じています。
それにしても、、、DAC8PRO は、予想を遙かに超えて、素晴らしいです!
OKTO社のPavelさんへも、完璧に動作している旨を伝えたところ、珍しく速攻で返信があり、喜んでおられました。ASRのスレッドは、見てくれているそうで、励ましのエールも、もらいました。
ASRスレッドにも書きましたが、DAC8PROは、ウォーミングアップをほとんど必要としない印象があります。起動直後から、ほぼ最高品位の再生が得られます。
書込番号:23401799
![]() 1点
1点
dualazmakさん
おはようございます。
ここ横浜も今日は湿度も低く快晴です。
>マズルカ集は、何枚かの名演を持っておりますが、Barshaiのアルバムも大いに気に入りました。録音品位も期待に違わず好感が持てます。全体を通してダイナミックレンジが広く、優れたピアノ録音だと思います。MIRAREレーベルのピアノ録音、気に入ってます。
ご感想をありがとうございます。優れた演奏・録音ということで未着ですが私も楽しみにしております。
>ASRスレッドにも書きましたが、DAC8PROは、ウォーミングアップをほとんど必要としない印象があります。起動直後から、ほぼ最高品位の再生が得られます。
常にスタンドバイモードになっているのでしょうか。ともかく常時臨戦態勢はユーザーにとりまして嬉しい配慮かと思います。
ということは、DAC8 Stereo も対しても大きな期待が持てそうですね。今後も Okto 社には目が離せませんね。
最後に、Mola-Mola DAC の評論記事が来月の中旬から下旬にかけて発行予定になっていますHIFICRITIC 誌(Apr - Jun 2020)に掲載予定であるとのことですのでそれを楽しみにしているところです。
それでは、また。
書込番号:23402512
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
>常にスタンドバイモードになっているのでしょうか。ともかく常時臨戦態勢はユーザーにとりまして嬉しい配慮かと思います。
いや、スタイバイモードの可能性もあるかもしれませんが、電源は一括On/Off の給電ラインから取っているので、電源供給直後にスイッチオンして、すぐに最高品位の再生になっているように感じます。
エージングは、必要なさそうですが、いずれにしても、全8チャンエルを、のんびりと、少なくとも48時間連続で、比較的大音量(ハイゲイン)設定で、慣らし運転、エージングしてみます。DAC8PROだけのエージングなら、アンプは電源OFFでも可能ですので。。。。
さて、もちろんご存知のことと思いますが、念のため。。。。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?pages/Audio_DAC_Performance_Index/
今のところ、やはり Mola Mola Tambaqui (USB/XLR) がトップランクのようですね。価格もトップですが・・・・
HIFICRITIC 誌の記事が出るころには、発注されるのでしょうか?
是非、入手されて、Naim ND555 enthusiastsさんの評価をお聞かせ下さい。。。期待しています!
私のマルチプロジェクトにおいて完璧なまでに理想的な8チャンネル実装の DAC8PRO の健闘は、驚異的ですね。コスパ的にも。。。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
OPPO SONICA DAC も、 amimir さんの測定と評価では、予想外に印象が良かったようで、わりに高位にランクされています。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/oppo-sonica-usb-dac-and-streamer-review.11845/
SONICA DAC利用のとシングルアンプ環境も温存しつつ、DAC8PROを使ってマルチ環境も構築できるのは、EKIOの利用も含めて、本当にタイムリーで、凄いことだと、あらためて感慨を深めております。
2月初旬、米国滞在中の EKIO と DAC8PRO の「遭遇」が、私のプロジェクトにとっては、まさに決定的に幸運でした。
書込番号:23403914
![]() 2点
2点
皆さん、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-402307
にて少し詳細に報告しておきましたが;
1.DAC8PRO の驚異の S/Nとリニアリティー、
2.EKIO の優れた高速内部処理(内部的には 64 bit floating で計算処理しているらしい)、
のお陰により、EKIOのチャンネルゲイン設定でアッテネーター設定(必要なら左右バランス設定も)を行わせることで、位相や S/N を含む総合的な音響品位に全く問題や劣化を与えないことを確認できました。
従って、DAC8PROのマスターボリュームだけを使い、DAC8PRO のチャンネル相対ゲイン設定は使う必要がない、というわけです。
相対ゲイン(アッテネーター)設定をDAC8PROにやらせる場合は、8チャンネル全てについて、その設定値を「記憶」しておいて、起動の都度、設定を確認する必要があるので、少し煩わしいかな、と思っていたのですが、EKIO の各設定ファイル(configuration ファイル)では、もちろんゲイン設定も保存できますので、やはり、EKIO にやらせる方が使いやすいと判断しています。
DAC8PRO の性能には驚くばかりですが、EKIO の余裕を保った高速処理性能と出力音響品位にも、あらためて畏怖の念を深めています。
書込番号:23410479
![]() 2点
2点
皆さん、
申し遅れましたが、ASRにて、「装置内部の拡大接写画像をフォーラムで共有するのは、様々な観点から、どうだろうか?」、との微妙な議論があったので、ここでも、ASRでも、DAC8PRO内部回路の詳細な接写拡大画像は撤去いたしました。
書込番号:23411780
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
前スレッド;
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/
の4月初旬あたり以降、特に5月9日の書込番号:23391893 あたりで、Naim ND555 enthusiastsさんからもお勧めいただいている
Apollon のNCMP8200;
https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/
および Apollon 社の設計&実装の評価などについて情報収集中です。
4月8日の書込番号:23327802と書込番号:23328401 のところでも書きましたが;
>Apollon製品とNord製品の内部比較、面白いですね。Apollonでは、SP端子へ行く配線が、
>+も、−も、同じ赤い配線で少し驚きです。組み付ける際に逆に配線するリスクはないのでしょうかね?
について、ずっと疑念が晴れなかったのですが、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/apollon-as1200-review-and-teardown.9373/post-245585
で、この記載を見つけました。
> @Apollon Audio used Neotech OCC wires, twisted from module to binding posts. They told me
>they deal with the red-red color using a multimeter to check which one is the phase.
>These wires are very rigid/solid and won't move from the position you see on pictures.
要するに、この赤−赤ケーブルは、厳選して選ばれた OCCケーブルで、厳密に位相を測定しながら正しく配線されており、しかも、このケーブルは、かなり固くて、容易に動いたり、振動しない、とのことです。しっかりと捻られていることにも、もちろんノイズ相殺などの理由があるのですね。
総合的に見て、Naim ND555 enthusiastsさんもご指摘の通り、 Nord ONE よりも Apollon NCMP8200 の方が、設計と実装のレベルが高い、また Appolon のユーザー対応とサービスレベルは業界最高だ、との記述も、随所で散見されました。
このあたりも、Burning Sounds さんが、自国の Nord ONE ではなく、Apollon NCMP8350 を選択した理由かも知れない、と推察しております。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/
書込番号:23412196
![]() 1点
1点
追加情報ですが、公開されている Apollon社製アンプの内部写真で見られる、随所に盛られている白い樹脂は、振動抑制/防止のための、固いセラッミック樹脂だそうです。
書込番号:23412249
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは。
Apollon Audio power amps に関してですが、Burning Sounds さんのスレッド
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/
において私に取りましては以下の2点(Burning Sounds さん投稿)が特に印象的でした。
#1: After considering several brands I settled on the Apollon Audio NCMP8350 as their amps appeared to have a tidy build and a good price. (I initially ordered the NC8200, but there was an issue with the Hypex NC252MP modules, so Apollon offered me a very good deal on the larger NCMP5308 which uses the NC502MP modules.
#13: Before I purchased the amp I asked Apollon for some pictures of the internal layout (there were none on their website at the time) as I was aware of potential issues regarding EMI and inrush current. Apollon were very responsive to my questions and their layout looked neat and tidy to me and was part of my decision to go ahead and purchase from them.
さて、客観的に見ますと dualazmakさんにとりまして EKIO/Okto DAC8 PRO との出会いは奇跡に近いものがあったかのように感じられます。
もし DAC8 PRO が存在していなければ、 Burning Sounds さんの装置投稿写真にみられるような Mytek 8CH DAC などに帰着するのであろうと思います。
また、EKIO がもし存在していなければ、もはや五里霧中の状況が現在でも続いていたやも知れません。
dualazmakさんにとりまして長い旅行が終わらんとしているように思えます。
もう一歩です。その結果を皆さん同様、私も楽しみにしております。
それでは、また。
追伸: Mola-Mola DAC に対する私の情報収集も残すところ HIFICRITIC April-June 2020 issue における評論記事 (Martin Colloms 執筆予定)のみとなりました。その記事内容を十分に吟味したのちに購入するかどうかの最終判断する予定でいます。
書込番号:23412550
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
おはようございます。
Naim ND555 enthusiastsさんが、ご指摘、ご賢察の通りでございます。
まず、Burning Soundsさんのスレッドですが、非常に参考になりますね。私も、隅から隅まで熟読いたしました。彼がこのスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/
を建てたのは、2018年の5月5日ですので、もう2年も前です。
Hypex 社や Apollon社は、その後、 Burning Soundsさんや、その他の ASRの常連達、および欧米各国のオーディオエンスーからの指摘や要望を受けて、多くの改良を加えてきていることも、各所で学びました。
それらを総合的に勘案すると、私のプロジェクト/システムには、Apollon のNCMP8200;
https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/
が、タイミング的にも、スペック的にも、また消費電力(突入電力も!)の面からも、最適かも知れないと、現時点では考えております。
もうすぐ ステレオ 2-way 4-channel の DENTEC DP-NC400-4 (Hypex NC-400 を2基搭載)
http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html
を2台、XLRバランス入力仕様で、無償で試聴させていただけることになりましたので、この経験も踏まえて、絶対に焦らずに、慎重にマルチチャンネルアンプの選考を進めたいと思います。
DENTEC DP-NC400-4 の電源部分は、かなりのヘビーデューティーに見えるので;
http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html
どんな音響再生になるのか、楽しみではあります。
でも、何しろ高価で、コストパーフォーマンス的には、大いに悩むところですね。
一方では、昨日の時点で、こんなこと;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hypex-ncore-vs-class-a-amps.9204/post-403169
を書き込む御仁もおられるので。。。。
ことアンプ群については、昨年末、大晦日時点の初心に戻って、まともな、XLR入力仕様の、クラスABの、(メンテナンス対応も考慮しつつ)国産の(!)、「プリメインアンプ」または「パワーアンプ」を、将来の使い回しや現システムでの定期循環交換(これも興味あり、均等にエージング?)も含めて、同じものを4台揃える、という選択肢も、全く放棄したわけではございません。(定期循環交換は、もちろん Apollon NCMP8200でも、ケーブル差し換えで、容易に可能ですが。。。)
>客観的に見ますと dualazmakさんにとりまして EKIO/Okto DAC8 PRO との出会いは奇跡に近いものが
>あったかのように感じられます。
先にも書きましたが、本当にその通りの「奇跡」でございます。
あの、2月初旬頃の、カリフォルニアでの「奇跡の数日間」、ですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
しかし、そこに辿り着けたのも、ここで、それまでに、情報交換および多くの貴重なご示唆を頂戴した皆様のおかげでございます。
>dualazmakさんにとりまして長い旅行が終わらんとしているように思えます。
最初にマルチチャンネル環境構築へ向けてスレ建てしたのが、年末の大晦日でしたので、長かったようでもあり、あっという間であったようにも、感じます。 しかし、約半年で、よくここまでたどり着けたものだと、感慨はひとしおでございます。
当方で「自前の」マルチアンプ群の導入も完了して完璧に「音楽」を堪能できるようになった頃に、双方の同一再生環境で Mola-Mola Tambaqui DAC と DAC8PRO の比較試聴などを、させていただける機会があれば、最高に楽しいだろうな、などと夢想し始めております。
まだまだ、慎重に「自前の」アンプ群を導入するまでは、しばらく「最初のゴール」までの「旅」は続きますので、引き続き、よろしくご指導、情報交換の程、お願い申し上げます。
書込番号:23413253
![]() 1点
1点
皆さん、
蛇足です、、、
自慢する意図は、全く、皆目、ないのですが、4月9日に建てた ASR の私のスレッド:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
への訪問&閲覧回数が、たった6週間にもかかわらず、約9,000回になっていて;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc
非常に驚いています。
参加して書き込んでくれる人達は、かなり限定されていて、数も多くはないのですが、これほど頻繁に閲覧があるということは、どなたかが激励してくれたように、マルチ環境を志す比較的初心者への、啓発的、教育的な価値や側面は、少々あるのかもしれません。
書込番号:23413272
![]() 1点
1点
訂正です。
誤)
>彼がこのスレッド;
>https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/
>を建てたのは、2018年の5月5日ですので、もう2年も前です。
正)
彼がこのスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/
を建てたのは、2018年の3月5日ですので、もう2年2ヵ月以上も前です。
書込番号:23413292
![]() 1点
1点
今、実際に試してみて確認できたのですが、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc
で表示される
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
の閲覧回数には、スレ主=私の頻繁なアクセス回数は含まれていないので、その意味では、非常にフェアな指標ですね。
ASRは、内容的には、どちらかというと「測定重視、測定オタク」的な側面が強いですが、フォーラムページの総合的な設計、柔軟性、サービスなどは、長年の変遷と経験を経て、非常に良くできていると感心しております。
書込番号:23413330
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんにちは。
>DENTEC DP-NC400-4 の電源部分は、かなりのヘビーデューティーに見えるので;
http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html
どんな音響再生になるのか、楽しみではあります。
でも、何しろ高価で、コストパーフォーマンス的には、大いに悩むところですね。
Hypex Ncore modules には Hypex SMPS (Switch Mode Power Supply) が最も似合うと私は考えておりますが、dualazmakさんによる Dentec 御試聴後にこの件については言及致したいと思います。
>当方で「自前の」マルチアンプ群の導入も完了して完璧に「音楽」を堪能できるようになった頃に、双方の同一再生環境で Mola-Mola Tambaqui DAC と DAC8PRO の比較試聴などを、させていただける機会があれば、最高に楽しいだろうな、などと夢想し始めております。
もし Mola-Mola DAC を購入致しました場合にはいつでも dualazmakさんにお貸し出来ますのでその時にはご遠慮なくお申し出下さい。幸いこの機器は大きさ・重さとも大型製品ではありませんのでその取り扱いが比較的楽かと思われます。
>ASRは、内容的には、どちらかというと「測定重視、測定オタク」的な側面が強いですが、フォーラムページの総合的な設計、柔軟性、サービスなどは、長年の変遷と経験を経て、非常に良くできていると感心しております。
ASRメンバーの中には投稿文の脚注にご自身の装置(機器名)を明記されている方もお見かけ致しますので
私に取りましてはそれが参考になる場合もございます。
ともかくASRにおけるスレッドは日に日に厖大化していますので、それらを追いかけるのが一苦労ですが、ASRは極めて面白いフォーラムの一つであることには間違いないとことに同感です。
それでは、また。
追伸: Stay at Home の毎日を余儀なくされておりますので、余り出費せずに音楽を聴こうという目的で
USB DAC/HPA dongles (AudioQuest DragonFly のようなもの)の中華製品を取り寄せてはそれらの聴き比べを細々と行っています。非常に良い機種が見出された暁には、USB DAC/HPA Dongles というテーマでこの価格コム掲示板においてスレを立ち上げようかとも思っておりますが、それの対するレスポンスは皆無に近いかも知れませんね。
書込番号:23413766
![]() 1点
1点
ualazmakさん
遅くなってしまいました。
>申し遅れましたが、ASRにて、「装置内部の拡大接写画像をフォーラムで共有するのは、様々な観点から、どうだろうか?」、との微妙な議論があったので、ここでも、ASRでも、DAC8PRO内部回路の詳細な接写拡大画像は撤去いたしました。
そういうことになりましたか、削除お疲れ様でした。
とても参考になりました。写真は脳みそにストレージしました。
私は ICE PowerやHypex は触ったことがありませんが、D級アンプを10台以上 自作したり、改造したりしています。
D級アンプは アンプユニット同志が スイッチング速度(300KHz以上)で相互に非同期で電源の奪い合いをします。(オシロで電源波形を確認しました。)
なので 1アンプユニットあたり1個の電源を与えて アンプユニット間の相互干渉を断ち切るのが高音質化の大きな手法です。
そういう点で 1アンプユニット/電源の構成のApollon も DENTEC も良いように思います。
ApollonがHypexのスイッチング電源に対して DENTEC はトランス電源を使っています。
僕は、Dに級アンプ作っていて スイッチング電源よりもトランス電源のほうが音質が良かったんで DENTEC のように トランスとコンデンサにエネルギー貯めてアンプに供給する方が親近感を覚えますね。
dualazmakさんがDENTECに対して どう評価を下すのか楽しみにしています。
書込番号:23414370
![]() 2点
2点
BOWSさん
詳細画像関係ですが、必要でしたら、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
のPM (パーソナルメール)機能で、BOWSさん名でご連絡下さい。 ASR Forum へのメンバー登録が必要かも知れませんが、、、
私のハンドル名 dualazmak をクリックして、「Start conversation」で、PMシステムに入れます。個人間で会話やファイルのやりとりができます。実名やメアドは、相互に開示する必要はありません。PM内では、日本語でも問題なさそうですし、PM内での日本語利用も試してみたいと思っております。
一方では、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/apollon-as1200-review-and-teardown.9373/post-245585
なんか、Apollon製品の内部接写画像をバンバン掲載しているので、私の例の詳細画像も「全く問題なしですよ!}という声も多数なんですが、「ちょっとどうかな?」という意見も聞かれたので、まずはOKTO社と Pavel さんに敬意を表して、詳細接写画像は撤去した次第です。
>1アンプユニットあたり1個の電源を与えて アンプユニット間の相互干渉を断ち切るのが高音質化の大きな手法です。
>そういう点で 1アンプユニット/電源の構成のApollon も DENTEC も良いように思います。
>ApollonがHypexのスイッチング電源に対して DENTEC はトランス電源を使っています。
>僕は、Dに級アンプ作っていて スイッチング電源よりもトランス電源のほうが音質が良かったんで
>DENTEC のように トランスとコンデンサにエネルギー貯めてアンプに供給する方が親近感を覚えますね。
はい、素人の私にも、薄々ですが、察しがつくようになってまいりました(笑)。
おそらく、Naim ND555 enthusiastsさんからも、その辺りをご指摘、ご指南いただけそうに感じております!
とは言っても、高価な新品DENTEC DP-NC400-4 2台(XLR仕様)を拝借中に Apollonと比較試聴するわけではないので、印象としても、ようやく本格的なマルチアンプ環境で、LC-ネットワークとアッテネータを介せずに、SPユニット群を直接各アンプで駆動し、音の鮮度に感激するだけだとは思いますが。。。
EKIO と DAC8PRO に畏怖の念を深める毎日ですが、、、、
YAMAHA NS-1000 の WO, Be-SQ, Be-TW の潜在能力と筐体設計やアラインメントにも、あらためて大いに驚かされるばかりです。これも、凄いことですね。
書込番号:23414609
![]() 2点
2点
日付は2017年9月ですが、この記事;
http://ybn-okayama.jugem.jp/?eid=153
では、Ucd-180 が使われていて、この方は(も)スイッチング電源とトランス電源を比較されたそうで、
「店のトランスを使ったUcD-180と比較して聞きましたが、個人的にはトランス電源の方が好みに近いようです。個人差があるので何とも言い難いですが、比較視聴が出来た良い機会でした。」
だそうです。
書込番号:23415105
![]() 1点
1点
この方(お店)は、こんなことも。。。
https://www.facebook.com/ybn.okayama/posts/489337378067281/
この巨大トランスは、DENTEC DP-NC400-4 のトランスと似ているように見えますね。
書込番号:23415110
![]() 1点
1点
皆さん、
いつもの愚痴になりますが、、、
このような記事を見ると、皆さんを含めて(!)、日本にもこの方面の知識と技術を備えた方々は、多々おられるように見受けますが、Nord社、Apollon社、そしてOKTO社の製品のような、世界の市場で受け入れられる「製品」が日本から登場しないのは、とても残念です。
国内市場だけでは、企業として利益が見込めないのは明らかなので、世界的な展開ができなければ「製品」としては成り立たないと思われますが、やはり、デザインも含めて国際的マーケティングのセンスや強い意思、自己ブランド確立志向、がなければ欧州勢には追いつけない。。。
どうして、こんな状況になってしまったのでしょうね?
書込番号:23415140
![]() 1点
1点
dualazmakさん
紹介いただきありがとうございます。
英語を読むのに時間がかかるので 余裕のある時に眺めてみます。
トランス電源とスイッチング電源の音の比較ですが、僕が空気録音した結果をYoutubeに挙げています。
https://www.youtube.com/watch?v=0hilfC0oKqc&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=R0SipCDoe4s&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=bLvulZnmFoU&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=6VQCjQC2bmY
この頃は動画の編集が下手で 画面おかしいですが御容赦ください。
もっと容量の大きなスイッチング電源も試しましたが、雑味が多い印象だったので 改造する気も起こりませんでした。
スイッチング電源を極めるために 1次側の整流とかスイッチング速度などをチューニングすると 良くなる可能性があるのは承知していますが、そこまでやっていません。同じ時間と費用かけるなら トランスのほうが楽そうだったので トランスの容量、整流ダイオード、コンデンサをアップグレードしていきました。
この後、コンデンサを1Lの牛乳パック程度の巨大なサイズのに変えて ステレオと左右独立を比較した動画がこれです。
https://www.youtube.com/watch?v=X5FcrgYKvME&t=379s
https://www.youtube.com/watch?v=UjFOUyEV0E0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=AqMoTr-yn_w&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=yUHo2QP4xY4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_4SnifZ4jds&t=200s
左右独立させて 電源が2倍になると 静けさと立ち上がりがかなり違いました。
最終的には 600Wの電源になりましたが、実際には30Wくらいしかアンプに流れていないので 壮大な無駄遣いです。
今までの経験上、部品のサイズは大きく重い方が音が良いです。
書込番号:23415263
![]() 2点
2点
BOWSさん
ありがとうございます!
これらの YouTube リンク、たしか以前(1月だった?)にも頂戴していたように思いますが、あらためて拝聴させていただいております。
私の場合、8チャンネルのマルチアンプが必要ですので、起動時の突入電流や常用時の消費電力も、重要な要素ですね。その辺りも慎重に考慮すると、やはり手慣れていて経験豊富な、Nord社や Apoloon社の製品が無難なのかも知れません。
そうそう、1月〜2月あたりの「クラスABのプリメインアンプ4台利用」への拘りには、その要素(消費電力面)もあったのでした。
もちろん、DENTEC DP-NC400-4の音響品位にも大いに期待しているので、到着時には消費電力面もよく伺っておきます。何しろ2台必要ですので。。。
書込番号:23415341
![]() 1点
1点
そういえば、TEAC の AP-505 も、Hypex特別仕様NCoreモジュール採用で、電源はトロイダルトランスですね。
https://teac.jp/downloads/catalogs/teac_audio/ebrochure_ap-505_201906.pdf
そして、
https://www.phileweb.com/review/article/201906/10/3426_2.html
では、
>こうしたクラスDアンプは、増幅方式ではPWM変調器を使用してパルス波を生成、MOS-FETを使って最終増幅され、ローパスフィルターを通過して出力される。一時はデジタルアンプと呼ばれることもあったが、この方式は純然たるアナログアンプなのである。その音質も、10年ほど前とは比較にならないほど高音質となり、例えばAB級アンプと音質で区別することは、もはや困難になっていると言えるであろう。
>AP-505はこの出力段のみならず、入力段も魅力的である。信号が持つ音楽情報を鮮度高く伝送する高音質オペアンプ「MUSES 8820E」を、RCA/XLRの両入力に採用。XLRバランスでは、音の鮮度を失わないようにカップリングコンデンサーを排除している。この入力段の電源も実に高品位で、左右の整流回路を大型トロイダルトランスの出口から完全に分離し、4,700μFの大容量コンデンサーを左右に各4式(左右合計8式)搭載した。これにより理想的な平滑回路を実現し、左右のセパレーション向上を図っているのである。
と紹介されていました。これ、年始に何度も、何度も、読んだ記憶があります。
予算的に許容ならですが、後々の修理やメンテナンス対応なども考えると、AP-505 を4台、という選択肢も、あり得るかもしれない。。。 とも考えております。
おそらく、パワー的には、私のシステムには十分かと思いますし、コンパクトで4台導入しても、巨大にはならない点も、魅力的ではあります。
書込番号:23415389
![]() 1点
1点
皆さん、
ちょっと嬉しくて、、、書かせていただきます。
先ほど、私の ASRスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
のPM (personal mail) システムで、この分野では多大な貢献をされている、あの Mitch Barnett さん;
https://www.amazon.com/dp/B01FURPS40/#customerReviews
から、非常に丁重な励ましの連絡をもらいました。
「非常に楽しく、興味深く、毎日、見てます。 頑張って下さい。」、とのこと。
このリンクも知らせてくれました。
http://www.acourate.com/freedownload/XOWhitePaper.pdf
まあ、暗に「もっと勉強しろ!」という叱咤激励かも知れません。
測定や最適化のサービス事業も手がけている;
https://accuratesound.ca/
Mitchさんからは、「売り込み」的な内容は全くなかったのですが、EKIOを十分に使いこなしてから、Acourate も使ってみるのも、面白いかな、と思い始めています。 これこそ、「泥沼」になるかもしれませんね。
もちろん、EKIO の高貴なまでに簡潔な機能と優れた音質も、非常に高く評価しております。
当面は、EKIO + DAC8PRO + Multi-channel Amplifier(s) を、step-by-step で、楽しみながら完成させることに、まずは集中します。
書込番号:23418441
![]() 2点
2点
dualazmakさん
こんばんは。
Mitch さんは室内音響のプロですので、dualazmakさんと Mitch さんとの今後のコミュニュケーションが非常に楽しみですね。
そうそう、Mitch さんと言えば、Kii Three の評論記事も書かれております:
https://audiophilestyle.com/ca/reviews/kii-three-loudspeaker-review-r735/
それでは、また。
追伸: Ncore 発明者である Bruno Putzeys 氏のインタービュー記事などを再び読解中です。
彼はいわゆる天才の一人ですのでそれらの記事の内容もずっしリと重みがあって私には読解(特に技術に関する内容)が難解ですが、今月中には何とか読み終える予定です。
書込番号:23418660
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
先ほども ASR のPMで、Mitch Barnett さんと、追加の情報交換をさせていただいておりましたが、この資料;
http://www.acourate.com/freedownload/XOWhitePaper.pdf
も勉強しています、と彼に伝えたところ、意外にも、ご存じなかったようで、「おお、これは素晴らしい解説です。知りませんでした。今後、他の皆さんにも勧めます。そういえば、dualazmakさんのポストでも、紹介してくれてましたね!」、と仰せでした。
この資料、クロスオーバーの理解を深めるのに最適で、よくできています。
Butterworth (BW)、Bessel、Linkwitz-Riley (LR)、Hardman、Linear Phase (LIR) の各フィルタタイプの違いや特徴、特に位相問題、を理解するのに、大いに役立ちます。
もっとも、この資料を書いている Paul Williamsさんは、Linea Research 社の人のようですので、最後の方では、恐らく該社の特許技術である、主に産業用の Linear Phase-LIR (linear Impulse Response) フィルターの礼賛になっていますが。。。。
私は、たまたまネット検索で見つけて、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-396364
と、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-401168
で紹介しておりました。
さて、、、皆さんは(も)、Mitchiさんの有名な、これ;
https://www.amazon.com/dp/B01FURPS40/#customerReviews
は、既にご存知かと思いますが、念のためにお知らせします。
書込番号:23420377
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんばんは。
例の書籍はアマゾン日本からでも購入可能です:
https://www.amazon.co.jp/Accurate-Sound-Reproduction-Using-English-ebook/dp/B01FURPS40/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1590152390&sr=8-1
それでは、また。
書込番号:23420452
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、
>例の書籍はアマゾン日本からでも購入可能です:
ありがとうございます。はい、承知しております。ASRでは、敢えて米国アマゾンの当該ページを紹介させていただきました。
皆さん、
ASRの私のスレッドで、この投稿;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-407794
と、それ以降で、オーディオ クロスオーバー(チャンネルデバイダー)の基礎を理解するのに最適な公開情報や書籍へのリンクを共有し始めております。ご興味がおありでしたら、ご覧下さい。
また、皆様からも、この趣旨に沿って、有用なリンクを、ここか、ASRのスレッドで頂戴できれば幸いです。
ここで頂戴できれば、英語の資料でしたら、ASRスレッドでも共有させていただきます。
書込番号:23421302
![]() 1点
1点
皆さん、
ASRの;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-411328
でも共有しましたが、ソフトウェアチャンデバ(クロスオーバー) EKIO の内部処理は;
"EKIO uses IIR filters. The processing is done using a cascade of second order transposed direct form II biquad sections. Every calculation is done using 64 bit floating point numbers."
だそうです。
EKIO の内部処理が、FIR なのか、IIRなのか、ずっと頭に引っかかっていたのですが、昨日、開発者の Gillaumeさんに確認したところ、上記の回答がありました。
FIR と IIR の比較については、検索すると多くの情報がヒットしますが、この分野に詳しくない私には、完全な理解は困難です。
それでも、特長や「適しているケース」については、ここ:
http://www.allisone.co.jp/html/Notes/DSP/Filter/Digital/FIR-IIR/index.html
などが参考にはなります。
ソフトウエアの実装と実行面では;
>IIR は極と零点を組み合わせてフィルタを実現するため自由度が高く、零点だけ*で特性を実現せねばならない FIR に比べて、遥かに少ないメモリと演算量で所望特性を実現できることが多いです。
(中略)
>このため、高速性が必要な場合や演算量を抑えたい場合は、IIR での実現を考えた方がよいでしょう。
>
>FIR はインパルス応答全体が入るだけの係数メモリと遅延メモリを必要とし、 演算量もインパルス応答の長さ(サンプル数)に比例しますので、 インパルス応答が長いと IIR に比べて不利になります。
>【注意】インパルス応答全体が入らないからといって、単純に「尻尾」を切り捨てると、周波数特性が (たぶん無視できないほど) 劣化してしまいます。
>ただし IIR の設計実装は FIR より難しく、安定性判別やノイズ(S/N)の推定には、それなりの知識を必要とします。
だそうです。
EKIOは、その簡潔性、優れたGUI、チャンネル数制限なし、高速で軽いCPU処理、そして何よりも非常に優れた総合音質(位相特性も含めて)、などの観点から非常に高く評価しておりますが、内部処理の詳細については公開されておりません。
どうやら、 LUPISOFT社の Guillaume さんは、非常に優れた音響&電子技術者で、さらに優秀なプログラマー兼ソフトウェアデザイナーであると再認識させられております。
フランスには、時々天才的な数学者が現れますが、少しその香りが。。。
書込番号:23427915
![]() 1点
1点
こんなページも。。。
http://www.differencebetween.net/science/difference-between-iir-and-fir-filters
このページ;
https://www.advsolned.com/difference-between-iir-and-fir-filters-a-practical-design-guide/
の、"Advantages, Disadvantages" は、分かりやすいですね。
特に;「IIR はアナログフィルターを模倣するのには適している!」 そうです。
また、添付画像の部分が、LUPISOFT の Guillaume さんの情報に、ピッタリの部分ですね。
書込番号:23428067
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんにちは。
Acourate by AudioVero (Germany)
https://www.audiovero.de/en/acourate.php
宛に EKIO についての所感などをお問い合わせをされたらいかがでしょうか?
第三者的に見ますと EKIO & Acourate softwares を両立させて今後は完璧化を図られるといかがとは思いますが。
それでは、また。
追伸: 極(poles)や零点(zeros) は複素関数論では学部2,3年次に習得します。極は特異点の一種ですが極の近傍では現象的に関数の行動は穏やかですが、真性特異点ですとその近傍では現象的にただならぬことが生じます。
なお、フランスには天才数学者がいますがドイツにもそれに負けず劣らずの天才数学者がいます。
書込番号:23428076
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
こんばんは。
>第三者的に見ますと EKIO & Acourate softwares を両立させて今後は完璧化を図られるといかがとは思いますが。
Mitch さんからも、その方向を示唆されております。EKIOで、まず完成させてから、次を考えましょう!
閑話休題。。。
>なお、フランスには天才数学者がいますがドイツにもそれに負けず劣らずの天才数学者がいます。
実は、私は(も?)、数学史のファンでして、「リーマン予想」や「フェルマーの最終定理」、「ゴールドバッハ予想」などの、どちらかというと数論関係の書物(といっても非専門の啓発書物)をよく読んでおり、ドイツの歴史上の著名数学者も名前と主な業績は、そこそこ知っています。戦前のゲッティンゲンの黄金時代、凄かったのですね。
最近、何度目かで読み直して、ハマっているのは;
「素数に憑かれた人たち リーマン予想への挑戦」
https://www.amazon.co.jp/%E7%B4%A0%E6%95%B0%E3%81%AB%E6%86%91%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%9F%E3%81%A1-%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E4%BA%88%E6%83%B3%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6-John-Derbyshire/dp/482228204X/ref=tmm_hrd_title_0?_encoding=UTF8&qid=1590485936&sr=8-1
だったりします。
グロタンディーク、ヴェイユ、コンヌ達の功績や人生も、面白いですね。
そういえば、京都大学望月新一教授の、超難解な宇宙際タイヒミュラー理論を用いた ABC予想は、最近、正しい証明として認知されたらしいですね。
https://www.47news.jp/news/4844193.html
査読に7年半かかったそうですが、その査読の正否を理解で来る人も、ほとんどいないそうで、、、
さて、ASRの例のスレッド、4月9日のスタートからの閲覧回数が、なんと1万回を超えました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc
ちょっと、怖くなってきました。。。 マルチアンプをいくつか試してその様子を共有してから、スレッド収束の方向性を考えたいと思います。
まあ、あの DAC8PROのレビュースレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
のように、どこかの時点で、放置モードに入ってもいいのかもしれませんが。。。
書込番号:23428444
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんにちは。
ここ横浜では午後になってやっと晴れて来ました。
本日も遅い朝食前に散歩に出かけて、軽くドイツビール(Jever)と英国ビール(Samuel Smith)を引っ掛けてから今日の作業に入っています。
さて、率直に申し上げて、ASR においての収穫はさほど多くは無いように思われますがいかがでしょうか。
(私は USB DAC/HPA dongles について ASR を徘徊致しておりますが収穫はそれらの内部画像写真のみです。皆さんの posts の大概の内容は信頼性に欠けており殆ど参考にはなりません。)
本格的とも言えそうなステレオマルチアンプシステムに関しましては、やはり Linkwitz Lab のウェブサイトがかなり参考になるような気がします(斜め読みですが)。
http://www.linkwitzlab.com/index.htm
http://www.linkwitzlab.com/frontiers.htm#I
ASR も大衆酒場の装いがあってそれはそれで良いのですが純粋なオーディオ探究者にとりましては一つの階段に過ぎないような気がします。
それでは、また。
書込番号:23430013
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
ありがとうございます。
ASR Forum で、例の方が、EKIO が IIR filter なら、理論的には post-ringing (post-echo) の可能性がある、と仰せでしたので、先ほど、少し検証して ASR のスレッドで共有しておきました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-412672
幸いにして、私の、かなり鋭敏な(?)テスト環境では、EKIO による post-ringing, pre-ringing は、全く聞こえませんでしたし、EKIOや E-460 のピーク(VU)メーターでも見られませんでした。
このあたりも含めて、EKIO の内部処理は、かなり高度に、うまく、設計されていて、可能性があるとしても post-ringing や pre-ringing をうまく排除しているか、可聴レベル以下に押さえ込んでいるように思います。
さて、ASR の全体的な感想ですが、少しずつ Naim ND555 enthusiastsさんのご感想に近づきつつございます。もちろん、私は、ステレオマルチアンプシステムの初心者で、「本格的」なレベルには遙かにほど遠い、と思ってはおります。
Burning Soundsさんからも、 Linkwitz Lab のウェブサイトを勧められており、それ以前からも、私も、ちょくちょく眺めております。やはり、本格的で、レベルが高く、信頼に値する、と思いますし、なによりも、勉強になりますね。
もっと突っ込んで「オーディオ探究者」になりたいと思う反面、なるべく早々に一旦完成させて、「音楽探究者」に戻りたい、とも強く思う、今日この頃です。
Iddo Barshai の3枚セット、来ましたか? 私的には、やはり、ピアノ演奏録音がほとんど存在しない「クープラン曲集」が、ユニークですが、とてもお気に入りです。
書込番号:23430824
![]() 1点
1点
dualazmakさん
>Iddo Barshai の3枚セット、来ましたか? 私的には、やはり、ピアノ演奏録音がほとんど存在しない「クープラン曲集」が、ユニークですが、とてもお気に入りです。
HMV Japan (HMV&BOOKS) 経由で注文中なのですが入荷未定であるという案内が3日前に届きました。
私も出来るだけ早く聴きたいと首を長くしているのですが...
それから、Linkwitz Lab に Link されているフォーラム (OPLUG Forum) において
'ekio' および 'Acourate' として検索しましたら以下のようでした。
Linkwitz Lab > OPLUG Forum
https://oplug-support.org/
Search: ekio (1件)
https://oplug-support.org/search.php?keywords=ekio
Search :Acourate (28件)
https://oplug-support.org/search.php?keywords=Acourate
それでは、また。
書込番号:23431283
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
今日は、とある事情で在宅していて、のんびりと、久々の5月のそよ風を楽しみながら、これを書いています。
メンデスルゾーンの無言歌集の「5月のそよ風」を思いながら、、、昔、弾いていました。
確かに、EKIO の利用や評価の報告は、ほとんど見られないのです。私も、散々サーチしましたが。。。
先ほど、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-413303
にも書きましたが、
LUPISOFT の Guillaume さんは、なんだか「孤高の存在」のように感じられます。
音楽が好きで、クロスオーバーソフトも、自分で「ちょこっと」作ったが、簡潔性と音質だけで勝負で、内部処理についてざまざまな議論に加わる意思は皆無、大々的なマーケティングの意思も皆無、「少しお小遣い稼ぎになれば、それでいいや!?」 とのGuillaumeさんの方針と姿勢への共感を強くしています。
この方面では初心者の私は、とにかく簡潔無比で高度に完成されたGUI設計と、なによりも優れた音質に「一目惚れ」して使い始め、ASRでも、ここでも、EKIO の伝道師的な役目を厭いませんが、ASR の御仁のように、内部構造や測定評価に拘る面々には、得体の知れない EKIO は、許せない存在なのかも知れませんね。
IIR かFIRか、linear phase か minimum phase か、などなどの、内部処理の技術論は、確かに泥沼でキリがないので、Guillaumeさんは、そこへ引きずり出されることを意図的に、敢えて避けているのだと理解できるようになってきました。
シンプル イズ ベスト で、EKIO の IIR 12 dB/OCTのLRフィルターによるクロスオーバーで、期待している優れた音響改善が得られるなら、当面は、それ以上のクロスオーバー沼には、足を踏み入れない覚悟を固めようかと思案中です。
それほどまでに、EKIO の総合音質は、素晴らしいのです!
とにかく、私の既存環境のマルチ化と私の耳には、EKIOは、現在のところ、必要十分で、最適であると感じており、その意味でも、ASR の例のスレッドで、どこまで共有と情報交換を継続すべきか、悩み始めています。
1つの「潮時」 は、6月末に DENTEC DP-NC400-4 (XLR inputs) 2台をお借りして、その様子を報告、共有した頃かも知れません。
その後は、暫く放置モードへの移行を宣言しておく、のもいいかも? と思います。
その後、Apollon製品を手配するとしても、入手までには、マレーシアの Hypexモジュール製造工場の状況も絡んで、時間がかかりそうですので。。。
書込番号:23432004
![]() 2点
2点
そうそう、DIYAudio Forum では、2016年2月に、Guillaumeさん自らが EKIO のリリースを紹介されておられました。
このスレッドです。
https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/272975-ekio-digital-loudspeaker-crossover-software.html
2月に購入した EKIO は、ver 1.0.6.0 ですので、2019年にマイナーバージョンアップされたものだと思います。
添付画像のクレジットに、Version 1.0.6.0 Copyright 2015-2019 Lupisoft と書かれていますので。。。
頻繁なバージョンアップはなさそうですし、既にシンプルな機能と音質は、高度に完成されているように思います。
DIYAudio で"EKIO"で検索すると、私のものを含めて、9件だけ、ヒットします。
https://www.diyaudio.com/forums/search.php?searchid=22827802
検索結果、添付画像でも、貼っておきます。
書込番号:23432031
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんにちは
EKIOよさそうですね、使い勝手を教えて頂けませんか。PC電源を入れれば、WIN操作なしでDAC8とつながり、家電のように機能するのでしょうか?
EKIOは2台のDAC8を16chとしてコントロールできますでしょうか?
書込番号:23436120 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
あいによしさん
こんばんは、お久しぶりです。
昨年末の大晦日から皆さんの多大なご支援をいただき、第1ゴール目前まで到達しました。
まずは、心からの御礼を申し上げます。
ここと、ASR の私のスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
で情報交換を継続しておりますので、引き続き、よろしく!
このASRスレッド、4月9日に建ててから、何と既に1万1千回以上の訪問閲覧があり、非常に驚いております。
訪問閲回数は、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc
で確認できます。
さて、驚異的な性能と音質の DAC8PRO;
https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
はもちろんですが、
EKIO の予想を超えた性能と音質にも、非常に驚いております。
EKIOは、使い勝手も、機能も、音質も、非常に素晴らしいと感じております。
>PC電源を入れれば、WIN操作なしでDAC8とつながり、家電のように機能するのでしょうか?
もちろん!
一旦、ASIO4ALL と専用ASIOドライバーによる I/Oが確立でき、お好みのクロスオーバー(チャンデバ)設定が作成できれば(何種類でも別名で保存できます)、Windows 10 の起動後に自動的に EKIOが立ち上がり、指定したクロスオーバー構成ファイルを自動読み込み、そして自動で演奏状態になり(秒単位で演奏開始の遅延も可能)、EKIO設定画面は最小化されてタスクバーにアイコン表示のみ、という設定が、非常に簡単に可能です。
>EKIOは2台のDAC8を16chとしてコントロールできますでしょうか?
EKIO は、入力チャンネル数も、出力チャンネル数も、無制限ですので、ASIOドライバーまたは Windows WDM が16チャンネルを認識さえすれば、EKIOから16チャンネルへの 192 kHz 24 bit でのUSB出力が可能です。
念のため、DAC8PROを2台繋いだ際に、DAC8PROに添付されている専用 DIYHNK ASIO USBドライバーと WDMが、16チャンネルをきちんと認識するかどうか、このポスト;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-415386
でOKTO社とDAC8PRO利用中の仲間(何人かは、既に2台持っている!)に確認しています。
回答があり次第、ここでお知らせします。
書込番号:23436848
![]() 2点
2点
あいによしさん
EKIOから複数の DACへのASIOドライバー およびWDMドライバー出力については、私も、DAC8PRO、OPPO SONICA DAC、 ONKYO DAC-1000S の3台を、同時に3本の USBケーブルで USB 2.0 ポートに繋いで、合計12チャンネルへEKIOから同時に問題なく流せることを徹底的に確認済みです。ASIOでも、WDMでも、どちらでも可能です。
これ(複数のDACへのEKIOからの入力)を、ASRフォーラムで紹介すると、、必ず、「理論的には、しばらく鳴らしていると DAC間での同期のずれが発生するので、DAC間でシンクロさせる仕組みがない限り、それな完全に邪道だ!」、とがなり立てる輩(やから)が登場するので、ASRでは紹介していませんが、それぞれの ASIOドラーバーのバッファサイズを大きめの値で統一し(ASIO設定では 2048, EKIO設定では 5120)、In/Out のLatency Compesation も 512 に統一しておけば、私の実験では、数時間の連続運転でも、同期のずれが発生することはありません。 詳細設定については、EKIOを導入されたら、お手伝いできます。
このあたり、EKIO の音響処理は 192 kHz 24 bit ではありますが、内部的には、64 bit浮動小数点で非常に高速な演算を行っており、12チャンネル同時の少し複雑なチャンデバ処理でも、CPU処理的には軽々の余裕余裕ですし、出力は 192 kHz 24 bit ですので、最近の DACでは、これまた余裕余裕で「信号が来たらバッファには溜めずにリアルタイムでDAC処理!」ですので、懸念されているようなDAC間での同期のずれは、ほとんど発生しない、と見ています。また、詳細は不明ですが、EKIOは、かなり頻繁に、同期信号の初期化を自動的に行っているように見えます。
8チャンネルのマルチチャンネルパワーアンプ、またはモノラルパワーアンプ8台、またはステレオパワーアンプ4台、を決めて繋げば、私のプロジェクトの第1ゴールは達成! となりますので、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-409752
で写真でも紹介しいるように、物理的な配線も、完璧に準備完了しております。
6月末に、あの高級な DENTEC DP-NC400-4 (XLR inputs)
http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html
を2台、無料で試用させていただくことが決まっており、楽しみにしております。
その後、DENTEC DP-NC400-4や Nord ONE, Apollon NCMP8200 などを含めて、マルチアンプの最終決定に進みます。
一方、いまだに、優れた、好みの、プリメインアンプを4台導入する選択肢も、完全には放棄しておりません!
欧米でも、「DAC8PROを使っているが、自分はパワーアンプとの間に好みのソリッドステートプリアンプや球管プリアンプを入れている音の方が好きだし安心して長時間聴ける。」、と仰せの非常に熟練&老練なオーディフリークも、何人かおられますので。。。。 このあたりは、やはりSP群の特性や性能とも相まって、最終的には好みの問題、ですね。
アンプ選びは、いろいろ(できれば無料イタメシ、おっとタイプミス、無料お試し、や、安価なレンタル、で)試しつつ、じっくりと楽しみたいと思っております。
もしEKIO をお使いになるなら(是非、仲間になってください!)、導入時のI/O確立などで少々難儀される場合には、いつでもヘルプさせていただきますので、ご安心ください。
そうそう、EKIOへの I/O確立の詳細は、英語ですが、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-369800
で画像もたくさん使って、わかりやすく紹介しております。
一旦、適切に確立できれば、その後は非常に安定しております。何日間も連続で鳴らしても、一切、問題は発生しません。
AnyDesk などのセキュアな遠隔操作ソフトを仕込んでいただき、ラインか何かでAnyDeskアドレスと一時PWをご連絡ただければ、あいによしさんの立ち会いの下で、ライントークでお話しながら、私がそちらのPCを遠隔操作してご支援することも、簡単にできますよ。
あと、余談ですが、DAC8PRO には、AES/EBUのXLRプラグのデジタルステレオ出力があり、ここにはチャンネル1&2のデジタル信号が常時出力されていますので、AES/EBUデジタル入力端子がある 192 kHz 24 bit 対応のステレオDACへは、ここからも繋ぐことができます。あくまで、チャンネル1&2のスルー同時出力ですが。 これも、ONKYO DAC-1000S には、XLRプラグの AES/EBU入力端子があるので、実機で検証済みです。
書込番号:23436850
![]() 2点
2点
もうひとつ、重要(!)な情報です。
最近、ここで;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-408327
OKTO社の Pavel さんが、「DAC8PROは、いまは受注を抱えて生産に追われているが、一段落して、少し在庫を持てるようになったら、少々価格を高めに改訂するかもしれません。」、と仰せでした。
最近、ハード的にも、ソフト的にも改善(ファーム ver.1.32)されて性能アップとブラッシュアップが行われ、私のDAC8PROも、もちろん、この最新バージョンです。
購入を考えられるなら、値上げ前のご発注をお勧めします!
書込番号:23436975
![]() 2点
2点
EKIO を使われるのでしたら、Windows 10 は、今では当たり前ですが、必ず 64 bit 板を使い、メモリは最低でも、16 GB 以上載せてください。やはり、Windows 10 PRO 64 bit をお勧めします。
その他、CPUの性能レベル、SSD などについては、それほど高級なものは全く必要ありません。必要でしたら、私のオーディオ専用自作PCの詳細など、お知らせします。
マザボ直結の USB 2.0ポート(または 3.0 でもOKですが、私は敢えて音響関係では安定感のある USB 2.0 で DACを接続、DACメーカーによっては、USB 3.0 よりも USB 2.0 を推奨)は、もちろん複数必要です。
外付けのUSBハブを経由したDACの接続は、ほとんどのDACメーカーが、OKTO社 DAC8PROを含めて、「それはダメです!」、と言っております。
書込番号:23437061
![]() 1点
1点
あいによしさん、皆さん、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-415936
で、こんな投稿がありました。日本語に訳すと;
>プロフェッショナルはおそらく、「適切な」ASIOサポート、低レイテンシドライバーなど、
>ワークステーションで必要なものをすべて備えたProインターフェイスでAES入力を
>使用します。AES入力を使用する場合、クロックはとにかくAES信号から生成されるため、
>個別の同期入力は必要ありません。
全ての民生用DAC、たとえば私が所有している ONKYO DAC-1000S でも、AES/EBU入力があるので、ここへ DAC8PRO のAES/EBU出力(=チャンネル1&2のスルーデジタル信号)、を入力した場合には、DAC-1000S は自分のクロックは使用せずに、AES信号からクロックを生成するので、原理的には、DAC8PROと DAC-1000S の間でクロック=同期のずれは発生しない、と解釈していいのでしょうかね?
もちろん、DAC8PROのチャンネル1&2も、そのスルー信号をAES経由で受信する DAC-1000S も、受信後に、それぞれでDA変換するので、それぞれのDA変換過程で同期がずれる可能性があることは理解できます。
私が想定しているのは、サブウーファー YST-SW1000 への入力を、WOのSPレベルからの分岐ではなく、できれば RCAラインレベルでの入力にしたいので、そのためだけに DAC-1000S または OPPO SONICA DAC (こちらは XLR端子ではなく同軸デジタル入力)
を使うというオプションです。 上記の DAC8PROのAESから取る場合には、いずれにしてもウーファー帯域との共通で、YST-SW1000内部のハイカットフィルターでハイカットすることにはなるのですが。。。。
一方、源流のEKIOで、DAC8PRO に加えて DS-1000S または SONICA DAC を認識させて使う場合は、もちろん完全にサブウーファー帯域とウーファー帯域を分けることが可能です。
書込番号:23438079
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
電源ONで家電と同じなら、うちでも使えそうです、ご回答ありがとうございます。
EKIOを試したのですが、ハンドシェイクがうまくいかず音がブチブチ異音も聞こえます。
考えられる原因はありますでしょうか?
>USB (asynchronous, UAC2.0 compliant) 8-channel I/O, up to 384 kHz / 32 bit, 4xDSD (DSD512) or DoP128
>4x AES/EBU (resampling-free, up to 384 kHz / 24-bit)
>を満たす特別仕様DAC8PROの製造提供が可能かどうかを OKTO社へ問い合わせております。
入手されたのはカスタム品でしょうか?
購入は書込番号:23225991の通り、支払いはクレジットでしょうか?
書込番号:23439470
![]() 1点
1点
あいによしさん
ご心配ご無用です。
私も、最初は、ルーティング、ハンドシェイクで、少し悩みましたが、全体を理解できるときちんと設定できます!
ASIOを含めて、音響関係のドライバ類がたくさんあっても、全く問題ありません。
今晩21時頃にでも、すこしチャット的にヘルプさせていただけますが、如何ですか?
すべて、192 kHz 24 bit に統一することも、重要なキモですよ。
いま、ざっと見て気付いたところをお知らせします。
まず、昨晩の設定では、音楽はどこから鳴らされていますか?
例えば、ブラウザのYouTubeですか?
それとも、JRiver などのソフトですか?
ブラウザなどでは、 Windows の WDM ドライバを使いますし、
JRiverなどからでしたら、Windows の WDMやカーネルミキサーは全てスルーして ASIO4ALL経由の全て ASIOでならせます。
貼っていただいた画像からだけ、ご指摘しますと、
EKIO の Sampling Rate は、192000 に設定、 Driver はASIO4ALL v2を選択して、buffer size は5120 に、
ASIO4ALLパネルで、ASIO Buffer Size を最大の 2048 に、Latency は、In、 Out 両方とも 512 に設定して下さい。
ASIO4ALL パネルで、VB-Audio Hi-Fi Cable In だけを指定して、
その後、EKIOの Driverで None(なし)を選択し、それから再度 ASIO4ALL を選択して認識、反映させます。
これ、EKIO用のASIO4ALLパネルの設定を触った後は、いつも、「一度 EKIOの Driverで None(なし)を選択し、それから再度 ASIO4ALL を選択して認識、反映させる!」、が1つのキモです。
それから、全て 192 kHz 24 bit に設定! ですよ。
JRiver から ASIO4ALL または VB-AUDIO Hi-Fi Cable へ出力なら、 JRiver の DSP設定で、全てを 192 kHz 24 bit に統一する必要があります。
そして、JRverから ASIO4ALL への出力では、のもう一つの JRiver 用のASIO4ALLパネルがタスクバーに現れますので、そこで VB-AUDIO Hi-Fi Cable OUTへのルーティングのみを設定します。
ブラウザなどからVB-AUDIO Hi-Fi Cable へ出力なら、Windows の既定のスピーカーを VB-AUDIO Hi-Fi Cable にしてから、サウンド設定で VB-AUDIO Hi-Fi Cable を正しく 192 kHz 24 bit 構成にしてやる必要があります。
では、今晩、21時頃、よろしければ、ここでお知らせ下さい。
私が購入した DAC8PRO は、通常製品です! それで、完璧ですので、ご安心下さい。
支払は、単純にクレジットです。 FedEx 航空貨物で届きます。
かなり受注を抱えているようなので、1,2ヵ月待たされるかも知れませんが、値上げ前に発注されることをお勧めします!
書込番号:23439838
![]() 1点
1点
あいによしさん
VB-Audio Virtual Cable;
VBCABLE_Driver_Pack43.zip (1.09 MB - OCT 2015), Donationware
https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm
VB-Audio Hi-Fi CABLE & ASIO Bridge;
HiFiCableAsioBridgeSetup_v1007.zip (3.82 MB - MAR 2014) , Donationware
https://www.vb-audio.com/Cable/#DownloadASIOBridge
ASIO4ALL 2.14;
ASIO4ALL_2_14_English.exe (452 KB - MAY 2017)
http://www.asio4all.org/
Ekio-1.0.6.0-install.exe (6.5MB, now Version 1.0.6.0, US$149 Net Price for one license)
http://www.lupisoft.com/ekio/
のインストールが無事に終わっているようですが、念のため、PCは再起動しておいて下さいね。
書込番号:23440076
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
>今晩、21時頃
ご心配頂き、誠にありがとうございます。
貼り付けて頂いた資料でトライしてみますので、申し訳ありませんが、又の機会どうしてもでお願いさせて下さい。(業務続行中で、帰宅は深夜見込みなのです)
書込番号:23441190 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
あいによしさん
了解です。おつかれ様でございます。
必要に応じて、いつでも、ご連絡下さい。 うまく時間が合えば、相談しましょう。
もちろんのことですが、ブラウザ(私は Chromeを常用)で、YouTube やストリーミングラジオなどを聴く際には、既存のスピーカーとして Hi-Fi Cable Input (VB-Audio Hi-Fi Cable) を使い、Windows のカーネルミキサー経由になりますので、添付のように音量が通るようにしておく必要があります。
では、JRiver やブラウザから、すんなり EKIO 経由で再生できることをお祈りしております。
難渋したら、いつでもお知らせ下さい。
書込番号:23441325
![]() 2点
2点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
ASRの私のスレッドへの投稿;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-416319
で、この4チャンネルアンプ;
https://www.audiophonics.fr/en/power-amplifier/audiophonics-hpa-q400et-amplificateur-4-voies-class-d-purifi-4x400w-4-ohm-p-14452.html
を2台使うのはいかがですか、と勧めてくれる人がいるのですが、どう思われますか?
アンプとしては、PURIFI 1ET400A moduleを使っていて、電源には Hypex SMPS1200A400 が使われています。スペック的には、かなりよさそうに見えます。
PURIFI 1ET400Aについては、検索すると、こんな記事も見かけました。今年の1月17日付けです。
https://ause-audio.com/?p=2423
「次世代ハイエンド製品に採用したい」、とのことです。
お手すきの際に、ご意見をお聞かせ下されば幸いです。
書込番号:23441439
![]() 1点
1点
Purifi Audio 1ET400A については、例によって、ASRで amirmさんが評価していて、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-purifi-1et400a-amplifier.7984/
かなりの高評価を獲得しています。
書込番号:23441509
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは。
>ASRの私のスレッドへの投稿;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-416319
で、この4チャンネルアンプ;
https://www.audiophonics.fr/en/power-amplifier/audiophonics-hpa-q400et-amplificateur-4-voies-class-d-purifi-4x400w-4-ohm-p-14452.html
を2台使うのはいかがですか、と勧めてくれる人がいるのですが、どう思われますか?
アンプとしては、PURIFI 1ET400A moduleを使っていて、電源には Hypex SMPS1200A400 が使われています。スペック的には、かなりよさそうに見えます。
PURIFI 1ET400A module を用いたアンプに対する Amir 氏によるASR の記事は既に知ってはいました。
Bruno Putzey 氏発明の Class D amp modules としては UcD module, Ncore module に続く最新の世代となるのが PURIFI 1ET400A module と思われますので性能はこれまでで最高かと思います。
が、しかし、Audiophonics (France) による DIY 製品であるということが私には悪い意味で非常に気になります。
Audiophonics はそのウェブサイトによるとオーディオショップであって中華アンプなども販売しています。
中華アンプと言っても様々ですが、このショップは Audio-gd 社の製品も堂々と扱っています。
Audio-gd 社の製品に対しては ASR において Amir 氏が全く評価していませんし、いろいろと問題のある製品らしいです。
実は、私も直接 Audio-gd 社から試しにヘッドフォンアンプを購入しましたが、それは音楽性皆無の塊に過ぎませんでした。
PURIFI 1ET400A module は素晴らしいアンプであると思います。Apollon Audio 社でも 3CH アンプを製造しているようです。
https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/
PURIFI 1ET400A modules を用いた 4CH アンプ の製造の可能性などに関して Apollon 社に御相談をなさって見てはいかがでしょうか。
それでは、また。
書込番号:23441826
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
おはようございます。早速に貴重な情報をいただき、感謝申し上げます。
>が、しかし、Audiophonics (France) による DIY 製品であるということが私には悪い意味で非常に気になります。
このあたり、まだまだ私には鼻が効きませんので、非常にありがたい情報です。
>PURIFI 1ET400A module は素晴らしいアンプであると思います。Apollon Audio 社でも 3CH アンプを製造しているようです。
https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/
貴重な情報です! 見ております。これまでの Apollon社の情報やその技術的な拘りも踏まえて内部写真を見ていますが、惚れ惚れするデザイン、配置、配線、、、素晴らしいですね。これでも、税込2,690ユーロなのですね。 本当に、これを3台、すぐにでも欲しくなります!
3台で9チャンネルあれば、1チャンネルは予備として温存できる、、、、 どれかのチャンネルが故障したら、Apollon社に交換モジュール送付を依頼して、その到着を待つ間でも音楽を聴ける、は、私でもモジュール交換できるかも、と思いますが、国内の信頼できる技術者に有償でも依頼して。。。。
「ダメダメ、焦ってはろくなことはないよ!」、と自分に言い聞かせております。何しろマルチチャンネルアンプの選択は、非常に慎重に進める方針なのでした。1年程度かけてもいいから、慎重に進めるべし、です。
昨日リンクをお知らせした、
https://ause-audio.com/
の動向も、少し気になりますが、ハイエンドアンプに使う、との方針だそうですので、やはり8チャンネル必要となると、非常に高価になりそうです。なによりも、非常に小さな個人企業のようですので、ここに頼るのは、少し怖くて躊躇せざるを得ないですね。ウェブサイトを見る限りは、好感が持てるのですが。。。 ここも、いつも私が危惧しているように、国内市場にしか興味がなく、その意味では採算企業としての存続は、、、困難かも知れません。やはり、優秀な欧州勢には追いつけない。。。
ちょっと落ち着いたら、お勧めのように、Apollon社とコンタクトを開始しようか、と思案中です。
https://www.apollonaudio.com/3-channel-purifi-1et400a-apollon-audio/
を見て、とてもテンションが高くなっておりますが、よく頭を冷やしてから次のステップを考えます。
また、この Apollon製品については、ASRの私のスレッドで情報をくれた Nabussanさんにも知らせておきます。
ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23442167
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんにちは。
追記事項ですが、Apollon Audio website によりますと Purifi 1ET400A modules を用いたアンプとして以下の2機種も商品化されています。
(2CH) Apollon Stereo
https://www.apollonaudio.com/apollon-audio-purifi-1et400a-stereo-amplifier-input-buffer-board/
(1CH) Apollon Monoblock
https://www.apollonaudio.com/purifi-1et400a-apollon-audio-monoblock/
それでは、また。
書込番号:23442569
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは
説明図を貼って頂きありがとうございます、週末やってみます。
ところでリモコンは購入されたのでしょうか?
書込番号:23444136
![]() 1点
1点
あいによしさん
>説明図を貼って頂きありがとうございます、週末やってみます。
お手伝いや情報が必要でしたら、何なりとお知らせ下さい。
>ところでリモコンは購入されたのでしょうか?
リモコンも一緒に発注して、一緒に届きました。Apple Remote ですが、とても軽くて、おしゃれで、高機能です。
是非、一緒に購入されることをお勧めします。 きちんと、DAC8PROとペアリングされて届きます。
書込番号:23444315
![]() 2点
2点
皆さん、
どんな風に書かれているのかな?、と漠然とした興味で、Wikipedia の Audio Crossover 解説を見ていたのですが、かなりまともな、現代に即した、教科書的解説になっているので、すこし驚きました。
https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_crossover
私は、 Google Chrome をブラウザとして常用していますが、試しに、始めてブラウザの「日本語に翻訳」の機能を使ってみたら、割にまともな日本語に翻訳されますね。最近の AI翻訳も、進歩しているのですね。
書込番号:23445896
![]() 2点
2点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
これまでも、各所で繰り返し議論されていることですが、このスレッドの議論、なかなか面白いです。
”What to trust ear or measurement?”
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-to-trust-ear-or-measurement.13696/
たまらず、私も1つ投げました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-to-trust-ear-or-measurement.13696/post-419601
そして、そこのスレ主さんが引用されているこの2つのビデオインタビュー、かなり有名なので、御承知かと思いますが;
https://www.youtube.com/watch?v=EQqFqOj5-wk
https://www.youtube.com/watch?v=JW7fg_yfza4
ご参考まで。。。
書込番号:23446666
![]() 2点
2点
皆さん、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-420921
に詳しく書いておきましたが、DAC8PRO の前面には、高品位なヘッドフォン出力があり、ここには CH-1 と CH-2 のラインレベル信号が常に出ています。そして、これは、もちろん、DAC8PRO のマスターボリュームおよびチャンネルゲインの制御下にあります。
ということは、左右のサブウーファー YST-SW1000 への「ラインレベル入力」に、このヘッドフォン出力が RCAアンバランスケーブルで行えるわけです!!
さきほど、試してみて、もちろん完璧に動作しました。これで、ちょっとした悩みだった YST-SW1000 への「ラインレベル入力」が解決できました。
ちょっと、気付くのが遅く、「目から鱗」 でした。
書込番号:23448196
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは。
6.35mm TRS -> 2 x RCA Female Adapter で非常に優秀なものとしては
DAP Audio Xcaliber XGA18
が良く知られています。
参考文献:https://archive.org/details/XcaliberProfessionalAudioConnectors/mode/2up
入手先:https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=xga18&_sacat=0&_sop=15
それでは、また。
書込番号:23454408
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
ありがとうございます。
いまは、私のケーブルやアダプターの箱の中に転がっていた、安物のこの2つで繋いでいます。直角になるので、DAC8PRO の横へ回せて便利です。もちろん、いずれも接点クリーナーで、丁寧に、綺麗に、クリーニングしております。
ご紹介いただいた DAP Audio Xcaliber XGA18 は、しっかりしているようですので、これとRCA直角(L型)アダプターを使う手もありそうですね。 でも、何しろ前面ですので、あまり出っ張るのは、避けたい。。。。
定評ある 「6.35mm TRS 直角(L型)オスプラグ−メスプラグの短い(30CMほど)程の延長コード」があれば、それでDAC8PRO の横へ回してから DAP Audio Xcaliber XGA18 を繋ぐのがよさそうですので、そんな延長コードも探してみます。
書込番号:23454561
![]() 1点
1点
皆さん、こんばんは。
さて、昨日、ここを見ている友人から、「YAMAHA MX-A5200 は、MX-A5000 から大きく進化して優秀になってるよ、これも検討したら?」、との連絡があったのですが、どうなのでしょうか?
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/mx-a5200/index.html
Hypex や Purifi の D-Class アンプモジュールを使ったマルチチャンネルアンプの導入に、かなり傾きつつあるのですが、ASRフォーラムの一部では、この種のアンプとデジタル電源からの電磁ノイズや、周辺機器への電磁障害/電磁干渉が話題になったりもしているので、旧来の「大トロイダルトランス+大容量キャパシター」型のマルチチャンネルアンプも、完全に排除しない方がいいのかも、と少し慎重になっております。
その意味では、もちろん、優秀な「従来型」のパワーアンプやプリメインアンプも、もちろん検討対象候補ですが。。。
まずは、YAMAHA MX-A5200 について、実機のご利用経験も含めて、ご示唆や情報を頂戴できれば幸いです。
書込番号:23458681
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
>YAMAHA MX-A5200 、MX-A5000 、どうなのでしょうか?
静かになって輪郭がよりはっきりし、力強さも5200のほうがよさそうです。ただし、より更新の変化が大きかったのはプリの方です。
書込番号:23458894
![]() 2点
2点
あいによしさん
ありがとうございます。
ここで、いくつかの測定結果が報告されていますね。
https://www.youtube.com/watch?v=JTqC2_-nnzU
書込番号:23459275
![]() 1点
1点
ここで測定結果の詳細が報告されていました。
https://www.audioholics.com/av-preamp-processor-reviews/yamaha-cx-a5200-mx-a5200/conclusion
書込番号:23459291
![]() 2点
2点
あいによしさん、皆さん、
MX-A5200 では、CH-3 と CH-4 をブリッジできるので、このような接続が可能なのですね?
CH-3+CH-4 (bridged) L&R for WOs (woofers)
CH-2 L&R for SQs (squawkers)
CH-5 L&R for TWs (tweeters)
CH-6 L&R for STs (super tweeters)
書込番号:23459369
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんにちは
プリ購入で視聴会も何度か行って比較しています。
5200の売り(5000に対し)は以下です。
・シャーシ強化
・GND強化
・ブリッジ接続対応
マルチアンプなので、アンプとスピーカーは直結、駆動力はほどほどでOK。
NS-1000、SWと同じメーカー。
コンパクト。
もし故障した場合メーカー対応がわりとよい。
お使いのシステムに向いてそうでは?
書込番号:23459699 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
あいによしさん、皆さん、
ちょうど今日は在宅ですので、色々調べておりました。
>ブリッジ接続対応
>もし故障した場合メーカー対応がわりとよい。
に加えて、
https://www.audioholics.com/av-preamp-processor-reviews/yamaha-cx-a5200-mx-a5200/conclusion
の評価でも、そこそこ優秀なようです。
まずは、国産の、リコール対応や修理対応がしっかりしているメーカー製のマルチアンプで、一旦、プロジェクトを第一段階の完成形に固めておくことも、よさそうに思い始めています。
XM-A5200 のXLR入力での S/N が 116 dB 以上、というスペックには、少し驚いております。
測定評価の報告では、CH-3+CH-4 のブリッジモード(WO駆動?)では、S/N も歪みも、さらに改善されているようですので、その点にも魅力を感じます。
単体パワーアンプや欧州製の Class-Dマルチアンプも非常に魅力的なのですが、それらは、今後、ゆっくり、じっくり、検討する楽しみに残しておく。。。 方がいいのかも知れませんね。
もし使ってみるなら、添付のような接続になるのか、と思案中です。
書込番号:23459794
![]() 2点
2点
訂正: XM-A5200 ではなく、 MX-A5200 です。 失礼しました。
書込番号:23459826
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは
おかげさまで、EKIOで音が出るようになってきたのですが疑問が出てきました
DAC8PROの2台運用は可能なのでしょうか?
書込番号:23460751
![]() 1点
1点
あいによしさん
お使いの機器類が異なるので、どこまで支援できるか分かりませんが、今晩、よく検討してみます。
その前に、EKIOへは ASIO4ALLを経由するとして、源流では、どの機器からASIO4ALLへ信号を出されているのですか?
どうも、EKIO からの OUT先が 192 kHz 24 bit になっていないか、入力(源流)側の ASIO4ALL で、そのOUT先が必要のないOUTに設定されていて、EKIO が OUTに指定できないので、赤Xになっているような??
◆ プレーヤー機器から ASIO4ALL へ出力では、そのプレーヤーのASIO4ALLパネルで、VB Audo Hi-Fi Cable − Out: 8x8-384kHz, 24Bits 「のみ」が選択されていること、
◆ ASIO4ALL for EKIO では、
IN =VB Audo Hi-Fi Cable Out: 8x8-384kHz, 24Bits 「だけ」、
OUT=帯域分割後のチャンネルを出力したい機器のASIO OUT が選択されていること(複数DACの指定も可能です)、
その出力相手先でも 192 kHz 24 bit で受け取れる設定になっていること、
が必要です。
EKIOからの帯域分割後の出力先が fireface であることは、貼っていただいた画像から理解できます。
あと、DAC8PRO には、8チャンネル対応の専用 ASIOドライバーが添付されてきますので、そのドライバーが2台のDAC8PROを認識すれば、16チャンネルが使えることになりますが、まだ、OKTO社や ASR Forum での実証回答がありません。
添付画像は、JRiver から ASIO4ALL に出力し、ASIO4ALL がそれを VB-AUDIO Hi-Fi Cable へ渡し、EKIOがそれをVB-AUDIO Hi-Fi Cableから受け取り、 チャンデバ後に DAC8PRO へ流している際の状態です。
全て 192 kHz 24 bit で、ASIO BRIDGEでも、そうなっていることにご注目下さい。
DIYNHK USB Audio が DAC8PROに添付されてくる(発送時にメールで送られてくる)専用ASIOドライバーでして、これがインストールされていると、EKIOの出力先としてDAC8PRO の CH-1 〜 CH-8 が選択できるようになります。
DAC8PRO 2台を繋いだ際に、1つの DIYNHK USB Audio ASIO で CH-1 〜 CH-16 が選択できるか、または DIYNHK USB Audio が2つ現れて、それぞれで CH-1 〜 CH-8 が使えれば、よろしいわけですね。
書込番号:23461478
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
詳細なヒントありがとうございます、音はでましたが理解が追い付いてないです。
週末取り組んでみます。
ただしパソコン立上げに時間がかかり、OSでASIO4ALLの設定が必要になった場合,導入のハードルは高そうですね。
PCを連続稼働でクリアにしてもDACの通電しっぱなしは難しいです。
書込番号:23462957
![]() 1点
1点
あいによしさん
>ただしパソコン立上げに時間がかかり、OSでASIO4ALLの設定が必要になった場合,導入のハードルは高そうですね。
>PCを連続稼働でクリアにしてもDACの通電しっぱなしは難しいです。
私の環境の場合、音楽を聴く際にPCとアンプを立ち上げますが、PCは、ASIO4ALLの I/O を含む設定を確立しておくと、次回の起動(スタンバイモードではなく、完全に電源オフからのコールドスタート)で、Windows 10 の起動に続くEKIO自動起動で動作(プレイ)状態に入るまで、PCの電源オンから約80秒です。
ASIO4ALL も、一度適切に設定できれば、次回起動でそのI/O設定が、正しく読み込まれますので毎回の設定は不要ですし、EKIOがデフォルト指定設定ファイルを読み込んでプレイ状態になるには数秒しかかかりませんので、あくまで私の環境では、ですが、音楽再生専用PCでの運用で、特段の不都合や「まどろっこしさ」は、感じておりません。
アンプのウォーミングアップには、いつも、10分以上はかけていますので、アンプのスタンバイが、やはり律速になっております。
書込番号:23464702
![]() 2点
2点
あいによしさん
>5200の売り(5000に対し)は以下です。
>・シャーシ強化
>・GND強化
>・ブリッジ接続対応
この情報、ここで紹介されていましたね。ようやく見つけました。
https://www.phileweb.com/news/d-av/201809/05/44960.html
なるほど、納得です。
MX-A5200 を、我が家の環境で試聴できる手立てを探っております。
書込番号:23466024
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんにちは
>私の場合、PCの電源オンから約80秒です。
>ASIO4ALL も、一度適切に設定できれば、次回起動でそのI/O設定が、正しく読み込まれますので毎回の設定は不要です
週末やってみておっしゃる通りでした。
うちはキッチンのTV用なので起動が遅いとまずいのですが、スリープから音がでるまで10秒04、これなら使えそうです。
PC起動中でもDACの電源OFFで音を止め、しばらく経ってDACの電源ONで何事もなかったように音が出るので
専用静音PCをサーバーみたいに連続稼働でよいかなとも考えています。(これなら瞬時)
ASIO4ALLがうまくいかなかった理由もわかりました。
起動順で、ASIO4ALL→EIKOが失敗。実はEIKO起動でEIKOがASIO4ALLをもうひとつ立ち上げて裏画面にいました。
裏画面のASIO4ALLに気が付かず、最初のASIO4ALLを触るので、固まってました。
EKIOでASIO4ALLに設定、EKIO再起動でEKIOで起動された裏画面のASIO4ALLで行先を指定ならうまくいきました。
書込番号:23470884
![]() 1点
1点
あいによしさん
>EKIOでディレイとゲインを反映させる方法をご教示頂けませんでしょうか?
添付の3枚の画像を、その順序でご覧下さい。
単純なステレオ2帯域分割、クロス 100 Hz で、まず、EQ のOut-1フィルターでゲインとディレイを与え、
次に、それに加えて、I/Oパネルのチャンネル1に対して、グループゲインとグループディレイを加えています。
基本的に、
1.EQ の各フィルタにおけるゲインとディレイは、そのクロスポイントにおけるゲインとディレイを設定、
2.I/O パネルにおけるゲインとディレイ(ms単位で数値入力)は、その帯域グループ全体のゲインとディレイを設定、
で、トータルのゲインとディレイは、1.と 2.の合計になります。 ディレイを加える毎に、理論フェーズ(位相)が複雑化する様子も表示されます。
書込番号:23471595
![]() 2点
2点
あいによしさん
>測定も出来るのでしょうか?
EKIO には測定機能は備わっておりませんが、EKIO独自のテキスト形式で EQ設定を書き出し、それをテキスト編集して読み込むことができるようです。ekio取説の18〜20ページをご覧下さい。
例えば、Woofer帯域について、周波数、ゲイン in dB、位相回転 を次のようなテキストファイルで、書き出し、読み込み、が可能なようです。
# Woofer A measurement
0 -50.4277416519 -181.087643279
5 -49.8484750329 -188.610750555
10 -47.6752662956 -202.691690774
15 -47.1882385137 -203.055846114
20 -44.4884864254 -210.713279311
25 -44.0139520572 -206.436586045
私は、EKIO のこの機能は、煩雑そうなので使っておりません。
一方で、以前ご紹介したように、REWソフトウェアを使って、EKIOのサウンドを ECM8000測定用マイクで拾い、REW の Wavelet解析で解析して、EKIOのディレイ設定や、SWの微妙な位置調整に活かしております。
以前ご紹介したように、REW-Wavelet は、EKIO のディレイ設定を ms 単位で正確に反映することを、ラインレベル信号でも確認しております。
このあたりは、ASRフォーラムでも、かなり詳しく報告しております。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-370501
から
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-370529
あたりをご覧下さい。
位相問題については、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-371429
から
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-372421
で詳しく述べています。
書込番号:23471695
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
ご回答ありがとうございます。
ディレイとゲインはI/OとEQどちらも個別に数値が入り、合算が波形で見れるのを確認しました。LONGとSHORTの使い分けを想定しているようですね。
測定はECM8000測定用マイクで拾い、REW の Wavelet解析ですね、ちょうどECM8000があるので週末試そうと思います。
書込番号:23471741 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 2点
2点
皆さん、
YAMAHA社および都内の某ディラー様との相談の結果、 MX-A5200 を、6月20日土曜日に我が家に配送で、試聴および検証用に、1週間ほど、無償で、貸し出していただけることになりました。
昨日、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-429373
で、英語で、次の内容を書いております。
以下は、その内容を Google Chrome に自動翻訳させたものです。
**************************************************************************************************
Nabussan さん、
素敵なコメントや提案をありがとうございます。
>とにかく、ピュリファイ(Purifiデジタル)アンプに関して、オスカーワイルドの知恵を思い出させてください。
>「誘惑を取り除く唯一の方法は、それに屈することです。」
はい、同意します。
Apllon Purifi 1ET400Aの 4ユニットは、まだ私の候補リストのトップにあります!
ただし、最終的に決定する前に、YAMAHA MX-A5200などの従来の非デジタルアンプを試し、HypexおよびPurifiデジタルアンプモジュールの代表としてDP-NC400-4などのデジタルアンプも試したいと思います。
MX-A5200よりもDP-NC400-4を本当に好む場合は、HypexとPurifiの比較に焦点を当てることに進みます。
MX-A5200 試用の主な理由の1つは、CH3 + CH4 BTL(ブリッジ)モードで、ウーファーを最大200 Wレベルまでかなり低い歪み値でドライブすることです。ウーファーのBTLプッシュプル駆動は、通常のシングルアンプ動作と比較して、高速でクリアな低音を提供するはずです。
https://www.audioholics.com/av-preamp-processor-reviews/yamaha-cx-a5200-mx-a5200/conclusion
私のホームオーディオ設定/環境では、ウーファーやスコーカーが100 Wレベルに達することはめったになく、ツイーターやスーパーツイーターも30 Wレベルに達することはめったにないと思います。MX-A5200の、これらの電力レベルでの歪み値は、十分許容できるように見えますが、いかがですか?
もちろん、SPドライビング(スピーカー駆動)における「パワーリザーブ/マージン」の重要性はよく認識しています...
私はACCUPHASE E-460を使用しており、特にこのプロジェクトでは、常にリファレンスサウンドであり(特にピアノのサウンド!)、比較的マイルドな(そして少しウォームな)サウンド特性を非常に気に入っています。
ご存知のとおり、クロスオーバー設定を使用せずにDSD音源をネイティブ ストリーミングで聴くために、E-460 + LCネットワークシステムを完全に温存します。したがって、客観的な測定値としてはデジタルアンプシステムの方が遙かに有利であるとしても、フルデジタルアンプシステムに飛び込む場合は、総音響特性が大幅に変化する可能性があることに少し懸念があります。これは常に私にとって一種のジレンマですが、私は決定を下す必要があります。
いずれにせよ、あなたの素晴らしい提案を心に留めて、最終決定を下す前に、私のマルチチャネルプロジェクトで複数のマルチチャネルアンプを慎重にテストします。
または、プロジェクトの「ベースアンプシステム」としてMX-A5200を1つ使用(購入)することは可能であり、その価値があるかもしれません。その後、さらに、究極のマルチチャンネルアンプを探すという冒険を続ける、ということになります。
HypexとPurifiは、デジタルアンプモジュールの開発と改善に引き続き重点を置いており、さらに、一部の新会社が、イノベーション競争に参入する可能性もあります。
**************************************************************************************************
書込番号:23471771
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは。
>YAMAHA社および都内の某ディラー様との相談の結果、 MX-A5200 を、6月20日土曜日に我が家に配送で、試聴および検証用に、1週間ほど、無償で、貸し出していただけることになりました。
非常に素晴らしいお知らせですね。無償での貸出とのこと、YAMAHA 社のこの製品に対する絶対の自信が感じられます。
ともかく、その結果が非常に楽しみです。
なお、本日、HIFICRITIC April-June 2020 issue が私の手元に届きました。
Mola Mola Tambaqui DAC/HPA に対する Martin Colloms 氏による評論記事を真っ先に熟読致しました。
簡単に言えば、彼による評点は予想よりは低い評点 200 marks でした。
dCS製DAC や MSB製のDAC が既に 250 marks を獲得していることから、私による Mola Mola Tambaqui DAC/HPA の購入は残念ながら見送りということに決定致しました。
それでは、また。
書込番号:23471817
![]() 2点
2点
皆さん、
それから、、、
例の DENTEC DP-NC400-4 2台(XLR入力仕様)は、少し遅れておりますが、7月17日あたりに、無償貸与(貸出)していただけることになりました。
http://www.soundden.com/dentec/shin-amp/dp-ncd.html
書込番号:23471826
![]() 2点
2点
あいによしさん
EKIOですが、I/Oをうまく設定できると、非常に安定していて、高品位な音質です。
内部的には、 64bit浮動小数点による高速処理だそうです。フィルター計算はIIR処理です。
ASIO4ALL も、動作の状況を理解できれば、非常に良くできたソフトであることが分かりますね。
ASIO4ALL は、自らが音響出力を受け取る ASIOドライバーとして機能するだけではなく、他の全ての ASIOドラーバーのさらに上位に鎮座して、全てのASIOによる I/O を振り分ける機能がある、と理解できます。
さて、EKIO の I/O チャンネル数無制限の有料版は入手されましたか?
書込番号:23473388
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
>EKIO の I/O の有料版は入手されましたか?
はい、試しているのですが、8chのFirefaceではチャンネル不足です。
書込番号:23473903
![]() 1点
1点
あいによしさん
>はい、試しているのですが、8chのFirefaceではチャンネル不足です。
DAC8PRO には、XLRバランス入力8チャンネルに加えて、AES-EBU によるステレオ4チャンネル(8チャンネル)の入力ポートがあります。
(また、1系統のAES-EBU出力端子もあり、ここへはCH-1, CH-2 のデジタル信号が常に出ています。)
AES-EBU入力では、DAC同期信号はAES-EBU信号から与えられますので、DAC8PROはその内部クロックを使いません。従って、複数のDAC8PROを1台のPC、または同期している複数のAES-EBUデジタル出力機器、に繋ぐ場合でも、原理的には、「同期ずれ」の問題は発生しません。プロが、録音スタジオなどでAES-EBUを好んで使う主な利用は、ここにあります。
私のマルチ環境では、8チャンネルの USB ASIO接続で十分なので、AES-EBU入力は使いませんが、AES-EBU入力を利用して、2台以上の DAC8PROへ同期入力する方法や必要となる機器について、ASR の DAC8PROフォーラムで、世界中の皆さんからの示唆をお願いしてみました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-431814
翻訳すると;
***************************************************************
こんにちは
DAC8PROが、私のマルチチャネルプロジェクトで完全に正常に動作していることに、非常に満足しています。
私は現在、日本のオーディオ愛好家の友人に、DAC8PROをかなり頑丈なマルチチャネルシステムに搭載することを推奨および提案していますが、「2台」のDAC8PROを同期して操作するのは難しいようです。 彼は8つ以上のチャネルを必要とします(ただし、彼の大きなシステムについては完全には理解していません)。
DAC8PROへのAES-EBU入力を使用する場合、同期クロックはAES信号によって提供され、DAC8PROはその内部クロックを使用しないことを知っています。「1台の」PCから「2台の」DAC8PROへの適切なAES-EBU入力を確立できたとしたら、彼の大きなシステムで2台のDAC8PROを同期して使用できると思います。
私の場合は、フルUSB ASIO入力を使用しています(私にはそれで十分です!)。
一方、どのように、また、どんな追加機器を利用すれば4チャネルAES-EB入力をDAC8PROに適用できるのか、そして私の友人が達成したいと望んでいる2台のDAC8PROへ、同時にAES-EBUを入力する方法については、ほとんど知りませんので、皆様の提案やコメントを大歓迎いたします。
***************************************************************
何らかの示唆や回答があれば、お知らせいたします。
お使いの FireFace のご利用では、何チャンネル必要ですか?
書込番号:23474317
![]() 1点
1点
あいによしさん
速攻で、1つの示唆がありました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-431937
*******************************************************************
4つのAES出力を提供するさまざまなインターフェイス(USB、Firewire、PCI(-e))があります。デジタル出力に影響を与えるワードクロック入力があるかどうかはわかりませんが、A / Dコンバーターを同期することのみを目的としていることがよくあります。XMOS USBオーディオチップは外部クロックをサポートしているため、それをサポートするインターフェイスが見つかった場合は、それらの複数を使用できます。
他のいくつかの可能な解決策、私がテストしたものはありません:
* RME HDSPe AES
* Dante Virtual Soundcard(またはインターフェイス、たとえばRME digiface Dante)が複数のDante-> AES / EBUアダプターまたはFocusrite RedNet D16Rに給電
*同じ、DanteをRavennaの代わりに使用
* a Smyth Realiser A16 Pro-D(まだ実際にはまだ発表されていません)
*******************************************************************
書込番号:23474333
![]() 2点
2点
あいによしさん
私からも、御礼とコメントを投げました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-431959
***************************************************************
Zooqu1ko様こんにちは
迅速な対応ありがとうございます。
私のプロジェクトからの勧めによって、私の友人は1台のPCでソフトウェアクロスオーバーEKIOを使用したいと思い、彼は同期AES-EBUルーティングを介してEKIOの出力の14または16チャネルを2つのDAC8PROに割り当てたいと考えています。
彼はすでにEKIOの1つのライセンスを購入しました。これにより、EKIOで無制限の数の入出力チャネルを使用できます。
あなたの親切なコメントと提案を読んで理解しましたが、EKIOが複数のAES-EBU同期デバイスを適切に認識した場合、彼はAESデバイスの後に設定される2つのDAC8PROでマルチチャネルシステムを実現できますよね?
***************************************************************
書込番号:23474358
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんにちは
2台同期のご確認ありがとうございます、安堵しましたので
2台オーダーさせて頂きました。
Order comments
I will buy this with the introduction of Mr. dualazmak
FirefaceはA/Dとして使いEIKO専用で静音PCを手配予定です。
DAC8はとりあえず2台あればよさそうです。
>彼は8つ以上のチャネルを必要とします(ただし、彼のシステムについては完全には理解していません)。
失礼しました、また少し増えましたが、以前はこんな感じです。(大したものではなくキッチンTVにスピーカー置いてドラマとか音楽番組をちょっといい音で聞きたいという、ありふれたパターンです。)
書込番号:22614172
書込番号:23474593
![]() 2点
2点
あいによしさん
>2台同期のご確認ありがとうございます、安堵しましたので2台オーダー
DAC8PRO + EKIO の仲間が増えること、とても嬉しく思います。恐らく、日本では2番目のご発注でしょうか?
それも、2台オーダーとは、驚きました。
恐らく、AES-EBU入力については、あいによしさんは、かなりのエキスパートであるのでは、と拝察申し上げます。
私は、2月15日に発注して、このご時世ながら、5月9日に受け取りました。
現在、かなりの注文を抱えているようですので、3、4ヵ月は待たされるかも知れませんね。
今後とも、必要に応じて情報交換やご教示を、お願い申し上げます。
書込番号:23475334
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
>AES-EBU入力については、かなりのエキスパート
>今後とも、必要に応じて情報交換やご教示を、
いえいえとんでもないです。
2台同期の解決策は未だわかりませんが、来るのは当分先
dualazmakさんも気にかけて頂いてるし、やってみようかと
こちらこそ、宜しくお願い致します。
書込番号:23475924
![]() 2点
2点
ひとつの思い付きです:
Okto DAC8 Pro website には添付画像のようなものが含まれています。
DAC8 Pro 2機の同期の方法のヒントがそこにもにあるかも知れませんね。
それでは、御幸運を!
書込番号:23476010
![]() 2点
2点
あいによしさん、Naim ND555 enthusiastsさん
おはようございます。
Naim ND555 enthusiastsさんがご指摘のように、もともとDAC8PRO は、その名前の通り、プロ向けに開発されたものですので;
AES-EBU 入力 8チャンネル
USB 入力 8チャンネル
USB 出力 8チャンネル
アナログ出力 8チャンネル
が備わっていて、これら全てを同時に利用できます。凄いことですね。
私の単純なマルチチャンネルプロジェクトでは、御承知の通り、8チャンネルで USB IN --> analog OUT で簡潔なのですが、恐らく録音スタジオやスタジオクロスオーバーとの連携では、USB OUT や AES-EBU IN も駆使して、多様な利用が行われているはずです。
図の中央と右の I/O では、USB OUT も使われていますが、これはUSB OUT で同期クロック信号を送っているのかも知れません。
いずれにしても、DAC8PROの XMOS 処理では、Zooqu1koさんが;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-431937
で書いてくれたように;
「XMOS USBオーディオチップは外部クロックをサポートしているため、それをサポートするインターフェイスが見つかった場合は、それらの複数を使用できます。」
ですので、このあたりが、あいによしさんのシステム構築の参考になりそうな気がしております。また、OKTO社の Pavel さんと直接相談されたら、プロの使用例も含めて、いろいろ示唆が得られるはずです。
今後、ASRフォーラムでも、AES-EBU IN を利用した高度な使用例も報告されるようになると予想しておりますので、そのような情報が見つかりましたら、お知らせします。
さて、週末には、いよいよ、ようやく、YAMAHA MX-A5200 でマルチアンプ駆動を行いますし、7月中旬には、DENTEC DP-NC400-4 を2台、貸与していただけますので、慎重に、楽しみながら、マルチチャンネルアンプの選定を進めます。
やはり、Naim ND555 enthusiastsさんもご指摘の Apollon社の Rurifi モジュール採用アンプに、大きな興味があるのですが。。。。
https://www.apollonaudio.com/apollon-audio-purifi-1et400a-stereo-amplifier-input-buffer-board/
このステレオ機を4台揃えられたら、最高かもしれない、、、ですね。
4台あれば、定期的に駆動SPを入れ替えて均等にエージングできるし、万が一、どれかが故障しても、その単体機能をE-460 でバックアップしている間に修理に出せば、その間も音楽は聴けますし、、、、
Apollon PURIFI 1ET400A を、何とか「我が家で!」試聴できないものか、、、どこかの時点で、Apollon社との直接対話を開始したいと思います。
「誘惑を克服する唯一の方法は、それに屈することである!(Oscar Wilde)」、と Nabussan さんが私の背中を強く押すのですが、用心、用心、慎重に、慎重に、、、、
マルチチャンネルアンプの選択については、是非とも、今後も情報交換とご教示を、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23476051
![]() 1点
1点
いま、ふと思ったのですが、昨日お知らせしたように、DAC8PRO には、1系統のAES-EBU 出力があり、ここには CH-1 + CH-2 のデジタル信号が常に出ています。
ということは、このAES-EBU出力を2台目の DAC8PROの AES-EBU入力に「同期を取るためだけの目的で」繋ぐと、
「XMOS USBオーディオチップは外部クロックをサポートしているため、それをサポートするインターフェイスが見つかった場合は、それらの複数を使用できます。」
に従って、同期信号はこの AES-EBU から得て、1台目と同期するのかも知れませんね。それをやりながら、音響信号はその同期の下で DACとしては USBの 8チャンネルでも、合計16チャンネルでも、同期している、、、となるのでしょうかね?
書込番号:23476075
![]() 2点
2点
dualazmakさん、Naim ND555 enthusiastsさん、
ご確認ありがとうございます。
>AES-EBU出力を2台目の DAC8PROの AES-EBU入力に「同期を取るためだけの目的で」繋ぐ
きたらやってみますね。
書込番号:23476162 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 2点
2点
dualazmakさん、おはようございます。
>ということは、このAES-EBU出力を2台目の DAC8PROの AES-EBU入力に「同期を取るためだけの目的で」繋ぐと、
「XMOS USBオーディオチップは外部クロックをサポートしているため、それをサポートするインターフェイスが見つかった場合は、それらの複数を使用できます。」
に従って、同期信号はこの AES-EBU から得て、1台目と同期するのかも知れませんね。それをやりながら、音響信号はその同期の下で DACとしては USBの 8チャンネルでも、合計16チャンネルでも、同期している、、、となるのでしょうかね?
その方法は真っ先に思いついておりますが、手取り早く Okto社の Pavel氏に直接尋ねてみれば、正しい解答が得られるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、御幸運を!
書込番号:23476193
![]() 1点
1点
>手取り早く Okto社の Pavel氏に直接尋ねてみれば、正しい解答が得られるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
考えることは、一緒ですね!
今、ASR で投げましたし、ASR経由で OKTO社の Pavel さんへもASRフォーラムの PM(personal mail)システムで、返答をお願いしました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-432912
*******************************************************************************
【Zooqu1koさんのコメント:】
EKIOにどんな制限があるのか​​わからないので、そもそも複数の異なる「サウンドカード」への出力をサポートしていないかもしれません。AES / EBUの16以上のチャネルを持つ単一のインターフェースがおそらく最善の策です。これは一種のプロオーディオの問題であり、プロオーディオフォーラムやプロオーディオストアでより多くの資格のあるヘルプが利用可能になることを期待しています。さらにいくつかの提案があります。たとえば、ここhttps://www.soundonsound.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=60373
RME HDSPe AESは、最も安価で、最も面倒なオプションである限り、サポートされているオペレーティングシステムに固執します。
予想されるサンプリングレートは明確ではありませんが、48kHzを超えると、オプションがさらに制限されたり、より大きな予算が必要になったりします。
【私から】
Zooqu1koさん、そして
OKTO RESEARCHのPavelさん、こんにちは。
Zooqu1koさん、追加のコメントをありがとうございます。
EKIOは、マルチチャネル出力を利用可能なUSBオーディオデバイスのいずれかに割り当てることができます。たとえば、EKIOが個別のASIOドライバーを使用してマルチチャンネルをDAC8PROおよびOPPO SONICA DACに送信できることを確認できました。ただし、この場合は、すべてASIOモードです。つまり、2つのDACが同期していません。私が説明したように、私の友人は2つのDAC8PROを同期して使用したいと考えています。
そして、私と私の友達は間違いなくすべてを192 kHz 24ビットで処理したいと思っています。
(私のシンプルな8チャンネルUSB ASIO-> DAC8PROケースでは、192 kHz 24ビットで完璧です。)
ちなみに、DAC8PROには常にCH-1 + CH-2デジタル信号を出力するAES / EBUデジタル "OUT"が1つあることを知っており、疑問に思っています。このAES / EBU OUTを2番目のDAC8PROのAES / EBU INに接続すると、2つのDAC8PROは自動的に同期しますか?
私はまた、この問い合わせのためにOKTOのPavelにPMします。
*******************************************************************************
書込番号:23476271
![]() 1点
1点
>RME HDSPe AESは、最も安価で、最も面倒なオプションである限り、サポートされているオペレーティングシステムに固執します。
この部分、自動翻訳は正反対に誤訳していますね。
>I assume that the RME HDSPe AES is the both the cheapest and the least troublesome option, as long as you stick to a supported operating system.
正しくは;
「RME HDSPe AESは、それがサポートされているOS上であなたが運用する限り、最も安価で、最もトラブルが少ないオプションだと思います。」
と読めます。
書込番号:23476305
![]() 1点
1点
今、
https://synthax.jp/hdspe-aes.html
を見ていましたが、このボードと、附属(または別売?)の、「各種 D-Sub 25ピン AES/EBUケーブル」(16チャンネル AES/EBU)を使うと、2台の DAC8PRO を同期モードで使えるかも、、、、と思いました。
これ以上の「深入り」は、私の利用環境には不要ですので、あいによしさん(とNaim ND555 enthusiastsさんも?)にお任せします。
もちろん、Pavel さんから反応があれば、ここでもお知らせします。
書込番号:23476327
![]() 2点
2点
あいによしさん、Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
もう一度、正確に整理しておきます。
もともとDAC8PRO は、その名前の通り、プロ向けに開発されたもので;
AES-EBU デジタル入力 8チャンネル
USB 2.0 ケーブル1本による;
USB デジタル入力 8チャンネル
USB デジタル出力 8チャンネル
アナログ(XLRバランス)出力 8チャンネル
に加えて、
AES-EBU デジタル常時出力 ステレオ1チャンネル(CH-1 + CH-2)
RCA アンバランスアナログ常時出力 ステレオ1チャンネル(CH-1 + CH-2) (前面ヘッドフォン出力端子)
が全て備わっていて、これら全てを同時に利用できます。
デジタル I/O は、192 kHz 24 bit まで対応、
USBでの I/O は、1 bit 2xDSD にも対応、
です。
凄いことですね。
書込番号:23476398
![]() 2点
2点
>これ以上の「深入り」は、私の利用環境には不要ですので、あいによしさん(とNaim ND555 enthusiastsさんも?)にお任せします。
私もあいによしさんにお任せ致します!
それにしましても、Okto社の Pavel氏の対応がもっと敏速であれば良いといつも思うのですが、同社には広報担当者が他にいないのでしょうか。
まあ、これは私の悲観する問題ではありませんが。
書込番号:23476451
![]() 1点
1点
ASR における Zooqu1ko氏によるコメントを Google Translate (Firefox) にて自動翻訳させたら以下のようになりました。
まあまあですね。
------------------------------------------------------------------------------------------
EKIOにどんな制限があるのかわからないので、そもそも複数の異なる「サウンドカード」への出力をサポートしていないかもしれません。 AES / EBUの16以上のチャネルを持つ単一のインターフェースがおそらく最善の策です。 これは一種のプロオーディオの問題であり、プロオーディオフォーラムやプロオーディオストアでより多くの資格のあるヘルプが利用可能になることを期待しています。 さらにいくつかの提案があります。 こちらhttps://www.soundonsound.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=60373
RME HDSPe AESは、サポートされているオペレーティングシステムを使用している限り、最も安価で問題の少ないオプションだと思います。
予想されるサンプリングレートは明確ではありませんが、48kHzを超えると、オプションがさらに制限されたり、より大きな予算が必要になったりします。
-------------------------------------------------------------------------------------------
書込番号:23476506
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
Google Chrome より Google Translate の方が、まともですね。
さて、添付画像、ご参考まで。
ご教示いただいた、CALIBER DAP アダプタ、本日到着しました。
しっかりしていて、いい感じです。
書込番号:23476562
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんにちは。
>ご教示いただいた、CALIBER DAP アダプタ、本日到着しました。
しっかりしていて、いい感じです。
CALIBER DAP adapters の存在は、英国にある Graham Slee 社という、特にヘッドフォンアンプで有名な会社から教えて頂きました。お役に立てて光栄です。
閑話休題:別のスレを立ててそこで詳しく言及していますが、Network Audio (Streaming Audio) 関連機器として
Network Switch, Ethernet cables で良いものがやっと見つかりました。
それでは、Okto DAC8 Pro に関しましては、今後も dualazmakさんとあいによしさん御両者間の意見交換を私としましては第三者として楽しみにしております。
それでは、また。
書込番号:23476659
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
>別のスレを立ててそこで詳しく言及していますが、Network Audio (Streaming Audio) 関連機器として
Network Switch, Ethernet cables で良いものがやっと見つかりました。
ご連絡、ありがとうございます。時折、拝見させていただきます。 先ほども、眺めさせていただきました。非常に参考になります。
PCネットワーク環境には、私も、かなり以前から拘っておりまして、私が住んでいる千葉県市原市で光ケーブルを引き込んだのは我が家が第1号でありました。現在の光環境では、常時、上り下りとも 400 Mbps 以上の速度ですので、非常に快適で、YouTube や KUSC のストリーミングが途切れることは、まずありません。
宅内のルーター&大元ハブには、少し高価でマニアックな、マイクロ総合研究所の8ポートGBタイプ MR-GL2000 を愛用しており、宅内LANは、スマホ利用(5G無線Wi-Fi アクセスポイント)以外は、全てCat-6 以上のGB有線LANの主義でして、全部で7台あるハブ(8ポート、16ポート)も、もちろんGB対応です。
また、仕事と趣味を兼ねて使っている3台のワークステーションには複数の LANポートや LAN ボードを持たせて、独立系統の 10 GB LANで連携したりしております。
こと音響関係については、今のところ、「しっかり音楽を聴く」にあたっては、デジタル信号であれ、アナログ信号であれ、音楽信号がLANケーブルやSW HUB を流れることは、断固忌避する主義で、PCオーディオに徹しています!,,,,
と断言したいところなのですが、お知らせしたように、最近では、BGM的に YouTube や KUSC もよく聴いていますので、その意味では、音楽信号がLANケーブルやSW HUB を経由していることは、否めません(笑)。
一方では、TV関係は(も)、数年前から全て光TVにしており、TVのみならず宅内の全PCおよびスマホでも視聴できるように、また外出先や必要なら海外からも視聴できるように、LAN内にピクセラの XIT-AIR100W を置いたりしておりますので、これは、もう完全に LANやHUBに依存しています。地上デジタル、BS/CSデジタル、全チャンネルの快適な視聴が可能です。
現在は、全ての非圧縮音源ファイルを、バックアップの意味も兼ねて、いくつかのPCのSSDおよびNAS に多重保存していますが、今後、純粋 Hi-Fi 音響関係も、少しずつネットワークオーディオに移行する可能性は十分にありますので、Naim ND555 enthusiastsさんの Network Switch, Ethernet cables スレッドは、大いに参考にさせていただきます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23477357
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
5200レンタルの交渉力はすごいですね、週末(週明け?)のDAC8PROとのインプレッションに注目しています。
未だ練られたLCネットワークに分があるけど、アンプ直結のマルチの可能性は高いとかを予想します。
遮断特性はリンクウィッツ、ベッセルを散々いじりましたが、うちではバターワース-48dB/octでスパっと切って凸凹をパライコで補正した方が、すっきりにごらずで好印象でした。
書込番号:23477884
![]() 2点
2点
あいによしさん
>5200レンタルの交渉力はすごいですね、週末(週明け?)のDAC8PROとのインプレッションに注目しています。
>未だ練られたLCネットワークに分があるけど、アンプ直結のマルチの可能性は高いとかを予想します。
はい、楽しみです。
よく考えると、アキュの E-460 も温存していますので、例えば中音域を広くカバーするベリリウムSQを E-460 で駆動し、WOは MX-A5200 のBTL(CH-3+CH4 のブリッジ)で駆動する、などの組み合わせも、試してみる価値があるかも知れません。
何しろ、NS-1000 のベリリウムSQは、歪みがほとんどない非常に優れもので、かなり広い音域をカバーしているので、E-460 の感触を維持するには最適かも。。。。
いずれにしても、LCネットワークを取っ払った音を聞くのは、感動なのでしょうね。
特にWOのスピード感とクリアさに期待しています。
>遮断特性はリンクウィッツ、ベッセルを散々いじりましたが、うちではバターワース-48dB/octでスパっと切って凸凹をパライコで補正した方が、すっきりにごらずで好印象でした。
そうですか。とても参考になります。
特に「すっきりにごらずで好印象」(!)、と聞くと、試してみたいですね。こちらでも、EKIOの様々な configファイルを作って試してみます。
BW 48 dB/Oct の場合、各帯域チャンネル間での「位相」は、どのように調整されていますか? どのフィルターで位相反転をチェックされていますか?1つ飛びでしょうか?
EKIO の印象は如何ですか?
私のようなチャンデバ初心者には、簡潔さに徹したEKIO の設計と機能、そして安定した動作は、使いやすく、分かりやすく、好ましいと思っております。
書込番号:23478142
![]() 1点
1点
あいによしさん
ASR で、例の Zooqu1ko さんから、応答がありました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-433544
以下、Goole Translate による自動翻訳です。
*************************************************************************
本日3:29 AMNew#1,609
【dualazmakさんのコメント:
ちなみに、DAC8PROには常にCH-1 + CH-2デジタル信号を出力するAES / EBUデジタル "OUT"が1つあることを知っており、疑問に思っています。このAES / EBU OUTを2番目のDAC8PROのAES / EBU INに接続すると、2つのDAC8PROは自動的に同期しますか?】
マニュアルによると、それはうまくいくはずです。
【DAC8PRO マニュアルの内容
USB / A
USB / AESは、1番目のAES / EBUから復元されたマスタークロックを使用してUSBホストからのオーディオデータ転送のペースを設定する独自の動作モードです。これは、AES / EBU入力によって回復されたデータが8つのUSB入力チャネルを介して完全にビットホストのUSBホストに転送され、記録または処理してUSB出力チャネルに送り返して再生できることを意味します。 DAC8 PRO。
UAC2オーディオデバイスはUSBホストの現在のサンプリング周波数を変更できないため、受信したAES / EBU信号のサンプリング周波数がUSBホストで選択されたものと一致しない場合、DAC8 PROは警告メッセージを表示します。 AES / EBU送信デバイスのサンプルレートをUSBホストのUAC2ドライバーのサンプルレートに一致させるのはユーザーの責任です。】
したがって、1つのDAC8PROをPure USBモードで実行し、AES / EBUを2番目のDAC8に接続して、その1つをUSB / AESモードで実行します。
*************************************************************************
OKTO の Pavel さんからは、まだ応答がありませんが、何か回答があれば、お知らせします。
書込番号:23478165
![]() 2点
2点
あいによしさん
Zooqu1koさんのコメントの最後の部分は、
「したがって、1つのDAC8PROをPure USBモードで実行し、AES/EBUを2番目のDAC8に接続して、その2番目の DAC8PROを USB/AESモードで実行します。」
ということですね。
私の予想が、うまく機能することを祈っております!
書込番号:23478201
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんにちは
同期のご確認ありがとうございます。
dualazmakさんの規模ですと2台運用もありえると思います。
>各帯域チャンネル間での「位相」は、どのように調整されていますか?
マイクで音を拾って、以前お知らせしたフリーソフトで波形確認です。
>EKIO の印象は如何ですか?
プロ機のRAMSAやベリンガーに比べ、動作を止めないと操作は出来ません、ASIOを再認識させないと飛んでしまったり、プロ機の音を途切らせない考えかたとは違い脆弱さを感じます、DBX VENUは音場補正付きだし、プロ機と比べるとコスパは微妙ですが、オーディオ機器アキュのチャンデバと比べると圧倒的に安いと思います。
うちのイコライザーは1chで8バンドしかなく、EIKOはchもバンド数も事実上制約なさそうなところは魅力です。動画再生と併用すると処理落ちするので音専用のPCはほしいと思っています。
書込番号:23478224 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 2点
2点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
丁度いいタイミングで、私が支援しているこのグループの、素晴らしい4Kビデオがアップされました。
https://www.youtube.com/watch?v=hb1_GaI-1yI
録音も、なかなかの優れものです。
是非、視聴、試聴してみてください。 この手の音楽が、お嫌いでなければ、ですが。。。。
実は、このコンサートの観客の中には、、、、、
書込番号:23478708
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんにちは。
コンサートビデオのご紹介誠にありがとうございます。
今週末にそれを楽しもうと思います。
もしかしましたら、このコンサートの客席にdualazmakさんも観客のおひとりとしてご鑑賞されていたのではないかしら?
それでは、明日からのYAMAHA amp の御試聴結果を私も楽しみにしております。
取り急ぎお礼まで。
追伸: Okto DAC8 Pro 2機の同期がとれたという状況下で、EKIO が直ちに16CHとして DAC8 Pro を認識出来るのか、私にはその点が不案内です。
書込番号:23478753
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
>追伸: Okto DAC8 Pro 2機の同期がとれたという状況下で、EKIO が直ちに16CHとして DAC8 Pro を認識出来るのか、私にはその点が不案内です。
私も、不案内です(笑)。 Windows WDM または ASIO4ALL または DIYNHK USB ASIO が16チャンネルを認識さえすれば、EKIOは、そのどれにでも出力できるのですが、、、、
あいによしさんにお任せしましょう!。 EKIO以外にも、色々お使いのようですので、あいによしさんの2台の使いこなしを楽しみにさせていただきます。
書込番号:23478782
![]() 2点
2点
あいによしさん
DAC8PROが届いたのが5月9日でしたが、それから1ヶ月上経った本日、FedEx から請求書が来ました。
関税 0円
消費税 3500円 (課税標準額69326円の 7.8%で10円未満は切り捨て)
地方消費税 1400円 (課税標準額5300円の 22/78 で10円未満は切り捨て)
取扱手数料 1000円 (FedEx社の取り分)
合計 7700円
です。関税は非課税としながらも、ちゃっかりと消費税の名目で課税されるのですね。
東京税関長名の輸入許可証明書が添付されていて、EUR仕入価格に対する消費税の計算詳細なども書かれていますが、こんなもののようです。
スマホでバーコード読み取り−クレジット払い
または
FedEx ビリングオンラインに登録して、オンラインでクレジット払い
または
添付の振込用紙で、コンビニで現金払い
の3つの支払方法が使えますが、最も安全で確実そうな、「コンビニで現金」で支払いました。
もちろん「払込受領証明」部分とコンビニのレジ受付明細は、しっかりと保存します。
ご参考まで。
書込番号:23479295
![]() 1点
1点
訂正です。
関税 0円
消費税 5300円 (課税標準額69326円の 7.8%で10円未満は切り捨て)
地方消費税 1400円 (課税標準額5300円の 22/78 で10円未満は切り捨て)
取扱手数料 1000円 (FedEx社の取り分)
合計 7700円
です。
書込番号:23479303
![]() 2点
2点
dualazmakさん、Naim ND555 enthusiastsさん、こんばんは
関税関係6%でしょうか、消費税よりは安い感じ、
以前の個人輸入は郵便為替で送金したりで大変でしたが、
今はとても楽ですね。
>16CHとして DAC8 Pro を認識出来るのか、私にはその点が不案内です。
>あいによしさんにお任せしましょう!。
人柱っぽくグッドラックといわれたようで、なぜか気分がすぐれません。。。
書込番号:23479653
![]() 2点
2点
皆さん、
まずは、速報です。
YAMAHA MX-A5200 デモ機による試聴検証を完了しました。
MX-A5200 は、マルチチャンネルアンプとして、機能的には完璧に動作しますが、残念ながら、アキュフェーズE-460+LCネットワークシステムとの比較試聴において、音質や総合的音響品位の観点では、一聴して、ほとんど全ての面で、かなり劣っており、私のプロジェクトでは、使えません(使いません)。 ましてや、マイクを持ちだして各種測定を行う気持ちにも、なれませんでした。
詳細は、今から、各種の画像も含めて ASRスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
で報告してから、また、今晩、こちらに戻ってまいります。
「反面教師」の観点では、非常に有意義な機会でした。
少なくとも、アキュゲーズ E-460 と同等か、それ以上の性能と音響品位のアンプでなければ、私のマルチアンプ環境では、全く使えないことを深く学んだ2日間でした。
それほどまでに、EKIO, DAC8PRO, E-460(!)、自作 LCネットワーク、NS-1000+YST-SW1000+T925A の現況が非常に優れており、最適化されていることを深く再認識させられました。
のちほど、今晩にでも、いろいろ意見交換させていただきます。
書込番号:23482835
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんにちは
最適化がポイントだと思います。
>マイクを持ちだして各種測定を行う気持ちにも、>なれませんでした。
何か大きな問題があるかもしれません
測定して、違いは何かを調べられたらいかがでしょうか?今後の機器の入れ替えで有意義だと思います。
書込番号:23482946 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんにちは。
>MX-A5200 は、マルチチャンネルアンプとして、機能的には完璧に動作しますが、残念ながら、アキュフェーズE-460+LCネットワークシステムとの比較試聴において、音質や総合的音響品位の観点では、一聴して、ほとんど全ての面で、かなり劣っており、私のプロジェクトでは、使えません(使いません)。 ましてや、マイクを持ちだして各種測定を行う気持ちにも、なれませんでした。
ということでしたか。
ASR 最新投稿を拝見致しました。その結果ですが私にはさほど驚きはございませんでした。
今後も旅路を前に前にと進めて下さい。
前進あるのみです!
それでは、また。
書込番号:23483059
![]() 0点
0点
あいによしさん
ASRでの報告を、一通り終えて、戻ってきました。
色々トライしたのですが、やはり、MX-A5200 を E460 に対応させること自体が、どだい、無理なように思います。
どうやっても、僅かではあるが顕著な、スモキーさ(濁り感)、ブーミー感、分解能の低さ、音像定位感の悪さ、が残ります。
Reference Sound System に戻すと、まさに、梅雨空から梅雨明けの素晴らしい快晴に移った感があります。
MX-A5200試聴機(新品ではない)に問題があるのかも知れませんが、やはり、AVアンプを使うことは、当面、諦めました。
まずは、7月下旬に DP-NC400-4 2台(新品をお借りできます)を試してから、次のステップを考えます。
それほどまでに、現在の Reference System の総合品位が高いのですが。。。。
書込番号:23483065
![]() 1点
1点
訂正です。
色々トライしたのですが、やはり、MX-A5200 を E460 に「対抗させる(競わせる)」こと自体が、どだい、無理なように思います。
失礼しました。
書込番号:23483068
![]() 1点
1点
dualazmakさん、Naim ND555 enthusiastsさん、こんにちは
音の抜けですか、本質的にお金がかかる部分でとてもやっかいだと思います。
書込番号:23483093 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 2点
2点
皆さん、
もう一度、再確認のために、全てのケーブル接続を慎重にやり直しまして、また MX-A5200 の背面の小さなディップスイッチ類の設定も、もちろん電源オフ状態で完璧に確認し、再試聴していますが、総合評価は変わりませんね。
あくまで想像ですが、背面に沢山あるRCA -XLR 切り替え、ブリッジ設定切り替え、インピーダンス切り替え、チャンネル連結切り替え、などのディップスイッチは、音響信号が通るにもかかわらず非常に小さくて、心許ない気がします。
このあたりの部品の選択なども、総合的な音のクリアさ、分解能、抜けの良さ、などに微妙に影響しているのかも知れません。
7月17日頃に、無料で試聴させていただける DENTEC DP-NC400-4 2台の音響品位が、非常に楽しみです。
いずれにしても、MX-A5200 を自宅試聴せずに購入しなくて、正解でした。
ここまでシステムを追い込んでくると、アンプの素性を明快に、鋭敏に、反映するので、アンプの選択は、本当に難しいことを痛感しております。
Apollon の Purifiモジュールデジタルアンプ、この環境で試してみたいものです。
書込番号:23483765
![]() 1点
1点
皆さん、
3月か4月だったか、例のSPケーブル切替ボードを制作した際に、4連装のトグルスイッチ(たしか耐圧600Vのもの)を使って、SPラインを切り替えることを試したのですが、その際にも、今回のアンプと似たような音響の曇り、濁りを経験し、速攻でトグルスイッチを取っ払って、ターミナル端子で強固なネジ止めによるケーブル切り替えにしたところ、嘘のように曇りと濁りがなくなりました。
このときに、トグルスイッチの内部構造などを散々調べたら、高電圧回路を通電状態のままで切り替える際に発生する恐れがあるアーク放電を接触金属版からサイドへ逃すために、かなり強力な、小さな永久磁石を内蔵していることを知りまして、これが音響劣化の原因であろうと推測しました。
同じ要因ではなさそうですが、MX-A5200 の、あまりにも小さな、沢山のディップスイッチは、音響劣化の何らかの原因になっているのではないかと想像しております。
書込番号:23483815
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは
アキュを投入が効果的なのはどこだったでしょうか?うちでは700〜6.5kHzでした。
書込番号:23483887 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
途中でかきこんでしまいまいした、
次に効果があったのは150〜700Hzでした。
ここにパイオニアのアンプを入れると厚みと抜けが改善するのですが、オーディオ的な色付も感じました。
書込番号:23483906 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
あいによしさん
>アキュを投入が効果的なのはどこだったでしょうか?うちでは700〜6.5kHzでした。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-436135
の最後の方で、NS-1000 のベリリウムドームミッドレンジ(スコーカー;Be-SQ)だけをアキュの E-460 で駆動して、他のSPs は全て MX-A5200 で駆動した様子を、簡単に報告しています。やはり、そのレンジだけ(EKIOのMONOスイッチでSQだけ聴くと)、クリアーで分解能が格段にアップしました。カバー領域は、 600 - 6,000 Hz ですので、あいによしさんの場合と全く一緒ですね。
何しろ、 NS-1000 は、非常に優れた Be-SQ と Be-TW が最大の特徴と「売り」でして、特に Be-SQ は全カバー域と大音量でも歪みがほとんどゼロで、世界中のスタジオでも長く使われた大きな理由のひとつです。この音域は、人の耳でも最も感度がいいので、アンプの特性や素性を、モロに反映して聴き取れますね。
書込番号:23483932
![]() 1点
1点
>あいによしさん
>次に効果があったのは150〜700Hzでした。
>ここにパイオニアのアンプを入れると厚みと抜けが改善するのですが、オーディオ的な色付も感じました。
なるほど、です。
ようやく、マルチアンプシステムの共通言語と共通感覚でお話ができるようになり、嬉しく思います。
マルチチャンネルアンプの選定、慎重に進めます。
なんだか、初心に戻って(?!)プリメイン E-380 を3台、なども試してみたくなってきました。これも、無償で貸し出し、なんて虫のいい話は、なさそうですが。。。。
いっそ、この際ですので、アキュに再度、直談判してみても、とも思いますが、先日ちょっと打診した際には、3,4台を同時に試聴貸出は前例がない、とやんわり拒否されました(笑)。
書込番号:23483954
![]() 1点
1点
dualazmakさん、おはようございます。
>まずは、7月下旬に DP-NC400-4 2台(新品をお借りできます)を試してから、次のステップを考えます。
>7月17日頃に、無料で試聴させていただける DENTEC DP-NC400-4 2台の音響品位が、非常に楽しみです。
次回はご期待通りの結果が得られると本当によろしいのですが。
もし、万が一、思った結果が得られなかった場合には DENTEC さんの対応が...(それは考えたくないですね)
老婆心ながら、「隣の芝生はもう青くは見えない」ことを願っています。
書込番号:23484378
![]() 1点
1点
dualazmakさん、Naim ND555 enthusiastsさん、こんにちは
>もし、万が一、思った結果が得られなかった場合には
>E-380 3台
ありえますね、すごい金額になりそう
アンプは1種類がベーシックな考え方ですが、マルチは必要帯域のポイント投入でいいような気もします(スピーカー帯域ごとに能率もアンプに要求される特性も違ってくると思います。)、どうしてもアキュフェーズ ならPX-650の中古をさがされてはいかがでしょうか?
書込番号:23484740 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
確かに、マルチ環境は整ったので、柔軟に運用&対応できますね。
ASRフォーラムあたりでも、中音〜高音〜超高音の帯域では、小パワーの球管アンプを愛用している人の拘りも、頻繁に目にいたします。
じっくりと試行錯誤するのも楽しい、と発想を変えて、球管アンプも視野に入れつつ、色々試してみたいと思います。
書込番号:23484799
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんにちは。
ASR におけるdualazmakさんの投稿の内容を時系列で追ってみますとかなりのダッチロールの連続であることが見て取れます。
第三者的に見ますとdualazmakさん一体何を目指してそれをどのような過程を踏んでいかに実行するかがあまり明らかでないように感じます。
ASR の他のメンバーも出来ることならdualazmakさんに示唆を与えたいとは思っているのでしょうが、ダッチロールの繰り返しによる制御不可能な状況を見ると、彼らも多少とも困惑しているのではないかと思います。
最近の YAMAHA amp の試聴結果もこのアンプが劣っていたとしか不明ですし、どこがどう劣っていたのかを丁寧に説明しないと第三者であるASRメンバーには到底理解されぬと思われます。
YAMAHA社にも誇りがあると思います。劣っていたという言葉は同社にとってどう感じられるのでしょう。
次回はDENTECですか。DENTEC社のオーナーとの関係が最終的に気まずくならぬことを願っています。
なお、DENTEC amps の試聴結果につきましてはこのスレッドではなく ASR にて拝見させていただきます。
老婆心ながら、苦言を述べさせていただきました。
書込番号:23485016
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、こんにちは
思慮不足すみません。
書込番号:23485141 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
アイコン訂正
書込番号:23485146 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
Naim ND555 enthusiastsさん
>老婆心ながら、苦言を述べさせていただきました。
ありがとうございます。
ここでも、ASR でも、私としては、step-by-step で首尾一貫している心づもりなのですが、読者の視点からのご指摘は、非常にありがたく存じます。
YAMAHA MX-A5200 に関する ASR での「私の結論」は、あくまで Reference Sound と比較した私の感触ですので、少し書き直しておきました。
一方、主観的な比較や、客観的な「測定論議」に深入りすると、ASRの;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-to-trust-ear-or-measurement.13696/
のような、非常に興味は深いのですが、終わりのない議論に陥ることが明らかなので、敢えて a little bit inferior, with my ears の詳細に立ち入ることは避けています。Nabussan さん、Burinig Sounds さん、Keesさん、Kees Huizingaさんあたりから、そのうちに反応がありますので、必要に応じて簡潔に応答するつもりです。(すでにPMシステム経由では、いくつか頂戴しております。)
ASRの私のスレッドについては、時折、PMシステムで ASRの数名の重鎮の方々(Mitchcoさんも含む)とも、継続の是非を含めて相談させていただいておりますが、閲覧回数が14,000回を超え;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc
日々、ご覧いただいている方も多いようで、教育および啓発の観点からも、図解や写真での紹介や解説を重視した私のスレッドは、是非とも継続して欲しい旨を("should be the best thread of the year in member area?"とも)伺っておりますので、しばらくは継続しますが、メーカー名を特定した上での比較検討の記載については、ご指摘の旨に慎重に配慮いたします。
もっとも、ASRでも、 DIY AUDIO でも、遙かに辛辣な表現や不調法法な投稿や評論は多々見られますが、私としては、Naim ND555 enthusiastsさんの御主義と同様に、「数少ない日本からのactive参加者として」も、各方面に配慮し、紳士的で、マルチシステムの初心者にも有意義なスレッドとして、しばらく続けてみたいと存じます。
さて、このスレッドは、「スピーカーなんでも」 のカテゴリーですし、皆様の貴重なご支援にも支えられて、 NS-1000, YST-SW1000, T925Aのスピーカー群を使った私のプロジェクトでは、ソフトウェアチャンデバEKIOと DAC8PRO によるマルチ環境の構築は、既に完全に達成され、今後はマルチチャンネル対応のアンプを試行錯誤して選択する段階となりましたので、もはや「スピーカーなんでも」の範疇には馴染まなくなりつつあることも自覚しております。
また、このスレッドと ASRスレッドを並列で主催することも、かなり負担になりつつありますので、今後は、英語のみになりますが ASRでの情報交換へ重心を移す方向へ「徐々に」移行する方針です。(ブラウザーのAI翻訳も、そこそこまともになってきていますし。。。)
特に、Naim ND555 enthusiastsさんからも、たびたび貴重な情報をいただいているように、Hypex や Purifi のデジタルアンプモジュールを使ったマルチチャンネルアンプについては、欧米のフォーラムサイトで情報交換すべき、と強く感じております。 そういえば、2月上旬時点における OKTO DAC8PRO の「発見」と、その後の導入経緯も、その側面が強い状況と推移でございました。。。
ただし、このスレッドは、敢えて「終了」や「締め」の宣言はいたしませんので;
ソフトウェアチャンデバ、ソフトウェアチャンネルデバイダー
ソフトウェアクロスオーバー、
EKIO、
マルチチャンネルDAC、
DAC8PRO、
マルチチャンネルアンプ、
マルチチャンネルスピーカー駆動、
NS-1000、NS-1000M、YST-SW1000, T925A
などのキーワードに馴染む話題についての情報交換の場として、引き続きご利用いただきたく存じます。
もちろん、必要に応じて、私も応答、参加させていただきます。
また、プロジェクトの新たな進展、特にマルチチャンネルアンプの評価や選択について ASR の私のスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
で詳しく書き込んだ際には、その旨を、ここでも簡潔にアナウンスさせていただきます。
書込番号:23485768
![]() 2点
2点
あいによしさん
DAC8PRO の2台同期利用については、新たな情報が入りましたら、ここでもお知らせいたしますが、可能であれば、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
の現在の最後の81ページあたりとそれ以降を、時折、眺めていただくと、情報の投稿があるかも知れません。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/page-81
もちろん、ASR のPM(個人間メールシステム)でOKTO社のPavelさんから連絡があれば、必要に応じてお知らせ申し上げます。
書込番号:23487872
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは
ご連絡ありがとうございます、はやく来ないかと思っているのですが、順番待ちですね。
>マルチチャンネル対応のアンプを試行錯誤して選択する段階
日本のソフトチャンデバでたぶん草分けだと思います。運用で気付き等ありましたらご開示をお願いします。
書込番号:23488650
![]() 1点
1点
あいによしさん、
了解です!
皆さん、
ASR のPMシステムで、時折、あのご高名な Mitchcoさんとお話ししていますが、Posさん、Igor Kirkwood さんともお話しさせていただいていたので、そろそろスレッドに少し本格的に参加してくれるようにお願いしておりました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-9
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-10
遅まきながら、今日、知ったのですが、Pos さんは、例の RePhase ソフトの開発者であるらしく、Igorさんは、Mitchcoさんと同様に、かなり著名なサウンドエンジニアで、ご自分のプロスタジオを運営されているようです。
Posさんが、さかんに RePhase での測定や調整を強調されていたのは、当然だったのですね。
さらに驚いたことに、Igor Kirkwoodさんは、ご自身のスタジオモニターとして YAMAHA NS-1000 を愛用されており、マルチアンプ環境を構築されている(いた)そうで、私のプロジェクトに大いに注目してくれています。Posさんと Igorさんの間でも、かなり専門的な FIR, IIR あたりの議論が始まっています。
ASRの私のスレッドにおける御両所の専門的な議論の進展については、私のような初心者は、おそらく眺めさせていただくだけになりますが、非常に参考になりそうです。
Kirkwoodさんによると、NS-1000 の Be-SQ, Be-TW は、非常に応答特性が優秀で歪みも最少なので、FIRでも、IIRでも、うまく設定すればかなり急峻なフィルターを設定しても、位相問題は発生しにくい、とのことです。私には、詳細の厳密な理解は困難ですが、どうやら NS-1000(改)をメインSPとしてマルチチャンネル対応を進めている私のプロジェクトの方向性は、あながち間違っていないようで、少し安堵していります。
今後、Posさん、Kirkwoodさん、Mitchcoさん、を含む皆さんから、私のプロジェクトについても、非常に有意義な提案や示唆が得られそうで、大いに期待しております。
書込番号:23488925
![]() 1点
1点
非常に驚いたことに、Kirkwoodさんの経験では、YAMAHA NS-1000 の Be-SQミッドレンジでは、500 Hz あたりで 12 dB/Oct で切るよりも、375 Hz あたりで 80 dB/Oct でスパッと切ることもお勧めだそうです。
EKIOでは、48 dB/Oct が最大傾斜ですが、DP-NC400-4 が来たら、375 Hz で 48 dB/Oct も、是非、試してみたいと思います。やはり、NS-1000 の Be-SQ、恐るべし。。。。
書込番号:23488983
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは
>375 Hz あたりで 80 dB/Oct でスパッと切る
40年以上前、マルチでJBL2440+2350(カットオフ220Hz)を使って350Hzくらいでつなぐのが流行ってました。
うちもマルチアンプシステム/ 出原 真澄さん (アキュフェーズの創業メンバー)の著書が出て感化されてました。
(当時は-24dB/octだったかも)
クラシックではコーンのまとわり付いたような音をきらって、ホーンを下げて使い(350Hz)
ジャズではマッシブな華やかさを狙って高めでつないでました。(1kHz)
周波数を下げてみるとエネルギーのあるホーンの音が細くなり、コーンに負け始めます。
コーンはD130の流れをくんだE120を使っていましたが、3kHzくらいは余裕でホーンみたいな鳴りっぷり、どこでもつながってしまう感じでした。(E120は低音がぜんぜん出ないので、SWが必要)
>EKIOでは、48 dB/Oct が最大傾斜
アキュは-96 dB/Oct行けたけど、-48 dB/Oct ですでに切った先は無音みたいな感じなので-48 dB/Oct で充分だと思います。
(フィルターの次数は6の倍数なので-80はかなり不思議な感じです)
マルチは何でもありなのですが、ユニットは余裕のある帯域を使い、相互干渉しないようにスパッと切ってつなぐ、周波数の凸凹はパライコで細かく補正(余裕のある帯域なので可能)、ユニットの取付け位置の差は、音の波形の山を揃えるようにタイムアライメント補正がよいと思います。
375 Hzをネットワークで試すのはほぼ不可能(スパッとつながないと振幅大で壊す)、マルチだとユニットの限界が引き出せますが、飛ばすこともあるのでお気を付けください。(音量が小さいとけっこう行けますが、うちは調子に乗って、ツィーターやミッドバスを飛ばしました。)
書込番号:23490065
![]() 1点
1点
あいによしさん
もろもろ、ありがとうございます。非常に参考になります。
Kirkwood さんの -80dB/Oct は、私も不思議に思っていますが、プロ用機材(または Kirkwood さんのDIY?)では、傾斜が無段階可変のフィルターなども、あるのかも知れませんね。
Be-SQ のローカットで375Hz は、確かに少し怖いですね。現在が 600Hz -12dB/Oct ですので、やはり500Hz以下の設定は、傾斜をきつくしても破損の可能性があるので、慎重に考えます。というか、私のレベルでは、避けた方が無難に思います。いまさら、Be-SQ を中古で部品調達して交換、などは絶対に避けたいので。。。
Kirkwoodさんは、何度も破損させながら、ギリギリの設定を追い込んだ上での発言かも知れません。そのあたりも、あいによしさんのご助言で、察しがつくようになってきました。用心、用心、ですね。
書込番号:23490193
![]() 0点
0点
あいによしさん
それから、例の保護コンデンサー;
68μF for Be-SQ,
10μF for Be-TW,
10μF for ST T925A
は、当面、安全のために堅持いたします!
書込番号:23490205
![]() 1点
1点
>例の保護コンデンサーは、当面、安全のために堅持いたします!
それがよいです、ドームスピーカーはホーンドライバーより振幅には強いと思いますがベリリューム振動板は貴重ですので。
書込番号:23490285
![]() 1点
1点
あいによしさん
あいによしさんがDAC8PROを2台(!)発注されたこと、および DAP8PRO のAES/EBU出力(CH1+CH2)で2台目との同期が取れること(ほぼ確実!)、に触発されて、私も、「2台目の購入」には向かってはおりませんが、他のDACとの同期接続に惹かれております。
とにかく、私のマルチ化環境では 192 kHz 24 bit 処理が可能であれば、いいわけですので。。。。
DAC8PRO のマニュアルや、巷の記述を見ると、「一般的に、またプロ業界では、」 AES/EBU でデジタル信号を受け取るDAC機器(やDDC機器)は、「AES/EBUで供給される同期信号を使ってDAC処理を行う」ので、そのDAC機器の内蔵クロックジェネレーターによる(同期)信号は利用せずに、受け取った AES/EBUの同期信号に従ってDAC処理を行う、と理解できます。
以前にもお知らせしたように、現在、私は、DAC8PRO1台以外にも、
OPPO SONIDA DAC 1台、
ONKYO DAC-1000(S) 1台、
KORG DS-DAC-10 3台(リスニングルームに1台、書斎に1台、アメリカ帰りで戸棚保管が1台)、
を持っており、中でも ONKYO DAC-1000(S) は、古い機種ではありますが、192 kHz PCM の処理においては、現在でもトップクラスの音響品位を持つと言われておりますし、私もそれを如実に実感しております。
また、添付画像のように、DAC-1000(S) は、AES/EBUデジタル入力を含む、豊富な入力系統を持っておりますので、DAC8PRO のAES/EBU出力(CH1+CH2) を DAC-1000(S) に繋ぐと、DAC-1000(S) がDAC8PROと「同期」するか、否か、に大きな興味がございます。
もし、この方法で DAC-1000(S) が DAC8PRO と同期するのであれば、現在 DAC8PRO のヘッドフォンOUTからアダプター利用 RCAアンバランスで左右のサブウーファーYAMAHA YST-SW1000 へ入力しているRCAラインを;
DAC8PRO CH1+CH2 (AES/EBU デジタル出力) → DAC-1000(S)でDAC処理 (RCAアンバランス) → 左右のYST-SW1000へRCA入力
に切り替えることが可能になります。しかも、マスターボリュームは、もちろん DAC8PROが担当できます。
原状の DAC8PRO ヘッドフォン端子からの RCA接続でも十分に機能はしているのですが、やはり前面端子でのアダプター変換は、少々不格好(目障り)ですので、可能であれば避けたいところなのです。
そこで、念のため、確認のために、オンキヨー株式会社へ次の質問を入れてみました。
***************************************************************************
オンキヨー株式会社 御中
貴社 DAC-1000(S) を愛用させていただいております。
現在、マルチチャンネルオーディオシステムにて、源流のWindows 10 Pro PC内部のソフトウェアチャンデバ(クロスオーバー)で、すべて 192 kHz 24 bit でクロスオーバー(チャンネルデバイダー)処理を行い、8チャンネル(ステレオ4-way)を8チャンネルのマルチチャンネルDACである OKTO 社のDAC8PROへ導いてDAC処理させております。
さて、この DAC8PRO には、1系統の AES/EBUステレオ出力があり、CH1+CH2 のデジタル信号が常に出力されております。
もし、この AES/EBUデジタル出力を DAC-1000(S) の AES/EBU入力に接続した場合(実際に可能で機能することは確認済みです)、OKTO DAC8PRO と DAC-1000(S) は、DAC処理において「同期」しているか、否か、をお伺い申し上げます。
一般的には、AES/EBU でデジタル信号を受け取るDAC機器は、「AES/EBUで供給される同期信号」を使ってDAC処理を行うので、その機器内部(この場合は DAC-1000)のクロッククジェネレーターによる同期信号は利用せずに、受け取った AES/EBU信号に従って同期したDAC処理を行うと理解しておりますが、この理解でよろしいでしょうか?
具体的な利用目的ですが、利用しているサブウーファー(左右2台)が RCAアンバランス入力を持っているので、DAC8PROとマルチアンプによるステレオ4-way(8チャンネル)によるウーファー+サブウーファー(CH1,CH2)、スコーカー(CH3,CH4)、ツイーター(CH5,CH6)、スーパーツイーター(CH7,CH8)駆動に加えて、DAC8PRO のAES/EBU出力(=CH1,CH2)をDAC-1000(S) に繋ぎ、そこから RCAアンバランスで左右のサブウーファーへ入力いたします。利用している左右2台のサブウーファー(YAMAHA YST-SW1000)は、ボリューム機能および可変ハイカットフィルターを内蔵しておりますので、55Hzでハイカットいたします。
この際に、DAC8PRO と DAC-1000(S) が DAC処理において「同期している」ことが必要になる、というわけです。
何卒よろしく、ご回答のほど、お願い申し上げます。
***************************************************************************
ONKYOから回答があれば、その内容など、共有させていただきます。
書込番号:23492062
![]() 0点
0点
あいによしさん
先ほど(18時頃に)オンキヨー株式会社のカスタマーメールサポートチームから回答が来ました。
その主旨は;
「基本的にはDAC8PROからの信号がデジタルオーディオインターフェースの規格である IEC60958 に則ったデジタル信号であれば、DAC-1000の入力は同規格に準拠しているものとなります為、齟齬は生じないと思われます。」
とのことです。
もちろん、DAC8PROは、プロ用途も想定されているDACですので、そのAES/EBUデジタル出力は、IEC60958 に完全に則っており、従って DAC-1000(S) は、 DAC8PRO と「同期する!」、となります。
実際に、昨晩〜今朝、JRiver→EKIOの音楽再生で、DAC8PRO の AES/EBUデジタル出力(CH1+CH2)を ONKYO DAC-1000(S)に繋ぎ(専用のASIOドライバーをASIO4ALL & EKIOがきちんと認識して出せます)、そこからRCAアンバランスで左右のサブウーファー YST-SW1000 へ入力して、他のSP群の音(EKIO の8チャンネルXLR出力を束ねて CH3+CH4へ → E-460 → SP群)と共に、長時間連続で鳴らしていましたが、同期の「ずれ」や「ドリフト」は全く発生しておりませんので、DAC-1000(S)は DAC8PRO と完全に同期していることが、実際にも確認できました。
これで、サブウーファーへのRCA入力は、他のSP群と完全に「同期させて」、DAC-1000(S)から流すことができることが確定しました。
つまり;
「1台目の DAC8PROの AES/EBUデジタル出力(CH1+CH2)を、2台目の DAC8PRO、または2台目の他のDAC(AES/EBU入力あり)へ入力することで、最初のDAC8PROと2台目(以降)のDACを同期させることができる。」
ことが確認できました。
あいによしさんが目指されている、 Windows 上で、ASIO4ALL, WDM または DIYNHK USB ASIO が、2台のDACの16チャンネルを、同時に、どの方法で、どのように、認識できるかは、もう一つの課題ではありますが。。。。 少なくとも、私が必要としているDAC8PRO の CH1+CH2 の信号を DAC-1000(S)で「同期再生」することは、可能となりました。
これは、DAC8PROを使い始めている世界的にも少数の方々にとっても、有益な情報であると考えられますので、ASR の私のスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
で「閑話休題」的に紹介すると共に、本件に関して先日来Zooqu1koさんと情報交換している;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/page-81
でも、近日中に簡単に触れておきます。
書込番号:23492888
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんにちは
>私も、他のDACとの同期接続に惹かれております。
>先ほど(18時頃に)オンキヨー株式会社のカスタマーメールサポートチームから回答が来ました。
行動力がすごいですね、8chだと不足だし追加は必要なケースも多いと思うのですが情報が少ないですね。
うちはFirefaceも8chあり192/24も通るのですが、
今使っているチャンデバがRAMSAの4chを何台も入れてるので、DAC8ならすっきり、の考えです。
ソフトチャンデバの方が何でもありの高機能でよさそうだし、
EKIOと対になり、マイクでf特と位相回転を測定し、EIKOに補正値を渡せるソフトがあれば面白そうですね。
書込番号:23493573 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
あいによしさん
ひとつ、訂正です。
>しかも、マスターボリュームは、もちろん DAC8PROが担当できます。
と書きましたが、これは間違いでして、DAC8PRO の AES/EBUデジタル出力(CH1+CH2)は、CH1+CH2 デジタル信号のスルー出力ですので、DAC8PRO のボリュームおよびゲインは効いていません。
つまり、もし2台目のDACが得たこの CH1+CH2の音響信号を、(同期目的だけではなく)実際に音として利用する場合は、その先における音量コントロール(例えばサブウーファー内蔵のボリュームによる調整)が必要になります。
この点では、私のシステムの場合には、やはりDAC8PRO のヘッドホン出力からRCAで取って、YST-SW1000へ繋ぐ方が、DAC8PROを完全にマスターボリュームとして使えるので、便利ではあります。
書込番号:23495798
![]() 1点
1点
あいによしさん
もちろん、DAC以降の下流の音量バランスを一旦適切に固定して、源流のPC上のチャンデバソフト(EKIOなど)をマスターボリュームとして使うなら、問題なしですね。
書込番号:23496188
![]() 1点
1点
あいによしさん
ご参考まで;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-440802
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-440984
書込番号:23498883
![]() 1点
1点
皆さん、
サブウーファー YST-SW1000 へのRCA入力を、DAC8PROからAES/EBU同期信号(CH1 + CH2)を受ける DAC-1000(S) で行うことにしましたので(全て 192 kHz 24 bit)、再度、マスターボリュームコントロールについて検討し、JRiver (または Roon)でコントロールすることでも、ビット落ちや音質劣化がない(問題とならない)ことを確認しました。
詳細は、こちらをご覧下さい。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-448875
書込番号:23515818
![]() 1点
1点
早速、ASR の常連/重鎮から反応があり、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-449248
以降で、USB や BT (Blue Tooth) 接続のボリュームコントローラーを JRiver (やRoon ?)で利用することについて、情報交換が行われております。
DROK;
https://www.amazon.co.jp/Mini-%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%96-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-PC%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%94%A8-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B07FJMR9R7/ref=sr_1_fkmr2_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=drok+usb+%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0&qid=1594069788&sr=8-1-fkmr2
は、うまく使えそうです。有線USB接続ですが。。。
私は BTは嫌いで、有線USB派ですので、使ってみようかと思案中です。
書込番号:23517275
![]() 0点
0点
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-450001
にも書きましたが、JRiver の上部コントロール領域内のどこかにマウスポインター(マウスカーソル)がある際には、マウスのホイールも 0.5 dB ステップのボリュームコントローラーとして機能するのですね。
これは、多くの方々にとっては、当たり前の機能かも知れませんが、最近までJRiver のボリュームコントロール機能を使用してこなかった私にとっては、「遅ればせながら」の嬉しい新発見でした。
マウスポインターをJRiver の上部のどこかに置いておくことが前提ではありますが、この機能が使えることは、私(もちろん無線マウスを常用)には非常に便利で、DROKなどの USBボリュームコントローラーを購入する必要性は低くなりつつあります。
書込番号:23518604
![]() 0点
0点
あいによしさん、皆さん、
先ほど、ASRにて OKTO社のPavel さんの書き込みがありました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-450024
私の質問と、それへの回答は、次の通りです。
***************************************************************
dualazmak said:
By the way, I am just aware of and wondering that we have one AES/EBU digital "OUT" in DAC8PRO which always gives CH-1 + CH-2 digital signal; if we would connect this AES/EBU OUT into AES/EBU IN of the second DAC8PRO, then the two DAC8PROs would be automatically in sync, or not?
I will also PM to Pavel of OKTO for this inquiry....
dualazmak の問い合わせ:
ちなみに、DAC8PROには常にCH-1 + CH-2デジタル信号を出力するAES / EBUデジタル "OUT"が1つあることを知っています。このAES / EBU OUTを2番目のDAC8PROのAES / EBU INに接続すると、2つのDAC8PROは自動的に同期しますか?
私はまた、この問い合わせのためにOKTOのPavelにPMします。
Pavel さんの回答:
I confirm this is going to work for syncing two units set to receive audio data over USB. The unit set to "Pure USB" mode will become a "master" unit, providing its clock to the other one, set to "USB/AES" mode, which will accommodate its frequency of data requests to the USB host in a way to be fully in sync with the signal received over its AES/EBU input. We have yet to test how a USB host running Windows will cope with two units and whether Thesycon, ASIO4ALL or both drivers will need to be used.
これは、USB経由でオーディオデータを受信するように設定された2つのユニットを同期する場合に機能することを確認しています。「Pure USB」モードに設定されたユニットは、「マスター」ユニットになり、「USB / AES」モードに設定されたもう一方にクロックを提供します。これにより、USBホストへのデータ要求の頻度に対応できますAES / EBU入力で受信した信号と完全に同期している。Windowsを実行しているUSBホストが2つのユニットにどのように対応するか、Thesycon、ASIO4ALL、または両方のドライバーを使用する必要があるかどうかはまだテストしていません。
***************************************************************
ということで、私の確認検証を追認してくれた形です。
Windows 上で、USB接続された2台の DAC8PROがどのように認識されるか、されないかは、残念ながら「まだテストしていない」そうですが、OKTO社では DAC8PRO のファームウェアーと専用の ASIO ドライバーの改良アップデートを進めていることも、別途、聞いていますので、早晩、AES/EBUで同期させた2台の DAC8PRO の16チャンネルを認識するようになるかもしれませんし、それを期待しております。(私のプロジェクトでは、当面、8チャンネルで事足りておりますが・・・)
取り急ぎ、お知らせします。
書込番号:23518820
![]() 0点
0点
あいによしさん
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-450063
で Pavel さんへ感謝すると共に、私の検証結果とその利用についても知らせておきました。
また、2台のDAC8PRO を AES/EBU digital (CH1+CH2) OUT/IN で同期させた状態で、Windows 10 PCから、2本の USB 2.0 ケーブルで両方のDAC8PROに繋いだ際に、専用ASIOドライバー DIYNHKASIO が16チャンネルを正しく認識するかどうかを試して下さい、もし正しく16チャンネルを個別に認識しないなら、DIYHNK ASIO ドライバーを改良/アップデートして、16チャンネルを認識するようにして下さい、との希望も伝えておきました。
書込番号:23518918
![]() 0点
0点
あいによしさん、皆さん、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-450024
における Pavelさんの最後の回答、すなわち Dacapaloozaさんの疑問である;
「なぜ DAC8PRO には、(同期)クロック入力端子がないのか?」
に対する回答は、重要で、非常に示唆に富むものです。
**************************************************
As answered in one of the subsequent posts, the AES/EBU or SPDIF signal already contains the clock. More than that, the AES/EBU or SPDIF frequency is equal to 2x the bit rate (or 128x sample rate), which (even though it has the biphase-mark coded audio data on it) makes it much easier for the receiver (and less prone to errors - jitter) to recover the bit clock from than from a slow word clock supplied through a separate connector. The dac8 PRO uses a combination of a very good receiver chip and Sabre's jitter eliminator in order to achieve the specified performance, even when using its AES/EBU inputs (regardless of whether AES/EBU or SPDIF signal is being fed to them). SPDIF and AES/EBU are, unlike UAC2 USB, synchronous protocols, so a significant timing error would lead to immediate loss of sync or audible sample drops.
I am afraid that there is a strong similarity between the idea of clocking in the pro audio and luxurious cables in the consumer audio. Trying to keep DACs fed with AES/EBU signal in sync using an external word clock kind of reminds trying to improve sound quality with directional cables placed on elevators.
先の投稿の1つで回答(私=dualazmakの質問への回答)されているように、AES EBUまたはSPDIF信号にはすでにクロックが含まれています。それ以上に、AES/EBUまたはSPDIF周波数は2倍のビットレート(または128倍のサンプルレート)に等しく、バイフェーズマークでコード化されたオーディオデータが含まれている場合でも、レシーバー(信号を受ける機器)ではるかに簡単です(そしてエラー(ジッター)が発生しにくいため、別のコネクタを介して供給される低速のワードクロックからビットクロックを回復できます。 dac8 PROは、AES/EBU入力を使用している場合でも(AES/EBUまたはSPDIF信号が供給されているかどうかに関係なく)、指定されたパフォーマンスを達成するために、非常に優れたレシーバーチップとSabreのジッターエリミネーターを組み合わせて使用​​します。 SPDIFとAES/EBUは、UAC2 USBとは異なり、同期プロトコルであるため、重大なタイミングエラーが発生すると、同期が失われたり、サンプルの音が途切れたりします。
プロオーディオでのクロッキングのアイデアとコンシューマーオーディオでの豪華なケーブルには強い類似点があると思います。外部ワードクロックを使用してAES/EBU信号が供給されたDACの同期を維持しようとすると、エレベーターに設置された指向性ケーブルを使用して音質を改善しようとしていることがわかります。
**************************************************
書込番号:23519008
![]() 0点
0点
皆さん、
このスレッドでのレス(返信)数が自己レスを含めて190件に達しました。
返信数が200件に達すると、それ以上の返信ができなくなるようですので、新スレッドへ移行いたします。
【続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム 】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab
にて、引き続き、よろしくお願い申し上げます。
なお、ここでも、英語ですが、情報交換を行っておりますので、ご覧いただき、ご参加下さい。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
書込番号:23523466
![]() 0点
0点
返信数が200件を超えると、このスレッドには返信できなくなります
「買収協議を開始するための予備契約を締結したと発表」
書込番号:23477407 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
>プリンセス・オブ・ザ・クリスタルさん
https://www.phileweb.com/news/audio/202006/13/21756.html
ここで見ました。
書込番号:23477430
![]() 1点
1点
>kockysさん
ファイルウェブ(`・ω・)b
書込番号:23478595 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
皆さん、
昨年末から、下記それぞれのスレッド;
【複数のプリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道か?】
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284
【続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776
【チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab
【ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIO】
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
にて貴重な情報交換をさせていただき、その結果として、
PCソフトウェアであるLUPISOFT社のチャンネルデバイダー(クロスオーバー)EKIO;
http://www.lupisoft.com/ekio/
http://downloads.lupisoft.com/ekio/EKIO_user_manual.pdf
と
ステレオ4-way 8-チャンネル DAC機である OKTO RESEARCH社の DAC8PRO;
https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf
を用いて、
1. Windows 10 Pro 64bit PC内部で、Roon や JRiver MC26 から 192 kHz 24bit のステレオデジタル信号をAD変換なしで EKIO に入力して 192kHz 24bit のままでステレオ4-way 8-チャンネルのデジタルチャンネルデバイダー処理=帯域分割(クロスオーバー処理)を行い、
2. デジタル8-チャンネルをUSBケーブル1本で同時に DAC8PROへ 出力して DAC変換させ、それぞれのアナログ音声信号をアンプ群(ステレオアンプ4台、またはモノラルアンプ8台)に導いて、ステレオ4-way 8-チャンネルのマルチアンプオーディオ環境を構築する、
ことを計画中です。
これに、左右1台ずつの独自アンプ内蔵サブウーハー(YAMAHA YST-SW1000 2台)が加わりますので、実質的には、ステレオ5-way のマルチアンプ環境となる予定です。
現在の私の環境、アンプ、スピーカーの詳細につきましては;
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776
の最初のあたりに詳しく記載しておりますので、ご興味がおありの方はご覧下さい。
再録になりますが、今回のマルチアンプ化の対象であるスピーカー群について紹介します。
構成は、3-wayのメインスピーカー (ウーファーWO、スコーカーSQ、ツイーターTW)に加えて、左右にスーパーツイーターST、およびこれも左右にアンプ内蔵の強力なサブウーファーSWを使い、実質的には5-wayの構成です。
長年愛用しているメインスピーカーは、メンテナンスと改造を重ねて今でも絶好調な YAMAHA NS-1000 です。 NS-1000Mではありません。(NS-1000 の前面バッフル、側板、天板、定番は NS-1000M より 5mm 厚く、背面板は、何と 15 mm も厚く、総重量は 39 kg で
NS-1000M より 8 kg も重くなっています。)
従って;
WO 30 cm コーン
SQ 8.8 cm ベリリウム ドーム
TW 3.0 cm ベリリウム ドーム
です。
https://sawyer.exblog.jp/12639976/
で報告されている方に全く同感で、SQおよびTWのアッテネーターは、-4 〜 -5 dB の設定で WO とのつながり、バランスが最高で、総合能力をフルに発揮してくれており、バリバリの現役です。
http://audio-summit.co.jp/2019/04/04/ns-1000m%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%B4%97%E6%B5%84%EF%BC%89/
http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/
あたりを参考にして、昨年夏にアッテネーターを完全分解&洗浄してオーバーホールし、さらに;
http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/
を参考にして、NS-1000は3端子化して各ユニットに直結し、内部のクロスオーバネットワークとアッテネーターは撤去し、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス化しております。
クロスオーバーは、NS-1000 オリジナルとほぼ同様の;
500Hz,両側 -12 dB/Oct
6000Hz, 両側 -12 dB/Oct
です。
STは、非常に高能率なホーン型 FOSTEX T925A で、アッテネーターは -15 dB あたりで鳴らしております。低域カットは、 1.5 μF コンデンサー一発のみですので、 約 8 kHz, -6 dB/Oct 傾斜で、NS-1000 のTW とかなり重なっていますが、 -15 dB アッテネーター設定で最適化しており、10 kHz 以上で本領を発揮させています。この ST は、NS-1000 のスピーカー架台の中に配置しており、WO と SQ を、TW と ST で上下から挟むという、ちょっと特殊な配置にしております。
左右の SW は、YAMAHA YST-SW1000 2台で、120W 5Ωの強力アンプ内蔵、歪0.01%、カットオフ周波数 30 Hz〜130 Hz 連続可変(-24dB/oct)、レベル調整可能、位相反転可能、全てリモコン操作可能、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過去2回のヤマハでのメンテナンスを経て、いまでも完動、現役です。
ソフトウェアチャンネルデバイダー EKIOは、既にチャンネル数無制限の有償版を入手して試用を開始しており、その「さわり」の状況については、スレッド;
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
の最後のあたりで、少し情報交換させていただきましたで、そちらもご覧下さい。
次の応答欄から、引き続き、準備状況およびマルチアンプ構築状況について情報交換させていただきます。
![]() 5点
5点
BOWSさん、あいによしさん、Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん
先週金曜日に帰国し、3連休は時差調整と体調管理を兼ねて、スピーカー配線(アンプ群選択)の「端子&ケーブル板」を工作しました。添付イメージをご覧下さい。
SPケーブルの「物理的な繋ぎ替え」で、従来の環境と、チャンデバ環境を、簡便に切り替えられるようにしております。
8連装電磁リレーを使って、一挙に、いつでも切り替えられるようにすることも考えたのですが、劣化の可能性がある電磁リレー接点は避け、原始的ではありますが、もっとも確実な「ケーブルのネジ止め繋ぎ替え」で切り替えることにしております。
ご覧のように、チャンデバ−マルチアンプ接続では、少なくとも試行錯誤の間は、ツイーター(TW)とスーパーツィーター(ST)には、保護コンデンサーを噛ませておく予定で、そのための端子ラグも用意しました。
マルチアンプ環境で、TWは 6 kHz以上、STは 9 kHz 以上あたりで鳴らす予定ですので、TW および ST の保護コンデンサーとしては、10μFのフィルムコンデンサーをそれぞれの+ラインに噛ませておこうと思っておりますが、この場合 TW, STの両者について
1.10μFのフィルムコンデンサー1個
2.5μFのフィルムコンデンサー2個を並列
のどちらがお勧めでしょうか?
大きな金色の抵抗器2個は、8Ω 100W の「ダミースピーカー」であり、アンプ群やLCネットワークを、「無音でエージング」する際に使います。
書込番号:23251905
![]() 3点
3点
今後もいつでも聴けるように継続して維持しておく、「LCネットワーク+アッテネーター」では、先日もお話ししたように、WOラインの 47μFコンデンサー2個を、電解コンデンサーからフィルムコンデンサーに変えて、ダミースピーカーを使って、3日間連続で大きな音量出力でエージングしました。
添付写真の、ボックスの底あたりの白い大きなコンデンサー2個が、47μFのフィルムコンデンサーです。
エージングも済ませて、非常に快適な音響品位が得られており、この現在の音響がマルチアンプシステム構築の「基準音響品位」となります。
そうそう、OKTO社の Pavel さんとは、メールで頻繁にやりとりしており、DAC8PRO 受注の確認もしっかり頂戴しました。もちろん、製作と検査を完了して、日本向けに出荷される際には連絡をもらうことになっています。EC圏からの個人輸入ですので、税関では非課税であることを願っておりますが、どうなりますことか。。。。 まあ、課税されても、大した税額にはならないでしょう。
書込番号:23251939
![]() 2点
2点
BOWSさん、皆さん、
お礼を忘れておりましたが、8Ω 100W の金色の「ダミースピーカー」は、
書込番号:23189263
でBOWSさんからご教示いただきました。
これなら、かなり大出力でアンプやLC回路をエージングしても、発熱は微々たるものですので、安心して「無音長時間エージング」でき、とても便利です。
あらためて、ご教示、ありがとうございました。
書込番号:23252055
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは
通過帯域が通ればよいので下記ではいかがでしょうか?
JA-0801:600Hz/66μF/DCP-FC001-1000//Ecap100v-56.0μF
JA-05138:6kHz/6.8μF/DCP-FC001-680
T925A:8.4kHz/4.7μF/DCP-FC001-470
書込番号:23252221 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
訂正JA-05138→JA-0513
書込番号:23252230 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
あいによしさん
ご教示、ありがとうございます。
当面、ツィーター、スパーツイーターに加えて、スコーカーにも保護コンデンサーを噛ませておくべき、と理解しました。
CDP-F シリーズのフィルムタイプ保護コンデンサーは、アマゾンサイトでも;
◆ステレオ誌での各社コンデンサー比較テストにおいて、トップクラスの 評価を得ています
◆高音質設計
◆自作スピーカーに最適
と書かれており、安心して使えそうです。 早速入手して端子板に組み付けます。
3.5SQリード線をハンダ付けし、圧着端子で端子ラグに取り付ける予定です。
書込番号:23252766
![]() 1点
1点
あいによしさん
スコーカー YAMAHA JA-0801 用の保護コンデンサーですが、ECap100V-68μF 1個でも問題なさそうに思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:23252780
![]() 1点
1点
dualazmakさん
精力的に活動されていますね。
オーディオ機器と言うより 電力盤のようで 力強いです。
>1.10μFのフィルムコンデンサー1個
>2.5μFのフィルムコンデンサー2個を並列
この選択ですが、過去の経験から コンデンサ、抵抗等のパーツは 大きい、重い、硬い 方がベターです。
コンデンサスピーカーがあるくらいなんで パーツは微振動するので 大きい、重い、硬い 方が余計な付帯音がつかなくて、静かです。
そういう意味でオススメが
JantzenAudio フィルムコンデンサー Superior Z-Cap10.0μ \7,569
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27414815
ですね。
カマボコくらいのサイズでデカイですが、この真っ赤なコンデンサは良いです。
今セール中なのでかなりお得です(ふだんは\9,800くらい)
さすがに この値段が出せない場合は
Mundorf フィルムコンデンサー Evo450-10.0μF
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=124303850
1,861円(内税)
このあたりか
JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap10.0μF \1,110
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27413786
PARCのCDP-Fシリーズは何十個も使っていますが、上記のコンデンサよりやや雑味があるので音を通過するコンデンサよりも、電源のバイパスコンデンサに使うことが多いです。
それと、保護用のコンデンサですが音響用とは言え電解コンだとディテール表現が削がれるのでポリプロピレンコンデンサにしたいところです。かなり高価になりますが...
書込番号:23253131
![]() 2点
2点
BOWSさん
引き続き、よろしくご指導下さい。
>オーディオ機器と言うより 電力盤のようで 力強いです。
はい、スピーカーケーブルやバナナプラグ類は、かなり高価なものを含めて、これまでも色々使ってきましたが。。。。 バナナプラグは絶対に「禁忌」とする主義と境地に到達しております(笑)。
昨年夏のLC外付けボックス化の工作以来、全て撚銅線CVTケーブルに統一し、アンプからLCボックスまでの左右それぞれ7mは、5.5SQ (AWG10) ケーブルで、LCボックス内は、3.5SQ (AWG12) で、そこからSPユニット群への配線は 5.5SQ または 3.5SQ を使い、LCボックス内は全てハンダ結線、アンプやSPへの結線は、JIS規格配電用のニチフ裸圧着端子(錫メッキ銅製)としております。 NS-1000 内部の配線も、もちろん 3.5SQでハンダ結線です。
強固にネジ締め固定しますので、この方式、特に錫メッキ銅製圧着端子、が最も信頼性が高く、経時変化/経年変化も最小化できる、との結論です。性能的にも、予算的/価格的にも、最高の選択であると結論、確信しています。
圧着レンチ(ペンチ)は、定番の LOBSTER AK-15 を使っています。しかし、大量の配線工作では腱鞘炎になりそうなので、充電式ハンディ圧着機 KLAUKE EK50MLJ (ドイツ製で魅力的)を買うことを、本気で考慮中ですが、、、、高価ですね。
https://www.youtube.com/watch?v=9_F7Z7zbwaA
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B1-Klauke-%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E5%9C%A7%E7%9D%80%E6%A9%9F-EK50MLJ-%E5%A5%A5%E8%A1%8C6-4%C3%97%E9%AB%98%E3%81%9525-3%C3%97%E5%B9%859-3cm/dp/B07LGFP1HC
さて、保護コンデンサーですが、保護といっても音響信号が通過するので、仰せの通り、「それなり」のフィルムコンデンサーにするべきか、と考えております。現在のLCボックスでも、「それなり」のフィルムコンデンサーを使用中ですし。。。。。
そこで、以下の選択を想定しておりますが、如何でしょうか?
SQ保護: JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap68.0μF
【メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサー 68.0μF】
7,549円(内税)
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27414037
TWおよびST保護: JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap10.0μF (ご示唆の通り)
【メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサー 10.0μF】
1,110円(内税)
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27413786
これで、(7,549 + 1,110 x 2) x 2 = 19,538円(税込) ですね。
書込番号:23253308
![]() 2点
2点
>dualazmakさん
Jantzen Film Capacitors ですか?
Canada, Ontario に位置する Parts Connexion では現在 25%OFF での提供中です。
https://www.partsconnexion.com/Jantzen-film-caps.html
ついでながら、Parts Connexion にはパーツなどの購入の際にお世話になりました。
御参考まで。
書込番号:23253832
![]() 2点
2点
Naim ND555 enthusiastsさん
>Canada, Ontario に位置する Parts Connexion では現在 25%OFF での提供中です。
>https://www.partsconnexion.com/Jantzen-film-caps.html
ありがとうございます。この店は知りませんでした。
DAC8PROが届くまで、まだ暫くかかりそうなので、保護コンデンサーの入手も急ぐ必要はありません。
現在の為替レート ¥110.45/USD で計算しても、日本で買うより遙かに安価に調達できるので、Parts Connexion へ発注したいと思います。
今後も、特に急がない汎用品の購入では、このサイトを有効利用できそうで、大変嬉しい情報を頂戴しました。
心より感謝申し上げます。
書込番号:23253866
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
>当面、スコーカーにも保護コンデンサーと理解
はい当面です、いじっている時期のポカよけで半年くらい様子見て問題ないと判断されれば抜かれてもよいと思います。最近のアンプはDC漏れとか、高速リレーでスパッと切れてSPを壊すような事はなさそうですし。
>JA-0801 用の保護コンデンサー、ECap100V-68μF 1個でも問題なさそうに思いますが、
電解コンだけでは応答性の問題で音がよくないので、フィルムコンをパラって中高域の改善をねらっています。
Jantzenについては知った上でPARCをすすめています。
PARCも10uF1個\1050-なので、それなり高いですが音は上位グループです。もし落ち着いて余裕が出たら入れ替えて音の違いを楽しむのもありだと思いますが、先々は抜くかもしれず、NS1000卒業でシステム大幅変更やネットワーク回帰の可能性もあります。保護コンに凝るならもっといいムンドルフ MCAPとかありますし、高価なものはいろいろ調べて別途購入がよいと思います。
書込番号:23254149 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
あいによしさん、
および Naim ND555 enthusiastsさん、BOWSさん
>先々は抜くかもしれず、NS1000卒業でシステム大幅変更やネットワーク回帰の可能性もあります。
>保護コンに凝るならもっといいムンドルフ MCAPとかありますし、高価なものはいろいろ調べて別途購入がよいと思います。
ありがとうございます。かなり悩ましいところですね。
あいによしさん、Naim ND555 enthusiastsさん、BOWSさん
実は、先頃交換した WO ライン用の白い大きな 47μF2個(左右で合計4個)は、MUDORF MCAP250-47t です。
大きな容量のコンデンサーを厳密に比較試聴したことがなかったので、ものは試し(!)で、1月末にコイズミ無線で Jantzen CrossCap47.0μF と MUDORF MCAP250-47t を購入して、はじめて比較試聴して、私の環境では MUNDORF MCAP250-47t の方が、特にピアノサウンド低音域の晴明感が、ほんの僅かですが、よさそうに感じたので、これを採用しました。 この辺りも、凝れば凝るほどキリがなく、価格的にも、どんどん上がっていくことを実感しました。
マルチアンプ環境における「保護コンデンサー」は、先々抜きたい!、と思っていますので、本当に悩ましいところですが、マルチアンプ群(ステレオ4台、またはモノラル8台)を最終的に選択して「本プロジェクト」の最終形態に落ち着くまでには、この先まだ少なくとも1年ほどかかりそうですので、そこまでの期間は、アンプ群も交換しつつ(たとえば YAMAHA XM4080 で試行開始?)、
1.チャンデバ−マルチアンプの試行実験
2.現在の E-460→LCネットワーク→SP群で、いつものように「音楽」を堪能
を結構頻繁に、日常的に、行ったり来たりすることになりますので、比較の観点からも、1.のマルチアンプ環境でも、 2.のLCネットワーク環境でも、「同程度の品位」のコンデンサーを使いたい、と考えております。
予算面も度外視はできませんので、総合的に考えて;
SQ保護: JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap68.0μF
TWおよびST保護: JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap10.0μF
とすることにしましたので、ご理解下さい。
皆様からの貴重なご示唆とご教示に、心より感謝申し上げます。
Naim ND555 enthusiastsさん
昨晩遅くに Parts Connexion へ UPS WORLDWIDE SAVER 配送(送料 USD19.95)で発注したところ、今朝には発送完了のメール連絡と、 UPSからもトラッキング番号通知メールがあり、3月2日(月曜日)には配達される、とのことです。 この配達の日取りは、カナダ米国時間なのか、日本時間なのか、???ですが、来週前半には届きそうです。 思いのほか的確、迅速な対応のようですね。 送料を含めても、国内で購入するより遙かに安価で調達できますので、今後も、Parts Connexion は使えそうです。
書込番号:23254694
![]() 2点
2点
皆さん、
私の書斎のサブオーディオシステム環境;
SPは Klipsch ProMedia 2.1 THX、
DACは 24bit 192kHzでは定評がある ONKYO DAC-1000S を単独利用
の PC に;
VB-AUDIO VIRTUAL CABLE,
VB-HiFi CABLE & ASIO Bridge,
EKIO
をインストールし、Roon および JRiver MC26 からの 24bit 192kHz での EKIOへの入力とステレオ4-way 8-チャンネル分割、全チャンネルの DAC-1000Sへの同時同期出力を確認しました。
今週末には、リスニングルームのメインオーディオシステムにて、OPPO SONICA DAC を使って、同様に試験を開始します。
まずは、現在の単独アンプ ACCUPHASE E-460 と LCネットワーク環境使い、EKIO帯域分割設定についての試行錯誤が開始できるのも、EKIOの利点ですね。
取りあえず、EKIOのチャンデバ設定は、添付画像の状態から始めます。
皆さんのどなたかが、同様に EKIO を試して下さると、非常に有益な情報交換が可能になると思われますが、いかがでしょうか??
書込番号:23254718
![]() 2点
2点
>dualazmakさん
Parts Connexion の迅速な対応はよろしかったですね。お役に立てて嬉しいです。
なお、到着予定日時の表示ですが、FedEx の場合は確か「到着地」時間表示であったかと記憶はしていますが、もし間違いでしたらごめんなさい。
UPS もそうかも知れませんね。Tracking サイトでの時間表示を「到着地時間表示」に切り替えればはっきりするかと思います。
また、hificollective という英国のショップもいろいろ商品を揃えているようです。
ただし、このお店は私は利用したことはありませんが、御参考まで。
https://www.hificollective.co.uk/
書込番号:23254916
![]() 0点
0点
dualazmakさん
おおーっ、システムが着々と出来上がってきていますね。
>実は、先頃交換した WO ライン用の白い大きな 47μF2個(左右で合計4個)は、MUDORF MCAP250-47t です。
>大きな容量のコンデンサーを厳密に比較試聴したことがなかったので、ものは試し(!)で、1月末にコイズミ無線で Jantzen CrossCap47.0μF と MUDORF MCAP250-47t を購入して、はじめて比較試聴して、私の環境では MUNDORF MCAP250-47t の方が、特にピアノサウンド低音域の晴明感が、ほんの僅かですが、よさそうに感じたので、これを採用しました。 この辺りも、凝れば凝るほどキリがなく、価格的にも、どんどん上がっていくことを実感しました。
白いコンデンサなのでMundrfだろうなと思っていたんですが、Mcapでしたか
だいぶ値段が違いますね。
この「ほんの僅か」にコストがかかるのはハイエンド・オーディオもコンデンサも同じです。
>マルチアンプ環境における「保護コンデンサー」は、先々抜きたい!、と思っていますので、本当に悩ましい
DC漏れに関して安全なのは、真空管アンプを使うことですね(^o^)
出力トランスからDCは流れません。
市販品だとよっぽどの故障が無い限りDC漏れを起こすようなアンプは無いですけど
>SQ保護: JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap68.0μF
>TWおよびST保護: JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap10.0μF
音色の統一ということでも良いんじゃないでしょうか
Naim ND555 enthusiastsさん
Parts Connexionの紹介ありがとうございました。
やすいですね。特に赤のZ capが
Canadaと言えば、DIgi-Keyに何回も発注しているんですが、Parts Connexionは1回だったか頼んだ覚えはあります。円安にシフトしているので早いうちに頼んだほうが良さそうですね。
書込番号:23254940
![]() 0点
0点
BOWSさん、Naim ND555 enthusiastsさん、あいによしさん、皆さん、
本当に心強い先輩諸氏、ありがとうございます。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
当方、米国で例の研究にも関係しておいたので、先週末に帰国後、念のため、14日間は自宅で「自分を隔離」しており、在宅リモートワーク状態です。 それで、Roon - EKIO でBGM的に音楽を聴きながら、仕事も(!)しております。今のところ、至極健康です。
Roon で聴くストリーミングラジオ局も、BGMにはいいですね。
私は、 KUSC Classical の大ファンです。
https://www.kusc.org/
さて、EKIO の試験運転、非常に面白いですね。
まず、ASIO4ALL, VB-AUDIO VIRTUAL CABLE, VB-HiFi CABLE & ASIO Bridge, EKIO帯域分割、 8-チャンネルUSB-DAC同期出力、の「安定性」ですが、昨晩から20時間連続で鳴らしていましたが、米国での初期テストで経験していた同期ドリフトによる(?)僅かなプツプツ音の発生も皆無で、驚くほど安定しています。全体的な音響品位もとても優れており、このテスト環境では、non-EKIO再生と較べて、聴覚上の差は、全く感じられません。
余談で、再録ですが、Klipsch ProMedia 2.1 THX は安価ですが、非常に優秀で、音色的にも、音響品位的にも、至極「まとも」です。
https://www.audioreputation.com/klipsch-promedia-2-1/
「ニアフィールドリスニング」で、EKIO設定を確認するのには、非常に適したスピーカーであると、あらためて感心しております。
EKIO も、Roon も、CPUに加えて、GPUが使える際には効率的に GPUエンジンも利用しているようです。添付キャプチャーをご覧下さい。
EKIOの Inputs/Outputs パネル上では、8チャンネルそれぞれの solo ボタンをクリックすると、全チャンネル再生から瞬時に単一チャンネル再生に切り替わるので、とても便利で楽しめます。
何度もお話し&ご紹介しておりますが、
”SONY SUPER AUDIO CHECK CD”
https://www.discogs.com/Various-Super-Audio-Check-CD/release/12859958
の各トラックをうまく使うと、ほとんどのパラメーター設定を、聴覚的に確認できます。
特に、トラック20の、『高域リニアリティ・チェック「Bimmel Bolle」古典オルゴール』 は、超高域のみならず、低音域も豊かで、史上希に見る超絶音源(!笑)であり、全域のバランス、定位、位相、ディレイの聴覚確認が、この音源だけで、ほとんど可能です。この音源を8チャンネル個別で、また帯域毎に、鳴らしてみると、チャンデバの設定と性能が一目瞭然かつ一聴瞭然になります。
もちろん、TrueRTA ソフトと測定用マイク ECM8000 も持っており、TrueRTAをシンクロスコープモードで使ってディレイ調整を客観的に測定することもやりたいと思っておりますので、DAC8PROを入手したらご指導をお願いしたく思います。
書込番号:23255056
![]() 2点
2点
皆さん、
本日夕刻に、リスニングルーム、メインオーディオシステム用のオーディオ再生専用PCに EKIO をインストールして試験を開始しました。
DAC8PRO は、まだ入手できていないので、8チャンネル全てをOPPO SONICA DAC へ同時同期入力して、現在のE-460 と LCネットワークボックス経由で再生するというテスト環境です。
このWindows 10 Pro 64bit PCは、オーディオ再生専用の完全ファンレス無音PCで、CPUもさほど強力なものではありません。
M/B: GigaByte Z77MX-D3
CPU: Intel Core i7-2600S (GPU内蔵) 4コア、8スレッド
MEMORY: 16 GB
OS and Software SSD: 512 GB Windows 10 Pro 64bit
DATA SSD: 3 TB
主なオーディオ関係ソフト: Roon, JRiver MC26, AudaCity, TrueRTA, MySpeaker, などなど
これに、
ASIO4ALL
VB-AUDIO VIRTUAL AUDIO CABLE
VB-AUDIO VIRTUAL Hi-Fi Cable / ASIO BRIDGE
EKIO
を管理者権限で順次インストールしました。
(念のために、一つインストールする都度、PCを再起動しています。)
Roon と JRvier は、DSP設定で、全ての音源(PCM も DSD も)を 192kHz 24bit で出力する設定にして、ASIO4ALL へ出力させ、それを VB-Virtual Cable 経由で EKIO に取り込み、4帯域、ステレオ4-way 8チャンネルに帯域分割し、8チャンネル全てを同時同期で OPPO SONICA DAC へ(R, L へ4チャンネルずつ)入力しています。
この状態で、Roon からリアルタイムサンプルレート変換させながら EKIO を動かしている状態は、添付の画面キャプチャーの通りです。
このPC環境でも、添付画像3枚目のように、EKIO のCPU利用率は約16%、Roon のCPU利用率は約7%程度で、PC処理として十分な余裕があり、6時間連続で鳴らしていますが、全く破綻やノイズ発生はありません。
添付画像1枚目の下部の通り、
Roon-RAAT出力用の ASI4ALL のBuffer Size は 2048 Samples、
EKIO入出力用のASI4ALL のBuffer Size は 512 Samples、
の設定で、極めて安定して連続再生しています。
現在の試験は、OPPO SONICA DAC 1台へ全チャンネルを出して、通常の E-460 と LC-ネットワーク経由でSP群を鳴らしていますが、この試験環境でも、クロスポイント、フィルタタイプ、傾斜、ゲイン、帯域ディレイ、などなどを際しながら調整してリアルタイムで聴けますので、面白いですね。
この環境でも、試験的にLO (WO) をゼロ基準にして、MID (SQ)、HI(TW)、および SH(ST) の3帯域を 3〜7 ms ディレイさせてやると、低域のスピード感と全体の音像定位が向上することが、はっきりと聴き取れます。 デジタルチャンデバ設定の面白さと泥沼(?)が、見えてきました。
もちろん、DAC8PROを入手してマルチアンプ環境を構築することが最終目的ですので、いまのシングルDAC-シングルアンプ試験環境でチャンデバ設定を変えて遊ぶのは、あまり意味がないことは、重々承知しているのですが。。。いろいろ勉強できますし、これだけでもハマってしまいそうです。
いずれにしても、私のメインオーディオシステムPCで、ASIO4ALL、仮想I/Oケーブル類、 ROON、 JRMC、 EKIO を、何の問題もなく、余裕を持って、非常に安定して、動かせることが確認でき、ほっと一息ついております。
早く DAC8PROを入手してマルチアンプ環境を試したいのですが、Pavel さんからの出荷連絡はまだありませんし、週明けからは超多忙になりそうで、少々憂鬱です。
書込番号:23257566
![]() 2点
2点
次の課題は、ステレオアンプ4台、または、モノラルアンプ8台の調達です。
試験段階でもステレオ4-way 8チャンネル駆動から始めたいので、中古品かレンタル品から始めて、段階的に進めるべく、いろいろ考察、検討中です。
まずは、DAC8PRO の入手が先決ですので、これが手に入ってから、本格的に動くつもりです。
書込番号:23257578
![]() 2点
2点
今日、OKTO社の受注状況確認サイトにログインしてみたら、私の DAC8PRO のステータスが、"Awaiting Processing" から "Processing" に変わっておりましたので、どうやら製造工程、検査工程、配送予定、には乗っているようです。
ついでに、ペアリングして同梱してくれる DAC8PRO用のリモコン、といっても Apple Remote (価格 25ユーロ)、も今日、発注しました。
書込番号:23258105
![]() 2点
2点
皆さん、
日本時間の26日の深夜にカナダの Parts Connexion に発注した;
SQ保護: JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap68.0μF 2個
TWおよびST保護: JantzenAudio フィルムコンデンサー Standard Z-Cap10.0μF 4個
ですが、なんと、なんと、先ほどUPS便で配達されてきました。もちろん、関税などは取られていません。
時間的にも、国内のネットストアで調達するのと、あまり差がないですね。
書込番号:23258275
![]() 2点
2点
dualazmakさん
早く着いてよかったですね。
Digi-Keyによく発注しますが、時差の関係で金曜の夜にオーダー入れて 月曜に着くことが多いんでそんなもんだと思います。
置いとくのも何なので ツィーター等に使って事前にエージングしておくと DAC8PRO が来た時に、熟れていていいかもしれませんね。
書込番号:23258375
![]() 1点
1点
>置いとくのも何なので
手持ちのDACで始められたらいかがでしょうか?
書込番号:23260196
![]() 2点
2点
BOWSさん、
>ツィーター等に使って事前にエージングしておくと,,,,,
仰せの通りで、ここでもお勧めいただいた黄金の8Ω100Wダミースピーカー、既に端子板に組み付け済み、が大いに役立ちます!
家人にも嫌がられずに、「無音の少し大音量(!)」で、心ゆくまで、徹夜で、いや昼夜連続で、エージングします!
あいによしさん、
>手持ちのDACで始められたらいかがでしょうか?
そうも思っているのですが、明日から超多忙で、、、、、
DAC8PRO の発送連絡があるまで、小休止しようかな、と思っています。
と言いつつも、次の応答欄をご覧下さい。。。。こんな情報も!!
書込番号:23260451
![]() 3点
3点
皆さん、
例の、 DAC8PROの「脅威の性能」レポート;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
の Audio Science Review フォーラムにデビューし、上記報告へ投稿することで DAC8PROの情報共有に参加し始めていますが、そこで、オランダの方から、ソフトウェアチャンネルデバイダー(クロスオーバー)dePhonica (開発者はロシア在住)の情報をもらいました。
これは、EKIOより安価で、もっと手の込んだ設定が可能で、 IIRフィルター と FIR フィルターの使い分けや組み合わせも可能で、FFT FIR では、128 000 までの tap が適用できるようです。 フルバージョンの価格は、69.95ユーロです。
https://dephonica.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=1jK7sJr9i7M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2dBozhhflyA
入力フォーマットも、EKIOよりも柔軟で;
16-bit integer, 24-bit integer and 32-bit floating point
Two input channels and up to 8 output channels
Output to DirectSound, ASIO and Kernel Streaming audio devices
Processing completely in 64 bit floating point precision
EKIOで少し苦労する入出力も、dePhonica では;
Built-in WDM driver for stream input from common audio and video players, browsers, navigation and other software
Built-in ASIO Sink driver for stream input from audio players with ASIO support
Low latency: about 50 msec when using IIR filters and crossover output stream into ASIO device
だそうですので、ASIO4ALL やVB-AUDIOの仮想ケーブル類は不要のようです。
面白そうなので、このdePhonicaでも遊んでみたいのですが、当面時間が取れそうにありません。
また、各種のディープな詳細設定は、私の現在の理解を超えている面も、多々ありそうです。
皆さん、dePhonica お試し、いかがでしょうか?
どなたか、dePhonica で「スレ建て」されませんか? 私も、DAC8PRO が手に入ったら合流しますよ。
これの紹介動画などを眺めていると、もはやチャンデバ(クロスオーバー)処理は、PC内で、GUIで、ハイビットデジタル処理が主流になりつつあるように感じ始めています。
これを使っているオランダの方も、 DAC8PROを発注して到着待ちだそうですので、有用な情報交換ができそう、と期待しています。
超高価な TRINNOV ALTITUDE32 などの出番や市場は、もはや、、、どうなのでしょうね。
書込番号:23260536
![]() 2点
2点
dePhonica Ver3 は、Review Build が無料でダウンロード&お試し可能なようです。
https://dephonica.com/version3/
書込番号:23260567
![]() 1点
1点
>dualazmakさん
>DAC8PRO の発送連絡があるまで、小休止しようかな、と思っています。
もしかしましましたら発送までにはかなりの時間待たされるやも知れませんね。
以下は御参考までに。
https://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/331847-dac8-launch-tour-announcement-10.html
それでは、御幸運を!
書込番号:23263448
![]() 0点
0点
Naim ND555 enthusiastsさん
おはようございます。
OKTO社の Pavel さんとは、(応答はスローモーションですが)メール連絡が維持できており、またオーダー後は、受注サイトにログインして状況確認ができています。
私の発注は2月15日で、オーダー状況表示は、しばらくの間 ”Awaiting Processing" の状態でしたが、2月25日頃に "Processing" に変わっていますので、製造&検査のラインには乗っているようです。
昨年11月20日に、某所で、Pavelさんが;
"We are now building and shipping around 5 DAC8 PROs a week. This number should significantly increase in the beginning of December, so hopefully we will be able to ship the vast majority of orders before Christmas."
と書かれていますので、製造体制が強化されていることを信じつつ、時折オーダー状況を確認しながら気長に待ちます。どれほどのオーダーを抱えているのかは???ですが、、、
私は(も)、この先の数ヶ月間、いや半年以上かな、本業の仕事で超多忙が続きそうですので、ちょうど適切なペースかも知れません(笑)。
書込番号:23263477
![]() 1点
1点
皆さん、
◆EKIO の I/Oの安定性
および
◆EKIO のチャンデバ動作の安定性
について情報共有させていただきます。
例の保護コンデンサー(キャパシター)6個の無音エージング(8Ω100W のダミースピーカーDummy SP 利用)を兼ねて;
1.Roon → VB Audio Hi-Fi Cable → ASIO4ALL → EKIO → ASIO4ALL → OPPO USB ASIO → OPPO SONICA DAC → Accuphase E-460 → Dummy SPs
2.JRiver MC26 → VBAudio Hi-Fi Cable →ASIO4ALL → EKIO → ASIO4ALL → OPPO USB ASIO → OPPO SONICA DAC → Accuphase E-460 → Dummy SPs
の動作について、1.を36時間、2.を24時間、それぞれ連続運転して、「安定性」を検証しました。
結果は、あたりまえではありますが、全く問題なく、非常に安定して I/O およびチャンデバ動作が連続動作しております。
さて、DAC8PRO の取説には添付画像のように、USB/AES/EBU についても書かれておりますので、DAC8PRO が到着した暁に、これをPCに USB接続すると、Windows WMD が8台の USB Audio DAC として認識することに加えて、どうやら AES/EBU オーディオデバイス、または USB-SPDIF オーディオデバイスとしても認識されると考えられます。 これがその通りであれば、VB Audio Hi-Fi Cable は不要で;
Roon → DAC8PRO's USB-SPDIF → ASIO4ALL → EKIO → ASIO4ALL → 8チャンネル DAC8PRO USB WDM (ASIO) → DAC8PRO → マルチアンプ群(ステレオアンプ4台、またはモノラルアンプ8台) → スピーカー群
という I/O の流れも可能かも知れません。
DAC8PRO が到着すれば、まず PC に USBケーブル1本で繋いでみて、Windows 10 Pro の WMD機能が DAC8PRO をどのように認識するのか、よく確かめてみます。
一方、PC内部における EKIO チャンデバ処理(24bit 192kHz)の総合的な「音響品位」ですが、私のテスト環境における試聴では、非常に優れた「音響品位」であると判断できます。 やはり、チャンデバ処理前に AD 変換工程がなく、Roon や JRIver から、直接 24bit 192kHzで EKIOへ入力できることには、音響品位的にも、大きなメリットがあると感じられます。
もし外部チャンデバ、たとえば DBX DriveRack VENU360 や BEHRINGER/ DCX2496 ULTRA-DRIVE PROなどで、アナログ音声信号を入力してAD変換後にチャンデバ処理、さらにDA変換してアンプへ繋いでいる方がおられましたら、いちど、PC内部での EKIO 処理(直接 24bit 192kHzデジタル入力)との「音響品位」の差を比較していただけると嬉しいのですが。。。。。
私=スレ主は、ソフトウエアチャンデバ(まずは EKIO)を使ってマルチアンプシステムを構築することに決定したため、VENU360 や DCX2496 の購入利用の予定はなく、同じ環境での比較試聴はできないのです。
書込番号:23266819
![]() 3点
3点
>dualazmakさん
閑話休題:
Okto DAC8 Stereo を装置の一部に組み込んでいる音質チェックはいかがでしょうか。
https://www.instagram.com/sunshipaudio/
DAC は Okto DAC8 Stereo です。
https://www.instagram.com/p/B9B--h6omWb/
Okto 以外の DAC と思われます。
https://www.instagram.com/p/B8zGBMfoHzI/
書込番号:23267875
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
ありがとうございます。ゆっくり眺めさせていただきます。
Audio Science Review Forum でも、DAC8PRO や DAC8 STEREO の評価や、欧州でのデモツアー(?)が話題になっていますね。
皆さん、
EKIO をトライされる際には、内部処理が 24bit 192kHz ですので、Roon や JRiver からの出力信号 や VB-AUDIO Virtual Hi-Fi Cable の詳細プロパティ(コントロールパネル − サウンド − VB AUDIO Hi-Fi Cable Input ー 詳細)を、すべて 24bit 192kHz に統一しておく必要があります。
もちろん、Roon や JRiver の DSP設定でも、「すべて 24bit 192kHz で出力」に設定し、Roon の Device Setting の "VB-Audio Hi-F- Cable" - "SHOW ADVANCED" でも、"MAX Sample Rate (PCM)" を "Up to 192kHz", "MAX Bits Per Sample (PCM)" を "24" に設定しておくことが無難です。
ASIO4ALLの EKIO panel(タスクバーにアイコンが表示→クリックして展開)で I/Oルート設定を変更した際には、一旦 EKIOのドライバー設定を "None" にしてから、再度 "ASIO4ALL" を選択すると、EKIO は ASIO4ALL 管轄下のルート変更を正しく認識します。
ほんの時折ですが、EKIO起動後に、ASIO4ALL もしくは EKIO が、USB-DAC の正しいコントロールを失っていることがあり、この場合には、EKIO起動後に、USB-DAC の電源をオフにしてからオンにする、または USBケーブルを一度抜いて、また繋ぐ、 を行うことで正しく認識されて、EKIOを PLAY すると、 USB-DAC が 24bit 192kHz 入力にセットアップされる、ということがありました。
いずれにしても、一旦、正しく適切な I/O ルートが確立できると、その後は、極めて安定して動作しています。
書込番号:23268074
![]() 3点
3点
皆さん、
超多忙ではありますが、上で報告したI/Oルーティングの確立に加えて、夜な夜な EKIO のチャンデバ設定の習得&試聴、で楽しんでもおります。
◆シングルDAC +シングルアンプで、EKIOによるステレオ4-way 8-channel チャンデバ マルチアンプ環境をシミュレーションする!◆
です。
従来のEKIOを通さない音響(24bit 192kHz)と、 EKIOで帯域分割(チャンデバ、クロスオーバー)した音響を、同一のシングルDAC +シングルアンプで比較試聴しながら、EKIOのチャンデバ設定を試験&試聴しております。
EKIO は、dePhonicaに較べるとシンプルなチャンデバであり、dePhonica の IIR-FIR 設定のような高度な設定はできませんが、その分、私のようなチャンデバ初心者には分かりやすく、使いやすい、と感じております。
私の環境では、フィルタタイプとしては B/W (Butterworth)型 よりも L/R(Linkwitz-Riley)型の方が、微妙に、僅かに、音の晴明感(ベールの剥がれ方?)の点で、好ましいようです。
添付画像は、ディレイ、ゲインをなども含めて、現在、最も好ましく感じられる EKIO の設定です。
これらの設定で、晴明感や音像定位は non-EKIO音響と同等かそれ以上に優れており、また中音域〜高音域〜超高音域の設定パネルで少しのディレイを設定することで、超低音域〜低音域の晴明感とスピード感が改善されている印象があります。
DAC8PROが到着したら、そして、マルチアンプ群も準備できましたら、このあたりのEKIO設定から試してみたいと思っておりますが、これらの設定をご覧になって、チャンデバ先輩諸氏のご意見やコメントが頂戴できれば幸いでございます。
書込番号:23269675
![]() 2点
2点
皆さん、
上の 書込番号:23266819 において;
>さて、DAC8PRO の取説には添付画像のように、USB/AES/EBU についても書かれておりますので、DAC8PRO が到着した暁に、これをPCに USB接続すると、Windows WMD が8台の USB Audio DAC として認識することに加えて、どうやら AES/EBU オーディオデバイス、または USB-SPDIF オーディオデバイスとしても認識されると考えられます。 これがその通りであれば、VB Audio Hi-Fi Cable は不要で;
>
>Roon → DAC8PRO's USB-SPDIF → ASIO4ALL → EKIO → ASIO4ALL → 8チャンネル DAC8PRO USB WDM (ASIO) → DAC8PRO → マルチアンプ群(ステレオアンプ4台、またはモノラルアンプ8台) → スピーカー群
>
>という I/O の流れも可能かも知れません。
と書きましたが、この点について、Audio Science Review Forum にて、既にDAC8PROを入手されている「名うて」の常連の方から確認を頂戴しました。
Windows 10 は、WMD 機能で DAC8PRO を8台のUSB-DAC として認識することに加えて、1台の USB/AES/EBU/SPDIF タイプLINE AUDIOデバイスとしても認識するとのことです。 したがって、VB-Audio Hi-Fi Virtual Cable は不要になります。
Roon や JRiver から、この LINE AUDIOデバイスへ出力し、それを ASIO4ALL経由でEKIOに入力できる、となるはずです。
書込番号:23269749
![]() 2点
2点
皆さん、
もし私と同様に、 ASIO4ALL と VB-Audio Hi-Fi Cable との連携 I/O で EKIO を試されるなら、もう一つの留意点(忘れがち)があります。
Windows - コントロールパネル - サウンド - Hi-Fi Cable Input ー プロパティ - 詳細 で、"24ビット、192000 Hz (スタジオの音質)" を選択することはもちろんですが、その下の排他モードのチェックボックスは、外しておく必要があります。 これは、Roon (または JRiver) と ASIO4ALL (とEKIO) が、同時に Hi-Fi Cable Input を使うことを許容する必要があるからです。
書込番号:23271347
![]() 3点
3点
dualazmakさん、こんにちは
準備着々ですね、ゆくゆくはdePhonicaとの比較をされるのでしょうか、ソフトチャンデバというのは可能性が高そうですね。
昨今は映像付きコンテンツが増えており、外部からPCにSPDIFが入った場合のソフトチャンデバのレイテンシが気になりますね。
ファンレスの専用小型PCでM.2 SSDにOS入れて不要ソフトを停止すれば、ハンドシェークのミスもなく家電並みの扱いになるかもしれません。(ソフト供給元と国内専売の代理店契約でも結ばれては?)
書込番号:23272617
![]() 1点
1点
あいによしさん
こんばんは。
>ファンレスの専用小型PCでM.2 SSDにOS入れて不要ソフトを停止すれば、ハンドシェークのミスもなく家電並みの扱いになるかもしれません。
私のリスニングルームにおけるオーディオ再生専用PCまさにそれで、小型ではありませんが、完全ファンレス、OSとソフトは 512 GB SSD に、音源は 3TB SSD に、搭載しております。それで本格的にEKIOをテスト中です。
DAC8PRO到着に備えて、サブウーハー(SW)YST-SW1000 は、これまでは E-460 のプリアウト接続から、ウーハー(WO)スピーカーレベルの分岐(WOへの入力端子で分岐してWOとSWへ入力)に変更しており、EKIOの低音域はローカットしていませんので、WOは 45 Hz あたりから、 SWは20 Hzあたりから、綺麗に鳴っています。
SW YST-SW1000 は、ボリューム、可変ハイカット(現在65 Hz設定、-24 dB/Oct)、位相反転、それぞれの機能を内蔵しているので、最適化は、今までと同様です。 YST-SW1000 には、ラインレベルまたはスピーカーレベルの、いずれかの入力ができるので、大変便利です。内部に強力な120W 低音駆動専用アンプを持っており、スピーカーレベル入力は4.7kΩの抵抗を介して内部アンプへ入力されますので、ライン入力でも、スピーカーレベル入力でも、音質やスピード感に差はありません。
これで、DAC8PRO とアンプ群(ステレオ4台、またはモノラル8台)が揃えば、例の端子板上でSPケーブルをつなぎ替えるだけで、ステレオ4-way 8-channel, これに左右のSWも加えると、ステレオ 5-way 10-channel のマルチアンプ環境が構築できる準備が整いました。
現在も、実質的には、シングルアンプでステレオ 5-way 10-channel のSP群構成ですので、それを一挙にマルチアンプ化できることになります。
これに向けて、EKIOのチャンデバ(クロスオーバー)設定を、事前に、同じSP群でシミュレーションできているのは、非常に幸いです。
大晦日以来、あいによしさんや BOWSさんが、何度も 「24 bit 192kHz処理で、ディレイ=タイムアラインメントも含めた最適なチャンデバ処理とマルチアンプ環境が構築できれば、その晴明感、音像定位に、驚嘆されることでしょう。」 と仰せであったことが、そろそろ、テスト環境でも、如実に実感できております。 ありがとうございます。
さて、今後の最大の課題であるアンプ群(ステレオ4台、またはモノラル8台)の調達ですが、DAC8PROの到着を待たずに、一挙に候補の新品を揃えてしまおうか、とも思い始めているのですが、やはり DAC8PRO が手に入ってから、粛々と進めるべし! と、焦る心を押さえる、なだめる、毎日です。
何しろ、E-460 も温存しますので、DAC8PROが到着したら、8チャンネル全てについて、E-460 を使って、各チャンネルの「音出し確認!」こそが、最初にやるべきことですよね。。。。
>(ソフト供給元と国内専売の代理店契約でも結ばれては?)
そこまでは。。。。(笑)
私自身は、一人のアマチュアオーディオフリークとして、マルチアンプ環境で音楽を楽しめれば、それで十分に幸せである、と考えております。
OKTO社にしても、EKIO の LUPISOFT社にしても、dePhonica にしても、いまやインターネット上で、国境など関係なしの事業展開と商品展開ですので、もはや、いまや、国内専売代理店などという枠組みは、意味をなさないのではないかと考えております。
もっとも、私の場合は、ソフトもハードも、あらゆる情報交換も、全て英語での対応で(様々な意味で日本語よりも楽なので)、このように気楽なのですが。。。 日本語化が必須なら、その対応も含めた国内代理店などもあり得るのかも知れませんが、営利ベース、採算ベースには乗らないでしょうね。
前スレッドでもお話し&ご紹介した、国内で例のLAN伝送ベースの高価なマルチアンプシステムを開発販売されている、あのご高名な方とも、情報交換を継続しているのですが、先週、EKIO や dePhonica の情報もお知らせしたところ、「貴殿のように、PC上での I/O環境とチャンデバソフトの設定が可能な方なら、今や、PC+ソフトウェアで現在最高レベルのチャンデバ(クロスオーバー)処理ができる時代になっています。」、との心強いコメントも頂戴しました。
書込番号:23273461
![]() 3点
3点
あいによしさん、皆さん、
PC内部で、Roon や JRiver MC26 から、直接 24bit 192kHzで EKIOへ入力できることが確認、確立できましたので、、、、
昨晩遅くには、Roon や JRvier を立ち上げずに、一般的なwebブラウザー、つまり Google Chrome、MS Internet Explorer、MS Edge などで、ストリーミングラジオや、YouTube の高画質高音質ビデオコンテンツをストリーミング再生する際に、きちんとEKIOを通してチャンデバ再生できるかを検証しました。
これは、非常に容易で、完璧に可能です!
VB-Audio Hi-Fi Cable は、Windows 10 のWMD機能によって "Hi-Fi Cable Input" というサウンドデバイスとして認識されますので、これを Windows 10 における「既定の通信(再生)デバイス」に指定し、詳細設定で「24ビット、192000 Hz (スタジオの音質)」を指定、排他モードをチェックオフしておけば、webブラウザーは、この"Hi-Fi Cable Input"に 24bit 192kHzでサウンドを出力しますので、それを ASIO4ALL経由で EKIO に入れてやるだけでチャンデバ処理させることができる、という至極当たり前でシンプルな I/Oです。
添付画像は、YouTube の最高画質(4K)&最高音質のビデオクリップをストリーミング再生している状況と、ストリーミングラジオ局を再生している状況です。ブラウザーは、いずれも Google Chrome です。
最高画質(4K)&最高音質のビデオクリップのストリーミング再生で、サウンドをEKIOでリアルタイムチャンデバさせても、動画とサウンドがずれる、シンクロしない、ことは、一切ありません。
当たり前ではありますが、この観点においても EKIO は軽快で、優秀で、安定しています。
書込番号:23275115
![]() 2点
2点
dualazmakさん、こんばんは
>ディレイ=タイムアラインメントも含めた最適なチャンデバ処理、テスト環境でも、如実に実感
聴感で合わせたのでしょうか?すごいですね
測定で答え合わせもいかがでしょうか?
フリーソフトで音を出しEMC8000でひろって遅れを測るだけ、例えばウーファーとスコーカーを
600Hzでクロスさせた状態にする。
WaveGraph:600Hzの正弦波を1波長だけ描く
Audacity:1波長をチャンデバ経由アンプ、スピーカーへ出力(発音録音同時に可能、Lch出力、RchEMC8000)
SPwave:録音データ読み込み、サブmSで出入力の時間差測定
測定系を変えずウーファー、スコーカーとも600Hzで測り、差分がディレイ補正の対象です。
書込番号:23014670
オシロがベターかもですが、ディレイの差分なら使えると思います。
書込番号:23277274 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
dualazmakさん
サボっていてすみません。
精力的に活動されていますね。
ぼくも あいによしさん とおなじく一度測ってみたらと思います。
極端な話、音楽のような連続波なら アライメントが1波長ズレていても気が付かないので
せっかく正確にタイムアライメント調整する究極の手段手に入れたのだから最後まで詰めないと...
で、単発サイン波の測定ですが、提唱者の一人の別府さんが自身の記事で書かれています。
http://www.aedio.co.jp/beppu/RG/RG1996-6pp59-65.pdf
また、スピーカー作成記事で ほぼ理想形を測定されています。
http://www.aedio.co.jp/beppu/RG/RG1997-9pp34-39.pdf
この最後のページ(なぜか2枚ある)
これはオシロで観測した波形ですけど、録音して波形見ればリアルタイムじゃないけど見ることは出来ます。
ちなみに、あいによしさんが書いているようにwave Geneとかで単発サイン波のデータを作成しても、DAC通す時にデジタルフィルターで前後に尾ひれが付いた音がスピーカーから出てくるので こんな波形にはなりませんし、さらに振動板の共振とかいっぱい盛った波形になります。
でも、タイムアライメントを少しづつずらせていると いちばんきれいな波形になるはずです。
書込番号:23277361
![]() 3点
3点
あいによしさん、BOWSさん
おはようございます。 ありがとうございます。
はい、 「そろそろ、そう来るだろうな?!」 と予想しておりました。
私も、現在のシングルDAC−シングルアンプのテスト環境でも、ECM8000 を持ち出したい衝動を必死に押さえております。
一方では、NS-1000のSP達の性能も、人間の(私の?)聴覚も、なかなかの優れものであると再認識させられております!
例えば、EKIOで、フィルタタイプを B/WからR/Lに変えても、減衰傾斜を 6 dB動かしても(位相も変化)、一つのクロスを 50 Hz ずらしても、ゲインを1 dB上下させても、一つのディレイを 1 ms変化させても、リスニングポイントで、それぞれの微妙な音響の変化をきちんと聴き取ることができます。ちょっとした感動体験ですね。
ただし、御承知の通り、現在のテスト環境は、シングルDAC−シングルアンプであり、チャンデバした信号はアンプで増幅後、まだ 「 LC+アッテネーター」ネットワークボックスを通っておりますので、ECM8000を持ち出して「測定」するのは、やはり DAC8PRO+新アンプ群 が揃ってからにしようと、強く自制しております(笑)。 本業の仕事(研究)も、超多忙状態ですし。。。。。
今、ECM8000を持ち出せば、確実に、睡眠時間が致死的に減ります!
聴覚に頼った EKIOチャンデバ設定ですが、やはりSony Technology Laboratory "SUPER AUDIO CHECK CD" の数々のテスト音源;
https://www.discogs.com/Various-Super-Audio-Check-CD/release/12859958
が、非常に役立ちます。 特に;
トラック2: 位相チェック
トラック3: 5点定位
トラック8: サインスポット 20Hz〜20kHz
トラック9: サインスイープ 20Hz〜20kHz
トラック10: オクターブ・バンド・ノイズ・スポット
トラック12: ピンクノイズ
トラック20: 広域(いや、超低域〜超高域)リニアリティ(と位相)チェック;巨大古典オルゴール(高音エネルギーが超絶)
を聞きながら、各帯域ごとに調整、(時折、左右別々に各チャンネルごとに調整)、最後に全帯域を音出し調整すると、「ECM8000による測定は不要かも?」と感じてしまいます。
余談ですが、例の「国内でLAN伝送ベースの高価なマルチアンプシステムを開発販売されている、あのご高名な方」 との最近の情報交換で、「EKIOのチャンデバ処理は、IIR処理で軽快なのでしょうね。しかし、厳密に測定すると IIRではどうしても波形が少し変化しますので、弊社製品では FIR方式を採用し、それに加えて(企業秘密の)波形処理を加えています。」、と仰せでした。 そこで dePhonica の IIR-FIR 連携機能(私には、まだ理解できない)もお知らせしたら、先にご紹介したように 「なるほど、なるほど、、、貴殿のように、PC上での I/O環境とチャンデバソフトの設定が可能な方なら、今や、PC+ソフトウェアで現在最高レベルのチャンデバ(クロスオーバー)処理ができる時代になっています。」、とのコメントを頂戴しました。
DAC8PROが到着したら、ECM8000も使って「測定」したいとは思っていますが、当然ながらリスニングルームの「音響効果」も大きいので、厳密な測定による波形やディレイの測定で音響を詰めていくことに加えて、究極的には自分の「聴覚」による最適化を尊重したいと考えております。
あいによしさんも、BOWSさんも、ご理解、ご経験のように、測定による最適化と、聴覚による最適化は、必ずしも一致しませんよね?
さて、、、
私の DAC8PRO は、まだプラハの工房で on "Processing" の状態です。 他の方々(オーダー番号も公開!)の入手状況を他所で見聞しているのですが、それを参考にすると、私の DAC8PRO は、2〜3週間以内に検査が終わりそうな様相です。欧州も COVID-19 の感染拡大で、物流配送にも影響が出始めるかも、、、、と懸念しておりますが、DAC8PROが来れば、さらに睡眠時間が削られることが明白なので、「ゆっくり、ゆっくりで、いいですよ!」 が本心でもあります。
一方では、新アンプ群(ステレオ4台、またはモノラル8台)を、どうしようか??? 楽しい悩みです。
書込番号:23277708
![]() 2点
2点
Audacity も、もちろん使ってます。
10年ほど前に、2年程かかって、暇を見つけては、LP約500枚をアナログ再生でAudacity に取り込んで、カートリッジのスクラッチポップノイズを丁寧にカットし、AIFFでライブラリに保存、を延々とやってました。
それに較べると、CD、SACD 合計約2000枚のリッピングとライブラリ化は楽でしたね。 私の音源の場合、タグ情報を自分で入力する場面が多く、それなりに時間がかかりましたが。。。。
書込番号:23277712
![]() 3点
3点
>当然ながらリスニングルームの「音響効果」も大きいので、厳密な測定による波形やディレイの測定で音響を詰めていくことに加えて、究極的には自分の「聴覚」による最適化を尊重したいと考えております。
Room Equalization Wizardというフリーのソフトを使えば、Wavelet解析を用いて、部屋の影響も含めたタイムアライメント測定ができるよ。
参考に、昔AVアンプでの位相補正後にREWで測定したものを貼っておく。位相補正後でも20Hz〜90Hzあたりは20ms程度遅れている。
書込番号:23277911
![]() 2点
2点
tohoho3さん、皆さん
>Room Equalization Wizardというフリーのソフトを使えば、Wavelet解析を用いて、部屋の影響も含めたタイムアライメント測定ができる
貴重な情報、ありがとうございます。 DAC8PROとアンプ群も揃って、本格的にEKIOチャンデバ−マルチアンプ環境を構築したら、Room Equalization Wizardも使って測定してみたいと思います。
その一方で、頂戴した測定例を見て、「低音域のディレイの形状」が、現在の私のテスト環境と類似していることも、当然かも知れませんが、少し驚いております。
添付画像左側は、現在のテスト環境で、ソフトチャンデバEKIOのステレオ4帯域のチャンデバ(クロスオーバー)を、まず、ディレイ設定一切なしで最適化した際の、EKIO出力の理論周波数特性カーブ(上段)と理論グループディレイカーブ(下段)です。 各フィルタは、L/R(Linkwitz-Riley)型、傾斜はご覧のように -24 dB/Oct または -48 dB/Octで、ゲインや位相も最適化設定済みです。
ディレイ設定一切なしの左画像の状態では、下段の総合ディレイカーブ(白線)の形状は、tohoho3さんが提示されたRoom Equalization Wizardによる測定例の形状(黒点線)と、よく似ております。当方では、LOとMIDのクロスポイントを約600Hz に設定しており、理論ディレイ曲線も 20Hz〜550Hzの低音チャンデバ帯域で、相対的に遅れる理論曲線になっております。 なお、このグラフの縦軸は、msなどの絶対値ではなく、帯域毎のディレイの相対値を表しているようです。
次に、この状態から、他のチャンデバ設定を一切変更せずに、MD(中音)、HI(高音)、SH(超高音)の3帯域を、聴覚に頼って最適な状態にディレイさせ(LO低音域に同期するようにディレイさせ)、その結果を理論グラフで表示させたのが、右側の画像です。
聴覚によるディレイ設定最適化に利用した音源は;
1.低音〜高音を含む、大梵鐘一撃による最大ピーク音の秀逸音源
2.大太鼓とティンパニの強奏を含むオーケストラ秀逸音源(ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番3楽章、など)
3.ベース、ドラムスの名演を含むピアノジャズトリオの秀逸音源
4.オーディオチェックCD遮音チェック オクターブ・バンド・ノイズ・スポット音源
などです。
あえて出力理論グラフは見ずに、聴覚だけで聴き込みながら、3帯域のEQパネルで、MD(中音)、HI(高音)、SH(超高音)の3帯域をLO(低音域)に同期するように最適ディレイさせてから、理論出力ディレイカーブを確認すると、右画像のようになっており、白線の総合ディレイ曲線が、ほぼフラットになっていました。
この結果からも、聴覚に頼ったディレイ設定も、まんざら邪道ではなさそう、と思っています。
もちろん、最終的には、一度、ECM8000を使って、ご紹介いただいたRoom Equalization Wizardなどで、部屋の音響特性も含めた総合的なディレイ設定=タイムアラインメントを実測してみたい、と考えております。
書込番号:23278942
![]() 3点
3点
Audio Science Reviewの
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measuring-time-delay.7644/
のスレのmitchcoさんの投稿を見ると、 Audiolensという有償のソフトを使用して補正すると、理想的なwavelet応答が
得られているみたいだ。こんな応答今まで見たことないと書いているやつもいる。
書込番号:23279522
![]() 2点
2点
tohoho3さん、Naim ND555 enthusiastsさん
余談ですが、Wavelet理論とそのフィルター応用は、医療関係の2次元、3次元の画像解析でも、よく使っています。
また、Wavelet解析の理論構築と広範な応用に大きな功績があった Prof. Dr. Truong Nguyen, 現在University of California San Diego, Jacobs School of Engineering, Electronic and Computer Engineering (ECE)の Chairman、 は結構親しい友人です。彼は、もともとベトナム人ですが、ベトナムの大学卒業後に米国に渡って、苦学、苦労しながら Wavelet で名を上げました。 今度会ったら、趣味のオーディオ解析でも使ってるよ、と話しておきます。喜ぶことでしょう。
書込番号:23280148
![]() 2点
2点
ちょっと訂正です。 The Electrical and Computer Engineering (ECE) department です。
書込番号:23280233
![]() 2点
2点
皆さん、
今までお話ししてきたように、DAC8PRO入手後は、ステレオ4-way 8-channel 利用で、DAC8PROとアンプ群(ステレオ4台、またはモノラル8台)に;
低音域(WO=Woofer)
中音域(SQ=Squawker)
高音域(TW=Tweeter)
超高音域(ST=Super-Tweeter)
をEKIOチャンデバで分けて、それぞれ担当させますが、サブウーファー YAMAHA YST-SW1000 左右に1台ずつへの入力;
超低音域(SW=Sub-Woofer)
については、低域をカットしないWOラインからの分岐を想定しています。(想定していました。)
しかし、できれば、SW帯域とWO帯域についても、EKIOで分割して、必要に応じて個別にクロスポイント、フィルタータイプ、減衰傾斜、ゲイン、ディレイなどを設定したい思っております。(SW帯域の位相反転については、SW=YST-SW1000自体に位相反転スイッチがあり、リモコンで反転も可能ですので、リスニングポイントに座って、正逆の切替ができます。)
そこで、よくよく考えると、YST-SW1000 は、内部に強力な低音専用アンプを持っていて、そこへのラインレベル入力(RCAアンバランス)ができ、また EKIOからは、DAC8PROへの8チャンネル出力のみならず、PCにUSB接続している他のDACへも臨機応変に出力できるので、SW帯域だけは、DAC8PROではなく、OPPOSONICA DAC または ONKYO DAC-1000S へ出して、そのラインアウト(RCAアンバランス)から左右の YST-SW-1000 へ入力することができます。
この場合、DAC8PROとの厳密なデジタル同期はできませんが、総合的なディレイに関しては、EKIOで柔軟に調整が可能ですので、試みる価値は十分にあると思い始めております。超低音域ですので、厳密なデジタル同期の必要性は低い、とも思います。
それで、現在のシミュレーション環境で、添付画像のように、ステレオ 5-way 10-channel の EKIOチャンデバ設定を試しております。もちろん、これで何の問題もなく、SW, WO, SQ, TW, ST が、全て駆動できています。
書込番号:23286110
![]() 2点
2点
皆さん、
昨晩、実際に SW超低音帯域を別DAC = ONKYO DAC-1000S に出力し、そこからのRCAアンバランス信号を左右の YST-SW1000へ繋いで、実際にチャンデバ設定試行錯誤、音出し、試聴してみました。
左側の添付画像のように、ASIO4ALL は、ONKYO DAC-1000S を USB HS Audio Device 出力デバイスとして認識、もちろんOPPO SONICA DAC も出力デバイスとして認識されています。
そこで、SW超低音域である SL-L と SL-Rを、それぞれ DAC-1000S の L と R へ出力させて左右のSWへRCAアンバランスで繋ぎ、その他の WO、SQ、TW、ST のステレオ4-way 8-channel は、OPPO SONICA DAC へ出力し、そこからXLRバランスでE460 へ入力して鳴らしています。
右側の添付画像が、チャンデバ設定です。
下段の Group Delay の縦軸の数値は、相対値ではなく、理論上のディレイをミリ秒(ms)で表しています。
この設定トライアルでは、
SW帯域のハイカットを L/R型 36 dB/Oct, 50 Hz に、
WO帯域のローカットを L/R 型 24 dB/Oct, 50 Hz に、
それぞれ設定しており、面白いことに、グループ毎、フィルタ毎のディレイ設定を特に行わなくても、20〜100 Hz あたりの理論総合ディレイは、白線のように、ほぼ 10 ms 以内に収まっています。クロスポイントにおける減衰傾斜を左右で異なる傾斜に設定すると、位相的な相殺によるのでしょうが、このように理論出力ディレイを軽減させることができるようです。 (YST-SW1000 本体のハイカットダイアルは、もちろん 50 Hz を上回る 75 Hz に設定しています。)
周波数過渡特性カーブ(中段)のように、理論合成出力曲線(白線)においても、クロスポイント付近に大きな凹みは見られません。
さてさて、一番大切な聴覚上の音域間のつながりや、超低音域〜低音域(SW〜WO担当音域)のスピード感、晴明感、音像定位、ですが、とても素晴らしく、これまでWO帯域をローカットせずに、WOとSWへ分岐出力していた音響と比較して、顕著な改善が実感できます。
もっとも、SW帯域だけを別DAC→SW(アンプ内蔵) で鳴らしていますので、SW帯域の音量は、他の帯域(今はE-460 で一括コントロール)とは別に、EKIOのゲインまたは YST-SW1000 のリモコン操作で調節する必要がありますが、リスニングポイントに座ったままで、一つのリモコンで左右の YST-SW1000 のボリュームを一括で上下できますので、それほど苦にはなりません。 もちろん、E-460 のボリュームも、別リモコンで操作しています。
今回、始めて、源流側(PC内部)でSW音域とWO音域をチャンデバ分割し、別々のアンプで鳴らしてみたのですが、20Hz〜500Hz におけるスピード感、晴明感、音像定位が顕著に改善されたことは、少なからず新鮮な驚きでした。
EKIOによる10チャンネルのチャンデバ設定初期プロファイルの作成も含めて、ここまでのシミュレーションを完了できました。
DAC8ROとアンプ群(機種選定中)が到着すれば、ステレオ 5-way 10-channel のマルチアンプシステムを比較的順調に構築できそうな気分になってまいりました。 さらなる音響改善は、、、、大いに期待できそうです。
書込番号:23288021
![]() 2点
2点
一部、訂正です。
正しくは;
この画面の設定トライアルでは、
SW帯域のハイカットを LR型 36 dB/Oct, 50 Hz に、
WO帯域のローカットを LR型 48 dB/Oct, 50 Hz に、
それぞれ設定しており、
です。 失礼いたしました。
書込番号:23288036
![]() 2点
2点
各チャンネルや YST-SW1000 のゲイン&ボリュームを一旦固定した後、もちろん、10チャンネル全て一括マスターボリュームコントロールおよびミュート(一時出力停止)を、EKIOの I/Oパネル上でマウス操作できますので、最終的には、これがマスターボリュームコントローラーとして利用できます。
書込番号:23288649
![]() 2点
2点
皆さん、
本日は、指定かつ強制の代休で在宅しておりましたので、誘惑に抗しきれず、チャンデバ帯域間ディレイの測定と調整(の習得)に着手しました。
まず、(普段は嫌っている)JAVA環境の最新版 JAVA Runtime Environment 8u241 WIndows 64 bit をインストールし、次に そのJAVA環境下で動く、 tohoho3さんから情報を頂戴した、音響測定(&設定)フリーソフトウェア Room Equalization Wizard (REW) 64bit 板をインストールして使い始めました。
まずは、EKIOによる帯域グループ毎のディレイ設定と、それをREW のWavelet解析で正しく認識できることを確認するため、スピーカーを鳴らしてマイクで収録する前に、ステレオ 5-way 10-チャネル を全て OPPO SONICA DAC に入力し、SONICA DAC のアンバランス出力をRCAラインケーブルで PC の Realtek Audio のラインインに直結して、測定(Measurement機能)を行いました。
EKIOのチャンデバ設定は添付画像の通りで、REW測定では、「4.512k log sweeps 0 Hz to 20,000 Hz at -17 dB 512k length」を4回 L+R で発信&受信させ(合計計測時間 21.8秒)、REW の Specrogram - Controls - Mode で Fourier ではなく、Wavelet を指定し、まずはチャンデバでのディレイ設定一切なしで、Wavelet 解析画像を表示させました。その結果が添付画像の2番目です。
アンプ、スピーカー、部屋環境の影響を全く受けていない綺麗なライン再生音響であり、チャンデバを含めた総合出力として、超低音域 15 Hz〜 60 Hz は、 15 ms ほどの遅延を示しています。
つぎに、EKIO のディレイ設定と REW測定の正確さを検証するために、EKIO の I/O パネルにて、LO低音域(L,R)を強制的に 50 ms 遅延させて、同様にライン信号を測定した結果が3番目、右画像です。このように、綺麗にクロスオーバーポイント 50〜60 Hz において 50 ms のディレイが測定され、EKIOのグループディレイ設定とREWによる Wavlet計測の正確さが検証できました。
測定用マイク ECM8000 (CEntrance Mic Port PRO利用でUSB接続)を使った音響測定については、次の応答欄でお見せします。
書込番号:23290184
![]() 2点
2点
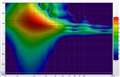 |
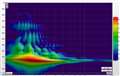 |
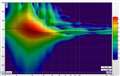 |
|---|---|---|
REW Wavelet解析:音響実測、EKIOディレイなし |
REW Wavelet解析:音響実測、EKIOディレイ最適設定 |
REW Wavelet解析:音響実測、EKIOディレイ最適設定、低音部を拡大 |
次に、いよいよ、測定用マイク ECM8000 (CEntrance Mic Port PRO利用でUSB接続)を用いて、EKIOのチャンデバ設定音響を REW のWavelet解析で測定しました。
昨日お話ししたように、超低域 SL帯域の左右信号を ONKYO DAC-1000S へ繋いでDAC変換させ、そこからRCAアンバランスケーブルで左右のサブウーファー(SW) YAMAHA YST-SW1000 に入力して鳴らし、その他の LO, MD, HI, SH のステレオ4-way 8-channel は、全て OPPO SONICA DAC へ入力して アキュ E-460 と LC-ネットワーク経由で、WO、SQ、TW、ST を鳴らし、リスニングポイント(一辺約 4 m の正三角形の頂点位置)に測定マイクを耳の高さに三脚固定しました。
まず、EKIOのディレイ設定一切なしで、REW - Wavelt 解析した画像が左側1番目の添付画像です。 この測定では、スピーカー群後方のスライドドア、リスニングポイントのソファー後方のスライドドアは、いずれも閉めておりましたので、定在波の影響と思われるディレイジャンプが 60 Hz, 75 Hz 付近に現れております。
そこで、スピーカー群後方の奥行き約 3.5 m のダイニングルーム、リスニングポイント後方の奥行き約 4.5 m の和室、へ通じるスライドドアを全開放し、側面の厚手カーテンも閉めて、普段しっかり音楽鑑賞をする際と同じリスニング空間にしてから、EKIOチャンデバの SL(サブウーファーSW) 帯域以外の LO(→WO)、MD(→SQ)、HI(→TW)、SH(→ST)、4帯域8チャンネルのディレイ設定を少しずつ変えながら REW - Wavelet 測定解析を繰り返し、特に低音部分 SW - WO のディレイのつながりが平坦で、しかも 15 Hz 〜 20,000 Hz の全域で特異的なディレイジャンプが見られない設定を探ってみました。
その過程では、多くの Wavelet測定解析スペクトルを得ておりますが、このテスト環境=シミュレーション環境で、ほぼ最適と思われるデイレイ設定による Wavelet測定解析画像を、2番目の添付画像(15 Hz 〜 20,000 Hz全域)でお見せします。
また、3番目の添付画像は、この最適化状態の15 Hz 〜 200 Hz 付近を拡大表示させたものです。
聴覚的にも、この REW - Wavelet 測定解析結果のディレイ設定状態で、非常に優れた音像定位、スピード感、晴明感、解像度、が得られております。
ちなみに、今日の、この最適ディレイ条件は;
SL: 0 ms(基準)
LO: 28 ms
MD: 10 ms
HI: 5 ms
SH: 5 ms
という設定です。
単純に、「無響室」の様な環境を想定するなら、LO: 28 ms で最適であれば、 MD、HI、SH も 28 ms以上で「最適つながり」 になりそうに思いますが、そのように設定すると、このスペクトルのような、全域にわたる、綺麗で、「ほぼ理想的なディレイつながり」 にはならず、いくつかのディレイジャンプが発生したりしますので、部屋環境を含めたトータルの音響ディレイを「実測」しながら、チャンデバのディレイを設定することの重要性も認識させられております。
また、EKIO のグループディレイ設定を一つの帯域で 2 ms 上下させるだけでも、REW - Wavelet 測定解析スペクトル画像上で音場特性の変化がきちんと表現されるので、この測定系は、なかなかの優れものである、と実感できました。
DAC8PRO と新アンプ群を入手後、最終的に構築する当面の目標 = ステレオ 5ウェイ、10チャンネルのマルチアンプシステム においても、このテスト環境=シミュレーション環境(SP群はこのテスト環境のまま)と同等以上の総合ディレイ特性(補正)が実現できるであろう、との確信を持つことができました。
tohoho3さん、REWをご紹介いただき、ありがとうございました。
書込番号:23290432
![]() 2点
2点
二つ上の【書込番号:23290184】 の強制ディレイ検証画像のキャプションが、10 ms になっていましたが、 50 ms が正しいので、訂正しておきます。
書込番号:23290493
![]() 2点
2点
もう一つ、訂正です。
【書込番号:23290432】
>その過程では、多くの Wavelet測定解析スペクトルを得ておりますが、このテスト環境=シミュレーション環境で、ほぼ最適と思われる>デイレイ設定による Wavelet測定解析画像を、2番目の添付画像(15 Hz 〜 20,000 Hz全域)でお見せします。
>
>また、3番目の添付画像は、この最適化状態の15 Hz 〜 200 Hz 付近を拡大表示させたものです。
正しくは;
<その過程では、多くの Wavelet測定解析スペクトルを得ておりますが、このテスト環境=シミュレーション環境で、ほぼ最適と思われ<るデイレイ設定による Wavelet測定解析画像を、2番目の添付画像(15 Hz 〜 200Hz 領域)でお見せします。
<
<また、3番目の添付画像は、この最適化状態の15 Hz 〜 200 Hz 付近の縦軸方向を拡大表示させたものです。
失礼しました。
書込番号:23290518
![]() 2点
2点
>ちなみに、今日の、この最適ディレイ条件は;
>
>SL: 0 ms(基準)
>LO: 28 ms
>MD: 10 ms
>HI: 5 ms
>SH: 5 ms
>
>という設定です。
と書きましたが、これは誤認でした。
やはり最適設定は、
SL: 0 ms(基準)
LO: 28 ms
MD: 28 ms
HI: 25 ms
SH: 25 ms
あたりでした。
さらに REW - Wavelet を習熟いたします。
書込番号:23290557
![]() 2点
2点
リスニングポイントでの測定をしたんですね。REWのWavelet解析は結構面白いでしょう。
同じ測定データから、Controls->Freq. Resolutionで、周波数分解能を低くれば、時間軸分解能の高い画像が得られ、
周波数分解能を高くすれば、時間軸分解能の低い画像が得られ(量子力学の不確定性関係みたいに)、面白いですよ。
思っている以上に部屋環境の影響が大きいことがわかると思うよ。
書込番号:23290837
![]() 2点
2点
参考に、Controls->Freq. Resolutionで、周波数分解能を低くして、時間軸分解能の高めた場合の画像と、
周波数分解能を高くして、時間軸分解能の低くした場合の画像を貼っておく。
書込番号:23290991
![]() 2点
2点
tohoho3さん
全く同感です。REWの Wavelet 解析は、感度と精度も高く、とても面白いと実感しています。これほどの性能を持った測定系であることに、大いに驚いております。
実は、私が勤務する研究所で(も)、もろもろの事情(お察しの通り)が発生し、昨日から14日間、在宅で「巣ごもり」状態になってしいましました。(幸いにして、私は、今のところ全く健康ですが。。。) オーディオで試行錯誤するには、「巣ごもり状態」は好都合ですので、ご指摘の点を含めて、いろいろ検討してみます。
リスニングルームの状態やその改善を測定&視覚化できるという意味でも、REW - Wavelet 解析は素晴らしいソフト、しかもフリーソフト、ですね。
引き続き、ご指導、情報交換をお願いします。
書込番号:23291034
![]() 2点
2点
tohoho3さん
ほぼ最適と思われるEKIO帯域ディレイ設定;
SL: 0 ms(基準)
LO: 28 ms
MD: 28 ms
HI: 28 ms
SH: 28 ms
にて、REW-Wavelet 測定し、ご示唆いただいた3条件で、全帯域 15 Hz 〜 20,000 Hzを表示させてみました。もちろん、マイクはリスニングポジションです。
なかなか、面白いですね。
書込番号:23291157
![]() 2点
2点
dualazmakさんの部屋は和室ですかね。俺のに比べると、定在波も反射波も少ないみたいですね。
書込番号:23291179
![]() 2点
2点
今日は、快晴、無風、低湿度ですので、開放できる窓を全て開放した状態で、同様に測定しました。
聴覚的にも、ほぼ最高のセッティングであるように感じております。
特に、超低音域〜低音域〜中音域 のスピード感、晴明感、解像度、音像定位が、これまで経験したことがないような最高状態です。
今から、各帯域毎に、位相の再確認、さらに厳密に5点定位を調整し、各種の音楽音源を聴いてみます。
(各帯域の位相は、EKIOで設定済みです。)
書込番号:23291190
![]() 2点
2点
リスニングルーム(リビングルーム)は、5m X 4m のフローリング洋室(絨毯敷)、SP群の背後のスライドドアを開放すると、4m X 4mのダイニングルームと開放連結、またリスニングポジション(3人掛けソファー)の1m後方スライドドアを開放すると、5m X 4mの畳和室(襖や障子、押入、床の間、もあり)に開放連結です。
リスニングルーム(リビングルーム)の天井は、吸音性能が高い多孔質石膏製の厚手の天井タイル材を多数貼っております。
定在波の発生は、かなり押さえられる環境になっていると思います。
書込番号:23291217
![]() 2点
2点
dualazmakさんの真ん中の画像(周波数分解能が1/24オクターブのもの)と同じ縦横スケールになるようにしたものを貼ってみた。
それでも、広い帯域に渡っていっぱい定在波が立ってるな。特に48Hzのは強烈。まあ、八畳間の縦横寸法に一致しているので如何ともし難いな。
書込番号:23291357
![]() 2点
2点
tohoho3さん
お互いに、とても参考になりますね。ありがとうございます。
差し支えなければ、もしお使いであれば、チャンデバの機種やプロスオーバー設定、ディレイ設定、などを、簡単で結構ですので、教えて下さい。
書込番号:23291385
![]() 2点
2点
市販のスピーカー(B&W 683s2)をTEAC AX-505というアンプで鳴らした場合の測定なので、チャンデバとかクロスオーバー、ディレイ設定はありません。測定はECM8000というマイクとKOMPLETE AUDIO2というオーディオ・インタフェースを使用したときのものです。
書込番号:23291422
![]() 2点
2点
tohoho3さん
ECM8000 は、私も同じものを CEntrance MicPort Pro(USB給電で48 Vファンタム電源も供給)利用で USBケーブル1本でPCに繋いでいます。これは、本当に優れた音響測定用マイクですね。いつも、重宝しております。
皆さん
聴覚による慎重な調整に加えて、「音響測定用マイクロフォン+フリーソフト REW (Room Equalization Wizard)+そのWavelet測定解析機能」 で実測することにより、帯域ディレイや定在波の状態を含め、リスニングルームの実環境における総合的で客観的な音響測定も可能となり、各種の条件設定に活用できるようにもなりました。
これにより、EKIOによるPC内部でのフルデジタル ステレオ 5-way 10-channel チャンデバ(クロスオーバー)にて、帯域ディレイを含めて、ほぼ最適なチャンデバ設定の候補条件を見つけることができました。
これで、DAC8PRO と新アンプ群を用いて、当面の目標である;
「デジタル音源 → フルデジタル10-チャンネル ソフトウェアチャンデバ(クロスオーバー) → マルチDAC群 → マルチアンプ群」
で、サブウーファー(SW)、ウーファー(WO)、スコーカー(SQ)、ツイーター(TW)、スーパーツイーター(ST) を、それぞれ独立アンプでステレオ駆動する準備が、ようやく整いました。
DAC8PRO は、2月15日に OKTO RESEARCH社(チェコ国、プラハ)に発注し、現在は製品検査の段階にあるそうです。
発注時のOKTO社からの連絡では、「通常では」受注から1〜2ヵ月で納品できる、とされてはおりますが、欧州の物流配送にも混乱が予想されますので、入手までには、まだ、しばらく時間がかりそうです。
書込番号:23292184
![]() 2点
2点
皆さん、
EKIOによるステレオ 5-way 10-channel 設定後の、F特性(周波数応答特性)の「測定」については、まだ紹介していなかったので、EKIOチャンデバ設定のさらなる最適化も含めて、本日、実測などを行いました。
まず、EKIO で私のSP群に合わせたステレオ 5-way 10-channel 最適(?)設定と、10チャンネル全てを OPPO SONICA DAC へ出力して、RCAアンバランスのラインレベル信号のF特性を計測した結果です。
アンプやスピーカーを経由しない、ラインレベル出力が EKIO の設定の通りになっているか、の確認ですが、EKIO設定を微妙に触っても、正確にラインレベルに反映されます。
添付画像は、以下の測定に使用した、本日固定の EKIO設定です。
書込番号:23297976
![]() 2点
2点
このライン信号レベルにおける REW Wavelet 解析です。
3枚目と4枚目の画像では、先日と同様に、EKIO のディレイ設定と REW-Wavelet解析を確認するために、EKIOで LO帯域 50Hz 〜 600Hz を強制的に 50 ms ディレイさせて、きちんと反映されるかどうかを検証しています。
綺麗にディレイが反映/測定されています。
書込番号:23297990
![]() 2点
2点
つぎに、SL帯域を ONKYO DAC-1000S に出力してRACアンバランスでサブウーファーへ繋ぎ、その他の LO、MD、HI、SH 領域を OPPO SONICA DAC へ出力して E460 とんうぇっとワークボックス経由で WO、SQ、TW、STを駆動し、全域の実音響をリスニングポジションで 音響測定用マイク ECM8000 で拾って、実音響の F特性を計測しました。
この段階では、まだ EKIOにおけるディレイは、一切設定していません。
ピンクノイズ、ホワイトノイズ、サインスイープ の3種で測定しておりますが、40Hz 〜 100Hz の低音域は、3つの方法で少しずつ異なるF特性を示しています。 このあたりは、リスニングルームの残響にも影響されるので、この差が生じることは理解できます。
一方、160Hz 付近と 400Hz 付近のディップは、3つの測定方法に共通しておりますので、これは定在波、共鳴波、または反射波の影響であると考えられ、今後、家具の配置変更や厚手カーテンの開閉で解消できると考えておりますが、本日はそのままにしております。
書込番号:23298012
![]() 2点
2点
これに、EKIO で LO、MD、HI、SH 領域を、いずれも 29 ms ディレイさせて、 SL領域とLO領域の「ディレイ繋がり」を平坦化、および「全域におけるディレイのジャンプ」を最小化すると、このようになりました。
書込番号:23298040
![]() 2点
2点
また、このようにディレイを最適化設定しても、F特性には、ほとんど影響がないことも、もちろん確認しております。
本日の、測定と設定は以上の通りですが、ディレイを含めた、この EKIO設定において、聴覚的にも非常に優れた;
スピード感(特に超低音〜低音域)、
晴明感、
解像度、
音像定位、
いわゆる「ベールが何枚も剥がれた」ソノリティ、
が得られております。
DAC8PRO の到着と、完全マルチアンプ駆動によるステレオ 5-way 10 channel システムの構築を楽しみにしておりますが、シングルアンプ+アクティブサブウーファー の環境であっても、フルデジタルのチャンデバ(チャンネルデバイダー、クロスオーバー) EKIO を活用するメリットは非常に大きいと実感しております。
書込番号:23298072
![]() 2点
2点
最も標準的な、
◆すべて -12 dB/Oct 傾斜、
◆NS-1000 標準のクロスポイントである 600 Hz, 6000 Hz
◆SW と WO は 50 Hz でクロス、
◆STは 9,000 Hz 以上を担当、
という設定は、位相反転と正逆設定もシンプル、総合出力も全域でほぼフラット、理論出力のディレイも最少、総合的な音響品も良好、ですので、DAC8PRO到着後の5-Way 10-Channel マルチアンプ環境では、やはり、この「標準設定」からEKIOチャンデバ設定の試行錯誤を始めるべきである、と肝に銘じております。
書込番号:23304530
![]() 2点
2点
>dualazmakさん
>Consequently, I need 3 new fully XLR capable pre-main amplifiers with high quality attenuator/volume to drive squawkers (SQ), tweeters (TW) and super-tweeters (ST).
My current candidates, also in consideration of my budget, are;
ACCUPHASE E-270 (for SQ?)
SONY TA-A1ES (for SQ and/or TW?)
TEAC AX-505 (8Ohm 70Wx2)
NMODE X-PM7 MKII (one bit digital 8Ohm 20Wx2, XLR for mono, so maybe for TW and/or ST)
SOULNOTE A-0 (8Ohm 10Wx2, so for TW and/or ST)
Your comments and/or suggestions for the selection of XLR capable amplifiers will be highly appreciated.
こんにちは。
例の YAMAHA XM4080 Poweramp は Class G とのことですが、Class G ではないのですが以下の PA も国内で入手は出来るようです。これは Class AB とのことです。
https://procable.jp/crown/s_75.html
https://www.thomann.de/gb/tamp_s75.htm
但し、安価ですので家庭用としてはどうなのかについて私は何とも言えません。
なお、全くの余談ですが 英国の Arcam がClass G amp を発売していますね。
それでは。
書込番号:23304984
![]() 0点
0点
Naim ND555 enthusiastsさん
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/page-65
や、その前後における私の英語での情報交換もご覧いただけているようで、ありがとうございます。
今日、そちらでもYAMAHA XM4080 についての情報交換を英語でお願いしていますが、特に海外では、評価記事は、ほとんど見られませんね。
そこでも書きましたが、私が見つけた唯一の情報は、ドイツ発信で、
https://www.thomann.de/gb/yamaha_xm_4080.htm#bewertung
だけで、これによれば、性能的にはよさそうですが、冷却ファンが少し耳障りなようですので、使う場合には、ファンを静音タイプに交換するか、ファン回転速度コントローラーをつけるか、した方がよさそうと思っています。このあたりは、PC自作で経験が多々ありますので、容易に可能です。
一方、YAMAHAに問い合わせたところ、「ファンは可変スピードファンなので、常時回転はするが、家庭用の負荷範囲なら、おそらく十分に静音ですよ。」 との回答も得ています。
https://jp.yamaha.com/products/proaudio/power_amps/xm_series/specs.html#product-tabs
によれば、XM4080 は;
8Ω 80W X4、 SN比 103dB (20Hz - 20kHz)、全高調波歪率≦0.1%、ダンピングファクター≧100 (RL=8Ω, 100Hz)
ですので、そこそこ使えるのではないかと考えています。 負荷保護回路、電源投入時の一時ミュート、などもあり、業務用ですので、YAMAHAの修理やメンテナンス体制もしっかりしているのでは、とも期待しています。
>例の YAMAHA XM4080 Poweramp は Class G とのことですが、Class G ではないのですが以下の PA も国内で入手は出来るようです。これは Class AB とのことです。
>https://procable.jp/crown/s_75.html
>https://www.thomann.de/gb/tamp_s75.htm
>但し、安価ですので家庭用としてはどうなのかについて私は何とも言えません。
ありがとうございます。 これらは、私も検討しておりますが、スペック的にも、信頼性やメンテナンス対応の点からも、対象外になっています。
また、XM4080 のような、 XLR入力対応(必須)、8Ω80W 程度(これ重要!)の4チャンネル独立アンプ、Yラグ対応スピーカー端子、というような機種は、ほぼ見当たりませんね。
XM4080 は、レンタルで試してみることもできそうなので、DAC8PROが手に入ったら、 XM4080 2台をレンタルしてみようか、とも思案中です。 1台にL側の4チャンネルを、もう1台にR側の4チャンネルを、それぞれ駆動させる方針です。
そのXM4080(2台レンタル?)によるテストも経た上で、最終的にアンプ群を選定しますが、現在の大本命は、「SONY TA-A1ES を4台導入(!)」です。。。。
書込番号:23305284
![]() 2点
2点
YAMAHA A-S2100 を4台、の選択肢も考慮中です。
(DAC内蔵の?)新機種が出る予定だそうで、YAMAHAのページでは、最近、A-S2100の生産終了がアナウンスされましたが、まだ各所に新品在庫はありますね。
もちろん、ST以外のSP群が全て YAMAHA製であることも事実ですが、現在は ACCUPHASE E-460 を使っているように、SP群とアンプ群のメーカーを揃える、という嗜好や意図は、全くありません。 一方では、A-S2100 は、XLR入力対応、高品位なボリュームおよび左右バランス調整機能もあり、いまだに「プリメインでマルチアンプ」に拘っている私のプランには、最適なようにも思えます。
定格消費電力は 350 W ですが、信号無入力時の消費電力は、如何ほどでしょうかね?
ちなみに、ACCUPHASE の E-380 は、8Ω定格消費電力が 423W で、無入力時は 46W ですので、A-S2100 の無入力時は 35〜40W ほどですかね。
書込番号:23316258
![]() 2点
2点
>dualazmakさん
全てはスレ主さんの御決断・御選択でしょうけれども、そんなにお金を掛けなくとも何とかなるだろうと私は思っております。
ASR における Digital front-end の問題は時間の問題として解決することでしょう。
私でしたら DAC 以後のプランを次のように考えております:
Trafo-based passive preamplifier (10ch) --> Appolon Audio NCMP 8200 (8ch) stereo power amplifier for TW, SQ, WO and SW units.
Trafo-based passive preamplifier (10ch) -->an appropriate stereo power amplifier for ST units.
*当該の YAMAHA SW (YST-SW1000) の内蔵アンプは使用しません。
*私でしたら DAC 以後にいかなる integrated amplifiers も絶対に使いたくありません(まあ、好みの問題でしょうか)。
Appolon Audio NCMP 8200:
https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/
なお、添付画像はスレ主さんから無断でお借り致しましたのでどうかお許し下さい。
それでは。
追伸:OKTO DAC8 Stereo をあるYouTube再生で数回試聴しましたが、その結果として私はこの DAC を wishlist から外しました。
書込番号:23316420
![]() 0点
0点
Naim ND555 enthusiastsさん
ASR での英語のやりとりもご覧いただき、ありがとうございます。 そちらでの画像の一部を貼っていただきましたので、ここでも、現在の3案を、添付の通り、共有させていただきます。
DAC8PROに加えて、もう一つの DAC(ここでは SONICA DAC) をSW専用に用いる第1案は、ご紹介したように実証もしているのですが、再生時間が経過するに従って、2つのDAC間の同期のドリフトが避けられないでしょう、との指摘もあり、それはそれで納得です。
そこで、SWとWOの相対的ディレイ調整はできませんが、第2案と第3案想定しています。いずれも、E-460 のプリアウトを使って、シミュレーション検証を完了しています。 実は、SW YST-SW1000 は、前後に動かせるようにしてあるので、物理的に動かしてディレイを微調整できますので、第2案または第3案を優先的に検討する予定です。
やはり、どうしても、人柱的にも、プリメインアンプの利用に拘っている私としては、「それなり」のプリメインを導入して、ひとまず第3案を実現したく思っています。
Appolon Audio NCMP 8200 のご紹介、ありがとうございます。よく勉強してみます。
いずれにしましても、DAC8PROが到着したら、Windows 10 での認識や内部撮影画像(接写も!)を含めて、ここでも紹介、共有させていただきます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23317242
![]() 3点
3点
>dualazmakさん
>やはり、どうしても、人柱的にも、プリメインアンプの利用に拘っている私としては、「それなり」のプリメインを導入して、ひとまず第3案を実現したく思っています。
OKTO DAC8 PRO Outputs が 8ch であるという観点からやはり第3案が最も無難のように思います。
YAMAHA SW 内蔵アンプを使用しないと OKTO DAC8 PRO を用いての 5way 設計は厳しそうですね。
プリメインアンプの選択肢 は極めて少ない (XLR 入力モデルは更に少ない)と思いますが、是非最適解を見出されることをお祈りしております。
ところで、ポーランド製の Mytek DACs にも確か ES9028PRO が用いられていると思いますが東欧では ES9028PRO が高く評価されているのでしょうか?
それでは、ASR への投稿再開を心待ちにしております!
書込番号:23317297
![]() 2点
2点
>Naim ND555 enthusiastsさん
>OKTO DAC8 PRO Outputs が 8ch であるという観点からやはり第3案が最も無難のように思います。
>YAMAHA SW 内蔵アンプを使用しないと OKTO DAC8 PRO を用いての 5way 設計は厳しそうですね。
ありがとうございます。 かなり心強く感じております。 当面の計画としては、第3案を優先いたします。
>ところで、ポーランド製の Mytek DACs にも確か ES9028PRO が用いられていると思いますが東欧では
> ES9028PRO が高く評価されているのでしょうか?
実は、OKTO社のPavelさん、EKIOを開発&提供している LUPISOFT社の Guillaumeさんとも、何度もやりとりしており、ES9028PROの利点も見えてきました。
DACチップの最適利用には、それを利用&コントロールする XMOSと組込コントロールソフト(いわゆるファームウェア)の設計と実装が極めて重要だそうですが、ES9028PROについては、ESS社から提供される情報や日常的なESS社との連携が豊富で、ES9028PROの機能と性能を最大限に引き出せる環境が整っているようです。
また ES9028PROは、安定して、常に100%品質のチップが、適正価格で、潤沢に、調達できることも大きな要因だそうです。
Pavel さんは、ES9028PROは本当に凄いDACチップで、利用開発側でも大いに「やる気」が鼓舞されます、というような感触を述べておられました。
また、多くのスタジオを含む「業務用」音響機器の世界でも、その性能と供給安定性が高く評価されて、ES9028PROが多用されていることも欧州の民生用オーディオ業界で利用が進んでいる背景になっているようです。
また、ASR や DiyAudio における情報交換を眺めていますと、最近の欧州における民生用オーディオ機器への真摯で本格的な取り組みに較べて、日本と米国では、スマホやスマートスピーカーへの対応に見られるような迎合的な製品開発が中心で、適正価格で、「まともな」(DAC8PROのような)製品の開発は、もはや行われていないのでは? とも指摘されており、私も同感です。これも、本格的な(?)ピュアオーディオに取り組む人々の減少と、それに伴って開発投資を回収できる市場がほぼ壊滅、という現況を見ると、私には寂しい限りですが、致し方ない状況ですね。
従って、この方面では、ご指摘の Mytes社も含めて、欧州勢の台頭と「元気さ」を、大いに歓迎し、期待し、応援したいと思っております。 これは、ソフトウェア、ハードウェアの両方に共通した認識です。EKIOのLUPISOFT はフランスです。。。
また、「なぜ東欧か?」ですが、恐らく、東欧では平均的な賃金水準が日本、アメリカや西欧よりもまだまだ低いので、技術力のある少数精鋭の中小企業が、得意分野、得意製品に集中して開発&製品化し、小規模なニッチ企業(個人事業)の人々が、平均的な生活を送れる賃金水準で、またプライドと楽しさを維持しながら仕事と生活ができれば、それが一番の幸福である、という社会的、文化的な背景が大きく寄与しているように思います。
私は、アメリカ、カナダと西ヨーロッパ諸国を中心に、非常に多くの滞在や訪問経験があるのですが、東欧圏は観光やコンサート目的でしか訪問したことがなく、今回の OKTO社との情報交換で、はじめて、このような印象を強くしました。
本当に小さな企業達ですが、インターネットのお陰でビジネス展開は完全にグローバルであり、ある意味で新しいビジネスモデルになりそうな予感と期待を感じています。
日本でも、何人かの優れた技術者と小規模集団が、この分野に取り組んではおられます(おられました)が、残念ながらグローバルに展開ができる製品、発信(これが下手!)、サービスの提供に到達している事例は非常に希であり、とても残念に思います。ピュアオーディオ市場の急激な縮小を考慮すると、国内市場だけをターゲットにしているようでは、生き残りは、ほぼ不可能でしょうね。
書込番号:23317605
![]() 3点
3点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
先日、Naim ND555 enthusiastsさんからお知らせいただいた;
Appolon Audio NCMP 8200:
https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/
も見ているのですが、
こちらの、自由に組めるアンプもあるのですね。
https://www.kjfaudio.com/product/ma-01-flexible-amplifier/#slot-1
8Ω 75W の NC122MP (ステレオ)を4つ選択して、8チャンネルで組んでみると、USドルで $1,844.25 (税別) だそうです。先ほど、このページのチャットから問い合わせたら、
1.受注から3週間で日本へ向けて発送できる。
2.ファンは、12cmの PMW超静音ファンで、かなり熱くならないと回らないし、回っても、ほとんど無音です。家庭オーディオなら、ほとんど回りません。
3.100V 50Hz 電源でも、もちろん大丈夫。
だそうです。
Hypex NCore アンプモジュールの選択などは、まだ知識が不足しているのですが、この KJFAudio MA-01 およびそのアンプモジュールの選択など、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
書込番号:23326762
![]() 2点
2点
これも、同じコンセプトで、同じアンプモジュールの選択可能、ですね。
https://www.nordacoustics.co.uk/product-page/nord-one-mp-ncxxx-4-8-122-500w-custom-configurable-channel-amplifier-black
こちらは、100-240V 50/60Hz 仕様で、ファンレスのようです。
スピーカー端子の配列は、こちらの方がYラグ結線に適しているように見えます。
Channels 1-2 を NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω for Woofers, and branch into Sub-Woofers)
Channels 3-4 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω for Squawkers)
Channels 5-6 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω for Tweeters)
Channels 7-8 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω for Super-Tweeters)
としてみると、日本への送料込みで 1,619ポンドだそうで、約21〜22万円ほどです。
このあたりも、欧州勢が頑張っているような気がします。
もちろん、皆様のご意見を伺いつつ、熟慮いたします。 軽々に発注は、、、いたしません(笑)。
書込番号:23326895
![]() 2点
2点
俺の持っているTEAC AX-505は、NC122MPを使用しているみたい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124207/SortID=22642862/
にレビューを書いてます。すでに見てると思うけど。
書込番号:23327254
![]() 1点
1点
tohoho3さん
ありがとうございます。拝見しております。
「AX-505 または AP-505 を4台揃える!」、という選択肢も、もちろん考慮しておりました。
一方では、これらのマルチアンプや、DAC8PROなどのマルチDAC を含めて、「アンチ超高級、アンチ超高価格」を標榜している真摯で真面目そうな欧州勢の小規模〜中規模オーディオメーカーの台頭は、大いに歓迎すると共に、目が離せなくなってきました。
https://www.kjfaudio.com/product/ma-01-flexible-amplifier/#slot-1
と
https://www.nordacoustics.co.uk/product-page/nord-one-mp-ncxxx-4-8-122-500w-custom-configurable-channel-amplifier-black
について、皆様からのご意見、ご感触を楽しみにしております。
書込番号:23327305
![]() 2点
2点
https://www.nordacoustics.co.uk/product-page/nord-one-mp-ncxxx-4-8-122-500w-custom-configurable-channel-amplifier-black
のNord One MP NCXXX 4-8 122-500W を;
Channels 1-2 を NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)
Channels 3-4 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
Channels 5-6 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
Channels 7-8 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
の構成で調達して、さらに現有の Accuhase E-460 もウーファー駆動と Pre-Outによるサブウーファーへの入力に利用し、2チャンネルは余りますが、Nord One MP NCXXX 4-8 122-500W を、スコーカー、ツイーター、スーパーツイーター用に臨機応変に使ってみる、という選択肢もありそうに思っています。
つまり、添付計画図の Amprefier-2, 3, 4 としてマルチアンプ Nord One MP NCXXX 4-8 122-500W を使う、という想定です。
これがあると、いろいろ駆動アンプ群も接続を変えて、遊べそう、楽しめそうですし、ウーファーとスコーカーの音質的、音響品位的な繋がりも、試行錯誤して最適な設定を探れるのでは、とも考え始めています。
書込番号:23327359
![]() 2点
2点
>dualazmakさん
取り敢えずですが、
Hypex Ncore (Hypex Electronics B.V. オランダ)がどのような音響的性格を所有しているかを検証しているところです。
https://www.youtube.com/results?search_query=Hypex+Ncore+
特に、
https://www.youtube.com/watch?v=3Homf90FfBw
次に、Marantz EU からは PM10 (Hypex Ncore NC500 OEM 仕様)が YouTube にて試聴出来ます。
https://www.youtube.com/results?search_query=Marantz+PM10
故 Ken Ishiwata 氏の登場を願いますと
https://www.youtube.com/watch?v=E_rVelm6l-E&t=5s
Hypex Ncore の音響的可能性が見いだせたならば問題の 8-ch amplifiers に話は移ります。
高価過ぎるものでは、米国 ATI Amplifier Technologies 社の製品 AT 528NC があります。
https://www.ati-amp.com/AT52XNC.php
その User Manual は
https://www.ati-amp.com/manuals/AT500NC%20Manual%20May%202018.pdf
ですが Rear Panel Layout を眺めるだけでも有益かと思います。YouTube であれば
https://www.youtube.com/results?search_query=ATI+amplifier
欧州製に話は変わります。
まず、英国製の KJF Audio MA-01 についての YouTube は
https://www.youtube.com/results?search_query=MA-01+amplifier
この製品ですが、Real Panel Layout が素人ぽい感じがしますしどうしてファンまで必要なのかは良く理解出来ませんでした。
また、KJF Audio はアンプ製造を得意としている会社とは私にはどうしても思えませんでした。
次に オーストリア製の Apollon Audio NCMP 8200 と英国製の Nord Acoustics Nord One との比較ですが
スレ主さんにとりましては後者の方が好ましいように思えます。Real Panel Layout も ATI 同様使い勝手が良い良い様ですし。
それらの YouTube は
https://www.youtube.com/results?search_query=Apollon+amplifier
https://www.youtube.com/results?search_query=Nord+amplifier
最後に Apollon Audio 製品と Nord Acoustics 製品の内部画像を添付しておきます。
私のおすすめは Nord Acoustics Nord One といったところでしょうか。
それでは、また。
書込番号:23327802
![]() 1点
1点
>Naim ND555 enthusiastsさん
ありがとうございます。 私も、一昨日から Hynex Ncore およびそれを使った8チャンネル連装マルチアンプの情報を、YouTubeや他の各所で眺め始めておりました。
また、tohoho3さんからもリマインドがあった Hynex NC122MPおよびそのOEM特別バージョン(?)を搭載している TEAC MX-505, MP-505 は、何度も試聴する機会がありましたので、音響の傾向は理解しており、好ましく感じています。
KJF Audio と Nord Acoustics の比較ですが、KJF Audio MA-01 のサイトを見てから、Nord Acoustic社のサイトと Nord One MP NCXXX 4-8 122-500W のページを見て、その後、もう一度 KJF Audio社のサイトを一覧して、Naim ND555 enthusiastsさんと全く同様の印象を持ちました。 KJF Audio は、DIYスピーカー関係が本業で、アンプは、恐らく、どこか他社に下請け生産させているのかも知れません。バックパネルのデザインや機能性、特にSP端子の配置と間隔には、一見して疑問を感じました。
その点、Nord 社は、アンプやDACが専門のようで、8チャンネル連装の Nord One のバックパネルは、一見してアンプユーザーの使い勝手をよく理解しているな、と見受けましたが、これも Naim ND555 enthusiastsさんも御同感ですね。このデザインが、初めて見た高価なATI Amplifier Technologies 社 528NC のバックパネルと酷似していることは、大きな驚きでした。
そんなこんなで、書込番号:23327359に書いたように、Accuphase E-460 も活かしつつ Nord One MP NCXXX 4-8 122-500W を利用することを少し本格的に考え始めております。
Apollon製品とNord製品の内部比較、面白いですね。Apollonでは、SP端子へ行く配線が、+も、−も、同じ赤い配線で少し驚きです。組み付ける際に逆に配線するリスクはないのでしょうかね? その点でも、Nord の配線には、経験とプロ意識を感じます。これなら、将来的に必要になれば、自分でHynex Ncore基板を調達して換装することも、かなり容易にできそうに思います。
「プリメインアンプをマルチアンプ環境でも利用する!」という昨年来の拘りから脱却しなければなりませんが、性能的にも、価格的にも、Nord One MP NCXXX 4-8 122-500W は魅力的に感じます。
アンプモジュールの選択;
Channels 1-2 を NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)
Channels 3-4 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
Channels 5-6 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
Channels 7-8 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
は、どう思われますか? KJF Audio も、 Nord Acoustics も、メールやチャットでの問い合わせに対して、NX252MP と NC122MP の間で音色や音響品位には差はないし、差を聴き分けることは恐らく不可能です、と応えてきました。
最終的にどう使うかは未定ですが、Channels 3-4 も NC252MP にして、
Channels 1-2 を NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)
Channels 3-4 を NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)
Channels 5-6 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
Channels 7-8 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
という構成にしておく方が、もしSPユニットを交換する場合でも、柔軟で余裕のある利用が可能かな? とも考えております。
書込番号:23328401
![]() 2点
2点
>dualazmakさん
>KJF Audio も、 Nord Acoustics も、メールやチャットでの問い合わせに対して、NX252MP と NC122MP の間で音色や音響品位には差はないし、差を聴き分けることは恐らく不可能です、と応えてきました。
NC252MP と NC122MP との相違に関してではないのですが、Amir 氏が NC500 と NC400 の比較に関して ASR において何か言及していたような気がするのですが、それをこれから探してみようかと思います。
甚だ簡単ですがご報告まで。
書込番号:23328606
![]() 1点
1点
>dualazmakさん
それが見つかりました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-nord-one-nc500-amp.7704/
における #1 Conclusions の中で Amir 氏は次のように述べておりました。その一部をそのまま引用します。
"Conclusions
I went into this review expecting better results than I achieved. Despite higher designation, the NC500 seems to be a lower performing module than NC400. How much the input buffer board adds to this, is unknown until we test other variations." (引用おわり)
それでは、また。
書込番号:23328627
![]() 2点
2点
>dualazmakさん
NC122MP および NC252MP に対する Datasheet における諸特性の比較をしたところ S/N 比では後者の方が数値が良いようですが、聴感上では感知出来ぬ差異なのでしょう、多分。
既にご存知のように ASR でも NC252MP などの Hypex Ncore 採用のアンプの測定・評論記事が散見出来ますが、NC122MP と NC252MP との間の御選択はdualazmakさん次第かなと思います。
それから以下の Calculator は実用的であると良いのですが。
https://www.doctorproaudio.com/content.php?2273-calculators-proaudio-sound-dmx&langid=1#calc_spl
それでは、また。
書込番号:23329189
![]() 2点
2点
Naim ND555 enthusiastsさん
貴重な情報、まことにありがとうございます。
私のみならず、Hynex Ncoreモジュールによる多連装アンプ、マルチアンプ、に興味を待たれる方々にとっても、大いに参考になることでしょう。
>それから以下の Calculator は実用的であると良いのですが。
>https://www.doctorproaudio.com/content.php?2273-calculators-proaudio-sound-dmx&langid=1#calc_spl
最終的には、リスニングルーム環境において聴覚に頼ったチューニングを行うことは必須ですが、このようなシミュレーション計算サイトの利用も、これまた大いに参考になりそうです。 暇を見つけて、勉強してみます。
さて、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/page-68
でも大いに盛り上がっていますが、OKTO社のホームページがリニューアル公開されました。
https://www.oktoresearch.com/
DAC8PROのページも、I/Oルーティングの多様性や仕様が理解しやすいように改訂されています。
https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
昨日、Pavel さんから連絡があり、私のDAC8PRO は、もうすぐ、1週間以内に、発送されるそうです。嬉しいことに、欧州域内でのこの種の物流配送は、ほぼ正常だそうですが、このご時世ですので、日本に到着してからも、通関を含めて遅延があるかもしれません。 気長に待つことといたします。
このスレッドも、非常に長くなりましたので、DAC8PROが到着したら、新スレッドへ移動したいと考えております。
その際には、もちろん、ここでもアナウンスさせていただきます。
書込番号:23329857
![]() 2点
2点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
ASR (Audio Science Review) フォーラムの何人かの方々に煽て(おだて)られて、そこの Member Area で、ここと同じような内容の新スレッド;
"Multi-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC"
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
を立ち上げておりますので、ご興味がございましたら、覗いてみて下さい。またご遠慮なくご参加下さい。 英語ですが。。。
ASRといっても、参加の皆さん全部が、ここでお付き合いいただいている皆様ほど、この方面に精通しているわけではなさそうですが、欧米、特に西欧〜東欧圏のオーディオ製品やソフトウェアについて、有益な情報が得られることを期待しつつ、立ち上げてみました。
どんなレスが投稿されるか、興味津々ではございます。
書込番号:23331735
![]() 2点
2点
位相の問題で、rephaseを使えと言ってるやつがいるな。
前に持っていたsonyのAVアンプで、位相補正すると低音がタイトになったので、rephaseを使ったり、Frieve Audio M-Classを使ったりしたみたけど、うまくいかなかったな。スレ主さんが使う気があり、うまく使えた場合は教えて下さい。
これに関連して、検索すると、Room Shaperというソフトがあり、
https://audiophilestyle.com/ca/reviews/home-audio-fidelity-room-shaper-review-r855/
にレビューがあるが、スピーカでは制御できない300Hz以下での領域での定在波特性(200msを超える長い時間減衰特性)を左右のチャンネルで個別に制御できるみたいなので、俺は時間があれば試してみようと思う。
書込番号:23336609
![]() 2点
2点
>tohoho3さん
そうなんですね。
"Multi-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC"
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
において、「RePhase を使え!」と、再三再四ポストを入れてくるこの人は、ちょっと???ですので、忌避するつもりです。
ASRにおいても、私が強調しているように、私の目的は、現在の「今でも素晴らしいと確信している音響」を、マルチアンプ駆動で、さらに少しでも改善することですので、位相問題を含めて、現在の音響を大きく変化させる方向性は、断固拒否です。
それで、まずは、EKIOを使うとしても、紹介しているように現在の音響を殆ど変化させない設定を慎重に探し、DAC8PRO当直後は、その設定を優先的に試みる、という step-by-step の戦略です。
それから、REW-Wavelet なども使ってみて実感しているのですが、私の究極の目的は、快適に音楽を楽しむ、音響ではなく音楽!、ですので、自分の耳と脳の感性を、最も大切にしたいと思っています。
というわけで、ASRでは、世界各国の人たちが、いろいろコメントしてくれますが、軽々に受け入れるつもりは、毛頭ございません。
引き続き、ここも、ASRも、ご覧いただき、ご意見などお聞かせいただければ幸いです。
書込番号:23338325
![]() 3点
3点
youtubeを検索していたら、Room shaperの空気録音があった。
https://www.youtube.com/watch?v=qy0mpzXtjGs&t=11s
補正なしと1:20あたりからのRoom shaperを比較すると、Room shaper使用時は定在波の影響が抑えられて
結構低音がタイトになっている。
書込番号:23338903
![]() 1点
1点
>tohoho3さん
ありがとうございます。聴いて見ます。
まずは、現計画のステレオ 5-way 10-channel のマルチアンプシステムを;
The simpler, the better
The simplest, the best
の方針に沿って構築し、その後、必要に応じて RePhase や Room Shaper などの利用も検討したいと考えております。
書込番号:23339462
![]() 1点
1点
皆さん、
つい先ほど、ASRの私のスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
の
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-3
で頂戴した情報によれば、まだOKTO社のホームペジでは一切触れられておりませんが、DAC8PRO (および DAC8 STEREO?)で使える 8-channel I/O対応の ASIOドライバー(評価版?)があるそうで、入手できそうです。
DAC8PROの到着後、このASIOドライバーによる JRiver や Roon から EKIO への I/O なども試してみて、情報共有が許容されるようであれば、ここでも紹介させていただきます。
まあ、こんな情報やドライバーをもらえるのも、ASRでスレッドを建てたメリットかも知れません。
書込番号:23339523
![]() 1点
1点
皆さん、
以前のここでの議論の繰り返しにもなっていますが、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/are-pre-amps-necessary.9327/page-6#post-376511
にて、マスターボリュームおよび帯域分割後のゲインや左右バランスコントロールをどこでやるべきか、の議論をやっております。
ご興味がございましたらご覧下さい。
書込番号:23347385
![]() 1点
1点
>dualazmakさん
こんにちは。
今日は月曜日であいにくの雨です。
DAC-->Poweramps の間に (Line) Preamp を介在させることについてですが、私の知る限りにおいてハイエンドの世界では Preamp はやはり必要かと思います。
私は、Name Audio 製品のパルチザンの一人ですので Naim Audio Community に属しております。
最近では、次のような試みをされた方がいるようです。
https://community.naimaudio.com/t/dcs-bartok-as-a-one-box-solution/6432/254
(Post 252 by Dunc)
ASR, Stereophile Magazine, TAS Magazine のようなアメリカ物の大部分は音響的表現にとどまっていますが英国物は音響的表現は当たり前で音楽的表現にも踏み込んでいます。
英国物では PRaT という省略語を音楽的表現の一つとして多用します。Micro detail, Macro detail という単語も同様に多用されています。
私は英国派ですので ASR, Stereophile Magazine, TAS Magazine のようなアメリカ物はどうしても斜め読みに近いです。
閑話休題:
COVID-19 の影響により自宅謹慎の身ですので、海外ビールを取り寄せては毎日試飲を続けております。
チェコ産のビールは昔はとても美味でしたが、それも懐かしく感じられる今日この頃です。
https://www.beeradvocate.com/beer/top-rated/cz/
さて、dualazmakさんの DAC8PRO の発送も近いかと思いますが、door to door と言えども COVID-19 の影響のため受け取り時にサインは不要ということで配達員の方から直接手渡しは全く必要なくなりました。プラハからですと貨物は約4日間でご自宅に到着するのではないかと予測しております。
それでは、また。
書込番号:23349860
![]() 1点
1点
>Naim ND555 enthusiastsさん
こんばんは。 ありがとうございます。
なんとなく感じてはおりましたが、Naim ND555 enthusiastsさんの Audio Scene でのお姿が、少し明瞭になりました。
今日、ASRの私のスレッド3ページ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-3
で引用した MattHooperさんのコメント;
"I've tried passive pre-amps before, and also some DACs that offered volume control (e.g. an old Meitner DAC and my current Benchmark DAC).
Whenever I ran a DAC directly in to my amps (monoblock tube amps) instead of whatever pre-amp I had on hand, I was always struck with the sense of clarity and smoothness...the impression of very "direct, uncolored" sound going straight in to the amps to my speakers. Problem is I always gravitated back to an active pre-amp because for whatever reason the direct signal to my amp from a DAC seemed to lack the same body/density of sound and I found it unsatisfying after a while.
Problem is that just remains subjective anecdote and there was no easy way to blind test between the DAC using volume control directly in to the amps vs using my pre-amp."
は、とても共感できる内容でした。
私も、やはり、何らかの、好みの、プリアンプまたはプリメインアンプ(インテグレーテイッッドアンプ)を介在させる方向に回帰し始めています。それで、Nord One MP NCXXX 4-8 122-500W 発注は、まだ躊躇しております。プリアンプ4台と Nord One という思い切った選択もあり得るかも知れませんが、そこまで予算拡大するか? というジレンマもあります。
それもあって、ハード的なシステム構成の動作確認は、YAMAHA XM4080 2台で、8チャンネル独立でやろうかと思っています。 サブウーファーも含めると、ステレオ5-way 10-channel の動作確認ですね。これまでの、かなり周到な準備の結果からは、まともに動くのは当たり前なのですが、やはり独立8チャンネルアンプで、EKIOクロスオーバーも含めて、早く動作確認して、LCネットワークを介さない音を確認したい、というわけです。
各チャンネル毎に E-460 を介在させて、総合的な音響(音楽!)を確認してみることもできますし、E-270 や E-360 を3台(?)ちょっと借用して試してみる、また YAMAHA A-S3000 や A-S2100 を4台調達(時限調達?)して試してみる、なんてことも気長にやってみたいと思います。
とにかく、DAC8PROが来れば、アンプ構成を、気長に試すことができるので、楽しみではあります。
OPPO SONICA DAC と E-460、外部LCネットワークボックス経由のSP駆動系は、私の基準リファレンス音響ですので、いつでもそこへ回帰できるように温存します。
チェコビール!嬉しいお知らせです。
実は、10年ほど前だったか、家内と二人でプラハに6日間滞在し、昼間は観光やボヘミアングラスの店を物色、夜は音楽会三昧したことがあり、スメタナホールでコンサートを堪能したあと、プラハの素敵な路地の店でチェコビールを注文して、大いに感激したことがあるのです。
東欧は、各地でローカルな地ビールがあって、いいですよね。特にあのチェコビールは、銘柄は忘れましたが、最高でした。現地で、音楽会のあとでしたので、そのプラセボ効果もあったのでしょうが、地ピールは、やはり現地で飲むのが最高なのでしょうね。 また行きたいな〜、と話してはいるのですが、、、、
欧州へは、少なくとも今後数年間は、足を踏み入れるべきではないかも知れませんし、われわれ東洋人は、当面、「招かれざる客」と見なされるかも知れません。。
あの美しいイタリア北部にも研究仲間の友人も多く、ベネチア近郊のパドバ大学医学部の友人からは、3週間前に、「医療関係者として最善を尽くすが、これが最後の連絡になるかも知れない。祈ってくれ!」との悲痛なメールが来てから音信不通になっています。とても心配していますが、、、祈るしかありません。
世界は、昨年秋までの、グローバリズム礼賛の平和ボケな状況には、もう戻れないのではないかと、暗澹たる気分ですね。
昨日20時からのNHK BS の特集番組、ご覧になられましたか? ポストコロナで、世界の体制、経済、思想がどのように変容するかという重厚な特集でしたが、私の思うところとほぼ一致していました。 残念ではありますが。。。
さて、もうすぐ Pavelさんから DAC8PRO発送の連絡があるのでは、と心待ちにはしておりますが、確かに COVID-19 の影響もあるので、少しは遅れるかも知れませんね。それもあるので、XM-4080 2台の発注は、DAC8PRO実物の顔を見てからにするつもりです。 ただ、COVID-19 にも関連して、私の本業(医薬品研究分野です)でも、自宅謹慎の部分的解除以降=5月6日以降、また超多忙になりそうで、ここやASRスレッドの書込対応も、頻繁にはできなくなる可能性が高くなっています。
余談ですが、「なんで今頃??」の感が強いのですが、ASRで OPPO SONICA DAC の、実測評価レポートが、3月に出ていました。
例によって、amirmさんのレポートです。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/oppo-sonica-usb-dac-and-streamer-review.11845/
DAC8PROには遙かにおよびませんが、この評価を見る限りでは、SONICA DAC は最近のDAC新製品群と比較しても、実測的には、いまでも健闘している部類なようで、愛用者の一人としては、嬉しく思っています。 SONICA DAC + E-460 も、いつでも聴けるように温存します。
今後とも、よろしくお付き合いいただければ、幸いに存じます。
書込番号:23350405
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
もしクラシック音楽に抵抗がなければ、ですが、
https://www.kusc.org/
はご存知ですか? ここのインターネットストリーム放送を、自宅巣ごもりで仕事中にも、BGMとしてよく聴いています。EKIOチャンデバのテストも兼ねながら。。。 基本的に、商業コマーシャルとは無縁のサイトですので、安心して聴けます。お喋りもごく最小限で、クラシック音楽を24時間、流しています。
昨年まで、San Diego の北のLa Jolla (ラ ホヤ)地区研究学園都市に数年間滞在してたので、そこでも、通勤ドライブ中も含めて、よく聴いていました。
書込番号:23350462
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんにちは。
KUSC のご紹介を誠にありがとうございました。
今もそれを聴きながらこのレスを書いています。
ところで、私の記憶にはないのですが、dualazmakさんの現有装置において
OPPO SONICA DAC --> Accuphase E-460 Integrated Amp
の volume controls 介在有無の聴き比べの結果はいかがでしたでしょうか?
これら2機種に対するマニュアルを拝見しました限りですが、
(a) OPPO SONICA DAC を Bypass Mode (Bypass All Inputs) として E-460 の volume control を使用する。
(b) E-460 を EXE PRE mode にしてその power amp section を用いて OPPO SONICA DAC の volume control を使用する。
(c) OPPO SONICA DAC および E-460 両方の volume controls を同時に使用する。
の3通りの選択が考えられますがいかがでしょうか。
Computer Audio に Pure Audio のおける所作をそのまま適用させることが難しい部分も有りそうですので、
DAC --> Poweramp に Preamp を介在させた方が良い結果が得られるのか否かは使用する DAC にも依存するかも知れませんね。となれば Preamp 介在はこの場合にはもしかしましたら絶対条件とは言いきれないかも知れませんね。実験あるのみですか。
最後に、私も OPPO SONICA DAC に良い印象を持っています。
https://www.gramophone.co.uk/features/article/product-of-the-month-oppo-sonica-dac
OPPO Digital 社製の PM-1 Planar Magnetic Headphones を過去に一時期使用していたことがありますが良い印象を私に残してくれましたし。
それでは、また、
追伸:YAMAHA XM-4080 にも volume control が付いていますので Okto DAC8 PRO-->Poweramps に Preamp 介在が果たして必要なのかを実験によって結論が導き出せるような感じがします。御幸運を!
書込番号:23355673
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
こんばんは。
KUSC 気に入っていただけたようで、何よりです。
下手なお喋りやコマーシャルがない! これが最高ですね。
選曲も、なかなかセンスがあると思いますし、ストリーミングの音質も、それなりに優秀ですね。
仕事中のBGMや、毎日の自転車型エルゴメーター運動時のBGMに、よく聴いています。
先月来、リスニングルームのソファーの後方に自転車型エルゴメーターを持ち込んで、毎日、夕刻に30〜45分、230〜400 kcal の汗だく運動をやってますが、KUSCを聴きながらの運動ですと、つらさを忘れて続けられます。
BGM的に聞いていても、おや? これはいいな! と思う曲や演奏も多々あり、ついつい音源を見て購入してしまうことも、、、月に1、2回に厳しく(!)制限していますが、ありますね。
KUSCで知った最近の大きな収穫を一つだけ、ご紹介します。
44.1 kHz の標準的なCDですが、イスラエルのピアニスト Iddo Bar-Shai がフランソワ クープラン(Francsois Couperin)のクラヴサン曲集を素晴らしい録音でピアノ(!)で演奏したアルバムです。
https://www.amazon.co.jp/F-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-Francois-Couperin-Errantes-Bar-Shai/dp/B00AWVSECI/ref=tmm_acd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
ここでサンプルも聴けます。
https://www.prestomusic.com/classical/products/8029227--francois-couperin-les-ombres-errantes
CDを入手してリッピングしたのですが、あまりにも素晴らしい演奏と録音なので、フランスの Mirare Production へ 「DSD音源はリーススしていないの?」 と問い合わせたら、「弱小レーベルですので我が社は標準CDフォーマットしか発売してません。」との回答でした。 それでも、現在最高レベルの録音(と演奏)だと確信しております。
Mr. Christian Meyrignac
Mirare Productions
16 rue Marie-Anne du Boccage
44 000 Nantes - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 40 84 11 49
Fax : +33 (0)2 40 73 64 70
Mail : cmeyrignac@mirare.fr
書込番号:23356429
![]() 1点
1点
さて、
>(a) OPPO SONICA DAC を Bypass Mode (Bypass All Inputs) として E-460 の volume control を使用する。
>(b) E-460 を EXE PRE mode にしてその power amp section を用いて OPPO SONICA DAC の volume control を使用する。
>(c) OPPO SONICA DAC および E-460 両方の volume controls を同時に使用する。
>の3通りの選択が考えられますがいかがでしょうか。
さすがですね。鋭いご観察とご明察、感服しております。
はい、何度も試みております!
まず、(b) ですが、E-460 のプリとパワーを分離して、EXT PRE mode でパワーアンプとして使う際は、残念ながらRCAアンバランス入力となります。もちろん、かなり高価なRCAアンバランスケーブルでOPPO SONICA DAC と繋いで、SINOCA DAC のボリュームをマスターボリュームとして使い、何度か試聴しています。確かに、高品位のサウンドですが、(a), (c)と比較すると、やはり SONICA DAC では、XLRバランス接続に、微妙ではありますが、軍配が上がりますね。XLRの方が、僅かにベールが離れた晴明感が感じられます。
そのためもあって、XLRバランス接続で、(a) または (b) の使用としております。この両者にほとんど差はないのですが、私の耳では、やはり(a)の方が、僅かに優るように思います。SONICA DAC の Volume をBypass All Input にすると、ES9038PROのデジタルボリューム回路を一切経由しないで出力される設計ですので、これを使わない方が、僅かに優れた音響かな、と感じます。
その僅かな差が、判別できるほど、E-460 と NS-1000の総合性能が、つまり、プリ部も、アンプ部も、非常に優れている、とも言えますね。自作の外付けLC-ネットワークも含めて。。。
このあたりが、DAC8PROのボリュームとゲインでどうなるか、楽しみでもあり、一抹の不安もなきにしもあらず。。。。。 ASRでの、あの圧倒的な高評価に信頼を寄せつつも、、、最後は自分の耳と脳で判断すべし! ですね。
一方、DAC8PROでも各ゲインをゼロに設定すれば、ESS9028PROのデジタルゲイン回路は完全にバイパスする設計です、とマニュアルにも書かれていますので、そうするならアンプレベルでのゲインコントロールの出番となります。 OPPO SONICA DAC の経験では、それが一番よさそうかも、とも思っています。マスターボリュームは、やはりDAC8PROを使うことになりますが。。。。
>Computer Audio に Pure Audio のおける所作をそのまま適用させることが難しい部分も有りそうですので、
>DAC --> Poweramp に Preamp を介在させた方が良い結果が得られるのか否かは使用する DAC にも
>依存するかも知れませんね。となれば Preamp 介在はこの場合にはもしかしましたら絶対条件とは
>言いきれないかも知れませんね。実験あるのみですか。
まったく同感でございます。私の環境で、私の耳と脳で、実験あるのみ、ですね。
XM-4080 は、各チャンネルに Volume が付いているとはいえ、所詮PAタイプのアンプですので、音質的には多くを期待しないつもりですが、EKIO出力を「20 Hz 〜 25 kHz でフラット」に設定したら、マスターボリュームコントロールに加えて、DAC8PRO and/or 各アンプでの SQ, TW, ST に対するアッテネーション(および必要に応じてL-Rバランス調整)は必須ですので、それらをアンプレベルで試してみる(特に TW, STをどの程度絞るか?)には、XM-4080 のボリュームも意味がありそうに思っています。もちろん、SPユニット保護にも使えますし(保護コンデンサも噛ませるとしても)。
E-460 を使い込んでいる経験に照らして、いまでも、高品位なプリメイン4台を使う選択肢は大いにあり得る、と考えておりますので、XM-4080 は、それをシミュレーションするにも好都合かな、と思っています。
1年くらいかかってもOK、OK のペースで、最終的なアンプ構成(プリアンプの是非も含めて)を、じっくり楽しみながら試行錯誤したいと考えております。
それでも、NORD ONE は、魅力的ですね。その、はやる心を抑えつつ、step-by-step! を自分に言い聞かせる毎日です。
書込番号:23356437
![]() 1点
1点
1点追加です。
OPPO SONICA DAC の、XLRバランス出力とRCAアンバランス出力の比較ですが、E-460 を標準プリメインアンプとして利用して、XLR入力とRCA入力の比較も、もちろんやっております。
当然ながら、XLRの方が入力レベルが高いのですが、同じ音量にして聴き比べた場合、やはりXLRバランスに、ほんの僅かの差ですが、軍配が上がります。かなり耳が肥えてきた家内に、ブラインドで聴き比べさせても、「XLRの方が、ほんの少しだけどクリアーね。」、と答えます。
このあたり、DAC8PRO はボリュームやゲインを経由しても、SONICA DAC よりも音響品位的に優れている! と期待しております。Pavel さんも、ES9028PROの利用とXMOS設計には、絶対の自信があります、とのことですので。。。
書込番号:23356481
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
OKTO DAC8PRO に関するこのレビュー(4月4日投稿);
https://theartofsound.net/forum/showthread.php?68601-Okto-Research-DAC8-Pro-multi-channel-DAC
参考になります。
ほんの一部ですが、翻訳して引用すると;
>「オクトは私が今まで所有した中で最も静かなDACであると確信できます。」
>「しかし、測定がどれほど優れていても、結局のところ、私たちの耳が、私たちがサウンドを気に入っているかどうかの最終的な判断者です。ジークフリートリンクウィッツが『目に重要なことは必ずしも耳にとって重要ではない...』」と言っていたので。。。」
COVID-19 の影響でしょうか? 私の DAC8PRO は、まだ最終的な品質検査中だそうです。
書込番号:23356961
![]() 1点
1点
自明ですが、書込番号:23356437 の一部訂正です。
誤): そのためもあって、XLRバランス接続で、(a) または (b) の使用としております。
正): そのためもあって、XLRバランス接続で、(a) または (c) の使用としております。
書込番号:23357238
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんにちは。早速のご返信に感謝致します。
最初に、
>44.1 kHz の標準的なCDですが、イスラエルのピアニスト Iddo Bar-Shai がフランソワ クープラン(Francsois Couperin)のクラヴサン曲集を素晴らしい録音でピアノ(!)で演奏したアルバムです。
https://www.amazon.co.jp/F-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-Francois-Couperin-Errantes-Bar-Shai/dp/B00AWVSECI/ref=tmm_acd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
ここでサンプルも聴けます。
https://www.prestomusic.com/classical/products/8029227--francois-couperin-les-ombres-errantes
に関しましては後日にご返信させていただきたいと思います。
次に、
>OKTO DAC8PRO に関するこのレビュー(4月4日投稿);
https://theartofsound.net/forum/showthread.php?68601-Okto-Research-DAC8-Pro-multi-channel-DAC
参考になります。
に関しましてはご紹介下さりましたURLにて原文をチェック致しました。
その中でその著者である Gordon 氏(Halfway Tree) が以下のように述べております:
"Anyway, onto the Okto Research DAC8 Pro (about £1k) which I’m now using in my main digital system: Fan-less i7 PC running JRiver>>Okto Research DAC8 Pro>>Apollon Audio NCMP8350>>Linkwitz LX521.4."
Linkwitz LX521.4 は 4-way-multi-amp-loudspeakeer system ですが、私が興味深いと感じましたのはそれを 8ch multi-amp である Apollon Audio NCMP8350 によって 「preamp 介在せずに」直接ドライブされていることです。Okto Research DAC8 Pro はその意味(「preamp 介在せずに」)でも有望かも知れませんね。
また、同氏は以下のようにも述べております:
"For me a multi-tone IMD test is one of the most revealing. This is a test most similar to music and here the Okto produces outstanding results, pretty much on a par with the Mola Mola Tambaqui, a 2 channel DAC which costs 10 times more. So with its low noise floor, and excellent low level linearity, jitter and IMD measurements there is the potential for the Okto to excel at retrieving low level detail. For my needs it fits the bill perfectly."
この中で高額な Mola Mola Tambaqui DAC に言及されていますが、この DAC も私は以前から関心を以って追跡している DAC の一つなのです。Okto DAC8 Pro 恐るべし。
また、再び同氏からの引用ですが、
"Okto are about to release a 2 channel DAC (with built-in Raspberry Pi option) which should perform even better than the 8 channel unit as they will sum the 8 DAC channels for an even lower noise floor."
幸い、私の手元には Matrix Audio X-Sabre Pro DAC が有りますのでそのうちに Okto DAC8 Stereo との比較試聴も興味深いかも知れないと思っております。
最後に、dualazmakさんの DAC8 Pro の無事なるご到着をお祈りしております。
それでは、また。
書込番号:23357645
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
こんばんは
そうなんですよね。
私も全文を興味深く読んでいましたが、逐一ここで引用することは少々憚られました。
私も、「DAC8PRO恐るべし!?」の感を強くしております。
また、ご指摘の通り、pre-ampを介在させずに、8-channel Nord ONE に XLR入力して SP群を駆動するのが、最もシンプルで高音質かも知れない、やはり最終的な到達点はそこかな、と思い始めております。
私の希望構成の Nord ONE でも、価格的には、ちょっとしたHi-Fiプリメインアンプ1台相当程度かより安価ですので、CPもよさそうです。
さて、ASRの方にも書きましたが、恐らく COVID-19 の影響で、OKTO社の生産体制が、back up running に入っているようで、スローダウンしている様子です。私の DAC8PRO order #106 は、出荷寸前なのですが、状況は十分に理解できますので、気長に待つことにいたします。
COVID-19は、非常に危険な状況です。くれぐれも、ご安全にお過ごし下さい。
書込番号:23358014
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
私のASRスレッドで、今日、John1959さんからもらった情報です;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-4#post-380126
I have a DAC8PRO on order too (#116), which I expect to arrive within a few weeks, and I just ordered a nice Nord Acoustic configurable multichannel amp. I heard from Colin North of Nord Acoustics that those Hypex NCxxxMP modules are made in Malaysia and that the factory is in lockdown for quite some time because of COVID-19. Unsure is when they open again. Even the Hypex company, based here in the Netherlands, doesn't have all the OEM modules on stock anymore . On the Nord website it's announced that they run out of the NC500MP (1x500W) and NC252MP (2x250W). There are still several other options available though. Other small manufactures who build their Hypex amps on order (e.g. Apollon, Audiophonics to mention a few) probably will have the same problem now or in the near future. I think nobody can tell when the lockdown will be over or production will start again. So it's probably wise, if you think about buying a multichannel amp build with these modules in the near future, not to wait too long with ordering.
要するに、Hypex NCxxxMP モジュールを実製造しているマレーシアの生産ラインが COVID-19 の影響で止まっているので、オランダの Hypex本社でもモジュールの在庫がなくなりつつある、従って Nord ONEを含めて、Hypex NCxxxMPアンプモジュールを搭載している多くの製品の供給に、今後、影響が出るでしょう、とのことです。
どうやら、John1959さんは、私のプロジェクトとよく似たシステム構築を考えておられるようです。
まあ、私は、DAC8PRO到着後、YAMAHA XM4080 2台で検証してから、プリメインアンプの利用も含めて気長に検討し、最終的には Nord ONE へ進む可能性が高い、という step-by-step で登りますので、Nord ONEを発注するとしても、焦らずに、気長に楽しみます。
その間にASRの私のスレッドで、John1959さんから DAC8PRO + Nord ONE の検証レポートがもらえれば、嬉しいですね。
DAC8PROが到着したら、「続 続 。。。。。」 の新スレッドへ移行する予定です。
もちろん、ここでもその旨、アナウンスいたします。
書込番号:23358051
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
>44.1 kHz の標準的なCDですが、イスラエルのピアニスト Iddo Bar-Shai がフランソワ クープラン(Francsois Couperin)のクラヴサン曲集を素晴らしい録音でピアノ(!)で演奏したアルバムです。
https://www.amazon.co.jp/F-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-Francois-Couperin-Errantes-Bar-Shai/dp/B00AWVSECI/ref=tmm_acd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
ここでサンプルも聴けます。
https://www.prestomusic.com/classical/products/8029227--francois-couperin-les-ombres-errantes
ですが、2,3ヶ所に、面白い、かすかな雑音(?)が入っています。どうやら、ピアノを置いている舞台フロアは固いが響きのよい木製のようで、ピアニストの左足の革靴がそのフロアに触れるような(?)音です。
いずれにしても、素晴らしい録音です。この手の音楽がお嫌いでなければ、是非、CDを入手されて、印象をお聞かせ下さい。
全てのトラックが感動的ですが、敢えて一つ、と言われれば、昔ピアノを弾いていた私の好みですが、
トラック−10 La Misteriese ですかね。。。。
最近のオーディチェック音源の一つとしても聴き込んでいます。
書込番号:23358104
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんばんは。
>2,3ヶ所に、面白い、かすかな雑音(?)が入っています。どうやら、ピアノを置いている舞台フロアは固いが響きのよい木製のようで、ピアニストの左足の革靴がそのフロアに触れるような(?)音です。
いずれにしても、素晴らしい録音です。この手の音楽がお嫌いでなければ、是非、CDを入手されて、印象をお聞かせ下さい。
雑音(靴音のようにも聞こえますが)に関しましては私もそのような感じを受けました。
さて、今しがた、アマゾン日本にそのCDを発注致しました。
多分、英国からの発送ということで到着までしばらく時間が掛かりそうですが、楽しみに待つことに致します。
その演奏の印象につきましてはそののちにお知らせ出来るかと思います。
全曲は1時間強ですが、とりあえずはCMにもめげずに次の YouTube で楽しもうと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=DCwkMSTFV_E
それでは、また。
書込番号:23358245
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
なんか、無理強いしてしまったようで、申し訳ございませんでした。
音楽の好みは、人それぞれですので、この種の「お勧め」は、いつでもスルーしていただいて、全く問題ございません。
あの数ヶ所の雑音は、ピアノのペダルアクション音のようにも聞こえますが、邪魔にはなりませんね。
私は、、、、
Iddo Bar-Shai のショパン マズルカ集も、非常に好評なようなので、手配してしまいました。。。。
https://www.amazon.co.uk/Chopin-Mazurkas-Iddo-Bar-Sha%C3%AF/dp/B00BDOWCO4/ref=sr_1_11?dchild=1&keywords=iddo+bar-shai&qid=1587764780&sr=8-11
これも Mirare レーベルですので、録音にも期待しつつ。。。
御安全にお過ごし下さい。
書込番号:23358670
![]() 1点
1点
dualazmakさん
おはようございます。
実は、私は Iddo Bar-Shai の演奏にはかねがね関心がございましたのでクープラン作品集のご紹介を大変嬉しく思います。
言い忘れておりましたが、私は慨しましてクラシカルミュージック専門で聴いております。
さて、Iddo Bar-Shai によるハイドン・ショパン・クープラン作品集を3CDにまとめた収録版(輸入盤)も発売されているということを後で知りましたので、昨日発注のクープラン作品集をキャンセルリクエスト致しまして、上記の収録版を HMV JAPAN 宛に発注し直すことに致しました。
https://www.hmv.co.jp/en/artist_%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86_000000000017977/item_%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AB%EF%BC%9D%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%9C%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%B3%EF%BC%9A%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%82%BF%E9%9B%86%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%91%E3%83%B3%EF%BC%9A%E3%83%9E%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%82%AB%E9%9B%86%E3%80%81%EF%BC%A6%EF%BC%8E%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%EF%BC%9A%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%B5%E3%83%B3%E6%9B%B2%E9%9B%86%EF%BC%88%EF%BC%93%EF%BC%A3%EF%BC%A4%EF%BC%89_6722955
それでは、どうぞお体をご自愛ください。
書込番号:23358750
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
3枚組は、知りませんでした! 3枚でこの価格なら、CPもよろしいですね。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23358805
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん、
閑話休題です。
私のASR Forum の例のスレッド;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
ですが、先ほど初めて、ここ;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc
で閲覧回数を見たら、何と4月9日のスレ建てから今日までの短期間で、4,203回も閲覧されていました。
世界中が COVID-19 で自宅巣ごもり状態で、オーディオに興味がある皆さんも、暇を持て余しつつ見てくれているのだと思いますが、DAC8PRO の登場も相まって、みなさん興味津々なのかも知れません。
ここで皆さんから頂戴した貴重な情報やご示唆も、大いに参考にして、また取り入れて、 ASR のスレッドが維持できているので、あらためて皆さんへ心から感謝申し上げます。
それにしても、まだ DAC8PRO の到着を待ちながらのプロジェクト準備段階なのに、これほど多くの閲覧や投稿があることには、非常に驚いています。やはり、EKIOなどのソフトウェア デジタル チャンデバ(クロスオーバー)と DAC8PROなどの多連装DACによる Hi-Fi マルチアンプ環境の構築には、結構、世界中のオーディオファンが注目しているようです。
私の "step-by-step" 構築方針と、"The simpler, the better"、"The simplest, the best" のポリシーが、どこまで理解されているのか、まだよく分かりませんが、しばらく、のんびりと、真摯に続けてみます。
投稿者の中には、 Burning Sounds さん(やはり英国の方)のように、非常に丁寧に投稿/指導してくれる人もおられるので、その点は嬉しく思っています。 一方では、かなりいい加減な投稿者も、もちろん見受けられますが、うまく丁寧に、丁重に、スルーしていると納得される様子です。 ひとつ面白いのは、欧州の人か、アメリカ人か、ほぼ投稿内容から推測できることで、十中八九当たってますね。
それから、ASR Forum の Forum web デザインは、とても良くできていて、その点はスレ主としても非常に快適です。表示画面も長年の工夫を経て、綺麗で洗練されていますし、投稿における自由度、リンクの張り方、画像の挿入、などなど、よく考えられています。
さらに、一度書き込んだ投稿を、かなり柔軟に改訂できるのは、この種の情報交換 Forumサイトでは、嬉しい機能です。
今後とも、こちらでも、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23364537
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんにちは。
ASR のおける dualazmakさんのスレッドを興味深く拝見させていただいております。
更なる御進展をお祈りしております。
最近まで私は Mola-Mola Audio Tambaqui DAC/HPA について調べておりました。もしそれが可能ならば貸出試聴を申し出たいと思います。
さて、ここからが本論ですが、その中でこのDACの設計者は Ncore などの発明で知られる Bruno Putzeys 氏なのですが、彼のこれまでの業績などについても調べてみました。
彼はドイツにある Kii Audio の共同創業者であって Kii Three Active Loudspeakers も手掛けていることが判りました。
その Kii Three Active Loudspeakers で Bruno Putzeys 氏がその enclosure 内部で行っていることと同様なことを dualazmakさんは外部で行おうとなさっているのではないかと私は判断致しました。
すなわち、Kii Three Active Loudspeakers に対して、dualazmakさんは同様な御計画を YAMAHA NS1000 + にて実行されるということで dualazmakさんのこの御計画は成功間違いなしと私には思われます。
それでは、また。
References:
https://www.kiiaudio.com/for_home.php
https://www.kiiaudio.com/files.php
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1218/Kii_Three_Active_DSP_Loudspeaker_Review.htm
https://www.hifinews.com/content/kii-audio-three-loudspeaker
https://www.youtube.com/results?search_query=kii+three
https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/bruno-putzeys-the-sound-of-music-extended-play
書込番号:23366082
![]() 1点
1点
追記事項です:
Mr Bruno Putzey (1973 -) Brussels, Belgium
Inventor of UcD (Hypex) Netherlands
Inventor of Ncore (Hypex) Netherlands
Co-Founder for Purifi Audio in Denmark
Inventor of Purifi 1ET400A Class D Amp Module (425W/4ohm)
--> NAD Masters M33 DAC/AMP
Co-Founder for Kii Audio in Germany
CTO
Inventor of Kii Three Active Loudspeakers
Mola-Mola Audio in Netherlands
-> Kaluga Monoblocks
-> Tambaqui DAC/HPA
-> Makua Preamp
Grimm Audio in Netherlands
-> AD1 A/D Converter
-> LS1 Loudspeakers
ともかく、Bruno Putzey 氏は多岐にわたり御活躍です。もう驚嘆しかないです。
書込番号:23366195
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
これまた貴重な情報、まことにありがとうございます。
確かに、Mr. Bruno Putzeyは、凄い人ですね。
私も、早晩、Hypexアンプモジュール採用製品で、彼のお世話になりそうです。
ご紹介しているように、私は、昨年夏に NS-1000 の LC-ネットワーク+アッテネーターを「外付け」ボックスに移動し、その際に全てのコンデンサー(キャパシター、全てフィルムコンに変更)とコイル(全て空芯コイルに変更)も更新して、その音響改善効果に大きな感銘を受け、それがきっかけで今回のマルチチャンネル−マルチアンプ環境構築プロジェクトを開始しました。
また、NS-1000 の筐体デザインとSPユニットの「凄さ、驚異の性能」を、あらためて非常に強く再認識させられたことも事実です。
これは、海外の方からも賛同が多々ありますが、本当に驚くべきことですね。NS-1000、NS-1000M 恐るべし!です。YST-SW1000 も凄いですが。。。
そこに、PCソフトウェアチャンデバ(クロスオーバー)と多連装DAC = DAC8PRO が、ちょうどいいタイミングで、絶妙に連携できることを認識したわけです。
Kii Three Active Loudspeakers の方向性は、私と同じですが、なんとなんと物理配置的には逆で、 PC+多連装DAC+多連装アンプ を全部SP筐体内に取り込んで(押し込んで)一体化し、それなりの超高価な製品として販売する、という戦略ですね。PCとソフトウェアの運用やオーディオDIYとは疎遠、それでも Hi-Fi オーディオ指向、の富裕層へは、このようなコンセプトの製品でも市場があると見込んでいるのでしょう。それは、それとして理解できます。
日本の SK Audio の、あのご高名な方とも年初から何度かやりとりさせていただきましたが、該社の製品も、コンセプト的には似ていますね。色々お話ししていたら、「貴殿のような知識とスキルがある方なら、PCと多連装DACを使って、我が社の製品に相当するようなことは、いまでは何でもできる時代になっていますよ。」 とのコメントも頂戴しました。
PCハードとソフトウェアチャンデバの柔軟性を知り、それをある程度使いこなせる私のような人間から見ると、PCも、連装DACも、連装アンプも、全部をSP筐体内に収納するのは、電磁ノイズと振動の観点からも、「あり得ない!」 としか思えないのも事実です。
なにしろ、どうあがいてもCPUを含むPCは電磁ノイズの大発生源ですし、SP筐体内は、強烈な空気振動のルツボですので、そこへ全部押し込んで、いくらノイズ対策や振動対策を施しても、私が現在達成している総合的な音響品質を超えるとは、到底信じられません。
そのあたりは、Kii Three Active Loudspeakers の評価と実試聴で確認するしかないのでしょうが。。。購入初期には許容でも、何年も鳴らしていたら、内蔵のPCや連装DACには、連装アンプにも、必ず悪意影響が出るはず、と想像します。
この想像と較べると、NS-1000 の、40年(!)を経ても全く色あせない、現在でも最高位に君臨する、総合性能は、本当に驚嘆すべきものだと思います。
一方、私は(ここの皆さんも?)、PCとソフトウエアチャンデバEKIO+DAC8PRO で、あの超高価な TRINNOV ALTITUDE32 と同等かそれ以上の処理と音響品位が達成できることを、すでに、ほぼ確実に確認できています。
ということは、、、今後のオーディオシーンは、TRINNOV ALTITUDE32、 Kii Three Active Loudspeakers、LINN EXACT に代表されるような、非常に高価な一体型製品市場と、私が指向しているような、「PC+ソフト、多連装DAC(DAC8PROのような高性能でリースバブル価格)、NORD ONE のようなリーズナブル価格の多連装アンプ」、を自由に組み合わせて、柔軟に構築する Hi-Fi DIY的市場、の2極へ分かれていくのかも知れませんね。
今や、総合的な音響品位の観点で両者の間に大きな差があるとは、、、私としては思えませんが。。。。
その意味では、ASRの私のスレッドは、LINN, TRINNOV や Kii Audio からは、疎まれる、嫌われる存在かもしれませんね。
また、多連装アンプ群についても、XM4080や Nord One MP NCXXX 4-8 122-500W で、十分に高品位な音響のシステムが完成できるなら(できると確信しています!)、高級 Hi-Fi アンプメーカーからも疎まれるスレッドになるのかも、、、、とも考えてしまいます。OKTO社の Pavel さんも同様なことを仰せでした。
まあ、ターゲットになる「客層」が基本的に異なるので、DIY的オーディオ趣味人の世界として無視されるだけかもしれませんが。。。(そう願っています!)
とにかく、私は、EKIOのLUPISOFT社や、OKTO社、Nord Acoustics社、などの方向性を歓迎し、大いに応援したいと思います。
https://theartofsound.net/forum/showthread.php?68601-Okto-Research-DAC8-Pro-multi-channel-DAC
におけるGordon(Halfway Tree) 氏のコメントを見て、私もMola Mola Audio Tambaqui DAC の情報を眺めていますが、これはこれで凄い製品ですね。価格も凄いですが。。。。
是非、評価機を入手して下さい。Naim ND555 enthusiastsさんの実機評価を楽しみにさせていただきます。
今後とも、様々な情報交換とご指導、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23366710
![]() 1点
1点
dualazmakさん
>PCハードとソフトウェアチャンデバの柔軟性を知り、それをある程度使いこなせる私のような人間から見ると、PCも、連装DACも、連装アンプも、全部をSP筐体内に収納するのは、電磁ノイズと振動の観点からも、「あり得ない!」 としか思えないのも事実です。
問題のSP筐体内に収納されているのは、DSP, DAC, AMP ですが、PC は収納されていません。
この Kii THREE の存在意義ですが、私のつたない考察では、ソースに繋げば音楽試聴準備が直ちに整うことが出来るスピーカーであるということです。
外付けの DAC, AMP に要する費用を考慮すれば、Kii THREE はそれほど高価には感じないという私の金銭感覚に疑問符が付くのでしょうか。
日本国内で Kii THREE を使用ている方のブログです:
https://www.for-artist.com/blog/nikki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%80kii-three%E6%8A%95%E5%85%A5/
https://www.for-artist.com/blog/nikki/kii-audio-kii-tree%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8b%e3%82%89%e5%b0%91%e3%81%97%e7%b5%8c%e3%81%a3%e3%81%a6/
それでは、また。
書込番号:23367225
![]() 1点
1点
そのブログ(コラム)には以下の続きがございました。
https://www.for-artist.com/blog/column/kii-tree-bxt-%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb-%e6%98%a8%e4%bb%8a%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/
https://www.for-artist.com/blog/column/spl%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%a9%9f%e6%9d%90%e3%80%81kii-threebxt%e3%80%81igs-audio%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%a9%9f%e6%9d%90/
書込番号:23367351
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
>問題のSP筐体内に収納されているのは、DSP, DAC, AMP ですが、PC は収納されていません。
了解です。そうなると、Kii THREEは、SK AUDIOさんのPCS-3000;
http://www.skaudio.jp/pcs-3000.html
および VT-EtPDAC
http://www.skaudio.jp/audioif.html#etpdac
と、非常によく似たコンセプトのように見受けました。VT-EtPDAC も、専用PCボードとの接続はLANケーブル1本で、専用プロトコル、といっても業務業界では一般的な DANTEプロトコール、だそうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab
の 2020/01/22 22:07 書込番号:23185041 をご参照下さい。SK Audio の小森様とのやりとりです。
ちなみに、SK AUDIO の VT-EtPDAC も、アンプはHypex NX252MP を4基採用、ですね。ここでも、Hypex 恐るべし!ですね。
Kii THREE も、VT-EtPDAC も、やはり全段 192 kHz 24 bit 処理ですね。
SK AUDIO小森様との、突っ込んだ情報交換では、「DANTEプロトコール準拠と言うことで、やはり弊社の製品群は、どちらかというと録音業界の業務用途を意識して設計&提供しています。」と仰せでした。 ご紹介いただいた Kii THREEブログの方も、マスタリングスタジオでのご利用、とお見受けいたしました。 家庭の Hi-Fiオーディオ環境で使われている方は、おられますかね?
今後、Kii THREEやSK AUDIO社製品を家庭での Hi-Fiオーディオ環境で利用した報告や、そこでの従来型オーディオ装置との総合的な音響品位の比較報告が楽しみです。
Naim ND555 enthusiastsさん、是非、その方向で検討されて、色々お聞かせ下さい!
書込番号:23368213
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
私の現マルチアンプ化プロジェクトのコスト面ですが。。。。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284
でお話ししていたように、1月初旬時点には、本当に、本気で;
ACCUPHASE DF-65 1台
ACCUPHASE P-4500 4台、または E-270 4台
の導入を想定していました。
それが、現在では;
EKIO 1ライセンス USD149
DAC8PRO 1台 EURO1,163 (リモコン、送料込み)
Nord ONE ステレオ4連アンプ 1台£1,619(送料込み)、未定ですが。。。
の構成=約37万円で、アキュDF-65 チャンデバ構成+アンプ群を遙かに凌駕する、フルデジタルのマルチアンプ環境が構築できることが明らかになりつつありますので、当初の構想と比較すると、性能的にはずっと優れているのに、コスト的には1/10〜1/20で実現できてしまいそうです。これに保護コンデンサーやSPケーブルの微々たる出費は、オンされますが。。。。
ここでの Naim ND555 enthusiastsさん、BOWSさん、あいによしさん、を含む皆さんとの情報交換と貴重なご示唆を経て、この状況にたどり着けたことは、ある意味、驚異的なことだと、あらためて実感し、感謝しております。
やはり、ソフトウエアチャンデバと DAC8PROの登場によって、この方面ではパラダイム変化が起こっていることを実感しております。
書込番号:23368311
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
閑話休題、again です。
このグループ Voices of Music の活動は、陰ながら少々支援し、応援しています。
https://www.youtube.com/watch?v=pdsyNwUoON0
https://www.youtube.com/watch?v=LSmqY1RIxPY&feature=em-lsp
他にも、たくさん、優れた画質と音質の演奏がアップされています。
これも、、、いつも癒やされます。涙が。。。。
https://www.youtube.com/watch?v=uczsnta4Hcg
書込番号:23368347
![]() 1点
1点
dualazmakさん
>および VT-EtPDAC
http://www.skaudio.jp/audioif.html#etpdac
と、非常によく似たコンセプトのように見受けました。VT-EtPDAC も、専用PCボードとの接続はLANケーブル1本で、専用プロトコル、といっても業務業界では一般的な DANTEプロトコール、だそうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab
の 2020/01/22 22:07 書込番号:23185041 をご参照下さい。SK Audio の小森様とのやりとりです。
ちなみに、SK AUDIO の VT-EtPDAC も、アンプはHypex NX252MP を4基採用、ですね。ここでも、Hypex 恐るべし!ですね。
こんにちは。
早速、御指定の S&K Audio VT-EtPDAC の紹介ページを見ました。そこでの VT-EtPDAC における Power Amp Module が ICE Power 製のものですが、それらがアップグレードされて Hypex NC252MP に変更予定ということですね。その価格では Kii THREE の方に惹きつけられますが。
>今後、Kii THREEやSK AUDIO社製品を家庭での Hi-Fiオーディオ環境で利用した報告や、そこでの従来型オーディオ装置との総合的な音響品位の比較報告が楽しみです。
Kii THREE は海外(特に欧米諸国)在住の audiophiles の間ではとても話題性のあるスピーカーのように私には思えます。
余談ですが、HIFICRITIC 誌の Editor-in-Chief である Martin Colloms 氏によれば「 Kii Three は QUAD ESL 63 を感じさせると」 Kii THREE に対する印象を述べていますが、私は実は QUAD ESL 63 を所有しています。
また、S&K Audio 製品につきましては日本国内のオーディオマニアのごく一部で話題になっているかとは予想されますが、いかんせん高価過ぎという感じ(ゴトーユニットも同様な感じ)を受けます。
それならば、彼らはLINN 製品を買おうと思うかも知れませんね。
S&K Audio 製品に関するフェイスブックも拝見しましたが、率直に申しますと、「ニッポンのオーディオここにあり」という感じが致しまして少々めまいを覚えました次第です。
それでは、また。
書込番号:23368410
![]() 1点
1点
dualazmakさん
YouTube のご紹介誠にありがとうございます。
今夜、それらを堪能致したいと存じます。
取り急ぎ御礼まで。
書込番号:23368430
![]() 0点
0点
Naim ND555 enthusiastsさん
S&K AUDIO は、技術的には最先端で優れている(?)のでしょうが、それに頼りすぎて、デザインやマーケティングのセンスが、、、、、
こんな所でも、技術的に優れた日本の製品でも、やはり世界的には認知されず、通用しない、という一端を見る思いがします。
最近の欧州勢は、マーケティングのセンス面でも、日本やアメリカ勢の先を走っていますね。
書込番号:23368498
![]() 1点
1点
dualazmakさん
>S&K AUDIO は、技術的には最先端で優れている(?)のでしょうが、それに頼りすぎて、デザインやマーケティングのセンスが、、、、、
こんな所でも、技術的に優れた日本の製品でも、やはり世界的には認知されず、通用しない、という一端を見る思いがします。
最近の欧州勢は、マーケティングのセンス面でも、日本やアメリカ勢の先を走っていますね。
全く同感です。やはり国民性と言いましょうか音楽に対する姿勢の違いでしょうか。
アメリカ勢では、私の知る限りでは、Dan D'Agositino, Audio Research, Magico などが非常に元気のように思います。
音楽に対する国民性に関しましては、Kii THREE を導入されたチーフプロデューサー・エンジニア(Hiro)氏のコラム・ブログでも興味深いことに言及されていますね。
https://www.for-artist.com/manager-top/
英国におけるCOVID-19 が終息に向かう時期になってからでも Martin Collom 氏(彼も Naim Audio のパルチザンの一人です)にemailを送って Mola-Mola DAC のことや Hypex Class D Amp Module などに関しての彼の持ち得ている印象などを尋ねてみます。
それでは、また。
書込番号:23368717
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん、皆さん
本日 OKTO Research の Pavelさんから連絡があり、私の DAC8PRO は、5月4日月曜日に FedEx Express国際梱包便でプラハを出発する、とのことです。 恐らく、来週末頃には、手元に到着することでしょう。 例の、フルコンパチブルな ASIO ドライバー (Windows環境用)も、先行して頂戴しました。
書込番号:23373568
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんばんは。
遂に DAC8 発送とのこと来週週末が楽しみですね。それに対する試聴結果を楽しみにしております。
>このグループ Voices of Music の活動は、陰ながら少々支援し、応援しています。
https://www.youtube.com/watch?v=pdsyNwUoON0
https://www.youtube.com/watch?v=LSmqY1RIxPY&feature=em-lsp
他にも、たくさん、優れた画質と音質の演奏がアップされています。
これも、、、いつも癒やされます。涙が。。。。
https://www.youtube.com/watch?v=uczsnta4Hcg
最初の演奏はとても普段着の合う演奏かと感じました。
残り2つの演奏はかなり自制心の効いた演奏で正座して聴くべき演奏かと感じました。
特に、最後の演奏(BWV 904) については YouTube で他の演奏者の演奏も聴いて見ましたが、その中では
https://www.youtube.com/watch?v=Y5I6wl_HToA
が私にとりましては印象に残りました。
ついでながら、Kii THREE には片CH6個ドライバー(そのうち1つがmidrange, 1つがtweer)を各1つにつき 250W/4ohm の Hypex amp module で駆動しているようですが、どうして 250W/4ohm のmodule が選ばれたのか少し興味が湧きました。
それでは、また。
書込番号:23373735
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
>https://www.youtube.com/watch?v=Y5I6wl_HToA
>が私にとりましては印象に残りました。
聴きました。これも、いいですね。 YouTube でも、そこそこの音質で優れた演奏が聴けることは、本当に嬉しいことです。
>遂に DAC8 発送とのこと来週週末が楽しみですね。それに対する試聴結果を楽しみにしております。
発注したのが2月15日でしたので、このご時世下では、まあ許容な納期かと。。。
ASRでの情報では、昨年、6ヵ月待たされたという方もおられましたので。。。
XM4080 の手配は、DAC8PRO の顔を見てからにします。
DAC8PROが到着したら、今日Pavelさんから送られてきた例の ASIO Driver による I/O も含めて、Windows 10 および EKIO による DAC8PRO の認識と I/O を、まずじっくり検討、検証します。
音質面では、エージング(Burn-In)も兼ねて、まずは2チャンネルずつのステレオDACとして利用し、OPPO SONICA DAC の音と、厳密に試聴比較する予定です。
柔軟なEKIOから、DAC8PRO と SONICA DAC へ、同時に、同じステレオチャンネルを送れますし、ACCUPHASE E-460 には XLRバランス入力が隣り合わせで2系統(BAL, CD-BAL) があるので、曲を流しながら瞬時に切り替えて比較試聴ができます。 DAC8PROは 8チャンネルですので、4回繰り返せば、DAC8PROのチャンネル間の音質差(あるはずがないですが)も確認できますね。
Nord ONE ですが、先日(4月8日)、書込番号:23328401で見ていただいたように、次のように考えております;
************************************************************************************
性能的にも、価格的にも、Nord One MP NCXXX 4-8 122-500W は魅力的に感じます。
アンプモジュールの選択;
(案−1)
Channels 1-2 を NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)
Channels 3-4 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
Channels 5-6 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
Channels 7-8 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
は、どう思われますか? KJF Audio も、 Nord Acoustics も、メールやチャットでの問い合わせに対して、NX252MP と NC122MP の間で音色や音響品位には差はないし、差を聴き分けることは恐らく不可能です、と応えてきました。
最終的にどう使うかは未定ですが、Channels 3-4 も NC252MP にして、
(案−2)
Channels 1-2 を NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)
Channels 3-4 を NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)
Channels 5-6 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
Channels 7-8 を NC122MP (2X125W 4Ω、2X75W 8Ω)
という構成にしておく方が、もしSPユニットを交換する場合でも、柔軟で余裕のある利用が可能かな? とも考えております。
************************************************************************************
Kii THREE も、S&K AUDIO の VT-EtPDAC も、どうやら NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)相当品を使っているようですね。Kii THREEにおける、この選択の理由などについて、情報を入手されましたらご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
やはり、能率の低い大型のSPユニットの余裕駆動も想定している、と単純には考えますが、TW駆動用にもこれを使っているなら、他にも理由があるのでしょうね。
私のシステムの場合、Be-SQ, Be-TW, Horn ST は、いずれも非常に高能率ですので、上の(案ー1)でも十分に余裕かな、と見ておりますが、価格的には大差ないので、案ー2 としておくことも検討中です。
書込番号:23373925
![]() 2点
2点
dualazmakさん
>Kii THREE も、S&K AUDIO の VT-EtPDAC も、どうやら NC252MP (2X250W 4Ω、2X200W 8Ω)相当品を使っているようですね。Kii THREEにおける、この選択の理由などについて、情報を入手されましたらご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
やはり、能率の低い大型のSPユニットの余裕駆動も想定している、と単純には考えますが、TW駆動用にもこれを使っているなら、他にも理由があるのでしょうね。
Kii THREE の場合にはステレオ仕様ではなくモノラル仕様のアンプモジュールを使用したかったので NC250 MP を採用したのではないかと推測されます、多分。NC122 MP 相当ののモノラル仕様は製品リストにはなさそうですし。
NC122 MP と NC252 MP の写真を比較して見ましたが、当然ながら後者のパワーサプライ(SMPU)の方が重厚感があります。価格差がほとんどなければ、また細かなスペックを気になさるのであれば後者の使用を優先されるという考えもあるかとは思いますが。といったところでしょうか。
それでは、また。
書込番号:23374031
![]() 1点
1点
訂正です:
(正)パワーサプライ(SMPS)
(誤)パワーサプライ(SMPU)
書込番号:23374048
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんばんは。
ARSへの最新の投稿を拝見させていただきました。
YAMAHA NS1000(M) に関する websites ですがもう既にご存知と思いますが、以下のようなものも存在しています。
http://www.troelsgravesen.dk/Yamaha-NS1000.htm
http://www.thevintageknob.org/yamaha-NS-1000.html
甚だ、簡単ですが。
書込番号:23378154
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
おお、ありがとうございます。これらも、なかなか参考になりますね。
「日本の仲間からお知らせがあったので、、、」として、ASR のポストに追加しておきます!
書込番号:23381276
![]() 1点
1点
皆さん、
本日、先ほど、DAC8PRO (order #106 2月15日に発注) がリモコンと共に到着しました。
おそらく、日本初でしょうか?
もうすぐ、「続々 。。。。」 の新スレッドを建てて、情報共有させていただきます。
また、ASR の;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
でも前進しますが、のんびりしていられるのが明日10日の日曜日までですので、情報共有の速度は、かなり低下しそうです。
書込番号:23391780
![]() 1点
1点
皆さん、
追加の関税などは、一切発生せず、普通に FedEx で配送されてきました! まだ、開梱してませんが。。。。
書込番号:23391831
![]() 1点
1点
dualazmakさん
こんにちは。
dualazmakさんの DAC8 Pro が本日無事にご到着ということで嬉しく思います。やっと今その時が来ましたね。
さて、このスレッドの新規移転前に Hypex Ncore based class D 8CH amp に関しまして私なりに整理しておくことに致しました。
これはあくまでの私の見解ですので、dualazmakさんにとりましては全く強制力などございません。
それらに対する私の推薦順に以下列挙致します:
(i) Appolon Audio NCMP8200 (Austria) EUR1,890 + s/h EUR130
https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/
Appolon Audio の選択理由につきましては、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/
における Burning Sounds による posts が大変参考になるかと思います。Burning Sounds が英国内ではなく海外(Austria) からわざわざ購入したということは何かしら大きな意味があるかと思います。
(ii) Nord Acoustics Nord One MP NC252 (Speaker Output Wire: Silver Plated Pure Cu 14AWG)
GBP1,639 + s/h GBP120
ここで option として Speaker Output Wire: Silver Plated Pure Cu 14AWG を選択しました。
(iii) Nord Acoustics Nord One MP NCXXX 122-500W
上記のいずれの機種も良心的価格で提供されているかと思います。
これで、私の本日のテーマは終わりです。
それから、Kii THREE に追記しておきますと Stand Subwoofers (BXT) を使用する意味が私には全く理解できません。BXT 無しの Kii THREE (専用スタンド付き)で十分に完成されていると思いますのでその完成度に水を差すような BXT はいけませんね。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/stand-subwoofers-like-the-genelec-w371-kii-bxt-etc-ideally-with-dsp-multi-drivers.11300/
そういえば、QUAD ESL63 に subwoofers を組み合わせている ASRメンバーもいるようですが、人の好みは人それぞれですね。
ということで、dualazmakさんの DAC8 Pro をテーマにした新規スレッドを楽しみにしております。
それでは、また。
追伸: ASR における DAC8 Pro スレッドは本日も盛り上がっているようですね。
書込番号:23391893
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
いろいろ、まことにありがとうございます。
一押しの;
>(i) Appolon Audio NCMP8200 (Austria) EUR1,890 + s/h EUR130
>https://www.apollonaudio.com/apollon-ncmp8200-hypex-based-multichannel-class-d-amplifier/
ですが、あらためて添付画像のようにチョイスしても、1,890ユーロ+送料130ですので、総額約23〜25万円、となるので、Nord ONE の同様の構成と価格的には大差ないですね。 前にもお知らせしましたが、私のASRスレッド
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
や DAC8PRO スレッド
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
でも、Burning Sounds さんのコメントや真摯な応答は、非常に信頼ができると思っておりますので、仰せの背景は、とても納得できます。
Nord ONE と並行して、Appolon Audio NCMP8200 も候補とさせていただきます。
ASR における DAC8 Pro スレッド、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/page-73
の前後は、ごく一部の人達の AV I/O で盛り上がってますが、ちょっとついて行けないので、沈静化へのコメントを投げましたが、収まらないでしょうね。
では、今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23392213
![]() 1点
1点
dualazmakさん
https://www.apollonaudio.com/client-reviews-experiences-apollon-audio-amplifiers/
御参考まで。
大変失礼致しました。Appolon ではなく Apollon でした。
それでは、また。
書込番号:23392639
![]() 1点
1点
Naim ND555 enthusiastsさん
タイポミス、私も結構頻繁にやってます。気になさらないで下さい(笑)。
ASRの常連の方々などは、我々よりも遙かにひどい英語やタイポミスが多々あっても、意味が通じればお構いなし、ですよね。
Burning Sounds さんには、また私のASRスレッドにもお越しいただきたいので、本日午後に、
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multichannel-amps-for-active-systems.2417/post-394591
をポストさせていただきました。
届いた DAC8PROは、取説も電源ケーブルも同梱されていない質素な梱包ですが、緩衝材はしっかりしてました。USB 2.0 ケーブル1本と、もちろんですが、追加発注した Apple Remoteリモコンはきちんと同梱されています。取説は、最新版をダウンロードさせるという、至極合理的な主義ですね。
明日、写真(外観も、内部も)を撮って、まずは先行でもらった専用ASIOをインストール、Windows 10、ASIO4ALL による認識、それらを含めて EKIO による I/O認識、あたりから検証/検討を始めたいと考えております。 私の場合は、当面使わないと思いますが、AES/EBU 4系統とそれに連携する USB in/out が、Windows などによってどのように認識されるのかも、興味津々です。
期待が大きいボリュームですが、取説にも添付画像のように書かれていて、予想通りのマスターボリュームおよび8チャンネル個別ゲイン設定が可能ですので、各チャンネルのマスターに対する相対ゲイン(左右バランス設定も兼ねる)を一旦決定すれば、その相対値を維持したままマスターボリュームを上下できるという、私の目的にとっては理想的なボリューム、ゲイン機能ですね。マスターボリュームを絞ることさえ忘れなければ、パワーアンプ群への直結でも、SPユニットを損傷する可能性は極めて低い、と感じています。ASRの各所でも、マスターボリュームおよびゲインでかなり絞っても、音質劣化がほとんどない驚異的な性能(!)が実証されているので、大いに楽しみです。 XMOSを含めた、それなりのエージングは必要だと思いますが。。。。
このマスターボリュームおよびゲインが、本当に優れものであれば、緻密に準備およびシミュレーションしてきたように、EKIOからは全域でほぼフラットでゲインおよびディレイ設定なし、LR 12dB/OCT傾斜の最も単純に位相補正/調整可能な simple is best な5帯域チャンデバ(クロスオーバー)設定にてASIO経由でDAC8PROへ送り、各チャンネルDAC変換後に、ES8028PRO内蔵(と XMOS連携)のデジタル精密ゲイン調整によって現行のアッテネーター設定を模倣させれば、、、もう完璧、ですね!
というはやる心を抑えつつ、step-by-step で、OPPO SONICA DAC との総合音質比較から始めて、ゆっくりと前進します。
と言いつつも、少なくともマルチアンプトライアル中は、例のちょっとハイグレードな SQ, TW, ST 系統の保護コンデンサー(キャパシター)は、エージングも終了しているので、噛ませておくつもりです。
このあたりも含めて、ここでも新スレッド立ち上げ、でした! 立ち上げましたら、もちろん、ここでも、その旨をアナウンスいたします。
そうそう、国内の、とあるアンプ工房様が、Hypex NC400 を2台使ったステレオ 2-way 4-channel の高価なデジタルアンプ2台を XLRバランス入力仕様で、完全無償で試聴用に貸し出します、と仰せですので、相談中です。これが実現する際には、お知らせしますね。
書込番号:23393394
![]() 2点
2点
私も、訂正です!
誤) ES8028PRO内蔵(と XMOS連携)
正) ES9028PRO内蔵(と XMOS連携)
失礼しました。
書込番号:23393431
![]() 1点
1点
dualazmakさん、こんにちは
きましたね、おめでとうございます。
NS1000がどう化けるか、パッシブに比べ自由度が高いので、dualazmakさんの感性次第ですね。いきなり鮮度の高い音でとまどうかもしれません。
書込番号:23394935 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
あいによしさん
お久しぶりです。 はい、ようやく到着しました。
DAC8PRO 使ってみて実感しておりますが、本当に、予想以上に、高性能で、「まさに恐るべし!」 です。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
の私のスレッドで、先に紹介を始めていますが、ここでも、近日中に新スレッドを建てて移行します。
それにしても、ここでの、これまでの、皆様からの多大なご支援もあって、上記のASR Forum スレッドは、なんと、ほぼ1ヵ月で7,000回を超える閲覧訪問があり、とても驚いております。COVID-19 の「巣ごもり=暇」の効果も大きいのでしょうが。。。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc
中には、啓発的にも教育的にも素晴らしいスレッドだ、と煽ててくれる方々もあり(お世辞?)、それはそれで励みになります。
ASR Forum 重鎮の2,3名の方々からも PM(個人間交信)を頂戴しており、「最近のベストスレッドだ!教育価値も高いので、頑張って続けて下さい。。。」、とのコメントを頂戴しております。
書込番号:23396853
![]() 3点
3点
皆さん、
このスレッドも大変長くなりました。貴重なご支援、ありがとうございました。
ようやく DAC8PRO が入手できましたので、新スレッドへ移行いたします。
『続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23398907/
にて継続しますので、引き続き、よろしくお使い下さい。
なお、ここでも、英語ですが、情報交換を行っておりますので、ご覧いただき、ご参加下さい。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
書込番号:23398934
![]() 0点
0点
Raspberry pi(通称ラズパイ。低価格のシングルボードコンピューター)をデジタルチャンデバ兼ファイルプレーヤーとして使って低価格マルチアンプシステムが作れます。
http://audio2.amanogawa.info/
コンセプトは簡単お手軽にそこそこ高音質!
高級機材をつぎ込んで究極の高音質を目指すのも良いですが、簡単お手軽なマルチアンプも楽しいですよ。
構成
ラズパイ(pi2 pi3 pi4のいずれか+電源、microSDカード、ケース、ヒートシンク等)
使用するのはすべて無料のフリーソフト。
AVアンプ(7.1ch対応のもの)
スピーカー(適当な3wayのもの。自作でも市販品改造でも可)
ラズパイとAVアンプはHDMI(96kHzLPCM8ch)で接続。
ラズパイで帯域分割してAVアンプに出力します。
AVアンプのスピーカー出力は7chあるので3way+サブウーファーまでいけます。
音量調節もAVアンプのリモコンで行えるので楽ちん。
お手軽と言っても手は抜きません。
各チャンネル16384tapのFIRフィルタ(いくらでも増やせるけどこれで十分)
帯域分割は直線位相、イコライザは最小位相特性で高音質を目指します。
またマルチアンプの調整には測定がほぼ必須ですので測定の話題もありです。
興味のある方は返信ください。
情報交換しましょう!
ベテランの方も、初めて自作スピーカーを作ってみたい初心者の方もどうぞ。
気軽に、ゆるい感じでマルチアンプを楽しみましょう。
![]() 2点
2点
ラズベリーパイ4と今回関係ないけどJetson nanoで遊んでますので参考になります。
書込番号:23283103
![]() 1点
1点
Jetson nano は随分高性能ですね。
linuxの場合にはALSAでHDMI 8chがサポートされていれば簡単にマルチアンプができますよ!
(mpdとBruteFIRあたりをインストールすれば良いはずです)
書込番号:23283823
![]() 1点
1点
Raspberry Pi 4はバグ修正版のNOOBS 3.3.1に置き換えます。
ラズパイと比較してJetson nanoは不安定、アイコンダブルクリックしてもアプリが立ち上がらなかったり
勝手に再起動したり。
機械学習、AIとは何かのデモ用ですね。
書込番号:23284008
![]() 0点
0点
この自粛の暇に任せて同じようなことを考えていた者です。あれこれ検索していたら引っかかってこちらに飛んできました。
よろしくお願いします。
私が実現したかったイメージとしては、ラズパイをroon bridgeにして、PCM変換させずにHDMI経由でDoP(dsdマルチチャンネル)をNative再生に対応したAVアンプに通してroonを活用したいという感じです。
インテル製のNCUでHDMI2.0対応の物を使うと同様のことはできそうなのはわかって来たのですが、もう少し手軽に同様のことが試せないかと・・・。
7ch可能と記載がありますが、PCM変換ではなくNativeでも行けますか?
>ラズパイで帯域分割
この辺りは私はあまり詳しくないのですが、確証はなくてもうまく行きそうな構成があるなら、ぜひ買って試してみたいのです。
書込番号:23375216
![]() 0点
0点
大学時代からマーティンローガンをメインにしてきた自分にとっては非常に嬉しいニュース。
エリアスだったが、静電型の良さにほれ込んだ一方、アンプ選びがこんなにも難しいものと、
勉強になった機材だった。1オーム、2オームというありえないような負が続き、並みのアンプ
ではまったくダメだった。当時マランツのプリメインでA級にして20Wとかで駆動させていたこともあったが
考えるとアンプは死にそうになっていたんだと思う。
これを鳴らすのにアキュの500Lを購入することになった。
最新機はペア80万のESL機から入るようで、どれくらい進化しているか楽しみ。音圧は91db
となっていたが、負担は多分変わらず低オームになりアンプを困らせると予想。
鳴りが独特の静電型、ボーカルの優しさは唯一といっても良い位。
実質ペア30万位の安い小型ESL機もでてほしいものです。
![]() 4点
4点
>はらたいら1000点さん
こんにちは。
"80万円のESL” というのは実際にはESLの上位機の ESL X という機種のようですね。
現地価格はペアで$4000または$4500(仕様違いでしょうか?)のようです。
現地価格の約2倍、かさばる上に住宅事情もあって数が出ないでしょうし、残念ながら想定通りの値付けでしょうか?
MLの静電型で一番安いのはElectroMotion ESL で現地価格はペアで$2500-$3000くらいのようですね。
仮に日本に導入したとしても60万円以上になりそうですねぇ。現地価格なら30万円なのですが。
30万円で売ってくれれば見た目もおしゃれな感じですし、市場も広げられると思うんですけどねぇ。
ただ、展示機を確保したりしたらコスト的にやむを得ないのだとは思います。
なお、エリアスの4オームに対して今のは6オームになってて能率も少し上がってると書いてありますね。(でも1.6@20kHzってのは2万ヘルツで1.6オームということかも?)
https://www.safeandsoundhq.com/products/martin-logan-electromotion-esl-x-floorstanding-speaker-factory-refurbished-pair
https://www.amazon.com/MartinLogan-ElectroMotion-ESL-Electrostatic-Speakers/dp/B01B2405BG/ref=psdc_3236453011_t3_B00557YW66
https://www.martinlogan.com/en/product/electromotion-esl
自分は静電型はヘッドホンのみでスピーカーは平面磁界型のMagnepanですが、いろいろ選択肢が増えるのは嬉しいですね。
でも直販でも日本にも発送するか、国内価格をなんとかするかはしてほしいですね。
Magnepan の2世代前のローエンドモデルMMGなんて現地価格は$600だったのに日本ではディーラーが変わってからは実売でも22万円とかでしたもんねぇ。安くてコストパフォーマンス最高が売りのマグネパンなのにとても残念に感じています。壁から1m近く離したり必要があったりで住宅事情やアンプへの要求の高さを考えると仕方ないかなとは思いますけどね。
書込番号:23344210
![]() 1点
1点
お知らせありがとうございます
私はエリアスを25万位で買った記憶が有ります。
マーティンは重く、でかいのと、ニッチな商品なので代理店の取り分も仕方ないかもしれません。
マグネパンMMG 家にいれてましたよ。初期だったので11万で購入しました。
とても好きな出方でしたが、10万で売れたので転売してしまいました。また欲しいです。
どちらもあの独特の音場感がたまりませんね。
書込番号:23344426
![]() 1点
1点
>はらたいら1000点さん
MMGは一時期メインシステムで使っていて今はリビングのシステムにて使っています。メインは1.7に変えました。どちらも中古です。
MMGはマグナライザーというスタンドを使っていますが、垂直になって音場がぐっとよくなって、あと低音も思ったよりも大きく改善しました。
個人制作のスタンドで掲示板での噂通り話好きなおじさんで何度もメールをやり取りしました。とてもいいスタンドです。
私はヘッドホンではない静電型スピーカーはQuadしか聴いたことがないのですが Martin Logan もいつか聴いてみたいです。
逆に Magnepan は日本の代理店では最小モデルは2世代前のMMGしかサイトに載っていなくて、現行のLRSはおろかその前のMMGiすら載っていなくて寂しい限りですね。
書込番号:23344521
![]() 1点
1点
スタンドは私も色々やってみました。
立て気味の方が日本の部屋環境だと良い感じがします。
マーティンは全く別物ですね。立体感はマーティンの方が
出ると思いますが、何せ鳴りません。マッキンとかクレル
何かじゃないとまともに音にならないとか言われていましたね。
電源力が必要という事ですね。
今度のは高いのでショップで試聴だけになるかもしれません。
でも独特あの音を日本の方に聴いてもらえるようになるのは
良かった。
書込番号:23344614
![]() 2点
2点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
-
【欲しいものリスト】PC構成20251031
-
【欲しいものリスト】メインPC再構成
-
【Myコレクション】自作構成
-
【欲しいものリスト】pcケース
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
スピーカー
(最近5年以内の発売・登録)