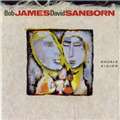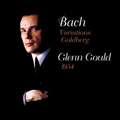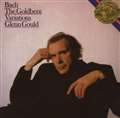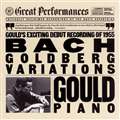���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S1056�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 119 | 59 | 2020�N2��12�� 14:22 | |
| 62 | 21 | 2020�N2��11�� 19:59 | |
| 12 | 22 | 2020�N2��8�� 02:21 | |
| 19 | 63 | 2020�N2��6�� 14:08 | |
| 11 | 9 | 2020�N2��5�� 20:19 | |
| 16 | 7 | 2020�N2��3�� 18:54 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
���x�A������Ȃ�����Ȃ̂ł����A���ɂȕ����t�������������B
����ADIATONE DS-500N ��YAMAHA NS-10MT���i���Ŏ�ɓ��ꂽ�̂ł����A
�i10MT�̕���500N���}�V�ł������j�����C�}�C�`�ł����B
�����ɁA�Ƃɂ������X�|���W���킵����ċl�߂���A���ƂȂ��ǂ������ɂȂ�܂����B
�����ŁA�o�X���t�|�[�g�̍ǂ����������Ē��������̂ł��B
�܂��A�ގ��͉����g�����H�@���܂荂�����͎̂g�������Ȃ��̂ŁA�z�[���Z���^�[�ɂ�����̂ł��肢���܂��B
���ɁA���ȍH���@�B����܂ł͂����Ȃ��Ă��Y��ɔ��~�Ƃ�1/4�~�Ƃ��ɍH������@������A�����ĉ������B
����A�G�b�W�̃_���v�܂ɂ��Ă͓h��ւ����s���\��ł����A���݂̓G�b�W��܂őΉ����Ă��܂��B
![]() 7�_
7�_
����ɂ��́B
�X�|���W�g�p���܂����A�r�ځi������j�ȂǑf�ނłn�j�Ǝv���܂��B
�����͊��C��Ɏg�p����r�ڂ̃X�|���W�݂����Ȃ̂��Ƃɂ���A
��������[�������Ďg���Ă܂��B���̔��������d�v�łǂ̒��x
��C�������邩���������ł��ˁB�����͍D���D���ł��B
�����ԍ��F16305164
![]()
![]() 6�_
6�_
Kyushuwalker����A����ɂ��́B
>�ގ��͉����g�����H
�^�I�����ۂ߂ċl�߂Ă��A�ቹ�̓_���v�ł��܂��ˁB�ގ��▧�x�A�傫���ɂ���ĉ��͂��낢��ς��܂�����A���Ў肶���ȃ��m�ł��ꂱ�ꎎ���Ă݂܂��傤�B
���ɂ��̎�́u�Z�b�e�B���O�v�Ɋւ��ẮA����I�Ő�́u�����v�͂Ȃ��Ǝv�����ق�����낵���ł��B���̍D�݂͐l���ꂼ��ł�����A�Ⴆ��A���u�������g���Ɖ���������v�ƌ������Ƃ��Ă��A���������������Ă݂���u�����v�̌��ʂ������肷�邱�Ƃ͂悭����܂��B
�I�[�f�B�I�́A�g���C���G���[�ł��B���ۂɎ����Ă݂āA�u�����ł��Ȃ��v�A�u�����ł��Ȃ��v�Ǝ��s���낵�Ȃ���A���Ёu���������̐����v�������Ă��������B�ł͂ł́B
�����ԍ��F16305251
![]() 8�_
8�_
Kyushuwalker����A���ӂ́B
�@�����g��SP�ł͖����ł����A�ȑO�u�o�X���t�����v�̗F�l�ɂ����������̘b���B
�@
�G�Ђ���n�܂�A�ȁA�Â��ю��Z�[�^�[���ۂ߂����A�X�|���W�e�ߍׂߊe��A���A�X�`���[���A
�i�{�[���A�g�C���b�g�y�[�p�[���X�E�E�E�E�E�E�B
���̎��ɂ͂ǂꂪ�ǂꂾ�����ʂ�����̂��H�����ǂ��Ȃ������͊F�ڕ����炸�d�����B
���z�͍ŏI�I�ɃS�����|�[�g�ɃM���E�M���E�l�߂Ă��܂��܂����B
���l�I�ɂ͎g���Ă���SP�̑召�Ɋւ�炸�A�F�u�o�X���t�^�C�v�v�ł��B
�C�ɂȂ�l�͋C�ɂȂ��ł��傤�ˁ[�H
�N���V�b�N��w�Ǖ����Ȃ��A�u�ʎ��v�̃W�W�C�ɂ͂킩��Ȃ����E�ł��B�@
�����ԍ��F16305308
![]()
![]() 7�_
7�_
�͂炽����P�O�O�O�_����
�����X�|���W���A�ۂ߂Ďg���肪����܂����ˁB
���ꂾ�ƁA�������Ƃ����тɂȂ炸�Ɍ��h�������������ł��B
500N�͌��ɂ���̂ŁA�܂����h���͋C�ɂ��܂��A
10MT�͑O�ɂ���̂ŁA��肭�ӂ��������ł��B
�܂��A�l�b�g������Ζڗ����܂��B
Dyna-udia����
���肪�Ƃ��������܂��B
���Ƃ��ƃo�X���t�̉����s�����Ȃ������̂ŁA�D��ł͎g��Ȃ������̂ł����A
�܂����܂ɂ͂������Ǝv���āA�����������A�����Ă݂܂����B
���s����Ƃ����͕̂������Ă���̂ł����A���l�̈ӌ���A�C�f�A�͉����ƎQ�l�ɂȂ�܂��B
�Ƃ��ɌÂ����̂͂Ɋւ��ẮA�݂Ȃ��ꂱ�ꎎ���Ă���͂��ł�����B
�z��X�|���W�Ȃ炽���̂悤�ȕ��ł����A������Ƃ������h�����ǂ����������A
����ɒ��߂ł���̂��������ȂƎv���܂��āB
���m�b��q�Ǝv��������ł��B
�����ԍ��F16305320
![]() 4�_
4�_
�l�I���W����@
�����́B�����z���ł��Z���������k�ł��B
�������̂��F�l�ɋ߂������ł��B
���U�Ŗ��^�̃r�N�^�[SX-500���Ă��܂��܂����B
����́A�X�^���h�t����15000�~�A����肿����ƍ��������̂ł����A�X�^���h�t���ł����A
�����w�ǂȂ��A�����D�݂ŁA�悢�������������Ǝv���܂��B
�������_���E�E�E�A�X�^���h���{���ɂ������Ă��āA���݂̂Ƃ��땪���ł��܂���B
�����悤�ȑ傫���̃X�s�[�J�[���R��ɓ��ꂽ�킯�ł����A�ǂ���������̏o������������܂��B
�Ȃ��悤�ɁA���ꂱ�ꂵ�Ă݂܂��B
���̍D�݂͂��Ԃ�Ⴄ�Ǝv���܂����A�I���W�l�������đʎ����Ƃ͎v���Ă��܂���B
���̓N���V�b�N���܂����A�R���T�[�g�z�[���͉��͗ǂ��Ȃ��Ă��R�K�̈�ԑO���D���ł��B
�I�P���ɂ͍��̂����̃V�X�e���͍��ЂƂł����A�o�C�I�����͂��ꂢ�ɒ�����Ǝv���܂��B
�����W���Y���܂����A�}�C���X�f�C�r�X�A�\�j�[�������Y�ӂ�̂����L�����Ȃ̂��D���ł��B
500N�͂���Ȋ����ł����B
�����ԍ��F16305380
![]() 1�_
1�_
Kyushuwalker����A����ɂ��́B
>���s����Ƃ����͕̂������Ă���̂ł����A���l�̈ӌ���A�C�f�A�͉����ƎQ�l�ɂȂ�܂��B
>�Ƃ��ɌÂ����̂͂Ɋւ��ẮA�݂Ȃ��ꂱ�ꎎ���Ă���͂��ł�����B
����|�A�������܂����B�o�X���t�|�[�g�̌��a�ɑ��T�C�Y���傫�����x�������قǁA�^�C�g�Ɉ������܂������ɂȂ�܂��B�X�s�[�J�[�ɕt�����Ă����p�̃X�|���W���A���S�ɋl�߂�Ζ��^�Ƌ�ʂł��Ȃ��悤�Ȋ����ɂȂ�܂��B
�Ⴆ��B&W CM1�Ƃ����ቹ���ƂĂ��L���ȃX�s�[�J�[������܂��B���̊��o�ł́A(�������X�s�[�J�[�X�^���h�ɐݒu������Ԃł�)���̋@��̒ቹ�͑������Ĉ�a���������܂��B�Ƃ��낪������A�ʂ肷����̃V���b�v�̓X���ŁA���̂������ቹ���������܂���CM1���������܂����B
CM1������Ȗ��������̂����̂́A���߂Ăł��B���ɋ����A�X������Ɂu����Ȃɒቹ���������܂���CM1�����̂͏��߂Ăł��I�v�Ɛ��������܂����B
����Ƃ��̓X������̓j�����Ə��A���ʂ̃o�X���t�|�[�g����X�|���W��e�������Č����܂����B�܂����������̓X�|���W���l�߂Ă���Ƃ͎v���܂���A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ���i�ł���(��)�B���Ԙb�Ŏ��炵�܂���(^^�U
�����ԍ��F16305400
![]() 12�_
12�_
Kyushuwalker����
�@���̗F�l�Ƃ����͖̂^�L������̍u�t�Ȃǂ����Ă���҂ł��B
�@�N�ɕ��������H�����œǂ��H�ˑR�˔��q���Ȃ����Ƃ������o���钆�ł�
�@�d�b�ŌĂт���悤�ȁu����v�Ȓj�Ȃ�ł����ˁ[�E�E�E�E�E�B
�@�N���V�b�N�������Ă��邭���Ɂu���ނ�JAZZ�D���v�Ȃ�ł���B
�@�v�����œ����j�ł�����@��I�т�g��������肭�s���Ȃ��Ƒ��l�̎���E�E�E�E�B
�@���͓���JAZZ�ł������L���E���L���̂͋��Ȃ�ł��B
�@�ǂ��炩�Ƃ����Ɓu���E�v�ƌ������Y�킷���܂����A�A�N�̋������͂ǂ��ɂ��ʖځH
�@J�E�z�|���Ƃ�B�E�P�b�Z���̃M�^�[��C�E�x�[�J�[��A�E�t�@�[�}�[���D���Ȃ��Ƃ���
�@JAZZ�ɓ������̂Ŕ��l���l���킸�u�T�b�p���n�E�X�b�L���n�v����ł��B
�@���m�ɂ́uJAZZ���C�[�W�[���X�j���O�v�t�@���ƌ������Ƃł��ˁB
�@���̔ނ͂����u�A�[�V�[�v�Ƃ������A�u�M�^�M�^�E�R�b�e���v�Ȃ�ł��B
�@�D�݂̍���Ȃ����ɖ���������������̂ł����A�u�ނ̉��y�Z���X�v�ɂ�
�@�h�����Ă���̂ŁE�E�E�E�E�B
�@
�@�Z���X���ǂ��Ă����y�m���������Ă��A�I�[�f�B�I���s�͈���ɒ���Ȃ��l�ł��B
�@���������̗g����Ɂu���^SP�v���Ă�����Ƃǂ����̕��Ɠ����ł��ˁI
�@SX-500�Ƃ����Ƃ��̖���uSX-3�v�̌�p�@�ł��傤���H
�@�uSX-3�v�͒Z���Ԏ茳�ɂ���܂������A���ł͖]�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȗǂ�SP�ł����ˁB
�����ԍ��F16305435
![]() 2�_
2�_
�����₷���t�F���g�������ł���
����Ȋ����ɔ��~�ɂ���ƃ|�[�g���U���g�����������Č������キ�Ȃ�܂�
�Ƃ͂����A����ς�o�X���t�̉��ɕς��͂Ȃ��̂őS���ǂ��̂��D�݂ł�
���~�̒��x�ɂ���Ă͋�C�̋C�����x�������Ȃ�߂��ăm�C�Y���C�ɂȂ�̂ŁA�����͒��߂��܂�
�ŁA����ς薧���ǂ��ƂȂ�����A�C��������������ƍ��߂ăO���X�E�[�����l�ߍ����
�|�[�g�ɂ��t�F���g���l�߂܂��傤(�������O���X�E�[���͌��N�̖ʂŗǂ��Ȃ�)
�����ԍ��F16305555
![]()
![]() 6�_
6�_
Dyna-udia����
�����A�z�[���Z���^�[�ɍs���Ă��낢�딃������ł��悤�Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁACM-1�A���N�̍����A�����r���O�̏��V�X�e�����l���Ă������A
�P���E�b�h��R-K731�ƈꏏ�ɔ������Ƃ��āA���Ȃ肢�낢�날��܂����B
���ǁA���r���O�ɂ�R-K731 ��!0MT ������܂��B
�l�I���W�l
�����ɖ��^�����̂́A��͂�A�z�ł������B���p���������B
�ŋ߂��ꂱ��������Â��������Ă���̂́A���K��T���ł�����܂��B
������ƌÂ��X�s�[�J�[�ŗ��K���āA���삵�Ă݂悤���v���n�߂�����ł��B
�N���v�g���̃X�s�[�J�[�ɖڂ�t�����̂ł����A
�����l�i�o���Ȃ�A���Â����������邵�A��������������܂�����B
���łɁA���X�����Ă���܂����A�^�o�R�͂����~�߂�7-8�N�B
���`�A���̃I�[�f�B�I���i�͔���܂���ˁB���Ԃ�^�o�R�̃��j�����݂��Ă܂��B
���͊��S�Ɏ~�߂āA�J�^�J�i�ƕ������̎g���������ł���悤�ɂȂ�܂����B
�D�ӓI�Ɏg���Ƃ��́u�����v�A�����Ƃ̎��́u�^�o�R�v�ł��B
�����̉��ƃo�[�{�����������n���̃W���Y�o�[���D���ł����B
�����ԍ��F16305621
![]() 2�_
2�_
sasahirayu����
���������b�ɂȂ�܂��B
���肪�Ƃ��������܂��B�t�F���g�͎����Ă݂܂��B
500N�̓G�b�W��܂�h���Ă��܂����A�{�i�I�ɂ͈�x�炵�āA
�G�b�W�̃_���v�܂����ꂢ�ɂƂ������Ɠh�蒼�����悤�Ǝv���Ă��܂��B
����܂ŁA���낢�뎎���āA�|�[�g���ӂ������ǂ����������܂��B
�Ƃ���ŁA�l�I���W����͏��܂������ASX-500����ɓ���܂����B
�{���ɂ��ꂢ�ŁA�����w�ǂ���܂���B
�������������ƂɁA�X�^���h���������ĂƂ�Ȃ��̂���_�ł��B
�ǂ�����ĊO�������A�v�Ē��ł��B
������A���̃X�s�[�J�[�[�q���g���ɂ����̂ŁA�������悤�Ǝv���Ă��܂��B
������ӂŗ��K�������ƁA�E�[�n�[�̃L���r�l�b�g�����삵�Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F16305662
![]() 2�_
2�_
�l�I���W�l
SX�V���[�Y�A�I�[�f�B�I�̑��Ղƃr�N�^�[�z�[���y�[�W�Œ��ׂĂ݂܂����B
���݂�SX�[M3�Ƃ��A�E�b�h�R�[���Ƃ��ǂ������ȋC�����܂��B�ł��A�ǂ����ȁ`�H
������A�̂�SX-900�Ƃ�SX-1000�ɖ��͂������܂��B
���t�I�N�ł�����ƖԂ낤���Ƃ����C�ɂȂ�܂��B
���̓p�C�I�j�A��S-955���Ԃ��Ă���̂ł����A�Ȃ��Ȃ������o��������܂���B
�������A������ӂ��ƂȂ�ƁA�ł��ǂ�Ȋ�����邩�E�E�E�B
500N��10MT�͐E�ꂩ��ł̍D����_���ĉ^�э��݂܂������A
SX-500�̓X�^���h�t���������̂ŁA�g�[���{�[�C���̑傫���ŁE�E�E�A
���Ȃ肠���ꂽ�������܂����B
�߁X�A�n���~��NA-751�Ƃ����I�[�f�B�I���b�N���������Ǝv���Ă���̂ŁA
�܂��܂��傫�ȕ��͌������ɂȂ��ĎQ��܂����B
�����ԍ��F16305848
![]() 0�_
0�_
Kyushuwalker����
�������ɖ��^�����̂́A��͂�A�z�ł������B��
�@���������A�A�z���Ȃ�Ďv���Ă����܂����B
�@�u���v�D���̕��́A�ň��u�o�X���t�v�ǂ��ł��܂��Ηǂ��ł����A���^�Ɍォ�猊���J����
�@�l�ɏo��������Ƃ͂���܂���B
�@SX�V���[�Y�����낢��Ȍ^�ɔ��W������ł��ˁ[�B
�@�u���˖Ґi�vJBL��m���Ă���Ƃɂ�������SP�ɕ��C�������Ƃ����������ŁI
�@S-955�̓p�C�I�j�A�ɂ��Ắu�S�b�c�C�vSP�ł����ˁB
�@�傫���E�d���̊��ɂ́u�D�������v�������悤�Ȑ̂̋L�����H
�@���̍��̑�^����3WAY�Ȃǂ́A���̎���ł͑���Ȃ������Ȃ��㕨�ł��ˁB
�@DIATONE��TRIO�A�����Ⓦ�ŁA�����܂�SP������Ă�������Ȃ�Ė��ł��ˁH
�@���X�v���o��SP��PIM-16�Ƃ��Q���R�c�Ƃ�Coral8CX-50���̓����E���J�j�J��2WAY�̏��^SP����I
�@����ȃm�X�^���W�b�N�ȑz�����^���m�C��Precision���Փ���������
�@�����Ȃ̂����m��܂���ˁH
�����ԍ��F16305923
![]() 2�_
2�_
>>���Ȃ肠���ꂽ�������܂���
����ς肗
�O�ʖ��C�Ō����ڂ͂����ł���
�X�^���h�t���Ń��r���O�ɂ͒u���Ȃ���ł����H
�c����SX-700���ǂ��Ǝv���܂�
���^�Ƃ̕������͂������܂����H
�����ԍ��F16305924
![]() 1�_
1�_
Kyushuwalker����A�͂��߂܂��āB
SX-500�̑�̓l�W�~�߂���Ă��Ȃ��ł��傤���H�{�l�W4�{�B
�����ԍ��F16306334�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�l�I���W�l
���ɂ��m�X�^���W�[�͂���̂ł��B
���f����JBL��D���ŁA�N���V�b�N��JBL���Ƃ��������Ă��܂����B
�f�����V�����̍D���������̂ŁA���̉��b�ɂ��������āA���݂Ɏ����Ă��܂��B
�܂�A������Ɣ����Ă��������͂����ɒ����Ă����Ƃ����킯�ł��B
�ǂ����Ă��A�X�y�[�X�̊W�Ŗ���Ă���Ȃ������̂��A�傫�ȃX�s�[�J�[�Ȃ̂ŁA
���܂ł��傫�ȃX�s�[�J�[�ɖ���������̂��Ǝv���܂��B
����̏����ȃX�s�[�J�[�͂������Ȃ̂ł����A�ǂ����������肫�܂���B
sasahirayu����
�����̉ł�NS-1000MM��NS-!0MT�͑傫���������Ⴂ�܂����A����ւ��Ă��S���C�Â��Ȃ����x�ł��B
�������A���m�g�[�����D���Ȃ̂ŁA�ؖڒ��̂����ɂ��Â��X�s�[�J�[�͂��Ăт���Ȃ��Ǝv���܂��B
�s�A�m�u���b�N�̃g�[���{�[�C�Ȃ�A����������Ɖł�OK���邩���m��܂��A
����Ȏ荠�ȍ����̕���u������A�L���^���[�̑���ɂ��܂����A�����}�[�L���O���܂��B
���Ȃ݂ɁA���͏c����蔠�`���D���ł��B
������ނ�����
�͂��߂܂��āA�����́B
�����A�˂���4�{���Ă���̂ł����A������O���Ă��������Ă���̂ł��B
�����炭�A�R���N���Œ����Ă���̂��Ǝv���܂��B
�J�b�^�[�i�C�t�͌܌��J��ɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA�����z�[���Z���^�[�ɍs���āA
�j�����s�A�m�����Ă��āA�N���b�ƉĐ�邩�ǂ������Ă݂܂��B
����͂������������Ă���̂ŁA����o���Ȃ����Ƃɂ��܂��B
�����ԍ��F16306469
![]() 1�_
1�_
�����ł������܂������ǃK���e�[�v�̏d�˓\��ŏ[�� ����y�Ȃ�ł����߂ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/20443310995/SortID=15975535/#tab
�����ԍ��F16307804
![]() 3�_
3�_
Dyna-udia�����
>�Ⴆ��A���u�������g���Ɖ���������v�ƌ������Ƃ��Ă��A���������������Ă݂���u�����v�̌��ʂ������肷��
>���Ƃ͂悭����܂��B
�������
>�Ⴆ��AV�m�X�^���W�[���u���A�X�`���[�����g���Ɖ���������v�ƌ������Ƃ��Ă��A���������������Ă݂���
>�u�����v�̌��ʂ������肷��`
���w�E�������ł���ˁBhttp://bbs.kakaku.com/bbs/20443011011/SortID=16286158/#tab
�����ԍ��F16307845
![]() 1�_
1�_
>�@�u���v�D���̕��́A�ň��u�o�X���t�v�ǂ��ł��܂��Ηǂ��ł����A���^�Ɍォ�猊���J����
>�@�l�ɏo��������Ƃ͂���܂���B
http://sakumo.kir.jp/V_kraft/AUDIO-3menteSP6-102_AURATONE_SUPER-SOUND-CUBE.html
http://sakumo.kir.jp/V_kraft/AUDIO-3menteSP6-113_DIATONE_DS-500_DBSpecial.html
http://www.kameson.com/audio/SX-900-2.htm
���ƃw�b�h�z���ł͂���Ȃ��̂�http://www.phileweb.com/review/article/201211/08/644.html
�����ԍ��F16307905
![]() 1�_
1�_
HDMaister_����
����ɂ��́B
�K���e�[�v�͂�����Ɣ��������悤�ȋC�����܂��B
���ʐ^�ɂ�����܂������A�|�[�g���͂̓h���������Ă܂����A�ēh�����Y��ɂƂ͂����Ȃ��悤�ł�����B
�����A����ł͂܂Ƃ��Ȗ��^�X�s�[�J�[���Ȃ��̂Łi�N���v�g���͗ǂ������ł����A���������j�A
����A�V�^�X�s�[�J�[���Ȃ�o�X���t�|�[�g�̍ǂ����́A���낢�뎎���Ă����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�l�I���W��������^�̃o�X���t���ɂ��Ă͂��������Ǝv���܂��B
�����炭�A���F�B�͖��h�Ȃ疧�^�A�o�X���t�h�̓o�X���t�^�Ńu���Ȃ��̂ł��傤�B
�c��̃I�[�f�B�I�t�@���́A�����S�j���̃X�s�[�J�[�Ƃ��ɂ͑����ꏭ�Ȃ���e�����Ă��܂�����B
�́ANS-1000M�Ƃ�S-955�̃o�X���t���͌��\����܂����B
���͂ƌ����A���^���D���ł��A����ς�o�X���t���ǂ������Ǝv������A�ڈڂ肪�������̂ŁE�E�E�B
����ɂ��Ă��ASX-900��500N�ɂ킴�킴�����J����Ȃ�Ă��������Ȃ��E�E�E�B
�u�I�[�f�B�I��̐V���v�Ƃ����z�[���y�[�W�����Љ�����肪�Ƃ��������܂��B
SX-900�́A�܂��܂��~�����Ȃ�܂����B
�����ɍڂ��Ă����E�b�h�R�[���X�s�[�J�[���~�����X�s�[�J�[�̈�ł��B
�����ԍ��F16308115
![]() 1�_
1�_
>����ɂ��Ă��ASX-900��500N�ɂ킴�킴�����J����Ȃ�Ă��������Ȃ�
�������ǂ����Ƃ͂����Ă� �킴�킴���X�s�[�J�[���o�X���t�ɂ���Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B
�������^�T�C�Y�ł͖��^���D���ł��� �Z���^�[�`�����l���ȂǏ��^�ł̓o�X���t���g���܂����A�䂪�Ƃ̎�@
�d�u �s�Q�T�P�{�Ȃ�38cm�E�[�t�@�[�ł���܂����o�X���t�|�[�g�`���[�u�������Ȃ��S�ʃo�b�t���Ɍ�����
�����̃o�X���t�����ɂ��������Ŗ��Ă܂��B
�����ԍ��F16308460
![]() 2�_
2�_
HDMaister_����
PA�p�E�[�n�[�͎v���Ƃ��날���āA�p�X���܂����B
�E�[�n�[�쐬�͏�����ɂ�藈�N�ɂȂ肻���ł��B
�͂炽����P�O�O�O�_����
�܂����Ē����Ă���ł��傤���H
����Ă̑e�߂̃X�|���W�����ĎQ��܂����B
���C�E���^���́u�����g�t�B���^�[10×500×500mm�v1480�~�B
100mm���Ő��āA�Б�250mm�ł�����Ƃ��߂Ɋ����āA
DS-500N�̃o�X���t�|�[�g�ɋl�߂Ă݂܂����B
�ቹ�����܂��āA�����������������ł��BSX-500 ���D�������B
�������A���߂������Ȓ����Ŏ����邩��A���Ȃ肢���A�C�f�A�ł��ˁB
����͒����Ă����܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
sasahirayu����
�t�F���g�����̂��������Ă݂܂��B
DS-500N�͑��������ł��ˁB
SX-500�Ƃǂ������D���ł����H
�l�I���W�l
�uDouble Vision�v�ӂ肪�A�I���W�l�Ƃ̐ړ_�ł��傤���H
�{�[�J�����A�x�[�X��������Ƃ��������ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F16309231
![]() 0�_
0�_
�����Ԉ���Ă܂����B�@�S�ʃo�b�t�� �� �O�ʃo�b�t��
PA�p�E�[�n�[�͂����߂��܂���B���Ƃ��ďo�������̂ł��B
����ƃK���e�[�v���Ɠh�����S�z�Ȃ�A�G�A�R���̃_�N�g�ǂ��G�A�R���z�Ǘp�p�e�Ȃ̓t�F���g��X�|���W����
���Ԗ�����C�̏o������X�g�b�v�ł��A���t���O�����R�Ȃ̂ł������Ƃ������܂��B
http://item.rakuten.co.jp/encho/4971275092037/#10021675
�����ԍ��F16309825
![]() 1�_
1�_
HDMaister_����
�z�Ǘp�p�e�͔S�y�̂悤�ōH�͊ȒP�A�֗��O�b�Y�ł��ˁB
���Ԃ߂�̂Ɏg�������Ƃ�����܂��B
�����A�I�[�f�B�I�ɗ��p����̂́A�C�}�C�`�C���̂�܂���B
�F�l���낢�남���b�ɂȂ�܂����B
�X�|���W���p�́A�X�|���W���킵�̂悤�ȕ����ۂ��鎖����l���Ă��܂����̂ŁA
�����X�|���W�������Ďg���̂̓q�b�g�ł����B
�c���̒������ǂꂭ�炢�ɂ��邩�ŁA���Ȃ�ׂ������߂ł��܂��B
���\�ʔ����ł��B
���ɂ����ꂱ�ꎎ���Ă݂܂��B
�����ԍ��F16311321
![]() 0�_
0�_
�X�|���W�������ȒP�����ł��������ł���
�t�F���g�͕K�v�����Ǝv���܂�
DS-500�͎����������Ƃ������ł���
���ɂ���SX-500�Ɣ�ׂĂǂ����������A��ŏڂ��������ĉ�����
S-07��SX-V1���ؐ��łƂĂ��Y��ȃX�s�[�J�[���Ǝv���܂���
�̂̓��{�X�s�[�J�[�͂������������Ă��Đ����ł���
�C�O�X�s�[�J�[�͍����̂������ǂ��Ă��A�㋉�N���X����Ȃ��ƌ����ڂ͈����ł�
���l�D�݂̃X�s�[�J�[�ō��̃��}�n�̃u�b�N�V�F���t�͂ǂ��ł��傤
����I�t���b�g�ȃX�s�[�J�[��\���Ă��ƂŁA�s�A�m�u���b�N�̎����͑��̃��[�J�[�Ɣ�ׂĐ[�݂�����܂�
������ŗǂ������̍��ł��Ă����ƃ��k�G�b�g���炢�����v�����Ȃ��ł�
���ꂱ�ꔃ���Ɖ��������邩���m��܂���
���ɓK�����E�[�t�@�[��Q�������v�ł�
�o�X���t�̃X�s�[�J�[�̌����ǂ��Ŗ��ɂ���ƁAQ���Ⴂ�̂ōŒቹ������Ȃ������m��܂���
Linkwitz Transform�ȂǓd�C�I�Ȓ���������������ǂ������m��܂���
�ȒP�ȃO���C�R�ɂ���ł��A��̋߂������ɂȂ�܂�
�����ԍ��F16311610
![]() 2�_
2�_
������ƓI�O��ȕԎ���������܂��A���Ƃ��ƃo�X���t�{�b�N�X�ɂ̓o�X���t�Ɍ������j�b�g���g���Ă���Ǝv���܂��B���S���ɂ��ĔȂǂłӂ����ł��܂��ƁA�v���f0�l���ς���Ă��܂��A�\�����ʉ��ɂȂ邱�Ƃ͍l�����܂��ˁB�o�X���t�̉��J�u�������ȏꍇ�́A�^�I�����ۂ߂ē���ɂ��Čy���l�߂Ă��Ƃ����Ǝv���܂��B�o�X���t�|�[�g���O�ʃo�b�t���ɋĂ���ꍇ�A�����^�I���ł͋����߂ł��̂ōD���ȐF�̂��̂��g���Ƃ����ł��傤�B���̌o���ł̓X�J�X�J�ł͂Ȃ���������ƃX�|���Ɣ�������x�̋l�ߕ��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F16313732
![]() 2�_
2�_
�g�^�}��������A�����́B
>�o�X���t�|�[�g���O�ʃo�b�t���ɋĂ���ꍇ�A�����^�I���ł͋����߂ł��̂ōD���ȐF�̂��̂��g���Ƃ����ł��傤�B
�䂪�Ƃ̃X�s�[�J�[�͔w�ʃo�X���t�Ȃ̂ł����c�c�ȑO�g���Ă����A���v�͒ቹ���o�����Ă����̂ŁA�O����͌����Ȃ��w�ʃo�X���t�|�[�g�ɁA�܂����F�̃^�I��(��)���l�߂Ă������Ƃ�����܂��B
>���̌o���ł̓X�J�X�J�ł͂Ȃ���������ƃX�|���Ɣ�������x�̋l�ߕ��������Ǝv���܂��B
�^���ł��B
�����ԍ��F16313781
![]() 3�_
3�_
sasahirayu����
�����͉J�������̂ŁA�ߌォ���500N�̃o�X���t�|�[�g�̒����ɖv�����Ă���܂����B
�y�߂��A���߂Ɋ������������������Ȃ̂ł����A���S�ɍǂ��Ƃ�����ƃ_���݂����ł��B
���i�K�ł�500N�̃o�X���t�|�[�g���X�|���W�ōǂ�������SX-500��肢���Ǝv���܂��B
�����痼���Ƃ��F�X���Ă݂܂����ǁE�E�E�A��Ȃ��Ȃ����肵�āE�E�E�B
S-07��SX-V1�A�����Ƃ��}�z�K�j�[�̖��C�ނŏ��������[����Ȃ��ł��ˁB
���莝���̃X�s�[�J�[�����܂������ł�����A�I�[�N�V�����ŗ��Ƃ��Ă݂����C�����܂��B
YAMAHA�̃u�b�N�V�F���t�̒��ł�NS-BP400��750���f�U�C���I�ɍD���ł��B
YAMAHA�̃s�A�m�u���b�N�t�B�j�b�V����CM-5��800�V���[�Y��肸���Ƃ����ł��ˁB
�ʐ^�ł́i�c�ɂł͂Ƃ��Ă������͔q�߂܂���j�A�_����EPICON�̍��͂��������ł����B
�����ANS-10MT�Ɠ����悤�ȃT�C�Y�ł����A10-MT�Ɏ�����Ďg�����Ǝv���܂��B
Linkwitz Transform�͐��N��ɓ������čs������g���C���܂��B
���̂Ƃ���d�C��H�͕��i�̏ꏊ���m�F�ł�����x�ŁA�v�Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ����E�ł��B
�Ƃ肠�����A�{��5���قǒ������܂����B
�\��Ƃ��ẮASX-WD5KT��g�ݗ��Ă����āi�h���Ƃ��̗��K���ł��邵�j�A
500N��SX-500��!0-MT��&�������āA�e��G���N���[�W���[�L�b�g�ł��낢�����Ă݂��̂��A
�E�[�n�[������Ă݂āA���܂���������ANS-1000M�̕�C�������ł��Ă݂悤�Ƃ����v��ł��B
����L�b�g�͒T���A�X�s�[�J�[���^��ǃA���v���F�X����܂����A���������y���������m��܂���B
���N�g���炩�A�o�C�N��Ԃ���I�[�f�B�I�ɃV�t�g���������Ă܂��B
�܂��A����������邩�A�O����܂ł͐F�X���Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F16313912
![]() 0�_
0�_
Dyna-udia ����
���O����͌����Ȃ��w�ʃo�X���t�|�[�g�ɁA�܂����F�̃^�I��(��)���l�߂Ă������Ƃ�����܂��B
���w�ʃo�b�t���������Ƃ���Ƃ܂����F�͉f���܂��˂��B�����Ȃ����̂������ł����H�i�j
�����ԍ��F16314014
![]() 2�_
2�_
�g�^�}��������
�����A���܂��܂��̃^�I�������Ȃ����������ł�(��)
�����ԍ��F16314048
![]() 2�_
2�_
�g�^�}��������
�I�O��ǂ��납�A�I���˂Ă���Ǝv���܂��B
DS-500��500N�ɂȂ�Ƃ��A�T�C�Y���ς���Ă��܂�����A�A
���[�J�[�͂���Ȃ�̍H�v�������̂��Ǝv���܂��B
���������悤�ɁA�X�|���W�̏�ɃK���e�[�v�Ȃǂ�\�薧�x������������A
�t�ɃX�|���W�݂̂̕����ǂ��悤�Ɋ����܂����B
�����́A����X�|���W�̗ʂ߂��ėV��ł��܂����B
�^�I���Ȃǂ������Ă݂悤�Ǝv���܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
Dyna-udia����
���������b�ɂȂ�܂��B
60�˂ɂȂ�܂łɁA�l���Ō�̃X�s�[�J�[�I�т��������Ǝv���Ă��܂��B
���܂ŁA�o�X���t�͔����Ēʂ��Ă��܂������A�����̃X�s�[�J�[������ӂ݂�ɁA
�o�X���t�͔�����A���Â����Ȃ����Ƃ��A�������܂����B
�����X�s�[�J�[�ł��ꂱ��������āA���̂����Ō�̑I�������悤�Ǝv���܂��B
YAMAHA NS-1000M�̃t�����X�g�A�ɂȂ邩�A����ɂȂ邩���m��܂��B
����܂ŁA�F�X������Ȃ�����X���b�h�𗧂Ă�Ǝv���܂����A
��낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F16314058
![]() 0�_
0�_
Dyna-udia ����
�����悤�Ȑl�������Ă܂��Ȃ��B�i�j
�����ԍ��F16314116
![]() 0�_
0�_
���g�^�}��������A�����́B
>�����悤�Ȑl�������Ă܂��Ȃ��B�i�j
���������ʂ�̂悤�ł�(��)
��Kyushuwalker����A�����́B
>���܂ŁA�o�X���t�͔����Ēʂ��Ă��܂������A
>�����̃X�s�[�J�[������ӂ݂�ɁA�o�X���t�͔�����A���Â����Ȃ����Ƃ��A�������܂����B
�͂��B���������ʂ�A����ɋ߂��ł��ˁB
���ł�����AATC�Ƃ����I���͂���܂����B
http://www.electori.co.jp/atc.html
(���͈ȑO���炸���ƁA���ɂ��A����肪�o�����ȏ�Ԃł�(^^;)
�����ԍ��F16314267
![]() 1�_
1�_
Dyna-udia����
����SCM�V���[�Y�̓l�b�g�Ō������A�������������ł��ˁB
�肪�o�Ȃ����Ȃ����l�i���A�w���ӗ~��������܂��ˁB
�����ǁA15�C���`�̃T�u�E�[�n�[��100���~�����Ă邵�E�E�E�B
���^�ɂ͂����g�ݍ��킹����Ă��ƂȂ̂��E�E�E
����ς�15�C���`�T�u�E�[�n�[�͎��삵���Ȃ������B
ATC�Ƃ������[�J�[�͊o���Ă����܂��A���肪�Ƃ��������܂����B
�N���Ƃ�ƁA�����悩��_���ɂȂ��Ă����܂��̂ŁA
�_���ɂȂ��đʎ��ɂȂ�O�ɁA�����X�s�[�J�[����ɓ��ꂽ�����̂ł��B
�����ԍ��F16314447
![]() 1�_
1�_
Kyushuwalker����
�o�X���t�̉��������ĕ�������Ƃ����̂́A�R�[�����̗�������o�ăX�s�[�J�[�{�b�N�X�̒��Ŕ��˂��������������炻��������Ȃ��Ƃ������ƂȂƎv���܂��B������Ɨ��\�Ȍ������ŁA���[�J�[�̕����ǂނƃ��J�b�Ɨ���Ǝv���܂����ǁA�낭�Ȕ�������ĂȂ����炻���������ƂɂȂ�̂�������܂���B�ق�Ƃɐ^�ʖڂɍ��ꂽ�o�X���t�{�b�N�X���畷�����Ă��鉹�͂̂т₩�Ŕ��������^�̉������̂��Ǝv���܂��B
�o�C�I�����Ȃǂ̊y������̊J�����o�X���t�Ɠ����ł����A���݂̂悤�ȉ������o�Ȃ����̂�����ΐ_�l�̂悤�ȉ����o���̂�����܂��ˁB�ǂ�����U�����̔������͌��ł��B�o�C�I�����̌��ɓ�����̂��X�s�[�J�[���j�b�g�ƍl����A���i�X�s�[�J�[���j�b�g�j�͐��m�ȉ������y���������ċ�������ׂ��A�o�C�I�����{�́i�X�s�[�J�[�{�b�N�X�j�͍ō��̋����������Č��̉���������ׂ��Ƃ������Ƃł��傤�B
�������A���͒��ډ��Ƃ��Ă͂قƂ�Ǖ������Ă��܂���̂ŁA�o�C�I�����̉��͖{�̂��������������قƂ�ǑS�ĂƂ������܂��B�X�s�[�J�[�̏ꍇ�͑O�ʂ���o�Ă��鉹�̂ق����f�R�����̂ŁA���[�J�[�����[�U�[�������������Ƃ��낪�����Ȃ�ɂȂ��Ă䂭�̂�������܂���B
�����ԍ��F16315252
![]() 1�_
1�_
ATC�̓G���N���[�W���[�e�ʂ��R�������o�X���t�Œ��x�ǂ����x�̗e�ʂł������C�̈��k���L�ђ�R������Ƌ����͂��ł��B
���������͂Ȏ��͉�H�ŋ����I�ɃX�g���[�N����������ł��� ���̃T�u�E�[�t�@�[�I�Ȃ����ł͖{���̖��^�̂���
�Ƃ��낪�o�Ă��܂���B
���^�̏ꍇ�ł������G���N���[�W���[�e�ʂ̂�����̂ł����ATC�̂悤�ȐU���Ō��a�ɋ߂��}�O�l�b�g���a�������Ȃ�
��ʓI�ȃX�s�[�J�[���j�b�g�ł�ATC���͂����`�ƋC�����̂������������܂��B
ATC�͉����Ō����Ζ��^�̊���ň��킸�@����ȃ^�C�v�ƌ������������ł��傤�B
���^�̗ǂ��𖡂킢�������Celestion Ditton 22�@��@KEF 140���@�G���N���[�W���[�e�ʂ̂�����̂ł��Ɩ��^�{����
�ǂ������Ƃ��ł���͂��ł��B
�����ԍ��F16315462
![]() 1�_
1�_
�g�^�}��������
>�^�ʖڂɍ��ꂽ�o�X���t�{�b�N�X���畷�����Ă��鉹�͂̂т₩�Ŕ��������^�̉������̂��Ǝv���܂��B
���̎��Ɋւ��Ă͖��^�Ɋւ��Ă�
�ˏ[���ȗe�ʂ������č��ꂽ���{�b�N�X���畷�����Ă��鉹�͂̂т₩�Ŕ������o�X���t�̉������̂��Ǝv���܂��B
�Ƃ������܂��B
�o�X���t�̂����s���Ă����ꌾ�Ō����Ɖ����̑f���炵�����^�X�s�[�J�[����낤�Ƃ���o�X���t�^�C�v��10�{���x��
�L���r�e�ʂ��K�v�Ł@�E�[�t�@�[���a16cm���x�̂��̂ł��o�X���t�ł�38cm�^�C�v�Ɠ������炢�̑傫���ɂȂ��Ă��܂�����ł��B
�������̎��ɋC���t�����o�܂̓Z�_���^�C�v�̏�p�Ԃ̃����X�s�[�J�[���₯�ɍ������� ���̗��R���l�����Ƃ���E�E
�G���N���[�W���ƂȂ镔�����g�����N���[���� �z�[���I�[�f�B�I�̃X�s�[�J�[�ł͂܂����蓾�Ȃ��傫��������������
�ƂȂ�@���ꂪ�[�X�Ƃ��� �X���t�ł͏o���Ȃ��ɂ݂̂Ȃ��S�n�ǂ�����t�ł��邽�̂��Ɨ������܂����B
�����x�����o�X���t�^�C�v�Ȃ疧�^�̉������̂��Ǝv���Ă�F�l�͎���Ȃ��� �{���ɑf���炵�����^�X�s�[�J�[��
�܂������ꂽ�����Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
ATC���x�̃T�C�Y���������̂Ȃ�܂��o�X���t�̂������͗D��Ă��邩��ł��B
�����ԍ��F16315571
![]() 3�_
3�_
�g�^�}��������A����ɂ��́B
>�o�C�I�����Ȃǂ̊y������̊J�����o�X���t�Ɠ����ł����A
>
>�ق�Ƃɐ^�ʖڂɍ��ꂽ�o�X���t�{�b�N�X���畷�����Ă��鉹��
>�̂т₩�Ŕ��������^�̉������̂��Ǝv���܂��B
�g�^�}�������������ɂȂ������ƂɈ������Č����A�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�̌��̊J������̖{�̂̓o�X���t�ɑ������܂��B����A�M�^�[�̌��̓��j�b�g�ɂȂ�܂��B�o�X���t��薧�̕����u�����������v�Ƃ����_�@�ōs���A�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�̖{�̂́u�Ȃ����������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂�(��)�B����ł͈��̌�����`�ł��ˁB
�����H�@�o�X���t���H�@�̂悤�Ȍ^���ɋɒ[�ɂ�����锭�z�́A�u���ۂ̉��v�����Ɂu�^���ł��̂��l����v�`����`�ł��B�����ĐX�����Ȃ����z�ł��ˁB�u���ۂ̉��v�����A�u�v���l�ł��̂��l����v�̂Ƒ哯���قł��B(�X���傳��̂��Ƃł͂���܂���̂ŔO�̂���)
�����ԍ��F16315581
![]() 2�_
2�_
Dyna-udia����
�y��ƃX�s�[�J�[�̉��̏o�����ꏏ�ɂ���Ă��c
�y��̋����̓}�C�N�ŏE�����i�K�ŁA���������Ă��܂�
�\���Ȓቹ���o�Ă���Ȃ�A�o�X���t�ŋ���t�������K�v�͖����ł�
HDMaister����
���^�͔������������Ă��ቹ�͂��܂葝���܂���
40Hz��40���b�g����200���b�g�����ׂ�ƂقƂ�Ǖς�炸
40���b�g���̕����t���b�g�ł�
��C�̈��k�ɂ��c�݂́A�����ɒ[�ɏ��������Ȃ���Ζ�薳���ł�
ATC��������Ȃ������牽�ɂȂ��ł��傤��
1���K�E�X����ƒቹ���o�Ȃ��Ȃ�̂ŁA��ʓI�Ȏ��͂��Ǝv���܂�
�����ԍ��F16315868
![]() 3�_
3�_
HDMaister����
���o�X���t�̂����s���Ă����ꌾ�Ō����Ɖ����̑f���炵�����^�X�s�[�J�[����낤�Ƃ���o�X���t�^�C�v��10�{���x��
�L���r�e�ʂ��K�v�Ł@�E�[�t�@�[���a16cm���x�̂��̂ł��o�X���t�ł�38cm�^�C�v�Ɠ������炢�̑傫���ɂȂ��Ă��܂�����ł��B
�E�i�C�X�������݂ł��B�������^=�ߋ��̈╨�I�Ȉ��ՂȎv�����݂�����܂����B
�o�X���t���������ꂼ��̌�����������킯�ł����A����̃I�[�f�B�I����ɂ́A�o�X���t�̂ق�����葽��������Ă���Ƃ������ɍl�����ق����ǂ��ł��傤�ˁB
�ł������\���܂��āA500���b�g���Ƃ������܂Ƃ��Ȕ���������蓮�������肷��̂͋C�̉����Ȃ�悤�ȍ�Ƃł�����ˁB
���ƁA�Ԃ̃g�����N���[���Ɏ��t�����ꍇ���S�Ȗ�����ۂ��Ȃ�����̓o�X���t�ɋ߂�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F16315887
![]() 4�_
4�_
HDMaister���� �ǐL�ł��B
�ŏ��Ɏ����ꂽ�o�X���t�Ɩ��̑ш�ʗʊ��̐}�ł����A���Ɋւ��Ē����܂Ńt���b�g�ɏo��X�s�[�J�[���j�b�g�͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��Ⴀ�Ȃ��ł��傤���ˁB�R�[�����̒��a1���[�g���A�{�b�N�X�̑傫��5000���b�g���A�d��3�g���Ƃ��A�A�A�i�j�������݂����Ƃ��Ă��g�����������Œ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤�B
�o�X���t�̐}�Ɋւ��Ă͒���悪�����Ē�悪�����Ƃ������ւ��킩��ɂ����ł��ˁB
���������}�ł͂Ȃ��Ď��g���ш�̃O���t��œ������j�b�g���g�����ꍇ�̖��ƃo�X���t�̈Ⴂ���������ق����������肷��Ǝv���܂��B�X�s�[�J�[���j�b�g���Ǝ��g�������Ɛ����o�X���t�{�b�N�X�ł̑ш悪������Ă��܂��̂ł���Ŏ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F16315930
![]() 3�_
3�_
�g�^�}��������
�T�u�E�[�t�@�[�͖��̂��̂������ł���
�A�N�e�B�u�̓d�C�I����݂Őv���ėe�ՂɎ��g�������W��L����̂�
B&W KEF FOSTEX Victor Velodyne Paradigm SVS
�Ȃǂ�����Ă���̂�m���Ă��܂�
�����ԍ��F16315953
![]() 2�_
2�_
sasahirayu����
�����^�͔������������Ă��ቹ�͂��܂葝���܂���
40Hz��40���b�g����200���b�g�����ׂ�ƂقƂ�Ǖς�炸
40���b�g���̕����t���b�g�ł�
�E���^�̒��ʼn������オ��̂͒����ł��B�n�k�̂悤�ȗh��̂悤�ȉ��ł��B�������̃O���t�Ō����ƂQ�OHz�t�߂ł��ˁB���炩��200���b�g���̂ق��������������ł��B
�@�o�X���t�ő��������̂͂�����ቹ���̂���ш�50Hz�`100Hz�̉��ł��B������20Hz�t�߂̉��͑�^�̖��^�ɔ�ׂ�Əo�ɂ����Ȃ�܂��B
�����ԍ��F16315964
![]() 4�_
4�_
�b�ɂȂ��Ȃ������Ă����܂��E�E�E�A
���̎Ԃ̃E�[�n�[�������g�����N�̂��Ȃ�̕�������苒���Ă��܂��B
����͖��^���ȁH�@�ቹ�Ɍ����Č����A�܂��܂��̉��ł��B
���������A������NS-1000M��sasahirayu����ɋ����Ă�����āA�ቹ�u�[�X�g��������A
25Hz���炢�̉��Ō��̖{�I���K�^�K�^�h��܂�����B
���`��A������Ƙb������Ă邩�ȁH�@���炵�܂����B
�����ԍ��F16315997
![]() 0�_
0�_
�g�^�}��������
30Hz�Ŕ�ׂ��1dB���傢�ŁA�����牽�����Ċ������܂���
40Hz����100Hz�ɂ�����40���b�g���̕����t���b�g�ł�
�������j�b�g���Ɣ���傫������o�X���t�̕����ቹ�͏o�܂���
���ɕ�������Ď��g�����t���b�g�ɂ���o�X���t���
�ߓn�����̗ǂ������ɂȂ�Ɗ����܂���
�����ԍ��F16316027
![]() 3�_
3�_
sasahirayu����
���^�͂����܂ōŒ��20Hz���ǂꂾ���o�邩���J�M�ł��B������̒ቹ���͌����Ă����̎��݊������߂�l��20Hz����Ȃ̂ł��B�܂��A�u�[�X�g�����ቹ��SN�䂪�����Ȃ�܂��B�Ȃ��Ȃ�A�Œቹ��������グ�����ɒቹ����J�b�g���Ė�����蕽��ɂ��Ă��܂�����ł��B�ɒ[�Șb�A���̉�����90db�̃E�[�n�[�ł����ۂɖ��Ă���Ƃ���70db����Ă���̂�����ł��B���̕�SN�������Ȃ�Ƃ������Ƃł��B������̉𑜗͂��O�[���Ɨ����܂��B�ł��A�����������Ɋ����Ƃ����������̂ق����{���̒�悾�Ǝv������ł��܂����Ƃ��|���ł��ˁB
����^�̖��^�͍��̂͑�ρB�l�i����ρB�ړ�����ςł����A���R�Ȓ������Đ����邱�ƂƁA�ɂȂƂ��̓{�b�N�X�̒��ɓ������ґz�ɂӂ����̂������ł��B
�X�s�[�J�[���j�b�g�ƃX�s�[�J�[�{�b�N�X�̍��͉����������݊��ł�����̂ł͂Ȃ��A���j�b�g�ɉ��������e�ς�o�X���t�|�[�g�̃T�C�Y��������܂��B�V�r�A�[�Ɍ���{�b�N�X�̍ގ��܂Ń��j�b�g�ɍ��킹�邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B���ꂼ��̓���������̂ł�����{�b�N�X�̌`����l�i�A�]�_�Ƃ̕]����A���̑傫���ȂǂŔ��f����̂ł͂Ȃ����낢��ƌo�����Ȃ��炻�ꂼ��̎g�������l���Ă������Ƃ��K�p���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F16316140
![]() 3�_
3�_
Kyushuwalker����
HDMaister����̏������݂̒��ɂ������̂́A�g�����N���[������C������Ƃ������������Ǝv���܂��BKyushuwalker����̃X�s�[�J�[�͗e��̒��ɓ����Ă���悤�ł��̂Ńo�X���t�������킩��܂���BBOSE�̃X�s�[�J�[�͓Ɠ��̉�������������������܂������A��{�I�ɂ̓o�X���t�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F16316193
![]() 1�_
1�_
�l�X�ȃX�s�[�J�[������l�X�ȕlj�������܂��B�e���m�X�Ȓቹ��B
�ǂ�ȃ\�[�X�łǂ�ȉ����o�邩�H�o�邩����Ȃ��������邩�H
�\�[�X�ɒ����ɍČ�����Ă������Ă鉹�͂قڕǒቹ������ˁB(��)
���̗ǂ��[���ቹ��͂Ȃ�
�ƂȂ����ꍇ�A�l�X�ȓ���������悤�ɂ��v���ˁB
�����ċC�����ǂ��͂���ς�l�̎��ł������f�͕t���Ȃ��B
���낵���܂ł̃e�B���p�j�[�̍Č���I���K���̒��ቹ�悪�o�ĂĂ�������Ƃ̌q����͂ǂ����I
�S�Ă̓o�����X�ł��B
�Ƃ̏ꍇ 30�w���c�ȉ��������グ�鉽�̂������悪���Ă��L�щ߂��邭�炢�L�т�B
��������[����Ȃ����炢�L�т�B
�o��Ⴂ���Ă���Ȃ��ˁB
�����ԍ��F16316802
![]() 0�_
0�_
�g�^�}��������@�����J�ȃR�����g���肪�Ƃ��������܂��B
>�Ԃ̃g�����N���[���Ɏ��t�����ꍇ���S�Ȗ�����ۂ��Ȃ�����̓o�X���t�ɋ߂�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ǝv���܂��`
�m���ɂ����ł��ˁB���� �����͓˂����܂�邱�Ƃ�\�z���Ă܂����B�����Ɍ����Ί��S�Ȗ����Ƃ͌����Ȃ��̂ł���
���Ȃ��Ƃ��o�X���t�|�[�g�͖����A�ȒP�ɂ͋�C�̈ړ����ł��Ȃ��̂Ńo�X���t���͖��ɋ߂��Ǝv����ɏo���܂����B
����ƌ�����Ă���l�����܂����A���^�̔��e�ʂ𑝂₷�̂͒ቹ�𑝂₷�̂��ړI�ƌ�����艹���̌���ł��B
�܂�N���}�̃G���W���Ō����|���s���O���X�����炵�ĐU���̋�C�o�l�̑�������������� ��莩�R�ɃX�g���[�N
������ׂɑ傫�������g���̂ł��B
�܂�40���b�g����200���b�g���Œቹ�̗ʂ݂̂��ׂĂقƂ�Ǖς��Ȃ��Ƃ��@�Ⴆ��̒��ˊ����40cc�̋�C��
����Ĉ�������̂Ƃ�200cc�̋�C�����Ĉ�������̂ł͂ǂ�������R�Ȃ��������������邩�Ƃ����n�i�V�ł��B
�G�A�[�T�X�y���V�������N���}��V�����Ɏg���Ă�悤�ɋ�C�̒�R�͑z���ȏ�ɑ傫�����̂ł��B
�X�s�[�J�[�ɂ́@�@�X�s�[�J�[�G�b�W�@�A�R���Q�[�V�����_���p�[�@�����ċ�C�_���p�[�ƂR���̒�R���@�܂��
�僊�[�O�v���M�u�X�𒅂�������Y�n�����Ƃ��}����ꂽ�̂����Ă�����̂ŁA�o�X���t�|�[�g���爳�͂�������
�f���o������C���݂Ă������Ȓ�R������̂����邩�Ǝv���܂��B
�R��ɐU���ł̒�R�y���ɂ̓o�X���t������e�ʃ{�b�N�X�̖��Ȃ̂ł��B
�����ԍ��F16317040
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����
�����̗ǂ��[���ቹ��͂Ȃ�
�ƂȂ����ꍇ�A�l�X�ȓ���������悤�ɂ��v���ˁB
�����ċC�����ǂ��͂���ς�l�̎��ł������f�͕t���Ȃ��B
���낵���܂ł̃e�B���p�j�[�̍Č���I���K���̒��ቹ�悪�o�ĂĂ�������Ƃ̌q����͂ǂ����I
�E���ǍŌ�͂��̖��ɓ˂��������ł���ˁB���̖�肪�����ł���I�[�f�B�I�E�Ɋv�����N����ƌ����܂��ˁB
�����ԍ��F16317188
![]() 0�_
0�_
HDMaister����
��������邱�Ƃ������Ƃ��ł��ˁB
�������A��C�˂̎������ł͂Ȃ��A�U���̎��ʁi�d���j�⎥�����x�A�������A�G�b�W�̓����₷���A�U���̍ގ��ȂǁA�X�s�[�J�[���쓮�����ł̗v�f�͑���ɂ킽��܂��B�܂��A���^�̋�C�˂ɂ��ă{�b�N�X�̗e�ʂɊW����͎̂�ɒ��ł��ˁB�X�s�[�J�[���j�b�g�̍Œዤ�U���g���̕t�߂ŋN�����C�˂̒�R���ɗ͌��炷���߂ɑ傫�ȋ�C��������Ƃ������Ƃł�����A���e�ʂ̋�C���ɂ����C�����k����Ĕ������ăX�s�[�J�[���j�b�g�̐U���ɗ^����e���́A���ׂĂ̎��g���ɉe�����y�ڂ��Ă���Ƃ����悤�ȃj���A���X�̂Ƃ炦���͌���ނ�������܂���ˁB
�����ԍ��F16317231
![]() 0�_
0�_
�����b���ɂ��Ă����܂��A�b��������łɂ��������B
�Ⴆ�AGlenn Gould �� Goldberg Variations�B
1954�N�ł�NS-1000M�ł͒����܂��ADS-500N���Ɗӏ܂Ɋ����܂��B
1981�N�ł�NS-1000M�̕����������ȂƎv���܂��B
1990�N�ł́A1955�N�^���ł����ANS-1000M�ł͂܂��������ł��B
���F�����Đ��͖����Ǝv���Ă���̂ŁA�����Ɋy�������������邩���Ǝv���܂��B
�̘̂^����X�^�W�I�^���łȂ������Ƃ��ɂ́ADS-500N�������悤�ȁE�E�E�B
�R���T�[�g�z�[���̘^���͂�����Ɣ����ł��B
���\�X�s�[�J�[�͂��Ԃ�Ȃ��̂��ȁH�Ǝv���n�߂܂����B
�ŋ߂̒�\���̏��^�o�X���t�X�s�[�J�[�����ɓ���Ď����Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�ŏI�I�ɗ���������́A�o�X���t�̏��^�u�b�N�V�F���t�ƃT�u�E�[�n�[�Ȃ̂��ȁH�H�H
�����ԍ��F16317773
![]() 1�_
1�_
Kyushuwalker����
�X������ق��Ƃ��āA�X���̎��Ƃ͒��ڊW�Ȃ����Ƃ�����������������Ő\����܂���B
Kyushuwalker����́u60�˂ɂȂ�܂łɁA�l���Ō�̃X�s�[�J�[�I�т��������Ǝv���Ă��܂��B�v
�Ƃ���������Ă��܂����A�����̕��䂩���э~���S���ł��傤���H
�������C�Ȃ����Ƀ��C���̃V�X�e�����Ȃ��̂ɂ��Ă��������Ǝv���A���낢��ƈ������������Ă����̂ł����A�Ђ��Ȃ��Ƃ���Ƃ�Ƃq�ɗ��z�̃V�X�e�����g�݂�����܂����B����A�Â����t�E�E�E�Ⴆ�u�M����҂����~����v�Ƃ��A�u�O����ΉԊJ���v�Ƃ��A�u�@����A����ΊJ�����v�Ƃ��A�V���v���ŏ����ȋC�����������ĉ��y�����y���݂��������B�����͂������������܂ŏo�Ă��邩������܂����B
�����ԍ��F16318247
![]() 0�_
0�_
�g�^�}��������
�X���̎��Ȃ�āA�X�|���W�ʼn������Ă܂��̂ŁA�C�ɂȂ��炸�ɏ�������ʼn������B
�F�l�̂��b���y�����q�����Ă���܂����B
���������Ă����āA�X����Ȃ̂ŎQ�����Ȃ��Ƃ܂������ȂƎv���������݂������̂ł����A
���b�̓��e���A�������炢����������Ȃ��ŁA�����̕�����Ȃ����Ƃ������܂����B
�����̕��䂩���э~���̂��H�ƌ�����A�ǂ��Ȃ�ł��傤�H
���g���Ă���NS-1000M�������Ⴄ���̂ɕς��悤�Ǝv�����̂ł����A
�A���R����������A�������肷�邤���ɁA���������X�s�[�J�[�Ɏv���Ă��܂����B
�l���Ō�̃X�s�[�J�[�I�тƌ����Α傰���ł����A�����X�s�[�J�[�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��̂ł��B
�Ƃ肠�����A�X�s�[�J�[�̂��Ƃ��A���R�����Ă݂āA����������Ă݂Ă���A
�����ǂ������ȃX�s�[�J�[�������I��ł������肳���悤�Ǝv���Ă��܂��B
���������悤�ɁA�V���v���ŏ����ȋC��������ł��ˁB
�����ԍ��F16318413
![]() 0�_
0�_
�K���e�ł��X�|���W�ł���t���Ă����ł��g���čǂ��Ηǂ������̘b�� ���ƈႤ�b�������X�ƃG���h���X�ŃX�p�C��������̂͂ǂ����Ǝv��
�����̂�肽���悤�ɂ���Ηǂ��b������Ȃ��ł����H��l�ɂȂ�܂��傤��
�����ԍ��F16319782
![]() 0�_
0�_
�r���Ƃ������ɐ����ꂽ�C���ł��ˁB
�F�l�A����ɂďI���Ƃ��܂��傤�B
�����ԍ��F16319879
![]() 1�_
1�_
����v���܂��B
�����A�@�����܂�����A���N���t�g�ƌ������[�J�[�̃X�s�[�J�[�̌䎎�������E�߂��܂��B
SX-500�͖����ɑ�ƕʂ��ꂽ�̂ł��傤���H
�I����ɂ��ז����܂����B
�����ԍ��F16324173�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������ނ�����
���������f�U�C���͂��������������悭�čD���ł��B
�����c�ɂ��̂Ȃ̂ŁA���̃X�s�[�J�[�̎����͂�����Ɠ�������m��܂���B
�����Ƃ����ȂƂ���ɒu���Ă�������̂ɂƎv���܂��B
���������Ƃ��ɂ́A�����Ă݂܂����A�Փ���������Ƃ��Ԃ�{��ꂻ���ł��B
SX-500�́A�ʐ^�̂悤�Ȕ��������X�N���[�p�[���g���āA�藣�����Ƃ��ł��܂����B
�����ԍ��F16336749
![]() 0�_
0�_
����v���܂��B
���ꂢ�ɗ���Ă悩�����ł��ˁB
���̌�̃h���`�F�U��G�e���m���ǂ��ł��ˁA�h���`�F5�ʂŔ����ւ��悤���Ɠ����͍l���Ă����C�����܂��B
�A���N���t�g�ł������炭�A�����\�ȓX�܂͂��Ȃ�����Ă���Ǝv���܂��B
����傫�ȃX�s�[�J�[���傫�ȃX�P�[���Œ��̃L�����͖��^�ȏォ���A�Ǝv���܂��B
15�C���`�E�[�t�@�[�̂��敗�ɕ�܂��l�Ȓ��ł͂Ȃ��̂ł������̃X�s�[�J�[�ł͓����Ȃ����̗l�ȋC�����܂��B(�l�I�Ȋ��z�ł�)
�����|�ꂽ��A�Ə����S�z�ɂȂ�ӊO�Əd���X�s�[�J�[�ł��B
�E�b�h�R�[���ł����A���^�̃t�������W���g���Ă��܂��B
���ɂƂ��Ă̗ǂ����̂͂����ē�����O�A�Ȃ��Ȃ�Ύ₵�����̂Ɗ����܂��B
����ȋ@��ł��A2�E�F�C��g�[���{�[�C�̕��͂킩��܂��B
���X�y���܂�Ă��������A����v���܂����B
�����ԍ��F16342982�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�l�̓��}�nNS10T�g���Ă܂��A���[�N�}���Ŕ�����
�����̌R����ْf���Ċɂ��ۂ߂Đς߂Ă܂��B
�F�X��������ʂ��ǂ蒅���܂����B
�����ԍ��F23225915�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�y���݂̃V�X�e���z
�Đ��@��A���ݎg�p���Ă���V�X�e��
���A�i���O�A���v Lepy LP-V3S
YAMAHA BP200
�������� �j�A�t�B�[���h�ł���
��������T�u�E�[�t�@�[�lj����A���v�����ւ������̂ł���
https://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2017/07/Fostex_PM-SUB8_Manual_JP.pdf
�̃}�j���A�����������@��Ƃ̐ڑ��̕��@��
SMSL SU-8�iDAC�j - SUB8�i�T�u�E�[�t�@�[�j-AL-502H�i�p���[�A���v�j - BP200�i�X�s�[�J�[�j�̌q�����Ŗ��Ȃ��ł��傤���H����ƑS�ăP�[�u����RCA�ɂȂ�̂ł��傤���H�K�v�ȃP�[�u���ɂ��Ă��A�h�o�C�X�Ⴆ��Ɗ������ł�
�\�Z��8���~���ƌ�5000�~�̏������Ɛe�̋��ł����T�u�E�[�t�@�[�ݒu�̋��͏o�܂���
�����ԍ��F23178249�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23165724/
�O�X���ł��B��������g�p������@�������ł����V�X�e���Ƃ��Ă͂��̏ꍇ�ǂ̗l�ȍ\���łǂ̗l�ȏ��ԂƃP�[�u���Ōq���Ηǂ��ł��傤���H��芸�����h�R����Amazon7���܂�20%�|�C���g�Ҍ����n�܂����珇�ԂɌo�ϓI�ɖ����̂Ȃ��͈͂ōw�����悤�Ǝv���܂�
�����ԍ��F23178274�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���˃��J �a�l���� ����ɂ��́A
�O��X���ŃT�u�E�[�t�@��Sub mini������܂����̂ŁA�������ɐ������܂��B
�ڑ��̓A���v����T�u�E�[�t�@���݂��g���̃X�s�[�J�[�P�[�u���Őڑ����܂��B
���ɃT�u�E�[�t�@�̃X���[�[�q����BP�Q�O�O��LR���킹�Đڑ����܂��A���̃P�[�u����mini�֕������Ă��܂��B
�A���v����BP�Q�O�O�ɂ̓T�u�E�[�t�@�o�R�Őڑ�����킯�ł��A����ɂ���č��E�ǂ���̒ቹ���T�u�E�[�t�@����o�܂��B
�K�v�Ȃ��̂͑��ɂ���܂���B
�����ԍ��F23178407
![]() 3�_
3�_
�˃��J �a�l����A����ɂ��́B
�Ƃ肠�����ł����A����������̃f�^�����͖������Ă��������B
�m���A���O�̃X���ŁA����������ɂ͎����Ɋւ��Ȃ��łق����Ɨv�]���Ă܂�����ˁB
�܂��A�X���̓��e�Ƃ����i�̎d�l�Ƃ��ׂ��ɏ����l�Ȃ̂ŁA�n���l��ς������Ƃ��C�����Ă��Ȃ��ł��傤�B
����������A����ɂ��́B
���ς�炸�̃f�^�����O���ŁE�E�E
>�O��X���ŃT�u�E�[�t�@��Sub mini������܂����̂ŁA�������ɐ������܂��B
>�ڑ��̓A���v����T�u�E�[�t�@���݂��g���̃X�s�[�J�[�P�[�u���Őڑ����܂��B
>���ɃT�u�E�[�t�@�̃X���[�[�q����BP�Q�O�O��LR���킹�Đڑ����܂��A���̃P�[�u����mini�֕������Ă��܂��B
Fostex PM-SUBmini2�ɂ́A�A���v�̃X�s�[�J�[�o�͂���ڑ�����[�q�͂Ȃ��ł��B
https://www.fostex.jp/products/pm-submini2/
���C�����͂����o���܂���B
������X�s�[�J�[�P�[�u���ł͂Ȃ��܂���B
�ǂ����A����ȃf�^�����R�Ə�������̂��ƁA�����Ȃ���Ɉ��R�Ƃ������ł��B
�����ԍ��F23178433
![]()
![]() 20�_
20�_
���˃��J �a�l����A����ɂ���B
�ߋ��̃X������o�߂͂�����x�͔q�����Ă���܂����B
�I�[�f�B�I�̂��Ƃ��w�тȂ���������O�ɐi��ł���p����܂����v���ƂƂ��ɁA�I�[�f�B�I���Ă����Ȃ��Ɖ��߂Ďv������ł��B
�ŏI�I�ɗǂ��I�[�f�B�I�V�X�e�����\�z�ł��邱�Ƃ�����Ă���܂��B
���ς�炸���X�ȍr�炵�s�ׂ�����悤�ł��ˁi�����ԍ��F23118319�A23118362�Q�Ɓj�B
�f�^��������������ƒ������ĉ����闊��������y������R��������Ⴂ�܂����A�X����l�ɂ�����܂��Ă͍r�炵�ɋ������Ɋ撣���ĉ������ˁB
�����ԍ��F23178446
![]() 8�_
8�_
�˃��J �a�l����A����ɂ��́B
���Ė{��̕��ł����A
>��������g�p������@�������ł���
�����@���g�p����K�v�͂���܂���B
2����P�[�u���ŏ\���ł��B
���R�͑O�X���ɓ��e���Ă��������̂ł킩��Ǝv���܂��B
�z���̕��@�ɂ��Ăł����A
�T�u�E�[�t�@�[���g���ꍇ�A�ǂ��ʼn��ʒ���������̂��A�ɂ��܂��B
�Ƃ����Ă��A2����ɂ��Ă��ASW���o�R����ɂ��Ă��A
SU-8�ʼn��ʒ������Ȃ��ƁASW�̉��ʂ��A�S�̂̉��ʂɓ������Ȃ��Ȃ�܂��B
SU-8�͏��L���Ă��Ȃ��̂ŁA�����R���ʼn��ʒ����ł���̂��m�F�ł��܂���B
�܂��A�����R���ʼn��ʒ����ł����Ƃ��Ă��A
DAC�`�b�v�����̃f�W�^���{�����[�����g���Ă���Ǝv���̂ŁA
�r�b�g����邱�ƂɂȂ�܂�����A���܂�D�܂������@�ł͂Ȃ���������܂���B
�������������Ȃ���A����Ŗ��͖����̂ł����B
���̂�����́A�ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂ł��傤���H
�܂��APM-SUB8�͗ǂ����i�ł��������͂Ȃ��ł�����A
���̂����ƈ���SW�Ƃ����I�������A�l����K�v�����邩������܂���B
�����ԍ��F23178452
![]() 3�_
3�_
���˃��J �a�l����
�������݊ԈႦ�Ă��܂��܂����A���݂܂��X���[���Ă��������B
��blackbird1212����
���w�E���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F23178490
![]() 1�_
1�_
���˃��J �a�l����
�F�X�ς݂܂���ł����B�iRCA����A�_�v�^�[�͎g�p�ł���Ƃ������Ƃł��B�j
�z���́i��RCA�P�[�u���j
�P�[�X�@�@SU-8���T�u�E�[�t�@�[��AL-�T�O�QH�`�X�s�[�J�[�@�i�T�u�E�[�t�@�[����RCA�M��������j
�P�[�X�A�@SU-8��RCA����AL-502H�`�X�s�[�J�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�u�E�[�t�@�[
�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23178632
![]()
![]() 3�_
3�_
�w���\���DAC�ɂ̓����R���͗L��܂������ʒ����@�\�͖����Ǝv���܂��B�T�u�E�[�t�@�[���ɂ͉��ʒ����͖����̂ł��傤���H�z�肵�Ė����������Ȃ̂őΏ��@���ڂ��������ĖႦ��Ə�����܂��B��blackbird1212����
�����ԍ��F23178837�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����������̗����o���Ȃ����͉����I�[�f�B�I���������͂��ł����A�|���Ă������̔��Ȃ̂ɒm���͏��S�҃��x���Ȃ̂Ǝw�E����Ă���ؒ������Ӎ߂������ɔ�Q�҃d�����Ă��鏊�ł��ˁc
�����I���������z���āA���m�ł���L��܂���
������x�Ɖ��̃X���ɗN���Ȃ��l�ɋF��܂�
�����ԍ��F23179574�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 14�_
14�_
�˃��J �a�l����A�����́B
�T�u�E�[�t�@�[�ɂ͉��ʒ����̃{�����[���͂��Ă��܂��B
�ł����A�V�X�e���ɍ��킹�Ē���������A�ȍ~�͌Œ�Ŏg�����̂ł��B
�ł�����A�{�����[���܂݂͖{�̂̔w�ʑ��ɂ��Ă���@�킪�����ł��B
AV�A���v�Ŏ��������悤�ł����A
AV�A���v�̓{�����[���ɘA������SW��p�̃��C���o�͂�����̂ŁA
�����ɂȂ��őS�̂̉��ʒ����ƘA�����Ă��܂��B
�ł��̂ŁASW�̉��ʂ���̂Ƃ��Ē�������Ȃ�A
���ʒ����{�����[���́ASW�ɕ�����O�ɂȂ��ƁA
�S�̂̉��ʂƈꏏ�ɂ͒����ł��Ȃ��킯�ł��B
�ꕔ�̃v�����C���A���v�ɂ��ASW�o�͂�������̂�����܂��̂ŁA
�T�u�E�[�t�@�[�Œ���⋭�������̂ł�����A����𗘗p���������A
����̕ύX�ɂ͓K���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
SMSL SU-8�{AL-502H��5���߂��킯�ł����A
���ꂾ������ADENON PMA-60�͂ǂ��ł��傤���H
https://kakaku.com/item/K0000992262/
PC�p��USB�APS4�͌��f�W�^���A�X�}�z��bluetooth�A
�Ƃ����悤�ɓ��͂��g�������邱�Ƃ��o���܂����A
SW�p�̃v���A�E�g�����Ă��܂��B
�{��1��Ŋ������Ă܂�����z���ɂ��ĔY�ނ��Ƃ��Ȃ��ł����A
�R���p�N�g�ŏc�u�����o���܂��B
�T�u�E�[�n�[�͓���p�Ƃ��āA
YAMAHA YST-FSW150������ł��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
https://kakaku.com/item/20448811128/
�\�Z�Ɍ��肪����킯�ł����܂����Ⴂ�̂ł�����A
���̂����肩�瑵����̂��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ͎v���܂��B
�Ȃ��A�T�u�E�[�t�@�[�̂Ȃ����ɂ��Ăł����A
����������ւ̒��ӂɂ́A�b����₱�������Ȃ����߂ɏ����Ȃ������̂ł����A
AL-502H�iBTL�o�́j���g���ꍇ�ɂ́A�����ȒP�ɂ����Ȃ��������܂��B
�T�u�E�[�t�@�[�̓��͂ɂ��ẮA���C���o�͂����ł͂Ȃ��A
�A���v�̃X�s�[�J�[�o�͂��Ȃ�����̂�����܂��B
�ł����A�@��ɂ����
�u�p���[�A���v�̏o�͂�BTL���ƂȂ��Ȃ��v
�Ƃ������̂�����܂��B
�Ƃ������ABTL�A���v�̐ڑ��ɂ��Ή����Ă���Ɩ������Ă���������Ȃ��ł��B
���m�ɏ����Ă���̂́AFOSTEX�̏㋉�@�킭�炢��������܂���B�����ł��B
https://www.fostex.jp/products/cw200d/
�Ⴆ�A
SU-8-[RCA]- AL-502H-[�X�s�[�J�[�P�[�u��]-SW-[�X�s�[�J�[�P�[�u��]-BP200
���̂悤�ɂȂ���AAL-502H�ł̉��ʃR���g���[����SW������ł���̂ł����A
���̂��߂ɂ́ASW��BTL�o�͂̃p���[�A���v�ɑΉ����Ă���K�v������܂��B
BTL�o�͂̃p���[�A���v�́A�X�s�[�J�[��2��̃A���v�́{�[�q�ԂɂȂ��̂ŁA
�ʏ�̃A���v�o�͂́|���A�܂�GND�[�q�����g���܂���B
�ł����A���ʂ̓��͒[�q�Ƃ����̂́A�|��������GND�ɐڑ�����Ă��܂��B
�����炱���A�A���o�����X�̃w�b�h�z���[�q��GND���ʂ�3�ɂŎg����킯�ł��B
�Ƃ����킯�ŁASW�̃X�s�[�J�[���͂́|����GND�ɐڑ�����Ă���ƁA
BTL�o�͂̃p���[�A���v�̕Б��̏o�͂�GND�ɐڑ�����Ă��܂��A
�ň��̏ꍇ�A���v�o�͂��V���[�g���Ĕj�����Ă��܂��܂��B
������A�A���v�̏o�͂�BTL�̏ꍇ�A���ՂɃX�s�[�J�[�ڑ����o����
SW���g���Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��킯�ł��B
���낢��ƍl�������đI�A���v�\���ł͂���Ƃ͎v���̂ł����A
���W�����l����ƁA���Ɠ���I���ł�����̂ŁA
�l�������������ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23179720
![]() 1�_
1�_
���˃��J �a�l����
����ɂ��́B
SMSL�@SU-8�̓A�}�]�����̐����ł͉��ʒ��ߋ@�\�͂���悤�ł��B���r���[�ɂ��ł���Ƃ����R�����g������܂��̂ŁA���������l���Ȃ�Δ̔��X�ɒ��ڊm�F���ǂ��Ǝv���܂��B�i�W���i���Ȃ����ؐ��i�͖₢���킹�ł����m�F�ł��Ȃ��̂������ł��j
���ꂩ��
���߂ɂ��̋@�킾�����w������Ă��]���������R�X�p�̗ǂ�DAC�ł����猻��V�X�e���̉����A�b�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�i�ŋ߂̐V������DAC�͊m���ɉ������ǂ��ł��B�j
�����ԍ��F23179858
![]() 1�_
1�_
���˃��J �a�l����
���͂悤�������܂��B
���͒m���͂���܂���́A�i������������Ă��܂��B
�˂�����_�̋����o�Ȃ��Ďc�O�ł������A�T�u�E�[�t�@�[�̋��͏o���悤�ł��ˁB
�ǂ������ɔ��W����邱�Ƃ����F�肵�Ă���܂��B
�����ԍ��F23179874
![]() 2�_
2�_
����Ă悭������܂��T�u�E�[�t�@�[��g�ݍ��킹��͓̂���\���ɂȂ�ƌ������Ƃł��ˁHpma60�͕s������l�ł����A���������Ȃ玞���I�ɂ�70�����낻��o�����Ȃ̂ő҂��������ǂ������ł����ˁH
�����ԍ��F23181226�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��cantake����
��blackbird1212����
���l���Ă���\�����ƃT�u�E�[�t�@�[���̊g�����ɓ�L��ƌ������Ƃł��傤���HPMA60���͂��̌�p�@��ӂ��_���������ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F23184489�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�˃��J �a�l����A�����́B
�O�ɂ������܂������ASW��1�x���ʒ�����������A�ȍ~�͌Œ�Ŏg�����̂Ȃ̂ŁA
�S�̂̉��ʒ����ƘA���ł���悤�ɃZ�b�g����K�v������܂��B
�Ƃ������A���������悤�ɃZ�b�g���Ȃ��Ƒ�ώg���ɂ������̂�����ł��B
�ł�����A
>SU-8�iDAC�j - SUB8�i�T�u�E�[�t�@�[�j-AL-502H�i�p���[�A���v�j - BP200
���̂悤�Ȕz�����ƁA�uSU-8�v�ʼn��ʒ�������K�v������܂��B
cantake����́ASU-8�̃����R���ʼn��ʒ����\�Ƃ����b���o�Ă��܂����A
���ʒ����ł��Ă��ADAC�`�b�v�̃f�W�^���{�����[�����g���̂ŁA
���ʂ��i�遁�r�b�g�����A���ƂɂȂ�̂ʼn������C�ɂȂ�܂��B
�܂������R���ł������ʒ����ł��Ȃ��̂ŁA���ʕω��̒i�K�����傤�ǂ悭�g���邩���킩��܂���B
AL-502H���{�����[���t���Ȃ̂ŁA�ǂ����K���ȉ��ʂɒ������ČŒ肵�Ďg�����ƂɂȂ�܂��B
�ł��̂ŁA���܂肨���߂ł���g�ݍ��킹�ł͖����Ǝv���܂��B
���������@�Ƃ��ẮA�X�s�[�J�[�o�͂��Ȃ�����SW���g�����@�ł����A
���̏ꍇ�́AAL-502H�̃X�s�[�J�[�o�͂�BTL�i�o�����X�o�́j�Ȃ̂ŁA
�o�����X�o�͂̃A���v���Ȃ����Ƃ��o����SW���K�v�ɂȂ�܂��B
����SW�Ńo�����X�Ή��̂��̂͂قڂȂ��Ǝv����̂ŁA
FOSTEX��CW200D�i����6��������Ɓj�Ƃ����z�ɂȂ�܂��B
�Ƃ������ƂȂ̂ŁA��̌^��SW�p�̃v���A�E�g������
PMA-60�Ȃǂ͂ǂ����Ǝv�����̂ł����A
�g���u�����C�ɂȂ�ƂȂ�ƁA������Ɠ���Ƃ��낪����܂��B
�܂��APMA-60�̌�p�@�ɂ��Ăł����A
�Z���T�C�N���ŏo�邩�ǂ����Ƃ����͔̂�����������܂���B
�Ȃ��Ȃ�APMA-50��PMA-60�̏ꍇ�́ADDFA����ꐢ�と���Ƃ���
�g�p���i�̐����オ�������킯�ł����A��O����͂܂������悤�ł��B
�ŐV��PMA-150H(2019/9����)������BTL�Ŏg���Ă��邾���ł��B
PMA-60�̕s��ɂ��Ăł����A����͂Ȃ�Ƃ����f������Ƃ���ł��B
�������̂ǂꂾ���ɕs����o�Ă���̂��킩��Ȃ�����ł��B
���Ƀg���u����������A���e���Ȃ��킯�ł�����A�g���u�������̌̐��͂킩��Ȃ��킯�ł��B
�E�`�ł́A������g���u�������ƌ���ꂽ����PMA-50���g���Ă��܂������A
���܂ɓd��������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����邾���ŁA�d���P�[�u��������č��������Ύ���̂ŁA
�C���ɏo�����̑傫�ȃg���u���͂Ȃ�4�N���قǎg���܂����B
TV�����̍Đ��Ɏg���Ă����̂ŁA���N����AV�A���v�Ɠ���ւ��܂����B
�Ƃ������ƂŁA�g���u�������邩�Ȃ����͑S�̂Ƃ��Ă̓p�[�Z���e�[�W���ł����A
�l�ɂƂ��ẮA�����肩�O�ꂩ�̓���ł����Ȃ��킯�Ȃ̂ŁA����Ƃ���ł��B
�����A�����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł��B
PMA-60�ȊO���ƁAPC�p��USB���́A���f�W�^�����́ASW�o�͗L��ƂȂ�ƁA
YAMAHA��A-S801�i5.4���قǁj������ɂȂ�̂ŁA�傫���Ȃ��Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F23185445
![]() 2�_
2�_
YAMAHA A-S801�̓��g���ȃf�U�C���������̂ōD�݂ł���
�艿��������̕��������̂ŃN���X��ł��傤���A�����ʍĐ����y�����r���[�������������Ɠ��ɖ�薳�������ł����A���@���Z�[�t�Ȃ̂ł���͗ǂ��ł��ˁI���݂ɐF�̓��}�n�͂�͂�V���o�[���ǂ��ł��傤���H�i�n�[�h�I�t�ɒu���Ă���70�N��̃��}�n�A���v�͑S�ăV���o�[�������j��blackbird1212����
�����ԍ��F23186025�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ʔ̓X�Ń��}�n��A801��}�n�܂ރ��[�J�[�̃t���O�V�b�v�ō����Ă݂܂�����I�x����1�܂�DALI�ɂ����͊������̂ł���͖����܂��ˁc
���݂�801�Ɣ�ׂ�Ɗe�Ѓt���O�V�b�v�͖��炩�ɒቹ��d�ቹ�̗ʂ⎿�����サ�ă{�[�J���ш�����C�������Ă�Ƃ�̂��銴���ɂȂ�܂��ˁB����801���\�������ǂ������ł����A�����̂̓X�s�[�J�[�I�тł��ˁB��blackbird1212����
�����ԍ��F23186665�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�˃��J �a�l����A�����́B
>���݂ɐF�̓��}�n�͂�͂�V���o�[���ǂ��ł��傤���H
�����ł��ˁA�V���o�[�̕������ꂢ���Ǝv���܂���YAMAHA���ۂ��ł��B
�E�`�ɂ���Â��Z�p���[�g�͍��ł����ǁiC-70+B-70)�B
>�e�Ѓt���O�V�b�v�͖��炩�ɒቹ��d�ቹ�̗ʂ⎿�����サ��
>�{�[�J���ш�����C�������Ă�Ƃ�̂��銴���ɂȂ�܂��ˁB
�܂��A���ꂪ���i���ł�����킯�ł�����B
�����A���̍���ł��錴���Ƃ����̂́A�傫���͕��i�̍��ɂȂ�킯�����ǁA
������̘c�݂������@�ɂȂ�قǏ��Ȃ��Ȃ�A�Ƃ������Ƃ��傫���ł��B
�c�݂Ƃ����̂́A�G���ł͂Ȃ��t�щ��̑����ɂ���đ�����{���͂Ȃ��{�������ŁA
����ɂ���āA�������̉��ʂ������ɑ����Ă��܂��A���ΓI�ɒቹ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A
�Ƃ������Ƃ����ʋ@��ł͋N�����Ă��āA��ʋ@��ł͂��̉e�����������Ȃ�̂ŁA
���ΓI�ɒቹ�̗ʂ�������悤�Ɋ�������Ƃ����Ƃ���ł��B
������A���ʂ������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�t�ɗ]�v�ɑ����Ă��܂����ƂŁA
�ቹ�Ƃ������ȉ������ΓI�Ɍ�������}�X�L���O���ꂽ�肵�Ă��܂��̂ŁA
�@��̃O���[�h���グ��ƁA���܂܂ŕ������Ȃ�����������������A
�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���������悤�ɂȂ�킯�ł��B
�g�����W�X�^�A���v�̏ꍇ�́A����̘c�݂�����̂ŁA
�����Ƃ��Ƃ������Ƃ����邳�������ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���������̂ŁA��ʋ@�͉����L���Ɋ�������킯�ł��B
�^��ǃA���v�̏ꍇ�́A�t�щ����������c�ݒ��S�Ȃ̂ŁA
�����L���ɂȂ����悤�Ɋ����镔���������̂ł����A
�c��ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��ł��B
�X�s�[�J�[�́A�Ƃ肠�����A���v�����Ă���A
�������l���Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�A���v��ς��Ă݂āA���R�X�p�Ƃ�����NS-BP200��
�ǂ��܂ŗǂ��Ȃ邩�������Ă݂Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
SW������A���Ȃ�C���[�W���ς��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23187458
![]() 1�_
1�_
��blackbird1212����
�m����BP200��X���Ŏ������ĂƂĂ��D��ۂŃR�X�p�ŋ��ƌ����闝�R��������܂����B�A���v���|�C���g�Ҍ����������ɔ����āA�l�q�����鎖�ɂ��܂��B
������Oberon1��BP200���Ɨǂ���������Oberon1�̓��j�^�[���̉��Ɋ����Ă��܂��܂������{�[�J���̖肪�ǂ���ۂł��č����Ƃ��͏����d�������ۂł��B�𑜓x�����͓I�ł��ˁB
�����ԍ��F23194708�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ǓX����YAMAHA s a801�ƃf�m�� pma60�ƃf�m�� 800ne�Œ�����ׂ�800ne��1�ԍD�݂������̂Ŏ����Ɏg�����I�x���� 1��800ne�ɂ��ăT�u�E�[�t�@�[�͒��߂鎖�ɂ��܂��i�������N�����̂��m���ł����j
�F����e�ɃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B��blackbird1212����
�����ԍ��F23224427�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��cantake����
�N�ł��ԈႦ���������Ƃ͗L��̂ŋC�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ��ł���B
�����ԍ��F23224568�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�y�g����������p�r�z
�p�\�R���ɐڑ����ăX�s�[�J�[����ǂ������o�������B
���EDM��Electric�Apop�n�̉��y���Ă��܂��B
��ˌ��ĂŎg�p���܂��B
�y�d������|�C���g�z
�������d�����Ă��܂��B
�X�s�[�J�[�A�A���v���ɍw�����邱�Ƃ����߂ĂȂ̂ŁA����@�Ƃ��āA�ł��邾���ǂ������o�����炢���ȁA���炢�ɍl���Ă��܂��B
�y�\�Z�z
\50,000
�y��r���Ă��鐻�i�^�Ԃ�T�[�r�X�z
YAMAHA R-N303(�v�����C���A���v�j
ONKYO D-112EXT�i�X�s�[�J�[�j
�������߂�����܂����狳���Ē��������ł��c�B
�y������e�A���̑��R�����g�z
��L�̓�̏��i�������Y��ł��܂��B
�X�s�[�J�[�A�A���v���w�����邱�Ǝ��̂����߂ĂŁA�����Ȃ�ɐF�X�ƒ��ׂĂ݂��̂ł����A���̂Q���w�����邱�ƂŃp�\�R���Ɛڑ��ł���̂����s���ł��B
DAC�Ƃ����̂��p�\�R���ƌq���ۂɍ��������o�����߂ɂ͏d�v?�ɂȂ�ƔF�����Ă��܂��B
YAMAHA R-N303 �ɂ�DAC�̋@�\����������Ă��邻���Ȃ̂ł����A������̃A���v���g�p����ADAC���g�p���Ă���̂Ɠ������ƂɂȂ�̂ł��傤���H
�������ʼn��y�͕����܂��ł��傤���c�B
���݁AONKYO D-112EXT���l���Ă��܂����A�����I�ɂ͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H
���i�I�[���j������̂��d�v�Ȃ̂ł��傤���c�B
�A���v�ƃ��V�[�o�̈Ⴂ�̓��W�I�������邩�����Ȃ����̈Ⴂ�A�Ƃ����F���ŊԈႢ�Ȃ��̂ł��傤���c�H
���W�I�����肪�Ȃ����߁A�p�\�R���Ɍq���邱�ƂƉ������ǂ���\��Ȃ��̂ŁA�v�����C���A���v��I�����܂����B
���ɂ��������߂̃v�����C���A���v������܂����狳���Ă������������ł��B
�p�\�R���ɐڑ����邱�ƂƁA�X�}�z��ڑ����邱�Ƃ��ł�������̂ŁABluetooth��Wifi�̋@�\���Ȃ��Ă����v�ł��B
��낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F23212743�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���j�t�ł�����
�A���v��DAC��
�f�W�^���A�i���O�ϊ��̓f�W�^�����͂ɑΉ�����Ȃ���Ă܂���ˁH
�p�\�R������f�W�^���o�͉͂����g����̂ł����H
�I���̃A���v�͌����͂Ȃǂ��������p�\�R���ł͂悭�g��usb�͂Ȃ������ł����H
�����ԍ��F23212753�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���j�t�ł�����
�����͂ł��B
�܂��A���v�Ȃ̂ł����A�o�b�Ƃ̐ڑ��́uYAMAHA R-N303(�v�����C���A���v�j�v�ɂ����ẮA�v���|�e���ڑ��̏ꍇ�ɂ̓��C�����X���[�^�[���K�v�ł��B���łɂ��̊��������Ă���Ȃ�Ζ�肠��܂���B
���̑��̂o�b�ڑ��ł��ƌ��P�[�u���A�������͓����P�[�u���ɂȂ�܂����A�ڑ��\��̂o�b���ɒ[�q������܂����H
�������̗��p�Ŗ�肠��܂���B
�ȏ�ɂǂ���������ꍇ�́A�j�d�m�m�v�n�n�c�̂j�`�|�m�V�͔@���ł��傤�B�����ڂ͏����ȃA���v�ł��̂ŁA���X�s���Ɋ������邩���ł����A�����͂t�r�a�ڑ��̂c�`�b�𓋍ڂ��Ă���̂ŁA�t�r�a�[�q�͂ǂ�Ȃo�b�ł�����Ƃ������܂��̂Őڑ��\�ł��B
�������X�s�[�J�[�o�͂�����܂��B���Ƃ��l�i�����͓I(���iCOM�łQ�R�T�O�O�~)�Ȃ̂ŁA���̂Ԃ�X�s�[�J�[�ɗ\�Z���܂��B
�X�s�[�J�[�Ƃ��ẮA�c�`�k�h�̂r�o�d�j�s�n�q�Q�@�n�m�j�x�n�Ȃ�c�|�T�T�d�w�Ȃǂ͔@���ł��傤�B
���͂c�`�k�h�ł������f���̂y�d�m�r�n�q�P�Ȃ̂ł����ǁA���̌�p�@�Ȃ�ǂ����Ȃ̂ł͂Ƃ̎v���ł��B
�܂����̂��݂̂͐l���ꂼ��Ȃ̂ŁA�o����A���X�ň�x������Ă݂鎖�������߂��܂��B
�����ԍ��F23213051
![]() 2�_
2�_
���j�t�ł�����
����ɂ��́B
> �������d�����Ă��܂��B
�q�ϓI�ȃX�y�b�N���炭�鉹���ɂ��Ă̓R�����g�ł��܂����A���ۂɎ��Œ������ۂɂǂ������邩�ɂ��Ă͐l���ꂼ��̍D�݁A�������ɂ���Ĉ���Ă��܂��̂ŁA�ŏI�I�ȉ����̔��f�̓X���傳��ɂ����ł��܂���B
���ɃX�s�[�J�[�͎������Ă����g�̎��Ŏ��ۂɉ����m���߂Ă݂�̂���ԗǂ��ł��B
> �p�\�R���Ɍq���邱�ƂƉ������ǂ���\��Ȃ�
R-N303�ɂ�PC�ڑ��ł���USB�[�q���t���Ă��Ȃ��̂ŁAPC��USB�P�[�u���ł̐ڑ��͕s�ł��B
PC��USB�[�q����o�͂���ꍇ�́A�ʓr�A�@��i��FUSB-DAC�BUSB����/�����f�W�^���ϊ���j���K�v�ɂȂ�܂��B
PC�ڑ��\��USB�[�q���t���Ă��ă��[�Y�i�u���ȃv�����C���A���v���ƁA���ɂ����E�̂���P���E�b�h KA-NA7������ł��傤���B
R-N303�ɂ͌��Ɠ����̃f�W�^���������͒[�q���t���Ă���̂ŁAPC�Ƀf�W�^�������o�͒[�q�i���܂��͓����j������A���܂��͓����P�[�u���Őڑ��ł��܂��B
> �p�\�R���ɐڑ����邱�ƂƁA�X�}�z��ڑ����邱�Ƃ��ł�������̂ŁABluetooth��Wifi�̋@�\���Ȃ��Ă����v�ł��B
Bluetooth�AWi-Fi���s�v�Ƃ̂��Ƃł����A�X�}�z�ƃA���v�Ƃ̐ڑ����@��p�r�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�z�肵�Ă��܂����H
R-N303�ɂ�USB�[�q�͕t���Ă��܂���B
���̂܂܂ł͏��s���ŋ�̓I�ȃA�h�o�C�X�ɂ����Ǝv���܂��̂ŁA�ȉ��̓_�𖾂炩�ɂ����葽���̐l����L�v�ȏ����邩������܂����B
�X�s�[�J�[�ƒ����ʒu�̋����́H
�E�f�X�N���PC�e�ɒu���ăf�X�N�O�̈֎q�ɍ����Ē����̂��H
�E�����S�̂ɉ����������āA������x���ꂽ�ʒu�Œ����̂��H�����̑傫���́H
�X�s�[�J�[�̐ݒu�X�y�[�X�́H
�E�f�X�N��Őݒu�X�y�[�X�������Ă���̂��H
�E��r�I�]�T�̂��鏊�ɒu���̂��H
�EONKYO D-112EXT���x�̃T�C�Y���x�X�g���H������傫���Ă��ǂ����A�����������x�^�[���H
PC�̒[�q�́H
�E�f�W�^���o�͂��t���Ă���̂��H
�EUSB�ł̐ڑ����l���Ă���̂��H
�X�s�[�J�[�̎�ނ́H
�E�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�i�A���v�����^�j�ł��ǂ��̂��H
�E�p�b�V�u�X�s�[�J�[�i�A���v������^�j�{�v�����C���A���v�̑g�ݍ��킹���ǂ��̂��H
�����ԍ��F23213164
![]() 2�_
2�_
���j�t�ł�����
����ɂ��́B
�T���~�ȉ��ł͗ǂ��g�ݍ��킹�Ǝv���܂����A�X�s�[�J�[�͓������[�J�[��NS-BP401�i2.2���j���]���������@��ł��B
�i�I���L���[�͉�Ќo�c�̖�������܂��̂Łj
���̃A���v�́APC����USB�o�͂Œ��ڃA���v�ɓ��͂ł��܂���̂ŁAUSB������ɕϊ�����A�_�v�^�[���K�v�ɂȂ�܂��B
�i�Q�l�FNFJ�̔���FX-AUDIO�̐��i�łR��~�ȉ��ł���܂��B�j
���}�n�̋@��̓l�b�g�AWifi�����p���Ă����֗��ȋ@��Ǝv���܂��B
PC�̉��y�f�[�^���T�[�o�[�Ƃ��āA���̋@��ł��炷���Ƃ��ł���@�\������܂��B
Wifi�͑S���K�v�����Ȃ�A�A�}�]���ɂ�����܂����ATopping��MX�R�Ƃ�SMSL��SA300�Ȃǂ�1.5�����炢�Ńf�W�^�����͂��ł��܂����u���[�g�D�[�X�@�\������܂��B�R���p�N�g�ł��B���������������猟�����Ă݂Ē��������Ǝv���܂��B
���炵�܂����B
�����ԍ��F23213214
![]() 1�_
1�_
���j�t�ł�����
�p�\�R���Ȃ�������̂���
http://www.kripton.jp/fs/kripton/pc_audio_speaker/ks-1hqm
���̂悤�ȃX�s�[�J�[���y�ʼn����ǂ��ł��B
�A���A���̍D�݂͂���܂����B
�����ԍ��F23213335�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>kockys����
�ԐM�������肪�Ƃ��������܂��B
�m�F�����Ƃ���A�p�\�R���ɂ́AS/PDIF OUT�Ƃ����[�q�����Ă��܂����B
���̒[�q�ł���Ύg�p�\�ł��傤��...?
�����ԍ��F23213500
![]() 0�_
0�_
�j�t�ł�����A������
��S/PDIF OUT�ł���Ύg�p�\�ł��傤��...?
�\�ł��B�A���v�̓������͂ɂȂ��܂��B
�����ԍ��F23213516�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���j�t�ł�����
�p�\�R����SPDIF����̂ł��ˁB
�ł�����ڑ��\�ł��B
�����ԍ��F23213520�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Â����̑�D������
�����́A�ԐM�������肪�Ƃ��������܂��B
���C�����X���[�^�[�͂���܂��I
PC���ɂ�SPDIF OUT�Ƃ����[�q������܂����B
���̒[�q���Ɠ����P�[�u���ł̐ڑ��ɂȂ�̂ł��傤���H
�����ɖ��͂Ȃ��ł��傤���E�E�E�H
�l�X�ȏ��i�������Ă����������肪�Ƃ��������܂��B�������Ă݂܂��I
�����ԍ��F23213546
![]() 0�_
0�_
��DELTA PLUS����
�����́A�ԐM�����������肪�Ƃ��������܂��B
���ŏI�I�ȉ����̔��f�̓X���傳��ɂ����ł��܂���B
�����ł���ˁA�ŏI�I�Ɍ��߂�̂́A�����̍D�݂��Ǝv���̂ł����A�n���Z�݂Ȃ̂łȂ��Ȃ���葵���̂��邨�X�ɍs���̂������ł���ˁE�E�E�{���͂��낢��ƕ�����ׂĂ�������l�������̂ł����A�Ȃ��Ȃ��������ł��B
��PC�Ƀf�W�^�������o�͒[�q�i���܂��͓����j������A���܂��͓����P�[�u���Őڑ��ł��܂��B
�m�F�����Ƃ���SPDIF OUT�Ƃ����[�q������܂����̂ŁA���̓_�͖��Ȃ������ł��I
���X�}�z�ƃA���v�Ƃ̐ڑ����@��p�r�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�z�肵�Ă��܂����H
�ڑ����@�Ƃ��ẮA��ʓI�ȃI�[�f�B�I�P�[�u���i3.5mm?)���l���Ă��܂����B���̐ڑ����@�ł͉��̗��������肵�܂��ł��傤���H
Bluetooth��Wifi�Őڑ��ƂȂ�ƁA�����Ƃ������Ƃ������ĉ����������Ă��܂��̂ł�...�Ƃ����s��������A�u���ڐڑ��̂ق����ǂ����낤�v�Ƃ����l���Ɏ���܂������A���ۂǂ��Ȃ�ł��傤�E�E�E
���ȉ��̓_�𖾂炩�ɂ����葽���̐l����L�v�ȏ����邩������܂����B
������f�l�Ȃ��̂ŁA�ʂ��肪�����Ă��݂܂���B���lj������Ă��������܂��I
�E�X�s�[�J�[�ƒ����ʒu�̋����́H
�f�X�N���PC�e�ɒu���ăf�X�N�O�̈֎q�ɍ����Ē����܂��B
�X�s�[�J�[�̐ݒu�X�y�[�X�́H
�f�X�N��ł����A��r�I�]�T�͂���܂��B
����DIY�Ńf�X�N���쐬���悤�ƍl���Ă���̂ŁA�X�y�[�X�Ɋւ��Ă͂��܂�l�����Ȃ��Ă����v�ł��I
�EONKYO D-112EXT���x�̃T�C�Y���x�X�g���H
�傫���Ă��������Ă��\��Ȃ��̂ł����A�T�C�Y���傫���ق������\���ǂ��̂ł���A�����炪�D�܂����ł��I
PC�̒[�q�́H
�E�f�W�^���o�͂��t���Ă���̂��H
SPDIF OUT�[�q�����Ă��܂��B
�EUSB�ł̐ڑ����l���Ă���̂��H
��艹���ǂ��ق��̐ڑ���I���������ł��B
�ƂȂ�ƁASPDIF OUT�[�q�̂ق����ǂ��̂ł��傤���H�H
�X�s�[�J�[�̎�ނ́H
�E�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�i�A���v�����^�j�ł��ǂ��̂��H
�E�p�b�V�u�X�s�[�J�[�i�A���v������^�j�{�v�����C���A���v�̑g�ݍ��킹���ǂ��̂��H
���ɃA���v�����������Ƃ��A������������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��B�������ǂ��������̑I�����������Ǝv���Ă��܂��I
�����Ȃ��Ă��܂��A���݂܂���I
�����ԍ��F23213596
![]() 0�_
0�_
��cantake����
�����́A�ԐM�����������肪�Ƃ��������܂��B
���X�s�[�J�[�͓������[�J�[��NS-BP401�i2.2���j���]���������@��ł��B
���ׂĂ݂܂����IONKYO D-112EXT�Ɠ������炢�]�����ǂ��A�l�I�ɂ��C�ɂȂ��Ă���̂ł����A��r�̎d�����C�}�C�`�킩��܂���B�B�B
�������̂������悭�āA���������܂�ǂ��Ȃ��I�݂����Ȃ̂�����܂�����ȒP�ɂō\���܂���̂ŋ����Ă���������K���ł��B
��USB������ɕϊ�����A�_�v�^�[���K�v�ɂȂ�܂��B
�ڑ��Ɋւ��ẮAS/PDIF OUT�[�q������܂����̂Ŗ��͂Ȃ������ł��B
�����}�n�̋@��̓l�b�g�AWifi�����p���Ă����֗��ȋ@��Ǝv���܂��B
�����Ȃ�ł��ˁI�f�l�ڐ����ƁA��͂薳���ڑ��͉����̗Ɍq����̂ł́E�E�E�Ƃ����s��������A�ɗ͔����čl���Ă����̂ł����A���ۂ̂Ƃ���ǂ��Ȃ�ł��傤���E�E�E
�����������������猟�����Ă݂Ē��������Ǝv���܂��B
���肪�Ƃ��������܂��I���낢��ƌ������Ă݂܂��I
�����ԍ��F23213614
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�����́A�ԐM�����������肪�Ƃ��������܂��B
�����Ȃ�ł��ˁI���m�������܂����I
�����ԍ��F23213622
![]() 0�_
0�_
��kockys����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��I
�ǂ������ł��B���m�������܂����I
�����ԍ��F23213626
![]() 0�_
0�_
���j�t�ł�����Ή��P�[�u��
����ɂ��́B
R-N303�̓l�b�g�v���[���[�A���v�ł��̂ŁAPC��USB�Œ��ڂ̐ڑ��͂ł��܂���B���ADLNA�Ή����Ă܂��̂�LAN�o�R��PC�̒��̃f�[�^�Ȃ�NAS�̂Ȃ��̋Ȃ̍Đ��͉\�ł��B
Windows Media Player �Ȃ�Win�[���Ȃ�W�������Ȃ̂ł��ꗘ�p����Ɨǂ��ł��B
PC�Q�[������PC�̉������������Ȃ瓯���̃f�W�^���P�[�u���ڑ��ł��ˁB������PC��LAN���܂����X�C�b�`�n�u�o�RLAN��R-N303�̕���������������ł͗ǂ����Ǝv���܂��B
ONKYO�̃X�s�[�J�[���A�Ȃ��Ȃ��̉��ŁA��܂���B���̗\�Z�ł͗ǂ��I�����ƁB
����PC�ɂ�D-112E���������̂�����܂��B
�����ԍ��F23213724�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���j�t�ł�����
SPDIF��USB�Ȃ��USB�̕����ǂ�������ł����ǂˁB
�����͑z��ł��B�g���Ă�SPDIF�̕i�����s���ŁB�B
�������A�A�i���O�Ńp�\�R������o�͂��l����Ƃقڍ����Ȃ����x���Ǝv���܂����B
�����ԍ��F23213736
![]() 0�_
0�_
���j�t�ł�����
�����́B
�X�s�[�J�[�̓I���L���[�̂͑O�ʃo�X���t�ŁA���}�n�͔w�ʃo�X���t�^�C�v�ł��B�w�ʂɑ����̗]�T��Ԃ��Ƃ�Ȃ��ꍇ�͑O�ʃo�X���t�^���ǂ��Ǝv���܂��B�i���܂͔w�ʃ^�C�v�������ł��B�傫���Ƃ��f�U�C��������܂����B�j
�Ȃ��I���L���[�͌o�c�j�]�ŁA���݂͖w�ǂ̃I�[�f�B�I���i�̓X�g�b�v���Ă��܂��B�S�z�͖�����̏ꍇ�̃����e�ʂł��B
�X�s�[�J�[�̉����͌l�ɂ���čD�݂�����܂��̂ŁA�������ꂽ�����ǂ��ł��傤�B���[�J�[�ɂ���ĉ��F�Ƃ����j�b�g�̍ގ��ɂ���Ă����\�Ⴂ�܂��B�C�O���[�J�[�ł�DALI�̃X�s�[�J�[���l�C������܂��B
�u���ꏊ�ŁA�X�s�[�J�[�X�^���h���K�v�ɂȂ�ꍇ������܂��B�n���~���i���������ł��B
�����ԍ��F23213775
![]() 1�_
1�_
���j�t�ł�����
������ł��B
�w���C�����X���[�^�[�͂���܂��I
PC���ɂ�SPDIF OUT�Ƃ����[�q������܂����B�x
�ł���A���̃��}�n�A���v�ɐڑ��\�ł��ˁB
���C�����X���[�^�[�̐ڑ����@�̓��}�n�̃z�[���y�[�W�ɂ���܂��B
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n303/index.html
�r�o�c�h�e�@�n�t�s�̐ڑ����@�͂�������Q�Ƃ��������B�@�Ȃ���p�̃P�[�u���͕K�v�ł����ǂˁB
https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/connect-spdif.html
�����I�ɂ͂ǂ�����f�W�^���M���ł̂����ɂȂ�܂��̂ŁA�o�b����̃A�i���O�ڑ��ɔ�ׂ�Έ��肵�������ɂē��ɖ��ɂȂ�Ƃ͎v���܂���B
�������A�����ȉ������x���������o���ΐ肪����܂��A������\�Z���c��ɂȂ��ė��܂��̂ŁA�F�l�́u�I�[�f�B�I�̒�Ȃ����v�Ƀn�}���Ă��܂����ƌ�������������܂��B
����́A������ڎw���Ă���̂ł͖����ƍl���āA�ǂ���̐ڑ��ł���薳���ƌ�����̂ł͂Ǝv���܂��B
�{���ɍׂ������������o���Ɛ肪����܂���̂ŁA��߂Ă����܂��傤�B
�����ԍ��F23213794
![]() 1�_
1�_
���j�t�ł�����
�NjL���܂��B�A���v��DAC�ɂ��Ăł����APC�I�[�f�B�I�ʼn����D��Ȃ�\�Z���̋@��Ƃ���
DAC�i��P���j
�@Topping��D10�@�ASMSL�̂P�O���N�L�O�o�[�W�����@�i�������USB�o�X�p���[�j
�A���v�i��2���j
�BTopping��TP-60�@�C�A�����b�N��AL-502H
�Ȃǂ͕]���������ėǂ��Ǝv���܂��B�N�`�R�~�Ȃǂ����������ĎQ�l�ɂ��Ȃ�܂��B
DAC�͐V�����`�b�v���ڂ̂��̂��f�W�^���Z�p�̐i�����͂₢�ł�����A���Ȃ�Ⴄ�Ǝv���Ă��܂��B
�A���v�ADAC�̓g�����X�d���̕����]�����ǂ��ł��������Ȃ�܂��BTP-60�̓g�����X�d���ł��B
�����^�C�v�Ȃ珫���I�ɂ��ADAC����ʋ@��i�Ⴆ��SMSL��M�T�O�O�Ƃ��j�ɂ���Ύ�߂�Ȃ��O���[�h�A�b�v���\�Ǝv���܂��B
�܂������l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�s���ɂ�NAS�i��3.5���`�j���w������Ηǂ��Ǝv���܂��B
�Q�l�ɂȂ�K���ł��B�ǂ��I�[�f�B�I���C�t���ǂ����I
�����ԍ��F23214067
![]() 0�_
0�_
���j�t�ł�����
R-N303�̓��V�[�o�[�ƌĂ��^�C�v�ł��ˁB���W�I�Ƃ������A���낢��ȋ@�\�����������@�����V�[�o�ƌĂ�邱�Ƃ������ł��B
PC�Ƃ̐ڑ��̓l�b�g���[�N�Đ��ɑΉ����Ă���Đ��\�t�g��������n�C���]�܂߂ėL��LAN�܂��͖���LAN�ł��s����̂ŕ֗��ł��ˁB
�������̃X�}�z�� iPhone �ł�����AirPlay���g���Ė���LAN��CD�����܂ł͗Ȃ��ő��邱�Ƃ��\�ł��B
Android��PC����ł�iTunes �� Apple Music �ł����� AirPlay�ŊȒP�ɑ����悤�ł��BCD�����܂ł͗Ȃ��Ŗ����ő���܂��B
�����A�����ɉ����Ƃ����Ӗ��ł͓��N���X�̃v�����C���A���vA-S301�̕����]�v�ȋ@�\���Ȃ��d�ʂ��d���̂ʼn����ǂ��\���������Ǝv���܂��B
�����͗����Ƃ̌��ˍ������Ǝv���܂��B
���������Ă��鉹���Ŕ��f������ǂ��Ǝv���܂��B
�@�l�b�g���[�N�X�g���[�~���O�i�L��LAN�܂��͖���LAN�j�F�n�C���]�܂ő���� 192kHz/24bit �Ȃ�
�@AirPlay�i����LAN�o�R�ƂȂ�܂��j�FCD�����܂ŗȂ��ő���� �t���k 44.1kHz/16bit �Ȃ�
�@Bluetooth�F�R�[�f�b�N�ɂ��܂����A��L���͂����Ɖ��������B
���Ȃ݂ɁAApple Music �� Amazon Music�iHD�\�L���Ȃ��ȁj�͕s�t���kAAC256bps 44.1kHz/16bit�Ȃ�
�ƂȂ�A�f�[�^���̂�CD�������͂����ԗ��ABluetooth���͂����Ԃ����A�Ƃ����̂���ʓI�ł��B
�n�C���]���Ȃ��̂ł���� AirPlay �ŏ[���Ƃ������Ƃł��B
S/PDIF �Ƃ����̂̓f�W�^���@����Ȃ��f�[�^�`���̂��ƂŁA�ڑ��[�q�͐F�X����܂��B
�����p�ł悭�g����̂������iRCA�[�q�j�ƌ��iTosLink�j�ł��B���ۂɂ͑��ɂ������iBNC�[�q�j��AES/EBU�iXLR�[�q�j�Ȃǂ�����܂��B
�[�q�����a8mm���̊ۂ���������яo���Ă��Ē����I�����W�Ƃ��̃v���Ő^�ɏ����Ȍ����Ă����瓯���iRCA�j�ł��B���ʂ̐Ԕ��P�[�u����}���Ƃ���Ɠ����`�ł��ˁB
�����p�J�p�J����W�A�܂��͎��O�����̍����W���t���Ă��Ē����Ԃ������Ă�������iTosLink�j�ł��B
�����ł����ł��ǂ����S/PDIF�ł��B
�m�[�gPC�Ȃǂ���3.5mm�C���z���W���b�N�ƌ��p�ƂȂ��Ă�����[�q������܂����A�����u���p�\�R�����Ƃ��܂�Ȃ����Ǝv���܂��B
�r�b�g���[�g�̍����n�C���]�f�[�^�𑗂肽���ꍇ��192kHz����f�[�^�̏ꍇ��USB�łȂ��Ƒ���Ȃ����Ƃ�����܂�������������������Ă���A���v�ł�192kHz�܂ł����Ή����Ă��܂���B
�܂��A�悭����f�W�^�����͒[�q�ł͓����AUSB�A���A�̏��ʼn����������Ƃ������ƌ����Ă��Ď������o�������ʓI�ȋ@��ł͂������Ǝv���܂��B�����A����f�[�^�̓f�W�^���f�[�^�ł����A�m�C�Y��d���ϓ��Ȃǂ̉e���ŁA����o�����A�P�[�u���A�����ꂼ�ꂪ���Ȃ艹���ɉe�����܂��B���یq���Œ����Ă݂Ĕ��f������ǂ����Ǝv���܂��B���̉����D���Ƃ����l�������肵�܂����A�Ɠ��ȓ���������̂ł��������l������̂������ł��܂��B
DAC�́A�f�W�^�� to �A�i���O �R���o�[�^�i�ϊ���j�ł��̂ŁA���ʼn����ۂɂ͕K���o�R���܂��B
�X�s�[�J�[��C���z���ʼn��y���Đ��ł���@��Ȃ�A�X�}�z�ł�PC�ł�DAC�͕K�������Ă��܂��B
�A���v�����ǂ��Ă�DAC���ǂ��Ȃ��Ƃ������{�g���l�b�N�ɂȂ�̂ŁA���ɂ������l�͉��̂����P��DAC���g�����Ƃ�����܂��B
��������Ă���悤�ȃt���T�C�Y�R���|�ɂȂ��̂ł����PC��X�}�z����DAC�͂ł���Δ����������ǂ����Ǝv���܂��B
�܂���DAC�����A���v���ē������ꂽDAC�𗘗p���āA�����I�ɊO�t���P��DAC���������Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23214402
![]()
![]() 0�_
0�_
���j�t�ł�����
����ɂ��́B
> �n���Z�݂Ȃ̂łȂ��Ȃ���葵���̂��邨�X�ɍs���̂������ł���ˁE�E�E
�����ł��Ȃ��Ȃ珉�u�ѓO�ŁuYAMAHA R-N303�{ONKYO D-112EXT�v�̑g�ݍ��킹�ł������Ȃ��Ƃ͎v���܂��B
�����AD-112EXT�͔̔��I�����f�����Ǝv���̂ł����A���l�ł����i�Ŏ�ɓ���̂ł����HD-112NFX�̊ԈႢ���ȁH
> �i�X�}�z�ƃA���v�́j�ڑ����@�Ƃ��ẮA��ʓI�ȃI�[�f�B�I�P�[�u���i3.5mm?)���l���Ă��܂����B���̐ڑ����@�ł͉��̗��������肵�܂��ł��傤���H
> Bluetooth��Wifi�Őڑ��ƂȂ�ƁA�����Ƃ������Ƃ������ĉ����������Ă��܂��̂ł�...�Ƃ����s��������A
�A�i���O�P�[�u���ł̐ڑ��Ƃ������Ƃł��傤���B
���̏ꍇ�A�X�}�z���Ńf�W�^������A�i���O�ɕϊ������̂ł����A�X�}�z��DAC�@�\�͉����Nj��Ƃ����ʂł͕s���Ȃ悤�Ɏv���܂��B
�X�}�z�ƃA���v�̃A�i���O�P�[�u���ڑ��i�L���ڑ��j�����AAirPlay�iWi-Fi�ڑ��j�̕����������ǂ��Ɗ����邩������܂���B
���k��Bluetooth�iSBC�AAAC�j�`���͉��������O����܂����A
Wi-Fi�ڑ��ł̔k�i�܂��͉t���k�j�`����L���ڑ��Ɣ�ׂ��ꍇ�A���������ʐM���萫�̕������O�����̂��Ǝv���܂��B
> �EUSB�ł̐ڑ����l���Ă���̂��H
> ��艹���ǂ��ق��̐ڑ���I���������ł��B
USB�ڑ��ƌ�/�����f�W�^���ڑ��ł́A���͉����̈Ⴂ�͍l���Ȃ��Ă悢�Ǝv���Ă��܂��B
�A���AUSB�ڑ��ƌ�/�����f�W�^���ڑ��A���邢�͌��P�[�u���ڑ��Ɠ����P�[�u���ڑ��ł͉������Ⴄ�Ƃ�������������̂ŁA�����̓X���傳�M������̂�I�����Ă��炤�ق��Ȃ��ł��ˁB
> �p�\�R���ɐڑ����邱�ƂƁA�X�}�z��ڑ����邱�Ƃ��ł�������̂ŁABluetooth��Wifi�̋@�\���Ȃ��Ă����v�ł��B
Wi-Fi�܂߃l�b�g���[�N�@�\�͕t���Ă��������l�I�ɂ͕֗����Ƃ͎v���܂��B
�E����l�b�g���[�N���PC��NAS�̉������Đ��ł���
�ESpotify���̃X�g���[�~���O�Đ����ł���
�E�X�}�z�A�v���ł̑��삪�\�i���}�n���ƁuMusicCast�v�j
etc.
���\�Z50,000�~��R-N303�i���i�R���ň����i\27,820�j��I�������ꍇ�́A�X�s�[�J�[�ɉ�c�z����22,000�~�ł��ˁB
�EDALI SPEKTOR2�@\29,650
�EYAMAHA NS-B330�@\30,653
���������r�Ώۂɂ͂Ȃ肻���ł���������Ɨ\�Z�I�[�o�[�ł��ˁB
�i�Q�l�jhttps://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000403654_K0001015801_K0000973456_K0001054500_K0000815792&pd_ctg=2044
�X�s�[�J�[�̋��e���̘͂b�́A���̕��̃A�h�o�C�X�̂Ƃ���ł��B���ʂɎg���͈͂ł͋C�ɂ���K�v�͂���܂���B
�C���s�[�_���X�i���F�I�[���j�̘b�ł����A�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X���A���v�̑Ή��C���s�[�_���X�ɓK�����Ă����OK�ł��iD-112EXT��6���AR-N303��AorB�F6���ȏ�Ȃ̂�OK�j�B
�����ԍ��F23215204
![]() 2�_
2�_
2020/02/07 21:28�i1�N�ȏ�O�j
���j�t�ł�����
���̂����߂�
DAC�FS.M.S.L Sanskrit 10th D/A�R���o�[�^�[
��10,530-
�A���v�FFOSTEX�@AP20d
��14,573-
�X�s�[�J�[�FONKYO D-112NFX
��20,000-
�v�F��45,000-
�����i�͑S�ăA�}�]��
�X�^���h�F�c��̗\�Z��5000�~���炢�Ŕ��������
PC�I�[�f�B�I�Ȃ�DAC����ASIO���炢�͎g���������ǂ��Ǝv���܂��BPC�I�[�f�B�I�̏ꍇ��PC��̃{�����[���͍ő�ɂ��ăA���v�ʼn��ʒ������ǂ��Ǝv���܂�����茳�ɒu����T�C�Y�̃A���v��DAC��I�т܂����B�����R���ł����ʑ�����o����l�Ƀv���A���v�@�\�t����DAC���I��ł��܂��B�f�X�N�g�b�v�ŏ��^�X�s�[�J�[�������Ƃ��Ă��X�^���h�͐�Ɏg���������ǂ��ł��B
D-112EXT�����ۂɎg���Ă��܂����x�^�u���Ə����������o���̂ł͉_�D�̍��ł��B
�����ԍ��F23215932
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���l�X�ȏ���A�h�o�C�X�������������肪�Ƃ��������܂��I�I
�݂Ȃ��璸����������ɃI�[�f�B�I��������Ă��������Ǝv���܂��B
�܂������₳���Ă����������Ƃ����邩�Ǝv���܂��A���̍ۂɂ͋X�������肢�������܂��I
�����ԍ��F23216357�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776
�y���@�����v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד��H�z
����̔h���ŁA�{�X���b�h�𗧂Ă����Ă��������܂��B
�f�W�^���`�����l���f�o�C�_�[�iCDV�j�A�Ⴆ�� DBX VENU360 2�䗘�p�̃X�e���I�S�ш敪���A�Řc�܂Ȃ��͈͂Łu��Ɂv�Ȃ�ׂ��������C�����x���� CDV���o��܂ŏ��������A���̌�A�e�p���[�A���v�֓��͂��钼�O�ɁG
�P�C�ш斈�̍��E�o�����X�����ƃA�b�e�l�[�^�[�i�����{�����[���j�����A
�Q�D����ɑS�ш擯���̃}�X�^�[�{�����[�������i���������ĂW�A�{�����[�������j�A
���A���i�ʂɍs�������ƍl���Ă���܂��B�@
�܂�A���ׂĒ������ݒ��́A�V�X�e���S�̂̉��ʒ����� �Q�D�̃}�X�^�[�{�����[���P�ōs���Ƃ��������ł��B
(�ŏ㗬�� CDV�q���O�̃v���A���v�ł͉��ʒ����͍s�킸�A�Œ�n�C���x���� CDV�ւȂ��܂��B�j
CDV����̓o�����XXLR�ŏo�Ă��܂����A�p���[�A���v�ւ̓��͂�XLR�ł��̂ŁA�P�D�A�Q�D�̑S�i���o�����X��H�ŏ����������̂ł��B
�����A�P�D�̌ʒ�����ɁA�P�D�̂S�̃A�b�e�l�[�^�[�i�����{�����[���j���A���̌ʐݒ荷���ێ������܂܁A�A�����ď㉺�ɓ�������Ȃ�A�Q�D�͕s�v�ƂȂ�܂����A�P�D�̃o�����X�ƃA�b�e�l�[�^�͕s�p�ӂɓ������Ȃ��悤�ɒ����Œ肵�Ă����āA�Q�D�̃}�X�^�[�{�����[���ɓ��������A�悳�����ɍl���Ă���܂��B
���ɍ����ȃo�����X�R���g���[���[���A�b�e�l�[�^�[�i�X�e���I�j�̑g�ݍ��킹���S��p�ӂ��A���̌�ɁA����܂����ɍ����ȂW�A�̌����{�����[���i�A�b�e�l�[�^�[�j���g���Ύ���ł������ɂ��v���̂ł����A���܂��p���������ɁA����������������āA�P�D�Q�D������������@�A�K�ȒP�̕��i�i��L�b�g���i�j��g�ݍ��킹����@�A�Ȃǂɂ��Ă������A�����������肢�\���グ�܂��B
�iCDV���̊e�ш惌�x�������@�\�́A��U���Ȃ荂�߂Őݒ肵����A�����͊�{�I�ɌŒ肵�ĐG��Ȃ��A�Ƃ������j�ł��B�j
���ꂪ�����ł���G
�E�[�n�[(WO)�A�X�R�[�J�[�iSQ)�̋쓮�ɂ́A�\���ȋ쓮�͂����������i�ʃp���[�A���v�Q����A
�c�C�[�^�[�iTW)����уX�[�p�[�c�C�[�^�[�iST�j�쓮�ɂ́A������o�́i�����d�́j�ō��i�ʓ����p���[�A���v�Q����A
���ꂼ�ꗘ�p����v��ł��B
![]() 0�_
0�_
�u�W�A�{�����[���v�A�u�P�O�A�{�����[���v�A�u�Q�Q�A�@�{�����[���v�@�ȂǂŌ�������ƁA�������Ƃ��l���Ă���l�́A����������悤�ł��B�F����A�����H�삵�Ă�����悤�ŁA���Ȃ�~�����������ł��B
���ȕւɁA�d�q�I�Ɏ���������@�ȂǁA���肻���Ɏv���̂ł����A�A�A�A�@��낵���������A�������������B
�����ԍ��F23181316
![]() 1�_
1�_
dualazmak����A������
��U�N���[�Y���ꂽ�̂ŏo�����ꂽ���Ǝv���Ă���܂����B
�����Ȑړ_���A���A�b�e�l�[�^�[�Ƃ��S�Đ��҂��l�b�g�ɏグ�Ă����肵�܂��B
�A���o�����X���o�����X��H�AA/D�ADAC�A10�N���炢�O�ɂ͎�����悭����Ă��܂����B
����ł����߂�ƁA���G�����čs���A���Ԃ������邵�Ϗグ��Əo����o�J�ɂȂ�܂���B
�o�������̂������o�Ȃ�������A�m�C�Y�����Ȃ�������ŃI�V�����g���đΏ��̊������Ȃ��Ǝ��ł��܂��B
�������̋@�킪��荞�܂�Ă����̂Ƀo�����X�������ꂽ��A�悭�Ȃ�ۏ�����܂���B
���Ȃ�A�̂߂荞��ł���Ȃ�̉���肪�o����̂�10�N���炢������Ǝv���܂��B
�����̖ړI�Ɉ�ԋ߂��͈̂ȉ��ł́H
�A���v�̃{�����[����傫�ڂɏグ�āA
VENU360�̓��͒����Ńt���r�b�g�߂��ɂ��������A
�i�r�b�g�����͔������Ȃ��j
�o�͒����Œʏ퉹�ʂɂȂ�悤�Ƀp���[�֑��荞�ށB
�i�A�i���O�Œ��������j
����Ă��Ȃ��̂̓o�����X���͂Ȃ̂ŁAE-460��E-480�ɂ���B
VENU360�̓��o�͒����͈͂��L���̂͂悢�����̌�Z�������Ǝv���܂��B
�iDF-65�ł����o�͂łP�i���Ƃ������Ă��邾���ł��j
�����ԍ��F23181325
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����A�����́B
�C�O�o���́A�Q���͂��߂��牺�{�܂łł��B�@
���̍ۂɂ́A�č��ł̃}���`�A���v�������A�����T���A�Ǝv���Ă��܂��B
�{���A�C�V�m���{�̓X���l�Ƃ��A�˂�����ł��b���ł����̂ł����A�f�W�^��CDV�ւ̓��͂ł́A�����Ń��C�����x���𗎂Ƃ������ʂ��i��ƁA�ǂ����Ă��r�b�g�������������₷���A���ꂪ�ő�̖��A�Ƃ̂��ƁB�@�������ADF-65 �ł�VENU360 �ł��A�������Ƃł��B
���̃l�b�g�����ł́A�v���A���v��v�����C���A���v�Ń{�����[����H��ʂ�Ȃ� REC-OUT �[�q������Ȃ�A�������� CDV�֓��͂���̂��x�X�g�ł��A�Ƃ̃R�����g���U�����Ă���A�����Ă���܂��B
�A�L����DF-65�J���҂��A������ĔF�����Ă���A�ŋ߁A���͒i�̃Q�C�����i��������j�����グ���炵���ł����A����ł������v���ōi���ď����ʂŒ����Ƃ��ɂ́A�ǂ����Ă������ɉ��������邻���ł��B
CDV�����S�Ɂu�ʉ߂��Ă���v�A�e�ш斈�̍��E�o�����X�����ƌ��������A�����đS�̂̃}�X�^�[�{�����[���R���g�����A���s�����Ƃ����z�I�ł���A���ꂱ���������i�ʂȃv�����C���A���v���g�����Ƃ��l�����ő�̗��R�ł��B
����ɁA�ł��p�ɂɑ��삷��y�V�X�e���S�̂̉��ʒ����z���A���A�ǂ��ł�邩�H�H�A����� �yCDV�ʉߌ�ɁA�ЂƂ̃{�����[���_�C�A���ōs���ׂ��I�z�A���������Ă݂����̂ł��B�@
����ɁA�e�ш斈�̃��x���i�����j�����ƍ��E�o�����X�������A�yCDV�ʉߌ�Ɂz�A�ȕւɌʃ_�C�A���ł�肽���̂ł��BCVD���́A�W�ӏ��̃��x�������i���E�o�����X���������˂�j��p�ɂɂ�邱�Ƃ́A��ɔ��������̂ł��B
�}���`�`�����l�������`�ŁA���̕����Ŋ����ɐ�������Ă�����X���A������悤�ł��B
���Ȃ݂ɁA�����̃v���A���v�Ƃ��ẮA�C�V�m���{����̗�̃p�b�V�u�v���A���v�W���^�i���͂��o�͂��ARCA or XLR�ʼn\�j���g���āA�قڌŒ�̃n�C���x����XLR�o�����X�� CVD�֓��͂��邱�Ƃ��A���݂̗D��I�����ł��B
�����̃A���v�Q�A����TW, ST �쓮�o�����X�\���A���v�́A���o�͂ō����\�ȃA���v���C�V�m���{����œ����������Ă����������Ƃ�����ɓ���Ă���܂��B�@SQ�쓮�p���[�A���v���A�����ɍs�������m��܂���B�@���̂�������A�{���A���������k�ł��܂����B�@WO�i��SW�j�̋쓮�ɂ́A���ʁAE-460 �̃p���[�����g�����j�ŁA�C�V�m�̓X���l���A���������D�G��E-460 �������Ă���Ȃ�A��������ׂ��ł��傤�A�Ƌ��ł����B
�ȏ��z�肵�āA���̃X���b�h�ł́A�uCDV�ʉߌ�v�́A���Ȃ�n�C���x���ȃA�i���O���C���M���ɂ��āA�p���[�A���v�֓��͂��钼�O�ɁA
�P�D�e�ш悲�Ƃ̍��E�o�����X�����ƃ��x�������A
�Q�D�S�̂̃}�X�^�[�{�����[�������A
���ǂ̂悤�Ɏ����ł��邩�A�ł��Ȃ����A�ɓ������ď����������ĉ������B
�Ȃ��A���E�̓���SP���j�b�g�Ԃɂ����Ă��A���E�̔\�����A���ɔ����ɂł͂���܂����A�قȂ邱�Ƃ�����͎̂��ۂɌo�����Ă���܂��̂ŁA���Ƃ��ẮA�u�e�ш斈�̍��E�o�����X�����v���A�K�{�Ƃ��Ă���܂��B�@�ш斈�ɒP�ƂŖ炵�āA�T�_��ʂ������ɒ������邱�Ƃ́A���ɏd�v�ł��B�@������A�P�D�Q�D������A�ώG��CDV�ݒ��G�炸�ɁA�ȒP�ɔ��������\�ł��B
�����ԍ��F23181487
![]() 0�_
0�_
dualazmak����A����ɂ���
���v�����C���A���v�Ń{�����[����H��ʂ�Ȃ�
�� REC-OUT �[�q������Ȃ�A�������� CDV��
�����͂���̂��x�X�g
�Ⴂ�܂��A�����o�͂����̂܂�CDV�֓����̂��x�X�g�ł��B����Ƃ���CD�v���C���[�͕��ʂɂ��邵�APC������o���܂��B�n�C���]�ł����9624�~�܂�VENU�ł������A�v���A���v�ł͂Ȃ���ւ�BOX�ɂȂ�܂��B
���A�L����DF-65�J���҂��A������ĔF�����Ă���A���ŋ߁A���͒i�̃Q�C�����i��������j
�������グ���炵��
VENU360�Ȃ���̓Q�C���ŊȒP�ɂł���b�ł��B
���P�D�e�ш悲�ƍ��E�o�����X�����ƃ��x������
���Q�D�S�̂̃}�X�^�[�{�����[������
�����E�̔\�����A���ɔ����ɂł͂���܂����A
���قȂ邱�Ƃ�����͎̂��ۂɌo�����Ă���܂��̂ŁA
���R�̂��Ƃł�
VENU360�Ȃ�w�e�`�����l���o���o���ɔ������x�������\�x�ŃA�i���O���ł܂��B���̒��Ń��x���������ă��[�C���s�[�_���X�ŏo���̂ƁA���̊O�Ńp�b�V�u�ŗ��Ƃ��̂ł͔��̒����L���ł��B�p���[���O�ł��p�b�V�u�ʂ�����n�C�C���s�[�_���X�ŒZ���p���[�ɂȂ��ł��m�C�Y������Ղ�����ł��B
���肽�����͖��Ȃ��ƌ����Ǝv���܂����ǁB
��������Ȃ�A�p���[�A���v�Ɉ��������ƁA�����Ń��^�A�b�e�[�l�[�^��g��ŗ��Ƃ��܂��B
�܂��ŏ��\���Ŏn�߂đS�̑����킩������A�@�艺���������悢�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23181734�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����A���͂悤�������܂��B
�P�D�}�X�^�[�{�����[���R���g���[���́A�ǂ��ł��ׂ��A�Ƃ��l���ł��傤���H�@���́ACDV�ʉߌ�ɂ����j�ł��B
�Q�D���������ʂŒ��������ꍇ�ACDV�̎�O�ōi��ƁA�ǂ����Ă��r�b�g�������������₷���Ȃ�܂��B���̂��߁A���������ʂŒ����Ƃ����ACDV�ʉߊ����܂ł͔�r�I�u�剹�ʁv�ŏ������������̂ł��B
�R�D�����̉��ʂɉ����āA���̂��т� DCV�̓��̓Q�C���i��o�̓Q�C���j������̂́A�����I�ł͂���܂���B
�i�钆�ɋɏ����ʂŃ����[�g�\�������Ƃ�����A�ƑS�̂��k����悤�ȑ剹���Ńt���I�[�P�X�g���̍ŋ��t��p�C�v�I���K�������Ƃ�����܂��B�j
�S�D�O�ɂ��\���グ�܂������A���́A�y�Ȃ�W�������ɉ����āA�ш斈�̃��x����A���E�o�����X���A���܁A���������p�ɂɁA�������܂��B���́A������ALC�l�b�g���[�N�{�b�N�X�̂R�i���E�łU�j�̤�r�p�C�s�v�C�r�s�@�A�b�e�l�[�^�[�ł���Ă��܂��B�@����ɁA�v�n�̃��x���ƃo�����X��������ƁA���v�W�g�̍��E�o�����X�ƃA�b�e�l�[�^�[�Ƃ����I�ɔ��������邱�ƂɂȂ�܂��B�@������A�S�ē���I��CDV�����̐ݒ�ōs�����Ƃ́APC����̃R���g���[���ł��A�������Q���NVENU360 �ɂ��ĕʁX�ɍs�����Ƃ́A�ώG�őς����܂���B
���Ȃ݂ɁA����AHarman-DBX�̕č��{�Ђɂ��m�F���܂������AVENU360 �̂o�b�R���g���[���\�t�g�ɂ́A�Q���A�g���đ��삷��@�\�͂���܂���B�P���ݒ��A�ݒ���e��PC�ɋL�^���A�Q��ڂł��̐ݒ�p�����[�^�[��ǂݍ��ނ��Ƃ͉\�ł����A����ł͍��E���S�ē����ݒ�ɂȂ�̂ŁA���E�̈قȂ�������́A�ǂ����Ă��ʂɂW�`�����l���̊e�p�����[�^�[��G��K�v������܂��B
���݂̃V�X�e�����o�C���C�������O�ڑ��́u�S-way �N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�{�R�A�b�e�l�[�^�[�v�O�t���{�b�N�X�o�R�@�ł��傢�ɖ����ł��鉹�����y����ł���܂��̂ŁA����ɉ��P�����҂��ă}���`�A���v�V�X�e���������̂ł���A���̓���I�Ȕ������̗e�Ղ��A�ȕւ��A�܂����̎g������A���܂߂āA���Ȃ�ו��ɂ��S���Čv�悷��K�v������ƍl���Ă���܂��B
�Ƃ������ƂŁA���̃X���b�h�ł́ACDV�ʉߌ�̍��E�o�����X�����ƃ��x�������A�ɓ��������Ă��������܂��B
�����ԍ��F23181932
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
�����ł́A���̃X���b�h�̃^�C�g���ɓ��������ĉ������B
�}���`�A���v�\�z���@��i�ߕ��̘b�ɂȂ�ƁA�O�X���b�h�ƑO�X�X���b�h�̋c�_�Ɣ��U�ɋt�߂肵�āA���̃X���b�h�̎��₩��O��܂��B
�����ACDV�ʉߌ�̍��E�o�����X������x�������A����у}�X�^�[�{�����[���R���g�����A���{���ɖ��d�ŁA���I�ł���A�Ɣ[���ł���A������������āA���̃X���b�h�͏I���������܂��B
�����ԍ��F23181944
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����́A�u�ד��v���ƌ��_����Ă����܂����A���́ACDV�ʉߌ�Ƀ}�X�^�[�{�����[���R���g���[�����s���A���̌�i�̂S��̋쓮�A���v�́A�����\�ȃv�����C���A���v�iXLR���́A������i�ʂȃo�����X�����Ɖ��ʒ����𗘗p�j�ł����������A�ƍ��ł��{�C�ōl���Ă���܂��B
����Ȃ�A�����ڎw���ACDV�ʉߌ�̃}�X�^�[�{�����[���R���g���[���ƁA�ш斈�̍��E�o�����X�������{���x�������A����Ɋe�ш斈�̃~���[�g�������A�ȕւɍs�����Ƃ��ł��܂��B
�Ƃ����킯�ŁA���̃X���b�h�ł́A
CDV�ʉߌ�́u�W�A���}�X�^�[�{�����[���R���g���[���v
���A�ő�̉ۑ�ł��B
�����ԍ��F23181964
![]() 0�_
0�_
�F����A
�U�A�܂łȂ�A�������^�C�v�i�H�j�ŁG
http://www.san-ei-denpa.com/jyucyuu/009/indexi.html
������悤�ł��B
�W�A�������ł��邩�ǂ����A�����Ă͌��܂����A�����I�ȕi�ʂ͋^��ł��̂ŁA���Z�̂��ӌ�������������K���ł��B
�ėp�^�C�v�Ȃ�A�W�A���A����܂��B
http://www.san-ei-denpa.com/jyucyuu/002/indexi.html
����ɒ��ׂČ��܂����A����ȊO�ɂ��u�A���{�����[���v�Ȃǂɂ��āA�������A������������������K���ł��B
�����ԍ��F23181981
![]() 0�_
0�_
�u�o�����X�����_�C�A���v�@�ɂ͍S�炸�ɁA�ш斈�ɁA�܂����E�ɍ��i�ʃA�b�e�l�[�^�[���g���i���v�W�j����Ńo�����X�ƃ��x�������Ă���A�W�A���A�b�e�l�[�^�[�֓����A�̂��@�B�I�A�z���I�ɂ͍ł��V���v�������m��܂���B
�{�b�N�X������Ȃ�A�u�W�̑ш�ʃA�b�e�l�[�^�[�i�S�ш捶�E���ꂼ��j�@�{�@�W�A���}�X�^�[�{�����[���v�@�Ƒz�肵�Ă���܂��B
�Ƃ����킯�ŁA�����p�ŋƖ��p�̃A�b�e�l�[�^�[�ɂ��āA���̃T�C�g
http://www.san-ei-denpa.com/toriatukai/v_attenuator.html
�����Ă���܂����A�ǂꂪ�œK�Ȃ̂��A�Ȃ��Ȃ����f������ł��B
���̕��ʂɏڂ������̂����������҂��܂��B
�����ԍ��F23182011
![]() 0�_
0�_
���`�����l���̉��ʒ����ł����A���@�Ƃ��Ắ@
1.�d�q�{�����[���i�o�b�t�@�A���v�����j
2.�ϒ�R �{ �o�b�t�@�A���v
3.��R�ؑ֎��A�b�e�l�[�^ �{ �o�b�t�@�A���v
4.�g�����X��
�@�̂S�������l�����܂��B
�@(�l�I�ɂ�)���ɂȂ�قǁ@�����͏オ��܂����A��p�Ǝ�Ԃ��{�����܂��B
�@�l�͂P�`�R�܂ł�����Ƃ��Ƃ�����܂��B
�@��Ńg�����X���ȊO�̓o�b�t�@�A���v�t���Ă܂����A�����Ȍ`���̃��C���A���v���������Ă��܂������A���i�ʂȉϒ�R�g���Ă��o�b�t�@�������Ɓ@���͐��^�ł��ꂢ�Ȃ�ł����A�����ׂ��ė͋����������ĉ��������܂��B
�@�ϒ�R��ʉ߂���ƁA�O�i�̃A���v�̋쓮�͂���R�̂ɐH���Ďc��J�X�݂����ȐM���������̉ϒ�R�`�p���[�A���v�܂ł̃P�[�u���ɗ���쓮�͕s��(���ԗe�ʂ̏[���d)�ɂȂ邩�炾�ƍl���Ă��܂��B
�@8ch�o�b�t�@�A���v���K�v�ƂȂ�Ɨ��h�ȑ��`�����l�����C���A���v�ł��ˁB
�@�g�����X�́A�G�l���M�[���قڕۑ������܂ܐM���ϊ�����̂Ł@���͐M���̐U�������ύX�����ā@���̂Ԃ�d���o�͔\�͂͑����̂ōi���Ă������������o�b�t�@�A���v�v�炸�ł��B
�@�P����l�̌o�����q�ׂĂ�����
�P�D�d�q�{�����[���̓o�b�t�@�������Ă���̂ł��Ȃ�y�ɂȂ�܂��B
�@���������[�J�[�������ʂ�ۏ��Ă���Ă���̂ŃM�����O�G���[�̐S�z������܂���B
�@�`���l�����₵�Ă�������Ȃ������ōςނ̂ŋ@�\�I�ɂ͕���̂��悤������܂���B
�@�����炭����̔Еz���Ă��邱�̊�Ȃ@�܂���4ch�`�����f�o�p�Ȃ̂ňꖇ�ōς݂܂��B
http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/EVC3318Manual.pdf
�@�ƁA�悳�����Ȃ�ł��������I�ɂ�CP(�R���_�N�e�B�u�v���X�`�b�N)�{�����[���ɕ����܂��B
http://www.easyaudiokit.com/bekkan/offm20080503/offm.html
�@�ȑO�A�����炭����(�q������j���Q����������I�t�~�Ł@�ϋvOPAMP��r�������Ă̂�������Ƃ��ɁA�l�̓X�C�b�`��ւ����OPAMP�Q��ނ��ւ���������OPAMP��r��p�A���v���������ĎQ�����܂���(�I�y�A���v�̒�����ׁI�i���̂Q�j
�@���̃A���v�ɂ͓��������� CP2500���g�p���Ă��܂��B
�@�ڑ��ς�����A�d�q�{�����[�� CS3310��PGA2311���g����悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���̎��͂V�l�Ł@���S�Ƀu���C���h�Ŕ�r������ł����A���ʂ�
�@15�@�풆 CS3310��9�ʁ@PGA2311 ��14�ʂ̃u�[�r�[�܂ł����B
�@�����Ă��Ė��炩�ɁA�R���v���b�T�[�����������悤�Ȋ����ł����B
�@���̔�r�ȗ��@���傢�Ɠd�q�{�����[���ɂ͖l�I�ɂ̓l�K�C���[�W�����Ă܂��B
�@�V����MUSES�̓d�q�{�����[���ɂ͊��҂��Ă����ł����@�܂������Ă܂���B
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06469/
�@�Q�ȍ~�����낢�뒷��/�Z������܂����@��ق�
�����ԍ��F23182184
![]()
![]() 1�_
1�_
dualazmak����A����ɂ���
�ő剹�ʂŃr�b�g������U��܂����A�ȂƂ��ď����ʂ̃t���[�Y������܂��̂ŁA�����r�b�g�������Ă����ʂɕ����܂��B�����_�}���`���n�߂ĂȂ��̂Ƀr�b�g�����ɉߕq�ɂȂ肷���Ă�����悤�Ɋ����܂��B
�}���`�̃����b�g�̓��j�b�g�Ԃ̃^�C���A���C�����g��ƃA���v�̃��j�b�g�����ɂ��쓮�͑��傪�ƂĂ��傫���ł��B
�A�L�����r�b�g���������炷���߁A�����ɃQ�C�����グ�����炢�ŁA�o���Ƀ}�X�^�[�{�����[���̋@��͔̔����Ă܂���B���v���قƂ�ǂȂ��Ǝv���܂��B
�����ł��A�v����2V�o�܂����ʏ펎���ŃA�L���Ǝ����l����CDV�͓��o�͂�1Vp�Ńt���r�b�g�ɒ������Ă��܂��A����ł��\���}���`�̌��ʂ͏o�Ă��܂��B
����������Ă���X�ɂ悭�������l���͂���Ȃ̂ŁA�lj���E-270�Ȃ�A�A���A�b�e�[�l�[�^�[������̂��ד��Ƃ������ĂȂ����ے�����Ă��܂���B
�ŏ��\���ŃX�^�[�g���S�̑������������̃X�e�b�v�Ń��X�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�v���́A360�ƃA���v�A�ǂ�����A���A�b�e�[�l�[�^�Ŏg������̂ł��B
�n�߂�Ǝ}�t�������Ƒ傫�ȉۑ�ɋC�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23182213�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��BOWS����
���肪�Ƃ��������܂��B
��͂�A�d�q�{�����[���I�ȕ����A���낢�날��̂ł��ˁB
���܂���4ch�`�����f�o�p�Ȃ̂ňꖇ�ōς݂܂��B
��http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/EVC3318Manual.pdf
���ƁA�������Ƃ��l���āA����Ȋ�܂ō���Ă���l������Ƃ́A�����ł��B
���V����MUSES�̓d�q�{�����[���ɂ͊��҂��Ă����ł����@�܂������Ă܂���B
��http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06469/
������g���Ẳ�H�^��v�ɂ��傢�Ɋ��҂��Ă���܂��B
���肷���̍ۂɁA����ɂ��낢�낲�����������B
�����_�ŁA�ŗǂ̕��@�������Ă���A�C�V�m���{������܂߁A�ǂ����œ����Łu�W�A�A�b�e�l�[�^�[�{�}�X�^�[�{�����[���v�{�b�N�X������Ă����������Ƃ��l���܂��B
�����ԍ��F23182242
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
������������Ă���X�ɂ悭�������l���͂���Ȃ̂ŁA�lj���E-270�Ȃ�A�A���A�b�e�[�l�[�^�[������̂��ד��Ƃ������ĂȂ����ے�����Ă��܂���B
���肪�Ƃ��������܂��I
���Ƃ��A�t���I�[�P�X�g���ŋ��t�̉������A�����ʂŒ����Ƃ����A�����Œ����Ƃ����AS/N�I�ɂ͂Ȃ�ׂ������ł����Ăق����A�Ƃ����P���Ȕ��z�ł��B�@��U�\�z����������A�����͉̂����ł͂Ȃ����y�ł���A�Ƃ�����{���͕��ՁA�s�ςł��B
�������炭�A���̃X���b�h�̎�|�̒��ŁA�����������Ă������������A��낵�����肢�\���グ�܂��B
���̌�A�����I�ɔ��f���A�S�̍\���̍ŏI�g�тƁA�i�ߕ����A���炽�߂ďn���������܂��B
�����ԍ��F23182260
![]() 1�_
1�_
�P���ɁA��L�ł��B
���U�A�܂łȂ�A�������^�C�v�i�H�j�ŁG
��http://www.san-ei-denpa.com/jyucyuu/009/indexi.html
��������悤�ł��B
���W�A�������ł��邩�ǂ����A�����Ă͌��܂����A�B�B�B�B
�ɂ��āA�O�h�d�g�l����A�����������܂����B
��8�A�܂ʼn\�ł��B
��8CP2508-S(�V�[���h�t���j�W����R�lA5K,A10K,A50K,A100K�̏ꍇ�@�P��32,200�~(�ō�)�ł�
���W���O��R�lA2K,A20K�̏ꍇ�P��43,990�~(�ō�)�ł�
���[����2�������ł�
�������ł��B
BOWS����̂��b���f���ƁA���ł͓d�q���ɗD�ʐ������肻���Ȃ̂ŁA���̂W�A���ɑ���\���͒Ⴂ�Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F23182271
![]() 0�_
0�_
�u�}�X�^�[�{�����[���v�@�Ō������Ă�����A���
�S�����l�̂��Ƃ��l���āA����Ă������������悤�ł��B�B�B
http://a011w.broada.jp/gpae/pga.html
�����ԍ��F23182416
![]() 0�_
0�_
dualazmak����A����ɂ���
������������낻���ł��ˁB
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1230/044/amp.index.html
�����ԍ��F23182452�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
��������������낻���ł��ˁB
��https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1230/044/amp.index.html
���ɋ����[�����A���肪�Ƃ��������܂��B
����A�����ԍ��F23173470�@�Ŏ����Җ]�����A�����\CPU��őS�Ă̏������\�Ȃ͂��ATRINNOV ALTITUDE32 �̋@�\�S���{���ŁA������������悤�ȕ������ł��ˁB�@�K���o�Ă���Ƃ͎v���Ă��܂����B�@���ڂ��ăt�H���[�������Ǝv���܂��B�@�s�ꂪ����A���ł��ˁB
PC���́A�n�[�h�A�\�t�g���ʂƂ��������ӂŁA���b�������悤�ɂQ�Z�b�g�� Xeon �x�[�XPC-Workstation ���A�䂪�Ƃł��A����I�ɁA������������̂ɂ��A�g���Ă��܂��B�@�{���ɍŋ߂� CPU, GPU �̐i���͋��ٓI�ł��ˁB�@�摜�����A���������Aweb surfing �ȂǂȂǗl�X�ȏ��������ő��点�Ă��ACPU, GPU�@�p���[�I�ɂ͗]�T���\���ɂ���܂��B�i���́APC�Q�[���͂��܂���B�j
�����ԍ��F23182800
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����A�F����A
http://www.skaudio.jp/pro.html
�����Ă��܂����A�܂��ɑҖ]���Ă������̂��o�ꂵ�Ă������G������܂��B�@��������t�H���[�������ł��B
���ꂪ�g�����Ȃ��āA���`�����l���ɂł����R�Ƀ`�����f�o�����i���R�A�ʑ��A�^�C���A���C�������g�A�f�B���C�Ȃǂ����R���݁H�j�ł��āAASIO �h���C�o�[�o�R�Ńf�W�^���o�͂ł���Ȃ�ADAC���䂩�ADAC���ڂ̍��i�ʃv�����C���A���v�𐔑�p�Ӓm��A�����ڎw���Ă���}���`�A���v�����A�����Ƃ����Ԃɂł��Ă��܂��̂����m��܂���B
�����ԍ��F23182823
![]() 0�_
0�_
�܂������ł͂���܂����A�n�C�G���h�I�[�f�B�I�@��Ɋr�ׂ�Aꡂ��Ɍ����I�ȉ��i�ł��ˁB
http://www.skaudio.jp/audioif.html#etpdac
CPU�`�����l���f�o�C�_�[�\�t�g�A�A4-way�}���`DAC �Ȃǂ��S�đ����Ă���悤�ȁA�A�A�A
������̐��E�ɍs�������A�����̂����m��܂���ˁB
������ƁA���ߑ������Ȃ��璭�߂Ă���܂��B
�����ԍ��F23182874
![]() 0�_
0�_
http://www.skaudio.jp/audioif.html#etpdac
��VT-EtPDAC�@�����Ă���ƁA�e�p���[�A���v�̔\�͂₻�̕��U�̊ϓ_������A�܂��Ɏ���SP�Q���쓮���邽�߂ɓ��������悤�� DAC����4-way�}���`�`�����l���A���v�ł��ˁB��
���̍����\PC-Workstation �ɁA
Dante PCIe-R Soundcard�G
http://www.skaudio.jp/pcadapter.html#pcie-r
�����āA�����̃\�t�g���d����ŁALAN�P�[�u���P�{�� VT-EtPDAC �Ɍq���A���z�I�Ȍ��ݍō��� �S-way �}���`�A���v������������i�H�j�A�Ƃ����C�����Ă܂���܂����B
����A�{���Ɂu�ڂ���v�ł��B�@
�ǂ����āA���܂ŁA���Ă��Ȃ������̂��ƁA���Ȃ�����ł��B
�ǂ����A DF-65 �P����x���A����ȉ��̗\�Z�őS�������̂����A���@��x�A���̏��X����Ƃ悭���k���Ă݂����Ǝv���܂��B�@
��͂�A���\�j�[�̉����Z�p�҂́A�����B�B�B�Ƃ������A���i�B�j���]��ł�������𗝉����Đ��肳��Ă���A�ƌ��܂����B
���̉�Ђ��A�����ɔ��W���Ă���邱�Ƃ��A�S�����]���܂��B
����ł́A���肷��Ȃ�A��Ђ������ɑ������Ă���ԂɁA���߂ɓ����ׂ����Ƃ��A�v���n�߂Ă��܂��B
�����ɂ悵����A��L�A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F23182962
![]() 1�_
1�_
�X����̘A���A�������������B
�����ɂ悵����A
mpp.dsp �\�t�g�E�F�A�̏Љ�Ǝd�l�A���Ă��������܂����H
�����ł�;
http://www.skaudio.jp/software.html#mpp.dsp
�S�đ����Ă���悤�ȁA���
�����ԍ��F23182979
![]() 0�_
0�_
dualazmak����skaudio���[�h�ɓ������悤�Ȃ�ł����A�]���H����i�ގ��̒m���Ƃ��Ēm���Ă����������ǂ��Ǝv���̂ŏ����Ƃ��܂��B
�@1.�d�q�{�����[���i�o�b�t�@�A���v�����j�@
��2.�ϒ�R �{ �o�b�t�@�A���v
�@3.��R�ؑ֎��A�b�e�l�[�^ �{ �o�b�t�@�A���v
�@4.�g�����X��
�@�ϒ�R��������|�s�����[�ȕ��@�ł��B
�@C�̎��^�ɒ�R�̂��h�z����Ă��ā@���̏�𐠓��q���������ŁA�e���j�b�g�d�˂ĂȂ���@���`�����l���Ή��\�ł��B
�@���̕����̓�����
�E���`�����l���i�͎��v�����Ȃ��A�����@�����ĉ�]�g���N���K�v�ŏd���Ȃ�B
�E�i�������ɁA��R�̂̓h�z�������ɂ���]�p�������ł��e���j�b�g�Ō��������قȂ�B���ɍi�������i�M�����O�G���[�j
�E�o�N�ω��Ő����q�ƒ�R�̂̊ԂɎ_�����Ȃǂ��`������A�ƃK���K���G��������i�K���I�[���j
�E��R�̂Ƃ��ẮA�J�[�{������ʓI�����A���i�ʃ{�����[���ł̓R���_�N�e�B�u�v���X�`�b�N(CP)���g�p�����B
�@CP�́A�����ɗD��A�o�N�ω��ɂ��������A�������̒��ӓ_�������B
�@��
�@�C�_�����ɒ��ӏ���������܂��B
http://www.kaijin-musen.jp/34.html
>��舵����̒��ӁF�@�M�Ɏア�f�ނŏo���Ă���̂ŁA�n���_�t�����̔M�̊|�������ɋC�����Ă��������i�ڈ��͒ቷ�n���_��3�b�ȓ��j�B �܂��A�U���m�C�Y���E���ꍇ������̂ŁA�m�u�i�c�}�~�j�̓v���X�`�b�N���𐄏��������܂��B >�\����A���������x���E�A�b�e�l�[�^�[�ȊO�̗p�r�ɂ͎g���܂���B
>�m�u�i�c�}�~�j�͗U���m�C�Y�h�~�̂��߁A�v���X�`�b�N���𐄏��������܂��B
�@�C�_�����ł��̌������Ƃ���A�����ǂ��Ƃ������Ƃʼn��t���[�̋����n���_�Ƃ��Z�_�̍����n���_���g���l�������Ă��ŁA�x�������Ă�����Ă܂��B�����苤���n���_�ŃT�N�b�Ƃ���Ԃ�ɂ͖��Ȃ��Ƃ������Ƃł����B
�@�l�͉����ƒl�i�Ƃ̗��Ƃ����Ł@2CP2500���悭�g���Ă܂��B(�ݐ�10�ȏ㔃���Ă�)
�@�s�̕i�Ő��\���~�N���X�Ŏg�����x������Ȃ��ł��傤���H
�@�����8�A�{�����[�����Ƃ��Ȃ�ǂ������ł��B
�@�o�b�t�@�A���v�Ɋւ��Ă͌�ق�
��3.��R�ؑ֎��A�b�e�l�[�^ �{ �o�b�t�@�A���v
�@23�ړ_���̐������[�^���X�C�b�`�Œ�R�l���ւ�����@�Ł@�ߋ���3��ނقǍ��܂����B
�@���_
�@�@�����͍ō�
�@�@�o�����X�^�C�v��H�^�A�b�e�l�[�^���̓���ȃA�b�e�l�[�^������B
�@�@�M�����O�G���[�����Ȃ�(��������R��I�ʂ����)
�@�@�K���I�[���ɂȂ�Ȃ��B
�@�������A���낢�댇�_������܂��B
A.�f�J�C
B.����
C.���i���B�������ւ�
D.���̂ɂ��̂�������Ԃ�������B
�@A.���[�^���X�C�b�`�̒[�q�ɒ�R����������̂ő傫�ȃ��[�^���X�C�b�`�g���܂��B���`���l�����ƃo�J�ł����Ȃ�܂��B
�@B.�����x���[�^���X�C�b�`�͍���Ă��郁�[�J�[�����Ȃ������o�Ȃ��̂ō����ł��B
�@�@����Ƒ����̒�R���K�v�ł��B
�@�@23�ړ_�̃A���o�����XL�^�A�b�e�l�[�^���ɂ́@(23-1)x2x2=88�@��R���K�v�ł��B
�@�@�����ɒ�]�̂���DALE�̖��U��������R�g�����Ƃ���Ɓ@\500@�Ƃ��ā@��R������\44,000 �s���܂��B
http://www.kaijin-musen.jp/45.html
�@�`�b�v��R�g�����A�b�e�l�[�^������܂����A��R�͑傫���ďd���ق��������ǂ��X��������܂��B
�@C.�A�b�e�l�[�^�̌v�Z���Œ�R�l���o���ł����A�s�b�^���̒�R�̍ɂ��L��Ƃ͌���܂���B
�@�@���肷��ƍŒ�w�����@1000�Ƃ����C�Ō����Ă���̂Œ��B��T�����ƂɂȂ�܂��B
�@�@�܂��A��R�l�̐��x�������ꍇ�A�����w�����đI�ʂ��Ă��ƂɂȂ�ƃR�X�g�����B���I�ʂ������ւ�ɂȂ�܂��B
�@D. ���܂�F�m����Ă��܂��A��R��ւ����̃A�b�e�l�[�^�̖��́A�悭�g���|�W�V����������R�̃G�[�W���O���i�܂Ȃ����Ƃł��B
�@�V�i�̒�R�ɉ����M���𗬂��Ă�邱�Ƃɂ��U�����Ő������̃X�g���X�������Ă���G�[�W���O�͉ϒ�R�ł��K�v�ł��B
�@���̕����̃A�b�e�l�[�^�ł́A�ő�ɋ߂��|�W�V��������1����ꂸ�A�ʓd���Ȃ��̂Œ�R�͐V�i�̂܂܂ł��B�悭�g���|�W�V��������@�߂����Ɏg��Ȃ��|�W�V�����ɉƋ}�ɂ��Ȃ�Ă��Ȃ������o���肵�܂��B
�@�@���̖����y�����悤�Ƃ�����A�g�ݕt����O�̒�R���o���̏�Ԃŕ��ׂĐ�ɃG�[�W���O���Ă����̂��L���ŁA�l�͂��̂��߂ɒ�R�𐔏\�{�ɉ����M���𗬂�������������čŒ�100���ԃG�[�W���O���Ă���g�ݕt���Ă܂����B
�@�����88x2=176�ӏ��̃n���_���K�v�ł����A���̃n���_�t���ώ�������͂̋Z�ʂ��K�v�ł��B
�@�s�̂̃A�b�e�l�[�^�́@����Ȏ�Ԃ�����ĂȂ��̂Ŏ��삵���ق����[���������A�b�e�l�[�^�����܂����A��Ԃ�������܂��B
�����ԍ��F23183117
![]()
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�@�������ɖʔ������A���������z�[���I�[�f�B�I����Ȃ��ăv���I�[�f�B�I�ł��ˁB
�@�z�[���I�[�f�B�I����A�]���̑��u�Ɍq���Ȃ��Ɣ���Ȃ���ł����ALAN�����łȂ���PC������S�đ���A�����ā@�����̃A���v�ADAC�̂����q���Ȃ�...�z�[���I�[�f�B�I����h�����ꂻ���ł����A�v���I�[�f�B�I�ł͎s�ꐫ�����肻���ȋC�����܂��B
>http://www.skaudio.jp/audioif.html#etpdac
>��VT-EtPDAC�@�����Ă���ƁA�e�p���[�A���v�̔\�͂₻�̕��U�̊ϓ_������A�܂��Ɏ���SP�Q���쓮���邽�߂ɓ��������悤�� DAC����4-way�}���`�`�����l���A���v�ł��ˁB��
�@���������肪�������̂ł����A��_�@4�`���l���X�e���I�Ł@�d��7kg���Ă̂��J���߂���悤��...
�@�����͂ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁH
�����ԍ��F23183131
![]() 0�_
0�_
��BOWS����
��dualazmak����skaudio���[�h�ɓ������悤�Ȃ�ł����A
���₢��A�܂��܂��ł���I�@
���ƌ����Ă��A��p�I�[�f�B�I�v���Z�b�T�ւ�ASIO���͂́A192 kHz/24 bit ������̂悤�ł��B
�����Ƃ��A DBX VENU360 �Ȃǂ̃`�����f�o���g���Ȃ�A���������� 96 kHz/24 bit �ł��̂ŁA������ɂ��Ă� 2xDSD(DSD256) �����Ȃǂ́A�_�E���T���v�����O����K�v������_�ł͓����ł����B��
���Љ���悤�ɁA���́A���݁A4xDSD (DSD256)�����́AES9038PRO �`�b�v��USB-DAC �փl�C�e�B�uDSD streaming�ŏo�͂��Ă���܂�.�B�c�`�b�Ƃ��Ă� PCM 768kHz/32bit, DSD 22.6 MHz/ I bit �܂őΉ��ȋ@���DA�ϊ������Ă���܂����A����DA�ϊ���̉����ƁAS&K AUDIO�V�X�e�����p�ima�� 192 kHz/24bit�@�ł��傤�j�ɂ�����o���ł̉����i�����i�ʁj�ɁA������̗D��́A�ǂ��Ȃ̂��H�H�@���ۂɁA����SP�Q�̊��Ŕ�r�������Ȃ��Ƃ킩��܂��A���̂悤�Ȕ�r���\�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�lj��̖L�x�ȏ��A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B
����;
���l�͉����ƒl�i�Ƃ̗��Ƃ����Ł@2CP2500���悭�g���Ă܂��B(�ݐ�10�ȏ㔃���Ă�)
���s�̕i�Ő��\���~�N���X�Ŏg�����x������Ȃ��ł��傤���H
���@�����8�A�{�����[�����Ƃ��Ȃ�ǂ������ł��B
���@�o�b�t�@�A���v�Ɋւ��Ă͌�ق�
�́A���ɋM�d�ȏ��ŁA����Ȃ玄�ł�����H��ł������Ɏv���Ă��܂��B
��ŋ��L�����悤�ɁA�O�h��������ł́ACP2508-S�i�V�[���h�t���j�̂W�A���͓������Ă���邻���ŁA���i�����Ղ��܂����B
�g���Ȃ�A�W����R�l�̎d�l��OK�ł��ˁH
�ш斈�̃��x�������i�o�����X���������˂�j�̂��߂Ɏg���O�i�́i�W�A���q����O�́j�W���ACP2508-S �ł����ł��ˁH
�g���ׂ��d�����܂߂āA�o�b�t�@�A���v�ɂ��Ă��A��낵���������������B
��D. ���܂�F�m����Ă��܂��A��R��ւ����̃A�b�e�l�[�^�̖��́A�悭�g���|�W�V����������R��
���G�[�W���O���i�܂Ȃ����Ƃł��B
����A�����Ă݂�A�S�����̒ʂ�ŁA���ɔ[���ł��B�@�P�̖ӓ_�ł��ˁB�@���肪�Ƃ��������܂��B
���̃G�[�W���O�̓_�ł́A���_�[��R�����^�`�b�v���g���d�q���{�����[���́A�ǂ��Ȃ̂ł��傤���H
�����������肪�������̂ł����A��_�@4�`���l���X�e���I�Ł@�d��7kg���Ă̂��J���߂���悤��...�����͂ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁH
�����A���\�I�ɂ��A�r�W�l�X���f���I�ɂ��A�����^�₠�肩�ȁA�Ǝv���Ă��܂��B�T�E���h�{�[�h���� LAN�P�[�u���P�{�Œ����A�Ƃ������Ƃ́A���̃V�X�e���ł́A���̃}���`�A���v�̗��p����Ώ����A�Ƃ����r�W�l�X���f���ł��ˁB�@�T�E���h�{�[�h�ɂS�� USB 2.0 or 3.0 �|�[�g�����邩�A�܂��� PC�̑��� USB �|�[�g�S�|�[�g���g����悤�ɂȂ��Ă��āAASIO�h���C�o�[���S�g���āA�S��̂��D�݂� USB-DAC�֏o�͂ł���A���D�݂̃A���v�S����g����͂��Ȃ̂ł����A���������Ə����ɂȂ�Ȃ��A�Ƃ������f���̂悤�ł��B
��͂�A TRINNOV ALTITUDE36 �̋@�\��S�������Ă��������PC-�`�����f�o���~�����ł��B�B�B
�����ԍ��F23183365
![]() 0�_
0�_
��BOWS����
���S�D�g�����X��
�ɂ��Ă��A��낵���������������B
�C�V�m���{����́A��̃p�b�V�u�A���v�Q�́A����ɑ���������̂ł���Ɨ����͂��Ă���܂��B�������A���[�^�[���[�ؑփ{�����[�����܂߂āA����̓n�[�h�����������A�ƌ��Ă��܂����B�B�B
�����ԍ��F23183392
![]() 0�_
0�_
���������A���[�^�[���[�ؑփ{�����[�����܂߂āA����̓n�[�h�����������A�ƌ��Ă��܂����B�B�B
�ł͂Ȃ��A���[�^���[�ؑփX�C�b�`�@�ł��ˁB
�����ԍ��F23183411
![]() 0�_
0�_
��BOWS����
�f�l�̑f�p�ȋ^��ł����A�A�A�A
��ʂ�SP���j�b�g���̃A�b�e�l�[�^�[�́A�o�����X�^�i�C���s�[�_���X���j�̂g�^�ł���ˁB
�悭�g����Ƌ��� 2CP2500 �� CP2508-S �́A�g�^�ł͂Ȃ��Ɨ������Ă���܂����A�����g�����Ƃ��Ă���悤�ȃ��C�����x�������M���������A�b�e�[�l�[�g����ɂ������ẮA�o�����X�^�C�v�g�^�łȂ��Ă��\��Ȃ��A�Ɨ������Ă�낵���ł��傤���H
�����ԍ��F23183431
![]() 0�_
0�_
BOWS����
S&K AUDIO �̃V�X�e���́A���P�̑傫�ȋ^��_�́A�V�X�e���\�z��A�S�̂́u�}�X�^�[�{�����[���R���g���[���v�@�́A�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ɍs���̂��H�@�ł��B�@������APC �\�t�g�����ł��Ȃ�A�Ȃ̔��q�ɁA�X�s�[�J�[��j������댯�����������Ɍ����܂��ˁB
��͂�A�����ł��������������Ă���悤�ȁACDV�ʉߌ�̃}�X�^�[�{�����[�����K�{�Ȃ悤�Ɏv���܂����A�ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁB
���̓_�����́AS&K �̏��X����Ƀ��[���Ŏ��₵�Ă݂܂��B
�����ԍ��F23183443
![]() 0�_
0�_
dualazmak����A������
S&K AUDIO�̂����������Ԃ�i��ł܂��ˁB
���Y(�l�i�����Ă�������H)�炵���̂ŁA�ŏI�I��5Way�ŗ\�Z���ꂭ�炢�ŃC���v�b�g���Ă����̂����肩������܂���ˁB
��X����ւ��ł���A���ʂ͗\�Z��}���Đi�߂�ꂽ�炢�����ł��傤���H
CDV�o�͑��̉��ʒ����ɂ��Ă̓{�����[������R���A�b�e�[�l�[�^�̕������͂悢�Ǝv���܂��B�Ⴆ�Ή��ʂ͏������3�X�e�b�v�ɍi��AE-460�p�Ŕ������B�g�p���̓{�����[�����i�����Ƃ��납��ACDV�t���r�b�g�ɋ߂��Ƃ���܂Ŏ����グ��B
����Ȃ�˔����ŃX�s�[�J�[���\���͂��Ȃ艺����Ǝv���܂��B�����傪��-dB���K���킩��Ȃ��̂� �ACDV�̏o�̓Q�C�������ő�܂��ɒ��ׂČ��߂�̂͂������ł��傤���H
�����ԍ��F23184667�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ł��B
�@1.�d�q�{�����[���i�o�b�t�@�A���v�����j�@
�@2.�ϒ�R �{ �o�b�t�@�A���v
�@3.��R�ؑ֎��A�b�e�l�[�^ �{ �o�b�t�@�A���v
��4.�g�����X��
�@�M�������p�̃g�����X�͐������̗��_������܂��B
�E������ɂ���āA�M���̐U���̑����A�������o����B
�E�d����K�v�Ƃ��Ȃ��̂œd���m�C�Y�͖����B
�E���͂ɑ��ā@�����̓`�������͂��邪�A�قƂ�ǃG�l���M�[������Ȃ��B
�EDC��ʂ��Ȃ��B
�E���t/�s���t�̐M���ϊ����ȒP�ɏo����B
�@���ꂾ���̗��_������ɂ�������炸�g�����X�ɂ��M���ϊ��́A����I�[�f�B�I�ł͂قƂ�ǎg���Ă��܂���B
�@����͈ȉ��̌��_�����邽�߂ł��B
�E�v/�������E�l�Z�ł���A���郁�[�J�[�������Ȃ��B
�E�Ȃ̂Ł@�����ł�������A���Y�ɂȂ邱�Ƃ������[����������B
�E�S�S�ɓ������������̂Ȃ̂ő傫���A�d���B
�E�M��������P�̃g�����X���K�v�i���`���l�����Ɛ���������j
�E���C�ϓ���U���Ɏキ�A����������B�d���g�����X���狭�͂Ȏ����R�ꂪ����ꍇ�A������E���ăn�����o��B
�E�ш搧��������B���C�h�����W�ɂ��悤�Ƃ���ƍ��x�ȋZ�p�̓������K�v
�E�g�����X�̑�ւ��f�o�C�X�����݂��邽�߁A�킴�킴�g�����X�g��Ȃ��B
�@�Ȃ̂Ō���@���_�����_��啝�ɏ���R�̗̈悪�c���Ă��܂��B
A.�^��ǃA���v�ɂ�����o�͊ǂ̍��C���s�[�_���X(3K�`12K��)���X�s�[�J�[(4�`16��)�Ɉ���������o�̓g�����X
B.MC�J�[�g���b�W�̏o�͐M��(0.1�`0.3mV)��MM�J�[�g���b�W���x��(1�`3mV)�Ɉ����グ��MC�g�����X
C.�X�s�[�J�[�̃f�B�o�C���f�B���O�l�b�g���[�N�ɂ����Ē��������������A�b�e�l�[�^�p�g�����X
�@�`�����f�o�ʉߌ�ɑ��`�����l�������Ɍ������ς���Ƃ����̂́A������Ō�������ύX�ł�DC�J�b�g���o����g�����X�̓������������ǂ����@�ł��B
�@�������A���C�����x���ʼn��ʒ������\�ȃg�����X�����Ă��郁�[�J�[���قƂ�ǖ����A�C�V�m���{�͐����Ȃ����[�J�[�ł��B(���ۂɃg�����X�����Ă���̂͊O����������܂���)
�@8ch�̘A�����ʒ����ƂȂ�ƁA23�ړ_�Ƃ���IN�Q�[�q�AOUT24�[�q�̃g�����X���W�A���ʂ��ւ���8��H23�ړ_�̍����x���[�^���[�X�C�b�`���K�v�A�X�C�b�`�A�g�����X�A�o�����XIN/OUT�[�q��ڑ����邽�߂̔z�����l����ƁA���Ȃ��|����ȑ��u�ɂȂ�܂��B
�@�g�����X�`�X�C�b�`�Ԃ����Ł@24x8=192�{�̔z��������܂��B�ׂ��z���ɂ��Ȃ��ƕs�\�ł��ˁB
�@�Q�l�̂��߂ɂ׃X�|�[�N�I�[�f�B�I�̃X�e���I�A�b�e�l�[�^�̓����ʐ^���Ă݂�ƁA���Ȃ�ׂ������k���Ȕz�����Ă��܂��B
http://www.arkgioia.com/catalog/BespokePassivePre_catalog.pdf
�@���̂S�{�̋K�͂Ȃ�Ł@���������쐬�ł���̂����f������Ǝv���܂��B
�@�J�X�^���ɂȂ�̂œ�����p�����������ƂɂȂ肻���ł����o������ꐶ�̕ł��ˁB
�@����Ɓ@�����ЂƂd�v�ȓ_��....�g�����X�ɂ͊e�X�̓Ǝ��̉�������܂��B
�@�ȑO�A�l�͗F�l����MC�g�����X�𐔐�~����P�T���~�ȏ�̂܂łP�O��ވȏォ���W�߂āA������ׂ��������Ƃ�����܂����A�����ɑS�Ẵg�����X�̉�������Ă��܂����B
�@���������ƂɁA�d�l�〈�����Ɖ�����v���܂���B����ςȊO���̃g�����X����V���{������������A��ꂩ���̊O���̂��琐�X���������o���肵�܂��B
�@���������́A�ǂ̃g�����X���ǂ��̂������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����E�ł����B
�@�ȏオ�l�̃g�����X�ɂ�鉹�ʒ����̌����ł��B
�@���f�̂��߂ɁAdualazmak����́@�C�V�m���{���玎���@����Ď����̍��̊��ʼn����C�ɓ��邩�ǂ����������Ƃ��I�X�X�����܂��B
�����ԍ��F23184688
![]()
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����A
S&K Audio �̃V�X�e���ɂ��ẮA�A�A��قǁA�Y�Ђ̏��X�l����f�����ŐV���̈ꕔ�����L�����Ă��������܂��B
���_�Ƃ��ẮA�����炭���㐔�N�Ԃ́A�l�q���ł��B��
�����ԍ��F23184821
![]() 0�_
0�_
BOWS����
�M�d�ŖL�x�ȏ��A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�Ȃɂ��A�u�I�[�f�B�p�{�����[���A�A�b�e�l�[�^�[�v�̋��ȏ��A����ŐV�̎Q�l����������Ă��������Ă��銴�o�ł��B�{���ɕ��ɂȂ�܂��B�@����炲���������ł��A���̃X���b�h�̑��݂ƕۑ��̉��l���ƂĂ��傫���Ȃ��Ă���Ǝv���̂́A�������ł͂Ȃ��ł��傤�I
�ǂ̕����ɂ��A���F�A�����A�꒷��Z�A�����邱�Ƃ��A���ɖ��m�ɗ����ł��܂����B
���̂悤�ȑf�l���A�y�X�Ɏ��쓥�ݍ��ނ悤�Ȑ��E�ł͂Ȃ����Ƃ������ɂȂ�A���ӂł��B
���C�V�m���{���玎���@����āA�A�A�A�A
�͂��A�����������܂��B
�����ԍ��F23184843
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����A�݂Ȃ���A
�X���b�h�̎�|����O��ċ��k�ł����A����́u��蓹�v�̃t�H���[�A�b�v�ł��B�B
�{���AS&K Audio �̏��X�l�Ɖ��x���̃��[�������ŁA�M�d�ȏ��Ղ��܂����B
�P�D�\�z�̂Ƃ���A���ׂ�PC��̏����ł���APC��������x�����\�ł���A��p�T�E���h�J�[�h�͕K�������K�v�ł͂Ȃ��A�b�o�t�ƃ\�t�g�E�F�A�Ŋ������āAASIO driver �o�R�ŁA�S�`�����l���ꊇ�� 196 KHz/24 bit�M���� LAN�o�R�ŁA�SDAC���ڂ̐�p�X�e���I�S-way�}���`�A���v VT-EtPDAC �֑���Ƃ����A��� LINN �̃l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�V�X�e���Ɨގ��̃R���Z�v�g�ł��B
�Q�DWindows 10 �ɁA�\�t�g�I�ɐV�������z�����{�[�h�iVirtual Audio Cable�j�� WASAPI �Ή��őg�ݍ��܂�AWindows ��̃v���[���[�\�t�g�iROON �� JRiver �ȂǂȂǁj����A���̉��z�����{�[�h�� WASAPI �œ��͂���ƁA���������pDSP�\�t�g�@MPP.DSP�@�ցA����܂�WASAPI�Œ�����܂��B�`�����f�o���܂ޏ������s���Ă���AMPP.DSP �́AASIO �ŁA�X�e���I�S�`�����l���𑩂˂āAGB-LAN �l�b�g���[�N�o�R�� VT-EtDAC �֓��͂��A�S���DAC��DA���āA�S�̃p���[�A���v�֓��͂���A�Ƃ�������ł��B
�R�DPC �ł̃\�t�g�����́A192 kHz/24bit �̏���������ł���A�S�Ẳ����f�[�^�́A192 kHz �ɃA�b�v�T���v�����O�A�܂��̓_�E���T���v�����O���Ă��� WASAPI�i�r�����[�h�@�ʼn��z�����{�[�h�֗����K�v������܂��B
�S�D�`�����f�o�𒆐S�Ƃ���\�t�g�����́A FIR�`���̒����ʑ��t�B���^�[�����ł���A��ʓI�Ȏs�̃f�W�^���`�����f�o�̃A�i���O�����ގ��� IIR�����Ɋr�ׂāA�ƂĂ��傫�ȗD�ʐ������邻���ł��B
�T�D�뜜�����Ƃ���A�}�X�^�[�{�����[���́AMMP.DSP ��Ń\�t�g�I�ɃR���g���[���A�������ŁA�s��USB�{�����[���R���g���[���[���q���ƁAMMP.DSP�����̐M��������肷��̂ŁA�����Ȏs��USB�{�����[���R���g���[���[���g����A�Ƃ̂��ƁB�@�ʐ^�Ō����Ƃ���A�}���`�A���v VT-EtPDAC �ɂ́A�{�����[����~���[�g�@�\�͊F���ł��̂ŁA�|�b�v�m�C�Y�ȂǁA�܂��A���� Windows �� ���̃\�t�g����i����āH�A�r�����[�h�Ƃ͂������̂́jWASAPI�o�R�ő傫�ȉ����M������������ASP�Q��j������\�����傫���ł��ˁA�Ƃ̎��̎���ɑ��āA�u���̂��߁A�g���̂ł���A�����S��SP���j�b�g�ɂ́A�ی�R���f���T�[�����܂��Ă��������B�v�Ƃ̂����߂�����܂����B ���̓_�A�뜜�����悤�ɁA���Ȃ�|���ł��ˁB
�U�D�iBOWS���w�E�̂悤�ɁA�j�}���`�A���v VT-EtPDAC �̃A���v���̃O���[�h�A�b�v��i�߂Ă���A�S���ȍ~�ɉ��ǔł� VT-EtDAC���o�ׂł���܂ŁA�������~���Ă��邻���ł��B
�V�D���ǔł̃A���v�́A
https://www.hypex.nl/product/nc252mp-oem/76
���S��ڂ���Ă��邻���ŁA�����f�W�^���A���v�ł��ˁB�_���s���O�t�@�N�^�[�� 5000 ���x�ŁA�h���C�u�\�͂͏\���A�Ƃ̂��ƁB���^���A���d�ʂ� 1.2 kg �قǑ������Ă���B➑̂������傫���Ȃ�i���s���� 5 cm�قǁj�B�@�i���́A�f�W�A���̓����I�ȃm�C�Y���A�܂��܂��S�z�A���ɏ����ʎ��B�B�B�j
�W�D�S�i 192 kHz/24bit �����ŁA�c�`�b�`�b�v��TI���A�������܂߂��V�X�e���g�[�^���̕i�������|�I�ɍ����̂ŁA�s�̂̂�����DAC�Đ��������i�ʂȉ����Ɏ��M����A�Ƃ̂��ƁB
�X�D�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�Ɩ��p�r�ł̕��y�����҂��Ă���A�ƁB�iBOWS����A�����@�j�B
���̂ق��A�\�j�[����ɂ�����DSD�t�H�[�}�b�g����o�܂̕��䗠�I�Ȃ��b�Ƃ���ɑ��鏬�X�l�̌��݂̊��G�A�����ĉ��ǔ� VT-EtDAC�{�\�t�g�̗\�艿�i���f���܂������A�����ł́A�����ďЉ����������Ă��������܂��B
�Ƃ����킯�ŁA�傫�ȋ����͐s���Ȃ��̂ł����A���Ƃ��ẮA���炭�A���N�Ԃ́i�H�j�A�l�q���ł��B
�����ԍ��F23185041
![]() 0�_
0�_
�f�W�^���`�����f�o�A�A�i���O�`�����f�o�A�ɂ��ẮA��T������A���Ȃ�f�B�[�v�Ȏ������ʃ��|�[�g�̉{���Ȃǂ��܂߂āA�O��I�ɍĊw�K�A�Č������ł��B
�`�����f�o�I��ƁA���̌�i�ɂ�����{�����[���^���x���^�Q�C�������A���E�o�����X�����A�܂ǂȂǁA�����ɂł��A�i�x���Ƃ��Q���ɊC�O�֏o�����O�܂łɁj�A���݂̎��́u�ĔF���A�Y�݁v�ȂǁA���m�点�������܂��B
�����ԍ��F23185116
![]() 0�_
0�_
dualazmak����A������
��L���肪�Ƃ��������܂��B�p�\�R���̗L��]��CPU�p���[���ƃX�J�ȃf�[�^�ʂ̉����͎��݂Ȋ����ł��ˁB
�L���̓\�t�g�Ńn�[�h�͒l�t���̃l�^�Ɍ����Ȃ����Ȃ��A���̂����C�O���ł��o�Ă������ł��B
�ی�R���f���T�[�̓A���v��DC�R���Ƃ��}���`�ł͕��ʂɓ���܂��̂ŁA�\�t�g�����ŗL�̃l�K�Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B
�J�����ƌq�������̂Ȃ�A���̂������������b�����邩������܂���A���ʂ�CDV�Ɏ��g��ŁA�����悭�Ȃ�̂��m�F���Ȃ��炪��Ƃ��Ċy�����̂ł́H
BOWS����A������
���P�O��ވȏォ���W�߂āA������ׂ�����
���������ł���
MC�g�����X�̘b�Ƃ͂Ȃ������A�I���g�t�H��MC20�̍��ȗ��Ȃ̂�40�N�Ԃ�ł��B
�A���v��MC�|�W�V�����ł̓m�C�Y�������A�g�����X���n���ɂȂ�̂ł����g���C�_���ɃK�T�K�T�Ɋ����Ă���ƃj�X�Ōł߂Ă����Ă����������A�������芪�����I���G���g�R�A�̕����悩������A���ɂ��ăG�|�L�ɐZ���Ĉ��͂Ȃׂɓ���ĒE�A�Ƃ�
�Ƃ����TAD�̃V�X�e���͂܂��g���Ă���̂ł����H
�����ԍ��F23185398
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@����������Ȃ������̂ŕ⑫���܂��B
�o�b�t�@�A���v
�@�ϒ�R�����̃t�F�[�_�[�{�b�N�X�������A���������Ȃ��A���������Ȃ��s���A�ȉ��ʒ������Ǝ咣����l�����܂����A�l�Ƃ��Ắ@�R��������łV���n�Y�����Ǝv���Ă��܂��B
�@�O���珑���Ă���悤�ɁA�ϒ�R���R�ؑ֎��̃A�b�e�l�[�^�[�ōi�����ꍇ�A�O�i�̃G�l���M�[�̂قƂ�ǂ��R�ŔM�ɂ��ď������Ďc��J�X�̂悤�ȃG�l���M�[�����o�Ă��܂���B�������A�{�����[���ʒu�ɂ���ďo�̓C���s�[�_���X���ω�����Ƃ�����V�ȑ㕨�ł��B
�@�v�����C���A���v��p���[�A���v�Ȃ�A�����z���ʂ��Đ��`�\��cm�ŃA���v�ɓ��͂ł���̂Ŗ��ɂȂ�܂���B
�@�Ƃ��낪�A�t�F�[�_�[�{�b�N�X���ƁA�p���[�A���v�̊ԂɁ@���G�ɕ��V�e�ʂƃC���_�N�^���X������݂��������C���P�[�u�����P�`�Q���قǓ���܂��B
�@�c��J�X�œd�������\�͂����������ϒ�R�̏o�͂́@������쓮����\�͂Ɍ����Ă���̂ō�������ꂽ��ɃC���s�[�_���X���ς���ă|�W�V�����ɂ���đ������葾�����肷�鉹�ɂȂ�܂��B����𐴑^���ƕ]������ꍇ������܂���...
�@�ȑO�A���쒇�Ԃ��W���ăA�b�e�l�[�^�[���X����������Ē�����ׂ������Ƃ�����܂����A���m�ɂ���Ē��x���Ⴂ�܂����A�i��Ƃǂ�����������܂��B
�@�ŁA�������@�P�[�u���ɂ���ĉ����S���S���ς��B�c��J�X�݂����ȃG�l���M�[���ʂ��Ă���̂Ł@�P�[�u���̎��ɂ���ĉ����傫���ς��͓̂����ł��B
�@�Ƃ��낪�o�b�t�@�A���v���܂��Ă݂�ƁA�i���Ă����͂���܂葉���܂���A����ƃo�b�t�@�������P�[�u���ς��Ă��ω����������Ȃ�܂����B�������A�o�b�t�@�̃m�C�Y������Ă���̂�SN�͈������܂��B
�@�l�̌o����A�{�����[���ɃA���v�ɓ˂����ވȊO�̓o�b�t�@�A���v���K�{���Ǝv���܂��B
>��ʂ�SP���j�b�g���̃A�b�e�l�[�^�[�́A�o�����X�^�i�C���s�[�_���X���j�̂g�^�ł���ˁB
�@�C���s�[�_���X���͍����Ă��܂����AH�^�ł͂���܂���B
�@��ʓI�ȃX�s�[�J�[�͂Q�[�q�����Ȃ��A�O�����h���K�v�Ȃ��̂őS�ăA���o�����X�ł��B
�@�A�b�e�l�[�^�����猩��Ɓ@���[�p�X�t�B���^����ʉ߂��Ă������̓C���s�[�_���X���o�̓C���s�[�_���X(�X�s�[�J�[���j�b�g�j�����(8���Ȃ�)�@�ɂ��Ȃ��Ɠ���_�������ăJ�b�g�I�t���g�����Y�����肵�܂��B
�@���̂��߂�L�p�b�h�^�A�b�e�l�[�^���g����ł����A���́`�����_�i�㑤�j�̒�R�Ɛ����_�`�O�����h(����)�̊e�X�̒�R�̕ω�������]�p�ɑ��ē���łP�̉ϒ�R�őΉ��ł��Ȃ��̂Ł@�㑤�Ɖ����̂Q�̓���ȕ��z���������ϒ��ɂ����킹�Ďg���܂��B�Ȃ̂Ł@�X�s�[�J�[�p�̃A�b�e�l�[�^�͕�������ł��B
>�悭�g����Ƌ��� 2CP2500 �� CP2508-S �́A�g�^�ł͂Ȃ��Ɨ������Ă���܂����A�����g�����Ƃ��Ă���悤�ȃ��C�����x�������M���������A�b�e�[�l�[�g����ɂ������ẮA�o�����X�^�C�v�g�^�łȂ��Ă��\��Ȃ��A�Ɨ������Ă�낵���ł��傤���H
�@�A�b�e�l�[�^�Ɋւ��Ắ@���������Ɉꗗ�\������܂��B
http://www.ko-on.co.jp/technology3.html
�@���ꂢ�ɂ܂Ƃ܂��Ă����ł����A���������....
�@2CP2500 �� CP2508-S�́@�A���o�����X�pL�^�ɂȂ�܂��B
�@���������Ă܂��A�o�͑��̃C���s�[�_���X�̓{�����[���ʒu�ɂ���ĕω����܂��B
�@��������ǂ����̂��@T�^�@�ŏo�̓C���s�[�_���X�����̓C���s�[�_���X�ƈ�v���Ĉ��ɂȂ�܂��B
�@�C���s�[�_���X�̋K��̌����������p�@��Ŏg���܂��B
�@����L�^��HOT/COLD�ɑ��Ĕw�����킹�ɂ����U�^�̃o�����X�A�b�e�l�[�^�ɂȂ�܂��B
�@���Ⴊ����Ȃ�
https://devipoke.blog.fc2.com/blog-entry-1119.html
�@H�^�A�b�e�l�[�^�́@���T�^��w�����킹�ɂ��ăo�����X�Ή��ɂ������̂ł��B
�@���z�I�ł����A���͂�ϒ�R�ō��͖̂����������Ē�R�ؑ֎��ō�邱�Ƃ������ł����A�P�|�W�V�����������R�T��ւ��ł��B
�@�����炷���߂Ɂ@����H�`���g���܂��B���ꂾ�Ɓ@��R�R��ւ��邾���ł��ށB
�@���ۂɂ���Ƃ���Ȃ̂ɂȂ�܂��B
http://www.macoteau.com/maco/index.php?logid=962
�@�������������Ȃ�̂Ŕ����Ă܂������ǁ@�o�����X�Ή��̃A�b�e�l�[�^�ɂ��悤�Ƃ���ƂP�`���l��������Q�̉ϒ�R���K�v�łP�̂܂݂�8CH���ʒ������悤�Ƃ����16�A�{�����[�����K�v�ł��B
�@8ch�ɂ���Ȃ�ACDV�`�}�X�^�{�����[���́@�A���o�����X���A�������͍��E�Q�̂W�A�{�����[���ɂ��ā@L/R�Q��Ƃ�
�@�AS&K Audio �Ɋւ��ẮA�ʔ�����肪�Ƃ��������܂��B
�@�Ȃ��Ȃ��ʔ����\�����[�V�����ł����A���O��PC�ɂ���AS&K Audio �̃v���Z�b�T�ɂ���AOS��̃\�t�g���Z�����Ȃ�Ł@���͂�CPU�g���Ή��Z���͉̂\�ł��傤�B
�@�����A�\�t�g���Z�̏ꍇ�A�v�Z���Ԃ�APC�Ȃ�ő��̊��荞�ݏ����Ƃ����Ă���Ɓ@�o�̓^�C�~���O�����ɂȂ���ȁH�Ǝv���܂����B
�@PC�Ƀ}�X�^�[�N���b�N�ǂ�����Ď�荞�ނ̂����ē�ł�������������悳�����B
�@���Ȃ��Ƃ� 8ch��DAC���ڑ�������Ł@DAC��������DDC�Ƀ}�X�^�[�N���b�N�˂�����œ��������������悳�����Ɏv���܂��B
�@�Ȃb�����U���Ă��܂����悤�ł��݂܂���B
�����ԍ��F23187043
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
>�Ƃ����TAD�̃V�X�e���͂܂��g���Ă���̂ł����H
�@�������܂����B
�@�傫�����①�ɂ��炢����̂����r���O�ɂQ�䂠���ā@�Ƒ�����u�ז��I�̂ĂĂ����v�ƌ���ꑱ�����̂���ȗ��R�ł�(T T)
�@����ƁARay Audio��^���ā@�o�[�`�J���c�C���ɂ�����ł����A��^�E�b�h�z�[���Ƒ���a�E�[�t�@�[�̃o�[�`�J���c�C���̏ꍇ�A�E�[�t�@�[�̊Ԃ����ꂷ���Ă��ā@�㉺�E�[�t�@�[�̃^�C���A���C�����g���������ā@�㉺�����̃T�[�r�X�G���A�����\�����Ƃ��A�z�[���̃R���g���[���ɋꂵ�肵�Ă���Ł@Dynaudio��2way��������ɁA�������̕����k���ȉ������Ă��邱�ƂɋC�����ăh�i�h�i���܂����B
�@���ł���^�z�[���̉����k������Ȃ����ǁ@�����炩�Ȃ�ōD���Ł@������x��肽���Ƃ͎v���Ă��܂��B
�����ԍ��F23187067
![]() 1�_
1�_
BOWS����
�{���ɏڍׂŐ[���ȘA���u���Ղ��A���ӂɊ����܂���B
���ׂāA�u�Ȃ�قǁI�A�Ȃ�قǁI�I�v�������Ȃ���������Ă��������Ă���܂��B
���@8ch�ɂ���Ȃ�ACDV�`�}�X�^�{�����[���́@�A���o�����X���A�������͍��E�Q�̂W�A�{�����[���ɂ��ā@L/R�Q��Ƃ�
�ŏI�I�ɁA���ɔ[���������܂����B
S&K Audio�ł����A���̂Ƃ���A��̋Ɩ��p Detante �V�X�e�����̂��̂̂悤�ł��BLAN�o�R�ŃX�e���I�Sch�̐M���� ASIO driver �ő���o���̂ŁA�����A�Œ�ł��A���� VT-EtDAC�A���v�� DAC �փ}�X�^�[�N���b�N���g����\���ɂ��Ȃ��Ƃ܂�����Ȃ��H�Ƒf�l�Ȃ���v���Ă���܂����B
�s���A�I�[�f�B�I����ŁA���������ėpPC��ŏ�������̂́A�댯�ŕ|���ł��ˁB�������@Windows OS �ł��̂ŁAWASAPI ���o�͂ȂǁA�܂��܂��M�p�ł��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
TRINNOV ALTITUDE36 �����z���͓̂����ł����A��pLINUX ��̐�p�\�t�g�Łu��p�@�v�@�ɂ��Ă���̂ŁA��͂�R���Z�v�g������Ƃ��Ă͔[���ł��܂��ˁB�������A�\�Z�I�ɁATRINNOV�ɂ͎�o���ł��܂��B���
����ƁA���́A���̂Ƃ���A�f�W�^�������M����LAN�œ`�������l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�́A�l�X�Ȋϓ_����������Ă���APC-USB�I�[�f�B�I�ɓ������Ă��܂��B����ŁAOPPO SONICA DAC ���AUSB-DAC �@�\�������g���Ă��܂��B���ł� ES9038PRO ��DA�i�ʂ́A�傢�ɋC�ɓ����Ă���܂��̂ŁB���
�����ԍ��F23187180
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����A
��������܂����悤�ɁA
�u����ŁA���̊��ŁA�ǂ̂悤�Ƀ}���`�A���v�V�X�e�����������H�v�@
�ɂ��āA�قڕ��������ł܂��Ă��܂����̂ŁA�T���ɂ����āA�����ڂ����������Ă��������܂��B
���̑O�ɁA������e���ł����A�ЂƂ������������B
���݂̊��̃x�X�g�ȏ�Ԃ��A���̒��o��̢���ƂȂ�܂��̂ŁB�B�B�}���`�A���v�V�X�e���������O�ɁA���݂́uLC�N���X�I�[�o�[�{�A�b�e�l�[�^�[�v���A����ɃG�[�W���O���ăx�X�g�̏�Ԃɂ��Ă��������ƍl���Ă���܂��B�i��N�̉ĂɃ��m�x�[�V�������Ĉȗ��A�܂��܂��G�[�W���O�s���ł��B�j
�uLC�N���X�I�[�o�[�v�{SP�Q���G�[�W���O����ɂ́A�z���C�g�m�C�Y�܂��̓s���N�m�C�Y���A������x�̉��ʂŁA������x�̎��ԁA����Ă��������Ƃ͗������Ă��܂����ASP�Q�̃G�[�W���O�͍ς�ł���ł��̂ŁA�u�����̘A���v������uLC�N���X�I�[�o�[�v�A���ɐV�������R���f���T�[�B�A���G�[�W���O�������̂ł��B
�ǂ����ŁA���̖ړI�ɂ́ASP�̑���ɤ�R�OW �قǂ̔��M�d���i�������LED�d���ł͂Ȃ��A�G�W�\���^�C�v�̔��M�d���I�j��ڑ����ăz���C�g�m�C�Y�܂��̓s���N�m�C�Y�����Ă���낵���A�Ȃ�ċL�ڂ����������L��������̂ł����B����@���M�����ǍD�ȁA�Q�OW�قǂ̑�^�W����R���g���ׂ��ł��傤���H
�����ŁA�uLC�N���X�I�[�o�[�{�A�b�e�l�[�^�[�v���G�[�W���O������@�A���̍ۂ̉��ʃ��x���A�����Ăǂ̒��x�̎��Ԃ��A���ɂ��Ă������������B
�����ԍ��F23187245
![]() 0�_
0�_
dualazmak����A������
��LC�N���X�I�[�o�[�{�A�b�e�l�[�^�[�v���A����ɃG�[�W���O���ăx�X�g�̏�Ԃɂ��Ă�������
�����d���R���������Ă�����A�n���_�M�ŗ���̂œd�������ĉ����܂��B
�̂�����͎̂���A���v�ł������A�R���f���T�̑����牓�����Ŕz�����J�b�g��DC�d���œd���R���f���T�̑ϓd���K�i�l��24H�����܂����B�Ȃ��鎞�̓R���f���T�̑��ɕ��M�N���b�v�𗧂āA���ɔM���`���Ȃ��悤�Ƀn���_�t���Ŗ߂��܂����B
�l�b�g���[�N�͓d���R�����g��Ȃ��悤�ɂ��Ă����̂ŁA�G�[�W���O�͂��܂���ł����B
����NP�̓d���R�����g���Ă���ꍇ�͋ɐ���ς��Ēʓd���鎞�A��U�d�ׂ��Ă��������������悢�ł��傤�B
���̕����̓��J�I�ȐU����^���ė����������鎖���G�[�W���O�ɂȂ�Ǝv���̂ł����A�ړ�������ƌ��̖؈���ɂȂ邩������܂���ˁB
BOWS����A������
���Ƃ����TAD�̃V�X�e���́H
���������܂����B
���傫�����①�ɂ��炢����̂����r���O�ɂQ�䂠���ā@
���o�[�`�J���c�C���ɂ�����ł����A��^�E�b�h�z�[���Ƒ���a�E�[�t�@�[�̃o�[�`�J���c�C���̏ꍇ�A�E�[�t�@�[�̊Ԃ����ꂷ���Ă����㉺�E�[�t�@�[�̃^�C���A���C�����g���������ā@�㉺�����̃T�[�r�X�G���A�����\�����Ƃ��A
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B�����Ɠ����悤�ȏƂ́B�B�B�E�[�t�@�[�͕���ł����Ǝv���Ă����̂ł����A���ǂP�{�Â�ch����U���ă^�C���A���C�����g�����n���ɂȂ�܂�����B���E�ɒu����150Hz�ŃX�p�b�Ɛ��Ďg���Ƃ悢�悤�ł��B
�����ԍ��F23187416
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
���肪�Ƃ��������܂��B
����A�A�L�o�̃R�C�Y�~�����ɗ�������Ď�C����Ƃ��b�����Ă�����A�t�B�����R���f���T�[�ł��A������x�̃G�[�W���O�͕K�v�ł���A�Ƌ��ł����̂ŁA���₳���Ă��������܂����B
�����ԍ��F23188185
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����A�F����A
��A�����獡���܂�;
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284
��
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776
����ɁA�����̖{�X���b�h;
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/
�ɂ����āA�c��ȏ������A�M�d�ŖL�x�Ȃ������A�������Ղ��A�S���犴�Ӑ\���グ�܂��B
�悤�₭�A�u���̃I�[�f�B�I���v�ɂ�����u�}���`�A���v�\�z�v�̎��݂ւ̓����A�قڌ����Ă܂���܂����̂ŁA�ȉ��̒ʂ�A�������̏����ɕ����āA�������Ă��������܂��B
�܂��́A�Ę^�ɂȂ�܂����A����́u��v�ƂȂ�A���́u���݂̃V�X�e���v���A�㗬���珇�ɁA�Ȍ��ɂ܂Ƃ߂܂��B
��������v�����C���A���vE-460�܂ł�;
Windows 10 Pro 64bit �����\��������PC ��� Roon or JRiver MC26
��
ASIO driver
��
USB 2.0 Cable �i�����āAUSB 3.0 �ł͂Ȃ� USB 2.0�j
��
OPPO SONICA DAC (ES9038PRO)
�@�@�@�@PCM �V�U�W��Hz/32 bit, DSD 22.6 MHz (DSD512) �܂őΉ�
��
XLR�o�����X (4.0 Vrms)
��
�A�L���t�F�[�Y E-460 �v�����C���A���v
�ł��B�@
OPPO SONICA DAC �́ARCA�A���o�����X�o��(2.0 Vrms) ���g���܂����AES9038PRO �����̃{�����[���R���g���[���[���g����̂ŁARCA�A���o�����X�� E-460 �̃p���[�A���v���ɒ������邱�Ƃ��\�ł��B�@SONICA DAC �́AUSB-DAC�@�\�������g���Ă���A�l�b�g���[�N�v�����[�Ƃ��Ă̋@�\�̓I�t�ɂ��Ă��܂��B
SP�Q�́A��悩�珇�ɁG
�P�D�T�u�E�[�n�[�iSW�j�@YAMAHA YST-SW1000 ���E1�䂸��2��G
�@�@�@�@�i�Ǝ��A���v�A-24 dB/Oct�σn�C�J�b�g�A�σ{�����[���A�ʑ����]�{�^���A���ꂼ������G�@�����R������\�j
2�D�R�[�q�����Ċe���j�b�g�����ɉ������� YMAHA NS-1000 (NS-1000M �ł͂Ȃ��ANS-1000)
�@�@�@�@30 cm �R�[���^�E�[�n�[�iWO�j
�@�@�@�@8.8 cm �x�����E���h�[���^�X�R�[�J�[�iSQ�j
�@�@�@�@3.0 cm �x�����E���h�[���^�c�C�[�^�[(TW)
�R�D�X�[�p�[�c�B�[�^�[ FOSTEX T925A�@�iST�j
�̎����T-way�\���ŁAWO�ASQ�ATW�AST �p�̃N���X�I�[�o�[LC�l�b�g���[�N��H�� SQ�ATW�AST�̃A�b�e�l�[�^�[�iATT�j�́A�O�t���{�b�N�X�����Ă��܂��B
E-460 ����@SP�Q�ւ�PRE-OUT����уo�C���C�������O�ڑ���3�n����;
1�DE-460�� PRE-OUT
�@�@�@�� RCA�P�[�u�� �� ���E��SW�ցi���ꂼ��{�����[��������ATT����j
2�DE-460��SP�o�͂a
�@�@�@�� WO�p�l�b�g���[�N�i500 Hz, -12 dB/Oct�X�j �� WO
3�DE-460 ��SP�o�͂`
�@�@�@�� SQ�p�l�b�g���[�N�i500, 6kHz, -12 dB/Oct�X�j �� SQ ATT �� SQ
�@�@�@�� TW�p�l�b�g���[�N�i6kHz, -12 dB/Oct�X�j �� TW ATT �� TW
�@�@�@�� ST�p�l�b�g���[�N�i10 kHz, -6 dB/Oct�X�j �� ST ATT �� ST
�Ƃ��Ă���A�B��ATT���o�R���Ȃ�WO�̉��ʂƍ��E�o�����X�� E-460 �Œ������A�������ɂ��āASW�ASQ�ATW�AST �̃��x���i���ʁj�ƍ��E�o�����X���A���ꂼ��Ɨ����āA�������ł���\���ł��B �������ASP�P�[�u���̐ڑ����]�ŁAWO�ASQ�ATW�AST�@���ꂼ��̈ʑ����]�͉\�ł����ASW�͂��ꎩ�̂ňʑ����]�{�^���������Ă��܂��BSONY Super Audio Check CD �̗D�ꂽ�ʑ��m�F���������5�_��ʉ�����p���āASW�AWO�ASQ�ATW�AST ���ꂼ��P�ƂŖ炵�Ȃ���A�܂��S�̂�炵�Ȃ���A�ʑ��m�F�^�ݒ�ƍ��E�o�����X���������s���Ă���܂��B
����ŁALC�l�b�g���[�N�o�R�Ƃ��ẮA���̃I�[�f�B�I�o����ŁA�����Ƃ��D�ꂽ3����������ʂ������Ă���A���X�j���O�|�W�V�����iSP�Q����4 m�j�ɂ����đ����i�R�l�|���\�t�@�[�Łj���E�Ɉړ����Ă��A������ʂ��u���邱�Ƃ�����܂���B
���łɂ��Љ���悤�ɁAMySpeaker �� Real RTA�Ȃǂ̃\�t�g�ƁABehringer ECM8000�}�C�N���g���āA�ʁA����уg�[�^���̎��g�����������𑪒肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�����ԍ��F23188188
![]() 0�_
0�_
�`�����l���f�o�C�_�[�ƐV�K�A���v�Q�̓������������āA���ɏd�v�Ȋ�ł��鑍���I�ȁu���݂̉����i�ʁv�ł����A���̂悤�Ȕ�r�����́A�p�ɂɂ���Ă���܂��B
�ō��i�ʂł���ƒ�]������_�E�����[�h�w���� 4xDSD (DSD512) �����A
���Ƃ���N�A���E�ō���̃s�A�m�^���i�H�j�Ƃ��Ęb��ɂȂ������c�^���̃V���p���G
https://ascii.jp/elem/000/001/691/1691362/
https://www.e-onkyo.com/music/album/nycc27306/
DSF 11.2 MHz/1bit = DSD 22.6 MHz (DSD512)
�̃A���o������T���v�������Ƃ��A
�������� JRiver MC26 �̃t�H�[�}�b�g�ϊ��Ń_�E���T���v�����O���āG
DSF 5.6 MHz/1bit = DSD 11.2 MHz (DSD256)
DSF 2.8 MHz/1bit = DSD 5.6 MHz (DSD128)
AIFF 192 kHz/24bit
AIFF 44.1 kHz/24bit
�i�������A�e��mp3���k���\�j
�̊e�A���o�����쐬���邱�Ƃ͗e�Ղɂł��܂��̂ŁA�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Đ����āA���ꂼ��́u�����i�ʁv��r�������邱�Ƃ��ł��܂��B
���̌��݂̃V�X�e�����ŁA���̔�r�������s���ƁADSD512, DSD256, DSD128, AIFF192, AIFF 44.1 �̏��ŁA�u�����i�ʁv���ቺ���Ă������Ƃ����m�Ɏ��ʂł��܂����A�Ɛl�ɒ������Ă��u�����i�ʁv�̍��l�ɔF�����܂��B
����AB&W 800D3 �������ȃv���A���v�{�p���[�A���v�Ŗ炵�Ă���A���݂��ɉ����Ȃ��Őh煂ȓ��D�̗F�l�����Ă���܂������A�u���X�j���O���[�������قȂ�̂ŁA���ڔ�r�͂ł��Ȃ����A�����������łƂĂ������������Ǝv����B�v�A�ƌ����Ă���܂����B
�����ԍ��F23188192
![]() 0�_
0�_
���āA���̊�����}���`�A���v���ւ̈ڍs�ŁA�܂��ŏ��Ɋm�F�������̂́A�u�`�����f�o�iCDV) �܂ł̏㗬�͌���ƑS������j�ɌŒ肵�Ă����AWO�ASQ�ATW�AST�p��LC�l�b�g���[�N��ATT�̔r���A�����ĐV�A���v�R��ɂ��SQ�ATW�AST �̋쓮�Łu�����I�ȉ����i�ʁv���A����ɉ��P�ł��邩�A�ۂ��A�ł��B�@�i�܂���WO�́A���L E-460 �̃p���[���ŋ쓮���܂��B�j
�����ŁA�ő�̌��O�́ADF-65 �� VENU360 �Ȃǂ̃f�W�^��CDV�ł́A���̓������96 kHz/24bit �ւ�AD�ϊ��ACDV������ɍĂ� 96 kHz ����A�i���O�M���ւ�DA�ϊ��A�Ƃ����@AD-����-DA �̉ߒ����������Ȃ��A�Ƃ����_�ł��B���ꂪ�s���ł��̂ŁA�f�W�^��CDV����́A��̏����ŏq�ׂ�DSD512, DSD256, DSD128, AIFF192�́u�i�ʂ̍��v�́A���͂�F���ł��Ȃ��Ȃ�̂ł́A�܂茻�݂� DSD512 �Đ��́u�����i�ʁv�́A���Ȃ���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������O�ł��B
���̌��O�ɑ���A�ЂƂ̃A�v���[�`�Ƃ��āA�f�W�^��CDV�ł͂Ȃ��A�����ăX�e���I�S-way(�S�ш敪��)�́i���i�ʂȁj�A�i���OCDV�̓�������n�߂�A�������A�����ł̏������Ő[���w�� XLR-RCA���ݕϊ��̖���������邽�߁A�܂��͏㗬���牺���܂ŁA�ŒZ������RCA�A���o�����X�ڑ��œ��ꂵ�Ď����Ă݂�A�Ƃ����I�������l���Ă���܂��B
�K���ɂ��AWO�ASQ�ATW �́AYAMAHA NS-1000➑̂ɑg�ݍ��݂ł��̂ŁA�����A���C�������g�I�ɂ�������ƌŒ肳��Ă���A�K�v�Ƃ���� SW �� ST �͑O��i���E�j�̈ړ����\�ł��B�i��^�̃z�[�����j�b�g�͎g�p���Ă��Ȃ����Ƃ͍D�������ƍl���܂��B�j
�܂��A�S�ш敪���A�i���OCDV�Ńo�^�[���[�X�^�t�B���^�[��H -12 dB/Oct �̃N���X�i����Ɠ��l�̃N���X�X�j�ł���A�����I�ɂ́A��摤����A���A�t�A���A�t�@�̈ʑ����]�ƂȂ�͂��ł��̂ŁA�e�ш�̈ʑ��`�F�b�N�Ɣ��]�����͗e�Ղł���ƍl���܂��B�����āA�N���X�|�C���g���g���̏㉺���������\�ł���A�S�ш�Ԃ́u�Ȃ���v�̔������i�f�B�b�v�̉���j���\�ł́A�Ǝv���܂��B
����ɁA�u���m�����\���v�̂S�ш敪���A�i���OCVD�����E�ɂP�䂸�������A���ꂼ��ɂ����đш斈�ɊȕւɃQ�C�������ł���A�ш斈�̃Q�C���ƍ��E�o�����X������CDV�̃��[�^�[���[�Q�C���_�C�A���W�Ŕ��������ČŒ肷�邱�Ƃ��\�ł��B�@�S�̂̃}�X�^�[�{�����[�������́A�����̃v�����C���A���v�̃{�����[���ʼn\�ł���ADAC���� CDV��RCA��������ꍇ�ɂ�SONICA DAC �� ES9038PRO�{�����[���_�C�A���ʼn\�A�ƂȂ�܂��B
���̕��j�Ői�߂�ꍇ�A�D�܂����u�i���v�́A���m�����\���S�ш敪���Ή��A�ш斈�ɃQ�C�������\�A�N���X�|�C���g���㉺�ɔ������͉\�A�Ƃ����u�A�i���OCDV�v������ł��邱�Ƃ������ƂȂ�܂��B�����ɂ͂Ȃ�܂����A�\�Z�I�Ɏ��܂鉿�i�ŁA���̂悤�Ȍ��@��́A�Ȃ��ɂ������炸�A�Ƒz�肵�Ă��܂��B�@�������A�����I�ȕ���������H�̍\���ƌX�t�B���^�[�������A�悭�m�邱�Ƃ͕K�v�ł��B
�Ȃ��AE-460 �̃v���A�E�g���� CDV�q���ꍇ�ASW�ւ̓��͂ɂ��ẮAE-460 �̃w�b�h�z���o�́i�}�X�^�[�{�����[���L���j���� RCA�P�[�u���ŁA���܂łƓ��l�ɍ��E��SW��RCA���͂ł��܂��i�܂�ACVD�͒ʂ��Ȃ���SW�q���j�B�@SW YST-SW1000 �́A�X�s�[�J�[���x�����͂��ł���̂Łi���̏ꍇ�͓����̑傫�Ȓ�R�Ń��C�����x���ɗ��Ƃ��Ă���j�AWO�pSP�[�q���番��SW�q�����Ƃ��\�ł��B
���܂��ẮA���̐i�ߕ��ɂ��āA���ӌ��A�������Ղł���K���ł��B�@
���̐i�ߕ��ɑ傫�Ȗ�肪�Ȃ���ARCA�ڑ��\�ȐV�p���[�A���v�R��A����TW�p�AST�p�̓A���v�͏��o�͂ŏ\���A�ɂ��Ă��AE-460 �Ƃ́u�Ȃ���v���l�����A�����߂₲�������A���肢���܂��B
�����ԍ��F23188199
![]() 0�_
0�_
dualazmak����A����ɂ���
�A�i���O�`�����f�o�̓^�C���A���C�����g����o���Ȃ��ł��B-24dB/oct��I��ł�360�x�x��ŁA500Hz�N���X���Ƃ�������70cm����̉��Ȃ̂�PA�Ȃ炢����������Ȃ����ǁA�ƒ���ō��i�ʂɍĐ����ƈ�a���傫����������܂���B
�����ԍ��F23188468�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
���݂�LC�l�b�g���[�N�ɂ�鉹��̂Ȃ���Ɋr�ׂĈ�a�����Ȃ����ƁA�܂��T�d�ȏ���ɂ��ƁA����SP�Q�ւ̕����ɂ�NS-1000�̃I���W�i��LC�l�b�g���[�N�Ɠ��� -12 dB/Oct �X���ł��K���Ă���ƍl�����邱�ƁA�z�肵�Ă�������A�i���O�`�����f�o�ł� -12 dB/Oct ���W���ł��邱�ƁA�ȂǂȂǂ����Ă��A-12 dB/Oct ���ߑł��Ői�߂�S�Â���ł��B
�A�i���O�`�����f�o�ŁA���̑I���̏ꍇ�A�����A���ɑ��āA�ǂ̂悤�ɒx���A�����A�Ƒz�肳��܂����H
�܂��A�������O���Ă��� DSD512, DSD256, DSD128 ������̍��i�ʉ����̍Đ��i�ʂɂ��āA�f�W�^��CDV���p�ƁA�A�i���OCDV���p���r����ƁA�����ɂ悵����́A�ǂ̂悤�Ȃ��o���◝�_�I�ȑz����������ł����H
����������z�肵�Ă��郂�m�����S�����`�����f�o�́A�̂� SANSUI CD-10 �Ƃقړ��l�̕����ł��B
https://audio-heritage.jp/SANSUI/etc/cd-10.html
��H�}������܂����A�f�l�̎��ɂ́A���̉�H�̓����͂悭�����ł��܂���B
BOWS����́A���̉�H�A�悭�����m�ł��ˁB�@
�����A�Â��`���ł��̂ŁA�l�X�Ȃ����O�����낤���Ƃ́A�e�Ղɑz���ł��܂��B���
�����i�́A���m�����\���œY�t�ʐ^�̂悤�ȑO�ʂɂȂ�A�e�ш�̃Q�C���������\�A�܂��ʐ^�̂悤�ɂR�|�C���g�̃N���X���g���̑O���HIGH CUT ����� LOW CUT ���ϐݒ�ł���Ƃ������j�[�N�ȃA�i���O�`�����f�o�ł��B
�Q�C���_�C�A�����A�J�b�g�I�t�_�C�A�����A���쒆�ɁA���ۂɉ����Ȃ���A���R�ɒ����\�ł��B�@�E�`�����l���p�A���`�����l���p�@�̂Q��ɕ����܂��̂ŁA�ш斈�ɍ��E�o�����X�������\�ɂȂ�܂��B�@�ݒ�@�\�Ƃ��ẮA���̗v����S�Ė������Ă���܂��B
�����ԍ��F23188711
![]() 0�_
0�_
dualazmak����A������
��-12 dB/Oct ���ߑł��Ői�߂�S�Â���ł��B
-18�A-24�������ꂽ�炢�����ł��傤���H�����Ƃ�����������܂���B
���}�n�����-12�͑Ë��̑I������
���A�i���O�`�����f�o�ŁA�����A���ɑ��āA�ǂ̂悤�ɒx���A�Ƒz�肳��܂����H
CR�t�B���^�[�Ȃ̂�-6dB���Ƃ�90deg����܂��B-12dB�Ȃ�180deg�E�[�t�@�[�͒x��A�X�R�[�J�[�͐i��
���Đ��i�ʂɂ��ăf�W�^��CDV���p�ƁA�A�i���OCDV���p���r����ƁA
�������ɂ悵����́A�ǂ̂悤�Ȃ��o���◝�_�I�ȑz����������ł����H
���͌����̃Z���T�[�Ő����������Ēb���Ă����̂Ŋ�{�I�Ɉʒu�Ƌ����Ɋւ��Ċ��x�������ł��B
���̔g�������x��ł��Ȃ��獇���A���Ȃ�̉���Č�������ɂȂ�̂�dualazmak��������o���ρB
�������A�A�i���O�͑��l�b�g���[�N��CDV�������x��ō��킹�鎖�ɂȂ�܂��B
�f�W�^���͍��{�I�Ƀ^�C�~���O������������邽�߁A����Č����͍X�ɔ��^�I�ɂȂ�܂��B
�X�s�[�J�[�̍��A���A�ቹ�����������ăn�����Ă������Ȃ̂ɁA
���Y�����s�ɂȂ�A����Ă��R�[���X���Ƃ悭�͕������邯�ǁA�܂�����Ȃ�݂����Ȋ����ł��傤���B
���������O���Ă��� DSD512, DSD256, DSD128 ������̍��i�ʉ���
���ʂ͔F�߂܂����A��L�̌��ʂɔ�ׂ�Ƃ̂Lj����x�̃X���[�Y�������A
���y�ő厖�Ȃ̂�20kHz�~�܂�A�X�s�[�J�[�̓��������傹��A�i���O�Ȃ̂ł�����ׂ������Ă�����Ȃ�ł�
������������z�肵�Ă��郂�m�����S�����`�����f�o�́A�̂� SANSUI CD-10 �Ƃقړ��l�̕����ł��B
�Ȃ������Ȃ��Ă��܂����̂ł��傤�H�A�L����CDV�̃A�i���O�͂�߂��悤�ł�����
�������i
���ʂ̃f�W�^��CDV���g���|���Ă���A�s�����Ă�����̂�����������̕����悢���̂ɂȂ肻���ł��B
���Q�C���_�C�A�����A�J�b�g�I�t�_�C�A�����A���쒆�ɁA���ۂɉ����Ȃ���A
�����R�ɒ����\�ł��B�@�E�`�����l���p�A���`�����l���p�@�̂Q��ɕ����܂��̂ŁA
���ш斈�ɍ��E�o�����X�������\�ɂȂ�܂��B�@�ݒ�@�\�Ƃ��ẮA���̗v����S�Ė������Ă���܂��B
3���~��DCX2496�ł��ȒP�ɂł��܂��B�������p�����g���b�N�C�R���C�U�[��F���̓ʉ����_���ŕ�\�B
�p�\�R����ʂŃO���t�B�J���ɂ�����܂��B
�܂����ʂ̎�����A���X�ɃO���[�h���グ�āA�悭�Ȃ����̂��m���߂Ȃ��炪��Ƃ��Ē����y���߂�Ǝv���܂��B
���������M���Ȃ��ă|�`������A�����ƈ����Ă����̂��������Ƃ��̌o�����������܂��H
�����ԍ��F23189165
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@�����������܂��Ă���̂ŏ��Ԃ�
>�uLC�N���X�I�[�o�[�v�{SP�Q���G�[�W���O����ɂ́A�z���C�g�m�C�Y�܂��̓s���N�m�C�Y���A������x�̉��ʂŁA������x�̎��ԁA����Ă��������Ƃ͗������Ă��܂����ASP�Q�̃G�[�W���O�͍ς�ł���ł��̂ŁA�u�����̘A���v������uLC�N���X�I�[�o�[�v�A���ɐV�������R���f���T�[�B�A���G�[�W���O�������̂ł��B
�@�R���f���T�̃G�[�W���O���ǂ��ł����ǁA�A�b�e�l�[�^�O���Ē�R�l�𑪂��ČŒ��R�ɕς��������ǂ��ł���B
�@�I�X�X���́@DALE �̊�����RNS-10B�ł��B
http://www.kaijin-musen.jp/49.html
�@�l�̓X�s�[�J�[�̃`���[�j���O�ōŏ��Ɏ��t����̂��A�b�e�l�[�^�̊����Œ��R���ł��B
�@�܂݂̂����A�b�e�l�[�^�́A�����Œ��R�ɑS�����Ȃ��܂���B
�@�����ς��邾���ł������Ԃ�i�����܂��B
>�ǂ����ŁA���̖ړI�ɂ́ASP�̑���ɤ�R�OW �قǂ̔��M�d���i�������LED�d���ł͂Ȃ��A�G�W�\���^�C�v�̔��M�d���I�j��ڑ����ăz���C�g�m�C�Y�܂��̓s���N�m�C�Y�����Ă���낵���A�Ȃ�ċL�ڂ����������L��������̂ł����B����@���M�����ǍD�ȁA�Q�OW�قǂ̑�^�W����R���g���ׂ��ł��傤���H
�@�l�̓A���v�̃G�[�W���O�̂��߂̃_�~�[�X�s�[�J�[�Ƃ��ā@100W�̃��^���N���b�h��R�g���Ă��܂��B
�@����Ȃ�
https://jp.rs-online.com/web/p/panel-mount-fixed-resistors/1623595/
�@�����܂ł��p�l���}�E���g�^�C�v�Ȃ�ŁA����Ƀq�[�g�V���N�t������Ԃ�100W���M�������e�B�[���Ă���̂Ł@�P�̂Ŏg�����́@10W���炢��ڏ��ɂ�����������ł��B
�@�������Ȃ��ƉΏ����܂���
�@����ƁA�A�i���O�`�����f�o�����̂��ǂ����ȂƎv���܂��B
�@�^�C�����C�����g�̌��́A�����ɂ悵����ɂ��܂�������
>����������z�肵�Ă��郂�m�����S�����`�����f�o�́A�̂� SANSUI CD-10 �Ƃقړ��l�̕����ł��B
>https://audio-heritage.jp/SANSUI/etc/cd-10.html
>��H�}������܂����A�f�l�̎��ɂ́A���̉�H�̓����͂悭�����ł��܂���B
>BOWS����́A���̉�H�A�悭�����m�ł��ˁB�@
�@�l�́A�A���v��v���Ē��g��m���Ă���҂Ƃ��āA���̎�̃��[�e�B���e�B�̑����`�����f�o�͂���܂�D���ł͂Ȃ��ł��B
�@���[�^���X�C�b�`�Ŏ��g���I�����āA�X���[�v������I��������Ďg�����肪�ǂ���ł����A�����̃M�������e�B���������ł��B
�@�t�B���^�Ɏg��OPAMP�̃t�B�[�h�o�b�N���[�v��1mm�ł��Z���������̂ł����A�����ɃN���X�I�[�o�[���g���ؑւ̂��߂́@���g�����Ɍ��܂����l�̃R���f���T������܂��B
�@CD-10�̂悤�ȃ��[�^���[�X�C�b�`�Ŏ��g����ؑւ�����@�\���ƁA��`���[�^���[�X�C�b�`�`�R���f���T�`���[�^���[�X�C�b�`�`���cm�P�ʂŒ����Ȃ�A���̊ԁ@�U���m�C�Y���E�����������ăm�C�Y�}�[�W����������A���U�}�[�W�����オ�邽�߁A�ʑ��ۏؑ��₵�āi�A���v�̐��\�𗎂Ƃ��āj�Ώ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�v�͎G������������A�����݂����肷�郊�X�N�������܂��B
�@�A�L���t�F�[�Y�͂���������ā@�A�i���O�`�����f�o�̓��[�^���[�X�C�b�`�ł͂Ȃ��A�N���X�I�[�o�[���g�����̃t�B���^���p�ӂ��ĕ����I�ɑ}���ւ��Ă܂��ˁB
�@�����ȃ`�����f�o�́A���[�^���[�X�C�b�`��ւ����������ł����A�����i�قǁ@���W���[�������ւ��������Ă܂��ˁB
�@DAC�Ńn�C���]�̃��[�g���グ�Ă��A�����̃A�i���O�ŗ��Ă��܂��Ɩ{���]�|�̂悤��..
�����ԍ��F23189263
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����A���͂悤�������܂��B
�����������O���Ă��� DSD512, DSD256, DSD128 ������̍��i�ʉ���
�����ʂ͔F�߂܂����A��L�̌��ʂɔ�ׂ�Ƃ̂Lj����x�̃X���[�Y�������A
�����y�ő厖�Ȃ̂�20kHz�~�܂�A�X�s�[�J�[�̓��������傹��A�i���O�Ȃ̂ł�����ׂ������Ă�����Ȃ�ł�
���̎�|�A�悭�����ł���̂ł����ADSD512������DSD256������ SONICA DAC ��DA�ϊ�����������ׂ�ƁADSD512�����̕����A�������A�\�m���e�B�[�i�H�j�A�ɗD���̂ł��B������A�u�����P���x�[�����������v�ł��傤���H�@
���́A�����Đ��́u�������A�\�m���e�B�[�v���A���ɏd�v�����Ă��܂��B�������A����ɂ͒P�Ȃ� S/N�䂾���ł͂Ȃ��A�����̗v��������ł��邱�Ƃ͗������Ă��܂��B
���o�ɗႦ��Ȃ�A�A�����J�̃R�����h���n�̊����ȉ����̌��ƁA���{�̂���ȏ゠�蓾�Ȃ������ȉ����̌����r�ׂ�ƁA���炩�ɑO�҂̓������A���������D��܂��B����́A�����f�W�J���ŎB�e���Ă��A���m�ɈႢ�܂��ˁB�@���̍��́A��͂��C���̋͂��Ȑ����C�ʍ��i���x�������ł��j�A���V�����q�Z�x�̂킸���ȍ��i�����Ȍ��U���̍��j�A�܂��P���ɋC�������i�H�j�A�ȂǂɋA������ƍl�����Ă��܂��B�@�@
���̃V�X�e���ŁADSD512���� �� DSD256������DA�ϊ����Ē�����ׂ�ƁA���̎��o���̌��Ɠ����悤�Ȓ��o����������̂ł��B
�f�W�^���`�����f�o�ɂ���A�A�i���`�����f�o�ɂ���A�`�����f�o�����邱�ƂŁA���̂悤�ȁu�������A�\�m���e�B�[�v�ɂ����钮�o��̍��������������Ȃ��Ȃ�Ȃ�A�������`�����f�o�̑傫�Ȍ��E�̂ЂƂŁA�}���`�`�����l���ɍs�������X�̒��ɂ��ALC�l�b�g���[�N�ɖ߂��Ă���l�������Ƃ����A���R�̈�[�����m��܂���ˁB
�����ɂ悵������ABOWS������A�����I�ȁu�������A�\�m���e�B�[�v�̊ϓ_������A�f�W�^���`�����f�o���A�i���O�`�����f�o�ɗD��A�Ƌ����Ɨ������܂������A�����l���Ă�낵���ł����H
��3���~��DCX2496�ł��ȒP�ɂł��܂��B�������p�����g���b�N�C�R���C�U�[��F���̓ʉ����_���ŕ�\�B
���p�\�R����ʂŃO���t�B�J���ɂ�����܂��B
�Ċm�F�ł����ADCX2496�ł́A�Q���A����������@�\�ƃP�[�u����������Ă��āA�p�\�R��GUI�\�t�g����A���������ł���A�Ɨ������Ă��܂����A�n�j �ł����H�@�iHarman�{�ЂɊm�F�����Ƃ���ADBX VENU360 �ł́A�Q��̘A�������͂ł��Ȃ��B�j
�����ԍ��F23189634
![]() 0�_
0�_
BOWS����A���͂悤�������܂��B
���@�R���f���T�̃G�[�W���O���ǂ��ł����ǁA�A�b�e�l�[�^�O���Ē�R�l�𑪂��ČŒ��R�ɕς��������ǂ��ł���B
����A�����F����Ɏw�E����A���߂��܂��B
�����A��N�Ă� ATT�Q���A���ׂĊ��S�ɕ������Đ�āA�������P�̌��ʂɋ����܂����̂ŁAATT���Œ��R�ɕς������Ƃ͎v���Ă��܂��B����ł́A����́u�ד����I�v�Ƃ����l�������̂ł����A���y�W�������i���ɃN���b�V�b�N�ƃW���Y�j�ɉ����āAATT�ݒ������ɒ������邱�Ƃ�����̂ŁA�Ȃ��Ȃ��Œ��R���ɓ��ݐ�Ȃ��ł���܂��B
�ؑփX�C�b�`��t���āA�iSQ��TW�����ł����j�N���V�b�N�p�Œ��R�ƃW���Y�p�Œ��R��I���ł���悤�ɂ���A�A�A�̂́A���肩������܂���ˁi�j�B
���l�̓A���v�̃G�[�W���O�̂��߂̃_�~�[�X�s�[�J�[�Ƃ��ā@100W�̃��^���N���b�h��R�g���Ă��܂��B
���@����Ȃ�
��https://jp.rs-online.com/web/p/panel-mount-fixed-resistors/1623595/
���肪�Ƃ��������܂��B���B���܂��B
PC����̂��߂ɁA�M�`���O���[�X�⏭����^�̃q�[�g�V���N�́A�H��I�ɓ]�����Ă��܂��B�����āA�G�[�W���O���́A��@�̎㕗�ł��B�B�B
��DAC�Ńn�C���]�̃��[�g���グ�Ă��A�����̃A�i���O�ŗ��Ă��܂��Ɩ{���]�|�̂悤��..
�����ɂ悵����ւ̊m�F�Əd�����܂����A�����I�ȁu�������A�\�m���e�B�[�v�̊ϓ_������A�f�W�^���`�����f�o���A�i���O�`�����f�o�ɗD��A�Ƌ����Ɨ������܂������A�����l���Ă�낵���ł����H
�����ԍ��F23189657
![]() 0�_
0�_
BOWS����A����ɂ���
�����[�^���X�C�b�`�Ŏ��g���I�����āA
���X���[�v������I���������
�������̃M�������e�B���������ł��B
������������ăN���X�I�[�o�[�̃t�B���^���
�������I�ɑ}���ւ��Ă܂��ˁB
���邠��b�ŏ��Ă��܂��܂����B
�p�C�I�j�A��D-23�ł���āA���b�N�X�L�b�gA506���g���Ă܂�����B����40�N�O�̘b�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F23189664�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������A�����Y��Ă���܂����B
�A���v��k�b�l�b�g���[�N���A�i��R�_�~�[�r�o���q���Łj�G�[�W���O����ۂɎg���ׂ������́A�s���N�m�C�Y���œK���Ǝv���܂����A�@���ł����H
���̍ۂ̉��ʂ�A�K�ȃG�[�W���O���Ԃɂ��Ă��A�������������B
�����ԍ��F23189667
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@�G�[�W���O�@���ɃE�[�t�@�[��ΏۂƂ��Ȃ��ꍇ�ŃL�[�ɂȂ�̂́A�����悪������������Ă��邱�Ƃł��B
�@�z���C�g�m�C�Y���ǂ���ł����A�炵�Ă���Ƌ����܂��i�j
�@�ŁA�����̃C�x���g�ň�i�ق̐������A����̂����炬�����Ă�����ł����A�R�����Ǝv���܂����B
�@����̂����炬����̉���g�`���Ă݂�Ƃ�������������������Ă���̂Ł@�l�͂����������W�̎��R���ŃG�[�W���O���邱�Ƃ������ł��B
�����ԍ��F23189693
![]() 0�_
0�_
BOWS����
���肪�Ƃ��������܂��B
���́u����̂����炬�v�������Ă���G�[�W���O�pCD�A�����A�R�C�Y�~�����̎�C����A����A�����ĉ������A�Ɗ��߂��܂����B
���̉����A�ǂ����l�b�g����_�E�����[�h�ł���悤�Ȃ�A�����N���������������B�����T���Ă݂܂��B
�������A�_�~�[�r�o��R�����āA�Â��ɃG�[�W���O���܂���I
�G�[�W���O���̃{�����[���ƁA���ԁA�ɂ��Ă��������������B���
�����ԍ��F23189756
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�ēx�ABEHRINGER�W�����Ă��܂����B
�D�w�̂��߂ɁA�����m�Ȃ炲�����������B
�A�i���O�`�����f�o CX3400 V2
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19057/
https://static.bhphotovideo.com/lit_files/84883.pdf
�́A���m�������[�h�ł͂S�`�����l���Ή��ŁA�u�f�B���C��v������܂��B
Filter �́ALinkwitz-Riley 24 dB/Oct �ł��B
�r�n�m�h�b�`�@�c�`�b�@���� XLR �œ��͉\�ł��B
�ǂ̂悤�ɁA�����ɂȂ�܂����H
�����ԍ��F23189827
![]() 0�_
0�_
dualazmak����A����ɂ���
�������ɂ悵������ABOWS������A�����I�_����A�f�W�^���`�����f�o���A�i���O�`�����f�o�ɗD��Ɨ������܂���
���ʒʂ�ł��B
��DCX2496�ł́A�Q���A����������@�\�ƃP�[�u����������Ă��āA�p�\�R��GUI�\�t�g����A���������ł���Ɨ������Ă��܂��B
�{�̓��m��RJ45�łȂ��APC��ʂŐؑւ��������Ǝv���܂��B������PC����̓p����������Ȃ̂ō��ǂ��H�ł���
��DBX VENU360 �ł́A�Q��̘A�������͂ł��Ȃ��B
���EUSB�Ȃ̂Ŋe�X�Ȃ���PC��Ő�ւ��Ŏg���܂��H
1���3WAY��L/R�Ƃ����L/R�A�����܂�
2��ڂ�ST��L/R�Ƃ����L/R�A�����܂��B
�A���ƌ����Ă��N���X���g�����炢�H�Ȃ̂�L/R�ŕ����Ċe�X6WAY�ʼn^�p�̕��������₷�����ł��B
�p������������������PC�͌������Ȃ����ǁAUSB�͂��������]���Ă�����Ȃ̂�VENU�̕����v���V�����̂ō����I�Ȃ̂ł́H
�� CX3400 V2�͂ǂ̂悤�ɁA�����ɂȂ�܂����H
PA�@�ނ�g�߂ȉ��i�Œ��������|���V�[�݂����ȃ��[�J�[�ł�����13,000�͂�肷�������A
���̃R�X�g���������ȃ��[�J�[�ł������ǂ��f�B���C��͕s���ƌ��_�t�����̂ł́H
�����ԍ��F23190023
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
����DBX VENU360 �ł́A�Q��̘A�������͂ł��Ȃ��B
�����EUSB�Ȃ̂Ŋe�X�Ȃ���PC��Ő�ւ��Ŏg���܂��H
�������A���ꂪ�ł��邱�Ƃ́ADBX�{�Ђɂ��m�F�ς݂ł��B
���A���ƌ����Ă��N���X���g�����炢�H�Ȃ̂�L/R�ŕ����Ċe�X6WAY�ʼn^�p�̕��������₷�����ł��B
�����A��������Ȃ�A�f�W�^���`�����f�o�ł��A�A�i���O�`�����f�o�ł��A���߂���Q��ŁAL/R�ŕ����Ċe�X6WAY�ʼn^�p�������ł��B
���p������������������PC�͌������Ȃ����ǁAUSB�͂��������]���Ă�����Ȃ̂�VENU�̕����v���V�����̂ō����I�Ȃ̂ł́H
�����Ȃ�ł���ˁBUSB�|�[�g�́A�����]���Ă܂��ˁB
USB-RS232C�A�_�v�^�́A�Q�Z�b�g�����Ă܂����AVENU360 ��USB�ڑ��̕����֗��Ŋm���ł��傤�ˁB
�F�X���[�U�[���r���[�����Ă���ƁA�����I�ɂ́A�f�W�^���`�����f�o�ł��A�A�i���O�`�����f�o�ł��ADBX�� BEHRINGER �ɗD��悤�ł��ˁB
�����ԍ��F23190097
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h���A���X���U�C���ɂȂ��Ă܂���܂����̂ŁA�����ŁA��U�A���߂����Ă��������܂��B
�^�C�g�����u�`�����l���f�o�C�_�[�ŕ�����Ƀo�����X�����x�������H�v�@�ɑ��鎄�̗����́A
�P�D�w����\�ȃ��H�����[��������A�b�e�l�[�V�����ɂ́A�l�X�ȕ��������邪�A��������Ɉ꒷��Z������A���C�����x���̕i�ʂ𗎂Ƃ����Ƀ��x����������œK�ȕ��@�͂Ȃ��B�x
�Q�D�w��������\�ȃ��x���ŁA�`�����f�o������ɁA�M���i�ʂ𗎂Ƃ����Ƀo�����X��x�������@�\���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�x
�R�D�w�}���`�A���v�V�X�e���\�z�ɂ́A����ł̓f�W�^���`�����l���f�o�C�_�[���g���A�`�����f�o�ʉߌ�̐M���́A��i�Ȃ�ׂ��H�j��������邱�ƂȂ��A�p���[�A���v�ɓ��͂���ׂ��ł���B�x
�ƂȂ�܂����B
�����ɂ悵����ABOWS����A�����̖L�x�Ȃ������A������A�������A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�`�����f�o�ʉߌ�̃A���v�Q�̑I���ɂ��ẮA���ꂼ��ɕK�v�Ƃ����u�i�ʁv�Ɓu�쓮�́��o�́v���l�����A�T�d�Ɍ����������܂��B�@���i�ʂȁi�v�����ƃp���[���̕������\�ŁAXLR�o�����X���͉\�ȁj�v�����C���A���v���g���\���́A�ˑR�Ƃ��Ďc���Ă���܂��B
�܂��A�}���`�`�����l������T�d�Ɏ��s����ё̌�������ɁA�����������āA�����LC�l�b�g���[�N���ɖ߂�\��������܂��̂ŁA�V�K�ɓ�������A���v�Q�́A��������ۂ̃��Z�[���o�����[���悭���Ă��Č��肵�����ƍl���Ă���܂��B
�K�v�ɉ����āA���́u�X�s�[�J�[�Ȃ�ł��f���v�ŁA�܂��X���b�h�𗧂Ă����Ă���������������܂���B
���̍ۂɂ́A���������A��낵�����t�������̂قǁA���肢�\���グ�܂��B
�������A���̃X���b�h���p�����Č��܂��̂ŁA�lj��̏��₲�������������܂�����A���m�点�������B
�����ԍ��F23190887
![]() 2�_
2�_
dualazmak����A����ɂ���
��DBX�� BEHRINGER �ɗD��
BEHRINGER�͓����̃A�i���O���S�������Ƃ������d�����L�b�g�Ŕ����Ă���i���B�j�A���o�͂�A/D�ADAC���O���ɏo���i���o�j����������@������܂��ADBX��������������܂����������Ƌt�]������̂��ʔ������E�ł��B
���g����NS-1000�ł������ɂ�鉹������ŁA�|���u���ł͓����Ȃ����̂�������ꂽ�Ǝv���܂��B
�}���`�ɂ���ƃ��j�b�g�̞g���Ȃ��Ȃ���ނ��o���ɂȂ��Ă���̂łƂ܂ǂ���������܂��A�����̎��R�x����C�ɍL����܂��̂Ń��j�b�g���m�̂����ƃx�X�g�ȃN���X���g���Ƃ��X���[�v���������ė����肵�܂��B
�������LC�l�b�g���[�N���ɖ߂�\��������
�����ł��r���t�����g2�{�ɃA���v�̎R�ɋ^�������LC�l�b�g���[�N�ɖ߂����������Ă��܂��̂ł��邩������܂���A
���RLC�l�b�g���[�N�Ƀ}���`�̌��ʂf�����܂����̂Ń}���`�Ƀg���C���ē�����̂������Ǝv���܂��B
���K�v�ɉ����āA���́u�X�s�[�J�[�Ȃ�ł��f���v�ŁA�܂��X���b�h�𗧂Ă����Ă���������������܂���B
���͏����ł��ˁB
�����ԍ��F23191552
![]() 1�_
1�_
>�����ɂ悵����ւ̊m�F�Əd�����܂����A�����I�ȁu�������A�\�m���e�B�[�v�̊ϓ_������A�f�W�^���`�����f�o���A�i���O�`�����f�o�ɗD��A�Ƌ����Ɨ������܂������A�����l���Ă�낵���ł����H
�@�����v���܂����A�ŏ��̓f�W�^���ł��낢��J�b�g�A���h�g���C������ăX�L����g�ɒ����Ă���A�f�B�o�C���f�B���O�l�b�g���[�N��A�i���O�`�����f�o�Ɏ���o�����ق����A��������܂ł̎��Ԃ��Z���čς݂����ł��B
>���̉����A�ǂ����l�b�g����_�E�����[�h�ł���悤�Ȃ�A�����N���������������B�����T���Ă݂܂��B
�@�l���g���Ă���̂͗F�l�����^���Ă�������ł���
�@�T���Ă݂�Ƃ���Ȃ̂��ǂ������ł��B
https://www.youtube.com/watch?v=64eIdY9GQN4
https://www.youtube.com/watch?v=5_WOKisJBdg
�@����{�쒹�̐��������ł����A���̖ړI�ɂ͖쒹�̐��͗v��Ȃ�(^o^)
>�A�i���O�`�����f�o CX3400 V2
�@�^�C���A���C�����g�̕K�v����F�����đg�ݍ���ł����̂��낤�Ǝv����ł����A�ǂ�����Ēx�������Ă��邩��ł��ˁB
�@�܂��A�}���`�A���v�͈�ؓ�ɍs���Ȃ��ł��傤���@������x�̕���Ǝ��Ԃ��x����Ȃ��Ɣ��f�ł���Ƃ���܂ōs���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@��C�ɐ��������悤�Ƃ����ɁA�s�x�@�_��ɔ��f���ꂽ�����ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23193424
![]() 2�_
2�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�����m���ɁA�I�m�ɁA�t�H���[���Ă��������A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�T�d�Ɍv�悵�āAstep-by-step �Ŏ��g�ޏ����ł������܂��B
��i�̃A���v�Q�́AFoolish-Heart����������������������A
http://www.nmode.jp/product/x-pw1-mk2/
���u���m�������[�h�v�ŗ��p���邱�Ƃ��������ł��B�u���m�������[�h�v�ł́AXLR�o�����X���͂��ł��āA�{�����[���������\�ł��̂ŁA���E�o�����X���e�Ղɔ������ł��A�A���v�����ł̃N���X�g�[�N�������[���ɂł��܂��̂ŁB�B�B�B�@�������ă{�����[�����قڌŒ肷��A�}�X�^�[�{�����[���́A�����̃v���A���v�܂���DAC�̃{�����[���ōs���K�v������܂����A�`�����f�o�ւ̓��͂Əo�͂́A�������x���Ɉێ��ł��܂��̂ŁA���̈Ӑ}�ɉ������V�X�e���ɂȂ�܂��B
�����āAX-PW1-MK�U�́A���m�������[�h�ł̗��p�ł��A���i�I�A�\�Z�I�ɂ͋��e���ȁA�Ƃ��v���܂��̂ŁA�܂��P����肵�āu���F��X�s�[�h���A�o�̗͂]�T�v�Ȃǂ��������Ă݂����ƍl���Ă���܂��B
����ł́A�A�A
�Q�����{����̕č��o�������ď����ɒǂ��Ă���܂��B�A������Ă���u���O���ꂽ���Ɉ��������ւ̓W�J�v�ɂ�����ł���A���炭�߂�Ȃ��Ȃ�\���������A�䂪�Ƃł̖{���I�[�f�B�I���y�Ɏ�肩����̂́A������ɂȂ肻���ł��B
������A�u�X�s�[�J�[�Ȃ�ł��v�f���̐V�X���b�h�ŏ������A�����������肢����ۂɂ́A��낵�����t�������̂قǁA���肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F23193733
![]() 2�_
2�_
dualazmak����A����ɂ���
���č��o�������ď����ɒǂ��Ă���܂��B
�����炭�߂�Ȃ��Ȃ�\��������
�����ł̓t�F�[�Y6���ۂ��Ȃ��Ă��Ă܂����A
�ǂ������������������B
��X-PW1-MK�U�́A�\�Z�I�ɂ͋��e���ȁA
���Ƃ��v���܂��̂ŁA�܂��P����肵��
�}���`�Ȃ̂Ŏ�Ԃ͈����ȃA���v��ch�m�ۂ��A�̂��ɒu���ς��������悢�̂ł́H(�����̊��o�Ⴂ�H)
����Ɠd���X�C�b�`�ł����A�����ł̓v���A�܂Ƃ߂�CDV�A�p���[��3�̑��삪����ώG�Ɗ����Ă��܂��B�@��z�u������A�g��������������K�v�ł��B
�����ԍ��F23195529�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�h���X���b�h�Ƃ��āG
�y�\�t�g�E�F�A�`�����l���f�o�C�_�[ EKIO�z�@�@�i2020/02/06 09:18�j
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
��݂��Ă���܂��̂ŁA����������������������B
�����ԍ��F23213144
![]() 1�_
1�_
���ݕ\��̃X�s�[�J�[�̍w�����������Ă��܂��B
���킹�ăA���v�̍w�����������Ă���̂ł����A
�����X�s�[�J�[���A���v�����S�҂ł���ׁA�A�h�o�C�X��������K���ł��B
���ݍl���Ă���̂́ATEAC UD505+AP505 �ł��B
�莝���̃w�b�h�z�����g���������߁A���̂悤�ȍ\�����l���܂����B
�g�p���͎����̃p�\�R���f�X�N�ł��B
�S�z�Ȃ̂́A�o�͂ɂ��Ăł��B
Autograph mini/gr (8��)�̘A�����e���́iRMS)�����Ă݂�ƁA50W�ł����B
AP505�̒�i�o�͂́A
STEREO�ABI-AMP���쎞
115W + 115W (4���A1kHz�ATHD 0.8%)
70W + 70W (8���A1kHz�ATHD 0.8%) �ƂȂ��Ă��܂��B
����́A���ʂɎg�����ꍇ�ƃo�C�A���v�g�p�����ꍇ�ŏo�͓͂����Ƃ������Ƃł��傤���c�H
���͕��ʂ�STEREO�Ŏg���\��Ȃ̂ł����A
�X�s�[�J�[��RMS��50W�ŃA���v�̒�i�勭����70W�Ƃ����Ƃ���ɕs��������܂����B
��͂�A�p���[�A���v�̏o��<�X�s�[�J�[�̋��e���͂��]�܂����̂ł��傤���H
���S�҂Ȏ���Ő\����܂��A��낵�����肢�v���܂��B
�܂��A���̃X�s�[�J�[�ɃI�X�X���̃A���v������܂�����A�h�o�C�X������Ɗ������ł��B
�����ԍ��F23202902�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��ScTO����
�^���m�C�̏��^�X�s�[�J�[��2��A�^���m�C�̗����
FYNE AUDIO��1�험�p���Ă�҂ł��B
�^���m�C�̃X�s�[�J�[�͒ʏ��LUXMAN��T���X�C�̏d�ʋ��A���v��e�N�j�N�X�̒����A���v�𗘗p���Ă܂����A
�ŋ߃����e���ꂽ�A�p�� �I�[���E�f�U�C���Ё@Aura�@Evolution VA100�U(MK�U) �v�����C���A���v����肵�܂����B
���^�̃A���v��60W(8��)�̃��f���ł��B
���ɓ����p�����Ȃ̂��A�r�[�g���Y��N�C�[���̋Ȃ��Ɖ��̃����n����X�s�[�h�����������܂��B
�p�����A���v�͍������Ǝv���܂��B
�V�i����
https://s.kakaku.com/kaden/integrated-amplifier/itemlist.aspx?pdf_ma=652
�����ԍ��F23202950�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��ScTO����
�A���v�o�͂��X�s�[�J�[���e���͂��z���Ă��Ă��S����薳���ł��B
�S�{�z���Ă���A���v���g���Ă��܂������A���̖������������ł��B
�o�C�A���v�쓮����Ɠ��̃A���v�Œቹ���쓮����Ǝv��ꏟ���ł����A���ŋ쓮���Ă��܂��B���������l�ł��̂ŁA�X�e���I�Đ��Əo�͕͂ς��܂���B
�����ԍ��F23202991
![]()
![]() 0�_
0�_
ScTO����A����ɂ���
��STEREO�A115W + 115W
��BI-AMP�A70W + 70W
�����ʂɎg�����ꍇ�ƃo�C�A���v�g�p�����ꍇ��
���o�͓͂����Ƃ������Ƃł��傤���c�H
�o������E���Ⴄ�����A�������ʂȂ瓯�����b�g���o�Ă���Ǝv���܂��B
���X�s�[�J�[��RMS��50W��
���A���v�̒�i�勭����70W
RMS�͘A�����͂ŁA���y�͎R�J���������A�A���ɂ���Ƃ������������b�g�A���ʂɎg���ɂ͑S�����Ȃ��Ǝv���܂��B(�C�ɂ����g�����炢�����ł��傤���H)
�����ԍ��F23202996�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 0�_
0�_
��ScTO����
���͂悤�������܂��B
���́A�I�[�g�O���t�E�~�j�̓��b�N�X�}����l-505uX�U���g���Ė炵�Ă܂��B
�A�L����E-470�ł��炵�Ă��܂������A��͂莄�ɂ̓��b�N�X�}���̂������肭��̂ŁA���b�N�X�}���g�p�ł��B
���Ȃ݂ɁA���̊F�l������������Ă��܂����A�A���v�̍ő�o�͂Ƃr�o�̍ő���͂͋C�ɂ��邱�Ƃ���܂���B
�܂��A��ʉƒ�ł���A2�`3�v�Ŗ炵�Ă����\�ȉ��ʂɂȂ�܂��̂ŁA20�`30�v�Ŗ炷�ƌ����̂͂܂������Ǝv���܂��B
�܂��Ă�ő���̓I�[�o�[�ɂȂ������ƁE�E�E��������A���v�d�����ꂽ�܂܂r�o�P�[�u�����Ƃ��̎�舵���~�X�̕���
�댯�ł��B
���Ȃ݂ɃA���v�d�����ꂽ�܂ܐڑ��@��(�A���v����)���āA�A���v�Ƃr�o���Ă������e�����͎̂��ł��B
����ȏo�͂��g���̂͑���a�E�[�t�@�[�g�p�̑�^�t���A�^�C�v���炢�ł́H�@�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23203021
![]()
![]() 4�_
4�_
�o�C�A���v�ł͏o������E�������ł��B
AP505�Ȃ�o�C�A���v�쓮���ABTL�ڑ����ăo�C���C�������O�������߂��܂��B
�����ԍ��F23203026
![]() 0�_
0�_
�Ԃ��Ē�o�̓A���v�ōő剹�ʁA�����Ԏg�p������̂��댯�ł́H
�����ԍ��F23203099
![]() 0�_
0�_
��ScTO����
�䎿��̓��e�����e�ł��̂ŁA�����͂�����
YouTube �� TANNOY Autograph mini/gr �̉��ł������Ă��Ƃ͂������̂��͂łŌ��߂�ꂽ�炢�����ł��傤���H
https://www.youtube.com/results?search_query=TANNOY+Autograph+mini+gr
�����ԍ��F23203146
![]() 0�_
0�_
�q�[�A�����́B
�X����l�A����̌����ł����I�A
���̃^���m�C�̃X�y�b�N���l����H�A
�����ǂ�ȃA���v�w�}�b�L���̃Z�p���\�Ƃ�����D���x�ł��A��薳���点�܂���I�B(��)
�ǂ��炩�ƌ����ƁH�A���݂̊��ʼn��o���������Ē����āA���̍Đ��������m�F���āA�������ǂ��āE�����������̎��ȕ��͒����āA���̓��e�𐧍ق��Z�߂čēx���e���������F����̂������Ƃ̗��ꓙ�͔@���ł��傤���H�B
�����H�A�w5W�{5w�̐^��ǁx�ł��A�w20w�{20w�̒���D���x�ł��A�w200w�{200w�̃}�b�L���̃Z�p���\�g�x�ł��I�A
�g�e�X�̑���i���͕��j�h �̍Đ��o�������ł�����ˁ`�I�B(��)
�ꉞ����̊ϑ��ł��I�A�Q�l���ɁB
�������炸�A�h��B
�����ԍ��F23205929�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��fmnonno����
�������߂������Ē����Ă��肪�Ƃ��������܂��I
����̎Q�l�ɂ����Ē����܂�
��Minerva2000����
���肪�Ƃ��������܂��I���S���Ďg�����Ƃ��ł��܂�
�������ɂ悵����
���肪�Ƃ��������܂��A�C�ɂ����g���Ă݂܂�
���Â����̑�D������
����肪�Ƃ��������܂�
�A���v��SP�Ă�����͕̂|���ł��ˁc�C�����܂��I
���I���t�F�E�X����
�Ȃ�قǁc�����������̂Ȃ�ł���
��Naim ND555 enthusiasts����
���Љ���������肪�Ƃ��������܂�
�������Ă݂܂����ASP�I�т͓���ł���
���f�[��-�G��������
�A�h�o�C�X�������肪�Ƃ��������܂��I
�����ԍ��F23211778�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�V�����z�[���V�A�^�[�����āA���t���Ă���Z���^�[�X�s�[�J�[�̈ʒu�����܂炸�Ƃ肠�����ʼn��ɃX�s�[�J�[�ł��̏�Ƀ��j�^�[��u���Ă����ł����A������Ă����̂ł��傤��?
���j�^�[�A�[�������t�������������̂ł��傤��?
���肢���܂��B
![]() 4�_
4�_
End_098����A����ɂ���
�Z���^�[�́A���j�^�[���ɒu���̂���ʓI�ł��B
���j�^�[�A�[�����g���������A���Ǝv���܂��B
�������j�^�[���E�Ƀt�����g�X�s�[�J�[������Ȃ�
�Z���^�[�̉����t�����g�ɐU�蕪���A�Z���^�[���X�Ŏg�����@���悭����܂��B
�Z���^�[����A�Z���^�[���X�Œ�����ׁA�������藈����Ŏg���悢�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23204021�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 1�_
1�_
�X�s�[�J�[�ɒ��Ƀ��j�^�[��u���Ă��邪�e�����邩�Ƃ������ƂȂ�A�����ɉe������ł��傤���ǂ悭�����邩���������邩�̓P�[�X�o�C�P�[�X�ł��傤�B
�����ԍ��F23204064
![]() 3�_
3�_
End_098����
�X�s�[�J�[�����j�^�[�̑���Ȃ�A��ʓI�ł͂���܂���A���݂܂���������܂��B
���b�N���Ă̂���̂���ʓI���Ǝv���܂��B
���ɂ̂���̂͐l���ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA���b�N�g�����A���j�^�[�A�[�����܂ߕǕt�����悳�����ł��B
�����ԍ��F23204298�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�Z���^�[�X�s�[�J�[�̓Z���t�Ƃ����C���̉����o���X�s�[�J�[�Ȃ̂ŁATV�̈ʒu����݂ċɒ[�ɏ�̕��Ƃ����̕����Ɛl��TV�̐^�Œ����Ă�̂ɐ��͏�̕����璮������A���̕����璮������Ƃ��Ȃ邾�낤���Ǖ����Ĉ�a���Ȃ��������ł����ł�������Ȃ��H
���j�^�iTV�j�̉��ɃX�s�[�J�[���Ă����̂͑O�iTV�̏ꍇTV��̏�j�ɒu���Ɖ�ʂ�������ƉB�ꂿ�Ⴄ����Ƃ��ȂƎv�����ǁA������a���Ȃ���ʂ̉B��Ȃ��Ƃ��������炻�̂܂܂ł����Ǝv��
�������ɂȂ��Ǝv�����ǃX�s�[�J�[�̏��TV���ڂ��Ă�Ƃ��������炻��͂��Ȃ��ق����������낤��
�����ԍ��F23204363
![]() 2�_
2�_
��End_098����
����ɂ��́B
�u�Z���^�[�X�s�[�J�[�̏�ɕ���?�v�Ƃ����\�肩��@����ɁA�Z���^�[�X�s�[�J�[�̏�Ƀ��j�^�[���u���u���v���Ă���Ƃ������ł���ˁH
�ǂ�ȃX�s�[�J�[�A���j�^�[���͕�����܂��A��ʓI�ȃZ���^�[�X�s�[�J�[�ɂ����ẮA���[�J�[�͏�ɒ��Ƀ��j�^�[��u�����Ƃ͑z�肵�Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
���j�^�[���u���肵�����ɒu���v�Ƃ������ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A�Z���^�[�X�s�[�J�[�̖ʐς̖�肾���łȂ��A�����o��Ώ��Ȃ��炸�U�����邱�Ƃ����܂���ƁA�Z���^�[�X�s�[�J�[�̏�ւ̒��u���͔����������ǂ��Ǝv���܂��B
�l�I�ɂ̓��j�^�[�A�[�����g�p����̂���낵�����Ǝv���܂���B
�����ԍ��F23207533
![]()
![]() 3�_
3�_
��End_098����
���j�^�[��ʂɐG���ĐU�����Ă���悤�Ȃ�~�߂������ǂ��Ǝv���܂��B
���Ƃ͕s����łȂ���Ηǂ��ł��傤�B
�����ԍ��F23207751�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 0�_
0�_
�F���肪�Ƃ��������܂��I
��������l���܂��ˁI
�����ԍ��F23207764�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�X�s�[�J�[]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
-
�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�X�s�[�J�[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j