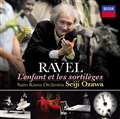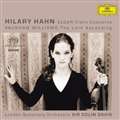���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S2594�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2016�N2��24�� 21:54 | |
| 663 | 200 | 2016�N2��24�� 21:48 | |
| 2 | 4 | 2016�N2��23�� 23:12 | |
| 13 | 10 | 2016�N2��20�� 13:06 | |
| 11 | 5 | 2016�N2��20�� 11:44 | |
| 5 | 4 | 2016�N2��18�� 17:34 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
etymotic research�̃C���z���̉����D���ŁAPC�ł�ER4�A���o�C���ł�hf5�����p���Ă���܂��B
���������ꂸ���ꂢ�ɖ�A���̕���\���D��Ă���Ƃ��낪�D�݂Ȃ̂ł����A
�����������蒷���ԑ������Ă���Ǝ������邽�߁A�����悤�ȉ��̌X���̃w�b�h�z����T���Ă��܂��B
�����Ŏg�p����\��Ȃ̂ŁA���R�ꓙ�͋C�ɂ��܂���B
��낵�����肢���܂��B
![]() 1�_
1�_
�������������܂��B
���������X���Ƃ͌����܂��APreSonus��HD7��SHURE��SRH440�͑S�̓I�ȃt���b�g���Ɖs�߂̍����ŋC�ɓ������ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B�������������B
�����ԍ��F19544498
![]()
![]() 0�_
0�_
m40x�Ƃ�k271mk2�Amdr-7506�Ȃǂǂ��ł��傤�H�������͐����ȂƂ���A�����������z�ȕ����ǂ��Ȃ���̂������ł��B
�����ԍ��F19545399�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 0�_
0�_
Bang&Olufsen�@B&O Play Form 2i LE
������ƂP�������܂����ǁA�A�A
�����ԍ��F19548316
![]()
![]() 0�_
0�_
�F�l�A�x��Ă��݂܂���B��Ă��肪�Ƃ��������܂����B
���X�܂Ŏ������J��Ԃ��AATH-AD500X���w���������܂����B
�ŏI�I�ɑ������̗ǂ��őI���������ߑS���������ꂽ���̂�I�Ԍ��ʂƂȂ�A���݂܂���ł����B
�����ԍ��F19626380
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h����̑����ł�
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=19478842/
�d�����Z�����̂łȂ��Ȃ��ԐM�ł��Ȃ������ł����A�F����̍l���������ė~�����ł�
�����ԍ��F19589777�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
�e�r����
���̃��C�u�ł��d�C��ʂ��Ă������A�����ł͂Ȃ��Ǝv���܂�
�����ԍ��F19589782�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
�}�X�^�[���������Č����Ă��Ȃ��́H
�����ԍ��F19589794
![]()
![]() 6�_
6�_
�����O����
�����̃��C�u�ł��d�C��ʂ��Ă������A�����ł͂Ȃ��Ǝv���܂�
���Ă����ƁE�E���O����̍l���錴����
�L�[�{�[�h�FNG
�G���L�M�^�[�FNG
���̑��d�q�y��S�āFNG
���Ă��Ƃł���ˁH
JAZZ�{�[�J�����d�C�����ł����炱���NG�ł��ˁB
���Ȃ����~�N�̂悤�Ɍ��������݂��Ȃ��Ȃł��u����炵���v�Đ�����̂��I�[�f�B�I�̖ʔ����Ƃ��낾�Ǝv����ł����E�E�E
�F����͂ǂ��v���Ă��܂����H
�����ԍ��F19589818
![]() 10�_
10�_
�����т��单����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂�
�m���Ƀ}�X�^�[�����������Ƃ���Ȃ炽���ւ�킩��₷���ł�
�����������̉����Ė����ł�����A���f�̂��悤�������ł����
�����ԍ��F19589838�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
�����e�r����
�d�q�@����g�����������܂߂�Ƙb����₱�₵���Ȃ邩�Ǝv���܂�
�Ⴆ�Ώ����~�N�Ȃ炻����쐬���Ă�����̋@����ł̏o���������ɂȂ邩�Ǝv���܂�
�����ԍ��F19589858�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
�����O����
���d�q�@����g�����������܂߂�Ƙb����₱�₵���Ȃ邩�Ǝv���܂�
�����邱�Ƃ͗����ł��܂��B
����܂��B
�����E�E�E���O����̒�`�ł͌����Đ����Ĕ��ɋ����Ӗ��ł̉��ł����Ȃ��E�E�Ɗ����܂��B
�܂�E�E
���݈�ʂ̕����u���y�v�Ə̂��Ă��郂�m��9�����́u�����Đ��v�ł͂Ȃ��B
�ƂȂ�܂����E�E�E�\���܂��ˁH
�����ԍ��F19589886
![]() 8�_
8�_
�����e�r����
���������b�ł����ACD��n�C���]��SACD�Ɍ������܂܂�Ă���Ǝv���܂����H
�召����lj��H���ꂽ���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł����
�����ԍ��F19589903�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
�Ȃ��Ȃ�������ł��ˁB
���t�ҁi���y�̍���j����������������ɓ`�������Ǝv�������u�����v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁB
����ēd�C���g�������A�����t���낤���W�����Ǝv���܂��B
�����A�`�B����Ԃɏ����������ς���Ă����܂����A�����肪������������ǂ������f����͖̂����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F19589909
![]() 8�_
8�_
�����O����
��H
���O����͈�ʓI�ȉ��y�}�́i�n�C���]�ECD���j�ɂ����錴���Đ��͑��݂��Ȃ��Ƃ��l���Ȃ�ł����H
�����ԍ��F19589918
![]() 6�_
6�_
�����e�r����
���̒ʂ�ł���
�����Đ���ڎw���Ȃ�A����PCM���R�[�_�[�����g���Đ��^���邵���Ȃ��Ǝv���܂�
�����ԍ��F19589930�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
�����O����
�������Đ���ڎw���Ȃ�A����PCM���R�[�_�[�����g���Đ��^���邵���Ȃ��Ǝv���܂�
�Ȃ�ق�
�Ƃ������Ƃ́E�E���y�Đ��ƌ����Đ��͑��e��邱�ƂȂ��ʕ��ł���ƌ������Ƃł����H
�����ԍ��F19589969
![]() 6�_
6�_
�Ȃ̂�
�����т��单����̏������݂̗l��
�I�[�f�B�I�̐��E�ɂ����Ă�
�G���W�j�A�̎v�������߂�ꂽ�}�X�^�[�������������Ƃ���̂��Ó����Ǝv���܂�
�����ԍ��F19589972�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
�l�I�ɂ́u�����Đ����ĉ��ł����H�v����Ȃ��āu�N�����ǂ��Ɗ����鉹���ĉ��ł����H�v�Ȃ�ł����B
���̌��t�����{�l�����̌��t�̎w�����̂���̓I�ɋq�ω��o����`�ŗ������Ă͂��Ȃ��悤�Ȃ�ŁA
���̂悤�Ȃ��̂��{���Ɏ��݂���Ȃ猩��(������)�݂����Ƃ����{��������܂����ǂˁB
�g�݂�Ȃ��ǂ����Ċ�����ɈႢ�Ȃ��ƃ{�N����M���Ă�܂Ȃ����h�ł͂Ȃ��g�{���ɂ݂�Ȃ��ǂ����Ċ����鉹�h�����݂��邱�Ƃ��ؖ����ė~�����B
�łȂ�����̎咣�͐��藧���܂���B
�����ԍ��F19589976
![]() 6�_
6�_
��air89765����
���I�ɂ̓X���b�h���r�炵�����Ȃ���ł���
�Ȃ̂ł����Ă��̕\��ɂ��܂���
�����ԍ��F19589992�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
��̏������݂ŕ��c�������o���Ă��܂����悤�ł����A�܂������Ƃ͐����̂��Ƃł���ˁB
�e�r�Ă���̋�ʂ�A�L�[�{�[�h��G���L�M�^�[���̃��C���o�͂����y��̓A���v��ʂ������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����~�N�ɂ��Ă����̐��������ł���ƌ����܂��B���̓T���v�����O���ꂽ���ł����A���i������^���̑ΏۂƂ��Ċm�����Ă���ȏ㌴���ƌ����Ă��܂��Ă����Ȃ��ł��傤�B
�����āA��̃X���Ŏ��������������Đ������C�u�Č��Ƃ����̂����X���\�����܂����i��
�m���ɒʏ�̃��C�u�ł͉��t��PA�����肾�Ƃ���Ȃ��̍Č����Ă������ʔ�������܂���B���ہA���C�u�����R�[�f�B���O�������̂�CD�����ꑽ���o����Ă��܂����A�ǂ��^���̂��̂͒��������Ƃ�����܂��B�N���V�b�N�͂��̐�����ǘ^�����������邱�Ƃł��傤���B
�����Đ��Ƃ͂��̂܂܂̈Ӗ��ŗ��z�ł��B
�A���A�I�[�f�B�I�ň�ʓI�ɑÓ����Ǝv������e�ƂȂ�ƁA���̗��z�ɋ߂Â���Ƃ����b�ɂȂ��Ȃ��ł����ˁB
�R���g���[�����[����}�X�^�����O�X�^�W�I�ōĐ�����Ă��鉹���Č��ł������Ӗ����z�ł����A�����Đ��Ƃ͂܂������Ⴄ�ł��傤�B��̃X���ŏq�ׂ܂������A�}�̂��f�W�^���ł���ȏ�A�^���Ŋ��Ɍ����͎����Ă��܂�����B���ǂ͌����Ƃ̌덷���k�߂邱�Ƃ����ł��܂���B�ߊϓI�ɂȂ��Ă��܂��܂������A���̍����k�߂�ɂ͌�����Ƃ������ʂ𓊓����邵���Ȃ��ł��傤�˂��B
�����ԍ��F19589995
![]() 8�_
8�_
�b�͕ς��܂���
��air89765����
���̃i�C�X�̐������Ăǂ��v���܂����H
�ǂ���玄��back�ɂ̓p�g����������悤�ł�
�����ԍ��F19590015�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
�����I�ɂ̓X���b�h���r�炵�����Ȃ���ł���
����͒����ǂ������B���ẴX���r�炵����B���������ǁB
�����ԍ��F19590035
![]() 10�_
10�_
���U�������͂�
���̃R�����g������킩��܂����A�������ݐ��͏��Ȃ��ł���
���l�����͍̂D���ł���
�����ԍ��F19590045�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
�����O����
�Ȃ�قǂȂ�قǁE�E�E
�u��ʓI�ȉ��y�}�́i�n�C���]�ECD���j�ɂ����錴���Đ��͑��݂��Ȃ��v
�u���y�Đ��ƌ����Đ��͑��e��邱�ƂȂ��ʕ��ł���v
���O����̂��l�����m�F�ł��܂����B
���n�ł����B
�ŁA���̍l��������
�������Đ���ڎw���Ȃ�A����PCM���R�[�_�[�����g���Đ��^���邵���Ȃ��Ǝv���܂�
���Ă͎̂^���ŁA�̂̓J�Z�b�g��DAT�����Đ��^���Ă܂����B
�����E�E�����u�ʔ����Ȃ��v�킯�ł��B
���R�ŁA�����͂��̐������o�����Ă�킯�ŁA�R�s�[�͂���ȏ�ɂ͂Ȃ�܂���ˁB
���Ⴀ�E�E����ȏ�Ɂu��������v����ڎw���Ȃ�����Ă̂����̍l���ł��B
�����ԍ��F19590073
![]() 10�_
10�_
���̃p�g��������
�i�C�X��Q�l�ɂȂ������|�`�|�`����̂͂�߂Ă���
�����ԍ��F19590076�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
���i��ǂ��o����҂̍��݂Ɍ�����B���i�R���ւ̎d�Ԃ����ĂƂ����ȁB
�����ԍ��F19590089
![]() 7�_
7�_
���i�̊Ǘ��l�̔\�̖͂�������������ɂȂ��Ă��
�����ԍ��F19590135�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
�����̃i�C�X�̐������Ăǂ��v���܂����H
�܂��ł����A���炢�ɂ����B
���ƂŒN�����₢���킹�����^�C�~���O�ł܂������Ȃ��ł����B
�����Ă��Ȃ����������邩��ʔ������đ_���Ă���悤�ɂ������܂��B
�����I�ɂ̓X���b�h���r�炵�����Ȃ���ł���
�ł��u���i�̊Ǘ��l�̔\�̖͂�������������ɂȂ��Ă�ˁv�Ƃ������������Ƃ��A
�u�i�C�X�̐������Ăǂ��v���܂����H�v�Ƃ������X���ɃX���^�C�ɖ��W�ȐU��Ƃ��A
�u���������X���𗧂Ă�v�̂͏[���r���v�f�Ȃ�ł����ǁA�����͂�����ł����H
�����Đ��Ƃ͂Ȃ�ł����H�Ȃ�Ă̂͋c�_�̗]�n���Ȃ��A
�u�������̂܂܂̉��v�Ƃ������ƂŏI���ł́H
���́u���ꂪ�{���ɒN�����ǂ��Ɗ����鉹���ǂ����H�v
�������͂��ł����B
�łȂ���ΑO�X���Ƃ͊W�����������ł͂Ȃ��Ǝv���܂���B
�����ԍ��F19590405
![]() 8�_
8�_
��air89765����
���ɂƂ��Ă͑O�X������̑����Ȃ�ł�
�����ɂ������Đ��Ƃ������̂����̐��̒��ɑ��݂��邩�̂悤�ȏ������݂ł��������
�����݂Ō����Đ��ɐ��������l������Ǝv���܂����H
�����炵����������u�����C���[�W�Đ��v�Ȃ炠��Ƃ͎v���܂���
�����ԍ��F19590748�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
���y��^�����鎞�ɍ쐻�҂��z�肵����(�Ⴆ�T�E���h�`�F�b�N�ŗp���������߂��̂���)�������ł�?
�S���������𑵂���͓̂����������܂��A�����I�ɑ��݂���Ƃ͎v���܂����ǁB
�����ԍ��F19590918�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�������ɂ������Đ��Ƃ������̂����̐��̒��ɑ��݂��邩�̂悤�ȏ������݂ł��������
��茴���ɋ߂��A�����ڎw�����@��A�o���邾���߂��Č��o�������m�͂���ł��傤�B
�u�����Ƃ͉����v�u���������݂��邱�Ɓv�́A�N�����m���Ă���悤�Ȋ��m�̎����ł���A���߂Ė₤���Ƃł͂Ȃ��B
�Ȃɂ����́E�����t�E���R�E�̉����̂܂܂����ŕ������ꂪ�����ł���Ƃ��������ł�����A���������Ƃ͎��͂������ē�����Ƃł͂���܂���B
�������Ȃ���N���m��Ȃ����A���̎��݂��ؖ��o���Ă��Ȃ��̂ɂ��ւ�炸�˔@�Ƃ��đO�X���Ō��ꂽ��̉��E���m�Ȃ鎊���̉��c�g�N�����ǂ��Ɗ����鉹�h�͋����[���ł��ˁB
�������g�N�����ǂ��Ɗ����鉹�h�ȂǂƂ������̓r�����Ȃ��A�l�m�����p�[�t�F�N�g�ȉ����{���Ɏ��݂���Ȃ�A����͐����Ă݂����A�ǂ�Ȃ��̂��m�肽������ł��B
�����ԍ��F19590946
![]() 5�_
5�_
��air89765����
�Ċm�F�ł���
�u�N�������ǂ��Ɗ����鉹�����݂���v�Ə������̂͂ǂȂ��ł��傤��
���̃X���b�h���猩����������ł��傤����
�����ԍ��F19591046�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���l�̓Z�C�E�`����
�����y��^�����鎞�ɍ쐻�҂��z�肵����(�Ⴆ�T�E���h�`�F�b�N�ŗp���������߂��̂���)�������ł�?
�����Ƃ����̂͑��݂���Ƃ���Έ�ł���ˁH
��L�̗������Ƃǂ��Ȃ�ł��傤�H
���͂�����������ӂ�Ȍ��������݂���ƒ�`������ӂ�ɂȂ�Ǝv����ł����E�E
�����ԍ��F19591069
![]() 5�_
5�_
�����e�r����
�ł��A�f�l��PCM���R�[�_�[�Ř^�������ɔ�ׂ�A������̓I�ł���B
�Ⴆ�A�������ł������Ƃ��A���͂̊��őS�R�قȂ鉹�ɕ������܂���ˁB
���A��X���c�_���Ă���̂͏��p�Ř^�����ꂽ���y�̘b�ł�����A�v���t�F�b�V���i���ɊǗ����ꂽ�Đ������A���R�[�f�B���O���ɂ͂���͂����Ǝv���̂ł����A�ԈႢ�ł����ˁB
�����ԍ��F19591247�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�����O����
���N�������Ă��ǂ����̌�
2016/01/11 10:51�@[19480728]
>�ǂ����A�N�������Ă��ǂ��Ƃ�������悸�͖ڎw���ׂ��Ȃ̂ɁA
>���̒i�K�ɍs���Ȃ��Łu�D�݁v���S�ĂȂ�ł���A���i�R���́B
���X���^�C�A�����Đ��̌�
2016/01/11 15:53�@[19481625]
>�����A�ǂ̃��[�J�[���ڎw�������B
>�[���n�C�U�[���i�ꉞ�j�ڎw���Ă���炵���ˁA���i���ƁA�����Ďv������w
>���ɂ��A�ǂ̃��[�J�[�������������������A�^���ɒ������ď����Ă�ł���B
���u�N�������Ă��ǂ����v�Ƃ͒�������ςƍD�݂̗���
2016/01/11 20:03�@[19482415]
>���y����Ă���l�A����Ă����l�Ȃ�킩��Ǝv���܂����A�t�҂���ԍS�邱�Ƃ̈�͉��F�i���傭�j�ł���ˁB
>�Đ��E�Č����鎞�ɉ��F�i�˂���j���t���Ă�����A�ǂ��v���܂����H
>�����A�[�e�B�X�g�������猙�ł���(^^;)
2016/01/11 20:32�@[19482528]
>�������E�����H�ו��E�������E�����D������Ȃ�ł��A�{���ɗǂ����̂́A�N���G��Ă��A������ł���B
>�ǂ����̂ɐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ��A�o�����Ȃ�����A���������܂�Ȃ������ɂȂ��B
# �o���̂���Ȃ��łȂ�"���"��"�q��"�̋�ʂ��o���Ă��Ȃ�
���(�D��)�Ƌq��(����)������ւ��Ă���A�Ƃ������B
�u�N�������Ă��ǂ��Ƃ������낤�Ɩl���v���v�Ɓu�N�������Ă�(�^�̈Ӗ���)�ǂ��Ƃ����v�̎��Ⴆ�܂��͖���ւ��B
�����ԍ��F19591258
![]() 5�_
5�_
���l�̓Z�C�E�`����
���ł��A�f�l��PCM���R�[�_�[�Ř^�������ɔ�ׂ�A������̓I�ł���B
�q�ϓI�^���F���������t���ꂽ�����^�����ꂽ�����Ő��ʂ͈�i�l���^�̏ꍇ�j
�����y��^�����鎞�ɍ쐻�҂��z�肵����(�Ⴆ�T�E���h�`�F�b�N�ŗp���������߂��̂���)�������ł�?
��ϓI�ӌ��F��������������҂��z�肵�������^�����ꂽ�����Ő��ʂ͕����i�R�R�����Ⴂ�j
�����͈�ł���H
������������ǂ����Ƃ��đI�Ԃ�ł��傤���H
����ӂ₳��r���������B
�c�_���Ԃ�邩��B
�����A��X���c�_���Ă���̂͏��p�Ř^�����ꂽ���y�̘b�ł�����A�v���t�F�b�V���i���ɊǗ����ꂽ�Đ������A���R�[�f�B���O���ɂ͂���͂����Ǝv���̂ł����A�ԈႢ�ł����ˁB
���͊Ԉ���Ă�Ǝv���B
���p�^�����ꂽ���y�̘b���đO������ɉ����܂����ˁH
�l�̓Z�C�E�`���������肷��͎̂��R�ł��B
�����ԍ��F19591329
![]() 5�_
5�_
�����e�r����
�q�ϓI�^���F���������t���ꂽ�����^�����ꂽ�����Ő��ʂ͈�i�l���^�̏ꍇ
���Œ��������ƁA�f�l���^���������������Ƃ����A�咣�ł����H
������Đ������Ƃ��āA���Œ��������Ɠ�����(�I�[�f�B�I���x���ł̘b)�ɕ������邱�Ƃ͖����ł��傤�B
�ŁA�����̓I�[�f�B�I�̃X���b�h�ł��傤?���p�ō��ꂽ�����ȊO�͕ʂ̘b�ł���B
�����ԍ��F19591421�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�ɒ[�Ȃ��Ƃ������A����N�\�ȉ��t�͌������Đ����Ȃ��ŏ�肢���t�����o����V�F�t�̂悤�ȋ@��̕����A�ǂ����ɒ��������Ⴄ��������Ȃ��ł���ˁB
���R�A�����Đ����g�N�����ǂ��Ƃ������h���Ƃ͌���Ȃ��킯�ł���ˁB
���t������ł́g���������ǂ����������Ⴄ�悤�Ȗ��V�F�t�̖��t���h���I�[�f�B�I�@�퐻��҂̘r�̌����ǂ���ł���ˁB
�u�����������̍����v�Ɓu�N�����ǂ��Ƃ������v�̊Ԃɂ́A�W���������킯�ł���ˁB
������HD650�̂悤�Ȕ@���ɂ������Ƃ͉����悤�Ȏ��g�������Ɍ�����w�b�h�z��������������ł����ˁB
�Ƃ����I�[�f�B�I�@���n�鑤�̐l�ԂɌ������Đ��������Ƃ����z���������̂ƁA
���ꂩ�炻���������Ƃ��@��̐�`�Ƃ��Ă͂���ȏ�Ȃ����炢����������������������g�֗��Ȑ�`����h�Ƃ��Ďg���Ă��邾�����Ǝv���܂��������Đ�
�܂����̃C���z���w�b�h�z�����鑤�̐l�Ԃ́A�u�����������v�����u�݂�Ȃ��D�݂₷�����v�ɍ��킹�ĉ������Ă���悤�Ɋ����܂���B
�u�����Đ���Nj��������ǂ���܂蔄��Ȃ��I�[�f�B�I�@��v�����u�s���R�ȉ������ǂ݂�ȂɍD�܂�₷�������I�[�f�B�I�@��v�̕������l�������̂́A
����Ȃ���Α����Ȃ��E���������Ă��o���Ȃ��Ȃ�킯������A���R�����Ȃ�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F19591447
![]() 6�_
6�_
������R(���E�ցE)
�����������̒�`�ł�낵���ł��傤���H
�����͂������Ǝv���ł��傤���c���ɂ͂�����CD����̉��̕������͂���܂��B
�ّ�ł͎��X�s�A�m�A���@�C�I�����A�T�b�N�X���̃Z�b�V���������܂��B
�������͂����茾���āA�s�[�X�J���畷�����̕���������艽�{���������F�ŕ������Ă���܂��B
����z���g�A���̃s�A�m����CD�̕������߂������f�G�ȉ������܂��B
�Ⴆ�Ώ\���Ȓ������Ă��Ȃ�YAMAHA�̃O�����h�s�A�m�őf�l���炷�̂ƁA�X�^�C���E�F�C�A�x�[�[���h���t�@�[�A�x�q�V���^�C�����v���̃s�A�m���t���ō��̘^���Z�p�̉���e����ׂ���Ƃł͓V�ƒn�̈Ⴂ������܂��B
�N�����ǂ��Ɗ����鉹�́A�t�҂̗͗ʂƘ^���Z�p�ɂ���Ă��Ȃ����Ă��܂���B
���C�u�n�E�X�ł̖����ȃ~���[�W�V�����̉��ƌ|�p����N���X�ł̗L���ȑt�҂̉��ł͑S���Ⴂ�܂��B
�����ɉ������҂������łȂ��ł��傤���H
�����ԍ��F19591469
![]() 12�_
12�_
����̂́A�u�����������v�͈�����Ȃ����ǁA�������鉹�͕���������Ă��Ƃł���ˁB
�܂��A�[�e�B�X�g�̒��o�ƒ�����̒��o�͓����ł͂Ȃ�����A�Ӑ}�����ʂ�̉����`���Ȃ�Ă��Ƃ͐����t�ł�����͖�����������Ȃ����A
�����t��^�����Ă��Đ��i�K�ł͍Đ��@�펟��ň���������o��킯������A�ǂꂪ�����������\�Ȃ̂͐���҂����Ƃ������ƂŁA
����܂����ǒ�����Ɍ����͂������ē`��邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ��������ɂȂ�܂�����ˁB
���܂��ɂ̓A�[�e�B�X�g���Ӑ}�����͂��̌��������Ƃ���@��Ŗ��t�����ꂽ���̕��������ɂ͗ǂ����ɕ������܂����A�Ȃ�Ă̂��炠�蓾��킯�ł���ˁB
�����Ȃ�Ƃ������������ɂǂ���̉��l������́H�Ƃ��������ɂȂ�܂��B
���nj����Ȃ�Ă̂́A�I�[�f�B�I�@�퐻�쑤�̂����܂ł����z�Ɛ�`����ȏ�̈Ӗ��͖����Ǝv���܂����ǂˁB
����Ȃ��Ƃ��l������́A�X�������̈�ԍD���ȉ��Œ�����������قNJy�����Ǝv���킯�ł��B
�����ԍ��F19591474
![]() 7�_
7�_
>�������Ȃ���N���m��Ȃ����A���̎��݂��ؖ��o���Ă��Ȃ��̂ɂ��ւ�炸�˔@�Ƃ��đO�X���Ō��ꂽ��̉��E���m�Ȃ鎊���̉��c�g�N�����ǂ��Ɗ����鉹�h�͋����[���ł��ˁB
�ʂɓ�����Ƃł͂Ȃ��A�~�V����������ڎw���Ηǂ�����������
�����Đ��ł���K�v�Ȃ��A�����̃I�[�f�B�I����Z���Ŕ����ƕ]������Έ������f�͂��Ȃ���
�����ɂ���l�����͂a���O�������D���݂������ǁA������͍D�������̓x�������傫������
�����ԍ��F19591480
![]() 4�_
4�_
������Ȃ��Ƃ��l������́A�X�������̈�ԍD���ȉ��Œ�����������قNJy�����Ǝv���킯�ł��B
�����v���Ȃ�ǂ��������f�͏o���Ȃ��͂������
�D���Ɨǂ��͂܂������Ⴄ����
�����ԍ��F19591496
![]() 5�_
5�_
�����Đ��ɂ��������Ă̂͒m�����������Ă��Ƃ�ˁ`�B
�ϑz���߂����B�����ɖ����߂���B
�����ԍ��F19591505
![]() 3�_
3�_
�������v���Ȃ�ǂ��������f�͏o���Ȃ��͂������
���D���Ɨǂ��͂܂������Ⴄ����
���̗ǂ����������߂Ă����ǂ��ɂ���̂����l��������ɂ킩�邱�Ƃł��B
���njl�̊��o�Ƃ����D�݂��ǂ������f�����肵�Ă��܂���ˁB
�N�ɂ����ʂ����ǂ������������Ȃ���]���o����l�͊F���ł��B
�������D����ɂ�N����ɂ���O�Ȃ��ˁB
�����ԍ��F19591539
![]() 4�_
4�_
�����������iPA�A�M�^�[�A���v���܂ށj�͂����Ƃ���
�������^���̐l�͂��܂����H
�����ԍ��F19591654
![]() 4�_
4�_
��߂ɂ��A�v���[�`
������ �Đ����ɑ��A�^���̑f�ނƂȂ����A���Ƃ̉��B
����āA�u�����v�Ɓu�Đ����v�́A�ʂ̂��̂ł���A�u�����Đ��v�Ƃ������t���́A�Ӗ��������Ȃ����A�����āA����ɈӖ����������悤�Ƃ���Ȃ�A�u����Ȃ������ɋ߂��Đ����v�Ƃ�����߂ɂȂ�B
���R�[�h�ɂ���ACD�ASACD�A�n�C���]�ɂ���A���ɕҏW���ꂽ���ł���A�}�X�^�[�����������B
����āA�I�[�f�B�I�@��ɂ��u�����Đ��v�Ƃ����g�����́A�{���̈Ӗ��Ƃ͈قȂ�ʕ\���ł���B
�����ԍ��F19592087
![]() 7�_
7�_
���l�̓Z�C�E�`����
���ŁA�����̓I�[�f�B�I�̃X���b�h�ł��傤?���p�ō��ꂽ�����ȊO�͕ʂ̘b�ł���B
���͈Ⴄ�Ǝv���܂����A�Z�C�E�`���ӌ�������ꍇ�ɐ錾����A����͂���ł�����Ȃ��H���Ďv���܂��B
�����i�����j�͈�ŁA�����Ă��܂����m�ł����A���������݂��Ȃ����m�͍Đ����ꂽ�����������i�Ə̂��郂�m�j����������킯�ł�����B
�����ԍ��F19592437
![]() 6�_
6�_
�l�́A
�����F ���̍Đ��n�ɓ��͂���鉹���̂��ƁBUSB�ACD�A���C�����́A���R�[�h�A
�@�@�@�@�@�d�g�A�l�b�g���[�N����̃p�P�b�g�����瓾���鉹�B��{�Đ��ł���
�@�@�@�@�@���̂ł���B
�����F ���̌����ɓ����Ă���y��ڒ����Ă���Ƃ��̉��B�d�q�y��ɂ��Ă�
�@�@�@�@�@�l�́A�����ƌ������Ƒ����Ă��Ȃ��B���Ɍq���Ŗ炷���œd�q�y���
�@�@�@�@�@�L�����N�^�[���ς�邽�߁B
�@�@�@�@�@����͍Đ��ł��Ȃ��B���̎��̑t�҂̉��t����œ������͓̂�x�Ɠ����Ȃ�
�@�@�@�@�@(�Ǝv������)�B�^�������A���̘^�����͑S�������ƌĂ�ł܂��B
MIDI
�T���v��
��������(�{�[�J���C�h��)�F
�@�@�@�@�@����͕ʁB�Đ��\�����A�\�����ɂł���B���ꂾ���͏�L�̌����Ɛ����Ƃ�
�@�@�@�@�@�J�e�S�����Ⴄ�Ǝv���B�ǂ��炩�ƌ����Ό����ƌĂԁB
���čl���Ă�ˁB
�܂��A�C�R���C�W���O��R���v����ꂽ�肵����̉��́A�����Ƃ������A���H���Ƃ������Ƃ�
���邩������܂���ˁB�B�N�Ƙb�����邩�Ō��������ς��܂��ˁB
�����ԍ��F19592674
![]() 6�_
6�_
�������Ē�`���邢�݂́A���܂薳���ł��傤�B
�Ⴆ�A�s�A�m�B�s�A�m�����n���}�[�Œ@���ĐU�������āA�����̃{�f�B��U�������ĉ���傫�������ł��B
������A�}�C�N�͋�C�̑a����U���̐U���G�l���M�[�ɕς��āA������R�C���Ǝ��œd�C�G�l���M�[�ɕς����ł��B
�Ƃ���ƁA�}�C�N�̃C���s�[�_���X�������A���X�̓d�C�I�ȓ����̉e�����܂��B�������U���̕����������B���̎��_�ŁA�������ᖳ���ł��ˁB
�X�s�[�J�[�Ŗ炷�̂������ŁA����Ȋw�f�ނŏo�����U�����A�d�C�G�l���M�[�ŐU�������܂��B����܂��A�d�C�I�ȓ����╨���I�ȓ����Ȃǂ̉e�����܂��B
����Ɍ����A�s�A�m���Ɩ̃{�f�B�̐U�����A���������f�ނ̈Ⴄ���̂�U�������Ă��A���������o��킯���Ȃ��B
�s�A�m�̐����Č�����Ȃ�A�����s�A�m��p�ӂ��āA���t�҂̎w�⑫�^�т��A���̂܂܍Č�������ȊO�ɂ͂���܂���B
�܂�A�����v�z�Ƃ́A�l�Ԃ��I�[�f�B�I��\��������A�I�[�f�B�I�̍Đ������`���[�j���O����ۂɎg�p����錾�t�ł����āA�m�ł�����Ԃ���`�������̂ł͖����̂ł��B
�����Ƃ́A�v�z�ł��A
�����ԍ��F19596545�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���b�s���O�͒j�̃��}�����Ɗ������I�J�V�C�̂����邭�炢������
�u�����Đ��Ƃ́v���P�Ȃ�V�����ł�������Ȃ��̂���
�����ԍ��F19596600
![]() 3�_
3�_
���̗���
�����ԍ��F19596603
![]() 4�_
4�_
������A������Ƌ��������Ƙa������Ƀi�C�X�����̂�
�T�T���q��JBL��D�����H�A����l���Ȃ̂�
�����ԍ��F19596611
![]() 3�_
3�_
��D�����ĂȂ납
�����ԍ��F19596615
![]() 4�_
4�_
�I�[�f�B�I���āA�@���Ɏ��Ă邩���A�킩���ȁB
�����ԍ��F19596707�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
������`�A���z����`�A�A�A�ʎ��h�A��۔h�A�A�A
�܂��A�����̎v�z�ɗ�������A�N���̌䌾�t��L��������A�����̋��菊����������
�����ԍ��F19596746�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
����T�ɂ͌����܂��A�I�[�f�B�I�ł͍����Ȑ��i�قnj����Ƃ̍����k�߂Ă����X���ɂ���܂��B�A���A������Ηǂ��Ƃ��������̘b�ł͋l�܂�Ȃ��̂ł��傤�ˁB
�^�����Ő^���ȃ��[�J�[�̕�������ɉ����ẮA�����ł��傤�ˁB
�������L���������B�����ɂ͌��x������B
�I�[�f�B�I�Ƃ́A���z�ƑË��̕\����́B
�����ԍ��F19596783�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�N�������ǂ����ƔF�߂镨�͂���B
����A����ˁB
�����Ă���ƁA�o���l�ŁA�����̃n�[�h���ς���ˁB
�܁A�I�[�f�B�I���������Ȃ����A�����Ă�ق����A���͔삦�Ă�B
�����ԍ��F19596797�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�������Ă邩�A�����ĂȂ����ŁA�v�������(���z�{�H)���A���|�I�ɈႤ���B
�����ԍ��F19596807�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���ɂƂ��āA�I�[�f�B�I�Đ��ɂ����錴���Ƃ́A
�E�^���G���W�j�A�ƃ~���[�W�V�������^�����j�^�[�̑O�ŕ����āA�����OK�Ƃ�����
�����Đ��Ƃ́A
�E��L�̉��������̕����ōČ����邱��
�^�����j�^�[�̑O�ŕ����Ă��Ȃ��̂ɁA�����̕����̍Đ����u�������Đ��ł��Ă���Ɖ��Ŕ��f���邩�H
�E�ǂ�ȉ����ł��ǂ����ŕ����Ă���Ȃ�A�����Đ��ł��Ă���Ɣ��f����
�E�ꕔ�̉������������ɕ�������Ȃ�A�Đ����u���������f�t�H�������Ă���Ɣ��f����
�ǂ����͏�ɍD�݂̉����H
�E�ǂ����ƍD�݂̉��͕�
�E���t���̗ǂ��������K�������D�݂̗����ł͖����悤��
�E�����Đ����������D�݂Ŗ������Ƃ����蓾��
�����ԍ��F19597321
![]() 6�_
6�_
�I�[�f�B�I�Đ��ɂ�錴���Ȃ���
�w�b�h�z���A�C���z���g�������_���������
�}�C�N�^���̋����������B���ɂ��Ă��܂�����
�����ԍ��F19597631
![]() 4�_
4�_
�����Ƃ́A���t�҂��u���̉����I�v�ƁA�d�グ�������Ǝv���Ă܂����B
�A���v�ʂ������ł��A���t�҂��\����������������Ȃ�A���ꂪ�������ƁB
�i�Ȃ�ƂȂ��ł����A�����Ƃ́u����ȉ��ɂȂ����Ⴂ�܂����v���Ď��H�Ɠǂݎ���Ă��܂��܂����B�B�B�j
CD�ɂȂ������̏ꍇ�A���t�҂͑S�Ĕ[�����Ă����ł��傤���ˁH�H
���̊��o�͏\�l�\�F�B
�]���āA�����̑��������\�l�\�F�B
���L�͓���̂ŁA���l�̉��߂Ǝ����̊��o���ׂ邱�Ƃ��A�I�[�f�B�I���y���ނ��Ƃ��Ǝv���Ă��܂����B
�����@�ނ��t�ł鉹�́A�����@�ނȂ�C���v�b�g�ɒ����ȃA�E�g�v�b�g���ł���B�Ƃ��������x�̉��߂ł����B
���̏ꍇ�A��̒ʂ茴���̉��߂������Ɏ�ϓI�Ȃ��߁A�����ȋ@�ނɐH�w�������Ȃ����R���ƍĔF���ł��܂����B
�F�X�Ȉӌ�������A�����[���ǂ܂��Ē����܂����B
�����ԍ��F19597635
![]() 4�_
4�_
�����́A�X����ł�
���͎v���ɂł���
�y��Ƃ������̂͂��������鉹���傫���ł����
�g�̂ŐU���������郌�x���ł�
����̓R���T�[�g�z�[�����ʼn����̋q�Ȃ܂ʼn���͂��Ȃ�������Ȃ����炾�Ǝv���܂���
����ɔ�ׂĎ���̃I�[�f�B�I�Đ����ɐ����Ɠ������x���̉��ʂ��o������������Ă�����͂��Ȃ菭�Ȃ��Ǝv����ł���
���̓_�ɂ������Đ�������Ƃ���闝�R�����邩�Ǝv���܂�
�����ԍ��F19598268�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
����Ɍ��y�l�d�t�c������SP�Ɣ�r�����_�u���E�[�n�[�Y�̉��������
���t�҂͏���ɉ��ʗ}���邩��s�����ƌ����Ă�����
�����ԍ��F19598293
![]() 3�_
3�_
�I�[�f�B�I�ɂ�����u�����Đ��v�Ƃ����̂́A�ꔭ�^��̂��̂̂��Ƃ������Ă���̂ł��傤���B
����ȊO�̃o���h�ɂ��^���̏ꍇ�A�e�y��́A���Ԃɉ��B�肵�Ă����A�e�g���b�N�ɘ^������A���ґ��̈Ӑ}�̂��ƂɁA���ʒ����A��ʌ��߁A�G�t�F�N�g�����AEQ�����A�~�b�N�X�_�E���A�}�X�^�����O���o�āA�}�X�^�[����������܂��B
�i�~���[�W�V�������W�܂��āA���[�����[���ӌ������킵�Ȃ���A���Ԃɉ��t���Ă����ꍇ������܂����A���ԂɃX�^�W�I�ɂ���Ă��āA�Q�A�R�e�C�N�B���āA���������ƋA���Ă�������������܂��j
���ꂩ��쐬���ꂽ�Đ����������́A����Ȃ��Ƃ͈ӎ������A�����Ă���킯�ł����A�u�����Đ��v�ɂ��������́A�������������Ɋւ��ẮA�ǂ��l���Ă������ł��傤���B
�����ԍ��F19598375
![]() 3�_
3�_
���������A
�Ⴆ�A�s�A�m���A���`�`���ƒe�������̉�����A�̏d�������ăo�[���I�Ɩ炵�����̃_�C�i�~�b�N�����W���āA16/44.1��CD�ɋL�^�o����킯���Ȃ��B
������A�R���v���b�T�[�Ƃ��g�����x���킯�����B
32/384�ł�����邩�ǂ�����������ˁB
�A�i���O�̋L�^�́A�q�X�m�C�Y��o�C�A�X�d����C�R���C�U�[�����̖��ŁA���l�Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�҂��͓̂�����ˁB
�m�C�Y���_�N�V�������Z�p�͐i��ł邯�ǁA�������^��邩�ƂȂ�ƁA�܂��܂��B
����ł��A�f�W�^���^�������}�V��������Ȃ���������B
�܁A�����Ɍ����A����̘b�̒ʂ�A�Ⴆ�}�C�N���V���A�ɂ��邩�AAKG�ɂ��邩�A�[���n�C�U�[�ɂ��邩�A�m�C�}���ɂ��邩�A�I�[�e�N�ɂ��邩�A�\�j�[�ɂ��邩�A�A�A�ŁA�S�����F�Ⴄ����ˁB
�����������Ƃ��Ę^�邱�Ƃ́A�s�\�B
����=�����Ƃ���Ȃ�A���̂悤�Ș^���͂��̐��ɂ͑��݂����Ȃ��B�����͌��Ƃ�����`�ɂȂ��B
����=�}�X�^�[�Ƃ���Ȃ�A�܂��A�����ł��ˁB
�������A���̏ꍇ�̌����́A���̉���ҏW���đn�����l�݂̂��m��B
���̒N���m��p�������܂���B
���ꂪ�A�����ł���A�����ł���B
�����ԍ��F19598427�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�u�N�����ǂ��Ɗ����鉹���ĉ��ł����H�v
������A���̐��ɂ͑��݂��Ȃ��B
���̒���100%�S�Ă̐l���A�ǂ����Ɗ�����I�[�f�B�I���u�́A���̐��ɂ͑��݂��Ȃ��ł��B
�t�ł��ˁB
�N�����A�����Ƃ͊����Ȃ����͑��݂���B�ł���ˁB
���Ԃ�B
�����ԍ��F19598443�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���������A���悻���f�̗v�f�Ƃ���100%�߂������\�����ɂ���Ĕ��f�����I�[�f�B�I�ɁA��ς�����Ȃ��Ȃ��B�B�B
������̐����ł���A�N���������Ƃ͊����Ȃ��ł��낤���������́A�D�݂̖��ł��傤�B
B&W���D���Ȑl�AKEF���D���Ȑl�A�t�H�X���D���Ȑl�AJBL���D���Ȑl�Aetcetc
�{�l�̏���ł��ˁB
�����ԍ��F19598459�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�X���傳���
�i�C�X���j�͏��������ȁH
�����ԍ��F19598565
![]() 4�_
4�_
�X���傳��A��^���܂���
http://item.rakuten.co.jp/merry-net/us366-voset-ecb/
�{�i�I��DTM��mobi����ɂł������Ă���
�����ԍ��F19598570
![]() 3�_
3�_
���ǁA���̃X���ʼn���₤�Ă���̂��ɂ��ẮA
����
�����Đ��Ƃ́A�������x�Đ�(������hi-fi)�B
�ł�����Ȃ����ȂƎv���܂��B
���̍Đ��Ώۂ̊y�Ȃ̏o���̗ǂ������͂��̂܂܂���̂܂�
�Č������B�����Ē��F�Ȃǂ��Ă͂����Ȃ��Ƃ�����O�Ԃ��
�т��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁB
�����A�������x�Đ��Ƃ�������͐�Βl�������Ƃ���������
����̂Ō����Đ�(�������x�Đ�)�Ƃ����͎̂d���Ȃ����ǁA
���z�ɂȂ��Ă��܂��ƁB
�X�^�W�I����o�ׂ��ꂽ�}�X�^��100%�Č��ł������
������Đ��ł��Ă��飂Ƃ���A����͂���ŗL�ӂ��ȂƂ�
�v���܂��B�����I����Ȃ��ł����ǂˁB���炭���̐��쌻���
�������Ƃ������@���Ȃ��Ǝv����B
���y�𐧍삷�鑤����Ȃ��A�y�Ȃ����ɗ������炵����
�����Ă���(���̓l�b�g���痎�Ƃ���)�}�̂��������Ƃ������Ƃ�
������Ȃ��ł����H
����𒉎��ɍĐ��ł��邱�Ƃ��A�����Đ��ł��Ă���ł�����
�Ȃ����ƁB
�����ԍ��F19598744
![]()
![]() 6�_
6�_
����
�w�b�h�z���͐U���Ŗʐϋ����̂ɁA���܂ōĐ��ł���͉̂��̂ł����H
�����ԍ��F19598757
![]() 3�_
3�_
>�w�b�h�z���͐U���Ŗʐϋ����̂ɁA���܂ōĐ��ł���͉̂��̂ł����H
�ۖ��͐U���Ŗʐϋ����̂ɁA���܂ŕ�������̂Ɠ��������B
�}�C�N�͐U���Ŗʐϋ����̂ɁA���܂ŏE����̂Ɠ��������B
�����ԍ��F19598767
![]() 5�_
5�_
���肪�Ƃ�
�ŁA���㏬�^�X�s�[�J�[�Ńp�C�v�I���K���Œ��܂ōĐ��ł���̂���܂���ˁA������
�ۖ��Ɠ���������
�����ԍ��F19598788
![]() 3�_
3�_
�d�ቹ�Đ��\���^SP�̌^�Ԉꗗ�L�ڂ����肢�v���܂��B
�K�����݂���͂���
�����ԍ��F19598795
![]() 3�_
3�_
�Đ������i���R�[�h�ACD�ASACD�AUSB�������A�n�C���]�ȂǂȂǁj�ɁA�L�^���ꂽ�����A�u�����ɍĐ�����v�ƌ����Ƃ��낪�A�悭�킩��Ȃ���ł��B
�N���A�ǂ�����āA�u�Đ������𒉎��ɍĐ����Ă���v���ǂ����f����̂ł��傤�B
�ǂ�ȍĐ����u���g���Ă��A�Đ����ꂽ����]������̂́A������ł���A������́A���ꂪ�A�Đ������𒉎��ɍĐ����Ă��邩�ǂ����f����ړx�͎����Ă��܂���B
������̌o���ƚn�D�ɂ���āA���f���邵���Ȃ��Ƃ������܂��B
�I�[�f�B�I�ƊE�ł́A�u�����Đ��v�Ƃ����̂��A�т̌���̂悤�ɂȂ��Ă��܂����A�u�����Đ��v�Ƃ������t���̂��̂�����ł͂Ȃ��̂ł����B
������ƊE�p��B
�ł�����A�u�����Đ��Ƃ͉��ł����H�v�ւ̉́A�u�P�Ȃ�ƊE�p��ł��B�C�ɂ���K�v�͂���܂���B�v�ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F19598885
![]() 5�_
5�_
�ȑO�A���E�O�僌�[�x��S�Ζ��̎��̖����̐l��������ɂ��܂�����
�^���ɗ���������肵�Ă��炵�����ADAW�A�v���ɂ��ڂ�������
�A�r�[���[�h�Ȃǂ̎�v�X�^�W�I�ɍs�����b��
�����ł̓z���t�L�ƌ����Ă��܂�����
���̐l�ɂ��C�ɓ���o�^����ƁA�o�^��Ԃ����̂�ROM��ł��傤
�����ԍ��F19598904
![]() 3�_
3�_
>�N���A�ǂ�����āA�u�Đ������𒉎��ɍĐ����Ă���v���ǂ����f����̂ł��傤�B
���f�ł���͂����Ȃ��ł���ˁB�������Ĕ��f�ł�����̌����Ɨǎ��A
���͓��������킹�Ă��Ȃ��̂ŁB
��Βl�I�ȕ������A�Ⴆ�ł����A���E�ŗB��̃��t�@�����X���Ƃ������̂�
1�Z�b�g�����g�ݏグ�āA���E���݂̂Ȃ���œ��ӂ��āA�������ɂ����
���߂��Ƃ��܂��B�̐S�Ȃ̂́A�X�^�W�I�̊��ł͂Ȃ��Ƃ������ƁB
��������o�Ă��������A������܂������悤�Ɋ�Ƃ��č��肵���������g����
�g�`���L�^���܂��B���̃f�[�^�ƁA�����Ƃ̃V�X�e���ŏo�Ă��������A
������v������A�Đ������𒉎��ɍĐ����Ă���ɂȂ�܂��B�v�͐l�̊�����
���荞�܂Ȃ��Ƃ���Ŕ��f���Ȃ��Ƃ����Ȃ����낤�ȂƁB
����́A���f�Ƃ��������A�ؖ�����Ƃ����Ӗ��łƂ炦�����������ł��ˁB
�܂��A����Ȃ̖ϑz�ł��̂ŁB���f����̂́A���ǐl���ꂼ��̎�ςɂȂ���
���܂��܂���ˁB�Ƃ��������i�A������A�����ɍĐ����Ă�ȁ[����čl����
���Ȃ��Ǝv���B�����疳���̂Ɠ����ł��B�ӎ������������悢�̂��ȁB
>�ł�����A�u�����Đ��Ƃ͉��ł����H�v�ւ̉́A�u�P�Ȃ�ƊE�p��ł��B
>�C�ɂ���K�v�͂���܂���B�v�ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ł���ˁB
������Ƌ����Ȃ��Ƃ������ƁA�����Đ��������@�̓����Ƃ���Ȃ�A
�����@�͗v���A�C�ɂ���K�v�Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł��B
�����Ƃ����ƁA�����Đ����ł��Ă���Ȃ�A�����ɂ���I�[�f�B�I�̃u�����h�A
�i�ڂ͑��݈Ӌ`����Ȃ��Ȃ�܂��B
�����A��Ƃ��Ă̈�������Ȃ��Ȃ��Ȃ����B�B�B
������ƈႤ�b�ɂ���܂����ǁA�����Đ��Ƃ͊W�Ȃ��ł����A�������̂���@�ނ�
���������Ƃ�����]�͂���܂���ˁB
�����ԍ��F19598951
![]() 3�_
3�_
red����͑ސE�����̂���
�݂�ȂŃ}�X�^�����O�X�^�W�I���w�Ƃ��ʔ���������
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7920820/#tab
�����ԍ��F19598974
![]() 3�_
3�_
�\�j�[�E�~���[�W�b�N�E�X�^�W�I�A�̂����ɂ��������Ȃ�A�����ł���B
http://www.sonymusicstudio.jp/mob/pageShw.php?site=studio&ima=1626&cd=introduction
�����ԍ��F19599096
![]() 3�_
3�_
�G���W�j�A�������傭������
�����ԍ��F19599136
![]() 5�_
5�_
������@appleTV�͉��̖��ɂ������Ȃ�����
���݂�amazon �v���C���r�f�I���p�ł���TV���A�v���ɂ��邵
STB�͕s�v�ł���
4K���h���r�[�T���E���h�̏ꍇ�͕K�v����
�����ԍ��F19599148
![]() 3�_
3�_
�������āA���k�����A�u�����Đ��v�Ƃ������t�̋N����T���Ă݂��B
Rickenbacke�����w�E���ꂽ�悤�ɁAHigh Fidelity�i�������x�A���Č����j������uHi-Fi�v���痈�Ă���ƍl���Ă悢�B
Hi-Fi��Wiki�Œ��ׂĂ݂��Ƃ���A���̈ꕶ���ڂɂƂ܂����B
����1950�N��ȍ~�A�l�X�ȃI�[�f�B�I���[�J�[���u�����ɂ�蒉���v�Ƃ����Ӗ��́u�n�C�E�t�B�f���e�B�[�iHigh Fidelity�j�v�Ƃ������t���}�[�P�e�B���O�Ɏg�p����悤�ɂȂ�A����Ɉ�ʓI�ɂȂ����B
���́uHigh Fidelity�v�Ƃ������t�͂ǂ����ŏ��Ɏg�����̂��Ƃ����ƁA
����1930�N��ɕč�RCA�r�N�^�[�Ђ��A�]����SP�^�����y���ɉ����̂悢�wRCA Victor High Fidelity Recording�x�\���A���Ђɐ�삯�ăn�C�t�@�C�^���̃��R�[�h��o���Ɏ������B
�����������ǁuHigh Fidelity�v�Ƃ����ꂪ���Ԃɒ蒅����悤�ɂȂ����B
�܂�A�u�����Đ��v�̌ꌹ�ƂȂ���̂́A�A�����J�ɂ������̂ł���B�����āA�uHigh Fidelity�v�i�����ɂ�蒉���j�̖ڎw�������̂́A�u��艹���̂悢���̂����A�}�[�P�b�g�ɒ��邱�Ɓv�ł������ƌ����Ă悢�B
�ŋ߁A�I�[�f�B�I���[�J�[���͂����Ă���u�n�C���]�Đ��v�Ɋւ��Ă��A
�����n�C���]=���𑜓x�̈Ӗ��ŁA�n�C���]�����͉��̏��ʂ�CD�̖�6.5�{(* 192kHz/24bit�̏ꍇ)����܂��B
������A�[�e�B�X�g�̑��Â�����C�u�̋�C���ȂǁACD�ł͒������Ȃ������f�B�e�[����j���A���X����������A�����ɋ߂������Ȃ�ł��B
�O���̌�A�����Ȃ�u������v���g���āA�㕶�Ɍ��т���̂́A���X����������Ǝv���̂����A
�n�C���]�i���𑜓x�j�������ɋ߂����A�Ƃ����\�����A�n�C���]�i���𑜓x�j����荂�����ȉ�
�Ƃ���A�������������͏����A�����Ƃ��邱�Ƃ��f���ɓ`���悤�Ɏv����B
�����ɂĎ���B
�����ԍ��F19599686
![]()
![]() 5�_
5�_
�����̈Ӗ��Ȃ�Ēm���Ăē�����O����B�݂����Ɏv��ꂪ�������A�����܂Řb������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�I�[�f�B�I�����t�Ō��������͍̂���ɂ߂܂���B
�����ȃX���̒��ŗ���͂�����Ȃ��Ƃ�������́A�I�[�f�B�I�Ƃ����̂����͂킩���ĂȂ��B
����̗���͂�����Ȃ��ł͂Ȃ��A�Ȃ̓`����͂��Ȃ��A�`���悤�Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ������B
�����ԍ��F19599736
![]() 5�_
5�_
NAMM Show 2016���n���|�[�g
�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�A�}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�ADTM�Ȃ�
http://info.shimamura.co.jp/digital/namm-show
���{�̊y��t�F�A
http://musicfair.jp/
�����ԍ��F19601355
![]() 3�_
3�_
�{���̃����S�̖��̓����S�ɂ����o���Ȃ�
�v�z���ێ����鐸�_�́A���C�łȂ���Ȃ�Ȃ������B
http://biglife21.com/companies/622/
�����ԍ��F19601701�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��i�ق̎В����A���܂ɂ́A���������ȁ[�Ǝv���邱�ƌ����ˁB
http://www.ippinkan.co.jp/cm/paradox_1.htm
�����ԍ��F19601719�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���E�̃I�[�f�B�I�����[�h���Ă������[���b�p������ł́Ahi-fi�c�_�����x���J��Ԃ������ʁA�e���[�J�[�̎v�z�́Ahi-fi����Good-Reproduction�ƌ����l�����ɕς���������ł��B
�����̍��������ƌ������ɖ����������Ă���̂ł��ˁB
Hi-fi �����̍������� ����ɂȂ���邩������܂���ˁB
�����ԍ��F19601744�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�I�[�f�B�C�̖��͂́A�u�Č����v�ɂ���B
���A��Ԃ̐�����āA���Ȃ���ɂ��āA�L�^���ꂽ���������x�ł��A�Đ����y���ނ��Ƃ��ł���B
�ŏ��́A���m�����Ńm�C�Y���Ђǂ����̂ł������ł��낤�B
�������A�Z�p�҂̓w�͂ƃe�N�m���W�[�̔��W�ɔ����A�����́A���傶��ɉ��P����Ă������B
�Ȃ��A�����Ȃ������ւ̒Nj�������Ă����̂��B
���ƓI�ȑ��ʂ��傫�ȕ������߂�̂́A���R�̂��Ƃł͂��邪�A�Z�p�҂̒T���S�Ƃ����]�ރ}�[�P�b�g�j�[�Y�Ɏx�����Ă���Ƃ������Ƃ𗯈ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����́A�I�[�f�B�I�Ɍ������b���ł͂Ȃ��A���ƃr�W�l�X�̊�{�ƌ����Ă悢�B
�Ȃ��A�u�����Ȃ������ւ̒Nj��v���N����̂��B
����Ɋւ��ẮA�w�p�I�ȉł͂Ȃ����A�u���悢���́v�����߂�K�����l�ނɂ͔�����Ă���A���ꂪ�A�����A�l�ނ̕��������̔��W�̌����͂ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�I�[�f�B�I���A��̉��y���A���ł��Đ��ł�����̂Ƃ��Ĕ������ꂽ���̂ł��邱�Ƃ���A���̋��ɂ́A�L�^���ꂽ���t���̂��̂̒����ȍČ��Ƃ���̂́A���R�ł���B
�����A���݂̘^���Đ��e�N�m���W�[�ł́A����́A�s�\�ł��邪�A�������������Ȃ��A�Ƃ͌�����Ȃ��B
SF�I�Șb���ɂȂ邪�A�f��u�g�[�^�����R�[���v�̂悤�ɁA�]�ɂȂ�炩�̎h����^���A�����������ۂɉ��t���ɂ��āA���ʼn��y���Ă���ƍ��o�����邱�Ƃɂ��A��̉��y��Ǒ̌����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ邩������Ȃ��B
�����ԍ��F19601903
![]() 2�_
2�_
>Hi-fi �����̍������� ����ɂȂ���邩������܂���ˁB
������������Ȃ����Ǝv�������Ƃ�����܂��B
�����ԍ��F19601920
![]() 2�_
2�_
�w�b�h�z���E�C���z���́wHi-Fi�x��wHi-Res�Ή��x�͐�`����ȏ�̕��ł͂���܂����ˁ`(^_^;)
�����ԍ��F19601946
![]() 2�_
2�_
>�w�p�I�ȉł͂Ȃ����A�u���悢���́v�����߂�K�����l�ނɂ͔�����Ă���A���ꂪ�A
>�����A�l�ނ̕��������̔��W�̌����͂ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�����ƑO�Ƀh�L�������^���ōs���w���ۂ����Ƃ�������Ă����e���r�ԑg��(�������̔ԑg����������)�A
���X�l�Ԃ�(���ɒj����)������ŁA�������ē�����l���ɑ��čK�����𖡂킢�B�B�B
�Ƃ��������������āA���ꂪ����Љ�ɂ����ẮA�����A���_�A���́A���~�ɂ���ւ���Ă���
�Ƃ����b������܂����B
�����ԍ��F19601952
![]() 2�_
2�_
��EXILIM�Ђ�܂���
�܂��w�b�h�z���C���z���̕����Č����̉\���������B
�������̉e���Ȃ�����B
������n�C�t�@�C�ƌĂԂ��͌㐢�ɔC���܂��B
�����ԍ��F19601965�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�h���I�ȕ\��������ƁA�u�ʂĂ��Ȃ��~�]�v�ł��B
�����ԍ��F19601978
![]() 2�_
2�_
�u�n�C�t�B�C�v�Ƃ������t���g���n�߂�1950�N��ɔ�ׂ�A���܂̃R���|���x���ŁA�\���u�n�C�t�@�C�v���ƁA�v���܂��B
�������W�J�Z����A�R���|�ɔ����ւ���ƁA���̎��́A���̉����Ɂu�т�����|���v���܂��B
����ŁA���܂�Ηǂ��̂ł����A�l�ɂ���ẮA���炭����ƁA�ȁ`�A�ቹ���ア�ȁA�Ƃ��A����̐L�т�����Ȃ��ȁA�����Ɗ��炩�ȉ��ɂȂ�Ȃ����ȁA�ƂȂ�܂��B
�����Ȃ�ƁA��́A�����z�̒��g�Ƃ̑��k�ŁA�����玟�ւƁB�B�B
�͂��A�킽���������ł��B
�����ԍ��F19601997
![]() 3�_
3�_
2016/02/18 10:10�i1�N�ȏ�O�j
�������Đ��Ƃ͉��ł���
�����u�L���b�`�R�s�[�v
���������������L�^���鎖�͕s�\�ł��B
�����ԍ��F19602041
![]() 3�_
3�_
�����e�r����
���͋t�ɁA���̃X�O���ɉ������Œ肷��w�b�h�z���E�C���z���Ŗ{����Hi-Fi�i�������j�͓���Ǝv���܂����ǂˁB
��mobi0163����
���u�n�C�t�B�C�v�Ƃ������t���g���n�߂�1950�N��ɔ�ׂ�A���܂̃R���|���x���ŁA�\���u�n�C�t�@�C�v���ƁA�v���܂��B
�S�����̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
�\���Ǝv���Ƃ���Ŗ����ł���l�����Ԃ��ԍK���B
�����ԍ��F19602048
![]() 3�_
3�_
��EXILIM�Ђ�܂���
�r���͋t�ɁA���̃X�O���ɉ������Œ肷��w�b�h�z���E�C���z���Ŗ{����Hi-Fi�i�������j�͓���Ǝv���܂����ǂˁB
�n�C�t�@�C�̒�`�]�X�͖������Ă���͂Ȃ�łł��傤�H
���o����肭�x���Ĝ�������^����Ɖ��肵���ꍇ�o���邾���m�o�_�o�̂��ɔ����̂͂����������L�����Ǝv���܂�������(^_^;)
�����ԍ��F19602335�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����e�r����
�l�I�ɂ́A���̐^���ɉ������Œ肵����Ԃł̃X�e���I�Đ��͓�����ʂ���Ƃ��Ă���A�{�������ɐ����Ē������Ƃ���{�Ƃ��鉹�y���t�����̂܂܂ɒ������Ƃ͓���ƍl���܂��B
���̍l���Ɏ���܂łɂ͂��낢��Ȍ��Ƃ��낢��Ȑ��i�̎������J��Ԃ��Ă��܂������A���Ԃɔ��\���邽�߂ɋq�ϓI�Ȍ��������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����܂ł��l�I�Ȍ����̍����Ƃ��Ă��܂��B
�������炸m(_ _)m
�����o����肭�x���Ĝ�������^����Ɖ��肵���ꍇ�o���邾���m�o�_�o�̂��ɔ����̂͂����������L�����Ǝv���܂�������(^_^;)
�����ɉ������ރJ�i���^�C���z�����A���̊O�ɌŒ肷��w�b�h�z���̕����������Ɗ�����l�������Ǝv���Ă��܂������B
�����ԍ��F19602693
![]() 3�_
3�_
�]����ʂɊւ��ẮA�����w�I�ɂ��u�킩��Ȃ��v�����ł��B
�����搶�̂������A���F��\���グ�܂��B
Q:�w�b�h�z���ʼn����Ƃ��C���̒��Ɋ����Ă��܂��i������ʂ���j�͉̂��̂ł��傤���B�܂��C��������P����Z�p���������ƕ����܂����B
A:���̗��R�ɂ��Ă͂܂��悭�������Ă��܂���B�w�b�h�z���ŕ����ƁC�ʏ핷���Ă��鉹������̕�����Ȃ��Ȃ�܂��B
���̂��߁C�]�ɓ����Ă��鉹�h���͔����I�Ȃ��̂ƂȂ�C�����Ԏ��ԍ��ƃ��x���������ʼn��Ƃ������ʒu�𐄒肵�悤�Ƃ��邽�߂ɁC���ׂē��̒��ɒ�ʂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B
J. Blauert: Spatial Hearing�iThe MIT Press, ISBN0-262-02413-6,1997�j�Cp.139�ł́C�w�b�h�z���ɂ����鉹���͊e��������̉��������i���E���̊O������������������j��Ɏˉe����C�������ʁiLateralization�j�ƌĂԂƋL�q����Ă��܂��B
���o�n�̐����w�����������i������C���̖��̉𖾂��Ȃ���邩�Ǝv���܂��B
�@��ʂɊւ���_���͌Â��CH. Wallach: On sound localization. J. Acoust.Soc.Am.�C10, 270--274 (1939)�ŁC�����ԃ��x�����C���ԍ��Œ�ʂ��ω����邱�Ƃ��q�ׂĂ��܂��B
���̌�C�����ԃ��x�����C���ԍ��̋c�_������ɍs���C�����g���ł͎�ɗ����Ԏ��ԍ��C������g���ł͗����ԃ��x�����◼���M���̕���� ���ԍ�����ʂ̎肪����ɂȂ�Ɛ�������Ă��܂��B
������1970�N��ɐ����ʁi�������S���獶�E�ɑΏ̂ɕ������ʁj��̒�ʂ́C�����ԃ��x�����C���ԍ������łȂ��C����̌`��ɂ����˔g�̃X�y�N�g���\���i���F�j�Ɠ����̐U��ɑ���X�y�N�g���ω��ŁC�㉺��������m�o����Ƃ������e�̘_�����������\����Ă��܂��B
�@���ɉ��P����Z�p�ł����C������Â����猤�����i�߂��Ă��܂��B1886�N�p�������Ől�Ԃ̓����`���͋[�����_�~�[�w�b�h��p���C���̌ۖ��ʒu�Ƀ}�C�N���z���������^�����@�i�_�~�[�w�b�h�^���j���ŏ��ɓW������܂����B�������Ȃ���C�O���̉������㓪���ɒ�ʂ��Ă��܂��Ⴊ�����C���ׂĂ̐l�ɓ��l�Ȓ�ʊ��������Ȃ����Ƃ����܂��ɖ��_�Ƃ���Ă��܂��B
���̗�Ƃ��āC�l�Ԃ͌����ʂ��q���ł��̂ŁC�����X�ł̌㓪���̎U�����̃_�~�[�w�b�h�^���́C�g�̖т��t�����炢�̗Տꊴ������C���̌������Ƃ�낵�����Ǝv���܂��B
�@�w�b�h�z����p�������O������ʋZ�p�́C�������Ԃł̌ۖ��ʒu�̉��h���ƃw�b�h�z���������ł̌ۖ��ʒu�̉��h���Ƃ������ɂȂ�悤�Ƀw�b�h�z���̓d�C�M�����͂�^���邱�ƂŎ������Ă��܂��B
���̍l�����ɉ����āC�������玨�܂ł̓`�B���Ƃ��ē����`�B���iHRTF�FHead Related Transfer Function�j���p�����C�ߔN�̃f�B�W�^���M��������p���������x�ȑ���ɂ��C���O������ʂ������������܂��B
������ɂ��Ă��C����C�l���Ƃ̓`�B����ėp���ł���Z�p�����߂��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
(���c�����F�����Z�ȑ�C���������F��B��)
�����ԍ��F19603285
![]() 3�_
3�_
��ɏq�ׂ��悤�ɁuHi-Fi�v�Ƃ����p�ꂪ���y�������A�I�[�f�B�I�̋Z�p���x���͒Ⴉ�������߁A�`���V�X�e���ɂ����ē��͐M���𒉎��ɓ`�����ďo�͐M���Ƃ���x�������x�ł��邱�Ƃ��u�������x��Hi-Fi�v�ƕ\�����B
�������A���̌�̓`���Z�p�̐i���ɂ��A�uHi-Fi�v�̈Ӗ�����Ƃ���͕ω����Ă����A�����A�Z�p�I�ȈӖ������͂Ȃ��Ǝv����B
�I�[�f�B�I�e�Ђ́uHi-Fi�v�̎g�����́A�l�X�ł���B
http://www.sony.jp/audio/whatsnew/trial_listening.html
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/special/hifi-history/
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents
http://jp.technics.com/aboutus/
�����ԍ��F19603400
![]() 3�_
3�_
mobi0163����
���̂悤�ȕ����A�悭�����ׂɂȂ��܂��ˁB�������ł��B
������������A�����n�C�t�@�C�Ƃ������t�͎���ɂȂ����Ǝv���Ə����܂����B
�n�C�t�@�C�Ƃ������t�́A�����̃n�C���]����(�Ɗ����ď����܂�)�̂悤�ɁA���������
�V�����C�m�x�[�V�����ƌ������炢���ł����ˁA�ׂ��Ɍq���肻���ȗv�f�������莟��A
�Ӗ����������ς��Ă����Ȃ���A�ĊO�A���t���̂͂����Ǝg��ꑱ���Ă����̂����B��
�v���悤�ɂȂ�܂����B
�n�C�t�@�C�́A���Ȃ�A�n�C���]���܂܂��f�W�^���������w���Ă���ƌ����Ă�����
�Ȃ������ł��ˁB�܂�����͎��̏���Ɏv���Ă鎖�B
�Ƃ������ƂŁA�I�[�f�B�I�Ƃ����������A������Ƃ��i�����Ȃ���A�����Đ��Ƃ���
���t�̎w�����̂�����ŕς���Ă����āA���݂����ȏZ�l�ɂ���ċc�_��������
�����̂ł��傤�ˁB
(�����A1930�N��ARCA�ɁA����DSD�̊y�Ȃ�������Ȃ�ƌ������낤�ȁB�B
�Ƃ��ϑz����Ɩʔ����ȁB�B)
�����ԍ��F19603496
![]() 2�_
2�_
����(�����A1930�N��ARCA�ɁA����DSD�̊y�Ȃ�������Ȃ�ƌ������낤�ȁB�B
�Ƃ��ϑz����Ɩʔ����ȁB�B)
�n�C���]�R���|����������ŁADSD���������āA
�u���́A���̔��i�X�s�[�J�[�j�̒��ɁA���l�̃I�[�P�X�g���������Ă��āA���t���Ă����ł���B�v
�ƌ�������A�M����Ǝv���܂��B
�́A�p�\�R�������y���͂��߂����A��i���A���q�Ј��ɁA�u���̃p�\�R���Ɍ������Ęb��������ƁA�����Ă�����v�ƌ�������A���̏��q�Ј��́A�u�p�\�R������A����ɂ��́v�Ƃ܂��Ō�肩���܂����B
���̏��b���A���ł́A������O�ɂȂ�܂����B
���悻�A�l�Ԃ��z���ł��邱�Ƃ̑����́A�����\�Ȃ��̂炵���ł��B
�u�����Đ��v���A�u���v�Ƃ͌�����܂���B
�����ԍ��F19603593
![]() 2�_
2�_
�����́A�R�s�y��Y�ɂ��������܂���B
��������A�R�s�y���܂����B�iQ�P�Q�U�j
�����A�����ǂɓd�b���āA���l�т��Ă����܂��B
http://www.asj.gr.jp/qanda/101150.html
�����ԍ��F19603617
![]() 2�_
2�_
��mobi0163����
�͂��߂܂��ā@������
�����悻�A�l�Ԃ��z���ł��邱�Ƃ̑����́A�����\�Ȃ��̂炵���ł��B
�f���炵�����t�ł��ˁB
�������ꂪ�����ł���A�����I�ɐl�ނɂƂ��āu�K�v�������̂ł��傤���H�u�s�K�v�������̂ł��傤���H
�i�}�W�Ɏ��₵�Ă����ł͂���܂���B�j
�����ԍ��F19603663
![]() 2�_
2�_
���`��
�e���[�J�[��hi-fi�̎g�����́A�A
�[�l�����I�[�f�B�I����Ȃ���A���Ă����A��ʂ̂��߂Ɏg���Ă�C������B
������A�W�������������֗��Ȍ��t�I�ȁB
�����ԍ��F19603680�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���u�����Đ��v���A�u���v�Ƃ͌�����܂���B
���̃}�C�N��X�s�[�J�[�̓��쌴���ł͖����ł��ˁB
�������ς��Ȃ��ƁB
�����ԍ��F19603697�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����[�i�U���g�[�}�C�N�[�d�C�M���[�����[�d�C�M���[�X�s�[�J�[�[�U���g�j�[����
���́i�j�̒��̎d�g�݂�ς��Ȃ��ƁA�����ł��ˁB
��C�U���𗘗p���Ă������A����ł��傤�B
������A�u�g�[�^�����R�[���v�B�B�B�i�����́A�W���[�N�Ȃ̂ŁA�����Ă��������j
�����ԍ��F19603764
![]() 2�_
2�_
�}����������A�i���ɕs�\�B
�����ԍ��F19603966
![]() 3�_
3�_
�����Đ����Ă���Ȃɏd�v�H
�����Ċy������Ό������낤��������������������낤���ǂ��I�c�Ǝv���Ă��܂����ł��B
�c��������킩�����̂́A�u�����Đ��v�Ƃ����L�[���[�h�������������ł��̎��͂̂������������Ղ�B
�ǂ���Ŋe���[�J�[�����̂����̃L�[���[�h������ȂɍD��Ŏg��������킯���I�c�Ɣ[�����܂����B
�����ԍ��F19603969
![]() 3�_
3�_
����̉��y����ɂ����āA�u�����v�Ƃ����T�O���̂����B
�����ԍ��F19604005
![]() 2�_
2�_
>�����v�Ƃ����T�O���̂����B
�ł��A�ʂɍ\��Ȃ���ł����A�u����ґ����͂������Ǝv���Ă��鉹�v��\�����t������ɗ~�����B
�����ԍ��F19604046�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���l�̓Z�C�E�`����
���A�u����ґ����͂������Ǝv���Ă��鉹�v��\�����t������ɗ~�����B
���ӂ��܂���B
���������u�����v�Ƃ������t���̂��I�[�f�B�I�̐��E�Ɏ������ނ̂��i���Z���X���Ǝv���Ă���܂��B
�u����̌��t�v���ǂ����̂�������Ɨǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F19604087
![]() 3�_
3�_
NHK�Z���ł́A�����I�ɂ́A�e�ƒ�ւ̕��y������ɓ���āA22.2ch�����Ɍ����Ă̎������s���Ă܂��B
http://www.nhk.or.jp/strl/publica/rd/rd148/PDF/P33-44.pdf
�����ԍ��F19604131
![]() 2�_
2�_
��NHK�Z���ł́A�����I�ɂ́A�e�ƒ�ւ̕��y������ɓ���āA22.2ch�����Ɍ����Ă̎������s���Ă܂��B
�߂������ɂ����Ă̓i���Z���X�B
�^�����ƍĐ����̊u����́A�ǂ����߂�H
�����ԍ��F19604164
![]() 2�_
2�_
�ʐ^�̂悤�Ɂu�����܂܂��Č�����v�u���i�����v�݂����Ȋ��o�ŗǂ���Ȃ��ł����ˁB
�����܂ł���̔��e�Ŏg���\�����u�����Đ��v�ł��ǂ��Ǝv�����A���Ɉӎ����Ȃ��Ă��ǂ����B
�����ɌŎ�����v���̕]�_�Ɠ��m���X���_�����J��L�������Ƃ����������ǁA����Ȃ��ƍ��A�}�`���A���m�ōČ�����K�v�͂Ȃ��ł��傤�ˁB
�l�I�ɂ́A�����̒��ł̃��t�@�����X�@�������Ă����Ɨǂ����ȂƂ͎v���܂��B
����Ȋ����B
�����ԍ��F19604202
![]() 2�_
2�_
�啪�c�_���i�悤�ł��ˁi��
���ǂ̂Ƃ���N�����������Ƃ̖������������߂�s�ׂ͋Ȃ��̂ŁA�Ȃ��̂ɓ����͌�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B
�������Ă��Ă����������c�_�D���Ȑl���܂���ˁB���͍D���ł��i��
�l�I�Ɍ����Đ��ɂ��Ắh���z�I�Ȑ����t�Ǝv�킹��Đ��h�Ƃ����Ӗ������Ŏg�������Ƃ���B
���̐�Ε]�����ł���l�͂��Ȃ��ł��傤���A��͂肻�̎v�킹�Ԃ������]������ɂ͌o�����K�v�ł��傤�ˁB�o�����Ȃ��Ƃǂ����Ă��^����ꂽ���̂ɗ��邵���Ȃ��A�]����ƂȂ錳�̉��t���C���[�W�ł��Ȃ�����ł��B�̂ɑO�X���Ō����Ă����i�R����̉��t�o���Ƃ������t�ɂ��d�݂�����܂����B
�����Ė߂�܂����Aair���`���ŋ��߂Ă����h�N�������Q����قǂ̗ǂ����h�͌����Đ���+��������Ή\�����H
���ɒl������̂͗Ⴆ�Ύa�V���ł�������A�k�����ł�������A�J�����ł������肷�邩������܂���B�ł����ۓI�Ȍ��t�Ō����h�D�݁h������܂��ˁB���đS�Ă����˔��������i���������ł��傤���B�������ȊO�̐��i�͕K�v�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����ؖ����邱�Ƃ͗e�Ղł���ˁB�������͂Ƃ�ł��Ȃ����z�Ȃ����ŏ��荇�����l�������͂��ɂ��邩������܂���B�����A���̗l�ȋc�_�͂��܂�ɕs�тȂ̂Ŋ��������ׂ��ł��傤�B���ꂪ�������Ǝv���܂��B
�]�k�Ƃ��܂����ADSD���̃n�C���]�����ɂ͉\��������ł��邩������܂���B�܂��܂��S�R���W���[�ǂ��낪�o����Ă��܂��A���Ȃ�O����^�����̂͏����n�C���]�ōs���Ă��܂��B��X�̎�ɓ͂��Ă���CD�Ȃ͌��X�n�C�T���v�����O�Ȃ��̂��_�E���T���v�����O���������ۂߍ��܂�Ă����ł��B�܂�c��ȏ��i���j���̂Ă��Ă����Ƃ������ƂȂ�ł����A�^����Ԃ��̂܂܂̏��ʂ�ۂ����܂ܐ��ɏo�Ă��鐻�i�i����DL�����������̂��ȁH�j�ł���Ό����ɋ߂��Ƃ������Ƃ������邩������܂���ˁB����n�C���]�͏����āB
�����ԍ��F19604226
![]() 4�_
4�_
���o���K���E�a�l�f�t�m����
���ʐ^�̂悤�Ɂu�����܂܂��Č�����v�u���i�����v�݂����Ȋ��o�ŗǂ���Ȃ��ł����ˁB
�ʐ^���i���Ă܂��ˁB��
�����ԍ��F19604240
![]() 2�_
2�_
�n�C�r�W�����̌������ANHK�Z���ŁA1964�N����A�n�߂��Ă��܂��B
�����I���o�āA�悤�₭���y���܂����B
22.2ch�������A����������������J�n�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19604279
![]() 2�_
2�_
�u���A���n�C���]�v�u�t���n�C���]�v�u�n�C�T�E���h�v�u�X�[�p�[�T�E���h�v�u���v���T�E���h�v
�ǂ����A�������肱�Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F19604331
![]() 3�_
3�_
���ʂ̐l����́u����ōō��̉��Œ�����̂ˁv���Ďv�킹�āA�~�j�R���������������������i�g���Ă������g�킹�Ėׂ��閂�@�̌��t�B
���̃X���ɏ������ނ悤�ȕ��X����́A���ł���������u�s���A�[�`�v�Ĕq�܂��O��I�ɍō��̕��i�i�ƊF����Ɍ����Ă�����́j���g���|���āA���ۂɂ��������R�X�g��������ł���������A�K���ɒl�i�����āA�ׂ��閂�@�̌��t�B
���X�A�K���ɂ�肷���āA���i�R���Ƃ������T�C�g�Ń{���N�\�ɏ������܂�āA���i�Ƃ��Ă̎������I���Ă��܂����Ƃ�����B
�܂��A���̌��t���D���Ȑl�B�̒��Ɂu���i�v�Ƃ����Љ�I�Ȕw�i�𗝉����Ȃ��]�݂��̕��������A���ʂ̐l�����ɃR�X�g�Ƌ@�\�Ɖ����̃o�����X���l���ėǐS�I�ɍ�������̂܂Ń{���N�\�ɏ������ނ��߁A���ʂ̑f�l�������ǂ�ō������Ă��܂��B
�ŋ߂́u�n�C���]�v�Ƃ������@�̌��t���D��Ŏg���n�߂Ă���B
�����ԍ��F19604380
![]() 3�_
3�_
�������I���o�āA�悤�₭���y���܂����B
����ł�22.2�����������I��Ƃ������ŁB
���͂��̍��A�����ɂ͑��݂��Ă��Ȃ��͂��ł��̂ŁA����̊m�F�͂��肢���܂�����B��
�����ԍ��F19604425
![]() 3�_
3�_
mora�Ae-onkyo�̃V���O���`���[�g�́A�u�A�j�\���v�̃I���p���[�h�B
http://mora.jp/ranking?term=lrank24&genre=hires
http://www.e-onkyo.com/ranking/single/
�����ԍ��F19604460
![]() 2�_
2�_
���ŋ߂͢ʲڿޣ�Ƃ������@�̌��t���D��Ŏg���n�߂Ă���
����͌����Ă�B
�������u�s���A�E�I�[�f�B�I�v�̎����͂���Ȃ�ɍ����ȋ@��ɑ��Ă����g���Ȃ����ǁA
�u�n�C���]�Ή��v�Ɓu�����Đ��v�͂���قǂ������Ȃ����i�B�ɑ��Ă��ϋɓI�Ɏg���Ă�����A�n�[�h�����Ⴂ���ɂ͐��]���ʂ͍������ȁA�֗��Ȗ��@�̎����B
�����Ƃ�
���^����Ԃ��̂܂܂̏��ʂ�ۂ����܂ܐ��ɏo�Ă���
�Ƃ������ƂŃn�C���]�������A�����Đ��Ƃ������z�����߂āc�Ƃ����������Ƀu���͖����݂����ł���ˁB
���ׂẴI�[�f�B�I�@�킪�ڎw�����z�ɂ��āA�����͂�����Ƃ����ɓ��B�������m�͖������z�̓��B�_�������Đ��c�ł��傤���B
�܂��������A���z�Ƃ��Ď����܂�ɁA�����Ɏg���߂��Ĉ����ۂ���`����ɐ��艺�����Ă���C�����Ȃ��ł��Ȃ��B
�����ԍ��F19604553
![]() 3�_
3�_
�u�n�C���]�v�Ƃ��������Ȃ�Ȃ����t���悭�m��Ȃ����ɁA�e�L�g�[�ɔ������܂������i�ɖʔ����̂�����B
���ꂪ������B
http://kakaku.com/item/K0000585230/
���ƁA�n�C���]��ɂ��ĊJ�����ꂽ�ɂ�������炸�A�n�C���]�}�[�N���g���Ȃ��B
�n�C���]�̋ƊE��`�O�Ɋ�悳��āA�Đ����g���ш�F5Hz�`35kH������B
�ǂ����݂��A�w�ǂ̔N���ɂ͕������Ȃ��̂ɂˁB
USB-DAC�Ȃ���̂ƃn�C���]�}�[�N����̃w�b�h�z�����Ă��܂��A���p�̒����ƂȂ邪�A�L�O�ɔ��炸�ɂƂ��Ă���B
���X�g���Ă݂邪�A���͂Ƃ��ɕs���͂Ȃ������肷��B
�����ԍ��F19604690
![]() 3�_
3�_
�n�C���]�ƈ���āu�����Đ��v�}�[�N�A�Ƃ������̂͑��݂��Ȃ��悤�����E�E�E�E
�����ԍ��F19604785
![]() 3�_
3�_
���{�I�[�f�B�I��������ꗗ
http://www.jas-audio.or.jp/jas-cms/wp-content/themes/jas/public/images/contents/about/info/2014/2014_002.pdf
�����ԍ��F19604835
![]() 3�_
3�_
�n�C���]�}�t�B�A�̊F�l�ł��ˁB
�ł͓��{�����Đ�����̖����ɑ����������i�R���̏Z�l�̕��𐄑E�����Ȃ�A�ǂȂ��H
�����ԍ��F19604984
![]() 2�_
2�_
�����́A�]���m����ړ`�������ɂȂ�炵����
�����ԍ��F19605172
![]() 2�_
2�_
WIN����A���v���Ԃ�^ ^
�A����������w
���낢�날��܂����A�݂�Ȍ��C�ł���Ă܂�^ ^
��������WIN����������ł��āA���O�Ă�ł��Ă�����Łi��
�������ď����ƐU��܂���w
�V���v���ɁA�����ʂ�A�u�^���v�u�Đ��v�ŗǂ���ł����ǂ�^^;
�ȒP�Ɍ����ƁA��a���������Ȃ���Ηǂ���ł���ˁB
���B�݂����ɉ��y����Ă����iWIN����͂���Ă��邩�j�l�͊y��ł��������A�ʂɊy�����Ă��Ȃ��Ă��A���Ƃ��������Ƃ��A���ł������Ǝv���܂��B
�I�[�f�B�I�I�ɏ����ƁA�F�t�����ĂƂ���ł��傤���B
���ꂪ����ƁA�ǂ����Ă���a����������i�����₷���j�B
��ՓI�ɐF�t������肭�����āA���̂������u�ǂ��v��������P�[�X������ł��傤�B
��̍D�݂��ĉ����H
���čl�������ɁA���ꂩ�Ȃ��Ɓi�Ⴄ���ȁH
�ł��A���̃W��������A���̊y��A���̉����ł��ꂪ���Ă͂܂邩���Ă����Ɓc�����ł��ˁB
�F�t���Ȃ��A�t���b�g�ȍĐ����A���ʂƂ��Ĉ�ԁu�ǂ��v���ȁA�����ȈӖ��ŁB
WIN����ɂ͈Ⴄ���Č����邩��������w
������Ƙ^���āA������ƍ���Ă����ACD�ł��т����肷�邮�炢�ǂ����Ŗ�܂��B
�ł��ADSD�Ƃ��n�C���]�͂���ς�ǂ���ł���ˁB
�܂��A�{���̓A�i���O�Ř^���āA�A�i���O�ō���āA�A�i���O�ōĐ����Ă����̂���Ԍ����ɋ߂����ȁB
���̒��ɂ́u���z�v�ɋ߂������o���Ă���l���������܂��B
�l���m�邾����3���c���Ă��Ƃ́A�����Ƃ����ς������ł��傤�B
�{���ɒm�肽���̂ł���A�f���ł����������ĂȂ��Œ����ɍs���Ηǂ������ł͂Ȃ����ƁB
�܁A�f���ł̂������ʔ����ł�����w
�����ԍ��F19605275
![]() 4�_
4�_
�܁A�F�ƌ����A�A�A
�}�C�N�ʼn����E�������_�ŁA�}�C�N�̐F�����Ă邵�B������L�^���鑕�u�͑S�ă}�C�N�̓��͐M����悸�͑������˂Ȃ炸������H�̐F�����B�A�i���O�ŋL�^���Ă����̑��u�̐F���t�����A�f�W�^���L�^�ł�AD�ϊ��Ȃǂ̐F�����B
�~�L�V���O�A�_�E���R���o�[�g�A�}�X�^�����O�܂ł̉ߒ��ő��u�̐F�����BCD�̃X�^���p�[���ߒ��ŐF�����BCD���Y�̉ߒ��ŐF�����B
CDP�ŐF�����B
�A���v�ŐF�����B
�X�s�[�J�[��w�b�h�z���ŐF�����B
���̎�������͉��l��������܂���B
�����L�^���čĐ�����ߒ��ł́A100%�F�����܂��B��O�͂��肦�܂���B
�ʐ^���ꏏ�ł��B
�≖�Ȃ�A�t�B�����̐F�����B
�����t�̐F�����B
�����L����̃����v�ق��̐F�����B
��掆�̐F�����B
���ƁA�ʐ^�Ƙ^���͎��Ă���ꍇ������܂��B
�Ⴆ�A�ʐ^�͍\�}�̒��ŕ\�����������̂��������邽�߂Ɉӎ��I�ȃg���~���O�������肵�܂��B���邢�́A�킴�Ɣw�i�����邱�Ƃ�����܂��B
���y���ꏏ�ł��B�\�����������̂ɂ���āA�}�C�N�̃Z�b�e�C���O�ς��܂��B�܂��A�@��A�u�����͊y�킩��߂����������A�{���ȂǁB�Ⴆ�A�s�A�m�Ȃ�w�̓���(����Ղ̕��͋C�H)�܂Ń��A���ɘ^�肽���Ȃ献�Ղ̋߂��Ɏd���݂܂��B
�h���������Ĉꏏ�ł��ˁB���Ƀo�X�h���̓}�C�N�̕����≓���߂��ł܂������Ⴄ���ɂȂ�܂��B
�Ō�ɁA�A�A
���y���ʐ^���A�v���̕\���҂́A�@�ނ⌴���A�ޗ��A��@�ɂ��F��������A�ω������肷�邱�Ƃ�O���ɒu���Đ��삵�܂��B(�n��ł����ˁA�ނ���)
�����Ƃ����A�F���t�����Ƃ�ω����邱�Ƃ��t��ɂƂ��ĕ\�����邱�Ƃ�����܂��B
�Ƃ������Ƃł��傤�ˁB
�����ԍ��F19605448�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��mobi0163����
�u�ꂳ�� �L���ȕ��ł���(��)
��w�̕����w�̋����ł��ˁB
�����������Ђ̕����A�I�[�f�B�I�ɂ��Ĉ꓁���f���Ă���T�C�g�Ȃ̂ŁA�ʔ����ǂ߂āA�Q�l�ɂ��Ȃ�܂��B
BBS���Ă��ĂāA���܂ɉ��サ�����ɂȂ�ƁA�u�ꂳ��o�Ă��ĂȂ��߂�Ƃ��낪���܂����T�C�g�ł���ˁB
�����ԍ��F19605489�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������H�w�̌������ł���B
�I�[�f�B�I�̎���Ȋw�Ƃ��ĎQ�l�ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F19605686
![]() 2�_
2�_
> 22.2����
�T�u�E�[�n�[�ɑ������郆�j�b�g�́A�O����2�����Ȃ�ł��ˁB
�O���1���Ȃ̂��Ǝv�����B�B
�����ԍ��F19606037
![]() 2�_
2�_
>�����́A�]���m����ړ`�������ɂȂ�炵����
���������K���P�[�ɍ��`���Ƃ����������ʼn���`����Z�p������܂����ˁB
�����������̂̓I�[�f�B�I�I�ɂ͎g������̂Ȃ낤���B�B
�����ԍ��F19606748
![]() 2�_
2�_
�ŋ߂́A�i�C�X��M�ԗV�т����s���Ă�̂��ȁH
�����ԍ��F19607541�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�v���C���[�́A���X�i�[�̎��ɓ͂����ɁA�ǂ�قǂ̎v���������Ă����ł��傤���B
�X�^�W�I�^���ł͂Ȃ��A���C�u��^�����Ĕ���ꍇ�A�u����ȉ��͎����̉�����Ȃ��I�v�Ɣ��点�Ȃ��R�_���������邩�A�����������Ă��܂����B
���v�D��Ƃ����l���������ƁA�Ȃ��ł��B�B�B
�����͂���Ȃ��̂����m��Ȃ��ł����A�R�ł��R�_�����������ė~�����B
���́A���̃R�_�����Ɍh�ӂ����߁A�̔�����Ă��鉹�����u�����v�ƌĂт����ł��B
�Đ����͂���܂��E�E�E
�����ԍ��F19607795
![]() 2�_
2�_
�ڎw���I�i�C�X10000�_�������肵�Ă���
�����ԍ��F19607797
![]() 2�_
2�_
���O������́u�����Đ��Ƃ͉��ł����H�v��
�����Ō������Đ�����̂́A�����I�ɍĐ��s�\�ȉ����ƌ��_���Ă�낵���̂ł��傤���ˁH
�ǂ��ł������O����H
�����̒�`�����܂����͂����肵�Ȃ��̂ŁA�������x(hi-fi)�̍Đ���ڎw���ƍl���Ă͂������ł����B
�����ԍ��F19608055
![]() 3�_
3�_
����ȂɁu�����Đ��}�[�N�v���C�ɓ���܂����̂��H
�����ԍ��F19608067
![]() 2�_
2�_
10000�z�����ˁ[
�ł��A����ȉɂ�����Ȃ�A�����ƌo�ϊ����ɍv�����ė~�����ȁB
�����ԍ��F19608157�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����ł͊F�l�A���낻��A�����Đ��̒�`�\���܂��B
�I�[�f�B�I�ɂ����錴���Đ��Ƃ́A�F�������Đ������߂��u�����Đ��}�[�N�v���\��ꂽ�I�[�f�B�I�@�킪�t�ł鉹�̂��Ƃł���B
�l�ނ̗��j�ɂ����āA���������Đ��}�[�N�̔F���I�[�f�B�I�@��͑��݂����A�n���l�͖������̉��������̂͒N�����Ȃ��B
�F�������Đ�����͖������̍\�����𖾂炩�ɂ��Ă��Ȃ����A�u���i�R���v�Ƃ����f���ɃJ�L�R�~�����Ă��郁���o�[�̒��ɐ���ł���炵���B
���̍\�����́A�n���l�ɔ�ׂĐ����{�̉s�����o�������A���Ȃ�̕Ύ��I�Ȑ��i������Ƃ��A���X�A��������ƈُ�ȍs���ɏo��ꍇ������̂ŁA���܂�h�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�����ԍ��F19608318
![]() 2�_
2�_
�������I�b�X��������
�����́A�܂�ł�
�܂Ƃ߂ł���
�����Đ��Ƃ͌��z���A�Ƃ������Ƃŗǂ��ł����H
�����ԍ��F19608584�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
����������S���j�����
�����ԍ��F19608671
![]() 2�_
2�_
>�����Đ��Ƃ͌��z���A�Ƃ������Ƃŗǂ��ł����H
�s�\����Ȃ���
�����Ŏg����y��Ɠ��������g���Ηǂ�
PC�����Ȃ������{�l���g�����V�X�e���𑼐l�ɂ��܂����������V�X�e�����g���Č��o����
�o���h�Ȃ�R�s�[�o���h���Ηǂ����A�I�[�P�X�g���Ȃ�y��c���g���Ηǂ�
�ȒP�Ȃ��Ƃ���Ȃ���
�I�[�f�B�I�Ƃ����g�ɂ�������Ă͌�������鎑�i�͂Ȃ���
�I�[�f�B�I�ɂ�錴���Đ��́E�E���z����
�����ԍ��F19608697
![]() 3�_
3�_
�������ɃR�s�[�o���h�Ō����Đ��͖����������ł��傤���H(^_^;)
�����ԍ��F19608782
![]() 3�_
3�_
�����O����
�ȁA�\���ǂ��蓚���̂Ȃ����₵�Ă�����Ƃ���H
����ɂ���Ȃ�w
�����ԍ��F19608783�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�l�Ԃ���S���������t�͖�������(^^�U
�Č����̂��鉹�����Č����Ƃ��Ȃ�������Ȃ����ȁH
�����ԍ��F19608915
![]() 3�_
3�_
���Ȥ�\���ǂ��蓚���̂Ȃ����₵�Ă�����Ƃ���?����ɂ���Ȃ�w
���X����̏ꍇ�����ł��邱�Ƃ�錾(����)���Ȃ��炵�Ă���̂ł���ȂɃ^�`�͈����Ȃ��B
�����l�����͍̂D���ł���
�킴�ƒނ��Ă킴�ƒނ��āc�̑o�����ӂ̊W�̂悤������A����قǖ��Ȃ��B
�����ԍ��F19609013
![]() 2�_
2�_
�����킴�ƒނ��Ă킴�ƒނ��āc�̑o�����ӂ̊W�̂悤������A����قǖ��Ȃ��B
KY�Ȑl�́A���ꂪ�킩���Ă��Ȃ��B
���̏�A���l���排������āA�������ƋA���Ă��܂��B
���̕����A���ӔC�B
�����ԍ��F19609064
![]() 4�_
4�_
�菑���̌��e������B�ׂ�ɁA������R�s�[�������̂�����B
���{�͌��{�A�R�s�[�̓R�s�[�Ȃ̂́A�����B
�������A�R�s�[�́A���{���R�s�[�������̂�����A�����ɂ͊W��������B
�����ƍĐ����������B
�ʂ��̂����ǁA�����ɂ͊W��������B
�u�����Đ��v�Ƃ������t�ɂ́A�o���A�m������g���āA���̊W�����v�l����ɒl���閽�肪���݂��Ă���B
�����ւ�ʔ������肾�ƁA�킽���͎v���B
�����ԍ��F19609182
![]() 4�_
4�_
���������t�͈�����ł�����
�������Ŏg����y��Ɠ��������g���Ηǂ�
��
���o���h�Ȃ�R�s�[�o���h���Ηǂ����A�I�[�P�X�g���Ȃ�y��c���g���Ηǂ�
�ł͖����ł��ˁB
�����t���Ε�����܂����A�������ɂ��Ă��ʂ̉��ɂȂ�܂��B���Ȃ莗�Ă���Ƃ͌�����ł��傤���i�j
�����ԍ��F19609305
![]() 3�_
3�_
���ۂ̌����Ƃ͘^�������O�̌��X�̉��ł��邯��ǁA�I�[�f�B�I�̐��E�ł́A�{�[�J���Ɗy�Ȃ̉��̃o�����X�Ƃ��������ꂽ��Ԃŏo���オ�������y�f�[�^���I�[�f�B�I���[�J�[�����蕶��Ō����Ƃ���̌����ł���ˁI
��������F�X�ł��傤�A�ꔭ�^�������A�{�[�J���A���t�ʘ^��̂�����̂ł��傤�I
�����𒉎��ɍČ�����Ƃ����̂́A���y�f�[�^�𒉎��ɍČ����鎖���Ǝv���܂���I
�����𒉎��ɍČ�����w�b�h�z���Ȃ�w�b�h�z���[�q�ɏo�͂��ꂽ���y�f�[�^�𒉎��ɍČ�����w�b�h�z���̎��ł���ˁI
�����t�������Ƃ��āA���̌����𒉎��ɍČ�����Ƃ������́A����Œ��������ƁA�����ʒu�Ř^�����ꂽ�����A�����ɕ�������Ƃ������ł���ˁI
�����ԍ��F19609321�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�ˑR���݂܂���B
�菑���Ȃ�A�킩�邯�ǁA
���[�h�ň���������̂��R�s�[������A�p�b�ƌ��ɂ͂킩��Ȃ��ł��E�E�E
�悭�������炩���āA�킟�A�ǂ����悤�ƔY��ł��܂����A3�b��A�ǂ����ł�������I
�Ƃ������ƂŔz�z��������Ă܂��E�E�E�܂��A���ɖ��Ȃ��̂ł����ǁA
�Ȃ�ƂȂ����{���c�������Ƃ����C����������̂ł����E�E�E
����͂����ƁA�C�ɂȂ邱�Ƃ��E�E�E�݂Ȃ���A�i�C�X�����ł��ˁ`�����ŁA
�_�`���E�N���u���ɁE�E�E���肢���܂��B
���ނ���A����Ƀi�C�X�����Ȃ�I�������A������Ȃ����`�I
�����ԍ��F19609345
![]() 4�_
4�_
�܂�
���z�ŗǂ�����Ȃ��ł����B
�u�����̓��}���X�A���l����̓I�J���g�v�����̐��E�B
���}���X�˂��i��ł��������I
�����ԍ��F19609360
![]() 4�_
4�_
�����𒉎��ɍČ�����Ƃ������͉��̗��̓I�ȍL����͂ӂ��܂�܂����ˁA�A
�����ԍ��F19609455�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�u�����Đ��v�Ƃ�����ΓI�ȉ����o�邩�ǂ����ł͂Ȃ��A�u�����Đ��ɂǂꂾ���߂������Ƃ�邩�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�������q���Ȑl�قǁA�u����͈Ⴄ�v�Ɗ����A�݊��Ȑl�قǁA�u����͌����Ɩw�Ǔ������I�I�v�Ɗ����邱�ƂɂȂ�B
�����Łu�����Đ��}�[�N�v�ł͂Ȃ��āA�u�����Đ��ɕ�������}�[�N�v�ɂ��ẮA�u�q�������p�v�Ɓu���ʂ̂����p�v�ɕ����Ĕ��s���邱�ƂƂ��邪�A�u���ʂ̂����p�v�͑傫�Ȍ��ׂ̂Ȃ���ʂ̃I�[�f�B�I�u���i�v�ɂ��Ă͑S�ď��F����B
����A�u�q�������p�v�Ƃ��Ȃ�ƁA���̐l�̒����⎨�̌`�ɂ���ĕ����������قȂ邽�߂ɁA�ǂ̃��x���̒������������ɖ������˂Ȃ�Ȃ��B
�u�q�������p�v�̐��i�w���ɍۂ��ẮA���@�Ȕ��s�̃X�[�p�[���͐f�f���ʏؖ����̒�K�v�Ƃ���B
���̒��s�킸�ɒ������}�b�`���Ȃ������w�������ꍇ�A�u�����Đ��ł͂Ȃ��I�I�v�ƃN���[�������ĕԕi����]���Ă�����ɉ�����`���͂Ȃ����̂Ƃ���B
�ȏ�A�u�F�������Đ�����v��蔭�\����܂����B
�����ԍ��F19609540
![]() 3�_
3�_
���������𒉎��ɍČ�����Ƃ������͉��̗��̓I�ȍL����͂ӂ��܂�܂����ˁA�����̉����i�Z�p�j
�����ԍ��F19609579
![]() 2�_
2�_
�h������x�[�X�A�M�^�[�ŁA�u�S�[�X�g�m�[�g�v�Ƃ������Ƃ������A�t�@������܂��B
�������邩�A�������Ȃ����̉��ʼn��t�����A�B�����I�ȑt�@�ł��B
�O���[�u���������������Ɏg���܂��B
���̉����A��������l�́A�u�q�����v�A�������Ȃ��l�́u���ʎ��v�ł��傤�B
�����ԍ��F19610085
![]() 3�_
3�_
����A�i�C�X�̃n�b�L���O�����ɖ߂�܂����ȁB
�����ԍ��F19610300
![]() 6�_
6�_
������������オ���Ă���̂Ŋ����ĕʂ̐������B
�h�����Ɗ���������Đ��Ƃ͉����h
���ǂ����ɋA���ł���Ηǂ��̂ł́B�����������Ƃł���Ό�����m��Ȃ��Ă��l���x���Ŏv���Ƃ���͂��邵�]���ł���B
�Ⴆ�Ύ��̏ꍇ�A�����Ǝv�킹��ɂ͂悭������Ȃ̖������ƁB�i�R����̌����Ă邱�ƂƔ��܂��ˁB
���Ă��ăI�[�f�B�I�}�j�A�͕Ȃ���������̂ł��傤�B�Ȃƌ����Ă͂��܂�ɒ��ۓI��������܂��A�y���A�ǂ����s���R�Ɋ����邱�Ƃ̖������Ƃł��ˁB��ԊȒP�Ɍ��ɂ߂�̂͐������Ƃł��B���Ƃ����͕̂s���R�����@���Ɍ���A�N�ł��]���̊�ɂ��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�{���Ȃ玩���̐���^���������̂��̂��ł��ǂ��̂�������܂��A�N�ɂł��ł��邱�Ƃł͂���܂���B�A���A�l�̐��ł�����ɒ[�Ȃ��̂������A������x�͒N�ɂł�����ł���͂��B���̐�������ƕ@�l�܂��ĂȂ��H�Ƃ��A�T�s���h�����ĂȂ��H�Ƃ��B���Ӑ[�������ƕs���R�����������Ă���͂��ł��B�y��̉��̕s���R���ɋC�Â��̂͂���̉��p�ł��ˁB��͂�o�����K�v�ƂȂ�܂����A����m������̔��f������͂Ȃ��ł��傤�B
�T�E���h�G���W�j�A�͎����̐��ł��炩�����i���j�^�[�����j������Ă��܂��܂����A�I�[�f�B�I�ɂ����Ă����p�͂ł��܂��B
���i�ɂ����Ă͎������J��Ԃ��A�Ȃ�ׂ��h�ȁh�̖������̂�I�т����ł��ˁB
�����ԍ��F19610731
![]() 6�_
6�_
����A�Q�O�P�R�N�W���Ɂu�T�C�g�E�E�L�l���E�t�F�X�e�B�o�����{�v�i���Z�C�W�E�I�U���@���{�t�F�X�e�B�o���j�ŏ����w���ɂ��A�㉉���ꂽ���x���̃I�y���u���ǂ��Ɩ��@�v�����^���ꂽ�A���o���������F��:�̌��u���ǂ��Ɩ��@�v�����A�O���~�[�܍ŗD�G�I�y���^���܂���܂��܂����B
��L��CD���^���܂���܂����A�Ƃ������Ƃ́A���t�̃��x�������������̂͂������ł����A�^���̉������悩������A���t�̃f�B�e�B�[����j���A���X����������^���������̂ł��傤�B
�I�[�f�B���[�J�[����́A�u���t�̎w�g���܂ł킩��悤�ȗ֊s�̂��鉹�������ł�������Ŋ������܂��B�v�ȂǂƂ悭�����܂��B
������ƁA�҂��Ă��������B���������邽�߂ɂ́A�Đ����鉹�y�f�[�^�ɂ�����������Ă��Ȃ��Ƃ����܂���B����́A���y�f�[�^�𐧍삷�鑤�̐l�����̎d���ł��B
�I�[�f�B�I���[�J�[����̎d���́A���삳�ꂽ���y�f�[�^�𐳊m�ɍĐ����邱�Ƃł��B
���y�f�[�^�̍Č����������ɗD�G����i������ׂ��ł��B
�u���Ђ̃I�[�f�B�I�V�X�e���́ACD�̉��y�f�[�^������߂Đ��m���������ōĐ����܂��B�v
�������A���ꂾ�Ɓu����v�ɂȂ炢�̂ŁA��L�̂悤�Ȍ��������Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����ƁA�����f�[�^�����y�f�[�^�Ȃ̂ŁA���y���Č����Ă���Ǝv���Ă��܂��̂�������܂���B
�܂��A�����v�������C�����͂킩��Ȃ�����܂���B���`�x�[�V�����̖��Ƃ��āB
�ƒf�ƕΌ��̃R�����g�ł��B
�����ԍ��F19611367
![]() 3�_
3�_
�B�����I
�|�b�v�X�̂��Ԃ�
�ȑOTV�ŏ��C�J�̂��Ԃ��ƃh���J���̂��Ԃ��̈Ⴂ��������Ă���
�����A���^SP��20Hz�Đ����A�C�m�E�GSP���Ƃ��m��Ȃ����A�r�[���Ōۖ��_���Ȃ�\�Ȃ̂���
�����ԍ��F19611398
![]() 2�_
2�_
���I�ɂ́A�����Đ���ڎw��������
���̉������g���Ăǂꂾ���ǂ����������o���邩�A
��������߂ēw�͂��Ă��������Ǝv���܂�
�����ԍ��F19615565�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���������A�́A
�o�C�m�[�����Ƃ����̂ɛƂ����悤�ȁE�E�E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E9%8C%B2%E9%9F%B3
�܂��́A�}�C�N���o�C�I����g���Čۖ��ō�낤���E�E�E�l�������邩�疳�����H�H�H
���႟�A�N���[���œ�����āA�]�ɋL�^�������̂��A�ڐA���悤���E�E�E�L���[���������B
�����ԍ��F19615881
![]() 3�_
3�_
�X����̖��O����A���_�������������̂ŁA����ɂĂ��J���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�ӂƁA�v���Ă��܂��܂����B
�X�e���I�ƃT���E���h�ł́A�ǂ���̕������̉��t�ɋ߂�������̂��A�ƁB
�l�I�ɂ́A�����̓X�e���I�A�Տꊴ�̓T���E���h�A���Ǝv���̂ł����A�T���E���h�̋Z�p�������Ɣ��B���āA�������X�e���I�Ɠ����ɂȂ�����A�T���E���h�̕������̉��t�ɋ߂�������悤�ɂȂ�̂ł��傤���B
����Ƃ��A�����̃T���E���h�V�X�e�������`�[�v�Ȃ̂ŁA����Ȃ�̐ݔ��A���𐮂��A���܂ł��A�X�e���I���T���E���h�̕������̉��t�ɋ߂�������̂ł��傤���B
�b���������Ԃ��悤�ł��݂܂���B���i���A���������̂ŁBm(_ _)m
�����ԍ��F19616454
![]() 1�_
1�_
���Ȃƌ����Ă͂��܂�ɒ��ۓI��������܂��A�y���A�ǂ����s���R�Ɋ����邱�Ƃ̖������Ƃł��ˁB��ԊȒP�Ɍ��ɂ߂�̂͐������Ƃł��B
�y�����s���R���ƁA�����[�l�����I�[�f�B�I�̗̈�ł��B�A���v���X�s�[�J�[��CDP�������~�ȏ�̂��̂��A���Ȃ��Ƃ��s���R�ȉ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��B
�����Ƃ��A�ŋ߂̕��y���i�т̐��i�͒ቹ��̂��ǂ��Ƃ����A���I�ɂ͂�낵����ʕ���������悤�Ɏv���܂��B�Ȃƌ������́A�����������t����F������悤�Ɏv���܂��B
���y���i�т�����̃N���X�ɂ́A���̂悤�Ȗ��t���Ȃǂ��Ȃ��B���R�Ȋ����̂��̂������Ǝv���܂��B
����Ɍ����A�Ȃƌ��������A�F�ƌ������A���ƌ������A�����������̂��y���ނ̂��I�[�f�B�I���Ǝv���܂��B
CDP��DAC���A���v���X�s�[�J�[���w�b�h�z�����A���������ăW�������≹���ɂ���Ďg���V�X�e����ς���̂�����ł�����B
�����ԍ��F19616615�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
>���I�ɂ́A�����Đ���ڎw��������
>���̉������g���Ăǂꂾ���ǂ����������o���邩�A
>��������߂ēw�͂��Ă��������Ǝv���܂�
�����̃X���ɏW�������X�S���ŁA�e�X�̃V�X�e���Ō����Đ���ڎw������
������A���Ԃ�݂�ȈႤ���ʂɂȂ��Ă��܂��Ǝv���܂��B�@�ނ̐��\�����
�Ⴂ�Ȃ�ł���H�Ƃ����Ӗ�����Ȃ��āA�ڎw���Ă���p���݂�ȈႤ�̂ŁA
���������I�ɃV�X�e���ɑ��Ă̑���������Ⴄ�̂��Ǝv���Ă��܂��B
���O����̂������ɂȂ�ꂽ�A���̕����I�Ă���Ǝv���܂��B
���̃X���A�ʔ��������ł���B���肪�Ƃ��ł��B
�����ԍ��F19616858
![]() 1�_
1�_
>�l�I�ɂ́A�����̓X�e���I�A�Տꊴ�̓T���E���h�A���Ǝv���̂ł����A�T���E���h�̋Z�p�������Ɣ��B���āA�������X�e���I�Ɠ����ɂȂ�����A�T���E���h�̕������̉��t�ɋ߂�������悤�ɂȂ�̂ł��傤���B
5.1�`�����l���r�`�b�c�������
����łT�{�̃X�s�[�J�[��p�ӂ���Ό��\�A���A���݂����ł���
��ł����������w�b�h�z���̏ꍇ�͂Q�Ȃ�Ō����Đ��͕������Ă�悤�Ȃ���ł�
�����ԍ��F19618700
![]() 0�_
0�_
�q�����[�E�n�[�����D���Ȃ̂ŁASACD Saround�����Ă��܂����A���̂R�������ł��A�T���E���h�̓x�����A�����Ԃ�����܂��B
���ǁA
�Đ������{�I�[�f�B�I���u�{���[���A�R�[�X�e�B�N�X�A���̂R�v�f�������肩�ݍ����ƁA���Ȃ�A�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19618930
![]() 2�_
2�_
�ǂ��܂ŋ߂Â��邱�Ƃ��ł��邩�A���Ă����̂́A�P�Ȃ郆�[�U�[���x���ł́A���ǂ̂Ƃ���A��������Ă��Ƃł����ˁB
���͉��H���Đ��Ŗ������邱�Ƃɂ��܂��E�E�E���āA�����ƁA������������o���A������ł������͂�����܂��ˁB
���̂悤�ɓ݊��Ȏ��قLj��オ��A���Ă��Ƃ̂悤�ŁB
�����ԍ��F19619881
![]() 1�_
1�_
���̏���Șb�ł���
���F�Ɋւ��Ă͌����������鑶�݂ł��闝�z���Ƃ������̂����݂���Ǝv���܂�
����͂�����]�`���o�鉹�ȂƎv���܂����A
���͌������̕����Ă��]�`�͏o�Ȃ��ł�
�����t�ɂ����Č����͂�����Y��ȉ��ł����Ċ������鉹�ł͂Ȃ�����
���t����肢�I���Ɋ������邱�Ƃ͂���܂����ǂ�
���Z�����܂�AV���D�̃A�_���g�r�f�I�̕���������������̂Ɠ�����������
�����ԍ��F19620123�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ቹ���������́A�ďグ�ĒJ�ԍ���������D�܂��̂Ɠ����H
�����ԍ��F19620249�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Q�X�ȗႦ�Ŏ��炵�܂����B
�����ԍ��F19620253�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�R���T�[�g�ɍs���āA�u�����t�v���̂ƁA��������^�����u���C�u�^���v�����Ƃ̈Ⴂ�ɂ��āB
���C�u���ƁA�R���T�[�g���ɂ���ẮA������������������A���Ȃ�������A�Ȃɂ���ẮA�₽��ቹ������������A�ׂ������̃j���A���X�܂Œ������Ă��Ȃ�������B
����A���̃��C�u�Ղ��ƁA���^���ꂽ�������܂��ҏW����Ă��āA������̕����y���߂��肵�܂��B
�R���T�[�g�z�[���Œ����u�����v�́A���������X�O���A���ډ��͂P�O�����x�ł��B���̒��ډ��������Ƃ���Ȃ�A��قǏ����ȉ��ŁA�ڂ̑O�ɐw���Ȃ�����A���������Ƃ͓���Ǝv���܂��B
�u�����v���A���Č��\�A������Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19620427
![]() 1�_
1�_
�������Đ��Ƃ͌��z���A�Ƃ������Ƃŗǂ��ł����H
���[�J�[�̐�`����ł��B
�N�����ǂ��Ɗ����鉹���o���@�B������Ȃ��
�܂��@�N�����ǂ��Ɗ����鉉�t�Ȃ�A�����Ȃ肪���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł́H
���j�^�I�ʼn𑜓x�̍������u��
�ǂ��^���̉����A�f���炵���ǂ��������ꂽ�ꍇ�͗ǂ�����
�������̂b�c���������ŕ������ꂽ�ꍇ�́A�S�R�ǂ����u�Ƃ͎v���Ȃ��ł��傤
�����͑f�ނŁA�I�[�f�B�I�@��͖��t��
�f�ނ�C���ɍ��킹�āA�����ɔ��������Ǝv����悤�ɖ��t�����邩
���傹���������Ċy���ޕ��ł��@���l�Ƀ_����������悤�Ȑl�͂��������ł��傤
�����ԍ��F19621621
![]() 0�_
0�_
NHK �����������W�u�j���A��"�������v"�̐^���v
�E�X�s�[�J�[�A�A���v�����X�ɔ�������
���������������B�B�B
https://www.nhk.or.jp/asaichi/2016/02/22/01.html
�����ԍ��F19621705
![]() 0�_
0�_
������
���R���T�[�g�z�[���Œ����u�����v�́A���������X�O���A���ډ��͂P�O�����x�ł��B
��قǂЂǂ��Ȃ���Ȃ��Ƃ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB�����Ƃ����z�[���ł���Ȃ�̐ȂȂ�ꎟ���˓������ډ���⋭����i���ډ��Ƃ��Ē�������j�悤�ɐv����Ă܂�����B
�����̒��ډ��������Ƃ���Ȃ�A��قǏ����ȉ��ŁA�ڂ̑O�ɐw���Ȃ�����A���������Ƃ͓���Ǝv���܂��B
�y�킩��̉������������Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B��ɏ��������ˉ����܂߂����ډ��E�z�[���g�[���Ƃ�������Ԑډ��A�o�����܂߂Č����ł��B
�^�����ꂽ�������āA�y�킩��̉������o���悤�ȕϊ����̍Đ����l���Ă�Ȃ�A�����Đ��Ƃ͈�ԉ����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F19621713
![]() 2�_
2�_
�������ǁA������������ɁB
https://www.nhk.or.jp/strl/publica/kenkyushi/pdf/15.pdf
�����ԍ��F19622402
![]() 0�_
0�_
�������͑f�ނŁA�I�[�f�B�I�@��͖��t��
���f�ނ�C���ɍ��킹�āA�����ɔ��������Ǝv����悤�ɖ��t�����邩
������Ɠ����������܂��A�A�A
���̗ǂ��I�[�f�B�I���u�́A���ዾ�ɂȂ��āA�����̈����������ƁA����₷���Č����܂��B
�������A�I�[�f�B�I���u�̃N�I���e�B�ł��B
�����ԍ��F19622558�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������Ɠ����������܂��A�A�A
���̗ǂ��I�[�f�B�I���u�́A���ዾ�ɂȂ��āA�����̗ǂ��������ƁA����₷���Č����܂��B
�������A�I�[�f�B�I���u�̃N�I���e�B�ł��B
���̈����I�[�f�B�I���u�́A���ዾ�ɂȂ��āA�u�����̈����v�������ƁA����₷���Č����܂��B
�������A�I�[�f�B�I���u�̒�N�I���e�B�ł��B
�����ԍ��F19622713
![]() 2�_
2�_
������Ɠ����������܂��A�A�A
�����̈����l�́A���ዾ�ɂȂ��āA�u�l�̈����v�������ƁA����₷���Č����܂��B
�������A�����̈����l�̒�N�I���e�B�ł��B
�����ԍ��F19622805
![]() 1�_
1�_
�����w�I�ɂ́A�u�����Đ��v�Ȃ�T�O�́A���݂��Ȃ��B
����̂́A�u������v�Ɓu����Đ��E����Č��v������B
�����ԍ��F19623001
![]() 0�_
0�_
�����̈������ި����u�ͤ���ዾ�ɂȂ��Ĥ������̈�����������Ƥ����₷���Č����܂������������ި����u�̒ḵ�è�ł��
���̈����I�[�f�B�I���u�́A�s���g����Ȃ����ዾ�Ȃ̂ŁA�u�����̈����v�������ƁA������Č����܂��B
����������ި����u�̒ḵ�è�ł��
�c�������ȋC�����܂��B
�ǂ�����A�ƈ�������B������Ƃ��܂��B
�_���ȃI�[�f�B�I���u�ŕ�����A��B���������ɕ������܂��B
�܂��܂��̃I�[�f�B�I���u�ŕ�����A��B���܂��܂��ȉ��ɕ������܂��������Č�����A�̕���������������Ȃ��悤�ɕ������܂��B
�����I�[�f�B�I���u�ŕ�����A�͂ƂĂ��ǂ����ɕ�����B�̓_���ȉ��ɕ������܂��B
�c���ꂪ�I�[�f�B�I���u�̃N�I���e�B�ł��B
A�����͂܂��܂��ȃI�[�f�B�I���u��肢���I�[�f�B�I���u�̕������|�I�ɂ������ɕ������A
B�����͂����I�[�f�B�I���u���܂��܂��ȃI�[�f�B�I���u�̕����������ɕ�������c�Ȃ�ċt�]���ۂ�����܂��B
B�����͓K�x�Ɏ�_���B���Ă�����Č��Ȃ܂��܂��ȃI�[�f�B�I���u�̕��������悤�ɕ������Ă��܂��A
B�������肵�������Ȃ��ł���ƁA�����I�[�f�B�I���u�̕������������������Ă��܂��Ȃ�Ă��Ƃ�����܂����A
���ۂɂ͂����I�[�f�B�I���u�́A�܂��܂��ȃI�[�f�B�I���u�ł͍Č�����Ȃ��ł����AB�����ɉB����Ă���ו��̎�_�𒎊ዾ�Ō���悤�ɂ��ׂĂ������炳�܂ɂ������������Ă��܂��̂ł��ˁB
�����ԍ��F19623264
![]() 0�_
0�_
���̐��E�Ő��������Ă����v���̘^���G���W�j�A�ƃv���̃~���[�W�V�����̃R���{�łł��Ă��鉹����
���������͊�{�I�ɑ��݂��Ȃ��Ƃ����̂��A���̔F���ł��B
�]���āu���������v�Ɗ�����͍̂Đ����܂��͕������ɖ�肪����A�ƍl���Ă����ł��B
50�N�̃I�[�f�B�I�o���ōŋ߂悤�₭���������Ɗ����鎖�́A�قƂ�ǖ����Ȃ��ė��܂����B
�܂��A�N�̂�����������܂��ǁB
�����ԍ��F19623342
![]() 2�_
2�_
�����ۂɂ͂����I�[�f�B�I���u�́A�܂��܂��ȃI�[�f�B�I���u�ł͍Č�����Ȃ��ł����AB�����ɉB����Ă���ו��̎�_�𒎊ዾ�Ō���悤�ɂ��ׂĂ������炳�܂ɂ������������Ă��܂��̂ł��ˁB
HIFI���邢�͌����Đ���ڕW�Ƃ����ꍇ�A���̂悤�ȃI�[�f�B�I���u���u�����v�ƌ������ƂɂȂ��Ă������Ǝv���܂��B
������^��������Ȃ�ł���������y���ނ��Ƃ�ڕW�ɂ���A���̂悤�ȑ��u�́u�悭�Ȃ��v���u�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�����ɁA���Ƃ��Ό��y��̉�������������������悢�Ƃ������u��������킯�ŁA���̏ꍇ�͓���̉����ɑΉ��������u�������̂ŁA���̂悤�ȃI�[�f�B�I���u�́u�悭�Ȃ��v�A�����Ă܂��܂��ȃI�[�f�B�I���u���u�悭�Ȃ��v�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�y��I�I�[�f�B�I���u���u�����v�ɂȂ�܂��B
�ǂꂪ�������͌l�̚n�D�ł��ˁB
�܂��A�����I�[�P�X�g���ƃR���T�[�g�z�[���ł̘^���ł��A�u����d���v�u����\�d���v�u�}�X�̏d���v�u�X�̊y��̎����d���v�Ȃǁi�d������^��������܂��j�ɂ���āA�傫�������ς��܂��B
�I�[�P�X�g�����R���T�[�g�z�[���ŏo���Ă������͂��Ȃ��ł��A�ǂ̃^�C�v�̘^���ł������Đ����ɂ���I�[�f�B�I���u�͂���܂���B
�������A
���̃I�P�ƃz�[���̑g�ݍ��킹�����̉����A�^���̃^�C�v�Ɋւ�炸����Ȃ�Ɂu�����Đ��v���鑕�u
�^���̈Ⴂ�m�ɏo���āu�����Đ��v���鑕�u
������܂��B�����Č����Đ��ƌ������t���g���Ă݂܂������A�ǂ������̒u�����ł��蓾�Ă��܂��܂��B
����ɉ��y�̃W�������ւ̓K�����l����ƁE�E�E
�����Đ��ƈ���Ɍ����Ă��A�v���Ƃ���͐獷���ʂŎ��E�����Ȃ��ł��ˁB
�ȏ�A�������ł����B
�����ԍ��F19623403
![]() 0�_
0�_
�Ⴆ�A�A���̎�ς�����܂����A�A
���W�J�Z���x���ł��V�`���G�[�V������p�r�ȂǁA����ŏ\���Ɋy���߂�P�[�X�͑�R����킯�ŁB�ł��A���̕ӂ�̉����ł͉����̃N�I���e�B��MP3�Ȃǂ̃��x���ŏ\�����ȂƁA�ނ��냁�����̗e�ʂȂǂ��l�������MP3�̂ق����ǂ�����������܂��B
���y���i�т̃I�[�f�B�I�́A��͂薡�t�����Z���ƌ������A�킴�ƐF��t���Ă�Ƃ������A�A�A����Ȋ��������܂��B����́A����Ŋy���߂܂����A�����̎����������ς��܂�����A����������ɂ����Ȃ�Ǝv���Ă܂��B
�n�C�N�I���e�B�ȃI�[�f�B�I���u�ł́A�����ƌ����f�ނ𒉎��ɍĐ����܂�����A�����̎��������ɔ����Ă��܂��B
����Ȋ������Ǝv���܂��B
�����̐��E�Ő��������Ă����v���̘^���G���W�j�A�ƃv���̃~���[�W�V�����̃R���{�łł��Ă��鉹���� ���������͊�{�I�ɑ��݂��Ȃ�
������J-Pop�n�̎��̈������ڗ����Ă�悤�Ɏv���܂��B�����A�^���G���W�j�A�̎��̒ቺ�ł��ˁB���ł��f�W�^������������悤�ɂȂ��āA�Ȃ�ł��@�B�C���ŁA�^���G���W�j�A�̒��ɂ͂낭�����ە����o�����w�K�����Ȃ��ŁA�@�B�œK���Ɍ떂�����Ă�̂��ȁH�ƌ�����i����R����܂��B
��ςŋ��k�ł����A����J-Pop �̌���͎��̗ǂ��������J��H�����Ǝv���܂��B�C�O��Pops�ƊE�ł����{�Ƃ̑傫�ȍ��͂Ȃ����ǁA���{�̌�����̓}�V���ȁH
���̐��̒��ł́A�ǎ��̑��̂ƁA�Ꮏ�̕��������肠���Ă܂��ˁB
50�N��60�N��ƌ����A���u�͖ܘ_�A�i���O�ŁA�������I�[�f�B�I���������̐�������݂�A������x���B�ł��A�r�̗ǂ��G���W�j�A�́A������g�����Ȃ��čH�v���ėǂ�������w�͂����Ă����悤�Ɏv���܂��B
���́A�u���[�m�[�g���[�x�����x�������f�B�E���@���Q���_�[�̂悤�ȁA�r�����̃G���W�j�A�̍�i�́A�Ⴆ50�N��A60�N��ł��A���̓����̘^���@�ށA�ҏW�@�ނ̃N�I���e�B���l����Α����ȉ����ł��B
�����ԍ��F19623863�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��������^��������Ȃ�ł���������y���ނ��Ƃ�ڕW�ɂ���A���̂悤�ȑ��u�́u�悭�Ȃ��v���u�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���Ȃ��Ƃ��A���̃X���̃^�C�g���̂悤�ɁA�����Đ��Ƃ́H�ƌ��������l����Ȃ�A
���������́A�������悭�킩��N�I���e�B�̃I�[�f�B�I���u��Must�����ł͖����ł��傤���H
�����Ƃ͉����Ƃ���ŁA�����ς̔Z�����I�[�f�B�I���u�ŁA�ǂ�ȉ��y�����̎������ŃX�|�C�����āA�����D�݂̉��F�Œ����Ƃ����b��Ȃ�A�u������^��������Ȃ�ł���������y���ނ��Ƃ�ڕW�ɂ���A���̂悤�ȑ��u�́u�悭�Ȃ��v���u�ɂȂ��Ă��܂��v�͓������Ă�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19623882�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�܂��A���p�ł���܂���B
�u�R���v���b�V�����ƃ��~�b�^�[�v�ɂ��Ăł��B
http://www38.tok2.com/home/shigaarch/OldBBS/43compression.html
�����ԍ��F19623917
![]() 0�_
0�_
������CD�́A�R���v�����܂����Ă܂��B
�����ԍ��F19624059
![]() 1�_
1�_
��������Ɠ����������܂��A�A�A
���̗ǂ��I�[�f�B�I���u�́A���ዾ�ɂȂ��āA�����̗ǂ��������ƁA����₷���Č����܂��B
�������A�I�[�f�B�I���u�̃N�I���e�B�ł��B
�����̈����I�[�f�B�I���u�́A���ዾ�ɂȂ��āA�u�����̈����v�������ƁA����₷���Č����܂��B
�������A�I�[�f�B�I���u�̒�N�I���e�B�ł��B
Minerva2000����̋�ʂ�ł����A�������܂�Ă���F����͗����ł��Ȃ��ł��傤�ˁB
���̃I�[�f�B�I���܂������܂ŒB���Ă��܂���i�ǂ��������y���A�����܂Ř^���������̂����Ȃ��A�K�v���������Ȃ��̂ŁA�����Ă��܂� ��
�������A�c�O�ł����A�^���������A�K���ɍ�����Ƃ����v���Ȃ���i�A���i������͎̂������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19624063
![]() 1�_
1�_
�����Đ��Ƃ����Ӗ��������I�ɍl����ƁA�u�ǂ��v���Ƃ��u�����v���A�u�ǂ��v���u�Ƃ��u�����v���u�Ƃ��������]�����͖{���Ȃ���ł��ˁB
�Đ����ꂽ�����A�����i����͉����Ƃ����_�͂Ƃ肠���������Ă����āj�ɂǂꂾ���߂����A�Ƃ����]�����ɂȂ�̂ł��B
������u�ǂ��v�u�����v�Řb���Ă��邤���́A�����Đ��Ƃ͖{�����W�Șb�ɂȂ�܂��B
�����Ɋւ��Č����A�����̎��͖��W�ŁA����𒉎��ɍČ����邱�Ƃ������ꂽ�����Đ����u�ƂȂ�܂��B
���ꂪ�����I���Ƃ����͂���܂����A������w������̂��K���Ȃ��Ƃ��ƌ����^��A���y���Ƃ����I�[�f�B�I���u�{���̖����ɍœK���Ƃ������͂���܂��B
�����́A���y���Ƃ����{���̖ړI�ɂ̂��߂ɂ́A�K�x�Ɋy��I�ȃI�[�f�B�I���D�݂܂��B
�����ԍ��F19624999
![]() 1�_
1�_
���͎����̍D���ȋȂ��y�������������ł����B
�Ȃ̂ł��̃X���ɏW�܂���X�̂悤�Ȃ������͂Ȃ��B
�ł������y����������I�[�f�B�I���u�̐i���͊F����̂悤�ɂ��������X�̂������ł���Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F19625864�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�I�[�f�B�I���u�̎����グ��A�����̏�Ԃ��悭�킩��B�ƁA���������̘b�ł��B
�����̎����ǂ���A�����ǂ��ƌ������Ƃ��킩��B
�����̎���������A�����C�������鎖������B
���ꂾ���̎��ł��B
�������������Ⴀ��܂���B
�����A�I�[�f�B�I�ƌĂ�镨�́A���\�������]���̑S�Ăł��邪�䂦�ɁA��ς�D�������̃E�F�C�g���オ��㕨���ƌ������Ƃł��B
��V�Ȃ̂́A���������ƌo���́A���̐l�̃��m�Ȃ̂ŁA���̂悤�Ȍo�����ŃI�[�f�B�I���u�̕]���͕ς��B
���ꂾ���̎��ł��B
�����ԍ��F19626235�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���u�R���v���b�V�����ƃ��~�b�^�[�v�ɂ��Ăł��B
�L��̂ɁA���A����₷���꓁���f����A���샌�x�����Ⴂ�܂��B
�R���v���b�T�[=���̃_�C�i�~�b�N�����W�̕��ϒl������āA���̃o�����X���ł��邾���ۂ��āA�s�[�N�ƃm�C�Y�ɖ������ŏ��l�̊Ԃɔ[�߂悤�Ɠ����܂��B
���~�b�^�[�́A�s�[�N���z������̂���e�͂Ȃ��Ԃ�������܂��B
����₷�������A�����������ł��B
�����ԍ��F19626269�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�R���v���b�T�[������������ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�̋N���Ɍ����鏏�ƂɂȂ�܂��B
���~�b�^�[���|��������ƁA�i�X�����傫���Ȃ�V�`���G�[�V�����ŁA�s���R�ȃ|�C���g�̂Ƃ���ŁA�����Ȃ艹�ʂ������܂��B
�����ԍ��F19626281�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�f�B���C�ƃ��o�[�u�A�G�R�[�́A�ǂ��ɂĂ���悤�ł��Ⴂ�܂���
�f�B���B�́A���̉����L�����āA������ƒx�点�ĉ����d�˂܂��B���̎��ɉ����d�˂邩�ƁA�d�˂�^�C�~���O�����A�d�˂閈�̌����ʂ��w�肵�܂��B
�G�R�[�́A���̉������[�v���Ȃ��猸�������Ă����܂��B���[�v�����Ȃ��猸�������鎖���ł��܂��B
���o�[�u�͎c���Ƃ������܂����A�����t�˂𗘗p�������ł��B�A�i���O�̎���ɂ́A���̐k�����X�v�����O�ɓ`���āA�X�v�����O���t�˂��s�b�N�A�b�v�ő����Ă܂����B
�G�t�F�N�^�[�͐F�X����܂����A���Ĕ�Ȃ镨����R����܂��B
�����ԍ��F19626316�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɋ߂����C�ɂ�����Ȃ�A�}�C�N�Z�b�e�C���O���I
�����ԍ��F19626351�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��͘^���Z�p�҂̘r
�����ԍ��F19626357�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����B&W P7�����p���Ă��܂��B�|�[�^�u���w�b�h�z���͌���P7�����������Ă��Ȃ����ߕK�R�I��P7�������o���@������Ȃ��Ă��܂��B�����������邽��P7�ƌ��݂Ɏ����o����悤�ȃ|�[�^�u���w�b�h�z���������ЂƂw�����悤�ƍl���Ă��܂��B
���݂̃|�[�^�u����
AK100�U�`Cypher Labs straight analog interconnect cable�`FIIO E12A
�\�Z 4���~�`5���~��
���
�EOPPO PM�3
�EMaster&dynamic MH40
�EMEZE 99 classics gold
�Edenon AH-MM400
�ł��BMEZE�̐V���i�ȊO�͈ȑOX3 2nd gen�g�p���ɒ��������Ƃ�����܂����A���݂̊��ł͂܂����������Ƃ�����܂���B�㗬���Ⴄ�̂ō��̊��Œ����ƈȑO�������Ƃ��ƈ�ۂ��F�X�ς���Ă��邩������܂���B
�E�O�o�g�p����ł����Ƃł��g������
�E�����Ԃ̎g�p�ł�������ꂵ�Ȃ��A������������
�EP7�Ƒ傫���H�������Ȃ��X���Ȃ���
�E�����ڂ���r�I�I�V�����Ȃ��̂��ǂ�
�E�g�p�p�x��P7��5�F5���炢�ɂȂ�\��
��L�̌��̂Ȃ��łЂƂ��ꂾ�I�Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ����܂炸�Y��ł��܂��BP7�̉����܂�₩�ŗ��������Ă��ĂƂĂ��D���Ȃ̂ł����A�E�H�[�������ǑS�̓I�ɂ��������𑜓x�������e������������Ƃ��Ă���w�b�h�z���������Ȃƍl���Ă��܂��B
��L�̌�⒆���Ƃ��ꂪ�I�X�X���A��L�����̊�]���Ƃ��ꂪ�����ȂǃA�h�o�C�X�����������炤�ꂵ���ł��B��낵�����肢���܂��B
![]() 0�_
0�_
����͓���ł��ˁB�ŏ��ɖl��99 Classics�͎����������Ƃ�����܂���̂ł��̋@��ɂ��Ă͐G��邱�Ƃ��o���܂���B
���āAP7�̂����Ɗ撣���ė~����������������Ƃ���ƒ�����̎�̈Â����ȂƎv���܂��B�����͉𑜂��Ă��������Ȃ��ł��傤���BPM-3�͌֒����̏��Ȃ����R�ȉ����AMH40�͖���߂̒�����ƃt���b�ƍL���鉹��AMM400�̓h���C�o�[�̉s����̃n�E�W���O�Ŋۂ߂��������ȂƎv���܂��B
P7�̉�������ōl����ƌ��ɋ������Ă��Ȃ����i���߂�Beoplay H6�A������P7�̎ア�������ł��₤�ł��낤�w�b�h�z���Ƃ��čl�����MH40��misericordiae����̋��������̒��ł̓x�X�g���ȂƎv���܂����������ł��傤�B
�����ԍ��F19579076
![]()
![]() 2�_
2�_
��sumi_hobby����
�I�m�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂�(^-^)
�������������ł̍ŗL�͌���MH40�ł����B
B&O H6���ȑO�����čD�݂̉��ł����B�����ڂ��I�V�����ł�(>_<)
99 classics�ȊO�͒n���̃��h�o�V��r�b�N�J�����Ŏ������邱�Ƃ��ł���̂ŁAP7����������ō��̊��ʼn��߂Ē�����ׂĂ݂悤�Ǝv���܂�(*^^*)���ꂩ��ǂ�ɂ��邩�l���Ă���w�����悤�Ǝv���܂��B
�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂���(^-^)
�����ԍ��F19579117
![]() 0�_
0�_
�����ς݂ł���99 classics�̏����y���B
�����[�J�[�C���z���������ł�������������ቹ�z���ł��B�_�炩�����X���B����肪���Ă���11 classics�̃w�b�h�z���ŁB
���X�|���X�̗ǂ��Ƃ����_�ł͂�����ł�����܂��AP7�̊��炩�ɒʂ�����̂͂���܂��B�ǂ�ȃW�������ł�������x�点�܂����ݏd�Ƃ�������ۂ͂���܂���B
���̑ш�͎��R�Ȋ����œ��Ɏア�����͊������Ȃ��ł��B����̓{�[�J���⍂�悪�ቹ�̏�Ɋm��ƌ`������Ă��Ď��R�Ō��݂̂��銴�����D��ہB���Ȃ�Ⴂ�Ƃ���܂ŏo�Ă���̂�jazz�ł̓E�b�h�x�[�X�̖���͔��͂���܂��B�����������͋C�ł�(�t�Ɍ����ΈÂ߂ł�)�B
�������͑S�̂ŕ��ł���銴���ŗǂ��̂ł����w�b�h�o���h�����̕t�����ɔ������܂��Ĕ������Ⴂ�܂���w ��������_�B
�Ƃ����킯�œ��ӃW��������jazz�ł������̃W�����������ϓ_�ȏ�͎��܂��B
���������������Ő[�����ݍ��ޒቹ���~�����Ȃ�A���ȃw�b�h�z���ł��B
�����ԍ��F19582439�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��A.���ނ���
MEZE 99 classics�̏�肪�Ƃ��������܂�(^-^)
����͂���ς�MH40���w�����܂���(*^^*)P7�Ɩ炵���͈قȂ�܂����A�E�H�[���ȉ����Ȃ̂Œ�����ꂵ�Ȃ������ł��B�O�o���̐V���Ȃ����ɂ��悤�Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂���(*^^*)
�����ԍ��F19623083
![]() 0�_
0�_
���߂Ă̎���ɂȂ�܂����X�������肢���܂��B
�C���z�����������Ă��炸����ł��g�p���Ă��܂������A����炢�ł͎��ɕ����l�ߍ��ނ͎̂~�߂悤���Ǝv������w�b�h�z���Ɏ���o�����Ǝv���Ă��܂��B
�莝���̃C���z���ł��C�ɓ���́AIM03��E700M�œ����ʂ�悤���Y��ȍ����Ǝז������o����炸���܂�Ɨʊ��̂���ቹ���D�݂ł��B
�h���C�o�ɂ��ቹ�̕\���ɈႢ������܂����A�ǂ�����������邽�ߍb������ł��B
�w�b�h�z���T���ł́A���ɍ����̖���������悤�ȃ^�C�v�̕���T���Ă��܂����I�X�X������܂��ł��傤���H
�\�Z��5���قǂł悭�����W�������̓��^���n�A�ڑ���̓p�\�R����ZX100�ɒ��h���ɂȂ�܂��B
�܂��W���Z��Ȃ̂ŏo����Ζ��^�Ŏ������^�C�v�̕����ƗL��ł��B
�A�h�o�C�X���肢���܂��B
�����ԍ��F19599917�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
ATH-A2000X�͔@���ł��傤���B
�����͂ƂĂ��Y��ɖ点��w�b�h�z���ł����A�ቹ�̎����������Ȃ��Ǝv���܂��B
���Y�I���ōɌ���̂悤�ł����A�^�����ƌ������Ƃŏ㋉�@�������ɍw���\�ł��B
�����ԍ��F19600369
![]() 3�_
3�_
�����ł��ˁB�\�Z����t�Ȃ�I�[�e�N��ATH-A1000Z�A�ł����̃w�b�h�z���͂��������ቹ���o��̂Ŗ{���ɕK�v�ŏ����Ȓቹ�Ȃ�\�Z�������Ȃ�����ł���AKG��K550MKII�������̂��ȂƎv���܂��B�����ł�E700M�������Ƃ������Ȃ�ATH-A1000Z�ŗǂ����Ȋ����ł��ˁB
�����ԍ��F19600629
![]() 1�_
1�_
ZX100���}����A1000Z�͖{���̉����o�Ȃ��̂���⌜�O�ޗ������B
A2000X��A1000X�̕����Ȃ����܂Ƃ��ɖ�܂��BZ�ɂȂ��ăh���C�o�����V����Ă���|�[�^�u���ł��炵��Ȃ��������B
ZX100���}���Ȃ��ATH-MSR7�̕������������BIM03���𑜓x�͕����邪�AIM03��艹����������ǂ��ăC���z����艹�X�P�[���̑傫�����y���߂邵�A
IM03�ł�������悤�ȃI�[�e�N�炵���L���ǂ��⍂���̂���т₩���A���������܂������ז����Ȃ����X�s�[�f�B�[�Ŗ�����������ቹ����������BIM03���D���Ȑl�ɂ͊��߂₷�����B
���݂ɑf�̍����̐L�щ�����
A2000X��A1000X��MSR7��A1000Z
���炢�ł��B
A2000X�͍������AA1000X�͂�⍂�����A1000Z��MSR7�̓o�����X�^�C�v�BIM03�̃C���[�W�̓o�����X�^�C�v�̕��ɋ߂������B
�𑜓x��2000X��1000X��1000Z��MSR7
�|�[�^�u���炵�Ղ���MSR7��1000X��2000X��1000Z
�����ԍ��F19600958
![]() 3�_
3�_
ATH-WS1100�ƌ����Ă݂�B
�������ǂ����A����̂���т₩�������邵�A�P�[�u�����E���Ȃ̂�3m���炢�̃P�[�u����ʓr�w������ΉƂł��\���g����Ǝv������
�����Ȃ��Ƃ��Ǝg���Ȃ�MSR7����WS1100�����߂��
�����ԍ��F19601367
![]() 3�_
3�_
��KURO��D������
�ԐM�L�������܂��B
���Y�����i���Ǝ����@�T���̂���ς����ł�����x�����Ă݂����Ǝv���܂��B
��sumi_hobby����
�ԐM�L�������܂��B
���ۂɕ����Ȃ��Ǝ������[���o����̂�������܂���Љ����2�@��Ƃ��������Ċm�F�������Ǝv���܂��B
��air89765����
�ԐM�L�������܂��B
A1000Z�̌��R�~���Ƃ����|�[�g��q�����܂����B
���|�[�g���ŁuX�͈�a��������Z�͕ρv�Ə�����Ă��܂����A�A���v�o�R�Ɣ�ׂċ�̓I�ȈႢ�������ĉ������B
���Ǝ���p�ɃA���v�͗p�ӂ��������ǂ������ł����H
��round0����
�ԐM�L�������܂��B
�܂������������͂���܂��A���̃w�b�h�z���i�D�ǂ��ł���ˁB
air89765����ɏЉ����MSR7�Ɛ����r�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19602374�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��������ɍs���Ă��܂����B
�l�I�Ɉ�ԋC�ɓ������̂�A1000Z�ł��B
�A���v�o�R�ƒ��h���ŕ�����ׂ܂������A�꒮���ĈႢ��������܂����B
�������h���ł����Ɉ�a�����o����ӏ��͖��������̂Œ��h���^�p�ł������������ȂƎv���܂����B
�����Ȃ��Ȃ��ǂ������̂ŁA�������x���������J��Ԃ��čŏI���f�������Ǝv���܂��B
����A2000X�ł����A����������ꏊ�ɂ͓X�܍ɁE���ÂƂ�����܂���ł����B
�܂��ߏ�ɑ傫�߂̓X�܂����ӏ�������̂Ŏ����̍ۂɒT���Ă݂܂��B
�Ō�ɐ��i�w���܂ňꌎ�ȏ�|����Ǝv���܂��̂ŁA���u�ɂȂ�Ȃ��悤�����ň�U���߂����Ē����܂��B
�F����A�h�o�C�X�L�������܂����B
�����ԍ��F19606272�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
2016/02/20 07:10�i1�N�ȏ�O�j
�����ς݂ł���A2000X�Ȃ�Ae�C�A�z������̒��ÃR�[�i�[�ɁA3�X�܂Ƃ��ɂ��L��݂����Ȃ̂ŁA�s�������������d�b�m�F���čs���Ă݂�Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�E�H�[�N�}���́AZX2�AZX100�AF887�����ݏ��L���Ă��܂����AZX100�ɂ́AA2000X�͗ǂ������Ǝv���܂��B
���̕��������Ă���l�ɁAZX100�ł��炵�₷���ł��ˁB
���𑜓x�ŁA���������^�̃`�^���n�E�W���O�̃w�b�h�t�H���ł��B
���𑜓x�ŁA������̐L�т��f���炵���̂ŁA���Ȃ�C���p�N�g�͗L��܂����ˁB
ZX100�́A�ቹ����ǂ��o��DAP�Ȃ̂ŗǂ��}�b�`���Ă��銴���͂��܂����ˁB
A1000Z��ZX100�ɂ́A�ǂ������Ă���Ǝv���܂��B
�P�[�u���̐��ނ��W����6N�����̗p����Ă���l�ł����ˁB
�����S�n�̗ǂ��Ȃ�A1000Z�A�L���b�L���ȍ��𑜓x�̃C���p�N�g�̋������f���Ȃ�A2000X�ƌ��������ł��傤���B
������ZX100�ɍ��킹��Ȃ�AA2000X��A1000Z�������߂��Ă����܂��B
���������܂߁c
�ł́A�ł́B
�����ԍ��F19608662�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���A���b�N�X�E�}�[�t�B�[����
�ԐM�L�������܂��B
e�C���z������ɂ͊��܂��̂ŗ\�肪����s���Ă݂����Ǝv���܂��B
�C���p�N�g�̂��鍂���Ƃ͋����[���ł�
�����ԍ��F19609557�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2016/02/20 12:58�i1�N�ȏ�O�j
�V�i���ǂ�������AA2000X�̓m�W�}�I�����C����39800�~�ōw���o���܂��B
(�{���A�h�b�g�R���I�[�v�����i)
���^�C�v�Ȃ̂ŁA�V�i�̓l�b�g�w���ɂȂ�Ǝv���܂��B
�X���ł́AZ�Ƀ��j���[�A�����ꂽ���f���ɂ���ς���Ă���̂Łc
�Q�l�܂Łc
�����ԍ��F19609593�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2016/02/20 13:06�i1�N�ȏ�O�j
���߂�Ȃ����B
�i��ŁA����49800�~���炢�̂Ƃ��낵���A�ɂ������Ă��܂���ˁB
���^�C�v�ɂȂ�̂ŁA�s��Ɍ���ɂȂ�̂ŁA�������ċC�ɓ���A���������ǂ���������܂���B
�ł́A�ł́B
�����ԍ��F19609618�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
BOSE��Bluetooth�w�b�h�z�����g���ă��C�����X����߂�Ȃ��Ȃ����̂ł����A
�C���z���ō������A�����ԋ쓮�A�ڑ����萫�̎O���q����������̂ŃI�X�X���Ƃ��A
��r�������|�[�g�Ƃ��������狳���ĉ������B
JBL����ɃC���z������ł�Bluetooth�̔g�������Ă��܂����ˁB
�����I�ɂ�iPhone����C���z���ڑ����������Ȃ�Ƃ����\������܂��ˁB
���N�̃u�[����Bluetooth�C���z���H
�I���L���[���I�[�e�N��Bluetooth�C���z�����o���Ă��܂������A
�l�I�ɋC�ɂȂ�̂́ABOSE��Bluetooth�C���z�����o�����肷��ł��傤���H
�����ԍ��F19607633�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�wSUDIO VASA Bla�x�͔�r�I�����ł����}�g���ȉ��ł��E�߂ł���B
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000079890/001/X/page1/recommend/
BT�C���z���̒��ł͕ςɒቹ�������Ȃ��A�^�b�`�m�C�Y�ƕNJ����ア�̂��ƂĂ��ǂ��ł��B
�R���p�N�g�Ȃ̂�8���ԋ߂��o�b�e���[�������܂��B
���ӓ_�Ƃ������A���F�̃A���~�n�E�W���O�����i�ʐ^�����Ԃ��ۂ��ł��B
���̓u���[�����̂ł����A�ʐ^���ƃC�G���[�S�[���h���ۂ������̂Ɍ����͐ԓ��F�ɋ߂��ł��B
�܂��ςȐF����Ȃ��̂ł��܂�Ȃ��̂ł�����
�����ԍ��F19607702
![]() 2�_
2�_
���C�����X�̃����b�g���ăP�[�u�����������ƂŁA�P�[�u�������܂Ȃ��A�Z�����Ȃ����B
����Ɖ��u�Œ����闘���B
�f�����b�g�͓d�g��Q�Ƃ��x���Ƃ��o�b�e���[�������ԂƂ��B
���������߂�l�̓A���v���g����������邩��A��͂胏�C���[�h�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�R�X�p���ǂ��Ȃ��Ă邵�ABluetooth�͊����ł����ˁB
�ŁA�����͗����d���Ń��C�����X�ł��B
���L�@��
�C���t�H���FAppleLuckyBag�ɓ����Ă�JayBird BlueBuds X
�w�b�h�t�H���FJBL Synchros S400BT
�X�s�[�J�[�FJBL Authentics L8
�����ԍ��F19607904
![]() 2�_
2�_
JLab Epic Bluetooth 4.0 Wireless Sports Earbuds with 10 Hour Battery and IPX4 Waterproof Rating, Black
���Ă̂��g���Ă܂��B
�t�B�b�g�Ɋ����ƁA�Y���ɂ����Չ��w�����������������ł��B�������݂�$99���炢�ł����B
iphone�Ƃ��ƃy�A�����O���X���[�X�ŁA�d�r�͂P�O���Ԏ����܂��B
Bose��BT+NC�o������A�w�b�h�z���ł��C���z���ł���Δ�����ł����ǂˁB
�����ԍ��F19608022
![]() 2�_
2�_
�X�|�[�c�p�ł����ǁA��r���|�[�g�͂���Ƃ��Q�l�ɂ��܂����B
http://thewirecutter.com/reviews/best-wireless-exercise-headphones/
�����ԍ��F19608037
![]() 3�_
3�_
�ŋ߁A�l�������������ł�Philips��TX2BT�ƃ\�j�[��MDR-EX750BT���D��ۂł��ˁB�����Ƃ�NFC������Ă���̂Ń����^�b�`�Őڑ��Ɛؒf���邱�Ƃ͉\�ł��B
TX2BT�͍��̂���ቹ�ƃL���L�����������A�NJ��̏��Ȃ��J���I�ȉ����������̃{�b�N�X���X�^�C�v�ł��B���y�A���Đ���5.5���ԂƂ������Ƃł����炿����ƒZ�߂ł����ˁB
MDR-EX750BT�͓����{�b�N�X���X�ł��l�b�N�o���h�^�C�v�ł����A�����瑕�������قȂ邩�Ƃ����Ƃ��������킯�ł͂Ȃ��ł��BTX2BT�̃L���L���ȉ��ɔ�ׂ�Ɨ��������������ŁA�ł������W�̍L�������������鉹�ł��B���y�A���Đ���7.5���ԂƂ������Ƃł�����T2XBT���͒��߂ł��B
�����ԍ��F19609383
![]() 0�_
0�_
���܂�OSTRY��KC06A���g���Ă����̂ł����f�����Ă��܂������߁A�����ւ����������Ă���̂ł����A�����������߂������Ă��������B
���i�т́A3���O��܂ł̂��̂Ō������Ă��܂��B
�悭�����ȂƂ��ẮA�M�y�ł�B'z�A�m�y�ł͗L���ǂ����HR/HM�S�ʂ��Ă��܂��B
�d�����鉹�Ƃ��ẮA����`��悪�����C���z�����D�݂ł��BKC06A���w��������e�C���z���Ŋ���������đI�̂ł����A�w������KC06A��SE215SPE-A�Ȃǂ��D�݂̉��ł����B���̕ӂ�������ꃉ���N����̂�T���Ă��܂��B�܂��A����ȏ�ɒ�悪�����C���z���͉����������Ă��܂��悤�Ȉ�ۂ�����A��悪������悢�킯�ł��Ȃ��Ɗ����܂����B
�����ԍ��F19599797�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����ȂƂ���ł�ie80�������ł��傤�B
���ɂ�Aurisonics BRAVO KICKER������̓n�}��������s�����ƁB
�h�����X�A�M�^�[�A�x�[�X�̓m���ǂ��������Ă���܂��B�����͂�����ƍr���ۂ��A�����{�[�J���͏��������ꂪ���ɒ������邩������܂���B
�����ԍ��F19600379�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 2�_
2�_
JVC��HA-FX850�͂������ł��傤�B���̉��i�тƂ��Ă͒ቹ�K�b�c���A�������̌��ʂ����ǂ��_�C�i�~�b�N�ꔭ�炵�����̌q����̗ǂ��ƍL�������W��������܂��B�M���M���ȃX�s�[�h���͂���܂����b�`�ȉ����y���߂܂���B���ɉ��ɏo�����肪�傫�����Ȃ̂ʼn\�ł���Ύ������������E�߂��܂��B
�����ԍ��F19600556
![]()
![]() 1�_
1�_
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
IE80��HA-FX850�͈ȑO����C�ɂȂ��Ă����C���z���ł����̂ł���2�@��𒆐S�Ɍ����������Ǝv���܂��I
���x�C���z���̎������ł��鏊�ɍs���Ď������Č��߂����Ǝv���Ă���̂ł����A����ȊO�ɂ��A�X���Ƃ��č��������ȃC���z�����������狳���Ă��������B
�����ԍ��F19602867�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
RHA��T20������Ύ������Ă݂Ă��������B�����v���t������ł͈�ԃ��^���ɍ����C���z���ł��B
�����ԍ��F19603169�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 2�_
2�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�C���z���E�w�b�h�z��]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����z����PC
-
�y�~�������̃��X�g�z�V�o�b2025
-
�yMy�R���N�V�����z�������30��PC
-
�y�~�������̃��X�g�z�v�����^�w��2025
-
�yMy�R���N�V�����z15���炵��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h
- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��
�i�Ɠd�j
�C���z���E�w�b�h�z��
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j