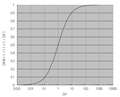���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S810�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2013�N2��11�� 17:39 | |
| 366 | 102 | 2013�N2��10�� 20:26 | |
| 12 | 3 | 2013�N2��5�� 22:25 | |
| 1 | 1 | 2013�N1��21�� 14:49 | |
| 11 | 10 | 2013�N1��14�� 21:00 | |
| 189 | 54 | 2013�N1��9�� 00:19 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�v�����C���A���v > Carot One > ERNESTOLO
�T�G�N��PCOCC�������i�ɕt�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�ݒ���I���W�i���ɖ߂��ă��j�^�[�p�ɂ��Ă��郉�_�[�P�[�u���Ōq���ł݂��B
�@���_�[�P�[�u���Ƃ����̂͐F�t���������̂őf���ɃV�X�e�����\�z�ł��邪�f���Ȃ̂ō����i�̍X�ɏ�̊����ŋ@��≹���̖��_���킩��B���i���i�w������STAX SR-001MK2�ƈꏏ�Ɏ��������Ă��邵�A�������ɂ��g�p�����̌�P�[�u���ύX�Ō��_���B�����@���Ƃ��Ă���B�Ȃ̖����]�����K�v�ȏꏊ�Ɏg���Ƌ@��\�͂Ȃ����Ƃ��Ȃ��B
�@�J���g�ƌĂ��I�[�f�B�I���E��������͌Â��Ȋw�I���_����Ȃ̂��낤�B�d���C�w���猩��Ɨʎq�d���͊w�̓J���g�Ɍ�����̂��낤���B�Ƃɂ����J���g�n�P�[�u���̍ʼnE���炵���B
�@�����Ɗ����������������f���ȉ��ɂȂ����B���M���N�������̉��x���オ��̂�҂B�����Ƃ̉��x�������肵��Ղ�f�q�̉��x�����҂A���x�͕����̉^���A�U���ł��邩���ʂ̃m�C�Y�̌��ł��邪�A�����E���m�C�Y�Ŗ����Ă���̂œ��ɗ}���������Ƃ��Ȃ���Ζ��͖����B�䂪�Ƃ�CDP��SACD�͋ɕ��ׂĂ���B30�N�O����ɕ������邱�Ƃ���{�ɂ��Ă���B
�@�܂����̃P�[�u���ɖ߂����P�[�u����R���甭�M��������̂�҂B�^��ǂ̎���Œg�߂Ă������BE=1/�ɂȂ̂ō���قnj�������B
�@��R���������Ȃ�����悪�L�т邽�߉����̃R���g���[���̓P�[�u���̒�����ގ��ōs���Ƃ����B
�@��R�l���傫���Ɣ��M���Ēf������B�q���[�Y��d�C�R�^�c�ł���B�R�^�c�ɂ̓T�[���X�^�b�g�Ƃ�����َ�����̖c�����Œf������@�\������B�I�[�f�B�I���i�͍����ȃP�[�u���œ���ȕω������邱�ƂŎ����̃C���[�W�̐��E���\�z���Ă����̐��E�ł���B�v���p�͎��p�i�Ȃ̂ň�ʓI�Ȃ��͈̂������g�p���邽�߂ɂ͎��i���v��B
�@�ǎ��̃P�[�u���͍����ł��邪�����ȕ��ʂ̃P�[�u���������Ƃ͎v��Ȃ��B�S���������[�J�[�̓��ꃍ�b�g���i�Ōł߂��ق����������낤�B���������ł���̂ň��ނ̒������ʼn��Ƃ��ł���B
�@�t���̃P�[�u���ł������������Ă���悤���B�������C�ɓ����Ă����炤���ȕύX�̓o�����X��������낤�B�Ⴂ�������̉����Ŕ��Ɍ��C�̂��鉹�ɕς�����B�X�s�[�h����������̂͂�ނȂ����������悪����т₩�ɂȂ蒆��ɔS�肪���܂���ɒe�ނ悤�Ȋ�������������B
�@���̑���A�S�̂̉𑜓x�͎���ꂽ�B�����d���Ȃ����悤�Ȋ���������͓̂d�q���猩����R���S�����Ă��錋�ʂ��낤�B���̑��x�͈��łȂ������ɂ�葬�x���ς��B���܂�����z�����������肷��B�d�q���g�̐��������̂ŁA�������E����������o���Ă���悤�ɁA�d�q���̕ω��ɔ������Ή����悤�Ƃ��Ă���Ƃ݂ĊԈႢ�͖������낤�B�����ʐ^�ŋL�^�Č����Ă����悤�ɉ������͓d�C����d�q�ɒu�������悤�Ƃ��Ă���B�����������Č��ł���悤�Ȋ����Ő��i������Ă���悤���B���L���͖ʔ������̂������Ă����B
�@�Ȃɉ����ĕω����������Ȃ�AMullard CV4003�d�l��FAB���ăv���������ւ��Ďg�p�ł���B�^��ǎ��̂̓l�b�g��2�{2���~���炢�����A�^��nj����̎�Ԃ�o�C�A�X�����̂��Ƃ��l����Ƃ�����������Ȃ��BMullard ECC88�̓e�X�g���Ɍ������Ē����������Ȃ�悩�����B
�@���݂̓I���W�i���ɖ߂��Ă���B����͂��̐��i�̃`���[�j���O���̂ɋ������N��������B
���l�̍�������E�����Ă݂悤�Ƃ����C�ɂȂ����̂͏��߂Ă̂��ƂŖʔ����`���[�j���O���Ǝv���B���N�e����ł���TELEFUNKEN�{LUXMAN�̐��E����CAROT ONE�̐��E�֍s���Ă݂�̂��ʔ����C������B
![]() 1�_
1�_
mmiom����@�@����ɂ��́B�@�I���W�i���e�B�Ȃ��l���ł��ˁB
���ɂȐ܂Ɂ@�����������B
�I�[�f�C�I�@�́@LINK�W
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/audio.html
�����ԍ��F15749951
![]() 1�_
1�_
mmiom����A�͂��߂܂��āB
���X�쓮�͂�����̂ŐF�X�����Ă݂����Ȃ���̂ł��ˁA���Ђ�������l�̃R���Z�v�g�œo�ꂵ�Ȃ����ȁA�Ǝv���Ă��܂��A�G�O�v�����g �����Ƃ��B
���̊��ł͍��̂Ƃ���_�C�\�[�̓r���̃R�[�h�̂�2�{�ɂȂ��Ă���~�j�W���b�N���D�݂ł��B
����v���܂����B
�����ԍ��F15750318�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
�A���v�̎d�g�݁E�\���E�X�y�b�N�ɏڂ������ɋ����Ē��������̂ł��B
�c�e�i�_���s���O�t�@�N�^�[�̒l�j���ŋߋC�ɂȂ��Ă��܂��B
���܂��܍l���悤������̂͒m���Ă��܂����A����A�L���t�F�[�Y
�̋Z�p�̕��ɕ������Ƃ���A�Ȃ������Ă��c�e�l�̓A���v
�ɂƂ��Ă͐��\�̍ł��킩��₷���w�W�ł���Ƃ̉ł����B
�i���̂悤�ɉ��߂ł��܂����j
�f�W�^�����͋쓮�͂������ƌ����Ȃ�����l���̂��̂�
�I���L���[�̂V�u�k�Ȃǂł��U�O���x�ł��ˁB
���܂�D�]����Ă��Ȃ����l�ł�����܂��̂ŁA��r���ɂ���
�̂ł����A���ǂǂ�ȕ����ł���g�����X(�d�����j�̑傫��
�����̂c�e�l�����߂���̂Ȃ̂��ȁA���Ƃ��z�����Ă��܂��B
�ŋ߃f�W�^�����̏��^�@�ł͂���܂����Q��قǎ����ɍw��
���Ă݂܂������A�\�z�����쓮�͂Ƃ����Ƃ���͊����܂���B
�f�W�^�����̃X�b�L�������A�������銴���͂킩��܂����A
�G���ł��������悤�ȁu��i�T�O�v�ł��P�O�O�v�݂����v
�ȂƂ��́H�H�H�Ɋ����܂��B
�p�C�I�j�A�̂`�|�T�O�C�V�O�ł̓f�W�^�������Ȃ���傫��
�g�����X���������Ă��܂��ˁB�C�O���Еi�̃f�W�^���i��
���z�ȃ^�C�v�̓g�����X���傫���悤�Ɏv���܂��B
�c�e�͂r�o���ǂ̂��炢�˂�������A�������邩�̒l�A
�Ƃ��A�L���̕��Ɍ����A�C�ɂȂ��Ă��܂��B
�ǂ̕����ł���u�c�e�l�͂ǂ̂悤�ȍ\���ł���Α傫��
�Ȃ�̂��H�v�����������̕���������������Ē���
�����̂ł����B
�f�W�^����
![]() 0�_
0�_
���߂�Ȃ����B�u�D�]�v�́u���\�v�̌뎚�ł��B
�����ԍ��F15682335
![]() 1�_
1�_
�͂炽����P�O�O�O�_����
�̂̃A���v�̃J�^���O�ɂ́A��T�_���s���O�t�@�N�^�[�̐��l�������ėL��܂����ˁB
�����A�����́ASP���ǂ�ʐ���o���邩���x�Ƃ����o���Ă܂���B
�_���s���O�t�@�N�^�[�̐��l���ǂ̒l���傫����Ηǂ����ēǂL���������B
�����A�傫����Α傫���قǗǂ����Ċ��������̂ňӖ�������Ȃ������Ǝv���܂��B
��G�c�ȏ����́A�o�͂̑傫���ł̔��f�ɕς��܂����B�i�f�l�l���ł��j
�Ⴆ���8����100W�̃A���v��4���Ȃ�200W���Ċ����ł܂���2����400W�̐��l�������ėL��Α���Ȃ�ǂ��A���v���낤�Ɛ���B
�����I�ɔ���Ղ��̂ŒP���Ȑl�Ԃɂ́A�œK�B
�^��ɓ�����Ȃ��Đ\����܂���B
�����ԍ��F15683614
![]() 2�_
2�_
2013/01/28 21:17�i1�N�ȏ�O�j
�����݁`(^_^)v
�c�e�̓A���v�o�̓C���s�[�_���X�ƃs�[�X�J�C���s�[�_���X�̔�Œ�`����A���������܂肠��ቹ�ɂȂ�ƌ����܂����A�P�O�O�ȏ�ł͍��͕�����ɂ����Ƃ��B
�A���A�s�[�X�J�P�[�u�����݂ŏo�̓C���s�[�_���X���K�肳���̂ŁA�ׂ������P�[�u�����g���ƃA���v�c�e�������Ƃ������I�ɂ͒Ⴂ�l�ɂȂ�܂��B
�c�e���グ��ɂ͕��A�ҁA�m�e�a���������̂���ʓI�̂悤�ł��B
�s�[�X�J�P�[�u�����܂߂ċ쓮����P���E�b�h���h���C�u�͗��_��c�e������Ƃ��B
�c�e�������ƍd�����ɂȂ�Ƃ������܂�����A�ϋ@�\������悢�ł���ˁB
�A���v�d���́A��C���s�[�_���X���̏u���d�������\�͂����E���܂��B
�r�C�ʂ݂����Ȃ���ł����ˁ`
�f�W�A���̓C�}�C�`��ۈ���������(^_^;)
�����ԍ��F15684206
![]() 4�_
4�_
���ӂ́B
�@�����u�_���s���O�t�@�N�^�[�l�v���ӎ����Ă����̂�38cm�E�[�t�@�[���g����
�@���j�b�g�Łu���A���v�v�h���C�u�����Ă������ł��傤���H
�@(DF���X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X÷�A���v�̓�����R�j
�@���ƌ������Ƃ͂킩���Ă͂��܂���DF�l���傫����悢�̂��H��������悢�̂��H
�@�̋c�_�����������_��W�J���邾���Łu�P�[�u���ʼn����ς��_���v�Ǝ�����������H
�@�ǂ��DF�l���낤������a�̃V�X�e�������Ȃ�̉��ʂōĐ����Ȃ��̂Ȃ�
�@�w�ǁuDF�l�v�̈Ⴂ�ɂ�鉹�̈Ⴂ���������Ȃ��̂ł́H
�@ALTEC��A-7�Ƃ�A-5�����̗ǂ�10W���x�̋��A���v�Ŗ炷�ƒቹ���獂���܂�
�@�o�����X�̗ǂ����ł��Ȃ�̑剹�ʂŖ点�܂��B
�@�ŋ߂̃v�����C���Ȃ�A�Z�p���[�g�Łu���SW�v�̕��Ŗ炵�Ă��ቹ��������
�@�������邱�Ƃ������̂́uDF�l�v�������Ă��Ȃ�����B�ƁA������l�����܂��ˁB
�@����aSP��DF�l�̑傫���A���v���q����ƒ��̐����E�����オ�藧�������蓙��
�@�L�����I�ƌ����l������A�S�ш�ɗL�������邵�A������ɂ͖��W�Ƃ����l���B
�@���A���v�̏ꍇ�͓�����R�������邽�߂ɁuNFB�ʂ����Ȃ�����v�A���v��uOTL�^�v
�@������Ă��܂�������A���A���v�{����aSP�ɂ͗L���Ȃ̂����m��܂���B
�@TR�A���v�ȍ~�͌����݁u100�v�ȏ��DF���������A���v���w�ǂɂȂ�܂�����
�@�ŋ߂̂悤�ɏ����aSP�Œቹ���쓮���镨�Ƃ̈��ʊW���ǂ��Ȃ̂��́H�ł��B
�@�ŋߌ����Ă���u�E�[�t�@�[�̋t�N�d���h�~�v�ׂ̈̃o�C�A���v�ڑ��B
�@����������a�⒆���a�̃E�[�t�@�[�̗p�V�X�e���ɂ͂��܂�K�v�������Ƃ�
�@�v���̂ł����ADF�l��K���ɂ��đ���a�E�[�t�@�[�́u�R���g���[���v������
�@�ƌ������z�͓������ȂƂ��v���܂��B
�@�₽��ƕ��c�������P�[�u��������̘b���Ƃ����߂̃v���p�A���v�ɂ�DF�l��
�@1000-3000�ƌ����悤�ȃA���v���q���Ή����ς��I�ƌ������Ă��܂���
�@����Ȃ��Ƃ������Ă���̂́u�����̓X��v�����B
�@�u��̓����E�E�E�v�Ɠ����ŐM����l�͋~����̂����m��܂���B
�����ԍ��F15684231
![]() 5�_
5�_
A-7VL �̃_���s���O�t�@�N�^�[�� 60 �ƒႢ�̂́A�f�W�^���A���v������ł��傤�ˁB
�f�W�^���A���v�̒��Ńg�����X���傫���Ȃ��@��́A���ۂɓd���e�ʂ����Ȃ��Ă��ǂ����猩�h�����C�ɂ���������Ă�����A���邢�̓��C���̓d�����X�C�b�`���O�d���ɂ��Ă��܂��āA�g�����X�̓T�u�̓d���ɂ����g���Ă���^�C�v�ł��邱�Ƃ�����ł��傤�ˁB���[�U�[�ɂ���������������̂��ʓ|���ƍl���郁�[�J�[�̒��ɂ́A���[�U�[�ɛZ�тČ��h�����ő傫�ȓd���g�����X�𓋍ڂ���Ƃ����I�������邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F15684507
![]() 1�_
1�_
���l�I���W����
���̃P�[�u��������́A�u�Ȃ�قǁI�v�Ɗ��S���邱�Ƃ�������܂����A�u�I�J���g�v�ȃg���f�������Ǝv���邱�Ƃ������āA���]���ꂿ�Ⴄ�ƃ��o�C�Ɗ����܂����ˁB
�����A���v�̏ꍇ�͓�����R�������邽�߂ɁuNFB�ʂ����Ȃ�����v�A���v��uOTL�^�v������Ă��܂���
������Ɗ��Ⴂ�ł͂Ȃ��ł��傤���H�B
NFB�ʂ𑽂�����Γ�����R�͉�����܂����ANFB�ʂ����Ȃ�����Ɠ�����R�͏オ��܂��̂ŁB
�uOTL�v���o�̓g�����X�������ƂŁANFB�������ς��|���邱�Ƃ��o���ē�����R�������ADF��傫������i���ꂾ���ł͖����ł����ǁj���߂̂��̂ł��B
�d���g�����X��DF�l�Ƃ̒��ڂ̊W�͂���܂���A�܂��傫���g�����X�̂ق�����ʓI�ɋ쓮�͂ɗ]�T�͏o��ł��傤���ǁB
�Nj��A���v�ɔ�ׁA�����̃A���v��DF���傫���̂́A�f�ށi�g�����W�X�^�j�̉����������ׁA���̉��P�̂��߂ɑ�ʂ�NFB���|�������ʁADF���傫���Ȃ����̂ɉ߂��܂���B
�i�߂��܂���Ƃ����̂͌����߂���������܂��B�j
�܂��A�J�^���O�X�y�b�N���������ʁADF�l�̑傫�������`���Ă��܂��B
�������Nj��ɋ߂��ƌ�����FET���g�p�����A���v�́A�g�����W�X�^�ق�NFB���ʂɎg�p���Ă��܂���B
�X�s�[�J�[�ɂ����܂����ǁADF�͐̂̃X�s�[�J�[�iSP�j�Ȃ�R�ȏ�A����SP�Ȃ�20�ȏ������Ηǂ��Ƃ����Ă��܂��B
�����ԍ��F15684529
![]() 3�_
3�_
�͂炽����P�O�O�O�_����A�����́B
���ɍŋ߁A�A�L���t�F�[�Y�ł�DF�ɂ�������Ă���悤�ł��ˁB���ɉ�����܂���DF�̓A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�ɑ���X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�̔�Ƃ��Ē�`����܂��B�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�Ƃ́A�A���v���͉̂��y�M��������@��ł����A�����������̃A���v�����C���s�[�_���X�i�����Ō����Ƃ���̓�����R�j���Ӗ����܂��B
���ɃX�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X������l�ŌŒ肳���Ȃ�A�v���ɂ����ăA���v�̏o�̓C���s�[�_���X���o������艺���邱�Ƃ�DF�l�͍����Ȃ�܂��B�����Z�p�I�Ȃ��b�ł����A���y�M���̓A���v�ƃX�s�[�J�[��Ȃ��Ƃ��Ēʂ邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�A���y�M���̓A���v�ƃX�s�[�J�[��2�ӏ��̃C���s�[�_���X���o�R���邱�ƂɂȂ�܂��B�o�������A���v���̃C���s�[�_���X�������邱�ƂŁA�X�s�[�J�[�̕��������܂�܂��BDF�l�����߂邱�Ƃɂ��i�A���v�̃C���s�[�_���X�������邱�Ƃɂ��j�A���y�M���ɂ��C���s�[�_���X�ϓ��ɑ�����I�ɃX�s�[�J�[�ւ̕������m�ۂ���邱�Ƃ���X�s�[�J�[�ւ̃h���C�u�͂��グ����ʂ�����Ƃ���Ă��܂��B
���ǂ̕����ł���u�c�e�l�͂ǂ̂悤�ȍ\���ł���Α傫��
���Ȃ�̂��H�v
DF�l�̓g�����X�̑傫���Ƃ͂��܂�W�Ȃ��ł����A�ŋ߂̃A�L���t�F�[�Y�̓A���v�̏o�̓C���s�[�_���X����������@�Ƃ��ăX�s�[�J�[�[�q�̖{���ɒ��O����t�B�[�h�o�b�N��H���|������@������Ă��܂��i�J�����g�E�t�B�[�h�o�b�N������H�j�B�[�I�Ɍ����ƐM�����ʂ��H��̃C���s�[�_���X��������H�v�ɂ��DF�l�͑傫���Ȃ�܂��B
�����ԍ��F15684562
![]() 7�_
7�_
�c�L�T��an�p������
�@Rouge��������Ă��܂������ǑS���̊��Ⴂ�ł��ˁB
�@�����Ă��邱�Ƃ��S���u�t�v�ł����B
�@���̂����肪�u�e�L�g�[�W�W�C�v�̖ʖږ��@�Ō�����܂��B
�@�A���v�����삳�����Ȃ��{�̊�{�Ō�����܂��ˁB
�����ԍ��F15684596
![]() 3�_
3�_
2013/01/28 22:56�i1�N�ȏ�O�j
�A�L���`�U�O���c�e�P�O�O�B
���b�N�X�l�W�O�O�̂V�O�O�ɑR�H���Ă��A�}�C�i�[�`�F���W�ł`�U�T���S�O�O�ɁB
�����č���`�Q�O�O���P�O�O�O�ɂȂ�܂����B
�X�s�[�J�[�C���s�[�_���X���U���Ƃ��A���a�P�����̓�����R����������O�D�O�Q�Q���Ƃ��܂��B
�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O�̏ꍇ
�A���v�P�ƃC���s�[�_���X�F�O�D�O�U��
�P���P�[�u���ڑ����̑����C���s�[�_���X�F�O�D�O�W�Q��
�����_���s���O�t�@�N�^�[�F�V�R
�Q���P�[�u���ڑ����̑����C���s�[�_���X�F�O�D�P�O�S��
�����_���s���O�t�@�N�^�[�F�T�W
�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O�O�̏ꍇ
�A���v�P�ƃC���s�[�_���X�F�O�D�O�O�U��
�P���P�[�u���ڑ����̑����C���s�[�_���X�F�O�D�O�Q�W��
�����_���s���O�t�@�N�^�[�F�Q�P�S
�Q���P�[�u���ڑ����̑����C���s�[�_���X�F�O�D�O�T��
�����_���s���O�t�@�N�^�[�F�P�Q�O
�Ȃ�ڂP�O�O�O�����Ă��A�P�[�u���q������E�E�E�E�E
������(^_^;)
�����ԍ��F15684886
![]() 8�_
8�_
�����ł��ˁADF���傫���ق����������ɂȂ�Ƃ͌����܂���ˁB
�̃e�N�j�N�X��DF�l�ς̃A���v�������āA���ɂ��邱�Ƃ��o�����悤�ł����ADF���傫����Ηǂ��̂Ȃ�i�Z�p�I�ɂ͉\�Ȃ̂Łj�ADF�l�����A���v�̎嗬�ɂȂ��Ă���͂��ł��ˁB
�����ԍ��F15685207
![]() 4�_
4�_
���͂悤
���͖炵�ɂ����X�s�[�J�[���g���Ă܂���
�ǂ����A���v�ƃX�s�[�J�[�P�[�u���ɐ[���W�����邩�ȂƊ����܂��ˁB
���Ɠd���g�����X����Đ������Y��Ȑ����g�𑗂�ƃC�L�C�L���ƕ������܂��B�iB�AAB��) �܂肱����_���s���N�t�@�N�^�[�ɔ�햧�ڂȊW������܂��B
�����̃X�s�[�J�[��炷�ꍇ�A����p���[�A���v���g���Ă��X�s�[�J�[�P�[�u�����ׂ��������Ȃ�V���{���������܂����A��e100W�N���X�i�v�����C��)�ł��S�c���������g�������������Ă���܂����ˁB
�� �_���s���N�t�@�N�^�[�������Ɨǂ��A���v���H
�A���v�̗ǔۂ̍���͌X�̃X�s�[�J�[��炷�ɑ��������邩���T�Ɍ����Ȃ������m��Ȃ��B
�����ԍ��F15686213
![]() 5�_
5�_
���͂悤�������܂��B
��ϊF��������̉��悹�Ē����ƂĂ����肪�����ł��B
�������\���ׂđ����̒m���ʂ͕t�����̂ł����A���nj��_��
�o�����܂��ł����B
�܂��g�����X���̂̑召���c�e�̑召�ɂ͑傫���ւ��Ȃ�
���͂킩��܂����B����͖ڂ���ł��ˁB�����Ƃ����v����
���܂����̂ŁB
�P�[�u���ʂł̍��E�����ɗ����ł��܂��B�ɑ��P�[�u����
���@�g�p���������Ȃ��A�����̋���������܂��B
�c�e�l�͐̂���Ód�^�i�}�[�e�B�����[�K���@�j���g�p���A
���x�܂��}�O�l�p�����w�����悤�Ƃ��Ă��邽�߁A����
�Ód�^�ł͂Ȃ��ɂ���A�C���s�[�̏㉺���������A���v
���S���������̂ŁA�������Ă������Ǝv��������Ȃ̂ł��B
�P�O�O������Ώ\���Ƃ͎v���Ă��Ȃ���A�����傫�ڂ̎莝��
�A���v�ɂ���ƑS�̂ɗ]�T���o��B�S�O�O��U�O�O�Ȃǂ��
�傫�Ȓl�̂��̂͑��������Ƌ쓮�����ł�̂��Ȃ��ƁB
�f�W�^���@�̂c�e�l���Ⴂ�̂��܂�������Ɨ����ł��Ă���
����B�쓮�͂������ʂƌ����鏊�Ȃ͂ǂ����炭��̂��H
���ێg�p���Ă݂Ă��m���ɂ��܂荂����ۂ��Ȃ��B(�@�B��
����ꂽ���̂ł����j
�܂������Ē����邱�Ƃ�����܂�����A�����ăR�����g����
�����ł��B�����I�Ȃ��ӌ��������A�����ĎG�����ł͓����
�Ȃ����������ł��B
�\�Z�͌����Ă���̂ł����A�ɑ��n�P�[�u���g�p���Ă݂܂��B
�i�C���s�[�ȉ�������̂Łj
�����ԍ��F15686274
![]() 1�_
1�_
�ǐL�Ȃ̂ł����B
�c�e�l��������Ȃ��A���v�ł���������ǂ̈ʂ����ׂ鎖����
�\�Ȃ��̂ł��傤���B
�Ⴆ�f�m���@�݂͂�Ȃ킩��Ȃ��ł��ˁB���\�傫�ڂ̒l��
�ł�悤�ȁA�݂�ȂP�O�O�̂悤�ȁE�E�E
�l�ɍS���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�����w�W�l�Ƃ��Ēm����
���������Ȃ��ƁB�t���t���Ȃ�āB
�����ԍ��F15686535
![]() 0�_
0�_
2013/01/29 11:00�i1�N�ȏ�O�j
����ɂ���(^_^)v
�_���s���O�t�@�N�^�[�̓_�~�[���[�h�����܂��Đ��x�̗ǂ��f�W�}���ő���\�ł��B
���莖��͌���������q�b�g���܂���B
�����ԍ��F15686614
![]() 1�_
1�_
�����Ȃ̂ł����B
�����܂ł����牽���R���Ă��܂����B
�l�����Ȃ̂��A���ʂǂ��Ȃ邩�����ł���͈͂�
�s���Ă݂����ł��B�n���V���b�v�̕��ɂ���ق�
���̘b����������A�X���̎��@�ł���Ă݂悤����
�Ȃ������Č����Ă���܂����B����͂��肪�����ł��B
�A�L����b�N�X�A�}�b�L���Ȃǂقڊe�ЂȂ�ł�
����̂ŁA����͊y���݁B
�����A�I�[�f�B�I�D���Ȃ��x�͂����̉����Ƃ������A
�l�̍������̂�g��ǂ��Ȃ�́H�P�[�u���ς���
��������ǂ��Ȃ�́H�݂����ȋ^��͂����܂��ˁB
�������ʂ��o�邩�ǂ����B
���̑�莄����]���X���ɓ���Ă��ꂽ�}�O�l�p��
�l�l�f�����ɂȂ�x�����Ă��܂����B���Z�ň�������
��������܂������E�E�E
�~���������̂ŗǂ������ƌ����A�ǂ���������ǁB
�����l�l�f�͓���Ȃ��ƁE�E�E
�������͎̂������������E�E�E�������ǂȂ��B
�}�O�l�p���B
�����ԍ��F15688049
![]() 2�_
2�_
�͂炽����P�O�O�O�_����A�����́B
����オ���Ă���Ƃ��닰�k�ł����A�Ȋw�I�ɂ́A�u�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X���A���v�̓�����R�Ŋ���v�Ƃ����s�ׂɂ��܂�Ӗ������o���܂���BDF���傫�����Ƃ̒萫�I�Ȍ��ʂ́A�̂�ۂ[�I�ɐ�������Ă��܂��̂ň��p���܂��F
>�o�������A���v���̃C���s�[�_���X�������邱�ƂŁA�X�s�[�J�[�̕��������܂�܂��BDF�l�����߂邱�Ƃɂ��i�A���v�̃C���s�[�_���X�������邱�Ƃɂ��j�A���y�M���ɂ��C���s�[�_���X�ϓ��ɑ�����I�ɃX�s�[�J�[�ւ̕������m�ۂ���邱�Ƃ���X�s�[�J�[�ւ̃h���C�u�͂��グ����ʂ�����Ƃ���Ă��܂��B
�ł͒�ʓI�ɂ͂ǂ��ł��傤���H�X�s�[�J�[�̒�i�C���s�[�_���X��6���Ƃ����Ƃ��ADF=50�̃V�X�e���ł̓A���v�i�{�P�[�u���j�̒�R��0.12���ADF=100�̃V�X�e���ł�0.06���ł��B�A���v�̏o�͓d�����ǂꂾ���̌����ŃX�s�[�J�[�ɓ`�B����邩�Ƃ����ƁA�O�҂ł� 6/6.12�A��҂ł� 6/6.06 �ŁA���҂̍��� 20�Elog(6.12/6.06) = 0.086dB �ł��B
���̎����Ƃ���́A�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�����g���ɂ���ĉ���6���`���܂ŕϓ������Ƃ��āA���V�X�e����f���ɁA�ő� 0.086dB �̍����o�邩������Ȃ��Ƃ������Ƃł��BDF=500�̃V�X�e����DF=1000�̃V�X�e���Ƃ̍��Ȃ�A�ő�ł� 0.0087dB �ł��BDF�Ƃ������l�́A�Z�p�_�I�ɂ͂��܂�Ӗ�������Ƃ͎v���܂���B
����A���l��͂ǂ��܂ł�DF�������V�X�e�������邱�Ƃ��~�\�ŁA���[�J�[�ɂƂ��Ă͎��ɓs���̗ǂ��w�W�Ȃ킯�ł��B�F�X�Șb�𑍍�����ƁADF�Ƃ́A�A���v���[�J�[���Z�[���X�g�[�N�̂��߂ɂЂ˂�o���A�P�[�u����������ɏ������`�Ő��̒��ɗ��z���Ă����̂��낤�ƍl���Ă��܂��BNFB�𑽂�������DF=1000�̃A���v���ł���ƁA�ɑ��P�[�u���łȂ���A�P�[�u����������X�|�C������v�Z�ɂȂ�c�Ƃ��������@�ł��B
��L��f���ɂ��Đ������܂������A�����鐧���ɂ��Ă��������ƂŁA�����I�ɂ́i���q�g�������������邩�ǂ����Ƃ����_�ł́jDF�͂���������10������イ�Ԃ�ł����āA�^��ǃA���v�������Α��̃V�X�e���Ŏ����ł��Ă���b�ł��傤����ADF���l������Ӗ��͂Ȃ��A�Ƃ����̂��^���ł��傤�B
�����ADF�̘b�̑����͔�r�I�����ʂł̉�H�̗��_�I���삪�O��ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��i��`�̖��ł��j�B�����Đ����œd���n�̓d�������\�͂����イ�Ԃ�ł��邩�ǂ����͕ʂ̘b�ŁA���������ꍇ�̓g�����X�̑傫�����ǂ��́A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�����Ƃ��A���̂悤�Ȕ����Đ����\�Ȋ��������ɂǂꂾ�����邩�Ƃ����b�ł�����ǁB
�����ԍ��F15689579
![]() 10�_
10�_
����ɂ��́B
��ς��ڂ����ł��ˁB���_�͎������ׂ܂����B
�X�y�b�N�Ƃ͂����A�A�L���t�F�[�Y���l�͑厖
�d�v�ɂ݂Ă��܂��B
���ʂǂ��Ȃ邩�A���̐S�ł����t�@���Ƃ���
�͒l�̑召�ł̊y���݂����������Ă�������
���̂ł��B
�����ԍ��F15690883�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
2013/01/30 21:38�i1�N�ȏ�O�j
�c�e�Ɋւ��ĉ��߂��قȂ�悤�ł����E�E�E�E
�h���C�u�͌���̒������u���C�N�_�E������ƁA�t�N�d�͑ϐ����ƁB
�A���v �� �s�[�X�J�Ԃ́A�����郍�[�o���n�C�̃C���s�[�_���X�W�ɂ���܂��B
����A�{�C�X�R�C�������ɂ��t�N�d�͂́A�s�[�X�J �� �A���v�̂��߃n�C�o�����[�̊W�ɂ���܂��B
�_���s���O�t�@�N�^�[�������ƁA�s�[�X�J�ւ̋��d�̓X���[�Y�ɁA����t�N�d�͔͂�X���[�Y�ɂȂ�A���ʋt�N�d�͗ʂ��f�J���E�[�n�[�̐����͂����シ��ƍl����ׂ��ł��傤�B
�����ԍ��F15693631
![]() 1�_
1�_
��������A�����́B
����������ăG���W�j�A�������ł����A�u�l����ׂ��ł��傤�v���ăg�R�����A���Ȍn�̔����ł͂Ȃ��ł��ˁB�Ȋw�I�A���́A�l�������ō��E�������̂ł����H
�����̖��́A�n�C�o���Ȃ��c�͂���W����܂���B�v�̓A���v�`�X�s�[�J�[�Ԃ̕��[�v�𗬂��d�����A�X�s�[�J�[�i�{�C�X�R�C���j�̓��������߂�킯�ł����A�����ɂ̓X�s�[�J�[�Ƃ����A�����̃C���s�[�_���X�����݂��Ă���ŁA����ƒ���ɑ��݂����R���A����1/100�ł���̂�1/1000�ł���̂ƂňႤ��ł����H�Ƃ������Ƃł��B
������c�ƓI�ɕ\������ƁA�u��ʓI�� DF=100 ����A�q�g�P�^��� DF=1000 �̃V�X�e���ɉ��ς���ƁA�َ����̉��������܂��v�ƂȂ�܂��B �u�Ȃǂ������I�v�ƁA�ӂ��̐l�͎v�����낤���Ƃ�_���Ă���킯�ł����A�G���W�j�A������Ă���킯�ł�����A"DF"�̔����҂ɂ́A�ƊE�͂������Ɋ��ӂ��ׂ��ł��傤�B
�����ԍ��F15694367
![]() 10�_
10�_
2013/01/30 23:30�i1�N�ȏ�O�j
�W���邩�������A�Ⴂ�����邩�������͎��Ŋm�F�������낵�B
�،�����������̂���̂ɁA���ɒ��Ⴗ�邩�͌l����B
�����A�i���`�����̉Ȋw�̉��̂̏������݂����������ɗ������͖��f����(�P�́P)
�P�[�u���_�����ǂ��͑ޏ�`(�P�́P)
�����ԍ��F15694414
![]() 3�_
3�_
��������
�Ȋw�I�ɂ͔��_�ł��Ȃ��|�A�������܂����B
�����ԍ��F15694569
![]() 9�_
9�_
2013/01/31 00:04�i1�N�ȏ�O�j
�S�R�W�������ƂɊւ���Ȋw�I�����i�b�V���O�y�ыt�N�d�͉e���ɑ���l�@�i�b�V���O�̎|��������(^^�U
�ł́`
�����ԍ��F15694613
![]() 2�_
2�_
�G���W�j�A�ɂ����|�~����܂���ˁB��㗬���ƁA��������͏��H
�����ԍ��F15694743
![]() 7�_
7�_
��ʓI�ȔF���Ƃ��āA�X�s�[�J�[�P�[�u���𐔕S���[�g�������悤�Ȍ���ŁA�c�e1000�`5000���x�̓����Ƀ`���[�j���O���ꂽ�p���[�A���v���g���Ă���悤�ł��B
������́A�c�e5000�ȏ�ł��B�h�[���K�͂ŁA���S���Ă��g���������B
�p���[�Ɋւ��Ă��A�u���b�W����m�g�p�Ȃ�o��9000W/8���ƁA�����p�A���v�̃p���[�������A�z�炵���悤�Ȑ����ł��B
http://proaudiosales.hibino.co.jp/amcron/15.html
��ʉƒ�ŁA�X�s�[�J�[�P�[�u���P�O���ȓ��A�����͐����Ŏg�p����ꍇ�́A�c�e�͂P�O���x����Ώ\���ƌ����Ă��܂��B
�莝����DIATONE DS-9Z�̎�舵���������ɂ́A�c�e�T�ȏ�̃p���[�A���v�𐄏��Ɩ��L����Ă��܂��̂ŁA�T���x�ł��\���Ȃ̂ł��傤�BDIATONE�����L���Ă���̂ł�����B
�A�L���t�F�[�Y�́u�c�Ƃ���v���c�e�̐������d������̂́A���̂ł��傤���H
���������āA�~�����Ȃ邨�����������邩��ł��傤�ˁA�ԈႢ�Ȃ��B
���f���`�F���W���ƂɁA�������������グ��͉̂��̂ł��傤���H
�������������Ȃ�����������邩��ł��傤�ˁA�ԈႢ�Ȃ��B
���a�̍��A���Y�����Ԃ�1000cc�̃t�@�~���[�J�[�\����ƁA�܂��Ȃ��L�c�����Ԃ�1100cc�̃t�@�~���[�J�[�\���E�E�E
���Ă܂��ˁB
100�n�͂̎��́A110�n�͂��B
�����Ȃ�200�n�͂ɂ��Ȃ��̂́H
����ł́A�p�����Ĕ��葱���邱�Ƃ��o���Ȃ�����ł��ˁB
��ʉƒ�p�̖����p�A���v�ŁA���Ƃ���DF�����グ�āA���������A���v�̐��\��DF�̐����ɔ�Ⴕ�Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ��������L��������ƁA�t�ɂ��̃��[�J�[�̃A���v���F�����Č����Ă��܂��Ƃ������Ƃ��A�����ɂ����ł��ˁB
������́ADF1500�������ł��B
�J�����̃o�����X�E�p���[�A���v�ł́ADF5000��\�肵�Ă���Ƃ��B
�n�߂�DF�������ɂ��邩�����߂đ����Ă���̂�������܂���B
������ɂ��Ă��ADF���݂ăA���v��I�ԕ��X���炷��ƁA���͓I�ȃA���v�ƌ��������ł��B
�A�L���t�F�[�Y��A200���A�R�X�g/DF��(�j���A�y���ɗD��Ă���H��������܂���B
http://www.audiodesign.co.jp/Power.htm
�����ԍ��F15695357
![]() 11�_
11�_
�Y�ꂳ��
����
ATC��100slpt�Č���������ʋ@��̃X�s�[�J�[������܂��B
���̃X�s�[�J�[�͖����i�Ȃ�ǂ̒��x�A���v��ǂ�ȃX�s�[�J�[�P�[�u�������g���Ȃ�ߕs���Ȃ����Ă�Ƃ��l���ł�����
���݂ɂ���ɏオ���Ă�A�L���t�F�[�Y�̃V���[�Y�i�A���v)�ł��\���܂���B
�����ԍ��F15695447
![]() 2�_
2�_
���[���E���t����
������̌��ł����A�����́u�c�e�l�ɂ��āI�I�I�v�Ƃ����X���ł��̂ŁA���͂����_���Ă��܂��B�� 2013/01/29 22:47�@[15689579] �����Q�Ƃ��������B
�����ԍ��F15695486
![]() 6�_
6�_
2013/01/31 08:29�i1�N�ȏ�O�j
����A���v�łc�e�l��ς��Ȃ��璮����ׂł�������萳���������͏o�Ȃ��ł��傤�B
�A�L���̃R�����g���C���`�L�Ń_�C�A�̃R�����g�����������ď؋�������܂���B
�T�ȏ���ĈӖ��������ڍוs���ł��B
�T�����͒����ɑς��Ȃ����������ˁB
�P�O�O�O�ȏ�͍���Ƃ����Ӗ��Ƃ��ł͖��������ł�����A�g����߂��a瀂̌��B
�F�X�����������������ƍl������ɁA���������Ƃ��Ȃ��ϑz�ŝ�������͉̂��Ƃ����ꂵ���ł��ȁE�E�E�E�E
�����ԍ��F15695498
![]() 3�_
3�_
2013/01/31 08:32�i1�N�ȏ�O�j
�E���t����
�ʓ|�ȃ��c���킴�킴�Ăъ�s�ׂ̓X���傳��ɂƂ��Ė��f����(^_^;)
�U�S�U�S(�P�́P)
�����ԍ��F15695509
![]() 2�_
2�_
���Y�ꂳ��
�قق��`
�������o���Ȃ��H
�A�L���̃A���v��m��Ȃ�����������Ȃ��ł��H
�܂��͌v�Z�o���Ȃ������Ȃ��Ƃ��c(��)
���͖Y�ꂳ��Ȃ�Ǝv���o��B(��)
�͂炽���炳��
���̊F����
���ӂȔ]���v�Z�␄�����l���͂����o���Ă��l�����ɂ��鉹�i�X�s�[�J�[����)�̕]���͖������Ď�������܂����B
�����ԍ��F15695563
![]() 3�_
3�_
����ɂ��́B
�܂��܂��B�l�����͐F�X�����Ă悢�ł��傤�B�������g�Ɂ{�ƂȂ�
���̂ݎQ�l�ɂ����Ă�����������ł��B
�������c�e���ĂȂ�ł����ˁB�t�@�[�X�g���b�g�̃A���v�Ȃ�
�P�O�v�o�͂łc�e�P���Q�Ŋ���������Ƃ����G���]�ł�����A
��H�̓e�B����悤�T�ł��P�O�ł��ǂ��킯�ł��B
����A�L���Ɍ��炸�A���b�N�X�A�I���L���[�Ȃǂ��̒l���召
�����Ă����\���Ă��郁�[�J�[������܂��B���̒l���e�Б���@
�ɂ���ăo�����͂Ȃ����̂��A�����̋^�������܂����A
�T�O�ł���U�O�ł���A�������X�y�b�N��̔��f�v���ɂ���悤
�Ƃ����\���郁�[�J�[�͗��h�ł��B
�P�[�u�����E�����Ȃǂ̏����ɂ���Ăc�e�l���������A�Q�l�ɂ���
���̔��f���\�ł��傤�B�������Ȃ��Ƃ��l���傫���Ɓu�r�o��
�����x���オ��v�Ƃ����͓̂��ɓ����ꂻ���ł��B
���@�S�����_���ς��܂����A������_�^��_������܂��B
�E�f�W�^���A���v�̂c�e�l�͂����H
�@���܂荂���Ȃ��悤�ł��ˁB��ʓI�ɋ쓮�͂�����ƕ]����
�@�Ȃ��炻���ł��Ȃ��悤�ȁB�j���[�t�H�[�X��G�\�e���b�N
�@�Ȃǂ̂��̂͌��\�����̂ł��傤���ˁB
�@�t�Ƀf�W�^�������ƒႢ�A�Ⴍ�Ȃ邨�b���E�E�E
�@�\�ł����瑱���ċ����Ē��������ł��B
�����ԍ��F15695575
![]() 0�_
0�_
������
������ƒ��ׂĂ݂܂����B
�����p�^��ǃA���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[
�@�I�N�^�[�uRE280 MK�U�i\1,008,000�j�@DF=8
�@Quad�U-FORTY�i�y�A\924,000�j�@DF=20
�����p�f�W�^���A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[
�@�I���L���[ A-1VL�i\168,000�j�@DF=25
�@Nuforce IA-7E�i\220,500�j�@DF=4000
�����p�g�����W�X�^�[�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[
�@LUXMAN L-507uX�i��430,000�j�@DF=205
�@PASS XA200�i�y�A\5,000,000�j�@DF=30
�@HEGEL H-1�i\315,000�j�@DF=1000
�@�A�L���t�F�[�Y�@A-200�i�y�A\2,600,000�j�@DF=1000
�@�I�[�f�B�I�f�U�C��DCPW-100�i\285,000�j�@DF=1500
�Ɩ��p�p���[�A���v
�@�A���N����IT5000HD�i\777,000�j�@DF=5000
�����̏��܂��āA���āA�{��ł��B
�͂炽���炳��i�X���傳��j�H���A
������A�L���t�F�[�Y�̋Z�p�̕��ɕ������Ƃ���A�Ȃ������Ă��c�e�l�̓A���v
�ɂƂ��Ă͐��\�̍ł��킩��₷���w�W�ł���Ƃ̉ł����B
�i���̂悤�ɉ��߂ł��܂����j
�A�L���t�F�[�YA-200�̃J�^���O�ɂ́A����Ȉ�߂�����܂��B
�u����ɂ��ɂ߂Ē�o�̓C���s�[�_���X�̃p���[�A���v�������A����ɍō��O���[�h�̑f�ނ��H�E�p�^�[���Z�p�Ȃǂ���g���邱�Ƃɂ��A�u�_���s���O�E�t�@�N�^�[:1,000�v�ȏ�ƂȂ���ٓI�Ȓl��B�����܂����B�v
�����A�����̂悤�ȉ��߂〈������ʂɒʗp����̂ł���A��L�̃A���v���g���\���h�ɕ��ׂ�ƁA
�@�P�ʁ@�A���N����IT5000HD�i\777,000�j�@DF=5000
�@�Q�ʁ@Nuforce IA-7E�i\220,500�j�@DF=4000
�@�R�ʁ@�I�[�f�B�I�f�U�C��DCPW-100�i\285,000�j�@DF=1500
�@�S�ʁ@HEGEL H-1�i\315,000�j�@DF=1000
�@�S�ʁ@�A�L���t�F�[�Y�@A-200�i�y�A\2,600,000�j�@DF=1000
�@�U�ʁ@LUXMAN L-507uX�i��430,000�j�@DF=205
�@�V�ʁ@PASS XA200�i�y�A\5,000,000�j�@DF=30
�@�W�ʁ@�I���L���[ A-1VL�i\168,000�j�@DF=25
�@�X�ʁ@Quad�U-FORTY�i�y�A\924,000�j�@DF=20
�@�P�O�ʁ@�I�N�^�[�uRE280 MK�U�i\1,008,000�j�@DF=8
�ƂȂ�܂��B
���āA���̏��ʂɁA�ȂӖ�����܂����ˁH
�h�[������N���X�̍L�����ŁA�X�s�[�J�[�P�[�u���𐔕S���[�g�������悤�Ȏg����������ꍇ�A4�ʈȏ�̃A���v����Z���N�g�����������S�m���ŁA�C�x���g���ɃA���v�̐S�z�������ɍςނł��낤�A�Ƃ������炢�̈Ӗ��͂��肻���ł����A��ʉƒ�ŃI�[�f�B�I�Z�b�g��g�ޏꍇ�́A�u�ǂ�ł����D���Ȃ��̂��I�v�Ƃ����̂��A�u�Ó��Ȉӌ��v���Ǝv���܂��B
�܂�A�uDF�̒l�ɂ�������ăA���v�I�т�����K�v�͖����v�Ƃ����̂����_�ɂȂ肻���ł��B
�ȑO�ADF�l�L���Ă��Ȃ�DENON�ɁADF�l�ɂ��Ē��ږ₢���킹���������Ƃ�����܂����A�uDF�l�̓A���v�̐��\�Ƃ��āi�̔��헪��j�d�����Ă��Ȃ��̂ŁA�i����͂��Ă��邪�j���L�͂��Ȃ����A�������Ƃ����܂���B�v�Ƃ�����|�̕Ԏ��ł����B
�܂��A�I���L���[�ɂ��A�uA1VL��DF=25�Ɋւ��āA���̃A���v�ɔ�ׂ�ƒ�߂����H�v�Ƃ����Ӗ������̎�����������Ƃ�����܂����A�u���p��A�\���Ȓl�ŁA�S�����Ȃ��B�v�Ƃ�����|�̉�����������Ƃ�����܂��B
���A�L���̃R�����g���C���`�L�Ń_�C�A�̃R�����g�����������ď؋�������܂���B
���T�ȏ���ĈӖ��������ڍוs���ł��B
���T�����͒����ɑς��Ȃ����������ˁB
�uDF�T�ȏ�𐄏��v�ƃX�s�[�J�[�̎戵�������ɖ��L����1980�N���DIATONE�̒S���҂̂ق����A�uDF�͍��������A���v�Ƃ��č����\�Ȃ̂��v�Ƃ����i��ۂ�������悤�Ƃ��Ă���j���݂̃A�L���t�F�[�Y�̉c�ƒS���ҁ��J�^���O�L�҂��A��قǓK�őÓ��Ȍ�������Ă���Ƃ��鍪���́A����ȂƂ���ɂ���܂��B
�����ԍ��F15697312
![]() 11�_
11�_
����ɂ���
�J�i���̂g�o�ɁA�c�e�ƃP�[�u�����̒�R�̐����l���L����Ă��܂��̂ŁA�������܂��B
�����ԍ��F15697685
![]() 1�_
1�_
2013/01/31 22:42�i1�N�ȏ�O�j
�X����|�����ς��Ƃ�܂��Ȃ��E�E�E�E
���������́A
�rDF�l�͂ǂ̂悤�ȍ\���ł���Α傫��
�Ȃ�̂�?
�Ƃ̎���B
�g�����X�Ƃ̈��ʂ�z�肳��Ă���ꂽ�悤�ł����E�E�E�E
�ŁA�c�e�������Ƒf���炵�������悢�A���v�ł���I
�Ȃ�Č����Ă���͎�芸������������܂���B
�ܘ_�A�A�L���c�Ƃ��J�^���O���B
�rDF�l�ͱ��߂ɂƂ��Ă͐��\�̍ł��킩��₷���w�W�ł���
������₷���ƌ����Ă܂��ˁB
�z���}�ɕ�����₷�����ǂ����͂��Ă����i��
�r
�u�����ݸޥ̧���:1,000��ȏ�ƂȂ���ٓI�Ȓl�v
���ٓI�Ə����Ƃ�悤�ł����A�R�O�O�O�A�S�O�O�O�N���X�͒��E���g�����ٓI���Ă����肩�i��
�r���Ĥ���̏��ʂɤ�ȂӖ�����܂�����?
���A�����ŕ��ׂĉ������Ă��ł����H
�c�e�̑傫�����Ԃł���H
���h�ȈӖ�������܂����ȁB
�o�͂��f�J�C���ԂƂ��A�d�����ԂƂ��A�F��ȏ��Ԃ�����܂���ȁB
�����̂��ƁB
�����ԍ��F15698641
![]() 3�_
3�_
�r�����������@�q������������
�����̏������݁g���e�h�����C�ɏ����Ȃ��悤�ł����A������蔽�_���Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂���B
�����̔̔����i�R�����g��A���ԓ��m�̓�ꍇ������ł́A�ǎҏ������H���C���ł��傤����A���ɂ̓X�p�C�V�[�ȃJ�L�R�~���݂��Ă��ǂ��ł��傤�B
���ŁA�c�e�������Ƒf���炵�������悢�A���v�ł���I
���Ȃ�Č����Ă���͎�芸������������܂���B
���ܘ_�A�A�L���c�Ƃ��J�^���O���B
���rDF�l�ͱ��߂ɂƂ��Ă͐��\�̍ł��킩��₷���w�W�ł���
��������₷���ƌ����Ă܂��ˁB
�n�n�I�i��
�����̔z���Ȃ̂�������܂��A���������߂�P���Ȃ��Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂���B
�A�L���t�F�[�Y�̌��uDF�l�́A�A���v�ɂƂ��Ă̐��\�̎w�W�ł��v�́A�����ł́A�P���ɁA
DF���������A���v�̐��\������
DF���Ⴂ���A���v�̐��\���Ⴂ
�Ɓu�ǂށv�Ƃ���ł��B
���ŁA�c�e�������Ƒf���炵�������悢�A���v�ł���I
�Ƃ���ŁA�A�L���t�F�[�Y�́A���������̃A���v���u�����ǂ��A���v�v�ȂǂƂ́A�����Ă�����Ȃ��ł��傤�B���ɁA�I舂ɂ����������j���A���X�Ō������点��c�Ƃ�����A�Ĕ��h�~�̎w���������Ȃ��ł����ˁH
�A���v�͑�����ł��̂ŁA���m�T�V�Ƃ��āA�����ǂ��H�����H���g�����Ƃ͖����ł��傤�B
�u���\�������������O�̐M���ɒ����ɁA�X�s�[�J�[���쓮����\�͂������v
�Ƃ������m�T�V�����A�A�L�����[�g�E�t�F�[�Y�Ђ̋��߂�u�A���v�̐��\�v���ƁA���^�N�V�͉��߂��Ă��܂��B
���������āA��A�̃A�L���t�F�[�Y�u�c�Ƃ���v�̃R�����g�́A�f���ɁA
�u�Z�p����g����DF�l��1000�Ƃ������ٓI�ȍ��l��B�������A����A-200�́A���ٓI�ȍ����\�A���v�ł��B�v
�Ƃ�ނ̂��u�����v�ł��B
�u�����ǂ��A���v�v�ȂǂƂ������t�������o���āA�u�X����|�����ρv���Ă���̂́A���[�W������̂ق��Ȃ�ł��ˁB
���r���Ĥ���̏��ʂɤ�ȂӖ�����܂�����?
�����A�����ŕ��ׂĉ������Ă��ł����H
���c�e�̑傫�����Ԃł���H
���v�ł����H
�����ł����H
�A�L���t�F�[�Y�̏�����A���v�̐��\�̎w�W��DF�l�̍�����̗p���āA
DF�l�̍��������A���v�̐��\��������
�ɕ��ׂĂ݂܂������A
�uDF�l���āA�A���v�̐��\�̎w�W�ɂȂ��Ă��܂����H�Ȃ��ĂȂ��ł��傤�H�v
�ƁA�wDF�l�̍���ŃA���v�̐��\����閳�Ӗ����x������������ł��B
���[�W������A���U�ƁA�Ԉ���Ė����Ă��܂��H
����Ȃ�A�����ƁA���L���Ă��������B
�͂炽���炳��i�X���傳��j�̋^��́A
�i�m���Ă��āA�m��Ȃ��ӂ�����Ă���̂�������܂��E�E�E�j
���rDF�l�͂ǂ̂悤�ȍ\���ł���Α傫��
���Ȃ�̂�?
���Ƃ̎���B
���g�����X�Ƃ̈��ʂ�z�肳��Ă���ꂽ�悤�ł����E�E�E�E
���t�Ƀf�W�^�������ƒႢ�A�Ⴍ�Ȃ邨�b���E�E�E
�ɑ��āA��̓I�ȃA���v��DF�l�ׂĕ��ׂāA
�u���Ɉ��ʊW�݂͂��Ȃ��悤�ł����A�������ł��傤���H�v
�Ƃ����₢�����g���h���Ă���̂ł��B
���ׂĂ݂�A��ڗđR�ł��傤�H
��������A���������o���܂����H
���Ƃ��A
�^��ǃA���v�́ADF����߁B
�f�W�^���A���v������Ⴂ�Ƃ͌���Ȃ��B
�d���̌`���i�g�����X�̃T�C�Y�A�X�C�b�`���O�Ȃǁj�Ƃ̑��֊W���Ȃ������B
�J�J�N�ɂ���Ⴕ�Ȃ��B
�ȂǂȂǁB
�������ł����H
�ŋ߂̃��[�W������́A�u���O�̃J�L�R�~�́A���̋C�ɓ���Ȃ��B�����A�������ނȁ`yo�`�v�Ƃ�����|�̃J�L�R�~���ڗ��������ł��B
�����ƁA�t�c�[�ɁA���݂��������Ă����������肵�܂��H
�o���܂��H
�����ԍ��F15699736
![]() 15�_
15�_
����ɂ��́B�����D�y�͒g�����ł��I�T�x������B
�}�C�i�X�T�x�łȂ��E�E�E
���āA�����c�e�l�������Ɖ����ǂ��Ȃ�Ƃ͍l���Ă܂���B
�u���҂Ȃv�Ƃ����Ƃ��ł��ˁB�A�L���Z�p�̕������
�����܂Łu�˂���������\�͓x�v�Ƃ����ԓ��ł����B
���̎��ۂɊւ��Ă��l���ꂼ��l�����̈Ⴂ�������Ă�낵���ł��B
�݂�ȓ������ɂȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��ł��傤�B�ł�����Q�l��
�����Ē����A�����ɉ����Ƃ������邩�����ł��ˁB
���ǂ��݂���Ȃ��l�Ȃ̂Ńn�b�L�����Ȃ��̂ł��傤�B
�ڊo�߂悳��̃J�i���g�o�����ʔ����ł��ˁB�P�[�u���ł�
���ʓI�Ȓl�ϓ��͑����̂悤�ł��ˁB�����͎��ɂ͐V����
���ł����B
�f�W�^���A���v�̒l���������ō����Ȃ��̂͂킩��܂��ł��傤���H
�Ԉ���Ă܂����ˁB�����̂�������Ȃ��B�f�W�^������i�o�͈ȏ��
�u�p���t���v�Ƃ�����ꑫ��A�\������鏊�Ȃ͉��Ȃ̂ł��傤���B
��������͖��Ȃ����Ǝv���܂����A�F����^��Ɏv���܂��H
�܂���_�A�f�W�^���A���v�́u����d�͂̍����Ăǂ�����ԗv���Ȃ�
�ł��傤�v�p�C�I�j�A�̂`�T�O�C�V�O���ĂV�O�����b�g�ł����A��
����w���������X�e�[���̏��^�T�Q�S�̓p�C�I�j�A���o�͂͏�����
�ł����P�Q�O���b�g���x�Ȃ�ł��ˁB��ʓI�ɑ傫�ȏo�͂�傫��
�d���𓋍ڂ���Ƃ����̏���傫���Ȃ�C�����܂����A�p�C�I�j�A
�@�������傫���d���������Ă��Ȃ���d�͂����Ȃ�Ⴂ��ł���ˁB
�Ȃ����낤�H�����̓��[�J�[�Ɏ��₵�Ă����Д�r�ł̉͂���
�Ȃ��̂ŁA�m���Ă�����ɕ��������Ȃ����Ȃ��āB
������Ƃc�e�Ɨ�����ł����B
�����ԍ��F15700018
![]() 1�_
1�_
2013/02/01 09:16�i1�N�ȏ�O�j
�r�����̔̔����i���Ă⤒��ԓ��m�̓�ꍇ������łͤ�ǎҏ������H���C���ł��傤����
�����������I�������C�������Ђ����Ă܂��ˁ`
�X���傳�������������ŁA��l�̉�b�A��l�̗V�тƂ��Đڂ��Ă�����悤�ł��B
�������݂��Ă�F������ˁB
������u���O�B���x����Ă���I��ꍇ���͎~�߂�I�v���ĕ����܂���ł���i���
�r���݂��������Ă����������肵�܂���?
�c�e�ς̎���A���v�ɂāA���l�Ŕ�r�������N��l�Ⴂ��������Ȃ������B
�݂����ȏ��Ȃ�劽�}�ł����A�J�^���O�X�y�b�N�̌l�I���߂ɂ��u�f������v�͂��f��ł��ˁE�E�E�E�E
���͊m��G�r�f���X�������̂Ɂu�ς��v�A�u�ς��Ȃ��v�Ǝ咣����̂͂ǂ�����������Ǝv���Ă��܂��B
���ɂƂ��ăE�T�M��������Ԃ̂���l�B
�����炱���A��ꍇ���ɂ����s�m�薳�p�ȃR�����g�͔@���Ȃ��̂��ƌ����Ă��ł����ˁE�E�E�E�E
�܂��A���������A�_���s���O�t�@�N�^�[�ŃA���v��I��������͐悸�͂����ł��傤���ˁE�E�E�E�E�E�E
�����ԍ��F15700097
![]() 3�_
3�_
�͂炽����P�O�O�O�_����
�� �܂���_�A�f�W�^���A���v�́u����d�͂̍����Ăǂ�����ԗv���Ȃ�
�� �ł��傤�v�p�C�I�j�A�̂`�T�O�C�V�O���ĂV�O�����b�g�ł����A��
�� ����w���������X�e�[���̏��^�T�Q�S�̓p�C�I�j�A���o�͂͏�����
�� �ł����P�Q�O���b�g���x�Ȃ�ł��ˁB
���Ђ̃z�[���y�[�W�����Ă݂܂������A
http://pioneer.jp/components/pureaudio/lineup.html
http://www.rasteme.co.jp/product/audio/hda-524/hda524.html
A-70 �́u����d�́i�d�C�p�i���S�@�j 74 W�v�A
HDA-524 �́u����d�� �ő�120W�v�A
�ƕ\�L����Ă���A�v�����@���قȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�������A�d�C�p�i���S�@�̏���d�͂́A�A���v�̉��ʂ��ő�o�͂̐�����1�̉��ʂɂ����Ƃ��Ɍv�������l�Ƃ������m�ȋK�肪�������ƋL�����Ă��܂��B����͖@�����L���Ă��܂��̂ʼn��߂̃u���̂Ȃ��l���Ǝv���܂��B
���X�e�[���Ђ̂ق��́u�ő�v�ƕ��L����Ă��܂��̂ŁA�����ł����A������ǂ���ɉ��߂���Ή��ʂ��ő�ɂ������̏���d�͂Ȃ̂��ȁA�Ǝv���܂��B����̐^�U�͂��̃��[�J�[�ɕ����Ă݂Ȃ��ƕ�����܂��B
�����ԍ��F15700141
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́B
�����ł��ˁB�ő�d�͂ł��ˁB����v�w�����Ă�����Ɣ�r���Ă݂悤��
�l���Ă܂����B
���X�e�[���͎����T�O�v�ʂȂ̂����B
����ɂ��Ă����ׂĒ������c�e�̑召�����ł���ˁB
��w�u�����́H�v�̐��̋^�f���悬��܂��B
�j���[�t�H�[�X�̂S�O�O�O�͂������B�v���@���e�Ђǂ��Ȃ̂�
������H�H�H
�����ԍ��F15700217
![]() 1�_
1�_
������
���������_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ����w�W�́A���̐��l����ʓI�ɏ����������^��ǃA���v����ɂł����p��ł��B
�_���s���O�t�@�N�^�[�F�P�A�Q�A�E�E�E�T���炢�܂ł́A�������P�Ⴄ�ƁA�X�s�[�J�[�̓����i�����́��d�C�I�Ɏ~�߂�́j�ɁA����������炩�ȍ����������悤�ł��B
�����̃A���v�ɂȂ��āA�_���s���O�t�@�N�^�[���ꌅ�ȏ�A�P�O�`�P�O�O�O�`�P�O�O�O�`���ƂȂ�A�オ�����킯�ł����A���̎��_�ŁA�u�_���s���O�t�@�N�^�[�v�Ɓu�X�s�[�J�[�̐����v�Ƃ����W���A���قLjӖ����Ȃ��Ȃ��Ȃ����Ƃ����̂��A���̗p��i�w�W�j�̗��j�̂悤�ł��B
�ʔ����ߋ��X���b�h�������܂����i��
���Q�l�E�E�E
http://bbs.kakaku.com/bbs/20432010189/SortID=7627750/
�����ԍ��F15701917
![]() 5�_
5�_
2013/02/01 22:29�i1�N�ȏ�O�j
������
�P�[�u�����݂ōčl���Ă݂܂��B
���a�P�����̓����̂P��������̒�R���O�D�O�Q�Q���A�X�s�[�J�[�C���s�[�_���X�U���A�P�[�u�����Q���Ƃ��āA
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�O�D�X�X
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�T �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�S�D�W
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�X�D�R
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�T�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�R�V
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�T�W
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�P�Q�O
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�P�O�O�O�O �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�P�R�S
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[�� �� �����_���s���O�t�@�N�^�[�P�R�U
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���������P�[�u���q������T�`���Ă��܂��B
���ɁA�����Z���P�[�u���ŁA�P�[�u���C���s�[�_���X�������邱�Ƃ��l���Ă݂܂��B
���a�Q�D�Q�S�����A�P���̓����̒�R�͂P/�P�O�̂O�D�O�O�S�S���ɒቺ���܂��B
�e�_���s���O�t�@�N�^�[�̃A���v�̎����_���s���O�t�@�N�^�[�́A
�P�F�O�D�X�X���O�D�X�X�X
�T�F�S�D�W���S�D�X�W
�P�O�F�X�D�R���X�D�X
�T�O�F�R�V���S�W
�P�O�O�F�T�W���X�R
�P�O�O�O�F�P�Q�O���T�V�U
�P�O�O�O�O�F�P�R�S���P�Q�O�O
���F�P�R�U���P�R�U�R
�A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���f�J�C���A�P�[�u���ɂ������l�����ς��܂��B
�P�O�O�ȏ�ł͍����悭������Ȃ��A�Ă̂́A���̓P�[�u���e�����l�����Ă��Ȃ��R�����g�Ȃ̂�������܂���B
�@�����Ύ����č��_���ʔ��������ł��B
�����ԍ��F15702822
![]() 3�_
3�_
�͂炽����P�O�O�O�_����
>���āA�����c�e�l�������Ɖ����ǂ��Ȃ�Ƃ͍l���Ă܂���B
>�u���҂Ȃv�Ƃ����Ƃ��ł��ˁB
���\�������݂�����܂������A�ӂ��ɔ��f����Ɓu���҂ł��Ȃ��v�A�ł͂���܂��B
������̕��Ȃ��B�Ȋw�I�ɂ��Ӗ����Ȃ��B�I���L���[��DENON���ے�I�B����Ȃɂǂ��ł������w�W�ɂ��āA�܂��߂ɐ�������C�ɂȂ�Z�p�҂͏o�Ă��Ȃ��ł��傤�B�����������_���s����Ȕ~�G���W�j�A�i���u�~�v�͊֓����j���A�U���𐄏����邭�炢�̂��̂ł��B
>�܂��܂��B�l�����͐F�X�����Ă悢�ł��傤�B�������g�Ɂ{�ƂȂ�
>���̂ݎQ�l�ɂ����Ă�����������ł��B
�X���傳���������u�{�ƂȂ���v�Ƃ͂Ȃ�ł��傤�H���炭�A�K�������u�����v�ł͂Ȃ��̂��낤�Ǝv���܂��B�Ȃ�A�A�L���t�F�[�Y�̉c�Ƃ�灛���P�[�u���ɃZ�[���X�g�[�N�����肢����̂��A�͂邩�Ɍ����I���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F15703523
![]() 9�_
9�_
2013/02/02 01:09�i1�N�ȏ�O�j
�����̎��⊴���ŕ�����Ȃ����Ƃ������ɂƂ��Ăǂ��ł��悢�Ƃ��邱�ƂƁA��ʘ_�Ƃ��Ăǂ��ł��悢�Ƒ��l�ɉ����t���邱�Ƃ̋�ʂ��t���Ȃ������҂������݂������ȁA�ŋ߂́i��
�����ԍ��F15703681
![]() 6�_
6�_
������
�_���s���O�t�@�N�^�[�Ɋւ��ẮA���ׂ�����ŁA���݂̂Ƃ���A�A�L���t�F�[�Y�A�I�[�f�B�I�f�U�C�����A�d�����Ă��邱�Ƃ����Ă���悤�ł��B
�܂��A�X�s�[�J�[�P�[�u���������K�v������Ɩ��p�̃p���[�A���v�ł��A���p��̏d�v�Ȏw�W�Ƃ��Ė��L����Ă��܂��B
����ŁA�f�m���A�I���L���[�́A�K�v�ȏ�ɐ������d�����Ă��Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B
�I���L���[�́ADF�l���グ�邱�Ƃ����A���A�҂��ŏ����ɂ��邱�Ƃ��d�����Ă���Ƃ܂Ō��y���Ă��܂����B
���̃X���b�h�ɂ́A�_���s���O�t�@�N�^�[�Ɋւ��āA���ɂ��A��R�̏�W�܂��Ă���Ǝv���܂��B
�����ɖڂ�ʂ�����ŁA
�_���s���O�t�@�N�^�[�ɒ��ځA100���1000�̕������͓I���B
�_���s���O�t�@�N�^�[�́A10�ȏ゠��C�ɂ��Ȃ��ėǂ��̂��B
���̑�
�ƌ�����ɁA�������̌����ɕ������̂́A���R�Ȃ��Ƃł��B
�`�E�`�E�`�E�`
���[�W������
���[�W������̐S�����A�悤�₭�A���肩���Ă��܂����B
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ƁA���^�N�V�̃J�L�R�~����A�ȉ���2�s�ځu���l�ɉ����t����v�Ƃ������́i�v���b�V���[�j����������āA��ɂ������Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB
�������̎��⊴���ŕ�����Ȃ����Ƃ������ɂƂ��Ăǂ��ł��悢�Ƃ��邱�ƂƁA
����ʘ_�Ƃ��Ăǂ��ł��悢�Ƒ��l�ɉ����t���邱�Ƃ�
����ʂ��t���Ȃ������҂������݂������ȁA�ŋ߂́i��
����̃J�L�R�~�ł́A
��������u���O�B���x����Ă���I��ꍇ���͎~�߂�I�v���ĕ����܂���ł���i���
�Ƃ��A������Ă��܂����B
�N���A�u�ӌ��������t���v���肵�Ă��܂���B
���ꂼ�ꂪ�A�����̎��_����A�����̌������q�ׂĂ��邾���ł��B
���t�̕\����A�u���������ӂ��Ɏ���v�ӏ������邩������܂��A�����͓����̌f���ł�����A�����I�ɂ������������t���邱�Ƃ͕s�\�ł����A���������A������̓`���������Ƃ��A���̂܂ܓǂݎ�ɓ`�����̂ł�����܂��A�t��������B
�܂��A�u���O�B���x����Ă���I��ꍇ���͎~�߂�I�v�ȂǂƁA�J�L�R�~�����������܂���B
�i���[�W������������j
���̃t���[�Y�́A���[�W������̓��̒��Ő��ݏo���ꂽ���̂ł��B
�����g�̐��ݏo�������t�ɑ��āA�ꌾ��悵�Ă���Ƃ����\�}�ɂ́A���낻��C�Â��ė~�����Ǝv���܂��B�L�b�J�P��^�����̂��A��A�̃��^�N�V�̃J�L�R�~��������������܂��E�E�E
���ӌ��������t���Ă���킯�ł͂���܂���̂ŁA�O�̂��߁B
�����ƈقȂ�ӌ��ɑ��āA�g�Ȃ�قǁh�Ɓu���e����v�ԓx�́A���Љ�ł��A���ɍ����̃l�b�g��̃R�~���j�P�[�V�����ł��A�ƂĂ��d�v�ȑԓx���ƁA���^�N�V�͎v���܂��B
���e�Ƃ�
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%AF%9B%E5%AE%B9/
���A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���f�J�C���A�P�[�u���ɂ������l�����ς��܂��B
�P�[�u���ɂ��E�E�E�u���ς���v�Ə�����܂����B
���^�N�V�́A�g�Ȃ�قǁh�Ɗ��e���܂���B
�������A�g�I舂��ȁh�Ƃ��v���܂��B
�����g�ŁA����A
�����͊m��G�r�f���X�������̂Ɂu�ς��v�A�u�ς��Ȃ��v�Ǝ咣����̂͂ǂ�����������Ǝv���Ă��܂��B
�Ɓg���h���Ă���b��ɒ�G����Ǝv���邩��ł��B
����ʂ��t���Ȃ������҂������݂������ȁA�ŋ߂́i��
����́A���͂�A�ӌ��ł͂���܂���B
��排����Ƃ��A�l�i�ᔻ�Ƃ������t�ɒ�G���܂��B
�u�s�K�ؔ����v�Ƃ�����ł��B
�����ԍ��F15704017
![]() 13�_
13�_
�́A���b�N�X�i���Ж��̓��b�N�X�}���ŁA���̃��b�N�X�͉��ϕi��Ж��j��SQ301�Ƃ����v�����C���A���v���g���Ă��܂����B
���̋@��̓_���s���O�t�@�N�^���A80, 10, 2�̎O�i�K�ɐ�ւ����܂����B
�X�s�[�J�[�͎R����SP-LE8T�ł������A10��2�ł͉����ɑ卷������A2�͒ቹ���u�J�u�J�Œ����ɑς��܂���ł����B
80��10�ł͂قƂ�Ǎ��������A80�̕��������ቹ�̒��܂肪�ǂ����ȁ[�A�Ƃ������x���ł����B
���̍��̓V���b�v�ł�������X�s�[�J�[�P�[�u���Ɠd�C�X�ōw�������Ǔ��z���pVVF�P�[�u���̍����A�����Ə����������L��������܂��B
�X�s�[�J�[�P�[�u���ʼn����ς��Ȃ��Ǝv���Ă�����́ADF��10�ȏ゠��Ζ��Ȃ��ł��傤�B
�f�W�^���A���v�́A�Ō�̃A�i���O�Ɋ�����Ƃ���ŁA�n�C�J�b�g�p�̂k�����i�R�C���j������̂���ʓI�Ȃ̂ŁA���̃R�C���̒�R�������A�c�e�����������Ă���̂ł��傤�B
�f�W�A����DF���������̂́A���̃R�C�����ǎ��Ȃ̂��A�R�C����ɓ���Ȃ��ėǂ���H��̍H�v������Ă���̂ł��傤�B�v�͍��悪�J�b�g�ł���Ηǂ��̂ŁB
�����ԍ��F15704508
![]() 3�_
3�_
����ɂ��́B
�{�ƂȂ���́{�ƂȂ���ł��ˁB�����Ƃ����\���ł��Ȃ��B
�����������A��Ɏ��Ȃ����̂ł����ł�������ł��B
���[�����̖��̍��A�l�ɂ���Ă̍D�݂��Ȋw�␔���ŕ\������
�Ȃ��悤�Ȃ��̂ŁA�ʂɐ��l�̑召�Ŕ��f���Ă���킯�ł�
�Ȃ��B���l���o���Ă��郁�[�J�[������A���\�厖�Ɍ��Ă���
�A���ʂǂ��Ȃ���̂��ˁA�Ƃ��������ł��B
�I�[�f�B�I�Ƃ��A����Ȃ���́u���v������@�B�ł��傤�B
�����̒��Ŋy���߂�A�ǂ̂悤�ɉ��߂������ėǂ��킯�B
�Ⴄ���ȁB
�����ԍ��F15704682
![]() 3�_
3�_
�v�_�̓��[�W�����������Ƃ���Ȃ��B
�����ŏ��ɏ������������݂ŃX�s�[�J�[�P�[�u�����ɑ��ɂ�����Ə����܂������A�n�C�E�p���[�A���v�ɃZ�b�e�B���O������������B
�܂��ʓr�d���g�����X�̏ꍇ�I
DF�l���オ�������낤�ƔF�������̂͒��o�̓v�����C���̎��B
�i�����͂��������Ɗ����܂���)�B
���Ƃ���DF�l�i�����͐�����)���������A���v�ɋɑ��P�[�u�����q���Ő����͂������邩�H������
����͋��炭�����Ԃ̊g���肩�ȁB
���������������������ƂȂ�Ɖ��b�͏�������������Ȃ��B
���m��Ȃ��Ə����Ă�̂̓e�X�g���ĂȂ�����B
���݂Ɏ���ATC�X�s�[�J�[�̏ꍇ�������Ă܂��B
�����ԍ��F15704951
![]() 3�_
3�_
2013/02/02 11:21�i1�N�ȏ�O�j
�ő��P�[�u���X�����̂Q�̃O�_�O�_���ȁi��
�E�T�M����
��ꍇ�����̗���]�X���̂����h�Ȗό��ϑz�����Ă̂ɐ悸�͋C�t���܂��傤�B
�ŁA�ŋ߂͖���ւ�����ɂȂ�ꂽ�̂ł����ˁE�E�E�E
�c�O�ł��E�E�E�E�E
�����ԍ��F15705126
![]() 8�_
8�_
�F������ɒׂ����Ƃ͎v�����ǁc
�����͑�̏o�����Ă܂��B100���z���܂����B
�����]���B
�E�T�M������o�����A���v����ϕ������������B(��)
�E�A���N����
���̃A���v��DF�l�͈̂������B�ǂ�ȃX�s�[�J�[�ł��点��ƌ����G�ꍞ�݁B��������ȉ��i�I�[�f�B�I�̉�)���D�ޕ��͂��Ɛh�����ł����B
�F����Ȃ������̖��������D�������ĕ��͍D�݂̓��ɓ���ł��傤�B
�E�w�[�Q��
���̃��[�J�[�Ɋ��҂��đ��c4000��G�A�W���[�_���E�m�[�g�A�t�H�XG2000���������́ASN�����܂�ǂ��Ǝv��Ȃ������B��ʃN���X�̃~�J�����p���[�A���v�͗ǂ��ƕ����܂��B�w�[�Q���Ȃ��ʃN���X��Z�p���[�g���I�X�X���B
�E�I�[�f�B�I�f�U�C���B
�Z�p���[�g��20���N���X���n�C�G���h�V���[�ʼn��x���I�i�X�s�[�J�[���O)
SN�͔��ɗǂ��B
�������T�b�p�����߂��Ă܂��B
�Ɩ��A���v���F�͂���܂����A�A�����ɐ₦�Ȃ����ł͂���܂���B����������F�C���d����͎���o���Ȃ��ł��傤�B�Ղӂ��Č������E�}�Y���i�J���n�M)�̐H���ɋ߂��B(��)
���ƂȂ�ł��ˁB
�I�[�f�B�I�f�U�C���Ė��O���t���Ă���Ɉ̂��L�b�g��g�ݗ��Ă������B�B�t�F�U�[�^�b�`�������������Ɋ�����B
�G���g���[�E�N���X�̓I�[�f�B�I�_�T�C���Ė��O�������������m��Ȃ��B
�E�j���[�E�t�H�[�X
���̃��[�J�[�͌l�I�ɍD���ȃ��[�J�[�ł��B
������B&W15�C���`801��炵�����́A�����r�₦�Ă܂����B
�Z�p���[�g×2���炢�K�v�����m��Ȃ�
�E�I�N�^�[�u
���̃��[�J�[�̃v�����C����SN���C�}�C�`�ł����B���X�b�L���������F�A
�炵���X�s�[�J�[�̓N�A�h���B
�Z�b�e�B���O���|���N�����������̂��H
���������̃I�N�^�[�u�B
�X�s�[�J�[�P�[�u����ς��Ă݂����B�����ƃA���v�̌������Έ����P�[�u���B
�������
����������肭�z�����Ă���Ċ����ł��B
�ȉ���
�͂炽���炳�w�E���Ă���f�W�^���A���v�B
���̂����[�G���h���L�тȂ��o�Ȃ��B
����`�����ʊ��͑f���炵�����ˁB�����n�C�G���h�u�b�N�V�F���t���������m��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F15705424
![]() 2�_
2�_
NuForce�Ђ̓��{��T�C�g�ɁA�̔��I���̕\�����t���Ȃ�����c���Ă��� IA-7V3 �̃y�[�W�����Ă݂܂����B
http://www.nuforce.jp/highend/products/ia7v3_01.html
����ƁA�����o�蒆�̓Ǝ��̕����̐v�ł���Ȃǂ��������͓I�Ȑ����������Ă���A�ǂ�ł���ƃ��N���N���Ă��܂��B
���ɁA���̃T�C�g���́A�v�����C���A���v�ȊO�̎�X�̐��i�̃y�[�W�����낢�댩�Ă݂܂����B���̉�Ђ͓����f�W�^���P�[�u����HDMI�P�[�u�������z�Ȓl�i�Ŕ����Ă����ЂȂ̂ł��ˁB�ʂɃv�����C���A���v�郁�[�J�[�������f�W�^���P�[�u����HDMI�P�[�u�����Ă͂����Ȃ����Ƃ͂���܂��A���̊����ł́A���̎��_�ŁA������H�Ɗ����܂����B�����������炻�������J�e�S���[�ɑ������ЂȂ̂ł͂Ȃ����ƁA���������܂����B
�����f�W�^���P�[�u����HDMI�P�[�u���ȊO�ɂ��A���Ƃ���CD�v���[���[ CDP-8�A
http://www.nuforce.jp/highend/products/cdp8_01.html
�̐����̃y�[�W��ǂ�ł��A������H�Ɗ����܂����B
������O���ɒu���āA������x IA-7V3 �₻�̑��̃A���v�֘A�̐��i�̃y�[�W�̐�����ǂނƁA���̓_���^��Ɋ����܂����B
�E���[�J�[�͎��g�œ��쌴�����f�W�^���A���v�ƌ����Ă����Ȃ���A���̒���Ɂu�A�i���O �X�C�b�`���O�A���v�v�Ƃ��Ă�ł��āA�ǂ����ɓ�����������Ă��銴�������܂��B
�E���[�J�[�͎��g�Ń_���s���O�t�@�N�^�[�������ƌ����Ă��܂����A�ł͂��̃A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[�͂ǂ������������ł���̂��H�Ƃ����^�₪����܂��B
FAQ ��ǂނƁA
http://www.nuforce.jp/highend/faq.html
�X�s�[�J�[���ڑ�����Ă��Ȃ���ԂŁA�d����ON�ɂ��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ����|�̋L�q������܂��B���ꂾ�Ƒ���ɂ����ł���ˁB
�E�Z�p����������y�[�W�ł���A
http://www.nuforce.jp/highend/info/20080418_01.html
��ǂ�ł݂܂������A��ԉ��̂ق��ɁA
�� �M�������͂��ꂽ�Ƃ��ɂ́A���̃m�C�Y�͑��E���邱�ƂɎg�p���邽�߁A�o�͐M���ɍ����邱�Ƃ͂���܂���B���̖��M�����m�C�Y�̓X�s�[�J�[�̋߂��Ɏ�����ƕ������邩������܂��A�A���v�̒ʏ퓮��Ɋ�Â����̂Ō̏�ł͂���܂���̂ŁA�����S���������B
�Ə����Ă���܂����A�o�͐M���ɍ������ĂȂ��̂ɃX�s�[�J�[�̋߂��Ɏ�����ƕ�������́H�Ƃ����^��������Ă��܂��܂��B
�Ȃɂ�������[�܂��Ă���̂ł͂Ȃ����A���邢�͐������Ȃ����Ƃ������Ă���̂ł́A�Ƃ����^�O������Ă��܂��܂��B���̂��Ƃ́A���̃A���v�͖{���Ƀf�W�^���A���v�Ȃ̂��A���邢�́A�_���s���O�t�@�N�^�[�������Ƃ������Ƃ͖{���Ȃ̂��A�Ƃ����^�O�ɂ��Ȃ���܂��B
�����ԍ��F15706037
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́B
�h�r�n�݂����Ȑ��E�������܂���A�e�Џo���悤�ŗl�X�Ȓl��
�o�Ă���\���͊����Ă��܂����B���{���[�J�[�͂܂���������o�Ă����
���܂��傤�B
�܂��܂���������̂��ӌ����肪�Ƃ��������܂��B�F�l�̈ӌ���l����
���Q�l�ɂ����Ē����Ēl�̕]�������Ă݂����ł��B
�u��������ǂ������v�u�����ƍ������̂ɂ��Ă݂����ȁv
����Ȋϓ_�ŋ@�ޑI�т��y���ނ̂����͗ǂ��Ǝv����ł��B
�t�Ƀt�@�[�X�g���b�g�̂r�h�s�P�݂����ɂc�e���T�Ƃ������Ȃ�
���̂̂ق������������Ă��܂����B
���̂�����ŃN���[�Y�ɂ����Ē��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F15707217
![]() 3�_
3�_
�����̂�����ŃN���[�Y�ɂ����Ē��������Ǝv���܂��B
���߂ɒ��߂����������ł��ˁB
�Ⴄ�����ɍs���Ă���݂��������B
���{�ƂȂ���́{�ƂȂ���ł��ˁB
�g�[�^���|�ɂȂ����悤�ȋC�����܂����B
�����ԍ��F15707343
![]() 1�_
1�_
���ʂɃv�����C���A���v�郁�[�J�[�������f�W�^���P�[�u����HDMI�P�[�u�����Ă͂����Ȃ����Ƃ͂���܂���
�P���Șb�ł����A�j���[�t�H�[�X��DAC���̔����Ă܂����A���j�o�[�T���v���C���[���̔����Ă܂�����A���̊W�ŃA�N�Z�T���[��̔����Ă��邾�����Ǝv���܂��B
�����z�Ȓl�i�Ŕ����Ă����ЂȂ̂ł��ˁB
1�A2���~��̃P�[�u���Ȃ�����Ƃ͌����܂��A���ʍ��z�ȃC���[�W���Ȃ��C�����܂����A���l�ς̈Ⴂ�ł��傤���B
�������������炻�������J�e�S���[�ɑ������ЂȂ̂ł͂Ȃ����ƁA���������܂����B
���������J�e�S���[���ĂȂ�Ȃ�ł��傤�H
�I���L���[��f�m���A�}�����c�ł��C�O�P�[�u�����[�J�[�̑㗝�X������Ă��܂����A���b�N�X��A�L���A�G�\�e���b�N�͎��Ѓu�����h�Ŕ̔����Ă܂���B
�I�[�f�B�I���[�J�[���A�A�N�Z�T���[���܂߂Ĕ̔����Ă���̂͂߂��炵���b�ł͂Ȃ��ł����B
�����ԍ��F15707489
![]() 3�_
3�_
���̃X�����ƃ��[�W������̓��e���S�Ă��ˁB
���Ƃ͎����܂ߒ��ԃ��x���B
�����[�W������
��قǐ�̏������݂ł����������Bm(_ _)m
�����r�ꂽ��ۂł���������ɂ�A-200����Ԗ��O���o�Ă܂����B
�m���Ƀ��[�J�[�̐�`����ɂ͔��͂����
���ꂾ�����ڂ𗁂тĂ�A���v���Ǝv���܂��ˁB
����A-200
���w������������Ă���͓d�C��ɒ��ӂ��܂��傤�B�o�J�H���H�i��
�����ԍ��F15707524
![]() 2�_
2�_
���[�W������
���݂��A��������A���݊�ꂽ�悤�ʼn����ł��B
���ŁA�ŋ߂͖���ւ�����ɂȂ�ꂽ�̂ł����ˁE�E�E�E
���c�O�ł��E�E�E�E�E
�u����ւ��v�Ɍ����Ă��܂��܂����H
�Ԃ�Ă͂��Ȃ�����ł����B
�����āA���t�Ŏ����ƁA
�u����������������v�̂���ł��B
�y�{���̈Ӗ��z
�����̎����w�i�����ʂ����Ƃ���������l�����B
�l��̋@���⎖�̐^���Ȃǂ�I�m�Ɏw�E���悤�Ƃ�����̂̌����B
����ꍇ�����̗���]�X���̂����h�Ȗό��ϑz�����Ă̂ɐ悸�͋C�t���܂��傤�B
�ϑz�Ƃ́i�E�L�y�f�B�A���A�ꕔ���p�j
�P�j���I�������s�\�Ȏv�����݂̂��ƁB�ϑz���������{�l�ɂ͂��̍l�����ϑz�ł���Ƃ͔F�����Ȃ��i�ނ���a�����Ȃ��j�ꍇ�������B���_��w�p��ł���A����������ł���ɂ�������炸�A�m�M���ُ�ɋ��łł���Ƃ������Ƃ�A�o���A���A�����ɂ���Ē����s�\�ł���Ƃ������ƁA���e�����I�ł���Ƃ������Ƃ������Ƃ���Ă���B
�Q�j����I�ȉ�b�ł��p�����邱�Ƃ����邪���̂Ƃ��͂������킵���l�����z��\���A�K�������a�I�ȈӖ��������܂ނ킯�ł͂Ȃ��y���Ӗ��Ŏg���Ă���B
�P�j�ł���A��X�������o������A�r�����悤�Ƃ�����A����������������肷��ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�Q�j�ł���A��X�������o������A�r�����悤�Ƃ�����A����������������肵�Ă��ǂ��ł��傤�B�ނ���A����I�ȉ�b�̂قƂ�ǂ��A���x�̍���������A�u�ϑzA vs �ϑzB�v�̉��V���A�uA�h vs B�h�v�̔h�������݂����Ȃ��̂ł��B
���邢�́AA�h�̒��ł̒��Ԃ̊m�F��Ɓi��ꍇ���Ɍ����邱�Ƃ�����j��AB�h�̒��ł̒����������哱���������E�E�E�j���Q�����āA����Ȃ��̂ł��傤�H
�����āA������ɂ��Ă��A�P�j�ł���Q�j�ł���A�l�b�g�̌f����ł́A��ʂ͂قڏo���܂���A������x�ւ�����Ƃ���ŁA�u���e����v�̂��x�^�[�ł͂Ȃ����H
���ꂪ�A���^�N�V����A���[�W������ւ̓`���Ȃ̂ł��B
�ϑz�ό��͋�����I
�ǂ��܂ŋ����Ȃ��āA�ǂ����狖�����A�Ƃ������x���́A�ӎ�����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���H
�Ƃ���ŁA�u���e�ł��Ȃ��v�ƁA�ǂ��Ȃ�̂��H
���E���Ń��A���ȕ������ς��Ȃ��̂�����A�����Ɓu���̐^���v�������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���������A���E�ł��L�j�ȗ��ō���Ɂu���a�ȍ��i�̕��a�Ȏ���j�v�ɕ�炵�Ă����X�Ȃ̂ł�����E�E�E
�����ԍ��F15709540
![]() 5�_
5�_
�����̎g���Ă����A���v��DF�l���m�F���Ă݂܂����B
���́A�J�E���^�[�|�C���g�̃p���[�A���v��8.9���������A��͈�ԏ��^�y�ʂ�YBA YBA3��300�ȏ���Ă̂��E�E�E
�����Ă�̂ŏC���\��i�����C���ɏo���邩�A���邩�ǂ������s���j�̃N������KSA-50s�́ADF�l�s�������A��ʋ@���KSA-100s��DF�l60�ȏゾ����50���L�邩�ǂ����H
�������̋@��́A8������50W����1�����ׂ܂őΉ���1�����טA��400W�o�͂̏����Ɍ��킹��ΐ����A���v�B
�m���ɏ�ʋ@�����SP�̐����͎͂ォ�����l�ɂ͎v���B
������SP�B�ɂ́A����a�E�[�t�@�[���ڋ@�������̂ł����DF�l���C�ɂ��Ȃ��Ă��点�Ă��̂��A�����̊������݂��̂��H�i�ʎ��́A���o���Ă���j
���䂵����ĂȂ����`�d�ቹ�������Ղ肵���ቹ�ƍ��o���Ă�\�����傩���m��Ȃ��B
�����ԍ��F15710340
![]() 0�_
0�_
2013/02/03 11:50�i1�N�ȏ�O�j
�E�T�M�����
���e
�v�������Ԃ̂́A
�����炩
�����[��
�d���̋������Ȃ�
�����肩�H
�ŁA�u�����������v�͐^�t�C���[�W�B
�R�����g�A��ꍇ���A����E�E�E�E
�ό��ϑz�ǂ��납��排����̗ނ��ƁB
������ɂ���A���e�Ȃ�l���Ȃ�����Ă�����Ȃ��Z���t���ƁB
���e���|�Ƃ���̂ł���A�u�ό��v�A�u�ϑz�v���]���ɕ�����ł��u���ɂ��Ȃ��v�A�u�����ɂ��Ȃ��v�����炵�A�X�ɂ́u�e�ՂɎא��v����錾����T�ނ��Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B
���݂ɁA���{�́u�����Ӗ��ł̌��_�̎��R�v���×����Ă��銴������܂��B
�u�ǂ��Ӗ��ł̌��_�����v�A���������オ���߂��Ă���Ɗ����鎟��ł��B
�X���傳���
�c�e�Ɩ��W�Șb��A���炵�܂���m(_ _)m
�����ԍ��F15710648
![]() 2�_
2�_
�\��Y����͏����܂����F
>���������J�e�S���[���ĂȂ�Ȃ�ł��傤�H
���̈�ۂł����A��{�I�ɕ\�������w�I�ŁA�Z�p�I�ɂ����܂��Ȑ�`���傪�����ȂƎv���܂����A����͂��Ă����A���Ƃ���CDP-8�̃y�[�W�A�uPhilips/Sony���̃s�b�N�A�b�v���J�j�Y���g�p���v�̂Ƃ����
>���̃G���[�����́A���R�[�f�B���O���ɐ������܂�Ă��Ȃ��y�I�A����I���W�i���ȏ��̒lj��ł���A�{���̃p�t�H�[�}���X������Ă��܂����ʂ݂܂��B
�Ƃ���܂��B����́A���͋Z�p�I�ɋ��U�̋L�ڂ��Ǝv���܂��B���Ђ̐��i�̗ǂ���j���_��ɐ�`����̂͂ǂ��̃��[�J�[������Ă��邱�Ƃ��Ƃ͎v���܂����A�����܂Ō�����ƁA�u�����������[�J�[�v�Ȃ̂��낤�A�Ǝv���܂��ˁB
�����ԍ��F15710716
![]() 3�_
3�_
�c�e�ɂ��Ă̋Z�p�I�Ȃ��b���A���������킩��₷�������Ă݂܂��B�X�s�[�J�[�̒�R��Rs�A�A���v�̓�����R��Ra�A�P�[�u���̒�R��Rc�Ƃ���
DF = Rs / ( Ra + Rc )
�Ƃ����̂͂����ł���ˁB���m�ɂ͕��f�C���s�[�_���X�ł����A�����Ƃ����Ƃ����ς���̃{�����݂����Șb��Ȃ̂ŁA������R�ōl���Ă��悢�ł��傤�B�����Ŏ��̂Q�̃V�X�e�����l���܂��B
�`�F�@Rs = 8���@Ra = 0.008�� Rc = 0.04���@�i DF = 167�@�j
�a�F�@Rs = 8.04���@Ra = 0.008�� Rc = 0���@�i DF = 1005�@�j
�u�Q�̃V�X�e���v�Ə����܂������A���ۂ͓����V�X�e���ŁA�X�s�[�J�[�P�[�u�����������������ŁA�����ɂȂ蓾�܂��B�a�͒�R0���ł��̂ŁA���ɑ��P�[�u���Ƃ������Ƃł��B�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�͂킸���ɈႢ�܂����A����́A���Ƃ��P�[�u���������ɋC�����P���オ�����ƍl���Ă��ǂ��ł����i�{�C�X�R�C���̒�R�̉���������Ȃ��̂ł��j�A�܂��덷�͈͂Ƃ������Ƃł��B
�������A�v�Z��c�e�̒l�͑傫���قȂ�܂��B�~�G���W�j�A�I�ɂ́u���ς����v�ƂȂ�܂����A�P�[�u�����I�ɂ́u�A���v�̐��\�̔������邽�߂ɋɑ��P�[�u���������߂��܂��v�ƂȂ�܂��B
�������A�o�������肷��͍̂ŏI�I�ɃX�s�[�J�[�ɗ����d�� I�ł��B����́A�I�[���̖@������A��H���̑S�N�d�͂� E �Ƃ��āA
I = E / ( Rs + Ra + Rc )
�ŁA��L�A�c�e���傫���قȂ�Q�̃V�X�e���œ����Ȃ̂ł��B�d���̎��� Rs�ARa�ARc �ɂ��đΓ��ł�����A����炪�ȂɂɗR������̂��A�X�s�[�J�[�P�[�u���̂ǂ��瑤�ɑ��݂���̂��Ȃǂ́A�d�C��H�I�ɂ͊W����܂���B
�͂炽����P�O�O�O�_����A�����������b�̓v���X�ɂȂ�܂����H
>�I�[�f�B�I�Ƃ��A����Ȃ���́u���v������@�B�ł��傤�B
>�����̒��Ŋy���߂�A�ǂ̂悤�ɉ��߂������ėǂ��킯�B
>�Ⴄ���ȁB
�ǂ̂悤�Ɏ���y���ނ��A�ǂ̂悤�ɏ�����̑I�����邩�͌l�̎��R���Ǝv���܂����A�S�n�悢�������邽�߂Ɏ������y������Ƃ���A���_�����������̃A�h�o�C�U�[����Ƃ��ẮA������Ƃǂ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F15710747
![]() 5�_
5�_
���[�W������
�܂��܂��A���s���ł��ˁB
�����݂ɁA���{�́u�����Ӗ��ł̌��_�̎��R�v���×����Ă��銴������܂��B
���u�ǂ��Ӗ��ł̌��_�����v�A���������オ���߂��Ă���Ɗ����鎟��ł��B
�ȑO�������܂������A�N���u�ǂ��Ӗ��ł̌��_�����v���s�Ȃ���̂ł��傤���H
����ȁg���ʂȌ����h���A�N�ɗ^������̂ł��傤���H
���[�W������̎�ϓI��ŁA���l�̌��_�����ׂ����ǂ��������������邱�ƂɁA�댯�������܂��H
�����Ȃ��悤�ł���A�u�|�����Ɓv�ł��ˁA���Ԃ�B
�g���ʂȌ����h�E�E�E�����E�E�E���̍l����i�߂Ă����ƁA���̒����ǂ��Ȃ�̂��́A���E�̗��j����w�Ԃ��Ƃ��o����Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁA
���^�N�V�ɂƂ��āA�u���������������邱�Ƃ́A���e�ł��邽�߂̎�i�̈�v�Ȃ̂ł��B
���̌��t�̈Ӗ����ʂ��Ȃ��悤�ł���A���̘b�́A���̕ӂł��I���ɂ��܂��B
�����ԍ��F15710786
![]() 5�_
5�_
2013/02/03 12:44�i1�N�ȏ�O�j
�E�T�M�����
�u���e�v�̃{�[�_�[���C�����N������������H�Ƃ̕��s���A�T�ⓚ�E�E�E�E�E�E
�I���ɂ��܂��傤�B
�ł́B
�����ԍ��F15710870
![]() 2�_
2�_
���e�˂��`
���[�W������́A���̃X���ŊW�Ȃ��b�������āA�Ō�ɃX���傳��ɘl�т����Ă܂��B
�E�T�M����͂ǂ����I�H
���̃X���ł܂������W�Ȃ��b�����C���𒋊Ԃ�����݂ق������������Ƃ��Ƀc���c���B(��)
�ŁA�X���傳��ɊW�Ȃ��b�����Ă��l�т�����ĂȂ��B
���ĊF����
�ǂ������邩���ȁI
�X���傳��
�W�Ȃ��b m(_ _)m �X�C�}�w���B
�����ԍ��F15710938
![]() 4�_
4�_
���[�W������
�ǂ����A�ʂ��Ȃ��悤�ł��ˁB
���[�W�����A����I�ɁA���l�Ɍ������āu���O�̃J�L�R�~�͖ό��ϑz���B�����A�������ނȂ�I�v�ƁA������Ő��������āA�u���_�����v�����s����Ă���̂ŁA������ƁA�ǂ��Ȃ̂�`�ƁA����N���Ă��邾���Ȃ�ł����ˁB
���e�̐������́A���l�̌������K�����Ȃ��ꍇ�́A�[���l����K�v�͖����ł��傤�ˁB
�V���v���ɁA����Ȋ����ŁA�������ł��傤���H
�����ƈӌ��̍���Ȃ����l�̌������K�����悤�Ƃ��Ă��邩�ǂ����H
�K�����悤�Ƃ��Ȃ������e�ł���B
�K�����悤�Ƃ���i���_���������s����j�����e�łȂ��B
���������A�Ǘ��l���폜���܂�����A�Q���҂����q�c���������āA���l�ɑ��Č��_�������s�Ȃ��K�v�ȂǂȂ����A����Ȍ������Ȃ��ł��傤�B
�����Ă��邱�Ƃ́A�V���v���Ȃ�ł����ˁB
�Ƃ���ŁA���^�N�V���A������ł����A�Љ�ʔO��A�֊��Ǝv����J�L�R�~�Ɋւ��āA�u�����ׂ��ł͂Ȃ��v�ƒ������܂������E�E�E����ꂽ���{�l�ɂ́A�Ӗ����S���ʂ��Ă��Ȃ��悤�ŁA���ς�炸����ŃS�`���S�`�������Ă��܂��̂ŁA�Ȃɂ���������A�Ƃ������ʂł����E�E�E
����ɂĎ��炵�܂��B
�����������܂����B
�����ԍ��F15711117
![]() 6�_
6�_
����ɂ��́B
���������Ӗ������ɂ͂킩��Ȃ��B
�ǂ̂悤�Ɏ������݂邩�A�Ȋw�����邩�͎��R���Ƃ����Ă��ł��B
���R�ł���B�����y���͂��Ă��Ȃ��B
���[�������Ȋw�ʼn��߂���̂����\�B�l�ɂ��l�������Ȋw�ʼn��߂�
���\�B�D���ɂ����炢����ł��B���͍D���ɂ��܂��B�����Ɂ{�ƂȂ�
���낤�����݂̂������ɓ����Ƃ��������ł��B
�Ƃ肠�����N���[�Y�ł�낵���ł��傤�B
�����ԍ��F15711653
![]() 6�_
6�_
2013/02/03 16:41�i1�N�ȏ�O�j
�����Č����A���\�I���y�̐��E�ɗB�ꖳ��̎����Ȃ��݂��Ȃ��B
�S�l����ΕS�l�S�l�́u�o���v�A�u�̌��v�݂̂����݂���B
�u���͎������y������v�Ƃ͈ꌾ�������ĂȂ����m�ɁA�u���̂��O�͎������y������v�Ɨ��ށB
����ȗ��s�s�s�тȏ��Ƃ͋��e����ē��R�B
�����t���ƌ��킸���ĉ��ƌ����ׂ����H�H�H
����̌���������m���炵���u�����ɂƂ��Đ^���ɋ߂����m�v��I�����悤�Ƃ���X���傳��ɂP�[���ȁB
�����N���[�Y�ł悢�Ǝv���܂��B
�����l�ł����B
�����ԍ��F15711786
![]() 3�_
3�_
�͂炽����P�O�O�O�_����
>���������Ӗ������ɂ͂킩��Ȃ��B
��H������Ƃ�����������͂���܂���B�ǂ����킩��Ȃ��̂ł��傤�H
>�ǂ̂悤�Ɏ������݂邩�A�Ȋw�����邩�͎��R���Ƃ����Ă��ł��B
>���R�ł���B�����y���͂��Ă��Ȃ��B
�i�����j
>���͍D���ɂ��܂��B�����Ɂ{�ƂȂ�
>���낤�����݂̂������ɓ����Ƃ��������ł��B
��̂��Ƃł�������̎�̑I���͎��R�ŗǂ��A�Ǝ������ɏ����܂����B�����A�u�D���ɂ���v���Ƃ́A�i�Ȋw�I�j�������d�����邱�ƂƁA�K�������������Ȃ��Ǝv���܂����A�������ł��傤���B
���Ƃ��Ύ���[15710747]�̑O�i�ŏ������v�Z�͉Ȋw�I�����ł����āA���́u�ӌ��v�ł͂���܂���B���������A�I�[�f�B�I�t�@���̖����悤�Ȏ�����������邱�Ƃ́A�͂炽����P�O�O�O�_����ɂƂ��Ă͓���̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͎v���Ă��܂��B
���̃X���́A���Ȃ����A�L���t�F�[�Y�̃Z�[���X�g�[�N����c�e�ɋ�����������ė��Ă�ꂽ�̂ł���H���̖`���ɂ�
>�A���v�̎d�g�݁E�\���E�X�y�b�N�ɏڂ������ɋ����Ē��������̂ł��B
�Ƃ���܂��̂ŁA�Ȋw�I�����ɂ��Ă��m��ɂȂ肽�������̂ł͂Ȃ��ł����H�u�Ȋw�I�v�ƌ�����̂͂����������̓��e���炢���Ƃ͎v���܂����A�F�����Ԃ������Č��\�ȏ������݂����ꂽ�킯�ł�����A�X����Ƃ��āA����炩��ǂ̂悤�Ȍ��������ɂ��āA�܂Ƃ߂������Ă��ǂ��͂Ȃ��ł����H
�ӂ��ɉ��߂���ƁA�u�c�e�͂P�O���x�ȏ゠��C�ɂ���K�v�͂Ȃ��v�̂悤�ȁA��ʂɌ�����b���m�F���ꂽ�����ł���悤�Ɏv���܂��B�����A���̉��߂������t�������͂���܂���B�͂炽����P�O�O�O�_����̉��߂͂������ł��傤���H
�����ԍ��F15712740
![]() 3�_
3�_
2013/02/03 20:53�i1�N�ȏ�O�j
�s���������t�N�d�͂����݂��Ȃ��ϑz��H���_����(�P�́P)
�r��H���̑S�N�d�͂� E �Ƃ��Ĥ
I = E / ( Rs + Ra + Rc )
�Ť��L�DF���傫���قȂ�2�̼��тœ����Ȃ̂ł�
�d�C�����ꂢ�Ȃ���Ԃ���ʓd�����u���E���g����u�v�̂ݐ��藧�b�B
�v�̓X�^�e�B�b�N�Șb�B
�{�C�X�R�C���͕����ʂ�_�C�i�~�b�N�ɓ����B
�����o�遁����
����͋t�N�d�͂���������B
�t�N�d�͂̓X�s�[�J�[���A���v�B
�����n�C�o�����[�B
�_���s���O�t�@�N�^�[���P�O�{�Ⴄ�Ȃ�A���C���s�[�_���X���P�O�{�Ⴂ�A�C���s�[�_���X�u�A���v�}�b�`���O�̔����x�������ω�����B
���ꂪ�ǂ̒��x�L�ӂ��ǂ����͍ŏI�I�ɂ͎����f�����Ȃ��B
�����A���Ȃ��Ƃ��X�^�e�B�b�N�Ȉ�u�̂ݐ��藧���͔�Ȋw�I���{�̃f�^�������B
�͂炽���炳��ɂ��I�Ԏ��R�A����������B
��萳�����Ȋw�I������I�Ԏ��R�A�������ȁi��
���̗B��Ȋw�I�ȃR�����g�����������������Ȋw�I����������H
����͂ˁ`�`�`�A���m�ł͂Ȃ��C���`�L�����炾��(�P�́P)
�����ԍ��F15713060
![]() 1�_
1�_
�F�l��ς��肪�Ƃ��������܂����B�܂�����J�l�ł����B
�ꉞ�X���b�h��Ȃ̂ŎU��̂��m�点��v���܂��B
�����ԍ��F15713062
![]() 2�_
2�_
�����̏������������炷�ׂēǂݕԂ��܂��Ă݂܂������A
�\�ɊF�l�̈ӌ����Q�l�ɏo���A��ρ{�Ƃł��܂����B
�{���ł��B���Ӓv���܂��B
�܂����̊F�l�̂��m�点��ǂ܂�Ċ��������A����������
���R���ƌ������Ƃ��Ō�ɕt�����������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F15713168
![]() 2�_
2�_
�r�����������@�q������������
>���ꂪ�ǂ̒��x�L�ӂ��ǂ����͍ŏI�I�ɂ͎����f�����Ȃ��B
��H���_�I�Ȃ��b���n�܂�̂��Ǝv���i���Ď��͎v���Ă܂��j�A����������o�Ă��Ȃ��܂܁A�ؓ��n�̓W�J�ƃI�`�ł��ˁB����Ȃ�����~�G���W�j�A�Ȃ̂ł��B����
>I = E / ( Rs + Ra + Rc )
�ɂ����āAE���u��H���̑S�N�d�́v�Ə����Ă��܂��B�܂�A�t�N�d�͂�E�̒��Ɋ܂܂�Ă��܂��B�����āA�{�����f�C���s�[�_���X�ł���Ƃ������܂����B�܂�㎮�͕��f�̈�̎��ł����āA�^�C���h���C���̏����܂�ł���̂ł��B
�����A���̋c�_��O��ɂ�����A�N�^���X�������ł���̂ŁA�C���s�[�_���X�����͎����Ƃ��܂����B�������A�h �� E �Ƃ͕��f���ł���Ƃ������Ƃ�������Ă��܂���B�܂�
>�����A���Ȃ��Ƃ��X�^�e�B�b�N�Ȉ�u�̂ݐ��藧���͔�Ȋw�I���{�̃f�^�������B
�Ƃ����͉̂�H���_��m��Ȃ��~�G���W�j�A�̒m���s���ł����Ȃ��A��Ɉ��p�������́A�e�u�Ԃ��ׂĂŐ��藧���̂ł��B
�����ԍ��F15713499
![]() 4�_
4�_
�Y�ꂳ��@������B
�������܂Ō�����ƁA�u�����������[�J�[�v�Ȃ̂��낤�A�Ǝv���܂��ˁB
�H�H�H
����������ɑ��āA����ƌ�������������ł����A���̖Y�ꂳ������̂��ȁH
�ʂɍ\���܂��A�������吶���Ă͉Ȋw�I�Ȓm��������߂���͉̂��̂��낤�B
�w�b�h�t�H���ɂ͊w������̏�A�͂��܂����A�����܂ŃI�[�f�B�I�ł͂Ȃ��Ȋw�I�Ȓm���������m�Ȃ̂͋C�ɂȂ鏊�ł����H
�����������A�I�[�f�B�I�t�@���̖����悤�Ȏ�����������邱�Ƃ́A
�I�[�f�B�I�}�j���́A���݂Ă��ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�X�s�[�J�[�������Ƌ쓮�ł����牽�����ėǂ���ł�����(�j
����H������Ƃ�����������͂���܂���B�ǂ����킩��Ȃ��̂ł��傤�H
�Y�ꂳ��̌����Ă邱�Ƃ́A�m�����Ȃ��l�Ԃɂ͂���������Ȃ��ł���B
�܂�łǂ�`�����ł���݂����ɗ���s�\�ł����A�����I�[�f�B�I�ɋ������Ȃ��M�������̔ɎQ�����Ă��闝�R����ԕ�����܂��ǂˁB
�����ԍ��F15713550
![]() 8�_
8�_
2013/02/03 22:44�i1�N�ȏ�O�j
�rI = E / ( Rs + Ra + Rc )
���̎����������m�́A�C���s�[�_���X���a�������Ȃ�A�d���l���������Ă��ƁB
�r�o�������肷��͍̂ŏI�I�ɽ�߰���ɗ����d�� I
�܂�A Rs �F�i Ra + Rc�j�Ȃ�_���s���O�t�@�N�^�[�ɖ��W�ɓd���l�h���K�肳��o���������ƁB
�rDF��10���x�ȏ゠��C�ɂ���K�v�͂Ȃ�
�P�O�����͋C�ɂ��˂Ȃ�Ƃ��㎮�͎����Ă��Ȃ��B
�܂��A�P�O�ȏォ�P�O�O�ȏォ�͊m�肵�Ƃ�ȁB
���ǁA�����͌��׃C���`�L���f���Ȃ�(�P�́P)
��o���͂��������ς��₩����������Ł`�`�`
�X����̂͂炽���炳��X�錾�₵��C�ǂ߂�`(�P�́P)
�����ԍ��F15713841
![]() 2�_
2�_
�\��Y����
>������B
�u�����́v�ł���B
>����������ɑ��āA����ƌ�������������ł����A���̖Y�ꂳ������̂��ȁH
�F�X�Ȑl�̌����������Ă悢���ƁB������ƕi�̂Ȃ��������ڗ����[�J�[���Ǝv���܂������A����CDP-8�̃y�[�W�ł͕s�R�Ȑ������C�ɂȂ����̂ŁB
>�Y�ꂳ��̌����Ă邱�Ƃ́A�m�����Ȃ��l�Ԃɂ͂���������Ȃ��ł���B
���f�C���s�[�_���X�̘b�͓�������m��܂���ˁB�N�ɂł��킩��₷���悤�ɐ�������͎̂�Ԃ�������̂ŁA����ɂ���Č��t��ς��Ă��܂��B�m�����[���قǑf�l�ւ̐��������܂����̂ł��B�����܂��܂��ł����B
�����A�i�����Ă��˂��ɉł���Ƃ͌���܂��j�s���ȓ_�͎��₵�Ă��������B
�����ԍ��F15713886
![]() 1�_
1�_
�r�����������@�q������������
>���̎����������m�́A�C���s�[�_���X���a�������Ȃ�A�d���l���������Ă��ƁB
�����ł��ˁB
>�܂�A Rs �F�i Ra + Rc�j�Ȃ�_���s���O�t�@�N�^�[�ɖ��W�ɓd���l�h���K�肳��o���������ƁB
Rs�ARa�ARc �̂ǂꂩ���ς���DF���ς��i�\��������j�̂ŁA�uDF�ɖ��W�ɓd���l�h���K�肳���v�͐���������܂��ADF�͉Ȋw�I�ɂ͂��܂�Ӗ��̂���p�����[�^�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
>�P�O�����͋C�ɂ��˂Ȃ�Ƃ��㎮�͎����Ă��Ȃ��B
�Ȃ���o���W�����P���ł��ˁB���Y����[15710747]�ŁA�u�c�e����Ⴂ�ł����͓����v�Ƃ������������邽�߂ɏ��������̂ŁA��L���������߂̂��̂ł͂���܂���B�u�P�O�����v�]�X�̓E�T�M����̂����e�ɏ�����Ă������ƁB
�����ԍ��F15714118
![]() 1�_
1�_
2013/02/03 23:50�i1�N�ȏ�O�j
�r�DF����Ⴂ�ł����͓�����Ƃ������������邽��
�c�e���T�ƂP�O�O�O�ŏo���������ɂȂ鐔�����f���͌��׃C���`�L�����(�P�́P)
�����ꂵ�������(�P�́P)
�Ƃ��ƂƑގU����ˁB
�I�����ގU�ˁB
�����ԍ��F15714275
![]() 0�_
0�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ��������͕�����₷���Q�l�ɂȂ�܂��B�����A���A�N�^���X�����̑傫�ȃX�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X��
Zs=r+Rs+j��L[��]
(r�F�X�s�[�J�[�̓�����R�ARs�F���̃G�l���M�[�ɂȂ����d�C��R�������Aj��L�F���A�N�^���X)
�Ƃ��Ă��������ꂽ��ŁA���ƌ������ƂŎ��g�����������A�܂��C���_�N�^���X�Ƃ̐ς�r��Rs�̒l�Ɣ�ז������܂��A�Ƃ������Ƃ�j��L=j×2��f×L��0�Ƃ�������������₷���ł��B����́u�C���s�[�_���X�����͎����v�݂̂Ə�����Ă͂��܂����قڒ����Ƃ��čl����ɂ͏�����a���������܂����B
���������A�L���̐�`����DF�l�Ƃ͉�Hz�ɑ���l�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F15715306
![]() 2�_
2�_
�[�ǁ@�L�[
�X���b�h��Ƃ��Ď��Z�߂���ׂ��A�Ƃ����w�E������A
��قǃA�L���t�F�[�Y�̂ق��ɃJ�b�`���������╶��
���点�Ē����܂����B���Ȃ����Ɨǂ��ł����B
���̌��ʂ��炻����ǂ��l��������R���Ƃ����킯�ł��B
�A�L���t�F�[�Y�͐������Ȃ��Ƃ��邩�A�l�͊W�Ȃ���
���邩�A���R�ł��ˁB���y���݂ɁB
���b�N�X��l�̌��J�����Ă���Ă��郁�[�J�[�����
������肵�Ă݂܂��B�������Ԃ����邩������܂���
�ԓ����Ȃ��P�[�X�������ł��傤�B�������܊p
�ł��̂ŁB
�e�ЈɒB�ɒl���o���Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB
�l���Ⴂ���爫�����Ȃ����A�ǂ�����ǂ��Ƃ�������
�Ȃ��B�e�X���ǂ����߂��邩�ł�����ˁB���R�Ȃ�ł��B
�����͂܂��A�L���t�F�[�Y�i�\����\�I�ȃ��[�J�[����
�ŊԈႢ�Ȃ��ł��傤�H�j�ɐ�w�����Ă��������Ă����܂��B
���ʂ͂܂�����ɂ��E�E�E
�����ԍ��F15715344
![]() 1�_
1�_
�_���s���O�t�@�N�^�[�ɂ��ď����܂����ANuForce�Ђ̃��[�J�[�T�C�g�ɂ́A
http://www.nuforce.jp/highend/technologies.html
�� NuForce�A���v�ł́ARF�m�C�Y��}�����邽�߂́A�����g�p�R�������[�h�`���[�N�Ƃ��Ă��@�\����X�s�[�J�[�[�q�ւ̃��C�������O����H��ɉ������Ă��܂��BNuForce�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[���X�s�[�J�[�[�q�Ōv�������Ƃ���A�t�����C�������O�̃C���s�[�_���X�Əo�̓`���[�N�f�������l��160���x�ɂȂ�܂��B
�Ƃ����L�q������܂��B
�ł́A IA-7V3 �̃_���s���O�t�@�N�^�[�� 160 �Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H�Ƃ����^�₪����܂��B
�Ȃ��ANuForce�Ђ̐��i�ɂ��Ă͈ȍ~�͎��́A
[15715918] http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000126742/SortID=15715918/
�̃X���b�h�ɏ����܂��̂ŁA���̏����ďЉ���Ă��������܂��B
�����ԍ��F15715926
![]() 1�_
1�_
�~�G���W�j�A����A�����́B
>�c�e���T�ƂP�O�O�O�ŏo���������ɂȂ鐔�����f���͌��׃C���`�L�����(�P�́P)
���Ⴂ�܂����āBDF=1005�̃V�X�e����DF=167�ɉ�����ɂ̓P�[�u���� 0���� 0.08���ɂ���悭�A���̂Ƃ��S��R�͂قƂ�Ǖς��Ȃ��̂ŁA�����ς��܂���B
�ł�DF=5�ɉ�����ɂ� 1.6���̃P�[�u�����K�v�ŁA�S��R��2�������܂��B���낻�땷�������ł���l���o�Ă������ł��B�u���[�v�Ȃ�Ƃ����ƃA�������ǁB
�E�T�M����� Minerva2000 ����̓��e�ɂ���o�����ɂ��� DF=10�ȉ����Ɩ��ȗR�ł����A�[���ł��܂��B���ׂ��C���`�L������܂���B
>�Ƃ��ƂƑގU����ˁB
���䂱�ƌ�������E�T�M����u���_�����v���Č������ł���B�������ƕ�������͂Ȃ����ǁB
>�I�����ގU�ˁB
�ƌ����l�̘b�ɃP�`������̂́A��H���_�I�ɂ́u�C�^�`�̂Ȃ�Ƃ��v�ƌ����܂��i�p���������ď����Ȃ���j�B�Ă��A�Ȃ�Ń[���W�[�k���H
�����ԍ��F15718852
![]() 4�_
4�_
�̂�ۂ�
>���������A�L���̐�`����DF�l�Ƃ͉�Hz�ɑ���l�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�͏�p���g���тł͂��܂�f��������܂��ADF �́A���̒��ł́u8���v���g�p���銵�킵�Ȃ̂ŁA�u��Hz�ɑ���l�v���́A�A���v�̂c�e�̃X�y�b�N�Ƃ��Ă͏d�v�ł͂Ȃ��C�����܂��B
�ނ���A�O�ɏ����܂������A�ǂꂭ�炢�̐M�����x���ł̒l�Ȃ̂����C�ɂȂ�܂��B�����̈�ł͓d���n���܂߂ă��o�X�g�ł���K�v������܂����A�t�ɏ��M���ł̓[���N���X���݂�DF����������\�������肻���ł��B�ł��A���[�J�[�ɂƂ��ēs���̗ǂ��g�R���Œ�`����̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F15718869
![]() 3�_
3�_
2013/02/04 23:49�i1�N�ȏ�O�j
�]�~�\�^�߂���
�r�ł�DF=5�ɉ�����ɂ� 1.6���̹���ق��K�v�Ť
�ǂ���c�����`�`�`(�P�́P)
�J�^���O�X�y�b�N�̃A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���T�Ȃ�A�W���X�s�[�J�[�ɑ��ăA���v�C���s�[�_���X���P�D�U����낪���`�`�`(�P�́P)
����Ȏq���x���̃y�e���ɂ͔~�����������|�����킢(^w^)
�����ԍ��F15718928
![]() 1�_
1�_
>�]�~�\�^�߂���
�u�~�v�ɂ����Ă������B�B
>�J�^���O�X�y�b�N�̃A���v�_���s���O�t�@�N�^�[���T�Ȃ�A
�P�[�u������Ȃ��ăA���v��DF�����������킯�ł����B�A���v�ʼn����Ă��P�[�u���ʼn����Ă��A�S��R���Q�������āA�X�s�[�J�[�̃_���s���O�������Ȃ�̂͂���Ȃ��ł�����A
>�c�e���T�ƂP�O�O�O�ŏo���������ɂȂ鐔�����f���͌��׃C���`�L�����(�P�́P)
�Ƃ͂Ȃ�܂���B�ł��A�A���v��ς����������A�c�e�̍����Ă���A�A���v�̍����Ă���킩���ł���B
# �~�̉����ĂȂ�ł����ˁB�f�����l�Ȃ��H
�����ԍ��F15719101
![]() 2�_
2�_
2013/02/05 00:37�i1�N�ȏ�O�j
�_���s���O�t�@�N�^�[���Ӗ��_�҂������ׂ��������f���́A
�_���s���O�t�@�N�^�[�݂̂��قȂ肻��ȊO�͓����H�̉��z�A���v������Ƃ��āA
�_���s���O�t�@�N�^�[���������ꍇ�͉��i�d���j���ς��A������x�ȏ�ɂȂ����特�i�d���j���ω����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������f���B
�����o�������͕���������B
�����f�݂̂�����B
�����牴�͂����������B
���W�ƍ��ꂷ��Ȃ�͂悤������(�P�́P)
I = E / ( Rs + Ra + Rc )
����ł͑S�����ɗ�����C���`�L����(�P�́P)
�����A���Ɍ�o���₩��lj��͋p���B
�B��Ȋw�I�ƍ��ꂵ���C���`�L���������Ŏ����Ă݂���I
�����ԍ��F15719170
![]() 2�_
2�_
�����莸�炵�܂��B
�u���E�|�E�~�̗Ⴆ�ɂ͖{���A�㉺�̍��ȂǂȂ��v�Ƃ����P�V�[�����A���̘A�h���w�~�����搶�x�ɂ�����܂������A����͂��Ă����A�_���s���O�t�@�N�^�[�ɂ��āB
��TEAC HA-501�̃_���s���O�t�@�N�^�[�Z���N�^�[�Ƃ́H
http://monoadc.blog64.fc2.com/blog-entry-131.html
�̒��ŁA�l�i���̋L���ɂ��Ɓh�_���s���O�t�@�N�^�[�Z���N�^�Ƃ͏o�͒[�q�ɒ���ɓ����R�̑傫����ς�����́h�Ƃ̂��ƁB�r�o�P�[�u���̒�R��ς���̂Ɠ����ł��ˁB
���ǁA�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ͕����ʂ茸���i�܂��͐��k�j�ɂ�����v���A�����������v���̂����̂P�ɉ߂��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���ꂪ�����_���s���O���V�I�F�����W���i�Ăŕ\�����j�Ƃ������Ƃł���A�Ӗ������͈���Ă��āA�e���͂͂����Ƒ傫���̂��Ǝv���܂����ǁB
�����ԍ��F15719415
![]() 4�_
4�_
�鉤����
�����Ӗ�����܂��B
�͂��߂܂��āI
�����ɂ��e���B
�����ɏڂ�������܂��A�A
���N�ʂ���p���[�A���v���t���[�e�B���O�Z�b�e�B���O�����Ƃ���_���s���O�i������)�����ɏo�܂����B
����͒��ԓ��̕ʃX���ł����x�������Ă܂����A�A�����������[�Ȃ��o�܂��I
������������X�s�[�J�[�P�[�u���̒�R�l�ȏォ���m��Ȃ��B
���̌��ۂ͒m�l�̃I�t��ł��o���ς݂ł��āc�A�R���o�̃G�A�t���[�e�B���O�{�[�h�ݒu) �ɂėL�閳�����o���B
���̂ɐ��U��DF�l�����サ�����ۂ��N����̂��I�i���炭DF�E���l�f�[�^�ł��オ�����Ă�ł��邾�낤)�B
�l�I�ɂ�
�K�������d���g�����X�W��E�P�[�u����R�ȏ�ɉ�������e���͂͂��肻���ł��B
���̌����i��Ƀt���[�e�B���O)�̓X�s�[�J�[�Z�b�e�B���O�ł��_���s���O�̌���ɌW���ł��낤�B
�����ԍ��F15719882
![]() 1�_
1�_
>�_���s���O�t�@�N�^�[���������ꍇ�͉��i�d���j���ς��A������x�ȏ�ɂȂ����特�i�d���j���ω����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������f���B�i�����j
>�B��Ȋw�I�ƍ��ꂵ���C���`�L���������Ŏ����Ă݂���I
�Ȃ�قǁB������̎��Ŏ咣���邱�Ƃ́A�u�X�s�[�J�[�̓��������߂�̂͂����𗬂��d���ł���v�Ƃ������R�̂��Ƃł����A�����ό`���Ă݂܂��B
I = E / ( Rs + Ra + Rc ) = E / Rs�E( 1+ 1 / DF )
�����ŁA�قȂ�X�s�[�J�[�Ԃł̐����͂�d���l�Ő�Δ�r���邱�ƂɈӖ��͂Ȃ��̂ŁA�X�s�[�J�[���Œ肵�čl����ARs�Ŋ���Ӗ��͂���܂���B�܂��AI��E�Ƃ͔�Ⴗ��̂����R�ŁA���͔��W���ł��B�]���āA�����u�_���s���O�t�@�N�^�[�v���`����Ƃ����
DFW = 1 / ( 1+ 1 / DF )
�ƂȂ�܂��i"W" �́u�Y��v�̈Ӗ��j�BDFW�́ADF=0�̂Ƃ���0�ADF=���̂Ƃ���1�ƂȂ閳�����ʂł����ADF=10�̂Ƃ��ɂ��ł�0.91�ADF=50�ł�0.98�Ȃ̂ŁA����ȏ�́u�J�������ĉv���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�������ł���H����͈ȑO��������ł����ǂˁF
�X�s�[�J�[�P�[�u���ʼn����ς��̂�����Ƃ��ς��Ȃ��̂� #2
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9419840/#9424465
�����ԍ��F15719909
![]() 1�_
1�_
�_���s���O�E�t�@�N�^�ɂ��āA�O�O���āA�Ȃ�ƂȂ����_�I�ȃT�C�g������������A
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/9722dynamicspeaker.pdf
http://www3.coara.or.jp/~tomoyaz/higa0004.html
http://www7a.biglobe.ne.jp/~sigotnin/audio/audio004.htm
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/4999/main/bcs.html
���������ȁB
���_�Ƃ��ẮAHi-Fi�X�s�[�J�͒�d���쓮��O��ɍ���Ă��邩��A�_���s���O�E�t�@�N�^�͍������悢���A10���x�ŏ\���ł���A�������Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�����ԍ��F15720217
![]() 3�_
3�_
2013/02/05 23:36�i1�N�ȏ�O�j
�rDFW = 1 / ( 1+ 1 / DF )
�� �c�e�m�t���c�e/�i�c�e�{�P�j
���lj�c������₁E�E�E�E�E�E
�����͊w��_���łǂ���(�P�́P)
�A�z�N�T�E�E�E�E
�܂��A�k�ق�M���邵�������p���Ȃ����Ɨ���(^^�U
�����ԍ��F15723219
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B
>���̋c�_��O��ɂ�����A�N�^���X�������ł���̂ŁA
>�C���s�[�_���X�����͎����Ƃ��܂����B�������A�h �� E �Ƃ�
>���f���ł���Ƃ������Ƃ�������Ă��܂���B
��L�̂悤�ɒ��Ɍ��肹���Ƃ��A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�������Ă��郊�A�N�^���X�����������ł��邮�炢�ƂĂ��������Ɖ��肷��ƁA�M������p���g���т͈̔͂ŕς��Ă�DF�l�͂قڈ��Ƃ������Ƃł��ˁB
��L�̖Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̋L�q�̒��łЂƂC�ɂȂ����_�Ƃ��āuI��E�͕��f���ł邱�Ƃ�������Ă��Ȃ��v�Ƃ���܂����AI = E / ( Rs + Ra + Rc )�̎��ɂ����܂���Rs + Ra + Rc �������Ɖ��肳��Ă�����̂ŁA�K�R��I��E�͓����ƂȂ�܂��B�܂�d���ɑ���d���̈ʑ����͂Ȃ��A���̏ꍇ�ł���I��E��a+jb�̂悤�ȕ��f���ł͂Ȃ������ł̎戵���ƂȂ邩�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F15723529
![]() 2�_
2�_
�щ��i�I�r�������j����
>���ǁA�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ͕����ʂ茸���i�܂��͐��k�j�ɂ�����v���A�����������v���̂����̂P�ɉ߂��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B
�����ł�����܂���B�������ɁA�X�s�[�J�[�ł͌ŗL�U����}���邽�߂ɋ@�B�I�����𑝂₵�Đ�����������Ȃǂ��Ă��܂����A�X�s�[�J�[�͓d���͂ŋ쓮���ĉ����o���@��ł�����A�t�ɓd���͂ɂ�鐧�������͂ł��邱�Ƃ��e�Ղɗ����ł���ł��傤�B�c�e���ɒ[�ɒႢ�Ɓi���Ƃ��P�ȉ����Ɓj��悪�{��������������킩��悤�ɁA�d���͂ɂ�鐧���͏d�v�Ȃ̂ł��B
���́ADF��傫�����Ă����Ă����̌��ʂ�10���������Ƌ}���ɓ��ł��ɂȂ�̂ɁA1000�Ƃ���1000�Ƃ��A���Ӗ��ɍ���DF�l�������\�ł��邽�߂ɉc�ƓI�ɗ��p����A�w���҂ɍ����^����`�ŃA���v��X�s�[�J�[�P�[�u���̔̑��ɗ��p����Ă��邱�Ƃł��B������y���ނ̂���̂����ł��傤���A������������𗹉�������ŃI�g�i�̊y���݂��������Ă���l�́A���Ȃ菭�Ȃ��ł��傤�B
�A�L���t�F�[�Y�Ƃ��Ă͉c�Ə�̏d�v�{��̂ЂƂ�DF�𐘂����Ǝv���܂����A�s�ꂩ��̂܂��߂Ȏ���ɂǂ������邩�́A��Ƃ̎p���������ŁA�������ɒ��ڂɒl���܂��B
�����ԍ��F15723563
![]() 7�_
7�_
�̂�ۂ�
>I = E / ( Rs + Ra + Rc )�̎��ɂ����܂���Rs + Ra + Rc �������Ɖ��肳��Ă�����̂ŁA�K�R��I��E�͓����ƂȂ�܂��B
���������Ƃ���ł��B
>�܂�d���ɑ���d���̈ʑ����͂Ȃ��A���̏ꍇ�ł���I��E��a+jb�̂悤�ȕ��f���ł͂Ȃ������ł̎戵���ƂȂ邩�Ǝv���܂��B
���̓��v���X�ϊ��̈�̉�H�������Ƃ��ď����Ă���̂ł����A�e�u�Ԃ��Ƃɐ��藧�����̕������ƍl���Ă��������Ė�肠��܂���B��ʂ݂̂Ȃ���ɂ͂��̂悤�ɓǂ�ł��������Ӑ}�ł��B
�����ԍ��F15723727
![]() 4�_
4�_
[15719909]�ł̎��̓��o���A��������������܂����̂ňȉ��ɒ�������Ƌ��ɁA�����⑫���܂��B
I = E / ( Rs + Ra + Rc ) = E / ( Rs�E( 1 + 1 / DF ) )�@�@�i�����ʂ��ꕔ�����Ă��܂����j
�� 1 / ( 1 + 1 / DF )�@�߁@DFW
DFW���A�����͂���萳�����\�킷�ʂł��B�{���͏�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɓd���i�����d���j�̑傫���ł��B�����́i���[�����c�́j�͓d���ɔ�Ⴗ��̂ŁA�����I�C���[�W�͖����ł��ˁB�ނ����ʂ� DF �̂ق����A�����I�ɂ͂Ȃ��킩��܂���B
DF �� DFW �̊W���O���t�ɂ������̂�Y�t���܂��BDF�͂�������10�܂ł������A�Ƃ������Ƃ�������Ă��܂��B�ȏオ�A�r�����������@�q������������[15719170]�ŏo���ꂽ����ɑ���ł��B���������l�ł�����A�u�Ȃ�قǁA�[�����܂����v�Ƃ͌����Č���Ȃ��킯�ł����i�j�B
�Ƃ���ŁADF=100�ł��܂��܂��A�Ƃ�������邩�������邩���m��܂���ˁB����ȏ����ȍ��͕�����������̂��H�Ƃ����b�Ƃ͕ʂɁA�������������͋��͂ȂقǗǂ��̂��H���l����K�v������܂��B
�͊w���K�������Ƃ����邩���́u�ߏ萧���v���������ł��傤�B���l�ɁA�X�s�[�J�[�ɂ���Ă͓d������������������ƒ��̗����������Ȃ�܂��B�^��ǃA���v���d���쓮�A���v�ɂ������I�[�f�B�I�t�@������������Ⴂ�܂���ˁH�����͒P�Ƀu�J�u�J�̉����D�݂Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�X�s�[�J�[�ɍ�����DF������ǂ��I�����Ă���Ƃ����\�����A�Ȋw�I�ɂ��蓾��̂ł��B
�����������Ƃ��炵�Ă��A�s���߂�����DF���͖��Ӗ��ƍl���܂��B���̂��߂Ɏ������̂��Ȃ��̂����l����ׂ��ł��傤�B
�����ԍ��F15726968
![]() 7�_
7�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B
�����̓��v���X�ϊ��̈�̉�H�������Ƃ��ď����Ă���̂ł���
I = E / ( Rs + Ra + Rc )�ɂ͂�����������(=s)���܂݂܂��A���ԗ̈�Ƃ��Ă�t�Ɉˑ�������̌`�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��ł��B���̂悤�Ȏ��̌`����́A����I�ɂ�E��I�͎����l���������̂Ƃ��čl����ꍇ�������A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̂����������悤�Ȃ���u�Ԃ��������ɂ��邷�Ȃ�A
i(t)=��2Esin(��t)/( Rs + Ra + Rc )�@(E:�����l�d���Ai(t)�F�u�Ԃɗ����d��)
�ƕ\���܂��B�Ȃ��A�����ł��܂�Ӗ��͂Ȃ��ł��������ă��v���X�ϊ��̈�̉�H�������Ƃ���Ȃ�A
i(s)=��2E×(��/(s^2+��^2))/( Rs + Ra + Rc )
�ƂȂ�܂��ˁBDF�̂��b����E�����Ă��܂������܂���B
�����ԍ��F15727276
![]() 4�_
4�_
�̂�ۂ�
��������邱�Ƃ������킩��܂��A����ł͖��ӔC�ȋC������̂ŁA�ǂ��킩��Ȃ����ɂ��ď��������܂��B
>I = E / ( Rs + Ra + Rc )�ɂ͂�����������(=s)���܂݂܂��A
�ł́A
I(s) = E(s) / ( Rs + Ra + Rc )
�Ə����悢�ł��傤���B��H���_�̋��ȏ��͂Ƃ������A"s"���ȗ�����̂͂悭���邱�Ƃł��B����ɁA���������ʂ̐l�ɂ͗����ł��Ȃ��̂ŁA�]�v�ł��傤�B
>i(t)=��2Esin(��t)/( Rs + Ra + Rc )�@(E:�����l�d���Ai(t)�F�u�Ԃɗ����d��)
���������Ă���E(s)�̎��͈̂�ʓI�ȕ��f���ł���A�����g�Ƃ�������͂���܂���B�����e�p�����[�^��啶���ŏ������̂́A���g���̈�ł̕\���Ƃ��Ă̊��Ⴞ����ł��B���ԗ̈�̎����Ɨ��_����ʐ��������₷���ł����A���������u���v���X�ϊ��v�Ɍ��y����K�v������܂���B
���Ƃ����Ď��ԗ̈�̎��̓d���l�Ɂu�����l���g���K�킵�v�Ƃ����̂����ӂł��܂���B����������2���������A�ӂ��ɐU�����g�p����ق����ނ��땁�ʂ��Ǝv���܂��i�ǂ����ł���肠��܂��j�B
�܂��A���ԗ̈�ł̐����g�� exp(i��t) �̎��������̂ŁA�Ȃ� cos �ł͂Ȃ� sin �Ȃ̂��낤�A�Ƃ��v���܂��B
>�����ă��v���X�ϊ��̈�̉�H�������Ƃ���Ȃ�A
>i(s)=��2E×(��/(s^2+��^2))/( Rs + Ra + Rc )
���v���X�ϊ���̎��ɁA�����g�̎����l���v�Z�����ۂɏo�Ă����2�����邱�Ɓi��ɏ������悤�ɁA���g���̈�̎��ŁA�����g�ł���Ƃ��鐧��͕K�v����܂���j�A�ւ�s�Ƃ����݂��Ă��邱�ƁA���ӂƉE�ӂŒP�ʂ̎����������Ă��Ȃ����ƂȂǁA�F�X�s�v�c�ł��B
�Ȃ��A�ȏ�͎���ł͂Ȃ��A�ԓ���v���E�v�]������̂ł͂���܂���B�{�_�ƈ�E���Ă���̂ŁA�ł���Έ�������Ȃ��ł������������̂��{���ł��B
�����ԍ��F15727897
![]() 4�_
4�_
2013/02/07 00:09�i1�N�ȏ�O�j
��c�������掩�^�̃C���`�L�p�����[�^��s���������Ă̂͂悭���������B
���A�A���v�̃C���s�[�_���X�݂̂��ω������ۂɓd���A�d�����ǂ̂悤�ȐU�镑�������A�_���s���O�t�@�N�^�[���P�O�����Ƃ���ȏ�łǂ̂悤�ȏo���ɂȂ邩�Ɋւ���ؐ����������B
�v�́A�������Ƃ邩�T�b�p���Ӗ��t����(�P�́P)
�r�ȏ�͎���ł͂Ȃ���ԓ���v����v�]������̂ł͂���܂���{�_�ƈ�E���Ă���̂Ť�ł���Έ�������Ȃ��ł������������̂��{���ł��
�����̌����������Ƃ��������A����ɂ̓R�����g���T���邱�Ƃ�]�ނƂ͗�����(�P�́P)
��E�Ǝv���Ȃ玩��ގU������H
���͏ؖ������������ɂ͕K���ًc�L���������̂ň������炸�B
�����ԍ��F15727984
![]() 5�_
5�_
�̂�ۂ�A���т��т��݂܂���B
>�����̌����������Ƃ��������A����ɂ̓R�����g���T���邱�Ƃ�]�ނƂ͗�����(�P�́P)
�Ƃ����˂����݂��~�G���W�j�A���炠��������A�Ƃ����킯�ł�����܂��A�̂�ۂ�͂��Ƃ���[15715306]��
>�Y��悤�ɂ��������Ȃ��������͕�����₷���Q�l�ɂȂ�܂��B
�Ƃ���������Ă���ȂǁA���������Ă�����e���̂Ɉ٘_���������Ȃ킯�ł͂Ȃ��A����ɉ�H�̕\���̗��V�Ȃǂɂ��āA�u��a���v���邢�́u�C�ɂȂ�v�Ƃ������b������Ă���A�Ǝ��͗������Ă��܂��B����͂�낵���ł��傤���H
���Ƃ��ẮA���������b�𑱂���͕̂s�тȂ̂Ŕ��������A�Ƃ����C�������ɕ\����������ł��B�_���̐������ȂǂɊւ�邨�b�ł���A������̌���ł͂���܂���B
�����ԍ��F15728252
![]() 4�_
4�_
������Ɗ��Ⴂ���Ă��܂����B
>i(s)=��2E×(��/(s^2+��^2))/( Rs + Ra + Rc )
�̂�ۂ�́A�d�����Ƃ��Ă܂����ԗ̈�� sin(��t) ��z�肵�āA��������v���X�ϊ������A�����āi�悭�킩��܂��jE�͎����l�Ƃ��闬�V�Ƃ������Ƃł��ˁBi(s)���������ł���̂Ɉ�a���͂���܂����A��������V�Ƃ���A�����Ƃ��ĊԈႢ�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
���́A�܂����v���X�ϊ��̈�i���g���̈�j�Ŏ��𗧂ĂĂ���A�K�v�Ȃ�C���p���X�Ƃ������g�Ƃ��̃X�e�B�~�����X���l���Asin �͖ʓ|�Ȃ̂� exp ���g���c�݂����ȗ��V�ł��B
���������V�̈Ⴂ�������ď����������܂������A���̒��x�̘b�Ǝ��͗������܂����B
�����ԍ��F15728517
![]() 3�_
3�_
����ɂ��́B
��������̐����肪�Ƃ��������܂��B���ꂪ�������ɂ����Ȃ���
���Ă��邩������܂���̂ŁA���̑����͉��߂��V�X���b�h��
�s���Ă����܂��B
�Ƃ肠�����A�A�L���t�F�[�Y����A�}�����c����͉�
���X�ɒ����Ă��܂��B���ɂ̓��b�N�X�A�f�m���A�I���L���[����
�ւ����₵�Ă���܂��̂ŁB
��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F15728910
![]() 3�_
3�_
IT5000HD(����� IT9000HD �� IT12000HD)�̎d�l���A
http://proaudiosales.hibino.co.jp/amcron/15.html
�Ō��Ă݂܂������A
�� �_���s���O�t�@�N�^�[�i20Hz�`100Hz�A8���j 5,000 �ȏ�
�Ə�����Ă��܂��ˁB
���ʏ����́u20Hz�`100Hz�v�͏d�v���Ǝv���܂��B����(�ƌ����Ă���������100Hz����)���g�������O���Ă���̂ŁA���̌���ꂽ�������ő������_���s���O�t�@�N�^�[�̒l�͍��߂ɏo�Ă���Ɨ\�z����܂��B
���Ȃ݂ɃI���L���[�� A-7VL �́A
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purecomponents/amplifier/a7vl/spec.htm
�� �_���s���O�t�@�N�^�[ 60�i1kHz�A8���j
�Ə�����Ă��āA100Hz �ɔ�ׂ��10�{�̎��g���ł̑���l�ł��ˁB
�����ԍ��F15729433
![]() 1�_
1�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�݂Ȃ��܁A�����́B
>���������Ă�����e���̂Ɉ٘_���������Ȃ킯�ł͂Ȃ��A
>����ɉ�H�̕\���̗��V�Ȃǂɂ��āA�u��a���v���邢��
>�u�C�ɂȂ�v�Ƃ������b������Ă���A�Ǝ��͗������Ă��܂��B
>����͂�낵���ł��傤���H
���̒ʂ�ł��B���ɂ͂��������ꂽ���͊Ȍ��ɕ�����₷�����Ƃ͊����܂������A���̐����ƂɋC�ɂȂ�_���������Ƃ��������A���̓_�ɂ��Ă��b����������ł��B�܂�����ȏ�ɁA���������ꂽ������̓I�ɂ͂ǂ̂悤�ȏ�������z��ɂ��l���Ȃ̂��A��萳�m�ȈӐ}��m�肽���Ƃ����C�������珑�����݂��܂����B�܂肨�������ꂽ���̋�̐������������݂͂�����������ł��B
>i(s)���������ł���̂Ɉ�a���͂���܂�
���������ʂ�Ai(s)��I(s)�ł��ˁB
�{�肩�炸�ꂽ�Ƃ��������̂ŁA���̂�����ŁB
�����ԍ��F15731880
![]() 3�_
3�_
�͂炽����P�O�O�O�_����
���Ƃ肠�����A�A�L���t�F�[�Y����A�}�����c����͉𑁁X�ɒ����Ă��܂��B
���}�ɁA���ʂ����\���Ă��������܂��H
���\����Ȃ��ƁA���낢��ȉ����ނƎv���܂��̂ŁB
���̃X���b�h�ŁA�I���L���[�ƃf�m���̂Q�Ђɂ��āA���[�J�[�̌�����₢���킹�ĕ����g�B��̃L�����N�^�[�h�Ƃ��āA���̃��[�J�[�̌����ɂ͋���������܂����A�Y��悤�ɂ��������Ȃ����A�u�A�L���t�F�[�Y�̃G���W�j�A�ɑ��āv�₢���������ʂ�m�肽���Ƃ����D��S������܂��̂ŁA���肢���܂��B
�����ԍ��F15744841
![]() 3�_
3�_
2013/02/10 19:04�i1�N�ȏ�O�j
��芸�����A�S���[�J�[���o�����Ă���̌��\���x�^�[���Ǝv���܂��B
�܂����Ƃ͎v���܂����A�������đ��Ђɕ킦�̉�����ƍ���܂�����ˁB
�����ԍ��F15744956
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́B
����ł͑��Ђ���i���ƃf�m���A�I���L���[�A���b�N�X����j�̉�
�����������痈�Ȃ��i�����_�܂��j�\��������܂��̂ŁA�Q�Ђ�
���ԓ������m�点���܂��ˁB
�����Ȃ��ēǂ݂ɂ����Ȃ��Ă���_�����邩�Ǝv���A�ʂɗ��ĂĂ����ق���
�悢���ȁA���Ċ����ł��̂Łu�c�e�l�ɂ��ćA�v�Ƃ��Ă݂܂��B
�����ԍ��F15745354
![]() 2�_
2�_
�v�����C���A���v > Nuforce > IA-7V3/SI [�V���o�[]
[15706037] http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15682249/#15706037
�̑��������̃X���b�h�ɏ����܂��B
���� Nuforce IA-7V3 �Ƃ����A���v�́A���[�J�[�ɂ��ƁA������f�W�^���A���v�ƌĂ����̂ł��邪�A�A�i���O�X�C�b�`���O�A���v�Ƃ����Ǝ��̕����ł���A�Ƃ������������悤�ȕ�����Ȃ��悤�Ȑ����ɂȂ��Ă��܂��B
���[�J�[�T�C�g�́A
http://www.nuforce.jp/highend/products/ia7v3_01.html
http://www.nuforce.jp/highend/technologies.html
http://www.nuforce.jp/highend/caution.html
����������Ă݂܂������A�����ɍs���l�܂��Ă��܂��܂����B�ق��ɂȂɂ���͂Ȃ��ł��傤���H
![]() 0�_
0�_
����Ȃ���������c
���[�J�[���тɔ̔��㗝�X�Ɏ��₷�鎖��]�݂܂��B
�����ԍ��F15716633
![]() 5�_
5�_
�㗝�X�ɂԂ������������������킴�킴����肵�ĊO�x���߂�K�v�����ł����H
�����ԍ��F15717350
![]() 5�_
5�_
����ς�₵����@�t�t�t
�����ԍ��F15722742
![]() 2�_
2�_
�v�����C���A���v > MCINTOSH > MA7000
�g�́c�����́B�����Ƃ̋߂��̋i���X��MA7000����܂����B�N�y�̕��ŃX�s�[�J�[��B&W���ł����B�J���I�P�Ɏg�p���Ă܂����B
![]() 1�_
1�_
�Ȃ���ґ�Ȃ��Ƃ��낤!!!
�C�y�Ɋy����ł��������ƃI�[�i�[������Ă���悤�ł��ˁB
�����ԍ��F15650404
![]() 0�_
0�_
�Ȃ��ɂ܂��A����AMP�̃��r���[��N��������Ă��Ȃ��̂��낤�c
TRX-88PP �ŏ��i�����������Ă�
�u���������Ƀq�b�g���鏤�i�͌�����܂���ł����B�v�ƂȂ��Ă��܂��܂�
�N�`�R�~�f���ł�
���̃X�s�[�J�[�ł̎���X���P���̂�
���́A�I�[�f�B�I�̎����o�������Ȃ��A�F���g�p���Ă��鉹��E�����E��ʁE�𑜓x�E���X�̗p��Ǝ����̒��������@�̉��Ƃ܂��܂���v���Ȃ��̂ŁA�Q�l�ɂȂ�悤�ȕ��͂͏����܂���
�^��ǂ̌^�Ԗ��̉��̓����Ȃǂ��悭�킩��܂���i���̌�A���������܂������c�j����A���r���[�Ȃǂƌ������̂Ƃ͒������u���z���v�ƂȂ��Ă��܂��܂�
�����A����AMP�ɍ��ꍞ��ł��܂��܂����A�܂��A�N������������Ă��Ȃ��悤�ł��̂ŁA�������̎������X�������Ē��������Ǝv���܂�
�i���̑��̃X���Ɠ����l�Ȍ������X����܂������e�͉������j
�悾���āATriode / Goldmund�̎�����ɍs���Ă܂���܂���
���X�ْ����Ȃ���̏��߂Ă̎�����ł���
�i���Ȃ��Ȃ���X�܂ł̒ʏ�̎����s���Ă���܂����A������Ȃǂƌ������낵�����̂́c ����ĐH���邩���c(^_^;)�j
�ŏ���Triode�A����Goldmund�A�e�P����
�ł����A����AMP������̎��ԓ��ɂ͏Љ�݂̂ʼn��o���͂���܂���ł���
������I����ɊF������₱����CD���ꂽ��A�����������c
���͉����������Ă��Ȃ����� TRX-88PP �����ė~�����Ɛ\���o���Ƃ���A�����������Ē����܂���
�����ړ��Ăɗ����������ɉ��l�����炵���݂����ł�
�i�������肱����̕������Ԃ������Ȃ��Ă��܂��܂����R(^�B^)�m�j
�g������
CDP�FESOTERIC K-05
AMP�FTriode TRX-88PP
SP�FPIEGA CX70.2
ESOTERIC �� PIEGA �� Goldmund �̎������Ɏg�p���Ă������̂ł�
���̃A���v�i�g�������H�j�ƂĂ��ǂ������ł��I
�S�̓I�ɗ͋����A���݂�����A���₩�ȉ��c�A
�X�s�[�J�[����������ቹ�܂Ŋ��炩�Ɍq����A���y���ƂĂ��y�������������o���܂���
���b�N����A�N���V�b�N�AJAZZ�A�|�b�v�X�A�ǂ̃W�������������Ă��āu���y���ėǂ��ȁ`�I�v�Ǝv�킹�Ă���邻��ȂЂƎ����߂����܂���
����E�����E��ʁE�𑜓x�c�A��`�A���̕ӂ������Ȃ̂ł�
�\����܂���i���r���[�ɂ͂Ȃ�܂����ˁj
�Ƃɂ����A�y�����I�I�I�̈ꌾ
�r���� Goldmund �̃v��AMP���g�� TRX-88PP ���p���[AMP�Ƃ��Ď������܂���
���̉����ǂ���������悤�ɂȂ�A����ʼnf��Ƃ���������A�䎌�Ɍ��ʉ��≹�y���킳���Ă��䎌���ׂ�邱�Ƃ������f�悪�y���߂邩������Ȃ��Ɗ����܂���
�������A���̃v�����O���� TRX-88PP �P�̂ɖ߂����r�[�u���`�A����ς肱�������ǂ��ȁ`�I�v�Ɖ��߂Ċ���������ł�
���Ԃ��o���A�F�X��CD�i������CD�͎����Ă����̂�Y��܂����j����芷���Ē����Ă������A���̎����ɂ͂���AMP���������Ɛ[�݂ɂ͂܂��āc
���́A���̃A���v�𒆐S�ɃI�[�f�B�I�̑g�����̖ϑz���肪���̒������邮��Ɓc
���S�ɐ����Ă��܂��܂����i�g�����͂���ŗǂ��́c�H�j
�{�̂́A�傫���c�I�@����A�f�J�C�I�I
���͂���ȑ傫�ȃv�����C��AMP�͏��߂Č��܂������iW460mm × D430mm × H180mm�j�^�ォ�猩��Ɛ����`�ɋ߂��ł���
���b�N�ɓ���Ă����v���̖₢�ɂ́A�㕔��15�`20cm�ʁH�i���ۂɂ͎w���L���Ă���ʁc�j����Α��v�Ƃ̎�
�r���A�^��ǁiPower����KT88�j�̒�����Ɏ���������܂�����������M���Ƃ������������A�ق�̂�g�������x�ł���
�i���̕ӂ���������ƃ��r���[�ۂ��c�H�j
�g�[���R���g���[���iBASS / TREBLE�j���t���Ă�̂��ǂ��ł���
���ʂ������Ē������ɂ��ꂪ����Ɨǂ��̂ł͂ƍl���Ă���܂�
���͒[�q��PHONO�iMM�j���t���Ă���̂��܂��ǂ����ł��c
���ȃo�C�A�X�Ő^��nj������̃����e�t���[���^��Ǐ��S�҂ɂ͊������@�\���Ǝv���܂�
���̑��̎d�l��WEB�Ō������Ē����������ڂ����i�m���ȏ�j�ڂ��Ă���Ǝv���܂��̂Ŋ����������܂�
���̎��_�ł́A���ۂɓX�܂Ŕ�������鎞����9���̒����ł͂Ƃ̎��ł���
�{�i�I�ȃ��r���[�����҂��ꂽ�F�l�ɂ͐\����܂��A����Ȏ����������܂���
�ł��A����AMP�ɋ����������Ē��������́i����ȕ��͂ł͂��Ȃ������c�j���Ў������Ă݂ĉ�����
�F����̎����̊��z��r���[�����҂����Ă���܂�m(_ _)m
�������i�ǁj���肪�Ƃ��������܂���
�Ō�� �����͖{�� (^_^;)��
�A�[�g�N���[�ƌ���Shop�����blog�ɏЉ���ڂ��Ă��܂����̂ŁA�����N���Ă����܂�
http://artcrew.sblo.jp/article/57765361.html
![]() 4�_
4�_
���Ȃ��ɂ܂��A����AMP�̃��r���[��N��������Ă��Ȃ��̂��낤�c
�܂��N���������ĂȂ������Ǝv���܂���B
�n�C�G���h�I�[�f�B�I�V���[���C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[�ŁA�݂�Ȏ����o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�ʐ^�̃J�[�y�b�g������ƃm�W�}�ł����H
������������ł��ˁB
�l�I�ɂ́A�g���C�I�[�h��CD�v���C���[�@TRV-CD5SE�̕�������������܂����B
�����ԍ��F14989348
![]() 1�_
1�_
�\��Y����
������
���������肪�Ƃ��������܂�
> �ʐ^�̃J�[�y�b�g������ƃm�W�}�ł����H
�z�J�X�ł̎�����ł���
����ς�p�ɂɎ������Ă�����͕���̂ł���
> �l�I�ɂ́A�g���C�I�[�h��CD�v���C���[�@TRV-CD5SE�̕�������������܂����B
Triode��14�F00�`15�F00
amp�FTRX-M300
TRV-P845SE
player�FTRV-CD5SE
TRV-DAC1.0SE
sp�FB&W 802 Series Diamond
Goldmund��15�F30�`16�F30
PreAMP�F�c�H
PowerAMP�F�c�H × 2 (^_^;) m(_ _)m
�̍\���ł������A�o���Ƃ��S�n�悢���y�ɏ������������ł�
���̌�̎���^�C�����I����A����AMP�Ɏ��Ԃ������Ē����܂���
�C���t������c19�F00���߂��Ă���܂���(^_^;)
���̂�������͖��C�Ȃlj����ւ��c
����̃n�C�G���h�I�[�f�B�I�V���[�A���W�A�C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[�ւ͍s���Ă݂����Ǝv���܂�
��������A�܂����̌��ł��c�I
���������� Goldmund �̓C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[�ɏo���Ȃ������ł�
�В����A�V����Goldmund Japan�ɂȂ����̂łQ�N�o���Ȃ��Əo���Ȃ��悤�Ȏ������Ă��܂���
����ʼn��W�̕��֏o�W���邻���ł�
�����ԍ��F14989514
![]() 1�_
1�_
���z�J�X�ł̎�����ł���
������ς�p�ɂɎ������Ă�����͕���̂ł���
���͉��l�X�ō��T���s���Ă��܂��B
CD�v���C���[�̌��ɁA�Ȃ��SOUL NOTE��TRIGON�������Ă����̂����R��������܂����B
���Ȃ�ʎ���u�����h������A�Ȃ�Œm���Ă��邩�Ǝv���Ă��܂����B
�ł�TRIGON�͈ꎞ���X�܂œW�����Ă����炵���Ƃ͕������̂ł����A���܂�������ēW���@����������b���܂����ǂˁB
������ʼn��W�̕��֏o�W���邻���ł�
���W�o�W����̂ł����B
���W�́A�Ίۓd�C��e���I���Aon and on�Ŏ�������J�Â��܂�����A�������̕����ʔ��������m��܂����B
�����ԍ��F14989543
![]() 1�_
1�_
> ���͉��l�X�ō��T���s���Ă��܂��B
PRIMARE�̃A���v�ł����H
���r���[�₲���z��UP���y���݂ɂ��Ă���܂�
> CD�v���C���[�̌��ɁA�Ȃ��SOUL NOTE��TRIGON�������Ă����̂����R��������܂����B
> ���Ȃ�ʎ���u�����h������A�Ȃ�Œm���Ă��邩�Ǝv���Ă��܂����B
SOUL NOTE�͍ŏ���DYNAMIC AUDIO�Œ����܂���
�́X�ADYNAMIC AUDIO�����H�̔��Α��ɓX�܂��\���Ă������ɗ��p���Ă��̂ł����A�ƌ����Ă��������ċÂ��Ă����킯�ł������̂ŁA���͖{���ɉ�������������Ȃ���Ԃł�
�̂��������ɂ��X�������ďł��ĒT���Ă��܂�����������܂������� (T_T)
> �ł�TRIGON�͈ꎞ���X�܂œW�����Ă����炵���Ƃ͕������̂ł����A���܂�������ēW���@����������b���܂����ǂˁB
�����Ȃ̂ł����H
�l�b�g�ł̃I�[�i�[����B�̂����z�����āA�S�ʓI�Ɍ��C�ȉ��炵���Ǝv�����̂Ō��ɓ��ꂽ�̂ł��c
���̏ꍇ�́A�I�[�f�B�I�W�̋L�����ڂ��Ă���blog����̒m�����w�ǂȂ̂ŁA���ł������̏�Ԃł�
���Ɠ��ɓ��ꂽ���Ƃ��q�����Ă��Ȃ��̂��߂������ł�
���ƁA���ɈӖ��͖����̂ł����A�������O�������̖������[�J�[����ɋ������킢�đI��ł��鏊������܂�
����̎�����ɍs�����̂��^�̐s���c�I
���₢��A�I�[�f�B�I�̊y������m�鎖���o�����c�I�̂ŗǂ������Ƃ��Ă����܂�
���Ƃ́A���܂�̂߂荞�܂Ȃ��l�ɏ��������Ԃ������Ď��������čs�������Ƃ������܂��i�������ȁ`�I�H�j
> ���W�́A�Ίۓd�C��e���I���Aon and on�Ŏ�������J�Â��܂�����A�������̕����ʔ��������m��܂����B
on and on���ĐV�x���ł����H�A�L�o����͌��\����������悤�ł���
�i����Ƃ��A�L�o���ӂɏꏊ�ł����̂ł��傤���H�j
�Ȃ��y�������Ȃ̂ŁAShop����̎�������s���Ă݂܂�
��肪�Ƃ��������܂���
�����ԍ��F14989708
![]() 0�_
0�_
��on and on���ĐV�x���ł����H�A�L�o����͌��\����������悤�ł���
�A�L�o�����ł͂Ȃ��L�y���̃P���E�b�h�r�N�^�[�̃V���[���[���ŃE�b�h�R�[���R���|�̎��������܂���B
���N�́Aon and on�ŃI�N�^�[���̃t�H�m�C�R��LINN LP12�Ń��R�[�h���������܂����������ǂ������ł����A�e���I������ł̓��b�N�X38�Z�p���[�g�ƃI�N�^�[��V80�Ő^��ǃA���v������ȂNJy���߂܂����B
�^��ǃI�[�f�B�I�t�F�A���y���߂邩���m��܂���B
http://kankyuu-fair.com/
���상�C�������m��܂����̂������Ń��A�Ȑ^��ǂ���ɓ���Ǝv���܂��B
�܂��A���͑吷���ł��Ȃ�̔M�C�ɕ�܂�l�������̂ł����A�^��ǂ̔M�������ꂪ�Ȃ��ĘU���ď���������������܂���(�j
���N�̖͗l�ł����A���i�����_�����|�[�g���Ă���Ă܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13604739/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%90%5E%8B%F3%8A%C7%83I%81%5B%83f%83B%83I%83t%83F%83A
�����ԍ��F14991901
![]() 1�_
1�_
�\��Y����
������
> �A�L�o�����ł͂Ȃ��L�y���̃P���E�b�h�r�N�^�[�̃V���[���[���ŃE�b�h�R�[���R���|�̎��������܂���B
> ���N�́Aon and on�ŃI�N�^�[���̃t�H�m�C�R��LINN LP12�Ń��R�[�h���������܂����������ǂ������ł���
> �e���I������ł̓��b�N�X38�Z�p���[�g�ƃI�N�^�[��V80�Ő^��ǃA���v������ȂNJy���߂܂����B
�I�[�f�B�I�D���̐l�B�ɂƂ��āA10�`11���͖Z�������y�������ԂȂ̂ł���
> �^��ǃI�[�f�B�I�t�F�A���y���߂邩���m��܂���B
> ���상�C�������m��܂����̂������Ń��A�Ȑ^��ǂ���ɓ���Ǝv���܂��B
> �܂��A���͑吷���ł��Ȃ�̔M�C�ɕ�܂�l�������̂ł����A�^��ǂ̔M�������ꂪ�Ȃ��ĘU���ď���������������܂���(�j
> ���N�̖͗l�ł����A���i�����_�����|�[�g���Ă���Ă܂��B
���|�[�g���ǂ܂��Ē����܂���
����A���܂��܂��̐^��ǂ̃A���v�̉��ɍ��ꍞ��ł��܂����̂ł����c�Ȃ��y�������ŗǂ��ł��ˁI
�������s���Ă݂����ł�
�o���邾���A�����̏ꏊ�������Ď��������b���Ȃ���A�y����ł݂����Ǝv���܂�
�\��Y����͑����̏����������ŁI
���́A�n�C�G���h�V���[�ƃC���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[�ʂ����m��܂���ł���
�܂��܂��A���肪�Ƃ��������܂���
�����ԍ��F14992583
![]() 0�_
0�_
Rock&Blues����A����ɂ��́B
>����E�����E��ʁE�𑜓x�c�A��`�A���̕ӂ������Ȃ̂ł�
>�\����܂���i���r���[�ɂ͂Ȃ�܂����ˁj
���r���[�ɂ͐l���ꂼ��X�^�C��������܂�����A�`�ɂƂ��ꂸ�ARock&Blues���������ɂȂ������Ƃ����̂܂܂������ɂȂ�����Ǝv���܂���B���̂ق����l�̃}�l�łȂ��I���W�i���e�B���o�܂����A�����͂�����܂���B�ׂ������Ƃ͋C�ɂ����A�܂������Ă݂܂��傤�I�@�ł͂ł́B
�����ԍ��F14998437
![]() 2�_
2�_
Dyna-udia����
������
Dyna-udia�����blog��ǂ��q�����Ă���܂�
Soulnote�̉��������Ǝv�������������́ADyna-udia�����blog����ł���
����ȕ��ɐl�ɑ��̐l�ɓ`����ꂽ��ǂ��̂Ɂc
�Ǝv���̂ł����A�����̌��t�ɂ��邾���ł����Ȃ��킵�Ă��܂�
�Ȃ̂ŁA��A�̊F����͐����ȂƉ��������S���Ĕq�����Ă���܂�
�������A���S���邾���łȂ��A�傢�ɎQ�l�ɂ����Ē����Ă��܂�
�������A�l�ɓ`����͓̂���ł���
���ꂩ��A�����Ȃ�ɗǂ��ȂƎv����������肭�`������l�ɁA�Ȃ�Ƃ������Ă������Ǝv���܂�
�������̃X���Ō������܂������낵�����肢�v���܂�
���肪�Ƃ��������܂�
�����ԍ��F15001198
![]() 0�_
0�_
ROCK & BLUES����B�����V���i�Ƃ͂����A�Ȃ����R�~�A���r���[���Ȃ��̂��낤�Ǝv���Ă��܂����BR��B����́A���y���̂��y�����Ȃ����Ƃ̃R�����g�ŁA�^��ǃA���v���������Ă���i���Ƃ����āA�C�O�̍����ȃZ�p���[�g�A���v�͍��������邵�A�Ȃ��������̂������j�g�Ƃ��Ă͑傢�ɎQ�l�ɂȂ�܂����BSPEC���ǂ��A���A���悪�]�X�Ƃ������͓I��
���r���[���Ȃɂ��u�y�����Ȃ����v�Ƃ��������z�͋M�d�ł��B���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F15610449
![]() 1�_
1�_
chounan����
�����炱���A���肪�Ƃ��������܂�
���Q�l�ɂȂ����ȂǂƖܑ̂Ȃ������t�܂Œ�����ϋ��k���Ă���܂�
��̂̍��Y���[�J�[�̗����I�[�f�B�I�����ẮA��肠�����͂���Łc��
�����ւ��Ă��������ł��̂ŁA�傻���Ȏ��������܂���
���̎�����̎��Ɂu�y�������y����v��̌��ł����̂͂Ƃ��Ă��K���Ȏ��������̂�������܂���
�����͐�̒� PIEGA �� Premium1.2 �� 5.2 ���ɍs���Ă��܂���
�o���Ƃ��ALINN �̃l�b�g�I�[�f�B�I�H�i�^�Ԃ́H�H�j�Ƃ̑g�ݍ��킹
Premium1.2 �̕��������̍D�݂̉��ɋ߂������ł�
���� SP �� TRX-88PP ���Ƃǂ�ȉ����o���Ă���邩�ƁA�ϑz���Ȃ���ł̎����ł���
����AMP���Ƃ����ƌ���̉��ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă���܂����A���ۂɑg�ݍ��킹�Ȃ��ƕ���Ȃ������������S�҂̔߂����Ƃ���ł�
�R�����g���肪�Ƃ��������܂�
�����ɂĎ���v���܂���
�����ԍ��F15619591
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > DENON > PMA-2000AE
blackbird1212���Q�Ƃ��ꂽ�X���ł́A���̎��ۂ��N�����A���v�̋@�킪 PMA-2000AE �ł����������Ȃ̂ŁA�f�����ł̏�L��ړI�Ƃ��āA���̃A���v�̋@��̃J�e�S���[�ɓ��e�����Ă��������܂��B�����Ă��̃J�e�S���[��I�Ȃ��Ƃ����K�R�����Ȃ��̂ŁB
���Ȃ݂Ƀ��[�J�[�z�[���y�[�W�̂��̋@��̃y�[�W�ł��B
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=382c2279-a153-4d3c-b8fa-81b930454f67&SubId=479b4983-5474-41c6-a7ff-3daba39918c0&ProductId=7819bca4-bd34-41ad-906a-167dec0b48d8
�����ɂ́u�V���O���v�b�V���v����H�v�Ƃ����L�q������܂��B����قǓ���ł͂Ȃ���H���Ǝv���܂��B
��p�@�ɂȂ�܂��� PMA-2000SE �Ȃ�A�����ȒP�ȃu���b�N�_�C�A�O�����������Ă���܂��ˁB
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?CatId=382c2279-a153-4d3c-b8fa-81b930454f67&SubId=479b4983-5474-41c6-a7ff-3daba39918c0&ProductId=b014a732-1437-40fc-8581-adbca35bfe75
![]() 1�_
1�_
blackbird1212����ɂ��́B
�v�����ʂ̂��Љ�肪�Ƃ��������܂��B���̌��ʂ̒��́u680mV�v�Ƃ��������Ɓu30mV�v�Ƃ�����������v�Z����ƁA���̃m�C�Y�́ACD���Đ��������ɔ�ׂĖ� -27dB �Ƃ����傫���ɂȂ�܂��Bblackbird1212�������ꂽ�m�C�Y�̑傫�������ꂮ�炢�̑傫�����Ǝv���Ă���Ƃ������Ƃł����H���͂���͑傫������l���Ǝv���܂��B���̊��Ŏ����������m�C�Y�̉��́A�ȑO���猾���Ă���悤�ɁA�X�s�[�J�[�Ɏ����߂Â��Ă���ƕ������鏬���ȉ��ł��B
���������āA���� -27dB �Ƃ����l���������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ́A���̎Z�o�̌��ƂȂ�u680mV�v�Ƃ��������Ɓu30mV�v�Ƃ����������������Ȃ����Ƃ��l�����܂��B���邢�́Ablackbird1212����̊��ł͖{���ɂ��������傫�ȃm�C�Y���o�Ă���̂�������܂��A�ȑO���猾���Ă���悤�ɁAblackbird1212����̃A���v�ƃX�s�[�J�[�ł͂ǂ�ȉ����������Ă���̂��͎��͒m����@���Ȃ��̂ŕ�����܂���B
�����ԍ��F15532917
![]() 1�_
1�_
������A�����́B
���������X���𗧂ĂāA���Ԏ������������Ă���̂ł��������܂��B
�����ɑ��Ėϑz�œ������Ă��A���ꎩ�̂��łɋZ�p�҂̑ԓx�ł͂���܂���B
�d�C�W�̋Z�p�҂Ȃ�A�܂����Ɏ��g�Ōv�����Ċm�F���܂��B
����́A�����P�Ƀf�W�^���}���`���[�^�[�i�f�W�^���e�X�^�[�j�Ōv�������l�ł��B
�P���Șb�ł��B
�X�s�[�J�[�[�q��mV�P�ʂ̌𗬂��v���ł���e�X�^�[�Ȃ���Ȃ��A
�������ł������̃V�X�e���̐��l���v�����Ă��������B
���������猾�t�Ŕ��_���悤�Ƃ��A�N�ł����ׂ邱�Ƃ̏o����P���Ȏ����Ȃ̂ł��B
���̐��l�́A�A���v��X�s�[�J�[�̏ɂ���ĕς��܂��B
�ł�����A���̌v���l�ׂ��Ƃ���ňӖ�������܂���B
���Ȃ̂́A
�E�������ɂ́A�ق�0V�ł��邱�ƁB�i�܂莨�ɕ�������悤�ȃz���C�g�m�C�Y�͏o�Ă��Ȃ��j
�E�������������ΐ��\mV�̐��l��\�����邱�ƁB�i�܂艹���o�遁�d�����������邱�Ɓj
�E�ʏ�̉��y�Đ�������A1V�O��̐��l��\�����邱�ƁB�i�܂�v���V�X�e���͐���j
�Ƃ���3�_���m���߂��邱�Ƃł��B
�悤����ɁA�����咣���Ă���悤�ȁA
�A�����ĉ��̏o�Ă���z���C�g�m�C�Y���������Ă���A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�z���C�g�m�C�Y���o�����Ă���̂Ȃ�A�������ł��d���͕\�������킯�ł�����B
����Ȃ��Ƃ́A�I�[�f�B�I�A���v���g���Ă���A�N�ł��o�����邱�Ƃł��B
��������A���v�̓d�����Y��āA�X�s�[�J�[�R�[�h���Ȃ��ւ��悤�Ƃ��āA
�G�����特���o���̂Ńr�b�N�������A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��B
����Ӗ��A�펯�I�Ȗ��ŗL��A�A���v�̉�H���킩���Ă���̂Ȃ�A
�z���C�g�m�C�Y���������Ă���ȂǂƂ����f�^�����͎v���������܂���B
����ȃf�^�������v�������Ƃ����A�d�C��H�̒m���̂Ȃ��؋��ł��B
������̂Ƃ���ł͉��������������ł����A����̓��C���A���v�̑����������������A
�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X���������A�\�����Ⴂ���A�l�b�g���[�N�̉e�����A�Ƃ��ł��傤�B
����Ȃ��Ƃ̍l�@���o���Ȃ��̂��A�d�C��H�̒m�����Ȃ�����ł��B
�����A������Ԉ���ăX�s�[�J�[���̂͂���ł�����A
�莝���̈�Ԉ����t�������W�X�s�[�J�[���g���Ă��܂��B
�l�b�g���[�N���Ȃ������ł�����A���͂�����Əo��̂�������܂���B
�ł��A�{���I�ȈႢ�͂���܂���B
�������������ΐڐG�m�C�Y�ʼn����o��̂ł��B
�������ꂾ���Ȃ̂ɁA�d�C�̑f�l�ł͂Ȃ��ƍ��ꂷ��l���A
����ȒP���Ȃ��Ƃ𗝉��ł��Ȃ��A�Ƃ����������������̂ł��B
����ȏ���邱�Ƃ͂���܂���B
���ۂɌv��ΒN�ɂł��킩�邱�ƂŁA���̎����͗h�邬�悤���Ȃ����Ƃł�����A
��z���_�Ŕ��_���邱�Ƃ͖����ł��B
�����ԍ��F15534596
![]() 8�_
8�_
2012/12/27 12:31�i1�N�ȏ�O�j
�E�ʎ���
�{�����[���K��
�ڑ��Đ��@��I�t��ԂŁA�A���v�̂ݓd���I���ŌÂ��K�������������{�����[�����O���O���ƃX�s�[�J�[���琷��Ƀo���o��������������̂͂悭�m��ꂽ�b�B
�E���錟��
�X�s�[�J�[�Z�p���[�g�^�e���r�i�X�s�[�J�[�P�[�u���Őڑ��j�̓d�������A�@�햢�ڑ��̊O�����͒[�q��I���B
���̏�ԂŃX�s�[�J�[���̃P�[�u���[�q�̃P�[�u������������ƃK�T�K�T�m�C�Y�������B
�ȏ�͎����I�����B
�r�����ɑ��Ėϑz�œ������Ăं��ꎩ�̂��łɋZ�p�҂̑ԓx�ł͂���܂���
�S�������ł��B
�ϑz���i�����Ȃ�Ή����ł��肢���܂�(�P�́P)
�����ԍ��F15535582
![]() 5�_
5�_
blackbird1212����ɂ��́B
�܂��A����A�b��ɂ̂ڂ��Ă��鉹��2��ނ���܂��B�ЂƂ�blackbird1212����blackbird1212����̃A���v�ƃX�s�[�J�[�̊��ŕ����ꂽ���A�����ЂƂ͎������̊��ŕ��������ł��B
�z���C�g�m�C�Y�]�X�́A�������̊��ŕ���������������邽�߂̂��̂ł��Bblackbird1212����̊��̉��ځA����������̂ł͂���܂���B�ȑO���猾���Ă���悤�ɁA����blackbird1212����̊��̉���m����@���Ȃ��̂ŁA�ސ��ɂ��A���̊��ŕ������鉹�Ɠ������̂�blackbird1212����̊��ł����Ă���̂ł͂Ȃ��ł����A�Ɗm�F���������ł��B���̐������ꂽ���blackbird1212�������ے肳���̂ł���A�������ł͂Ȃ��̂ł��傤�B
�b���͂����肳���邽�߂ɁA�����ň�U�A�ׂ�������āAblackbird1212����Ɋm�F�����Ă��������܂����A���̃z���C�g�m�C�Y�̐����ł́A�S�\�S�\�A�J�T�J�T�A�Ƃ��������̉����A�X�s�[�J�[�Ɏ����߂Â��Ă���ƕ������鏬���ȉ�(����� -27dB ���͂����Ə����ȉ��ł�)�Ƃ��ĕ������邱�Ƃ�blackbird1212����͔ے肳���̂ł����H
�����ԍ��F15536852
![]() 4�_
4�_
������A�����́B
���łɁA�r�����������@�q��������������������Ă����������̂ŁA
����3��ނɑ����Ă��܂��B
����3��ނ̉��́A
�d���̓������A���v�ɂȂ��ꂽ�X�s�[�J�[�̃P�[�u����Б������O���A
�X�s�[�J�[�[�q�ɐڐG������A�Ƃ��������s�ׂɂ���Ĕ����������̂ł��B
�܂�A�����s�ׂɂ���Ĕ����������ł�����A��{�I�ɂ͓������̂ł��B
���̔������闝�R�������ŁA�ڐG�m�C�Y�����ƂȂ��Ă��܂��B
>�X�s�[�J�[�Ɏ����߂Â��Ă���ƕ������鏬���ȉ��Ƃ��ĕ������邱�Ƃ�
>blackbird1212����͔ے肳���̂ł����H
�������A�ے�Ȃǂ��Ă��܂��H
���̑召�́A�A���v��X�s�[�J�[�̊��ɂ���ĕς�邱�Ƃ͂��łɏ����Ă���܂��B
���ꂼ��̊��ňႤ�`�Ŏ��ɂ��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�ł�����A���ɕ������鉹�ł͔��f������悤�̂ŁA�d���𑪂��Ă��܂��B
�܂�A�b�͂��łɉ��ł͂Ȃ��A�v���ł���d���̘b�ɂȂ��Ă��܂��B
�������łɓd������Ă���̂ł�����A��������v�������d���Œ��Ă��������B
�d���𑪂�͂����肷�邱�Ƃł��B
���������A����-27dB�Ƃ��������́A���̒����d�����犷�Z�������̂ł��傤�B
������A���̈Ⴄ���ۂ̉��Ɣ�ׂ�͖̂��Ӗ��ł��B
���Ȃ݂ɁA���������ŕʂ̃X�s�[�J�[��CD�𗬂��A1.4V���炢�̐��l���\������܂��B
�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�������Ⴄ����ł��B
�ł���d���́A�X�s�[�J�[��ς��������ł��ς���Ă��܂��܂����A
���ɕ������鉹���A���낢��ƕς���Ă��܂��܂��B
�ł�����A�ʂ̊��Ŏ��ɕ������������ׂ邱�ƂɈӖ��͂���܂���B
�ʏ�̌v���Ȃ�A�_�~�[��R���Ȃ��đ��肷��̂ʼn��Ȃo�܂����B
����Ȃ��ƁA�d�C�̒m��������Γ�����O�̂��Ƃł���B
�ēx�����܂����A�d�C��H�̒m��������A
>�z���C�g�m�C�Y�]�X�́A�������̊��ŕ���������������邽�߂̂��̂ł�
����ȃf�^�����Ȑ����͎v���������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�ϑz�ś���������ׂ�O�ɁA�d���𑪂��Ă��������B
���ꂪ���ׂĂł��B
�����ԍ��F15537372
![]() 5�_
5�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�u�X�s�[�J�[�P�[�u���̂��O���ʼn����d����炪�o�܂����v���x�̎����ł���A�d�C��H�̒m���̂Ȃ����w���ł��ł���ł��傤�B���͂��̃��J�j�Y���ł��B
blackbird1212����ɂ��Ă����������ł��Ă͂��Ȃ��̂ł�����A��L�������Ȃ��Ă������ɓd�C��H�̒m���������đ��̒N���ɂ͂��ꂪ�Ȃ��A�Ȃǂƌ��̂͘_�����߂��Ⴍ����ł��邱�ƂɋC�Â��܂��傤�B���M�����Ղ�Ɍ���Ă�����blackbird1212����ɂ��Ă��A[15471171]��
>�{���Ƃ������́A�[�q�̂Ԃ������Ռ����ŁA���̐U�����{�[�q����NFB��H��ʂ��ď��i�ɖ߂�A
��������ăX�s�[�J�[����o�͂��ꂽ���̂ł��B
�Ƃ����A�i�����v���ɂ́j�����������j�[�N�ȉ������q�ׂĂ���������ɂ����܂���B
�����������X�̖��́A�u�I�[�f�B�I�̃V���[�g�I�H�ɂ��āv�̃X���ŕ��ꂽ���̂̌����͂Ȃɂ��A�Ƃ������Ƃł��B�����ׂ̏�ԂŃX�s�[�J�[�P�[�u���̂��O�������Ă킸���ȉ����d�����o���Ƃ������ۂ���A�X�s�[�J�[���ڑ����ꂽ��C���s�[�_���X�̏�ԂʼnΉԂƏł��Ղ����悤�ȑ�d�������ꂽ�ƌ��_����̂́A����肷���ł��B
�Ȃ��A�X�s�[�J�[�P�[�u���̂��O�������͏�q�̂悤�Ɍ���ł͈Ӗ����s���ł����A�����{�ʂŎ������Ă݂��Ƃ���A���̊��Œʏ풮���Ă��鉹�ʂł͉��͕������܂���ł����i�X�s�[�J�[���傫���̂ŁA���O�������Ȃ���c�C�[�^�[�ɂ҂����莨�Ă邱�Ƃ��ł��܂��j�B
�����A�A���v�̃{�����[����ڂ����ς��グ��ƃm�C�Y���������܂��̂ŁA���̏�ԂŃX�s�[�J�[�P�[�u���̂��O����������������������肵�Ă݂܂����B���̏ꍇ���ڐG�����u�Ԃɓ��ʂȉ�����������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�ڐG���Ă���m�C�Y���������A�ڐG���Ă��Ȃ���Ε������Ȃ��A�Ƃ����ł����B�܂�A������̊ϑ����ʂƂ����ނ˓����ł��B���R�ł����A�m�C�Y�͒ʏ퉹�ʂ�-27dB�ȂǂƂ����傫�ȃ��x���ł͂���܂���B
blackbird1212����̂����E�\���Ƃ͎v���܂��A�r�����������@�q������������̂����炷��ƁA�@��̃O���[�h�Ȃǂɂ��̂����m��܂���ˁB
�����ԍ��F15537927
![]() 3�_
3�_
2012/12/28 12:00�i1�N�ȏ�O�j
�d�C�m���̗L���]�X�͂��Ă����A�����b�̖���ւ��̓������E�E�E�E�E
�_�_
�E�X�s�[�J�[�܂ł̐M���o�H�̂ǂ����ŐڐG�m�C�Y������������A���ꂪ�����H����ăX�s�[�J�[��艹�Ƃ��čĐ������B
�E�Đ�����郌�x�����ʏ탌�x���ɑ債�Ăǂ̒��x���H
�{���I�ƌ�������������̂����Ȃ��̂��H
�萫�I�Șb�ƒ�ʓI�Șb�Ȗ�ł��B
���������̔��[�́A
�r��߰���[�q�Ʊ��߂�AUX�[�q�Ă����Ă��܂����߰���[�q��AUX�[�q����߰���[�q��AUX�[�q�c��̂悤�Ȕ��U��ԂɂȂ�ł����������ٷް�����܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��
�ł��傤�B
�d�C�I�m���ȑO�ɁA���̂悤�ȏ���������O��ɑ���l�@���d�v�ł��B
�r���߂̽�߰���[�q�����F��RCA����ف����POD?��̖{�́��Ԕ���RCA����ف����߂�AUX�[�q���ŏ��ɖ߂�
��������グ�����[�v���C���������ł��B
�f���M���Ɖ����M�����������Ă��ł�����B
���ł��L��ł��ˁB
���̋^��⒍�߂������A���̂悤�Ȃ��Ƃ𗅗�̂͑���f�Ǝw�E����Ă���̂ł��傤�B
���������Ƃ��āA
�u1.�ȸ�����ACײ݂Ɖ��F����ق�����?���Ă��褉��F����ٌo�R�Ž�߰���[�q�ɘR�d?
����͕|��(��o��)�v�����R�����g���܂����B
�����܂ł�����ł���A�u�V���[�g�v�Ȃ�L�[���[�h�ɂāA�Z���L�������؏o���鉺�n��p�ӂ��Ă��܂��B
������ɂ���AiPod���ڑ���Ԃ��V���ɔ���������ɁA�����̏C���Ȃ�P������Ď���҂̖������ɋ��͂��邱�ƂȂ��A�������قɍS�D���鎩�Ȓ��͏������݂��T����ׂ��ɂ͓Ó����ˁB
�����ԍ��F15539238
![]() 2�_
2�_
2012/12/28 12:20�i1�N�ȏ�O�j
��A�̓^���͌��ǂ����������Ƃł��B
�E���ɖ������`���X�p�ŃL�����L�������Ă���B
�E�ʂ肩�������a���K���Ȉē��ō���������B
�E�T��ŕ����Ă��O�삪�a����ɓ˂����ݓ����B
�E�a����ƊO��̏�O�������n�܂�`������u�v���C(�P�́P)
�ʓ|�����Ȃ�ŏ������˂����ނȁI���Ă��Ƃ���ˁB
�����ԍ��F15539273
![]() 6�_
6�_
�r�����������@�q������������A����ɂ��́B
>�����b�̖���ւ��̓������E�E�E�E�E
�����ł��ˁB
��������A
>���̐������ꂽ���blackbird1212�������ے肳���̂ł���A
>�������ł͂Ȃ��̂ł��傤�B
���̂悤�ȁA�����Ƃ��Ƃ�锭�����o�Ă��܂��̂ŁA�ȉ��ɂ܂Ƃ߂Ă����܂��B
�E�����̊T�v
�d���̓������A���v�ɂȂ��ꂽ�X�s�[�J�[�̃P�[�u����Б������O���A�X�s�[�J�[�[�q�ɐڐG������A���������
�E�����̌���
������A�r�����������@�q������������Ablackbird1212��3�l���ɁA
�X�s�[�J�[����K�T�S�\�Ƃ���������������̂��m�F����
�E�ł͂Ȃ����̉����o��̂��ɂ���
������̃z���C�g�m�C�Y��
>���������Ă���m�C�Y�Ƃ́A�O����������悤�Ɏc���m�C�Y�ł��B
>�A���v�̓d�������ă{�����[�����グ�Ă���A�X�s�[�J�[����o���ςȂ��̃m�C�Y�̂��Ƃł��B
>�z���C�g�m�C�Y�n�̃m�C�Y�́A�o���ςȂ��ł���Ί���Ă��܂��A
>�o�����Ă��Ă����݂��C�ɗ��߂Ȃ��Ȃ�܂��B
>������X�s�[�J�[�P�[�u����t���O�����邱�ƂŁA
>���̎c���m�C�Y���X�s�[�J�[����o����o�Ȃ������肷��̂ŁA
>�C�ɗ��߂�悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
�z���C�g�m�C�Y���ɑ���l�@
���̐��Ȃ�A�z���C�g�m�C�Y�͏�ɏo�Ă��邱�ƂɂȂ�̂ŁA
�����o���Ă��Ȃ���ԂŃX�s�[�J�[�[�q�̓d���𑪂�A������̓d�����ϑ�����A
���̓d���́A�X�s�[�J�[�[�q�ɃP�[�u����ڐG�A����������s�����Ƃ��ł��A
��������m�C�Y�ɊW�Ȃ��A�����͂��ł���B
blackbird1212�ɂ���������
��������0.2mV
�X�s�[�J�[�P�[�u���ڐG�A�����������10mV�`30mV
�������ɂ͂قڃ[���{���g�ŗL��A
�X�s�[�J�[����m�C�Y����������ꍇ�́A10mV�ȏ�Ƃ������l�������Ă���̂ŁA
������̃z���C�g�m�C�Y���͊Ԉ���Ă���Ƃ������Ƃ��m�F�ł��܂����B
���̌o�܂���A������ɂ͓d���𑪂��Ċm�F���Ă��������Ɨv�]���Ă��܂��B
�Ƃ͂����Ă��A�d�C��I�[�f�B�I�̒m��������A�i�Ƃ������펯���x�����Ǝv�����j
���̂悤�ȍr�����m�ȃf�^�����ł���u�z���C�g�m�C�Y���v�Ȃǎv���������܂���B
�܂��Ă킩��Ȃ��Ƃ��u�d�C�ɂ��đf�l�ł͂Ȃ��v�Ƒ��l�Ɏ咣����̂ł���A
�d�����v��Ζ����ɓ������o�邱�Ƃ��炢�A�m���Ă��ē��R���������Ōv��ł��傤�B
����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ŁA��̂킩��Ȃ������咣����̂�������ł��B
�ł�����A�u�P�[�u���ʼn��͕ς�̂��ς�Ȃ��̂��H�v�X���ɂ����āA
gggW�����[15427030]�u���͑f�l�ɕ�����₷����������p�������܂���v�ɑ���
�������[15427230]�u���͑f�l�ł͂Ȃ��̂Łv�ƕԂ�����������
�u�d�C�W�i�v���W�Ȃ̂��H�j�̌��l�ł���v�Ǝ咣�����Ɨ������Ă��܂����A
���ꂪ�S���̃f�^�����ł���A�Ƃ������Ƃł��B
�܂�u������ɂ͓d�C��H�̒m�����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ͏ؖ����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�ł�����A�������ŗ����ł��Ȃ�����ɁA�ϑz�ō��グ���f�^�����𓊍e����̂�
�T�����炢�����ł����A�Ɛ\���グ�Ă���̂ł����˂��B
�����ԍ��F15540383
![]() 7�_
7�_
2012/12/28 21:06�i1�N�ȏ�O�j
�u���b�N�o�[�h���� ������
���āA�萫�I�ɂ͎c���u�T�[�v�m�C�Y�łȂ��̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
�Ռ����]�X�͎����悭������܂���E�E�E�E�E
�萫�I�ɐ��ΉԂ��������錏�ƁA�u�{���v�̒�ʓI���ʂ����m�c���ł��傤���B
�ȉ��A�I�[�f�B�I�ɑS�����W�Ȏ��̑̌��B
���������ނ̓d��������ׂ��A�d���P�[�u���̒��Ԃɐ݂�������܃X�C�b�`������A�X�C�b�`���I���ɂ����u�ԁA�u�{���b�v�ƌ������Ɛ����ΉԂł͂Ȃ��l���݂����Ȃ������܂����B
�������͎��̏��Ɉ���������܃X�C�b�`�ł���A�M�����Ȃ���Ί��d�����܂���ł����B
�ܘ_�A���ɂ͉Ώ��Ղ�ł��Փ������܂���B
���Ȗڌ��҂��������܂����̂Ŏ��̔��������Ė�ł�����܂���B
������Ȃ番���邩������܂���ˁB
����Ȃ��Ƃ�������Ă��ƂŁB
�����ԍ��F15540866
![]() 2�_
2�_
blackbird1212����A�����́B
>>�����b�̖���ւ��̓������E�E�E�E�E
>�����ł��ˁB
blackbird1212����́u������ɂ͓d�C��H�̒m�����Ȃ��v�Ƃ����咣������Ă��܂��ˁB������͂���ɂ��Ă͘_�]���Ă��炸�A�ublackbird1212�������Ă�������͉Ȋw�I�ɂ͒t�قł���v�A�̂悤�Ȃ��Ƃ��咣���Ă��܂��B������u����ւ��̓����v�Ɗ����Ă���������̂����m��܂���ˁB
�������A�u������ɂ͓d�C��H�̒m�����Ȃ��v�Ƃ������ƂƁA�ublackbird1212����͓d�C��H�ɂ��đf�l�ł���v�Ƃ������ƂƂ́A�Ɨ��̎��ۂł��B
����܂Ŋm�F�ł������Ƃ́A���X���̎��̂Ɋւ���blackbird1212�������Ă�������ɂ��āA����܂ňȏ�̐����͂Ȃ��̂ŁA���̎咣�ɂ��Ă͐����������Ƃ������Ƃł��B
�����������������X��������̂ł�����A���̂̌����ɔ���c�_�͗L�v���Ǝv���܂��B�lj�����������܂�����A���҂����Ă���܂��B
�����ԍ��F15541339
![]() 3�_
3�_
blackbird1212����ɂ��́B
�� >�X�s�[�J�[�Ɏ����߂Â��Ă���ƕ������鏬���ȉ��Ƃ��ĕ������邱�Ƃ�
�� >blackbird1212����͔ے肳���̂ł����H
��
�� �������A�ے�Ȃǂ��Ă��܂��H
�� ���̑召�́A�A���v��X�s�[�J�[�̊��ɂ���ĕς�邱�Ƃ͂��łɏ����Ă���܂��B
�� ���ꂼ��̊��ňႤ�`�Ŏ��ɂ��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�Ƃ���������Ă��܂����A
�� �ēx�����܂����A�d�C��H�̒m��������A
�� >�z���C�g�m�C�Y�]�X�́A�������̊��ŕ���������������邽�߂̂��̂ł�
�� ����ȃf�^�����Ȑ����͎v���������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�Ƃ�����������Ă��܂��B
����2�͖������܂��H�m�C�Y���ǂ��Ƃ��d�����ǂ��Ƃ���_����O�ɁAblackbird1212���ǂ̂悤�Ș_���ł��̂悤�Ȏv�l������Ă���̂����͂����肳���邱�Ƃ��d�v���Ǝv���܂��̂ŁA�����Ŋm�F�����Ă��������܂��B�������Ă���̂��������Ă��Ȃ��̂��̌��������������������B
�����ԍ��F15543602
![]() 3�_
3�_
������A�����́B
�������Ă��܂���B
�ǂ����������Ă���̂ł����H
�����ԍ��F15544090
![]() 6�_
6�_
blackbird1212����ɂ��́B
blackbird1212����́A
�� >�X�s�[�J�[�Ɏ����߂Â��Ă���ƕ������鏬���ȉ��Ƃ��ĕ������邱�Ƃ�
�� >blackbird1212����͔ے肳���̂ł����H
��
�� �������A�ے�Ȃǂ��Ă��܂��H
�� ���̑召�́A�A���v��X�s�[�J�[�̊��ɂ���ĕς�邱�Ƃ͂��łɏ����Ă���܂��B
�� ���ꂼ��̊��ňႤ�`�Ŏ��ɂ��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�Ƃ���������Ă��āA�����ł͎��̓��e�����p����Ă��܂����A���̈��p�́A�������e�������̈ꕔ�����ł���H����͂����g�ŗ�������Ă��܂����H
�����Ablackbird1212����Ɋm�F�������Ƃ́A
�� ���̃z���C�g�m�C�Y�̐����ł́A�S�\�S�\�A�J�T�J�T�A�Ƃ��������̉����A�X�s�[�J�[�Ɏ����߂Â��Ă���ƕ������鏬���ȉ�(����� -27dB ���͂����Ə����ȉ��ł�)�Ƃ��ĕ������邱�Ƃ�blackbird1212����͔ے肳���̂ł����H
�ł���H�����ł�blackbird1212����͎��̃z���C�g�m�C�Y�̐�����ے肵�Ȃ��Ƃ���������Ă����ł���ˁH
���̈���ŁA
�� �ēx�����܂����A�d�C��H�̒m��������A
�� >�z���C�g�m�C�Y�]�X�́A�������̊��ŕ���������������邽�߂̂��̂ł�
�� ����ȃf�^�����Ȑ����͎v���������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�Ƃ�����������ł���ˁH�����ł�blackbird1212����͎��̃z���C�g�m�C�Y�]�X���f�^�����Ȑ����Ƃ���������Ă����ł���ˁH
blackbird1212����͂�����ƌ���Ȃ��̂ł����H
�����ԍ��F15544918
![]() 1�_
1�_
������A�����́B
�� >�X�s�[�J�[�Ɏ����߂Â��Ă���ƕ������鏬���ȉ��Ƃ��ĕ������邱�Ƃ�
�� >blackbird1212����͔ے肳���̂ł����H
������́A�X�s�[�J�[���特���������邱�Ƃ��m�F���Ă��܂���ˁB
�ł�����u�����������v�Ƃ������Ƃ͔ے肵�Ă��܂���B
�܂��A�������������Ƃɂ��ẮA�A���v��X�s�[�J�[�ɂ���ĕς��ł��傤�Ə����āA
�u���������������v�Ƃ������Ƃ��ے肵�Ă��܂���B
���̕����́A�����������Ƃ����u�����v�ł��B
�ł�����A����ɂ��Ĕے肷�闝�R������܂���B
[15479618]
>���̊��ł��A�S�\�S�\�A�J�T�J�T�A�Ƃ��������̉��͒������܂��B
�O�ɂ����̂悤�ɏ����Ă��܂��B
�� ���̃z���C�g�m�C�Y�̐����ł́A
���̕����́A������̍l�������_�i�z���j�ł����āA�u�����v�ł͂���܂���B
�ł��̂ŁA�u�����v�̕����Ɓu�z���v�̕����ɕ����ĉ��Ă���܂��B
�����āA�u�z���v�̕����́A�d���𑪂�Ƃ��������ɂ���Ĕے肵�Ă��܂��B
������̂Ƃ���ʼn����������̂́A�A���v�ƃX�s�[�J�[�̊����Ⴄ����ŁA
�����o�錴�����Ⴄ����ł͂���܂���B
�X�s�[�J�[�R�[�h�̕А����O���ăX�s�[�J�[�[�q�ɂ��������Ƃ����A
�����s�ׂ����ďo�����ł�����A�����o�闝�R�������ł��B
���ꂪ�ꏊ�ɂ���ĉ��̏o�錴��������Ă��܂��Ƃ�����A���ꂱ���I�J���g�ł��B
�u�P�[�u���ł͉����ς��Ȃ��h�v����D���ȁA�u�Ȋw�I�����v�i�d���𑪂�Ƃ����j�ɂ����
������́u�z���C�g�m�C�Y���v��ے肵�Ă��܂��B
�u�u���C���h�e�X�g�v�ɔ�ׂ�A��قNJm���Ȏ����ł��B
�z���C�g�m�C�Y���u������v�����������킯�ł͂���܂���B
���ɂ���ĉ��̑傫�����ς���Ă��邾���ŁA���̏o�錴���͓����ł��B
�z���C�g�m�C�Y�ł͂���܂���B
�Ȃ��A-27dB�ɂ��ẮA���̍������Ȃ����l�ł��̂Ŏg�p�͂�߂Ă��������B
������́A�������i�ǂ�ȉ��ʂʼn��y���Ă��邩���m��Ȃ����A
�����Ɏg���Ă���A���v���m��Ȃ����A
680mV�Ƃ������l���A�ǂ��CD�̂ǂ�ȋȂŕ\�����ꂽ�����m��܂���B
���������ACD�͌ʂɎ��^����Ă��鉹�̑傫�����Ⴂ�܂�����A
����CD�ɍ��킹�ă{�����[���͏㉺������̂����ʂł��B
���܂��܁A�傫�ȉ��̏o��CD���ʒu�Ƀ{�����[����ݒ肵�āA
���̏�����CD�����̂ŁA680mV�ƂȂ����Ƃ������Ƃ�������܂���B
�ł�����A-27dB�����特���傫���Ƃ������R�ɂ͂Ȃ�܂���B
�܂�A������̕��������Ɣ�r����͖̂����Ȃ̂ł��B
������܂��A�d�C��I�[�f�B�I�̒m��������Ώ펯�Ȃ̂ł��B
�X�s�[�J�[�́A���ꂼ��̐��i�ɂ���āAdB/m/w�̏o�͉������Ⴂ�܂���ˁB
�A���v���A���ꂼ��̐��i�ɂ���āA�o�͂���W�����Ⴂ�܂���ˁB
���̍������āA���̑召���ׂ邱�ƂɈӖ��͂���܂���B
�����ԍ��F15545217
![]() 5�_
5�_
���������Ȍ��ɓ�����Ȃ�A
> ���̃z���C�g�m�C�Y�̐����ł́A
���̕����́A������̏���ȑz���ł���Ԉ���Ă���̂Ŏ����Ŕے肵�Ă��܂�
>�S�\�S�\�A�J�T�J�T�A�Ƃ��������̉����A�X�s�[�J�[�Ɏ����߂Â��Ă���ƕ������鏬���ȉ�
���̕����͎���
>(����� -27dB ���͂����Ə����ȉ��ł�)
���̕����͎�����F������̂ŊԈႢ�ł�
>�Ƃ��ĕ������邱��
���̕����͎���
>��blackbird1212����͔ے肳���̂ł����H
���̕����͎��╶
�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���̂ŁA�S����ے���m����o���Ȃ��킯�ł��B
�ے肷��u������������v�Ƃ����������ے肵�Ă��܂����A
�m�肷��u�z���C�g�m�C�Y���v�Ƃ����ԈႢ���m�肵�Ă��܂����ƂɂȂ�B
������A�������ē����邵���Ȃ���ł����A�ǂ����Ԉ���Ă܂����H
�܂�u���̃z���C�g�m�C�Y�̐����ł́v�Ɓu�Ƃ��ĕ������邱�Ɓv�Ɉ��ʊW���Ȃ��̂ɁA
����Ɉ��ʊW������悤�ȍ\���ɂ��Ă�̂��Ԉ���Ă���Ƃ������ƁB
�����Ɛ��_�̔z�u���O��t�ŊԈႢ�ł�����B
�\���I�ɂ�
���́u�����v�́A���́u���_�v�Ő����ł��܂����A�����ے肷��̂ł����H
�Ƃ����̂����������ǁA������̂�
���́u���_�v�ł́A���́u�����v�ƂȂ�܂����A�����ے肷��̂ł����H
�ƂȂ��Ă��ŁA���͂��j�]���Ă���B
�����ԍ��F15545473
![]() 5�_
5�_
�r�����������@�q������������A�����́B
>�����ΉԂł͂Ȃ��l���݂����Ȃ������܂���
�ʔ����̌����������ł��ˁB
�����ɗ��R���l����Ȃ�A����܃X�C�b�`�̃X�C�b�`���ނɗӐ����g���Ă��āA
�����̗��R�ŗӂ��o�Ă��Ă��܂��āi���Ƃ��Ηΐƈꏏ�ɂƂ��j�A
���ꂪ�X�C�b�`ON�̃X�p�[�N�ŔR�����Ƃ��ł��傤���ˁB
���́A�ΉԁA���A������t�Z�I�ɗސ����邵���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����A���̃A���v��80W/8���A160W/4����ۏ��Ă��āA��C���s�[�_���X�ɋ����悤�Ȃ̂ŁA
���ʂ̃A���v�Ȃ�ی��H�����������ȏ�ʂł��A�d���������Ă��܂������ł��B
�����AC�����͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����炭USB�[�q��USB�Ή�AC�A�_�v�^���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F15545516
![]() 4�_
4�_
�d�C��H�̒m��������blackbird1212�����AC�����͂Ȃ��Ǝv���Ă���킯�ł��ˁB
�����ԍ��F15545572
![]() 1�_
1�_
������A�����́B
iPod�ɂ̓g�����X�Ƃ�AC100V�p�d����H�͂��ĂȂ�����A
��p�R�l�N�^��USB�[�q����p�\�R����AC�A�_�v�^�[���炵�����d�ł��Ȃ����ǁA
����Ȃ��Ƃ��m�炸�ɉ����Ă�킯�ł����H
iPod��AC100V������R�[�h�͑��݂��܂����˂��H
�����ԍ��F15545594
![]() 4�_
4�_
blackbird1212���ǂ̂悤�Ș_���Ŏv�l����Ă���̂�������ƕ�����܂����B�l�̎����blackbird1212�������g�̓��̒��ʼn��ς��āAblackbird1212����͂��̉��ς�������ɑ��ĉ��Ă���킯�ł��ˁB
���̉��ς̎d�����I���ł���A�l�̎����blackbird1212������ɏC��������t���������肷��Ύ��₵���l�͂����ɂ��������ƋC�Â��܂����A������I�ɍ���Ă���̂łȂ��Ȃ��l�ɋC�Â���ɂ����킯�ł��B
��̓I�ɂ́A�����O��w�E�����悤�ɁAblackbird1212����͎������e�������̈ꕔ���������p���Ă��āA���p���ꕔ�Ȃ����łȂ��Ablackbird1212����̓��̒��Ŏ�����ꕔ������āA����ɑ��ĉ��Ă��܂��B
�f���ɕ\������镶���Ƃ��ẮA����Ɉ��p���Z�߂ɂȂ��Ă��邾���Ɍ����Ă���̂ŁA�͂����猩���l�́u�����Ȃ�ƌ��Â炢����Z�߂Ɉ��p�����̂��ȁv���炢�Ɏv���Ă��܂��܂��B���p���A�l�̕��͂ɏ���ɏC��������t���������肷��A����͕s���Ȉ��p�ł��肨�������Ƃ����ɓ˂����܂��ł��傤���A������˂����܂�悤������܂���B
�܂����A���p��Z���������ƂƓ������Ƃ̒��ł�����Ă���̂��Ƃ́A�N���v��Ȃ��ł��傤�B1�̕��̈ꕔ�����ȊO�ɁA���������������ꍇ�ɁA���������Ă��̒��̕��̂��������̂Ă�悤�Ȃ��Ƃ�����݂����ł��B���p���Ă���A����Ďv�l���Ă��邱�Ƃ��܂����߂܂����A���p���Ă��Ȃ�����̎v�l�͂���ɕ�����ɂ����Ȃ�܂��B
���������F����������blackbird1212����̂����e��ǂ߂A�Ȃ�قǂȁA�Ǝv������̂���ł��B���ǁA�l�̎���ɖʂƌ������ē����ĂȂ��킯�ł�����A�b�����X�ƏI���Ȃ��̂ł��B
�����ԍ��F15548994
![]() 3�_
3�_
>���ǁA�l�̎���ɖʂƌ������ē����ĂȂ��킯�ł�����A
>�b�����X�ƏI���Ȃ��̂ł��B
������A���̌��t�͂������肻�̂܂܂�����ɂ��Ԃ����܂��B
���Ȃ������A�l�̕�������ɉ��߂��āA�����̓s���̗ǂ��悤�ɋȉ����Ă��܂����A
�l�ɒʂ���悤�ȓ��{�ꂪ�����Ă��܂���B
[15545473]�ʼn�������悤�ɁA������̓��{��͊Ԉ���Ă��܂��B
�܂Ƃ��ɕԎ��̏o���Ȃ�����������Ă����āA���̌��������͂Ȃ��ł��傤�B
����Ƃ��A�܂Ƃ��Ȏ��╶���Ǝv���Ă���̂ł����H
-27dB�̌����A[15545217]�ŏ������Ƃ���A������̏���ȉ��߂ŁA
����𗝗R�ɂ��ĉ��̑召���ׂ�̂͏Ύ~�疜�ł��B
���ꂪ�����ł��Ȃ��̂Ȃ�A������̓��{��lj�͂��Ⴂ�̂ł��傤�B
�܂Ƃ��Ȏ���������āA����ɔ��_���邱�Ƃ��o���Ȃ�����Ƃ����āA
��̂킩��Ȃ��������������Ă���Ƃ́A�������l�ł��ˁB
�����ԍ��F15549220
![]() 4�_
4�_
2012/12/30 23:16�i1�N�ȏ�O�j
�l�l�ɓ�ȕt����O�ɁA�r�����m�Ȓ����̎ߖ����悾��B
�r���߂̽�߰���[�q�����F��RCA����ف����POD?��̖{�́��Ԕ���RCA����ف����߂�AUX�[�q���ŏ��ɖ߂�
iPod�{�̓��ʼn����M���Ɖf���M�����~�b�N�X�_�E���H�����ȂA�d�C�m���ȑO�̂`�u�펯���猃������E�Ȃ�łȂ��́H(�P�́P)
�u���b�N�o�[�h����̃R�����g�Ɉꕪ�̌��������Ƃ͌���Ȃ����A�悸�͔������Ԓʂ�ɌȂ̃R�����g�̃P������̂��}�i�[���Ă��B
����ȊȒP�Ȃ��Ƃ���o���Ȃ��Ȃ�Ƃ��ƌf������ގU���ׂ����ˁB
�����ԍ��F15549345
![]() 4�_
4�_
blackbird1212����ɂ��́B
�� �ے肷��u������������v�Ƃ����������ے肵�Ă��܂����A
�� �m�肷��u�z���C�g�m�C�Y���v�Ƃ����ԈႢ���m�肵�Ă��܂����ƂɂȂ�B
�� ������A�������ē����邵���Ȃ���ł����A�ǂ����Ԉ���Ă܂����H
�ƁA���������Ƃ������Ƃ́Ablackbird1212����͎��̎w�E��F�߂Ă���킯�ł��ˁB���Ȃ킿�Ablackbird1212����͂����g�̓��̒��ŁA���̎�������ς��āA���̉��ς�������ɑ��ĉ��Ă����킯�ł��ˁB
blackbird1212����́A���̉��ςɐ�����������Ǝ咣����Ă���悤�ł����A���̍����� [15545473] ���������A
�� > ���̃z���C�g�m�C�Y�̐����ł́A
�� ���̕����́A������̏���ȑz���ł���Ԉ���Ă���̂Ŏ����Ŕے肵�Ă��܂�
�� >(����� -27dB ���͂����Ə����ȉ��ł�)
�� ���̕����͎�����F������̂ŊԈႢ�ł�
��2�_�����ł���ˁH
�Ƃ������Ƃ́A���ɂ���2�_�ɍ������Ȃ���Ablackbird1212����̉��ςɐ��������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B����͂�낵���ł����H
�����ԍ��F15549783
![]() 2�_
2�_
�����قǎ��́A
�� �ƁA���������Ƃ������Ƃ́Ablackbird1212����͎��̎w�E��F�߂Ă���킯�ł��ˁB���Ȃ킿�Ablackbird1212����͂����g�̓��̒��ŁA���̎�������ς��āA���̉��ς�������ɑ��ĉ��Ă����킯�ł��ˁB
�Ə����܂������A������ƊԈႦ�܂����B�߂������ɒ����������̂𓊍e���܂��B
�����ԍ��F15549838
![]() 2�_
2�_
�����������̂𓊍e���܂��B
blackbird1212����ɂ��́B
�� [15545473]�ʼn�������悤�ɁA������̓��{��͊Ԉ���Ă��܂��B
�� �܂Ƃ��ɕԎ��̏o���Ȃ�����������Ă����āA���̌��������͂Ȃ��ł��傤�B
�� ����Ƃ��A�܂Ƃ��Ȏ��╶���Ǝv���Ă���̂ł����H
���� [15545473] �������w�E�������ς𗠕t������̂ł��B�����ɂ́A
�� �ے肷��u������������v�Ƃ����������ے肵�Ă��܂����A
�� �m�肷��u�z���C�g�m�C�Y���v�Ƃ����ԈႢ���m�肵�Ă��܂����ƂɂȂ�B
�� ������A�������ē����邵���Ȃ���ł����A�ǂ����Ԉ���Ă܂����H
�ƁA������Ă���A�����Ƃ������̈��̉��ς����Ă��邱�Ƃ���������Ă��܂��B���Ȃ킿�Ablackbird1212����͂����g�̓��̒��ŁA���̎�������ς��āA���̉��ς�������ɑ��ĉ��Ă����킯�ł��ˁB
�Ȃ��A���ς̐������ɂ��ẮA�����قǏ��������̂����̂܂ܐ������܂��B
�����ԍ��F15549885
![]() 2�_
2�_
blackbird1212����ɂ��́B
blackbird1212�����ꂽ�����́A[15540383] �ɁA
�� �z���C�g�m�C�Y���ɑ���l�@
�� ���̐��Ȃ�A�z���C�g�m�C�Y�͏�ɏo�Ă��邱�ƂɂȂ�̂ŁA
�� �����o���Ă��Ȃ���ԂŃX�s�[�J�[�[�q�̓d���𑪂�A������̓d�����ϑ�����A
�� ���̓d���́A�X�s�[�J�[�[�q�ɃP�[�u����ڐG�A����������s�����Ƃ��ł��A
�� ��������m�C�Y�ɊW�Ȃ��A�����͂��ł���B
�Ə����Ă���ȏ�A�A���v�̃X�s�[�J�[�[�q(�A���v���̏o�͒[�q)�̗��[�Ƀe�X�^�[�Ăđ��������̂��Ǝv���܂��B�������A�d���̑�����Ƃ��ẮA�X�s�[�J�[�̃X�s�[�J�[�[�q(�X�s�[�J�[���̓��͒[�q)�Ƀe�X�^�[�Ăđ����肩��������͂��ł��B���҂͈Ⴄ���̂𑪂��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�d���𑪂邱�Ƃ������o�����̂�blackbird1212����̂ق��ł��B���̓X�s�[�J�[���炱�������傫���̉����o��A�Ƃ��������Ă��܂���B�Ȃ�blackbird1212����͑O�҂̓d���𑪂��āA��҂̓d���͑����Ă��Ȃ��̂��H�X�s�[�J�[����o�鉹�̑傫���Ɩ��Ɋ֘A����d���́A�O�҂ƌ�҂̂�����ł��傤���H���͌�҂̂ق����ƍl���܂��B���������đO�҂𑪂��������͕s�\�����Ǝ��͍l���܂��B
�����ԍ��F15549952
![]() 2�_
2�_
blackbird1212����ɂ��́B
blackbird1212����́A���ɑ��d���𑪂�Ǝ咣����Ă����ł���ˁH
����Ȃ̂ɁA
�� ���������A����-27dB�Ƃ��������́A���̒����d�����犷�Z�������̂ł��傤�B
�� ������A���̈Ⴄ���ۂ̉��Ɣ�ׂ�͖̂��Ӗ��ł��B
�Ƃ���������Ă���̂͂ǂ������Ӗ��ł����H���Ɏ������̊��œd���𑪂��Ă��A���̊���blackbird1212����̊��Ƃ͈Ⴄ��ł���ˁH���Ӗ��Ȃ̂ł����H
-27dB�́A���������Ƃ���u680mV�v�Ɓu30mV�v�����ӂɊ��Z�ł���l�ł��B������-27dB���_���Ȃ̂��Ƃ����玄�́A-27dB �ƌ�������Ɂu�u680mV�v�ɑ���u30mV�v�̔䗦�v�ƌ��������邾���ł����A���̌��������ɂȂ�̈Ӗ�������̂ł����H
�ēx�����܂����A�d���𑪂邱�Ƃ������o�����̂�blackbird1212����̂ق��ł���B�d���͈قȂ���Ԃł̔�r�Ɏg����̂ł����H�g���Ȃ��̂ł����H
�����ԍ��F15550032
![]() 2�_
2�_
>���ɂ���2�_�ɍ������Ȃ���Ablackbird1212����̉��ςɐ��������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
>����͂�낵���ł����H
�������B
>�\���I�ɂ�
>���́u�����v�́A���́u���_�v�Ő����ł��܂����A�����ے肷��̂ł����H
>�Ƃ����̂����������ǁA������̂�
>���́u���_�v�ł́A���́u�����v�ƂȂ�܂����A�����ے肷��̂ł����H
>�ƂȂ��Ă��ŁA���͂��j�]���Ă���B
������́A�\�����̂��̂��Ԉ���Ă���Ƃ����_�����Y��Ȃ��B
����́A���_���������Ă��Ԉ���Ă��Ă��A���{��̍\���Ƃ��ĊԈ���Ă��܂��B
�ł�����A������̎��╶�͊Ԉ���Ă��܂��B
���ꂪ�Ԉ�����\���ł͂Ȃ��Ƃ����������K�v�ɂȂ�܂��B
�u�z���C�g�m�C�Y���v�Ƃ������_�́u�������������v�Ƃ����u��������ɂ���v���炱���o�Ă������̂ł��B
���_���玖���������o�����悤�ɏ������Ƃ́A�����̐��ڂɂ������Ă��܂��B
�ł�����ԈႢ�ł��B
�����ԍ��F15550060
![]() 4�_
4�_
������A�����́B
�܂��A��Ȃ��Ƃ������o���܂��ˁB
�O�ɂ��������Ƃ���A�d�������̑傫����\���Ă͂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�X�s�[�J�[���A���v���X�s�[�J�[�P�[�u�����Ⴄ����ł��B
���ꂩ��A680mV�Ƃ������l���A�ǂ�ȉ��̑傫������������\���Ă͂��܂���B
�����A����680mV���L�^����Ƃ��Ɏg�����Ȃ��A���ׂăs�A�j�b�V����������ǂ��ł����H
����ł��A30mV�͂ƂĂ��傫�ȉ����Ƃ����܂����H
�����Ȃ��ł���B������Ӗ����Ȃ��Ƃ����̂ł��B
������́A�u���̌v�����d���v�Ɓu�����ŕ��������̑傫���v���r���Ă����ł��B
���������ɂ��āA������ׂ邱�Ƃ��o����̂ł����H
��̓I�Ȕ�r�Řb������A
JBL DD67000(8��)�̏o�͉������x���́A96dB/1m/2.83V
DALI HELICON 300 MK2(4��)�̏o�͉������x���́A86dB/1m/2.83V
�܂�A�����d���������Ă��A�o�Ă��鉹�̑傫����10dB���̍�������킯�ł��B
������A���ŕ��������Ɠd�����r����͖̂������Ƃ������Ƃł��B
������͎��̉����Ȃ����A����������̉����Ȃ��킯�ł��B
�����ŁA�X�s�[�J�[����o�鉹�Ƃ����B���Ȋ��r�����āA
�X�s�[�J�[�[�q�̓d�����v�邱�ƂŁA���ʂ̎w�W�����킯�ł��B
����ɁA�d���𑪂�̂́A
�������ɂق�OV�i�܂�z���C�g�m�C�Y�͏o�Ă��Ȃ��j
����ڐG������Ɠd�����オ��i�o�Ă��鉹�̓z���C�g�m�C�Y�ł͂Ȃ��j
CD���������1V�O��̓d���ɂȂ�i�v�����u�͐����������Ă���j
����3�_���m�F���邽�߂̂��̂ł��B
���l�ɂ������Ӗ����Ȃ��̂ł��B
�����ԍ��F15550150
![]() 3�_
3�_
������
�����d���́A�X�s�[�J�[�̃X�s�[�J�[�[�q�����Ōv�����Ă��܂��B
�A���v�̗��̓R�[�h���������Ă�̂ƁA
���ꂱ���Ԉ���đ��̒[�q�ɐG�����肷��댯������܂�����B
�����ԍ��F15550204
![]() 3�_
3�_
blackbird1212����A����ɂ��́B
blackbird1212����̎����̂��͉��L�ł���ˁi[15511808] �j�F
>��������0.2mV��\��
>�o�i�i�v���O���ăX�s�[�J�[�[�q�ɂ�������遨10mV�`30mV��\��
>�o�i�i�v���O���X�s�[�J�[�[�q�ɑ�����0.2mV��\��
>�����W���𗬂�V�����W�ɐ�ւ��āA�s�[�N�z�[���h��������CD��
>�ō���680mV��\��
�����Ă���́A�f�W�^���}���`���[�^�[�̌𗬃����W�A�X�s�[�J�[�̃X�s�[�J�[�[�q�����Ōv�����ꂽ�Ƃ̂��ƁB�Ƃ��ɖ��Ȃ̂́u10mV�`30mV�v�̕������Ǝv���܂��B
���̐����Ƃ��āA�A���v�������E�������ɓ����x��DC�d�����o�͂��Ă���A�Ƃ������J�j�Y����z������͎̂��R���Ǝv���܂��B���̐����Ƃ��ɋ����咣����킯�ł͂���܂��Ablackbird1212���咣���ꂽ
>�[�q�̂Ԃ������Ռ����ŁA���̐U�����{�[�q����NFB��H��ʂ��ď��i�ɖ߂�
�̂悤�Ȃ悭�킩��Ȃ����J�j�Y���������o�����ƂȂ��A���R�Ɍ��ۂ�����ł���Ǝv���܂��B�f���������̊F����Ƃ̏�L�̂��߂ɂ��A�������y�уX�s�[�J�[�ڑ����ŁA�A���v�̃X�s�[�J�[�o�͒[�q��DC�d���𑪒肳��Ă݂Ă͂������ł��傤���B
�����ԍ��F15551312
![]() 2�_
2�_
������ƕ⑫�ł��B���͏�ŁA
>�u���R�Ɍ��ۂ�����ł���Ǝv���܂��B�v
�Ə����܂������A��L�u���ہv�Ƃ́A�X�s�[�J�[�P�[�u���̂��O�������ł����炩����d�����o��A�Ƃ������ۂ��w���܂��B�Ȃ����́u���ہv�́A���i�������j�̊��ł͍Č����Ă��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B��قlj��ʂ��グ�Ȃ�����A�Ȃɂ��������Ȃ��̂ŁB
�����ԍ��F15551356
![]() 2�_
2�_
2012/12/31 12:39�i1�N�ȏ�O�j
�r��قlj��ʂ��グ�Ȃ����褂Ȃɂ��������Ȃ��̂š
�Ȃ̊����S�Ăł͂Ȃ��B
���L�H���ɂČ��ؕs�\�Ȃ�ގU����B
�ّ����
�팟���f��
�p�C�I�j�A�o�c�o�T�O�T �A�X�s�[�J�[�Z�p���[�g�P�[�u���ڑ��^�C�v
������
��ʃ��r���O
���C��ғ��A�e���r�^��G�A�R���ғ��ňÑ��������Ȃ荂�������B
�X�s�[�J�[�P�[�u�����������ŁA�X�s�[�J�[����T�O�Z���`���x�̋����̎��ɂ͂�����Ƃ����K�T�S�\������������B
�e���r�i�A���v�j�{�����[���͒ʏ펋�����x�̉��ʐݒ�B
�t���X�P�[���U�O�ɑ��A�Q�R������^��菬���߁B
�����ԍ��F15551469
![]() 4�_
4�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A����ɂ��́B
�\����Ȃ��̂ł����A���Ȃ��͓d�C��H�̒m�����Ȃ����A���{��𗝉����邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA
�R�~���j�P�[�V�������Ƃ邱�Ƃ��s�\���Ɣ��f���Ă��܂��B
�ł�����A���X�͂��Ȃ�����ł����A�Ӗ��s���ȗ���������߂��������B
�E�Ȃ����{�ꂪ�����ł��Ȃ��Ɣ��f���邩�Ƃ������R
>�Ȃ����́u���ہv�́A���i�������j�̊��ł͍Č����Ă��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�������A�Ⴂ�܂��B
������Ǝ��́A�u�����o�邱�Ƃ��m�F���āv�u�����o�闝�R�v�ɂ��ċc�_���Ă��܂��B
�ł�����A���Ȃ��Ƃ�����ł͗��ꂪ�܂�ňႢ�܂��B
������ƍl���邱�Ǝ��́A���̖��ł̂��Ƃ���܂�ŗ������Ă��܂���B
���ʂɓ��{�ꂪ�����ł���A�ԈႦ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����o�Ȃ��Ƃ������́A���ɂ͂킩��܂���B�Ȃɂ��ς�������Ȃ̂�������܂���ˁB
�u�X�s�[�J�[�P�[�u����[�q�ɂ�������Ă������o�Ȃ��v�Ƃ����X���ł����ĂāA�ʃX���ŒT���Ȃ����Ă��������B
���̃X���ɎQ������̂́A���ꂪ�Ⴄ�̂ł�����Ӗ�������܂���B
�E�d�C��H�̒m�����Ȃ��ƍl���闝�R
>��قlj��ʂ��グ�Ȃ�����A�Ȃɂ��������Ȃ��̂�
������A���łɕʃX���ɂċL�ڂ��Ă��邱�Ƃ̂Ȃ̂ł����A
���̌��ۂ̓��C���A���v���ŋN�����Ă��邱�Ƃł��B
�{�����[�����グ��ƕ�������̂́u�v���A���v�v�̃m�C�Y�ł��B
�ł�����A�{�����[���̈ʒu�i�v�����C���AAV�A���v�ł��j�͊W����܂���B
1���X�ڂŁA���������N���Ă���A���v�̃u���b�N�_�C���O����������킩��Ƃ���A
�{�����[���̓��C���A���v�����O�ɓ����Ă��܂��B
�܂�A���C���A���v�Ƀm�C�Y������A����͏o���ςȂ��Ȃ̂ł��B
���ꂪ�����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�d�C��H�̒m�����Ȃ��Ɣ��f�ł��܂��B
��������A�z���C�g�m�C�Y��������邽�߂Ɂu�{�����[����傫������Ɓv�Ƃ����\���͂��Ă��܂����A
���̎����Łu�{�����[�����ő�ɂ��Ă���v�Ƃ͋L�ڂ��Ă��܂���B
>DC�d���𑪒肳��Ă݂Ă͂������ł��傤��
���Ƃ�����́A�u���v�ɂ��ċc�_���Ă��܂��B
�ł�����uDC�d���v�͊W����܂���B
���Ȃ���AC��DC�̋�ʂ����Ȃ��̂ł��傤���H
�Ƃ������ƂŁA���Ӗ��ȗ����͂���߂��������B
�����ԍ��F15551833
![]() 5�_
5�_
2012/12/31 14:46�i1�N�ȏ�O�j
��|�����Ȃ���y����ł܂��i��
�nj���
�o�c�o�T�O�T�̃{�����[�����l�����U�O�Ƃl�����O�ɂ��Ĕ�r�B
�K�T�S�\���ʂ͕s�ρB
�����A�{�����[����i�ł̔������ۂƂ̃u���b�N�o�[�h������͐������Ǝ��͍l����B
�����ԍ��F15551919
![]() 4�_
4�_
��������|���i�j�Bblackbird1212����A����ɂ��́B
>���Ƃ�����́A�u���v�ɂ��ċc�_���Ă��܂��B
>�ł�����uDC�d���v�͊W����܂���B
���d�r���X�s�[�J�[�ɂȂ��ƁA�Ȃ����u�ԂƗ������u�ԂɃX�s�[�J�[���特���o�܂����A����������u�K�T�K�T�A�S�]�S�\�v�Ƃ��������o�܂���B�܂�u���v�ɂ�DC�d�����W���Ă���\�����傠��ŁA��L�u�W����܂���v�́A������������l���Č��ł��Bblackbird1212����͂���ɔ��_�ł��܂����H
�A���v��������Ԃł����炩��DC�d�����o���Ă���A�����悤�Ȃ��Ƃ��N���邾�낤�Ɨe�Ղɑz���ł��܂��B�܂��A������v�����Ȃ���������A�u�Ռ����v����ʂ�Ƃ�������������ꂽ�̂ł��傤����ǂ��B
>>�Ȃ����́u���ہv�́A���i�������j�̊��ł͍Č����Ă��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
>
>�������A�Ⴂ�܂��B
>������Ǝ��́A�u�����o�邱�Ƃ��m�F���āv�u�����o�闝�R�v�ɂ��ċc�_���Ă��܂��B
>�ł�����A���Ȃ��Ƃ�����ł͗��ꂪ�܂�ňႢ�܂��B
�܂��܂����������܂��傤�B�ʏ�̃{�����[���ʒu�ŁA���̊��ł́u�K�T�K�T�A�S�]�S�\�v���܂߂Ă��������������܂��A������̊��ł��A�c���m�C�Y���c�C�[�^�[�Ɏ��ĂĂ悤�₭����������x�Ƃ̂��Ƃł����B�܂��A�������������Ƃ��̗l�q���A�c���m�C�Y���P�ɕ��������蕷�����Ȃ�������Ƃ������͋C�ŁA���̓_�ł����̊ϑ��Ɠ��l�ł��B����炩��Ablackbird1212����̊��ŋN���Ă��錻�ۂ͂܂��ʂ̂��̂ł���\���������ƍl����͎̂��R�ł��傤�B�������A����͎��������l���Ă��邾���̂��Ƃł����āA���Ƃ��狭���咣����킯�ł͂���܂���B
>���̌��ۂ̓��C���A���v���ŋN�����Ă��邱�Ƃł��B
>�{�����[�����グ��ƕ�������̂́u�v���A���v�v�̃m�C�Y�ł��B
�킩���Ă��܂���B�v�́A���������u���̌��ہv�́A�O�q�̒ʂ莄�������̊��ł͋N�����Ă��Ȃ��������Ƃ������Ƃł��B�{�����[�����グ���Ƃ��̘b�����Ă��܂����̂��]�v�ŁA���������Ă��܂����̂����m��܂���ˁB
�Ƃ������Ƃł܂Ƃ߂܂����Ablackbird1212����̊��ŋN���Ă��錻�ۂ�������郁�J�j�Y���Ƃ��ẮAblackbird1212��������ꂽ�u�Ռ����v����ʂ���́A�A���v�������E������Ԃ�DC�d�����o���Ă��邱�ƂɋN������A�Ƃ����ق������ǂ������ŁAblackbird1212����̊��ŁA�������̃A���v�̏o�͓d���𑪒肷�邱�Ƃ��A���ۂɂ��Ă̗�����[�߂�Ǝv���܂��B���ꂪ�������Ƃ͌���܂��A���ɗǂ������A�����_�ł͌�������Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F15552397
![]() 2�_
2�_
2012/12/31 17:30�i1�N�ȏ�O�j
���ǁA
�f�^������A�����郂�m��ᔻ����ߒ��ɉ����āA�ᔻ�҂�葽������ӂ�ȃR�����g�����M���ꂽ�̂��悢���ƂɁA���[�̃f�^����������ނ�ɐV���Ȃ���ӂ�݂̂��c�_�ΏۂƂ��Č떂�����̂��{�X���̎�|���Ă��Ƃ�(�P�́P)
�t��̍\�����ˁi��
�����ԍ��F15552437
![]() 4�_
4�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
>���d�r���X�s�[�J�[�ɂȂ��ƁA�Ȃ����u�ԂƗ������u�ԂɃX�s�[�J�[���特���o�܂����A
>����������u�K�T�K�T�A�S�]�S�\�v�Ƃ��������o�܂���B
>�܂�u���v�ɂ�DC�d�����W���Ă���\�����傠���
>��L�u�W����܂���v�́A������������l���Č��ł��B
>blackbird1212����͂���ɔ��_�ł��܂����H
����ƁA����ڐG������Ɖ����o������Ƃǂ����т��̂ł��傤���H
��̓I�ɐ������Ă��������܂���ł��傤���H
>�A���v�������E�������ɓ����x��DC�d�����o�͂��Ă���
�Ƃ���DC�d�����W���Ă���Ƃ���������ł����A���iAC�j��DC�͂ǂ�ȊW�ł��傤���H
�Ȃɂ��A���{�I�Ɋ��Ⴂ�����Ă���悤�ɂ����v���܂��ǁB
�����ԍ��F15552546
![]() 4�_
4�_
blackbird1212����ɂ��́B
�� �\���I�ɂ�
�� ���́u�����v�́A���́u���_�v�Ő����ł��܂����A�����ے肷��̂ł����H
�� �Ƃ����̂����������ǁA������̂�
�� ���́u���_�v�ł́A���́u�����v�ƂȂ�܂����A�����ے肷��̂ł����H
�� �ƂȂ��Ă��ŁA���͂��j�]���Ă���B
�Ȃɂ���Ƃ���Ă���̂���������܂���B
���Ƃ��A����2�̕��͂��������Ƃ��܂��B
�E�����S�������邱�Ƃ͖��L���͂̐��Ő����ł��܂����A�����ے肷��̂ł����H
�E���L���͂̐��ł̓����S�������܂����A�����ے肷��̂ł����H
blackbird1212����́A�O�҂̍\���͐������āA��҂͕��͂��j�]���Ă���ƍl����̂ł����H
�� ���ꂩ��A680mV�Ƃ������l���A�ǂ�ȉ��̑傫������������\���Ă͂��܂���B
�� �����A����680mV���L�^����Ƃ��Ɏg�����Ȃ��A���ׂăs�A�j�b�V����������ǂ��ł����H
�� ����ł��A30mV�͂ƂĂ��傫�ȉ����Ƃ����܂����H
�� �����Ȃ��ł���B������Ӗ����Ȃ��Ƃ����̂ł��B
680mV�̎��ɂ��ׂăs�A�j�b�V����������A30mV�͑傫�ȉ����Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B���ׂăs�A�j�b�V����������A�ł��B�ŁAblackbird1212���g�����Ȃ͂��ׂăs�A�j�b�V���������̂ł����H
�� ����ɁA�d���𑪂�̂́A
�� �������ɂق�OV�i�܂�z���C�g�m�C�Y�͏o�Ă��Ȃ��j
�� ����ڐG������Ɠd�����オ��i�o�Ă��鉹�̓z���C�g�m�C�Y�ł͂Ȃ��j
�� CD���������1V�O��̓d���ɂȂ�i�v�����u�͐����������Ă���j
�� ����3�_���m�F���邽�߂̂��̂ł��B
�� ���l�ɂ������Ӗ����Ȃ��̂ł��B
����ɂ��Ă��������m�F���������Ƃ͂���̂ł����A����������̂��Ƃ̊m�F�̂ق����D��x�������Ǝv���̂ŁA��ɂ��܂��B(���������ǂ��̓d���𑪂��Ă���̂����͂����肵�Ȃ��̂ŁB)
�� �����d���́A�X�s�[�J�[�̃X�s�[�J�[�[�q�����Ōv�����Ă��܂��B
�� �A���v�̗��̓R�[�h���������Ă�̂ƁA
�� ���ꂱ���Ԉ���đ��̒[�q�ɐG�����肷��댯������܂�����B
����ƁA
�� �z���C�g�m�C�Y���ɑ���l�@
�� ���̐��Ȃ�A�z���C�g�m�C�Y�͏�ɏo�Ă��邱�ƂɂȂ�̂ŁA
�� �����o���Ă��Ȃ���ԂŃX�s�[�J�[�[�q�̓d���𑪂�A������̓d�����ϑ�����A
�� ���̓d���́A�X�s�[�J�[�[�q�ɃP�[�u����ڐG�A����������s�����Ƃ��ł��A
�� ��������m�C�Y�ɊW�Ȃ��A�����͂��ł���B
����͖������܂��H
�X�s�[�J�[�̃X�s�[�J�[�[�q�̓d�����v�����Ă���Ȃ�A�X�s�[�J�[�[�q�ɃX�s�[�J�[�P�[�u����t�������ƊO�������Ƃł́A�d���͈قȂ�̂ł͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F15553530
![]() 2�_
2�_
>blackbird1212���g�����Ȃ͂��ׂăs�A�j�b�V���������̂ł����H
�����������Ƃ�����A�ǂ��ł����H
������A�ǂ��CD�̂ǂ�ȋȂ��ǂ�ȑ傫���ōĐ������̂��m��Ȃ��̂ɁA
�w�W�ɏo���Ȃ��ł���A�Ƃ������ƁB
>�X�s�[�J�[�̃X�s�[�J�[�[�q�̓d�����v�����Ă���Ȃ�A
>�X�s�[�J�[�[�q�ɃX�s�[�J�[�P�[�u����t�������ƊO�������Ƃł́A
>�d���͈قȂ�̂ł͂Ȃ��ł����H
�卷�͂Ȃ����A�d�����o�Ă��邩�o�Ă��Ȃ����ׂ邾���Ȃ̂Ŗ��Ȃ��ł��B
�{���ɁA�����̌o�����Ȃ���ł��ˁB
�A���v�̓������v���������ƂȂ���ł����H
���������u�P�[�u���ʼn��͕ς��Ȃ��h�v�Ȃ���A�P�[�u���ɂ������̂͂��������ł���B
�ǂ�ȃP�[�u�����g���Ă��A���͕ς��Ȃ���ł���B
��������e���Ȃ��ł���B�d�������Ȃ���B
��������ׂĂȂ��ŁA�d���𑪂�����ǂ��ł����H
����Ƃ��A�~���o���Ƃ��𗬂̏��d���𑪂��e�X�^�[�����ĂȂ���ł����H
�v���n�Ȃǂ̓d�C�ɋ����Ȃ�A�����Ă�Ǝv���܂����H
�����ԍ��F15554333
![]() 4�_
4�_
blackbird1212����A������ɉ��܂��B
>>���d�r���X�s�[�J�[�ɂȂ��ƁA�Ȃ����u�ԂƗ������u�ԂɃX�s�[�J�[���特���o�܂����A
>>����������u�K�T�K�T�A�S�]�S�\�v�Ƃ��������o�܂���B
>>�܂�u���v�ɂ�DC�d�����W���Ă���\�����傠���
>>��L�u�W����܂���v�́A������������l���Č��ł��B
>>blackbird1212����͂���ɔ��_�ł��܂����H
>
>����ƁA����ڐG������Ɖ����o������Ƃǂ����т��̂ł��傤���H
>��̓I�ɐ������Ă��������܂���ł��傤���H
���d�r�iDC�j�ʼn����o��킯�ł�����A�A���v��DC�d�����o���Ă���i���d�r�̑���ɂȂ��Ă���j�̂��u���v�̌����ł͂Ȃ����Ƃ����̂͂��蓾�鉼�����Ǝv���܂��B���̘_���͂��������������܂����H�Ȃ����́Ablackbird1212�����
>���Ƃ�����́A�u���v�ɂ��ċc�_���Ă��܂��B
>�ł�����uDC�d���v�͊W����܂���B
�Ƃ����咣�����ł��邱�Ƃ��A�����������玦���܂����B�ēx���������܂����A���_�ł��܂����H�����ŁA�����o���̓I���J�j�Y�����ǂ�����A���d�r�iDC�j�Łu���v�͏o��̂ŁA�A���v��DC�d���������Łu���v���o�Ă�������������܂���B�u���v���o���̓I�ȃ��J�j�Y���ɂ��Č��y���Ȃ��Ă��uDC���v�̉����̐������͒S�ۂ����̂ŁA�����Ă��̐����͂��܂���B
>>�A���v�������E�������ɓ����x��DC�d�����o�͂��Ă���
>�Ƃ���DC�d�����W���Ă���Ƃ���������ł����A���iAC�j��DC�͂ǂ�ȊW�ł��傤���H
�uDC�d���������łǂ̂悤�ɉ��iAC�j���������Ă���̂��H�v�Ƃ���������ł���Ɨ������ăR�����g���܂����A��L�Ɠ������R�ɂ��A���Ƃ��Ă͂���ɂ��Ă����Đ������܂���B
�Ō��blackbird1212����Ɏ��₢�����܂��B��A�̋c�_�ɂ���āA�d�C��H�̒m�����������blackbird1212����́A�X�s�[�J�[�P�[�u���̂��O�������ʼn���d�����ϑ����ꂽ���R�Ƃ��āA�������ɃA���v���o�͂��Ă���DC�d���������Ƃ͍l���Ă��Ȃ��A�Ɨ�������̂����R�ł��B���̗����Ő������ł��ˁH
�����ԍ��F15559353
![]() 3�_
3�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A����ɂ��́B
>�X�s�[�J�[�P�[�u���̂��O�������ʼn���d�����ϑ����ꂽ���R�Ƃ��āA
>�������ɃA���v���o�͂��Ă���DC�d���������Ƃ͍l���Ă��Ȃ��A
>�Ɨ�������̂����R�ł��B���̗����Ő������ł��ˁH
�����Ɍ����ΊW�[���ł͂���܂��A��{�I�ɂ͂����ł��B
>�uDC�d���������łǂ̂悤�ɉ��iAC�j���������Ă���̂��H�v�Ƃ���������ł���
>�Ɨ������ăR�����g���܂����A��L�Ɠ������R�ɂ��A
>���Ƃ��Ă͂���ɂ��Ă����Đ������܂���B
�l�̗��_�ɕ���������̂�������A�������������̂��ł��傤�B
�o���Ȃ��̂Ȃ�A�����̃f�^�����Ƃ������Ƃł��B
���Ȃ݂ɁA���͎����Ōv�����d���������Ă��܂��B
��������d���̕ω��������Ă��������B
�����ԍ��F15559647
![]() 3�_
3�_
blackbird1212����ɂ��́B
���͐���A�����S�Ɩ��L���͂��ɂ������͂���܂������A���݁A����ɑ���blackbird1212����̌������������̂�҂��Ă����Ԃł��邱�Ƃ��A�����ɂ��m�点���܂��B
�����ԍ��F15561527�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���́A������A�d�����v�����Ď������m�F���Ăق����ƁA
������ɗv�]���Ă��܂����A���̌��ʂ�������Ȃ��̂ŁA
�����҂��Ă����Ԃł��邱�Ƃ����m�点���Ă����܂��B
���̈�_�����グ�Ă��A
������́A���l�̎���ɂ͓������A���l�Ɏ��₾�����J��Ԃ����ƂŁA
�b�̋��˂��Ȃ��悤�Ƃ��Ă���Ƃ����Ӑ}�����m�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�i�Ƃ����Ă��A�Ԃ��Ă��鎿��́A�f�ňӖ��������ł��Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ō����Ă���̂ł���)
���Ȃ݂ɁA�E�`�̌v�����ʂ̃m�C�Y���ł����̂�
�Ѓ`����200W/8���Ƃ����Z�p���[�g�̃p���[�A���v�Ƃ����̂������ł͂���B
���_���킩���Ă���A�ǂ��ł��ǂ����Ƃł͂���̂����B
�߁X�A50W�̃p���[�A���v�̌v�����ʂ��o���܂��傤�B
���̂ق����A�F����̎g�p���ɋ߂��ł��傤�B
�������A�m�C�Y��3mV���炢�̂͂��ł��B�i�L���Ȃ�ŞB���ł����j
�����ԍ��F15561715
![]() 4�_
4�_
blackbird1212����A�����́B
>�����Ɍ����ΊW�[���ł͂���܂��A��{�I�ɂ͂����ł��B
���肪�Ƃ��������܂��B�m�F�ł����A�A���v����������DC�d�����o�͂��Ă��Ȃ��Ă��u���v�͏o��A�Ƃ������Ƃł�낵���ł��ˁH����Ă����炨��������Ă��������B
>�l�̗��_�ɕ���������̂�������A�������������̂��ł��傤�B
>�o���Ȃ��̂Ȃ�A�����̃f�^�����Ƃ������Ƃł��B
���_���������ӔC�͂��{�l�ɂ���܂��B���̕s�����w�E����l�́A�w�E�̍�����������ׂ����Ƃ͎v���܂����A�ΈĂ̐����܂ł���̂��u�v�Ƃ́A�������Ș_���ł��B
����ɁA���̓X�s�[�J�[�P�[�u���̂��O�������ɂ�����u���v�̌����ɂ��āA�i�\���Ƃ��Ăł����j�uDC���v�������Ă��܂��B�����āADC�d���������Łu���v���o�邱�Ƃ́A���d�r�̎����ŗ��t���Ă��܂�����A�u����������v�ł��Ȃ���f�^�����Ƃ����̂��A�������Ș_���ł��B
�����Ƃ��A���Ƃ��ẮuDC���̗����v��������Ȃ��������@���Ȃ��̂ł����A���d�r�̎����͊ȒP�ɂł��܂����A�����d�C�̒m��������A��������܂ł��Ȃ������ł���͂��ł��B�A���v���i�ǂ̒��x�jDC�d�����o���Ă���̂����A���肵�Ă݂�ΊȒP�ɂ킩�邱�ƂŁA����ɂ���Ď��́uDC���v��ے肷�邱�Ƃ��e�Ղ��Ǝv���܂��B�ǂ̂����肪blackbird1212����ɂƂ��ċ^��Ȃ̂����킩��Ȃ��̂Ő����ɍ���A�Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B
>���Ȃ݂ɁA���͎����Ōv�����d���������Ă��܂��B
>��������d���̕ω��������Ă��������B
blackbird1212�����肵�Ă��邩��ƌ����Ď��ɑ�������߂�̂��A�������Ș_���ł��B���̊��ł́u���v���o�Ă��܂���̂ŁA���肷��Ӌ`���킩��܂���Bblackbird1212����̊��ł́u���v���o�Ă��ēd�����ϑ�����Ă���Ƃ������Ƃł��̂ŁA���ɂ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F15582853
![]() 2�_
2�_
blackbird1212����Ɏ��₵�܂��B���������A���̐�̓��e�̖`���̈��p�ɂ���u�l�̗��_�v�Ƃ́A�Ȃɂ�������邽�߂̂ǂ̂悤�Ȃ��b�ł��傤���H
�Ƃ����̂́Ablackbird1212����̐��́A�s�����w�E���邽�тɓ��e���ψق���ȂǁA���_�̑̂��Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ́A[15518065][15518074]�Ȃǂŏq�ׂ܂����B��������܂������A�낭�ɉ�����܂���B���X�́u�I�[�f�B�I�̃V���[�g�I�H�ɂ��āv�ł̎��̌����ɂ��Ă̋c�_�ł������A���̌�A�X�s�[�J�[�P�[�u���̂��O�������̘b�ɂȂ��Ă��āA���ǂ��������u���_�v�̎��Ԃ��Ȃ�Ȃ̂��킩��܂���B���Ƃ���
>�{���Ƃ������́A�[�q�̂Ԃ������Ռ����ŁA���̐U�����{�[�q����NFB��H��ʂ��ď��i�ɖ߂�A
>��������ăX�s�[�J�[����o�͂��ꂽ���̂ł��B
�ɂ��āA�u�Ռ����v�����̊Ԃɂ��d�C�M���ɕς���Ă����Ȋw�������͎w�E���܂����B���̌�A�u�Ռ������v��������邽�߂ɓˑR�X�s�[�J�[�P�[�u���̂��O�������̘b���o�Ă��܂����i�Ǝv���܂��j�B���������V�X�e���ł́A�X�s�[�J�[�͏I�n�ڑ����ꂽ��Ԃɂ���܂��B�P�[�u�����O���Ă��܂��͕̂s���R�ŁA����Ȃ玄���������uDC���v�ł������ł��Ă��܂��܂��B
���������u�Ռ������v�������I�Ɍ�����̂ł���A�X�s�[�J�[���Ȃ����܂܁A�Ȃɂ��Œ[�q��@���Ă݂āA�ǂ̒��x�̓d����i�X�s�[�J�[����́j�����o��̂��A�����@������炪�傫���Ȃ邱�ƁA�������������≏���ł��d���≹���������邱�ƁA�Ȃǂ��m���߂�ق����������Ǝv���܂����A�������ł��傤���H
�����Ƃ��A�����̌��ʂ���A�u�I�[�f�B�I�̃V���[�g�I�H�ɂ��āv�̃X���ɂ����鎖�́A���Ȃ킿�ΉԂ��o�Ē[�q�ɏł��Ղ����悤�Ȏ��Ԃ��ǂ���������̂����傫�Ȗ��ł����B
�����ԍ��F15582865
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B
�ȂA��������폜���ꂽ��ŁA���C���o�Ȃ��ł��B
�^�c���A������߂���ƌ����Ă���悤�ł��B
�N���폜�˗�������ł��傤�ˁB
�Ƃ���ŁA�Y��悤�ɂ��������Ȃ������
>�m�C�Y�͒ʏ퉹�ʂ�-27dB�ȂǂƂ����傫�ȃ��x���ł͂���܂���
�Ə����Ă��܂���ˁB
������A�����l�ɁA����ȃf�^�����������l�Ƃ͋c�_�ȂǏo���Ȃ��̂ł���B
�����A���Ȃ����̃f�^�����ɂ������̂ɂ͔��܂�����B
���Ȃ݂ɁA�d�r�ƃX�s�[�J�[�̎����ł����A
�X�s�[�J�[�̋ɐ����`�F�b�N���邽�߂ɕ��ʂɍs���Ă��邱�ƂŁA
�����o��̂��m���Ă܂���������O�Ȃ��Ƃł��B
�����������Ă��炢���������̂́AAC��DC�̊W�Ȃ̂ł����A�i�荞��Ō�����
�u�X�s�[�J�[�R�[�h����������Ă���Ƃ���DC�d���͂ǂ��Ȃ�A�ǂ�����Čv�邩�v
�Ƃ������Ƃł��B�����܂ŏ����ƈӖ����킩�邩�ȁH
�u-27dB�v�ɂ��čēx�����Ă����܂��B
���́u-27dB�v�Ƃ������l�́A���̒���680mV��30mV�Ƃ����d���l���g���āA
��������Ɂu30mV÷680mV�v���f�V�x�����Z�������̂ł��B
�ł�����A-27dB���\���Ă���̂́u680mV��30mV�̓d���̑傫���̔�v�����ł��B
�ł����A�Ȃ�������l�Ƃ��u���̑傫���v�Ƃ��Ĉ����Ă��܂��B
���ꂪ�f�^�����ł͂Ȃ��Ȃ�Ȃ̂ł��傤���H
>�m�C�Y�͒ʏ퉹�ʂ�-27dB�ȂǂƂ����傫�ȃ��x���ł͂���܂���
���̕���
>�m�C�Y�͒ʏ퉹�ʂ́u680mV��30mV�̓d���̑傫���̔�v�ȂǂƂ����傫�ȃ��x���ł͂���܂���
�����u����������킯�ł��B
������́A
>�u-27dB�v�́u�傫�ȉ��v�ł���ˁH
�Ə����܂������A���l��
>�u680mV��30mV�̓d���̑傫���̔�v�́u�傫�ȉ��v�ł���ˁH
�����u����������킯�ł��B
����l�́A�d����Ɖ��̑傫�����ׂ���Ƃ����A�֗��Ȏ��Ɠ����������̂悤�ł��B
��k�͂��Ă����A�d�C�̒m���ǂ��납�A���{��Ƃ��Ă��������Ă��Ȃ��킯�ł��B
����ȃf�^�����Ȓm���ƃf�^�����ȓ��{���ɂ��Ă�����܂���B
�ł��̂ŁA���́u-27dB�����̑傫���Ƃ��Ĉ����f�^�����v���ؖ��|�C���g�Ƃ��āA
������ƖY��悤�ɂ��������Ȃ�����̓d�C�̒m���̓f�^����
�Ƃ������_�ɂ��܂��B
�Ȃ��A���エ��l���玄�ɂ��Ă��낢�돑�����Ƃ����邩������܂��A
���̖ړI�́u������ɂ͓d�C��H�̒m�����Ȃ��v�𖾂炩�ɂ��邱�ƂŁA
���ɒm���������Ă��Ȃ��Ă��W�Ȃ���ł��B
���x�������Ă��ł����A����l�͗������Ȃ��悤�ł��B
�ł�����A�헪�ア�������Ȃ��Ƃ������Ă��邱�Ƃ����邵�A
���������悤�Ƃ���㩂邽�߂ɞB���Ȃ��Ƃ������Ă��邵�A
�܂Ƃ߂ď����Ȃ��ŏ��o���ɏ�����������Ă���킯�ł��B
������_���Ă��Ӗ����Ȃ���ł���B
�͂��߂́u���U�v�ł������A����͑f�l�ɂ��킩��悤�ɐ�������̂������ŁA
���X�ɕ����������炵�Ă����āA���̃X���ł̓z���C�g�m�C�Y���������̂ł����A
�܂�����ł��\���ȏؖ��͏o���Ă���̂ł����A
�ŏI�I�ɂ́u-27dB�v�����_�ɂ��܂����B�i������ꂽ���炾���ǁj
�܂��A���ꂾ�����낢�돑���Ă���A
������̒m���������������Ƃ������Ƃ́A�����̐l�ɂ킩�����Ǝv���܂��B
�ȏ�ł��B
������A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A���悤�Ȃ�B
�����ԍ��F15583704
![]() 5�_
5�_
blackbird1212����A����ɂ��́B
�d�C��H�̒m����������Ȃ�A���X���̎��̂̌����ɂ��ė�Âɋc�_�𑱂���̂����Y�I���Ǝv���܂��B�������A�P�ނ����悤�Ȃ̂ŏ����܂Ƃ߂܂��B�܂��A�Ȃɂ��ƌ����������ċc�_��ł��낤�Ƃ���̂́A���������Ȃ������̏퓅��i�ł��ˁB�c�_�ł͂悭�o�����܂��B�ŁA
>���̖ړI�́u������ɂ͓d�C��H�̒m�����Ȃ��v�𖾂炩�ɂ��邱�ƂŁA
>���ɒm���������Ă��Ȃ��Ă��W�Ȃ���ł��B
�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�����g�̓d�C��H�̒m�������������f�l���x���ł��邱�Ƃɂ͔��_�Ȃ��ƍl���܂��B���ہu�Ռ������v���܂ށu���_�v�͂��e���Ȃ܂܂ł�����A���X���̎��̂̌�����������邱�Ƃ��Ablackbird1212����͕������ꂽ�ƍl���܂��B
�ȉ��A����Ȃǂ�����܂��̂ŕ⑫���Ă����܂��B
>�Ƃ���ŁA�Y��悤�ɂ��������Ȃ������
>>�m�C�Y�͒ʏ퉹�ʂ�-27dB�ȂǂƂ����傫�ȃ��x���ł͂���܂���
>�Ə����Ă��܂���ˁB
>������A�����l�ɁA����ȃf�^�����������l�Ƃ͋c�_�ȂǏo���Ȃ��̂ł���B
>�����A���Ȃ����̃f�^�����ɂ������̂ɂ͔��܂�����B
���́A���̊��Ŏ��������Ă��܂�����A��ň��p����Ă���u�ʏ퉹�ʁv�Ƃ́A���̊��ł̒ʏ퉹�ʂł����āA�f�^�����ł͂���܂����B������ȂƂ���Ɍ���������̂������������߂�̂͏�Ȃ��ł��B
>���Ȃ݂ɁA�d�r�ƃX�s�[�J�[�̎����ł����A
>�X�s�[�J�[�̋ɐ����`�F�b�N���邽�߂ɕ��ʂɍs���Ă��邱�ƂŁA
>�����o��̂��m���Ă܂���������O�Ȃ��Ƃł��B
�������d�r�̎����̘b�������̂́Ablackbird1212�����
>���Ƃ�����́A�u���v�ɂ��ċc�_���Ă��܂��B
>�ł�����uDC�d���v�͊W����܂���B
�Ƃ����咣�����ł��邱�Ƃ��������߂ł��B���d�r�ŃX�s�[�J�[���特���o�邱�Ƃ��悤�₭blackbird1212����͗������ꂽ�̂Łi���炭�A���Ɏw�E����čQ�ĂĎ��������̂ł��傤�j�A�����g�̎咣�����ł��邱�Ƃ��킩�����͂��ł��B
�܂��Ablackbird1212����̂����e�ɂ́A�d�C��H�̒m���]�X�����邱�ƂȂ���A2013/01/06 23:01�@[15582853]�Ȃǂł��w�E���Ă���悤�ɁA�_���������������Ƃ����X���邱�Ƃ��A���炽�߂Ďw�E���Ă����܂��B
�����ԍ��F15585133
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A����ɂ��́B
����ȏ�p�̏�h��͂��Ȃ��Ă������Ǝv�����ǁB
>���̊��ł̒ʏ퉹�ʂł����āA�f�^�����ł͂���܂����B
������A-27dB�͉��ʂ���Ȃ������ׂ��Ȃ��Ə����Ă����ł���B
����������������ǁAdB���Z���Ă���Ή��ł���ׂ���Ǝv���Ă�̂��ȁH
>>�ł�����uDC�d���v�͊W����܂���B
���ꂳ���A�킴�ƈ��������邽�߂ɏ����Ă����ł���B
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����́AAC��DC�̈Ⴂ�𗝉����ĂȂ��悤������B
>���d�r�ŃX�s�[�J�[���特���o�邱�Ƃ��悤�₭blackbird1212����͗������ꂽ�̂�
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����́A
AC��DC�̈Ⴂ�Ƃ��A���v�̏o�͂̍\�����܂�ŗ������ĂȂ��悤�����ǁA
AC��DC�̈Ⴂ�́A�傫���ƕ��������ς�邩�ǂ��������i�ς��̂�AC�j�B
������AAC�̂����u���Ƃ炦�āA���ꂪ+12V���Ƃ�����A�����DC��+12V�Ɠ������́B
�A���v�̏o�͂́ASEPP�̗��[�ɂ������Ă�{�|���\V�́uDC�d���v��
���͑��ŃR���g���[�����ĘA���Ϗo�͂����邱�ƂŁuAC�d���v�����o���Ă邾���B
������A�A���v�o�͂́{�������ɂ��čl����A�i���g�������Ă��������ǁj
�傫�����ς�邩�狷�`�̒����ł͂Ȃ�����ǁA�u�����v�Ƃ����čL�`�̒����ɂȂ��ł���B
�d�r�͂���Ɠ������ł��B
�d�C�̊�b�Ȃ�ŁA���܂���u�����ŏؖ������v�Ƃ������Ă��������B
�����ԍ��F15585393
![]() 4�_
4�_
�Ȃ�قǁBblackbird1212����́A���������Ȃ����{�_�Ƃ͊W�̂Ȃ��b���ǂ�ǂ�o���Ă���̂ŁA���X�b���I���Ȃ��킯�ł��ˁB�{�_����ǂ�ǂ���Ă����̂ŁA���̂����^�c���ɍ폜�����A�ƁB
�Ƃ肠�����{�_�ɂ��āA����blackbird1212����̐��͂��͂◝�_�̑̂��Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ�Ablackbird1212����̒m�������������f�l���x���ł��邱�Ƃ�_�q���Ă��܂������A���_���Ȃ����Ƃ������ɖ��m�ɂ��Ă����܂��B
�ł́A�e�ׂȂ��������ɂ��Đ������܂��B
>������A-27dB�͉��ʂ���Ȃ������ׂ��Ȃ��Ə����Ă����ł���B
���悢����Ƃ��_���Ƃ��A�킯���킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ˁB�������Ɂu-27dB�v�́u���ʁv����Ȃ��ł���H���́u�m�C�Y�͒ʏ퉹�ʂ�-27dB�ȂǂƂ����傫�ȃ��x���ł͂���܂���v�Ə����Ă��܂��B�m�C�Y�ƒʏ퉹�ʂ̑傫�����ׂĂ���̂ł�����A���̒��x��dB�Ō�邱�Ƃ͂܂�������肠��܂���B
>������A�A���v�o�͂́{�������ɂ��čl����A�i���g�������Ă��������ǁj
>�傫�����ς�邩�狷�`�̒����ł͂Ȃ�����ǁA�u�����v�Ƃ����čL�`�̒����ɂȂ��ł���B
>�d�r�͂���Ɠ������ł��B
>�d�C�̊�b�Ȃ�ŁA���܂���u�����ŏؖ������v�Ƃ������Ă��������B
���̕ӂ̕��̘_�����߂��Ⴍ����ł����c���d�r�̂��b�́A�������ɂ킴�킴���������Ə������̂悤�ȏ����I�Ȃ��̂ł��B���̏����I�Ȃ��b���킩���Ă���Ablackbird1212����̂悤��
>���Ƃ�����́A�u���v�ɂ��ċc�_���Ă��܂��B
>�ł�����uDC�d���v�͊W����܂���B
�Ƃ����悤�ȁA�Ԉ���������͂��Ȃ��̂ł��B���̎w�E�ɂ����blackbird1212���A�uDC�d���v�Ɓu���v�Ƃɂ͊W������Ƃ������̎咣�𗝉����ꂽ���Ƃ́A�܂��ǂ������Ƃ��Ă����܂��傤�B
�����ԍ��F15586088
![]() 2�_
2�_
>�m�C�Y�ƒʏ퉹�ʂ̑傫�����ׂĂ���̂ł�����A
>���̒��x��dB�Ō�邱�Ƃ͂܂�������肠��܂���B
�ŁA���́u-27dB�v�͂ǂ�����o�Ă��������ŁA�ǂ�ȈӖ��������ł����H
�Ȃ��u-27dB�v�Ȃ̂ł����H
>>������A�A���v�o�͂́{�������ɂ��čl����A�i���g�������Ă��������ǁj
>>�傫�����ς�邩�狷�`�̒����ł͂Ȃ�����ǁA�u�����v�Ƃ����čL�`�̒����ɂȂ��ł���B
>>�d�r�͂���Ɠ������ł��B
>>�d�C�̊�b�Ȃ�ŁA���܂���u�����ŏؖ������v�Ƃ������Ă��������B
>���̕ӂ̕��̘_�����߂��Ⴍ����ł����c
���āA�ǂ̘_�����߂��Ⴍ���Ⴞ���A�������������肢�܂����H
�����ԍ��F15586200
![]() 5�_
5�_
>�ŁA���́u-27dB�v�͂ǂ�����o�Ă��������ŁA�ǂ�ȈӖ��������ł����H
>�Ȃ��u-27dB�v�Ȃ̂ł����H
����͒P��blackbird1212����̂������ł���ˁB���������Ȃ�����ɂ������������Ă���Ƃ��肪����܂���̂ŁA���������܂���B������������R�ŃX���[���邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���m�点���܂��B
>���āA�ǂ̘_�����߂��Ⴍ���Ⴞ���A�������������肢�܂����H
�������܂����Bblackbird1212�����
>�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����́A
>AC��DC�̈Ⴂ�Ƃ��A���v�̏o�͂̍\�����܂�ŗ������ĂȂ��悤�����ǁA
�Ə�����Ă��܂����A���̍�����������Ă��܂���B���̌�̕��������Ȃ̂��Ǝv������A
>AC��DC�̈Ⴂ�́A�傫���ƕ��������ς�邩�ǂ��������i�ς��̂�AC�j�B
�̂悤�Ȍ��m�̏������Ă��邾���ł��B���m�̏��Ȃɂ����o���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�_�����߂��Ⴍ����v�ƕ\�����܂����B
�����ԍ��F15586792
![]() 2�_
2�_
���Ǔ�����邾���ł��ˁB
����ŏI���ɂ��܂��B
�{���ɁA���悤�Ȃ�B
�����ԍ��F15586894
![]() 7�_
7�_
blackbird1212���ގU����A��������̎���ɂ��肪�Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ�Ȃ��Ȃ����̂ŁA��̂�����ɉƃR�����g�����܂��B
>�ŁA���́u-27dB�v�͂ǂ�����o�Ă��������ŁA�ǂ�ȈӖ��������ł����H
>�Ȃ��u-27dB�v�Ȃ̂ł����H
�����܂ł��Ȃ��Ablackbird1212����̌v�����ʁA���Ȃ킿�m�C�Y��30mV�ƁA�ʏ�{�����[���ʒu�ł�CD�Đ�����680mV����o�������ł���A���̊��ł̃m�C�Y�̏����������`�����邽�߂ɏ��������̂ł��B�����ł́A�����l�Ԃł���ȏ�u�ʏ�̉��ʁv���ɒ[�ɂ͈��Ȃ����낤�Ɨ���������Łi���_�����̈Ⴂ������\����D�荞��Łj�����܂����B
�Ƃ��낪blackbird1212����͂��̌�[15550150]��
>�����A����680mV���L�^����Ƃ��Ɏg�����Ȃ��A���ׂăs�A�j�b�V����������ǂ��ł����H
�Ƃ����ɒ[�Șb������A������������́u���ׂăs�A�j�b�V���������̂ł����H�v�Ƃ�������ɂ͓����Ă��܂���B���炩�ɋZ�p�_�ł͂Ȃ��A�u������ɂ͓d�C��H�̒m�����Ȃ��v�ƌ������߂̌����ɗ��p���Ă��܂��Bblackbird1212����Ƃ͂���������i����邩���ł���Ƃ������Ƃ��A�f���������݂̂Ȃ��܂̂��Q�l�܂łɎw�E���Ă����܂��B
���āA�Z�p�_�ɖ߂�Ablackbird1212����̊��ł̃m�C�Y�̑傫���ɂ��čl���܂��Bblackbird1212����́A�����d���ł����̑傫�����Ⴄ��Ƃ���[15550150]��2��ނ̃X�s�[�J�[�������Ă����܂����A�����������ق��ŁA
>DALI HELICON 300 MK2(4��)�̏o�͉������x���́A86dB/1m/2.83V
�Ƃ̂��Ƃł��B�m�C�Y���x���͍ő�30mV�Ƃ̂��Ƃł�����A������47dB/1m�قǂ̌v�Z�ł��B����́A����l��v�Z�ɂ��Ȃ�덷������Ƃ��Ă��A���ʂ̐l�ɂ̓X�s�[�J�[�Ɏ����Ȃ��Ƃ��y�X��������A�m�C�Y�Ƃ��Ă͑傫�ȉ��ł��B������⎄�̊��Ŋϑ�����Ă���m�C�Y���͂邩�ɑ傫�����Ƃ͖��炩�ŁA�������J�j�Y�����ʂł���ƍl����ׂ��ł��B
�������blackbird1212����̂����e��q������ƁA�������Ɠ������ۂ����l�̊��ł��N�����Ă��邱�Ƃ����R�ł����āA����ɕ������Ȃ��ϑ��ɑ��ẮA�����I�����Ȃ��d�C��H�i���邢�͓��{��j�𗝉����Ă��Ȃ��A�ƒf���Ă��܂��Bblackbird1212����ɒP�ɉȊw�I�Z���X���Ȃ��̂����m��܂��A�Ƃ�������������b��f��I�Ɍ�邩���ł���A�Ǝw�E���Ă����܂��B
�����ԍ��F15592338
![]() 6�_
6�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�v�����C���A���v]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
-
�y�~�������̃��X�g�z�J�����{�����Y
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�v�����C���A���v
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j