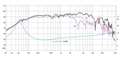���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S58�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 2016�N5��8�� 22:53 | |
| 1 | 1 | 2016�N4��28�� 15:25 | |
| 27 | 10 | 2016�N3��7�� 12:31 | |
| 24 | 28 | 2016�N4��3�� 11:58 | |
| 2 | 0 | 2015�N8��24�� 21:09 | |
| 12 | 6 | 2015�N6��22�� 20:14 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
����A���N�i2016�N�j�����[�X���ꂽSOULNOTE�̃v�����C���^�A���vA-1�ɐG��邱�Ƃ��o���܂����B
�@���i��17���~���Ƃ������ƂŁA�O��sa3.0�̌�p�@��Ƃ����������o���܂����A�܂������Ⴄ���i�̂悤�ł��B���������A���u�����h����ɂ��Ă�����ؓN��傪�A�v�ɂقƂ�NJ֗^���Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B
�@�A�i���O�A���v�ƃf�W�^���A���v�̃n�C�u���b�h�\���ł�����sa3.0�Ƃ͈قȂ�AA-1�͏����̃A�i���O�A���v�ł��B�傫�ȃg���C�_���^�g�����X�𓋍ڂ��A���@�i���s���j�Ə���d�͂Ɣ��M�ʂ͑����܂����B����̃p�l�����̗p�������b�N�X�́A�Ȃ��Ȃ���낵���ł��B�X�s�[�J�[�[�q��sa3.0�ɔ�ׂ�Α傫�߂ŁA����Ȃ�P�[�u���̑������y�ł��傤�B
�@�X�s�[�J�[��PMC�̐��i���q���Ă��܂������A�O��sa3.0���͂��߂��̃N���X�̃A���v��PMC�Ƃ̃R���{�̉��͒��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA���̃A���v�ɔ�ׂ�A-1���̂��ǂ��������i�̉��Ȃ̂��̓n�b�L���Ɣc���͏o���܂���ł������A�L�т�ꖡ�������x������݂��d�������T�E���h�ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂����B�Ȃ��A�X�^�b�t�̘b���Ɓu�����Č����Asa3.0�̌�p�ł͂Ȃ��Asa1.0�̏㋉�łƂ����ʒu�t�����v�Ƃ̂��ƁB
�@�X�s�[�J�[��I�Ԃ悤�ȃN�Z�̋����͖����݂����Ȃ̂ŁA���Ȃ��Ƃ�10���~��̃A���v�ł́u�g���鐻�i�v�ł���̂͊m���̂悤�ł��B
�@�Ȃ��A�{�����[�������x�����ƂɃ����[���ւ���悤�ȕ����ɂ��Ă���炵���A���ʂ�ς���ƃJ�`�J�`�Ɖ����o�܂��B�C�ɂȂ�l������ł��傤���ǁA���̕������̗p�������Ƃɂ���ăM�����O�G���[�i���E�̉��ʂ̈Ⴂ�j�����������ނ��Ƃ��o�����Ƃ̂��Ƃł��B
�@�y�A�ɂȂ�CD�v���[���[��C-1�͂��̃N���X�ł͒������uCD��p�@�v�ŁASACD�ɏd����u���Ȃ����X�i�[�ɂƂ��Ă͑I���������������ł�
![]() 7�_
7�_
�����́B
�ǂ�ȃT�E���h�Ȃ̂��y���݂ł��ˁB
�l�I�ɂ͌���J���[�̃u���b�N�̕������̃f�U�C���ɂ͍����̂��ȂƎv���܂��B
C-1�̂ق��́ASACD��K�v�Ƃ��Ȃ����[�U�[�ɂ� �h ���� �h�̃��f���ɂȂ邩������܂���ˁB
�����ԍ��F19813717�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
����ɂ���
��肪�Ƃ��������܂��B
���̓��������I�p�l���փX�p�C�N��3�{���ł��ˁAhttp://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20160415_753338.html
�R�l�N�^�[�̔r���A�����NFB�Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�����オ��悭���ނ������������ł��傤���B
�����ԍ��F19813917
![]() 4�_
4�_
�\�E���m�[�g��PMC�͑������ǂ��悤�ł��ˁB
A-1��Sa1.0�̉�������ł���A�ƂĂ������[���ł��B
�ȑO�A�_�C�i555�� Sa1.0��PMC�̃g�[���{�[�C���q���Œ��������Ƃ��L��܂����A
10W �����Ȃ����̃A���v�ł��A���A���ȉ����K���K���炵�Ă܂�����B
�\����90db���炢�ŁA�U���n�̌y���X�s�[�J�[�Ȃ�A�^��������݂����ł��B
Sa1.0�͍w����A�T�N�قǎg���Ă܂������A�M�����O�G���[���Ђǂ��A�̏�������̂ŁA�c�O�Ȃ��������܂����B
�����A�\�E���m�[�g�̒��ł�Sa1.0����ԍD���ł��B
�{�����[�����A���v�XRK-50�Ƃ��A�����[��P�~�R���A�[�q�ނɐM�����̗L��p�[�c���g���čĐv����A
�����v���C�XUP���Ă� �܂����������Ǝv���A���v�ł��B
���|�[�g�A�Q�l�ɂȂ�܂����B
���� A-�P���������Ă݂����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19814066
![]() 4�_
4�_
C-1�̃h���C�u���J�͂ǂ����ł��傤��
DVD���J�̉��ǔł���
�����ԍ��F19814557
![]() 3�_
3�_
�����́B
�����E�������
�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��B
sa1.0���g�p���Ă��܂���
��ʌ݊��ł���Ȃ�ΐ����������ł��ˁB
�o����\�E���m�[�g�Ōł߂��V�X�e���ŁB
��GR1�t�@������
sa1.0�͌̏ᑽ����ł��ˁE�E�E�E
�t�@���_�����^���̃`���[�����l���Ă��܂�����
�A���v�Ɋւ��Ă͂�������Ă݂����ł��B
�����ԍ��F19858092
![]() 1�_
1�_
�@���X�ǂ��������܂���B->ALL
�@sa1.0�͉ߋ��Ɏg���Ă��܂����B���͋C�ɓ����Ă��܂������A�\��������߂̃X�s�[�J�[�ɍX�����ċ쓮����̂̓L�c���Ȃ������ƂƁA�����R�����������Ƃɑ��ĉƐl����N���[���������̂Łi�j�A��ނȂ�������܂����B�������Ȃ���A�q����X�s�[�J�[�̒�i�̑������ǂ���A���ł����̃N���X�̃x�X�g�o�C�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@A-1�͎d�グ�̓V���o�[�ƃu���b�N������܂����A���ی��������̓V���o�[�̕������X�j���O���[���ɉf����Ɓu�l�I�ɂ́v�v���Ă��܂��B
�@���[�J�[�̃X�^�b�t�̘b�ɂ��ƁA��{�I�Ɍq���X�s�[�J�[�͑I�Ȃ����A�i���Ƃ���FOCAL�݂����Ȕ����������j�ǂ��炩�Ƃ�����PMC�̂悤�ȃ��j�^�[���̓W�J������X�s�[�J�[�̎��������悭�o���Ƃ̂��ƁB
�@�W�Ȃ��ł����A��ؓN���ƃM�^���X�g���V�������ɂ��M�^�[�E�f���I�uNecogi�v�̃~�j�A���o���us�o�r�a�v�����łɔ����܂����B17�����炢�������^����Ă��炸�A���̓_�ł̓R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����̂ł����i�j�A�������ɉ��͗ǂ��ł��B�I�[�f�B�I�̃`�F�b�N�p�ɂ��g�������ł��B
�����ԍ��F19858905
![]() 1�_
1�_
�{���I�N�^�[�u��V80SE������2���Ԓ��������܂����B���z�Ƃ��Ă�V110���r���Ɏv���邭�炢���╪�����ɗD��Č��Ȃȉ����o�Ȃ��ł��B�A�L���̏�ʃv���{A���p���[�ɋ߂���ۂł����ˁB������͋C�����D�����ł����B
����ƒቹ���^��ǃv�����C���Ƃ͎v���Ȃ��o���������܂��ˁB�h���b�v�`���[�j���O�Ń|�����Y���𑽗p����Djent�t�@�Ȃǂ���a�������炵����܂��B���̃f�U�C���Ɖ����Ȃ�A�L����b�N�X�Ɣ�ׂĂ����i�Ό��ʂ͏\���Ɍ����߂�Ǝv���܂����B
�����ԍ��F19756600�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����͂���
V80SE�w���҂ł��B
���̐��i�̌��R�~�����߂Ă݂Ċ������ĕԐM�����Ē����܂����B
���͍w����4�����o���A����Ɗ��炵���I����������ł��B
�����C���P�[�u���Ɠd���P�[�u����F�X�����Ă���Œ��ŁA���̐��i�̐��\�������o�����ߎ��s���뒆�ł��B
�������́A�u���b�N�{�b�N�X�ł̂������������̂ł��傤��?
�����ԍ��F19827046
![]() 0�_
0�_
LP-2020�������P
LP-2020�̉��������P�����Γ̗��Z���Љ�܂��B
���ɒቹ�̏o�Ȃ��A���^�t�������W�X�s�[�J�[���g���Ă�����ɂ͍œK�ȕ��@�ł��B
��p�͂킸�����P�O�O�~
�S����������ɂ��������ɒቹ�����܂��B
![]() 5�_
5�_
LP-2020�������P
�ȑO�ALP-2020�Ƀw�b�h�z����ڑ����āA����AMP�͌y�����ׂ̎��͍ō��̉��ɂȂ邱�Ƃ��A�m�F���܂����B
���A
60���F8���i�T���X�CST-60�j�̃g�����X���g���ăX�s�[�J�[�ɂȂ��Ɠ��l�ɍ��𑜓x�̉�
�ɕς�邱�Ƃ��m�F���Ă܂��B
���ǂ��̃A���v�͒�C���s�[�_���X�ł͖{���̎��͂��o�Ă��Ȃ��̂ł��B
���ȒP�ȕ��@�ʼn������P�ɐ������܂����B
10���i�Q�v�j�̒�R���X�s�[�J�[�ƒ���ɂȂ������ł��B
�S��ň������܂��āA���𑜓x�ɂȂ�܂��B
�ቹ�̓X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�������Ȃ�ׁA��R�������܂���̂ŁA
�������背�x���������Ȃ�܂��B
�A���A�X�s�[�J�[�̓��́A������͍ő�Q�v���x�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F19656338
![]() 4�_
4�_
��anallog 33����
������(^_^)/
�����̒��ł̓䂪�܂�������܂����B
��Ȃǂ̍����x�P�[�u���قlj���������
�����ȃP�[�u���قǏ��x�ɍS�炸��R�l�������悤�Ȋ��������Ă܂����B
�܂��A�ǂ��P�[�u���͉����������̂ŁA�A���v�̃{�����[�����グ��K�v������܂���
�������l����ƁA�R�O�OW�ȏ�̃n�C�p���[�A���v�ŃP�[�u���̊Ԃ�100�����Ƃ��q�����琦���̂��ȁH
�����ԍ��F19658011
![]() 4�_
4�_
���ׯ�� ��ׯ�� ��۲����
���e���肪�Ƃ��������܂��B�@���̕��@�ł̓X�s�[�J�[�E�R�[�h�ׂ͍��`�b�R�[�h�ŏ\���ł��B
�`���l���E�f�B�o�C�_�[���g�����}���`�A���v�E�V�X�e�����R���p�N�g���A��������������ׁA�������Ă��܂��B
���̊��ł́A�����p�A�����p�ɂ͐��v����Ώ\���ł��B
�ቹ�͎s�̂̃T�u�E�E�[�n�[���g�p���Ă��܂��B
���A�����������͒�R�l���P�O���`�P�T�����@�X�s�[�J�[�ɂ��œK�l���Ⴂ�܂��̂ŁA���ӂ��ĉ������B
�ŏI�������͂P���P�ʂɍs���Ί����ł��B
�܂��͂P�O�����珉�߂āA�������B
�s�̂̃T�u�E�E�[�n�[�@1��@�@LP-2020�@2��� �`���l���E�f�B�o�C�_�[�ŊȒP�Ƀ}���`�A���v�E�V�X�e�����ł��܂��B
�����ԍ��F19660385
![]() 3�_
3�_
��anallog 33����
�����_���ł��ˁB�@��R���X�s�[�J�[�ɂȂ��ƒቹ�̓X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�������ׁA�������背�x����������Ƃ�
���̍��܂Œm��܂���ł����B
�����@�͑��̃v�����C���A���v�ł��L���ł��傤���H�@���������Ȃ�[���\�[���P�ɑ�\�����ቹ�̏o�Ȃ��X�s�[�J�[�ւ�
�Ώ��@�ɂȂ�܂����E�E
�����ԍ��F19661087
![]() 2�_
2�_
�@�X���傳�Ӑ}���Ă���Ă��邩�ǂ����͕s���ł����A���̕��@���g���ƃX���傳�����Ă���悤�ɓ����ɕω��������܂��B
�@�Ⴆ�A�A���v��10���̒�R������ԂŁA�t�H�X�e�N�X�̃X�s�[�J�[FF165WK�ɐڑ������ꍇ���l���Ă݂܂��B
�@�A�b�v�摜��FF165WK�̃C���s�[�_���X����������ƁA50Hz z=64���A1KHz z=10���̃C���s�[�_���X�i��R�l�j�ɂȂ��Ă܂��B
�@�o�̓C���s�[�_���X0���̃A���v�ɒ���10��������ƁA�o�̓C���s�[�_���X��10���ɂȂ�A��R�����ʼn������v�Z����ƁA50Hz�̉�����-1.26dB�A1KHz�̉�����-6.0dB�ɂȂ�܂��B1KH������l0dB�Ƃ����50Hz�ł́A+4.74dB�ɂȂ�A���Ȃ�ቹ����������邱�Ƃ��킩��܂��B
�@�ȏ�̂悤�ɂ���20Hz�`20KHz�͈̔͂ōׂ����v�Z����A������R������Ԃł̃X�s�[�J�[���g�������̃O���t�𗝘_�I�ɋ��߂邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
�@���̕��@���g���āA�C���z���̎��g��������ω������邽�߂̒����R����̉����R�[�h��t���œY�t���Ĕ̔����Ă��郁�[�J�[������܂��B�iETYMOTIC RESEARCH��ER4PT�F�����������グ��ER4S�̓����ɕς��� �j�������A���̕��@�̓X�s�[�J�[��C���z���̃C���s�[�_���X�����Ɉˑ�����̂ŃC���s�[�_���X�����̕ω������Ȃ����̂͌��ʂ������Ȃ�܂��B�Ⴆ�A�C���z���̃C���s�[�_���X���������l�őS���ω����Ȃ��ꍇ�́A��d���쓮�Ɠ�����ԂɂȂ�A��R�����͏�Ɉ��ɂȂ�̂ŁA���g���ɂ�鉹���̕ω��͐����܂���B
�@���������̎�@�ɂ͌��_������܂��A�C���z���Ȃ�قƂ�ǖ��ɂȂ�܂��A�X�s�[�J�[�̏ꍇ�́A�_���s���O�t�@�N�^�[��������̂ŁA�E�[�t�@�[�̋t�N�d�͂��z���ł����Ƀ{���[�Ƃ������܂�̂Ȃ��ቹ�ɂȂ��Ă��܂��ꍇ������܂��B���̂ւ�ɋC��t����ΗL���Ȏ�i�Ƃ������܂��B
�����ԍ��F19662316
![]() 1�_
1�_
��HDMst����
�F�X��肪�Ƃ��������܂��B�X�̓������Ⴄ�̂ŁA�������Č��Ȃ��Ƃ킩��܂���B
���p�C������
���e���肪�Ƃ��������܂��B��ϊ��ӂ��Ă���܂��B�@�[����������Ă���A������������K�v������܂���B
����
LP-2020�̉������P�̎����ł����Ȃ��Ă��܂��܂����B���̃A���v�͒�C���s�[�_���X�Ɏア�l�ł��B
�g�����X�g���Ɨǂ��Ȃ�̂ł����A�A���v�Ɠ����ʔ�p��������̂ł����߂ł��܂���B
�����ŁA��R�ł͂ƁA����Č����特�����悭�Ȃ�A�ቹ�����P����܂����B
�p�C������̐����̗l�ɒቹ�̃_���s���O�t�@�N�^�[�ቺ�ɂ͒��ӂ��K�v���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19663496
![]() 2�_
2�_
http://info.shimamura.co.jp/digital/knowledge/2014/01/16805
����ɂ��W���Ă�̂ł��傤���H
�����ԍ��F19664137
![]() 2�_
2�_
�@HDMst����ցA
�@��R�����̘b���܂܂��̂ŁA�W���Ă邩�ƕ������A�����͊W���Ă�Ƃ����܂��B
�@�A���v�̓��o�͂́A���[�o���n�C����{�ɂȂ��Ă܂����A600��-600���̎n���́A�M���̓d�����v�Z���₷���̂ŁA���X�j���O�|�C���g�œ���̉������x�����K�v�ȏꍇ�Ɍv�Z�����₷���Ȃ�A�Ɩ��p�Ƃ��Ďg���ꍇ�͕֗��ł��B
�@�Ⴆ�v���A�E�g�̏o�͂̍ő�d����2V�̏ꍇ�A600��-600���Ńp���[�A���v�Ɏn���ƁA��R�����Ńv����1V�A�p���[�A���v�̓��͕�����1V�ƂȂ�̂ŁA���̃p���[�A���v�̓��͊��x�̋K�i������1V�Ȃ�A�A���v�̃{�����[�����ő�̈ʒu�ɂ���ƁA���̃p���[�A���v�̒�i�o�͂�������Ƃ������Ƃ��A�d�l��������A���������v�Z���Ȃ����킩��܂��B�Ȃ̂ʼn����ݔ���ݒ肷��ꍇ�͂ƂĂ��֗��ł��B
�@���������̏ꍇ��2V�ő����1V�̓��͐M���ɂȂ��Ă��܂��̂Ō����������Ȃ�܂��B
�@��ʉƒ�Ŏg���ꍇ�́A���̂悤�Ȍv�Z�͑S���K�v�Ȃ��̂ŁA���[�o���n�C�ɂ��Ă����Ό����悭�M�����`���܂��B�Ȃ̂Ń{�����[�����グ���ɂ��ւ�炸������������������Ƃ����g���u�����Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B
�@�ŋ߂̃A���v�̓��̓C���s�[�_���X�͂قƂ�ǂ�47K���ʂɐݒ肳��Ă�̂ŁA2V�̐M����600��-47K���Ŏn����,1.97V�̐M����������܂��A��قǂ̃A���v�ł����A�{�����[�����ő�ɂ��Ȃ��Ă��A��i�o�͂��ȒP�ɓ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�܂��t�̏ꍇ�A�n�C�o�����[�ɂ���Ǝ��̓d�����������Ȃ��A���ׂ��傫���Ȃ�A�d���~�����������Đ��m�ȐM�����n�����ł��Ȃ��Ȃ�A����������ɘc�ޏꍇ������̂ŁA���̐ڑ����g���邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�M���̓����ɂ��Ăł����A�A���v�̓��o�͂̃C���s�[�_���X�́A���g���ɂ���ĕω����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�X�s�[�J�[���Ȃ����̂Ƃ��̂悤�ɁA�C���s�[�_���X�ɂ���Ď��g���������ω����邱�Ƃ͂���܂���B�i��d���쓮�ɂȂ�܂��j�B�Ȃ̂Ń��[�o���n�C�̏ꍇ�́A���o�͂̃C���s�[�_���X�͂��낦�Ȃ��Ă��A�M���͐��m�ɓ`��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���[�J�[���A���v�́A���̓C���s�[�_���X�������Ă��A�����ɉe������قǂ̃m�C�Y�͓���Ȃ��悤�ɐv���Ă���̂ŁA�C�ɂ���K�v�͂���܂���B�i�m�C�Y�̏�Ԃ𑪒肷������킩��܂��j
�����ԍ��F19664590
![]() 1�_
1�_
�p�C������d�C�ɐ������ڂ����ł��ˁB������肪�Ƃ��������܂��B
�������w������(�ȉ��H�E�E)���w�͂̎��ɂ͗�����������̂�����܂��B
���[ �n�C�ŕ�����̂͂��ꂭ�炢�ł��B
https://www.youtube.com/watch?v=MSHr4ubuD64&ebc=ANyPxKrOmer-X1MYgzRXkT7-l6gx7zocK9NNamaIQun_wNPHMS57k_ib-uSwW9AJFVfv-i0Rju0HzKHvhnciaDg5Q9x2aCLSJQ
�����ԍ��F19664907
![]() 3�_
3�_
�킩��ɂ����̂ŁA�����̉摜���t�o���܂����B
�I�[���̖@����m��Ȃ��Ă��A���ʂ̃C���[�W�������Ē�����Ηǂ��Ǝv���܂��B
�A���v�̏o�͂�
������ł͂W�W�@�ɁA�@�ቹ�̂��O�ł́@�W�S�Q�@�ɓd�͂����z����܂��B
���̗�̗l�ɂ��O�t�߂ł͒�R�ɂ�鑹�������Ȃ��A�d�͂̂قƂ�ǂ��X�s�[�J�[�ɓ`���܂��B
�����܂��ɕ߂炦�Đ�������A���̒�R�Œ�����̃��x����������B�Ƃ������ł��B
�����ԍ��F19667337
![]() 0�_
0�_
����܂ŁA�ȉ��̍\���Ŋy����ł��܂����B
�A���v�F�}�����cPM8003
CDP�F�}�����cSA7003
NOP�F�}�����cNA7004
SP1�F�_�C���g�[��DS-77Z
SP2�F�_�C���g�[��DS-200ZX
���ɉ����I�ɕs�����������킯�ł͂���܂��A�����Č����A77Z����200ZX�ɐ�ւ����ۂɒቹ���X�J�X�J�ɕ������A
�V���J�V���J��������̂������C�ɂȂ��Ă��܂����B
(�ŏ�����200ZX�Œ����Ă���Ƃ��͂����܂Ŋ��������Ƃ͂���܂���ł������c)
���y�̃W�������Ƃ��Ă̓N���V�b�N�A90�N��JROCK�A90�N��Being�n�������ł��B
�����ŁA�_�C���g�[�������t�I�N�Ń|�`�����Ƃ�����C�ɂȂ��Ă����T���X�C�̃A���v����r�I�ǂ���Ԃŏo�i����Ă����̂�
�|�`��܂���(��)
AU-��607NRA2�Ȃ̂ŁA���݂̃A���v�Ɠ��O���[�h�������͌o�ߔN�����l������ƃ_�E���O���[�h�ł����A�T���X�C�̃A���v�Ƀ_�C���g�[���̃X�s�[�J�[�Ƃ������N�������g�ݍ��킹���悤�₭�������܂���(��)
�����ڑ����ĉ��o�����Ă݂�ƁA�������ɏd�_���u����Ė��t������PM8003�Ɣ�r���Ă��������͓����������͂���ȏ�A�ቹ��PM8003���o�Ă��銴�������āA200ZX�ɐ�ւ��Ă���������O�ɏo��悤�ɂȂ�܂����B�T���X�C�t�@�������ł�����������������̂������܂����B
�A���v�ƃv���[���[�̓��ꊴ�͕���Ă��܂��܂������A�ǂ�����Ƃ���NRA2�̊O�ς���D���Ȃ̂ŁA�S�Ăɂ����Ė����̂����O���[�h�_�E��(�H)�ɂȂ�܂����B
![]() 6�_
6�_
�T���X�C�̃A���v�@�m���Ɍ�����̂����݂�����܂���ˁB
���̃O���[�h�_�E���ɂ́@����Ƃ�����̎������� �����߂��܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9583104/?Reload
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000234852/SortID=18757598/?Reload=
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000234852/SortID=18757598/?Reload=
�����ԍ��F19565167
![]() 1�_
1�_
�Nj��A���v�ł����B
�e������N��̎�ŊNj��A���v������ĂāA
���ƂɋA�������ɒ����Ă܂���B
����ƌ����ǂ����X�����������܂���(*^^*)
�����͂܂��q�����������̂ŁA�傫���Ȃ�܂ł�
���̃V�X�e���Ōq�����Ǝv���Ă܂���B
�����ԍ��F19567117�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�q�[�A���ӂ́B
����ɔ������āI�A�y��"�c�b�R�~(���ӂ͂���܂���I)��\���܂��B����I�B
��U�O�V�Ń����N�_�E��(�H)�c�c�H��ł����I�A�����z���܂��̂ɁH�A������"�U�O�V"���ƁH�A�������炩�Ƀ����N�A�b�v�Ɉׂ����v���܂���I�B
�������s�̃}�����c�O���[�h���ƁH"�P�S�ԃN���X"�Ɉׂ锤�Ȃ�ł����H�B(����I�ɂ����m�����̂��ȁH)
�b�����ז��v���܂����I�B
�������炸�A�h��B
�����ԍ��F19567494
![]() 3�_
3�_
�����̕��ʓ�������ƌ��s�ł�20�`30���N���X��
�����̂͂ǂ����ŕ��������Ƃ���܂�(��)
����ōl����Ɗm���Ƀ}�����c��14�ԃN���X��
�Ȃ�܂��ˁB�����A������607�V���[�Y�̓G���g���[
�N���X��507�̏�Ȃ̂ŁA���s�ōl�����8005
������ɑ�������̂��Ȃ�(((^_^;)
�����ԍ��F19567532�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��ׂ��炩�킢�����ł��B
���オ�Ⴂ�܂��B
�����Ƃ����߂�70�N��80�N��ł��B
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=19570025/
�T���X�C�Ő���オ�蒆�Ȃ�ŁA����Ƃ��Q���������B
���Ȃ݂ɂ��̐l�͌��s�A�L���̃Z�p�����507ux����̃T���X�C�ł��B(��)
�����ԍ��F19574215�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�́A�p�C�I�j�A��SA8800�U�ʼn��y���Ă������Ƃ�����܂��B
�������e���̂ł����B
���ꂩ��}�����c��PM-80a�ɕς����킯�ł����A�t�����g�̃c�}�~���啪�X�b�L�������Ȃ��Ƃ�����ۂł����B�ܘ_�����ς��܂�������(��)
�A���v�Ƃ��Ă�70�N���80�N��̂��̂͂����̂ł��傤���A�c�}�~���炯�̃t�����g�p�l����A���[�^�[�͂ǂ����D���ɂȂ�Ȃ���ł�(((^_^;)
90�N��̃X�b�L���Ƃ������b�N�X���D�݂ł��B
�����ԍ��F19574314�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Ȃ�قǁI
�m���ɃV���o�[�œ��ꂳ��Ă܂��ˁI
�O��SA8004���g���Ă܂������A�����v���X�`�b�N�Ȃ�ł���B
�h���C�o�[��������Ɏ��܂����B
�ŁA�C���V��3�_�x���ɂ��ꂽ�猋�\���ʂ���ł����B
�_�C���g�[���̃X�s�[�J�[���Y��ł��ˁ[�B
�ؖڂ��������B
�Ȗʂ��������B
���������������ȁ[�B
�����ԍ��F19574367�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��77Z-200ZX����
�͂��߂܂���
��傤��������̌���
�����Ȃ݂ɂ��̐l�͌��s�A�L���̃Z�p�����507ux����̃T���X�C�ł��B(��)
���̒��{�l�ł��i�j
�Y��ȃV�X�e���ł��ˁI
�_�C���g�[���̒��x���ǂ������B
SANSUI�����ł���ˁA�����������̓S���[�J�[�ł��i���ށ��j
�����ԍ��F19574470�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��傤��������
�_�C���g�[����2��ނƂ����t�I�N�ŏ�Ԃ��������̂��|�`�b����ł�(��)77Z�Ɋւ��ẮA1�O��77HRX�Ɛ��������܂������A77HRX�̓��j�b�g�t���[���̃A���~�_�C�J�X�g�����C�Ȃ��߁A���H���Ă�����̂�A4�T�C�h���E���h�o�b�t�������̌p���ڂ��牻�ϔ�������Ă�����̂��������߃p�X���܂����B
���Ɋւ��ẮA���^���L�̃^�C�g�Ȓቹ���S�n�����ł��B�^�C�g�ł���Ȃ���Ȃ��炩�Ȍ����J�[�u�̒ʂ茋�\���܂ŐL�т܂��B�ŋ߂̂����������鏬�^�o�X���t�ł��o�����Ƃ��ł��Ȃ����ł��B
�G�b�W�͏����d�߂������̂ŁA��������u���[�L�t���[�h��h���ē�����Ă��܂�(��)
200ZX�́A�ቹ���X�|�C����������ɒ������������ƑO�ɏo�Ă��邽�߁A�{�[�J�����ɂ͍œK�ł��B���^2way�̃o�X���t�ł����A�ŋ߂̒ቹ�����������悤�Ȃ��̂ɔ�ׂ�Ɛ����^�C�g�ȉ��ł��B�����Đ��ɍS�����_�C���g�[���炵�����ł��B
�O���A������
�O���A������̏������݂͂����y���݂Ɍ��Ă��܂��B�V�������m�̃��r���[���A�Â��ǂ�����̎Y���̃��r���[�̕������Ƃ��Ă͌��ĂĊy�����ł�(��)
���X�j���O�����V�X�e���������ǂ����̂��������̂悤�ŁA���݂����ɃS�~���W�߂ĕ��u�����ɉ������݂Ȃ��炱����܂蒮���Ă���̂Ƃ͖Ⴂ�܂���(��)
�T���X�C�̃A���v�͐̂��瓲��Ă܂����B�e���̉e���ŃI�[�f�B�I�ɏ��������������n�߂����́A������������T���X�C�̃A���v�ƃ_�C���g�[�������Ƃ��Ă����̂ł����A���������o�����ɂ͂ǂ���������Ȃ��Ă���A�����킸���_�����v���o������܂�(T^T)
�T���X�C�̃A���v��MR�ȍ~�̃��m�ŒT���Ă��܂����B907�n�͒��Âł����\�Ȓl�i������̂ƁA�X�s�[�J�[�[�q���̊W�Ńp�X�ACP���ǂ�707�n��607�n�ɍi���Ă܂����B����^�ǂ�607�n�Ō�(MOS Ltd�͏���)��NRA�U���o�Ă܂����̂ŁA�䂪�Ƃ̍�����b�Ɍ����āAPM8003���I�[�N�V�����ɏo���ĉ���肷��̂������ɏ���������ꂽ�̂Ń|�`��܂���(��)
���Ɋւ��ẮA�������܂Ńo�����X���ǂ��A�c�̂��鉹���o���܂��ˁB������20�N�߂��O�̃��m�ł����A�ŋ߂̃A���v�ɑS�R�����Ă��܂���B
�����ԍ��F19574564�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��77Z-200ZX����
��͂�t����Ɏh�����������̋@������A��l�ɔ����Ă���l�������̂ł��傤�ˁB
���Îs����T���X�C�A�_�C�A�g�[���A���}�n�AJBL���̓����l�C�������@��͍��ł����\�����l�����Ă܂�����ˁB
�����������ƃ����e���Ă��铖���̓���̋@�킪���ƃ��[�Y�i�u���ɔ�����̂͂��肪�����ł��B
�������_�C�A�g�[���͂܂����o���Ȃ̂ŋ@�����Γ������Ă݂����ł�(^^��
�����ԍ��F19574664
![]() 0�_
0�_
�O���A������
�_�C���g�[���Ɋւ��ẮA���[�J�[�Ƃ��Ă�DS-1000�V���[�Y�����t�@�����X�Ƃ��Ă����悤�ŁADS-10000��DS-20000�V���[�Y�Ƃ��������ʎd�l�����ꂪ�x�[�X�ƂȂ��Ă��܂��B���Ƃ��ẮA27cm�̃E�[�t�@�[�͂�����ƒቹ�s�����Ɗ�����̂ŁADS-2000�V���[�Y���o�����X�������Ǝv���̂ł��B�����A�{�����X�R�[�J�[�͎��̎��ɂ͍���Ȃ��炵���ADS-77�n��DS-800�n�̂悤�ȃR�[���X�R�[�J�[�̕����q���肪�ǂ��������Ă��܂��܂���(��)
�O���A������ɂ́A�l�I�ɂ�DS-V3000��V5000�������_���ė~�����Ǝv���Ă܂�(*^^*)
�����ԍ��F19574791�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��77Z-200ZX����
�_�C�A�g�[����SP�͒��Âł��܂Ɍ����������̃E�[�n�[�������Ă݂�̂ł���
��̃R�`�R�`�Ɍł܂��Ă�̂ł��ꂪ�ቹ�s���̌����Ȃ̂��Ȃ��Ďv�����肵�Ă܂��B
�Ȃ̂ŃE�[�n�[�G�b�W�̓�����͕K�{�ł��ˁB
������1000HR�Ƃ��ɓ���č��ł��C�ɂȂ��Ă܂��B
�����ASP�X�^���h����1000�p��������KENWOOD�ڂ��Ă܂����B
���ł��X�^���h�����Ă܂�(��)
�����ԍ��F19574819
![]() 0�_
0�_
�E�[�t�@�[�̃r�X�R���C�h�ƌĂ��_���v�ނ͊m���Ɍo�N�ɂ��d�����Ă�����̂������ł��ˁB�V���R�����~�l�[�g�N���X�G�b�W�ɒ���ւ���̂���Ԃ����̂ł��傤���A�_�C���̃E�[�t�@�[�̏ꍇ�͉��^�̒���ւ��ɂȂ�炵���A������ƐG�肪�����܂���B���i�����\����悤�ł����B
�Ȃ̂ŁA�݂Ȃ���V���i�[�ł��������Ƃ��ĉt�̃S����h������A�N���|����A�[�}�I�[����h���ă}�b�T�[�W�����肵�ē�����Ă�悤�ł��B
�N���|���͍ŏ��ɓh���Ă݂܂������A���ǃG�b�W�����̃r�X�R���C�h�ɂ͑S�����ʂȂ��̂ŁA�u���[�L�t���[�h�œ�����Ă��ł�(��)
���m�����m�����ɁA�����߂͂ł��܂��A����ʂƎ����͔͂��Q�ł��B
1000HR�͂����X�s�[�J�[���Ǝv���܂���B����2000HR�̃E�[�t�@�[�̌����ڂ��l�I�ɔ��Q�ɍD���ł����ǁB
�����ԍ��F19575241�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���A�������������̓v�����C���A���v�̔ł���(((^_^;)�X�s�[�J�[�̘b�͂܂��ʂ̋@��ɁB
�T���X�C�̃A���v�Ɋւ��āA���_�����f���������ł��B
�@���͍��̂Ƃ��낷�����͂Ȃ��̂ł����ANRA�U���v���A���v�Ƃ��āA���̃p���[�A���v���ɐڑ�����悤�Ȏg�����͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H
�Ƃ����̂��ANRA�U�ɂ̓v���A�E�g�[�q�̂悤�Ȃ��̂���������Ȃ����߂ł��B
�A�t��NRA�U���p���[�A���v�Ƃ��āA���̃v���A���v����ڑ�����ꍇ�A�p���[�A���v�_�C���N�g�[�q2�n���̂ǂ��炩���g�p��������̂ł��傤���H
�Ƃ����̂��A�p���[�A���v�_�C���N�g�[�q�ɐڑ����Ă��{�����[���̓X���[���ꂸ�A���ʒ��߂��ł��邩��ł��B���̃v���A���v��ڑ������ꍇ�A���ʒ��߂��ǂ���ł��ł��Ă��܂��܂���ˁH
�BMR���ɂ̓p���[�A���v�_�C���N�g�[�q�̑��ɁA�\�[�X�_�C���N�g�X�C�b�`�����Ă���悤�ł��B
(NRA�U�ɂ̓\�[�X�_�C���N�g�X�C�b�`�͕t���Ă܂��A�Ȃ����������������ł���H)
����́A�v�������X���[���ăp���[���ɒ�������悤�Ȑڑ��ɂȂ�Ǝv���̂ł����A�p���[�A���v�_�C���N�g�[�q�Ƀv���[���[���̋@���ڑ�����̂Ɖ����Ⴄ��ł��傤���H
�����A�@�\�I�ɓ����Ȃ̂ł���A�Ȃ�2�ʂ�̐ڑ����ł���K�v���������̂ł��傤���H
�v�́A�T���X�C�v�����C���A���v�̎g�p���@���C�}�C�`�s���Ƃ��Ă��Ȃ���ł��B
�Ⴆ�ANRA�U�̑O�Ɏg�p���Ă����}�����c��PM8003�́A�v���A�E�g�[�q�A���C���C���[�q�A�\�[�X�_�C���N�g�X�C�b�`�����Ă���A�v���A���v�Ƃ��Ă̎g�p�A�p���[�A���v�Ƃ��Ă̎g�p�A�v�����X���[�Ńp���[�������̎g�p�A�v������ʂ����v�����C���A���v�Ƃ��Ă̎g�p�ƁA�@�\�Ƃ��Ċ��S�ɕ������Ă������ߕ�����₷��������ł��B
�����ԍ��F19578504�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��77Z-200ZX����
�@SANSUI AU-��607 Mos Premium�����L���Ă���҂ł��B������̔ł��Ȃ�O�Ɏ��₳���Ă���������
�̂ł����p���[�A���v�_�C���N�g�[�q�̓��C�����͂̂悤�ł��BMAIN-IN �Ǝv����AV�A���v(YAMAHA
RX-V773)��PRE-OUT�[�q���� 607 �� �p���[�A���v�_�C���N�g�[�q�Ɍq���ł݂����̖��悤�ȉ�����
���܂���ł����B�@CDP���q���ł݂��畁�ʂɉ��������̂Ń��C�����͂̂悤�ł��B
�@SANSUI��MAIN-IN PRE-OUT�[�q�̕t���Ă�����̖̂ڈ��́AD�V���[�Y�ȑO��X07�̌��F���G��
�炪�t���Ȃ����̂炵���ł��B���ہA�ŋ�H/O�� AU-D607(AU-607�����������H)�̎��������āA�w�ʒ[�q
��PRE-OUT��MAIN-IN��������Ă���̂��m���߂܂����B
�@���V���[�Y�̍����@�ɂ̓o�����X���͒[�q���t���Ă��܂����AMAIN-IN�APRE-OUT�[�q�̑���Ɍ�
���Ă��܂��܂��B�܂����̓�����̂���(��̓I�Ȍ^�Ԃ≹��)�͑��ɂ��ڂ���������������������Ǝv
���̂ł����̕�����̓��e�����҂����������B
�@�u���[�L�t���[�g�͌��ʂ�����܂������I�H���͍ŋ�DS-251 MK�U�̃G�b�W������݂܂����B�N���|��
���C�g�͊����̌��ʂ��������܂������A�܂��܂��\���ł͂Ȃ�(��)�Ɗ����Ă��܂��B���̂���(�D�揇�ʂ͒Ⴂ)
����Ă݂������Ƃ̈�ł��B
���n���̃��T�C�N���V���b�v�ɏo�Ă���DS-251 MK�U�̃G�b�W�ɔ�ׂĂ܂��d���ł��B
�����ԍ��F19581641
![]() 1�_
1�_
�I�[�f�B�I�̑��ՂɁA���̃A���v�̃u���b�N�_�C���O����������܂���B
http://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-alpha607nraii(8).JPG
�p���[�A���v�_�C���N�g�́A�v�����̂��ׂĂ��p�X���āA�����ʂ�p���[�A���v�ɒ����ł��ˁB
T-KAWA ����̐����ŏ[�����Ƃ������̂ł����A���������������c���Ă���̂Ń����N���Ă݂܂����B
�l�̌l�I�Ȉӌ��ł����A�v�����C���A���v�́A�v���Ƃ��Ďg���A�p���[�Ƃ��Ďg���Ƃ��������A�P��➑̂Ƀv�����ƃp���[���������Ă���̂��ő�̗��_�ł���Ƃ������̂ŁA�Ɨ������g�������Ă̂͂��܂�l���Ȃ��Ă�������Ȃ����Ȃ��Ƃ�
�Z�p���[�g�̕����㋉�I�ȍl���̐l�������̂ł����A�悭�ł����v�������ƁA�������x���ō��ꂽ�Z�p�ł́A���炩�Ƀv�������̕����L���Ȗʂ������ł��B���ɁA�R���̃v�����C���A���v�́A�u�Ë��v�����Ȃ������x�������̂ŏ��X���Ǝv���܂��B
�p���[�A���v�Ƀ{�����[�����t���Ă��闝�R���Ă̂͂���܂���
���̃p���[�A���v�Ƒg�ݍ��킹�āA�o�C�A���v�ȏ�̃}���`�A���v��g���ɃA���v�Ԃ̃��x���������K�v�ɂȂ鎖������̂ŁA���̒��߂̂��߂ɂ��������������B
�Ƃ����̂���ԑ傫�ȗ��R�ł��B
�����ԍ��F19582227
![]() 2�_
2�_
T-KAWA����
�������L���������܂��B
�Ȃ�قǁA�P�Ȃ郉�C�����͒[�q�Ƃ��Ă̈����Ȃ�ł���(((^_^;)
�Ƃ������Ƃ́A�v���A���v�Ƃ��Ă��p���[�A���v�Ƃ��Ă��g�p�ł��Ȃ��A�����ȃv�����C���A���v�ƂȂ��ł���(��)���������A�ȑO�g���Ă�PM-80a�ɂ����̂悤�Ȓ[�q�͖��������悤�ȁB
��̋����悤�ȉ����Ă��Ƃ́A�T���X�C�������}�n�����{�����[�����߂��ł��Ȃ������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B
�p���[�A���v�_�C���N�g�[�q�����C�����͒[�q�Ȃ̂ł���AMR���ɂ���\�[�X�_�C���N�g�X�C�b�`�Ɠ����ɂȂ�܂��ˁB�����@�\���Ȃ��ʁX�ɑ��݂��Ă����̂ł��傤��(��)���l����Ƃ�����ƕs�v�c�Ɏv���܂��B
�u���[�L�t���[�h�Ɋւ��ẮA1�N�͗]�T�Ō��ʂ��������܂��B�h����30������1���Ԓ��x�ŏ_�炩���Ȃ�܂����瑦����������܂��B
�����A�����܂ł����ȐӔC�ƂȂ�܂��̂ŁA���̓_�͗��ӂ��Ă����ĉ������B
�����ԍ��F19582229�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
Whisper Not����
�����肪�Ƃ��������܂��B
���Ƃ��Ă̓Z�p���[�g�Ƃ��Ă̎g�p�͑S���l���Ă��Ȃ��̂ł����A�u���b�N�}�������ۂɁA�{�����[���t���̃p���[�A���v�Ƃ��Ă̎g�p�͂ł���̂ł́H�ƒP���Ɏv���������Ȃ�ł���B
���X�T���X�C�̓g�����X���[�J�[�Ƃ��Ă��̒n�ʂ�z�����̂ŁA�p���[�u���b�N�ɂ͐�̎��M������A�h�v���A���v�Ƃ��Ă͎g���ȁI�p���[�A���v�Ƃ��Ă͂�����̃��[�J�[�ɂ͕�����I�h���炢�Ɍ����Ă���̂��ȂƏ���ɑz�����Ă܂���(��)
�����AT-KAWA����̕��Ńp���[�A���v�Ƃ��Ă̎g�p�͂ł����A�P�Ȃ郉�C�����͂Ƃ��������ɂȂ�Ƃ������ʂ������Ƃ̂��Ƃ���AMR���ɂ̓\�[�X�_�C���N�g�X�C�b�`���݂��Ă���v�����X���[�Ńp���[���������ł���̂ɁA���ł킴�킴�p���[�������p�����ɕʒ[�q�Ƃ��Đ݂��Ă���낤���H�ƕs�v�c�Ɏv��������ł��B
���͌��݁A�p���[�A���v�_�C���N�g�[�q��NA7004��SA7003��ڑ����Ă��܂����A���܂ɂ̓v������ʂ������������Ă݂����Ȃ邱�Ƃ����邽�߁A���̓x�ɗ��̒[�q��ڑ��������̂����ɖʓ|�L�������Ă��܂��B
�Ȃ̂ŁA�ǂ����������Ȃ�\�[�X�_�C���N�g�X�C�b�`�ł͂Ȃ��A�p���[�A���v�_�C���N�g�[�q�̕������悩�����̂ɂƂ�����Ǝc�O�Ɏv���̂ł��B
�����ԍ��F19582522�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���ǂ����������Ȃ�\�[�X�_�C���N�g�X�C�b�`�ł͂Ȃ��A�p���[�A���v�_�C���N�g�[�q�̕������悩�����̂ɂƂ�����Ǝc�O�Ɏv���̂ł��B
�܂���
����Ӗ��A�ґ�ȔY�݂ł���˂�
��傤�����В���A�O���A�����U��������B�Ɩ��x�y��������Ă�̂ł����A707�f�B�P�C�h�̃X���ŃC�V�m���{����ւ̃����N��\���Ă����܂����B
�_�C���g�[���ƎR���͈ꎞ���AOEM��g�Ȃ�Ă��Ă��肷���ł���A�ǂݕ��Ƃ��Ĕ��ɖʔ����̂Ő���݂Ă݂Ă��������B
�_�C���g�[���̃X�s�[�J�[�ɂ��Ă��A�R���̃A���v�ɂ��Ă��A�ǂ��ł��Ă��܂���ˁA�悭�ł��Ă���Ƃ������A�R�O�N�O�Ɋ��ɁA����ł��ʗp����ǂ��납�A����@�ł������ĂȂ����Ɏ���o���Ă����Ǝv���܂��B
�l���A�_�C���g�[���̂W�O�N��̃X�s�[�J�[�ƎR���̑g�ݍ��킹���Ă̂͑�D���ł���B
�����ԍ��F19582614
![]() 1�_
1�_
��77Z-200ZX����
>���͌��݁A�p���[�A���v�_�C���N�g�[�q��NA7004��SA7003��ڑ����Ă��܂����A���܂ɂ̓v������ʂ���
���������Ă݂����Ȃ邱�Ƃ����邽�߁A���̓x�ɗ��̒[�q��ڑ��������̂����ɖʓ|�L�������Ă��܂��B
�@���̏ꍇ�͂Ȃ��@�ނ�CDP�ƃ`���[�i�[���炢�̂��̂������̂Ńv�����ɂ͂Ȃ����A�p���[�A���v�_
�C���N�g�ɂȂ��ł��܂����B���X�n���̃��T�C�N���V���b�v�Ŕ��N�ȏ㔄�ꂸ�ɂ����̂��Ă݂�
(�Ŕ���16,000�~)�Ƃ������̂ŁA�o�����X�[�q���t���Ă����̂Ńo�����X�ڑ��̉��Ƃ������̂��Ă݂�
���ăI�N�ł��̂��߂�CDP(DENON DCD-1650GL)�܂Ŕ����܂����B�o�����X�ڑ��͉����܂�ׂ�Ȃ��o�Ă�
�銴�������܂������AJAZZ�A�t���[�W�������̂ł��܂������킸�A�����ŃC���e�O�e�[�e�b�h�|�W�V������
�͉��������Ă���悤�Ȃ��s���R�Ȉ�ۂ�����A�p���[�A���v�_�C���N�g����Ԃ������肢�����ł����B
�܂��A�C���e�O���[�e�h�|�W�V�����ł̓K�����o��(16,000�~������H)���Ƃ�����A�C���e�O���[�e�h�|�W�V��
���ł͂قƂ�ǎg��Ȃ������ł��ˁB
�@������̐ڑ��ł����C����YAMAHA A-2000a�ɔ�ׂĖ�������ƂȂ������߃��C���ɂ͂Ȃ炸�A����
�[�q����������(PHONO�ACD�ATUNER�AAUX�ATAPE×3�n���A�p���[�A���v�_�C���N�g×2�A�v���Z�b�T�A
XLR ����ɂ��Ă������Ȃ�)�t���Ă���̂Ńe���r�p�̃A���v�ɂ��悤���Ƃ��v���܂������A�@�����R�����g
����ONKYO R-200 Liverpool�̕����֗��Ɏg����̂ŁA���݂͕����̋��ɕ��ςݏ�Ԃł�(��)�B
�@RX-V773�Ƃ̃v���E�p���[�ڑ��ł͏o����������(�قƂ�lj��R��̃��x��)���߁ARX-V773�̃{�����[
�������Ӗ��ɂȂ�A607�̃{�����[�����グ�Ă���Ƃʼn�̋����悤�ȉ��Ƃ�����Ԃł����B���C�����͂Ƃ�
�������̂Ńv���E�p���[�ڑ��ł͂Ȃ��ARX-V773��ZONE2�o��(�ʎ��A���v�����o�͒[�q)����607�̃p��
�[�_�C���N�g�ɂȂ����畁�ʂɉ����o�܂������A����Ȃ�BD���R���璼��607�ɂȂ������������Ƃ���
���ƂŁu�Ȃ���ăv���E�p���[�ڑ��v����߂܂����B
�@BD���R�̒��ڐڑ��ł�RX-V773�ł�607�ł�A-2000a�ɏ����ڂ͂���܂���ł����B���ہARX-V773
�ł͐��ׂ̍���������ONKYO D-057F(�g�[���{�[�C�X�s�[�J�[)���AA-2000a�ł͖쑾���ቹ���o��
�т����肵�����̂ł��B
�@�v���E�p���[�ڑ�(�قƂ�ǂ̏ꍇ�v���A���v�̉��ɂȂ�܂�)������l�̓��@�Ƃ��Ă͂��C�ɓ���̃X
�s�[�J�[��AV�n�ƃs���A�n�̗����Ŗ炵�����Ƃ����̂��̂�����ARX-V773��A-2000a�Ńv���E�p���[
�ڑ������Ă��܂������A���R�[�_�[�̉����o�͂�A-2000a��AUX�ɐڑ���������NS-1000M�̉����ł�
�悩�����ł���(A-2000�V���[�Y��NS-1000M��炷���߂̃A���v�Ƃ����Ă��܂���)�B
�@���݂ł̓e���r�O�ɒu���Ă����@�ނ�����(�e���r�֘A�̃����R�����悭�����悤�ɂȂ�܂��� ��)�A
�s���A��AV�����S�ɕ�����A-2000a�ANS-1000M�ADCD-1650GL�AVICTOR JL-B37R(���R�[�h�v���[���[)�A
TEAC RW-02(CD���R�[�_�[)�AVICTOR TD-F1(�J�Z�b�g�f�b�L)�ASANSUI T-��7(�`���[�i�[)���R�[�h���
CD��烉�W�I�����Ă��܂��B
�@R-200���e���r�p�̃A���v�ɂ���ONKYO D-200��DIATONE DS-251MK�U���Ȃ��ł��܂��B����Ȃ킯
��RX-V773�͎������HDMI��ւ���ɂȂ��Ă��܂�(RX-V773�̓��W�I�ɐ�ւ���ƃe���r�������
�Ȃ��Ȃ�̂ŁA�`���[�i�[�@�\���o�Ԃ�����܂���)�BRX-V773�ɂ͌���SANSUI S-��7�Ƃ����X�s�[�J�[��
�Ȃ��ł��܂��B�ቹ���V�A�^�[���ۂ������o��̂ŁA�莝���̃X�s�[�J�[�ł͂��ꂪ���RX-V773��
�����������悤�ł��BNS-1000MM(�`�r�Z�����j �� �V�A�^�[������搂�����)�����������肭�鉹�ł�(��)�B
�@���Ƃ�����SANSUI�Ɏ��]���Ă���킯�ł͂Ȃ��AD907X���~�����Ǝv���Ă��܂��B�n���̃��T�C�N���V���b�v
�f���@��D607F�ƃe�N�j�N�X�̌Â��X�s�[�J�[(�Z�����j��������傫���T�C�Y)�Ȃ�ł����A�x�[�X��
�u�[���Ɩ苿���������ł��B�u607�ł��̉��Ȃ�907�͂ǂ�ȉ�������̂��v�Ɗ��҂��������̂ɏ\����
���ŁAD�V���[�Y�ɂ͂܂����͂������Ă���ACD�[�q�̂���D907X���~�����Ǝv���Ă��܂��B�Ƃ͂����旧
���̂Əo��������Ȃ��Ɣ����Ȃ��̂ŁA�������邩�����݂��t���Ȃ���Ԃł�(���)
�����ԍ��F19583346
![]() 2�_
2�_
�]�k�ł����c
�}�����c�ƃP���u���b�W�I�[�f�B�I�̃����R���{�^��(�A���v��CDP)�� �قڋ��ʂ��Ă��邱�ƂɋC�t���܂����B
���܂Œm�炸�ɂQ�{�Ȃ�ׂĎg���Ă��܂���(���)
![]() 2�_
2�_
�ߓ������\���Nmode�̐V�^�A���v�AX-PM100���������Ă��܂����i�ڑ����Ă����X�s�[�J�[��Dynaudio�̂��̂ł��j�B
�@���ʃ��f����X-PM7�������������W���̍L���≹���̗������E����̑傫���Ɋ��S�������̂ł����A����X-PM100�͗͋����≷�x���������A���i�Ƃ��Ė������܂�Ă��銴������܂��B
�@X-PM7�ł́u��^�X�s�[�J�[���\���X�s�[�J�[�ɂ͌����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������O���c�����̂ł����AX-PM100�͂ނ���Z�p���[�g�A���v���q���ē��R�Ǝv����e�Ђ̑�^�X�s�[�J�[��N�X�Ɩ炵�Ă��܂���قǂ̋쓮�͂̍������M���܂��B�d�������������m�������Ă���̂ł��傤�B
�@�\�艿�i��50���~��ɂȂ�Ƃ̂��Ƃł����A������̕��������ł͂��Ԃ̃N���X�ł̓_���g�c�ɂȂ�Ɨ\�z���܂��B
�@�������A�����R���͖����B�w�b�h�t�H���[�q��g�[���R���g���[�����A��������B�A���v�ɑ��@�\��]�ރ��[�U�[�ɂ͕s�����ł��B�ł��A�����D��Ő��i��T���Ă��郊�X�i�[�ɂ͗L�͂ȑI�����ɂȂ�Ǝv���܂��B
![]() 4�_
4�_
�����́B�����l�ł��B
����X-PM7�������͢�����A���v���ȣ�Ǝv���܂�����(�v���[���[��SOUL NOTE �A�X�s�[�J�[��FOSTEX�ł���)�A����ȏ�̎����ƂȂ��Nmode(�V���[�v������܂�)�̏W�听�ƌ����Ă�����������܂���ˁB
���ɂ͉��������i�ł���(��)�A���i�A���̌X���A���^�ŃV���v���ȃf�U�C�����l���܂��ƁA�X�s�[�J�[���v���[���[�̑I���̕�������̂��ȁH�ƁA�v���܂��B
����������Ȃ�ǂ�ȋ@�킪�ǂ��Ƃ��l���ł����ˁH
�ł͂ł́B
�����ԍ��F18884591�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�@�艿�����܂�܂����ˁB�ŕʂ�480,000�~�A�ō�518,400�~�Ƃ̂��Ƃł��B������50���~��ł��傤���B
���v���[���[�̑I���̕�������̂��ȁH
�@Nmode�̓v���[���[���o�����Ƃ͓��ʍl���Ă��Ȃ��悤�ŁA���ʂ͑��Ђ̐��i�����킹�邱�ƂɂȂ肻���ł��B���Ƃ��Ă�LUXMAN��ESOTERIC������ł��傤���E�E�E�E�ł����^�ł͂Ȃ����猩���ڂ̓C�}�C�`�����B�V���b�v�ł�PS AUDIO�̐��i���q���Ă��܂������A�C�O�u�����h���ʔ������Ǝv���܂��B
�@���ɂ��܂荇��Ȃ��Ǝv����̂�DENON��MARANTZ�̃v���[���[���Ƒz�����܂��B�����ڂ̃}�b�`���O���ǂ��Ȃ����A���������A�L�����[�g�n��Nmode�Ɖ��̒��F�̔Z��DENON��MARANTZ�Ƃ͑������ǂ��Ƃ͎v���܂���B
�@���ƁAX-PM100��X-PM7�ɔ�ׂĉ��s�����ƂĂ��傫���ł��B�����X-PM7�̂��悻�{�̃T�C�Y�̃g�����X��ς�ł��邽�߂ŁA�X�y�[�X�E���[�e�B���e�B�̖ʂł͕s���ł����A�T�E���h����̂��߂ɂ͒v�����Ȃ��̂�������܂���B
�@����́A�e�Ђ̃t���b�O�V�b�v���̃X�s�[�J�[��炷�Ƃ�����Ă݂����ł��B
�����ԍ��F18887227
![]() 1�_
1�_
����������A�����́B
���Z�����̂ɁA�ԐM�L���������܂��B
����PS AUDIO�łł������܂����ˁB����ł���(��)�B
�T�C�Y���傫���悤�ł����A�d���̋����̘b���͕�������������܂���B
CD�v���[���[�̔����\��͂Ȃ���ł��ˁB���̓g�����X�|�[�g+X-DU1�A�z���̈�ł����N���[�N�̃X���b�g�C���̃v���[���[�Ȃ��ʔ������ȁH�Ǝv�����肵�Ă܂��B
����ɂ��Ă��A�G�k���[�h�͐��Y�I���̃y�[�X�������悤�ł��ˁB
���͍w���\��͂���܂���(��)�A���ꂩ��A�L���A
���b�N�X�̍w�����l���Ă�����ɐ����Ă��炢�����u�����h���Ǝv���܂��B
�ł́A���炵�܂��B
�����ԍ��F18887383�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���݂܂���A������̕����������ĂȂ�ł��傤���H������Ɠ���āB
�����ԍ��F18889544
![]() 1�_
1�_
��������̕����������ĂȂ�ł��傤��
�@���t�ʂ�̈Ӗ��ł����ǂˁB
�@�܂��u�I�[�f�B�I�ɂ����镨�������Ƃ͉����v�Ƃ������Ƃɖ��m���ڍׂȒ�`������킯����Ȃ��Ǝv���܂����A�ʏ�u������������ʂ�v����荹�������P�[�X���Ă̂́A���Ƃ��Θc���Ƃ��Af�����W�Ƃ��A�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ��AS/N��Ƃ��A���������u��i��Ő��l�Ƃ��ċL�ڂ������́v����ɂ̂����邱�Ƃ������ƔF�����Ă��܂��B
�@�������A����͂����܂Ōv����ȂǂŌv�������l�i�������A�S���[�J�[�I�ɑ����������ɓ��ꂳ��Ă���킯�ł��Ȃ��j�ɉ߂��Ȃ��B
�@���āu������̕��������v�Ƃ́A�����ʂ蒮���肪�������u�c����f�����W�A�_�C�i�~�b�N�����W�AS/N�䓙�X�̃��x���v�̂��Ƃ��Ɓi���Ȃ��Ƃ��l�I�ɂ́j���_���Ă��܂��B
�@������u������̕��������������v�Ƃ����̂́A�u�������������A�c����f�����W�A�_�C�i�~�b�N�����W�AS/N�䓙�X�̒l���D��Ă���悤�Ȉ�ۂ���i�܂�́A�������ł���j�v�Ƃ������Ӗ��Ŏg���܂��i���Ȃ��Ƃ��A���͂ˁj�B
�@������J�^���O�l���ǍD�ł����ۂɒ�������u�c�݂��ۂ��āA����E��悪�L�т��ɁA�X�b�L�����Ȃ����v�ł����Ȃ������Ƃ������ԁi���̋t�̃P�[�X���R��j�ɑ�������̂́A���蓾�邱�Ƃł��B
�@�������u������̕��������v���e���X�i�[�̃C���v���b�V�����ɏ������Ă���ȏ�A����͕��ՓI�Ȋ�ł͂Ȃ��ł��B�����A�����_�ł�X-PM100�͒�i���������\����Ă��܂���B����Ȓ��ŁA���ꂾ���u�c����f�����W�A�_�C�i�~�b�N�����W�AS/N�䓙�X���D��Ă��邱�Ƃ�������ەt�����鉹�v�����Ă����̂̓X�S���Ǝv���܂������A�G�z�Ȃ��瓯�l�̊��z�������X�i�[�����Ȃ��Ȃ��Ƒz�����܂��B
�����ԍ��F18895591
![]() 2�_
2�_
�Ȃ�قǁB���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F18897996
![]() 2�_
2�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�v�����C���A���v]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
-
�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�v�����C���A���v
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j