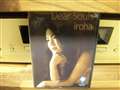���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S436�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 2011�N3��27�� 20:47 | |
| 58 | 197 | 2011�N8��3�� 07:51 | |
| 3 | 0 | 2011�N1��29�� 17:19 | |
| 2 | 8 | 2011�N2��23�� 00:23 | |
| 93 | 199 | 2011�N2��13�� 23:27 | |
| 577 | 200 | 2011�N1��29�� 14:32 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�o�b�I�[�f�B�I�Ȃǂ��e�[�}�ɐ��Ԙb����X���́u�p�[�g�R�v�ł��B
�u�Ȃǁv����ꂽ�̂́A�o�b�I�[�f�B�I�ƒ��ڊW�Ȃ����b���n�j�Ƃ����Ӗ��ł��B
�O�̃p�[�g�Q�́A������Ă��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12533084/
�ł݂͂Ȃ���A����������낵�����肢���܂��B
![]() 0�_
0�_
baldarfin����
����͂܂��c�c���̗\�z���͂邩�ɒ�����fo.Q�̗ʁc�c���͂∠�R�ł�����
����킽���̂o�b�ł������M�\���m��ł��B�^���ł��܂���˂����(��)
���������U�̃v���ł��˂���
�����ԍ��F12652426
![]() 0�_
0�_
���������Ƃ��E�E
�U��̃X�s�[�J�ɃG���b�N��BS203A���g���Ă��܂��B
�b�c�o���`�u�A���v�ŋ쓮���Ă�������͂܂��܂��̉����o�Ă����̂ł����A�o�b�I�[�f�B�I�ɂ��ASOtM�̂c�`�b�ɂ��A�����̃p���[�A���v�ŋ쓮����ƁA���̃X�s�[�J�̍Ŏ�_�i�ቹ���Â��ɂ��A���ꂪ�������ɂ��Ԃ��ĉ�������j��������悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B�X�s�[�J�ɓ���M���̑ш悪�L���Ȃ������Ƃ̌��ʂƎv���܂��B
�o�X���t�|�[�g�ɕt���̃X�|���W���l�߂Ă��قƂ�lj��P���܂���B�܂��g���Ă����X�s�[�J�E�A�_���g�l�|�P�Ȃ炱���������͖��������̂ł����A���܃A�_���̓��C���V�X�e���̃��A�E�X�s�[�J�Ɋi�グ���Ă��邵�E�E�E
�����ԍ��F12654103
![]() 0�_
0�_
�F���� ����ɂ��́c
�͂��߂܂���
�Ȃɂ��������Ȃ��Ȃ�������
�G���b�N�̓o�C���C���[�ł����ˁB�V���O���H
�W�����p�[�Ȃ烏�C���[�E���[���h�̃I�A�V�X���m�[�h�X�g��Norse�V���[�Y���I�X�X���������Ă݂Ă͂Ǝv���܂��H
���Ƃ̓X�g���[�g�E���C���[�܂��̓A�R���o�P���ł����ˁB
�ň������Ȃ�X�s�[�J�[�����z����ς��邩�c�c
�ǂ���Q���[�g�������H
����őʖڑʖڂȂ���P��͂킩��܂���
�����ԍ��F12654346
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����A�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B
�������A�u�P�[�u�������v�̃��x���ʼn�������悤�Ȗ��łȂ��A�X�s�[�J�̕i���A�\���̖��Ǝv���Ă��܂��B
�}���d���a�ɂ������āA���ꂱ�ꂢ�����āA�u�킸���̉��P�v�Ŗ�����������A�����̓X�s�[�J�����̕����ōl���Ă��܂��B
�����ԍ��F12654389
![]() 0�_
0�_
��Ƃ���ł��ˁ`�B
���t���Ȃ�
�ގU���ǂ���������܂���B�B
���������G���b�N���w������Ƃ��̓f�W�^���A���v(�j���[�E�t�H�[�X�܂��͍ŒჍ�[�e���j���Z�b�g�ƍl���܂��ˁB
�Ȃ��Ȃ��C����X�s�[�J�[�ł��B�B
�����ԍ��F12654457
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����
�A�R���oPOWER MAX10000��SPC-REFERENCE
�͑ϐ≏�����قȂ�܂����H
�����ԍ��F12654805
![]() 0�_
0�_
�������L������
�ϐ≏���ȒP�Ɍ����Ȃ�ꏏ����Ȃ��I
�\��̌������Ⴄ���܂��͋��x���ǂ����H (�����o���|���G�`�����j
���V�J�V�e�d���P�[�u���ɁH�H
���ȐӂȂ�I�X�X���ƌ����������c�ǂ�����(��)
��������d���P�[�u�����l����Ȃ�p���[10000�̕������S�ʂŌ����Έ��S�ł��傤�ˁB
�X�s�[�J�[���t�@�����X1.8���P���A
���t�I�N�ŏo�Ȃ����ȁH
���̌�
����Ă��炲�߂�Ȃ����Bm(_ _)m
�����ԍ��F12655135
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������@
���}���d���a�ɂ������āA���ꂱ�ꂢ�����āA�u�킸���̉��P�v�Ŗ�����������i�����j
�d�x�d���a���ҞH���A�����Ȃ����f�Ɏv���܂��B
���C���V�X�e���̃o�����X������ăZ�b�g�A�b�v���K�v�ɂȂ�ł��傤���A
ADAM�ƃX���b�v�����̂���ĂȂ̂ł́H
�������L��������������������@
���������ēd���P�[�u�������SPC-REFERENCE�����l���ł��傤���H
�ϐ≏�������邱�ƂȂ��狖�e�d���łǂ̒��x�ς��邩�̕�����肩���c
��i��600V15A���x�̑ϐ�������Ζ��Ȃ��]�p�ł������ł����A
SPC-REFERENCE�͂��̕ӂ肪���m���Ȃ̂��C�ɂȂ�܂����A
�M���Ɏセ���ȃ_�~�[�`���[�u�������ς������Ă�̂����}�ł��܂���B
����PCOCC-A�̒P���������]�Ȃ�OYAIDE��EE/F-S 2.0���Ď������܂��B
�����g���Ă��܂��������z���p�Ȃ̂ŕ��ׂ̖ʂł͉��̐S�z������܂���B
���̂�����ʂ�EE/F-S 2.6�قǂł͂���܂��Ƃ�ł��Ȃ��d���ł��B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�����������g����CV-S 5.5�Ɨǂ��������܂��B
���Ȃ݂ɕ���SP�P�[�u���A�����A�P���̉����z���p�ł�����A
�������PSE�@�ł͓d���P�[�u���ւ̓]�p�͌�@�x�ł��B�������炸�B
�����ԍ��F12655450
![]() 2�_
2�_
redfodera����
�������܂����B
�����ԍ��F12655690
![]() 1�_
1�_
Redfodera����v���Ԃ�ł��B
>�d�x�d���a���ҞH���A�����Ȃ����f�Ɏv���܂��B
�d���a�́A���C���t���Ɠ������炢�|���ł���
�`�c�`�l�̂g�l�|�P���A���C���V�X�e���̃��A�E�X�s�[�J�Ƃ��đf���炵�������U��Ȃ̂ŁA�����z�u�]���ł��Ȃ��̂ł��B
http://web1.kcn.jp/haruem/center_rear_sp.html
�`�c�`�l�̂g�l�|�P�������P�y�A�������A�`�c�`�l�̃v���p�r�P�w�i�A�N�e�B�u�j�B
�ӂƍl�����o�l�b�̂c�a�P�����邢��Stirling Broadcast�@LS-3/5a�B
�������A�c�C�[�^�̃��x�������X�C�b�`�̕t���Ă���A�_�����֗��B
�����ԍ��F12655948
![]() 0�_
0�_
�F����A���ӂ́B
�� �����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
���̂Ƃ���Afo.Q����ԗǂ������Ȃ̂ŁAfo.Q���g���Ă��܂��B
�����Afo.Q�������U�͂������A�������ĐU����������܂ł̎��Ԃ��Z���ifo.Q�́A�O�D�R�b�O��i�P�b��1/3���炢�H�j���j�A�������j���[�g�����Ȑ��U�ނ�����A�����ɂ�����ɏ�芷���܂��B
�N���A���������f�ނ���Ȃ����Ȃ��c�B
�@
�@
�� �V�n�n������
�c�ŏ��͂�����Ɛ��U���Ă݂��A����n�܂�����ł����B���ԂƋ��ɁA�����āA����Ȃ��ƂɁB
�ł��A�܂��܂����J��i�������j��������������܂��BDAC��w�b�h�z���A���v�́A����ȊÂ���Ԃł͂Ȃ��ł��B
�p�\�R���͑傫��fo.Q����������K�v�����i������������j�A����������������o���̂��ʓ|�c�A�Ȃ̂ł܂��܂����r���[�ł��B
�M�\���Ɋւ��ẮACerelon�P�D�VGHz�i�Q�O�O�Q�N���炢�́j�Ȃ̂Łc�B�P�R�O�����炢�܂ł́A�N���b�N�A�b�v�ł���]�T������܂��B
����ł��A�q�[�g�V���N�ɁA���̂�\�肷���āA�I�[�o�[�q�[�g�������Ƃ͂���܂��i�ǂ����A�\��Ƃ��ɊԂɋ�C�������Ă������߁A���M�����Ɉ����Ȃ����̂������������悤�ł����j�B
�������Ƃ����̂܂ܐ^������Ȃ��Ă��A�����I�[�f�B�I�̉����ōs���l�܂������ɁA������Ƃł������̎Q�l�ɂȂ�������Ȃ��A�Ǝv���āA���낢��Ȏ��������Ă��܂��B
�@
�@
�u���U�̃v���v�c�͂�����Ɓc�B
�܂��A������Ȃ����Ƃ��炯�A�g�������Ƃ̖����I�[�f�B�I�p�̐��U�ނ��������c�B�ǂ��ɂǂ�������A�����ǂ��Ȃ邩�A���s�����ԁB
�P�O�N���炢�A�{�C�ł��낢����g�܂Ȃ��ƁA�u�v���v�͖����Ȃ��悤�ȋC�͂��܂��B
���������A�A�}�`���A�̒������炢�H���ȁB
���낢�돑���Ă܂����A�܂��A���ԕ��x���̂��Ƃ������Ǝv���܂��i������������A���������ς���Ă��܂��\��������c���݂܂���j�B
�����ԍ��F12656140
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
���ӂƍl�����o�l�b�̂c�a�P�����邢�͂ӂƍl�����o�l�b�̂c�a�P�����邢��Stirling Broadcast�@LS-3/5a�B
���ނށA�ǂ��X�s�[�J�[�Ȃ͂��ł����c
�t���A�ƂĂ��厖�Ȃ��Ƃ����Y��ł́H
���{��/�R���f���T�[�A�n�C���n�̃g�����W�F���g���f�t�H���g�ɂ��Ă��܂��Ă���A
�����Ȃ�\�t�g�E�h�[���ɖ߂��Ă��܂��đ��v�Ȃ̂ł��傤���B
�]�k�ł���BBC���j�^�[��D���l�Ԃ̓�������݂āA
Stirling Broadcast��LS-3/5a�͂��܂ЂƂ������肫�܂���B
�B���Ȍ������ł����C�M���X�l�����Ȃ��Ȃ���SPENDOR�Ɠ����ŁA
�E�G�b�g�Ȋ��G����������ނ��Ē������܂��B
�G�A�R���Ŗ�����ɏ���������C�݂����Ȃ�ł���B
�����ԍ��F12656180
![]() 2�_
2�_
������
LS3���Ƃ��W�������i�R���������@���Y���͉p���H
http://www.u-audio.com/shopbrand/001/O/
�����ԍ��F12656295
![]() 1�_
1�_
>���{��/�R���f���T�[�A�n�C���n�̃g�����W�F���g���f�t�H���g�ɂ��Ă��܂��Ă���A�����Ȃ�\�t�g�E�h�[���ɖ߂��Ă��܂��đ��v�Ȃ̂ł��傤���B
���������A�����ł����B�����Stirling���W�������i�������̂��C�ɂȂ�B���₤�������Ԃ��Ƃ���ł����B����l�Ƃ����i�r�Q�[�^�ł��ˁB
��͂�A���{��/�R���f���T�[�A�n�C���n�ɂ��܂��B����ƁA�T�C�h�v���X���A�X�s�[�J���̂̌`�Ɍ��肷��Ƃ����߂Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B�T�C�h�v���X�F�����͈����͂Ȃ�����ǁA�����̃X�s�[�J�����܂Ƃ��ɃZ�b�g�ł��Ȃ��B
�n�C���n���ƁA�G���b�N�N���G�������炵�Ȃ��̂�(!)�A�����A�_���N�����Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F12656446
![]() 0�_
0�_
�g�c�N
QUADRAL PICO��2�����15�����@�@�@�͒u���Ƃ���
���x�̓��V�[�o�ƕ������킹
http://yoshidaen.jp/shopdetail/016002000009/order/
�����ԍ��F12656680
![]() 1�_
1�_
������T�C�h�v���X��
http://www.anthonygallo.jp/products/strada_01.html
���ݒu�Ł@�@�ւ�
�����ԍ��F12656759
![]() 1�_
1�_
�|�`����l����A�A���\�j�[�M�����͉���ǂ������₯�ǁA�T�C�h�v���X�����ł����B
���{���n�Œ����́A����܂����H
�����ԍ��F12658138
![]() 0�_
0�_
�����������Ȃ��Ȃ�������
�h�C�c�̍ē��� �ėA���������[�J�[���c
�m�����A���P�[�u���̎�舵���㗝�X�B
�X�s�[�J�[�����{���̂悤�������悤�ȁB�B
���s�����^�̓����X�s�[�J�[(���j�H���]���ǂ��炵���ł��B
�T�C�Y�I�ɂ��X���[��&�~�j�A���^�C�v�B
����Đ��^�ł��B
�����ԍ��F12658221
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
�����{���n�Œ����́A����܂����H
�����̂ł͂���܂��A����Ȃ̂ǂ��H�ł�����A
ADAM�̗l�ɂ������Ƃ͖�܂����[�U�[�ۛ���PIEGA�c
�ł�����͎t���̂��D�݂̃^�C�v�Ƃ͈Ⴂ�����ł��ˁB
���菬�����ł������l�i���ǐS�I��mhi��Evidence MM01A�͖ʔ������݂����B
�����ԍ��F12659370
![]() 2�_
2�_
������
�}�[�N���_�j�G���@�Q�^�Ԃ������̂�
http://www.mark-daniel.jp/products.html
CAV
http://www.cav-japan.co.jp/product/index.php?product=v70nw
�����ԍ��F12661255
![]() 1�_
1�_
���̃X���́u�܂��܂�CD��SACD�ŗǂ��������߂Ɂv�������p�����X���ł��B
�݂Ȃ��܁A��낵�����肢���܂��B
�܂��܂�CD��SACD�ŗǂ��������߂̍H�v��A�D�G�^����CD/SACD�̏����A���Ђ��肢���܂��B
�߉ނɐ��@�ɂȂ��Ă��܂��܂����A��ʂ�CD��SACD�ŗǂ��������߂̍H�v�Ƃ��ẮA�ǎ��ȃv���[���[�A�A���v�A�X�s�[�J�[�����邱�Ƃ͊�{�Ƃ��āA
�P�D�v���[���[��A���v���������肵����i�I�[�f�B�I���b�N�j�̏�ɐݒu���A�X�s�[�J�[�����U���������B�I�[�f�B�I�{�[�h��C���V�����[�^���g�����Ƃ����ʓI�ȏꍇ������B
�Q�D�P�[�u���ɏ㎿�Ȃ��̂��g���B�ΏۂƂȂ�P�[�u���͓d���P�[�u���A�X�s�[�J�[�P�[�u���ARCA�A�i���O�P�[�u���A�v���[���[�ɂ���ẮA�����P�[�u���A���P�[�u���AHDMI�P�[�u��������B
�R�D�d�����𐮂���B����ɂ̓N���[���d���̓����A�f�W�A�i�Q�n���̓d����H�������݁A�m�C�Y�t�B���^�̓����Ȃǂ�����B
�S�D�����̉����𐮂���B����ɂ��Ắi�R�D�ɂ��Ă��ł����j�����������Ȃ��Ȃ�������̃X���ɂ���܂łɏڂ������������܂��̂ŏȗ������Ă��������܂����A��ʂɑz������Ă���ȏ�ɏd�v�ł��B
��L�ȊO�ɂ��������A����܂ł̃X���ő����̋M�d�ȃA�h�o�C�X���Ă��܂��̂ŁA������̕������Q�Ƃ��������B
�ł́A��낵�����肢���܂��B
![]() 0�_
0�_
���͂悤�������܂��B
�p�[�g�U���߂łƂ��������܂��B
�挎���{�ɃN���[���d���̃C�����b�g�v���O�������������܂����B
���̃C�����b�g�v���O(�W���f���J���j�����B
�Ȃ��Ȃ��̐��i�ł��Ď��R�́A�����r���A&�G�l���M�b�V���ł���܂��B
���N�����肩��ǂ����@��̃C�����b�g���m�C�Y�܂��͉��̕ϒ��̍����̓R�R�ɂ���Ǝv���A���������Ă݂܂����B
���̃O���[�h�A�b�v�͂������f���ɂ����ʂ���ł��ˁB
���̏����̓G�[�W���O���K�v�ł��ē��ɓ��ɃO���[�h���オ��̂�����܂��B�B(����܂��d�������j
�����ōς݁A����p�������I�X�X���ł��B(�P�[�u���R�l�N�^�[�����W�E�������b�L�₻�̑��̃��b�L�ł������������Ȃ��A�C�e�����ƁB
�����ԍ��F12623467
![]() 2�_
2�_
2011/02/08 11:34�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A����ɂ��́B�v���Ԃ�ł��B
���傢���傢�������ނ��Ƃɂ��܂��B
�d���́A������x�m�����v�邵�}�j�A�b�N�ł����A�u�Q�O�O�u��������v
���ꂪ�~�ǂ߂��Ǝv���Ă��܂��B�Q�O�O�u�d���̂ق����쓮�͂�����A����Ȃ̂ł��B�}���V�����ł��A���d�Ղ���Q�O�O�u�����������Ă���l��m���Ă��܂��B
�����ԍ��F12623630
![]() 1�_
1�_
2011/02/08 13:07�i1�N�ȏ�O�j
���݂܂���B�ŏ�����}�j�A�b�N�ɓ˂��i��ŁB�قƂ�ǖ������Ă��������Ă����܂��܂���B
�ӂƁA���������T�C�g�������܂����B�P�����_�E���g�����X�P���V��~�F
http://www.e-kasuga.net/goods.asp?id=810
�݂�ƁA�P�[�u���A�v���O�A�R���Z���g�̓z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă���悤�Ȕėp�i�B�d���Q�O�O�u���P�O�O�u�ɂ��Ă��邾���B
����ƁA�d���P�O�O�u����A�����v���O�A�����P�[�u���A�����R���Z���g���g���ăA���v�ɋ��d����̂ƁA�ǂ��炪�ǂ��Ⴄ���H�@
�f���ŏ������A�R�e�R�e�̉��ϊ�ł������H�@�ʔ������Ȏ����ł͂���܂��B
�����ԍ��F12624037
![]() 1�_
1�_
�~�l���o����
����͂ǂ��ł���`
����Ƀ_�E���g�����X200V���Ȃ�
�����Ȃ�ƈ�ʉƒ�50�`�_��
��������8�X�P�A���x�ł����v�ł����H(���̏���SV38�X�P�A�j
�܂��̓��[�^�[�����z�dVVR14�X�P�A���x�ł��H(��CV22�X�P�A�j
����
�ǂ��炪�������シ�邩�H
�Ă���������X�}�j�A�b�N�ł�����f^_^;�B
�����ԍ��F12624367
![]() 0�_
0�_
2011/02/08 15:00�i1�N�ȏ�O�j
Minerva��������[���E���t�����100V�h�ł��ˁB
200V�h�̎����猾���A�����d�͂Ȃ�A�d���������قǓd���͌���i�ς����j���߁A�����ݐ��͒f�ʐςP�^�Q�ł��݂܂��B���a�Ɋ��Z����ƂP�^�S�B
�܂�P�U�X�P�A�̐��́A�W�X�P�A�ōςނ悤�ɂȂ�܂��B
�������d�������������ŁA�d�������\���{���g�ɏグ�đ��d���邱�Ƃɂ���āA�d���̒f�ʐς̑�����h���܂��B
�����ԍ��F12624435
![]() 1�_
1�_
�{�[�J���́e�V�f���������Ă�����Ă���悤�Ȃ̂ł��������͉��ł��傤���H
�ǂȂ����A�A�h�o�C�X�����肢���܂��B
�����ԍ��F12624977
![]() 1�_
1�_
��̎���������܂��B
����̂b�c�ɋN������ł����B
�����ԍ��F12625194
![]() 1�_
1�_
>�����ݐ��͒f�ʐςP�^�Q�ł��݂܂��B���a�Ɋ��Z����ƂP�^�S�B
�f�ʐ�2�{�Ȃ�A���a(���邢�͒��a)��1/��2���Ǝv���܂����B
�����ԍ��F12625821
![]() 0�_
0�_
2011/02/08 21:03�i1�N�ȏ�O�j
1/4�łȂ��P�^��Q�ł����ˁB���������Ă��������܂��B
�����ԍ��F12626012
![]() 0�_
0�_
�������ݐ�
���ƃ}�j�A�b�N�߂����ł���f^_^;
��`���l������
�g�����X200V���ǂ��Ƃ�100V���ǂ��́A����܂������悩��f^_^;
�S�ẴI�[�f�B�I�@���200V�A���v���x�X�g�ƌ�������Ȃ��ƌ����ƈꏏ�ŁB
�܂��g�����X�ł��g�X�ȃ��[�J�[�����邵�c
�����͉����Ƀg�����X�Ă���ǂ����H
�܂��ǂ̎��(�����j�̃A���v�Ȃ�g�����X�Ŗ���������\���o�邩�H
�g�����X���g���Ĕ����o����ꏊ�o���Ȃ��ꏊ���K���o�Ă��邵�c
���ۈ�T�ԂقLjȑO�̃f�W�^���O�i�^�b�v���d�����܂������c
�����n���̂���𑜓x�̂��������ΉƊ��̏ꍇ�^�b�v���d�̕����o�܂����ˁB
�����ԍ��F12626074
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ��܁B�����́B
���[���E���t����,
���肪�Ƃ��������܂��B�܂���낵�����肢���܂��B
�N���[���d���̃C�����b�g�v���O���������Ɍ����ł����B�m���ɏ����̓s���A�ŗǂ��Ƃ����̂͗ǂ������܂��ˁB
�g�����X�̑I���͂ނ������ł��ˁB���Ȃ肪�o���A�p���[�������Ȃ�ꂸ�ƂȂ�ƈꋓ�ɍ��z�ɂȂ��Ă��܂��C�����܂��B
>�����n���̂���𑜓x�̂��������ΉƊ��̏ꍇ�^�b�v���d�̕����o�܂����ˁB
�Ȃ�قǁA���������ꍇ������̂ł��ˁB��͂��ؓ�ł͂������ނ������ł��ˁB
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
���v�Ԃ�ł��ˁB�܂���낵�����肢���܂��B
�������猾���Ă��Q�O�O�u���͌��ʂ�����Ǝv���܂��B�ł�����͎��̏ꍇ�́A����̂��y���݂Ƃ��ĂƂ��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B���ʂ͂P�O�O�u�łǂ��܂ōs���邩�撣���Ă݂����ł��B
�Q�O�O�u���Ƀg���C����Ƃ��́A�傢�ɎQ�l�ɂ����Ē����܂��B
�����ԍ��F12626786
![]() 0�_
0�_
2011/02/09 10:16�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A��낵�����肢���܂��B
�Q�O�O�u���Y�Ɨp�P���g�����X�ɂ��f�̋��d�i�킽���́A�u�P���v���|�C���g���Ǝv���Ă��܂��A�u�����v�̓_���j���A�u�P�O�O�u�������E���A�N�Z�T���v�Ɣ�r���A�f���ł�����ʔ����ł����A�����̂��Ƃł͔�r���������܂���ˁB
�X���Ⴂ�C���������̂ŁA����Ŋb�x��Ƃ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12628533
![]() 1�_
1�_
�q�b�`�P�[�u�����a�k-�P�ɂr�o�P�[�u�����r�o-�P�ɕύX���܂����B
���ʁF�����ʒu�����m�ɂȂ����B
�@�@�@�]�v�ȉ��̋������Ȃ��Ȃ����B
���̑ʎ��ɂ͍��̂Ƃ��낻�ꂮ�炢�̕ω��ł��B
�G�[�W���O����Ă���Ζ�����Ă��邩������܂���
�]�v�ȉ����Ȃ��Ȃ������߁A���ɒ����₷���ł��B�~�l���o����Ɋ��ӂł��B
�����ԍ��F12628900
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
200�u�̃_�E���g�����X�͒P�����|�C���g�Ȃ̂ł��ˁB�Q�l�ɂ��܂��B���R�͉�������̂ł��傤���H
�I�X���K����A
�X�s�[�J�[�P�[�u�����O�H�d���H�Ɛ��ł����B�����C�����ǂ�������悤�ɂȂ����Ƃ̂��ƂŁA�ǂ������ł��ˁB
�����ԍ��F12630590
![]() 0�_
0�_
�O�H�d���̓X���������Ă����̂ł����A�r�o�|�P�̒[���i�ڑ����j�ɂ͎_���╅�H������
�����������Ă��邽�߁A��x�ڑ������瑝�����߂����邾���Ŕ������������Ȃ��ł��ǂ�������
�����҂̎��Ƀs�b�^���ł��B
�����ԍ��F12630663
![]() 2�_
2�_
2011/02/09 20:42�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A�O��Mt.T2���P���E�Y�Ɨp�s���������Ă����Ē������̂��o���Ă��܂����H�@�P���ɑウ��ƁA�A���v�̉��ʂ�G���Ă��Ȃ��̂ɁA���ʂ��オ�����悤�ɃG�l���M�[�������܂����B
�����ŁA�����t�����g�E�A���v�����A��������P���s���ɕύX���Ă܂��B����ŁA�킸���̂r�^�m�̒ቺ�ƈ������ɁA�R���g���o�X�̉𑜓x���������オ��܂����B
����āA����ȗ��A�p���[�A���v�����͂r�^�m�����A�G�l���M�[�d���̕��j�ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F12630769
![]() 1�_
1�_
�I�X���K����A
�����������������Ă���Ƃ͒m��܂���ł����B����͎�ԗv�炸�ǂ��ł��ˁB
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
�O��Mt.T2����ɁA�����ĉ����������Ȃ��Ȃ��������ł�����܂������A���̎��ɒP���E�Y�Ɨp�s�������L��������܂���B�@�������݂ł͂��̔�r���������̑O��ł���Ă������Ƃ́A�ǂ݂܂������������ז��������ԑтł͂Ȃ������悤�ł��B�܂��A�P���E�Y�Ɨp�s�������ւ����Ă���C���[�W���v�������т܂���B�����Ă����̂ł����ˁH
�����ԍ��F12631397
![]() 0�_
0�_
�F����@������(^^)/
�~�l���o����
�V�X�����肪�Ƃ��������܂���
����������낵�����肢���܂��B
�E�`�̎O�H�d���̓J���e�b�g�ł��i�j
�X�s�[�J�[�̒[�q���͂���Ȋ����B
���摤�͂�����ƍׂ��ĕs�����Ȃ��B�B�B
�����[�q�g���������肵�ėǂ��̂ł���
�͂��݂��̂��čD������Ȃ��̂ł��̂܂��(^^;)
�܂��A�d���P�[�u���͂b�c�o�ɁB
�q�b�`�P�[�u���͂b�c�o�`�A���v�ɁB
���͂w�k�q�P�[�u�����~�����ł��ˁB
�����߂b�c�ł����A�e�B�[�g�b�N���R�[�Y����
��������Ă���A�ʉ�-iroha-�́uDear Souls�v�ł��B
�������ł����ʔ���������̋Ȃ�����܂��B
�����b�c�|�q�Ȃ�ł���������Ƃ������̂��B�B�B
���w���͂����炩��B�@�@���B�҂ł͂���܂���i�j
��
http://www.t-tocrecords.net/store2.html
�����ԍ��F12632049
![]() 1�_
1�_
�F����
���͂悤�������܂��B
�~�l���o����
���g�����X�����ɂ�����݂��o���o���鏊��T���B
���o�������x�g�����X�̉����Ă݂�B
�^�b�v�̃����n���𑜓x�̌��ł����E�E�E
�����X�g���[�g�ɒ�������A����Ȋ����ł��傤���I
���������s���͂�����̐[�����̓g�����X�ݒu�̕����o�܂��ˁB(�Ɗ��f�W�^���O�i�j
����ƎO�H�d���͐l�C�����ł��ˁ`�B
���̓T�G�N��A�R���o�ł߂ł����A�A�O�H�d��������Ȋ����ł��傤���H
�F�̏��Ȃ���{�I�j���[�g��������D�݂ł͂���܂��B�B
�����ԍ��F12632931
![]() 1�_
1�_
2011/02/10 09:19�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A�L���ɂȂ���A�����������̂����m��܂���B
���̂Ƃ��A�Y�Ɨp�����͂��܂����ŁA�Y�Ɨp�P���͗͋����B���j�I���d�@�̕����͉��̐[�����ł����B
�����Ă��܁A�E�`�ł̓��j�I���d�@�s����P���E�����X�C�b�`��ւ��ɂ��āA��ɒP���Œ����Ă��܂��B
Minerva����A�d�C�H���m������u�u�e���łQ�O�O�u���z�����Ă��炦�A�E�`����Q�O�O�u�R���Z���g�ƁA���j�I���d�@�̒P���E�����s���ƁA�v�����C���A���v�������čs���܂����E�E�E���NStrike_Rouge����Ƃ�������ɗ����Ƃ��̃��x���W��ɂȂ�܂����A�������Ă����Ă��������B
�����ԍ��F12633166
![]() 1�_
1�_
�ԐM����200������ƁA���̃X���b�h�ɂ͕ԐM�ł��Ȃ��Ȃ�܂�
�����܂������Ȕ������������Ƃɑ���Ӎ߂��Ƃ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv�����̂悤�ȃX������菑�����܂��Ă��������܂����B
�Y�ꂳ��
���u��H�v�Ɍg����Ă���J���҂̕��ł����獡�̔����Ɋւ��Ă͎Ӎ߂����Ă��������܂��v�̂悤�Ȃ��l���͔r������邱�Ƃ����������߂��܂��B
�m���ɂ��̔����͂��낢��Ƃ܂��������Ə�������ł���v���ҏȂ��Ă���܂����B��H�v�҂Ƃ������t�͂������Ƃ����v��������H�v�̂ł���悤�Ȓm����L���Ă��Ȃ��Ƃǂ����Ń{�����łĂ��܂��c�c�܂�͔��[�҂̑f�l�ƕς��Ȃ��ł��Ƃ����Ӗ������Ō������������̂ŗ]���ȏ������݂�������������悤�ł��B�]�v�Ȉꌾ�ȏ㌾�t���炸�ł����B�Ȍ�C�����܂��B
���V�n�n������̂���������́A�d�C��H�̉Ȋw�I�Ȋ�b�m���������łȂ����Ƃ��킩�邾���ɁA�Ȃ����̓��e�R�̎����ł��邩�̂悤�Ɍ�邱�Ƃ��ł���̂��A�ƂĂ��s�v�c�ł��B
���͈ȑO���������Ƃ���d�q��H�ɂ��Ă͋ɁX��{���̊�{�����������Ă���܂���B�������玩���Ȃ�ɂǂ����ăI�[�f�B�I�ɂ������������̂��g���Ă��邩���l���Ĕ������Ă����̂Ŗ����ꒃ�ȗ��_���o�ė���͓̂�����O�ł��B���̔����̒��̂قƂ�ǂ͎����Ȃ�̍l���������������Ă��܂����B�ʂɓd�q��H�̒m����m���Ă��܂��Ƃ����悤�Ȕ����͂Ȃ������Ǝv���܂������Ⴂ�������̂Ȃ炲�߂�Ȃ����B
�X�C�b�`���O�d���̔��M�ɂ��Ă͓K�ȑ�����Ȃ��ƍ����g�m�C�Y����������\�����������Ƃ͒m���Ă��܂��B���������̌����������������ł��ˁB�����g�̃m�C�Y���������₷���B������Ă��o��\�������邩��I�[�f�B�I�ɂ͂��܂�g���Ȃ���ł��B�Ƃ������ق����悩�����ł��傤���H�������Ɉ��p�����T�C�g�ł�20�`100KHZ�Ŕ��U����Ə����Ă���܂��������ۂ͐l�̎��ŕ������鐔KHZ���甭�U���Ă��܂��B�����ł��������ŕ�������������Ȃ�ׂ����������͎̂g�������Ȃ��ł��B���͂��������ނ̂��ʓ|������Ƃ܂�܈��p�����̂̓_���ł����ˁB�����������p�������������̂ňȌ�C�����܂��B
���o�͂̃X�C�b�`���O�d���𓋍ڂ����p�C�I�j�A�̃v���Y�}���j�^�[���g�p���Ă��܂����X�C�b�`���O�d�����L�̍����g�m�C�Y(�L�[���Ƃ����ƂĂ��������ł�)���������Ă��܂��B���y�Đ�����Ƃ��̓��j�^�[����Ă��܂���������̂ق��������g�m�C�Y�͔������Ȃ��̂��Y��ȉ��ŕ������Ƃ��ł��܂��B���ꂪ�A���v�������獢��ł��傤�ˁB���y�ɍ������ăL�[���Ƃ�����������������̂ŁB����g�̉��Ȃ牽�Ƃ����܂����܂����������͏��������ł��n���Ɏ��ɂ��܂��B
����200�X�����Ă���Ӎ߂̕��͂������Ȃ������̂ł����œ��ꂳ���Ă��������܂����B�Y�ꂳ�w�E�����̂����R���Ǝv���܂��B���������������������Č������Ȃ��悤�ȕ��͂�������悤�ɂ������Ǝv���܂��B
![]() 3�_
3�_
CD�v���[���[ > DENON > DCD-1500SE
���܂Ŏg�p���Ă���PHILIPS LHH600B DECADE EDITION ���̏Ⴕ���̂ōw���������܂����B1650���l���܂�����600�̌㊘�ł͖�s���ƍl����C��1500�܂Ń����N�𗎂Ƃ��܂����B���g�̎ʐ^�����Ă��܂���҂͂��Ă��Ȃ������̂ł����A�͂����{�̂������グ�ė\�z�ȏ�ɏd�������̂Ŏv�킸���Ă��܂��܂����BCD�������z�́A���y�̕\�ʂ����ɕ\�����Ă���ȂƊ����܂����B�ȑO�̋@��Ɣ�r���ď��ʂ͈��|�I�ł��B�Ƃɂ�������ȉ��������Ă܂��I�ɕ������Ă��܂��B���̓X�s�[�J�[�̏㉺���E�ɂ����ƍL����܂��B�O�ɏo��^�C�v�ł͂Ȃ����ɍL����^�C�v�ł��B������͂��Ȃ肢�����ɂ��Ă���Ɗ����܂����B�����͂��l�i�Ȃ肩�Ǝv���܂��B�}�g��A�e���ȂǂƂ������\���͋��߂�ׂ����Ȃ����ȂƁB�g�[�^���ł݂Ă��̒l�i�̃v���[���[�Ƃ��Ă͗ǂ��o���Ă���Ǝv���܂��B
�Ƃ͂����A�ȑO�̋@��Ɣ�ׂĂ��Ȃ荘���Ȉ�ۂɂȂ��Ă��܂��܂����B�Ƃɓ]�����Ă���P�[�u�������{�������Ă݂�600�̋ɑ��t���P�[�u��������悪�����Əo�č����̈�ۂ͂Ȃ��Ȃ����̂ł����t�ɉ𑜓x�������Ă��܂��܂����B�S�̂̃o�����X�͏����̕t���P�[�u���������̂ł�����Ŏg�p���Ă��܂��B���̂�����̓g���[�h�I�t�̊W�Ƃ������Ƃł��傤���B�ߋ��ɃP�[�u���iLC-OFC���������ȁj�������Ă݂������Ƃ�����̂ł����A�X�s�[�h���͂����������o�����X������Ă��܂��悢��ۂ�����܂���ł����B����ȗ������P�[�u�����g�p���Ă��܂��B�������A�����������P�ł��Ă������o�����X�����܂肩���Ȃ����̂��������ȂƔY��ł��܂��B���̋@��ɉ����~�̃P�[�u���͖{���]�|�Ȃ̂ōl���Ă��܂��A�l�b�g�Ō���������MOGAMI�̃P�[�u�����育��ł悳���Ȃ̂ōw�����l���Ă��܂��B�ǂȂ��������������ł͂���܂��H
![]() 0�_
0�_
������
���g����600�̋ɑ��t���P�[�u���Ƃ����̂́A
�F�̓O���[�ŁA�����d�߂̃P�[�u���i�������L��j�ł��傤���H
�i�ł�����PHILIPS��CD�v���[���[�ɁA���͍����Ă܂����ˁB
�����ł��A�����W�͏������������Ă��܂������A
���킢�̂��鉹�͖��͂ŁA����PHILIPS���C���g�����X�Ƌ��ɁA�����g���Ă��܂��B
�P�[�u���͒���I�ɃN���[�i�[�Ŗ����A�������Ă���̂ŃN���A���͋y��_�ł��B
���C���P�[�u���́A���Ƀ��C���[���[���h�A�I���g�t�H���A�]�m�g�[���AMIT�A�T�G�N�i���j�ƁA�g���Ă��܂����A
PHILIPS�̃P�[�u�����̔����Ă���A�����ɂł��w����������i�ł��B
��PHILIPS�̕t���P�[�u���Ƃ������Ń��X���������܂������A
MOGAMI�̃P�[�u���͎g�������������A�����ɗ��Ă����炵�܂����B
�����ԍ��F12552310
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
����MOGAMI�̃P�[�u���͎g�������Ƃ�����܂���BMOGAMI�͂ǂ��炩�ƌ�����PA���̃v���p�Ƃ����������ŁA���܂�R���V���[�}�[�E�I�[�f�B�I�p�Ƃ��Ďg���Ă��Ă͂��Ȃ��悤�Ɏv���܂��̂ŁA����݂�����܂���B���O���l�b�g�ł����������A�X���ł͂��܂茩�����܂���B
����͂��Ă����A�d���P�[�u�����G�[�W���O���ʂƌ����܂��傤���A�g���Ă��邤���ɉ������Ȃ�Ă��܂��B�����܂��g�p���Ԃ��Z���̂Ȃ�A���f�����ɐ������g������ł݂Ă͔@���ł��傤�B
�������Ȃ�Ă��Ă���A����ł��܂��s�������������ɃP�[�u���`�F���W�ɒ��킷��Ηǂ����Ǝv���܂��B����܂ł̓P�[�u��������A���Â̏o���Ȃǂ�T��������Ԃɓ��Ă��Ă͔@���ł��傤�B
�����ԍ��F12555182
![]() 0�_
0�_
������
audio-style����
�����ł��O���[�̌ł���ł��B�v���[���[�ƃP�[�u���Z�b�g�ʼn���肵�Ă�Ȃ�Ĕ����ł���ˁB����P�[�u�����g���܂킵�Ă݂�600�̏d�S�̒Ⴓ�͂��̃P�[�u���Ɉˑ����Ă������Ƃ��n�b�L�����܂����B���̃P�[�u���̓��X�����Ȃ������h�o�b�Əo�Ă��銴���ł��B�{���ɗǂ��P�[�u���ł��ˁB1500�Ƃ̑����͂��܂����ł������BPHILIPS��CD�v���[���[�ɉ��͍����Ă܂��ˁB���y�����Ƃɂ����ă����W���̗D�揇�ʂ͂��قǍ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB����A�����ւ��Ă��炽�߂�600�̂悳���ĔF�����܂����B�̏Ⴕ���̂��܂��ƂɎc�O�ł��B
586RA����
�R���V���[�}�[�p�͐F��ɂ��Ă���̂őI������͂����Ă��܂��B����͂��܂�F�͕t�������Ȃ����̂ł�����B�G�[�W���O�ł����B�܂���T�Ԃقǂł��̂ōŒ�ꃖ�����x�͗l�q���Ƃ������Ƃ���ł��傤���B�m���ɒʓd�J�n������ǂ���������悤�ɂȂ��Ă��Ă���̂ł����A�������Ȃ�Ă��Ă���̂��������Ȃ�Ă��Ă���̂��s���ł��B���������悤�ɍ����炭�������Ԃɓ��Ă����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12557777
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
>�R���V���[�}�[�p�͐F��ɂ��Ă���̂őI������͂����Ă��܂��B
����͂�����ƌ�����Ǝv���Ȃ��B��������Ă��邠�܂�P�[�u���W�ɒm���̂Ȃ����B���R���V���[�}�[�p�͐F�t�����K������Ǝv���Ă������Ȃ��̂ŁA���̌����������Ă����܂��B
�v���p�Ƃ����Ɛ������Ɏv���܂����A���ƃI�[�f�B�I�Ɍ����Č����Ή����Ńv���p�𗽂��R���V���[�}�[�p�͑�R����܂��B����
�����ł��B����͎�̐��i�ł����āA�R�X�g�x�O���̍��ɂȂ��Ă��邩��ł��B�v���p�͕i�����������Ƃ��K�v�ł����A��v����Ԃ������肵�܂��B�����Ďg���Ղ����ƂȂǂ��d�v���Ǝv���܂��B
�ŁA�v���p�͊O�ςȂ�Đ^�����Ȃ����̖����ŁA�����܂ŕt�����X�s�[�J�[�Ƃ��A���b�N�}�E���g�o����T�C�Y�̃A���v�Ƃ��A���b�N�}�E���g�̂ɔp�M�̓t�@���ɗ���Ƃ��A�P�[�u���͑����čd���ďd���R���V���[�}�[�p�Ƃ͈���ď_�炩���Ď����ǂ����̂Ƃ�����B�v����g�p�ړI���Ⴂ�܂��̂Ńe�C�X�g������Ă��邾���ł��B
�������������xrcd���̃��C�i�[�m�[�c������ƁA���Ƃ��ăR���V���[�}�[�p�Ƃ��Ĕ̔�����Ă���@���P�[�u�����g���Ă����肵�܂��B
�R���V���[�}�[�p�����灛���ƌ�������ς̂悤�Ȃ��͎̂����ꂸ�ɁA�������ǂ��Ǝv������̂�T���w�͂����邱�Ƃ��̗v���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12558540
![]() 1�_
1�_
�����玸�炢�����܂��B�@���̎g�p���Ă���d���P�[�u���́APCOCC-A�̓����ɋ����b�L�̃t���e�b�N�̃v���O(����łP�T�O�O�O�~�ʁj���g���Ă��܂��B�@�܂��G�[�W���O���ł��̂ʼn��Ƃ������܂��B�@�P�[�u���̌��������ʼn��͖{���ɕς��܂��ˁB�@�s�����̃I�[�f�B�I�V���b�v������@�����̖ڎw���Ă��鉹�ɑ��ǂ��A�h�o�C�X���Ă����Ǝv���܂��B
�����䂤�����@���X�ɂP��������Z��@�����@�����@�Ƃ����Ă���܂����B
����P�[�u���͎s�̕i�����������̂͂��肪�����ł��ˁB
�i�������@�����̖����@�łɂꂽ���ςł����ǁB�j
�����ԍ��F12664519
![]() 0�_
0�_
�d���P�[�u���̎���ł����A�������ł��ˁB�܂��Ɏ�̐��E�ł��ˁB�d���P�[�u���Ƃ����A�����I�[�f�B�I�ɔM���グ�Ă�������ɍw�������@��ɂ͋ɐ��̔����\�����������̂ł���1500�ɂ͗L��܂���B�ɐ���ς���Ɩ�͕ς��Ǝv���̂ł������s��Ȃ��Ȃ����̂ł����ˁB
���������P�ɂ��Ăł����A�������炭���y���Ă���CD�v���[���[�̃h���C�u�\�̖͂��Ȃ̂ŃP�[�u�������ł͎��̊�]�����Ȃ���͓̂���Ɣ��f���܂����B�w�����͊��҂��Ă��Ȃ������̂ł���������̍Č��\�͂��v���Ă��������ǂ������̂ŗ~���o�Ă��܂����̂ł��B�����̃��[�Y���ɋN�����Ă��邱�Ƃł��̂ł�����߂܂��B���������̒l�i�ł����܂ōĐ��ł���Ƃ͗ǂ�����ł��ˁB
�����ԍ��F12673310
![]() 1�_
1�_
����ɂ���
�������I�[�f�B�I�ɔM���グ�Ă�������ɍw�������@��ɂ͋ɐ��̔����\�����������̂ł���1500�ɂ͗L��܂���B
1500�͎g���ĂȂ��̂ł����A
�t���̓d���R�[�h�̃v���O�i�R���Z���g�ւ̍��������j�Ɂ��̃}�[�N�͕t���Ă��܂��H
���}�[�N���t���Ă���A�ɐ��̓}�C�i�X�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�ɐ��\���ɂ��́A����ɏ�����Ă��Ȃ��̂�����܂��ˁB
�����������P�ɂ��Ăł����A�������炭���y���Ă���CD�v���[���[�̃h���C�u�\�̖͂��Ȃ̂ŃP�[�u�������ł͎��̊�]�����Ȃ���͓̂���Ɣ��f���܂����B
���l�Ɋ����܂��A�P�[�u���ނ̌��������Ŋ�]�����Ȃ���͓̂���ł��傤�ˁB
�X�E�B���O�A�[���̃h���C�u���J���ǂ�������ł��傤�B
PHILIPS��CD�v���[���[��������x�g���Ă݂����ł��ˁB
�����ԍ��F12683274
![]() 0�_
0�_
audio-style����A�����́B
�����}�[�N���t���Ă���A�ɐ��̓}�C�i�X�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�c�O�Ȃ�����Ă��܂���ł����̂ŕ����Ĕ��f���܂����B
��PHILIPS��CD�v���[���[��������x�g���Ă݂����ł��ˁB
�g�������ł��ˁB�����Ɏg�p���Ă���h���C�u���J�͓������Ȃ�̍��]���������ƋL�����Ă��܂��B����LHH600�͂܂��̂Ă��ɂƂ��ėL��܂��B�g���C���蓮�ŊJ���ēV���͂���CD���蓮�Ń`���b�L���O���Ă�����ƍĐ��ł���̂ł���B�x���g�W�̃g���u�����Ǝv���̂ʼn��Ƃ��Ȃ肻���ȋC������̂ł����E�E�E�ȑO�}�����c�̂����Ƃ��b������@����蕷���Ă݂��̂ł����ێ畔�i���Ȃ��̂Ŗ������Ƃ����Ă��܂��܂����B���܂��ɂ�����߂���Ă���܂���B�i�j
�����ԍ��F12694506
![]() 0�_
0�_
�o�b�I�[�f�B�I�Ȃǂ��e�[�}�ɐ��Ԙb����X���́u���߂ăp�[�g�Q�v�ł��B
�u�Ȃǁv����ꂽ�̂́A�o�b�I�[�f�B�I�ƒ��ڊW�Ȃ����b���n�j�Ƃ����Ӗ��ł��B
�ł݂͂Ȃ���A����������낵�����肢���܂��B
![]() 4�_
4�_
�F�l�A�����́@�Ȃ����v���Ԃ�ł��B
�`������@��������Ⴂ�܂�^^
�d���Ō��\�����ς�邱�Ƃ�m��A�V�����d���P�[�u�����w��
���[��A���₩�߂��Đ��k�ȊG�����Ă���悤���E�E�E
�d������������������A�m�C�Y�t�B���^�[�t���Ă݂�E�E�E�����Ȃ����C��
�����������ȊO�ɕt����A�A�A��H�ς�������ȁH;�@�C�����I�ɗǂ��Ȃ��������H^^;
�g�����X�d��������ꏊ��A�z����F�X�ƌJ��Ԃ��E�E�E
�����A�g�����X�d���A���v�ɗǂ��Ȃ����Č������ǁA�����ς���Ēቹ�̗ʊ�������
�ƂĂ��S�n�悭�����₷���Ȃ����ł͂���܂��I�@
����ς�l���ꂼ����Ⴄ����A�����Ŏ����Č��Ȃ���ƁA���炭�����Ă��
����H�@�o�C�I�����̉����a�f�l���x���ɁB�B�B���ۂ̉�����������@���Ă�悤�ȉ��ɁE�E�E
�����A�A�A�ŏ��̂���ԗǂ������E�E�E(Ʉt-�*)
�ƁA�`������̌�����A��邱�ƂȂ����Ə��ɂ͂܂��ԂɊׂ��Ă���܂����i�j
�����A�o�b�I�[�f�B�I����̉��Ƃ��Ă͂ǂ�����̂Ă������A�A���v�p�Ƀp���t�����ƕ]����
�������쏊��2000�̕��̎����@�݂��o�������肢���Ă݂܂���
http://ns-t.com/products/trans/nsit2.html
�ƂĂ��ǂ������甃�����ƂɂȂ�Ǝv���܂����ADAC�A�A���v�A�X�s�[�J�[�ɕC�G���鉿�i
���̉��ɂ͂܂荞�݉߂��āA�����Ԉ���Ă���C���A�A�A�A(;^_^A
�v���N��D��!!����
���C���Ă��ł��Ȃ��̂ɂW�������̂ł��ˁA�A�A�u���ꏊ�������炩�ȁH�i�j
���C���@�́A�P�䂾���q���Ƃ��ł��傤���H
> ���߂�CD-R���Ă������A���̍��������������Ȃ���ΐl����Έ�����ȁc�Ǝv���������̍��c(���)�B
�E�E�E�E���������Ă��܂��܂�����i�j�i�b�c�h���C�u�ɂ��������̂ŁA��@���� (><)
�Ă����͂����Ǝ���Ă��������� ^^
�V�n�n������
�r�n���l�̃J�[�h�z���ȏゾ�����̂ł��ˁE�E�E
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ����������ċA�낤�Ǝv���܂��i�j
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
�I�J���g���i�Ȃ̂ɁA�����\�Ƃ������̂Ő���ޗ���Ō��܂���
�����ԍ��F12533424
![]() 1�_
1�_
�b�r���ő����Ă��܂��܂����@<(_ _)>
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
�I�J���g���i�Ȃ̂ɁA�����\�Ƃ������̂Ő���ޗ���Ō��܂����̂�
���j���f������Ƃ��ɁA�ꏏ�Ɏ����čs�����Ǝv���܂��B
�v���N��D��!!����
�����낻�뎩�l���E���₷���c^^;
������x��ł� ^^b
�_���������ꂽ�A�Z�b�e�B���O�̃m�E�n�E�Ƃ��������������ł��i�j
�����ԍ��F12533478
![]() 1�_
1�_
�������A���j���͂����̂o�b��
�Q�O�O�u���P�O�O�u�g�����X�o�R
�P�O�O�u����
�ʼn��̈Ⴂ���m�F�ł��܂��B�o�b�ł��Ⴄ�̂ŁA�A���v�A�v���[���Ȃ�Ȃ�����ł��B
�����ԍ��F12533508
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
�X�����Ă����l�ł��B
�O�X���ł͎�藐���Ď��炵�܂����B
�������
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�@�ރ��^�N�Ȃ̂Ő[�݂ɂ͂܂�ƑΏ��ł����J�[�l���p�j�b�N���N�����悤�ł�(���
�悭�ʐ^�ɂ��Ƃ���̂ł����A�m�C�Y�t�B���^�Ƃ̓m�C�Y���_�N�V�����̂悤�Ȃ��̂ł��B
�ア�ƃm�C�Y���ڗ����A����������Ƃ̂��肵�����R�Ȋ��C�̂Ȃ��G�ɂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�悤�͂ǂ��炪�ǂ����͐l���ꂼ��ł����A�T�O�Ƃ��Ă͂��̂悤�ɂȂ�܂��B
�t�F���C�g�R�A��V�[���h�Ƃ͂������������̂ł��ˁB
�P�[�u���̊T�O�ł����A���H�̂悤�Ȃ��̂ł��B
��ʉƒ�̉����z���͈�ʓ��̂悤�Ȃ��́A�R���Z���g����@��܂ł̓P�[�u���ɂ���Ĉ�ʓ��ɂ��_���ɂ��������ɂ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B
�V�[���h�̊T�O�͌i�F�͌���邪�J���炵�̓��H�������̂��A�i�F�͌����Ȃ����V��ɍ��E����Ȃ��g���l�����H�������̂��Ƃ������o�ł��B
�����̊T�O�ׂ͍����H�Ȃ珬���ȎԂ����ʂꂸ�A�傫�����H���Ƒ傫�ȎԂ��ʂ��Ƃ��������ł��ˁB
�T�O�I�Ȃ��̂����낢��ƈړ]���������̂ق��ɏ����Ă������Ǝv���Ă��܂��B
����ȍ~�͊e���Ŏ����Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F12533898
![]() 2�_
2�_
�F������
�V�����X���ł���낵�����肢���܂��B
���r�n���l�̃J�[�h�z���ȏゾ�����̂ł��ˁE�E�E
���̃J�[�h�̌��ʂ��T�E���h�J�[�h�̉��̌X���Ƃ͐^�t�̉��̌X���ɂȂ����̂Ō��ʂ��傫���o���悤�Ɋ������̂�������܂���BHDD�A�N�Z�X�ߑ��⍂�����̉��Ƃ�(���\���ǂ��������킽����PC���ƂقƂ�ǔ������܂��c�c)�Ȃ�USB�炵���s����ȂƂ���������܂��B�������܂�悭�Ȃ��Ă��Ȃ��̂�������܂���B���̃J�[�h�����ł͂��܂�ǂ����ʂ������Ȃ��悤�Ɋ����܂����B���̃J�[�h���܂߂Ă��낢�������Ďn�߂Č��ʂ��o��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��̂ł����������s���낵�Ă��������Ǝv���܂��B
�����O�̏������݂ɂ��������Ɩ��p��PCI�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X���g�����ق����͂邩�ɗǂ����������ł��傤�ˁc�cPC�I�[�f�B�I���ɂ߂�̂Ȃ炱����ӂɗ͂�����ׂ��Ȃ̂ł��傤���l�i�������ł��c�c�ł��N���b�N���͂��C�ɂȂ��ċC�ɂȂ��ē��ɓ��Ɏg���Ă݂����Ȃ��Ă��Ă��܂�����
�����P�[�u�����͂��̂������ċ��j���A�x���Ɠy���ɂȂ肻���ł��B����̓����P�[�u���O�[���`���[�j���O�Ŏg�p�����z���ނƓ����f�ނɎg�p���Ă���̂œ����P�[�u���̔������̂܂܋z���ނƂ��Ďg����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����炻�̔����̂ǂ̏ꏊ�ɂ��悤�����l���Ă��܂��B���܂Ŏg����Ƃ����̂͂ƂĂ����肪�������i�ł��B�P�[�u���{�̂�1�x�������������Ă���������Ƃ�����̂Ŋ��҂ł������Ȃ̂Ŋy���݂ɑ҂��Ă��悤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12534108
![]() 1�_
1�_
�V�n�n������
������ł��B
�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�ł����A�ǂ���̐��i�����T���ł��傤�H
�Q�l��RME HDSP 9632(PCI�ڑ�)�ł���
TOMOCA\79695
���t�[�`���C�i���[��\59328
���t�I�N\37500�`
�ł��B
�Q�l�܂łɂǂ���
�����ԍ��F12534270
![]() 1�_
1�_
�`������@
�����d���̍��Ԃɂ��낢�뒲�ׂĂ݂܂����BPCIEX�d�l�̂������ł��ˁB���낢�댩�čs��������HDSPe AIO���悳�������ȂƎv���܂����B����ɂ������R��24bit192KHz�o�͂ɑΉ����Ă�����o�͂��L�x��PCIEX�Ŏg�p�ł���Ƃ���Ɏ䂩��܂����B
�N���b�N���͂̑��݃{�[�h�܂ōw�������11���߂������v�Z�ɂȂ�̂ł����ɂ͖����ł��ˁB�v���A���v�̍w�������Ɏ�������ɏ��Ԃɍw�����Ă����K�v�����肻���ł��B
�m�C�Y��͂ǂ����Ă��C�ɂȂ�悤�Ȃ�J�[�{�����̃m�C�Y�t�B���^�[�V�[�g�ł����ɂ͂�����Ǝv���̂ł܂���ɂ���Ǝv���܂��B�܂��̓}�X�^�[�N���b�N�̊m�ۂ����Ȃ��Ⴂ���܂���ˁB�����Ȃ����ǁc�c������Ď����W�߂����܂�(��)
���̃I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�𓊓�����Ƃ킽����PC���z60�������܂�����
������Ƃ�肷�������ȂƖҏȒ��ł�����
�����ԍ��F12536908
![]() 1�_
1�_
PC��60���ł����A�������ł��ˁB
AIO�̓��C���Ŏg�p���Ă��܂��B
9632�Ƃ̈Ⴂ��PCI��PCI-E���A�ŏ����C�e���V�̍��ł��B
PCI-E�̂ق����m�C�Y�ɋ����Ȃnj����܂����A
���͂�PCI���Ȃ��Ȃ��Ă����܂��̂�AIO�̂ق����ǂ��ł����A
���i����1���~�قǂɂȂ�܂��B
TOMOCA��\88360�ł��ˁB
9632WCM��\21945�ł����B
���i���C���i�b�v�̓V���^�b�N�X�̃y�[�W�Ō���܂��B
AIO��VISTA�̏ȓd�͋@�\��PCI�̏ȓd�͂�OFF�ɂ��Ȃ��ƃu���[�o�b�N�ɂȂ�܂��B
��������1�����قǎg���܂���ł����B
�����ӂ��������B
�N���b�N�ɂ��Ă̋L�q�͂��邦�ނ���̂Ƃ���ł��炩���킩��܂����A���LURL�����Q�l���������B
http://plaza.rakuten.co.jp/amoknoan/diary/200412060000/
�����ԍ��F12537235
![]() 1�_
1�_
�`������@
>AIO��VISTA�̏ȓd�͋@�\��PCI�̏ȓd�͂�OFF�ɂ��Ȃ��ƃu���[�o�b�N�ɂȂ�܂�
�����g���Ă���windows7�ł�����Ȃ������ɂȂ肻���ł��ˏ�肪�Ƃ��������܂��B
�o�b�̃p�[�c��(���\�ʂ�)�������̂���I�肷�����Ă����獂�z�p�[�c����ɂȂ��Ă��܂��܂�������
���\�͔��ɍ����ł����m�C�Y�͒����d�͔ł̂b�o�t�ɔ�ׂ��炷�����ł��傤�ˁB�m�C�Y�̉e���Ȃ�ĕ����Ă��Ă��قƂ�NjC�ɂȂ�܂��Œ���̑�͂��Ă��܂��B���i�̓N���b�N�������I�ɗ��Ƃ��ē������Ă���̂ł��Ȃ荂���ׂœ������Ȃ�����M���Ƀm�C�Y���̂�悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B6�R�A12�X���b�h��DDR3-2000MHz�͂����܂����ł���B���ƂтȂ�Ă��͈̂�؋N����܂���(��)
���͊F����̒����d�͂���N���b�N�d�l��CPU���g�����ق��������Ƃ����l���Ƃ͐^�t�̂��Ƃ����Ă��܂��B�z���ȏ�Ɉ��肵���������łȂ��Ă����̂ł�����X�y�b�N��PC�ɖ߂�܂���悗��
�����ԍ��F12537399
![]() 1�_
1�_
�F�l�@������
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
���Q�O�O�u���P�O�O�u�g�����X�o�R�@�P�O�O�u���ځ@�ʼn��̈Ⴂ���m�F�ł��܂�
�g�o�Ŏ���g�����X�d���g�p����āA�F�X�������낳�ꂽ�̂�q�����Ă܂����̂�
�������������������Ǝv���Ă��܂����B�@���肪�����ł��@<(_ _)>
�X�����Ă̂����Y��Ă���܂����@�����l�ł� ^^
�`������
�m�C�Y�t�B���^�ł����A���̂悤�Ȋ����ł���
�g�����X�d�����A���v�Ɏg�p����̂������X���ł������d�������A���������
�E�E�E����A�����b�g�����ō������ꂽ�悤�ȁH�i�j
�������ꂽ�Ŏv���o���܂������A�c�`�b�������������̂q�l�d���i�Ƒ��̐��i�݂�����
�`������́ARME���i�F�X�Əڂ������ł����Afireface�ƃs���A�I�[�e�B�I�n��DAC��
������ׂ��ꂽ������܂��H
�܂������ɍs���܂����A���̍����Y����Ȃ��̂ł���ˁB�B�B�B
�V�n�n������
SOtM�͍��܂ł̃J�[�h�Ƃ̍�������ׂł�����
���̕ӂ�͂o�b���ꂼ��ł��̂ŁA���̗������傫�����ł��ˁ@�������\�z�ł��Ȃ��E�E�E
�i�����@�݂��o�����ށ@�i><�j
�N���b�N�W�F�l���[�^�[�̂��b����ĂāA�������C�ɂȂ��Ă���i�ق���̏��i�ł���
�������I�@SA-50�����邩��A����ɃN���b�N�W�F�l���[�^�[��t����A�����ŋ��H�I
�Ǝv���A�b�c���܂�����ړ������Ď������Ă݂܂���
�E�E�E�����������A�A�A���̂b�c�v���C���[�́A�M��Atoll�̃A���v�ƃf�B�i�̃X�s�[�J�[����
�M�C��D������Ă��܂����낵���v���C���[�������E�E�E��
�O�ɂ���ċC�Â��Ă������A���X����Ă��܂��܂����@���قł���^^;
�����A�O�ƈ���ėǂ�����������B������ꂵ�Ȃ������ł��@���ς�����������ȁH
����ȉ����D���ȕ������邩���H�Ƃ��������ŕ����܂�����
���ɂ͕����y�����������Ă��܂܂����@���X����ł��B
�����ԍ��F12537933
![]() 1�_
1�_
�V�n�n������
jubee����̌f���ł͂��{�l���uPC��windows�ł���Ă����E�E�E�v�`�X�Ƃ���������Ă܂����A��͂�CD-R�̉����ɓ������Ă���PC��PC�łȂ��Ȃ�������ł���Ǝv���܂��B
PC�g�����X�|�[�g�ɂ�����PC�͕K�v���ł�����d���Ȃ��ł���ˁB
�{�N�̏ꍇ�͂��߂�������Ɏ����̎g�p���鐫�\���������(���ۂɂ͂���ł��I�[�o�[�X�y�b�N�ł���)�A���ɔz�������\����I�т܂����B
�����A�߂ڂ������������Ńp�[�c���Ƃ̉��͂킩��܂��A�������������Ă��܂���ˁB
�K�v�Ȑ��\������w�������킯�ł����āA����ɔ����������̗ʂ͔�ׂĂ݂Ȃ��Ƃ킩��܂��A�{�l���[�����ċC�ɂ��Ȃ��̂ł��������K�v���ł�������Ȃ��Ǝv���܂���B
�͂��߂�����Ȃ�ėp�̃��C���}�V���ŋ��p���邵���Ȃ��ł�����B
�����Ȃ�̃m�E�n�E��������x�ł܂��Ă���]�T�����������_�Ő�p�@���d�グ������Ǝv���܂��B
���y�Đ��ɕK�v�ȃX�y�b�N�Ȃǂ���܂�������ł��݂܂����B
�������
������Ajubee����̌f���ł��͂��߂͎g���Ă����nj��ǎg��Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B
�����u���b�V���A�b�v����Ă����Ƃ������Ďז��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����Ɋւ��Ă͑���ۂŌ��߂Ă��܂��B
�����Ă��邤���ɂ킩��Ȃ��Ȃ邩��ł��B
�������G�[�W���O�Ƃ����̂�����̂������ł��̂œ���Ƃ���ł��B
���p�w�b�h�z���ł��Ԃ��ƒg�C�^�]��1���ԂقǕK�v�ł����A
���i�g��Ȃ��p�[�c���ӂƂ��Ă݂�Ƃ��܂��ۂ��ǂ��Ȃ������Ƃ������Ƃ����邩�Ǝv���܂��B
�{�̔�������O�ɕ����Ă���\��������܂��ˁB
�K��PC�̏ꍇ���i�g�����̂ł�����ڑ������ςȂ��Ŋ��炵�^�]���o���܂��B
���炭�炵�Ă����Ă��珉�߂ĕt�ւ��ɂ�鉹���̕ω��Ƃ������̂����f���₷���Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�H
�����������茳�ɂ���@�ނł����炵�炭�Ȃ����ςȂ��ɂ��Ă݂Ă����Ă��������B
DAC�ł����A�͂Ȃ��烂�j�^�����O�@�ނɂ����������Ȃ��ADAC���̂������͂��Ă��܂������A�����ȑO�̒i�K�ł����B
�悤�₭Mytek�̐��i�����ɂ��Ȃ��Ă�Ǝv�����̂ŃI�[�_�[���n�߂��i�K�ł��B
�������ɍs���ĕ������̂m�Ɋo���Ă���͉̂f���Ɖ��̃v���̕����g�p����Ă�CHORD DAC64�ƃC�[���C���z����FOSTEX HP-A7�ł��ˁB
DAC64�̓f�X�N�g�b�v�}�V����FireFace400�A�׃����K�[�H�C�R���C�U�AYAMAHA�v���Z�b�T�ARosendahl Nanoclocks �ADAC64�AYAMAHA MSP7�Ƃ����@�ނł����B
��������ۂ͉��Ȃ��s���Ȃ��ł��B
�I���W�i���X�L����OS�ƃ��f�B�A�v���C���[�AMP3�Ƃ��g�p����Ă܂������AWAVE��MP3�ő卷�Ȃ��Ƃ������ł����̂Ŋ����F�����Ȃ������̂��H(�}���V�����̈ꎺ�ł����B)
�Ӂ[��Ƃ�����ۂ����Ȃ������ł��ˁB
FOSTEX HP-A7�̓m�[�gPC��Vista?iTunes�Đ��Ńw�b�h�z����HD800�ł����B
�܂��A�w�b�h�z���͍����@�ł��̂ōL�����������Ȃ��Ă܂������A���ȓ��������������ł��������ƋA��܂����B
�����Ⴄ��@�ޒP�̂̉��������Ȃ��̂���_�ł��ˁB
�������ėB��������͎̂O�؊y��TOOLS��VXT4�ł��B
�͂��ߕ������Ƃ��̓��[�G���h�̐L�тɃ��~�b�^�[���Ȃ��X�^�b�t���ԈႦ�Ăق��̃X�s�[�J�[�Ŗ炵�Ă�̂��Ǝv���܂�����B
�܂��A�����DAC�̘b�ł͂Ȃ��ł����B
��������g�͕���������ׂ��ꂽ���Ƃ͂���܂����H
��������DAC�͂������ł����H
23���������������ĉ����������Ȃ��Ȃ��������֎����Q������܂���ˁB
�M���M���ł����A�����ĂȂɂ��������Ȃ��Ȃ�������������������̂ł����玎����ɑ݂��o�����܂����B
��[�z���@�͂ǂ����悤�B
�������͋��s�ł����A�����Ԃ������Ύ����ɂ����܂����H
�����ԍ��F12538413
![]() 1�_
1�_
�`������ ������
> �����������茳�ɂ���@�ނł����炵�炭�Ȃ����ςȂ��ɂ��Ă݂Ă����Ă�������
����́A�N���b�N�W�F�l���[�^�[�̎��ł��傤���H
�����ĂȂ��ł���[�i�j�@�@�ƌ������A�����܂���E�E�E
�b�c�v���C���[��SA-50�̉����X���̊m�F�̂��߂����ł� ^^;
> ��������g�͕���������ׂ��ꂽ���Ƃ͂���܂����H
�N���ɕ�����ׂĂ̊��z�ł���
�����A���̓��C���o�͂�RME�͈Ⴄ�̂ŁA�Ԃɉ��������Ă���͂��Ȃ̂�
����̍��Ȃ̂����m��܂���̂ŁA�܂������ɍs���ė��܂�
�`����������C���z���ɍs���ꂽ�ƌ������́A���{���܂Ŏ����ɍs����Ă�̂��ȁH
���̎��������̂́A���{���̃V�}��������ł��B
> ��������DAC�͂������ł����H
DAC�́ACEC��DA53N�ƁAnu force��udac-2�ł�
�b�c�v���C���[��SA-50�ɂ�DAC���͂�����̂ŁA�O�̃X���͂���Ŏ����Ă̊��z�ł�
�����A��������SA-50�ւ̌��⓯�����͂Ńe�X�g���ĂȂ���E�E�E
> 23���������������ĉ����������Ȃ��Ȃ��������֎����Q������܂���ˁB
> �M���M���ł����A�����ĂȂɂ��������Ȃ��Ȃ�������������������̂ł����玎����ɑ݂��o��
�݂��o�����ĉ����H�i�j
���������͋��s�ł����A�����Ԃ������Ύ����ɂ����܂����H
�����@����͎��ԍ�肽���ł���
�O�X����A���������ǂ̂悤�ȉ������Ă���̂������ÁX�ł����̂� ^^
�����ԍ��F12538619
![]() 1�_
1�_
>����́A�N���b�N�W�F�l���[�^�[�̎��ł��傤���H
�m�C�Y�t�B���^�[�̈�ۂ��F�����Ȃ������悤�Ȃ̂ł��̌��ɂ��ď����Ă݂܂����B
>�V�}�����ł��B
�n�}�Ŋm�F���܂����B
��V�{�Ђ̋߂��ł��ˁB
�ȑO������ƃI�[�f�B�I�W���܂������m�[�`�F�b�N�ł����B
RME�̋@�ނ������Ă����ł���ˁH�H
�t���A�͊o���Ă܂����H
�����Ă���悤�Ȃ�s���l�q���Ă�������炢���Ă��܂���
>DAC�́ACEC��DA53N�ƁAnu force��udac-2�ł�
DAC����������Ƃ͂����܂����B
�{�N��������DAC����ł��ł����A�҂��������ł��ˁB
http://www.vintageking.com/Mytek-Digital-Stereo192-DSD-DAC
>�݂��o�����ĉ����H�i�j
�����A���݂܂���A��ꂪ�����Ă܂���(��
HDSPe AIO�ł��B
�\���ɖ��J����9632������ȊO���ꂵ�������Ă܂���̂�(^^;�U
>�O�X����A���������ǂ̂悤�ȉ������Ă���̂������ÁX�ł����̂� ^^
200V��CV-S 5.5sq����������ł����A�������肫������ׂ����Ɉ����Ă��܂����̂ŏd�S�����������܂܂Ȃ�ł���ˁB
DAC���Ȃ��̂Ŋ����O�̉��ł����A���̓_���������������B
�P�[�u���͂��łɂ���̂ŋ߁X3.5sq���������݂܂����B
���Ƃ����K702��OS���Ƃ̉����`�F�b�N�ł����ˁB
��pOS�A�œK��OS�A10.3.6��3�ɂȂ�Ǝv���܂��B
Vista��2k������܂����A�C���X�g�[�����ĂȂ��̂ŁE�E�E�B
SSD��OS�C���X�g�[�����Ă܂����AKINGSTON�u�����h�͓����ł��e�ʂ��Ⴂ�܂��̂ł����ӂ��������B
���Ȃ݂Ƀ��[���A�h���X�͂��萔���������܂���
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9832348/
�̌��R�~��Ctrl+F�Łu11236002�v�ƌ������Ă���������łĂ��܂����O�O���|�|��
���낢��Ƒ���������Ă܂����A���ۂ͑�l���߂ł�(��
�����ԍ��F12538827
![]() 1�_
1�_
������ƊF����̍l������ے肷��悤�ȏ������݂ɂȂ��Ă��܂���������܂���B����������Ȃ̂ŕ��̗��������ɂȂ��Ă��܂���������܂���B���e�͂��������B
�`������@
>jubee����̌f���ł͂��{�l���uPC��windows�ł���Ă����E�E�E�v�`�X�Ƃ���������Ă܂����A��͂�CD-R�̉����ɓ������Ă���PC��PC�łȂ��Ȃ�������ł���Ǝv���܂��B
���͂o�b�I�[�f�B�I�Ƃ͉��Ǝ��₳�ꂽ�炱�����܂��B
�o�b�I�[�f�B�I�Ƃ͂o�b�̖��\�����t���Ɋ��p���Đ�����^���܂ōs�����Ƃ��ł������݂̃s���A�I�[�f�B�I���x���Ɠ����̉�����ڎw������
�ƂȂ�܂��B�����ŏd�v�Ȃ̂͂o�b�̖��\�����t���ɐ������Ƃ������Ƃƕ��݂̃��x���Ƃ����Ƃ���ł��B
�������Ɍ��܂ŒNj�����̂ł���Ύ��̗ǂ�CDP���g�����ق��������ł��BPC�Ńs���A�I�[�f�B�I�̐��E�Ɛ^�������珟������͖̂���������܂��B�˂��l�߂Ă����������ɂ͂Ȃ�ł��傤���Đ���p�̃s���A�I�[�f�B�I�Ɣ�ׂ��炨�e���Ȃ��̂ɂȂ�̂͂킩�肫���Ă��܂��B
�ł͂Ȃ�PC�I�[�f�B�I���L�܂�n�߂Ă���̂��c�c�킽����PC�I�[�f�B�I�͈��̃l�b�g���[�N�v���C���[���ƍl���Ă��܂��B�l�b�g���[�N�v���C���[�ɂ͋y�Ȃ�������ɕC�G���鉹���Ƃ��̋C�ɂȂ�Ή��ł��ł����y�Đ��ȊO�ɂ�����Đ���l�b�g�E�ɘ_�������Q�[�������č��i���̉��ŗV�ׂ鍡�܂ł̃I�[�f�B�I�Ƃ͈Ⴂ����Ӗ����ɂ̖��\�������˔������V�����I�[�f�B�I���ꂪPC�I�[�f�B�I���ƍl���Ă��܂��B�Ȃ̂ōĐ���p�̐�p�@�����Ƃ����͎̂��͎^���ł��܂���B
�킴�킴��X�y�b�N�Ȑ�p�@����邮�炢�Ȃ��̂��悤�ʼn��Ƃł��Ȃ艽�ł��ł��鍂�X�y�b�N��PC���g�����ق������낢��Ȃ��ƂɎg���܂��BPC�̂����Ƃ����ׂ��Ă��܂�����PC�I�[�f�B�I�̈Ӗ����Ȃ��Ƃ͎v���܂��H
���̍l������s����CD�h���C�u�����܂�K�v�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�ŋ߂̃R�X�g�p�t�H�[�}���X�d���̃h���C�u���ǎ��Ȃނ�����CD�h���C�u���g�����ق��������ǂ��Ȃ�Ƃ͎v���܂��B������CD�h���C�u������Ƃ��͂������������b�s���O�̂Ƃ������ł͂Ȃ��ł��傤���H
��荞�f�[�^���G���[�Ȃ����m�ɏ������ނ��߂ɂ����������h���C�u���K�v�ɂȂ�ł��傤���APC�I�[�f�B�I�̂悤�ɒʏ��������HDD�����荞�f�[�^���Đ�������̂ɂ͐��m�ɏ������ނ��߂̃h���C�u�͕K�v����܂���B
�悭�f�[�^�̃��X���Ƃ��G���[���Ƃ��b���o�܂������̃G���[��X�͍Đ����荞�ޏ�ł܂������Ƃ����Ă����قNjC�ɂȂ�܂���B�Ȃ��Ȃ���̏ꍇPC����荞�ݒ��ɔ��������G���[���C�����Ă��܂�����ł��B����Ȃ�100%�ɋ߂��f�[�^����荞�ނ̂ł������荞�ގ��_�ʼn��������Ȃ�Ƃ����̂͂��肦�܂���B�G���[��X�ɂ���ĕς�鉹������l�͐l�Ԃ���Ȃ��Ǝv���܂��B
���X��G���[���N����Ɖ����������Ȃ�̂͊F����������m���Ǝv���܂��B����������͗��_��̘b�Ŏ��ۂ�PC���G���[���C�����Ă��܂��̂łقƂ�lj��ɕω��͏o�܂���B�ω����o���Ƃ��Ă�0.001�b���Z�����Ԃł̕ω��ł��傤�B���̂悤�ȉ��͕��������邱�ƂȂ�ĂƂĂ��ł��܂���B���炩�ɉ��������Ȃ����E����т�����Ȃǂ̌��ۂ̓f�[�^�̃��X�������ł͂���܂���B���̌����̓t�@�C���𐳊m�ɓǂݎ��Ȃ��n�[�h�E�F�A�̖��E�\�t�g�E�F�A�̖��ł��B�ʎq����T���v�����O���g���������Ȃ��1�b������̉��Z���EHDD��h���C�u�ւ̃A�N�Z�X�ʂ����ɑ傫���Ȃ�܂��B���̂悤�ȃt�@�C���≹�����_�E���N���b�N������PC�ōĐ�����Ƃǂ��Ȃ邩�c�c���Z���Ԃɍ���Ȃ��Ȃ胁������HDD���ǂݏo���������݂��ǂ����Ȃ��Ȃ�G���[�������A����т≹���̗̌����ƂȂ�܂��B
���������������ނ��ƂɂȂ肻���Ȃ̂Œ��f���܂��B
�����ԍ��F12541543
![]() 1�_
1�_
�����y�Đ��ɕK�v�ȃX�y�b�N�Ȃǂ���܂�������ł��݂܂����B
����͎������ӌ��ł��B�Đ����邾���Ȃ獡����o����Ă����Ԓ�X�y�b�N�����̂ł��������Ǝv���܂��B�������Đ����Ȃ���l�b�g���y���ށA���ނ����Ȃǂ����Ă�����ǂ��Ȃ�ł��傤���H�ꎞ�I�ɕ��ׂ��������������ʼn��Ƃт��������܂��B�����łȂ��Ă��Đ����x��������Ȃǂ̍Đ��G���[���N����ł��傤�B���̖ڎw���͍̂����ׂ̃Q�[���Ȃǂ����Ă������Y��ɏo�邻���PC���\�z�������̂ł��B���ꂾ���̂��̂ł���ǂ�Ȃ��Ƃ����Ă����Ȃ��łł��܂�����B
�������V���O���R�A��PC���f���A���R�A�̂ق��������ǂ��Ƃ����������݂��������Ƃ�����܂���������������x���������ߍĐ��ɃX�g���X�������炸�������Đ��ł��邩�特�������̂ł����ėǂ�������m�C�Y���������Ȃ��͊W����܂���B�̂�CPU������CPU���m�C�Y(���E)�̋����͂��܂�ς���Ă��Ȃ����Ǝv���܂��B������₷���߂̃N�[���[�̃t�@���̃m�C�Y���̂ɔ�ב傫���Ȃ������ߍ���CPU���m�C�Y�������Ƃ�����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ���ł��傤���H
������ƒE�����Ď����ł������Ă���e���ǂ��킩��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł����ł�߂Ƃ��܂��B�b����₱�����Ȃ�܂��̂�(��)
�Ƃ肠��������PC�I�[�f�B�I�̓n�C�X�y�b�NPC�̂ق��������̂ł͂Ȃ����_�𗝗R���݂ŏ������݂����Ă��������܂����B���e�͈Ӗ��s����������܂��c�c
�Ƃ܂�PC�I�[�f�B�I�ɂ��Ă̎��Ȃ�̍l���X�Ə������܂��Ă��炢�܂����B��������ď�������ł���Ǝ����̍l����������Ⴄ���ƂɋC�Â�����܂��B���͎��Ȃ�̕��@�ōœK��PC�I�[�f�B�I�����\�z�������Ǝv���܂��B����ɂ��Ă��㔼�̕��͂��ŏ��̘_�肩��E���������ĈӖ��s���ȓ��e�ɂȂ��Ă邗��
�����ԍ��F12541766
![]() 1�_
1�_
�V�n�n������
���݂܂���A�C�ɏ��悤�Ȃ��Ƃ����������Ă��܂����悤�ŁE�E�E�B
-�uPC��windows�ł���Ă����E�E�E�v�]�X�Ƃ���������Ă܂����A��͂�CD-R�̉����ɓ������Ă���PC��PC�łȂ��Ȃ�������ł���Ǝv���܂��B-
���t���炸�ł����ˁB
PC�g�����X�|�[�g�ɑ��ĉ��^�I�Ȃ��ӌ��ł����̂ŁA���̏����݂ɑ��ĉ��^�I�ł���
�V�n�n������̔ėp���̏�ɐ��藧��PC�g�����X�|�[�g�Ɗ�{���ӌ��ł��B
��p���ɂ��ėp���A�����̌��@�ɂ��^�������Ă���̂͊m���ł��B
CD-R�ł����v���Ă����̂�PC�ł͂��߂܂����B
�X�^���X�Ƃ��Ă͋@�ރ��x���p�[�c���x���ȉ��̘b�ɂ͂��܂�G��Ȃ��悤�ɂƂ������̂ł��B
�����̏ꍇ�́A���\�����߂Ă��Ȃ��̂ʼn������l�����đg�ނ��Ƃ��o���܂�����B
�V�n�n������̏ꍇ��PC�ł̏����\�͂����߂��̂Ńn�C�X�y�b�NPC�őg�ނ��Ƃ��o���܂�����B
����ł����Ǝv���܂��B
�߂ڂ������������Ŏ��ۂǂ��炪���������͂킩��Ȃ��ƍl���܂��B
��p�@�Ɋւ��Ă͓��ɐ[���Ӗ��͂Ȃ���ł����A
���C���}�V���[������Ă�̂ł������܂��A
���C���}�V���Ɛ藣�����Ǝv��ꂽ�̂Ȃ�T�u�}�V���\�z�����肾�Ǝv���܂��B
�[�I�Ɍ����܂��Ɖ��^�I�Ȃ̂�PC��PC�łȂ��Ȃ�قǂ̐�p���ł��B
PC�̊�{�X�y�b�N�Ɋւ��Ă͍��̃��C���}�V���ł��܂�Ȃ��ł���B
�Ƃ������Ƃł��ˁB
���Ȃ݂Ƀ��X��G���[��S�z���ďȓd�̓}�V����g��ł�̂ł͂Ȃ��ł��B
�����Ȃ��EMI��ł��ˁA�A���`�m�C�Y�̂��߂ɂ���Ă��邾���ł��̂ł������肢�܂��B
�����ԍ��F12541934
![]() 1�_
1�_
�`������
�������������Ɗ��Ⴂ�����Ă����悤�ł��B�m�C�Y�Ɋւ��Ă͈ȑO�ŋ߂̍��N���b�N��CPU�̓m�C�Y�̉e�����傫���Ƃ����b�����Ă���̂������܂��āc�c���̂Ƃ��̂��Ƃɂ��Ă̂��b�ł��B
��PC��PC�łȂ��Ȃ�قǂ̐�p���ł�
������ւ�ȑ����������ĉߕq�ɔ������Ă��܂��܂����B�\����Ȃ��c�c(��)
�����ԍ��F12541977
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɁACD-R�����PC�ʼn����ǂ��Ȃ�悤�ɐ����������Ă܂����B
��l���͐�p�@���̊���p�ӂ���Ă܂������A����Q���̎����ɂ͂��ꂪ�킩�炸
��l���̊J�ꂽ��@���݂�PC��PC�łȂ��Ȃ�̂ɋC�������Ƃ���߂܂����B
�S�����̃m�E�n�E���Ȃ������ɂ͔ėp���Ɍ�����i����������ł��B
���������Ɍ��܂ŒNj�����̂ł���Ύ��̗ǂ�CDP���g�����ق��������ł��B
�����������ւ���܂��ˁB
�������Ɍ��܂ŒNj�����̂ł���Ύ��̗ǂ��f���v���P�[�^���g�����ق��������ł��B
CD-R�ł̎�i��PC�g�����X�|�[�g�̎�@�������̒��ł��Ԃ��Ă��܂��B
���͎����̒��Ő������ĕ����Ă�Œ��ł��ˁB
�����ԍ��F12542006
![]() 0�_
0�_
���������b�����Ă���Ƃo�b�I�[�f�B�I�͂ق�Ƃɏ\�l�\�F�Ȃ��̂ȂȂ��Ǝ����������܂��B�o�b�I�[�f�B�I�ɒ��ސl�����镪�������̓��e������Ă���c�c���ʂ̃I�[�f�B�I�ł͂���Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�܂���B
�����l����Ƃق�Ƃɉ����[���ʔ����ł��B
�����ԍ��F12542044
![]() 0�_
0�_
PC�Ƃ��������͂Ȃ����܂���ˁB
�܂��A���Ƃ���PC�őP����������������͂���܂��E�E�E�B
PC���I�[�f�B�I���l���ꂼ��獷���ʂł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F12542180
![]() 0�_
0�_
�ԐM����200������ƁA���̃X���b�h�ɂ͕ԐM�ł��Ȃ��Ȃ�܂�
������N�@(����1)
�@�܂��ŏ��Ɍ��t�̒�`�𖾂炩�ɂ��Ă����܂��B�^�C�g���Ɏg�����u���Œ����v�ɂ́A��d�ӌ��@�Ȃǂ̓��ʂȃ`�F�b�N�@�͊܂݂܂���B�����������ʂɓ��퐶���ʼn��y���Ƃ��́u���Œ����v���Ӗ����Ă��܂��B
�@�ŁA���́u���Œ����v�s�ׂ͂��������Ӗ����Ȃ��̂��H�@���ʂȃ`�F�b�N�@�łȂ��A����I�ȕ��ʂ̒����������āu�����ς�������v�ł̓_���Ȃ̂��H�@����\���ł���B���ꂪ���X���̖���N�ł��B��������h�����A�����u�ς��v�A�u�ς��Ȃ��v���S�ʂ������܂��B
�@�I�[�f�B�I�̐��E�ɂ́A�����ς�邩������Ȃ��v�f�Ƃ��̉\������������������Ă��܂��B���Ƃ��Γd���P�[�u����X�s�[�J�[�P�[�u�ɂ�鉹�̕ω��B�W�b�^�[�̉e���ƁAUSB-DAC�ɂ�����A�V���N���i�X(��)�]���ɂ�鉹�̈Ⴂ�̊W�BCDP�ɂ��Đ��ƁA���y�t�@�C���Đ��Ƃ̉��̈Ⴂ(�G���[����etc)�A�C���V�����[�^��I�[�f�B�I�{�[�h�ɂ�鉹�̕ω��c�c�B
�@����������Ή�X���[�U�́A���邱���̑���ɂ킽�鉹�̕ω����A���X�Ƀ`�F�b�N�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂ���܂��B
�@���Ĉ���A�u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ���́A�u����@��ɂ��v���A�������͓�d�ӌ��@�ʼn��̂��������q�ω��ł��Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B�łȂ���Ή��̕ω��͋q�ϓI�ɗ����ꂽ�Ƃ͂����Ȃ��v�Ǝ咣����Ă��܂��B
�@�ł����O�q�̒ʂ�A���̕ω��������ׂ��v�f�͖����ɂ���̂�����ł��B���A���������Ă���Ԃɂ��A�I�[�f�B�I�ƊE�ł̓A�b�v�E�g�D�E�f�C�g��(��)�V���ȁu���̈Ⴂ�̉\���v�����X�ɒ���Ă��܂��B�������ɂ͎��Ԃ�����܂���B�v�킸�u�ӂ��̏��̎q�ɖ߂肽���I�v�ƌ��������Ȃ�̂�����ł��B
�@�Ђ邪�����āu�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ��咣�����A����@��ɂ��v�����d�ӌ��@�ɂ́A���Ȃ�̎�ԂƃG�l���M�[�A���Ԃ�������܂��B���Ȃ킿�O�q�̂悤�Ȍ�����l����A�Ƃ��Ă������I�ł͂Ȃ��̂�����ł��B
�@���Ƃ��E�F�u�T�C�g�u�I�[�f�B�I�̉Ȋw�v�̕M�҂ł���u�ꎁ�́A���ؖ@�Ƃ��ău���C���h�e�X�g���咣����Ă��܂��B�ł������̎u�ꎁ���g�A�ȉ��̂悤�Ɂu�����I�łȂ��v�Ǝw�E���Ă��܂��B
--------------------------------
���u���������q�ϓI�����Ƃ́H�v(�I�[�f�B�I�̉Ȋw)
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/objective.html
��ʘ_�Ƃ��Ă̓u���C���h�e�X�g�ȊO�ɂ͖����Ƃ����̂����̎咣�ł���B(����)�u���C���h�e�X�g������Ώ��Ȃ��Ƃ�����ς͔r���o����킯�ł��邪�A�����ȃe�X�g�����s����̂͑�ςőf�l�̎�ɕ����Ȃ��B�Ƃ��������Ƃŋc�_�͂����������ʂ��Ȃ��Ƃ����̂�����ł͂Ȃ��낤���H
---------------------------------
�@�����œ��X���ł͖`���Ɍf�����ʂ�A�u�ӂ��̎����ł̓_���Ȃ̂��H�v�Ɩ���N���܂��B���_�����ɂ����A�u�q�ϓI�Ȃ��̂̌����v�����邱�ƂŁA�}���I�ɃR���g���[�����ꂽ�ӎ��ƒm�o�ɂ��u�q�ώ����v���Ă��܂��B
�@���́u�q�ϓI�Ȃ��̂̌����v�Ƌq�ώ����ɂ��ẮA�ڂ����͎��̃u���O�̈ȉ��̋L���ɏ����܂����B�����̂��Q�l�ɂȂ�B
���w�d���P�[�u���ʼn��͕ς�邩?�@�`�q�ϓI�Ȃ��̂̌����̂����߁x
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-77.html
![]() 2�_
2�_
������N�@(����2)
�@�ł́A�܂����̃X�^���X���J�����܂��B�I�[�f�B�I�̐��E�ɂ́A�����ȃI�J���g�E�c�[����I�J���g�v�l����绂��Ă��܂��B�����Ɍ����āA���͂��̎�̂��̂ɂ͋���������܂���B
�u�ς��A�ς��Ȃ��v�_���Ŏ�荹�������u�I�J���g���ꂷ��v(��)�̎����̂����A�������ۂɎ��ʼn��̕ω����m�F�����͓̂d���P�[�u���݂̂ł�(��������)�B���������Ă��܂̂Ƃ���A�u�����ς��v�Ǝ��l�����y����͓̂d���P�[�u������Ƃ��܂��B
�@���Ă����������́A�u���R�[�h�v���[���̐��U��Ɍ��ʂ�����̂͗����ł���B�����ǃA���v�̉��Ƀ{�[�h��C���V�����[�^��~���ĉ��̈Ӗ�������́H�v�ĂȌ��n�l�Ԃł��B
�@����Ȏ��ł�����ώc�O�Ȃ���(��)�A�u�d���P�[�u���ʼn����ς��v���Ƃ͎����Ƃ��ĔF�߂Ă��܂��B����͂Ȃ����H�@�����g�����ۂɎ��Œ����A���̕ω����m�F���Ă��邩��ł��B(��q���܂����A���́u�q�ϓI�v�ɒ����Ă��܂�)
�@���ɂƂ��Ắu�����̎��Œ��������ʁv�����ׂĂł���A����ȊO�̗��_��@���A�Z�I���[�A���K�ɂ͂��܂苻��������܂���B�Ȃ��Ȃ�I�[�f�B�I�́A�����̎��Ōl�I�ɒ����Ċy���ނ��̂�����ł��B
�@�䂦�ɕ��ʂ̕��@�Ōl�I�ɒ����A���̕ω���̊���������܂��B����𑼐l�ɏؖ����Č����悤�Ȃ�ăJ�P�����v���܂���B�܂��A���ꂪ�I�[�f�B�I�E�ł͂ǂ�Ȍ`�ŃZ�I���[������Ă��邩�H�@�ĂȂ��Ƃɂ�����܂苻��������܂���B
�@�Ⴆ�u�I�[�f�B�I�̐��E�ł́A�X�s�[�J�[�̉��ɂ��܂��C���V�����[�^�́w3���x�X�g�x�Ƃ���Ă��邩�H�@����Ƃ�4���H�v�ĂȂ��Ƃɂ͊S����܂���B
�@�����Ă���Ȃӂ��Ɂu�}�j���A����T���v�̂ł͂Ȃ��A�����Ŏ��ۂɂ���Ă݂�(����)�A�����̎��ʼn��̈Ⴂ���m�F�����(�ϑ�)�I��肾����ł��B���ꂪ������[���ł��܂��B
�@���������u�����v�Ɓu�ϑ��v�́A�u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ��M��u�Ȋw�v�̊�{�ł��B���Ƃ��ΑO�o�A�u�I�[�f�B�I�̉Ȋw�v�Ǘ��l�̎u�ꎁ���A�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
---------------------------
���u���������q�ϓI�����Ƃ́H�v(�I�[�f�B�I�̉Ȋw)
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/objective.html
�����@���͍ŏ��͉��肩��n�܂�A�����̎����E�ϑ����J��Ԃ������ʂ����̉���ɖ������Ȃ����Ƃ��m���߂��͂��߂āu�q�ϓI�Ȏ����i�@���j�v�Ƃ��ĔF�߂���킯�ł���B
---------------------------
�@���Ɠd���P�[�u���Ƃ̊W�ɒu�������܂��傤�B�܂���ɁA�u�d���P�[�u���ʼn����ς��v�Ƃ������肪�Љ�ɑ��݂��܂����B�ŁA������������������͓d���P�[�u�����g���A�����̎����E�ϑ����J��Ԃ�(���Ȃ킿������)�A�������ʂ����̉���ɖ������Ȃ����Ƃ��m���߂܂����B�����Ď��́u�d���P�[�u���ʼn��͕ς��v�ƌ��_�t���܂����B���Ȃ킿�Ȋw�I�ȑԓx�ł��B
�����ԍ��F12483565
![]() 1�_
1�_
������N�@(����3)
�@���́A�u���̉��͊w�p�I�ɕς���Ă��邩�H�v�ȁ[��Ă��Ƃ͂ǂ������Ă����ł��B�l�Ԃ̎��ɂ͒������Ȃ����A�w�p�I�ɂ͕ς���Ă���H�@����Ȃ��́A�u���y�I�ɂ́v�܂������Ӗ�������܂���B
�u�l�Ԃ̎��ɂ͒������Ȃ����A����@��ɂ��v���Ŋm�F���ꂽ�B����Ŋw�p�I�ȗ��t������ꂽ���v
�@�ǂ��ł������ł�(��)�B���͊w�p���ɂ߂����̂ł͂Ȃ��A���y���y���݂����̂ł��B�u���ʂ̕��@�v�Ŏ��R�Ɏ��Œ����đ̊��ł���̂łȂ���A���ꂪ������w�p�I�ȃv���C�N�X���[�ł��낤���Ӗ��������܂���B
�@����Ⴆ�ł���A�����̎��Œ����ĉ��̕ω����m�F�ł��Ȃ��̂ɁA�u����A�����Ȋw�������̊w�p�`�[������d�ӌ��@�Ŋm�F���܂����B�������特�͕ς��܂��v�Ȃǂƌ����Ă��������N���[���ł����ł������H�@���ꂱ���ނ�̃v���V�[�{����Ȃ���ł����H
�@�w�p���ɂ߂����l�́A��d�ӌ��@�ł��@��v���ł�����ɂ������̂ł��B��������A�J���P�[����܂ւ�B�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A���͉��̕ω��𑼐l�ɏؖ����Č����悤�Ȃ�Ďv���܂��A�����̎��Ŋm�F����̂��u�����ɑ��āv����������͂�����܂��B�×���茾����u���y���y���ނ��Ƃ́A����߂Čl�I�ȉc�݂ł���v�Ƃ����i���͂��������Ӗ��ł��B
�@�Ƃ��낪�ł��B���ꂪ�u�ς��Ȃ��v�h�̕��X�Ƃ܂�Ŋ��ݍ����܂���B�����Ă��݂̂Ȃ��������A�ӂ����Ɩڂɂ́u���ʂɎ��Œ��������ʂȂӖ����Ȃ��v�A�u����Ȃ��̂̓v���V�[�{���v�̈�_����Ȃ�ł�����B�����B
�@���̕ω��𑼐l�ɏؖ����Č�����C�ȂǂȂ��A�l�I�ɉ��y���y���݂��������̎����猩��A�ނ�̂ق�������ۂǁu�����ς��Ȃ����Ƃ������咣���������Ă���v�悤�Ɍ������ł����A�ǂ��Ȃ�ł��傤���H
�@���̎�̋c�_�ɂ�����u�ς��Ȃ��v�h�̏퓅��́A�u�ӌ����咣���鑤�ɂ������ؐӔC�A�����ӔC������v�Ƃ������̂ł��B�Ƃ��낪���͌l�I�Ɋy���݂��������B����A�ނ�́u�����ς��Ȃ����Ɓv�𐺍��ɋ����咣���������Ă���Ƃ����v���܂���B����Ȃ�ނ�̂ق��ɂ����A���ؐӔC������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�ɂ�������炸�u�ς��Ȃ��v�h�́u����ɗ��ؐӔC�͂Ȃ��v�Ƃ���ɂӂ�Ԃ�A�����ł͎����������Ɏ咣�����͂������܂��B���������ǁ[�Ȃ��Ă��ł��傤�������(��)
�@���₻���ނ�ɂ����āA�u���͕ς��Ȃ��v�ƌl�I�ɍl���錠���͂���܂��B�����̉ƂłЂ�����ƁA������ǂ܂Ȃ��`���V�̗��Ɂu���͕ς��Ȃ��b�v��100�����������R�ł��B
�@�ł����N�̖ڂɂ��G�꓾������̏�ł���f���ŁA���̕ω����y����ł���l�Ɍ������Ă������ے�I�ȃ��X�������̂͂ǂ��Ȃ�ł��傤�B�l��s���ɂ�������A���l�̖��f�ɂȂ鏑�����݂��Čf���ŋ������̂ł��傤���B
�@���⎄�͑�O�ғI�ȗ���ɗ����A�q�ϓI�ɂ��̂�������l�Ԃł��B�ł����炻�̃e�̏������݂����Ă��A�����Ċ���I�ɂȂǂȂ�܂���B�u�����A���̐l�͂����l���Ă���ȁv�ŏI���ł��B����ǂ��납���Y�I�Ń��W�J���ȋc�_���������鑊��Ȃ�A������_���邱�Ƃ����肦�܂��B
�@����������A����I�ɂȂ����������͎̂����ł��B��������܂���B�����ėႦ�Ύ���Ōl�I�ɉ��y���y����ł���l�̂Ƃ���փY�J�Y�J�Ɖ��������A���ւ��R�j��y���ŏオ�荞�݁A�����ł����{��ꂽ�Ƃ�����ǂ��ł��傤�H
�u���܂��͓�d�ӌ��@��������̂��H�@�ق��A���[��ȓd���P�[�u�����g���Ă���ȁB�n�b�B��������Ȃ��̂ʼn��͕ς��Ȃ��B���܂��̓d���P�[�u���Ȃɑ��݉��l�͂Ȃ���B����ɂ��Ȃ��̉ċx�݂̎��R�����A��������[����߂���������ɂ̓f�L��������˂��`�B�q���̏h��̂ق����܂��}�V��b��v
�@���ꂶ�Ⴀ�N�����āA�u���̉Ƃ���o�čs���Ă��������b�I�v�Ƌ��т����Ȃ�̂������ł��傤(��)
�����ԍ��F12483571
![]() 4�_
4�_
������N�@(����4)
�@���������u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ��_�O�ȂƂ���́A�u�ӂ��̎����v��ے肵�Ă���Ƃ���ł��B�u����@��ɂ��v���A�܂��͓�d�ӌ��@�w�ȊO�x�̃`�F�b�N�@�ł́A�v���V�[�{���ʂ̉\�������邩��Ӗ����Ȃ��v�Ƃ����̂���������ł��B
�@����ˁA���̂��c�c�I�[�f�B�I�@�탁�[�J�[�̉����߂����āu�l�Ԃ̎��v�ōs����킯�ł���B�������Œ����A�u�����A�������傢�ቹ����ߋC���ɂ��悤���v�ĂȂ��Ƃ�����I�ɍs����킯�ł��B
�@�ɂ�������炸�u�P�Ɏ��Œ��������ʂ���Ӗ����Ȃ��v�Ȃ�Ď咣�������X�́A�ł̓��[�J�[�̉����߂��̂��̂�ے肳���̂ł��傤���H�@
�@���������܂��B�ȉ��́A���{�e�L�T�X�E�C���X�c�������c�̐Ԗx �������A�d�q�Z�p���uEDN Japan�v�Ɋ��_�l��2�y�[�W�ڂ���̈��p�ł��B
���w�I�[�f�B�I�i���ƃN���b�N�W�b�^�[�@�`�f�W�^���I�[�f�B�I����������ݓI�ۑ�ɔ���x�@
�Ԗx �� �@���{�e�L�T�X�E�C���X�c�������c
http://ednjapan.cancom-j.com/issue/2007/09/6/28/2
--------�y����������p�J�n�z-----------
�@�W�b�^�[�������ȏꍇ�ɂ́A�I�[�f�B�I���\�̗͐����Ƃ��Ă͌���Ȃ��B�������A�������\�ȉ����̕ω��Ƃ��ĉe����������ꍇ������B�M�҂́A����܂ł̃f�W�^���I�[�f�B�I�����f�o�C�X�̊J���ɂ����āA�e���DIR��p���Ď������s���Ă����B�����]���p�̃��j�^�[�V�X�e���ɂ����āA����DIR�f�o�C�X��ς��邾���ŁA���������ɑ傫���ω�����Ƃ����o�������Ă���B���̉����̕ω��́A�P�Ɂu�ቹ���o�Ȃ��v�A�u�������L�т�v�Ƃ��������x���̂��̂ł͂Ȃ��B�ǂ����͉̂���≹���̍Č����ɗD������ŁA�������̂́A�P�������ʓI�ɉ������Ă��邾���A�Ƃ������x���ƂȂ�B�������ǂ̂悤�ɕς��̂������t�Ő�������͔̂��ɍ�����A�\�Ȍ����̓I�ɐ��������݂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B
���̎�̌��̑傫�����ς��
���ڂ̑O�ʼn��t���Ă���悤�Ȏ��݊��̍Č����ω�����
�����̏�ɋ����킹��l�̐����ς��Ƃ������C�z�̕ω���������
�����t���P���ɂȂ�i�ǂ�ȋȂ��Ă��y�������͋C�ɂȂ��Ă��܂��j
�@�܂�A���y�̍Đ��ɂ����ẮA���̉��߂��قȂ��Ă��܂��قǂɉ������ω�����̂ł���B
�@�܂��A�f�W�^���I�[�f�B�I�����f�o�C�X�̊J���ɂ����ẮAPLL��H���`���[�j���O����ߒ��ł��������s���B���̍ہAPLL�̃��[�v�t�B���^�̒萔��ς���ƁA������W�b�^�[�̗ʂɂ͂قƂ�Ǖω����Ȃ��ꍇ�ł������A���炩�ɉ������ω����遖2)�B
�@���̂悤�ɁA�W�b�^�[�͉��������傫���ς��Ă��܂��̂ł���B
-------�y���p�͂����܂Łz--------
(�Q�l1)�@���{�e�L�T�X�E�C���X�c�������c�������
http://focus.tij.co.jp/jp/general/docs/gencontent.tsp?contentId=37105
(�Q�l2)�@�����́uDIR�v(�f�W�^���I�[�f�B�II/F���V�[�o�j�ɂ��ẮA�����_�l��1�y�[�W��(�ȉ�)�ɉ��������܂��B
http://ednjapan.cancom-j.com/issue/2007/09/6/28
�@���ĐԖx���͏�L�̂悤�ɁA�u����܂ł̃f�W�^���I�[�f�B�I�����f�o�C�X�̊J���ɂ����āA�e���DIR��p���Ď������s���Ă����v�A�u�f�W�^���I�[�f�B�I�����f�o�C�X�̊J���ɂ����ẮAPLL��H���`���[�j���O����ߒ��ł��������s���v�Ə�����Ă��܂��B
�@�ł́u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ���͐Ԗx���ɑ��A�u���Œ��������ʂ͈Ӗ����Ȃ��v�Ƃ��������̂ł��傤���H�@
�����ԍ��F12483576
![]() 3�_
3�_
������N�@(����5)
�@���邢�͂���ȋ����[���f�[�^������܂��B
------�y����������p�J�n�z--------
�y�����zA-V�p�M���������@
http://www.jaist.ac.jp/ricenter/tokkyo/miyahara2.html
�y�������ҁz�k����[�Ȋw�Z�p��w�@��w��
�y�����ҁz�{���@���@(���Ȋw�����ȋ����j
�@�@�@�@�@���эK�v�@�i���Ȋw�����ȁj
(�O��)
�y�]���̋Z�p�z�]���̉�����ʐ���́A������ʕ����݂̂Ɋւ�����̂ł���B����́A�����Ԃɉ������ƁA�ʑ����������A���̒�ʕ����𐧌䂷����̂ł���B��̓I�ɂ́A�X�e���I�M���̉E�M���ƍ��M���Ƃ̊ԂɁA�U�����y�шʑ�����d�C��H�ɂ�萶����������@�ł���B�������A���̕��@�ł́A�����̎��A���Ȃ킿�����̑傫����V���[�v���A�L���芴�ɂ��Ă͐��䂷�邱�Ƃ͍���ł���A���ۍs���Ă͂��Ȃ������B(����)
�y�\���z�����M���̎��Ԏ������K�ɉe���̂Ȃ��͈́i���y�̈�ۂ˂Ȃ��͈́j�ŗh�炪����i�ϒ���������j���Ƃɂ��A���������R�ɂڂ����邱�Ƃ��ł���B�f�W�^���I�[�f�B�I�M���̏ꍇ�A�Ⴆ�T���v�����O���g���i���[�h�E�N���b�N�j�������PLL��H��VCO(Voltage Controlled Oscillater)�d�������ԓI�ɕϓ�������Ȃǂ̕��@�ŃN���b�N�ɃW�b�^�[�������邱�Ƃɂ�莞�Ԏ��ɗh�炬�i�W�b�^�[�j��^���邱�Ƃ��ł���B�A�i���O�I�[�f�B�I�M���̏ꍇ���ڑ���ɂ�莞�Ԏ��ɕϒ��������邱�Ƃ��ł���B
�y���ʁz�l�Ԃ̒��o�͐M���̃��x�������݂̂Ȃ炸�A�u���ԕ����̐L�яk�ݘc�݁v�ɏ]���̏펯���z���������Ⴂ�ɍ������x��L���邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B����ɂ��A�����Đ��݂̂̏ꍇ�ɂ́A���Ԏ������ɑ��݂���L�яk�ݘc�݂��������邱�Ƃɂ��A�|�p�Ƃ��\����������ۂȂ킸�ɍČ����邱�Ƃ��\�ł���B(�㗪)
--------�y���p�͂����܂Łz----------
�@��L�̕����ɂ́A�w�l�Ԃ̒��o�́A(����)�u���ԕ����̐L�яk�ݘc�݁v�ɏ]���̏펯���z���������Ⴂ�ɍ������x��L���邱�Ƃ����炩�ɂȂ����x�Ƃ���܂��B
�@�ł�������A�u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ���́A�u�P�Ɏ��Œ��������ʂ͈Ӗ����Ȃ��v�Ƃ������Ⴂ�܂��B
�@������u�k����[�Ȋw�Z�p��w�@�v�A�����Е��́u�l�b�g��̎��������킩��ʓ����̏������ݎҁv�ł��B���Ď��͂��������A�ǂ����M�p��������̂ł��傤���H
�����ԍ��F12483582
![]() 3�_
3�_
������N�@(����6)
�u�P�Ȃ鎎���ł͈Ӗ����Ȃ��v�A�u��d�ӌ��@�łȂ����画�f�ޗ��ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����������X�́A�ł͂���������X���[�U���I�[�f�B�I�@����O�ɓX���ōs���u�����v�ȂLjӖ����Ȃ��A�i���Z���X�ł���Ǝ咣�����̂ł��傤���H
�@�͂��܂��u�l�͗����ɏZ��ł���̂Ŏ����ł��܂���B�X�s�[�J�[A�ƃX�s�[�J�[B�A�ǂ���������ł����H�@��ςł������狳���Ă��������v�ȁ[��Ă������o�J�Ȏ���ɑ��A�u���Ƃ��Ǝ����ȂLjӖ����Ȃ��̂��B������҂Ɍ�����܂܁A�w�肳�ꂽ�@����v�A�u����Ȃ��̂̓N�W�����Ō��߂Ƃ���v�Ƃł����������̂ł��傤���H
�@�Ƃ�ł��Ȃ��b�ł��B
�@�I�[�f�B�I�̊�{�͎����ł��B���ׂĂ͎����Ɏn�܂�A�����ɏI���܂��B���Ƃ��u�b�V�F���t�^�X�s�[�J�[�̒�ʂƁA�X�s�[�J�[�X�^���h�̓V�Ƃ̐ړ_�͂ǂ���������̂��x�X�g���H�@����̓l�b�g��̌f���Ŏ��₷��Ή�������̂ł��傤���H
�@�������B����ȊȒP�Șb�ł͂���܂���B���ɉ҂�A���u������(�܂��̓n�C�v���b�h)�̃C���V�����[�^�����܂��̂��x�X�g�ł��v�ƁA�����������ꂪ�u�q�ϓI�����v�ł��邩�̂悤�ɓ������Ƃ��܂��B
�@�ł����̊������͐l���ꂼ��A�D�݂��l�ɂ��獷���ʂł��B�܂肻�̉́uA����̉��̍D�݁v�A�uA����̒������y�v�ɂ�����}�b�`�������@�ł���ɂ����܂���B���Ȃ킿A����̎�ςł��B
�@���l�̎�ςł͈Ӗ�����܂���B�����ł͂Ȃ��u�����v�ɂƂ��ĉ����x�X�g�Ȃ̂��H�@���ꂪ���Ȃ̂ł��B���A����͎����̎��Ŏ��ۂɎ������A�����Ŋm�F����ȊO�Ɋm���߂邷�ׂ͂���܂���B
(����������ςł͂Ȃ��q�ϓI�Ȃ��̂̌��������A�����̍D�݂ɂƂ��ꂸ���̒��Ŕ��f�ޗ����q�ω�������œ�����҂��������)
�@���ď�ɂ������C���V�����[�^�͒P�Ȃ���ł��B
�u�A���v�����������B�����̃X�s�[�J�[�������D�݂ɖ点��A���v�͂ǂꂩ�H�v
�u���ʂ�������ԕ\���̓��ӂ�CD�v���[���͂Ȃ����H�v
�u��悪�������܂�A���𑜓x�n�C�X�s�[�h�ȃX�s�[�J�[��T�������v
�@���ׂĂ͎������J��Ԃ��A�����̎��ŒT����������܂���B�u�P�Ȃ鎎���ł͈Ӗ����Ȃ��v�ȂǂƎ�����ے肷��̂́A�I�[�f�B�I�̂��ׂĂ�ے肷��̂Ɠ����ł��B
�@���Ȃ킿�u�����͈Ӗ����Ȃ��v�ȂǂƂ��������́A�I�[�f�B�I��m��Ȃ���O���̃g���`���J���Ȓ����ɂ����܂���B
�����ԍ��F12483584
![]() 1�_
1�_
������N�@(����7)
�@���悢�捡��͊j�S�ɔ���܂��B����I�Ȏ������ʂ̐ςݏd�˂������A�q�ω��ɂȂ���Ƃ������b�ł��B
�@���ꂼ�ꑮ�����قȂ�s���葽���̐l�Ԃ���������Љ�ɂ����āA�������Ɍ��m���(���݂����m��Ȃ�)A����AB����AC����AD����c�c(������)���A�Ⴆ�u�������̃`���R���[�g�v��H�ׂ��Ƃ��܂��傤�B
�@�����Ĕނ�(���Ȃ킿�T���v��)����l�ɁA�u���̂��َq�͊Â��B�ł�������ƊÂ����Ă������v�Ɗ������Ƃ��܂��B�����āA�܂������������z�������T���v�������L�ӂȐ��ʂɒB�����Ƃ��܂��B
�@�Ƃ�����́u�������̃`���R���[�g�v�Ȃ镨�̂́A(1)�Â����َq�ł���A(2)�������Â������������}���������u�����Ɣ����v���Ƃ��A�m�F���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�܂�(1)�A(2)�͏\���Ɂu�m���炵���v�ƃ}�[�P�e�B���O�E���T�[�`�ɂ���Ċm�F����܂����B�}�[�P�e�B���O�����̌��ʂ��f�[�^������A�q�ω����ꂽ�킯�ł��B
�@���́u�������v�̂悤�Ȋ�Ƃ́A���������Ȃ��u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ���Ƃ͈قȂ�A���邱�������}�[�P�e�B���O�E�f�[�^�����Ƃɏ��i�����ǂ��A���邢�͐V���i���J������w�͂𑱂��Ă��܂��B
�@�����ā������́u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ���̂悤�ɁA�u����ނ�(�T���v��)�́w�Â�����x�Ƃ������z�̓v���V�[�{��������Ȃ��B��d�ӌ��@�ōs���ĂȂ�����Ӗ����Ȃ��B����Ȃ���������ȃf�[�^�����Ƃɏ��i�J������̂͊댯���B��߂悤�v�ȂǂƂ͍l���܂���B
�@�Ȃ��Ȃ炱�������l�̎�ς��W�߂��f�[�^�ɂ͉��l������A���̎�̃}�[�P�e�B���O�E���T�[�`�͗L���ł��邱�Ƃ����łɗ�����A�펯�����Ă��邩��ł��B�����Ď������̌���Љ�͂܂��ɁA���������}�[�P�e�B���O�ɂ�蓮���Ă���̂ł��B
�@���{�����Ă���̂́A�����Đ��T���ł͂���܂���B���{�Љ�������I�ɓ������Ă���̂́A�}�[�P�e�B���O(������L����`�Ȃ�)�ł��B�u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ���́A���̌��R���鎖���ɖڂ�w���Ă͂Ȃ�܂���B�Ȃ��Ȃ炻��́u�q�ϓI�����v������ł��B
�@�������킩��ł��傤�B
�u�������̃`���R���[�g���Â��v�̂Ɠ��l�A�u�f�m���̃A���v�ɂ͒ቹ�̗ʊ�������v�Ƃ��������́A�₦�Ԃ��郆�[�U�X�̒��N�ɂ킽�鎎���ł��łɊm�F����A�L�����m����Ă��܂��B�펯�����A�蒅���Ă��܂��B
�@���Ȃ킿����ŗL�ӂȃq�A�����O���ʂ��Љ�ɐ������͐ς��A���L�ӂȔN�������������Ƃɂ��A���ꂪ�q�ω����ꂽ�킯�ł��B
�@����ɂ́u�������̃`���R���[�g���Â��v�̂Ɠ������A���N�ɂ킽�閳���̃��[�U�̃q�A�����O���ʂɂ��A�u�d���P�[�u���ʼn����ς��v���Ƃ͂��łɊm�F����A�q�ω�����Ă��܂��B
�@��d�ӌ��@�̂悤�Ȕ����I�Ȓ������łȂ��A�������ʂ̓���I�Ŏ��R�ȉ��̒��������̐ςݏd�˂ɂ��A�u�q�ω��̎������v���i�̂ł��B
�@���Ȃ킿���茋�ʂ��f�[�^���E���l������Ă��悤�����܂����A��d�ӌ��@�ł��ꂪ�s���ĂȂ��낤���A�u�d���P�[�u���ʼn����ς��v���Ƃ͂��łɏ\���q�ςÂ����Ă���̂ł��B
�@�Ȃ��u�q�ρv�̈Ӗ��ɂ��Ă͂܂�����A����I�ȍޗ��������܂��B
�����ԍ��F12483586
![]() 3�_
3�_
������N�@(����8)
�u�����ς��v�A�u�ς��Ȃ��v�̋c�_�ɂȂ�ƁA�₽��ɓo�ꂷ��̂��u��ρv�Ɓu�q�ρv�Ȃ錾�t�ł��B�����������̐��m�ȈӖ���T�O�ɂ��Ă͋��ʗ������Ȃ��܂܁A�߂��߂��l�̎v�����݂Ō��t���������p����Ă��܂��B
�@�ŁA�u�ЂƂ�̐l�Ԃ������Ŋ��������Ɓv�͂��ׂĎ�ςœ��ĂɂȂ�Ȃ��A�ȂǂƂ����f�^�����Ș_�@���܂���ʂ�̂ł��B
�@�����ł͂Ȃ��A�l�Ԃ́u�q�ϓI�ɂ��̂�����v���Ƃ��ł��܂��B�Ώە���O�ɂ��ė�ÂɈ���A�g�������A�u�������̖ڂ̑O�ŋN���������ۂ͖{�����H�v�A�u�����܂������ʂ̌��ۂł���\���͂Ȃ����H�v�Ɛ₦���u�^���S�v�����B�����āu������ځv�ł��̂����āA�q�ϓI�Ɏv�l���邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�@�ɂ�������炸�u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ���́A�u�������g�Ŋ��������Ɓv�͂��ׂĎ�ς��A���ĂɂȂ�Ȃ��A������ׂ����@�ŋq�ω����Ȃ��ƈӖ����Ȃ��A�ƌ����͂���Ȃ��Ƃ��������Ⴂ�܂��B
�u�ς��Ȃ��v�h�݂̂Ȃ���ɂ́A�������炢�����Ăق������̂ł��B�ł͎�������ɂ��܂��傤�B�ȉ��̕��͒��A���p�L���t�̕����́ugoo�����v�Ɍf�ڂ���Ă��镶�͂ł��B
---------------------------------
�y�q�ρz
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/54335/m0u/%E5%AE%A2%E8%A6%B3/
>�����҂ł͂Ȃ��A��O�҂̗��ꂩ��ώ@���A�l���邱�ƁB�܂��A���̍l���B��������B
>�u���Â��������g���\���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�v
----------------------------------
�u��O�ҁv�̂������ƂɁA�u�̗��ꂩ��v�Ƃ����\�������邱�Ƃɒ��ڂ��Ă��������B���Ȃ킿�u�����ҁv�ł����Ă��A���̐l���u��O�ғI�ȗ���ɗ����āv�ώ@���A���̂��l����u�q�ρv�Ȃ̂ł��B
�u�ς��A�ς��Ȃ��v�̃e�[�}�ɑ����킩��₷�������A�����҂��u�����҂̗���v�Ŏ��Ȃ̗��v�����A�����̎咣��ʂ����߂ɍl�������ȓI�Ȏv�O���u��ρv�ł��B
�@����A�����҂ł����Ă��u��O�ғI�ȗ���v�ɗ����A���Ȃ̗��v���肽���咣�ɂƂ��ꂸ�ɂ��̂����邱�Ƃ��u�q�ρv�ł��B���Ȃ킿�l�Ԃ́u�q�ϓI�ɂ��̂�����v���Ƃ��ł���̂ł��B
----------------------------------
�y�q�ϓI�z
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/54339/m0u/%E5%AE%A2%E8%A6%B3/
>����̗���ɂƂ��ꂸ�A������������l�����肷�邳�܁B�u�\�Ȉӌ��v�u�\�ɕ`�ʂ���v
-----------------------------------
�@���͂��������܂ł��Ȃ��ł��傤�B�����ɏo�Ă���̂����疾���ł��B���Ƃ������҂ł����Ă�����̗���ɂƂ��ꂸ�A������������l�����肷�����́u�q�ϓI�v�ł��B
�@����������������Ȃ���⑫���܂��傤�B�u�q�ϓI�ɂ��̂�����v�Ƃ͂ǂ�ȈӖ����H�@�����ʂ̃X���ɏ��������̂��ȉ��Ɉꕔ���p���܂��B
------�y����������p�J�n�z---------
��Dyna-udia�@[12393833]
���Ƃ���A���A�f�m���̃A���v�����L���Ă���Ƃ��܂��BA����͉䂪�q���킢���ŁA�����̃A���v�ɂ͌��_���Ȃ��Ɗ����܂��B�u������������A�p���`�������āA�ቹ����������o�āc�c�v�B�ŁA��O�҂�A����Ɂu�f�m���̃A���v�͒ቹ���{�P���ˁH�v�Ƃ����ƁAA����̓��L�ɂȂ��Ĕ��_���܂��B
���̂Ƃ�A����͉䂪�q���킢���ŁA�u�q�ϓI�ɂ��̂��l����v���Ƃ��ł��Ă��܂���B���Ȃ킿A����̎v�l�͂���߂Ď�ϓI�ł��B
�Ƃ��낪����A�����悤�Ƀf�m���̃A���v�����L���Ă���B����́A�f�m���̃A���v�̒����ƒZ�����q�ϓI�Ɏd�������čl���邱�Ƃ��ł��܂��B�䂪�q���킢���Ŋ���(���)�ɗ�����A�u�f�m���̃A���v�͂��ׂĂ��炵���v�A�u���_�ȂǂȂ��v�ȂǂƂ͍l���܂���B���̂Ƃ�B����̎v�l�͏\���Ɂu�q�ϓI�ł���v�Ƃ����܂��B
-----�y���p�͂����܂Łz-------
�@��Ɉ��p����A����̐S���͂��Ă݂܂��傤�BA����͎����̏��L��(�f�m���̃A���v)�ɑ��鈤�����������܂�A�I�[�f�B�I�@��Ƃ����P�Ȃ�u�n�D�i�v�ɂ����Ȃ����̂��u����Ɠ��ꉻ�v���Ă��܂��B�܂�q�ϓI�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂���B
�@�ŁA�����̈��p�i(�f�m���̃A���v)�������ł��}�C�i�X�]�������Ǝ��䂪�����A�u�܂�Ŏ��������ꂽ�悤�Ɂv�����܂��B�����Ă���������Y��ė�Â��������A�q�X�e���b�N�ɔ������܂��B����߂Ď�ϓI�ȑԓx�ł��B
�@����Ȃӂ��Ɋ���ɍ��E���ꐳ��Ȕ��f�͂������l�A��ϓI�Ȏv�����݂ɂƂ���ăo�C�A�X�̂��������v�l�����ł��Ȃ��l�͂�����܂��B(���ꂪ�u�����v�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B���̕��͂͂��������u�ǂ���������/�����v�̂悤�ȁu���l���f�v���܂߂��A�W�X�Ƌq�ϓI�ɕ��͂��Ă��邾���ł�)
�@�ł�������AB����̂悤�Ȑl�����܂��BB����݂����Ɂu������ځv�������A�q�ϓI�Ȃ��̂̌����ŁA���L���ł���f�m���̃A���v��d���P�[�u���̒������������邱�Ƃ͓��R�ł��܂��B
�@���Ȃ킿�����҂ł���l�̎v�l�╪�͂Ƃ����ǂ��A���ꂪ�q�ϓI�Ȏv�l�Ɋ�Â��s�������L�ӂȃT���v�����肦��킯�ł��B
�����ԍ��F12483595
![]() 3�_
3�_
������N�@(����9)
�@���āA�ЂƂ܂����_�ł��B�����̏��L��(�I�[�f�B�I�@��)���g���Čl�I�ɉ����y����ł���Ƃ��́A���������A�����l���悤�����R���R�ł��B�����Ղ�Ǝ�ςɂЂ���A���������̊��o���y���݂������̂ł��B
�@�ł����ЂƂ��ъO�������ď��M����ꍇ�A�Ƃ��ɂ͎�����U��Ԃ��Ă݂邱�Ƃ��K�v�ł��B�u�����̊��o�͐��������H�v�A�u�v�����݂ɂƂ���ĂȂ����H�v�A�u�{���ɉ��͕ς�����̂��H�v�B�܂莩�����^���Ă݂�Ƃ������Ƃł��B
�u�^���S�v�Łu������ځv�������A�����̊��o���`�F�b�N����B��O�ғI�ȗ���ɗ����A�q�ϓI�ɍl����B�ŁA�q�ςƂ������̃t�B���^�[�ɂ��������͌��ʂ��A�O�Ɍ������Ĕ��M����B
�@�ЂƂ�ЂƂ肪���������ԓx�ŏ�M����A���ꂪ���̂��ƎЉ�ɍ~��ς���A�����I�Ƀf�[�^���E�q�ω�����čs���܂��B����@����d�ӌ��@�Ȃǂ̓���ȕ��@���g��Ȃ��Ă��A�\���m���炵�����͌��ʂ������܂��B
�@�܂��A�������Ĉ����̂��鎩���̏��L��(�I�[�f�B�I�@��Ȃ�)���q�ω��ł���A���Ƃ��N���������̈��@���}�C�i�X�]�������Ƃ��Ă��A���̈ӌ���W�X�Ƌq�ϓI�ɕ������Ƃ��ł��܂��B
�u�����A���̐l�͂����������������Ă���̂��B������A�����낤�v
�@�Ӗ��̂Ȃ��{��ɂƂ��ꂽ��A�r�X��������̔g�ɖ|�M����Ȃ��Ă��݂܂��B���ꂾ���łȂ����l�̈ӌ����Âɕ������Ƃɂ��A�����ł͂��܂܂ŋC�Â��Ȃ������|�C���g�ɋC�Â��郁���b�g������܂��B
�u���܂܂Ŏ����͂��̋@����w���炵���x�Ƃ����v��Ȃ������B�����ǂȂ�قǁA���������Z�����������̂��v
�@�����鏊�L���ɑ���}�C�i�X�]�����ÂɌ������A�����̔F��������ɍ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B����Ȃӂ��Ɂu�q�ϓI�Ȃ��̂̌����v�ɂ́A�����b�g�������̂ł��B
�@�Ȃ��A���̃X���͎��R���_�̏�ł��B�ǂȂ��������ꂽ���e�ɑ��A�������������ł͂���܂���B�����ł͂Ȃ��A�����́u�s���葽���@�@�s���葽���v�̈ӌ������̏�ł��B�݂Ȃ����R�ɁA�������ɔ����Ȃ����Ă��������B
�@�ł͌��ݓI�Ő��Y�I�ȋc�_�����܂��傤�B
�����ԍ��F12483597
![]() 4�_
4�_
�݂Ȃ���A�����́B
�K���ɘ_�_���o���Ă݂܂��B���ꂼ��̘_�_�ɂ����������z�₲�ӌ�������A�݂Ȃ����R�ɏ�������ł��������B�܂���i�فE�����T��̕��͂��ނɂ��܂��B
--------------------------
���uiPod�@/PC�@/���b�s���O�\�t�g������r�e�X�g�v
http://www.ippinkan.com/i-pod_pc_net_audio.htm
�ꕔ�̃}�j�A�́ACD�̃f�[�^�[����荞�ނƂ��A�g�p����h���C�u��O�t���h���C�u�̏ꍇ�͐ڑ��P�[�u���ʼn����ς��ƌ����܂����A���̍��܂ł̌o���ł́A�����ɉ����ς�����Ƃ����L���͂���܂���B(����)�l�I�ɂ͎�荞�݂̃n�[�h�E�F�A�Ɋւ��Ă͂��قǐ_�o���ɂȂ�K�v�͂Ȃ��ƍl���܂��B
--------------------------
�ȏ�A�h���C�u�ɂ�錰���ȉ��̈Ⴂ�͂Ȃ��A�Ƃ���Ă��܂��B�Ƃ��낪����A�Ƃ��ǂ������q�ǂ��Ă���ȉ��̃u���O�Ǘ��҂̕��́A�u�{���ɕς��̂��H�v�Ƌ^��������Ȃ���Plextor Premium2���������Ƃ���A�����̒�ʂ��̑����ς�����Ƃ����܂��B
----------------------------
��PC�I�[�f�B�I������ ���̓� �| Plextor Premium2(�l��`)
http://hei30per.blog34.fc2.com/blog-entry-255.html
�@���āA�uLaShell Griffin / Free�v�Ɓu���˒q�G / LIVE!�v�����b�s���O�����Ƃ���ŁA�ȑO����CD�h���C�u�Ń��b�s���O����WAV�f�[�^�Ɣ�r���Ē����Ă݂悤�B(����)
�@����LaShell�B�O�t���ł̈Ⴂ�͕�����Ȃ��B�������A�{�[�J����������BLaShell�̌���15cm�قǏオ�����̂��B����̐����������A����ɂ܂Ƃ����Ă������̐������������B���ʂƂ��āALaShell�̐��͐��炩�ɐ���ŁA����������Ԃ����悤�Ɋ�����B���[���A�O���P��B�ς��[�B
-----------------------------
�ӌ����H������Ă���悤�Ɍ����܂����A����ɂ��ĉ������ӌ��̂�����͂����܂����H�@���Ĉ��������A�܂���i�فE�����T��̕��͂ł��B
-----------------------------
���uiPod�@/PC�@/���b�s���O�\�t�g������r�e�X�g�v
http://www.ippinkan.com/i-pod_pc_net_audio.htm
�n�[�h�E�F�A�Ɠ�������荞�݃\�t�g�E�F�A�[�ɂ�鉹�̈Ⴂ���AiPod��3��ނ̃w�b�h�z���o�͂̍�����ꡂ��ɏ������A�قƂ�ǗL�Ӌ`�ȍ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B
��荞�ݑ��x��G���[�����ݒ�̂���Ȃ��ł����͂قƂ�Ǖς�炸�A�g������̗ǂ��\�t�g��CD�����b�s���O����Ώ\���ȉ����Ńf�[�^�[����荞�߂�ƍl�����܂��B
-----------------------------
�ȏ�A���b�s���O�\�t�g�ɂ�鉹�̈Ⴂ�͂قƂ�ǂȂ��Ƃ���Ă��܂��B�����G���[�����ݒ�̗L���Ɋւ��Ă����A�G���[��������K�v�̂��鎖�Ԃ��������Ƃ��ɂ͂���ɂ�艹�̈Ⴂ����������悤�Ɏv���܂����A�ǂ��Ȃ�ł��傤���H�@�����Ĕ��ɋ����������ꂽ�̂��ȉ��̂�����ł��B
-----------------------------
���uiPod�@/PC�@/���b�s���O�\�t�g������r�e�X�g�v
http://www.ippinkan.com/i-pod_pc_net_audio.htm
Windows XP�ł́u�J�[�l���~�L�T�[�v�����҂ɂ���Ă܂����A���Ȃ��Ƃ��u���ʂ��ő�i��������������ƃf�W�^���̈�ʼn������N����j�v�ɂ��ĕ�������A���͕ς��܂����傫�Ȉ��e���͂Ȃ��Ɣ��f���Ă��܂��B
�܂��A�J�[�l���~�L�T�[���o�C�p�X����/���Ȃ��ƁA�t�@�C�������k����/���Ȃ��̉����ω��̌X���͂悭���Ă��āA�ǂ�����u���_�I�ɉ��̏��x���グ�遁�f�[�^�̏��x���グ��v�قǁA�u�����o���o���ɕ�������āA��������X���������v�������܂����B
-----------------------------
PC�I�[�f�B�I�ɂ����āAWindows XP�����ł̓J�[�l���~�L�T�[���o�C�p�X�����邱�Ƃ��Z�I���[�Ƃ��ĕK�{�ł��邩�̂悤�Ɍ���Ă��܂����A���͂�������u�傫�Ȉ��e���͂Ȃ��v�Ƃ���Ă��܂��B
����A����ȏ�ɋ������������̂����i�̂�����ł��B�v��A�u�f�[�^�̏��x���グ��قlj����o���o���ɕ�������A�������鉹�ɂȂ�v�Ƃ������͂ł��B�����P���ɉ��߂���A(1)�f�[�^�̏��x���オ��Ίe�y�킻�ꂼ��̕��������悭�Ȃ�A(2)�f�[�^�̏��x���オ��Β�������A�ƂȂ�܂��B
�܂��u��������v�Ƃ����̂͑����Ɏ�ϓI�ȗv�f�Ȃ̂ŁA���܂�ӎ����Ă��Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂�(�Ȃ���������������������̂��H�@���̉��̍D�݂̌X�����炨�悻�̎@���͂��Ă��܂����A����͖{��ł͂Ȃ��̂Ŋ������܂�)�B
�ŁA(1)��(2)����z������Ɓc�c���Ԉ�ʂɁu�悢�����v�Ƃ���Ă��鉹�قǁA��������𑜓x�̍����u�N���V�b�N�����̉��ł���v�Ƃ����������ЂƂ��藧���܂��B�s���A�I�[�f�B�I�̐��E�ł͉��y�I�ɂ̓N���V�b�N�������h�ł�����A�P�Ɂu�悢���v�Ƃ�������͂��Ȃ킿�u�N���V�b�N�����̉��v���w���A�Ƃ������Ƃł��B
����A���Ƃ��n�[�h���b�N�ł���A��������𑜓x�̓N���V�b�N�قǖ��ɂȂ炸�A���Ȃ킿�f�[�^�̈��k�Ɋւ��Ă��N���V�b�N�قǖ��ɂȂ�Ȃ��A�Ƃ������������藧���܂��B
���̂ւ���ڏq����Ƃ��̂����������Ȃ�̂ŁA�����͊������܂��B�ЂƂ݂Ȃ���ɂ���Ă���Ƃ���A�u�P�Ɂw���������x�Ƃ������l�̕����͂��݂̂ɂ����A�w�����̂悭�������y�������鉹�Ȃ̂��ǂ����H�x�ɍő�̒��ӂ��܂��傤�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����Ȃ����̂ŁA�ЂƂ܂����̂ւ�ŁB
�����ԍ��F12485413
![]() 1�_
1�_
�܂��A���̎�̋c�_�ŁA�N�ƌ��킸�����O�̒i�K�Łw�ς��x�܂��́w�ς��Ȃ��x�̉��������ĕ����ԓx�͊Ԉ���Ă��܂��B
�����O�͏�Ɂw�ς��̂��A����Ƃ��ς��Ȃ��̂��x�Ƃ����j���[�g�����ȗ���ŕ������Ƃ���ł��B���ꂩ�ɕ������҂����Č������ׂ��ł��B
�����ĂP�Ԃ܂����̂��A���������Ȃ��Łw�ς��x�Ȃ����w�ς��Ȃ��x�Ɣ������Ă��܂����Ƃł��B
�����āA�w�ς��h�x�w�ς��Ȃ��h�x���ꂩ�ɑ�����l�Ԃ����݂���Ƃ����i���̓��ނ������Ȃ��Ƃ����j�F�����̂����ł��B
�����O�Ɏ��ׂ��ԓx�́w�ς�邩�A����Ƃ��ς��Ȃ����H�x�ł��B���������āw�ς��h�x�̓P�[�X����Ŏ��̏u�ԑ��ς��Ȃ��h�ɂȂ肦�A�t�Ɂw�ς��Ȃ��h�x�͑��ς��h�ɂȂ肦�܂��B
�܂�f����ɐ�ΓI�ȕς��h�ς��Ȃ��h�͎��݂����A���ۂɋ���͎̂��̂悤�Ȑl�ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�P�E���������Ȃ��ŕς��Ȃ��ƌ����l
�Q�E���������Ȃ��ŕς��ƌ����l
�R�E��������ς��Ȃ��Ɗ������l
�S�E��������ς��Ɗ������l
�P�ƂQ�͘_�O�ł��B���������Ȃ��Ō����Ă��邱�Ƃ͉��̐M�ߐ�������܂���B
�R�ƂS�͂���ɂQ��ނɔh�����܂��B
�b�E�������ʂɂ����ĕς��Ȃ����ς��Ȃ��ƌ����l
���E�����ʂ͕ς�邪�����ʂ͕ς��Ȃ��ƌ����l
�b�͎��ۂ̎��s������Ƃ͌����A�v�����݂��G�X�J���[�g���q�ϐ��������Ă���\��������܂��A�ς�鈽���͕ς��Ȃ��Ƃ������_����ɂ��肻�̎v�����݂ɂ��������ď����ߕt���Ă���\��������܂��B���̕�����L�j���[�g�����Ȉӎ����痣�ꂸ�Ɍ������\���̍������Ƃ������A�M�ߐ��͉��̂������ł��B
��ΓI�ς��h�A��ΓI�ς��Ȃ��h�A�����������Ƃ�����A���̌������Ƃ͊ԈႢ�ł���\���������ł��B
�M�ߐ��̂��锭���́A�R�Ȃ����S�̉��^�C�v�̔���������l�ł��ˁBDyna���͂���ɊY�����܂����玄�͂��̉����z��������x�Q�l�ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F12485498
![]() 3�_
3�_
Dyna-udia����@����ɂ���B
�Z�������Ԃ̒��A��ςɒ������͂ł̖���N����J�l�ł�(���݂Ō����Ă����Ȃ��ł�����ˁj
�l�I�ɂ́A���y��I�[�f�B�I�͐�����S��L���ɂ��镨���Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�����Șb�A�����g�ɂ͏�������_�������Ȃ�Ă���Ȃ������܂�K�v�Ȃ��Ǝv���܂��B
�{���AONKYO�̎�����ɍs�������A���͔��ɋC�ɓ���܂������A������I����A��l�̂��q�����[�J�[�̒S���҂Ɂu�A���v��DAC�������������m�C�Y�������Ăǂ����炱���Ƃ��v�A����ȋ@�B�̓����I�Șb���i���Ƙb���o���Ď����̎咣���c�Ƃ̒S���҂ɔF�߂��������悤�Ȋ����ŏ�����b���Ă��܂����B���̐l�́A�����̒m�����Ђ��炩�����������ŁA�I�[�f�B�I�͉��y�����̂Ȃ̂ɁA�I�[�f�B�I�łȂɂ��Ă���̂��낤�Ǝv���܂����B�m�C�Y�Ȃ@�B������������Ȃ��d����������Ă��邵����������n�߂��L�����Ȃ��Ǝv���܂��B
���y�͊����Œ������̕��ł���A�Ȋw�I���l�◝�_�Ȃƕʕ����Ǝv���̂ł����A�ǂ����l�ɂ���Ă͓��ŗ����ŕ����Ă���l�����Ȃ��炸����̂��ƁA�����̎�����ɍs���Ďv��������ł��B
�����g�́A�d���ʼn��͕ς��Ǝv���Ă��܂��B�����A�����ς��Ƃ����Ă��ǂ������ɕς��Ǝv���l������݂����ł����A�v���X�ɕς��ꍇ������}�C�i�X���ɂ��ς��Ǝv���Ă��܂��B
����ƕς��ƌ����Ă��Ⴆ�AONKYO�̃A���v�ɓd���R�[�h��ς�����YAMAHA�̉��ɂȂ�Ƃ��ADENON�̉��ɂȂ�Ƃ����I�ȕω��͂Ȃ������܂ł��X�p�C�X�A�⋭�I�ȃC���[�W�ł��傤���B
���������Ӗ��ł͖{���̃I�[�f�B�I�@��̃L�����N�^�[�̉����ς��Ȃ��Ƃ����Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ��ł��傯�ǁA���������ς��Ƃ����\���ł͂Ȃ��I�[�f�B�I�̖{���̐��\�������o�����߁A����⋭����ƌ������ق����C���[�W���I�m�ȋC�����܂��B
������Ǝx���ŗ�ȕ��͂ɂȂ肷���܂������A�ǂ�ȕ]�����悭�Ă��A���z�ȋ@��ł��A�Z�p�I�ɗD��Ă��Ă����l���C�ɓ��邩�ǂ������Ǝv���܂��B������Dyna-udia�����������悤�Ɏ����͑厖�ł��ˁB
�Ō�́A��������ϓI�Ȉӌ��ɂȂ��Ă��܂��Ă��݂܂���B
�����ԍ��F12485563
![]() 3�_
3�_
air89765����A���ӂ́B
�����邱�Ƃ́A�悭������̂ł����A���ۂɂ͂���������₱������ʂ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�i�����Ȃ��ŁA�u�ς��v�u�ς��Ȃ��v����łɎ咣����̂́A�m���ɍ���҂ł��ˁB
�����A�u���_��ł́c�c�Ȃ���ǁv�ƌ����ӌ����炢�́A�ǂ����Ȃƌ����C�͂��܂����c�i�����܂ł����_��ŁA���ۂ͈Ⴄ�����c�ƌ����ӌ��Ȃ�j�j
�@
�@
���́A�u��ɕς��i�������͕ς��Ȃ��j�ƌ����l�v�Ɓu��ʂɂ���ĕς��ꍇ�ƕς��Ȃ��ꍇ������Ƃ����l�v�Ȃ�ł����A���̐M�ߐ��ɂ��āA�ȒP�ɐ蕪������̂ǂ����H
�@
�@
�u��ɕς��v�Ǝ咣����A�̋ɒ[�ȗ�������܂��ƁA
1. �Ⴄ�Ȃ̓����Ă���CD���Đ�����ƁA�����ς��B
2. �Ⴄ�w�b�h�z���i�Ⴄ�@��j�Œ����ƁA�����ς��B
�ƌ����̂��l�����܂��B
�i���̏ꍇ�A���2�́A�����ς�邩�ǂ��������ꂽ��A���͕ς��Ɠ�����Ǝv���܂��j
���̏ꍇ���ƁA�u�ꍇ�ɂ���ĕς������ς��Ȃ������肷��v�A�Ƃ����l�̕����M�ߐ��������ƌ����ėǂ��̂��ǂ����H
�X�ɁA�c�_�ɂȂ肻���Ȃ��Ƃ��ƁA
3. �ႤCD�h���C�u�ōĐ�����ƁA�����ς��B�iPC�I�[�f�B�I�Łj
4. �Ⴄ�n�[�h�f�B�X�N�ōĐ�����ƁA�����ς��B
5. USB-DAC��USB�P�[�u����ς���ƁA�����ς��B
6. USB�P�[�u���ɕt��������𗎂Ƃ��ƁA�����ς��B
�c�c
�i�������́A�ǂ����ȁH3�`5�͌o������܂����c�j
�z���͂��n���Ȃ̂ŁA���܂�ǂ��Ⴊ�o�Ă��Ȃ���ł����A�l�X�ȃ��x���̂��Ƃ�����̂ŁA���܂�ȒP�ɂ͐蕪�����Ȃ��C�����܂��B
�@
air89765������ꂽ�����Ƃ́A������̂ł����A���͂ɂ��āA�ȒP�Ɂ���×�ɕ����Ă��܂��ƁA������ƈႤ�C�����܂��B
���������A���G�Ȏ����ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����A�ǂ��ȂƂ�����Ɓc��肭�����Ȃ��̂ł����A���̐l�̎p���݂����Ȃ��̂��d�v�ȋC�����܂��B
�����ԍ��F12485890
![]() 0�_
0�_
������
�{�������Ă܂��ˁi�j
�ς��ƌ����ė�����ĂĂ��A�����̊��E���ŕ�����Ȃ���Δ������l�������̂�
���́A���Œ��������Ӗ��������h�ł�
���́A���C���P�[�u���E�X�s�[�J�[�P�[�u���E�d���P�[�u���E�t�r�a�P�[�u���ł̈Ⴂ�͂���܂���
(�o�b�I�[�f�B�I�ŁA���z35���قǂ̃V�X�e���ł�)
���C���P�[�u�����ŏ��Ɋ������ƌ��������������ŁA�f���Ȃ�ĂȂ�
���ƌ����I�[�f�B�I�G����X�̕��̈ӌ��ʂ��������������ł�
�̂Ɋ撣���Ĕ������A���v�i30�����j�������ł��ǂ����ɂ������ƁA1000�~���x�̃P�[�u������
3����̒Z���P�[�u���֕ύX���܂����@�G���Ȃǂ����Ă�Ƒf���炵���]����
����������������悤�ȕω�������̂ƁA((o(�P�[�P)o)) ���N���N���Ȃ���ύX
�E�E�E�E�E����H�@�����ς�����̂��ȁH�H�H(^^;;;;;;;
�Ƃ������x���ŁA30���ʂ܂�Ńe�X�g�̂悤�ɕ����āA����Ɓ@���������̋�����
�܂�₩�ɂȂ��Ă��Ƃ̃��x���A�A�A�A�A��������͍����ȃP�[�u���͔����܂���ł���
�ŋ߁A�I�[�f�B�I�M���Ĕ������̂ŁA�ł͂o�b�I�[�f�B�I�����Ă݂悤��
�X�s�[�J�[�A�A���v�A�c�`�b���w�����F�X���Ă�ƁA���C���P�[�u���͕ω������Ȃ��Ƃ̎�
�ӂނށA����Ȃ畨�͎����œd���P�[�u���ς��Ă݂悤��
�債�Ċ��҂��Ă܂���ł������A�ω������邩�m�肽���ׂɁA2����̃P�[�u�����Ă݂܂���
���ʂ́A�A�A�v�������ς��܂����@��������܂�͗ǂ����ǒቹ������
������ƃX�b�L���������łȂ��E�E�E(^^;
�����̎��͂��܂�M�p�ł��Ȃ��̂ŁA�C���̈Ⴄ����A�ē~�A���ԂȂǕς��Ĕ�ׂ܂�����
����ς�Ⴂ�܂����̂ŁA�d���P�[�u�����ĕς��ȁ`�Ƒ̊����܂����B
�������߂āA�X�s�[�J�[�P�[�u�����ς��悤�Ǝv���܂������A����͕t���ւ���̂��ʓ|�E�E�E
�Ƃ������ƂŁA�Z���N�^��2�����Đ�ւ������Ńe�X�g�o����悤�ɂƁA���قȔ�������
�P�[�u����1m1000�~������4��ޔ����Ă݂Ď����܂������A������ω��͂���܂���
�i�x���f���A�J�i���A�S�b�T���A�`�d�s��4�j
�������i�т������ʂ̂��߂��A�d���P�[�u�����̈Ⴂ�͊����܂���ł���
������N���ɕς����ĂĂ��A�S�b�T���ȊO�͕����邩������Ȃ������x��
�i�S�b�T���͉𑜓x�͗ǂ��̂ł����A�ȂL�����������������̂Ŕ���Ղ������ł��j
�Ō�ɂt�r�a�P�[�u���ł����A�f�W�^�����o�͂��邾���̕��ŁA��ԈႢ�����Ȃ����낤�Ǝv���Ă܂�����
���̊��ł̓X�s�[�J�[�P�[�u���i���ꉿ�i�сj�����L��܂����̂�
����́A������Ƃт�����Ŋ�������Z�ł͂���܂������A�F�X�����H�ڂɂȂ�E�E�E(;´�t�M)
���b�s���O���ɂ��Ẳ��̕ω��ł����A�o�b�I�[�f�B�I�̃V�X�e�����܂��܂��Ȃ̂����m��܂���
���͊����ꂽ���͖����ł��B
������r�f�X�g�ł����A������i�ق���̃��r���[��O�ɓǂ݂܂�����
foobar2000�ɂ��ẮA�����l��XP�Ŏ������Ƃ��ɂ͓����l�ɂ��U���Ă��ۂ͎܂���
�����A�@�킪�����i���߂Ăn�r�����ł��j�łȂ��ƁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ȃ�
��AFrieve Audio�Ȃ̃e�X�g������ĂȂ��̂ŁA��i�ق���̕��ł�
�o�b����̕����ɔ�ׂāA�o�b�������̃`�F�b�N��e�X�g�́A�܂��܂��ł͖����̂��ȁH�Ƃ�
��ۂ��܂����B
�����Ȃ肷���Đ\����܂���@<(_ _)>
���̃X���ŁA�{���ɕς��́H�Ǝv������������Ď�������A�Ⴂ��̊����ꂽ�����o�Ă���
���v�������ăP�[�u���ނ������ł������Ȃ��Ă����Ɨǂ��ȂƎv���܂� ^^
�����ԍ��F12486360
![]() 4�_
4�_
�@�ǂ����A�����l�ł� -> �g�s��a�B
�@���āA�����̃{�[�h�ɂ����܌����u�P�[�u���ʼn��͕ς��Ȃ��BCD���f�B�A�ʼn��͕ς��Ȃ��B�A���v�ł����͕ς��Ȃ��B�����ς��Ȃ�������ς��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ𐺍��ɑi�����m�Ƃ��̍��В��B�̌��������Ă݂�ƁA���ʂ��Ă��邱�Ƃ��ЂƂ���܂��B
�@����́A�N���u�����ς��i���邢�́A�ς��Ȃ��j�v�Ƃ������Ƃ���w�I�E�����w�I�Ɍ����悤�Ƃ��Ă��Ȃ����Ƃł��B
�@�I�[�f�B�I�V�X�e���ɂ����āu�����ς��i���邢�́A�ς��Ȃ��j�v�Ƃ������Ƃ�F�m����̂͑����ł͂Ȃ��ł��B����͐l�Ԃ̎��ł���͂��ł��B�Ȃ��Ȃ�A�I�[�f�B�I�V�X�e���̃��[�U�[�͈�ʂ̉��y�t�@��������ł��B�@�B�ł͂���܂���B
�@A�Ƃ����A���v��B�Ƃ����A���v�͎��g���������Ⴄ���特���قȂ�E�E�E�E�Ƃ����������͂悭����܂����ǁA�Ȃ�ǂ����Ď��g���������ς��Ɖ����ς��Ɗ�������̂��A�ǂ��������o�i�]�j�̃��J�j�Y���łǂ̂悤�Ɂu�����ς��v�ƒm�o�ł���̂��E�E�E�E�Ƃ��������Ƃ܂œ˂�����ōl�@���Ȃ��ƁA�u�����ς�����̂ǂ��́v�Ƃ����ӌ��́i�����Ɍ����j�o���Ȃ��킯�ł��B
�@���Ƃ��A���g��������A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[��W�b�^�[�l���ς��Ȃ����特���ς��Ȃ��A���ꂼ�u�Ȋw�I�ȍl�@�����I�v�ƌ��߂���̂́E�E�E�E���͂����Ƃ��u�Ȋw�I�v�ł͂Ȃ��̂ł��B����Ȃ͉̂��y�M���̃����[�X�������̐����ɉ߂��Ȃ��B�葤�̃��X�i�[�͂ǂ��Ȃ̂��������Ȃ��ƁA�u�����ς��i���邢�́A�ς��Ȃ��j�v���ǂ����́u�Ȋw�I�Ɂv���_�t�����܂���B
�@������ɂ���A�����������Ɂu�����ς��i���邢�́A�ς��Ȃ��j�v�ƌ�������A���́A����̋�����Y����Ȑl�Ԃƌ��������Ȃ��ł��傤�ȁB
�����ԍ��F12487182
![]() 5�_
5�_
�P�[�u���ɋ����ĉ����ς��̂͑̌��㔻��܂��i�d���P�[�u���͔���܂���ł����j���A�P�[�u���ōD�݂̉����Ă���X�́A�������y�̃W���������ɃP�[�u���̍����ւ�������Ă�̂��ȂƁ@�ӂƋ^��Ɏv���܂������A��������Ă�̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F12487384
![]() 5�_
5�_
�ς��A�ς��Ȃ��ƈȑO�ɕς���Ă��ω����F���o���Ȃ��ꍇ�����邩�ȂƎv���܂��B
�ǂ����������Ƃ����ƁA�@��̃L�����N�^�[�������ꍇ�A�ω������������P�[�u���̏ꍇ�͕ω��������ɂ����Ǝv���܂��B�t�ɕȂ����Ȃ��@��̏ꍇ�A�P�[�u���������������ʼn��̕ω����o�₷�����ߔ��ɗ������₷���Ǝv���܂��B�x���L����]�m�g�[���̃P�[�u���������������A�G���̃��r���[�ʂ�߂��ĕ]�_�Ƃ̊��z�͓I�m�ȂƎv���܂����B
�ς��Ȃ��h�̐l�ɂ́A�����̋@�킪�F�t�����Z�����߁A�P�[�u���ނ̃L�����N�^�[���F���o���Ȃ��̂�����̂��ȂƎv���܂��B
���E�������@�����������Ă܂��B
�������ɑi�����m�Ƃ��̍��В��B�̌��������Ă݂��
������̋�����Y����Ȑl�Ԃƌ��������Ȃ��ł��傤�ȁB
���܂�h���I�Ȉӌ��͕ʂ̏��ŝ��߂܂��̂ŁA���������I�u���[�h�ɕ��ŋ��������I�m�Ȉӌ����Ǝv���܂�������������Ă��܂��Ǝv���܂���B
�����ԍ��F12487518
![]() 1�_
1�_
�����́A�u��ɕς��i�������͕ς��Ȃ��j�ƌ����l�v�Ɓu��ʂɂ���ĕς��
���ꍇ�ƕς��Ȃ��ꍇ������Ƃ����l�v�Ȃ�ł����A���̐M�ߐ��ɂ��āA
���ȒP�ɐ蕪������̂ǂ����H
�@
baldarfin����ɂ��́B
���A�ǂ��������܂���B�O�L����
>>�b�E�������ʂɂ����ĕς��Ȃ����ς��Ȃ��ƌ����l
>>���E�����ʂ͕ς�邪�����ʂ͕ς��Ȃ��ƌ����l
�Ƃ������������������̂ł����A�w�����u�ς��v�܂��͉����u�ς��Ȃ��v
�Ƃ�����Ɋ��z������P�[�X�x�E�E�E�Ƃ����ς��ς��Ȃ��c�_
�����݂���A�Ƃ�����O��ɂ����Ă̍l�@�ł��B
�����������������܂���B
�ၨ�f�W�^���P�[�u���ECD-R���f�B�A�E�f�W�^���g�����X�|�[�g�E�d���P�[�u�����̗v�f�ʼn����ς�邩
�N�����u�Ⴄ�v�ƔF�����邱�Ƃ��o���A�ӌ������Ȃ����̂ɂ��Ă�
�����ł͌��y���Ă��Ȃ��A�Ɖ��߂��Ă���������Ɗ������ł��B
�ၨ�w�b�h�z����X�s�[�J�[��ς���Ɖ����ς��E�Ȃ��Ⴆ�Ή��͈Ⴄ�E�̎肪�Ⴆ�ΐ����Ⴄ�A�ȂǁB
���́u�b�E�������ʂɂ����ĕς��Ȃ����ς��Ȃ��ƌ����l�v�Ƃ́A
�u���̓f�W�^���P�[�u��A��B�ňႢ���������B������C��D�ł��Ⴂ��������͂����B�v
�u���͊�A�Ńf�W�^���P�[�u���̈Ⴂ���������B�������B�ł�C�ł�D�ł��Ⴂ�͂���Ɍ��܂��Ă�v
�u����A�EB�EC�Ƃ������s�������特���ς�����B������D�`Z�����邱�Ƃʼn��͕ς��̂��v���̂悤�Ɍ��߂��邱�Ƃ�A
�u����CD-R�b��CD-R���ňႢ�������Ȃ������B������CD-R����CD-R���ł��Ⴂ�������Ȃ��ɈႢ�Ȃ��v
�u���͊�A��CD-R�̉��Ⴂ�������Ȃ������B�������B�ł�C�ł�D�ł��Ⴂ�͖����v
�u���͓d���P�[�u���̉��Ⴂ�Ȃ�Ċ����Ȃ��B�����瑼�l�������Ȃ��͂����������邱�Ƃ͎v�����݂��v
�̂悤�ɍl���Ă��܂����Ƃɂ���āw���͕ς��̂��A����Ƃ��ς��Ȃ��̂��x
�Ƃ����j���[�g�����Ȏ��_�Œ������Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����Ԃ��w���܂��B
�����A�Ńf�W�^���P�[�u���̉��Ⴂ�������Ă��܂��ʂ̊�B�ł́u���Ȃ���������Ȃ��v�B
�܂������C��CD-R�̉��Ⴂ���킩��Ȃ��Ă��A�����D�ł�CD-R�́u���Ⴂ�͂킩�邩������Ȃ��v�B
���́u��������Ȃ��v����ɁA��ɋ^���Ă�����A
���܂ł̌��ʂɊ�Â��Ď��̌��ʂ����߂��Ď��s���Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
���鎞�_�Łu���͕ς��Ȃ��v�u���͕ς��v�̉��ꂩ�ɕ�����ۂ����������Ƃɂ���āA
�w���͕ς��̂��A����Ƃ��ς��Ȃ��̂��x�Ƃ����j���[�g�����Ȏ��_�������Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��ƁA
���f�ɕ�E�ԈႢ�������āA���̂��ƂŁh�^���h���牓�������Ă��܂����Ƃ����O�������̂ł��B
�u���E�����ʂ͕ς�邪�����ʂ͕ς��Ȃ��ƌ����l�v�Ƃ����̂͂��̃j���[�g������
���_���������ƂȂ����s�������Ă���A�Ƃ����������������̂ŁA
���̂悤�ȁu�q�ϐ��v������Ȃ��l�̔����́A������x�Q�l�ɂ���ɒl����A�Ǝv�����̂ł��B
�����ԍ��F12487573
![]() 1�_
1�_
2011/01/10 10:14�i1�N�ȏ�O�j
�_�_�̈�ɁA�q�ϓI�Ȉӌ��A��ϓI�Ȉӌ��������Ă܂����A�����̎����Ă�I�[�f�B�I�Z�b�g�̉��́A�����ꂽ���̂ł���A
���鎩���̍D�݂ɍ����悤�ɃZ�b�e�B���O��P�[�u����ς��č���Ă��鎩�������̉F���ł��B
�����Ȃ�ɋq�ϓI�ɕ]�����鎖�͂ł��Ȃ��͂Ȃ��ł����A���Ȃ��炸�����ɂ͎v������Ƃ�����ς�����܂��B
�ł́A�V���b�v�̎����͂ǂ����ƌ����ƁA���ʂȏꍇ�������A�X���ɂ��鏤�i����I�Z�b�g�Œ��������Ȃ��̂ŁA
�����ȈႢ�ȂLjӖ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�ł����F��ȑg�ݍ��킹�Œ����Ă݂�ƒ��ɖ��炩�Ɏ������D���ȉ����o�����̂������āA
����͂�����Ƃ����Ⴂ�Ȃ�Ȃ��A�ς��ƒ����ŗǂ��Ǝv���܂��B
�ǂ��Ƃ������Ƃ������̂́A���̐l�̉��y��I�[�f�B�I�Ƃ̂������ŕς���Ă�����̂ł�����A
�����ɂ��]���́A���̐l�̎�ϓI�Ȉӌ����Ǝv���Ă��܂��B
�A���A��O�������āA�I�[�f�B�I���������A�F��ȃX�s�[�J�[��A���v��b�c�o���g�p�����o��������A
�]�������������莝���Ă���x�e�����̈ӌ��͋q�ϐ��������ČX���ɒl���܂��B
���̌f���ł͂����������x�e�����̕����ԐM���Ă���������̂ŁA���ɎQ�l�ɂȂ�܂��B
�����A�S�������m��Ȃ��Ƃ��납��A���̌f���ł̃A�h�o�C�X�𗊂�Ɏ������J��Ԃ��܂����B
�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�������A�h�o�C�X�́A�I�O��Ȃ��̂�����A�x�e�����ƌ����ǂ��A������ϓI�Ȉӌ���
�������܂�邱�Ƃ͂���ƔF�����Ă��܂��B
�͂����茾���A���ł́A���Ƃ��x�e�����̈ӌ��ł��Q�l�ɂƂǂ߁A���ۂɒ����Ă݂Ĕ��f���邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�ł����A���S�҂͂����͍s���܂���B�Ȃɂ��킩�炸����������Ă��Ă���̂ł�����A
���S�҂��u��ϓI�Ȉӌ����������v�A�Ə��������Ɂu��ϓI�Ȉӌ��͖��Ӗ��v�Ɛ�̂Ă�̂͌����߂����Ɗ����܂��B
���ɃP�[�u���ɂ��Ⴂ�ł����A�ς�邩�ς��Ȃ����͒u���āA
�I�[�f�B�I�Z�b�g�̃o�����X����������ɂȂ邱�Ƃ��|���Ď��͂܂�����o���܂���B
���ɈႢ���������Ƃ��Ă��A�A���v��ς���قǂ̑傫�ȈႢ������Ƃ͎v�����A
����ƈ����ւ��Ƀo�����X��������炢�Ȃ�A�I�J���g��1�Ɗ�����Ď���o���Ȃ��̂���̍s�����ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����Ō����o�����X�́A������ʁA����A�r�m�A�ቹ�̗ʊ��A�Ȃǂ��w���Ă��܂��B
�ł����A���������̃I�[�f�B�I�̉����Ă�ƖO���Ă���̂������B
�����ŗV��ł݂悤�ƌ������ƂŃP�[�u����ς��āA�����ȕω����y���ނ��Ƃ͗L�肾�Ǝv���܂��B
���l�I�ȈႢ�̖������ʼn����ς�邱�Ƃ́A�����Ă����镶���̑��ɂ������āA
�����ς��h�̈ӌ����ς��Ȃ��h�̈ӌ����ǂ�����������ƌ����̂����_�ł͂Ȃ������ł��傤���B
���Ȃ��Ƃ��A�@�퐻��҂�Z�p�ҁA���邢�͂b�c����҂Ȃǂ̃v���́A���l�Ő��\��������ƕ]�����Ă����Ȃ��ƍ���܂��B
����A��X�A�}�`���A�͉��ł��L��ł��B�ܘ_�P�[�u���ʼn��͕ς��܂��B
�Ȃ��Ď�ςł�����B
�����ԍ��F12487674
![]() 3�_
3�_
�q�ϓI�Ȏ��͎������킹�ĂȂ��̂ŁA
�q�n�l���Ńt���t���B
���̓I�J���g�ł��Ⴂ��F�������甃���Ă��܂��܂��B(��
�����ԍ��F12488047
![]() 1�_
1�_
��air89765����
>�P�Ԃ܂����̂��A���������Ȃ��Łw�ς��x�Ȃ����w�ς��Ȃ��x�Ɣ������Ă��܂����Ƃł��B
����Ɋւ��ẮA(baldarfin������������ɂȂ��Ă��܂���)�A�u���_�I�ɂ́w�ς��/�ς��Ȃ��x���낤�v�ȂǂƗ\�z�E���͂���̂͂����Ǝv����ł��B�����̒m��Ȃ����_������Ȃ�Βm�肽�����A�m�I�D��S���o���܂��B
�������̘_�@�̉�������ɁA�ނ��������P�[�X����������̂������ł��B����͎��ۂɎ��Œ������特���ω����Ă���̂ɁA���̉��̕ω������_�ʼnȊw�I�E�Z�p�I�ɑ̌n�t�����ĂȂ��ꍇ�ł��B�d���P�[�u���Ȃǂ͓T�^�ł��B
���̏ꍇ�A���̉��̕ω��͎��ԓI�ɂ́u����̒i�K�v�ɂ���A�u�����E�ϑ��Ɋ�Â��Ȋw�I�Ȗ@������҂ߒ��ɂ���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂�(�`�̏�ł�)�B���Ȃ킿�����ŁA�Ȋw�I�ȗ��t�����d��u�ς��Ȃ��v�h�ƁA���ۂɎ��Œ��������ʂ��d������u�ς��v�h�ɕ�����Ă��܂��܂��B
�Е���(1)�u�Ȋw�I�E�Z�p�I�ɗ��_�t�����ĂȂ�����ς��Ȃ��͂����v�Ɗ拭�Ɏ咣���A�����Е���(2)�u���ۂɎ��Œ������特�̕ω��͂���̂��B�Ȃ������Œ����Ă݂Ȃ��̂��H�v�ƂȂ�܂��B���̑Η��̍\�}���Œ肳��A�i���Ɍ���邱�Ƃ�����܂���(��)
>�w�ς��h�x�w�ς��Ȃ��h�x���ꂩ�ɑ�����l�Ԃ����݂���Ƃ����i���̓��ނ������Ȃ��Ƃ����j�F�����̂����ł��B
�ΏۂɂȂ�A�C�e��(�P�[�u���ACD-R�̏Ă����Ȃ�)���ς��Γ��R�A�u�ς��E�ς��Ȃ��v���قȂ�͂��ł��B�ł������Ԃ́A�u���ׂẴA�C�e���ʼn����ς��v�Ƃ��������悤�Ɍ�������ƁA�u���ׂẴA�C�e���ʼn��͕ς��Ȃ��v�Ƃ��������悤�Ɍ�������̓��ނɓ���Ă銴���ł��ˁB
�ŁA�Ȃ�����Ȃӂ��ɕ�̂��H�@�Ƃ����l�Ԃ̃����^���e�B�͂����u���O�L�����A���͂��łɏ����Ă���̂ł����A�C����������u���O�̕����A�������̌f���ɃA�b�v�������ł��B
>�����A�Ńf�W�^���P�[�u���̉��Ⴂ�������Ă��܂��ʂ̊�B�ł́u���Ȃ���������Ȃ��v�B
>�܂������C��CD-R�̉��Ⴂ���킩��Ȃ��Ă��A�����D�ł�CD-R�́u���Ⴂ�͂킩�邩������Ȃ��v�B
>���́u��������Ȃ��v����ɁA��ɋ^���Ă�����A
>���܂ł̌��ʂɊ�Â��Ď��̌��ʂ����߂��Ď��s���Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�u�ߓx�̈�ʉ��v�͌�������_�ɂȂ���\��������A�Ƃ������Ƃł��ˁB���Ƃ��ΔC�ӂ̊����Ƌ@��ň�x���������Ă݂ĉ����ς��Ȃ��������_�ŁA
�u�d���P�[�u���ʼn��͕ς��Ȃ��v
��������d���P�[�u���́A���ׂĂ̊����ʼn����ς��Ȃ�(�ߓx�̈�ʉ�)
�ƌ��_�t����ƌ��ɂȂ�\��������A�ƁB�����[���ł��B�m���ߋ��ɂ����A�ȉ��̂悤�Ȕ���������Ă����L��������܂��B
�u�����ς��Ȃ����Ƃ������Ŏ����ďؖ�����A�Ƃ����Ă��A��@�펎���������ł͏I���Ȃ��B�ς��܂���ł����A�Ɣ��\���Ă��A�ς��h����w���̋@��͎����ĂȂ��̂��H�x�A�w���͂���������x�ƒ��������������ďI��肪�Ȃ��v
�ł�������ė���Ԃ��A�����ς�邱�Ƃ��������₷���d���P�[�u������@�펎���ΏI���b�ł���ˁB���Ƃ��Ή䂪�Ƃɂ���L���o�[�P�[�u����PK-10�Ƃ��A(���͎����ĂȂ��ł����A���Ԃ�ω����킩��₷������)�I���C�f��TUNAMI�n�Ƃ��B
�����̂�����@��ʼn��̕ω����m�F�ł���A���Ȃ��Ƃ��u�d���P�[�u���ʼn����ς��v���Ƃ͗�����܂��ˁB�u������d���P�[�u���́A���ׂĂ̊����ʼn����ς��v�ȂǂƉߓx�Ɉ�ʉ������������͂ł��܂��A���ۂɁu�C�ӂ̋@��͔C�ӂ̊��ʼn����ς�����v�킯�ł�����B�܂肱�̎����ł͏��Ȃ��Ƃ��A�u�d���P�[�u���ʼn��͕ς��Ȃ��v�Ƃ��������͔ے肳��邱�ƂɂȂ�܂��ˁB
�����ԍ��F12489854
![]() 1�_
1�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z���C���A�b�v�O���[�hv4.23
-
�y�~�������̃��X�g�z�\�Z23�����x
-
�y�݂�ȂŃ����N�t���z5�N���H�R�X�p�z��AMD�Q�[�~���OPC�\�����F����3��
-
�y�~�������̃��X�g�z�C���z��
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
�i�Ɠd�j
CD�v���[���[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j