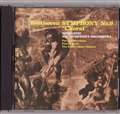���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S436�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 2010�N10��9�� 08:41 | |
| 17 | 25 | 2013�N11��24�� 09:18 | |
| 0 | 0 | 2010�N9��3�� 20:22 | |
| 5 | 3 | 2010�N9��29�� 21:46 | |
| 170 | 197 | 2010�N12��15�� 08:38 | |
| 0 | 1 | 2010�N8��8�� 15:23 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
���}�n�A�}�����c����l�b�g���[�N�v���C���[���o��݂����ł��ˁB
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100906_391989.html
tangent�ALINN�Aetc...���������܂������A���{�̃��[�J�[���撣����
�o���Ă���̂͂��ꂵ������ł��B
����ς�PC�I�[�f�B�I�����y���Ă��邩��ł����˂��B
CD�v���C���[�݂����ɂ����ȉ��i�тƎ�ނ��ł��PC�����Ă�l������
����オ��Ǝv���������̍��ł��B
���͔��N�O��CD-S2000��A-S2000�����������ł����A
�������Ă܂��������߂āA�u���b�N���f���Ƃw�k�q�[�q�����郄�}�n��NP-S2000�������ɍl���Ă��������ȂƎv���܂��B
![]() 4�_
4�_
�����g�}�g����@����ɂ���B
����A-S2000���g�p���Ă܂���B
�ŋ߂̃��}�n��A-S300�Ƃ��V���i���o���Ă�����ϋɓI�ł��ˁB
DENON,ONKYO,�}�����c�Ɣ�ׂ�ƃu�����N�����������������l�C�͂܂��܂����Ǝv���܂����A���i���C���i�b�v�������Ə[�����Ă����Ɛl�C���o��悤�Ɋ撣���ė~�����ł��B
NP-S2000�͎��������������ł����A�����g�}�g����݂�����CD-S2000�����g�p�����ƃv���C���[���D�G������NP-S2000���ƕ�����Ȃ������m��܂���ˁB
�����ԍ��F11936008
![]() 0�_
0�_
�\��Y����
����ɂ���B���̂Ԃ₫�Ƀt�H���[���肪�Ƃ��������܂��B
�\��Y����̃I�[�f�B�I�̊��z��R�����g�����Q�l�ɂ����Ă��������Ă��܂��B
A-S2000�̃��r���[�͍w���O�̎Q�l�ɂ����Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
����CD-S2000�ł����ŋ߂͂��܂�g�p���Ă��܂���(��)
PC��NAS�ɂ����Ղ蒙�߂Ă��鉹�y�f�[�^��AV�A���v�̃l�b�g���[�N�@�\��
���p����A-S2000�ōĐ��Ƃ����p�^�[���������ł��B
����ς��y�ɒ��������Ȃ������ɍĐ��ł���Ƃ���ɊÂ����Ⴂ�܂��B��
�Ȃ̂�CD-S2000�Ɖ��̔�r���C�ɂȂ�܂����l�b�g���[�N�v���C���[�͍��̎����̃X�^�C����
�҂�����ƃn�}��̂Ŋ撣���Ē��߂Ĕ����鉿�i�т������Ƒ����ė~�����Ǝv���܂��B
PC�I�[�f�B�I�����ł���B
�����ԍ��F11939122
![]() 1�_
1�_
�����g�}�g����@����ɂ���B
�������PC�I�[�f�B�I���ꉞ����Ă��܂���(�j
PC����Cambridge Audio��DacMagic���g�p����A-S2000�Ɍq���ł܂��B
http://review.kakaku.com/review/K0000109195/ReviewCD=339589/
���̏ꍇ�ACD�v���[���[�������䂪�Ƃ̃p�\�R������ǂ������o��̂��Ƌ^��Ɏv���Ă��܂��̂ƁA�m�C�Y���̌��ł���p�\�R�����M�p�o���Ȃ��Ăǂ����Ă��ʖڂł���(��)
���ہA������ׂ�ƃv���C���[�������ăO���[�h���オ��قǁA�����J�������ĕ����C�Ȃ�Ȃ���Ԃł��B
�ŋ߂�You Tube�̉�����radico���̂Ɏg�p���邮�炢�ł����A����ł��֗��������̂ŏ������Ă܂��B
�����ԍ��F11939721
![]() 1�_
1�_
�\��Y����
���������PC�I�[�f�B�I���ꉞ����Ă��܂���(�j
����v���܂����Bm(._.)m �����ł����ˁB
USBDAC�͂܂��ǂꂪ�������������f�X�������ɂ͏ڂ������������̂�
���������������ē����������ł��B
�\��Y���������AMP�Ƃ������ƂŁA���ꂩ����F�X�ƎQ�l�ɂ����Ē��������Ǝv���܂��B
��낵�����肢���v���܂��B
�����ԍ��F11956136
![]() 0�_
0�_
�����g�}�g����A���v���Ԃ�ł��B
�T���X�ł����܂���B
USB���͑�����DAC/HPA2����茳�ɑ����������肩��e�X�g�͂��Ă��܂����B
�ŋ߁AUSB��AES/EBU��S/PDIF�ւ̃R���o�[�g�pDDC�B�����̂ŁA
�莝����USB���͂̂Ȃ���ʓI��DAC���S��PC���Ŏg����l�ɂȂ�܂����B
�N����MAC-Pro�ł���������PC�I�[�f�B�I����C�ɉ��������悤���������ł��B
���B�����C���^�[�t�F�[�XDDC:StyleAudio CARAT-T2
http://styleaudio.jp/php/t2.php
�����ԍ��F11996908
![]() 1�_
1�_
�����g�}�g����A�F����A���͂悤�������܂�
���Y�̒P�i�l�b�g���[�N�E�v���[���[���V�������ꂽ�悤�ł��ˁB
AV�A���v�̒����ȏ�̃��f���ɂ́A�ȑO���瓯�l�̋@�\�����ڂ���Ă����̂ŁA����̓Z�p���[�g���Ƃ����Ӗ��������������ł��B
��PC��NAS�ɂ����Ղ蒙�߂Ă��鉹�y�f�[�^��AV�A���v�̃l�b�g���[�N�@�\��
���p����A-S2000�ōĐ��Ƃ����p�^�[���������ł��B
�ق��5���O�Ƀ��C���̃f�B�X�N�g�b�v�p�\�R����V��������ł����A��������������ɁAAV�A���v�iDENON AVC-3808�j�̃~���[�W�b�N�T�[�o�[�@�\���g���āA�u�l�b�g���[�N�E�I�[�f�B�I�v���n�߂Ă݂܂����B
���r���O�̃��C���V�X�e���Œ����Ă���̂ł����A�\�z�ȏ�́g�������h�ɋ����A�g���₷�������Q�ŁA�莝����CD�����X��HDD�ɓ���Ă���Ƃ���ł��B
�����ŁAPC���I�[�f�B�I�Ɏg���n�߂�5���قǂ̒����S�҂ɂ��A�����I�Ȏ���Ȃ�ł����A
�P�jPC�I�[�f�B�I
�Q�j�l�b�g���[�N�E�I�[�f�B�I
�Ƃ����̂́A�������̂Ȃ�ł��傤���H
PC�I�[�f�B�I�ƌ�����ƁA�Ȃ�ƂȂ��A
�P�|�P�jPC�̃A�i���O�o�́��I�[�f�B�I�p�A���v�`
�P�|�Q�jPC��USB�[�q���iDDC���jDAC���I�[�f�B�I�p�A���v�`
�Ƃ����g�������C���[�W���Ă��܂��܂��B
�f�W�^�����A�i���O��PC�ōς܂��Ă��܂����A
�f�W�^���M���̃f�R�[�h��PC�����ōς܂��āA�J�[�l���~�L�T�[�i�E�C���h�E�Y�E���f�B�A�E�v���[���[�̏ꍇ�j���̏������o���f�W�^���M�������o���C���[�W�ł��B
�W�b�^�[�]�X�ƁA�C���C���Ɩ�肪�w�E����Ă���悤�ł�����܂��B
�l�b�g���[�N�E�I�[�f�B�I�́A
�Q�|�P�j�f�R�[�h�ȑO�̃f�W�^���f�[�^�[��LAN��������AV�A���v�ɓ`�B��AV�A���v�i�Ȃ����͒P�i�̃l�b�g���[�N�v���[���[�j���Łq�f�R�[�h�`DAC�`�v���A���v�`�r
�Ƃ������ɉ��߂��Ă��܂��B
������́A�f�W�^���f�[�^�[�]�����ɂ́A�W�b�^�[��肪�����Ȃ��悤�ɂ��v���܂��B
�l�b�g�Ō�����������ł́A�P�j�ƂQ�j�̈Ⴂ�m�ɂ�������ɂ��ǂ蒅���Ȃ������̂ł����A�p��̎g�������݂����Ȃ��͈̂�ʓI�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
�܂��APC���g�����I�[�f�B�I�ƈ���Ɍ����Ă��A�f�W�^���f�[�^�[�̈����Ɋ��ʂ���̕��@������悤�Ɏv���܂����A�F����́A�ǂ̂悤�ɕ��ށ���������Ă���̂ł��傤���H
�g�����ČN�h�ɂȂ��Ă��܂��܂����A���e�͂��������܂��E�E�E�B
�����ԍ��F12013511
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂�
����̋^��_�́A���Ȃʼn����������܂����B
���������������܂����B
�uNet Audio�v�Ƃ������t�ŁA�̌n������Ă����ł��ˁB
���Q�l�܂łɁ�
http://nekosannooheya.cocolog-nifty.com/daiichimusen/2010/09/netaudio-55ee.html
�����ԍ��F12017948
![]() 1�_
1�_
2010/10/06 10:03�i1�N�ȏ�O�j
��H�̃E�T�M����A���Љ�̃l�R����̃y�[�W�͕�����₷���̂ŊȒP�ɓǂ߂܂����B
�����̏ꍇ�́A�u��������̂b�c���_���{�[���ɓ���āA�b�c���b�N�������v�̂��B��̓��@�ł��B�c�`�b�͎����Ă���̂Łi���[�����h��UA-25EX�j�A�b�c�����b�s���O���ĕ����Ă݂܂��B�����l�R����̕łɂ���悤�ɃJ�[�l���~�L�T�[��������邽�߂̃\�t�gfoober2000������Ƃ���܂��B
�����͂n�r���h�t�a�t�m�s�t�h�݂̂ɂ��Ă���̂ŁA�ǂȂ���UBUNTU_10.04�ł��J�[�l���~�L�T�[������ł��邩�ǂ����A�����Ă��������B�����ł����ׂĂ݂܂��B
���l�b�g�I�[�f�B�I���������͂��C���o�Ă��܂����B
�����ԍ��F12018425
![]() 1�_
1�_
2010/10/06 10:23�i1�N�ȏ�O�j
"ubuntu"�ł�ASIO�ł͂Ȃ��A���A���^�C���E�J�[�l���Ƃ����\�t�g������悢�݂����ł��B
�����ԍ��F12018480
![]() 1�_
1�_
������
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
OS���E�C���h�E�Y�Ȃ�AUSB����J�[�l��������������i���̃f�W�^���f�[�^�[�����o���A�N�Z�T���[�Ƃ��āA
���ڂ��Ă�����̂�����܂��B
zionote Co.,Ltd.�́uM2TECH Hiface Evo�v�Ƃ���USB-DDC�ł��B
http://www.zionote.com/m2tech/evo.html
������ɂ��Ă��ACD�ɕς��f�W�^���v���[���[�Ƃ��āA���ꂩ���NetAudio������킯�ɂ͂����܂���ˁB
���������ł͂Ȃ��A��������܂���B
���Ƃł��ACD�Ձ�CDP�̓��r���O�E�I�[�f�B�I����͕Еt��������ŁA���C�A�E�g���I�[�f�B�I�Ƃ̕t�����������݂Ȃ����āA
����́A�l�b�g���[�N�E�I�[�f�B�I���S�ɃV�t�g���n�߂Ă��܂��B
���R�[�h��CD��SACD�́A������j�T�K�̉����Ƃ��āA�Z�J���h�V�X�e���ŗV�ԁB
���C���̃��r���O�ł́ANetAudio��p�����s���A�I�[�f�B�I���n�f�W/BS/�u���[���C����AV�G���^�[�e�C�����g��V��ł����B
����ȍ\�z�𗧂ĂĂ��܂��B
�����ԍ��F12019746
![]() 1�_
1�_
2010/10/06 22:06�i1�N�ȏ�O�j
����������AWindows�͎g���Ă��Ȃ���Ubuntu�Ƃ����n�r(Linux�̈��)�ł��B
���[�e���V�[�̒Z���J�[�l�������邽�߁A���y�p�̃J�[�l��-rt(ubuntu-studio)���C���X�g�[�����܂����B�������t���[�ł��BWindows�Ȃ�ASIO4ALL�̃C���X�g�[���ɂȂ�ł��傤���ALinux�ł̓J�[�l�����܂邲�Ǝ��ւ��Ă��܂��܂��B
Generic�ȃJ�[�l���Ɣ�r����ƁA���|�I�ɈႢ�܂���I�I�@Generic�ȃJ�[�l���ł̓U���U�����������ŁA�����ɂ����F�͂o�b���y�Ƃ��������ł��肵�Ă܂������A�J�[�l��-rt�ł́A
���������������������悤�Ƀ��A���Ń_�C�i�~�b�N��
�ɂȂ�A���ʂ̂b�c�v���[���̉��ɋ߂Â��܂����B���≺��Ȃb�c�v���[���ȏ�̉����ł��B���܂܂ł̂o�b���y�Ƃ����̂́A�n�r�̊�{�̂Ƃ���Œx�����N����A�s�v�Ȏ��Ԃ̂��ꂪ�������Ă����̂ł��ˁB
����ň�Ԃ̃{�g���l�b�N��˔j�����̂ŁA���Ƃ̓��b�s���O���邢�͔z�M�\�t�g�̍w�������āA�W�����W�����������ƂɂȂ�܂��B���܂��Ă���b�c��A���l�߂ɂȁ[��I
�����āA���̑傫�ȃX�e�b�v�̓l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�B����͂����Ɛ�I
����`�r�b�N�����܂����B
�����ԍ��F12020949
![]() 1�_
1�_
2010/10/06 22:32�i1�N�ȏ�O�j
�������~�j�R���|����{�i�I�[�f�B�I�ɂȂ������炢�̕ω��Ȃ̂ŁA�ǂȂ����ڂ������̐��������肢���܂��B
�����ԍ��F12021129
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A��H�̃E�T�M����A�����́B
����MAC�Ȃ̂ł���l�Ƃ�����Ⴂ�܂����A������Řb��Ȃ̂́uAmarra�v�ł��B
�uAmarra�v���̂͂��������̂��炠������ł���7���ɐV���@�[�W�����������[�X����܂��āA
�t���E�R���|�[�l���g���{���@�[�W��������z�Ŕ̔������悤�ɂȂ����̂ʼn�Ђœ������܂����B
http://startlab.co.jp/proaudio/amarra.html
�G���g���[�E�N���X��CDP�Ɠ����l�ȉ��i�ł���iTunes���o���Ƃ͉_�D�̍��ł��B
MAC�ł����\�t�g������܂����i�����i�ł����炻���������y�͂��Ȃ��ł��傤���A
���l�����������w���������Ǝv�킳���قlj����ʂł̗D�ʐ��������܂������A
�u�f�W�^���E�f�[�^�����特�͕ς�Ȃ��v�Ƃ͂�͂茾����Ȃ��ƒɊ����܂����B
�J�������̂�SonicSolutions�̌n���ЂƂ����̂����S���L��ł��B
�}�X�^�����O�E�c�[���ł͒�]�̂����ЂŌl�I��ADC�n�[�h�͖�����SonicSolutions��������܂���B
�uAmarra�v�͂ǂ��炩�Ŏ����ł���Ƃ��낪����܂������x�`�F�b�N���Ă݂ĉ������B
����l��MAC�����~�����Ȃ��Ă��܂���������܂����B
�����ԍ��F12021236
![]() 0�_
0�_
2010/10/06 23:02�i1�N�ȏ�O�j
Redfodera����A�Ȃ�قǃ~���[�W�b�N�E�v���C���[�ʼn����Ⴂ�܂����H���ł��ꏏ�Ǝv���Ă��܂����B
Ubuntu_Studio�ł�"Totem"���W���ɂȂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F12021311
![]() 1�_
1�_
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061201/255561/
��OS�ɂ��CD-R�̉����̎���������Ď����Ă݂��̂ł����A��������CD-R��OS�Ō��\�����ς��������L��������܂��B
�������̂�WINDOS XP��ME�ł����AME�̕����L�ѐL�є������ǂ����C�ȉ���XP���Ƃ�����Ƌ����ŋl�܂��ĕ�������PC�I�[�f�B�I��OS���d�v�ȗv�f�ŁA�Đ��\�t�g�ɂ���Ă����̈Ⴂ������A�X�ɏ������肻���ł��B
PC�̓m�C�Y�̑��A��CD-P�Ɣ�ׂė�镨�ƍl���Ă��܂������A�S��ƂƂĂ��������Ŗ肻���Ŏ����Ă݂����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12021730
![]() 1�_
1�_
2010/10/07 07:36�i1�N�ȏ�O�j
����������ɂ��́B������n�r�ɂ��Ⴂ�̍ۂɁA
http://nekosannooheya.cocolog-nifty.com/daiichimusen/2010/09/netaudiousbdd-b.html
�����ɏ�����Ă���悤�ɁuWindows�����������́A���y�A����A�Q�[�������ł͂���܂���B�N�����A�I�����A�x�����Ȃǂ̃V�X�e����������Ȃ���Ȃ�܂���B�������A�������X�̃A�v���P�[�V�����\�t�g���܂��Ȃ��Ă����̂ł́A�p�\�R���ɂƂ��đ傫�ȕ��S�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�ݒ�����G�ɂȂ�܂��B�����ŁA�������ꊇ���ĊǗ�����̂��u�J�[�l���~�L�T�[�v�ł��B���������A�p�\�R���œ��Ɉӎ����邱�ƂȂ��������y����ł�����̂͂��̂������Ȃ̂ł��B�������A�����܂ł��u�J�[�l���~�L�T�[�v��Windows�ɂ����鉹���Đ��̓K������}���Đ݂���ꂽ���̂ł�����A�����I�ȍl���͂��܂肳��Ă���܂���B�v
�J�[�l���~�L�T�[����������i���Ƃ��܂����ł��傤���H�Ƃ�ꂽ��ł̔�r�Ȃ�u�@�\�����Ȃ��Â��n�r�̂ق��������ǂ��v�Ƃ����̂͏\���[���ł�����̂ł��B
�����ԍ��F12022561
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́`��@�~���[�W�b�N�E�v���[���[�̃A�}�[���ɋ����[�X�ł��B
�����ɏ������܂����B�̖w�ǂ�Win�@���p�ł��傤����AMac�@�̉�������̏��͏��Ȃ��M�d�ł��B
�A�}�[�����p�ŁA�������オ���\�L��ƃl�b�g��ŎU�����܂��̂ŁA�C�ɂ͂Ȃ��Ă��܂������E�E�E�B
������~�j�Ŗ�S���A�t���o�[�W�����Ŗ�W���́A��̑�����ł��܂��܂��ˁ���
�ŏ��̕~�����A���ɂ͍��߂��܂��B�E�E�E��ł������͗~�����Ȃ��B
���A�J�L�R�����Ⴂ�܂����B����B�ǂ����X���[���Ă��������܂��B
�����ԍ��F12023311
![]() 2�_
2�_
2010/10/07 12:45�i1�N�ȏ�O�j
�l�b�g���[�N�v���[���̌f�����A�o�b�\�t�g�̘b���ɃV�t�g���Ă��܂��āA�X���傳�f�C���H�@
�O���A���y���M������A�`�u�ɓ������ꂽ�n�r�hUbuntu�|studio�h�Ȃ�t���[��MS-DOS�@�ɃC���X�g�[���ł��܂���B�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X(UA-25EX)���h���C�o����Ȃ��Ă���Ȃ��F�����Ă���܂����B
�����ԍ��F12023384
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A�J�L�R���肪�Ƃ��������܂��B
���X���傳�܁A��|������ė��Đ\�������܂���B
���[�����h(UA-25EX)���Љ�肪�Ƃ��������܂��A�����Mac�ł�������ł��ˁO�O
�����ɂ��A��apogee-duet���g�p���Ă���A���K�I���R����������̂�����O/I��
�ύX��\�肵�Ă���܂���B
OS��Ubuntu��Mac�ɓ����\��Ȃ��ł��BWin7�͔����Ă܂���VMware�����w���ς݂ł��B
�ł��A����肪�t������������邩�ǂ������킩��܂���B����
�D�_�s�f�Ȏ��ɖ����͂���̂��H�@�����I
�����ԍ��F12023793
![]() 0�_
0�_
������
�}�炸���H���S�Ҍ����̃n�i�V���W�J���Ă��āA�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��i��
�uUSB�n�v��NetAudio�̏ꍇ�APC���珃���ȉ��y�f�[�^�[�����o���ɂ́A�J�[�l������̂��߂ɁA��p�\�t�g�̓�����ݒ�̕ύX���K�v�Ȃ�ł��ˁB
�������A�J�[�l����PC�ʂɎg���ɂ͕K�v�ȋ@�\�ł�����A�u�I�[�f�B�I��pPC�v�łȂ�����A�C���C���ƕs�ւɂȂ肻���ł��B
OS�̃A�b�v�f�[�g�ɁA�}�C�i�[�ȃt���[�\�t�g�����Ă����邩�ǂ������s���v�f�ɂȂ肻���ł��B
DLNA�@�\���g�����u�l�b�g���[�N�n�v�Ȃ�APC�������̃T�[�o�[�Ƃ��Ď�y�Ɏg�������Ȃ̂ŁA���^�N�V�́A��������ʂ�Nj����Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�E�E�E���̎G�����P�N���炢�͍w�ǂ��Ȃ��ƁA�m���̌n����ꂻ��������܂���ˁE�E�E(��
�����ԍ��F12024508
![]() 1�_
1�_
CD�v���[���[ > SONY > NAC-HD1
�O���HDD�������o���܂����̂ŕ��܂��B
�n�[�h�f�B�X�N�́ASeagate Barracuda 7200.9(ST3250824A) 250GB ���� HITACHI CinemaStar(HCP725050GLAT80) 500GB �Ɍ����ł��B
��N�قǑO�Ƀg���C���܂�����Linux�p�[�e�B�V�����̓R�s�[�������̂�MBR�̐ݒ肪�o���Ȃ��������߂��N���o�������߂Ă��܂����B����A�h�n�[�h�f�B�X�N���ȒP�R�s�[�h�Ƃ����u�k�a�R�s�[���[�N�X�P�P�i���ʗD�ҔŁj�v�̃o�b�N�A�b�v���[�e�B���e�B�\�t�g�������hMBR�̃R�s�[�h�Ƃ������̂Łh������D�D�h�Ǝv���Ďg���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�A���A���ۂ�WEB�Œ���Ă���CD�N���́uLB �R�s�[ ���[�N�X11�@�N��CD�iLinux/Dos�Łj�쐬�v���O�����@build 10868�v���g���܂����B����CD�N���łł���WindowsPE�ł͉��̂��R�s�[�̓r���Ŏ~�܂��Ă��܂��܂����B�i�Ǝv���܂��B�m���P���Ԉȏ�҂��܂����������ω����܂���ł����j�B�{�̂��g���Ă��܂��s�����͒肩�ł͂���܂���B
IDE�C���^�[�t�F�[�X��2���HDD���W�����p�[�s����ύX���}�X�^�[�ƃX���[�u�Őڑ����܂��B
CD(Linux/Dos��) ���N���B�u�n�[�h�f�B�X�N�̃R�s�[�v��I������ƃf�B�t�H���g�Ńf�[�^�̈悪�g������܂��B���̎��I�v�V�����Œlj������̂́u�f�B�X�N�R�s�[�̌�ASID(�Z�L�����e�B���ʎq)�̕ύX���s���v�ł��BSID�̕ύX���K�v���ǂ���������܂���ł������`�F�b�N�����܂����B�R�s�[���Ԃ͖�X���Ԃł��B�b��25MB�ʂ̓]�����x�ł���IDE�C���^�[�t�F�[�X��ʂɏo����Δ{�̑��x�ł̃R�s�[�ɂȂ�܂��B�T���Ԋu���炢�Ői�s���X�V����܂��̂ōQ�ĂȂ��ʼn������B�Ō�Ɋm���g�u�[�g���[�_�[�̐ݒ�Ɏ��s���܂����h�Ƃ̃��b�Z�[�W���������̂ō�����_�����Ǝv���܂������_�����ƂŐڑ��������Ƃ��܂��N���ł��܂����B�i�W�����p�[�s����SELECTABLE�ɖ߂��ĉ������j
�g�p���A�g�V�X�e�����s����ł��B�ݒ��ύX���ċN�����܂��h�Ƃ̕\�������ꂽ�̂Ŏv�����āu�V�X�e���������v��HDD�̏��������s��USB�n�[�h�f�B�X�N�Ɏ擾�����o�b�N�A�b�v���畜�����s���܂����i��12���ԁj�B���̌�A10�����炢CD�̎�荞�ݓ�1�T�Ԏg���܂��������肵�Ă��܂��BLPCM(�k)�ł�CD��荞�݂ł���430���Ԃ��\�ł��B�{���ɂ��ꂵ���ł��B
�g���C�͂��ꂮ������ȐӔC�ł��肢���܂��ˁB�o�b�N�A�b�v���擾���Ă���n�߂ĉ������B
�ȏ�
![]() 4�_
4�_
����������l
��σv���t�F�V���i���Z�����Ă���܂��B���������đ҂��Ă��܂����I�I
������PC�͑f�l�œ��e�������ł��܂���B�����Ή����f���炵���ł��ˁB
NAC-HD1�̋@�\�͑�ϗD�ꕨ�ʼn��̑�e�ʃV���[�Y�������Ȃ��̂�
�킩��܂���B��������Ɣ��f�d���Ȃ��ł��B���������Ď��ȐӔC��
�e�Ղɑ�e��HDD�ɕύX�\�@��҂ݏo�����z���C�g�E�i�C�g���Ȃ킿
�u����������v�o��I�I
���āA����HD1�Q�T�OG��HDD�e�ʑ���Ȃ��A���ݖ��t�߂��ł��B
����A�f�l�ł�������₷��HDD�����菇�������Ă���������
���肪�����̂ł����I�I(500G,1RB���̌����j
�E�K�v�\�t�g�i�t���[�A�L�����́j
�E�K�v�n�[�h�Əڍ����ڑ��i���E�n�[�h���́A���j
�E�ڍ菇�i�f�l�ɂ��킩��菇:���߂čw������PC�戵���������x���j
�E���ӎ���
�ȏ�A���̂���NAC-HD1�̕t�����l�g��̂��߂ɂ�
��ςł�����낵�����肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F11894232
![]() 0�_
0�_
�\�j�[�̂m�`�b�|�g�c�P�̂g�c�c���������܂����B�E�G�X�^���f�W�^���̂Q�s�a�ł��B������c�莞�ԂQ�V�O�O���ԂƂłĂ��܂��B���ۂɂ����邩�ǂ����킩��܂��A���̂Ƃ��됳��ɓ��삵�Ă��܂��B
���ȐӔC�ōs���Ă��������B��ؐӔC�͕����܂���B
�K�v�ȃn�[�h�͂v�h�m�c�n�v�r�̂o�b�ƃE�G�X�^���f�W�^���̂Q�s�a�̂g�c�c�D
�r�`�m�v�`�@�r�t�o�o�k�x�̃V���A���`�s�`�p�h�c�d�ϊ��A�_�v�^�B�W�����p�[�Q�B
�\�t�g�͂`�b�q�n�m�h�r�@�s�q�t�d�h�l�`�f�d�@�g�n�l�d�@�Q�O�P�O�B�j�m�n�o�o�h�w�̍ŐV�ŁB
�o�b�̕�����₷���Ƃ���ɂr�n�m�x�Ƃ����z���_�[����肱����r�n�m�x�Ƃ������L�z���_�[�ɂ��܂��B
�͂������g�c�c���}�X�^�[�ɂ��Ăo�b�Ɏ��t���`�b�q�n�m�h�r�@�s�q�t�d�h�l�`�f�d�@�g�n�l�d�@�Q�O�P�O�Ńh���C�u�̃o�b�N�A�b�v���Ƃ�܂��B
�o�b�ɐV�����g�c�c�����t���`�b�q�n�m�h�r�@�s�q�t�d�h�l�`�f�d�@�g�n�l�d�@�Q�O�P�O�Ńh���C�u�̕��������܂��B
�j�m�n�o�o�h�w�̍ŐV�łło�b���N�����f�o�`�s�d�c�Ƃ����\�t�g�Ńf�[�^�[�̈���L���܂��B�j�m�n�o�o�h�w�̍ŐV�ł͂k�h�m�t�w�̃\�t�g�Ȃ̂łȂ��Ȃ����܂������܂��A���s���Ă����̃o�b�N�A�b�v������̂ł�������Ă��Ȃ����Ă��������B����������g���C���Ăł��܂����B�Y��Ă��܂������A��������Ă���b�c�h���C�u�̃W�����p�[���X���[�v�ɂ��Ă��������B
�����ԍ��F12519044
![]() 2�_
2�_
asiaasiaasia����
�҂��ɑ҂����V�X�e�����p�g��̏���ϑf���炵���Ǝv���܂��B�Ƃ���Ŏ��̓n�[�h�A�V�X�e���ύX�\�t�g�Ȃǂ̃I�y���[�V�����������Ƃ���܂���B�\����܂��f�l�ł��Ή��ł���
�菇�����������肢�����܂��B�����A�菇�A�s���������̎����낵�����肢�������܂��B
���ۗLPC�O�@Vista SP2�AHDD:�PTB�iRAID1)�A�������[�F�SGB �A�����R�D�T�^�x�C�F3��
�@�@�@�@�@�@�@�@NEC Lui���f��M
������Q��
�@SATA�ϊ��A�_�v�^�̕i���ƁA�ǂ��Ɛڑ����@�i�Ȃ��K�v�FHD1-HDD��IDE?�j�H
�A�W�����p�[2���ǂ��ƁA�ǂ��ɁA�ǂ�Ȏ菇�ŋ�̓I�ڑ��@�iPC?)
�Bacronishome2010�͍w���i��6K�~�j�H
�CKNOPPIX(GPATED�����j��CD�ɖ����_�E�����[�h�H
���菇Q>
�DSATA�ϊ��A�_�v�^�[��HD1-HDD�ɐڑ��APC-SATA�[�q�ڑ��H
�EPC��D:�̈�i250GB�ȏ�j�Ƀ\�j�[�z���_�쐬�BHDI-HDD���}�X�^�[�Ƃ�
��̓I�ɂǂ̂悤�ɂ��邩�H�@������ACRONIS�\�t�g�N����HD1-HDD����t�H���_�Ƀo�b�N�A�b�v�H
�F���ɐVHDD(�E�G�X�^���QTB)�̕i���Ƌ�̓I���t���@�iPC�̂ǂ��ɁA�ǂ̂悤�Ɂj�H
�GKNOPPI���N����GPATED�ŋ�̓I�̈�g��@�Ə�����Ԃ��A�ǂ����ǂ̂��炢�̒l�Ɋg�傷��̂��H
�HLINUX�̂��߂Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ��Ƃ��邪�A�ǂ�Ȏ����s���e�Ɛ����菇�@�H
�H���Ƃ���A���Ă�CD�h���C�u�W�����p�[���X���[�u�ɂ���Ƃ��邪�A��̓I�ɂǂ����ǂ�����̂��H�iHD1?)�܂��Ȃ�����̂��H
�ȏ�A�E�������킩��ʎ҂̋Y���\����܂���B
�I�[�f�B�I���V�X�e���~�����asiaasiaasia�����낵�����肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F12528732
![]() 0�_
0�_
�܂��ŏ��Ɏ��ȐӔC�ōs���ĉ������B
�o�b���N�������Ƃ��a�h�n�r��ʂ��o�܂����B
�h�c�d�̃C���^�[�t�F�C�X�͂��Ă��܂����B������m�F����g��ʼn������B
�@SATA�ϊ��A�_�v�^�̕i���ƁA�ǂ��Ɛڑ����@�i�Ȃ��K�v�FHD1-HDD��IDE?�j�H
NAC-HD1���h�c�d�Ȃ̂ŃV���A���`�s�`�̂g�c�c�����t����̂ɂ̓A�_�v�^�[������܂��B
�r�`�m�v�`�@�r�t�o�o�k�x�̃V���A���`�s�`�p�h�c�d�ϊ��A�_�v�^�Ō������ĉ������B�o�b�p�[�c�V���b�v�ɂ���Ǝv���܂��B�ʔ̂Ŕ����܂����B�Q�`�R��~���炢�B�h�c�d�̂g�c�c����ɓ������܂���B�Q�s�a�̂g�c�c�Ƃh�c�d�P�[�u���̊ԂɎ��t���܂��B
�A�W�����p�[2���ǂ��ƁA�ǂ��ɁA�ǂ�Ȏ菇�ŋ�̓I�ڑ��@�iPC?)
�E�G�X�^���f�W�^���̂Q�s�a�̂g�c�c�͂V�ԂƂW�ԃs�����W�����p�[�łȂ��K�v������܂��B�V���A���`�s�`�p�h�c�d�ϊ��A�_�v�^�����t�����Q�s�a�̂g�c�c�͂h�c�d�̃}�X�^�[�ɂȂ�܂��̂ŁANAC-HD1�̌�������Ă���b�c�h���C�u���A�X���[�v�ɂ���K�v������܂��B�b�c�h���C�u�̐K�ɃX���[�v�Ə����Ă���܂��B
�Bacronishome2010�͍w���i��6K�~�j�H
�x�d�r
�CKNOPPIX(GPATED�����j��CD�ɖ����_�E�����[�h�H
�o�b�̂킩��₷���Ƃ���ɂh�r�n�C���[�W���_�E�����[�h���Ăc�u�c�Ƀ��C�e�B�C���O�\�t�g�ŏĂ��܂��B
�DSATA�ϊ��A�_�v�^�[��HD1-HDD�ɐڑ��APC-SATA�[�q�ڑ��H
��L�Q�ƁB
�EPC��D:�̈�i250GB�ȏ�j�Ƀ\�j�[�z���_�쐬�BHDI-HDD���}�X�^�[�Ƃ�
��̓I�ɂǂ̂悤�ɂ��邩�H�@������ACRONIS�\�t�g�N����HD1-HDD����t�H���_�Ƀo�b�N�A�b�v�H
�f�X�N�g�b�v�ʼnE�N���b�N�V�K�쐬�z���_�[���O�r�n�m�x�ł����Ǝv���܂�
�o�b�ɂh�c�d�̃C���^�[�t�F�C�X�͂��Ă��܂����B�����ɂh�c�d�P�[�u����NAC-HD1�̂g�c�c���Ȃ��āi�}�X�^�[�ɂ��܂��j������ACRONIS�\�t�g�N����HD1��HDD����t�H���_�Ƀo�b�N�A�b�v���܂��B
�F���ɐVHDD(�E�G�X�^���QTB)�̕i���Ƌ�̓I���t���@�iPC�̂ǂ��ɁA�ǂ̂悤�Ɂj�H
�E�G�X�^���f�W�^���@�Q�s�a�@�g�c�c�Ō������ĉ������B�W�O�O�O�~���炢�ło�b�V���b�v�Œʔ̂Ŕ����܂��B
�GKNOPPI���N����GPATED�ŋ�̓I�̈�g��@�Ə�����Ԃ��A�ǂ����ǂ̂��炢�̒l�Ɋg�傷��̂��H
��ʂň�ԉE�̗̈�̒[���܂�ň�ԉE�܂Ŋg�����܂��B���ɂ��̗̈�̍��[���܂�łT�O�f�a���炢�܂ŏk�����܂��B���ɉE����Q�Ԗڂ̗̈�̉E�[���܂�ʼnE�����ς��܂łɊg�����ۗ����Ă��鑀������s������N���b�N���܂��B�P�D�W�s�a���炢�ɂȂ�܂��B���������Ƌ��낵���قǎ��Ԃ�������܂��B
�HLINUX�̂��߂Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ��Ƃ��邪�A�ǂ�Ȏ����s���e�Ɛ����菇�@�H
�k�h�m�t�w�͗E�m������Ă���̂ŁA�Ȃ��Ȃ����܂��s���Ȃ����Ƃ�����܂��B�ċN��������ŏ�������Ȃ������肵�܂����B
�H���Ƃ���A���Ă�CD�h���C�u�W�����p�[���X���[�u�ɂ���Ƃ��邪�A��̓I�ɂǂ����ǂ�����̂��H�iHD1?)�܂��Ȃ�����̂��H
�A�_�v�^�[��t����ƐV�����g�c�c���}�X�^�[�ɂȂ�܂��B���̂��߂b�c�h���C�u���X���[�v�ɂ��܂��B�b�c�h���C�u�̐K�̃X���[�v�Ə������Ƃ���ɃW�����p�[���������݂܂��B
�����ԍ��F12535748
![]() 1�_
1�_
asiaasiaasia����@
�����̏�����L��������܂��B�Ƃ�킯�E�������킩��Ȃ��҂ւ̂��e�ȉ�
���߂Ċ��ӂ������܂��B��{���s�����̂��ߎ��Ԃ�������Ԏ����x��Đ\����܂���B
�ˑR�Ƃ��ĕ��s���ł܂���������܂Ŋ��Ԃ������肻���ł��B���J�Ȏ菇�v���Z�X�ł킩�������Ƌy�ю��ⓙ���ēx�����Ă��������܂��B���w�����肢�\���グ�܂��B
�P�D��{�ۑ�
�E������PC(NEC �o�����[�X�^�[Lui���f���F2009�N���ACore2QuadCPU2.8Ghz vistaUltimate)
�@��3.5�^�x�C���ڂ�PC�{�[�h�C���^�[�t�F�[�X��SATA��������܂���B�iIDE�Ȃ��j
�EHDD�ۂ��ƃo�b�N�A�b�v�\�t�gRoxio�����ڍς݁B�����ACRONIS�\�t�g�̑��藘�p��
�E������PCHDD(RAID1�ݒ�F�P�s�a�j�̐ݒ�ύX�Ƃ̃g���u���͔������Ȃ����B�Ō��O�����B
�Q�D�n�[�h�ڑ��E�ݒ�ʂ̗ސ�
�@HD1-HDD(���j��IDE-SATA�ϊ����PC��SATA�ڑ�
�A�VW-HDD(2T)�͒���PC��SATA�ɃP�[�u���ڑ�
�R�����g�F�ꋓ�ɇ@����A�Ɋۂ��ƃo�b�N�A�b�v�i�\�j�[�t�@�C���͍쐬���Ȃ��B
�B�VHDD(2T)���p�[�e�[�V�����ύX��AHD1�̂�IDC-SATA�ϊ����t��HD1�ɓ��ځB�i�V�|�U�ԃW�����p�[�j�BHD1��CD�h���C�u���X���[�u�ɃW�����p�[���{�B
�R�D�\�t�g�����y�уf�[�^�ڍs�菇�i����j
�C�@�@�A�����{��roxio�ۂ��ƃo�b�N�A�A�b�v�Ň@�f�[�^���A�Ɋۂ��ƃo�b�N�A�A�b�v����B
�@�@NG�ł����Acronis Home�w�������{�B���̔��f�ł悢���H
�D�@�ۂ��ƃf�[�^�ڍs������������A�j�m�n�o�o�h�[�b�c��CD�h���C�u�ɑ}������B
Q1:�����\���̃p�[�e�[�V�����l�͏����@�����e�l�Ȃ̂��H�@
Q2:�����I�Ƀp�[�e�[�V�����ύX��ʂ��o��̂��H
Q3�F�A�̐VHDD�͂ǂ��̗l�ɕ\������邩�H�@���̎��d�vPC-����HDD�h���C�u���\�������̂��H�܂�������Ԉ���ĕύX�����郊�X�N�͂Ȃɂ��H
Q4:vista�Ńp�[�e�[�V�����ύX��iex.C: D:��C:�g������ꍇ�j,�b�F�g���l����́A���̌�D:���k�������Ǝv���Ă�����LInux�̏ꍇ�͈قȂ�����@���H
Q5:���������ăp�e�[�V�����ύX���������ƔF������̂��H
���̕ӂ��Ƃ�Ɩ��n�ł킩��܂���ł����B
�E�@�D�����������VHDD(2T)��sata-IDE�ϊ�������t��HD1�ɓ��ڂ���B
�FHDD�W�����p�[���{�̓p�[�e�[�V�����ύX��ɂ���̂�?
Q6:�ϊ��핪�̎������傫���Ȃ�HD1�ɓ��ډ\�Ȃ̂��H
�ȏ�A���w�������߂��Ȃ��珟��Ȏ菇�������Ă݂܂����B���낢�뗝�R�܂߂��R�����g��ύX�菇�����w����낵�����肢�\���グ�܂��B
HD1�̊�����PC�V�X�e���̓��e�����ɑ�ϕ��ɂȂ�܂��B�{���Ȃ�ʂ̃X�����ɕ����ׂ�������������܂���B���̃N�`�R�~���p����Ă�������������\����܂���B
�����ԍ��F12541983
![]() 1�_
1�_
�P�D��{�ۑ�
�E������PC(NEC �o�����[�X�^�[Lui���f���F2009�N���ACore2QuadCPU2.8Ghz vistaUltimate)
�@��3.5�^�x�C���ڂ�PC�{�[�h�C���^�[�t�F�[�X��SATA��������܂���B�iIDE�Ȃ��j
�����̂o�b�͎���Ȃ̂ŁA�h�c�d�����Ă���܂��B�Ȃ̂�NAC-HD1������o�����g�c�c�ɃA�_�v�^�[�����t���āA�o�b�̃V���A���`�s�`�̐M�����Ɠd���ɂȂ���ł���Ǝv���܂����A�����ĂȂ��̂ŁA���ȐӔC�ł��肢���܂��B
�EHDD�ۂ��ƃo�b�N�A�b�v�\�t�gRoxio�����ڍς݁B�����ACRONIS�\�t�g�̑��藘�p��
���o�b�N�A�b�v�\�t�gRoxio�͂ǂ�ȃ\�t�g�Ȃ̂��킩��܂���̂ŁB�������܂���B�o�b�N�A�b�v�\�t�g�@�t���[�Ō������Ă݂Ă��������B����݂����ł���B�k�h�m�t�w�̂f�o�q�s�d�c�̑�����p�[�e�B�V��������@�t���[�\�t�g�Ō������Ă݂Ă��������B�v�h�m�c�n�v�r�ł�����݂����ł��B
�E������PCHDD(RAID1�ݒ�F�P�s�a�j�̐ݒ�ύX�Ƃ̃g���u���͔������Ȃ����B�Ō��O�����B
������͂킩��܂���B���ȐӔC�ł��肢���܂��B
�Q�D�n�[�h�ڑ��E�ݒ�ʂ̗ސ�
�@HD1-HDD(���j��IDE-SATA�ϊ����PC��SATA�ڑ�
����L�Q�ƁB
�A�VW-HDD(2T)�͒���PC��SATA�ɃP�[�u���ڑ�
���x�d�r
�R�����g�F�ꋓ�ɇ@����A�Ɋۂ��ƃo�b�N�A�b�v�i�\�j�[�t�@�C���͍쐬���Ȃ��B
���܂����g�c�c���o�b�ɂȂ��ŁA�o�b�N�A�b�v�\�t�g�ŕ�����Ղ����O��t���o�b�̂g�c�c��ɕۑ����܂��B
���ɐV�g�c�c���Ȃ��ŁA�o�b�N�A�b�v�\�t�g�ŕ������܂��B
�g�c�c���Ȃ�����A�͂�����������肷��Ƃ��͂o�b�̓d������Ă��������ˁB
�B�VHDD(2T)���p�[�e�[�V�����ύX��AHD1�̂�IDC-SATA�ϊ����t��HD1�ɓ��ځB�i�V�|�U�ԃW�����p�[�j�BHD1��CD�h���C�u���X���[�u�ɃW�����p�[���{�B
���V�g�c�c�ɕϊ�������t���g�ݍ��݂܂��B�W�����p�[�͂V�|�W�Ԃł��B
�R�D�\�t�g�����y�уf�[�^�ڍs�菇�i����j
�C�@�@�A�����{��roxio�ۂ��ƃo�b�N�A�A�b�v�Ň@�f�[�^���A�Ɋۂ��ƃo�b�N�A�A�b�v����B
�@�@NG�ł����Acronis Home�w�������{�B���̔��f�ł悢���H
���܂��t���[�\�t�g��T���Ă݂�����Ǝv���܂��B
�D�@�ۂ��ƃf�[�^�ڍs������������A�j�m�n�o�o�h�[�b�c��CD�h���C�u�ɑ}������B
���a�h�n�r�ōŏ��ɂb�c���N������悤�ݒ肵�܂��B�łȂ��Ƃv�h�m�c�n�v�r���N�����܂��B
Q1:�����\���̃p�[�e�[�V�����l�͏����@�����e�l�Ȃ̂��H
��NAC-HD1�Ɠ������e�̂g�c�c���ł��܂��B�@
Q2:�����I�Ƀp�[�e�[�V�����ύX��ʂ��o��̂��H
���k�h�l�m�t�w���N��������ݒ聄�f�o�`�s�d�c�Ɛi�݂܂��B
�o�b�ɂȂ����Ă��邷�ׂĂ̂g�c�c���łĂ��܂��̂ŁA�ԈႦ�Ȃ��悤�ɁB
Q3�F�A�̐VHDD�͂ǂ��̗l�ɕ\������邩�H�@���̎��d�vPC-����HDD�h���C�u���\�������̂��H�܂�������Ԉ���ĕύX�����郊�X�N�͂Ȃɂ��H
��NAC-HD1�͂k�h�m�t�w�Ȃ̂łق��̂g�c�c�Ƃ͖��炩�ɈႤ�p�ɕ\������܂����A�ԈႦ�Ȃ��悤�ɁB�ق���L�Q�ƁB
Q4:vista�Ńp�[�e�[�V�����ύX��iex.C: D:��C:�g������ꍇ�j,�b�F�g���l����́A���̌�D:���k�������Ǝv���Ă�����LInux�̏ꍇ�͈قȂ�����@���H
��NAC-HD1�͂v�h�m�c�n�v�r�Ƃ͈�����\��������܂��B
Q5:���������ăp�e�[�V�����ύX���������ƔF������̂��H
���̕ӂ��Ƃ�Ɩ��n�ł킩��܂���ł����B
���ۗ�������������{������N���b�N�������Ɛ����Ԍ㊮�����܂����Ƃł܂��B
�E�@�D�����������VHDD(2T)��sata-IDE�ϊ�������t��HD1�ɓ��ڂ���B
���x�d�r
�FHDD�W�����p�[���{�̓p�[�e�[�V�����ύX��ɂ���̂�?
���ŏ�������Ă����܂��B
Q6:�ϊ��핪�̎������傫���Ȃ�HD1�ɓ��ډ\�Ȃ̂��H
�����肬����܂�܂��B
���ŏ��ɂ������܂������A�v�h�m�c�n�v�r�p�̃t���[�̃\�t�g��T���Ă�����������悤�Ɏv���Ȃ��B���͂��܂���ł������B�����Ă��܂���̂Ŏ��ȐӔC�ł��肢���܂��B
�����ԍ��F12544031
![]() 2�_
2�_
asiaasiaasia�������
A.V&PC�V�X�e���@���n�̓V�g�l
�����̃h�f�l�ւ̏ڂ����������Ɉ߂𒅂��Ȃ������n���̗��������L��������܂����B
���̐��E��o�c�ӎv����ɂ����K���Ă��炢�������̂ł��B���ۋ�����NO1���\�ł��傤�B
�f�l�̎��ɂ�����̑Ή����u�����Ă����悤�ȋC���������܂��B
�ēxasiaasiaasia��������m�F�A�����g���C�������Ǝv���Ă���܂��B
�������pPC�͍w����Q�N�ł���Ɗe��o�O��s���萫���痣�E�������ԂɂȂ�܂����B
�������������Ƃō���̂悤�ȓ��e�����{����̂ɁA���Ȃ�i�[�o�X�ɂȂ��Ă���܂��B
�]���ĉ����ƍׂ�������ɂȂ�܂����B
asiaasiaasia����̂��A�������܂��Ċ�{�I�ۑ肪�����Ă��āA���V�͑����܂����B
����T�d����_�Ɏ������Ă��������Ǝv���܂��B
�܂��܂������ɂ͎��Ԃ�������Ǝv���܂����A��������܂����炲�w����낵��
���肢�\���グ�܂��B���߂Č��\���グ�܂��B
�����ԍ��F12544238
![]() 0�_
0�_
��e��HDD�����������̊F�l
���悢��A��Q�R�OGB�Ɗ�HDD�ő�e�ʋ߂��ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�F�l�̂�������@���Q�l�Ƀg���C���o�債�܂������A�����f�X�N�g�b�vPC�̓������J�������߂ĂŁA�C���^�[�t�F�[�X�R�l�N�^�[���PC�{��HDD�ւ̏�Q���X�N���l����ƁA
�C�U���s���S�O���Ă��܂��B
�����Ŏ���ł����APC�����Ɋ���HDD���C���^�[�t�F�[�X�����ɁA�O������USB�C���^�[�t�F�[�X���Ŋ���HDD���쐬�����i�͂������܂���ł��傤���B
�i�lj��\�t�g���C���^�[�t�F�[�X�@��͂��܂�Ȃ��j
�����悤�ł�����A�����̕��䂩���э~������ŊF�l�̊���������i�Ŏ��{���邵������܂���ˁI�I�B
�Ō�̃_��������@��낵�����肢���肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F12939778
![]() 0�_
0�_
����������
asiaasiaasia����
�������߂łƂ��������܂��B
�����ȑO���狻�������肢���͎��݂悤�ƍl���Ă���܂������A�������ꂽ���҂̕��̎����ǂ݂܂��܂����킵�悤�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B
������
���������₳���Ē��������̂ł����A�h�o�C�X������ΗL��ł��B
�`�D�����g�c�c�͂P�s���Q�s��\�肵�Ă��܂����n�[�h�I�ɗe�ʂ��������Ƃ��Ă�
�@�@�ȑO������グ���Ă���\�t�g�ʂł̂S���Ȃ̐����̓N���A�[�ł���̂ł��傤���H
�@�@�g�c�c�ւ̎�荞�݂͊�{�S�ă��j�A�o�b�l�ł��B
�a�D�����p�̂g�c�c�́A�r�`�s�`���h�c�d�ϊ��A�_�v�^�����Ăr�`�s�`�h���C�u���g�p����
�@�@�g�c�P�����삷��Ǝv���邩�H
�b�D�����菇�Ƃ��āA�g�c�P�{���̃o�b�N�A�b�v�@�\�𗘗p���āA�g�c�P�̃f�[�^���o�b��
�@�@�o�b�N�A�b�v���Ăg�c�c�����O���A���̌�t�H�[�}�b�g���������p�̂g�c�c���g�c�P�Ɂ@�@���t���Ăo�b�Ƀo�b�N�A�b�v�����f�[�^���g�c�P�̕����@�\�Ō��ɖ߂��Ȃ����H
�c�D�����p�̂g�c�c�ɃZ�N�^�S�j�̐V�����^�C�v�̂g�c�c��p�����ꍇ�̃����b�g�f�����b�g�@�@�Ȃlj������C�Â��ɂȂ�܂����狳���Ă��������B
�ȏ�ł��B
�X�������肢���܂��B
�����ԍ��F13128441
![]() 0�_
0�_
���b�N�t�H�[������A
�������ł��B
> �`�D�����g�c�c�͂P�s���Q�s��\�肵�Ă��܂����n�[�h�I�ɗe�ʂ���������
> ���Ă��ȑO������グ���Ă���\�t�g�ʂł̂S���Ȃ̐����̓N���A�[
> �ł���̂ł��傤���H
> �g�c�c�ւ̎�荞�݂͊�{�S�ă��j�A�o�b�l�ł��B
4���Ȃ̐����͕ς��Ȃ����ł��B
�N���v�Z���Ă��܂�����CD1��=500MB20�ȂƂ���ƁA
1GB��CD2��40�ȁA1TB(1000GB)��CD2,000��40,000�ȂɂȂ�܂��B
�����1TB���傫��HDD�ɂ��Ă��Ӗ����Ȃ����ɂȂ�܂��B
> �a�D�����p�̂g�c�c�́A�r�`�s�`���h�c�d�ϊ��A�_�v�^�����Ăr�`�s�`
> �h���C�u���g�p���Ăg�c�P�����삷��Ǝv���邩�H
SATA�h���C�u�ւ̊������������̂ʼn\�ł��B
> �b�D�����菇�Ƃ��āA�g�c�P�{���̃o�b�N�A�b�v�@�\�𗘗p���āA�g�c�P
> �̃f�[�^���o�b�Ƀo�b�N�A�b�v���Ăg�c�c�����O���A���̌�t�H�[�}�b�g
> ���������p�̂g�c�c���g�c�P�Ɂ@�@���t���Ăo�b�Ƀo�b�N�A�b�v����
> �f�[�^���g�c�P�̕����@�\�Ō��ɖ߂��Ȃ����H
�h�t�H�[�}�b�g���������p�̂g�c�c�h�ł�HD1���N�����܂���B
�F�����J����Ă���̂͂��̓_�ł��B
HDD��linux��os���R�s�[������ŋN�����鎖�ɂȂ�܂��B
> �c�D�����p�̂g�c�c�ɃZ�N�^�S�j�̐V�����^�C�v�̂g�c�c��p�����ꍇ��
> �����b�g�f�����b�g�Ȃlj������C�Â��ɂȂ�܂����狳���Ă��������B
3TB��HDD�̎������Ă���̂ł��傤���`�D�̗��R�ɂ��Ӗ����Ȃ��ł����A
����HD1��OS�ł̓T�|�[�g���Ă���Ƃ͎v���܂���B
���̊����͉��̖����Ȃ������ł��B
���b�N�t�H�[�����������g���C���Ă݂ĉ������B
�����ԍ��F13169984
![]() 1�_
1�_
����������
���X���肪�Ƃ��������܂��B
�������m�F�������̂ł����A�b�̃t�H�[�}�b�g���������ł͋N�����Ȃ��Ƃ����̂͂��̏ꍇex2�Ƃ������i�b�N�X�̃t�H�[�}�b�g�̂��Ƃł���ˁH
���i�b�N�X�̃t�H�[�}�b�g����O��ł��̂g�c�c���N�������邽�߂ɍX�Ƀ��i�b�N�X�̂n�r���C���X�g����Ă��Ȃ��ƑʖځH�Ƃ������߂ŋX�����ł��傤���H�v����ɂg�c�P�̓��i�b�N�X�̂n�r�ŋN�����Ă���o�b�I�ȑ������ł��ˁH
�ȒP�ɂ܂Ƃ߂�Ƃb�c�N���̃��i�b�N�X���g�c�P�̂g�c�c����N������悤�ɂ���n�j�Ȃ�ł��ˁB
�c�ɂ��Ăł����A����Q�s�̂g�c�c�uST2000DL003�v���w�������̂ł����A
�����͂��ꂩ��̂n�r�Ŏ嗬�ƂȂ�P�Z�N�^�S�j�^�C�v�̕��ł����A���݂܂ł͂P�Z�N�^�T�P�Q�̕��������悤�ł������ꂩ��͂S�j�^�C�v�̕��ɐ�ւ��悤�Ȑ���������܂����A���̂S�j�^�C�v���g�c�P�ł͎g���Ȃ��Ƃ������Ƃł��ƍ��̂����ɂP�Z�N�^�T�P�Q�^�C�v�̕����u�����Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��ȂƂ������ɂȂ�܂����H
�����l�ŏ����ł����g�c�P�̃V�X�e���������Ă����悤�ȋC�����܂��B
���낢�뒲�ׂĒ���o��悤�Ɋ撣�肽���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13183000
![]() 0�_
0�_
���b�N�t�H�[������A
�������ł��B
> ���i�b�N�X�̃t�H�[�}�b�g����O���
> ���̂g�c�c���N�������邽�߂ɍX�Ƀ��i�b�N�X�̂n�r���C���X�g����Ă��Ȃ��ƑʖځH
�����ł����D�D�D
> �b�c�N���̃��i�b�N�X���g�c�P�̂g�c�c����N������悤�ɂ���n�j�Ȃ�ł��ˁB
OS(Tigar?�Ƃ�����Linux OS)�̒���HD1�̐���A�v�����܂܂�Ă���悤�Ȃ̂ŁA
���̂��̂ł͂Ȃ����g�p���Ă���Linux�p�[�e�B�V�����̃R�s�[���K�v�ł��B
���̌�AMBR(Master Boot Record)��ݒ肵�܂��B
���ꂪ�ł��Ȃ���Η����オ��܂���B
> ����Q�s�̂g�c�c�uST2000DL003�v���w�������̂ł����A
> ���ꂩ��̂n�r�Ŏ嗬�ƂȂ�P�Z�N�^�S�j�^�C�v�̕��ł����B
���ɂ��������̂ł��ˁB���炵�܂����B
���N�O��HD1 Linux OS�ł�WindowsXP�Ɠ������p�t�H�[�}���X�����邩
�ň��g�p�ł��Ȃ��\��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13191971
![]() 0�_
0�_
������������
�⑫���肪�Ƃ��������܂��B
�g�c�P�̂g�c�c�ɃC���X�g����Ă��郊�i�b�N�X�ɂg�c�P����̃A�v��������Ƃ͒m��܂���ł����B
�����Ȃ�ƐV���ɂg�c�c�Ƀ��i�b�N�X���C���X�g���Ă�����A�v�����ꏏ����Ȃ��Ƒʖڂ��Ƃ������Ƃ�����܂����B
��������ƊF���������ꂽ�悤�Ƀo�b�N�A�b�v�������p�g�c�c�ɕ������Ă��̃p�[�e�V�������g��������łȂ��Ƒʖڂł��ˁB
�����Ċ����p�g�c�c�͂P�Z�N�^�T�P�Q�^�C�v���g���B
�C���[�W���͂߂ė��܂����B
��̓o�b�N�A�b�v�\�t�g�ƃp�[�e�V�������g������\�t�g������Ύ��g�߂����ł��B
�P�Z�N�^�T�P�Q�o�C�g�̂g�c�c�͕i���ɂȂ�O�Ɋm�ۂł��ˁB
�����ԍ��F13199362
![]() 1�_
1�_
�o�C�N�X�g�[������ցB
asiaasiaasia�ł��B
�f�X�N�g�b�v�o�b�̌̏Ⴊ�S�z�ȗl�ł����A�f�X�N�g�b�v�o�b�͂������o���Δ����܂����ANAC-HD1�͐��Y�I���i�Ȃ̂Ŕ����܂���B�i���ÂȂ炠��悤�ł����j�B�܂�NAC-HD1�̎����ɂg�c�c�͎����Ō������Ȃ��ł��������Ɩ��L���Ă���܂��B
NAC-HD1���炵�Ăg�c�c���������ĉĂ��܂����ꍇ�\�j�[�͏C�������Ă���Ȃ��\��������܂��B�Ȃ̂łg�c�c�������Ȃ��ŁA����Ȃ��Ȃ������Ȃǂ��ėe�ʂ���Ȃǂ��Ă͂������ł��傤�B
�����ԍ��F13261591
![]() 1�_
1�_
asiaasiaasia����
�����@���ڂ������������������܂������A�������s���S�O���Ă�f�l�ɂ���
�T�W�F�X�`�����ɂݓ���܂��B�S�O�̗��R��PC�������J���n�[�h�C���^�[�t�F�X�Ή��ł����B
����ŋ�,�w���\���3D�m�[�g�u�b�N�o�b��USB3.0(5GBPS)�A�C�N�X�y���G���g�l�U�D�O�ȏ㏈�����ɂȂ��Ă���悤�ł��B���������Ă����O��Ɉȉ��̂悤�ɍl���܂����B
�P�D�n�[�h�C���^�[�t�F�[�X�i�m�[�gPC�ڑ��BPC�n�[�h�J���s�v�j
�EUSB3.0��USB-IDE�ϊ���ɂ��HD1-HDD�C���^�[�t�F�[�X����B
�E�V�P�s�a�g�c�c�Ƃ�USB-SATA�ϊ���ŃC���^�[�t�F�[�X����B
������USB3.0�̕ϊ���̔��͊m�F���Ă܂���B�iUSB2.0�ł͗����Ƃ��̔����i����j
�Q�D�\�t�g�Ή�
KNOPPIX(GPATED�����j�����i�b�N�X�n�\�t�g�A�p�[�e�[�V�����ύX���͍��܂ł�
asiaasiaasia�����������������Ƃ���B
�R�D����̑Ή��Ɖۑ�
�E�Q�O�P�P�N�~�m�[�g���f���Ƃ���ƂP�O���ȍ~�̍w���Ɗ����g���C�B�i�ă��f���ł��j
�E��L�n�[�h�C���^�[�t�F�X�Ń\�t�g�ғ����邩�̌��O
�iKNOPPIX�[GPATED�����@���i�b�N�X�A�p�[�e�[�V�����ύX���j
�E���b�N�t�H�[�����w�E��HDD,1�Z�N�^�[�T�P�Q����ŋ߂͂SK�d�l�ύX�X���̂��Ƃ�
�@HD1�p�A��̓I1TB,�Z�N�^�[�T�P�Q�̋�̓IHDD�i���������肢�܂��B�iWD,buffero,etc)
�@�@����Ȃ��Ƃ��l���Ă���܂��B�T�W�F�X�`�����L��������܂����B
�����ԍ��F13265037
![]() 0�_
0�_
�o�C�N�X�g�[������A
�������ł��B
�o�C�N�X�g�[������̂��C�����{���ɂ悭�킩��̂Ŋ��������܂��s����������Ă��܂��B
���̂킩��͈͂ŕԐM���܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��ĉ������B
�P�D
�@USB2.0�̐��i�ł����Ă�USB3.0����(���ʌ݊��̂���)�g�p�\�Ȕ��ł��B
�Q�D
�@KNOPPIX�[GPARTED�ɂ��Linux�p�[�e�[�V�����̕ύX�͉\�ł����A
�@Acronis TrueImage Home 2010�ɂ��o�b�N�A�b�v/���X�g�A���g�p�����
�@���X�g�A���Ƀf�[�^�����g�����܂��B
�@�����]���ł��g�p�ł���悤�Ȃ̂ł܂�����Ŏ����ꂽ��@���ł��傤���B
�@���̃\�t�g�Ŋg���ł���̂�GPARTED�͕K�v�Ȃ����ł��B
�R�D
�@USB�ڑ�����DISK��ΏۂɃo�b�N�A�b�v/���X�g�A���o���邩�ł���ˁB
�@���Ԃ�\���Ǝv���܂��B
�@����USB�ڑ���DISK�ɑ���MBR(Master Boot Record)�̃R�s�[���o���邩��
�@�S�z�ł��B�O��CD-ROM�̃t�@�[���A�b�v�����̐ڑ��Ŏ��s�����̂�..
�@������C�ɂȂ�̂�DISK�̉�]���x�ł��B
�@nac-hd1��DISK��7200��]�̂��̂ł����B
�@����DISK�̓v���b�^���傫���Ȃ�L���b�V������ʂɋl�܂�Ă��܂��̂ŁA
�@SATA�f�B�X�N���g�p����ƌ������ł����5400��]�̂��̂ł�
�@"�ǂݏo�����Ԃɍ���Ȃ�"���Ď��͂Ȃ���������܂���B
�@���v���낤�ʂ̊��o��������܂��A�C�ɂȂ�Ƃ���ł��B
�@���̓_�́uSATA�f�B�X�N5400��]�Ŗ��o�Ă��Ȃ���v�Ƃ̕�����Έ��S�Ȃ̂ł���..
�o�C�N�X�g�[������A�Ȃł���JAPAN�̂悤�ɒ��߂��撣���ĉ������ˁB
�������܂��B
�����ԍ��F13291563
![]() 1�_
1�_
����������
�T�W�F�X�`�����L��������܂��B�X�����HDD���������������������ɑ����̊F����
���낢��Ȋp�x�Ŋ����W�J�ɉ����܂����B�܂��ɍ����h�_�܂ɒl���܂��B
���������܂ŁA�f�l�̎��̎���ɂ��ڍ������������܂����B
�m���͑��������̂̎��s���ł��Ă܂���B���u�m�s����v�Ƃ͂悭���������̂ł��ˁI
�m�[�g�w���͏�����ɂȂ�̂ŁA�T�W�F�X�`�����ɂ��VHDD�i�d�l�F1TB,�Z�N�^512,7200��]�j�͑��߂ɍw���������Ǝv���܂��B�Ȃł����W���p���̂�����߂����_��Ƃ�
�撣��܂��B�L��������܂����B
�����ԍ��F13292200
![]() 0�_
0�_
���X����������̂��C��������̂ł����A�g�c�P�̂g�c�c���u�N���[���g�c�c�v�̂悤�ɃA�v���P�[�V�����ɗ��炸�ɑ�e�ʂg�c�c�ɃR�s�[���Ďg�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H
�������̕��������܂����炲�������������B
�����ԍ��F13663094
![]() 0�_
0�_
���������ԂԂ������Ă��܂��܂������A�܂��f�B�X�N�������`�������W����Ă�����͂���������ł��傤��?���͂悤�₭�����قNJ������������Ƃ���ł��B�Ƃ����Ă��A��e�ʉ��ł͂Ȃ�SSD250GB(SAMSUNG)�ւ̌����ł����E�E�E
���܂͂܂��o���b�N��Ԃł���(�S���u�b�V����1�ǂ����֍s���Ă��܂����̂�(��))
�g�p�����c�[����LB�R�s�[���[�N�X12�ł��BMBR���A�X�V����悤�Ƀ��b�Z�[�W�͏o�܂������A���̂܂g���Ă��܂��BCD�Ɋւ��ẮA�W�����p�ݒ肪�ǂ��ɂ������Ă��Ȃ������̂ŃW�����p�Ȃ��ł����A�Ƃ肠�����Đ��͂ł��܂����B
�n�[�h�Ƃ��ẮASATA-USB�ϊ��L�b�g�ƁAPATA-SATA�ϊ����(�}�U�[��PATA���Ȃ����̂�)�����ł��BWindows���LB�R�s�[���[�N�X���N�����Ă��܂������܂����BTrueImage2009�Ŏ��s���Ă����̂����܂��������̂ŁA�L�p�ȏ��������Ă��������Ă��肪���������ł��B
SATA�ł���������e�ʂ̂��̂������Ŏ�ɓ���悤�ɂȂ�A�e�ʃA�b�v�ɒ��킵�悤�Ǝv���܂��B������������LB�R�s�[���[�N�X�Ŋg���܂łł�����b�L�[�ł��ˁB
SSD�͏������݉ɂ�����܂����A�ǂݍ��݂Ɋւ��Ă͂��Ȃ�̎��Ԏg�p�ł���ƕ��������Ƃ�����܂��BNAC-HD1�̂悤�ȗp�r�ɂ͂҂����肾�Ǝv���܂��B���͂Ƃ�����A��肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F15761734
![]() 0�_
0�_
naoyuki1����
�������߂łƂ��������܂��B�r�r�c�Ɋ����Ƃ̂��ƁA����̗���ɉ������Ή��ł��ˁB
���āA�������܂����{���Ă���܂��A�t�r�a�R�D�O�Ή���PC�擾���܂����̂ł���
�ڑ��Ńg���C���悤�Ǝv���Ă��܂��B�ʏ��HDD���l���Ă��܂����AHDD�d�l�̓Z�N�^�T�O�O
�Ƃ̂��Ƃł����A���ݓ���\��HDD�̃Z�N�^�͂S�O�O�O�i�S�j�j�ł��B
�Z�N�^�S�O�O�O�d�l�ł̓_���Ȃ�ł��傤�ˁH
�T�O�O�f�`�P�s�a�A�V�S�O�O��]�ŃZ�N�^�T�O�O��HDD�i���B�y�т����ւ̑Ή��@
������܂����炲�������肢�������܂��B
�����ԍ��F15763046
![]() 0�_
0�_
CD�v���[���[ > Densen Audio Technologies > B-420 [�u���b�N]
�G���Ȃǂł͂悭�������Ė��O���悭�m���Ă��邯�ǁA���ۂ��X�Ō������Ȃ����������������Ƃ��Ȃ��ł��������͂���܂��B
�����o���邨�X�Ƃ����g�p���͂��炵���̂��ȁH
![]() 0�_
0�_
CD�v���[���[ > SONY > SCD-XA5400ES
OTOTOY�Ƃ������y�z�M�T�C�g��DSD�f�[�^���z�M(�̔�)����Ă܂�^^
DSD�̔z�M�͂��ꂪ"��"�Ƃ̂��ƁB
http://ototoy.jp/music/
���g�b�v�y�[�W
http://ototoy.jp/feature/index.php/20100812
��DSD�z�M����Ă���Ȃ̓��W�y�[�W�@
�����_�E�����[�h(�w��)���܂������A
�������ǂ��͖̂ܘ_�A�Տꊴ�E��C��(���ʂ���?�E������?)�������Ē����������܂����c�B(�C�C�Ӗ���)
�ł����A�c�O�Ȃ���f��DSD�^���f�[�^�ł͂Ȃ��A�~�L�V���O�̂��߂Ɉ�x24bit/192kHz PCM�ɕϊ�����Ă��邻���ł�>_<
����̓��C�u�ꔭ�^��DSD�̈��Ƃ��ė��Ƃ��Ă݂܂����B
DSD�f�B�X�N�ɂ���APS3(���ׂĂ̋@��)�ł����̉������������Ƃ��ł��܂��B
�W�����������l�����ł͂Ȃ���������܂��c�A���Ђ���������B
![]() 2�_
2�_
�D��H�̃q���R����ɂ���
�����M�d�Ȍ䋳�����肪�Ƃ��������܂��B���悢��DSD�f�[�^�z�M���͂��܂����Ƃ̃j���[�X���f���A���悢�挻�sVAIO�ɂ�DSD�f�B�X�N�쐬�@�\�������ė~�����Ǝv���܂����B�Ƃ���őD��H�̃q���R����́A�u���K�[�̑��D�}�X�^�[�q���R����ł����H����ł͊���SCD-XA5400ES����������DSD�f�B�X�N�����ӏ܂Ȃ����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���HJBL4307�ōĐ�����SCD-XA5400ES��SACD��DSD�f�B�X�N�̈Ⴂ�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤���H����䋳���������B
�����ԍ��F11869829
![]() 1�_
1�_
��H�̃q���R������
�T�C�f���}�X�^�����O�̃z�[���y�[�W�ŁA�����̃A�}�]���̐��^��5.6MHz��DSD�����Ŕz�M���Ă���悤�ł��BAUDIOGATE�������2.8MHz�ɂ���DSD�f�B�X�N�ɂ��ł������ł��B���Ԃ̂���Ƃ������Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂��B����ɂ��Ă��~�������܂łɂȂ�Ƃ�SCD-XA5400ES���Ȃ����ȂƂ��v������A�����葁��SCD-XE800����肵�Ă��܂������Ƒ��ς�炸��X�Ƃ��Ă��܂��B��r������������XA5400ES�̒�ʂƒ��̈��芴���Ƃ邩XE800�̃f�B�X�N�ǂݍ��݂̔����̂悳�Ɩ������i�ƂȂ�Ƃ����Ă��l�i�̎荠���j���Ƃ邩�A�n�����b�g�ł��B���H��SCD-XA1200ES��SCC-X501�����f���`�F���W����DSD�f�B�X�N�Đ��@�ɂȂ��đI�����𑝂₵�ė~�����Ɩ]�ގ���ł��B
�����ԍ��F11962837
![]() 1�_
1�_
�D��H�̃q���R����ɂ���
��ς����b�ɂȂ��Ă���܂��B
�X���Q�V���t���́u�`�uwatch�v�́u���{����DigitalAudioLaboratory�Łv��433��:�uDSD�y�Ȕz�M�̃��R�[�f�B���O����ƍĐ����̎��ہ`PS3�ł��Đ��B���C�u�̕��͋C/��C�����Đ� �`�v�Ƒ肵��DSD�z�M�̎�ނ��o�����̂ŕ������܂��B���L�̃A�h���X�ł��B
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/20100927_396389.html
�����ԍ��F11987993
![]() 1�_
1�_
�́A�k�o�ŕ��������ɂ͂��炵���D�G�^���������Ɗ������̂��ACD�����ꂽ���̂��ƃK�b�J�������Ƃ����b���A����CD�v���[���[�̔��������̍��͗ǂ������܂����B
�����Ƃ��čl������̂́A
�P�D������CD�v���[���[��DAC���\���Ⴉ�����B
�@�@�@�����A���̈���CD���Ɗ����Ă������̂ł��A�\���N��ɐV�^CD�v���[���[�ŕ�����
�@�@�@���\�ǂ����ŕ����邱�Ƃ�����܂����B
�Q�D���ɃN���V�b�N�ł́ACD�̃_�C�i�~�b�N�����W�̑傫�����ߐM���āA���܂�R���v���b�V�������������Ɏ��^���Ă��܂��A�������x���ŗʎq���m�C�Y���ڂ��Ă��܂��Ă����B
�@�@�@�Ⴆ�A��̃e���[�N�̃`���C�R�t�X�L�[�u����1812�N�v�ł̓J�m���C�̃��x����
�@�@�@���킹�Ď��^�������߂ɁA�I�[�P�X�g���̉������ΓI�ɏ����ȉ��Ŏ��^����Ă���A
�@�@�@�I�[�P�X�g���̔������ł̂������芴����������A�k�o�ɔ�ׂė���Ă��܂����B
�@�@�@���̏ꍇ�A���ʂ��グ�Ă��A�ʎq���m�C�Y����������邾���ŁA��������CD��
�@�@�@������Ƌ~���悤������܂���B
�R�D�k�o����p�̃}�X�^�[�e�[�v�������̃A�i���O�Đ����u�̓������l�����āA����������グ�Ă��������̂�����A��������̂܂g����CD���삷��ƁA���s�q�Ŕ����̗ǂ�CD�Đ����ł́A�P�ɍ��悪�����グ���Ă���ɗ��܂炸�A�c���ۂ����ɉ��̂Ȃ��������ŁA�����ɑς��Ȃ����ɂȂ�B
�@�@�@�{�����Y��ȍ������Đ�����Ă��鑕�u�ŁA�������C�R���C�U�Ŏ����グ�Ă��A
�@�@�@�������L���ɂȂ����Ƃ͊����Ă��A�c���ۂ������ɑς��Ȃ����ɂȂ邱�Ƃ͂܂�
�@�@�@����܂���B�܂�A����͍Đ����u���̑Ή����\�ł��B
�@�@�@���̌o���ł́ACD�v���[���[��A���v�̓d���P�[�u���̌����ŁA�X�g���X�̖���
�@�@�@��������ƐL�т���������₩�œ����ȍ����ɂȂ�܂����B
�@�@�@����ɂ��A����܂ō����������Ċy���߂Ȃ��Ǝv���Ă���CD�̂قƂ�ǂ́A
�@�@�@���܂��Đ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
���ɁA���ɃI�[�P�X�g����SACD���ACD���ނ��뉹��������������Ƃ������������܂��B
�����Ƃ��čl������̂́A
�@SACD��CD�ɔ�ׁA�_�C�i�~�b�N�����W���L���̂ł����A���҂Ƃ��I�[�P�X�g���̍ŋ����́A�قړ������ʂł��B�܂�Ŏ㉹�����Ƀ_�C�i�~�b�N�����W���L���̂ł��B���̂���SACD��CD���A�R���v���b�V�����ʂ͏��Ȃ��ł��܂��B�܂�SACD�ł̏����ʁA�Ⴆ�t���[�g�̓Ƒt�ł̉��ʂ́A�ŋ����Ƃ̍����傫���Ƃ�A���ʂƂ���CD�ł̃t���[�g�Ƒt��艹�ʂ��������Ȃ�܂��B���̂悤�ȏ����ʂ⒆���ʂŁASACD��CD��艹�����������^�����X���ɂ���܂��B���̂��Ƃ��ASACD���ACD���ނ��뉹��������������Ƃ��������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����ɑΏ�������@�́A�N���V�b�N��SACD�Đ����ɂ́A3dB����4.5dB�ق�CD�Đ�����艹�ʂ��グ�邱�Ƃł��B�`�u�A���v�̒��ɂ́uSACD�Q�C���v�Ə̂��āASACD�Đ����ɉ��ʂ�3dB�܂���6dB�グ��@�\�ɂ��ASACD�̍������Đ����͂���Ƃ��Ă���@�킪����܂��B
![]() 6�_
6�_
2010/08/12 23:17�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A���炢���l�߂̖���N�ł��ˁB�������Ɍ�����Ƃ���ŁA�c�|�����W�̍L���D�G�^�����ƃ{�����[�������������Ȃ邵�A�����łȂ��^���͏����ȉ��ŕ����Ă��傤�ǂł��i���Ȃ��Ƃ��N���V�b�N�^���̏ꍇ�j�B
�ǂ��^�����{�����[����������ƁA�S���t�̕����Řc�݂��o�邱�Ƃ�����܂��B����͑��u�������܂��͗�������������A�ƂȂ�܂��̂ŁA���u���������悭����̂��I�[�f�B�I�}�j�A�̏K�Ȃł��B�������A��������Ȃ��l�A�ł��Ȃ��l�́A�����ȉ��ł��ǂ���������u�^���v���D�ނł��傤�ˁB
���Ƃ��b������ƁA���͍ŋ߁A�������H�𑖂�Ԃ̒��ŁA�����Ȃ̂b�c���܂������A�Ԃ̒������邳���āA���������͕������Ȃ����A�傫�ȉ��̕��������傫���������ĎQ��܂����B�r���ŃA���}�E���g���܂����B�ԓ��ŕ����Ȃ��t�����̂Ȃ��|�b�v�ȋȁA���x���̍����^���������ł��ˁB
�����ԍ��F11754851
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A���͂悤�������܂��B
�����ł��ˁA�uSACD�Q�C���v�̐����ł��A�ő剹�ʎ��ɘc�݂���������ꍇ�́A���̋@�\��OFF�ɂ��Ă��������Ə����Ă���܂��ˁB
�����������H�ł́A�N���V�b�N�̋Ȃ͑S�������܂���B����100km�ŃG���W�����펞3000��]�ȏ�ɂȂ�܂����B��͂�A�������ʂ������|�b�v�X�A���̌n�ɂȂ�܂��ˁB
�����ԍ��F11755626
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
�����Ƃ��ǂ�������Ȃ�����������Ă�redfodera�ł��i���I�j
�N���b�V�b�N�͖�O���ł����_�C�i�~�b�N�����W�̑傫�ȃ\�[�X�͂��낢��Ȗʂœ���ł��ˁB
���^�i�K�̃��x���̐ݒ肩�炵�ĔY��ł��܂��܂��B
Minerva2000����
�uoverture1812�v�͉����ƕ��c�������o���\�[�X�ł����Đ����̊�S/N�Ɉ�ԉe������ނ��ł��ˁB
�������H���q���̃��[�h�m�C�Y�Ȃǂ͍ł�����̂ł������Ԃ̎��͂̑������ĈӊO�ɂ���܂�����ˁB
�܂��ǂ��܂ő傫�ȉ����o���邩�ł��\�[�X�ɑ��郆�[�U�̕]���Ɋւ���Ă��܂�����A
AV�A���v�́uSACD�Q�C���v�Ƃ��������A�ꗝ����Ȃ��Ǝv���܂��B
�t���A�����������Ă���܂��B
���ǂ��^�����{�����[����������ƁA�S���t�̕����Řc�݂��o�邱�Ƃ�����܂��B
CD-DA�œ��ɓ��X�����邱�Ƃł����A�ŋ߂͑����̃\�[�X�Ř^�����x�������߂��܂��B
PC�x�[�X�ŕҏW����l�ɂȂ��Ă��烌�x���̒ǂ����݂��e�ՂɂȂ������Q�������܂��B
�w�b�h�}�[�W���������߂��ăN���b�v���O�A�Ƃ��������ɂ���Ă͗e�ՂɃN���b�v���܂����A
24/32bit�����16bit�ւ̃G���R�[�h������ɂ���̔w���������Ă��͂��܂��B
�G���R�[�h�ł�16bit�̃_�C�i�~�b�N�����W����16bit�ȏ�̃_�C�i�~�N�X�����������邽�߂ɁA
�ɒ[�Șb�����܂������߂̋Z�p�Ƃ��Ē�����тɔ��ʂ̃m�C�Y�������Ă܂��iApogee�́uUV22�v�Ȃǁj
�f�B�U���ĉ��y�\�[�X�ɂ͖�ɂ��łɂ��Ȃ���p�O��������Ȃ��̂��H�Ƃ����C�����Ă��܂��B
���͏�L���R��10�������\��̐V��̃}�X�^�����O�ɑ��Ď����X�^�b�t��NG��ʍ������̂ŁA
NG�o�����{�l���ċx�ݕԏ�ōă}�X�^�����O�ɗ�������Ă���܂��i���j
�����ԍ��F11757445
![]() 2�_
2�_
�F�l�A�����́B
redfodera����A
�Đ����̑����ɂ���������Ȃ��A�Y��ɕ�������ŏ����ƁA���̍Đ������Y��ɕ�������ő剹�̍��A�܂�Đ����̃_�C�i�~�b�N�����W���d�v�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����炭���y�\�[�X�Ƃ��Ă�SACD�́u��i����j�v�Ƃ��ẮA��ʂ̍Đ����̃_�C�i�~�b�N�����W���قڃJ�o�[�o���Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B
����A���y�\�[�X����鑤�́A������̃_�C�i�~�b�N�����W���C�ɂȂ�܂��B
�A���v��~�L�T�[�A���R�[�_�[���̓d�q�@��̃_�C�i�~�b�N�����W�͂����炭�傫�Ȗ��͖����̂ł��傤���A�}�C�N�͂ǂ��ł��傤���B
5.1�`�����l���̘^���ł́A�Œ�5�{�̃}�C�N������Ώ\���̂͂��ł����A�����ɃI�[�P�X�g���̘^���̑����̃P�[�X�ŁA���\�{�̃}�C�N���g���Ă���̂́A�}�C�N�̃_�C�i�~�b�N�����W�A�܂��Y��ȉ��ŏW���ł���ŏ��̉��ƍő�̉��̍����A�������\�N���܂�i������������ł��傤���B
�����ԍ��F11758394
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����A�����́B
�������A�X�^�b�t�ƃR���r�j�ٓ��Ŕӂ��у^�C�����ł��i�߁j
�N���V�b�N�̎��^�ɂ����ʂ����G���W�j�A�̘b�ł���Minerva2000����̗\�z�ɋ߂�����͂��邻���ł���B
�G���W�j�A��v���f���[�T�A����ɃA�[�e�B�X�g�̗��z��ӌ�������܂�����P�[�X����Ȃ�ł����A
�����̃G���W�j�A�̗��z�̓z�[�����^�Ȃ璮�O�Ńt���n�E�X�ɂ��Ă���x�X�g�̃��X�j���O�E�V�[�g��T���o���A
�t���n�E�X�̂܂܂��̃V�[�g�Ńo�C�m�[�����̃s���|�C���g�Ŏ��^�������̂Ɛ\���Ă���܂��B
�ł�����ł͏E������Ȃ����Ƃ����̂����Ȃ蔭�����Ă��܂����̗��R�͎�Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̂��ƁB
�}�C�N�̃_�C�i�~�b�N�����W�ɉ����ăt���n�E�X�ɂ����z�[����S/N�ƃ_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��e������邻���ł��B
�~���[�W�b�N�E�z�[���͊�{�I�Ƀt���n�E�X�Ŗ{���̉�����������l�ɐv����Ă��邻���ł��B
�N�����Ȃ�������߂�����c���┽�˂̉�荞�݂��傫���Ȃ�ȂǁA����������Ȃ��Ƃ��낪�����Ƃ��B
�}���`�E�}�C�N�Ŏ��^����w�i�ɂ̓Z�p���[�V�����A�_�C�i�~�b�N�����W�A�A���r�G���X����ʁX�ɗp�ӂ��āA
�ҏW��~�L�V���O�̍ۂɏ����ł������̍ޗ���f�ނƂ��Ďg����l�ɂ��邱�Ƃ݂����ł���B
�����ԍ��F11758754
![]() 2�_
2�_
redfodera����A
�ǂ������d�����A���݂܂���B
�Ȃ�قǁA�z�[����S/N�ƃ_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��e�������̂ł��ˁB
���V�����̂a�c������ƃX�e�[�W��ɂ�������̃}�C�N���ݒu����Ă��܂����A�܂��A�����̃N���V�b�N�b�c�̉�����Ȃǂł́A�V��ނ̃}�C�N���g�p�����Ƃ��A�S�W�b�g�̃~�L�V���O�R���\�[�����g�p�����Ƃ������Ă���A���ς�炸�}���`�}�C�N�Ŏ��^���Ă���悤�Ȃ̂ŁA�^��Ɋ����Ă���܂������A�������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F11758952
![]() 1�_
1�_
2010/08/13 22:59�i1�N�ȏ�O�j
��Ґ��N���V�b�N�^���ł́A�Q�`�R�{�̃}�C�N�ł͑��肸�A�⏕�}�C�N���g���̂��펯�Ǝv���܂����A�f�m���̃����|�C���g�E�G�f�B�V�����͏펯�͂���̎g���������������Ⴞ�Ǝv���܂��B
http://www.hmv.co.jp/search/index.asp?target=MUSIC&category=1&adv=1&keyword=%83%8F%83%93%83%7C%83C%83%93%83g&site=&type=sr
��ԕ\���͂������f���炵���ł����A�𑜓x�A�c�����W����������m�ۂ���Ă��܂��B�}�C�N�͂a���j���Ƃ���Ă���A�P�X�W�O�N��̂b�c�^���ł����A�ւ��Ȃr�`�b�c�����̂��������^�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11758991
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A�����́B
�����N��̍ŏ��ɏЉ�Ă���A�C���o���w���̃}�[���[��5�Ԃ́A�����i�艿3,300�~�j�������Ă���܂��B�Ȃ��Ȃ��f���炵���^�����Ǝv���܂��B
�����A���̉�����ɂ́A�u���̘^���͂a���j�А��^���p�}�C�N���t�H���i4006�|Pressure�^�C�v�j2�{�����ɂ��^������{�Ƃ��A�ꕔ�ɕ⏕�}�C�N���t�H�����g�p���Ă���܂��B�v�Ə����Ă���A���S��2�{�����ł͂Ȃ��悤�ł��B
�����́u�����|�C���g�E�G�f�B�V�����v�Ƃ͈Ⴄ�̂�������܂���B
�����ԍ��F11759230
![]() 1�_
1�_
Minerva����@����ɂ���
�����̈���CD���Ɗ����Ă������̂ł��A
���\���N��ɐV�^CD�v���[���[�ŕ�����
�����\�ǂ����ŕ����邱�Ƃ�����܂���
�܂������A���̂Ƃ���ł��ˁB
���u�i�ƃ��X�i�[�j�̐��\�����シ�邱�ƂŁA��L�̂悤�ȗ�𑽂��o�����܂����B
���Ƃ��A1952�N�̃g�X�J�j�[�j�̑��b�c�Ȃǂ́ASACD�����ɖ点��悤�ȃV�X�e���\���ɂȂ��āA���߂Ă��̊����������̕��ɂ��܂����B
���u�̕����I�����͂��������Ƀ\�[�X�ɑ��Ă̊Ԍ����L����悤�ł��B
�����ԍ��F11759828
![]() 0�_
0�_
2010/08/14 06:25�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A�f�m���̃}�[���[�̂S�Ԃ́A���S�Ƀ����|�C���g�ɂȂ��Ă��܂��B
���ꂩ��A�P�X�X�O���ARTS�̃}�[�N�A�����f���X�]�[�������ȑS�W�̓����|�C���g�ł��B
http://www.hmv.co.jp/product/detail/812041
����͗������W�������A���߉��Ƃ܂�Ȃ��^�����Ǝv���܂������A��Ԃ��ǂ��o�Ă��邱�ƂɋC�Â��A���x�ł������鈤���ׂ��^���ɕς��܂����B
�X�s�[�J�̃C�N���v�X��A�^�C���h���C����yoshii9�݂����ȃR���Z�v�g�̘^���ƌ�������悢���H�@�I�[�f�B�I�͖ڂ̑O�Œ����悤�Ȕ��^�����厖�ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ��ƋC�Â����Ă����^���ł��B
�W���Y�̃g���I���A�����|�C���g�Ř^�����炨�����낢�Ǝv���̂ł��B
�����ԍ��F11759891
![]() 0�_
0�_
�F�l�A���͂悤�������܂��B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
�����u�̕����I�����͂��������Ƀ\�[�X�ɑ��Ă̊Ԍ����L����悤�ł��B
���������v���܂��B�@�u�̘̂^���́A�����̍Đ����u�̃��x���̒Ⴓ�ɍ��킹�ĕςȉ��������Ă����̂ŁA����̍����I�[�f�B�I���u�ŕ����Ɖ��������B�v�Ƃ����̂͑��v�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����ł��A����Ȃ�Ƀ��C�h�����W�Ńp���[�̂���V�X�e���ł��������Ăn�j���o���Ă����͂��ŁA���ꂪ���������ɑς��Ȃ����ɂȂ��Ă���Ƃ�����A�g���Ă��鑕�u���^���������ǂ��ł��傤�B
�����Ƃ��u�����ɑς��Ȃ��v���u���b�N�͕����ɑς��Ȃ��B�v�Ɠ����ŁA�l�̍D�݂̖��Ƃ��Ăł���A�q�ϓI�ɂ́A�̘̂^�����ǂ������o�Ă���̂ł���A���u�ɖ��͖����̂ł����B
�g�X�J�j�[�j���̎ʐ^��q�����܂����B���o�[�g�E�V���E�����c��1952�N���_�Ŋ��Ă����Ƃ͋����ł����B���o�[�g�E�V���E�����c���������Ă���b�c�́ATELARC�́u�J���~�i�E�u���[�i�v���������Ă��܂��A���̂b�c���D�G�^�����Ǝv���܂��B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
�f�m���ł����S�ȃ����|�C���g�^��������̂ł��ˁB
�����m���Ǝv���܂����A�́A�A���h���E�V�����������n�݂����V���������E���R�[�h�ł̓����|�C���g���^�͓I�ɐi�߂Ă���A������X�^�b�N�X�̃R���f���T�[�w�b�h�t�H���ŕ����̂ɂ͂܂������Ƃ�����܂��B�z�[���̍L��ȋ�Ԃ���������^���ł����B
���������̌�A�u�����̋��߂Ă��鉹�͂���ł͂Ȃ��B�v�ƋC�t���܂��āA�P�ނ��܂����B
��͂莄�̋��߂Ă���̂̓��C�h�����W�ŁA�_�C�i�~�b�N�A�܂�u�K�c�[���v�Ɨ���Ŋy��A���NJy��A���y��Ȃ̂ł����B
�W���Y�̃g���I�������|�C���g���^�������̂��D�݂ƌ������͂�����Ǝv���܂��B�ł����͔�юU�銾���}�C�N�ɂ�����悤�ȁA�ߐژ^�����D�݂ł��ˁB
�����ԍ��F11759999
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
���Љ��CD�͂����̃G���W�j�A���ЂƂ̗��z�ƍl������^���@�ɂǂ����߂����̗̂l�ł��ˁB
���I�[�f�B�I�͖ڂ̑O�Œ����悤�Ȕ��^�����厖�ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ��ƋC�Â����Ă����^���ł��B
�z�[���Ɠ��̉��̋������Ƃ����̂͂���Ǝv���܂����炻�̃z�[���̂Ȃ��ʼn��t���y�����X�i�[�̏�ԁA
����������Ԃ��̂��̂��p�b�P�[�W����_�����܂܂ꂽ�^�C�g���Ȃ̂�������܂���ˁB
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��
�����X�^�b�t�Ƙb�����Ƃ�����̂ł������H�����߂��郊�}�X�^�[���l�����̂���Ȃ����ƁB
���ł�����ł��֊s���������肳������������̃��x���������グ�ďd�S�����������肳���Ă܂����A
�y��̉��F�����Ԃ邱�Ƃ��u�������Ɓv�Ƃ������o���w�i�ɂ���̂�������܂��A
�A���T���u���Ƃ͗l�X�Ȋy�킪���ꂢ�ɏd�Ȃ荬���荇���ċ������`�����̂Ǝv���Ă��܂��B
���ꂼ��̊y�킪�����\������Ȃ��Ń\���p�[�g���ۗ��������蔺�t�Ɨn���������肪�{���̎p�Ɗ�����̂ł����E�E�E
�ǂ������}�X�^�[�Łu�����v���Ă��܂����l�Ȉ�ۂ���^�C�g���ɂ��x�X�������܂��B
Minerva2000����@
���T�͒������}�X�^�����O�̌���ɗ�������Ă��܂�������ɂ��������b����ӎ����Ă��܂����A
�x�e�̎��ɃX�^�b�t���C���]�������˂ĉ��i.com�̃I�[�f�B�I�����������`���Ă����ł���B
�ނ�Ȃ�ɐF�X�Ɗ����邱�Ƃ�����l�ł�����ǂ��`�Ń��X�i�[����Ƀt�B�[�h�o�b�N�ł���A
�܂��I�[�f�B�I�E�t�@���̊F����ɖM�l�A�[�e�B�X�g��POPS�ł��y����ł��炦��^�C�g�������邩���B
�����ԍ��F11760026
![]() 3�_
3�_
redfodera����@����ɂ���
�����}�X�^�[�Łu�����v���Ă��܂����l�Ȉ�ۂ���^�C�g��
�ȑO�͏�L�́u���������I�v�Ɠ{���Ă܂������i���X�i�[�̐��\���オ�����̂Łj�ŋ߂͍l����ς��܂����i����
���Ƃ��A�I���W�i���������炩�����ꂽ���������ɂȂ��āA���y�̉��߂��ς���Ă��܂����ƂɂȂ��Ă��A����͂��̎��_�ł̐��쑤�i�v���j�̔��f�Ȃ̂ŁA��X���낤�Ƃ��ӌ��ł�����̂���Ȃ��ł��B
���������P���́A�u�ׂ���Ή��P�������v�ł����Ǝv���܂��B
����ɁA���}�X�^�ՁA�S�Ă�NG����Ȃ��āA���Ȃ��邢�͂ǂ����̃p�[�g�Łu�S�n�悢�����v���K������܂��̂ŁA����Ȃ�Ɋy���߂܂���B
�u��]�̂ɂ�鉹�y�Đ��ɍS��ҁv�Ƃ��āA�ƊE�̔ɉh�Ƒ�����ɂ��肢���Ă����܂��B
�����ԍ��F11761019
![]() 0�_
0�_
redfodera����A�@����ɂ��́B
�M�l�A�[�e�B�X�g��POPS�ŁA�I�[�f�B�I�I�ɂ��y���߂���̂̃����[�X�����҂��Ă��܂��B
�ŋ߁A�M�l�A�[�e�B�X�g��POPS�Ŏ������S�����̂́A���ꌧ�Ŋ������Ă���O���[�v�AK.K.B.�̃t�@�[�X�g�A���o���ł��B�@�^���A�~�L�V���O��mAru����ƌ��������S������Ă��܂��B���̕��́A�z�[���̂o�`�V�X�e���̉��������ɂ��ւ���Ă����āA���܂������AK.K.B.�����z�[���̉������������̕����s���Ă��������ł��B���̃z�[���́A���s�ʂ��S���Ȃ�����`��ŁA�o�`�V�X�e���ɂ�FUNCTION-ONE���g���Ă��܂����B���t���������̃~���[�W�V�����ɂ����̉����͑�ύD�]�������ł��B
�z�[���̂o�`�V�X�e���̉����������������ƁA�A���o���̘^���A�~�L�V���O��������������l���̂��A���A���C�u�������̃C���[�W���A�A���o���ɂ��Z���ɔ��f����Ă���A���D�G�^���ł����B
�����ԍ��F11761581
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
���̃X�������������Ȃ��Ă��Ă���悤�ł����A�ŏ��̍��ɏo�Ă��������ɃX���B
>���͍ŋ߁A�������H�𑖂�Ԃ̒��ŁA�����Ȃ̂b�c���܂������A�Ԃ̒������邳���āA���������͕������Ȃ����A�傫�ȉ��̕��������傫���������ĎQ��܂����B
>���Ԃ̎��͂̑������ĈӊO�ɂ���܂�����ˁB
�ŋߖʔ������������Ȃ��Ȃ����Ɗ����闝�R�̈�[����������ӂɂ���Ɗ����Ă��܂��B�����A�ŋ߉��y���f�o�C�X�Ƃ���iPod�Ȃǂ�DAP���嗬�ɂȂ��Ă��Ă��܂����A���������f�o�C�X�͎��ɓ˂����݂Ȃ��牮�O��ړ����ɕ��������������Ǝv���܂��B
���̏ꍇ�A���y�̃_�C�i�~�N�X���傫���ƁA���w�E�ɂ������悤�ɁA���肪���邳�߂��ĉ��y���r��r��ɂȂ�܂��B�]���āA�������ƃt�H���e�����̉��y���s�����X�����B���b�v���Ƃ������s���Ă��闝�R�̈�[�������ɂ���悤�ɂ��v���܂��B�m���Ɉړ����͂����������y�������Ղ��ł��B
�ł��A����̂Ȃ����y�Ȃ�āA�����g��Ȃ��`���̂悤�Ȃ��́B�����ɖO���Ă��܂��܂��B������ŋ߂̋Ȃ͒Z���Ȃ̂��E�E�E�B
�{���悩�����悩�ł͂���܂��A�\�j�[���E�H�[�N�}���𐢂ɏo�����͉̂��y���ނ̑����������̂����m��Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂��B���ꂪ�o�����́A�܂�ʼnf��݂����ɗz���̉������[�c�@���g���Ȃ��������̂Ŋ����������̂ł����A���ꂪ�嗬�ɂȂ��Ă��鎖�ʼn��y�̒��������ω����A���ꂪ���y�ɂ����X�j���O�X�^�C���̕ω��ɍ��킹���ϗe�����߂ė����B
����ɕ����Ȃ��畷�����y�́A���܂薼�Ȃł͍����ł���ˁB�����܂Łh�Ȃ���h�ŕ����Ă��܂�����A�ӎ������o�ɏW�����Ă͓]�蕨�ɂԂ������肵���˂܂���B�łɂ���ɂ��Ȃ�Ȃ��A�����S�n�ǂ����ł����OK�B���u�̑O�ł����ߖʂ��ĕ����悤�Ȓ��������̂��鉹�y��NG�B
���[��A�s�K���ȘA���B
�Â��b�ɂȂ����̂ŁA�b��]���B
>�F����ɖM�l�A�[�e�B�X�g��POPS�ł��y����ł��炦��^�C�g�������邩���B
�傢�Ɋ��҂��Ă���܂��B���ł�CD��xrcd��SACD�A����Ƀu���[���C�B�X�ɂ͍ŋߗ��s�̃u���[�X�y�b�N�Ƃ�SHM�ł��o���A��̉����ʼn��������ꂿ�Ⴂ�܂��B(^O^)v
��k�͂��Ă����A���̗ǂ������͑劽�}�ł��̂ŁA�����i�����厖�I�j�����Ă������܂��̂Ŋ撣���ĉ������B
�ł��A���܂葽���Ȃ������m��܂��i���������Ă��Ȃ��������H�j�A���̗ǂ��M�y�������\����܂���ˁB
���Ɏ��́A��і��q����́h�A�g���N�V�I���h�Ȃ������`�F�b�N�Ɏg�����肵�܂��B�P�Ȗڂ́hCosmic Moon�h�Ńu���u�������ቹ�̖���Ղ���y���݁A�T�Ȗڂ́h�l�G�h�ł͏o�����̃M�^�[�ƃx�[�X�A�����ă`�[���ƌ����A���ł����ˁA����B�g���C�A���O���̂悤�ȉ��܂ł̃A�R�[�X�e�B�b�N�Ȏ��R�ȋ������Ă��܂��B
�����ԍ��F11762728
![]() 2�_
2�_
2010/08/15 09:08�i1�N�ȏ�O�j
586RA����̉����`�F�b�N�b�c�̘b���o���̂ŁA�`�F�b�N�̂��ƂɐG��܂��ƁA���͐X���G�̂r�`�b�c�i�s�G�C�G�X;AVEX�j�̃g���b�N�T�ō����̎����������`�F�b�N���Ă��܂��B�`�F�b�N����Ƃ��͉��y�͕������ɁA�����������ɂ̂ݒ��ӂ𒍂��ł܂��B����Ȕ������o��Ƒ�ɏ��o���܂��B���̉����������ɋ������镔���ɂ͂��ځi�����H�j�ɂ����������Ƃ͂���܂���i�����̕������܂߂āj�B�����̌��N�f�f�͂��������ɂ��āA�u�b�c��r�`�b�c��ǂ����ŕ������߂́v�f�f�͌���������Ă���A�Ƃ������b�ł����B
�����ԍ��F11764773
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
�������A���゠�肪�Ƃ��������܂��B
�X�^�b�t�݂̂�Ȃƈꏏ�ɂ����҂ɉ�����l�Ɋ撣�肽���Ǝv���܂��B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��
��]�́A���ɂ��d�v�Ƃ����������̗Ƃł��i���j
Minerva2000����@
���Љ�̃^�C�g���A�@����݂ă`�F�b�N���Ă݂܂��B
586RA����
��і��q����AMIDI����̃A���o������D�ꂽ���̂����������ł���B
������q����AEPO����AMIDI�̓A�[�e�B�X�g�����I�ȃ��[�x���ł������ˁB
�A���o������ł��Ǝ��̃X�^���X�������Ă����ƕ����Ă��܂��B
�t��
�����ł���@������PCM1630�̃R���x���V�����Ŕz�z���ꂽ�e�X�gCD�����݂����܂��B
20�N�O�̂��̂ł������j�A��16it�ł͋��w�̃}�X�^�����O���{���ꂽ�A�C�e���̂ЂƂƎv���Ă܂��B
�����ԍ��F11764987
![]() 1�_
1�_
2010/08/15 14:30�i1�N�ȏ�O�j
Red����A�e�X�g�b�c����ł�����A�������e�X�g���܂��B���Ȃ�̓�ւ̃e�X�g�̂悤�Ȃ̂ŁA���҂ƕs���ŁE�E
���������ɂ͑�R���E�y�ƍs���̂ŁA���ꂩ��������Ȃ�A����ł���@�����肽�����̂ł��ˁB
�����ԍ��F11765962
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
��і��q����̘b��ɂ��āA���ז����܂��B
redfodera����
�ˑR�ł����A�ǂ������������肢���܂�!
���l�́AMIDI����̑�і��q������A�����ƌÂ�1980�N�O��̃A���o��(RCA���[�x��)�̉��Â���ɍD���������Ă��܂��B����30�N���O�Ȃ̂ɁA�����ƂĂ����A���ɒ�ʂ��܂��B����͊y����^�����@���V���v��������Ȃ̂ł́A�Ə���ɑz�����Ă��܂��B
���̌�́A�d�q�@��ɂ�鉹�Â��肪�ڗ����A�����͗ǂ��Ȃ��Ă����ʓI�ȉ��ɂȂ��āA�}�ɃK�����ƕω����Ă��܂��B
���̂悤�ȉ�(�^��?)�̈Ⴂ�́A�@��̕ω��Ƃ���������̕ω��ɂ����̂Ȃ̂ł��傤��?
�������A�[�e�B�X�g���͂��߃A���o������ɂ��������l�B�̍l�����ɂ��̂����m��܂��A�����w�i�����肻���Ȃ̂ŁA�������l��redfodera����ɂ��f���������A���ז���������ł��B��낵�����肢���܂� <(_ _)>
�����ԍ��F11766503
![]() 1�_
1�_
�F�l�A�����́B
hanzou-1����A
�̂̑�і��q����̘^���͗ǂ��A���̌�͂��܂�ǂ��Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�c�O�ł��ˁB
���̓A���o�����쓙�ɂ͊ւ���Ă��܂���̂ŁAredfodera����̂悤�ɁA���̔w�i�̐����͂ł��܂���B
�ł���і��q����̃A���o������҂��A��ɂ��u�ǂ����ɕ�������v�悤�ɓw�͂���Ă̌��ʂȂ̂ł��傤�ˁB
�����X���b�h�Łu�ǂ����ŕ������߂Ɂv�ƊȒP�ɏ����Ă��܂��܂������A���́u�ǂ����v�Ƃ����̂́A�l�ɂ���đ����ɈقȂ�̂ł��傤�ˁB
����G���̑Βk�ŁA�����ȃW���Y�v���f���[�T�[���u�ǂ����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��H�v�ƕ�����đ����Ɂu���鉹�v�Ɠ����������ł��B�̂悭�s�����W���Y�i���ł�JBL�̃o�b�N���[�h�z�[������o���o���̃g�����y�b�g��T�b�N�X�ƃK���K���̃h�����X���A����r�V�o�V�ƒ@����銴���Ĕ��ł��Ă���A�܂��Ɂu���鉹�v�ł����B�����ŁA�I�X�J�[�E�s�[�^�[�\���E�g���I�́uPlease Request�v�݂����Ȗ����n�̃A���o�������N�G�X�g����q������ƁA���肩�甒���ڂŌ����Ă������̂ł����B
���Ȃ�u�ǂ����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��H�v�ƕ������ƁA�u���t�Ƃ��`���悤�Ƃ��Ă��鉹�y�I�������ő���ɗ^���Ă���鉹�v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�ł�������Ɗi�D�t�������ŁA�Ƃ�Ă��܂��܂����B
������������̂́A��{�I�ɂ͉��t�Ƃ������鉹���̂��̂ł����āA�z�[���̔��ˉ���A�܂��Ă₻�̔��������Y��Ȍ����̎d���Ɋ�������̂ł͂���܂���̂ŁA���ɂƂ��Ă����͕t���I�Ȃ��̂ł��B
�l�ɂ���ẮA�z�[���̂r�Ȃ̂ǐ^�̓���Ȃŕ�����I�[�P�X�g���̉����A���̃z�[�����������܂߂āA����ŕ����邱�ƂɊ�����������������ł��傤�B
�ł������I�[�P�X�g���Ŗ{���ɕ����������̐Ȃ́A�w����̎w���҂̂ƂȂ�̗������Ȃł��B���̐Ȃ͂r�Ȃ�100�{�x�����Ă������Ă��炦�Ȃ��ł��傤�B�z�[���̑S�Ȃ���߂āA�w���҂������Ă����Ή\�ł��傤���B
���̕��ʂɂ͕����̂��s�\�ȉ��Ɍ���Ȃ��߂������A������ƕς�������܂��A���ɂƂ��ẴI�[�P�X�g���̗��z�Ƃ���ǂ����ł��B
�F�l�́A�u�ǂ����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��H�v�ƕ������Ƃǂ��A�������܂����H
�����ԍ��F11776392
![]() 5�_
5�_
�ԐM����200������ƁA���̃X���b�h�ɂ͕ԐM�ł��Ȃ��Ȃ�܂�
CD�v���[���[ > DENON > DCD-755SE
�V���b�v�]���ł��������i2010�N8��3�� 22:34�@[120705]�j�̂ł���8��2���Ƀ_�E���v���C�X���i�𒍕����܂����������m��̃��[���͗��܂���ł����B
8��3���ɖ₢���킹�̃��[���𑗂�A���̕Ԏ��������̂�8��5���̂����߂��ł����B
8��6���̒���ő��������[���ŘA������ƕԐM�͂������܂������A�ԐM�ɂ�������
�����m�莟��A�u�����m�胁�[���v�𑗐M�����Ē��������̎�z��
�i�߂����Ē����܂��̂ŋX�������肢�\���グ�܂��B
��
�́u�����m�胁�[���v�͂��܂����Ă��܂���B
������8��7���ɏ��i�͓͂��܂����B�i���i�������[�������Ă��܂���ł����̂ł�����ƃr�b�N�����܂����B�j
�A���̐��ɖ�肪����V���b�v�̋C�����܂��B�I�[�N�V�����Ɋ���Ă��鎄�Ƃ��Ă͕s���������܂����B
���i���͖̂�肪���������i������펯�I�Ȕ͈́j�̂ł����A�����ȕ��͍w���������Ȃ��ł��ˁB�}���̎����g���Ȃ��Ɗ����܂��B
���i�ƊW�̖����������݂Ő\����Ȃ��̂ł����A�V���b�v�]���̕ύX���@��������Ȃ������̂ł�����ɏ������܂��Ă��������܂����B
����̃V���b�v�I�т̎Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B�i���i�̒l�i�͂����̍ň��������������ł��B�j
![]() 0�_
0�_
���͂��̃V���b�v��_�E���v���C�X�̏ڍׂȃ��[���͒m��Ȃ��̂ł����A���[���̎�M��(�ڋq��)�̐ݒ�̖��Ń��[�����͂��Ă��Ȃ��A�Ƃ����\���͂Ȃ��ł��傤���H
���̃V���b�v�̃z�[���y�[�W�̈ē������Ă݂�ƁA
http://www.a-price.co.jp/guide/guide_8.jsp
�ɂ�4��ނ̃��[�����A�R���s���[�^�[�����ɂ�莩�����M�����悤�Ɍ����܂����A�X���傳��ɂ͂���炪���ׂē͂��Ă��炸�A�V���b�v�̐l���蓮�ő��M�������[���݂̂��͂��Ă���悤�Ɍ����܂��B(����Ƃ�1�Ԗڂ́u�����ԐM���[���v�����͓͂����̂ł��傤���H)
�^���Đ\����܂��A���̃y�[�W�ɂ�������Ă��܂����A��M���̐ݒ�ɖ��͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͊m�F�ς݂ł��傤���H
�܂��A���[���̖��͕ʂɂ��āA�_�E���v���C�X�Ƃ��������́A���D(?)������ڋq���ɍw���̋`�����������e�ՂɃL�����Z�����ł��Ȃ��Ȃ�̂��A����Ƃ���������O�Ȃ�ڋq�����R�ɃL�����Z���ł���̂��A�Ƃ������[���̎�茈�߂��ǂ��Ȃ��Ă���̂����d�v���낤�Ǝv���܂��B
�������L�����Z���\���Ƃ�����A����̌��Ōڋq�����X�N�ɂ��炳�ꂽ���Ԃ́A��������8��6�����珤�i���͂���8��7���܂ł́A1�`2���Ԃ݂̂ł��̂ŁA����قLj����Ή��ł͂Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B(�������V���b�v���̖��Ń��[�������M����Ă��Ȃ��̂��Ƃ�����A���ڂ�ȑΉ��ł��邱�Ƃ͂��������Ǝv���܂����A�������v���I�Ȗ��Ƃ܂ł͌����Ȃ��Ǝv���܂��B)
�����ԍ��F11735139
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z���C���A�b�v�O���[�hv4.23
-
�y�~�������̃��X�g�z�\�Z23�����x
-
�y�݂�ȂŃ����N�t���z5�N���H�R�X�p�z��AMD�Q�[�~���OPC�\�����F����4��
-
�y�~�������̃��X�g�z�C���z��
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
�i�Ɠd�j
CD�v���[���[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j