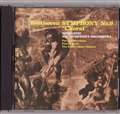���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S440�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 171 | 197 | 2010�N12��15�� 08:38 | |
| 3 | 1 | 2010�N12��13�� 14:21 | |
| 10 | 6 | 2010�N12��13�� 13:47 | |
| 11 | 4 | 2010�N12��10�� 11:31 | |
| 12 | 2 | 2010�N12��7�� 13:03 | |
| 0 | 0 | 2010�N12��3�� 15:00 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�́A�k�o�ŕ��������ɂ͂��炵���D�G�^���������Ɗ������̂��ACD�����ꂽ���̂��ƃK�b�J�������Ƃ����b���A����CD�v���[���[�̔��������̍��͗ǂ������܂����B
�����Ƃ��čl������̂́A
�P�D������CD�v���[���[��DAC���\���Ⴉ�����B
�@�@�@�����A���̈���CD���Ɗ����Ă������̂ł��A�\���N��ɐV�^CD�v���[���[�ŕ�����
�@�@�@���\�ǂ����ŕ����邱�Ƃ�����܂����B
�Q�D���ɃN���V�b�N�ł́ACD�̃_�C�i�~�b�N�����W�̑傫�����ߐM���āA���܂�R���v���b�V�������������Ɏ��^���Ă��܂��A�������x���ŗʎq���m�C�Y���ڂ��Ă��܂��Ă����B
�@�@�@�Ⴆ�A��̃e���[�N�̃`���C�R�t�X�L�[�u����1812�N�v�ł̓J�m���C�̃��x����
�@�@�@���킹�Ď��^�������߂ɁA�I�[�P�X�g���̉������ΓI�ɏ����ȉ��Ŏ��^����Ă���A
�@�@�@�I�[�P�X�g���̔������ł̂������芴����������A�k�o�ɔ�ׂė���Ă��܂����B
�@�@�@���̏ꍇ�A���ʂ��グ�Ă��A�ʎq���m�C�Y����������邾���ŁA��������CD��
�@�@�@������Ƌ~���悤������܂���B
�R�D�k�o����p�̃}�X�^�[�e�[�v�������̃A�i���O�Đ����u�̓������l�����āA����������グ�Ă��������̂�����A��������̂܂g����CD���삷��ƁA���s�q�Ŕ����̗ǂ�CD�Đ����ł́A�P�ɍ��悪�����グ���Ă���ɗ��܂炸�A�c���ۂ����ɉ��̂Ȃ��������ŁA�����ɑς��Ȃ����ɂȂ�B
�@�@�@�{�����Y��ȍ������Đ�����Ă��鑕�u�ŁA�������C�R���C�U�Ŏ����グ�Ă��A
�@�@�@�������L���ɂȂ����Ƃ͊����Ă��A�c���ۂ������ɑς��Ȃ����ɂȂ邱�Ƃ͂܂�
�@�@�@����܂���B�܂�A����͍Đ����u���̑Ή����\�ł��B
�@�@�@���̌o���ł́ACD�v���[���[��A���v�̓d���P�[�u���̌����ŁA�X�g���X�̖���
�@�@�@��������ƐL�т���������₩�œ����ȍ����ɂȂ�܂����B
�@�@�@����ɂ��A����܂ō����������Ċy���߂Ȃ��Ǝv���Ă���CD�̂قƂ�ǂ́A
�@�@�@���܂��Đ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
���ɁA���ɃI�[�P�X�g����SACD���ACD���ނ��뉹��������������Ƃ������������܂��B
�����Ƃ��čl������̂́A
�@SACD��CD�ɔ�ׁA�_�C�i�~�b�N�����W���L���̂ł����A���҂Ƃ��I�[�P�X�g���̍ŋ����́A�قړ������ʂł��B�܂�Ŏ㉹�����Ƀ_�C�i�~�b�N�����W���L���̂ł��B���̂���SACD��CD���A�R���v���b�V�����ʂ͏��Ȃ��ł��܂��B�܂�SACD�ł̏����ʁA�Ⴆ�t���[�g�̓Ƒt�ł̉��ʂ́A�ŋ����Ƃ̍����傫���Ƃ�A���ʂƂ���CD�ł̃t���[�g�Ƒt��艹�ʂ��������Ȃ�܂��B���̂悤�ȏ����ʂ⒆���ʂŁASACD��CD��艹�����������^�����X���ɂ���܂��B���̂��Ƃ��ASACD���ACD���ނ��뉹��������������Ƃ��������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����ɑΏ�������@�́A�N���V�b�N��SACD�Đ����ɂ́A3dB����4.5dB�ق�CD�Đ�����艹�ʂ��グ�邱�Ƃł��B�`�u�A���v�̒��ɂ́uSACD�Q�C���v�Ə̂��āASACD�Đ����ɉ��ʂ�3dB�܂���6dB�グ��@�\�ɂ��ASACD�̍������Đ����͂���Ƃ��Ă���@�킪����܂��B
![]() 7�_
7�_
2010/08/12 23:17�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A���炢���l�߂̖���N�ł��ˁB�������Ɍ�����Ƃ���ŁA�c�|�����W�̍L���D�G�^�����ƃ{�����[�������������Ȃ邵�A�����łȂ��^���͏����ȉ��ŕ����Ă��傤�ǂł��i���Ȃ��Ƃ��N���V�b�N�^���̏ꍇ�j�B
�ǂ��^�����{�����[����������ƁA�S���t�̕����Řc�݂��o�邱�Ƃ�����܂��B����͑��u�������܂��͗�������������A�ƂȂ�܂��̂ŁA���u���������悭����̂��I�[�f�B�I�}�j�A�̏K�Ȃł��B�������A��������Ȃ��l�A�ł��Ȃ��l�́A�����ȉ��ł��ǂ���������u�^���v���D�ނł��傤�ˁB
���Ƃ��b������ƁA���͍ŋ߁A�������H�𑖂�Ԃ̒��ŁA�����Ȃ̂b�c���܂������A�Ԃ̒������邳���āA���������͕������Ȃ����A�傫�ȉ��̕��������傫���������ĎQ��܂����B�r���ŃA���}�E���g���܂����B�ԓ��ŕ����Ȃ��t�����̂Ȃ��|�b�v�ȋȁA���x���̍����^���������ł��ˁB
�����ԍ��F11754851
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A���͂悤�������܂��B
�����ł��ˁA�uSACD�Q�C���v�̐����ł��A�ő剹�ʎ��ɘc�݂���������ꍇ�́A���̋@�\��OFF�ɂ��Ă��������Ə����Ă���܂��ˁB
�����������H�ł́A�N���V�b�N�̋Ȃ͑S�������܂���B����100km�ŃG���W�����펞3000��]�ȏ�ɂȂ�܂����B��͂�A�������ʂ������|�b�v�X�A���̌n�ɂȂ�܂��ˁB
�����ԍ��F11755626
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
�����Ƃ��ǂ�������Ȃ�����������Ă�redfodera�ł��i���I�j
�N���b�V�b�N�͖�O���ł����_�C�i�~�b�N�����W�̑傫�ȃ\�[�X�͂��낢��Ȗʂœ���ł��ˁB
���^�i�K�̃��x���̐ݒ肩�炵�ĔY��ł��܂��܂��B
Minerva2000����
�uoverture1812�v�͉����ƕ��c�������o���\�[�X�ł����Đ����̊�S/N�Ɉ�ԉe������ނ��ł��ˁB
�������H���q���̃��[�h�m�C�Y�Ȃǂ͍ł�����̂ł������Ԃ̎��͂̑������ĈӊO�ɂ���܂�����ˁB
�܂��ǂ��܂ő傫�ȉ����o���邩�ł��\�[�X�ɑ��郆�[�U�̕]���Ɋւ���Ă��܂�����A
AV�A���v�́uSACD�Q�C���v�Ƃ��������A�ꗝ����Ȃ��Ǝv���܂��B
�t���A�����������Ă���܂��B
���ǂ��^�����{�����[����������ƁA�S���t�̕����Řc�݂��o�邱�Ƃ�����܂��B
CD-DA�œ��ɓ��X�����邱�Ƃł����A�ŋ߂͑����̃\�[�X�Ř^�����x�������߂��܂��B
PC�x�[�X�ŕҏW����l�ɂȂ��Ă��烌�x���̒ǂ����݂��e�ՂɂȂ������Q�������܂��B
�w�b�h�}�[�W���������߂��ăN���b�v���O�A�Ƃ��������ɂ���Ă͗e�ՂɃN���b�v���܂����A
24/32bit�����16bit�ւ̃G���R�[�h������ɂ���̔w���������Ă��͂��܂��B
�G���R�[�h�ł�16bit�̃_�C�i�~�b�N�����W����16bit�ȏ�̃_�C�i�~�N�X�����������邽�߂ɁA
�ɒ[�Șb�����܂������߂̋Z�p�Ƃ��Ē�����тɔ��ʂ̃m�C�Y�������Ă܂��iApogee�́uUV22�v�Ȃǁj
�f�B�U���ĉ��y�\�[�X�ɂ͖�ɂ��łɂ��Ȃ���p�O��������Ȃ��̂��H�Ƃ����C�����Ă��܂��B
���͏�L���R��10�������\��̐V��̃}�X�^�����O�ɑ��Ď����X�^�b�t��NG��ʍ������̂ŁA
NG�o�����{�l���ċx�ݕԏ�ōă}�X�^�����O�ɗ�������Ă���܂��i���j
�����ԍ��F11757445
![]() 2�_
2�_
�F�l�A�����́B
redfodera����A
�Đ����̑����ɂ���������Ȃ��A�Y��ɕ�������ŏ����ƁA���̍Đ������Y��ɕ�������ő剹�̍��A�܂�Đ����̃_�C�i�~�b�N�����W���d�v�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����炭���y�\�[�X�Ƃ��Ă�SACD�́u��i����j�v�Ƃ��ẮA��ʂ̍Đ����̃_�C�i�~�b�N�����W���قڃJ�o�[�o���Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B
����A���y�\�[�X����鑤�́A������̃_�C�i�~�b�N�����W���C�ɂȂ�܂��B
�A���v��~�L�T�[�A���R�[�_�[���̓d�q�@��̃_�C�i�~�b�N�����W�͂����炭�傫�Ȗ��͖����̂ł��傤���A�}�C�N�͂ǂ��ł��傤���B
5.1�`�����l���̘^���ł́A�Œ�5�{�̃}�C�N������Ώ\���̂͂��ł����A�����ɃI�[�P�X�g���̘^���̑����̃P�[�X�ŁA���\�{�̃}�C�N���g���Ă���̂́A�}�C�N�̃_�C�i�~�b�N�����W�A�܂��Y��ȉ��ŏW���ł���ŏ��̉��ƍő�̉��̍����A�������\�N���܂�i������������ł��傤���B
�����ԍ��F11758394
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����A�����́B
�������A�X�^�b�t�ƃR���r�j�ٓ��Ŕӂ��у^�C�����ł��i�߁j
�N���V�b�N�̎��^�ɂ����ʂ����G���W�j�A�̘b�ł���Minerva2000����̗\�z�ɋ߂�����͂��邻���ł���B
�G���W�j�A��v���f���[�T�A����ɃA�[�e�B�X�g�̗��z��ӌ�������܂�����P�[�X����Ȃ�ł����A
�����̃G���W�j�A�̗��z�̓z�[�����^�Ȃ璮�O�Ńt���n�E�X�ɂ��Ă���x�X�g�̃��X�j���O�E�V�[�g��T���o���A
�t���n�E�X�̂܂܂��̃V�[�g�Ńo�C�m�[�����̃s���|�C���g�Ŏ��^�������̂Ɛ\���Ă���܂��B
�ł�����ł͏E������Ȃ����Ƃ����̂����Ȃ蔭�����Ă��܂����̗��R�͎�Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̂��ƁB
�}�C�N�̃_�C�i�~�b�N�����W�ɉ����ăt���n�E�X�ɂ����z�[����S/N�ƃ_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��e������邻���ł��B
�~���[�W�b�N�E�z�[���͊�{�I�Ƀt���n�E�X�Ŗ{���̉�����������l�ɐv����Ă��邻���ł��B
�N�����Ȃ�������߂�����c���┽�˂̉�荞�݂��傫���Ȃ�ȂǁA����������Ȃ��Ƃ��낪�����Ƃ��B
�}���`�E�}�C�N�Ŏ��^����w�i�ɂ̓Z�p���[�V�����A�_�C�i�~�b�N�����W�A�A���r�G���X����ʁX�ɗp�ӂ��āA
�ҏW��~�L�V���O�̍ۂɏ����ł������̍ޗ���f�ނƂ��Ďg����l�ɂ��邱�Ƃ݂����ł���B
�����ԍ��F11758754
![]() 2�_
2�_
redfodera����A
�ǂ������d�����A���݂܂���B
�Ȃ�قǁA�z�[����S/N�ƃ_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��e�������̂ł��ˁB
���V�����̂a�c������ƃX�e�[�W��ɂ�������̃}�C�N���ݒu����Ă��܂����A�܂��A�����̃N���V�b�N�b�c�̉�����Ȃǂł́A�V��ނ̃}�C�N���g�p�����Ƃ��A�S�W�b�g�̃~�L�V���O�R���\�[�����g�p�����Ƃ������Ă���A���ς�炸�}���`�}�C�N�Ŏ��^���Ă���悤�Ȃ̂ŁA�^��Ɋ����Ă���܂������A�������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F11758952
![]() 1�_
1�_
2010/08/13 22:59�i1�N�ȏ�O�j
��Ґ��N���V�b�N�^���ł́A�Q�`�R�{�̃}�C�N�ł͑��肸�A�⏕�}�C�N���g���̂��펯�Ǝv���܂����A�f�m���̃����|�C���g�E�G�f�B�V�����͏펯�͂���̎g���������������Ⴞ�Ǝv���܂��B
http://www.hmv.co.jp/search/index.asp?target=MUSIC&category=1&adv=1&keyword=%83%8F%83%93%83%7C%83C%83%93%83g&site=&type=sr
��ԕ\���͂������f���炵���ł����A�𑜓x�A�c�����W����������m�ۂ���Ă��܂��B�}�C�N�͂a���j���Ƃ���Ă���A�P�X�W�O�N��̂b�c�^���ł����A�ւ��Ȃr�`�b�c�����̂��������^�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11758991
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A�����́B
�����N��̍ŏ��ɏЉ�Ă���A�C���o���w���̃}�[���[��5�Ԃ́A�����i�艿3,300�~�j�������Ă���܂��B�Ȃ��Ȃ��f���炵���^�����Ǝv���܂��B
�����A���̉�����ɂ́A�u���̘^���͂a���j�А��^���p�}�C�N���t�H���i4006�|Pressure�^�C�v�j2�{�����ɂ��^������{�Ƃ��A�ꕔ�ɕ⏕�}�C�N���t�H�����g�p���Ă���܂��B�v�Ə����Ă���A���S��2�{�����ł͂Ȃ��悤�ł��B
�����́u�����|�C���g�E�G�f�B�V�����v�Ƃ͈Ⴄ�̂�������܂���B
�����ԍ��F11759230
![]() 1�_
1�_
Minerva����@����ɂ���
�����̈���CD���Ɗ����Ă������̂ł��A
���\���N��ɐV�^CD�v���[���[�ŕ�����
�����\�ǂ����ŕ����邱�Ƃ�����܂���
�܂������A���̂Ƃ���ł��ˁB
���u�i�ƃ��X�i�[�j�̐��\�����シ�邱�ƂŁA��L�̂悤�ȗ�𑽂��o�����܂����B
���Ƃ��A1952�N�̃g�X�J�j�[�j�̑��b�c�Ȃǂ́ASACD�����ɖ点��悤�ȃV�X�e���\���ɂȂ��āA���߂Ă��̊����������̕��ɂ��܂����B
���u�̕����I�����͂��������Ƀ\�[�X�ɑ��Ă̊Ԍ����L����悤�ł��B
�����ԍ��F11759828
![]() 0�_
0�_
2010/08/14 06:25�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A�f�m���̃}�[���[�̂S�Ԃ́A���S�Ƀ����|�C���g�ɂȂ��Ă��܂��B
���ꂩ��A�P�X�X�O���ARTS�̃}�[�N�A�����f���X�]�[�������ȑS�W�̓����|�C���g�ł��B
http://www.hmv.co.jp/product/detail/812041
����͗������W�������A���߉��Ƃ܂�Ȃ��^�����Ǝv���܂������A��Ԃ��ǂ��o�Ă��邱�ƂɋC�Â��A���x�ł������鈤���ׂ��^���ɕς��܂����B
�X�s�[�J�̃C�N���v�X��A�^�C���h���C����yoshii9�݂����ȃR���Z�v�g�̘^���ƌ�������悢���H�@�I�[�f�B�I�͖ڂ̑O�Œ����悤�Ȕ��^�����厖�ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ��ƋC�Â����Ă����^���ł��B
�W���Y�̃g���I���A�����|�C���g�Ř^�����炨�����낢�Ǝv���̂ł��B
�����ԍ��F11759891
![]() 0�_
0�_
�F�l�A���͂悤�������܂��B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
�����u�̕����I�����͂��������Ƀ\�[�X�ɑ��Ă̊Ԍ����L����悤�ł��B
���������v���܂��B�@�u�̘̂^���́A�����̍Đ����u�̃��x���̒Ⴓ�ɍ��킹�ĕςȉ��������Ă����̂ŁA����̍����I�[�f�B�I���u�ŕ����Ɖ��������B�v�Ƃ����̂͑��v�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����ł��A����Ȃ�Ƀ��C�h�����W�Ńp���[�̂���V�X�e���ł��������Ăn�j���o���Ă����͂��ŁA���ꂪ���������ɑς��Ȃ����ɂȂ��Ă���Ƃ�����A�g���Ă��鑕�u���^���������ǂ��ł��傤�B
�����Ƃ��u�����ɑς��Ȃ��v���u���b�N�͕����ɑς��Ȃ��B�v�Ɠ����ŁA�l�̍D�݂̖��Ƃ��Ăł���A�q�ϓI�ɂ́A�̘̂^�����ǂ������o�Ă���̂ł���A���u�ɖ��͖����̂ł����B
�g�X�J�j�[�j���̎ʐ^��q�����܂����B���o�[�g�E�V���E�����c��1952�N���_�Ŋ��Ă����Ƃ͋����ł����B���o�[�g�E�V���E�����c���������Ă���b�c�́ATELARC�́u�J���~�i�E�u���[�i�v���������Ă��܂��A���̂b�c���D�G�^�����Ǝv���܂��B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
�f�m���ł����S�ȃ����|�C���g�^��������̂ł��ˁB
�����m���Ǝv���܂����A�́A�A���h���E�V�����������n�݂����V���������E���R�[�h�ł̓����|�C���g���^�͓I�ɐi�߂Ă���A������X�^�b�N�X�̃R���f���T�[�w�b�h�t�H���ŕ����̂ɂ͂܂������Ƃ�����܂��B�z�[���̍L��ȋ�Ԃ���������^���ł����B
���������̌�A�u�����̋��߂Ă��鉹�͂���ł͂Ȃ��B�v�ƋC�t���܂��āA�P�ނ��܂����B
��͂莄�̋��߂Ă���̂̓��C�h�����W�ŁA�_�C�i�~�b�N�A�܂�u�K�c�[���v�Ɨ���Ŋy��A���NJy��A���y��Ȃ̂ł����B
�W���Y�̃g���I�������|�C���g���^�������̂��D�݂ƌ������͂�����Ǝv���܂��B�ł����͔�юU�銾���}�C�N�ɂ�����悤�ȁA�ߐژ^�����D�݂ł��ˁB
�����ԍ��F11759999
![]() 1�_
1�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
���Љ��CD�͂����̃G���W�j�A���ЂƂ̗��z�ƍl������^���@�ɂǂ����߂����̗̂l�ł��ˁB
���I�[�f�B�I�͖ڂ̑O�Œ����悤�Ȕ��^�����厖�ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ��ƋC�Â����Ă����^���ł��B
�z�[���Ɠ��̉��̋������Ƃ����̂͂���Ǝv���܂����炻�̃z�[���̂Ȃ��ʼn��t���y�����X�i�[�̏�ԁA
����������Ԃ��̂��̂��p�b�P�[�W����_�����܂܂ꂽ�^�C�g���Ȃ̂�������܂���ˁB
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��
�����X�^�b�t�Ƙb�����Ƃ�����̂ł������H�����߂��郊�}�X�^�[���l�����̂���Ȃ����ƁB
���ł�����ł��֊s���������肳������������̃��x���������グ�ďd�S�����������肳���Ă܂����A
�y��̉��F�����Ԃ邱�Ƃ��u�������Ɓv�Ƃ������o���w�i�ɂ���̂�������܂��A
�A���T���u���Ƃ͗l�X�Ȋy�킪���ꂢ�ɏd�Ȃ荬���荇���ċ������`�����̂Ǝv���Ă��܂��B
���ꂼ��̊y�킪�����\������Ȃ��Ń\���p�[�g���ۗ��������蔺�t�Ɨn���������肪�{���̎p�Ɗ�����̂ł����E�E�E
�ǂ������}�X�^�[�Łu�����v���Ă��܂����l�Ȉ�ۂ���^�C�g���ɂ��x�X�������܂��B
Minerva2000����@
���T�͒������}�X�^�����O�̌���ɗ�������Ă��܂�������ɂ��������b����ӎ����Ă��܂����A
�x�e�̎��ɃX�^�b�t���C���]�������˂ĉ��i.com�̃I�[�f�B�I�����������`���Ă����ł���B
�ނ�Ȃ�ɐF�X�Ɗ����邱�Ƃ�����l�ł�����ǂ��`�Ń��X�i�[����Ƀt�B�[�h�o�b�N�ł���A
�܂��I�[�f�B�I�E�t�@���̊F����ɖM�l�A�[�e�B�X�g��POPS�ł��y����ł��炦��^�C�g�������邩���B
�����ԍ��F11760026
![]() 3�_
3�_
redfodera����@����ɂ���
�����}�X�^�[�Łu�����v���Ă��܂����l�Ȉ�ۂ���^�C�g��
�ȑO�͏�L�́u���������I�v�Ɠ{���Ă܂������i���X�i�[�̐��\���オ�����̂Łj�ŋ߂͍l����ς��܂����i����
���Ƃ��A�I���W�i���������炩�����ꂽ���������ɂȂ��āA���y�̉��߂��ς���Ă��܂����ƂɂȂ��Ă��A����͂��̎��_�ł̐��쑤�i�v���j�̔��f�Ȃ̂ŁA��X���낤�Ƃ��ӌ��ł�����̂���Ȃ��ł��B
���������P���́A�u�ׂ���Ή��P�������v�ł����Ǝv���܂��B
����ɁA���}�X�^�ՁA�S�Ă�NG����Ȃ��āA���Ȃ��邢�͂ǂ����̃p�[�g�Łu�S�n�悢�����v���K������܂��̂ŁA����Ȃ�Ɋy���߂܂���B
�u��]�̂ɂ�鉹�y�Đ��ɍS��ҁv�Ƃ��āA�ƊE�̔ɉh�Ƒ�����ɂ��肢���Ă����܂��B
�����ԍ��F11761019
![]() 0�_
0�_
redfodera����A�@����ɂ��́B
�M�l�A�[�e�B�X�g��POPS�ŁA�I�[�f�B�I�I�ɂ��y���߂���̂̃����[�X�����҂��Ă��܂��B
�ŋ߁A�M�l�A�[�e�B�X�g��POPS�Ŏ������S�����̂́A���ꌧ�Ŋ������Ă���O���[�v�AK.K.B.�̃t�@�[�X�g�A���o���ł��B�@�^���A�~�L�V���O��mAru����ƌ��������S������Ă��܂��B���̕��́A�z�[���̂o�`�V�X�e���̉��������ɂ��ւ���Ă����āA���܂������AK.K.B.�����z�[���̉������������̕����s���Ă��������ł��B���̃z�[���́A���s�ʂ��S���Ȃ�����`��ŁA�o�`�V�X�e���ɂ�FUNCTION-ONE���g���Ă��܂����B���t���������̃~���[�W�V�����ɂ����̉����͑�ύD�]�������ł��B
�z�[���̂o�`�V�X�e���̉����������������ƁA�A���o���̘^���A�~�L�V���O��������������l���̂��A���A���C�u�������̃C���[�W���A�A���o���ɂ��Z���ɔ��f����Ă���A���D�G�^���ł����B
�����ԍ��F11761581
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
���̃X�������������Ȃ��Ă��Ă���悤�ł����A�ŏ��̍��ɏo�Ă��������ɃX���B
>���͍ŋ߁A�������H�𑖂�Ԃ̒��ŁA�����Ȃ̂b�c���܂������A�Ԃ̒������邳���āA���������͕������Ȃ����A�傫�ȉ��̕��������傫���������ĎQ��܂����B
>���Ԃ̎��͂̑������ĈӊO�ɂ���܂�����ˁB
�ŋߖʔ������������Ȃ��Ȃ����Ɗ����闝�R�̈�[����������ӂɂ���Ɗ����Ă��܂��B�����A�ŋ߉��y���f�o�C�X�Ƃ���iPod�Ȃǂ�DAP���嗬�ɂȂ��Ă��Ă��܂����A���������f�o�C�X�͎��ɓ˂����݂Ȃ��牮�O��ړ����ɕ��������������Ǝv���܂��B
���̏ꍇ�A���y�̃_�C�i�~�N�X���傫���ƁA���w�E�ɂ������悤�ɁA���肪���邳�߂��ĉ��y���r��r��ɂȂ�܂��B�]���āA�������ƃt�H���e�����̉��y���s�����X�����B���b�v���Ƃ������s���Ă��闝�R�̈�[�������ɂ���悤�ɂ��v���܂��B�m���Ɉړ����͂����������y�������Ղ��ł��B
�ł��A����̂Ȃ����y�Ȃ�āA�����g��Ȃ��`���̂悤�Ȃ��́B�����ɖO���Ă��܂��܂��B������ŋ߂̋Ȃ͒Z���Ȃ̂��E�E�E�B
�{���悩�����悩�ł͂���܂��A�\�j�[���E�H�[�N�}���𐢂ɏo�����͉̂��y���ނ̑����������̂����m��Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂��B���ꂪ�o�����́A�܂�ʼnf��݂����ɗz���̉������[�c�@���g���Ȃ��������̂Ŋ����������̂ł����A���ꂪ�嗬�ɂȂ��Ă��鎖�ʼn��y�̒��������ω����A���ꂪ���y�ɂ����X�j���O�X�^�C���̕ω��ɍ��킹���ϗe�����߂ė����B
����ɕ����Ȃ��畷�����y�́A���܂薼�Ȃł͍����ł���ˁB�����܂Łh�Ȃ���h�ŕ����Ă��܂�����A�ӎ������o�ɏW�����Ă͓]�蕨�ɂԂ������肵���˂܂���B�łɂ���ɂ��Ȃ�Ȃ��A�����S�n�ǂ����ł����OK�B���u�̑O�ł����ߖʂ��ĕ����悤�Ȓ��������̂��鉹�y��NG�B
���[��A�s�K���ȘA���B
�Â��b�ɂȂ����̂ŁA�b��]���B
>�F����ɖM�l�A�[�e�B�X�g��POPS�ł��y����ł��炦��^�C�g�������邩���B
�傢�Ɋ��҂��Ă���܂��B���ł�CD��xrcd��SACD�A����Ƀu���[���C�B�X�ɂ͍ŋߗ��s�̃u���[�X�y�b�N�Ƃ�SHM�ł��o���A��̉����ʼn��������ꂿ�Ⴂ�܂��B(^O^)v
��k�͂��Ă����A���̗ǂ������͑劽�}�ł��̂ŁA�����i�����厖�I�j�����Ă������܂��̂Ŋ撣���ĉ������B
�ł��A���܂葽���Ȃ������m��܂��i���������Ă��Ȃ��������H�j�A���̗ǂ��M�y�������\����܂���ˁB
���Ɏ��́A��і��q����́h�A�g���N�V�I���h�Ȃ������`�F�b�N�Ɏg�����肵�܂��B�P�Ȗڂ́hCosmic Moon�h�Ńu���u�������ቹ�̖���Ղ���y���݁A�T�Ȗڂ́h�l�G�h�ł͏o�����̃M�^�[�ƃx�[�X�A�����ă`�[���ƌ����A���ł����ˁA����B�g���C�A���O���̂悤�ȉ��܂ł̃A�R�[�X�e�B�b�N�Ȏ��R�ȋ������Ă��܂��B
�����ԍ��F11762728
![]() 2�_
2�_
2010/08/15 09:08�i1�N�ȏ�O�j
586RA����̉����`�F�b�N�b�c�̘b���o���̂ŁA�`�F�b�N�̂��ƂɐG��܂��ƁA���͐X���G�̂r�`�b�c�i�s�G�C�G�X;AVEX�j�̃g���b�N�T�ō����̎����������`�F�b�N���Ă��܂��B�`�F�b�N����Ƃ��͉��y�͕������ɁA�����������ɂ̂ݒ��ӂ𒍂��ł܂��B����Ȕ������o��Ƒ�ɏ��o���܂��B���̉����������ɋ������镔���ɂ͂��ځi�����H�j�ɂ����������Ƃ͂���܂���i�����̕������܂߂āj�B�����̌��N�f�f�͂��������ɂ��āA�u�b�c��r�`�b�c��ǂ����ŕ������߂́v�f�f�͌���������Ă���A�Ƃ������b�ł����B
�����ԍ��F11764773
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
�������A���゠�肪�Ƃ��������܂��B
�X�^�b�t�݂̂�Ȃƈꏏ�ɂ����҂ɉ�����l�Ɋ撣�肽���Ǝv���܂��B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��
��]�́A���ɂ��d�v�Ƃ����������̗Ƃł��i���j
Minerva2000����@
���Љ�̃^�C�g���A�@����݂ă`�F�b�N���Ă݂܂��B
586RA����
��і��q����AMIDI����̃A���o������D�ꂽ���̂����������ł���B
������q����AEPO����AMIDI�̓A�[�e�B�X�g�����I�ȃ��[�x���ł������ˁB
�A���o������ł��Ǝ��̃X�^���X�������Ă����ƕ����Ă��܂��B
�t��
�����ł���@������PCM1630�̃R���x���V�����Ŕz�z���ꂽ�e�X�gCD�����݂����܂��B
20�N�O�̂��̂ł������j�A��16it�ł͋��w�̃}�X�^�����O���{���ꂽ�A�C�e���̂ЂƂƎv���Ă܂��B
�����ԍ��F11764987
![]() 1�_
1�_
2010/08/15 14:30�i1�N�ȏ�O�j
Red����A�e�X�g�b�c����ł�����A�������e�X�g���܂��B���Ȃ�̓�ւ̃e�X�g�̂悤�Ȃ̂ŁA���҂ƕs���ŁE�E
���������ɂ͑�R���E�y�ƍs���̂ŁA���ꂩ��������Ȃ�A����ł���@�����肽�����̂ł��ˁB
�����ԍ��F11765962
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
��і��q����̘b��ɂ��āA���ז����܂��B
redfodera����
�ˑR�ł����A�ǂ������������肢���܂�!
���l�́AMIDI����̑�і��q������A�����ƌÂ�1980�N�O��̃A���o��(RCA���[�x��)�̉��Â���ɍD���������Ă��܂��B����30�N���O�Ȃ̂ɁA�����ƂĂ����A���ɒ�ʂ��܂��B����͊y����^�����@���V���v��������Ȃ̂ł́A�Ə���ɑz�����Ă��܂��B
���̌�́A�d�q�@��ɂ�鉹�Â��肪�ڗ����A�����͗ǂ��Ȃ��Ă����ʓI�ȉ��ɂȂ��āA�}�ɃK�����ƕω����Ă��܂��B
���̂悤�ȉ�(�^��?)�̈Ⴂ�́A�@��̕ω��Ƃ���������̕ω��ɂ����̂Ȃ̂ł��傤��?
�������A�[�e�B�X�g���͂��߃A���o������ɂ��������l�B�̍l�����ɂ��̂����m��܂��A�����w�i�����肻���Ȃ̂ŁA�������l��redfodera����ɂ��f���������A���ז���������ł��B��낵�����肢���܂� <(_ _)>
�����ԍ��F11766503
![]() 1�_
1�_
�F�l�A�����́B
hanzou-1����A
�̂̑�і��q����̘^���͗ǂ��A���̌�͂��܂�ǂ��Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA�c�O�ł��ˁB
���̓A���o�����쓙�ɂ͊ւ���Ă��܂���̂ŁAredfodera����̂悤�ɁA���̔w�i�̐����͂ł��܂���B
�ł���і��q����̃A���o������҂��A��ɂ��u�ǂ����ɕ�������v�悤�ɓw�͂���Ă̌��ʂȂ̂ł��傤�ˁB
�����X���b�h�Łu�ǂ����ŕ������߂Ɂv�ƊȒP�ɏ����Ă��܂��܂������A���́u�ǂ����v�Ƃ����̂́A�l�ɂ���đ����ɈقȂ�̂ł��傤�ˁB
����G���̑Βk�ŁA�����ȃW���Y�v���f���[�T�[���u�ǂ����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��H�v�ƕ�����đ����Ɂu���鉹�v�Ɠ����������ł��B�̂悭�s�����W���Y�i���ł�JBL�̃o�b�N���[�h�z�[������o���o���̃g�����y�b�g��T�b�N�X�ƃK���K���̃h�����X���A����r�V�o�V�ƒ@����銴���Ĕ��ł��Ă���A�܂��Ɂu���鉹�v�ł����B�����ŁA�I�X�J�[�E�s�[�^�[�\���E�g���I�́uPlease Request�v�݂����Ȗ����n�̃A���o�������N�G�X�g����q������ƁA���肩�甒���ڂŌ����Ă������̂ł����B
���Ȃ�u�ǂ����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��H�v�ƕ������ƁA�u���t�Ƃ��`���悤�Ƃ��Ă��鉹�y�I�������ő���ɗ^���Ă���鉹�v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�ł�������Ɗi�D�t�������ŁA�Ƃ�Ă��܂��܂����B
������������̂́A��{�I�ɂ͉��t�Ƃ������鉹���̂��̂ł����āA�z�[���̔��ˉ���A�܂��Ă₻�̔��������Y��Ȍ����̎d���Ɋ�������̂ł͂���܂���̂ŁA���ɂƂ��Ă����͕t���I�Ȃ��̂ł��B
�l�ɂ���ẮA�z�[���̂r�Ȃ̂ǐ^�̓���Ȃŕ�����I�[�P�X�g���̉����A���̃z�[�����������܂߂āA����ŕ����邱�ƂɊ�����������������ł��傤�B
�ł������I�[�P�X�g���Ŗ{���ɕ����������̐Ȃ́A�w����̎w���҂̂ƂȂ�̗������Ȃł��B���̐Ȃ͂r�Ȃ�100�{�x�����Ă������Ă��炦�Ȃ��ł��傤�B�z�[���̑S�Ȃ���߂āA�w���҂������Ă����Ή\�ł��傤���B
���̕��ʂɂ͕����̂��s�\�ȉ��Ɍ���Ȃ��߂������A������ƕς�������܂��A���ɂƂ��ẴI�[�P�X�g���̗��z�Ƃ���ǂ����ł��B
�F�l�́A�u�ǂ����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��H�v�ƕ������Ƃǂ��A�������܂����H
�����ԍ��F11776392
![]() 5�_
5�_
Minerva2000����
���X�����A���肪�Ƃ��������܂�!
>�����I�[�P�X�g���Ŗ{���ɕ����������̐Ȃ́A�w����̎w���҂̂ƂȂ�̗������Ȃł��B
�Ȃ�ق�! ��x�����Ă݂����ł��ˁB�����A���������Œ����Ă�Ɠ�ɂȂ肻���ł�(^ ^)
���ɂƂ��Ắu�ǂ����v��Minerva2000����ɋ߂����o�����m��܂���B���̓\�����珬�Ґ��܂ł̋K�͂̉��t���D���ŁA�I�[�f�B�I�ɋ��߂�u�ǂ����v�́A�ڂ̑O�Ő��ʼn��t������̂����肵�Ă���A�R�[�X�e�B�N�ȃ��A���e�B�ł��B�剹�ʂ͋��ł����E�E�BMinerva2000�����������悤�Ƀz�[���̔������͋��߂��A���ɋ@��ʼn��H���ꂽ�G�R�[�͍D���ł͂���܂���B(�Ȃ��A��і��q����̘b���D�݂̖��ł���A�ǂ������ł͂���܂���̂ŁA�O�̂���)
���̐́A���y�z�[���ł��Ȃ������ȉ��ŁA�o�b�n�̖����t�`�F�������Ԃ��(���t�ƂƎ��̋�����3m���炢�ŁA���̊Ԃɐl�������Ȃ���)�ŕ������Ƃ��͊������܂����B�y�킻�̂��̂��o���]�C�̋����������Ă��������͂�����ƒ����܂������A����ȉ����I�[�f�B�I�Őg�߂ɒ�������ǂ��ȂƎv���Ă��܂��B
�������A���̂悤�ɐ����t���Č��������Ƃ����l����������A�X�s�[�J�[����o�鉹�y�����ׂĂ��Ƃ����l��������Ǝv���܂��̂ŁA�������߂邩�͍D�݂̖��ł��ˁB������I�[�f�B�I�͕����L���Ėʔ����̂ł͂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11781179
![]() 2�_
2�_
hanzou-1����A
�w�����̎w���҂Ɠ����ʒu�ŕ����Ă�����A��ɂȂ�̂ł͂Ɨǂ������܂����A�w���҂͉��\�N�ƕ��������Ă��A��ɂȂ��Ďw���������~�߂��Ƃ����b�͕����Ȃ��̂ŁA���v���Ǝv���܂���B
���ہA���b�N�R���T�[�g�̂o�`�̑O�̐Ȃɔ�ׂ���A��̖��悤�ȉ��ŁA1/20�ȉ��̉��ʂł��傤�B�́A�o�`�̑O�̐ȂŃ��b�N������A���炭���肪���Ă��܂����B
���I�[�f�B�I�ɋ��߂�u�ǂ����v�́A�ڂ̑O�Ő��ʼn��t������̂����肵�Ă���A�R�[�X�e�B�N�ȃ��A���e�B�ł��B
�Ȃ�قǁA�������͋��߂Ă����Ȃ��̂ł��ˁB
�ŋ߂̍���SACD�v���[���[�ł͂Q�b�g��p�������̂́A�O���Q�b�g�ŏ\���ŁA�������̔������͂��܂�d�����Ȃ���������������������܂���ˁB
SACD�̃}���`�`�����l���^���̒��ɂ́A�t�����g�X�s�[�J�[�̂͂邩����ɁA��������ʂ�����̂�����܂����A�Q�b�g�w�̍Đ��ł��A����ɂ͋y�Ȃ����̂́A�������Ə����ʂ��Ă���̂�����܂����B
�����ԍ��F11784234
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����@hanzou-1����@���߂܂���
>�����I�[�P�X�g���Ŗ{���ɕ����������̐Ȃ́A�w����̎w���҂̂ƂȂ�̗������Ȃł��B
>���̐Ȃ͂r�Ȃ�100�{�x�����Ă������Ă��炦�Ȃ��ł��傤�B�z�[���̑S�Ȃ���߂āA
>�w���҂������Ă����Ή\�ł��傤���B
�w���҂̂ƂȂ�͕s�\�ł�����A���ۂɕ����ƂȂ�ƍőO��̐^�ł��傤���B
�����̉��t��ɒʂ��Ă��܂��ƁA�����őO��́A�w���҂̏��������̐Ȃŕ�����Ă���A�T�X�y���_�[������Ă�����������������܂��B������Minerva2000����Ɠ����D�݂̕��Ȃ̂ł��傤(�Ђ���Ƃ��Ă��{�l?)�B
�w���҂̈ʒu�ł������ɂȂ肽���̂ł���A�ق�̒Z�����Ԃŏ������Ă��܂��܂����A�薼�̂Ȃ����y��Ƃ��ǂ�����Ă���A�f�l���w����������ɉ��債�Ă݂Ă͂������ł��傤�B
>�w�����̎w���҂Ɠ����ʒu�ŕ����Ă�����A��ɂȂ�̂ł͂Ɨǂ������܂����A
>�w���҂͉��\�N�ƕ��������Ă��A��ɂȂ��Ďw���������~�߂��Ƃ����b�͕����Ȃ�
>�̂ŁA���v���Ǝv���܂���B
�w���҂͂܂����v�ł��傤�B��Ȃ��̂͋��ǂ��������y��Cl�Ƃ�Fg�ł��B���ۂɓ�ɂȂ����A�Ƃ����b���������܂����A���������ĉ��t���Ă���A�Ƃ����b���������܂��B
�s�b�c�o�[�O�̃I�P���ɂ������Ƃ��ATrp���q��ł͂Ȃ��f�J�C���Ő����A���ꂶ��O�ɂ���؊ǂ͊���Ȃ����낤�ȁA�Ǝv�������Ƃ�����܂��B
>���ہA���b�N�R���T�[�g�̂o�`�̑O�̐Ȃɔ�ׂ���A��̖��悤�ȉ��ŁA1/20�ȉ��̉���
>�ł��傤�B�́A�o�`�̑O�̐ȂŃ��b�N������A���炭���肪���Ă��܂����B
�o�`���g���R���T�[�g�́A���b�N�łȂ��A�r�o�̑O�łȂ��Ă��N���V�b�N���f�J�C�����������Ƃ�����܂��B������ׂ̂��Ȃ��ŁA����������Ă��āB�܂�ō���ł����B
�@
�Ȃ��A���́A����l�ƈقȂ�A���t��ł́A�z�|���̌��̕��ŁA�L���ȃz�|���g�|����������ATutti�Ŋe�y�킪���悭�u�����h���ꂽ�����D���ł��B
�����ԍ��F11784818
![]() 1�_
1�_
���H���t��������A�͂��߂܂��āB
>�w���҂̂ƂȂ�͕s�\�ł�����A���ۂɕ����ƂȂ�ƍőO��̐^�ł��傤���B
�őO�ƁA����̋��njQ���y���A�O���̌��t�҂ɎՂ���\���������̂ŁA4��ڂ̒����������͂��ꂽ�Ƃ���ŕ����Ă���܂��B
>�薼�̂Ȃ����y��Ƃ��ǂ�����Ă���A�f�l���w����������ɉ��債�Ă݂Ă͂������ł��傤�B
�N���P��̑��Ńe�i�[�p�[�g��o�X�p�[�g���̂����Ƃ�����܂��̂ŁA�����c�̑O���Ɉʒu���邱�Ƃ�����ƁA�I�[�P�X�g���̑S�̂����n����ߐڈʒu�ŕ����邱�Ƃ�����܂��B�g�����y�b�g�͋q�ȕ����������Ă��܂��̂ŁA��ɂ��Ȃ肻���ɂȂ��ǂ������ł��B�������n�߂����A�{�Ԃő��ۂ̋߂����������Ƃ�����A���̉����Ă������肠�����Ă��܂��܂����B
>��Ȃ��̂͋��ǂ��������y��Cl�Ƃ�Fg�ł��B���ۂɓ�ɂȂ����A�Ƃ����b���������܂����A���������ĉ��t���Ă���A�Ƃ����b���������܂��B
�m���ɃN�����l�b�g��t�@�S�b�g�t�҂͑�ς����ł��ˁB
>�s�b�c�o�[�O�̃I�P���ɂ������Ƃ��ATrp���q��ł͂Ȃ��f�J�C���Ő����A���ꂶ��O�ɂ���؊ǂ͊���Ȃ����낤�ȁA�Ǝv�������Ƃ�����܂��B
�C�O�̃I�P�̋��ǂ͐q��łȂ����ʂ��o�����Ƃ�����܂��ˁB�́A���j���O���[�h�t�B���Ń`���C�R�t�X�L�[�̑�4�ԁi�w���҂̓������B���X�L�[�ł͂Ȃ��A����ł������j�������A�Ƃ�ł��Ȃ��Z���͂̂���g�����y�b�g�ɋ��Q���܂����B
>�o�`���g���R���T�[�g�́A���b�N�łȂ��A�r�o�̑O�łȂ��Ă��N���V�b�N���f�J�C�����������Ƃ�����܂��B
�����ł��ˁB�A���W�F���E�A�L�̃R���T�[�g�ł��o�`���������鉹�́A����Ă͂��܂���ł������A�t���I�[�P�X�g����5�{�ȏ�̑剹�ʂł����B�@�������A���i�剹�ʂ����炢�ȉƓ����A���C�Ȋ�ŕ����Ă���̂ŋ����܂����B���t���n�܂��Ă����A�e�B�b�V���Ŏ���������Ă͂߂Ă�������ł����B
>�Ȃ��A���́A����l�ƈقȂ�A���t��ł́A�z�|���̌��̕��ŁA�L���ȃz�|���g�|����������ATutti�Ŋe�y�킪���悭�u�����h���ꂽ�����D���ł��B
�������������D���ȕ��������Ǝv���܂��B�ł����̓z�[���̌��̕��ŐS�n�ǂ������Ă���ƁA���C���P���Ă���^�`�Ȃ̂ł��B��͂�u���鉹�v�ŁA�ڂ����J���ĕ����̂��D���Ȃ̂ł��B
�����ԍ��F11785338
![]() 1�_
1�_
2010/08/20 00:12�i1�N�ȏ�O�j
�������낢�_���ɂȂ��Ă��܂����A���͕��ʂ̂ǐ^�̐Ȃ���ԍD���ł��B
�ǐ^���ƒ��ډ��ƊԐډ��̔䗦�́A���l�I�ɂ͕�����܂��A�C�����I�ɂ͂V�F�R�ŁA���\���ډ��̔䗦�������̂ł��B�ŋ߂��������̂ɂȂ�Ă��܂��āA�c�����������Ղ�����ꂽ�^���͌h���C���ɂȂ��Ă��܂��B�������A�����牽�ł����N�̂q�b�`�̃g�X�J�j�[�j�m�a�b���̂悤�ȃf�b�h�ȃX�^�W�I�^���͍D�݂܂���B
�Ⴆ�A�Α���̋���̃R���T�[�g�ɉ��x���s���Ă��̉����f���炵���Ǝv���悤�ɂȂ�ƁA�c�����������Ղ�����ꂽ�^�����D�ނ悤�ɂȂ邩������܂���B
����ƃs�b�R���t�҂̎��͑��v���A�Ƃ����v���܂��B����K�v�ł��ˁB
�����ԍ��F11785579
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����@586RA����@����ɂ���
���F�l�́A�u�ǂ����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��H�v�ƕ������Ƃǂ��A
���������܂����H
�u�W���������킸�A���t�҂�����`�������̂��A���̎v�������X�i�[�ɓ`��鉹�v�ł��B�u�����͂̂��鉹�v�ƌ��������Ă��悢�ł��B�����I�����͗ǂ��ē�����O�ł��̂ň��p�͂��܂���B
�ƂƂ�ŁA586RA����I�X�X���́u��і��q����́h�A�g���N�V�I���h�v����肵�܂����BJ-POP�ɂ͒��������C�h�����W�Ńn�C�X�s�[�h�ȃn�C�t�@�C���ł��B���̗ǂ������邱�ƂȂ���A�T�E���h���f���炵���I�@�u�G�����v�ɋ߂��C���[�W�ł����A�����ƗY��ő@�ׁA�܂����{��̔��������ĔF�������Ă���܂��B80�N�����́u�V�j�t�B�G�v�u�R�p���v����20�N�����Ă܂����A��і��q�H���͑S���u���Ă��Ȃ��A���̓����x�E����ɐ������������܂���B
�u��і��q�F�A�g���N�V�I���v���{�l�ł��邱�Ƃ������o����GOOD-MUSIC�ł��B
586RA����A�ǂ����y�̏Љ�A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F11786062
![]() 1�_
1�_
�F�l�A���͂悤�������܂��B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
22�����߂Â��Ă��܂����ˁB�O��lj����ꂽ���̂́AMinervan Black,�v���W�F�N�^�A�T�u�E�[�t�@�ɂȂ�܂��B
>���͕��ʂ̂ǐ^�̐Ȃ���ԍD���ł��B
�N���V�b�N���D�Ƃ̕��̑����́A���̐Ȃ����D���ł͂Ȃ��ł��傤���B��ԁA�o�����X�����Ă���Ǝv���܂��B
>�Ⴆ�A�Α���̋���̃R���T�[�g�ɉ��x���s���Ă��̉����f���炵���Ǝv���悤�ɂȂ�ƁA�c�����������Ղ�����ꂽ�^�����D�ނ悤�ɂȂ邩������܂���B
���������P�[�X�������ł��傤�ˁB���̏ꍇ�A�I�[�P�X�g�������߂ĕ������̂��A���w�Z�̍u���ŁA���������������W�őO����2��ڂ̐Ȃŕ��������Ƃ��A�e�����Ă��邩������܂���B
>����ƃs�b�R���t�҂̎��͑��v���A�Ƃ����v���܂��B����K�v�ł��ˁB
�s�b�R���̍��������ɗǂ��Ȃ���������܂���ˁB����\�v���m�̎�̕����A�u�\�v���m�̎�́A�̂ǂ��甭���鋭��ȍ����̐U���ŁA�F�����O���O���ɂȂ��Ă��܂��B�v�ƌ����Ă��܂������A�}�E�X�s�[�X���͂߂ĉ̂��킯�ɂ��������A�h���悤���Ȃ��ł��ˁB�ł��Y��ȃ\�v���m�̎肪�������ƒm��ƁA������Ƌ����߂ł��ˁB
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
>�u�W���������킸�A���t�҂�����`�������̂��A���̎v�������X�i�[�ɓ`��鉹�v�ł��B�u�����͂̂��鉹�v�ƌ��������Ă��悢�ł��B�����I�����͗ǂ��ē�����O�ł��̂ň��p�͂��܂���B
�Ȃ�قǁA���́u�ǂ����v�̐����͐����͂�����܂��ˁB���y�I������`�������ꍇ�������ł��傤���A�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��̕\���̕����A���L�͈͂��J�o�[���Ă��܂��ˁB
�O�q�����Βk�ŁA�u�ǂ����Ƃ͔��鉹���B�v�Ƃ������̑���́A�u�����������v�Ɠ����Ă��܂��āA�u����Ȃ́A��{���̊�{���B�v�Ɠ˂����܂�Ă��܂����B
�u��і��q�F�A�g���N�V�I���v�͂���Ȃɂ��炵���̂ł��ˁB����͕����Ȃ��Ƃ����܂���ˁB
���́A���˒q�G����́unatural�v�⌳���Ƃ�����́u�n�C�k�~�J�[�v���D�^���ōD���ł��B
�����ԍ��F11786286
![]() 1�_
1�_
2010/08/20 07:29�i1�N�ȏ�O�j
�v���W�F�N�^���V�������̂ł����ASt.Rouge�����Ȃ�̋����������Ǝv���܂��B
�\�v���m�̎�̎����K�^�K�^�ɂȂ��Ă���Ƃ����b�́A���������Ƃ�����A�`�����͂߂Ă���ЂƂ�����Ƃ��B
�����ԍ��F11786308
![]() 0�_
0�_
�c�O�Ȃ���V���ł͂Ȃ��A�v���W�F�N�^���T�u�E�[�t�@���A�O��̓T�[�r�X�ɏo���Ă��Ė����������̂��A�߂��Ă��������ł��B
�T�u�E�[�t�@�͕��i�͂܂��g���܂��A�v���W�F�N�^�̕��́A�������̓_�ł��𑜓x�̓_�ł��C�ɂȂ�̂ł����A����Ȃ��̂��Ɗ�����Ďg���Ă��܂��B
�����ԍ��F11786342
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����A����ɂ��́B���v���U��ł��B
�����Minerva2000����̃v���t�B�[�����炱���������܂����B[�ǂ���]��Nj�����Ă�������Q�W����Ă��܂��̂ŁA�����Q�������ĉ������B
��N�قǑO�̍��ۃI�[�f�B�I�V���[��[Viola]�̃f���œ��ނ̑��u���p�ӂ���Ă��܂����B���G1�𒆐S�Ƃ����V�X�e���A������͋���ȃE�[�t�@�[�ƃz�[��SP�̃V�X�e���ł��BG1�̓R���T�[�g�z�[���Ɛ����ς��Ȃ��������Ă��܂����B������̃V�X�e���͖җ�ȉ��ʂŐK���r���r��������ł��B
G1�̉����܂ł͌�҂̃r���r���h�ł������A���҂��ׂ�Ǝ���G1�̉���h�ł��邱�Ƃ��n�b�L�����܂����B���ꂪ���|���Ńv����C-7����C-800f�ɁA�s�m�C�Y�[���g�����X�t��[SYLVAN]�̓����ƂȂ�܂����B���A�Ŏ����\�t�g�ɂ����܂����A�R���T�[�g�z�[�����i�Œ������Ɛ����ς��Ȃ��������߂ďo�܂����B
�������A�ȑO�̕���h���U�锚�������Y����܂���B�I�[�P�X�g���ł͍őO��Œ������ł��B�呾�ۂ̕��̗h���U��͂Ȃ��Ȃ�܂������A����̕������ɋ߂��C�����܂��B����̑̌��͐��Ŋm�F���悤�Ǝv���Ă��܂��������Ɏ������܂���B
����A����͈ȑO��苭��ɂȂ����悤�ȋC�����܂��BMinerva2000����d���P�[�u�����F�X�Ƃ�����܂������A�X���͕ς��܂���B���C���P�[�u���͌����ł����A����ō����}����Ɛ��ɋ߂�CD�̉����ʖڂɂȂ�܂��B���A�g�p���Ă��郉�C���P�[�u�����I�[�f�B�I�V���b�v�Ŏ�Ă���45���~�̃P�[�u���Ƒ��F�Ȃ������̂ŁA���̂܂g���Ă��܂��B
����ł��ꕔ��CD�͍��悪���������C�ɂ͂Ȃ�܂���B�g�[���R���g���[���̒����͈͂Ǝv���̂ł����AC-800f�ɂ̓g�[���R���g���[��������܂���B����������Ă���ƃV�X�e���̍\�z����������o���o���܂��BBD�Đ��ɐ�ւ��Ĉ��S���鎖���x�X����܂����B
���V���������ɂ��������悤�ł��ˁB���y�Ƃ����������Ƃ͈ӊO�ł����B���y�ɂ͐̂��特�y�Ö@�ƌ������t������悤�ɖƉu���i��[���B]�̋@�\�������������p�����邻���ł��B�����2�`3KHZ�̉����ǂ������ŁA��҂������������������҂ɖ����A30���ԁA���[�c�@���g�̋��t�Ȃ�������ꃕ����ɑ��B�̓X�g�b�v���āA��N��ɂ͊������������ł��B���V�����̓��[�c�@���g�������Ȃ̂��ȁH
����ȍ���̏o��쑾�Y�̃V���Z�T�C�U�[�����t���Ă݂܂����B2�`3KHZ�����Ղ�Ǝv����[���a�̎�]�ł��B�{�����[�����グ��ƁA���̐��ݐ��������[�]��]���}�b�T�[�W����Ă���悤�ŁA�ƂĂ��C�����ǂ��ł��B
�����ԍ��F11787281
![]() 2�_
2�_
�掿�ɂ�����肳��A����ɂ��́B
���v���Ԃ�ł��B
�E�[���A�d���P�[�u���ł̕ω��͏��Ȃ������ł����H
���̏ꍇ�́A�ω��̑傫�ȏ��ɁA
�d���P�[�u�����X�s�[�J�[�P�[�u�����q�b�`�A�i���O�P�[�u�����q�b�`�f�W�^���P�[�u��
�̏��Ԃł��ˁB
���b�N�X�}���̃Z�p���[�g�A���v�̃n�C�G���h���g���Ă��܂��̂ŁA�d���P�[�u���̓��b�N�X�}����JPA-15000���t�����Ă����Ǝv���܂��B���̃P�[�u���́A�m���c�C�X�g�A�m���V�[���h�̂Q�c���s���ł����A�����͑�ϗǂ��Ǝv���܂��̂Ō��������K�v���͂��܂�Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�A�L���t�F�[�Y�̌ܐ�~���Ȃ��t���d���P�[�u���Ƃ͑�Ⴂ�ł��B
�������b�N�X�}���̂��̃P�[�u���ɂ͋ɐ��\�����Ȃ����߁A���ۂɕ����ăX���[�Y�ȉ����o�������T���K�v������܂��B
�b�c�v���[���[�̓d���P�[�u���ɁA�O�H�d���̂o�b�|�P���g����Ƃ�荂�悪���炩�ɂȂ�悤�ɂ��v���܂����A���ۂɂ͌������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂���ˁB
���Ŏ��ʊm���͈�ʂɍ����̂ɁA�w���҂Ŋ��ɂ�����l�͏��Ȃ���������܂���ˁB�I�[�f�B�I�]�_�Ƃł��A���疾���A�R���h�O���A�����S�j���́A��r�I�ɎႭ���ĖS���Ȃ�܂������A�݂Ȃ���ْ��^�̉����D�݂������悤�ł��B�����b�N�X�ł��鉹���D���ȕ��͒������ł��邩������܂���B
�ǂ���玄�̗]���͒Z�������ł��B�����쑾�Y�̃V���Z�T�C�U�[���Ă݂悤���ȁB
�����ԍ��F11788542
![]() 2�_
2�_
Minerva2000����
���b�c�v���[���[�̓d���P�[�u���ɁA�O�H�d���̂o�b�|�P���g����Ƃ�荂�悪���炩��
�����A�o�b�|�P����z���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�쑽�Y��CD�̓O���~�[�܂�������Ƃ��ɍw�����܂������A���܂ɂ́A�������������ǂ��Ǝv���܂���B[���a�̎�]�͏܂��l������ȑO�̍�i�ł����A�������^��[���_]��Minerva2000����D�݂̉�������Ǝv���܂��B���͂̓e���[�N��[�J�m���C]�Ɏ������̂ł��B22���̃��[�W������̃I�t��ɊԂɍ������A�����瑬�B�ő���܂��B����ɂ��܂��Ă��R�s�[���đ���Ԃ��ĉ������B
�����ԍ��F11789414
![]() 2�_
2�_
�掿�ɂ�����肳��A
�����A���B�ő����Ă���������Ƃ́A���k�ł��B���肪�Ƃ��������܂��B
�掿�ɂ�����肳����A�����ʂɗ�����@�����A���Ђ�������肭�������B���s�w����20�����炸�ōŊ��w�ɒ����܂��B
PC-1�ő_���ǂ���A�������炩�ɂȂ�Ɨǂ��ł��ˁB���́A����͎g�������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�����̎G���ł̂��낢��ȃI�[�f�B�I�]�_�Ƃ̕]��������ƁA�܂��ԈႢ�Ȃ��Ǝv���̂ł����B
�����ԍ��F11789802
![]() 2�_
2�_
2010/08/22 19:11�i1�N�ȏ�O�j
�����̓X�����Minerva����̂�������K�₳���Ă��������܂����B���z�̉����ɏ������݂܂����B
http://engawa.kakaku.com/userbbs/390/#390-94
�����ԍ��F11797995
![]() 1�_
1�_
�F�l�A�����́B
�{���́A�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������̂�����ɂ��A���[�W������ɂ����Ē����A��������s���܂����B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A���[�W������A�������������炨�z�����������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B���낢��ȍ������\�[�X���y���܂��Ē����܂����B
���}�n�̒����`�u�A���v��KEF��iQ70�̑g�ݍ��킹�Ƃ��ẮA�܂��܂��̉����o�Ă���Ɗ����Ē������̂ł͂Ǝv���܂����A.....
�������A�����l�����������̌������b�c�̈ꕔ�ŁAiQ70�̃E�[�t�@����U�肵�ē��銴�o������A600W��40�g���ȉ������T�u�E�[�t�@�����Ă��������Ȃ��������������܂����B���̗ǂ������l�Ƃ��A�����Ƀ��}�n�̒����`�u�A���v��KEF��iQ70�̑g�ݍ��킹�ɂ����̌��E��������ꂽ���ƂƎv���܂��B
�����l�̎����܂ꂽ�\�[�X�ƁA�����p�ӂ����\�[�X�i�f�W�^�������̘^��܂ށj���ւ��Ď������i�߂邤���ɁA�厸�s�����Ă��܂��܂����B
�����l���������ꂽ���A�掿�ɂ�����肳��A�����قǑ��B�ł����߂̂b�c�i�쑽�Y�j���͂��Ă��邱�Ƃ����b���A�����Ɏ�����ł����̂ł����A�Ȃ�ƍĐ����Y��Ă��܂��܂����B
�掿�̂�����肳��A�����������B�ł����蒸�����̂ɁA�{���ɐ\����܂���B
�����l���A��ꂽ��A�u���_�v��-10dB�ōĐ����Ă݂܂����B����͐������ۂ̒ቹ�ł��ˁB
iQ70���琦�܂�������Ƀ_���s���O���������ቹ�����o���Ă��܂����B����ł��A����B���̒ቹ�ƃe���[�N�̃J�m���C���A-5dB�ł����������Ă���A�����l�̈�ۂ��傫���ς�����̂ł͂Ɖ���܂�܂��B
�����͏������A�����������M���Ǐ�ԂŁA�ߌ�������̑̒��łȂ��A�J�m���C���S���ł͂Ȃ��A���܂��ɁA�掿�̂�����肳���߂́u���_�v�������l�ɂ����������Y��A���炭��������܂���B
�ł��A���̗��҂������������Ă�����A�啪��ۂ͕ς�����ł��傤���A���̒��̌������b�c���������͎̂����ł��B�T�u�[�t�@�����Ă����������A�P�Ɉ�a���̗ʂ������������Ȃ̂́A�P���Ȗ��ł͂Ȃ��悤�ł��B�܂��J�m���C��쑽�Y�́u���_�v�͂��܂��Đ��ł��Ă���̂ŁA���̂Ƃ��ē�����ł��B�ቹ�̎����Ⴄ�̂ł��傤���H�@�܂���������܂�����A���Ƃ����P�Ɍ����A�`�������W�������Ǝv���܂��B
�܂��A���[�W������̂���ɂ��A�@�����܂�����A���Ўf�킹�Ă������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11798870
![]() 2�_
2�_
Minerva2000����A�����́B
�������I�t��A�����l�ł����B
��iQ70���琦�܂�������Ƀ_���s���O���������ቹ�����o���Ă��܂����B
����͂���ŗǂ��Ǝv���܂���B�����Ĕߊς��鎖�͂���܂���B�����p���[�A���v��M-7f����M-800A�ɐ�ւ����Ƃ��ɓ����l�Ȍo�������܂����B�|10db�ł͉��ʕs�������m��܂��A����h���U��A�K�������グ����悤�ȉ����o��͂��ł��B���ꂪM-800A�ɂ��Ă���͋��͕ς��܂��A�W���ɂȂ�܂����B����h���U���Ă������͕����ɂȂ�܂����B�R���T�[�g�̑呾�ۂ̉��͐��ɋ߂��Ȃ����悤�Ɋ����܂����A[���_]�̑��ۂ̉���M-7f�̕������͂�����A���͍D���ł��B
�����ԍ��F11799680
![]() 2�_
2�_
�掿�ɂ�����肳��A���͂悤�������܂��B
�u���_�v�̑��ۂ̉��́AM-7f�̕������͂�����܂����H�O���[�h�A�b�v���Ă��A�S�Ă̓_�Ŗ����x�����シ��̂́A�ނ������悤�ł��ˁB
����̒ቹ�̌������A�b�c�̌��ł����A�掿�̂�����肳��̃V�X�e���Ȃ�A�Œ��ɃK���ƐL�тāA���ȃu�[�~���O��ԂɂȂ邱�Ƃ͖����Ǝv���܂��B���̃u�[�~���O��Ԃ́ADSP-AX4600��Diatone DS-1000�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł͕��������Ƃ��Ȃ����̂ł��B
�J�m���C��쑽�Y�̑��ۂ����Ȃ��āA��̂b�c�Ŗ�肪����̂́A�O�҂̏u���I�ȉ��ɂ́ADSP-AX4600�̓d����H�̓d���������Ȃ�Ƃ��ǂ����Ă��邪�A��҂ł͎����I�Ȓቹ�̂��߁A�R���f���T�[�Œ~����ꂽ�d�͂��g�������Ă��܂��A�u�[�~�[�ȉ��ɂȂ����̂��Ƃ��v���܂������A��҂ŁA�ŏ��܂Ƃ��ȉ��ŁA1�b��Ƀu�[�~�[�ȉ��ɂȂ�Ȃ番��܂����A�o�������炸���ƃu�[�~�[�Ȃ̂ŁA���̌����ł͂Ȃ������ł��B�܂�DS-1000�Œ����u�[�X�g���ĕ����Ă������Ƃ�����܂����A����ȕςȃu�[�~�[�ȉ��͕��������Ƃ�����܂���B
�܂�40�g���ȉ��̑剹�ʂ̒ቹ��iQ70�����Ă������A�����U������60�`80Hz�̃u�[�~�[�ȉ����o�Ă���̂��Ƃ��v���܂������A�T�u�E�[�t�@��SX-DW75��40Hz�ȏ���J�b�g���Ă���̂ɓ����u�[�~�[�ȉ�������ɏo�Ă��܂����̂ŁA���̌����ł��Ȃ������ł��B�܂��J�m���C���쑽�Y�̑��ۂ�40Hz�ȉ��͂�����������Ă���͂��ł��̂ŁA�܂��܂����̌����Ƃ͍l�����܂���B
�ƂȂ�ƁAiQ70�̌��ŁA��̂b�c�����Ƃ͑����������Ƃ��l�����܂����ASX-DW75����������u�[�~�[�ȉ�������ɏo�Ă��܂����̂ŁASX-DW75�Ƃ������������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A�Ȃ��ǂ�����܂���B
6��Ԃ��炭��A��ΓI�ȃG�A�{�����[���̕s���������Ƃ��l�����܂����ADS-1000�Œ��u�[�X�g��Ԃł͕��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA���ꂪ�����ƌ��ߕt����̂�����������悤�ł��B
�Ƃ������ƂŁA���̂Ƃ���m���錴�����v�������A���������đ�Ă��v�����Ȃ��A�������Ԃł��B
�����ԍ��F11800730
![]() 2�_
2�_
�F�l�A�����́B
���̂b�c�ł����A�����y���݂����b�c�̗ނł͂���܂���̂ŁA�u����Ȃ��͖̂����v�ƍl���邱�Ƃɂ�����}�ɋC���y�ɂȂ�A���C�ɂȂ��Ă��܂����B
���̊y���݂����b�c���A���ׂč������ŕ��������ŏ\���ŁA���������Ȃ������ꕔ�̂b�c�܂ō������ōĐ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͑S���Ȃ��킯�ł��B
�������AiQ70�������ȍ������ł���Ƃ́A�S���l���Ă͂��炸�A�Ⴆ�A�V�����e�B�w���́u�V���E����v�̖`���̍Ō�ő呾�ۂ��u�h�[���v�Ɩ�Ƃ���́AJBL��K2-S9900�̕\���̂ق��������Ƌ��͂ŁAiQ70�ł̓u�[�~�[�ł͂Ȃ��𑜓x�������͂�����ƕ������͂��܂����AJBL�̍Œ��Ɍ��������͂ȉ��̕\���͖����ł��B
�悤�₭�A������O�̂��ƂɋC�Â��܂��Ĉ���S���܂������A�����������Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F11804062
![]() 2�_
2�_
Minerva2000����A�����́B
����CD�͒��̎�����`�F�b�N����ׂɈӐ}�I�ɍ��ꂽCD�ł͂Ȃ��ł��傤���B�����s�̕i�Ƃ��Ĕ������Ă���Εs�K�iCD�ł��B���������x���̒���g�������Ă���Ƒz�����܂��B���ׂ̈Ƀo�[�X�g��Ԃ��o��̂��Ǝv���܂��B���x�A�^�����x�����ُ�ɏグ�Ę^�����āA������Đ������ꍇ�Ɠ����ł��B
�������ł��呾�ۂ̋����͑�ςɋC�����ǂ��ł����A����g�̓_���̉��A���͔��d�̉��A�������H���̉����ƌ��Q�̕��ނɓ���܂��B���y����Ŏx��Ȃ������̃u�[�~���O�͖������ꂽ�����ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11804136
![]() 3�_
3�_
�掿�ɂ�����肳��A�����́B
�A�h�o�C�X���ǂ������肪�Ƃ��������܂��B���܂ŕ��������̖����o�����X�̂b�c�ł����̂ŁA�ʐH����Ă��܂��܂����B
�u����Ȃ��͖̂����v�ƍl���邱�Ƃɂ�����C���y�ɂȂ�܂����B
�܂����̒��ɂ͂Ƃ�ł��Ȃ��n�C�G���h�X�s�[�J�[�i�ꎮ200���h���j������܂��̂ŁA���̂b�c������Ȃ�ɗǂ����ŕ�������n�C�G���h�����݂��邩������܂���B���ɂ͑z���ł��܂��B
�����ԍ��F11804217
![]() 2�_
2�_
���̂b�c�ɂ��ĕ⑫���܂��ƁA�\�[�X�s���́A���x�����������Ă��Ȃ��b�c�|�q�ł����B
��͂肱����܂Ƃ��ɍĐ��ł���n�C�G���h�͖����ł��傤�B�n�C�G���h��100�g���ȉ����܂Ƃ��ɍĐ����Ă��܂��܂��̂ŁB
�����ԍ��F11807041
![]() 2�_
2�_
2010/08/24 20:29�i1�N�ȏ�O�j
�F������(^_^)v
�~�l���o����
����͂����Ґ��ɂ��肪�Ƃ��������܂���m(_ _)m
�������������łj�d�e����Ԍ��C�n�c���c�ɉ̂��Ă���܂�����I
�������`�u�A���v�ŁI
�ܘ_�A�X�s�[�J�[�Z�b�e�B���O�≹���O�b�Y�ɂ��H�v�ςݏd�˂̎������ő�̗v���Ƃ͎v���܂����B
���[�G���h�͌��a�N���Ŗ���������͓̂��R�ł����A�O���[�X�}�[���̃g�����W�F���g�͂��Ȃ�撣���Ă����Ǝv���܂��B
�^���̃\�i�X�ɂ͈������Ɓi��
���āA�b��̃Q�Q�Q�ł����A�����w�C���[�Ɣ��ގq�y�уL���O�R���O�ŃX�b�J���Y��Ă��܂��܂���(^_^;)
�掿�����߂̈�i�͎��̋@���(^O^)
�������Ȃ��Ȃ�������
�����H�[�̂悤�ȃ��r���O�ɂ��܂��܂����i��
�����O�b�Y���ʂ��A�F�X�悫�̌����o���܂����B
�T�C�Y�����ʊ��͑f���炵���ł��I
���肪�Ƃ��������܂���(^O^)
�����ԍ��F11807284
![]() 2�_
2�_
�r�����������@�q������������A�����́B
����́A���H���z�������������肪�Ƃ��������܂����B
���������������łj�d�e����Ԍ��C�n�c���c�ɉ̂��Ă���܂�����I�������`�u�A���v�ŁI
�o���L�x�ȃ��[�W������ɁA���������Ă���������ƁA����܂ł̋�J�����ꂽ�v���ł��B
�O���[�X�}�[���̃��C�u�^���́A�^�����̂����ٓI�ɂ��炵�������ł��ˁB
�ʂ̂Ƃ���ŐG����Ă��܂����A�䂪�Ƃ̍ő�̃l�b�N���c�u�c���R�[�_�[�i����ƃv���W�F�N�^�ł����A�R�c�Ή���҂��Ă���ƁH�H�j�ɂ���܂��B�߂������ɍX�V�\��ł��̂ŁA���̋�������Ă�܂����z�����������B
�掿�ɂ�����肳���߂̂b�c�͐����ቹ�������Ă���A���Q���܂��̂ŁA���[�W�������̑���a�E�[�t�@�ł��Ђ��������肢�������̂ł��B
�����ԍ��F11807563
![]() 2�_
2�_
2010/08/24 21:56�i1�N�ȏ�O�j
�~�l���o����
�k���ă��X��ǂݕԂ��܂��ƁA���ނ���ɍ��g�H���ꂨ��ꂾ�����̂ł���(^_^;)
�ɂ��W��炸�A�n�������ē����Ă�w�܂ł����蒸�����k�ł��B
���āA�ʃX���ł̌����]�X�́A�f�B�W�^���f�[�^�̂܂ܓ`���ł��A���k�����ł͌��E������Ƃ̈Ӗ������ł��B
�^���v���Z�X���ɂ��������肻���ł���(^_^;)
�䂪�Ƃɂ����Đ����������\�t�g�Ƃ��āA�e���[�N�̃f�B�W�^���o�b�n������܂��̂ŁA�����Đ������������B
���݂ɁA�����L�x�Ȍo���͎U�����炢�ł��i����
�����ԍ��F11807870
![]() 2�_
2�_
2010/08/24 22:05�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A���͏t�̍ՓT�̃o���G���������납�����ł��B�U��t���炵���U��t�����Ȃ��A����炵�Ă��邾���̂悤�ɂ�����������ǁE�E�E�H�����q�Ȃǂ̉��̂��y���߂܂����B�L���O�R���O�͋��|���������ĉ��x���ς����Ǝv���܂���ł����B���͂b�c�|�q�͈�؎������܂Ȃ������ł����B
�����ԍ��F11807926
![]() 1�_
1�_
�F����A�����́A
hanzou-1����A
���X����ϒx���Ȃ�\����L��܂���B
RCA����̑�і��q����̃A���o���͂قƂ�ǒ��������Ƃ��Ȃ��L�������܂�肩�ł���܂���B
����͐����ł���MIDI�Ɉڂ��Ă���̓��[�x���̃e�[�}�ƌ����ׂ��|���V�[�̉e���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���[�x���̖��̂̒ʂ�A�����A�A�}�`���A�ɂ���C�ɐZ������MIDI�����ɂ��ł����݂��g���āA
�d�q�y��ł����Ƀ|�b�v�ł��ăi�`�������ȉ��y��n�����邩�ɎQ���A�[�e�B�X�g���^�����Ă����͂��ł����A
���̃e�[�}�ɉ����Đ��삪�i�߂�ꂽ���̂Ɛ��@���܂��B
�܂���і��q���g���L�[�{�[�h���������ł�����V���Z�ɂ�������x�̒m���ƊS�������Ă����l�ŁA
�V���Z+�V�[�N�G���T�[���g�����}�e���A���Ŏ���ϋɓI�Ƀv���v����i�߂���ƕ����Ă��܂��B
�y�킪���ʓI�ɒ�������̂�MIDI������T���v�����O�����������炭���C���^�肵�Ă�������ł��傤�B
���݂͓d�q�y����A���v�Ŗ炵�ă}�C�N�ŋ�Ԃ��Ǝ��^����������Ă܂����A
������8�r�b�g�����Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǃV���Z��T���v���[�̉������̂��̂̎������サ�Ă��܂��B
10�N20�N�ʼn��y�Ɋւ�邢�낢��ȕ���ŋZ�p���i���������Ƃ��ۂ߂Ȃ��������Ǝv���܂��B
Minerva2000����@
������ł̃I�[�f�B�I�E�T�~�b�g�A�������Ŏ��肪�����������l�q�����b�̒[�X����f���܂��B
�@�ދ@��͂��납�d�C�d������f�W�^���Z�p�ɂ܂Ő��ʂ������ł�����A
���Q�����ꂽ�F����Ƃ��݂��ɗǂ��h���ɂȂ�ꂽ�݂����ł��ˁB
�Ƃ����I�[�f�B�I�͓Ƃ葊�o�ŗ��̉��l�ɂȂ肪���Ȑ��E���Ǝv���܂����A
��O�҂̗����Ȉӌ��⊴�z���ĕ|�����ʂłƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂���ˁB
�����@��ƃ^�C�~���O�������ǂȂ����ƈꏏ�ɃT�~�b�g�ɎQ���������Ǝv���Ă��܂��B
Strike Rouge����
���v���Ԃ�ł��ˁB
�o����֎~�ɂȂ������̃X���ł͌����ɂ�����ɉ��܂���܂�����i�����j
�����ҁA�v�����炸�A�E�\����ő����d����Ƃ͎v��ȂB
����͂���s���ł������܂�����B
����ɂ��Ă��R�����r�A���r�N�^�[��K2�`�[���ɂ͒E�X�B
����Ȏ��g�����烁�f�B�A�ɕ��荞�߂�Ƃ́E�E�E�����A�M������A�Ƃ��������i��j
�����ԍ��F11808378
![]() 3�_
3�_
2010/08/24 23:19�i1�N�ȏ�O�j
red����
���v���Ԃ�`
�Ured�����`�i�䔚
*�o�ցH�X���Q��
�ŁA�����ɉ��܂��ꂽ�H
�܂��܂��䌪�����i��
�T�~�b�g�ł��L���b�`���[�~�b�g�ł����ł���������A���ꏏ���܂����B
���_�́A���A�����A�֓��Ɗe�n�ɂ���܂����`
����I
���[������͂��ȁI
mbfrouge02@yahoo.co.jp
�V�[�e�b�N�T�~�b�g�͏o�ȃm���}�ł����`
�����ԍ��F11808454
![]() 2�_
2�_
�r�����������@�q������������A
���̒��A�S�O���قlj��V���ő��ނ��肵�Ă�����A���M���ǂɂȂ��ċC���������Ȃ�A���̃V�����[�ő̂��₵�A�G�A�R���������āA��@�̕��ĂăN�[���_�E�����Ă��܂����B
�����������������̂������_����ԂɂȂ��������ł������A�O�ɏo�ĊO�C���z�����猳�C�ɂȂ�܂����̂ŁA������Ɗ�蓹���܂����B�������Ēx���Ȃ���f�������̂ł͂Ǝv���Ă��܂����B
�`�`�b�͔�t�̈��k�����ŁA�k�̂k�o�b�l�ɔ�ׂ�Ɖ����͌����Ɍ����Η����Ă���Ǝv���܂����A�����Ɍ������Ă���ꍇ������Ǝv���܂����A�������ł��傤���H�m�g�j�̘^���ɂȂ��߂Ȃ��Ƃ����ʂ����邩������܂��B
�e���[�N�̃f�B�W�^���o�b�n����BACHBUSTERS�̂��Ƃł��傤���H����͎��������Ă���܂��BTime Warp�͂������ł����H������h���E�h�[�V�[��Ȃ̋Ȃ������Ă��܂��B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
�t�̍ՓT�̃o���G���C�ɂ����Ă��������ėǂ������ł��B���̐U��t���́A�������̓`���̃j�W���X�L�[�̐U��t���Ɋ�Â������̂������ł��B�������̈ߑ��́A�㔼�ɘ^�悵�Ă����āA���������Ȃ������A�x�W���[���o���[�c�̈ߑ��i�قƂ�lj����g�ɂ��Ă��Ȃ��悤�ȁj�ɋ߂����������ł����B
�H�����q�Ȃǂ̉��̂��y���߂܂������B�������\�D���ł��B
�L���O�R���O�͋��|���������V�[�����肨�������܂������A�S�̂Ƃ��Ă݂�A�L���O�R���O�ƃA���E�_���E�̃��}���X�f��ŁA�����܂��B
�b�c�|�q�̌��ɂ��ẮA���̊��Ⴂ�̏������݂�����A�{���Ɉ�a�����������̂͂b�c�|�q�P�������ł����B
redfodera����A
�s�����t���A���ł���l�ł��z�����������Č��\�ł���B����́A�d���W�ɂ��Ă͂���l�ɂقƂ�ǐ������Ă���܂��A���b�������Ǝv���܂��B�䂪�Ƃ̃I�[�f�B�I�����͋ɂ߂ċ����̂ŁA��l�ŗ���������ǂ����Ǝv���܂��B�������A�ǂȂ����Ɠ�l�ŗ����Ă��\���܂��A3�l�ŗ�����Ǝ_���œ|���l���o�邩���B
�����ԍ��F11808770
![]() 3�_
3�_
2010/08/25 08:49�i1�N�ȏ�O�j
���͂悤�������܂�(^_^)v
�~�l���o����
�X�C�}�Z���A�_�f���ʏ�������m�ł�(^_^;)
�K�C�h�t�������ē��A���S�g���Ɋ��ӂ��Ă���܂�m(_ _)m
�a�c�Ȃ�A�F�X����܂����炨�����łȂ����̂̓����^�����܂���B
��ʂ�A�A�i���O���ォ��m�g�j�̘^�����D�݂łȂ����m�ł�(^_^;)
�������������Ĉ������ފ����E�E�E�E�E
��ƕ��A�`�����Ȃ��̂��Ȃ��`�H
���k�����̂ɕK���f�R�[�_�e�����A���]�����[�g���Ⴂ�ł����A��������ł͊撣���Ă�̂�����Ǝv���܂��B
�Ⴆ��WOWOW�̂T�D�P�T���E���h���ł��ˁB
�o�b�n�͂��̃o�X�^�[�Y�ł��I
���[�G���h�������I
�����ԍ��F11809855
![]() 4�_
4�_
�r�����������@�q������������AMinerva2000����A�����́B
�r�����������@�q������������A���̐߂͑�ςɂ����b�ɂȂ�܂����B����\���グ�܂��B
���������������Ĉ������ފ����E�E�E�E�E
���͑S���t�ł��BCD��SACD�̕������������܂��B�N���V�b�N�̏ꍇ�A�������@���̂��鉹�ɒ�������̂ŁA�ő������Đ�����鉹�ʂɏグ��Ɛ����t�ɋ߂��Ȃ�܂��B
���NHK�̕����͉��ʖL���ɒ������܂��B����͉��ʂɊW�Ȃ��S�n�ǂ��������܂��B�@�����܂��܂��ł���B�����BShi�Ř^�悵��BD�A���W���[�E�m�����g���̃x�[�g�[�x���̌����ȑ��Ԃ�EXTON��SACD�A�A�V���P�i�[�W�w���̓����Ȃ𗼕��Ƃ��������t���ă��s�[�g�Đ��ɂ��A�F�l�ɒ����Ă��炢�܂����B
�ڑ���BD�̓V���[�v��HD100��SA1(DAC���)��C-800f��M-800A�ł��B(�p���[��A���o��)
SACD�̓}�����cSA�|�VS1��C-800f��M-800A�ł��B(�p���[�E�o�����X�ڑ�)
�����M800A�̓��͐ؑւ�����Əu���ɉ������r���鎖���o���܂��B���ʂ��グ����A�i������A�������ւ��Ă��邤���Ƀu���C���h�e�X�g�̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�܂����B�F�l��BD�̕��ɌR�z�������܂����B
�܂��A[SYLVAN]�̓����̂Ƃ��ɓ����a�G���W�j�A�����O�̎R�������A���܂��܂��{�l���ʂ��Ă���T���g���[�z�[����BD������܂����̂ŁA�����Ă��炢�܂����B5.1CH��BD���R�AX90�A�v���AAX4600�A�p���[�AM-800A�̍\���ł������A�I�[�f�B�I�̉����Ƃ��Ă͏[�����Ƃ��n�t�������炢�܂����B
BShi�͕����J�n�ȑO�̎�����������^������Ă��܂����A�N�X�������ǂ��Ȃ��Ă���悤�ȋC�����܂��B����M800A�̔��M��[KURO]�̔��M��[KURO]�̉f���̓J�b�g���ĉ��t���Ă��܂��B
�����ԍ��F11811297
![]() 4�_
4�_
Minerva2000����A���Q�W�̊F���܁A������
�掿�ɂ�����肳��̋�
�����NHK�̕����͉��ʖL���ɒ������܂��B
������͉��ʂɊW�Ȃ��S�n�ǂ��������܂��B
���@�����܂��܂��ł���B
BS hi�̉��ł����A�����̊��ł́A�uCD��ʂ���v�Ƃ̔F���ł��B
�u�S�n�ǂ��������܂��v�Ƃ����g�R���A�������Ă���C�ɂȂ��Ă��܂��B
���k���Ă���Ƃ��̖��ł͂Ȃ��A�u�o�����X���ǂ��v�̂��A�u�����S�n���ǂ��v��ł��ˁB
NHK�ɂ́A�����喇����[���Ă��܂����A�g���̉����Ȃ狖�����I�h�Ƃ����S���ł��B
�N���̍g���̍���ȂA�����������ςȂ��f�X�E�E�E�����Ɉ�x����Ə������Ⴂ�܂����i��
BD/DVD/HDD���R�[�_�[��SONY BDZ-95X�ŁA�X�e���I2Ch�̓A�i���ORCA���v���A���v�Ƃ����ڑ��ł��B��́AHDMI�Œ��ڃe���r�ɁB
HDD��DR���[�h�Ř^��^�^���������̂����̂܂܍Đ�����̂��ō��ŁA
BD�Ƀ_�r���O�������̂��Đ�����ƁA���X�A�����������܂��B
�ʂ��Ɖ����ɂ���ĕς��܂����A�X�e���I2Ch�Đ��̏ꍇ�A
�P�j�V���O�����C���[�kSACD�iSHM-SACD�j
�Q�j��LP ���R�[�h
�R�j��BS hi HDD��
�S�j���n�C�u���b�hSACD��BS hi BD�_�r���O��
�T�j���b�c
�Ƃ�����ۂ������Ă��܂��B
�ډ��A�b�c�̉������コ����ׂ��A�{�`�{�`�V��ł���Ƃ���ł��B
�b�c�̉������A�������m�̉��₩�����i�J�i�J�o�Ȃ��āA���b�p���A�ǂ����f�W�^���L���i�����ăL�c�C�j�����@������Ȃ���ۂȂ�ł��ˁ`
�����ԍ��F11811574
![]() 4�_
4�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�r�����������@�q������������A
���ꌧ�ɏZ��ŋv�����̂ł����A�n���ɂ���Ȃɏڂ����Ȃ��債���K�C�h���ł������݂܂���B��㐶�܂�̐l�ł�����ɍs�����̂́A���w�Z�̉����ł����Ƃ������������Ƃ������܂����A�ӊO�ɂ��č��l�ό��q�̐l�C�X�|�b�g�������肵�܂��B�č��ɂ�1600�N����̂悤�ɑ�̗̂��j�I���������F�������炾�����ł��B
�u���[���C�̃����^���̌��A���S�������肪�Ƃ��������܂��B
�ł�������Ԃ��ʓ|�ł����A�z�����̃g���u���������Ƃ͌����܂���̂ŁA����͉��������Ă��������܂��B
��͂�m�g�j�̘^���́A���D�݂ł͂Ȃ��ł����B�m���ɗD�����I�Ȕj�]�̂Ȃ��^���ł͂���A�f�W�^���o�b�n�̂悤�Ș^���͊F���ł��ˁB
�ł��������̂��Ȃ��A�C�����̗ǂ��^���ł���Ȃ���A���ēx���������^���̂悤�ȋC�����܂��B�m�g�j�̗̉w�Ȃ̘^�����D���������肵�܂��B
�����ԍ��F11811784
![]() 3�_
3�_
�掿�ɂ�����肳��A
��H�̃E�T�M����A�����́B
����l�Ƃ�BS hi�̘^�����D�]������闧��ł��ˁB����A�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������ƃ��[�W�������z���ɂȂ������ABS hi�ł̃m�����g���w���̃��[�c�A���g��g���̍���ł̃X�[�U���E�{�C�������H�����q����������������܂����B�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������́A�H�����q����̒�߂̐����D�]������Ă��܂����B
��͂�m�g�j�ɂ͂m�g�j�̉���������A�e���[�N�ɂ̓e���[�N�́A�f�b�J�ɂ̓f�b�J�́A�����f�B�A�ɂ̓����f�B�A�̉���������܂��̂ŁA�D�݂��������̂ł��傤�ˁB
��H�̃E�T�M����A
�b�c�����A�������ǂ��Ȃ��ł����H�@�b�c���ǂ��Đ�������A���ƌ��݂̂��鉹�ɂȂ邩�����Ȃ̂ł��ˁB�܂��ɂ��ꂪ�A���̃X���ŊF�l�̏O�m�����W�������Ɗ���Ă�����̂ł��B
�����ԍ��F11811877
![]() 2�_
2�_
2010/08/25 20:04�i1�N�ȏ�O�j
�F������(^_^)v
�掿����
�N���V�b�N�������y���܂�Ă��邲�l�q�����ł��B
�c�`�b�Ɛڑ��[�q�̍�������̂ŁA�����ȉ�����r�Ƃ͌����Ȃ��ʂ�����܂����A�g�ݍ��킹����ł͏\���ȃN�I���e�B������Ƃ̊��z�Ȃ�ł��ˁB
�^�t�̌��ʂ������[���ł��B
���̏ꍇ�́A�D�݃W�������������Ⴄ�̂ŁA�p�b�P�[�W���f�B�A�Đ���簐i���邱�Ƃɂ��܂��i��
�E�T�M����
����܁I
�E�T�M�������g���ӏ܂���Ƃ͈ӊO�ł����I
�ŁA���D�݂ɍ����ƁB
�b�c���₽�猵�����]���ł���(^_^;)
�m���ɏ����̎M�̓X�J�X�J�̔����炢���m���ڗ����܂������A�ŋ߂͗D�G�^���Ղ���������������̂ł����E�E�E�E
�V���O�����C���[�͐���ߊl�������v���܂�(^O^)
�~�l���o����
�m���ɒn���ό��͂��܂�����(^_^;)
�����I�t��̃Q�X�g���}�����ۂɏ��߂ĒʓV�t�ɍs���܂�������i��
�������A���\�����g�����]���������������܂�����A���̉������p�v�����Ƃ��Ă͊y���݂��o���܂����ˁB
�A�i���O�ڑ�������Ȃ������ł��B
�����g�͎��݂����ȃe���[�N�h�ɂ͍���Ȃ��̂����ł�(^_^;)
�a�c�͖��������@��ɂł��i��
�}�C�J���łR�c�o�C�I���ė��ĉ�������(^O^)
�����ԍ��F11811916
![]() 2�_
2�_
���[�W������̓e���[�N�h�������̂ł����H
���͎����A�Ƃ̂b�c�̍ő����[�x���̓e���[�N�ł��B2�Ԗڂ��f�b�J�A3�Ԗڂ��O�����t�H���ł��B���Ȃ݂ɍD�݂łȂ��̂́A�̂���d�l�h�ł��B
�ł�����ȍ������h��Ɋg�U���郁���f�B�A����ԍD���������肵�܂��B
�����@��Ԃ̐ڑ��̓f�W�^���ł͂Ȃ��A�A�i���O�ڑ����ŋ����ƐM���Ă��܂���B
�R�c�o�C�I���ăo�C�I�n�U�[�h�̐V��ł��傤���H�@�f��͂����ς�WOWOW�Ŋӏ܂��Ă���A�V����͊F�ڎ������킹�Ă��܂���̂ŁB
�����ԍ��F11812128
![]() 2�_
2�_
2010/08/25 21:11�i1�N�ȏ�O�j
�~�l���o����
�����I�ɂ͔h�ƌ�������̔h���ł͂Ȃ��̂ł����A�����I�ɍD�݂ł��B
�Q�Ԗڂ̍D�݂͖����Ƃ���ł����A�r�N�^�[�j�Q�ł��傤���H
�������R�[�h�͂��Ԃ��߂��ł���(^_^;)
�e���[�N�́A�o�b�n���A����������x�C�_�[�}�[�`���A���m�������M���D��ŕߊl���Ƃ�܂��i��
���[�h�V���[�Ō��āA�a�c�ōēx�掿����������Ŕ�r����̂��z�[���V�A�^�[�̊y���݂ł���ˁB
�o�C�I�̓o�C�I�n�U�[�h�S�ŁA�������[�h�V���[�ł��B
���݃��[�h�V���[���ł́A���~�x�݂Ɍ����\���g���Ȃ��Ȃ��ł����B
�f�B�J�v���I�Ɠn�ӌ��̃C���Z�v�V�������b���ł���(^O^)
�����ԍ��F11812287
![]() 2�_
2�_
���[�W������A
�e���[�N�̉����́A�u�d���A��悪���͂��肷���A���悪���邳���v�ƌ����Čh���������������܂����A�������̉����͍D���ł��ˁB�����A��H�̃E�T�M����́A���D�݂ł͂Ȃ��ł��傤�B
�r�N�^�[�j�Q���N���A�ł������肵�����ōD���ł��B��������AA���ւ̊�e�͖ʔ����ł��B
�e���[�N��Time Warp���A�����������łȂ��Ȃ為�ЁA�ߊl���Ă��������B�A���剹�ʍĐ��ɂ͂����ӂ��������B
�f��̐V���肪�Ƃ����������B�ߏ��Ƀ}�C�J���V�l�}���ł��܂����̂ŁA�RD�A�o�^�[��RD�A���X�C�������_�[�����h�͌��܂����B�ǂ�������掿�ł����ˁB�RD�o�C�I���w���ς݂̃N���b�v�I�����t�B���^�[�Ō��悤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11812540
![]() 2�_
2�_
�F����A�����́B ���ז����܂��B
redfodera����
�ˑR�̑f�l�̎���ɁA���J�Ȃ��ԐM���A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B
> ����͐����ł���MIDI�Ɉڂ��Ă���̓��[�x���̃e�[�}�ƌ����ׂ��|���V�[�̉e���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
> ���[�x���̖��̂̒ʂ�A�����A�A�}�`���A�ɂ���C�ɐZ������MIDI�����ɂ��ł����݂��g���āA
> �d�q�y��ł����Ƀ|�b�v�ł��ăi�`�������ȉ��y��n�����邩�ɎQ���A�[�e�B�X�g���^�����Ă����͂��ł����A
> ���̃e�[�}�ɉ����Đ��삪�i�߂�ꂽ���̂Ɛ��@���܂��B
���[�x���Ƃ��Ẵe�[�}/�|���V�[������̂ł��ˁB�A���o���̐���҂�A�[�e�B�X�g�������A���o���̃|���V�[�����߂�̂��Ǝv���Ă��܂����B
> �y�킪���ʓI�ɒ�������̂�MIDI������T���v�����O�����������炭���C���^�肵�Ă�������ł��傤�B
> ���݂͓d�q�y����A���v�Ŗ炵�ă}�C�N�ŋ�Ԃ��Ǝ��^����������Ă܂����A
> ������8�r�b�g�����Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǃV���Z��T���v���[�̉������̂��̂̎������サ�Ă��܂��B
�����Ȃ�ł����B���ɂȂ�܂����B�A���v�Ŗ炵���d�q�y��̉����܂��}�C�N�Ř^������Ȃ�āA�ƂĂ��������邨�b�ł��B
(���݂܂���A�m��Ȃ��͎̂����������E�E)
������������і��q����́A1978�N��"Mignonne(�~�j����)"����1990�N��"NEW MOON"�܂łŁA����ȍ~�̃A���o���͒����Ă��܂���B�ŋ߁A20�N�Ԃ�ɃI�[�f�B�I���X�V�����������ŁA�̂�CD�������ƁA�^���̈Ⴂ���͂�����ƒ�����������悤�ɂȂ�A�Ȃ�����ȂɈႤ�̂��Ƌ������������̂ł��B�����ŁA�v�킸���₵�Ă��܂��܂����B
���t�����������A�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
redfodera����̃N�`�R�~�͂��������[���ǂ܂��Ē����Ă���A���ɂȂ�܂��B
(red����̓N���}�Ɋւ��Ă��f�l�ł͂���܂����(^-^))
����Ƃ���낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F11812849
![]() 2�_
2�_
2010/08/26 08:04�i1�N�ȏ�O�j
���͂悤�������܂�(^_^)v
�~�l���o����
�e���[�N���d���Ɗ��������Ƃ͂���܂����(^_^;)
�d���Ɗ�����ꍇ�A�t�ɃV�X�e���̉����d���\�����������肵�āH
���̂�����̔��f�͓���ł����(^_^;)
���t�@�����X�f�B�X�N�Œ�悪�����炸���悪���ɂ��Ȃ��悤�ɁA�g�[���R���Ȃ胋�[���`���[�j���O�ŃC�R���C�W���O���A�M���Ƃ̍��͘^���������Ɗ����̂��x�^�[���Ǝv���܂��B
�f���̏ꍇ�A�Ⴆ�A�o�^�[�̂a�c�͑f���炵�����掿�ł����A�m�C�W�[�ȎM���悤������܂��B
���̃m�C�W�[�ȎM���ɃL���C�ɍĐ����悤�Ƃ͂��܂����(^_^;)
���イ���ƂŁA�A�o�^�[�a�c�͒������߂ł��I
�����ԍ��F11814330
![]() 1�_
1�_
Minerva����A����ɂ���
���[�W������A���Ђ��ł��B
�e���[�N�́u�x�C�_�[�}�[�`�v���傭���傭�����Ă܂���B
�悤�₭�ّ�ł��u�ቹ�ł����ĂȂ��v���o���邭�炢�ɒቹ���[�����Ă��܂����B
���[�W���@���ƁA���Ƀw�r�[���p���`�����ł��܂����ǁA�E�`���Ə���������蔇���Ă��āA�K�����ɔ����銴���ł��B
���āA
���ɖ�Ȃ��Ղ��A�Ȃ�Ƃ����邱�ƂŁA�V�X�e���̃X�p�C�����A�b�v�������߂�Ǝv���܂��B
�u��肭��Ȃ��Ձv�̕M���ՂƂ��āA�|���܂��́u�C���v���b�V�����Y�v��g���Ă����܂��B
���^�N�V�͒��N�A�V�X�e���`�F�b�N�Ɏg���Ă��܂��B
�܂�₳�Z���t�R�[���X�Ő����d�ˁA�R�[���X�Ȃ̂��A�t�щ��Ȃ̂����ʂ�����ȂƂ���ɉ����ĂP�O��ȏ�̊y�킪�\��P�̂悤�ɐ܂�d�Ȃ��ăA�����W����A�c�����W���傫���̂ŁA�I�[�f�B�I�V�X�e���́u���y���v�`�F�b�N�ɍœK�ł��B
���̖炵��A�R���B�Y�̃I�[�f�B�I�}�j�A�ւ̒��킩������܂���B
�𑜓x���Â��ƁA�w�|��̑f�l���t�ɕ�����
�𑜓x�̏グ�����ԈႤ�ƁA�����Ⴒ���Ⴕ���E���T�C�����̉��y�ɂȂ�܂��B
���Ƃ��ƁA�f�[�^������Ȃ��i�s���S�ȁj���f�B�A�ł���b�c�́A
�@�u���̗֊s����Ȃ��āA���̗}�g���͂����肳���āA�𑜓x���グ��v�̂��x�X�g�Ɗ����Ă܂��B
�u�C���v���b�V�����Y�v�̓V�X�e���̖��_�����݉������A������@���������Ă���܂����B
�����ԍ��F11814585
![]() 1�_
1�_
2010/08/26 09:37�i1�N�ȏ�O�j
�~�l���o����A�����O����v���Ă���̂ł����A�e���[�N�̘^���͏����̂��̂��܂߂āA�d���Ȃ��ł���B��{�I�Ƀt���b�g�ł����A�}�C�N�̈ʒu�������č�����������ቺ�C���ɂ܂Ƃ߂Ă���܂��B���ɂ́A����Ȃ���������̂ł��B
�����ԍ��F11814598
![]() 0�_
0�_
2010/08/26 11:39�i1�N�ȏ�O�j
����ɂ���(^_^)v
�ڊo�߂悳��
���v���Ԃ�ł�(^O^)
�x�C�_�[�}�[�`�������ɗ����Ă܂��ł��傤���H
�V�b�J���������̓X�s�[�J�[�Z�b�e�B���O���̂ł����A�ڊo�߂�V�X�e���̒��̓N���A�ő��肪�����_�œ��M���̂��Ǝv���܂��B
�����ɗʊ��������ΐ��Ɏ����̒�悩�Ǝv���܂��B
�ŁA����炵���H�M�̍Đ��ł����H
�����ł��Ȃ�(^_^;)
��������X�Ƀs���|�C���g������v����Ȃ�A���̍l�����͐������Ǝv���܂��B
�炵�ɂ����M�͐F�X����Ǝv���̂ł����A�����炷�������������Z�b�e�B���O�Ƌt�s����ꍇ�͔Y�݂܂����(^_^;)
�ǂ̎M���̂Ă邩���^���̕����ꓹ�H
�������Ȃ��Ȃ�������
�����ςȃs�[�N�������A�t���b�g�������������Ƒ����Ă���܂��B
�z�[���V�X�e���Ƃ̑����̓s�b�^�����Ċ����܂��B
�����ԍ��F11814985
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́A���[�W������̒ǂ������ł��i�j
�r�`�b�c�Ƃ����A�k���̂a�h�r�C�c�`�b�`�o�n�C�n�m�c�h�m�d�C�Q�k������A����Ƀv���X���ăC�M���X�̂k�h�m�m�����C�ł��傤���B
�a�h�r�̃V�������E�x�U���[��k�h�m�m�̃_���f�B���E�R���\�[�g�ȂǁA���ɉ����o�Ă��邩�y���݂ɂ��Ă��܂��B
�����A�����̃V�X�e���ł́A�r�`�b�c�̂��肪���݂����قNJ������܂���B
�܂��A���F�͏����Ȃ̂Łi��j
�r�`�b�c�͒�����̃��x������߂Ȃ̂ŁA�Đ����ɂ̓{�����[�����Rdb���炢�グ�Ē����Ă܂��ˁB
�Ȃ��A�r���̍ő��������[�x���́A�_���g�c�łm�`�w�n�r�A���_��brilliant�ł��i���j
�r�`�b�c�Ɍ���A�a�h�r�Ƃc�`�b�`�o�n�ł����ˁB
�����ԍ��F11815201
![]() 2�_
2�_
2010/08/26 13:11�i1�N�ȏ�O�j
�ǂ������đ��`��
�䂪�s�����Ƀl�^�L��i��
�Ȃ�ڐԂƍg�������F�₩�炿�イ�āi��X
�i�`�s�o���� ����ɂ���(^O^)
�I�[�f�B�I�X���ɂ悤�����I
�i�`�s�o����͕�������ł鐔�����[�����ł�����A�I�[�f�B�G���X�}�C�X�^�[�͊ԈႢ�����ł��ˁB
���L�V�X�e���Ȃ�A�E�T�M�����߂̃V���O�����C���[�r�`�b�c�̗D�ʐ��͕����锤�ł���B
�ߊl���Ă݂ĉ������ȁB
�Ԃ��Ȃ����m�\��ł����A�P�O���ɊJ�Â����V�[�e�b�N�����ɍ��킹�č��N���������d�F�t�߂ɂđ剃������{�\�肾���B
������I
�F��ȃ}�C�X�^�[�B�I
�I�[�f�B�I�A���y�A�f��A�K���v���A�ԁA���ł��L��`(^O^)
�����ԍ��F11815332
![]() 1�_
1�_
�F���� ����ɂ��́`
�~�l���o����
�����l�ł��B
AAC�̌����o�Ă���Ŏ����Ȃ�B
���BShi�̃X�^�[W�̃G�s�\�[�h�V���[�Y�ƂQ�N�O�ɂ�����WOWOW�̃G�s�\�[�h�V���[�Y�̔ԑg�ɂāc
���̓��[�W��������ꂽ�悤��WOWOW�̕������݂����艹�����D�݂ł��ˁB
�ǂ���BShi�̉��̓X�b�L���i�`�������B
���������G���W�j�A���ǂ����f�批�����N���V�b�N�����ɍ��킹�Ă�悤�Ȃ��`
�܂��͋Ɩ��@�ނ��̂��̂��p�C�I�j�A�n�̃i�`�������u���̂悤�Łc
�f��T���E���h�͂���ς�WOWOW���ȁ`�Ǝ��g�v���܂��ˁB
�ڊo�߂�ĂԐ����������邳��
���̒|���܂肠�P��CD�͎����Ă܂��B
�m���ɉ����͑��������惆�j�b�g�̈����X�s�[�J�[�Ȃ�T�V�X�Z�T�\������Ĉꔭ�ŃA�����o�܂��B(���̂��s���j
����11�Ԗڂ̍����ł����ˁH �Ȗ��́Hm(_ _)m
�S�n�悢���ቹ�B
���̃A���o���̃x�X�g���Ǝv���܂��B
�]�k�ł����B
�t������
���j�����̒m�荇���W�߂ăI�t����J�Â��܂��B
�U���ɂ���ꂽ����萏���Ɨl�ς��`���[�j���O���܂����B
�o�b�n����X���G����|������
�܂��]�V���SHMCD �u���[���X�o�C�I�������t�ȁF�w�����N�E�V�F�����O(���[�x���FJVC�j���Ă��炢�܂��B
�܂����z�������ɂł�
�����ԍ��F11815467
![]() 1�_
1�_
2010/08/26 14:04�i1�N�ȏ�O�j
�i�`�s�o����A����ɂ��́B�_���g�c�Łu�m�`�w�n�r��brilliant�v�ł����H�i��j
SACD�Ȃ�A���ƃy���^�g�[���AChannel�N���V�b�N�X������܂��BExton�����͘^���ǂ��Ǝv�������Ƃ�����܂���B
���[���E���t����A���ǂ��ꂽ�����ŁA�{�i������ł��ˁA�܂����ʂ����Ă��������B
�����ԍ��F11815532
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
���[�W������A
�����������Ȃ��Ȃ�������A
���e���[�N�̉����́A�u�d���A��悪���͂��肷���A���悪���邳���v�ƌ����Čh���������������܂����A�������̉����͍D���ł��ˁB
�����]���������́A���������Ȃ��ł���B��́AJBL4344�����ꂽ���̂���ɂ��ז����A���̓��������Ă���x�X�g�����̂b�c�ł��������AJBL4344�ł͗ǂ����Ŗ邾�낤�Ǝ��g���X�Ŏ������̂��J���[���w����Round-Up��3�Ȗڂ́uThe Magnificent Seven�v��剹���ōĐ�������ŕ������ꂽ�u�����z�v�ł��B����Ȃɂ��炵�����͂Ŗ��Ă����̂ɂƁA�����̈Ⴂ�ɋ����܂����B
���̕��́A�^���m�C��G.R.F. Memory����ԍD���ȉ����ƕ����Ă���̂ɁA���̂�4344���w������āA�u���̈����v�Ɍ������Ă����̂ł����B
�́A�č��̃I�[�f�B�I�V���b�v�ŁA���悪�h�h��ɏo�Ă���ȁA�Ǝv���`�F�b�N������A�e���[�N�́uPOMP & PIZAZZ�v��1�Ȗځu�I�����s�b�N�E�t�@���t�@�[���v�ł����B�������A���̂b�c�͌��n�ő����w�����܂����B
�e���[�N�ł����V�����w���̃x�[�g�[���F����5�Ԃ́A���悪��l�����ł��ˁB
�A�o�^�[�a�c�͒������߂ł����B�@���̃q���C���ɂ͂����ЂƂ̂߂肱�߂Ȃ��ł��ˁB�G���@�E�O���[����i�I�~�E���b�c�Ȃ�J��Ԃ����Ă��ǂ��̂ł����B
�i�`�s�o����A
SACD�̃N���V�b�N�̓��x�����Ⴂ���Ƃ������̂ŁA�RdB���炢�̓{�����[�����グ�������ǂ��ł��ˁB
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
���悤�₭�ّ�ł��u�ቹ�ł����ĂȂ��v���o���邭�炢�ɒቹ���[�����Ă��܂����B
����Ȃ�A�e���[�N�́uTime Warp�v�P�Ȗڂł��ˁB���́u�����ĂȂ��v�͍ō��ɂȂ�ł��傤�B
���[���E���t����A
�����BShi�̃X�^�[�E�H�[�Y�̃G�s�\�[�h�V���[�Y�ƂQ�N�O�ɂ�����WOWOW�̃G�s�\�[�h�V���[�Y�ł́A�������i�Ⴂ�ł����ˁB
�f�����u�s�J�`���E�v�K�����������Ă����悤�ŁA�������Ǝ��K�������̂��Ǝv���Ă��܂��܂����B�ł��́A�����̂������Q���M�G�t�w���́u�t�̍ՓT�v�͌��\���͗ǂ������ł��B����͂m�g�j�̘^���ł͂Ȃ��ł����B
�����ԍ��F11817996
![]() 1�_
1�_
>�I�[�f�B�G���X�}�C�X�^�[
����A��q���Ȃ����i��j
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ����������Ă���`���l���E�N���V�N�X�Ƃ����A�f���g���̎��ɍD���ȃC���@���E�t�B�b�V���[�̃z�[���E�O���E���h�ł����A�@������l�i�����c
�C���@���̃h���H�V�A�����������ǖ����肪�o���B
���������A�b�o�n���r�`�b�c�͂R�j�~�Ȃ̂ŁA���V���C�l���w���Œ��������̂������Ă����ÔՑ����҂��ɂȂ�܂��B
�W���}���̃}�[���[�݂����ɗD�G�^���̂r�`�b�c���ǂ�ǂ�����ŏo�Ă����Ί�������ł����B
���Ȃ݂ɁA�{���̊l���̓q�m�e���̎��W���P�ՂQ�^�C�g���i�Ƃ��ɃR���Q����؍G���������j���i�`�y�y�̒��ÔՂS�_�B
�ŋߍw�������b�c�œ��ɗǂ������̂��P���y�̂d�l�h�^���P�P���{�b�N�X�B
�N�����y���[�A�o���r���[���A�W�����[�j�A�����ăP���y�ƁA�̂̂d�l�h�^���͍ŐV�^������قǖ��������Ă�낵���A�Ǝv���Ƃ���ł��B
�����ԍ��F11818296
![]() 1�_
1�_
2010/08/26 23:26�i1�N�ȏ�O�j
�F������(^O^)
�E���t����
WOWOW�h���o�ꂵ�ă�������(^_^;)
�^�������A�����͑���o���C�R���C�W���O�͑S�R�Ⴄ��������܂��B
�ŁA���F�X�`���[�j���O����܂������H
�U�����Ă܂��H
�~�l���o����
���I�A�x�R�x�̕��ł��ˁI�i��
�������A�^���m�C�D���̂i�a�k�g���Ƃ�(^_^;)
�s�v�c�ȑI���ł��ˁE�E�E�E
�X�^�[�E�H�[�Y�̃T���E���h�����Ȃ�Ⴂ�܂����I
����o���ł����ˁH
�A�o�^�[�̓X�g�[���[�ł͖����掿�������߂Ȃ�ł�(^_^;)
�f��a�c�̌���x�X�g�M���Ǝv���܂���B
�����L�����Ō����ΐV�Ȑ��q����w�C���[�ł����āi��
�����ԍ��F11818360
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂�
�D�݂̃��[�x�����W�߂āA������ƌ����̂��A�u�b�c��r�`�b�c��ǂ����ŕ������߂́v��̕��@�ł��傤�B
�������A��̑��u�ł��ׂĂ�d���Ƃ����̂́A���X���������肻���ł��B
�ŐV�^���̍������ՂƁA�Â��ǂ�����̖��Ղ��A�Ƃ��Ɋ��\�ł��邩�H
�����ŁA�v���[���[����݂��āA���ꂼ��ɓ��ӂȉ����i���[�x���j�����t������Ƃ������@������܂��ˁB
�ڊo�߂悳�A���H����Ă��܂��B
����A�v���[���[�ɉ����ăv���A���v�i�v�����C����`�u�A���v�̃v���A�E�g���܂ށj����݂��āA�C���≹���ɂ���ăv���A���v�O���ւ���Ƃ������݂��A�ӎ����Ďn�߂Ă݂܂����B
�X�s�[�J�[�ƃp���[�A���v�͕s���Ƃ��āA�v���A���v�O���ւ��Ďg�����ƂŁA���ꂼ��̃v���[���[�̓��ӕ��������ŁA�����������y�𖡂키���Ƃ��ł������ł��B
�����ԍ��F11819473
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ��܁A���͂悤�������܂��B
���[�W������A
�����Ă��܂������H���p���������B���A�����ȃA���@���M�����h�g���̕������ɕ���Ă��܂��܂����B�i��
���́A�^���m�C�D���łi�a�k�g���̕��̂��D���ȃ��[�x���͉��ƁA�d�l�h�ł����B
��H�̃E�T�M����,
CD�ɍ��킹�āA�v���A���v�ȑO����������Ƃ́A�f�G���ґ�ł��ˁB
�́A�k�o�̎���ɂ͂k�o�ɍ��킹�ăJ�[�g���b�W���������邱�Ƃ�������O�ł������A�b�c�v���[���[�̎���ɂȂ��āA�����������Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
�c�`�b�{�[�h���C���ɂ���Ĕ����������ĕύX�\�Ȃb�c�v���[���[�������悤�ł��ˁB
�����ԍ��F11819667
![]() 1�_
1�_
2010/08/27 09:20�i1�N�ȏ�O�j
>�^���m�C�D���łi�a�k�g���̕��̂��D���ȃ��[�x���͉��ƁA�d�l�h�ł����B
�d�l�h�Ƃ͎�Ƃ��ĉ��t�Ɗ�őI�ԃ��[�x���ł��ȁB1960��ȑO�̘^���Ȃ璮���܂����E�E�E
��H�̃E�T�M����̂悤�Ȓ�ĈȊO�ɁA�b�c�v���[���̃f�B�W�^���t�B���^�[��ւ��͗L���ł����H
���Ƃ��\�j�[SCD-XA9000ES�ɂ̓t�B���^�[�ɂ̓X�^���_�[�h��option�������āA
�X�^���_�[�h�����ʂ������A�L�������W���ƍL����ԕ\���������ł��B
option���Ȃ߂炩�ȃ^�b�`�ŃG�l���M�[��������A������ʂ����ĂȂ̂������ł��B
����ɂ��������Ă���܂��B���͂����X�^���_�[�h�ŁAoption���������蒮�������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�܂������Ă݂܂��B
�����ԍ��F11819949
![]() 0�_
0�_
2010/08/27 09:34�i1�N�ȏ�O�j
�i�`�s�o����A�C���@��=�t�B�b�V���[�̃h���H�W�C�X�́A�̃t�B���b�v�X�A���܃`���l���E�N���V�N�X����o�Ă��Č�҂��܂������ǂ��ł���`�B�^���A���t�Ƃ���
�`���l���E�N���V�N�X�͂��܂Q�O���N�œ��ʉ��i�łĂ܂���I�������ł����H
http://www.hmv.co.jp/search/index.asp?adv=1&genre=700&catnum=CHANNEL20
�W���}���̃}�[���[�͂����ł��ˁB���t�A���i�A�^���O���q������Ă܂��B���߂ă}�[���[�����l�ɂ́A�o�[���X�^�C���Ȃ��A�������̂ق��������߂ł��B
�̂̂d�l�h�^���͂悩�����ł��ˁB�N�����C�^���X���p�����y�@�Ȃ�i�ł����B
�����ԍ��F11819988
![]() 0�_
0�_
2010/08/27 11:47�i1�N�ȏ�O�j
�F����ɂ���(^O^)
�i�`�s�o����
�K���_���}�C�X�^�[�����Ē�q�̓n�����炢�����i��
�{���̊l�����āA�܂��������ߊl�H
�E�T�M����
�CD��SACD��ǂ����ŕ������߂̣�̃��[�x�����Ė�ł��Ȃ�(^_^;)
�D���Ȏ��̖����͉����H�ƁA���̎������|�����ޕ��@�_�̈Ⴂ���Ă�����ł��傤���H
�c�`�b���܂ރv���C���[��v���ɂ��A�W���X�g�͗L���ȕ��@�_���Ǝv���܂��B
�������Ȃ���A����ł͂������Ȃ����ƌ������������݂��܂��B
��^�V�X�e����剹�ʂŖ炵���ꍇ�ɁA�X�s�[�J�[�A�����A�A���v�A�v���C���[�A�R���e���c���܂ރg�[�^���ł̑e����茰�݉�������Ă̂����̊��z�ł��B
�Ⴆ�A�i�|�b�v�̉����̓��W�J�Z�A�~�j�R������̊�������܂��B
�e���[�N�́A�F��ȃV�X�e���A�F��Ȋ��ɂĔj�]�����Ⴂ���S���ĕ����郌�[�x�����Ɗ����܂��B
�^�̗D�G�^���Ƃ́A����͈͂̍L���M�ł͂Ȃ��낤���H�ƍl���Ă��܂��B
�m�l�̉Ƃŕ����đf���炵���Ǝv���|�`�������̂́A����ŕ�������K�b�J���H�ł͍L�܂�܂���ˁB
�~�l���o����
�^���m�C�ƌ����A�L���O�_�����C�����Ȃ�n�C�G���h���o�ꂵ�܂����B
���߂Ă݂Ă͔@���ł����H�i��
�}���`�E�F�C�ł��B
�d�l�h�ƌ�����͂�r�[�g���Y�ł����ˁH
�����ԍ��F11820485
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����
�^���������āA�L���V�ɂȂ��ă}�X
������11�Ԗڂ̍����A�S�n�悢���ቹ�B
�����̃A���o���̃x�X�g
�P�P�Ȗځu�����v�B���̋ȁAJ-POP�Ƃ��Ăُ͈�Ȃc�����W�ł��B���̓R����炷�ׂɐV�z���܂����i��
���ꂪ�x�X�g�ɖ郍�[���E���t����̃V�X�e���́A�������Ƃ����̔\�͂̍����A�o�����X�̗ǂ����f���܂��B
�����������Ă��������ˁB
�P�O�Ȗڂ́u�{�C�ŃI�����[���[�v�͍X�Ɏ苭���āu�˂���̕���\�v���K�v�A�����ɖ����o���鉹���ɒB���Ă܂���B
�o�����A�u�C���v���b�V�����Y�v�����シ��A���̔Ղ͑S�Č��シ��B�E�`�ł͂����ł��B
�����ԍ��F11822237
![]() 0�_
0�_
>�d�l�h�ƌ�����͂�r�[�g���Y�ł�����
����ᔄ��グ�Ȃ�r�[�g���Y�����E�ꂾ���ǁA�d�l�h�Ƃ����܂��̓t�����F���̑��A���Ƀ}���A�E�J���X�ł���B
�i����Ƀr�[�g���Y�́u�A�b�v���E���R�[�h�v�����j
�b�a�r�Ȃ�A�{�u�E�f�B�����ł��r���[�E�W���G���ł��o�[�u���E�X�g���C�U���h�ł��Ȃ��A�܂��̓}�C���X�Ŏ��Ƀh���X�E�f�C�B
���łɂ����A�킽�����I�ɂ́A�e���[�N�Ƃ����J���[����v�����B���A�p�[���H�E�������B���A�W�����E�s�U�����ł��i�j
�����ԍ��F11822342
![]() 1�_
1�_
�F����A�����́B
Minerva2000����A���݂������B�쑽�Y��CD���͂��܂����B������[�X�^�����[��u���b�N]��CD�A���肪�Ƃ��������܂��B����ŁA�����ĉ����������Ȃ��Ȃ������o���ꂽ�ۑ�̃t�B���^�[�ɂ��ăe�X�g���܂������A���[���̎����������A���x���Ȃ荂���A�����̓t�B���^�[1�A2�A3�̈Ⴂ�͔F���ł��܂���ł����B�S�āA�����l�ɒ������܂��B�t�Ɍ����t�B���^�[�ɂ���Č��I�ɉ������ς��Ƃ͌����Ȃ������ȈႢ�ł��B���x�������ƊF�A�S�n�ǂ��������Ă��܂��܂��B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
���b�c�v���[���̃f�B�W�^���t�B���^�[��ւ��͗L���ł����H
SA-7S1�ɂ͎O�̃t�B���^�[������܂��BCD��SACD�ł͕v�X�A�p�r���Ⴂ�܂��B
SACD�t�B���^�[(�P)
�@DSD�f�[�^�ɑ��ăt�B���^�[�����O�����Ȃ��_�C���N�g���[�h�ł��B�I���W�i���f�[�^���@���̂܂܍Č����܂��B�f�̂܂܂̎����Ƌ�Ԃ��\������܂��B
SACD�t�B���^�[(�Q)
�@DSD�f�[�^��100KHZ�������������������܂��B�܂������A�t���M���p�ɕv�X23���ڂ��@�ꂽDAC���Ώ̂ɓ��삳���邱�Ƃɂ��A����\��D�悳���A����w�̊��炩�ȃT�E�@�@���h�������B
SACD�t�B���^�[(�R)
�@DSD�f�[�^��100KHZ�������������������܂��B�����A�t���M���p�ɕv�X�����p�[�P�[�W�@������Ă���23��DAC���A�Ώۓ��삳���A���炩���Ƀ_�C�i�~�b�N�ȕ\���������܂��B
CD�t�B���^�[(�P)
�@�v���G�R�[�A�|�X�g�G�R�[���Z�������ŁA���ʂ������A���[�������≹���̈ʒu�W�����@�m�ɍČ�����܂��B(�����o�蒆)
CD�t�B���^�[(�Q)
�@��Ώ̃C���p���X�����ƌĂ��������������t�B���^�[�ł��B�v���G�R�[�ɑ��ă|�X�g�@�G�R�[�������Ȃ��Ă��܂��B�A�i���O�I�ȃT�E���h�X���ł��B
CD�t�B���^�[(�R)
�@�C���p���X�����͓��ڂ���Ă���t�B���^�[���A��ԒZ�������B�����𑜊���ۂ�����@����Ƃ����o�����X�ł��B
���̑���[�m�C�Y�V�F�[�o�[]��[DC�t�B���^�[]���v�X�ɕt�����\�ł����A���ш���̃m�C�Y�������g�ш�ɃV�t�g������A�s�K�v�Ȓ����M�����J�b�g���܂��B�ȏ�͎���Ɛ��i�ē��̔����ł����A�ǂ����Ă������̍D�݂�CD�ASACD�ɐݒ肵�Ă��܂��܂��B
���̏ꍇ��[���̉�]���ŏd�v�����܂����̂ŁA[�t�B���^�[�R]���̗p���Ă��܂��BCD�ł́A���ꂪ�x�X�g�Ǝv���܂������ASACD�ł�[�t�B���^�[�P]�̕����N���A�ŗǂ��ꍇ�����邱�Ƃ��ŋ߂ɂȂ��ċC�Â��܂����B�\�t�g�ɂ���čœK�ȃt�B���^�[��I������̂����z�ł��傤���A�����͖ʓ|�Ŏd��������܂���B����ǂ��āA���y�͂������̂��ɂȂ��Ă��܂��܂��B����CD��[�t�B���^�[�R]�ASACD��[�t�B���^�[�P]�ɌŒ肵�Ă��܂��B�t�B���^�[�̑I���ł͌��I�ȕω��͂���܂���̂ŁASACD�̃V���O�����C���[�͉��l������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11822468
![]() 2�_
2�_
�F���� �����́`�B
�ڊo�߂�ƌĂԐ����������邳��
���̒|���܂肠�B
��ȖڂƓ�Ȗڂ̉������x�����Ⴂ�ɂ܂������܂��B
���n�� �𑜓x���グ��Ɓc���s���L�c���B�܂��n�[���j�[���ς������邩���ł��ˁB
�߂������Ȋɂ��Ƃ����Ƒʖڂȗ\�����B
�m���ɓ�V�ȃ\�t�g�ł��B
���[�W������
���₢�� ���N�̓z�[���Z���^�[�ʂ��ŕǂ�M��܂���c
�~�����A�C�e���͎R�قNJC�قǂ���܂����c
�Ƃ肠���������
�F����ƃ��C���C�K���K�������Ă��炢�蒼�������܂�K�v�Ȃ���Ήf���̕��ɂ��͓���悤���ƁB�B�B
�����ԍ��F11822583
![]() 1�_
1�_
�F�l�A�����́B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
���̂d�l�h���D���ȕ��̕]���|�C���g�́A�I�[�P�X�g���̌����@�ׂŁA���炩�����������������A�������Y�킾�Ƃ������̂ł����B���̓_�A�f�b�J��O�����t�H���A���������������e���[�N�̓o�c�Ƃ̂��Ƃł����B���܂�ɂނ��o���̌��̉�������Ƃ̂��ƁB���Ȃǂ́A������ǂ��̂ł����B
�o�r�R�ł��r�b�g�}�b�s���O�^�C�v��3�ʂ�I�ׂ܂��B���Ԃɓ���ǂ��Ēlj�����Ă������̂ŁA�Ō�̃^�C�v�R�������Ǝg���Ă��܂������A������^�C�v�P�ɖ߂�����A���͂��ꂪ��Ԃ̍D�݂ł����B
���[�W������A
���e���[�N�́A�F��ȃV�X�e���A�F��Ȋ��ɂĔj�]�����Ⴂ���S���ĕ����郌�[�x�����Ɗ����܂��B
�e���[�N�́A�J���[���w���̃V���V�i�e�B�E�|�b�v�X�E�I�[�P�X�g���n�Ƃ����̏��N���V�b�N�n�ŁA���̃o�����X�����Ȃ�Ⴄ�悤�Ɋ�����̂ł����A�ǂ��ł��傤�H
���N���V�b�N�n�́A�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�����������悤�ɁA���悪��l���߂̂��̂������ł����A�V���V�i�e�B�E�|�b�v�X�E�I�[�P�X�g���n�͔h��ȍ���̂��̂�����悤�Ɏv���܂��B
�i�a�k�g���̕��Ƃ́A���̌�10�N�قǂ��Ă�����āA���̌�̃I�[�f�B�I�ɂ��Ďf�����Ƃ���A���̏\�N�قǂ͎d�����Z�����āA�I�[�f�B�I���������y���ޗ]�T���Ȃ��A�i�a�k�̓^���m�C�ɕς��邱�Ƃ��Ȃ��A���̂܂܂ɂȂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B���̓W���ʂ�����ɂ��Ă���Ƃ̂��ƂŁA�����C�����ł����B
�^���m�C�ƌ����A�ߏ��̃W���Y�i�����A�o�b�L���K���E���j�^�[�����܂����B�������ɃI�[�f�B�I�t�@�C���ł͂Ȃ����ʂ̂��q�A�܂�W���Y�����������̂ł͂Ȃ��A���������R�[�q�[������H�����Ȃ���A�F�l�Ƃ�����ׂ肵���������̕������āA�剹�ʂŕ��������Ƃ������̂��c�O�ł����B�����ʂł��������̂łȂ��C�z�̉��ł��B
�掿�ɂ�����肳��A
�����A�͂��܂������B
�����x�������ƊF�A�S�n�ǂ��������Ă��܂��܂��B
���͋t�ŁA����̍����A�����x�ł́A������艹�����������܂��B�������p�����Ƃ��������D���Ȃ̂ł����A���̊������キ�A���̐�����������Ă���悤�Ɋ����܂��B
�o�r�R�ł̃r�b�g�}�b�s���O�^�C�v�́A�m���ɉ����ς��܂����A�̂̃J�[�g���b�W�̂悤�ɑ傫���ς����̂ł͖������߁A�\�t�g�ɂ���Đ�ւ���悤�Ȗʓ|�Ȃ��Ƃ͂���Ă��܂���B
�����ԍ��F11823082
![]() 1�_
1�_
2010/08/27 22:48�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A���̐l�̌����d�l�h�̂悳�͓������Ă��܂��ˁB���͑@�ׂʼn��Ɉ������C���ł��B�̂̃t�B���b�v�X�����̌n���ł����A��Ԃ̓t�B���b�v�X�̂ق����L���̂ŁA���̓t�B���b�v�X�̂ق����D���ł��B
���t�B���b�v�X�̓��{�l�G���W�j�A���������Ђ��A�t�@�C���m�e�E�E���̃t�@�C���m�e���V���O�����C���[�r�`�b�c���o���n�߂��̂ł����A�u���b�N�i�[�̑�V�Ԃ́A�����t���Ă���悤�Ȃ������^���ł��B
http://www.hmv.co.jp/product/detail.asp?sku=3680467
�掿�ɂ�����肳��A�n�C�G���h�E�v���[���[�͂��낢��ȃ`���[�j���O���ł���̂ł��ˁB�������A�Ղ��Ƃɕς���͖̂ʓ|������Œ�ɂȂ�܂��ˁB��������������A��ԑ傫�ȕω��͉����̈Ⴂ�ƌ����܂��ˁB
�����ԍ��F11823231
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A���͂悤�������܂��B
�A�o�^�[�a�c���c�u�c�Z�b�g
�|���܂��́u�C���v���b�V�����Y�v
�X�_�[���w���̃u���b�N�i�[��7��
�������قǒ������܂����B�����������ɂ͓͂��\��ł��B
�ǂ�ȉf���A�������y���݂ł��B
�����ԍ��F11824876
![]() 1�_
1�_
�lj��ŁA���[�W���������Ă���ꂽ�O���[�X�}�[���̃��C�u�ՂƁA�����������Ȃ��Ȃ����������Ă���ꂽ�l�[���E�������B�w���̃��[�O�i�[�𒍕����܂����B
�O�҂͖����ɂ͓͂��܂����A��҂�10���قǂ����邻���ł��B
�����ԍ��F11825226
![]() 1�_
1�_
2010/08/28 10:06�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A�A�O���V�u�ł��ˁ`
�l�[���E�����E�J�B�̃��[�O�i�[�i�V�����h�X�j�́A�I�[�f�B�I�E�}�j�A�����̃_�C�i�~�b�N�ȉ��t�E�^���ŕK���C�ɓ�����Ǝv���܂��B
�X�_�[���̃u���b�N�i�[�́A�z�[���̍ŏ�ȂŒ������ł��̂ŁA�ڋ߂��Ē������ł͂���܂��A����Ă���������������܂���(^^)�@�t�@�C���m�e�̓t�B���b�v�X�̈�`�q���p���ł��邩�炩�A���������X���ł��B
�����ԍ��F11825253
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
�u�����t���Ă���悤�Ȃ������^���ł��B�v�ɂ���ǂ��������Ē������܂������A�Ȃ�قǁA���������X���̘^���Ȃ̂ł��ˁB�t�B���b�v�X���k�o���R�[�h����̃C�E���W�`�̎l�G�͍D���Ș^���ł����̂ŁA���_���A���Ċ����悤�ɓw�߂܂��B
�����ԍ��F11825403
![]() 1�_
1�_
2010/08/28 17:25�i1�N�ȏ�O�j
�F����ɂ���(^_^)v
�i�`�s�o����
�m���Ƀ����S��(^_^;)
�������������͂�}�C�X�^�[���ˁ`
�I�C���͎G�H�n�Ȃ���Łi��
�}�C���X�ˁE�E�E�E
�ّ�̂d�l�h��\�H�̓p���[�X�e�[�V�������������ȁH
�ڊo�߂悳��
��͂�s���|�C���g�M���Ă��Ƃł��ˁB
�ّ�̂܂��̓J�o�[�A���o���̃��N�G�X�g���P���̂݁B
�܂�����ق̂ڂ̂����B
�E���t����
�����I�t������I
���ʊy���݁`
�N���������H
���|�[�g���`
�~�l���o����
�V���V�i�e�B�n�Ƃ̔�r�Ƃ��͂��ĂȂ��ł���(^_^;)
�����P�b�^�C�ȎM�����C���ł�����i��
�i�a�k�ŕ��u�ł������E�E�E�E
��������Ă��ł��傤���H
���āA���x�̊W�Ō����A���������C�n�ł̉����͓��{�ł͖�����ĕ�������Ƃ������܂��B
�~��Ȃ�悢�̂��ȁH
�n������Ɖ��x���x�����肵�Ă悢�����ł��ˁB
�A�o�^�[�Ɩ��I�}�[���ߊl���߂łƂ��������܂���
�����^�C�����[�v��ߊl���܂��ˁB
�����ԍ��F11826970
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�����ĉ����������Ȃ���������A
�{���́A�X�_�[���w���̃u���b�N�i�[��7�Ԃ����܂��āA�Ƃ肠�������y�͂��������܂����B
����͂܂��ɁA�u�����t���Ă���悤�Ȃ������^���ł��B�v�̂Ƃ���ł����B�z�[���̍ŏ�̐Ȃŕ����Ă���C���[�W�ł��B
�V���[�l�E�����O�w���̃u���b�N�i�[��8�Ԃ́A�J���I�Ń_�C�i�~�b�N�ȉ��ŁA����͂���ŗǂ��̂ł����A��7�Ԃɔ�r����A�������ǂ���傫���A��̃z�[���̂ǂ��ŕ����Ă���̂��ǂ�����Ȃ��^���ł��B
��ʂ̃N���V�b�N�̂r�`�b�c�́[5���a�ŕ����̂�W���Ƃ��Ă���̂ł����A��7�Ԃ�-6.5dB���x�X�g�ł����B��8�Ԃ̕��̓N���V�b�N��SACD�Ƃ��ẮA�^�����x��������CD�Ɠ���-8dB�ŕ����܂����B
���̃X�_�[���w���̑�7�Ԃ͑����A�����Ղ̒I�ɕ��ׂ邱�Ƃɂ��܂����B
���[�W������A
�e���[�N�̃P�b�^�C�ȎM�Ƃ��ẮA�uRound-Up�v�������߂ł��B���̖�����n�̂��ȂȂ��A���C�t���e�̎ˌ����������Ă��܂��B���ɖ`���̋��̖����͏o�F�ŁA�E�`�����{�̔_�ƂɂȂ����悤�ł��B�I�[�P�X�g���ȂƂ��Ă��E�B���A���e�����Ȃ͔��͂�����܂��B
�i�a�k����u����Ă�����́A���łɊS�����Ă���A�]���ċC�ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ��������ł����B
���x�̂��Ƃ͐����C�ŁAH2O�܂蕪�q��18�ł��B�����C�͕��ς���29�ł��̂ŁA���x�������Ƌ�C�̖��x��������܂��B����Œ�悪�K�c�[���Ɨ��ɂ����Ȃ�̂����H����Ȗ�Ȃ����H�@�E�[�t�@�̃R�[������_���p�[�������z���āA���̐ꂪ�����Ȃ�̂����B
���Ȃ݂ɁA���x�������Ȃ��Ă��A���x�������Ȃ��Ă������͑����Ȃ�܂��B�����������Ȃ�Ɠ������g���ł��g���������Ȃ��āA�����ԉ��т���̂��H�@��������肻���ɂȂ��ł��ˁB�Ȃ��ǂ�����܂���B
�A�o�^�[�Ɩ��I�}�[���͖����͂��̂Ŋy���݂ł��B�^�C�����[�v�����Еߊl���Ă��������ˁB
�����ԍ��F11828945
![]() 1�_
1�_
2010/08/29 07:45�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A�X�_�[���̑�V�ԑ��������ł��ˁB
>�V���[�l�E�����O�w���̃u���b�N�i�[��8�Ԃ́A�J���I�Ń_�C�i�~�b�N�ȉ��ŁA����͂���ŗǂ��̂ł����A
>��7�Ԃɔ�r����A�������ǂ���傫���A��̃z�[���̂ǂ��ŕ����Ă���̂��ǂ�����Ȃ��^���ł�
���̂Ƃ���ł��ˁBMinerva������u��Ԃ̕\���v�ɒ��ڎn�߂܂����ˁB
�V���[�l�����O��"Oehms"�Ƃ����������[�x���ŁA���C�u�^���B
�X�_�[���̓t�@�C���m�e�ŁA�Z�b�V�����^���B���i�������B���ǂ́u�f�B�X�N����ɂ������ԁv�̍����Ǝv���܂��B�V���O�����C���[�Ƃ������Ƃ��{�ɂȂ��Ă��܂��B
�����t�@�C���m�e�̃V���O�����C���[�Ղɍ���Ƃ����ڂł��B
�����ԍ��F11829762
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
�m���ɁA�t�@�C���m�e�̃V���O�����C���[�Ղ͍���Ƃ����ڂ��K�v�ł��ˁB���ډ����C���łȂ��Ƃ��\���y���߂邱�Ƃ�����܂����B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
�|���܂��́u�C���v���b�V�����Y�v���܂����B�P�P�Ȗڂ̍������ō��ł��ˁB�S�C�T�C�U�ȖځA�W�C�X�ȖځA12�Ȗڂ���15�Ȗڂ����̃_���s���O�̌������o���Ƃ����A�S�̂̃o�����X�Ƃ����A���炵�������ł��B3�Ȗڂ̓G�R�[�����߁A7�ȖځA10�Ȗڂ͍��悪���߂ň�a��������܂����B
�[���A�P�[�u���E�C���V�����[�^��d���P�[�u����5�ݒu���Ă���A�ēx�����Ă݂܂��ƁA���̈�a�����������Ȃ��A����͐L�тĂ͂��邪�A���x�������蕷���Â炭�Ȃ��Ȃ�܂����B�܂�����̕���\�������A�Œ��܂ł�������L�тė͋����A�ቹ�̕\����L���ɂȂ�܂����B
���[�W������A
�A�o�^�[�̉掿�������������ł��ˁB���ɉ掿�͂���܂Ō������Ƃ��Ȃ����x���ŁA��ʂ��݂邾���ō��ꍛ�ꂵ�܂��B�v���W�F�N�^�̐Ԃ���������Ƃ̂��w�E�ŁA���̌�F���x���グ�Ă����𑝂��Ă��܂��B
���I�}�[���̕��́A�P�[�u���E�C���V�����[�^�̂��������̑O�̎����A�������オ���������ŁA�ꖡ�ƃX�C���O���������Ă��܂����B
�����ԍ��F11833778
![]() 1�_
1�_
�ݒu�����P�[�u���E�C���V�����[�^�̎ʐ^�ł��B
�����ԍ��F11833832
![]() 1�_
1�_
Minerva����A����ɂ���
�U����U�����Ă��܂����悤�ŁA���k���Ă���܂��B
��3�Ȗڂ̓G�R�[�����߁A
��7�ȖځA10�Ȗڂ͍��悪���߂ň�a��������܂����B
�n�C�A���̂R�Ȃ͖炷�̂�����Ȃł��B�������Ȃ��w�E�A���ł��B�P�[�u���C���V���őꂽ�|�A�q�����܂����B
���h�n�ł��傤���B�������A���`��A�P�[�u���C���V���ł������A���E�ɓ��肻���ł��ˁB
�S�҂ɑ}�������I�[�P�X�g�����ۗ�������ƁA������₴����܂����A������������������Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F11834463
![]() 0�_
0�_
2010/08/30 08:23�i1�N�ȏ�O�j
���͂悤�������܂�(^_^)v
�~�l���o����
����H
�K�X�ǍH������܂����H�i��
�A�o�^�[�́u�掿�v�����ł���I
�t���v���W�F�N�^�Ō�����i��
�P�U�F�X�₵�A���J�������悢���炱���̉掿���ȂƎv���܂�(^O^)
�A�o�^�[�͐��ۂ��掿�ł����炻�̂܂܂ł��i�R���R��
�e���[�N�̋��ł��ˁi��������
�u���b�N�i�[�Ɩڊo�߂悳��̂܂����K�{�ŎM�U�����ł���(^_^;)
���x�Ƃ̊W�͐F�X����ł���(^_^;)
���l���Ă݂܂��ˁB
�P�[�u�������E�E�E�E�E
�m���Ƀ��o���i��
�����ԍ��F11834901
![]() 1�_
1�_
���͂悤 �������܂��B
����͔����������I�t���܂��āc
�|���܂肠�A�u���[���X��ԁA �W���j�t�@�[�E�E�H�[���Y�̃n���^�[(8�Ȗځj���Ă��炢�܂����B
�W���Y���ɋؓ����ȉ��ɕ����������Ă܂��āA�A
�F����ŕ������{�����[���A�b�v�Ŋ��ŖႦ�܂����B�A
�\�t�g����ẮA����ȕ���\�͓����Č����̂�����A�A
�����Ɖ𑜓x���ƌ����\�t�g���B
�F�D�G��CD�����畷�������ƂȂ������c(��
�܂��I�t��ɓ���N���A�E�X�g���[�����Q�̃}�[�N�E���r���\����100������DAC���܂��ĕ����Ă���Ɛ悸�悸�������Ǝv���܂��B�B(����̓r�b�N���j
���̊��z��A����M800A�ӂ�ł��G�G���ȂƁB�B�B ��
�N���ɂ����ė~�����a�����NjC���ł��B(��
�����ԍ��F11835245
![]() 0�_
0�_
2010/08/30 17:43�i1�N�ȏ�O�j
���[���E���t����A����͐�������悤�ł��ˁB
���̂`�s�b�̑�^�X�s�[�J���Ȃ炷�`���p���[�A���v�̈З͂ɁA�������������A����̊F������������Ǝv���܂��B���̈������܂���������������A���̏������[���`���[�j���O��������킯�ł��ˁB
�N���V�b�N�ɂ̓`���b�ƃ��C�u�C�����Ǝv���܂������A���b�N�ɂ͂��̂��炢�ł悢�̂����m��܂���B
���艹�����i�Ń`���[�j���O���ɂ߂悤�B�悢�A�C�f�A���o���牏���ɂ��������݂��肢���܂��B
�����ԍ��F11836709
![]() 0�_
0�_
�����́` �����l�ł��B
�ŋߎv���ɂ܂������̃X�s�[�J�[�̓p���[����Ȃ����Č����̂��ȁ`�B
�X�s�[�J�[�f�����X�g���[�V�����ŕ��������܂ōs���Ă܂���B
�߂��͂��Ƃ͋߂��ł����c
�Ă�������̃p���[�A���v�̓�������E������Ƃ̂��ƕ�����܂����B
���̎��͉����Ő������܂��B�B
�����ԍ��F11836951
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A�@
���U����U�����Ă��܂����悤�ŁA���k���Ă���܂��B
�|���܂��̂b�c���Ă���A�P�[�u���C���V�����[�^�̓��������߂��̂ł͖����̂�
���S�����͕s�v�ł���B�b�c���O�ɍޗ��͎d����Ă��܂����̂ŁB
����ɁA���̃C���V�����[�^�̓~�l�����@�H�[���ŁA�ޗ����5��530�~�i����ō��j�ł��̂ŁA���S�z�����B
����͐��̊p�ށi3����×3����×45�����j��140�~�A7.5cm���̃J�b�g5��̓T�[�r�X�A
�����v���[�g�@78�~�T��
�h���ƃl�W�i�X�e�����X���j�͉Ƃɂ��������̂��g�p
�ŁA���v��530�~�ōς݂܂����B
�p�ނ͍��h�̕����ǂ��Ǝv���܂����A�߂��̃z�[���Z���^�[�ɂ́A����ȟ������ޗ��͂���܂���ł����B�܂������v���[�g����������Ȃ�A�X�e�����X���̕����ǂ��ł��傤�B
���[�W������A
�Ƃ�720�o�v���W�F�N�^�[�ł��������掿���m�F�ł��܂����̂ŁA�t���n�C�r�W�����v���W�F�N�^�[���Ƃ����Ƃ����Ɛ����ł��傤�ˁB
�e���[�N�̋��͎����Ă݂�i�����Ⴄ�H�j���l������܂���B
���[���E���t����A
���Ă�������̃p���[�A���v�̓�������E������Ƃ̂��ƕ�����܂����B
���E����������O�ɁA�d���n���̋����͂������ł��傤�H�������łɂ���Ă�����̂ł��傤���H�@�������炷�݂܂���B
�����ԍ��F11838597
![]() 0�_
0�_
�~�l���o����
����ɂ��́`
�ȑO���i�����_���p���[�A���v��3KVA�����܂����Ƃ���c
�₢�������������������銴���Ɂc
������ �\�t�g�Ɋ���Ă�A���Ƀg�����X�͂ǂ����Ɓc
���݃p���[�A���v�ɂ̓N���C�I��3.5SQ���g���Ă܂��B
������������~�l���o����̃A�h�o�C�X���ǂ��q���g�ɂȂ邩���ł��B
�őP��CP�l�������ԗǂ������ł��ˁB
���݂Ƀp���[�A���v�B
�q�u���[�J�[�P�Ɓ�5.5VVR�����z�����I�[�f�B�I�O���[�h�R���Z���g���N���[���d���t��3.5SQ�����i���`�N�}4���^�b�v(�q��A���~���j���N���C�I3.5�P�[�u�����o���[�A���u�ł��B
�^�b�v�r�����ăR���Z���g���������l���Ȃ��Ƃ����܂���ˁB(��)
�����ԍ��F11840343
![]() 0�_
0�_
2010/08/31 20:23�i1�N�ȏ�O�j
�F������(^O^)
�E���t����
�����F�X���n���������悤�ŁB
�W�F�j�t�@�[�́A�^�C�g���i���o�[�A�t�F�C�}�X�u���[���C���R�[�g���Ԃɂ��Ƃ�܂����B
�N���A����̈�t�h�i���h���C�ɂȂ�܂��ˁI
��̂�����ȎU�����E�E�E�E
�ّ�̓R���Z���g�������ˁ`
�~�l���o����
�A�j���Ȃ���}�g�����сI
�X�g�[���[�������ߏo���Ȃ��̂ł����ꃌ���^�����܂���(^O^)
�Ƃɂ����A�X�g�[���[�������̂��ʼn掿�������`�F�b�N����A�z�D����(^_^;)
���̎M�����ɁA�J�E�J�E�I
�����ăI�b�N�X�I
���オ��낵���悤��m(_ _)m
�����ԍ��F11842205
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
���[���E���t����A
�d���n���́A�����ɗ͂������Ă��܂��ˁB������������Ƃ���A�N���[���d���t��3.5SQ�����i�ƃN���C�I3.5�P�[�u���ɂȂ肻���ł��ˁB
�掿�ɂ�����肳��ɂ����߂����O�H�d���̃P�[�u���́A�p���[�A���v�ɂ��\���g����Ǝv���܂����A���v���[���[���ɓK���Ă���Ǝv���܂��B�@�ׂŊ��炩�ȍ��������҂ł���Ǝv���܂��B
�p���[�A���v�ŕ���\�������_�C�i�~�b�N�ȉ���_���ɂ́A�o�r�I�[�f�B�I��XPL-1.8MK2���K���Ă���Ǝv���܂��B�A�����͂��n�[�h�ō���͍אg�ɂȂ邩���m��܂���B�����i�ł͂Ȃ��P�[�u���P�̂ł̓I���C�f��TSUNAMI NIGO�����͂Ȓ�悪�_���A���܂�n�[�h���͏o�Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�O�҂̍ގ���PCOCC-H�A��҂�PCOCC-A�ł��B�`�̓A�j�[���i�Ă��݂��j�����ς݁A�g�̓A�j�[�����������ŁA�ǂ�����T�X�P�ȏ�ł��B�A�j�[�������̗L���ł��Ȃ艹�̌X�����قȂ�܂��B
�d���n���́A�ǃR���Z���g�����̍ŒZ�o�H��A�uSimple is Best�v���K���������Ă͂܂炸�A�r���ɗǎ��̓d���P�[�u�����o�R�����邱�ƂŁA�������������҂ł���Ǝv���܂��B
���[�W������A
�A�j���Ȃ���}�g�����тł����I�@�܂����ז��������ɂł����肳���Ē��������Ǝv���܂��B
�����̎M�����ɁA�J�E�J�E�I
�̂̂s�u�̂b�l�Łu�J�E�J�E�I�@�J�E�J�E�I�@�݂�Ȕ����A�����Ό��I�v�Ƃ����̂�����܂��āA����ɑR���Ă����̂��u�ԉ��i�������I�j�Ό��v�ł����B
�����ԍ��F11842676
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����A�����́B
�O�H�̓d���P�[�u���APC-1�͖����A�͂��܂��B�����̓S���t�ŋA�肪�x���Ȃ�܂��̂ŁA���ʂ͖�������ł���Ǝv���܂��B
�����̓��j�o�[�T���Ŕ������Ă���V���O�����C���[��SACD���͂��܂����B����͏��V�����w���A�T�C�g�E�L�l���̃u���[���X2�ԑ��ł��B���ʂ��グ��Ɛ��Ɛ����ς��Ȃ��������܂��B�������^�ŃV�F�G���U�[�h�̃��]�\�v���m�͒������m�ł����B
�����ԍ��F11843121
![]() 0�_
0�_
�掿�ɂ�����肳��A���͂悤�������܂��B
�P�[�u�����͂��܂����B�d���P�[�u���͕K���G�[�W���O���K�v�ł��̂ŁA�ŏ������Ă���͂ǂ����H�Ǝv���Ă����炭�䖝���ĕ��������Ă��������B�G�[�W���O��50�`100���Ԃ�����͕̂��ʂł��B
���V�����w���A�T�C�g�E�L�l���̃u���[���X2�ԑ��͘^�����ǂ������ł��ˁB�N���V�b�N�ŃV���O�����C���[��SACD�͐�ʍw�������u���b�N�i�[��7�Ԃ����ł��B�|�s�����[�n�͒��ׂ���3������܂����B
�����ԍ��F11844329
![]() 0�_
0�_
���͂悤 �������܂��B
�m���ɃP�[�u�������͂����ɂȂ�܂��B
�d���^�b�v���G�����Ń��b�N�V�����^�b�v����ꂽ�����ǂ��Ƃ��c����R���Z���g���ڍ������Ƃ� ���낢��ӌ����ʂ�܂��B
�d���P�[�u���ł͉��F�̑ш���x�̕ω��Ȃ�Ŋ�������Ȃ��́H�ɂȂ�܂����A�A�B
�����ĕt���i�Ɣ�ג����A�A���߂ďd�v��������܂��B�B
���[�W������
�� M800A���n���I�[�f�B�I�V���b�v�ɓW���B
��Đ��������������ρB
�a�C�̍Ĕ��ԈႢ�Ȃ��B�B
�w��ꋰ�낵������x�ɂȂ�̂��|���ł��B(��)
�����ԍ��F11844668
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
��̉������P�[�u���C���V�����[�^�ł����A�����v���[�g�Ɩ؍ނ̊ԂɃP�[�u��������ŌŒ肷��\���ł��������̂��A���҂��l�W�Ŗ��������A�����v���[�g�̏�ɃP�[�u�����ڂ��邾���̍\���ɕύX�����Ƃ���A������̕��������I�ɍD�܂����Ɗ����܂����B
�P�[�u���C���V�����[�^�̎g�p�ŁA�S�̓I�ɉ����s���A�ɂȂ�A�g�Q�g�Q�����h���������āA�𑜓x�������オ��A���g�������W���L���銴���ł��B
�A���A�d���P�[�u���قǂ̑傫�ȕω��ł͂Ȃ��A������Ƃ����`���[�j���O�A�C�e���ƌ������Ƃ���ł��B
��������u�X�s�[�J�[�P�[�u���̓I�[�f�B�I�̐������ł���̂ɑ��A�d���P�[�u���́A�I�[�f�B�I�̖��^�����߂�^�����ł���B�v�ƌ����Ă��܂������A�ŏ��́u�P�[�u�����Ƃ��ŁA�������������ȁv�Ǝv���Ă��܂������A���ł͂����v���Ă����������p�����������炢�ł��B
�����ԍ��F11847805
![]() 0�_
0�_
2010/09/01 23:13�i1�N�ȏ�O�j
�F������(^_^)v
�ڊo�߂悳��
�E���t����
�~�l���o����
�x����Ȃ���A�C���v���b�V�����Y��ߊl���܂����̂ŃC���v�����i��
�悸�́A�P�A�T�A�X�A�P�T�̂S�Ȃ����N�G�X�g�Ƃ��Ԃ��Ă܂�(^_^;)
����͂��Ă����A�R�A�V�A�P�O���K�V���K�V���C���Ȃ̂̓~�l���o����Ɠ����ł��B
���ʓ_�́A�R�ȂƂ���ԌÂ��W�S�N�^�����ē_�ł��B
�܂��́A�W�S�N�ɃV���K�[�\���O���C�^�[�Ƃ��ĕ��A�����ł����A�t�����̋Ȃł��ˁB
�V�ƂP�O�̓��C�i�[����̓J�b�v�����O�̂Q�ȂƂ���܂�����X���͓������Ǝv���܂��B
�u���v�s���\��₷���ł��ˁB
�E���t���C�ɓ���̂P�P���悢�̂ł����A�����W���A����̍L������͂P�Q���ّ�x�X�g�ł��ˁB
���_�H�͂P�S���ȁH
�ŁA�ǂȂ����G��Ȃ������_�����͑�D���ł��B
�A�����C�X�������������ƂȂ������̂ł����A�܂�₪�A���Ƀv���[���g������ł��ˁ`
�����_�ĒN��˂�H
�R�{�����_�H
�����_�����V���^�b�g�H
�Ǝv������A���̃~�h���l�[���������Ƃ́i��
�����_�A���J�b�g�炵���ł���B
���]�H�Ƃ��ẮA�^�����Â��N�Z���m�H�R�Ȃ������A���N�G�X�g���l�����Ղ��P���Ɏv���̂ł����A�F����@���H
�~�l���o����
�J�E�ɑR�����J�I�E�͒m������ł�(^_^;)
�Ă��A�J�E���m������ł���`
�����ԍ��F11847851
![]() 0�_
0�_
Minerva2000����
�P�[�u���C���V���̌��́A��͂舳���������u�����������R�Ȃ�ł��ˁB�C���V���̑f�ނ�S�y��u�`���S���ɂ�����A���͂ǂ�����ƈ��肵�A���œV�ォ��݂艺������SN���ǂ��Ȃ���̂́A�͊������ނ���̂ł��傤�ˁA�����ƁB�P�[�u���C���V���̓����́A�|���ē�̑��݂܂��B����Ƃ�����P�[�u���ɂ���Ă��܂������Łc�B
���[�W������@����ꂳ�܂ł��B
���^�����Â��N�Z���m�H�R�Ȃ������A
�����N�G�X�g���l�����Ղ��P���Ɏv���̂ł���
���[�W���@�̉����͊�{���\�t�g�����₩�Ȃ̂ŁA�����Ղ��X���ɂȂ�̂ł��傤�ˁB�ّ�Ɗ�{�V���[�v�X���ŁA���ɂP�P�́u�����v�̓G�b�W�������ă��@���w�C�������ۂ����ɂȂ�܂��B
�����_�̓A���̂��Ƃ�������ł����A�u�����q�v�݂����Ȉ�ʖ����Ǝv���Ă܂����B
�����ԍ��F11848642
![]() 0�_
0�_
2010/09/02 10:14�i1�N�ȏ�O�j
���͂悤�������܂�(^_^)v
�ڊo�߂悳��
�Q�S�O�S�͂U�O�O����オ�x�����E���h���C�o�[�̃z�[���ł�����A�o�C�I�����g�Ȋ炪���锤�Ȃ�ł����A�_�炩���ƃR�����g�������������̂��{�l�͕s�v�c�Ɏv���Ă��肵�܂��B
�����V�����Ŗ�O���C�u���Ă܂������A���̏_�炩���ɂ͒����������E�E�E�E
�����_�̓��C�i�[�Œm��܂����B
�A���̌����j���i�K���Ƃ́j�ɂ܂�₪�������ȂƂ��B
�w�C�W���[�h�݂����Ȃ���ł��ˁB
�P�P�͒��悪�����オ���Ă銴������܂��B
������ٲݼ��̓����ͤ�|���ē�̑��݂܂������Ƃ����鹰��قɂ���Ă��܂������Łc�
�ڂɕ����т܂����i��
�E���t����
���w��ꋰ�낵������x�ɂȂ�̂��|���ł��(��)
�E���t����Ɖ��l�̂ǂ��炪�����ɁH�i��
�j���A�`�`�`�i����
�����ԍ��F11849266
![]() 0�_
0�_
���́B
�Q���[�E�J�[�̂w�q�b�c���o�邻���ł��B
http://www.hmv.co.jp/news/article/1009020026/
�}���قŎ肽�P���y�̃u���S�^�u���T�͌��\�ȉ��ł����i�}�X�^�[�͓��{�����p�ɑ����Ă����R�s�[���Ƃ̂��Ɓj�̂ŁA�Q���[�E�J�[�̕������ґ�ł��ȁB
http://www.hmv.co.jp/product/detail/3624172
�����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ����ǁA�}���قŎ����悤�Ȃ�A�h���H�R���͐����Ă݂����ł��B
�����ԍ��F11849987
![]() 0�_
0�_
Minerva2000����A����ɂ��́B
�O�H�d����PC-1��CDP�Ɍq���܂����B�G�[�W���O�ȑO�̉��ł��D���G�ł��B�S�̂̑ш�̃o�����X���C�ɓ���܂����B�ȑO�̃P�[�u���́A������ɒ�������Ă����ׂ��A���悪�����]���ɂȂ��Ă���悤�ł��B��̓I�ɂ̓\�t�g�ɂ���āA�o�����ŏo�Ȃ����A����̉��ʕs���������Ă��܂����B�]���āA�����ʎ��͍��悾�����ڗ����s�����ȉ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B
���ɌÂ�CD�ŁA�������������CD�ł́A�����ɑς��Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��܂����B����ŁA�~����CD�������o�Ă������ł��B����ȉ��͑��̃V�X�e���ł��o��̂��Ǝv���A�I�[�f�B�I�X�Ɏ������ނ��߂ɗp�ӂ��Ă���2����CD�̂���1���̓N���A���܂����B�����ꖇ�͂ǂ����悤���Ȃ�CD�̂悤�ł��B
�ȑO�̉��̓s�A�m�Ƒt�̉��ŁA���{���̉����o��悤�ɒ������܂����̂ŁA����CD���������Ƃ����ꂪ�����Ȃ��Ă��܂��B����̉��ʂ����������ʁA����̓��������s�����݂ł��B���̕ӂ��G�[�W���O�������Ɣ�ׂĂ݂悤�Ǝv���܂��B
PC-1�͋����悤�Ƀl�b�g�ł��������Ȃ��̂ł��ˁB�I�[�f�B�I�X�Ɉ�T�ԂقǒT���Ă��炢�܂��������[�g�Ȃ��ł��B�����s���ő��̓d����Ђ̓}�C�i�[�ȕ���̃I�[�f�C�I���i����P�ނ����ׂɑf�ދ��������ŁA�R���V���[�}���i�͂��̗l�Ȍ`�ɂȂ����̂ł��傤�ˁB�W���p���G�i�W�[��8N�ASP�P�[�u�����g�p���Ă��܂����A����M�d�i�ɂȂ�܂����B�O�H�d���̗ǐS�������܂��B
�����ԍ��F11850006
![]() 0�_
0�_
�F����ɂ��́`�B
�掿�ɂ�����肳��B
�O�HPC-1�w�����߂łƂ��������܂��B
���낢�뎎�s����̍Œ����Ǝv�����B
���������M��̑O�́ACD�v���[���[�̓d���ʼn����x�X�g���B�B
���낢������Ă��܂����B
������ �v���[���[�̓d���P�[�u����4�N�ړ��Ȃ��̃P�[�u�����g���Ă܂��B
�~�l���o��������Ă܂������ACD�v���[���[�̓d���P�[�u���͉^�����ł��B
�����̐��͎��̃V�X�e���ɂƂ��Ċ̒��̊̂ł��āA�A���̋@��͕t���P�[�u����[�J�[����Ă��v���[���[�����͐�ΕύX�����Ǝv���Ă܂��B
�ȑO�ɂ��̘b��red����Ƃ�PTQ�̃X���Œk�`�����킵�܂����B
�w�v���[���[�̓d���P�[�u�������t�@�����X�ɂ��Ƃ��Ȃ��ƐV�����w�������P�[�u���̓������S�R�͂߂Ȃ��x����Ȃ����������L��������܂��B
���̃V�X�e���Ɏ���Ă܂�����CD�v���[���[�̓d���P�[�u���͉^�����ł��B�B
�����ԍ��F11850243
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
���[�W������A
�P�Q���x�X�g�ł������B����͈ӊO�ł����B�P��Q�ƌX���͎��Ă���Ǝv�����̂ł����B
�u�J�E�J�E�v�̂s�u�̂b�l�͖�50�N�O�ɕ�������Ă��܂����B�m���U�E�s�[�i�b�c���e�[�}�\���O���̂��Ă����u����ڂ�ʃz���f�[�v�Ƃ����̔ԑg�̂Ȃ��̂b�l�������悤�ȋC���B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
�P�[�u���C���V�����[�^��1�A1���~������Ε|�����ƂɂȂ�܂����A���̂悤��1��100�~����50�ӏ��ɐݒu���Ă�5��~�ł��݂܂���B�@����A5�ݒu���܂������A�����Ƒ��₷�\��͂���܂���B
�掿�ɂ�����肳��A
�G�[�W���O�ȑO�̉��ł��D���G�Ƃ̂��ƂŁA�܂����S���܂����B�G�[�W���O�ɂ���č��̃o�����X�͂��̂܂܂ɁA����̓������Ɛ�̗ǂ��������Ηǂ��ł��ˁB�����Ȃ�\�������܂��B
���[���E���t����A
��CD�v���[���[�̓d���P�[�u���͉^�����ł��B
�d���P�[�u���͉^�����ł��Ƌ��Ă���������������āA�S�����ł��B�������́A���ł�����l���Ă��_���ŁA�������邵���Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F11851466
![]() 0�_
0�_
���[���E���t����
���肪�Ƃ��������܂��B�d���P�[�u���͏d�v�ł��ˁB�R���T�[�g���n�܂�������̂��̐��ݐ����]�C�̂��鉹�A����͒��X�A���u�ł͍Č�������T�O�N�̃I�[�f�B�I�l���Ŕ��Β��߂Ă��܂����B�s�A�m�ł̉������őI�P�[�u����[SYLVAN]�̑g�ݍ��킹�����R�ɂ��A����ɋ߂������o���Ă���܂����B����ŌŒ肵�Ă��ǂ��̂ł����A�����ꕔ�̃\�t�g�ł����ʗp���܂���B
���ɋ߂�����Nj�����̂��ǂ��ł����A�S�Ă��S�n�ǂ�������Nj����d�v�ŁA�����̉��y����ł͕s���ł��BPC-1�̃G�[�W���O���������ė��҂��������鎖��ڎw���Ă��܂��B
Minerva2000����@
�O�H�d���̓��[�U�[�̖ʓ|���̗ǂ���ЂƂ݂܂����B���i�ɑ��鎩�M�������Ă��܂����A���������[�U�[����Ԏ�����ɂ��Ă��܂��B�b���g���Ċ��z���������[�U�[�o�^�����鎖�ɂ��܂����B
�����ԍ��F11852375
![]() 0�_
0�_
�掿�ɂ�����肳��A
�O�H�d���H�Ƃ̃z�[���y�[�W�ɂ́A�d���P�[�u���ʼn��̉����ς�邩�̗��R�̈�[��������Ă��܂��ˁB
http://audio-cable.co.jp/SHOP/PC1-15M.html
�X�s�[�J�[�P�[�u���ʼn����ς��͔̂F�߂邪�A�d���P�[�u����50Hz�܂���60Hz�̐����g�d��������Ă��邾��������A�����ς��Ȃ��ƍl���Ă�����ɂ́A�Q�l�ɂȂ�ł��傤�B
�����ԍ��F11853046
![]() 0�_
0�_
Minerva2000����A����ɂ��́B
[PC-1]�A���X�A���q���ǂ��ł��B���������āA����̂���CD�̖w�ǂ��܂Ƃ��ɒ�����悤�ɂȂ�܂����B�O�̃P�[�u���Ő��ɋ߂�CD�͈ő����������A�s�N���ɂȂ������x�ł��B�X�ɁA�ǂ�������Ȃ�CD��SA-7S1��[�D�݂̉��ݒ�]�ŁA[�m�C�Y�V�F�[�o�[]��[DC�t�B���^�[]��ON�ɂ���ƌ��Ⴆ�鉹�ɂȂ�܂����B����ŁACD�̔Y�݂͂Ȃ��Ȃ�܂����B�ǂ����A���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F11874151
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́`
�掿�ɍS�肳��
�ǂ��d���P�[�u���ɏ��肠���ėǂ������ł��ˁB
CD�v���[���[�̓d���P�[�u���̓j���[�g����������Ǝv���܂��B
�F�t���́A�v����p���[�ɔC���������ǂ��ł��B
����ł������́A�]��F�t���͂Ȃ�SN�d���A���撆�S�̐F�Â��P�[�u���ł��B
�����Ɍ����ƃX�s�[�J�[�ɍ��킹���F�Â��ɂ��Ă܂��B�B
�X�s�[�J�[���ǂ��C�����ǂ����Ă���邩�c
�S�ó��B
�����ԍ��F11874435
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�掿�ɂ�����肳��A
�����߂����d���P�[�u���ɂ������̗l�q�A�����ł��B�O�H�d���H�Ƃ�D.U.C.C���̂́A���E�ō����x���̓��̂��Ǝv���܂��B
����ɕ������߂A�����̂���Ȃ��������҂ł������ł��B
���[���E���t����A
��CD�v���[���[�̓d���P�[�u���̓j���[�g����������Ǝv���܂��B
���̒ʂ肾�Ǝv���܂��BCD��SACD�ɘ^������Ă���\�[�X�ŁA�_�炩�����͏_�炩���A�d�����͍d���\������̂��A����Ǝv���܂��B
�����A���͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA�d�����ɏd�_��u���Ă��܂��B�d�������_�炩������̂́A��r�I�ȒP�ŁA�Ⴆ�X�s�[�J�[�P�[�u���������āA��R�l���グ��ƃ_���s���O�t�@�N�^�[���ቺ���āA�_�炩�����ɂȂ�܂��B�܂��Ód�e�ʂ̑傫�߂̂q�b�`�A�i���O�P�[�u�����g���A���悪�ቺ���ă}�C���h�ȏ_�炩�����ɂȂ�܂��B
�������A��U�_�炩���Ȃ��ăG�b�W�݂̓��������A������ƈ������܂��ăG�b�W�̗��������ɂ���͓̂���Ǝv������ł��B
�X�s�[�J�[�P�[�u���̒�R�l���A�A�i���O�P�[�u���̐Ód�e�ʒl���[���ȉ��ɂ͂ł��܂���B
�����ԍ��F11874838
![]() 0�_
0�_
2010/09/07 21:24�i1�N�ȏ�O�j
�F������(^_^)v
�~�l���o����
�P�Q�ӊO�ł����H
���݂Ƀ~�l���o����̃x�X�g�͂ǂ�ł����H
���āA����Ђ��Ȃ�����������A�����ł����w�b�h�t�H������������o���ă��j�^�����O���Ȃ���X�s�[�J�[���`�F�b�N�������Ƃ��ĊJ���܂����i��
�w�b�h�t�H���ŕ����Ă��R�A�V�A�P�O�̓N�Z���m�ł���(^_^;)
�P�P�͂�͂蒆�悪���������オ��C�������H
�ԉ��ƌ����Ζ��l����I�i��
�����ԍ��F11875639
![]() 1�_
1�_
���[�W������A�����́B
��͂莄�̃x�X�g�͂P�P�ł��ˁB�@�Œ��ւ̐L�тƃ{�[�J���̉��ꊴ�A�_�C�i�~�b�N�ȗ}�g���ŁA�������|���Ă���悤�Ɋ����܂��B
����̎����オ�芴�́A�قƂ�NJ����܂���ˁB�ނ���{�[�J�������Ɉ�������ŁA�L��ȃX�e�[�W���������Ă��܂��B
����A�P�Q�ƂP�S�́A�P��Q���͗ǂ������ł��B
�����ԍ��F11875738
![]() 1�_
1�_
���[�W������
�C���v���b�V����11�͂��d�������ł��ˁB
15�������A���Ă��������āc
�������⌵�����ł��B
����ԈႦ��Ɣς��B���ɉ����������ł��B
�~�l���o����
�X�s�[�J�[�P�[�u���́A���̃X�s�[�J�[�̓����������o���P�[�u�����Ɓc
������L����ڂƎv���ł��B(�������������j
�𑜓x���グ����ɂ߂���́A���N�O�Ɏ~�߂܂����B
�A�N�Z�T���[�ł̉𑜓x�A�b�v��܂��ɂ߂���́A�d���P�[�u���̖�ڂɁB
���݂Ƀ��C���P�[�u���ɋ��߂�̂�SN�ł��B
�������ꂵ���Ȃ��ł��ˁB
�܁`��������̎�ϓI�Ȏ��ł�����c�P�[�u���ɋ��߂���̂͐l���ꂼ��ł��ˁBf^_^;
�����ԍ��F11875799
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����
[PC-1]���g����7S1�̃t�B���^�[��[1]�ɐݒ肵�A[�m�C�Y�V�F�[�o�[]��[DC�t�B���^�[]��ON�ɂ����LP���R�[�h�̂悤�ȉ����o�܂����B��������CD���̃t�B���^�[1�̓}�����c�̓����o�蒆�̈Ӗ���������܂����B�C�E���W�`���t�c�̎l�G��35�N�O�̐V��LP��25�N�O��CD�ł��B
LP���R�[�h�͂������ǂ������̂ł����ACD�͂�������A���ʂ������A�o�C�I�������₽��ɂ��邳�����ł����B����ł������̒艿��\3,200�~�ł��B�ǂ����悤���Ȃ�CD�̕��ނɓ���Ă��܂������A���̖ڂ�����@��ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F11876033
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����A
���̏ꍇ�A�P�[�u���ɋ��߂�̂́A�|�p���ł͂Ȃ��A���A�����A�ʎ����ł��ˁB�܂�j���[�g�����ɁA���ɂ������]�����ƂȂ��A�܂��t�������邱�ƂȂ��A���̂܂܈����o�����Ƃł��B
�������{�ɃP�[�u���̑I�������Ă��܂��ˁB�A���v��X�s�[�J�[�Ƃ̑������C�ɂ������Ƃ͂Ȃ��ł��B
�掿�ɂ�����肳��A
�V�r�P�̐ݒ�ŁA�y���߂�b�c�������ĉ����ł����B�ʐ^�̎l�G�́A2��ڂ̘^���ɂȂ�̂ł��傤���H�@���̎����Ă����k�o�́A�m�����@�C�I�������t�F���b�N�X�E�A�[���ł����B
�b�c�͍ŋ߂͉��i�������Ȃ��Ă��܂��ˁB�����̔������e���[�N�̂b�c��3,500�~�ł������A���A�g�l�u���Ō����900�~��ł��B
�����ԍ��F11876245
![]() 1�_
1�_
2010/09/07 23:07�i1�N�ȏ�O�j
�~�l���o����
�P�P�ł������I
�܂��A�����������f�J���C�͂��܂���(^_^;)
����w�b�h�t�H�����j�^�����O�������ĉ������ȁB
�I�������ł���B
�P�P�͖`���̓d�b���Ȃ��Ȃ��i��
�l�I���z�Ƃ��ẮA�������W�I�ɒ����G�l���M�[�����������x�X�g�ɂȂ�Ȃ����R���ȁH
�E���t����
�������Ȃ番����܂������d���������H
�P�T�̉w�B
�T�r�̕����͂Ȃ��Ȃ���ς��Ǝv���܂�(^_^;)
�����ԍ��F11876391
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂��B
���[�W������
����15��
�T�r�̕����B��Ȗڂ̈ꕪ�߂������肩�珙�X�ɁB
11�Ԃ͕\���̎d���s���������B
�����o���ƒ����݂����ȓ��������B(��
�e�͊��ƌ����̂��ȁ`
���������ԈႦ����T�s��(��
�������Ì��ɐݒ肷��ƍׂ��������܂ŃE�j���E�j���Ɉׂ肻���C�z�B
�Ƃ̏ꍇ�t���b�g�o�����X�����𑜓x���グ���ݒ�ɂ��Ă܂��B
�����ԍ��F11877643
![]() 1�_
1�_
2010/09/08 08:56�i1�N�ȏ�O�j
���͂悤�������܂�(^_^)v
�E���t����
�P�P�͒�������߂Ȃ��ƃ��������{�P�{�P�ɂȂ�܂���(^_^;)
���̂P�Ȃ͖ڊo�߂�V�X�e���ɂ̓x�X�g�}�b�`���O�Ɨ\�z���Ƃ�܂��B
���𑜓x�͓��M����I
�����ԍ��F11877860
![]() 1�_
1�_
�E���t����A���[�W������@����ɂ���
�P�P�ȖځA���������ڂł���I
�܂��A�`���́u�w�Ȃ炵���v�ł��A���Ɠ����G�ꍇ���������u�p�`�b�v
�h�����̓^�C�g�ŁA�����オ�艺����Ƃ��X�s�[�h������܂��B
���́A�e�͂ɕx�݁A���n�C�X�s�[�h�ŁA���g���A�����U�������������ł��B
�����ĂȂɂ��A�U��ꂽ�I���i�ɓd�b���Ă������������Ղ�̈��D�I�g�R����Ȃ��Ǝv���Ȃ�����A���S�ɐU���Ȃ������ȃI���i�R�R���A���������邩�H�@
�ȂǂȂǁ@�ł��B
�����ԍ��F11877986
![]() 0�_
0�_
������
�|���܂�₳��́u�C���v���b�V�����Y�vAMCM-4200�ł����A
�ّ�ł́A�ǂ̋Ȃ��g�t�c�[�ɖ��āh���܂��܂��B
�����Â炢���Ƃ��Ȃ��A�܌��������Ƃ��Ȃ��B
CD�v���[���[�ɂ�鍷�͑傫���ł����A��ƂȂ鉹�����J�����̂ŁA�t�ɕ]��������悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��f�X�B
���Ȃ݂ɁA���݂̃}�C�x�X�gCDP�́A�ŋߓ������Ă������胁�C���̍����߂�
SONY BDP-S360
�Ƃ������[�G���hBD�v���[���[�ł��i��
�Q���Ńu���[���C�����邽�߂Ƀ`���C�Ɠ���������ł����A���܂�̂b�c�Đ��̉��̗ǂ��ɁA�f����H���g�p���邱�ƂȂ��E�E�E�i��
�b�c�Đ��ɉ����ẮA1650AE��SA7001��u������ɂ��āAD-NE830�������킵�Ă��܂��B
�ŐV��BD�p�s�b�N�A�b�v���f�R�[�_�[�������̂��H�H�H
���R�͕�����܂��A��12,800�œW����������Ă���BD�v���[���[���炱��ȉ����o�Ă���Ȃ�ăV���W�����i�C�`
���̉��������Ȃ̂��H
����܂Œ����Ă����t�c�[��CDP�Ƃ́A�������Ⴄ�B
�����A���������ł̓��J�����ł��i��
���ꂼ��̊y��̉��F�̖炵�����A
�܂�₳��×�Q�̕����A
�B�Y����×�Q�`�R�H�̃R�[���X�����A
�w�i�̃I�[�P�X�g���A�g���C�A���O����V���o�������߂��A�ȂǂȂǁA
��`�S�����Ȃ��H�J�i�H�H
������m��Ȃ��ƁA�`�����Ɩ��Ă��邩�ǂ��������J�����̂ł��B
�����ȊO�̕��ɒ����Ē����Ă���A���ʂ�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11879780
![]() 1�_
1�_
2010/09/08 19:41�i1�N�ȏ�O�j
��H�̂���������A���[�G���hBD�v���[���[�łb�c�̉��͗ǂ��͂��͂Ȃ��A�Ƃ�������ς��A�����܂߂ĊF����Ƃ������܂��B���̃��[�G���h�v���[���������đ��̉ƒ��K�₳��Ă͂������H�@���邢�͑��̕��ɒ����Ă��炤�Ƃ��E�E�E
�����̐��E�A�ƑP�Ɋׂ�₷���̂ŁA���̐l�̑��u���̂��厖�A���̕��ɒ����Ă��炤�̂��厖
�����ԍ��F11879865
![]() 1�_
1�_
��H�̃E�T�M����
���^�N�V�͋M���̎��̊m������M�����Ă��܂��B
BDP-S360�͐�قǒ������܂����B
�G�[�W���O���I�������,�o�|�[���ƑΌ������Ă݂܂��ˁB
�y���݃B�`
�����ԍ��F11880005
![]() 1�_
1�_
��H�̃E�T�M����A�����́B
BDP-S360�͂��炵���R�X�g�E�p�t�H�[�}���X�̎�����̂悤�ł��ˁB
�Ƃ���ŁA�A�i���O�o�͂ł̕]���ł��傤���H�@����Ƃ��f�W�^���o�͂ł��傤���H
�����ԍ��F11880877
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂�
BDP-S360�ł����A�������A�|���ƒu���Čq���������ł͂���܂���B
�P�T�Ԃقǂ����āA�A���R���ᖡ�������ʂł��B
�q�����u�Ԃ́A�u�o�[���ƌ��C�ȉ��ŁA���������CDP�n�̉��v�����Ă��܂������A
���C�Ȃ����ł͂Ȃ��A�����Ȃ�ʉ��F�̉�͓x�i×�𑜓x�j�������Ă����̂ł��B
�V���o���̌��݂��A�K�c�[���ƕ�������I
�������ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
�����̃��[�G���h�v���[���������đ��̉ƒ��K�₳��Ă͂������H�@
�����邢�͑��̕��ɒ����Ă��炤�Ƃ��E�E�E
���Q���ĉƒ�K��ł��̉����m�F����̂́A��q�̂悤�ɓ���Ǝv���܂����A���̃V�X�e���łǂ���̂��͋���������܂��B
������ɂ��Ă��A���̃V�X�e���ɓ���܂���ɂ́A�P�T�Ԉȏ�̋ᖡ�͕K�v���Ǝv���܂��B
���̕��ɂ́A�߂������ɒ����Ă��炨���Ǝv���Ă��܂��B
���ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��
��BDP-S360�͐�قǒ������܂����B
�����I���������������ł����I�I
�s���������ł��ˁA����A��������悤�ȋC���E�E�E�i��
�܂��A����������ɂ͍��ǂ��J�J�N�ł����A�����D�݂łȂ��Ƃ��A�u���[���C�̓t�c�[�Ɍ����܂��̂ŁE�E�E�i�ꊾ
���I�ɂ́A���R�[�h��r�`�b�c�iSHM-SACD�j�̕����ł͂Ȃ��A
�u�b�c�炵���A�����n�����K�b�c�̂��鉹�v���o�Ă��܂����A�u�Ӑ}�I�ł͂Ȃ��v�Ƃ��낪�D�܂������ƁB
�����ԍ��F11882038
![]() 1�_
1�_
��Minerva2000����
���Ƃ���ŁA�A�i���O�o�͂ł̕]���ł��傤���H
������Ƃ��f�W�^���o�͂ł��傤���H
�������A�u�A�i���O�o�́v�ł��i��
�v���A���v�܂ł́A�u�P���v��RCA�P�[�u���i����n�j���g�p�B
�d���P�[�u���͕t���i�i���K�l�[�q���́A�b�L�̗l�ł��j�B
1500VA��EI�R�A�E�A�C�\���[�V�����E�g�����X���狋�d�B
HDMI�P�[�u�����t���e���r�Ɍq���ƁA�����ڂ₯���̂ŁA�p���B
�e���r��_���Ȃ��Ƃ��_���ŁA�_����Ɨ]�v�_���B
D�[�q�ł��_���B
���ʁA�o�͂�RCA�[�q�`�v���A���v�݂̂Ƃ��Ă��܂��B
�f���͎ʂ��܂���I
�ݒu�ꏊ�����@�ɂ���āA�����R���R���ς��܂��B
�u�̃��b�N�ɒ��u���v����ɋᖡ���܂����B
���̂��A�g��Ȃ��Ȃ����e��C���V�����[�^�[���~�����͂���̂��L��]���Ă���̂ŁA
�����͒����ɂł��o����̂ł��i���}
�����_�ł̌��ʂ́A
�̃{�[�h�i�N�A�h���X�p�C�A�j�̏��2.6mm���̃R�[���A���{�[�h��~���āA
���̏�ɒ��u�����x�X�g�A
�ƂȂ�܂����B
�̃{�[�h�ɒ��u�����ƁA���X�g�������h�i�������j��������̂ł��B
�C���V�����[�^�[�ȂǂŐ��U��������ƁA�g�V���o���������Ȃ�h�ȂǁA
�v���[���[�̗ǂ����킪���X��������܂��B
�g���Ⴖ��n���A���Ⴖ��n�̂܂܁A��肱�Ȃ��h�ƌ��������ł��i�y��
���̂ւ�́A���[�G���h�̑�햡��������܂���ˁB
���Ȃ݂ɁA���C���ʼn����킹�Ɏg�����b�c�́A�R�`����
�r���b�W�E�o���K�[�h�U�^�吼���q
�T�ȖځuTEA FOR TWO�v
http://www.hmv.co.jp/en/product/detail/270141
�����ԍ��F11882059
![]() 1�_
1�_
2010/09/09 06:34�i1�N�ȏ�O�j
��H�̂���������A�|���u���łȂ��A���낢��l��������ŁA���O�ɏ��������Ă��璮���ꂽ�̂ł��ˁB���炵�܂����A�������ł��B
�u�������j�o�[�T���v���[���łb�c���ɂ́v�̃m�E�n�E���܂Ƃ܂肻���ł��ˁB
�����������ΑO�ɂc�b�c�|�P�U�T�O�̃`���[�j���O�����Ă��܂����ˁB�������^�����āA����ւ�����������̂ł����A�S���ւ���ƃV���[�v�ɂȂ肷���B���Q�̓I���W�i���̂܂܁A�O�̃g���[�̐^���ɁA�u���b�N�_�C�������h���P���ނƃx�X�g�ɂȂ�܂����B�����n���Ȃ�A���������̓r���Ɋ��܂��̂ŁA�܂��������Ă��������B
�����ԍ��F11882132
![]() 1�_
1�_
��H�̃E�T�M����
�����́uCDP���E�t�F�`�v�͕a�C�ł��̂ŁA�C�ɂȂ���ʂ悤�ɁB
����BDP-S360��43�@��ڂ�CDP�ɂȂ�܂��i��
�����Ⴖ��n���A���Ⴖ��n�̂܂܁A��肱�Ȃ�
���������Ƃ���I�@���ꂪ�b�c�o����̑�햡�ł��B
�b�c�o���d�����P�O�L�����z���Ă���ƁA�u�D�����v�Ɓu�M�w�l�v�Ɓu�G�ˁv����ɂȂ�܂��̂ŁA�D�݂���Ȃ��̂ł��B
�o�����\���o���Ȃ��u�j�V�r�ȗV�ѐl�v�̂悤�Ȃb�c�o�����̂����ł��B
�@
�����ԍ��F11884524
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
��H�̂���������A
�����Ȃc�u�c�v���[���[�łb�c���A�i���O�o�͂ŕ����ƁA���̎�����𑜓x�ɕs�����o���邱�Ƃ�����܂����A���̂���������z����ꂽ�Z�b�e�B���O��@�͂��炵�����̂�����܂��ˁB
�V�ɐ��U�p�̂�����Ƃ��͍ڂ����Ă��܂��H
�����ԍ��F11884805
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂�
�������ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
DCD-1650AE�̐��U�`���[�j���O�́A���낢����ɂȂ�܂����B
��肷����ƁA����̉����ł̓n�C�G���h�H�݂����ȏo���ɂȂ�̂ł����A���ȉ����������Ă��܂��A���ǁA���ɖ߂����ƂɂȂ�B
�������ꂽ���[�J�[�i�̏ꍇ�A�����̍D�݂ɍ��킹�āA�g������Ƃ������t���h���炢�̃`���[�j���O���A�ǂ����~���Ɗw�т܂����B
���ǁA1650AE�́A�m�[�}���̏�ԂŁu�f�m���̉��Â���v�����߂Ɏg���Ă��܂��i���i�́A�Q����BGM�p�ł��j�B
�������́A�V�����̎~�܂�w�̂��i���a�R�����ȓ��j�ɏZ��ł���܂��̂ŁA�߂������ʂ�̍ۂ́A����A��������艺�����B
�܂��A�A�тɂ�郋�[���`���[�j���O���ɂ߂��u�������Ȃ��Ȃ����@�v�ւ��A����A���f�������ĉ������܂��B
���ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��
���o�����\���o���Ȃ��u�j�V�r�ȗV�ѐl�v�̂悤�Ȃb�c�o�����̂����ł��B
�ƌ������Ƃł�����ABDP-S360�͍��i��������܂���i��
�����A�u�j�V�r�ȗV�ѐl�v�Ƃ����I�g�i�̕��͋C�ł͂Ȃ��A
�u�V�R�n�A�X���[�g���V�тʼn��y����Ă�v�݂����ȁA�Ƃ炦�ǂ���̂Ȃ��ؓ��n�̊����ł��i�Ӗ��s���E�E�E
�����ԍ��F11886766
![]() 1�_
1�_
2010/09/10 06:21�i1�N�ȏ�O�j
��H�̂���������A
>�������ꂽ���[�J�[�i�̏ꍇ�A�����̍D�݂ɍ��킹�āA�g������Ƃ������t���h���炢�̃`���[�j���O���A�ǂ����~���Ɗw�т܂����B
���̋��n�ɋ߂��ł��ˁB�����t�j���t�j���̔��ɓ������A���v�Ȃ�A���낢��Ǝ������āA�ω����y���ނ̂͊y�����ł����A�~�h���`�n�C�G���h�@��́A������Ƃ������t�����x���D�܂����ł��B
>�������́A�V�����̎~�܂�w�̂��i���a�R�����ȓ��j�ɏZ��ł���܂��̂ŁA�߂������ʂ�̍ۂ́A����A��������艺�����B
>�܂��A�A�тɂ�郋�[���`���[�j���O���ɂ߂��u�������Ȃ��Ȃ����@�v�ւ��A����A���f�������ĉ������܂��B
���肪�Ƃ��������܂��B��O�y�j���E���ɂȂ�܂����A���N���ɁA�������������Ă��������B���̂g�o���J���ă��[�������������B
�����ԍ��F11886796
![]() 1�_
1�_
��Minerva2000����
�������Ȃc�u�c�v���[���[�łb�c���A�i���O�o�͂ŕ����ƁA���̎�����𑜓x�ɕs�����o���邱�Ƃ�����܂����`
�����Ȃ炻�̒ʂ�Ȃ�ł����A����́A�u����I����͈Ⴄ�]�v�Ƃ������ł����B
�q���̃T�b�J�[�����Ă��āA���Ƃ͓������Ⴄ�q�����ڗ����Ėڂ������悤�Ȋ����Ƃł��\���܂��傤���B
�꒮���ď��ʂ������̂ł����A�ʏ�̂b�c�o�̉��Ƃ͕��͋C���Ⴄ�����ł��B
�\�j�[�́u�v���V�W�����h���C�u�g�c�v�Ƃ����a�c�ǂݎ�胁�J�j�Y�����A�����҂ł͂Ȃ��悤�Ɋ����܂��B
http://www.sony.jp/bd-player/products/BDP-S370/feature_2.html#L1_30
�g�s�b�N�A�b�v���Ⴄ�h�����Y���Ă���Ƃ������A���̕ӂ͂��܂̂Ƃ���g���h�ł����A
�u�a�c�̏���ǂݎ�邽�߂̍ŐV���J�ɂ��Ă݂�A�b�c�̏���ǂݎ�邱�ƂȂǒ��ёO�v
�Ƃ����I�[���̂悤�Ȃ��̂���������̂ł��B
�ŁA���[�G���h�Ȃ�ł͂́A�����������g�f�̉��h���o�Ă���B
���U�ɂ��ẮA���ǁA�R�[���A���{�[�h��~���������ł��B
�����Ă���̂́u�A�C�\���[�V�����g�����X���狋�d����v�Ƃ����������Ǝv���܂��B
�����ɁA��ʗp�̕ǃR���Z���g�ɒ��h�����Ă݂��Ƃ���A�g���߂��h�������ă����������Ă��܂����B
����ł��A�|�e���V�����͊����܂��̂Łu�g�����Ȃ��Ă݂����Ȃ鉹�v�Ƃ������z�ɕύX�͂���܂���B
�����ԍ��F11886803
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ��܁A���͂悤�������܂��B
��H�̃E�T�M����A
���̗L���ȃS�[���h�����g�̒������c�u�c�v���[���[�́A�p�C�I�j�A�̈����Ȃc�u�c�v���[���[�̃h���C�u�Ɗ�͂��̂܂ܗ��p���A����_��➑́A�d����H�A�A�i���O�o�͒i�����Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA����́A�Z�b�e�B���O��➑̗̂��z�I�Ȑ��U���������A�A�C�\���[�V�����g�����X�œd���̋�����B�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��ˁB
����ɂa�c�h���C�u�ɂ����P���ʂ�������āA���炵�������o��悤�ɂȂ����悤�ł��ˁB
�����ԍ��F11886831
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ��܁A����ɂ��́B
CD��SACD��ǂ����ŕ������߂ɂ́A�d���P�[�u�����d�v�ł����A�X�s�[�J�[�P�[�u�����d�v���Ǝv���܂��B
��T�̓��j���ɁAAET��6N14G�A�X���̃X�s�[�J�[�P�[�u���ɃA�R�[�X�e�B�b�N�E�����@�C�u��SPC-Reference�A50�������p���������Ƃ���A�������オ�����Ɋ������܂����B
����Ȃ��ƂŁH�ƕs�v�c�Ɋ�������Ǝv���܂����A���ۂɉ������オ�������܂����B
���݁A�����ȃX�s�[�J�[�P�[�u�����g���Ă����A�����ɉ����̃l�b�N������ƍl���Ă�����Ȃ�A�����X�s�[�J�[�P�[�u���̌p�������́A�����Ă݂鉿�l������Ǝv���܂��B
�p�������ɂ́A�W���C���g�E�X���[�u��p���A�������܂����B
�����ԍ��F11928882
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����A�����́B
���[���ʂ͐����ł��ˁB�P�[�u�����w���������Ɉ�N�Ɉ��͖��[���V���������Đڑ�����悤�Ɍ����܂����B���ꂾ�����[�̓V�r�A�Ȃ̂ł��傤�ˁB
PC-1�����������ɃG�[�W���O���������܂����B���������S�ĉ������A����̉��ʂ��A�b�v���܂����B�����Ƃ���2db���炢�ł��傤���B������������Ȃ��ꂽ�����ŁA�o�C�I�����̐L�т��ǂ������ɂȂ�܂����B����ő剹�ʂ������ʂ�GOOD�ł��B
�����ԍ��F11930530
![]() 0�_
0�_
�掿�ɂ�����肳��A�����́B
�X�s�[�J�[�P�[�u���ŁA���[���ʂ͂�͂肠��Ǝ������܂����B���̂��A�ŁA�����ɃP�[�u���̃O���[�h�A�b�v���o���܂��B
PC-1�͂��܂��V�X�e���ɂȂ���ł����悤�ł��ˁBPC-1�ɂ��ẮA���낢��ȃI�[�f�B�I�]�_�Ƃ̃��r���[��ǂ݂܂������A�掿�ɂ�����肳���g�p�̂a���v�̃X�s�[�J�[�ƁA�����g�̍D�݂̌X������A��ϗǂ������Ǝv�����E�����Ē����܂����B
�C�ɓ����ĉ����ł����B
�����ԍ��F11931316
![]() 0�_
0�_
��H�̃E�T�M����@�F����@�R���j�`�n
BDP-S360 �̃v�`�ł��B
��H�̃E�T�M����A�H��
���u�V�R�n�A�X���[�g���V�тʼn��y����Ă�v�݂����ȁA
���Ƃ炦�ǂ���̂Ȃ��ؓ��n�̊����ł��i�Ӗ��s���E�E�E
�����ΑS�R�Ӗ��s������Ȃ��āA���̂܂܂̗Ⴆ�ł�
�e�͂������āA�������ǂ��āA�����Ċ��炩�ł��B�������A�����̒���������Ă��Ȃ��̂ŁA�u���̂b�c�͂���ȉ��Ŗ�n�Y�v�Ǝv���Ė]�ނƁA���҂Ƃ͈Ⴄ���߂Ŗ�܂��B���̂�����͍D���������͂����蕪�����Ƃ��ł��傤�B
���M���ׂ��́A���͂ȁu����уK�[�h�v���@�\���Ă�悤�ŁA�b�c�Đ����ɖ{�̂������グ�āA�T�p�قǂ̍�������Q�O��قǎ��R���������Ă݂܂������A����т��܂���B
�a�ݕt���ɂȂ�܂��ˁA���̉��@����Ȃ��y�����B
�ǂ̂b�c���Ӑ}���Ȃ����̃T�v���C�Y������܂��B
�g�ݍ��킹��A���v�ł����A�\�j�[�̃f�W�A���Ƃ̑��������Q�ł����B
����Ő^��ǃA���v�Ƃ̑����͑S���_���ŁA�u�}�g�̂Ȃ��A�C�ȉ��v�ɂȂ��Ă��܂��A�A���v��I�ԗ��R�͕s���ł��B
�����ԍ��F11943757
![]() 1�_
1�_
������
���ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��
BDP-S360�̂��������|�[�g��L���������܂��B
������S360�́A���C�������t�@�����X�̔�����q�v���[���[�ƂȂ��Ă���A�R���}�X�Ƃ��āH���X���g����Ă��܂��i��
���̃v���[���[�̉��y�\���������ƁA���̃v���[���[����l����������悤�ɂȂ�̂ŕs�v�c���ʔ����ł��B
��X�������C�ȉ��t�́A�n�C�G���h���܂߂Čo���������A�a�ݕt���ł��B
���Ȃ݂ɁA�p���[�A���v��Nmode X-PM1�ł��̂ŁA�f�W�^���A���v���Ƃ����̂��ǂ��̂�������܂���B
��������S360�ɖ�����ꂽ�����̎������������Ȃ����̂�������Ȃ��H�̂ŁA
���̏T���ɃA�L���t�F�[�Y�̃t���b�O�V�b�v�����鎎����ɍs���āA�����̎��̕ω����m�F���Ă��悤�Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F11962430
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂�
�v�`�ł��B
���[�G���h�E�u���[���C�E�v���[���[BDP-S360�ɂ��b�c���t�́A
�莝����TRIODE TRV-88ST�i�Nj��A���v�j�Ŗ炵���Ƃ���A�u����Ȃ��v���Ƃ��������܂����B
�c�������ăk�P���ǂ��A�M���M���ꍞ��ł��钆���悪���Ȃ��A�}�f�Ȃb�c�o�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
����ł́A�A�X���[�g�ȃv���[���[�̐^���������܂���B
���N�́ANmode X-PM1�̂܂܁A�~�����z�����ƂɂȂ肻���ł��B
�K�����Ǝ����ς��āA���Y�n�C�G���h�̗Y�A�A�L���t�F�[�YC-3800����I�ڎ�����A�s���Ă��܂����B
�X�s�[�J�[�FB&W 802 Diamond
�p���[�A���v�FM-6000×2
�v���A���v�FC-3800
�f�W�^���E�v���[���[�FDP-800�{DC801
�A�i���O�E�v���[���[�FVPI Scoutmaster�U�{C-27
�i�P�[�u���W�͊�{�I�ɃA�L���t�F�[�Y�̏����i���g�p�j
�n�C�G���h�ȕ��X�́A���������������߂Ă����ł��ˁ`�i�t���t��
�����̎��������A����������āg���Ǝ��h�ƂȂ肻���ł��B
�n�C�G���h�ȋ@�ނ������Ă��āA�|���Ƃ���炵���ݒu���������ł́E�E�E
�����ԍ��F11975788
![]() 1�_
1�_
������
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��
> �b�c�Đ����ɖ{�̂������グ�āA�T�p�قǂ̍�������Q�O��قǎ��R���������Ă݂܂������A����т��܂���B
������āA�ڊo�߂�ƁA����̋V���ǂ����H
��H�̃E�T�M����
�����Ƃ��߂łƂ��������܂�
�A�`�Ƃ������A��`�Ɏv����̂͋C�̐�������
����ł́@
���炵�܂�
�����ԍ��F11979763
![]() 2�_
2�_
��Show Jhi����
������̋V���ǂ����H
�����ǂ��B��]�n�V���肳��́A�K�{�A���ɑ嗤����
���E�T�M����
�b3800�̕����R����1�����P�Q�{�i�P�Q�O�O�O�O��F�j�ł��B
�v���Ƃ��Ă͔j�i�̗e�ʂł����A�_���͓d���̋[���c�b���A����Ƃ��n�C�G���h�ӏ����H�H
������ɂ��Ă��A�����Ȃ��@�ł��傤�˂�
�����ԍ��F11980167
![]() 1�_
1�_
�F����A�����������Ă���܂��B
Pioneer���f�B�A�E�v���C���[����GOLDMUND�ւ̃��^�����t�H�[�[�̂��b������܂������A
���݁A��ԋC�ɂȂ郁�^�����t�H�[�[����������A�C�e����OPPO BDP-83SE Nuforce Edition�ł��B
http://www.nuforce.jp/highend/products/oppo_01.html
�V���b�v�E�u�����h�̎s�̕i�`���[�j���O�E���f�����Ă�����������܂����A
�n�[�h�E���[�J�[���瑼�Ђ̐��i���J�X�^�}�C�Y�����Ⴄ�̂��Ē������Ȃ��Ǝv���Ă܂��B
���L��SONY�̃��f�B�A�E�v���C���[��BD-R�v���C���[�芷���悤���v�Ă��Ă��ł����A
�Đ���p�@�Ȃ���N�I���e�B���ǂ̒��x���������C�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F11988136
![]() 0�_
0�_
2010/09/29 23:11�i1�N�ȏ�O�j
����ɂ���Red����A���̋@��oppo�͎����C�ɂȂ��Ă���A�`���b�ƒ����������ł����A�ڂ������|�[�g�͂����ɂ���܂��B
http://community.phileweb.com/mypage/entry/1427/20100925/20747/
�����̂P�O�O���~�̃v���[��Unidisk�Ɣ�ׂāA����ȍ��͂Ȃ������Ƃ̂��Ƃł��B
�����u���[���C��{�i�I�Ɍ���Ȃ甃�������̂ł����E�E�E
�����ԍ��F11988556
![]() 0�_
0�_
redfodera���� �A�����́B���v���U��ł��B
�������̋@��͋C�ɂȂ��Ă��܂��B�R���Z�v�g��2CH�����ɂ�������Ă���悤�ŁABD�̃A�i���O�������v���Ɍq�������Ȃ��Ă��܂����B5.1CH���t�����g���[������ƍX�ɗǂ��Ȃ�悤�ȋC�����܂��B�����A���Ԃ̃e���r���̏�Ŕ����ւ�����Ȃ��A���K�I�ɓ���肪���܂���B
�����ԍ��F11997981
![]() 0�_
0�_
2010/10/02 06:11�i1�N�ȏ�O�j
�掿�ɂ�����肳��A����ɂ��́B
Redfedora����́A�ǂ����֍s���Ă��܂����悤�ŁB�B�B
���̋@��͂�������ł��܂���B������NuForce�ł͍ɂ��c���Ă��邩������܂���B
OPPO�̃z�[���y�[�W�ɂ͂���BDP-93�����\����Ă��܂��ˁB������������B
http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-93/
���̂����A��������ǂ���NuForce��BDP-93SE���ł�ł��傤�B
���̂悤�ȊO�����́A���[�W�����t���[�ł��邱�ƂƁA�a�c�̓ǂݍ��݂������̂������炵���ł��B
���[�W�����t���[�āA�ǂ�������Ȃ��̂ł��B�����Ă��������B
�����ԍ��F11998649
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A����ɂ��́B
����������ł����B�T�C�N���������ł��ˁB�܂�BD�͌̏Ⴊ�S�z�ł��B�t�����͉߂������̂̃t���[�Y���ĉ�������Z�b�g���������v���o���܂��B�w������ƕK���T�[�r�X�ɗ��Ă��炢�܂����B�O�����ƂȂ�ƍX�Ɍ̏Ⴊ�S�z�ł��ˁB
���[�W�����t���[�͑S���m��܂���ł����B�����͒��쌠�̊W�ŃR�s�[�K�[�h�����邱�Ƃ͒m���Ă��܂������A�s�̂̃\�t�g�ɂ����邱�Ƃ͓��R�Ƃ��āA����̎�ނł��傤���BGoogle�̌����Œ��ׂĂ݂܂����B
http://www.region-free.net/
�����ԍ��F11999153
![]() 0�_
0�_
2010/10/02 10:28�i1�N�ȏ�O�j
�掿�ɂ�����肳��A���[�W�����t���[�͕�����܂����B����
������̑傫�ȓ��F�͂n�o�o�n��P���u���b�W�I�[�f�B�I�͂a�c�̓ǂݍ��݂����������ł��B
�f�m����}�����c�́A�a�c�����Ă���Đ�����܂ŁA�g���������ς�����Ĉ��ގ��Ԃ����邻���ł����A�n�o�o�n��P���u���b�W�I�[�f�B�I�͂����ɍĐ����n�܂邻���ł��B���͂��̑����ŊO�����i�P���u���b�W�ɒ��ځj�����Ǝv���܂��B�C���͑㗝�X��ʂ��̂Ŏ��Ԃ�������܂����E�E�E
����ƍ��Y�i�̓A�i���O�ڑ��͂��܂������ŁA�g�c�l�h�ڑ�����͂ł����A�����̊O�����́u�A�i���O�ڑ����������߂��܂��v�Ə����Ă��邭�炢�ŃA�i���O�̉����ǂ������ł��B����͂b�c�ɂ������܂��B�I�[�f�B�I�A�N�Z�T���̊L�R�搶�̎����L�ɂ����������Ă���܂��B
�����ԍ��F11999402
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
���f�m����}�����c�́A�a�c�����Ă���Đ�����܂ŁA�g���������ς�����Ĉ��ގ��Ԃ����邻���ł�
�����Ȃ�ł��B���t�̓r���Ń\�t�g�����ւ���Ƃ��ł��C���C�����܂��BCDP���݂̃X�s�[�h������Ɖ������v���܂��B
���C���͑㗝�X��ʂ��̂Ŏ��Ԃ�������܂����E�E�E
�����ł��ˁB�}�����c�̂悤�ȃV�X�e��������Ă���Ύ��Ԃ����Ŏ�Ԃ͗]�肩����܂���B�A������Ƒ�z�ւ�����p�ӂ��ĖK��A�C������������ƁA�܂��A�͂��Ă���܂��B
���u�A�i���O�ڑ����������߂��܂��v�Ə����Ă��邭�炢�ŃA�i���O�̉����ǂ������ł��B
�v�X�A�~�����Ȃ��Ă��܂����B�O�����Ƃ͏�Ȃ��A�̂̃\�j�[�ł�����A�Ƃ����ɂ���Ă����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F11999780
![]() 0�_
0�_
Minerva2000����A����́B
���Љ�����d���P�[�u���APC-1��CDP�̓d���Ɏg�p���Ă��܂����������ǂ��ł��B80�N���DDD�^���ɂȂ��������CD�͉��������]���������悤�ł����A���̓������Ɖ��ꂪ�n�b�L���ƍČ�����ŋߔ������V���O�����C���[��2CH�ASACD�����Տꊴ�ł͏���܂��B������ADD���������ǂ��ł��B���ʖL�Ŕ��ɐS�n�ǂ������܂����A�{���̐��̉��͊������������̂��鉹�ł�����ADDD�^���̕������ɋ߂��ł��B
����ɋC��ǂ����ăv���ƃp���[�̓d���P�[�u��������ɂ��悤�Ǝv���܂���Minerva2000����̉���ł�LUX�����̂��̂ł��ǂ��ł��傤�ˁB���Ƀp���[��50Kg�߂�����܂��̂ň�l�ł͓������܂���B
�����ԍ��F12020851
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A�掿�ɂ�����肳��@
���ǂ����֍s���Ă��܂����悤�ŁB�B�B
���݂܂���B
���X�����Ă����̂ɋC�����Ă���܂���ł����B
�V�����ߋ����̊W�Ŏ����Ԃ̔֗���Ă��ăI�[�f�B�I�W�͂��܂�`�F�b�N���ĂȂ�������ł��B
�C�ɂȂ��Ă���Ԃ�OPPO�̓f�B�X�R���ł����i���j
BDP-83SE Nuforce Edition�͂܂������ł��Ă܂���Cambridge Audio�͎����ł��܂����B
�掿�͍D�݂������ɕ����ꂻ���ł��������͂������肵�Ă�������Ǝv���܂��B
�v���[���X�����߂ŁA���X�A�����C�ꃊ���@�[�u�݂����Ȗ�������邱�Ƃ�����܂����A
��H�I�ɋ߂������g���Ă���̂����Ђ�DAC Magic�ƃj���A���X�͋߂���ۂ��܂����B
SONY��BD-R�̏�ʋ@��������y������炵�����Ă���Ă��܂����B
�����ԍ��F12021401
![]() 0�_
0�_
2010/10/07 10:25�i1�N�ȏ�O�j
Redfodera����A�P���u���b�W��������܂������B
�����C��݂����ɂȂ�͖̂��ł����A�C���V�����[�^�̊O�t���ƁA�≏�g�����X�����Œǂ����߂�Ǝv���܂��B���|�[�g�L��������܂����B
�����ԍ��F12022968
![]() 0�_
0�_
�F�l�A�����́B
�掿�ɂ�����肳��A
PC-1�̒��q���ǂ��悤�ŗǂ������ł��ˁB�v���ƃp���[�͕t���̓d���P�[�u���Ŏ��͏\�����Ǝv���܂����APC-1�Ɍ��������ƁA�܂��قȂ鉹���ɂȂ�Ƃ͎v���܂��B������ύX����邩�ǂ����́A�掿�ɂ�����肳��ɂ��C���������Ǝv���܂��B
�R�����g��ǂ܂��Ē����āA�ȑO���炨�ڂ낰�Ȃ���A�v���Ă������Ƃ��A���ĂɂȂ��Ă��܂����B����́ACD��SACD���Ă����Ԃ̎O�̕ω��ɂ��Ăł��B
���i�K�F���O
����́A�I�[�f�B�I�V���b�v�̎������ŕ������A�䂪�Ƃ�CD��SACD�̉��͈������A����͑f�l�̃Z�b�e�B���O�����A�����̉��������������̂Ŏd�����Ȃ��ƒ��߁A�䖝���Ă���i�K�ł��B
���i�K�F�ے�
����́A���Ȃ�Đ����̃��x�����オ��A�����CD��SACD���ƁA�I�[�f�B�I�V���b�v�畉���̉����o��悤�ɂȂ������A���̒��ɂ͘^���̈���CD��SACD�������ƒQ���Ĕے肵�ACD��SACD��I�ʂ���i�K�ł��B
��O�i�K�F��m��
����́A���ɂ̍Đ����x�����B�����ꂽ�i�K�ł��B�u�v���̃��R�[�f�B���O�G���W�j�A���A�v���̘^���@�ނ��g���Ę^�����A������v���̃I�[�f�B�I�Đ����u�ōĐ����A������v���̃~���[�W�V�����������Ăn�j���o���č��ꂽCD��SACD�Ɂi���t�̈������̂͂����Ă��j�^���̈������̂͊�{�I�ɖ����B�v�ƌ������Ԃł��B�ǂ��CD��SACD�����ꂼ��̉��̗ǂ������\�ł��鋆�ɂ̒i�K�ł��B
�掿�ɂ�����肳����A���悢�悱�̒i�K�ɓ��B���ꂽ�̂��Ǝv���܂��B
�������́u���R�[�h�|�p�v�ɂ́A�u80�N��̃f�W�^���^���́A�܂��Z�p�҂��f�W�^���^���@�ނɊ���Ă��Ȃ����߁A�^�����������A90�N��ɓ����Ă悤�₭�A�f�W�^���^�����ǂ��Ȃ��Ă����B�v�Ƃ̋L�q������܂��B�����Ƃ������L�����ɂ́u80�N�㏉���̃f�W�^���^�����������ǂ��B�v�Ƃ̋L�q������܂����B
�v���̃��R�[�f�B���O�E�G���W�j�A���A�V�����^���@�ނ��g�����Ȃ���悤�ɂȂ�̂�10�N������Ƃ́A�u�s�u�̃����R�����Ȃ�Ƃ��g����悤�ɂȂ�̂�1�N���������B�v�Ƃ����̂Ɠ����ʔn���������Ƃ��Ǝ��͎v���܂��B�v���Ȃ�2�A3��������Ί����ɂ��̓�����c�����āA�ǂ��^�����\�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12025164
![]() 1�_
1�_
Minerva2000���� ����ɂ���
�����t�̈������̂͂����Ă��j�^���̈������̂͊�{�I�ɖ����B
���ƌ������ԁB�ǂ��CD��SACD�����ꂼ��̉��̗ǂ���
�����\�ł��鋆�ɂ̒i�K�ł��B
���@�`�@��O�i�K�̂��b�́A�����^���v���܂��B
�����ǂ��b�c��悭�Ȃ��b�c������A�K�R�I�ɉ����ǂ��Ղ�����A����������Ă���ƁA�������y�n�D�ɂȂ�A�����{�l���C�Â��Ȃ����Ƃ��A��Ԃ̖��ƍl���Ă��܂��B
�A���A��O�i�K�֓��B����ɂ́A�@�퐫�\���x���A�b�v���g�����Ȃ��A�ɉ����A���X�i�[���\�̃��x���A�b�v���s���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12036859
![]() 1�_
1�_
�F����A���͂悤�������܂��B
���d�����A���R�[�f�B���O�ɂ͂��ꂱ��֗^���Ă��铖���ɂƂ��Ă͌��������E�E�E
�A�[�e�B�X�g���l�̎q�ł��āu�D���ȉ��v���Ă������������܂��B
������Lo-Fi�ȉ��i�Ⴆ��bit���̒Ⴂ�r�ꂽ�T���v�����O���j���g��������l�����܂����A
�h�����̉��̓i�`�������E�R���v���b�V�������~��������A�i���O�Ř^���Ă���Ƃ�������܂��B
�������͐l��{�̃A�[�e�B�X�g�̈ӌ��ł����Ă������܂ł����ȕ\���ɑ��邱�����ł����āA
�K�������I�[�f�B�I�E�t�@�C���̍D�݂�����Hi-Fi�ł͂Ȃ������肵���Ⴄ���̂ł��B
�������ǂ�ȃ\�[�X�ł����Ă��o�W�F�b�g�������낤�Ɛ���`�[���̓x�X�g��s�������Ƃ�����̂ł��B
�A�[�e�B�X�g�̈ӌ��d���Ȃ���G���h�E���[�U�[�����炩�̖���������̂�ڎw���Ă���܂��B
�����I�[�f�B�I�E�t�@�C���̊F����̗v�����x�����Ė��ɍ����ł�����ˁi���j
���̈�܂ʼn��������B���Ă���Ă��邩�́A�����A�^��ł��i��j
Minerva2000����̑�O�i�K�ɒp���Ȃ��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃƃv���b�V���[�̂�����redfodera�ł����B
�����ԍ��F12037001
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ��܁A���͂悤�������܂��B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
���^���A���肪�Ƃ��������܂��B
���́A���܂����i�K�Ȃ̂ł����A�P�[�u���ނ╔���̃`���[�j���O�ŁA����܂ō��悪�����Â炢�Ɗ����Ă���CD�i�]���Ę^��������CD���Ǝv������ł����j����A����܂ŕ��������Ƃ̂Ȃ��A���X�����N��ȍ��悪���������o��������A���i�K�̐�ɑ�O�i�K���L�肤��̂ł́A�Ɗ���������ł��B
��Ƃ���A��O�i�K�ɓ��B����ɂ́A���R�[�f�B���O�G���W�j�A��~���[�W�V�������ǂ��Ƃ��������A�����̍D�݂̉��̌X���Ƃ͊��S�ɍ��v���Ă��Ȃ��Ƃ��A���̌X���̈Ⴂ�́A����͂���ŗǂ��Ƃ���A���X�i�[���̃L���p�V�e�B�̑傫�����������Ă����K�v������Ǝv���܂��B
redfodera����A
���̑�O�i�K���́ACD��SACD�������ł���悤�ɂȂ�A���R�[�f�B���O�G���W�j�A��~���[�W�V�����́A���̃��x���ɂȂ�܂łɃt�B���^�[���������Ă���Ƃ����u���P���H�v�ɗ����Ă���܂��B
���̃t�B���^�[�ɂ����葹�˂����A�t�B���^�[���o���̕����쐬�����u�G�L�Z���g���b�N�v��CD��SACD����������Ƃ���A�q�ϓI�Ɂu�^���������v���̂����邩������܂���B
�u�^��������CD��SACD�͊�{�I�ɖ����v�Ƃ͌����Ă��A���̌X���̍D�݂́A�v����f�l�Ɋւ�炸�A�獷���ʂ��Ǝv���܂��B�]���܂��āA���̌X���̍D�݂��҂����荇�����Ƃ͏��Ȃ��ł��傤�B�ł����̌X���̈Ⴂ�͈Ⴂ�Ƃ��ĔF�߁A���ꂼ��̉��̌X���̗ǂ����y���߂�̂����z�I�ł͂Ȃ��ł��傤���H
�Ⴆ�A�I�[�P�X�g����CD�����A���ډ���̂̉����D���Ȑl�ł��A�z�[���g�[���������Ղ�̘^�����u�^��������CD�v�Ɣ��f�����A���̖L���ȋ������y���߂�L���p�V�e�B�̑傫�������Ă�悤�ɂȂ�Ƃ��炵���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12037324
![]() 1�_
1�_
Minerva2000���� ����ɂ���
���^�N�V�͍����Ȑf�f�ŁA��l�i�K�ɋ���Ǝv���Ă��܂��B
�ǂ̂b�c�ASACD�ɂ����Ă��A�u�����v�ł͂Ȃ��A���u�ӏ܁v���[�h�ɂȂ�A���u�̑��݂͈ӎ���������Ă܂��B
��l�i�K�́u�I�[�f�B�I���u�̑��݂��ӎ���������A�P���ɉ������������ɂ����ԁi���A�r�o��������Ƃ͈Ӗ����Ⴂ�܂��j�v�Ə���ɒ�`���܂����B
�����Ȃ������������́A�ӎ����v�ŁA�����E����E��ʁE�ו��𑜓x�̒Nj��͑S�Ď̂ĂāA�u�}�g�̑召�v�u�˂���̉𑜓x�v�u�˂���̃R���g���X�g�v�ɏœ_���i���Ă��瓹���J���܂����B�������\�[�X����ʼn����E����͏o�܂����A�o���Ȃ�̑��̌��ʂł��B
�J�M�̓v���A���v�ł����B
�l�X�Ȍ��������āA���͏������ǂ��Ȃ��āA���Ď��ɉ����Ɏ�����悤�Ɩ��������A�v���̕ύX�͌��ʐ�傩�Ǝv���܂��B
���ƁA�������w�E�����Ă����I�[�f�B�I���ԒB�Ɋ��ӂł��ˁB���������ł͂ǂ����Ă��u�ЂƂ�悪��̉��v�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F12038634
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
�����[���u��l�i�K�v�̂��b�A���肪�Ƃ��������܂��B
���́u��O�i�K�F��m��v�ł́A�X�s�[�J�[����o�Ă��鉹�ɑ��āA���͂�ᔻ��ے�̈�ؖ�����Ԃł���A���邪�܂܂Ɏ�����Ԃł��̂ŁA�h�u�����v�ł͂Ȃ��A���u�ӏ܁v���[�h�ɂȂ�A���u�̑��݂͈ӎ���������Ă܂��B�h�̒i�K���Ӗ����Ă��܂��B
�q�ׂ��Ă���u�ӎ����v�v�̂�����ł́A���̗����ł́A���i�K�F���O�A����i�K�F�ے�A�̏�Ԃ����݂��Ă���悤�ɂ��犴���Ă��܂��܂��B
����͎��̗���������Ȃ��������Ǝv���܂����A��O�i�K��˂���������l�i�K�̃C���[�W�����ɂ́A�͂����肵�܂���B
���̗����̃J�M�́u�v���A���v�v���Ǝv���̂ł����A���̓����łǂ��ς���āA���̌��ʂƂ��Ăǂ̂悤�ɐV���ȑ�l�i�K�Ȃ̂��A��낵����ΐ����肦��ƁA�傢�ɎQ�l�ɂ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12039953
![]() 1�_
1�_
Minerva2000���� ����ɂ���
�����A�����Ȃ�ł��ˁB
�~�l���o����́u��O�i�K�v�͂ƂĂ��L���͈͂�ԗ����Ă��܂��B
�Ȃ���^�N�V�͂܂��A��O�i�K�ł����B���炵�܂����B
�ӎ����v�͂Q�˂R�ŁA��@�̓v���A���v�ɂ����̂ł��B
���R�Ƃ����C���[�W�Ȃ�ł����A�I�[�f�B�I�����ъ�����@�̂悤�ɁA�W�X�Ǝd�������āA
���X�̐����̒��ō��q�ɓO������Ԃ������āu��l�i�K�v�ƕ\�������������̂ł��B
�ł́A��l�i�K��V������`�����Ă��������B
�u�ڊo�߂�v���A���i�R���ɓo�ꂵ�Ȃ��Ȃ������A��l�i�K�ɓ������ƁA���l�����������B
���̃n�[�h���͂��Ȃ荂�����ł��B
�����ԍ��F12040250
![]() 0�_
0�_
�ڊo�߂�ƌĂԐ��������邳��A
�����ł��B
�����̃n�[�h���͂��Ȃ荂�����ł��B
���̃n�[�h���͉z���邱�ƂȂ��A���i�����i.com�ł̂���������҂��Ă���܂��B
�����ԍ��F12040344
![]() 1�_
1�_
�F����@������
�D�݂̉��ŁA�D���ȉ��y��������Ζ�������^�C�v�Ȃ̂ŁA
�I�[�f�B�I�̒������̒i�K�����́A���ɂ͓�����b�ł��B
���J�M�̓v���A���v�ł����B
�l�X�Ȍ��������āA���͏������ǂ��Ȃ��āA���Ď��ɉ����Ɏ�����悤�Ɩ��������A�v���̕ύX�͌��ʐ�傩�Ǝv���܂��B
�����g�ǂ̃��x���i�i�K�j�ʼn��y�������Ă���̂��͕ʂɂ��āA�v���͏d�v���ƔF�����Ă��܂��B
�v���A���v�́ASP��p���[�A���v�ɔ�ׂ�CP�ł͈��|�I�ɕs���ȗl�Ɋ����Ă��܂����A
�I�[�f�B�I�̎���ɍS��A�v���A���v�̑��݂͏d�v�ŃV�X�e���̗v���Ƃ��v���Ă��܂��B
���̑唼�̓X�s�[�J�[�Ō��܂�ƌ����܂����A�l�I�ɂ̓A���v�̓X�s�[�J�[�Ɠ������Ɗ����鎞�������A
���ɁA���̕i�ʂ≹�F�̕����́A�v�����S���Ă����Ȗ������Ǝv���܂��B
�|�p�̏H�ł��ˁB
10�����܂ŁA�h���˓����ی|�p��2010�h���Â���Ă��܂��B
�l�I�ɁA���͂Ȃ��狦�͂����Ă��������Ă��܂��B
�����̌��I�Ȍ|�p�Ƃ̕����o�i����Ă��܂��̂ŁA�����̂�����͐���A�����ɂȂ��Ă������������ł��B
�����ԍ��F12050900
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ��܁A���͂悤�������܂��B
�̂̓v���A���v�Ƃ̓t�H�m�C�R���C�U�[�t�����C���Z���N�^�[�̈ʒu�t���ŁA�����ς�t�H�m�C�R���C�U�[�����̉������d������Ă����悤�Ɏv���܂��B
���C���Z���N�^�[�����͕K�v���I�ȑ��݂ŁA�p���[�A���v�Ƀ{�����[��������A�v�������Ŏg������A�v�����͂ƃp���[�A���v���ړ��͂ʼn������ς��Ȃ��̂��A�ǂ��v���A���v�Ƃ�����������܂����B
�����̕��ɋ��ʂ���l�����́A�v���A���v�ʼn��������Ȃ邱�Ƃ͂����Ă��A�ǂ��Ȃ邱�Ƃ͖����Ƃ������̂ł����B
���̓{�����[���t�����C���Z���N�^�[�Ƃ����ʒu�t���ŁA�{�����[�������̍����������d������Ă���悤�Ɏv���܂��B�����Ƃ��{�����[����ʂ����ƂŃv���[���[����̉��������シ��̂ł͂Ȃ��A�����ɗȂ����ʕω������邩�A�ł���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12057393
![]() 1�_
1�_
audio-style����
�����̕i�ʂ≹�F�̕����́A�v�����S���Ă����Ȗ���
�u���t���炸�v�̃��^�N�V�̃t�H���[�A���肪�Ƃ��������܂��B
��L��30�����ŁA�S�Ă�����Ă��������܂����B
Minerva2000����
���v���A���v�ʼn��������Ȃ邱�Ƃ͂����Ă��A
���ǂ��Ȃ邱�Ƃ͖����Ƃ�������
�������ɗȂ����ʕω������邩
�v����K�v���ƍl���A�u�N�x�̏����x�����v�ƁA�u���y���̕t���v��V���ɂ����āA�x�^�[�Ǝv����@���I����̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12057551
![]() 0�_
0�_
�~�l���o���� ���͂悤�������܂��B
���I�ɂ́A�p���[���̃g�����X�ƃv�����Ƃ̓Ɨ��B
��������g�������ǂ����ȂƁB
���Ɩ��̓{�����[�������ȂƁB
�Ƃ���ŁA�d���P�[�u�������삵�܂����B
�Ⴄ�X���ł́A���\���܂������B
�A�R���o�̃p���[�X�^���_�[�h�B(3.5SQ�j
�v���O�̓I���C�f�B�x�����E����IE�ɁB�R���Z���g���p���W�E���B
�X�s�[�h���C�͊��CSN���ǂ��B���̃p���[�X�^���_�[�h�͋v���Ԃ�̃q�b�g�ł��ˁB
���̑O�܂ŃT�G�N�̓d���P�[�u���蔄��ɂ��悤���Ǝv���܂������B����ς�A�R���o�����ȂƁB
�j���[�g�����ŕȂ��Ȃ��B����Ӗ��D�_�s�f���ǂ����ʂɁB(��)
�\�t�g�Ɋ���ĉ₢���A�n�V���M�߂����A����
�������������������ȂƁB ����d���̃v���O�̌��ʂ��Ƃ��v���܂���
�����ԍ��F12062504
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����A�����́B
�����ł��ˁB��ʂɃZ�p���[�g�A���v�̉����ǂ��̂́A�d������������Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B
�d���P�[�u�������삳��܂������B
�A�R���o�̃p���[�X�^���_�[�h(3.5SQ�j�́A�����A�R���o��5.5SQ��ʃP�[�u�����]�����ǂ��ł��ˁB������̕�������\�Ɨ͊����ǂ��悤�ł��B�P�[�u���͑�����Ηǂ��Ƃ������̂ł͖����̂ŁA�I�����ނ������ł��ˁB
�v���O��P-046�AIEC�R�l�N�^�[��C-004�ł��傤���H
����̓d���P�[�u���̉����ǂ��ƋC�����ǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F12064349
![]() 0�_
0�_
�����́`
�~�l���o����
����̎��� �ޗ������ł��䂤�ɔ���2���͉z���Ă܂��B�B
3.5�ɂ������R�B
���X�|���X �t�b�g���[�N���ܘ_�ł����B
��n�M��[�c�����������ނƂ�5.5����Y���ɂ��ĂQ�܂�B
���ꂾ�Ɨ����ɃX�g���X������Ǝv���B
�� �݂��o���P�[�u�����{�A�R���o����a����܂������ǁB
����܂��Ƃ�ł��Ȃ����i���Ƃɗ��܂����B�B
�����ԍ��F12065349
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
���[���E���t����A
�I���C�f��P-037��5.5SQ��Tunami�@Nigo��ڑ����鎞�́AY���ɂ��ē���܂����ˁB���ɃX�g���X���������Ă���Ƃ͊����܂���ł������B
�݂��o���P�[�u���Q�{���y���݂ł��ˁB�悯��A�܂������z�����肢���܂��B
�����ԍ��F12065759
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
�������P�[�u���e�X�g�J��Ԃ��B
�`���b�Ǝ���(��(��)
������瑼�̃��[�J�[(CSE�j�̃P�[�u�����e�X�g���˂čs���Ă܂��I
����̕]���ł����c�B�����܂ł������������ł����c
�����������ƌ����\�����s�b�^���ł��āB���ƌ����ďu���͑���Ȃ��ƌ������Ƃ��Ȃ��B
�|�p���ɓ��������~�b�N�X�������B
�r�m�グ�ė֊s�\���A����Ȋ����ł��B
�����p���[�X�^���_�[�h�B
���̃P�[�u�������s�����o�ė��̊��ɗD��Ă܂��B
���{�����[�����グ��Ɣς������܂����c�B
�Č����܂��̂������W���L�����Č����\���ł��B
�����Q���O��̐��i�Ȃ�D��Ă܂��B
�����l�i�Ȃ�l�C�̃]�m�g�[�����ǂ��C�����܂��B�B
�����ԍ��F12074038
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A����ɂ��́B
���[���E���t����A
�d���P�[�u���̃��r���[�A���肪�Ƃ��������܂��B
��͂�A�v���O��IEC�R�l�N�^�[�̍��������āA��⎩��̂ق������D�݂Ƃ������Ƃł��ˁB
���삪�ʓ|�Ƃ������ɂ́A�A�R���o���i���ǂ���������܂���ˁB
�����ԍ��F12074533
![]() 0�_
0�_
�~�l���o����
���炭IE�R�l�N�^�[�B
�����p���[�X�^���_�[�h�����̍��A���̉����Ȃ甃�������ł��B
�Ƃ̏ꍇ�A�ȑO�ɂ��������݂��܂������A�\�t�g�Ɋ���ĕ@�ɓ˂��悤�ȁA���₩�߂��ȏꍇ���`���z���B
���ꂶ��Ȃ������D��ɂ��܂����ˁB��
���̐[���������������ɂ������B
����������̏ꍇ ����Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B(��)
���čޗ��Ɋ|�������F�ɂȂ邩�ǂ����S�����m���B
�������V�ѐS�Ƃ����̂��ȁ`�B
�܂�������{�ƂȂ�܂��ˁB
�M���k�`���[�u�A�O���ԃW���P���̑��́A����ɂ���܂��Ĕ��ς��̑��͂ǂ������̊����i�Ƃ܂������ς��܂���B
�����ԍ��F12075648
![]() 0�_
0�_
���[���E���t����A
�M���k�`���[�u�A�O���ԃW���P���������ł����B�@�����͔��ς����łȂ���͂艹�ɂ��e������悤�ł��ˁB�@���U���ʂ̉e����������܂���B
�����ԍ��F12076189
![]() 0�_
0�_
Minerva2000����A�����́B
�����A�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������ƈꏏ�ɂ��݂��g���t�H�j�[�z�[���̐����t���ė��܂����B�Ȗڂ̓}�[���[�̌����ȑ�Z��[�ߌ��I]�ł��B130�l�̑�Ґ��őO��15�Ԗڂ��炢�̓����Ȃł��B���y�͂̉����o���r�[�A����͔@���Ȃ�SP�ł�����Ȃ��Ǝv�������͂����蓧�������Q�̉��ł��B����ł������ʂɂȂ�Ǝ��̃V�X�e���ł��܂�̂Ă����̂ł͂Ȃ��ȂƎv���܂������A�������̒Nj��͂܂��܂��Ɗ����܂����B��͂�A���܂ɂ͐����t��̌�����K�v������܂��ˁB
�ƂɋA��SACD�A�}�[���[ / Sym, 6, : Zinman / Zurich Tonhalle O�����t���܂����B����̌��̉������ۂ�肫�������ł��BPC-1�̂��A�ő啪�_�炢�������ł������A�܂��ł����B�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������ɂ�15��Ŏg���ׂ�SP��8��Ŏg���Ƃ���ɖ���������A�g�D�C�^�[���e�B�V���ōǂ��ł���܂����B����ɂ�蒚�x�ǂ��Ȃ�܂����B��������܂������ł��B
�����ԍ��F12181420
![]() 0�_
0�_
�掿�ɂ�����肳��A�����́B
�܂�����̌��̉������ۂ�肫�������ł������B���̃I�P�̃}�[���[��R�Ԃ������Ă��܂����A�����ɐݒu���������|�C���g�}�C�N�^���ł͖��������Ǝv���܂��B
���̉����ߐڃ}�C�N�Ŏ��^���Ă��邩�炩������܂���ˁB���@�C�I�����͋߂��ŕ����ƁA�z�[���ŕ����悤�ȏ_�炩�����R�����A���Ȃ荂�悪�����Ƃ��낪����܂��B
�e�B�b�V���̎g�p�́A�������ǂ��A�C�f�A�ł��ˁB
����ȊO�Ŏv�����̂́A�X�s�[�J�[�P�[�u���̌����ł��ˁB�P�[�u���ł͓d���P�[�u���̎��ɉe�����傫���悤�Ɏv���܂��B
Van den Hul�̃X�s�[�J�[�P�[�u�������悪�_�炩���ƕ��������Ƃ�����܂��B���Ђ̃X�s�[�J�[�P�[�u���̓^���m�C�̍����X�s�[�J�[�̓����z���Ɏg���Ă����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12181648
![]() 0�_
0�_
2010/11/09 21:24�i1�N�ȏ�O�j
�掿�ɂ�����肳��A���݂��g���t�H�j�[�z�[���ł̐V���{�t�B���A�悢���t��ł����ˁB
�z�[���̉����͑�σN���A�łr�^�m���悩�����ł��B�������̐Ȃ�����������Ɣ��ˉ���������A���̃I�[�f�B�I���u�Ɣw��ׂɂȂ�Ǝv���܂��B���̉��Ȃ�A�ō����̃I�[�f�B�I���u�A�ō��̕����Œ����I�[�f�B�I�ł��B
���t�͎�X�����A�����悤�ȃe���|�Ő��i�͂�����܂����B�v���Ԃ�Ɋ����̗ǂ��}�[���[���܂����B�V���{�t�B�������͂������ł��ˁB
�掿�ɂ�����肳��́u�����������v���R���𖾂ł��܂����B���t��ł͂܂����������Ȃ������Ƃ̂��ƂȂ̂Ŏ��̓������͋p���B
�����̉����܂������A�a���v��801�X�s�[�J���u�傫�ȕ����p�Ƀ`���[�j���O���Ă���v���߃g�E�B�[�^�̃��x�������Ƃ��ƍ����ݒ肳��Ă��邱�Ƃ������Ƃ킩��܂����B
�܂�A�a���v��801�̐v�҂́A����Ȏ��ߋ����Œ������Ƃ�z�肵�Ă��Ȃ����߁A�g�E�B�[�^�̃��x����傫�ȕ����̋��܂œ͂��悤�ɁA�傫�߂ɒ������Ă���̂ł��B
�ӂ��i�a�k�Ȃǂ̃X�s�[�J�ɂ́A�g�E�B�[�^�ɂ̓��x���܂݂�����܂����A���̃X�s�[�J�͂��Ă��Ȃ����߁A�g�E�B�[�^�ɔ��������Ԃ�����A���傤�Ǘǂ������ɂȂ�܂�����@����ʼn����ł��B�掿�ɂ�����肳��A�����ōH�v���Č��h���̂悢���@���l���o���Ă��������B
�����ԍ��F12190960
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A����ɂ��́B
���݂��̃}�[���[�A�悩�����ł��ˁB���t���Ԃ�80���ŁA��������ȂȂ̂ŁA�O����Ǝv���܂������A�S�����̐S�z�͂���܂���ł����B�t���I�[�P�X�g���̌��̉��͍����𒈂ɎT���U�炵���悤�ȉ��A�ȑO�ɒ��������̋L���ɊԈႢ�͂���܂���ł����B���̉����ȑO�̃}�����c��SA14�ŏo�Ă����i��3�{�������ʋ@��ASA-7S1�ł͏o�Ȃ��̂ł��傤���B�����l�ɏo�Ă����̍L���肪����܂���B�܂��A����̕��V�����Ȃ��ƒ������C�����܂���B
�^���������|�C���g�}�C�N�̂����ł��傤���B�e�Ђ̘^�����@�Ȃǂ͕�����܂��A�t�����w�E�̃t�B���b�v�X�n�͗ǂ��悤�ł��B����DDD�͑S�ėǂ��ł��B����̓g�D�C�^�[�Ƀe�B�V����킹�Ȃ��Ă�OK�ł��BADD�₻�̑��̔Ղ͕K�v�������܂��B
�����t���Ă��܂��Ǝ����̃V�X�e���̉��̓K�b�J������̂ł͂Ǝv���Ă��܂������A��L�̃t�B���b�v�X�n�Ȃǂ͍��ꍛ�ꂷ�鉹�ł��B���������N��������BD�̉��ł������ł�����e�o�J�ł��傤���B����ŁA�I�[�f�B�I�̕��͈��S���Ē����܂��B�t���AMinerva2000����A�F�X�Ƃ��肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F12193419
![]() 0�_
0�_
2010/11/10 12:15�i1�N�ȏ�O�j
�掿�ɂ�����肳��A�����t���Ċy���݁A��������ƂɎ����̑��u���蒼������A����ň�Γł��ˁB
���ꂩ��s�������z�[���́A
�݂ȂƂ݂炢�A�~���[�U���A�I�y���V�e�B�A�����|�p����E�E�E
�ǂ̃z�[���������������ڔ������Ȃ̂ŁA�s���܂��傤�B
�x�O�ɑ���L���āA�厩�R�̒��̒����~���[�Y�p�[�N���y���́A�ꔑ����ŗV�ׂ܂���B
�����ԍ��F12193594
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A���͖ܘ_�ǂ��ł����A�I�[�f�B�I���悢�ł���B���A������݂��P���������R�ɏo���܂��B�C�ɓ������\�t�g������ƈ���������Ă��܂��BSACD��CD�ƃ��f�B�A��I�т܂���B�ł��A��{�ƂȂ�ō��̃\�t�g���~�����ł��B�����SACD�̍ŐV�^���A�V���O�����C���[�ɋ��߂܂������^���������Ⴄ�悤�ł��B�}���`�^����D�悷�邹�����A2CH�͌���Ȃ�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���BSACD�������ɂȂ��������SACD�̕����D���G�ł��B���ꂪ�ō��Ǝv����SACD������܂����狳���ĉ������B
�����ԍ��F12194181
![]() 0�_
0�_
2010/11/10 17:58�i1�N�ȏ�O�j
�掿�ɂ�����肳��̑��u�����߂Ē����Ă킩�������Ƃ́A
���Ȃ��}�C�N�ʼn���d�������^���̂ق����������ǂ������ł��B
�}�[���[�̂悤�ȑ�Ґ��́A���̕����ł͔��ɓ���Ǝv���܂����B�X�s�[�J�̒�͂͂��炵���̂ł����A���̕����ł́E�E�E�����̗��ւ��Ɋ��҂��Ă���܂��B
�����ŁA�x�[�g�[�x���A���[�c�@���g�����ȂȂǒ����Ґ������t�@�����X�ɂ��邱�Ƃ������߂��܂����A�r�`�b�c�Ń����|�C���g�^���ƂȂ��
�h�a�h�r�h�C"Channel_Classics"���v�������т܂��B
http://www.hmv.co.jp/search/list?genre=700&keyword=SACD&advanced=1&formattype=1&direction=&label=Bis
http://www.hmv.co.jp/search/list?genre=700&keyword=SACD&advanced=1&formattype=1&direction=&label=Channel
���̒�����Ȃ�ׂ����K�͂Ȃ̂�I�ׂA�r�^�m���ǂ��̂ŃR���T�[�g�z�[���̂悤�ȁu���������������v���������邵�A�掿�ɂ�����肳��̑��u�ɍ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12194690
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������ASACD�̂��Љ�A���肪�Ƃ��������܂��BBIS�Ȃ牽���������Ă��܂����A�F�A�n�C�u���b�g�Ղł��ˁB�����Ɣ�ׂ�Ɛ̍w������[STEREO��]���E�œ��{�t�H�m�O���������̃e���[�N��(32CDD-80108)�|�X�g�z�����̕����^�����ǂ��ł��BSACD�͒��߂悤���ȁB
�����̕����ł́E�E�E�����̗��ւ��Ɋ��҂��Ă���܂��B
���ɂ�92�ɂȂ��e������܂��B���ւ��̉��Z�܂��͔N���̗̑͂ƃX�g���X�����S�ɂȂ�܂��̂ŁA�啪��ɂȂ�܂��B���������r���O�͕ʂɂ��Č���15��͐�L�o���܂���̂ŁA����ȉ��̕����ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12195091
![]() 0�_
0�_
2010/11/10 20:34�i1�N�ȏ�O�j
�掿�ɂ�����肳��A���łɃt�B���b�v�X�n�ƌ������̂ŁA�t�B���b�v�X�̂b�c�͐D�荞�ݍς݂Ǝv���Ă��܂����B
�܂��܂����₳��邩��A�t�B���b�v�X�ȊO�̃��[�x�����������̂ł��B
�܂��a�h�r��e���[�N�Ȃǂ̃��[�x���͂r�`�b�c�ȏ�̖c��Ȑ��̂b�c���o���Ă��܂��̂ŁA�b�c�Ղ����R�l�����Ă��������B
���ɁA�y���^�g�[�����t�B���b�v�X���n�ł��B�������y���^�g�[���͂r�`�b�c���ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F12195473
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������́A�傫�ȕ����Ŏg�����Ƃ�z�肵���X�s�[�J�[�͍��悪�����グ���Ă���Ƃ������w�E�ɋ����������A�G���ustereophile�v�Ō��J����Ă���X�s�[�J�[�̎��g�������ׂĂ݂܂����B
�e�X�s�[�J�[�̓����}�̐}�S(�܂��͐}�T�j�������
Nautilus 801
1KHz����2KHz�ɔ�r���A10KHz�Ŗ�3dB�̏㏸�������܂��B
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/207/index9.html
Nautilus 805
1KHz����2KHz�ɔ�r���A10KHz�ł̏㏸�͓��ɂ͌����܂���B
http://www.stereophile.com/standloudspeakers/168/index7.html
B&W�̂��̃V���[�Y�ł́A�傫�ȃX�s�[�J�[�͍���̏㏸�������܂��B
KEF Reference 207/2
1KHz����2KHz�ɔ�r���A10KHz�Ŗ�1.5dB�̏㏸�������܂��B
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/208kef/index4.html
KEF Reference 201/2
1KHz����2KHz�ɔ�r���A10KHz�Ŗ�2.5dB�̏㏸�������܂��B
http://www.stereophile.com/standloudspeakers/708kef/index4.html
KEF�̂��̃V���[�Y�ł́A�傫�ȃX�s�[�J�[�̕�������̏㏸�����Ȃ��悤�ł��B
�Q�l�܂łɑ��̃X�s�[�J�[�ł́A���L�̂悤�ł����B
KEF iQ9
1KHz����2KHz�ɔ�r���A10KHz�ł̏㏸�͓��ɂ͌����܂���B�������A�����ɂ͖���iQ90�ł͍��悪�㏸���Ă���悤�Ɋ����܂��B
http://www.stereophile.com/budgetcomponents/206kef/index3.html
Pioneer S-1EX
1KHz����2KHz�ɔ�r���A11KHz�Ŗ�5dB�̏㏸�������܂��B
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/307piosex/index4.html
Helicon 400 Mk.2
1KHz����2KHz�ɔ�r���A10KHz�Ŗ�4dB�̏㏸�������܂��B
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/308dali/index4.html
���^�̃X�s�[�J�[���ɗ�O������܂����A�����ނˑ傫�ȕ����Ŏg���邱�Ƃ�z�肵�Ă���X�s�[�J�[�͍��悪�㏸���Ă���悤�ł��B
�掿�ɂ�����肳���g����Nautilus 801�́A��r�I�߂��ŕ������Ȃ�A����������}���߂ɂ���H�v�͕K�v�̂悤�ł��B
�����ԍ��F12196436
![]() 0�_
0�_
2010/11/11 07:46�i1�N�ȏ�O�j
Minerva����A�����̃A�_���g�l�|�P�ɂ́A�c�C�[�^�̃��x���X�C�b�`�����Ă��܂��B���E���E��Ƃ���A�킽���̏ꍇ�A����̋�Ԍ��������҂ł��Ȃ��߂��������j�A�t�B�[���h�Œ����Ă���̂ŁA�u��v�܂��́u���v�ɂ��Ă��܂��B
�u���v�ɂ��Ē����Ɩ��炩�ɉ₢�����ɂȂ�܂��B
�i�a�k�����̂悤�ȃ��x���X�C�b�`������܂��B
�����ԍ��F12197664
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A
JBL��EVEREST DD66000�ƃX�^�W�I���j�^�[�V���[�Y�ɂ́A���撲���p�̃A�b�e�l�[�^�[���t���Ă��܂��ˁB
DD66000�́A±0.5dB���������ł��Ȃ��悤�ł��̂ŁA���܂�����ڂ͂Ȃ���������܂���B
�X�^�W�I���j�^�[�V���[�Y�͕č��̃z�[���y�[�W�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A���{��p���f���̂悤�ł��ˁB
�́A�_�C���g�[���̃X�s�[�J�[����荂������ڎw�����߁A���撲���p�̃A�b�e�l�[�^�[���������ƂɏՌ�����JBL�͂��̌�A�z�[�����[�X�̃X�s�[�J�[���獂�撲���p�̃A�b�e�l�[�^�[���͂������ƁA���������Ƃ�����܂��B
JBL�̃X�s�[�J�[�Z�p�҂́A�́A�ǂ̃X�s�[�J�[���[�J�[���������ƕ�����u�_���g�c�Ń_�C���g�[���ł��B���̃��[�J�[�̃X�s�[�J�[�͍w�����ĕ������邽�тɁA����������ɂȂ�܂��B�v�ƃC���^�r���[�œ����Ă��܂����B
�����ԍ��F12197786
![]() 0�_
0�_
2010/11/11 09:31�i1�N�ȏ�O�j
�Ȃ�قǁA�r�o�t���̃A�b�e�l�[�^�͕֗��ł��邵�A�������ቺ����E�E�E�Ƃ����킯�ł����B
�掿�ɂ�����肳��ւ̃A�h�o�C�X�Ƃ��ẮA
�c�C�[�^�ɑ܂��Ԃ���̂��f�U�C���I�E�����I�ɒ�R����Ȃ�A�c�C�[�^�̑ш�ł���R�D�R���g���ȏ��ቺ���������ȃg�[���R���g���[�����K�v�ƂȂ�܂��B
�Ƃ������Ƃ͕��ʂ�BASS,TREBLE�̂Q�ш�łȂ��A�}�����cPM8004�ō̗p�̃g���C�E�R���g���[���̂悤�Ȃ��̂ō��撲�����K�v�ɂȂ�Ǝv���܂����B�E�E���̂R�̑ш�̃R���g���[�����ł���v���A���v���K�v�A���邢�̓O���t�B�b�N�C�R���C�U�[
�O���t�B�b�N�C�R���C�U�[���A�v���p�Ȃ�Q�O���~�ȓ��Ŏ�ɂ͂���̂ł����A�s���A�I�[�f�B�I�p�ƂȂ�ƂP�O�O���~�߂��ɂȂ�܂��ˁB
�����ԍ��F12197901
![]() 0�_
0�_
�~�l���o���� �F���� ����ɂ��́`
�掿�ɂ�����肳��
�v�������ăX�s�[�J�[�����͂ǂ��ł���`�B
�X�s�[�J�[�P�[�u����������E�E�͂����Ăł����I�H
�܂��I�[�f�B�I�E�e�N�j�J�Ɠ�{�g���Ȃ�I�[�f�B�I�e�N�j�J�̎x�z�͂������Ǝv���B
(�A���v�̃X�s�[�J�[�[�q�o���������ꏏ�ł����狰�炭��������)�B
�X�[�v���̃X���[�h��{�ɂ��Ă݂ẮH���ƃI�[�f�B�I�N�G�X�g�̒����N���X�B
�Q�̃��[�J�[�́A�i�`�������E�t���b�g�o�����X�ʼn���Đ��ӂɂ��Ă܂��B
�܂��́A�i�m�e�b�N�E�V�X�e���Y:�S�[���f���X�g���[�_#79NANO3���~�e�b�h�B
�i�ʂƃo�����X���▭�ł��B
�����ԍ��F12198689
![]() 0�_
0�_
�t���AMinerva2000����A���[���E���t����A�����́B
�F�X�ƃA�h�o�C�X�����肪�Ƃ��������܂��B����̂����ƌ����Ă��ꕔ�̃\�t�g�����ł��B����������o�C�I�����̉����d�����Ȃ�����e�͈͂ł��B�ꕔ�̃\�t�g�ׂ̈ɍ��Č�����Ă��錷�y��Q�̉��̕��V�������Ȃ��鎖�̕������낵���ł��BAV�̉������x�ǂ��ł����A�ꕔ�̒��ډ������^�������f�B�A�݂̂Ƀg�D�C�^�[�ɃX�|���W��킹����@���x�^�[�Ǝv���Ă��܂��B
���[���E���t����AB&W�m�[�`���X�̓��[�����X�f�B�L�[�����Ō�Ɏ�|�����z�����鍂���\SP�ł��B�d�ʂ����100kg�ȏ������܂�����A��������Ƃ͑ւ����܂���B
SP�P�[�u�����A���v����l�œ������̗͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂Œ��߂ł��B(�C�ɓ���Ȃ����������o�Ă���Εʂł���)����ƋC�ɓ����������o���̂ł�����B
�����ԍ��F12199565
![]() 0�_
0�_
2010/11/11 19:00�i1�N�ȏ�O�j
�掿�ɂ�����肳��A
�u�ꕔ�̒��ډ������^�������f�B�A�݂̂Ƀg�D�C�^�[�ɃX�|���W��킹����@���x�^�[�Ǝv���Ă��܂��B�v
�|�|�������ɂ���̓^�_�łł�����@�����A���̕��@�Ƃ̉��i�������肷����̂ŁA���ꂪ�x�X�g�ȕ��@�ł��ˁB���̂����܂��̐�ɃX�|���W�����l�q��z�����Ă��y�����ł��ˁB�ł�����ʐ^�������Ă��������B
�����������̋������ł��ėǂ�������ꌏ����
�����ԍ��F12199768
![]() 0�_
0�_
�~�l���o����
���Ă邩�ȁ`�B
�ȑO�X�s�[�J�[�P�[�u���̃X�s�[�J�[��20�p��(�A�R���o���t�@�����X�j�������ĉ����_�C�i�~�b�N�ɁB
�������N�ɂł������z���R���Z���g�{�b�N�X����8�X�P�A��20�p��ւ��s�������ȂƁB
���@�푤���狗��������܂��B
�v���[���[�ƃv�����̃f�W�^���O�i�R���Z���g�B
8��5.5�X�P�A�ɁB(�A�R���o���j
�ω��̓x�������ǂ��ς�邩�H�y���݂ł��B
�����������A�R���o��RAS-14�Ɠd��K�̃R���Z���g�v���O(�I�X���X�j�𒍕����܂��B
�ܘ_����p�B
�ȂA�R���o�̉��H�ŏ��X���f�ł����c(��)
�܂����r���[�Ȃ����Ă��炢�܂��B
�����ԍ��F12325497
![]() 0�_
0�_
���[���E���t����A
�����́B�@�A�R���o��SPC-REFERENCE���Q���w�����ăo�C���C�������O�̂��߁A�S�������܂����̂ŁA���m�ɂ�50�����̌p�������ł��ˁB
�����_�ň�Ԃ͂����肵�����̕ω��́u���̐�ƃ_���s���O���i�i�Ɍ��サ�A���ۂ̉��������m�ɂȂ�A���͂ȉ��̐c���o�Ă����v���Ƃł��ˁB
�Ǔ��z���P�[�u���̌p�������ł����B���̌��ʂɂ͋���������܂��ˁB
�Ǔ��P�[�u���Ȃ�A�I���C�f��2.6�܂���2.0������PCOCC�̒P�����������낻���ł��ˁB
�A�R���o�̉��͌��\�D���ŁARCA�P�[�u���i�P���j��R���Z���g�x�[�X���A�R���o���ł��B
�܂����r���[�����肢���܂��B
�����ԍ��F12325779
![]() 0�_
0�_
�����́`�B
�ǐL
���Ȃ݂ɉ����z��8�X�P�A�͓���&�Z�F��11�b�ŁA�V�[���h������CV�P�[�u���ł��B
��50���̂P�ɂȂ�̂��ȁ`�B
�P�[�u���̔����ہ��@��̓�����ɒ��ځB(��)
���T�ɂł��A�R���o���i�͂���14�̃��r���[�����X����~�l���o����ɂ����܂��B
�����ԍ��F12326300
![]() 0�_
0�_
�~�l���o����
�A�R���o�FAC�X�^�r���U�[(RAS-14�j���w���B
��鐔���ԁA�N���[���d��(�f�W�^���O�i�j�ɂăe�X�g���܂��B
���̃P�[�u���̌��ʂ͎v�����ȏ�B
������������B�A�R���o�v���O����P�[�u�����ꏏ�ɃZ�b�e�B���O�B
��͂�IE�R�l�N�^�[�ʼn����ς��ƌ����Ȃ��ȁ`�B
�@��̓�����A�X�s�[�J�[�̓�����́A���ɓd���d���ɍ�p�����Ǝv���܂��B
�N���[���d���̃P�[�u����AET�ł���AET�̉�����Ȃ��ł��B
�ȑO�݂��o���Ŏ肽�A�R���o�̓d���P�[�u���̉��B
����͕�����Ȃ������Ǝ����B
���ƒ��x��ϓI�ȗv�f�͔ے肵�܂��A�A�@��̃v���O���ʼn����ς��͊ԈႢ�Ȃ������ł��B
�ȑO�ɘb�����A�����z��(�R���Z���g�{�b�N�X�����z���j���A�A�R���o���̓I���C�f�̒P���ɕς�����ǂ��ω����������邩�B
�y���݂ł��B(^_^)v
�����ԍ��F12342994
![]() 0�_
0�_
���[���E���t����A
���r���[���ǂ������肪�Ƃ��������܂��B
�A�R���o��AC�X�^�r���U�[(RAS-14�j�́A�D���G�̂��l�q�łȂɂ��ł��B
�����d���P�[�u���ł́A�v���O��IEC�R�l�N�^�͉����ɑ傫�ȉe��������Ǝv���Ă��܂��B
�ړ_�������ɏd�v�Ȃ悤�ł��ˁB�ړ_�n�ł́A�u���[�J�[�̌��������ʂ�����܂����B
�Ǔ��z���P�[�u���̌p���������������Ƃ̂��ƁA��낵����A�܂����r���[�����肢���܂��B
�����ԍ��F12343275
![]() 0�_
0�_
���߂܂��āA���S�҂ł������Ԃɂ���ĉ������B
����PMA-2000�VR�ADBP-4010UD�AS2000�ATU-1500�A47Z2000
�̃V�X�e���ŁA��ɉ��y���y����ł��܂��Bblu-ray �͂Ȃ��Ȃ��ǂ������Ǝv���̂ł����A
�b�c�̉������܂����̊����ł��B
���Ȃ�ɒ����������ʁE�v���[���[�̉��ɃK���X��~���A��I�̗��ʂɁ��Q�S�O�����X����\��B
�E�b�c���g���C�ɏ悹�Ă��̏�Ƀ��[�x���ʂ����킹�āA�ʂ̂b�c���d�˂P�O�b��ɏ�̂b�c�����o���čĐ����Ă��܂��B
�܂��A���d������I�[�f�B�I�d����ʂɉ��L�d�l�łЂ��\��ł��B
�u���[�J�[�FSCBR-20AS�A�P�[�u���FVVR3.5mm3�c�i����t�j�A�ǃ^�b�v�FWN1318
�Ȃɂ���肪�Ȃ������������������Ƒ��m�܂��B��낵�����肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F12364599
![]() 0�_
0�_
�I�X���K����A�����́B
���v���[���[�̉��ɃK���X��~���A
����̓v���[���[�ɑ��Đ��U��p�������āA�ǂ����ʂ�����ꂻ���ł��ˁB
����I�̗��ʂɁ��Q�S�O�����X����\��B
����͓d���g��ɂȂ�܂��ˁB�����X���ł͖����ł����A�I���C�f�̓d���g�z���̂�����̓d���^�b�v���ɓ\�荞��ł���܂��B
���b�c���g���C�ɏ悹�Ă��̏�Ƀ��[�x���ʂ����킹�āA�ʂ̂b�c���d�˂P�O�b��ɏ�̂b�c�����o���čĐ����Ă��܂��B
����́A�Ód�C��ɂȂ肻���ł��ˁBCD�ŗǂ��������߁A���낢��ƓƎ��̍H�v������Ă���̂́A���炵���ł��B
���u���[�J�[�FSCBR-20AS�A�P�[�u���FVVR3.5mm3�c�i����t�j�A�ǃ^�b�v�FWN1318
�I�[�f�B�I�]�_�Ƃ̕��c���̐��E�ł́A�u���[�J�[�F�e���p�[���H�Ɛ���100V��p�^�C�v�A�P�[�u���F�Z�F�d�H�������̃G�R�P�[�u���@VVF2.0mm�A�ǃR���Z���g�F�I���C�fR1�x�����E��
�ƂȂ�܂��B�\�Z������A�P�[�u���̓I���C�f��PCOCC-A�̒P��2mm�̃P�[�u�����ǂ������ł��B
�����ԍ��F12368453
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A����ɂ��́B
�ԐM�����Q�O�O���ɋ߂Â��܂����̂ŐV���ȃX���𗧂Ă܂����B
�u�܂��܂�CD��SACD��ǂ����ŕ������߂Ɂv
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2049/?ViewLimit=0#12369783
��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F12369799
![]() 0�_
0�_
�ԐM����200������ƁA���̃X���b�h�ɂ͕ԐM�ł��Ȃ��Ȃ�܂�
CD�v���[���[ > SONY > SCD-XA5400ES
�{���̃t�@�C���E�F�u�ɁA�I���L���[��2.8MHZ��DSD�M���ɂ�鉹�y�z�M���͂��߂�Ƃ̋L�����f�ڂ���Ă��܂����B
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101210_413353.html
�p�\�R���ł̍Đ��p�̃\�t�g�Ƃ���AUDIOGATE�ADSD�f�B�X�N���Đ�����@��Ƃ���SONY��PS3��SACD�v���C���[�𐄏����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B���悢��DSD�Đ������y���n�߂��悤�Ŋy���݂ł��B
![]() 2�_
2�_
�ǂ��ǂ�^^
�Ȃ�قǁA���Ԃ͂�������ȂƂ���܂Ői��ł��܂������c�B
�܂��T�C�g�͗ǂ����ĂȂ���ł����c�A
���܂��DSD���×����邠�܂�A
�w�A�i���O����������AudioGate�ɓ˂�����ł݂��x�Ƃ��A
�wDSD������ʂɏڍׂȃZ�b�e�B���O�A�����Ȃ�ĕs�v���낤�x
�Ƃ����G�ȉ������L�܂��Ă��܂��̂��뜜���Ă��܂��B���̓_�͎��z����J�ɏI��邱�Ƃ�����Ă��܂���^^;
�ƁADSD�Ƃ�����SACD�ƈ���čĐ��Y��AAudioGate�ł̕ϊ���������ł���ˁc�B
SACD�����܂蕁�y���Ă��Ȃ��������R���A
�wiPod��PC�ɓ���ċC�y�ɕ����Ȃ��x�Ƃ�
�w�����̃t�F�C�o���b�g�A���o������肽���x
�Ȃǂ������炠�܂�ɂ��߂������܂�>_<;�@(������ƈႢ�܂�����?w)
�Ƃɂ����A"���쌠�ی�"��"�������̕��y"�ɂ͌���ǂ�����悤�ł����A
�A�[�e�B�X�g�A���[�x���̕��ɂ͂������O�b�ƒ������Ă�����āc�A
�����̊Ԃ͎s��̓�����������ė~�����Ǝv���܂��B
�͂��c�A�T�C�g������ƃN���V�b�N(�A�R�[�X�e�B�b�N�y��)�ȂǁAOTOTOY�������D�݂̃W�����������������Ă��܂���^^;
�t�g�R�����ɉ߂��܂����[>_<
�����b�X�~�}�Z���ł���^^;
�����ԍ��F12360954
![]() 1�_
1�_
CD�v���[���[ > SONY > SCD-XA5400ES
�T�C�f���}�X�^�����O�̃u���Ohttp://saideramastering.blogspot.com/�ɂ��܂���KORG��AUDIOGATE�̃t���[�ł\���c�B�b�^�[�̃A�J�E���g������ΒN�ł��g���邻���ł��B����łقƂ�ǂ�PC��CD����PCM�������A�b�v�T���v�����O����DSD�f�B�X�N�삷�邱�Ƃ����[�R�X�g�ɂł���悤�ɂȂ�܂��ˁB���̂悤�Ɋ��������Ă����̂�DSD�f�B�X�N���Đ��\��SCD-XA5400ES��SCD-XE800�̗ǂ�����w�����Ă���悤�ɂȂ����̂ł͂ł͂Ȃ��ł��傤���H
![]() 1�_
1�_
������ww ���̊Ԃɂ��X�S�C���Ƃ�^^
�^�P�`�N��������A����ɂ��́B
��肪�Ƃ��������܂��B
�Ƃ��Ƃ��t���[�łł����c^o^;
�c�C�b�^�[�A�J�E���g���K�v�Ȃ��Ƃ�A
�����c�C�[�g�Ƃ����������Ȃɂ��C�ɂȂ�܂����c�B
�L�܂��Ă������Ƃ��l�����KORG�̑�p�f�ł��ˁBS�Ђ����K���Ă��������c�B
(�A�J�E���g���̂��ʓ|�ł����c)
�������������̂ŃC���C���ƒ��ׂĎ�����Ă������Ǝv���܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B�ł͂ł�^^
�����ԍ��F12268275
![]() 1�_
1�_
�D��H�̃q���R����ɂ���
���������b�ɂȂ��Ă���܂��B
�{���̃t�@�C���E�F�u�̎R�V�������{���g���[
http://www.phileweb.com/magazine/labo/
�ł��ADSD�̉��y�z�M��AUDIOGATE�̏����t���t���[���ɂ��āA���W��g��ł��܂����B������@��ɐ���DSD�f�B�X�N�Ƃ��̍Đ��@�����y���ė~�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F12279766
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́B
�c�C�b�^�[�A�J�E���g�����܂��āAAudioGate�̃t���[�g�p�n�߂܂����B
������������ɉ������ǂ������ň��S���Ďg����\�t�g�ł��B
���Љ�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂���^^
����܂Ńf�B�X�N�ɂ��邱�Ƃ���l���Ă܂������A
DSD��PC�ōĐ��ł���Ƃ����̂́A�ӊO�Ƒ傫���ł��ˁB
�Ή��t�@�C���`�����啝�ɑ����܂������A
���ꂩ���DL�w������`���ɐ����������Ȃ�A�o������݂���^^;
WEB��ł����W���g�܂��悤�ɂȂ�܂������A���ꂩ��̐���オ������҂ł��܂��ˁB
(�����ȃt�@�C���`���̓��o�͂��o����̂ŁA
����PC�I�[�f�B�I����Ă�����ɂ��傫�ȉ��b�����ł���)
�܂��Ȃɂ�����܂������点�Ă��炢�܂�^^
�ł͂ł́B
�����ԍ��F12296486
![]() 2�_
2�_
�D��H�̃q���R����ɂ���
�D��H�̃q���R�����SONY�@DSD DIRECT�@�ƁAKORG AUDIOGATE�Ƃ����Q��ނ�DSD�ϊ��ҏW�\�t�g�̔�r�̂��b��ϕ��ɂȂ�܂��BAUDIOGATE�̕������삪�y���Ƃ����̂̓t�@�C���E�G�F�u�������̋L���œǂ��Ƃ�����܂������A�D��H�̃q���R����̃��|�[�g�ł͗\�z���Ă����ȏ�ɍ�������悤�ŋ����܂����B���̌X���������ςƖ��Ƃ������Ƃł��Ȃ�Ⴂ������̂ł��ˁB��������҂̔�r�Ȃnj䋳�������肽�����肢�������܂��B
�����ԍ��F12302131
![]() 2�_
2�_
�D��H�̃q���R����ɂ���
�D��H�̃q���R����̃u���O��DSD����L�@����҂Ǝ�����r�҂�q���������܂����BDSD�@DIRECT����AUDIOGATE�̕������ʃ��x���������Ƃ̂��Ɠ���ϕ��ɂȂ�܂����B�ǂ�������Ƃ��F�X�Ƃ������������X�������肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F12348357
![]() 1�_
1�_
�^�P�`�N��������A����ɂ��́B
���т��яЉ�Ă��������܂��ċ��k�ł�^^
�Z�p�I�Ȗʂɂ͂��ԈႢ����������A�e���[�x���ňႢ���������肷�邩������܂��A
�K�i�̑�Ƃ��Ă͑傫�ȊԈႢ�͖����ƍl���Ă��܂��B
(+�˂����܂ꂻ���ȕ������A�����̕��ɋ����������Ă��炤���߂̃G�T�ɂȂ邩��w)
������AudioGate�ł̕ϊ����ADSD Direct�ƈႢ�A������PS3�ł���قڒN�ɂł������邱�Ƃ��o���鉹������ɂȂ����Ǝv���܂����B
DSD�ϊ��ł��ꂾ���̉����ł�����ASACD��DSD���^���̍ĕ]���ւƂ��q�����ė~�����ł�^^
�����ԍ��F12360837
![]() 1�_
1�_
CD�v���[���[ > Nuforce > CDP-8/SI [�V���o�[]
Nuforce��CDP-8��o�^���ĖႢ�܂����B
���r���[�A�N�`�R�~�����肢���܂��B�܂��A�V���b�v�̂��S���җl�ɂ͉��i�o�^�����肢���܂��B
�R���p�N�g�ȃv���C���[�ł����������ł���ˁB
�u���b�N�͂�����ɂȂ�܂��B
http://kakaku.com/item/K0000126744/
![]() 2�_
2�_
�\��Y����A����ɂ��́B
�V�A�C�e���̂��o�^�葱���A�����l�ł����B
�ŋ߂�Nuforce�͉�Ђ��̂��̂ɐ���������܂��ˁB
�R���p�N�gDAC&��PC��iPod���[�U�𖣗��������Ǝv���A
���Ђ̐��i���̂ɂ������j�o�[�T���E�v���C���[�܂Ŕ������܂����B
�uOPPO BDP-83SE Nuforce Edition�v
http://www.nuforce.jp/highend/products/oppo_01.html
����������2���Ɏ��������ۂɈ�x���r���[�����X���𗧂Ă����Ƃ�����܂��B
�����̃I�t�B�V�����E�T�C�g�̃����N��Ȃǂ��ς��Ă��܂��܂����̂ŁA
���X���������Ă݂����̂��R�s�y�����Ē����܂��B
CD Player CDP-8
http://www.nuforce.jp/highend/products/cdp8_01.html
�X���̃f���@�̑g�����͓����A���㗝�X�q����ł����B
PIEGA��TP3�{�����X�^���h��Nuforce�̃v�����C��IA-7V3�̑g�����ł��B
���Ɍl�I�����ŃA���v��KRELL��S-300i�ɐ�ւ���m�炢�������Ă��܂��B
�P�[�u���̓V���b�v�����̃i�m�e�b�N�œ��ꂳ��Ă��܂����B
�����\�[�X�Ɏ��Q�����͓̂����ɂ͂��Ƃ�������S�^�C�g���ł��B
�P�jMiles Davis�uFore��More�v
�Q�jCassandra Wilson�uTraveling Miles�v
�R�jRoxy Music�uAvalon�v
�S�jSteely Dan�uGaucho�v
�����̑��ɂ��X�̎����p�N���V�b�N�𐔓_���肢���܂����B
Nuforce�̃A���v�Ƃ̑g�����ŋC�ɂȂ����̂���דI�Ȓ�����̖���ł��B
�s�`�J�[�g��M�^�[�̃n�[���j�b�N�X���ƂĂ��ۗ����Ē������Ă��܂����A
�X�v���b�V����N���b�V���Ȃ��y��n�̃V���o������������悤�Ɋ����܂��B
�d���Ƃ������L���L�����Ɨ]�C�����������l�Ŕ{�������ߑ��ŃG�t�F�N�e�B���Ȉ�ۂ��܂����B
TP3�͎���ł��g���Ă��Ď����Ȃ�ɃL�����N�^�[�E�C���[�W�͒͂�ł���̂ŁA
�ŏ��̓A���v�̃L�����N�^�[���Ǝv���܂������V���b�v�̕��̐����ł́A
�ǂ���CD�v���C���[�̃L�����N�^�[�炵����������������悭���₳���Ƃ̂��ƁB
���̕ӂ�̓A���v��KRELL�ɐ�ւ��Ă�����Ă�����m�F�ł��܂����B
�R���g���o�X�͒��̗͊������}���߂ł����s�b�`�����ĂŁA
�������̉𑜓x�͂Ȃ��Ȃ��D�G���Ǝv���܂��B
���ݍ��ޏd�������L�����ƃ^�C�g�ɖ��ăh���C�u���Œ�������^�C�v�ł��B
�t�B���K�����O�Ȃǃv���C���[�̃j���A���X�͂�������`���Ă���܂��B
�܂�Miles���I�[�v������~���[�g�ɐ�ւ��G�̊Ԃɕ�������Ő��������ƁA
�X�^���h�}�C�N�Ɍ������Đ��������A�}�C�N�܂ł̍����⋗���̈Ⴂ���A
�͂�����炵������u�Ԃ����x�������Ă���ɂ͂ƂĂ���������܂����B
�V���Z�̉��̗n�����݂�L����͏o�F�Ŋ�d�ɂ��d�˂����F�̈Ⴂ��
�G�t�F�N�g�����Ȃǃf���P�[�g�ɖ炵�����Ă���čD��ۂł����B
�A�R�[�X�e�B�b�N�y��ł͋����������������������������y��ł͏�肭��p���Ă��銴���ł��B
���H�[�J���̓N�[���ł����Ԃ�˂��������̂��Ղ�Ɋ����邱�Ƃ�����܂����A
�j���A���X�͂ƂĂ��ׂ����f���o����Ă���l�ł��B
���̂����u���X��b�v�m�C�Y���ςɋ�������Ē����Â炢�Ƃ������Ƃ�����܂���B
�Z���V�e�B���ȃ^�C�v��TP3�ł͓Ɠ��̋��������C�ɂȂ�܂������A
FOSTEX��GX100�Ȃǃf�B�e�[�����ڍׂɕ`�����肾�Ə��X�����������ł��B
�_�C�i�~�b�N�ɒ�������X�s�[�J�[�A�ĊO�A�����������ȋC�����܂����B
�͉����̐��i�ɍׂ����j���A���X�⋗�������̊���t�����������͂����Ă������B
JBL�Ȃǂ̃A�����J���E�X�s�[�J�[�A�ӊO�ɑg�����₷���Ǝv���܂��B
����ɋr�F�������镔�������Ȃ�����܂��A
�f���P�[�g�ȕ\���͂Ɨ��̓I�ȋ�Ԃ⋗������`�����Ƃɒ��������i�ł��B
���i�I�ɂ������̖ʂł�N-mode�Ƌ������镔���ł����A
�l�I�Ƀ����n����������Nuforce�̕��ɌR�z���グ�����ł��ˁB
�ꌩ�A�X���b�g�E�C���̃J�[�E�R���|�H���ă��b�N�X�A
�D�݂������ꂻ���ł��������͈ӊO�ɍ�����������܂��B
���������R���͈����ۂ��ē���Ɣ������ɖ��Ȃ̂��C�ɂȂ�܂����B
�܂���➑̂̓d�����̓m�[�gPC�p�̑�U���AC�A�_�v�^�[�R�Ƃ��Ă��܂��B
����������➑̂ɂ����̂ł�����������������Ăق��������ł��B
�I�v�V������T�[�h�p�[�e�B�ŋ����d�����ł�Γ����������������Ⴄ�Ǝv���܂��B
�R�X�g�̖ʂł�����o������Ă��镔�������X����܂����A
���̃N�I���e�B�ł��̒艿�ݒ�͊��}���^��������p�f�Ǝv���܂��B
�l�I�v�]�Ƃ��Ă͂������̏�̃N���X�Ő��i���o�Ă���Ȃ�A
�f�W�^���ƃA�i���O�̗����Ńo�����X�E�A�E�g���ė~�����ł�(^_^)
�����ԍ��F11643803
![]() 3�_
3�_
redfodera����@������B
�l�I�ɍD���ȃ��[�J�[��o�^�˗������Ă܂������A���i�o�^����Ȃ����Ƃ������A�ŋ߂͓o�^����Ă��郁�[�J�[�ŐV���i�┄��؏��i�������Ă���̂������Ĉ˗����|���Ă܂���
Nuforce�Ȃ炷���o�^�����Ǝv���܂������v�f���O��܂���(��)
�X�s�[�J�[�͂����o�^������܂����A�A���v��CDP�͊C�O���[�J�[�̏ꍇ���I�ȃI�[�f�B�I�V���b�v�����Ȃ����ߓ���ł��B�܂����i���������[�J�[�Ɣ�ׂ�ƍ��z�Ȃ̂ƃ}�C�i�[�Ȃ��ߎ�舵���������Ă��o�^�Ƀ����b�g���Ȃ��̂�������܂���B
�����A�����ꂱ�̃T�C�g�������Ɛ���オ��V���b�v���o�^���������ꍇ���l���ĐF�X�ȃ��[�J�[��o�^�������Ǝv���Ă��܂��B
�Ƃ���ŊC�O���[�J�[�ł��u���[���C�Ή��̃��j�o�[�T���v���C���[���o�Ă��܂����ˁB
�l�I�ɂ�Cambridge Audio��Azur650BD���C�ɂȂ�܂��B
http://naspecaudio.com/cambridge-audio/%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%ab-blu-ray-sacd-disk%e3%80%80%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a4%e3%83%bc/
�m���E�W�����[�Y�₳���܂�����DVD�̃��C�u�Ղ��������Ŋy���݂����̂Ń��j�o�[�T���v���C���[�͌������܂���B�����A�u���[���C��SACD�܂Ŋ|�����Ă��̉��i�ł����特���I�ɂ͂ǂ��Ȃ̂��ȂƎv���܂��B�ꎞ���A���j�o�[�T���v���C���[���e�ГP�ނ��ău���[���C�Ή��^�ŐV���i���o�Ă��Ă���̂��y���݂ł��ˁB
�����ԍ��F11656502
![]() 3�_
3�_
�\��Y ���� ������
�@���̋@���č��ōw�����܂����B�@���i�͔閧�ł��B
�@�`�b�A�_�v�^�[���m�[�g�p�\�R���̓d���^�C�v�ł��̂ŁA���{
�����ł����Ȃ��g���܂��B
�@�f���炵���f�U�C���Ƒ�����@�ŋC�ɂ���܂����A���́A�i���[
�i�ш悪�����j�ȋC�����܂��B
�@���ƁA���ʂ̃\���b�h�ȃA���~���o���p�l���ɑ��āA�O��
�̎������قȂ�A���X��a��������܂��B
�@���ꂩ��A���s�����ӊO�ƒ����āA�`�b�A�_�v�^�[�̒u���ꏊ
�ɋꗶ���܂����B
�����ԍ��F12054342
![]() 2�_
2�_
�F����R���j�`�n�B
�V���o�[���܂����B�u���r���[�v���{�ςł��B
�����ԍ��F12346184
![]() 1�_
1�_
CD�v���[���[ > ���}�n > CD-S300
��P�N�O�ɍw�����܂����B
��������b�c�̓ǂݍ��݂ɕs��������܂����B���}�n����_���̃A�h�o�C�X���������̂ł����A�ۏ؊��Ԃ��������̂ł��ɏC�����Ă��炢�܂����B
��ɂt�r�a���͂�iPod���Ȃ��ł��܂����B
���̋@�\�͑�ςɕ֗��Ő��\���ǂ����ߏC���������Ă܂����B
���}�n�̂`�u�A���v�ɂb�c�r�|�R�O�O�̃A�i���O�o�͂ƃf�W�^���o�͂��Ȃ��ł����A�A���v�Ő�ւ��Ĕ�r�����Ƃ��뉹�ʁE�����������ł��܂���ł����B�悭�ł��Ă܂��B
���͑喞���ł��B������i�`�������T�E���h�Ȃ�ł��傤���A�������Ȃ����ꂢ�ł��B
�C�����Ԓ��^�Ђ̃v���C���[���֕i�Ŏg���Ă܂����B�Ђǂ������̏Ⴀ��ł������C����͂������ėǍD�ɂȂ������̂ł��B�b�c�|�r�R�O�O������������Ɠ��삷�邾���ŁA���̗ǔۂ͂Ȃ������ł��B
����̏C���Ō̏Ⴊ�Ĕ����Ȃ����Ƃ�����Ă܂��B
�b�c���P�������t����V������Ȃ�ŁA���p�������ł��B
���}�n������ĉ������B
![]() 3�_
3�_
����ɂ��́B
�`�����ƒ���Ɨǂ��ł��ˁB
>�b�c���P�������t����V������Ȃ�ŁA���p�������ł��B
���������ӁI
LP�̍��Ȃ�ċV���������Ƒ�ςł�����ˁB�ŋ߂�PC�����g���ĉ��y�f�[�^�����b�s���O���Ă��������́A��ϕ֗��ł����ǁA�֗��߂��ĉ�����Ȃ��̂�u���Y��Ă��܂��Ă���C�����鍡�����̍��ł��B
�����ԍ��F12332469
![]() 7�_
7�_
���������N�O�ɍw���A�R�������炢�g���āA�ǎ悪�s����ɂȂ�A�C���B
���̌̂�������Ȃ������݂����ł��ˁB�@�C��(���j�b�g�����H)��͂��[���Ə����B
�@
����USB�[�q�̎g����R���|�����Ȃ��A�܂��f�U�C�����C�ɓ����čw�����܂����B
���̏ꍇ�́ACD���ƂƂ肠����iTunes��MP3�ɕϊ��A���������Z�߂�CD-R�ɏĂ��A�{�@�Łu�����������v�ł��B
�����ԍ��F12332908
![]() 2�_
2�_
CD�v���[���[ > SONY > NAC-HD1
���܂���ł�����ǁANAC-HD1�̓V�̏�ɂ̂���̂�
�҂�����̑傫��(43cm×26cm)�̐l�H�嗝��http://item.rakuten.co.jp/alukom/amz-mes/
�������܂����B
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����z���C���A�b�v�O���[�h�ŏI�e
-
�yMy�R���N�V�����z����p�\�R��
-
�yMy�R���N�V�����zSUBPC 2025 WHITE
-
�y�~�������̃��X�g�za
-
�y�������߃��X�g�z���N�̂����ɂ���őg�ߓI�Ȏ���Q�[�~���OPC��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2025�N12���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2025�N12���z

�^�u���b�gPC
- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2025�N12���z

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
CD�v���[���[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j