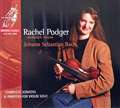このページのスレッド一覧(全439スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2011年2月23日 00:23 | |
| 93 | 199 | 2011年2月13日 23:27 | |
| 203 | 197 | 2011年2月7日 22:54 | |
| 3 | 0 | 2011年1月29日 17:19 | |
| 577 | 200 | 2011年1月29日 14:32 | |
| 130 | 47 | 2011年1月27日 23:08 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
CDプレーヤー > DENON > DCD-1500SE
今まで使用していたPHILIPS LHH600B DECADE EDITION が故障したので購入いたしました。1650も考えましたが600の後釜では役不足と考え一気に1500までランクを落としました。中身の写真を見てあまり期待はしていなかったのですが、届いた本体を持ち上げて予想以上に重かったので思わず笑ってしまいました。CDを聞いた感想は、音楽の表面を上手に表現しているなと感じました。以前の機種と比較して情報量は圧倒的です。とにかくこんな音が入ってます的に聞かせてきます。音はスピーカーの上下左右にぐっと広がります。前に出るタイプではなく奥に広がるタイプです。中高域はかなりいい線にきていると感じました。中低域はお値段なりかと思います。抑揚や陰影感などといった表現は求めるべくもなきかなと。トータルでみてこの値段のプレーヤーとしては良く出来ていると思います。
とはいえ、以前の機種と比べてかなり腰高な印象になってしまいました。家に転がっているケーブルを何本か試してみて600の極太付属ケーブルが中低域がぐっと出て腰高の印象はなくなったのですが逆に解像度が落ちてしまいました。全体のバランスは純正の付属ケーブルがいいのでこちらで使用しています。このあたりはトレードオフの関係ということでしょうか。過去にケーブル(LC-OFCだったかな)をかえてみたたことがあるのですが、スピード感はあがったがバランスが崩れてしまいよい印象がありませんでした。それ以来純正ケーブルを使用しています。しかし、腰高感が改善できてしかもバランスがあまりかわらないものが無いかなと悩んでいます。この機種に何万円のケーブルは本末転倒なので考えていませんが、ネットで検索したらMOGAMIのケーブルが手ごろでよさげなので購入を考えています。どなたか情報をお持ちではありませんか?
![]() 0点
0点
こんばんは
お使いの600の極太付属ケーブルというのは、
色はグレーで、少し硬めのケーブル(方向性有り)でしょうか?
非売品でしたがPHILIPSのCDプレーヤーに、音は合ってましたね。
当時でも、レンジは少し狭く感じていましたが、
味わいのある音は魅力で、私はPHILIPSライントランスと共に、今も使っています。
ケーブルは定期的にクリーナーで磨き、消磁しているのでクリアさは及第点です。
ラインケーブルは、他にワイヤーワールド、オルトフォン、ゾノトーン、MIT、サエク(他)と、使っていますが、
PHILIPSのケーブルが販売していれば、直ぐにでも購入したい逸品です。
ついPHILIPSの付属ケーブルという事でレスをいたしましたが、
MOGAMIのケーブルは使った事が無く、お役に立てず失礼しました。
書込番号:12552310
![]() 0点
0点
こんにちは。
私もMOGAMIのケーブルは使ったことがありません。MOGAMIはどちらかと言えばPA等のプロ用といった感じで、あまりコンシューマー・オーディオ用として使われてきてはいないように思いますので、馴染みがありません。名前もネットでしか聞かず、店頭ではあまり見かけません。
それはさておき、電源ケーブルもエージング効果と言いましょうか、使っているうちに音がこなれてきます。もしまだ使用時間が短いのなら、即断せずに数ヶ月使い込んでみては如何でしょう。
音がこなれてきてから、それでもまだ不満があった時にケーブルチェンジに挑戦すれば良いかと思います。それまではケーブル研究や、中古の出物などを探索する期間に当てられては如何でしょう。
書込番号:12555182
![]() 0点
0点
こんばんは
audio-styleさん
そうですグレーの固いやつです。プレーヤーとケーブルセットで音作りしてるなんて反則ですよね。今回ケーブルを使いまわしてみて600の重心の低さはこのケーブルに依存していたことがハッキリしました。このケーブルはロスが少なく音がドバッと出てくる感じです。本当に良いケーブルですね。1500との相性はいまいちでしたが。PHILIPSのCDプレーヤーに音は合ってますね。音楽を聞くことにおいてレンジ感の優先順位はさほど高くないということですね。今回、買い替えてあらためて600のよさを再認識しました。故障したのがまことに残念です。
586RAさん
コンシューマー用は色を売りにしているので選択からはずしています。今回はあまり色は付けたくないものですから。エージングですか。まだ二週間ほどですので最低一ヶ月程度は様子見といったところでしょうか。確かに通電開始直後より良く聞こえるようになってきているのですが、音がこなれてきているのか耳がこなれてきているのか不明です。おっしゃるように今しばらく研究期間に当てたいと思います。
書込番号:12557777
![]() 0点
0点
こんにちは。
>コンシューマー用は色を売りにしているので選択からはずしています。
これはちょっと誤解だと思うなぁ。これを見ているあまりケーブル関係に知見のない方達がコンシューマー用は色付けが必ずあると思われてもいけないので、私の見解を書いておきます。
プロ用というと凄そうに思いますが、ことオーディオに限って言えば音質でプロ用を凌ぐコンシューマー用は沢山あります。ただ
高いです。それは趣味の製品であって、コスト度外視の作りになっているからです。プロ用は品質が高いことも必要ですが、丈夫が一番だったりします。そして使い易いことなども重要かと思います。
で、プロ用は外観なんて真っ黒なだけの無骨で、取っ手まで付いたスピーカーとか、ラックマウント出来るサイズのアンプとか、ラックマウント故に廃熱はファンに頼るとか、ケーブルは太くて硬くて重いコンシューマー用とは違って柔らかくて取り回しが良いものとか・・・。要する使用目的が違いますのでテイストが違っているだけです。
高音質が売りのxrcd等のライナーノーツを見ると、時としてコンシューマー用として販売されている機器やケーブルが使われていたりします。
コンシューマー用だから○○と言う先入観のようなものは持たれずに、自分が良いと思えるものを探す努力をすることが肝要かと思います。
書込番号:12558540
![]() 1点
1点
横から失礼いたします。 私の使用している電源ケーブルは、PCOCC-Aの導線に金メッキのフルテックのプラグ(自作で15000円位)を使っています。 まだエージング中ですので何とも言えませんが。 ケーブルの交換だけで音は本当に変わりますね。 行きつけのオーディオショップがあれば 自分の目指している音に対し良きアドバイスしてくれると思います。
かくゆう私も お店に1日中入り浸り あれや これや ときいておりました。
自作ケーブルは市販品よりも安くつくのはありがたいですね。
(しかし 興味の無い 嫁にばれたら大変ですけど。)
書込番号:12664519
![]() 0点
0点
電源ケーブルの自作ですか、すごいですね。まさに趣味の世界ですね。電源ケーブルといえば、私がオーディオに熱を上げていた時代に購入した機器には極性の白い表示があったのですが1500には有りません。極性を変えると鳴りは変わると思うのですが流行らなくなったのですかね。
腰高感改善についてですが、ここしばらく音楽を聴いていてCDプレーヤーのドライブ能力の問題なのでケーブル交換では私の希望をかなえるのは難しいと判断しました。購入時は期待していなかったのですが中高域の再現能力が思っていたよりも良かったので欲が出てしまったのです。中低域のルーズさに起因していることですのであきらめます。しかしこの値段でここまで再生できるとは良い時代ですね。
書込番号:12673310
![]() 1点
1点
こんにちは
>私がオーディオに熱を上げていた時代に購入した機器には極性の白い表示があったのですが1500には有りません。
1500は使ってないのですが、
付属の電源コードのプラグ(コンセントへの差込口側)に△のマークは付いていませんか?
△マークが付いていれば、極性はマイナスになっていると思います。
極性表示についは、取説に書かれていないのもありますね。
>腰高感改善についてですが、ここしばらく音楽を聴いていてCDプレーヤーのドライブ能力の問題なのでケーブル交換では私の希望をかなえるのは難しいと判断しました。
同様に感じます、ケーブル類の交換だけで希望をかなえるのは難しいでしょうね。
スウィングアームのドライブメカが良かったんでしょう。
PHILIPSのCDプレーヤーをもう一度使ってみたいですね。
書込番号:12683274
![]() 0点
0点
audio-styleさん、こんばんは。
>△マークが付いていれば、極性はマイナスになっていると思います。
残念ながらついていませんでしたので聞いて判断しました。
>PHILIPSのCDプレーヤーをもう一度使ってみたいですね。
使いたいですね。こいつに使用しているドライブメカは当時かなりの高評価だったと記憶しています。実はLHH600はまだ捨てずにとって有ります。トレイを手動で開閉して天板をはずしCDを手動でチャッキングしてあげると再生できるのですよ。ベルト関係のトラブルだと思うので何とかなりそうな気もするのですが・・・以前マランツのかたとお話しする機会があり聞いてみたのですが保守部品がないので無理だといわれてしまいました。いまだにあきらめきれておりません。(笑)
書込番号:12694506
![]() 0点
0点
PCオーディオなどをテーマに世間話するスレの「改めてパート2」です。
「など」を入れたのは、PCオーディオと直接関係ないお話もOKという意味です。
ではみなさん、引き続きよろしくお願いします。
![]() 4点
4点
皆様、こんばんは なんだかお久しぶりです。
秦璃さん いらっしゃいませ^^
電源で結構音が変わることを知り、新しい電源ケーブルを購入
うーん、穏やか過ぎて精緻な絵を見ているようだ・・・
電源環境も悪そうだから、ノイズフィルター付けてみれば・・・悪くなった気が
そうか音響以外に付ければ、、、ん?変わったかな?; 気持ち的に良くなっただけ?^^;
トランス電源をつける場所や、配線を色々と繰り返し・・・
あっ、トランス電源アンプに良くないって言うけど、凄く変わって低音の量感増えて
とても心地よく聴きやすくなったではありませんか!
やっぱり人それぞれ環境違うんだから、自分で試して見なきゃと、しばらく聴いてると
あれ? バイオリンの音がBGMレベルに。。。太鼓の音が湿った皮叩いてるような音に・・・
あぁ、、、最初のが一番良かった・・・(ノд-。*)
と、秦璃さんの言われる、やることなすこと沼にはまる状態に陥っておりました(笑)
ただ、PCオーディオからの音としてはどちらも捨てがたく、アンプ用にパワフルだと評判の
中村製作所の2000の方の視聴機貸し出しをお願いしてみました
http://ns-t.com/products/trans/nsit2.html
とても良かったら買うことになると思いますが、DAC、アンプ、スピーカーに匹敵する価格
沼の奥にはまり込み過ぎて、何か間違っている気も、、、、(;^_^A
プレク大好き!!さん
メイン焼きでもないのに8台もあるのですね、、、置く場所無いからかな?(笑)
メイン機は、1台だけ繋ぐとかでしょうか?
> 初めてCD-Rを焼いた時、音の差を感じさえしなければ人生絶対違ったな…と思う今日この頃…(苦笑)。
・・・・お茶噴いてしまいましたよ(笑)(CDドライブにかかったので、代替機求む (><)
焼き料はちゃんと取ってくださいね ^^
天地創造さん
SOtMのカード想像以上だったのですね・・・
そして何も聞こえなくなったさんから貰って帰ろうと思います(笑)
そして何も聞こえなくなったさん
オカルト商品なのに、視聴可能とあったので数種類頼んで見ました
書込番号:12533424
![]() 1点
1点
話途中で送ってしまいました <(_ _)>
そして何も聞こえなくなったさん
オカルト商品なのに、視聴可能とあったので数種類頼んで見ましたので
日曜お伺いするときに、一緒に持って行こうと思います。
プレク大好き!!さん
>そろそろ自粛離脱しやすか…^^;
もう手遅れです ^^b
ダメだしされた、セッティングのノウハウとかお聞きしたいです(笑)
書込番号:12533478
![]() 1点
1点
ゆっこんさん、日曜日はうちのPCで
200V→100Vトランス経由
100V直接
で音の違いを確認できます。PCでも違うので、アンプ、プレーヤならなおさらです。
書込番号:12533508
![]() 1点
1点
そして何も聞こえなくなったさん
スレたてお疲れ様です。
前スレでは取り乱して失礼しました。
ゆっこんさん
コメントありがとうございます。
機材ヲタクなので深みにはまると対処できずカーネルパニックを起こすようです(苦笑
よく写真にたとえるのですが、ノイズフィルタとはノイズリダクションのようなものです。
弱いとノイズが目立ち、かけすぎるとのっぺりした平坦な活気のない絵になってしまう。
まぁ、ようはどちらが良いかは人それぞれですが、概念としてはこのようになります。
フェライトコアやシールドとはこういったものですね。
ケーブルの概念ですが、道路のようなものです。
一般家庭の屋内配線は一般道のようなもの、コンセントから機器まではケーブルによって一般道にも農道にも高速道にもなるということです。
シールドの概念は景色は見れるが雨ざらしの道路がいいのか、景色は見えないが天候に左右されないトンネル道路がいいのかという感覚です。
太さの概念は細い道路なら小さな車しか通れず、大きい道路だと大きな車が通れるという感じですね。
概念的なものもいろいろと移転した縁側のほうに書いていこうと思っています。
それ以降は各自で試してみてください。
書込番号:12533898
![]() 2点
2点
皆さんこんばんは
新しいスレでもよろしくお願いします。
>SOtMのカード想像以上だったのですね・・・
あのカードの効果がサウンドカードの音の傾向とは真逆の音の傾向になったので効果が大きく出たように感じたのかもしれません。HDDアクセス過多や高負荷時の音とび(性能が良いせいかわたしのPCだとほとんど発生しませんが……)などUSBらしい不安定なところも見受けられます。正直あまりよくなっていないのかもしれません。このカードだけではあまり良い効果が得られないように感じました。このカードも含めていろいろ対策をして始めて効果が出るのではないかと思っていますのでもう少し試行錯誤していきたいと思います。
少し前の書き込みにもあった業務用のPCIオーディオインターフェースを使ったほうがはるかに良い音がするんでしょうね……PCオーディオを極めるのならここら辺に力を入れるべきなのでしょうが値段が高いです……でもクロック入力が気になって気になって日に日に使ってみたくなってきていますww
同軸ケーブルが届くのが早くて金曜日、遅いと土日になりそうです。今回の同軸ケーブル前回ルームチューニングで使用した吸音材と同じ素材を箱に使用しているので同軸ケーブルの箱がそのまま吸音材として使えるようになっています。今からその箱を部屋のどの場所につけようかも考えています。箱まで使えるというのはとてもありがたい製品です。ケーブル本体も1度実物を見させてもらったことがあるので期待できそうなので楽しみに待っていようと思います。
書込番号:12534108
![]() 1点
1点
天地創造さん
こんばんわです。
オーディオインターフェースですが、どちらの製品をお探しでしょう?
参考にRME HDSP 9632(PCI接続)ですと
TOMOCA\79695
ヤフーチャイナモール\59328
ヤフオク\37500〜
です。
参考までにどうぞ
書込番号:12534270
![]() 1点
1点
秦璃さん
今日仕事の合間にいろいろ調べてみました。PCIEX仕様のがあるんですね。いろいろ見て行った結果HDSPe AIOがよさそうだなと思いました。これにした理由は24bit192KHz出力に対応しており入出力も豊富でPCIEXで使用できるところに惹かれました。
クロック入力の増設ボードまで購入すると11万近くいく計算になるのですぐには無理ですね。プリアンプの購入資金に手をつけずに順番に購入していく必要がありそうです。
ノイズ対策はどうしても気になるようならカーボン製のノイズフィルターシートでも中にはればいいと思うのでまあ後回しにすると思います。まずはマスタークロックの確保をしなきゃいけませんね。お金ないけど……がんばって資金集めをします(汗)
このオーディオインターフェースを投入するとわたしのPC総額60万いきますww
ちょっとやりすぎたかなと猛省中ですww
書込番号:12536908
![]() 1点
1点
PCに60万ですか、すごいですね。
AIOはメインで使用しています。
9632との違いはPCIかPCI-Eか、最小レイテンシの差です。
PCI-Eのほうがノイズに強いなど言われますし、
もはやPCIもなくなっていきますのでAIOのほうが良いですが、
価格差は1万円ほどになります。
TOMOCAで\88360ですね。
9632WCMが\21945ですか。
製品ラインナップはシンタックスのページで見れます。
AIOはVISTAの省電力機能でPCIの省電力をOFFにしないとブルーバックになります。
おかげで1ヶ月ほど使えませんでした。
ご注意ください。
クロックについての記述はえるえむさんのところであらかたわかりますが、下記URLもご参考ください。
http://plaza.rakuten.co.jp/amoknoan/diary/200412060000/
書込番号:12537235
![]() 1点
1点
秦璃さん
>AIOはVISTAの省電力機能でPCIの省電力をOFFにしないとブルーバックになります
私が使っているwindows7でもおんなじ感じになりそうですね情報ありがとうございます。
PCのパーツを(性能面で)いいものばかり選りすぐっていたら高額パーツばかりになってしまいましたww
性能は非常に高いですがノイズは低消費電力版のCPUに比べたらすごいでしょうね。ノイズの影響なんて聞いていてもほとんど気になりませんが最低限の対策はしています。普段はクロックを自動的に落として動かしているのでかなり高負荷で動かさない限り信号にノイズがのるようなことはないと思います。6コア12スレッドにDDR3-2000MHzはすさまじいですよ。音とびなんてものは一切起こりません(笑)
私は皆さんの低消費電力かつ低クロック仕様のCPUを使ったほうがいいという考えとは真逆のことをしています。想像以上に安定したいい音でなってくれるのでもう低スペックのPCに戻れませんよww
書込番号:12537399
![]() 1点
1点
皆様 こんばんは
そして何も聞こえなくなったさん
>200V→100Vトランス経由 100V直接 で音の違いを確認できます
HPで自作トランス電源使用されて、色々視聴錯誤されたのを拝見してましたので
そこもお聞きしたいと思ってしました。 ありがたいです <(_ _)>
スレ建てのお礼を忘れておりました お疲れ様です ^^
秦璃さん
ノイズフィルタですが、そのような感じでした
トランス電源をアンプに使用するのも似た傾向でしたが電源よりも、もう一つ悪く
・・・いや、メリット無しで魂抜かれたような?(笑)
魂抜かれたで思い出しましたが、DACを視聴した時のRME製品と他の製品みたいな
秦璃さんは、RME製品色々と詳しそうですが、firefaceとピュアオーティオ系のDACと
聞き比べされた事あります?
また視聴に行きますが、あの差が忘れられないのですよね。。。。
天地創造さん
SOtMは今までのカードとの差がある為でしたか
この辺りはPCそれぞれですので、差の落差も大きそうですね しかも予想できない・・・
(視聴機貸し出し求む (><)
クロックジェネレーターのお話されてて、自分も気になってた逸品館さんの商品ですが
そうだ! SA-50があるから、それにクロックジェネレーターを付ければ、もう最強?!
と思い、CDをまたもや移動させて視聴してみました
・・・そうだった、、、このCDプレイヤーは、熱いAtollのアンプとディナのスピーカーから
熱気を奪い取ってしまう恐ろしいプレイヤーだったんだ・・・と
前にやって気づいてた事を、今更やってしまいました あほですね^^;
ただ、前と違って良い部分があり。聴き疲れしなかったです 環境変わったせいかな?
こんな音が好きな方も居るかも?という感じで聞けましたが
私には聞く楽しさが消えてしまました 中々難しいです。
書込番号:12537933
![]() 1点
1点
天地創造さん
jubeeさんの掲示板ではご本人が「PCとwindowsでやってる限り・・・」伝々とおっしゃられてますが、やはりCD-Rの音質に特化していきPCがPCでなくなったからであると思います。
PCトランスポートにおいてPCは必要悪ですから仕方ないですよね。
ボクの場合はじめたあたりに自分の使用する性能を満たした上で(実際にはそれでもオーバースペックですが)、音に配慮した構成を選びました。
実質、めぼしをつけただけでパーツごとの音はわかりませんし、いちいち試してられませんからね。
必要な性能だから購入したわけであって、それに伴った音質劣化の量は比べてみないとわかりませんし、本人が納得して気にしないのであればそれも必要悪ですから問題ないと思いますよ。
はじめたばかりなら汎用のメインマシンで共用するしかないですから。
自分なりのノウハウがある程度固まってから余裕があった時点で専用機を仕上げればいいと思います。
音楽再生に必要なスペックなどありませんから安価ですみますし。
ゆっこんさん
こんばんわ、jubeeさんの掲示板でもはじめは使ってたけど結局使わなくなったといわれています。
環境がブラッシュアップされていくとかえって邪魔になるということですね。
試聴に関しては第一印象で決めています。
聞いているうちにわからなくなるからです。
しかしエージングというのがあるのも事実ですので難しいところです。
愛用ヘッドホンでも間が空くと暖気運転に1時間ほど必要ですし、
普段使わないパーツをふとつけてみるとあまり印象が良くなかったということがあるかと思います。
本領発揮する前に聞いている可能性がありますね。
幸いPCの場合普段使うものですから接続しっぱなしで慣らし運転が出来ます。
しばらく鳴らしておいてから初めて付替えによる音質の変化というものも判断しやすくなるのではないでしょうか??
せっかくお手元にある機材ですからしばらくつなげっぱなしにしてみてあげてください。
DACですが、はなからモニタリング機材にしか興味がなく、DAC自体も検討はしていましたが、導入以前の段階でした。
ようやくMytekの製品が理にかなってると思ったのでオーダーし始めた段階です。
試聴しに行って聞いたのを明確に覚えているのは映像と音のプロの方が使用されてるCHORD DAC64とイー☆イヤホンのFOSTEX HP-A7ですね。
DAC64はデスクトップマシンにFireFace400、べリンガー?イコライザ、YAMAHAプロセッサ、Rosendahl Nanoclocks 、DAC64、YAMAHA MSP7という機材でした。
聞いた印象は可もなく不可もなくです。
オリジナルスキンのOSとメディアプレイヤー、MP3とか使用されてましたし、WAVEとMP3で大差ないという方でしたので環境が芳しくなかったのか?(マンションの一室でした。)
ふーんという印象しかなかったですね。
FOSTEX HP-A7はノートPCにVista?iTunes再生でヘッドホンはHD800でした。
まぁ、ヘッドホンは高級機ですので広くそこそこなってましたが、数曲頭だししただけでそそくさと帰りました。
環境が違う上機材単体の音が聞けないのが難点ですね。
試聴して唯一驚いたのは三木楽器TOOLSのVXT4です。
はじめ聞いたときはローエンドの伸びにリミッターがなくスタッフさんが間違えてほかのスピーカーで鳴らしてるのかと思いましたよ。
まぁ、これはDACの話ではないですが。
ゆっこんさんご自身は聞くきくらべされたことはありますか?
そもそもDACはお持ちですか?
23日ゆっこんさんもそして何もきこえなくなったさん宅へ試聴参加されますよね。
ギリギリですが、そしてなにもきこえなくなったさんが了承いただけるのでしたら試聴会に貸し出ししますが。
んー配送法はどうしよう。
もしくは京都ですが、お時間が合えば試聴にこられますか?
書込番号:12538413
![]() 1点
1点
秦璃さん こんばんは
> せっかくお手元にある機材ですからしばらくつなげっぱなしにしてみてあげてください
これは、クロックジェネレーターの事でしょうか?
買ってないですよー(笑) と言うか、買えません・・・
CDプレイヤーのSA-50の音質傾向の確認のためだけです ^^;
> ゆっこんさんご自身は聞くきくらべされたことはありますか?
年末に聞き比べての感想でした
ただ、他はライン出力でRMEは違うので、間に何か入っているはずなので
それの差なのかも知れませんので、また視聴に行って来ます
秦璃さんもeイヤホンに行かれたと言う事は、日本橋まで視聴に行かれてるのかな?
私の視聴したのは、日本橋のシマ無線さんです。
> そもそもDACはお持ちですか?
DACは、CECのDA53Nと、nu forceのudac-2です
CDプレイヤーのSA-50にもDAC入力があるので、前のスレはそれで試しての感想です
あっ、そいえばSA-50への光や同軸入力でテストしてないや・・・
> 23日ゆっこんさんもそして何もきこえなくなったさん宅へ試聴参加されますよね。
> ギリギリですが、そしてなにもきこえなくなったさんが了承いただけるのでしたら試聴会に貸し出し
貸し出しって何を?(笑)
>もしくは京都ですが、お時間が合えば試聴にこられますか?
おっ これは時間作りたいですね
前々から、いったいどのような音が鳴っているのか興味津々でしたので ^^
書込番号:12538619
![]() 1点
1点
>これは、クロックジェネレーターの事でしょうか?
ノイズフィルターの印象か芳しくなかったようなのでその件について書いてみました。
>シマ無線です。
地図で確認しました。
上新本社の近くですね。
以前ぐるっとオーディオ関係回りましたがノーチェックでした。
RMEの機材がおいてあるんでしょね??
フロアは覚えてますか?
おいてあるようなら都合様子見てちょっくらいってきます♪
>DACは、CECのDA53Nと、nu forceのudac-2です
DAC二つもお持ちとはうらやましい。
ボクもここでDAC頼んでるんですが、待ち遠しいですね。
http://www.vintageking.com/Mytek-Digital-Stereo192-DSD-DAC
>貸し出しって何を?(笑)
ああ、すみません、主語が抜けてました(汗
HDSPe AIOです。
予備に未開封の9632がある以外それしか持ってませんので(^^;ゞ
>前々から、いったいどのような音が鳴っているのか興味津々でしたので ^^
200VでCV-S 5.5sqを引いたんですが、うっかりききくらべせずに引いてしまったので重心が下がったままなんですよね。
DACもないので完成前の音ですが、その点ご了承ください。
ケーブルはすでにあるので近々3.5sqも引き込みますが。
やるとすればK702でOSごとの音質チェックですかね。
常用OS、最適化OS、10.3.6の3つになると思います。
Vistaや2kもありますが、インストールしてないので・・・。
SSDにOSインストールしてますが、KINGSTONブランドは同じでも容量が違いますのでご注意ください。
ちなみにメールアドレスはお手数おかけしますが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9832348/
の口コミでCtrl+Fで「11236002」と検索していただければでてきますm^^m−−m
いろいろと大口たたいてますが、実際は大人しめです(爆
書込番号:12538827
![]() 1点
1点
今回ちょっと皆さんの考え方を否定するような書き込みになってしまうかもしれません。説明が下手なので腹の立つ書き方になってしまうかもしれません。ご容赦ください。
秦璃さん
>jubeeさんの掲示板ではご本人が「PCとwindowsでやってる限り・・・」伝々とおっしゃられてますが、やはりCD-Rの音質に特化していきPCがPCでなくなったからであると思います。
私はPCオーディオとは何と質問されたらこう回答します。
PCオーディオとはPCの万能さをフルに活用し再生から録音まで行うことができかつ並みのピュアオーディオレベルと同等の音質を目指すもの
となります。ここで重要なのはPCの万能さをフルに生かすということと並みのレベルというところです。
音質を極限まで追求するのであれば質の良いCDPを使ったほうがいいです。PCでピュアオーディオの世界と真っ向から勝負するのは無理があります。突き詰めていけばいい音にはなるでしょうが再生専用のピュアオーディオと比べたらお粗末なものになるのはわかりきっています。
ではなぜPCオーディオが広まり始めているのか……わたしはPCオーディオは一種のネットワークプレイヤーだと考えています。ネットワークプレイヤーには及ばないがそれに匹敵する音質とその気になれば何でもでき音楽再生以外にも動画再生やネット・極論を言えばゲームだって高品質の音で遊べる今までのオーディオとは違いある意味究極の万能さを兼ね備えた新しいオーディオそれがPCオーディオだと考えています。なので再生専用の専用機を作るというのは私は賛同できません。
わざわざ低スペックな専用機を作るぐらいなら対策のしようで何とでもなり何でもできる高スペックのPCを使ったほうがいろいろなことに使えます。PCのいいところを潰してしまったらPCオーディオの意味がないとは思いませんか?
その考えから行くとCDドライブもあまり必要なくなってきます。最近のコストパフォーマンス重視のドライブより良質なむかしのCDドライブを使ったほうが音が良くなるとは思います。しかしCDドライブが活躍するときはせいぜいがリッピングのときだけではないでしょうか?
取り込んだデータをエラーなく正確に書き込むためにそういったドライブが必要になるでしょうが、PCオーディオのように通常内蔵したHDDから取り込んだデータを再生するものには正確に書き込むためのドライブは必要ありません。
よくデータのロスがとかエラーがとか話が出ますがそのエラーやロスは再生や取り込む上でまったくといっていいほど気になりません。なぜなら大抵の場合PCが取り込み中に発生したエラーを修正してしまうからです。限りなく100%に近いデータを取り込むのですから取り込む時点で音が悪くなるというのはありえません。エラーやロスによって変わる音を聞き取れる人は人間じゃないと思います。
ロスやエラーが起こると音質が悪くなるのは皆さんもご存知だと思います。しかしそれは理論上の話で実際はPCがエラーを修正してしまうのでほとんど音に変化は出ません。変化が出たとしても0.001秒より短い時間での変化でしょう。そのような音は聞き分けることなんてとてもできません。明らかに音が悪くなった・音飛びがするなどの現象はデータのロスが原因ではありません。この原因はファイルを正確に読み取れないハードウェアの問題・ソフトウェアの問題です。量子数やサンプリング周波数が高くなると1秒あたりの演算数・HDDやドライブへのアクセス量が非常に大きくなります。そのようなファイルや音源をダウンクロック化したPCで再生するとどうなるか……演算が間に合わなくなりメモリやHDDも読み出し書き込みが追いつかなくなりエラーが発生、音飛びや音質の劣化の原因となります。
もう少し書き込むことになりそうなので中断します。
書込番号:12541543
![]() 1点
1点
>音楽再生に必要なスペックなどありませんから安価ですみますし。
これは私も同意見です。再生するだけなら今売り出されている一番低スペック名ものでも事足りると思います。しかし再生しながらネットを楽しむ、書類を作るなどをしていたらどうなるでしょうか?一時的に負荷がかかっただけで音とびが発生します。そうでなくても再生速度が落ちるなどの再生エラーが起こるでしょう。私の目指すのは高負荷のゲームなどをしても音が綺麗に出るそんなPCを構築したいのです。それだけのものであればどんなことをしても問題なくでできますから。
たしかシングルコアのPCよりデュアルコアのほうが音が良いという書き込みを見たことがありますがこれも処理速度がいいため再生にストレスがかからず音源を再生できるから音がいいのであって良く言われるノイズが多い少ないは関係ありません。昔のCPUも今のCPUもノイズ(磁界)の強さはあまり変わっていないかと思います。それを冷やすためのクーラーのファンのノイズが昔に比べ大きくなったため今のCPUがノイズが強いといわれるようになったのではないんでしょうか?
ちょっと脱線して自分でも書いてる内容が良くわからなくなってきたのでここでやめときます。話がややこしくなりますので(汗)
とりあえず私のPCオーディオはハイスペックPCのほうがいいのではないか論を理由込みで書きこみさせていただきました。内容は意味不明かもしれませんが……
とまあPCオーディオについての私なりの考えを長々と書き込ませてもらいました。こうやって書きこんでいると自分の考え方がぜんぜん違うことに気づかされます。私は私なりの方法で最適なPCオーディオ環境を構築したいと思います。それにしても後半の文章が最初の論題から脱線しすぎて意味不明な内容になってるww
書込番号:12541766
![]() 1点
1点
天地創造さん
すみません、気に障るようなことを何か言ってしまったようで・・・。
-「PCとwindowsでやってる限り・・・」云々とおっしゃられてますが、やはりCD-Rの音質に特化していきPCがPCでなくなったからであると思います。-
言葉足らずでしたね。
PCトランスポートに対して懐疑的なご意見でしたので、この書込みに対して懐疑的であり
天地創造さんの汎用性の上に成り立つPCトランスポートと基本同意見です。
専用化による汎用性、利便性の欠如にも疑問を抱いているのは確かです。
CD-Rでそう思っていたのでPCではじめました。
スタンスとしては機材レベルパーツレベル以下の話にはあまり触れないようにというものです。
自分の場合は、性能を求めていないので音質を考慮して組むことが出来ましたよ。
天地創造さんの場合はPCでの処理能力を求めたのでハイスペックPCで組むことが出来ましたよ。
それでいいと思います。
めぼしをつけただけで実際どちらが音がいいはわからないと考えます。
専用機に関しては特に深い意味はないんですが、
メインマシン納得されてるのであればいりませんし、
メインマシンと切り離そうと思われたのならサブマシン構築もありだと思います。
端的に言いますと懐疑的なのはPCがPCでなくなるほどの専用化です。
PCの基本スペックに関しては今のメインマシンでかまわないですよ。
ということですね。
ちなみにロスやエラーを心配して省電力マシンを組んでるのではないです。
自分なりのEMI対策ですね、アンチノイズのためにやっているだけですのでご理解願います。
書込番号:12541934
![]() 1点
1点
秦璃さん
こちらもちょっと勘違いをしていたようです。ノイズに関しては以前最近の高クロックのCPUはノイズの影響が大きいという話をしているのを見つけまして……そのときのことについてのお話です。
>PCがPCでなくなるほどの専用化です
これをへんな捉え方をして過敏に反応してしまいました。申し訳ない……(汗)
書込番号:12541977
![]() 0点
0点
ちなみに、CD-R時代はPCで音が良くなるように切磋琢磨してました。
先人方は専用機並の環境を用意されてましたが、後期参入の自分にはそれがわからず
先人方の開拓された手法をみてPCがPCでなくなるのに気がついたときやめました。
全盛期のノウハウがない自分には汎用性に欠く手段だったからです。
>音質を極限まで追求するのであれば質の良いCDPを使ったほうがいいです。
そっくり入れ替えれますね。
音質を極限まで追求するのであれば質の良いデュプリケータを使ったほうがいいです。
CD-Rでの手段とPCトランスポートの手法が自分の中でかぶっています。
今は自分の中で整理して分けてる最中ですね。
書込番号:12542006
![]() 0点
0点
こういう話をしているとPCオーディオはほんとに十人十色なものなんだなあと実感させられます。PCオーディオに挑む人がいる分だけその内容も違ってくる……普通のオーディオではこんなことにはなりません。
そう考えるとほんとに奥が深く面白いです。
書込番号:12542044
![]() 0点
0点
PCという根幹はなくせませんからね。
まぁ、もともとPCで善し悪しを言うつもりはありませんが・・・。
PCもオーディオも人それぞれ千差万別ではないでしょうか。
書込番号:12542180
![]() 0点
0点
返信数が200件を超えると、このスレッドには返信できなくなります
このスレは「CDやSACDで良い音を聞くために」を引き継いだスレです。
最近はPCオーディオやネットワークオーディオがさかんに喧伝されています。いくつかの雑誌を読みましたが、本命はやはりネットワークオーディオでしょう。
LINNが先行していますが、コストパフォーマンスは現時点で十分高いとは、言えないようです。
それでネットワークオーディオに乗り出すのは3年後とし、それまではCDやSACDの皿を回して音楽を楽しもうと思っています。(映像付きの音楽は、デジタル放送録画やBDとなります)
みなさまの「こうすればCDやSACDの音が良く聞こえるようになった」との経験談や、好録音のCDやSACDをご紹介いただければと思います。
私のお勧めのSACDは
Celine Dion/A New Day Has Come
シングルレイヤーで、強烈な低域と澄み切ったボーカルが楽しめます。2CHとMultiCHで低音のバランスが違います。
グレースマーヤ/Last Live at DUG
これは言わずもがなの好録音で、低域に力があります。
クラシックでは、
パーヴォ・ヤルヴィ指揮シンシナティ交響楽団のベルリオーズ「幻想交響曲」です。
我が家では-3.5dBで再生していますが、広大なダイナミックレンジです。
![]() 4点
4点
Minerva2000さん ご無沙汰しております。
オーディオは押しなべて、機器を生かすも殺すも電源でしょう。
「CDやSACDで良い音を聞くために」は電源(環境)が素晴らしいと幸せになれますね。
これ以上書くと価格コム恒例の無意味で疲れるだけの「激論」になるのでパスしますが・・
よって私からの一押しCDです。
最近といってもチョット経ちますが、「超優秀演奏」かつ「超優秀録音」そして「超見事なジャケット写真」と
3拍子揃った通常CD/Harmonia mundi/2009.9録音/場所Berlin Teldex Studio /
「J.S.Bach・無伴奏ソナタとパルティータ BWV 1004-1006」/Vn:イザベル・ファウスト。
ムローヴァもウカウカしておれない素晴らしい演奏です。
「1704年製ストラディヴァリウス・Sleeping Beauty 」のガット弦を、完全ノンヴィブラートで、
ジャケット写真どおりの、まさに「凛」と弾ききった驚異的なテクニックと演奏、
そして響きの美しいテルデック・スタジオの空気感まで見事にとらえた完璧な録音です。
クラシックファン必聴の1枚ですよ。
書込番号:12371863
![]() 3点
3点
オーディオ初心者ですが、仲間入りさせて下さい。
私はシステムにはあまりお金をかけず、できるだけリアルな音を出そうと思っています。
このまえやったのに、プレーヤーの上板裏面に#240の黒い紙ヤスリを貼り付けました。
結果、CD、SACDの音がクリアになりました。
実は紙ヤスリの黒い部分は炭化珪素という素材で電磁波を吸収するそうです。(ステルス爆撃機と同じ素材)
ヤスリの目の粗さは音に影響するようでして、私の場合は#240が好みの音でした。
そのため上棚のチューナーもクリアで好みの音になりました。
これから電源関係に手を入れていこうと思っています。
書込番号:12373013
![]() 4点
4点
Minerva2000さん こんばんは(^^)/
初めまして。前スレからロムさせて頂いてます。
プロフィールも拝見しましたが、オーディオ関係は
かなり泥沼でいらっしゃいますね(笑)
私はSACDプレーヤーは持っていないのですが
とある方のご厚意でSA−11S2をお借りしていて
最近はSACDシングルレイヤー盤に嵌りつつあります。
ご紹介のグレース・マーヤのライブ盤は私も愛聴盤で
クロ沼住人の方々にも超勧めまくっていました。
私のお気に入りは5曲目のモナ・リサと9曲目のサニー。
実際のライブと同じような熱気が伝わってくる好録音で
皆さん気に入って下さるので彼女のファンとして嬉しい限りです。
ライブにも良く行きますが、このアルバムのような豪華な構成は
あまりなくて、ギターやベース、ドラムなどのトリオが多いです。
あ。ピアノはもちろん本人の弾き語りがほとんどですが。。。
最近購入したのもではダイアナ・クラールの「ルック・オブ・ラブ」の
シングルレイヤー盤が良かったですね。
クラシックでは、超ベタですが(笑)クライバー/ウィーンフィルの
ベートーベンの第五・第七交響曲のシングルレイヤー盤も良かったです。
書込番号:12373346
![]() 3点
3点
みなさま、おはようございます。
yamaya60さん、
電源系統は大事ですよね。
ご紹介の「J.S.Bach・無伴奏ソナタとパルティータ BWV 1004-1006」はすばらしそうですね。
神尾真由子の「パガニーニ・24のカプリース」と比べていかがでしょう。こちらの録音は、再生機器によっては、高域にキツサが感じられるかもしれませんが。
悠々快適さん、
プレーヤーの上板裏面に#240の黒い紙ヤスリを貼り付けました、とのことですが、これはプレーヤーの上の棚板の裏側に貼り付けたとの理解でよろしいでしょうか? プレーヤーを分解して天板の裏側に貼り付けられたのではないですよね?
私は電磁波対策として意識的に行ったのは、自作電源タップ内に電磁波吸収体を貼り付けたくらいで、この効果があったのかどうかも良くわかっていません。
プレーヤーの上の棚板の裏側に貼り付けるのであれば、簡単ですので試してみたいと思います。
ブレーカーですが、オーディオアクセサリ冬号を見ると、福田氏は河村電器産業製を新たに推薦されていました。
柴犬の武蔵さん、
はじめまして。別スレでは良くROMさせてもらっています。
グレースマーヤはルージュさんが来られた時に持ち込まれたもので、いっぺんで気に入りました。同じく9曲目のサニーがお気に入りですが、3曲目のBei Mir Bist Du Schonも好きです。ドイツ語の発音もきれいですね。
ダイアナ・クラールの「ルック・オブ・ラブ」も良さそうですね。「When I Look in Your Eyes」は持っていますが、録音傾向は同じでしょうか?これもハイブリッドではないですね。
クライバー/ウィーンフィルのベートーベンの第五・第七交響曲のCDは持っていますが、SACDのシングルレイヤー盤はすごく良さそうですね。
書込番号:12373942
![]() 2点
2点
みなさん、こんにちは
vamava60さん
>「J.S.Bach・無伴奏ソナタとパルティータ BWV 1004-1006」/Vn:イザベル・ファウスト
そんなに良いのだったら、ムローヴァを持っているため、家内が怒るかもしれないですが内緒で買います。
Minerva2000さん
>プレーヤーの上の棚板の裏側に貼り付けたとの理解でよろしいでしょうか?
そうです。私は両面テープで裏面全体に貼り付けました。
>福田氏は河村電器産業製を新たに推薦されていました
残念、SCBR-20AS をオークションで買っちゃいました。
>録音傾向は同じでしょうか?これもハイブリッドではないですね。
傾向は同じでハイブリッドではないです。私はダイアナのフアンなのですが、コステロの影響を受けてか、 LIVE IN PARIS から後はぱぁっとしないですね
私のお勧めCDは・The Essential(ニール・ダイアモンド) ・SIMON AND GARFUNKEL'S GREATEST HITS
SACDはThe Chopin Ballades & Scherzos(ルービンシュタイン)
ジャズで録音、曲編成、演奏、価格で一押しが blu-rayのCHRIS BOTTI IN BOSTON 音楽フアン必聴だと思います。
書込番号:12374287
![]() 2点
2点
Minerva2000さん
こんにちは、多分はじめましてですよね?
前スレからROMさせて頂いております。
今年ぽちったCDから
Jennifer Warnesの「Well」の24K GOLD盤と
ハンク・ジョーンズの「Jam at Basie featuring Hank Jones」
の2点を推します。
5万円のガラスCD盤も興味あるんですがちょっと手が出せないです(汗)
書込番号:12374769
![]() 3点
3点
みなさま、こんばんは。
ヨッシー441さん、
はじめまして。お名前は、あちらこちらのスレで存じ上げております。よろしくお願いします。
みなさまのご推薦の中から、派生CDも追加して、ひとまず下記のCD、SACDを注文しました。
1.無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番、第3番、ファウスト
2.Diana Krall Look of Love (SACD)
3.Jennifer Warns Well
4.Jennifer Warns The Hunter
5.Jam at Basie featuring Hank Jones
6.Hank Jones Last Recording (SACD)
7.Live at Basie With Hank Jones (SACD)
Hank Jonesの3枚は、すぐに届きそうですが、残りの4枚は一括で年末頃になりそうです。
聞くのが楽しみです。
悠々快適さん,
blu-rayのCHRIS BOTTI IN BOSTON は良いですね。
ソニースタイル大阪でかないまる氏の解説で視聴し、早速購入しました。前にご紹介した幻想交響曲も、時期は違いますが、同じところで、総額430万円のソニーのハイエンドシステムで聞かせてもらい、衝撃を受け早速購入したものです。その時は、私だけでしたのでサービス?で大音量で聞かせてもらいましたが、300ワット×2のアンプの安全装置が働いて音がでなくなりました。(笑)
書込番号:12376688
![]() 2点
2点
Minerva2000さん こんばんは、お寒うございます。
>神尾真由子の「パガニーニ・24のカプリース」と比べていかがでしょう。
「写真2左」ですね。これも優秀録音盤ですね。
最近、ユリア・フィッシャーも同曲を録音しています。「写真2右」。
(DECCA/2008.9 & 2009.4録音/通常CD/場所:ミュンヘン・オーガスト・エバーディングホール)
これも神尾盤と同じように細身で高解像度の録音ですが、
フィッシャーが大変洗練されたテクニックで鮮やかな演奏をしています。
しかし、神尾盤の方が演奏に力感があって集中力を感じます。
録音は甲乙つけがたしですが、演奏から受ける「エネルギーのほとばしり」をとって神尾盤の方が私の好みです。
悠々快適さん
>ムローヴァを持っているため、家内が怒るかもしれないですが内緒で買います。
ムローヴァ盤はこのCDですか?「写真3」
(ONYX/無伴奏ソナタ・パルティータ全曲/通常CD2枚/2007.3&2008.10録音/場所:イタリア・ボルツァーノ)、
あるいはムローヴァが若い頃フィリップスから出していたものですか?
「写真3」のCDならフィリップス時代とは使用楽器が違いますので、
(現在、彼女は1750年製ガダニーニのガット弦をバロック弓で弾いているようです)
かなり録音が違う上に、曲から受ける印象が違いますね。
このムローヴァ盤では、ガット弦のガダニーニで弾いているせいかヴァイオリンの音がファウスト盤と比べて割りと太いです。
当然、録り方にもよるのでしょうが・・・
これも残響を豊かに取り入れ、ホールに漂う空気感と彼女の冴え渡ったテクニックを見事にとらえた優秀録音ですが、
ファウスト盤と比べ、どちらをとるかといわれたら、これは、もう好みの問題でしょうね。
あと「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全曲」盤では、
チョット録音が古いですが、バロック・ヴァイオリンの名手レイチェル・ポッジャー盤も優秀録音です。
「写真4」(CHANNEL CLASSICS/1997〜1999年録音/場所:オランダ/通常CD2枚)
ところで、ヴァイオリン曲は最新盤でも、オケものと比較すると通常CDが割りと多いですね。
しかもSACDのものより録音が良いのが多い。
また、最近のヴァイオリニストは圧倒的に女性上位で、しかも美人が次から次へと出てくる。
オッサンやオバサン奏者のCDは骨董品になってしまいましたよ。
書込番号:12376863
![]() 2点
2点
vamava60さん
私の持ってるムローヴァは1番2番が1993年6月28日-30日、3番が1992年8月10日-12日録音されたものでフィリップスがだしたものです。
今月は既にblu-ray5枚、SACD5枚、CD1枚買っているので、グレースマーヤ/Last Live at DUG を買うだけにします。
家内に知れないようにこっそり買いましょう。
書込番号:12377315
![]() 1点
1点
みなさま、おはようございます。
>また、最近のヴァイオリニストは圧倒的に女性上位で、しかも美人が次から次へと出てくる。
リサ・バティアシュビリ、ヒラリー・ハーン、ユリア・フィッシャー、ジャニーヌ・ヤンセン、諏訪内晶子と枚挙にいとまがありませんね。
先月のNHK音楽祭にジャニーヌ・ヤンセンが出ており、BSで初めて聞きました。なめらかな演奏でしたが、力量的には神尾真由子の方が上のような気がしました。
書込番号:12378618
![]() 1点
1点
CD、SACDを現状システムで更に良い音で聴くために以下の工事を電気屋さんに依頼しています。
元電源から家庭用電源とは別にオーディオ用電源を下記仕様でひく
・ブレーカー:SCBR-20AS ・ケーブル:CV-S5.5 3芯 ・壁タップ:SWO-DX ULTIMO
(壁タップを SWO にした理由はアンプの電源ケーブルにゾノトーンを使用しているので
高音域を出すためです。)
なにぶん、初心者のため間違った選択をしているかもしれません。
こうしたほうがよい音できけますよとの、アドバイスを教えて頂ければとカキコミしました。
書込番号:12381095
![]() 2点
2点
皆さん こんばんは。
ミネルバさん
今回も宜しくお願いします。
少々変わりダネですがクィーンの「メイド・イン・ヘブン」と長渕 剛の「いつかの少年」を推薦します。
去年くらいからクラシックやジャズ一辺倒ですが、原点に戻りブリティッシュサウンドのような魂の入った曲もチラホラ。(笑)
先ほどまでクィーンを聴いてまして。録音が良い曲が多いと再認識。
久しぶりに聞いたフレディの声は天まで突き上げる。
こんな感じでしょうか。
あと長渕の兄貴の曲ですが、24ビット:ライヴ盤。
オフ会で皆さんに聞き応えのあるアルバムと絶賛。
スタジアムライヴのイロハを教えてくれます。
またここ数日、主要電源系のケーブルをアコリバ系に総入れ替え。
奥行き、空間再現性に拍車をかけた音色に。
とくにACスタビライザーRAS-14は、情報量が非常豊富になります。
システムに「合えば」倍の値段のアンプに辺境する逸品ですね。
是非貸し出し等をされては!と思います。
書込番号:12381725
![]() 2点
2点
みなさま、おはようございます。
ローンウルフさん、
こちらこそ、今回もよろしくお願いします。
クィーンの「メイド・イン・ヘブン」はショッピングカートに入れました。
長渕 剛の「いつかの少年」の方は、ネットではなく別ルートで、他とまとめて購入することを考えます。国内発売版はネットではあまり安くありませんので。Hank Jones関係3枚も国内発売でしたので、別ルートで購入しました。
アコリバのRAS-14も凄く良さそうですね。アンプにも良いそうですが、プレーヤーにも良さそうですね。価格がパワースタンダード電源ケーブル2本分以上なのが難点です。
そのケーブル2本買うより、RAS-14を2本買って既存電源ケーブルに継ぎ足す方が、効果がありそうで悩みどころです。
PS:最近ノートPCを買いなおしたところ、書き込みのフォームに少し長い分を入力した時、漢字変換すると変換後の文字が、フォームの下の方に移動して隠れてしまい、入力が面倒だったのですが、IE8の問題と分かり解決しました。
書込番号:12383158
![]() 1点
1点
SHM仕様で作られたアラウのリスト ピアノ作品集
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88-%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86-%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A6-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA/dp/B003EW4JNA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1292640929&sr=8-2
うたい文句[音が見える!躍動する!世界が初めて耳にする、別次元のクオリティ]
はだてじゃなかった!!本当にすばらしい音です。自信を持ってお勧めします。
SACD再生機でないと聴けません。
書込番号:12384082
![]() 2点
2点
SHM仕様SACD【第1回 2010年6月23日発売タイトル】は以下です。
●ロック/ポップス 10タイトル
「レット・イット・ブリード/ザ・ローリング・ストーンズ」
「フーズ・ネクスト/ザ・フー」
「いとしのレイラ/デレク・アンド・ドミノス」
「461オーシャン・ブールヴァード/エリック・クラプトン」
「童夢+2/ザ・ムーディー・ブルース」
「彩(エイジャ)/スティーリー・ダン」
「シンクロニシティー/ポリス」
「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ/ヴェルヴェット・アンダーグラウンド」
「フィルモア・イースト・ライヴ/オールマン・ブラザーズ・バンド」
「ホワッツ・ゴーイン・オン/マーヴィン・ゲイ」
●ジャズ 5タイトル
「ゲッツ/ジルベルト/スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト」
「ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン/ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマン」
「至上の愛/ジョン・コルトレーン」
「エラ・アンド・ルイ/エラ・フィッツジェラルド」
「サラ・ヴォーン・ウィズ・クリフォード・ブラウン+1/サラ・ヴォーン」
●クラシック 5タイトル
「ブラームス:ドイツ・レクイエム/カラヤン指揮ベルリン・フィル、他」
「サン=サーンス:交響曲第3番《オルガン》/バレンボイム指揮シカゴ交響楽団、他」
「バルトーク:管弦楽のための協奏曲、他/ショルティ指揮シカゴ交響楽団」
「リスト:ピアノ作品集/クラウディオ・アラウ(ピアノ)」
「バッハ:管弦楽組曲第1番、第2番/リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管弦楽団、他」
書込番号:12384818
![]() 2点
2点
SHM仕様SACDの最新情報は下記サイトです。
http://www.universal-music.co.jp/u-pop/special/sacd/sampler.html
書込番号:12384917
![]() 2点
2点
もう考えるだけでワクワクしちゃって又カキコしちゃいます。
オーディオ専用回路をひき、アンプとプレーヤーにRAS-14をかまして、SHM仕様SACDで好きなアーティストのサウンドを家で聴く・・・・もう興奮してしまいます。
老境に入ってから、こんな至福の時がやってくるとは嬉しいかぎりです。
書込番号:12385996
![]() 2点
2点
みなさま、こんばんは。
悠々快適さん、
SHM-SACDのご紹介ありがとうございます。
SHM-SACDのうたい文句は、CD層なし、2CHのみの非圧縮、新素材採用ですが、本当に通常のハイブリッドSACDより音が良いのでしょうか? もちろん、同じマスタリングで同じバイナリデータとしての比較ですが。
1500円でサンプラーが出ているようで、買って試せば良いのでしょうが、SHM-CDの時に試した時には、高域がはっきりと出て良い音のように感じたものの、リッピングしてみると、C1エラーが減っている訳でもなく、むしろ増えているものもあり、その音の良さと感じたものも、単に新素材の響きが載っているだけでは、と思ってしまいましたが。
それとSHM-SACDで出いるものの大半は、昔LPを購入して聞いたことがあり、再度SHM-SACDとして購入して聞いてみたいと思うものがほとんど無いので、困ったものです。
書込番号:12386131
![]() 1点
1点
ミネルバさん、こんばんは
>通常のハイブリッドSACDより音が良いのでしょうか? もちろん、同じマスタリングで同じバイナリデータとしての比較ですが
SHM SACDは最良の音源を探し出してリマスタするようですので、同一条件での比較は困難と思います。
手持ちのハイブリッドSACD と比較すると音がしっかりとしていて太くて臨場感があります。
家内のスタンウエイに近い音がスピーカーから聞こえてきます。
私は好きなアルバムはSHM仕様に変えていくつもりです。
書込番号:12386267
![]() 2点
2点
みなさま、こんばんは。
悠々快適さん、
>SHM SACDは最良の音源を探し出してリマスタするようですので、同一条件での比較は困難と思います。
となると、例の1500円のサンプラー購入しかないようですね。
>手持ちのハイブリッドSACDと比較すると音がしっかりとしていて太くて臨場感があります。
この比較対象のハイブリッドSACDのタイトルは何でしょう?
書込番号:12387081
![]() 1点
1点
返信数が200件を超えると、このスレッドには返信できなくなります
すいませんおかしな発言をしたことに対する謝罪しとかないといけないと思いこのようなスレを作り書き込ませていただきました。
忘れさん
>「回路設計に携わっている開発者の方でしたら今の発言に関しては謝罪させていただきます」のようなお考えは排除されることを強くお勧めします。
確かにこの発言はいろいろとまずかったと書き込んでから思い猛省しておりました。回路設計者という言葉はいいたとえが思いつかず回路設計のできるような知識を有していないとどこかでボロがでてしまう……つまりは半端者の素人と変わらないですという意味合いで言いたかったので余分な書き込みが誤解を招いたようです。余計な一言な上言葉足らずでした。以後気をつけます。
>天地創造さんのご発言からは、電気回路の科学的な基礎知識お持ちでないことがわかるだけに、なぜその内容を当然の事実であるかのように語ることができるのか、とても不思議です。
私は以前も言ったとおり電子回路については極々基本中の基本しか理解しておりません。そこから自分なりにどうしてオーディオにそういったものが使われているかを考えて発言していたので無茶苦茶な理論が出て来るのは当たり前です。私の発現の中のほとんどは自分なりの考えが多く混じっていました。別に電子回路の知識を知っていますというような発言はなかったと思いますが勘違いさせたのならごめんなさい。
スイッチング電源の発信については適切な対策をしないと高周波ノイズが発生する可能性が高いことは知っています。しかしその言い方が悪かったですね。高周波のノイズが発生しやすい。対策をしても出る可能性があるからオーディオにはあまり使われないんです。といったほうがよかったでしょうか?たしかに引用したサイトでは20〜100KHZで発振すると書いてありましたが実際は人の耳で聞き取れる数KHZから発振しています。少しでもいい音で聞きたかったらなるべくそういうのは使いたくないです。文章を書き込むのが面倒だからとまんま引用したのはダメでしたね。こういう引用が混乱を招くので以後気をつけます。
高出力のスイッチング電源を搭載したパイオニアのプラズマモニターを使用していますがスイッチング電源特有の高周波ノイズ(キーンというとても高い音です)が聞こえています。音楽再生するときはモニターを切っていますがそちらのほうが高周波ノイズは発生しないので綺麗な音で聞くことができます。これがアンプだったら困るでしょうね。音楽に混じってキーンという高い音が混じるので。低周波の音なら何とかごまかせますが高い音は小さい音でも地味に耳につきます。
もう200スレを超えており謝罪の文章が入れれなかったのでここで入れさせていただきました。忘れさんが指摘されるのも当然だと思います。もう少し私も国語を勉強して誤解されないような文章を書けるようにしたいと思います。
![]() 3点
3点
■問題提起 (その1)
まず最初に言葉の定義を明らかにしておきます。タイトルに使った「耳で聴く」には、二重盲検法などの特別なチェック法は含みません。私たちが普通に日常生活で音楽を聴くときの「耳で聴く」を意味しています。
で、その「耳で聴く」行為はそもそも意味がないのか? 特別なチェック法でなく、日常的な普通の聴き方をして「音が変わったぞ」ではダメなのか? いや十分である。これが当スレの問題提起です。そこから派生し、音が「変わる」、「変わらない」問題全般を扱います。
オーディオの世界には、音が変わるかもしれない要素とその可能性が数多く横たわっています。たとえば電源ケーブルやスピーカーケーブによる音の変化。ジッターの影響と、USB-DACにおけるアシンクロナス(非同期)転送による音の違いの関係。CDPによる再生と、音楽ファイル再生との音の違い(エラー訂正etc)、インシュレータやオーディオボードによる音の変化……。
言い換えれば我々ユーザは、日夜これらの多岐にわたる音の変化を、次々にチェックし続けなければならない状況にあります。
さて一方、「変わらない」派のみなさんは、「測定機器による計測、もしくは二重盲検法で音のちがいを客観化できなければ意味がない。でなければ音の変化は客観的に立証されたとはいえない」と主張されています。
ですが前述の通り、音の変化を検証すべき要素は無数にあるのが現状です。かつ、今こうしている間にも、オーディオ業界ではアップ・トゥ・デイトに(笑)新たな「音の違いの可能性」が次々に提示されています。私たちには時間がありません。思わず「ふつうの女の子に戻りたい!」と言いたくなるのが実情です。
ひるがえって「変わらない」派のみなさんが主張される、測定機器による計測や二重盲検法には、かなりの手間とエネルギー、時間がかかります。すなわち前述のような現状を考えれば、とうてい現実的ではないのが実情です。
たとえばウェブサイト「オーディオの科学」の筆者である志賀氏は、検証法としてブラインドテストを主張されています。ですがその志賀氏自身、以下のように「現実的でない」と指摘しています。
--------------------------------
■「そもそも客観的事実とは?」(オーディオの科学)
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/objective.html
一般論としてはブラインドテスト以外には無いというのが私の主張である。(中略)ブラインドテストをすれば少なくとも先入観は排除出来るわけであるが、厳密なテストを実行するのは大変で素人の手に負えない。といったことで議論はいっこう収斂しないというのが実情ではなかろうか?
---------------------------------
そこで当スレでは冒頭に掲げた通り、「ふつうの試聴ではダメなのか?」と問題提起します。結論から先にいえば、「客観的なものの見方」をすることで、抑制的にコントロールされた意識と知覚による「客観試聴」を提案します。
この「客観的なものの見方」と客観試聴については、詳しくは私のブログの以下の記事に書きました。何かのご参考になれば。
■『電源ケーブルで音は変わるか? 〜客観的なものの見方のすすめ』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-77.html
![]() 2点
2点
■問題提起 (その2)
では、まず私のスタンスを開示します。オーディオの世界には、いろんなオカルト・ツールやオカルト思考が跋扈しています。率直に言って、私はこの種のものには興味がありません。
「変わる、変わらない」論争で取り沙汰される「オカルトすれすれ」(笑)の事物のうち、私が実際に耳で音の変化を確認したのは電源ケーブルのみです(今日現在)。したがっていまのところ、「音が変わる」と私個人が言及するのは電源ケーブル限定とします。
さてそもそも私は、「レコードプレーヤの制振対策に効果があるのは理解できる。だけどアンプの下にボードやインシュレータを敷いて何の意味があるの?」てな原始人間です。
そんな私ですが大変残念ながら(笑)、「電源ケーブルで音が変わる」ことは事実として認めています。それはなぜか? 私自身が実際に耳で聴き、音の変化を確認しているからです。(後述しますが、私は「客観的」に聴いています)
私にとっては「自分の耳で聴いた結果」がすべてであり、それ以外の理論や法則、セオリー、慣習にはあまり興味がありません。なぜならオーディオは、自分の耳で個人的に聴いて楽しむものだからです。
ゆえに普通の方法で個人的に聴き、音の変化を体感すればおしまい。それを他人に証明して見せようなんてカケラも思いません。また、それがオーディオ界ではどんな形でセオリー化されているか? てなことにもあんまり興味がありません。
例えば「オーディオの世界では、スピーカーの下にかますインシュレータは『3個がベスト』とされているか? それとも4個か?」てなことには関心ありません。
だってそんなふうに「マニュアルを探す」のではなく、自分で実際にやってみて(実験)、自分の耳で音の違いを確認すれば(観測)終わりだからです。これがいちばん納得できます。
こうした「実験」と「観測」は、「変わらない」派のみなさんが信奉する「科学」の基本です。たとえば前出、「オーディオの科学」管理人の志賀氏も、以下のように述べています。
---------------------------
■「そもそも客観的事実とは?」(オーディオの科学)
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/objective.html
物理法則は最初は仮定から始まり、多くの実験・観測を繰り返した結果がその仮定に矛盾しないことが確かめられはじめて「客観的な事実(法則)」として認められるわけである。
---------------------------
私と電源ケーブルとの関係に置き換えましょう。まず先に、「電源ケーブルで音が変わる」という仮定が社会に存在しました。で、それを見聞きした私は電源ケーブルを使い、多くの実験・観測を繰り返し(すなわち試聴し)、試聴結果がその仮定に矛盾しないことを確かめました。そして私は「電源ケーブルで音は変わる」と結論付けました。すなわち科学的な態度です。
書込番号:12483565
![]() 1点
1点
■問題提起 (その3)
私は、「その音は学術的に変わっているか?」なーんてことはどうだっていいです。人間の耳には聴き取れないが、学術的には変わっている? そんなもの、「音楽的には」まったく意味がありません。
「人間の耳には聴き取れないが、測定機器による計測で確認された。これで学術的な裏付けが取れたぞ」
どうでもいいです(笑)。私は学術を極めたいのではなく、音楽を楽しみたいのです。「普通の方法」で自然に耳で聴いて体感できるのでなければ、それがいくら学術的なプレイクスルーであろうが意味を持ちません。
いや例えばですよ、自分の耳で聴いて音の変化を確認できないのに、「いや、○○科学研究所の学術チームが二重盲検法で確認しました。今日から音は変わります」などと言われていったい誰が納得できるんですかぁ? それこそ彼らのプラシーボじゃないんですか?
学術を極めたい人は、二重盲検法でも機器計測でも勝手にやればいいのです。あたしゃ、カンケーありまへん。繰り返しになりますが、私は音の変化を他人に証明して見せようなんて思いませんし、自分の耳で確認するのが「自分に対して」いちばん説得力があります。古来より言われる「音楽を楽しむことは、きわめて個人的な営みである」という格言はそういう意味です。
ところがです。これが「変わらない」派の方々とまるで噛み合いません。だってあのみなさんったら、ふたこと目には「普通に耳で聴いた結果なんか意味がない」、「そんなものはプラシーボだ」の一点張りなんですから。やれやれ。
音の変化を他人に証明して見せる気などなく、個人的に音楽を楽しみたいだけの私から見れば、彼らのほうがよっぽど「音が変わらないことを強く主張したがっている」ように見えるんですが、どうなんでしょうか?
この種の議論における「変わらない」派の常套句は、「意見を主張する側にこそ立証責任、説明責任がある」というものです。ところが私は個人的に楽しみたいだけ。一方、彼らは「音が変わらないこと」を声高に強く主張したがっているとしか思えません。それなら彼らのほうにこそ、立証責任があるのではないでしょうか?
にもかかわらず「変わらない」派は「おれに立証責任はない」とばかりにふんぞり返り、自分では試しもせずに主張だけはし続けます。いったいどーなってるんでしょうかこれは(笑)
いやそりゃ彼らにだって、「音は変わらない」と個人的に考える権利はあります。自分の家でひっそりと、だれも読まないチラシの裏に「音は変わらないッ」と100万回書こうが自由です。
ですが誰の目にも触れ得る公共の場である掲示板で、音の変化を楽しんでいる人に向かってしつこく否定的なレスを書くのはどうなんでしょう。人を不快にさせたり、他人の迷惑になる書き込みって掲示板で許されるのでしょうか。
いや私は第三者的な立場に立ち、客観的にものを見られる人間です。ですからそのテの書き込みを見ても、決して感情的になどなりません。「ああ、この人はそう考えているんだな」で終わりです。それどころか生産的でロジカルな議論が成立する相手なら、もちろん討論することもありえます。
しかし一方、感情的になる方もおられるのは事実です。無理ありません。だって例えば自宅で個人的に音楽を楽しんでいる人のところへズカズカと押しかけ、玄関を蹴破り土足で上がり込み、耳元でこう怒鳴られたとしたらどうでしょう?
「おまえは二重盲検法をやったのか? ほう、こーんな電源ケーブルを使っているんだな。ハッ。だがそんなもので音は変わらないんだ。おまえの電源ケーブルなんかに存在価値はないんだよ。それにあなたの夏休みの自由研究、いっしょーけんめいやった割にはデキが悪いわねぇ〜。子供の宿題のほうがまだマシよッ♪」
これじゃあ誰だって、「私の家から出て行ってくださいッ!」と叫びたくなるのも道理でしょう(笑)
書込番号:12483571
![]() 4点
4点
■問題提起 (その4)
そもそも「変わらない」派のみなさんが論外なところは、「ふつうの試聴」を否定しているところです。「測定機器による計測、または二重盲検法『以外』のチェック法では、プラシーボ効果の可能性があるから意味がない」というのだから驚きです。
いやね、あのぅ……オーディオ機器メーカーの音決めだって「人間の耳」で行われるわけですよ。音を耳で聴き、「ああ、もうちょい低音を締め気味にしようか」てなことが日常的に行われるわけです。
にもかかわらず「単に耳で聴いた結果じゃ意味がない」なんて主張される方々は、ではメーカーの音決めそのものを否定されるのでしょうか?
一例を挙げます。以下は、日本テキサス・インスツルメンツの赤堀 肇氏が、電子技術誌「EDN Japan」に寄せた論考の2ページ目からの引用です。
■『オーディオ品質とクロックジッター 〜デジタルオーディオが抱える潜在的課題に迫る』
赤堀 肇 日本テキサス・インスツルメンツ
http://ednjapan.cancom-j.com/issue/2007/09/6/28/2
--------【ここから引用開始】-----------
ジッターが微小な場合には、オーディオ性能の劣化は数字としては現れない。しかし、聴き取り可能な音質の変化として影響が現われる場合もある。筆者は、これまでのデジタルオーディオ向けデバイスの開発において、各種のDIRを用いて試聴を行ってきた。音質評価用のモニターシステムにおいて、このDIRデバイスを変えるだけで、音質が非常に大きく変化するという経験をしている。その音質の変化は、単に「低音が出ない」、「高音が伸びる」といったレベルのものではない。良いものは音場や音像の再現性に優れる一方で、悪いものは、単調かつ平面的に音が鳴っているだけ、というレベルとなる。音質がどのように変わるのかを言葉で説明するのは非常に困難だが、可能な限り具体的に説明を試みると以下のようになる。
●歌手の口の大きさが変わる
●目の前で演奏しているような実在感の再現が変化する
●その場に居合わせる人の数が変わるといった気配の変化が生じる
●演奏が単調になる(どんな曲を聞いても楽しい雰囲気になってしまう)
つまり、音楽の再生においては、その解釈が異なってしまうほどに音質が変化するのである。
また、デジタルオーディオ向けデバイスの開発においては、PLL回路をチューニングする過程でも試聴を行う。その際、PLLのループフィルタの定数を変えると、いわゆるジッターの量にはほとんど変化がない場合でさえも、明らかに音質が変化する*2)。
このように、ジッターは音質をも大きく変えてしまうのである。
-------【引用はここまで】--------
(参考1) 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
http://focus.tij.co.jp/jp/general/docs/gencontent.tsp?contentId=37105
(参考2) 文中の「DIR」(デジタルオーディオI/Fレシーバ)については、同じ論考の1ページ目(以下)に解説があります。
http://ednjapan.cancom-j.com/issue/2007/09/6/28
さて赤堀氏は上記のように、「これまでのデジタルオーディオ向けデバイスの開発において、各種のDIRを用いて試聴を行ってきた」、「デジタルオーディオ向けデバイスの開発においては、PLL回路をチューニングする過程でも試聴を行う」と書かれています。
では「変わらない」派のみなさんは赤堀氏に対し、「耳で聴いた結果は意味がない」とおっしゃるのでしょうか?
書込番号:12483576
![]() 3点
3点
■問題提起 (その5)
あるいはこんな興味深いデータもあります。
------【ここから引用開始】--------
【特許】A-V用信号処理方法
http://www.jaist.ac.jp/ricenter/tokkyo/miyahara2.html
【特許権者】北陸先端科学技術大学院大学長
【発明者】宮原 誠 (情報科学研究科教授)
小林幸夫 (情報科学研究科)
(前略)
【従来の技術】従来の音像定位制御は、音像定位方向のみに関するものである。それは、両耳間に音圧差と、位相差を生じさせ、その定位方向を制御するものである。具体的には、ステレオ信号の右信号と左信号との間に、振幅差及び位相差を電気回路により生じさせる方法である。しかし、この方法では、音像の質、すなわち音像の大きさやシャープさ、広がり感については制御することは困難であり、実際行われてはいなかった。(中略)
【構成】音響信号の時間軸を音階に影響のない範囲(音楽の印象を損ねない範囲)で揺らがせる(変調をかける)ことにより、音像を自然にぼかせることができる。デジタルオーディオ信号の場合、例えばサンプリング周波数(ワード・クロック)発生器のPLL回路のVCO(Voltage Controlled Oscillater)電圧を時間的に変動させるなどの方法でクロックにジッターを加えることにより時間軸に揺らぎ(ジッター)を与えることができる。アナログオーディオ信号の場合も移相器により時間軸に変調をかけることができる。
【効果】人間の聴覚は信号のレベル方向のみならず、「時間方向の伸び縮み歪み」に従来の常識を越えたけた違いに高い感度を有することが明らかになった。これによれば、音響再生のみの場合には、時間軸方向に存在する伸び縮み歪みを減少することにより、芸術家が表現したい印象を損なわずに再現することが可能である。(後略)
--------【引用はここまで】----------
上記の文中には、『人間の聴覚は、(中略)「時間方向の伸び縮み歪み」に従来の常識を越えたけた違いに高い感度を有することが明らかになった』とあります。
ですが一方、「変わらない」派のみなさんは、「単に耳で聴いた結果は意味がない」とおっしゃいます。
かたや「北陸先端科学技術大学院」、もう片方は「ネット上の実名さえわからぬ匿名の書き込み者」です。さて私はいったい、どちらを信用すればいいのでしょうか?
書込番号:12483582
![]() 3点
3点
■問題提起 (その6)
「単なる試聴では意味がない」、「二重盲検法でないから判断材料にならない」とおっしゃる方々は、ではそもそも我々ユーザがオーディオ機器を買う前に店頭で行う「試聴」など意味がない、ナンセンスであると主張されるのでしょうか?
はたまた「僕は離島に住んでいるので試聴できません。スピーカーAとスピーカーB、どちらを買えばいいですか? 主観でいいから教えてください」なーんていうおバカな質問に対し、「もともと試聴など意味がないのだ。だから回答者に言われるまま、指定された機種を買え」、「そんなものはクジ引きで決めとけよ」とでもおっしゃるのでしょうか?
とんでもない話です。
オーディオの基本は試聴です。すべては試聴に始まり、試聴に終わります。たとえばブッシェルフ型スピーカーの底面と、スピーカースタンドの天板との接点はどう処理するのがベストか? これはネット上の掲示板で質問すれば解決するのでしょうか?
いいえ。そんな簡単な話ではありません。仮に回答者のAさんが「金属製(またはハイプリッド)のインシュレータをかますのがベストです」と、あたかもそれが「客観的事実」であるかのように答えたとします。
でも音の感じ方は人それぞれ、好みも人により千差万別です。つまりその回答は「Aさんの音の好み」、「Aさんの聴く音楽」にいちばんマッチした方法であるにすぎません。すなわちAさんの主観です。
他人の主観では意味ありません。そうではなく「自分」にとって何がベストなのか? これが問題なのです。かつ、それは自分の耳で実際に試聴し、自分で確認する以外に確かめるすべはありません。
(※ただし主観ではなく客観的なものの見方をし、自分の好みにとらわれず頭の中で判断材料を客観化した上で答える回答者ももちろんいる)
さて上にあげたインシュレータは単なる一例です。
「アンプを買い換えたい。うちのスピーカーを自分好みに鳴らせるアンプはどれか?」
「情報量が多く空間表現の得意なCDプレーヤはないか?」
「低域が引き締まり、高解像度ハイスピードなスピーカーを探したい」
すべては試聴を繰り返し、自分の耳で探すしかありません。「単なる試聴では意味がない」などと試聴を否定するのは、オーディオのすべてを否定するのと同じです。
すなわち「試聴は意味がない」などという言説は、オーディオを知らない門外漢のトンチンカンな珍説にすぎません。
書込番号:12483584
![]() 1点
1点
■問題提起 (その7)
いよいよ今回は核心に迫ります。日常的な試聴結果の積み重ねこそが、客観化につながるというお話です。
それぞれ属性が異なる不特定多数の人間が生活する社会において、たがいに見知らぬ(存在さえ知らない)Aさん、Bさん、Cさん、Dさん……(無限大)が、例えば「○○屋のチョコレート」を食べたとしましょう。
そして彼ら(すなわちサンプル)が一様に、「このお菓子は甘い。でもちょっと甘すぎてしつこい」と感じたとします。そして、まったく同じ感想を示すサンプル数が有意な数量に達したとします。
とすればこの「○○屋のチョコレート」なる物体は、(1)甘いお菓子である、(2)ただし甘さをもう少し抑えた方が「もっと売れる」ことが、確認されたことになります。つまり(1)、(2)は十分に「確からしい」とマーケティング・リサーチによって確認されました。マーケティング調査の結果がデータ化され、客観化されたわけです。
この「○○屋」のような企業は、試聴もしない「変わらない」派のみなさんとは異なり、日夜こうしたマーケティング・データをもとに商品を改良し、あるいは新商品を開発する努力を続けています。
そして○○屋は「変わらない」派のみなさんのように、「いや彼ら(サンプル)の『甘すぎる』という感想はプラシーボかもしれない。二重盲検法で行われてないから意味がない。こんないいかげんなデータをもとに商品開発するのは危険だ。やめよう」などとは考えません。
なぜならこうした個人の主観を集めたデータには価値があり、この種のマーケティング・リサーチは有効であることがすでに立証され、常識化しているからです。そして私たちの現代社会はまさに、こうしたマーケティングにより動いているのです。
日本を動かしているのは、決して菅サンではありません。日本社会を実質的に動かしているのは、マーケティング(調査や広告宣伝など)です。「変わらない」派のみなさんは、この厳然たる事実に目を背けてはなりません。なぜならそれは「客観的事実」だからです。
もうおわかりでしょう。
「○○屋のチョコレートが甘い」のと同様、「デノンのアンプには低音の量感がある」という事実は、絶え間ざるユーザ個々の長年にわたる試聴ですでに確認され、広く公知されています。常識化し、定着しています。
すなわち同一で有意なヒアリング結果が社会に数多く堆積し、かつ有意な年月がすぎたことにより、それが客観化されたわけです。
さらには「○○屋のチョコレートが甘い」のと同じく、長年にわたる無数のユーザのヒアリング結果により、「電源ケーブルで音が変わる」ことはすでに確認され、客観化されています。
二重盲検法のような非日常的な聴き方でなく、ごく普通の日常的で自然な音の聴き分けの積み重ねにより、「客観化の自動化」が進んだのです。
すなわち測定結果がデータ化・数値化されていようがいまいが、二重盲検法でそれが行われてなかろうが、「電源ケーブルで音が変わる」ことはすでに十分客観づけられているのです。
なお「客観」の意味についてはまた次回、決定的な材料をご提示します。
書込番号:12483586
![]() 3点
3点
■問題提起 (その8)
「音が変わる」、「変わらない」の議論になると、やたらに登場するのが「主観」と「客観」なる言葉です。しかしこれらの正確な意味や概念については共通理解がないまま、めいめい個人の思い込みで言葉だけが乱用されています。
で、「ひとりの人間が自分で感じたこと」はすべて主観で当てにならない、などというデタラメな論法がまかり通るのです。
そうではなく、人間は「客観的にものを見る」ことができます。対象物を前にして冷静に一歩、身を引き、「いま自分の目の前で起こった現象は本物か?」、「何かまったく別の現象である可能性はないか?」と絶えず「疑う心」を持つ。そして「検証する目」でものを見て、客観的に思考することができるのです。
にもかかわらず「変わらない」派のみなさんは、「自分自身で感じたこと」はすべて主観だ、当てにならない、しかるべき方法で客観化しないと意味がない、と見当はずれなことをおっしゃいます。
「変わらない」派のみなさんには、辞書ぐらい引いてほしいものです。では私が代わりにやりましょう。以下の文章中、引用記号付の部分は「goo辞書」に掲載されている文章です。
---------------------------------
【客観】
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/54335/m0u/%E5%AE%A2%E8%A6%B3/
>当事者ではなく、第三者の立場から観察し、考えること。また、その考え。かっかん。
>「つくづく自分自身を―しなければならなくなる」
----------------------------------
「第三者」のすぐあとに、「の立場から」という表現があることに注目してください。すなわち「当事者」であっても、その人が「第三者的な立場に立って」観察し、ものを考えれば「客観」なのです。
「変わる、変わらない」のテーマに即しわかりやすくいえば、当事者が「当事者の立場」で自己の利益を守り、自分の主張を通すために考えた利己的な思念が「主観」です。
一方、当事者であっても「第三者的な立場」に立ち、自己の利益や守りたい主張にとらわれずにものを見ることが「客観」です。すなわち人間は「客観的にものを見る」ことができるのです。
----------------------------------
【客観的】
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/54339/m0u/%E5%AE%A2%E8%A6%B3/
>特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりするさま。「―な意見」「―に描写する」
-----------------------------------
もはや説明するまでもないでしょう。辞書に出ているのだから明白です。たとえ当事者であっても特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりすればそれは「客観的」です。
もう少し例を挙げながら補足しましょう。「客観的にものを見る」とはどんな意味か? 私が別のスレに書いたものを以下に一部引用します。
------【ここから引用開始】---------
■Dyna-udia [12393833]
たとえばAさんが、デノンのアンプを所有しているとします。Aさんは我が子かわいさで、自分のアンプには欠点がないと感じます。「躍動感があり、パンチがあって、低音もたくさん出て……」。で、第三者がAさんに「デノンのアンプは低音がボケるよね?」というと、Aさんはムキになって反論します。
このときAさんは我が子かわいさで、「客観的にものを考える」ことができていません。すなわちAさんの思考はきわめて主観的です。
ところが一方、同じようにデノンのアンプを所有しているBさんは、デノンのアンプの長所と短所を客観的に仕分けして考えることができます。我が子かわいさで感情(主観)に流され、「デノンのアンプはすべてすばらしい」、「欠点などない」などとは考えません。このときBさんの思考は十分に「客観的である」といえます。
-----【引用はここまで】-------
上に引用したAさんの心理を分析してみましょう。Aさんは自分の所有物(デノンのアンプ)に対する愛着が強いあまり、オーディオ機器という単なる「嗜好品」にすぎないものが「自我と同一化」しています。つまり客観的に見ることができません。
で、自分の愛用品(デノンのアンプ)を少しでもマイナス評価されると自我が傷つき、「まるで自分が非難されたように」感じます。そしてすっかり我を忘れて冷静さを失い、ヒステリックに反応します。きわめて主観的な態度です。
こんなふうに感情に左右され正常な判断力を失う人、主観的な思い込みにとらわれてバイアスのかかった思考しかできない人はもちろんいます。(それが「悪い」という意味ではありません。この文章はそうした「どっちがいい/悪い」のような「価値判断」を含めず、淡々と客観的に分析しているだけです)
ですが一方、Bさんのような人もいます。Bさんみたいに「検証する目」をもち、客観的なものの見方で、所有物であるデノンのアンプや電源ケーブルの聴き分けをすることは当然できます。
すなわち当事者である個人の思考や分析といえども、それが客観的な思考に基づき行われる限り有意なサンプルたりえるわけです。
書込番号:12483595
![]() 3点
3点
■問題提起 (その9)
さて、ひとまず結論です。自分の所有物(オーディオ機器)を使って個人的に音を楽しんでいるときは、何を感じ、何を考えようが当然自由です。たっぷりと主観にひたり、自分だけの感覚を楽しみたいものです。
ですがひとたび外へ向かって情報を発信する場合、ときには自分を振り返ってみることも必要です。「自分の感覚は正しいか?」、「思い込みにとらわれてないか?」、「本当に音は変わったのか?」。つまり自分を疑ってみるということです。
「疑う心」で「検証する目」をもち、自分の感覚をチェックする。第三者的な立場に立ち、客観的に考える。で、客観という名のフィルターにかけた分析結果を、外に向かって発信する。
ひとりひとりがこうした態度で情報発信すれば、それがおのずと社会に降り積もり、自動的にデータ化・客観化されて行きます。測定機器や二重盲検法などの特殊な方法を使わなくても、十分確からしい分析結果が得られます。
また、こうして愛着のある自分の所有物(オーディオ機器など)を客観化できれば、たとえ誰かが自分の愛機をマイナス評価したとしても、その意見を淡々と客観的に聞くことができます。
「ああ、この人はそういう見方をしているのか。それもアリだろう」
意味のない怒りにとらわれたり、荒々しい感情の波に翻弄されなくてすみます。それだけでなく他人の意見を冷静に聞くことにより、自分ではいままで気づかなかったポイントに気づけるメリットもあります。
「いままで自分はこの機器を『すばらしい』としか思わなかった。だけどなるほど、そういう短所もあったのか」
愛する所有物に対するマイナス評価を冷静に検討し、自分の認識をさらに高めることができます。こんなふうに「客観的なものの見方」には、メリットが多いのです。
なお、このスレは自由討論の場です。どなたかがされた投稿に対し、私が反応する場ではありません。そうではなく、ここは「不特定多数 対 不特定多数」の意見交換の場です。みなさんご自由に、たがいに発言なさってください。
では建設的で生産的な議論をしましょう。
書込番号:12483597
![]() 4点
4点
みなさん、こんばんは。
適当に論点を出してみます。それぞれの論点にもし何か感想やご意見があれば、みなさんご自由に書き込んでください。まず逸品館・清原裕介氏の文章を題材にします。
--------------------------
■「iPod /PC /リッピングソフト音質比較テスト」
http://www.ippinkan.com/i-pod_pc_net_audio.htm
一部のマニアは、CDのデーターを取り込むとき、使用するドライブや外付けドライブの場合は接続ケーブルで音が変わると言いますが、私の今までの経験では、顕著に音が変わったという記憶はありません。(中略)個人的には取り込みのハードウェアに関してはさほど神経質になる必要はないと考えます。
--------------------------
以上、ドライブによる顕著な音の違いはない、とされています。ところが一方、ときどき私も拝読している以下のブログ管理者の方は、「本当に変わるのか?」と疑問を持ちながらPlextor Premium2を試したところ、音像の定位その他が変わったといいます。
----------------------------
■PCオーディオお試し その弐 − Plextor Premium2(個人主義)
http://hei30per.blog34.fc2.com/blog-entry-255.html
さて、「LaShell Griffin / Free」と「綾戸智絵 / LIVE!」をリッピングしたところで、以前内蔵CDドライブでリッピングしたWAVデータと比較して聴いてみよう。(中略)
次にLaShell。前奏部での違いは分からない。しかし、ボーカルが違った。LaShellの口が15cmほど上がったのだ。高域の成分が増え、中域にまとわりついていた音の成分が消えた。結果として、LaShellの声は清らかに澄んで、少しだけ若返ったように感じる。おーっ、前言撤回。変わるんだー。
-----------------------------
意見が食い違っているように見えますが、これについて何かご意見のある方はおられますか? さて引き続き、また逸品館・清原裕介氏の分析です。
-----------------------------
■「iPod /PC /リッピングソフト音質比較テスト」
http://www.ippinkan.com/i-pod_pc_net_audio.htm
ハードウェアと同じく取り込みソフトウェアーによる音の違いも、iPodと3種類のヘッドホン出力の差よりも遙かに小さく、ほとんど有意義な差はないと思われます。
取り込み速度やエラー訂正設定のあるなしでも音はほとんど変わらず、使い勝手の良いソフトでCDをリッピングすれば十分な音質でデーターが取り込めると考えられます。
-----------------------------
以上、リッピングソフトによる音の違いはほとんどないとされています。ただエラー訂正設定の有無に関していえば、エラー訂正する必要のある事態が生じたときにはそれにより音の違いが発生するように思いますが、どうなんでしょうか? そして非常に興味を引かれたのが以下のくだりです。
-----------------------------
■「iPod /PC /リッピングソフト音質比較テスト」
http://www.ippinkan.com/i-pod_pc_net_audio.htm
Windows XPでは「カーネルミキサー」が悪者にされてますが、少なくとも「音量を最大(音を小さくするとデジタル領域で音質劣化が起きる)」にして聞く限り、音は変わりますが大きな悪影響はないと判断しています。
また、カーネルミキサーをバイパスする/しないと、ファイルを圧縮する/しないの音質変化の傾向はよく似ていて、どちらも「理論的に音の純度を上げる=データの純度を上げる」ほど、「音がバラバラに分解されて、聞き疲れる傾向が強く」感じられました。
-----------------------------
PCオーディオにおいて、Windows XP環境下ではカーネルミキサーをバイパスさせることがセオリーとして必須であるかのように語られていますが、氏はあっさり「大きな悪影響はない」とされています。
一方、それ以上に興味を引かれるのが下段のくだりです。要約すれば、「データの純度を上げるほど音がバラバラに分解され、聴き疲れる音になる」という分析です。これを単純に解釈すれば、(1)データの純度が上がれば各楽器それぞれの分離感がよくなる、(2)データの純度が上がれば聴き疲れる、となります。
まず「聴き疲れる」というのは多分に主観的な要素なので、あまり意識しても意味はないと思います(なぜそういう音が聴き疲れるのか? 氏の音の好みの傾向からおよその察しはついていますが、それは本題ではないので割愛します)。
で、(1)と(2)から想像すると……世間一般に「よい音だ」とされている音ほど、分離感や解像度の高い「クラシック向きの音である」という推測がひとつ成り立ちます。ピュアオーディオの世界では音楽的にはクラシックが多数派ですから、単に「よい音」といえばそれはすなわち「クラシック向きの音」を指す、ということです。
一方、たとえばハードロックであれば、分離感や解像度はクラシックほど問題にならず、すなわちデータの圧縮に関してもクラシックほど問題にならない、という仮説が成り立ちます。
このへんを詳述するとものすごく長くなるので、説明は割愛します。ひとつみなさんにご提案するとすれば、「単に『いい音だ』という他人の文言はうのみにせず、『自分のよく聴く音楽が生きる音なのかどうか?』に最大の注意を払いましょう、ということになります。長くなったので、ひとまずこのへんで。
書込番号:12485413
![]() 1点
1点
まず、この手の議論で、誰と言わず聞く前の段階で『変わる』または『変わらない』の仮定を作って聞く態度は間違っています。
聞く前は常に『変わるのか、それとも変わらないのか』というニュートラルな立場で聞くことが大切です。何れかに偏った期待を無くして検証をすべきです。
そして1番まずいのが、聞きもしないで『変わる』ないし『変わらない』と発言してしまうことです。
そして、『変わる派』『変わらない派』何れかに属する人間が存在するという(その二種類しかいないという)認識自体が誤りです。
聞く前に取るべき態度は『変わるか、それとも変わらないか?』です。したがって『変わる派』はケース次第で次の瞬間即変わらない派になりえ、逆に『変わらない派』は即変わる派になりえます。
つまり掲示板上に絶対的な変わる派変わらない派は実在せず、実際に居るのは次のような人であるということになります。
1・試しもしないで変わらないと言う人
2・試しもしないで変わると言う人
3・試した上変わらないと感じた人
4・試した上変わると感じた人
1と2は論外です。試しもしないで言っていることは何の信憑性もありません。
3と4はさらに2種類に派生します。
甲・あらゆる場面において変わるないし変わらないと言う人
乙・ある場面は変わるがある場面は変わらないと言う人
甲は実際の試行があるとは言え、思い込みがエスカレートし客観性を欠いている可能性があります、変わる或いは変わらないという結論が先にありその思い込みにしたがって状況を決め付けている可能性があります。乙の方が上記ニュートラルな意識から離れずに検証した可能性の高いことを示し、信憑性は乙のが高いです。
絶対的変わる派、絶対的変わらない派、がもし居たとしたら、その言うことは間違いである可能性が高いです。
信憑性のある発言は、3ないし4の乙タイプの発言をする人ですね。Dyna氏はそれに該当しますから私はその音感想をある程度参考にしています。
書込番号:12485498
![]() 3点
3点
Dyna-udiaさん こんにちわ。
忙しい時間の中、大変に長い文章での問題提起ご苦労様です(嫌みで言っている訳じゃないですからね)
個人的には、音楽やオーディオは生活や心を豊かにする物だと思っていますので、正直な話、私自身には小難しい理論が理屈なんていらないしあまり必要ないと思います。
本日、ONKYOの試聴会に行った時、音は非常に気に入りましたが、試聴会終了後、一人のお客さんがメーカーの担当者に「アンプにDACを内蔵させたらノイズが入ってどったらこうとか」、そんな機械の内部的な話を永延と話し出して自分の主張を営業の担当者に認めさせたいような感じで小難しい話していました。この人は、自分の知識をひけらかしたいだけで、オーディオは音楽を聴くものなのに、オーディオでなにを聞いているのだろうと思いました。ノイズなんか機械内部だけじゃなく電源から入ってくるしそれを言い始めたキリがないと思います。
音楽は感性で聴くもの物であり、科学的数値や理論なんかと別物だと思うのですが、どうも人によっては頭で理屈で聞いている人も少なからずいるのだと、今日の試聴会に行って思った次第です。
私自身は、電線で音は変わると思っています。ただ、音が変わるといっても良い方向に変わると思う人もいるみたいですが、プラスに変わる場合もあればマイナス側にも変わると思っています。
それと変わると言っても例えば、ONKYOのアンプに電源コードを変えたらYAMAHAの音になるとか、DENONの音になるとか劇的な変化はなくあくまでもスパイス、補強的なイメージでしょうか。
そういう意味では本来のオーディオ機器のキャラクターの音が変わらないといっても間違いではないでしょけど、私が音が変わるという表現ではなくオーディオの本来の性能を引き出すため、音を補強すると言ったほうがイメージが的確な気がします。
ちょっと支離滅裂な文章になりすぎましたが、どんな評判がよくても、高額な機器でも、技術的に優れていても私個人が気に入るかどうかだと思います。だからDyna-udiaさんがいつも言うように試聴は大事ですね。
最後は、物凄く主観的な意見になってしまってすみません。
書込番号:12485563
![]() 3点
3点
air89765さん、今晩は。
言われることは、よく分かるのですが、実際にはもう少しややこしい場面があるのではないでしょうか?
(試さないで、「変わる」「変わらない」を頑固に主張するのは、確かに困り者ですね。
ただ、「理論上では……なんだけれど」と言う意見くらいは、良いかなと言う気はしますが…(あくまでも理論上で、実際は違うかも…と言う意見なら))
問題は、「常に変わる(もしくは変わらない)と言う人」と「場面によって変わる場合と変わらない場合があるという人」なんですが、その信憑性について、簡単に切り分けられるのどうか?
「常に変わる」と主張する、の極端な例を書きますと、
1. 違う曲の入っているCDを再生すると、音が変わる。
2. 違うヘッドホン(違う機種)で聴くと、音が変わる。
と言うのも考えられます。
(私の場合、上の2つは、音が変わるかどうか聞かれたら、音は変わると答えると思います)
この場合だと、「場合によって変わったり変わらなかったりする」、という人の方が信憑性が高いと言って良いのかどうか?
更に、議論になりそうなことだと、
3. 違うCDドライブで再生すると、音が変わる。(PCオーディオで)
4. 違うハードディスクで再生すると、音が変わる。
5. USB-DACのUSBケーブルを変えると、音が変わる。
6. USBケーブルに付いた汚れを落とすと、音が変わる。
……
(こっちは、どうかな?3〜5は経験ありますが…)
想像力が貧困なので、あまり良い例が出てこないんですが、様々なレベルのことがあるので、あまり簡単には切り分けられない気がします。
air89765さんが言われたいことは、分かるのですが、文章にして、簡単に○と×に分けてしまうと、ちょっと違う気がします。
もう少し、複雑な事柄ではないでしょうか?
私も、どうなんだといわれると…上手くかけないのですが、その人の姿勢みたいなものが重要な気がします。
書込番号:12485890
![]() 0点
0点
こんばんは
本腰入ってますね(笑)
変わると言われて立証されてても、自分の環境・耳で分からなければ買う価値が無いので
私は、耳で聴くしか意味が無い派です
私は、ラインケーブル・スピーカーケーブル・電源ケーブル・USBケーブルでの違いはありました
(PCオーディオで、総額35万ほどのシステムです)
ラインケーブルが最初に感じたと言うか試した物で、掲示板なんてなく
情報と言えばオーディオ雑誌や店の方の意見位しか無かった頃です
昔に頑張って買ったアンプ(30数万)を少しでも良い音にしたいと、1000円程度のケーブルから
3万台の短いケーブルへ変更しました 雑誌などを見てると素晴らしい評価で
さぞかし感動するような変化があるのと、((o( ̄ー ̄)o)) ワクワクしながら変更
・・・・・あれ? 何か変わったのかな???(^^;;;;;;;
というレベルで、30分位まるでテストのように聞いて、やっと あぁここの響きが
まろやかになってるやとのレベル、、、、、そこからは高価なケーブルは買いませんでした
最近、オーディオ熱が再発したので、ではPCオーディオをしてみようと
スピーカー、アンプ、DACを購入し色々見てると、ラインケーブルは変化が少ないとの事
ふむむ、それなら物は試しで電源ケーブル変えてみようと
大して期待してませんでしたが、変化があるか知りたい為に、2万台のケーブルを買ってみました
結果は、、、思ったより変わりました あれっ締まりは良いけど低音減った
ちょっとスッキリしすぎでない・・・(^^;
自分の耳はあまり信用できないので、気分の違う日や、夏冬、時間など変えて比べましたが
やっぱり違いましたので、電源ケーブルって変わるんだな〜と体感しました。
味をしめて、スピーカーケーブルも変えようと思いましたが、これは付け替えるのが面倒・・・
ということで、セレクタを2つ買って切り替えだけでテスト出来るようにと、あほな買い物を
ケーブルは1m1000円未満の4種類買ってみて試しましたが、これも変化はありました
(ベルデン、カナレ、ゴッサム、AETの4つ)
ただ価格帯が同じ位のためか、電源ケーブル程の違いは感じませんでした
ある日誰かに変えられてても、ゴッサム以外は分かるか分からないかレベル
(ゴッサムは解像度は良いのですが、なんかキンつく部分があったので判り易かったです)
最後にUSBケーブルですが、デジタルを出力するだけの物で、一番違いが少ないだろうと思ってましたが
私の環境ではスピーカーケーブル(同一価格帯)よりも有りましたので
これは、ちょっとびっくりで嬉しい誤算ではありましたが、色々買う羽目になり・・・(;´д`)
リッピング時についての音の変化ですが、PCオーディオのシステムがまだまだなのかも知れませんが
私は感じれた事は無いです。
音質比較デストですが、私も逸品館さんのレビューを前に読みましたが
foobar2000については、同じ様にXPで試したときには同じ様にやや篭ってる印象は受けました
ただ、機器が同じ(せめてOSだけでも)でないと、なんとも言えないのではないかなと
後、Frieve Audioなんかのテストもされてないので、逸品館さんの方では
PCからの部分に比べて、PC内部側のチェックやテストは、まだまだでは無いのかな?との
印象を受けました。
長くなりすぎて申し訳ありません <(_ _)>
このスレで、本当に変わるの?と思われる方が増えて視聴され、違いを体感された方が出てきて
需要が増えてケーブル類が少しでも安くなってくれると良いなと思います ^^
書込番号:12486360
![]() 4点
4点
どうも、お疲れ様です -> トピ主殿。
さて、ここのボードにも時折現れる「ケーブルで音は変わらない。CDメディアで音は変わらない。アンプでも音は変わらない。ああ変わらないったら変わらない」ということを声高に訴える御仁とその腰巾着達の言い分を聞いてみると、共通していることがひとつあります。
それは、誰も「音が変わる(あるいは、変わらない)」ということを医学的・生理学的に検証しようとしていないことです。
オーディオシステムにおいて「音が変わる(あるいは、変わらない)」ということを認知するのは測定器ではないです。それは人間の耳であるはずです。なぜなら、オーディオシステムのユーザーは一般の音楽ファンだからです。機械ではありません。
AというアンプとBというアンプは周波数特性が違うから音も異なる・・・・という言い方はよくされますけど、ならばどうして周波数特性が変わると音が変わると感じられるのか、どういう聴覚(脳)のメカニズムでどのように「音が変わる」と知覚できるのか・・・・といったことまで突っ込んで考察しないと、「音が変わったのどうの」という意見は(厳密に言えば)提示出来ないわけです。
たとえば、周波数特性やアンプのダンピングファクターやジッター値が変わらないから音も変わらない、これぞ「科学的な考察だぁ!」と決めつけるのは・・・・実はちっとも「科学的」ではないのです。そんなのは音楽信号のリリース側だけの精査に過ぎない。受け手側のリスナーはどうなのかを検証しないと、「音が変わる(あるいは、変わらない)」かどうかは「科学的に」結論付けられません。
いずれにしろ、音も聴かずに「音が変わる(あるいは、変わらない)」と言い張る連中は、視野の狭い夜郎自大な人間と言うしかないでしょうな。
書込番号:12487182
![]() 5点
5点
ケーブルに拠って音が変わるのは体験上判ります(電源ケーブルは判りませんでした)が、ケーブルで好みの音を造ってる方々は、聴く音楽のジャンル毎にケーブルの差し替えもされてるのかなと ふと疑問に思いましたが、多分されてるのでしょうね。
書込番号:12487384
![]() 5点
5点
変わる、変わらないと以前に変わっても変化が認識出来ない場合もあるかなと思います。
どう言う事かというと、機器のキャラクターが強い場合、変化率が小さいケーブルの場合は変化が感じにくいと思います。逆に癖が少ない機器の場合、ケーブル交換しただけで音の変化が出やすいため非常に理解しやすいと思います。ベルキンやゾノトーンのケーブルを交換した時、雑誌のレビュー通り過ぎて評論家の感想は的確なんだと思いました。
変わらない派の人には、自分の機器が色付けが濃いため、ケーブル類のキャラクターが認識出来ないのもあるのかなと思います。
元・副会長さん ご無沙汰してます。
>声高に訴える御仁とその腰巾着達の言い分を聞いてみると
>視野の狭い夜郎自大な人間と言うしかないでしょうな。
あまり刺激的な意見は別の所で揉めますので、もう少しオブラードに包んで仰った方が的確な意見だと思いますが誤解を招いてしまうと思いますよ。
書込番号:12487518
![]() 1点
1点
>問題は、「常に変わる(もしくは変わらない)と言う人」と「場面によって変わる
>場合と変わらない場合があるという人」なんですが、その信憑性について、
>簡単に切り分けられるのどうか?
baldarfinさんこんにちは。
あ、どうもすいません。前記した
>>甲・あらゆる場面において変わるないし変わらないと言う人
>>乙・ある場面は変わるがある場面は変わらないと言う人
という分け方をしたものですが、『音が「変わる」または音が「変わらない」
という二つに感想が二分するケース』・・・という変わる変わらない議論
が存在する状況、という大前提においての考察です。
書き方が悪くすいません。
例→デジタルケーブル・CD-Rメディア・デジタルトランスポート・電源ケーブル等の要素で音が変わるか
誰もが「違う」と認識することが出来、意見が二分しないものについては
ここでは言及していない、と解釈していただけると嬉しいです。
例→ヘッドホンやスピーカーを変えると音が変わる・曲が違えば音は違う・歌手が違えば声が違う、など。
この「甲・あらゆる場面において変わるないし変わらないと言う人」とは、
「私はデジタルケーブルAとBで違いを感じた。だからCとDでも違いを感じるはずだ。」
「私は環境Aでデジタルケーブルの違いを感じた。だから環境BでもCでもDでも違いはあるに決まってる」
「私がA・B・Cという試行をしたら音が変わった。だからD〜Zあらゆることで音は変わるのだ」等のように決めつけることや、
「私はCD-R甲とCD-R乙で違いを感じなかった。だからCD-R丙とCD-R丁でも違いを感じないに違いない」
「私は環境AでCD-Rの音違いを感じなかった。だから環境BでもCでもDでも違いは無い」
「私は電源ケーブルの音違いなんて感じない。だから他人も感じないはずだし感じることは思い込みだ」
のように考えてしまうことによって『音は変わるのか、それとも変わらないのか』
というニュートラルな視点で聴くことが出来なくなってしまった状態を指します。
ある環境Aでデジタルケーブルの音違いを感じてもまた別の環境Bでは「違わないかもしれない」。
またある環境CでCD-Rの音違いがわからなくても、ある環境DではCD-Rの「音違いはわかるかもしれない」。
この「かもしれない」を常に、常に疑ってかかり、
今までの結果に基づいて次の結果を決めつけて試行してはいけない、ということです。
ある時点で「音は変わらない」「音は変わる」の何れかに偏った印象を強く持つことによって、
『音は変わるのか、それとも変わらないのか』というニュートラルな視点を持つことが出来なくなってしまいますと、
判断に偏り・間違いが生じて、そのことで”真相”から遠ざかってしまうことを懸念したものです。
「乙・ある場面は変わるがある場面は変わらないと言う人」というのはこのニュートラルな
視点を失うことなく試行し続けている、という事実を示すもので、
このような「客観性」を失わない人の発言は、ある程度参考にするに値する、と思うものです。
書込番号:12487573
![]() 1点
1点
論点の一つに、客観的な意見、主観的な意見をあげてますが、自分の持ってるオーディオセットの音は、耳慣れたものであり、
日夜自分の好みに合うようにセッティングやケーブルを変えて作っている自分だけの宇宙です。
自分なりに客観的に評価する事はできなくはないですが、少なからずそこには思い入れという主観が入ります。
では、ショップの試聴はどうかと言うと、特別な場合を除けば、店頭にある商品から選んだセットで聴くしかないので、
微妙な違いなど意味がないと思っています。
ですが色んな組み合わせで聴いてみると中に明らかに自分が好きな音を出すものがあって、
それはちょっとした違いなんじゃなく、ぱっと聴きで良いと思えます。
良いとか合うとかいうのは、その人の音楽やオーディオとのつきあいで変わってくるものですから、
試聴による評価は、その人の主観的な意見だと思っています。
但し、例外があって、オーディオ歴が長く、色んなスピーカーやアンプやCDPを使用した経験があり、
評価軸をしっかり持っているベテランの意見は客観性があって傾聴に値します。
この掲示板ではそういったベテランの方が返信していただけるので、非常に参考になります。
私も、全く何も知らないところから、この掲示板でのアドバイスを頼りに試聴を繰り返しました。
振り返ってみると、頂いたアドバイスは、的外れなものもあり、ベテランと言えども、偏った主観的な意見を
書き込まれることはあると認識しています。
はっきり言えば、今では、たとえベテランの意見でも参考にとどめ、実際に聴いてみて判断することが出来るようになっています。
ですが、初心者はそうは行きません。なにもわからず質問を書いてきているのですから、
初心者が「主観的な意見を下さい」、と書き込んだ時に「主観的な意見は無意味」と切り捨てるのは言い過ぎだと感じます。
次にケーブルによる違いですが、変わるか変わらないかは置いて、
オーディオセットのバランスを崩す原因になることが怖くて私はまだ手を出せません。
仮に違いがあったとしても、アンプを変えるほどの大きな違いがあるとは思えず、
それと引き替えにバランスを崩すくらいなら、オカルトの1つと割り切って手を出さないのも一つの行き方ではないでしょうか。
ここで言うバランスは、音像定位、音場、SN、低音の量感、などを指しています。
ですが、毎日自分のオーディオの音を聴いてると飽きてくるのも事実。
そこで遊んでみようと言うことでケーブルを変えて、微妙な変化を楽しむことは有りだと思います。
数値的な違いの無い中で音が変わることは、あげておられる文献の他にもあって、
音が変わる派の意見も変わらない派の意見もどちらも正しいと言うのが結論ではなかったでしょうか。
少なくとも、機器製作者や技術者、あるいはCD製作者などのプロは、数値で性能をきちんと評価してもらわないと困ります。
一方、我々アマチュアは何でも有りです。勿論ケーブルで音は変わります。
なんたって主観ですから。
書込番号:12487674
![]() 3点
3点
客観的な耳は持ち合わせてないので、
ROM専門でフムフム。
私はオカルトでも違いを認識したら買ってしまいます。(汗
書込番号:12488047
![]() 1点
1点
■air89765さん
>1番まずいのが、聞きもしないで『変わる』ないし『変わらない』と発言してしまうことです。
これに関しては、(baldarfinさんもお書きになっていますが)、「理論的には『変わる/変わらない』だろう」などと予想・分析するのはいいと思うんです。自分の知らない理論があるならば知りたいし、知的好奇心も覚えます。
ただこの論法の延長線上に、むずかしいケースが発生するのも事実です。それは実際に耳で聴いたら音が変化しているのに、その音の変化が理論で科学的・技術的に体系付けられてない場合です。電源ケーブルなどは典型です。
この場合、その音の変化は実態的には「仮定の段階」にあり、「実験・観測に基づく科学的な法則化を待つ過程にある」ということになります(形の上では)。すなわちここで、科学的な裏付けを重んじる「変わらない」派と、実際に耳で聴いた結果を重視する「変わる」派に分かれてしまいます。
片方は(1)「科学的・技術的に理論付けられてないから変わらないはずだ」と頑強に主張し、もう片方は(2)「実際に耳で聴いたら音の変化はあるのだ。なぜ自分で聴いてみないのか?」となります。この対立の構図が固定され、永遠に交わることがありません(笑)
>『変わる派』『変わらない派』何れかに属する人間が存在するという(その二種類しかいないという)認識自体が誤りです。
対象になるアイテム(ケーブル、CD-Rの焼き方など)が変われば当然、「変わる・変わらない」も異なるはずです。ですが実態は、「すべてのアイテムで音が変わる」とおっしゃるように見える方と、「すべてのアイテムで音は変わらない」とおっしゃるように見える方の二種類に二分されてる感じですね。
で、なぜそんなふうに偏るのか? という人間のメンタリティを分析したブログ記事を、実はすでに書いてあるのですが、気が向いたらブログの方か、こっちの掲示板にアップするつもりです。
>ある環境Aでデジタルケーブルの音違いを感じてもまた別の環境Bでは「違わないかもしれない」。
>またある環境CでCD-Rの音違いがわからなくても、ある環境DではCD-Rの「音違いはわかるかもしれない」。
>この「かもしれない」を常に、常に疑ってかかり、
>今までの結果に基づいて次の結果を決めつけて試行してはいけない、ということです。
「過度の一般化」は誤った結論につながる可能性がある、ということですね。たとえば任意の環境下と機種で一度だけ試してみて音が変わらなかった時点で、
「電源ケーブルで音は変わらない」
=あらゆる電源ケーブルは、すべての環境下で音が変わらない(過度の一般化)
と結論付けると誤りになる可能性がある、と。興味深いです。確か過去にばうさんが、以下のような発言をされていた記憶があります。
「音が変わらないことを自分で試して証明しろ、といっても、一機種試しただけでは終わらない。変わりませんでした、と発表しても、変わる派から『この機種は試してないのか?』、『次はこれを試せ』と注文をつけ続けられて終わりがない」
でもこれって裏を返せば、音が変わることを聴き分けしやすい電源ケーブルを一機種試せば終わる話ですよね。たとえば我が家にあるキンバーケーブルのPK-10とか、(私は持ってないですが、たぶん変化がわかりやすそうな)オヤイデのTUNAMI系とか。
これらのうち一機種で音の変化を確認できれば、少なくとも「電源ケーブルで音が変わる」ことは立証されますね。「あらゆる電源ケーブルは、すべての環境下で音が変わる」などと過度に一般化した言い方はできませんが、実際に「任意の機種は任意の環境で音が変わった」わけですから。つまりこの実験では少なくとも、「電源ケーブルで音は変わらない」という言説は否定されることになりますね。
書込番号:12489854
![]() 1点
1点
前スレは、[12132755]
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12132755/
です。
前スレの冒頭と同じ内容を転記します。
オーディオ関連の掲示板では、CDのメディアの種類やCD-Rの焼き方を工夫することでCDプレーヤーから出てくる音が良くなる、という話題を良く見かけます。
しかし、そのような工夫をしなくてもCDプレーヤーから出てくる音はすでに良い状態なのです。すなわち、メディアの種類や焼き方を工夫することと、CDプレーヤーから出てくる音の良さとの間に、因果関係はありません。
![]() 1点
1点
やっぱりお地蔵さんアイコンじゃないと調子狂うわねえ…
認識を合わせておいたほうが見通しがよいと思うので書いてみます。みなさん、特に変わる派のみなさんは、CDをCD-Rに複製したときに、バイナリデータは変わるとお考えでしょうか?…気にされてないかたが多いような感じはしますが。
その筋のかたには周知の事実と思いますが、少なくともネット上では「変わらない」という認識が主流です。例えばOISUさんからご紹介のあったAV Watchの藤本氏の実験ではバイナリは一致していますし、個人のブログ等でも同様です。もちろんC1エラー程度はCD原盤でも普通に生じているようなので、ピットレベルで一致しているということではなく、CIRC訂正後の.wavでは一致している、という意味です。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20010409/dal05.htm (藤本氏によるバイナリコンペア)
前スレでは、Be-myersさんやespoir_gameさんは、ご経験から変わるとお考えのようですね。世の中には粗悪なメディアもあるようですし、粗雑な扱いやドライブの劣化等、条件によってはデータ化けが生じて当然だと思いますが、そうした「事故」のような場合を除けば、普通は変わらないようです。「普通」っていうのは、オーディオファンならメディアや機器の選択や扱いに多少の気配りはするでしょう…くらいの認識でいかがしょうか。
これについては私も試してみたことがあります。やりかたは基本的には藤本氏と同じで、CDからリップした.wavと、CD-DAイメージで複製したCD-Rからリップした.wavを、WaveCompare というフリーウェアで比較するという方法です(とても簡単です)。このソフトの作者は、先にair89765さんが紹介されているリンクと同じかたのようですね。DOSプロンプトから fc /b コマンドで比較したのでは一致しない理由も、このソフトのページに書いてあります。使用したPC、メディア、複製ソフト、リッピングソフト、はいずれもごく一般的なもので、オーディオグレードみたいなものではありません。書き込み速度は自動(16倍程度)です。で、今まで確認したのはCD数枚程度ですが、完全に一致しています。つまり、平凡な環境で何も考えずに複製しても、普通バイナリは一致するようです。
なお、リッピングしづらいCDがあるとのお話もありましたね。それだとダメかも知れませんが、それはCDの読み取りの問題であってCD-Rへの書き込みの話ではないですし、そういうケースがあまり多いようなら、読み取り機器が「普通」ではないかも知れません。
ただ、普通のCDPはPCのドライブと違って再生時にリトライをしないので、エラー訂正に失敗しやすいのかも知れませんね。redfoderaさんの主張がこれに当たると思います。しかし調べてみるとそう単純でもなく、むしろCDPのほうが良いのでは、という話もあります(一般論では語れないでしょうが)。二羽のウサギさんも[12166765]でそのようなことをおっしゃっていますが、実は私も似たような経験があります。なので、少なくともうちの環境では、バイナリ一致するようなCD(-R)なら(それが普通と思いますが)、CDPでエラー訂正に失敗すること(CUエラー)はまず無いだろうと想像しています。
それに、変わる派のかたの話では、音の変わり方は音場感だとか解像度だとか、全体の微妙な雰囲気に関わるもののようなので、CUエラーが原因だとすれば、CD一枚に数箇所みたいな話では説明がつかず、それが間断なく生じていると考えざるを得ませんが、これは世の中で言われている話(例えば中島平太郎氏の著述など)とはあまりに乖離していて不自然です。
そういえばプレク大好き!!さんはC1エラーなどの数を数える環境を持ってたと思うのでよく知ってるハズ…あれ、待てよ … ってことは 「0.1秒以内のブランク」みたいなものは殆ど発生していないことも知ってるハズだと思うけど、高品質CDスレでは「だまてん」してたのかしら。。
書込番号:12389108
![]() 3点
3点
旧スレでは新スレは無視!とのことで
こちらでは客観的な和んだ議論を期待したいです。
そもそもスレタイトルは「工夫しなくてもCDプレーヤーの音良い」なので、変わる派の方々はここでは否定派にあたります。
あまり荒らさないで欲しい限りです。
藤本氏の実験等参考にその他いろいろと調べた結果、
「バイナリは変わらない」
「ジッターの揺らぎは聴感上の音に影響はない」
「音が変わって聴こえるのはエラー訂正の際のサーボがDACに悪戯をしているのではないかという推論がある」
以上3つの結論が自分の中では有力になってきました。
変わる派の方がよく言う
音の密度、臨場感、立体感が違うというフレーズは
機器やメディアを変えた際のリスニングポイントのズレからによるものだと思っています。(10センチ顔をスピーカーに近づけ聴けば立体感が増して聴こえる等、リスニングポイントの違いが及ぼす聴こえ方の違いは大きいです。)
3番目のサーボ等の悪戯に関して、藤本氏やCDドライブメーカーの方もまだ主観の域をまだ超えておらず、謎のままです。(ちなみにメディアの違いによる音の差、自分の耳では違いが解った試しがないです)
変わると思う方々に聞きたいのですが
例えばDACとCDPを独立させた場合(CDPのデジタルアウトをアンプに接続)、サーボの影響は受けないので音は変わらないと思うのですが、それでも変わって聴こえるのでしょうか?
書込番号:12391151
![]() 2点
2点
>リスニングポイント
ヘッドホンでも違いが出る訳なので、リスニングポイントでは否定出来ませんので、まずこの説は消えます。
>DACとCDPを独立させた場合
わかりやすい例でPS2の光出力と10万クラスのCDPの光出力を、それなりのクラスのDACに繋いだ場合はわかりやすいです。PS2はかなりわかりやすい例ですから、いくら何でもこれならわかるでしょう、後は試すか試さないかの違いだけ。
>主観
結局、変わる変わらない、誰のいかなる判断も主観です。
何故なら音を受容する最終の器は外耳と内耳・蝸牛神経・聴覚野という聴覚器、それを判断するは大脳皮質連合野による主観的判断であることが厳然たる『客観的事実』だからです。
音判断の客観的基準は実在しません、誰のどのようなブラインドテストも、どこの誰がどうやるかだけの違いで、その人物自身の主観であることにはいかなる状況であれ違いはなく、主観以外の判断は存在しないのであり、主観を否定すれば音の判断それそのものが存在しないことになります。
書込番号:12392234
![]() 2点
2点
air89765さん
あいかわらずからみずらく困惑しております。
まずリスニングポイントの件について、
ヘッドホンにおいてリスニングポインは存在しません。あくまでもスピーカーでのチェックにおいての話です。
CDPの違いの話など誰もしていません。ここのスレはCD-Rの違いによるものです。
>主観的判断であることが厳然たる『客観的事実』だからです。
主観的判断=客観的事実
が聴覚においては成り立たないということ、既知の事実ではないでしょうか?(思い込み等)
>主観以外の判断は存在しない
いやデジタル(DACとCDPを独立させる実験)においてはバイナリチェックで違うか違わないかの客観的判断はできます。
例えば
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20010416/dal06.htm
の下の方に書いてあります。
もしくはdaw等にデータを取り込み2つのファイルのうち一つの位相を反転させる。そして同時に再生。データが同じなら音は打ち消しあって音は出ない。音が違えば違うであろう要素が残る。
このように主観以外の方法で音を比べる客観的判断は可能です。
最後に旧スレであなたこのスレをアホらしいとおっしゃっていました。ならばスルーすれば良いのではないでしょうか?もしくはスルーできないなにか理由があるのでしょうか?
ここからはair89765さんに言っているわけではないです。
メディアの違いで音が変わるか変わらないか、自分では聴き分けられませんが、実際は違うかもしれないし違わないかもしれない。この症例は現状の科学で完璧に解明されていないと思います。
よってここのスレにはとても意義を感じます。
否定派が「変わらない」と断定すると「文末に『思う』をつけろ!」等と大荒れ、理路整然としたばうさんの意見には「屁理屈という捨て台詞」おまけにアホ扱い。
このような発言をされる方々のオーディオ論は全く参考にならないですね。
書込番号:12393105
![]() 3点
3点
>まずリスニングポイントの件について、
>ヘッドホンにおいてリスニングポインは存在しません。
>あくまでもスピーカーでのチェックにおいての話です。
|変わる派の方がよく言う
|音の密度、臨場感、立体感が違うというフレーズは
|機器やメディアを変えた際のリスニングポイントの
|ズレからによるものだと思っています。
と書いていらっしゃいます。
これは、”CD-Rの音が変わって聴こえる、というのは、
リスニングポイントのズレによるものである”という説でしょう。
それに対して
>>ヘッドホンでも違いが出る訳なので、リスニングポイントでは否定出来ませんので、
>>まずこの説は消えます。
のように、「リスニングポイントの存在しないヘッドホンでもCD-Rのメディア毎の
音質違いは出て来る」と言っている訳です。
だから「リスニングポイントの無いヘッドホンでもCD-R毎のメディアの音違いは
出て来るということは、CD-Rの音が変わって聴こえる、というのは、
リスニングポイントのズレによるという説は間違いではないか?」ということです。
つまり、CD-Rの音が変わって聴こえることはリスニングポイント以外の、
ヘッドホンとスピーカーに共通した別の要因によるものであろう、ということです。
リスニングポイントによるものであれば、
「音の密度、臨場感、立体感が違う」などの印象が
スピーカー固有に出て来なければおかしいはずですから。
>CDPの違いの話など誰もしていません。ここのスレはCD-Rの違いによるものです。
すいませんこれは当方の読み違いでした、この件については未検証でした。
前記は取り消します、大変失礼致しました。
>バイナリチェックで違うか違わないかの客観的判断はできます。
それが一致すると音が同じに聴こえるかどうかの証明は出来ませんから、
結局そこから先の音判断は主観になります。いかなる客観的データを示しても
結局最終段階は主観による音判断になります、変わらないとする判断も全て主観です。
>最後に旧スレであなたこのスレをアホらしいとおっしゃっていました。
>ならばスルーすれば良いのではないでしょうか?
アホらしいと言ったのは、検証することなしに理論のみで否定するスレ主の
主張(によって作ったスレ)のことです。それ以外の人の意見の全てがアホらしい訳ではありません。
>理路整然としたばうさんの意見には
検証の無い空想物語を理路整然とは呼びません。
理路整然とは「話や議論などの筋道がよく整っている様子」です。
彼は「実験と理論」を主張しています。それなのにその前者を欠落させ
机上の空論だけの二枚舌では筋道を通したことになりません。
書込番号:12393381
![]() 2点
2点
みなさん、こんにちは。
このスレのお題は「メディアの種類や焼き方による音の違い」なので私は変わる派でも変わらない派でもないのですが、議論を整理するために少し茶々を入れます。
電源ケーブルでも何でもそうなのですが、「変わらない派」の方々の論法は大雑把に言って以下の通りです。
(1)耳で聴いたら「そう聴こえた」では単なる主観だ。それでは意味がない。
(2)音の違いを主観でなく客観化できなければ、音が変わったことの証明にはならない。
(3)「変わる派」は、音の変化を客観化できてない。ゆえに音は変わらない。
過去に出た議論を総合すると、上記(2)の「客観化」とは、(A)計測機器などによるデータ化・数値化、を指すようです。(この変わらない派の言説には落とし穴(※1)があるのですが後述します)
さて根本的な疑問ですが、客観化=(A)だとするには、当然、「音の変化はすべてデータ化できる」ことが大前提としてなければなりません。でなければ「音は実際に変わっているが、『この種の音の変化』に限ってはデータ化できません」みたいなケースが出てくるからです。これでは何の証明にもなりません。
であれば例えば、「音に艶が出た」ことは、どんなデータで表すことができるのでしょうか? また「音に躍動感が出た」ことは、どんなデータで表記されるのですか? 枚挙にいとまがありませんが、このほか「音の密度感」はいかなるデータで書き表されるのですか?
逆に「躍動感」はデータや数値では表せません、というならば、「音に躍動感が出た」ことは客観化できない、って話になります。すなわち躍動感は、「耳で聴いて峻別するしか方法がない」って話です。
あっというまに結論が出ましたが、変わらない派の唱える「客観化」なるものがいかに曖昧で実体がないか、ということです。こんなテキトーな概念に基づいて「音は変わらない」と断言するなんて、とんでもない話ですね(笑)
もうひとつ、上のほうで「変わらない派の落とし穴(※1)」と書いたことについて説明します。変わらない派は「客観化」=データ化・数値化であるかのように喧伝しますが、「耳によるヒアリングの積み上げ」も客観化のひとつである、ことを見逃しています。
それはどういうことか?
(a)たとえばAさんが聴いても、Bさんが聴いても、Cさんが聴いても、Dさんが聴いても、Eさんが聴いても、みな同じように「躍動感がある」と感じるならば、この「躍動感がある」という体感は十分に「確からしい」ということです。(マーケティングの世界では、こんなことは常識です)
(b)かつ、たとえば「マランツのアンプは高域に艶がある」のように、何年にもわたって無数のユーザがヒアリングしてきた結果、すでに定着している既成事実は、十分に「確からしい」ということです。
前者(a)は数(人数)による客観化であり、後者(b)は年数(時間の経過)による客観化です。「変わらない派」はあたかもデータ化・数値化だけが客観化であるかのように言いますが、データ化・数値化以外の客観化の方法を見逃していては、そもそも議論が成り立ちません。
【結論】
耳で聴いた結果も、データの取り方次第で十分に「客観化」だといえる。
書込番号:12393782
![]() 5点
5点
みなさん、こんにちは。
ひとつ補足します。
この種の議論になると主観、客観という言葉が乱用されますが、どうも「主観と客観」の意味を正確に理解されてない方が多いようです。そのひとつは、「Aさんという人間が自分で考えたり感じたりしたことは、すべてAさんの主観だ」という誤解です。
そうではなく、人間は「客観的にものを考える」ということができます。話をわかりやすくするため、具体例をあげます。
たとえばAさんが、デノンのアンプを所有しているとします。Aさんは我が子かわいさで、自分のアンプには欠点がないと感じます。「躍動感があり、パンチがあって、低音もたくさん出て……」。で、第三者がAさんに「デノンのアンプは低音がボケるよね?」というと、Aさんはムキになって反論します。このときAさんは我が子かわいさで、「客観的にものを考える」ことができていません。すなわちAさんの思考はきわめて主観的です。
ところが一方、同じようにデノンのアンプを所有しているBさんは、デノンのアンプの長所と短所を客観的に仕分けして考えることができます。我が子かわいさで感情(主観)に流され、「デノンのアンプはすべてすばらしい」、「欠点などない」などとは考えません。このときBさんの思考は十分に「客観的である」といえます。
すなわち一人の人間が考えたこと=「すべて主観である」とする考えは、まちがいです。一人の人間が「客観的にものを考える」ことは十分に可能です。
書込番号:12393833
![]() 5点
5点
air89765さん
あまり取り乱さないで下さいませ。
リスニングポイントの話、
もしかしてあなたがブラインドテストで聴き分けられたことからのお話でしょうか?
だとしたやっと理解できました。
これに関しては、air89765さんはあまりデジタルにはお強くなさそうですし、
ブラインドテストとしての信憑性がいろいろな意味でなく思うので私は参考にしていません。
>それが一致すると音が同じに聴こえるかどうかの証明は出来ませんから
12393105のリンク先をもう一度お読みください。
air89765さんには勉強になりますよ!
>アホらしいと言ったのは、検証することなしに理論のみで否定するスレ主の
主張(によって作ったスレ)のことです。それ以外の人の意見の全てがアホらしい訳ではありません。
↑
矛盾していませんでしょうか?
↓
>スレを引き継いでまで話し続ける価値ある話題じゃ無いんだよね、あほらしくて。もうこの変わらないシリーズはいい加減おしまいで充分。
以後このような粘着性の強い「思い込み」の押しつけはスルーさせていただきます。
書込番号:12394373
![]() 2点
2点
OISU 様
こんばんは、私は取り乱しておりません。
OISUさんは、「客観化」ということを繰り返し主張されながらも、
ご自身は度々強い主観のみに基づいた早とちりの結論をなさってしまっております。
このような傾向が以前からあった為に、「理路整然」と論を述べて行く為にも、
またご自身のスタンダードにご自身が忠実であるという、意見としての客観性と信頼性を
高める為にも、もう一度ご自身のご意見を整理なさる作業をお勧めする次第でございます。
たとえば、
>あまり取り乱さないで下さいませ。
>ブラインドテストとしての信憑性がいろいろな意味でなく思うので私は参考にしていません。
この二つの文章はOISUさんが強い主観のみで語られる方だということを如実に示しております。
前者に関しては、まったくそのような客観性がございません。
”OISUさんが私の文章に対して持った印象・主観”がその全てであります。
後者に関しては、私のブラインドテストの信憑性が具体的にどのように低いのか、
OISUさんは客観的証拠を何もお示しになってはおりません。
私は、前スレにて具体的なブラインドテストのやり方を完全開示しました。
したがって、その内容が客観的にどのように間違っており、どのように
信憑性が無いのかを、正しいやり方を示してそれとの対比により示す
ことによる示すことは容易であります。これが「客観化」です。
その作業をなさらず、ただ主観的印象という感想を述べたのみで終わるようでは、
OISUさん自身の今まで主張されて来たことが信憑性が無かったことになります。
OISUさんは、「正しいブラインドテスト」という主観的印象を示し、
かつそのブラインドテストの客観的な正しさを何もお示しになっておりません。
その内容すらも開示していらっしゃいません。ただただ、ご自分の頭の中の主観で
ご自身のやり方は正しく、airのやり方は間違いであるとの盲信的主観にて全てを解釈なさり、
自分は正しくairは間違いと決め付け、書き綴っているに過ぎません。
リスニングポイントのOISUさんのご主張に関しても、
何の客観性もございません。
寧ろ私は、「ヘッドホンでもスピーカーでもCD-R違いは出る」
「したがって、リスニングポイント違いはCD-Rが違って聴こえることの根拠とはならない」
という「OISUさんにとっての客観性を示す」指摘をしたのです。
ところがOISUさんはその客観性を無視し、
「air89765さんはあまりデジタルにはお強くなさそうですし、
ブラインドテストとしての信憑性がいろいろな意味でなく思うので私は参考にしていません。」
というご自身の『主観』こそをその客観性に優先し、
そのような主観こそを最大の根拠としてそれを否定なさっているのです。
このようにOISUさんは、客観性が重要であると語りながらも、
その実は終始客観よりもご自分の強い主観的意見を優先する傾向にございます。
「ばう氏の意見が理路整然である」というOISUさんの主観的印象に関しても、
何らOISU様は客観性をお示しになっておりません。
ばうさんの意見がどうして理路整然であるのか、その客観的根拠をお示しください。
私は前記したように、どうしてばうさんの意見が理路整然では無いのか、
彼の意見の矛盾性を示すことによってそれが理路整然という言葉の意味に合致
しない事実を提示することで客観化を試みました。
OISUさんのご意見は、そのどれもがこのような客観性を欠いたものです。
もう一度、ご自身のご意見を整理なさり、「主観的意見ではなく客観的意見を述べるように」
というご自身のスタンダードにまずはご自身が忠実であられるように、
OISUさん自身のご意見の信頼性を高めてから発言されるといいと思います。
>矛盾していませんでしょうか?
矛盾しておりません。
このOISUさんの主観的意見に関して、何故矛盾ではないかという
客観性を示させていただきます。
私はこのように書いております
|スレを引き継いでまで話し続ける価値ある話題じゃ無いんだよね、
|あほらしくて。もうこの変わらないシリーズはいい加減おしまいで充分。
|アホらしいと言ったのは、検証することなしに理論のみで否定するスレ主の
|主張(によって作ったスレ)のことです。
私は、無検証で理論とか思い込みのみでスレを立て、妄想を述べることを
「あほらしい」と書き、そのようなシリーズはおしまいでいいと書いています。
つまり、そのような妄想によって新たにスレを立てる行為を否定しています。
そのばう氏のスレに書き込むそれ以外の人の意見には言及せず、
そして私が今回返答したのは(私があほらしいとした対象外の)OISU様の意見に対してであり、
そのような意見に対して話し続ける価値が無いなどとは私はどこにも書いておりません。
事実、当スレはばう氏の1のみでしたらスルーするつもりでした。
ところがその他の意見が投稿されたので、それに関して意見を述べさせていただいただけです。
よって、矛盾しておりません。
OISUさんはまたもや、どうして矛盾するという客観性を示しておられません。
>以後このような粘着性の強い「思い込み」の押しつけはスルーさせていただきます。
などのような主観的思い込みの典型例のような強い押し付けのみで相手の意見を強力に決めつける前に、
まずはご自身が「思い込み」のレベルから一つ上の客観性を常にお示しになることによって、
ご自分の主張に信頼性を持たせることが第一であると思います。
書込番号:12394743
![]() 2点
2点
>私は、前スレにて具体的なブラインドテストのやり方を完全開示しました。
>したがって、その内容が客観的にどのように間違っており、どのように
>信憑性が無いのかを、正しいやり方を示してそれとの対比により示す
>ことによる示すことは容易であります。これが「客観化」です。
上記、タイプミスです。
×正しいやり方を示してそれとの対比により示すことによる示すことは容易であります。
○正しいやり方を示して、それとの対比により示すことは容易であります。
の間違いです。
ここはタイプミスを直すだけでなく、前記の主張の中でも
重要項目と考えておる為に再度ピックアップ致しました。
「客観化」というOISUさん自身の主張に関して、OISU氏は
自ら発言した「正しいブラインドテスト」のやり方と、
「airのブラインドテストがどのうよ間違っているか」
という客観性を示さなければなりません。
# 「客観化」がOISUさんの主張なのですから
それなのに今までの段階では、OISUさんの主観が語られて来た形跡しかございません。
その「正しいブラインドテスト」と「間違ったブラインドテスト」が
どのようなものであるかが客観化された試しが、現段階ではありません。
「正しいブラインドテスト」と「間違ったブラインドテスト」があるとしたら、
それはどういうものであるのか、それは客観的にも参考になると思います。
書込番号:12394832
![]() 3点
3点
OISU殿、 air89765殿
お若いかたがた、元気があるのはよろしいが、ただの揚げ足の取り合いになっておるようじゃ。じじいには読み辛うてかなんわい。お題について整理されて、本筋に戻られてはいかがかと思うてな…。
まず、 air89765殿の「主観以外の判断は存在しない」は、それはそうなんじゃが…聴き分けができたと仰る御仁がおったとして、それが音響装置から出てくる音自体が変わっているせいなのか、それとも思い込みやら実験の不備やらのせいなのか、をなるたけ切り分けることがお題のひとつ、とじじいは思うてをる。
air89765殿はご自分では目隠し試験をされて納得されておるようじゃが、はたから見るとちと寂しいのう。また、 OISU殿、「信ぴょう性がないから参考にできない」など、頭ごなしの物言いもいくらかあるやに思いますぞ。air89765殿にどのような落ち度があるのじゃろうか?ご留意下され。信ぴょう性てなものは、おのずとにじみ出たりもするものでな…。
つぎに、air89765殿、貴殿がCDとCD-Rとを聴き分けられた環境では、CDP内のDACを使用しておるのかの?それとも別体のDACを使用しておるのかの?どんな接続だと差がわかりやすい(わかりづらい)か、ご存じかな?それがわかると、多少なりとも音質が変わる原因に近づけるかも知れんと思うてな。手間をかけてすまんが、教えてくだされ。
おふたかた、年寄りに免じてよろしゅうに。
# ばうさんもこれくらいキャラ変わりしてくれないとね〜。
書込番号:12395877
![]() 2点
2点
忘れようにも覚えられない、ウケました(笑)
かなり魅力的なキャラに仕上がっています。
さて、デジタル接続でDACに繋いで差がわかるのか…それともわからないか、検証してみます。先日のはCD内DACです。
私としては、そろそろいい加減『わからんかった』的な結果が出て欲しいなとすら思います。
いちいち音が変わると面倒だから嫌なんだ、実は(笑)
書込番号:12396217
![]() 1点
1点
皆さん、今晩は。
CD-Rに限らず、デジタルで記録してそれを再生する場合、音が変わるかどうかについてはいくつかのポイントがあると思います。
私自身の、頭の中の整理も兼ねて書いて置きます。
まず、デジタル信号に限ると、
1. バイナリが変化しないのかどうか。
2. ジッターの大きさがどれくらいか(問題になるのは、デジタル→アナログの部分)。
3. バイナリ、ジッター以外の何かの、音質にかかわる要素が存在するかどうか。
デジタル信号そのもの以外では、
4. サーボやエラー訂正等の動作をすることでの、電圧変動が、
(1) クロック回路に影響して、クロックがゆれる(ジッターが生じる)
(2) アナログ回路に影響して、音質に変化を起こす。
と言うようなものが考えられます。
1. バイナリについては、チェックするソフトがあるようですので、確認は可能ですね。
これが、変わっていれば、当然でて来るアナログの音も変化するはずです(聞き分けができる程度かどうかは別として)。
市販のCDを、CD-Rにコピーしたとしても、CIRCを使った訂正後は、バイナリ変化なしではないかと私は思っています(確認したわけではありません)。
ぜひ、ここは確認すべき点ですね。誰が見ても、「客観的」に分かる部分だと思います。
(YESがNOかが、ハッキリ分かるはず)
2. ジッターについては、必ず存在するはずです。時間的なゆらぎが完全に「ゼロ」と言うクロックは存在しませんから。
そして、デジタル→アナログ変換時に、デジタルデータにジッターがあれば、音の波形が歪むわけですから、音質になんらかの影響を与える可能性があります。(録音時のジッターは、ここでは無視してます(すみません))。
問題は、そのジッターによって、デジタル→アナログの処理に影響があるかないか。
影響がある場合、それを検知できるのかどうか。
私も詳しいことは知りませんが、
到着する時間差が、処理に影響しない時間帯の幅に収まる限界=許容されるジッター
と言うのがあり、
サンプリング周波数などで決まり(詳しい計算方法は知りません)
44.1kHz/16bitだと、5.5097×(10のマイナス11乗)秒
96kHz/24bitだと、1.977×(10のマイナス13乗)秒
となるそうです。
ただ、いくつかのチップを通過したり、オーバーサンプリングをしたりすると、その1/2、1/3、1/4と許容値が小さくなるとのこと。
同一源クロックを使用する4チップを通過し、4倍オーバーサンプリング状態では、許容範囲がその1/16になり、最低限クリスタルクロックレベルの精度以上(27MHzで、1/10000程度のゆらぎ以下)が必要だそうです(私は、そのあたりの計算等は知りません。本に書いてあるのを写しているだけですので、ご容赦を)。
このあたり、詳しい方がいれば、教えて頂けるとありがたいです。
とにかく、様々な原因で、どの程度のジッターが生じるのか。その大きさが、音質に影響あるのか、検知できる範囲なのかどうかが問題だと思います。
3. ここは、現在不明な部分です。すべて、ジッターなどで説明できるのか、それともどうしても他の要素を入れないと説明できないのか。
デジタルオーディオでは、まだ分からない部分が多々あるような気がします。
と言って、分からないことは何でもここに入れるというのも、思考停止ですし。
まずは、現在分かっている理論(?)で、すべてを説明付けるよう努力すべきでしょうね。
デジタルデータの世代落ちとか、リッピング環境の違いで、同じハードディスクに記録されたファイル(バイナリは同じらしい)の音質が違うんじゃないかとか…いろいろ……。
4. とにかく、読みにくいとザーボなどが多くなる、エラーが多いとエラー訂正動作が多くなる。
これらが多いと、そのときにそれなりの電流を消費する。
そのため、微小であっても、電源電圧が変動(低下?)する。(ノイズの問題もあるかも)
そのため、クロック回路やアナログ回路に微小な影響を与え、それが音質の変化として現れる。
という理屈ですね。
CD-Rへの書き込みエラーが多いと、上記が理由で、音質が変わる可能性がある、などなどという理屈になります。
これも、それを検知できるのどうかが問題になると思います。
オーディオCDについては、同じバイナリでも、プレスする工場で音質が違うようです。
→http://www.spatiality.jp/articles/cd
また、有名なXRCD(ビクター)の場合、音質が違うので、ガラスマスターの製作機械やプレスする機械などを指名し、運転するオペレーターも特定個人を指定して作成しているとのこと。
→http://blog.livedoor.jp/jazzaudiofan/archives/51033138.html
(参考)
→http://www.xrcd.com/index_jp.html
これらのこと、バイナリの違いではなさそうに思います。
何が違うんでしょうね。
CD-Rへのコピーにも、関係ありそうな気はしますが…。
書込番号:12396846
![]() 2点
2点
…さて面白い結果が出ました。
今回生涯初に、CDプレーヤーからデジタル(同軸)出しした状態でCDとCD-Rの音を比較しました。
今まで変わりを感じていたのは、全てプレーヤー内蔵DACを通したアナログ出力の例です。
結果ですが…『CDとの差がわかりませんでした』
私がわからないから同じと決め付け出来ませんが、少なくとも私は正しく判別することは不能です。何か違いがあったとしても気のせいで充分済む範囲内です。
外部DACでCD-RとCDを比較したのは初めてですが、一つ感じるところがありました。
それはいつものプレーヤー内蔵DACのアナログ出力で感じていた、CD-Rの音への違和感が無くなったことです。
CD-Rは外部DACを使った方が、音が良いと感じました。
今のとこ、CD-RとCDは、プレーヤーアナログ出力で違いを感じ、デジタル出力で違いを感じない…という途中経過になっています。
私は理屈はわかりませんので、後の判断は皆様にお任せします。。。
書込番号:12396966
![]() 1点
1点
air89765殿、手間をかけてすまんの。じじいには難しいことはようわからんので解説はOISU殿に任せるとして、
…って、じじいキャラは結構消耗するので、ふつうに、ちょっと前のDyna-udiaさんの投稿にコメントします。
>(変わらない派の言う)「客観化」とは、(A)計測機器などによるデータ化・数値化、を指すようです。
おおいに誤解されていますよ。カカク板で計測機器などによる数値化を求めた人っていたかしらね…というか、「変わる」という主張をどのように行うかは変わる派の裁量で決められるべきで、変わらない派が要求する性質のものではありません。ただしその主張が、結果として客観性を持っているかどうかが問われます。学会での論文発表などもまったく同様です。変わらない派が、変わる派の主張の中に存在する不備を指摘したり、やりかたの改善提案をするなどはあるでしょう。
計測機器による観測や理論的アプローチは、主張を客観化するための有力な手段ですが、人間の官能(主観)検査を観測手段にすることもじゅうぶん可能だと思います。代表的な例としてダブル・ブラインドテスト(DBT)がよく挙げられますね。念のため書きますが、DBTは一例であって、要は客観的に説得力があれば良いのです。つまり、
>耳で聴いた結果も、データの取り方次第で十分に「客観化」だといえる。
は、おっしゃるとおりだと思います。ただし、「自分は先入観なく客観的に聴いて、変わって聴こえました。AくんとBさんもそう言っていました。」では、小学生の自由研究としても良いお点はもらえないでしょう、ということです。
書込番号:12397159
![]() 6点
6点
こんばんは
> 焼き方を工夫しなくても音は良いか?
悪いメディアで悪いプレイヤーで高速で焼くと、良い悪い以前に音飛びしません?
1年たったら読めなくなったり、音飛びが頻繁発生したりもありますよね
音質が良くなるかについてですが
ミニコンポや、普通のAVシステム(総額30万程度)では、私はほぼ違いは分からないです
ただ、スピーカーをちゃんとセットしていて、30万のピュアオーディオシステムでは
違いは感じられました
でも、音に興味が薄い人は、それでもどっちもどっちレベルではないでしょうか?
違いが分かる、分からないは
リスナーの少しでも良い音で鳴らしたい(真剣に違いを判断したいレベル)
良ければよいかな(空間や定位って何?)のレベルによって
全然変わってくるのでは無いかな〜と?
それなりのシステムで、聞き比べて10回当てれば100万円!
なんかで真剣にテストすれば、かなりの人は違いを感じれると思うのですが(笑)
それと、飲み物とかも私には水道水より良いかな?ってレベルでも、水にこだわる人は拘りますし
音質についても、こだわる人は重要問題ですが、ばうさんのように別にこだわらない人は
わずかなレベルなんてどうでも良いでしょうし、このスレに意味有るのかな〜と、、、、(^^;
書込番号:12397629
![]() 2点
2点
忘れようにも憶えられないさんへ
少し脱線してしまいましたね。失礼しました!
(そのつもりはなかったのですが、、)
CDPとDACをデジタル接続でつなぐことでバイナリが一致する。
そしてスピーカーからの出音は?これも同じである。ここまでは確かなようですね。(デジタルケーブルの違いで出音は変わる!とかはおいといて)
すなわちバイナリ一致という実験は客観性があるということだと思います。(某aつっこみ隊長への挑戦状ではありません笑)
baldarfinさんへ
baldarfinさんの目的と考察、とても解りやすく、自分の説明不足さに泣けてきます。。
1、に関しては同意見です。
2、のジッターに関しては現在リサーチ中です。
自分の現段階ではジッターの多少の揺らぎではイルカやコウモリで無い限り感じ取るのは不可能という持論です。
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf
ここの考察部が参考になるかもしれません。
問題なのは4ですね。
サーボの悪戯によるものなのでしょうか?(自分もそんな気がします)
サーボの影響を極力排除した、CDP DAC独立作戦でデータが変わらないということは、やはりエラー訂正がDACになんらかの影響を与えているということなのでしょうかね。
この4の問題、もしこの悪戯で音が変わるというならば基盤を離すなどの開発は今後可能ですね。
ん〜この4の問題ばかりはよくわからないです。。ただやはりこの4の問題も人間の耳で感知できるかは?です。
書込番号:12397819
![]() 0点
0点
スレ主さんのコメント
>CDのメディアの種類やCD-Rの焼き方を工夫することでCDプレーヤーから出てくる音が良くなる、という話題を良く見かけます。
>しかし、そのような工夫をしなくてもCDプレーヤーから出てくる音はすでに良い状態なのです。
airさんの途中経過
>今のとこ、CD-RとCDは、プレーヤーアナログ出力で違いを感じ、デジタル出力で違いを感じない…という途中経過になっています。
(注:違いを感じ=音の劣化を感じ=元のCD盤の方が音が良かった)
airさんは、ようやく、スレ主さんと同様の見解に到達したようですね。
ご苦労様でした。
めでたし、めでたし・・・で良いのでは?
書込番号:12397934
![]() 1点
1点
忘れようにも憶えられないさん
>おおいに誤解されていますよ。カカク板で計測機器などによる数値化を求めた人っていたかしらね…
それ、知ってて知らばっくれてますよね?(笑)
ばうさんが過去に何度も、電源ケーブルにより音が変わるかどうかは『測定機器による測定、または二重盲検法により客観化されてないから、音は変わらない』、『音は変わる、と言いたいなら、これらの方法で証明し客観化せよ』と主張していますよ。ご興味がおありなら過去ログをお調べください。(私は面倒なのでやりません)
>ただし、「自分は先入観なく客観的に聴いて、変わって聴こえました。AくんとBさんもそう言っていました。」では、
>小学生の自由研究としても良いお点はもらえないでしょう、ということです。
相手の感情を逆立てることにより、優位に立とうという煽りキャラぶりは相変わらずですねぇ。いや私は別に『この掲示板にいる「変わる派」のAさん、Bさん、Cさん、Dさんがみんな「変わる」と言っているから変わるんだ』などとは言っていませんよ。
この社会に存在する、互いに見知らぬAさん、Bさん、Cさん、Dさん……(無限大)の人たちが同じ感想を持てば、彼らの体感は十分に「確からしい」。これを否定するならそもそもマーケティングは成立しない、と言っているんです。
書込番号:12398394
![]() 7点
7点
>めでたし
実用上CDプレーヤーは内蔵DACのアナログ出力で使うことが多い訳だし、電源ケーブルでもデジタルケーブルでもUSBメモリでも、何でもかんでも一緒くたに考える、単純思考はあまりいただけないね。
本当に変わる例、変わりを感じない程度の例、変わらない例、全てあるかもしれず、何でも頭から信じるのではなく確かめてみることが大事だろう、それこそ、『変わらない』というプラシーボの魔法にかからないように。
実際試行して『変わらない・或いは変わる』そう感じたことにはどちらも一理あるはずだろう、常に両方の可能性を考え、どうしてそうなったかの原因を探り、間違っても試しもせずに変わるとか変わらないとか決め付けず、真相を追求しなきゃいけない。
一つ『変わりがわかりにくい・わからない』例が出たことは幸いであろう、それは『変わることへの盲信や期待・そのプラシーボ効果』がもたらしたものではないということで、変わらない例があったことで変わる例にも意味が出る。
何もかも一緒くたに論じるのではなく、何なら変わらなくて何なら変わるかってことを、きっちり分けた方がいい、それには必ず原因があるはずだから。
書込番号:12400315
![]() 2点
2点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
-
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
-
【欲しいものリスト】O11D mini v2 White SL no LCD build
-
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
CDプレーヤー
(最近5年以内の発売・登録)