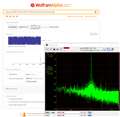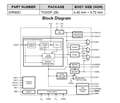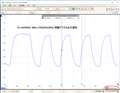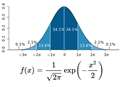���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S1461�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 853 | 200 | 2018�N4��30�� 14:14 | |
| 1 | 2 | 2018�N4��27�� 19:19 | |
| 4 | 2 | 2018�N4��23�� 20:59 | |
| 0 | 3 | 2018�N4��16�� 06:12 | |
| 908 | 200 | 2018�N4��15�� 19:13 | |
| 3 | 20 | 2018�N4��15�� 15:53 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
HAP-Z1ES�������ɂ��w�����悤�ƍl���Ă���҂ł����A�w���ɓ������āA�O�t��BD�h���C�u�������ɍw�����ׂ��������Ă��܂��B
�Ƃ����̂́A�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���L�q���l�b�g��ɎU������邩��ł��B�������ꂪ�{���Ȃ�A�gCD���ڃ��b�s���O�h�̂��߂̊O�t���h���C�u���w�����܂��B
�������A���̈���Łu�o�C�i������v����Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N����Đ����āA���Œ����Ă킩��قlj������قȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��v�Ƃ���ӌ�������܂��B���������炪�{���Ȃ�A�����dBpoweramp����PC���b�s���O���ɍs�����߂̃\�t�g���w�����܂��B
�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H
���������܂�����A���̌��ʁA�ǂ���̉������ǂ��������A���邢�͕ς��Ȃ����������A�����Ă������������Ƒ����܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21724280/
����̑����ł��B
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����@�@�����͂ł��B
�w�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H�x
��L�́A�o���܂���B
�ƌ����̂��A�����Ȃ�]�����悤�ɂ��A�㏑������Ă��܂��̂ł��B
��ɂo�b�]���Ń��b�s���O���ꂽ�Ȃ������ԂŁA�O�t���h���C�u�Ń��b�s���O���悤�Ƃ���ƁA���ɂ��̋Ȃ͂���܂��B
�㏑�����܂����H�ƕ����Ă��܂��B
���Ȃ��c���Ȃ킿���b�s���O���~�ł��B
�o�b�]�����́A�����Ă��Ȃ��̂ŁA�㏑�����Ă���̂��A���ĂȂ��̂��s���ł����H
�����ԍ��F21754329
![]() 4�_
4�_
�V�����X���ɂȂ����̂ŁA���̋@�킪���������Ƀf�[�^�]����LAN�o�R�ɍi�������R���l���Ă݂�Ƃ��������ł�
CD���b�s���O�͌�t���̋@�\�ł������
���Ԃ�ł����A�ڋq�������]�낤�Ǝv���܂�
�����ԍ��F21754564�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�Â����̑�D������A�����́B
���PC���b�s���O�����t�@�C����]�����Ă��ꂪHAP-Z1ES��ɂ����ԂŁA�gCD���ڃ��b�s���O�h�����悤�Ƃ���ƁA�u���ɂ��̋Ȃ͂���܂��B�㏑�����܂����H�v�ƕ����Ă���̂ŁA�Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES��ɋ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��ˁB
����ł́A���Ԃ��t�ɂ���悢�̂ł͂Ȃ��ł����H
��ɁgCD���ڃ��b�s���O�h������B���ꂩ��APC���b�s���O�����t�@�C����]������B���̂Ƃ��A�]����HAP Music Transfer���g���A�����炭���ڃ��b�s���O�̃t�@�C�����㏑������Ă��܂��ł��傤�B
�ł��AExplorer����́AHAP-Z1ES�͒P�Ȃ�O�t���n�[�h�f�B�X�N�Ɍ�����̂ł���ˁB�Ȃ�APC���b�s���O�����t�@�C���̖��O��ύX�������Explorer�ŃR�s�[����A�Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES��ɋ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
����łł������ȋC�����܂����A�i���͂܂������Ă��Ȃ��̂ŁA�m�F�ł��܂��j�ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F21754696
![]() 5�_
5�_
���́u�O�t���n�[�h�f�B�X�N�v�Ƃ����̂́u�l�b�g���[�N�n�[�h�f�B�X�N�v�̊ԈႢ�ł����B
�Ƃɂ����AExplorer�ɂ��PC����HAP-Z1ES�Ƀh���b�O&�h���b�v�ŃR�s�[�ł���͂��ł��F
http://helpguide.sony.net/ha/hapz1es/v1/ja/contents/TP0000774183.html
�����ԍ��F21754743
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����
�F����̋c�_�������[���ǂ܂��Ă�����Ă��܂��B
�����ɂ��o�����̂ŁA����Ă݂܂������A�����̎��ł͔��ʕs�\�ł���(��;)
1, �uIO-Data DVR-UA24EZ2A�v���q���Œ��ڃ��b�s���O�B
2, Windows10 ��PC��ŁuHAP Music Transfe�v���g��HAP-Z1ES�ɓ]��
�����Ȃ�ʃt�H���_�ɓ���܂����̂ŁA�u���ɐ�ւ��邱�Ƃ͂ł��܂���B
��������
HAP-Z1ES �� �o�����X�P�[�u�� �� STAX SRS-4170
�ł��B
���X���쐫�̌��オ���ړI�ŁuHAP-Z1ES�v���w�������̂ŁA����قlj����]�X��Nj�����C�͂Ȃ��̂������ȂƂ���ł͂���܂��B���݂܂���A���������O�삩��̈ӌ��ƌ������ƂŁc�c
�����ԍ��F21754758
![]() 10�_
10�_
Symbolist_K����A�O�X���̃R�[�f�B�l�[�^�[�������l�ł����B
�O�X���̊p�c����̃u���O�ǂ�ł��炢�����Ə����Ă����̂ŁA���p���Ƃ����B
���͐��P�O�N�O���́A�I�[�f�B�I�@��v���d���Ƃ��Ă��܂����B���̎��̓I�[�f�B�I�v�͗��_�����܂薳���A�_�l�̂悤�ȉ�������҂Ǝg�p���i���x�z���Ă���悤�Ɋ����A�r�f�I�v�ɓ]���܂����B���̌㑪���J�����o�āA���܂����̐��E�ɊW���Ă݂�Ƃ܂��ȑO�̂悤�ȏ�����悤�Ɏv���܂��B
���i�A�����������I�ɐi�����Ă��܂�����A�]���𖾁A�����ł��Ȃ��������ł����Ă��e�ՂɑΉ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�t�ɐv�\�͂͑މ����Ă��邽�߁A���ҍ��킹�Đi������~���Ă���悤�ɂ��v���܂��B
�m���ɐ��ɏn�m�������́A���̓��ɂ��Ă͏ڂ����ǂ̂悤�Ȏ��ɂ��������܂��A�����O���ƑS���������Ȃ��ƌ������Ƃ������Ȃ��ė��Ă��܂��B
������̓`�B�̓C���^�[�l�b�g�̔��B�ɂ���āA����I�Ɍ��サ�܂����B����ɂ���ĒN�ł����ƂƓ��l�ȏ�����肷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂������A���̐^�U�f����\�͂͏]���̂܂܁i�ނ���ቺ�j�̂��߁A���Ɍ�������f�����邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B���ߑ��H
�T���v�����O���[�g�̍������������̂ł͂Ȃ��A�ł��������݂���CD�������ɗǂ������ōĐ��ł��邩���d�v�ƍl���Ă��܂��B���̃f�o�C�X�Z�p��p�����384kHz24b���x�̐M�������͗e�ՂɎ����ł��܂��������Đ��p�Ƃ��Ă͂��܂�Ӗ�������܂���B
���̂P�N�I�[�f�B�I�v���Čo�����܂������A�����������d�������ƃV�~�����[�V��������p���ĉ�͂���A�ȑO�s���ł����������A���ł�������x�𖾂ł���̂ł͂Ȃ����ƍĔF�����Ă��܂��B
DAC�v�ɓ������Ă͖w�ǂ̉�H���V�~�����[�V�����ł���͂��A���茋�ʂƍ��v������悤�ɂ��Ă��܂��B
����ǂނƁA���̐v�҂�DAC�������Ȃ��Ă��邯�ǁADAC�ɐ��\�����o�����ȁB
�����ԍ��F21754811
![]() 8�_
8�_
Symbolist_K����A�����́B
�����A�h�肪�o���i���j�BSymbolist_K����[21754278]
>�����̂ŁA�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�ǂ�œ��e�������܂�ŋ����Ă��������B
��������ǂ�ǂ����āE�E�E�ǂ������Ȉ���(��)�H
�Ƃ���Łu�X�e���I�T�E���h���̊p�c��Y���v�ƁuATI Labo�̊p�c����v�͈Ⴄ�l�Ȃ�ł����ˁB�����قNjC���t���܂����B�ȉ��A�����܂ł��l�̊��z�Ƃ��f�肵�Ă����܂��B
�܂��u�ǂ�ǂ����̂P�i�@����j�v�̕����́A�c�`�b����Ȃ��Ă`�c�b�Ȃ�ł��ˁB���̓������[�v���ɂc�`�b������A�Ƃ�������Ȃ̂ŁA�u�Ȃ�ł��̕����H�v�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B���̕������瓾����{�X���Ɋ֘A������́A�u�N���b�N�W�b�^�[�łr�m�q�i�r�m��j����������v�Ƃ����A������O�̎����ł�������܂���B��������O�ꂽ�������m�C�Y�ł�����ˁB
���Ɂu�ǂ�ǂ����̂Q�i��������j�v�́A�p�c����̃u���O�ł́uSPDIF�̏ꍇ����JITTER�́v�Ƃ����������烊���N����Ă���ɂ��ւ�炸�ASPDIF�Ƃ͂Ȃ��W�Ȃ��A�O�L�����ɑ����uPLL��LOOP�t�B���^�[�Ő��������v���T�|�[�g���邾���̈Ӗ���������܂���B�����������O�̎����ŁA��͂�A�u�Ȃ�ł��̕����H�v�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B
�uPLL��LOOP�t�B���^�[�Ő��������v�ƃW�b�^�[�̍��搬�������������킯�ł����A�u���O�ł́u�ʂ͂킸���ł������M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��v�ƁA���_����Ă��܂��B���́A����͂Ȃ��Ȃ��Ɏ�O�݂��Ș_�����Ǝv���܂��B
���̌f���Ŕ��_����@��^�����Ă��Ȃ��i�Ǝv����j�p�c�����ᔻ���邱�Ƃɂ͐T�d�ł���ׂ��Ǝv���܂����A���Ƃ��Ă͎����������������Ȃ��A�ƌ��_���Ă����܂��B�E�l���ȂЂƂȂ̂����m��܂��A��O�݂��͂�����ƁB
�����A�������̂Q�͂������낢�ł��B
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf
�A�u�X�g�����p�����
>�W�b�^�[�����ʂ��ē���ꂽ�ő�̃W�b�^�[
>�����U���́A�W�b�^�[���g��2 Hz�ȏ�ɂ����āA2ns����������B�]���̎��g���ϓ����m�����̌��ʂƔ�
>�r����ƁA���̒��x�̃W�b�^�[�������ɗ^����e����҂����m���邱�Ƃ͍���ł���Ɨ\�z�����B
�Ƃ̂��Ƃł����A��̐Ԗx�������p����Ă���
>����ŁA�Ԗx��m�P�n�́A�f�B�W�^���C���^�t�F�[
>�X��̃r�b�g�X�g���[���ɃW�b�^�[�������āA������
>�̉����̕ω��ׂĂ��邪�A�������ʂɂ��ē��v
>�I������s�������ʁA�U��80ps�̃W�b�^�[�̗L�����A
>�팱�҂͗L�Ӎ�����ŕ������������Ƃ�������Ă�
>��B
�ƁA�y���u�ς��E�ς��Ȃ��v�_���Ȋ����ł��B�����A�������̂�
>����n�̃m
>�C�Y���x�������i�ʂȃf�B�W�^���@��ɂ����ēT�^�I
>��-130dBFS�^Hz�ȉ��ł���ꍇ�A�����M����p����
>�W�b�^�[�U�����m���͐�ps�`��10ps���x�ł���B
�Ƃ����L�q�ł��B�����Ƃ͌�����ps�`��10ps�͋����ׂ������ł��B�l�Ԃ̌��m���Ƃ��Ă̓X�S�����Ăɂ킩�ɂ͐M���������̂ł����A����ɂ͕����i�����j��������Ă��Ȃ����Ƃ����̂悤�ȋ^���������܂��B����́ASymbolist_K����ɒ��҂ɕ����Ă��炤�����Ȃ��悤�ȁE�E�E�h��Ԃ�(��)�B
�����ԍ��F21755054
![]() 8�_
8�_
�s�����g�����R����A�����́B
���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�������ɂ��o�����̂ŁA����Ă݂܂������A�����̎��ł͔��ʕs�\�ł���(��;)
���ۂɒ�����ׂĂ݂Ă̋M�d�Ȃ����z����������A���ӂ������܂��B
�s�����g�����R����́u��ʂł��Ȃ��h�v�̂R�l�ڂɂȂ�܂����I
�Ƃ���ŁA�]����HAP Music Transfer���g���Ă��A�gCD���ڃ��b�s���O�h�����t�@�C���Ƃ͕ʂ̃t�H���_�ɓ������̃t�@�C�����㏑�����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��ˁB
���Â����̑�D������
HAP-Z1ES�Ƀt�H���_������������Ă����āAPC���b�s���O�����t�@�C�����gCD���ڃ��b�s���O�h�����t�@�C���Ƃ͕ʂ̃t�H���_�ɓ]������Α��v�������ł���I
�����ԍ��F21755344
![]() 5�_
5�_
MAX���O�Y����
�u���̋@�킪���������Ƀf�[�^�]����LAN�o�R�ɍi�������R�v�́A�����炭�́A���ł�PC�I�[�f�B�I�^�t�@�C���I�[�f�B�I�炭����Ă���WAV��AIFF��FLAC��ALAC��DSD��DSF�̃t�@�C����PC�ɂ��ߍ���ł���l���^�[�Q�b�g�ɂ�������BPC����͑O��Ƃ��āB
�������A���̌�AHAP-Z1ES�������ǂ��ƕ������āAPC����ɂ��܂芬�\�łȂ����X�������悤�ɂȂ����̂ł��傤�B�\�j�[�ɂ��A�u�wCD���b�s���O�ɂ͂ǂ�ȃ\�t�g���g�������̂��x�w�p�\�R�����g��Ȃ���CD���b�s���O������@�͂Ȃ��̂��x�Ƃ������₢���킹�����[�U�[���瑽����ꂽ�̂ŁA�p�\�R�����X�ŊO�t���h���C�u���璼�ڃ��b�s���O�ł���@�\��lj�����A�b�v�O���[�h�ɓ��ݐ����v�����ł���B
�����ԍ��F21755347
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
�O�X���ł͑����̏������݂��肪�Ƃ��������܂����B
���T���v�����O���[�g�̍������������̂ł͂Ȃ��A�ł��������݂���CD�������ɗǂ������ōĐ��ł��邩���d�v�ƍl���Ă��܂��B���̃f�o�C�X�Z�p��p�����384kHz24b���x�̐M�������͗e�ՂɎ����ł��܂��������Đ��p�Ƃ��Ă͂��܂�Ӗ�������܂���B
�p�c�����CD�X�y�b�N�i44.1kHz/16bit�j�ł����Ă�DAC����ŏ\���������ɂ��邱�Ƃ��ł��A���Ȃ��Ƃ�384kHz/24bit�͈Ӗ����Ȃ��A�Ƃ�������Ȃ̂ł��ˁB�ł́A384kHz/24bit�͈Ӗ����Ȃ��Ƃ��āA�ǂ��܂łȂ�Ӗ�������Ƃ��l���Ȃ̂ł��傤�ˁH 192kHz/24bit�܂ŁH ����Ƃ�96kHz/24bit�ŏ\���H �ł��A�̗p����ES9018��384kHz/32bit�܂ŁAES9038PRO��768kHz/32bit�܂őΉ����Ă��ł���ˁB
���Ȃ݂�ES9038PRO ���̗p����OPPO Sonica DAC��SOULNOTE D-1�AAK4497���̗p����TEAC NT-505�́A768kHz/32bit���Đ��ł��邱�Ƃ��ւ��Ă��܂��ˁB����ȉ����A�����Ă܂��ǁB
AIT-DAC-zn2�i347,800�~�j�́A���i�I�ɂ�SOULNOTE D-1�Ƃ��������ł����A���h���͈����ł��ˁB
����ɔ�ׂ��烁���R��Dela�ł����������悭�����܂��BHAP-Z1ES��N-70AE�Ȃ�Ăނ��Ⴍ���Ⴉ���������ł���˂�
�Ȃ�ƂȂ��A�����@����Ē����Ă݂�H�w�������܂���B�i�����܂ŁA��Ȃ̂́u���v�ł����j
�����ԍ��F21755350
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�ق�Ƃ��ɘ_����ǂ�ł����܂�ŏЉ�ĉ������āA���肪�Ƃ��������܂����I
���Ȃ݂ɁA�X�e���I�T�E���h���̊p�c��Y���́u�̂��v���ŁAAIT Labo�̊p�c����i���̖��O�͕s���j�́u�������v����Ǝv���܂��i�v���t�B�[���Ɂu���O�Fkkt�v�Ƃ���̂ŁBDAIGO���I���j�B
AIT Labo�p�c����͎�O���X���݂Ȃ�ł����B�_���̎g��������c�����I�Ȃ�ł��ˁB�u�ʂ͂킸���ł������M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��v�������킩��Ȃ����A��ɖ��ɂȂ��Ă����u�{�������v�Ƃ̊֘A���悭�킩��܂���ˁB���ꂩ��A���܂�l�̂��Ƃ͌����܂��A�₽��ƂЂ炪�Ȃ̔����������ł��ˁB
���āA�u�ǂ�ǂ����̂P�i�@����j�v�͓ǂ܂Ȃ��Ă�������ł��ˁI �悩�����ł�(��)
�ł��A�u�ǂ�ǂ����̂Q�i��������j�v�͖ʔ�����ł��ˁB�ł́A�����p���p�����Ɠǂ�ł݂܂��B
��������I�[�f�B�I�}�j�A�̈ꕔ�ɂ́AAC�d���̎��ɍS��X����������B�������A���̉Ȋw�I�����͖R�����A�v���O��P�[�u�������i���Ȃ��̂Ɍ����������Ƃɂ��v���\�ȓd�C�I�e���≹���I�e���́A���܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�ȂA�u�I�[�f�B�I�}�j�A�v���f�B�X���Ă܂��ˁB
�����肳�ꂽ�W�b�^�[�́A�]���̌����œ���ꂽ���g���ϒ��ɑ��錟�m���i�����Ƃ����x�̍����ϒ����g���RHz�ɂ����āA�W�b�^�[�U���Ɋ��Z����Ɩ�S�`10ns�m13�n�j�ȉ��ł������B����ď]���̒��o�I�m������́A���肳�ꂽ�W�b�^�[�́A�����I�ɂ͖��̂Ȃ��ʂł���ƍl������B
���ߔN�ł́A�b����m14�C15�n���A�f�B�W�^���̈�ɂ����ĉ��y�M���ɐl�H�I�ȍL�ш掞�Ԃ�炬�������āA���̌��m���𑪒肵�Ă���B���̌��ʁA�ł����x�̍����팱�҂���уT���v���Ȃ̏ꍇ�ł��A�����l�ŕ\�����W�b�^�[�̌��m����500ns���x�ł������B
������ŁA�Ԗx��m�P�n�́A�f�B�W�^���C���^�t�F�[�X��̃r�b�g�X�g���[���ɃW�b�^�[�������āA������̉����̕ω��ׂĂ��邪�A�������ʂɂ��ē��v�I������s�������ʁA�U��80ps�̃W�b�^�[�̗L�����A�팱�҂͗L�Ӎ�����ŕ������������Ƃ�������Ă���B�������ނ�̎����ł́A���ۂɍĐ������A�i���O�����M���ɂǂ̒��x�̃W�b�^�[���܂܂�Ă����̂������m�Ɍ�����Ă��炸�A�����ɂ͂������̉������{�����I�[�f�B�I�@�킪�g�p����Ă��邽�߁A��ʐ��̂��錋�ʂł��邩�ǂ����ɂ��ċ^�₪�������B
���m���̑��茋�ʂ́A80ps�`4ns�`10ns�`500ns�܂ŁA�܂��܂��i��ԉ��͈�ԏ�̖�P�����̂P�I�j�Ȃ�ł��ˁB���̒��ŁA���̐Ԗx���́u80ps���v�͋^���Ă܂��ˁI
���āA���q�˂�
������n�̃m�C�Y���x�������i�ʂȃf�B�W�^���@��ɂ����ēT�^�I��-130dBFS�^Hz�ȉ��ł���ꍇ�A�����M����p�����W�b�^�[�U�����m���͐�ps�`��10ps���x�ł���B����p���y�M���͉ߋ��̑���m�V�n�Ɠ�����RWC-MDB2001No.2�m10�n��p�����B���̏ꍇ�̃W�b�^�[�U�����m���͂Rns�m�V�n�ł���
�Ƃ����L�q�ł����A�u�S�D�l�@�v�̍ŏ��̕�����
�����y�M���𑪒�M���Ƃ����ꍇ�ɂ́A���o���ł���Rns�ȏ�̃W�b�^�[�͑���ł��Ȃ������B
�Ƃ�����߂������ł���B������A����@��̑���u���o���v�̊ԈႢ�Ȃ�Ȃ����Ǝv����ł����B
�����炭�A�@��ɂ��W�b�^�[�U���́u���o���v���A�����ł͐�ps�`��10ps�A���y�ł͂Rns�����Ęb�Ȃ�Ȃ��ł����H �l�Ԃɂ��u���m���v�ł͂Ȃ��B�Ⴄ���ȁH
�����ԍ��F21755354
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����@���͂悤�������܂��B
�ʃt�H���_�E�E�E�ł����H�@���́A�䂪�Ƃ�USBDAC�̋@�\������CD�v���[���[��2�䂠��܂���
�v���[���[�ŁA�f�B�X�N���g���Ắu���v�Đ��ƁA�m�[�gPC�Ƀ��b�s���O����USB�ڑ��@iTunes�ł̍Đ��Ł@�u���v����̂��ȁH
2�䋤�Ɏ����Ĕ���Ȃ��H�@�͌o���ςł����AHAP-Z1ES�̍w���ړI���A���ɂ̂��[����Đ����̍\�z�Ȃ̂�
�s�����g�����R����Ɠ����ӌ��ŁA����قǒNjy����C�����͕����Ă��܂���̂ŁA���̕ӂ�ň������炸�ł��B
�����ԍ��F21755449
![]() 4�_
4�_
�Y�ꂳ�ʔ����Ƃ����̂ŁA
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf
��ǂ݂��������A�u��͐M���v���ĉ�����Ƃ����Ƃ���ō��܂����B
�O�O��ƁA
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/emm180.pdf
�ɉ��������ȁB
�悭�킩��ǁA���ԗ̈�̑���M���i���g����_c�̏��������gAsin(��_ct)��t��Jsin��_jt�Ƃ��ăW�b�^��t���A���Ȃ킿�A
Asin(��_c(t+Jsin��_jt)�j����q���x���g�ϊ��ʼn�͐M���̋������������߂�ƁA��͐M���̎��������Ƌ��������̔��arctan
�ł���A����M��Asin(��_c(t+Jsin��_jt)�̏u���ʑ��p��(t)����_c(t+Jsin��_jt)�����܂�B�]���āA�W�b�^�g�`Jsin��_jt���A
����M�����狁�߂���B������t�[���G�ϊ��������̂��W�b�^�X�y�N�g�������H
�����ԍ��F21755773
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����A����ɂ��́B
����ɂ��Ă��A�s��Ȏ���X���ł���ˁB�Ƃ��ƂƔ����Ē����Ă݂��E�E�E���ē˂����݂�12�l���炢���畷�����Ă������ł�(��)�BDAIGO����A����Ȃ��ăJ�N�^����̌��A���肪�Ƃ��������܂����B
>���m���̑��茋�ʂ́A80ps�`4ns�`10ns�`500ns�܂ŁA�܂��܂��i��ԉ��͈�ԏ�̖�P�����̂P�I�j�Ȃ�ł��ˁB���̒��ŁA���̐Ԗx���́u80ps���v�͋^���Ă܂��ˁI
�܂��A�Ԗx���i���炭���{TI�j���f�B�X���Ă���ۂ����ҁi��������j�̌��ł͂���܂����ǂˁB����ɂ��Ă��A�O�X���̕č��_���ɂ�錟�m���i10ns�`300ns�j��肸���Ԃ�Ⴂ������̂́A���{�l�Ȃ�ł͂̑@�ׂȒ��o�E�E�E�Ƃ������Ƃł͑����Ȃ��ł�(��)�B
�_���ɂ���悤�ɌÂ������̐M�����ɂ͒��ӂ���K�v�����肻���ł����A�܂��A�_���Ɂu�����Ƃ����x�̍����ϒ����g���RHz�ɂ����āv�Ƃ���������������܂��B��s�������ǂ߂Ȃ��̂Ő����ł����A����̓W�b�^�[�̈���E�������RHz�ŌJ��Ԃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����B���ꂾ�ƕč��_���̂悤�Ȃ`�a�w�@���͂��Ȃ茟�m���������肻���ł��ˁB����Ȃ킯�Łu���m���͂��ꂱ��v�ƌy�X�ɂ͌����Ȃ��Ɨ������ׂ��ł��傤�B
�������A�N���b�N����IC�̃x���_�[�����А��i��i�삷��_���������̂͗����ł���Ƃ��āA����ɉʊ��ɗ�����������w�̌����͊�Ƃ���̉����͓���ꂻ�����Ȃ��A�Ȃ�̓��ɂȂ�̂��A�ЂƎ��Ȃ���S�z�ɂȂ�܂��B����Ȍf���ł���ȒP�ɍ�i���j�B
>������A����@��̑���u���o���v�̊ԈႢ�Ȃ�Ȃ����Ǝv����ł����B
Symbolist_K����́u�u���_���v�������ł����A�̂͂�����ĎZ�����ł��Ȃ��j�q�̂��ƂƎv���Ă��܂����B���̌㑽���̐l���o�����o�āA�ŋ߂ł͍��������̕�����܂������A�����܂�������\�͂�L����ЂƂ����ۂ���̂ɂ͐S��I�h���L�܂��Btohoho3���������Ă����悤�ɁASymbolist_K�����������H
��k�͂Ƃ������A���͎������������悤�ɓǂ�ł��āA���������A����Ȃ��ău���_����Symbolist_K����ɐ�ɂ���������Ăق�����������ł��B���m�ɂ́A����@�펩�̂̓s�R�b�𑪒�ł��܂����A��A�̕]���t���[�S�̂Ƃ��āA�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21755976
![]() 7�_
7�_
�����ł��B
>����̓W�b�^�[�̈���E�������RHz�ŌJ��Ԃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����B
�́A�Ⴂ�����ł��B����������ƃW�b�^�[�i�ʑ��j���̂��RHz�ŕϒ������悤�ł��B����Ȃɂ�����肵���W�b�^�[�܂ōl���Ă���Ƃ̓C���[�W���Ă��܂���ł����B
������ɂ��Ă��A���ꂾ���������h�����Ă�����A���^�C���ň�a���������₷���Ƃ������ƂŁA�L���ɗ���`�a�w�ɔ�ׂ�Ƃ����Ԍ��m����������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21756099
![]() 5�_
5�_
�Â����̑�D������A���͂悤�������܂��B
�u���b�s���O���@�͈Ⴄ���o�C�i���͓����Q�t�@�C����HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɋ�����������ōĐ������r����v���Ƃ͂���Ă��Ȃ��̂ł��ˁB
�Ƃ������Ƃ́A�O�X���ɏ������܂ꂽ�A
�����`���ƁA���ۂɒ��������̂̌o���Ƃ��āA���̑ʎ�(������)�ł́A�����ς蕪����܂���(�͂͂́I)
��
���ʐ^�ɕt���܂����l�ȁA�O�t���h���C�u�c����́A���܂��܃m�[�gPC�p�ɊO�t���h���C�u�������Ă���
���̂Ŏg���Ă܂����A�f�B�X�N�g�b�vPC�Ń��b�s���O�����f�[�^��LAN�o�R�œ]�������Ă܂����A�u���v
���Ȃ�Ă����ς�ł��B
�Ƃ����̂́APC���b�s���O�ō�������鉹�y�̃f�[�^�̍Đ���CD���ڃ��b�s���O�ō�����ʂ̉��y�̃f�[�^�̍Đ��Ƃ��r���Ă̘b�������킯�ł����B
����ł��A�uPC�]���ƊO�t���h���C�u�ł̃��b�s���O�ł́w���x�v������Ȃ������ƌ����Ă���̂ŁA�����悤�ȋȁi�Ⴆ�Γ����̎�̕ʂ̉̂Ƃ��j���r���Ă̂��b�������̂ł���ˁB
�ł���A�܂��u�T�v�I�ł͂���܂����A���̃X���ł͌Â����̑�D����������������u��ʂł��Ȃ��h�v�̂��P�l�ɐ��������Ă��������܂��B
�����ԍ��F21757752
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/emm180.pdf
�́A���ɂ͓�����ēǂ߂܂���B
�u�t�[���G�X�y�N�g���v�Ƃ��u�q���x���g�ϊ��v�Ƃ������ς�ł�^^;
�����ԍ��F21757753
![]() 3�_
3�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���_�߂ɂ������肠�肪�Ƃ��������܂��B
���[�ƁA���́u�u���P���_���v�ł��B�u���P�W���v�Ȃ�ʁu�u�P�_���v�B�u���w�n�v�Ȃ�ʁu������n�v��
�ŋ߁u���P�W���v�����Ă͂₳��Ă���̂ŁA���̑ɂɈʒu���邱�Ƃ��������Ă݂܂����B
�u�u���_���v�Ə̂���ƁA�ȂA�H��܂��Ƃ����肵�Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ����������܂�(��)
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����́u���P�W���v�ł���ˁH
�u���n���q�����T�[�r�XRikejo�v�i�Ȃ�ăT�C�g������܂����j�ɂ��A
�����P�_���i���n�j�q�j�ƃu�P�_���i���n�j�q�j�̘b�ƂȂ�܂����B���ǁA���P�W�������P�_���ƌ��������肷��̂́A���ǂ͏o��ꏊ���Ȃ�����ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�u�P�_���ƃ��P�W���́A���݂��ɔ�����Ƃ������������ƂłȂ��āA���ǂ͒m��Ȃ��܂܂ɏI���Ƃ��������ł��傤���BT����̑�w�ł́A���H�n�̊w���́A���̊w���Ɗu������Ă��������ŁA���̂悤�ȑ�w�͑����ł���ˁB
http://www.rikejo.jp/unclassified/article/1199.html
�������ł��˂�����
���āA
���܂��A�Ԗx���i���炭���{TI�j���f�B�X���Ă���ۂ����ҁi��������j�̌��ł͂���܂����ǂˁB����ɂ��Ă��A�O�X���̕č��_���ɂ�錟�m���i10ns�`300ns�j��肸���Ԃ�Ⴂ������̂́A���{�l�Ȃ�ł͂̑@�ׂȒ��o�E�E�E�Ƃ������Ƃł͑����Ȃ��ł�(��)�B
������������ƃW�b�^�[�i�ʑ��j���̂��RHz�ŕϒ������悤�ł��B����Ȃɂ�����肵���W�b�^�[�܂ōl���Ă���Ƃ̓C���[�W���Ă��܂���ł����B
������ɂ��Ă��A���ꂾ���������h�����Ă�����A���^�C���ň�a���������₷���Ƃ������ƂŁA�L���ɗ���`�a�w�ɔ�ׂ�Ƃ����Ԍ��m����������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
������Ȃ킯�Łu���m���͂��ꂱ��v�ƌy�X�ɂ͌����Ȃ��Ɨ������ׂ��ł��傤�B
�Ȃ�قǁB�����ɂ���Č��m���̒l�͂��Ȃ�㉺����̂ł��ˁB�����ē��{�s�h�̐Ԗx���́A�Ӑ}�I�Ɍ��m��������������ɂ��Ă����Ƃ������Ƃł����B
���������A�N���b�N����IC�̃x���_�[�����А��i��i�삷��_���������̂͗����ł���Ƃ��āA����ɉʊ��ɗ�����������w�̌����͊�Ƃ���̉����͓���ꂻ�����Ȃ��A�Ȃ�̓��ɂȂ�̂�
��������w�́u���w�̐��_�v��ǂ�ł݂܂����F
http://www.tuis.ac.jp/university/spirit/
�u�����_�Ƒ�w�̑n�ݎҁA�|�{���g�͕����E�O���E�_�����E���M��b���C���ߑ�����D�ꂽ�����Ƃł���ƂƂ��ɁA���p�I�ȉ��p�Z�p�ɗ͂𒍂��u���w�v�̏d�v�����������Ȋw�҂ł�����܂����B
�@��������w�ł́A�|�{���_�W�I�Ɍp�����A�����������ĐV�����������l�ވ琬�����w�̐��_�Ƃ��A���̋��痝�O���u������w��`�v�Ƃ��Ă���̂ł��B�v
�ܗŊs�ɗ��Ă������čŌ�܂ŎF���R�ɒ�R�����|�{���g�́u�|�{���_�v���p�����Ă���Ȃ�A����Ȋ�Ƃɂ��ׂ��������悤�Ș_���������Ȃ�āu�^������Ɓv���ĂƂ��낶��Ȃ��ł��傤����
�����ԍ��F21757756
![]() 6�_
6�_
>���ɂ͓�����ēǂ߂܂���B
�����Ǝ��Ԃ�����A
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/backcontents.htm
�́u��b����̎��g�����́i�P�j�v����ǂ߂ASymbolist_K�������痝���ł���͂��B
�����ԍ��F21757794
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����A����ɂ��́B
>���_�߂ɂ������肠�肪�Ƃ��������܂��B
�u��k�v���ď���������(��)�B�u�u�P�_���v�ł����ˁi������ƒp���������j�B���͉��吶�ł����A���y������Ă���l�Ő��w�ɂ߂��ይ���l���ĈĊO�����ł���i�s�^�S���X�Ƃ��j�B
>�Ȃ�قǁB�����ɂ���Č��m���̒l�͂��Ȃ�㉺����̂ł��ˁB�����ē��{�s�h�̐Ԗx���́A�Ӑ}�I�Ɍ��m��������������ɂ��Ă����Ƃ������Ƃł����B
�݂Ȃ���ɂ킩��Â炩�����Ǝv���̂ŁA�킩��₷�������܂��B�u10ns�̃W�b�^�[�v�ƌ������ꍇ�A���Ԏ������̐U����10ns�ł��邱�Ƃ͂킩��܂����A���ꂪ�ǂ�ȋK�����Ŕ������Ă���̂������܂���B�Ƃ������A�O�X���Łu�����_���E�W�b�^�[�v�Ƃ����ꂪ�������悤�ɁA�L�����g���������܂ނ̂����ۂƎv���܂��B
�l�Ԃ̌��m���̎���������ꍇ�ɂ͐��䂳�ꂽ�W�b�^�[���킴�Ɖ�����K�v������܂����A�����Ƃ��P���Ȃ͈̂����g���̃W�b�^�[�ł��傤�B���ۂƂ͂�������Ă��܂����A�ނ��댟�m�͂��₷�����ł��i��������̘_���ɂ�����������Ă��܂��j�B
����ɁA���_���ɂ����̎��g����3Hz�̂Ƃ��ɂ����Ƃ��킩��₷���Ƃ̂��Ƃł��B������������3Hz�̃r�u���[�g���������ĕ�������Ƃ������Ƃł��B�����������3Hz�����肪�킩��₷�����ȋC�����܂��ˁB�����Ă��̂Ƃ��̌��m���́A�W�b�^�[�U�����Z��4ns�`10ns�Ƃ̂��Ƃł��B
�v����ɁA���Ԃ��炩������A�����Č��m���₷��������T���āA�悤�₭4ns�`10ns�ł���Ƃ������Ƃł��B���Ă݂�Ɠ��{�s�h�́u80ps���v�́A���̌��������K�v�͂���܂��傤���A�Ȃ�炩�̖��������肻�����Ǝv���ق������R���Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁA�J�N�^����́u���M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��v�Ƃ����b�́A�Ⴆ��3Hz�̂悤�Ȓ��W�b�^�[�őS�́i�L��j�Ƀr�u���[�g���������Ă��܂��v�Ƃ������Ӑ}�Ȃ̂����m��܂���B�������A��������̘_�������p����̂́A�������ɂ͋t���ʂ��Ƃ��킩�肾�����̂ł��傤���ˁE�E�E�B
>��������w�́u���w�̐��_�v��ǂ�ł݂܂����F
���Ȃ��Ƃ��A�_���ɂ͌����҂Ƃ��Ă����������������܂��B
�����ԍ��F21758877
![]() 6�_
6�_
��`�A���͂܂��W�b�^�̊�{���A�悭�킩��Ȃ��B
�W�b�^�Ƃ́A�O���ɂ��M���g�`�̃^�C�~���O�i�ʑ��j�̕ϒ��i�Y�ꎁ�̌����r�u���[�g�j�ł���B
https://www.edn.com/design/test-and-measurement/4423170/The-many-faces-of-jitter
�ɂ��ƁA
�W�b�^���܂ސM���g�`�Ɨ��z�I�ȃN���b�N���r���邱�Ƃɂ��A���Ԍo�߂ɑ���W�b�^�ʂ�
�ω����킩��B������t�[���G�ϊ��������̂��W�b�^�X�y�N�g�����ł���B
�ŁA���̃W�b�^�X�y�N�g�����́Ahttp://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf�̘_����
�W�b�^�X�y�N�g�����Ɠ����Ȃ́H�@
���肢�A�Y��l�A�D����������āB
�����ԍ��F21759690
![]() 4�_
4�_
tohoho3����
�u�����Ǝ��Ԃ�����A
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/backcontents.htm
�́u��b����̎��g������ (1) �v����ǂ߂v
�ǂ������ȃe�L�X�g�̂��Љ�肪�Ƃ��������܂��B
�����͂���܂����A���ؒ��J�Ȑ����̂悤�ł����A���Ԃ��d�d�d
�u��b����̎��g������ (1) �v���珉�߂āu��b����̎��g������ (29) �v�܂ł��āI
������Ɛ����������āA�����ǂ݊���Ă��Ȃ�����Ȃ̂ŁA�������炭�炵�܂��B
�u�����s��̏h��v�Ƃ����Ă��������I
�����ԍ��F21760148
![]() 4�_
4�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
����[�A��k�͍������������ɂ��Ă��������I(��)
�������ɕ��c�~��ɑ��c�[�B�R���A�Z�N�n���A�R���j���N�ⓚ�I
�u����͂����牽�ł��A����͂����牽�ł����e�͉������v���āA����͂������̃Z���t�����āI��
����͓e���p�B
����ł������A���炵�܂����B���傾�ƁA���������u�u�P�W���v�ł��ˁB���y�͌|�p�ł����̂ˁB�u���y�����w�ȁv�Ƃ����邵�B�ł��A�s�^�S���X���u���y������Ă���l�Ő��w�ɂ߂��ይ���l�v�Ƃ͋��قȁI(��) ����������Ȃ�A�u�N�w�E���w������Ă�l�ʼn��y�ɂ��߂���ڂ����l�v�ł���B�s�^�S���X���c�̋��c�l�����B�s�^�S���X���������w����̋A���ł���ˁB
���呲�Ő��w�◝�H�w�ɂ��ڂ����l�Ƃ��āA������ƍl���Ă݂Ďv�������̂́A��{���ꋳ���ƃw���x���g�E�t�H���E�J���������炢�ł��B���Ƃ͖Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ł��傤���B���ɒN�����܂����H
������e���p�B
�����_���ɂ����̎��g����3Hz�̂Ƃ��ɂ����Ƃ��킩��₷���Ƃ̂��Ƃł��B������������3Hz�̃r�u���[�g���������ĕ�������Ƃ������Ƃł��B�����������3Hz�����肪�킩��₷�����ȋC�����܂��ˁB
���ꂪ�悭�킩��܂���B�u3Hz�̂Ƃ��ɂ����Ƃ��킩��₷���v���Ăǂ��������Ƃł����H
�l�Ԃ̎��̉��͈͂��āA�ł��悭���������҂ł��悻20Hz�`20kHz�ł���ˁB88���s�A�m�̈�ԉ��̌��̃��̉���27.5Hz�A�����ȃX�s�[�J�[���o���鉹�́AB&W��800 D3��15Hz�`28kHz�A�����JBL��EVEREST DD66000�ł�27Hz�`50kHz�ł��B3Hz���ĕ������܂����ˁH �������Ȃ����ł��A�J�N�^����́u���M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��v���ɂ���悤�ɁA���ꂪ�L��ɉe�����邱�Ƃɂ���āA���S�̂Ƃ��āu�ς�����ȁv�Ƃ킩����Ă��Ƃł����H �������A����ł��u3Hz�̂Ƃ��ɂ����Ƃ��킩��₷���v���Ă��Ƃ͂Ȃ��C������̂ł����B�Ⴆ�A3kHz�Ƃ��̕�������ۂǂ킩��₷���Ȃ��ł����H
�����ԍ��F21760149
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����A
�u3Hz�v�́A���Ԏ���̃W�b�^�̗h��i�U���j�̎��g���ŁA�M�������̎��g���i88���s�A�m�̈�ԉ��̌��̃��̉���27.5Hz�Ƃ��j�ł�
�Ȃ��ł���B
�����ԍ��F21760226
![]() 5�_
5�_
���t�ŏ����ƕ������̂ŁA���̎��������ăT�E���h���ł���AWolframAlpha�Ƃ����T�C�g���������̂ŁA
���g��1kHz�̏���sin(1000×2��)t�̈ʑ��p(1000×2��)t�Ɏ��g��5Hz�̐����g�W�b�^sin(5×2��)t��t������
sin((1000×2��)t�{sin(5×2��)t)
�̉���ɂ��Ă݂��B
https://www.youtube.com/watch?v=R5sWh_nxgzE
�܂��A�p��̃y�[�W�����ǁA
http://www.sereneaudio.com/blog/what-does-jitter-sound-like
�ł��W�b�^�̉�����B
�����ԍ��F21760866
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
�����A����͂Ƃ�ł��Ȃ����Ⴂ�����Ă��܂����i���p���������j^^�U
3Hz�̓W�b�^�[�̐U���̎��g���A�Ȃ�ł��ˁB�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����i [21756099] �j���u����������ƃW�b�^�[�i�ʑ��j���̂�3Hz�ŕϒ������悤�ł��v�Ə�����Ă����̂����O���Ă��܂����B
tohoho3�����p���ꂽ�܂Ƃ߂̃T�C�g�ihttps://www.edn.com/design/test-and-measurement/4423170/The-many-faces-of-jitter�j�̂U�̃O���t�̂����́gJitter Spectrum�h�ŁAX�������g���AY�����W�b�^�[�ƂȂ��Ă܂����A���̏ꍇY���̃X�P�[����Hz�ł��悢�̂ł��傤���H �悭����Y���́gjitter amplitude�h�ƂȂ��Ă��ĒP�ʂ��悭�킩��Ȃ������肵�܂���ˁB���̓�������̘_���ł́AJitter Spectrum��Y���͎���=ns�Ő}���Ă��܂���ˁB�Ȃ̂ŁA���g���Ƃ����AX�����Ƃ���v���Ă��܂����B����ƁA�J�N�^����́u���M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��v�b�������Ɠ��ɂ������̂ŁA�g3Hz�h�Ƃ����u���M���v�̂��Ƃ��Ƒ����_���Ă��܂��܂����B�ǂ������݂܂���B
�����ԍ��F21760943
![]() 4�_
4�_
>X�������g���AY�����W�b�^�[�ƂȂ��Ă܂����A���̏ꍇY���̃X�P�[����Hz�ł��悢�̂ł��傤���H
�W�b�^�Ƃ́A���Ԏ���̊�ʒu�ɑ��鎞�Ԏ������̕ϓ��ʂȂ̂ŁA�P�ʂ�s�i�b�j�Ǝv���B
�����͌o�ߎ��Ԃ̈Ӗ��ł̎��Ԃ��Ǝv���B
�����ԍ��F21761033
![]() 4�_
4�_
tohoho3����A����ɂ��́B
>���肢�A�Y��l�A�D����������āB
�ׂ������Ɉ����������ďo�����Ȃ��G���W�j�Atohoho�������ڂɁA��Â��݂ɂ����Ɨ������ĎВ��ɂȂ銯��K���E�E�E�݂����ȁi�\�j�[���Ă���Ȋ����̉�ЁH�j�B
���傤���Ȃ��̂ŏ��w�������ɁB1Hz�̃N���b�N�ɍ��킹�āA�ł낤�搶�̋�C�C���ł��o�����Ƃ��܂��傤�B�W�b�^�[���Ȃ���ΐ��m�ɂP�b�Ԋu�Łu�e�v������Ă��܂��B�u�U��0.1�b�̃N���b�N�W�b�^�[�v�Ƃ́A�N���b�N�̗��z�ʒu�ɑ���-0.1�b�`+0.1�b�̃Y��������Ƃ������Ƃł��B
���ʂȃP�[�X�Ƃ��āA-0.1�b�`+0.1�b�̊Ԃ������P���̃T�C���g�ŋK���I�ɕω�����Ƃ��܂��傤�B��������ƁA�u�e�v������Ă���Ԋu�͐��m�ɂP�b�ł͂Ȃ��A����𒆐S�ɁA�i�����P���Łj�P�b���k�艄�т��肵�܂��B����Ȃ�킩�邩����H
��������̖��ɖ߂��čl����ƁA�{���̉��̍��������������Ȃ�����Ⴍ�Ȃ����肷�邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�A�r�u���[�g�B�_���ł̓��E�E�t���b�^�[�̐�s���������p����Ă��܂����A�������Ƃł��B
���Ȃ݂Ɂu�e�v������Ă���Ԋu���P�b��������Ƃ��Y����̂́A�W�b�^�[��-0.1�b���邢��+0.1�b������̂Ƃ��ł͂Ȃ��A���傤�Ǘ��z�ʒu�ɂ���Ƃ��ł��B�܂�N���b�N�ʒu���̂��̂ł͂Ȃ��W�b�^�[�̎��Ԕ������|�C���g�Ȃ킯�ł����A�����͎����ōl���Ă݂܂��傤�i�h�b�v���[���ʂ��߂��ł����ˁj�B
>�ŁA���̃W�b�^�X�y�N�g�����́Ahttp://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf�̘_����
>�W�b�^�X�y�N�g�����Ɠ����Ȃ́H
EDN�̋L�q�͂�����ƃA�o�E�g�ł����A�����ƌ��Ă悢�Ǝv���܂��BEDN�̌����u���z�N���b�N�v����ʂɂ͖��m�Ȃ̂ŁA�M����P�Ƀt�[���G�ϊ������̂ł͂��߂ŁA����̘_���ł̓q���x���g�ϊ����o�Ă���킯�ł��ˁB
�����ԍ��F21761449
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A
�������킩��₷���B�L��������܂����B
�Ƃ���ŁA�F���c�q�J���Ƃ����C�J�R���Ƃ��A�̐���1/f�h�炬�����̎�͐S�n�悢�ƌ����Ă��邪�A
����1/f�h�炬�Ƃ́A�W�b�^�̎��g�������̗h�炬�Ȃ̂��H
�ł���A�W�b�^���Ȃ��������ł͂Ȃ��A�l�H�I��1/f�h�炬�W�b�^��t������ƁA���O�̍����t���Ɠ��l�ɁA
�Ɖu�����Ƃ���������̂��낤���H
�����ԍ��F21761590
![]() 5�_
5�_
>����1/f�h�炬�Ƃ́A�W�b�^�̎��g�������̗h�炬�Ȃ̂��H
���[�~���� 1/f �Ƃ͒m��Ȃ��������ǁA�P�Ɏ��g�����̗̂h�炬�ł悢���ƁB�܂��ʑ����h�炢�ł����g�����h�炮�킯�ł����B
�u�r�u���[�g�v�͊��ɍČ��ɐ������Ă�����ł��ˁB���₢�B�ق߂Ă����܂��B
�����ԍ��F21761693
![]() 5�_
5�_
�Y�ꂳ��ɂ��J�߂���������Ƃ͌��h�ł������܂��B
���v���o�������ǁA�e�̗Ⴆ�́A�t�@�C���}�������̗ʎq�͊w�ł̗ʎq�̗��q���Ɣg�����̈Ⴂ��
�����ł���܂����ˁB
�����ԍ��F21761827
![]() 4�_
4�_
Symbolist_K����A�O�̂��߁B
�������̂�����ɂ��Ă͎ɒ킩��̉ō����Ă��܂��B���h�ɉ����ł���悤�ɂȂ��Ă��˂�����͂��ꂵ���ł��i�܁j�B
�Ȃ��A���͉��呲����Ȃ��ĉ��吶�ł����E�E�E�ߋ����O�F��������v�Z������͋֎~�ł��B
Don't think. FEEL!
�����ԍ��F21762055
![]() 5�_
5�_
�����́ASymbolist_K�����Ȃ��ȁB
�Y�ꂨ�o���܂́A������ƃJ�`���Ƃ��镨���������āA�O�X���݂����Ɉꐶ�Y��Ƃ����G���������肷�邪�A
���������̂͊m���ŁA���͍D�������B
�����ԍ��F21762647
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
tohoho3����
���������肪�Ƃ��������܂����B
���낢��ȕ����ɂ���W�b�^�[�̒�`�𗅗Ă݂�ƁF
���W�b�^�[�Ƃ́u�f�W�^���M���̎��Ԏ��̗h�炬�v�B
���W�b�^�[�Ƃ́u�M���g�`�̃^�C�~���O�̕ϒ��itiming modulation�j�v�B
���W�b�^�[�Ƃ́u�f�W�^���M���̗L�ӏu�Ԃ̗��z�I�Ȏ��Ԉʒu����̒Z���I�Ȉʑ��ϓ��v�B
�u���z�I�Ȏ��Ԉʒu�vTn�͗��z�I�ȃf�W�^���g�`���������l�ƌ����_�B�u�L�ӏu�ԁvtn�͎��ۂ̃A�i���O�g�`���������l�ƌ����_�B�W�b�^�[���Ȃ킿�ʑ��ϓ���n�́A����2�̍���n=tn�|Tn�B
���W�b�^�[�ʂ͎��ԁi�ʑ��j�h�炬�̑傫���B�܂�W�b�^�[�ʂ͎��ԂȂ̂ŒP�ʂ�S(�b�j�ŁA�܂��������Ƃɕϓ�����̂ŕϓ��ʂϒl�����ăW�b�^�[�ʂƂ���B
�ȂǂƂȂ��Ă���̂ŁA�ЂƂ��ƂŌ����A�u�W�b�^�[�����ԁi�ʑ��j�h�炬�v�Ƃ������Ƃł���ˁB
�����āu�W�b�^�[�ʁ��W�b�^�[�U���iamplitude�j�����ԗʁv�ł���ˁB
�����A��L�̐����́A���ꂼ��A
https://www.edn.com/design/test-and-measurement/4423170/The-many-faces-of-jitter
�ɂ���U�̃O���t�̂����̂ǂ̃O���t�Ɋ�Â��Č����Ă���̂��ɒ��ӂ���K�v������܂��ˁB
�����ŁAtohoho3����̂��w�E�́A
���u3Hz�v�́A���Ԏ���̃W�b�^�̗h��i�U���j�̎��g��
�Ƃ����̂́A�gJitter TIE�h�̃O���t�ɉ����Ď��Ԏ���łRHz���̝���������A�r�u���[�g���������Ă���A�Ƃ������Ƃł����āA������t�[���G�ϊ������gJitter Spectrum�h�̂w���̎��g���̘b�ł͂Ȃ��̂ł���ˁB
�gJitter Spectrum�h�̂w���́u���g���v�́u�M�������̎��g���v�A�܂�u88���s�A�m�̈�ԉ��̌��̃��̉���27.5Hz�v�Ƃ��̒l�ŁA�gJitter Spectrum�h�Ƃ͐M�������̂ǂ̎��g���̂Ƃ���ɂǂꂾ���̃W�b�^�[�U�������ԗʂƂ��Ă��邩�Ƃ������Ƃ��������̂ł���ˁB
�Ƃ��������ł����Ă܂��ł��傤���H
�����ԍ��F21762782
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
�u1/f�h�炬�v�Ƃ����̂��ʔ����b�ł��ˁB
Wikipedia�ɂ��A
��1/����炬�Ƃ́A�p���[�i�X�y�N�g�����x�j�����g�� f �ɔ���Ⴗ���炬�̂��ƁB������ f �� 0 ���傫���A�L���Ȕ͈͂��Ƃ���̂Ƃ���B�s���N�m�C�Y�͂���1/����炬�����m�C�Y�ł���A1/���m�C�Y�Ƃ��Ă��B���R���ۂɂ����Ă����邱�Ƃ��ł��A��̗�Ƃ��Ă͐l�̐S���̊Ԋu�A�낤�����̉��̗h����A�d�Ԃ̗h��A����̂����炮���A�ڂ̓������A�ؘR����A�u�̌�����Ȃǂ�����B�܂������I�ɂ́A�����̒�R�A�l�b�g���[�N�����Ƃ��ċ�������B
������ʑ��ϓ��̈�킾�Ƃ�����A�W�b�^�[�ł���Ƃ������Ƃł��ˁI
������̂܂Ƃ߃T�C�g�ɂ��A
https://matome.naver.jp/odai/2144492447223820901
1/����炬�������̐������A�[�e�B�X�g�́F
�E�F���c�q�J��
�EMISIA
�ELIA
�E���C�J�R��
�E����Ђ�
�E���i�p��
�E�g�c���a
�E��{����
�E�����Ƃ�
�E�쓇����
�EMs.OOJA
���Ƃ��B
�����ԍ��F21762786
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���炢�����܂����B�܂�����ɂ��ݐЂł������I ��w�@���ł��傤���H
�ł��A�O�X���ŁAMinerva2000����Ƙ_���𑱂��Ă͂�10�N�A�݂����Ȃ��Ƃ�����������Ă��悤�ȋC���d�d�d
����Ɓd�d�A����A�����炭���n�̐_���_�q�������̂ł��ˁI
�����ԍ��F21762809
![]() 6�_
6�_
Symbolist_K����A
Wikipedia�́u1/����炬�Ƃ́A�p���[�i�X�y�N�g�����x�j�����g�� f �ɔ���Ⴗ���炬�̂��Ɓv�͊ԈႢ�݂����ł���B
http://www2.gol.com/users/somestic/1fyuragi.htm
�ł́A
�u���y�����̂܂܃t�[���G���́i���g�����́j����ƁA���y�̎��g���X�y�N�g�������͂���A���̎��g���ш�ͤ�}�� 20�`20KHz �ɂȂ�܂��B����A���y�̂�炬�͂����X�y�N�g���̎��g���ш�́A�}�� 0.005Hz�`5Hz ���炢�ɂȂ�܂��B���̎��g���ш�̈Ⴂ�������A���͂��Ă�����e�̈Ⴂ���悭�\���Ă���Ǝv���܂��B�v
�ƌ����Ă���B���Ԏ��ł̃W�b�^�i�r�u���[�g�j�g�`���t�[���G�ϊ������W�b�^�X�y�N�g�����̋��x��1/f�ɔ�Ⴗ��Ƃ������Ƃ��H
�����ԍ��F21763009
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
�����p�̏��������̘_�q�ł́A�u�����I�ɂ́gP��1�^���̃ɏ�h�ŕ\����܂��v�ƒ�`���āAX�������g���AY�����p���[�Ƃ����X�y�N�g���O���t��ł̌X�������y�̐��������߂�ƌ����Ă��܂��ˁB���̂Ƃ���=1�̏ꍇ��1/����炬�ŁA�O���t��45�x�̌X���ƂȂ�A���y�Ƃ��Ắu���Ґ��ƈӊO�����j�R�����A�K�x�ȑ����ƓK�x�ȕω��̃o�����X���Ƃꂽ���y�v�ɂȂ�Ƃ������b�ł��ˁB
Wikipedia�́u1/����炬�Ƃ́A�p���[�i�X�y�N�g�����x�j�����g�� f �ɔ���Ⴗ���炬�̂��Ɓv�Ƃ�����`�́gP��1�^���̃ɏ�h�Ƃ����W���������Ă��邾���ŁA�u���̔����W�̒��Ń�=1�̏ꍇ�݂̂�1/����炬�ł���v���Ƃ���肵�Ă��Ȃ����炨�������A�Ƃ������Ƃł���ˁB
���y�̐����Ƃ̏d�v�ȊW�ɂ��Č���Ă��镔�������p���܂��F
��
�����F�����I�ɂ́gP��1�^���̃ɏ�h�ŕ\����܂��BP�̓p���[�Af��frequency�̓������Ŏ��g����\���܂��B1�͕���1/���̕��q�ŁA1/���͎��g���̋t���ł����� ���g�����{�ɂȂ�Ƥ�p���[P�� 1/2(����)�ɂȂ�B���g����10�{�ɂȂ�����p���[��1/10�ɂȂ�c�Ƃ������W�ł��B
�@�����Ɏ��g���A�c���Ƀp���[���Ƃ藼�ΐ��O���t�ŕ\���܂��B�}�S�i�X�y�N�g���O���t�j�����Ă��������B�����̎��g��1Hz�O��̂�����̃p���[�������Ȃ�ƃX�y�N�g���͐��������ɋ߂Â��܂��B�܂�ɂ̒l���������Ȃ�܂��B�t�̏ꍇ�̓ɂ̒l���傫���Ȃ�܂��B�gP��1�^���̃ɏ�h�̐��������̂��Ƃ�\���Ă��܂��B
�@�ɂ͎w����1/���́g1�^����1��h�̂��Ƃł��BF��1�恁f������ł��B�܂��=1�̏ꍇ��1/����炬��45�x�̌X���ɂȂ�܂��B���̃ɂ͂�炬�̐�����\���w���ł��B
�c���F�ɂƂ�炬�̐����̊W�́H
�����F�ɂ�2�̏ꍇ�́A�ω��̏��Ȃ��P���ȁg1�^����2��h��炬�ƂȂ�܂��B�������ꂪ���y�Ȃ�h���̎ア�P���ȉ��y�ɂȂ�g1�^����2��h��炬�X���̉��y�ł��B�ɂ�1���傫���Ȃ���A���̌X�������܂�܂��B�o�ɂ��A���g�Ƌx���ɓ����Ƃ������Ă��܂��B
�c���F�X�y�N�g���O���t�̏�ł͌X����60�x���炢�ɂȂ��Ă��܂��ˁB
�����F�ɂ�1�̏ꍇ�́A�K�����ƈӊO�����o�����X�ǂ��Ƃ�Ă���1/����炬��\���܂��B1/����炬�̉��y�́A���Ґ��ƈӊO�����j�R�����A�K�x�ȑ����ƓK�x�ȕω��̃o�����X���Ƃꂽ���y�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�o����Ԃōł����_�̈��肪�������ԂƂ������Ă��܂��B
�c���F����͗ǂ��m��ꂽ45�x�̌X���ł��ˁB
�����F�ɂ�0�̏ꍇ�́A�K�����̂܂������Ȃ��h���̋����g1�^����0��h��炬�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�ɂ�1��菬������0�ɋߕt�����A���y�͎h���̋������̂ɂȂ�܂��B�ْ��Ƌ����������˂�U�����鐫��������Ƃ������Ă��܂��B
�c���F����͐����ɂȂ�킯�ł��ˁB
�����F���̂悤�Ƀɂ͂�炬�̐�����\���d�v�Ȏw���Ȃ̂ł��B
����A���̂悤�ȕ��͂ʼn��y�̌X�����킩��Ƃ́A�Ȃ�Ƃ������[���ł��ˁI
�����ԍ��F21763447
![]() 5�_
5�_
>Wikipedia�́u1/����炬�Ƃ́A�p���[�i�X�y�N�g�����x�j�����g�� f �ɔ���Ⴗ���炬�̂��Ɓv�Ƃ�����`�́gP��1�^���̃ɏ�h�Ƃ���
>�W���������Ă��邾���ŁA�u���̔����W�̒��Ń�=1�̏ꍇ�݂̂�1/����炬�ł���v���Ƃ���肵�Ă��Ȃ����炨�������A��
>�������Ƃł���ˁB
����́A���܂�{���I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
���y�̐M���g�`�i�I�V���X�R�[�v�ő��肵���O���t�A���������ԁA�c�����U���j���t�[���G�ϊ������A�p���[�X�y�N�g�����x
�i���������g���A�c���ɑ傫���i�p���[�j�j�̃O���t�ɂ́A���y�Ɋ܂܂��u20Hz�`20KHz�v�̂��܂��܂Ȏ��g�������̑傫��
���\����Ă���B���̃O���t�̎��g�������̑傫����1/f�ɔ�Ⴕ�Ă��邩��1/f�h�炬�Ƃ����̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƁB
����́A���O�Ɉ��p�����A
�u���y�����̂܂܃t�[���G���́i���g�����́j����ƁA���y�̎��g���X�y�N�g�������͂���A���̎��g���ш�ͤ�}�� 20�`20KHz �ɂȂ�܂��B�v�̕���
���̕���
�u����A���y�̂�炬�͂����X�y�N�g���̎��g���ш�́A�}�� 0.005Hz�`5Hz ���炢�ɂȂ�܂��B���̎��g���ш�̈Ⴂ�������A���͂��Ă�����e�̈Ⴂ���悭�\���Ă���Ǝv���܂��B�v
���������B����́A��Ő��������u20Hz�`20KHz�v�̊e���g���������h�炢�ł��āA���̗h�炬�̎��g�����u0.005Hz�`5Hz�v
�Ƃ������ƁB�O�̓���https://www.youtube.com/watch?v=R5sWh_nxgzE�́A1kHz�̏����i1�̎��g�����������Ȃ��j�Ɉʑ��p��
�h�炬�Ƃ���5Hz�̎��g���̐����g�����Z�������̂ŁA�悭����ƁA�Y�t�}�̃I�����W�Ŋۂ����������̏����ȏc�̐Ԑ��i�X�y�N�g���̃s�[�N�ʒu�̎��g���i1kHz�ߖT�j�������Ă���j�����g��5Hz�ŗh�炢�ł���̂��킩��B�Ȃ̂ŁA1/f�h�炬�̎��g���Ƃ́A
���̎��g���̂��ƂŁA���y�̐M���g�`�Ɋ܂܂����g�������i�M���g�`���t�[���G�ϊ��������́j�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��{���B
���Ɖ��͉��߂����B
�����ԍ��F21763564
![]() 5�_
5�_
����Atohoho���́A������Ƃق߂�����T�{���Ă邵�B�܂������B
Symbolist_K����[21762782]
>�Ƃ����̂́A�gJitter TIE�h�̃O���t�ɉ����Ď��Ԏ���łRHz���̝���������A�r�u���[�g���������Ă���A�Ƃ������Ƃł����āA������t�[���G�ϊ������gJitter Spectrum�h�̂w���̎��g���̘b�ł͂Ȃ��̂ł���ˁB
�����A���Ȃ�Ԉ���Ă���Ǝv���܂���B�ȂA�В��̓�������(��)�B�t�[���G�ϊ��͗������Ă��܂����H�ȉ��������Ⴂ���Ă��Ȃ���E�E�E���ĂȂ��Ǝv���܂����B
��̂ق��ŏ������u3Hz�̐����g��W�b�^�[�v��EDN�́gJitter TIE�h�̃O���t�ŕ\���A�܂���3Hz�̐����g�ł��B������t�[���G�ϊ��i�e�e�s�j�������̂��gJitter Spectrum�h�ł����A���̗�̏ꍇ��3Hz�̈ʒu�Ɉ�{�������C���X�y�N�g���������܂��B
>�gJitter Spectrum�h�̂w���́u���g���v�́u�M�������̎��g���v�A�܂�u88���s�A�m�̈�ԉ��̌��̃��̉���27.5Hz�v�Ƃ��̒l�ŁA�gJitter Spectrum�h�Ƃ͐M�������̂ǂ̎��g���̂Ƃ���ɂǂꂾ���̃W�b�^�[�U�������ԗʂƂ��Ă��邩�Ƃ������Ƃ��������̂ł���ˁB
�����ł͂Ȃ��ł��B�M�����g����100Hz���낤��1kHz���낤���A3Hz�̃s�b�`�̃r�u���[�g��������Ƃ������Ƃł��B���E�E�t���b�^�[�Ƃ����ق����킩��₷���ł����ˁB�܂��J�Z�b�g�e�[�v�����R�[�h���A�������܂ꂽ���ɂ͂��łɐg�̎���ɂ͂Ȃ������̂Ńs���Ƃ��Ȃ����ǁE�E�E�i��ɂ����������ǁA���ꂱ��v�Z�֎~�j�B
�����ԍ��F21763801
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����ɂ́A�t���[��WaveSpectra��WaveGene�Ƃ����A�M����́^�����\�t�g�E�F�A��
�_�E�����[�h���āA�V��ł݂�Ƃ��������ˁB
�܂��Ahttps://www.youtube.com/watch?v=R5sWh_nxgzE�̓���̂悤�ɁAWolframAlpha�Ƃ����T�C�g�ŁA
play���߂��g���āA�����̉����Ȃ���AWaveSpectra�Ń��A���^�C���g�`�^�X�y�N�g�����\��������
�V�Ԃ̂����������ˁB
�����ԍ��F21764119
![]() 5�_
5�_
tohoho3����[21760866]��
>sin((1000×2��)t�{sin(5×2��)t)
>
>�̉���ɂ��Ă݂��B
�ł����A���̔g�`�̃W�b�^�[�U���͉�ns�ł��傤���ˁH��̓I�Ȑ������Ƃ킩��ɂ����̂�
�M���̊p���g�� �F��o���Q��×�P�O�O�O �i�PkHz�j
�W�b�^�[�̊p���g�� �F��j���Q��×�T �i�THz�j
�Ƃ�����
sin { ��o t + sin (��j t) }
�Ƃ�������܂��B�����ό`���܂��i����������܂���j�B
sin [ ��o { t + 1�^��o �Esin (��j t) } ]
���̒��́@1�^��o �Esin (��j t) �̕������W�b�^�[�����ŁA���Ԃ̎����������܂��i������Ɠ��������j�B�܂�W�b�^�[�U����
1�^��o �� 1�^(�Q��×�P�O�O�O) �� �P�T�X�ʂ�
�ƂȂ�܂��B�l�Ԃ̌��m���Ƃ���鐔�����R�P�^�ȏ�傫���̂Ŋy�ɂ킩��킯�ł��ˁB�t�ɁA�W�b�^�[�U�� J �b�̔g�`����肽���̂ł����
sin [ ��o { t + J�Esin (��j t) } ]
�Ƃ���悢�ł��B�͂�����80ps�̃W�b�^�[�͌��m�ł���ł��傤���H�������A��ɏ������悤�ɁA�����ɏ������̃W�b�^�[���������͎��ۂƂ͂�������ăW�b�^�[�����m���₷���ł��傤�B
�����ԍ��F21764128
![]() 6�_
6�_
�⑫�ł��B
80ps�Ƃ������x���ɂȂ�ƍĐ����u���̃W�b�^�[�̂ق����傫���\�����������ɂ���܂����A�����łȂ��Ă��������W�b�^�[���ƍĐ����W�b�^�[�Ƃ̊��i���A���j�̂悤�Ȃ��̂������邩������܂���ˁB�Z���I�Ȕ��f�͋֕����Ƃ͎v���܂��B
�����ԍ��F21764175
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
��̂��w�E�́A
���_���ɂ���悤�ɌÂ������̐M�����ɂ͒��ӂ���K�v�����肻���ł����A�܂��A�_���Ɂu�����Ƃ����x�̍����ϒ����g���RHz�ɂ����āv�Ƃ���������������܂��B��s�������ǂ߂Ȃ��̂Ő����ł����A����̓W�b�^�[�̈���E�������RHz�ŌJ��Ԃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����B
�������ł��B
>����̓W�b�^�[�̈���E�������RHz�ŌJ��Ԃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����B
�́A�Ⴂ�����ł��B����������ƃW�b�^�[�i�ʑ��j���̂��RHz�ŕϒ������悤�ł��B
�ɉ����Č��y����Ă����s�����́A
Hisao Sakai, �gPerceptibility of Wow and Flutter,�h Journal of Audio Engineering Society, 18, 290-298�i1970�j
�ł����A���̘_���̓l�b�g��ł͓ǂ߂܂���ł����B���̑���A�������v�Y���ɂ��w���E�E�t���b�^�[�x(1973�j��ǂ݂܂����F
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/29/12/29_KJ00003053553/_pdf
���_���́A
�����g���ϓ������m�ł���ϓ��ʁi���m���j�͑����̐l�X�ɂ���đ��肳��Ă��邪�A�}-3�Ɏ����悤�ɂ��̌X���͂قڈ�v���Ă���B���ꂩ��킩��悤�ɁA�ϓ����g����2�`5Hz�̂Ƃ��ł��������ϓ��ʂŌ��m����A���̒l��0.1���̕ω����Ȃ킿1000Hz�̐M����1Hz�ω����Ă������͂���������邱�Ƃ������Ă���B�ϓ����g�����M�����g���ɋߐڂ����ꍇ�ɂ́A���m�����}���ɏ������Ȃ邪�A�y���Ȃǂɂ��̌��͂�����Ȃ��B��ʂɂ͐M�����g���ɂ�錟�m���̈Ⴂ�͏������B
�Ƃ������Ƃ��w�E���A���ۂɁAShower & Biddulph (1936)�ASchecter (1948)�AZwicker (1952)�AStott (1955)�AComerci (1955)�A�����Sakai (1957) �̂��ׂĂ̐�s�����ŁA�t���b�^�[���g�����ϓ����g������3Hz�̂Ƃ��Ɍ��m�����ŏ��ɂȂ�Ƃ������ʂ������ʂ��o�����Ƃ������Ă��܂��B
������A�u�����Ƃ����x�̍����ϒ����g���RHz�ɂ����āv�Ƃ�����̋L�q�̍����́A�u�����̎������ʂ������ł������v�Ƃ��������̂��Ƃ݂����ł��ˁB
����ɁA���̋��́w���E�E�t���b�^�[�x�_�����Q�l�����Ƃ��Ă���A�������t�́w���E�E�t���b�^�[�̋K�i�x�i2010�j���ǂ݂܂����F
http://www.jas-audio.or.jp/jas-cms/wp-content/uploads/2010/12/201011_18-24.pdf
���̘_���̏d�v�Ȏw�E�����p����ƁF
���������E�E�t���b�^�[���e�������琶���A�e��̎����������E�E�t���b�^�[���������ꂽ���̂ł���Ƃ���A�e�X�̃��E�E�t���b�^�[���g���Ƃ��̕ϓ��ʁi���E�E�t���b�^�[�ʁj�̊Ԃɂ͒�����W������B
��
(a) �M���̎��g���ɂ͊W�Ȃ��B
(b) �M�����͕������̂ق����������ڗ��B���������ۂɂ͉��y���b�Ȃǂ̕������̓��x���̕ω���r�u���[�g�̂悤�ɁA���łɎ��g���ϓ����Ă���ꍇ�������̂ł킩��ɂ����B
(c) �������͌����������قǖڗ��B�s�A�m�̏ꍇ�͂ނ��뎝�����I�ȕ��������邽�ߖڗ��B
(d) �ϓ��g�`�i���E�E�t���b�^�[�j�́A�g�����̍����g�`�A���Ȃ킿�p���X�I�ȕϓ��̕��������g�I�ȕϓ����ڗ��B
(e) �M�����̑傫���ɂ͂��܂�W�Ȃ��B
(f) �ϓ��̎����i���E�E�t���b�^�[���g���j��3Hz�O�オ�ڗ��B��q�̏d�Ȑ��i������Ȑ��j�͌��m���̎��g�����������߂�ꂽ���̂ł���B
(g) �v���O�����ɂ�鍷�́A�\52-1�Ɏ����悤�Ƀs�A�m�Ƒt���ڗ����A�V���z�j�[�A�j���̏��ɂȂ��Ă���B
�����̋L�q���瓱���o���鎄�ɂƂ��Ă̋��P�́A�u�M���̎��g���v�Ɓu�ϓ����g�������E�E�t���b�^�[���g���v�͂悭��ʂ��ׂ��Ƃ������Ƃł��B
���āA�����������utohoho3����̂��w�E�́A�w�u3Hz�v�́A���Ԏ���̃W�b�^�̗h��i�U���j�̎��g���x�Ƃ����̂́A�gJitter TIE�h�̃O���t�ɉ����Ď��Ԏ����3Hz���̝���������A�r�u���[�g���������Ă���A�Ƃ������Ƃł����āv�܂ł͂悩�����̂ł���ˁB�܂�u3Hz���̝����v�Ƃ́u�ϓ����g���v���w���Ă���A�u�M�����g���v�ł͂Ȃ��ƁB�ł��A����ɑ����u������t�[���G�ϊ������gJitter Spectrum�h�̂w���̎��g���̘b�ł͂Ȃ��̂ł���ˁv���܂��������ł��ˁB�u�gJitter Spectrum�h�̂w���̎��g���v���܂��u�ϓ����g���v�̒l�ŁA���̂x���͕ϓ��ʂ�U���̎��Ԃŕ\�������̂ł���ˁB
������A�P�Ɂu�gJitter Spectrum�h�̂w���̎��g���v���u�M�����g���v���Ƒ��Ƃ��肵����ł���ˁB�u�gJitter Spectrum�h�̂w���́u���g���v�́u�M�������̎��g���v�A�܂�u88���s�A�m�̈�ԉ��̌��̃��̉���27.5Hz�v�Ƃ��̒l�ŁA�gJitter Spectrum�h�Ƃ͐M�������̂ǂ̎��g���̂Ƃ���ɂǂꂾ���̃W�b�^�[�U�������ԗʂƂ��Ă��邩�Ƃ������Ƃ��������̂ł���ˁv�Ə������̂��A�������̑��Ƃ�����_�������I�ɌJ��Ԃ��������ł���B
�܂�A�O���t�̓ǂ݊ԈႢ�Ƃ����܂����A������Ɗᐸ��J�����Č��ԈႢ�����܂����Ƃ����܂����A�_���ǂ����Ɏߓǂ݂��ăT�{�������Ƃ����܂����A����łƂ���܂����B���߂�Ȃ����B
���M�����g����100Hz���낤��1kHz���낤���A3Hz�̃s�b�`�̃r�u���[�g��������Ƃ������Ƃł��B���E�E�t���b�^�[�Ƃ����ق����킩��₷���ł����ˁB
�͂��A���ł͂������Ƃ킩��܂����B
�t�[���G�ϊ��ɂ��ẮA�������ł��B
�Ƃ肠�����A����F
http://www.yukisako.xyz/entry/fourier-transform
��ǂ݂܂������A���ꂶ��_���ł����H
�����ԍ��F21764680
![]() 6�_
6�_
tohoho3����
��WolframAlpha�Ƃ����T�C�g�ŁAplay���߂��g���āA�����̉����Ȃ���AWaveSpectra�Ń��A���^�C���g�`�^�X�y�N�g�����\�������ėV�Ԃ̂����������ˁB
�V�т̂��Љ�肪�Ƃ��������܂��B
���������V�т����Ȃ���A�ڂƎ�Ǝ����g���Đ����Ɋ���e����ł䂭���Ƃɂ���āA���������g���čl���Ă��邾�������͂₭�A�{���̈Ӗ��ł́u�����v�ɓ��B�ł��邩������܂���ˁI
�����ԍ��F21764748
![]() 6�_
6�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A���ɍ��킹������L��������܂����B
�������킩��₷�������ł��B���t�������Ƃ���͂��邯�ǁA�{���͗D������ł��ˁB
Symbolist_K����A
>�t�[���G�ϊ��ɂ��ẮA�������ł��B
>�Ƃ肠�����A����F>
>http://www.yukisako.xyz/entry/fourier-transform
>��ǂ݂܂������A���ꂶ��_���ł����H
������Ȃ��ł����B�Y�ꂳ��̎��ɂ�����������ł���悤�Ɋ撣���Ă��������B
�����ԍ��F21764754
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����͒@����Ĉ�^�C�v�ł��ˁB�������뒿�����B���E�E�t���b�^�[�͗��j���������������ĕ����͂������肻���ł��ˁB�Ƃ���ŁA
>�ڂƎ�Ǝ����g���Đ����Ɋ���e����ł䂭���Ƃɂ���āA���������g���čl���Ă��邾�������͂₭�A�{���̈Ӗ��ł́u�����v�ɓ��B�ł���
�́A�������ׂ����Ƃ��Â��v���܂��B�Ƃ����̂��A�r�u���[�g�Ƃ����E�E�t���b�^�[�Ƃ������Ō����o���Ă����ăi�j�ł����Atohoho3����̉� https://www.youtube.com/watch?v=R5sWh_nxgzE ���āA�����͕������Ȃ��ł���ˁH�����͂قڈ��ŋ��オ���Ă��銴���ł��B�Ȃ̂ŁA�����Ƃ悭�l����K�v������܂��B
��X�̉F���ɂ����鎞�Ԃ� t �ŋL�q����Ă���A���̐i�ޑ����� dt/dt = 1 �ň��ƔF������Ă��܂��B�������W�b�^�[������n�ł͂��ꂪ
t' = t + J sin(��j t)
�ɂȂ��Ă���̂Ɠ������Ǝv���܂����A���̐i�ޑ����͉�X�̎��� t �ő�����
dt'/dt = 1 + J��j cos(��j t)
�ł��B���������Ĕނ̌n����������p���g�� ��o �̏����͉�X�ɂ�
��o�^{ 1 + J��j cos(��j t) } �� ��o { 1 - J��j cos(��j t) }
�̂悤�ɕϒ�����ĕ������܂��i������ J��j << 1 �Ƃ��ĂP���ߎ����s���܂����j�Btohoho3����̗�ł�[21764128]�ŏ������悤�� J = 1�^��o �Ȃ̂ł�����������
��o - ��j cos(��j t)
�ƂȂ�܂��B����́A��o = 1kHz �𒆐S�Ƃ��ă�j = 5Hz �h�炮���Ƃ������܂��B���ϗ��̔����̈Ⴂ�� 1kHz �t�߂� 60Hz ���炢�ł�����A���̗h�炬���r�u���[�g�ƌ����͖̂����ł��ˁB����ł��ASymbolist_K����[21764680]�ɂ���
>�ϓ����g����2�`5Hz�̂Ƃ��ł��������ϓ��ʂŌ��m����A���̒l��0.1���̕ω����Ȃ킿1000Hz�̐M����1Hz�ω����Ă������͂����������
�Ƃ̂��Ƃł��B��̗�ł� J��j = 0.5% �Ȃ̂ŁA�U���̗h�����Ȃ���Β����Ƃ��̂ł��傤�B�������A���{�s�h�� J = 80ps�����ƁA��j = 5Hz �Ƃ��� J��j = 4e-10 �ł�����˂��E�E�E�B
�܂��A���E�E�t���b�^�[�ɏڂ�������܂��Atohoho3����̉������E�E�t���b�^�[�ŏo���͖̂�������Ȃ��ł��傤���H�ʂ̌��ۂƂƂ炦��ׂ�����Ȃ����Ǝv���̂ł����B
�����ԍ��F21766142
![]() 6�_
6�_
�����Ȃ����Ă݂�ƁA����ς胏�E�E�t���b�^�[�̂悤�ȋC�����Ă��܂����E�E�E�B
�����ԍ��F21766146
![]() 3�_
3�_
tohoho3����́A�W�b�^�[ 1��s/100ns/10ns/1ns/100ps ������̉��� youtube �ɃA�b�v���悤�A�Ȃ�Čv��͂���܂��H
�����ԍ��F21766154
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A
�v�Z�Ƒ��삪�ʓ|�Ȃ�ŁA
sin((1000×2��)t�{0.05×sin(5×2��)t)
sin((1000×2��)t�{0.5×sin(5×2��)t)
sin((1000×2��)t�{5×sin(5×2��)t)
��3���A�b�v���܂����B
https://www.youtube.com/watch?v=2rgF2ZJjrJU
�����ԍ��F21766261
![]() 5�_
5�_
tohoho3����A���肪�Ƃ��������܂����B��Œ����Ă݂܂��B
����ƁA�ԈႦ�܂��� m(_ _)m �B
>���������Ĕނ̌n����������p���g�� ��o �̏����͉�X�ɂ�
�@��o�^{ 1 + J��j cos(��j t) } �� ��o { 1 - J��j cos(��j t) }
�Z�@��o×{ 1 + J��j cos(��j t) }
���̌�̌��ʂ͕ς��܂���B���傤�͒��q������E�E�E�B
�����ԍ��F21766342
![]() 3�_
3�_
>���傤�͒��q������E�E�E�B
���₢��A���܂ł̋c�_��ʂ��āA�u�q�J���̌�v�̓������ׂ̃Z���t�u�ނ���A�����Ȃ����i���������j�͎̂��ł��B�v�Ƃ���
�S������Ȃ��ł����H
>��o �̏����͉�X�ɂ�
>��o�^{ 1 + J��j cos(��j t) } �� ��o { 1 - J��j cos(��j t) }
>�̂悤�ɕϒ�����ĕ������܂�
���X�y�N�g�����̍L���肩��킩��܂���B
�����ԍ��F21766463
![]() 5�_
5�_
���[21766342]�̒������ԈႢ�ŁA����[21766142]�̌v�Z�Ő������ł��B�ǂ����ɂ��Ă����傤�͒��q�����ł��E�E�E�B
������tohoho3�����Symbolist_K������A�z�����Ă��Ȃ�����������Ă����̂ŁA�������ɑz��O�ɋ����Ȃ�������(��)�B
tohoho3�����youtube���Ă݂܂������A������W�b�^�[�����Ȃ���ł��킩��܂��ˁB�����������B�I���W�i���� 159��s �������̂ŁA����̈�Ԃ����Ȃ���i0.05�{�j�� 8��s �ł����ˁB�܂��W�b�^�[����������̂ŁA��قǂ܂��������邩���m��܂���B���q�����̂Ŗ{���͂���ɂāE�E�E�B
�����ԍ��F21766858
![]() 4�_
4�_
>������W�b�^�[�����Ȃ���ł��킩��܂��ˁB�����������B
WolframAlpha��Web�T�C�g�ʼn����o���ƁA�T���v�����O���[�g���Ⴂ���炩������܂���ˁB
Web�T�C�g��̉����Đ������Ƃ��̌������̃T���v�����O���[�g��\��������@��N���m��܂��ˁH
�X�s�[�J�ōĐ�����ƁA���܂��܂Ȕ��˔g�������ĐU���̂�炬�����g���̂�炬�ƕ����Ⴆ��\��
������܂���ˁB
https://www.youtube.com/watch?v=R5sWh_nxgzE#t=30
�̕����͏��������ǁA�X�s�[�J�ōĐ�����ƁA���̊��ł́A1�b�����ŗh�炢�ł���悤�Ɋ�����B
���邢�́A�O�X���Ńp�C�����\���Ă���
http://sonove.angry.jp/doppler.html
�̃h�b�v���[�c�Ȃ̂��H
�����ԍ��F21767471
![]() 4�_
4�_
�����������Ƃ���Ȃ��āA������W�b�^�[�����Ȃ���F
>sin((1000×2��)t�{0.05×sin(5×2��)t)
�ł����A�W�b�^�[�U���� 0.05�^(1000×2��) = 8��s �ł��B����Ă��錟�m���Ƃ��Ċɂ߂Ǝv���� 300ns �ɑ��Ă����P�P�^�ȏ�傫���̂ŁA�킩���ĕ��ʂł��B80ps �̃W�b�^�[�U���ɂ���Ȃ�[�����T���₵��
sin((1000×2��)t�{0.0000005×sin(5×2��)t)
�Ƃ���K�v������܂��B�������A�T�C�g�����̎��ԕ���\�ɑΉ����Ă���Ɗ��҂���ق��������ȋC�����܂��ˁB
���ƁA�ŏ���youtube���e�݂����ɁA���t�@�����X�̏�����������ׂ���ق��������ł��ˁB�����ƒ����Ă���Ǝ������������Ȃ��āA�����ł��c��ŕ������銴�������Ă��܂��B
�����ԍ��F21767808
![]() 5�_
5�_
>�T�C�g�����̎��ԕ���\�ɑΉ����Ă���Ɗ��҂���ق��������ȋC�����܂��ˁB
�ł��ˁB192kHz�T���v�����O�ł�5.1��s���̃T���v���ʼn���\�����Ă�̂ŁA80ps�̍��Ȃ�ĕ\���ł���ȁB
�������A�T�C�g�̎��ԕ���\�ɂ����E�ɉ����āAyoutube�ɃA�b�v���邱�Ƃɂ�鉹�f�[�^�̈��k�ł����ԕ���\��
���������̂ŁA
sin((1000×2��)t�{0.0000005×sin(5×2��)t)
�̉���youtube�ɃA�b�v���Ă��Ӗ��Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F21768158
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
tohoho3����
��sin [��o{t+1�^��o�Esin (��j t)}]
���̒���1�^��o�Esin (��j t) �̕������W�b�^�[�����ŁA���Ԃ̎����������܂��i������Ɠ��������j�B�܂�W�b�^�[�U����
1�^��o��1�^(2��×1000)��159��s
�ƂȂ�܂��B
�Ƃ������Ƃ�
sin {(1000×2��) t�{sin (5×2��) t)} �̉��Fhttps://www.youtube.com/watch?v=R5sWh_nxgzE �́A
�u�M�����g��1kHz�̏����ɁA�ϓ����g��5Hz�E�U��159��s�̐����g�W�b�^��t���������v�Ȃ̂ł��ˁB
�m���ɂP�b�ԂɂT��h�炢�ł��܂����A���̗h�ꕝ��159��s�Ƃ������Ƃł��ˁB
https://www.youtube.com/watch?v=2rgF2ZJjrJU ��
sin {(1000×2��) t�{0.05�Esin (5×2��) t)} �̉��̕����́A�u�M�����g��1kHz�̏����ɁA�ϓ����g��5Hz�E�U��8��s�̐����g�W�b�^��t���������v�ł����A�h�炬�͕�������悤�ȕ������Ȃ��悤�ȁB
sin {(1000×2��) t�{0.5�Esin (5×2��) t)} �̉��̕����́A�u�M�����g��1kHz�̏����ɁA�ϓ����g��5Hz�E�U��80��s�̐����g�W�b�^��t���������v�ł����A�P�b�ԂɂT��h�炮���̗h�ꕝ���A159��s�̔������ƌ����A�������炢�̂悤�ȁB
sin {(1000×2��) t�{5�Esin (5×2��) t)} �̉��̕����́A�u�M�����g��1kHz�̏����ɁA�ϓ����g��5Hz�E�U��80��s�̐����g�W�b�^��t���������v�ł����A�P�b�ԂɂT��h�炮���̗h�ꕝ��796��s�Ƃ������Ƃł����A�m����80��s��159��s�Ɣ�ׂĂ����Ȃ范�����h�炢�ł��܂��ˁB
tohoho3�����
��https://www.youtube.com/watch?v=R5sWh_nxgzE#t=30
�̕����͏��������ǁA�X�s�[�J�ōĐ�����ƁA���̊��ł́A1�b�����ŗh�炢�ł���悤�Ɋ�����B
�Ƃ������Ƃł����A���̊��ł́A���̗h�炬���Ȃ��悤�ɕ������܂��B
�O�X���Ńp�C�����\���Ă���
https://youtu.be/dlt5FgCEuk4
�݂����ȁu�����v�ł͂Ȃ��ł����H
��sin {(1000×2��) t�{0.05�Esin (5×2��) t)} �ł����A�W�b�^�[�U���� 0.05�^(1000×2��) = 8��s �ł��B����Ă��錟�m���Ƃ��Ċɂ߂Ǝv���� 300ns �ɑ��Ă����P�P�^�ȏ�傫���̂ŁA�킩���ĕ��ʂł��B
����A���ꂾ���Œ����Ɨh�炢�ł邩�ǂ����킩��ɂ����ł���B
���ŏ���youtube���e�݂����ɁA���t�@�����X�̏�����������ׂ���ق��������ł��ˁB
�����A8��s�̂�� https://www.youtube.com/watch?v=R5sWh_nxgzE#t=30
�̏��������Ɣ�r����ƁA������Ɨh�炢�ł���悤�ȋC�����Ă��܂��ˁB
��80ps �̃W�b�^�[�U���ɂ���Ȃ�[�����T���₵��sin {(1000×2��) t�{0.0000005�Esin (5×2��) t)}�Ƃ���K�v������܂��B�������A�T�C�g�����̎��ԕ���\�ɑΉ����Ă���Ɗ��҂���ق��������ȋC�����܂��ˁB
8��s�̂�ł�����Ɍ������悤�Ȋ����Ȃ̂ŁA�U��80ps�Ȃ�Đ�킩��Ȃ��ł���ˁB
�����ԍ��F21768341
![]() 6�_
6�_
���݂܂���A��Ŏ��̍Ōオ���ׂāg)}�h�ɂȂ��Ă܂����A�J�b�R���������܂��A�g}�h�����ɒ������ĉ������B
���J�b�R������蒆�J�b�R���g�����������₷���Ǝv���ĕς����Ƃ��ɏ����Y��܂����B
�����ԍ��F21768363
![]() 3�_
3�_
���ĊԈႦ�܂������A�Đ�����g�`�̃X�y�N�g���͂�������1jHz±��Hz�ɓ���̂ŁA�T���v�����O���[�g��44.1kHz�ł����肪���܂��B����̗�ł�100ms�̎��Ԃ�������80ps�Ƃ��̗h�����Č����邱�ƂɂȂ�܂����A����͉\���Ǝv���܂��B
�����A�����̃X�y�N�g���͗����㕝�[���ł����Atohoho3����̓��e�摜�ł͂����炩���������܂���ˁH������ւn�[�h�i���j�I�Ȍ��E�ł����ˁB�g�[�^���I�ȃW�b�^�[��\�킵�Ă���\��������܂��ˁB�K�E�V�A���ɋ߂��̂Ń����_���������傫���̂����m��܂���B�Ȃ��A
>�̕����͏��������ǁA�X�s�[�J�ōĐ�����ƁA���̊��ł́A1�b�����ŗh�炢�ł���悤�Ɋ�����B
�ɂ��ẮA���̂ق��ł͖��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F21768368
![]() 5�_
5�_
×�@1jHz±��Hz
�Z�@1kHz±��Hz
���A��Ƃ��A��Ȃ����B
�����ԍ��F21768380
![]() 3�_
3�_
>�Đ�����g�`�̃X�y�N�g���͂�������1jHz±��Hz�ɓ���̂ŁA�T���v�����O���[�g��44.1kHz�ł����肪���܂��B
�Ƃ������ƂȂ̂ŁA
sin((1000×2��)t�{0.005×sin(5×2��)t) ->�X�y�N�g���̎R�̒������킸���ɗh�炢�ł���
sin((1000×2��)t�{0.0005×sin(5×2��)t) ->�X�y�N�g���̎R�̐������肪�킸���ɗh�炢�ł���
sin((1000×2��)t�{0.00005×sin(5×2��)t) ->�X�y�N�g���̎R�̈�ԉ��̕t�������킸���ɗh�炢�ł���
�悵�Ă݂��i�ꉞ��Ԃ�����ɏ����̏ꍇ�������j�B
https://www.youtube.com/watch?v=HQJNjAQcDSI
youtube�̍ō������ʼn����ꍇ�́A���̏������ݎ��Ԃ��炵�炭���Ă���AGoogle Chrome�ŁA
�ݒ�->�掿��4k���I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă���A4k�掿�ōĐ���������ł��傤�B
�����ԍ��F21768495
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
youtube���Ă�����ō��掿��2160p�ɏオ������ł����H �m��Ȃ������I
���܂ł�1060p�Œ����Ă�������Ȃ̂��ǂ����킩��܂��A�h�炬���������Ղ��Ȃ����悤�ȁB
sin {(1000×2��) t�{0.005�Esin (5×2��) t} �̉��͐U��800ns�ł��ˁB�Ȃ����U��8��s�̉����h�ꂪ�傫����������悤�ȁB�Ƃɂ����h��ĕ������܂��B
sin {(1000×2��) t�{0.0005�Esin (5×2��) t} �̉��͐U��80ns�B�܂��h��ĕ������܂��B
sin {(1000×2��) t�{0.00005�Esin (5×2��) t)} �̉��͐U��8ns�B����́A������Ƃ킩��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F21768543
![]() 5�_
5�_
×���܂�1060p�Œ����Ă���
�Z���܂�1080p�Œ����Ă���
�����ԍ��F21768554
![]() 2�_
2�_
>�����A�����̃X�y�N�g���͗����㕝�[���ł����Atohoho3����̓��e�摜�ł͂����炩���������܂���ˁH������ւn�[�h
>�i���j�I�Ȍ��E�ł����ˁB
����́AFFT�̑����ɋN������悤�ł��Bhttp://www.fidelix.jp/technology/jitter8.html���Q�ƁB
�����ԍ��F21768732
![]() 5�_
5�_
tohoho3����A���肪�Ƃ��������܂��B
�܂�
>����̗�ł�100ms�̎��Ԃ�������80ps�Ƃ��̗h�����Č����邱�ƂɂȂ�܂����A����͉\���Ǝv���܂��B
�Ə��������A�u�v���܂��v�Ɠ������̂́A�T���v�����O���g���̂ق��͖��Ȃ��̂ł����A�ł͂ǂ��܂ł��ׂ����h�����Č��ł��邩�Ƃ����ƁA�c���̕���\�����ł��Byoutube�ɏڂ�������܂��A�掿�ݒ�Ɖ������ĊW�����ł����H
����16�r�b�g�Ƃ���ƁA���傢���傢�v�Z���������ł́A�����0.00005�{�i�W�b�^�[�U��8ns�j������ł͂��łɂ��Ȃ�������A�܂��Ȃ�Ƃ��A���炢�����E�E�E�B
�ŁA���������z�ł����ASymbolist_K����̊��z������ł͂����������܂��ˁB�ł��A�u8ns�v�Ɓu�����v������ĕ������܂��B�Ƃ������A���ʂ��������Ȃ��ĕ������܂��H�C���z���ł������Ă݂܂������A�����ł��B�Ȃ̂ŁA�Ȃ�̈Ⴂ���Ă���̂��悭�킩��܂���B
�Ƃ����킯�ŁA�f�l���x���̌��m���e�X�g�͂�����������������������Ƃ������Ƃ��킩��܂����B���o�I�ɂ́A80ns������ɂȂ�ƁA������Ɖ��ʂ����낦����A�u���C���h�ł͒��������ł��Ȃ��l�������������ȋC�����܂��B
>����́AFFT�̑����ɋN������悤�ł��B
�Ȃ�قǁB���ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F21768803
![]() 5�_
5�_
>�掿�ݒ�Ɖ������ĊW�����ł����H
������Ɠǂ݂ɂ������ǁA
https://blogs.yahoo.co.jp/nightwish_daisuki/63912067.html
���Q�l�ɂ��Ă��������B
�����ԍ��F21768863
![]() 5�_
5�_
�@���炭�Ԃ�ł��B�݂Ȃ��������܂ꂽ���e�����ƂɃW�b�^�[�̉�����������Ɠ���t�@�C�����쐬���Ă݂܂����B
�@�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɋ������Ă��������������A
sin [ ��o { t + J�Esin (��j t) } ]
�@���g���āAtohoho3����ɋ����Ă�������T�C�g�𗘗p���č쐬���Ă܂��B�i���̃T�C�g�ʔ������܂��j
play sin(1050*2*pi*(t+(10*10^-9)*sin(30*2*pi*t))) for 60 seconds
�@����Ȋ����ŁA�1050Hz�����g�ŃW�b�^�[�̎�����30Hz�A���ԐU����100��s�`1ps�B�i1050Hz��fs=44100Hz�ŕϒ��g�ɂ��r�[�g���������Ȃ����g���ł��B����30Hz�͒����������ňႢ���킩��₷���悤�ȋC�������̂Łj
�@youtube���ƁA�Ĉ��k����ĉ�����80dB�ȉ��̐M�������k�ϒ��m�C�Y�ɉB��Ă��܂��̂ŁA
https://yahoo.jp/box/UOv11b
�@���特�������k�̓���̂܂܃_�E�����[�h�ł���悤�ɂ��Ă���܂��B�����AVI�t�@�C���ŃR�[�f�b�N��H.264�A������PCM-44.1KHz-16bit�̂܂܂ɂ��Ă���܂��B�T�C�g�ŕϊ����ꂽ�������ɂ܂܃T�E���h�~�L�T�[��ʂ���44.1KHz-16bit-wav�t�@�C���ŃL���v�`���[�������k�̂܂�AVI�t�@�C���ɓ���Ă܂��B
�@PC�ŕҏW���Ă���̂ŁA100ps�ȉ��̓m�C�Y�t���A�Ƀ}�X�L���O����AFFT�O���t�ł͊m�F�ł��Ȃ����ǂ���PC�̃I���{�[�hDAC�ł�1ns��100ps�̔g�`�̈Ⴂ�܂ł͊m�F�ł��܂��BFFT�̓T���v����131072�i�ő�j�ɂ��Ă��邽�߁A�m�C�Y�t���A�͏��������ɂ����-130dB�ʂɕ\������Ă܂��B
�@�b���ς��܂����A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̐����A
sin [ ��o { t + J�Esin (��j t) } ]
���g���āA
http://sonove.angry.jp/jitter_sim01.html
�Ŏ�������Ă�iA�j���V�~�����[�V�������������Ă݂܂����B
�@�A�b�v�}�̂悤�ɃO���t���قƂ�Ǔ����ɂȂ�܂��B�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�������ł��B
�����ԍ��F21769150
![]() 7�_
7�_
tohoho3����
���������A�����̃X�y�N�g���͗����㕝�[���ł����Atohoho3����̓��e�摜�ł�
���������炩���������܂���ˁH������ւn�[�h�i���j�I�Ȍ��E�ł����ˁB
������́AFFT�̑����ɋN������悤�ł��Bhttp://www.fidelix.jp/technology/jitter8.html ���Q�ƁB
�Q�Ɛ�̂���Ȃ�Q�Ɛ�ł���National Instruments�́wFFT�Ƒ������𗝉�����x��ǂ�ł݂܂����B
�u�@�@�@�@�@�@�M���̓��e�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�����g�i�U�����x���d�v�ł���ꍇ�j�@�@�@�@�@�t���b�g�g�b�v��
�@�P����g���̐U���𐳊m�ɑ��肷��ꍇ�@�@�@�@�t���b�g�g�b�v���@�@�@�@�v
�u�t���b�g�g�b�v���́A���̑��Ɠ����悤�ɐ����Ȑ��̌`������Ă��܂����A�[����������Ƃ�������������܂��B���̂��߁A���C�����[�u�̃X�y�N�g�������Ȃ�L����܂��̂ŁA���̑��ɔ�ׂĐM���̐^�̐U���ɋ߂��l�������܂��B�v
�Ƃ����L�q���炵�āA���ݑ��肵�Ă���悤�ȉ��̏ꍇ�A�t���b�g�g�b�v�����œK�Ȃ悤�ł��ˁB�i�Ƃ���ŁA�u�[�������v���ĉ��ł����H�j
���� http://efu.jp.net/soft/ws/dist/meas_dist.html �ɂ��uFlat top���ł͖{���̒l�ɋ߂����ʂ������Ă��܂��v�Ƃ���܂��B�i���̃T�C�g�����Y�̑���ɊW����̂��ǂ����悭�킩��܂���^^;�j
tohoho3����youtube�ɃA�b�v����Ă��铮��̍�����WaveSpectra�̉�ʂ́A�t���b�g�g�b�v�����g���Ă���̂ł����H
����ɂ��Ă��AWolframAlpha���Ă������ł��ˁI ���ł��v�Z�����Ⴂ�܂��ˁI tohoho3����ɕ���ĐF�X�ȃW�b�^�[��������Ē����Ă݂Ă��܂��B�i�}�C�N���Ȃ��̂�WaveSpectra�Ŏ��g�����肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����j
�����ԍ��F21769154
![]() 5�_
5�_
�p�C������A���v���Ԃ�ł��B
��tohoho3����ɋ����Ă�������T�C�g�𗘗p���č쐬���Ă܂��B�i���̃T�C�g�ʔ������܂��j
�ł���ˁI ���̃T�C�g������l�A�V�˂ł��ˁI
��1050Hz��fs=44100Hz�ŕϒ��g�ɂ��r�[�g���������Ȃ����g���ł��B
�Ȃ�قǁI
������30Hz�͒����������ňႢ���킩��₷���悤�ȋC�������̂�
�����ł����H �����Ă݂������ł́Atohoho3�����5Hz�̕����Ⴂ���킩��₷�������ł��B
�ŁA���ے����Ă݂����ʂ́F
100��s�͖��炩�B
10��s�͂悭�����Ɨh��Ă���B
1��s�͗h��Ă���Ƃ����Ηh��Ă���C���d�d�d
100ns�͂悭�킩��܂���B�i5Hz�ł�80ns�܂ł͂킩�����̂ł����j
����ȉ��͑S�R�킩��܂���B
���Ȃ݂ɁA�uyoutube���ƁA�Ĉ��k����ĉ�����80dB�ȉ��̐M�������k�ϒ��m�C�Y�ɉB��Ă��܂��v�Ƃ����̂�tohoho3����youtube�ɏグ�Ă���U��5Hz�̏�����ɉe������܂����H
�����ԍ��F21769217
![]() 5�_
5�_
������x�A������WolframAlpha���特���o���Ē����Ă݂܂����B
sin {(1000×2��) t�{0.005�Esin (5×2��) t} �̐U��800ns�̉��͗h��Ă܂��B
���Asin {(1000×2��) t�{0.0005�Esin (5×2��) t} �̐U��80ns�̉��͎��M�Ȃ��Ȃ�܂����B
�Ƃ����̂��A�t�� sin (2000��t) �̏������������炢�h��Ă���C�����Ă�������ł��B
�킩��Ȃ��Ȃ�܂����B�����ł��傤���H
�����ԍ��F21769248
![]() 5�_
5�_
�@����A�b�v���������k�����̓���Ɍ��ׂ�����܂����B
�@�W�b�^�[�̐M�����x�������₷�����邽��FFT�̑ш��800Hz�`1300Hz�ɍi���ĕ\�������̂��ԈႢ�̂��Ƃł����B
�@�A�b�v�}�@�͐���g���������k������20Hz�`20KHz�i����j��FFT�ł��B�W�b�^�[10ns�ȉ��ł̓W�b�^�[�ȊO�̍����g�ƕϒ��g��-80dB���炢�̐M�����x���ŏ���Ă��āA�W�b�^�[�m�C�Y���}�X�L���O����Ă��܂����߁A������חp�Ƃ��Ă͈Ӗ����Ȃ���Ԃł��B�O���t����̓W�b�^�[���x���̊m�F�����͂ł���悤�ł��B
�@youtube�ōĕϊ����ꂽ���̃O���t�͐}�A�ɂȂ�܂����A10ns�ȉ��ł͍Ĉ��k�ɂ��ϒ��m�C�Y�ɖ�����Ă��܂��āA�W�b�^�[�m�C�Y�̊m�F����ł��Ȃ���Ԃł��B
�@�Ȃ̂ł�����ɂ��뒮����ׂ�͓̂���Ǝv���܂��B
�@
�����ԍ��F21769401
![]() 6�_
6�_
����1000Hz�Ə���1000Hz+�W�b�^�[100ns�̉���PC�̃T�E���h�~�L�T�[���璼��FFT�O���t�ɂ��Ă݂܂����B����20Hz�`20KHz�Ō���ƁA�����Ȃ̂ɍL��ɕϒ��g�������������Ă��āA�W�b�^�[100ns�̂��̂ƌ����������Ȃ����炢�ɂȂ��Ă܂��B�����̂����ł͖����Ǝv���܂��B�@
�����ԍ��F21769412
![]() 5�_
5�_
�������̓p�C������I ����Ȃ��Ƃ܂Œ��ׂĂ��������Ă��肪�Ƃ��������܂��I
�ق�Ƃ��ɏ���1000Hz�Ə���1000Hz+�W�b�^�[100ns�̉����A�قƂ�Nj�ʂł��Ȃ����炢�ɂǂ�����ϒ��g���炯�ɂȂ��Ă܂��ˁB
���̎��͂�肠�����v�݂����ł���(��)
����͊��1000Hz�ł��邹���ŁA1050Hz�ł����fs=44100Hz�ł���A�ϒ��g�ɂ��r�[�g�͔�r�I�������ɂ��������̂ł��ˁB
�������A���1000Hz�ł���A1050Hz�ł���A����PC���ł́A������������W�b�^�[��100ns�����x�ɋ߂��悤�ł��B
�����ԍ��F21769440
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����A
>tohoho3����youtube�ɃA�b�v����Ă��铮��̍�����WaveSpectra�̉�ʂ́A�t���b�g�g�b�v�����g���Ă���̂ł����H
youtube�̓�����悭����ƁAWaveSpectra�A�v���̏�̕��ɁA�uBlackman�@H7�v�Ə����Ă���̂��킩��B
WaveSpectra��WaveGene���_�E�����[�h���āA���낢�둋����ς��Ă݂Ăǂ��Ȃ邩�V��ł݂Ă��������B
Blackman�@H7�ł��A��ɏ������悤�ɁA
1kHz�̏��������g��±5Hz�ɑ��݂���W�b�^���g�������̐U���̂�炬�ɋN�����āA
WaveSpectra�ő��肵���X�y�N�g���g�`�i�R�ɂ������j�ɋ͂��Ȃ�炬�������B
�����ԍ��F21770206
![]() 4�_
4�_
�Ė����ނ��ڂ��Ă��邤���ɋ���ȏ�E�E�E�B�p�C�������`(@_@)�B
tohoho3����[21768863]�A���肪�Ƃ��������܂����BPC�̐ݒ肪16�r�b�g�������̂��m�炸�E�E�E�B
���́u16�r�b�g�v�̕\���\�͂��C�ɂȂ��Ă���A�܂��A�p�C������̌f�ډ摜�������J�b�R�����̂łȂ�Ƃ��R�ł��ƁA���`���Ă݂܂����i����R�ł��ĂȂ����ǁj�B
�O���t�́A�W�b�^�[�U��100ns�i�W�b�^�[���g��30Hz�j�̔g�`�Ə����̍������v�Z�������̂ł��B�c���́A�����̐U�����P�Ƃ����ꍇ�̑��Βl�ŁA�ő�l�� 6e-4 ���ł��B16�r�b�g�̍��݂� 1/2^16 = 1.5e-5 �Ȃ̂ŁA40�X�e�b�v���x�ō��ތv�Z�ł��i�W�b�^�[���g�����ς���Ă������ł��j�B�ƂĂ��Ȃ߂炩�Ƃ͌����܂��A�܂��傴���ςɂ͍Č��ł��Ă���Ǝv���܂��B
�W�b�^�[��10ns�ɂȂ�ƁA�P���ɂ��̐U����1/10�ɂȂ�܂����A�����Ȃ�Ƃ��͂�A10ns�̃W�b�^�[�g�`�͂��̕З����c��Ȃ��Ǝv���A���̎���p�C������[21769401]�̃O���t�ɕ\��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
24�r�b�g�ɂ����3�P�^�����P����v�Z�ł����A�p�C������ɂ��Ə����ł��܂��ʂ̃m�C�Y���x�z�I�ɂȂ�悤�Ȃ̂ŁA���܂�Ӗ��Ȃ������ł��ˁB
�Ԗx���́u80ps�v��1999�N�̕����̂悤�ł����A������80ps�̃W�b�^�[�݂̂��t������Ă����̂��A��������̌����҂Ȃ炸�Ƃ��^�������Ȃ�Ƃ���ł��B
�����ԍ��F21770682
![]() 5�_
5�_
�����ŁA�Y�ꎁ���o�̃W�b�^���K���Ă������B
�p���g����o�i���g��2��o�j�A�U��1�̏���sin(��ot)�̈ʑ��p��ot�ɁA�p���g����j�A�U��J�̐����g�W�b�^Jsin(��jt)
�����Z���邱�Ƃɂ��A�W�b�^���t�����ꂽ�����g�`��\���Ɓi���Ȃ킿�AJsin(��jt)�ɂ��ʑ��p��ot�̕ϒ��ƍl����Ɓj�A
sin(��ot�{J×sin(��jt))
�ƂȂ�B��������g���̈�\���i���ԗ̈�g�`�̃t�[���G�ϊ��ł���X�y�N�g�����j�Ƃ���
���₷�����邽�߂ɁA�u���ʑ��p(��ot�{J×sin��jt)�̎��Ԕ������u���p���g���ł��邱�Ƃ���A
��X�̎��ɂ�
�u���p���g������o�{J��jcos(��jt)
�Ƃ��ĕ�������B���Ȃ킿�A���������g�̊p���g����o�̎���ŁA�ő���g���Έ�±J×��j
�̑��єg���A�p���g����j�Ŏ��g������ŐU�����Ă���i���Ȃ킿�A�r�u���[�g�j�B
����ō����Ă���̂��Ȃ��H
���Ƃ���A���
�u1kHz�̏��������g��±5Hz�ɑ��݂���W�b�^���g�������v
��
�u1kHz�̏��������g��±5Hz×J�ɑ��݂���W�b�^���g�������v
���������H
�����ԍ��F21770758
![]() 2�_
2�_
tohoho3����
��youtube�̓�����悭����ƁAWaveSpectra�A�v���̏�̕��ɁA�uBlackman�@H7�v�Ə����Ă���̂��킩��B
���݂܂���A�����܂Ō��Ă܂���ł����B
�u7���u���b�N�}���E�n���X�����v�������̂ł��ˁB
�����Ɋւ��ẮA���National Instruments�̐����ł͂悭�킩��Ȃ��̂ŁA�K�Ȃ��̂�F�X�T���܂������A�ǂ����̑�w���̑��_�F
http://www.kochi-tech.ac.jp/library/ron/2005/2005ele/1060251.pdf
��ǂނƁA���̖����ɂ��ĂȂ�ƂȂ��킩��܂����B
��Blackman H7�ł��A��ɏ������悤�ɁA1kHz�̏��������g��±5Hz�ɑ��݂���W�b�^���g�������̐U���̂�炬�ɋN�����āAWaveSpectra�ő��肵���X�y�N�g���g�`�i�R�̂������j�ɋ͂��Ȃ�炬�������B
����͐��
������o �̏����͉�X�ɂ�
������o�^{ 1 + J��j cos(��j t) } �� ��o { 1 - J��j cos(��j t) }
�����̂悤�ɕϒ�����ĕ������܂�
�����X�y�N�g�����̍L���肩��킩��܂���B
�̗h�炬�����ĂƂ��̂́ABlackman H7�ł�Flat top�ł����l���Ƃ������b�ł���ˁB
��WaveSpectra��WaveGene���_�E�����[�h���āA���낢�둋����ς��Ă݂Ăǂ��Ȃ邩�V��ł݂Ă��������B
�_�E�����[�h���ĐF�X�ݒ�͌��Ă���̂ł����A�V�Ԃɂ̓}�C�N���K�v�ł���ˁB�܂��}�C�N��Ȃ���Ȃ�܂���B������h��Ƃ������Ƃ�^^;
�����ԍ��F21770896
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����A
�}�C�N�͕K�v�Ȃ��ł��B�p�C������̏������݂Ƀq���g������Bwindows10�ł���A�^���f�o�C�X�ɃX�e���I�~�L�T��
����͂��B�Ȃ���A�E�N���b�N�Ŗ����ȃf�o�C�X��\�����ėL���ɂ���B���̌�AWaveSpectra�̘^���f�o�C�X�ݒ�ŁA
�X�e���I�~�L�T��I������B����ŁAPC��ōĐ����Ă��鉹�̔g�`�������͂��B
�����ԍ��F21770954
![]() 6�_
6�_
tohoho3����
�����A�������I �g�`�\���ł��܂����I ����ŗV�ׂ܂��I
Windows 7 �Ȃ�ł����A�R���g���[���p�l���́u�^���f�o�C�X�v�ŁA�}�C�N�����C�����͂��u�ڑ�����Ă��܂���v�������̂ł�����߂Ă���ł����A�E�N���b�N�Ŗ����ȃf�o�C�X��\�����āu�X�e���I�~�L�T�[�FRealtek High Definition Audio�v��L���ɂł��܂����B����ŁAWaveSpectra�̘^���f�o�C�X�ݒ�ł��X�e���I�~�L�T�[��I�����邷�邱�Ƃ��ł��āA�����o���Ɩ����g�`���o�܂����I
���������肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21771035
![]() 5�_
5�_
>���������H
�����E�s�����ȑO�ɁA��������
>�u���p���g������o�{J��jcos(��jt)
������A�����������ĂȂ��ł���BJ �͎��Ԃ̎���������A��Q���͖������ʂɂȂ����Ⴄ�ł���B
�t�͑�̓��͂Ȃ������E�E�E�B
�����ԍ��F21771085
![]() 4�_
4�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A
J�́A��ԏ�Œ�`���Ă���悤�ɁA���ԕϓ��̗ʂł͂Ȃ��A�ʑ��p�̕ϓ��̗ʁid����Jsin(��jt)�j�Ƃ��Ē�`���Ă���̂ŁA
J�͖������ʂł��B
�����ԍ��F21771175
![]() 2�_
2�_
>J�́A��ԏ�Œ�`���Ă���悤��
��`���Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��ł��ˁB���̒��ɍ������Ă��邾���ł�����B���������A���܂܂ł����ƁA�u�W�b�^�[�U���v�͎��Ԃ̎����i�P�ʂ͕b�j�Ƃ��Ĉ����Ă��āA�L�� J �ŕ\���Ă��܂��B�ˑR����ɕς��Ă��܂��ẮA���l�ɓ`���킯������܂���B
�V���ȗʂ�����Ȃ�A���m�̗ʂ��炫����ƒ�`���Ȃ�������܂���B���ہA���Ȃ��́uJ�v�ɂ͂ǂ�ȕ����I�Ӗ�������̂��A�ǂ����Ă�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���ɂ͂����ς�킩��܂���B
�����ԍ��F21771218
![]() 4�_
4�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A
�킴�ƁA�u�����ς�킩��܂���v�ƌ����Ă�ł��傤�H
���������g�́A�U��A�ƈʑ��p����p����Asin(��)�ƕ\�����Ƃ��ł��A�ϐ���A�ƃ������ł���B
���̐����g�ɔ����ȊO���������Ƃ���B���̊O���ɂ��A�U����dA�A�ʑ��p��d���ω����āA
���������gAsin(��)��(A�{dA)sin(���{d��)�ƕω�����ƍl����̂����R�ł���B
A�{dA�́A�U��������dA�̕ϓ������邱�ƂȂ̂ŁA�U���Ύ��ԕ\���i�I�V���X�R�[�v�ł̑���j
�ł́A�����g�̐U�������̕ϓ��i�����g��\���Ȑ��̏c�����̌����Ƃ��Č����O���j��
����B�������A���G�ɂȂ�̂ŁAA�͕ω����Ȃ��Ƃ��āAA��1�Ƃ����B
����A�����g�ł͈ʑ��p���́A�p���g����o�Ǝ���t��p���āA������t�ƕ\�����̂ŁA
���{d���́A��t�{d���ƂȂ�B���̈ʑ��p�̕ϓ�d�����A�ȒP�̂��߂ɁA�U��J�A�p���g����j��
�����gJsin(��jt�j�̊O���Ƃ��������ł���B
�����ԍ��F21771477
![]() 2�_
2�_
�����A������Ȃ����āB
�܂��A����Symbolist_K����ƃp�C������̋��ʔF���ł��� J �́A���Ԃ̎����������A�P�ʂ͕b�ł��B���������ɕς�����}�Y���A���炢�̂��Ƃ͗��������ł����ˁH
���ɁA��X�� J �́A�Ⴆ�ΑO�X���̃p�C������[21732866]�̃I�V���̐}����A���ڂ���𑪒肷�邱�Ƃ��ł��A�����I�Ӗ��������ł��B
���Ă��Ȃ��́uJ�v�́A�I�V�����肩�瓾���� J ���킩���Ă��A��{�g�̎��g�����킩��Ȃ��ƌ��܂�Ȃ��ł��ˁB�G���Ȏ��g���������܂ވ�ʂ̃I�[�f�B�I�M����������ǂ�����̂ł��傤���H
���Ȃ��́uJ�v�́A���w�I�ɂ͈ʑ��p�̗h���̐U���ł��ˁB�����̃W�b�^�[��\�킷�Ƃ��Ɏ��������ȒP�ɂȂ邾���ŁA�����I�Ӗ��₻����`���鍇�����͂Ȃ�Ȃ̂��킩��Ȃ��A�ƌ����Ă����ł��B
�����������e�ɍu�`���Ă�����ǁA�킩���Ă邩����ˁE�E�E�B
�����ԍ��F21771656
![]() 5�_
5�_
��������Ă܂��������Ă����E�E�E
�u�_���v�Ƃ����Ă����\����͎̂��R�ł��B�ŋ߂͑傫�Ș_���⌤�����ʂ̉������ԈႢ�����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA�������@���K�łȂ�������A��ςŌ��ʂ��˂��Ȃ����Ă����肷����̂͂��܂�����܂��B�p�b�Ǝv�������̂Ȃ�A�C���t���G���U�̗\�h�ڎ�Ȃǂł��B���ʂɂ��Ă̌�������A�\�h�ڎ�ɂ͂قƂ�nj��ʂ��Ȃ��Ə����ꂽ�����_���Ɣ��Ή^���ŏW�c�ڎ킪�Ȃ��Ȃ����̂ł����A���ꂪ�����̑嗬�s�̗v���ɂȂ��Ă��܂��B
�Ȋw�ł́u�l�C�`���[�v��u�T�C�G���X�v�Ȃǂ̒����ȎG���ɔ��\���ꂽ�����ł��A�������ʂ������邩�ʂ̉Ȋw�҂⌤���@�ւ������āA�͂��߂ĐM�ߐ��������Ă����܂��B���قǑ傫�Șb��ɂ��Ȃ�Ȃ��I�[�f�B�I�W�ł������蔭�\����悤�Ș_���́A���N�H�i�̌������ʂƓ��l�ŁA���ӓI�ɂ˂��Ȃ����Ă���\���������Ƃ݂�ׂ��ł��傤�B
�ǂ�ȏ����łǂ�ȃf�[�^��������̂��H
�u�����E�h�l�X�Ȑ��v
https://www.aist.go.jp/science_town/living/living_10/living_10_01.html
����Ă��邱�Ƃ̋K�͂�ݔ��͂Ƃ������A���̂��炢�͂�����Ə�����Ă����Ȃ����Ƃɂ́A�ǂ����̒N��������ȉ\�����Ă�����x�̐M�ߐ������Ȃ��A����������Ƃ��ĉ������ǂ��ł���ƌ��͖̂�肪�����Ǝv���܂��B�ł��A�������ʔ����Ęb��ɂł���Ƃ����̂��I�[�f�B�I�̊y���ݕ��Ȃ̂����m��܂���ˁB
�����ԍ��F21771669
![]() 5�_
5�_
�Ɠd��D���̑�コ��
�u�����E�h�l�X�Ȑ��v��ISO���ۋK�i���A18�N�Ԃ����đ��蒮��ҏq�ז�19,000�l�����200����̔��f���W�߂����ʁA2003�N��50�N�Ԃ�ɉ������ꂽ�Ƃ͒m��܂���ł����B���������肪�Ƃ��������܂��B
�������͂Ȃ���A�uHAP-Z1ES�ɉ�����gCD���ڃ��b�s���O�h�ƁgPC���b�s���O�h�̉������v�ɂ��Ă̔��f���W�߂����Ǝv���Ă��̃X���b�h������Ă���܂��B���̂Ƃ���A���ۂɎ��Œ�����ׂ����ʂƂ��āA���Ȃ��Ȃ���A�U������̔��f���W�܂��Ă��܂��B
�܂����̃X���b�h�́A���̔��f�̎��W����ړI�Ƃ��A�u�ς��v�Ƃ������f�A����сu�ς��Ȃ��v�Ƃ������f�̂��ꂼ��̔w��ɂ��闝�_�I���t���̒Nj��ړI�Ƃ����Ă���܂��B
��҂ɉ����ẮA�u�ς��v���Ƃ̍����Ƃ��āA
�E���䗲���̗��_��Minerva2000�����p�����uDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ�A���������A�i���O�g�`���̂��ώ����邩��v�������
�E�p�C������ɂ��uDA�ϊ����ꂽ�A�i���O�g�`�ɃA�i���O�m�C�Y�g�`������邩��v���A
����o����܂����B
�܂��T�ؓI�Ȋ֘A���_�Ƃ��āA
�EBenjamin & Gannon�ɂ��u�W�b�^�[���m���͏�����10ns�A�y�ȍĐ�����30ns�`300ns���x�v���A
�E���v�Y���ɂ��u�W�b�^�[���m��4ns�`10ns�v���A
�E�Ԗx�����ɂ��u�W�b�^�[���m��80ps�v���A
�E�b���莁���ɂ��u�W�b�^�[���m��500ns���x�v���A
�E�p�C������ɂ��u�W�b�^�[���m��10ns�`100ns�i�����g�ƕϒ��g�̃}�X�L���O�ɂ��j�v���A
�EATI Labo�̊p�c����ɂ��u�W�b�^�[�ɂ���Ē��{�����t�����ꂻ�ꂪ�L��ɉe������v���A
�E�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɂ��u��o�̏����́A��o�^{1+J��j cos(��j t)} �� ��o {1-J��j cos(��j t)} �̂悤�ɕϒ�����ĕ�������v���A
�Ȃǂ̗l�X�Ȑ�����o����A�����ɒl���鉼���ł���Ƃ��ċc�_�̑ΏۂƂȂ��Ă��܂��B
���̂����A���v�Y����NHK�����Ȋw��b�����������A�Ԗx�����͔����̂��E�̔�������{�e�L�T�X�C���X�c�������c�����A�p�c�����DAC��A���v���E�̔�����ATI Labo�����ł������肵�āA���ɂ͂��̗���ɂ��A�Ɠd��D���̑�コ��̂��w�E�̂悤�ɁA�����̏����̈Ӑ}�I�ȕΌ��E�c�Ȃ��^������̂�����܂��B�ł��A����Ȃ炻��ŁA���̈Ӑ}��ᔻ���邱�Ƃɂ��܂��F�����[�܂邱�Ƃ����҂ł���Ǝv���܂��B
������Ă��邱�Ƃ̋K�͂�ݔ��͂Ƃ������A���̂��炢�͂�����Ə�����Ă����Ȃ����Ƃɂ́A�ǂ����̒N��������ȉ\�����Ă�����x�̐M�ߐ������Ȃ��A����������Ƃ��ĉ������ǂ��ł���ƌ��͖̂�肪�����Ǝv���܂��B
�ǂ�ȗ��_�ł����Ă��A����ɖӖړI�Ɉˋ����Ă���Ȃ���ł��傤���A���ꂪ�����Ƃ��Đ��������ǂ�����ᔻ���鎋�_�����킸�A��ɉ�����㈖@�I�Ȃ����ŋc�_��i�߂���ŏo���ꂽ���ʂ����čs���A�����̘_�҂����̏W���m�ɂ���ĐF�X�ƗL�v�Ȓm�������܂�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F21771971
![]() 6�_
6�_
�@youtube�̈��k�ϒ��g�ɂ�鉹�����C�ɂȂ����̂Œ��ׂĂ݂܂����B�i�A�b�v�}�j
�@�����̃_�E�����[�h��́A
https://yahoo.jp/box/3lpl5p
�@1050Hz���� fs44100Hz-16bit
�Ayoutube�ɃA�b�v���[�h��_�E�����[�h���ĉ����̂ݒ��o����wav�ɕϊ�
�B�g�`�G�f�B�^�\�t�g�Ň@�̈ʑ����]�g�`�ƇA�������o�͂��Ă̍����̂ݒ��o
�Cyoutube���k�ɂ��m�C�Y�݂̂̉���
�@���k�m�C�Y�̐M�����x����-80dB�Ȃ̂Œʏ�̉��ʂł͑����������܂���B���ω������x������⏬�������ŋL�^����Ă���N���V�b�N�����ȂǂŁA�{�����[�����グ�Ē����Ă�ꍇ�́A�����̃V�[���Œ������郌�x�����Ǝv���܂��B
�D�̓m�C�Y��-70dB�ɑ���
�E�̓m�C�Y��-60dB�ɑ���
�E�Œ����Η̌����̕ϒ��m�C�Y�̉��F���킩��܂��B
�����M�����x��-80dB�̃m�C�Y�́A���y���Ƃ��ɉ����������Ȃ����x�̃��x���Ȃ̂ŁAyoutube�ł�������l�����Ĉ��k�������Ă���̂��Ǝv���܂��B
�@�W�b�^�[�̐����T�C�g�̃O���t������ƐM�����x����-80dB���炢�̃W�b�^�[�����傤��10ns���x�Ȃ̂ł��̂��炢�̃m�C�Y���x�������o�I�ɒ������邩�������Ȃ����i���ʂł��邩�ł��Ȃ����j��臒l�ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����܂��B
http://sonove.angry.jp/jitter_sim01.html
������̃T�C�g�̍ڂ��Ă���iD�j�̃O���t
�����ԍ��F21772003
![]() 8�_
8�_
�c�_�����M���Ă���Ƃ�����������݂����Ő\����Ȃ��ł����A�A�A�A�B
DAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ������́A�o�̓A�i���O�g�`�ւ̉e���́A�W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ邱�ƂŎ��g���ϓ����N���邱�Ƃł͂Ȃ��A�A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�ł��B�����Đl�͂��̘c�ɂ͔��ɕq���ŁA���ꂪ���m���ɎO�����̑傫�ȍ����o�闝�R�ł��B
��̓�������̘_���͑O�҂̐����Ƃ��Ă���A���ł��BDAC�̓���\�͈͂���N���b�N�W�b�^�[�̈�Ől�̌��m��������ʂ�̂́A�������Ȃ��̂ł��傤�B
�O�҂̐����x�[�X�ɋc�_�𑱂��Ă��X���傳��̋^��u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̂��߂̊O�t���h���C�u���w�����ׂ����H�v�ɂ͓��ɖ��ɗ����Ƃ��Ȃ��̂ł́B
�����ԍ��F21772159
![]() 3�_
3�_
�Y�ꎁ�̓����ǂ��ėD�����Ƃ���͑�D�������A�q�X�e���b�N�ɂȂ�̂͌�������B�܂��A�������炵�傤���Ȃ����H
�Y�ꎁ�̒����������āA�ȉ��̂悤�ɏ��������Ă݂��B
���������g�́A�U��A�ƈʑ��p����p����Asin(��)�ƕ\�����Ƃ��ł��A�ϐ���A�ƃ������ł���B
���̐����g�ɔ����ȊO���������Ƃ���B���̊O���ɂ��A�U����dA�A�ʑ��p��d���ω����āA
���������gAsin(��)��(A�{dA)sin(���{d��)�ƕω�����ƍl����̂����R�ł���B
A�{dA�́A�U��������dA�́i�����ȁj�ϓ������邱�ƂȂ̂ŁA�U���Ύ��ԕ\���i�I�V���X�R�[�v�ł�
����j�ł́A�����g�̐U�������̕ϓ��i�����g��\���Ȑ��̏c�����̕��Ƃ��Č����O���A�ʏ��
�m�C�Y�ƌ�����j�ł���B�������A���G�ɂȂ�̂ŁA�U�������̕ϓ����Ȃ��Ƃ��āAA=1�AdA��0
�Ƃ����B
����A�����g�ł͈ʑ��p���́A�p���g����o�Ǝ���t��p���āA������t�ƕ\�����̂ŁA
���{d���́A��t�{d���ƂȂ�B���̈ʑ��p�̕ϓ�d�����A�ȒP�̂��߂ɁA�U��J�A�p���g����j��
�����gJsin(��jt�j�̊O���i�ʏ�́A�����g�W�b�^�ƌĂ�AAC�d�����g����X�C�b�`���O�d����
�X�C�b�`���O���g���ȂǂɋN���������̂�����j�Ƃ��������ł���B��ʉ�����ɂ́Ad������j(t)
�Ƃ�����������ŁA��j(t)�͔C�ӂ̎������ł������_�����ł��悢�B
�����ł́A���������gsin(��t)������g�ƍl���A�ʑ��p(������t)�̕ϓ�d�����W�b�^�ƌĂ�ŁA
�W�b�^���܂ޏ��������g��sin(���{d���j�ŕ\���Ă��邪�A�W�b�^�̈�ʓI�Ȓ�`�i���Ԏ���ł�
��ʒu����̕ϓ��ʁj�ōl����ꍇ�́A�ʑ��p��������t�Ŗ����I�ɋL�q���邽�߂ɁA������
�p���g���ւ�p���āAsin(��t�{d��)�ŕ\���K�v������B���̐����g�́A����������t�Ƃ��Ă��A
�ʑ��p���i����t�j�Ƃ��Ă��A�`�����ł���A�ʑ��̔����ȕϓ��id���j�ɂ��A�����gsin(��t)��
���Ԏ��i�ʑ����j�����ɕϓ����Ă��邱�Ƃ�\���Ă�i���Ȃ킿�Ad�����I�V���X�R�[�v�ő��肷��ƁA
�����g��\���Ȑ��̉��i���Ԏ��j�����̕��Ƃ��Č����W�b�^�ł���B������A�C�p�^�[����
���Ԏ������̕��j�B
�ʑ��̔����ȕϓ��id���j�����Ԃ̔����ȕϓ��idt�j�ɏ��������Ȃ��Ɨ������Â炢�Ƃ����̂ŁA
d������j(t)�Ƃ��āA�W�b�^���܂ޏ��������g��sin(��t�{��j(t))�ƕ\���A�ʑ��p�̕�����t�{��j(t)
����(t�|��j(t)�^��)�ƕό`����ƁA�ʑ��̔����ȕϓ��id������j(t)�j�����Ԏ���ł͔����ϓ�
(��j(t)�^��)�ƂȂ�A�ϓ���(��j(t)�^��)�����ԂŎw��ł���̂ŁA�������₷���B
�����ԍ��F21772420
![]() 3�_
3�_
�����A����ꂽ(��)�B���āAMinerva2000����ւ̓˂����݂̓u�P�_���̃X���傳��ɏ���܂��āA�p�C�������
>���ω������x������⏬�������ŋL�^����Ă���N���V�b�N�����ȂǂŁA�{�����[�����グ�Ē����Ă�ꍇ�́A�����̃V�[���Œ������郌�x�����Ǝv���܂��B
�ɂ��āA�m�C�Y�t���A�͐M�����̃��x���ɂ͂��Ȃ��̂ł��傤���H�P���ɁA������������ʂȂ�A�m�C�Y�������i���߂�10dB���炢�́j����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����B
�����ԍ��F21772439
![]() 4�_
4�_
���m�C�Y�t���A�͐M�����̃��x���ɂ͂��Ȃ��̂ł��傤���H�P���ɁA������������ʂȂ�A�m�C�Y�������i���߂�10dB���炢�́j����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����B
�@youtube��OGG���k�Ȃ̂Ŏ����Ă݂�ƁA���w�E�ǂ���������ʂɂ����鈳�k�m�C�Y�̃��x���͂��Ȃ艺����悤�ł��B
�@�z���C�g�m�C�Y���ۂ��m�C�Y�t���A��PC����DAC �̎c���m�C�Y�̂悤�Ȃ̂ŁA�{�����[���̈ʒu��M���̑傫���ɂ͈ˑ����Ȃ��݂����ł��B
�@
�����ԍ��F21772962
![]() 5�_
5�_
�p�C������A�ǂ������萔�����܂����B
���̃m�C�Y�g�`���낭�Ɍ����ɋ����Ŏ��₵�Ă��܂��܂����B�m�C�Y�t���A�͌���Ȃ��ł���ˁB���炵�܂����B���k�m�C�Y�͌����̃X�y�N�g������芪�������Ȃ̂ŁA�����ɂ����ʂɂ�肻���ł��B���������킯�ŁA�����ʂł����k�m�C�Y�ɂ͂Ȃ��Ȃ��C�Â��ɂ����A���܂��ł��Ă���킯�ł��ˁB
�]�k�ł����A[21770682]�ŏ������A�����ȃW�b�^�[��16bit�łǂ��܂ŕ\���ł��邩�ɂ��āA�킩��ɂ��������Ǝv���̂ʼn��`���Ȃ����܂����B�W�b�^�[�U��10ns�i�W�b�^�[���g��30Hz�j�̔g�`�Ə����̍������v�Z�������̂ł��B���݂���g�`�ł͂Ȃ��̂ł킩��ɂ����ł����A10ns�̍Č��������Ƀf���P�[�g����������������ł��B
���������ςȌv�Z�ł͂���܂����A�����͍ő�ł�16bit�� 1LSB ���x�����Ȃ����߁A���Ȃ肢�������Ȕg�`�ɂȂ�܂��B1ns�̃W�b�^�[�ł͌����g�`�Ƃ̍��͂قږ����ɓ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21773260
![]() 6�_
6�_
����CD�����b�s���O�����Ƃ��A���ڂ̏ꍇ��PC����]�������ꍇ�̉��̈Ⴂ�����邩�Ƃ������Ƃ���ˁB
�������G���[���Ȃ��i�����Ă�CD�̃G���[�����@�\�uCIRC�v�Œ����ł���G���[�Ȃ�B http://www.pc-audio-fan.com/special/pureread2/20110307_5281/�Q�Ɓj�s�b�����O�ł��Ă���ΈႢ�͖����B����HDD�ɓ����f�[�^���L�^�����킯������Ⴂ������킯�Ȃ��B����Ǝv���̂͋C�̂����I
�����ԍ��F21773351
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�킩��₷�������ǂ����ł��B
�@�Ƃ������Ƃ�10ns�̃W�b�^�[�̔g�`�͍��}�ɂȂ邯�ǁA16bit�����̕���\�ł͍Č��ł���M���M���M�����x���Ȃ̂ŁA�E�}�̂悤�ɕό`���A��̎��g���ɂ����܂����W�b�^�[�U����10ns�ȉ��ƂȂ��16bit�����ł́A�قڍČ��ł��Ȃ������݂���ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
�@���������A16bit�����ŐM�����x����-90dB���炢�̐����g��DAC�o�͔g�`�́A���ꂢ�ȃT�C���J�[�u�ł͂Ȃ��A��`�g��O�p�g�������肠�����m�C�Y�̂悤�Ȕg�`�ɂȂ��Ă܂��B
�@
�����ԍ��F21773566
![]() 5�_
5�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̃O���t�V�~�����[�V������^�����Ă���Ă݂܂����B
�@500��s�̋���W�b�^�[�ō�}���܂������A�W�b�^�[���܂O���t�iRed�j������ƁA���Ԏ������̐U���ϒ����m�F�ł��܂��A���������̐U���͈��ɂȂ��Ă܂��B
�����ԍ��F21773654
![]() 5�_
5�_
�p�C������A���������A�����������Ƃł��B
�W�b�^�[ 1ns �ɂȂ�� 16bit �ł͍��̑��݂�\�����邱�Ƃ��s�\�ł��B�܂��A16bit���Ɣ������ʂ� -20log(2^16)=-96dB �����肪���E�Ȃ̂ŁA���������悤�ɃJ�N�J�N�ɂȂ�܂��B
����ɂ��Ă��A���̉�̓G�N�Z���ۏo���Ȃ��ǁA�p�C�����`���Ƃȁ`�J�b�R������ł���ˁB�Ȃ�ł���i��j�B���������A�C�R�����u�V���b�v�Ƃ��������Ɍ����Ă��܂����Btohoho���͏��m�����ǁA�܂�����͂���ł��킢��(���)�B
�����ԍ��F21773827
![]() 4�_
4�_
Minerva2000����A���v���Ԃ�ł��B
�܂����ӌ������������A���肪�Ƃ��������܂��B
���āA
��DAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ������́A�o�̓A�i���O�g�`�ւ̉e���́A�W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ邱�ƂŎ��g���ϓ����N���邱�Ƃł͂Ȃ��A�A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�ł��B�����Đl�͂��̘c�ɂ͔��ɕq���ŁA���ꂪ���m���ɎO�����̑傫�ȍ����o�闝�R�ł��B��̓�������̘_���͑O�҂̐����Ƃ��Ă���A���ł��B
�Ƃ̂��b�ł����A��������̘_���ɁuDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ������́A�o�̓A�i���O�g�`�ւ̉e���́A�W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ邱�ƂŎ��g���ϓ����N����v�Ə����Ă���ł��傤���H
��������̘_���̍[�T�ɂ́A
���������̎�ނ̃f�B�W�^���I�[�f�B�I�@��ɂ�����T���v�����O�W�b�^�[����̌��ʂ��������B��͐M����p�����W�b�^�[����́ACD-R���f�B�A�̐������[�J�̈Ⴂ�A�M���̃r�b�g�p�^�[���A�f�B�W�^���M���`���n�ADAC, ADC�����ăv���[���̃N���b�N���U��ȂǁA�����̗v�����A�I�[�f�B�I�@��̔��ׂȃW�b�^�[�����ɉe����^���Ă��邱�Ƃ��������B
�Ƃ���܂��B�܂�o�̓A�i���O�g�`�ɐ����Ă���c�݂ɂ́A�N���b�N�̃W�b�^�[�����łȂ��A�L�^���f�B�A�̃��[�J�[�����A�M���̃r�b�g�p�^�[���A�`���`���l���̓����Ȃǂ̕����̗v���ɂ��e��������Ƃ�������ł��B�����Ă��̘_���͊�{�I�ɂ��̘c�݂𑪒肵�Ă��邾���ł��B�Ⴆ�ADVD�v���[���[�̏o�͔g�`�Ɋւ��āA���̂悤�Ɍ����Ă��܂��F
��DVDA�P�ɂ����āA�����g���b�N�i24bit,96kHz,2-ch�j�ɏ����M�����L�^���ꂽDVD-Video�f�B�X�N���Đ����ē���ꂽ���茋�ʂ�Fig.11�Ɏ������B�܂��A�����v���[���ɂ����āADVD-Audio�t�H�[�}�b�g�i24bit,96kHz, 2-ch�j�ɂċL�^���s����DVD-R�f�B�X�N���Đ����ē���ꂽ���茋�ʂ�Fig.12�Ɏ������B�����ƁAFig.5�Ɏ�����CD-R�Đ����̑��茋�ʂ��r����ƁA�R�҂Ŗ��炩�ɃW�b�^�[�X�y�N�g�����قȂ邱�Ƃ�������B���̈Ⴂ�̌������A���f�B�A�A�L�^�t�H�[�}�b�g�A�v���[����DAC���쓮����T���v�����O�N���b�N�̂�����ł��邩�����_�ł͖��炩�łȂ��B
�W�b�^�[�X�y�N�g���̕ψق̌��������f�B�A�A�L�^�t�H�[�}�b�g�A�v���[����DAC���쓮����T���v�����O�N���b�N�̂�����ł��邩�킩��Ȃ��ƌ����Ă���̂ɁA�u�N���b�N�̃W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ邱�ƂŎ��g���ϓ����N����v�̂��ǂ����ȂǁA�킩��悤���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����H
�ނ��낱�̘_���́A���̂悤�ȒP���ȉe���W����肵���Ƃ��錤�������̂悤�ɔᔻ���Ă��܂��F
DA�^AD�ϊ����̃T���v�����O�N���b�N�ɐ����鎞�Ԃ�炬�i�T���v�����O�E�W�b�^�[�j�́A�^����Đ����ɂЂ��݂������炷�����̂ЂƂł���B�f�B�W�^���C���^�t�F�[�X�iAES�^EBU�K�i�M���j��̃W�b�^�[���Đ����̉����ɉe����^���邱�Ɓm�P�n�A�����̈Ⴂ�����m�ł��鉹�y�Đ����̊Ԃɂ́A���Ԃ�炬�̗ʂɈႢ��������m�Q�n�A���̎w�E�͂��邪�A�����̌����ɂ����ẮADA�ϊ���̃A�i���O�M���Ɋ܂܂��W�b�^�[�̉e�����ɑ��肨��ѕ]�����Ă���Ƃ͌����������B�W�b�^�[�Ɖ����Ƃ̊W�ׂ�ɂ́A�Đ������邢�̓f�B�W�^���L�^��̃f�[�^�ɁA�W�b�^�[�ɂ��ǂ̂悤�ȉe�����ǂꂾ�������I�Ɋ܂܂�Ă��邩���A��ʓI�ɑ��肷�邱�Ƃ��d�v�ł���B
�v����ɁA���̘_���́u�Đ������邢�̓f�B�W�^���L�^��̃f�[�^�ɁA�W�b�^�[�ɂ��ǂ̂悤�ȉe�����ǂꂾ�������I�Ɋ܂܂�Ă��邩���A��ʓI�ɑ��肷�邱�Ɓv���������Ă�����̂ŁA����̃W�b�^�[���o�̓A�i���O�g�`�ɂ��̂܂܍ڂ邱�Ƃ��m�F������̂ł͂���܂���B�ނ���A�o�͔g�`�ɂ͗l�X�ȗv�f�̉e��������A�u�ɂ߂ĕ��G�Șc�v�ƂȂ��Ă���ƌ����Ă���Ƃ��Ƃ��̂ł͂Ȃ��ł����H
���ɁA�u�W�b�^�[�̓A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�ł���v�Ɖ��肵�āA���������ł���Ȃ�u�l�͂��̘c�ɂ͔��ɕq���ŁA���ꂪ���m���ɎO�����̑傫�ȍ����o�闝�R�ł��v�ƌ����鍪���͉��ł����H
������ڂ����������ĉ������B
��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F21774493
![]() 7�_
7�_
���a�W�X�N����A����ɂ��́B
�u�������G���[���Ȃ��s�b�����O�ł��Ă���ΈႢ�͖����v�Ƃ����̂̓f�W�^���̈�̘b�ŁA�����̃t�@�C�����n�[�h�f�B�X�N�̉~�Տ�̂ǂ��ɂǂ̂悤�d�C�I�����ő��݂��Ă��邩�Ƃ������A�i���O�̈�ł͈Ⴂ������\��������Ƃ����̂��A�O�X���̑S�̂ŋc�_����Ă������Ƃł��B
�ڂ����͑O�X���ihttp://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21724280/�j
�̍Ō�̕��ɂ���u�܂Ƃ߁v�i [21754310] �j���������������B
�����ԍ��F21774514
![]() 3�_
3�_
tohoho3����
�u�q�X�e���b�N�ɂȂ�̂́E�E�E�E�������炵�傤���Ȃ��v�Ƃ����������́A����ȏ�ł͂���܂����A���̂������A����Ȃ��A�E�g�ɋ߂��ł��ˁB
�q�X�e���[(�ꌹ�̓M���V����́u�q�{�v�ł���)�������ɓ��L�ł��邱�Ƃ��������A�Ⴆ�u�j�����]�낪��������v�Ƃ������́A�ߔN�̌����ł́A���ׂāu�����Ȃ��v�Ƃ���Ă��܂��B
�����ԍ��F21774836�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��Symbolist_K����
�f�W�^���I�ɓ����ł��A�i���O�M���Ƃ��ă~�N���I�ɂł��Ⴂ������A���ꂪDAC���o�ăA�i���O�����M���ɕϊ�����Ă����̈Ⴂ���킩���ł͂Ȃ����ƌ������Ƃł����H
�����ԍ��F21775006
![]() 2�_
2�_
Symbolist_K����A
���ʔ����A�\����Ȃ��B�Y�ꎁ�̐��i���G�S�O�����Ŏ����Ă��邪�A
�s�^�b�Ƃ������Ȃ��ȁB
http://www.egogram-f.jp/seikaku/kekka/abaaa.htm
���߂����ȁB
�����ԍ��F21775057
![]() 4�_
4�_
���a�W�X�N����
�����Ȃ�ł���B���ہA�G���Y�̕Њ��ꂳ���p�c��Y���́A���҂��r�������ʁA�u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̕����i�i�ɉ����ǂ��v�Ɣ��f����Ă��܂��B
���̌��Ƃ��āA���Œ����āA���̂悤�ɔ��f���ꂽ�������݂���ȏ�A������\�Ƃ��錴�����Nj�����A�Q�̉�������o����܂����B
�P���́A�\�j�[�̋��䗲���ɂ��n�[�h�f�B�X�N�Ɋւ�����������p�������̂Łihttp://kanaimaru.com/AVQA/0f.htm�j�F
��0����1�A1����0�֔��]����^�C�~���O�́A���̃A�i���O�̓ǂݏo�����g�`���ア�ƁA�O���O���Ǝ��ԓI�ɑO��ɗh��܂��B�h��Ă��ǂݏo���^�C�~���O�܂łɂ͕K�����肵�܂��̂Łi�����Ȃ�悤�ɃT�[�{�n�����삵�Ă��܂��j��͂萔���͊ԈႢ�܂���B�Ƃ��낪�g�`�����]����Ƃ��ɂ͓d���ɃX�p�C�N�m�C�Y������܂��B�g�`���O���O���h��Ă���ƁA���]�m�C�Y���o��^�C�~���O���O���O���ɂȂ�܂��B���ꂪ��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�Ɖ������Q���܂��B�܂��R�s�[���͌��ɔ�ׂ�Ɨh�ꂪ�����Ȃ�̂ŁA�������ς���čs���i��ʓI�ɂ͗��čs���j�̂ł��B
�܂�A�uDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ�A���������A�i���O�g�`���̂��ώ����邩��v�iMinerva2000����ɂ��v��j�ł���A����̓A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Ђɂ��u�V���b�g�E�m�C�Y�ɂ�郉���_���W�b�^�[�ƁA������H����̃f�[�^�ˑ��W�b�^�[�v�ɓ�����܂��ihttp://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5718JAJP.pdf�j�B ����ɂ���ĉ�������Ƃ������Ƃł��B
�����P���́A�p�C������ɂ����̂Łi[21729066]�j�F
���Q�̓���f�[�^�̏������܂ꂽ�ʒu���Ⴄ�ƁA���ꂼ��̃f�[�^���V�[�N����w�b�h�̓������Ⴂ�܂��B�w�b�h�̓X�s���h�����[�^�[�œ����̂ŁA���̓s�x��������ׂ�������܂��B����ɂ���Ĕ������������g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�i�f�W�^���f�[�^��]�����邽�߂̃A�i���O�]���g���܂ށj�Ȃǂ��A�M�����C����A�[�X���C������A�i���O��H�ɓ��荞�肷��ƁA�A�[�X�p�^�[����z���p�^�[���ɂ���ăO�����h���[�v�m�C�Y���������A���ʂƂ���DAC����o�͂��ꂽ�����������Ȃ�Ƃ������Ƃ͕��ʂɍl�����܂��B
�܂�A�uDA�ϊ����ꂽ�A�i���O�g�`�ɃA�i���O�m�C�Y�g�`������邩��v�iMinerva2000����ɂ��v��j�ł���A���̕s�K���ɔ�������u�����_���W�b�^�[�v�ɂ���ĉ�������Ƃ������Ƃł��B
���̗́A�������A���Œ����Ă킩��ނ��̂��̂Ȃ̂��H
���̋^��ɑ��āA���⒮���Ă��킩��Ȃ������ƌ���ꂽ���͂S�l��������Ⴂ�܂����B
�ł��A�����Ė��炩�ɂ킩�����ƌ���ꂽ�����܂��A�O�q�̂悤�ɁA�Q�l�������������̂ł��B
�����ԍ��F21775380�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K���� �����́B
��������̘_���ɑ����ď����Ɓu����n�ɃW�b�^�[���t�����ꂽ���́A�ϑ��M���ւ̉e���́A�W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ邱�ƂŎ��g���ϓ����N�������Ɓv�ƂȂ�܂��B
�_���̂Q�D��͐M����p����W�b�^�[����@�̖`���́i�P�j�����Q�Ƃ��Ă��������B
�N���b�N�W�b�^�[�ɂ����DAC�ł̉����ω����ǂ��Ȃ邩�A�Ƃ����ł��d�v�Ȏ��_���Ȃ��A�P���ȁi�P�j���ŋc�_��i�߂��̂ŁA���ׂĂ����Ӗ��Ș_���ɂȂ�܂����B
�i�P�j���͕t�����ꂽ�W�b�^�[���ϑ��M���ɍڂ�Ƃ������Ƃ����\�����Ă��炸�A���ꂪ�W�b�^�[�t���ɂ��B��̉����ω��Ƒz�肵�Ă��܂����A���ꂪ���������ԈႢ�̌��ł��B
�i�P�j���̑���ɁA�N���b�N�W�b�^�[�t�����́ADAC�ł̃A�i���O�g�`�����V�~�����[�V���������鐔�����{���K�v�Ȃ̂ł����B
>�u�l�͂��̘c�ɂ͔��ɕq���ŁA���ꂪ���m���ɎO�����̑傫�ȍ����o�闝�R�ł��v�ƌ����鍪���͉��ł����H
�Ԗx����̎������ʂ�����ł��B
�����ԍ��F21775480
![]() 3�_
3�_
��Symbolist_K����
�S�������Ă��̓�ʂ�̌��ۂ��������Ƃ��Ă�����͓d���ɉe�����y�ڂ�����AHDD�ɋL�����ꂽ�ʒu�ɂ���ĈႢ��������Ƃ������Ƃł���ˁA����̓��b�s���O�̈Ⴂ�Ƃ͊W�Ȃ��̂ł́H�t�ɒ��ڃ��b�s���O�̂ق����d���ɉe�����ꂽ��AHDD�ɋL�����ꂽ�ꏊ�ɂ���Ă͈������ɍ�p����\�������Ă���̂ł͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F21775535
![]() 3�_
3�_
�V�k�S�Ȃ���AMinerva2000����Ƃ̉ߋ��̋c�_�̌o�����炵�܂��ƁE�E�E
Symbolist_K�����
>�u�l�͂��̘c�ɂ͔��ɕq���ŁA���ꂪ���m���ɎO�����̑傫�ȍ����o�闝�R�ł��v�ƌ����鍪���͉��ł����H
>
>������ڂ����������ĉ������B
�Ə�����Ă���킯�ł����AMinerva2000����͗��H�w�ɏڂ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�ڂ��������v���邱�Ƃ͋��炭�����ł��B����āA�Ȃɂ��̗��R�����Ă������ł͐������Ȃ����A�܂��͂킯�̂킩��Ȃ����������āA�u�킩��Ȃ��ق��������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����������ΑO�X���������������悤�ȁH�]�v�Ȍ��o��������������B
�����ԍ��F21775994
![]() 6�_
6�_
2018/04/25 10:08�i1�N�ȏ�O�j
8�{�I�[�o�[�T���v�����O�Ŕ{����t�����Ă��邾���Ȃ̂��B
�����ԍ��F21776912
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����������������肪�Ƃ��������܂��B
�ł��A�u�\���v�߂��������t�ł����A���ł�Minerva2000����u�Ԗx����̎������ʂ�����ł��B�v�Ƃ��������������������Ă���̂ŁA�u�㌾�v�̂悤�ȕςȊ����ɂȂ��Ă܂����ǁH
�����ԍ��F21776922�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�s�v�h�m�a�h�q�c�@�g.�Q�U�S����A����ɂ��́B
�u8�{�I�[�o�[�T���v�����O�Ŕ{����t�����Ă��邾���v������A�����ǂ��Ȃ̂ł����H
���������ڂ������������������B��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F21777199
![]() 4�_
4�_
���a�W�X�N����
�����ł��ˁA��̑�Q�̃p�C������̐��Ɋ�Â��A�gCD���ڃ��b�s���O�h�ō�����t�@�C���̕���������������ꍇ�����蓾�邱�ƂɂȂ�܂��ˁB
�p�C������̐��ł́A�t�@�C�����n�[�h�f�B�X�N��̍D�����Ȉʒu�ɑ��݂���Έ������Ȉʒu�ɑ��݂����艹���ǂ��Ȃ�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�gCD���ڃ��b�s���O�h�ō�����t�@�C����PC���b�s���O�ō�����t�@�C���Ɉ�`�I�ȗD��͂Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�����āA�n�[�h�f�B�X�N�̑����SSD���g���Ή������͂قڍ�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�������A��P�̃\�j�[�̋��䗲���̐��Ɋ�Â��A��`�I�ɁgCD���ڃ��b�s���O�h�ō�����t�@�C���̕��������ǂ����ƂɂȂ�܂��B
�Ƃ����̂��A�f�[�^�L�^�Ɖ����Ɋւ�����䎁�̋L�q�ɁA
����ʓI�Ƀf�W�^���f�[�^���������悢�̂́ACD����̃��b�s���O�ł͓ǂݏo��������ł��B�h���C�u���Ƃ��Ɏw�ߗp�Ɏg�������C���Y��ȃN���b�N��HDD�ɂ��͋����L�^����邩��ł��B�Ƃ��낪������R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���̂ŁA�������ς��̂ł��B
�Ƃ������ۂ̐���������A����HDD�̎d�g�݂�HAP-Z1ES�ɉ��p����ƁA
�u�gCD���ڃ��b�s���O�h�́ACD����ǂݏo���ꂽ�f�[�^���AHAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɁA���C���Y��ȃN���b�N�Œ��ڗ͋����L�^�����̂ʼn����ǂ��BPC���b�s���O�́A�f�[�^��HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɂQ���I�ɃR�s�[�����̂ŗ��B�v
�Ƃ������Ƃ����肳��邩��ł��B
�����ԍ��F21777458
![]() 4�_
4�_
���͐������ŕ\���̂Ŗ������Œ������̂ł��B
������������łȂ��ł��̂Ő���w�����Ē����Ă݂ĉ������A���͂��Ȃ��Ǝv���܂����
����SONY�ɖ₢���킹���ĉ��Ă��܂��B
SONY�Ƃ̖œ��e�͏����܂��S�̂̕��͓��e�ł���������Ǝv���܂��B
����ł��^���̂������SONY�Ƀ��[���Ŗ₢���킹�Ă݂ĉ������B
�ȊO�ƒ��J�ɉ��Ă���܂��ASONY�̃T�|�[�g�͉\�ƈႢ�������肵�Ă��܂��B
�����ԍ��F21777603
![]() 1�_
1�_
�w���ł͂Ȃ�
���X�Ɖ����ǂ��Ȃ̂ł����H�V�тł���
�����ԍ��F21777712
![]() 4�_
4�_
ABEBIREX����A����ɂ��́B
�����T�|�[�g�́u�\�j�[�g�������k�����v�Ƀ��[���Ŗ₢���킹�܂����B
���̎�����e�́A���̃X���b�h�̎���Ɠ����ŁA�p�c��Y���̕��͂��o�T�ƂƂ��Ɉ��p������ŁA�u���̂悤�ɁA�gCD���ڃ��b�s���O�h�̉���PC���b�s���O�̉����i�i�ɂ��炵���Ɣ��f���ꂽ������������Ⴂ�܂����A�\�j�[�l�ł͂��̂悤�Ȏ��ۂ��m�F����Ă��܂����A����Ƃ����b�s���O���@�ɂ�鉹�����͓��ɔF�߂Ă��Ȃ�������ł����H �\�j�[�l�̌��������Ƃ��Ă̂�������������������������K�r�ł��B�v�Ƃ������̂ł��B
�S���قǂ������Ď�����ɂ́AABEBIREX����ւ̂��̂Ƃ͈���āA�f�����ւ̏������݂��ւ����肷��悤�ȕ����͈����܂���ł����B�҂ɂ���Ĉ������Ⴄ�̂ł��傤���A���邢�͎����u���������v�����߂�����ł��傤���A���̉��e�͎��ɂ������肵������Ȃ��̂ŁA�u�����ɍ����o��\���͂���v����ǂ��A�u���̍��ق���̈Ⴂ�Ƃ��Ċ������邩�ǂ����ɂ��ẮA���q�l���X�̊������ɂ���Ă��ς�邩�Ƒ����܂��v�Ƃ����ς���Ȃ����̂ł����B
ABEBIREX����ւ̉ɂ͂����Ɠ��ݍ����e��������Ă������̂ł��傤���H �������A���Ƃ����ݍ����e��������Ă����ɂ���A�Ȃ��Ɂu���O�֎~�v�Ȃ̂��B���e���u�������͓��ɂȂ��v���������߁A���ꂪ�L�܂�ƊO�t���h���C�u�̔���s���ɉe�����邩��ł��傤���H ����A�ł��A�����\�j�[�͊O�t��BD/DVD�h���C�u�͍���Ă��Ȃ��̂ŁA����͊W�Ȃ��ł���ˁB
�ނ���A�L�߂Ă�����������A���̂��ƂɊS�̂���A�Ⴆ���̃X���b�h�̓ǎ҂Ȃǂ́A�����̕����₢���킹�����ă\�j�[��������Ƃ������������̎�Ԃ��Ȃ��Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H ����ǂ��납�A�\�j�[�̃E�F�u�T�C�g�̂p���`�̃y�[�W���ڂ��Ă��悢�Ǝv���܂��B����ɉ��̕s�s��������܂��傤���B
������ɂ���A���������������̓\�j�[�́u���������v�ł���͂��Ȃ̂ŁA�܂����O�֎~�Ƃ������Ă��Ȃ��̂ŁA�S����F�l�Ɍ����āA�����ɂ��Љ�����Ǝv���܂��F
�u���q�l
�܂łɂ����Ԃ����������܂��āA���ɐ\�������܂���B
�uHAP-Z1ES�v�ڑ������h���C�u����̃��b�s���O�ƁA�p�\�R���ł�
���b�s���O�ɂ��ăt�@�C���̉����������邩�ɂ��Ă��ē����܂��B
����Ȃ���A�C���^�[�l�b�g��̏������݂ɂ��Ă͕��ЂƂ��ăR����
�g�����Ă�����������ɂ͂������܂��A���b�s���O�̕��@���قȂ�
���ƂŁA����G���R�[�_�[���ς��܂��̂ŁA�ŏI�I�ȉ����ɍ����o
��\���͂��邩�Ƒ����܂��B
�������A���̍��ق���̈Ⴂ�Ƃ��Ċ������邩�ǂ����ɂ��ẮA
���q�l���X�̊������ɂ���Ă��ς�邩�Ƒ����܂��̂ŁA�����������
���m�Ȃ��ē��͍���ł������܂��B
�{���ł���A��葁����L���ē��������グ�邱�Ƃ��ł���悩��
���̂ł����A�����Ԃ������������ʂƂȂ��Ă��܂������ƁA�d�˂Ă��l
�ѐ\���グ�܂��B
-------------------------------------------------------------------------
�\�j�[�g�������k����
-------------------------------------------------------------------------�v
�d�d�d�Ƃ������̂ł����B
���ɂ������肵�����̂ŁA�܂�A�u�g���n�[�h��\�t�g���ς��̂ʼn��������o��\���͂��邯��ǂ��A���̍��ق���̈Ⴂ�Ƃ��Ċ������邩�ǂ����͂��q�l���悾�v�Ƃ������b�ł����B
���ꂪ�\�j�[�́u���������v�ł���Ƃ���Ȃ�A����͗v����Ɂu�����������邩�ǂ����͂悭�킩��܂��A���ɂ����Nj�����C������܂���v�Ƃ������ꂾ�Ǝv���܂��B
���������A�gCD���ڃ��b�s���O�h���ł���悤�ɂ����̂́APC����ɂ��܂芬�\�łȂ����X��HAP-Z1ES���悤�ɂȂ������ʁA�\�j�[�ɂ��A�u�wCD���b�s���O�ɂ͂ǂ�ȃ\�t�g���g�������̂��x�w�p�\�R�����g��Ȃ���CD���b�s���O������@�͂Ȃ��̂��x�Ƃ������₢���킹�����[�U�[���瑽����ꂽ�̂ŁA�p�\�R�����X�ŊO�t���h���C�u���璼�ڃ��b�s���O�ł���@�\��lj�����A�b�v�O���[�h�ɓ��ݐ����v�Ƃ������ƂȂ̂ŁAPC���삪��ł͂Ȃ����ɂ͕K�v�̂Ȃ��@�\�Ƃ����ʒu�Â��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����炻���ϋɓI�ɐ������邱�Ƃ����Ȃ��B����䂦�ɂ����A�gCD���ڃ��b�s���O�h�̂��߂́u�����h���C�u�v���Љ��y�[�W���Q�N�Ԃ��X�V����Ă��炸�A���܂��ɔ̔��I���ɂȂ����h���C�u�������Ă����肷��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F21777788
![]() 6�_
6�_
Symbolist_K����A
�u�g���n�[�h��\�t�g���ς��̂ʼn��������o��\���͂��邯��ǂ��A���̍��ق���̈Ⴂ�Ƃ��Ċ������邩�ǂ����͂��q�l���悾�v
���[�J�[�Ƃ��ẮA����ȕ\���œ�����̂����R����ȁB�X�s�[�J���悭�G�[�W���O�ʼn����ς��Ƃ������ǁA���̃X�s�[�J��
����ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȓ����ŕ\�����ē����Ă���B
�u�X�s�[�J�[�̐��\�́A��g�p�ɂȂ�ɂ�Ĕ����ɕω����܂��B�X�s�[�J�[���₽�����ɕۊǂ���Ă����ꍇ�A
�h���C�u���j�b�g�̃_���s���O�ނƃT�X�y���V�������{���̋@�B�I���������߂��܂ŁA���炭���Ԃ��|����܂��B
�h���C�u���j�b�g�̃T�X�y���V�����͉��ʂ�\�[�X�ɂ����܂����A�炵�n�߂Ă���P���Ԃ��炢�ŏ��X�ɂق���Ă��܂��B
�X�s�[�J�[���Ӑ}���ꂽ���\�����߂��܂łɂ����鎞�Ԃ́A�J���܂ł̕ۊǏ�����A�ǂ̗l�Ɏg�p����邩�ɂ����
�قȂ�܂��B�ڈ��Ƃ��ẮA���x�ɂ��e�������肳����ׁA���g�p�����łP�T�ԁA�܂��Ӑ}���ꂽ�f�U�C��������
�B���邽�߂ɁA����15���ԃX�s�[�J�[��炷���Ƃ�������ł��������B
���炵���ԁi���Ȃ��Ƃ��P�������x�j�͒����قǗǂ��Ƃ����Ă��܂����A����̓X�s�[�J�[�̉����ω����邱�Ƃ���������
���V�������Ɋ���Ă��邱�Ƃ̕����傫���Ƃ����،�������܂��B���ɁA�g�p�J�n����ɂ́A�����O�ɏo�߂��铙�̈�a��
����������A�����d�����������肵�܂����A���̏ڍׁi�f�B�e�B�[���j�Ȃǂ����܂Ŏ��ɂȂ�Ă����X�s�[�J�[����������
�Ȃ����ׂł���A���炵���Ԃ����K�v�ƂȂ�܂��B�����̊��炵���Ԃ̌�̃T�E���h�͖��m���Əڍׂ����������ƂȂ�
���炩�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B�v
�����ԍ��F21778006
![]() 2�_
2�_
��Symbolist_K����
https://www.sony.jp/support/inquiry_mail-kiyaku.html
���e�����J���邱�Ƃ̓\�j�[�I�ɂ̓A�E�g�ł��B
�C��t���ĉ������B
>>�g���n�[�h��\�t�g���ς��̂ʼn��������o��\���͂���
���ꂪ�����ɋ߂��̂ł́B
�����ԍ��F21778177
![]() 1�_
1�_
�u�H��̐��̌�����͂���ԁv�E�E�E������ƈႢ�܂��ˁB
�u��ډ��ڊ}�̓��v���������ȁB���邢�́u��̓��i������j���M�S����v�B
����̈Ӗ��ł͂Ȃ��āA����Ȋ����ł�����Ȃ��́A�Ǝv���܂��B�閧�̉ԉ��͂����Ƃ��Ă����Ă����E�E�E���ď��͂���܂���ˁB
�Ƃ͌����Ă��A�̈��n�� "Don't think. FEEL!" �́A���͍D������Ȃ��ł��B�I�[�f�B�I���玩�R�ɂȂ�Ȃ��Ǝv������B���j�Ֆ����q�C�B�����ĉ��y�����B
"Think out, thereafter feel FREE!" �Ƃ��������ł��傤���B�ǂ��܂ōl���邩��Symbolist_K����ł����A�u�S�[���v�ȂȂ��ł��傤����A�قǂقǂɁB
������������B
�����ԍ��F21778240
![]() 3�_
3�_
��Symbolist_K����
���̂���CD��ǂނƁA�ǂݎ��Ȃ������f�[�^��CD�h���C�u�̃f�[�^�⊮�@�\�ɂ��⊮����A�r�b�g�p�[�t�F�N�g�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���ꍇ������܂��B����������ǂݏo���āA��v����܂ŌJ��Ԃ��܂��B���̕��@�ɂ��A�����̏��ł���r�b�g�p�[�t�F�N�g�ɋ߂��Ȃ�悤�������s���܂��B�������A�ǂݎ��Ȃ��ӏ�����������ꍇ�ɂ́A�m���E���g���C�Ȃ�(����)�n��I�������������肵�ēǂݎ���ꍇ������܂��B
�}�j���A���̈ꕔ�R�s�[�ł��B
�m�r�b�g�p�[�t�F�N�g�ɋ߂��Ȃ�v���q���g�ł��B
Pure Read���Ńr�b�g�p�[�t�F�N�g�ŃR�s�[�o�����PC�]���̕����L�����Ǝv���܂��B
�\�j�[���G���R�[�_�[�ł̉����̕ω��͔F�߂Ă��܂��B
���̕ӂ��펯�I�ɍl����Γ�����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21778268
![]() 1�_
1�_
��Symbolist_K����
CD-AUDIO�����b�s���O������A���b�s���O�������f�[�^��CD�ɓ����Ă��鉹�Ɠ������A ���邢�́A�m��Ȃ������Ƀf�[�^��Ԃ������Ă��܂��A���̉��ƈႤ�̂����m�F���邱�Ƃ͌����ɂ͂ł��܂���B�����b�s���O���s���A�f�[�^���r������@�ł́A����̃��b�s���O���Ƀh���C�u�������ꏊ�ŕ�Ԃ����Ă��܂��ƌ��o�͓���Ȃ�܂��B
���ǁA���̉��ƈႤ���ǂ�����m�点�Ă����̂�Pure Read�@�\�𓋍ڂ����h���C�u�̂݁B�p�C�I�j�A��Pure Read���ڃh���C�u�Ńp�[�t�F�N�g���[�h�����I�ђ����A�������b�s���O�ł��Ă���A���f�[�^�͌��̉����ƒS�ۂł��܂��B���A�p�[�t�F�N�g���[�h�ł́A�f�[�^��Ԃ��ǂ����Ă��K�v�ȏꍇ�̓f�B�X�N����̓ǂݏo���𒆎~�������܂��B�ł��̂ŁA�����Đ��ɂ��������̓p�[�t�F�N�g���[�h�ł̃��b�s���O�𐄏��������܂��B
�Q�l�܂łɁAPure Read4+�̐����ł��B
PIONNER��Pure�@Reed���ڃh���C�u�Ńp�[�t�F�N�g���[�h�Ń��b�s���O����A�m���Ƀr�b�g�p�[�t�F�N�g�ł��B
SONY��100���r�b�g�p�[�t�F�N�g�ɂ͑Ή����Ă��܂���B
�r�b�g�p�[�t�F�N�g�̃��b�s���O�ɍS��Ȃ��PIONEER��Pure�@Read���ڃh���C�u�Ńp�[�t�F�N�g���[�h�Ń��b�s���O��HAP�|Z1ES�ɃR�s�[���邱�Ƃł��B
�X����l���{���ɍ�������]�ނȂ�PIONEER��Pure Read���ڃh���C�u���w�����邱�Ƃł��B
���t�V�т��y����ł���̂ł���Ύ��̏o�Ԃ͂���܂���B
�����ԍ��F21778309
![]() 1�_
1�_
Symbolist_K����A�O�̂��߁B
CD�̃G���[�����ɂ��Ă͑O�X��Minerva2000�����[21726506]�ƁASymbolist_K�����[21728369]�̂������F
>����ł�����A�Ƃ肽�Ă�dBpoweramp���̗g������A�v���N�X�^�[�̃h���C�u��T�����肷�邱�Ƃ��Ȃ��̂�������܂���ˁB
�������x�����܂��B�m�[�gPC�̌��w�h���C�u�ō������b�s���O���Ă��A�G���[�����Ɏ��s�����o���͂���܂���B�������Ŏ������̂��悢�ł��傤�B
�����ԍ��F21778380
![]() 4�_
4�_
��Symbolist_K����
�����܂ŏ����ėǂ��̂������܂�����
���̕��͂�ǂ��ǂ�ł��炦��Ε�����Ǝv���܂����A��SONY�w�����̐l�x���烁�[���ʼn��Ă܂��B
�I�y���[�^�[�̉Ƃ͈Ⴂ�܂��B
�������W�b�^�[���̖���������x�������Ă������ł��B
��������͎��̍l���Ƃ����`�ŏ������Ē����܂��B
�r�b�g�p�[�t�F�N�g�̃f�[�^��L����PC�ɃR�s�[����̂���Ԃ��Ǝv���܂��B
����ȏ�͏����܂���B
�ȏゲ���������肢���܂��B
�����ԍ��F21778441
![]() 2�_
2�_
ABEBIREX����
�����̕��͂�ǂ��ǂ�ł��炦��Ε�����Ǝv���܂����A����SONY�w�����̐l�x���烁�[���ʼn��Ă܂��B�I�y���[�^�[�̉Ƃ͈Ⴂ�܂��B
�������A����͓ǂ�ł��킩��܂���ł����BSONY�w�����̐l�x���烁�[���������Ƃ́B
���^���̂������SONY�Ƀ��[���Ŗ₢���킹�Ă݂ĉ������B�ȊO�ƒ��J�ɉ��Ă���܂��ASONY�̃T�|�[�g�͉\�ƈႢ�������肵�Ă��܂��B
�Ə�����Ă���̂ŁA���R�T�|�[�g������Ă�����̂Ǝv���Ă��܂�����B���ʂ̐l��SONY�w�����̐l�x�ɓ`��͂Ȃ��̂ŁA���ʂɃT�|�[�g�ɖ₢���킹�邵���Ȃ��ł͂Ȃ��ł����B
���Ȃ݂ɁA���̓\�j�[�́u���������v���������������|�\���o�āA�I�[�f�B�I�̗����ɂ����𗧂Ă������玿�₵�Ă���Ɩ��L���܂����B���������̓I�y���[�^�[�������̂ł��傤���A�S�`�T�����ɂ��������Ƃ������Ƃ́A��̐l�Ƒ��k���Ă��̂悤�Ȏ�|�ł̎���ւ́u���������v���܂Ƃ߂�̂��g�c�I�Ȃ��̂��K�v�������̂�������܂���B�܂��́u������̓��e�ɂ���ẮA�\�j�[�O���[�v��ВS��������蒼�ڂ������Ă��������ꍇ���������܂��v�Ƃ���̂ŁA�����������Ƃ������̂�������܂���B
������̃X���b�h��HAP-Z1ES�̎g�p�@�̂��ǂ������̂��߂ɋc�_�����ł���̂ŁA�����u���������v���������������|�\���o�āA�I�[�f�B�I�̗����ɂ����𗧂Ă������玿�₵�Ă���Ɩ��L���Ă���ȏ�A�����l�Ƃ��Ď�����ł����Ă��A������������̏�̎v�l�̗ƂƂ��ă\�j�[�̌����̍l���������p���ċc�_���邱�Ƃ́A�������₵���Ă��������ړI�ɂ܂��ɉ������̂ł���A
https://www.sony.jp/support/inquiry_mail-kiyaku.html
������̏����P����тQ�ƏƂ炵���킹�Ă݂Ă��A���̖ړI�ɂȂ���ꗂ�����̂Ƃ͎v���܂���B
���ƃT�|�[�g�̂��Ƃ�𑍍��I�ɔ��f����A��`�I�Ɂu�\�j�[�I�ɂ̓A�E�g�v�ƌ��߂�������Z���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F21778531
![]() 6�_
6�_
ABEBIREX����
�O�X���̋c�_�����ǂ݂ł��傤���H
�O�X���ł�Pioneer��Pure Read���g�������APlextor��PlexTools Professional���g���������܂�W�Ȃ��Ƃ����ӌ�����o����܂����B
Minerva2000����i [21726506] �j�ɂ��F
��C2�G���[�����o���Ȃ������G���[��C2�G���[�ƌĂт܂��B����܂�EAC�ő��ʂ�CD�����b�s���O���Ă��܂������AC2�G���[�����͈ꖇ��CD��10����x�N���������Ƃ͂���܂����AC2�G���[�̌o���͖����ł��B�܂�0�A1�̃f�[�^�͊����Ƀ��b�s���O�o���Ă��܂����B
����C2�G���[��10��N������WAV�t�@�C�����Đ����Ă��A�ǂ��Ő��`��Ԃ������͒N��������Ȃ��ł��傤�B�܂艹���͕ς��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�܂�A������u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�ɂ������K�v�͂Ȃ��A�Ȃ��Ȃ�A�Ⴆ��C2�G���[��10��N���������炢�ł͉����͕ς��Ȃ�����A�Ƃ̂��Ƃł��B
���������A�O�X������т�����̃X���ł̓f�W�^���̈�̘b�Ƃ��āA�u���b�s���O���ꂽ�t�@�C���̃o�C�i������v���邱�Ɓv�͓��R�ƌ���Ă��܂��B�ɂ�������炸�A�A�i���O�̈�̏������ɂ���ĉ����ω�����͉��̂��Ƃ������Ƃ��l�X�ȑ��ʂ���Nj�����Ă��܂��B
�u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�̃f�[�^��L����PC�ɃR�s�[����̂���ԁv�ƌ��߂���̂́A�f�W�^���̈�̘b��s���Ɋg�����ăA�i���O�̈���̏ۂ��Ă���A���҂𑍍��I�ɔ��f���闧�ꂩ��͍����ɖR�����A�����⏬���Ƃ��������܂���B
�����ԍ��F21778558
![]() 6�_
6�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�gDon't think. FEEL!�h �͌����āu�̈��n�v���Ƃ͎v���܂����I
�w�R����h���S���x�̃u���[�X�E���[�̂���ɑ����Z���t���������ł����H
�gDon�ft think. FEEL! It�fs like a finger pointing away to the moon. Don�ft concentrate on the finger, or you will miss all the heavenly glory.�h
https://www.youtube.com/watch?v=e2bl4eHIs5w
���̃Z���t�̌��ɂȂ��Ă���̂́A�u�����w���w�̘b�v�Ƃ��������T�t�̑T�ⓚ�ł����A�v����ɁgFEEL!�h�Ƃ����̂́u�^���ς��邱�Ɓi���������邱�Ɓj�v�̔�g�ł���A����ɑ��āgthink�h�Ƃ����̂́u�ڂ̑O�̌��ۂɍS�D���Ė{�������Ȃ����Ɓi���w�����邱�Ɓj�v�̔�g�ł��B
�u�������邱�Ɓv�͊y�����ł���ˁB�w�����茩�Ă��Ă��ʔ������Ȃ�Ƃ��Ȃ��B
�܂��ɁA�����ł́u���y�����Ƃ́v�y�����A�u�����v����ł͂��傤���Ȃ��Ƃ������Ƃ��w�����t�Ƃ��Ȃ蓾��̂͂Ȃ��ł��傤���H
���y���gFEEL!�h�������B���ꂪ���̊���Ƃ���ł��B
�ł��A�u���v�����u��ډ��ځv��������܂���ˁB38���L���̔ޕ����璭�߂Ă��邩��������̂ł����āA���ʂɒ���������{�R�{�R�ł����̂ˁB
�ނ���A�u�ڕa�ݏ��ɕ������j�v�ł����ˁB
�����ԍ��F21778604
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����
�r�b�g�p�[�t�F�N�g�ł����̈Ⴂ�͂Ȃ��A�Ƃ̉��߂̐l���Ȃ�CD���b�s���O�ł͂���������ɍS��̂ł����H
�r�b�g�p�[�t�F�N�g��100���̏�Ԃł��A��ԉ��̗ǂ���Ԃł��B
��������̈Ⴂ�͖����Ƃ�����̂ł���A�ǂ̏�Ԃ������ĉ�����ԗǂ��Ɣ��f�����̂ł����H
���ۂɒ����Ă݂������ł����H����ł�SONY�̂����Ƃ���D�݂̖��ł��B
�f�[�^�I�ɂ̓r�b�g�p�[�t�F�N�g����ԉ����ǂ��Ȃ��ԂƂ����̂͊ԈႢ����܂���B
�Ȃ��Ȃ��CD�̃f�[�^��100���R�s�[����邩��ł��B
���ʂɍl�����100���̃f�[�^�ɓG���킯����܂���B
�⊮�����Ƃ����Ă����S�ɕ⊮�����ۏ͂���܂���A100���̃f�[�^��120���ɂȂ邱�Ƃ͂������܂���B
���ꂾ�����炾��ƌf���ɏ������ނ̂ł���������̎��Ŋm���߂邱�Ƃ������߂��܂��B
�����ԍ��F21778734
![]() 6�_
6�_
�Y�ꂳ��̏����ԍ��F21778240���ǂ�����o�Ă����̂��킩���̂����ǁA�Ԃ��폜���ꂽ�H
�uCD���ڃ��b�s���O������Ɖ����悭�Ȃ�v�Ƃ����̂����������A�d���P�[�u����ς���Ɖ����悭�Ȃ�Ƃ��A
�d���̋ɐ������킹��Ɖ����悭�Ȃ�Ƃ��A�D�D�D�I�[�f�B�I�̃I�J���g�I�ȂƂ���������Ŏ����̂����
����B���������ASymbolist_K�����WaveSpectra���g����悤�ɂȂ����̂�����A�����I�J���g�I�ȕω���
�s�Ȃ��ƁA�ǂ̒��x�̔g�`/�X�y�N�g�����̕ω��������̂��Ƃ��A�ǂ̒��x�̔g�`/�X�y�N�g�����̕ω���
���Œm�o�\���Ƃ���������͂��B�܂��A���܂ł̋c�_����A�����^���������ɂ߂�͂��\�������Ă����
�v���B��́AHAP-Z1ES���w�����Č��ʂ���Ă��������B
�����ԍ��F21779005
![]() 2�_
2�_
��Symbolist_K����
HP-Z1ES�͖{�̂�HDD����������Ă���l�b�g���[�N���AUSB�P�[�u�������g��Ȃ��Ă����ڃf�W�^���f�[�^���Đ��ł���̂����_�ł��A�����������I�ɑ傫���e�����Ă��܂��B
������Ƃ͍l����HDD�ɉ����̗ǂ����y�f�[�^�����Ă�邱�Ƃ��厖�ł��B
CD����ōl���܂��Ǝ��̗ǂ����y�f�[�^��CD���b�s���O�A�r�b�g�p�[�t�F�N�g�ɂȂ�܂��B
���ꂾ���ł��B
���Ƃ͉���������܂����ǂ������ōw�����Ď����Ă݂Č��ʂ������Ɍ��\���Ă݂ĉ������B
���ꂾ�����X�������Ă��܂��A���낻��X���傳��̎g�p���Ă݂Ă̌l�I�ӌ����m�肽���ł��B
���t�V�т͂�߂ĉ������B
�����ԍ��F21779277
![]() 4�_
4�_
��Symbolist_K����
�������̐��i���w�����ĂR�N�����p���Ĕ��ɋC�ɓ����Ă���܂��B�ȃf�[�^�������PTB�����낻�낢���ς��ɂȂ�܂��B�Ȃ̂ł��̌f���ɂ����ɋ��������薈���̂悤�Ɍ��Ă���܂���Symbolist_K�����N�������̃e�[�}�͂Q��ɕ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��قǑ傫���Ȃ�A�ߋ��ő�ŎQ�����Ă��������������ԐM�����ł��傫�ȕ��S���Ǝv���܂��B
�Ȃ̂Ŏ��͂���ōŌ�ɂ��܂��B
�P�D�u���C���Y��ȃN���b�N��HDD�ɂ��͋����L�^�����v
�Q�D�u�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���v
�����̒��ۓI�ȕ\���͂Ȃ�ł����ˁH
�P�D���C���Ȃ������N���b�N�ł��������ރ^�C�~���O�Ƃ������l�i�f�W�^����H�Łu���d�ʁv�Ɓu��d�ʁv����ʂ��鋫�ƂȂ�d�ʂ��w���j���N�����[���Ė�肪�Ȃ����ʂɋL�^���ꂽ���ʂ����A�u���C���Y��v�ɋL�^���ꂽ�S�������f�[�^��ǂݏo�����ق��������ǂ��Ȃ�͂����Ƃ������ƂȂ̂ł����ˁH
�Q�D�ǂ�ȍ��Ղł��傤�A�����ǂݏo�����Ƃ��ɂǂ��Ȃ��āA�ǂ����ɉe��������̂��A�z���ł��Ȃ��B
�f�W�^�������Ȃ̂ɉ�������ĕ������邩���t�Ƃ��ă~�N���i�i�m���邢�̓s�R�����m��Ȃ��j�̈�̃A�i���O�I�Ȍ��ۂ⓮��������o���Ď�����[�������悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���E�E�E
�����A����ĕ�������̂͋C�̂������Ǝv�����ǁE�E�E�A
����ł́E�E�E�B
�����ԍ��F21779456
![]() 4�_
4�_
ABEBIREX����
���r�b�g�p�[�t�F�N�g�ł����̈Ⴂ�͂Ȃ��A�Ƃ̉��߂̐l���Ȃ�CD���b�s���O�ł͂���������ɍS��̂ł����H
���ɓ����Ă��܂���B�l�̔ᔻ������O�ɁA�l�̏��������̂��悭�ǂ�ʼn������F
�u�O�X������т�����̃X���ł̓f�W�^���̈�̘b�Ƃ��āA�w���b�s���O���ꂽ�t�@�C���̃o�C�i������v���邱�Ɓx�͓��R�ƌ���Ă��܂��B�ɂ�������炸�A�A�i���O�̈�̏������ɂ���ĉ����ω�����͉��̂��Ƃ������Ƃ��l�X�ȑ��ʂ���Nj�����Ă��܂��B�v
�f�W�^���̈�̘b�ƃA�i���O�̈�̘b�͕����ċc�_���Ȃ���A���lj����c�_���Ă���̂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�B
�f�W�^���̈�ł́AMinerva2000������ꂽ�i [21726506] �j�A�u����C2�G���[��10��N������WAV�t�@�C�����Đ����Ă��A�ǂ��Ő��`��Ԃ������͒N��������Ȃ��ł��傤�B�܂艹���͕ς��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�v�Ƃ������Ƃɐs���܂��B
����Ƃ����Ȃ��́A�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ń��b�s���O���ꂽ�t�@�C����C2�G���[�����Ȃ�����C2�G���[�����������b�s���O�ł̃t�@�C�����A�u���C���h�Œ��������邱�Ƃ��ł���̂ł����H
���r�b�g�p�[�t�F�N�g��100���̏�Ԃł��A��ԉ��̗ǂ���Ԃł��B��������̈Ⴂ�͖����Ƃ�����̂ł���A�ǂ̏�Ԃ������ĉ�����ԗǂ��Ɣ��f�����̂ł����H
�ł�����A���Ƃ��o�C�i������v���Ă��Ă��A�i���O�̗̈�ʼn��͂�����ł��ς��̂�����A�A�i���O�̏�Ԃ��ł��D�����ȂƂ��̉�����ԗǂ��̂ł��B�u�w���b�s���O���ꂽ�t�@�C���̃o�C�i������v���邱�Ɓx�͓��R�ƌ���Ă��܂��B�ɂ�������炸�A�A�i���O�̈�̏������ɂ���ĉ����ω�����͉��̂��Ƃ������Ɓv��Nj����Ă���̂����̃X�����ƌ����Ă���ł͂Ȃ��ł����B
�����������O�̏������݂���悭�ǂ݂������A�܂��Ă₱�̃X���b�h���s�X���b�h�̘b�̗���Ȃǂ܂������ǂ�ł��Ȃ��A�����Ȃ�o�ꂵ������̂��Ȃ��ɁA���́u���t�V�т͂�߂ĉ������B�v�Ȃǂƌ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����B
�u���ꂾ�����X�������Ă��܂��v�̂́A�X���b�h�̎�|���悭��������Ē��J�ɋc�_��i�߂ĉ�����_�҂̕��X�����������邩��ł��B������u���t�V�сv�ł���Ƃ��A�u���炾��ƌf���ɏ������ށv�Ƃ��Ə̂���̂́A�ő����̏������݂�����Ă���Minerva2000�����p�C�������Y��悤�ɂ��������Ȃ������tohoho3������n�߂Ƃ��鑽���̕��X�Ɏ���ł��傤�B�ނ�͊F�A���t�V�т����Ă���̂ł����H
�܂��A�ǂ݂������A���̃X�����p�C������ɂ���Ē��ꂽ�u�f�W�^���̖��ƃA�i���O�̖��͐蕪���Ę_���܂��傤�v�Ƃ��������ʔF���Ƃ��Ă��邱�Ƃ�m������Ȃ����Ȃ��ɂ́A�ǂ����Ă��̃X�������̂悤�Ɍp�����Ă���̂��Ȃǂ܂����������ł��Ȃ��ł��傤���B���ꂪ�킩���Ă���A��o���̂悤�Ɂu�r�b�g�p�[�t�F�N�g��100���̏�Ԃł��v�A�u�r�b�g�p�[�t�F�N�g��100���̏�Ԃł��v�Ƃ����J��Ԃ������Ȃ�Ă��Ƃ������킯������܂���B
����HAP-Z1ES�������������ɂ��Ă��A���Ȃ��Ɏw�}�����؍����͂���܂���B�����u���̃X���b�h�̎�ړI�́AHAP-Z1ES�ɉ�����gCD���ڃ��b�s���O�h�ƁgPC���b�s���O�h�̉������ɂ��Ẵ��[�U�[�̕��X�̔��f���W�߂邱�Ƃł���v�Ə������̂��ǂ�ł��Ȃ��̂ł��傤���A���Ƃ����������ł��̔��f���������Ƃ��Ă��A����͂P���f�ɂ����܂���B�P�̔��f�������܂����A����͂��̃X���b�h���I���ɂ��邩�ǂ����Ƃ͂܂��ʂ̖��ł��B
���������A���̎���������m��������ɂǂ����Ă��̂悤�Ȏw�����ł���̂ł����H ������������A���̂Ƃ���ł͍��X�s�[�J�[�����Ă��āAHAP-Z1ES�����ł͂ȂȂ��K�ȃX�s�[�J�[������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������Ȃ����A���邢�̓A���v�����Ă��邩������Ȃ����B���邢�͉Ƃ������Ēu���ꏊ���Ȃ���������Ȃ����A���邢�́A���Ȃ��ɂƂ��Ă�15���~�͑債�����z�ł͂Ȃ���������Ȃ������ɂƂ��Ă͑���ł��邩������Ȃ����B����ȉ\�ȏ������z�����邱�Ƃ��Ȃ��̂ł����H ���낢��Ȃ��Ƃ����Ă��Ă��A�����g�����ۂ�HAP-Z1ES���w�����邩�ǂ����͒��ړI�ȊW�͂Ȃ��̂ł��B
�Ƃɂ����A�����������̂ł���A���ݓI�Ȃ��Ƃ��������������B�l�̘b��ǂ݂������ɔᔻ����̂͂�߂ĉ������B�܂����ӔC�Ɏw�}������̂���߂ĉ������B�ꂪ�r��܂��̂ŁB�C�ɓ���Ȃ���A�ʂɎQ�����Ȃ�����������̂��Ƃł͂���܂��H
�����ԍ��F21779520
![]() 5�_
5�_
ABEBIREX����̂����e��q�����Ďv�������Ƃ������܂��B
�܂�[21777603]����AABEBIREX����́ASONY����̉�f���ɐM�p����^�C�v�̂����Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����B�܂��A����"SONY"�Ƃ́A��L�����e����́u�T�|�[�g�����v�Ƃ����v���܂����A[21778441]�ł́u�\�j�[�����̐l�v�ƂȂ��Ă���A�Ȃ������ŕώ������̂��^��Ɏv���܂����B
����ɁA�����ł́u�I�y���[�^�[�̉Ƃ͈Ⴂ�܂��v�Ƃ���A���ꂩ�炷��ƁA�I�y���[�^�[�̉��u�\�j�[�����̐l�v�̉̂ق���M�p����^�C�v�̂����Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����B
�������A���Ƃ��u���Ȃ��܂鎁�v�́A�u�\�j�[�����̐l�v���ے�����Ƃ��l�����܂����A���̌��͕K�������M�p�ł��Ȃ��A�Ƃ����̂��X���b�h�̗���ł��B�����������_���炷��ƁAABEBIREX����̂����f�͐Ȋ��������܂��B
���ɋZ�p�_�ɋ߂��Ƃ���ł́A
>��������͎��̍l���Ƃ����`�ŏ������Ē����܂��B
>�r�b�g�p�[�t�F�N�g�̃f�[�^��L����PC�ɃR�s�[����̂���Ԃ��Ǝv���܂��B
�Ƃ���܂��B���������Ԃ������������̊��ɂ͈Ӗ��s���ł��B�Ƃ����̂́A���������Ȃɂ��l���Ȃ��Ƃ��u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�łӂ��ł��B�uPC�ɃR�s�[�v�̈Ӗ����킩��܂��A�uPC����HAP-Z1ES�ɃR�s�[�v�̈Ӗ��ł��傤���ˁB�u�L���Łv�Ƃ�������ɂ́u�������ǂ��v�Ƃ������Ƃł��傤���A���̌��[21778734]��
>�f�[�^�I�ɂ̓r�b�g�p�[�t�F�N�g����ԉ����ǂ��Ȃ��ԂƂ����̂͊ԈႢ����܂���B
�ȂǂƏ�����Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�������Ɓu�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�łȂ��Ȃ�̂ł��傤���B����͐M���������ł��B�Ȃ��u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�Ƃ�����ɂȂ��݂��Ȃ��̂ŃO�O���Ă݂܂��ƁA������ABEBIREX�������́u�p�C�I�j�A��Pure Drive�v�ɍs��������܂��B�Ȃ�قǁB
�O�q�̏����Ă��܂��ƁAABEBIREX����́u���̘̋b�v���r�I�ȒP�ɐM������l�Ȃ̂��낤�Ɛ������܂��B�������ł����ӂ���PC�p���w�h���C�u�Ŏ����Ă���A�����Ԉ���������ɂȂ������낤�Ǝv���̂ł����B
>������Ƃ͍l����HDD�ɉ����̗ǂ����y�f�[�^�����Ă�邱�Ƃ��厖�ł��B
�i�����j
>���t�V�т͂�߂ĉ������B
�m���ɃX���̓��e��ABEBIREX����ɂ͓���A���邢�͂����g�̒��ł��Z�p�_����������Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂����A�������̉��l�ς���邱�Ƃ͂܂��ǂ��Ƃ��āA�����t���͗ǂ��Ȃ��ł��ˁB�c�_�ɋ����Ȃ���Ε��u�ł悭�͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F21779524
![]() 5�_
5�_
�����܂���A�X���傳��Ƃ��Ԃ����B
�����ԍ��F21779528
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
SONY�̒��̐l�Ƃ����͎̂������Ă��X���A�O�t��BD�h���C�u�ڑ��F���ŏ��������̂ł��B
���̃X���ɂ����̃X���傳��̓��X���Ă���̂�SONY�̒��̐l�̉���̓X���傳��͗������Ă��邩�ƁB
�S���W�Ȃ��X���ɃX���傳�����Ă��Ă����Ȃ�u���ڃ��b�s���O��PC�R�s�[�̉������v
�ł̉��͕ς��Ȃ��h�Ƃ��Ӗ��̂킩��Ȃ��h�ɂ�����܂����B
���͕�����Ȃ��Ƃ����������ŕς��Ȃ��Ƃ͌����Ă܂���B
SONY�̐l�̂��Ƃ͐M�p���Ă��܂��B
��Symbolist_k����
�l�̃X���ɂ͊W�Ȃ��Ƃ���ɓ����Ă��āA�X���傳��̃X���Ɏ�������Ȃ�ɓ��e�������Ă���Ǝv�����Ƃ������Ă��@�����B
��Ɋ������̂̓X���傳��A���Ȃ��ł��B
�r�b�g�p�[�t�F�N�g�Ƃ�100���R�s�[���ꂽ��Ԃł��A99�����m�������������ł��B
�m����������Ή����������Ȃ�m�����オ��̂ł́A������������Ƃ͌����Ă܂���B
�����ȉ�������{���ɐl�Ԃ�������������ACD���ڃ��b�s���O�h�ʼn����ǂ��Ȃ�̂��H�ȂǂƂ����^����o�Ȃ����ƁB
���A�m���̖���SONY�̐l�̉��Q�l�ɏ������Ē����܂����B
���f�Ȃ悤�ł��̂ł���Ŏ��炵�܂��B
�����ԍ��F21779574
![]() 4�_
4�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�������Ă��X���� �h �O�t��BD�h���C�u�ڑ��F���h�X���ł����B
���̋L���Ⴂ�ł����A���������Ē����܂��B
����Ŗ{���ɏI���ɂ����Ē����܂��B
�����ԍ��F21779614
![]() 5�_
5�_
�@����܂ł̏������݂̒��ɂ́A�ƂĂ��L�p�ȓ��e���܂܂�Ă���̂ŁA�ȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂����B
�@�}�@�ƇA��SSD��HDD��̉����f�[�^�i�o�C�i�����S��v�j��FFT�ł����A�Ƃ��ɓ����̕ω��͂���܂���B�v�̓f�[�^�[�̐��l���O���t�ɂ��������Ȃ̂ŁA�o�C�i������v���Ă���ȏ�A�������܂��ꏊ������Ă��f�[�^���̂ɕω��͂���܂���B�i�f�W�^���̈�̘b�j
�@���̃X���̃^�C�g���wCD���ڃ��b�s���O�h�ʼn����ǂ��Ȃ�̂������ĉ������x���炷��A�f�W�^���̈�Ńo�C�i������v�������_�Ńf�W�^���f�[�^�̗͂Ȃ��Ƃ������ƂŌ��_�͏o�Ă܂��B
�@���̌�A�}�X�^�[�N���b�N�i�A�i���O��`�g�j�̃W�b�^�[�ɂ�鉹���̘b���o�ă��X����������ԂɂȂ��Ă܂��B
�@�}�B��SSD��̃t�@�C���A�C��HDD��̃o�C�i����v������DAC�o�͂����Ƃ��̃A�i���O�g���A�X�ɘ^�����Ă���ēx�o�͂����Ƃ��̔g�`��FFT�ŕ\�����Ă܂��B
�@�Ȃ���U�^�������̂��́AD/A�ϊ���2��s�����Ƃɂ���ăW�b�^�[�ɂ��g�`�̕ω����o�₷���̂ł͂Ȃ����ƍl�������߂ł��B
�@�B�C�́A�ꌩ�����Ɍ����܂����A�g�傷��Ɓi�}�D�A�E�j�m�C�Y�t���A�̌`�ƃW�b�^�[�Ǝv����T�C�h�o���h�̌`���Ⴂ�܂��B�i���F�́���̒��j
�@�����̃m�C�Y�̒��ɂ́A�W�b�^�ɂ��m�C�X��c��M�G����A�A�[�X���C����������Ă���A�[�X���[�v�m�C�Y�ȂǁA�����̌����ɂȂ�m�C�Y�����R�܂܂�Ă܂��B
�@�ł����āA���̃X���ł́A�W�b�^�[�̉e���̂ق����A��MP3��-80dB���x�̈��k�ϒ��m�C�Y���������ω��ɉe�������蒮��������̂��ȒP���Ƃ����ӌ����������̂ŁA�ǂ̂��炢�̎��ԕϒ��̃W�b�^�[�������ƁA�l�̊��o�ł������������̂��Ƃ��������e�����C���ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA����܂łɎ����ꂽ������O���t�����Ƃɓǂݒ����Ă݂�ƁA�W�b�^�[�ɂ�鉹�����ǂ̒��x����̂����A������x�A��ʓI�ɂ킩��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă܂��B�X���̖{��Ƃ͊O��Ă܂����B
�@�@�Ȃ̂ňꌩ�A���t�̗V�т̂悤�Ɍ����܂����A���e�͂��Ȃ�[�������ɓ��ݍ���ł���Ǝv���܂��B�W�b�^�[�ɂ�鉹���ɋ���������́A�ǂݒ����Ă݂�Ɩʔ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21780079
![]() 6�_
6�_
���Ȃ���U�^�������̂��́AD/A�ϊ���2��s�����Ƃɂ���ăW�b�^�[�ɂ��g�`�̕ω����o�₷���̂ł͂Ȃ����ƍl�������߂ł��B
USB�`���H���K�`�K�`�Ɍł߂���Ԃ���Ȃ��C���𗎂Ƃ��āC�_�C�\�[�ӂ�̎���USB�P�[�u���Ŏ��݂���ƁC�����g�`�ŕ`�ʂ��ė��܂���B
�����ԍ��F21782494
![]() 2�_
2�_
��U����ƌ����Ă����Ȃ���܂��o�Ă��Ă��܂��܂����B
��͂�I�[�f�B�I�}�j�A�Ƃ��ċ���������̂ł������������B
���ǂ�`�����ł���
���₳���ĉ������B
�ȑOEAC��CD���R�s�[����ꍇ�Z�L���A���[�h�ƃo�[�X���[�h�ʼn����Ⴄ�Ə������݂��Ă��܂�����
�o�C�i������v���Ă��������Ⴄ�Ƃ��������ŋX�����ł��傤���H
������Ƙb������܂�����������ΗL��ł��B
�����ԍ��F21782528
![]() 2�_
2�_
�o�[�X���[�h���o�[�X�g���[�h���������Ē����܂��B
�����ԍ��F21782535
![]() 2�_
2�_
���ȑOEAC��CD���R�s�[����ꍇ�Z�L���A���[�h�ƃo�[�X���[�h�ʼn����Ⴄ�Ə������݂��Ă��܂������o�C�i������v���Ă��������Ⴄ�Ƃ��������ŋX�����ł��傤���H
���p������̌����ŋX�����ł���B
EAC�̃A�v������Ȃ��Ă��C�G���[�����@�\���������[�h�́C�O�㗧�̕`�ʂ��R�����X���Ɏd�オ��܂���B
�\�j�[�̃A�v���ɂ��Ă��CApple�̃A�v���ɂ��Ă��B
�����ԍ��F21782570
![]() 3�_
3�_
���ǂ�`�����ł���
���肪�Ƃ��������܂��B
���@�@EAC�@Pure Read 4�@�A�m�[�gPC�Z�L���A���[�h�@�B�m�[�gPC�o�[�X�g���[�h
3��̕��@��CD���b�s���O�����Ă݂܂����B
���A�b�v���[�h���ł��B
�������I���܂�������J�����Ē����܂��B
�����ԍ��F21782594
![]() 2�_
2�_
���b�s���O����Ȃ��ł����CUSB�]����Isochronous������Bulk Pet�����B
�O�҂̕����C�O�㗧�̕`�ʂ��R�����X���̉���炵�܂���B
�ƁC�O�҂̓��[�J��������Ԍ�����ŁC��҂̕����f���ɘA���œ`������܂��B
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet
http://www.itf.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/170915BulkPet.pdf
�����ԍ��F21782611
![]() 2�_
2�_
���������I���܂�������J�����Ē����܂��B
�ʼn_�ɃA�b�v���Ă��_���Ȃ�ł���B
�A�b�v����l�́C�m��ƒm�o�F���o���ĂāC�������ĂȂ��ƂˁB
����s�\���ł��ƁC���ɂ��Ȃ�Ȃ��ł���B
�����ԍ��F21782632
![]() 2�_
2�_
���ǂ�`�����ł���
�����Ȃ�ł����A�ł����������������Ȃ̂ŃA�b�v�����Ă��������B
�A�b�v���Ă�i�K�ʼn������ƕς���Ă��܂���������܂��B
�����ԍ��F21782652
![]() 2�_
2�_
��ABEBIREX����
�������Ȃ�ł����A�ł����������������Ȃ̂ŃA�b�v�����Ă��������B
�����ł炸�ɁB
����̃��b�s���O�t�@�C���̎d�オ����x���C�ǂ̒��x����c�����Ă���ł��傤�B
�����ԍ��F21782728
![]() 2�_
2�_
Pure read4+
http://fast-uploader.com/file/7080389528685/
�m�[�gPC�@�Z�L���A
http://fast-uploader.com/file/7080391529053/
�m�[�gPC�@�o�[�X�g
http://fast-uploader.com/file/7080393176376/
CD���烊�b�s���O�������_�Ńo�C�i���͈�v���Ă��܂��B
�o�C�i������v���Ă��鎞�_�ʼn��͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B
�܂��_�E�����[�h�ɂ���ĉ����ω�����Ƃ����l�����邩������܂���B
�ɂȐl�����܂�����HAP-Z1ES�ɃR�s�[���Ē����Ă݂ĉ������B
���̊��ł͉�肪���邳������ł��܂���B
�l�I�Ȃ��Ƃł������a�����ō����͓�����ꂽ�̂ł����Q�܂��B
�܂����q���オ�����炨�ז����邩������܂���B
�����ɂ��Ă͐��q�����Ȃ̂ł������������B
�����ԍ��F21782774
![]() 2�_
2�_
ABEBIREX����
���Ȃ��̂悤�ɁA���C�ŃE�\�����A���������Ԃ��āu�����̓\�j�[�����̐l����M�d�ȏ�������������A�\�j�[�Ƃ̖�����̂Ō��J�ł��Ȃ��v�Ȃǂƍ��b�����A�l�̘b��ǂ܂��ɔᔻ�������A�����Ȑl�X���^�ʖڂɋc�_���Ă��邱�Ƃ��u���t�V�сv���ƌ��߂��Ē������A�u���炾��f���ɏ������ނ̂͂�߂�v�ƌ����A���ӔC�ɐl�Ɏw�}�����A���l�̃X���b�h���r�炵�Ă����Ȃ���A�����̂��Ƃ��߂��A�uABEBIREX����̂����f�͐Ȋ��������܂��v�ƕ]������A�u�X���̓��e��ABEBIREX����ɂ͓���v���炻��Ȃ��ƂɂȂ�̂��낤�Ɣ��f������A�o�c���������ɂ��������ƌ��������āA�ꌾ�̎Ӎ߂������A����I�Ɂu����Ŗ{���ɏI���ɂ����Ē����܂��B�v�ƌ����ē��������Ă���ȏ�̒Njy������Ă����Ȃ���A�����ɂ��u��U����ƌ����Ă����Ȃ���܂��o�Ă��Ă��܂��܂����v�ȂǂƂ��ǂ��Ȃ���ēo�ꂵ�Ď����������炾��Ə������݂��ł���悤�ȁu�ȁv�l�Ԃ��������Ƃ�����܂���B
�P�D���C�ŃE�\�����B
���\�j�[�̃T�|�[�g���
���₢���킹�̉��[�����e�́A�f�����ւ̏������݂͋֎~�ł��B
�Ƃ̃��[�������܂����B
���ۂ́A
�u�Ȃ��A���Ђ��瑗�M�����Ă�������
���q�l�ւ̂��́A���q�l�l���Ăɂ��₢���킹��
����������ړI�ł����肷����̂ł������܂��B
�����[���ł̂��₢���킹�̍ۂ̒��ӎ���
https://www.sony.jp/support/inquiry_mail-kiyaku.html
���̂��߁A���ɋ������܂����A���q�l�ւ̉��e�ɂ��܂��Ă�
Web�T�C�g��SNS�ł̌��J�����T�����������܂��悤
���肢�\���グ�܂��v
�Ƃ����˗������Ɋ܂܂�Ă��������B���ꂾ���̂��ƂȂ̂ɁA�uSONY�Ƃ̖œ��e�͏����܂���v�ȂǂƂ��������Ԃ��āA�������������ʂɃ\�j�[����������̂悤�Ɍ���������B��̂悤�Ȃ��Ƃ��˗�����Ă��A���́u���ӎ����v�Ɂu���Ӂv���Ă��Ȃ���A����ɉ���S������邢���͂Ȃ��ł��傤�B����Ƃ��A��������i��Łu�͂��͂����ӂ��܂���v�Ɛ\���o���̂��B�Ƃɂ����A���̂悤�Ȉ˗����ɓY�����Ă��������ł͉��̍S���͂�����܂���B���ꂪ�Ȃ��uSONY�Ƃ̖v�ɂȂ�̂��B������������Ȉ˗������Y�����Ă������Ƃ��^�킵���B�\�j�[�����[���ł̉ɁA�E�F�u�y�[�W�̒��ӎ����ւ̃����N��\�邾�낤���B�����N��ł́u���ӂ���v�{�^���������ď��߂ėL���ɂȂ�悤�ɂȂ��Ă���̂ɁB���ւ̉ɂ͂���Ȃ��̂͂���܂���B
�����ăT�|�[�g�Ƃ��Ƃ肵���Ƃ����Ă����Ȃ���A�r������u�\�j�[�����̐l�v�Ƃ̂��Ƃ肾�����ƌ���|���B
�Q�D���C�ŃE�\���� ���̂Q
�u����Ŗ{���ɏI���ɂ����Ē����܂��B�v����̑����́u��U����ƌ����Ă����Ȃ���܂��o�Ă��Ă��܂��܂����B�v
���Ȃ��́u�{���v�Ƃ����̂͂���قnjy�����̂Ȃ̂ł����H
�R�D���C�ŃE�\���� ���̂R
��Pure Read�ł̃��b�s���O�ɂ��Ă͂�����������V�����X���𗧂āA�������Ē�����������܂���B
�ƌ����Ă����Ȃ���A���낤���Ƃ������o�����͂��̃X���ɖ߂��Ă��ď����B
�S�D�X���Ⴂ�Ȃǂ����܂��Ȃ�
���ǂ�`�����ł���
���₳���ĉ������B
�ȑOEAC��CD���R�s�[����ꍇ�Z�L���A���[�h�ƃo�[�X���[�h�ʼn����Ⴄ�Ə������݂��Ă��܂�����
�o�C�i������v���Ă��������Ⴄ�Ƃ��������ŋX�����ł��傤���H
������Ƙb������܂�����������ΗL��ł��B
�ǂ�`�����ł����̏������݂������̂͂��̃X���ł͂Ȃ��A���Ȃ��̃X���ł��傤�B�����̃X���ɏ����ꂽ���Ƃ��c�����Ă��Ȃ��̂ł����H �X�����Ⴂ�܂��B
�����ԍ��F21783084
![]() 5�_
5�_
�T�D���x�����Ă��l�̘b���Ȃ�
�����������x�������痝������̂ł����B���̃X���ł́u�f�W�^���̈�̘b�Ƃ��āA�w���b�s���O���ꂽ�t�@�C���̃o�C�i������v���邱�Ɓx�͓��R�ƌ���Ă��܂��B�ɂ�������炸�A�A�i���O�̈�̏������ɂ���ĉ����ω�����͉��̂��Ƃ������Ƃ��l�X�ȑ��ʂ���Nj�����Ă��܂��B�v�Ƃ����S��قǂ��Ȃ��Ɉ��ĂČ����Ă��܂����A�����ł��Ȃ��̂��A�������������Ȃ��̂��ǂ���Ȃ̂ł����H
��Pure read4+
http://fast-uploader.com/file/7080389528685/
�m�[�gPC�@�Z�L���A
http://fast-uploader.com/file/7080391529053/
�m�[�gPC�@�o�[�X�g
http://fast-uploader.com/file/7080393176376/
CD���烊�b�s���O�������_�Ńo�C�i���͈�v���Ă��܂��B
�o�C�i������v���Ă��鎞�_�ʼn��͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B
�܂��_�E�����[�h�ɂ���ĉ����ω�����Ƃ����l�����邩������܂���B
�ɂȐl�����܂�����HAP-Z1ES�ɃR�s�[���Ē����Ă݂ĉ������B
����ȉɂȐl�͂��܂���B���O�̃p�C������̏������݂ɂ��i [21780079] �j�u���̃X���̃^�C�g���wCD���ڃ��b�s���O�h�ʼn����ǂ��Ȃ�̂������ĉ������x���炷��A�f�W�^���̈�Ńo�C�i������v�������_�Ńf�W�^���f�[�^�̗͂Ȃ��Ƃ������ƂŌ��_�͏o�Ă܂��B�v�Ƃ������̂�ǂ�ł��Ȃ��̂ł����H
�o�C�i������v���Ă���t�@�C�����R���A������N���E�h����_�E�����[�h���Ăǂ�����̂ł����H
�N���E�h�̃T�[�o�[�̃n�[�h�f�B�X�N��̈ʒu�̈Ⴂ�ō�������Ƃł��H
�����ł��Ȃ��Ȃ痝���ł��Ȃ��Ȃ�ɁA����Ȃ�Ώ��Ȃ��Ƃ��ʂ̃X���ɉ����Ę_����̂����ʂ̐_�o�̎�����ł��傤�B
�U�D�������Ƃ��Ђ�����J��Ԃ��ăX���̔�����Q���
�uPure read�v�A�uPure read�v�A�uPure read�v�A�uPure read�v�A�u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�A�u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�A�u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�A�u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�B
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�������u���������Ȃɂ��l���Ȃ��Ƃ��w�r�b�g�p�[�t�F�N�g�x�łӂ��ł��v�Ƃ���������Ă�ł͂Ȃ��ł����B����ɑ��Ă͉��������Ȃ��B���Ȃ��͐l�ɉ����������Ă�����āA���ꂪ�����̎咣�ƐH������Ă��Ă��A�܂�łȂ��������̂悤�ɂӂ�܂���̂ł��ˁB
�V�D���l�̔ᔻ�͕��C�ł���̂ɁA�������ᔻ���ꂽ��A�����������Ă�����Ă��A������������
��������Ă��̃X���ɍēo�ꂷ��̂Ȃ�A���Ȃ��͏��Ȃ��Ƃ��A
�������p���Ă��Ȃ��́u�r�b�g�p�[�t�F�N�g�v�ɂ������AMinerva2000����i [21726506] �j�́u����C2�G���[��10��N������WAV�t�@�C�����Đ����Ă��A�ǂ��Ő��`��Ԃ������͒N��������Ȃ��ł��傤�B�܂艹���͕ς��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�v�Ƃ������t�ɑ��āA
�܂��A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����́u�m���ɃX���̓��e��ABEBIREX����ɂ͓���A���邢�͂����g�̒��ł��Z�p�_����������Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂����A�������̉��l�ς���邱�Ƃ͂܂��ǂ��Ƃ��āA�����t���͗ǂ��Ȃ��ł��ˁB�c�_�ɋ����Ȃ���Ε��u�ł悭�͂Ȃ��ł��傤���B�v�Ƃ����ɑ��āA
�����āA���Ȃ��́u���t�V�сv�Ƃ��������ɑ��āA�u�ꌩ�A���t�̗V�т̂悤�Ɍ����܂����A���e�͂��Ȃ�[�������ɓ��ݍ���ł���Ǝv���܂��B�v�ƗD�������_����āA�l�̘b��ǂ����Ƃ����Ȃ����Ȃ��̂��߂ɂ��̃X���b�h�Ɛ�s�X���b�h�̘b�̗�����킩��₷���v�Ă����������p�C������ɑ���
������̂���V�Ƃ������̂ł��傤�B
����������ɁA������������悤�Ȑl�ƁA�ǂ����āu�c�_�v�Ȃǂł��܂����H
�����ԍ��F21783086
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����
���̂��߁A���ɋ������܂����A���q�l�ւ̉��e�ɂ��܂��Ă�
Web�T�C�g��SNS�ł̌��J�����T�����������܂��悤
���肢�\���グ�܂��v
���̕��͂�ǂ�Ŏ������J�֎~�Ǝ��͎~�߂܂����B
https://www.sony.jp/support/inquiry_mail-kiyaku.html
���HP�̕��͂ɓ��ӂ��Ă͂��߂ă��[���̂��₢���킹�T�[�r�X�𗘗p�ł���d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
�̂Ŏ��͓��ӂ������ƂɂȂ��Ă��܂��B����ă��[���̓��e�͏����܂���B
�ʃX���Łh�\���I�ɂ͂�����Ƌɒ[�Ō����^������������܂��Ə����Ă��܂��B
�m���ɋ֎~����Ƃ͏����Ă��܂���w���T�����������܂��悤���肢�\���グ�܂��B�x�ł����B
�\�������܂���ł����B
���̐l�̂�����͎��̕ʃX���ŏ����Ă���A�X���傳����Q�����Ă���̂ł�����x��������Ă��邩�Ǝv���܂��B
������̃X���Łw���̐l�x�̕��͂������Ă��荬�����������Ƃ͂��l�ђv���܂��B
����PC�Ƃ̑����̍��Ȃ̂�HAP-Z1ES�̃l�b�g���[�N�������܂��������A�����[���ł��������Ă��钆�ŒS���҂��ς��A���̕����玄�̕\���ł����wSONY�̒��̐l�x����̂������������Ă��܂����B
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���Ȃ�ɉ�������ł��������e�������Ă��܂����B���炢�����܂����B
���p�C������
�킽�ɂׂ̈Ƀ��X���Ē������悤�ł����ԐM�����܂���ł����A���炢�����܂����B
�ǂ�`�����ł���̃R�����g�͋����[���ʃX���Ŏ��₷��Ηǂ��������̂������������Ń��X���Ă��܂��܂����B
���J�������y�f�[�^�̓f�W�^���i�ł̍ŏI�m�F�̂���ł����B
��������@�Ń��b�s���O�������y�f�[�^��HAP-Z1ES�ōĐ����Ă݂āA�Ⴂ�����邩�ǂ����m�F����B
��������͂܂������Ă��܂���HAP-Z1ES��CD���ڃ��b�s���O�������̂�PC�ɃR�s�[���o�C�i������v�������Ƃ��m�F���܂����B
�������ǂ�`�����ł��̈ӌ�������A�I�[�f�B�I�ɂ͈ꌩ�������������I�J���g�I�v�f������܂��B�܂����͉����ς��Ȃ��h�ł͖����A�����킩��Ȃ��h�ł���܂��B
HAP-Z1ES��CD���ڃ��b�s���O�̉����ƁA��L������HAP�|Z1ES�ɃR�s�[�����ے�����ׂ�A��tohoho3�������Ă��ꂽWaveSpectra��WaveGene���g�p���Ă݂�B
�ƁA���������Ȃ�ɍl���܂����B�ł����a�C�����œ����ɂ��Ȃ�׃t�@�C���f�[�^�����J���A�N�������Ē������������Ǝv�����J���܂����B
���͓��ł͂킩���Ă��Ă��ЂƂЂƂ��H�Ŋm�F�������^�C�v�ł��B
���̖ʂł̓I�J���g�I�ł����邩�Ȃ��܂鎁�����H�^�C�v�łƂĂ����h���Ă���܂��B
�ȏ�b���S������A�X�������ɂȂ�܂�������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21783157
![]() 2�_
2�_
���ABEBIREX����̕��͉͂������������̂��悭�킩��Ȃ����ǁB
>���̖ʂł̓I�J���g�I�ł����邩�Ȃ��܂鎁�����H�^�C�v�łƂĂ����h���Ă���܂��B
�Ƃ����Ă���悤�ł͂܂��܂����ȁB����ɂ́A�_��̈ȉ��̌��t��i�悷��B
�w�тĎv�킴��A����㦂��B
�v���Ċw����A�����w���B
���Ȃ킿�ASymbolist_K����̌�����
�u���������V�т����Ȃ���A�ڂƎ�Ǝ����g���Đ����Ɋ���e����ł䂭���Ƃɂ���āA���������g����
�l���Ă��邾�������͂₭�A�{���̈Ӗ��ł́u�����v�ɓ��B�ł��邩������܂���ˁI�v
���d�v�BABEBIREX����ɂ́A�C���^�[�l�b�g���Ŗ������Ă���I�[�f�B�I�̃I�J���g�܂����̐����̊ԈႢ��
��������悤�A�{���̈Ӗ��ł́u�����v�ɓ��B�ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ����҂���B
�����ԍ��F21783382
![]() 3�_
3�_
ABEBIREX����
ABEBIREX����́u��������Ǝv���܂��v�ȂǂƉ��x��������Ă��܂��ˁB�ł�������g���A���l�̌������Ƃ̗����ɓw�߂�ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
���H�Ŋm�F�������̂͂킩��܂������A���b�s���O�����t�@�C�����A�b�v���đ��l�̔��f�����̂ł͈Ӗ����킩��܂���B�u�����������v�u�킩��Ȃ��v�����̈ӌ����Ԃ��Ă�����ǂ�����̂ł��傤���B���b�s���O�̂��������ăA�b�v�����t�@�C�����f���̂��ӌ��Ԃ������������Ƃ����Ȃ�Ӗ��̂���������Ǝv���܂����A�܂��������Ȃ��ł��傤�B
���l�̈ӌ��ɍ��E����A�В[����u���H�v����̂����R�ł����A�܂��ɗ��j�Ֆ����q�C�ł��B
�ʓ|�ȗ������������Ȃ����ɂ���܂ł̃X���b�h���n�ǂ���Ƃ܂ł͌����܂��A���������̂����K�ł�����A���߂ď�̃p�C������[21780079]�Ɍf�ڂ̐}�����Ă��������B�����āA�O�X���̃p�C������[21732094]�f�ڂ̐}�����Ă��������BMP3-320kHz�̈��k�m�C�Y�������ɑ傫�������킩��Ǝv���܂��BABEBIREX�����WAV�t�@�C���iCD�����j��MP3-320Kbps�����̈Ⴂ���������܂����H
�Ȃ��A�ȏ��ABEBIREX����ɁA�����Ȃ�Ƃ��{�X���̈Ӌ`�𗝉����Ă��������������߂ɏ����܂����B�Ƃ��ɕԓ���v��������̂ł͂���܂���B
�����ԍ��F21784032
![]() 4�_
4�_
���b�s���O�t�@�C���̕i�������Ȃ����ˁB
���q������i�ł������B
���q�����C���[�W���C���E��������C�����O�ꂽ���o�������̂́C��̍�i���炶��Ȃ��ł���B
�o�[�X�g��荞�݂��C���̃��m�����C�����O�ꂽ���o���}�����ĂĈ��肵�Ă܂����C�X�����Ȃ�����B
�����ȃw�b�h�z�����C���z���͒�������C�����O�ꂽ���o�̈�a����}���Ă���܂����C���ڂȃw�b�h�z�����C���z�������a���������Ē�������o�Ă��܂��܂���B
�ŁC���̃A�b�v�����̏o������C���f���x���ł��ˁB
�n�b�L�������āB
�����ԍ��F21784128
![]() 3�_
3�_
�F�l��
�X���̐i�s���ז����A����v���܂����B�Ȍ㏑�����݂����������Ē����܂��B
���A���̃X���̊F�l�̂��ӌ����Q�l�ɂ����Ē����܂��ăI�[�f�B�I���C�t���y���܂��Ă��炨���Ǝv���܂��B
���ǂ�`�����ł���
����������܂�����h�O�t��BD�h���C�u�ڑ��F���h�X���ɂ��z���������B
���܂����Ă���܂��B
�����ԍ��F21784217
![]() 2�_
2�_
�����������悤�Ȃ̂ŁA�������g�̗������܂Ƃ߂܂��B
�X���b�h�̂���Ɋւ��āA���Q�W�҂ł���]�_�Ƃ̃C���v�����L�ۂ݂ɂ͂ł��Ȃ����A�f�l�̗����͒u���Ă����Ƃ��āA�\�j�[�̌��劲�Z�t�ł��邩�Ȃ��܂鎁���uCD���ڃ��b�s���O�̂ق��������ǂ��v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��咣����Ă���̂Ŗ������������킯�ł��ˁi���̉����ɂ��Ă�Symbolist_K����[21726337]�ɗv����܂��j�B�������Q�W�҂��Ǝv���܂����A�Z�p�_�Ƃ��ċ��ʂ��Ă���Ζ�肠��܂���B
���̉����Ń|�C���g�ƂȂ�̂�
>�f�W�^������1��0��������܂��A���ۂ̋L�^�͂ӂɂ�ӂɂ�ȃA�i���O�̔g�`�ŏo���Ă��܂�
�Ƃ������Ƃł��B�\�����傰���ł����A�܂��悢�ł��傤�B�����͂Q�̏��������琬���Ă���A�������������ꍇ�Ɍ��萬�����܂��B���ꂼ����ᖡ���܂��B
��ڂ̏�������
>�R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c��
�Ƃ������̂ł��B����ɂ͎R�قǓ˂����݂ǂ��낪����܂����A�������ɓ��ӂ��邩���͂قڂ��Ȃ��̂ŏڏq���܂���B�������Ȃ��܂鎁�̂��b�ɂ́ACD�h���C�u���f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y�ɂ͌��y���Ȃ����Ƃ��w�E���Ă����܂��B
��ڂ̏�������
>�g�`�����]����Ƃ��ɂ͓d���ɃX�p�C�N�m�C�Y������܂��B�g�`���O���O���h��Ă���ƁA���]�m�C�Y���o��^�C�~���O���O���O���ɂȂ�܂��B���ꂪ��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�Ɖ������Q���܂��B
�Ƃ������̂ł��B����͏�L��ڂ̏����������������Ƃ��O��ł����A�����Ă��̑O��ōl���܂��B
����ɂ���͂�R�قǓ˂����݂ǂ��낪����܂����A�u�E�E�E�N���b�N��h�炷�v�܂ł̕��������S�ɔ�����̂͂��Ȃ�ʓ|�ł��B���������J�j�Y���͂ǂ�����A��������DA�ϊ��̃N���b�N���h��邱�Ƃʼn�������������̂��A����������悢�ł��B
�i�����Ȃ����̂ł��������܂��j
�����ԍ��F21785122
![]() 5�_
5�_
�i�����ł��j
��������̘_���ł́A�g�ы@����܂ߐ������̋@��ł̃W�b�^�[�����肳�ꂽ���ʁA�u�W�b�^�[�������g���QHz�ȏ�ɂ����ĐU���Qns�����ł������v�Ƃ���Ă��܂��B���̕����̕����ł��A�W�b�^�[�U���͂�������300ps���x�ł��B
����Ől�Ԃ̌��m���́A��������̘_���ł͐�s��������i���L��O�������j�W�b�^�[�U��4ns�`500ns�A�O�X���ň��p���ꂽ�č��_���ł�10ns�`300ns�ƂȂ��Ă���A�W�b�^�[�̉e���͒����Ƃ�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�������m����80ps�Ƃ��镶��������悤�ł����A���̗��R�ɂ���Ă��Ȃ�^�킵���ƍl���܂��B���Ȃ킿���̕������ˏo���ď����Ȓl�ł��邱�ƁA��������̘_���ŋ^�`���悳��Ă��邱�ƁA���҂��N���b�N����IC�̃��[�J�[�����ł��������Ƃ��痘�Q�W�������^���邱�Ƃł��B�܂��A�X���b�h�Q���҂ł��̕�����ǂ݁A�����ł���l����l�����܂���B
����ɁAtohoho3����ƃp�C������̂��s�͂ŃW�b�^�[��������ꂽ�i�̂Ɠ����ȁj�������쐬����A���ۂɒ����Ă݂����G�Ƃ��āA80ps���͋ɂ߂ċ^�킵���Ǝv���܂��B
�ȏ���܂Ƃ߂܂��ƁA�`���ɏ��������Ȃ��܂鎁�̎咣�ɂ͊�d�ɂ���肪����A�M���ɑ�����̂ł͂Ȃ��ƌ��_������܂���B
�֑��Ȃ���ADA�ϊ��̃N���b�N���h��邱�ƂŐ����鉹���̗��q�g�������������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���r�W�E����Z�V�E�����g�����N���b�N�W�F�l���[�^�[�̌��ʂ��E�E�E�Ƃ������Ƃł����A�܂������Ƃ��Ă����܂��傤���B
�����ԍ��F21785127
![]() 5�_
5�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
>DA�ϊ��̃N���b�N���h��邱�ƂŐ����鉹���̗��q�g�������������Ȃ�
�Ƃ������肪�����Ƃ���ƁA
�u�f�W�^���P�[�u����g�����X�|�[�g�̈Ⴂ�ʼn������ς�闝�R���W�b�^�[�ȊO�ɂ���v
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���̗v�������������
�u�R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���v
���̍��Ղ����W�ł��邱�Ƃ̐����������ƒP�Ȃ�ϑz�ł���B
�Ȃ��A���̌o���ł��ƁA�O���N���b�N�����悤���AGalvanic�A�C�\���[�^�[�����悤���A�g�����X�|�[�g�ɂ�鉹���̍��͑��݂��܂��B
�ł�����A�W�b�^�[��d�C�m�C�Y�ȊO�ɂ������ω��̗v�������肵���������낪���������m��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B
�����ԍ��F21785289�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�l�̓Z�C�E�`����A�����́B
>>DA�ϊ��̃N���b�N���h��邱�ƂŐ����鉹���̗��q�g�������������Ȃ�
>
>�Ƃ������肪�����Ƃ���ƁA
�����������uDA�ϊ��̃N���b�N���h��邱�ƂŐ����鉹���̗��q�g�������������Ȃ��v�Ƃ����̂́u����v�ł͂���܂���B���̐�̓��e��ǂ�ł���������킩��܂����A�����̘_������́u�A���v�ł��B
�t�ɁA���̒��ɁuDA�ϊ��̃N���b�N���h��邱�Ƃʼn���������v�Ƃ������������邱�Ƃ͒m���Ă��܂����A������̂ق����Ȋw�I�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�ӂ��̃I�[�f�B�I�t�@���ɂ͂����������F���͂Ȃ������m��܂���ˁB�������A�N���b�N���₽��h���Η���͓̂��R�ł���B
>�u�f�W�^���P�[�u����g�����X�|�[�g�̈Ⴂ�ʼn������ς�闝�R���W�b�^�[�ȊO�ɂ���v
>�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�u�f�W�^���P�[�u����g�����X�|�[�g�̈Ⴂ�ʼn������ς��v�Ƃ����������^�ł���Ȃ炻���Ȃ�܂��ˁB���������ꂪ�^�ł��邩�ۂ��̓X���Ⴂ�Ȃ̂ŁA���̋c�_�͂�߂܂��傤�B
>���̗v�������������
>�u�R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���v
>���̍��Ղ����W�ł��邱�Ƃ̐����������ƒP�Ȃ�ϑz�ł���B
�ȂɂƂȂɂ����W�Ȃ̂��A�Ȃɂ��ϑz�Ȃ̂��A�_�����s���m�łȂɂ�����������Ă���̂��킩��܂��A���̐�̓��e�̘_���ł́u�R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���v�Ƃ�������͐^�ł��U�ł��悭�A������ɂ��Ă����Ȃ��܂鎁�̎咣�͐��藧���܂���B�l�̓Z�C�E�`����̂ق��������̘_���𗝉����ꂸ�ɂȂ�炩�̖ϑz�����Ă���͂��ł��B
�����ԍ��F21785374
![]() 5�_
5�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
>�u�f�W�^���P�[�u����g�����X�|�[�g�̈Ⴂ�ʼn������ς��v�Ƃ����������^�ł���Ȃ炻���Ȃ�܂��ˁB
��?
�^�ł���B
���ۂɒ�����10�l��9�l�ʂɂ́B
���v����������ł͖����̂œK���ł����ǁB
�܂��A���Ⴂ���͉����ȂɍS�炸�A���ł������ɂȂ炸�A�F�X�ȉ��y�������ǂ��Ǝv���܂��B
�����ɍS��͔̂N����Ċ��������Ă���ŏ\���ł����ˁB
�ł́A���݂��P���I�[�f�B�I���C�t��
�����ԍ��F21785416�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�@�܂��V���Ȏ��������Ă݂܂����B���ɕԓ��͂���܂���B
�@������-60dB�ȉ��i���ς�-80dB-100dB���x�j�̔����m�C�Y���A�����̉����ɗ^����e���̎����B�����̃_�E�����[�h��́A
https://yahoo.jp/box/qfN5bg
�@���ʂ̃W���Y��CD�����i16bit�j
�A���ʂ̃N���V�b�N-�V���p����CD�����i16bit�j
��������̓_�C�i�~�b�N�����W��144dB�ʂ͕K�v�ɂȂ邽��24�r�b�g�����ɂȂ�܂��B
�B�����@�̃W���Y��-60dB�Ɍ������Ă���A�̃V���p���ɉ����č���
�@�����Ă������V���p�������������܂���B
�C�����B�̍�����������W���Y-60dB�����̂ݒ��o
�@���e�́A�i�B�W���Y-60dB + �V���p���j - �i�A�V���p���i�ʑ����]�j�j�� �W���Y-60dB ���c��B
�@�Ƃ����P���ȕ��@�ł��B�i�W�b�^�[���܂܂ꂽ��������W�b�^�[���������o���̂Ɠ������@�j
�D�W���Y-60dB��ʏ�M�����x��0dB�ʂɑ�������Ƈ@�Ɠ������y���������܂��B�i���ۂɃV���p���̃s�A�m�ȂɃW���Y-60dB���m�C�Y����ɓ����Ă��邱�Ƃ̏ؖ��j
�@���o���ꂽ�C�W���Y-60dB�̐M���́A���x�����Ⴂ���߁A�ʏ�g�p���Ă���{�����[���ʒu�ł͑����������܂���B���̉��y�M���̂قƂ�ǂ�-80dB�`-100dB�ʂɏW�����Ă���̂ŁA������B�V���p���̋ȂɊ܂܂��ϒ��m�C�Y�ƍl�����ꍇ�A�m�C�Y���x�����猩�āA�قڎ��ԐU��10ns�̃����_���W�b�^�[�ɑ�������ʂ̃����_���ϒ��m�C�Y�����݂��邱�ƂɂȂ�܂��B�Ȃ̂ł��̕ӂ̈Ⴂ���킩�邩�ǂ�������̃`�F�b�N�|�C���g�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�@�A�ƇB�̉������ׂĂ݂āA�ϒ��m�C�Y�i�ʉ��y-60dB�j�̉e���ɂ�鉹���̈Ⴂ�͊�����ꂽ�ł��傤���B-80dB�ȉ��̕ϒ��m�C�Y�͒P�Ƃł͒������Ȃ��̂Ō������ɂǂ̒��x�A�e����^���邩�͕�����Â炢�����ł͂���܂��B
�@�Ƃ���ŁA�f�W�^���ŋL�^�����Ƃ��̍��ՂƂ��ŃV���b�g�m�C�Y��ϒ��m�C�Y���������ĉ�����������ACD�g�����X�|�[�g�ʼn������ω�����Ƃ����Ȃ�A���̏ꍇ�̉����ɉe����^����ϒ��m�C�Y�̃��x���͂ǂ̂��炢�ɂȂ�̂ł��傤���ˁB���k�ϒ��g��W�b�^�[�m�C�Y�̂悤��FFT�O���t�Ŋm�F�ł���Ǝv���̂ł����ADAC�o�͂��ꂽ����FFT�Ō��Ă݂������̂ł��B
�@��������A�����m�F�����ł��낤�m�C�Y�̌`���A�������̂��̂���͂��邱�Ƃɂ���āA�������ς�錴�����𖾂ł��邩������܂���B
�@
�����ԍ��F21785503
![]() 5�_
5�_
��̃p�C������̎����́A�ŋߗ��s���MQA�̃R�[�f�b�N�̌����݂����ł��ˁB
>��?
>�^�ł���B
>���ۂɒ�����10�l��9�l�ʂɂ́B
>���v����������ł͖����̂œK���ł����ǁB
�Ə����Ă����邯�ǁA�O�X���ɂ����������A�d�v�Ȃ̂�2���Ă����B
�u���V�[�{���ʂ͑傫�����낤�ȁB�u�����h�C���[�W���悭�����łȂɂ�獂�������ȋ@�\���t�����@���������A
�����ǂ��Ȃ�͂����Ƃ����o�C�A�X�͑����傫���A������A�����ĕ����Ă��邤���ɍ������ʂ�
���܂��āA�����ς���Ă�������̂��낤�ȁB
�O�ɁA�Ⴄ�X���œ\����
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej1978/34/12/34_12_1079/_pdf
�ɂ��A�u�����h��m�����O���[�v�́A�c�̑����J�Z�b�g�e�[�v���c�����Ȃ���������ƌ����Ă���B
�܂��A���������ƃX�����r��錳�����A�u���V�[�{�i�Ö��j���ʂ͑傫���B
�F�l�ɂ�����܂��ẮA�C���^�[�l�b�g��Ɉ���Ö����ɂ͂��ꂮ��������ӂ������B
�����ԍ��F21785674
![]() 4�_
4�_
���a�W�X�N����
�m���ɂ��������悤�ɁA�Q�����Ă���������푽�l�ł���������̂ŁA�����̂Ƃ���̂悤�ɁA�Ή��ɒǂ�ꂽ��A�ԐM����̂ɋ�S��v���邱�Ƃ�����܂����A������Ă���̂ɉz�������Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�Ȃ������Ȃ������Ă���܂��B
���āA
���P�D�u���C���Y��ȃN���b�N��HDD�ɂ��͋����L�^�����v
���P�D���C���Ȃ������N���b�N�ł��������ރ^�C�~���O�Ƃ������l�i�f�W�^����H�Łu���d�ʁv�Ɓu��d�ʁv����ʂ��鋫�ƂȂ�d�ʂ��w���j���N�����[���Ė�肪�Ȃ����ʂɋL�^���ꂽ���ʂ����A�u���C���Y��v�ɋL�^���ꂽ�S�������f�[�^��ǂݏo�����ق��������ǂ��Ȃ�͂����Ƃ������ƂȂ̂ł����ˁH
�����̓\�j�[�̋��䗲�i���Ȃ��܂�j���̕\���Ȃ̂ł����A�ނɂ������������Ƃł��B�������A���́u���C���Y��ȃN���b�N�v�Ƃ����\���͂��܂�ɂ����w�I�ŁA���̃X���ł������̕��ɔᔻ�𗁂тĂ��܂��B
���̎咣�̌��ɂȂ��Ă���̂��A�����̎��̂悤�Ȍ����ł��ihttp://kanaimaru.com/AVQA/0f.htm�j�F
���f�W�^������1��0��������܂��A���ۂ̋L�^�͂ӂɂ�ӂɂ�ȃA�i���O�̔g�`�ŏo���Ă��܂��B�ǂݏo���Ƃ��ɁA������x�ȏ�̓d����1�A������x�ȉ���0�Ƃ��邾���ł��B�ӂɂ�ӂɂ�Ƃ́A1�ƋL�^�������̂́AHDD��ł�1�ł͂Ȃ��āA����O�a�l��1�Ƃ�����A0.7�`1.0���炢�ɋL�^����Ă���Ƃ������Ƃł��B0�ƋL�^�������̂�0�`0.3���炢�ł��傤���B�����0.5���炢�ŏォ�����Ŕ��肷��A�����Ƃ��Ă͂��Ƃɖ߂�܂��B������HDD���������ǂݏo�����Ƃ��̔g�`�͂��Ȃ����Ȃ��̂ŁA��������̂������傫���������܂��B���������0��1�ɒ�����܂�����A�f�W�^���ɂȂ�킯�ł��B
���Ƃ��낪�A����0����1�A1����0�֔��]����^�C�~���O�́A���̃A�i���O�̓ǂݏo�����g�`���ア�ƁA�O���O���Ǝ��ԓI�ɑO��ɗh��܂��B�h��Ă��ǂݏo���^�C�~���O�܂łɂ͕K�����肵�܂��̂�(�����Ȃ�悤�ɃT�[�{�n�����삵�Ă��܂�)��͂萔���͊ԈႢ�܂���B�Ƃ��낪�g�`�����]����Ƃ��ɂ͓d���ɃX�p�C�N�m�C�Y������܂��B�g�`���O���O���h��Ă���ƁA���]�m�C�Y���o��^�C�~���O���O���O���ɂȂ�܂��B���ꂪ��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�Ɖ������Q���܂��B�܂��R�s�[���͌��ɔ�ׂ�Ɨh�ꂪ�����Ȃ�̂ŁA�������ς���čs��(��ʓI�ɂ͗��čs��)�̂ł��B
�܂�A�n�[�h�f�B�X�N��ɂ�����ۂ̋L�^�͂ӂɂ�ӂɂ�ȃA�i���O�g�`�ł���A���̂ӂɂ�ӂɂ�x�������傫����0����1�A1����0�֔��]����Ƃ��ɔۉ��Ȃ��o�锽�]�m�C�Y�̃^�C�~���O���O���O���ɂȂ���DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�̂ʼn����������Ȃ�Ƃ��������ł��B
�������A�u�n�[�h�f�B�X�N��ɂ���L�^���w�ӂɂ�ӂɂ�x�ł����Ă����̖����Ȃ��v�A�Ȃ����́u���������n�[�h�f�B�X�N��ɂ���L�^�́w�ӂɂ�ӂɂ�x�ł͂Ȃ��v�Ƃ������_����o����Ă��܂��B
�p�C������i [21729066] �j�́u�ӂɂ�ӂɂ�v�Ȕg�`�ł���A�C�p�^�[���̌`���������āA
������̓f�W�^���M���̓]���g�i�A�C�p�^�[���j�̘b�ł��B�i�A�b�v�}�j�B�]���g�̓A�i���O��`�g���g���Ă���̂ŁA�g����f�o�C�X��P�[�u���Ȃǂ̐��\�ɂ���Č`�ω����܂��B�E��������ȏ�ԂŁA�A�C���J���Ă܂��B�����̓A�C�����Ă��܂��B�f�W�^���œ]������ꍇ�A�A�C�p�^�[���̒�ӂ��o�C�i��0�A��ӂ��o�C�i��1�ŁA���ԕω��Łi000�A001�A010�A011�A100�A101�A110�A111�j���d�ˍ��킹�Ă܂��B�Ȃ̂ō��}�̏ꍇ���������Ă���̂�1��0�̋�ʂ����Ȃ����ߓ]���ł��܂���B�E�}�̓A�C���J���Ă܂����E���̓A�C���������W�b�^���傫���Ȃ��Ă܂��B����ł����Ƃ��ǂݎ����ԂɂȂ��Ă����Ƃ��āA�����̂ӂɂ�ӂɂ�̔g�`�œ]���������ʂ̃f�[�^�̃o�C�i������v���Ă���ΐ��m�ɓ]�����ꂽ���Ƃ��Ӗ����܂��B���m�ɓ]���ł��Ă���A�]���g�̌`�ǂ��ق����ǂ������ŏ������܂�Ă���Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B
�Ƃ��āA���䎁�́u�R�s�[���͌��ɔ�ׂ�Ɨh�ꂪ�����Ȃ�̂ŁA�������ς���čs��(��ʓI�ɂ͗��čs��)�̂ł��v�Ƃ����咣��ے肳��Ă��܂��B
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����i [21733769] �j�́A�u���Ȃ��܂鎁�̐��A�܂�X�g���[�W�����̂ӂɂ�ӂɂ�f�[�^�������ŃN���b�N�W�b�^�[�������A�ӂɂ�ӂɂႪ�R�s�[��ɂ���`�i�������͑���j����Ƃ�����͖��O�v���Ƃ��āA���ɂ悤�ɏq�ׂĂ����܂��F
���g�c�c��r�r�c�����̃f�[�^�͂���ȂɁu�ӂɂ�ӂɂ�v����Ȃ��ł���B��{�I�ɂ́i���Ȃ��Ƃ����[�J���ɂ́j�悭�����Ă��āA��������̗h����������x�łӂ����Ǝv���܂��B�܂��A���܂ɂ͏o���̈����Z�N�^��Z��������܂��傤���B
�������������āA���Ȃ��܂鎁�̐���M���Ă݂܂��傤�B�g�c�c��r�r�c�����̃A���v�Ȃǂ���������m�C�Y�����Ƃ����Ȃ�A�b�c�h���C�u����������T�[�{�m�C�Y�̘b���o�Ȃ��̂͂Ђǂ���O�݂�����Ȃ��ł����A�Ƃ������Ƃł��B�ނ���b�c���ڃ��b�s���O��̂r�r�c�����f�[�^���ӂɂ�ӂɂ�ɂȂ肻���Ȃ��̂ł��B
�������HAP-Z1ES�ɃR�s�[������ǂ��ł��傤���B����̂r�r�c�̓I�[�f�B�I�M���������ɂ͂����ւ�ȗ]�T������܂�����A�����̂ӂɂ�ӂɂ�͂ނ��낷�����萮�`�����ł��傤
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����́A���̂�����̏������݂ł܂����l�����܂Ƃ߂��Ă���̂ŎQ�l�ɂȂ����ĉ������B
�����ԍ��F21785697
![]() 5�_
5�_
���ɁA
���Q�D�u�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���v
���Q�D�ǂ�ȍ��Ղł��傤�A�����ǂݏo�����Ƃ��ɂǂ��Ȃ��āA�ǂ����ɉe��������̂��A�z���ł��Ȃ��B
���ɂ��ǂ�ȍ��Ղ��킩��܂���B�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����������Ă��܂����A���䎁���ǂ����Ă��Ƃ���n�[�h�f�B�X�N����̃f�[�^�ǂݏo���̂Ƃ��ɂ����������Ղ��c�邱�Ƃ��������A�b�c���̑��̔}�̂���̓ǂݏo���ɂ��Ă͌���Ȃ��̂����s�v�c�ł��B
�������āA���A���Ɂu��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�v�Ƃ������Ƃ��������Ƃ��Ă��A���̃W�b�^�[��l�Ԃ͂ǂ�قnj��m���邱�Ƃ��ł���̂����Atohoho3����A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�p�C�������ɂ���ĒNj�����Ă��܂��B
���̂��߂̊�b�ƂȂ镶���Ƃ��āA��������̌����҂����ɂ��_�����������܂����F
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf
���̘_���̌��_�́F
���W�b�^�[�����ʂ��ē���ꂽ�ő�̃W�b�^�[�����U���́A�W�b�^�[���g��2 Hz�ȏ�ɂ����āA2ns����������B�]���̎��g���ϓ����m�����̌��ʂƔ�r����ƁA���̒��x�̃W�b�^�[�������ɗ^����e����҂����m���邱�Ƃ͍���ł���Ɨ\�z�����B
�Ƃ������̂ł��B���̌��_�Ɋ�Â��A���Ƃ��u��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�v���Ƃ��������Ƃ��Ă��A�I�[�f�B�I�I�ɂ͉��̖����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
����ɑ���ًc�̐\���Ă�����Ă���̂�Minerva2000����i [21772159]�A[21775480] �j�ŁF
��DAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ������́A�o�̓A�i���O�g�`�ւ̉e���́A�W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ邱�ƂŎ��g���ϓ����N���邱�Ƃł͂Ȃ��A�A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�ł��B�����Đl�͂��̘c�ɂ͔��ɕq���ŁA���ꂪ���m���ɎO�����̑傫�ȍ����o�闝�R�ł��B��̓�������̘_���͑O�҂̐����Ƃ��Ă���A���ł��B
���_���̂Q�D��͐M����p����W�b�^�[����@�̖`���́i�P�j�����Q�Ƃ��Ă��������B
���i�P�j���͕t�����ꂽ�W�b�^�[���ϑ��M���ɍڂ�Ƃ������Ƃ����\�����Ă��炸�A���ꂪ�W�b�^�[�t���ɂ��B��̉����ω��Ƒz�肵�Ă��܂����A���ꂪ���������ԈႢ�̌��ł��B
�Ƃ���Ă��܂��B
�܂��A�W�b�^�[�̌��m����80ps�Ƃ����ƂĂ������Ȃ��̂ł���Ƃ��錤��������i�Ԗx���C�ΐ�q���C���эK�v�C�{�����C �g�f�B�W�^���E�I�[�f�B�I�E�C���^�t�F�[�X�iAES�^EBU�j��jitter�Ɖ����̊W�C�h�d�q���ʐM�w��Z�p�����CEA99-40, 1-�W�i1999�j�j�A����Ɋ�Â��ĐԖx�����́u�W�b�^�[�������ȏꍇ�ɂ́A�I�[�f�B�I���\�̗͐����Ƃ��Ă͌���Ȃ��B�������A�������\�ȉ����̕ω��Ƃ��ĉe����������ꍇ������v�Ƃ��āA���̂悤�Ȕ����ȃW�b�^�[�ł����̂悤�Ȃ��Ƃ��N���蓾��Ƃ��Ă��܂��ihttp://ednjapan.com/edn/articles/0709/01/news016_5.html�j�F
���E�̎�̌��̑傫�����ς��
�@�E�ڂ̑O�ʼn��t���Ă���悤�Ȏ��݊��̍Č����ω�����
�@�E���̏�ɋ����킹��l�̐����ς��Ƃ������C�z�̕ω���������
�@�E���t���P���ɂȂ�i�ǂ�ȋȂ��Ă��y�������͋C�ɂȂ��Ă��܂��j
�����ŁAtohoho3�����p�C�������܂��܂ȑ傫���̃W�b�^�[��������ꂽ�������쐬����Ă���A��������ۂɒ����Ă݂āA�{���̌��m���͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂���������Ă���d�d�d�Ƃ����̂�����ł��B
���f�W�^�������Ȃ̂ɉ�������ĕ������邩���t�Ƃ��ă~�N���i�i�m���邢�̓s�R�����m��Ȃ��j�̈�̃A�i���O�I�Ȍ��ۂ⓮��������o���Ď�����[�������悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���E�E�E
�������A����ĕ�������̂͋C�̂������Ǝv�����ǁE�E�E
�����A��������ĕ�������̂̓v���V�[�{��������܂���ˁB�����āA�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̂��咣������������A���䗲�������Ă��邱�Ƃ͂���������t�����낤�Ƃ������ƂɂȂ�̂�������܂���ˁB
�ł��A�܂��܂��c�_�͐s������Ă��܂���̂ŁA���_���o��̂͐�̂��ƂɂȂ�ł��傤�B
�����ԍ��F21785706
![]() 4�_
4�_
�����E�̎�̌��̑傫�����ς��
�@�E�ڂ̑O�ʼn��t���Ă���悤�Ȏ��݊��̍Č����ω�����
�@�E���̏�ɋ����킹��l�̐����ς��Ƃ������C�z�̕ω���������
�ƎU�炩�����o������C�ƎU�炩�Ȃ��o���ɕς���Ē��a�����邩��ˁ[�B
��ʊ��������Ȃ�̂ŁC���p������ȌX���͏o�ė��܂���B
�ŁC��ɋ��������T���v�������B
���@�ɂă_�C���N�g���b�s���O���������t�@�C���̕����CPC���b�s���O���������t�@�C�������C�d�オ��o���f���͗D�G�B
�܁[�CPC���b�s���O�t�@�C�������߂��āC���@�̃_�C���N�g���b�s���O�͕��ʂȂ�ł����ˁB
�ƁCWeb�̃��r�������C�L���������o���������̃��b�s���O�����߂����̂ł��傤�B
�����ԍ��F21786070
![]() 2�_
2�_
���āA���̌������ȒP�ɏq�ׂ܂��B
DAC�ɂ����ăW�b�^�[�������ɉe�����y�ڂ��̂́A�N���b�N�W�b�^�[������ł���A���ꂪDAC�ɉ������邱�ƂŃT���v�����O�藝������A�A�i���O�g�`�ɘc�������炷���Ƃɂ��܂��B
�]���Čv�����ׂ��́A�N���b�N�W�b�^�[��������ꂽ���̃A�i���O�g�`�̘c�ɂȂ�܂��B
�Ƃ��낪��������̘_���ł́A�W�b�^�[��DA�ϊ���̃A�i���O�g�`�ɂ��̂܂��A���̎��g���ϓ��������ω����Ƃ��Ă��܂��B
���̂��ߌv���̓A�i���O�g�`�̃W�b�^�[�X�y�N�g���ɂȂ��Ă��܂��B
�܂艹�����ς�錴�����ԈႦ�Ă��邽�߁A�v�����@���ԈႦ�Ă����ł��B
���̌v�����@�ł̓N���b�N�W�b�^�[�ɂ��DAC�ł̉����ω��͑����邱�Ƃ͂ł��܂���B
���̑����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������͊ȒP�ɂł��܂��B
���P�[�u������p�ӂ��܂��B����͐��S�~�̃v���X�e�B�b�N�t�@�C�o�[���̌��P�[�u���A�����͐Ήp���̌��P�[�u���B���̗��҂ł͓`���W�b�^�[�ʂ��قȂ邽�߁ADAC�ɋ��������N���b�N�̃W�b�^�[�ʂ��ς��܂��B���̂��ߗ��҂̉����̈Ⴂ�͖����ł��B
�������҂̌v�����@�ő��肵�Ă��A�l�����m�ł������ȃ��x���̃W�b�^�[�X�y�N�g���̈Ⴂ�͏o�Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�܂艹���ω��͐l�ɂ͌��m�s�\�Ɣ��肳��܂��B
����𓌋�����Ȃ�A���P�[�u���ɂ�鉹�����͖����̂ɁA�����������Ƃ�����v���Z�{���A�Ƃ������f�ɂȂ�܂��B
���̔��f�́A��������̌v�����@���Ԉ���Ă���A�ƂȂ�܂��B
���̂���܂ł̏������݂�ǂ�Ă��A�����ɓ�������̘_���̊�{�I�Ȍ��ɋC�t���Ȃ��������A���̋c�_�ɎQ�����Ă��Ȃ��͎̂c�O�Ȃ��Ƃł��B
�ߋ��̎����ɂ�薾�炩�ɂȂ��Ă���悤�ɁA�N���b�N�W�b�^�[�̌��m���ƃA�i���O�g�`�̃W�b�^�[���m���ł͓ȏ�Ⴄ�̂ł��B�A�i���O�g�`�ɃW�b�^�[�������ĕ�����ׂ�͈̂Ӗ�������܂���BDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[�������ĕ�����ׂ�̂��Ӗ��̂�������ł��B
�J��Ԃ��܂����A�N���b�N�ɉ�����ꂽ�W�b�^�[�̓A�i���O�g�`�ɂ��̂܂܍ڂ�A�Ƃ��铌������̂悤�Ȋ��Ⴂ�͂��Ȃ��ł��������B
�����ԍ��F21786361
![]() 4�_
4�_
�ǂ�`�����ł���
�����E�̎�̌��̑傫�����ς��
�@�@�E�ڂ̑O�ʼn��t���Ă���悤�Ȏ��݊��̍Č����ω�����
�@�@�E���̏�ɋ����킹��l�̐����ς��Ƃ������C�z�̕ω���������
���ƎU�炩�����o������C�ƎU�炩�Ȃ��o���ɕς���Ē��a�����邩��ˁ[�B
��ʊ��������Ȃ�̂ŁC���p������ȌX���͏o�ė��܂���B
�����A�Ⴂ�܂��B����́A�o���o���ȏo�����܂Ƃ܂�悤�ɂȂ�Ƃ��A���̂悤�ɉ����ǂ��Ȃ�Ƃ����b�ł͂���܂���B�W�b�^�[���ڂ��ĐM�������邱�Ƃɂ���āA���x�������̍Č��x�����Ȃ��A�g���͋C�g�A �g��C�� (�[�X��)�h �A�g��ʊ��h�͌���������ƌ����Ă��܂�
���̕\�����o�Ă�������Ƃ����āA���ɂł������ɔ�т��Ȃ��ŁA���Ȃ��Ƃ��O��̕������ǂ�ł���i���邢�͏o�T�_����ǂ�ł���j���f���ĉ������B
��Web�̃��r�������C�L���������o���������̃��b�s���O�����߂����̂ł��傤�B
�p�c��Y���̋L���̂��Ƃł��傤���B���̍���������܂���ˁB
�����@�ɂă_�C���N�g���b�s���O���������t�@�C���̕����CPC���b�s���O���������t�@�C�������C�d�オ��o���f���͗D�G�B
���̂������̏����O�̌^�̓��{���̃p�C�I�j�A�@�����������������ł����H
�����ԍ��F21786779
![]() 5�_
5�_
�����������爫�������B
��������������������B
����̂�����́C��������������������ɑ��Ă̋L�ڂ���B
�ʂ������Ȃ��Ă̎����������Ȃ�C�t�ɖ邾�����B
�h�`���ɂ��Ă��C�ω�����ɂ͎w�E����ω��ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F21786827
![]() 2�_
2�_
�����Ƒ��l�������ł���悤�ȓ��{��ŏ����ĉ������B
������̂�����́C��������������������ɑ��Ă̋L�ڂ���B
������A�ǂ��̘_���ɃW�b�^�[���ڂ邱�Ƃɂ���āu��������������������Ɂv�Ȃ邱�Ƃ�����Ə����Ă���܂����H
���ʂ������Ȃ��Ă̎����������Ȃ�C�t�ɖ邾�����B
���̗ʂ������Ȃ��āA���̎����������Ƃ����b�ł����H
�������̋t�ɖ�̂ł����H
���h�`���ɂ��Ă��C�ω�����ɂ͎w�E����ω��ɂȂ�܂����B
�����ω�����ƁA�N���ǂ��w�E�����ω��ɂȂ�̂ł����H
���Əq�����������L�q����ƁA�w�Z�ŏK���܂���ł������H
�����ԍ��F21786866
![]() 5�_
5�_
�����C�w�Z����Ȃ�����B
�N���C�P�ɁC�����o���Ȃ���������B
�����ԍ��F21787044
![]() 3�_
3�_
�ǂ݂ɂ����̂ŁA�����ɏ������g��h��t����̂���߂ĉ������B
����Ȃ��Ƃ����Ă��w�Z�ł͒��ӂ���A�Y�킳�ꂽ�͂��ł��B
�����͊w�Z�ł͂���܂��A���̂悤�ȏ��w�Z���x���̍���̘b�������ł��Ȃ��A�`�����烌�x���̍���͂͑O��ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A�����ɂ����킩��Ȃ��p��@�̓Ƃ�悪��ȓ��{����g���Ă��F�̖��f������ł��B���͂��Ȃ��̍���̐搶�ł�����܂���̂ŁA�����������̂悤�Ȃ��Ƃ𒍈ӂ�����������܂���B
�����ԍ��F21787073
![]() 7�_
7�_
�Ƃɂ����A�����ԍ� [21786866] �̎��̎���ɓ����Ȃ����Ǝ��́A���Ȃ��ɂ͂��̃X���́u�c�_�v�Ȃǂǂ��ł��悭�A���Ȃ��������̌����������Ƃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ����킵�Ă��܂��B
�������̏������� [21786070] ��ǂݕԂ��Ă݂āA���ꂪ���̃X���̕�������܂������O�ꂽ���̂ł���Ƃ��v���ɂȂ�܂��H ���ꂪ�킩��Ȃ��̂ł���A���Ȃ��͍앶�݂͂̂Ȃ炸�lj�́E�����c���͂ɂ������Ă���ƌ���˂Ȃ�܂���B
�Ƃɂ����A���̃X���b�h�ʼn����c�_����Ă���̂��A�������Ă��珑������ʼn������B���ꂪ�X���b�h�ɎQ������Œ���̍�@�ł���B
�����ԍ��F21787113
![]() 7�_
7�_
�@���ڑ��̘b���o�Ă܂����APCM���ő��M�����ꍇ�A���M����D/D�R���o�[�^�[�̐��\���������A���P�[�u���������ƃt�@�C�o�[���Ŕ��˂������Ȃ��M����DAC���ɓ��B���鎞�ԂɃY���i�W�b�^�[�j��������͕̂�����܂��B
�@���̏ꍇ�A�W�b�^�[�ɂ���Ď������Y������Ԃ́A���M���i���]���j�N���b�N�����̂܂g���ƁA�o�͂��ꂽ�A�i���O�M���ɃW�b�^�[���������Ԃŏo�͂����āA���������邱�Ƃ͂��肤��b�ł��B
�@�������A�����Ŗ��ɂȂ��Ă���̂́A���葤�̊O���N���b�N�ł͂Ȃ��A��M����DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g�����Ƃ��ɔ�������W�b�^�ɂ��ċc�_���Ă���̂Ō����Ⴂ�̓��e�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�@���]���ŃW�b�^�[���������Ă��A���̂܂�DAC�ŃA�i���O�ϊ������킯�ł͂Ȃ��A��M����DAC���̃o�b�t�@�[�������Ɉ�U�A���y�f�[�^�Ƃ��āA�o�C�i����v�̏�Ԃŏ������܂�A���̃f�[�^�����]���ɂ��W�b�^�[�Ƃ͖��W�ȁADAC�����̍����\�}�X�^�[�N���b�N�ŏo�͂���킯�ł�����A���]���Ŕ�������W�b�^�[�̉e���́A�o�b�t�@�[�������Ɏ�荞�܂ꂽ���_�ŁA�����Ȃ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���ɁA����ꂽ�f�W�^���f�[�^��1�T���v�����������菭�Ȃ������肷��ꍇ�́ADAC���̃}�X�^�[�N���b�N���g���Ă����������邱�ƂɂȂ�܂����A���̏ꍇ�͂��������o�C�i������v���Ȃ���Ԃœ]������Ă邱�ƂɂȂ�A�W�b�^�[�ɂ����̂ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�]���G���[�ɂ����̂ƍl�����܂��B
�����ԍ��F21787124
![]() 5�_
5�_
Minerva2000����́A�܂������Z�p�I�ȗ������Ȃ��܂ܓK���ɏ����Ă邾���Ȃ̂ŁA���������Ă���̂������ς肾���A
>�J��Ԃ��܂����A�N���b�N�ɉ�����ꂽ�W�b�^�[�̓A�i���O�g�`�ɂ��̂܂܍ڂ�A�Ƃ��铌������̂悤�Ȋ��Ⴂ�͂��Ȃ��ł�����
>���B
����ɂ��ẮA
http://www.analog.com/jp/analog-dialogue/articles/analyzing-and-managing-the-impact-of-supply-noise-and-clock-jitter-on-high-speed-dac-phase-noise.html
���킩��₷���B
���ԗ̈�i�I�V���X�R�[�v�\���j�ł́A�N���b�N�̃W�b�^�i�h�炬�j�ɂ��ADAC�o�͂̊K�i���̑J�ڎ��ԃ|�C���g�̊Ԋu���h�炮�B
����������ƁADAC�o�͂̊e���U�l�̎��Ԏ���ł̊Ԋu���A�N���b�N��1�����̎��ԂƂ���A�N���b�N�ɃW�b�^��
���݂���Ɓi1�����̎��Ԃ��h�炮�Ɓj�ADAC�o�͂̊e���U�l�̎��Ԏ���ł̊Ԋu���h�炮�B
��������g���̈�ŕ\������Ɓi�t�[���G�ϊ����ăX�y�N�g�����\������Ɓj�A�i�e���U�l�̎��Ԏ���ł̊Ԋu�����Ԋu�Ƃ���
�Ӗ��ł́j���z�I��DAC�o�́i���ԗ̈�ł̊K�i���j���t�[���G�ϊ������X�y�N�g�����ƁA�W�b�^�̑��݂���N���b�N�g�`
�isin(��t�{d��)�ŋߎ��j���t�[���G�ϊ������X�y�N�g�����Ƃ̏�ݍ��݂ł���B
���������āA�N���b�N�ɑ��݂���W�b�^��DAC�o�͂ɂ��̂܂܌����ƍl���ėǂ��B
�����ԍ��F21787197
![]() 2�_
2�_
�p�C������A�����́B
>��M����DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g�����Ƃ��ɔ�������W�b�^�ɂ��ċc�_���Ă���̂Ō����Ⴂ�̓��e�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�����Ⴂ�̓��e�ɂȂ��Ă͂���܂���BS/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A�`������Ă����N���b�N���g�p���܂��B
�ȑO�Љ��EDN�̋L���u�I�[�f�B�I�i���ƃN���b�N�W�b�^�[ �v��ǂ�ł��������B
�����ԍ��F21787256
![]() 2�_
2�_
tohoho3����
�����炱�����������Ă���̂������ς肾���A
>���������āA�N���b�N�ɑ��݂���W�b�^��DAC�o�͂ɂ��̂܂܌����ƍl���ėǂ��B
�ǂ��킯�����ł��B�T���v�����O�藝������Ă݂ĂˁB
�����ԍ��F21787266
![]() 2�_
2�_
Minerva2000����́A�܂�����������
�Y�ꂳ���
Minerva2000����͗��H�w�ɏڂ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�ڂ��������v���邱�Ƃ͋��炭�����ł��B����āA�Ȃɂ��̗��R�����Ă������ł͐������Ȃ����A�܂��͂킯�̂킩��Ȃ����������āA�u�킩��Ȃ��ق��������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���ȁB
�Ȃ�ŁA�u�T���v�����O�藝�v�Ȃ�i�j�B
�����ԍ��F21787418
![]() 3�_
3�_
�݂Ȃ��܂�����
���̓I�[�f�B�I�ɂ��āA�܂��A�l�Ԃ̊��o�I�ȕ����S�ʂɂ����āA���ۂɉȊw���ǂ��t���Ă��Ȃ��Ƃ����̂��������Ǝv���Ă��܂��B
��ʐl�����b�s���O�ɂ�鉹�������l�b�g���ɂĉȊw�I�Ɍ����悤�Ƃ���ƌ��E�͗���͂��ł��B
����͂���Œm�I�D��S�����������̂Ŗʔ����̂ł����A���̎�@�ɂČ����_�Ō��_���͓̂�����Ǝv���܂��B
�X���傳���҂̑̌�����ɉ��������ĂĔ��f����Ƃ������_����A�������Ȃ͂��̉Ȋw�Z�p�ɗ���Ƃ��������ɋc�_����߂��̋C�����܂��B
�����̌��k���ɗU�������Ă������������Ǝv���܂����A
Minerva2000����̈ȉ��̏�������
>���P�[�u������p�ӂ��܂��B����͐��S�~�̃v���X�e�B�b�N�t�@�C�o�[���̌��P�[�u���A�����͐Ήp���̌��P�[�u���B���̗��҂ł͓`���W�b�^�[�ʂ��قȂ邽�߁ADAC�ɋ��������N���b�N�̃W�b�^�[�ʂ��ς��܂��B���̂��ߗ��҂̉����̈Ⴂ�͖����ł��B
�X���傳���̂悤�ȃf�W�^���P�[�u���̈Ⴂ�ɂ�鉹������F���ł��邩�ŋc�_�̕��������ς��Ǝv���܂��B
���̈Ⴂ������Ȃ��l�ɂ́A�W�b�^�[�̉e���͒m�o���E�ȉ��Œ����Ƃ�Ȃ����ƂɂȂ���Ď��ŊԈႢ�ł͖��������ł��B
�ŁA���b�s���O���@�̈Ⴂ�ɂ�鉹���̍��͌��P�[�u���̂�����y���ɏ������̂ł��B
�܂�A���b�s���O�̕��@�Ȃǖ������Ė��͖������ƂɂȂ�܂��B
Symbolist_K����̓f�W�^���P�[�u���ɂ�鉹���̍��ɂ��Ăǂ����l���ł����H
�p�C������A
SSD��HDD����̏o�̓f�[�^���������Ă܂������A�����̍��������Ĕ��邩�炠�̗l�ȃf�[�^��������ꂽ�ƍl���Ă�낵���̂ł��傤���H
�����ԍ��F21787655�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���l�̓Z�C�E�`����
��SSD��HDD����̏o�̓f�[�^���������Ă܂������A�����̍��������Ĕ��邩�炠�̗l�ȃf�[�^��������ꂽ�ƍl���Ă�낵���̂ł��傤���H
�@�������ݔԍ�[21780079]�̃O���t�ł��傤���B������̐M����1050Hz�̋�`�g���g���Ă��āA�O���t�ǂ݂�3Hz�����̃W�b�^�[��-110dB�A�W�b�^�[�m�C�Y���x���ł����A���傤��1ns���炢�ɑ������܂��B������ׂĂ���`�g�̍����g�̎G���Ƀ}�X�L���O����ĈႢ�͑S���킩��Ȃ���Ԃł��B
�@�Ȃ̂ŁA�܂��͕ۑ��ꏊ�̈Ⴂ�Ƃ������A�W�b�^�[�ɑ�������ϒ��m�C�Y�������������ŁA�~���������A10ns�̃W�b�^�[�������郉���_���ϒ��m�C�Y���������Ƃ��ɁA�ǂ̒��x�A�����ɈႢ���o��̂����`�F�b�N���邽�߂ɍ�����̂��A�������ݔԍ��i21785503�j�̉����ɂȂ��Ă܂��B
�@������̉����̇A�V���p���ƇB�V���p��+10ns���炢�̃����_���W�b�^�[�����̕ϒ��i�W���Y���y�j�Œ�����ׂ���悤�ɂȂ��Ă��܂����A��������ׂĂ���ƁA�s�A�m�̘a���̎c�������̋������̈Ⴂ�ʼn����̈Ⴂ���킩��悤�ȋC�������̂ł����A�ȏ��������_���Đ��ɂ��āA�u���C���h��ԂŐ�ւ��Ă��邤���ɁA�Ⴂ���킩���ĂȂ����ƂɋC�Â��܂����B
�@�����������d�˂邤���ɍ����̂悤�ȏ�ԂɊׂ��Ă����̂������ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�@�Z�C�E�`����Ȃ�A�A�ƇB�̈Ⴂ�͂����ɕ�������̂Ȃ̂ł��傤���B
�����ԍ��F21787889
![]() 4�_
4�_
Minerva2000�����[21786361][21787266]�ɂ��ĊȒP�ɃR�����g���܂��B
���ӌ��̒��g�͊�{�I��[21775480]�̌J��Ԃ��A���ς�炸�u���O�͊Ԉ���Ă���v�̘A�Ăŋ�̐�������܂���B���̍���10�N���i�����Ȃ��̂́E�E�E��ѐ�������ƌ�����ł��傤���B
�V���ɉ�������u�T���v�����O�藝�v�]�X��EDN�̋L���̎���ł��傤�ˁB�������A��������̘_���͂Ȃ��T���v�����O�藝�Ɉˋ�������̂ł͂Ȃ��A���z�ʒu���炸�ꂽ�N���b�N�̉e����_���Ă��܂��B���_�ɂȂ��e���͂���܂���B
�����ԍ��F21788008
![]() 5�_
5�_
���X���傳���̂悤�ȃf�W�^���P�[�u���̈Ⴂ�ɂ�鉹������F���ł��邩�ŋc�_�̕��������ς��Ǝv���܂��B
���b�s���O�ɕt���Ă���������B
���ŁA���b�s���O���@�̈Ⴂ�ɂ�鉹���̍��͌��P�[�u���̂�����y���ɏ������̂ł��B
�C�G�C�G�B
ABEBIREX���������T���v��������B
1�|3��45�̑���́C���p������I�Ɏ������P�[�u���ƁC��ŏo�ė����l�Ȍ��P�[�u���Ɠ��l�ȍ��Ƃ��ďo�Ă܂���B
�ŁC�y���ɏ������ŕЕt���Ă͊ԈႢ����B
�����C�����ɍ��E����܂��B
�����ԍ��F21788026
![]() 1�_
1�_
�ǂ�`�����ł���
���Ȃ��͂��������N�Ɍ����Ă��̂������Ă���̂ł����H ABEBIREX����Ɍ����Ăł����H
ABEBIREX����͂��͂₱���ɂ͂��܂���B���̗��R���������Ȃ��̂ł����H�i����A�܂����j
���̗��R�̈�́A���Ȃ���ABEBIREX����̃X���ɏ��������ƂɊւ��鎿��������ł��āA���X���b�h�̎�|����O��鉹���̃A�b�v�����ꂽ�̂ŁA����Y��悤�ɂ��������Ȃ������̔�펯���߂����Ƃɂ���܂��B���̉����̍ŏ��̂R�ւ̃����N�͂����Ɏc���Ă��܂����A���ꂩ��ABEBIREX����͂����������Ȃ���ABEBIREX����̎���̑ΏۂƂȂ鏑�����݂����������̃X���ɁA�R��ׂ��A�������ړ������߂��čs����܂����B���̌�A�����ɐV���ɂQ�̉������A�b�v����ĂT�ɂȂ����悤�ł����A����͂�����̃X���b�h�Ƃ͊W����܂���B���Ȃ��͂���ABEBIREX����̃X���ł����T�̉����̕]��������Ă���̂ɁA�Ȃ������������Ă����ɂ��̌o�܂��킴�킴�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����H
��ABEBIREX���������T���v��������B
1�|3��45�̑���́C���p������I�Ɏ������P�[�u���ƁC��ŏo�ė����l�Ȍ��P�[�u���Ɠ��l�ȍ��Ƃ��ďo�Ă܂���B
������A���̂T��̉����͂����ɂ͂Ȃ��A����������̈�Ƃ���ABEBIREX����͎����̃X���Ɉ����z���ꂽ�B�����ł��Ȃ��͌��ɂȂ鏑�����݂����A����ɂ��̂T��̉����̕]�������Ă���̂�����A�X���Ⴂ�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��͂����Ȃ��B���̐�]�I�ȓ��X����A�Q�d�R�d�̃X���Ⴂ�ɁA���Ȃ��͂�����C�����Ă��Ȃ��̂ł����H
�����C�����Ă��Ȃ��̂��Ƃ���A���Ȃ��͂��͂╶���c���͂��Ȃ��ǂ���ł͂Ȃ��A�����̂Ȃ����E�ɐ����Ă��閳�����Ȕ]�\���̎�����Ƃ����l����ꂸ�A�����C�����Ă���̂ɕ��C�ł���Ă���̂��Ƃ���A�S�邽��݊����̎�����Ƃ����l�����܂���B
���������A���������ԍ� [21787113] �Ō��y�����������݂́u��@�v�ɂ��Ă̒A�������͓ǂ܂ꂽ�̂ł����H�u�����ԍ� [21786866] �̎��̎���ɓ����Ȃ����Ǝ��́A���Ȃ��ɂ͂��̃X���́u�c�_�v�Ȃǂǂ��ł��悭�A���Ȃ��������̌����������Ƃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ����킵�Ă��܂��B�v�Ɛ\���グ���w�E�͓ǂ܂ꂽ�̂ł����H�u�������̏������� [21786070] ��ǂݕԂ��Ă݂āA���ꂪ���̃X���̕�������܂������O�ꂽ���̂ł���Ƃ��v���ɂȂ�܂��H�v�Ƃ�������͓ǂ܂ꂽ�̂ł����H
�����ǂ�ł��Ȃ��Ƃ���A����͋c�_�����炩���ߋ��ۂ���s���ȑԓx�Ƃ������̂ł��傤�B�����ǂ�ł���Ȃ�A�ǂ�ł��ĉ��̔������A����ɑ�������Ȃ��̂��Ƃ���ƁA����ŕ��C�ł����鐸�_�\���́A���͂�P�Ȃ�u�s��@�v�ł͍ς܂���Ȃ��A�lj�́A�����c���́A�R�~���j�P�[�V�����́A���f�́A�����͂Ȃǂ���ؔ����Ȃ��u����I�ȓ݊����v�Ƃ��������悤����܂���B������̏ꍇ���A���́u�c�_�̏�v���\�����������肦�Ȃ����̂ł��B
���Ȃ��͑��l�̎����A��A�w�E��A�����ɂ܂������������ŁA�I�قǂ�������X���b�h�̎�|�ɓڒ������A���������̌����������Ƃ����������Ă���̂ɁA�N�ł���ǂ����Ă��Ȃ��Ɓu�c�_�v�Ȃǂł���̂ł����H
�����ԍ��F21788112
![]() 6�_
6�_
Minerva2000����
�܂�Minerva2000����̑�O��ɂȂ��Ă���F
��S/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A�`������Ă����N���b�N���g�p���܂��B
�͒[�I�ɊԈႢ�ł��B�u�ȑO�Љ��EDN�̋L���w�I�[�f�B�I�i���ƃN���b�N�W�b�^�[ �x��ǂ�ł��������v�Ƃ������Ⴂ�܂����AMinerva2000�����悭�ǂ܂ꂽ�����悢�Ƃ������܂��B
�ihttp://ednjapan.com/edn/articles/0709/01/news016.html�j�F
�����ׂẴf�[�^�̓V���A��������A�N���b�N�͂��̃V���A�������ꂽ�M���ɖ��ߍ��܂��B���������ɂ́A������CDR�i�N���b�N���f�[�^���J�o���j��H���K�v�ƂȂ�B���̋@�\�́A�f�W�^���I�[�f�B�I�̐��E�ł́A�u�f�W�^���I�[�f�B�II/F���V�[�o�iDIR�j�v�ƌĂ��B
�����ۂ̃I�[�f�B�I�V�X�e���ł͂��Ȃ�d�v��D-A�ϊ��ɂ�����W�b�^�[�̉e�����������ʂ���m�F����B�}5�Ɏ������̂��A�����ɗp�����V�X�e���\���ł���B���̎����ł́A�W�b�^�[���A�i���O�M���ɗ^����e����m�邽�߂ɁA�ȉ���2�_�ɒ��ڂ��邱�Ƃɂ����B
�EDIR�̈Ⴂ
�E�C���^�[�t�F�[�X�̈Ⴂ�i�����ڑ��ƌ��ڑ��j
�����ɒ��ڂ������R�́A���̂悤�ȃV�X�e���ɂ�����W�b�^�[�����̎�v��������2�ł��邩�炾�B�Ȃ��ADIR�̔�r�ɂ́A�M�҂炪�J�������uDIR9001�v�ƁA�f�[�^�V�[�g�ɃW�b�^�[���\���K�肳��Ă��Ȃ��������А��i���g�p�����i�ȉ��AA��DIR�ƕ\�L����j�BDIR9001�̃W�b�^�[�́A���ڑ��ł������ڑ��ł��قƂ�Ǎ��͂Ȃ��A�����l��40ps�ȉ��ł���B����AA��DIR�̃W�b�^�[�����l�́A�����ڑ��ł�240ps�A���ڑ��ł�900ps�ł������B
�Ԗx�����g�p����TI�А��́uDIR9001�v�̃u���b�N�}���A�b�v�����̂ł������������B
�gClock and Data Recovery�h�́uDIR9001�v������PLL��p���ĂȂ���邱�Ƃ��킩��܂��B�܂��A�b�v�����Ԗx�_���Ɏ�����Ă���u�}5�@�����ɗp�����V�X�e���̍\���v���������������BDAC��IC��DIR�ŕ������ꂽ�N���b�N�ڎg���̂ł��B�i������DAC�P�̋@�ɂ�DIR�`�b�v��DAC�`�b�v�̗������܂܂�Ă��܂��j S/PDIF�ł̓I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�Ɂu�`������Ă����N���b�N�v���g���Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B
���������āAMinerva2000�����ꂽ���F
�����P�[�u������p�ӂ��܂��B����͐��S�~�̃v���X�e�B�b�N�t�@�C�o�[���̌��P�[�u���A�����͐Ήp���̌��P�[�u���B���̗��҂ł͓`���W�b�^�[�ʂ��قȂ邽�߁ADAC�ɋ��������N���b�N�̃W�b�^�[�ʂ��ς��܂��B���̂��ߗ��҂̉����̈Ⴂ�͖����ł��B
�́A�uS/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�͓`������Ă����N���b�N���g�p����v�Ƃ�����O��̂��ƂɂȂ���Ă��܂����A�u�`���W�b�^�[�v�́u�I�[�f�B�I�Đ��N���b�N�̃W�b�^�[�v�Ƃ͊W�Ȃ����߂ɁA�p�C������i [21787124] �j�̂��w�E�̂悤�ɁA���Ӗ��Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B�u�`���W�b�^�[�v�́u�I�[�f�B�I�Đ��N���b�N�̃W�b�^�[�v�Ƃ͊W�Ȃ����Ƃ́AMinerva2000���ȑO�Љ�ꂽEDN�͍̉��_���ihttp://ednjapan.com/edn/articles/1208/24/news015.html�j�ɂ������Ă���܂�����B
�u�`���W�b�^�[�v���W����Ƃ���A�I�[�f�B�I�M�����̂��e������DIR�̃}�X�^�[�N���b�N�̃W�b�^�[��������Ƃ��ɁA�I�[�f�B�I�M���ɍڂ��Ă���`���W�b�^�[�����̈ꕔ�Ƃ��ĉe������ɂ����܂���B�Ԗx�_���ł́A�W�b�^�[�̏��Ȃ��uDIR9001�v�Ƃ�葽��A��DIR���r���āA
���}10�Ɛ}11�́AA��DIR�ɂ����铯���ڑ����̃X�y�N�g�����ł���B������́A�I�[�f�B�I�M���̗L���ɂ��A���Ȃ�傫�ȍ���������B�}10����A�I�[�f�B�I�M�������݂���ꍇ�ɂ́A�N���b�N��X�v���A�X�̃X�y�N�g�����ߖT�ɃT�C�h�o���h�����݂��邱�Ƃ�������B����́A�I�[�f�B�I�M���ɂ��A�N���b�N�ɕϒ����������Ă��邱�Ƃ�\���Ă���B
�Əq�ׂĂ��܂����A�u�I�[�f�B�I�M���v���̂ɂ����DIR�̃N���b�N�ɕϒ���������̂ł����āA�u�`���W�b�^�[�v�ɂ���ĂƂ͌����Ă��܂���B�܂��Ă�A�����ł́uS/PDIF�ڑ�������`������Ă����N���b�N�v�Ȃǖ��W�ł��B�����炱���A�Ԗx�_���́A
�����g�p��Ԃł̓I�[�f�B�I�M���͕K�����݂��A���̎��g����U���͍��X�ƕω�����B���̈���ŁA�N���b�N�M���̓I�[�f�B�I�M���Ƃ͖��W�ɏ�Ɉ��̎������ޕK�v������B�]���āA�N���b�N�̕i�����I�[�f�B�I�M���ɂ���Ĉ������邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ�DIR�ɂ����R���Ă͂܂�B���J�o����̃N���b�N�̎����I�[�f�B�I�M���Ɉˑ����Ȃ����Ƃ́A�I�[�f�B�I�i���̗�h�����߂ɔ��ɏd�v�Ȃ��Ƃł���B
�ƌ��_�Â��Ă���̂ł��B
�����ԍ��F21788258
![]() 5�_
5�_
���ɁA��������̘_���ɂ��Ăł����A
��DAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ������́A�o�̓A�i���O�g�`�ւ̉e���́A�W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ邱�ƂŎ��g���ϓ����N���邱�Ƃł͂Ȃ��A�A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�ł��B
����̓�������̘_���͑O�҂̐����Ƃ��Ă���A���ł��B
���_���̂Q�D��͐M����p����W�b�^�[����@�̖`���́i�P�j�����Q�Ƃ��Ă��������B
���i�P�j���͕t�����ꂽ�W�b�^�[���ϑ��M���ɍڂ�Ƃ������Ƃ����\�����Ă��炸�A���ꂪ�W�b�^�[�t���ɂ��B��̉����ω��Ƒz�肵�Ă��܂����A���ꂪ���������ԈႢ�̌��ł��B
����ʼn��������̂��悭�킩��܂���B�_���́i�P�j���̕��������p���܂��ƁF
���p���g����c�̐����g��DA�ϊ����A��������AD�ϊ����鑪��n���l����B���̑���n�ɂ����āADA�ϊ������M���𑪒�M���AAD�ϊ���̐M�����ϑ��M���Ƃ���B���̂Ƃ�����n�ɂ����āA�C�ӂ̐U���ϓ�a(t)�ƁA�p���g����m�A�U��J�ł��鐳���g�̃W�b�^�[���t�����ꂽ�Ƃ��̊ϑ��M���̎��Ԕg�`x(t)�������B
x(t)��a(t) sin (��c (t�{J sin (��m t)))�@�@�@�@�@(1)
����́A�W�b�^�[�𑪒肷�邽�߂ɐl�דI�ɃW�b�^�[�������邽�߂̎��ł���ˁB���̂悤�ɒ莮�����Ă����āA���̐l�דI�W�b�^�[�𑪒肵�ĉ��������̂ł����H
�O�ɂ������܂������A���̘_���́u�Đ������邢�̓f�B�W�^���L�^��̃f�[�^�ɁA�W�b�^�[�ɂ��ǂ̂悤�ȉe�����ǂꂾ�������I�Ɋ܂܂�Ă��邩���A��ʓI�ɑ��肷�邱�Ɓv���������Ă�����̂ŁA����̃W�b�^�[���o�̓A�i���O�g�`�ɂ��̂܂܍ڂ邱�Ƃ��m�F������̂ł͂���܂���B�����āu��ʓI�ɑ��肷��v���߂Ɏ��Ԃ�P�������Đݒ肵�Ă��邾���ł��B������A����������
�������ł͒P�����ׂ̈ɃW�b�^�[�g�`�𐳌��g�ŕ\�������A���_�I�ɂ́A�����g���g���ƁAAD�ϊ��ɂ�����i�C�L�X�g���g�����邢�̓[�����g���Ƃ̍����ō����g���Ƃ���W�b�^�[�g�`�𒊏o���邱�Ƃ��\�ł���B���̑����@�́A����n�ɑ��݂���c�݂�G�������̉e������B�����ŁA����M�����T���v�����O���g���̂P�^�S�ł��鏃����p��������ƁA����ɋ߂����̐M�����g����p����������s���A����ꂽ�W�b�^�[�X�y�N�g�����r���A���ʂ���X�y�N�g�������𒊏o���邱�Ƃɂ���āA�c�݂�m�C�Y�̉e�������Ȃ����邱�Ƃ��ł���B
�Əq�ׂĂ��܂��B
�d�v�̂Ȃ̂́A�u�W�b�^�[�g�`�v�Ɓu�U���ϓ��g�`�v���ĂƂ炦�邱�ƂŁA���̂��߂̒莮���ł�����܂��B
Minerva2000����́A
�uDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ������́A�o�̓A�i���O�g�`�ւ̉e���́A�A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�v�ł���A
�u�i�P�j���̑���ɁA�N���b�N�W�b�^�[�t�����́ADAC�ł̃A�i���O�g�`�����V�~�����[�V���������鐔�����{���K�v�v�ƌ����܂����A����Ȃ�A���́u�A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�v���V�~�����[�g���鐔�������������������B�i�����炭����ȕ��G�Ȑ����͎g�����̂ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂����j
���������A�uDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ������́A�o�̓A�i���O�g�`�ւ̉e���v�ƌ����܂����AMinerva2000����́u�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A�`������Ă����N���b�N���g�p���܂��v�Ƃ������Ƃ��O��ɂ���Ă���̂ŁA���̑O��̊�ŁuDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ������v�̂��Ƃ��l���āA�u�o�̓A�i���O�g�`�ւ̉e���v��z�肵�Ă����Ӗ��Ȃ�Ȃ��ł����H
�܂��A
�����u�W�b�^�[�̓A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�ł���v�Ɖ��肵�āA���������ł���Ȃ�u�l�͂��̘c�ɂ͔��ɕq���ŁA���ꂪ���m���ɎO�����̑傫�ȍ����o�闝�R�ł��v�ƌ����鍪���͉��ł����H
����������ڂ����������ĉ������B
���Ԗx����̎������ʂ�����ł��B
�Ƃ����������ł������A������u��O��v�̊�Â��Ă̂��������Ƃ���A�čl���Ă����������������܂��B�����A�������A����ł��������͕ς��Ȃ��Ƃ����̂ł����Ă��A����Ȃ炻��ŁA�u�Ԗx����̎������ʁv�̉����ǂ����߂����炻��������̂��A�����炪���؉\�Ȍ`�ł��������������B
�����ԍ��F21788317
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
>��������̘_���͂Ȃ��T���v�����O�藝�Ɉˋ�������̂ł͂Ȃ��A���z�ʒu���炸�ꂽ�N���b�N�̉e����_���Ă��܂��B���_�ɂȂ��e���͂���܂���B
���ς�炸�������Ă��܂���ˁB��������̘_���̓T���v�����O�藝�����E�������̉e���̎��_�������Ă���A���̒v���I���ׂ��Ԉ�������_��ł��܂��B
�������������P�[�u�����g���������s���A��������̘_�����S�Č��ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�ł��傤�B
�����ԍ��F21788355
![]() 2�_
2�_
��Symbolist_K����
���̕��ʂ̊�b�m�����S���Ȃ����ł��邱�Ƃ����O���Ă���܂����B������ǂ�ł��A����Ɍ�����d�˂Ă��܂��B
�܂��ŏ��͎d���̖������Ƃł����A��������ɂ�������Ԃɗ�����ƁA�����������̌���������e�ؐS�͎����Ă��܂��܂��B
��_�����ADIR�ł�PLL�ł��`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���B
�����ԍ��F21788379
![]() 2�_
2�_
Minerva2000����
����ԂȂ̂�Minerva2000����Ȃ̂ŁA����������̃X�^�C����^���Ă݂��̂ł���B
�������A��{�́u�悭�킩��Ȃ�����A���������������v�Ƃ����ԓx�ł��傤�H
�u���P�[�u���ɂ�鉹�����͖����v�Ȃ�Č��_�́A��������̘_���̂ǂ����ǂ��ǂ�ł��o�Ă��܂���B�ނ���A��������̘_���́u���f�B�A�̍��A�L�^�t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�A��DAC���쓮����T���v�����O�N���b�N�v�ȂǑ��l�ȃW�b�^�[�̑��݂�F�߂Ă���̂ŁA�u�`���W�b�^�[�v���͔̂F�߂Ȃ��킯������܂���B���͑O��A��������̘_���͑��l�ȃW�b�^�[�̑����I�c�݂����Ă�����̂ł���Ƃ������Ƃ�����s�����Ę_���Ă݂��̂ɁA���ړI�Ȕ��_�́u�i�P�j��������v�����ł����B�u�i�P�j�����ǂ����߂����灃�W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ邱�ƂŎ��g���ϓ����N���遄�ƌ����Ă���ƌ��邩�v�ɂ͂������͂Ȃ��̂ł����H
�����č�����uDIR�ł�PLL�ł��`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���v�A�̈ꕶ�ł����H ���̍��������������������B
�܂��O��́A���J�ɍ����̒����肢�����̂ɁA�����́u���̍����͐Ԗx����ɂ��������ʂł��v�̈ꕶ�ł�����ˁB�����獡��͂����܂Ō���s�����Č���̍l�����q�ׂĂ݂��̂ɁA���ɂ��ς��Ȃ��̂ł����H
�u�Ԗx����̎������ʂ��ǂ����߂���̂��H�v��u�w�A�i���O�g�`�̋ɂ߂ĕ��G�Șc�x���V�~�����[�g���鐔���͂ǂ����������̂ɂȂ�̂��H�v�Ƃ������̎���ɂ͂������ɂȂ�Ȃ��B
����łǂ�����ė�������Ƃ��������̂ł����H
�����ԍ��F21788427
![]() 3�_
3�_
�l�̓Z�C�E�`����
�܂��AMinerva2000����̋�����ꂽ���P�[�u���̌��ɂ��Ăł����A���S�~�̃v���X�e�B�b�N�t�@�C�o�[���̌��P�[�u���ƐΉp���̌��P�[�u�����r����A��҂̕��������ǂ��̂͂�����܂����Ǝv���܂��B����́u�`���`���l���v�ɂ��W�b�^�[���قȂ邩��ł��B
�����P�[�u����USB�P�[�u���̉������ɂ��Ă��A��{�I�ɂ͓����ł��B
���̍l���͐�s�X���ŏڂ��������܂������A���������ȉ��̒ʂ�ł��F
�f�W�^���P�[�u�����܂߁A������P�[�u���́u�`���`���l���v�̈ꕔ�ł���B�u�`���`���l���v�́A�p�b�V�u�Ȃ̂Ŕ������郉���_���W�b�^�[�͖����ł���قǏ��������̂́A�`���l���̒�R�A�C���s�[�_���X�s�����A�\����ʂȂǂɂ���Č����݁A���g����������l�łȂ��Ȃ邽�߁A�����Ԋ��ށB�V���A���M�����`���l����ʂ邤���ɁA�g�����X�~�b�^��������n���ꂽ��N���b�N�R���̃f���[�e�B�T�C�N���c�����̕����Ԋ��Ƒg�ݍ��킳��ăf�[�^�ˑ��W�b�^�[���`������B����ɂ��M���ɍ����g�������A�`���l�������ݏo�����W�b�^�[����蕡�G������B����炷�ׂĂ̌��ʁA�`���`���l�����o�߂��ă��V�[�o�ɓn�����Ƃ��ɂ́A�M���͂��Ȃ�t�j���t�j���ɂȂ�B
������x�t�j���t�j���ɂȂ��Ă��ADAC�ł̃��J�o���Ō��ɖ߂�̂Ŗ��Ȃ��B��������R�̑傫������i�ׂ�����j�P�[�u����A�C���s�[�_���X�s�����̐r�������P�[�u����A�\����ʂ݂�����P�[�u���\�\�܂�A�ȃP�[�u���\�\�g������A�P�[�u�������������肷��A�����ɕs�s���𗈂��قǃt�j���t�j���ɂȂ��Ă��܂��̂Ŗ��ƂȂ�B
������A�ɒ[�Ɉ����̃P�[�u���͌����Ďg���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�P�[�u���ɂ���āi���Ȃ��Ƃ����������ւ́j�u���͕ς��v����ł���B
�������A�t�ɁA�ƂĂ��Ȃ��ǂ��P�[�u�����g�����ꂾ�������ǂ��Ȃ�̂��ƌ����A�����Ƃ�����Ȃ��B�Ƃ����̂��A������x�ǂ��P�[�u�����g���ĐM���̗�������x�ɂƂǂ߂���A�M�������V�[�o�ɓn�����������ɁA���V�[�o�����O�̃}�X�^�[�N���b�N���g�����N���b�N�E���J�o�����s���ߒ��ŁA�W�b�^�[���قڐ��邩��B������A������x���i���̃P�[�u�����g���Ă���A����ȏ㍂�i���̃P�[�u���Ɍ������Ă��A���V�[�o����o�͂����M���̕i���͂قƂ�Ǖς��Ȃ��i����䂦���Œ����Ă��킩��Ȃ��j�\��������B���������̏ꍇ�A���́u������x���i���ȃP�[�u���v�Ƃ����̂��ǂ̒��x���i���ł���悢�̂������肷��̂��܂�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�����ԍ��F21788445
![]() 4�_
4�_
Symbolist_K����
>����ԂȂ̂�Minerva2000����Ȃ̂ŁA����������̃X�^�C����^���Ă݂��̂ł���B
�͂��A�^����̂͂S�O�N�����ł��A
>�����č�����uDIR�ł�PLL�ł��`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���v�A�̈ꕶ�ł����H ���̍��������������������B
�����������Ă��A��������������邾���Ȃ̂Ŏ~�߂Ă����܂��B�����ŕ�����܂ŕ����Ă��������B
>����łǂ�����ė�������Ƃ��������̂ł����H
��������ƌ����Ă����ʂȂ��Ƃ�������܂����B
PS�F���������˂������������������Ă���ƁA�܂��Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɓ˂����܂ꂻ��(��)�B
�����ԍ��F21788461
![]() 3�_
3�_
Minerva2000����
�X�^�C����^�����̂�Minerva2000����ɒ������͂������Ă����������߂̝��ߎ�ł����āA�u��{�́A�킩��Ȃ����炨�������������A�Ƃ����ԓx�ł��v�ƌ����Ă���ł��傤�B���ʁA�Q�A���ł͑�Q���̕������d�v�Ȃ̂ł��B
�ł͂��������܂����A�u�����Ȃ��v�̂Ɓu�������Ȃ��v�̍��͂����������ł����H
����́u�������Ȃ��v�̂Ɓu����������v�̍��Ɠ����ł͂Ȃ��ł����B
�������������Ă��A��������������邾���Ȃ̂Ŏ~�߂Ă����܂��B�����ŕ�����܂ŕ����Ă��������B
�ȑO�ɏ����܂������A���̃X���́u�W���m�v�́u������Ɓv�ɂ���āA�l�ōl���Ă��邾�������y���ɑ傫�ȃV�i�W�[�I�m�݂������Ƃ�ڎw���Ďn�߂܂����B���������҂ɑ��āA�����܂ł��������̂Ȃ�A���߂Đ�̎��̎���̈���炢�ɂ́i�킽���́u�悭�킩��܂���v�ƂT��͌����Ă���̂�����j�A�����̉���t���œ����āA���Ƃ͎����ōl���Ȃ����Ƃ��炢�����Ă��悢�ł͂Ȃ��ł����H
�����ł킩��܂ŕ����Ă���S�O�N�����邩������Ȃ�����Ȃ��ł����B
�����ԍ��F21788540
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����
>���̃X���́u�W���m�v�́u������Ɓv�ɂ���āA�l�ōl���Ă��邾�������y���ɑ傫�ȃV�i�W�[�I�m�݂������Ƃ�ڎw���Ďn�߂܂����B
�X���傳�s�i���ł͖����ł��ˁB
>�����ł킩��܂ŕ����Ă���S�O�N�����邩������Ȃ�����Ȃ��ł����B
���Ȃ��Ȃ炻��ł�������������܂��A����ŗǂ��ł͂Ȃ��ł����H�@�����l�����邱�Ƃ��o���āB
�����ԍ��F21788562
![]() 2�_
2�_
Minerva2000����
���̑Ή��ł��A���̌��t�̎}�t���߂ɂ��蓚���āA�̐S�ȕ����ɂ͂܂��������������т��p�����悭�킩��܂����B
���܂��ɏ�k���ʂ��Ȃ��B
��͂�A����ł��Ȃ������́u�������Ȃ��v�̂��Ƃ悭�킩��܂����B
�����ԍ��F21788576
![]() 8�_
8�_
Symbolist_K�����
���������Ǝv���Ă�����ɑ��ẮA����l��������������Ƃ킩��܂�����A���肳��Ȃ����Ƃ��������߂��܂��B�l�b�g�ł͂悭�A����̂������������ɐ^�ʖڂɑΉ����Ă��邤���ɁA�����̕������������Ȃ��Ă��܂�����A��J���ɂ�������悤�Ȑ��_��ԂɊׂ���������������܂��B�������悤�Ƃ��Ȃ�����ɒ����������A�˂�̂͋M�d�ȘJ�̖͂��ʌ����ł��B
Symbolist_K����͖c��ȏ����L�����ĕ��s�������A�v�_���܂Ƃ߂�\�͂ɒ����Ă�����悤�Ȃ̂ŁA�������炳��Ɉ�����ݍ���ł킩��ɂ������e���킩��₷���悤�Ɋ��ݍӂ��ď����Ƃ��A�������������փG�l���M�[���g���Ă���������ƌl�I�ɂ͊������v���܂��B
�l�b�g�̌������̐l���ɂ͏펯���ʗp���Ȃ����Ƃ����X����܂��̂ŁA���A���Ɠ����̉��l��u���̂͊댯�ł��B�����܂Ńl�b�g�̂��ƂƂ��āA�y�����������ׂ��Ƃ���͂��������ׂ����ƙG�z�Ȃ���A�h�o�C�X�����Ă��������܂��B�܂��A���������܂ɏ������݂����Ă����ĉ������Ȃ����Ƃɂ��āA�����ł��l�ѐ\���グ�܂��B
�����ԍ��F21788680
![]() 8�_
8�_
Minerva2000����
���Ⴀ�A��������P�_�����B
��DIR�ł�PLL�ł��`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���B
���ꂪ�A�L�^���ɃV���A�������ꂽ�M���ɖ��ߍ��܂ꂽ�N���b�N�̂��Ƃ��w���Ă���̂��Ƃ�����A���Ȃ��Ƃ��Ԗx�_������͌����Ⴂ�ł��B�Ԗx�_���ł͋L�^���̃W�b�^�[�ƍĐ����̃W�b�^�[�͕����Ę_�����Ă��܂�����B
�����āA���Ƃ����̈Ӗ��Łu�`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��v�Ȃ��ƌ����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��Ƃ��Ă��A���Y�̍Đ����̕����ɉ����āADIR��PLL�ɂ���ĕ�������邱�Ƃɂ͈Ⴂ�͂Ȃ��ł��傤�B
���������̂�������
��S/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A�`������Ă����N���b�N���g�p���܂��B
�������̂ł���B�u�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�v���uDAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����v�Ƃ����̂͊��S�Ȍ��ł͂Ȃ��ł����A�Ԗx�_���ɏƂ炵�Ă��B�ǂ����āu�`���H�o�R�̃N���b�N�̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v���Ƃɂ���āA�u�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N��DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ��ے�ł���̂ł����H �_�����j�]���Ă��܂��B
�ƌ����Ă݂Ă��A�ǂ����u�������Ȃ��v�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21788683
![]() 6�_
6�_
�Ɠd��D���̑�コ��
�����肪�Ƃ��������܂��B
���e�Ȃ����t���|���Ă��������A�����C������܂����B�ł��A���͂��Ƃ��Ƃ����������ƂŐ��_�I�ɎQ������͂����͂��Ȃ���ł��B���͗����܂����B���Ɂu�X���b�h�ɂ��W���m�̓����v��@�ł������ꂽ�̂ɂ́A���̎Q���҂̂��Ƃ��v���āA�җ�ɕ��������܂������B
�Ȃ�ׂ��u�W���m�v���Ăэ��ނ��߂ɂ��A�Ɠd��D���̑�コ��������Ă�������悤�ɁA�ߖڐߖڂŗv�_���܂Ƃ߂�悤�ɂ��悤�Ǝv���Ă��܂��B�Y��悤�ɂ��������Ȃ������p�C��������Ƃ��ǂ����l�������Ă�������̂ŏ������Ă��܂��B
�����������܂ɏ������݂����Ă����ĉ������Ȃ����Ƃɂ��āA�����ł��l�ѐ\���グ�܂��B
���������A�Ƃ�ł��Ȃ��B���傭���傭�������Ȃ����Ƃ��������肷��̂͑S�R���v�ł���B�P�O�₢�|���ĂP���Ԃ��Ă��Ȃ��Ƃ��A�P�O�O�₢�|���Ă���ƂP�Ԃ��Ă���Ƃ��A��������ԂȂ����Ȑl�Ƃ������Ȃ̂ł����āA����ł̓X���b�h�ŋc�_����Ӗ����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�����ԍ��F21788729
![]() 5�_
5�_
�p�C������A
EDN�̋L����ǂނ悤�ɂƂ̂��ƂŁAURL�������܂������A�ԈႢ�ł����B
���l�т��Ē������܂��B7,8�N�O�ɂ��̋L����ǂ��ɂ̓N���b�N�E�f�[�^�E���J�o����PLL�̐������L�����ƋL�����Ă����̂ł����A������߂ēǂނƂ��̂����肪�����Ȃ��Ă��܂��B�]���ĎQ�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��B
���߂ďЉ�܂��B
S/PDIF�CAES/EBU���L�̖��
www.spatiality.jp/pcaudio-research/pcaudio-learning/jitter-cause
�N���b�N�E�f�[�^�E���J�o��
https://ja.wikipedia.org/wiki/�N���b�N�E�f�[�^�E���J�o��
�����͎Q�l�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21788784
![]() 1�_
1�_
����Ԃ͎��̃L�����Ȃ̂ŁA�܂˂��Ȃ��ŗ~�������ǁH�ȉ��V�k�S�Ȃ���B
�����������P�[�u���̘b�́AMinerva2000����[21786361]�ŏo���Ă������̂ł��F
>���P�[�u������p�ӂ��܂��B����͐��S�~�̃v���X�e�B�b�N�t�@�C�o�[���̌��P�[�u���A�����͐Ήp���̌��P�[�u���B���̗��҂ł͓`���W�b�^�[�ʂ��قȂ邽�߁ADAC�ɋ��������N���b�N�̃W�b�^�[�ʂ��ς��܂��B���̂��ߗ��҂̉����̈Ⴂ�͖����ł��B
>
>�������҂̌v�����@�ő��肵�Ă��A�l�����m�ł������ȃ��x���̃W�b�^�[�X�y�N�g���̈Ⴂ�͏o�Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�܂艹���ω��͐l�ɂ͌��m�s�\�Ɣ��肳��܂��B
>
>����𓌋�����Ȃ�A���P�[�u���ɂ�鉹�����͖����̂ɁA�����������Ƃ�����v���Z�{���A�Ƃ������f�ɂȂ�܂��B
>
>���̔��f�́A��������̌v�����@���Ԉ���Ă���A�ƂȂ�܂��B
�܂�A�u��������̌v�����@���Ԉ���Ă���v���Ƃ��������߂̍ޗ��̂͂��ł��B�������u�Ԉ���Ă���v���Ƃ̐�����
>�������҂̌v�����@�ő��肵�Ă��A�l�����m�ł������ȃ��x���̃W�b�^�[�X�y�N�g���̈Ⴂ�͏o�Ă��Ȃ��Ǝv���܂�
�ł�������܂���B�����Ɂu��������̌v�����@���Ԉ���Ă��邱�Ɓv�̗��R�͈�ؘ_�q����Ă��܂���B�܂�A���P�[�u���ŃN���b�N�W�b�^�[���ς�낤���ς��܂����AMinerva2000���u��������̌v�����@���Ԉ���Ă��邱�Ɓv�̐��������Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��{���ł��B
����Ȋ����ŁA�W�̂Ȃ��b�ő�����J�������킩������Ȃ��̂ŁA�����ȊF���܂ɂ�����܂��Ă͌��P�[�u���̘b�͑���ɂ��Ȃ����Ƃ������߂��܂��B
�����ԍ��F21788867
![]() 6�_
6�_
���A�������BMinerva2000����[21788461]�̂����҂ɂ������Ă����܂��傤�B
>��������ƌ����Ă����ʂȂ��Ƃ�������܂����B
>
>PS�F���������˂������������������Ă���ƁA�܂��Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɓ˂����܂ꂻ��(��)�B
�Ƃ������ƂŁA����[21775994]��
>Minerva2000����͗��H�w�ɏڂ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�ڂ��������v���邱�Ƃ͋��炭�����ł��B����āA�Ȃɂ��̗��R�����Ă������ł͐������Ȃ����A�܂��͂킯�̂킩��Ȃ����������āA�u�킩��Ȃ��ق��������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�́u�\���v�ʂ�ɂȂ�܂���(��)�B�̂��炱��Ȃ������Ƃ��������Љ�܂��B�O�X���ł������N�����X���ł����B
�uHMDI�P�[�u���̈Ⴂ�ʼn掿���ς��Ƌ���X�ցB�v
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12871923/#12928634
�����ԍ��F21788988
![]() 6�_
6�_
Minerva2000����
�����߂ďЉ�܂��B
S/PDIF�CAES/EBU���L�̖��
http://www.spatiality.jp/pcaudio-research/pcaudio-learning/jitter-cause
�����ǂ܂��āA�����Ő��������Ƃ��A�l���������̐�������ɐM����悤�Ɏd�����悤�Ƃ������l���̂悤�ł����A������A���Љ�̃y�[�W�̋L�q�͌Â��ł��ˁB
��S/PDIF��AES/EBU�́C�f�W�^���P�[�u��1�{�Őڑ����ς݉����o��悤�ɂ��邽�߁C�f�[�^�M���ƃN���b�N�M���������ĒʐM������Ńg�����X�|�[�g�i���葤�j���N���b�N��Master�ɂȂ�CDAC���N���b�N��Slave�ɂȂ�Ƃ����������̗p���Ă��܂��B�f�W�^���@�퓯�m�̓�����Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ͊��ɏq�ׂ܂������CMaster�Ƃ̓N���b�N�̊�ƂȂ鑤�̂��Ƃ��Ӗ����CSlave�Ƃ�Master����ɓ��삷�鑤�̂��Ƃ��Ӗ����܂��B���̂��߁C�g�����X�|�[�g���̋@��̃W�b�^�[�ʂ������ꍇ�ɂ́C����DAC���̃W�b�^�[�ʂ����Ȃ������Ƃ��Ă��C�g�����X�|�[�g���̉e�����ăW�b�^�[�ʂ������Ă��܂��d�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�Ƃ���܂����A����͌Â��}���`�r�b�g�^��DAC�̏ꍇ�ł��ˁB
�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�Ԗx�����p����TI�А��uDIR9001�v�̂悤�ȁuDIR��S/PDIF���V�[�o�[����DAC�`�b�v�Ԃ̓`���v�ɂǂ̃N���b�N����ԑ���Ƃ������ł��BMaster/Slave�̘b�́uS/PDIF���V�[�o�[�܂Łv�̋��̖��ł��B
�������ɁA�Â��}���`�r�b�g�^DAC�̓T���v�����O���g���̎����ŃT���v���z�[���h�����ւ��邱�Ƃŏo�͂܂��̂ŁA�N���b�N�̃^�C�~���O�Ƃ��Ă�LRCK�i�T���v�����O���g���ƍ��E�̃`���l���w��N���b�N�j�̕i�����ł��d�v�ƂȂ�AMater���������M���̃N���b�N�̉e����F�Z���c���Ă��܂��ł��傤�B
�������A���݂̃������g����DAC�̏ꍇ�͘b���Ⴂ�AMCK�i���DAC�`�b�v�̃V�X�e���N���b�N�j�̃^�C�~���O���ł��d�v�ƂȂ�A���M���̃N���b�N�̉e����啔���r�����邱�Ƃ��ł��܂��B
������̋L�q�ɂ��F
http://www.ezto.info/stpress/2016/09/597.html
���܂�DAC�`�b�v�ɂ���Ă�SRC�i�T���v�����O���[�g�R���o�[�^�[�j�𓋍ڂ��Ă��āABCK�ALRCK�ADATA��3�_�Z�b�g�Ƃ͔���MCK����͂����MCK�̃N���b�N���g���ɍ��킹�ăT���v�����O���[�g��ϊ�����DAC�`�b�v�ȑO�Ŕ�������W�b�^�[�̉e����r������B�Ƃ������@�\��������̂�����܂��B
���X�ɁA���͂��ꂽMCK����BCK�ALRCK���A�o�͂ł���DAC�`�b�v������ADAC�`�b�v�����������N���b�N�ɍ��킹�ăf�[�^���o�͂��Ă��炦��ADAC�`�b�v�ɓ��͂���MCK�̕i���ɒ��͂���悢���ƂɂȂ�܂��B
������̋L�q�̌��_�́F
����������ƁA�ŏI�I��DAC�`�b�v�ɓ��͂���uI2S��MCK�ABCK�ALRCK�̕i���������Ƃ��d�v�v�Ȃ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ�
�ł���A�A�������Ƃ��āA�Â��}���`�r�b�g�^DAC���g���悤�ȏꍇ�́A
��USB DDC�ADAC�iDAI�ADAC�`�b�v�j�S�Ă��X���[�u�i�Ǐ]���[�h�j�̃N���b�N�œ���
����̂ŁA
���ŏ㗬��USB�z�X�g�iPC�j���o�͂���USB�V�X�e���N���b�N�i�}�[�J�[�M���j�̕i������ѓ`���i���A�X�Ɋe�X�e�[�W�̃N���b�N�Ǐ]���\��W�b�^�[�����Ɉˑ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�Ƃ���܂��B
�ł����AEDN�͍̉��_���ɂ��u���݂̃I�[�f�B�I�pDAC�f�o�C�X��ϊ������̊ϓ_�Ō���ƁA���̂قƂ�ǂ̓����ϒ��������̗p���Ă���v�����Ȃ̂ŁA���Ƃ����M����S/PDIF��AES/EBU�łȂ����Ă��Ă��A���M���̃N���b�N�̉e�����A�ŏI�I�ɂ́A�����̕����Ŕr���ł���Ƃ������Ƃł��B
���Ȃ��Ƃ��AMinerva2000��������悤�ɁA�uS/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N��DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g��Ȃ��v�ȂǂƂ����Ƃ͑S������܂���̂ŁA�O�̂��߁B
�����ԍ��F21789055
![]() 4�_
4�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����������u�\���v�������������̂ɁA��������������Ƃ��ł��Ȃ��Đ\����܂���ł����B
������Ȋ����ŁA�W�̂Ȃ��b�ő�����J�������킩������Ȃ�
�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ����Ċ̐S�ȕ������͂��炩�����肷��̂ł��傤�ˁH
�͂��炩���Ӗ����s���ł��B
��͂�u�������Ȃ�����v�Ƃ����v���܂���ˁB
�����ԍ��F21789081
![]() 5�_
5�_
Minerva2000�����ɂ��Ă���A�X�����s�тɂȂ�̂ŁA�������܂��傤�B
���̕ӂŁA�p�C�������y��wav�t�@�C����1/f��炬��t������ȒP�ȕ��@���Љ�Ă��ꂽ��A
���������ǁB
�����ԍ��F21789126
![]() 2�_
2�_
tohoho3����
Minerva2000����̎��̃X���iPart 1�����Part 2�j�ł�28��̂����������ׂēǂݕԂ��Ă݂܂����B
����ŋC�������̂ł����AMinerva2000����͑����̘_�����Љ�͂���A����Ɋ�Â��āA���邢�͂����ᔻ���Ď��_��W�J����邱�Ƃ͂����Ă��A���ۂɘ_�����當�͂��u���p�v���Ăǂ̋L�q�̕����Ɉˋ����Ă��邩�A���邢�͔��_���Ă��邩����̓I�Ɏ�����邱�Ƃ͂߂����ɂȂ���ł��ˁB�Ƃ������A28�������P������܂���ł����B
���ꂪ�A��́u�i�P�j���v�ł����B���́u�i�P�j���v�̂݁B����������̂��������낵������܂���ł����B
�����Ƙ_����K�Ƀp���t���[�Y���Ă���Ȃ�Ƃ������A�������ɓs���̂������߂ł����������Ă��Ȃ��̂Łu���p�v�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
�����ԍ��F21789161
![]() 6�_
6�_
�܂��܂��Θ_�̎����ɂ͒������̂ŁA�c�_���p�����邽�߂Ƀp�[�g�R�����܂����B
�����������̃X���b�h�ɂ����e�������F
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21789166/
��낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F21789169
![]() 3�_
3�_
����́APart 1�Ƃ͈���āA����ɑ��铚���������Ȃ��P�[�X�������A�ƂĂ��}���I�ȁu�����v������悤�ȋc�_�̂܂Ƃ܂�Ԃ�ł͂���܂���ł����̂ŁA������Ȃ��p���c�_�Ƃ����Ă��������܂��B
�����ԍ��F21789172
![]() 3�_
3�_
����ł́A�݂Ȃ��܁A�p���X���ł�����܂��傤�B��@���悤�I
�����ԍ��F21789175
![]() 3�_
3�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > �p�C�I�j�A > N-30AE
DENON��DNP-730RE���g���Ă܂����ANAS�o�R�ōĐ����Ă��鎞�ɂ悭�ˑR�t���[�Y���܂��B�d������Ă���ɓd���R�[�h�����������Ƒ��������ł����A����ɂ͔Y�܂���܂��B
N-30AE�̍w�����l���Ă��ł����A���̋@������̂悤�Ȍ��ۂ͋N����̂ł��傤���H
���ƁA�����ɂ��Ăł����ADNP-730RE�����P����邩�ǂ����ȂǁA���̂ւ�����u���������ł��B
![]() 1�_
1�_
�����n����
�\�t�g�̃o�O��������܂���B�t�@�[���E�F�A�̃A�b�v�f�[�g���`�F�b�N���Ă݂Ă��������B
�ǂ����Ă����P����Ȃ��ꍇ�́A������胁�[�J�[�T�|�[�g�ɕ����������悢�ł��傤�B
�����I�ɂ̓W�b�^�[��@�\�̂��邢�܂��g����DENON��DNP-730RE�̕����悢�悤�Ɍ����܂��B
�����ԍ��F21782073
![]()
![]() 0�_
0�_
���n���̊ق���
�t�@�[���E�F�A�m�F���܂������A�ŐV�ł��B
����ł����X�t���[�Y����̂ŁB
�ꉞ���[�J�[�ɐu���Ă݂܂����ǁB
�����ł�DENON�̕����L�����H�Ƃ̂��Ƃł����A��Ԓm�肽���̂�N-30AE�ł���ʋ@��ł������ł����A�t���[�Y�̂悤�Ȍ��ۂ��N���邩�ǂ����ł��ˁB
���萫���d���������̂ŁB
�����ԍ��F21782197
![]() 0�_
0�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > �}�����c > NA7004 [�V���o�[�S�[���h]
�x����Ȃ���A�V�Õi��NA7004���w�����܂����B�����I�͔��ɋC�ɓ����Ă���̂ł���
�ǂ����Ă�App�ł̑��삪��肭�����܂���B
�������������\�O�ŁA��pApp�uWizz App�v�͂����_�E�����[�h�ł��Ȃ��悤�Łi��������Android�p���Ȃ��̂��H�j
���낢�뒲�ׂ�
Marantz remote app���C���X�g�[�����Ďg�p���Ă݂��̂ł����A�@��iNA7004�j���F�����ꂸ�A
IP�A�h���X����͂��Ă��A�u����������܂���v�ƕ\������܂��B
PC�ifoobar2000���C���X�g���[���j�𗧂��グ��ƁAPC�o�R��NAS��F������̂ł����A�R���e���c��I��ōĐ����悤�Ƃ���ƁA�A�v�����G���[�ɂȂ�܂��B
����ɂ��낢�뒲�ׂāAAVR-remote��BubbleUPnP�Ƃ����A�v��������ƁAAVR-remote�œd����ON/OFF���ł���悤�ɂȂ�A
BubbleUPnP��NAS�𑀍�ł���悤�ɂȂ�A����Ȃ�Ɋy���߂�悤�ɂȂ����̂ł����A
�ǂ����Ȃ�A�P�́i��p�H�j�A�v���ő���ł���悤�ɂ������Ǝv���Ă��܂��B
�F����́AAndroid�p�̃A�v���Ƃ���Marantz remote app�����Ȃ��A�g���Ă܂��ł��傤���H
�������́A���ɂ����A�v������������Ă��������B
![]() 0�_
0�_
�m��NA7004�͑Ή����Ă��Ȃ��͂��ł���B
�����ԍ��F21773448�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�����Ȃ�ł���ˁB�}�����c�̃����[�X�������
Marantz_Remote_App_press_release.pdf
iOS�ł͑Ή����Ă���悤�Ȃ̂ł����AAndroid�ł͑Ή����ĂȂ��݂����Ȃ�ł���ˁB
�Ȃ̂ŁA�P���ɊF����͂ǂ̂悤��App���������Ă���̂��^��Ɏv���A
���₳���Ă��������܂����B
�����ԍ��F21773482
![]() 3�_
3�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > DENON > DNP-730RE
NAS�o�R�ōĐ����Ă��鎞�ɂ悭���̋Ȃւ̕ς��ڂŃt���[�Y���܂��B
���̓s�x�d����Ȃ��ƃ_���ł����A����DENON�����ł����ˁB
�S�����肠������܂����H
![]() 0�_
0�_
���r���[�ɂ����l�̏������݂͂���܂����Nj@��̖�肾�Ǝv���܂��B
���Е����@�험�p���܂������ǃt���[�Y�͂قƂ�njo�����Ă��܂���B
�����ԍ��F21161922
![]()
![]() 0�_
0�_
��9832312e����
���[��A��͂肻���ł����B
DENON����ɖ₢���킹�悤���Ƃ��v���܂����A���܂���҂ł��������Ȃ��ł��ˁB
����������ł��B
�����ԍ��F21163348
![]() 0�_
0�_
�����n����
���Ȃ�������o���܂������B
��N�̒����ɍw�����A�m���Ɍ���ȏ�̕p�x�Ńt���[�Y���Ă��܂����B
�����A���̐������͋N�����Ă��܂���B
�t�@�[���E�F�A�̍X�V�̐��ʂ��ǂ����킩��܂��A���P���ꂽ�̂��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F21755392�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
HAP-Z1ES�̍w�����������Ă���҂ł��B���A�w���ɓ������āAUSB�O�t��DVD/BD�h���C�u�������ɍw�����ׂ����ǂ����Ŗ����Ă��܂��B
�Ƃ����܂��̂��A�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���L�q���l�b�g��ɎU������邩��ł��B�Ⴆ�A
https://www.phileweb.com/review/article/201511/16/1850_3.html
�ɂ��A�u�i�]���̂����Ń��b�s���O�������̂Ɣ�r���āj����HAP-Z1ES��CD���b�s���O�����W���j�E�~�b�`�F���wMingus�x��WAV�t�@�C���̉����������ǂ��B���̓����x���オ��A�I�[�v���`���[�j���O�̃M�^�[��W���R�E�p�g���A�X�̃����@�[���̌������x�[�X�̋������N�₩���B�W���j�E�~�b�`�F���̔����Ȑ��g�����N���ɂȂ�A���y�S�̂̃��A���e�B�[���������v���ƂȂ�v�Ɗp�c��Y���͏q�ׂĂ����܂��B
�܂��A���̃T�C�g�̃u���O�̕��́A
http://emuzu-2.cocolog-nifty.com/blog/2016/01/hap-z1eshap-s1c.html
�gCD���ڃ��b�s���O�h�̉��̗D�ʐ����m�M���āA����܂ł��łɑ�����CD�����b�s���O���Ă������ɂ�������炸�A���̂��ׂĂ��gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O���������Ƃɂ��āA���݃��b�s���O���ł��邻���ł��B
�������A�͂����Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ����肦��̂ł��傤���H PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C�����A�gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O�����t�@�C�����A�����A�Ⴆ��WAV�t�@�C���Ȃ�A�����o�C�i���\�f�[�^�ł����āA�����o�C�i���\�f�[�^�̉����ς��Ƃ������Ƃ����肦��̂ł��傤���H
�������̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ƃ�����A�o�C�i���\�f�[�^�Ƃ��ĈقȂ�f�[�^���gCD���ڃ��b�s���O�h�͍��o���Ă���Ƃ����l����ꂸ�A�Ƃ������Ƃ́ASony�̃\�t�g�ɂ����ǂ�ꂽ�gCD���ڃ��b�s���O�h�́A���������ǂ��Ȃ�H�v��������ꂽ���b�s���O�ł���̂ł��傤���H�i����Ȃ�A���̃t�@�C����PC�ɖ߂��Ă݂ĕ��ʂ̃��b�s���O�t�@�C���ƃf�[�^�I�ɔ�r���Ă݂�킩��͂��ł����B�j
�����ŁA�������˂��܂����APC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��ƁA����CD���gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O�����t�@�C���̍Đ��Ƃ����ŘA���I�ɔ�r���ꂽ���Ƃ̂�����͂����܂��ł��傤���H
���������܂�����A����A���̌��ʂ��A�u�������ɁgCD���ڃ��b�s���O�h�̕��������ǂ������v�Ƃ��A�u����A�Ⴂ���킩��Ȃ������v�Ƃ��A�u����A�t��PC���b�s���O�̕��������ǂ������v�ȂǂƋ����Ă�����������K�r�ł��B
����́A���ꂩ�玄��HAP-Z1ES�̍w���ƂƂ��ɍ\�z���悤�ƍl���Ă���V�X�e���S�̂Ɋւ����ł��̂ŁA�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B
![]() 8�_
8�_
���Ⴆ��WAV�t�@�C���Ȃ�A�����o�C�i���\�f�[�^�ł����āA�����o�C�i���\�f�[�^�̉����ς��Ƃ������Ƃ����肦��̂ł��傤���H
�@�f�W�^���M���́A���̔g�`�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�Q�i�@�̐��l�f�[�^�ł��B�f�o�C�X��ς��ă��b�s���O�����f�[�^�ł����Ă��A�o�C�i������v���Ă���ꍇ�́A���l�̓]���~�X�͂Ȃ��̂œ����f�[�^�ɂȂ�܂��B
�@���Ƃ��A���̃f�[�^��10000��J��Ԃ��ăR�s�[���Ă��A�ŏ��ƍŌ�̃o�C�i������v���Ă���A�f�[�^�̗i�G���[�j�͐����ĂȂ��̂ŁA���b�s���O�����o�C�i������v���Ă���2�̃f�[�^���A�����o�H�i�ڑ��j�Ɠ����I�[�f�B�I�@��ōĐ������ꍇ�́A�������ɂȂ�܂��B
�@�������o�C�i������v���Ă��Ă��A�I�[�f�B�I�ɂ̓v���V�[�{���ʂ�����̂ʼn����������Ē�������ꍇ������܂����A���̏ꍇ�́A�����Ă�{�l���C�ɓ�����������@������`���C�X����A���_�I�X�g���X�����Ȃ��Ȃ�A�ǂ����ʼn��y���y���߂�Ǝv���܂��B
�@�o�C�i������v���Ă��邩�ǂ����́Awav�t�@�C���̃f�[�^�����݂̂̔�r���K�v�ɂȂ�̂ŁAwav��p�̃o�C�i���`�F�b�N�v���O����������܂��B�\�t�g����WaveCompare�@for Windows�Ń_�E�����[�h��́A
http://efu.jp.net/soft/wc/wc.html
�@�g���Ă݂�ƂƂĂ��֗��ł��B����������CD��ǂݍ��݂������Ȃ���CDR�Ȃǂ���A�h���C�u��A���b�s���O�\�t�g��ς��ĕ������b�s���O���Ă݂āA���̃\�t�g�Ŕ�r���āA���S��v����ACD�h���C�u�ɂ��G���[�������͈�ؖ����ŁA���m�ɒ��o����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�����ԍ��F21724353
![]() 15�_
15�_
�p�C������
���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B
wav��p�̃o�C�i���`�F�b�N�v���O�����͕֗������ł��ˁB���x�g���Ă݂܂��B
�ł����A���͂܂�HAP-Z1ES�������Ă��Ȃ��̂ŁA�gCD���ڃ��b�s���O�h�œ���ꂽ�t�@�C����PC���b�s���O�œ���ꂽ�t�@�C�����r���邱�Ƃ��ł��܂���B
�����ACD��̃f�[�^�ƃr�b�g�p�[�t�F�N�g���ǂ����Ō����A�gCD���ڃ��b�s���O�h�����A�o�C�i���`�F�b�N�v���O�����Ȃ�AdBpoweramp�Ȃ�AEAC�Ȃ�A���낢��g����PC�ł̃��b�s���O�̕�����萳�m�����ł���ˁB
���������o�C�i������v���Ă��Ă��A�I�[�f�B�I�ɂ̓v���V�[�{���ʂ�����̂ʼn����������Ē�������ꍇ������܂����A���̏ꍇ�́A�����Ă�{�l���C�ɓ�����������@������`���C�X����A���_�I�X�g���X�����Ȃ��Ȃ�A�ǂ����ʼn��y���y���߂�Ǝv���܂��B
�Ƃ������Ƃ́A�p�C������́A��Ɉ��p�����p�c��Y���Ȃǂ́ASony������IO-Data DVR-UA24EZ2A��I�肵�āgCD���ڃ��b�s���O�h�����邱�ƂɋC�����ǂ��Ȃ��Ă��܂��āA���̐��_��ԂŒ������̂ŗǂ����ɕ��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ȃ̂ł��ˁB
�p�c��Y���̓X�e���I�T�E���h���̎��M�w�ɂ��āACD�̘^���ɂ��g����Ă���l�ł����A�����������Ƃ���A�u�W���j�E�~�b�`�F���̔����Ȑ��g�����N���ɂȂ�A���y�S�̂̃��A���e�B�[���������v���ƂȂ�v�Ȃ�āA�悭����Ȃ��Ƃ����������̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�ނ̑��̕]�_��ǂނƁA����Ȃɂ��������Ȑl�ł��Ȃ������Ȃ̂ł����B
�ł��A�gCD���ڃ��b�s���O�h���R���g���[������Sony�̃\�t�g�ɉ��炩�̗D�ꂽ�d�g�݂�����\�����̂Ă���܂���B
�ǂȂ����A���ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂�������Ⴂ�܂��H
�����ԍ��F21724406
![]() 7�_
7�_
���������b�ŃX���傪�o�C�i������v���Ă����特�͕ς��Ȃ��Ƃ����l���̎�����Ȃ̂ŁA�ԐM����l�͂��Ȃ��Ǝv���܂���
�o�Ă����������@���̂���Ȃ�ł��傤����ˏ�
�����ԍ��F21724412�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
MAX���O�Y����
����͌���ł��B
���́u�o�C�i������v���Ă����特�͕ς��Ȃ��Ƃ����l���̎�����v�ł͂���܂��A����Ƃ͈Ⴄ�l���̐l��@�����������܂���B
��ŁA�p�c��Y���̌������Ƃ������������琳������������Ȃ��Ƃ����^�O��悵�Ă���ł͂���܂��B
�o�C�i���]�X�́A������Ƃ������������������Ă��邱�Ƃ��q�ׂ��܂łŁA�{���͂悭�킩���Ă��炸�A�ނ��뎄�͎����̎��ɕ����������̂���̌����ƂƂ炦��̂ŁA���ɑ��錻���̑O�ł͊ϔO�◝�_�͂����Ɏ̂Ă܂��B
�����A���ۂɎ��Œ����āgCD���ڃ��b�s���O�h�̕��������ǂ��Ƃ�����������ق炢��������Ȃ�A���͂���ɒǐ����āA�O�t��DVD�h���C�u���āgCD���ڃ��b�s���O�h���������ł��B
���Œ����ėǂ��Ȃ�A�o�C�i�����ǂ��Ƃ��͂ǂ��ł��悢���A����ł����o�C�i������v���Ă���̂ɉ������ǂ��ƂȂ����Ƃ�����A�����������Ƃ�����ȂƎv���āA���ۂɉ����ǂ��������܂���B
�����ԍ��F21724421
![]() 9�_
9�_
��Symbolist_K����
0,1�̃f�W�^���f�[�^�ŋL�^����Ă���A�ƌ����Ă����S�ȋ�`�g�ŋL�^����Ă���̂ł͖����A�݂����A�i���O�I�Ȕg�`�ŋL�^����Ă��܂��B�݂��Ă��Ă�0,1��ǂ݈Ⴆ�邱�Ƃ͂���܂��A���݂̓肩���̒��x�������ɉe����^���܂��B
���ڃ��b�s���O�͂��݂̓肩���̒��x�����Ȃ��A�������ɂȂ�̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21724512
![]() 11�_
11�_
�h���C�u��\�t�g�̐��\�ɂ����E����邻���ł��ˁB
���������f�[�^��Ō��Ă��u����̓E�\�ŁA����������悤�ɂ��������ŁA���ۂ͂���ȒP������Ȃ��v�Ɛ��Ƃ��������Ă܂�����B
�����ԍ��F21724833�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 9�_
9�_
Minerva2000����
���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B
�Ȃ�قǁA�L�^���ꂽ0,1�f�[�^�̋�`�g�݂̓���̒��x���A�����ɉe����^����̂ł��ˁB
�����āA�����炭���ڃ��b�s���O������Ƃ���Sony�̃\�t�g���D�G�ł���Ƃ������Ƃł��ˁB
�������܂��ƁAPC���b�s���O����Ȃ�A���b�s���O�\�t�g�͑I�ԕK�v������܂��ˁB
�����m�����AdBpoweramp����Ԑ��m�Ȃ悤�ł��B
�i��������dBpoweramp��EAC�̌��ʂ��r���đO�҂̏������Ƃ��Ă��܂��B
http://www.dbpoweramp.com/secure-ripper.htm�j
���ڃ��b�s���O����Ƃ���Sony�̃\�t�g v.s. dBpoweramp�Ȃ�A�ǂ��炪���D�G�Ȃ̂��Ƃ������ɂȂ�܂��ˁB�ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F21725337
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����
��CD���ڃ��b�s���O�h���R���g���[������Sony�̃\�t�g�ɉ��炩�̗D�ꂽ�d�g�݂�����\�����̂Ă���܂���B
�@���Ⴂ���Ă���悤�Ȃ̂Ő������܂��B���b�s���O�̖ړI�́ACD�ɏ������܂ꂽ���l���A�ς��邱�ƂȂ����o���̂��ړI�ł��B���ʂȎd�g�݂͂���܂���B���m�ɓǂݎ��邩�ǂ����́A�h���C�u�̐��\�ɂ����܂����A�ǂݎ��Ȃ��f�[�^���������ꍇ�͕⊮��������A���̏ꍇ�̓o�C�i������v���Ȃ��̂ʼn��������邱�ƂɂȂ�܂��B�o�C�i������v�����ꍇ�͗͂���܂���B
�o�C�i������v���������ʼn����ς�邩�ǂ����̎����ł��B�_�E�����[�h��́A
https://yahoo.jp/box/zYGHd9
�@�t�@�C�����e�͎���3�����B�i��������o�C�i�����S��v�t�@�C���j
test01
test02
test03
�@�����̕ҏW���e�̎菇�ł��B
�@test01���R�s�[����test02���쐬�A�o�C�i����v�̊m�F�ς݁B
�A���y�G�f�B�^�iAudacity�j��test01��test02��W�J���āAtest01������30sec�`60sec�̋�Ԃ�test02�����̓��ꕔ���Ɠ���ւ���test03�ŕۑ��B�i�o�C�i����v�̊m�F�ς݁j
���������e�X�g���@
�@test03�̉�����30�b��60�b�̈ʒu�ʼn���������ւ��܂����A�Ⴂ���������邩�ǂ������|�C���g�ł��B
�@����͒N�������Ă��킩��Ȃ��̂����ʂł��B�o�C�i����v�Ƃ͓��������ł��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B��̓����������I�ɐ�\�肵�Ă��A�f�[�^�͌������Ɠ����ł��B
�����ԍ��F21725352
![]() 16�_
16�_
S_DDS����
���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B
�����ł����A�ł̓o�C�i���`�F�b�N�Ȃǂ��܂肵�Ă��Ӗ��͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
�h���C�u�̐��\�ɂ����E�����Ȃ�A���ڃ��b�s���O����ɂ��Ă��ASony��Q&A�̉̃y�[�W�Ő�������h���C�u�̂�����DVR-UT24EZ���g�����ALDR-PUC8U3T���g�����ABRXL-16U3V���g�����ł������ς���Ă���\��������܂��ˁB�i����ɂ��Ă��A����Sony��Q&A�̉́u2016�N4�����݁v�ƂȂ��Ă��āA�����Q�N���O�̂��̂Ȃ̂ɁA�X�V����Ȃ��̂ł��傤���H�j
�ƂȂ�ƁA�u��ԗǂ��h���C�u���g�������ڃ��b�s���O�vv.s.�u��ԗǂ��h���C�u��dBpoweramp���g����PC���b�s���O�v�̏����ƂȂ�܂��ˁB
�ǂ��炪���ǂ����ɂȂ�̂ł��傤���H
�u����Ȃ��́A��������HAP-Z1ES�ƊO�t���h���C�u���āA�����Ŏ����Ă݂�v�ƌ���ꂻ���ł����A�����������Ă݂����������܂�����A�ǂ����������������܂��B���肢�������܂��B
�����ԍ��F21725374
![]() 7�_
7�_
�p�C������
�⑫���������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B
������HAP-Z1ES�ɑg�ݍ��܂�Ă���Sony�̃��b�s���O�\�t�g�ɗD�ꂽ�d�g�݂�����Ƃ���A����͉�����t����������C�������肷����̂ł͂Ȃ��i����Ȃ��Ƃ�������ނ���ɂȂ�j�ACD�ɏ������܂ꂽ���l��ς��邱�ƂȂ����m�Ɏ��o���\�͂ł���Ƃ������Ƃł��ˁB
�v����ɁA�u���b�s���O�\�t�g�̗D�G���Ƃ͂��̐��m���ł���v�Ƃ������Ƃł��ˁB
Sony�̃\�t�g v.s. dBpoweramp�̑Ό��ɂ��Ă��A���̐��m���̏����ł���Ƃ������Ƃł��ˁB
�����āA��萳�m�ȕ������Ȃ��A�����ǂ��͂��ł���ƁB
�u�o�C�i������v���������ʼn����ς�邩�ǂ����̎����v�A�����Ă��������܂����B
test03��30�b��60�b�̈ʒu�ʼn���������ւ�邱�Ƃ́A���ł͑S���킩��܂���ł����B
�����ԍ��F21725406
![]() 7�_
7�_
���u�o�C�i������v���������ʼn����ς�邩�ǂ����̎����v�A�����Ă��������܂����B
test03��30�b��60�b�̈ʒu�ʼn���������ւ�邱�Ƃ́A���ł͑S���킩��܂���ł����B
�@�������łȂ��A���̃f�[�^���w�̌������ŕ����I�ɕ��͂��Ă�����Ă��Ⴂ�͂킩��܂���B�S�������f�[�^���m���r���Ă���̂Ɠ����ł�����B
�����ԍ��F21725487
![]() 8�_
8�_
�p�C������
���̔g�`���炵�đS����v����Ƃ������Ƃł��ˁB
�����o�C�i���͓������̂ŁA������Đ����u�ɂ����ďo�鉹�̔g�`�������ł���B��������ŋ�ʂł���͂����Ȃ��A�����Ȃ̂�����ƁB
�������܂��Ƃ�͂�ACD�ɏ������܂ꂽ���l��ς��邱�ƂȂ��Ȃ�ׂ����m�Ɏ��o�����Ƃ̂ł���������A���ǂ����b�s���O�ł���A���ǂ����̌��ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
����́uHAP-Z1ES�{Sony�̃\�t�g�v�Ȃ̂��͂��܂��uPC�{dBpoweramp�v�Ȃ̂��H
�g���h���C�u�̖�������܂����B
�����ԍ��F21725553
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����
CD�̃��b�s���O�ł̓h���C�u�ɂ���Ă��A�\�t�g�ɂ���Ă��������ς��܂��B
����͂O�C�P�̃f�[�^�������������Ă��Ȃ����特�����ς��̂ł͂���܂���B
�ǂ̃h���C�u�ł��\�t�g�ł��A��قǏ�������CD�Ŗ�������A���L��C2�G���[�͂܂��������܂���BC1�G���[�Ȃ犮�S�ɒ�������܂��̂ŁA�O�C�P�̃f�[�^�͐��m�ɓ����܂��B
---------------------------------------
CD�ł́A�o�[�X�g�G���[�ɑΉ����邽�߁A���̃f�[�^�ɒ����p���[�h�\������������t���A������̃t���[���ɕ��U���Ă���B���̎��̃��[�h�\������������C2�����Ƃ����B
���ۂ�CD��ǂݎ���ăt���[�����̌��������s�Ȃ����A�����Œ����ł��Ȃ����Ƃ�C1�G���[�Ƃ����B���U���ꂽ�f�[�^�����̏����ɖ߂����A���̎��ɂ�C1�G���[�̃f�[�^�̍s����͊m�F�ł��Ă���̂ŁA�����C2�����Œ�������B
C2�����ł�224�r�b�g��32�r�b�g�܂ł̃G���[������ł��邪�A���������ł�����������Ȃ��ꍇ��C2�G���[�ƌĂԁB
CD-DA(���yCD)�̏ꍇ�AC2�G���[�����������ꍇ�͑O��̐���ȃf�[�^�̕��ϒl���Ƃ铙�̕��@�ɂ��A�������邱�Ƃŕ�Ԃ���B
���̂��߁A�����͗��邪�A�h�����čĐ��͂ł���B
---------------------------------------
�Ȃ����b�s���O�̃h���C�u��\�t�g�ʼn������ς�邩�́A���\�j�[�̂����Ȃ܂鎁�̉�����Q�l�ɂȂ�܂��B
[111212]
�y�Ȃ��R�s�[���邽�тɉ������ς��̂͂Ȃ��ł����B
http://kanaimaru.com/AVQA/0f.htm
���O�Ԍo�R�Ń_�E�����[�h����ƁA��L�̃l�b�g���[�N��ʂ����Ƃɂ��W�b�^�[�����_�����O�������āA���̈Ⴂ���قƂ�Ǖ�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F21725618
![]()
![]() 8�_
8�_
�����̔g�`���炵�đS����v����Ƃ������Ƃł��ˁB
�@�o�C�i������v�������ꉹ�����Đ������Ƃ��Ă��A���̔g�`�͈�v���邱�Ƃ͂���܂���B
�@�����Ɍ����ƁA�T���v�����O���ꂽ�f�W�^���f�[�^�́A����K���ɏ]���č��ꂽ���U�f�[�^�i���l�����ꂽ�f�[�^�j�Ȃ̂ŁA���ꎩ�͉̂��̔g�`�ł͂���܂���B���̃f�[�^���T���v�����O�̋K�������ƂɁADAC��ʂ���D/A�ϊ����Ă͂��߂ĉ��̃A�i���O�g�`�̐M���ɂȂ�܂��B�A�i���O�����ꂽ�d���M���́A��H��\������f�q�ɂ��e�����āA�K�������܂��B
�@�T���v�����O�f�[�^���ꏏ�ł��A�A�i���O�����ꂽ���y�M���ɂ́A�K���m�C�Y��c���̂�܂��B
�@���̃m�C�Y��c�̓^�C�����C���Ŋm�F����Ǝ��Ԏ��Ń����_���ɔ������A�������ω����Ă���A����̂��̂͂���܂���B
�@�Ȃ̂ŁADAC����o�͂��ꂽ���y�g�`+�m�C�Y+�c�̍Đ����́A�����������J��Ԃ��čĐ������Ƃ��Ă��A�����ɂ͓������ɂ͂Ȃ�܂���B�܂�A�o�C�i������v���Ă��鉹�����A10��A���ōĐ������ꍇ�A���̓s�x������m�C�Y��c�������ɉ���邽�߁A�����I�ɂ͂��ׂĈ�������ɂȂ�܂��B
�@������ׂ�ꍇ�́A�f�W�^���ƃA�i���O�̐����𗝉�������ŁA�������Ę_����Ƃ킩��₷���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21725622
![]() 12�_
12�_
�p�C������
���݂܂���A�u�����I�ɕ��́v�Ƃ����̂�g�`�̂��Ƃ��Ɗ��Ⴂ���Ă��܂����B
��DAC����o�͂��ꂽ���y�g�`+�m�C�Y+�c�̍Đ����́A�����������J��Ԃ��čĐ������Ƃ��Ă��A�����ɂ͓������ɂ͂Ȃ�܂���B�܂�A�o�C�i������v���Ă��鉹�����A10��A���ōĐ������ꍇ�A���̓s�x������m�C�Y��c�������ɉ���邽�߁A�����I�ɂ͂��ׂĈ�������ɂȂ�܂��B
�Ȃ�قǁB�ł��A�������ɂȂ�Ȃ��Ƃ��Ă��A���Ƃ��ėD������悤�ȗL�Ӎ��͐������A����10��A���ōĐ������Ƃ��ɁA�Ⴆ�u�W�Ԗڂ���ԉ����ǂ������v�Ȃ�Ă��Ƃɂ͕��ʂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���ˁB�������Ȃ���A�u�W�Ԗڂ���ԉ����ǂ������v�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�\���͂O�ł͂Ȃ��A�ɂ߂ċH�Ȃ���Ȃ��Ă��܂����Ƃ��������肷��̂��A�i���O�̕s�v�c���Ȃ̂ł��傤���H
�Ƃ���ŁA�p�C������AMinerva2000���Љ�ꂽ���Ȃ��܂邳��̉�ǂ܂�܂������H
�p�C������́A
���f�W�^���M���́A���̔g�`�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�Q�i�@�̐��l�f�[�^�ł��B�f�o�C�X��ς��ă��b�s���O�����f�[�^�ł����Ă��A�o�C�i������v���Ă���ꍇ�́A���l�̓]���~�X�͂Ȃ��̂œ����f�[�^�ɂȂ�܂��B���Ƃ��A���̃f�[�^��10000��J��Ԃ��ăR�s�[���Ă��A�ŏ��ƍŌ�̃o�C�i������v���Ă���A�f�[�^�̗i�G���[�j�͐����ĂȂ��̂ŁA���b�s���O�����o�C�i������v���Ă���Q�̃f�[�^���A�����o�H�i�ڑ��j�Ɠ����I�[�f�B�I�@��ōĐ������ꍇ�́A�������ɂȂ�܂��B
�ƌ����܂������A���Ȃ��܂邳��ɂ��ΈႤ���ɂȂ邻���ł��B�f�W�^���f�[�^�������ł��A�����Ă��ꂪ�����n�[�h�f�B�X�N��ɂ������Ƃ��Ă��A�X�g���[�W��ɂ��邻�̂�����ɂ���ĉ����ς�邻���ŁA
�����ǁA�p�P�b�g�ɂ炷���Ƃ�key�Ƃ���A���̃��x���ɃN�Z���������Ƃ͉\�Ȃ�ł��B�����킢�f�W�^���f�[�^(PCM�̌X�̒l)�͕ω����܂���̂ŁA�������ێ������킳�����ĂA���ɖ߂����@�͂���̂ł��B
�Ƃ̂��Ƃł����A�ǂ��v���܂����H
�����ԍ��F21726319
![]() 7�_
7�_
Minerva2000����
�F�X�Ƃ��������肪�Ƃ��������܂��B
C1�G���[�͒����\�Ȃ̂Ŗ��Ȃ����AC2�G���[�͒����s�\����ԑΏۂȂ̂ŗ̌����Ƃ������Ƃł��ˁB
���ǂ̃h���C�u�ł��\�t�g�ł��A��قǏ�������CD�Ŗ�������A���L��C2�G���[�͂܂��������܂���BC1�G���[�Ȃ犮�S�ɒ�������܂��̂ŁA�O�C�P�̃f�[�^�͐��m�ɓ����܂��B
�������A��Ɉ��p���܂���Illustrate�̌��ɂ��܂��ƁA
http://www.dbpoweramp.com/secure-ripper.htm
C2�G���[�͂�����x�p�ɂɋN�����Ă��āAdBpoweramp��EAC�ŁgC2 error pointer�h���I���ɂ��Ă����ƁAC2�G���[���N�������ӏ���������x���b�s���O���Č��ʂ��r����B�����āAC2���m���ƂȂ�A�h���C�u��CIRC�ɕ�Ԃ�����Ȃ�AAccurateRip�������Ă���Ȃ肷��悤�ł��B
���Ȃ݂ɁA������̃u���O�̂炩������ɂ��A
http://erijapan.blog93.fc2.com/blog-entry-51.html
iTunes�́gC2 Error Info�h�̏����g���Ă��Ȃ������ŁAiTunes�ł͏ꍇ�ɂ���Ă͂��Ȃ�s���m�ȃ��b�s���O�ɂȂ�悤�ł��ˁB
http://ch.nicovideo.jp/rgb/blomaga/ar1170756
����ȃT�C�g�������܂����B���̕��̓p�C��������Љ�ꂽWaveCompare for Windows���g���Ĕ�r����Ă��܂����AiTunes�Ń��b�s���O�������ʂ́A�I���W�i����wav�Ƃ̓o�C�i���\�I�Ɂu���Ȃ�Ⴄ�v���̂ɂȂ邻���ł��I
���������āA��͂�\�t�g�ɗD��͂���悤�ł��B�idBpoweramp��EAC����iTunes�j
�܂��A��̂炩������H���A
���\�t�g���ł́uCIRC�G���[�����v�͂��Ă��Ȃ��̂ł�����ARipping�i���̗v�͂���ς�u�h���C�u���\�v�Ȃ̂ł��B�h���C�u�̓ǂݎ�萫�\���Ⴏ��\�t�g�������x�ǂ�ł��_���Ȃ��̂̓_���ł��傤�BC1��C2�̃G���[���������CIRC�ɂ��K��Ȃ̂ō��͖������߁A�v�͌��w�I�Ȑ��\�ɂȂ�Ǝv���܂��B
��͂�h���C�u�ɂ��D��͂���悤�ł��ˁB
�炩������̂܂Ƃ߂����ɗ��Ǝv���̂ň��p���܂��ƁA�h���C�u�ƃ\�t�g�̑g�ݍ��킹�łS�̃p�^�[��������悤�ł��F
��
�E�Z�L���A���b�p�[�F����h���C�u��p�E�E�E��\��uPlexTools Professional�v
�@����m������h���C�u�ƈ�S���̂ł���Ă�̂œ���͕ۏ���邪����h���C�u�ł����g���Ȃ��B
�E�Z�L���A���b�p�[�F�ėp�h���C�u�p�E�E�E��\��uEAC�v
�@������ă\�t�g�E�F�A�ł���Ă邩�����h���C�u�ȊO�ł��@�\���邪�ۏ̌���ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�h���C�u�̃t�@�[���ɂǂ�ȃo�O�����邩����������Ȃ��B
�E�Z�L���A�Ƃ͌����ĂȂ����b�p�[�F�ėp�h���C�u�p�E�E�E��\��F�uiTunes�v
�@������u�G���[�����v��ON�ɂ���Ƃ�����Ƃ���邯�ǁA�Z�L���A���b�p�[�قǂ͂����Ȃ��i��ʓI���p�ł̗�����D�悵�Ă���Ǝv����j�B�܂��A���[�h�L���b�V���@�\������h���C�u���ƒ��߂��Ⴄ�B
�E���b�s���O���x����@�\�t���h���C�u�E�E�E��\��uPureRead�V���[�Y���ڃh���C�u�v
�@�h���C�u�̃t�@�[���E�F�A�ŏ��u�B������p���[�e�B���e�B�Ő���ł���B�t�@�[�����x���Ȃ̂�PC����I/F�K�肵�Ă��Ȃ��悤�ȏ����g�������l�ȃ��g���C�ł���B
��ɋ�����Illustrate�̃y�[�W�ł��A�Â�Plextor�̃h���C�u���AMatsushita��NEC�̃h���C�u���D��Ă���ƌ�����Ă��܂��B���Ȃ��܂邳����A�u�Â��v���N��TEAC�̃h���C�u���������悢�̂͗L���ł��v�ƌ����Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F21726328
![]() 7�_
7�_
���Ȃ��܂邳��́u[111212]�y�Ȃ��R�s�[���邽�тɉ������ς��̂͂Ȃ��ł����B�v�ɑ���́A�����[���ł��B
���f�W�^������1��0��������܂��A���ۂ̋L�^�͂ӂɂ�ӂɂ�ȃA�i���O�̔g�`�ŏo���Ă��܂��B�ǂݏo���Ƃ��ɁA������x�ȏ�̓d����1�A������x�ȉ���0�Ƃ��邾���ł��B�ӂɂ�ӂɂ�Ƃ́A1�ƋL�^�������̂́AHDD��ł�1�ł͂Ȃ��āA����O�a�l��1�Ƃ�����A0.7�`1.0���炢�ɋL�^����Ă���Ƃ������Ƃł��B0�ƋL�^�������̂�0�`0.3���炢�ł��傤���B�����0.5���炢�ŏォ�����Ŕ��肷��A�����Ƃ��Ă͂��Ƃɖ߂�܂��B
�����Minerva2000����̂��w�E�̂��ƂƏd�Ȃ�܂��ˁB
���Ƃ��낪�A����0����1�A1����0�֔��]����^�C�~���O�́A���̃A�i���O�̓ǂݏo�����g�`���ア�ƁA�O���O���Ǝ��ԓI�ɑO��ɗh��܂��B�h��Ă��ǂݏo���^�C�~���O�܂łɂ͕K�����肵�܂��̂�(�����Ȃ�悤�ɃT�[�{�n�����삵�Ă��܂�)��͂萔���͊ԈႢ�܂���B�Ƃ��낪�g�`�����]����Ƃ��ɂ͓d���ɃX�p�C�N�m�C�Y������܂��B�g�`���O���O���h��Ă���ƁA���]�m�C�Y���o��^�C�~���O���O���O���ɂȂ�܂��B���ꂪ��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�Ɖ������Q���܂��B�܂��R�s�[���͌��ɔ�ׂ�Ɨh�ꂪ�����Ȃ�̂ŁA�������ς���čs��(��ʓI�ɂ͗��čs��)�̂ł��B
�����������̂Ȃ�ł��傤���I
���̎w�E���d�v�ł��F
����ʓI�Ƀf�W�^���f�[�^���������悢�̂́ACD����̃��b�s���O�ł͓ǂݏo��������ł��B�h���C�u���Ƃ��Ɏw�ߗp�Ɏg�������C���Y��ȃN���b�N��HDD�ɂ��͋����L�^����邩��ł��B�Ƃ��낪������R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���̂ŁA�������ς��̂ł��B
���ꂪ��������A�������Ɂu�gCD���ڃ��b�s���O�h�̉���PC���b�s���O�̉��ɗD��v�Ƃ����p�c��Y�������̎咣���������ꍇ�ɂ́A���̗��R�Ƃ��Ĉȉ��̉�������������܂��F
�u�gCD���ڃ��b�s���O�h�́ACD����ǂݏo���ꂽ�f�[�^���AHAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɁA���C���Y��ȃN���b�N�Œ��ڗ͋����L�^�����̂ʼn����ǂ��BPC���b�s���O�́A�f�[�^��HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɂQ���I�ɃR�s�[�����̂ŗ��B�v
�����������Ƃ����蓾��ȂƂ����C�����ɂȂ��Ă��܂��B
�������A���̋L�q���C�ɂȂ�܂��F
�������������Ȃ��Ă��܂����ꍇ�A������@������܂��B����̓l�b�g���[�N��ʂ����Ƃł��B�l�b�g���[�N�̓p�P�b�g�ʐM�Ȃ̂ŁA�A���g�`����x�����̌ł܂�Ƀo���o���ɂȂ�܂��B�܂��l�b�g���[�N�͒ʏ�ǂݏo�������N���b�N�������Ă��܂��̂ŁAHDD�ɏ������ނƂ��Ƀt���b�V���ȃN���b�N���g���܂��B
�Ƃ���APC���b�s���O�ł��A���̃f�[�^���iUSB�ڑ��ł͂Ȃ��jLAN��ʂ���HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɏ������܂��̂ł���A�t���b�V���ɏ������܂��̂ł���ł����̂ł͂Ȃ����H
����ɁA��xWAN���o�R����Ɗ��S�Ƀt���b�V���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��ˁB
�܂��܂��A���ڃ��b�s���O��PC���b�s���O�A�ǂ���̕����D��Ă���̂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�����ԍ��F21726337
![]() 7�_
7�_
���Ȃ��܂鎁�̓\�j�[�ɍݐЂ��Ă���v���̋Z�p�҂Ȃ̂ŁA�g���Ă���@�ނ�P�[�u���ނ̃��x������ʃs�[�v���Ƃ͈Ⴄ�Ǝv���܂��B
����͂��Ȃ��܂鎁�̃z�[���y�[�W�ɂ��Ƃ���ǂ���ɏ����Ă���܂��B�ׂ��ȃA�N�Z�T���[�ɂ����Ă��������ᖡ���������Z���N�g���Ďg���Ă����
����ɔ�ׂĂł����A�]�_�Ƃ̊p�c���͍��x�ł͂��邯�ǃA�}�`���A���x���̈���Ȃ��������ł̔��f�Ȃ̂ŁA���Ȃ��܂鎁�ƈӌ����H���Ⴂ�̂��d�����Ȃ����Ǝv���܂�
�ȒP�ɏ����ƁA�����]���Ɏg���ׂ�LAN��H�Ɏg���Ă��郋�[�^�[��X�C�b�`���O�n�u��LAN�P�[�u���̎����Ⴄ�낤�Ƃ������Ƃł���
�����ԍ��F21726484�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��Symbolist_K����
C2�G���[�����o���Ȃ������G���[��C2�G���[�ƌĂт܂��B����܂�EAC�ő��ʂ�CD�����b�s���O���Ă��܂������AC2�G���[�����͈ꖇ��CD��10����x�N���������Ƃ͂���܂����AC2�G���[�̌o���͖����ł��B�܂�0�A1�̃f�[�^�͊����Ƀ��b�s���O�o���Ă��܂����B
����C2�G���[��10��N������WAV�t�@�C�����Đ����Ă��A�ǂ��Ő��`��Ԃ������͒N��������Ȃ��ł��傤�B�܂艹���͕ς��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
1�A2m�̃C�[�T�l�b�g�P�[�u����ʂ������炢�ł̓W�b�^�[�����_�����O�͏o���܂���B�N���E�h�ւ̃A�b�v���[�h�ƃ_�E�����[�h���s���K�v������܂��B
�����ԍ��F21726506
![]() 10�_
10�_
��Symbolist_K����
������ȃT�C�g�������܂����B���̕��̓p�C��������Љ�ꂽWaveCompare for Windows���g���Ĕ�r����Ă��܂����AiTunes�Ń��b�s���O�������ʂ́A�I���W�i����wav�Ƃ̓o�C�i���\�I�Ɂu���Ȃ�Ⴄ�v���̂ɂȂ邻���ł��I
�@
�@����͑z���ł����A�������b�s���O��������̓o�C�i�����S��v�Œ��o���Ă邯�ǁAitunes�ŕۑ�������Ƃ��ɁA���������i�m�C�Y�V�F�C�r���O�j�����������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B
�@�A�b�v�}�̇C�͉��y�G�f�B�^���g���ĕۑ�����Ƃ��ɁA�f�B�U�����O�������I���ɂ��ăm�C�Y�V�F�[�r���O�������ĕۑ������ꍇ��FFT�i�����t�[���G�ϊ��O���t�j�ɂȂ�܂��B
�@���̏���������ƒ��o�ɕq���Ȓ�����ɑ��݂���m�C�Y�t���A�������邱�Ƃ��ł���̂ŁA�N���A�ȉ����ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B�o�C�i���͓��R��v���Ȃ��̂ŕ����I�ɂ͗ɂȂ�܂����A���o�I�ɂ̓N���A�ȉ����ɂȂ�܂��B
�@�Ȃ̂ł����ۑ����邾���̃\�t�g�Ɣ�ׂ�ƁA���Ԃ�ǂ����i�N���A�ȉ��j�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������̗\�z�������Ă���̂Ȃ�A�������l�ԍH�w���n�m���Ă���A�b�v���Ƃ��������ł��B
�@
�����ԍ��F21727215
![]() 10�_
10�_
�L����u���O�ł͂b�c���ڃ��b�s���O�ł͂Ȃ��uWAV�t�@�C���v�̉����������ď����ĂȂ��H�@HAP-Z1ES�ł�WAV�t�@�C���Ƀ^�O�Ƃ����O�Ƃ����ĊǗ����₷���Ƃ��B���͂��s���������g���Ă邯�lj��y�f�[�^�͂��ׂ�WAV�Ńt�@�C���̖��O��ύX���ĊǗ����Ă��邩�牽�̊W���Ȃ����ǂˁB����R�s�[������Ƃ��A�f�[�^����v���Ă���Ƃ��Ȃ�Ƃ��A���������b���Ⴄ�C������BWAV�t�@�C����HAP-Z1ES�Ȃ�֗��Ɏg���܂���B���ꂪ���̌`����艹�������ł���B�����������Ƃ������Ă��邾���Ƃ��ƁE�E�E�E
�����ԍ��F21727660
![]() 3�_
3�_
MAX���O�Y����
�������ɁA���Ȃ��܂鎁�͂悢�@�ނ����g�������m��܂��A
LAN�P�[�u���̓J�e�S���[6��SAEC SLA-500���g���A
http://kanaimaru.com/NWA840/008.htm
USB�P�[�u����SUPRA USB2.0�𐄏�����Ă��܂����A����Ȃɍ����ł͂���܂���B
http://kanaimaru.com/NWA840/009.htm
LAN�n�u�ɂ��Ắu�I�[�f�B�I�p�̃n�u�����݂��Ȃ��v�ƒQ����Ă��܂��B
�d���^�b�v�Ȃǂ́A���́u���Ȃ��܂鎮�^�b�v�v�������ɂ������ō���Ă��܂��܂��B
http://kanaimaru.com/NWA840/004.htm
�Ȃ̂ŁA����Ȃɂ������ꂽ���ł͂Ȃ��̂ŁA�����̎Q�l�ɂ܂������Ȃ�Ȃ��Ƃ��������Ƃ͑S�R�Ȃ��Ǝv���܂��B
�����āA�����������܂����̂́A�p�c��Y���̎咣�����Ȃ��܂鎁�̗��_���x��������Ƃ������Ƃł����B�i��l�̈ӌ��̐H���Ⴂ�ɂ��Ă͐G��Ă��܂���B�j
�J��Ԃ��܂��ƁA�p�c��Y���́u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̉���PC���b�s���O�̉��ɗD��v�ƌ�����B���̗��R�́A���Ȃ��܂鎁�̗��_�����p����A���̂悤�ɐ���������F
�gCD���ڃ��b�s���O�h�́ACD����ǂݏo���ꂽ�f�[�^���AHAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɁA���C���Y��ȃN���b�N�Œ��ڗ͋����L�^�����̂ʼn����ǂ��BPC���b�s���O�́A�f�[�^��HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɂQ���I�ɃR�s�[�����̂ŗ��B
�d�d�d�Ƃ����̂����̉����ł����B
�Ƃ����Ă��A�ق�Ƃ��ɁgCD���ڃ��b�s���O�h�̉������̂悤�ɗǂ��̂��ǂ����́A���ۂɒ�����ׂĂ݂Ȃ����Ƃɂ́A���ɂ͉��Ƃ������Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F21728356
![]() 8�_
8�_
Minerva2000����
���w�E���肪�Ƃ��������܂��B
C2�G���[�́A10����x�N�������Ƃ���ʼn����ɂ͉e���Ȃ��̂ł��ˁB
����ł�����A�Ƃ肽�Ă�dBpoweramp���̗g������A�v���N�X�^�[�̃h���C�u��T�����肷�邱�Ƃ��Ȃ��̂�������܂���ˁB
�u�W�b�^�[�����_�����O�v!�@�����1�A2m�̃C�[�T�l�b�g�P�[�u����ʂ������炢�ł͂ł��Ȃ��̂ł��ˁB�i���̂Ƃ����10m���炢�͂���܂������j
���N���E�h�ւ̃A�b�v���[�h�ƃ_�E�����[�h���s���K�v������܂��B
�ł́A�y�Ȃ̃t�@�C�����A��UGoogle Drive�Ƃ�Microsoft OneDrive�Ƃ�iCloud�Ƃ��ɏグ�āA�������璼��HAP-Z1ES�ɏ������߂悢�̂ł��ˁI
��������A���Ȃ��܂鎁��������悤�Ɂu�N�Z�������v���Ƃ��ł���̂ł��ˁB��������A�����炭�́g���ڃ��b�s���O�h�ŏ������܂ꂽ���̂ɑ��F�Ȃ��悤�Ȍ��C���Y��Ȏp�Ńn�[�h�f�B�X�N��ɑ��݂���悤�ɂȂ�̂ł��傤���H
�����ԍ��F21728369
![]() 7�_
7�_
�p�C������
��������肪�Ƃ��������܂��B
�����ł����AiTunes�̓��b�s���O��Ƀm�C�Y�V�F�[�s���O�����������Ă���̂ł����B�����Ă��N���A�ȉ��ɂȂ��Ă���ƁB
����Ȃ�A�uiTunes�͐��m���ɖ�肪����̂Ń��b�s���O�\�͂͗���Ă���v�ƌ��߂����O���͓P�����܂��BiTunes�ɂ͓Ǝ��̗ǂ�������ƔF�߂܂��B
�������A�m�C�Y�V�F�[�s���O���āAAAC�Ȃǂ̈��k���������Ƃ��Ɏg������̂ł���ˁB���Ƃ��ẮA���b�s���O�̓��b�s���O�����ɂ��ė~�����A���Ƃ��N���A�ȉ��ɂ��鏈�����Ƃ��Ă��A���b�s���O�Ƃ����s�ׂ͈͓̔��ʼn����ɑ��ď���ɏ������ė~�����Ȃ��ł��B���̏���������������A���b�s���O�͂ł��邾�����m�ɍs���Ă�����āA���̌��ʂɑ��ĕʂ̃\�t�g�łȂ�ADAC�łȂ�ł�����悢�̂ŁAiTunes�ɂ̓��b�s���O���z��������Ȃ��Ƃ͂�߂Ă������������B
�Ƃ����킯�ŁA���͂�͂�PC���b�s���O�ɂ�dBpoweramp���g���܂��B
�����ԍ��F21728402
![]() 9�_
9�_
��Symbolist_K����
�Y��Ȕg�`�ŏ������ނɂ̓h���C�u��\�t�g�̑I�����d�v�ł��ˁB
�W�b�^�[�����_�����O�Ńh���C�u��\�t�g�̃N�Z�͎���ł��傤�BJS PC AUDIO����I�[�f�B�I�p��HUB����������Ă��܂��B
�����ԍ��F21728421
![]() 8�_
8�_
�Ɠd��D���̑�コ��
���̍ŏ��̎���Ɉ��p���Ă���܂��悤�ɁA�p�c��Y�����n�߂Ƃ�����l���̕����A�u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̉���PC���b�s���O�̉��ɗD��v�Ƃ�����|�̂��Ƃ�������Ă��܂��B
�����ɁA�t�@�C���`����WAV�������ǂ��Ƃ������������ł��ˁB���p�����p�c��Y���̃I�[�f�B�I�]�_�́A�uCD���ڃ��b�s���O������WAV�t�@�C���̉����������ǂ��v�Ƃ����b�ł�������A�����ł��ˁB
WAV�̉��ɑ���FLAC�̉��͓����Ȃ̂����̂��B�����kFLAC�Ȃ�ǂ����B�����͎��͂܂����ؒ��ŁA���_�Ɏ����Ă��܂���B
WAV�̕������炩�ɉ����ǂ��Ƃ����l������A��ʂ����Ȃ��Ƃ����l�����āA�u���C���h�e�X�g�Ȃǂ����Ă݂Ȃ����Ƃɂ͌���ł��܂���B
�������ɁAHAP-Z1ES��WAV�ɑ��Ă���肭tag���^�p���Ă����悤�ł����A���X�ςɂȂ�����A�J�^���O���č\�z����ƕ��ꂽ�肷��Ȃǂ̕����邵�A�܂�HAP-Z1ES����G�N�X�|�[�g������ł͏�肭�����ۏ��Ȃ��̂��S�z�ȓ_�ŁA������WAV�Ȃ̂�FLAC�Ȃ̂��̍l���ޗ��ł��B
�����ԍ��F21728490
![]() 7�_
7�_
Symbolist_K�����
���p�c��Y�����n�߂Ƃ�����l���̕����A�u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̉���PC���b�s���O�̉��ɗD��v�Ƃ�����|�̂��Ƃ�������Ă��܂��B
����A�Ȃ�̂��Ƃ������Ă���̂��C�}�C�`�킩��Ȃ��̂����ǁA�o�b���g�����ƂȂ����ڃ��b�s���O�ł���@�\��L����o�[�h�Ɍ��肵���b�ł��傤���H�@�Ⴆ�A�`�Ƃ����@��Ń��b�s���O�����f�[�^���a�Ƃ����@��ōĐ�������A�`�̋@��͂o�b�ƕς��Ȃ��Ȃ�܂���ˁB����Ă邱�Ƃ͂����������Ƃł�����B����ł`�̋@��Ń��b�s���O�����f�[�^���`�̋@��ōĐ������Ƃ������������łȂ�Ƃ�����A����͒P�̂̃n�[�h�̒��̘b�Ȃ̂łȂ�Ƃł��Ȃ�܂���B�ǂ̂悤�ɗL���ȉ��ςł��ł���ł��傤�B���Ƃ��Ă͂Ȃ�̖��ɂ������Ȃ��ł��ˁB����ɂ����Ă��邾���̐��E�ł��B
�p�c��Y���̋L���ł����A�Љ��Ă��鉹���Ɋւ��ẮAWAV�ƂȂɂ��r���ėD��Ƃ��Ă��܂����H�@PC���烊�b�s���O��������WAV�f�[�^�Ɖ������r�����Ƃ����L�q���L���ɂ͏�����Ă��܂���B�u�Ƃ�����|�̂��Ɓv�Ƃ����̂͋�̓I�Ȃǂ�Ȍ��ł����H�@�قƂ�njl�̎�ςƊ��z�ɉ߂��Ȃ��ƌ����܂����A����Ȃ玩���ł���Ċm�F����ȊO�ɂ�邱�Ƃ͂Ȃ��ł���B
�����ԍ��F21728545
![]() 3�_
3�_
Minerva2000����
���Y��Ȕg�`�ŏ������ނɂ̓h���C�u��\�t�g�̑I�����d�v�ł��ˁB
�ł���ˁB����ς�\�t�g��dBpoweramp���g���A����PC�̃h���C�u�̓K�^�����Ă���̂œK�Ȃ��̂Ɋ������邱�Ƃɂ��܂��BPC���b�s���O�Ɋւ��ẮB
�����āA���ڃ��b�s���O�͂��ׂ��Ȃ̂��A���Ȃ��Ă��悢�̂��A���ꂪ���ł��B
���W�b�^�[�����_�����O�Ńh���C�u��\�t�g�̃N�Z�͎���ł��傤�B
�uPC���b�s���O�����t�@�C���̓N���E�h�o�R��HAP-Z1ES�ɓ���邱�Ɓv�[����A���Z�ɂȂ�܂��ˁI
���̋Z���g���A�N�Z�������Ă����v�I��
��JS PC AUDIO����I�[�f�B�I�p��HUB����������Ă��܂��B
http://jspcaudio.net/np/20170920/
����ł��ˁI 59,400�~�I
����͂ǂ��Ȃ�ł��傤���H �ق�Ƃ��ɉ����ǂ��Ȃ�n�u�Ȃ̂ł��傤���H �d������͗ǂ������ł����B
�u�L�b�g�̔��v�Ƃ����̂��Ђ�������܂��B�u�Ō�̃r�X����߂邾���ł���v�ƌ����Ă����āA����PSE�}�[�N�̎擾���ȗ��������ӔC��������Ă���悤�Ɍ����܂��ˁB���̉�ЁA�m��܂��A�M���ł��郁�[�J�[�ł��傤���H
������I�[�f�B�I�p��HUB�������܂����F
WaversaSystems�́uWSmartHub�v!�@148,000�~�I
http://www.oliospec.com/shopdetail/000000004482/
�ǂ��Ȃ�ł��傤���H �͂����Ă���ʼn��͗ǂ��Ȃ�̂��I�H
�����ԍ��F21728596
![]() 7�_
7�_
�Ɠd��D���̑�コ��
�`�̋@��Ń��b�s���O�����f�[�^���`�̋@��ōĐ����������A�a�̋@��Ń��b�s���O�����f�[�^���`�̋@��Ɉڂ��čĐ������肢�������ƌ����Ă���Ƃ����b�ł��B�`��HAP-Z1ES���Ƃ��āB
���p�c��Y���̋L���ł����A�Љ��Ă��鉹���Ɋւ��ẮAWAV�ƂȂɂ��r���ėD��Ƃ��Ă��܂����H�@PC���烊�b�s���O��������WAV�f�[�^�Ɖ������r�����Ƃ����L�q���L���ɂ͏�����Ă��܂���B
�������ɁAPC���烊�b�s���O��������WAV�f�[�^�Ɖ������r�����Ƃ͏�����Ă��܂���B�������A�u����HAP-Z1ES��CD���b�s���O�����W���j�E�~�b�`�F���wMingus�x��WAV�t�@�C���̉����������ǂ��v�Ƃ���A����܂ł�CD���ڃ��b�s���O�͂��Ă��Ȃ��āA���߂Ă�������Ă݂Ă̊��z���q�ׂĂ��镶���̒��ł́A���܂�t�@�C���`���ɏd���͒u����Ă��炸�A�p�����[�^�[�̓��b�s���O���@�Ȃ̂ł����āA�����CD���ڃ��b�s���O�ɂ���Ă��̉��̗ǂ����o�����Ƃ��������Ă��邱�Ƃ͎����ł��B�����āA�u���̓����x���オ��A�I�[�v���`���[�j���O�̃M�^�[��W���R�E�p�g���A�X�̃����@�[���̌������x�[�X�̋������N�₩���B�W���j�E�~�b�`�F���̔����Ȑ��g�����N���ɂȂ�A���y�S�̂̃��A���e�B�[���������v�Ƒ����܂����A���Ɣ�ׂāu���̓����x�����オ�聄�v�A�u�����Ȑ��g�������N���ɂȂ聄�v�A�u���y�S�̂̃��A���e�B�[�������������v�Ɗp�c���������Ă���̂��ƌ����A����܂ł̃��b�s���O���@�ɂ����̂Ɣ�ׂĂł��邱�Ƃ͖��炩�ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ꂪ�p�c���̌l�̎�ςƊ��z�ɉ߂��Ȃ����Ƃ͌����ɑ҂����A���ƌĂт��錵�����Ȃǂ���܂���B
�ŏI�I�ɂ͎����̎��Œ����Ă݂Ċm���߂邵���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂킩���������ŁA���������Ē�����ׂĂ݂������������������犴�z�����������������Ƃ��肢���Ă���̂ł���B
�����ԍ��F21728650
![]() 7�_
7�_
Symbolist_K����A�����́B�����������ʂ����m��܂��A��Âɍl���Ă݂܂��傤�B
���̒��ɂ͑吨�̐l�����܂�����A�u���ڃ��b�s���O�v���uPC�o�R�v��艹���ǂ��Ǝ咣����l�͂��ē��R�ł��B���������l�͐F�X�ȓ��@�ő傰���ɏ������Ă܂�����A���ׂ�����������L���Ƀq�b�g����̂��܂����R�ł��B
����A�킴�킴�u�ς��Ȃ��v�Ɛ����ɋ��Ԑl���āE�E�E���邩���m��܂��A���̓��@���قƂ�ǂ���܂���B�������Ƃ��āu�ʎ��v�ƌ��������܂ŁB�u�ς��v�Ƃ��������͋��͂Ȃ킯�ł��B
���������\���̒��ŁA�O�҂̌�������M���āu���ڃ��b�s���O�v���ǂ��ƌ��_����̂͂������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�t�F�C�N�j���[�X���������Ă���̂͂����m�̂Ƃ���B
����Symbolist_K���I�[�f�B�I�ł��т�H�ׂ�ƊE�W�ҁi���[�J�[�̋Z�t�A�]�_�ƁA�ƊE�T�C�g�W�ҁA�ꕔ�M�ҁj�̗��ꂾ������H�ƍl����킩��₷���ł��B�ނ�����̉s�����ƂƎv�����A�����▼�_���������Ă���l�Ǝv�����B�����ăI�[�f�B�I�]�_�̓v�����Ƃ��Ă��A�u�n�[�h�f�B�X�N�Ɍ��C���Y��ȃN���b�N�Œ��ڗ͋����L�^�����̂ʼn����ǂ��v�Ƃ����̂͂����ɂ��f�l���x���̉����ł��B�n�[�h�f�B�X�N�Z�p�҂��������畬�ѕ��ł́B�����Ƃ��A����SSD���낤�������b���J��Ԃ����̂ł��傤�B
���̃X���b�h�ł��F�X�u�����v���o�ꂵ�Ă��܂��B�Ȋw�҂������ł��Ȃ����ۂ�f�l���������Ă��܂��̂��I�[�f�B�I�̃X�S���g�R���ł��B���A
>������ׂĂ݂������������������犴�z�����������������Ƃ��肢���Ă���
�Ƃ̂��Ƃł����ˁB���炵�܂����B���̂Ƃ��낻�������l�͂��Ȃ��悤�ł����A���̌��l��l�o�Ă����炻���M����̂ł��傤���B�����m�̒ʂ艹���̎�ϓI��r�A���ɋL���ɗ��������́A�͂����ւ��܂������܂��B���̑傫�Ȍ덷�ɑ��āA���҂���鉹���̍��́i���ɂ������Ƃ��āj��r�ɂȂ�Ȃ��قǏ������ƍl����̂����R���Ǝv���܂����B
�����ԍ��F21728693
![]() 11�_
11�_
���uCD���ڃ��b�s���O�h�̉���PC���b�s���O�̉��ɗD��v
�Ƃ��������ł����A�o�C�i������v�����t�@�C���͓���̂��̂ɂȂ�̂ŁA���ڃ��b�s���O�����ق��������ǂ��Ȃ�āA�����I�ɂ��肦�܂���B�Ȃ̂ŁA�Ɠd��D���̑�コ��̂��w�E�̂Ƃ��肩�Ǝv���܂��B
�@�Ⴆ��100���~��CD�h���C�u�Ń��b�s���O�����f�[�^�ƁA1980�~�̗����łʼn��x�����g���C���Ȃ��烊�b�s���O�����f�[�^���L�����Ƃ��āA�o�C�i�����r�������v���Ă����ꍇ�A�g�p�����h���C�u��\�t�g�̐��\������ɂ�炷�A�Ȃ��̓����t�@�C���ɂȂ�̂ŁA���ڃ��b�s���O��������Ƃ��A���̉ߒ��͑S���W����܂���B���ꂪ�f�W�^���f�[�^�ł��B
�@�����Ɋւ��̂�DA�ϊ����Ă���̘b�ɂȂ�܂��B
�@���Ȃ݂ɉ����f�[�^�͐�����1��0�̐����݂̂ŏ������܂�Ă���̂ŁA1.01�Ƃ�1.3�̂悤�ȕ��������_�̐����͏������߂܂���B�Ȃ̂Ńf�W�^���̏ꍇ�̓o�C�i������v�������_�ŁA����2�̃t�@�C���̋�ʂ͂Ȃ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F21728705
![]() 14�_
14�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B
���͎����ė�ÂȂ���ł����A���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�����������\���̒��ŁA�O�҂̌�������M���āu���ڃ��b�s���O�v���ǂ��ƌ��_����̂͂������Ȃ��̂�
�܂���������������̂́A���͂܂��������_�Â��Ă��܂���B���낢��Ȉӌ����t���āA�\����T���Ă���i�K�ł���A����̗����M���Ă���킯�ł͂���܂���B�����������̏������݂Ŋp�c��Y����i�삷��悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����A����͂��̑O�ɓ����Ȃ��Ɋp�c��Y���̎咣��ے肷������������������̂ŁA���͋t�ɂ��̐l�ɑΘ_���o���Ă݂��̂ł��B����ɑO�ɂ́A���͊p�c��Y���ɑ��ĉ��^�I�ȗ�����Ƃ��Ă��܂�����B�v�l���������Ă��邾���ł��B
������A�킴�킴�u�ς��Ȃ��v�Ɛ����ɋ��Ԑl���āE�E�E���邩���m��܂��A���̓��@���قƂ�ǂ���܂���B
�����ł��傤���H �u�ς��v�Ǝ咣����l�ɑ��āA���Ⴀ�u���C���h�e�X�g�ł��킩��ȁA�ƃe�X�g�����v���āA�L�Ӎ����F�߂��Ȃ������ꍇ�ɁA�u�ق�A�ς��Ȃ�����Ȃ����v���Đ����ɋ��Ԑl�Ƃ��悭���邶��Ȃ��ł����B
�������ăI�[�f�B�I�]�_�̓v�����Ƃ��Ă��A�u�n�[�h�f�B�X�N�Ɍ��C���Y��ȃN���b�N�Œ��ڗ͋����L�^�����̂ʼn����ǂ��v�Ƃ����̂͂����ɂ��f�l���x���̉����ł��B�n�[�h�f�B�X�N�Z�p�҂��������畬�ѕ��ł́B
�ł��A�f�l����Ȃ���ł���A���̕��́B���Ȃ��܂邱�Ƌ��䗲���������m����܂��H ���\�j�[�z�[���G���^�e�C�������g���Ɩ{��HAV�������v���劲�Z�t�ł��BTA-DA3600ES��STR-DN2030�Ƃ�����AV�A���v�̐v�����ꂽ���ł��B��ՁE��H�v�A�e�����̂̑I�肩��A�n���_�̎��܂ŁA�����邱�Ƃɂ������l�ł���B�l�b�g���[�N�̋Z�t�ł�����܂��B�n�[�h�f�B�X�N�̒��g����ɂ��āA�m��Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂�����ǁB���̔ނ��A
����ʓI�Ƀf�W�^���f�[�^���������悢�̂́ACD����̃��b�s���O�ł͓ǂݏo��������ł��B�h���C�u���Ƃ��Ɏw�ߗp�Ɏg�������C���Y��ȃN���b�N��HDD�ɂ��͋����L�^����邩��ł��B�Ƃ��낪������R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���̂ŁA�������ς��̂ł��B
�Əq�ׂ��Ă���̂ŁA���͂���HDD�̐������gCD���ڃ��b�s���O�h�̃J�M������̂ł͂Ȃ����ƂӂƎv���������̂ł���B�ʂɔނ����������ŐM�p���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�t�ɋ��䗲���ɔ��_����悤�Ȑ��I�ȃm�E�n�E�����͎������킹�Ă��܂���B�ނ̐��ɏ���Ă݂ẮA������v�l�����ł��B
�����̂Ƃ��낻�������l�͂��Ȃ��悤�ł����A���̌��l��l�o�Ă����炻���M����̂ł��傤���B
����́u�ǂ��Ȃ�h�v�Ɓu�ς��Ȃ��h�v���ǂ����������œo�ꂳ��邩�ɂ��ł��傤�B�u�ǂ��Ȃ�h�v��������A�u�\���͂Ȃ��͂Ȃ��v�Ǝv���悤�ɂȂ�ł��傤�ˁB�����Ă���Ȃ�Ύ����̎��Ŋm���߂Ă݂悤���A�ƂȂ闬��ł��傤���B
�u�ς��Ȃ��h�v��������A���邢�͒N���o�Ă��Ȃ���d�d�d����ł���邩������Ȃ����A����Ȃ���Ȃ���������܂���B�\���܂����悤�ɁA�ŏI�I�ɂ͎����̎��Œ����Ă݂Ċm���߂邵���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂킩���������ł̂킪�܂܂Ȃ��肢�ł�����B
�������̎�ϓI��r�A���ɋL���ɗ��������́A�͂����ւ��܂������܂��B���̑傫�Ȍ덷�ɑ��āA���҂���鉹���̍��́i���ɂ������Ƃ��āj��r�ɂȂ�Ȃ��قǏ������ƍl����̂����R���Ǝv���܂����B
�g���W������܂���ˁB�ǂ�Ȃɏ������Ă��A����������Ȃ�ΒNj����悤�Ƃ����̂��I�[�f�B�I�̃��}�����Ⴀ��܂��I
�����ԍ��F21728726
![]() 10�_
10�_
�����Ȃ݂ɉ����f�[�^�͐�����1��0�̐����݂̂ŏ������܂�Ă���̂ŁA1.01�Ƃ�1.3�̂悤�ȕ��������_�̐����͏������߂܂���B
�������ԈႢ�ȂƎv���܂�
�u�������ށv�Ƃ����\�����g������ɂ́u�������߂�}�́v���w���Ă���̂ł����āA����͂����ł�HDD�̎����w���Ă���Ɨ������܂����A��������HDD��0��1�Ƃ����L�����̂��̂͋L�^����Ă͂��Ȃ��ł�
0��1�Ƃ������L���Ƃ������̂́AHDD����o��d�C�M����ǂݎ�������PC�����f���Ă��邾���ł�
�f�l�̋Y�ꌾ�Ȃ̂ł��Ă�킩�Ɂ`
�����ԍ��F21728737�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
�p�C������
�����ŏ��͂����v���Ă���ł���B�f�[�^��1��0�̐����݂̂ŏ������܂�Ă���̂ŁA�o�C�i������v����t�@�C���͂��Ȃ킿�����t�@�C���ł���A������Đ����������ς��Ȃ��ƁB
�ł��AMinerva2000���Љ�ĉ����������Ȃ��܂鎁�̋L���ihttp://kanaimaru.com/AVQA/0f.htm�j��ǂނƁA�����o�C�i���ł��n�[�h�f�B�X�N��ɂ��邻�̂�����̈Ⴂ�ʼn����ς��Ə����Ă�������ł���B��������A�ς��ꍇ�̉����Ɏ���܂����B
���Ȃ��܂鎁��������x���p���܂��F
���f�W�^������1��0��������܂��A���ۂ̋L�^�͂ӂɂ�ӂɂ�ȃA�i���O�̔g�`�ŏo���Ă��܂��B�ǂݏo���Ƃ��ɁA������x�ȏ�̓d����1�A������x�ȉ���0�Ƃ��邾���ł��B�ӂɂ�ӂɂ�Ƃ́A1�ƋL�^�������̂́AHDD��ł�1�ł͂Ȃ��āA����O�a�l��1�Ƃ�����A0.7�`1.0���炢�ɋL�^����Ă���Ƃ������Ƃł��B0�ƋL�^�������̂�0�`0.3���炢�ł��傤���B�����0.5���炢�ŏォ�����Ŕ��肷��A�����Ƃ��Ă͂��Ƃɖ߂�܂��B������HDD���������ǂݏo�����Ƃ��̔g�`�͂��Ȃ����Ȃ��̂ŁA��������̂������傫���������܂��B���������0��1�ɒ�����܂�����A�f�W�^���ɂȂ�킯�ł��B
���Ƃ��낪�A����0����1�A1����0�֔��]����^�C�~���O�́A���̃A�i���O�̓ǂݏo�����g�`���ア�ƁA�O���O���Ǝ��ԓI�ɑO��ɗh��܂��B�h��Ă��ǂݏo���^�C�~���O�܂łɂ͕K�����肵�܂��̂�(�����Ȃ�悤�ɃT�[�{�n�����삵�Ă��܂�)��͂萔���͊ԈႢ�܂���B�Ƃ��낪�g�`�����]����Ƃ��ɂ͓d���ɃX�p�C�N�m�C�Y������܂��B�g�`���O���O���h��Ă���ƁA���]�m�C�Y���o��^�C�~���O���O���O���ɂȂ�܂��B���ꂪ��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�Ɖ������Q���܂��B�܂��R�s�[���͌��ɔ�ׂ�Ɨh�ꂪ�����Ȃ�̂ŁA�������ς���čs��(��ʓI�ɂ͗��čs��)�̂ł��B
�p�C������Ȃ�A���̋L�q���ǂ��ǂ܂�܂����H
�����ԍ��F21728742
![]() 7�_
7�_
MAX���O�Y����
����A����Y�ꌾ���Ⴀ��܂����I
���u�������ށv�Ƃ����\�����g������ɂ́u�������߂�}�́v���w���Ă���̂ł����āA����͂����ł�HDD�̎����w���Ă���Ɨ������܂����A��������HDD��0��1�Ƃ����L�����̂��̂͋L�^����Ă͂��Ȃ��ł��B0��1�Ƃ������L���Ƃ������̂́AHDD����o��d�C�M����ǂݎ�������PC�����f���Ă��邾���ł��B
���̏������݂ň��p�������Ȃ��܂鎁�̐����Ƃ܂��ɕ������܂��B
���Ȃ��܂鎁�̌������̐M�ߐ����������v���ł��B
�����ԍ��F21728745
![]() 7�_
7�_
�����ۂ̋L�^�͂ӂɂ�ӂɂ�ȃA�i���O�̔g�`�ŏo���Ă��܂��B
�@����̓f�W�^���M���̓]���g�i�A�C�p�^�[���j�̘b�ł��B�i�A�b�v�}�j�B�]���g�̓A�i���O��`�g���g���Ă���̂ŁA�g����f�o�C�X��P�[�u���Ȃǂ̐��\�ɂ���Č`�ω����܂��B�E��������ȏ�ԂŁA�A�C���J���Ă܂��B�����̓A�C�����Ă��܂��B�f�W�^���œ]������ꍇ�A�A�C�p�^�[���̒�ӂ��o�C�i��0�A��ӂ��o�C�i��1�ŁA���ԕω��Łi000�A001�A010�A011�A100�A101�A110�A111�j���d�ˍ��킹�Ă܂��B
�@�Ȃ̂ō��}�̏ꍇ���������Ă���̂�1��0�̋�ʂ����Ȃ����ߓ]���ł��܂���B�E�}�̓A�C���J���Ă܂����E���̓A�C���������W�b�^���傫���Ȃ��Ă܂��B����ł����Ƃ��ǂݎ����ԂɂȂ��Ă����Ƃ��āA�A�����̂ӂɂ�ӂɂ�̔g�`�œ]���������ʂ̃f�[�^�̃o�C�i������v���Ă���ΐ��m�ɓ]�����ꂽ���Ƃ��Ӗ����܂��B���m�ɓ]���ł��Ă���A�]���g�̌`�ǂ��ق����ǂ������ŏ������܂�Ă���Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B
�@���̓A�i���O�̘b�ɂȂ�܂����A�Ⴆ�A�o�C�i������v�����f�[�^���A�n�[�h�f�B�X�N�̉~�Տ�̋L�^����Ă���ʒu�ɂ���ĉ������ς��ƈӌ�������܂����A����͍m��ł��B�@
�@���R�͊ȒP�ŁA2�̓���f�[�^�̏������܂ꂽ�ʒu���Ⴄ�ƁA���ꂼ��̃f�[�^���V�[�N����w�b�h�̓������Ⴂ�܂��B�w�b�h�̓X�s���h�����[�^�[�œ����̂��̓s�x��������ׂ�������܂��B����ɂ���Ĕ������������g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�i�f�W�^���f�[�^��]�����邽�߂̃A�i���O�]���g���܂ށj�Ȃǂ��A�M�����C����A�[�X���C������A�i���O��H�ɓ��荞�肷��ƁA�A�[�X�p�^�[����z���p�^�[���ɂ���ăO�����h���[�v�m�C�Y���������A���ʂƂ���DAC����o�͂��ꂽ�����������Ȃ�Ƃ������Ƃ͕��ʂɍl�����܂��B
�@�܂��́A�]���g�̃N���b�N��DA�ϊ��̉��̔g�`�̃N���b�N�Ŏg�����肷��ƁA���鑤�̓]���g�̗ɂ���Ĕ�������W�b�^�̉e���������āADAC�o�͂���鉹�̎��g�������ϒ����āiIM�c�j���������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�ȏ�̂悤�Ƀf�W�^�������ƃA�i���O�������čl����ƁA�ǂ��ʼn������ω����Ă���̂����킩��܂��B
�����ԍ��F21729066
![]()
![]() 15�_
15�_
���Ⴆ��WAV�t�@�C���Ȃ�A�����o�C�i���\�f�[�^�ł����āA�����o�C�i���\�f�[�^�̉����ς��Ƃ������Ƃ����肦��̂ł��傤���H
�O�ƂP�̗���ɂ����Ȃ��f�W�^���f�[�^�ł��̂Ńf�[�^�Ƃ��Ă͓����ł��Đ�����@��ɂ���ĉ��͕ς�܂��BCD���o�n�߂����ɊF�����悤�ɕ�������悤�ɂȂ�ƌ����܂��������ۂ͋@��ɂ���Đ����ƕς��܂�����B������ӂ̉B�������e���[�J�[�̃I�[�f�B�I���u�ɏo�Ă����̂ł����ߔN�̓I�[�f�B�I�̕���͂ǂ��炩�ƌ����Ƒ��ە���ɂȂ��Ă��܂����̂Ŏ��̔삦���l��������͂ǂ�������̂ł��傤���ˁI
�ŏI�I�ɃA���v�ƃX�s�[�J�[�ƋM�a�̎��̓A�i���O�ł���ˁH�����l����ō��̔��葕�u�͋M�a�̎��ł��B
�����ԍ��F21729230
![]() 3�_
3�_
Symbolist_K����A�ԐM�����肪�Ƃ��������܂����B
>�ł��A�f�l����Ȃ���ł���A���̕��́B���Ȃ��܂邱�Ƌ��䗲���������m����܂��H
�͂��B�������̕��ʁi�ǂ̕��ʁH�j�̌o���͒����̂ŁA�����O�͂悭�����Ă���܂��i�����Ɍ����ăA���ȃq�g���ȂƎv���܂��j�B�u�v���̌������Ƃ����琳�����̂ł́v�ƍl���Ă��܂��g�R������Â���Ȃ��ł��B
>�ʂɔނ����������ŐM�p���Ă���킯�ł͂Ȃ��A
�Ƃ������Ⴂ�܂����A��L�u�ł��A�f�l����Ȃ���ł���v���炵�āA���������o�C�A�X���������Ă��܂���ˁB�������ɑf�l�ł͂Ȃ��A�ł��u�v���v�Ƃ������́u�ƊE�̃q�g�v�Ƃ����ق����Ó��ł��傤�B
����ɁA�Z�b�g���ƕ��̃G���W�j�A���ʃf�o�C�X�̒��g�ɂ܂ŏڂ����Ȃ��̂͂����ӂ��ł���B�u�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���ĉ����ɉe������v�̂������ł���Θ_���ɂȂ��Ă����������Ȃ��Ǝv���܂����A�g�c�c�̓�����͂܂ł��قǂ̗]�T�́A���Ƃ̃I�[�f�B�I���ƕ��ɂ͂Ȃ��ł��傤�B�v�͑f�l�̉����ƕς��܂���B
>����́u�ǂ��Ȃ�h�v�Ɓu�ς��Ȃ��h�v���ǂ����������œo�ꂳ��邩�ɂ��ł��傤�B
�����`�I�ł���(��)�B��Âɍl����Ɓu���������Ǖς��Ȃ������v�Ə������ނ̂͑�������ȃq�g���Ǝv���܂����B
>�ǂ�Ȃɏ������Ă��A����������Ȃ�ΒNj����悤�Ƃ����̂��I�[�f�B�I�̃��}�����Ⴀ��܂��I
�Ȃ�قǁB�u���}���v�ƂȂ�ƁA��͂��É]�X�̘b�͖��ʂł����ˁB�����̂Ȃ��������炯�̋���y���ނ̂����R�A�ł��ˁB�Ȃ��A���킩��̂����͑����ł��傤���u�b�c�v���[���[�ɂ���ĉ������Ⴄ�v�Ƃ����͕̂ʂ̘b�ł��B�O�̂��߁B
�����ԍ��F21729392
![]() 10�_
10�_
����ʓI�Ƀf�W�^���f�[�^���������悢�̂́ACD����̃��b�s���O�ł͓ǂݏo��������ł��B�h���C�u���Ƃ��Ɏw�ߗp�Ɏg�������C���Y��ȃN���b�N��HDD�ɂ��͋����L�^����邩��ł��B�Ƃ��낪������R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���̂ŁA�������ς��̂ł��B
���Ȃ��܂�Ƃ����l�����̂悤�Ɏ咣���Ă���킯�ł����A�u���C���Y��ȃN���b�N�v�Ƃ����\���͉Ȋw�I�ł��傤���H�@��̓I�Ƀf�[�^�Ƃ��Ăǂ��Ȃ��Ă��邩�ł͂Ȃ��A�u���C���Y��v�ł���H�@�܂��f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���Ə����Ă܂����A�ǂ̂悤�Ɏc���Ă���̂��f�[�^���o���Ȃ����Ƃɂ͌����Ă��邾���ł��B���ɂ͗삪������Ɠ������x���̘b�ł��B���ƁA�P���炢�R�s�[������m�C�Y��獭�Ղ�炪���債�ĉ��y�f�[�^���܂������ʕ��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤���H�@�����������y�f�[�^�Ƃ����̂́A�o�b�̒��ł��낢��ƕҏW���ꂽ�f�[�^���f�B�X�N�ɏĂ���Đ��̒��ɏo���̂ŁA����Ȃ��ƌ����Ă��琧��i�K�łǂꂾ���R�s�[�Ƃ�����Ƃ��Ȃ��Ă��邩�H�@���ꂪ�X�^�W�I�̉��������肷��̂��B�݂����Șb�ɂȂ�܂���ˁB���y�����ЂŘb�����炱�ꂾ��I�[�f�B�I�}�j�A�͂Ɩ��f�����邱�ƊԈႢ�Ȃ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21729406
![]() 10�_
10�_
�uCD���ڃ��b�s���O�ʼn����ǂ��Ȃ�̂��v�ɂ��ẮA�R�s�[���������̂������Ă݂�����Ǝv���܂��B�܂��A�莝���̂b�c����荠�Ȓ����̋Ȃ��P�������b�s���O���܂��B������u���C���Y��ȃN���b�N�̉��y�f�[�^�@�v�Ƃ��܂��B��������R�s�[���s���A�R�s�[�����f�[�^������ɃR�s�[�A���l�̎菇���P�O�O��قnjJ��Ԃ��ė����f�[�^�����܂��B�O����ɂ��Ȃ�A�t�r�a��������r�c�J�[�h�Ɉړ������āA�𑣐i����Ƃ���ɗǂ��ł��傤�B�����f�[�^���u�����ڂ�Ƃ��ĉ����N���b�N�̉��y�f�[�^�v�Ƃ��āA����ɂP�O�قǕ������܂��B�����̃f�[�^����������̃v���C���[�ɂ܂Ƃ߂ĕ��荞�݁A�����_���Đ������܂��B
�u�����ڂ�Ƃ��ĉ������y�f�[�^�v�̒��ɂP�����u���C���Y��ȉ��y�f�[�^�v�������Ă���킯�ł�����A���������ɕ����邱�Ƃł��傤�B�ʂɑ��l�ɗ���Ȃ��Ă������Ŋm�F�ł��邱�Ƃł��B����ł��Ȃ��܂邳��̂����u��ʓI�v�Ɏ����������Ă��邩�ǂ����m�F����Ηǂ��̂ł��B�ł�����́A�����܂Ŏ������m�邽�߂̂��̂ł��B���l�Ɏ����Ƃ��Ĕ��M���邱�Ƃ͂ł��܂���B�l�b�g�̏��ł͐M���������������Ȃ��܂�����A���l�����A���ŏW�܂��ē������������Č��ʂ������Ȃ�����A�m�ł�����ɂ͂Ȃ蓾�܂���B�t�Ɍ����A���ΒN�ł��m�F�ł��邱�Ƃł��B�ł��A�����������������Ȏ咣������I�[�f�B�I�̌��Ђ������̊m�F��ƂɎQ�������Ƃ��������������Ƃ��Ȃ��ł��B�ǂ����Ă��Ȃ��̂ł��傤���ˁB
�����ԍ��F21729718
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����@�@�@����ɂ���
�����̂œr������ēǂ݂܂����B
�f�W�^���̖������AZ1ES��DA�ϊ���̃A�i���O�M���ł̈Ⴂ������̂��ȂƊ����Ă��܂��B
���悩�獂�悪�c�݂Ȃ��A�X�b�L�������ȉ��ł���A�����Ƀ��X�i�[���������サ���Ɗ�����ł��傤�B
�����ԍ��F21730301
![]() 1�_
1�_
��Symbolist_K����
JS PC AUDIO��DC���C���R���f�B�V���i�[��NAS�Ɏg���Ă��܂����A�V���b�v�z�[���y�[�W�̃��[�U�[���r���[�ɂ�����悤�ɁA�f���炵�����ʂ����Ă���܂��B
���̉�Ђ͗D�G�Ȑ��i�𑼎Ђ������ɒ��Ă���M���ł����Ђ��Ǝv���܂��B
HUB�ɂ��Ă������I�ɗD�G���Ƒz���͂��܂����A���~���o����HUB��������̂ɁA���̉��i�͂ǂ����ȁA�Ƃ͎v���܂��̂ł����߂͂��܂���B�I�[�f�C�I�pHUB�Ƃ������̂�����Ƃ����Q�l���ł��B
�I�[�f�B�I�pHUB�ʼn��̉������ǂ��Ȃ�̂��A�O�C�P�̃f�[�^�����m�ɓ]������Ă���Ή����͕ς��Ȃ��A�ƍl���Ă�����ɂƂ��ẮA�i���̓�A�I�J���g���i�ł��傤�ˁB
���鉼�݂�������ɂ́A���̉������������Ƃ���ΐ��N����A�Ɨ\�z����錻�ۂ��A���ۂɋN���邩�m�F����Ɨǂ��ł��B
�i�����j�n�[�h�f�B�X�N���ŃR�s�[����Ɖ������ς��̂́A�A�R�s�[�ɂ�肻�̉~�Տ�̋L�^����Ă���ʒu���ς�邱�ƂŃV�[�N���삪�ς��A�������鍂���g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�̃��x�����ς��̂������ł���B
�i�\�z����錻�ہj����R�s�[���Ă��A�ł������̗ǂ��ʒu�ɃR�s�[���ꂽ�����̉����ƁA�ł������̈����ʒu�ɃR�s�[���ꂽ�����̉����̊Ԃ̉����Ɏ��܂�B�܂��R�s�[���ĉ����ǂ��Ȃ�ƈ����Ȃ�́A���x���J��Ԃ��Γ����Ɏ�������B
���Ă��̌��ۂ͐��N����̂ł��傤���H���ۂɂ���Ă݂Ȃ��ƕ�����܂��A���N����Ƃ͎��ɂ͎v���Ȃ��ł��B
�����ԍ��F21730327
![]() 7�_
7�_
�p�C������
���������肪�Ƃ��������܂��B
�������̂ӂɂ�ӂɂ�̔g�`�œ]���������ʂ̃f�[�^�̃o�C�i������v���Ă���ΐ��m�ɓ]�����ꂽ���Ƃ��Ӗ����܂��B���m�ɓ]���ł��Ă���A�]���g�̌`�ǂ��ق����ǂ������ŏ������܂�Ă���Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B
�Ȃ�قǁA�f�W�^���ŏ������܂��f�[�^���̂ɂ̓o�C�i���̓��ꐫ���ۂ����킯�ł��ˁB
�������A���ꂪ�A�i���O�̐��E�ɒu����Ă������ɂ����āA�Ⴆ�n�[�h�f�B�X�N�̉~�Տ�̂ǂ��ɒu����Ă��邩�Ƃ����A�i���O�I�Ȕz�u�̈Ⴂ���A��������ǂݏo����čĐ�����鉹�ɈႢ�ݓ���ƁB
���܂��́A�]���g�̃N���b�N��DA�ϊ��̉��̔g�`�̃N���b�N�Ŏg�����肷��ƁA���鑤�̓]���g�̗ɂ���Ĕ�������W�b�^�̉e���������āADAC�o�͂���鉹�̎��g�������ϒ����āiIM�c�j���������邱�ƂɂȂ�܂��B
����̓V���N���i�X�]���͂�߂ăA�V���N���i�X�]���ɂ��ׂ����Ƃ����b�ł���ˁB
�f�W�^�������ƃA�i���O�������čl���邱�Ƃ̏d�v������L���܂����B
�����ԍ��F21730867
![]() 7�_
7�_
JTB48����
����́u�i�����̗R���͈قȂ邪�o�C�i���́j����WAV�t�@�C�����A�����v���[���[�iHAP-Z1ES�j�ōĐ����āA�����ς�邱�Ƃ����肦��̂��H�v�Ƃ����₢��������ł���B
�قȂ�v���[���[�ōĐ������特���قȂ�Ƃ����̂͂�����܂��̂��ƂƂ��āA���ɖ�莋���Ă���܂���B
�����ԍ��F21730869
![]() 7�_
7�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���Ȃ��܂鎁���������Ȃ����Ɗ��Ⴂ���A���炢�����܂����B
���������̕��ʁi�ǂ̕��ʁH�j�̌o���͒���
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�������v���̕���������ł��ˁB
���Z�b�g���ƕ��̃G���W�j�A���ʃf�o�C�X�̒��g�ɂ܂ŏڂ����Ȃ��̂͂����ӂ��ł���B�u�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���ĉ����ɉe������v�̂������ł���Θ_���ɂȂ��Ă����������Ȃ��Ǝv���܂����A�g�c�c�̓�����͂܂ł��قǂ̗]�T�́A���Ƃ̃I�[�f�B�I���ƕ��ɂ͂Ȃ��ł��傤�B�v�͑f�l�̉����ƕς��܂���B
�������̕���̘_���̃e�[�}�ɂȂ邩�Ȃǂɂ����ʂ���Ă���Y��悤�ɂ��������Ȃ����A���Ȃ��܂鎁���u�f�l���R�v�Ɣ��f�����̂Ȃ�A�S�����ł����ł��Ȃ����Ȃǂɂ͂������_����m�E�n�E�͂���܂���B����͂����ǖ{�E�̃n�[�h�f�B�X�N�Z�p�҂Ɍ��������������Ă݂邵���Ȃ��悤�ł��ˁB�n�[�h�f�B�X�N�Z�p�҂����Ȃ��܂闝�_�ɂ��Ę_�����Ă���悤�ȕ��͂́A������ƒT���Ă�������Ȃ��̂ŁA�����������玕��ɂ��|���Ă��Ȃ��̂�������܂��B
�����A�����u���}���v�ƌ������́A�u�����̂Ȃ��������炯�̋���y���ށv�悤�ȁgromance�i�������ꂵ����z�j�h�̂��Ƃł͂������܂���B�����ł������ǂ��Ȃ��������߂āA�����ȉ����ɂ������������肵���A�����̒��ʼn��Ƃ��������ĉ��̗ǂ��Ȃ����H�L�ȏu�Ԃɗ�����Ȃ����Ɩ͍����A�ʂĂɏ�肭�������Ƃ��ɂ͊��삷�邻�́gromance�i�`���S�A�킭�킭����S�j�h�̂��Ƃ��������̂ŁA���������S�̗L��l���A�ȉ��̂��Ƃɔᔻ���������͂���܂���B
�Ƃɂ������́A���̌f����ǂ܂�Ă�����X�̏W���m�ɂ���āA���̖��ɑ�����������o����邱�Ƃ��肤�݂̂ł��B
�����ԍ��F21730873
![]() 8�_
8�_
�Ɠd��D���̑�コ��
���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�������ɁA�u���C���Y��ȃN���b�N�v�Ƃ����\���͕��w�I�A��g�I�����܂��ˁB�����͂��������U���I�ɂ��������悳�����ł��B�u�����N���b�N�̉e����r�������v�Ƃ������ƂŁA���́u�����N���b�N�̉e���v�A�܂�W�b�^�[�̂��Ƃ����Ȃ��܂鎁�́u�N�Z�v�ƌĂ�ł��܂����A��g�������ł��ˁB
���P���炢�R�s�[������m�C�Y��獭�Ղ�炪���債�ĉ��y�f�[�^���܂������ʕ��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤���H
�����͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��A������̃p�C������́u�A�C�p�^�[���v�̂��b�������Ă���܂����B�]���̒i�K�ł͂ӂɂ�ӂɂ�ł��A�������܂ꂽ���ʂ̓o�C�i�����ێ������ƁB
������u�R�s�[���J��Ԃ��ΌJ��Ԃ��قlj�������v�Ƃ������Ƃ͂Ȃ���ł���ˁB�P��ł��R�s�[��������A���̗ƂP�O��R�s�[�����ꍇ�̗��r����ƁA�K��������҂̕��������Ă���Ƃ�����Ȃ��悤�ł��B����䂦�A
���R�s�[�����f�[�^������ɃR�s�[�A���l�̎菇���P�O�O��قnjJ��Ԃ��ė����f�[�^�����܂��B�O����ɂ��Ȃ�A�t�r�a��������r�c�J�[�h�Ɉړ������āA�𑣐i����Ƃ���ɗǂ��ł��傤�B
�Ƃ������Ƃ����Ă��A�́u���i�v�͂���Ȃ��悤�ł��ˁB
���u�����ڂ�Ƃ��ĉ������y�f�[�^�v�̒��ɂP�����u���C���Y��ȉ��y�f�[�^�v�������Ă���킯�ł�����A���������ɕ����邱�Ƃł��傤�B
�����Ȃ�ł���B���Ȃ��܂闝�_�ɂ������Ȃ�܂��B
�����l�ɂ������O���[�v�ɂ���Č�����ď��߂āA���Ȃ��܂闝�_�Ȃ炩�Ȃ��܂闝�_�̐��ۂ��A�m�ł�����Ƃ��Ċm�������[�Ƃ����̂͂��̒ʂ�ł��ˁB
�����ԍ��F21730876
![]() 7�_
7�_
����������A����ɂ��́B
�f�W�^���̖��ł͂Ȃ��A�A�i���O�̗̈�̖��ł���Ƃ������Ƃ́A���ɂƂ��āA����ɖ��炩�ɂȂ��Ă��܂����B
HAP-Z1ES�̗ǂ���DA�ϊ���̍������������ɂ��邱�Ƃ͊m���ł����A�����ɂȂ��Ă���A�i���O�̗̈�Ƃ́A�n�[�h�f�B�X�N�̓����\���̂��ƂȂ�ł���B
�����ԍ��F21730878
![]() 7�_
7�_
Minerva2000����
���������肪�Ƃ��������܂��B
�����ł����AJS PC AUDIO�̐��i�����ۂɎg�p����Ă����ł��ˁB�f���炵�����ʂ����Ă���Ƃ́A�^���Ă��݂܂���ł����B
�ł��A��͂�U���~��HUB���S�O���܂���ˁB
���I�[�f�B�I�pHUB�ʼn��̉������ǂ��Ȃ�̂��A�O�C�P�̃f�[�^�����m�ɓ]������Ă���Ή����͕ς��Ȃ��A�ƍl���Ă�����ɂƂ��ẮA�i���̓�A�I�J���g���i�ł��傤�ˁB
������܂��A�p�C������̗��_�ł͂ǂ��Ȃ邩�A���Ȃ��܂闝�_�ł͂ǂ��Ȃ邩�A�Nj����Ă݂����e�[�}�ł��ˁB
���i�����j�n�[�h�f�B�X�N���ŃR�s�[����Ɖ������ς��̂́A�R�s�[�ɂ�肻�̉~�Տ�̋L�^����Ă���ʒu���ς�邱�ƂŃV�[�N���삪�ς��A�������鍂���g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�̃��x�����ς��̂������ł���B
����́A�p�C������̏�̐������̂��̂ł��ˁB�����Ă��Ȃ��܂闝�_���A�����̐��������قȂ�܂����A��ł͂��̉������x��������̂ł��ˁB
���i�\�z����錻�ہj����R�s�[���Ă��A�ł������̗ǂ��ʒu�ɃR�s�[���ꂽ�����̉����ƁA�ł������̈����ʒu�ɃR�s�[���ꂽ�����̉����̊Ԃ̉����Ɏ��܂�B�܂��R�s�[���ĉ����ǂ��Ȃ�ƈ����Ȃ�́A���x���J��Ԃ��Γ����Ɏ�������B
����́A�����Ȃ��Ȃ��ł����B���͂��̌��ۂ͐��N����悤�Ɏv���܂��B�p�C�������Ȃ��܂����B��m�肵�Ă��镔���ł�����܂����A���N�����Ȃ��ł��傤���B�����A���ŕ����Ĕ��ʂ���킯�ł�����A�l�ɂ���āA���ʂł���l�Ɣ��ʂł��Ȃ��l���o�Ă���\���������A���͓����������܂���ˁB
�����ԍ��F21730889
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����
���Ȃ��܂邳��́A�������ς��̂́ADA�ϊ����ꂽ�A�i���O�g�`�ɃA�i���O�m�C�Y�g�`������邩��A�ƌ����Ă���̂ł͂���܂���B
�ނ̎咣��DAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ�A���������A�i���O�g�`���̂��ώ�����A�ƌ������̂ł��ˁB
�����ԍ��F21730950
![]() 6�_
6�_
��Symbolist_K����
�w�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���x
���`���ƁA���ۂɒ��������̂̌o���Ƃ��āA���̑ʎ�(������)�ł́A�����ς蕪����܂���(�͂͂́I)
�ʐ^�ɕt���܂����l�ȁA�O�t���h���C�u�c����́A���܂��܃m�[�gPC�p�ɊO�t���h���C�u�������Ă����̂Ŏg���Ă܂����A
�f�B�X�N�g�b�vPC�Ń��b�s���O�����f�[�^��LAN�o�R�œ]�������Ă܂����A�u���v�Ȃ�Ă����ς�ł��B
�O�t���h���C�u�̗��_�́A���b�s���O���ɃW���P�b�g�f�[�^���l�b�g�o�R�Ŏ�荞��ł���܂��B
�������A�h���C�u�̐��\�H�@�ׂ̈��@���Ȃ莞�Ԃ�������܂��B
�f�B�X�N�g�b�v�ꍇ�́A�����^�C�v�Ȃ̂��@���Ȃ�̑������b�s���O�ŁA�]�������\�����ł����A�W���P�b�g�f�[�^�͓]������Ȃ��̂�
�{�̍Đ����̕\�����AHDD�̃C���X�g�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�Ȃ̂ŗ]�T������A�O�t���h���C�u�Ń��b�s���O���Ă܂��B
�ǂ����ɂ���APC�]���ƊO�t���h���C�u�ł̃��b�s���O�ł́u���v������l�h���܂��B
�����ԍ��F21731236
![]() 17�_
17�_
��Symbolist_K����
���Â����̑�D������
��������͌����I�Șb�ɂȂ�܂��B
�@�A�b�v�}�̇@�ƇA�̓n�[�h�f�B�X�N�̈قȂ�Z�N�^����o�͂��ꂽ�o�C�i����v��2��wav�t�@�C�����g����DAC�o�͂����Ƃ��̃A�i���O�M���𑪒肵�����̂ł��B�m�C�Y�t���A�̔g�`���Ⴄ�̂ŕ����I�ɂ͈Ⴄ���ɂȂ�̂��킩��܂��B
�@�B�ƇC��wav�t�@�C���i�����k�j��MP3-320Kbps�i�s�t���k�j�̃A�i���O�M���̔�r�ł��B
�@�������Ƃ��āAMP-320Kbps�i���k�j�̉������A���ꂾ�����Ă���ɂ�������炸�A�قƂ�ǂ̐l��WAV�t�@�C���iCD�����j��MP3-320Kbps�����̈Ⴂ�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����̂�����ł��B�i�������܂߂āj
�@���������ƁA����t�@�C����DAC�o�́i�P�[�u�����܂߂Ă��ׂē���@�ނœ����ݒ�j�̉���������̂��@���ɓ�������킩��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21732094
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����
�i��1�j�n�[�h�f�B�X�N���ŃR�s�[����Ɖ������ς��̂́A�A�R�s�[�ɂ�肻�̉~�Տ�̋L�^����Ă���ʒu���ς�邱�ƂŃV�[�N���삪�ς��A�������鍂���g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�̃��x�����ς��A���̃A�i���O�m�C�Y���ADAC�Ő��m��DA�ϊ����ꂽ�A�i���O�g�`�ɉ���邩��ł���B
�i���Q�j�n�[�h�f�B�X�N���ŃR�s�[����Ɖ������ς��̂́A�A�O����P�A�܂��P����O�Ƀf�[�^�����]���鎞�ɔ�������X�p�C�N�m�C�Y�̔������������Ԏ������ɂ�炮���ƂŁADAC�ɋ�������鉹���Đ��N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ邽�߁ADAC����o�͂����A�i���O�g�`���̂�����邩��ł���B
�i���P�j�Ȃ���
A.HDD���~�߂�SSD���g��
B.���̔�������A�s�[�Ƃ��V�[�Ƃ��X�[�Ƃ��������ȃm�C�Y���Ȃ��悤�ɂ���A�܂�]���t�B���^�[��������B
�i���Q�j�Ȃ���
A.�W�b�^�[�����_�����O����
B.DAC�ɋ�������鉹���Đ��N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ�ɂ����H�v������
�ƂȂ��͑S���قȂ�܂��B�܂萳�����m���������ƁA���ʂȂ������p�ȑ�����邱�Ƃɐ��菟���ł��B
�����ԍ��F21732327
![]() 7�_
7�_
�p�C������A���������Ă�낵���ł��傤���B
�����ԍ��F21729066�@�ɃA�C�p�^�[�����f�ڂ���Ă��܂����A�f�[�^���[�g��10Gbps�ȂǂƂȂ��Ă���A�I�[�f�B�I�M���̓`���ɂ��Ă͑�������Ǝv���̂ł����A����͒P�ɍl�������̃T���v���Ƃ��������ł悢�ł��傤���H
�����ԍ��F21732543
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�@���w�E�ǂ���ł��B�ʓ|�������̂Ńl�b�g��̉摜���R�s�y���܂����B���g���������̂ő����r�f�I�J�[�h��BD���R�[�_�[�̉f���o�͐M�����Ǝv���܂��B
�@����A�b�v�����̂̓I�V���X�R�[�v�ő��肵���{���ł��B�i�P�[�u����RCA�s���R�[�h���p�j
�}1�͓����f�W�^���o�͐M���̃A�C�p�^�[���A�}2�͓������o�͐M�����̂��̂ɂȂ�܂��B
fs=44100Hz-16bit�̉����i���y�j�ł��B���g���͒Ⴍ�A2.8MH���ƂȂ��Ă���̂ŁA�W�b�^�����Ȃ��g�`�����ꂢ�ł��B
�����ԍ��F21732866
![]() 2�_
2�_
�p�C������A���肪�Ƃ��������܂����B���萔���������܂����B
�f�B�W�^���Ȑ��E�ʼn������ς��b������ꍇ�A�ς��h�������o���퓅��i���u�W�b�^�[�v�ł��B���́A�p�C������Ȃ�I�[�f�B�I�M���ł̃A�C�p�^�[�����o���Ă�����ł͂Ȃ����Ɠ���ł��āA����͎v�f�ǂ���ł����B
�����A�W�b�^�[�傫���ł���(���)�B[21729066]�Ɠ����x�A���\ps�������z�肵�Ă��āA�W�b�^�[�ʼn����͕ς�肻�����Ȃ��ł���E�E�E�Ƃ����W�J��`���Ă��܂����B�܂��W�b�^�[�̋N�����s���ł����A���̋C�ɂȂ�iD�^A�N���b�N�ł́j�}������͂����Ǝv���܂��B
���āA���Ȃ��܂鎁�̐��i�u���_�v�ƌĂׂ�悤�Ȃ��̂ł͂���܂���j�ɏ���čl���Ă݂�ƁA���������b�c�v���[���[�̃s�b�N�A�b�v�̏o�͐M�����ӂɂ�ӂɂ�̃A�i���O�ł���ˁB�����āA�b�c���o�ꂵ�������ɂ́A�T�[�{�̃m�C�Y�����������Ƃ������Ƃ�f�l�ł��m���āA�Ƃ������m�炳��Ă��܂����E�E�E�ƕ����܂����B���܂��O�̘b�Ȃ̂Łi���j�B
�ł���A�b�c����g�c�c��r�r�c�Ƀ��b�s���O�����f�[�^���A���łɐ���ɂӂɂ�ӂɂ�ɂȂ��Ă��ē�����O�̂悤�ȁB���ꂾ�Ƃg�c�c�I�[�f�B�I�T�[�o�[�Ƃ������i�����藧���Ȃ��ł���ˁB�Ȃ���O�݂��ȃj�I�C�������B
�����A�Ⴆ�r�r�c�Ŕ�������m�C�Y�ɂ��āA���Ȃ��܂鎁���̂����܂��Șb���������I�Ɍ����A�Z���X�A���v��烏�[�h���h���C�o����������m�C�Y�Ƃ������Ƃł��傤���A�����肩�o�̓o�b�t�@����ˁE�E�E�͂Ƃ������A�T�[�{�̃m�C�Y�Ɣ�ׂ�A�˂��B����ɁA�I�[�f�B�I�M������192kHz24bit�Ƃ��ł�1MB/s���x���ł��傤���B����̂r�r�c�Ȃ�x�x�݂ł����Ȃ��郌�[�g�ł�����A����@���悤�Ȃc�^�`������\���Ǝv����ł����ǂˁB
�����ԍ��F21732978
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����
���̐����̎d�������������悤�ł��B
���炽�߂Ă킩��₷���������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B
�p�C��������A�C�p�^�[���̂��b�̂Ƃ��ɁA�n�[�h�f�B�X�N����̍Đ��ʼn��������Ȃ�P�[�X�ɂ͂Q�ʂ�l�����邱�Ƃ��w�E����Ă��܂������A���̂Q�̉\�����i���P�j�Ɓi���Q�j�ł��ˁB�����āA���������Ȃ邻�̂Ȃ���́A�i���P�j�̏ꍇ�͉��Ɂu�s�[�Ƃ��V�[�Ƃ��X�[�Ƃ��������ȃm�C�Y�v��������Ă��܂��A�i���Q�j�̏ꍇ�͉������̂��̂�����܂���IM�c�Ȃǂŕϒ�����A�Ƃ������Ƃł��ˁB�����āA���Ȃ��܂闝�_�́i���Q�j�̗���Ȃ̂ł��ˁB
��
�i���P�j���������Ȃ�A��Ƃ��Ă�HDD���~�߂�SSD���g���悢�B�i�܂��͔]���t�B���^�[��������j
�i���Q�j���������Ȃ�A��Ƃ��ẮAA. �W�b�^�[�����_�����O����A�܂���B. DAC�ɋ�������鉹���Đ��N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ�ɂ����H�v������B
�Ȃ�قǁB����Łi���Q�j�̗�����Ƃ邩�Ȃ��܂鎁�́A�W�b�^�[�����_�����O�𐄏����ASSD�ɂ͂ނ���ے�I�Ȍ����������Ă���̂ł��ˁB�i���Ȃ��܂鎁�H���A�uSSD�Ȃǂ̑�e�ʂ̍����t���b�V���������́A���Ȃ�̃r�b�g���̃A�h���X���C�����o�b�T�o�b�T�Ɠ����܂��̂ŁA�����m�C�Y���������ɂȂ�܂��B�ǂݏo���ꂽ�A���f�[�^�ɂ͂��̃m�C�Y�����A��͂��L�̂悤�ȃA�i���O�I�ȃ_���[�W���܂��B�v�j
�ł���Ȃ�A�i���P�j�̐�����������ɂ�HDD��SSD�̉����r����悢���ƂɂȂ�܂��ˁB���ۂ�SSD�̕��������ǂ���A�i���P�j�����Ƃ������Ƃł��ˁB�������A���̌����܂�����ł����B
���Ȃ݂ɁA�i���P�j�̗�����Ƃ�Ȃ����Ȃ��܂鎁�́A�uSSD�̂ق����������悢�Ƃ����l�������ł����A�ӐM�ɋ߂����̂�����܂��B���̌����ł�HDD�̂ق����������悢���Ƃ��悭����܂��v�ƌ������Ă��܂����A�ǂ��ł��傤���H
�Ƃ���ŁAA. �W�b�^�[�����_�����O����̂́A��̓I�ɂ̓N���E�h���o�R�����ăR�s�[����悢�Ƃ������Ƃł������AB. DAC�ɋ�������鉹���Đ��N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ�ɂ����H�v������̂́A��̓I�ɂ͂ǂ�����悢�̂ł����H
�����ԍ��F21732987
![]() 5�_
5�_
�Â����̑�D������
�M�d�ȏ�����Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B
���ۂɑ̌����ꂽ���̂��ӌ�����Ȃ̂ŁA���̎��̌��k�����߂āA�Â����̑�D������f�����Ƃ��ł��܂����B
�����ł����ACD���ڃ��b�s���O�̉���PC���b�s���O�̉��A��ʂł��Ȃ��ł����I
���̂��b�ɂ���āA�܂��u�ς��Ȃ��h�v������l�ł����A�u�ǂ��Ȃ�h�v���܂���l�����o�łɂȂ�Ȃ�����ł́A�u�ǂ��Ȃ�h�v�̐M�ߐ����ꕔ�ʑ�����܂����B
�Â����̑�D������̂��b�ɏƂ炵���킹��ƁA���Ȃ��Ƃ��p�c��Y����������悤�ɁA�u�����Ȑ��g�����N���ɂȂ�A���y�S�̂̃��A���e�B�[���������v�Ɗ������邭�炢�꒮���Ă��̗ǂ���������悤�Ȗ��m�ȍ��ق�����Ƃ����̂́A���Ƃ��������Ƃ��Ă������܂őN���ȈႢ������Ƃ����̂́A�ǂ����r�F�ɋ߂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O���ʂ����Ȃ��Ȃ�܂����B
���Ȃ݂ɁAWAV�t�@�C�����Ǝv���܂����APC���b�s���O����WAV�t�@�C����HAP-Z1ES�ɓ]��������A���o���A�[�g������������Ƃ������Ƃł����A����̓A���o���A�[�g���^�O�Ƃ��ăt�@�C���ɖ��ߍ��܂�Ă��Ȃ����炾�Ǝv���܂��B�K�ȃ\�t�g�A�Ⴆ��dBpoweramp���g���AWAV�ɂ��A���o���A�[�g�ߍ���ł���܂��B
�����ԍ��F21732997
![]() 5�_
5�_
�p�C������
�X�Ȃ邲�������肪�Ƃ��������܂��B
�n�[�h�f�B�X�N�̈قȂ�Z�N�^�ɑ��݂���o�C�i����v�̂Q��WAV�t�@�C����DAC�o�͂��ꂽ�A�i���O�M���ł���@�ƇA�́A�m�C�Y�t���A�̔g�`�������ɈႤ�̂ŁA�m���ɕ����I�ɂ͈Ⴄ���ł��邪�A�g�`�ɂ͂��������ȍ������Ȃ��BWAV�t�@�C����MP3-320Kbps�t�@�C���͔g�`���B�ƇC�قǂ��傫���قȂ�̂ɁA���ɕ�������Đ����ꂽ���̍����킸���ł��邱�Ƃ��l����ƁA�@�ƇA�̍Đ����ꂽ���̍��ƂȂ�Ƃǂꂾ�����������̂ł��邱�Ƃ��I�d�d�d�����͂��Ռ��I�ł��B���Ȃ��Ƃ��AWAV�t�@�C����MP3-320Kbps�t�@�C�����������Ȃ��l�ɒ�����������͂����Ȃ��ł��ˁB���̎�����˂�������ƁACD���ڃ��b�s���O��PC���b�s���O�̉��̍��Ȃ�āA�܂��Ƃ�ɑ���Ȃ����̂ł��邩�Ɏv���Ă��܂��܂��B����͎Q��܂����B�u�ǂ��Ȃ�h�v�̐w�c�A�Ȃ����͂��Ȃ��܂鎁�ɂ͑�Ō��ł��ˁB
�����ԍ��F21733025
![]() 6�_
6�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�p�C������Ɛ��Ɠ��m�̓��֘b�݂����ɂȂ��Ă���̂ŁA�f�l�ɂ��킩��悤�ɉ�������肢���܂��B
���f�B�W�^���Ȑ��E�ʼn������ς��b������ꍇ�A�ς��h�������o���퓅��i���u�W�b�^�[�v�ł��B
�ł��A��������Ȃ��A�W�b�^�[�͗}������̂ŁA����͕ς��h�̍����ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��A�����炻����퓅��i�ɂ��Ă��邩�Ȃ��܂鎁�͌�肾�A�Ƃ������Ƃł��傤���H
���������A�u�ӂɂ�ӂɂᗝ�_�v�����������ƁH
���Ȃ��܂鎁�́uSSD����HDD�̕����A�����̏ꍇ�A�����ǂ��v�ƌ����Ă��܂����A��������������̂ł��傤���H
���ۂ�SSD�̕��������ǂ��̂ł����H
��낵����A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̗��_��W�J���Ă�����������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21733035
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����
�W�b�^�[�ɂ�鉹���̕ω��́AWAV�t�@�C����MP3-320Kbps�t�@�C�����������Ȃ��l�ɂ��ȒP�ɕ����������邱�Ƃ������ł��ˁB
�����ԍ��F21733041
![]() 2�_
2�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�@�摜�ǂ݂ōő�U���ϒ���10nsec���炢�Ȃ̂ōŋ߂�DAC�Ɣ�ׂ���2�����炢�Ⴄ�Ǝv���܂��B7-�W�N�O�̃}�U�[�{�[�h�ł������I�V���X�R�[�v�̓I�[�f�B�I�A�i���C�U�[�Ƃ��Ďg����㕨�ł͂Ȃ��̂ŁA���萸�x�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�g�p�����I�V���X�R�[�v�̓��̓V���[�g�ł̃m�C�Y�t���A���x���͏��������̕�Ȃ���-85dBV���x�Ȃ̂ŃW�b�^�����ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��B
�@�ӂ��͊O��DAC���̃N���b�N���g���̂ŁADAC���̃N���b�N���g���āA�A�i���O��H�̃m�C�Y�ł��Ă��鐻�i�Ȃ�A���̃}�U�[�{�[�h�o�͂��g���Ă��S�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�@������PC����SSD�̒��ɓ����Ă��܂����ASSD�L���b�V��������ACPU�ACPU�L���b�V���A�Ȃǐ��X�̏C����i�o�b�t�@�[�j��������ʂ��ďo�͂����]���g�̔g�`�ŁA������PC���̃I���{�[�hDDC�ƃA�[�X���C�������L����Ă���̂ŁA���Ԃ�]���g�`���ǂ��ŗ��Ă���̂��킩��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�������f�W�^���f�[�^�̓]���Ɋւ��ẮA�A�C�p�^�[�������ꂢ�ɊJ���Ă�̂őS�����Ȃ����x���ł��B
�����ԍ��F21733045
![]() 2�_
2�_
��Symbolist_K����
http://sonove.angry.jp/jitter_sim01.html
�@�O�O�����炱��ȃT�C�g������܂����B�W�b�^�Ɋւ�����ۂ̎����ŁA�q�g�̃W�b�^�ɑ���m�o���E��臒l��������Ă܂��B
##################���p#########################################
�y�܂Ƃ߂Ɖ����z�z
�@�l�Ԃ̒m�o���x�́A�����ł���������10nsec���炢�E�E�E�炵����B
�A���݂̈�����DAP�ł��]�T�Ő��\psec�B�@�̐l�Ԃ̌��E�ɔ�ׂĂ��W�b�^�[�͊��ɂQ�P�^�ȏ���Ⴂ�B
�@�����u����DAC�Ȃ�10psec���x�B�����W�b�^�[�ɂ��Ă͂�����t�Ő����̂��V�т̏ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�B����ł��W�b�^�[���C�ɂȂ�ꍇ�A�ŏI�o���ł���LINE��PHONE�A�E�g�̃W�b�^�[�X�y�N�g�����ϑ����܂��傤�B
�@�ǂ�DAC�ł��M�G��������ł��傤����m�C�Y�t���A�͎�����-140dB���x�Ǝv���܂��B
�@�܂�W�b�^�[���Z��1psec���x�̎G���͎c���Ă��邱�ƂɂȂ�܂�����A������DAP�Ɣ�ׂĂ�
�@�o���ł͂�������1�����x�̌䗘�v�����Ȃ����Ă��Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
################################################################
�@��������Ĉ��S���܂����B���L�}�U�[�{�[�h�̃W�b�^�́A�A�o�E�g�ȑ���ɂ���A10ns���x�Ȃ̂ŁA���̂܂g���Ă��S�����Ȃ����x�����Ƃ������Ƃ��킩��܂����B
�@�����i�����g�j��10ns�A���y�̏ꍇ��30ns�ȉ��Ȃ璮�����Ȃ��̂ŏ\���݂����ł��B�M�����ł͂Ȃ��A���y�����̂��ړI�����B
�@���̃T�C�g�̒��̐l�ɂ��ƁA���݂̐��\�̗ǂ�DAC�́A�W�b�^�X�y�N�g���̃m�C�Y�t���A�͎�����-140��B���x���ƌ����Ă܂��B�@����\������p�[�c�̔M�G�����x���̐��\�������ł��B���̃��x�����ƁA���y���Ƃ��̎������C�ɂȂ郌�x���ł��B���_��͂ł��邾�����������Œ����Ƃ悢���ɂȂ�Ǝv���܂����A���̏ꍇ�́A�S���������Ȃ��W�b�^�X�y�N�g�����x���Ȃ̂ŁA�C���̕ω��ʼn��F���ǂ̂悤�ɕς�邩�͒N�ɂ��킩��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21733077
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����
>�p�C��������A�C�p�^�[���̂��b�̂Ƃ��ɁA�n�[�h�f�B�X�N����̍Đ��ʼn��������Ȃ�P�[�X�ɂ͂Q�ʂ�l�����邱�Ƃ��w�E����Ă��܂������A
>���̂Q�̉\�����i���P�j�Ɓi���Q�j�ł��ˁB
�Ⴂ�܂��B��2�̘b�͂���܂���B
>�i���Q�j�̏ꍇ�͉������̂��̂�����܂���IM�c�Ȃǂŕϒ�����A�Ƃ������Ƃł��ˁB
�Ⴂ�܂��BIM�c�̓A�i���O�i�̘b�ŃW�b�^�[��DA�ϊ��Ƃ͊W����܂���B
�����ԍ��F21733169
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����
�p�C������̂��b�����p�����
�u���̓A�i���O�̘b�ɂȂ�܂����A�Ⴆ�A�o�C�i������v�����f�[�^���A�n�[�h�f�B�X�N�̉~�Տ�̋L�^����Ă���ʒu�ɂ���ĉ������ς��ƈӌ�������܂����A����͍m��ł��B�@
�@���R�͊ȒP�ŁA2�̓���f�[�^�̏������܂ꂽ�ʒu���Ⴄ�ƁA���ꂼ��̃f�[�^���V�[�N����w�b�h�̓������Ⴂ�܂��B�w�b�h�̓X�s���h�����[�^�[�œ����̂��̓s�x��������ׂ�������܂��B����ɂ���Ĕ������������g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�i�f�W�^���f�[�^��]�����邽�߂̃A�i���O�]���g���܂ށj�Ȃǂ��A�M�����C����A�[�X���C������A�i���O��H�ɓ��荞�肷��ƁA�A�[�X�p�^�[����z���p�^�[���ɂ���ăO�����h���[�v�m�C�Y���������A���ʂƂ���DAC����o�͂��ꂽ�����������Ȃ�Ƃ������Ƃ͕��ʂɍl�����܂��B�v
���ꂪ�i���P�j�ŁA
�@�u�܂��́A�]���g�̃N���b�N��DA�ϊ��̉��̔g�`�̃N���b�N�Ŏg�����肷��ƁA���鑤�̓]���g�̗ɂ���Ĕ�������W�b�^�̉e���������āADAC�o�͂���鉹�̎��g�����ϒ����āiIM�c�j���������邱�ƂɂȂ�܂��B�v
���ꂪ�i���Q�j�ł͂���܂��H
�����ԍ��F21733175
![]() 5�_
5�_
Minerva2000����
�u�W�b�^�[�ɂ�鉹���̕ω��́AWAV�t�@�C����MP3-320Kbps�t�@�C�����������Ȃ��l�ɂ��ȒP�ɕ����������邱�Ƃ������ł��ˁB�v�Ƃ������b�ł������A������Ƀp�C�����Љ��Ă���T�C�g�ł́A
���@�l�Ԃ̒m�o���x�́A�����ł���������10nsec���炢�E�E�E�炵����B
�A���݂̈�����DAP�ł��]�T�Ő��\psec�B�@�̐l�Ԃ̌��E�ɔ�ׂĂ��W�b�^�[�͊��ɂQ�P�^�ȏ���Ⴂ�B�����u����DAC�Ȃ�10psec���x�B
�Ƃ���Ă��܂��B
�悭�킩��Ȃ��̂ł����A������āA�u�W�b�^�[�Ȃ�ĂقƂ�ǒ�����邱�Ƃ͂���܂����v���Ă������b�ł����ˁH �ǂ��v���܂����H
�����ԍ��F21733191
![]() 5�_
5�_
�p�C������
�W�b�^�[�Ɋւ��鋻���[�������̂��Љ�A���肪�Ƃ��������܂����B
����͗v����ɁA�u��قǂЂǂ�DAC���g���Ă���̂łȂ���A�W�b�^�[�����ۂɒ������Ƃ͂܂��Ȃ��v�Ƃ������ƂȂ�ł���ˁH
�ǂ�DAC�ł��u�W�b�^�[���Z��1psec���x�̎G���͎c���Ă���v�Ƃ̂��Ƃł����A�u1psec���x�̎G���v���āu�l�Ԃ̒m�o���x�́A�����ł���������10nsec�v�Ƃ������̒m�o���x�̂P�����̂P�ł���ˁB
�����ԍ��F21733210
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����
>�]���g�̃N���b�N��DA�ϊ��̉��̔g�`�̃N���b�N�Ŏg�����肷��ƁA
HDD���̉������Đ�����Ƃ��A�]���g�̃N���b�N��DA�ϊ��̃N���b�N�Ƃ��Ďg�����Ƃ͂���܂���B���������ċL�ڂ���Ă��鉹���̗͋N���蓾�܂���B
�ЂƂQ�l�ɂȂ�G�s�\�[�h���Љ�܂��B
-------------------------------------------
�́A�����Ђ����o�b�t�@�𓋍ڂ����u�W�b�^�[���X�vDAC�����Ă��܂����B���o�b�t�@�ɒ��߂��f�[�^��DAC���̃N���b�N�œǂ݂������Ƃɂ��A���S�W�b�^�[���X������������搂��Ă��܂����B
������g����CD�g�����X�|�[�g���瑗���Ă���W�b�^�[�����S�ɎՒf����A�ǂ��CD�g�����X�|�[�g���g���Ă������������ɂȂ�A�Ǝv���čw�����������A���z�ȃg�����X�|�[�g�ƈ����ȃg�����X�|�[�g�̉�����r�������Ƃ���A���Ăȉ����������蜱�R�Ƃ��ꂽ�����ł��B
���̕���DAC�ɋ�������Ă���N���b�N�M���̃W�b�^�[�𑪒肵���Ƃ���A�g�����X�|�[�g�ɂ���ĈقȂ�W�b�^�[�ʂ��ϑ�����A�u�W�b�^�[���X�v�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ��������܂����B
���炭���Ă��̃��[�J�[�͔̔��𒆎~���A���̉��ǔł��̔�����邱�Ƃ�����܂���ł����B
�u�N���b�N�M���̃W�b�^�[��ጸ����H�v�v�̓��[�J�[�̊�v�҂�����H�v�ł����A������x�͒ጸ�ł��Ă����S�ȃW�b�^�[���X�͖����Ȃ悤�ł��B
�����ԍ��F21733379
![]() 8�_
8�_
��Symbolist_K����
���C�Â��Ǝv���܂����A���͖{�@�����L���Ă��炸�A�{�@�̍w���\�������܂���B
CD���ڃ��b�s���O�̉��̗D�ʐ����ǂ����Ŋm�F�����킯�ł������A����Ȃ��Ƃ����邾�낤�ƁA�P�Ɏ��̒m�������ɐ������Ă��邾���ł��B
���̗D�ʐ����c�_����̂́A�D�Ԃɂ��ׂ�ΒY�͂ǂ̎�ނ̐ΒY�ɗD�ʐ������邩�A�������c�_���Ă���悤���Ɗ����������������ł��傤�B
����CD���b�s���O�Ȃǂ��Ă��鎞��͋}���ɉ߂��������܂��B
���y�n�X�g���[�~���O�T�[�r�X�A�Ⴆ��Deezer HiFi�AGoogle Play Music�Ȃǂ�����������\�z������������Ɨǂ��ƁA�l�I�ɂ͎v���܂��B
�\�j�[���{�@�̌�p�@����o���\��͂����炭�����A��P�N�قǂŎs�ꂩ��t�F�[�h�A�E�g���邩������܂���B
�����ԍ��F21733768
![]() 3�_
3�_
�p�C������A���肪�Ƃ��������܂����B
Symbolist_K����A�ǂ������݂܂���B�ȉ��ɂ܂Ƃ߂܂��B
�v�̓p�C������̃A�C�p�^�[���̘b�Ŋ������Ă���̂ł����B[21732866]�̂悤�ɍL��ȃA�C���J���Ă���̂ŁA���̒��̂ǂ��œ]���N���b�N���ł���悤���R�s�[���ʂɉe������͂�������܂���B���̂��Ƃ�Symbolist_K�������������Ă���̂ł́B
���̎��_�ł��Ȃ��܂鎁�̐��A�܂�X�g���[�W�����̂ӂɂ�ӂɂ�f�[�^�������ŃN���b�N�W�b�^�[�������A�ӂɂ�ӂɂႪ�R�s�[��ɂ���`�i�������͑���j����Ƃ�����͖��O�ł��B
����ɂg�c�c��r�r�c�����̃f�[�^�͂���ȂɁu�ӂɂ�ӂɂ�v����Ȃ��ł���B��{�I�ɂ́i���Ȃ��Ƃ����[�J���ɂ́j�悭�����Ă��āA��������̗h����������x�łӂ����Ǝv���܂��B�܂��A���܂ɂ͏o���̈����Z�N�^��Z��������܂��傤���B
�����������āA���Ȃ��܂鎁�̐���M���Ă݂܂��傤�B�g�c�c��r�r�c�����̃A���v�Ȃǂ���������m�C�Y�����Ƃ����Ȃ�A�b�c�h���C�u����������T�[�{�m�C�Y�̘b���o�Ȃ��̂͂Ђǂ���O�݂�����Ȃ��ł����A�Ƃ������Ƃł��B�ނ���b�c���ڃ��b�s���O��̂r�r�c�����f�[�^���ӂɂ�ӂɂ�ɂȂ肻���Ȃ��̂ł��B
�����HAP-Z1ES�ɃR�s�[������ǂ��ł��傤���B����̂r�r�c�̓I�[�f�B�I�M���������ɂ͂����ւ�ȗ]�T������܂�����A�����̂ӂɂ�ӂɂ�͂ނ��낷�����萮�`�����ł��傤�E�E�E�Ƃ����������ł��B
������ɂ��Ă��AMinerva2000����ƃW�b�^�[�̘b���n�߂Ă͂�10�N�A�ł����B���Ԃ����ł�(��)�B
�����ԍ��F21733769
![]()
![]() 7�_
7�_
�p�C������̓\���������N
http://sonove.angry.jp/jitter_sim01.html
�����Ă����܂����悭�킩��ǁA
�v����ɁA�����g�̏����𑪒肵����A���̎��g���̋ߖT�̎G�����x�����A
���̋ߖT���O�̎G�����x����������オ���Ă�̂��i�Y�t�}�Q�Ɓj�A�W�b�^�̑���
�ɂ��e���ƍl���Ă����̂��ȁH
�����ԍ��F21734007
![]() 2�_
2�_
��tohoho3����@�ǂ����ł��B
�����̋ߖT���O�̎G�����x����������オ���Ă�̂��i�Y�t�}�Q�Ɓj�A�W�b�^�̑��݂ɂ��e���ƍl���Ă����̂��ȁH
�@�W�b�^�Ɋւ��ẮA�����̎g���Ă���@��ł͖��Ȃ��Ǝv���Ă����̂ŁA�ڂ������ׂ����Ƃ͂���܂��A��L�̓��e�Ȃ炻�̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B�i�ɂ킩�m���ł��j
�@���g�����ϒ�����̂ŁAFFT�ł����ƎO�p�ɐ���オ�����������������̂�炬�ɂ��W�b�^�̕����ł��B�ق��̕���ȕ����́A��������Ȃ̂Ńz���C�g�m�C�Y�̃m�C�Y�t���A�[�ɂȂ�Ǝv���܂��B�Ƃ������ƂȂ̂ŎO�p�̕����̐M�����x���������قǗ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
��Symbolist_K����
�܂��ʔ��������������܂����B�W�b�^���f�W�^���]���g�ł͂Ȃ��A���łɂ��낢��ȃm�C�Y��ϒ��̉e�����ďo�͂����DAC�̃A�i���O�M���̓d���g�`�Ő������Ă܂��B���̂ق��������I�ł��B�T�C�g�́A
http://sonove.angry.jp/doppler.html
�v��ƁA�i�A�b�v�}�Q�Ɓj
�@�C���z���i�w�b�h�z���j�Đ����ɁA�_�C���O�����i�X�s�[�J�[�Ō����R�[���j��100Hz�U���ɂ���ăh�b�v���[���ʂ��������ē���R�[�����瓯���Đ������10KHz�̏����̎��g����10KHz±��fHz�ϒ�����Ƃ������́B�i���̎������̕ϒ��͂܂��ɃW�b�^�Ɠ����ł��j
�A500ps��DAC�ŏo�͂��ꂽ���̔g�`��10KHz�̃W�b�^������FFT�\������Ă܂��B
�B���̂������̃o�C�i����v�Ŏg������`�g��wav�t�@�C���̃O���t�ŁA�X�P�[���͍��킹�Ă���܂��B�W�b�^�͔������Ă�Ƃ��Ă��A-120dB�̔�������m�C�Y�t���A�ȉ��̃��x���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�ӊO�ƃf�W�^���]���g�̃W�b�^�̉e���͏��Ȃ��悤�ł��B
�CMP3-320Kbps�̈��k�ɂ���Ĕ�������A������-80dB���牺�̕ϒ��c���A���������ƂɂȂ��Ă܂��B���̃m�C�Y���ϒ��g�ɂ����̂Ȃ̂ŃW�b�^�̓��ނ��Ǝv���܂��B
�ȏォ�琄������ƁA
�h�W�b�^�[�ɂ�鉹���̕ω��́AWAV�t�@�C����MP3-320Kbps�t�@�C�����������Ȃ��l�ɂ��ȒP�ɕ����������邱�Ƃ������ł��ˁB�h
�Ƃ����ӌ�������܂����A�t�̂悤�ȋC�����܂����ǂ��ł��傤�B�����̓W�b�^�Ɋւ��Ă͏ڂ����Ȃ��̂œI�͂��ꂩ������܂��B
�⑫
�@�X�s�[�J�[�̒ቹ��̐U���ɂ��h�b�v���[���ʂō������ϒ�����Ƃ��������̐����ł��B
�@���Ƃ��b�ŊȒP�ɐ�������ƁA�~�}�Ԃ̃T�C���������Ƃ��ɁA�~�}�ԁi�X�s�[�J�[�̃R�[���j���߂Â��Ƃ��̓T�C�����̉��i����R�[�����甭����10KHz�̏����j�������Ȃ�A�~�}�ԁi�R�[���j����������Ƃ��͎��g�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ������ۂł��B�܂��ɕϒ��c�̂��ƂŃW�b�^�Ɠ��ނł��B
�@���̌��ۂ̓t�������W�X�s�[�J�[�̏ꍇ�ɓ��Ă͂܂�܂��B�t�ɂ����A2�E�F�C3�E�F�C�X�s�[�J�[�V�X�e���̂ق����ϒ��c���������Ȃ�N���A�ȉ��F�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21735033
![]() 8�_
8�_
Symbolist_K����A�����́B
������Ƃ��ז����܂��ˁB
�p�C������A�����́B
�W�b�^�[�ɂ��Ăł����A�Q�l�}1�̂悤�ɕ��ނ���邻���ł��B
���̒��Ń����N��ł̎����ɊY������̂́uPJ�v�ɊY������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�ł����A���Ȃ��܂鎁�̏����Ă��邱�Ƃ�AMinerva2000����̃W�b�^�[�Ƃ����̂́A
����ł͂Ȃ����[�ɂ���ʌn���ɂȂ�u�����_���E�W�b�^�[�v���Ǝv���܂��B
�ł��̂ŁA�c�_����͌����O��̕����ɂ��Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�܂��A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
>���̒��̂ǂ��œ]���N���b�N���ł���悤��
�Ə����Ă���킯�ł����A
�Q�l�}2�̂悤�ɁA���̃Y�������������_���W�b�^�ɂ���Ĕ�������킯�ł��B
���Ȃ݂ɁA���̐}�̓A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Ђ̃A�v���P�[�V�����m�[�g�ɋL�ڂ���Ă������̂ł��B
�����āA�Ȃɂ�����̉e�������邩�炱���A�v�����邽�߂̌v���킪����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���ꂪ�e�����Ȃ��Ƃ����f�[�^���������Ȃ���Ă��������邱�ƂŁA���Ȃ��Ƃ������ƂŎ�������Ƃ͎v���܂��B
Minerva2000����́A
>�W�b�^�[�ɂ�鉹���̕ω��́AWAV�t�@�C����MP3-320Kbps�t�@�C�����������Ȃ��l�ɂ�
>�ȒP�ɕ����������邱�Ƃ������ł���
���̂悤�ɏ�����Ă���킯�ł����A
�E�`�ł��AESOTERIC�̃N���b�N�W�F�l���[�^�[G-02�iOCXO)��
10MHz�̃��r�W�E���}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[��ڑ�������A
���r�W�E����10MHz��UD-503�ɒ��ڂȂ����肵�Ďg���Ă��܂����A
���̌o������́A�W�b�^�[���������ƍl������ʼn��̕ω��͊�������̂ŁA
Minerva2000����̎咣�ɂ͓��ӂ��܂��B
�Ƃ������ƂŁA�W�b�^�[�ɂ��Čv���ƕ]��������̂Ȃ�A
���ނ���Ă��邷�ׂĂɂ��Č�����Ȃ��ƈӖ��͂Ȃ��ł��傤�B
�܂�A���ɂ��̃X���ɂ����āA���Ȃ��܂鎁�̔ᔻ������̂Ȃ�A
�����_���W�b�^�[�ɂ��Ă̕]�����K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21735147
![]() 10�_
10�_
���p�C������
�N���b�N�W�b�^�[��DA�ϊ��ɋy�ڂ��e����ǂ���������Ă��Ȃ��̂ŁA���̂悤�ȋL����\��t����ꂽ�̂ł��傤�B
���L�̋L�����Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
������Ă��܂��I�H �N���b�N�W�b�^�[�́u�^���v�����
http://ednjapan.com/edn/articles/1208/24/news015.html
�����ԍ��F21735267
![]() 1�_
1�_
Symbolist_K����A���炽�߂܂��āA�����́B
�{���̎���ɂ��Ẳł����A���܂�Y�ނ��Ƃ͂Ȃ����Ǝv���܂��B
HAP-Z1ES�͕K���w������Ƃ������Ƃł�낵���̂ł��傤���B
���Ƃ���Ȃ�A
>����PC�̃h���C�u�̓K�^�����Ă���̂œK�Ȃ��̂Ɋ������邱�Ƃɂ��܂��B
�Ƃ������Ƃ́A�f�X�N�g�b�v�@�̃h���C�u�����Ƃ������ƂɂȂ�̂��Ǝv���܂����A
�����USB�ڑ��̊O�t���ɂ���AHAP-Z1ES�ƕ��p�o���܂��B
�|�C���g�́A�h���C�u�ƃP�[�X��ʂɍw������Ƃ����Ƃ���ł��B
�h���C�u�́A����̍w���\�@����I�ԂȂ�Pioneer��5�C���`�h���C�u����ł��B
�������Ȃ�BDR-S11J-X�����Ǎ����̂�BDR-S11J-BK�ł�����B
BDR-S11J-X
http://kakaku.com/item/K0000938766/
BDR-S11J-BK
http://kakaku.com/item/K0000938765/
�P�[�X�̓��g�b�N��RS-EC5-U3X�iUSB3.0)��RS-EC5-EU3X�iUSB3.0&eSATA)
RS-EC5-U3X
http://kakaku.com/item/K0000848705/
RS-EC5-EU3X
http://kakaku.com/item/K0000848706/
����ɂ������Ȃ�A�ʔ���̐É��L�b�gRP-EC5-AI�̑g�ݍ��݁B
https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rp-ec5-ai/
�I���I�X�y�b�N�ł́A�É��L�b�g��g�ݍ��P�[�X(����i��)��
�h���C�u�܂ł��g�ݍ����̂�̔����Ă��܂��B
http://www.oliospec.com/shopdetail/000000005292/ct153/page1/order/
�h���C�u�́A���̂������p�ӂ���Ηǂ��ł��傤�B
�܂��A���Ȃ��܂鎁�̘b���A�悤�̓N���b�N���厖���Ƃ������ƂŁA
�o������A�h�o�C�X����Ȃ�ADAC�ߕӂɃ}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[�𓊓����邱�ƂŁA
DAC��������DAC�ɃN���b�N���͂��Ȃ�����̎�O�ŃN���b�N��@���������ƂŁA
�N���b�N�̗ɂ��e���Ƃ����̂́A���Ȃ茸�点��Ǝv���Ă��܂��B
HAP-Z1ES�ڎg���ƂȂ�ƁA���̎�͎g���Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F21735284
![]() 5�_
5�_
Minerva2000����
�p�C������̕��͂̓ǂݕ�������Ă����̂�������܂���B
�i���P�j�ɑ������镶�͂̓n�[�h�f�B�X�N�Ɋւ�����̂ł����A�����Ńn�[�h�f�B�X�N�Ɍ��肵���b�͏I����Ă��āA
�u�܂��́A�]���g�̃N���b�N��DA�ϊ��̉��̔g�`�̃N���b�N�Ŏg�����肷��ƁA���鑤�̓]���g�̗ɂ���Ĕ�������W�b�^�̉e���������āADAC�o�͂���鉹�̎��g�����ϒ����āiIM�c�j���������邱�ƂɂȂ�܂��B�v
����́A�n�[�h�f�B�X�N�Ƃ͊W�Ȃ��b�������̂�������܂���B
�Ƃɂ����AHDD���̉������Đ�����Ƃ��ɓ]���g�̃N���b�N��DA�ϊ��̃N���b�N�Ƃ��Ďg�����Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB
���́A�����Ђ����o�b�t�@�𓋍ڂ����u�W�b�^�[���X�vDAC�����Ă��܂����B���o�b�t�@�ɒ��߂��f�[�^��DAC���̃N���b�N�œǂ݂������Ƃɂ��A���S�W�b�^�[���X������������搂��Ă��܂����B
����̂��Ƃł��傤���H
http://www.kcsr.co.jp/decoder.html
�u�Ȃ����g�����X�|�[�g�A�v���[���[�̐��\�ɂ������Ȃ��A��ɉ����ɒ����ȍ����x��D/A�ϊ����s�����߁A�Ǝ��̔��^�W�b�^�[���XDigital Audio���V�[�o�[(FPGA)�𓋍ځB�������[��H�Ƀf�[�^���ꎞ�I�ɒ~���邱�ƂŁA���葤�Ƃ̃N���b�N�������z�����APLL�����S�ɔr���B���g�̃N���X�^���Ő������ꂽ���i���ȃ}�X�^�[�N���b�N�ɂ��A �W�b�^�[�̂Ȃ��s���A�ȃf�[�^��DAC IC�ɑ��荞�݂܂��B���Ȃ��嗬�\�[�X�ł���R���p�N�g�f�B�X�N�Đ��ɍőP��s�����܂��B�v
�Ƃ���܂����A�E�\��������ł��ˁI �u�Ȃ����g�����X�|�[�g�A�v���[���[�̐��\�ɂ������Ȃ��A��ɉ����ɒ����v�Ȃ�Ă��ƁA����킯�Ȃ��ł���ˁB
���s�@��SOULNOTE D-1�ł́A�u�N���b�N�ɒ���W�b�^�[�N���X�^�����̗p�v���炢�̉����ȕ\���ɂȂ��Ă܂��ˁB
�����ԍ��F21735393
![]() 5�_
5�_
Minerva2000����
CD���ڃ��b�s���O�̉��ɏ����D�ʐ����������Ƃ��Ă��APC���b�s���O�����t�@�C���ɃW�b�^�[�����_�����O���{���Ƃ���ɋ߂Â��邱�Ƃ��ł���̂ł���ˁA�����炭�͋�ʂ������Ȃ����炢�ɂ܂ŁB
������CD���b�s���O�Ȃǂ��Ă��鎞��͋}���ɉ߂��������܂��B
���y�n�X�g���[�~���O�T�[�r�X�A�Ⴆ��Deezer HiFi�AGoogle Play Music�Ȃǂ�����������\�z������������Ɨǂ��ƁA�l�I�ɂ͎v���܂��B
Deezer HiFi�͂���ĂȂ������̂ŁA���̋@�Ɂu�P���������g���C�A���v�ɃT�u�X�N���C�u���Ă݂܂����B
�f�X�N�g�b�v�A�v�����璮��1411kbps�̉��y�́A�m���ɂق�CD�ƕς��܂���ˁB�iWASAPI�r�����[�h����Ȃ��̂Ŏ��銴���ł����j
�ł��A�Ⴆ�u�x�[�g�[���F���V�Ԃ̓A�[�m���N�[���łŒ��������v�Ƃ��A�u�t�Ղ̓u�[���[�Y�łɌ���v�Ƃ����Ă��邶��Ȃ��ł����B�Ⴄ�o�[�W������p�ӂ���Ă�������Ȃ��B����ɁA�I�y�����S�R�Ȃ��̂ŁA���ɂƂ��ẮA���Ȃ��Ƃ�����ł́ADeezer HiFi�͎�����CD�R���N�V�����̑���ɂ͂Ȃ�܂���BGoogle Play Music��320kbps�Ȃ̂ŁA����ς肿����ƁB
HAP-Z1ES�͔���Ă���̂ŁA�����ȒP�ɂ͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂���I
�����ԍ��F21735410
![]() 6�_
6�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���������肪�Ƃ��������܂����B
�����A�p�C������̃A�C�p�^�[���̂��b�ŁA�t�j���t�j���̔g�`���낤���J�b�`�R�`�̔g�`���낤���]���������ʂ̃f�[�^�̃o�C�i������v���Ă���ȏ�A���m�ɓ]������Ă���A�]���g�̌`�ǂ��ق����ǂ������ŏ������܂�Ă���Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ킩��܂����B�t�j���t�j������`�^��������Ƃ��邩�Ȃ��܂���͎̂Ă܂����B
�����āA���������t�j���t�j������Ȃ��ł���ˁAHDD��SSD���B����Ȃ��ԂȂ����������̂�������A���̏�ɑ��݂��镡�G�Ő����ȃ\�t�g�E�F�A�������͂��Ȃ��ł���ˁB�iHDD ���t�j���t�j����������ACD�Ȃ����ƃt�j���t�j�����낤���A�t���b�s�[�f�B�X�N�Ƃ��A�x���k�[�C�f�B�X�N�Ƃ��AZip�f�B�X�N�Ȃ�Ă���Ƀt�j���t�j���Ȃ͂��A�y���y���������j�Ƃɂ����A�R�s�[�����100%�o�C�i���͈�v����A���̂��ƂɌo�R�����]���g�̌`��͊W�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��ˁB
SSD�́A���Ԃ���J�`�R�`�ł��ˁB
�����ԍ��F21735510
![]() 6�_
6�_
�p�C������
�܂������[�������̂��Љ�A���肪�Ƃ��������܂��B
�u�ۖ��ł͂ǂ̂��炢�h�b�v���[�c�݂��o�Ă���̂��낤���H�v
�Ƃ��A�ʔ����ł��ˁB
�u���y�����ʂ̉������x��80dBSPL���x����0.01um�`0.1um�قnjۖ��͐U������v
�uDAC�̎������W�b�^�[�Ƃ̔�r���l���Ă݂�ƁA525Hz��0.1um�̐U���Ƃ����̂́A�������W�b�^�[�Ō�����0.1um/����=1×10^-7/340��294nsec�̃W�b�^�[�Ɠ����̘c�݂��y�ڂ��B
�l�Ԃ͎��g�̌ۖ������c�݂��������ȉ��̘c�݂͌��m�ł��Ȃ��E�E�E�Ɖ��肷��ƁA���m�\�ȃW�b�^�[�͐��\nsec�`���Snsec���炢����ł���A�Ƃ�����������[7]�Ƃ�����Ȃ�ɐ������闝�R�ɂȂ�悤�ɂ��v���B�v
�ł��A���́u�l�Ԃ͎��g�̌ۖ������c�݂��������ȉ��̘c�݂͌��m�ł��Ȃ��v�Ƃ����O��́A�����������܂��ł��ˁB�͂����Ė{���ɂ����ł��傤���H�i�Ƌ^�����肪�Ȃ��ł����j
������ɂ���A�S�̓I�Ȍ��_�Ƃ��ẮA�u���ʂɃC���z���ʼn��y���ꍇ�Ƀh�b�v���[�c�݂��ӎ����邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�����肳��ɉe���̏��Ȃ��ƌ��ς����DAC�̃W�b�^�[�ɂ��Ă��A�Ƃ�킯�Ȑ��i�ł��Ȃ�����A��莋����K�v���Ȃ��悤�Ɏv����v�Ƃ̂��ƂŁA�O�̎����ɂ�錋�_�Ɠ����Ȃ̂ł��ˁB
�����ԍ��F21735564
![]() 5�_
5�_
���̃X�����Ď��쎩���ȋC�����Ďd�����Ȃ���
�Ƃ肪�R�l�������Ă���̂��ȏ�
�����ԍ��F21735605�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
blackbird1212����A�����́B
�W�b�^�[�̕��ނɊւ��邲�������肪�Ƃ��������܂��B
�������̃A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Ђ̕�����������Ă��������܂����B
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5718JAJP.pdf
�����_���W�b�^�[�Ɗm��I�W�b�^�[����ʂ���K�v������ƁB
�������A���Ȃ��܂鎁�̈ʒu�Â��͋t���Ǝv���܂��B
Minerva2000����̐�̂܂Ƃ߂Ɋ�Â��Đ������܂��ƁA
�i��1�j�n�[�h�f�B�X�N���ŃR�s�[����Ɖ������ς��̂́A�R�s�[�ɂ�肻�̉~�Տ�̋L�^����Ă���ʒu���ς�邱�ƂŃV�[�N���삪�ς��A�������鍂���g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�̃��x�����ς��A���̃A�i���O�m�C�Y���ADAC�Ő��m��DA�ϊ����ꂽ�A�i���O�g�`�ɉ���邩��ł���B
����̓����_���W�b�^�[�ŁA���̌��ʁA�Đ����Ɂu�s�[�Ƃ��V�[�Ƃ��X�[�Ƃ��������ȃm�C�Y�v��������Ă��܂��B��������莋����̂��p�C������B��Ƃ��Ă�HDD���~�߂�SSD���g���悢�B�iMinerva2000����͂��܂肱����͖�莋����Ȃ��B�j
�i���Q�j�n�[�h�f�B�X�N���ŃR�s�[����Ɖ������ς��̂́A�O����P�A�܂��P����O�Ƀf�[�^�����]���鎞�ɔ�������X�p�C�N�m�C�Y�̔������������Ԏ������ɂ�炮���ƂŁADAC�ɋ�������鉹���Đ��N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ邽�߁ADAC����o�͂����A�i���O�g�`���̂�����邩��ł���B
����͊m��I�W�b�^�[�̂����̃f�[�^�ˑ��W�b�^�[�̂����̃V���{���Ԋ��c�݂ŁA���̌��ʁA�Đ����̉������̂��̂����A�c�ނȂ����̓{�P��B���Ȃ��܂鎁���u�ӂɂ�ӂɂ�v�Ɣ�g���Ė�莋����̂�������B��Ƃ��Ă̓W�b�^�[�����_�����O������A���邢�̓N���b�N�M���̃W�b�^�[��ጸ����H�v���Ȃ���Ă���DAC���B�iMinerva2000����ɂ��A���̉����͏\���ɒm�o�\�B�p�C������^�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɂ��A�m�o�s�\�ȂقǏ������B�j
���Ȃ݂ɁA�����w�C���z���Đ����ɔ�������W�b�^�[�ƃh�b�v���[�c�ݗʂ̔�r�x�������Ă���̂͊m��I�W�b�^�[�̂����̎����I�W�b�^�[�B
�����R�̃W�b�^�[�͈قȂ鐬�藧���̂��̂Ȃ̂ŁA�����ċc�_���Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B
�\�\�\�Ƃ����܂Ƃ߂ō����Ă���ł��傤���H
�����ԍ��F21735618
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����
�c�O�Ȃ���S�������Ă��܂���B
�����w�C���z���Đ����ɔ�������W�b�^�[�ƃh�b�v���[�c�ݗʂ̔�r�x�̂ǂ������������̂����������������̂�������Ɨǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F21735655
![]() 1�_
1�_
blackbird1212����
�h���C�u�Ɋւ��邲�w��A���肪�Ƃ��������܂��B
HAP-Z1ES�́A�d�����ЂƂ����������A�K���w�����܂���B
��������PC�̃h���C�u�̓K�^�����Ă���̂œK�Ȃ��̂Ɋ������邱�Ƃɂ��܂��B
���Ƃ������Ƃ́A�f�X�N�g�b�v�@�̃h���C�u�����Ƃ������ƂɂȂ�̂��Ǝv���܂����A�����USB�ڑ��̊O�t���ɂ���AHAP-Z1ES�ƕ��p�o���܂��B
���́A���͂���Ɓu�i���܂�j�ς��Ȃ��h�v�ւƌX�������āACD���ڃ��b�s���O�͕K�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƌ^������܂��B���̗��R�́F
�P�D���̌�����̂����z�����̂Ƃ���A
�u�ς��Ȃ��h�v�F�P�l v.s.�u�ς��^�ǂ��Ȃ�h�v�F�O�l�\�\�ł���B
�Q�D�p�C�����u�m�o�s�\�ɋ߂��v�Ƃ��闝�_��W�J����Ă���B
�R�DMinerva2000����́u�ς��v�Ƃ������̂́A�u�W�b�^�[�����_�����O�v�Ȃǂ̑���Ă���Ă�����A���̏�ł�PC���b�s���O�Ȃ���v�����ł���B
�S�D�p�c��Y���̘b�͂ǂ����E�\�������B
�T�D�^�O�ҏW��PC��ł������B
�U�DCD���ڃ��b�s���O�Œ���HAP-Z1ES�ɓ��ꂽ�Ƃ���ŁAHAP-Z1ES���n�[�h�f�B�X�N���ł̈ړ���珑���������f�t���O�������Ă��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B�i������͂����ł��傤���H �ǂȂ�������������܂��H�j
�V�DHAP-Z1ES�ɉ������N�����āA�n�[�h�f�B�X�N�����������āA�o�b�N�A�b�v����̃R�s�[�Ŗ߂��Ȃ��ƂȂ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B
�d�d�d�Ȃǂ��l�����킹��ƁACD���ڃ��b�s���O�ɏ��ɓI�ɂȂ炴������܂���B�u�ς��^�ǂ��Ȃ�h�v��������o�ꂳ��Ȃ��ȏ�́B
�ł��A�܂��킩��܂���B�V�W�J�����邩������܂��B
���āA�@�ނ̂��Љ�肪�Ƃ��������܂����B
�I�Ԃׂ��h���C�u��Pioneer����Ȃ̂ł��ˁI
TEAC���P�ނ��APlextor��Liteon��OEM�ɐ��艺���������A�p�C�I�j�A�����Ȃ��̂ł��ˁB�ŁA�p�C�I�j�A��DVD�h���C�u���Ȃ��̂Ńu���[���C�ɂ��邵���Ȃ��̂ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA���Ȃ��p�C�I�j�A�ł�����
BDR-209BK�^BDR-209XJBK�^BDR-211JBK�^BRD-S16PX
������ł̓_���Ȃ̂ł����H
���邢�́A�f���v���P�[�^�[�p�ɍ��ϋv�����ꂽDVD�h���C�u�̃v���N�iLiteon�j��PX-891SAF Plus�̓_���ł����H
�O�t���P�[�X�̓��g�b�N���ǂ��̂ł��ˁB
HAP-Z1ES������܂��͒P�Ƃŏ\���Ɋy���݂����ADAC���Ȃ���ɂ��Ă��]�������̂��Ƃł��B
�����ԍ��F21735657
![]() 5�_
5�_
Minerva2000����
�ɂ킩�d���݂̂܂Ƃ߂ŁA�S�������Ă��Ȃ��Ă��݂܂���B
���萔�ł����A�Ԉ���Ă���Ƃ����Y�킵�Ă��������Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F21735662
![]() 1�_
1�_
��Symbolist_K����
blackbird1212����Ǝ����q�ׂ����ƈȊO�̐���S�������Ηǂ��ł��B
�����ԍ��F21735665
![]() 1�_
1�_
�Ƃ������Ƃ́A��͂�A
blackbird1212����̌���ꂽ�F
�����Ȃ��܂鎁�̏����Ă��邱�Ƃ�AMinerva2000����̃W�b�^�[�Ƃ����̂́A
����ł͂Ȃ����[�ɂ���ʌn���ɂȂ�u�����_���E�W�b�^�[�v
���������Ƃ������Ƃł����H
�����ԍ��F21735680
![]() 2�_
2�_
��MAX���O�Y����
�r���[�E�~���K�����Ⴀ��܂�����
�����ԍ��F21735688
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K�����
�S�D�p�c��Y���̘b�͂ǂ����E�\�������B
�p�c���Ɍ��炸�I�[�f�B�I���i�̃��|�[�g������]�_�Ƃ͕K���Ƃ����Ă����قǓ����悤�Ȃ��Ƃ������܂��B����͂����ł��傤�B����Ă݂������ʂ͊������Ȃ������B�ȂǂƏ����Ύ�����C���^�r���[���Ă��炦�Ȃ��Ȃ�܂��B���i�ɑ��čm��I�Ȉӌ����q�ׂ�̂͑�l�̎���Ƃ��Ă������ʂ��Ǝv���܂��B���́A�����������Q�W���痣�ꂽ�Ƃ���ɂ����ʂ̃��[�U�[�����l�̊��z�������Ƃ��ł��邩�ǂ����ł��ˁB
�T�D�^�O�ҏW��PC��ł������B
WAV�Ń^�O�̕ҏW���ł���悤�ɂȂ����͕̂֗��Ȃ̂ł����AHAP-Z1ES�ōĐ������Ƃ��������^�f�[�^�̗L�������ۏ���Ă��܂���B�܂�AHAP-Z1ES�̌�p�@���Ȃ��A���Ă��܂����悤�ȂƂ��ɋ�J���ē��͂����^�O����ɗ����Ȃ��Ȃ�\��������Ƃ������Ƃł��B����āA�ǂ��܂łق��̊��ƌ݊��������邩�Ȃǂ��m�F��������������������܂���B���S�ȂƂ��^�O�������Ă��A���R�Ɉړ����Ďg��������̂ł����A�g���Ȃ�������c��ȍ�Ɨʂ����ʂɂȂ�܂��BiTunes�ł������ɍ쐬���ꂽ�t�H���_�[��WAV�f�[�^�������Ă���^�O��������̂ł����A�o���Ă��܂��Ǝg���Ȃ��Ȃ�܂��BiTunes�̏ꍇ�͂����܂�iTunes�̒��Ńf�[�^��R�t�����Ă��邾�������m��܂���BHAP-Z1ES�ł̓t�@�C�����̂��̂ɂ�����悤�Ȃ̂ŁA�ǂ��ł��g����Ίm���ɕ֗��ł���ˁB
�����ԍ��F21736108
![]() 7�_
7�_
���́A���܂��ɃW�b�^���킩��Ȃ��B���܂܂ł̋c�_�ł̉��̒��ł̂܂Ƃ߂́A
�N���b�N�ɃW�b�^�����݂���ƁA�M���i�ȒP�̂��߂ɐ����g�̏����ɂ���Ƃ��āj�̎��ԗ̈�̔g�`��FFT�����A
���g���̈�̃X�y�N�g�����Ƀz���C�g�m�C�Y����ɉ��炩�̃W�b�^�R���̃X�y�N�g��������������B����́A
�W�b�^�ɂ��A�M���i�����g�j�̈ʑ��i���g���j���ϒ�����邩��ł���B�������A�M���̈ʑ���ϒ���������̂́A
�W�b�^�ȊO�ɂ����܂��܂Ȃ��́i�h�b�v���c�݁AMP3�̕ϊ��c�݂Ȃǁj������A�W�b�^�ɋN������c�݂́A��������
�������̂ŋC�ɂ���K�v�͂Ȃ��B
���ȁB
����ɂ��Ă��ASymbolist_K����A
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5718JAJP.pdf
��ǂ߂��ł��ˁB���̓W�b�^�̐��Ƃł����H
�����ԍ��F21736828
![]() 4�_
4�_
Symbolist_K����A�݂Ȃ��܁A����ɂ��́B�b�����G�ɂȂ��Ă���悤�ł����B
�܂��A���Ȃ��܂鎁�́u�ӂɂ�ӂɂ��`���v�͖����A�ł悢�ł���ˁB��������1MB/s���̒ᑬ���[�g�ł���I�[�f�B�I�M���̃f�B�W�^���R�s�[���N���b�N�W�b�^�[�̉e���ŕs���S�ɂȂ�Ƃ���̂͂��܂�ɂ������ł��B�Ȃ�blackbird1212����[21735147]��
>���Ȃ��܂鎁�̔ᔻ������̂Ȃ�A
>�����_���W�b�^�[�ɂ��Ă̕]�����K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�Ə����Ă��܂����A�����_���^���_����蕪����̂͒P�ɐl�Ԃ̗����̓s���ł��B���̒��̃V�X�e���͗����̃W�b�^�[���o�Ɋ܂�ŁA�I�[�f�B�I�M�������������������[�g�ł̓]�������Ȃ��Ă���̂ł�����A���Ȃ��܂鎁���������Ȃ��Ƃɕς��͂���܂���B
�ŁA���݂͂c�^�`�̐���N���b�N�̃W�b�^�[�����Ȃ̂��ǂ����A�Ƃ����c�_�ɂȂ��Ă��܂��ˁB������b�͒P���ŁA�p�C������[21733077]�̃����N��ň��p����Ă���AES Convention�̕������u�l�Ԃ̒m�o�̌��E�͊y�ȍĐ�����30ns�`300ns���x�A������10ns���x�v�Ƃ��Ă��āA�����N��̒��҂��V�~�����[�V�������g���������̌��ʂ����悭���邽�߂ɔ��_���ȃW�b�^�[���g�p���Ă���ɉ߂��܂���B
������̒��̋@��ɑ��݂���W�b�^�[�́A�O�o�̃A�W�����g��EDN�̎����ɂ����������ł�300ps���x�ŁA��L�y�ȍĐ����̌��E�����Q�P�^�������킯�ł�����A�W�b�^�[�����ł���Ƃ���̂͂�͂薳���ł��傤�B
�ƂȂ�A�W�b�^�[�ʼn���������Ƃ����ϑ��̐M�҂傤�����ᖡ���ׂ��ł��B���̃X���b�h���炻����ۂ��̂��E���Ă݂��
Minerva2000����[21733041]
>�W�b�^�[�ɂ�鉹���̕ω��́AWAV�t�@�C����MP3-320Kbps�t�@�C�����������Ȃ��l�ɂ��ȒP�ɕ����������邱�Ƃ������ł��ˁB
blackbird1212����[21735147]
>�Ȃɂ�����̉e�������邩�炱���A�v�����邽�߂̌v���킪����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
>���̌o������́A�W�b�^�[���������ƍl������ʼn��̕ω��͊�������̂ŁA
������ł����A��������q�ϓI�ȍ����͂Ȃ��A�����͂�����܂���B�u�W�b�^�[�ʼn���������v�Ƃ����ϑ��������Ȃ��Ȃ�A�ς��h�̗����𗝉����悤�Ƃ���w�͍͂��܂葹�ł����Ȃ��Ǝv���܂���B�ł��ASymbolist_K������ė��V�Ȃ�ł����(��)�B
�����ԍ��F21736884
![]() 8�_
8�_
�܂��������m���͎����ĂȂ��̂ł킩��Ȃ����Ƃ��炯�Ȃ̂ł����A���ۂɂǂ��������Ă��邩�����Ęb���i�s���邱�Ƃ͂悭����܂���ˁB�l�b�g�Ōl�����ʂ����������Ƃ����������ȏ��M������A�������������̂œ��ӌ����Ə�������Ă���l������B�ł��A�W�܂��ċq�ϓI�Ȍ����������Ƃ�����̂��Ƃ�������S���Ȃ��B�l�Ԃ̔F���Ȃ�ĞB���Ȃ��̂Ȃ̂ɁA�������Ȃ��ŕς�����Ƃ�������g�U�����B������I�J���g�ȂǂƝ�������邱�ƂɂȂ�B
�}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[�̘b���o�Ă܂����A�v���C���[�ɕʂ̋@���ڑ�������W�b�^�[�W�Ȃ���������̉e�����܂��ˁB���̐ڑ������@�킪�d����K�v�Ƃ�����A�d�������ς��܂���ˁH�@�ݒ�̕ύX�Ȃ�Ă��낤���̂Ȃ烁�[�J�[�������Ă�̂��킩��܂���B�{���ɕς�����̂̓W�b�^�[�����Ȃ̂����ł���킯�ł��Ȃ��̂ɁA���ʂ������܂����Ƃ����悤�ȏ�����������B�l�����Ȗ����ő�����o���͍̂D���ɂ���������Ƃł����A����������Ƌ�̓I�Ȍ����Ȃ��ƁA�ے肷����ɖ�肪����Ƃ����悤�Ș_�@�͐��藧���܂����ˁB
���Ȃ��܂鎁�����b�s���O�̈Ⴂ�ɂ���ăW�b�^�[�ɉe�����o�āA�������ω�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��咣���Ă���̂ł�����A���ۂɃT���v�����r���Č����Ȃ�������܂���B����K�v�Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂ł���A�Ȃ�ł���������ł���ˁB�I�[�f�B�I�̂����������������m�̘b�́A�����邱�ƂȂ��ӖړI�ɐM����l������̂���肾�Ǝv���܂��B�����������O��ɂ��ĕ������l���A�����ɗL���ȏ����W�߂�����܂�����ˁB�ے�I�Ȍ������������ł��A�����ł��邱�Ƃ������Ƃ����悤�ɏ������肵�܂��B�ǂ�ȓ��v�����ɘb���Ă���̂��A����������邱�Ƃ�����܂���B
���͓d���P�[�u���Ȃǂ͌������Č��ʂ��������Ă��邵�A�����炭�͘^���ŏؖ��Ȃǂ��\���Ƃ͎v���܂����A�Ȃ������Ȃ�̂��Ƃ�����������v�������肷��͓̂���ł����A�v�͎����ɂƂ��ēs���̗ǂ����̂��ǂ��Ȃ��Ă��悤�ƍ̗p���Ă������������Ȃ̂ŁA�����������M���邱�ƂɐϋɓI�ɂ͂Ȃ�܂���B�������������Ă��ăP�[�u����킯�ł͂Ȃ��ł�����ˁB�ł��A�M�S�Ƃ����Ȃ�Ƃ������A���ɂ��Ă��ςɔM�S�Ȑl�͋��܂���ˁB��M�I�őf���炵�����Ƃ��Ƃ͎v���܂����A�l�I�ɂ͂����܂ł�錳�C�͂Ȃ��ł��B
���Ȃ��܂邵���ɂ��ẮA�v���f���[�X�����\�j�[��Blu-ray�v���C���[�������^�����Ȃ̂ŁA�M���ł��邵�����肵���l�Ȃ�̗p�ӗ~�����܂�̂ł��肪�����ł��B�����̃X���b�h�̘b�͂��܂��܂Ƃ������ƂŁA��������Ƃ����v�z��m����L����l���ł���ƍl�������ł��ˁB�l�I�Ƀ\�j�[���D���Ƃ����̂�����܂��B
�����ԍ��F21737041
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����
���萔�ł����A�Ԉ���Ă���Ƃ����Y�킵�Ă��������Ȃ��ł��傤���A�Ƃ̂��v�]�ɂ��Y�킵�܂����B
�Y��́A�Ԉ�������A�����ł͖��Ӗ��ȏ����폜����Ƃ������j�ōs���܂����B
�i�n�[�h�f�B�X�N���ŃR�s�[����Ɖ������ς�錴���j
�O����P�A�܂��P����O�Ƀf�[�^�����]���鎞�ɔ�������X�p�C�N�m�C�Y�̔������������Ԏ������ɂ�炮���ƂŁADAC�ɋ�������鉹���Đ��N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ邽�߁ADAC����o�͂����A�i���O�g�`���̂�����邩��ł���B
�i��j
�W�b�^�[�����_�����O������A���邢�̓N���b�N�M���̃W�b�^�[��ጸ����H�v���Ȃ���Ă���DAC���B
�ǐL�F�N���b�N�W�b�^�[�������ɋy�ڂ��e���ɂ��ẮA�̂���ǂ����p����Ă��鉺�L�̋L���������Q�l�ɂȂ�ł��傤�B
�I�[�f�B�I�i���ƃN���b�N�W�b�^�[
http://ednjapan.com/edn/articles/0709/01/news016.html
�����ԍ��F21737105
![]() 2�_
2�_
��Symbolist_K����
�@blackbird1212���狳�������������}�Ɓ�Minerva2000����̃����N�ɂ���A�͍��ꂳ��̋L����ǂ�łȂ�ƂȂ��������܂����B
�@SPDIF��USB�̓`���N���b�N��̃W�b�^�[�́u�`���W�b�^�[�v�ł���A�I�[�f�B�I�@������̃N���b�N�Ƃ͒��ڊW�����B�܂�PC���̓]���g�Ɋ܂܂��]���W�b�^�i�ӂɂ�ӂɂ�ɂȂ鐬���j��D/A�ϊ��ɂ͊W�Ȃ��B�Ȃ̂ł��̓]���g���̂̃W�b�^�̘b�����Ă��Ӗ��͂Ȃ�
�ADA�ϊ��ɂ͋@����̃I�[�f�B�I�}�X�^�[�N���b�N���g���ăA�i���O�g�`�ɕϊ������̂ŁA�o�͂��ꂽ�A�i���O�M���̃W�b�^�ɂ��́A�}�X�^�[�N���b�N�̃W�b�^�̉e�������ɂȂ�B
�B���̃W�b�^�͎�ނ������ĉ����ɉe������͎̂����I�W�b�^�ł͂Ȃ��A�s�K���ɂɔ�������K�����̂Ȃ������_���ȃW�b�^�ŁA�s���I�h�W�b�^�ƌ����A�A�b�v�}�ł݂�Ɣg�`�̃g���K�[�ʒu����ŏ��̗����オ��ʒu�̕ϒ��̂��Ƃ������B�i��tj�̕����j
�B��tj�́A�����_���ɔ������A�K�E�X���z�i�A�b�v�}�j�ɂȂ��Ă��āA���̕������ʓI�ɉ�͂��邽�߂̑���@��͔��ɍ����Ȃ��̂ƂȂ邪�ADAC�̉����Ɋւ��d�v�ȕ����Ȃ̂ŁADAC�`�b�v��DAC�����@���v����Z�p�҂ɂ͕K�v�ȋ@��ɂȂ�B
�C���̇�tj�̐��l�́A�}�X�^�[�N���b�N�̐M�����̂��A�i���O��`�g�Ȃ̂ŁA�ڑ����ꂽPC��h���C�u�Ȃǂ̍����g�m�C�Y���e�����ė���\��������ADA�ϊ��ŏo�͂��ꂽ���̎��g����ϒ������ĉ������������ƂɂȂ�B����𐔒l������ɂ́A���̃s���I�h�W�b�^�̃K�E�X���z��ϕ����Ď����l�iRMS�j���Z�o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA��p�̑���@�킪�K�v�ɂȂ�B
�D�ȏ�̓��e�����ƂɎZ�o���ꂽ�W�b�^�̍ő�ϒ��iRMS�Ɉˑ��j�͍ŋ߂�DAC�Ȃ�10ps�`100ps���x�ɂȂ��Ă���B
�@�Ƃ������Ƃ������̂��ȂƎv���܂��B�Ȃ̂�PC���̃f�W�^���]���g�̃W�b�^��`����c�_���Ă��A�Ӗ����Ȃ������悤�ł��B
�@����ƃs���I�h�W�b�^�̃K�E�X���z��RMS�l�́A�����x�̐�p����킪�K�v�Ȃ̂Ő��m�Ȑ��l�́A�킩��܂��AFFT�̃O���t�����ĎO�p�ɐ���オ���Ă��镔���i�K�E�X���z�j�̂��Ƃ��w���Ă��āA���̐M�����x���͕��R�����̃m�C�Y�Ɠ��l�A�����_���ɔ�������m�C�Y�Ȃ̂Ł@FFT�T���v�����̏������������C�����āA���ۂ̉���dBSPL�ɒu��������A���̃m�C�Y���������邩�������Ȃ������킩��ƌ������Ƃ��Ǝv���܂��B�������邩�������Ȃ����̔��f�͉������x��0dBSPL�i20��Pa�j����ɂȂ�܂��B
�@���Ԃ�قƂ�ǂ̃q�g�ɂ͎�����10ns�ȉ��̃W�b�^�ɂ��m�C�Y�i�O�p�̕����j�Ȃ�A���v�I�ɒm�o���E���ɂȂ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F21737569
![]() 7�_
7�_
�݂Ȃ��܂����́B
Minerva2000���Љ��EDN�̋L���u�I�[�f�B�I�i���ƃN���b�N�W�b�^�[�v��q�����܂����B�ŏ��̃y�[�W�ł́A�u�f�W�^���I�[�f�B�I�V�X�e���̃N���b�N�Ƃ��ėp�����邱�Ƃ̑���PLL�ɂ́A10ps�`100ps�I�[�_�[�̃W�b�^�[�����݂���v�Ƃ���܂��B�Â��L���Ȃ̂ō��̃W�b�^�[�͂����Ə������āA������ɏ������u���������ł�300ps���x�v�͂��Ȃ�傫�߂ȋC�����܂����A�܂��܂��Ċm�F�ł����ƌ����܂��傤���B
�����A�Ɠd��D���̑�コ�u��l�̎���v�݂����Ȃ��Ƃ�����������Ă��܂����A����EDN�̋L���́A�N���b�N����IC(DIR)�̃x���_�[�������Ă�����̂ł��B�܂莩�А��i�̐�`�̂��߁A�N���b�N�̕i������́i�l�ԂɊ��m�ł�����x�Ɂj�d��ȉe��������A�Ǝ咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ������Ƃɗ��ӂ���K�v������܂��B��l�̎���ǂ��납�A�����������������Ă���̂ł��ˁB���ہA�L���̒��g��ǂ�ł݂�ƁA�N���b�N�W�b�^�[�Ɖ����Ƃ̑��ւ́A�ɂ߂Ċ��o�I�ɒf�肳��Ă���ɉ߂��܂���B
����A�Ȃ��f�W�����ȁE�E�E�Ǝv������A�W�N�O�ɓ������Ƃ������Ă��܂����B�����B���L�Ō�̂ق��ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12871923/#12905976
�����ԍ��F21737577
![]() 5�_
5�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����������Ă��܂��B
�Ȃ�8�N�O����i���������悤�ł��ˁB���̕��͍K������I�ɃW�b�^�[�̗������i�݂܂����B
8�N�O�̎����̎咣����A�傫���O�i���Ă���̂�������܂����H
���p�C������
���Ȃ藝�����i�܂ꂽ�悤�ʼn����ł��B�ł��܂���͒����ł���B
�����ԍ��F21737681
![]() 1�_
1�_
������Ȋ����łP�O�N�߂��̊Ԃ���Ă܂�(��)�B
�����ԍ��F21737733
![]() 1�_
1�_
�Ɠd��D���̑�コ��
���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
������Ă݂������ʂ͊������Ȃ������B�ȂǂƏ����Ύ�����C���^�r���[���Ă��炦�Ȃ��Ȃ�܂��B���i�ɑ��čm��I�Ȉӌ����q�ׂ�̂͑�l�̎���Ƃ��Ă������ʂ��Ǝv���܂��B���́A�����������Q�W���痣�ꂽ�Ƃ���ɂ����ʂ̃��[�U�[�����l�̊��z�������Ƃ��ł��邩�ǂ����ł��ˁB
�{���ɂ����ł���ˁA����������ď����Ă܂�����ˁI �����玄�́A�p�c��Y���̘b�����Â����̑�D������̂����z�̕����d�܂��B
��WAV�Ń^�O�̕ҏW���ł���悤�ɂȂ����͕̂֗��Ȃ̂ł����AHAP-Z1ES�ōĐ������Ƃ��������^�f�[�^�̗L�������ۏ���Ă��܂���B�܂�AHAP-Z1ES�̌�p�@���Ȃ��A���Ă��܂����悤�ȂƂ��ɋ�J���ē��͂����^�O����ɗ����Ȃ��Ȃ�\��������Ƃ������Ƃł��B����āA�ǂ��܂łق��̊��ƌ݊��������邩�Ȃǂ��m�F��������������������܂���B
dBpoweramp���g���ƃ^�O���t�@�C�����̂ɖ��ߍ���ł����̂ŁA���Ȃ��Ƃ��u��J���ē��͂����^�O���v���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��悤�ł��B
http://www.linn.jp/pdf/ds_news/20110203.pdf
�����Ō�����Ă��܂����A�t�@�C�����̂ɂ͊ԈႢ�Ȃ��^�O���t������Ă��āA���ꂪ�@�\���邩�ǂ����̓t�@�C���������\�t�g����Ƃ������Ƃł��ˁB�����āAMediaMonkey��KinskyDesktop�ł͂���������ƈ����Ȃ������ł��B
http://kotonohanoana.com/archives/6477
�����ɂ��ƁAfoobar2000��JRiver Media Center�͂����ƈ�����悤�ł��B
�����āAHAP-Z1ES�̃\�t�g�������ƈ�����悤�ł��ˁB
���Ȃ݂ɁAdBpoweramp��DSF�t�@�C���ɂ͑Ή����Ă��Ȃ��̂ŁADSF�t�@�C���Ƀ^�O�t������ɂ́AAudioGate���g���Ƃ悢�����ł��F
http://community.phileweb.com/mypage/entry/2408/20140114/40926/
�����ԍ��F21738194
![]() 5�_
5�_
��iTunes�ł������ɍ쐬���ꂽ�t�H���_�[��WAV�f�[�^�������Ă���^�O��������̂ł����A�o���Ă��܂��Ǝg���Ȃ��Ȃ�܂��BiTunes�̏ꍇ�͂����܂�iTunes�̒��Ńf�[�^��R�t�����Ă��邾�������m��܂���B
���̂悤�ł��ˁBiTunes�̓A���o���A�[�g�Ȃǂ��t�@�C�����̂ɖ��ߍ��܂��A�ǂ����̃t�H���_�[�ɓ���ĊǗ����Ă��邾���Ȃ̂ŁAiTunes�Ń��b�s���O����WAV�t�@�C���́AiTunes�ł̓A���o���A�[�g��������̂ł����A���̃\�t�g�ł͂��ꂪ����Ȃ��Ȃ�܂��B
���Â����̑�D������
�A���o���A�[�g��������Ƃ������b�ł������A���b�s���O��iTunes�Ȃǂ����g���ł͂���܂��H
�����ԍ��F21738195
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�������A�W�b�^�̐��Ƃǂ��납�A�S���̖�O���ł��B
����blackbird1212���g��ꂽ�A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Ђ̕����F
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5718JAJP.pdf
��ǂ�ł݂āA���߂ăW�b�^�Ɋւ��čl���n�߂�����ł���B�ɂ킩�d���݂ł�^^;
���̕����A�}���ɂ��܂Ƃ߂��ƂĂ��֗��Ɏg�������ŁA�i�����������Ă��邩�ǂ����͂Ƃ������j�F�X�ƍl����悷���ɂȂ�܂��B
�Ⴆ�Ύ��̂悤�ɍl�����܂��F
�����ԍ��F21738197
![]() 5�_
5�_
���̐}�ɂ����āA��Ƃ��āA
�E�u�g�����X�~�b�^ (Tx)�v��PC
�E�u�`���`���l���v��USB�P�[�u��
�E�u���V�[�o (Rx)�v��DAC
�\�\���Ƃ��܂��B
����Ƃ���́A�ʎq�����ꂽ�f�W�^���I�[�f�B�I�M����PC����USB�P�[�u����ʂ���DAC�ɓ`�����Ă����Ԃ�\�����ƂɂȂ�܂��B
���̂Ƃ��A
PC�ɂ�
�@1. �M���ʂɂ��RJ (�����_���W�b�^)
�@2. �����`�����C���̎��g�������ɂ��ISI (�V���{���Ԋ���)
�@3. EMI�̍����ɂ��PJ (�����I�W�b�^)
�@�������B
PC���p�����N���b�N�ɂ�
�@1. ���U��̔M�G���ɂ��RJ
�@2. ���U��̃X�v���A�X���g�ы��U�ɂ��PJ
�@3. ���U���H�̔���`���ɂ��DCD (�f���[�e�B�E�T�C�N���c��)
�@�������B
USB�P�[�u���ɂ�
�@1. ISI
�@2. �M����DCD������ꍇ�ɂ͎��g�������ƌ��������ɂ��DDJ (�f�[�^�ˑ��W�b�^)
�@����������B
������DAC�ɂ�
�@1. �V���b�g�E�m�C�Y�ɂ��RJ
�@2. ������H�����DDJ
�@���������邪�A���V�[�o�ɔ�������W�b�^�́A���V�[�o���������r�b�g�����ʂł��邩�ǂ����ɔ�ׂ�Ώd�v�ł͂Ȃ��B
�Ɠǂݓ��Ă邱�Ƃ��ł��܂��B
�Ȃ��A���V�[�o�ɂ����ẮA�W�b�^�̓��V�[�o���������r�b�g�����ʂł��邩�ǂ����ɔ�ׂ�Ώd�v�ł͂Ȃ��̂��ƌ����A�N���b�N�E���J�o�����s���ߒ��ŃW�b�^�����邩��ł��B�}�œ_���ɂȂ��Ă��āu���z�N���b�N�̏ꍇ�͓_����ڑ��v�Ƃ���e���W���A�z�V�X�e���ł͂Ȃ����Ă��炸�A�u��N���b�N�v�����PJ��DCD�̉e�����܂���B����ɁA�u��N���b�N�v�̑���Ƀ��V�[�o���O�̃}�X�^�[�N���b�N�Ɋ�Â��ăN���b�N�E���J�o�����s���邪�A���̉ߒ��Łu�W�b�^�E�N���[�j���O�v���Ȃ����̂ł��B
���̃v���Z�X�́A���̐}���ɂ���Ă悭�킩��܂��F
�����ԍ��F21738203
![]() 5�_
5�_
�V���A���I�[�f�B�I�M���́A���V�[�o�ɓ��B����܂łɁA�O�q�̗l�X�ȃW�b�^�̕����I�e���ɂ���ăt�j���t�j���ɂȂ��Ă��܂��B���̗����M��������A���V�[�o�͎��O�̃}�X�^�[�N���b�N��p���ăN���b�N�����A����ɂ��T���v�����O�E�|�C���g�̈ʒu�����肵�ĐM���̃��W�b�N�E���x���𐳊m�Ɏ��ʂ��܂��B����ɁA�e�T���v�����O�E�|�C���g�Ƃ���Ɋ֘A����f�[�^�J�ڂ̑��ΓI�Ȏ��Ԉʒu�ɂ���āu���z�I�Ȏ��Ԉʒu�v�����肳��܂��B���̉ߒ��Łu�W�b�^�E�N���[�j���O�v���Ȃ���܂��B�i�}�ŁA��r�I�t�j���t�j�����������͔g�`���A�o�͂����Ƃ��ɂ͔�r�I�J�`�R�`�ɂȂ��Ă���̂������\���Ă��܂��j
�u�W�b�^�E�N���[�j���O�v�Ɋւ��ẮA�Ⴆ�A���̕������Q�l�ɂȂ�܂��F
http://www.analog.com/media/jp/landing-pages/WEB_Lab/WCJ011.pdf
�Ȃ��AMinerva2000����̌�����A�u�N���b�N�M���̃W�b�^�[��ጸ����H�v���Ȃ���Ă���DAC�v�Ƃ́A�͍��ꎁ�ɂ��ihttp://ednjapan.com/edn/articles/1208/24/news015.html�j�A�u�N���b�N�W�b�^�[�̃��x���́A�I�[�f�B�I�}�X�^�[�N���b�N�̐������@�ɂ��قȂ�B��ʓI�ɂ͎�Ȑ������@�Ƃ��āA�i1�j�������U�N���b�N�A�i2�j�f�W�^���V���Z�T�C�U�[�E�N���b�N�A�i3�jPLL�N���b�N��3��ނ�����B�������A�������U�N���b�N���ł���W�b�^�[�ƂȂ�v�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�uPLL�̑���ɐ������U�N���b�N���g����DAC�v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�Ԗx�������ihttp://ednjapan.com/edn/articles/0709/01/news016_5.html�j�A�u�R�X�g�������Ȃ�Γd�����䔭�U��H�Ƃ���VCXO���g�p������@���L�����v�ƌ����Ă��܂��B
blackbird1212���A�u�E�`�ł��AESOTERIC�̃N���b�N�W�F�l���[�^�[G-02�iOCXO)��10MHz�̃��r�W�E���}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[��ڑ�������A���r�W�E����10MHz��UD-503�ɒ��ڂȂ����肵�Ďg���Ă��܂����A���̌o������́A�W�b�^�[���������ƍl������ʼn��̕ω��͊�������v���������̂́A�ނׂȂ邩�ȂƎv���܂��B
�܂��Ԗx�����ɂ��A�u��M���̃N���b�N�Ƃ��āAPLL�ɗ���Ȃ����@������B�Ⴆ�A��M���Ńf�[�^��D-A�ϊ�����O�ɂ�������FIFO�ifirst-in, first-out�j�������[�ɋL�^���A����𐅏����U�ɂ���W�b�^�[�̃N���b�N�œǂݏo�����ƂŃW�b�^�[��r���ł���v�Ƃ������ƂŁA����𗘗p�����̂�SOULNOTE sd2.0 �ihttp://www.kcsr.co.jp/decoder.html�j�ł��������A����قǐ����͂��Ȃ����������ł��B
�����ԍ��F21738209
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���_�߂ɂ�������A���肪�Ƃ��������܂��i�u���V�v���Ă������ƂȂ�ł���ˁH ����Ƃ��u���܂葹�v�Ȃ��Ƃ������Ă���s��p�҂��ĈӖ��ł����H���j�B
�����̒��̋@��ɑ��݂���W�b�^�[�́A�O�o�̃A�W�����g��EDN�̎����ɂ����������ł�300ps���x�ŁA��L�y�ȍĐ����̌��E�����Q�P�^�������킯�ł�����A�W�b�^�[�����ł���Ƃ���̂͂�͂薳���ł��傤�B
���Ɠd��D���̑�コ�u��l�̎���v�݂����Ȃ��Ƃ�����������Ă��܂����A����EDN�̋L���́A�N���b�N����IC(DIR)�̃x���_�[�������Ă�����̂ł��B�܂莩�А��i�̐�`�̂��߁A�N���b�N�̕i������́i�l�ԂɊ��m�ł�����x�Ɂj�d��ȉe��������A�Ǝ咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ������Ƃɗ��ӂ���K�v������܂��B��l�̎���ǂ��납�A�����������������Ă���̂ł��ˁB
�Ԗx�����́A�悭����A�u���{�e�L�T�X�E�C���X�c�������c�v�̐l�ł����ˁB
���O�̏������݂ŁA
���u�N���b�N�M���̃W�b�^�[��ጸ����H�v���Ȃ���Ă���DAC�v�Ƃ́A�uPLL�̑���ɐ������U�N���b�N���g����DAC�v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B
�Ə����Ă݂āA�܂��Ablackbird1212�����̌��ʂ�F�߂���́u���r�W�E���}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[�v�̂��Ƃ��Čf���Ă݂āA����Ȃ�A�������U��Ƃ����r�W�E���Ƃ͂ǂ�قǐ��m�Ȃ̂��ƁA���炽�߂Ċm�F���Ă݂܂����F
�u�N���b�N�W�F�l���[�^�[�̔��U��ɂ́A�Z�V�E���A���r�W�E���Ȃǂ̃A�g�~�b�N�N���b�N�i���q���v�j�Ɛ������g�������U�킪����B�����̏ꍇ�AXO�ATCXO�AOCXO�̏��ɐ��x�����܂�BDAC�ɓ������ꂽ�������U�킪XO�������ꍇ�A�v���X�}�C�i�X50ppm���炢�̐��x���ۂ����B���ꂪTCXO�AOCXO�ɂȂ�v���X�}�C�i�X1ppm�܂ʼn�������B���ꂪ���r�W�E���Ȃ�A�v���X�}�C�i�X0.00005pp���܂ʼn�����̂��B�Z�V�E�����q���v�Ȃ�v���X�}�C�i�X0.014ppt�ł���B�[���̐��������Ȃ�̂ŒP�ʂ�ς������Appt��1������1�A0.014ppt��1000������14�ɂȂ�B�v�ihttps://dime.jp/genre/144520/2/�j
���[��A�Ȃ�������Ď��Œ����Ă킩��Ƃ��킩��Ȃ����Ă����P�ʂ���Ȃ��C������B
����ł��Ablackbird1212����͂킩��Ƃ��������A���Ƃ��Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɑ��Đ����͂��Ȃ��Ƃ��Ă��E�E�E
����ɂ��Ă��A�u���r�W�E���}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[�v���Ă������ł���ˁB
�I�[�f�B�I�p�̐������U��ł��A�Ⴆ����͖�15���~�ł��ˁA�`�b�v��ŁF
http://www.ndk.com/jp/ad/2013/001/index.html
�����ہA�L���̒��g��ǂ�ł݂�ƁA�N���b�N�W�b�^�[�Ɖ����Ƃ̑��ւ́A�ɂ߂Ċ��o�I�ɒf�肳��Ă���ɉ߂��܂���B
�������ɁA�Ԗx�����̌��_�́F
�u�������A�W�b�^�[�ƒ�����̉����̊W�͂܂����炩�ł͂Ȃ��B�o���I�ɂ́A�W�b�^�[�̗ʂ����Ȃ��N���b�N�̂ق������������������邪�A�������ǂ�����Ƃ����āA�K�������W�b�^�[�̗ʂ��ŏ��ł���킯�ł͂Ȃ��B�W�b�^�[�̗ʂ́A�W�b�^�[�̕ϓ���A���Ȃ킿���̎��g��������\���킯�ł͂Ȃ�����ł���B�]���āA��������Nj�����I�[�f�B�I�@��̊J���ɂ����ẮA��͂�l�̎��ɂ�鎎���ƕ]�����s�����B�v
�Ȃ�Ƃ�����Ȃ�^^;
�����ԍ��F21738243
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
Minerva2000����
10�N�Ԃ��_������Ă���Ƃ́A�����ł��I
�wHMDI�P�[�u���̈Ⴂ�ʼn掿���ς��Ƌ���X�ցB�x�̃X���͂Ȃ��������ł��ˁB
������ł��A�Y��悤�ɂ��������Ȃ����u�ς��Ȃ��h�v�ŁAMinerva2000���u�ς��h�v��������ł��ˁI
�����ԍ��F21738250
![]() 3�_
3�_
�p�C������
�@�A�B�C�D�̊Ȍ��Ȃ܂Ƃ߁A���肪�Ƃ��������܂����B
��PC���̃f�W�^���]���g�̃W�b�^��`����c�_���Ă��A�Ӗ����Ȃ������悤�ł��B
�����́A�ȑO�Ƀp�C������̌���ꂽ�A
�u�t�j���t�j���̔g�`�ł����Ă��A�]���������ʂ̃f�[�^�̃o�C�i������v���Ă���ȏ�A���m�ɓ]������Ă���A�]���g�̌`�ǂ��ق����ǂ������ŏ������܂�Ă���Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��v
�Ƃ������Ƃł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���āA�܂Ƃ߂̇B�ŁA
�u���̃W�b�^�i�o�͂��ꂽ�A�i���O�M���������W�b�^�j�͎�ނ������ĉ����ɉe������͎̂����I�W�b�^�ł͂Ȃ��A�s�K���ɂɔ�������K�����̂Ȃ������_���ȃW�b�^�ŁA�s���I�h�W�b�^�ƌ����A�A�b�v�}�ł݂�Ɣg�`�̃g���K�[�ʒu����ŏ��̗����オ��ʒu�̕ϒ��̂��Ƃ������B�i��tj�̕����j�v
�Ƃ���܂����A�A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Ђ̕����ɂ��A���V�[�o�ɉe������W�b�^�́u�V���b�g�E�m�C�Y�ɂ��RJ�ƁA������H�����DDJ�v�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�����_���W�b�^�����łȂ��A�m��I�W�b�^�i�f�[�^�ˑ��W�b�^�j���܂܂�Ă��āA������̓K�E�X���z�ł͂Ȃ��ėL�E�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F21738265
![]() 5�_
5�_
Minerva2000����
�Y�킵�Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B
�v����ɁA�p�C������������ꂽ�悤�ɁA�uPC���̓]���g�Ɋ܂܂��u�`���W�b�^�[�v�i�ӂɂ�ӂɂ�ɂȂ鐬���A�n�[�h�f�B�X�N��̃Z�N�^�̈Ⴂ�ɋN��������̂��܂߂āj��D/A�ϊ��ɂ͊W�Ȃ��B�Ȃ̂ł��̓]���g���̂̃W�b�^�̘b�����Ă��Ӗ��͂Ȃ��v�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB
���́u�`���W�b�^�[�v�Ɋւ��镔�����A���W�Ƃ������ƂŁA�폜���ꂽ�Ɨ������܂����B
�����ԍ��F21738267
![]() 3�_
3�_
Symbolist_K����A
>http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5718JAJP.pdf
>��ǂ�ł݂āA���߂ăW�b�^�Ɋւ��čl���n�߂�����ł���B�ɂ킩�d���݂ł�^^;
���₢��A�W�b�^�ɂ��ď��߂čl�������āA�����ǂ�ł��ꂾ�������ł���̂͊����ɒl����ȁB
�Ȃɂ��̓d�q�@��̐v������Ă���l���H���邢��IQ�̍����l�ł��ˁB
�����ԍ��F21738437
![]() 4�_
4�_
2018/04/09 09:26�i1�N�ȏ�O�j
http://engawa.kakaku.com/userbbs/1193/#1193-67
�u�ǂ��������߂�l�v�Ɓu���o��Q��F�����Ă��Ȃ��l�v�������y�U�ő����Ă����Ӗ��ł���B
�����ԍ��F21738574
![]() 5�_
5�_
�s�v�h�m�a�h�q�c�@�g.�Q�U�S����̏������݂̃����N�Ŏv���o�������ǁA
���́AHAP-Z1ES�ł͂Ȃ�HAP-S1���g���Ă��邪�A
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579960/SortID=20206317/
�ɏ��������R�ɂ��A������CD���ڃ��b�s���O�@�\��flac�t�@�C�����������̂�PC�ɃR�s�[���āA48kHz 16�r�b�g�ɕϊ����āA�ēxHAP-S1�ɖ߂��Ďg���Ă���B
�����ԍ��F21739101
![]() 4�_
4�_
2018/04/09 17:05�i1�N�ȏ�O�j
http://jp.pioneer-audiovisual.com/components/networkaudio/philosophy.html
���ǁA�b�c�̃`���`�ȃf�[�^�����H���čĐ����Ă��B
�����ԍ��F21739263
![]() 1�_
1�_
Symbolist_K����A�����́B
���Ȃ��܂邳��̌o���ɂ��Ă����ǁA
���{��w���Y�H�w�����ƁB���͉�H���_�B
��t��w��w�@�H�w�����ȏC�m�ے��C���B���͐���H�w�B
���̌�SONY�ɓ��ЁB
AV�A���v�Ƃ��̊J���͌�N�̘b�ŁA���Ƃ��ƍ���CD�v���[���[���J�����Ă����l�ŁA
CDP-R1�{DAS-R1�Ƃ�CDP-R10�{DAS-R10�̐v�������l�Ȃ̂ł��B
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/cdp-r1.html
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/etc/das-r1.html
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/cdp-r10.html
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/etc/das-r10.html
�J���̉ߒ��ŁA���Ђɂ�����Ă������i�p�b�P�[�W��CD����n�������Ɨǂ��o����Ƃ������ƂŁA
�������Ă���IC�ɏ�w���ɋ���������ĊO����H��t�������邱�Ƃł���ɐ��\���グ�������ł��B
���̊J��������H�́ACD����n���f�W�^���Ńp�b�P�[�W�������Ƃ��Ɏg��ꂽ�����ł��B
�Ƃ����悤�Ȑl�Ȃ̂ŁA�@���̍H�w���ƂƂ����������҂݂����Ȑl�ŁACD�ł��v���Ȃ�ł���B
���R�f�W�^���Ƃ����������Ă��ē�����O�Ȃ�ŁA���������l��f�l�Ƃ������Ĕᔻ����͖̂��������肷���ł��B
�܂����������o���̐l���ƁA�o���タ����ƕς�����l�ł͂��邩�Ƃ͎v���܂����B
�}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[�ɂ��Ă��Ӗ��s���Ȕᔻ�������Ă���l�����܂����A
���R�[�f�B���O�X�^�W�I���v�����ŕK�{�̋@�\�Ƃ��Ďg���Ă�Ƃ������т�����킯�����A
�}�X�^�����O�ɁA����ɍ����x�̃Z�V�E���N���b�N���g���Ă���Ƃ���CD�������ł��B
�Q�l�i�����N��̉ߋ������Ƃ����ǂނƖʔ��������ł��j
�g�Z�V�E�����h ��Q�e�I�@�̕P - CESIUM ATOMIC CLOCK - SPECIAL EDITION�I��
https://blogs.yahoo.co.jp/namechan9999/15118697.html
>���Ȃ݂ɁA���Ȃ��p�C�I�j�A�ł�����
>BDR-209BK�^BDR-209XJBK�^BDR-211JBK�^BRD-S16PX
>������ł̓_���Ȃ̂ł����H
�ŐV�̃s���A���[�h4+���g����̂͋@�킪������̂ŁB
BDR-211JBK���ƃs���A���[�h3+�ɂȂ�܂��ˁB
http://pioneer.jp/pcperipherals/bdd/products/bdr_211j/
���ڂ�PC�����b�s���O�̕��@�ɂ�炸�A�ŐV�@�\�̂ق������S���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21739422
![]() 7�_
7�_
�A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Ђ̕����͂܂��A�`���P�[�u���ɂ���Ăǂ̂悤�ɐM�������邩���������Ă��܂��B����́A�`���l���̃V�X�e����SPDIF�ł�USB�ł�LAN�ł���{�I�ɓ��l�ɐ����ł��A�����P�[�u����USB�P�[�u����LAN�P�[�u����HDMI�P�[�u�����A������ʂ邱�Ƃɂ���āi����������A��i���������肷��Ȃ�����j�A�Ȃ��M��������̂��������Ă���܂��B
��̐}�ŁA�܂���N���b�N���甭����ꂽDCD��RJ��PJ�ƁA�g�����X�~�b�^���甭����ꂽISI��RJ��PJ�Ƃ����łɏ������ԂŁA�V���A���I�[�f�B�I�M�����`���`���l���Ɉ����n����܂��B�Ƃ͂����A���̒i�K�ł͐M���́A�}�̂悤�ɁA�܂���r�I�J�`�R�`�ł��B
�������A�`���`���l���́A�p�b�V�u�Ȃ̂Ŕ�������RJ�͖����ł���قǏ��������̂́A�`���l���̒�R�ƃC���s�[�_���X�s�����̑g�ݍ��킹�ƁA�\����ʂɂ���āA�����݁A���g����������l�łȂ��Ȃ邽�߁AISI�����݂܂��B
�V���A���M�����`���l����ʂ邤���ɁA�g�����X�~�b�^��������n���ꂽ��N���b�N�R����DCD������ISI�Ƒg�ݍ��킳���DDJ���`�����܂��B�iDDJ=DCD��ISI�j
DCD���Ȃ��ƐM���ɂ͊�������h�����Ȃ�����ǂ��A��N���b�NDCD�����݂���ƐM���ɋ����������h�������A�`���l�������ݏo����ISI����蕡�G�����܂��B����炷�ׂĂ̌��ʁA�`���`���l�����o�߂��ă��V�[�o�ɓn�����Ƃ��ɂ́A�M���́A�}�̂悤�Ƀt�j���t�j���ɂȂ��Ă���̂ł��B
��R�̑傫������i�ׂ�����j�P�[�u����A�C���s�[�_���X�s�����̐r�������P�[�u����A�\����ʂ݂�����P�[�u���\�\�܂�A�ȃP�[�u���\�\�g������A�P�[�u�������������肷��A�Ȃ�����t�j���t�j���ɂȂ�ł��傤�B
�ȏオ�u�`���W�b�^�v�ɂ��`���`���l���̉����̎d�g�݂ł���A����ɂ��u�Ȃ������̃P�[�u�����g���Ă͂����Ȃ��̂��v�������ł��܂��B�܂�́A�u�i���Ȃ��Ƃ����������ւ́j�A�P�[�u���ɂ���ĉ��͕ς��v�̂ł��B
�������A�t�ɁA�ƂĂ��Ȃ��ǂ��P�[�u�����g�����ꂾ�������ǂ��Ȃ�̂��ƌ����A�����Ƃ�����Ȃ��̂�����Ƃ���ł��B�Ƃ����̂��A������x�ǂ��P�[�u�����g���ĐM���̗�������x�ɂƂǂ߂���A�M�������V�[�o�ɓn�����������ɁA���V�[�o�����O�̃}�X�^�[�N���b�N���g�����N���b�N�E���J�o�����s���ߒ��ŁA�W�b�^�����邩��ł��B������A������x���i���̃P�[�u�����g���Ă���A����ȏ㍂�i���̃P�[�u���Ɍ������Ă��A���V�[�o����o�͂����M���̕i���͂قƂ�Ǖς��Ȃ��i����䂦���Œ����Ă��킩��Ȃ��j�\��������܂��B���������̏ꍇ�A���́u������x���i���ȃP�[�u���v�Ƃ����̂��ǂ̒��x���i���ł���悢�̂������肷��̂��܂�����Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B
�����ԍ��F21739494
![]() 6�_
6�_
���Ȃ��܂鎁�́A����Ⴂ���͗��h�ȃG���W�j�A�������̂�������Ȃ����A�ǂ����ŁA
�uUSB�P�[�u���ɂ͂ւ�������A�������牽�~���̂Ƃ���Ƀe�[�v�������Ɖ����ǂ��Ȃ�v�Ƃ����悤��
�b��ǂ�ŁA���̐l�̓I�J���g�n���Ɖ��͎v�������ǂȁB
����ƁA�W�b�^�͔��U��̎��g���̒Z������x�i�ʑ��G�����\�j�ɉe��������̂ŁA��������x�ɗD���Z�V�E��
�Ƃ��͊W�Ȃ���ł͂ƒN���������Ă����悤�ȁB
�����ԍ��F21739516
![]() 3�_
3�_
tohoho3����
>����Ⴂ���͗��h�ȃG���W�j�A�������̂�������Ȃ���
����͈Ⴄ�Ǝv���܂���B
�V�ˌn�͎Ⴂ������V�N�܂ŕςȂ܂�܂ŁA���܂�͂��Ȃ��̂ł��B
tohoho3����͂܂��߂ȏG�ˌn���Ǝv���Ă��܂����V�ˌn�͌����ł����H
�G�ˌn�ƓV�ˌn�̈Ⴂ�̂ЂƂƂ��ẮA
�G�˂͗����������Ȃ����̂͋��ۂ��邩����ȗ��������Ĕ[�����邩�����ǁA
�V�˂͗����o���Ȃ����̂ł��A���̂����킩�邩���A�Ƃ������ƂŎ����Ƃ���ł��B
�킩��Ȃ������̓I�J���g�Ɍ����邩������Ȃ����ǁA�ւ����𖾂���邩������Ȃ��ł�����B
>��������x�ɗD���Z�V�E���Ƃ��͊W�Ȃ���ł͂ƒN���������Ă����悤��
�Z�V�E����r�W�E���̒Z������x�͈����̂ł����H
�Z�V�E����r�W�E�����Z������x���������̂��ĂȂ�ł����H
OCXO�̕�������ł��傤���H
����������
����A�������H�E�E�E���v���Ԃ�B
�����ԍ��F21739696
![]() 3�_
3�_
�u�ǂ�������w�@�C���̓V�˂������Ă��邱�ƂȂ��v���āA���ɂ͂��悢��_�ɋl�܂����؋��ɂ��������܂��E�E�E�B
�����ԍ��F21739819
![]() 3�_
3�_
�uUSB�P�[�u���ɂ͂ւ�������A�������牽�~���̂Ƃ���Ƀe�[�v�������Ɖ����ǂ��Ȃ�v�Ƃ����悤��
�b��ǂ�ŁA���̐l�̓I�J���g�n���Ɖ��͎v�������ǂȁB
�Ƃ�����L�̋^��ɑ����
�G�ˌn�ƓV�ˌn�̈Ⴂ�̂ЂƂƂ��ẮA
�G�˂͗����������Ȃ����̂͋��ۂ��邩����ȗ��������Ĕ[�����邩�����ǁA
�V�˂͗����o���Ȃ����̂ł��A���̂����킩�邩���A�Ƃ������ƂŎ����Ƃ���ł��B
�킩��Ȃ������̓I�J���g�Ɍ����邩������Ȃ����ǁA�ւ����𖾂���邩������Ȃ��ł�����B
�����Ȃ��Ă܂��B���������d�v�Ȃ̂̓e�[�v�������Ɖ����ς�邩�ǂ����i���ۂ��̂��̂��ؖ��ł��Ȃ��Ȃ炻�ꂱ���Ӗ����Ȃ��j�Ȃ̂ł����A�����͊��S�ɃX���[����Ă��܂��B�����āA�v�͓V�˂������Ă������A�����������Ƃ�����̂��ƐM����������A�ǂ����ĂȂ̂���������͏ؖ�����邩������Ȃ��B�����炩�Ȃ��܂鎁�����������Ƃ͂��������Ǝv���Ă��A���̏ؖ�������ĂȂ��Ă��M�p�ł���B�������͔ے�͕s�K�ł���Ƃ��������ł��B
���������̂�M�S�Ƃ����̂��Ǝv���܂����A�I�J���g�ł͂Ȃ��@���ł��ˁB���������l���̐l�͂܂����_����ɂ����āA���̌��_�ɑ��ēs���̗ǂ����߂�������A�s���̗ǂ�����ڂɓ���܂���A���Ȃ��܂鎁�W�̉�b�͐������Ȃ��Ǝv���܂��B���l�͓��ɂ��Ȃ��܂鎁�ɑ��Ă͔ے�I�ł��m��I�ł��Ȃ��ł��B����͂Ȃ�̘b�����Ă��邩�ŕς���Ă��邱�ƂȂ̂ŁA�N���Ƃ�����܂�W�Ȃ����낤�Ƃ����X�^���X�ł��B
�����ԍ��F21740162
![]() 4�_
4�_
2018/04/10 00:04�i1�N�ȏ�O�j
https://www.sony.jp/msc/enjoy/products/feature/20140501/
�r�n�m�x�͂b�c�����K�i���������Ƃ�F�߂��A���H�����ĈВ����Ă�����Ȃ����[�J�[���ˁB
�b�c�ׂ̈ɂǂꂾ�������̉��y���D�Ƃ��ꂵ�߂�ꂽ���Ƃ��A���y�ƊE�̉��_�ƌ����ׂ����낤�ˁB
(^o^)� �� ���₷�݁[
�����ԍ��F21740223
![]() 5�_
5�_
���݂܂���A�Ō�̏������݁i [21739494] �j�ŁA�厖�ȂƂ���Ȃ̂ɁA�������ԈႦ�܂����F
�����h
�Z�����g
�����ԍ��F21740249
![]() 2�_
2�_
tohoho3����
�������A���̓N���V�b�N�D���̕��n�j�q�i�u�P�_���H�j�ŁA�w���R�|�x�̋g�c�G�a�̉��y�]�_��ǂ�ň炿�܂����B���܂ʼn��y�ɑ��ĕ��w�I�ȃA�v���[�`�������Ă��Ȃ������̂ŁA������ƉȊw�I�Ȃ��Ƃ��l�������Ȃ�����ł��B����Ȋw�łȂ���悢�̂ł�����
�����ԍ��F21740264
![]() 3�_
3�_
�s�v�h�m�a�h�q�c�@�g.�Q�U�S����A����ɂ��́B
���w�E���肪�Ƃ��������܂��B
�����N��ɋ����Ă������A�w�厖�Ȃ��̂������Ă����cCD�T�E���h�̂ǂł������Ƃ����x�F
https://www.barks.jp/news/?id=1000104767
�ǂ݂܂����B
���u���y�Ŋ�������v�Ƃ����͔̂]�̓����Ȃ킯�����A�ǂ�����X�͉��y��CD�ɍ��ݍ��ޒi�K�ŁA�]��������������p���[������������A��Ԍ��������c�|�������̂悤�ȕ������킬���Ƃ��Ă��܂��Ă����炵���B����̐������S�������ł��A���ɂ͕������Ȃ������g���܂�ł���ƁA�T�E���h�͐��X�������������ӂ��S�n�悢���y�ɕ�������B����͒�����ׂ��s���ΒN�ł��ȒP�Ɋ������錻�ۂ��B���̍����g���y�ڂ��]�ւ̊�����p�́A���y�݂̂Ȃ炸���R�E�̊����ł��m�F�ł��鎖���ŁA�Ȃ�ƁA�ł��F���ȉ������ɂ���̂͐X�̒��������肷�邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B���ƔM�щJ�т̒��Ȃǂ́A����ɉ����l�X�ȍ����g���܂�ł���A�l�Ԃ̔]�Ɍ��₩�ȉ��y��^���Ă����Ƃ��B�X�̎C��鉹�A���̉��A���A���A�����c�l�X�ȉ������荬���钆�A200KHz���̍L�͈͂ȍ����g�������Ă���̂́A�����͒��������肷�邱�Ƃ��������Ă���B
����́A�����w�҂̑勴�͎��̎咣�Ɋ�Â����̂ł����A�l���������܂��B
http://www.nttcom.co.jp/comzine/no013/wise/index.html
�ނ͂�����ł́A�������������g���A�u�l�ނ̔]�̔��B�𑣂����v�Ƃ܂Ō����Ă��܂��I
����ȉ��́u�|�������v�A�������ɁA�J�b�g���Ă��܂��̂͂��������Ȃ����܂��ˁB
��͂�A�n�C���]�������ׂ��ł��傤���I�H
�����ԍ��F21740295
![]() 4�_
4�_
tohoho3����
MAP-S1�̃N�`�R�~�́wDSEE HX�̍����Ԑ��\�ɂ��āx��
HAP-S1�̃N�`�R�~�́wDSEE HX�̍����Ԑ��\�ɂ��� ���̂Q�x
�����[���ǂ܂��Ă��������܂����B
tohoho3����ƃp�C������ɂ��F�X�ȑ���ɁA�d�v�Ȏ������܂܂�Ă���Ǝv���܂����B
�����ԍ��F21740330
![]() 2�_
2�_
blackbird1212����
�܂��A�F�X�����Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B
���䗲���A1980�N�ォ�炲����Ȃ̂ł��ˁB�m��܂���ł����B
CDP-R10�{DAS-R10�I �������������ł��ˁI�i���v200�������ǁj
����Ȃ��̂�v���ꂽ�����A�u�f�l���x���v�ƕ]���邽�߂ɂ́A����ɗD��Ȃɂ���v���邩�Ȃ��Ă��ď��߂Ă��̎��i������Ƃ������̂ł��傤�I
��̃P�[�u���́u�w�\�`���[���v�����āA����u����̓I�J���g����Ȃ��I�v�ƌ����āA���̌�����������Ă��܂���F
http://kanaimaru.com/Cable/C009.htm
http://kanaimaru.com/Cable/C010.htm
���U���Ɖ��̊W�́A�{�̃V���[�V�̒��ŋN���邱�ƂƁA�P�[�u���ŋN���邱�Ƃ͓����ł��B�܂��U�����ړ_�ɓ���܂��B����ƐڐG�̏�Ԃ��ς��U���ϒ���������܂��B�܂�g�`�̍������U���ŕϓ�����̂ł��B�����Ă��̐U���ϒ��̉��ւ̉e���̓A�i���O�P�[�u���ɂ���ׂ�ƃf�W�^���P�[�u���̂ق��������ł��B
���w�\�`���[���Ƃ́F �ȒP�ɂ����ƁA�P�[�u����̐U��(��ݔg)�̏����݁A�����Ƀ��J�I�ȉ��H�����܂��B���낢��ȕ��@������܂����A�ȒP�Ō��ɖ߂��閜�l�����̕��@���A��ݔg�̕�(�U���̑傫���ꏊ)�������āA�����Ƀe�[�v��\�邱�ƂŃ_���v����Ƃ������@
���W�b�^�ɂ͒l���傫����(�������h��Ă��邪)����܉����ɊQ�̂Ȃ����̂�����܂��B��ʓI�ɂ͑傫�ȃW�b�^������Ɖ����{�P�܂����A�������Ȃ���Ή��y�ӏ܂̎ז��ɂ͂Ȃ�܂���B
���̈���ŁA�ق�̂킸���ł������ɊQ�̂�����̂�����܂��B�P�[�u���Ŕ�������W�b�^�͒l�Ƃ��Ă͐����������̂ł����A�l�Ԃ͕q���ɍ����������܂��B
�Ȃ��q���Ȃ̂��̂��Ȃ��܂���ł��B
�l�Ԃ̎��͎h�������߂ăp���X�����Ă��̃p���X��]���������ĉ��Ɣ��f���܂��B���̂Ƃ����鉹��ƕʂ̉���̋���W�́A�p���X�̖��x�ƂƂ��Ƀp���X�̓����������W����Ǝv���܂��B�g�`�ɃW�b�^������A���̃W�b�^������̎��g�������������܂�ł���ƁA���̎��g���̐_�o�p���X�̔��������ɃN�Z���o�܂��B���ꂪ�������ς�錴���ł��B
�܂�����ł͂Ȃ������Ȃ̂ŁA�o���X���o��̂��ق�̂킸���ł��O���ォ�ł��̂����������������ς��ł��傤�B�W�b�^�ɂ�鉹�̕ω��͎��g�����������U���Ă���Ƃ��͂��Ȃ�݊��ŁA�����͒P�Ƀ{�P�邾���ł����A�W�b�^�Ɋ܂܂����g���ɃN�Z��������A���Ɋy���̉e�����鎞�͂��̂������_�o���Ɍ����ċ�������邱�Ƃ�����܂��B
���̗��R�́A���o���A�i���O�ʂ��p���X��ɕϊ����ė������Ă��邽�߁A�킸���ȈႢ�������Ƃ������̂������C���p�N�g�̑傫�Ȍ��ۂɕϊ�����Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B
�܂��A�I�[�f�B�I�̑����ʼn�������ł��Ȃ����R�́A���̎d�g�݂𗝉���������@���Ȃ�����ł����B
�\�\�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ炵���ł��I
�����ԍ��F21740383
![]() 4�_
4�_
Symbolist_K�����
����͂␦���ł��ˁB���������S���̋L����T���Ă���̂͂���������ς��Ǝv���܂����ǂˁB
���Ȃ��܂鎁�̍˔\�͐����w�ɂ܂ŋy��ł���Ƃ������Ƃł��ˁB��啪��Ƃ͈Ⴄ�悤�ȋC�����܂����A�ǂ����ŕ�����Ă���̂��A���邢�͂�����������ɏڂ������m�荇���Ȃǂ���̂����m��܂���ˁB�m���ɓV�˂�������܂���ˁB
�悭�`�u�V�X�e���ȂǂŃT���E���h�̈ʒu����o�鉹�ɑ��Đl�Ԃ̒��o���q�����Ƃ����邱�Ƃ�����܂����A���Ȃǂ��Ƃ���͐l�Ԃ��O���̏��͎�Ɏ��o�ɂ���ĔF������̂ɑ��āA���ʂ����Ƃ��������͉��ɂ���ĔF�����悤�Ƃ���B����Ď��E�̎��p�ƂȂ�����ɑ��Đl�Ԃ̒��o�͂��s�q�ɂȂ���̂Ɛ����ł���B�ȂǂƑf�l�Ȃ���ɍl���邱�Ƃ͂���܂��B���������̂Ƃ͂������Ⴂ�܂��ˁB
������ɂ��Ă��ǂ̕����ɑ��Ē��o���q���Ȃ̂��Ƃ����̂́A�����w���琶���w�܂Ō����Ώۂ��L���A�����Ȃǂ����Ď��o�ƒ��o�̑��֊W������o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�ł��A���̂��߂ɂ����������������邩�Ƃ����̂́A�ړI���Ȃ��ƂȂ��Ȃ��\�Z�͏o�Ȃ��ł��傤�ˁB���Ȃ��Ƃ��I�[�f�B�I�̂��߂Ƃ����͖̂������ۂ��ł��B�ł��ʔ������ł��B
�����ԍ��F21740396
![]() 4�_
4�_
blackbird1212����
������x�A����X�ŁA���r�W�E����Esoteric��Grandioso G1��̌��������Ƃ�����܂��BP1�{D1×2�{G1�{M1×2�{C1�Ƃ����u���ɂ̃G�\�e���b�N�v��B&W��800��炵�Ă�����ł����A����͂���͂������ł����B�ł��A��������G1���O���������Ă��Ȃ��̂ŁA���̉���G1���ǂ�قǍv�����Ă������͂킩��Ȃ��̂ł����B
�g�Z�V�E�����h�I ���������ł��ˁI ��̃V�X�e���Œ����Ɛ^�����������ꂻ���ł��ˁB
�h���C�u�̂��w�삠�肪�Ƃ��������܂��B
�Ȃ�قǁA�ŐV�̃s���A���[�h4+���g���������ȃ��b�s���O���ł���@��Ƃ������ƂŁABDR-S11J-X��BDR-S11J-BK�Ɍ���̂ł��ˁB�ǂ��炩�������Ō������܂��B
�����ԍ��F21740404
![]() 3�_
3�_
�P�[�u���́u�w�\�`���[���v�̌��������ǂ��ǁA�P�[�u���̒����Ō��܂����̉��̎��g���ł̒�ݔg�i���U�j�ɋN������
�Ƃ����̂͂܂������ł���Ƃ��āA�e�[�v�����Ă��̋��U�̑������ƁA�ʂ̓���̎��g���ŋ��U�����Ȃ����H
�����ԍ��F21740485
![]() 3�_
3�_
>��͂�A�n�C���]�������ׂ��ł��傤���I�H
http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/pdf/2006/17sentan_11.pdf
�ɁA���{�@�B�H�ƘA����ϑ����āA�勴 �͎����ψ����̃O���[�v���쐬�������|�[�g������B
�ǂ��Ȃ�ł����ˁB�ڂ����ǂ�łȂ����ǁA�Y�ꎁ�������悤�ɁA�����̎d���̐�`�������ɂ���
�Ƃ͎v�����A���O�̍����g���Ɖu�����A�X�g���X���������߂�Ƃ����͔̂F�߂�Ƃ��Ă��A
�n�C���]�����̉��O�����g�����Ƃ����̂́A���R�E�ɑ��݂��鍂���g�����ł͂Ȃ��A�}�C�N������
������̎G�������i���邢�́A���M���Ƃ̍��ϒ������j����Ȃ��́H���ꂾ������A
�����g���ш���̍����g������\�����ĉ��O�̑ш�ɊO�}����DSEE HX�̕����A
��莩�R�ɋ߂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������R�ŁA���́ACD��44.1kHz�A16�r�b�g�̃f�[�^��48kHz�A16�r�b�g
�ɕϊ����āADSEE HX���I���ɂ��čĐ����Ă���B
�����ԍ��F21740791
![]() 5�_
5�_
�Ɠd��D���̑�コ��
���Ȃ��܂鎁�͕��X�ɏ����U�炩���Ă���̂ŁA����������Ƃ܂Ƃ߂Ă����Ƃ��肪�����̂ł����A�O�O������o�Ă��܂���I
���l�Ԃ��O���̏��͎�Ɏ��o�ɂ���ĔF������̂ɑ��āA���ʂ����Ƃ��������͉��ɂ���ĔF�����悤�Ƃ���B����Ď��E�̎��p�ƂȂ�����ɑ��Đl�Ԃ̒��o�͂��s�q�ɂȂ���̂Ɛ����ł���B
�Ȃ�قǁB���o�͎��o�Ɣ�ׂĔ]�̂��Â��w�Ɍ��т��Ă���Ƃ������Ă��܂��ˁB
������ň��p�����勴�͎��̋L���̎��̂悤�Ȉ�߂��Q�l�ɂȂ�܂��F
�u�l�ԂɂƂ��ďd�v�ȃ����[�g�E�Z���T�[�ɁA���o�ƒ��o������܂��B���o�Ƃ����͎̂�̓I�ŁA�����ł�����x����ł���B�u�܂Ԃ��v�����Ί�����̎��o���̓��͂����ނ��Ƃ��ł��܂���ˁH
���������ɂ́u���Ԃ��v�Ȃ�Ă��̂͂���܂���B���B�͕�e�̂����̒��ɂ���������A�����Ė����Ă��鎞���A�₦�����肩�牟���Ă��鉹������鐶���𑗂��Ă��܂��B�����璮�o�́A�ꎞ���x�݂��Ȃ��Ƃ����_�ŁA�S����x�ƈꏏ�Ȃ�ł��B������o���g���Ȃ��Ă��l�Ԃ͐����Ă����܂��B�������A���B����芪���������Ƃ��ĂƂ炦��ۂɁA���o�͓��ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���Ƃ����܂��B�v
�܂��A���o���i��嗋��ƕ��t���o���i��O���K�ǂ��������Ă��邱�ƂƂ��W���邩������܂���ˁB
����ɂ��Ă��A���̂悤�Ȑ����I�Ȃ��ƂɊւ��鐄���́A�Ȃ��Ȃ�������̂�����ł����B
�����ԍ��F21740814
![]() 4�_
4�_
�݂Ȃ��܂���ɂ��́B
�X���b�h�̂���͂ǂ��ւ��A�������肩�Ȃ��܂鎁�_�ɂȂ��Ă��܂��Ă��ĕs�тł����A���������������̂ŃR�����g���܂��B
�Ɠd��D���̑�コ��[21740396]
>���Ȃ��܂鎁�̍˔\�͐����w�ɂ܂ŋy��ł���Ƃ������Ƃł��ˁB�i�����j�m���ɓV�˂�������܂���ˁB
�Ƃ������Ⴂ�܂����ASymbolist_K����[21740383]�ň��p����Ă��钆�Ő����w���ۂ����e�Ƃ�����
>�l�Ԃ̎��͎h�������߂ăp���X�����Ă��̃p���X��]���������ĉ��Ɣ��f���܂��B
�����ł��B�i���́j��p���X�I�ɐ_�o��`���Ƃ����b�͊W����ł͂����펯�I�Șb�Łi�Ə�����Symbolist_K�����ׂ����ł���)�A�����m���Ă��邭�炢�ŁA���������m���ł͂���܂���i�܂������V�˂Ȃ̂����m��܂���A���ăW���[�N�ł���j�B
�ŁA����ȊO�͉����ł����Ȃ��A���ꂪ���̂܂ɂ��u���ꂪ�������ς�錴���ł��v�ƒf�肳���̂͂����ւ�悭���郌�g���b�N�ł��B
���ꂩ��A���͏�L�̂Ƃ���A���Ȃ��܂鎁�̘b�͔��≯���₠���܂������������đf�l���x���ł���Ǝw�E���Ă��܂����A�������̂�f�l�ł���Ƃ͌����Ă��܂��A�ᔻ�����Ă��܂���B
��l�܂�C���̍\���s���Ǝ�ɐg��u���̂͌������ł��傤�B���Ƃ����������f���Ō��`�i����ł�j����悤���Ƃǂ����Ǝv���܂����A�����̂g�o�Ŗ��邭�炢�̂��Ƃ܂Ŕᔻ����̂͂�����ƐȂ��C�����܂��B�t�Ɍ����A�ς��h�̂��������������b�͂����Ƃ��Ă����āA����̉\����D�荞��Ŋy���ނ̂���l�̃I�[�f�B�I�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B
�����ԍ��F21740860
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
�w�厖�Ȃ��̂������Ă����cCD�T�E���h�̂ǂł������Ƃ����x�F
https://www.barks.jp/news/?id=1000104767
�̌��l�^�ł��ˁI
���{�@�B�H�ƘA����Ɉϑ�����ď����Ă���ȏ�A�����ɏ��Ǝ�`�I�Ȃɂ���������܂��ˁB
�]�̌����ˁu�n�C�p�[�\�j�b�N�E�G�t�F�N�g�v�̔����I�[�[�炵���ł��ˁB
�i�u�n�C�p�[�\�j�b�N�E�G�t�F�N�g�v�����������鍂���g������L�x�Ɋ܂ޔ���ȉ����A�����l�̔]���A�����A�����������܂ފ�]�����������A����f�������܂��܂Ȑ����A�S���A�s���������Ђ����������ہj
���勴��́A������ PET �����ɂ����āA�������]�g���g�����ƗL�ӂȐ��̑��ւ������]���̈悪����A����́A���y���������Ȃ����[�J�b�g����x�[�X���C���������ł͑O���t�^���O��𒆐S�Ƃ���̈�Ɍ�����̂ɑ��āA�A�����̐M���\���������A���y�Ƃ��Ē�������n�C�J�b�g���A�t�������W���̏������ł́A����ɓ����t���O��������邱�Ƃ����������Ă���[31]�B�����̂��Ƃ���A���y�̂悤�Ɏ��ԓI�ɘA���ȍ\��������������]�ɓ��͂���Ă��鎞�A�]������̃��[�h���ω����A�����g�����ɂ�郂�W�����[�^��p��]�[���ɓ`�B�����H�̃Q�[�g���J����āA�����ɍ����g�����̍�p���y�Ԃ��Ƃɂ��n�C�p�[�\�j�b�N�E�G�t�F�N�g���������ƍl�����B���̓��m�o���f���ɂ���āA���݂܂łɌ��������ꂽ���������̂��ׂĂ��A�����Ȃ���I�ɐ������邱�Ƃ��ł���B
�u���݂܂łɌ��������ꂽ���������̂��ׂĂ��A�����Ȃ���I�ɐ������邱�Ƃ��ł���v�Ƃ́A�������ł��ˁI
���n�C�p�[�\�j�b�N�E�G�t�F�N�g�́A�f�W�^���R���e���c�̋K�i�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��ASACD �� DVD �I�[�f�B�I�Ȃǃn�C�f�B�t�B�j�V�����E�f�W�^���I�[�f�B�I�E���f�B�A�̊J���̌_�@�ƂȂ��Ă���B����̃f�W�^���R���e���c�̏����̕�������]����W�]�����ŁA���̃n�C�p�[�\�j�b�N�E�G�t�F�N�g�Ƃ������ۂ��̂��̂ɂ��ďڂ������̂�c�����邱�Ƃ͏d�v�ł���B
�I�[�f�B�I�I�ɂ́A�u�n�C���]���v�A�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�iSACD��DVD-Audio�͋K�i�Ƃ��Ă͂������ɂ����Ă��܂����j
�Ƃ肠�����A�u�j�Z���]�v�ɂ��܂���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���A�ǂ��n�C���]�������܂��傤�I
�����ԍ��F21740867
![]() 4�_
4�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�u�����w���ۂ����e�Ƃ�����
>�l�Ԃ̎��͎h�������߂ăp���X�����Ă��̃p���X��]���������ĉ��Ɣ��f���܂��B
�����ł��B�i���́j��p���X�I�ɐ_�o��`���Ƃ����b�͊W����ł͂����펯�I�Șb�v
�����͒P�Ȃ�b�̖��ŁA����ɑ���
�����̂Ƃ����鉹��ƕʂ̉���̋���W�́A�p���X�̖��x�ƂƂ��Ƀp���X�̓����������W����Ǝv���܂��B�g�`�ɃW�b�^������A���̃W�b�^������̎��g�������������܂�ł���ƁA���̎��g���̐_�o�p���X�̔��������ɃN�Z���o�܂��B
�Ƃ����̂��A���Ȃ��܂鎁�́i�����w�I�j�咣�̍������Ǝv���܂����A����͂ǂ��Ȃ�ł��傤���H
�����w�I�ɑÓ����ǂ����́A�悭�킩��܂���B
���Ȃ��܂鎁�́u�����̂g�o�Ŗ���v��l�Ȃ̂ł��傤���B���낢��Ɗy�������ł͂���܂��ˁI
�����ԍ��F21740908
![]() 4�_
4�_
�܂��A�u��Â��v���̂��闝�_�ł͂���܂��B
������ɂ���A���_�͂����܂Łu�����v�ł����āA���ۂɉ����Ă݂ėǂ��Ȃ������Ƃ��m�F�ł��Ȃ���A�����̕����l�Ɋ��߂邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B���Ȃ��܂鎁�́u�w�\�`���[���v�ł������Ƃ��Ă���킯�ł͂���܂�����̂ˁB
�P�[�u���́u�w�\�`���[���v�ʼn����ǂ��Ȃ������Ƃ��A�ނ͊m���Ɏ��Œ����Ă���Ƃ͎v���܂��B�����́A�����̌o���ɐ����Ă��A�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i���͒����Ă͂��܂��j
�����ԍ��F21740994
![]() 4�_
4�_
Symbolist_K����
>�����̂Ƃ����鉹��ƕʂ̉���̋���W�́A�p���X�̖��x�ƂƂ��Ƀp���X�̓����������W����Ǝv���܂��B�g�`�ɃW�b�^������A���̃W�b�^������̎��g�������������܂�ł���ƁA���̎��g���̐_�o�p���X�̔��������ɃN�Z���o�܂��B
>
>�Ƃ����̂��A���Ȃ��܂鎁�́i�����w�I�j�咣�̍������Ǝv���܂����A����͂ǂ��Ȃ�ł���>�����H
���������̂����Ȃ��܂鎁�̂��܂��Ƃ���Ȃ�ł���ˁB��̈��p���͂Q�̕����琬���Ă��܂����A�O�i�́u�W����Ǝv���܂��v�Ƃ���悤�ɁA���������܂��ȊT�O���A����ɐ����Ō���Ă���ɂ����܂���B��i�́u�N�Z���o�܂��v�ƒf�肳��Ă��܂����A����͑O�i�̉��肪�O��ɂȂ��Ă��āA���ǑS�̂��i�����w�Ɋւ��Ă͋��炭�f�l�Ǝv����j���Ȃ��܂鎁�ɂ�鉯���ł�������܂���B
�����ƔF��ł���̂͂����������������u�b�̖��v�̕����ł�������܂���B���̂킸���ȏ��j���_��Ɍ���Ƃ��낪���Ȃ��܂鎁�̍˔\�ł���A�ƊE��}�j�A���炠�肪��������䂦�Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ł͓V�˂ƌ����邩���m��܂���B
�����������ۂ������Ŋm�F���Ă���̂��ǂ������������Ă����܂�Ӗ����Ȃ��Ǝv���܂����A���͉��^�I�ł��ˁB
�����ԍ��F21741055
![]() 7�_
7�_
�@�b���A�Z�p�I�Șb����A�����w�I�Șb���������āA����ɔ]�̓����Ɋւ��镔���܂Ŋ܂܂�Ă��܂��ƁA���̊Ԃɂ��]�̒��o�ɋN�����������v���V�[�{�[���ʂȂǂ��������Ă��܂��āA�{���ɂ͂����ĉ������ω����Ă���̂��ǂ����Ƃ��������������ɂ����Ȃ��Ă���悤�ȋC�����܂����ǂ��ł��傤���B
��������
https://youtu.be/dlt5FgCEuk4
�����̉����ł����A�J��Ԃ��čĐ�����ƁA�Đ����邽�тɉ����i���g���j���ǂ�ǂ��Ȃ��Ă��܂��������������܂��B���̏ꍇ�A�N�����������ω����Ă���Ǝv���Ă��܂����ǁA�����I�ɂ͉����ω����Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B
�����ԍ��F21741494
![]() 7�_
7�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����̂킸���ȏ��j���_��Ɍ���Ƃ��낪���Ȃ��܂鎁�̍˔\�ł���A
�Ƃ������Ⴂ�܂����A
���䎁�́A�j���_��Ɍ���Ă���Ƃ������A��������Ă���̂����ɂ͂����ς�킩��܂���B
���g�`�ɃW�b�^������A���̃W�b�^������̎��g�������������܂�ł���ƁA���̎��g���̐_�o�p���X�̔��������ɃN�Z���o�܂��B
�u�_�o�p���X�̔��������ɃN�Z���o��v�Ƃ����͈̂�̂ǂ��������Ƃł��傤���H �u�����ɃN�Z���o��v�Ƃ́H
�����ɑO�����Ⴂ���N�����Ă��܂��A�Ƃ������Ƃł��傤���H
����Ȃ�A�Ⴆ�A�h�~�\���~�h�\�ɕς���Ă��܂��̂ł��傤���H �����Ȃ�������y������Ă��܂��܂��B
�����o���A�i���O�ʂ��p���X��ɕϊ����ė������Ă��邽�߁A�킸���ȈႢ�������Ƃ������̂������C���p�N�g�̑傫�Ȍ��ۂɕϊ�����Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B
���o��嗋��̒��ɂ���@�т̉^���ɂ���ăA�i���O�ȉ���d�C�M���ɕϊ����Đ_�o�ɑ���A�Ƃ����̂͂����̂ł����A���̓d�C�M���̏������ς���Ă��܂�����A�u�����{�P��v�ǂ���̘b����Ȃ��āA�ʂ̉��y�ɂȂ��Ă��܂���Ȃ��ł����H
���̂��Ƃł��傤���H
�������������ۂ������Ŋm�F���Ă���̂��ǂ������������Ă����܂�Ӗ����Ȃ��Ǝv���܂����A���͉��^�I�ł��ˁB
���䎁�́A���Ŋm�F���Ă��邱�Ƃ����Ă��܂����F
http://kanaimaru.com/Cable/C010.htm
�u�w�ŃP�[�u���Ɍy���G��A���肶��Ɠ������Ă䂫�܂��B�t�b�Ɖ����ς��(�ቹ����������o����A�N�Z�����ƂȂ����Ȃ�����)�Ƃ���������܂��B���̕��@�͘A���I�ɏꏊ���T�[�`�ł��邱�Ƃł��B���ʂ������B�ł������S���ŋp���Ȃ��Ƃł��܂���B�Ȃ�ł������͂����ł����A���������̂͂܂��ɗ\�f����������I���B�S���킩��Ȃ��Ȃ�܂��B�S�ɂ��Ē����܂��B�v
http://kanaimaru.com/da5700es/1209HiVi.htm
�uUSB A�[�q������38mm�̂�����ɐU�����W�܂�߂�����悤�ł��B�����Ƀe�[�v�������Ɖ����ς��܂���B�e�t�����e�[�v��4mm���ɃJ�b�g���Ċ����Ă݂܂��傤�d�d�d����ς艹�ɗD�������o�Ă��܂����ˁB���Ƃ��Ƃ̎��������c���Ă��邵�A�����N���A�[�ł��B�v
�ނ̓E�\�����Ă���̂ł��傤���H�@���̂��߂ɁH
�����ԍ��F21742839
![]() 3�_
3�_
�p�C������
�܂������[����̂��Љ�A���肪�Ƃ��������܂��B
�u���������v�A�ʔ����ł��ˁB�m���ɁA�I���Ə��߂����[�v�����Ē����ƁA�����ɉ������オ���Ă����悤�ɕ������܂��ˁB
���o���܂��A���o���l�A�������ۂƂ��Ă��܂���Ղ����ʂ�����̂ł���A�v���V�[�{���ʂʼn��Ƃł��ς�肻���ł��ˁB�u�ǂ����Ȃ�v�Ǝ���ɍÖ��p�������邩�̂悤�ɁA�M���Ă���ΐM���Ă���Ƃ���ɕ�������̂�������܂���ˁB
���Ȃ��܂鎁�́A�u�w�\�`���[���v�Ƀg���C���Ă݂��Ƃ��ɁA�w�\�̏ꏊ���킩��Ȃ��ꍇ�́A���̂����ꂩ�ł���ƌ����Ă��܂��F
��
1. �����������̃P�[�u�����悭�ł��Ă��邩�A���X�j���O�������Ƀ}�b�`���Ă���B
2. �V�X�e���ɂ����܂ł̍����o���\�͂��Ȃ��B
3. �킩��Ȃ��Ǝv������ł���B
http://kanaimaru.com/Cable/C010.htm
�u�킩��Ȃ��Ǝv������ł���v�l�ɂ͕������Ȃ��I
�܂�ŁA�Ö��p��M���Ă��Ȃ��l�ɂ͍Ö��p�͂�����Ȃ��A�݂����ȁB
�����ԍ��F21742847
![]() 4�_
4�_
�u���V�[�{���ʂ͑傫�����낤�ȁB�u�����h�C���[�W���悭�����łȂɂ�獂�������ȋ@�\���t�����@���������A
�����ǂ��Ȃ�͂����Ƃ����o�C�A�X�͑����傫���A������A�����ĕ����Ă��邤���ɍ������ʂ�
���܂��āA�����ς���Ă�������̂��낤�ȁB
�O�ɁA�Ⴄ�X���œ\����
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej1978/34/12/34_12_1079/_pdf
�ɂ��A�u�����h��m�����O���[�v�́A�c�̑����J�Z�b�g�e�[�v���c�����Ȃ���������ƌ����Ă���B
�܂��A���������ƃX�����r��錳�����A�u���V�[�{�i�Ö��j���ʂ͑傫���B
�����ԍ��F21742941
![]() 4�_
4�_
����A����͂��Ȃ��܂鎁�����������l�Ɍ����Ă����B���ꂪ�\�j�[�ގЂ̌����ł͂Ȃ����Ƃ���v���Ă��܂��̂������Ȋ��z�����ǁA�V�˂𗝉����Ȃ����ɖ�肠�錩�����ɂ͌���ꂽ���Ȃ��ł��ˁB
������ɂ��Ă��\�j�[�͖��l�����̐��i�𑽂������Ă���킯�ł�����A�Ɠ��̊����͓V�˂��Ƃ��Ă����ė]�����ł��傤�ˁB����ɗ����ł��Ȃ��l�����������ł��傤����B�{�l�̑O�łǂ����ƕ����ꂽ��A���ł������D�����Ȃ�܂����������ɂ͌��������m��܂���B�������Ȃ��Ƃ��킩��Ȃ��Ƃ��͂�����ƌ����Ȃ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21743131�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ������
���w�E�̕����ɂ��Ă͗������Ă���܂��B�����w�͎������ݔ����K�v�Ȃ̂ŁA�l�̂�����Ƃ����v�����̂��V�тł͌����ł��܂���B�y���W���[�N�̂���ŏ����������ŁA�{�S���炩�Ȃ��܂鎁�̎咣�ɊS�����肵�Ă���킯�ł͂���܂���B���͎����ď펯�I�ɂȍl���������Ă���܂��B���������悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��A��ϐ\����܂���ł����B
�����ԍ��F21743145�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���Ȃ��܂鎁���Ă����U�O���߂��Ă�����ł��ˁB�����ƎႢ�����Ə���ɑz�����Ă���܂����B�����A���̔N��ɂȂ�ƒN�������͂͒ቺ������̂Ȃ�ł����ǂˁB���ꂪ�܂������Ŋ��Ă���̂ł����琦�������B
�����ԍ��F21743171�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
Symbolist_K����A
>���䎁�́A���Ŋm�F���Ă��邱�Ƃ����Ă��܂����F
���Ŋm�F�ł��������A�v����ő��肵�Ă��ω��������Ǝv�����ǂȁB���������ƁA
�܂��A�X�����r��錴���ɂȂ邪�B
https://www.youtube.com/watch?v=WE9pYUVvr00#t=75
���O�ɑ��̃X���ɓ\��������ŁA�����͐ϑw�Z���~�b�N�R���f���T���U���̉e�����邩��݂��������A
USB�P�[�u���Ƀe�[�v��\��Ƃ����悤�Ȕ����ȕω��ł͂Ȃ��AUSB�P�[�u�����K���K���@���ĉe��������邩�A
����Č�����ʔ��������H
�����ԍ��F21743236
![]() 3�_
3�_
�����ASymbolist_K������Ɠd��D���̑�コ����A�W���[�N�ŏ����Ă����ł��ˁB�}�W���X��������Ēp������������Ȃ��́B��ɂ������܂������A�炢����ł���������ʂ�������Ȃ��̂ŁA��݂�����悤�Ȃ��Ƃ͂قǂقǂɁE�E�E�B
Symbolist_K����[21742839]
>�ނ̓E�\�����Ă���̂ł��傤���H�@���̂��߂ɁH
�܂����������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�����A���ʂ̃G���W�j�A���u��������v�ƌ����ꍇ�́A���o�Ȃǂ̌덷���l�����ėL�ӂł���A�Ƃ����Ӗ��ł��i�_���ȃG���W�j�A�������ς����܂����j�B�ނ͂����������������͂��Ă��Ȃ��Ǝv���킯�ł��B
tohoho3����[21743236]
>���Ŋm�F�ł��������A�v����ő��肵�Ă��ω��������Ǝv�����ǂȁB
���Ȃ��܂鎁�̐����̒��ɂ̓W�b�^�[����ps�A���ʂ̉����ω�����dB�A�f�B�W�^���P�[�u����m�ȏ�ʼne�����o��A������l�Ԃ̌��m���́A�Ƃ������ɂ߂Ċ�{�I�Ȑ����������܂���i�����ɋ������Ȃ��̂Ŗڂɓ������͈͂ł����j�B
�ӂ��̒����̃P�[�u�������ŕϓ�����W�b�^�[�́A�����Ă�ps�ł��傤�B����͌��ł������0.3�~���A������0.3�i�m���[�g���i�ޒ��x�̎��Ԃł��B20kHz�̉��g�̔g���̂P�����̈ꂭ�炢�ő��ɂ��m�C�Y�͂����ς����邵�A����̌v����łƂ炦��͖̂����ł��傤�B������ł���A�@�эזE������āE�E�E�ƍl����ƁA�߂܂������Ă��܂�(��)�B
�����Ƃ��A���������}�f�Ȍv�Z�����Ă��܂��Ɓu�ς��Ȃ��v�Ƃ����o�C�A�X���������Ă��܂��̂ŁA������Y��āu�S���ŋp�v���Ȃ���Όv���������u�_�̎��v�͎����ł��Ȃ��A�Ƃ��������ł��傤���B
�����āA����tohoho3����̍����ŃP�[�u���k�`�ɂȂ��Ă���B
�����ԍ��F21743606
![]() 5�_
5�_
������
�w�\�͓e���p
USB�P�[�u���̐U����ɂ��ẮA���ʂ��L��Ǝv���܂���B
�����ԍ��F21744326�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�⑫�ł��B
�u�w�\�͓e���p�v�Ƃ����̂́A
�U����ɂ����āu�ł����ʓI�ȃ|�C���g�v�͓��R���邾�낤���ǎ��͒T�������������A�Ƃ����Ӗ��ŏ����܂����B
�����ԍ��F21744849�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
tohoho3����
�����[�������̂��Љ�A���肪�Ƃ��������܂��B
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej1978/34/12/34_12_1079/_pdf
��ǂ݂܂����B
�����Â������ł����A�������ʂɂ͐F�X�Ǝ����ɕx�w�E�������܂��ˁB
���ɁA�J�Z�b�g�e�[�v�̃u�����h����m��Ȃ��ꍇ�iBL�����j�ƒm�����ꍇ�iBR�����j�ɂ����鉹���̔��f�̍��قɂ��Ē��ׂ�ƁA�I�[�f�B�I�ɋ����S�̂���팱�҂́A�ǂ��u�����h�C���[�W�����u�����h�̃J�Z�b�g�e�[�v�ɑ��āA
�u���[�ɂ������v�A�u�Ƃ��������[��ꂽ�v�A�u�������[�����Ȃ��v�A�u���͂̂���[���̑���Ȃ��v�A�u���邢�[�Â��v�A�u��̂���[��̂Ȃ��v�A�u�L���ȁ[�n��ȁv�A�u����̂悢�[����̈����v�A�u�Ђ��݂̏��Ȃ��[�Ђ��݂̑����v
�̂X�̎w�W�ɂ��āA���ׂĂ̎w�W��BR�����ł̕]����BL�����ł̕]����啝�ɏ������B
�[�[�[�Ƃ����������ʂ́A�����v���V�[�{���ʂɂ��ĉ�������������A�ł��ˁI
���ꂩ��A�����̉��F�̕]���ɂ��āA���q���͂��s���āA
��P���q�����������q�i��\�I�ȕ\����F �N�₩�ȁ[�ڂ����A�͂�����Ƃ����[�ڂ₯���A�P���̂���[�����A���Ăȁ[�ڂ��肵���A����₩�ȁ[���C�̂Ȃ��A����̂悢�[������₵���A�s���[�݂��A���邢�[�Â��A�h��ȁ[�n���ȁA�ł��[�_�炩���j�\�\��ɍ���̓���
��Q���q���͓������q�i��\�I�ȕ\����F ���͂̂���[���̑���Ȃ��A�L���ȁ[�n��ȁA�L����̂���[�����ȁA�Ђт��[������A�o�����X�̂Ƃꂽ�[�A���o�����X�ȁj�\�\��ɒ����̓���
��R���q�������q�i��\�I�ȕ\����F ���ꂢ�ȁ[�����Ȃ��A���[�������A�Ȃ߂炩�ȁ[���炴�炵���A��̂���[��̂Ȃ��A���߂ׂ̍����[�e���A���邨���̂���[�������������A�q�X���ڗ��[�q�X���ڗ����Ȃ��j
�d�d�̂R���q���A���F�ɉe����^����S���I�v���Ƃ��Ďx�z�I�ł���A���̂R���q�őS���U��93%��������邱�Ƃ��ł��A���ɑ�P���q�����������q�͑S���U��46%���߂邱�ƁB
���F���K�肷��̂ɍł��d�v�Ȏ��g���̈�͍���ł��邱�ƁB
�u���F=tone, timbre�v�i�u���̑傫��=loudness�v�Ɓu���̍���=pitch�v�ȊO�̂��ׂẲ��̐������ꊇ���ĕ\�������I�v�f�j�̕]���́A�u����=acoustic quality, audio fidelity�v�̕]���Ɏx�z�I�ł��邱�ƁB
�\�\�\�Ƃ������ʕ��͂ɂ͑傢�ɂȂ�قǂƎv���܂����B����A������Ǝg���܂��ˁI
https://www.youtube.com/watch?v=WE9pYUVvr00#t=75
�Ō����Ă���̂́A�u�I�V���X�R�[�v���K���K���@���ȁv���Ă��Ƃł���ˁB�ł��A������ƒ@�������ł��ˁI��
�@���@���̂ƃP�[�u����@���̂ł͑S�R�Ⴂ�܂����A�P�[�u�����낤���@�킾�낤���A�@�����Ⴞ�߂ł��傤�I��
�����ԍ��F21745139
![]() 2�_
2�_
�Ɠd��D���̑�コ��
���Ȃ��܂鎁�A�\�j�[�ގЂ̗��R�͂ǂ��Ȃ�ł��傤���B
http://www.itmedia.co.jp/anchordesk/articles/0404/30/news026.html
�ɂ��AAV�A���v��TA-DA9000ES�����ߒ��ŁA��y�̏����Βj�Ɂu�\�j�[�̉�����邽�߂̃m�E�n�E��`���v���������ŁA���̂���i2004�N�j�́A�ނ������u�\�j�[�̉��v�����߂Ă���A�\�j�[�Г��ʼn�����i��ł����悤�ł��ˁB
���̌�A2012�N�̌����̎G���wHiVi�x�̋L���ŁA
http://kanaimaru.com/da5700es/1209HiVi.htm
TA-DA5700ES���J����������̂܂������̂Ƃ��ɁA���݂��\�j�[�̃G���W�j�A�ł���n�Ӓ��q�Ƃ�������ɃC���^�r���[���Ă����Łu�ւ��v�̂��Ƃ�����������Ă��ł���ˁB
����Ɛ��������E���Ă������̂ŁA�Г��ł��Â炭�Ȃ����̂ł��傤���B
���͈��ނ��āA�D������Ȃ��Ƃ̂ł���I�I���K�Ȑ����̂悤�ł��ˁB
�����ԍ��F21745140
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�I�[�f�B�I�ɂ������w�I�ȗ��t���͕K�v�ł���ˁB���w����Ȃ��̂ł�����B
�����Ȃ��܂鎁�̐����̒��ɂ̓W�b�^�[����ps�A���ʂ̉����ω�����dB�A�f�B�W�^���P�[�u����m�ȏ�ʼne�����o��A������l�Ԃ̌��m���́A�Ƃ������ɂ߂Ċ�{�I�Ȑ����������܂���
���ӂ��̒����̃P�[�u�������ŕϓ�����W�b�^�[�́A�����Ă�ps�ł��傤�B����͌��ł������0.3�~���A������0.3�i�m���[�g���i�ޒ��x�̎��Ԃł��B20kHz�̉��g�̔g���̂P�����̈ꂭ�炢�ő��ɂ��m�C�Y�͂����ς����邵�A����̌v����łƂ炦��͖̂����ł��傤�B������ł���A�@�эזE������āE�E�E�ƍl����ƁA�߂܂������Ă��܂�
�������A���Ȃ��܂鎁�͏�l���͂邩�ɗ��킷�钮�o�̎�����Ȃ̂ŁA���ɔނ��u�S���ŋp�v���Ĉ�̃v���V�[�{���ʂ����̐��_�͂ŎՒf�ł����Ƃ��ɂ́A���̎��̐��x�͂�����v�������̂ł��傤�B
Don�ft think, feel!
�����ԍ��F21745142
![]() 2�_
2�_
�l�̓Z�C�E�`����A�����́B
�P�[�u���̐U����ɂ����āu�ł����ʓI�ȃ|�C���g�v�����Ƃ��������Ƃ��Ă��A���̈�_�Ƀe�t�����e�[�v��������������Ȃ��āA�P�[�u���S�̂��C���V�����[�g���������Ȃ��ł����H �Ƃ������A���������A������x�̃��x���̃P�[�u���Ȃ�A���łɏ\���ɃC���V�����[�g����Ă�̂ł�����Ȃ��ł��傤���H ���Ƃ́A���ɒ��ɔ��킹�Ȃ��ŁA��������[�Ƃ��ł���ˁB
�����ԍ��F21745145
![]() 2�_
2�_
���āA�݂Ȃ��܁A�Y��悤�ɂ��������Ȃ���������w�E�̂悤�ɁA�ŋ߃X���b�h�̎�肩���E���݂Ȃ̂ŁA�����Ŗ{��Ɋւ��d�v�Ȃ��ӌ����Љ�����܂��B
���̏����̎���w�hCD���ڃ��b�s���O�h�ʼn����ǂ��Ȃ�̂��ǂ��������ĉ������B�x�̒��Ō��y�����A�u�hCD���ڃ��b�s���O�h�̉��̗D�ʐ����m�M���āA����܂ł��łɑ�����CD�����b�s���O���Ă������ɂ�������炸�A���̂��ׂĂ��gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O���������Ƃɂ��āA���݃��b�s���O���ł���v���́A�G���Y�̕Њ��ꂳ��Ƃ��������̂ł����A
http://emuzu-2.cocolog-nifty.com/blog/2016/01/hap-z1eshap-s1c.html
����܂ł��̃X���b�h�Ŏ��̌�������ĉ����������́A�u�ς��Ȃ��h�v�̌Â����̑�D����������l�������̂ŁA�u�ǂ��Ȃ�h�v�̕��ɂ����ӌ����������������Ǝv���A�G���Y�̕Њ��ꂳ��ɘA�������������܂����Ƃ���A�G���Y�̕Њ��ꂳ�玟�̂悤�Ȃ��ӌ����Ă��������܂����̂ŁA���������������āA�����ɑS����]�ڂ������܂��F
�u���āw�hCD���ڃ��b�s���O�h�͋�̓I�ɂǂ̂悤�ɉ����ǂ��̂��x�Ƃ̂��Ƃł����A�����̈�ۂ��v���o���܂��Ɓu����̂���߂��v�Ɓu����\�i�𑜓x�j�v�ł��傤���B
���̈Ⴂ�́A���L�̎R���S�b�������̈�ۂɎ��Ă��܂��B�܂肱�̎��Ɋ������u�}�X�^�����O�v�̈Ⴂ�ɋ߂���ۂ������B
http://emuzu-2.cocolog-nifty.com/blog/2015/08/post-efff.html
���������u�ǂ����v�Ƃ͉��ł��傤���H
�����́u�������D���ȉ��v���Ǝv���Ă��܂��B���傹��I�[�f�B�I�̐��E�́u�v�����݁v�B���l�����������Ɣ��f���Ă��A�������D���ȉ��́u�ǂ����v�B����đ��l�̕]�����C�ɂ���K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
����Ȏ����̔��f��́A�u�ŏ��ɕ��������̈�ہv�����ŁA������ׂ͂��܂���B�����ċ�̓I�Ɍ����A�u�{�����[�����ɒ[�ɏグ�Ă������Ƃ��ɁA���邳���������Ȃ������ǂ����v�B�iHAP-Z1ES��SRM-007tA��SR-009�j
���݂�FM�����̘^���Ɏg���Ă������NAC-HD1�́A���N���b�N�̉����ŁA�����ǂ��Ȃ�܂����B���̓_�ł́u���C���Y��ȃN���b�N��HDD�ɂ��͋����L�^�����v�̂��������ȁE�E�E�Ǝv���Ă��܂��B
�����Ď����́A�����̎t���H�̃x�e��������̃A�h�o�C�X�ʂ�AHAP�ɋL�^���ꂽ�����f�[�^�́A�o���邾�����H�i���ʒ����Ȃǁj���Ȃ����ɂ��Ă��܂��B�f�W�^���ƌ����ǂ��A���H�͈������邱�Ƃ͂����Ă��A�ǂ����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁB
�́A�f���M���̈��k�iCODEC�j�̎d�����������Ƃ�����܂��B���̂悤�ɍL�ш�̌��`���Ȃǂ�������������A���ш�̓`���H�ōL�ш�̉f��(TV)�M�����u�����Ƀo���Ȃ��悤�Ɂv���k���邩�E�E�E�B�]����́u�f�l���f�������āA�����Ɉ�a�����������v�����ł����B�ǂ�ȍ����ȋZ�p���g�������A�f�l�����āA����ɑ��ē`�����ꂽ�摜���u�A���b�v�Ɗ�������_���B�܂艹�����l�ŁA�Z�p�_�͕ʂɂ��āA�d�v�Ȃ��Ƃ͑f���ɒ������Ƃ��ɁA�u�������ǂ������邩�E�E�E�v�����ł́H
�n�[�h�̐v�҂�CD�̐���҂́A���ꂼ��g�����ɗǂ����Ɗ����ĖႤ���h�ɕ��S���Ă��܂��B����A������͂���ȋ�J�͂ǂ��ł��ǂ��A�����Ƀt�B�b�g���邩�ǂ����ŕ]�����܂��B
����ŗǂ��Ǝv���܂��B
���Ёu�����̎��ŕ����āv�A�������Ȃ�̕]���i���̉����D�������炢���j������邱�Ƃ����E�߂��܂��B�v
�G���Y�̕Њ��ꂳ��A�M�d�Ȃ��ӌ��A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21745165
![]() 4�_
4�_
��Symbolist_K����
���Ȃ��܂鎁��2013�N11��31���Ƀ\�j�[���N�ސE���܂����B
���̌�Čٗp�ɂȂ�A�����\�j�[�ɍݐЂ��Č�i�̎w���ɂ�����A�\�j�[���狋�^�����Ă��܂��B
�����ԍ��F21745221
![]() 3�_
3�_
Symbolist_K�����
��ώQ�l�ɂȂ�܂��Ƃ��Ȉӌ��ł��ˁB�P�[�u���ɂ��Ă������������y����ł��Ȃ炻��ł����̂ł����A����Ă��邱�Ƃ̐������Ƃ��Ó����Ƃ������n�߂�Ƃ������Ȃ��ƂɂȂ�܂���ˁB����ɂ��Ă����ژA�������Ƃ��s���I�ł��ˁB����͑���̕��ɗǎ��������Ă悩�����ł��ˁB
�����ԍ��F21745224
![]() 2�_
2�_
Symbolist_K����A
>�@���@���̂ƃP�[�u����@���̂ł͑S�R�Ⴂ�܂����A�P�[�u�����낤���@�킾�낤���A�@�����Ⴞ�߂ł��傤�I��
�Ƃ������ƂŁAiFi nano iONE�Ƃ���DAC�Ƃ��̓���USB�P�[�u���Əo��RCA�P�[�u����@���Ă݂܂����B
https://www.youtube.com/watch?v=icM8mnu8RiY
�Y�ꎁ�̌����悤�ɂ���ς葪��ł��Ȃ��݂����B�܂��A����Ɍ��ꂽ��A�����i�Ƃ��Ď��i����ˁB
�����ԍ��F21745607
![]() 3�_
3�_
youtube����Ɍl��������̂ŁA�A�b�v���������B
https://www.youtube.com/watch?v=5E_I4vcRQnc
�����ԍ��F21745681
![]() 2�_
2�_
�����Ⴄ���ۂ��āC�����I����Ȃ�����B
��Ȋۂ��ƁC�A���o���ꖇ�ۂ��ƂɈ���Ă�B
��b�ɂ������Ȃ������̃f�[�^���Ⴊ�݂������ŁC�u�u�b�I�v�Ƃ̌����Ȃ�Ⴄ�ƔF���o���邪�C�j���A���X�Ⴂ�͔���Ȃ�����B
�ƁC��̉��Ȃ画��Ȃ��Ƃ̂�����͔���܂����C�������ԓ��ɕ����C������݂��Ă�C���X�̔����ȍ��͔�r�����鎖�ɂ�蔻��Ղ��Ȃ�܂��B
��B
�ŁC�F�����ԈႦ�ċ��邵��B
�����I�Ȏ��ۂ���Ȃ�����B
���b�s���O�ɂĉ������Ⴄ�I�ƌ����̂�B
�����ԍ��F21747145
![]() 1�_
1�_
�����{��ŏ����Ăق����悤�ȁB
�����ԍ��F21747213
![]() 5�_
5�_
�����I����Ȃ�����B
��Ȋۂ��ƁC�A���o���ꖇ�ۂ��ƂɈ���Ă�B
���@���b�s���O�������������������]�X��B
�f�[�^���ȖʁX�����Ⴂ���āC�p�\�R�������Z�L���A���b�s���O���ĂāC���@���b�s���O���C���b�s���O�@�\�̃f�t�H���g���b�s���O�̃o�[�X�g���b�s���O�ł́C�ۂ��ƈ�ȁC�A���o���ꖇ�ۂ��ƈႤ�j���A���X�̍��ł��傤�B
�o�[�X�g���b�s���O�̕����O�㗧�̕`�ʂ��r��ꂸ�C���������ɁC�ƎU�炩�Ȃ��ŁC���̉��ɔ���d�オ��̂Ńj���A���X�`�ʂ͉���������ˁ[�B
�Z�L���A���b�s���O���͂ˁB
�����I����Ȃ�����B
��Ȋۂ��ƁC�A���o���ꖇ�ۂ��ƂɈ���Ă�B
���厖�Ȃ̂ŁC������܂����B
�����ԍ��F21747438
![]() 1�_
1�_
Minerva2000����
�����Ŕ��f���Đ\����܂���ł����B
���Ȃ��܂鎁���ސE���ꂽ�Ƃ������ƂƁA������Ă�����̂���̈�ۂŁA���͗I�I���K�Ȑ���������Ă�����̂Ǝv������ł��܂����B
���ۂ́A���Ȃ��܂鎁���ސE���ꂽ�̂͒�N�ɒB��������ɂ������A���������̌�\�j�[����Čٗp������Č�i�̎w��������Ă����ł��ˁB���炢�����܂����B
�����ԍ��F21747456
![]() 2�_
2�_
�Ɠd��D���̑�コ��
�G���Y�̕Њ��ꂳ��́A�u���O��q������ƁA�I�[�f�B�I�Ɋւ��ĐF�X�ƍH�v������Ď��s������J��Ԃ���Ă���̂ŁA���Y�̖��ɂ��Ă���ƌ������������Ǝv�����A�����܂����B�Ȃɂ���A���ۂɎ��Œ����Ĕ�r���ꂽ�����A�����͂ǂ�ǂ�Ċ��z���킹�ĉ����邾�낤�Ǝv������A�S�R����Ă���Ȃ����̂ł�����A�����炩��f���Ă݂܂����B�����āA�G���Y�̕Њ��ꂳ��̂��ӌ��ɂ��A�܂��Ȃ�قǂȂƎv���܂��B
����ňꉞ�A���̌��Ɋ�Â��u�ς��Ȃ��h�v�Ɓu�ǂ��Ȃ�h�v���P�P�ɂȂ����Ƃ������ƂŁB
�����ԍ��F21747460
![]() 2�_
2�_
tohoho3����
�P�[�u����@��������@���Ă��A�قƂ�njv���ł���悤�ȉe���͂Ȃ���ł��ˁB
�u���Ŋm�F�ł��������A�v����ő��肵�Ă��ω��������v�͂����Ƃ���A�@���Ă��e���Ȃ���A�P�[�u���ɏ��X�̐U���������Ă����ŕ����鉹�̕ω��͋N���肦�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
���Ȃ��܂鎁���A�P�[�u�����w�ŐG���������ʼn����ω�����̂�������Ƃ����̂́A��͂�܂�Ȃ̂ł��傤���H
�����ԍ��F21747462
![]() 2�_
2�_
�ǂ�`�����ł���
���b�s���O���@�̈Ⴂ�ɂ�鉹�����ɂ��āA�u��b�ɂ������Ȃ������̃f�[�^����v��F�������Ƃ��F�����Ȃ������Ƃ́A�N�������Ă͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�݂Ȃ��܁A���Ȃ��Ƃ�30�b�Ƃ��A�P���Ƃ��A�y�Ȃ̂�����x�̒����̕������m���r����Ă���Ǝv���܂��B�Ƃ����Ă��A���ۂɎ��Œ����Ĕ�r���ꂽ���z����ꂽ���͂Q�l���������Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F21747463
![]() 2�_
2�_
HAP-Z1ES�Ƀh���C�u�ڎ��t���ēǂݍ��������AWindows��MAC�Ƀh���C�u�����ēǂݍ��������A�w�o�C�i������v���Ă���x�Ȃ�f�[�^���ꗂ͂���܂���B
�f�W�^���f�[�^��0��1�̗���ł��B�w�o�C�i������v����x�Ƃ������Ƃ́A�Ȃ̍ŏ�����Ō�܂�0��1�̗����S�Ɉ�v���邱�Ƃ��Ӗ����܂��B
����Ȃ̂ɉ����ω�����킯�Ȃ��ł��傤�H�펯�I�ɍl����Ε����邱�Ƃł��B
�w2.5�C���`HDD�ɏ������ނƉ��������x�Ƃ��A�wSSD�Ȃ特���ǂ��x�Ƃ��������Ƃ͂���Ǝv���܂��B
�����A����̓h���C�u�̃��[�^�[�ɂ��m�C�Y�̖���d����H�̖��ł����āA�f�[�^�̖��ł͂���܂���B
�f�[�^�͕ω����Ȃ���ł��B
�����ǂݍ��ރh���C�u��l�b�g���[�N�ɂ���ăf�[�^���ω����Ă��܂�����A�p�\�R�����X�}�z�����藧���Ȃ��ł��B
������x�A�f�[�^�Ƌ@������čl���Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F21747737
![]() 4�_
4�_
�����Ȃ��Ƃ�30�b�Ƃ��A�P���Ƃ��A�y�Ȃ̂�����x�̒����̕������m���r����Ă���Ǝv���܂��B
���p������̎��Ԃ��āC�o��������ׂ������̃g�[�^�����Ԃ���Ȃ��́B
���̎��ԓ��̈ꕔ���ɃG���[�̑��Ⴊ�݂����Ƃ��Ă��C�ۂ��ƂɈႤ�͂Ȃ�����B
������Ȃ̏I��萔�b�ɑ��Ⴊ�݂����Ƃ��Ă��C���̕�����������B
�S�̂ɉe������́C���Ȃ��܂鉽�^���̃N���b�N�]�X�ł���B
�����ԍ��F21749051
![]() 0�_
0�_
��Symbolist_K����
USB�P�[�u���̐U����ɂ��Ăł����A
ifi�̃P�[�u���ɂ͂��Ȃ��܂鎮�ړ��^�́u����炵�����v�����Ă܂��B
http://www.phileweb.com/review/article/201711/13/2803.html
���݂Ɏ��������Ă��܂��āA�ړ�������ƃu���C���h�œ��Ă鎩�M�͖����ł����A�ς��܂��B
�S�̂��^�C�v�Ƃ��Ă�HELCA 1����\�ł��B
http://www.kryna.jp/product/helca.html
��������ʂ���܂����B(�ł��Aifi��USB�P�[�u�����d���P�[�u����RCA�P�[�u���Ɋ������Ƃ�D�悵�Ă��܂��B)
�I�[�f�B�I�p�ɑ�USB�P�[�u���ł��܂��܂�����̗]�n�͂���Ƃ������A����Ă��Ȃ��Ƃ������A
��������USB�̓I�[�f�B�I�Ɍ����Ă��Ȃ�����A�₪�Ė����Ȃ邾�낤�Ƃ����C�����Ă��܂��B
�܂��A�O���N���b�N�̘b����o�Ă��܂��B
�X���傳��ɂ͋���������������܂��A���܂�ɂ������̂Łc�s����̕��Ɍ����ď������݂܂��B
����UD505��10���~���x�̕��ł����NJO���N���b�N���q���ł܂����A
�ǂ��Ȃ�܂��B
�������A���ɂ���Ă͈Ⴂ�͕������Ƃ��v���܂��̂ŁA�����͐T�d�ɂ��������ǂ������m��܂���B
�܂��A���̊��ł̘b�ł����A
�N���b�Non�ŃX�s�[�J�[����ɉ��ꂪ�g����X���ɑ��āA�N���b�Non�ł͉����O�ɏo�Ă���X���ɂȂ�܂��B
���Ƃ��Ă͌���ɍL�����������ǂ��̂ł����A���̕ӂ�(���Ƀ{�[�J����)�O���ɗ��鉹���D�܂����͒��ӂ��������ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21749279�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�l�̓Z�C�E�`�����
���낢������͂��܂��A���g�p�̋@��ŊO���N���b�N���g�p����Ή��͊ԈႢ�Ȃ��ς��Ǝv���܂���B�����A����ɂ��l�����������āA�X�s�[�J�[�̌���ɉ��ꂪ�L����Ƃ����̂́A�s�c�|�l�P�Ƃ����U���~���炢�Ŕ�����p���[�h�E���j�^�[�X�s�[�J�[�ł��ȒP�ɂł��܂��B���̃X�s�[�J�[�͓����ɂc�`�b�𓋍ڂ��Ă��܂����A�N���b�N�͂���Ȃɔ�є����Ă������̂��g���Ă���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B�܂�A�����ς��̂͂����Ƃ��Ă��A�ǂꂭ�炢����ǂꂭ�炢�ɕς�����Ƃ�����̓I�ȏ�Ȃ����Ƃɂ́A�����P�ɕ����@�����炻�������N���b�N�̐��x�������Ƃ��A�������i���g���Ă��邩��Ƃ��A�����������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�����ł̓��b�s���O�ɂ���ăN���b�N�Ɉ��e�����o�ĉ��������Ȃ�Ƃ����b�̗���ŊO���N���b�N�̘b���o�Ă܂�����A�����Ȃ�ƃ��b�s���O���������f�[�^�ł͉��s���̂��鉹�ꂪ�o�Ȃ��Ȃ�̂��Ƃ��A�����܂ŃN���b�N�������Ȃ�̂��Ƃ��A���������b�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�܂�A�O���N���b�N�̘b�͂قƂ�NJW�Ȃ��̂ŕʂɏo���Ȃ��Ă��悢���̂Ȃ̂ł��BHAP-Z1ES�ɂ܂������W�Ȃ��킯�ł�����B
����łt�r�a�P�[�u���ɂ��Ăł����A�i���ɂ���ĉ��͕ς��܂���B�P�O�O�~�V���b�v�Ŕ����Ă���悤�ȃP�[�u���ł��A�f�[�^�]���ɂ͖�肪����܂���B�Ƃ��낪���y�̍Đ��ł̓v�`�v�`�m�C�Y���������肵�܂��B�܂��A��̓I�ȏ��i���͎��O���܂������A���ۂɌ������ĉ����ς��̂������Ă܂��B�ł����E�E�E
https://www.phileweb.com/review/article/201711/13/2803_2.html
��ʃ��f����Gemini3.0�������B������͂���ɃO���[�h���オ�������|�I�ȍĐ��������Ă����B���t���n�܂�O�Ɉ�u��������Ñ����̉𑜓x���炵�ĈႤ�̂��A���̃P�[�u��������S/N�������Ƃ������Bf�����W��Mercury3.0��肳��ɍL���A�����ɖ�����������̂���ۓI�ŁA�Ȃɂ����p���[������B�������ɐݒu���ꂽRF3�T�C�����T�[���ړ�����Η���������d���g�̎��g�����ςł���Ƃ̂��ƂŁA���ۂɓ������Ă݂��̂����A���ꂪ�u�n�}��v�Ƃ܂��DAC�̃O���[�h���オ�����悤�ȑ啝�ȉ�������������邱�Ƃ��ł����B
���̂悤�ɏ��i����������̂ł����A�u����������d���g�̎��g�����ςł���v�Ƃ���܂��B����͂��Ȃ��܂鎁�̗��_�ƊW������̂ł��傤���H
�����ԍ��F21749781
![]() 3�_
3�_
��L�̏������݂ɂ��Ăł����A���ׂ�Ƙb������ɒE������悤�ł��B������ɂ��Ă����l�͊O���N���b�N�����i���t�r�a���ے�͂��܂���̂ŁA�e�l���D���ɍl����Ηǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B�킸���V�O�p�̃P�[�u���ɂT���~���o���Ó����Ƃ��B����͔����l���l���邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
�b�̒E���A��ώ��炵�܂����B
�����ԍ��F21749818
![]() 2�_
2�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
�����r����CD |
�N�ł��m���Ă���悤�ȗL���Ȃ̉����f�[�^�B |
���܂�L���ł͂Ȃ����l�I�ɍ����]�����Ă���CD�̉����f�[�^�B |
�G�R�Ƃ��Ă��Ă�����ƒp�����������̃V�X�e���BPC�̃I�[�f�B�I�͂���ł���Ă܂��B |
�܂��E�����đ�ϐ\����Ȃ��̂ł����A�ǂ����Ă��^��Ɏv������e���o�Ă��܂��āA�N���킩����ɓ����Ă���������Ɗ������v���܂��B��́u�Z�V�E���N���b�N�v���g���ĕҏW���ꂽ�Ƃ������X���̂b�c�ł����A����炵�����̂����L���Ă��܂��āA������ƒ��ׂĂ݂܂����B�Ƃ����Ă��AAbleton Live9�ɓǂݍ���Ŏ��^����Ă��鉹�ʃ��x�����o���������ł��B���͂Ǒf�l�Ȃ̂œ�����Ƃ͂킩��܂��ł��܂���B
�ȑO�ɂi�|�o�n�o�̉��������Ƃ����b�肪�o�����Ƃ�����܂��āA���̂Ƃ����R�Ƃ��ꂽ�̂��摜�ɂ���悤�ȐU�ꕝ�̂Ԃ�ł��B���̂悤�Ȕg�`�́u���z�v�Ȃǂƌ����܂��āA�����^���i�ҏW�j�̗�Ƃ��ďグ���邱�Ƃ�����܂��B����ŁA���ꂾ���ł͂킩��Ȃ��̂Ŏ������L���Ă���s�A�m�\�i�^�̒��Ŕ�r�I�ɘ^�����x���������Ǝv���A���������t�\���̂��郊�X�g�́u�_���e��ǂ�Łv����A�����Ƃ����t���������Ȃ镔���Ŕ�r���Ă݂܂����B
����łȂ�ł����A���̃f�[�^���������ł̓Z�V�E���N���b�N���g���ĕҏW����Ă��Ă������̂͗ǂ��Ƃ͂����Ȃ��B�������A�Z�V�E�����g���Ă���Ƃ����Ŕ����邽�߁A�I�[�f�B�I�}�j�A���K���ɂȂ��ĉ��������\�[�X��ǂ����̂��Ƃ��Ė炻���Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤���H�@�܂�A�Z�V�E���ȑO�ɂ��������̉����͂ǂ��Ȃ̂Ƃ����킯�ł��B�}�j�A�̊Ԃł͖炷�̂���������Ƃ����]�����Ă���炵���ł��B�܂�A�����Ɩ炷�ɂ̓e�N�j�b�N���v��Ƃ��Ȃ�Ƃ��E�E�E
���ۂɒ��������z�͂����܂Łi�����f�[�^�����C���[�W�قǁj�����悤�ɂ͕������Ȃ��B�����A�������ƒ������Δ����B���X���؍D���Ȃ甃���ł��傤�Ƃ������Ƃ���ł��B�����A�����悤�Ɉ����������Ȃ��F���c�q�J���Řb�������Ƃ��͂܂Ƃ��ɕ����Ă��炤���Ƃ��ł��܂���ł����B�����܂ōő剹�ʂ̐U�ꕝ�i�S�̓I�ɃQ�C�������������j�ł����Đ��͂����ƕ�������Ƃ��i������ł����A���������ƌ��߂��Ă���̂ł��B���̂��Ƃ���l����ׂ����Ƃ́A�F���c�q�J�������߂ă��r�W�E���N���b�N���g���ĕҏW���Ă���A�I�[�f�B�I�}�j�A����]�����Ă��炦���Ƃ������Ƃł��傤���H�@�����A�F���c�q�J���͈�ʂ̐l�X����͈��|�I�ɍ����]�������ɓ��Ă���A�}�j�A�̎x���ȂǕK�v�Ƃ͂��Ȃ��ƍl���܂��B
�����Ȃ��Ă���ƃI�[�f�B�I�}�j�A�̂����u�������v�Ƃ͂��������Ȃ�Ȃ̂��A���߂čl���������܂��B���^��Ɏv���܂��B�������A�}�j�A�Ƃ����Ă��ЂƂ�����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����ȍl�������l������Ƃ����̂͏��m���Ă��܂��B
�����ԍ��F21750663
![]() 3�_
3�_
Ryo Hyuga����
���̃X���b�h�ł́A�f�W�^���̖��ƃA�i���O�̖����Ę_���Ȃ���A�_�_���N���A�[�ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃ����ʔF���ɂȂ��Ă��܂��B
�����āA���̃X���b�h�̂���܂ł̗���ł́A�u�f�[�^��]���i�R�s�[�j����Ƃ��ɂ́A�]���g�̌`��ɂ�����炸�A�o�C�i���̈�v�͕ۂ����v���Ƃ͑O��ɁA�u�Q�̃o�C�i������v�����f�[�^�̍Đ��ɂ����āA�����̃n�[�h�f�B�X�N�̉~�Տ�ɋL�^����Ă���ʒu�ɂ���ĉ������ς��v�\���͔F�߂��Ă��܂��B
���̗��R�ɂ͂Q�������āA���Ȃ��܂鎁�ihttp://kanaimaru.com/AVQA/0f.htm�j�ɂ��F
��0����1�A1����0�֔��]����^�C�~���O�́A���̃A�i���O�̓ǂݏo�����g�`���ア�ƁA�O���O���Ǝ��ԓI�ɑO��ɗh��܂��B�h��Ă��ǂݏo���^�C�~���O�܂łɂ͕K�����肵�܂��̂�(�����Ȃ�悤�ɃT�[�{�n�����삵�Ă��܂�)��͂萔���͊ԈႢ�܂���B�Ƃ��낪�g�`�����]����Ƃ��ɂ͓d���ɃX�p�C�N�m�C�Y������܂��B�g�`���O���O���h��Ă���ƁA���]�m�C�Y���o��^�C�~���O���O���O���ɂȂ�܂��B���ꂪ��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�Ɖ������Q���܂��B�܂��R�s�[���͌��ɔ�ׂ�Ɨh�ꂪ�����Ȃ�̂ŁA�������ς���čs��(��ʓI�ɂ͗��čs��)�̂ł��B
�܂�A�uDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ�A���������A�i���O�g�`���̂��ώ����邩��v�iMinerva2000����ɂ��v��j�ł���A����̓A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Ђɂ��u�V���b�g�E�m�C�Y�ɂ�郉���_���W�b�^�[�ƁA������H����̃f�[�^�ˑ��W�b�^�[�v�ɓ�����܂��ihttp://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5718JAJP.pdf�j�B
���̐��ɂ��AHDD�݂̂Ȃ炸SSD�ł������͕ς�邱�ƂɂȂ�܂��B��Ƃ��ẮA�N���E�h���o�R������Ȃǂ��ăW�b�^�[�����_�����O������A�N���b�N�M���̃W�b�^�[��ጸ����H�v���Ȃ���Ă���DAC�i�N���b�N�E���J�o����H��DDS��SRC��VCXO���g�������̂Ȃǁj���A���邢��OCXO��r�W�E�����g�����}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[��ڑ�����Ƃ��������Ƃ��������܂��B
�������A���̉����̈Ⴂ�����ۂɎ��Œ����������邩�ǂ����Ƃ������Ɋւ��ẮA�Ⴆ�Ή͍��ꎁ�ihttp://ednjapan.com/edn/articles/1208/24/news015_3.html�j�ɂ��F
���~�h�������W�E�n�C�G���h�O���[�h��D-A�R���o�[�^IC�̎��т��ɋ�����ƁA�q�X�g�O��������ɂ��}�X�^�[�N���b�N�̃W�b�^�[�ʂ�200ps�i�s�R�b�j�����Ł@����A���ۂ̃I�[�f�B�I�����ɂقƂ�lje�������ƌ�����B����200ps�Ƃ������l�́A��ʓI��SPDIF�f�R�[�_�[IC�̓���PLL�Ő��������}�X�^�[�N���b�N�̃W�b�^�[�̎��͒l�Ɠ����ł���B
�Ƃ����̂��@��̎���ł��邩�����A�l�Ԃ̒m�o�̌��E�́A����ABX�����ł́i"Theoretical and Audible Effects of Jitter on Digital Audio Quality," Eric Benjamin and Benjamin Gannon, AES Convention, September 1998�j�F
���l�Ԃ̃W�b�^�[�̒m�o��臒l�́A
�E�����ŁA10nsec���x�B
�E�y�ȍĐ����ŁA30nsec�`300nsec���x
�Ƃ������ʂ��o���̂ŁA�����̈Ⴂ�����Œ���������̂͂قڕs�\�ł͂Ȃ��̂��Ƃ����^�`���A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����i[21736884]���j�ɂ���Ē�o����Ă��܂��B
�����A�p�C������i[21729066]�j�ɂ��F
���Q�̓���f�[�^�̏������܂ꂽ�ʒu���Ⴄ�ƁA���ꂼ��̃f�[�^���V�[�N����w�b�h�̓������Ⴂ�܂��B�w�b�h�̓X�s���h�����[�^�[�œ����̂ŁA���̓s�x��������ׂ�������܂��B����ɂ���Ĕ������������g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�i�f�W�^���f�[�^��]�����邽�߂̃A�i���O�]���g���܂ށj�Ȃǂ��A�M�����C����A�[�X���C������A�i���O��H�ɓ��荞�肷��ƁA�A�[�X�p�^�[����z���p�^�[���ɂ���ăO�����h���[�v�m�C�Y���������A���ʂƂ���DAC����o�͂��ꂽ�����������Ȃ�Ƃ������Ƃ͕��ʂɍl�����܂��B
�܂�A�uDA�ϊ����ꂽ�A�i���O�g�`�ɃA�i���O�m�C�Y�g�`������邩��v�iMinerva2000����ɂ��v��j�ł���A�s�K���ɔ�������u�����_���W�b�^�[�v�ɓ�����܂��B
���̐��ɂ��ASSD���g���Ή������͂قڍ�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F21750732
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
tohoho3����
�������폜����邱�Ƃ��āA�����ł��ˁI
�m���Ɂw�N�`�R�~�f�����p�K��x�̑�S���ɉ��i�R���̉^�c�����s�K�ؔ������폜����|�������Ă���܂����A�p�g���[�����Ă��āA�폜������Ă���̂ł��傤���H
���̃X���́APart 2�ɂ͓��肽���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21750743
![]() 2�_
2�_
tohoho3����
�s�v�h�m�a�h�q�c�@�g.�Q�U�S����
�P�[�u���X���A�ʔ����ł��ˁB���A���߂ēǂ�ł��܂��B
�����ԍ��F21750746
![]() 2�_
2�_
�l�̓Z�C�E�`����
�Ɠd��D���̑�コ������w�E�̂悤�ɁAiFi�̃P�[�u���ɂ��Ă�����̂́uRF3�T�C�����T�[�v�Ƃ������̂ŁA�U����ł͂Ȃ��ARFI�Ȃ�����EMI�i�������g���ш�̓d���g�m�C�Y�j�̑�̂��߂̂��̂ł��ˁB
http://ifi-audio.jp/mercury.html
�ɂ��A
��iFi�ł�Mercury�ɓƎ��Z�p�ŊJ������RF3�T�C�����T�[�t�B���^�[���g�p���A���ꂼ�ꂪ�قȂ�ш�Ɍ��ʂ�����悤�ɂ��Ă��܂��B����ɁA�~�h���t�B���^�[�͈ړ����߂��\�ɂȂ��Ă���i�P�[�u���̓r�����ړ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��j�A�P�[�u���ɂ���Č`�������A���e�i���g�����h�i�킴�ƒ��q���͂����j�����AUSB�M���ɉe����^���邱�ƂȂ��A�ō��Ƀ��C�h�����W�ȃt�B���^�[�@�\���\�ɂ��܂��B
�Ƃ������Ƃł��B
�܂��A�����g�̓d���g���U�����N�����̂ŁA���̐U����ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��ł����B
����A���Ȃ��܂鎁�̃`���[�R�[�t���[�e�[�v�́A���������O���������d���g�ɂ��U�����P�A������̂ł͂Ȃ��A�ڑ������@�킩��`�B�����U�����P�A������̂̂悤�ł��B�i�łȂ���A����̌Œ肳�ꂽ�ʒu�Ɂu�U�����W�܂�߁v���������肵�Ȃ��ł��傤�B�j
����d���g�ɑ����ł���A�V�[���h����������̂���ʓI���Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁA
���N���b�Non�ŃX�s�[�J�[����ɉ��ꂪ�g����X���ɑ��āA�N���b�Non�ł͉����O�ɏo�Ă���X���ɂȂ�܂��B���Ƃ��Ă͌���ɍL�����������ǂ��̂ł����A���̕ӂ�(���Ƀ{�[�J����)�O���ɗ��鉹���D�܂����͒��ӂ��������ǂ��Ǝv���܂��B
�Ƃ���܂����A�������́u�N���b�Noff�ł͉����O�ɏo�Ă���X���ɂȂ�܂��v�ł��傤���H
�����ԍ��F21750752
![]() 2�_
2�_
�Ɠd����̍ڂ��Ă���g�`�����Ă킩��̂́A�u���z�v�ƌ����Ă���g�`�̕��́A�^�����܂��͕ҏW���ɁA
�����̂��邵�����l�ȏ�̑傫�ȓ��͉���������̏o�͂��傫�߂��āA���͂ɔ�Ⴕ���o�͂�
�����Ȃ������i���͉��̂��邵�����l�ȏ�̉��͑������ꂸ�U�������̉��ɂȂ�j�A���Ȃ킿�A
�c�݂̂��鉹�ɂȂ�Ƃ������Ƃ�\���Ă���B�ʏ�͉��������Ɗ�����͂��B�ȒP�Ɍ����A���͂Əo�͂�
���m�ɔ�Ⴕ�Ă���ꍇ�̂݁A�c�̂Ȃ��g�`���Č������B�̂̃P�[�u���X���̏����ԍ��F16180960���Q�ƁB
�W�b�^�ɂ��ẮA���͂悭�킩���B�N���b�N�W�b�^�ɂ��DA�ϊ���̏����i�����g�j�̎��g�����h�炮�Ƃ���i������
�����g�̈ʑ����G���܂��͎����I�ȊO���ɂ��ϒ�����Ƃ���j�Ȃ�A���̂悤�Ȕg�`��l�H�I�ɍ���āA
�ǂ̒��x�̎G���܂��͊O���̕ϓ����Ȃ�A�m�o�ł��邩�����Č�������̂ł́H�p�C�������Ă���A
�g�`������ė~�����ȁB
�����ԍ��F21750921
![]() 2�_
2�_
�Ɠd��D���̑�コ��[21750663]
�b�c����ɏڂ�������܂��A����l�������ł́B���^��̌��͂����g���C�Â��̂悤��
>�Z�V�E���ȑO�ɂ��������̉����͂ǂ��Ȃ̂Ƃ����킯�ł��B
�ɏW��邩�ƁB�_���ȉ������Z�V�E���ŗǂ��Ȃ�킯���Ȃ��ł��B���Ƃ͎֑��ł����A�Đ�������Z�V�E���ł���Z�V�E���̂����v�́i���ꂪ��������Ȃ�j���Ȃ�X�|�C�������ł��傤���A���������Z�V�E���^��Z�V�E���̉��������q�g�ɒ����Ƃ��̂��ǂ������A����܂ł̋q�ϓI��炷��ɂ߂ċ^�킵���ł��B�ꕔ�̃I�[�f�B�I�}�j�A�ɃZ�V�E���M�������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ����A��������ʂ̉��y�t�@���ɂ��Ă݂�u�Z�V�E�����āH���ː��o�������H�v���炢�Ȋ����ł��傤�B
tohoho3����[21750921]
�u�̂̃P�[�u���X���̏����v�́A����������ł���܂�Ӗ��Ȃ��ƌ��܂��B
��U���̐M�����A�������l�����߂ăN���b�v���Ă��܂�����A�u�����������v��ʂ�z���ĕ����Ɋ����Ȃ����ɂɂȂ��Ă��܂��܂��B�v���Ԉ��������A���v�̊����H
�I�[�P�X�g���̂c�����W���b�c�̂P�U�r�b�g�ɓ���Ȃ����͐̂������Ă��܂��B���̐̂̓A�i���O�Q�C���Ő��䂵�Ă������Ƃ����邻���ŁA�t���I�P����o���Ƃ���܂Ń\���ő��݊����������s�A�m���낭�ɕ������Ȃ��Ȃ�����i�ꉞ�A�c�݂܂���j�B
���͑��r�b�g�Ř^�����āA�Ȃ�炩�̈��k�����Ă���낤�Ǝv���܂��B�����Řc��������\�����Ȃ��͂Ȃ��ł��傤���A�Ⴆ�u1812�v�Ŗ{���̑�C���g���Ȃ�A���̃`�����l���������x���������A�����c�ނ��Ƃ͋ɗ͔����邭�炢�̍H�v�͂���Ǝv���܂��B�f�l�̐����͂��̂ւ�ŁB
�����ԍ��F21751327
![]() 3�_
3�_
���Ԍo�߂Ƌ��ɐ��ꗬ����鉹�͓�C�����B
�������݂���̂��C�S���l�����Ȃ��ʁX�Ȃ�ł��ˁ[�B
���N���b�Non�ŃX�s�[�J�[����ɉ��ꂪ�g����X���ɑ��āA�N���b�Non�ł͉����O�ɏo�Ă���X���ɂȂ�܂��B
���Ƃ��Ă͌���ɍL�����������ǂ��̂ł����A���̕ӂ�(���Ƀ{�[�J����)�O���ɗ��鉹���D�܂����͒��ӂ��������ǂ��Ǝv���܂��B
���������o�����C�D�݉]�X�ŕЂÂ��Ă���_���Ȃ�ł���B
�����������́C�P�ɁC���̉������������ɂƎU�炩���Ă��܂����o���B
�ŁC�O���N���b�N�̗͂���Ȃ��Ƃ��C�������̏o���Ŗ炵�ė��Ȃ��ƂˁB
�����������ˁB
�ŁC���b�s���O�̎d���ŁC���p������ȓ�̌X���֏o���オ��܂���B
�G���[�����@�\���g�������b�s���O�̕����C���̈����o���Ɏd�オ��܂���B�i�f�[�^���Ȋ��Ⴂ�ʁX�����b�s���O���Ă��܂����B�O�㗧�̕`�ʂ��R�����Ď��������j
�����ԍ��F21751336
![]() 2�_
2�_
�W�b�^�ɂ��āA
http://aitlabo.net/blog/?c=003
��������₷�����Ȃ̂ŁA�L�^�Ƃ��Ďc���Ă������B
���̒��҂ɂ��ƁA
�u���r�W���[�����U���j�b�g��6,834,682,612.8Hz����PLL(���g������)��p��5MHzor10MHz��VCXO���g�������艻���Ă�����̂Ȃ̂ŁA�ʑ��G��(JITTER)��xtal���Ă͂��Ȃ��B�v
���������B
�����ԍ��F21751465
![]() 3�_
3�_
��Symbolist_K����
ifi��USB�P�[�u���������o�������R�ł����ǁA���Ȃ��܂鎁�̗��_�W�����Ă�����ifi�̃P�[�u���ɂȂ�l�ȗގ������������̂ŁA��������ł݂܂����B
���̗ގ����ł����A
1. ifi�̃P�[�u���ɂ�3cm����3�̐��U���ʂ��L�肻���ȃX���C�_�[��������
�u2���o���邾�����[�ɔz�u����v�Ƃ��Ȃ��܂鎁�́u3.8cm�̈ʒu��U����v�̏ꏊ���߂��_�B
2. �S�̂�Ȃ��Ă��A�s���|�C���g�ł����ʂ�����ƍl���Ă���_�B
���Ȃ��܂鎁�̗��_�͍r�����m���A�Ƃ̎w�E���������̂Ŕ��ɂ܂ł͂Ȃ�܂��A3cm�t�߂Ƀs���|�C���g�ő鎖�͈Ӗ����L�肻���ł���A�ƌ�������������ł��B
>�������́u�N���b�Noff�ł͉����O�ɏo�Ă���X���ɂȂ�܂��v�ł��傤���H 
���w�E�̒ʂ�ł��B
>�����ŁA�������˂��܂����APC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��ƁA����CD���gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O�����t�@�C���̍Đ��Ƃ����ŘA���I�ɔ�r���ꂽ���Ƃ̂�����͂����܂��ł��傤���H 
����ł����A����DELA N1A���������Ă��܂��āADELA����ifi��igalvanic����USB�֘A�A�N�Z�T���[���g�p���ĉ^�p���Ă��܂��B
�܂��Ablackbird���Љ��Ă����悤�ȃ��b�s���O�p�̊O�t���h���C�u���g�p���Ă��܂��B
�ꉞ�A���b�s���O�ʼn��͕ς��h�ł����A
PC�Ń��b�s���O����DELA N1A�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��ƁA����CD���gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O�����t�@�C���̍Đ��ł́A����̃V�X�e�����Ƌ�ʂ��܂���ł����B
>�Ɠd����
>�O���N���b�N�̘b�͂قƂ�NJW�Ȃ��̂ŕʂɏo���Ȃ��Ă��悢���̂Ȃ̂ł��BHAP-Z1ES�ɂ܂������W�Ȃ��킯�ł�����B 
���݂܂���ł����B
���w�E�̂悤�ɃX���b�h�������đS�̂�c�����Ă��Ȃ��ł��B
�O���N���b�N�̘b��͎�艺�������Ă������������v���܂��B
>�ǂ炿���
�����������X�s�[�J�[�̘b������A�N�ɂ͊W�Ȃ��ˁB
(-_-)/~~~
�����ԍ��F21752109�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������������X�s�[�J�[�̘b������A�N�ɂ͊W�Ȃ��ˁB
�w�b�h�z�����C���z���g���̉���ɁC���ς�炸�C�s�[�X�J�C�u�[�X�J�C�X�s�[�J�̏o���ł��C�ǂ��������w�E�����B
�i�����Ȃ����ˁ[�B
����̃��R�[�h�v���[���̏o���Ⴆ�Ō����B
���R�[�h�X�^�r���C�U�����āC�N�̈��p������ȑO�҂̉����o�ė��邩��C���R�[�h�X�^�r���C�U�����Ȃ����̏o���́C��҂ł��悢��B
�I�Ȃ�ł���B
�ƁC���𗎂Ƃ��āC�v���I�ȃo�b�h�����֍s���߂��Ă��܂��̂́C�X���I�ȗႦ�Ō�������C���b�s���O�̎����Â��̂��낤�B
�s���߂��Ă��܂��B
�����ԍ��F21752374
![]() 1�_
1�_
���ǂ�`�����ł���
�ǂ炿��v���Ă����肸�����Ɖ��ɍL���g�����Ă����Ԃ��O���N���b�N����ꂽ�Ƃ��ŁA�O���Ƃ���Ɣ�ׂđO�ɏo�Ă�����Ă��ƁB
�ʂɃN���b�N���O���ƌ���ɑS���g����Ȃ��Ƃ������ł͂Ȃ�����B
�N���b�N��on/off�ł����܂ő傫���͕ς��Ȃ��̂ŁA�O�̂��߁B
�����ԍ��F21752442�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���������B
�m�[�}���̏o�����O�҂ŁC�N���b�N�̃A�V�X�g�ɂčX�ɐ[����B
�Ȃ�C����B
�N�͎̂���B
���������̂��D�݉]�X�ŕЕt����B
���ς�炸�����ĂȂ��āC�w�L�т��ċ��邾���B
�����ԍ��F21752478
![]() 3�_
3�_
tohoho3����
http://aitlabo.net/blog/?c=003
�́AATI Labo�ł���l�ŋ@�������Ă���������p�c����̃u���O�ł��ˁB
������ƒ��ׂ܂�����AATI Labo�Ŗ�35���~�Ŕ����Ă���DAC
�ihttp://www.zionote.com/2012/aitlabo/ait-dac-zn2-2/�j�́A����ꂽ���ɂ͉����ǂ��ƍD�]�Ȃ悤�ł��ˁB�iATI Labo�͖����Ŏ����p�ɋ@�ނ�݂��o���Ă���̂ŁA�݂Ȃ������ċC�ɓ��������甃���Ă���A�C�ɓ���Ȃ������l�͔���Ȃ������킯�ŁA����ꂽ���ɍD�]�Ȃ̂͂�����܂��Ƃ���������܂��ł����B�j
�Ƃ������A���ۂ�DAC���A������W�b�^�[��ɋ�S���d�˂Đv����DAC������Ă�����̂��b�Ȃ̂ŁA���̉ߒ��Ŏ������J��Ԃ��ĉ��ǂ�ςݏグ�Ă��邱�Ƃ����ĂƂ�āA�W�b�^�[�Ɋւ��邨�b�ɂ������͂�����܂��ˁB
���̃X���b�h�Ɋ֘A����L�q�����p���Ă����ƁF
�u�� JITTER�Ɖ���
JITTER�ɂ���ĉ��������邱�Ƃ́A�I�[�f�B�I�}�j�A�̊Ԃł͏펯�ɂȂ��Ă��܂����A���̗��R�ɂ��Ă͖��m�ɂ͐�������Ă��܂���B���̂��ߑÓ����ɋ^��̂���Ή����{����Ă���ꍇ������悤�ł��B
JITTER�ɂ���ĉ������ς��悤�ɂȂ����̂́A�����A�b�v�T���v�����O���Ƀm�C�Y�V�F�[�s���O���s����������DAC���̗p�����悤�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
��������DAC�ł�RANDOM JITTER������ƕ��� �ɂ���悤��S/N���������܂��BSPDIF�̏ꍇ����JITTER��PLL��LOOP�t�B���^�[�Ő�������邽�߁A�����̒��ɑ��ւ���ꍇ�������ł��B�܂�JITTER�ɂ���āA�ʂ͂킸���ł������M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂������Ӗ����܂��B�����ɑ��ւ���JITTER�ʂ͐�ns�ł����ʉ\�Ȃقǂł����A���ւ��Ȃ�JITTER�i���g������x�A���x���܂݁j�͎��S/N�̗��x�ł��܂艹���ɂ͉e�����Ȃ��ƍl���܂��B�v
�u�� JITTER�̔�������
JITTER�ɂ͉����M���̑��֗L���ɂ���Ĉȉ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
[���ւ���JITTER]
1 �`���n�̎��g�������ɂ�����
����͓�����(equalizer)��p����Ή������邪�A�����K�v�Ƃ���قǒ������ł͂Ȃ��B
2 �����C���s�[�_���X�̐����s�ǂɂ�锽��
��ʂɗp������RCA�R�l�N�^�͓����C���s�[�_���X����`����Ă��Ȃ��A����M�[�ł��������l�����Ă��Ȃ����Ƃ������B���̏ꍇ�R�[�h��(m)×3×5(ns)�ɔ��˔g����M�[�ɔ�����JITTER�̌����ɂȂ�B�i5m�Ȃ�75ns�͖����ł��Ȃ��l�j
3 ���M����H�̐��\�s�\��
LOGIC��H��SETUP,HOLD�s�\���A�A�i���O��H�̌Q�x������i���`�c�j�ɂ���Ĕ���
4 ��M���̂Q�l����H�̐U���ʑ��ϊ��ɂ���Ĕ���
�Q�l����H�i�d���R���p���[�^�j�͓��͐U���A�g�`�ɂ���Ēx�����Ԃ��ω�����B
[���֖���JITTER]
5 ���M���̎��g���ϓ�
�ʑ��ϓ����܂ށi���g���i�p���g���j�͈ʑ������ԂŔ��������l�j
6 �W�Q�g���d��
���g�����߂��ꍇ�A�ʑ��ϒ������iJITTER�j�ɂȂ�B
7 �@�B�I�U���ɂ���Ĕ���
���d�ipiezo�j�f�q�i�Z���~�b�N�R���f���T�AXtal���j�͓d�C�I�@�B�I�h���ŌŗL�l���ω�����B�܂���g���A�ʑ����ς��B
** DDS�iDirect Digital Synthesizer�j��p���Ē�JITTER�ƕW�Ԃ��Ă���ꍇ���������邪�A�����J���̌o�����猾����Xtal���20dB�`30dB�����B�܂��ݒ�l�ɂ���Ă͑傫�ȃX�v���A�X�������������g���JITTER�ƂȂ�B
JITTER�̒�`�͘A������ׂ̎����̕�
�����ɉe������JITTER�͐�10�`��kHz�Ǝv����̂ŁA��1000 CLOCK���ꂽ���̒l�ɂȂ�B�v
�����̋L�q����A�u�����M���Ƒ��ւ̂Ȃ����M���̎��g���ϓ��i�ڑ��ϓ����܂ށj��W�Q�g��@�B�I�U���́A���S/N�̗������炷���x�ł��܂艹���ɂ͉e�����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
����͗v����ɁA�u�`���W�b�^�[�v��RF�m�C�Y��@�B�I�U�������܂艹���ɂ͉e�����Ȃ��A�Ƃ������ƂŁA����ς肩�Ȃ��܂鎮�́u�w�\�`���[���v�ɂ͋^�╄�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�����āAtohoho3�����p���Ă�����F
�u���r�W���[�����U���j�b�g�����t����Ɖ������ǂ��Ȃ�ƌ����Ă��邪�A�����͉��^�I�ł���v�Ƃ������ƂƂ��̗��R�B
���Ȃ݂ɁA�p�c����̓W�b�^�[�}�����@�Ƃ��Ĉȉ��̂S���r���A
�u1�@PLL��p�����W�b�^�[�N���[�i�[�����@
�@2�@ESS����
�@3�@dara rate(Sampling Rate) Convertor����
�@4�@AIT�����v
���̌��ʁA��������AIT��������ԂƂ���Ă��܂����A���̂킯�́i���̗���͂킩��܂��j�F
�uAIT������FiFO�����i�t���[�����ł͖������䂳�ꂽ�j�ł��邽�ߊ�{�I�ɂ̓W�b�^�[�}�����ʂ͑傫���B��ʂɂ͂��̕����͓��o�͂̎��ԍ����傫���Ȃ�i���b�j���߉f�����������ӏ܂ɂ͓K���Ȃ����AAIT�͍ő�50ms���x�ł���̂Ŏx��Ȃ��ӏ܂ł���B�܂�3MODE VCXO���̗p���Ă���̂ŃW�b�^�[�N���[�i�[�����Ɠ��l�ȓ�����\�B�v
�u������FPGA����RAM���g�p���A���g�����͔��ɏ������Ȃ�悤���� �A�N���X�g�[�N���������Ȃ�PIN�z�u�A�g���[�X�ɂ��Ă��܂��B�v
�uISOCHRONOUS��JITTER�ƌ������A���g�����ω����邱�Ƃ����荂�������ɂ͑������������肻���B
���ASYNCHRONOUS�͂��̂悤�Ȗ��͉������邪�ASPDIF�ŃC���^�[�t�F�[�X��g�߂��̎�JITTER�����̌����ɂȂ�A�K�v�B����ɍ������̕��@�Ƃ��ē������܂߁A��X��Ă���Ă���B�����̕����͏�LJITTER���}���\�AESS�Е����̏ꍇISOCHRONOUS�ł�PC�̏�Ԃɂ���Ă͕s����ɂȂ�\��������B
����������ES9018��g�ݍ��킹����ꂼ��̌��_����������\��������B�v
����䂦�uES9018�����ES9038PRO�̗̍p�v
�Ƃ��B
�����ԍ��F21752524
![]() 2�_
2�_
�ǂ�`�����ł���
�l�̓Z�C�E�`����
����ł����A���̃X���̖{��Ɋւ��Ȃ����_�͑����ł���ĉ������B
�����ԍ��F21752529
![]() 4�_
4�_
�Ɠd��D���̑�コ��
�u�Z�V�E�����v�Ƃ����ǂ��AJ-POP��90�N�ォ��͂т����Ă���u���������v�ɖ����ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤�ˁB
�^�����̃N���b�N�ɃZ�V�E�����g���Ă��悤���ACD�ł͂Ȃ��ăn�C���]�����ł��낤���A���ʁu���z�g�`�v�Ƃ��u�C�۔g�`�v�ɂȂ��Ă�����A�~�L�V���O�̍ۂɃR���v���b�T�[�������Ă���Q�C�����グ���̂ł��傤�B
�n�C���]���������̂ɍ��z�����܂��ꂽ���̎��̃u���O���Q�l�ɂȂ�܂��F
http://jobless-fish.com/135
�u90�N�キ�炢����A���R�[�h�ƊE�ł͉��������Ƃ������̂��N�����Ă��܂��B���������Ƃ́A�Ȃ̉������M���M���܂ŏグ�悤�Ƃ�������̂��ƁB��ɉ̗w�ȂŒ������A���ۂɁA����J-POP��������ɐ̂�CD���ƁA�����������������肵�܂��B
�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ�����̂��Ƃ����ƁA�}�[�P�e�B���O�̂��߂ł��B�e���r��W�I�ŋȂ����ꂽ���ɉ����傫����Ζڗ��B���X�̎����@�Ŏ����������ɖڗ��͖̂ܘ_�������ɒ�������B�Ȃǂ̗��R�������ł��B���ۉ�����������@��̉��ʂ��Ⴍ�Ă��������₷�������肵�܂��B
�������A�Ȃ̉������グ�Ă����ƁA�_�C�i�~�b�N�����W���قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������_������܂��B��̕��ŏo�Ă����A120dB�̃_�C�i�~�b�N�����W���������N���V�b�N���y���Ȃ�����قǂ̃_�C�i�~�b�N�����W������Ă���̂��B����͉��ʂ̍����\���̈�ł��邽�߂ł��B�Ⴆ�A�����ʂő@�ׂɑt�ł邱�ƂŎ�X�������͋C���o������Ƃ������悤�ɁB
�_�C�i�~�b�N�����W�̖w�ǖ����Ȃł́A�ȑS�̂̔g�`�����z�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B��̗�̂悤�ɁB��bit�Ń_�C�i�~�b�N�����W���L������n�C���]���������u���C�u�I�̋ȂɕK�v�Ȃ̂��^�⎋���Ă����̂͂����������Ƃł��B�v
�Ȃ��킴�킴�R���v���b�T�[�������Ă���Q�C�����グ��̂��H
����́A����̉������A���̃A�N�Z���g���R���g���[�����邽�߂ł��B���ɉ̗w�Ȃł̓{�[�J��������Ȃ̂ŁA�{�[�J�����I�P�ɖ����ꂸ�ɕ����o��悤�ȉ��������邽�߂ł��ˁB�Ⴂ���A�L���Ȑ��ʂ̂����������A���͐��ʂɈ��肪�݂��A��������������Ȃ������̂�������܂���ˁB
��̓I�ȑ���ɂ��ẮA
https://ryochin.github.io/audio-dynamics/
http://niconico-toolbox.blog.jp/archives/1104124.html
�Ȃǂ��Q�l�ɂȂ�܂��B
DG�̃��[�����E�W���x���V���e�C���̃s�A�m�A���o���́A�s�A�m�̃_�C�i�~�b�N�����W���m�ۂ��邽�߂ɁA������̂悤�ȉ��H�͂����Ɍ����������@�Ƃ��Ă���̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21752553
![]() 2�_
2�_
�l�̓Z�C�E�`����
��ifi��USB�P�[�u���������o�������R�ł����ǁA���Ȃ��܂鎁�̗��_�W�����Ă�����ifi�̃P�[�u���ɂȂ�l�ȗގ������������̂ŁA��������ł݂܂����B
���̗ގ����ł����A
1. ifi�̃P�[�u���ɂ�3cm����3�̐��U���ʂ��L�肻���ȃX���C�_�[��������
�u2���o���邾�����[�ɔz�u����v�Ƃ��Ȃ��܂鎁�́u3.8cm�̈ʒu��U����v�̏ꏊ���߂��_�B
2. �S�̂�Ȃ��Ă��A�s���|�C���g�ł����ʂ�����ƍl���Ă���_�B
���Ȃ��܂鎁�̗��_�͍r�����m���A�Ƃ̎w�E���������̂Ŕ��ɂ܂ł͂Ȃ�܂��A3cm�t�߂Ƀs���|�C���g�ő鎖�͈Ӗ����L�肻���ł���A�ƌ�������������ł��B
�������Ă���悤�ł����A���Ȃ��܂鎁���u3.8cm�̈ʒu��U����v�Ƃ����̂́A
http://kanaimaru.com/da5700es/1209HiVi.htm
��ǂ܂ꂽ��킩��悤�ɁA����HiVi���ɕt�^�Ƃ��Ă��Ă�������20cm�̓��ʂȃP�[�u���ɂ����USB-DAC�@�\�𓋍ڂ��Ă���TA-DA5700ES��IBM�����ThinkPad���Ȃ��Ă݂��P�[�X�Ɍ���b�ł���A���̓���̐ڑ��ɂ����Ă͂��̒���20cm�̃P�[�u���́u�U�����W�܂�߁v���uA�[�q�̍�������3.8cm�̈ʒu�ɂ������v�Ƃ��������ł��B
�������A�P�[�u���̒������ς��A���邢�͋@�ނ��ς��A���̈ʒu�͕ς��Ƃ����b�ł��B
���̈ʒu�̒T�����́A
http://kanaimaru.com/Cable/C010.htm
�ɏڂ��������Ă���悤�ɁA�u�w�ŃP�[�u���Ɍy���G��A���肶��Ɠ������Ă䂫�܂��B�t�b�Ɖ����ς��i�ቹ����������o����A�N�Z�����ƂȂ����Ȃ�����j�Ƃ���������܂��v�Ƃ������@�ł��B
���̂Ƃ��A�uRF3�T�C�����T�[�v�̏����Ώۂł���O�������RF/EMI�m�C�Y�́A�S�����ɂ���Ă��܂���B
������DELA N1A���������Ă��܂��āADELA����ifi��igalvanic����USB�֘A�A�N�Z�T���[���g�p���ĉ^�p���Ă��܂��B�܂��Ablackbird���Љ��Ă����悤�ȃ��b�s���O�p�̊O�t���h���C�u���g�p���Ă��܂��B�ꉞ�A���b�s���O�ʼn��͕ς��h�ł����APC�Ń��b�s���O����DELA N1A�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��ƁA����CD�� �gCD���ڃ��b�s���O�h �Ń��b�s���O�����t�@�C���̍Đ��ł́A����̃V�X�e�����Ƌ�ʂ��܂���ł����B
DELA N1A�ɂȂ����O�t���h���C�u����DELA N1A�ցgCD���ڃ��b�s���O�h�����t�@�C����PC�Ń��b�s���O����DELA N1A�ɓ]�������t�@�C���Ƃ̔�r�A�Ƃ������Ƃł��傤���H
HAP-Z1ES�ɂ�����b�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�܂����l�Șb�Ȃ̂ŁA�u�T�v�ɓ�����ƌ��Ȃ����Ƃɂ��܂��傤�B
����ŁA�u�ς��h�v�̎咣�ɗ��_�I�ɂ͎^�����Ă�����̂́A���ۂɎ��Œ����Ă݂�Ƌ�ʂ����Ȃ������̂ł��ˁI
���A�X����A�����̃X���b�h�ōŏd�v�����Ă���̂́u���Œ����Ă݂Ă̔��f�v�ł��̂ŁA�����ł́A�l�̓Z�C�E�`����́u�ς��Ȃ��h�v�ƔF�肳���Ă��������܂��B
����ŁA�m���ۂɎ��Œ�����ׂ����̎��̌��Ƃ��Ă̊��z�n�Ƃ��āA
���u��ʂ����Ȃ��v�Ɣ��f���ꂽ���F �Â����̑�D������A�l�̓Z�C�E�`����
���u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̕��������ǂ��v�Ɣ��f���ꂽ���F �G���Y�̕Њ��ꂳ��A�p�c��Y���i��l�̎����j
�̂Q�Q�ɂȂ����Ƃ������ƂŁB
�����ԍ��F21752580
![]() 2�_
2�_
�ǂ��ł��������ƂȂ�ł����A�u�Z�V�E�����v�̃W���P�ʁA�W�F�V�J�E���r�b�g�ł���ˁB���W���[�E���r�b�g�̉�����́B���o�[�g�E�[���L�X�ḗw���W���[�E���r�b�g�x�͍D���ȉf��Ȃ̂ŁA����͂�����Ƃ��������Ȃ��B����������W�F�V�J�̃R�X�v�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�P�ɃW�F�V�J�̉摜�ɖ��̊���A�C�R�����Ă邾������Ȃ��ł����I ����̓_���ł��傤�B�����ƃf�B�Y�j�[�ɋ����Ƃ��Ă���̂ł��傤���H
�d�d�d�Ƃ�����ƌ����Ă��������āB �X���厩��{�肩��̒E���A���݂܂���ł����B
�����ԍ��F21752631
![]() 3�_
3�_
2018/04/15 08:37�i1�N�ȏ�O�j
�X�^�r���C�U�[�Ŏv���o�����B
Audio-technica�����ɂ̃A�i���O�v���[���[���Q�l�o�i������u�b�c�v�̓o��œ��̖ڂ��ςȂ������ȁB
�����ԍ��F21752815
![]() 1�_
1�_
Symbolist_K����A
�W�b�^�ʼn����ω����闝�R�́A�p�c����̃u���O��
SPDIF(�Ɍ��炸DIGITAL I/F�̖w��)���瓯��CLOCK���Đ�����ɂ�PLL(APC)��p���Ă���B���̂Ƃ��ʐM�̏ꍇ��erroro rate���ŏ��ɂȂ�悤�Ȑݒ���s�����Adigital audio �̏ꍇ�͉������d�����Ȃ���Ȃ炸��X�̉��ǁA��Ă��s���Ă���BPLL��Phase Locked loop(Automatic Phase Contoroll)�Ƃ���悤�ɐ���Ώۂ͈ʑ��ł���B���g��(�������͊p���g��)�͈ʑ������ԂŔ��������l�ł��邩��JITTER(�܂�ʑ��ϓ�)������M����PLL�ɓ��͂����ƁA�Đ�����clock(VCO)�͔����g�`�ɔ�Ⴕ�����g���ϓ�����������A���}�Q�ƁB�܂�͂��Ȃ��特��(���ɔ{������)�̎��g�����ω����邱�Ƃł�����B
���|�C���g�Ȃ̂��낤���H�u�Đ�����clock(VCO)�͔����g�`�ɔ�Ⴕ�����g���ϓ�����������v->�u�͂��Ȃ��特��(���ɔ{������)�̎��g�����ω�����v�̈��ʊW�����͕�����Ȃ��̂����A�W�b�^�̑�Ƃł���Y�ꂳ��A������肢���܂��B
�����ԍ��F21752971
![]() 1�_
1�_
Symbolist_K����
>����͗v����ɁA�u�`���W�b�^�[�v��RF�m�C�Y��@�B�I�U�������܂艹���ɂ͉e�����Ȃ��A�Ƃ������ƂŁA
AIT�p�c����́A�`���W�b�^�[��P�[�u���̋@�B�I�U�������܂艹���ɂ͉e�����Ȃ��A�Ƃ͌����Ă��Ȃ��̂ł́H
���P�[�u����HDMI�P�[�u���ł́A�O���[�h�ɂ���ĉ������ς��̂͗e�ՂɒN�ł������邱�Ƃł����A����͓`���W�b�^�[�̈Ⴂ�ɂ����̂ł��B
����N���b�N�W�b�^�[�̌��m�����U�OpS�Ƃ���Ă���̂͑Ó��ȂƂ���ł��傤�B60pS�̎��ԂƂ͌����^���P�D�W�p�i�ނɗv���鎞�Ԃł����A�l�̎��̊��x�̗ǂ��ɂ͋����܂��B
���m�����P�O�O��S���x�Ƃ��Ă��镶��������܂����A�U�O��S�Ƃ̍��͐�{�ȏ�ł��B�P�O�O��S���̃W�b�^�[���N���b�N�ɉ������DAC�͓��삵�܂���B�܂艹���o�܂���B
����̓N���b�N�W�b�^�[�����̂܂܃A�i���O�g�`�ɍڂ�ƍl���Ă��邽�߂ŁADAC��DAC�Ƃ��čl���Ă���̂ł͂Ȃ��A�h�b�v���[���ʔ������u�ƍl���Ă���̂ł��B
�����ԍ��F21752985
![]() 1�_
1�_
Symbolist_K�����
��120dB�̃_�C�i�~�b�N�����W���������N���V�b�N���y���Ȃ�����قǂ̃_�C�i�~�b�N�����W������Ă���̂��B
������͉��ʂ̍����\���̈�ł��邽�߂ł��B�Ⴆ�A�����ʂő@�ׂɑt�ł邱�ƂŎ�X�������͋C���o������Ƃ������悤�ɁB
���͂��̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��Ă����i�R���̃X���b�h�Řb�������Ƃ�����̂ł����A�I�[�P�X�g���̋�̓I�ȋȖ��������Đ��������̂ɁA�ǂ����Ă����ʂ̕ω��ɊW����Ƃ������Ƃ𗝉����Ă��炤���Ƃ��ł��܂���ł����B����ǂ��납������̗���͂��Ȃ��ł���Ƃ��A���{�ꂪ�����ł��Ȃ��ł���Ƃ��A����͂����������̂ł����B
���낢��ƌo��������A�A���v��X�s�[�J�[�������������Ă��āA�d�C�H�w�̒m��������悤�Ȃ��Ƃ������Ă���l�ł��A���y�Đ��ɂ�����_�C�i�~�b�N�����W�����ʂ̐U�蕝�ƊW���Ă���Ƃ���������O�̘b�𗝉����悤�Ƃ͂��܂���ł����B���ꂪ�P�l��Q�l�̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł��B�l�I�ɂ͂������l�����ł���Ǝv���̂ł����A�����������Ƃ������قǁA������ɖ�肪����Ƌ��e���Ă���̂ł��B�������ʂ̈�ʏ펯���ʂ�Ȃ��B�I�[�f�B�I�ɂ͂�������������������ʂ�����܂��B
���̃X���b�h�ł͂����������Ƃ��Ȃ��A��Âȉ�b�����藧���Ă���̂ŁA�ǂ߂ΎQ�l�ɂȂ镔�������X���邩�Ǝv���܂��B���ǂ͎����������Ăǂ��Ȃ̂����I�[�f�B�I�̂��ׂĂƂ͂����A���낢��Șb��ʔ�����������邱�Ǝ��̂́A�Ȃ����̂��邱�Ƃł͂Ȃ��ł�����ˁB�����莝���̋@�ނŊm�F�ł���悤�Ȃ��Ƃ�����܂�����A���Ԃ̎������ł���܂������͏o�������Ǝv���܂��B�����͂����Ă�PC�I�[�f�B�I�͎�肠�����@�킪����܂��悭�炢�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�����������Ƃ͂ł��܂��ǂˁB
�����ԍ��F21753273
![]() 3�_
3�_
tohoho3����
tohoho3����[21752971]
>�u�Đ�����clock(VCO)�͔����g�`�ɔ�Ⴕ�����g���ϓ�����������v->�u�͂��Ȃ��特��(���ɔ{������)�̎��g�����ω�����v�̈��ʊW�����͕�����Ȃ��̂���
���͑S�R�W�b�^�[�̑�Ƃ��Ⴀ��܂��i���̋̐l�́u�W�b�^�v�ƌ����܂��ˁj�A��L�́A�u��������ψق��遁����������v���A�킩��ɂ��������Ă��邾�����Ǝv���܂��B
���g�� fo �̃T�C���g�������āA���z�I�ɂ͌Œ�ł���ׂ��ʑ����A���g�� ��f ( <<fo ) �̃T�C���g��ɕω�����ꍇ�i�ʑ��G���j�A�p�C������̓\���������N�� <http://sonove.angry.jp/jitter_sim01.html> �̐}�̂悤�ɁAfo �̗��ׂ� fo±��f �̐������������܂��itohoho3����ɂ͂��傤�ǂ������K��肾�Ǝv���܂��j�B���������
tohoho3����[21734007]
>���̋ߖT���O�̎G�����x����������オ���Ă�̂��i�Y�t�}�Q�Ɓj�A�W�b�^�̑���
>�ɂ��e���ƍl���Ă����̂��ȁH
�������ł���ł��傤�B�p�c���́u�{�������v�͂悭�킩��܂��A�����͏c�������Ō���Ηv�͘c�ł�����A���p�Ȕ{�������̕t���ł���A���x�̈Ӗ������m��܂���B
�����ԍ��F21753374
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�L��������܂��B
http://sonove.angry.jp/jitter_sim01.html
�ł̐����́A�T�C���g�̉����M���̈ʑ��ɁA�ő�10nsec�̎��ԐU���i���Ԃ̃Y����1kHz�̎���������j�̃W�b�^
��lj�����ƁA�T�C���g�̎��g���̗�����1kHz�̃I�t�Z�b�g���g���ő��єg�������Ƃ����̂͗����ł����ł����A
DAC�𐧌䂷��N���b�N�ɓ����W�b�^��lj������ꍇ���ADAC�̏o�͂ł���A�i���O�M���̃T�C���g�̈ʑ���
�����W�b�^�ŕϒ�����ƍl���Ă������Ƃ������Ƃł��傤���H
�����ԍ��F21753484
![]() 1�_
1�_
tohoho3����
���A��̓��e�Ń����N�̒��肩���ƃT�C���g�]�X�̐������ԈႦ�܂������A�܂��������B
>DAC�𐧌䂷��N���b�N�ɓ����W�b�^��lj������ꍇ���ADAC�̏o�͂ł���A�i���O�M���̃T�C���g�̈ʑ���
>�����W�b�^�ŕϒ�����ƍl���Ă������Ƃ������Ƃł��傤���H
�ɂ��ẮA���m�ɂ͂c�`�b�̍\���ɂ���肻���ł����A���̂Ƃ��낻���l���邵�����傤���Ȃ��Ǝv���܂��B����܂��Ȃ��Ă��݂܂���B
�����ԍ��F21753551
![]() 2�_
2�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A
DAC�̓��쌴���ɂȂ��Ă����Ő�������ɂ͍��ݓ������b�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤���B
�d�˂ėL��������܂����B
�����ԍ��F21753673
![]() 1�_
1�_
Symbolist_K�����
���b�s���O�ɂ��Ă̎��l�̌����m�ɏ����Ă���܂���ł����̂ŁA�����ŏ������Ă��������܂��B
���ڃ��b�s���O�ʼn����ǂ��Ȃ邩�ɂ��ẮA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��A�ǂ���Ƃ������Ȃ��Ƃ����X�^���X�ł��B����͂͂�����Ƃ��������ǂ����ł������ɂ���܂��A����Ȃ�ǂ���ł��悢�ł͂Ȃ����Ƃ����l���ł��B���ɋ��d�ɂǂ���ł���Ǝ咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ����@�Ƃ����̂����ɂ͂���܂���B
�����ł���BPC��ŃR�s�[���������ʼn��������Ȃ�Ƃ�����A���낢��s���������Ȃ��ł����H�@�͂����茾���Č�����Ȃ��ł����H�@�Ⴆ�ΒN����CD�����肵�ă��b�s���O�����B���̏ꍇ�ACD�����b�s���O�������Ƃ�����܂����K�v������܂��B���������A���p�����A�����^���Ŏ肽�B�������������y�f�[�^�����l�ł��B�p�\�R������ꂽ��A�n�[�h�f�B�X�N����ꂽ��A���������g���u���Ńf�[�^�����Ȃ��Ȃ����߂ɁA�R�s�[���ĕێ�����͕̂��ʂɂ݂�Ȃ���Ă��邱�Ƃ��Ǝv�����A����ʼn������ǂ��Ƃ��l���Ă����肪�����͂Ȃ��ł��B
�ł��A�����ɂ��������@������L����@��������Ƃ�����A�����ɖ��m�Ȋm�M���Ȃ������Ƃ��Ă��A�m�F�ł��Ȃ����Ƃ������Ƃ��Ă��A�������ǂ��Ȃ�ƌ������邩���m��܂���B�D���ȉ��y�������ł��������Œ������߂ɍőP��s�����B�����������s�ׂɗ����͕K�v�Ȃ��Ǝv���܂��B�ł��A���ׂ����Ƒ��l�Ɏ咣����Ƃ��ɂ͍�����K�v�Ƃ��邵�A�����������邱�Ƃł��Ȃ��̂Ŏ�����������Ď��������y���ށB�����Ď��Ȗ����Ǝ��ȓ����B���ꂼ�I�[�f�B�I�B�ł����ˁB
�����ԍ��F21753744
![]() 4�_
4�_
[21752553] �̏������݂ł����A���p�����u���O�̓ǂݕ����ԈႦ�Ă��܂����B
http://jobless-fish.com/135
�̃u���O�́A�u�n�C���]���������̂ɍ��z�����܂��ꂽ�v�Ƃ����b�ł͂���܂���ł����B
�������́A�uCD�̉�����e-onkyo�ōw�����������Ȃ�48kHz/24bit�̃n�C���]�����̔g�`���ׂĂ݂�ƁA�n�C���]�̕��͐���Ȃ̂ɁACD�͍��z�������v�Ƃ����b�ł����B
CD�̕��ɂ����A�n�C���]�����ł͂���Ă��Ȃ��A����ȃR���v�|���E�����������Ȃ���Ă��āA����CD�ɂ͎��]�����R�B����J-POP��CD�ɓ��L�̊��s�͒Q���킵���Ƃ�����|�ł����B
�t��e-onkyo�̃n�C���]�����͗ǂ����������ł��B
�������āA���l�т������܂��B
�����ԍ��F21753978
![]() 2�_
2�_
Minerva2000����
��AIT�p�c����́A�`���W�b�^�[��P�[�u���̋@�B�I�U�������܂艹���ɂ͉e�����Ȃ��A�Ƃ͌����Ă��Ȃ��̂ł́H
AIT�p�c����̃u���O�ɁA
�u�����ɑ��ւ���JITTER�ʂ͐�ns�ł����ʉ\�Ȃقǂł����A���ւ��Ȃ�JITTER�i���g������x�A���x���܂݁j�͎��S/N�̗��x�ł��܂艹���ɂ͉e�����Ȃ��ƍl���܂��B�v
�Ƃ����L�q�ƁA
�uJITTER�ɂ͉����M���̑��֗L���ɂ���Ĉȉ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
[���ւ���JITTER]
1 �`���n�̎��g�������ɂ�����
2 �����C���s�[�_���X�̐����s�ǂɂ�锽��
3 ���M����H�̐��\�s�\��
4 ��M���̂Q�l����H�̐U���ʑ��ϊ��ɂ���Ĕ���
[���֖���JITTER]
5 ���M���̎��g���ϓ�
6 �W�Q�g���d��
7 �@�B�I�U���ɂ���Ĕ����v
�Ƃ����L�q���������̂ŁA�g�ݍ��킹��ƁA�����M���Ƒ��ւ��Ȃ�JITTER�ł���5, 6, 7�́u���S/N�̗��x�ł��܂艹���ɂ͉e�����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł����A����������Ŋp�c����́A
�uS/PDIF�ڑ��͕K�������̑��ւ̂���JITTER���������܂��̂ŁA���炩�̕��@�ŏ�������K�v������܂��v
�u�Ƃ��낪I2S/DSD�ڑ��̂悤�ɉ����Ƒ��ւ���JITTER(�ʑ��G��)�����Ȃ�CLOCK�𗘗p�ł���ꍇ�́A�b�����قȂ�܂��B�����Ƒ��ւ���JITTER����܂���̂ŗ}������K�v������܂���v
�Ƃ��q�ׂĂ��܂����B�Ƃ������Ƃ́A�`���W�b�^�[�������ɉe�����邩�ǂ����͐ڑ����@�ɂ��A�Ƃ����̂��p�c����̐^�ӂƂ������ƂɂȂ�ł��傤���B
������N���b�N�W�b�^�[�̌��m�����60pS�Ƃ���Ă���̂͑Ó��ȂƂ���ł��傤�B60pS�̎��ԂƂ͌����^��1.8cm�i�ނ̂ɗv���鎞�Ԃł����A�l�̎��̊��x�̗ǂ��ɂ͋����܂��B
�u�����ȃW�b�^�[�ł������ɉe������v���ƂɊւ��ẮA���Љ���������Ԗx�����̎��̋L�q���悭�킩��܂��ˁihttp://ednjapan.com/edn/articles/0709/01/news016_2.html�j�F
�u�f�W�^���I�[�f�B�I�V�X�e���ɂ�����W�b�^�[�̖��́A�f�[�^�G���[���N����Ƃ������Ƃ͈قȂ�B�f�W�^���I�[�f�B�I�V�X�e���ł͈����N���b�N���g�����Ⴂ���߁A�^�C�~���O�}�[�W���͏\���ɂ���B�]���āA�����̃W�b�^�[�ł̓f�[�^�G���[�͔������Ȃ��B
�@�ł́A�ǂ̂悤�Ȗ�肪��������̂��Ƃ����A�f�W�^���I�[�f�B�I�V�X�e���̑O��ł���T���v�����O�藝�����S�ɂ͐������Ȃ��Ȃ�̂��B�܂�A�T���v�����O�N���b�N�̃W�b�^�[�ɂ��A�T���v�����O�Ԋu�����X���X�ƕϓ����Ă��܂����Ƃ����Ȃ̂ł���B���̂��Ƃ́A�f�[�^���̂̓`����ۑ��̏�ł͖��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�f�[�^�G���[����������킯�ł͂Ȃ�����ł���B��肪�\�ʉ�����̂́AA-D�ϊ���D-A�ϊ��ɂ����Ă��BA-D/D-A�ϊ����̃W�b�^�[�́A�T���v�����O�Ԋu��ϓ�������B����������A�T���v�����O�藝�ɏ]�����ϊ����W�Q����邱�ƂŁA�I�[�f�B�I�M���ɑ��Ď��Ԏ������̕ϒ��������B���Ȃ킿�A�W�b�^�[�͖{���̃I�[�f�B�I�M���ɑ��Ęc�i�Ђ��݁j��^����̂ł���B���̌��ʁA�S�����g�c���iTHD�@�{N�j��_�C�i�~�b�N�����W�AS/N��i�M���ΎG����j�Ȃǂ̂�����I�[�f�B�I���\������B
�@�W�b�^�[�������ȏꍇ�ɂ́A�I�[�f�B�I���\�̗͐����Ƃ��Ă͌���Ȃ��B�������A�������\�ȉ����̕ω��Ƃ��ĉe����������ꍇ������B�v
�i�Ԗx�����͋@��鑤�̋ƊE�l�Ȃ̂ł��̑�l�̎������������ēǂނׂ��d�d�d�Ƃ����Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̂�����������܂������j
�����ԍ��F21754112
![]() 2�_
2�_
�Ɠd��D���̑�コ��
�����͂��̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��Ă����i�R���̃X���b�h�Řb�������Ƃ�����̂ł����A�I�[�P�X�g���̋�̓I�ȋȖ��������Đ��������̂ɁA�ǂ����Ă����ʂ̕ω��ɊW����Ƃ������Ƃ𗝉����Ă��炤���Ƃ��ł��܂���ł����B����ǂ��납������̗���͂��Ȃ��ł���Ƃ��A���{�ꂪ�����ł��Ȃ��ł���Ƃ��A����͂����������̂ł����B
���͎��́A���̃X���Ŏ��₵�܂��������݂�����̂��A���i�R���̃N�`�R�~�f�����g�����߂Ă̌o���Ȃ̂ŁA�����̎���ɂ܂��s�ē��Ȃ̂ł����A�Љ���������ߋ��́u�P�[�u���X���v�Ȃǂ�ǂ�ł݂�ƁA�Ȃ���������݂����ȕ���������悤�ł��ˁB�܂��A���̒������l�͂����ς�����̂ŁA���傤���Ȃ��ł��ˁB
�����̃X���b�h�ł͂����������Ƃ��Ȃ��A��Âȉ�b�����藧���Ă���̂ŁA�ǂ߂ΎQ�l�ɂȂ镔�������X���邩�Ǝv���܂��B���ǂ͎����������Ăǂ��Ȃ̂����I�[�f�B�I�̂��ׂĂƂ͂����A���낢��Șb��ʔ�����������邱�Ǝ��̂́A�Ȃ����̂��邱�Ƃł͂Ȃ��ł�����ˁB�����莝���̋@�ނŊm�F�ł���悤�Ȃ��Ƃ�����܂�����A���Ԃ̎������ł���܂������͏o�������Ǝv���܂��B
�p���X�������܂��̂ŁA������ł���낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F21754139
![]() 2�_
2�_
�Ɠd��D���̑�コ��
�����ڃ��b�s���O�ʼn����ǂ��Ȃ邩�ɂ��ẮA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��A�ǂ���Ƃ������Ȃ��Ƃ����X�^���X�ł��B����͂͂�����Ƃ��������ǂ����ł������ɂ���܂��A����Ȃ�ǂ���ł��悢�ł͂Ȃ����Ƃ����l���ł��B���ɋ��d�ɂǂ���ł���Ǝ咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ����@�Ƃ����̂����ɂ͂���܂���B
�������ł���BPC��ŃR�s�[���������ʼn��������Ȃ�Ƃ�����A���낢��s���������Ȃ��ł����H�@�͂����茾���Č�����Ȃ��ł����H
�͂��A�s�������ł��ˁB�����A[21735657] �Ŏ��̂悤�ɏ����܂����F
�u���́A���͂���Ɓu�i���܂�j�ς��Ȃ��h�v�ւƌX�������āACD���ڃ��b�s���O�͕K�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƌ^������܂��B���̗��R�́F�v
�u�R�DMinerva2000����́u�ς��v�Ƃ������̂́A�u�W�b�^�[�����_�����O�v�Ȃǂ̑���Ă���Ă�����A���̏�ł�PC���b�s���O�Ȃ���v�����ł���B�v
�u�U�DCD���ڃ��b�s���O�Œ���HAP-Z1ES�ɓ��ꂽ�Ƃ���ŁAHAP-Z1ES���n�[�h�f�B�X�N���ł̈ړ���珑���������f�t���O�������Ă��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B�i������͂����ł��傤���H �ǂȂ�������������܂��H�j
�V�DHAP-Z1ES�ɉ������N�����āA�n�[�h�f�B�X�N�����������āA�o�b�N�A�b�v����̃R�s�[�Ŗ߂��Ȃ��ƂȂ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B
�d�d�d�Ȃǂ��l�����킹��ƁACD���ڃ��b�s���O�ɏ��ɓI�ɂȂ炴������܂���B�v
�����̈�ۂ́A���������ł��B
�������ɖ��m�Ȋm�M���Ȃ������Ƃ��Ă��A�m�F�ł��Ȃ����Ƃ������Ƃ��Ă��A�������ǂ��Ȃ�ƌ������邩���m��܂���B�D���ȉ��y�������ł��������Œ������߂ɍőP��s�����B�����������s�ׂɗ����͕K�v�Ȃ��Ǝv���܂��B�ł��A���ׂ����Ƒ��l�Ɏ咣����Ƃ��ɂ͍�����K�v�Ƃ��邵�A�����������邱�Ƃł��Ȃ��̂Ŏ�����������Ď��������y���ށB�����Ď��Ȗ����Ǝ��ȓ����B���ꂼ�I�[�f�B�I�B�ł����ˁB
�����ł��B�����A�����̐l�Ɂu�������ǂ��Ȃ�ƌ�����v���܂���I �ł��A����͂��̃X���ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��Q�l�����Ȃ̂ŁA������Ɖ��^�I�ɂȂ炴������Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F21754168
![]() 2�_
2�_
�����ڃ��b�s���O�ʼn����ǂ��Ȃ邩�ɂ��ẮA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��A�ǂ���Ƃ������Ȃ��Ƃ����X�^���X�ł��B
�p�\�R���ł̃��b�s���O�B
�o�[�X�g��荞�݁C�Z�L���A��荞�݁B
���b�s���O�̎d���ŏo���オ�鉹���t�@�C���́C��Ȋۂ��ƁC�A���o���ꖇ�ۂ��ƈႢ�܂�����ˁB
���@�̎�荞�ݎd���ɂ���ẮC�o���オ�鉹���t�@�C���̓p�\�R�����b�s���O���l�Ɏd�オ����͕ς��ł��傤�B
�h�`���Ƃ����f�o���Ȃ��̂́C�ɁX���ʁB
�܁[�C�\�j�[�̉ߋ��̃p�\�R���A�v���̃f�t�H���g��荞�݂̓G���[�����@�\�������B
�ܘ_�C�A�b�v���̃A�v���������B
��USB�O�t��DVD/BD�h���C�u�������ɍw�����ׂ����ǂ����Ŗ����Ă��܂��B
����B
�p�C�I�j�A��9�n�h���C�u�{���g�b�N�̋����P�[�X�̃��m����CAstell&Kern AK CD-RIPPER MKII�{dBpoweramp CD Ripper�ɂăp�\�R�����b�s���O�ł���B
�p�C�̃h���C�u�̓��b�s���O���x�������Ȃ�߂��ŁC�X�����Ȃ����ˁB
�ŋ߂̃��m��B
�ŁC���@�̃��b�s���O�̎d���i�ݒ蓙�j�́C�V���v���Ȏ�荞�݂����ˁH
�]�v�Ȏ������Ȃ��ŁC�V���v���ȓ���Ń��b�s���O�ł�����ˁB
�����ԍ��F21754212
![]() 1�_
1�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����g�� fo �̃T�C���g�������āA���z�I�ɂ͌Œ�ł���ׂ��ʑ����A���g�� ��f ( <<fo ) �̃T�C���g��ɕω�����ꍇ�i�ʑ��G���j�A�p�C������̓\���������N��ihttp://sonove.angry.jp/jitter_sim01.html�j�̐}�̂悤�ɁAfo �̗��ׂ� fo±��f �̐������������܂�
���̎��g���ϓ��ɂ��A�����S�̂��e������̂ł��ˁB
���p�c���́u�{�������v�͂悭�킩��܂��A�����͏c�������Ō���Ηv�͘c�ł�����A���p�Ȕ{�������̕t���ł���A���x�̈Ӗ������m��܂���B
�p�c����ɂ��A�u��������DAC�ł�RANDOM JITTER������ƕ���*�ɂ���悤��S/N���������܂��BSPDIF�̏ꍇ�̂���JITTER**��PLL��LOOP�t�B���^�[�Ő�������邽�߁A�����̒��ɑ��ւ���ꍇ�������ł��B�܂�JITTER�ɂ���āA�ʂ͂킸���ł������M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂������Ӗ����܂��v�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�u�{�������v�Ƃ͂��̕t�����ꂽ���M���̂��ƂŁA����ɂ��L��̉������e������Ƃ������Ƃł��傤���B
���Ȃ݂ɁA�u����*�v�Ƃ́F
http://www.k.hosei.ac.jp/~yasuda/Academic%20society_2011_1.pdf
�ŁA
�uSPDIF�̏ꍇ�̂���JITTER**�v�ɂ��ẮF
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf
�ɏ����Ă���Ƃ������Ƃł����A
�����̂ŁA�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�ǂ�œ��e�������܂�ŋ����Ă��������B
�����ԍ��F21754278
![]() 2�_
2�_
�ƂĂ����_�ɒB�����Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA�c�_���p�����邽�߂Ƀp�[�g�Q�����܂����B
�����������̃X���b�h�ɂ����e�������F
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21754288/
��낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F21754293
![]() 2�_
2�_
�p�[�g�Q�ւƑ����܂����AGood�A���T�[��I�Ԃ��߂ɁA�b��I�ɂ��̃X���������ς݂ɂ��܂����B
Good�A���T�[�́F
�ł����e���������A���݂��ɋc�_���킹�Ȃ��炱�̃X���𐬒������A������ׂ������ւƓ����A�X����ɂ�������̂��Ƃ������ĉ�������
�EMinerva2000����
�E�p�C������
�E�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�̂��O���Ƃ����Ă��������܂����B
�����ԍ��F21754300
![]() 2�_
2�_
�b��I�ɉ����ς݂ɂ����̂ŁA�b��I�Ȍ��_�Ƃ��āA����܂ł̃X���b�h�̑��������Ă����܂��F
�� �W��̎���ɑ�������肷��ɂ������āA���t���ƂȂ闝�_�̓��ۂ�Nj�����ۂɂ́A�f�W�^���̖��ƃA�i���O�̖���蕪���Ę_���Ȃ���A�_�c�̑Ώۂ����m�ɂȂ�Ȃ��B�i�p�C������̎w�E�j
�m�f�W�^���̈�̎��ہn
�� �f�[�^��]���^�R�s�[����Ƃ��ɂ́A�u�`���W�b�^�[�v�ɂ��]���g�̋�`�݂̓���̒��x�Ɋւ�炸�A�]���^�R�s�[�̌��ʂɂ����ăf�W�^���f�[�^�Ƃ��Ẵo�C�i���̈�v�͕ۂ����B
�m�A�i���O�̈�̎��ہn
�� �Q�̃o�C�i������v�����f�[�^�̍Đ��ɂ����āA�����̃n�[�h�f�B�X�N�̉~�Տ�ɋL�^����Ă���ʒu�̈Ⴂ�ɂ���ĉ������ς��\���͑��݂���B
�� ���̗��R�ɂ͂Q������B�����Q���̂ǂ��炪�������ɂ���AHDD��ɋL�^����Ă���ʒu�̈Ⴂ�ɂ�鉹���ω��̉\�����x�������Ȃ�A�gCD���ڃ��b�s���O�h�ɂ����HAP-Z1ES��HDD�ɒ��ڋL�^���ꂽ���y�f�[�^�ƁgPC���b�s���O�h�ɂ���ċL�^���ꂽ���HAP-Z1ES��HDD�ɓ]�����ꂽ���y�f�[�^�Ƃ̊ԂɁA�o�C�i���͓���ł����Ă��A�Đ������Ƃ��̉����I���ق����݂���\���͂��邱�ƂɂȂ�A�ς��̂ł���A���̔}��o�H�̏��Ȃ�����gCD���ڃ��b�s���O�h�̕��̉����I�D�ʐ����\�z�����B
�� �P���́A���Ȃ��܂鎁�ɂ����̂Łihttp://kanaimaru.com/AVQA/0f.htm�j�F
��0����1�A1����0�֔��]����^�C�~���O�́A���̃A�i���O�̓ǂݏo�����g�`���ア�ƁA�O���O���Ǝ��ԓI�ɑO��ɗh��܂��B�h��Ă��ǂݏo���^�C�~���O�܂łɂ͕K�����肵�܂��̂Łi�����Ȃ�悤�ɃT�[�{�n�����삵�Ă��܂��j��͂萔���͊ԈႢ�܂���B�Ƃ��낪�g�`�����]����Ƃ��ɂ͓d���ɃX�p�C�N�m�C�Y������܂��B�g�`���O���O���h��Ă���ƁA���]�m�C�Y���o��^�C�~���O���O���O���ɂȂ�܂��B���ꂪ��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�Ɖ������Q���܂��B�܂��R�s�[���͌��ɔ�ׂ�Ɨh�ꂪ�����Ȃ�̂ŁA�������ς���čs���i��ʓI�ɂ͗��čs���j�̂ł��B
�܂�A�uDAC�ɋ��������N���b�N�ɃW�b�^�[���ڂ�A���������A�i���O�g�`���̂��ώ����邩��v�iMinerva2000����ɂ��v��j�ł���A����̓A�W�����g�E�e�N�m���W�[�Ђɂ��u�V���b�g�E�m�C�Y�ɂ�郉���_���W�b�^�[�ƁA������H����̃f�[�^�ˑ��W�b�^�[�v�ɓ�����ihttp://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5718JAJP.pdf�j�B
�� ���̐��ɂ��AHDD�݂̂Ȃ炸SSD�ł������͕ς�邱�ƂɂȂ�܂��B��Ƃ��ẮA�N���E�h���o�R������Ȃǂ��ăW�b�^�[�����_�����O������A�N���b�N�M���̃W�b�^�[��ጸ����H�v���Ȃ���Ă���DAC�i�N���b�N�E���J�o����H��DDS��SRC��VCXO���g�������̂Ȃǁj���A���邢��OCXO��r�W�E�����g�����}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[��ڑ�����Ƃ��������Ƃ���������B
�� �������A���̉����̈Ⴂ�����ۂɎ��Œ����������邩�ǂ����Ƃ������Ɋւ��ẮA�Ⴆ�Ή͍��ꎁ�ihttp://ednjapan.com/edn/articles/1208/24/news015_3.html�j�ɂ��F
���~�h�������W�E�n�C�G���h�O���[�h��D-A�R���o�[�^IC�̎��т��ɋ�����ƁA�q�X�g�O��������ɂ��}�X�^�[�N���b�N�̃W�b�^�[�ʂ�200ps�i�s�R�b�j�����ł���A���ۂ̃I�[�f�B�I�����ɂقƂ�lje�������ƌ�����B����200ps�Ƃ������l�́A��ʓI��SPDIF�f�R�[�_�[IC�̓���PLL�Ő��������}�X�^�[�N���b�N�̃W�b�^�[�̎��͒l�Ɠ����ł���B
�Ƃ����̂��@��̔\�͂ł��邩�����A�l�Ԃ̒m�o�̌��E�́A����ABX�����ł́i"Theoretical and Audible Effects of Jitter on Digital Audio Quality," Eric Benjamin and Benjamin Gannon, AES Convention, September 1998�j�F
���l�Ԃ̃W�b�^�[�̒m�o��臒l�́F
�����ŁA10nsec���x�B
�y�ȍĐ����ŁA30nsec�`300nsec���x�B
�Ƃ������ʂ��o���̂ŁA�����̈Ⴂ�����Œ���������̂͂قڕs�\�ł͂Ȃ����Ƃ����^�`���A�p�C������i[21733077]���j�ƖY��悤�ɂ��������Ȃ�����i[21736884]���j�ɂ���Ē�o����Ă���B
�� �����A�p�C������i[21729066]�j�̐��ɂ��F
���Q�̓���f�[�^�̏������܂ꂽ�ʒu���Ⴄ�ƁA���ꂼ��̃f�[�^���V�[�N����w�b�h�̓������Ⴂ�܂��B�w�b�h�̓X�s���h�����[�^�[�œ����̂ŁA���̓s�x��������ׂ�������܂��B����ɂ���Ĕ������������g�m�C�Y�⍂���g�m�C�Y�i�f�W�^���f�[�^��]�����邽�߂̃A�i���O�]���g���܂ށj�Ȃǂ��A�M�����C����A�[�X���C������A�i���O��H�ɓ��荞�肷��ƁA�A�[�X�p�^�[����z���p�^�[���ɂ���ăO�����h���[�v�m�C�Y���������A���ʂƂ���DAC����o�͂��ꂽ�����������Ȃ�Ƃ������Ƃ͕��ʂɍl�����܂��B
�܂�A�uDA�ϊ����ꂽ�A�i���O�g�`�ɃA�i���O�m�C�Y�g�`������邩��v�iMinerva2000����ɂ��v��j�ł���A�s�K���ɔ�������u�����_���W�b�^�[�v�ɓ�����B
�� ���̐��ɂ��ASSD���g���Ή������͂قڍ�������邱�ƂɂȂ�B
�m���ۂɎ��Œ�����ׂ����̎��̌��Ƃ��Ă̊��z�n
�� �u��ʂ����Ȃ��v�Ɣ��f���ꂽ���F �Â����̑�D������A�l�̓Z�C�E�`����
�� �u�gCD���ڃ��b�s���O�h�̕��������ǂ��v�Ɣ��f���ꂽ���F �G���Y�̕Њ��ꂳ��A�p�c��Y���i��l�̎����j
�����ԍ��F21754310
![]() 2�_
2�_
����ł́A�݂Ȃ��܁A�p���X���ł�����܂��傤�B��@���悤�I
�����ԍ��F21754318
![]() 2�_
2�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
HAP-Z1ES�AWINDOWS�P�O�m�[�gPC���ɓ�������LAN���C���^�[�l�b�g�ڑ����Ă��܂��B
HAP MUSIC�@TRANSFAR�ŃR�s�[�ׂ̈ɐڑ����悤�Ƃ���ƁuIP�A�h���X���قȂ邽�ߐڑ��ł��܂���v
�ƂȂ�܂��B
���ׂ��HAP��PC��IP�A�h���X�̉��ꌅ���Ⴂ�܂��B
����LAN���[�^�[����x���Z�b�g������AHAP�@MUSIC�@TRANSFAR���C���X�g�[�����Ȃ������肵�Ă��_���ł����B
�X�}�z�Ƃ͖���LAN�Őڑ��ł��Ă��܂��B
�����������@�������m�Ȃ�����ĉ������B
![]() 1�_
1�_
��ABEBIREX����
HAP��PC��IP�A�h���X�̉��ꌅ�������Ⴄ�͖̂��Ȃ��ł��B
�{�@�̃��Z�b�g�͎�����܂������H
�����ԍ��F21748248
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�{�̂̏����������܂������������ł��Ă��Ȃ��悤�ł��B
���y�f�[�^���c���Ă���A�A�b�v�f�[�g�����ꂽ�܂܂ł��B
���Âōw����������Ȃ̂ł����̏�ł��傤���H
�̏�ł���Εԕi�̓s��������܂��̂Œm���̂��邩���̕ԐM���X�������肢���܂��B
�����ԍ��F21749174
![]() 0�_
0�_
�{�̂ŃA���o���͈���폜�ł��܂����B
�A���A�n�[�h�f�B�X�N�̍ăX�L�����A�H��o���ݒ�����܂��Ă����y�f�[�^�̓N���[���ɂȂ�܂���B
�Q�O�P�R�N���ł����A�A�b�v�f�[�g���ŐV�̂܂܂ŃI�[�f�B�I�ݒ������������܂���B
�̏Ⴉ�Ǝv���ƐS�z�ł��B
�ǂȂ����m���̂�����X�������肢���܂��B
�����ԍ��F21749270
![]() 0�_
0�_
�{�̂ŃA���o���̍폜�͏o�����̂ł����A������������܂����y�f�[�^���P�O�Ȃɖ߂��Ă܂����B
�������ݒ蓙�̏��������o���Ă܂���B
�̏Ⴉ�ǂ������f���Ē��������Ǝv���܂��B
�ǂȂ����X�������肢���܂��B
�����ԍ��F21749450
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
�̏�̉\��������̂Ń\�j�[�ɑ��k����Ă͂������ł��傤�B
�����ԍ��F21749799
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���͂悤�������܂��B
��͂�̏�ł��傤���H
���t�I�N�Ōl�o�i�҂��璆�Õi���w����������Ȃ̂ł��Ȃ�c�O�ł��B
�Ƃ肠�����ʖڌ��ŕԕi�����肢���Ă݂܂��B
�t���s��̃��R�[���̑Ώۏ��i�ɂ��Ȃ��Ă��܂��̂ōŏI�I�ɂ�SONY�̂����b�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21749815
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
�H��o���ɖ߂��Ă��t�@�[���E�F�A�͖߂�܂���B
�܂��T���v���Ȃ͓�������ԂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F21749823
![]() 1�_
1�_
��mctoru����
�t�@�[���E�F�A�͏������ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��ˁB�����Ă���Ȃ��ǂ��݂���T���v���ł����B
�Ƃ肠�����̏�ł͂Ȃ������ł��B
���肪�Ƃ������܂��B
���Ƃ͖���LAN�ڑ����o����Ηǂ��̂ł����B
�����ԍ��F21750589
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
���[�^�[�Ɩ{�@�����Z�b�g���Ă��������Ȃ���Ȃ��̂��A�̏Ⴞ�Ǝv�����̂ł����B
���������ăt�@�[���E�G�A���߂�Ȃ�������A�T���v���������Ȃ��͕̂��ʂł��B
�����ԍ��F21750646
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
������������t�@�[���E�F�A�͖߂���́A�T���v���f�[�^�͑O�̎�����̃f�[�^���Ǝv���Ă܂����B
���̊��Ⴂ�ł����f���|�����܂����B
���肪�Ƃ��������܂��B
����LAN�ڑ��Ȃ̂ł����A�G�N�X�v���[���[��HAP-Z1es�̉��y�f�[�^���p�\�R���ɃR�s�[���邱�Ƃ͂ł��܂����B
�ԈႢ�Ȃ��q�����Ă��܂��B
�Ȃ�Hap Music Transfer����f�[�^�̃R�s�[���o���Ȃ��̂��s�v�c�ł��B
�����ԍ��F21750778
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
���L���Q�Ƃ��������B
http://helpguide.sony.net/ha/haps1/v1/ja/contents/TP0000165239.html
�����ԍ��F21750820
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�ǂ܂��Ē����܂����B
�w���v�K�C�h�̂Ƃ���h���b�O&�h���b�v�ʼn��y�t�@�C�����R�s�[���悤�ɂ��A�mHAP���Q�Ɓn����G�N�X�v���[���[���J���Ă���܂���B
���ڃG�N�X�v���[���[���J���܂��ƁAPC�́h�l�b�g���[�N�̏ꏊ�h�̂Ƃ����HAP-Z1ES��VAIIO�i�����L��PC�j������܂��B
HAP-Z1ES���特�y�f�[�^��PC�ɃR�s�[�ł��܂������̋t�͏o���܂���B
���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F21750878
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
���L���Q�Ƃ��������B
https://www.sony.jp/audio/update/?nccharset=ACDE0384&searchWord=Hap
�����ԍ��F21750952
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�{�̃A�b�v�f�[�g�͍ŐV�ł��B
���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F21751188
![]() 0�_
0�_
�ƂȂ�ƁA��͂�\�j�[�ɑ��k�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21751709
![]()
![]() 1�_
1�_
��Minerva2000����
���r���O�Ɏ�������Ń��f������L��LAN�Őڑ��A�E�C���X�\�t�g�̈ꎞ���f������Ă݂܂������ʖڂł����B
�X�}�z����̃R�s�[�͂Ƃ肠�����ł��܂�������̃A���o������ɕʂ�Ă�����]�v�ȕ��܂ŃR�s�[�����肵�đʖڂł����B
�Ƃ肠���������͔�ꂽ�̂ł��̕ӂŎ~�߂Ƃ��܂��B
�܂������F�X����Ă݂܂��B
�Ō�͕ԕi���\�j�[�ɑ��k�ɂȂ肻���ł��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21751835
![]() 0�_
0�_
PC�����������܂����疳��HAP-Z1ES�Ɩ���LAN�Ōq����܂����B
PC�Ƃ̑����̖��ł��傤���H
PC��VAIO�Ȃ̂�SONY���m�ő����������Ƃ����̂��ǂ����ƁB
����Ɖ����v���܂����B
�F�l���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21753752
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
��������ėǂ������ł��ˁB
�Q�l�܂łɋ����Ē��������̂ł����APC�̏������Ƃ͋�̓I�ɂ͉������ꂽ�̂ł��傤���H
�܂���HDD�̃t�H�[�}�b�g��OS�̓��꒼���͂���Ă��܂����ˁB
�P�ɃV���b�g�_�E���ƍċN���ł��傤���H
�����ԍ��F21753815
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
windows10�Łu�ݒ�v�́u�X�V�ƃZ�L�����e�B�v�ɂ���u�v����A�u����PC��������Ԃɖ߂��v���N�����u�l�p�t�@�C����ێ�����v��
���������܂����B
�E�B���X�\�t�g����K�v�������\�j�[��VAIO�A�v���܂őS�������܂����B
����ł���ƌq����܂����B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21753854
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
�����܂ł���܂������B
�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21753857
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z�T�[�o�[�p����PC �\����
-
�y�~�������̃��X�g�z10��7��
-
�y�~�������̃��X�g�z�����Y
-
�y����E�A�h�o�C�X�z����PC���ւ�����
-
�y�~�������̃��X�g�z����p�\�R��2025
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h
- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��
�i�Ɠd�j
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j