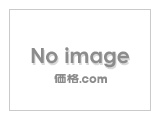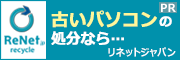�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �o�^���F2003�N 5��16��
���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S30�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2004�N4��14�� 00:02 | |
| 0 | 4 | 2004�N3��8�� 22:13 | |
| 0 | 41 | 2004�N2��16�� 23:31 | |
| 0 | 3 | 2004�N1��20�� 07:28 | |
| 0 | 10 | 2003�N11��2�� 10:16 | |
| 0 | 3 | 2003�N10��26�� 19:59 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�m�[�g�p�\�R�� > NEC > LaVie C LC700/6D
NEC�J��������A�ꕔ������܂����B
�������A���e�Ƃ��Ă͏�Ȃ��̈ꌾ�A�u���x�ݒ�̕ύX�͂ł��܂���A���̂܂܂��g�����������܂��v�ł��B
����ł́A121�T�|�[�g�̕����ϋɓI�ɕԎ����ł��܂����B�ڍׂ͈ȉ��̂悤�ł��B
�����g���̋@���CPU���x�Ǘ��ɂ��ݒ�ɂ��A�ꕔ�����鏈���ቺ���������܂��B
�����̉��x�ݒ���s�Ȃ������R�́APC�������̔��M�ɂ��ُ��h�����߂ƁA�ꕔ���M��}���ă��[�U�[�̍�Ɛ��ɔz���������߁B
�����̐ݒ�ɂ��ẮA�C���e���͓��ɋ֎~���Ă���킯�ł͂���܂���B�i���͖����H�j
���v�]����鉷�x�ݒ�ύX�ɂ��āA�C�����s�Ȃ����Ƃ��ł��܂���B
���C���ł��Ȃ����R�Ƃ��āACPU���x����̂��߂̃N���b�N�y�уt�@������̐ݒ肪���G�ł��邽�߁ANEC�Ƃ��Ă�����ł͏C�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�Ƃ������̂ł��B�ꕔ�����ɂ��邽�ߑO�シ����̂�����܂����A�T�˂��̓��e�ł��B
�J���������̏�F�߂��Ƃ����_�͑O�i�ł����A���̌オ�ǂ��ɂ����������̂ł��B
���[�U�[�Ƃ��Ă̓C���e�����ǂ��Ƃ������Ƃ́A�g�p����i�K�Ŗ�肪������ǂ̗l�Ȑv�����悤������Ȃ��ł��B�u���[�U�[�ɂƂ��Ė��ƂȂ�ݒ�Ŗ�����Ή��������Ƃ���ŁA�����Ƃ��Ă͖��Ƃ��Ȃ��v�ƃT�|�[�g�ɂ��`���Ă���܂����B�����̒��ׂ��͈͂ł��A➑̂Ƃ��ď\���Ȑv��̗]�T������̂ɁA�������Ȑݒ�̂��߂ɏ����ቺ�Ƃ����s������Ă����ł�����B
�X�Ɉ��R�Ƃ����̂��A�����Őv�������̂ł���ɂ��ւ�炸�A���G�����ďC���ł��Ȃ��Ƃ����Ԏ��ł��B��̂ǂ�Ȑv�����Ă���̂��E�E�E�����܂ŕ��G�Ȑv������Ȃ�A�Ō�̋l�߂ł��鉷�x�ݒ�ŕs����o���Ƃ����̂́A�]��ɂ���Ȃ��ł��B
�������Ȃ��ł����A�܂��t�F�[�Y�`�F���W�V�[�g�Ɋւ���Ȃǂ�����Ă��܂���̂ŁA�܂��҂��ł��ˁB
�ԓ����e���炷��ƁA���̏������݂����Ă���悤�ł��B���낻�덡��̑Ή����l���Ȃ��Ƃ����܂��E�E�E
![]() 0�_
0�_
K����O����A������B
�Ƃ肠��������������Ă��ƂȂ�ł����ˁB�����l�ł��B
NEC�̉ł����A���Ȃ�ɖ|���
�u�o���Ȃ����Ƃ͖������A����Ȃ߂�ǂ������Ėׂ���Ȃ����Ƃ͂������Ȃ��̂ŁA���̂܂܉䖝���Ďg�������邩�A�����̐V�������i�����Ă���B�v
�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B
�ނ������ɉa�͂��Ȃ���Ǝp�����ǂ��\��Ă���Ǝv���܂��B
�h煂ȕ\���Ȃ�܂������A�ނ�ꂽ���Ƃ��Ă͂��ꂭ�炢�����Ă��o�`�͓�����Ȃ��ł���(^^�B
�����ԍ��F2585697
![]() 0�_
0�_
MINIMI����A�ǂ����ł��B
�N���������Ă���Ȃ��ƁA��l���o��Ԃŋ������̂ŏ�����܂��B
���A���������čl����Ɣ��ɊԂ������ȂƎv���܂��B
���݁A������ւ��ƌ����ėǂ����炢NEC�̃m�[�g���ς���Ă��܂�����A121�̃��W���[���̃A�b�v�������Ă��A�V�@��Ή��ŊJ�����ɗ]�͂������Ǝv�����ł���B
�܂��A�ł�����A��������������ɂ͂ƒW�����҂͎����Ă��܂����E�E�E�����ƌ����ċC���㏸�͑҂��Ă���܂���A������Ƃ��Ă���ֈĂ��l�����ł��B
NEC�̋Z�p�͂́A�Ǝ��J���͂��猾���Ă��Ȃ�̂��̂��Ǝv���܂����A���悤�͊��ł�����Ǝv���܂��B�܂��A�Ǝ��J���H����\���������ȂƂ��낪����܂����A��������̈�ł��傤�B
�Ƃɂ����A���������˂�܂��B
�����ԍ��F2589679
![]() 0�_
0�_
2004/03/20 05:15�i1�N�ȏ�O�j
�j���̂n���߂܂��āB
�����@����w�����܂��āA���l�ɂb�o�t�g�p�����P�O�O���ɂȂ��ď���
���x���Ȃ�i�ƌ����܂����قڎg�p�ł��Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂��j����
������߂������Ă���܂����B
���͂o�b�ɗ]��ڂ����Ȃ��̂ŁA������߂Ă��܂��Ă��܂������A�j��
�̂n����̏������݂����Ċ����������܂����B
���̋@��Ɍ��ׂ������Ă���l�ōs�����Ă���l������ȂƁB
���������݂����Ȃ��̂�����ΐ��͂������Ǝv���܂��̂ŁA�撣����
�������ˁB
�����̃y�[�W�͗ǂ����Ă��܂��̂ŁA����������܂�����܂����肢
�v���܂��B
���̋@��͂��̖��ȊO�͉t�����������f���炵���Ǝv���܂��̂ŁA
����LC700�V���[�Y�ł��̖�肪�N���A���������ł��ˁB
�����ԍ��F2605332
![]() 0�_
0�_
�k�b�V�O�O�U�c���[�U�[���� �ǂ������߂܂��āB
�����f�U�C�����n�߂Ƃ��ċC�ɓ����Ă��܂��̂Łi�D�݂͕�����邩������܂��j�A����6D��厖�Ɏg���Ă�肽���Ǝv���Ă��܂��B
���܂ŁA�Ƃ����̂�NEC����ł��ˁB
�v�X�ɁA���Ƃ������ƂŁA�e���[�J�[�̃p�b�V����p���x������B����������������W���܂����B
���e���[�J�[Pentiam4-M�@��
NEC�@LC7006D-70���@LC7005D-70���@LC9005D-70���@
���Ł@G6C/X18PME-107.9���@
DELL�@�ݒ肵�Ă��Ȃ��悤�ł�
EPSON NT7000-100���@
�x�m�ʁ@�قƂ�ǎg���ĂȂ�
��NEC��Pentiam-M�@��
LavieM-92���@LavieRX-100���@LavieJ-90��
�Ƃ����킯�ł��B
�����ԍ��F2607750
![]() 0�_
0�_
�Ԃ������܂����B
���̊ԑ�ֈĂƂ��āA�t�F�[�Y�`�F���W�V�[�g�̃T�[�}���O���X�ւ̌����͉\���H�Ƃ����b�����Ă���܂����B
�ŁA�T�|�[�g�͂��Ȃ���C�őΉ������Ă��ꂽ�̂ł����A���ʂ̓T�[�}���O���X�ɑΉ������v�ł͂Ȃ��̂Ń��[�J�[�Ƃ��ĕۏႵ����Ȃ��̂łƂ����ԓ��ŏI����Ă��܂��܂����B
��l�܂�ł��A�e�Ɋp4���Ɏ����z���܂��B
�����ԍ��F2643771
![]() 0�_
0�_
2004/04/06 22:23�i1�N�ȏ�O�j
�j���̂n����J�l�ł��B
���͂m�d�b�̃m�[�g�͈ȑO�������Ă���]��ǂ��Ȃ��Ă����Ɏ�����Ă��܂��A
���̌�͂u�`�h�n�ɔ��������ĂR�N�ȏ�g���Ă��܂����B����͂��낻��
�m�d�b���ǂ��Ȃ��Ă��邾�낤�Ǝv���āA���̂V�O�O/�U�c�����̂ł���
����ȂɎg�p���ɓ��삪�����Ȃ�悤�ł́A������Ǝg���܂����ˁB
�j���̂n����̃��|�[�g�����Ă��āA�m�d�b�̃T�|�[�g�ɂ���������ł��B
���炭���̂o�b�����������A���͓�x�Ƃm�d�b�̂o�b�ɂ͎���o���Ȃ���
�v���܂��B�R�N�O�̂u�`�h�n�̕����b�o�t�̃N���b�N���͖�R���̂P�Ȃ̂ɁA
���|�I�ɑ̊����x�ŃT�N�T�N�����Ă���̂��ƂĂ�����ł��B
�{���ɂm�d�b�ɂ͂������肵�܂����B
�����ԍ��F2674047
![]() 0�_
0�_
�k�b�V�O�O�U�c���[�U�[����A�C�����͕�����܂��B
����98�����NEC��DOS/V��芷���̉e����H�������l�ł��̂ŁANEC�̃��[�U�[�؎̂Ă͂܂����ƌ��������͂��Ă��܂��B
�V���������Ă���\�͂͂���܂����A���ꂪ�蒅���Ȃ��A���[�U�[���ɂ��Ȃ�NEC�̓Ƃ�P����I�ȑ̎��Ɍ���������Ƃ��v���܂��ˁB
�e�Ɋp�A������ɔ���b�ł͂���܂���̂ŁA�Ƃ��Ƃ����Ă݂܂��B
�����ԍ��F2677995
![]() 0�_
0�_
2004/04/12 21:12�i1�N�ȏ�O�j
�����́A�j���̂n����B
���̂o�b�̗]��̃��X�|���X�̈����ɉ䖝�����E�ɒB���܂��āA�_������Win2000��
�C���X�g�[�����܂����B���ʂł����AGOOD�ł��B
�܂�ō��܂ł��������������̂悤�ɃT�N�T�N�����܂��B
�v���C���X�g�[���̃\�t�g�����������������Ȃ̂����m��܂��A���܂łh�d��
�R�����炢�J����web�{��������ƁA�����ɃT�C�g�Ԉړ����ُ�Ȓx���ɂȂ���
CPU�g�p�����P�O�O���ɂȂ��Ă��܂������A2000�ɕς��Ă���͖{���ɃT�N�T�N�ł��B
�g���Ȃ��m�[�g�ƌ����т��Ă����̂ł����A�悤�₭Pen4-M 2.0G�̈З͂�����
����悤�ł��B
�m�d�b����͎̉��Ԃ��|����Ǝv���܂��̂ŁA���Ԓׂ���Win2000���C���X�g�[��
���Ďg���Ă݂�̂��ʔ����Ǝv���܂��B�̊��̑������S���ƌ����Ă悢�قLjႢ�܂���B
�����ԍ��F2693577
![]() 0�_
0�_
�k�b�V�O�O�U�c���[�U�[����AWin2000�̌y���͗ǂ����ɂ��܂��ˁB
���̎g�������ƁADESK�̃T�|�[�g�Ƃ���DVD�ECD�̋L�^�ƈꕔ�f�����H�Ƃ��������̂ł�����A���̋@��̂�����̖��ł���L�[���͂̃��X�|���X�̈����͗]��C�ɂȂ��Ă͂��܂���ˁB
�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���[�J�[�K�i��]�肢����Ȃ��Ŏg���ق��Ȃ̂ŁA���̂Ƃ���ڂ������͍l���Ă��܂���B���ہACPU���x�̃��j�^�����O���ł�MoveiWriter�ł�DVD����ǂ����Ă��܂��B�ł�����A���X�|���X��菈���ቺ�̕����_���[�W���傫���ł��ˁB
�ꕔ�A�J��������̕ԓ����������̂ł����A�����ɒl���Ȃ��̂ŁA������̂T�Ƃ����`�ňꎞ�܂Ƃ߂̕��������݂܂��B
���݁A�V�K�̎�����s�Ȃ��Ă��܂��B
�����ԍ��F2697624
![]() 0�_
0�_
�m�[�g�p�\�R�� > NEC > LaVie C LC700/6D
�������݂������Ȃ�܂����̂ŁA����x�V�����X���b�h�𗧂Ă܂����B
�O���T�Ԍo���ď�121�Ɏf���܂������A�J��������̕ԓ��͂܂��̂悤�ł��B
�T�|�[�g�̕������@�Ŋm�F�����Ƃ̂��ƂŁA�m����5D����̐v�ł��ˁB
�T�|�[�g�̕����肪�Ƃ��������܂��B�����A���̂܂܂��g�����������A�ȂǂƂ����ԓ��ɏI���Ȃ��悤�Ɋ肢�܂��B
�ԓ�������܂ŁA�F�X��ACPI�AmobilePentiam4-M�AmobilePentiam4�APentiamM�ɂ��Ē��ׂ����Ƃ��A���炭�������݂����Ǝv���܂��B
����͍ŏ��Ƃ������ƂŁA�܂�ACPI�iBIOS�̑����OS����n�[�h�̊Ǘ����s�Ȃ����ɂ����V�X�e���j�ł̔M�Ǘ��ɂ��āBACPI�ɂ�����On-Demand mode�Ƃ����V�X�e���S�̂̃G�l���M�[�Ǘ��i�����I�ȏ���d�͍팸�j�̒��ŁA�M�Ǘ��̃p�[�g�ɁA����̃A�N�e�B�u�E�p�b�V����p�ݒ肪���݂��܂��B�����ł́A�A�N�e�B�u��p�̓t�@�����ɂ��\���I�ȗ�p�ŃV�X�e���̃p�t�H�[�}���X���ێ��������ɉ��̖�肪�������p�@�\�Ƃ��A�p�b�V����p�ݒ�̓t�@�����̍쓮��}�������Ɋւ������}���邪CPU�̃N���b�N�𗎂Ƃ��Ȃǃp�t�H�[�}���X�̒ቺ���������ɓI�ȗ�p�@�\�Ƃ��Ă��܂��B
�����ŁA���Ƀp�b�V����p�ݒ�ɂ���7006D�̐ݒ�ɖ����������Ă��܂��B�p�b�V����p�ݒ�͖{���쓮����}���ĐÏl�������߂�ݒ�ł���ׂ��Ȃ̂ł����A7006D�ł�CPU�N���b�N�ቺ�Ƌ��Ƀt�@����]�����Ƃ����ɂȂ��Ă��܂��B�������g�����Ƃ͌����������ł��ˁB
�Ȍ�A�����B
![]() 0�_
0�_
�����B
ACPI��SpeedStep�̊W�ɂ��ẮASpeedStep�����o�C���pCPU�ɕt�����ꂽ�N���b�N�R���g���[���@�\�ŁA�����ACPI�ɂ����OS���瑀�삷��Ƃ����W�ɂ���悤�ł��B�܂�ASpeedStep��CPU�̃N���b�N������s�Ȃ��@�\�ł͂��邪���ꎩ�̂͏���ɍ쓮���Ȃ��A�ǂ̗l�ȏ����Ŏg�p���邩��ACPI�̊��ݒ莟��Ƃ������Ƃł��B
�N���e�B�J����p���x�ݒ�ɂ��āAPentiam4�������[�X���ꂽ������̂��̂̂悤�ŁA���̐ݒ肪�쓮�iCPU���x���B����j�����Auto mode�iPentiamM�ł�Sarmal monitor 1�j�Ƃ����Ɨ�������p�V�X�e���������A�v���O�����������I����S4�Ƃ����X���[�v���[�h�Ɉڍs���܂��B�܂�A�V�X�e���͊��S�ɒ�~����킯�ł͂Ȃ��A��p�@�\���ێ�����CPU�̃N���b�N���Ɍ��܂ŗ}����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�M�\���������ɁA���j�^�[OFF�Ńt�@�����S�J�Ƃ�����Ԃ�����ɂ�����悤�ł��B
mobilePentiam4-M�ł́A�N���e�B�J����p�̑���Ƀp�b�V����p�ݒ�𗘗p���邱�Ƃ��F�߂Ă��܂����A���ꂪ���ɔ����Șb�ƂȂ�܂��B
ACPI�̖{�ƁA���ł̏ꍇ�ȂǂȂǁE�E�E
�܂��A�����܂��B
�����ԍ��F2512099
![]() 0�_
0�_
2�T�Ԍo���܂����A�������Ȃ��ł��E�E�E
���āAmobilePentiam4-M�Ńp�b�V����p�i���m�ɂ�On-Demand mode�j�̗��p���F�߂��Ă���ƑO�ɏ����܂������A���ۂɂ̓C���e���͑������肵�����p���l���Ă����悤�ł��B
�������������̂́AmobilePentiam4�̃f�[�^�V�[�g�ŁA���x�Ǘ��̒���On-Demand mode����CPU���x�Ǘ��Ɏg�p���邱�Ƃ��֎~������e���A�ʍ��������Ė��L���Ă��邱�Ƃł��B
Pentiam4�̃V���[�Y�́A�C���e���ɂƂ��č��X�y�b�NCPU�̑�\�ł�����APentiam4�̐��\���\����������Ȃ�PC�������̂͊�ƂƂ��Ă��}�C�i�X�ł��傤�B
�ȍ~�A�����̈���o�Ȃ��b�ɂȂ�܂��B
ACPI�{�Ƃ̃_�C�i�̘b�ɂȂ�܂����A2002�N�̃��f���Ɉꎞ�A�����Lavie�Ɠ������x�Ǘ����s�Ȃ��Ă���mobilePentiam4-M��NOTE���݂����悤�ŁAmobilePentiam4�̃����[�X�����Ɣ����ɏd�Ȃ�܂��B������PC���[�J�[�̒���mobilePentiam4-M���ڋ@�����݂����ڂ��Ă���̂��F�X����̂ł͂ƁE�E�EG5�ӂ肩��́A�p�b�V����p���x107.9���E�N���e�B�J����p���x108.9���ƁA�C���e���̎w���ʂ�ƂȂ��Ă���悤�ł��B
���������ׂ�����ł́AmobilePentiam4-M���ڋ@��90���������p�b�V����p��ݒ肵�Ă��郁�[�J�[�͑��ɖ����悤�ł����B
LavieC������̐v�ύX�������̂�2002�N���A���ɔ����Șb�ł��B
�����ԍ��F2531283
![]() 0�_
0�_
4�T�ڂɁE�E�E
�T1���x�Ŋm�F�̓d�b�����Ă܂����A������ԓ��͗��Ă��܂���ł����B
�T�|�[�g�̌��t��M����Ȃ�A�u�i�ԓ����x��Ă���Ƃ������Ƃ́j�J�����ł̒������s�Ȃ��Ă��邩��ŁA�ɏ\���ȏ�����Ă���ԓ������̂ł́v�Ƃ������Ƃł����B
�܂��A�����������Ƃ������Ƃ͉����l���Ă���Ǝv�������ł��B
���C�Ȃ��ݒ��ύX���Ă��܂�����A�܂��A�V���Ȕ���������܂����B
�d���ݒ�̃v���[���e�[�V�����Ŏg�p�����Ƃ���A�p�b�V����p���x�E�A�N�e�B�u��p���x�����I�ɉ^�p����Ă��邱�Ƃ��m�F���܂����B�ݒ�ɂ͐�q�̃p�b�V����p���x40���E�A�N�e�B�u��p���x70���Ɓi�ʏ�ݒ萔�l�j�p�b�V����p���x70���E�A�N�e�B�u��p���x40��������A���̏����̌��Ő�ւ����s�Ȃ��Ă��܂����B
�ȑO�̏������݂́APC�̎g�p�J�n�iCPU���x45���ȉ��j�ł̊m�F�ŁA���܂Ńv���[���e�[�V�����ł̉^�p���ɂ͊m�F���Ă��܂���ł����B�܂�������Ȏ��Ƃ́B
��A�m�F�������́A�N���b�N����ѐݒ�ύX�̃^�C�~���O�ƃt�@���̓���^�C�~���O�ł��B
1.CPU���x40�������ŕ��ׂ�������2.0GH���ғ�������ƁA���̂܂�70���܂�2.0GH���ō쓮�B70���Őݒ肪�ύX�i�p�b�V����p���x70���E�A�N�e�B�u��p���x40���j����A��p�ɍ��킹��0.6GH����0.9GH����1.2GH���Ɉڍs�B
2.CPU���x40���ȏ�ŕ��ׂ�������ƁA1.2GH���̂܂�50���܂ŁB�r��45���ʂŐݒ�ύX�A50����1.2��0.9GH�����s�����肫����B���̊ԁA�t�@���̓����CPU���x�ɊW�Ȃ��ϓ��B
3.CPU���x��������Ԃł́A�e���x�ɍ��킹���N���b�N�ŌŒ肳��A2.0GH���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
4.�����1�x�����m�F���Ă��܂��A�p�b�V����p���x70���E�A�N�e�B�u��p���x70���Ƃ������̂�����܂����B
������������ACPU���x�y�уt�@������ɂ��Ă͒P���ȃp�b�V���E�A�N�e�B�u��p���x�Ȃǂ�ACPI����ł͂Ȃ��悤�ł��B�t�@���ɂ��Ă�CPU���x�����ł��ϓ�������A�ʂ̉��x�Ǘ������p����Ă��܂��B
����ł͂������[�J�[�ȊO�A�肪�o���܂���B
�����ԍ��F2555628
![]() 0�_
0�_
�����C���������܂��B
�d���ݒ�v���[���e�[�V�����ł́A�e��p���x�ݒ�ύX�̃^�C�~���O���ł����A
��40���������i�p�b�V����p���x40���E�A�N�e�B�u��p���x70���j���̂܂�70���܂�1.2�`2.0GH���ō쓮�B
��40���`45���H���i�p�b�V����p���x70���E�A�N�e�B�u��p���x70���j1.2�`2.0GH���ō쓮�A��L�ƕς��Ȃ��H
��70���ɓ��B���A�ݒ肪�ς��i�p�b�V����p���x70���E�A�N�e�B�u��p���x40���j600H���ɃN���b�N�𗎂Ƃ��t�@�����ŋ�����p�B
���悭�͕�����Ȃ����A�v���[���e�[�V�����ŋN�����čŏ��ɕ��ׂ�������CPU���x�ŁA��p���x�ݒ肪�Œ肳���悤�ł��B
��70���ɓ��B�A�������͑��̓d���ݒ�ɕύX�����ꍇ�ɁA�i�p�b�V����p���x70���E�A�N�e�B�u��p���x40���j�Ɉڍs���܂��B
���̂��ƂŋC�ɂȂ����̂́A�l�Ȃ�قƂ�ǎg��Ȃ��悤�ȃv���[���e�[�V�����ɁA�Ȃ�����قǕ��G�Ȑݒ肪���݂���̂��Ƃ������Ƃł��B��́A�p�b�V����p���x40���̂܂�70���܂�1.2�`2.0GH���ʼnғ��������ƂŁA�{���Ȃ�CPU�N���b�N�𐧌䂵��CPU���x��������ݒ�̂͂��ł��B�܂��A70���ɒB������̋�����p�ł́A50�����܂ł͋�����p�������A���̌�̓p�b�V����p���x��70���ł���̂�2.0GH���ʼnғ����Ȃ��Ȃ�i�t�@���̓�����������j�Ƃ����̂��ςł��B�{���g����ׂ������ɂ���ݒ�����g���Ă��銴�������܂��B
�ŁA�v���o���̂������70�����z���ĉғ���������ł��B����������ƁA����ɊW�����ʂ̃��[�h������A���̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ�ݒ�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�C���e������������A�N���e�B�J����p�̑���ɓK�p�����p�b�V����p�ƍl����Δ[���̂����ݒ�ł��B�܂��A����Lavie�E��ɃI���ݒ�ōs�Ȃ��Ă���t�@������́A�A�N�e�B�u��p���x70���Ƃ����̂��{���̐ݒ�ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B
�Ƃɂ������̎��ŁANEC�Ɏ��������߂Ă���ݒ肪�{���͊��ɍ݂�̂ł́H�Ɗ����Ă��܂��B�i�[�g���Ă��Ȃ��̂��͔���܂��E�E�E
�����ԍ��F2562227
![]() 0�_
0�_
�m�[�g�p�\�R�� > NEC > LaVie C LC700/6D
�����ቺ�Ɋւ��錋�_�ƌ�����ɂȂ邩������܂���B
��X�̋^�������������e���A�ӊO�Ƌ߂��ɁA121�T�C�gNEC�J���҃C���^�r���[�ɂ���܂����B
�ȉ���SERIES26�̌��sLavieC�ɂ��Ẵ��r���[�̈ꕔ�ł��B
�E�E�E�O���[�X�́A�ێ琫�ŗ��̂ŁA�]���̃m�[�g�p�\�R���ł́A�t�F�[�Y�`�F���W�V�[�g�̏�ɃA���~�V�[�g���̂��Ă����w�\���̃t�F�[�Y�`�F���W���g���Ă��܂����B�ł��A����A�v���Z�b�T��̃q�[�g�X�v���b�_�[�̉��x��70�x�܂ł��������Ă͂����Ȃ���ł����A���܂ł̃t�F�[�Y�`�F���W�ł́A60�x�ȏ�ɂȂ�Ȃ��ƃt�F�[�Y�`�F���W�V�[�g���Ƃ��o���܂���B��r�I�Ⴂ���x�ł��A������Ɩ��������m�ۂ��邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��A�O���[�X���̗p����K�v����������ł��B
�����ɂ���u�v���Z�b�T��̃q�[�g�X�v���b�_�[�̉��x��70�x�܂ł��������Ă͂����Ȃ���ł����A���܂ł̃t�F�[�Y�`�F���W�ł́A60�x�ȏ�ɂȂ�Ȃ��ƃt�F�[�Y�`�F���W�V�[�g���Ƃ��o���܂���B�v�Ƃ������t����A���̎����̉��x�Ǘ��̍l�������A�q�[�g�X�v���b�_�[�̉��x��70�x�܂łƂ��Ă��邱�Ƃ����������܂��B
�܂��A60�`70���Ƃ������x�͈͂��A������LC7006D�ő��肵�����x�ω��ɕ������܂��B
����ɑ��āA�C���e���̃m�[�g�u�b�N�E�p�\�R���̔M�Ǘ��i�C���e�� �Z�p�T�C�g���j�ł́A�ȉ��̂悤�ɏ����Ă��܂��B
�i�C���e���T�C�g��蔲���j
�w�ǂ̃m�[�g�u�b�N�E�p�\�R���ɂ́A�ő哮�쉷�x���z����ƃN���b�N���x�𗎂Ƃ��A�X���b�g�� (�i��) �@�\������܂��B�������A�������͐��\�ቺ�ɂȂ���܂����A���̋@�\�Ɉˑ����ĔM�v������ׂ��ł͂���܂���B
���̍ő哮�쉷�x���z����ƃN���b�N���x�𗎂Ƃ�����̓m�[�gPC�̉��x�Ǘ��̓��A������Ƃ��Ă���CPU�N���b�N�𐧌䂷��p�b�V����p�ɂ�����Ƃ����܂��B
���̎��܂��āA
�i�C���e�� Pentium M �v���Z�b�T�Z�p�T�C�g��蔲���j
�C���e��(R) Pentium(R) M �v���Z�b�T���g�p����m�[�g�u�b�N�E�p�\�R���ł́A�K���M�Ǘ����s�Ȃ��K�v������܂��B�u�M�Ǘ��v�Ƃ͎�ɁA�v���Z�b�T�ɗ�p���u�𐳂������t���鎖�A����сA��p���u�̊��C�����������A�V�X�e���̊O�֔M��r�o���鎖���Ӗ����܂��B�M�Ǘ��̍ŏI�I�ȖڕW�́A�v���Z�b�T�̉��x����ɍő哮�쉷�x (Tcase) �ȉ��ɗ}���鎖�ł��B�C���e��(R) Pentium(R) M �v���Z�b�T�� Tcase���A�\ 1 �Ɏ����܂��B���̒l�́A�v���Z�b�T�R�A�E�P�[�X�\�ʂ̒��S�ő��肵�����̂ł��B
�\ 1�F �{�b�N�X �C���e��(R) Pentium(R) M �v���Z�b�T �ō����쉷�x
�i���j������g��1.4�`1.6GHz�ɂ��čō����쉷�x100��
�ō����쉷�x�Ƃ́A�v���Z�b�T������ɓ���\�ȏ���̉��x�ł��B
�ʏ�A�ō����쉷�x�Ƃ��ĕ\������Ă��鉷�x�́A���L�� "T-Junction" �������́A"T-Case" �̉��x�ɂȂ�܂��B
T-Junction�F�v���Z�b�T�E�R�A�����̉��x
T-Case�F�v���Z�b�T�E�R�A�ɁA IHS (�C���e�O���[�e�b�h�E�q�[�g�E�X�v���b�_) ����������Ă���ꍇ�A���̒��������̉��x
�ȏ�̂��Ƃ���A�C���e���ł͓��쉷�x�̍ō��l�̖ڈ��Ƃ��āA�v���Z�b�T�E�R�A�������̓q�[�g�E�X�v���b�_�̒�������100���Ƃ��Ă��邱�Ƃ�������܂��B
���̂��߁A�����̃��[�J�[��CPU���x100���O����p�b�V����p���x�ɐݒ肵�Ă���̂ł��傤�B
�N���e�B�J����p���x�͍X�ɍ����ł��ˁB
����ɑ��ANEC�ł́A��q�̂悤��LavieC�̐v�ɂ����ăq�[�g�E�X�v���b�_��̏���l��70���Ƃ��Ă��邱�Ƃ���A�p�b�V����p���x�ɒB����m���������Ȃ�͓̂��R�Ƃ����܂��B
�������Ȃ���ANEC���������p�ɑ���v�����ʂ������Ă���̂��A���̌����������ł��Y�t�\�t�g�ł͑��ЂƗ]��ς��Ȃ��\�͂������Ă��邽�߁A�փr�[���[�U�[�ȊO�ɂ͉e�������Ȃ��ƍl�����܂��B
�ȏオ�������g���l�Œ��ׂ�ꂽ���ł̌��_�ł���A����܂ł̎����̋^��ɓ�����ɏ\���Ȍ��ʂƍl���Ă��܂��B
���̂��Ƃ���ALC9005D�ELC7006D ����ѓ������̃��f���ɂ��āA�܂����\��̗]�͂�����Ȃ��牷�x�Ǘ��̐��������������邽�ߍ����ׂ̍ۂɃJ�^���O���\��100���o���Ȃ��Ǝ����Ȃ�Ɍ��_�t���āANEC�ɂ��̓_�����߂ĉ��P����悤���߂����Ǝv���܂��B
���������O�ɂ��̂��Ƃ��������Ă���������Ə������݂ɔ������������̂ł��傤���ˁH�₵������ł��B
Pentium 4-M���ڋ@�́A�l�I�ɔ��M�}���ƐÉ��̗����Ƃ������ɒ��킵�����f���ł������̂��ȂƊ����Ă��܂��B���x�Ǘ����ɂ߂邱�ƂŔ���PC�ɋ߂Â���������܂��A���̃T�C�Y�ł��̓d���V�X�e���ƃX�y�b�N����������x�X�g�m�[�gPC�ɂȂ�̂ł͂Ǝv�����肵�Ă��܂��B
�F�X�ȈӖ����܂߂āANEC�̊J���Z�p�Ɍh�ӂ�\���܂��B
![]() 0�_
0�_
2004/01/29 00:26�i1�N�ȏ�O�j
�j���̂n����A���肪�Ƃ��������܂��B
�����d���ݒ��ύX���āA_PSV�̉��x�ݒ肪�ύX����邱�Ƃ�
�m�F���܂����B�ʔ����ł��ˁB�Ƃ肠�����A_PSV�̐ݒ��ύX����
���@��T���Ă݂܂��B�����A�ݒ�ύX�ł����Ƃ��Ă��A���S��
���ȐӔC�ł��ˁA����́B
�����ԍ��F2400430
![]() 0�_
0�_
Intel�T�C�g�E�E�E�ȑO�ɂ����x�����������̂ł����A���������Q�ƕs�ɂȂ��ł���ˁB
ID�o�^�����܂������Ȃ����E�E�E
�Ƃ肠�����{�b�N�X�C���e��(R) Pentium 4 �v���Z�b�T�ƃ{�b�N�X �C���e��(R) Pentium(R) M �v���Z�b�T�̏��͎茳�ɂ���܂��B
�����A�ő哮�쉷�x�̈����������ɈႢ�܂��ˁB
Pentium 4 �ł́u�t�@���E�n�u�̒��������̏�� 0.3 �C���`�قǂ̏ꏊ�v�APentium(R) M �́u�v���Z�b�T�R�A�E�P�[�X�\�ʂ̒��S�v�ƂȂ��Ă��܂�����A����̈Ӗ�����������Ă���悤�ȁE�E�E
�{�b�N�X�C���e��(R) Pentium 4 �v���Z�b�T �ł̕\�L�i68�`78���j�̓v���Z�b�T�R�A�̒l�ł͂Ȃ��̂ł́H���s�����B
�����ԍ��F2400536
![]() 0�_
0�_
Mobile Pentium 4-M��Pentium 4�Ƃ́AL2�L���b�V���ʂ�FSB�������ł���قړ������\���ƍl�����Ă��܂��B
����ł́A2.50 GHz����̏ꍇ�A�O�҂�35.0 W�Ō�҂�61.0�ł��B
�d���͑O��1.30 V�A��҂͕�������܂����������ς�Ȃ��Ƒʖڂł��傤����1.525�B
15%���ł��B
����d�͓͂d����2��ɔ��Ƃ����̂�����ł�����A27%���ɂȂ�܂��B
������Mobile Pentium 4-M�̏���d�͂�61.0 W��27%���ɂȂ�Ȃ��Ɛ��\���ێ��ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
������TDP�͂�������Ⴂ�����ɂȂ��Ă��܂��ˁB
Mobile Pentium 4-M 1.60 GHz��Pentium 4 1.60A GHz���ƁA���̗�����TDP���قڈ�v���܂��B
�܂�1.60 GHz�ȏ�̃N���b�N�ł͂Ȃ�炩�̐��������Ȃ����Ƃɂ͔j�]���Ă��܂����ƂɂȂ�ł��傤�B
���m�������ɂ�TDP�̗L�������������_�ȉ����ʂ܂ŏo�Ă���1.50�A1.40 GHz�ƂŔ�r���ׂ��ł����APentium 4�ɓK�Ȕ�r�Ώۂ�����܂���B
�����ԍ��F2400568
![]() 0�_
0�_
�}���Œ����B
Pentium 4 �ł́u�t�@���E�n�u�̒��������̏�� 0.3 �C���`�قǂ̏ꏊ�v
�@�@�@�@�@�@�@��
Pentium 4 �ł́u�V���[�V��(�t�@���ƃq�[�g�V���N�����H)�v
���ԂȂ��A���ԂȂ��B
���G����A���������Ă璲�ׂĂ݂܂��B
�����ԍ��F2400581
![]() 0�_
0�_
Pentium 4�͉ߔM����Ǝ����I�ɏ������Ԉ����Ĕ��M��}���܂��B
3��Pentium 4��CPU�̃t�@�����~�߂Ă݂܂������A�}�U�[�{�[�h�Y�t�̃c�[����CPU���x�����j�^����ƁAT-Junction�Ŏ����ꂽ���x�ߕӂʼn��x�����t���܂����B
���̎��̏����\�͂͒ʏ��1/10���炢�ɂȂ��Ă܂������ǂˁB
Pentium 4��CPU���������ŏ\���ȔM�Ǘ����s����ł��傤���AMobile Pentium 4-M�����̃p�����[�^���g���K�ɂ��Ă���̂��͕�����܂��ABIOS������̓����|�����g���K�Ƃ��Ă���ƍl�����܂����ACPU�������x�͊m���ł��傤�B
TDP�͖��O�����̒ʂ���߂���ƁA�M�v�̃K�C�h���C���ŁA����CPU����������Ȃ炱�ꂾ���̔r�M�\�͂��m�ۂ���Ƃ����w�W�ł��傤�B
�K���������M�ʂ�\���Ă���Ƃ͌����܂���B
�����ԍ��F2400626
![]() 0�_
0�_
�����肳��ցB
Pentium4-M��TDP�ɂ��ẮA�C���e����35W�O��܂ł�����Ƃ���Ƃ����b������܂����ˁB
�r������CPU�N���b�N���҂����߂ɖ��������Ă����Ƃ������Ƃł��傤���H
���Ȃ݂ɁAPentium4�Ŏ������Ƃ��́A�R�A�̉��x�͂������ł������H
�����ԍ��F2400757
![]() 0�_
0�_
2004/01/29 22:40�i1�N�ȏ�O�j
35W�͂��Ă͏ȃX�y�[�X�f�X�N�g�b�v�ŁA���݂ł͔�r�I��^��
���^�m�[�g�ŗ�p�\��CPU���M�ʂ̌��E���Ƃ����Ă��܂��B
�ʏ�60W�������ʂ�P4�R�A�����m�[�g�p�ɓ]�p���邽��
�A�����M���̃N���b�N�_�E���@�\�������̂ł��傤�B
���ۃX�y�b�N�V�[�g�ɂ́u�ő唭�M�ʂ�TDP�l���邱�Ƃ�����̂�
�ڂ�����Intel�ɒ��ږ₢���킹�Ă���v�Ƃ����|�̒��߂�����܂��B
�����ԍ��F2403644
![]() 0�_
0�_
Kharu1����A���т��т��肪�Ƃ��������܂� �B
Intel�T�C�g�AUSA�܂Ō��ė]��ɂ��ō����쉷�x�̕\�L������Ă���̂ŁA���������A�J�������ăT�|�[�g�ɕ����Ƃ����ŏI��i���g���܂����B
�ŁA�����Ă݂���̂ł��ˁB
�܂�CPU��̉��x�Z���T�[�̈ʒu�ɂ��Ă͒��ג��Ƃ������Ƃł����A�ȉ��̏�����܂����B
�@�@�@�@CPU����̉��x�Z���T�[�ł̍ō����쉷�x�^CPU���g�ɂ��ߔM������x
Pen4-M1.6�`2.0�@�@�@ �@�@100���@/�@135��
���o�C��Pen4�@�@�@ �@�@�@100���@/�@135��
Pen-M�@�@ �@ �@�@100���@/�@125��
��{�I��Pentium 4�n���̉��x�Ǘ��͂ǂ���������Ƃ������Ƃ������ł��B
���ʂƂ��āAACPI�ɂ�鉷�x����ɂ킴�킴�����̃Z���T�[�ȊO���g���Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA�ǂ��ɕt���Ă��悤���ō����쉷�x��100��������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB
�܂��܂��p�b�V����p���x��70���ɂ��Ă���Ӗ���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�Z���T�[�̈ʒu�ɂ��Ă͏T�����ɘA�����Ă���邻���Ȃ̂ŁA�܂����̎��Ɋ�����₵�Ă݂܂��B
�����ԍ��F2408894
![]() 0�_
0�_
�Z���T�[�ʒu�ɂ��Ċm�F�����܂����B
���R�Ƃ����Γ��R�ł����AT-Junction�i�v���Z�b�T�E�R�A�j�̕����Ƃ������Ƃł����B
����ŁA���o�C��Pentium4-M��T-Junction�ō����쉷�x100���ɑ��āAPC�̉��x�Ǘ��͂�����Ȃ��ݒ�ɂȂ��Ă���������ƂɂȂ�܂��B
�����M�Ǘ����s�Ȃ���ŁA�`�b�v�Ƃ��Ẵv���b�Z�b�T�͊O�s�Ƀq�[�g�E�X�v���b�_�����Ă��āA����𒇉�ĕ��M���s�Ȃ����߁A�r�M�v�̓q�[�g�E�X�v���b�_��̉��x�ōl���Ă���悤�ł��B
���ہA�����肳���Kharu1���������悤�ɁA�r������CPU�M�Ǘ��̎w�W������TDP���B���Ȃ��̂ɂȂ��āAT-Case�i�v���Z�b�T�O�s���M�j���Q�l�ɂ����Ǘ��Ɉڂ��Ă��܂��B
�ł�����ALavieC�̃��o�C��Pentium4-M���ڋ@��T-Case��80�`85���A���o�C��Pentium4���ڋ@��70���܂ł�ڕW�ɐv���ꂽ�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�������A�̐S��CPU���M�ʂ̓����̓C���e������Ƃ������ƂŁA�ۏႳ�����̂ł͂Ȃ������킯�ł����B
���Ȃ݂ɍŋ߂�Pentium-M��T-Junction��100���ƌ����ȊO�A�����܂���ˁH
�����ԍ��F2429021
![]() 0�_
0�_
�E�E�E�����ANEC����̘A���҂��B
�ӂƎv���āA�ꕔ�ɂ���z�C�p�̌��Ǝv���鏬�����ǂ��Ńe�X�g���Ă݂܂����B
�\�z�ł͉��x�㏸�������Ȃ�̂ł͂Ǝv���Ă��̂ł����A�ӊO��ӊO�ACPU���x�ō��l��1�`2��������܂�����B
�����̏ꍇ������������܂��A�z�C���Ǝv������̂��ꕔ�����Ȃ����Ƃ���A�p�[�c�̌��ԁA���ɃL�[�{�[�h���ӂƃh���C�u������̎�荞�݂����邩�ƁB
�����ADVD�����ƈӖ����Ȃ������E�E�E���܂�ǂ����Ȃ��ł��ˁB
7006D�����ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��낻�낱�̏ꏊ�������Ă��܂���������Ȃ��̂ŁA��������������́A���f��������܂���7�E8D�ӂ�Ɍo�ߕ��������݂܂��B
�^�f���ɂ�����Ȃ�̏ꏊ�͂���܂����A�M�ߐ���������܂�����B
�ʌ��B��N�t���f���̕s��҂ɂ�6D�̏����ቺ�ȏ�̏Ǐ�̕��������̂��A�ӂƎv���o���܂����B
���A���̂��Ƃ������C�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F2437246
![]() 0�_
0�_
�����A����҂��Ă��邾���ł͎莝���������Ȃ̂ŁA����LavieC�V���[�Y��2nd�t�@������Ƃ������r�C�ɂ��āA�����ߌ�121�Ɏ��₵�܂����B
�O���6D��2nd���r�C���A�d�l�͔r�C�A���@�͋z�C�ł����Ɨǂ��킩��Ȃ��ԓ��ŁA�����͊Ԕ����ꂸ1�T�Ԓ��A���҂����Ƃ������ƂɁE�E�E
�����ɓo�^����܂������ˁB
121�̃T�|�[�g�̕��ɂ͎�Ԃ������Ĉ����ȂƎv���܂����A������m��ɂ͏����K�v�Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F2439010
![]() 0�_
0�_
���낢�����Ă�����悤�ł����b�o�t���蕪�����Ă݂܂����H
�����ԍ��F2439146
![]() 0�_
0�_
�m�Ȃ`���n����A��q�̂��ӌ��Q�l�ɂȂ��Ă��܂��B
����ꂽ�悤�ɁA��p�ݒ�������������Ȃ�y�������Ǝv���܂��B
�T�[�}���E�C���^�[�t�F�C�X�i�t�F�[�Y�`�F���W�V�[�g�j�̎g�p�@�ɂ���肪���肻���ł��B
�����ɂ��ẮA�ȑO��������������ł����A�L�[�{�[�h���ӂ̂͂�������������Ȃ��Ēf�O���Ă��܂��B
�����A�A�X�L�[�̎����ɂ���➑̃��f���̏����̕����ʐ^������܂����̂ŁA�����͂��Ȃ��Ă������ȂƎv��������Ă��܂���B
���̃��x���ł̓p�[�c�̈Ⴂ�͔��f�ł��Ȃ��ł��傤���A�f�[�^���W�߂ď��ł߂Ă���Ƃ����Ƃ���ł��B
�����ԍ��F2440514
![]() 0�_
0�_
3��ڂ̖₢���킹���A4��ځi2nd�t�@���̋��r�C�ݒ�j�̕ԓ�����ɕԂ��Ă��܂����B
LC7006D�Ɠ����t���f��LC9005D���A�r�C�t�@���Ƃ��Đݒ肳��Ă���Ƃ������ƂŁA�T�|�[�g�̕��͊J�����Ɋm�F���܂����̂ŊԈႢ����܂���A�Ɖ����C���̓������ԓ��ł����B
�����ɉ������4D�ȑO�̃��f���ɂ��čĊm�F�ł��܂���ł������A����͋z�C�ݒ�Ƃ������Ƃŗǂ���ł��傤�ˁB
�{�肩�班������āB
���A������121�T�|�[�g��ʂ��Ă���Ă��邱�ƂƂ����̂́A������N���[���Ƃ������t�ɏW���s�ׂł��ˁB
���߂čl���Ă݂āA����������ɂ���ĉ���������̂��Ƃ������Ƃ��l���Ă݂܂����B
���[�́A�^�f���̏t���f��LavieC�́u�N���b�N�����v�Ƃ����������݂���ŁA��������Ȃ���Ύ������C�Â������ǂ����B���ۂ��̃V���[�Y�̍w���҂�NEC�ւ̐M����@��̍������ɖ�����Ĕ��������������Ǝv���܂��B�����������̑����͏����ቺ�̉e������悤�Ȏg���������Ă��Ȃ��ł��傤����A���ɃN���[����������ł͂Ȃ��̂ł��傤�B
�����APC�Ƃ������i�͑��̗l�X�Ȑ��i�ɔ�ׂāA�ǂ�Ȑl�ł��t���X�y�b�N��v������\�t�g��������ΊȒP�Ɍ��E���\���o����܂��B�ł�����A���[�J�[�͍אS�̒��ӂ������ăJ�^���O�X�y�b�N���ő����������v��g�ސӔC������Ǝv���܂��B�ł��A�ŋ߂̐��i�T�C�N�����l�����100�������Ȃ��̂��Ƃ������܂��B
�߂��āA�����������邱�ƂƂ����̂́A����PC�S�ʂɊւ���m�����[�܂����ƌ����_�œ��Ă�����̂�����̂ł����A�@�J�������\�t�g��CPU�ɗ�����ςȂ��̂��̂���ŁA���ケ�̋@�킪�������肪���ʂɂłĂ��܂��\�����������@��NEC�ɋ��߂邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������Ƃ��啔���ł��B
���ۂ��̃T�C�Y�ł��̏����\�͂̃m�[�gPC�͒��X����܂���A�ł���X�y�b�N������Ȃ��ƌ�����܂Ŏg�����������g�R���ł��B�f�U�C���������̃c�{�ɂ͂܂��Ă��܂����B
���ʁA���̃V���[�Y�̃R���Z�v�g��PR���e�ɑ��āA�@��������ۂ̃X�y�b�N�Ƃ̍��ɕ����������Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B
��Ⴂ�Șb�Ŏ��炵�܂����B
�����ԍ��F2453488
![]() 0�_
0�_
�J��������̕ԓ����Ȃ��Ȃ����܂���ˁB
�C���e���{�T�C�g����A���o�C��Pentium4-M�A���o�C��Pentium4�APentiumM�̃f�[�^�[�V�[�g����M�Ǘ��̍��ڂ��E���A�p���Ɗi�����B
�L�[�ɂȂ錾�t�́ATCC(Therma�� control circuit)�AAutomatic Mode�AOn-Demando Mord�AThermal Monitor 1�2�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B
PentiumM�̃����[�X�������l����Ɩ�肪�݂肻���ł��ˁB
�ǂꂾ���̕������Ă��邩�킩��܂��A�ڍׂ͂܂�����B
����(���������ł���)��x�݂��܂��B
�����ԍ��F2462381
![]() 0�_
0�_
3��ڂ̕ԓ���10���o���Ă����Ȃ��̂ŁA121�ɘA�����܂����B
�L�^�ɂ͎c���Ă��悤�ł����A�ǂ����ق����炩���������悤�Ȕ������E�E�E
���ǁA�`�[�t�N���X�Ǝv����ڂ��������܂�Ԃ��̓d�b�ɏo�Ă��܂����B
����́A�q�[�g�X�v���b�_�[�ƕ��M�u���b�N�𒇉��T�[�}���E�C���^�[�t�F�C�X�i�t�F�[�Y�`�F���W�V�[�g�j���A60�����Ȃ��Ƃ��̐��\���ۏ���Ȃ����̂ł���̂ɁA�Ȃ�CPU�R�A���x��70���ʼn��x����Ǝv����N���b�N������s�Ȃ��̂��B70���ł̓q�[�g�X�v���b�_�[��i���o�C��Pentium4-M��80������j�Ŏ���60����������Ă��܂��A�{���̗�p���\���ʂ����Ă��Ȃ��B�Ƃ������̂ł����B
���R�ANEC��121�ւ͏ڂ�������n���Ă͂��Ȃ��悤�ŁA�T�|�[�g�̕������̗l�Ȑݒ�i�p�b�V����p�ɂ��āj�͂��Ȃ��͂��Ȃ̂ł����E�E�E�ƍ������悤�ŁA�lj�����������ĊJ�����ɂ��������Ƃ������ƂƂȂ�܂����B
�T�|�[�g�Z���^�[�����̕ǂ́A��͂�����悤�ŁE�E�E
�����ԍ��F2472926
![]() 0�_
0�_
DVDMovieWriter�ŁADVD�̈ꕔ��ҏW�����Ƃ�����Ă݂܂����B�������ɏd����Ƃł��B
����25����30���A24����20�`25���A23����15�`17���A22����10���ȉ��A1.2GH�������Ƃ������Ƃ���ł����B
20���ł́A�ȑO�ɍŏI�����ň���������Ƃ������Ƃ���ł����ˁB
���߂ĕt���\�t�g�ł͏����ቺ�����Ȃ����x���ɂ��Ă������������ł��ˁB
�E�E�E�ƁA�����ŏI���͂��������̂ł����A�ӊO�Ȍ��ۂ��������܂����B
��������2.5���ԁi��Ȃ���V�c�R�C�Ǝv���܂��j���߂����ӂ��70���ɒB���Ă������ቺ�������Ȃ�܂����B
����71���\�������܂������A��̂ǂ�Ȑ�������Ă���̂��i�����H�j�����ł��Ȃ��ł��B
�p�b�V����p���x�ݒ��70���̂܂܂ł��B
�V���ȓ䂪�������Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F2473389
![]() 0�_
0�_
K����O����A���v���Ԃ�ł��B
���ɂ́A�Ă�ł��čs���Ȃ����x���ɂȂ��Ă܂���(^^�B
�u�ӊO�Ȍ��ہv�ɂ��Ăł����A������x�����o��������܂��B
�ǂ�ȂɃx���`�}�[�N���ԉ����Ă��N���b�N�_�E�����������Ȃ���ł���ˁB
����������MobileMeter�����������̂�CPU���x�����x�܂ŏオ���Ă����̂�������Ȃ��̂��c�O�B
�m����̋���f���ɂ��������ۂ�����Ă����Ǝv���܂��B
���͍ċN����������Ƃɖ߂��Ă��܂��܂������c�B�ɂ������Ƃ�������?
���̌�u�ӊO�Ȍ��ہv�͋N�����Ă��܂���B�܂��{�C�Ō����Ȃ��Ȃ�������������܂����c�B
���܂��܉��x���䂪���܂������Ȃ����̂̂悤�Ȃ��̂��Ǝ��͉��߂��Ă��܂��B
�����ԍ��F2473545
![]() 0�_
0�_
MINIMI����A���v���Ԃ�ł��B
�������Ȃ�Ӓn�ɂȂ��Ă��܂��ˁB���̕��A�m���͑����Ă��܂��܂����B�{��͗͂Ȃ���đ傰���ł����i�j�B
���āA���܂őS�H��2���Ԃ��z���鏈���i���ׁj�͂��Ă܂���ł�������A����̌��ۂ͏��߂Ăł����B
�����ቺ���Ȃ����ۂ��N���āAMovieWriter��������A���̃\�t�g�Ŏ����Ă�70���̕ǂ��Ă��܂����B
�ċN����͍Ă�70����1.2GH���A���ɖ߂�B���܂ł����������ςȂ��A�Ƃ����킯�ɂ������܂��ˁB
�s���Ȍ��ۂł͂���܂������A70�����Ă���i�ō�72���j�̉��x�ω�����������p�\�͂̒ቺ�͌����Ȃ��̂ŁA�p�b�V����p���x�̐ݒ�ύX�Ŗ��i��ɔM�\���j�͂܂��������Ȃ��Ɗm�M�ł��܂����B
�����A�����^�b�`�{�^�������\�M���Ȃ��Ă��܂����ˁB
�������A��̂Ȃ�����ł��傤�E�E�E������x���͖̂ʓ|�ł����E�E�E
�����ԍ��F2473774
![]() 0�_
0�_
MINIMI����A�m�F��Ƃɒǂ��āu�ӊO�Ȍ��ہv�ɂ��Ă̖^�f���ł̘b���A������ɂȂ��Ďv���o���܂����B�悭�o���Ă��܂����ˁB�Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ�3�l�͌o�����Ă���킯�ł�����A�P���ȃC���M�����[�Ƃ��v���܂���ˁB
���ʂ̗��R������Ȃ�A7006D���̂ɗv�������鎖�ɂȂ�܂�����A���炩�̐ݒ肪����̂����B���܂��肽���Ȃ��ł����A�Ċm�F���āA����X�g�ɍڂ��悤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F2478846
![]() 0�_
0�_
�m�[�g�p�\�R�� > NEC > LaVie C LC700/6D
���x���\�̏オ���Ă����������̏����ቺ�ɂ��āA����A121�ɂ��鎿��Ƃ��肢�����܂����B
����܂ŏ�����Ă��Ȃ����e�Ǝv���܂��̂ŁA���L�҂̊F����ɕ��Ă珑�����݂܂��B
���̌��ւ̎����̃X�^���X�́ALC7006D�����߂�3�N�͎g�������Ƃ������ƁANEC�����Ȃ�̋C�z��������Ă��̋@�������Ă��邱�Ƃ͔F�����Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂ŁA����T�|�[�g�ɂ��肢�������e�ʼn��P�����Ȃ當��͂���܂���B
���������Ӗ��ŁA�T�|�[�g������ΒN���킩��l�[���ɂ��Ă���܂��B
�T�|�[�g�̕���M�p���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ł����A1�l�ōl���Ă���ƊԈႢ�����肻���Ȃ̂ŁA�ق��̕��̈ӌ����f�������Ǝv���܂��B
�O��Ƃ��āA�����ۗ̕L����LC7006D�Ŋm�F���������Ŏ���Ƃ��肢�����܂����B
���o�C��PC��CPU�̃N���b�N�Ɖ��x�����j�^�[����\�t�g�ƁA�^�X�N�}�l�[�W���[�p���āACPU�̉��x�E�N���b�N�ECPU�g�p�������j�^�[�������ʁACPU���x70���ŃN���b�N���䂪�����Ă��܂����B
�i���o�C��PC��CPU���x����ł̓A�N�e�B�u�E�p�b�V���E�N���e�B�J���̒i�K������A�p�b�V����CPU�̃N���b�N�𐧌䂵�ăV�X�e���_�E����������p���x�ݒ�l�ɂȂ��Ă��܂��B�j
���̃��[�J�[��NEC�̕ʃV���[�Y�ł́A���̃p�b�V���̐ݒ肪80���O��ƂȂ��Ă���悤��(���s���ł���)�A�������M�ɋC���g�������Ƃ��f���܂��B
�Ƃ��낪�A���̐ݒ肪���邽�߂ɏ����ቺ���p������Ƃ������ƂŁA���������j�^�[��������(����18��)�ł́ACPU�g�p��100����70���ɒB����ƁA1.2GHz�ɏ����𗎂Ƃ��A5���O���64���ɒቺ�����2.0GHz�ɕ��A���A2�����ł܂�70���ɒB����1.2GH���ւƂ����T�C�N�����J��Ԃ��Ă��܂����B
���̎��ŃT�|�[�g�ɁA���݂͗]����ƂȂ�Ȃ����A�����\�t�g�̗v���X�y�b�N���オ���Ă������ɑΉ��ł��Ȃ��APC�̃X�y�b�N��100����������Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁA���P�ĂƂ��ď����t�ł��ǂ��̂Ńp�b�V����p���x��80�����x�ɕύX����BIOS�����l���͂Ȃ����Ƃ������肢�����܂����B
�Z�p����̕��̈ӌ��͕����Ȃ����Ƃ������܂������A�u�v�]�͂��`�����܂�������͓���v�ƌ����܂����̂ŁA����l�q�����čēx121�������ɂ��q�˂��܂��Ƃ��܂����B
�ȏオ�T�v�ł����A121�ł�������������Ƃ��������̔F���͂���悤�Ȃ̂ŁA����̑Ή����������Ǝv���Ă��܂��B
���j�^�[�Ɏg�����\�t�g��MobileMeter�Ƃ����ȉ��̃T�C�g�̂��̂ł��B
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/
���ɂ�����C�Â������͂���܂����A�m���s��������̂ōĊm�F���Ă��炨�m�点�������Ǝv���܂��B�����Ȃ��Ă��݂܂���B
![]() 0�_
0�_
�j���̂n����A�͂��߂܂���
���́ALC7006D�̑O���f���ł���LC900/5D�̒��̃��f��LG20SSUJD���g�p���Ă��܂����AK����O����Ƃ܂����������Ǐo�܂��B
����MobileMeter���g���Ă܂����A��͂蓯���悤��CPU���x��70�x�ɂȂ����u�Ԃ�2GHz����1,2GHz�ɃN���b�N��������܂��ˁB
�ň���Ă��炷���܂��A�Ђ���Ƃ���
�����ɂ�����C�Â������͂���܂���
�Ƃ����̂͗�p�t�@���̓��삱�Ƃł���?
�C���ɂ��Ȃ荶�E����܂����A���̃}�V���͖����ׂ̂Ƃ��͕������ɂ������炢�ɂ������t�@�������A�����ׂ�������ƃt�@���̐����������܂��B������O�ł���(��)�B�ł��܂��܂����͐Â��ȕ��ł��B
������CPU���x������オ���čs���A70�x�ɒB���ăN���b�N��������ƁA�ς��ȂƊ�������x�Ƀt�@���������𑝂��̂ł��B����ł�PC�d����������̃t�@���m�C�Y���͉����������̂ŁA���̏�Ԃł��ō����ʼn���Ă���킯�ł͂Ȃ��悤�ł��B
����ɂ��Ă��Ȃςł���ˁB��������CPU���x�㏸��}���邽�߂ɗ�p�t�@�������̂����ʂ��Ǝv����ł����ACPU���x�͏オ��܂܂ɔC���Ă����āA���E�ɒB������N���b�N�𗎂Ƃ��Ĕ��M�����炵����ŁA��p�t�@���̃X�s�[�h���グ�Ĉ�C�ɗ�₷�B
���Ȃ݂ɉĂ̏��������Ɋe�퍂���ׂ̃x���`�}�[�N�\�t�g���g���Č������Ƃ��ɂ́A�����ׂ����������Ă����2GHz�œ��삷�鎞�Ԃ�1.2GHz�œ��삷�鎞�Ԃ̔䂪���P�F�R���炢�ɂȂ�܂����B
PenM�Ȃ炢���m�炸Pen4M��1.2GHz���ď��Ȃ��ł���ˁB
�����ɂ����͏��S�҂ō��̂Ƃ��뒷���ԍ����ׂ�������悤�Ȏg�����������Ȃ��̂ŁA�܂����̌��ɂ���NEC�ɖ₢���킹�����Ƃ�����܂��A�j���̂n����ɑ���NEC�̍���̑Ή��ɑ�ϋ���������܂��B
���Б��������炨�m�点���������c���ĉ�Ȃ��瑼�͖{��ł��ˁB�������Ȍ����B
�����ł����܂���ł����B
�����ԍ��F2365578
![]() 0�_
0�_
LC700/�UD���P�O��������g�p���Ă��邯��
�d����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ���ԂŎg�p���Ă��邯��
�g�p���Ȃ��Ƃ��͉t����OFF�ɂ��Ă܂���
�X�s�[�h�t�@���ł����x�͍��̎����S�O�x�O�ゾ��
�N���b�N�̗������݂������Ȃ��A�悭�RD�e�X�g�A�X�[�p�[���e�X�g���邯�ǖw�Ǔ�������
NEC�̏C���p�b�`�̓C���X�g�[�����Ă܂��H
ATI MOBILITY RADEON 9000�̏C���p�b�`�͕K���C���X�g�[�����Ă��������A���^�c�L�͉��������͂��ł��B
reo-310
�����ԍ��F2365692
![]() 0�_
0�_
MINIMI�@���� ���X���肪�Ƃ��������܂��B
���������Ŋm�F����Ă���������Đ����ق��Ƃ��܂����B
���ۂ̂Ƃ���A121�ɂ��̌���q�˂�̂𑊓����߂���Ă��܂������A�N�����Ƃ����Ă���Ȃ����ȂƂ��v���Ă܂����B
�����ɏ������̂��A���������œ����Ǐo�����T���̂��ړI��1�ł����B
�t�@���̌��ł����A��������_�ł͍݂�܂����ANEC�͉ߋ��ɔM�\���ƃt�@���̑����ւ̋��̖�肪�݂�A����Ӗ����̗��҂𗼗��������ʂ��ȁH�Ǝv�����肵�Ă��܂��B
�ł�����A70���Ńt�@�����A80���ŃN���b�N����Ƃ����ݒ�������̒��ɈĂƂ��Ă���܂��BNEC����ǂ��ł��傤���H�����Șb���ł͂Ȃ��Ǝv����ł����B
reo-310�@����A��肪�Ƃ��������܂��B
�X�s�|�h�t�@��(4.09J)�͎����g���Ă݂܂������AHDD�̏�������܂���ł����̂ō��͎g���Ă��܂���B(�����ݒ�ɖ�肪����̂��낤���H)
ATI�̏C���o�b�`�ɂ��ẮA�C���X�g�[��������̌��ʂō���121�ɂ��q�˂��Ă��܂��BMovieWriter�Ȃǂ́A�C�������Ȃ��Ǝg�����ɂȂ�܂���ł������B
�����ȂƂ���AATI�̏C���o�b�`�ɂ͉��x����ɂ��Ă̏C�����܂܂�Ă��鎖�����҂��Ă��܂������A70������̗�p���Ԃ̒Z�k�����ꂽ�̂��ȂƂ������x�̂��̂ł����B
�L�ڂ��ꂽ���e�ȊO�ɁA�N���b�N��ւ��̃��X�|���X�𑁂�����C�����܂܂�Ă����݂����ł��ˁB
���ƁA����20���ȉ����ƁA���Ȃ��Ƃ�20���͕��ׂ������Ȃ���70���t�߂܂ŏ㏸���܂���B
�C�������@
CPU�̉��x�㏸�̗v���Ƃ��ē��R�g�p����100���߂����Ƃ��Œ�����Ȃ̂ł����A����ȊO�ɃO���t�B�b�N�\���̕��ׂ������K�v������悤�ł��B
����CPU�g�p���ł��AMobileMeter��^�X�N�}�l�[�W���[�Ȃǂ̃��j�^�����O�\�t�g�̕����\���ȂǁA��ʂւ̕\�������G�ł������قlj��x���㏸���܂��B
���s���Ŋm�M�����Ă܂��APentiamu4�n��̃O���t�B�b�N����������@�\���e�����Ă�̂�������܂���B
�����@�F�@��q�̃N���b�N�ω��́@70��61��(1.2GHz)1���@61��70���i2GHz�j5���ł����B
�����ԍ��F2366421
![]() 0�_
0�_
�m�[�g�p�\�R�� > NEC > LaVie C LC700/6D
NEC���{���AATI�А� MOBILITY(TM) RADEON(TM) 9000 �f�B�X�v���C�h���C�o (LaVie C/LaVie G�p)�A�b�v�f�[�g���W���[��(Windows(R) XP��)
������܂����B
���e��
���́uATI�А� MOBILITY(TM) RADEON(TM) 9000 �f�B�X�v���C�h���C�o(LaVie C/LaVie G�p)�A�b�v�f�[�g���W���[��(Windows(R) XP��)(�ȉ��A�u�{�\�t�g�E�F�A�v�ƌ����� ��)�v�́A�ȉ���3�̖����C�����܂��B
1.�L�[���͂��g�p����A�v���P�[�V�������N�����A�L�[���͂����炭�����Ă��� �ƃ��j���[�\���ȂǃV�X�e���̓��삪�x���Ȃ��Ă���B
2.PC�̋N�����A�܂��́A�x�~��Ԃ���̕��A���ɁA��u�A�c�ȁi�����̔����j�� �\������邱�Ƃ�����B
3.��ʂ̕\���F�̐ݒ肪16�r�b�g�̏ꍇ�A���[�h�p�b�g�ŁA�����̃t�H���g�T�C�Y ��20�ȏ�ɂ������A�u�Z���v���A�ꕔ�̕����F������ɕ\������Ȃ��B
�C���X�g�[���������z�ł����A�c�Ȃ͂Ȃ��Ȃ�܂������Ȃ�
���X�|���X�͂������������ł��B
�����c�O�Ȃ̂͂RD�x���`�e�X�g�͎c�O�Ȃ��痎���܂���
FF11�x���`�QHigh�͂Q�S�U�T����Q�R�T�S�Ƀ_�E��
�RD�}�[�N�Q�O�O�P���U�O�O�O���܂����A�F�X�ݒ��ς��Č��܂���������قǕς�炸�A�C���p�b�`�����Ă������ύX��̊��z��('-'*)�����V�N��
![]() 0�_
0�_
ATI��CATALYST�ł͉��P�ł��Ȃ��̂ł��傤���B
�����ԍ��F2080316
![]() 0�_
0�_
ATI��CATALYST�̋L����ǂނƂX�T�O�O�ȏ�̓K�p�����݂�����
�X�O�O�O�ł������ł���ō��Ȃ��A���Ȃ݂ɃC���X�g�[���������Ă݂܂����A�c�O�Ȃ���͂�����C���X�g�[���o���܂���B
�X�R�A�͗����Ă��C�ɂȂ��Q���Ȃ��Ȃ��������X�|���X�͂悭�Ȃ�܂������疞�����ȁB
�����ԍ��F2080410
![]() 0�_
0�_
2003/10/31 23:44�i1�N�ȏ�O�j
reo-310�����
PC-LT5006D�̌f���� [2075125]�̎��̔�����ǂ�ł��������܂����ł��傤���H
�����ԍ��F2080640
![]() 0�_
0�_
�������`�i���������܂��悵�j�@����
�N���b�N�����̌����ȁA���Ȃ��ł�1.99�f�g�y�\������Ă邵
�e�e�P�P�̃x���`�Ȃ��10��ȏ�͂��Ă܂����A�����܂�
����ł�3�`4��̓��[�v���Ă܂��A�e�e�P�P�x���`2�����ŋ߂͂��Ă܂���B
[2075125]�͒������Ă݂�C������܂���B
�����ԍ��F2080846
![]() 0�_
0�_
2003/11/01 07:20�i1�N�ȏ�O�j
reo-310�����
�����ł����A����͂悩�����ł��ˁB
���萔�����������܂����B
�����ԍ��F2081262
![]() 0�_
0�_
�������`�i���������܂��悵�j�@���� �֕⑫���Ă����܂���
�����d���I�v�V�����̃v���p�e�B�[�́A�o�b�e���[�̍ő嗘�p�Ŋg���� Intel SpeedStep��L���ɂ��Ă܂��A�x���`�X�R�A�̓o�b�e���[�̍ő嗘�p�ł̐����ł��A�v���p�e�B�[�̕\���͕��i��1.2GHZ�\������Ă܂�
���ׂ��������1.99GHZ�\���ɕς��܂�
�X�R�A�������1.2GHZ�̃X�R�A���Ƃ͎v��Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F2081300
![]() 0�_
0�_
���u�p�\�R���̂����II�v���N��������S�ăf�t�H���g�ɂ��ꂽ�̂ŁA�V�X�e���̕����Ŗ߂�����RDMark�Q�O�O�P���N�����Ȃ��A�����N���T���Ă���悤�ł����A���߂���9000�̏C���p�b�`�A�y�уx���`�e�X�g�ۑ����D����C�ɕς��ăC���X�g�[�����Ȃ����Ă݂܂���
�Ȃ�ƃX�R�A�����̏�ԋ߂��ɖ߂�܂���
���Ȃ݂ɃX�R�A��
FF11�x���`�P �R�T�O�T
FF11�x���`�Q LOW �R�P�U�V
High �Q�S�T�Q
�RDMark2001 �P��ڂU�T�O�V�A2��U�U�R�Q�C3��U�V�R�R
4��ڂ͂������ɗ����܂�����
������̃C���X�g�[����̖��ŁA�x���`�X�R�A�ɂ͂�����e�����Ȃ������ˁH
�����ԍ��F2081890
![]() 0�_
0�_
2003/11/01 14:49�i1�N�ȏ�O�j
��������PC���g���Ă��܂��B����RADEON9000�C�����W���[�����C���X�g�[�����܂������C�����W���[���K�p��́u�p�b�P�[�W�̃o�[�W�����v��
�u7.84-030228a1-008233C�v�ƂȂ��Ă���121ware�Ōf�ڂ���Ă���o�[�W�����u7.90-030605m-009779C�v�Ƃ͈Ⴄ�\���ɂȂ��Ă��܂�������ł�����ł��傤���B�N�����̔����Ȗ͗l�̕\���͂���Ȃ��Ȃ�����ł��Ԃ܂��������Ƃ������܂����A�����Ǝ��ۂ̃o�[�W�������Ⴄ�̂ŕs���ł�����܂��B
�����ԍ��F2082091
![]() 0�_
0�_
2003/11/01 22:08�i1�N�ȏ�O�j
�����C�����W���[�����C���X�g�[�����܂����B
���������A�o�[�W�����ԍ�������Ă܂��ˁB����Ȃ��̂Ȃ�ł��傤���B
�����ԍ��F2083178
![]() 0�_
0�_
��蔭�����܂����A Microsoft Office Personal Edition 2003���C���X�g�[�����ăf�t���O�����s���悤�Ƃ�����A�̈悪�P�T���ȏ�Ȃ��Ƃł��Ȃ����Ƃɜ��R�B
�A�v���P�[�V�����\�t�g��D�h���C�u�ɃC���X�g�[������ςނ��Ƃł����A�s��ƃp�t�H�[�}���X�D�悷���C�h���C�u�ɃC���X�g�[�������ق������Ȃ��ł��ˁB
�o�b�N�A�b�v��DVD-RAM�Ɏ��A�ă��J�o���[���邱�Ƃɂ��܂���
�o�b�N�A�b�v�ɂ�DVD-RAM�͏d���A��x�g���Ƃ��̗L��������Ȃ��B
�ŏ��͂P�QGB�ɐݒ肵�܂������A�A�v���P�[�V�����\�t�g�����łP�OGB����邩�獡��͗]�T�����ĂP�WGB�ɐݒ肵�܂���
�n�[�h�f�B�X�N���J�o���[�̓z���g�y���ˁA���J�o���[�����Ȃ�Q�O��������Ȃ������A�O����Z�k����܂���
���ׂăA�v���P�[�V�����\�t�g��C�h���C�u�ɃC���X�g�[�����܂����A�e�ʂ͂P�O�D�UGB�ł��A���V�D�SGB�����獡��͗]�T�ł��ˁB
���W���[���̃w���v������ƁA�u7.90-030605m-009779C�v�Ƃ͏����Ă���ˁA�ʂɋC�ɂ��܂���A���̌��ۂ͏o�Ȃ�����
���낢��J�X�^�}�C�Y���Ă̋N�����Ԃ͂R�U�`�R�W�b�Ńf�X�N�g�b�v�̃A�C�R�����\���ł���قǑ����Ȃ����A�ŏ��̂P���P�O�b�͉��ȂH
���Ȃ݂ɋN�����Ă���̃������g�p�ʂ͂P�R�RMB�ł�
�X�^�[�g�A�b�v�ɓo�^���Ă���̂́A����LAN�W�A���@�\�}�E�X�A�m�[�g���APCGATE�A�X�s�[�h�t�@������
�RD���\������قLj����͗����܂���ł���
FF11�x���`�P�@�@�@�@�R�T�O�T
FF11�x���`�Q�@LOW �R�P�U�V
FF11�x���`�Q�@High�@�Q�S�T�Q
�RDMark2001�͋t�ɃA�b�v���āA�U�W�O�P�܂ŃX�R�A��L������
�x���`���s��������������Ȃ�C���p�b�`�Ă��ق������������ˁB
�����ԍ��F2084521
![]() 0�_
0�_
�m�[�g�p�\�R�� > NEC > LaVie C LC700/6D
10��20���t����PCGATE Personal Ver2.1 �A�b�v�O���[�h���W���[���i2003�N1��/3���o�א��i�p�j��121ware�ɃA�b�v����Ă܂��B
�����ڂ���V����Ă��܂��B
�O�̂̓C�}�C�`�������̂Ŏg�p���Ă��܂���ł������A2.1�͍��̂Ƃ���O�̂ł݂�ꂽ�u�X�g���[�~���O�����܂��Đ��ł��Ȃ��Ȃ�v���̖��͂���܂���B
�l�I�ɂ͂����������Ԃ�XP�W����FW�ƃ��[�^�[�݂̂Ŗ��Ȃ������̂ŕK�v�Ȃ��C�����܂����B
���܂��܌������̂ŃA�b�v���ꂽ�̂������O���������Ă��炢�܂����B
![]() 0�_
0�_
�m�[�g��������̃E�C���X��\�t�g�Ƃ̑������O�̃o�[�W�����ł͍ň��ł���������͂ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁH
reo-310
�����ԍ��F2054710
![]() 0�_
0�_
2003/10/23 19:44�i1�N�ȏ�O�j
����PCGATE2.1�ƌ��XPC�ɓ����Ă���NAV�ƕ��p���Ă��܂����A�O�o�[�W�����g�p�Ŋ�����ꂽ�ςȊ����i�������������H�j�͂���܂���B
XP�W����FW�Ŏg�p���Ă����Ƃ��Ɠ��ɈႢ�͊����Ȃ��̂ŁA�ǂ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F2055894
![]() 0�_
0�_
���������������܂����A�m�[�g���������Ă����̂Ƃ���������͂Ȃ��ł��B
�����ԍ��F2064928
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�m�[�g�p�\�R��]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����zA20?
-
�yMy�R���N�V�����z30���\��
-
�y�~�������̃��X�g�z�T�[�o�[�p����PC �\����
-
�y�~�������̃��X�g�z10��7��
-
�y�~�������̃��X�g�z�����Y
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h
- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��
�i�p�\�R���j