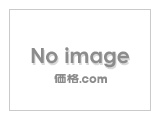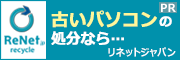ノートパソコン > NEC > LaVie C LC700/6D
処理低下に関する結論と言える報告になるかもしれません。
種々の疑問を解決する内容が、意外と近くに、121サイトNEC開発者インタビューにありました。
以下はSERIES26の現行LavieCについてのレビューの一部です。
・・・グリースは、保守性で劣るので、従来のノートパソコンでは、フェーズチェンジシートの上にアルミシートがのっている二層構造のフェーズチェンジを使っていました。でも、今回、プロセッサ上のヒートスプレッダーの温度を70度までしかあげてはいけないんですが、今までのフェーズチェンジでは、60度以上にならないとフェーズチェンジシートがとけ出しません。比較的低い温度でも、きちんと密着性を確保するためには、どうしても、グリースを採用する必要があったんです。
ここにある「プロセッサ上のヒートスプレッダーの温度を70度までしかあげてはいけないんですが、今までのフェーズチェンジでは、60度以上にならないとフェーズチェンジシートがとけ出しません。」という言葉から、この時期の温度管理の考え方が、ヒートスプレッダーの温度を70度までとしていることがうかがえます。
また、60〜70℃という温度範囲も、自分がLC7006Dで測定した温度変化に符合します。
これに対して、インテルのノートブック・パソコンの熱管理(インテル 技術サイトより)では、以下のように書いています。
(インテルサイトより抜粋)
殆どのノートブック・パソコンには、最大動作温度を越えるとクロック速度を落とす、スロットル (絞り) 機能があります。しかし、もちろんこれは性能低下につながりますし、この機能に依存して熱設計をするべきではありません。
この最大動作温度を越えるとクロック速度を落とす動作はノートPCの温度管理の内、今回問題としているCPUクロックを制御するパッシヴ冷却にあたるといえます。
この事を踏まえて、
(インテル Pentium M プロセッサ技術サイトより抜粋)
インテル(R) Pentium(R) M プロセッサを使用するノートブック・パソコンでは、必ず熱管理を行なう必要があります。「熱管理」とは主に、プロセッサに冷却装置を正しく取り付ける事、および、冷却装置の換気を効率化し、システムの外へ熱を排出する事を意味します。熱管理の最終的な目標は、プロセッサの温度を常に最大動作温度 (Tcase) 以下に抑える事です。インテル(R) Pentium(R) M プロセッサの Tcaseを、表 1 に示します。この値は、プロセッサコア・ケース表面の中心で測定したものです。
表 1: ボックス インテル(R) Pentium(R) M プロセッサ 最高動作温度
(略)動作周波数1.4〜1.6GHzについて最高動作温度100℃
最高動作温度とは、プロセッサが正常に動作可能な上限の温度です。
通常、最高動作温度として表示されている温度は、下記の "T-Junction" もしくは、"T-Case" の温度になります。
T-Junction:プロセッサ・コア内部の温度
T-Case:プロセッサ・コアに、 IHS (インテグレーテッド・ヒート・スプレッダ) が装着されている場合、その中央部分の温度
以上のことから、インテルでは動作温度の最高値の目安として、プロセッサ・コアもしくはヒート・スプレッダの中央部で100℃としていることが分かります。
このため、多くのメーカーがCPU温度100℃前後をパッシヴ冷却温度に設定しているのでしょう。
クリティカル冷却温度は更に高いですね。
これに対し、NECでは、先述のようにLavieCの設計においてヒート・スプレッダ上の上限値を70℃としていることから、パッシヴ冷却温度に達する確率が高くなるのは当然といえます。
しかしながら、NEC自負する冷却に対する設計が効果をあげているのか、この厳しい条件でも添付ソフトでは他社と余り変わらない能力を示しているため、へビーユーザー以外には影響が少ないと考えられます。
以上が自分自身が個人で調べられた情報での結論であり、これまでの自分の疑問に答えるに十分な結果と考えています。
このことから、LC9005D・LC7006D および同等直販モデルについて、まだ性能上の余力がありながら温度管理の制限が厳しすぎるため高負荷の際にカタログ性能を100%出せないと自分なりに結論付けて、NECにこの点を改めて改善するよう求めたいと思います。
もう少し前にこのことが分かっていたらもっと書き込みに反応があったのでしょうかね?寂しい限りです。
Pentium 4-M搭載機は、個人的に発熱抑制と静音の両立という難題に挑戦したモデルであったのかなと感じています。温度管理を緩めることで爆音PCに近づくかもしれませんが、このサイズでこの電源システムとスペックが両立すればベストノートPCになるのではと思ったりしています。
色々な意味も含めて、NECの開発技術に敬意を表します。
書込番号:2396152
![]() 0点
0点
自分のお脳のレベルではやや難解・・・
プロセッサが100℃になりますかね??
一覧を参照>>http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/8521/cpu_all.htm
書込番号:2396204
![]() 0点
0点
自分は同じ媒体のマシンを使用していますが、(量販店モデルLC550/5D)
pen4-M1.8Gですが、50℃を超えたことがありません。
今38度ですが、ファンが若干回っている感じです。
とても参考になりました。
ファンをとめるねじをきつくしたところ、若干温度が下がりました。
書込番号:2396462
![]() 0点
0点
CPU全体が100℃になる様な製品を売ってたのでは商品にならないでしょうね。
ましてや、そんなモノを空冷で冷やすなんてとんでもないと思いますよ。
ただ、CPUの中央の一部で有り得るからインテルも温度管理を喚起してるんでしょうね。
ヒートシンクや周辺部の温度管理の上限は70℃前後としてますね。
今のところ自分の興味があるのは、自分の所有しているPCの実力だけです。
書込番号:2396478
![]() 0点
0点
きこりさんのつっこみ、痛いです。
NEC開発者の言葉の中で確認できた、ということを言いたかったのが本筋です。
くどくなって申し訳ありません。
書込番号:2396584
![]() 0点
0点
2004/01/28 01:03(1年以上前)
こんにちは。
私も700/6Dユーザですが、うちのなんてGPUが動作していなくても
CPUの負荷だけで、簡単にクロックダウンが起こりますよ。
(たとえば1+1の計算の無限ループとか。)
K県のOさんのは、まだいいほうですね。
ところで私の考えはちょっと違っています。
CPUの温度が70℃になるとクロックダウンするのは、Pen4-mの
スロットル機能ではなく、ACPIのパッシブ冷却によるクロックダウン
と考えています。70℃はACPIの_PSV(Passive cooling threshold)
の設定ではないでしょうか。
クロックダウンに対するNECの回答は確か、
「SpeedStepによるものです。」
だったと思いますが、これもACPIによるパッシブ冷却機能と
いうことであれば納得ができます。
つまり、ACPIはPCおよび接続機器の電源制御のための規格ですから
冷却を電源制御つまり電圧降下?で行い、当然SpeedStepが動作して
クロックが落ちるという流れです。
私も700/6Dを購入してこの問題に遭遇してから調べているような素人
ですので、確証はありませんが。
ちなみにACPIによるものだとすると、BIOSの変更は不要なはずです。
ACPIによる電源制御はASL(ACPI Source Language)でコーディング
されているはずですから。
書込番号:2396847
![]() 0点
0点
2004/01/28 01:09(1年以上前)
CPU温度は100度まで上がりますけど、そこまで放っておくといろいろと問題が起きるので、それ以前のところで冷却ファンを回すだとか、スロットリングに入るだとか、する訳です。
書込番号:2396873
![]() 0点
0点
2004/01/28 01:32(1年以上前)
「最大ダイ温度」について
これは「プロセッサコアの温度が最大何℃の条件下でまで動作を
保障するか」という定義です。
従って、そのプロセッサが発熱により何℃まで温度上昇するかとは
別物です。
現在のCPUでは、白熱電球に相当する発熱がたかだか5mm四方の大きさに
集中しています。
冷却性能が不足した環境下では100℃程度は簡単に上がることが簡単に
創造できるかと思います。
書込番号:2396934
![]() 0点
0点
2004/01/28 01:36(1年以上前)
ずいぶん前に聞いた話なので記憶があいまいですが、
「温度上昇時のクロックダウンによる保護機能」は
初代Pentium4から搭載されていた機能で、CPU自体に
内蔵されており、ACPIなどの管理下に無くても動作
するものだったと思います。
書込番号:2396947
![]() 0点
0点
ふつうはこのクラスのノートではできればあってはいけないクロックダウンですね。
でもNECの場合はあってもおかしくないですよ。許容が少ないですからファン設計がね。
X505を分解したりして実験しましたが1GHzで動くのはせいぜい7分程度でそれ以降は熱くなってクロックが600に下がります。
アイスノンで冷やしてやれば常に1GHzで動作します。
こういう機種では当たり前のようにクロックが下がる設計にはなっていましたがこの機種ではしっかりファンがついているんだし、BIOS関連いじれたらクロック下げずにすみそうなんですがねぇ。
それかサーマルシートの不具合とか。
書込番号:2397139
![]() 0点
0点
なんだ今更という感じに盛り上がってますね。
Mobile Pentium 4-MのTDPを見ると、だいたそのクロックの上下のクロックどれも同じ。
消費電力はクロックに比例するのに。
1.40、1.50 GHzまでは小数点第一位まで有効数字が出てるのに、それ以上は30.0、32.0、35.0。
それを解釈すると、状況より処理能力を制限していることは一目瞭然。
つまりMobile Pentium 4-Mの仕様です。
この種の問題はMobile Athlon XPも同様。
同じコアなのに25とか35とか60Wと消費電力/発熱でカテゴリ分けなっているのだから。
書込番号:2397199
![]() 0点
0点
↑
さすがコンピュータにHDDがなかった頃から向かい合ってるから
恐ろしく詳しい。
書込番号:2397370
![]() 0点
0点
光秀さん、どうもです。
私も似たようなレベルですので、偉そうなことは言えませんし、ご意見参考になります。
PSV(Passive cooling threshold)については、同意見です。
7つぐらい前の書き込みで、今より情報の少ない私が似た内容を書いてます。
最大動作温度=パッシヴ冷却でいいと思いますが、インテルの日本サイトの書き方が紛らわしくて、表1の説明なんかは英文直訳のためか文章が読み取りづらいです。
光秀さんもインテルのサイトで読解にチャレンジしてみてください。
SpeedStepについては、本来の目的がCPUをいかに少ない電力消費量で効率よく運用するかというものですから、パッシヴ冷却=SpeedStepとするのはやはり無理がありますね。
ACPIについては、これから勉強というところです。とりあえず、ここまででNECに追加注文をつけるには十分と思います。
個体差なんですが、以前TailmonさんがLT500の書き込みで温度センサーの位置が関係しているのでは、と言っていた事を思い出しました。
測定位置によって結構差が出そうなので有り得る話ですね。
Tailmonさん、Kharu1さん指摘ありがとうございます。
私も「冷却を行った上で」という言葉が足りませんでした。
書込番号:2397440
![]() 0点
0点
2004/01/28 20:58(1年以上前)
しつこいかもしれませんがさらに補足^^;
まず、
Pentium-Mの
書込番号:2399391
![]() 0点
0点
2004/01/28 21:24(1年以上前)
↑書きかけで投稿してしまいました。失礼しました。
いくつか気づいた点があるので補足させていただきます。
121ware.comサイト内の開発者インタビュー記事中で述べられている
のは、前後の文章から判断して上位機種7D/8Dに採用されている
モバイルPentium4 3.06GHzや2.66GHzについてだと思われます。
これらのCPUの最大動作保障温度は70℃前後なので、NECはこちら
にあわせて70℃という温度を設定しているのでしょう。
K県のOさんが指摘されている「この時期の温度管理の考え方〜」という
文章の意味が良く分かりませんが、70℃という温度は上記のように設定
されていると思われます。
それより動作温度保障温度の高いCPU採用の本機種でも同様の
設定となっているのが問題の可能性がありますね。
なお、インタビュー中で触れられているフェーズチェンジシートとは
熱で溶融するタイプの熱伝導シートのことと思われます。
これは装着直後の状態では厚みがあり熱伝導性が良くありませんが、
最初の通電磁の熱により溶融して良く密着するタイプのものです。
メーカー製PCでは良く使われている素材です。
これを使わず、均一に塗布するのが難しいグリースを使っていることも
本機種で熱による処理低下が起きる原因かもしれませんね。
書込番号:2399488
![]() 0点
0点
2004/01/28 21:47(1年以上前)
>きこりさん
仕様書の解釈の仕方、間違ってますよ。
表記されているのは、あくまでもProcessor の100%での
動作を保証するためのTDPです。
例えば1.6,1.7,1.8GHzでTDPの値が30.0Wと同じなのは、
マージンを持たせた値を表記しているためで、
この例の場合1.6Gが一番マージンが大きいと言えるでしょう。
特に品質にばらつきがある電子部品等の場合、
大きめのマージンを持たせた値をカタログ表示する事はよくある事です。
TDP周りの仕様からは、間違っても
>それを解釈すると、状況より処理能力を制限していることは一目瞭然。つまりMobile Pentium 4-Mの仕様です。
なんて事はいえません。
書込番号:2399582
![]() 0点
0点
さて、それを満たす一例からはその可能性はあるでしょう。
では、そうで無い可能性はどう排除したのでしょう。
書込番号:2399701
![]() 0点
0点
2004/01/28 22:39(1年以上前)
横から失礼します。
スペックシートの解釈はきこりさんの方が正しいと思います。
半導体の消費電力は電圧の二乗と動作周波数の積に比例します。
従って、同じアーキテクチャ・プロセスで作られるCPUの消費電力が
周波数に比例しないことは考えられません。
次に、TDPは最大消費電力ではありませんが、負荷を一定に設定した
条件下で測定される値です。従って、ほぼ上記の法則が適用されますし、
マージンを取った記載がされることはありません。
また、スペックシート等の補足説明をよく読むと分かりますが、
TDPは実際のCPU使用時の一般的な状況での最大負荷下で想定される
消費電力であって、100%の動作保障をするための値ではありません。
書込番号:2399833
![]() 0点
0点
2004/01/28 22:42(1年以上前)
>きこりさん
ちょっと、気になったので質問なのですが、
>状況より処理能力を制限していることは一目瞭然。
これは具体的にどのような機能で処理能力を制限しているのですか?
書込番号:2399853
![]() 0点
0点
口を挟めない話が展開されてますね・・・
Kharu1さん、色々とありがとうございます。
話からすると、モバイルPentium4 シリーズのプロセッサ・コアもしくはヒート・スプレッダでの最大動作保障温度の情報をご存知ようなので、参考にしたいので教えていただけませんか。
色々探したのですが、明記されたものがみつからなくて。
あと、流れからすると、モバイルPentium4を使用した機種は全てパッシヴ冷却温度が70℃に設定されている可能性がありますね。
光秀さん、私の機体より症状が激しいようですね。
今回、121に電話をした中でサービスから「修理という形であずかるのでも・・・」という話がありましたので、問題が多いようであれば試しに掛け合ってみてはどうでしょう。
私は暖かくなるまでは影響が少ないので、NECさんの対応を待ってみますということで、保留としています。
あと、情報として1つ追加します。
電源設定でプレゼンテーションに設定するとクロックを頻繁に下げることは知っている方もいるとは思いますが、LC7006Dはこの設定でパッシヴ冷却温度を40℃に変更します。
このことから、光秀さんが言われるようにBIOS変更なしで冷却温度設定は可能だと思います。
ただし、ファン制御に関しては不明瞭な点が多いですね。
ちなみに、プレゼンテーションでのクロック変更は40〜47℃1.2GHz、48〜53℃900MHz、54〜?℃600MHzです。
書込番号:2399888
![]() 0点
0点
2004/01/28 22:54(1年以上前)
最大動作保障温度はIntelサイトにあるそれぞれのプロセッサの
スペックシートに記載があります。
書込番号:2399931
![]() 0点
0点
2004/01/29 00:26(1年以上前)
K県のOさん、ありがとうございます。
早速電源設定を変更して、_PSVの温度設定が変更されることを
確認しました。面白いですね。とりあえず、_PSVの設定を変更する
方法を探ってみます。ただ、設定変更できたとしても、完全に
自己責任ですね、これは。
書込番号:2400430
![]() 0点
0点
Intelサイト・・・以前にも何度か検索したのですが、あちこち参照不可になるんですよね。
ID登録もうまくいかないし・・・
とりあえずボックスインテル(R) Pentium 4 プロセッサとボックス インテル(R) Pentium(R) M プロセッサの情報は手元にあります。
ただ、最大動作温度の扱いが微妙に違いますね。
Pentium 4 では「ファン・ハブの中央部分の上方 0.3 インチほどの場所」、Pentium(R) M は「プロセッサコア・ケース表面の中心」となっていますから、測定の意味合いが違っているような・・・
ボックスインテル(R) Pentium 4 プロセッサ での表記(68〜78℃)はプロセッサコアの値ではないのでは?情報不足だ。
書込番号:2400536
![]() 0点
0点
Mobile Pentium 4-MとPentium 4とは、L2キャッシュ量とFSBが同じであればほぼ同じ性能だと考えられています。
それでは、2.50 GHz動作の場合、前者は35.0 Wで後者は61.0です。
電圧は前者1.30 V、後者は複数ありますが高く見積らないと駄目でしょうから1.525。
15%減です。
消費電力は電圧の2乗に比例というのが定説ですから、27%減になります。
理屈上Mobile Pentium 4-Mの消費電力は61.0 Wの27%減にならないと性能を維持できないことになります。
しかしTDPはそれよりも低い数字になっていますね。
Mobile Pentium 4-M 1.60 GHzとPentium 4 1.60A GHzだと、この理屈でTDPがほぼ一致します。
つまり1.60 GHz以上のクロックではなんらかの制限をしないことには破綻してしまうことになるでしょう。
正確を期すにはTDPの有効数字が小数点以下第一位まで出ている1.50、1.40 GHzとで比較すべきですが、Pentium 4に適切な比較対象がありません。
書込番号:2400568
![]() 0点
0点
急いで訂正。
Pentium 4 では「ファン・ハブの中央部分の上方 0.3 インチほどの場所」
↓
Pentium 4 では「シャーシ内(ファンとヒートシンク部分?)」
あぶない、あぶない。
光秀さん、私も勉強がてら調べてみます。
書込番号:2400581
![]() 0点
0点
Pentium 4は過熱すると自動的に処理を間引いて発熱を抑えます。
3個のPentium 4でCPUのファンを止めてみましたが、マザーボード添付のツールでCPU温度をモニタすると、T-Junctionで示された温度近辺で温度が平衡しました。
その時の処理能力は通常の1/10くらいになってましたけどね。
Pentium 4はCPU内部だけで十分な熱管理が行えるでしょうが、Mobile Pentium 4-Mいくつのパラメータをトリガにしているのかは分かりませんが、BIOS側からの働き掛けもトリガとしていると考えられますし、CPU内部温度は確実でしょう。
TDPは名前をその通り解釈すると、熱設計のガイドラインで、このCPUを実装するならこれだけの排熱能力を確保しろという指標でしょう。
必ずしも発熱量を表しているとは言えません。
書込番号:2400626
![]() 0点
0点
きこりさんへ。
Pentium4-MのTDPについては、インテルが35W前後までを上限とするという話がありましたね。
途中からCPUクロックを稼ぐために無理をしていたということでしょうか?
ちなみに、Pentium4で試したときの、コアの温度はいか程でしたか?
書込番号:2400757
![]() 0点
0点
2004/01/29 22:40(1年以上前)
35Wはかつては省スペースデスクトップで、現在では比較的大型の
薄型ノートで冷却可能なCPU発熱量の限界だといわれています。
通常60Wを超える消費量のP4コアを無理やりノート用に転用するため
連続発熱時のクロックダウン機能をつけたのでしょう。
実際スペックシートには「最大発熱量はTDP値を超えることがあるので
詳しくはIntelに直接問い合わせてくれ」という旨の注釈があります。
書込番号:2403644
![]() 0点
0点
Kharu1さん、たびたびありがとうございます 。
Intelサイト、USAまで見て余りにも最高動作温度の表記がばらついているので、頭が混乱、開き直ってサポートに聞くという最終手段を使いました。
で、聞いてみるものですね。
まだCPU上の温度センサーの位置については調べ中ということですが、以下の情報が聞けました。
CPUからの温度センサーでの最高動作温度/CPU自身による過熱回避温度
Pen4-M1.6〜2.0 100℃ / 135℃
モバイルPen4 100℃ / 135℃
Pen-M 100℃ / 125℃
基本的にPentium 4系統の温度管理はどれも同じだということだそうです。
結果として、ACPIによる温度制御にわざわざ既存のセンサー以外を使うとは思えないので、どこに付いていようが最高動作温度が100℃を下回ることはないですね。
ますますパッシヴ冷却温度を70℃にしている意味が分からなくなってきました。
センサーの位置については週明けに連絡してくれるそうなので、またその時に幾つか質問してみます。
書込番号:2408894
![]() 0点
0点
センサー位置について確認が取れました。
当然といえば当然ですが、T-Junction(プロセッサ・コア)の部分ということでした。
これで、モバイルPentium4-MのT-Junction最高動作温度100℃に対して、PCの温度管理はこれを超えない設定になっていればいいことになります。
ただ熱管理を行なう上で、チップとしてのプロッセッサは外郭にヒート・スプレッダを装着していて、これを仲介して放熱を行なうため、排熱設計はヒート・スプレッダ上の温度で考えているようです。
実際、きこりさんやKharu1さんが言ったように、途中からCPU熱管理の指標だったTDPが曖昧なものになって、T-Case(プロセッサ外郭放熱板)を参考にした管理に移っています。
ですから、LavieCのモバイルPentium4-M搭載機はT-Caseで80〜85℃、モバイルPentium4搭載機は70℃までを目標に設計された、ということになります。
しかし、肝心のCPU発熱量の動向はインテル次第ということで、保障されるものではなかったわけですが。
ちなみに最近のPentium-MはT-Junctionで100℃と言う以外、情報がありませんね?
書込番号:2429021
![]() 0点
0点
・・・只今、NECからの連絡待ち。
ふと思って、底部にある吸気用の穴と思われる小穴を塞いでテストしてみました。
予想では温度上昇が早くなるのではと思ってたのですが、意外や意外、CPU温度最高値が1〜2℃下がりましたよ。
自分の場合だけかもしれませんが、吸気穴と思われるものが底部しかないことから、パーツの隙間、特にキーボード周辺とドライブ側からの取り込みがあるかと。
ただ、DVDを動かすと意味がないかも・・・あまり良い情報じゃないですね。
7006Dも流通が少なくなってきてそろそろこの場所も消えてしまうかもしれないので、ここが消えた後は、迷惑かもしれませんが7・8D辺りに経過報告を書き込みます。
某掲示板にもそれなりの場所はありますが、信憑性が下がりますから。
別件。昨年春モデルの不具合報告者には6Dの処理低下以上の症状の方がいたのを、ふと思い出しました。
今、そのことが少し気になっています。
書込番号:2437246
![]() 0点
0点
ただ連絡を待っているだけでは手持ち無沙汰なので、このLavieCシリーズの2ndファンを主とした給排気について、今日午後121に質問しました。
前回は6Dの2nd給排気が、仕様は排気、実機は吸気でしたと良くわからない返答で、今日は間髪入れず1週間程連絡待ちをということに・・・
何かに登録されましたかね。
121のサポートの方には手間をかけて悪いなと思いますが、事実を知るには情報も必要なので。
書込番号:2439010
![]() 0点
0点
いろいろやっておられるようですがCPU周り分解してみました?
書込番号:2439146
![]() 0点
0点
NなAおOさん、先述のご意見参考になっています。
言われたように、冷却設定を微調整すればかなり軽減されると思います。
サーマル・インターフェイス(フェーズチェンジシート)の使用法にも問題がありそうです。
内部については、以前分解しかけたんですが、キーボード周辺のはずし方が分からなくて断念しています。
ただ、アスキーの資料にこの筐体モデルの初期の分解写真がありましたので、無理はしなくていいかなと思い手をつけていません。
私のレベルではパーツの違いは判断できないでしょうし、データを集めて状況を固めているというところです。
書込番号:2440514
![]() 0点
0点
3回目の問い合わせより、4回目(2ndファンの給排気設定)の返答が先に返ってきました。
LC7006Dと同等春モデルLC9005Dが、排気ファンとして設定されているということで、サポートの方は開発部に確認しましたので間違いありません、と何か気合の入った返答でした。
勢いに押されて4D以前のモデルについて再確認できませんでしたが、これは吸気設定ということで良いんでしょうね。
本題から少しそれて。
今、自分が121サポートを通してやっていることというのは、いわゆるクレームという言葉に集約される行為ですね。
改めて考えてみて、自分がこれによって何が得られるのかということを考えてみました。
発端は、某掲示板の春モデルLavieCの「クロック落ち」という書き込みからで、これを見なければ自分も気づいたかどうか。実際このシリーズの購入者はNECへの信頼や機種の高級感に魅かれて買った方が多いと思います。そういう方の多くは処理低下の影響を受けるような使い方をしていないでしょうから、特にクレームをつける問題ではないのでしょう。
ただ、PCという製品は他の様々な製品に比べて、どんな人でもフルスペックを要求するソフトさえあれば簡単に限界性能を出し切れます。ですから、メーカーは細心の注意をもってカタログスペックを最大限発揮する設計を組む責任があると思います。でも、最近の製品サイクルを考えれば100%完璧なものをとも言えませんが。
戻って、自分が得られることというのは、既にPC全般に関する知識が深まったと言う点で得ているものもあるのですが、 開発されるソフトがCPUに頼りっぱなしのものばかりで、今後この機種が抱える問題が普通にでてしまう可能性を避ける方法をNECに求めることができる、ということが大部分です。
実際このサイズでこの処理能力のノートPCは中々ありませんから、できればスペックが足りないと言われるまで使い続けたいトコロです。デザインも自分のツボにはまっていますし。
反面、このシリーズのコンセプトやPR内容に対して、如何せん実際のスペックとの差に腹が立ったというのも正直なところです。
場違いな話で失礼しました。
書込番号:2453488
![]() 0点
0点
開発部からの返答がなかなかきませんね。
インテル本サイトから、モバイルPentium4-M、モバイルPentium4、PentiumMのデーターシートから熱管理の項目を拾い、英文と格闘中。
キーになる言葉は、TCC(Thermal control circuit)、Automatic Mode、On-Demando Mord、Thermal Monitor 1・2というところでしょうか。
PentiumMのリリース時期を考えると問題が在りそうですね。
どれだけの方が見ているかわかりませんが、詳細はまた後日。
明日(もう今日ですが)一休みします。
書込番号:2462381
![]() 0点
0点
3回目の返答が10日経っても来ないので、121に連絡しました。
記録には残ってたようですが、どうもほったらかしだったような反応が・・・
結局、チーフクラスと思われる詳しい方が折り返しの電話に出てきました。
質問は、ヒートスプレッダーと放熱ブロックを仲介するサーマル・インターフェイス(フェーズチェンジシート)が、60℃を超えないとその性能が保証されないものであるのに、なぜCPUコア温度で70℃で温度制御と思われるクロック制御を行なうのか。70℃ではヒートスプレッダー上(モバイルPentium4-Mは80℃上限)で実質60℃を下回ってしまい、本来の冷却性能が果たせていない。というものでした。
当然、NECも121へは詳しい情報を渡してはいないようで、サポートの方もその様な設定(パッシヴ冷却について)はやらないはずなのですが・・・と困ったようで、追加質問を加えて開発部にうかがうということとなりました。
サポートセンターから先の壁は、やはり厚いようで・・・
書込番号:2472926
![]() 0点
0点
DVDMovieWriterで、DVDの一部を編集する作業をやってみました。さすがに重い作業です。
室温25℃で30%、24℃で20〜25%、23℃で15〜17%、22℃で10%以下、1.2GHz処理といったところでした。
20℃では、以前に最終処理で引っかかるといったところでしたね。
せめて付属ソフトでは処理低下をしないレベルにしていただきたいですね。
・・・と、ここで終わるはずだったのですが、意外な現象が発生しました。
処理時間2.5時間(我ながらシツコイと思います)を過ぎた辺りで70℃に達しても処理低下が無くなりました。
初の71℃表示を見ましたが、一体どんな制御をしているのやら(回数制限?)理解できない状況です。
パッシヴ冷却温度設定も70℃のままです。
新たな謎が発生してしまいました。
書込番号:2473389
![]() 0点
0点
K県のOさん、お久しぶりです。
私には、てんでついて行けないレベルになってますね(^^。
「意外な現象」についてですが、私も一度だけ経験があります。
どんなにベンチマークを長時間回し続けてもクロックダウンが発生しないんですよね。
ただ当時はMobileMeterが無かったのでCPU温度が何度まで上がっていたのか分からないのが残念。
確か例の巨大掲示板にも同じ現象が報告されていたと思います。
私は再起動したらもとに戻ってしまいましたが…。惜しいことしたかな?
その後「意外な現象」は起こっていません。まあ本気で検証しなくなったせいもありますが…。
たまたま温度制御がうまく働かない事故のようなものだと私は解釈しています。
書込番号:2473545
![]() 0点
0点
MINIMIさん、お久しぶりです。
私もかなり意地になっていますね。その分、知識は増えてしまいました。怒りは力なりって大げさですか(笑)。
さて、今まで全工程2時間を越える処理(負荷)はしてませんでしたから、今回の現象は初めてでした。
処理低下しない現象が起きて、MovieWriter落ち直後、他のソフトで試しても70℃の壁を超えていました。
再起動後は再び70℃で1.2GHz、元に戻る。いつまでも動かしっぱなし、というわけにもいきませんしね。
不可解な現象ではありましたが、70℃を超えてから(最高72℃)の温度変化を見る限り冷却能力の低下は見られないので、パッシヴ冷却温度の設定変更で問題(主に熱暴走)はまず発生しないと確信できました。
ただ、ワンタッチボタンが結構熱くなっていましたね。
しかし、一体なんだったんでしょう・・・もう一度やるのは面倒ですし・・・
書込番号:2473774
![]() 0点
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「NEC > LaVie C LC700/6D」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 5 | 2010/09/15 1:02:00 | |
| 12 | 2008/01/27 14:45:23 | |
| 33 | 2007/11/08 10:13:42 | |
| 7 | 2007/05/02 0:58:19 | |
| 16 | 2007/02/10 1:44:19 | |
| 16 | 2006/05/16 23:34:58 | |
| 3 | 2005/10/08 20:46:29 | |
| 9 | 2005/09/15 21:04:02 | |
| 3 | 2005/08/06 15:30:06 | |
| 1 | 2005/04/19 14:57:04 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】A20?
-
【Myコレクション】30万構成
-
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
-
【欲しいものリスト】10月7日
-
【欲しいものリスト】レンズ
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
4位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
満足度4.75