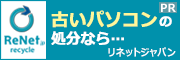このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2008年8月5日 08:22 | |
| 4 | 0 | 2008年8月4日 19:26 | |
| 5 | 17 | 2008年8月5日 02:10 | |
| 0 | 0 | 2008年7月31日 15:01 | |
| 1 | 8 | 2008年8月3日 19:10 | |
| 1 | 7 | 2008年8月2日 15:12 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
あらためて 満足です。(1回目の書込みはアンチととられたのかな)
この夏 保有3台のPCがすべて不具合になり
デスクトップ P3-800 電源死亡
ノート1 P2-450 液晶フレキ死亡
ノート2 MMX266 メイン死亡
デスクトップのCRTにノート1をつないで
せっせこデータの保存を行なっていました。
ATOMだからこのどれより快適です。
ノート1はモニターから外され共有USBハードディスクの子守り役になりました。
(200M+120M+120M+80M+40M+DVDRAM+mymio)
これで自宅では無線ストレージ状態です。(ルーターは無線対応だったので)
(必要時はVNC)
イラレ9 (CRT1400横幅もOK)と
動画(FFSADOWを適応)が快適に動くのがいいです。
あとはバッファローの交換ドライブの発売をまつのみですね。
みなさんは今後どのようなアイテムを接続されますか
私のやりたいことは
○ヨットレース結果のの洋上集計+速報送信
(これはほぼ目処が立ちました)
○USB GPSで自船の航跡収集
●船舶や車両から12Vから直接給電
端子は EIAJ3 が合うようです(ショップ購入済み)
接続ケーブルができたら再度報告いたします。
○USB端子も多くあるので
ビデオカメラからUSBハードディスクへのバックアップ
○USBワンセグ受信
などを考えています。
みなさまの今後の活用予定もお聞かせください。
なお付属のケースは電源部分に穴が開いていないのが不満ですが
ちょうどVAIO C1S用のエレコムケース(2重ファスナー)
がぴったりでこれならばしまったまま充電することが可能です。
(車の移動中に充電できます。)
ではでは
![]() 0点
0点
もし付属のケースに電源差込口が付いていたとしても、ケースに入れたまま充電すると発熱で逝きそうで怖いです。
書込番号:8170316
![]() 0点
0点
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
かれこれ10日近く使ってきましたが、もう、、、大満足です。
インストールしたソフトやディスクの空き具合、
使ってみての感想など、詳しくはブログにも書きましたが、
http://kuro277.cocolog-nifty.com/blog/
本当に
バッテリーが長持ちすること
コンパクトで、ホワイトがなかなかおしゃれ!
結構ソフトもさくさくと動いてくれる
(Web+音楽聞きながら+ワープロ等)
で、大満足です。
自宅でも、家のWi-fiにつなげば、ほんとにさくさく動いてくれます。
すっかりいまでは、XPS1210からこのEee-PCになってしまいました。
キーボードも普通に話す程度の速度では入力できますし。
いい感じです。値段的にもこれ以上高ければちょっと、、、ですが、
必要なものだけを安く手に入れることができたと思います。(満足)
![]() 4点
4点
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
静岡のZOA系列ショップで買いました
帰りの車の中で起動しかけて強制終了したのですが
家に帰ったらシステムが壊れていました。
いきなりDVDリカバーしました (絶対使わないつもりだったけど)
15分でリカバーできたので これからも頻繁にするかも
![]() 0点
0点
DVDでリカバリが楽だからといって頻繁にリカバリするとSSDの寿命を縮めるだけかと。
まぁ、リカバリは最終手段と思った方が良いかと。
書込番号:8164034
![]() 0点
0点
ひろ君ひろ君さんのスレからすみません。
LOVECOOKさん
そうなんですか?
なぜリカバリするとSSDの寿命が縮まるのですか?
物ですので消耗品ということはわかりますが
それいがいで決定的にやってはいけない理由を教えてください。
書込番号:8164172
![]() 0点
0点
リカバリは、イメージコピーされるだけだから、喩え10回リカバリしたところで、
SSDの寿命(10万回程度?)からすれば無視できる範囲でしょう。
書込番号:8164182
![]() 2点
2点
>あゆむ歩さん
SSDは読み込みが早い反面、HDDと比べると書き換え寿命が弱いのがデメリットです。
日々自分で作ったデータを更新したりという程度であれば気にならない程度ではありますが、
リカバリとなると中のデータをまっさらにして一からシステムを構築するわけです。
Windowsだけでも千個単位のファイルを一度に書き込んでいくわけですから、
そんな事を頻繁にすればどうなるかは想像つくと思いますよ。
>丸智小五郎さん
確かにSSDはそれなりの寿命ではありますが、
それはあくまで日々のファイル更新などの軽微なアクセスが続けばの話であって、
デフラグやリカバリなどはSSDにとってははっきり言って御法度と言っても良い位でしょう。
イメージをコピーすると言ってもデカいファイル1個コピーするって話ではありません。
デカいイメージの中の何千というファイルを1コ1コ書き込むのですから、
SSDにとっては無視出来る話では無いと思いますけど。
書込番号:8164357
![]() 0点
0点
LOVECOOKさん
SSDの書き換え寿命は、同一素子に対する書き換え回数で決まります。
喩え、1回に、全体として何千ファイル書き込もうが、同一の場所に繰り返され
ない限り、書き換え回数は1回だけです。
従って、リカバリ時のイメージファイルの書き込みは、それぞれの素子からすれば、
1回となるだけです。
書込番号:8164454
![]() 1点
1点
>デカいイメージの中の何千というファイルを1コ1コ書き込むのですから、
イメージファイルからのリカバリの場合は、いちいち内容をファイル単位に抽出したりしませんよ。
記録が二進数(0か1)で行われているのはご存知かと思いますが、この記録状態をセクタ単位で書き戻すので、丸智小五郎さんのおっしゃるように
>リカバリ時のイメージファイルの書き込みは、それぞれの素子からすれば、
>1回となるだけ
となります。
ただ、SSDの書き込み上限については、「素子単位での回数」ということが明言されているわけでもありません。
また、元々フラッシュメモリには、同一の素子に書き込みを集中させない仕組みがコントローラに実装されているので、ファイル単位の記録をしたからといって、その内容が同じひとつの素子に書き込まれるとも限りません。
よって実際のところは、寿命に近づくまで使い込まないとわからないでしょうね。
できるだけリカバリをしないような工夫はしたほうがベターでしょうし、かといって必要以上に書き込み上限を恐れるのもどうかと思います。
書込番号:8164848
![]() 1点
1点
少し補足しますと、
>SSDの書き換え寿命は、同一素子に対する書き換え回数で決まります。
これはカウントしていて上限を決めている、という意味ではありません。
それぞれの素子が独立して書き換え回数の寿命(バラツキがある)を持っているので、
最初にその素子の寿命を迎えたところからやられるということです。
おっしゃられるように、SSDに使用されるフラッシュメモリは元々書き換え回数に
制約があるものですので、それを前提に構成されています。
特に、ファイルの管理領域など更新頻度が高い部分は同一の素子が集中使用されない
ようになっていますし、長寿命を謳うものでは、更新頻度の高いファイルを
意図的に移動させて行くものがあります。ここらの方式は各社様々なようです。
書込番号:8165146
![]() 0点
0点
>イメージファイルからのリカバリの場合は、いちいち内容をファイル単位に抽出したりしませんよ。
元のイメージファイルはひとつでも、実際にSSDに転送する段階ではファイル単位となる筈です。
でないと、SSD側は認識できないでしょう。
一旦受け取ったファイルを、SSD側の論理で勝手に内部にアロケイトすることになります。
書込番号:8168142
![]() 0点
0点
>元のイメージファイルはひとつでも、実際にSSDに転送する段階ではファイル単位となる筈です。
>でないと、SSD側は認識できないでしょう。
はい、SSDであろうがHDDであろうが、ファイルシステムを認識しません。
システム部分まで含めて、ローレベルデータ(単純化すれば0と1の羅列)を書き込むだけです。
だからイメージファイルからのリカバリでシステム領域に不良セクタができると、システムとして読み込むことができなくなり失敗してしまうんです。
もしファイル単位でないと受け取れないとすると、そのSSDは互換性のある(ファイルのやり取り方法に一定の決まりがある)ファイルシステムしか使えないことになってしまいます。実際にはSSDはWindowsだろうがUnixだろうが使えるわけで、そんなことはありません。
>一旦受け取ったファイルを、SSD側の論理で勝手に内部にアロケイトすることになります。
これはコントローラが受け取ったデータをどこに配列するかの話で、ここに各メーカーの長寿命化・アクセス高速化(多重化)の秘密が隠れていますが、OS側から見れば、ストレージデバイスがどんな保存の仕方をしようが、きちんと保存してくれればいいわけです。
書込番号:8168473
![]() 0点
0点
そりゃー頻繁にすると言った私が悪いと言われればそれまでですが
月に1度程度のリカバーが 10万回程度予想される 素子の総合寿命まで
影響及ぼすもんなんでしょうか?
それより
布団の上で使うとか
上空1万メートルで多くの宇宙線にさらされるとかのほうが
影響が大きいんでないかい
私が言いたいのは
USB-DVDをお持ちでない方も多く購入されているそうなので
初期設定は慎重にされたほうがいい と言いたいんのです。
あぶなく使えなくなるところでしたから
書込番号:8168584
![]() 0点
0点
上空1万メートルで多くの宇宙線にさらされるような使い方をするご予定でもおありですか?
書込番号:8168844
![]() 0点
0点
HDDにせよSSDにせよ、何かとてつもなく広い、メモリ空間のようなフラットな空間があって
PC側のCPUが直接そこを自在にアクセスして読み書きしているようなイメージを持たれている
ようだが、それは違う。
HDDやSSDにはコントローラが組み込まれていて、内部は完全に本体CPUとは切り離され、独立した
閉じた管理領域となっている。CPUは直接内部にアクセスすることはできず、CPUから送られた
データは一旦バッファに入り、改めてディスク側のコントローラが独自に自分の都合で内部に
ストアするようになっている。
SSD/HDDは独立したマイコンシステムであり、バッファメモリを介して2つの別空間システムが
繋がっているという形である。
あと、繰り返しになりますが、リカバリを10回程度行ったところで、SSDの寿命からすれば
無視できるレベルです。全く恐れる必要は無いと思います。
書込番号:8168949
![]() 0点
0点
>月に1度程度のリカバーが 10万回程度予想される 素子の総合寿命まで
>影響及ぼすもんなんでしょうか?
フラッシュメモリのWikiを参照すると、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA
>フラッシュメモリは絶縁体となる酸化膜を貫通する電子が劣化させる為、消去・書き込み可能回数が限られており、少ない物では100〜300回、コントローラチップを集積して消去・書き込みが特定ブロックに集中しないように改良された物でも数万回から数百万回が限度である。
ここまで書き込み可能回数が増えたのも最近の話ですし、書き込み回数の上限なんて話はHDDではなかったことなので、ヘビーユーザであればあるほど神経質になるのです。
なお、実際に寿命を迎えたといわれているフラッシュメモリの記事があります。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080204_usb_memory_life/
こちらはUSBメモリですが、記憶装置としての動作原理や書き込み回数に上限がある点はまったく同じです。
なお、この記事のUSBメモリは、コントローラの多重アクセス制御による高速化を図っている点でSSDに近いです。寿命については特に謳われていませんが。
10万回なんて数字はあくまで想定される平均的な数字なので、実際にはそれより持つものもあれば早めにダメになってしまうものもあるでしょう。
ただ、リカバリという書き込み方法が、SSDにとって負荷の高い手法であることは確かだと考えてよいと思います。
書込番号:8168974
![]() 0点
0点
10万回という数字を何処から引いて来たのかは知らないけど、通常は保証値を示すものでしょう。
メモリチップのメーカーは、同じ技術を用いて試験用のチップを作り、そこに試験用のシステムから書き込みを繰り返して耐久性試験をしているのではないでしょうか。
SSDの形態に組んでWindowsからメモリ素子単位で10万回の書き込みをモニタした訳ではないでしょう。
書込番号:8169055
![]() 0点
0点
10万回というのは96年頃のインテルの4Mチップの仕様書に書いてあります。
この頃はお馬鹿な仕様である特定状態でバぐると
全消去(アスキースペースを2回送信)を始めて壊れるという
おっかないデバイスでしたが
私達の作った機器は破損素子の管理システムなんかは搭載していませんでしたが
市場(2万9千台稼動)で素子の破損例は報告を受けていません。
#開発途中ではフラッシュの寿命を気にする役員もいて
テストルーチンを作った覚えがありますが
ICEの数が限られており途中で打ち切ったように思います
書込番号:8169260
![]() 0点
0点
記憶をたぐると 94年末に発売した機器なので
開発していたのは94年夏だったかな
この機器はプログラムファイルの格納だけでなく
ユーザーデータ(オーディオ)の格納場所にフラッシュを用いており
ブート プログラム ユーザーデータ 1:3:12
プログラムはRAMに展開後実行
ユーザーが頻繁にデータを消去する機器でした。
ベータ機はバグ出し時に何度プログラムが飛んだことか
(94年当時はユーザーデータエリアにフラッシュを充てるなんて
チップメーカーさんもおよび腰でした。
当時は12v消去の時代なので 12vの供給 = プログラム保守 という考え
また、PCMCIAを推す SunDisk横浜のスタッフにはとてもお世話になりました。)
なんていうことは本質ではなくて
それよりも 初期セッティングは慎重にしてください という趣旨のスレです。
これ以上 しのごの言うやつがいるなら スレ著作者として
管理人にスレ削除を依頼します。
書込番号:8169860
![]() 0点
0点
他人の著作物まで勝手に削除するなよな。
そして、他人の著作の動機となった他の著作を消すのも同様。
共同作業による著作なのだから。
書込番号:8169927
![]() 1点
1点
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
EeePC901を出張時のサブノートとして購入しました。
自己責任でハードディスクを取り付けたり、バッファローの大容量SSDを取り付けたりとありますが...。
サブノートとして使うには、Cドライブ(4GBSSD)にOSを、Dドライブ(8GBSSD)にアプリケーションを、そして16GBのSDHCカードにファイルを保存するという方法は結構メリットでもあります。
というのも、出張に行く前に親機にSDHCカードを取り付け、データーをシンクロさせます。私の場合はPicasa2にためて置いた画像やPowerPointのファイルをシンクロさせています。出張の時にEeePC901に取り付けて使用すれば、親機で作成した最新のデータを出張先でも同じように扱えます。親機でデータを作成していると、結構出張の時サブノートにコピーしていないファイルがあって困ったりすることがありますが、この方法だったら簡単で確実です。
http://blog.livedoor.jp/kakurenisedora/
...たしかにUSBリンクケーブルなんかでつないでする方法もありますが、こっちのがスピードも速いし、シンプルでオススメです。
![]() 0点
0点
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
ノイズが少なくて、バッテリーの駆動時間も忘れるくらい長いEeePC901。
購入して、本当に良かったと思っています。
正直、iPhoneをほとんど買いかけていた自分がふみとどまって、こちらにして良かったと思っています。(といっても用途というか使うシーンが全然別なので、両方もてるのならそちらがいいでしょうけど、使える小遣いの都合上、このEeePC+AirEdgeしか選択できなかっただけとも、、、(^^;)
ブログの更新やネットをみながら、そこそこいい感じでお気に入りのイヤフォン(今はオーテクのATH-CK10です)を聞くことができる環境が手に入り大満足です。詳しい感想などは、
http://kuro277.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/lineouteeepc901_e018.html
にアップしています。
単なるウルトラモバイル機としてだけでなく音楽再生機器としてもラインアウト端子もついていますし、ノイズも少ないので結構つかえそうかもしれません。(^^;
![]() 1点
1点
確かにモバイルでの音楽再生環境としては理想的かも。
バッテリーの時間も保つし、プレイヤーと違ってコーデックの縛りとかも皆無だし。
私の場合はVPN接続で自宅デスクトップのiTunesライブラリを共有させて聴いてますけど、
イーモバでAACの192kbps辺りなら普通に聴けるのにはちょっと驚きました。
まぁ、さすがにロスレスはイーモバでは帯域足らずにマトモに聴けませんでしたけど、
192kbpsのAAC位なら外で聴く分には十分なので非常に満足してます。
iPodと違って容量の制約がほぼ無いんで曲選び放題ですし。
書込番号:8142006
![]() 0点
0点
>iPodと違って容量の制約がほぼ無いんで曲選び放題ですし。
iPodの方が大容量モデルがあるんじゃない?
書込番号:8143606
![]() 0点
0点
Bluetoothのヘッドホン使ってます。
ワイヤの煩わしさがなくてすごくいいですね。
聴いているのはもっぱらYahooミュージックばかりな
ので音質がどうとかは語れませんが。
前モデルのほうが音がよかったらしいので(スピーカがでかいし、
前面にあるから?)そっちも使ってみたいな。
書込番号:8144897
![]() 0点
0点
アフターショックさん、こんにちは。
無線で接続できるヘッドフォン、便利そうですね。
901X内蔵のスピーカーは、しょぼいですけど、普段使っているお気に入りの
イヤフォンやヘッドフォンを使ったとき、いままでのPCならいろんな
ノイズが入ることと、それを防ぐためにAC電源をはずしてバッテリー駆動に
したときには、すぐバッテリーが無くなってしまうことが多かったので、
今回の901Xはその面ですばらしいなあと、、思いました。
(特にオーディオテクニカのATH-CK10って高音域に敏感でサーっていう
ホワイトノイズがでやすい機種なので、結構再生する機器を選ぶんです。)
書込番号:8145328
![]() 0点
0点
>iPodの方が大容量モデルがあるんじゃない?
それ言っちゃおしまいなんですけどねぇ(笑)
まぁ、手持ちがtouchの32GBなんで今更更に大容量モデル買うのもなんだし、
何より出先でデスクトップに入ってる楽曲を入れ替えなしで気軽に聴けるのは結構楽ですよ。
あと大量な楽曲の中から検索かけるのはやっぱiTunesからの方が楽なんで。
書込番号:8146349
![]() 0点
0点
横から申し訳ございません。
LOVECOOKさんが仰っている下記の様な事をするためにはどの様にすれば良いでしょうか。。?
>何より出先でデスクトップに入ってる楽曲を入れ替えなしで気軽に聴けるのは結構楽ですよ。
自宅のPCを起動させていなくても可能でしょうか?
ちなみにあまり関係ないのかも知れませんが自宅の接続はNTTの光接続、有線LANです。
OSはXP SP3です。
外出先では本機にイーモバイルを使用致しております。
ご面倒かと思いますがもしお教え頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
書込番号:8146859
![]() 0点
0点
自宅のiTunesのライブラリを共有するのは少々厄介です。
また、自宅のiTunesのライブラリを外で聴くには家のPCが起動している上、
さらに自宅のPCでiTunesを起動させておく事が条件になります。
その辺の条件さえクリア出来れば、家のPCと本機をVPNで接続した上で、
本機と家のPCがあたかも同じネットワーク上に存在していると認識させてやれば、
家のiTunesのライブラリを外でイーモバの回線などを使って聴く事も可能っちゃ可能です。
ただし、これらを行うにはネットワーク管理の知識が必要になります。
上記の説明や用語が理解出来るようであればネットワークの構築は可能だと思いますが、
もし分からないようであれば、「hamachi」というソフトを使いさえすれば、
少々の手間でiTunesのライブラリを外で聴くことも可能です。
ただ、私自身がhamachiを使っているわけではありませんので、
hamachiの詳しい解説などはGoogleなどで検索かければ色々と出てきます。
それらのページの解説などを見て試してみると良いでしょう。
書込番号:8152005
![]() 0点
0点
ご回答ありがとうございます。
その後VPN接続を調べてみたのですが私には難し過ぎました。。(^^;
hamachiも調べさせて頂いたのですが家ではMacを使用している為ベータ版しかなく
少し厳しそうでした。
どうやらアップルのmobile meというのを使えば私にも出来そうなので
一度そちらをトライさせて頂こうと思います。
色々と有難うございましたm(__)m
書込番号:8163919
![]() 0点
0点
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
このマシンに1.8inHDDを増設する価値は非常に高いと思いますが、如何?
1.4GBの制約で余裕のなかったCドライブの空間が一気に広がる。
2.ディスクの総容量が数倍以上に拡大される。
3.アクセス速度もSSDに比べてさほど遜色がない。
4.バッテリ駆動時間低下もさして大きくない。
5.XPを含め全ての同包ソフトがそのまま使える。(Cマウントのための消去が不要)
6.60GBの大容量が相対的に安価な9千円台で手に入る。
7.ZIFケーブル1本を繋ぐだけで簡単に増設できる。
8.メインメモリを2GBに拡張しても休止領域などの問題が出ない。
9.仮想メモリ空間を既定の0から、余裕で拡張できる。
10.既設の4GB-SSDも、より高速なドライブとして活用できる。
11.5mm厚の1.8inHDDが丁度収まるスペースが最初から用意されている。
どうみても1.8inHDD前提のPCとして最初から設計されている、としか思えないw
![]() 0点
0点
EeePC買う人にとって
その辺のカスタムは遊びのひとつでしょうね
それが実用性的にどうかは人それぞれ
SSDだからこそのメリットもあるし
ZIFがおまけで付いていたというのも、EeePCならではのメリット
SSDのSLC高速タイプが32GB程度の大容量メモリが安価に入手できるようになるのが
一番幸せになれそうですが、容量がほしい人は
1.8HDDのスピンドルPCに変えてしまうのもありかと思いますよ
なんだかんだで、何度も初期化したりして遊ぶモバイルPCだし
今後も改造ネタが増えるのは楽しみの一つですね
用途に合わせて、複数のOSを手軽に持ち運べるのも楽しそうですし
書込番号:8136224
![]() 0点
0点
バッファローからD:ドライブ差し替えのSSDモジュールが発売されるようです。
簡単に容量upできるようになるのはうれしいのですが、値段がどうなるか。。。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0724/buffalo1.htm
今年はSSDのバイト単価が大幅に下がることを期待します。
書込番号:8136478
![]() 1点
1点
Dドライブ用ですか。容量的には十分でしょうが価格がHDDに比べてどの程度に
なるかですね。。
これが、Cドライブ用だと一気に利便性が高まるのですが、高速版だとただで
さえ高価なSSDが、更に手の届かない所へいってしまうのでしょうね。
あと、改造ネタとしては、昔ならディスク換装とくれば次はクロックアップと
相場が決まっていたのですが、このマシンではちょいと難しいでしょうね。
書込番号:8136714
![]() 0点
0点
SSDをHDDに換装すると、衝撃に強いと言うEeePCの利点が損なわれそうな気がします。
確かに興味はありますが、今はBuffaloの換装用大容量SSDの発売待ちしてます。
本当はCの換装用SSD(SLCタイプ)がD用のSSD並みの価格で出てくれれば言う事ないんですけどね。
書込番号:8157285
![]() 0点
0点
Cドライブの容量問題が解消するのは魅力的ですが…
>4.バッテリ駆動時間低下もさして大きくない。
んー、微妙?
EeePC 901-Xが他社よりも圧倒的にバッテリーでの稼働時間が長いのは、機械
的な駆動装置を持たないSSDとASUS独自の省電力システムの存在が大きいので、
やはりCドライブのHDD化は省電力に不利なのではないでしょうか。
(バッテリーの持ちを重視しないなら、無視して良い問題だと思いますが)
>7.ZIFケーブル1本を繋ぐだけで簡単に増設できる。
動作確認の取れている1.8インチHDDとZIFケーブルの種類は今のところ限られ
ており、改造にあたる行為を『簡単』とは呼べません。
SO-DIMMのメモリ交換レベルの作業とは危険度も難易度も違います。
>11.5mm厚の1.8inHDDが丁度収まるスペースが最初から用意されている。
DドライブのSSDを取り外さないとHDDが入りません。
あと1.8インチHDDはSSDと比較して相当量の熱を発生すると思われますが、SSD
で使用することを前提に設計されている901-Xの筐体にどれほどの冷却性能が
あるか未知数です。
冷却性能がHDDの熱発生量に追いつかず、PC底面やキーボードもかなり熱を帯
びることが予想されます。
EeePCにも海外ではHDD搭載モデルがありますが、筐体が900,901よりも大きく、
HDDの発生熱にも対応した冷却性能がたぶんあるのではないでしょうか。
それと比較すると、901-XではHDD搭載が可能であっても、あまり一般ユーザー
にはお勧めできませんね。
改造の趣味がある人にとっては良いオモチャですが(笑)
書込番号:8157609
![]() 0点
0点
さすがにSSDと1.8インチHDDと比較してアクセス速度が遜色無いってのは無理があるでしょ。
いかに遅いSSDと言えどそこはSSD、1.8インチHDDよかアクセス速度は全然マシ。
試しに手持ちの1.8インチHDD積んでベンチなり試してはみましたけど、
SSDと比べて3割ほど数値的にも性能落ちてたし、
全体的な動作ももっさりだったし。
まぁ、HDDにすりゃSSDと比べて書き込み速度は速いし、
外でデジカメのデータ入れたり出したりとかっていうならHDD積む価値はあるけど、
テキストデータとかデータ量少なくてすむならあえて1.8インチHDD積む理由は無いですわ。
仮に動画とか大量に持つならいっそ必要な時にポータブルHDDでも持った方が良い。
そこまでするとコンパクトなEeePCの存在意義に関わる気もするけど(笑)
まぁ、最近ポータブルHDDもかなりコンパクトで価格も手ごろだし、
あえて内蔵にこだわらないなら遅い1.8インチより速い2.5インチ積んだポータブルかと。
書込番号:8158580
![]() 0点
0点
>やはりCドライブのHDD化は省電力に不利なのではないでしょうか。
>さすがにSSDと1.8インチHDDと比較してアクセス速度が遜色無いってのは無理があるでしょ。
この辺は実際に1.8インチHDDを使わないときちんとした結果は出ません。
私の環境では1.8インチHDDを搭載して4時間使えますし、起動時間は別として動作速度に関しては遜色ありません。もちろん用途が簡単な文書作成やWebアクセス等に限定され、画像処理やエンコードなどは行わないことが前提での話ですが。
ただしHDDの機種に関しては、東芝MK6028GAL/MK8025GALを使った場合の話として限定してもいいと思います。
1.8インチで80GBを実現したこの世代のHDDが、30GB前後しかなかった従来のHDDより速いのは当然だし、従来の世代のHDDしか使っていなかった人が先入観を持つのも当然でしょう。
SSDだって、元はフラッシュメモリ。フラッシュメモリは元々HDDよりも遅い欠点があるといわれていたものです。これにコントローラや多重アクセスなどの改善を加えて今のSSDがあります。別の視点から言えば、こうした性能アップのための回路を省いた低価格フラッシュメモリ製品とも両立しているわけです。
すなわち単純にSSDだから1.8インチHDDだからといって速い遅いと決め付けることはできなくなってきているのです。
発熱に関しては美玖さんのおっしゃる通りで、私の場合はシリコンゲルシートにくるんで装着しているわけですが、熱の逃げ場は熱伝導用と思われるアルミシートが予め張ってある裏蓋に集中するようで、ディスクアクセスが多いと裏蓋はかなりの熱を持ちます。
この点は覚悟して増設すべきでしょう。
書込番号:8158863
![]() 0点
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】PC構成20251031
-
【欲しいものリスト】メインPC再構成
-
【Myコレクション】自作構成
-
【欲しいものリスト】pcケース
-
【欲しいものリスト】2025PC構成2
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
4位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
満足度4.75