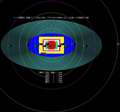AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
����ɋ߂���p46�x�Ŏ��R�ȕ`�ʂ��\�ȕW�������Y�i�ŒZ�B�e����0.45m�j�B���i��63,000�~�i�ō��j
����
�ň����i(�ō�)�F
¥17,000 (20���i)
�����Y�^�C�v�F�P�œ_ �œ_�����F50mm �ő�ax�����F73.5x54mm �d�ʁF280g �Ή��}�E���g�F�j�R��F�}�E���g�n �t���T�C�Y�Ή��F��
![]()

-
- �����Y 654��
- �P�œ_�����Y 355��
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G�j�R��
�ň����i(�ō�)�F¥55,800
(�O�T��F-200�~��![]() )
�������F2008�N12�� 5��
)
�������F2008�N12�� 5��
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G �̃N�`�R�~�f����
�i367���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S18�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 191 | 108 | 2018�N7��4�� 21:59 | |
| 4 | 6 | 2017�N11��16�� 06:29 | |
| 88 | 38 | 2017�N11��2�� 00:18 | |
| 38 | 5 | 2013�N10��14�� 04:15 | |
| 10 | 5 | 2012�N4��8�� 00:20 | |
| 1 | 2 | 2012�N2��3�� 20:03 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�����Y > �j�R�� > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
�̂���̃M�����ł�(´�_�`)
�Ȃ��A50�~�����W�������Y�Ȃ�ł��傤���H
��͂胉�C�J��50�~�����ŏ��ɂ�������Ȃ�ł��傤���H�H
�����ԍ��F19921474�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�l�Ԃ̖ڂŌ����Ă���͈͂��A�J�����̃t���T�C�Y�ł��悻�T�O�����̃����Y��t�����Ƃ������炾�ƕ��������Ƃ�����܂�
�����ԍ��F19921485
![]() 9�_
9�_
tmc393310���� ����ɂ���
50mm����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��@�t���T�C�Y��50mm�̉�p���@�l�Ԃ̌��Ă����p�ɋ߂����ߕW�������Y�Ƃ����Ă���Ǝv���܂��B
���ׁ̈@AOS-C�T�C�Y�ł�30mm�O��@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̏ꍇ�́@25mm�O��Ɓ@�Z���T�[�T�C�Y�ɂ��W�������Y�͕ς���Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19921486
![]() 11�_
11�_
�W�������Y�Ƃ́A�ŁA�������ĉ������B
�m�肽������������Ǝv���܂���B
��\�I�Ȑ��͂����炩����݂����ł��B
�����ԍ��F19921511
![]() 9�_
9�_
����ɂ���
��̓�l�Ɠ��ӌ��ł��A�l�Ԃ̎��p����35mm�t���T�C�Y�t�B�������ォ��p����Ă���ƕ����Ă��܂��B
�l�ɂ�莋�p�ɂ͌l�������邩�Ǝv���܂��̂ŁA�����܂ł������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ʏ̂ł��傤�B
�܂�50mm���L�p�������ꍇ�̃��K�~�����Ȃ����ƁA�]���ł̉��ߊ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ȃǂ������A
���R�ȉ��ߊ��������邱�Ƃ����R�̈�ł��傤�B
�����ԍ��F19921526
![]() 4�_
4�_
���̓��C�J��50mm�t���Ĕ����Ă���������x�����܂�;^_^A
�L���m���̓��C�J�̃R�s�[�A�j�R���͂��̃����Y��50mm�ō���Ă܂����B
�����ԍ��F19921532�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���C�J��50mm��t��������
����͐���
���R�Ɍ������p������
�������R�Ɍ������p�͂��������L���ƌ����Ă���
��ʂ̑Ίp���̋��������肪���R�Ɍ�����͈͂Ƃ̐�������
(�t���T�C�Y�Ŗ�43mm)
���R�Ɍ�����
������
�l�ɂ���ĈႤ
35mm(����)���ǂ��ƌ�����������
�����ԍ��F19921540�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 9�_
9�_
�������j�R����web�œǂ��Ƃ�����܂���
�l�Ԃ̎���Ɉ�ԋ߂��ƌ����Ă���̂�55mm�i35mm���Z�j�t�߂��W���ƌĂ�Ă���悤�ł�
���܂Ɂu�ŋ߂͕W�������Y��35mm�ɂȂ����v�ƌ����������܂���
�W�������Y��55mm�t�߂ŕς�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��B�i���R�ł����j
�����ԍ��F19921546
![]() 7�_
7�_
�@
�@�≖�i�t�B�����J�����j���ォ�炠��b�ł��B���܂ł̓t���T�C�Y�̃f�W�^���J�����ɓ��Ă͂܂�̂ł��傤���c�B
�@�����A50mm�`55mm���炢�̏œ_�����̃����Y��W�������Y�Ə̂���������傫�ȗ��R�́A���̃����Y��t���ăt�@�C���_�[��`�����Ƃ��Ɍ����鑜�̑傫��������Œ��ڌ����Ƃ��̑��̑傫���ƁA�قړ������炢�Ɍ����邩��ł��B
�����ԍ��F19921548
![]() 16�_
16�_
�������������̎��A���Ȃ炸��p���l�̖ڂƓ����A�Əo�Ă��܂����A���ۂɖڂ̉�p��50mm�����Y�Ƃ��Ȃ���������A
���̐l�͎��싷��ŁA�Ȃ���ςȕa�C�ł���ˁB�����a�@�s���������ǂ������B
�����ԍ��F19921553
![]() 15�_
15�_
�F��������悤�ɁA
35�o���ł̎g�p�ɂ�����50�o�̏œ_�������l�Ԃ̖ڂ̉�p�ɋ߂�����ł��ˁB
�����悤�ȊȒP�Ȑ��������ł����c
��
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/lensknowledge/howto_select/
������Normal�̕������N���b�N���Ă݂Ă��������B
���Ȃ݂�
APS-C�̃{�f�B�ɕt����ꍇ�́A35�o�O��̃����Y�ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F19921555
![]() 2�_
2�_
���炷�P�Q�R����
���A���Ȃ炸��p���l�̖ڂƓ����A�Əo�Ă��܂����A���ۂɖڂ̉�p��50mm�����Y�Ƃ��Ȃ���������A
��p�ł́@�ԈႢ�₷���ł��ˁ@���ߊ��Ƃ������ق����@�����Ă��邩������܂���B
�����ԍ��F19921567
![]() 8�_
8�_
�̂��猾���Ă��鎖������A�����Ȑ�������܂���˂��B
�����A�l�Ԃ̉�p�ɋ߂����R�ȕ`�ʂ����邩��ƈȑO���畷���y��ł��܂��B
�܂����ۂɂ́A�l�Ԃ̖ڂ͂����ƍL�������Ă���͂��ł����ǂˁB
���ۂɕW���P�œ_�����Y���g���Ă݂�ƁA
�c�݂������A�֒��������A���������R�ȕ`�ʂ�����Ȃ��B�Ɗ����Ă��܂��B
���������Ɖ��̓������Ȃ��Ƃ������ł����i�j
���Ζ]�����ɁA�ނ��L�p���Ɏʂ�Ƃ�����܂߁A�W���ƌĂ�鏊�Ȃ�������܂���B
�����ԍ��F19921574
![]() 0�_
0�_
�@
�@��p�ƌ����ƌ���������₷���Ǝv���܂���B����i���E�j�̍L���ł͂Ȃ��A�ڂ̑O�ɂ��鑜�i��ʑ́j�����Œ��ڌ����Ƃ��ƃt�@�C���_�[��ʂ��Č����Ƃ��ɁA�قړ�����p�ɂȂ�A���Ă��Ƃł��B
�@���������������ƁA��ʑ̂����Œ��ڌ����Ƃ��ƃt�@�C���_�[��ʂ��Č����Ƃ��ƂŁA�قړ����傫���Ɍ�����A���Ă��ƂɂȂ�A�t�@�C���_�[��ʂ��Č��Ă����R�ȑ傫���Ɋ������ł��B�قړ����傫���Ɍ�������Ă��Ƃ́A���������������Ă��Ƃł��B
�����ԍ��F19921598
![]() 15�_
15�_
����ɂ��́�
�����F�X�����ł����ǁE�E�E
1�j����Ō���i�F�́u�p�[�X�y�N�e�B�u�i���ߊ��j�v�ɋ߂����o�Ŏʐ^�Ɏʂ�B
�T�ˁE�E��������p�i��p�j��45°�ʂŕ`���������}�@�i���ߖ@�j�ŕ`�����G��E�E�E������p45°���x�B�e���ꂽ�ʐ^���A�����Ƃ�����̉��ߊ��ɋ߂��B�B�B
�܂�E�E�E�l�p���z������̑O�ɒu���āE�E�E���̊z���̒���`�����i�F�Ƃقړ����l�Ɏʂ�B�B�B
35mm�t�B�����t�H�[�}�b�g�i135���A���C�J���A�t���T�C�Y�j�̃J�����ŎB�e���āE�E�E�����̗l�Ȏʐ^���B��郌���Y�B�B�B
���ꂪ�œ_����50mm�ƌ����킯�ł��B
2�j���C�J���A�u���́v�œ_����50mm�A�@���œ_����51.6mm�̃����Y���u�W�������Y�i��j�v�ƒ�߂��B�B�B
�{���E�E�E���C�J���i35mm�t�B�����t�H�[�}�b�g��36.0��24.0mm�j�ŁA�O�q�̐�����p�i�Ίp���������ȁH�H�i�O�O�G�G�G�j�j45°�̃p�[�X�y�N�e�B�u���u���m�Ɂv���邽�߂ɂ́E�E�E36.0��24.0mm�̑Ίp����43.3mm�̏œ_�����łȂ���Ȃ�܂��B�B�B
���̃��C�J�̋K�����A�L���ƊE�ɍL�܂������߁E�E�E���̏œ_����50mm�̃����Y���u�W�������Y�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B
35mm�t�B�����t�H�[�}�b�g�p�i�t���T�C�Y�j�̃J�����ȊO�ɁE�E�E��̓I�ɏœ_��������mm���u�W�������Y�v�ƌĂԃ����Y�͑��݂��Ȃ��Ǝv���܂��i�O�O�G�G�G
�����̊��K�P���āE�E�E���t�n�̃J�����ł̓Y�[�������Y�ł�������p45°�𒆐S�ɍL�p���Ɩ]�������J�o�[���郌���Y���u�W���Y�[���v�ƌĂ�ł��܂��i�O�O�G�G�G
3�j���`�f�W�^���J�����ȑO�̊ԁE�E�E�ʐ^�ƌ������C�J�����u35mm�t�B�����J�����v�ŎB�e������̂Łi��ʑ�O�^���Ԑl�j�B�B�B
���̎��̖��c�����݂ł��c���Ă���ƌ������ł���
�Ȃ̂ŁE�E�E35mm�t�B�����t�H�[�}�b�g�ł͂Ȃ��A�R���f�W��t�H�[�T�[�Y�AAPS-C�t�H�[�}�b�g�J�����ɂ́u�W�������Y�v�ƌ����̂͑��݂��܂���i�O�O�G�G�G
���u�W���Y�[�������Y�v���Ă̂͂���܂���
���Q�l�܂Ł�
�����ԍ��F19921609
![]() 4�_
4�_
wiki�ł���
�W�������Y�Ƃ�
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA
�������
�y�W���z�Ƃ�
1.��ʂ̂���ׂ��p���������̂Ƃ��ẮA���肩���B
2.���ǂ���ƂȂ�ڂ��āB
3.�����ʂ̒��x�i�ɂ��Ȃ����Ɓj�B
�悤�̓��[�J�[���̗����Łu�W�������Y�v�Ƃ��A�����̐l�����ɔF�����ꂽ�������Ǝv���Ă܂��B
�W�������Y�Ƃ������肪�Ȃ��Ɩ]�������Y��L�p�����Y�Ƃ����\�����o���܂��� ^^
�|�b�v�X�Ƃ́H���b�N�Ƃ́H
�Ɠ����ł��B
���̐��E�̐l���������߂čL�߂����Ƃ���`�ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F19921643
![]() 2�_
2�_
���C�J��50�o�̓��C�J������Ɍ��߂����̂ł��B
���̂��߃��[�U�[����50�o�d����M3�͖]�����C�J�B35�o�d����M2�͕W�����C�J�ƌĂ�Ă��܂����B
���R�Ɍ�����œ_�����̓Z���T�[�̑Ίp�����ƃ��[�J�[�͍l���Ă��܂��B
���������Ӗ���43�o���o�����y���^�b�N�X�͗ǐS�I���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19921645�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�l�����̎ʐ^�����鎞�̉�p�ɋ߂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B
�l�������Ă��鎋��p�͂��Ȃ�L���ł����A���i�Ƃ��Č��Ă���͈͂ł����Z28mm���炢�͂��邩�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19921653�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���R�Ɍ������p�ɂ��Ď��������Ƃ�����܂��B
Aps-c��50mm��t���ė��ڂ��J���Ă݂�Ɩʔ����ł���B���R�Ɍ����ĎB��₷���ł��B
�l�ɂ���č�������̂ł����ˁH�����Ă݂ĉ������B
�����ԍ��F19921658�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�̂̓p�[�X�I�ɂ�85mm�̕����l�̊�ɋ߂��Ȃ�Ęb������܂����ˁB
������|�[�g���[�g�����Y�Ȃ�Č����Ă܂������B
���ہA50mm�g���₷����ł���ˁB
���ł����W���Y�[����������O�̗l�ɂ��邯�ǁB
�͔̂����Ȃ������ȁB
35�`70mm�����y���o�����̂���80�N��㔼����Ȃ����������H
50mm�͂����{�ʼn��ł��B���Ƃ��������������ȁB
���������Ӗ��ł͕W�������Y�Ƃ������邩���ˁB
���͕ʂɂ��āB
�����ԍ��F19921660�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��tmc393310����
���C�J��35mm�ł�50mm��^���āA���{�����̃��[�J�[�ł��̗p�������Ǝv���܂��B
���̃t���T�C�Y�@�́A���̋K�i���x�[�X�ɂ��Ă��܂��ˁB
�f�W�^�������ꂽ�����́A�Z���T�[�̃R�X�g���|����̂ŁAAPS-C��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ȃǂ����܂�ė��܂����B
APS-C�́A�L���m���̃Z���T�[��������Ə�������1.6�{�ŁA�L���m���ȊO��1.5�{�̂悤�ł��B
APS-C�̃L���m���̏ꍇ31mm�A�L���m���ȊO�̏ꍇ33mm��50mm�����ɂȂ�܂��B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A25mm��50mm�����ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F19921689
![]() 2�_
2�_
�܂��A�i���Z�j50mm�Ƃ������Ίp��p47�x�Ƃ������ق����q�ϐ�������ł��傤�ˁB
���l�Ԃ̖ڂŌ����Ă���͈͂��A�J�����̃t���T�C�Y�ł��悻�T�O�����̃����Y��t�����Ƃ������炾��
�����A�̂��炠�������ɂ���Ȃ��Ƃ������Ă���܂��B�������A�u�l�Ԃ̎����35mm�ɋ߂��v�u�l�̋Î��p��85mm�v�ȂǂƁA����ȊO�ɂ����낢��u�����v������܂��B
�ł��A����Ȃ��́A�ЂƂ��ꂼ�ꂾ���A�����l�ł��ɂ���ĕω�����̂ł������ĈӖ��͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�Ȃ����Ƃ����ƁA�ʐ^���͂��߂Ă��Ȃ�̊ԁi10�N�Ƃ��j50mm���������藈���g���ɂ��������Ƃ����o�������邩��ł��B
������ɁA50mm���W�������Y�Ƃ��č̗p����Ă����i�ŋ߂̓Y�[����̂ł����łȂ��Ȃ����j�̂́A�����Y�����������Ƃ��������Ă���Ǝv���܂��B�����������50mm�ł͂Ȃ��A40�`60mm�Ƃ�35�`70mm�����^�Ŗ��邢�����Y�����₷���B
�����A60mm�ɂ��Ȃ�Ɩ��炩�ɉ�p�������������܂��B�Ȃ̂�50�`55mm���̗p�����̂ł��傤�B�����Ƃ��A���̑O��Ƃ��āA�����Y�����ł��邱�Ƃ����肻���ŁA�����Y�Œ�@���ƁA�ނ���35�`40mm���炢���W���ɂȂ��Ă�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19921721
![]() 0�_
0�_
���̃t�H�[�}�b�g�͑Ίp�����W�������Y���ۂ���ł����A�Ȃ�35mm�ł�43mm�łȂ�50mm�Ȃ�ł��傤���H�H
�Q�l
6���U�Ίp���V�W�D�S���� �W��80����
�U���V�Ίp���W�X���� �W��90����
�U���X�Ίp��101���� �W��100����
�S���T���Ίp��154���� �W��150����
�����ԍ��F19921758�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�}�b�N�X�E�x���N�͍����������Ă͂��߂ĕt�������Y��50mm�Ƃ��Ă���͂��c(´�_�`)
�����ԍ��F19921766�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�m���ɃX�y�V�����r�[������̌����ʂ�ŁA
�W���������Ă̖]����L�p�Ȃ�ł����A�Ȃ�ł��̕W����50mm�Ȃ�ł��傤�ˁ`�`(´�_�`)
�����ԍ��F19921771�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�W���ƌ����Ă���������܂��B�S�O�������W���B�U�O�������W���B
�܂��A�L�p�łȂ��A�]���ł��Ȃ������肪�W���ł��傤�B
�p��ł�standard lens�����łȂ�normal lens�Ƃ����\��������܂��ˁB
�����ԍ��F19921776
![]() 1�_
1�_
>�Ȃ�ł��̕W����50mm�Ȃ�ł��傤�ˁ`�`
��l����������B
�����ԍ��F19921788
![]() 2�_
2�_
40-43-60���A50���L������������Ƃ��A���܂�ׂ����l���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
���F�ʏ̂ł��傤����B
�����ԍ��F19921796
![]() 2�_
2�_
���Ȃ�ł��̕W����50mm�Ȃ�ł��傤�ˁ`�`(´�_�`)
wiki��
�����C�J�̊���@�u�ƊE�W���Ƃ��Ē蒅�v�@�������̏œ_����50mm���œ_����51.6mm�ł���B
�悤�́A���ꂪ�L�܂������Ęb���ƁB
�����A���ɂ���ɑR�H���đ����[�J�[���W�Tmm�ŕW�������Y�Ƃ��ďo���āA���ꂪ���E�I�ɍL�܂��85�������W�������Y�Ƃ��Ē蒅���������m��܂����B
�����ԍ��F19921815
![]() 1�_
1�_
�����̃��C�J�̋Z�p�ҁi�W�ҁj�݂̂��m�闝�R�B
�����ԍ��F19921826
![]() 0�_
0�_
�l�Ԃ̎���p�ɂ��Ă���������悤�ŁA50mm������蒷�����낤�Ƃ��B
�܂���l���A���ꂪ�W���œ_�ł��ƌ��߂đ���E�d�l���߂̊�ɂ����̂ŁB
�����ԍ��F19921830
![]() 2�_
2�_
>�Ȃ�35mm�ł�43mm�łȂ�50mm�Ȃ�ł��傤���H�H
�����̃��C�J�̗͂��������������������ꂽ�B
���g���Ă���sRGB�����ăR�_�b�N�AHP�A�}�C�N���\�t�g�������i�߂������B
aps�����đ��5�Ђ��������悾���B
�͂̂��鏊��������͎̂d���Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F19921832�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��tmc393310����
�̂́A50mm�̑��ɁA40mm�E43mm(�Ίp���I�ɂ͕W��)�E45mm�E55mm�E58mm�����݂�������������܂����B
�ł��A���݂�40mm�A43mm�A55mm�A58mm��W�������Y�Ƃ��Ĕ������Ă��邩�Ǝv���܂��B
�t�����W�o�b�N�̒�����}�E���g�a�̑傫���ɂ��v��̐�������邩�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19921854
![]() 1�_
1�_
���̐́A�����̐l���g���Ղ��œ_������
��������40�`50�o���炢����������B
�V���b�^�[�X�s�[�h�\�L�̂悤��
������Ղ���̗ǂ��������ǂ������Ǝv���B
�����ԍ��F19921877�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2L���x�̃v�����g���ӏ܂���ۂ́u�ӏ܉�p�v�ɋ߂��u�B�e��p�v��I������Ɖ��ߊ������R�Ɋ����邩�炻�́u�B�e��p�v�̏œ_�����̃����Y��W�������Y�ƌĂ�ł��܂��B
�ߋ��̃X���b�h�ł̎����̓��e�ւ̃����N�ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=14760463/#14762368
�����ԍ��F19921890
![]() 2�_
2�_
�������Ă��闝�R�͌�t���ŁA�u�P�Ɉ�������v�Ƃ������̋Z�p�ł́u���₷����������v�����m��܂����i�j
���ƂȂ��Ắu�킩��Ȃ��v�����������B
�����ԍ��F19921900
![]() 7�_
7�_
tmc393310���� �ԐM���肪�Ƃ��������܂�
�����̃t�H�[�}�b�g�͑Ίp�����W�������Y���ۂ���ł����A�Ȃ�35mm�ł�43mm�łȂ�50mm�Ȃ�ł��傤���H�H
���50mm�ߕӂ��W�������Y�Ƃ��������Ǝv���܂��B
���ہ@�O�ɂ�����܂����@�y���^�b�N�X��43mm��j�R����58mm���W���ł����@�}�~����RB6×7��90mm��127mm�W���Ƃ��ă����Y�Z�b�g�Ŕ����Ă��܂������B
�ł����C�J�̏ꍇ�@�����W�t�@�C���_�[������܂��̂Ł@������œ_�����ウ��Ɓ@�t���[��������Ȃ��Ȃ�@�O�t���̃t�@�C���_�[�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��̂œ�������B
���C�JCL��40mm�o������������܂������@�Z�����܂��@�y���^�b�N�X��43mm���C�J�}�E���g�ŏo���������@�O�t���t�@�C���_�[�̂��߁@�Ȃ��Ȃ��ɐ�ɂȂ�Ȃ������@�L��������܂��B
�����ԍ��F19921938
![]() 0�_
0�_
���w�I�Ɂ@���f�@�̃����Y�\�������炶��Ȃ��́H
���C�J���ł́@�S�T�`�T�Tmm�t�߂́B
�����ԍ��F19921948
![]() 0�_
0�_
��tmc393310����
�]�k�ł����̂̃J�����̃J�^���O�ɂ�50�~����t�����J�b�g�����Ȃ炸�������悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F19921953�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
������
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/637508.html
�u1914�N�A�G�����X�g�E���C�c�Ђ̃I�X�J�[�E�o���i�b�N�́A35mm���J�������J�����܂����B�E���E���C�J�ł��v
�u���C�J�͏��^�Ōy�ʁB�������唻�J�����Ɠ��������Y�̉�p�ɂ���ƁA�œ_�����͒Z���Ȃ�܂��B���̂��ߔ�ʊE�[�x���[���Ȃ邽�߁A�i����J���đ����V���b�^�[���x�������܂��B�������ŃV���b�^�[�`�����X���d�������ʐ^���\�ɂȂ�܂����v
�Ƃ���܂��悖
�����ԍ��F19922012
![]() 2�_
2�_
���̑唻�J�������ˁB
�����ԍ��F19922019
![]() 0�_
0�_
�J�������C���`�̍��Ő��܂�Ă���A�[���ɂȂ��Ă������B
50�ɂ��������Ӗ��͂Ȃ��̂ł́B
�L�����ǂ������Ă����ŁB
�Ȃ�ŕW���O��1435mm�Ȃ́H
�݂����Ȃ��̂ł́B
�����ԍ��F19922029�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����A�Ⴄ���E�E�E
�P�ɓ�����p��������i����J���đ����V���b�^�[���x����������Ęb���E�E�E
�����ԍ��F19922034
![]() 0�_
0�_
���l�Ƙb���Ƃ��́A���ʂ̃��m�T�V�̃t���T�C�Y50mm���W�������Y�B
(����܂�����������Ȃ���)
�����I�ɂ͒P�ɋC�ɓ����Ă��邩��
30mm(35mm���Z��45mm)���u�W���v�����Y�B
�����܂Ŏ��������ɒʗp���鎄�I���m�T�V�B
�߂�ǂ��̂ł��܂�������Ȃ��B
���I��(���p���Ղ��Ƃ����Ӗ��ł�)�u�W���v�����Y�̃��m�T�V�͊e����������Ă���Ǝv���܂��B
��ʘ_��b���Ƃ���50mn���W�������Y�B
�����A46mm�̘b�A���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F19922049�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����A46mm�łȂ�43mm�̘b�ł����B
�ԈႢ�܂����B
45mm�̘b�����肪�Ƃ��������܂��B(o^^o)
�����ԍ��F19922085�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�M�u�A�b�v�B
���܂ŋC�ɂ����Ă��܂���ł��������ɂȂ�܂����B
�ǂ����50�����ɂ������R���`�����Ă��Ȃ��悤�ł���B
�}�b�N�X�E�x���N�ƃI�X�J�[�E�o���i�b�N����ɂ����킩��Ȃ��E�E�E
���̌��_�B
����ς�@���ƂȂ��Ă͂킩��Ȃ��@�ł��B
�����ԍ��F19922117
![]() 1�_
1�_
���łɒ�����唻�t�B�����̏ꍇ�ɂ��Ẵ��X������܂������A
�u�t�B������(�L����)�̑Ίp�����v�O��
���y���C�J�ȑO�z�́u�W���v�������悤�ł��ˁB
���́u���C�J�ŕW���v�́A����Ƃ����ߊ����ǂ��̂Ƃ��������A
�z�肵���ʐ^�T�C�Y�ƊϏ܋��������đz�莋�͂Ɠ����̃t�B�����̉𑜗͂���t�Z�������ʂȂǂ���œ_����50mm�Ƃ����|���A
�u�N�������Ȃ��������C�J����v
�ɏڂ����L�q����Ă��܂����B
���C�J���o��̍��́A�唻�Ȃǂ��u�ʐ^�B�e�@�Ƃ��ĕW���I�v�ł������킯�ŁA
����Ɣ�ׂ�ƃ��C�J���Ȃǂ́u���^�J�����v�́A
���傤�nj��݃t���T�C�Y�̃f�W�C�`������Ă�����X����u(������)�R���f�W�v�����Ăǂ��������H
�݂����Ȉʒu�t���������悤�Ɏv���܂��B
������A�u�掿�̗�邨��y�J�����v����A
�u�Ϗ܂ɑς�����𑜗͂����J�����v�Ƃ��Đv����ߒ��ŁA��L�̂悤�Ɂu�K�v�ȉ𑜗͂�z�肵���v���Ǝ��̂ɂ��傫�ȉ��l����������������܂���B
�Ȃ��A�t�B�����𑜗͈ȑO�ɁA���͂Ɖ�p����u�ʂƂ��Ă̕���\�v���v�Z����܂��B
(�ȉ��́u�N�������Ȃ������E�E�E�v�ł͂Ȃ��ĕʂ̏��Ђ������Ǝv���܂�)
���s�n�C�r�W�����ł́A����1.0�Ɓu������3H(��ʍ����̂R�{)�v�ɋ߂���������1920x1080��207��(��f)���d�l�Ƃ������Ƃ������m�̕��͑����Ǝv���܂����A
���C�J�ł͎���0.5�z���(����ɁA��������p���A�X�y�N�g����قȂ邯���)�u100���v�ȏ�ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ�������Ă����Ǝv���܂��B
�����e�����~�a��0.0333mm�̏ꍇ�A�Ίp������43.267�ɑ��Ė�1300�A������A�X�y�N�g��3:2�̖ʂƂ��ẮA��78���ɂȂ�܂��̂ŁA���̔�r�̏�ł��u�����v�Ƃ��Ă͌��\�Ȏv�����肪�K�v�������̂�������܂���B
�����ԍ��F19922186�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���C�J�����قɂ���E�A�E���C�J�ɂ́c42�~�������Ă���c
�Ɓu�_�����C�J�鍑�̔閧�v�ɂ͂��������Ă��܂��B
������킴�킴50mm�̃����Y������āA��X�̃��C�J�ɕt���Ĕ���o�����̂��A�N�Z���m�Ƃ݂Ă܂��B
�����ԍ��F19922190�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���l�Ƃ��Ă͕W������ʂ�����u(������W���Ƃ���)�蒅����ߒ��v�̂ق����C�ɂȂ�̂ł����A�u50�vmm�Ƃ����y�L���̂悢�����z�Ƃ��A�����(������Ȃ��H)�Ƃ���̖������傫�����������H
�����唻�⒆���Ɠ��l�ɑΊp�������炢�́u43�vmm��������A�߂����l�Ō��\�o�����Ă�����������܂����(^^;
�����ԍ��F19922218�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���肪�Ƃ��A���E����
���z�肵���ʐ^�T�C�Y�ƊϏ܋��������đz�莋�͂Ɠ����̃t�B�����̉𑜗͂���t�Z�������ʂȂǂ���œ_����50mm�Ƃ���
�킩��悤�Ȃ킩��Ȃ��悤�ȁH�H
���̓��ł͖����ł��E�E�E
���z�肵���ʐ^�T�C�Y�ƊϏ܋��������đz�莋��
�ӂ�ӂ�
�������̃t�B�����̉𑜗͂���t�Z�������ʏœ_����50mm
�Ȃ�ŁH
�����̋Z�p�ł�43�������50�����̕����𑜗͂���ɂł���Ƃ������ƁH
����������ʑ̂͐l�ōl���Ă���̂ł��傤���H
�����ԍ��F19922336
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
�������ڂ����悤�ł���(^^)
�����Y��l�Ԃ̊�ƌ����āA���͂�0.5�z��͎��p2���ɑ������A2���̊p�����ސ�^�̗��[�̐����������Ă����āA�����̃t�C�����̊������܂̌����̒��a��30����1�~���A�܂苖�e�����~0.03mm�����Ƃ��ĕ������ޒ�����50mm�̂悤�Ȃ��Ƃ��A�u�_�����C�J�鍑�̔閧�v��44�y�[�W�ɏ����Ă���܂��B
�ƂȂ�܂��ƁA�𑜗͂���݂āA35�~����43�~�������肾�Ɠ����̃t�C�����̊������܂���݂Ė������Ɗ����āA���p2���Ƃ����O���u��50�~���Ƃ����A�Ƃ킽���͗������Ă��܂��B
�m���ɁAhttp://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/637508.html
�ŏЉ�Ă���u�}�b�N�X�E�x���N���G���}�b�N�X���J������ہA�܂������Y�̉𑜗͂͂ǂꂾ���K�v�Ȃ̂����l���܂����B�c�c�v���[���ł��邩�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19922407�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�l�I�ɎQ�l�ɂ��Ă鎑���Ƃ���
http://cccpcamera.photo-web.cc/RussianCamera/TOPICS/Mitatouri/HyoujunnLenz.htm
�ł�(^^)
�m���ɁA�l�I�ɂ̓��C�J��50�~��������50�~�����W�����Ă��Ƃɂ��Ă��܂����A������A���J�����ƃ����Y�̃Z�b�g�̔����ƈ�����50�~�����t���Ă��邩��A�����W���Ƃ��čL�p�A�]���ƕ����Ă���̂ŁA���̋N�_�ƂȂ�W����50�~���ƍl���܂����A�Ȃ��50�~���Ȃ̂������ɂ킩��܂���B
�����ԍ��F19922466�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����S�O�O�P����
�����F�X�Ƃ������̂͂�����ł����A���[�J�[�̕��͂P�̊�ŕ�������Ă���킯�ł��B
�Ⴆ�Ύ��R�Ɍ������p�́A�f�q�̑Ίp���������w�L���x�œ_�������K�v�B
���C�J��50�o��W���Ɛݒ肵�����Ƃ��A�����Y�����̂ł��Ȃ��J������38�o�O��̃����Y�����Ă��܂����B
50�o�̓����W�t�@�C���_�[�ł͖��Ȃ������킯�ł����A���t�ɐ�ւ���������͖�肪�o��55�o�ɓ����Ė����������Ă����ł͂Ȃ��ł����B
�܂���35�o�J�����ȊO�ł��W�������Y�͑��݂��Ă���A�n�b�Z����80�o�͕W�������Y�Ƃ��Đ��E���̎ʐ^�ƂɔF������Ă���܂��B
���^��110�T�C�Y�A�Ⴆ�y���^�b�N�X�I�[�g110�ɂ��W�������Y�͑��݂��Ă���܂��B(�ǂ̃t�H�[�}�b�g���Ίp�������L��)
���悭�g��ꂽ�J�����̓��C�J�łł͂Ȃ��A66�̓��t�ł��B��ʑ�O��35�o�J�������g���悤�ɂȂ����̂͂��̌�B
�ʔ����̂�50�o�̘b���ʐ^�̑�w�Ƃ��ɍs�����l�ɕ����Ɓu����������v�Ɩ��m�ȓ������Ԃ��Ă���̂ł����A�A�}�`���A�̒��ɂ́u�������邩��v�Ɩ��������Ă��܂��l������݂����ł��ˁB
�����ԍ��F19922491�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����́�
������E�E�E�����̈�ł�����(^^;(^^;(^^;
�I�X�J�[�E�o���i�b�N���A���C�c�Ђɓ��Ђ��čŏ��̎d�����u�f��B�e�p�J�����v�ŁE�E�E
�����̉f��i16�o�t�B�����j�B�e�p�����Y�̕W�������Y���u1�C���`��25�o�v�ł���E�E�E
���̉f��p�̃����Y�̃��C���i�b�v���E�E�E1�C���`�A2�C���`�A3�C���`�A4�C���`�����������ŁE�E�E
25�o�A50�o�i5�p�j�A75�o�i7.5�p�j�A100�o�i10�p�j�ƌ����œ_�����̕\�������������ł��B
���̎��A�f��p�t�B�����̘I�o�e�X�g�p�̃J�������������āE�E�E�X�`���J����������B�B�B
���̘I�o�e�X�g�p�J�����ɑ�������Ă��������Y���E�E�E�f��p�����Y�́u5�����v�������ƌ����Ă��܂��B
�ŏ��́A����16�o�t�B�����́u1�R�}�v�����g���ĎB�e�������E�E�E�����L���Ɖ𑜂������E�E�E�u2�R�}�v���g������A��肭�s������
���ꂪ�E�E�E���C�J����135�t�B������36��24�o
�������炪�E�E�E�z���̐��E�ł�����(^^;�i��
�o���i�b�N����́A�h�`���Ă��E�E�E���́u�����L���v�ɑς�����𑜗͂��~�����āA�����Ɖ𑜂��郌���Y���x���e������ɂ��肢�����Ƃ���B�B�B
�o�����������̂��A���C�c�E�A�i�X�`�O�}�b�g�����Y50�oF3.5.�B�B�B
�ƌ������ŁE�E�E�u�f��p�����Y���v(^^;(^^;(^^;�i��
���́E�E�E���̐���M���Ă܂���
���łɁE�E�E���o�̂悤�ɁA������͂̃J�����͑唻�J�����⒆���J�����i�u���[�j�[�^120�t�B�����j�ł���E�E�E�傫�ȃT�C�Y�̃t�B�������g���Ă��܂����B�B�B
����̃t���T�C�Y��APS-C��t�H�[�T�[�Y���̋����t�H�[�}�b�g�̊W�Ɠ������E�E�E�����œ_�����ł���A�������T�C�Y�̃t�B�����͉�p�������Ȃ遁�]���Ɏʂ�B�B�B
�����̃����Y�v�̋Z�p�ł͏œ_�����̒Z�������Y�ŁE�E�E����a�ʼn𑜗͂̍��������Y�����̂���������̂��Ǝv���܂��B
�����炭�́E�E�E�Ίp�����s�b�^����43�o���E�E�E�����]�T�̂���50�o�i5�p�j�̕����v���₷�������i�f��p�����Y�̂���{�����邵��j�ƌ��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19922575
![]() 2�_
2�_
�X���傳��A�ǂ���(^^;
����0.5(����\120�b�p)�ŁA���L�̏œ_�����ɂ������p(�L�q��)����A�u�ʁv�Ƃ��Ă̕���\���v�Z���Ă݂܂����B
��D��43.3mm�AH=36mm�AV=24mm
���Zf=50mm�Ŗ�102��(�v17.2�{/mm���t�B�����̉𑜗�)�ł����̂ŁA��̃��X�̏ؖ��݂����ɂȂ�܂������A
���Zf��43.3mm�ł́u(100�N�ȏ�O�̓����Ƃ��Ă�)������ƌ������v�̂�������܂���ˁB
�����ۂɂ́u�v�`�{/mm�v�̉������`�{�ȏオ�K�v�ɂȂ�܂���
�y�v�Z�l�z
���Zf=35mm
D 2125�AH 1768�AV 1179 �� ��208��(�v24.6�{/mm)
���Zf��43.3mm
D 1719�AH 1430�AV 953 �� ��136��(�v19.9�{/mm)
���Zf=50mm
D 1487�AH 1238�AV 825 �� ��102��(�v17.2�{/mm) ����̃��X�Q��
���Zf��57.3mm
D 1298�AH 1080�AV 720 �� ��78��(�v15.0�{/mm)(���e�����~��������)
���Zf��67.5mm ���u��p�v�� �n�C�r�W�����́u3H�v�ߎ�(������0.5�̏ꍇ)
D 1101�AH 960�AV 540 �� ��52��(�v12.7�{/mm)
�E�E�E�v���Ԃ�ɎO�p�����g���܂���(^^;
�����ԍ��F19922611�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���肪�Ƃ��A���E����
�����J�ɂ��肪�Ƃ��������܂�m(_ _)m
�����킩���������B
�����ԍ��F19922660
![]() 0�_
0�_
�X�y�V�����r�[������A�ǂ���(^^;
�r�����̋Z�p�ł�43�������50�����̕����𑜗͂���ɂł���Ƃ������ƁH
�u�v�Z�v�Ƃ��āA
���ꕪ��\�ł���A��p���L���Ȃ�قǁu�ʁv�Ƃ��Ă̕���\(����킵���̂Łu�𑜗́v�Ƃ��܂��傤��)���傫���Ȃ��Ă����܂��B
�r����������ʑ̂͐l�ōl���Ă���̂ł��傤���H
100�N�قǑO�ł�����E�E�E
�܂��A��ʑ̂Ƃ��������A�n�C�r�W�����̋L�^��f����207���Ɠ����悤�Ɂu��ʂƂ��Ă̕���\�v�ȂƎv���܂��B
�Ȃ��A��́u�N�������Ȃ������E�E�E�v�ł́A
�ŏ��ɉf��p35mm�t�B�������g�����X�`���J�����������(����H)�̂́A
�u�����̃t�B�����͊��x�̃o���c�L���傫�����I�o�����肵�Ȃ��v�̂ŁA
(���b�g�P�ʁH��)�������T���v�����O�݂����Ƀt�B�����̈ꕔ��������ĎB�e���A���x�����ʂ��đ��胂�h�L������Ƃ����A�ǂ��炩�ƌ����ΘI�o�v�̈��̂悤�Ȏg���������Ă����A
�̂悤�Ȏ|��������Ă��܂����B
���Q�Ɨp�ɓ����́u���ʂ̘I�o�v�v�����p���Ă����Ǝv���܂����A
���̎���ǂ��납�A�����ƑO�ł��u��ʑ̑��ł͂Ȃ��A���Ε����̃t�B�����������ʓI�Ɍv������v�ړI�̘I�o�v���h�L���Ă��������낤���H�Ǝv���܂����B
��������Ďg���Ă݂�ƁA�ӊO�Ɏg���邵�A���̐v�҂͎ʐ^�B�e�̎�͂��邯��ǂ��a�C�������ő傫�ȑ唻�J�����Ƃ��S���ł̎B�e�͑傫�ȕ��S�������悤�ŁA���̘I�o�v���h�L���u�J�����Ƃ��Ďg�������v�Ƃ�����]���o�Ă��āA�����āu���������܂łɎ������v�݂����Ȃ��Ƃ�������Ă����悤�ȋL��������܂��B
���ʂ̃��C�J�֘A���Ђ�������������܂���B
�����ԍ��F19922687�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���݂܂���A�I�o�v���h�L���A���łɁ����S�O�O�P��������Ă��܂����B���炵�܂����B
�����ԍ��F19922690�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����1���炪����܂����B
�ȉ��� 3�F2�ł͂Ȃ��āA16�F9�ł̌v�Z�ł��̂ŕ⑫�����Ă��������܂��B
�r���Zf��67.5mm ���u��p�v�� �n�C�r�W�����́u3H�v�ߎ�(������0.5�̏ꍇ)
�rD 1101�AH 960�AV 540 �� ��52��(�v12.7�{/mm)
�����ԍ��F19922695�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���肪�Ƃ��A���E����
���S�O�O�P����̂��b�ƍ��킹�ē����̎���w�i�Ȃ��������ĂƂĂ��悩�����ł��B ^^
���ʂƂ��Ď��ɂƂ��ėǂ��X���ł����B
���̃X���͒N���������ɕW�������Y�ŋ^��Ɏv���ăO�O�������ɖ𗧂������ł��ˁI
�Ȃ낤�E�E�E�}�Ɏʐ^�B�肽���Ȃ��Ă����i�j
�����ԍ��F19922718
![]() 1�_
1�_
�����̃t�H�[�}�b�g�͑Ίp�����W�������Y���ۂ���ł����A
���C�J�̑O���ƁA
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Daguerreotyp-Apparat_zum_Portraitiren
�_�Q���I�^�C�v�@1841�N�@�Ίp(���a92mm)�@�����Y149mm
�|�[�g���[�g�p�Ȃ̂Œ��߂Ȃ̂ł��傤���B
https://de.wikipedia.org/wiki/Kodak_Nr._1
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Kodak_No._1
https://www.flickr.com/photos/nationalmediamuseum/sets/72157606845434332/with/2780165657/
No.1�R�_�b�N�@1888�@�Ίp(���a65mm)�@�����Y 57mm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%AF
�|�P�b�g�R�_�b�N�@1896�@6��9�@�����Y�s��
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%BC
�A���S�[�@1905�N�@��D�i8×10.5cm�j��[2]�A���D�i9×12cm�j��[2]�A�L���r�l�i13×18cm�j��
�Ίp�́A13.2�@15�@22.2
�����Y�́A60mm�A100mm�H
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%A0_(%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9)
�A�g���@1906�N�@4.5��6�@�Ίp7.5�@�����Y��6.5cm�A9cm�A7.5cm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%99_(%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9)
�x�x�@1909�N�@4.5×6�@�Ίp7.5�@�����Y��7.5cm
�@�@�@�@�@�@�@�@�@6.5×9�@�Ίp11�@�����Y��100mm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%AF
�x�X�g�|�P�b�g�R�_�b�N�@1912�N�@4��6.5�@�Ίp7.6�@�����Y��72mm�A84mm
�m���ɂȂ�ƂȂ��Ίp�ɋ߂������Y���t���Ă邫�����܂����B�B
���C�J�ȍ~�́A
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Zeiss_Ikon_Icarette
�C�J���b�g�@1925�N�@6��9�@105mm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%81%E3%83%8A
���`�i�@1934�N�@50mm
http://www.jnoir.eu/en/cameras/franka/rolfix/
�����t�B�b�N�X�@1935�N�@6��9�@105mm
https://sites.google.com/site/fromthefocalplanetoinfinity/argusc3
�A�[�K�X�@1939�N�@50mm
6��9���Ίp��肿����ƒ��߂ł���B
�����ԍ��F19922778
![]() 0�_
0�_
��tmc393310����
35mm���̈��t�̏ꍇ�A�~���[�����������߁A40�`50mm�̃t�����W�o�b�N���K�v���Ǝv���܂��B
�L���m��EF�}�E���g�F44mm
�j�R��F�}�E���g�F46.5mm
�I�����p�XOM�}�E���g�F46mm
�y���^�b�N�XK�}�E���g�F45.46mm
�~�m���^A�}�E���g�F44.5mm
���C�JR�}�E���g�F47.15mm
50mm�ɂ��������A�ȒP�Ƀ����Y���Ō�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19922930
![]() 0�_
0�_
tmc393310����
�J�����ɂ���Ĕ{���Ⴄ���猩�����������Ⴄ���ǂȁB
�����ԍ��F19922973�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
>35mm���̈��t�̏ꍇ�A�~���[�����������߁A40�`50mm�̃t�����W�o�b�N���K�v
���C�J��50�o�Ƃ����͈̂��t�ȑO�ł��B
���ꂩ��ł��ˁA�����Ă��郉�C�J���g���R���p�N�g�̒P�œ_�J����(���C�J�~�j)��50�o�𒅂��ĂȂ��̂ł���B
������݂Ă��ǂꂾ��50�Ƃ��������ɈӖ�������̂��B
�����ԍ��F19922978�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�v�����
���C�J����������������q�b�g����������
���̌�g�������Ă�����Ď��ł���
�����ԍ��F19922990�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������߂̕����A�Z�p�I�Ɋy����Ȃ������̂��ȁH
50�`55mm�ӂ肪���Ղ������̂ł͂Ȃ����ƁE�E�E
�����ԍ��F19923049
![]() 1�_
1�_
��tmc393310����
���C�JM�}�E���g��51.6mm���l�̌ܓ�����ƁA50mm�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
46.0mm�ȏ�54.9mm�ȉ����ƁA�X��50mm�ɂ��Ă���̂����H�H
���H�ɂȂ�܂����A90�x�̌����_�͍��̂�������Ǝv���܂��B
����Ɏ����Ă���̂����m��܂���ˁB
�����ԍ��F19923084
![]() 0�_
0�_
�X�����tmc393310����A
�Q�l�ƂȂ�HP�̂��Љ�肪�Ƃ��������܂���(^^)
�����ԍ��F19923095�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������Ǝ���̉Ƃ͂������ꂽ�ɂȂ�܂����ꌾ
�C�Ǝ���Ɏt������
50mm��p�͎����̗~���Ă��郌���Y������̂Ɉ�ԍ����Ă���ƌ����܂���
�܂�50mm���g���āA�����Ɗ�������C�h�����Y
�L���Ɗ�����Ζ]�������Y
�����ɓ��肷�郌���Y����
���ł͕W���Y�[����1�{�ڂ̃����Y�ɂȂ��Ă��܂���
�����ԍ��F19923127
![]() 2�_
2�_
���ڂŋ≖���t�̃t�@�C���_�[��`������A����̉E�ڂŌi�F�������Ƃ��A��a���Ȃ����ڂŌ����i�F���A�قڈ�v���Č�����̂�50mm�O��Ɨ������Ă��܂����B
�����ԍ��F19923739
![]() 1�_
1�_
>���ڂŋ≖���t�̃t�@�C���_�[��`������A����̉E�ڂŌi�F�������Ƃ��A��a���Ȃ����ڂŌ����i�F���A�قڈ�v���Č�����̂�50mm�O��Ɨ������Ă��܂����B
�t�@�C���_�[�{���ɂ���邵
���ڂƉE�ڂ��t�H
�ł�������Șb������܂���
�����ԍ��F19923816
![]() 1�_
1�_
�W�������Y�́A50mm�ɂȂ��Ă܂����H
���̎嗬�́AAPS-C���A35mm���Z��16-50�A18-55�A18-135�Ȃ̂ŁA24mm�`202.5mm���炢�łȂ��ł����H
3/4��14-42mm���ȁB
�P�œ_�t�WX100�V���[�Y�́A�J�^���O��@35mm�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Y���[�J�[�̃T�C�g���W�������Y�Ƃ��ẴJ�e�S���[�́A��L�̎�ނ��܂Ƃ߂Ėԗ����Ă��܂��B
�̂ɁA�T�Omm���W�������Y�Ƃ������Ƃɂ́A���������^��ł��B
�����܂ł�������Y���A35mm���Z��50mm�ƁA�������Ƃł��傤���B
APC-C�ł́A24�`35mmm�ł��傤���B
�����ԍ��F19928156
![]() 0�_
0�_
��tmc393310����
>>���C�JM�}�E���g��51.6mm���l�̌ܓ�����ƁA50mm�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
�����Y�̍�����l�b�g�Ŋm�F����ƁA�l�̌ܓ��ł͂Ȃ��A��̂�(ROUNDDOWN)�̂悤�ł��B
�܂��A51.6mm���̂Ă��Ă�50mm�ɂ͂Ȃ邩�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19928273
![]() 1�_
1�_
�r�����܂ł�������Y���A35mm���Z��50mm
�����������R�ɂ��̑O��ł��ă��X���܂������A�A���Ԃ�w�ǂ̕������̑O��Ń��X���Ă���Ǝv���܂��B
���܂��A�����Ƀs�b�^���̊��Zf=50mm�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��Ƃ��v���܂��B
�u�����v�Ƃ��ẮA���� i-Phone���͂��߂Ƃ���ui-Axis(����)(^^;�v�ɂ���āA���Zf=29mm�����肪�u�W���v�Ȃ̂�������܂���(^^;
�����ԍ��F19930065�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�� �����������R�ɂ��̑O��ł��ă��X
�� ���͂������R�Ƃ��Ă��̑O��Ń��X
�����ԍ��F19930169�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���u�����v�Ƃ��ẮA���� i-Phone���͂��߂Ƃ���ui-Axis(����)(^^;�v�ɂ���āA���Zf=29mm�����肪�u�W���v�Ȃ̂�������܂���(^^;
���A���ꂿ����Ǝv���܂��B
��p���肫�Ƃ������A���B��Ȃǂł悭�g���B�e�������Z���Ȃ������߁A�K�R�I�ɍL�p���l�C�ɂȂ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�܂��A�L�p���L�̃p�[�X���A�ォ��B���Ċ炪�������茩����悤�ɂ���ȂǁA���܂����p����Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19931148
![]() 1�_
1�_
�M�q���Ē�����A���X���肪�Ƃ��������܂�(^^)
�m���ɁAi-Phone�ȂǂŎB�e����Ă�����̐�Α����́u���Zf=��mm�v�Ƃ��A�w�NjC�ɂ��Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
����́A�J����(���m�ɂ͈�ʓI�ȃJ�����ɂ�����)�u�W���͊��Zf=50mm�v�Ɓu����Ă����v���Ƃ͎����ł��邯��ǂ��A
����i-Phene��X�}�z�Ȃǂ�(���̒m������)���Zf=50mm�O��̒P�œ_�@��͑S�����݂��Ȃ��A
����ȑO�Ɋ��Zf=50mm�P�œ_�̃R���p�N�g�J���������̎l�����I�̊Ԃɂ͖w�Ǒ��݂��Ă��Ȃ������R�ł��邱�Ƃ���A
(������ʂɂ�)�n�}�̊�_�݂����ȈӖ������Ȃ���������܂���ˁB
�����ԍ��F19931357�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�t�B�������̂���@���ڂŌ��Č�����傫�����قړ���
�T�O�������炢���@���邢�����Y�������ō���
���@�g���₷���@�����₷���@���Č������ŕW����
�́A�j�R���̐l�������Ă����悤�Ȋo��������܂�
�iF2 F3���g���Ă�������̘b���������ȁH�j
���́A�Z���T�[�T�C�Y���F�X����̂�
���̗���ŕW�����Ă̂��������Șb���Ǝv���܂���
�t�B�������痬���l�ɂ͂���ł��悩�����̂����H
�j�R���@E�Q�Ȃ́@�Q/�R�Z���T�[�Ȃ̂ɂ킴�킴�����Y����ā@��p
���킹�Ă܂������@�O�@�O
�����́A�t�B�������痣���10�N�Ԃ肮�炢�Ƀf�W�^����ᔃ������iD2X�j�������܂�����
�i���@�܂��Ă�t���b�O�V�b�v���n�[�t�T�C�Y���Ƃ͎v��Ȃ������j
D2X�̓v���̐l�̂������肾�����̂Łi�R���f�W���炢�́��j
��������́@�t�B�����̍��̒m�������������킹�Ă���܂���ł����̂Ł@�O�@�O
�����ԍ��F19931587
![]() 0�_
0�_
�D�H����A���o�ł������̃X���ł́u���Zf=50mm�v�Ƃ������ƂŁA�����I�ȃT�C�Y�����{���́u��p�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19931598�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
���́A�����Ȃ�܂���
�t�B�������t���T�C�Y�i�ꕔ�n�[�t������܂����j
���ā@�Â��l���̌��Ł@�T�O�������W���ł�����@�O�@�O
���܂�A�œ_��������p�ōl���Ȃ��Ɓ@�̂́A�����ɂȂ������Ⴂ�܂�
���Ȃ��A50�~�����W�������Y�Ȃ�ł��傤���H�@
�R�R�ł́A�Ƃ��Ă�������
�����ԍ��F19931796
![]() 0�_
0�_
�D�H����A�ǂ���(^^)
�������{�l�������̂��Ȃ�ł����A
�u��p�v�ɂ��Ă͂�����Ɩ�肪����܂��āA������ʂɂ́u�p�x�v���ʗp���Ȃ��̂��u���ʁv�Ȃ�ł����(^^;
�܂��A���Zf(�œ_����)�̓A�`�R�`�L�ڂ���Ă��Ă��A��p(�p�x)�����L����Ă��邱�Ƃ́u��ʓI�ł͂Ȃ��v�܂܁A������A�O�\�N�ɂȂ邩�Ǝv���܂����A������u���̂܂܁v���Ǝv���܂��B
�����āA���̊p�x���́A�����n������������ʂɂ́u�ƂĂ��Ȋw�Z�p���i���Ƃ͎v���Ȃ��v�悤�ȁu�p�x�ɂ��Ă̖����ꒃ�Ȋ��o�v������̂ŁA���Zf�̂ق����܂��܂��}�V���Ǝv���܂��B
�Ȃ��A�����X�ɂȂ�܂����A�u�Y�[���{��(�Y�[����)�v�Ɓu�]������o�ዾ�Ȃǂ̔{���v�Ƃ��ꏏ�N�^�ɂȂ��đ傫�Ȍ�����o�Ă���̂ŁA�ߋ��̃J�����̗��j�Ȃǂƌ�C���킹��v�Z������߂��Ȃ����Ƃ��܂߂āA
�������̂��Ɓu35mm�����Z��35mm�v���y�K���z�Ƃ���ƁA
�u�ߋ��̕W���F���Zf=50mm�v�Ɓu�����̃R���f�W�L�p�[�̍ő��͈́F���Zf=24�`25mm�v�Ƃ̒��ԕt�߂ɂȂ邱�ƁA
����Ƃ��čL���E�^�C�v�̖]������o�ዾ�̌��������E�͈̔͂ɓ���܂��B
�u�ǂ������������Ȃ�A����ɂ���Q(�H)�����Ȃ��v�Ȃǂ̗��_������A
����܂ł̏œ_�����̑���ɁA���Zf=35mm���邢�͑Ίp�����̖�0.8089�{���u�P�{�v�Ƃ��Ĉ����A�Ƃ������̂ł��B
�����Zf=50mm�ƗႦ�Ί��Zf=25mm�Ƃł́A�{�E�����̊W�ɂȂ�̂ŁA������Ɗ��o�̃Y�����傫������悤�Ɏv���܂��B
�Ȃ��A�Y�t�̉摜�́u���v���B�e����ꍇ�ŁA�e���������E��������]�����Ȃǂ̔{���Ƃ��āu100�{�v�̂Ƃ��̎����E�Ŕ�r���Ă��܂��B
�����Ȃ݂ɁA
���Zf=50mm�͑Ίp�����̖�1.16�{�A
��L�̊��Zf=35mm�K���ɑ��Ă͖�1.43�{[f/35]�B
�����ԍ��F19932378�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�W�������Y�A���C�J�`�̃����W�t�@�C���_�[�̎���́A50mm�����肪�A��Ԓ�R�X�g�ő���a�����Y�����₷�������Ƃ����̂�����܂���ˁB���ꂪ�A���t�̎���ɂȂ��āA�t�����W�o�b�N���L�т�ƁAF1.4�Ƃ������邳��50mm�����̂���������i�������A���w�I�Ɉ��肵�����i�Ƃ��Ă�50mm�Ƃ����Ӗ��ł��j�B
�ł�����A���Ƃ��A�j�R��F���o�����A�ŏ��̕W�������Y�̓j�b�R�[��S�I�[�g5.8����F1.4�ŁA���ꂪ50mmF1.4�ɂȂ�̂�2�N�قǂ������Ă��܂��B�i�x�[�X�̐v��S�}�E���g��50mmF1.4�������ł��j
���̑���AF2�̃����Y�͖��邳�Ŗ�������K�v���Ȃ��̂�50mm�ŏo�Ă��܂��B
�܂��A�}�N�������Y������55mmF3.5�Ƃ����`�ŏo�܂������A�����50mm���v�����iS�}�E���g�ł̓}�C�N���j�b�R�[��5����F3.5�ƂȂ��Ă��܂��j�̂ŁA55�����Ƃ����œ_�����ɂȂ����Ƃ����o�܂�����A�}�N�������Y�́u�W�������Y�v�ł͂Ȃ�����A�Ƃ������ƂŁA���̂��Ƃ��`�e-�c�̎���܂ŁA55�����̂܂܍���Ă��܂��i�v�͕ς��܂������j�B
���̈���ŁA�p���P�[�L�����Y�A�Ƃ����郌���Y�́A�ނ���l�Ԃ̎��E�Ƃ̑��������d�����āA���邳��~����Ȃ�����ɁA���^�y�ʂɍ��A�Ƃ��������Ɍ����Ă܂���ˁB�j�R���i�j�b�R�[���f�m45�����e2.8��`���j�b�R�[��45�����e2.8�o�Ƃ��j�͂��̖ړI�ŏo����Ă��܂��B
�����̓���Ƃ����_�ł́A�������邳�ł�50�����悩��]�����A�L�p������������Ă���C�ɑ�^�����āA�l�i���オ���Ă���̂����Ă���������A�킩��Ǝv���܂��B
�v����ɁA�l�̎��E�Ɉ�ԋ߂��̂̓��C�J�Ŋ��Z��43���������A��ԍ��₷�������̂�50�����������A�Ƃ������Ƃ����C�J��50������W���ƒ�߂����R�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�r�k�q�ł͂ނ���58���������₷���������ǁA���C�J��50������W���ƒ�߁A���ꂪ�ƊE�W���ƂȂ����̂ŁA50�����ɍ��킹����Ń��C�J�Łi135�t�B�����j�̕W����50�����Ƃ����̂��Ǝv���܂��B
������A�m�N�g�j�b�R�[����A��̖ڃ��b�R�[���Ȃ�58�����Ƃ������\���l����Έ�ԍ��₷���œ_�����ŏo�����i�o������Ȃ������H�j��ł��傤�B���̂ق��A�r�k�q�t�����̃h�C�c�����Y�ł�58�������Č��\�����ł����ˁB
�����ԍ��F19932655
![]() 0�_
0�_
�r�l�̎��E�Ɉ�ԋ߂��̂�
��������łɃ��X������܂����A�u�l�̎��E�v�Ƃ����͖̂�肪����Ǝv���܂��B
���̖��́u�̂��炻�̂悤�Ɍ�p���ꑱ���Ă��āA(��ώ���Ȃ���)����ΖӐM��Ԃɂ���v�̂ŁA���̂悤�ɕ������l�́A�Ⴆ�u�\�����̃A�N�Z������ɂ�鑛���̃��Y���v���O�\�N�ȏ���w�Ǖς��Ȃ��悤�ȁu�`���v�������p�������Ă��Ă���悤�Ɏv���܂��B
(��ώ���ł��݂܂���)
�u�l�̎��E�v�Ƃ����ƁA�{���͗���Ŏ��̂悤�Ȕ͈͂�(�����l�̐�Βl�Ƃ��Ă͂Ƃ�����)��w�I(�H)�펯�̂悤�Ɏv���܂��B
�E���E�F�P�W�O�`�Q�O�O�x
�E�㉺�F�P�R�O�`�P�S�O�x��������͍��E�����L�ڌ��ɂ��o���c�L����
�Ƃ͂������̂́A�u�l�̎��E�v�Ƃ͌����ȈӖ������ł͂Ȃ��A
(�ނ���A�u�Ȃɑ�U���Ȃ��Ƃ������Ă�H�v�Ǝv���Ă��d�����Ȃ��悤��)
�̂���u��������ꂽ���Ƃ�P�ɌJ��Ԃ��Ă��邾���v��������A���͂⊵�p��▍���̂悤�ȈӖ��������������ɉ߂��Ȃ��̂��낤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19932891�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>�Ƃ͂������̂́A�u�l�̎��E�v�Ƃ͌����ȈӖ������ł͂Ȃ��A
�����炱���ʐ^�E�ł͂����l����ƌ��߂āA���[�J�[�̕��ł�����ɏK���Đ��i�������Ă���̂ł͂Ȃ��ł����H
�Ƃ��낪���̃X���ł͕ςȏ�o�Ă�����A���C�J�ł̘b�Ȃ̂Ɋ��Z�A���Z�Ƃ����Ŋ��Z���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂��낤�Ǝv���Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F19932954�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̃X���́A���C�J���Ƃ�����135��(36x24mm�A�Ίp������43.3mm)��f=50mm���Ӗ����Ă���Ƃ͎v���܂����A
�X���̈�ԍŏ��ɖ��L���Ă��Ȃ��̂ŁA
�X���傳��̈ӌ��ƊW�Ȃ��u����ȉ��߁v���o�Ă��錴���ɂȂ��Ă���悤�ł��B
���������A�u�ȑO����̏펯�v�ɂ����ẮA�X����ɔ�������������Ƃ͎v���܂���B
���Ԃ�A�X���傳��́u�펯�I�ɁA�u�W���A50mm�v�Ƃ����A���R�u�A���v�̂��Ɓv�Ǝv���Ă���ł��傤���A���������v���܂��B
�������A���ł́u�B�e�@��v�Ƃ��āAiPhone���܂ރX�}�z����Α����A���ŃR���f�W�A
�f�W�C�`�ł�APS-C�ȉ��̎B���f�q�̂��̂��u�嗬�ɂȂ��Ă��܂����v���݁A�u�펯���A�Y������A�ς�����v�悤�Ɏv���܂��B
�]���̏펯���u�\���v�m����̊������A
�̂́u�m���Ă���w�v�������ł����Ă���ʂɈʒu���鏭���ł������n�Y�ł����A
���͂�u�P�Ȃ邲�������v�ɂȂ��Ă���̂�������܂���B
(�߂������Ƃł���)
���̃X���ł�����̕���135��(���C�J��)�Ɍ��肳�ꂸ�Ƀ��X����Ă���A
���̎���̃��X��ǂނƁA���ʍ��Ƃ��Ă͒P�ɑ��Ƃ���Ȃǂł͂Ȃ��A
�u�펯��(�ǂ�������)�ς�����A(����������)�Y������v�悤�Ɏv���܂����B
���Ɛ��N�`�\���N��ɂ́A�u���Zf(�œ_����)�v�Ƃ����O��L���Ȃ��ꍇ�́A���Ɣ�ׂ�ƍl�����Ȃ��悤�ȁu�o���G�[�V�����v�̉����Ԃ��ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
���̂悤�ȕω��ɍł��d�v�Ƃ�������(�ǂ������ɊW�Ȃ�)�x�z�I�Ȗ������ʂ����̂��A���̂悤�ȃX���ɏ�����邱�Ƃ��Ȃ��u�^�̐�Α����v���Ǝv���܂��B
���́A�I�[�f�B�I�u�[�����́u���g�������v�Ƃ͒j���̑傫�Ȋ����ɂ����Ĉ��̏펯�ł������A���ł́u����ȗp��A���������Ă���̂�����Ȃ�(���)�v�݂����Ȉʒu�t�����u���ʁv�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂�
�u���A�펯�Ǝv���Ă���w�v�́A�V�K�ł͂��܂葝�����A�ނ��납�Ă�Y�����������āu�ǂ��ł��悭�Ȃ�v�A�����܂߂ĉ���ŏ������݂��ł��Ȃ��Ȃ�����A���S���Ȃ�ɂȂ��Č������Ă����A
�u�^�̐�Α����v�̂���čX�Ɋ�߂���Ă����܂��B
�����āA�x���Ƃ��\���N��ɂ́u�ÓT�Ƃ��l�Êw�̘b�����Ă���悤�ȕ��ށv�̈����ɂȂ邩������m�܂���B
�����̎�ɍl�Êw���ꉞ�����Ă���̂ŁA���\�������������Ă��܂�(^^;
�����ԍ��F19933027�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ƃ͂������̂́A�u�l�̎��E�v�Ƃ͌����ȈӖ������ł͂Ȃ��A
��ʂ�ŊF���ߊ��̂��Ƃ��w���Č����Ă���Ǝv���܂��B
�m���Ɍ�p�ł��ˁB
���̓��ł͂��肪�Ƃ��A���E����̋��Ă���Ӗ������Ⴆ�Ă���\��������܂����E�E�E
��(�ނ���A�u�Ȃɑ�U���Ȃ��Ƃ������Ă�H�v�Ǝv���Ă��d�����Ȃ��悤��)
���̂���u��������ꂽ���Ƃ�P�ɌJ��Ԃ��Ă��邾���v
50mm�ߕӂł͑�U���Ƃ��ł͂Ȃ��A�������ʂ̊��o���Ǝv���܂���E�E�H
���̓Y�[�������Y���g���Ȃ���nikon��APS-C��32mm�ɂ��̊��o�����R�Ɗ����邱�Ƃ��o���܂����B
���C�J�Ƃ��W���Ƃ�����Ȃ��u���o�Ƃ��āv�[�����Ă����ł����ǁE�E�E
����Ȃ킯�Ȃ��������Ęb�ł��傤���H
�����ԍ��F19933069
![]() 0�_
0�_
>���肪�Ƃ��A���E����
>�E���E�F�P�W�O�`�Q�O�O�x�A�E�㉺�F�P�R�O�`�P�S�O�x
�l�Ԃ̎��E�́A�㉺���E�قƂ�Ǎ��́A����܂���B���E�F�㉺���S�F�R���炢���B
�ڂ�����邩�獶�E�Ɏ��E���L���ƍl�������ł����A���ڂ́A��̃^�[�Q�b�g�ɏœ_�����т܂��B
���E���L��������̂́A���ӎ��Ɏ�����E�ɐU�邩��ł��B
��u�̎��ԂŌi�F�Ȃnj��Ă��܂���B���̒��Ńp�m���}���������Ă��܂��B
���������āA�l�Ԃ̎��E�́A�X�C���O�p�m���}�Ɏ��Ă��܂��B
���ꂪ�A�L�p�c�݂�F���ł��Ȃ����R�ł�����܂��B
�����ԍ��F19933217
![]() 0�_
0�_
�K���X�̖ڂ����������Ă���̂�
�����ς藝���ł��܂���B
�ڂ͍��E�ɕt���Ă���̂����炠�肪�Ƃ��A���E�����
������ʂ藼��̎���͍��E�����ɍL����Ȃ��ł��傤���H
�Ȃ������ɂȂ��ł����H
�����ԍ��F19933240�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>�E���E�F�P�W�O�`�Q�O�O�x�A�E�㉺�F�P�R�O�`�P�S�O�x
�l�Ԃ̎��E�́A�㉺���E�قƂ�Ǎ��́A����܂���B���E�F�㉺���S�F�R���炢���B
�ǂ����������Ă鎖�͂S�F�R�ʂȂ̂ł́B�B
200�F140
180�F130
�����ԍ��F19933258
![]() 0�_
0�_
�X�y�V�����r�[������A�ǂ���(^^)
�͂��A���ߊ��A���邢�͊�炩�Ë����čL���Ӗ��Łu���o�v���ȁH�ƁB
�u�q�g�̉��ߊ��Ƃ��āE�E�E�v
�u�q�g�̎��o�Ƃ��āE�E�E�v
��҂̎��u�o�v�ɑ��āA���u�p�v�u�E�v�u��v�́A
�I���u�˂�v�ɑ��ẮA�I���u����v�̂悤�ȊԈႢ�����₷���悤�Ɏv���̂ŁA���͎��o�ł����Ă��A�u���R�ɕώ��v������������܂���B
�����l�̊ԈႢ�Ƃ��āA(���Zf)50mm�Ɓy50�x�z���Y������u�����v����܂���B
���܂�̂͒m��܂��A�l�����I���炢�͖]������o�ዾ�́y���|�����E�z�Ƃ��āu�W���v�̈����ɂȂ��Ă���̂��u50�x�v���Ǝv���܂��B
(���K�i(�p�{��)�̌v�Z�ɂ����āB�V(��)�K�i�̌v�Z�ł͖� 47.1�x)
����ɃA�b�v�́u�摜�v�ł́A���������E�̐V���K�i�L���܂���
�����ԍ��F19933468�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ƁA���E���E�Ə㉺���E�ł����A��ɉ��������̈�w�n�T�C�g(�����Ìn�ł��}�g���ȂƂ���)����̏��(�����\�N��)�ł��B
�㉺�͏�Ɖ����ʁX�ɏ�����Ă���A��{���ŋL�ڂ��܂������A�㉺140�x�̃\�[�X�����͕s���ł��̂ŁA
�O�̂��߂P�R�T(��75+60)�܂łɏC�������Ă��������܂��B
�����ԍ��F19933487�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���f��p�����Y�́u5�����v�������ƌ����Ă��܂��B
�@����͎����ǂ��Ƃ�����܂��B�W����50�~���Ȃ̂́A�Ȃ��ƌ�������ł�����A�Ó��ȉł��傤�B
�@�܂�A�W�������Y��50�~���Ƃ����̂̓��C�c���̗p��������B�������W���ɂ��Ĉ٘_������ł��傤���A�Ƃ肠�������C�c���A�Ȃ�5�Z���`��W���Ƃ������͏�L�̂悤�ȗ��R�ł��傤�B
�@�ł��A���������l��������A�x���[�N���������̉f��p�����Y��荂���\�ȃ����Y�����Ȃ������ƌ������Ƃł����肻���ł��ˁB
�@�e�b�T�[�^�C�v�́A�v�Z���鍀�ڂ����Ȃ��čςނ����ł����A���W�^�̃K�E�X�^�C�v�ł��ꂵ��ł���悤�ɑ��ʘp�Ȃ�����̂�����\���ł��B
�@�x���[�N�搶��43�~���͒m���Ă����ł��傤�B�ł������p���烉�C�J���p�ɂ���Ƒ傫���Ȃ�����������ł͉f��p5�Z���`�����Y���ǍD�ȉ掿�������Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���ǁA���m�ɂ�51.6�~����5�Z���`�����C�J���ɂ����鐢�E�̕W���ɂȂ����ƌ����킯�ł����ˁB
�����ԍ��F19933652
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́�
�X���傳��́E�E�E���Ɏ���̎�|��ς���ꂽ�Ƃ������H�H�i�O�O�G�G�G�@�_�_���i���Ă��܂�
>2016/06/01 19:30�@[19921758]
>���̃t�H�[�}�b�g�͑Ίp�����W�������Y���ۂ���ł����A�Ȃ�35mm�ł�43mm�łȂ�50mm�Ȃ�ł��傤���H�H
1�j�قړ���́u�p�[�X�y�N�e�B�u�i���ߊ��^��1�{�j�v�ɋ߂��f�����B�e�ł��郌���Y�ł��鎖�B
2�j���C�J�����Ђ̊�Łu����50�����i���œ_51.6�����j�v�̃����Y����̋K�i�Ƃ������B
3�j���̃J�������[�J�[���A���̃��C�J�̊�ɉE�ւȂ炦�������i�܂��E�E�E�����́u�͕킵���v���i�O�O�G�G�G�j�j�B
4�j���C�J���̗p�����B�e�X�e����35�����t�B�����t�H�[�}�b�g�������L���v�����g���L����ʂɕ��y�������B
���R�����u50�������W�������Y�v�ƌď̂����悤�ɂȂ������R�ł��鎖�ɋ^��������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��i�O�O�G�G�G�i�O�O�G�G�G�i�O�O�G�G�G
���́E�E�E���́H�H�@�}�b�N�X�E�x���[�N����́A�œ_�����u50�����v���̗p�����̂��H�H
���́E�E�E����܂ł̑�^�J�����i���J�����j���̗p���Ă����E�E�E�œ_�������t�H�[�}�b�g�T�C�Y�́u�Ίp�����̋ߎ��l�v�Őv���Ȃ������̂��H�H
35�����t�B�����t�H�[�}�b�g�̑Ίp������43.3�����Ȃ̂�����E�E�E����܂ł̐v��@�Ō�����40�����`45����������̏œ_�����Őv���ėǂ������n�Y�ł́H�H
���R�R�̉Ȃ�E�E�E�����Ȃ�E�E�E�l�@�Ȃ�E�E�E��T�����߂Ă�Ǝv���܂��i�O�O�G�G�G
���͌������܂���ł������ǁi���
�����ԍ��F19933764
![]() 0�_
0�_
���f���[�U����
�����܂���i�O�O�G�G�G�@����Ⴂ�ƂȂ�܂����B
�����ԍ��F19933821
![]() 0�_
0�_
���f��p�����Y�́u5�����v�������ƌ����Ă��܂��B
����͈Ⴄ���Ǝv���܂��B
���̉f��p�̃C���[�W�T�[�N����18✖24�~���Ŏʐ^�p�Ƃł͈Ⴄ���Ǝv���܂��B
�܂��A�C���[�W�T�[�N���̋����ɂ�肻����g�p����A���ӕ��ɂ͓����Ǝv���܂��B
����ŁA�x���[�N���m��1920�N�ʐ^�p�ɓK�������R�Q�S���\���̃����Y�̓������o�肳��܂����B�i�h�C�c�鍑����343,086.Kl 42h, Gr.4�j
��L�ɂ��A�f��p�̃����Y�Ƃ͈Ⴄ���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19934674�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����S�O�O�P����
�����́B
�Ƃڂ��ĕ����Ă���ƌ����Ă��d������܂��A����̎�|�͕ς��Ă���܂���B�S�O�ł��B
�u�Ȃ��A50�~�����W�������Y�Ȃ�ł��傤���H
��͂胉�C�J��50�~�����ŏ��ɂ�������Ȃ�ł��傤���H�H�v
�����ԍ��F19934700�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����S�O�O�P����
��35�����t�B�����t�H�[�}�b�g�̑Ίp������43.3�����Ȃ̂�����E�E�E����܂ł̐v��@�Ō�����40�����`45����������̏œ_�����Őv���ėǂ������n�Y�ł́H�H
���R�R�̉Ȃ�E�E�E�����Ȃ�E�E�E�l�@�Ȃ�E�E�E��T�����߂Ă�Ǝv���܂��i�O�O�G�G�G
���͌������܂���ł������ǁi���
�u�_�����C�J�̒鍑�̔閧�v�ɏ����Ă���܂��B2015�N11���ɔ������ꂽ�{�ł��̂ŁA����\���Ǝv���܂��B�������A�����Ă�����e������̂ŁA3�炢�͓ǂݕԂ��Ȃ���A�킽���͗����ł��܂���ł������c�i�j
�킽�����E�ƕ��A�l�b�g�ł����ׂ܂����A��͂肫����ƒ��ׂ�ɂ͖{��@�K�W��������܂��B���̈ꕶ�������Ă��邩��{���̂ł����A�܂��A�l�b�g�Œ��ׂ��֗��Ȑ��̒��ɂȂ����Ǝv���܂��c
�����ԍ��F19934738�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��tmc393310����
���͂�[�������܂���
�����I�H�H
���C�����Q���ꂽ�Ȃ�\����Ȃ�m�i_ _�j��
�����E�E�E�l�Ԃ́u�ځv�E�E�E��p�⎋��i�ƃt�H�[�}�b�g�̊W�j�̘b�́A�Ƃ����̐̂ɗ�������Ă��āE�E�E
���C�J�{���ǂ܂�Ă��錩�����̂Ȃ̂Łi�O�O�G�G�G�@
���C�J��50mm���K�肵�E�E�E����𑼂̃��[�J�[�E�E�E�Ƃ�킯�u���{�v�̃��[�J�[���R�s�[���C�J��ڎw���B�B�B
���{�̃��[�J�[���A���C�J�i�����W�t�@�C���_�[�j�ɍ��܂��Ĉ��t�ɕ����]����������E�E�E�s�������m�Łu50mm�v�ɂ�����葱�����B�B�B
�����āE�E�E���C�h�C���W���p�������E�𐧔e�������E�E�E���t�J�����̐��E�ł́u50mm���W�������Y�v�ƌ����ď̂��蒅�����B�B�B
�����[�����j���I�ȕ����́A���łɂ����m�H�H�@���邢�͊F���X����u�[���v���s�����̂ł͂Ȃ����H�H�Ǝv�������̂Łi�O�O�G�G�G
2016/06/01 19:30�@[19921758]
�����̃��X�ȍ~�E�E�E�b��́A�Ȃ����C�J�i�}�b�N�X�E�x���[�N�H�j���A�u50mm�v��I�����A������u��i�W���j�v�Ƃ����̂��H�H
�ƌ��������ɏœ_�͍i��ꂽ�Ǝv�����̂ł����H�H�i�O�O�G�G�G
������̂��ȁH�H�i�O�O�G�G�G
�ƌ������H�H
>�u�_�����C�J�̒鍑�̔閧�v�ɏ����Ă���܂��B
�ƌ������Łu�����ς݁v���Ă��ƂȂ�ł����ˁH�H
�����ԍ��F19936420
![]() 1�_
1�_
�����S�O�O�P����
�����́B
�킽���̎����
�u�Ȃ��A50�~�����W�������Y�Ȃ�ł��傤���H
��͂胉�C�J��50�~�����ŏ��ɂ�������Ȃ�ł��傤���H�H�v
�Ȃ̂ŁA��|�͕ς��Ă��Ǝv����ł����A�~�ߕ��͂����Ȃ�ł��ˁB
����ς胉�C�J����Ԃ��Ă����̂��S�ɂ���̂��ȁH�H
50 1.4G�������ł����ǂˁc
�����ԍ��F19937744�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ł�
��u��|�͕ς��Ă��Ɓv
�� �u��|�͕ς��Ă��Ȃ��Ɓv
�����ԍ��F19937755�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���b��́A�Ȃ����C�J�i�}�b�N�X�E�x���[�N�H�j���A�u50mm�v��I����
�@������v�́u���C�J�̗��j�v�ɂ��ƁA�ŏ��͉f��t�B�����̈�R�}���g�p����J�������쐬���A�����Y��5�Z���`�̃L�m�e�b�T�[��t���ăe�X�g�������A�����������|�X�g�J�[�h���x�܂ł����L���Ȃ������B
�@���̃J�����́A�f��̘I�o�e�X�g�p�J�����Ƃ��č쐬���ꂽ�ƌ����Ă��邪�A�o���i�b�N�{�l���������Ƃ���L�^�͂Ȃ��B
�@���ɓ�R�}���g�p����J�������쐬���A�����Y�Ƀ}�C�N���E�Y�}�[��6.4�Z���`/4.5��t����(1913�N)�B������E�����C�J�ƌĂ�ł���B���̕ӂŃo���i�b�N�ɑ��ă}�b�N�X�E�x���[�N�̉������n�܂����B
�@�}�C�N���E�Y�}�[���ɕs���������Ă����o���i�b�N�́A�}�b�N�X�E�x���[�N�̋��͂āA1924�N�Ƀ��C�c�E�A�i�X�`�O�}�b�g5�Z���`/3.5��t����6��̎��색�C�J��������B
�@�ȏオ���C�J��5�Z���`�o�܂ł��傤�B�Ȃ�43�~���ɂ��Ȃ������ƌ������P��5�Z���`�ō�����ƌ����̂������ł��傤���B
�����ԍ��F19939625
![]() 1�_
1�_
���f���[�U����
������?
���ڂ����ł��ˁI
���C�J�������ł����ǁA�j�R���������ł���I
�����ԍ��F19942597�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���炭�O�̎��̃��X�ւ̕⑫�ł�(^^;
���Zf=17�`50mm�̉�p��
�q�g�̎���(���E)�Ƃ̔�r�}�ł��B
(�㉺�͖w�Ǔ��l�A�������A���E�͐}���y���ɍL�����B
(���ʂ݂̂�)���ʏ�ŕ`��ł���͈͂ɂ����Ă̔䗦�́u����Ő��m�v�Ȃ�ł����A����ł���a��������Ǝv���܂��B���E�̌��E�O��͖w�Ljӎ����Ă��Ȃ����炩���H)
����}�ɂ����ẮA180�x���z����p�x��`��ł��܂���B
(���d�삩���d��A�v���ȂǂŁA�u2*tan(180/2)�v���v�Z���Ă݂܂��傤�BEXCEL�ł́u=2*tan((180/2)/(180/pi()))�v�Ȃǂ�)
����ǂ��납170�x�ł������u�����ꒃ�v�݂����Ȋ����ł��B
�}�g���ȃJ�����̃����Y�Ƃ��Ĕ��ɍL�����Zf=17mm�ł������u�����ꕔ�v�ł�����A
�u�q�g�̎���(���E)�ɋ߂��v�Ƃ����\�����C�ɂȂ��Ă��܂��̂ł�(^^;
�����ԍ��F19943610�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���肪�Ƃ��A���E����@����ɂ���
���ہ@�l�Ԃ̖ڂ̌�����͈͂́@�����ꂽ�Ƃ��肾�Ǝv���܂����@���ۂɂ͂�����ƌ�����̂́@20�`60�x�ʂƏ�����Ă���@�{������@���ʂɌ��Ă���ꍇ�́@50mm�ɋ߂�45�x�O��Ő������Ă���Ə�����Ă��܂����B
�ł��@�l�Ԃ̖ڂ͏W������Ɓ@��p�͋����Ȃ�@�ڂ��茩��ƍL�������邽�߁@��p�����ł͔��f�ł��Ȃ��̂Ł@���ߊ����d�v�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19944439
![]() 3�_
3�_
���X���肪�Ƃ��������܂�(^^)
��ρA��ʓI�F���A��w�I�Ó����A���̑�������ɑ�������̂����Ƃ������܂��A
��w�I�ȕ]��������Ă���悤�Ȏ����Ɋւ��܂��ẮA�Ⴆ�u�ٕ� ����v�Ȃǂʼn摜�������Ă��������ƁA
�����}�Ɖ��������o�Ă��܂��B
�܂��A���Zf=50mm�����̎���ɂ��܂��ẮE�E�E
�y�ȉ��͂܂��߂ȃ��X�ł��z
�E�E�E�E�T�������b�v��g�C���b�g�y�[�p�[�Ȃǂ̒��c�Ȃǂ�p�ӂ��Ă��������A
�P�ᎋ�̏ꍇ�́A���a�̖�1.2�{���x�̍����ŃJ�b�g�����~����Жڂɓ��ĂĔ`���āA�u���S�m�ۂ̏�v�ł��炭�����Ă݂Ă��������B
���ᎋ�̏ꍇ��(�l�Ǝg�p�p�x�ɂ��܂���)���a��1.3 �`1.7�{���x�̍�����2��(1�g)�J�b�g���āA
���ڂɂ��Ăāu���Zf=50mm�����̎���ɂȂ�悤�ɒ�����������ŁA
����Ɂu���S�m�ۂ̏�Łv���炭�����Ă݂Ă��������B
�����u���Ɉ�a�����Ȃ��v�A
���i����(�����ɂ����Ă�)�J�����̃t�@�C���_�[���̂悤�ɒ����`�����ςȂ��Ŗ����Ȃǂ̏ꍇ�����O����E�E�E
(���L�͔��ɏd�v�Ȏ��ł�)
�E�E�E�Γ����]�����Ȃǂɂ���ĕ��i���王�싷��ɂȂ��Ă���댯��������܂��̂ŁA�������邢�͂���ȏ�̏Ǐ���Q���o��O�ɁA��Ȃ��邢�͊O��(�ł���Δ]�⎋�_�o�̐��ア��Ƃ���)�ŁA
�\���Ȍ�������K�v������悤�Ɏv���܂��B
��L�͌����Ė\���̈��ł͂Ȃ��A���łɕ��ώ����̔������߂��Ă���҂̈�l�Ƃ��Ă�
�܂��߂ȃ��X�ł��B
�l�ɂ���Ắu�v�����݂ɂ�錩�������v������̂ł����A
���S�ɁA�܂��A�Ⴈ��ю��_�o��]�́u�ʏ�m���錒��v�ȏ�Ԃɂ����ẮA
�u�R��ׂ��������A����(���ˊ܂�)�v�Ƃ����̂�����A
�����łȂ��ꍇ�́A
�P�Ȃ�l��������`�咣�̂悤�Ȃ��̂ł͂���܂���̂ŁA��͂��w�I�Ȍ������K�v�ł��B
�����ԍ��F19945836�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Ȃ��A��L�̎��ӎ���́u�Օ��v�����Ă��A���ނ����肷��A����Ȃ�ɕ������肵�܂����A
����́u���Zf=50mm����v�Ƃ����ɂ͂ǂ����ȁH�Ǝv���܂�(^^;
�����ԍ��F19945918�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�l�Ԃ���3m������Ă����p46�x������ł��B 135�t�B�����̑Ίp������Ƃ����W�������Y��43mm�ł��B 1�_���Î������ꍇ�̉�p��100-105mm�����Y���炢���Ƃ����Ă��܂��B
�����ԍ��F21344729
![]() 1�_
1�_
����Ō����Ƃ��́u���ߊ��v�ɋ߂�����B
�u��p�v�ł͂Ȃ��A�����āu���ߊ��v�ƕ\���B
�ȏ�
�����ԍ��F21349057�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�t�@�C���_�[�{�����Ă̂��A�T�O�����̃����Y��t�������ɉ��{�ɂȂ�̂��H���Č��������Ƃ����K�i�Ɗ�ɂ���Đ��藧���Ă�\�L�Ȃ̂ŁA�T�O�������W�������Y�ł��B
�ǂ�ȃC���[�W�Z���T�[�̃J�����ł��t�@�C���_�[�{�����T�O�����̃����Y��t����������ɂ��Ă�̂ŁA�T�O�������W�������Y�ł��B
���݂ɔ{���̌v�Z�́A�J���������Y�̏œ_����÷�t�@�C���_�[�����Y�̏œ_�������{���ł��B
�ł���ŁA�t�@�C���_�[��`�����Ƃ��Ɏ��R�Ȍ��������W�������Y�̒�`�Ƃ���Ȃ�A�T�O÷�t�@���C���_�[�{���̃����Y�����̃J�����̕W�������Y�ɂȂ�܂��B
�v�Z�����ƁA�T�O÷X���t�@�C���_�[�{���@Y÷X���P�{�i����Ɠ����{���j�@Y=�t�@���_�[������Ԏ��R�Ɍ�����J���������Y�̏œ_����
�����A���R�Ɍ������p���ŕW�������Y���`����Ȃ�A�v�����g�������̊ӏ܋������`����K�v������܂��B�|�X�^�[�����ߋ����Ō����Ƃ�����L�p�����Y�̉�p�̕������R�����A�����������璭�߂�Ȃ�]�������Y�̉�p�̕������R�Ɍ����܂��B
�����ԍ��F21941284
![]() 0�_
0�_
�����Y > �j�R�� > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
���N�g�p���Ă���ƃs���g�����O������Ă��ďo�������X���[�Y�ɓ����Ȃ������ŁA�������͂k�u��AF�������Ȃ��ăs���g�����O���Ă��Ɠ����o���̂ł����A�F����͂ǂ��ł����H
�����ԍ��F21359201�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́B
�@�ǂ̃����Y������ȏǏ�ɂȂ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ��B�@���N���ĉ��N���炢�ǂ̂��炢�̕p�x�Ŏg���Ă��܂��H�@
���̃����Y�𑼂̂��������Ŏg���Ă������Ǐo�܂����H
���̂��������ő��̃����Y���g�������͏o�܂��H
�܂�A���̂T�O�P�S�f�������Ƃ����Č����͗L��܂����H
�����ԍ��F21359355
![]() 0�_
0�_
��Affogato����
���T�Œ����g���[�^�[�ׂ��
���_�́A���C�쓮�ׁ̈A�ϋv�������B
�Ə�����Ă��܂��B
DMF��p�ɂɍs����
�������Z���Ȃ肻���ł��B
MF�̃N���b�V�b�N�����Y�݂����ɁA�\�����ȒP�ł͖�������A
����ȃg���u�����o�₷���ł��傤�B
�����ԍ��F21359456�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��Affogato����
>> �s���g�����O������Ă��ďo�������X���[�Y�ɓ����Ȃ�
�s���g�����O����ő��삵�����A�u�����ڐ��v�͓����Ă��܂��ł��傤���H
���̏ꍇ�A���N�O�AAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED�̃����Y�ł����A
�u�t���^�C���}�j���A���t�H�[�J�X�v���o���Ȃ��Ȃ�A�C���ɏo�������Ƃ���܂��B
�Ȃ��AAF�͓��삵�Ă��܂����B
�����ԍ��F21359573
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́B
�������N�g�p���Ă���ƃs���g�����O������Ă��ďo�������X���[�Y�ɓ����Ȃ�������
�����O�̃O���X����Ă���̂�������Ȃ��ł��B�T�[�r�X�Z���^�[�Ō��Ē����āA�����O���X����Ă���悤�ł�����h���Ē����܂��B
�����ԍ��F21359960
![]() 0�_
0�_
gankooyaji13����ɂ���
5�N�ŏT1�`2��̃y�[�X�Ŏg�p���Ă����̂ł����{�f�B�͑����W�Ȃ��Ǝv���܂��B
�Ƃ肠����1.8G�����Ɏg�p���Ă��Ė��Ȃ��̂ł���������������g�p���Ă���ƃs���g�����O���ǂ��Ȃ邩�킩��܂���B
���Ƃ��Ǝ莝����f2.5�Ńs�������Ă��Ȃ��̂������Ǝv���Ă�����AF-C�Ńs���g���r������ǂ������Ă��Ȃ����ƂɋC�Â��s���g�����O��傫���Ă��Ɠ����o�����̂����������ł��������Ǝv���܂����B
�Œ������悤�ɓ����Ȃ��悤�ł��s���g�����O�����Ǝ��邵�T�[�r�X�Z���^�[�ŏC���̎��ɍČ�������̂ō����Ă��܂��B
��̎ʐ^�Ƃ���ɂ���
AF�݂̂Ńs���g�����O�͂��܂蓮�����Ȃ��̂ł����A�t�ɂ��ꂪ�����̂ł��傤��
������@������������ɂ���
�����ڐ��͓����Ă��܂���
�A���J���V�F������ɂ���
�T�[�r�X�Z���^�[�ň�Ă�����ĕ��������Ƃ�����̂ł����O���X�̘b�͒m��Ȃ������ł��B
����Č��܂��B
�����ԍ��F21359989
![]() 0�_
0�_
Affogato����
���[�J�[�ɁA�d�b�I
�����ԍ��F21361328�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����Y > �j�R�� > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Nikon��F1.4�܂ł����o�Ă܂���ˁB
����F1.2��F1.4���{�P�Ȃǂ͂����ĕς��Ȃ��̂ł��傤���H
�L���m�����o���Ă���Nikon���o���Ȃ��͉̂��̂Ȃ�ł��傤�H�H
�����ԍ��F19671333�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���P���^���E������
�P���Ɍ�ʕ����̌a���AAF���g�����Ԃł͏��������炾�Ǝv���܂����ǁB
�����ԍ��F19671392
![]() 5�_
5�_
���P���^���E������
�NjL���܂��B
�d�q�ړ_�̕������z�u�o���Ȃ����炾�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19671399
![]() 3�_
3�_
���P���^���E������
�⑫���܂��B
50mm�ł́A�\���I��Ai-S��50mm F1.2�����E���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19671403
![]() 3�_
3�_
��������@������������
�Ȃ�قǁB����ł͍����Nikon�����F1.2�̃����Y�͏o�Ă��Ȃ����ł��ˁB
�{�P���ʐ^�D���Ȗl�Ƃ��Ă͎c�O�ł�(T_T)
�����ԍ��F19671420�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ߋ��ɉ��x���o���b��ł��ˁB
�ڂ������Ƃ͂悭������܂��Z�p�I�ɖ������ۂ��悤�ł��B���s��F�}�E���g�ł́B
�����ԍ��F19671424
![]() 3�_
3�_
����Canon�ł́AF1.0�̃����Y�܂�
�L��܂���(�P^�P)�U
http://www.canon.com/c-museum/ja/product/ef283.html
���A�掿�̖��Ō��݂�F1.2�ɗ�����������[�ł�
Nikon�́A�܂��}�E���g�a�̖���
�����Ă܂����ǂ�
�����ԍ��F19671490�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
��kyonki����
��������4�o������
�ǁ[���ł��B
F1.0�̃����Y���������Ȃ�Ēm��܂���ł���(�K���K;
�����ԍ��F19671558�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���P���^���E������
�܂�����F1.0L�́A�`���̃����Y�ł�����˂�(�-_-�)
�����ᒆ�Âł�����ɓ���Ȃ��ł���
�v���~�A���t���Ă܂����烌�A�ł��鎖��
�ԈႢ�Ȃ��ł���d(�P �P)
�����ԍ��F19671596�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
��������4�o������
���[�ł������B�f�W�J���͐i�����Ă����̂悤�ȃ����Y���������Ă����̂��肤����ł��B
�����ԍ��F19671609�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�X�[�X�G�����{�����L���Ă܂����ˁI
�����ԍ��F19671622
![]() 2�_
2�_
���P���^���E������
�����ł��˂�
��ѐ�̌��̎��������
���Ȃ��Ȃ�܂�����
�݂�ȁA�D�����ɂȂ��Ă��܂��܂���
�܂��A���܂ɗ������܂���
���Ă�������ƌ��邩�ۂ���^_^;�H
�����ԍ��F19671634�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�{�P���Y�킳�́A���邳�����ł͖����Ǝv���܂���Bf1.2�́A�s���������V�r�A�ł��B
AF�̓\�j�[�̃^�C�v�łȂ��ƁH�H�H
50mm�łȂ�Nikon58mm�c�@�C�X55mm�̃{�P���Y�킳�́A���i�͈Ⴂ�܂����A�g�b�v�N���X���Ǝv���܂��B f1.4�ɂ��ւ�炸�A�ǂ�����s���̓V�r�A�ł����c
�����ԍ��F19671647
![]() 2�_
2�_
��������4�o������
�S�������v���܂��B
�l�͂܂��f�W�C�`����S�҂ł��̂ŕ��ɂȂ�܂����I
�����ԍ��F19671649�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��������
�l���g�����Ȃ��Ă邩�͕s��(���M����)�ł���
Nikon��58mmF1.4G�͐�������Ă��܂��܂����B
���̂Ƃ���1�ԋC�ɓ����Ă���܂��B
�c�A�C�X�Ƃ��͂܂��܂��悭�킩��Ȃ��̂�
������������ł��B
�����ԍ��F19671671�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���P���^���E������
�܂�Nikon�Řb���̂��A���ł�����
Canon��EF�}�E���g����
����F1.0������ɓ���}�E���g�a��
���肵���ƕ����Ă܂�(�P^�P)�U
http://plaza.rakuten.co.jp/utsurundesu/diary/200709220000/
�܂��ǂ��炪�A�����́A�킩��܂��ǂ�
�܂�����Ȋ�������(�-_-�)
http://s.kakaku.com/bbs/10501011808/SortID=10175885/
�����ԍ��F19671693�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��������4�o������
1.0L����40���Ƃ������ł���(�K���K;ܫ�
�����Șr�̂������ǁ[���Ă��~����������Ȃ���
�����ȒP�ɍw���ɂ������Əo���܂���B�B�B
�f���炵���ʂ肾�Ƃ͎v���܂����I�I
�����ԍ��F19671719�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�ȑOD800��AI Nikkor 50mm f/1.2S���g���Ă܂����B�J�����ƃn�����܂Ƃ����ĒP���Ɍ��s1.4�Ɣ�r���鐫���̉摜�ł͂Ȃ��ł��ˁB���Ȃ݂ɍ������s���i�Ȃ̂ŐV�i�Ŕ����܂��B
���ƒ����̃����Y�ɂȂ�܂�����MITAKON 50mm F0.95�Ȃ���9���~��Ŕ������ł����A�c�O�Ȃ���Nikon F�}�E���g�ł͏o�ĂȂ��݂����ł��ˁB�����MF�����Y�ł��B
�����ԍ��F19671853�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�L���m����50/F1.0�͈�x�茳�ɂ����Ă݂����Ǝv���A����AF����ꂽ��C���s�\�ł����̃I�u�W�F�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������|�������Ď肪�o�Ȃ���ł���˂��B
�L���m���ɕ����ł��o���Ă��炢�����Ȃ��B
�����ԍ��F19671869
![]() 4�_
4�_
58mm����ꂽ��ł��ˁB (^_^)
������Ƃ������Ŋ������ς�郌���Y�ł����A�͂܂�A���邢�����Y���܂߂Ă��A�ō���̃{�P���ƌ����Ă��܂��ˁB(�܂��l�����̕]�������Ĕ������̂ł���)
�����ԍ��F19671913
![]() 2�_
2�_
���ꂱ�����[�J�[�ɓd�b�I
���Ă䂤���c�ł���w
�����ԍ��F19671969
![]() 3�_
3�_
���P���^���E������
���[�Ȃ�
40���~�Ƃ����邻�[�ł�
�܂��ߋ��̃}�E���g�łł���
���̂�[�ȃ����Y������܂���
http://www.canon.com/c-museum/ja/product/s43.html
Canon�̑���a�����Y�́A
����Ӗ����ꂩ��n�܂����̂����H
�����ԍ��F19672113�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��������4�o������
1961�N������57000�~�I
�������Ȃ�10�{���炢�̒l�i�������[�ł��B�B(^_^;)
�����ԍ��F19672142�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
EF50mm��F1.4��F1.2L�ɂ��ẮA�f�[�^�ォ��{�P���l�@�������Ƃ�����܂��BF1.2L�̋������Ȃ��Ȃ����̂ŁA���͂܂��ł��Ă��܂��B
EF50mmF1.4
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n338348
EF50mmF1.2L
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n338478
������F1.2��F1.4���{�P�Ȃǂ͂����ĕς��Ȃ��̂ł��傤���H
��ۂƂ��ẮA�����Y���Ƃ��ꂼ��ł��B
�����ԍ��F19672152
![]() 1�_
1�_
��������4�o������
11���͖��͓I�ł��ˁI
�������ꂿ�Ⴂ�����ł�����(´�t�M|||)
�����ԍ��F19672231�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
50/1.2�Ɣ�ׂĂ݂܂������A
50mm���Ƃ���ȂɈ��Ȃ������H
��r�͂�����ɂ�����܂����B
http://www.kenrockwell.com/nikon/comparisons/58mm-bokeh/index.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/comparisons/50mm-f12/
�����ԍ��F19672237
![]() 2�_
2�_
����`��Q����
�{�P��Q�l�ɂȂ�܂����I
�l�̂悤�ȏ��S�҂��Ƃǂ̃����Y�������܂Ń{�P�Ă����Ζ����ł��I�I
�����ԍ��F19672263�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���P���^���E������
�ǂ��ł��傤�ˁE�E�E
�ł����̃��t�@�ł͎g���Ȃ������Y�Ȃ̂�
�g���Ă݂����Ȃ�\�j�[�@����
���݂͖��������ł��ˁB�B�B
�����ԍ��F19672319
![]() 2�_
2�_
��������4�o������
�\�j�[���ƃ�7�n��E�}�E���g�ł��傤���H
����Ƃ�A�}�E���g�̕��ł����ˁH
�����ԍ��F19672333�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���P���^���E������
�܂�FE�}�E���g�ł����
�g���邩���H���Ďv���܂��āE�E�E
�܂����������ƂȂ��ł����ǁE�E�E
�ł��R�������邩��ˁB�B�B
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review_2/20140602_651165.html
�����ԍ��F19672349
![]() 4�_
4�_
��������4�o������
�Ȃ�قǁB�\�j�[�ɂ���ȑΉ������Y�������ł��ˁI
��7R����Ȃ���悩�����ȁB�B
�����ԍ��F19672370�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���P���^���E������
�ł��ˁ`
�t���T�C�Y�~���[���X�̗��_��
�~���[�{�b�N�X�������̂Ńt�����W�o�b�N���Z���̂�
�����郌���Y���A�_�v�^�[��t����
�������o����_�ł���ˁO�O�G
�{���̃����Y���\�͏o���Ȃ��ł��傤��
�ł�
�Ƃ肠���������郌���Y�̖{���̌��w���\��
���\���邱�Ƃ��o�����ˁO�O
�����ԍ��F19672432
![]() 3�_
3�_
���P���^���E������
�����́B
���ݎ��̃V�X�e���ł͉�����50mm�P�œ_����ȂƂȂ��Ă���܂��āA
�����j�R���l����uAF-S NIKKOR 50mmF1.2G(E)�v�����\�E�����ɂȂ�����A
�u�������I�H�����[�I�v�Ƃ������Ȃ���X�y�b�N���Ȃ���3�b�Ń|�`�鎩�M������܂��B
���p��F1.2��F1.4���ǂ��ȂH�Ɩ���܂��ƁA�j�̃��}���Ƃ��������悤���Ȃ��̂ł����E�E�E�B
�o���Ȃ����R�͉��ƂȂ�������܂����A�o���Ȃ����Č������炻��ł����܂��Ȃ̂ŏo�Ă��Ăق����ł��i��]�j�B
�����ԍ��F19672479
![]() 3�_
3�_
��������4�o������
�Ȃ�قǁI�������t���T�C�Y�~���[���X�̗��_�ł������Ȃ�ł��ˁI
�ЂƂ��ɂȂ�܂����B����
�����ԍ��F19672506�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�]�E����
F1.2Nikon����o����ō��ł���ˁI
�Ȃ��Ȃ�����悤�ł���
�L���m���ɏo����Nikon�ɏo���Ȃ��̂����y���ł���B�B
�����ԍ��F19672522�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���L���m���ɏo����Nikon�ɏo���Ȃ��̂����y���ł���B�B
���̓L���m�����[�U�[�ł����A
���܂��ʌ����łȂ�F1.2�����邱�Ƃ���
����ʌ�����EF50mm F1.4���j�R���̂悤�ɑ����V�������Ă�I�Ǝv���Ă��܂���
�����ԍ��F19676012
![]() 0�_
0�_
�L�p�`�W���P�œ_��E�^�C�v�����}���ł��炢�����ł��ˁB
�����ԍ��F21325367
![]() 0�_
0�_
Nikon��F1.2�́A�m�N�g�j�b�R�[���ȊO�͂��܂�u�����v�Ƃ����]���ɂ͂Ȃ��ĂȂ��ł��˂��B
�i�m�N�g�j�b�R�[���ɉB��Ă��܂����Ƃ����ׂ���������܂��j
����a�����Y�Ƃ������̂́A�O�ʂ��傫���Ȃ�̂͂������ł����A���H���L���Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A��ʂ��傫���Ȃ��Ă͐������܂���B
���邢�����Y�̎�U���t�����Ȃ��Ȃ��o�Ă��Ȃ������̂͂��̂����ł��B�i�傫�ȃ����Y�𐳊m�ɓ������̂���������j
���̐́A�x�����w���o����55����F1.2�Ƃ��������Y�́A��ʂ�M42�}�E���g�̍i��A���s��������ł����A�����Y�̈ꕔ������Ď��߂��Ƃ�����b������܂��B�̂̃����W�t�@�C���_�[�J�����Ȃ�A�J�����{�̂Ƃ̘A���@�\������܂���A�}�E���g�a���肬��܂Ō�ʂ�傫���ł����̂ŁA�L���m����F0.95�Ȃ�Ă̂����������Ǝv���܂��B�i����ł�L�}�E���g�ɂł����ACanon7�̐�p�}�E���g�ł����j
Nikon�ł��A�d���i����g���n�߂��̂ŁA�i��A�����o�[�Ȃǂ��K�v�Ȃ��Ȃ�A�M���M���܂Ō�ʂ��L����F1.2�͎����ł��邩������܂���ˁBIF�ɂ��āA��ʂ��Œ�ł��郌���Y�\���ɂ���ł���A���ȁH
�����ԍ��F21325672
![]() 0�_
0�_
�����Y > �j�R�� > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
50mm�̒P�œ_�ŁA�w�����ǂ�ɂ��悤���Y��ł��܂��B
�{�f�B�͂c�V�O�O���g�p���Ă��܂��B
���ƒv���܂��ẮAAF-S NIKKOR 50mm f/1.8G�@or�@Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D�@or�@AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G�@�ł��B
���i�̈Ⴂ�͂���ǁA���\�ʂł́AAF-S NIKKOR 50mm f/1.4G�@�ɂ��悤���Ȃƍl���Ă���܂��B
���Ȃ݂ɁAAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED�@�͏������Ă���܂��B
�ǂȂ����A�ڂ���������܂�����A�䋳���̂قǁA�X�������肢�v���܂��B
![]() 2�_
2�_
http://ganref.jp/items/lens/list?sf3=&sf2=&sf1=&sf4=&sf5=&sf6=&sf7=&sf8=&lm=&dis=1&m13=&m55=&m96=&m27=&m29=&m15=&m28=&m16=1&m17=&m18=&m19=&m20=&m21=&m22=&m23=&m65=&m69=&sd=&cpn=&cpd=&we=&sflz=&lc=&sfl=&lfl=&fnm=&mf=&is=&wdr=&sort=&direction=&page=&search=1
��������Q�l�ɂ��Ă݂Ă͂������ł��傤���H
�����ԍ��F15012844
![]() 3�_
3�_
����ɂ��́B��BVLGARI������
50mm f/1.8G��50mm f/1.4G��50mm f/1.4D���ʂ�͂قړ�����
�v��ꂽ�ق����ǂ������ł��ˁB
����50mm f/1.4D��AF���Ŏ��ɉ�������̂ɑ���50mm f/1.8G��
50mm f/1.4G��AF���Ŏ��͖����ɋ߂���Ԃł��B
�����ԍ��F15013008
![]() 3�_
3�_
1.8G��1.4G�͖��邳�̈Ⴂ�ʂő傫�����Ȃ��ł���1.4D��G�^�C�v�ɔ�ׂ�Ə_�炩���Ƃ������V���[�v�ł͂Ȃ��`�ʂ����܂�
���Ȃ݂Ɍ��\�Ⴂ�܂���A�ŐV�v�̃V���[�v�ȕ`�ʂ��D�݂Ȃ��G�^�C�v�����Y�A�_�炩���`�ʂ��D���Ȃ��D�^�C�v�����Y�I�ȁE�E�E
�����ԍ��F15015386
![]() 5�_
5�_
�l�i��OK�Ȃ�AF1.4G�̕����قڂ��ׂāi���ӌ������\�͗�O)
�S�Ă̖ʂŗD��Ă��܂��B
http://slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/1432/cat/12
F1.8G��CA�i�F���k)�����ŁA���Ӊ掿��F1.4G�̂ق����ǂ��A����F5.6���炢�܂ōi��Ƃǂ�����ǂ��B
���͗��������Ă��܂����Af1.4G�̂ق����e�X�g���ʂǂ���ǂ��悤�ł��B
���������SLRgear�̕]���ł�������Ă��܂����AF1.4G�͊J������Speherical aberration�@�����Ȃ肠�邱�Ƃ͏�����肩�ȁA���ꂪ����̂ŊJ�����͂��̃����Y�͎���Resolution�ȏ�ɊJ���ł̉掿�͈���������̂ł��B
����F1.8G���������͂���܂����AF1.8�܂ōi��AAFS50f1.4G�͂��Ȃ�ǂ��Ȃ�܂��̂ŁA�ǂ����Ă�2���~���炢�̗\�Z�����p�ӂł��Ȃ��̂łȂ���AF1.4G�̕����ǂ��ł��傤�B
F1.8G�͓��{�ł͕K�v�ȏ�ɂ悭�����Ă��܂����A�C�O�̐��m�ȃe�X�g�ł͂���F1.4g�����Ƃ������ʂł��B
�ł��l�I�ɂ͗\�Z�������̂ł���AZeiss50mmf�QMakroPlanar���ǂ��Ǝv���܂��B
����Zeiss50mm��1.4����Nikon��AFS50mmf1.4G�̕����ǂ����AAF������̂ő����I�ɂ͂��ꂪ��Ԗ���ł��傤�B
�Ō�ɑ傫�����C�ɂȂ炸�A���Ӊ掿�͏d�v�łȂ��Ƃ����ꍇ��SLRGEAR�������悤�ɁA����Sigma50mmf1.4�̓{�P���ǂ��AFlare���o�ɂ����ǂ��ł��ˁB
�������Ӊ掿�ł͏�����F1.4G����Ԃł��BF1.8G�͂����܂ł��A���i�̊��ɂ͗ǂ������Y�Ƃ������Ƃł��A����ȏ�ł�����ȉ��ł�����܂���B
�����ԍ��F15017310
![]() 14�_
14�_
������ƐM�����Ȃ��̂ł����A1.8G���1.4G�̎��ӂ������Ƃ����͖̂{���ɗ����g���Ă���������̈ӌ��ł����H
���l���f�[�^�Ȃ�Ď��g�p�̏�ʂł͂ǂ��ł������A�܂萔�l�ɕ\���D�G���́A���ۂ̏�ʂł̗D�G���ƈ�v����Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
������Resolution�ȏ�ɊJ���ł̉掿�͈���������̂ł��B
�̐S�̉掿��������������A���ۂ̐��l���ǂ��Ă��S���Ӗ��Ȃ��Ȃ��ł��傤���H
�������������{�g�p������ۂł́A���Ӊ掿�̈��萫��ASPH��1.8G�̈����ł��B
���̌��ʂ͓��Ǝ҂Ńu���C���h�e�X�g�����Ă���ڗđR�ł����B
�Ⴆ1.4G�����l�I�ɗD��Ă���Ƃ��Ă��A������i���ɑO�{�P�̗��ꂪ�Ђǂ�����j��{�P�������Ă͊J�����g���Ȃ��̂͑傫�ȃ}�C�i�X�Ǝv���܂��B
�ے�I�Ő\����Ȃ��ł����A1.4G�̃l�K�e�B�u�Ȉӌ��Ƃ��ăX����l�̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B
�����ԍ��F16703768
![]() 11�_
11�_
�����Y > �j�R�� > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
���̂T�O�P�S�́C�\��̒ʂ�C
�i��H���̎d�l�ύX������܂����B
��]�҂ɂ́C�����ŏC���E�������邻���ł��B
�R�T�P�W���ŐV�J�^���O�ɂ́C�~�`�Ƃ������Ă���܂����C
���V�p�`�ł��B
�F����̃����Y�͂������ł����B
![]() 1�_
1�_
fuga8787����A����ɂ��́B
�i��̌��́A���̏��Ɠ����ł��傤���H
��
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503512029/SortID=11346607
���ɂP�N�߂��o���Ă��܂����A���ꂩ��܂����ǂ��ꂽ�Ƃ���
���ł��傤���B
���Ȃ݂ɁA�����͖����Ƃ�����Ȃ������̂ł����A�V����
�����ŏC���ł���Ƃ������Ȃ̂ł��傤���H
�����ɂȂ����̂Ȃ�A�����ɏC���ł��� (^^;
�����ԍ��F12700502
![]() 0�_
0�_
�@�����u�C�������Ȃ̂ŕۏ؊��ԊO�͗L���v���Ɨ������Ă��܂������A
>��]�҂ɂ́C�����ŏC���E�������邻���ł��B
�@�͊��������ł��ˁB
�����ԍ��F12700549
![]() 0�_
0�_
fuga8787����@����ɂ��́B
�@����]�҂ɂ́C�����ŏC���E�������邻���ł��B
�@��͂ǂ��ł��傤���H�@�j�R���̂g�o�ɂ͌�������܂���ł����B
�i���̒T�����������̂��H�j
�����ԍ��F12700612
![]() 0�_
0�_
�~�`�ƌ����Ă��A�i��H�̏W���̂ł́A���~�͂��蓾�Ȃ����A�����ɍS��̂��@�����ȂƁc
�g���ăi���{�̂��̂��Ǝv�����c
�X���傳��́A�����悤�ȃX�������ĉ���]��ł���̂��c
�����ԍ��F12700657
![]() 8�_
8�_
����L�^�����ŁA�V�i�ɂ�2�_�����Ă�������̂ł����A2�_�Ƃ��i��H�͘c�Ȍ`��ł����B
�~�̔������Y��Ȍʂ�`���Ă����̂ł����A���Α��̔����̓K�^�K�^�ł����B
���݂ɐ����ԍ���38����������n�܂郍�b�g�ł��B
���̓V�O�}����̔����ւ��������̂ł����A���܂��܃l�b�g���Âŗ���ł��������A�Y��ȉ~�`�������̂Ō��ǒ��Â��w�����܂����B
������̐����ԍ���31�������ł����B
�������b�g�ł������Ă����s����Ĕ����Ă���̂ł��傤���H
�����ԍ��F14407080�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����Y > �j�R�� > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G��AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G���Ƃǂ���̂ق���AF�������̂ł��傤��??
�܂��A�{�P���Ȃǂ��l�����Ă݂Ȃ���͂ǂ��炪�����I�ɏゾ�Ǝv���܂���??
�����ԍ��F14102634�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G �̔ɂ��A�S���������e�œ��e����Ă����܂��ˁB
�}���`�|�X�g�́A�֎~����Ă��܂��B
�����œ_�����Ȃ�A��ʓI�ɁA�����]���͉��i�ɔ��f����܂��B
�]���āAF1.4G����ł��傤�B
F1.4�܂ōi����J�������ł��܂����AF1.8G�ł͏o���܂���B
F1.8G�̕��͎����Ă��Ȃ��̂Ŕ�r�ł��܂��� (^^;
�����Y���̎ʂ�̈Ⴂ���y���ނƂ�������Ȃ��̂ŁA���݂܂���B
�����ԍ��F14102693
![]() 1�_
1�_
�����́BSP_RF����
AF���ŃX�s�[�h�E�{�P����1.8G���1.4G����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F14103745
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�����Y]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z�~�������̃��X�g
-
�y�������߃��X�g�z���X1440���Q�[������l����
-
�y�������߃��X�g�z���X�X���p
-
�y�~�������̃��X�g�z�V�Z�p�������@�̎���PC
-
�y�~�������̃��X�g�zDDR4�őË��\��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2026�N2���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2026�N1���z

�^�u���b�gPC
- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2026�N2���z

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�����Y
�i�ŋ�10�N�ȓ��̔����E�o�^�j