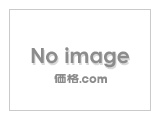
こんばんは 質問があります。
バランス入力端子に位相スイッチがありますが、
ノーマル 2番がGOID
リバース 2番がHOT
となっていますが バランスケーブルの 普通 は2番 HOT ですよね?
自作ケーブルRCA→XLR を2番HOT で今まで ノーマル設定で気がつかず使用してました。
ちょっとショックでした。
書込番号:9176922
![]() 0点
0点
クリスタルピアノさん、こんにちは。
>バランスケーブルの 普通 は2番 HOT ですよね?
最近は2番HOTに統一されていますが(AESが2番HOTを標準に推しているから)、オーディオ業界はまだ3番HOTを使いつづけてるメーカーもあるみたいです。理由はよくわかりません。
>ノーマル 2番がGOID
>リバース 2番がHOT
ノーマルは2番GOIDじゃなくて2番COLDですね。
片側がRCAならどのみち正相しかでてないはずなのでどっちがHOTでも何も問題ないです。
(私の記憶では505fはバランス入力はありますが、内部はアンバランスなはずなので)。
そもそも、出力がアンバランスなら無理にバランス(端子)にする意味はないと思いますよ?
(出力にバランスがあったとしても、一般家庭ではアンバランスで繋いだほうが良いと思いますけど)
書込番号:9179650
![]() 2点
2点
あ、書き忘れたので補足しますけど、
>>バランスケーブルの 普通 は2番 HOT ですよね?
ケーブルには2番と3番のどちらがHOTかは関係ありません。
(というよりそんな区別ありません)
あるのは接続するターミナルの2番と3番のどちらがHOT(正相)になるか、だけです。
書込番号:9179713
![]() 1点
1点
クリスタルピアノさん、はじめまして。
XLRバランス入出力が備わった機器だと使ってみたくなるのは心情だと思います。
もともとがバランス設計であれアンバランス設計であれ回路構成が異なりますから、
アンプ、CDプレイヤーともにRCAとは音調が異なることが少なくありません。
音調(音色)のバリエーションだと思ってソースや気分で使い分けるのも楽しいと思います。
当方もバランス設計のプリアンプからアンバランス設計のパワーアンプへXLR→RCAケーブルで繋いだり、
アンプとCDプレイヤー間をXLR、RCAの両方で繋いで使ったりしています。
HOT、COLD、GROUNDについてはsarlioさんのお話の通りです。
信号の方向指定がある導体(芯線)を使用したXLRケーブルも一部ですが存在します。
但しほとんどの製品は1番のGROUNDが決まっているだけです。
XLRバランス接続についてはけっこう多くのスレッドでコメントさせて頂きました。
参考になれば幸いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8984566/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20495010020/SortID=8107223/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20483510103/SortID=8572071/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20489910106/SortID=8728219/
書込番号:9180738
![]() 3点
3点
redfoderaさん
回答者が質問者になって申し訳ないのですが、ひとつ教えてください。
リンク先を一通りみたのですが、その中で『バランス接続ではゲインがあがるのでS/Nが向上する』と読める記述がありますが、本当ですか?
私の認識ではバランス回路では正相のHOTと逆相のCOLDを送出して、受側でCOLDを再度逆相にして外来ノイズをキャンセルする仕掛けだと思っていました。(ちょっと大雑把な説明ですけと゛)
この理屈でいうとゲインが倍になるのは仕組みによるもので送出レベルが高い訳ではないので、ノイズフロアも一緒に倍になるだけのような気がします。
業務機であればバランス出力は+4dBあるのでノイズフロアに有利なのは分かりますが、民生機ではどっちも−10なので全く意味ないどころかインピーダンスも低くなるし回路が複雑になるしで良いことはひとつもないと思うのですが、何か明確なメリットがあるのでしょうか?
もちろん、外来ノイズに強いというのは明確ですが、たかだか数メートルの配線ならバランス送信に頼らずとも十分だと思うのです。
書込番号:9182331
![]() 1点
1点
sarlioさん、こんばんは。
お久しぶりです。
>私の認識ではバランス回路では正相のHOTと逆相のCOLDを送出して、
>受側でCOLDを再度逆相にして外来ノイズをキャンセルする仕掛けだと思っていました。
>この理屈でいうとゲインが倍になるのは仕組みによるもので送出レベルが高い訳ではないので、
>ノイズフロアも一緒に倍になるだけのような気がします。
ご指摘の通りです。
ソースのゲインが上がると音量音圧ともに上昇するので特に省音量時にS/Nが良くなったと「錯覚」しやすいんですね。
人間の聴感上の錯覚現象について説明したかったのであって、直接的な音質改善に繋がるとの意図はありません。
実際にはノイズ・レベルも上がっているはずです。
>業務機であればバランス出力は+4dBあるのでノイズフロアに有利なのは分かりますが、
>民生機ではどっちも−10なので全く意味ないどころかインピーダンスも低くなるし回路が複雑になるしで
>良いことはひとつもないと思うのですが、何か明確なメリットがあるのでしょうか?
ケーブル単体で考えた場合は明確なメリットがあるアイテムもありますがCD-DAの再生ではあまりメリットがありません。
ケーブル単体のメリットをあえて挙げるなら・・・
RCAアンバランスの場合は構造上、S/N100dBを超えるケーブルはおそらく制作できませんが、
XLRのノンシールド・タイプですとダイナミックレンジ120dB前後のS/Nに関する理論値に近いケーブルが作れます。
市販ですとKIMBERやABBEY ROADにこのタイプのケーブルがあります。
銅メッシュやアルミ箔などで導体をシールドするケーブルが一般的ですしほとんどの物がこのタイプです。
実はシールドすることでS/Nに関してはコンプレッションされてしまいます。
方やノンシールドは名前の通りで外来ノイズに対するシールド構造を持っていません。
芯線+絶縁材だけの導体でケーブルを制作できるのがXLRバランス・ケーブルのメリットといえます。
理屈はsarlioさんのご指摘にある正相と逆相でノイズが相殺できるからです。
ただしXLRバランスといえどこのタイプでは外来ノイズが飛び込みやすくなるので長尺のケーブルはありません。
実用上メリットがない理由は・・・
CD-DA規格ではもともと120dBものダイナミックレンジを持っていませんから、
オーバー・スペックのケーブルを繋いだとしても意味がないんです(苦笑)
XLRノンシールド・タイプはあくまでも録音収録環境でこそ本領を発揮するケーブルです。
過去にその辺りに触れたカキコミもしておりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20499010103/SortID=8908943/
書込番号:9187790
![]() 1点
1点
redfoderaさん
ぶるぶるぶる、さむいですねぇ…。
>人間の聴感上の錯覚現象について説明したかったのであって、直接的な音質改善に繋がるとの意図はありません。
いちゃもんつけたみたいで申しわけありませんでした、なるほど、それならなっとくです。
>実はシールドすることでS/Nに関してはコンプレッションされてしまいます。
この話はよくわからないですが、シールドケーブルだと内から外へのノイズも出ていかないという類いの話でしょうか。平衡回路はコモンモードノイズには確かに強いですけどノーマルモードノイズには無力なので、やっぱり出所が同じオーディオ機でバランス出力があったところで大してメリットなどないと思います…(すみません、がんこで)。
それに、ダイナミックレンジの上が固定(それも大抵は小さく固定)の家庭環境ではダイナミックレンジが広ければ広いほどその恩恵である小さい音が暗騒音に埋もれて聴こえなくなってしまうので、広いダイナミックレンジのメリットに肖りにくいというのはありますよね。試聴室みたいな恵まれた環境で聴いているような人なら別ですけど。
とはいえ、確かにOldNeveやSSLのコンソールなんかでマイクプリの音をモニタリングしてるときに感じる微小ノイズ(フィンガリングとかリップノイズとか)のゾクゾク感はノンシールドのケーブルじゃないと味わえないかもしれないですね…、オーディオとはちょと違う世界の話ですけど。
すみません、ちょっと脱線しちゃいましたね。
つきあわせてしまってすみませんでした。
書込番号:9192534
![]() 0点
0点
クリスタルピアノさん、専門的な方向に脱線して申し訳ありません。
sarlioさん
>平衡回路はコモンモードノイズには確かに強いですけどノーマルモードノイズには無力なので、
>やっぱり出所が同じオーディオ機でバランス出力があったところで大してメリットなどないと思います…
>(すみません、がんこで)。
いえいえ、なんのなんの(笑)
原音再生というのかソースに対していかに忠実な方向を目指すかだと、sarlioさんのお話の通りだと思います。
回路的なことで言えばオペアンプ(要は石)の類いだと、接点は増えるしノイズは乗りやすいし、ですよね。
趣向からいくと当方の場合はピュア・オーディオ然としてくれる必要を感じないタイプなので、
音が変わったって平気なわけでむしろ気持ちよく聴かせてくれればバランスでもアンバランスでもかまわない人です。
出力トランスが大好きな人でライン・トランスの常用癖もあります。
で、こんなレビューもしちゃいましたがほとんどの方が喰いつきませんでした(苦笑)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8819370/
>家庭環境ではダイナミックレンジが広ければ広いほど
>その恩恵である小さい音が暗騒音に埋もれて聴こえなくなってしまう
家庭環境のダイナミックレンジに適切な数値というのがあるのかわかりませんがスペック上は大きい方が良いはずで、
実用上意味がないので切り捨てましただとCD-DAの再生周波数帯域と同じことになってしまいませんか?
間接的な影響も有る得るので聴こえないから不要とは考えたくないですね(笑)
>確かにOldNeveやSSLのコンソールなんかでマイクプリの音をモニタリングしてるときに感じる
>微小ノイズ(フィンガリングとかリップノイズとか)のゾクゾク感は
>ノンシールドのケーブルじゃないと味わえないかもしれないですね
お気持ちはわかります。
ちなみに実用上はメリット無いと言いつつノンシールド・タイプを自宅では使っています。
ケーブルのカスタマーさんにOYAIDEのPC-OCCで作ってもらって、最近、導入しました。
ゾクゾク感はしませんが新しい物を入れたワクワク感はありますよ(爆)
立ち上がりや消え際のレスポンスがシールド・タイプより良い様な感じがします(それこそ錯覚かもしれませんが・・・笑)
書込番号:9193415
![]() 1点
1点
redfoderaさん
私の与太話にお付き合いさせてしまってほんっとに申し訳ないです。
私自身は原音再生に特に拘りがあるわけではなく寧ろ色々遊びたいタイプなので、その筋の先達に見せたら卒倒するようなおもちゃも沢山もってます…。ただ、私は自分で納得がいかないことには気が済むまで疑ってみる性分のようで(人事のように語るのは、私もつい最近になって自分のこの性格に気づいたから…)、理解できないことはついつい質問責にしてしまいます。
>家庭環境のダイナミックレンジに適切な数値というのがあるのかわかりませんがスペック上は大きい方が良いはずで、実用上意味がないので切り捨てましただとCD-DAの再生周波数帯域と同じことになってしまいませんか?
適切な数値があるとは私も思ってはいません。例えば有名な1812Overtureには轟音のキャノン砲がオケに混じって鳴らされる録音がありますが、CDの理論上のダイナミックレンジ(6dB x 16bit = 96dB)の中ではキャノン砲の音量にあわせればオケの音量が足りずカサカサとか細い音になり、オケに合せればキャノン砲がバリバリと歪んで聴くに耐えない音になります。これが120dB確保できるなら現実的なコントラストで両者を慣らすことができるかもしれません。ただし、オケとキャノン砲の音量差が非常に大きいならば、オケを聴くための音量に合せて聴いているとキャノン砲はとてつもなく大きな音で再生されることになり、逆にキャノン砲を聴くための音量に合せて聴けばオケはチロチロと鳴るだけとなるでしょう。一般の家庭環境では再生音の音量にモラルという意味で上限があるので、ダイナミックレンジが広い音源のどの部分に音量を合せるか、それによっては(そして環境によっては)広いダイナミックレンジが必ずしもメリットではない、という意味
で先の書き方をしました。もちろん、この場はケーブルのダイナミックレンジの話なのでケーブルスペックとしての良し/悪しで問うならば私も「良し」で異存なしです。
※ちなみに、TELARCの1812Overtureのディスクジャケットには「貴方の再生装置にダメージを与える可能性があるので初回はボリュームを絞って聴きなさい」というワーニングが書かれています。
※実際の1812Overtureの録音ではキャノン砲だけ別録りして音量を合せて合成したり、ホールの外で鳴らしたのをオケに合せたりと工夫されてるようで、現実の音量差で録音されている訳ではないそうです(あたりまえですが)。
ワクワク感は大事ですね、モチベーション維持には特に必要です。
書込番号:9195955
![]() 1点
1点
お二人様
書き込みありがとうございます。
質問への答え、また、その他の内容も勉強になりました。
わからない内容もあったりですがありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:9248394
![]() 0点
0点
思いつくままで失礼します。
バランスはBTL接続なので倍とはいかなくともゲインは上がります。
物は違いますがプリメインアンプも初段のゲインを上げた設計の方が歪みが少ないようです。
結果的にSNも上がります。
初段にもMOS-FETを使うのもそのためで、
知る人ぞ知る金田式アンプは初段のゲインが高いので有名です。
バランス接続はインピーダンスも下がるためアンプにとってはストレスがかかります。
ラックスマンアンプを使っていたときバランス接続でしたが、
同じ素材のケーブルでもバランスの方が高音質ではないかと感じていました。
今思うとそれが原因ではないかと私は思っています。
書込番号:9250278
![]() 0点
0点
アンプに限って。
バイアンプでは問題ありませんが、
BTL接続は理屈では電圧2倍で、電力=Wは4倍です。
現実には2倍程度の出力です。
4倍の出力が得られるアンプは強靭な電源と冷却能力のある、
超高級品の一部のアンプしかありません。
またSNも全て数値で判断する事はできません。
ノイズがあるほうが聴きとりやすいと言う人間の聴覚の特性もあります。
WADIAの高級機は超高域を擬似的に付加した事で有名ですが、
超高域(20KHz以上)のノイズを出力に対して加えるだけのものまであります。
それでも楽器がしなやかに聞こえると言うのですから不思議です。
もちろん初段のゲインを上げる設計でSN比は向上しますが。
CDプレーヤーの出力信号レベルは規格化されて一定です。
シンプルなプリを高出力発生器として考えると、
プリアンプで音が良くなる理由もそこにあるとも思います。
その場合プリのSN比は重要になりますが。
書込番号:9276895
![]() 0点
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「LUXMAN > L-505f」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 11 | 2009/03/20 19:22:59 | |
| 13 | 2007/09/11 17:46:38 | |
| 11 | 2007/08/02 12:43:39 | |
| 20 | 2007/05/02 19:20:26 | |
| 8 | 2007/04/16 22:55:53 | |
| 1 | 2007/02/27 13:36:56 | |
| 20 | 2006/12/29 14:28:59 | |
| 0 | 2006/10/18 0:44:01 | |
| 0 | 2006/09/19 21:43:38 | |
| 5 | 2006/09/02 3:46:42 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
-
【おすすめリスト】おススメ用
-
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
-
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
-
【欲しいものリスト】AM5
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
プリメインアンプ
(最近3年以内の発売・登録)











