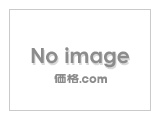
L-505fLUXMAN
�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �o�^���F2004�N11��15��
���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S13�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 2009�N3��20�� 19:22 | |
| 30 | 13 | 2007�N9��11�� 17:46 | |
| 2 | 11 | 2007�N8��2�� 12:43 | |
| 1 | 20 | 2007�N5��2�� 19:20 | |
| 1 | 8 | 2007�N4��16�� 22:55 | |
| 0 | 1 | 2007�N2��27�� 13:36 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�v�����C���A���v > LUXMAN > L-505f
�����́@���₪����܂��B
�o�����X���͒[�q�Ɉʑ��X�C�b�`������܂����A
�m�[�}���@�Q�Ԃ�GOID�@�@
���o�[�X�@�Q�Ԃ�HOT�@
�ƂȂ��Ă��܂����@�o�����X�P�[�u���́@���ʁ@�͂Q�ԁ@HOT�@�ł���ˁH
����P�[�u��RCA��XLR�@���Q��HOT�@�ō��܂Ł@�m�[�}���ݒ�ŋC�������g�p���Ă܂����B
������ƃV���b�N�ł����B
![]() 0�_
0�_
�N���X�^���s�A�m����A����ɂ��́B
���o�����X�P�[�u���́@���ʁ@�͂Q�ԁ@HOT�@�ł���ˁH
�ŋ߂͂Q�Ԃg�n�s�ɓ��ꂳ��Ă��܂����i�`�d�r���Q�Ԃg�n�s��W���ɐ����Ă��邩��j�A�I�[�f�B�I�ƊE�͂܂��R�Ԃg�n�s���g���Â��Ă郁�[�J�[������݂����ł��B���R�͂悭�킩��܂���B
���m�[�}���@�Q�Ԃ�GOID�@�@
�����o�[�X�@�Q�Ԃ�HOT�@
�m�[�}����2��GOID����Ȃ���2��COLD�ł��ˁB
�Б���RCA�Ȃ�ǂ݂̂����������łĂȂ��͂��Ȃ̂łǂ�����HOT�ł��������Ȃ��ł��B
�i���̋L���ł�505f�̓o�����X���͂͂���܂����A�����̓A���o�����X�Ȃ͂��Ȃ̂Łj�B
���������A�o�͂��A���o�����X�Ȃ疳���Ƀo�����X�i�[�q�j�ɂ���Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂���H
�i�o�͂Ƀo�����X���������Ƃ��Ă��A��ʉƒ�ł̓A���o�����X�Ōq�����ق����ǂ��Ǝv���܂����ǁj
�����ԍ��F9179650
![]() 2�_
2�_
���A�����Y�ꂽ�̂ŕ⑫���܂����ǁA
�����o�����X�P�[�u���́@���ʁ@�͂Q�ԁ@HOT�@�ł���ˁH
�P�[�u���ɂ͂Q�ԂƂR�Ԃ̂ǂ��炪HOT���͊W����܂���B
�i�Ƃ�����肻��ȋ�ʂ���܂���j
����̂͐ڑ�����^�[�~�i���̂Q�ԂƂR�Ԃ̂ǂ��炪HOT�i�����j�ɂȂ邩�A�����ł��B
�����ԍ��F9179713
![]() 1�_
1�_
�N���X�^���s�A�m����A�͂��߂܂��āB
XLR�o�����X���o�͂���������@�킾�Ǝg���Ă݂����Ȃ�̂͐S��Ǝv���܂��B
���Ƃ��Ƃ��o�����X�v�ł���A���o�����X�v�ł����H�\�����قȂ�܂�����A
�A���v�ACD�v���C���[�Ƃ���RCA�Ƃ͉������قȂ邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B
�����i���F�j�̃o���G�[�V�������Ǝv���ă\�[�X��C���Ŏg��������̂��y�����Ǝv���܂��B
�������o�����X�v�̃v���A���v����A���o�����X�v�̃p���[�A���v��XLR��RCA�P�[�u���Ōq������A
�A���v�Ƃb�c�v���C���[�Ԃ�XLR�ARCA�̗����Ōq���Ŏg�����肵�Ă��܂��B
HOT�ACOLD�AGROUND�ɂ��Ă�sarlio����̂��b�̒ʂ�ł��B
�M���̕����w�肪���铱�́i�c���j���g�p����XLR�P�[�u�����ꕔ�ł������݂��܂��B
�A���قƂ�ǂ̐��i�͂P�Ԃ�GROUND�����܂��Ă��邾���ł��B
XLR�o�����X�ڑ��ɂ��Ă͂������������̃X���b�h�ŃR�����g�����Ē����܂����B
�Q�l�ɂȂ�K���ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8984566/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20495010020/SortID=8107223/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20483510103/SortID=8572071/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20489910106/SortID=8728219/
�����ԍ��F9180738
![]() 3�_
3�_
redfodera����
�҂�����҂ɂȂ��Đ\����Ȃ��̂ł����A�ЂƂ����Ă��������B
�����N�����ʂ�݂��̂ł����A���̒��Łw�o�����X�ڑ��ł̓Q�C����������̂�S/N�����シ��x�Ɠǂ߂�L�q������܂����A�{���ł����H
���̔F���ł̓o�����X��H�ł͐�����HOT�Ƌt����COLD�𑗏o���āA��COLD���ēx�t���ɂ��ĊO���m�C�Y���L�����Z������d�|�����Ǝv���Ă��܂����B(������Ƒ�G�c�Ȑ����ł����ƁJ)
���̗����ł����ƃQ�C�����{�ɂȂ�͎̂d�g�݂ɂ����̂ő��o���x����������ł͂Ȃ��̂ŁA�m�C�Y�t���A���ꏏ�ɔ{�ɂȂ邾���̂悤�ȋC�����܂��B
�Ɩ��@�ł���o�����X�o�͂́{4dB����̂Ńm�C�Y�t���A�ɗL���Ȃ͕̂�����܂����A�����@�ł͂ǂ������|10�Ȃ̂őS���Ӗ��Ȃ��ǂ��납�C���s�[�_���X���Ⴍ�Ȃ邵��H�����G�ɂȂ邵�ŗǂ����Ƃ͂ЂƂ��Ȃ��Ǝv���̂ł����A�������m�ȃ����b�g������̂ł��傤���H
�������A�O���m�C�Y�ɋ����Ƃ����͖̂��m�ł����A�������������[�g���̔z���Ȃ�o�����X���M�ɗ��炸�Ƃ��\�����Ǝv���̂ł��B
�����ԍ��F9182331
![]() 1�_
1�_
sarlio����A�����́B
���v���Ԃ�ł��B
�����̔F���ł̓o�����X��H�ł͐�����HOT�Ƌt����COLD�𑗏o���āA
����COLD���ēx�t���ɂ��ĊO���m�C�Y���L�����Z������d�|�����Ǝv���Ă��܂����B
�����̗����ł����ƃQ�C�����{�ɂȂ�͎̂d�g�݂ɂ����̂ő��o���x����������ł͂Ȃ��̂ŁA
���m�C�Y�t���A���ꏏ�ɔ{�ɂȂ邾���̂悤�ȋC�����܂��B
���w�E�̒ʂ�ł��B
�\�[�X�̃Q�C�����オ��Ɖ��ʉ����Ƃ��ɏ㏸����̂œ��ɏȉ��ʎ���S/N���ǂ��Ȃ����Ɓu���o�v���₷����ł��ˁB
�l�Ԃ̒�����̍��o���ۂɂ��Đ��������������̂ł����āA���ړI�ȉ������P�Ɍq����Ƃ̈Ӑ}�͂���܂���B
���ۂɂ̓m�C�Y�E���x�����オ���Ă���͂��ł��B
���Ɩ��@�ł���o�����X�o�͂́{4dB����̂Ńm�C�Y�t���A�ɗL���Ȃ͕̂�����܂����A
�������@�ł͂ǂ������|10�Ȃ̂őS���Ӗ��Ȃ��ǂ��납�C���s�[�_���X���Ⴍ�Ȃ邵��H�����G�ɂȂ邵��
���ǂ����Ƃ͂ЂƂ��Ȃ��Ǝv���̂ł����A�������m�ȃ����b�g������̂ł��傤���H
�P�[�u���P�̂ōl�����ꍇ�͖��m�ȃ����b�g������A�C�e��������܂���CD-DA�̍Đ��ł͂��܂胁���b�g������܂���B
�P�[�u���P�̂̃����b�g�������ċ�����Ȃ�E�E�E
RCA�A���o�����X�̏ꍇ�͍\����AS/N100dB����P�[�u���͂����炭����ł��܂��A
XLR�̃m���V�[���h�E�^�C�v�ł��ƃ_�C�i�~�b�N�����W120dB�O���S/N�Ɋւ��闝�_�l�ɋ߂��P�[�u�������܂��B
�s�̂ł���KIMBER��ABBEY ROAD�ɂ��̃^�C�v�̃P�[�u��������܂��B
�����b�V����A���~���Ȃǂœ��̂��V�[���h����P�[�u������ʓI�ł����قƂ�ǂ̕������̃^�C�v�ł��B
���̓V�[���h���邱�Ƃ�S/N�Ɋւ��Ă̓R���v���b�V��������Ă��܂��܂��B
����m���V�[���h�͖��O�̒ʂ�ŊO���m�C�Y�ɑ���V�[���h�\���������Ă��܂���B
�c��+�≏�ނ����̓��̂ŃP�[�u���𐧍�ł���̂�XLR�o�����X�E�P�[�u���̃����b�g�Ƃ����܂��B
������sarlio����̂��w�E�ɂ��鐳���Ƌt���Ńm�C�Y�����E�ł��邩��ł��B
������XLR�o�����X�Ƃ����ǂ��̃^�C�v�ł͊O���m�C�Y����э��݂₷���Ȃ�̂Œ��ڂ̃P�[�u���͂���܂���B
���p�チ���b�g���Ȃ����R�́E�E�E
CD-DA�K�i�ł͂��Ƃ���120dB���̃_�C�i�~�b�N�����W�������Ă��܂���A
�I�[�o�[�E�X�y�b�N�̃P�[�u�����q�����Ƃ��Ă��Ӗ����Ȃ���ł��i��j
XLR�m���V�[���h�E�^�C�v�͂����܂ł��^�����^���ł����{�̂�����P�[�u���ł��B
�ߋ��ɂ��̕ӂ�ɐG�ꂽ�J�L�R�~�����Ă���܂����B
http://bbs.kakaku.com/bbs/20499010103/SortID=8908943/
�����ԍ��F9187790
![]() 1�_
1�_
redfodera����@
�Ԃ�Ԃ�Ԃ�A���ނ��ł��˂��c�B
���l�Ԃ̒�����̍��o���ۂɂ��Đ��������������̂ł����āA���ړI�ȉ������P�Ɍq����Ƃ̈Ӑ}�͂���܂���B
�������������݂����Ő\���킯����܂���ł����A�Ȃ�قǁA����Ȃ�Ȃ��Ƃ��ł��B
�����̓V�[���h���邱�Ƃ�S/N�Ɋւ��Ă̓R���v���b�V��������Ă��܂��܂��B
���̘b�͂悭�킩��Ȃ��ł����A�V�[���h�P�[�u�����Ɠ�����O�ւ̃m�C�Y���o�Ă����Ȃ��Ƃ����ނ��̘b�ł��傤���B���t��H�̓R�������[�h�m�C�Y�ɂ͊m���ɋ����ł����ǃm�[�}�����[�h�m�C�Y�ɂ͖��͂Ȃ̂ŁA����ς�o���������I�[�f�B�I�@�Ńo�����X�o�͂��������Ƃ���ő債�ă����b�g�ȂǂȂ��Ǝv���܂��c�i���݂܂���A���Łj�B
����ɁA�_�C�i�~�b�N�����W�̏オ�Œ�i��������͏������Œ�j�̉ƒ���ł̓_�C�i�~�b�N�����W���L����L���قǂ��̉��b�ł��鏬���������Ñ����ɖ�����Ē������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�L���_�C�i�~�b�N�����W�̃����b�g�ɏт�ɂ����Ƃ����̂͂���܂���ˁB�������݂����Ȍb�܂ꂽ���Œ����Ă���悤�Ȑl�Ȃ�ʂł����ǁB
�Ƃ͂����A�m����OldNeve��SSL�̃R���\�[���ȂŃ}�C�N�v���̉������j�^�����O���Ă�Ƃ��Ɋ���������m�C�Y(�t�B���K�����O�Ƃ����b�v�m�C�Y�Ƃ�)�̃]�N�]�N���̓m���V�[���h�̃P�[�u������Ȃ��Ɩ��킦�Ȃ���������Ȃ��ł��ˁc�A�I�[�f�B�I�Ƃ͂���ƈႤ���E�̘b�ł����ǁB
���݂܂���A������ƒE�������Ⴂ�܂����ˁB
�����킹�Ă��܂��Ă��݂܂���ł����B
�����ԍ��F9192534
![]() 0�_
0�_
�N���X�^���s�A�m����A���I�ȕ����ɒE�����Đ\����܂���B
sarlio����
�����t��H�̓R�������[�h�m�C�Y�ɂ͊m���ɋ����ł����ǃm�[�}�����[�h�m�C�Y�ɂ͖��͂Ȃ̂ŁA
������ς�o���������I�[�f�B�I�@�Ńo�����X�o�͂��������Ƃ���ő債�ă����b�g�ȂǂȂ��Ǝv���܂��c
���i���݂܂���A���Łj�B
���������A�Ȃ�̂Ȃ�́i�j
�����Đ��Ƃ����̂��\�[�X�ɑ��Ă����ɒ����ȕ�����ڎw�������ƁAsarlio����̂��b�̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
��H�I�Ȃ��ƂŌ����I�y�A���v�i�v�͐j�̗ނ����ƁA�ړ_�͑����邵�m�C�Y�͏��₷�����A�ł���ˁB
������炢���Ɠ����̏ꍇ�̓s���A�E�I�[�f�B�I�R�Ƃ��Ă����K�v�������Ȃ��^�C�v�Ȃ̂ŁA
�����ς�������ĕ��C�Ȃ킯�łނ���C�����悭�������Ă����o�����X�ł��A���o�����X�ł����܂�Ȃ��l�ł��B
�o�̓g�����X����D���Ȑl�Ń��C���E�g�����X�̏�p�Ȃ�����܂��B
�ŁA����ȃ��r���[�������Ⴂ�܂������قƂ�ǂ̕������܂���ł����i��j
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8819370/
���ƒ���ł̓_�C�i�~�b�N�����W���L����L���ق�
�����̉��b�ł��鏬���������Ñ����ɖ�����Ē������Ȃ��Ȃ��Ă��܂�
�ƒ���̃_�C�i�~�b�N�����W�ɓK�Ȑ��l�Ƃ����̂�����̂��킩��܂��X�y�b�N��͑傫�������ǂ��͂��ŁA
���p��Ӗ����Ȃ��̂Ő�̂Ă܂�������CD-DA�̍Đ����g���ш�Ɠ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��H
�ԐړI�ȉe�����L�链��̂Œ������Ȃ�����s�v�Ƃ͍l�������Ȃ��ł��ˁi�j
���m����OldNeve��SSL�̃R���\�[���ȂŃ}�C�N�v���̉������j�^�����O���Ă�Ƃ��Ɋ�����
�������m�C�Y(�t�B���K�����O�Ƃ����b�v�m�C�Y�Ƃ�)�̃]�N�]�N����
���m���V�[���h�̃P�[�u������Ȃ��Ɩ��킦�Ȃ���������Ȃ��ł���
���C�����͂킩��܂��B
���Ȃ݂Ɏ��p��̓����b�g�����ƌ����m���V�[���h�E�^�C�v������ł͎g���Ă��܂��B
�P�[�u���̃J�X�^�}�[�����OYAIDE��PC-OCC�ō���Ă�����āA�ŋ߁A�������܂����B
�]�N�]�N���͂��܂��V����������ꂽ���N���N���͂���܂���i���j
�����オ�������ۂ̃��X�|���X���V�[���h�E�^�C�v���ǂ��l�Ȋ��������܂��i���ꂱ�����o��������܂��E�E�E�j
�����ԍ��F9193415
![]() 1�_
1�_
redfodera����
���̗^���b�ɂ��t�����������Ă��܂��Ăق���Ƃɐ\����Ȃ��ł��B
�����g�͌����Đ��ɓ��ɍS�肪����킯�ł͂Ȃ��J��F�X�V�т����^�C�v�Ȃ̂ŁA���̋̐�B�Ɍ������瑲�|����悤�Ȃ����������R�����Ă܂��c�B�����A���͎����Ŕ[���������Ȃ����Ƃɂ͋C���ςނ܂ŋ^���Ă݂鐫���̂悤�Łi�l���̂悤�Ɍ��̂́A�������ŋ߂ɂȂ��Ď����̂��̐��i�ɋC�Â�������c�j�A�����ł��Ȃ����Ƃ͂�������ӂɂ��Ă��܂��܂��B
���ƒ���̃_�C�i�~�b�N�����W�ɓK�Ȑ��l�Ƃ����̂�����̂��킩��܂��X�y�b�N��͑傫�������ǂ��͂��ŁA���p��Ӗ����Ȃ��̂Ő�̂Ă܂�������CD-DA�̍Đ����g���ш�Ɠ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��H
�K�Ȑ��l������Ƃ͎����v���Ă͂��܂���B�Ⴆ�ΗL����1812Overture�ɂ͍����̃L���m���C���I�P�ɍ������Ė炳���^��������܂����A�b�c�̗��_��̃_�C�i�~�b�N�����W�i6dB x 16bit = 96dB�j�̒��ł̓L���m���C�̉��ʂɂ��킹��I�P�̉��ʂ����肸�J�T�J�T�Ƃ��ׂ����ɂȂ�A�I�P�ɍ�����L���m���C���o���o���Ƙc��Œ����ɑς��Ȃ����ɂȂ�܂��B���ꂪ120dB�m�ۂł���Ȃ猻���I�ȃR���g���X�g�ŗ��҂����炷���Ƃ��ł��邩������܂���B�������A�I�P�ƃL���m���C�̉��ʍ������ɑ傫���Ȃ�A�I�P�����߂̉��ʂɍ����Ē����Ă���ƃL���m���C�͂ƂĂ��Ȃ��傫�ȉ��ōĐ�����邱�ƂɂȂ�A�t�ɃL���m���C�����߂̉��ʂɍ����Ē����I�P�̓`���`���Ɩ邾���ƂȂ�ł��傤�B��ʂ̉ƒ���ł͍Đ����̉��ʂɃ������Ƃ����Ӗ��ŏ��������̂ŁA�_�C�i�~�b�N�����W���L�������̂ǂ̕����ɉ��ʂ������邩�A����ɂ���Ắi�����Ċ��ɂ���Ắj�L���_�C�i�~�b�N�����W���K�����������b�g�ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ӗ�
�Ő�̏����������܂����B�������A���̏�̓P�[�u���̃_�C�i�~�b�N�����W�̘b�Ȃ̂ŃP�[�u���X�y�b�N�Ƃ��Ă̗ǂ��^�����Ŗ₤�Ȃ�Ύ����u�ǂ��v�ňّ��Ȃ��ł��B
�����Ȃ݂ɁATELARC��1812Overture�̃f�B�X�N�W���P�b�g�ɂ́u�M���̍Đ����u�Ƀ_���[�W��^����\��������̂ŏ���̓{�����[�����i���Ē����Ȃ����v�Ƃ������[�j���O��������Ă��܂��B
�����ۂ�1812Overture�̘^���ł̓L���m���C�����ʘ^�肵�ĉ��ʂ������č���������A�z�[���̊O�Ŗ炵���̂��I�P�ɍ�������ƍH�v����Ă�悤�ŁA�����̉��ʍ��Ř^������Ă����ł͂Ȃ������ł��i������܂��ł����j�B
���N���N���͑厖�ł��ˁA���`�x�[�V�����ێ��ɂ͓��ɕK�v�ł��B
�����ԍ��F9195955
![]() 1�_
1�_
����l�l
�������݂��肪�Ƃ��������܂��B
����ւ̓����A�܂��A���̑��̓��e�����ɂȂ�܂����B
�킩��Ȃ����e����������ł������肪�Ƃ��������܂����B
�܂���낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F9248394
![]() 0�_
0�_
�v�����܂܂Ŏ��炵�܂��B
�o�����X��BTL�ڑ��Ȃ̂Ŕ{�Ƃ͂����Ȃ��Ƃ��Q�C���͏オ��܂��B
���͈Ⴂ�܂����v�����C���A���v�����i�̃Q�C�����グ���v�̕����c�݂����Ȃ��悤�ł��B
���ʓI��SN���オ��܂��B
���i�ɂ�MOS-FET���g���̂����̂��߂ŁA
�m��l���m����c���A���v�͏��i�̃Q�C���������̂ŗL���ł��B
�o�����X�ڑ��̓C���s�[�_���X�������邽�߃A���v�ɂƂ��Ă̓X�g���X��������܂��B
���b�N�X�}���A���v���g���Ă����Ƃ��o�����X�ڑ��ł������A
�����f�ނ̃P�[�u���ł��o�����X�̕����������ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂����B
���v���Ƃ��ꂪ�����ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�����ԍ��F9250278
![]() 0�_
0�_
�A���v�Ɍ����āB
�o�C�A���v�ł͖�肠��܂��A
BTL�ڑ��͗����ł͓d���Q�{�ŁA�d�́�W��4�{�ł��B
�����ɂ�2�{���x�̏o�͂ł��B
4�{�̏o�͂�������A���v�͋��x�ȓd���Ɨ�p�\�͂̂���A
�������i�̈ꕔ�̃A���v��������܂���B
�܂�SN���S�Đ��l�Ŕ��f���鎖�͂ł��܂���B
�m�C�Y������ق��������Ƃ�₷���ƌ����l�Ԃ̒��o�̓���������܂��B
WADIA�̍����@�͒�������[���I�ɕt���������ŗL���ł����A
������i20KHz�ȏ�j�̃m�C�Y���o�͂ɑ��ĉ����邾���̂��̂܂ł���܂��B
����ł��y�킪���Ȃ₩�ɕ�������ƌ����̂ł�����s�v�c�ł��B
������i�̃Q�C�����グ��v��SN��͌��サ�܂����B
CD�v���[���[�̏o�͐M�����x���͋K�i������Ĉ��ł��B
�V���v���ȃv�������o�͔�����Ƃ��čl����ƁA
�v���A���v�ʼn����ǂ��Ȃ闝�R�������ɂ���Ƃ��v���܂��B
���̏ꍇ�v����SN��͏d�v�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F9276895
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > LUXMAN > L-505f
�����́B
�T�O�T�����g���n�߂Ĉꃖ�����炢�o���܂����̂ł��낢��Ɨ]�T���o�Ă��ăP�[�u���ނ������肽���Ȃ�܂����B�܂�RCA�P�[�u���������Ђɂ������J�i���v�ɑւ����Ƃ�����ʁA��ʂ����Ȃ�ς��A�P�[�u���ł���Ȃɕς��Ǝ������A�������܂����B
�����Ŏ���Ȃ�ł����A�T�O�T���ȂǂŎg���Ă���v���ƃp���[�A���v���q���ł���R�̎��W�����p�[������������Ɖ����͌��シ��ł��傤���H�ǂȂ����o������Ă�������炵���ł��傤���H
�A�h�o�C�X�����܂��ł��傤���H
![]() 0�_
0�_
���̂ɃW�����p�[�V���[�g�s���������������̂��H
�����I�ɂǂ�Ȃ��s��������̂���̓I�ɏ����ꂽ�����E�E
���ԓI�ɂ́A
�������쏊�̂��̃N���X���炢�Ȃ���P���ʂ���ł��傤�B
�v�����C����p�I�[�O���C���V���[�g�s���B
http://aug-line.com/lineup/lineup.htm
����ƌ�����̂ق���
�����łƂ��ւ��Ђ��ւ��ł��C�ɏ������������܂����E�E
�����ԍ��F6649713
![]() 3�_
3�_
yamaya60����ԐM���肪�Ƃ��������܂��B�B�@�Q�l�ɂ����ĖႢ�܂����B
����A���ʂ�������茩���Ƃ��A�����P���ɂ��̘I�o���Ă���J�N�J�N�ƋȂ������s�����Ⴄ���̂ɑւ���Ɨǂ����ʂ�������̂ł́H�H�n�^�}�^����ȒZ�����i��ւ��Ă����ʂ͏o�ɂ����H�H�ƌo���҂̕��̌o���k�����Ă��炢�������傳���Ă��炢�܂����B
�P�[�u����ւ������ɁA���Ȃ�Ⴂ������܂��āA���̂悤�Ȍ��ʂ���������ȂƎv���Ă܂��B�@
���b�N�X�̏�ʋ@��̂悤��RCA�̒Z�����ł�������ł��傤�ˁByamaya60���狳���Ē������͎̂Q�l�ɂ����Ă��������܂������A�����Ȃ��̂Ŏ����Ȃ������ł��B
�����ԍ��F6650423
![]() 2�_
2�_
�V���[�g�s���̍����������\�ł��B
http://www.inpulse.co.jp/product/index.htm
��ʋ@��Ŏg���Ă���V���[�g�P�[�u���Ɍ����������葁���C�����܂��B
���̒[�q�ɉ�������̃V���[�g�s����v���e�N�^�[������܂��B
�g��Ȃ��[�q����m�C�Y������₷���̂ŏo����l�������ӏ��ł��B
���Ȃ݂ɍ����ł��B���삪�ł������ȋC�����܂��B
���b�N�X�̓d���P�[�u���͂�������o���Ă���̂ł����A
���C���܂߃A���v���i�̂P�����ڈ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F6650459
![]() 3�_
3�_
�f�W�S������
�����삪�ł������ȋC�����܂�
�I�[�f�B�I�̃P�[�u���̗ނ́A�����A�葤�̋@�킪
��K�i�����炵�Ă�����̂Ȃ�A���������S�Ď���ł��܂��B
�R�[�h����s���A�z���ނ����Ċ������܂őS�Ďs�̂���Ă��܂��̂�
���Ƃ͊e���̑n�ӂƍH�v�ƃm�E�n�E����ł��B
�o���オ��̎s�̕����͂邩�Ɉ������P���ʂ̍������̂����܂��B
�����ԍ��F6650789
![]() 3�_
3�_
Yamaya60����
�X���b�h�傳��Ƃ��A�_�u���Ă��܂��Ă��Ď��炢�����܂����B
�v���E���C�����ȊO�ɁA���̓V���[�g�s�����t�H�m�[�q�ɕt�����Ă���̂ŁA���������ł����Ǝv���Ă��܂��܂��B���̉ӏ��ɑ}��������Ă��܂����獢��ƍl���Ă���������邩������܂���B
�g�߂Ɏt��������Ȃ�m�E�n�E���ς߂�Ǝv���܂����A�Ɗw�ł͂Ȃ��Ȃ�����ł��B
�ǂ�ȒP���ȕ��ł������i�����ď��߂ė������鎖����������ł��B
�P�[�u���ɂ��Ă����[�����͌��������i������Ɛ��ވȊO�ɂ����c���g�p���Ă�����̂�����܂��B�V�[���h�̂܂Ƃߕ���V�[�X�̕t�����Ȃǃv���̎d�グ�����ăm�E�n�E��ς�ł��܂��B
���삪���オ��Ǝv����������܂����A������x�̓����͕K�v�ŁA���i�������������Ǝv�����̂������ł��B����ɂ͂����ɂ͂������Ȃ��y���������ɂ͂���܂��B
�l�ɂ͂����͌����Ȃ��Ǝv���܂����A���ɂ͂�������y���y���ގ��̂ЂƂł��B
�^��ǃA���v�����삷��̂ł����A���l�̍�������̂��W�b�N���ώ@������A�m�E�n�E���w�肷��̂��{���Ɋy�����Ƃ�������܂����i�����y�����ł����j�B
���icom.�ŃP�[�u���̎���������߂�����������܂��̂ŁA����̂��Ƃ��l���āu���ӎ����v
�N�������̂�s���v�͈�ؐӔC�͂����܂���̂ŁA����ɂ��Ă͌l�̐ӔC�ɂ����čs���Ă��������B�킩���Ă��鎖�Ƃ͂����A�X�������肢�v���܂��B
�����ԍ��F6652338
![]() 3�_
3�_
�X���Ƃ͊W�Ȃ��b�����ǁA�Z�p���[�g�A���v�Ɣ�ׂ��v�����C���A���v�̒����͐ړ_�̏��Ȃ��Ɣz���̒Z���ł���B
�Ȃ��W�����p�s���Ȃǂ��āA�킴�킴�ړ_�𑝂₵����A�z���̎��������肷�邩�ˁB
�����A���v�Ȃ炽�����ĉe���͂Ȃ���������Ȃ����ǁA�����v�����C���A���v�قǁA�W�����p�s�����̃v�����C�������X�C�b�`�Ƃ����Ă��ˁB
�v���ƃ��C�������̂����Ӗ��Ȃ������B�A�z���c�c�B
�����ԍ��F6653476
![]() 2�_
2�_
>�����A���v�Ȃ炽�����ĉe���͂Ȃ���������Ȃ����ǁA�����v�����C���A���v�ق�
>�W�����p�s�����̃v�����C�������X�C�b�`�Ƃ����Ă��ˁB
�����v�����C�������炱�����ՂɃZ�p���[�g�i�p���[�{�v���j���g���Ă�
�Q�g�̐V�K�w���͂��ɂ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���̓_�MAIN IN���PRE OUT��[�q������p���[���邢�̓v���̈���̍w��������
�܂��͌��݂̏���̃O���[�h�A�b�v���]�߂܂����������K�ʂł̗]�T������Ă��܂��B
���܂Ŏg�p���Ă����v�����C�����g�p�ł��܂����A�����Œi�K��ł����
���S�Z�p���[�g�������܂����玄�͂��̎d�l�̕��������Ɗ�����Ǝv���̂ł����E�E�E�E
>�v���ƃ��C�������̂����Ӗ��Ȃ������B
��LUX���[�U�[�����猾�킹�Ă��炢�܂�����̌^�Ƃ��Ă̈Ӌ`�ł�����
�L-505f��ɂ̓g�[���R���g���[����H�����o�C�p�X������
"�X�g���[�g�E�X�C�b�`"���������Ă���܂��B
�v�����C���Ƃ��Ă̏��x�ɂ����[�J�[�Ȃ�ɏ\����������Ă���悤�Ɋ����܂��B
���̏�ŃN���X�^���s�A�m�����Ă���V���[�g�P�[�u��������
�l�I�ӌ��ł�����������ʂ��l����Ɣ��ɖʔ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F6654699
![]() 1�_
1�_
�A���v���[�J�[�̉c�Ƃ݂����ȃZ���t�ł��ˁB
�Z�p���[�g�A���v�킹�邽�߂̔̔��헪�ɂ҂�����͂܂������ӌ��ŁB
�V���[�g�P�[�u���ύX�ʼn����ǂ��Ȃ�Ƃ������Ƃ́A���������ōŒZ�����łȂ������Ɨǂ��Ȃ�Ƃ������Ƃ���Ȃ��ł����B�܂�őP�̕��@���Ƃ炸�ɁA���������m�̏�ł���Ă�Ƃ������Ƃł���ˁB
�{�N�̂悤�Ƀv�����C���A���v���ŏI�I������I�[�f�B�I�t�@�C�����猩��A���[�J�[�͂����̂悤�ȃ��[�U�[���y�����Ă���Ƃ����v���Ȃ��B
�o�C�p�X�X�C�b�`�ɂ��Č��킹�Ă��炦�A�o�C�p�X�����特���ǂ��Ȃ�悤�Ȏ��̈����g�[���R���g���[���Ȃ��߂������ȁA�Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F6658262
![]() 2�_
2�_
���̃X���b�h�ł������悤�Ȏ����������Ă��������܂������A�Q�l�܂łɁB
����L-550A���g�p���Ă��܂��B�]�����牽���̃��[�J�[�ł��t���̃V���[�g�s���͉����I�ɂ��܂�ǂ���ۂ����������̂Ō�����O��Ɍ��������Ă��܂��B����L-550A�ł̉����]�������Ă݂܂����B
�@L-590A�t���̃s���P�[�u���i��C���i�Ƃ��ā�1000���炢���������ȁH�j�V���[�g�s��������̃O���[�h�A�b�v�ł�����{�I�ɂ͋C�x�ߒ��x�ł����A�w���̕K�v�͖����Ǝv���܂��B
�A�I���g�t�H����6.5N.AC-1000Q(@11000)���͂��̃P�[�u���̉������̍����i�P�[�u����蔲�Q�ɗǂ������ł��B�ቹ�̔n�͂Ɖ��̐ꖡ�����������N��̃A���v���Ǝv���قǗǂ��Ȃ�܂����B�����v�����Ȃ̂̓R�l�N�^�[���傫�����ċ����v���A�E�g�ƃ��C���C���ɐڑ�����ɂ͋@�펩�̂��S�z�ɂȂ�̂Ńp�X�����邵������܂���B
�B�T�G�N��SL-3030(@34000)�N�I���e�B�̍����͊������̂ł������̐�������Â������A���̃A���v�Ƃ̑����͗ǂ��Ȃ��悤�Ɏv���܂����B
�CW.W�̃|�����X�i��60000�j�o�����X�悭������������B���ʓI�Ɏ��͍����̃P�[�u���Ŏg�p���Ă��܂������̃x�X�g�̓I���g�t�H���ł��B
�����ʼn��i�A�R�l�N�^�[�̑��������܂��ăX���傳��̃P�[�u�������Ȃ�Ɍ�������ƃL���o�[��TONIK(��14000)�����肪�����߂��ȁH��͂����g�Ŋm���߂�̂��x�X�g�Ǝv���܂��B
�i������50cm�ł������̂ł����O��������CDP���ɂ��g�p�ł���̂�100cm�̕��������Ǝv���܂��j
�i���AJazz����ɒ����܂��̂ʼn��y�̃W��������D�݂̉��̌X��������Ă���X���[���ĉ������j
>����҂�� �����ł��B
�����ԍ��F6658315
![]() 5�_
5�_
�F�l���낢��A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B
audio-style���낢��Ȍo���k�����肪�Ƃ��������܂����B�@��͂肱�̕����������ɂ�鉹�̕ω��͂���̂ł��ˁBRCA�P�[�u����audio-style����̂������悤�ɕʂ̏ꏊ�ł��g���钷���ŗp�ӂ��Ă��߂��̂��������@�ł��ˁB�@�܂��A�J�i�����q���Č��܂��B
���@�J�i�����g���Ă���̂ł����A�ȑO�̃P�[�u�����特���ǂ��Ȃ����̂͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����A�J�i���̉��̌X���A�P�[�u���Ƃ��Ẵ��x���i�]���j���܂��킩��Ȃ��̂ŁA�����Ē������P�[�u�����Q�l�ɂ����Ă��炢�Ȃ��炢�낢�뎎�����Ǝv���܂��B
���b�N�X�̃V���[�g�P�[�u�����w�����悤�Ƃ��v���Ă��̂ł����A���Ȃ����ɂ��܂��B
�@
�����ԍ��F6658789
![]() 3�_
3�_
���͂悤�������܂��@audio-style����
L-550A �� L-590A �̃V���[�g�P�[�u���̌����͑�ώQ�l�ɂȂ�܂����B
L-590A �̍��ڂɋ����邭�炢�ł����炫���Ɖ�������̂��낤�Ǝv���Ă��܂�����
����قǂ̉��P�������Ȃ������Ƃ̎��Łu�����������̂��I�v�Ɩڂ���E���R�ł����B
���̑��P�[�u�������̃C���v���ɂ����ӂł��B���肪�Ƃ��������܂��B
���āA�������������ł͐\����Ȃ��̂łP���������܂��B
��J�l�u������� �h�SN����P���v�����C���W�����p�[ �h �ł��B
��ł������ɂ������Ȃ����̔��͂Ƌ�Ȃ�ł͂̍���̃N���A����������Ǝv���܂��B
����� �k/�q�y�A�@3,200�~�Ƃ������[�Y�i�u���Ȃ��l�i����ϖ��͓I�ł��B
��͌h��������������������Ǝv���܂�����x�������ɂȂ�ƕa�ݕt���ɂȂ邩������܂���O�O�G
�����ԍ��F6658948
![]() 2�_
2�_
����҂��A�ǂ������������ł��B
���̕��͂����ԁE�E�E�E
>��͌h��������������������Ǝv���܂�����x�������ɂȂ�ƕa�ݕt���ɂȂ邩������܂���O�O�G
����Ȃ��Ƃ͖����ł��B
���������Ă��邾�����Ǝv���܂��B
�I�[�O���C�������T�������������ł��B
�����ԍ��F6672114
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́B
���ꂩ��v���P�[�u���ɃJ�i�����g���Č��܂����B
���̌��ʂƂ��āA��͂艹�����ς��܂����B�@��ۂƂ��Ă͒ቹ���o��悤�ɂȂ�A�S�̂Ɍ��݂��ł܂����B����̈�ۂ͂��܂肩���Ȃ������̂ł����A���̖��x�������A��肢���A���v�ɂȂ�܂����B
���̃W�����p�[��ւ��������ʼn������ς��̂ł��ˁA���[�J�[�������Ƃ����W�����p�[����Ă��������̂ɁA�ł��ˁB
���ƁA�SN����P���v�����C���W�����p�[ ���C�ɂȂ�̂ł����A��Ƃ��͈����ɂ����̂ł����H�@�g�������Ƃ������̂ł킩��Ȃ��̂ł����A�悳�����ł��ˁB�����Ă݂����Ȃ�܂����B
�����ԍ��F6742683
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > LUXMAN > L-505f
���f���`�F���W���O�ł���505f���w�����܂����B����ƊȒP�ȃ��|�[�g�����܂��B
�f�m����AV�A���v�i���N�O�̃t���b�O�V�b�v�j�̂Q�`�����l���ł����\�������Ă����̂ł����A505f���Ɖ��̊g����A���̒�ʊ��A���Ċ����i�i�ɑ����A�������Ă��܂��B�w���O�̃C���[�W�ƈ���Ė���߂̑u�₩�ȉ������܂��B
�Ƃ͂����Ă��A�ቹ��̖��ēx���Ⴂ�̂ƁA������̎�̂����������Ă܂��i�܂��G�[�W���O���ł͂���܂��j�B���ʃ��f���Ȃ̂ł�����x�͎d���Ȃ���������܂��A��������P����悤�ȗǂ����@������܂�����A�����Ă��������B��̓I�ɋ����Ē�����Ə�����܂��B�B
�i�X�s�[�J���\�i�X�t�@�x�[���̂f�o�g�Ȃ̂Œቹ�悪�s���āH�Ȃ͎̂d���Ȃ���������܂���B�ꉞRCA�P�[�u���͍����n�H�iMIT��AVT1�j���g�p���Ă��܂��j�B
�����ɓd���P�[�u����Ex-Pro PACC�̂��̂Ɍ��������Ƃ���A�������������Ȃ�܂����i�j�B
���Ȃ݂ɁA���݁A��LAV�A���v�̃v����505f�ɐڑ����āi�Z���N�^����āj�}���`�`�����l���ɂ��Ă��܂��B�v�����ς��Ȃ��������AAV�A���v�P�̂̂Ƃ��Ɠ������i�Ȃ���AV�A���v�P�̂̎������m�C�Y��������j�����܂��B���l�i���x�̃p���[�A���v��lj�������@���l���Ă����̂ŁA���̏ꍇ�A�v�����C���A���v���w���������������A�b�v�ɂȂ����ėǂ������Ɗ����Ă܂��B
��낵�����肢���܂��B
![]() 0�_
0�_
�@�������́B505f���g����32�����قǂɂȂ�܂��BSP��Victor��700sp�Ƃ������Ȃ�Â����̂ł����C����Ȃ�ɖ������Ă��܂�(�������͎̂�ɌÊy�ŁC�`�F���o������[�g�����S�ł�)�BCDP�̓f�m����1650AZ�ł��B���āC����̂����ł����G�[�W���O�ŏ��X�Ɏ���ł��傤�B���b�N�̋��x�͂ǂ��ł��傤���B����505f�̋r���Ƀu�`���S��(5mm)��~���Ă��܂��B����ȏ�����Ɖ��ɍ����Ȃ��Ȃ�悤�ł��B�s���R�[�h�̓A�N���e�B�b�N�̒����i�ł��BSP�̐ݒu��ł����͂��낱��ς��̂ł��낢�뎎���Ă݂Ă��������B�����Ƃ̊W�Ȃǂ͂��ꂼ��̃��[�U�[�����s���낵�Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ����Ƃ������Ǝv���܂���B
�����ԍ��F6574280
![]() 0�_
0�_
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B���̓��b�N�ɋꏊ���Ȃ��A�A���v�̓t���[�����O�ɒ��u���ł�(^_^;)
�X�s�[�J�͑嗝�̃{�[�h�̏�ɒu���Ă��܂��B
�m���ɕ����ɂ���đ�͈Ⴄ�悤�ł��ˁB�G�[�W���O�̕ω������Ȃ��玎�s���낵�Ă݂܂��B
�u�`���S���͎g�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�����_�炩���Ȃ�����ɍs���悤�ȋL����ǂ��Ƃ�����̂Ŏ����Ă݂܂��B
�����ԍ��F6574581
![]() 0�_
0�_
�������́B
����������@�T�O�T�����w�����܂����B�@������DENON�@AVC-3500�@AV�A���v�QCH����̃O���[�h�A�b�v�ł��B�@��505f���Ɖ��̊g����A���̒�ʊ��A���Ċ����i�i�ɑ����A�������Ă��܂��B�@�����������������܂����B�@�@���낢�뎎��������@���f�������̂T�O�T���ɂ��܂����B�@
�@
���������̕������Ă��ꂵ���v���܂��B������̌f�������Ă���邩�������āB�@
���͂Q�T�Ԃ��炢�o�̂ł�����x���b�N�X�}���ɑ��邱�ƂɂȂ�܂������A�������Q����ɂ͖߂��Ă���Ƃ����Ή��̗ǂ��ł����B
��AAV�Ƀv���Ƃ��đg�ݍ��݉f������Ă��܂����ASP���x���Z�b�e�B���O���t�����g���Ȃ�グ�A�����߂ɒ������A�T�O�T�̃��H�����[�������܂肠���Ȃ��ł��ސݒ�ɂ��܂����B����ł����̂��͂킩��܂���������ōs�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F6576391
![]() 1�_
1�_
2007/07/26 07:37�i1�N�ȏ�O�j
���͂悤�������܂�(^-^)/
�T�O�T���w�����߂łƂ��������܂���
���āA����̂����ł����A�嗝�̃{�[�h�Ɉ�������邩������܂���ˁB
��e���͂܂����Ƃ͎v���܂����A�ؐ��{�[�h���͍d�߂̍���ɂȂ肻���ł��B
�悸�̓A���v�̃G�[�W���O�����ėl�q���݂ĉ������B
�����ԍ��F6577623
![]() 0�_
0�_
�N���X�^���s�A�m����
���������悤�Ȑl�����Ă��ꂵ������ł��B�v�����C���͂`�u�A���v�i�R�X�g�����������̂ł��j���������ɗL�����Ǝ������Ă��܂��B
�C���H�̑Ή����ƂĂ������悤�ň��S���܂����B���͂`�u�A���v�̐ݒ�������炸�Ƀv���o�͂�505f�ɏo�͂��Ă���̂ŁA505f�̃��x�������\�グ�āi�P�P���ʂɁj���`�����l���ƃo�����X������Ă���ł��B�Z���N�^��芷�����ۂɑ剹�ʂɂȂ�̂ŋC�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��s�ւł��ˁB
������AV�A���v��SP���x���ݒ��ς��Ȃ��畷����ׂĐݒ肵�悤�Ǝv���Ă܂��B
���A������505����TV��DVD/HDD���R�[�_���Ȃ��ĉ����Ă݂܂����i�`�u�A���v�I�Ȏg�����ŕςł����j�B�`�u�A���v�P�̂ŕ������ꍇ�������_�́A�m�C�Y���ڗ����Ƃł��B�����炭TV�A���R�[�h�̉����Ɍ��X�܂܂�Ă���m�C�Y���Ǝv���܂����A�����AV�A���v�ł͖w�Ǖ��������A���̓_�ł�����̈Ⴂ������̂��ȂƊ����܂����B�P��505f�̍��惌���W���L��������������܂��B
�r�����������@�q������������
�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B�\�i�X�͈ȑO�i�O�����h�s�A�m�̍��j�A�X�s�[�J�̃I�v�V�����{�[�h�ɑ嗝�{�[�h��̔����Ă����̂ŁA������Q�l�ɑ嗝���g�p���Ă��܂��B�m���Ƀt���[�����O�ɑ嗝�������u���Ȃ̂ŁA�e���͂��邩������܂���B�A���v�̏����Ȃ��獂�����l���Ă������Ǝv���܂��B
���̐��i�̓I�[�f�B�I�G���𐔏\�����Ă��A���ʃ��f���̂������L�����w�ǂȂ��͎̂₵������ł��B���x�o��505u�̏Љ�L����505f���ǂ̂悤�ɏЉ��邩�|���Ȃ�����y���݂ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F6577982
![]() 0�_
0�_
�@����ɂ���,������B���b�N�X��505�ƌ����^�Ԃ͌��\�Â��āC�����w��������1970�N�㏉�߂�SQ505�Ƃ����A���v������܂����B���b�N�X�Ƃ��Ă͈�ԑ䐔���o�鏤�i���Ǝv���܂��B
�@����,SP�̐ݒu�ł����嗝�̑�̏�ɒ��u���ł��傤���BDY�X�Ȃǂō��h�Ƃ��O�ނ̃L���E�u��܂��͉~����̕���(�������e�킠��܂�)���Ă���Ǝv���܂��B����𗘗p����Ƃ��낢�뎎���܂��B���͖�10cm�̍����̍��h�ƕO�̂��̂p���Ă��܂��B���h�̂ق��������d���Ȃ�悤�ł����O�̂ق����_�炩���Ȃ�悤�ł��B(�C���I�Ȃ��̂�����܂��ˁI)�l�I�ɂ̓X�p�C�N�͌����Ȃ��̂ł�����o���邾���̑f�ނ�T���Ă��܂��B��������,L-505f�̃t�H�m���͌��\���������ł���B
�����ԍ��F6580964
![]() 0�_
0�_
2007/07/27 10:24�i1�N�ȏ�O�j
����ɂ���(^-^)/
������
�v�����C���̃{�����[���́A���i�����ʒu�i�Ⴆ�X���j�ɌŒ肵�āAAV�A���v���Ń{�����[��������������ʓ��͐�ւ������l������ƃx�^�[��������܂���B
�L���[�u�́A�����l������܂����A���A�������肪�����̖ʂł͂悢��������܂���B
�G���L���ȂA�L���ł�����A�]��C�ɂ���K�v�͂���܂����i�j
�����ԍ��F6581235
![]() 1�_
1�_
���E�t�H���A����
����ɂ��́BSQ505���C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ܂����B�Â��Ă����{���[�J���̂������ڂ������������̂ł��ˁBLUX3��ڂ̃g�����W�X�^�E�v�����C���A���v�ł������Ƃ����̂͋����ł����B58,000�i1968�N7�������j�������̂��ǂ����͔���܂��B
��肪�Ƃ��������܂��B�w�������������ɐF�X���ׂĂ݂悤�Ǝv���܂��B�����LUXMAN�̋L���i�A���v�u�����h���W�j���������I�[�f�B�I�A�N�Z�T�����w���������ł��B����ȏ��ł��o������Ă��܂��B
�Ƃ���ŁASP�͂��w�E�̒ʂ�嗝�̏�ɒ��u���ł��B�����C���V�����[�^�����Ă����̕ω��������Ȃ������̂ƁA�ʒu�����̂��Ղ��ł������Ă��܂��B�̑f�ނ��z�[���Z���^�Ȃ��ɓ���₷���̂ŋ@������Ď����Ă݂܂��B
���������Ȃ����ƂɃt�H�m���͎g���Ă��܂��i����b�c�̂݁j�A���b�N�X�̓A�L���t�F�[�Y�ƈ���Ďn�߂��瑕�����Ă��邵�A��ւ��@�\�iMM/MC�ł��������H�j�������ăt�H�m�̉������ǂ��Ȃ猾�����Ƃ��Ȃ��ł��ˁi�A�L���t�F�[�Y�̓t�H�m�̒l�i�������̂œ��R�������ǂ��̂ł��傤���ǁj�B
�r�����������@�q������������
����ɂ��́B���x�������̃A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B���͉��y�����Ԃ��ɂ����HAV�A���v�̃p���[�Ƃ��Ă͎g�p���Ă��Ȃ��̂Ŗ������x���������Ă܂���B
�m���ɎG���L���͒L���ł��˂��B�������ŃV�X�e���S�̂�w�ǔ����������o�܂�����܂��i�j
���̋@��̏��͂��Ȃ菭�Ȃ��i�Ǝv�����j�̂ŁA�C�Â����_�������ƁA�m���ɏ�ʃ��f���i���b�N�X�}���A�A�L���t�F�[�Y�j�Ɣ�ׂ�Ɖ��̋����i�ꉹ�ꉹ�̖��Ă��j�A�����R���̈����ۂ��i����͋����Ȃ��ʂł����i�j�j������܂����A���ꂪ�C�ɂȂ�Ȃ��ʂ̉��̗ǂ��i�����R���ȊO�̑���̗ǂ��Ƒ����͓����j������A�����x�͂��Ȃ荂���ł��B
�܂��A�{�����[���𗎂Ƃ������i�����ʁj�A���ɒቹ���_�炩�߂ɂȂ�̂ŁA�Q��O�Ȃǂɉ��y���ɂ͒��x�ǂ��i���E�h�l�X�{�^���������Βቹ�������ł��܂��j�A�^���H�ɕ����Ƃ��͂�����x���ʂ��グ��Ώ[���ɗv���i�Ђ����ڂŏ�ʃ��f���ɋ߂����j�ɗv���ɉ����Ă���܂��B
�Ƃ͂����Ă���̂̏��L�҂��A���L�@���J�߂�̂Řb�������x�ɕ����ĉ������B�܂��A���̕\�������g���Ȃ��̂ŁA���ۂɔ�r�������đI��ł��������B
���ꂩ�甭������鎟�@��505u���w�����ꂽ���ցA����C���v���b�V���������肢���܂��B
���R�~�ɂ͊��Ɂu�g���݂̂����Y��ȉ��v�Ə������܂�܂��ˁB
�����ԍ��F6595001
![]() 0�_
0�_
���ȃ��X�ł��B�ԈႢ������܂���(^_^;)
��ʃ��f���i���b�N�X�}���A�A�L���t�F�[�Y�j�Ɣ�ׂ�Ɖ��̋����i�ꉹ�ꉹ�̖��Ă��j�A
�����̋����i�ꉹ�ꉹ�̖��Ă��j���Ȃ��A
���̕\�������g���Ȃ������̕\�������M���Ȃ�
�������܂�܂��ˁB���������܂�Ă��܂��ˁB
���炵�܂����B
�����ԍ��F6595039
![]() 0�_
0�_
�@������C�������������܂��B1968�N�����̕����ł���������w�̎��Ɨ����N12000�~�C�w�H�̃��[����30�~,��H45�~�ł�����B�F�l��SQ505����ɓ��ꂽ�̂��ƂĂ������܂��������ł��B����,L505f�̒��ł���550��590�ɂ͕�����ł��傤�B��͂�A���A���v�̒��̉����o���̓A���v�̏o�͐��l�ȏ�Ɏ����ł��܂��B�]����SP�̐ݒu�Œ��̕����������ōl���܂��BL505f�܂ł����b�N�X�̐̂̃A���v�̌X�����c���Ă���Ǝv���܂�(�Nj����̉����g�����W�X�^�ŏo�����Ƃ����̂�70�N��̃��b�N�X�̉����Ǝv���܂��B���̕ӂ��A�L���ƈႤ�Ƃ���ł��傤���j�BL505u�͂ǂ��炩�Ƃ�����550�����̉�����Ȃ����Ɛ��@���Ă��܂��B505f�̂悳�͂����Ƃ肵�����Ƒ@�ׂȍ���i���i�̊��ɂ́j�Ƃ������Ƃł��傤�B���낢��ȃ\�t�g�����y���݂��������B
�����ԍ��F6597489
![]() 0�_
0�_
���E�t�H���A����A����ɂ��́B
���Ԏ����x���Ȃ肷�݂܂���B������58,000�~�͍�����w�̎��Ɨ��T�N�߂��ɂȂ�܂��ˁB�����ł��B
505f�A�����y����ł��܂��B�����ƃX�y�[�X����������Nj��A���v�������Ă݂����ł����A505f�őł��~�߂ł����炢���Ȃ��i�j
�����ԍ��F6601300
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > LUXMAN > L-505f
�k�|505����ʔ̓X�Œ����A�悢��ۂ������܂����B����505���̓p���[�A���v�Ƃ��Ă��g����悤�Ȃ̂ŁA�}���`�`�����l���\�z�ɓ�����A505���Ńt�����g�Q�������������悤���ƍl���Ă��܂��B�v���[���[�ɂ̓f�m���c�u�c�|3930��\�肵�Ă���A�`�u�A���v������ɍ��킹�`�u�b�|3920�Ƃ��A�Q�����\�[�X�ł�3930��505���ڃA�i���O�ڑ��A�}���`�`�����l���ł̓f�m�������N��3920����t�����g�Q������505���Ƀv���A�E�g����v��ł����A���̏ꍇ���ƂȂ�̂�505����3920�Ƃʼn��̐������������ۂ��ł��B��قǂ̗ʔ̓X�ɂ͂`�u�A���v���Ȃ��A�܂��ߗׂ̕ʂ̗ʔ̓X��505����u���Ă���Ƃ��낪�������߂��̂悤�Ȏ��������邱�Ƃ��ł��܂���B���b�N�X�}���ƃf�m���Ƃł͉��̍�肪�Ⴄ�̂ł��傤���H�܂�505���̑���ɂo�l�`�|2000�`�d���g�����ق����}���`�`�����l�����ň�a���Ȃ��ǂ����ʂ�������̂ł��傤���H�Ȃ��A�X�s�[�J�[�ɂ��Ă͂܂������i�肫��Ă��܂���B
![]() 1�_
1�_
2007/04/28 22:08�i1�N�ȏ�O�j
���ӂ́�
�܂��A�u505���̓p���[�A���v�Ƃ��Ă��g����v���Ƃ͎g����̂ł����A�u�Q�����\�[�X�ł�3930��505���ڃA�i���O�ڑ��v����̂ƁA�u�}���`�`�����l���ł̓f�m�������N��3920����t�����g�Q������505���Ƀv���A�E�g����v�̂Ƃ�芷����Ƃ��A505���̔w�ʂɉ���ăv���O�������ւ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B���b�N�X�ł́A�t�����g�X�C�b�`�ЂƂŃv���E�p���[�̕������\�Ȃ̂́A�m���T�O�X�������ł��B
������A�z�[���V�A�^�[�ƂQ�����I�[�f�B�I�Ŏg���������邽�߂ɐv����Ă��Ȃ��A���v�ƌ����܂��B
�o�l�`�|2000�`�d��A�L���t�F�[�Y�̃v�����C���A���v�Ȃ�AEXT_PRE�X�C�b�`���t�����g�p�l���ɕt���Ă���̂ŁA�X�C�b�`��Ŏg���������ł��܂��B
�����ʂɂ��Č����A���ꃁ�[�J�[������Ƃ����Ζ���ł��B�������A�}���`�`�����l���Ŏg���̂́A�v�����C���A���v�̃p���[�A���v�������ł���A�p���[�A���v���Ńt�����g�X�s�[�J�̋쓮�͂����߂悤�Ƃ����ł�����A���[�J�[������Ă����A�̃X�s�[�J�Ƃ̈�a���͂��܂�o�Ȃ��Ǝv���܂��B�Ⴄ���[�J�[���g���Ă�����͂�����ł����܂��B
������A���ꃁ�[�J�[���ǂ����͋C�ɂ��Ȃ��Ă��悢�ƌ����܂��B
L-505���̂悤�ȉ������D���Ȃ�A�`�u�b�|3920�ȊO�̑I����������̂ł́H�Ǝv���܂��B�z�[���V�A�^�[�̋@�\���厖�ł����A���y���d������Ȃ�D���ȉ����ɂ�������������������ł���B�e���[�J�[�̂`�u�A���v���g���Ă��鏔��y�̘b�������ĉ������B
�����ԍ��F6280099
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A��肪�Ƃ��������܂��B
���u�Q�����\�[�X�ł�3930��505���ڃA�i���O�ڑ��v����̂ƁA�u�}���`�`�����l���ł̓f�m�������N��3920����t�����g�Q������505���Ƀv���A�E�g����v�̂Ƃ�芷����Ƃ��A505���̔w�ʂɉ���ăv���O�������ւ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B���b�N�X�ł́A�t�����g�X�C�b�`�ЂƂŃv���E�p���[�̕������\�Ȃ̂́A�m���T�O�X�������ł��B
����͒m��܂���ł����B�������U�W���͂�����ƌ������ł��ˁE�E�E�B�g��������]���ɂ��ċC�ɓ�����505���Ƃ̕��p�V�X�e���Ƃ��邩�A2000�`�d�����g���đ��쐫���d�����邩�����Ƃ���ł��B�Ƃ����505��+3920�Ŗ�R�W���ł����A����������`�u�A���v�i�`�u�b�|�`�P�P�w�u�A�r�q9600�j��P�ƂŎg���̂͂������ł��傤���H���̂�����̃N���X�ƂȂ�ƂP�O���~��̃v�����C���A���v�Ɠn�荇������͂�����Ă���悤�ɂ��v����̂ł����B
�����ԍ��F6281660
![]() 0�_
0�_
2007/04/29 13:40�i1�N�ȏ�O�j
SS-039����A����ɂ��́B�Y�܂����Ƃ���ł��ˁB
>����������`�u�A���v�i�`�u�b�|�`�P�P�w�u�A�r�q9600�j��P�ƂŎg��
���ǂ����ł��ˁB�l�͂`�u�b�|�`�P�P�r�q�������Ă��܂����A����͂`�u�b�|�`�P�P�w�u�̑O���f���ŁA�A�i���O���̗͗ʂ͂������������Ǝv���܂��B
�`�u�b�|�`�P�P�r�q�̃v���A���v���́A�Â������܂��܂��̃��x���ɂ���A�Ȃ��Ȃ���o���ł��B���̃p���[�A���v���̋쓮�͂́A1500AE�ȏ�2000AE�������Ǝv���܂��B�����ł͂`�u�b�|�`�P�P�r�q�ŏ��^�u�b�N�V�F���t�X�s�[�J���R��炵�Ă��܂����A�s���͂���܂���B
����ŁA�`�u�b�|�`�P�P�w�u�P�ƂŖ点��͈͂ł����A���^�u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�T��Ȃ�\���s����Ǝv���܂��B
�������A�{�i���E��^�X�s�[�J�������ƁA�`�u�b�|�`�P�P�w�u�A�r�q9600�̃N���X�ł����Ă��A�`�u�A���v�P�Ƃł͋ꂵ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@�쓮�͂�����Ȃ��ƁA�������ɑN�������Ȃ��Ȃ��āA�Â����������ɂȂ�܂��B�i�{�i��^�X�s�[�J����PMA-2000AE�ł��ꂵ�������m��܂���j
���̂悤�ɖ��m�Ȑ������͂ł��܂��A�z�肷��X�s�[�J�̋K�͂ƃA���v�̋쓮�͂Ƃ̊W�ɂ���āA���_������Ă��܂��B
�������ɂ`�u�A���v���ōς܂����Ƃ��ł���Ȃ��ԕ֗��ł��ˁB�`�u�A���v��䔃���āA�炵�₷���X�s�[�J��I�Ԃ��H�@�ꏊ�͂Ƃ邯��ǂ`�u�A���v�ƃv�����C���A���v�𗼕������āA�X�s�[�J�I���͈̔͂��L���Ă������A�ł��B
����ƁA�ǂ����Ă��T�O�T���ɂ������Ȃ�A���C���Z���N�^
http://www.luxman.co.jp/product/ac_as4-3.html
���g���A�A���v�̗��Ɏ��L���Đ芷���Ȃ��Ă��悭�Ȃ�܂��B
�r�����������@�q�������� ����A����ȉŁA�������ł����H
�����ԍ��F6282061
![]() 0�_
0�_
2007/04/29 22:41�i1�N�ȏ�O�j
������(^-^)/
�Ă�Ĕ�яo�āA���ז����܂��B
�Ȃ��Ȃ������Ȃ��l���ł��ˁB
�v���A�p���[�Ɨ��g�p�́A�Z�p���[�g�ɔ��W����ۂɁA�ǂ��炩�P�䂸�lj����鎩�R�x�����������ƍl���܂��B
�]���āAAV�̃t�����g�����Ȃ�T�O�T�̃v�����g�p�A�����C���v�b�g�Z���N�^�ŗႦ���C���P��AV�A���v�̃v���A�E�g��ڑ������OK�ł��B
�v�����Q�i�ʂ郍�X���C��������������܂��A�s���A���̉����ł͌��X����܂���̂ŁA�m�[�v���u�����ł���B
�Ȃƌ�����苭�s�˔j�ŃS�����i�T�Cm(_ _)m
�����ԍ��F6283632
![]() 0�_
0�_
2007/04/29 22:51�i1�N�ȏ�O�j
�Q�Ăă��X�����̂ŕ⑫�ł��B
�悸�A�T.�P�̉��F�Ɋւ��ẮA�A���v�����X�s�[�J�[�̑g�ݍ��킹���x�z�I�ł��B
�P���AV�A���v�ŋ쓮���Ă��X�s�[�J�[�g�ݍ��킹���ԈႦ��ƁA�Ƃ�ł��Ȃ�����ɂȂ�܂��B
���̂�����͂����ĉ����������Ȃ��Ȃ��������������ʂ�ł��B
���ɁA���z��AV�A���v�ւ̓����͑S�������ߏo���܂���B
���ɍ���HDMI1.3�閾���O�ł����珮�X�ł��B
���ɂT�O���~�̗\�Z������Ȃ�A�S�O���~�̃I�[�f�B�I�A���v�ƂP�O���~��AV�A���v���w����������i�i�ɍ������ŃV�X�e���g�����AAV�A���v�X�V�̎��R�x�����܂�܂���B
�T�O���~��AV�A���v�͊ȒP�ɂ͔����ւ����Ȃ��ł���H
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
����Ȃ��̂Ŕ@���ł��傤���H
�����ԍ��F6283679
![]() 0�_
0�_
2007/04/29 23:05�i1�N�ȏ�O�j
�r�����������@�q������������A�ǂ����ł�^^
������₷�������A�����Ȃ�܂��B�T�O�T���̂悤�ȃv�����C���A���v�ƁA�����Ȃ`�u�A���v��g�ݍ��킹��̂��������낤�B���C���Z���N�^���g��Ȃ��Ă��A�����������@������B
�b�c�Đ��̂Ƃ��́A
�v���[�����A�i���O�P�[�u�����T�O�T���̃v�����T�O�T���̃��C�����t�����g�r�o
�`�u�Đ��̎��́A
�v���[�����f�W�^���P�[�u�����`�u�A���v�̃v�����T�O�T���̃v�����T�O�T���̃��C�����t�����g�r�o
�ƂȂ�킯�ł��ˁB�`�u�Đ��̎��́A�v�������Q��ʂ�̂ŁA���������͒ቺ���邪�A�`�u����������ǂ����낤�A�Ƃ������Ƃł��B���̂Ƃ��́A�T�O�T���̉��ʂ��Œ肵�āA�S�`�����l���`�u�A���v�ňꊇ�������܂��B
�T�O�T�����������ɂ́A���̕��@�ōs�����A���C���Z���N�^���g�����A�D���ȕ���I�ׂ悢�ł��B���C���Z���N�^�̕����P�[�u�����]���ɗv��̂ō������܂����B
�����ԍ��F6283741
![]() 0�_
0�_
2007/04/29 23:35�i1�N�ȏ�O�j
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������
�u���C�N�_�E�����Ẵt�H���[�A���肪�Ƃ��������܂�(^-^)/
�A�`�R�`�ŋc�_��W�J���Ă���܂����AAV�����́A�P�[�u�����̉����̌������x���ɒB���Ă��Ȃ��Ƃ̌����ł��̂ŁA�ςɂ������g�ݍ��킹���A�f���Ƀv�����C�����͂Ŏx�ᖳ�ƍl���܂���B
��͂��C�����܂����A���ŕ����邱�Ƃ�������C�y�ɂǂ�����
�����ԍ��F6283859
![]() 0�_
0�_
�@���݁A505f�ƃp�C��AX4ASi�v���A�E�g���A���C���Z���N�^�[�i���b�N�XAS-44�j�����505f�̃��C���C���Ɍq���ł��܂��B
�@�ȑO�Ɉ����Z���N�^�[�������܂������A���������ăm�C�Y���Ђǂ������̂ŁA�Z���N�^�[���g���Ȃ�A������Ȃ��ق��������ł��B
�@
�@�v���v���ڑ��́A�{�����[����߂��Y���Ƒ�ςȂ̂ŁA��������҂ɂ͂����߂܂���B
�����ԍ��F6284797
![]() 0�_
0�_
2007/04/30 08:42�i1�N�ȏ�O�j
��������łɃt�H���[���Ă����܂��B
>�v���v���ڑ��́A�{�����[����߂��Y���Ƒ�ςȂ̂ŁA��������҂ɂ͂����߂܂���B
�v���v���ڑ����Ă���ƁA�`�u���Ƃ��v�����C���A���v�̃{�����[�������v�́u�R���v������܂ŏグ�āA���̃`�����l���ƃo�����X���Ƃ�܂��B���������āA�v�����C���A���v�̃{�����[�������v�́u�R���v�ɂ����܂ܓd����邱�Ƃ�����܂��B
���Ƀv�����C���A���v�łb�c�����Ƃ��āA�{�����[�������v�́u�R���v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�Y��Ă���ƁA�����Ȃ�剹�ʂ���яo���ċ����A�Ƃ������ۂł��B
�����ԍ��F6284841
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A�r�����������@�q������������AK���ver2����A��肪�Ƃ��������܂��B
K���ver2�����g���̍��i�ʂȃZ���N�^�[�͂P���~���炢������̂̂悤�ŁA������ƍl���Ă��܂��܂��ˁB���z�`�u�A���v�͑E�߂��Ȃ��Ƃ����̂��r�����������@�q������������̂��l���ŁA�m����505�������������V�X�e���ɂ���̂����z�ł����A�ώG��������`�u�A���v��{�ŗ������������Ƃ����l��������܂��B�Ȃ��A
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060324/sound.htm
�ɂ��A�v���[���[�ɐV�t�H�[�}�b�g�̃f�R�[�_�[������o�b�l�ɕϊ����邱�Ƃłg�c�l�h�@�P�D�P�ł��}���`�`�����l���]���ł���悤�ł��B�`�u�b�|�`�P�P�w�u�͂g�c�l�h�@�P�D�P������Ă���A�r�`�b�c�Ή��̃f�m�������N�ƍ��킹�Č���̊e��t�H�[�}�b�g�̃f�W�^���]���ɑΉ����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�A�Q�����̉����͕ʂƂ��Ă����ɒ�������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�X�s�[�J�[�ɂ��ẮA�������W��Ȃ̂ł��܂�傫�Ȃ��̂�u������͂Ȃ��A�`�u�A���v�̋쓮�͂ł����ɖ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B�Z���N�^�[���g�킸��505�������������@�����Љ�������܂������A�v���A���v�����Q�x�ʂ艹�����ቺ����Ƃ����̂��C�ɂȂ�܂����B��Ɂu�}���`�`�����l���ł̓f�m�������N��3920����v�Ə����܂������A�f�W�^���ڑ��ɂ�����炸�c�u�c�|3930�̃A�i���O�T�D�P�����o�͂��g���e�k�E�e�q��505���ɁA���̂R�D�P�������`�u�A���v�ɐڑ�������@�ł�����ɉ��͏o��̂ł��傤���H�{�����[���������ʓ|�ɂȂ�܂����A�c�r�o�����p�X�ł���`�u�A���v���g���Η]�v�Ȃ`�^�c�E�c�^�`�ϊ��������ɍς݁A�A�i���O�ڑ��ł����Ȃ��悤�Ɏv����̂ł����B
�����ԍ��F6287285
![]() 0�_
0�_
2007/04/30 22:41�i1�N�ȏ�O�j
>SS-039����
�u�f�W�^���ڑ��ɂ�����炸�c�u�c�|3930�̃A�i���O�T�D�P�����o�͂��g���e�k�E�e�q��505���ɁA���̂R�D�P�������`�u�A���v�ɐڑ�������@�ł�����ɉ��͏o��̂ł��傤���H�v
�Ȃ��Ȃ��T���S�����ł��ˁB�l�̃z�[���y�[�W�́u�}���`�`�����l���I�[�f�B�I�V�X�e����v�́u2-3. �`�u�A���v��ʂ��Ȃ��Ńv�����C���A���v���g�p����Ƃ��v�������������B
�v����ɁA�`�u�A���v�����S�ȂR�D�P�����A�i���O�A���v�Ƃ��Ďg���A�T�O�T�����t�����g�p�Ɏg���Ƃ������Ƃł��ˁB�`�u�A���v�́A�A�i���O���͂̃s���A�_�C���N�g���[�h�ɂ��āA�f�B�W�^�������͂��ׂăp�X�����܂��B�����A�`�����l�����x���A�X�s�[�J�K�͂Ȃǂ̐ݒ�͂c�u�c�|3930�ōs���܂��B
����ŁA���Ƀs���A�ȉ������y���߂܂��B�Ƃ��ɁA�������t�H�[�}�b�g�ł���r�`�b�c�}���`�̍Đ��ł́A���́u�s���A�l�X�v�͗L���ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
���_�̓{�����[���R���g���[�����Q���Ƃł����A�`�u�A���v�͂��a���l�\�����o�܂��B�T�O�T���̓c�}�~�̎���ɂ��a���l���ł��Ă���܂��B�����ŁA�����̐��l�����킹���Ƃ��o�����X����悤�ɂc�u�c�v���[�����͂`�u�A���v�Ŋe�������x�����Ă����܂��B
�����̃z�[���V�A�^�[�ł��A�{�����[���R���g���[���u�Q�v�ʼn^�p���Ă��܂����A�Ɛl����u�ʓ|�v�Ƃ̋��͗��Ă��܂��E�E
�����ԍ��F6287473
![]() 0�_
0�_
2007/04/30 23:32�i1�N�ȏ�O�j
�����́A���ז����܂�(^-^)�m~~
SS-039����
�v�����Q��ʂ郍�X�����O�����C�����͂悭������܂��B
���݂ɉ䂪�Ƃł́A�R�Q�O�O���烉�b�N�X�̃v��C7f���o�ă��b�N�X�̃p���[M800�ɐڑ����Ă��܂��B
�v���P�i�Ƃ̉������́AAV�����ł͖w�ǂ���܂���ƌ�����������܂���B
����Ĕz���̊W��A�v���v���ڑ��ɂ��Ă���܂��B
�ʓr�E�b�J���҂̌��ł����A�v���v���Ƃ͖��W�ɁA���͐�ւ���p���[�I�t���ɂ̓{�����[�����i���K��������̂��x�^�[�ł���B
�o�N�ω��Ŏv��ʃp���X�m�C�Y�����邱�Ƃ�����܂�����ˁB
���j�APCM�ϊ��ɂ��������������l���ɂ͑�^���ł��B
����������͎�����t�H�[�}�b�g�����C���ł���ASD DVD�ɉ����Ă̓����b�g���Ⴂ��������܂��B
PS3�ł�BD�Đ��ɂāA�����ネ�X���X�t�H�[�}�b�g��HDMI�ɂă��j�APCM�`�����AAV�A���v�Ńf�R�[�h����̂��ō������ł��傤�ˁB
�f�m�������N�̈З͂͒m��܂���B�S�����i�T�C�ˁE�E�E
�����ԍ��F6287726
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A�t�H���[�ǂ����ł��B
�r�����������@�q������������
�����͐�ւ���p���[�I�t���ɂ̓{�����[�����i���K��������̂��x�^�[�ł���B
�@
���̒ʂ�ł��ˁB
���̑��̑Ώ��Ƃ��āA�}�N���@�\�t���̃����R�����g���e������܂��B�i�����R�������̃A���v���Ɩ����ł����B�j
��PS3�ł�BD�Đ��ɂāA�����ネ�X���X�t�H�[�}�b�g��HDMI�ɂă��j�APCM�`��
i.link�ŁA����̂ł���v���C���[���o�Ă����Όl�I�ɂ̓x�X�g�ł��ˁB
�����ԍ��F6288128
![]() 0�_
0�_
2007/05/01 13:45�i1�N�ȏ�O�j
����ɂ���
K���ver�Q����
��������҂̂悱��莸�炵�܂���(^_^;)
i�����N�Ƃ������Ƃ́ADVHS���G�\�̃v���C���[��z��ł����ˁH
���̃v���Z�b�T�͉���z�肳��Ă��܂����H
�����ԍ��F6289451
![]() 0�_
0�_
������ƌ��t���炸�ł����ˁB
BD�v���C���[�ŁA�����ネ�X���X�t�H�[�}�b�g�����j�APCM�ϊ����āAi.link�I�[�f�B�I�[�q����o�͏o����AHDMI���f���݂̂Ɏg����̂ŁA�f���E�����Ƃ��ɍ��i���ɂȂ肻���Ȃ̂ŁB
�@�p�C���G�\������Ȃ�A�����Ă��ꂻ���ȋC������̂����E�E�E�BAX4ASi��i.link�[�q���L�����p�ł��܂����B
�����ԍ��F6289597
![]() 0�_
0�_
2007/05/01 17:50�i1�N�ȏ�O�j
K���ver�Q����
���j�APCM�ϊ�����i�����N�`���ˁE�E�E
�Ȃ���ˁB�������{�Ƃ̃\�j�[��i�����N����u���Ă܂�����(^_^;)
�p�C�I�j�A��AV�A���v�ɂ�i�����N�����ڂ���Ă܂����ˁB
�����f���Ɖ��������������n�[�h��K�i�ɐU���郊�X�N�͒ጸ����ƍl���܂��B
�������Ή��@��̖ʂ���́A�f�B�W�^�������o�͒[�q����ł��悢�Ǝv���܂����A�ш悪�s�����Ă܂�������(?_?)
�����ԍ��F6290058
![]() 0�_
0�_
�@�܂��A�\������o�Ȃ��ł��傤���A�o���炢���Ȓ��x�Ɏv���Ă��܂��B
S/PDIF�i���^�����j����LPCM24bit/192kHz�i2ch�j�����E�ł��̂ŁA�}���`ch����i.link��HDMI�����Ȃ��ł�����˂��B
�����ԍ��F6290511
![]() 0�_
0�_
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������̂g�o��q�������Ă��������܂����B�}�����c�̃v�����C���ɂ͕֗��ȋ@�\�������ł��ˁB505��+�o�l�|�P�T�r�P*�Q�ō\�������ꍇ��a���͏o��̂ł��傤���H
�r�����������@�q������������AK���ver2����A�f�W�^���]���̘b��Ő���オ���Ă��܂����A�i���O�`�u�A���v�̏ꍇ�A�c�^�`�ϊ��̓v���[���[���A�A���v���̂ǂ���ōs���̂��悢�̂ł��傤���H�c�u�c�|3930�N���X�̐��i�Ȃ�v���[���[���ōs���A�i���O�ڑ��ł����Ȃ��̂ł��傤���A�c�u�c���R�[�_�[�̂悤�ɂc�^�`�ϊ������n�ゾ������A�i���O�}���`�`�����l���o�͂��Ȃ��ꍇ�ɂ̓f�W�^���ڑ����L���A�Ƃ������߂ł悢�̂ł��傤���H
�����ԍ��F6290660
![]() 0�_
0�_
2007/05/01 23:01�i1�N�ȏ�O�j
>�}�����c�̃v�����C���ɂ͕֗��ȋ@�\�������ł��ˁB505��+�o�l�|�P�T�r�P*�Q�ō\�������ꍇ��a���͏o��̂ł��傤���H
�ك��[�J�[�َ̈�A���v�ō\������̂́A��߂��ق�������ł��B�r�`�b�c�}���`�̂悤�ȍ��������y�\�t�g���ꍇ�A�t�����g�E���A�ԂŁA���̃X���[�Y�ȂȂ��肪�����邩�ǂ��������炸�A����̐[���Տꊴ�������Ȃ������ꂪ����܂��B
�����ԍ��F6291289
![]() 0�_
0�_
�����ł����B�ł�����R�D�P�������͂`�u�A���v�Řd�����ق������������܂���ˁB505��+�`�u�A���v�̐��ōs���A�ڑ������낢�뎎���Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�����ĉ����������Ȃ��Ȃ�������A�r�����������@�q������������AK���ver2����A���낢��Ƃ��肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F6294096
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > LUXMAN > L-505f
L-505f����550A��590A�̍w�����l���Ă��܂��B�F�X�ȏ��ŁAL-505A��L-509A�̏��`���A���v�̗ǂ����q�ׂĂ���A���i��L-505f�ɔ�ׂĂ��Ȃ荂���ł��B505A��509A�͏����g�����W�X�^��A������͈͂ł̑��������Ă���̂ɑ��āA505f��2��C-������̃g�����W�X�^�������I�Ɏg���v�b�V���v���œ��삳���Ă���Ǝv���܂��B�]�������I�ɑO�҂́A�����̈�ő������Ă���ׂɘc�݂����Ȃ��A��҂̓N���X�I�[�o�����ł̘c�݂��o��Ɛ�������Ă��܂��B�܂��A�����I�ɑO�҂́A�o�͂��傫���o���܂��A��҂͏o�͂�傫���o���܂��B�ȏ�͌����I�Șb���ł��B�������A�J�^���O�f�[�^���������A505f�̑S�����g�c�ݗ���0.005%�ȉ��ł���̂ɑ��āAL-550A�͓��c�ݗ���0.006%�ȉ��AL-590A��0.005%�ȉ��Ǝ�����Ă���A�w�Ǖς�肪�L��܂���B����ŁA�����ŏo�͂��Ⴂ��A�������505A��509A��I������Ӗ�������̂ł��傤���H���ۂɔ�r���Ď������������Ƃ������̂ŕ�����܂���B�ǂȂ����A���ۂɕ�����ׂāA�����ł͕�����Ȃ��Ⴂ���m�F�����l���L������ĉ������B
![]() 0�_
0�_
����ɊԈႢ���L��܂����̂ŁA�������܂��B����505A,509A�Ə����Ă���̂�550A,590A�̊ԈႢ�ł��B��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F6111855
![]() 0�_
0�_
��505f��2��C-������̃g�����W�X�^�������I�Ɏg���v�b�V���v���œ��삳���Ă���Ǝv���܂��B
�I�[�f�B�I�A���v�łb������������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A�������̂ł��傤���B
�����ԍ��F6112324
![]() 0�_
0�_
�ԈႢ�܂����BAB������̃g�����W�X�^2���v�b�V���v���Ŏg���Ă���悤�ł��B
�����ԍ��F6115915
![]() 0�_
0�_
�^�C�K�[�E�E�b�Y����C����ɂ��́B
�@�ŋ߂̃A�i���O�E�A���v�̂قƂ�ǂ�AB�����̗p���Ă��܂����CAB���̉�H�v�͉~�n���ŁC�N���X�I�[�o�[�c�݂ɂ�鉹�̗͒����킯���Ȃ����x���܂łɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������C�s���A�E�I�[�f�B�I�ł͉��̗ǂ��̃C���[�W�Ƃ��āCA����AB���Ƃ����̂���ʓI�ł�����C�I�[�f�B�I�E���[�J�[�ł́C��t���b�O�V�b�v�@��A�����̗p����P�[�X�������ł��ˁB�t���b�O�V�b�v�@�ł�����C���[�J�[�̊�ƂȂ�Ȃ�������܂���B�P��A�����Ƃ��������łȂ��C���̉�H�E�p�[�c���������������Đv���Ă���܂�����C���ꂪ�����I�ɏo��������Ă���Ǝv���܂��B�ł��̂ŁC�P��A��������ǂ��Ƃ͌�����Ȃ��Ǝ��͍l���Ă��܂��B
�@�܂��A���v�̍����g�c�ݗ��́C�����킯�ł��郌�x�����͂邩�ɉ�����Ă��܂��̂ŁC�C�ɂ���Ȃ��Ă����ł��傤�B�X�s�[�J�[�̘c�݂̂ق����C�A���v�ɔ�ׂČ��Ⴂ�ɑ傫���ł�����ˁB
�@�^�C�K�[�E�E�b�Y������C���ۂɔ�r��������邱�Ƃ������߂��܂��B�����g�Œ����Ă݂āC���������Ȃ��Ǝv���A���v��I��ł��������ˁB
�����ԍ��F6117329
![]() 0�_
0�_
�W�����A�o�[����A�R�����g�L��������܂��B
�����߂̒ʂ肾�Ǝv���A��r�����ɍs���ė��܂����BL-505f��L-550A��B&W��804S���Ȃ��ŁA��ւ��ĕ������Ă��炢�܂����B���肪�������邳�������̂ŁA�������ɂ��������̂ł����A�����Ƃ��Ă͖w�Ǖς�肪�L��܂���ł����B���Ӑ[�������ƁA��͂�550A�̂ق����A���ꂼ��̉��̗��������悭�A���̓I�ɕ�������Ƃ��A���ꂼ��̉��̐��������Ȃ�A�����o���������Ȃ�悤�Ȉ�ۂ������܂����B�������A����قǑ傫�ȍ�������Ƃ͌�����܂���B���X����ł��ˁB�v�́A�����������ŁA���ɖ�������̂��Ƃ������̂悤�ȋC�����܂����B�A���v�����ނ���X�s�[�J�̑I�����L�[�̂悤�ȋC�����Ă��܂����B�N���V�b�N��̂ɕ����̂ŁA����TANNOY��Turnberry,���邢��STIRLING�N���X��B&W��803S,804S�N���X�łǂ���ɂ��悤���Ɩ����Ă��܂��B�A���v�̘b���Ŗ����ċ��k�ł����A���������߂���������ĉ������B
�����ԍ��F6127379
![]() 1�_
1�_
> �������A�J�^���O�f�[�^���������A505f�̑S�����g�c�ݗ���0.005%�ȉ��ł���̂ɑ��āAL-550A�͓��c�ݗ���0.006%�ȉ��AL-590A��0.005%�ȉ��Ǝ�����Ă���A�w�Ǖς�肪�L��܂���B
�S�����g�c�ݗ��Ƃ������̂́A�ÓI��(���ԓI�Ɉ��肵�����ő��肵��)�A����ȏ�ʂł̒l�ł��̂ŁA������x�ȉ��̒l�Ȃ����قǂ�������Ă��������̂Ȃ����l���Ǝv���܂��B
�܂��A���[�J�[���^���킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�l���Ⴗ����悤�ȋC�����܂��B���[�U�[���Ǝ��ɑ��肵�Ă��A�{���ɂ��̒l�ɂȂ�̂��H�Ƃ����^�₪����܂��B(��͂�A���[�J�[���^���Ă��܂��B��)
���[�J�[�́A0.006%��0.005%�̈Ⴂ����ʂł���قǂ̐��x��������@��������Ă���̂����Ɛ����ł��܂����A���ʂ̃��[�U�[�ł͂܂������ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F6128484
![]() 0�_
0�_
�^�C�K�[�E�E�b�Y����C����ɂ��́B
>������
�@�������[�J�[�Ζ����Ă������́C�S�����g�c�ݗ���0.1���܂ł�������ł��܂���ł����B���́C�p�\�R���Ő�p�\�t�g�̑����0.001���܂ő���ł���݂����ł����C���ۂɂ�������Ƃ͂���܂���̂ŁC���̑���l���������̂��͂킩��܂���B�����ߋ��̌o������0.1���ɋ߂Â��C������̘c�݂͂قƂ�NJ����Ȃ��Ǝv���܂��B
�@������̂��������ʂ�C�S�����g�c�ݗ��̐����ŃA���v�̗ǂ������͌��߂��Ȃ��ł��傤�ˁB
>�^�C�K�[�E�E�b�Y����
�@TANNOY��B&W�̂����߂������₳��Ă܂����C��������ł����Ɩ炵���̂̓I�[���h�E�^���m�C�̕��ނɓ�����̂����ł��̂ŁC������̋@��ɂ��Ă͂����Ƃ��ԓ��ł��邩�ǂ����B�V�����^���m�C��B&W�͓X��F�l��ł̎��������Ȃ�ł��B���̓I�[�f�B�I�G�����قƂ�Ǔǂ܂Ȃ������I�[�f�B�I�E�t�@���ł��̂ŁB�ǂ���̃��[�J�[��������Ǝ���Ŗ炵�Ă�����������̔ɂ�����������Ǝv���܂��̂ŁC����ȕ�����̃��X�܂��̓X�������Q�l�ɂ��ꂽ�ق����ǂ��Ǝv���܂��B
�@�ЂƂ����C�^���m�C�ɂ��Ă͈�x15�C���`������SP����������邱�Ƃ������߂��Ă����܂��B�ߋ��̃^���m�C��SP������15�C���`�����������Ȕ��ɂ���Đ��i�����Ă��܂����C���̃��j�b�g�����锠�ɂ���ėl�X�ȕ\��ɕω�����15�C���`�����́C��͂�^���m�C�̊炾�Ǝv���܂��B
�@�܂��N���V�b�N��ǂ��������Ƃ̂��Ƃł����C�I�P�����Ґ��̌��C���H�[�J���C�s�A�m�ȂǁC�ǂ�����܂��Đ������邩���C�@��I�т̖ڈ��ɂȂ�܂��B����JAZZ���قƂ�ǂŁC�N���V�b�N��CD�E���R�[�h��100�����x��������܂���̂ŁC�N���V�b�N�E�t�@���̕��̂��ӌ�����������ł��ˁB
�����ԍ��F6129628
![]() 0�_
0�_
�J�^���O�f�[�^�[�ƈقȂ�A�����@�̓f�[�^�[��A�c�݂����������Ă������@�ɔ�ׂāA���i�ɍ����i���g���Ă���̂ŃN���A�[����[�݂��S���َ����̕��ł��B�Ԃł����Ȃ�A����280�n�͂ł�2000���~�N���X��200���~�N���X�̎����ł����炩�ɈႤ�̂Ɠ������Ƃł��B
�����ԍ��F6239914
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > LUXMAN > L-505f
����AV�A���v�i�f�m��AVC3890N�j�ʼnf��ӏ܁E���y�ӏ܂��y����ł���܂��B
AV�A���v�ɂ̓s���A�_�C���N�g�Ƃ����@�\������܂��āA����̓t�����g2�����̂݉����o��@�\�ɂȂ��Ă܂��B
����ʼn��y���Ă܂����A�ŋ߂Ȃ����Ȃ����������Ă܂��B
�����ŁA�v�����C���A���v���w�����悤�Ǝv���Ă��܂��B
�X�s�[�J�[�̓��j�^�[�I�[�f�B�I��RS6�ł��BL-505����RS6�Ŗ炵�Ă������������Ⴂ�܂����H����܂����瑊���Ȃǂǂ̂悤�Ȋ����������Ă��������B���X�Ɏ������ɍs���Α����̂ł����A�F�l�̂��ӌ����Q�l�ɂ������Ǝv���Ă��܂��B
���i�������y�́A�N���V�b�N�i�s�A�m�n�j�I�y���A���܂�JPOP�ł��B
��낵�����肢���܂��B
![]() 0�_
0�_
���@�����ł��B���j�^�[�I�[�f�B�I�̃V���o�[RS6�ł��B
�����ԍ��F6054175
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�v�����C���A���v]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�������߃��X�g�z���X1440���Q�[������l����
-
�y�������߃��X�g�z���X�X���p
-
�y�~�������̃��X�g�z�V�Z�p�������@�̎���PC
-
�y�~�������̃��X�g�zDDR4�őË��\��
-
�y�~�������̃��X�g�zAM5
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2026�N2���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2026�N1���z

�^�u���b�gPC
- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2026�N2���z

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�v�����C���A���v
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j






