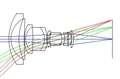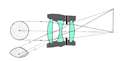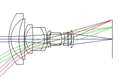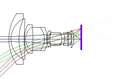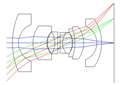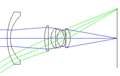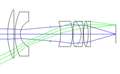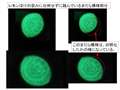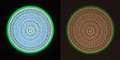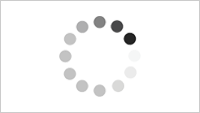OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g
| ¥- | |||
| ¥- | |||
| ¥- |
- �t�������Y
-
- �{�f�B
- �����Y�L�b�g
- �c�C�������Y�L�b�g


-
- �f�W�^�����J���� -��
- �~���[���X��� -��
OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g�I�����p�X
�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� [�V���o�[] �������F2011�N 7��22��
OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g �̃N�`�R�~�f����
�i9205���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S102�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 2011�N9��26�� 20:18 | |
| 618 | 193 | 2011�N10��3�� 14:32 | |
| 4 | 5 | 2011�N9��26�� 14:58 | |
| 96 | 17 | 2011�N9��3�� 20:45 | |
| 261 | 24 | 2011�N9��23�� 01:32 | |
| 50 | 21 | 2011�N9��1�� 17:13 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P3 �{�f�B
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20110926_479620.html
PEN E-P3�̃��|�[�g�L����M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8�̕����ڂ��Ă��܂����B
���i�ɂ��Ă̓L��������ʂ肪�����炵���ł��B
�{�P���Ȃ��Ȃ��ŁA�Ō�̕��̃c�^�̎ʐ^�����{�ł��t���ς������Ƃ��Ă�̂��A
���������ł��B�V�����V�X�e���ƃ}�b�`���Ă��ł��傤�ˁc
![]() 5�_
5�_
���������Y�ł���
�������t���ς��N���ɕ`�ʂ���Ă��܂���
�p�i��20�_���~�����ł����@������������ł���
���͍���c�C�������Y�Z�b�g��������Ȃ̂ł���
�lj������Y�ǂ�ɂ��悤�������܂���
�����ԍ��F13548987
![]() 2�_
2�_
45mm�ƃp�i20mm�����Ƃ��g���Ă܂����A���Ȃ�ǂ��ł��B�����A���V���̊J�����ƃI�[�o�[�x���ɂȂ�̂��B�܊p���邢�����Y�Ȃ̂ɁAISO200�X�^�[�g��������ƃA�_�ɂȂ��Ă�̂��ȂƁB
�Ȃ�Ƃ�ISO100�X�^�[�g�ɂ��ė~�������̂ł��B
�����ԍ��F13549372
![]() 1�_
1�_
���͂��̃����Y�w���ȗ����̃����Y�ɂ͂܂��Ă��܂��܂����B
20mmF1.7�������Ă��܂����Ԃ��B�鎞�͎g�������Ȃ��Ȃ�A45mmF1.8�ɕt���ւ��Ă��܂��B
�ŒZ�B�e������50cm�Ƃ���������Ԏc�O�ȂƂ���ō��N���[�Y�A�b�v�����Y�𒍕����Ă��܂��B
�����ԍ��F13549373
![]() 6�_
6�_
12mm�Ɠ����悤�ȐV�����f�U�C���������ł��ˁB
�V���o�[�{�f�B�[���ƍŋ������H
�����ɂ�45mm�̍�Ⴊ����܂��B
�|�[�g���[�g�ȊO�ł��������ł��ˁB
http://fotopus.com/naviblog/amy/osanpo/
�����ԍ��F13549412
![]() 1�_
1�_
�J���ł��s���g���������Ƃ��낪�V���[�v�ł����ł��ˁB
�����̎ʐ^�ɂ��ȒP�ɎB��Ă悳�����ł��B
�����A�����A�Â��A�Łu���̃I�����p�X�v�Ȃ̂��킩��܂��B
�d-620�����̂܂܈��菬�^�����Čy�ʉ����A�d�u�e�t���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ŏo���āA
�u���b�N�̂��̃����Y�������Ă����Ƃ����ȂƎv���܂����i�O�O�G�G�G�c
�����ԍ��F13550994
![]() 4�_
4�_
�����@45�~�������Ă��܂����@����Ɓ@VF-2�Ƃ�
���X�Ł@vf-2���Ď����Ă݂܂������@�������N��
����@��ɂ����ł���
�����ԍ��F13551182
![]() 2�_
2�_
�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P3 �{�f�B
�ʐ^�͋@�\���܂߂đS���̑f�l�ł��BE-P3����|���Ƀ����Y�J�^���O�����Ă��Ă���Ȏ��ɋC�����܂����B
�F�l�͂ǂ�ȕ��ɂ��l���ł��傤���B
�t�H�[�T�[�Y�����Y��ED9-18mmF4.0�`5.6�ƌ��������Y������܂��B
����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�ɂ�ED9-18mmF4.0�`5.6�ƌ��������Y������܂��B
�t�H�[�T�[�Y�����Y�̃t�B���^�[�a��72mm�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�̃t�B���^�[�a��52mm�ŎO�����������B�ŁA���i�͂ǂ����71,000�~�B
���[�J�[�ɕ������Ƃ��됫�\�I�ɂ͑傫�ȈႢ���Ȃ��BE-P3�������瓖�R�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�K�i�Ή��̃����Y�̕����D��Ă���ƌ�����A�Ƃ̂��Ƃł����B
���������ōl�����̂́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł��̂悤�ȓ���������̂������疾�邢�����Y����ė~�������̂��ƁB
�Ⴆ��ED9-18mmF2.8�Ȃ�Ă������̂��������ꂽ���т��Ĕ��������A�Ɗ���������B
�ʂ̃X���b�h��F2.8�̃����Y��F1.8�̃����Y�ɂȂ蓾�Ȃ��Ƃ̂��ӌ�������A��������ς薾�邢�����Y�ɂ͂��ꂾ���ő��݉��l������̂����A�Ǝv��������B
�t�H�[�T�[�Y�K�i�������ǂ��������Ȃ̂��B�{�i�d�l��E5�J��������Ƃ��̑傫���d���������牽���t�H�[�T�[�Y�łȂ����Ă��Ǝv����B
�t�����W�o�b�N���Z���Ȃ邱�Ƃɂ���ăt�H�[�T�[�Y�����Y�Ɠ���œ_�̂��̂��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�Ƃ��Ă�菬��������B�����������薾�邢�����Y�����邱�Ƃ����������i�J�^���O��j�̂����炻�����Ă͂ǂ����B
�����Ƃ����[�J�[���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�K�i�̃J�����͒P���ɃT�u�J�����̈ʒu�Â��ƍl���Ă���̂��낤���B���Ƃ���Ɛ����������������A�Ǝv����B����������ƃR���f�W�ŏ\���Ȃ�Ď��ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�����ȃ{�f�B�Ƀf�J�C�����Y�����邱�Ƃɂ͂Ȃ���肪�Ȃ��ނ��듖����O�̂��ƁB
������ɂ��Ă����s�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�̓t�B���^�[�a��58mm�ȉ��ɗ}�������߂����邢�̓R���p�N�g����_�������߂������Y�̃��C���i�b�v�ɕs�����o����B
���邢�����Y���~�����B
M.ZUIKO�@DIGITAL�@ED12mmF2.0�Ȃ�ăt�B���^�[�a42mm������ǂ����62mm�ɂ���������Ɩ��邢�����Y�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����E�E�E���Ƃ͂����P���ł͂Ȃ��̂ł��傤����ǁI�O�ʂ��f�J�N����Ǝ��ӌ��ʂ������Ȃ��Ƃ��E�E�E�ǂ�������܂��E�E�E�E
�Ⴆ�t�H�[�T�[�Y50mmF2.0�}�N����50mmF1.4�}�N���Ƃ����邢��60mmF1.4�}�N���Ȃ�ďo�������ȋC������B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�Ő_�����Y�ƌĂ��悤�ȃ����Y���J�����ꂽ��E�E�E�E�E
�F�l�͔@�����l���ł��傤���B
![]() 3�_
3�_
�������ł��ˁB
�S���̑f�l����Ȃ̂ɁA���p��������ς��������ŁB
�������炢�����ǁA�A�A
�������炢���ł��ˁB����ȏ�͎��ɂ͂킩��܂���B
�����ԍ��F13521207
![]() 3�_
3�_
�����́Bginganohikari����
��ς悭�����m�ł��ˁB
ginganohikari����̂��]�݂̃����Y���J���������Ă����Ηǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F13521238
![]() 2�_
2�_
�܂��A����~���[���X�͂P��t�̃T�u�܂��̓R���f�W����̃X�e�b�v�A�b�v�@�Ƃ��ďo����Ă���Ӗ����傫���ł������
�܂��傫���d���Ȃ鍂���\�����Y���o�������ł͂Ȃ��Ƃ������f�ł��傤
������͂P��t�̑����̕����̑�ւƂ��Ẵ~���[���X�V�X�e���ɂȂ�̂�
���̂Ƃ��ɂ́A�����Y�Ƃ̃o�����X�������Ȃ�Ă�������������������邱�Ƃ�����
���ʂɑ傫�ȃ����Y����R�o�Ă���̂ł��傤��
�P��t����~���[���X�ɂ����Ƃ��ɏ��^�y�ʉ��ł���͖̂{�̂Ȃ̂�
�����Y�͑傫���d���Ȃ�ꍇ�������킯�ł�
�~���[���X�ŏ��^�y�ʉ��ł���͍̂L�p�n�̃����Y�Ȃ̂ł���
�P��t�̂悤�Ƀ��g���t�H�[�J�X�ɂ��Ăނ���t�����W�o�b�N�����K�v�������̂Łc
�����ǂ��Ώی`�̐v�ɂ���ƃe���Z���̖�肪�o�Ă���
�������������������Ɩʔ��������Y���o���₷���Ȃ�̂ł����ǂˁ�
(*´��`)�m
�����ԍ��F13521286
![]() 2�_
2�_
���邢�����Y�͂��ꂾ���Ŗ��͓I�ł��ˁB
NOKTON 25mm F0.95
http://kakaku.com/item/K0000145739/
�����ԍ��F13521331
![]() 1�_
1�_
�I������������̂͂������Ƃ����ǁA���̎���m4/3�̃����Y��14/2.5������
�������Ȃ��Ă�����������Ă��܂��B���Ƃ̓A�_�v�^�łȂ���
�V��ł��܂��BTokina 11-16/2.8����NFD 100-300/5.6�܂ŁB
�l�I�ɂ̓p���P�[�L�ŒP�œ_�����Ă��ꂽ�牽�����������B
10/2.8�Ƃ��A40/2�Ƃ�14/2.5�̌y���Ƒ����ŏo���Ăق����Ȃ��B
�����Ȃ��
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̓������������Čy���ď����������Y���~����
����
NFD 50/1.4 + FD-EF + EF25II+ EF-m4/3���ƃn�[�t�}�N�����炢��
�Ȃ�̂��ȁBLSC���˂����瓖�{�o��C�����Ă�����
�i�{�������ˁA�}�N�������Y�Ƃ̓��v���C�X�ł��Ȃ����ǁj
�����ԍ��F13521340
![]() 2�_
2�_
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�n���AF���x���A����I�Ɍ��サ������A�����Y�Q���ŏ��i�肪F3.5�`F5.6�O���[�v�ƁA�ŏ��i�肪�`F�S�̂Q�Q�����K�v�����肻���ł��ˁB
�@M4/3�V�X�e�����W�ׂ̈ɂ�OLYMPUS����A���������肢�܂��B
�����ԍ��F13521341
![]() 2�_
2�_
���F�l�͔@�����l���ł��傤���B
�͂��I���������܂��傤��
�����Y�̔Ō���������C�C�ˁB
������E-P3�̔�����B
�����ԍ��F13521620
![]() 1�_
1�_
>���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
�t�B��������ɁA�~���[���X�Ǝ����\���̃����W�t�@�C���_�[�Ƃ����J����������܂��B
�~���[���X���l�ɁA�t�����W�o�b�N���݂������ł��܂��B
�����œ_�����ŁA���i��̃����Y���r�����ꍇ�����W�t�@�C���_�[�̃����Y�̒��ŁA�P��t�̃����Y���傫�ȃ����Y���������Ƃ������̂ł����A
�Ȃ��A�~���[���X���ƃ����Y�͑傫���d���Ȃ�̂ł����H
�����ԍ��F13522277
![]() 0�_
0�_
��hiderima����
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�������Ȃ�o�b�N�t�H�[�J�X�͕ς��Ȃ�����ł��˂�
�~���[���X�̓t�����W�o�b�N���Z�����A�����Y�������Ȃ�܂�
�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ���Ƃ��̃}�E���g�A�_�v�^�̕�����
�����Y�������Ȃ���Ă��Ƃł�
�L�p�n�̃����Y�̏ꍇ�͂P��t�̏ꍇ�������t�����W�o�b�N���v���邵���Ȃ��̂�
���̖�����蒷�������������t�����W�o�b�N���Z�������Y�����~���[���X�ł͏��^���ł���
�����ǂ��e���Z���̖�肪����̂Ŕ����Ƃ������Ƃ��ł��傤
�̂̃����W�t�@�C���_�[�̃����Y�̏ꍇ�A�]�������Y�͏��������Ȃ������ł���
�ǂ��炩�Ƃ����A�P��t�ł͍i��̘A���@�\���ǂ����Ă��K�v�������̂�
�����Y�������Ȃ�Ƃ�����������܂���
�����ǂ��A���̃����Y�ł̓~���[���X���P��t�������Y�ɂ`�e���[�^�[���d�q����̍i���������܂��Ȃ̂�
��{�I�ȃ����Y�̍\���͓����ƂȂ��Ă��܂����
�����ԍ��F13522389
![]() 1�_
1�_
>���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
>�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ���Ƃ��̃}�E���g�A�_�v�^�̕�����
>�����Y�������Ȃ���Ă��Ƃł�
���X�傳��́A4/3�����Y���g�p����̖]��łȂ��Am4/3�p�Ƀ����Y�v���������ė~�����Ƃ����Ă���̂��Ǝv���܂����B
>�����ǂ��A���̃����Y�ł̓~���[���X���P��t�������Y�ɂ`�e���[�^�[���d�q����̍i���������܂��Ȃ̂�
>��{�I�ȃ����Y�̍\���͓����ƂȂ��Ă��܂����
�����Ă�Ǝv���܂����B�t�����W�o�b�N���Z�����A�����悤�ȃ����Y�\���ł������������Y�Ŗ��邢�����Y����邱�Ƃ��\���Ƃ������܂��B
�����W�t�@�C���_�[�́A90mmF2.0�Ƃ�135mmF2.8�̃����Y�\��������Δ���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13522649
![]() 0�_
0�_
�\�j�[����p�i�Ɉڂ����~�m���^�̋Z�p�w�����邢�����Y���J�����Ă��܂��B
���N����a�����Y���Q�{�����ɂȂ�܂���O�O
�����ԍ��F13522791
![]() 1�_
1�_
ginganohikari����
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�p�̂��̃����Y
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�p�ɐV�����@�\������Ă�ŁI
�����Y���ł����A���i���ł����Ȃ��Ă������I�H
�����ԍ��F13523002
![]() 2�_
2�_
�����X�傳��́A4/3�����Y���g�p����̖]��łȂ��Am4/3�p�Ƀ����Y�v���������ė~�����Ƃ����Ă���̂��Ǝv���܂����B
���₢��l�͂��������Ӑ}�ŏ�������ł܂����
���t�����W�o�b�N���Z�����A�����悤�ȃ����Y�\���ł������������Y�Ŗ��邢�����Y����邱�Ƃ��\���Ƃ������܂��B
�����W�t�@�C���_�[�́A90mmF2.0�Ƃ�135mmF2.8�̃����Y�\��������Δ���Ǝv���܂��B
���̕ς͏œ_�������������Ƃ������܂���
�X�O�����A�P�R�T�����ł͒m��Ȃ��ł��˂����c
�����ԍ��F13523299
![]() 1�_
1�_
�f�q�T�C�Y�͑傫���قlj掿�ʂŐ�ΗL���ł��B�������ANEX��PEN(APS-C)���ׂČ���ƁA�{�f�B�T�C�Y�ɈႢ�͂���܂���B�ނ���NEX�̏������ɁA�ŋ߂�PEN���悤�₭�ǂ������A�Ƃ������Ƃ���ł��B�~���[�{�b�N�X�����݂�����Ă������t�ɔ�ׁA�~���[���X�ł́A�f�q�T�C�Y�̍����{�f�B�T�C�Y�ɉe�����ɂ����B���Ⴀ�A�~���[���X�ɂ����ď������f�q��ςރ����b�g�́H�ƍl����ƁA�����Y���������Ȃ邱�ƈȊO�Ȃ��Ǝv���܂��B
�t�H�[�T�[�Y��APS-C�ł́A����ISO�l�ł̃m�C�Y�ϐ��A����F�l�ł̔�ʊE�[�x�A�ǂ����2/3�i�A���t�̃T�u�Ƃ���3:2�t�H�[�}�b�g�Ŏg���Ȃ�1�i�AAPS-C���L���ł��B�L�b�g�����Y���^�����āA14-42/F3.5-5.6��14-42/F2.8-4.0�ɂ����Ƃ���ŁA����͒P��NEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�ł�������܂���B����ŁA�T�C�Y���������炢�ɂȂ��Ă���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̑��݈Ӌ`���Ȃ��ł��傤�B
�������A�I�����͑��������ǂ��ł�����A������x���C���i�b�v�����낦�A����a�����Y�������Ă���Ǝv���܂��B���ہA�p�i�\�j�b�N�������a�Y�[�������Y�̔������\�肳��Ă܂��ˁB
�����A�����܂ł��A�}�C�N���̋��݂́A�i���Z�e�l�̈Ӗ��Łj�Â����Ǐ����������Y������A���Ƃ��Ǝv���܂��B
�t�����W�o�b�N���Z���Ȃ��ăX�y�[�X�ƃ����Y�̐v���R�x�ɂł����]�T�����ɂ܂킷���B�������A�{�f�B����Y�̍����\���ɂ܂킷�������܂��B�ł��A������ăt�H�[�T�[�Y�̎v�z�������Ǝv���܂��B���̎v�z�ɋ����^�����郆�[�U�[���������܂������A���ƓI�ɂ͐������Ȃ������B�����āA�������s���J��Ԃ��܂��Ƃ����ӎv���A�I�����p�X�̃}�C�N���̃��C���i�b�v����͋��������܂��B
�����ԍ��F13524495
![]() 1�_
1�_
NEX�ł͏��^���̂��߂Ƀt�����W�o�b�N��Z���������āA�L�p���ŃP�����郌���Y�����邻���ł��B
�����ԍ��F13524642
![]() 8�_
8�_
>���ӂ�ׂȂƁ[�邳��
�@�@��ς��ڂ������S���Ă���܂��B
�@�@�u�����ǂ��e���Z���̖�肪����̂Ŕ����Ƃ������Ƃ��ł��傤�v
�@�@���Ăǂ��������Ƃł����B�����Ă��������B
�����ԍ��F13524753
![]() 0�_
0�_
�g�t�����W�o�b�N�h�̐��@�́A�����Y�������ǂ��Ő邩�i�}�E���g�ʂ��ǂ��ɐݒ肷�邩�j�ɂ���Č��܂邾���ŁA���w�I�Ȑ��\�Ƃ͊W����܂���B
�~���[���X�J�����̌��w�v�Ɏ��R�x�������̂́A�B���f�q�̑O�̃~���[�������Ȃ����Ԃ�g�o�b�N�t�H�[�J�X�h�̎��R�x����������ł��ˁB
NEX�̃t�����W�o�b�N��M4/3���Z���̂́A���Ԃ�{�f�B�f�U�C���E�T�C�Y����̗v�����傫���̂��Ǝv���܂��B
>�L�b�g�����Y���^�����āA14-42/F3.5-5.6��14-42/F2.8-4.0�ɂ����Ƃ���ŁA����͒P��NEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�ł�������܂���B����ŁA�T�C�Y���������炢�ɂȂ��Ă���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̑��݈Ӌ`���Ȃ��ł��傤�B
�uNEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�v�Ƃ́H
NEX��18-55mmF3.5-5.6��PEN��14-42mmF2.8-4.0���������p�͂قړ����ł����A���邳��2/3����1�i�Ⴂ�܂��B
�ǂ����Ȃ�A���̏œ_���F2.8�ʂ����炢�ɂ͂��ė~�����ł��B
�{�f�B�T�C�Y�́A���ʂɍl����A�C���[�W�Z���T�[�ȊO�i��H���i��X�C�b�`�E�o�b�e���[�Ȃǁj�͂قړ��������T�C�Y���K�v�ł��傤����A�Z���T�[�T�C�Y���̕����炢�����������Ȃ�Ȃ��i�Z���T�[�T�C�Y�̔䗦�ŏ��^���o�����ł͂Ȃ��j�ł��傤�B
M4/3�ł͎�u������{�f�B�ɓ�������Ă���Ƃ�����l����ƁA�������炢�̑傫�����Ƃ��Ă��A���݈Ӌ`�������Ƃ܂ł͌����Ȃ��̂ł́B
�܂��A��p���x��ł̉掿�������p����Ȃ����x�����Ƃ���A���������Y�T�C�Y�Ŗ��邭����Ȃ�A���̕����L���ƍl���邱�Ƃ��o���܂��B
����������A�����Y���݂Ő��~�����炢�̑傫���̍��ʼn掿�̍������p����Ȃ����炢�̈Ⴂ��������A���쐫�̂�������I�т܂��B���R�f�U�C���̍D�݂�����܂�����ǁB
�����ԍ��F13524802
![]() 7�_
7�_
�F�l�̂��ӌ��q�����Ă���܂��B
���S�������ċ������鎖�����ƂĂ������ł��B���Ӑ\���グ�܂��B
>gingaro����F
�@���ӌ��悭������܂��B
�@�Ƃ����������肷���邮�炢�ɂ悭������E�E�E�E�̂ł����������E�E�E�E
�@�I�����p�X���ăy��FT�̃f�U�C�����J���������[�J�[�Ƃ��čD���Ȃ�ł��B
�@�����Ƃ��ʐ^���炩�Ȃ蒷���ԉ��������Ă܂��čŋ߂܂��ڂ��s���������̂ł����E�E�E
>SLSAMG����F
�@�p�i���痈�N����a�����Y��2�{�����E�E�E�E�Ƃ̃R�����g�B
�@�p�i�̃T�C�g���Ă�������܂���ł����B
�@�n�e�I�ǂ�ȃ����Y�Ȃ̂ł��傤����̓I�ɋ����Ă��������B
>nightbear����F
�@�n�C�I�f�J���č����Ă������܂��B�Ƃ����Ă����x�͂���܂����ǁE�E�E(^0^;)
�@�킽���͈��t�̂��̎O�p�������ǂ��ɂ��D���ɂȂ�Ȃ��i�����Ƃ����͂��܂聢�łȂ����ǁj�B
�@�Ȃ̂Ńy��FT�̃f�U�C�����C�ɓ����Ă��̗��R�Ŕ������o�܂�����܂��B
�@����ɁA�Ȃ̂ŁAE-330���o���Ƃ��ɂ̓J�������߂Ăɂ�ɂ₵�����̂ł����B
�@�ŁA�y��E-P3�̃f�U�C�����D���Ȃ�ł��B
�@�Ȃ�Ƃ��D���ȋȐ��ŐF���ۂ����������Ă��܂��B
�@�܂�����Ȃ̂ɁI�����ȃf�J�����Y���ĉ��̈Ӗ�������́I�ƌ���ꂻ���ł���M4/3�p�ɗD���ȃf�U�C���̖��邢�����Y���J�����Ă���������I�b�P�b�P�[�Ȃ�ł���܂��B
�@�������ł���A�~���[���X��������O�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���˂��B
�@�Ȃ�����ȗ\�������Ă�̂ł����E�E�E�E�Â��ł��傤���I�H�I
�@�t���T�C�Y�̃~���[���X���o�Ă��邩���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E(^0^)�E�E�E�E�ł�
�@�I�����p�X�C���[�W���O�̋�Y�����邢�����̃C���[�W�ɂȂ�悤�F���Ă܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�����p�X�����I�I�I�I�I
�@
�����ԍ��F13524879
![]() 3�_
3�_
���g�t�����W�o�b�N�h�̐��@�́A�����Y�������ǂ��Ő邩�i�}�E���g�ʂ��ǂ��ɐݒ肷�邩�j�ɂ���Č��܂邾���ŁA���w�I�Ȑ��\�Ƃ͊W����܂���B
�~���[���X�J�����̌��w�v�Ɏ��R�x�������̂́A�B���f�q�̑O�̃~���[�������Ȃ����Ԃ�g�o�b�N�t�H�[�J�X�h�̎��R�x����������ł��ˁB
���_��͐������Ǝv���܂��B�����A���ۂɂ́AM�t�H�[�T�[�Y�Ń}�E���g�ʂ�背���Y�����ɑ傫����яo���������Y�͂���܂����ˁB�Ⴆ�AM.ZD9-18mm�����̃T�C�Y�Ɏ��܂����̂́A�u�t�����W�o�b�N�̒Z���v�̂������Ƃ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
>�uNEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�v�Ƃ́HNEX��18-55mmF3.5-5.6��PEN��14-42mmF2.8-4.0���������p�͂قړ����ł����A���邳��2/3����1�i�Ⴂ�܂��B
���������œ�����ʑ̂��A������p�A������ʊE�[�x�A�����m�C�Y���x���ŎB��Ƃ��܂��B�i�ȒP�̂��߁A�����P�i�Ƃ��܂��B�j
NEX��18mm�EF4.0�EISO800�ɑ�������̂�PEN��14mm�EF2.8�EIS4O0�ł��B
���̂Ƃ��V���b�^�[���x�������ɂȂ�܂��B���������Ӗ��ł��B
���܂��A��p���x��ł̉掿�������p����Ȃ����x�����Ƃ���A���������Y�T�C�Y�Ŗ��邭����Ȃ�A���̕����L���ƍl���邱�Ƃ��o���܂��B
PEN��ISO400�܂�OK�ȕ��Ȃ�ANEX�ł�ISO800���炢�܂�OK�Ɗ�����ł��傤�B�܂�A�f�q���傫����Ώ�p���x��͂��̕��L����܂�����A�\�LF�l�����邭���邱�Ƃ��A�������f�q�̃����b�g�Ƃ͌����܂���B
���݈Ӌ`���Ȃ��Ƃ����̂͏��������ł������ANEX���{�f�B����Ԃ��𓋍ڂ��邩������Ȃ����A�p�i�̂悤��IS���������Y���R���p�N�g�����邩������Ȃ��B�ł��A�����炭�A�C���[�W�T�[�N�����ێ������܂܁AM.ZD9-18��M.ZD14-150�̂悤�ȃ����Y�͏o���Ȃ��ł��傤�B���a������������Ή\��������Ȃ����ǁA�������ɊJ����F8�Ƃ��̃����Y�͂����ȈӖ��ŏo���ɂ����BM�t�H�[�T�[�Y�ł͂���Ӗ��A���X�Ƃ��ꂪ�ł��܂��B���������������A�K�i�Ƃ��Ẵ����b�g�́A�����ɂ���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13525168
![]() 0�_
0�_
�C���[�W�Z���T�[�̑傫�����Ⴄ����ƌ����āA�����Y���r����̂ɂ悭���Z�e�l�Ƃ���������������������Ⴂ�܂����A�{�P����r����̂Ȃ炢���m�炸�A���Z�e�l�ȂǂƂ��Ăe�l�����Z����r���鎖�̈Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂e�Q�D�W�̃����Y�́A�����܂Ŗ��邳�͂e�Q�D�W�̃����Y�łe�l�͂���ȏ�ł��ȉ��ł�����܂���B
�����ԍ��F13525358
![]() 17�_
17�_
���A�X�R�Z���_����
�����Ă���Ƃ���A��ʊE�[�x�i�ڂ��j���ӂ��߂��b�ł��B
�����Y�̖��邳�A���邢�͏œ_����÷�L�����a�A���̐��l������r���邱�ƂɁA���ꂱ���ǂ�ȈӖ����H
�̐S�Ȃ̂́A�o�Ă���摜�A�掿�ł��BF�l�Ƃ������l���A���ۂ̎ʐ^�ɂǂ��e�����邩�ł��B
�����ԍ��F13525439
![]() 0�_
0�_
�����́B
�p�i�̑���a�Y�[���Ɋւ���f�W�J��WATCH�̋L���ł���
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110826_473211.html
���a���܂��������Ă��܂��A2.8�ʂ��ƌ��킸2.0�ʂ����A�͂��܂�2.0-2.8�Ȃ�Ă����̂����҂��܂��B���ݗL��MFT�p�̃����Y�ɔ�ׂ�Ώ��X�傫���Ȃ�̂ł��傤�B����ł�24-70/2.8��70-200/2.8�ɔ�ׂ�Ώ\�����^�ł��傤�B���Ȃ�y���݂ł��B
�����ԍ��F13526545
![]() 1�_
1�_
�P���ɉ�p135���Z�Ƃ�DOF135���Z���ĕ��͕���ēǂނ��A
�����Ƃ��Ɏ����Ă������������̂��Ƃ��Ǝv���B
�p�i��FT 25/1.4��500g����mFT 200g�ɂȂ��Ă���̂��ЂƂ�
�ȂƂ͎v������
NFD 50/1.4 + FD-EF + EF25II+ EF-m4/3���߂��Ă݂��̂Œ����Ƃ��B
����傳��̎v���`��50/1.4�}�N���͂����Ƃ����肿�������ł���͂��B
�v�������܂Ƃ��Ɏʂ�����
�����ԍ��F13526866
![]() 4�_
4�_
gintaro����
>���������œ�����ʑ̂��A������p�A������ʊE�[�x�A�����m�C�Y���x���ŎB��Ƃ��܂��B�i�ȒP�̂��߁A�����P�i�Ƃ��܂��B�j
NEX��18mm�EF4.0�EISO800�ɑ�������̂�PEN��14mm�EF2.8�EIS4O0�ł��B
���̂Ƃ��V���b�^�[���x�������ɂȂ�܂��B���������Ӗ��ł��B
�c�ł�����A
�u14-42/F2.8-4.0�ɂ����Ƃ���ŁA����͒P��NEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ����X�y�b�N�v
�@�ł͂Ȃ���
�u14-42/F2.8-4.0�ɂ����Ƃ���ŁA����͒P��NEX�̃L�b�g�Y�[���Ɠ�����ʌ��ʁv
�@�Ƃ������Ƃł��B
�t�H�[�}�b�g���ς���Ă������Y�X�y�b�N�̐��l�͕ς��܂���B
�ς��͉̂�ʌ��ʁi��ʊE�[�x��p�[�X�y�N�e�B�u�j�ł��ˁB
�����ԍ��F13527155
![]() 14�_
14�_
ginganohikari����
�����ȃZ���T�[��4/3�EM4/3�ł�����A��͂肻�̃����b�g���ő�������������掿�̖��邢�����Y������ė~�����Ǝ����v���܂��B�قǂقǂ̑傫���ō����\�ȃ����Y������ƌ����Z�i�������āA4/3�Ƃ����Z���T�[�T�C�Y�Ɍ��߂��̂ł��傤����B
�������ꂽ12mmF2.0��45mmF1.8�̂悤�ȏ������Ė��邢�P�œ_�����Y�̃��C���i�b�v���A�ǂ�ǂ����ė~�����Ǝv���܂��B
�ӊO�ƒm���Ă��Ȃ����Ƃł����A�Z���T�[�T�C�Y���������Ɛڎʂ̌��������Y�����₷���ƌ��������b�g������܂��B4/3�p��ZD12-60mmF2.8-4.0�ȂǁA����1�{�Őڎʂ��܂߂ĂقƂ�ǂ̎B�e�����Ȃ��閜�\�����Y�ɂȂ��Ă��܂���ˁB
OM�p��50mmF2.0�Ƃ�90mmF2.0�ȂǂƂ����}�N�������Y����������[�J�[�ł�����A���邢�}�N�������Y�ɂ����҂������Ƃ���ł��ˁB
����F2.0�̋�����Y�Ȃǂ��������Ă��ꂽ�炤�ꂵ���Ȃ��B
�����ԍ��F13527389
![]() 13�_
13�_
ginganohikari����
�T�O����F0.95�o��݂����₩�甃���Č����Ă�[�I
�����ԍ��F13527594
![]() 2�_
2�_
��[�I
���Ƀj�R�����~���[���X�����܂�����
�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E(^0^)2525
���āA
�@�@�����Y�̃��C���i�b�v�͂ǂ��Ȃ��Ă�̂ł��傤�I�I�I�I�I
���悢�挃��͗l�ɁE�E�E�E
�����ԍ��F13529177
![]() 0�_
0�_
�t�����W�o�b�N���Z���Ǝ��ӌ��ʗ������₷���Ȃ�܂��B
�܂��A�]��������Ȃ�B
�t�����W�o�b�N�������ƍL�p�����Y�����ɂ����B
�m�����C�J�̒Z���t�����W�o�b�N39mm�̂�͕s�]�Œ����Ȃ����̂ł͂Ȃ����������E�E�E
�Z������Ƃ��܂�ǂ��Ȃ��̂ł��傤�ˁB
�f�W�^���̌��ݐv�����l�B�������b�g�f�����b�g���������Ă����Ă���̂�����ł����ANEX�w�c�ɂ͍������Ă����Z�p�͂������̂ł͂Ȃ����E�E�E�Ǝv�킹������C���A�b�v�������A�x���B
NEX���������������ɂ͈�ʓI�ɕW���ł����������Y���K�v�ł��B
�]���͍��x�����������̂��Q�l�Ɍ��Ă�����������������������������
���łɃ}�N�������Y���o��̂Ŕ����O�Ɏ����𗠑����炲���ɂȂ��ĉ�����������
�O�|�����������������Ŋ�b�v����_���Ȃ낤�ȁE�E�E
�Ƃ������A�����Y�̐v�Ń~�m���^�̐l��啪�ǂ��o�������ʂȂ̂œ��R�ƌ����Γ��R�ł��B
�t�����W�o�b�N�̒��������Ɋւ��ẮAM�t�H�[�T�[�Y�̕���������ɏo���Ă���Ǝv���܂��B
�����Y�Ɋւ��Ă̓p�i�w�c�̈ӋC���݂͐����ł��ˁB
�I�������K���ė~�����ł��I
���Ƀj�R������~���[���X���o�Ă���ƂȂ�ƁE�E�E
M�t�H�[�T�[�Y�����Ȃ������낤�ȁE�E�E
��������Ęb���Ă�����̂���������������܂���˂��B
�ʔ����@�\���ǂꂾ������Ă��邩+�f�U�C���Œx�����C�Ɏ��߂������m��܂���˂��B
�|�������ʔ����������A���G�ł��ˁB
�����ԍ��F13529692
![]() 1�_
1�_
>�t�����W�o�b�N���Z���Ǝ��ӌ��ʗ������₷���Ȃ�܂��B
�܂��A�]��������Ȃ�B
>�Z������Ƃ��܂�ǂ��Ȃ��̂ł��傤�ˁB
�܂���������Ȏ��Ȃ��ł���B
���w�I�Ȑ��\���t�����W�o�b�N�̂����ɂ�������l�������̂͂Ȃ��H
�����ԍ��F13530204
![]() 8�_
8�_
�F�����ȋc�_�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�����Q���B
�����l����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̗l�ɎB���f�q�������ȏꍇ�̗��_�͎���3�B
�P�D�B���f�q���������Ȃ����������Y�̑O�ʂ̖ʐς��������o����̂ŁA���ʂƂ��ă����Y�̃K���X�̗ʂ������Ă��̕������Y���y���Ȃ�B
�A���A�O�ʂ̖ʐς����邾���Ȃ̂Ń����Y�̒����͕ς��Ȃ��B(�Ȃ̂ŃL�b�g�̕W�������Y�͒������ɂ��Ďg��Ȃ����̒�����Z�����āA�����ڂ��R���p�N�g�ɂ��Ă���)
�Q�D�O�ʂ̑傫���������ꍇ�A�B���f�q���������Ȃ��������O�ʂƂ̖ʐς̔䗦���傫���Ȃ�A����a�����Y�ɂȂ�B�Ȃ̂œ����傫���̃����Y�ł����邢�����Y�����A�܂��A�O�ʂ��������Ȃ����������y���o����B
�������A����Ԃ�v�̓���͕��ʂ̑���a�����Y�ƈꏏ�Ȃ̂ŁA�������Čy���Ă��l�i�͈ꏏ�Ŕ��ɍ����ȃ����Y�ɂȂ��Ă��܂��B
�R�D�O�ʂ̑傫���������Ń����Y�̍\���������ꍇ�A�B���f�q���������Ȃ����������Y�̎g�p����镔�������S�������ɂȂ�̂ŁA�����Y�O�������̑��̘c�݂�F�̂ɂ��݂Ȃǂ̏����Ƃ����v������������C�ɂ��Ȃ��ėǂ��Ȃ��ɁA���S���̔������������������g����̂ŁA�ʂ�̂��������Y����������B
�������A�����Y���̂��͈̂ꏏ�Ȃ̂Ōy�������������Ȃ�Ȃ����A�O�������̂ĂĂ��܂����ߖ��邭���Ȃ�Ȃ��B
����Ȋ������Ȃ��B
�����ԈႢ�Ȃǂ�����w�E���������܂��B
�����ԍ��F13530484
![]() 0�_
0�_
���t�����W�o�b�N���Z���Ǝ��ӌ��ʗ������₷���Ȃ�܂��B
Tranquility����̂��������ʂ�A�ԈႢ�ł��ˁB
�t�����W�o�b�N���Z���قǁA�i��ʂ����ɂ���o���悤�ȍ\���ɂ��Ȃ��Ă��j�o�b�N�t�H�[�J�X�̒��������݂ɒ����ł��܂�����A���w�I�ɂ́A
�u�t�����W�o�b�N���Z�����Ƃ͂P�O�O�������b�g�ł����āA�f�����b�g�̓[���v
�ƌ����Ă悢�ł��傤�B
���łɁA�t�����W�o�b�N�Ƃ����̂��A�����Y�̃o�b�N�t�H�[�J�X�̈Ӗ����Ƃ��Ă��A���̒Z�������ӌ��ʂ�e���Z�����̌��@�������N�����킯�ł͂���܂���B
������A�ǂ̃��[�J�[���A�t�����W�o�b�N�͂Ȃ�ׂ��Z���Ƃ낤�Ƃ��܂��BM�t�H�[�T�[�Y�̃t�����W�o�b�N�̓{�f�B����Ԃ������邬�肬��A�������̂Ă���NEX�͂��Z���ł����B�ŁA�p�i�͂�����Ɩʔ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ���Ȃ��ł��傤���B
NOKTOR HyperPrime 50mm f/0.95�́ANEX�p��M�t�H�[�T�[�Y�p�œ����傫���̂悤�ł�����AAPS-C�̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[���Ă�̂ł��傤�ˁB�����I�ɂ�M�t�H�[�T�[�Y�͑f�q��APS-C���x�܂ő�^������悢�Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F13531563
![]() 0�_
0�_
���났��
�]������]�������Y�Ȃ�Ƃ������A�O�ʂ̑傫�������邳 �Ƃ͌���܂���B
���p�����}�ŗ��R���킩��ł��傤���H
gintaro����
>�����I�ɂ�M�t�H�[�T�[�Y�͑f�q��APS-C���x�܂ő�^������悢�Ǝv���Ă܂��B
����͂��蓾�Ȃ��ł��傤�B
M4/3�̌��������Y��4/3�̃Z���T�[�T�C�Y�ɍœK�������v�����Ă���ł��傤����B
�����ԍ��F13531637
![]() 11�_
11�_
>>�����I�ɂ�M�t�H�[�T�[�Y�͑f�q��APS-C���x�܂ő�^������悢�Ǝv���Ă܂��B
>����͂��蓾�Ȃ��ł��傤�B
>M4/3�̌��������Y��4/3�̃Z���T�[�T�C�Y�ɍœK�������v�����Ă���ł��傤����B
M4/3�̌��������Y��4/3�N���b�v���[�h�Ŏg���Ηǂ��Ǝv���܂��B���w�t�@�C���_�łȂ��̂ʼn��̖�������܂���B
���[�WM�t�H�[�T�[�Y�p�̃����Y�͕ʂɃ��C���i�b�v���܂��B
�E�f�q��傫�����Ă��{�f�B�͂��قǑ傫���Ȃ�Ȃ�
�E�t�H�[�}�b�g���Ƃɓ���s���肪����
�Ȃ�Α傫�ȑf�q��ς�ł����āA�œ_��������a�ɂ���ăC���[�W�T�[�N�����g��������Ηǂ��A�Ƃ�������ɂȂ��Ă����������Ȃ��Ǝv���܂��B
NOKTON25mmF0.95��������i���邭������́AAPS-C�p��32mmF0.95���������ȒP�ł��B
�b�����ꂽ���łɁA�d�T�̂Ƃ����������A�����`�^�̑f�q�𓋍ڂ��ĉ��ʒu�̂܂c�ʒu�B�e���\�ɂ���d�g�݂��I�����p�X���������Ă���Ƃ����\������܂������A���ɂ����Ȃ����Ƃ���A���̑f�q�͂��ł�Kiss��90�����炢�̖ʐς������܂��ˁB
���łɂf�g�P�Ȃ͂ЂƂ܂��傫�ȑf�q�𓋍ڂ��Ă܂����A���肦�Ȃ��͂Ȃ��b�Ǝv���܂��B�i�Ȃ��������Ƃ͎v���܂����B�B�j
�E�����炵�܂����B
�����ԍ��F13531748
![]() 0�_
0�_
>�傫�ȑf�q��ς�ł����āA�œ_��������a�ɂ���ăC���[�W�T�[�N�����g��������Ηǂ��A�Ƃ�������ɂȂ��Ă����������Ȃ��Ǝv���܂��B
�b�Ƃ��Ă͖ʔ����ł����A���̂悤�Ȏ��Ȕے�ɋ߂����Ƃ�4/3��M4/3������ė����G���W�j�A�����͂��Ȃ��Ǝv���܂��B�����4/3��APS-C�̃T�C�Y���͌����Ă���قǑ傫���Ȃ��āA�Ⴆ��A3�̌��e�ɂ��悤�Ƃ����APS-C�̕����ג����ł�����A���ۂɎg�p�o����ʐςōl����Ƃ��̍��͂���ɏk�܂�܂���ˁB
�C���[�W�T�[�N�����t���Ɏg���đΊp�������ɂ����c���ʒu�Ή��}���`�A�X�y�N�g�͂�����������܂���ˁB�ł��Z���T�[���d���Ȃ��Ď�u����\�͂ɉe���������ł����A�w�ʃ��j�^�[��1��t�Ȃ�t�H�[�J�V���O�X�N���[���������`�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ȂǁA���_�ɑ傫���Ȃ邾����������܂���B
�����ԍ��F13531837
![]() 11�_
11�_
Tranquility����
UP�����摜�����ɃZ���T�[�ʒu���������Ă݂܂����B
���̏ꍇ�A�����Y�̎�O�͑����������Ȃ��ƒʏ�̉摜�͓����܂����ˁB
�̉f���Ɋւ��Ă͐ԁA��ʏ�Ƃ����ꍇ�A�L�蓾�Ȃ������Ɍ����Ă��܂��B
�ǂ�����ĉ�������̂ł��傤�H
�A��ǂ��ʂ��ꍇ�A�Ԃ܂�O���̉f���𗎂Ƃ��K�v��������Ǝv���܂����Ⴂ�܂����ˁH
�܂����A���S���̉f���𗎂Ƃ��͂��͂���܂����ˁH
��ʍ\���Ȃ�Α傫���A�������ă����Y���������Ȃ��Ɓi���ɃZ���T�[���j�\���ȉf���ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E
������ؖ����邩�̂悤��NEX�̃}�N�����Ƃ�ł��Ȃ��\���Ȃ�ł��B
�t�����W�o�b�N���҂����́H�Ǝv�킹����Z���T�[���̓X�J�X�J�ł��B
NEX�̃t�����W�o�b�N�͒Z����ʂ�z���ĒZ������̂ł��B
��xNEX�̃����Y�����O���Č��������ǂ����Ǝv���܂��B
�܂��A�]�������Y�͂Ƃ��Ă�������
�����ԍ��F13534515
![]() 1�_
1�_
�T���X�ł���
���u�����ǂ��e���Z���̖�肪����̂Ŕ����Ƃ������Ƃ��ł��傤�v
�L�p�ɂȂ�Ȃ�قǁA�Ώی`�őf���ɐv����ƃo�b�N�t�H�[�J�X�i�����Y��[����Z���T�[�܂ł̋����j���Z���Ȃ�̂�
�o�b�N�t�H�[�J�X��Z����肽���Ƃ���Ȃ̂ł����P��t�ł̓N�C�b�N���^�[���~���[������̂�
�o�b�N�t�H�[�J�X��Z���o���Ȃ��̂ł�
�i���F�~���[�A�b�v���Ďg���A�~���[�{�b�N�X�ɂ߂荞�ރ^�C�v�̃����Y�͏�������܂��j
�����Ń��g���t�H�[�J�X�i�{���͏��i���j�^�C�v�ɂ��ăo�b�N�t�H�[�J�X���Ƃ��Ă��܂�
�������Ȃ��傫���d���Ȃ�킯�ł���
�~���[���X�̓����Y�̌��ɃZ���T�[�����Ȃ��̂Ńo�b�N�t�H�[�J�X��Z���o����̂�
�L�p�����Y�̐v�͈��|�I�Ɋy�ɂȂ�͂��Ȃ̂ł�
�����������c
�Ώی`�̃����Y�ł̓Z���T�[�ɑ��Đp�x�Ō����������Ă��܂��܂�
�t�B�����ƈ���ăZ���T�[�͂Ȃ�ׂ��܂������O������ĂĂ����Ȃ���
�t�H�g�_�C�I�[�h�Ɍ����͂��Ȃ��Ō��ʂ������Ă��܂��̂ł��c
�i���F�Z���T�[�̃t�H�g�_�C�I�[�h����˂̒�ɂ���悤�Ȕz�u�Ȃ̂Łj
�Z���T�[�̕\�ʂɂ���}�C�N�������Y�Ƃ��Ŋ撣���č������悤�Ƃ��Ă�����Ȃ̂ł���
�܂��܂������ł��Ă��Ȃ��̂Łc
���@�I�ɂ͖����Ȃ����掿�ɏ��^�y�ʂɂł���Ώی`�̃����Y������̂Ɂc
�o�b�N�t�H�[�J�X�߂ɂ��ăe���Z���g���b�N����ǂ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���
�i���F�e���Z���g���b�N���̂��������Y�Ƃ̓Z���T�[�ɂ܂��������������郌���Y�ł��j
�܂��ɃW�����}�ł���
�������������ł���ƐɎv���܂��i�j
�l�I�Ɋ��҂��Ă���Z�p�́A���ʏƎ˂b�l�n�r����
���ꂾ�ƃZ���T�[�\�ʂ���Ƃ���Ƀt�H�g�_�C�I�[�h������̂Ł�
�����ԍ��F13535114
![]() 0�_
0�_
�t�����W�o�b�N�͉掿�ɉe�����܂���
�����e���Z���̖�肪���邩��Z���Ă��������ɂ��������ł�
�����ǂ��m�d�w�̓I�[���h�����Y�V�т��l���Đv����Ă���̂�
�}�E���g�A�_�v�^�����Ղ��Ƃ������|�I�ȗ��_������܂����
(*´��`)�m
�m�d�w�̃g�����X���[�Z���g�~���[�����`�}�E���g�A�_�v�^�Ȃ��
�t�����W�o�b�N��������������܂��ˁi�j
���������e���Z���̖��Ńo�b�N�t�H�[�J�X�Z���o���Ȃ�����t�����W�o�b�N�����悤�Ȃ�Ă����͖̂��ʈȊO�̉��҂ł��Ȃ��ł�
�����I�Ƀu���[�N�X���[��������Ίm���Ƀt�����W�o�b�N��Z�����Ă�����
���̂������傫�ȗ��_�ɂȂ�̂ł������
�i��:���_�Ƃ�����茇�_�ɂȂ�Ȃ��ƌ������ق������������j
�K�i�͍��̋Z�p�����łȂ������̋Z�p�܂ōl���Č��߂Ă����Ȃ��ƒZ���ȋK�i�ŏI����Ă��܂��܂�
�t�H�[�T�[�Y�K�i�̂悤�Ɂc
���̂��܂�ɖ��ʂɂȂ����t�����W�o�b�N�͂܂ʂ��Ƃ��������悤�������c
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���{������o�����e�����P�������炢�t�����W�o�b�N�������Ƃ����c
���ꂶ�Ⴀ�J�������������Ȃ��W����������
���̎���ōō����Z�p�҂̊���_�őn��グ��ꂽ�悤�ȋK�i�ł����c�i�j
�i���F�܂��I����Ă͂��Ȃ����ǂ��j
�����ԍ��F13535179
![]() 3�_
3�_
DR-Z400S����
�����́B
�ЂƂm�F���Ă����܂��ˁB
�u�t�����W�o�b�N�v�Ƃ́A�����Y�������J�����̃����Y�}�E���g�ʂ���C���[�W�Z���T�[�ʂ܂ł̋����̂��Ƃł��B
�����Y�Ō�[����œ_�ʂ܂ł̋����́u�o�b�N�t�H�[�J�X�v�ƌ����܂��B
>UP�����摜�����ɃZ���T�[�ʒu���������Ă݂܂����B
���̏ꍇ�A�����Y�̎�O�͑����������Ȃ��ƒʏ�̉摜�͓����܂����ˁB
����ł͂Ђǂ��s���g���{�P�邾���ł��B
�u�����Y�̎�O����������v�Ƃ́H
>�ԁA��ʏ�Ƃ����ꍇ�A�L�蓾�Ȃ������Ɍ����Ă��܂��B
���݂܂���A���������Ӗ����킩��܂���B
>�A��ǂ��ʂ��ꍇ�A�Ԃ܂�O���̉f���𗎂Ƃ��K�v��������Ǝv���܂�
��������Ӗ����c�@���݂܂���B
>��ʍ\���Ȃ�Α傫���A�������ă����Y���������Ȃ��Ɓi���ɃZ���T�[���j�\���ȉf���ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E
>NEX�̃}�N�����Ƃ�ł��Ȃ��\���Ȃ�ł��B�t�����W�o�b�N���҂����́H�Ǝv�킹����Z���T�[���̓X�J�X�J�ł��B
E�}�E���g��35mm�}�N���ł��傤���B
�����͌��Ă��܂��A�����Y�\���}�����Ă����ɂ��������Ƃ͎v���܂���ł����B�����Ƃ��A���w�̐��Ƃł͂���܂���̂ŁA�\���}�����������łǂ��̂����̌����܂���ǁB
�Z���T�[�����X�J�X�J���Ƃ��Ă��A�����Ǝʂ郌���Y�͂�����ł�����܂���B
�����ԍ��F13535349
![]() 7�_
7�_
���t�����W�o�b�N�͉掿�ɉe�����܂���
�������e���Z���̖�肪���邩��Z���Ă��������ɂ��������ł�
�e���Z�����̊m�ۂ̂��߂ɂ́A�����Y�̌�ʂ��o�b�N�t�H�[�J�X�ɉ����ď\���Ȍa�������Ƃ��A�K�v�����ɂȂ�Ǝv���܂��B�o�b�N�t�H�[�J�X�̒��������Y�قǑ傫�Ȍ�ʂ��K�v�ɂȂ�܂��B�o�b�N�t�H�[�J�X��Z������Ƃ������Ƃ́A���ꂾ����ʂ��������ł���\���ɂȂ���킯�ł�����A�e���Z�����̖ʂł��A�Ƃ������e���Z�����̖��䂦�ɁA�t�����W�o�b�N�̒Z���͊�����ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F13535710
![]() 1�_
1�_
Tranquility����
�F�X�����Ă����������肪�Ƃ��������܂��B
�����̓t�����W�o�b�N�ƃo�b�N�t�H�[�J�X���������Ă��܂����B
�������G��������x�������A�F�l�̃R�����g��ǂݕԂ��Ă݂�Ƃ悤�₭�����ł��܂����B
���̊G���������炵�Ȃ������ǂ������ł��B���݂܂���B
�����A���̊G���������点���ɍl���āA�ꂩ��v����ƍL�p�͑f���ɍ��Ղ��ł��ˁB
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��̌����Ƃ���ANEX�͗��ʏƎ˂ƍ��킹��ΗD�ʂɗ��Ă�\�����傫���ł��ˁB
�������A����̃����Y�́E�E�E�D�ʐ��𗎂Ƃ����Ⴄ�����Y����B
���������Ȃ��ȁASONY�B
�F�X�F�l�̂��ӌ��ŕ��ɂȂ�܂����B
�F�X���������Đ\����܂���B
�b���͖ق��Ă��܂��B
�����ԍ��F13535723
![]() 2�_
2�_
gintaro����
�f�W�^���J�����Řb��ɂ����e���Z���g���b�N���́u�����e���Z���g���b�N�v�ł��B���w�n���瑜�ʂ����������������ɕ��s�ɂȂ�悤�ɐv����Ă��܂��B
���������āA�e���Z���g���b�N�����m�ۂ��邽�߂ɂ̓C���[�W�T�[�N���ɑ��ď\���Ȓ��a������ʂ��K�v�ɂȂ�܂����A�o�b�N�t�H�[�J�X�̒����ɂ���Ă��̒��a��ς���K�v�͂����������܂���B���̗��R�́A���p���������}������Η����ł���Ǝv���܂��B
�e���Z���g���b�N�����قǂقǂŗǂ��Ƃ������ƂɂȂ�A�o�b�N�t�H�[�J�X������������ʂ̒��a���������Ă��ނ��ƂɂȂ�܂��B
�t�����W�o�b�N�̒����͂�͂�e���Z���g���b�N���Ƃ͊W�Ȃ��A�P�ɋ����̒����ƃ{�f�B�̌����̃o�����X���ǂ���邩�ɂ���Č��܂�ɂ����܂���B
�����ԍ��F13535908
![]() 8�_
8�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
>���̂��܂�ɖ��ʂɂȂ����t�����W�o�b�N�͂܂ʂ��Ƃ��������悤�������c
�c�Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B
�C���[�W�Z���T�[�̑O�ɂ͕��������[�p�X�t�B���^�[��ԊO�J�b�g�^�z���t�B���^�[�A�S�~����SSW�t�B���^�[�A�V���b�^�[���j�b�g�Ȃǂ������āA���������v����Ƒ����Ȍ��݂ɂȂ邱�Ƃ��킩��܂��B
�J����������O�������[�p�X�^�ԊO�J�b�g�t�B���^�[�������Ă������������Ƃ�����܂����A����͔Ƃ��������u���b�N�Ƃ������t���ӂ��킵�����̂ł����B
�����ԍ��F13535926
![]() 10�_
10�_
��Tranquility����
�Ƃ������c
���ʂɃX�y�[�X�����邩�疳�ʂ��ґ�ɃX�y�[�X�g���Ă邾�������ł�
�d�e�}�E���g�̓��C�J���Ƃ��Ă̓t�����W�o�b�N���Z���ł���
���̃X�y�[�X�Ƀt���T�C�Y�̂ł����~���[���܂߂Ă���������߂Ă�킯�Łc
�S�S�����@�@�@�@�d�e�}�E���g�̃t�����W�o�b�N
�R�W�D�U�V�����@�t�H�[�T�[�Y�̃t�����W�o�b�N
�掿���ǂ���ł����Ă��S�ċ������Ƃ����Z�p�҂̖��S�����K�i�Ǝv���c
�t�H�[�T�[�Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����lj��X�f�J�C�J����������炷
�m�d�w�̓o��ł���Ɓc
�t�������Ɓc�I�����p�i�����������o�����Ƃ���Ƃ���������ł��傤�c
�l�I�ɂ͂S�O�O�ԑ�Ƃ����^�y�ʂŏo���Ă���Ă����L���m���̃T�u�ɔ������̂Ɂi�j
(*´��`)�m
�����ԍ��F13535951
![]() 0�_
0�_
>���ʂ��ґ�ɃX�y�[�X�g���Ă邾�������ł�
�f�ʐ}�����Ă����_�ȃX�y�[�X������悤�ɂ͎v���Ȃ��ł��B
>�d�e�}�E���g�̓��C�J���Ƃ��Ă̓t�����W�o�b�N���Z���ł���
���̃X�y�[�X�Ƀt���T�C�Y�̂ł����~���[���܂߂Ă���������߂Ă�킯�Łc
5mm�ȏ㒷���Ă��A�S�~���t�B���^�[������ꏊ����邱�Ƃ͏o���Ȃ������c
>�t�H�[�T�[�Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����lj��X�f�J�C�J����������炷
�u�Z�p�҂̖��S�v�ł����H
E-400/500/600�n�ȂǁA���������������Ǝv���܂����ǁB
PEN���o�ꂵ�����́A����܂łɖ��������傫���ƃX�^�C���ɊF����т����̂��Ǝv�����AE-PL1/2�����イ�Ԃ����Ǝv���Ȃ��B
4/3�́A�Z�p�҂��t�B�����@���p�ł͂Ȃ�DSLR�̗��z��ڎw�������̂Ȃ̂��Ɨ������Ă��܂��B
���̋Z�p�҂ɕ����u�~�߂�C�͖����v�������Ȃ̂ŁA����ɂ����҂����ė~�����ł��ˁI
�����ԍ��F13536003
![]() 14�_
14�_
���u�Z�p�҂̖��S�v�ł����H
�܂��A���^�y�ʋ@�������肪�S���Ȃ������ȂƎv���܂���
���Ɏc�O�Ȃ���c
�����A�t�H�[�T�[�Y�K�i�̔��\����
�P�P�O�t�B�����Ɠ������炢�̃T�C�Y�ƕ����ď��^�y�ʋ@�����҂����l�����Ȃ��炸�������낤�Ɂc
�o�Ă������ʂ�����ł�����ˁc
�l�͂������ɂ�������ł���
�W�N�z���ł����
�f�e�R�A�o�k�R�A�o�l�P�ƕK�v�ȃR�}���o�Ă����ȂƎv���Ă܂�
(*´��`)�m
�����ԍ��F13536014
![]() 1�_
1�_
>�����A�t�H�[�T�[�Y�K�i�̔��\���ɂP�P�O�t�B�����Ɠ������炢�̃T�C�Y�ƕ����ď��^�y�ʋ@�����҂����l�����Ȃ��炸�������낤�Ɂc
�t�B�����ƃf�W�^���̍��{�I�ȈႢ����������Ă��Ȃ�������ł��傤�ˁB
����E-1���o�Ă����͂悭������܂���ł������A����Ƀt�B����1��t�p�̃����Y���g�p�������̉掿���݂āAOLYMPUS�̃G���W�j�A���ڎw���Ă���Ƃ��낪�����o���܂����B
������ƁAE-1�������Ԃ����v���܂��B
�����ԍ��F13536027
![]() 8�_
8�_
gintaro����
>�o�b�N�t�H�[�J�X�̒��������Y�قǑ傫�Ȍ�ʂ��K�v�ɂȂ�܂��B
���݂܂���B
F���̏����ȃ����Y�Ńe���Z���g���b�N�������x�Ɏ������悤�����ꍇ�A���������Ƃ���ł��B
�u�C���[�W�T�[�N���ɑ��ď\���Ȓ��a������ʂ��K�v�ɂȂ�܂����c�v�Ə������̂́A���̂��Ƃ�����������ł������A�u�o�b�N�t�H�[�J�X�̒����ɂ���Ă��̒��a��ς���K�v�͂�������Ȃ��v�Ƃ����̂�F���̑傫���ƃe���Z���g���b�N���̒��x�ɂ��܂��ˁB�������s�\���ł����B
���炵�܂����B
�����ԍ��F13536086
![]() 2�_
2�_
Tranquility����A�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
��F���̏����ȃ����Y�Ńe���Z���g���b�N�������x�Ɏ������悤�����ꍇ�A���������Ƃ���ł��B
Tranquility����ɕ⑫���Ă��������܂������A�����̏������͌��t������܂���ł����B
�uTranquility����̂�����ꂽ�}�ŁA���w�n�i��ʁj���瑜�ʁi�B���f�q�j�̂P�_�Ɍ����������́u�~���v�ɂȂ��Ă���B���̉~���̎��������ɕ��s�ł��邱�Ƃ������e���Z���g���b�N���̒�`�B�~���̍L��������߂�̂��e�l�B�e���Z�������Y�ɂ����ẮA������1�_���琂���ɗ��~������ʂɎ��܂�K�v������܂�����A�o�b�N�t�H�[�J�X���������A��ʌa�͑傫���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ����̂��A�����̌��������������Ƃł��B
�������A����́A�K�v�����̈�ɉ߂��܂���̂ŁA������A�u�e���Z���̖�肪���邩��Z���Ă��������ɂ����v�Ƃ����咣�ɑ��锽�_�̍����Ƃ���悤�Ȏ����̏���������������������������܂���B
�������A�o�b�N�t�H�[�J�X���ǂ����̂��őP���A�Ƃ����̂̓����Y�̐v����ł��B
�i�����̏��L����l�t�H�[�T�[�Y�����Y�͂ǂ���A��ʂ̓}�E���g�ʋߕӂɂ���悤�ł��̂ŁA����Ȃ�Ƀt�����W�o�b�N�̒Z�������������v�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ȁA�Ƃ��v���܂��B�j
�����ԍ��F13536528
![]() 3�_
3�_
������E-1���o�Ă����͂悭������܂���ł������A����Ƀt�B����1��t�p�̃����Y���g�p�������̉掿���݂āAOLYMPUS�̃G���W�j�A���ڎw���Ă���Ƃ��낪�����o���܂����B
�l�������͂ł��Ă��邯�ǂ����鎖�̕������܂����Ă܂�Ȃ��K�i����
�掿��Nj����邵���Ȃ��K�i�ɂ��Ă��܂��Ă���
���ɑf���炵���ʔ������z�������̂ɂ��̉\���̈ꕔ���������������Ȃ��������ĂƂ��ł���
�܂��l�e�s���撣���Ă����������ǁ�
(*´��`)�m
�����ԍ��F13538170
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
Tranquility����������Ă���̂ŁA�����ǂ����ȂƂ��v���܂������ǁA
�e���Z���g���b�N���Ɋւ��ẮA����������������Ȃ�o�b�N�t�H�[�J�X��
��mm�ɂȂ낤���A��ʂ̒��a�́m�B���f�q�̒��a�{�o�b�N�t�H�[�J�X÷�e�l�n
���K�v�ŁA�t�H�[�T�[�Y�̂悤�Ƀt�����W�o�b�N�������ƕK�R�I�Ƀo�b�N
�t�H�[�J�X�������Ȃ�܂�����A���_�I�ɂ͓������邳�Ȃ�A������a��
��ʂ��K�v�ɂȂ邱�Ƃ͊m���ł��B
�����A�����ȃe���Z���g���b�N���ł͂Ȃ��A±15�x���x�܂łȂ�X���Ă��ǂ�
�Ƃ��������Ȃ�A�t�����W�o�b�N�������Ă��t�Ɍ�ʂ��������Ă���薳��
�Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B
�r�I�S���̓o�b�N�t�H�[�J�X���Z���ł����ǁA��ʎ��ӂ͌��������Ȃ��
�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�P���ȃ��g���t�H�[�J�X���e���Z���g���b�N����
�C�}�C�`�ł�����A�����ł��}�g���ȃe���Z���g���b�N�����m�ۂ��悤��
����ƁA������o�b�N�t�H�[�J�X���Z���Ȃ��Ă��傫���͂��܂菬�����ł�
�Ȃ��̂�����݂����ł��B
�ŁA�X�����ginganohikari����ւ̃��X�ł����A�f�W�^���ɑ������������\
�Ŗ��邢�����Y��v���悤�Ƃ���ƁA��ʎ��ӂł��B���f�q�ɑ��ĉ\��
��������𐂒��ɋ߂�����K�v������܂�����A��ʂɑ傫�ȓʃ����Y��u��
�Ȃ�������Ȃ��ł����A����ɂ���ă��C���̃����Y�Q�̐v�ɂ��H�v��
�K�v�ɂȂ�܂�����A���܂菬�����͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
���ہAm4/3�p�̃����Y�̌�ʂ�4/3�̓��X�y�b�N�̃����Y�Ɣ�r���Ă��A
�ނ���傫�����炢�ł��̂ŁAm4/3�̃����Y���������ł���̂͑O�ʂ̒��a��
�ƁA�o�b�N�t�H�[�J�X�����邽�߂̃��g���t�H�[�J�X�ɂ��邽�߂̑O�ʌQ
�̕��Ƃ������ɂȂ�Ǝv���܂��B
���������āAm4/3���L���ɂȂ�̂̓t�����W�o�b�N����40mm�ł���薳���v
�ł���70mm���Z���œ_�����̃����Y�Ƃ������ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����Am4/3�̃����Y�̑���a���ň�Ԗ��ɂȂ�̂́A�`�e�X�s�[�h��������
���邽�߂ɁA�S�Q�J��o���ł͂Ȃ��A�ł���Ώ������y�������Y���P������
�������ςނ悤�ɂ��Ȃ�������Ȃ��Ƃ������ŁA�ł�������Y�S�̂�
�J��o���A�ߋ�����̓t���[�e�B���O�łƂ����v���]�܂�������a�P�œ_
�����Y�́A�v������Ƃ����{�g���l�b�N������̂͊m���ł��B
���Ȃ݂ɁA�]���̍����h�C�c�̃����Y���Ă`�e���́A�قڕs�\�Ȃ�ł���ˁB
�l�e�Ńs���g�����킹��̂Ȃ炢����ł����Ԃ��|�����Ă��A�`�e���Ɖ��b��
�҂��Ă�������A�I���ȃ��[�U�[���ĂقƂ�ǂ��Ȃ��Ƃ����̂�����ł��ˁB
�����ԍ��F13539199
![]() 11�_
11�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
>���鎖�̕������܂����Ă܂�Ȃ��K�i����
���̎��͏o����Ǝv���܂���B
���邱�Ƃ̕����ǂꂾ���L�����邩�A
�ǂ��܂Ŗʔ����g���邩�̓��[�U�[�������ł��B
>�掿��Nj����邵���Ȃ��K�i�ɂ��Ă��܂��Ă���
�G���W�j�A�͓��R�掿��Nj����܂���ˁB���ꂪ�d���ł��B
����͂ǂ��̃��[�J�[�ł������ł��傤�B���@�̈Ⴂ�͂���ł��傤����ǁB
�����͕��ʂ̃��[�U�[�ɂ͎�̏o���Ȃ������ł��ˁB�I�����錠���͂����瑤�ɂ���܂����B
�掿�ȊO�ɖ��͂����o���邩�́A��������[�U�[�������ł��B
>���ɑf���炵���ʔ������z�������̂ɂ��̉\���̈ꕔ���������������Ȃ��������ĂƂ��ł���
�Ƃ����킯�ŁA�J�����̉\�����������邩�ǂ����͎g����ɂ��킯�ł����A�^�C�v������Ȃ��̂ł͂���������܂���B
�ǂ̃��[�J�[�̃G���W�j�A����ɂ��A�V�X�e���̉\�����������J���𑱂��ė~�����ł��ˁB
�|�����_�n����
�ڂ�������A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F13539335
![]() 9�_
9�_
�K�i�͈�ʐl�ɂ͎肪�o���Ȃ����������炱���Z�p�҂�������ƍl���Ȃ��Ƃ��߂ł���
���̈Ӗ��łe�s�͑厸�s���Ă�
�c�O�Ȃ���
�܂��j�b�`�Ȗ��͂͂��܂�Ȃ�����̂ō��X�Ȃ��甃�������\��ł���
(*´��`)�m
�y���݁�
�����ԍ��F13539507
![]() 0�_
0�_
�|�����_�n�����́B
> �����Am4/3�̃����Y�̑���a���ň�Ԗ��ɂȂ�̂́A�`�e�X�s�[�h��������
> ���邽�߂ɁA�S�Q�J��o���ł͂Ȃ��A�ł���Ώ������y�������Y���P������
> �������ςނ悤�ɂ��Ȃ�������Ȃ��Ƃ������ŁA�ł�������Y�S�̂�
> �J��o���A�ߋ�����̓t���[�e�B���O�łƂ����v���]�܂�������a�P�œ_
> �����Y�́A�v������Ƃ����{�g���l�b�N������̂͊m���ł��B
�`���b�ƕ������b�ł����C���ꂪ�����Z�p�I�ɗ\�z���Ă��������ӊO�ɋȎ҂̂悤�ŋ�풆�炵���CMicro4/3�p��HG(�|)�ɑ������郌���Y���Ȃ��Ȃ��o�����ɂ���悤�ł��B
Micro4/3(m.zuiko)�ł�HG�N���X�̃����Y���o���炻�̎��_�œ������������Ă��ǂ����ȁC�Ǝv���Ă���̂ł����C���̓��������ł���܂łɂ͂����������Ԃ�K�v�Ƃ���̂�������܂���� (^^;
�����ԍ��F13539514
![]() 3�_
3�_
�|���_�n������X�Ԉ���Ă���̂�
�������A�����ȃe���Z���g���b�N���ł͂Ȃ��A±15�x���x�܂łȂ�X���Ă��ǂ�
���Ƃ��������Ȃ�A�t�����W�o�b�N�������Ă��t�Ɍ�ʂ��������Ă���薳��
���Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B
�����̘b�͋��ʃ����Y�Őv�����Ȃ�ƌ��������ł���A�����Y�����m�������g����
�Ȃ��Ă��ẮA�ŐV�̃����Y�v�ɂ��Ă͌�鎑�i�������Ǝv���܂��B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Œ|�N���X���o�Ȃ��̂́A�v������ƌ������A
�R���Z�v�g�㍂���ȃ����Y�����Ă�����Ȃ��̂ŁA�����ȃ����Y�Q�ŏ\����������
�l�B�ɂ킴�킴����Ȃ������Y���o���Ӗ��������Ƃ����̂����̍ő�̗��R�ł��B
�I�����p�X�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ƌ����A�V�����W��������Nikon1�̂悤�ȃR���Z�v�g��
����ɍ���r�W�l�X�W�J�����Ă����̂ŁANikon1�ɏ��Ă�i���ł���Ώ\���ƍl����Ȃ�
���Ƀn�C�G���h�����Y���o���K�v�������ƌ����̂����̗��R�ł��B
�t�@�~���X�N���X�̃R�X�g�ŁA�ꗬ�V�F�t�̃��V�s����Ȃ����ƌ����̂́A
�P�Ȃ�䂪�ԂŁA�t�@�~���X�N���X�̃J�����ŏ\���������Ă���ڋq�{�����[����
�^�[�Q�b�g�Ƀr�W�l�X�W�J���Ă��邱�Ƃ��l����A����̍s�������T�˗����o����ƌ������̂ł��B
�����A��_�قȂ�_��������ANC���Ղ̋Z�p�v�V���߂��܂��������B
���w�V�~�����[�^�̐v�Z�p���}���ɏオ���Ă��Ă��邱�ƂƑ��܂��āA���ނ��ǂ����m��
��ɓ���A�ʃ����Y�ō��i�ʂȂ��̂�o���鎞�������������Ă���ƌ����_�ł��B
�Â����ʃ����Y�̐v�v�z��m�������ŁA���������ŋ߂̃J������������̂�
���{�I�ȊԈႢ���܂ނƎv���܂��B
�����ԍ��F13540799
![]() 1�_
1�_
�ʃ����Y�̂��܂˂��{�P�������Ȃ�ł����ǁA������ċZ�p��
�����ł��Ȃ��̂ł��傤���H�������ʃ����Y�g���Ă��郌���Y
�������Ă��܂����A�C�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F13540872
![]() 1�_
1�_
���ꂩ�������B
���{�I�ɊԈ���Ă���̂́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ʼn��̖��邭�𑜓x������
�L���m����t�H�[�T�[�Y�Ȃǂ̃����Y�����D�G�ȃ����Y���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ����H
�ƌ������ł��B
���݁A�L���m���̔n���ł����}�̂̃J��������Y�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃J��������
�o�ב䐔�������A����Ă��܂��B
�����āA�t�H�[�T�[�Y�́AE-5�ŏI���ƌ������̂́A���钆�ŁA�Ȃ��K�i�㐧����
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɁA���ꂱ���ʋ@��̎v�z��T�O���Ƃ��Ă����悤�ɋ��߂�̂��H
�J�������g���Ă��āA�����̋Z�ʂ��J������������A�V�����J�������~�����Ȃ�̂�
�����̗��B
�������A�����������ɁA�����̓s�������ŗ��z�����̂͒P�Ȃ�䂪�ԂŁA�ȑO�������܂�����
�J��������ɂ����āA����҂������̂�����A�������_�ł��������z���Ĕ����̂�
����҂̐ӔC�̔��e�ł���͂��Ȃ̂ɁA�u����ɖϑz�v�����ɂȂ�Ȃ��̂�
���[�J�[�Ɉ����Ɠ˂�����̂́A�P�ɐ挩�������������̘b�ł����āA�J�������[�J�[�ɂ�
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ������x�͂���܂���B
�����āA�R���f�W�����g��Ȃ��l���猩��A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y������A
Nikon1�₻�̑����ȃt�W�̃����Y�������J�����ƂāA�ǂ����Ƃ͐���������܂��B
���́A�J�������O�ɁA�}�E���g�a���ŏd�v�����ăJ���������i�I�j�w�i������܂��B
����́A��X�̂����ȉ\�����l���Ă̂��Ƃł��B
�I�����p�X�A�����ă}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A���������@�B�I�ȉ\�������A
�J������g�߂ȑ��݂ɂ��A�R���p�N�g�Ŏg���₷���J��������낤�Ƃ��Đ��ɏo�����J�����ł��B
�̂̃����W�t�@�C���_�[�J�����ɁANikon�@��F�V���[�Y�̃����Y�`�ʐ��\�����߂�l�͂��Ȃ������͂��Ȃ̂�
���́A�����W�t�@�C���_�[�Ƀf�W�^�����Ɠ����̐��\���u����Ɂv���߂�l�����܂��B
�Z�p�́A�i�����܂��B
�������A���Ԃ����Ԃ�����܂��B
�����𗝉������A�m�������g���Ȃ܂܂ŁA����ɂ��ꂱ�ꌾ���̂́A���{�I�ȑf�l�̊ԈႢ�ł��B
Tranquility������悤��
���@.���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
��>���鎖�̕������܂����Ă܂�Ȃ��K�i����
�����̎��͏o����Ǝv���܂���B
�����邱�Ƃ̕����ǂꂾ���L�����邩�A
���ǂ��܂Ŗʔ����g���邩�̓��[�U�[�������ł��B
�g�������l���Ȃ����[�U�[���A�V������������ɓ���Ă��A�܂��t�@�~���X��
�C���X�^���g�Ȃɂ����Ɠ������A�O������A�X�Ȃ�䂪�Ԃ����������ŏI���܂��B
�������̃g�C�����Y�́A��ω掿�������ł����A����͂���Ƃ��Ă̖����ƁA
�ʔ����ړI�ɔ����l���吨���܂��B
�ǂ����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł��邱�Ƃ𗝉����A���̔��e�ŁA�B�e�V�[�����H�v������I�肵��
�����̃X�^�C���ɂ������J���������[�U�[�������I�Ԃƌ������{�I�T�O��Y��Ȃ��ŗ~�����Ǝv���܂��B
����́A���[�U�[�Ƃ��Ă̖{���̂Ƃ߂ł�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13540873
![]() 4�_
4�_
���ʃ����Y�̂��܂˂��{�P�������Ȃ�ł����ǁA
���܂˂��{�P���������ɂ́A�����ꂩ�̐v�v�z���K�v�ł��B
��ɒf���Ă����܂����A�ʃ����Y��p����ۂ̍ő�̗��R�́A�����Y���R���p�N�g�ɂ��邽�߂ł��B
�P�D�����Y�Q�̍\����ς��A��F�l�ȃ����Y�v�ɂ���B
�Q�D�ʃ����Y���S���ȏ�p���āA�c�Ȏ�����ȊO�ɁA�F����������郌���Y��
�@�@���ꂼ��Q���ȏ�g���Đv����B
�R�D�����Y�Q�̎g�p���������炵�A�����Y��Ԃ�������v�i�R���p�N�g���Ƒ�������j������B
�^�}�l�M�{�P�������闝�R�́A���ډ��L�̋L�������ǂ�ł���������Ȃ��Ǝv���܂���
http://www.nikon-instruments.jp/jpn/tech/2-1-6-2.aspx
�G�o�l�b�Z���g��̂悤�ȊT�O�̌��ۂ��N�����Ă��܂��B
�����Y���R���p�N�g�ɂ��A���G�ɐ������̃����Y�Q�𑽗p����ƁA�����Y���m�̋����i��j
�ɂ���āA�����Y�̑��݊��ɂ��A��������قȂ��������Y���A�����������ܗ���
�ω�������̌q�����������Y�̂悤�ɋ@�\���邱�ƂŐ�����s�A�����ۂ����ł��B
�����Y�̕]�����A�P�ɉ𑜐������Ř_����l�́A�����ɂ��Ďw�W���B���Ȃ̂�
����܂��A�����ɂ͂���炪�ʐ^�Ƃ��đ傫�������Ɋւ���Ă��܂��B
�����Č����܂����A���邢�����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ŏo���ɂ����̂́A�ނ��낱����̗��R�ŁA
�ʂ̐v���Â��ƁA���邢�����Y�ł͂�����̂́A�t�H�[�J�X���Â��A
�{�P�~���o�Ȃ������Y�ƂȂ�A�����Y�̉��l�����Ȃ��Ă��܂����߂ł��B
�����ԍ��F13540919
![]() 1�_
1�_
�Ƃ͂����A�����̃����Y���������炢���Ȃƌ����P���Ȏv���͗������܂��B
���������b�ƁA���r���[�Ȓm���ʼn�����ĊԈ�����b�𐢊ԂɍL�߂Ȃ��ŗ~�����Ǝ��͎v���܂��B
�|���_�n���͂��ď�X�e���Z��������鎞�A��ʂ̃����Y�a���A�t�����W�o�b�N���
���ꂱ�ꌾ���܂����S�Ăɂ����Ĕ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B
����́A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�e���Z�������������߂�Ȃ�A�O�ʂ��ɗ͑傫�����āA
�����Y���傫�����s�ɍ��Ηǂ������ł���ƌ������Ƃł��B
�V�O�}�̑�C�̂悤�ȃ����Y������̂�����A�傫���̐���ȂǁA�P�ɃR�X�g��
����邩����Ȃ����̃R���Z�v�g�̖��ł���A�|���_�n���̒��r���[�ȏ���Ȏv�����݂�
����̒��ł̘b���ł͖������Ƃ��ɒf���Ă����܂��B
�����Ȃ�J�������[�J�[�̋K�i�ł����Ă��A�傫����傫�����A����Ă��ǂ����
�ǂ������Y�͍��܂��B
�������A����ł͌����̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃R���Z�v�g�����Ă��܂��B
����āA�t�����W�o�b�N�̖��ł��A��ʌa�̖��ł������B
�P�Ȃ�R�X�g�ƃR���Z�v�g�̘b���ŏd�v�ȉۑ肾�Ɖ��߂ďq�ׂĂ����܂��B
�|���_�n���̂悤�Ȓm�������Ԃ����f�l�I�Ȕ��z�ŁA�J�����̍\���ɑ��āA
���ꂱ�ꌾ���̂́A�R���Z�v�g���l���č�����J�������[�J�[�̎v�z�𗝉�������
�S�e�S�e�ƁA���Ђ�����A������ȗ����ɃP�`���b�v��
�\�[�X�������ĐH�ׂ�悤�Ȃ��̂ŁA���������c�_�͑S���Ӗ��̖����b���Ǝv���܂��B
�����Y�ɖ��邳�����߂�Ӗ��͂Ȃ�Ȃ̂��H
�悭�l���Ă݂�K�v������܂��B
���邢�����Y���~�����ƌ����̂́A
�P�D�{�P�~���o������
�@�@���@�i�}�C�N���j�t�H�[�T�[�Y�ł͍��{�I�ɑI�J�������Ԉ���Ă���
�Q�D�Â��V�[���ŃV���b�^�[���x���グ����
�@�@���@�����x�B�e�o����J������I��
�R�D��i�i���ĉ𑜐��̍��������Y���~�����Ӗ��Ȃ�
�@�@���@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł͂Ȃ��t�H�[�T�[�Y�̏��A�|�����Y�ƃZ�b�g�Ŏg��
�̂��{���Ǝv���܂��B
�ǂ��������V�[���ŁA�ǂ��������C���[�W�̎ʐ^���B�肽���̂��A����������ɏ����Ă�����
�B�e�e�N�j�b�N��A�I�ԃJ���������߂đI�肵�����Ȃǂ̉��������܂��B
���邢�����Y���g��Ȃ��Ă��A����Ԃ�[���̐Ԃ̑���������������A�����̕�����
�l�������B�e�ꏊ�I�тȂǁA�J�����ȊO�Ɏ������g���w�͂��ĉ����o������e�͂�����ł�����Ǝv���܂��B
�@�B�I�ȉۑ�Ɏ��_�������Ă����āA�P�Ȃ�ϑz��䂪�Ԃ̕s�тȋc�_��������
�����ȉ������T��c�_���������������ƌ��ݓI�ȓ����ɍs�������Ǝv���܂��B
�|���_�n�����u���́v�v�����ƌ����̂Ȃ�����Ƃ��Ȃ��Ԉ���������Y�v�̘b�ł͂Ȃ��A
�u�v���炵���v�u�B�e�e�N�j�b�N�v�Ɓu�N�����f���炵���Ƃ��Ȃ�B�e��v�ɂ��ĊJ�����ė~�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13541006
![]() 3�_
3�_
�u���鎖�̕������܂����Ă܂�Ȃ��K�i���ȁv
������������
���[�U�[�����鎖�̕��������Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ�
���[�J�[�����鎖�̕��������Ƃ����Ӗ�
�����ɂ͎g���ǂ��낪���邩�甃�����Ƃ��Ă邯�ǂ��ˁ�
(*´��`)�m
�����ԍ��F13541466
![]() 0�_
0�_
ginganohikari����
�N�̃N�`�R�~�Ȃ��H
�����ԍ��F13541493
![]() 0�_
0�_
���͂���pen-mini��12/2, 25/1.4, 45/1.8�̂R�{��MFT�f�r���[���邱�Ƃ�S�ɐ����܂������A
�~�������Ɗ���xISO50�A�����Ɨ~�������Ɗ���xISO25�̃{�f�B������Ƃ��ꂵ���ł��B
�����ISO800�ł��A����OK�ł��B
���i�R������Ŕq������f�G��MFT�̍�������ɂ��AISO200�Ŋ��ɏ����m�C�W�[�Ȃ̂��c�O������ł��B
�ł��AISO50�{�f�B�ƁA15/1.2�����������A���ׂẲƑ����s�J������MFT�Ƀ`�F���W�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13541801
![]() 1�_
1�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��@
���Ƃ������c
�����ʂɃX�y�[�X�����邩�疳�ʂ��ґ�ɃX�y�[�X�g���Ă邾�������ł�
�@���[��A�I�����p�X�̃S�~��Ƃ����ƒ����g�U���ɂ��SSWF����Ԃɒ��ڂ���܂����A
http://olympus-esystem.jp/technology/usf/
>(2)�z�R���̎ʂ荞�ݖh�~
>��Q�ɁA����ʂ�SSWF�Ƃ̊Ԋu���Ƃ邱�Ƃɂ��A�����Ȑo��������ʂɂ���A�ɂ����ʒቺ�����Ȃ����āA�摜�Ɏʂ荞�܂Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
���Ă̂�����̂ŁA���ʂȃX�y�[�X�Ƃ͌�����Ȃ��ł��ˁB
�@���̏؋��ɁA���[�p�X�t�B���^�[�̒����g�U���ȂǂőĂ��鑼�Ђ̋@��ŃS�~��肪�A�I�����p�X�^�p�i�\�j�b�N��薾�炩�ɗD��Ă���@��Ƃ������͖̂����ƔF�����Ă���̂ł����A���̔F���͊Ԉ���Ă��܂����ˁH
�����ԍ��F13542102
![]() 3�_
3�_
���e���}�[�N�t�@������@
�l�I�ɃS�~���@�\�ɂ͑S���������Ȃ��̂ł킩��܂��c
�����̎����Ă�J�����ɂ��t���Ă�̂�����͂��ł����F�����ĂȂ��i�j
�Z�p�҂̗��_�ŃX�y�[�X�ɈӖ�����������̂͂�����ł��ł���̂�
������X�y�[�X�����ʂɂȂ��Ă�Ƃ����Ă���̂ł͂Ȃ��ł�
���ǂ͉掿���悭�Ȃ�Ⴂ���������Ă̂�łǂ�ǂ�ǂ�ǂ��剻�����V�X�e���c
������x�ȏ�͑傫���Ȃ�Ȃ��悤�Ɋ撣�낤�Ƃ͎v��Ȃ������̂ł��傤
�K�i�����i�K�ł�����Ƃł����^�y�ʉ����ӎ����Ă��ꂽ��
�����Ƃ����Ɩ��͓I�ȃV�X�e���ɂȂ肦���̂ɂƂ����̂��c�O�łȂ�Ȃ�
���Ă��Ƃł�
�n�l�V�X�e�������グ���I�����p�X�ۂ��Ȃ��i�j
(*´��`)�m
�����ԍ��F13542128
![]() 1�_
1�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
>���[�J�[�����鎖�̕��������Ƃ����Ӗ�
4/3���������ɕ��������Ƃ������͖����ł��傤�B
�ǂ�ȋK�i�ł�����Ȃ�̓���������܂��B
>������x�ȏ�͑傫���Ȃ�Ȃ��悤�Ɋ撣�낤�Ƃ͎v��Ȃ������̂ł��傤
����������ʂ����̑傫���Ȃ̂ł́B
���̃V�X�e����肸���Ԃ����Ǝv���܂����B
�����ԍ��F13542327
![]() 2�_
2�_
m4/3�̋K�i�͏���16:9�̃Z���T�[�T�C�Y�ɑΉ��ł���悤�ɗ]�T���������Ă��Ȃ��������ȁH
�L���Ⴂ�������炲�߂�Ȃ����ł����B
�����ԍ��F13542328
![]() 0�_
0�_
m����Ȃ��ĕ��ʂ�4/3���B
�ł��Am4/3�ł������Ƃ�����͂��E�E�E
�����ԍ��F13542331
![]() 0�_
0�_
���l�I�ɃS�~���@�\�ɂ͑S���������Ȃ��̂ł킩��܂��c
�������̎����Ă�J�����ɂ��t���Ă�̂�����͂��ł����F�����ĂȂ��i�j
�ǂ����A���̂悤�ł��ˁi�j
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��̃����N��(groovingrowin)�ɂ���ʐ^(F51407195)���`���b�ƌ������Ă����������̂ł����A�E��ɂ���S�~�炵�����̂ɂ��Ă͓��Ɉӎ�����Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���Ȃ���ł��傤�˂��B
http://fotologue.jp/groovingrowin#/13275707/13275720
�l�I�ɂ́A�����ꂽ�\�}���D���Ȃ̂ŁA������������ɂ���S�~�̂悤�Ȏʂ荞�݂͂ǂ����Ă��C�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�����łȂ��Ƃ����l������Ƃ����̂͂킩��܂����`�B
���^���ɂ��Ă͑_����35mm�ł̃J�����̃T�C�Y�Ƃ������ƂŁA��������͓�����AF�J�����łł��傤�ˁBOM�̍���MF�J�����̃T�C�Y�͍ŏ��͈ӎ����ĂȂ������̂��Ǝv���܂��B
����͂�����Ɩܑ̖��������Ȃ��Ǝ����v���܂��B�����AE-420�Ƃ��́A�\�����������Ȃ��Ǝv���܂��B���̋Z�p�͂ō��A�������������Ȃ�Ƃ͎v���܂����ǂˁ`�B
�����A�S�~���ʂ�Ȃ����Ƃ��ӎ����ẴX�y�[�X�ł���A���͖��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F13542354
![]() 7�_
7�_
������������ʂ����̑傫���Ȃ̂ł́B
�I�����p�X�̋Z�p�͂����z�͂�����ȂɃ��x���Ⴂ�Ƃ͎v�������Ȃ�
�����Ȃ�߂�������c
�l�e�s�̏��������Ă��킩�邯�ǁA�I�����p�i�����^�y�ʉ��͂قƂ�Ǎl���ĂȂ��ł��傤
���N�ɓ����Ă���Ə��^�y�ʉ��ɖڊo�߂��悤�ł����i�j
�m�d�w�Ƃ������C�o�����o�����Ă���Ɓc
���e���}�[�N�t�@������@
���̎ʐ^�͂������p�ɊȒP�Ɏd�グ�������������
�W�p�Ŏd�グ��Ƃ����Y��ɃS�~�͏����܂���i�j
�S�~���@�\�͂ǂ��ł��������ǃS�~�͋C�ɂ��܂�
�����A�P��̎B�e�ʼn��S�J�b�g�ƎB���Ă��A�W���x���Ŏg���̂͂��̂����P�A�Q�J�b�g
����̃S�~��������ԂȂ�đS�̂̎�Ԃ���l��������X������̂�����
�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����
���ǎg���Ղ����l����Γ��R������x�̑傫���͕K�v�Ȃ̂�
�����@�͓��R�������l���č��킯�ł���
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�������������ő���Ɋ������������^�y�ʋ@���o����\�������S�ɂȂ������K�i�������̂��܂�Ȃ��Ƃ��ł��˂�
�����Y���掿�͂������������ǓO��I�ɏ��^�y�ʂȃ����Y���e�s�p�ɂ���悩����
���A�l�e�s�ł���Ă��邱�Ƃ��e�s�őS���o���Ȃ������i��낤�Ƃ����Ȃ������j�̂����������Ȃ�
(*´��`)�m
�����ԍ��F13542425
![]() 2�_
2�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
>�l�e�s�̏��������Ă��킩�邯�ǁA�I�����p�i�����^�y�ʉ��͂قƂ�Ǎl���ĂȂ��ł��傤
���ɔ�r�o����@�킪����܂���ˁB
���܂ǂ��A�ǂ̃��[�J�[�ł����^�y�ʉ��͍ŏd�v�_���ڂ̂ЂƂł��B
>�W���x���Ŏg���̂͂��̂����P�A�Q�J�b�g
����̃S�~��������ԂȂ�đS�̂̎�Ԃ���l��������X������̂�����
�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����
1���ɉ���J�b�g���B�e���Ĕ[�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�Ǝʐ^�Ƃ́A����ȗI���Ȃ��Ƃ͂���Ă����Ȃ��ł��傤�˂��B
�����ԍ��F13543218
![]() 5�_
5�_
�o���r�[�m��
���̏������݂����p���Ă��������܂��āA�ǂ����ł��B
�Ƃ���ŁA�|�����_�n����̋L�q�ł����A���i�������ȂƂ���͂���܂����B
��������A�o���r�[�m��̏������݂̕��Ɍ��i�Ƃ��ɋZ�p�I�Ȃ������j�����X�����܂��B�����ӂ��������B
�����ԍ��F13543371
![]() 6�_
6�_
�����܂ǂ��A�ǂ̃��[�J�[�ł����^�y�ʉ��͍ŏd�v�_���ڂ̂ЂƂł��B
�����������Ƃł�
����ƍ��N���珬�^�y�ʂ��d�����������I���A�p�i�����������Ȃ�
�W�N�O�ɂȂ�������Ƃł��l�����Ȃ������̂��c
��1���ɉ���J�b�g���B�e���Ĕ[�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�Ǝʐ^�Ƃ́A����ȗI���Ȃ��Ƃ͂���Ă����Ȃ��ł��傤�˂��B
�܂��A�ӊO�Ƀv���͂����܂ŋC�ɂ��ĂȂ���ۂ���
��ԋC�ɂ��Ă�̂͂ނ��뉿�i�ɂ���悤�ȃA�}�`���A���Ǝv���܂���
�t�B�����������Ă��l���ƃt�B�����̃S�~�̕����v���I�ɂ�������������̒m���Ă邵��
�����������S�~���@�\�͂ǂ��ł�����������
���ʂȋ@�\�Ƃ������Ă�킯�ł͂Ȃ��̂Ō���̂Ȃ��悤��
�������Ȃ�����A����ɂ��Ēm��Ȃ��ƌ����Ă邾���ł���
�����ԍ��F13543483
![]() 3�_
3�_
>�W�N�O�ɂȂ�������Ƃł��l�����Ȃ������̂��c
�������l���Ă����ł��傤�B8�N�O�����ē����ł��B
�����̃J������OLYMPUS�̂��̂����ُ�ɑ傫���ł����H
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��̂���]�i�\�z�H�j�ɓY��Ȃ������Ƃ��������ŁA
OLYMPUS�̃G���W�j�A�����^�����l���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł���B
>�܂��A�ӊO�Ƀv���͂����܂ŋC�ɂ��ĂȂ���ۂ���
�v�������܂��܂ł����c
���̒m�荇���̃v���ŃS�~�̎ʂ荞�݂��C�ɂ��Ă��Ȃ��l�͂��܂���B
�����Y�̐������{�f�B��p�ӂ���Ƃ��A�����Y�������͕K���������ɂ���Ƃ��B
4/3���[�U�[�́u�Y��Ă�v�ƌ����Ă��܂��B
�����ԍ��F13543753
![]() 5�_
5�_
�v�����S�~�̎ʂ荞�C�ɂ��Ȃ������玸�i�ł���(��)
����Ȑl�ɋ������킯���Ȃ�www
�����Ǒf���炵���I�����ł���
�����̓L���m�����C�������ǃL���m������Ԍ����Ƃ��������Ă邵(��)
�܂��e�s���厸�s�삾���D�������甃����
�I�����D��
(*´��`)�m
�����ԍ��F13543990
![]() 1�_
1�_
>�܂��A�ӊO�Ƀv���͂����܂ŋC�ɂ��ĂȂ���ۂ���
>�v�����S�~�̎ʂ荞�C�ɂ��Ȃ������玸�i�ł���(��)
�����Ă邱�Ƃ��Ⴄ�c
>�����Ǒf���炵���I�����ł���
���̂��Ƃł����H
�Ԉ�����������{���̂��Ƃ̂悤�Ɍ���ꂽ��A�߂������R�ɂ��A���邢�͍����̖����ᔻ�E�ے�E����ڂɂ���̂������Ȃ����ł��B
�����ł͂ǂ��ɂ����Ȃ��J��������Y������Ă���������⌤���ҁE�Z�p�҂ɑ��Ď���Ȃ��Ƃ��Ƃ͎v���܂��H
����ɂ��Ă��A�����Ȃ��̂��蔃���Ďg���Ă���Ȃ�āA�ʔ������ł��ˁB
�����ԍ��F13544120
![]() 11�_
11�_
����OM2�������Ȃ������̂ŁAE-P3���w�����܂����i���j�O�O
�����ԍ��F13544350
![]() 0�_
0�_
�v���͌��\
�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����
�S�~�̗L���͋C�ɂ���ƌ����Ă���̂ł���
�v�����S�~�t���Ŕ[�i������܂����ł���
�܂��A�G���Ƃ��ł��܂ɃS�~�ʂ��Ă܂����ǁi�j
���Ԉ�����������{���̂��Ƃ̂悤�Ɍ���ꂽ��A�߂������R�ɂ��A���邢�͍����̖����ᔻ�E�ے�E����ڂɂ���̂������Ȃ����ł��B
�l�͍����̂Ȃ��m��������������ł����ǂ�
���ǁA����������l��Tranquility�������Ƃ��ɂǂ������邩�̍��Ȃ����Ȃ̂ł���
�����͌����҂̋��̓��ɂ���킯�Ő������邵���Ȃ��킯��
�l�͂e�s�͑厸�s��Ŕ��ɂ��������Ȃ��Ɗ�����̂ł�
���z�͂��̂������悩�����̂Ɂc
���Ȃ݂Ɍ����Ȃ̂̓L���m���Ƃ�����ЂȂ̂�
�L���m���̃J�����͌����ł͂Ȃ��ł��˂�
���߂Ȃ�d���Ɏg���Ȃ����i�j
�ł�����Ԉ��|�I�ɂ킭�킭���Ȃ���Ђ̓L���m�����Ȃ���
�ق�Ƃɖʔ����Ȃ���Ђ��i�j
(*´��`)�m
�����ԍ��F13544449
![]() 2�_
2�_
�܂������ł��B
�u�Ԉ�����������{���̂��Ƃ̂悤�Ɍ���ꂽ��A�߂������R�ɂ��A���邢�͍����̖����ᔻ�E�ے�E����ڂɂ���̂������Ȃ����ł��B�v
��L�A��������������܂����B���ɒ������܂��B
�u�Ԉ�������������{���̂��Ƃ̂悤�Ɍ���ꂽ��A��������R�ɂ��A���邢�͍����̖����ᔻ�E�ے�E����ڂɂ���̂������Ȃ����ł��B�v
�c�ł����B���炵�܂����B
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
>�v���͌��\�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����
�S�~�̗L���͋C�ɂ���ƌ����Ă���̂ł���
�����Ȍ���������Ȃ��Ă��B
>�l�͍����̂Ȃ��m��������������ł����ǂ�
>���ǁA����������l��Tranquility�������Ƃ��ɂǂ������邩�̍��Ȃ����Ȃ̂ł���
>�����͌����҂̋��̓��ɂ���킯�Ő������邵���Ȃ��킯��
�����ł͂Ȃ��A�����E�J���҂����̓��𖾂������L�q�͂�����ł�������܂��B
���Ƃ��A4/3�V�X�e���J���҂��K�i���莞���炸���Ə��^�����l���Ă���Ƃ����،��B
http://www.four-thirds.org/jp/special/story.html
http://www.olympus.co.jp/jp/magazine/techzone/vol59/index.cfm
http://www.digitalcamera.jp/report/4-3SLR/43SLR-1.htm
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0704/27/news122.html
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2004/09/29/152.html
E-1�̋@�\�������
�u�{�f�B�ɂ́A�y�ʂŌ��S�ȃ}�O�l�V�E���������̗p���A�v���d�l�̃X�y�b�N�𓋍ڂ��Ȃ���A660g�̌y�ʉ��������B�v���J�����}�����g����œK�x�ȏd�����������Ă��܂��B�v
http://www.olympus-esystem.jp/products/e1/feature/f_s02.html
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��́u���^�����l���Ă��Ȃ��v�Ƃ��낢�남��������Ă��܂������A�S�Đ�����������ł��傤���B
�u���̂��܂�ɖ��ʂɂȂ����t�����W�o�b�N�͂܂ʂ��Ƃ��������悤�������c�v
�u�掿���ǂ���ł����Ă��S�ċ������Ƃ����Z�p�҂̖��S�����K�i�Ǝv���c�v
�u�܂��A���^�y�ʋ@�������肪�S���Ȃ������ȂƎv���܂��ˁv
�u���ǂ͉掿���悭�Ȃ�Ⴂ���������Ă̂�łǂ�ǂ�ǂ�ǂ��剻�����V�X�e���c�v
�u������x�ȏ�͑傫���Ȃ�Ȃ��悤�Ɋ撣�낤�Ƃ͎v��Ȃ������̂ł��傤�v
�u�K�i�����i�K�ł�����Ƃł����^�y�ʉ����ӎ����Ă��ꂽ��v
�u�l�e�s�̏��������Ă��킩�邯�ǁA�I�����p�i�����^�y�ʉ��͂قƂ�Ǎl���ĂȂ��ł��傤�v
�u�W�N�O�ɂȂ�������Ƃł��l�����Ȃ������̂��c�v
�����̖����ے�͖��ł͂Ȃ������悤�ł��ˁB
�Ƃ�����A�͂��炸��4/3�̑_�������炽�߂Ċm�F���邱�ƂɂȂ�܂����B
�܂��܂����҂����Ă��炢�����V�X�e���ł��B
�����ԍ��F13544551
![]() 15�_
15�_
�܂��A�I�����p�X�̃J�����ł��S�~���ʂ��Ă���ʐ^�͊��x���q�����܂����ǂˁ`
�ŋ߂̗Ⴞ�ƁA����ł����ˁi�ʐ^����A�V���b�^�[���x1/250�Ȃ̂ŁA���ł͂Ȃ��ł��傤�j�B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13298768/ImageID=971031/
���ƁA�S�~���@�\�̓y���^�b�N�X�͂��Ƃ��j�R����L���m���A�\�j�[�ɂ������g�U�������̂��̂��̗p����Ă���̂ŁA���͂�I�����p�X�̗D�ʐ��͉ߋ��̘b�ł��傤�B
���ƁA�J�����̑傫���Ɋւ��Ăł����A���傫�ȎB���f�q�𓋍ڂ��Ă���NEX�ɕ���Ă���悤�ł͂܂��܂��_���ł��傤�B
�V���[�Y�ŏ���E-PM1(109.5×63.7×33.95)�ł����A�o���A���O�����ڂ�NEX-C3(109.6×60×33)�ɂ��瓯����������Ă��܂��B
�B���f�q���������炢�̑傫���Ȃ̂�����A�����Ə������o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
E-1�̓t�@�C���_�[���\���v�A������(��˂̒�̂悤�ɏ����������ɂ���)���Ƃ���A���߂�APS-C���̃t�@�C���_�[�{���ɂȂ�悤�v���������Ƃ���AE-3��E-5��800g��ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�܂�A�܂Ƃ��ȃt�@�C���_�[���\�ō�����ꍇ�u�v���J�����}�����g����œK�x�ȏd���v�ƃI�����p�X�������Ă���660g�Ƃ͒��������̂ƂȂ�Ƃ������Ƃł��B
K-5��D7000�ȂǁA���Ђ͓����ȏ�̐��\��E-5�̂�����y����(600g��)�������̂ŁA�܂�Ƃ���́A�t�H�[�T�[�Y���̂��̂����^���Ɍ����Ă��Ȃ����A�I�����p�X�������Ɠw�͂��ׂ����������A�̂ǂ��炩�ł��傤�B
�����ԍ��F13545100
![]() 2�_
2�_
lifethroughalens����
����ɂ��́B
>�S�~���@�\�̓y���^�b�N�X�͂��Ƃ��j�R����L���m���A�\�j�[�ɂ������g�U�������̂��̂��̗p����Ă���̂ŁA���͂�I�����p�X�̗D�ʐ��͉ߋ��̘b�ł��傤�B
�ȑO�J�����G���ŃS�~��萫�\�̔�r�e�X�g������Ă��܂������A�����ł�OLYMPUS�̂��̂Ɉ���̒�������悤�ł����B
OLYMPUS�ɗD�ʐ��͖����Ƃ���q�ϓI�ȍ����͂���̂ł��傤���H
>���傫�ȎB���f�q�𓋍ڂ��Ă���NEX�ɕ���Ă���悤�ł͂܂��܂��_���ł��傤�B
>�B���f�q���������炢�̑傫���Ȃ̂�����A�����Ə������o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���̃N���X�̃~���[���X�Ń{�f�B�T�C�Y���x�z����̂́A�C���[�W�Z���T�[�̃T�C�Y�ł͂Ȃ��w�ʃ��j�^�[�̑傫���ł��B�ǂ���̃��[�J�[���A���[�U�[�����������j�^�[�ł����ƌ����Ȃ�����Ə���������Ǝv���܂��B
�Z���T�[�T�C�Y�������Ă���̂̓����Y�̑傫���Ɛ��\�ŁA����͏�ɋ������J���҃C���^�r���[�̒��ł������ɏq�ׂ��Ă��܂��ˁB
>E-3��E-5��800g��ɂȂ��Ă��܂��܂����B
E-1��E-3�̈Ⴂ�̓t�@�C���_�[�����ł͂���܂���ǁAE-1��OM���݂̑傫�������҂����l�����������̂Ɠ��l�AE-3��E-1���݂̑傫�������҂����l�͑��������ł��傤�B
E-3�Ǝ����|�W�V�����̈ႤK-5�ED7000���r����Ó����͂Ƃ������AE-5�͑傫���ƌ������̓��[�J�[���d�X���m���Ă���ł��傤�B����Ɋ��҂ł��B
�����ԍ��F13546117
![]() 7�_
7�_
�I�����p�X�A�����Ǝv���܂���O�O
�����ԍ��F13546580
![]() 0�_
0�_
�������Ȍ���������Ȃ��Ă��B
���Ď������l�̏������̓ǂ�łȂ��������炾���ł���
�K���ɓǂݔ���Ă����ȁH
���̔��_�͉��߂̈Ⴂ������܂��������ǁA���̕����͂��������Ȃ��H
�����Ɠǂ�ł�������
�c�_�ɂ��Ȃ��
���[�J�[�͂������Ƃ�������Ȃ��Ă�������܂��Ȃ̂�
���[�J�[�̌��������Ƃ�S���������Ɖ��߂���̂͂ǂ����Ǝv���܂����H
����ɖl�̈ӌ��͂͂Ȃ����琄���Ƃ��ď����Ă܂����H
�o�Ă������ʂƂ��Ă̐��i������
���^�y�ʉ��͖������Ă�Ƃ����v������̂��o���Ă��邵
�������^�y�ʉ����l���Ă����Ƃ��Ă�
�����̐l�����^�y�ʉ����l���Ă��Ȃ����̂��o���Ă���Ɗ�������
���ʁA���^�y�ʉ����l���Ă��Ȃ��̂Ǝ��������Ƃ������܂�
���̕ӂ��܂��̂̓j�R������
�c�S�O�͊m���ɂ߂�����y�����������̂����ǂ��c
�j�R���̓L�b�g�����Y���d�������������Y�������Ȃ����Ƃ����c
�V�X�e���ł͏d���̂Ɂc
�ł��������^�y�ʂ̂P��t�Ƃ����c�S�O������
�d�|�T�O�O���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�͔{���炢�Ȃ̂ɂ�����Ƒ傫���Ă�����Əd�����炢
�t�H�[�T�[�Y�ӂ����Ȃ�������c
(*´��`)�m
�����ԍ��F13546696
![]() 2�_
2�_
>���̔��_�͉��߂̈Ⴂ������܂��������ǁA���̕����͂��������Ȃ��H
�r���Ō����Ă邱�Ƃ��ǂ�ǂ�ϗe���Ă���悤�ɓǂ߂��̂ł����B�S�~�ɂ��Ă̂������B
���́u1���ɉ���J�b�g���B�e���Ĕ[�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�Ǝʐ^�Ƃ́A����ȗI���Ȃ��Ƃ͂���Ă����Ȃ��ł��傤�˂��B�v�ɑ��āc
>�܂��A�ӊO�Ƀv���͂����܂ŋC�ɂ��ĂȂ���ۂ���
>��ԋC�ɂ��Ă�̂͂ނ��뉿�i�ɂ���悤�ȃA�}�`���A���Ǝv���܂���
�Ƃ����ԓ�����
>�v�����S�~�̎ʂ荞�C�ɂ��Ȃ������玸�i�ł���(��)
�ƕς��
>�v���͌��\�S�~���@�\�̗L���͋C�ɂ��Ȃ�����
�S�~�̗L���͋C�ɂ���ƌ����Ă���̂ł���
�Ƃ����悤�ɁA�S�~�̗L���̘b�����̂܂ɂ��S�~���@�\�̗L���ɕς���Ă���悤�ɓǂ߂܂����B
���ł͂ǂ̃��[�J�[���S�~��葕�u�𓋍ڂ���悤�ɂȂ�܂����B
�v���A�}��킸�A�S�~��葕�u�̓��ڂ̊�]�����������̂��Ǝv���܂��B
�Ȃ��ɂ͂����Ă������Ƃ������������邱�Ƃ��킩��܂������B
>���[�J�[�̌��������Ƃ�S���������Ɖ��߂���̂͂ǂ����Ǝv���܂����H
�l���Ă����Ȃ����Ƃ��u�l���Ă���v�Ƃ͌���Ȃ��ł��傤�B
���Ȃ��Ƃ��u���^�y�ʉ��v��ڕW�̂ЂƂƂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
>����ɖl�̈ӌ��͂͂Ȃ����琄���Ƃ��ď����Ă܂����H
�u�l�͍����̂Ȃ��i�����́j�m��i�ے�j�������������ł����ǂˁv�Ȃ�ł���ˁH
�u���^�y�ʉ�������l���Ă��Ȃ��v�Ǝv�������萄���Ŕے��A�����Ă���悤�ɂ��������܂��ǁB
>�ł��������^�y�ʂ̂P��t�Ƃ����c�S�O������
�d�|�T�O�O���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�͔{���炢�Ȃ̂ɂ�����Ƒ傫���Ă�����Əd�����炢
�ǂ̃��[�J�[���u���^�y�ʉ��v�͏d�v�ڕW�̂ЂƂł��B
�ł�����A�ǂ̃��[�J�[�̐��i�ł��������炢�̏��^��������Ă���Ƃ������Ƃł��B
��ɂ������܂������A�Z���T�[�ȊO�͓����悤�ȍ\�����i���g���Ă���̂ł�����A�{�f�B�T�C�Y�̏��^���̓Z���T�[�T�C�Y�̑傫���̍����炢�����ς��Ȃ��B
��ɂ��������悤�ɁA�Z���T�[�T�C�Y�������Ă���̂̓����Y�̕��ł��B
>���̕ӂ��܂��̂̓j�R������
>�c�S�O�͊m���ɂ߂�����y�����������̂����ǂ��c
>�j�R���̓L�b�g�����Y���d�������������Y�������Ȃ����Ƃ����c�v
�Ƃ������Ƃ���ł��ˁB
�����ԍ��F13547064
![]() 9�_
9�_
�����m�肽�������̂̓^�}�l�M�{�P�������闝�R�ł͂Ȃ���
�������Z�p�ɂ��Ăł��B
���邢�͔ʃ����Y�g�p�����ǃ^�}�l�M�Ȃ������Y����Βm�肽���ł��B
�ʃ����Y���g�����R�ƃ^�}�l�M�ڂ��闝�R�͗������Ă��܂��B
�����ԍ��F13547120
![]() 2�_
2�_
���Ƃ����悤�ɁA�S�~�̗L���̘b�����̂܂ɂ��S�~���@�\�̗L���ɕς���Ă���悤�ɓǂ߂܂����B
�܂�����͂Ƃ��Ă���������
�ŏ�����S�~�͂��ɂ��Ȃ��Ƃ͏����Ă��Ȃ�
�r���ł�����������菑���Ă�ł���H
(*´��`)�m
�������[�i����Ƃ��S�~�����܂܂��Ȃ��ł��悳�����Ɂi�j
���l���Ă����Ȃ����Ƃ��u�l���Ă���v�Ƃ͌���Ȃ��ł��傤�B
���C�ł����܂�
�ǂ̊�Ƃ������Ƃ͂����܂��ǂ�
���Ȃ��Ƃ������_���������āA���_������Ȃ��̂͋ɂ�����܂��ł�
�����Ȃ��Ƃ��u���^�y�ʉ��v��ڕW�̂ЂƂƂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
�S�������͌����Ȃ�����
�u���^�y�ʉ���������Ƃł���������ȁH�v���炢�ŗD�揇�ʒႩ�����悤�ɂ��������Ȃ�
���Ȃ��Ƃ����N�ɓ���܂�
�܂��p�i�͂f�e�Q�����肩��l���n�߂����ȁi�j
�܂�����Tranquility����Ƃ͂�����b���Ă����s���ł���i�j
�������Ⴄ���Ƃ������Ă邾���Ȃ̂�
�l�͂e�s���v���I�ɂ��߂������̂͏��^�y�ʉ����s�\�ȋK�i�ɂ���Ǝv���Ă��܂��̂�
���^�y�ʉ����\�ȏ_��̂���K�i�ɂ��Ă����
�����Ƃ킩��₷�������̐l�ɃA�s�[���ł����Ǝv���܂�
���ꂪ�ق�ƂɎc�O�łȂ�Ȃ��c
�����ԍ��F13547132
![]() 2�_
2�_
�����i�܂ȂĂ��j����
���ɃY�[���Ƃ��P�œ_�Ƃ������ĂȂ������̂ł���
�K�������A�ʃ����Y���g��������Ƃ����āA���x�̖��ł����A
���قNjC�ɂȂ�Ȃ������Y������܂��B
�P�œ_�łT�O������F1.2�ł���
http://alphaeos.blog18.fc2.com/page-2.html
http://cweb.canon.jp/ef/lineup/standard/ef50-f12l/index.html
���̃����Y�Ȃ�A���قǃ^�}�l�M�{�P�͋C�ɂȂ�Ȃ����x�����Ǝv���܂��B
�Y�[���ł��Ɣʃ����Y���S���͕K�v�ɂȂ�͂��ł��B
�ʃ����Y���S���g�����v�́A����قNJy�ł͂Ȃ����̂ł��̂ŁA
�Y�[���p�Ƃ��ẮA���̂Ƃ��뎄�͌������Ƃ�����܂���B
���݂Ɏ�����ԍD���ȃ����Y��
EF70-200mm F2.8L IS II USM
http://kakaku.com/item/K0000079167/
�ł��B
�l�I�ɂ͌u���g���������Y����͂�D���ŁA�ʃ����Y��p���������Y��
�L�p�������TS-E�����Y�ȊO�A�{�P�~���D���ł͖����̂ł��܂�g���܂���B
�����ԍ��F13547507
![]() 0�_
0�_
���T�O������F1.2
EF50/1.2�̃T���v�����������Ă݂܂��������܂˂����Ă܂���orz
sigma50/1.4���͂܂����Ǝv���܂������A
���{�I��EF50/1.4���łȂ��ł�����ˁB�B�B
���������T���v���摜�����ׂĂ݂܂��B
�����L�p�����Y�ł�
�I�ׂȂ��̂Ŕʃ����Y�����Ă���̂��g���Ă܂��B
�����ԍ��F13547869
![]() 2�_
2�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
>�܂�����Tranquility����Ƃ͂�����b���Ă����s���ł���i�j
�������Ȃ��ł��ˁB���E�̌����E�l���������{����Ⴄ�悤�ł��B
���f���T���@�u�͂�Ԃ��v�̐���v���W�F�N�g�}�l�[�W���[�́w�u�͂�Ԃ��v���v�l�@�x�Ƃ��������̒��Łu���_�@���~�߂ĉ��_�@�ŕ]�����悤�v�ƒ��Ă��܂��B
�i��ǂ��������߂��܂��j
�����J������]������ۂɂ͂����������Ǝv���܂��ˁB
�Ⴆ��4/3�@��4/3�Z���T�[���̗p�������߂ɓ��������b�g�����_�@�ŕ]������B
�������ǂ�ȋ@��ɂ��_���ȂƂ��������킯�ł����A�������ʐ^���B�e����ɂ������ă����b�g�̕�������������ł��B
����Ƀ_���ȂƂ�����茩�Ă���Ɓu�A���������R���������v�ƂȂ��āA���ɋC���������B
>�e�s���v���I�ɂ��߂������̂͏��^�y�ʉ����s�\�ȋK�i�ɂ���Ǝv���Ă��܂�
�{�f�B�������Ă��Ȃ��Ƃ����v���邩������܂���ˁB
�����Y�̗ǂ��͎��ۂɎg���Ă݂Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ����̂ł��B
�����ԍ��F13548425
![]() 10�_
10�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
�ЂƂ����Y��Ă��܂����B
>�e�s���v���I�ɂ��߂������̂͏��^�y�ʉ����s�\�ȋK�i�ɂ���Ǝv���Ă��܂�
4/3�ȊO�̋K�i���ƁA�~���N���ȏ��^�y�ʉ����\�Ȃ̂ł��傤���H
�����ԍ��F13548853
![]() 2�_
2�_
������Ă��܂���
�l�͎����Ŏg���Ȃ���_�@�ŕ]�����܂�
�����炱�̂e�s�������\��ł�
�ł��e�s�����s�������R�̑傫�Ȉ�͏��^�y�ʉ����s�\�ȕ����ƌ����Ă��邾���ł�
��4/3�ȊO�̋K�i���ƁA�~���N���ȏ��^�y�ʉ����\�Ȃ̂ł��傤���H
�~���N���ȏ��^�y�ʉ��͖����ł��傤
�P��t�ł��邩����
�ł����ʂɏ��^�y�ʉ��ł��Ȃ��}�E���g�͂e�s�ȊO�ɂȂ���Ȃ����ȁH
�f�W�^���ɍœK�����ꂽ�P��t�̃}�E���g�͂e�s�ƃR���^�b�N�X�m�}�E���g�����Ȃ����ǂ�
�f�W�^���p�ő�^�������m�}�E���g�ł��璷���t�����W�o�b�N�ŗL���Ȃe�}�E���g��
�S�U�D�T�������P�D�T�������������̂S�W�����ł����߂Ă܂������
�t���T�C�Y�����Ȃ����Ă���d�e�}�E���g�łS�S����
���ꂪ����ł͊��S�ɓd�q����̃����Y�ł������C�J���ł͈�ԏ��^�y�ʉ����Ղ��ł��傤��
�J�����{�f�B�Ɋւ��Ắc
�܂��A�L���m���͂��܂菬�^�y�ʉ���D�悵�Ă��Ȃ��̂ŏo���ĂȂ����ǂ�
�t�B��������̂j�������͋��ٓI�Ɍy���������c
���̂d�e�}�E���g�̂S�S�����ɑ��Ăe�s�͂R�W�D�U�V�����c
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���P�^�S�Ȃ̂ɂT����������Ƃ����ς��Ȃ��c
�������{�g���l�b�N�ɂȂ��Ă���͖̂����ł�
(*´��`)�m
�I�����p�X�����������������̎��������邾���ł��c
�����ԍ��F13548922
![]() 2�_
2�_
���Ȃ݂Ƀ~���[���X�Ȃ�d�}�E���g�����ٓI�ɏ��^�y�ʉ��\�ł���
����̓~���[���X�����炾���c
�t�����W�o�b�N���P�W�����Ȃ̂͂ނ��돫���掿��Nj������ŗL���ɂȂ�ł��傤��
�e���Z���̖�肪�������ꂽ�Ƃ��ɂ�
�Ώی`�őf���Ȑv�̏��^�y�ʂȍL�p�����Y�����Ղ�����
�d�}�E���g�̓t���T�C�Y�ɂ��Ή��ł���̂�
�قڍ��̃T�C�Y�Ńt���T�C�Y�����Ă��܂��Ƃ����̂͋��ٓI�ł�
�����A���^�y�ʉ�����Ȃ�~���[���X�����Ȃ����Ċ����ł���
(*´��`)�m
�����ԍ��F13548930
![]() 1�_
1�_
�����ӂ�ׂȂƁ`�邳��
���W�N�O�ɂȂ�������Ƃł��l�����Ȃ������̂��c�@�����^�y��
�P�P�N�O�ɔ������ꂽ2/3�^��SONY��CCD���̗p����E-10�̃����Y9-36mm/F2.0-2.4
(���C�J���T�C�Y���Z35-140mm����)�̓t�B���^�[�a��62mm�ŁA�B���f�q�̃T�C�Y�̊�
�ɂ͑傫�������ł����ǁA������nikon��D1��CANON��D30�p��28-70mm/F2.8��t����
�����l����Ɣ��ɃR���p�N�g�Ōy�ʂ������悤�Ɏv���܂��B
���̌�t�H�[�T�[�Y���J�����ꂽ�킯�ł����ǁA�W�N�O�̋Z�p��O��ɂ���ƁAE-1��
���ЂƔ�r���Ă������\�Ȋ��ɏ��^�y�ʂ������Ǝv���܂��B���ł͒����ɂ����g���
�Ă��Ȃ�KODAK�̃t���t���[��CCD�̔��F�́A�����_�ł����͓I�ł��B
E-5�̓t�@�C���_�[���ǂ������ł����A���C�J���T�C�Y���Z��100-1000mm(F4-6.3��
F8-13�ɂ����Ƃ��Ă�)�Ƃ�600mm(F2.8��F5.6�ɂ����Ƃ��Ă�)�̃����Y��t���Ă�
�莝���B�e�ł��鎖���l����ƁA���ɏ��^�y�ʂ��Ǝv���܂��B
�܂��AE-5��菬�^�y�ʂ�APS-C�@�̓t�@�C���_�[���N�b�L�������Ȃ��ł�����A
�t�@�C���_�[�̌�������ɁA�����ł����^�y�ʂȋ@���I�ڂ��Ƃ��Ă��AE-5����
�I�������Ȃ��Ƃ������ɂȂ�Ǝv���܂��B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̑傫�����A�ǂ��o�����X���Ǝv���܂��B
�R���g���X�g�`�e�p�ɐv��ύX���Ă���́A�O�ʂ̒��a�ɍ��킹�ăt�B���^�[�a��
�����������蒾���^�C�v�ɂ���ȂǁA���R���p�N�g�Ɍ�����ׂ̍H�v�����Ă���Ƃ�
�v���܂����A��������������G����Ă����悤�ɁA���̐v�̉������Ƒ���a����
���Ȃ����悤�ł��B
�p�i�\�j�b�N������a�̃Y�[�������Y���J�����̂悤�ł����A�����̃����Y�Q��
�����Y�ɂ��ꂼ��쓮���[�^�[�����t���A�Y�[�~���O�ɂ��A�`�e�ɂ����ꂼ���
�쓮���[�^�[���g���Ƃ����V�Z�p�̂悤�ŁA��̃����Y�Q��P���̃����Y�ɁA����
�̖�ڂ�^���ă����Y�̖��������炷�����ł��镪�A����a���Ə��^�y�ʉ����\��
�Ȃ�悤�ł��B
�p�i�\�j�b�N�Ƃ��Ă̓p���[�Y�[���𓋍ڂ��邱�Ƃɂ���āA����p�ɕK�v�s����
�@�\���t���������܂�����A�o�k�}�E���g�̃����Y�ɑR�ł���悤�Ȓ������\��
�����Y���o�Ă���\��������܂��ˁB
���Ȃ݂ɂo�k�}�E���g���ƌy���Y�[�������Y�ł�1kg�ȏ゠��A�P�œ_�Ɏ����Ă�
�t�����W�o�b�N�̊W�ōł��y���ł��钆�]�������Y�ł���2kg�ȏ゠��܂�����
12-35mm��35-100mm��1kg����ďo�Ă�����A�ʔ������ƂɂȂ肻���ł��ˁB
���ɒP�œ_��F1.4�`F2�N���X�ň��������Y������킯�ł�����ACM��PV��V�l�}��
����ł����ڂ��W�߂�Ǝv���܂��B
�t�W�m����18-85mm/T2(F1.8���x�ɑ����H)�͂W���h�����Ƃ��H
RED�Ŕ̔����Ă��郌���Y�͓��{���ŁAZEISS�̒P�œ_�����Y��1/5�̉��i�������ł�����
����ł����\���~���܂�����A�������ł��ˁB
NEX�̃����Y�͉�ʎ��ӂ�MTF�����������ł����ǁA���^�y�ʉ��ׂ̈ɁA��ʎ��ӂ�
�]���ɂȂ��Ă���ׂ��Ǝv���܂����A�f�U�C���������̂��߁A�}�E���g�̑傫����
�����Y���̂�K�v�ȏ�ɑ傫�����Ă��銴�������܂��B
NEX���Ƃo�k�}�E���g�̃����Y�ɃC���[�W�T�[�N�����������������܂����ǁASONY��
ZEISS�̃Z�[���X��D���悤�Ȃ��Ƃ����܂����ˁB
�����ԍ��F13548973
![]() 3�_
3�_
���|�����_�n����
���̉��l�ςł������̒ʂ肾�Ǝv���܂���
�l�����̉��l�ςł͕]�����Ă��邩�甃���킯��
(*´��`)�m
�ł��t�Ɍ������̉��l���ł����]���ł��Ȃ��̂��e�s�V�X�e��
�����ɖ��_������Ǝv���Ă��܂�
�m�d�w�Ɋւ��Ă̓t���T�C�Y�ɑΉ��ł���}�E���g��
�����̃����Y�ɂ��Ă��܂��Ă��邩�烌���Y���ł����Ƃ͎v���܂���
�P�U�����Ɋւ��Ă�
�ł��W���Y�[���͂���Ȃ���ł��傤
�ł������ł͂Ȃ��t�W�c�{�^�Ƃ��~�����ł��ˁi�j
�c�`���~�e�b�h�݂�����
���[�^�[�����ł͓�����낤���ǂ��c
�d�}�E���g�͌���`�}�E���g�ɂ��낢�뉓�����Ă邩��
���͂�����̂͂���������ł͂Ȃ����ȁH
���̓_�l�e�s�̓p�i�̃t���O�V�b�v�Ȃ̂ŃK���K���ɐi�����ė~�����ł��ˁ�
�I�����Ƃ܂��e�s�ɉ������Ă銴���o�Ă邯�ǂ��i�j
�e�s���܂����������Ƃ���̂Ȃ�I�����Z���T�[�ʈʑ����`�e�̕��������悳���Ȃ̂ł����ǂ�
���̈Ӗ��ł��p�i�̃Z���T�[���~�߂Ȃ����ȁc�i�j
(*´��`)�m
�����ԍ��F13549001
![]() 0�_
0�_
�Ɩ��@����sony��PL�}�E���g�̃r�f�I���o���Ă��Ǝv���܂��B
�t�Ƀp�i��AG-AF105���o���Ă���̂ŁAmFT�̊��͂͂���Ȃ�
�Ȃ����ƍŋߎv���悤�ɂȂ��Ă��܂��BPL�}�E���g�̔e����
�H������ł����Ȃ����ȂƁB�B�B��������mFT�̃����Y
�������āA�R���V���[�}�[���f���g���Ă���l�ɂ������Y�I����
�����G���g���[����v�������܂őI�ׂ邮�炢�[�����Ă���͂��B
�r�f�I�ƊE�̐��͊W�Ƃ�����m��Ȃ����ǖϑz���Ă܂��B
�����ԍ��F13549325
![]() 1�_
1�_
nightbear����
����Ȃ疾�邢�����Y�������̂ɁI�ƒP���Ɏv�������Ƃ����[�B
�@4/3�p9-18mmF4.0�`5.6���t�B���^�[�a72mm�Am4/3�p9-18mmF4.0�`5.6���t�B���^�[�a52mm�A���i�͓����Ő��\���قړ����B�Ȃ疾�邢�����Y����������Ȃ��I�H�I
������A
�I�����p�X4/3�p7-14mmF4.0�ƃp�i�\�j�b�N��m4/3�p7-14mmF4.0�������ăp�i�\�j�b�Nm4/3�p�̓I�����p�X�̂ق�2/3�̑̐ςʼn��i�͔����I�I�I
������ăt�H�[�T�[�Y����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ����������������ł���H
����ȃJ�^���O�f�[�^������m4/3�p9-18mmF2.8�Ȃ�ă����Y���o�����Ȃ��I
�����������炻����Ĕ���ɂȂ邩���B�����������������C�̈�Ԃɔ������� �H
�܂��������������Ȃ��͉̂������R������낤�Ȃ��I�ʂ����Ă��̗��R�Ƃ́H
�������܂����[�J�[�͒P���Ɍy�����������̂��������������̂����˂��A�Ɣ����K�b�J���v����������E�E�E�E�E
�ł��A�I��m4/3�p9-18mmF4.0�`5.6���Ē��������̗p���Ă�̂�ˁB������Č��Ǖ��̂�������������ׂ̏��H�W�����I�g���Ƃ��͈�������o�����̂˂�(^0^;)
�v����Ɍy���������Ȃ�����イ���Ƃ��������������A�̂��I�@�ƁB
�o���r�[�m�����
�@>���邢�����Y���~�����ƌ����̂́A
�@�@�P�D�{�P�~���o������
�@�@�@�@���@�i�}�C�N���j�t�H�[�T�[�Y�ł͍��{�I�ɑI�J�������Ԉ���Ă���
�@�@�Q�D�Â��V�[���ŃV���b�^�[���x���グ����
�@�@�@�@���@�����x�B�e�o����J������I��
�@�@�R�D��i�i���ĉ𑜐��̍��������Y���~�����Ӗ��Ȃ�
�@�@�@�@���@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł͂Ȃ��t�H�[�T�[�Y�̏��A�|�����Y�ƃZ�b�g�Ŏg�@�@���̂��{���Ǝv���܂��B
�@�S�������ăz�{��Ƃ���ł��B
�@�J�����V�X�e���ɂ�645�V�X�e�������邵�A���̈����Q�V�X�e���i���������ȁI�j�Ƃ����ɏ��V�X�e���������đI�����͎��ɗl�X�B
�@����Ȓ��ɂ����āA�ȑO�ɂ������܂������ǁA���̓I�����p�X���D���Ȃ�ł��B
�@�����ۛ��Ɛ\���܂��傤�����̐̍��ƂȂ��Ă�30���N�O���I�I�����p�X�͈��t�J������M�V�X�e���ƌď̂��č\�z���Ă���܂����B
���������ǂ����炩�C�`���������t���āi�C�`�������t���͊m�����C�J���������ȁB�����V���������킵���L��������܂��jM�̓��ɁuO�v�̊���t���āuOM�V�X�e���v�Ƃ����B
�C�`�������t�����J�������[�J�[�͂��̓����̓J�������[�J�[�Ƃ��Đ��E�Ɋ����鉟����������ʑ��݂��������߂ɃI�����p�X�͎����r���Ă��]�܂��܂ꂽ��ł��傤�˂��B���͂���ȕςȊ����邱�ƂȂ����낤�Ǝv������ł����ǂˁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@
�����ԍ��F13549885
![]() 0�_
0�_
�������̑���
����ƑO�ɂ������܂�������ǁA���t�J�����̎O�p�����������ɂȂ�Ƃ��C�ɓ���Ȃ��B
�@�Ȃ̂ŃI�����p�X�y��FT���o���Ƃ��ɂ͂ɂ�܂肵�Ĕ���������ł��B
�@���N�OE-330�Ƃ����O�p�����̂Ȃ������J�����Ĕ���o���ꂽ�Ƃ��̓J�����G���߂ăj���j����������ł����B
�������������̓J�����ǂ���ł͂Ȃ������̂Ŕ����܂ł͎���Ȃ������̂ł����B
���[���A�I�����p�X��E-330�̌�p�@���o���Ă܂���ˁB
���̂Ȃ̂��H���̃V�X�e���W�����Ă�����ʔ��������낤�ɂƎv���̂ł��B
�����Ƃ����̒��͎O�p�������Ȃ��ƈ��t�J�����ł͂Ȃ��Ƃ��������������Ă��ꂪ���߂ɔ���Ȃ�������ł��傤���˂��B
�@�\��ꡂ��ɕ��G��������Ȃ���ׂ���Ȃ���ȁB
E-330�͎������肵�߂����߈��������Ă�̂����E�E�E�E�E�I�H�I
�Ȃ̂�E-P3���o���̂��@��ɂ������낻�딃���A���Ȃ��I�Ǝv��������B
E-P3�̃t�H���������ɗǂ��B
�قǂ悢�F�C����������B
�f�J�����Y���ďグ�ĕ��ʼn����C���ɂ����Ȃ��Ă��܂��B
����➑̂ɍ����������f�J�����Y���o���Ȃ����ȁ[�E�E�E�E�E(^0^)
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�~���[���X��➑̂�800mF8.0�~���[�����Y�𒅂������Ĉ���ɍ\��Ȃ��ł���I�Ȃ�Ƃ��~���N���Ȏ�������܂��I�H�I
�����_���ĎO�r���ĂĂ��m�͂��[��ԃf�J�����Y�g���Ă܂��B�J�����{�̂͑S�������������܂��B
�����I�ƁA�������p���t�H�[�J�X�̏��^�����Y�����Ď�����ăC�C�Ǝv���Ă܂��B
���^�ɍS��̂ł�����C�J�̒����������Y������Ζʔ����낤�ƁE�E�E
�Ⴆ�A�w�N�g�[��50mmF2.5 - L�}�E���g�B�������B3�Q6���B�G���}�[50mmF3.5�ɂ悭�����O�ς���������������O�ʂ��傫�����E�B�L�y�f�B�A������������Ă���(^0^)
���C�J��Q�������E�E�E30���N�O�̍��������ɐ��炳��ƁE�E�E�E�E�E�E(^0^)
�ʔ����Ă₪�Ĕ߂����E�E�E�ƂȂ��Ă͌����q������܂��ʂ��B
APS-C�t�H�[�}�b�g�ł��낤�ƁA35mm�t�H�[�}�b�g�ł��낤�ƃ{�f�B�����僌���Y���f�J�N�Ȃ邱�Ƃ͑S�������ĂȂ��̂ł�����ˁB
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y➑̂Ƀf�J�����Y�����邱�Ƃɂ͑S�������Ĉ�a���������Ă܂���B
�����Y�������o����̂����炠������O�ł���I
��̐��E�ł����́A�F�X�Ȋy���ݕ�������B����ŃC�C����[�Ȃ��́B
�����[���ł����A�I�����p�X��4/3�V�X�e���Am4/3�V�X�e���̏����̎p���ǂ��l���Ă���̂ł��傤���B
��O�Ȏs�ꌴ���������܂�����˂��B�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��B
�܂�����������āE�E�E�E�Ȃ�ĂȂ���ł��傤�˂��B�I�C�I�C���ނ�B
��ɂ͂��낢��ȍ₪����A�^�t�́u�܂����v�����̈�A�Ƃ̖�����f�����̂͂ǂ���̌�m�ł������E�E�E(^0^)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�����p�X������Ă˂��`�`�`�`�`
���������`�`�`�`�`�`��
�Ƃ͂����A���o�I�ȑ������ƈ���Č����I�Ȗ��ɗ����Ď��ɐF�X�Ȃ��ӌ����A���ɂ͌��H�}�����ĉ�����Ă�����������F�l�̃A�v���[�`�Ɋ��S���A�܂��S���犴�Ӑ\���グ�܂��B
�^�}�l�M�{�P���̃`���g���̉ۑ肾�̂ƃe�[�}���L�����Ă܂�����Ǒ�ςɖʔ����L�v�ł��B
��̉ۑ肩��l�X�ȃA�v���[�`���J�����Ă��邱�Ƒ�ϊ������ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃t�H�[�����ɖ��I�I�I�I�I
P.S.
�@�ԈႢ������܂����炲�w�E�̏�������Ă��������B
�����ԍ��F13549894
![]() 0�_
0�_
ginganohikari����
�I�����p�X�t�H�[�T�[�Y���I�����p�X�}�C�N���t�H�[�T�[�Y
�I�����p�X�t�H�[�T�[�Y���p�i�\�j�b�N�t�H�[�T�[�Y
�����Y�����i�ˁ[�E�E�E
�����ԍ��F13550121
![]() 0�_
0�_
nightbear����@
�@�Ȃ߂Ɍ��Ă܂��`�`�`�`�`
�@
�@�@�@�ł����̒��z
�@�������͍D���ł���
�@�@�@�@�@�@�@(^0^)(^0^)2525
�����ԍ��F13550240
![]() 0�_
0�_
ginganohikari����
�������ɁI
�Ł`�X�����Y���ɂȂ��Ă�̂������݂����₵�ȁB
�����ԍ��F13550269
![]() 0�_
0�_
ginganohikari����
������ƑO�ɂ������܂�������ǁA���t�J�����̎O�p�����������ɂȂ�Ƃ��C�ɓ���Ȃ��B
�@�Ȃ̂ŃI�����p�X�y��FT���o���Ƃ��ɂ͂ɂ�܂肵�Ĕ���������ł��B
�@���N�OE-330�Ƃ����O�p�����̂Ȃ������J�����Ĕ���o���ꂽ�Ƃ��̓J�����G���߂ăj���j����������ł����B
�������������̓J�����ǂ���ł͂Ȃ������̂Ŕ����܂ł͎���Ȃ������̂ł����B
���ԈႢ������܂����炲�w�E�̏�������Ă��������B
�O�ɂ��q�����܂�������ǁA���̂Ƃ��̓X���[���܂������A�Q�x�ڂȂ̂ŁE�E�E
�Ȃ��A�����͂ł��Ȃ��̂ŁA�w�E�̂݁i�j
�y�� FT �̑O�Ƀy�� F ���o�Ă��܂����AE-330 �̑O�� E-300 ���o�Ă��܂��B
�u�y�� FT ���o���Ƃ��ɂ͂ɂ�܂�v�ŁA�uE-330 ������o���ꂽ�Ƃ��̓j���j���v�ł́A�P���ジ�Y���Ă܂��ˁB
���݂ɁA���́AM-1�A�y�� F�AE-300 �̉�����w�����܂����B
�Ȃ��AE-P1 �̃f�U�C�����C�ɓ���܂������AEVF �Ȃ��ł͎��̎B�e�X�^�C���ɂȂ��܂Ȃ����A�uEVF ����������@����o���v���Ƃ́A�G���̑Βk�L���ȂǂŔ����Ă����̂ŁAE-P2 �̔�����҂��܂����B
�@�����ł́AE-5 �Ƃ̂Q��Ԑ��̏ꍇ�ł��A�o�Ԃ� E-P2 �̕������|�I�ɑ����ł��B
�����ԍ��F13550366
![]() 4�_
4�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
>������Ă��܂���
>�l�͎����Ŏg���Ȃ���_�@�ŕ]�����܂�
���ꂾ���l�K�e�B�u�Ȕ��������Ă����Ȃ���
�����͉��_�@�ŕ]�����Ă��邩��������ȂƂ́A�܂����������ȁB
>�����炱�̂e�s�������\��ł�
�����߂ɂǂ����I
�I�X�X���ł��I
>�ł����ʂɏ��^�y�ʉ��ł��Ȃ��}�E���g�͂e�s�ȊO�ɂȂ���Ȃ����ȁH
�Ȃ��ł����H
>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���P�^�S�Ȃ̂ɂT����������Ƃ����ς��Ȃ��c
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̒Z�ӂ�35mm�t���T�C�Y���11mm�Z����������A���[�p�X�E�ԊO�J�b�g�^�z���E�S�~���SSW�t�B���^�[�����Ă��t�����W�o�b�N��5mm�Z�k�o�����̂ł��ˁB�v�Z�ǂ���B
�t�Ɍ����A�t�����W�o�b�N�ɗ]�T�̖���EF�}�E���g�ł́A�f�W�^�����ɂ���ĕK�v�ɂȂ����t�B���^�[�̓���ꏊ�ɂ����Ƃ���J���Ă���͂��ł��B
����ɁA�����Y�������J�����̓t�����W�o�b�N�ʼn��s�������̐��@�������܂����A����ȊO�̓t�B�����J������莩�R�������܂��B4/3���������^�y�ʉ��ł��Ȃ��Ƃ�������闝�R���킩��܂���B
2007�N��E-410�̑傫���́A129.5×91×53mm�i��×����×���s�j�@��375g
��������Nikon D40�ł� 126×94×64mm�i��×����×���s�j ��475g
���Ȃ���EOS Kiss Digital X�ł́A126.5×94.2×65mm�i��×����×���s�j�@��510g
�ȏ�̂悤�ɁA4/3��E-410�̉��s���͑��̂��̂��10mm�ȏ㉜�s�����Z���ł��ˁB�d����100g�ȏ���y�ʂł��B�Z���T�[�T�C�Y�Ȃ�ɏ��^�y�ʉ�����Ă���ƌ�����̂ł́H
�����Y���݂��ƁA�����ƍ����L����ł��傤�B�����́A�{�f�B�̍����i�t�@�C���_�[�ȊO�̌��̕����j�Ƃ̃o�����X�ł��ˁB
�t�����W�o�b�N���Z��Kiss�́A�Ȃ���F�}�E���g��D40�������s���������ł��B
�Ƃ͂����A���@�̍��͌덷���x�ł��傤�B
�ǂ̃��[�J�[���������炢�撣���ď��^�y�ʉ����Ă��܂��B
>�t�����W�o�b�N���P�W�����Ȃ̂͂ނ��돫���掿��Nj������ŗL���ɂȂ�ł��傤��
>�e���Z���̖�肪�������ꂽ�Ƃ��ɂ͑Ώی`�őf���Ȑv�̏��^�y�ʂȍL�p�����Y�����Ղ�����
���x�������Ă��܂����A�t�����W�o�b�N�̐��@�͊W�Ȃ��ł��B
�~���[���X�ł́A�t�����W�o�b�N�����������Ă������Y�̈ʒu�����i�����j�ɃZ�b�g������ނ��Ƃł��B
���̂Ԃ�A�}�E���g�O�̋������Z���Ȃ�܂��B
>�d�}�E���g�̓t���T�C�Y�ɂ��Ή��ł���̂�
>�قڍ��̃T�C�Y�Ńt���T�C�Y�����Ă��܂��Ƃ����̂͋��ٓI�ł�
�{�f�B�͏���������ł��傤���A�����Y�͑傫���ł��傤�ˁB
���܂菬�^�y�ʂɊ��҂��Ȃ����������Ǝv���܂���B
���ƂŁu�����Y���������Ȃ��I�v�ƕs���Ɏv��Ȃ����߂ɂ��B
ginganohikari����@
����ɂ��́B
�߂ɃY���Y���ȓW�J�A�܂��Ƃɐ\�������܂���B
�����ԍ��F13550369
![]() 9�_
9�_
���l�K�e�B�u�Ȕ���
�l�K�e�B�u�ł͂Ȃ��ł���
���ʂɎ��s���������͂��Ă邾���ł�
���s�̕��͂��������̃|�W�e�B�u�ɂȂ���킯�ł�
��2007�N��E-410�̑傫���́A129.5×91×53mm�i��×����×���s�j�@��375g
����������Nikon D40�ł� 126×94×64mm�i��×����×���s�j ��475g
�����Ȃ���EOS Kiss Digital X�ł́A126.5×94.2×65mm�i��×����×���s�j�@��510g
����Ńt�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ȃ݂ɏ������Ɗ�����̂Ȃ炻��ł����Ǝv���܂���
���͂܂����������͎v��Ȃ��Ƃ��������ł�
���̕����͂�����s���Ă����s���̂͂Ȃ��ɂ����Ȃ�܂���
�����x�������Ă��܂����A�t�����W�o�b�N�̐��@�͊W�Ȃ��ł��B
���̂Ƃ��肾����
�t�����W�o�b�N���Z���ق����u����v�ł͂Ȃ��u���₷���v�Ə����Ă���̂ł�
�ɒ[�ȃ����Y�ł͂e�}�E���g�p�̃~���[�A�b�v���Ďg��
�~���[�{�b�N�X���Ɏv����������荞�`�̃����Y������܂��������
�ł���ʂ��t�����W�o�b�N�ʂ��˂��o���Ă���ƌ�ʂ����t���Ղ��Ƃ�������
���̃����Y�ł͂��܂�݂����Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂�
������t�����W�o�b�N�͒Z���ق������₷���̂ł�
�����ԍ��F13550400
![]() 2�_
2�_
Tranquility�@����
�@�@���������M�d�Ȃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�@�@�t�H�[�������Y���Y���ɂȂ�̂͑�ϗǂ����Ƃ��Ǝv���Ă���܂��B
�@�@��̃e�[�}�����؋��̂悤�ɕω����Ă����̂͂��ꂼ��̊y���݂�������傫�ȗv�f�ƍl���܂��B
�@�@�ω����邱�Ƃɂ���ĕ�����Ȃ������֘A��������������o����Ă���B
�@�@������Ă�͂�ō��̃A�v���[�`�Ǝv���܂��B
�@�@������́A�����Ŏ����̈ӌ����m���ɓ`���邱�Ƃ̓�����䂪���ƂƂ��Ċ����Ă܂��B
�@�@��c���J���āA�ǂ����Ă��̗l�ȉ��߁A�������o����̂��낤���H�@���b���������邱�Ƃ�����܂����A���̎�̉����ɂ͂�������G���������������Ԃ��|���Ȃ��Ɩ����Ȃ��Ƃ������ł��B
�@�@�Ȃ̂ŁA����ł�����ł��R�~���j�P�[�g���Ă������Ŏ����Ǝ��ʂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B
�@�@�@����̗l�X�ȓW�J���y���݂ɂ��Ă���܂��B
�����ԍ��F13550435
![]() 1�_
1�_
���łɌ����Ȃ��
�c�S�O���o�����_�ł̂e�s�͂d�|�T�O�O�ł�
�d�|�T�O�O�@�P�Q�X�D�T�X�S�D�T�U�U�@�S�R�T��
�c�S�O�@�@�@�P�Q�U�X�S�U�S�@�S�V�T��
�c�S�O�Ɉꎞ���S�s���Ă���
���̖�T������ɂd�|�S�P�O�łȂ�Ƃ������ԏサ�����ĂƂ��ł���
(*´��`)�m
�����ԍ��F13550436
![]() 2�_
2�_
>�ł���ʂ��t�����W�o�b�N�ʂ��˂��o���Ă���ƌ�ʂ����t���Ղ��Ƃ�������
>���̃����Y�ł͂��܂�݂����Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂�
>������t�����W�o�b�N�͒Z���ق������₷���̂ł�
�K�[�h��������������̂��Ƃł��B���g�Ń����Y�ʂ�ی삷��悤�ɐv����̂����ʂł��B
������ł����̂悤�ȗ�͂���܂��B
�����A���t�p�ł͌��ɐL���Ȃ��̂ŁA���̂悤�ȃ����Y�͏��Ȃ��ł��ˁB
�u���₷���v�ł́A�ǂ�����ꏏ�ł��傤�B
>�c�S�O�Ɉꎞ���S�s���Ă���
>���̖�T������ɂd�|�S�P�O�łȂ�Ƃ������ԏサ�����ĂƂ��ł���
�����ł����H
�킸��5�����ŐV�@�킪����Ǝv���܂��H
D50�@2005�N06��29�������@133×102×76mm�@��540g
�@�@�@�@��
���̊Ԗ�T����
�@�@�@�@��
E-500�@2005�N11��11�������@129.5×94.5×66mm�@��435g
�@�@�@�@��
���̊Ԗ�13����
�@�@�@�@��
D40�@2006�N12��01�������@126×94×64mm�@��475g�@
�@�@�@�@��
���̊Ԗ�T����
�@�@�@�@��
E-410�@2007�N04��21�������@129.5×91×53mm�@��375g
�����ԍ��F13550543
![]() 8�_
8�_
���K�[�h��������������̂��Ƃł�
�Ԃ����Ƃ��ɃK�[�h���Ԃ���Ƃ��ƃ}�E���g�ʂ��Ԃ���Ƃ��łǂ������L���H
�K�[�h�����Ȃ��Ă��������ł����₷���Ƃ�����Ǝv���܂����H
���ʂȃp�[�c�Ȃ̂ł�����
�P���ɃK�[�h������������ŏI���͂Ȃ��ł͂Ȃ��ł���
���Ⴂ���Ă���悤�ł����l�e�s���t�����W�o�b�N��������ƒ������Ƃ���������ł͂Ȃ��ł���H
�l�e�s�͋K�i�͂����̂����炪�����������ł���
���킸��5�����ŐV�@�킪����Ǝv���܂��H
�ł���킯�Ȃ��ł��傗����
�N���c�S�O�ɑR���Ăd�|�S�P�O���J�������Ƃ����܂������H
(*´��`)�m
�����ԍ��F13550573
![]() 2�_
2�_
>���ʂɎ��s���������͂��Ă邾���ł�
>���s�̕��͂��������̃|�W�e�B�u�ɂȂ���킯�ł�
����͌��_�@�̕]�����̂��̂ł��B
���i�̎��s�͂��ď����ɂȂ���Ƃ������Ƃ́A�J��������鑤�̕���������ł����H
������������A���Д[���o���鏬�^�y�ʋ@������Ă������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13550578
![]() 7�_
7�_
>�Ԃ����Ƃ��ɃK�[�h���Ԃ���Ƃ��ƃ}�E���g�ʂ��Ԃ���Ƃ��łǂ������L���H
�K�[�h���L���ł��ˁB
�}�E���g�ʂ��ƃ����Y�̒E���ɕs����o��\��������܂��B
�܂��A�s���g�������\��������܂��l�B
�}�E���g���K�[�h�̑���ɂ��Ă͂����܂���B
>�N���c�S�O�ɑR���Ăd�|�S�P�O���J�������Ƃ����܂������H
�u�c�S�O�Ɉꎞ���S�s���Ă���
���̖�T������ɂd�|�S�P�O�łȂ�Ƃ������ԏサ�����ĂƂ��ł���v
��r����Ώۂ��Y���Ă���Ƃ������ł��B
�����ԍ��F13550608
![]() 10�_
10�_
>���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
���ł��e�s�����s�������R�̑傫�Ȉ�͏��^�y�ʉ����s�\�ȕ����ƌ����Ă��邾���ł�
���C�J���T�C�Y�p��24-70mm����F2.8�ł��i��J����14-35mm/F2�ɕC�G���邾���̉𑜓x
����ӌ��ʂ������Ă��Ȃ���������A���\���l������Ώ\�����^�y�ʉ��ł��Ă����
�v���܂����c
CANON��EF�}�E���g�̂܂�24mm��18mm�̎B���f�q���������邾���̃����Y���o����
����Ă�����A�≖EOS����A���̂܂܃f�W�^��EOS�Ɉڍs���Ă�����������܂���
���C�J���T�C�Y�ɂ���������̂��_����������ł��傤�ˁB
�C���[�W�T�[�N��43mm��F2�̃����Y�ɕK�v��22mm�𑫂���65mm�̓��a���m�ۂ����}�E���g
�ɂ��Ă��ꂽ��A���C�J���T�C�Y�ł��ǂ�������ł����ǂˁB
���d�}�E���g�̓t���T�C�Y�ɂ��Ή��ł���̂�
SONY�̋Z�p�҂������������Ă���̂ł����H
�t�����W�o�b�N���Z�����Ȃ��Ă��A��ʂ̎��ӂ܂Ń}�g���ȕ`�ʂɂ���ɂ́A����Ȃ��
�}�E���g���a���K�v�ł�����A43mm�̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[����̂͂��Ȃ荢���
���傤�ˁB
�߂̌��ł�����ł���悤�ɂł����Ƃ��Ă��A�߂̌����ƃR�T�C��4�摥(cosine fourth law)
�ɂ���āA�B���f�q��̏Ɠx�͒Ⴍ�Ȃ�܂�����A��ʑ̑��ɓ˂��o�����傫�ȉ������Y
�Ŏ߂���̓��˓��i��ʑ̑����猩���i��̑��j��傫�����āA�����ł����ӌ�����
�������Ȃ�����A�g�C�����Y�̂悤�Ȏʂ�ɂȂ��Ă��܂��A�g���ɂ����Ȃ�ł��傤�ˁB
�i���L�p�����Y��O�̕����猩��ƍi��̌`���悭������܂����ǁA�߂ɂ��Ă��i�肪
�^�����������̕��������Ă���悤�Ɍ����A�X�ɐ^���ʂ��c��ł͂��Ă��傫��������
�͂��ł��B�j
�X�ɁA���[�p�X�t�B���^�[��ԊO���J�b�g�t�B���^�[�⎇�O���J�b�g�t�B���^�[���߂�
�����ʂ�ƁA�����ɒʂ���t�B���^�[��ʉ߂��鋗���������Ȃ�܂�����A���S�Ǝ���
�Ńt�B���^�[�̌������ς���Ă��܂����ƂɂȂ�A��肪�N���܂��ˁB
�t�B�����ƎB���f�q�ł͊����̏������S���Ⴂ�܂����A�t�B�������V���h�[�����S����
�����̂ɑ��A�B���f�q�ł͍��Ԃꂵ�Ă��܂��X��������܂�����A���ɂȂ��
�v���܂��B
���̕��ʐ����t�B���^�[�̋��ܗ����l�����Ȃ�������Ȃ��ȂǁA�t�B��������̐v��
�ʗp���Ȃ��ł��B
CONTAX�̃f�W�^�����t�̂悤�Ƀ��C�J���T�C�Y�ł�600����f�Ƃ����̂Ȃ�A�����Y
�ɗv������鐫�\�͂���قǍ����Ȃ��̂ŁA�g���Ȃ����Ƃ��Ȃ��ł��傤���ǂˁB
�������A���^�y�ʉ�����Ȃ�~���[���X�����Ȃ����Ċ����ł���
�����T�C�Y�̎B���f�q�̃J�����{�f�B�̏ꍇ�Ƃ����Ӗ��ł��傤���ǁA�{���ɏ��^�y�ʉ�
����ɂ́A�����Y�����^�y�ʉ����Ȃ���Ζ��Ӗ��Ȃ̂ŁA�B���f�q�����������邵���Ȃ�
�ł���B
nikon�̂P��4/3��2/3�̒��Ԃ̃T�C�Y�ł����ǁA�����Y�̐v�Ɋւ��Ă�Pentax�̂p���l
���Ȃ�L�b�`���Ɛv����Ă��܂�����A�\�R�\�R�̉掿�͓�����͂��ł��B
�����Ƃ��A�����Y���E�ɉƊO��Ă��܂��Ƃ����e�}�E���g�̋t�l�W�P���Ă��܂���
����̂ŁA�����C�ɂ��Ȃ�܂��c
�����ԍ��F13550620
![]() 7�_
7�_
���K�[�h���L���ł��ˁB
�����K�[�h���Č�ʂɕt����^�C�v�łȂ���̂��Ƃł����H
����Ȃ�}�E���g���̓K�[�h���L���ł���
����
�l�͌�ʂɕt����K�[�h�ōl���Ă܂���
�ł��d���Ȃ邯�ǂˁi�j
����r����Ώۂ��Y���Ă���Ƃ������ł��B
����͈Ӗ��s��
�J�����ł��ꎞ���A�e�s�Ƃ��Ă͑傫���ŋt�]���ꂽ�̂͂܂�����Ȃ�����
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ŗL���Ȃe�s�͈ꎞ���Ƃ͂����t�]���ꂽ�̂��c�O
�l�e�s���m�d�w�ɋt�]���ꂽ��
���j���J��Ԃ���Ă���c
�܂�����͋K�i�̖��ł͂Ȃ����p�i���{�C�ɂȂ��������S���Ă݂Ă��邪��
�����ԍ��F13550633
![]() 2�_
2�_
ginganohikari����
�N�X��������ȁ[�E�E�E�|�E�E�E
�����ԍ��F13550647
![]() 0�_
0�_
�����\���l������Ώ\�����^�y�ʉ��ł��Ă����
�v���܂����c
�����v���܂���
���̈Ӗ��ł͏��^�y�ʂł��傤��
��SONY�̋Z�p�҂������������Ă���̂ł����H
�����ȋL�҉�Ƃ��łł͂Ȃ��ł��������͂��Ă܂���
�������T�C�Y�̎B���f�q�̃J�����{�f�B�̏ꍇ�Ƃ����Ӗ��ł��傤���ǁA�{���ɏ��^�y�ʉ�
����ɂ́A�����Y�����^�y�ʉ����Ȃ���Ζ��Ӗ��Ȃ̂ŁA�B���f�q�����������邵���Ȃ�
�ł���B
���̒ʂ�ł���
�~���[���X�͌��\�������Ă܂������̗��_�͂P��t���{�f�B���������y������̂�
�{�f�B�̌`����v�̎��R�x�������̂Ŗ��ʂȂ�������Ȃ��`�ɂ܂Ƃ߂�����Ă����ł���
�i���F�܂��d�u�e�����Ŗ��ʂȂ�������Ȃ��J�����͏o�Ă܂��ǂˁj
�����Y�Ɋւ��Ă͂ނ���傫���d���Ȃ�ꍇ������܂���
�e���Z���̖����Ȃ�Ƃ����Ȃ��ƍL�p�����Y�ł��珬�^�����ɂ����c
�܂��ߓn���̃J���������ǂ����������Ɋy���݂ł��ˁ�
�܂��l�͈ꐶ�P��t�����C���J�������ȂƎv���Ă܂����c
�d�u�e�̌��_����������邩�ǂ����ł��˂��i�j
(*´��`)�m
�����ԍ��F13550682
![]() 1�_
1�_
�����i�܂ȂĂ��j����A�����́B
�^�}�l�M���ɂ����悤�Ȗ͗l�̃{�P�́AF1.4��薾�邢�ʃ����Y�ɑ���
������悤�ł����ǁA�j���[�g�������O��蕡�G�Ȋ��e�̂悤�ł�����A�S��
�̔ʃ����Y���̗p���������Y�ɏo��킯�ł͂Ȃ��ł����A�B�e������Y�[��
�����Y�Ȃ�œ_�����ɂ���Ă��o����o�Ȃ�������ł�����A�ʂɃ`�F�b�N����
�����Ȃ��ł���ˁB
���Ɩ��@����sony��PL�}�E���g�̃r�f�I���o���Ă��Ǝv���܂��B
F35��F3�̎����낤�Ǝv���܂����ǁAF35��3000���~�߂�����̂ɑ��āAF3��
�����Y3�{�t����2,205,000�~��RED ONE���݂ɂ��������߈Ղ��l�i�ݒ�ł�����
CCD��CMOS�̍��͂���܂����ǁAF35�̃����^���オ��30���~/���Ƃ��������l��
����ƁA�f����B��Ȃ甃�����Ⴆ���Đl������ł��傤�ˁB
NEX����NEX-FS100����60���~�ł�����A�Q����F35�������z�Ƃ����Ӗ��ł��A
�v�����[�V�����r�f�I��b�l���B��ɂ͂����������Ƃ͎v���܂����ǁA���̃����Y
���Ǝg�����ɂȂ�Ȃ��ł��ˁB
F3�p��35/50/85mm��T2.0�̒P�œ_PL�����Y3�{�������ʔ��肷��Ƃ�����������
�v���܂����ǁA��͂�18mm�A25mm�͗~�����ł�����A�p�i�\�j�b�N�ɑR����Ӗ�
�ł�18-50mm/F2�Ƃ�35-100mm/F2���x�̖��邢�Y�[����A18-85mm/F2.8���炢��
��r�I���邢�T�{�Y�[���͏o���ׂ��ł��傤�ˁB
18-200mm/F3.5-6.3�͖]���[�ŁA���߂�F4�͗~�����ł��ˁB
10-100mm/F2.8-3.5�Ƃ��APL�����Y���ƒ�ԂƂ��������Y�������ƂˁB
ginganohikari����A�����́B
7-14mm/F4���A9-18mm/F4.0�`5.6���A25mm/F1.4���A14-42mm/F3.5-5.6��4/3�p��
�����Y�̕����Am4/3�p�̃����Y���ǂ��݂����ł�����A����������ƕ��Q��
�N���邱�Ƃ��l������K�v������悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F13550715
![]() 7�_
7�_
������Ɩʔ��������̂Œ��ׂĂ݂܂����B
E-410�@2007�N04��21�������@129.5×91×53mm�@��375g
�@�@�@�@��
���̊Ԗ�48�����i�S�N�j
�@�@�@�@��
KissX50�@2011�N03��29���@129.9×99.7×77.9mm�@��450g
D5100�@�@2011�N04��21���@128×97×79mm�@��510g
�f�W�^�����t�̏��^�y�ʉ��́A���łɌ��E�܂ŗ��Ă���̂�������܂���B
�V�@�\�����ڂ���Ă���̂�����A���^���̓w�͂͑����Ă���̂ł��傤����ǁB
���̐��@��4/3�V�^�G���g���[�@���o����A���ł��\���ȋ����͂͂��肻���ł��ˁB
�܂��ANikon�ECanon�̗��@�Ƃ��A0.1mm����1�`2mm�ő����܂����Ȃ��悤�Ȑ��@�ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�����[���ł��B����قǐ��@���C�ɂ��郆�[�U�[�������Ƃ������ƂȂ�ł��傤�B
�킸�����~���ŏ��������̕��������̌���ꂿ�Ⴄ����A���[�J�[����ςł��ˁB
���ۂɎg�p���Ă���1�`2mm�̈Ⴂ���C�ɂȂ�l���A�{���ɂ���̂ł��傤���H
ginganohikari����@
�u���邢�����Y���~�����v�X���Ȃ̂ɁA
����Ɏ߂ɃY���Y���ȓW�J�A�܂��Ƃɐ\�������܂���B
�|�����_�n����@
��͂�M4/3�p�����Y�́A�t�H�[�J�X���x�̂��߂Ƀt�H�[�J�V���O�����Y���y�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��낪������ł��ˁB
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6�̏����II R�̉𑜂��r���܂������A���̂��̂ł́A�����̕������Ӊ掿�ŏ����Ă��܂����B
AF���\����̕���p��������܂���ˁB���ꂼ��1�{������r���Ă��܂���̂ŁA�̍��̉\�������R����܂����ǁB
�����ԍ��F13552207
![]() 10�_
10�_
���܂˂��ڂ��̓����Y�̌@�퍭�����^�̌@�퍭���Ɨ������Ă��܂��B
�V���v���ȍ\���̃����Y�ł��ł܂��BEF135/2.8SF�Ƃ��A����ɁB
�����m�����ł͔ʃ����Y���g�������̂͑����͂���ł܂��B
�R���f�W�������ł��B
�Ȃ�Ō@�퍭�����Ȃ��̂����悭�킩��Ȃ��ł��܂��B
�Ђ���Ƃ��ďo�Ȃ��Z�p�Ƃ������Y�Ƃ������m��Ȃ�������������Ȃ���
�v���ĕ����Ă݂܂����B�ʂɃ`�F�b�N���ĒT���Ă܂��B
�����ԍ��F13552372
![]() 1�_
1�_
�����ӂ�ׂȂƁ`�邳��
��d�}�E���g�̓t���T�C�Y�ɂ��Ή��ł���̂�
�������ȋL�҉�Ƃ��łł͂Ȃ��ł��������͂��Ă܂���
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100929_396897.html
���i���ۂɏ��i�����邩�ǂ����͕ʂƂ��āA�Z�p�I�ɂ́j
��NEX�ɂ��t���T�C�Y�Z���T�[�𓋍ڂ��邱�Ƃ͉\�ł�����B
�d�}�E���g�Ƃ͌����Ă܂���ANEX�Ƀt���T�C�Y�Z���T�[���ڂ���ׂɁA�V����
�}�E���g���l������Ƃ������ł��傤���ˁH
�d�}�E���g�̂̌��a58.9mm�A�t�����W�o�b�N18mm�ƃE�B�L�y�f�B�A�ɂ��ڂ��Ă��܂����ǁA
���ۂ̓��a��46.1mm�����Ȃ��ł�����A��43mm�̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[�����邱�Ƃ�
���C�J�l�X�̂悤�ɃI���`�b�v�}�C�N�������Y���V�t�g�����Ȃ��Ǝ��p�I�ł͂Ȃ��ł���
�������̂悤�Ȑv�ɂ��Ă��܂��ƁA���ʂɐv����e���Z���g���b�N���̎����l��
���Ȃ��Ă��ǂ��͂��̖]�������Y�������ăe���Z���g���b�N����������������ɐv��
�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ȃ�܂�����A�s�����ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA�d�e�}�E���g�̓��a�͖�51.2mm�A4/3�}�E���g�̓��a�͖�47.0mm�A�ł����ǁA
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/campaign/ds_ad01/mf_lens_02.html
�茳��E-5�̃}�E���g���m�M�X�ő���������ł́A�o���l�b�g�܂̓����̗L���a�͖�44.3mm
�}�E���g�̊O�a�͖�59.7mm�ŁA�̏��L���Ă����≖EOS�̃o���l�b�g�܂̓����̗L���a��
4/3����5mm�傫���������x�ł����B
m4/3�̏ꍇ�A�}�E���g�̓��a��4/3����6mm�������Ȃ��Ă��邻���ł�����A��41mm�ɂȂ�
�t�����W�o�b�N��20mm���l�����Ă���22mm�̃C���[�W�T�[�N���ɑ��āA�\���ȑ傫������
������Ǝv���܂��B
�d�}�E���g�̏ꍇ�A���Ƃ����a��58.9mm�ł������Ƃ��Ă��A���C�J���T�C�Y�̃C���[�W
�T�[�N���ɑ��Ă�����16mm�̗]�T���������A19mm�̗]�T������m4/3�������������Ȃ�
�킯�ŁA�{�f�B�[�̍���������25mm�͍������Ȃ��ƃ��C�J���T�C�Y�ɑΉ������邱�Ƃ�
�ł��Ȃ��ł��ˁB
Tranquility����A�����́B
�t�o�����摜��4/3�p��14-42mm/F3.5-5.6�ŎB�e�������̂ł����A�L�b�g�����Y�ł��D�G
���Ɗ����Ă��܂��B���������ʐ^�Ȃ�m4/3�ł��B���Ǝv���܂����A�z�[���h���̈Ⴂ
���炩�A14mm��1/2�b�̎莝���B�e�ł̎�Ԃ���4/3�̕����ǂ����������܂��B
�ЕG�𗧂ĂĂ��Ⴊ�̐��ł̎B�e�ł����A���ɂ͂܂�PEN�̃{�f�B�[���Ǝ�Ԃ�
����肭���p�ł��Ȃ��C�����Ă��܂��BE-5��14mm�Ȃ�2�b���炢�܂ł͉��Ƃ��g����R�}
��10%��Ƃ͂�������܂��̂ŁA�O�r�Ȃǎ������������Ȃ���O�ł̎B�e�ɂ͏d�܂���
���U���J�����Ƀs�b�^����PEN�̎�Ԃ����C�}�C�`�Ƃ����͍̂���܂���ˁB
���̎�̎B�e�̎��́A���邢�����Y�͕s�v�Ȃ̂ŁA�X���̎�|�Ƃ̓Y���܂���ł��ˁB
�����ԍ��F13552942
![]() 6�_
6�_
���J���N����@
�@���w�E���肪�Ƃ��������܂��E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E(^0^)
�@�I�����p�X�y��F�ɂ��Ă͒m���Ă܂����B
�@������F�ɂ��Ă͂ǂ����r��̂悤�ȋC�����Č��������̂ł����B
�@���̌����ς�Ƃ�����FT���o�Ă�����u�����v�Ɣ��f���čw���Ɏ������̂ł����B
�@E-330�̑O��E-300���������̂͒m��܂���ł����B
�@�����ł���˂��I�����Ȃ�330���ԍ��Ƃ��Đݒ肳��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�ˁB
�@
�@��Ƃ���A�ꐢ�ジ��Ă܂����B
�@E-330�Ńj���j�������̂�FT�Ńj���}���������Ƃ��v���o��������ł��B
�@�I�[�I�I�����p�X�������Ă�����[�Ȃ��́A�Ƃ����������I�I�I
�@FT�����������炱��E-330���Ƃ�E-300���J�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƁE�E�E(^0^)2525
�����݂ɁA���́AM-1�A�y�� F�AE-300 �̉�����w�����܂����B
�@�Ȃ��AE-P1 �̃f�U�C�����C�ɓ���܂������AEVF �Ȃ��ł͎��̎B�e�X�^�C���ɂȂ��܂Ȃ����A�uEVF ����������@����o���v���Ƃ́A�G���̑Βk�L���ȂǂŔ����Ă����̂ŁAE-P2 �̔�����҂��܂����B
�@�����ł́AE-5 �Ƃ̂Q��Ԑ��̏ꍇ�ł��A�o�Ԃ� E-P2 �̕������|�I�ɑ����ł��B��
�@���[�ށI���͂ȃI�����p�X�t�@���������������ł��˂��I�S��������ł��B
�|�����_�n����
��7-14mm/F4���A9-18mm/F4.0�`5.6���A25mm/F1.4���A14-42mm/F3.5-5.6��4/3�p�̃����Y�̕����Am4/3�p�̃����Y���ǂ��݂����ł�����A����������ƕ��Q���N���邱�Ƃ��l������K�v������悤�Ɏv���܂��B��
�@���w�E�̂悤�Ȋ������������Ă���܂��B
�@m4/3�@9-18mm�̌�������Ɏ���Ă݂�Ɛ��Ƀ`�[�v�B
�@����ɔ䂵��4/3�@9-18mm��ꡂ��ɐM���x���������Ɏv����B
�@���҂̈Ⴂ�ɂ���MTF�`���[�g���牽���ǂ߂�̂��J�X�^�}�[�Z���^�[�ɖ₢���킹���Ƃ���A
�@��ZUIKO DIGITAL ED9-18mm �� M.ZUIKO DIGITAL ED9�|18mm �̈Ⴂ�ɂ��ā�
�@�@��MTF �`���[�g�̓����Y�̒��S�����ƊO�������̉𑜓x��ǂݎ�邽�߂�
�@�@�w�W�ƂȂ�܂��B
�@�@����MTF �`���[�g ����� M.ZUIKO DIGITAL 9-18mm �̂ق��������Y���S�̉𑜓x���킸���� �D��Ă��邱�ƁAZUIKO DIGITAL 9-18mm �������Y���ӕ��̉𑜓x�Ɏ�D��Ă��邱�Ƃ��ǂݎ��܂����A�ǂ�����傫�ȈႢ�ł͂������܂���B
�@�@�������Ȃ���AM.ZUIKO DIGITAL 9-18�� �̃����Y��MSC�@�\�Ή��̃����Y�ƂȂ�܂��̂� PEN �V���[�Y�Ŏg�p����ۂ�AF����̑��x��É�����ZUIKO DIGITAL 9-18mm�ɔ�חD��Ă���܂��B
�@�@�����Y���\�ɂ��܂��Ă� MTF �ł͔��f�ł��Ȃ��_���������܂��̂ŁA�����܂Ő��\��]������ړx�̂ЂƂƂ��Ă����p���������B��
�@�Ƃ̉����܂����B
�@MTF�`���[�g����ǂݎ��郌���Y���\�͉̒ʂ�Ƃ��Ă����i�̐M���x�ƌ������ϓ_���炷��ƃN�G�X�`������������̂͂܂��ƂɎc�O�ł��B
�@�����������Ƃ���ɂ��I�����p�X��m4/3���ǂ��Ɏ����čs�����Ƃ��Ă���̂�������܂��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜������Ȃ��v�f�ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
Tranquility����@
���u���邢�����Y���~�����v�X���Ȃ̂ɁA
�@����Ɏ߂ɃY���Y���ȓW�J�A�܂��Ƃɐ\�������܂���B��
�@���������Ƃ�ł��������܂���B
�@�l�X�ɓW�J����Ă������Ŗ��邢�����Y�������ȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����ʃ����Y�A�ʃ����Y�Ȃǂ̑f�ނ����p���闝�_�I�w�i���܂߂Ă���q�V�q�V�ƕ������Ă��������ł���ςȎ��n�ł��B
�@�Z�p�������ꂱ���S�������Ŏ��g��ł���l�q�������яオ���Ă��܂�������B
�@�ł͂����Ă����q�l�Q�͐_�l�I���Ƃ��䂪�Ԏ����{�ʂł����炱�̎s��j�[�Y���ǂ������Ăǂ��������čs�����͋Z�p���������ł͔@���Ƃ�����Ƃ��낪����ł��傤�ˁB
�|�����_�n����@
����͂�M4/3�p�����Y�́A�t�H�[�J�X���x�̂��߂Ƀt�H�[�J�V���O�����Y���y�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��낪������ł��ˁB
�@M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6�̏����II R�̉𑜂��r���܂������A���̂��̂ł́A�����̕������Ӊ掿�ŏ����Ă��܂����B
�@AF���\����̕���p��������܂���ˁB���ꂼ��1�{������r���Ă��܂���̂ŁA�̍��̉\�������R����܂����ǁB��
�@AF���\����̕���p�ɂ��ẮA�����������낤�Ȃ��Ǝv���Ă܂����ǁA���W�r��ƍl���ċ߂������Ɋ��҂��܂��傤�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E(^0^)2525
�@����������ς�ǂ����Ă�m4/3������ǂ̗l�ȃV�X�e���ɂ��Ă����̂��m�ɂ��čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł́A�Ƃ��炽�߂Ďv���܂��ˁB
�|�����_�n����@
���t�o�����摜��4/3�p��14-42mm/F3.5-5.6�ŎB�e�������̂ł����A�L�b�g�����Y�ł��D�@�G���Ɗ����Ă��܂��B���������ʐ^�Ȃ�m4/3�ł��B���Ǝv���܂����A�z�[���h���́@�Ⴂ���炩�A14mm��1/2�b�̎莝���B�e�ł̎�Ԃ���4/3�̕����ǂ����������܂��B
�@�ЕG�𗧂ĂĂ��Ⴊ�̐��ł̎B�e�ł����A���ɂ͂܂�PEN�̃{�f�B�[���Ǝ�Ԃ��@������肭���p�ł��Ȃ��C�����Ă��܂��BE-5��14mm�Ȃ�2�b���炢�܂ł͉��Ƃ��g�@����R�}��10%��Ƃ͂�������܂��̂ŁA�O�r�Ȃǎ������������Ȃ���O�ł̎B�e�ɂ͏d�܂������U���J�����Ƀs�b�^����PEN�̎�Ԃ����C�}�C�`�Ƃ����͍̂���܂���ˁB
�@���̎�̎B�e�̎��́A���邢�����Y�͕s�v�Ȃ̂ŁA�X���̎�|�Ƃ̓Y���܂���ł��ˁB��
�@������������Ă͂��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@F3.5�̃����Y��F2.0�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��A�Ƃ�����|�̃��X������܂������B
�@���[�ށIPEN�̎�Ԃ����C�}�C�`�ł������B����܂����ˁB
�@���ꂩ��{�f�B�̃z�[���h���ł����AE-P3�́i���̃V���[�Y���܂߂āj�z�[���h���̓C�}�C�`�ł��B
�@�ł�����͂����ʎd�����Ȃ��Ȃ��Ƃ͎v���Ă܂��B
�@�f�U�C���ɍ��ꍞ��Ńz�[���h���ɍ��ꍞ�߂�悤�ȃJ�����B
�@��ґ���̐��E�ł��傤���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E(^0^)
�����ԍ��F13555020
![]() 0�_
0�_
�|���_�n���̉��L�̓��e
���^�}�l�M���ɂ����悤�Ȗ͗l�̃{�P�́AF1.4��薾�邢�ʃ����Y�ɑ���
��������悤�ł����ǁA�j���[�g�������O��蕡�G�Ȋ��e�̂悤�ł�����A
�Ȃ�т�
�����i�܂ȂĂ��j����
�����܂˂��ڂ��̓����Y�̌@�퍭�����^�̌@�퍭���Ɨ������Ă��܂��B
���V���v���ȍ\���̃����Y�ł��ł܂��BEF135/2.8SF�Ƃ��A����ɁB
�̗��҂̃^�}�l�M�{�P��������͂���́A���܂˂��{�P�����̏o���邩���{�I�ɗ������Ă��Ȃ��Ǝv���܂���B
�܂��A���܂˂��{�P�̐����Ƀj���[�g�������O���o���Ƃ��납�炵�ĊԈႢ�i�j
���ʃ����Y������A�R�q�[�����g���̌��ۘ_�����Ȃ�A�f�l�̐������Ń����Y�̌`����
�ސ��o���邱�Ƃ�����ł��傤���A�����͕����̔g���̌��̏W�܂�ŁA�Ȃ������[�U�[�̂悤��
�R�q�[�����g���ł͂���܂���ˁi�j
�|���_�n���̃{������͂�o���Ƃ��������ł��B
�����������ȂȂł͂���܂����i�j���������Ă�����E�E�E�B
���ꂩ��A�؍퍭����^���Ȃł�����܂����i�j
�܂��B����l�Ƃ��A���̂悭�������Ƌ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA�ԈႢ�����͎w�E���܂�����
�悭�����ׂ��������B
���ꂮ����u�ʃ����Y�v�̌��ł����A�u�ʃ����Y�v�Ƃ͉����ǂ����邽�߂�
�ǂ�Ȍ��w��p�����郌���Y�Ȃ̂��A������x��������Ă͂������ł��傤���B
�ēx�A���`�����Ă����܂����A�|���_�n���̘_�_����́A�p�[�v���t�����W�Ȃǂ�
���ۂɂ��Ă͑S�������o���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����āA���Ƃ����͔̂g�����������A�����͕����̔g���������������m�ł��邱�Ƃ�
���ӏ����Ƃ��ēY���Ă����܂��B
�|���_�n���́A�m�������Ԃ��Ă��܂����A���{�I�ɒt�قȘb�����c�_�o���Ȃ��悤�ł��̂ŁA
�����Y�v�҂Ȃ�тɁA�J�����̃}�E���g���ǂ����Ă��������K�i�ɂ������ȂǁA
���ꂱ�ꌾ���闧��ł͖����ƌ������Ƃ��X�ɕt�������Ă����܂��B
�ƌ�����ŁA���̃v���𖼏���ĊԈႢ���A�L�߂Ȃ��悤�ɋC�����Ă��������B
�����ԍ��F13555650
![]() 1�_
1�_
�����Y�ɂ�����u���v�̌��t���o���ɓ������Ă�
���߂ăt�[���G���w���w��ł���ɂ��Ă��������B
http://www.geocities.jp/eulers_formula/FourierOptics3.html
�łȂ��ƁA�吨�̐l���Ԉ�����m���������ƂɂȂ�܂��B
���̃v���𖼏����́A���Ƃ��炲���ӊ肢�܂��B
�����ԍ��F13555804
![]() 0�_
0�_
ginganohikari����A�����́B
�����āAPEN�̎�u��������Ђ�����Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��ł���B
EOS-1Dmk4��24-105mm/F4��t����ƁA24mm/1/4�b�̕����܂肪�AE-5��14-42mm/F3.5-5.6��t����
�P�b�ŎB���舫���Ȃ��ł����ǁAPEN�̏ꍇ�ACANON�⑼�Ђ��̓}�V�ł��AE-30�AE-5���
��u������ア�Ƃ����̂́A��u����@�\�܂ŃR���p�N�g���ŋ]���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����
������Ƃ��������Ȃ��Ƃ��������ł��B
�I�����p�X�̃{�f�B�[����u����̕����A�p�i�\�j�b�N�̃����Y����u������A���͂ł�����
�ł���A���̃����b�g�������ė~�����Ȃ��ł��ˁB
��f�̉摜��14mm�AF4�ŎB�e���Ă��܂����A���������F2�ŎB�e���Ă��܂��ƁA������14mm�ł�
��Ǖ��̉��܂Ńs��������悤�ɂ���͕̂s�\�ł�����A�i���ĎB�e����̂���Ԃ̎B�e�ł�
�i�肷�������ɂȂ閾�邢�����Y�́A�uF2�̃����Y��F3.5�̃����Y�ɂȂ蓾�Ȃ��v�Ƃ�������
�Ȃ肻���ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA�ȑO�g���Ă���Pentax 67�ŎB�e����ꍇ�́A55mm��F22���炢�܂ōi��Ȃ��ƃs����
���Ȃ��Ȃ��ł����A�莝���B�e�ȂǍl�����Ȃ��V�`���G�[�V�����ł�����A
�ǂȂ����AE-P3�{14-42mm/F3.4-5.6���������̕���14mm�A1/4�`2�b�������Ă݂Ă������������
���Ȃ��ł��傤���B�u����������悤�ɓ_�������ʂ��Ă���ƃx�^�[�ł��B
�����i�܂ȂĂ��j����A�����́B
�����܂˂��ڂ��̓����Y�̌@�퍭�����^�̌@�퍭���Ɨ������Ă��܂��B
�ꕔ�̐l�͂����咣���Ă��܂����A�����Y�����̐l����́A�F�߂��Ă��Ȃ��ł��ˁB
CANON�̐ϑw�^��܌��w�f�q���ƈӐ}�I��[�@�퍭]��t���Ă���킯�ł����ǁA����ɂ����
�u���܂˂��{�P�v���������Ă���Ƃ������́A�ؖ��ł��Ă��܂���B
���܂˂��{�P���n�b�L���l�K��ɋL�^���ꂽ�̂̓m�N�g�j�b�R�[���Ƃ�CANON��50mm/F1.2L
�����肩�炾�Ǝv���܂����A�����̃����Y�v�҂̌����ł͔ʂƋ��ʃ����Y�̌��Ԃ�
�ȗ��I�ɒP���Ȓ�����Ȑ��ő�����̂ł͂Ȃ��A�ʉ������Ȑ��ɂȂ��Ă��܂����߁A���e
���N���Ă���̂ł͂Ƃ������������̂ł����A�����ɒ萔�I�ɂƂ炦����悤�ȃ��x����
�B���Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
���o���r�[�m��
���Ȃ��̈��p���郊���N���s���g�O��Ȃ̂��Ƃ��Ă��C�ɂȂ�̂ł����A�j���[�g�������O��
�������������������F���ł��u����Łv�C�������ۂł��B
http://www.keirinkan.com/kori/kori_physics/kori_physics_1_kaitei/contents/ph-1/4-bu/4-3-4-1.htm
���Ȃ��Ƃ��A�l�K����掆�Ɉ����L�����o��������l�Ȃ�A�����L���@�̏W�������Y��
�Z�b�e�B���O���Ƃ��A�����T�C�Y�p�̃K���X���̃l�K�z���_�[�ŁA�j���[�g�������O����������
���܂��o��������͂��ł����ǁA�������������H�͑S�����@���Ă���݂����ł��ˁB
�����ԍ��F13556532
![]() 6�_
6�_
�|�����_�n����
�������Y�����̐l����́A�F�߂��Ă��Ȃ��ł��ˁB
��鑤�͒P���Ȍ@��Ղł͂Ȃ��Ǝ咣���Ă���̂ł��傤���B
���͂����ς�g�����ŁA�o��������ʃ����Y���g�p���Ă�
�����Y�Ń^�}�l�M�ڂ���������Ǝv���Ă��܂��B
�Z�p�I�ɂ͗����ł��Ă��Ȃ��ł��B�����I���Ǝv�������Ƃ���
�ʃ����Y�ɂ͌@�퍭�������āA�������������̂������
��������������܂����B
���ɐ�������Ȃ�m�肽���ł��B�f�l�I�ɂ͖������������
�Ǝv���Ă���̂ł����A�A�A�����Ȃ���ł����ˁB
�����͂���܂����A�����Y��ʂƂ��ɃS�~������Ɠ_�����{�P
�̒��ɔ��f����ăS�~���ʂ�Ƃ������ۂ��o���I�ɔc�����Ă��܂��B
DO�����Y�̓{�P����Ȃ��ăs���g�̂������_�����̎���ɓ��S�~���
�Ȃł邱�Ƃ�����݂����ł��ˁB
�����ԍ��F13556681
![]() 2�_
2�_
�����i�܂ȂĂ��j����
���Ȃ��̐M���鉼�����^���Ȃ�A�ʂɐϑw�^��܌��w�f�q�̈Ӑ}�I��[�@�퍭]��
�t����A���܂˂��{�P�͏����邱�ƂɂȂ�܂��B
DO�����Y�̏ꍇ�A�s���g�����������P�x�̕����̎���ɓƓ��ȃn�������܂�镾�Q��
������Ƃ������ۂ��m�F����Ă��܂����A�{�P�Ɋւ���Ɠ��ȓ����͍��̂Ƃ���A
�܂��m�F����Ă��܂���B
�������͂���܂����A�����Y��ʂƂ��ɃS�~������Ɠ_�����{�P
���̒��ɔ��f����ăS�~���ʂ�Ƃ������ۂ��o���I�ɔc�����Ă��܂��B
���̌��ۂ̕����A���܂˂��{�P�̌����ɋ߂��悤�ł��B
�����ԍ��F13556744
![]() 0�_
0�_
�|���_�n����
���Ȃ��́A����]�X�ł͂Ȃ��A�v���I�ɋZ�p�I�����̊ԈႢ��Ƃ��ď��A
����ɋC�Â��Ȃ��ł���Ƃ������Ƃł���B
�����Ȃ��̈��p���郊���N���s���g�O��Ȃ̂��Ƃ��Ă��C�ɂȂ�̂ł����A�j���[�g�������O��
���������������������F���ł��u����Łv�C�������ۂł��B
������������������ƌ����ϓ_���̊Ԉ���Ă��܂���B
�������������̂������ς�킩��܂���ˁB
�j���[�g�������O�����܂˂��{�P�Ɗ֘A���ċM����������������A����͌����Ⴂ����
�����Ă����ŁA�j���[�g�������O�������ŋN����Ȃ��ȂǂƎ��͌����Ă܂���
����c�Ȃ����Ă���̂ł����H
���Ȃ��́A�ʃ����Y�̌��ʂ���ނ��A�����킩���Ă��܂���ˁB
����ł�����k�ق��g���̂͑吨�̐l�̊ԈႢ�̂��Ƃł��B
�ԈႢ����M���͗����o���Ȃ����炢�A�t�قȒm�������������킹�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�
���̏�ŗǂ��������ׂ��ł��B
�����ԍ��F13556779
![]() 0�_
0�_
�|���_�n����
���������͂���܂����A�����Y��ʂƂ��ɃS�~������Ɠ_�����{�P
�����̒��ɔ��f����ăS�~���ʂ�Ƃ������ۂ��o���I�ɔc�����Ă��܂��B
�����̌��ۂ̕����A���܂˂��{�P�̌����ɋ߂��悤�ł��B
���̉���͂Ȃ�ł��傤�H
�����Ⴂ�������Ƃ��ł��B
�J��Ԃ��܂��A���܂˂��{�P�̌������悭�w��ł��珑���Ă��������B
�M���́A�{���ɒt�قȕ����ł�������Ă��܂���B
��܂Ƃ͉����A���Ƃ͉����A��������Ƃ͉����ȂǁA�����w�I�Ȍ��m�Ő������Ă݂Ă��������B
�Œ�ł��t�[���G�ϊ����ꂽ�A���̍������̊T�O���炢�͗���������łȂ��Ɩ����ł���B
���ꂪ�o���Ȃ���A�M�a�ɂ́A����̂��܂˂��{�P���������\�͂������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13556789
![]() 1�_
1�_
�o�J�炵���b���܂��|���_�n���������Ǝv���̂ŁA����̊ԈႢ���ɏ����č����グ��ƁB
�M�a��������
�����Ȃ��Ƃ��A�l�K����掆�Ɉ����L�����o��������l�Ȃ�A�����L���@�̏W�������Y��
���Z�b�e�B���O���Ƃ��A�����T�C�Y�p�̃K���X���̃l�K�z���_�[�ŁA�j���[�g�������O����������
�����܂��o��������͂��ł����ǁA�������������H�͑S�����@���Ă���݂����ł��ˁB
�j���[�g�������O�ƍ���̂��܂˂��{�P���ꏏ�ɂ��Ă��܂����A���{�I�ɈႤ���ۂł��B
���ꂩ��A�����ł͔ʃ����Y�ŋN����^�}�l�M�{�P�ɂ��ďq�ׂĂ���̂ł����A
�Ȃ��A���ʃ����Y�����g���Ă��Ȃ����e�̘b�ɏo�Ă���j���[�g�������O�Ȃǂ��o����
����̂ł����H
���ʂȘb�ɘb��c�Ȃ����ē�����O�ɁA�L�`���Ɠ�������̓��e�ł���A
�ʃ����Y�łȂ��A���܂˂��{�P�������邩���L�`���Ɖ�����Ă���ɂ��Ă��������B
�����Ȃ��Ƃ��A���ʃ����Y�Ńj���[�g�������O����������Ȃ�Č����b�́A���ዾ��������
�c�t�����̘b�����e�ł��B
���͂���Șb�����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�ǂ����������ݖ�ɑ���Ɛ��������肢���܂��B
�����ԍ��F13556796
![]() 1�_
1�_
�|�����_�n����@
��鑤�ɋ߂������Ƃ��Ă͉ߋ��ɂ��낢��T���Ă���
�u���S�~��̃����͂Ȃ�ł��傤�ˁB�ǂ�����
�����N�����ăj���[�g�������O���o�Ă���悤�ȋC��
���܂����A���邢�͔ʃ����Y���؍�^�̏ꍇ�͐؍�
�����A�܂��^�ō��`���̏ꍇ�͌^�̐؍퍭���o�Ă���
�Ƃ��l�����܂��B �v
http://www3.ezbbs.net/cgi/reply?id=nikkortokyod&dd=12&re=1872&qu=1
�ƃj�b�R�[���N���u�̌f����
�j�R���̌��Z�p�҂������l�������Ă���̂��݂�
���̓j���[�g�������O���͎����̒��ł͔ے肵�܂����B
�����Y�i�����Y����Ȃ��Ă������ł����j�����ʓ��m��
�Ђ����Ă��Ď��̂Ƃ���ꕔ�ł����ڂ��Ă��Ȃ��Ƃ���
�ŏo����̂��Ǝv���Ă���̂ł����A���̏ꍇ
���ʃ����Y�����̃����Y�ł��ϑ�����Ă������Ǝv���܂����B
�܂�EF135/2.8SF�̂悤�ɔʃ����Y�������Ă��郌���Y
�ł��ϑ������Ƃ����_������j���[�g�������O����
���̒��ł͐����ɓ����Ƃ������Ă��܂��B
�u�ʃ����Y���؍�^�̏ꍇ�͐؍�
�����A�܂��^�ō��`���̏ꍇ�͌^�̐؍퍭���o�Ă���v
�������Ƃ��Ă͍��̂Ƃ��뎄�̌o���ɍ��v���Ă��܂��B
���̋^��͗Ⴆ��Sigma 50/1.4�Ƃ��v�̐V�������̂�
�Ȃ�����������ďo���Ă��Ȃ��̂����C�ɂȂ��Ă��܂��B
�ʃ����Y�̌����͍���Ƃ����\���ɂ͂Ԃ���̂ł���
�s�\�Ƃ͏����ĂȂ����Ƃ������ł��B
�����̖Z��������J�����ꂽ��EF135/2.8SF�̍��ł��Y�t����
�L���m������ɂł������Ă݂悤���Ǝv���܂��B���邢��Sigma
��50/1.4�̃{�P���Ă݂܂��B
�������g�A�^������͂܂������ɂ���Ǝv���܂����A�������ł�
�߂Â��Ă�����Ǝv���Ă��܂��B
���͒P�œ_�͂ł��邾���ʃ����Y�������đI�Ԃ悤�ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F13557170
![]() 5�_
5�_
�|�����_�n����
OLYMPUS�̎�u����́AE-510����E-5�͒����g���[�^�[�AE-620��PEN�V���[�Y�̓X�e�b�s���O���[�^�[�g�p�ł��B
��͂蒴���g���[�^�[�̕����u���͂ƃp���[�������ł��傤�ˁBPEN��E-620�̓X�y�[�X�Ɠd�̖͂�肾�Ǝv���܂��B
�|�����_�n����
�����i�܂ȂĂ��j����
�o���r�[�m��
�ʃ����Y�̃{�P���Ɋւ��āA�ȉ��̋L����Nikon�̋Z�p�҂̕���
�u������ł̓{�P�̕����ɍ�肠�Ƃ��o�Ă��܂��܂����A�K���X���[���h�ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�v�Əq�ׂĂ��܂��B
http://www.nikon-image.com/enjoy/interview/works/2008/0812/
���Ȃ��Ƃ��A����̍��������̂ЂƂł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
�ŋ߂̔ʃ����Y�́A�قƂ�ǃK���X���[���h���Ǝv���܂����i�m�͂���܂���j�A����ł����S�~��̃{�P�ɂȂ邱�Ƃ�����̂́A�K���X���[���h�̕������퍭�����Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł��傤���B
����Ƃ��ANikon���i�̓z���g�ɏo�Ȃ��̂��ȁH�@
���͎g�p���Ă��Ȃ��̂ŁA�킩��܂���B
�ʃ����Y�̓��S�~�{�P�́A�_�����̃f�t�H�[�J�X���Ɍ���܂��B
�_�����Ƃ������ƂŁA���˖]�����~���[�̌�����Ԃ���������t�[�R�[�e�X�g��A�z���܂����B
�t�[�R�[�e�X�g�ł́A���ʂ̋��ʂ���̃Y����s���ȉ��ʂ��A�e�ɂȂ��Č����܂��B���S�~��Ɍ�����������A���S�~��ɉe�������܂��B
���˂Ƌ��܂̈Ⴂ�͂���܂����A���˖ʂ���ܖʂ̔����ȉ��ʂ������ŏœ_�Ɍ����������̒��Ŗ��x�̃����������邽�߂ɋN����A�����悤�Ȍ��ۂȂ̂ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă��܂��B
�����Y�ԂŌ���������̂��������Ƃ���A���ʃ����Y�ł������悤�Ȃ��Ƃ������Ă��s�v�c�ł͂���܂���B���������ʃ����Y�ł́A���̂悤�ȃ{�P�̕������Ƃ�����܂���B
�o���r�[�m��
>http://www.nikon-instruments.jp/jpn/tech/2-1-6-2.aspx
>�G�o�l�b�Z���g��̂悤�ȊT�O�̌��ۂ��N�����Ă��܂��B
>�����Y���R���p�N�g�ɂ��A���G�ɐ������̃����Y�Q�𑽗p����ƁA�����Y���m�̋����i��j
�ɂ���āA�����Y�̑��݊��ɂ��A��������قȂ��������Y���A�����������ܗ���
�ω�������̌q�����������Y�̂悤�ɋ@�\���邱�ƂŐ�����s�A�����ۂ����ł��B
�u�G�o�l�b�Z���g��i���j�v�́A�����S���˂���Ƃ��̌��ۂ̂悤�ł�����A�f�t�H�[�J�X���Ƃ͂܂������W�Ȃ��Ǝv����̂ł����c
�܂��A����ƃ����Y�Ԃ̊����ǂ��W����̂��A�������킩��܂���B
�f�l�ɂ��킩��₷��������Ă���������Ƃ��肪�����̂ł����B
�����ԍ��F13557291
![]() 10�_
10�_
Tranquility����A�����́B
Nikon�̋Z�p�҂̌��ł����ǁA�K���X�̌��������Ă�����̌����Ƃ�
�Ⴄ�݂����ł��ˁB
�����ܗ��̏Ɏq�f�ނ�������d���Ƃ͂����A�ʂɌ�������̂�
���ʂɌ�������̂ŕ\�ʂɎc�錤�����ɍ����o��Ƃ͎v���Ȃ��ł��ˁB
����̍��������ɂ���Ă����P����Ȃ��Ƃ�����A�ǂ��������ɂȂ�
��ł��傤�ˁB�X�ɃK���X���[���h���ƁA�����͕s�v�Ƃ����b�͕�����
�����Ȃ��̂ł����A���ł͌����s�v�Ȃ�ł��傤���H
http://www.olympus.co.jp/jp/news/2002b/nr020919llikej.cfm
�����ϑe�����x0.03��m�ȉ�������
�������3/100,000mm�ȉ����Ď��ł���ˁB
�����܂ŗ���ƁA���e���N����v�f�Ƃ��Ă͌��������Ɛv�҂�
�˂��ς˂�̂͂������Șb�ɂȂ肻���ł��B
�v��������Ȃ��H���Đ�������������N���Ă��Ă��ǂ�������
�C�����Ă��܂��B
http://www.oldlens.com/lens%20kyoushitsu04.html
�̃m�N�`���b�N�X50mm/F1.2�̌����𒆐S������ӂɂ����ă`�F�b�N����
�݂�ƁA���Ԋp�Ƀh�[�i�c�̂悤�Ȍ��̏W�܂肪�����Ă���̂�������
�܂����ǁA������ɂȂ��Ă���̂́A�����ƕ��G�Ȋ��e�ł���ˁB
���ǁA�l�X�ȗv�f������g��ŁA���S�~��̎ȁX�͗l���N���Ă���Ƃ���
�����悤���Ȃ���ł��傤�ˁA�����_�ł́B
�����ԍ��F13558760
![]() 3�_
3�_
�d��������܂���̂ł܂��́A�b���V���v�����N���e�B�J���ɂ��Ă����܂��傤�B
�؍퍭�A���^���̌��ł����B
����l�Ƃ��ǂ��̏ꏊ�ɏo���ǂꂭ�炢�̂ǂ����������ł����H
���L�̎���ɑ��Ă��������������B
���ʓI�Ɏ����ƁA����l�Ƃ��ԈႢ�ɋC�Â��ł��傤�B
�E����������ꏊ
�P�D�����Y����
�Q�D�����Y�\��
�R�D�����Y����
�E���̒��x�i��L�P�D�Q�D�R�D�ɑ��Ă��ꂼ�ꂨ�����������������Ƃ��l���Ȃ�A����Ƒz�肵�Ă���ꏊ�ɂ��Ă݂̂��������������j
�P�D�P�ʂ��ȏ�̏�
�Q�D�P�`�O�D�P�ʂ��̏�
�R�D�O�D�P�ʂ��ȉ��̏�
�E�A���W�����[�V�����i�����Y�\�ʂ̂��˂�j
�P�D����
�@�@���@���̒��x�́H
�Q�D�Ȃ�
�܂��́A���̎���ɓ����Ē�����A�܂��͂���l�̍l�����Ԉ���Ă��邩�����o���܂��B
�����āA����ɑ��ĉo���Ȃ����炢�B���ȃC���[�W�Ȃ�A���������m���ł͂Ȃ�
�ϑz�̎v�����݂̕������傫���͂��ł��B
��L����ɓ�����ׂ��A���g�ōl���Ă���r���ł킩�����ł��ǂ��ł��B
�܂��́A��L�̎���ɓ����悤�Ɠw�͂��Ă݂Ă��������B
���炭������Ƃ�����ɔ����������Ȃ��Ǝv���܂��B
�������Ȃ��ꍇ�����e���C���[�W�Œ��ۓI�ɕ߂炦�Ă���݂̂ŁA�����ȂǑS�����Ă��Ȃ��ƌ���
������̏ؖ��ł�����܂��B
���ꂩ��ATranquility����@
�܂ȂĂ�����͑f���ɂ킩��Ȃ��Ƌ����̂œ��ɂƎv���܂����A
����������ė~�����Ǝv���̂Ȃ�A���̃R�����g�ɔے肵�����e��t���ʎ��ł��B
�ے肷�遁���̊ԈႢ���w�E�ł���
���@�^����m������
�ƌ������Ƃł�����A�m��ʂ̂ɔے肵���������A�ʃ����Y�̂��܂˂��ڂ��Ȃǂ́A
��w���܂Ƃ��ɑ��Ƃ����l�Ԃ��A������Ƃ������p���̃��x���ʼn����Η����o���郌�x����
�b�ł���A�����ēƊw�ł���������悤�ɃL�`���Ɗw�ׂΗ����o����ɂ�������炸�A���炪�낭�ɕ����Ȃ��c�P�𑼐l�̎��ɂ�����낭�ɕ������Ă��Ȃ��l�Ԃɑ���
�u���ɂ킩��悤�ɐ�������v����������ƌ����̂́A��Ђ̎В����߂ł���������A
�Ɩ��ł͂Ȃ��̂Œv���܂���B
��������킩��Ȃ��Ƌ��Ă�����̂Ȃ��������܂����A�m���Ă���B
�킩���Ă���A���̓��e�͊Ԉ���Ă���Ƃ܂Ō����̂ł�����A����͋��Ⴄ�̂�
���`�I�ɂ��̂��b�ɂ͏��܂���B
�������炸�B
�Ō�Ƀq���g�������グ�܂��A�ʂ˂��{�P�́A���ۘ_����ł͂���܂���B
�����̎��ۂɂ���ċN���錻�ۂł��̂ŁA�ꍇ�����A�p�^�[�����P���K�v�ł��B
������J��Ԃ��܂����A�j���[�g�������O�ȂǑS���W����܂���B
�����ԍ��F13558858
![]() 1�_
1�_
Tranquility����
���u������ł̓{�P�̕����ɍ�肠�Ƃ��o�Ă��܂��܂����A�K���X���[���h�ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�v
���Љ�̃T�C�g�͎����ȑO�ڂ�ʂ��܂������ǁA�ŋ߂̃j�R���̃����Y�ł�
�l�b�g��̃T���v�������Ă���ƕ��ʂɏo�Ă�̂ŁA�K���X���[���h�̋��^
�ɍ�肠�Ƃ�����Ǝv���Ă��܂��B
���x�̖��ŁA�O�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�ƃ����Y���Ⴂ�܂������ł��B
AF-S 17-55/2.8
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503511873/SortID=11106238/
�����ԍ��F13558886
![]() 1�_
1�_
���ꂩ��A�|���_�n���������\��t�������e�ɈӖ��������Ƌ��܂�����
�t�[���G���w�̏����̂��b�̃y�[�W�B
http://www.geocities.jp/eulers_formula/FourierOptics3.html
�����ɂ̓|���_�n�����o���������Y�Ɋւ���b�̐}
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268246/SortID=13521111/ImageID=1011599/
���Ōq���A���������Y�������������I�ɐi��ł��邪���Ƃ�����ł���܂��B
���Ƃ���A��L�ʑ��Ȃǂƌ����T�O���l���Ȃ������Ƃ��A�����Y�̌��݂Ɋւ��Ă�
�K�v��������Ă��Ȃ��̂Ɠ������Ǝv���܂��B
�����Ń����Y�̌��݂��o�����̂ɂ͗��R������܂��B
�{���̂��܂˂��{�P�ɂ��֘A���Ă��邩��ł��B
���ꂩ��A�|���_�n�����o�������̃T�C�g�B
http://www.keirinkan.com/kori/kori_physics/kori_physics_1_kaitei/contents/ph-1/4-bu/4-3-4-1.htm
�X���b�g�ɂ����銱�ȂȂǂ́A�����R�q�[�����g���łȂ��Ƃ���ȕ��Ȍ��ʂɂ͂Ȃ�܂���B
�R�q�[�����g���Ǝ��R���́A���{�I�ɈقȂ�܂��B
�R�q�[�����g���̎��ۂ����R���ɓ��Ă͂߂čl����ƌ����̂́A�r���傫�ȊԈႢ��
�t�قȒm�������������ʂ��Ƃ�I�悷�郂�m�ł�����܂��B
���������R�q�[�����g�����������|���_�n���͐����o���Ȃ���������܂���ˁB
�l�ɂ��ꂱ��������Ȃ�A���߂đ�w�̕����̎����ŏo�Ă�����e���炢��
�������Ă���A�l�ɐ������Ă��������B
�ԈႢ�����肷���āA�Ԉ���Ă�����e���M���ɗ���������̂���ϋ�J�ł��B
�����A�m��Ȃ����������Ƃ����Ă���̂ł͂���܂���B
���m�Ȃ疳�m���ƌ�������ŁA���̃v�����Ƃ��A�����̃J�������g�������Ȃǂ�
�����ł̐����ɂȂ��W�̂Ȃ����т��t���āA�b���u�c�ȁv������̂�
�Ԉ���Ă���Ǝw�E���Ă���̂ł��B
�������ł��A�����A�Y���̓���̔��ڎ��́A�����͔������Ȃ��Ƃ̂��܂�����
�ォ��A�������������Ƃɂ��ė~�����ȂǁA�悭�����������m���Ƃ���������
�R�قǂ���܂����B
�d�˂āA�m���������ʃ��m���A���傾�A�j�R�����A�v���J�����}�����ƌ��������ŁA
��O�҂������������ꂪ�������ƐM����̂́A��̌�����肩��A�吨�̐l���w��ŗ~�������e�ł�����܂��B
���߂���ɂ́A�N���������Ă�������ł͂Ȃ��A�����I�ɘ_���I�ɐ��������e���������g��
����������ő��l�ɂ͐������ׂ��ł��B
�����łȂ��̂Ȃ�A�ŏ�����킩��Ȃ��A���͖��m���Ɛ������q�ׂ�ׂ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13558958
![]() 3�_
3�_
�����͒��w�܂ł����Ȃ���ĂȂ����ǁA
�_���I�ȕ��͂��ǂ����͂킩��掄�B
�����ԍ��F13558973
![]() 2�_
2�_
�����i�܂ȂĂ��j����
�ł́A�����Y�ɂ����錋���ɂ����āA���L�̂Q�_�ɑ��ē����Ē����Ȃ��Č��\�ł��̂�
��z�����Ă݂Ă��������B
�P�D���ʃ����Y�P���̎��̏œ_�t�߂̌������Ă���͈͂Ɖ𑜓x�ɂ��āB
�@�@�i�{����������T�O�ɂ����ẮA�t�[���G���w���g������������Ԋy�Ȃ͂��ł��j
�Q�D�������̃����Y���g�����ꍇ�́A�����Y�\�ʂ̓��ˊp�x�ƑS���ˊp�x�Ȃ�т�
�@�@�����Y�\�ʂł̎U���ɂ��āB
���̂Q�_�ɍl���Ē�����A��̋ʂ˂��{�P�̓����ɔ����߂Â��܂��B
�؍퍭���̘b������܂����A�����Y���ӂ��r��Ă���̂Ȃ�A�����U������
�n���肵�Ă��Ȃ������Y�̗l�ɃR���g���X�g�������܂��B
�܂��A��̐ݖ�ɂ͏����Ȃ������̂ł����A�����Y���ӂ̉e�����o��ƌ����ɂ�
�����Y�ޗ������ł̎U���܂��́A�����Y�\�ʂł̎U��������������A���ˌ���
�������Ȃ�A�����Y�[���ɂ͌����͂��܂���B
�ʃ����Y�̏ꍇ�A���ʂƈႢ�A�ǖʂ̕ϓ����傫�����Ƃ���A���ˌ��ɂ�����
�\�ʔ��˂Ȃǂ�������u�p�x�v������܂��B
��̏o���Ē������ʐ^�ł��ALED�Ɩ��ŋʂ˂��{�P���Ă���G���A�Ƃ����łȂ��G���A������܂��B
�����ŁA�ʃ����Y�́A������������������Ώœ_������ς���ړI�������������Y�Ƃ������܂��B
����́A�����G���A�ɂƂ��ẮA��_�ɍi���܂����A��ʊE�[�x�I�Ɍ����Ƃ�
���S�~��ɔ�ʊE�[�x���ϓ����Ă���Ƃ����܂��B
�ʂ̌�����������A���S�~��ɏœ_������ς��Ȃ���B�e����̂Ɠ����łȂ�����
��ʊE�[�x���Ȃ킿�A��������̋�ԋ��������S�~��Ɉ��k����Ă���ƌ������Ƃł�����܂��B
�����Y�́A����p�̎ߕ�������̌����I�ɉ����āA�@���āA�Ђ�L����
����ɂ���悤�Ȍ��ʂ��o���Ă��郂�m�ł����A�������s���ƁA�ʏ��
���̉𑜓x�͗ǂ��Ȃ郂�m�́A���ӌ��ʗ������o�Ă��܂��B
���ꂪ�A���ʃ����Y�̏h���ł��B
�ʃ����Y�͂������������Ӗ��Ŏg���Ă���ꍇ������܂����A
���������ƁA���x�͌��������������c�_����Ȃ�ǂ��̂ł����A�{�P�~
���Ȃ킿�A���H�ɂ��Ă̋c�_�͓��R�����Ȃ�ɂȂ�܂��B
�{�P�~�Ƃ́A�����Y��ʂ���H�ɂ����郀����A���ˁA�U���A������̂ƂȂ���
�o�Ă��郂�m�ł��B
���������Ǝv���܂����A���ˌ^�̃����Y�̓h�[�i�c�{�P���o�܂��B
�������A�ʐ^�̉悶�����ɂ́A�h�[�i�c��Ɏʂ�킯�ł͂���܂���B
��̐؍퍭�Ȃǂɂ����̂�����ƌ����b�ł���A�[���Ȃ̂��A�����Y���ʂ̘b�Ȃ̂�
���̉��߂̒�`�t����������łȂ��Ƙb���܂Ƃ܂�܂���B
����ċM�a�̉��߂Ƃ��ẮA��̐ݖ�ǂ��ɂǂ�����Ǝv���Ă���̂��A
�����₤�Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���������������B
�����ԍ��F13559112
![]() 1�_
1�_
���P�@�S��ʁ@���T�C�Y |
���P�@�s�N�Z�����{�@�g���~���O |
���Q�@�s�N�Z�����{�@�g���~���O |
���R�@�s�N�Z�����{�@�g���~���O |
�����i�܂ȂĂ��j����A�����́B
17-55mm/F2.8�ɋ߂�14-35mm/F2�ł�����ƎB�e���Ă݂܂������ǁA���S�~�ł͂Ȃ�
�ʂ̃p�^�[���̂悤�Ȃ��̂��o�Ă���{�P������܂��ˁB
�o����o�Ȃ�������A�F�Ƃ��A���邳�ɂ���Ă��o�����Ⴂ�܂����A��荭�������Y
�\�ʂ���^�Ɏc���Ă����Ƃ��Ă��A���̍����Ɠ��ȃp�^�[�����\������Ƃ͎��ł�
�Ȃ��ł����A�P���ł͂Ȃ��݂����ł��ˁB
�{�P�̕ό`�����Ȃ��̂̓t�H�[�T�[�Y�̃����b�g�̈�ł����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y
��p��F2��薾�邢�����Y���ƁA�ǂ��Ȃ�܂����ˁB
�����ԍ��F13560480
![]() 3�_
3�_
ranquility����̂��������t�[�R�[�e�X�g�ɋ߂��̂��Ȃ���
�v���͂��߂܂����B�l�b�g�ŃT���v�����݂�����ł͌����
�����Y���Ƃ��ꂢ�ȓ��S�~��̃{�P���ł�����������Ǝv���Ă��܂��B
�K���X���[���h�Ƃ����Ƃ��������܂������Ȃ����A�|�����_�n����
�̂�����ꂽ�悤�ȓ��S�~�����ł͐������ɂ����͗l���݂���ꍇ��
����Ǝv���Ă��܂��B�����o���I�ɔʃ����Y���g���Ă��Ȃ������Y��
���̃{�P�͗l�������郌���Y��m��Ȃ��ł��B
�i�����̕��s���̉\��������܂��B�j
���Ƃ͌����̑傫����������W����̂�������܂���B
�P��g���̂k�d�c�C���~�l�[�V�����ȂŃn�C���C�g�����łȂ�
�ꍇ�ɂ͋����ώ@������ۂ������Ă��܂��B�ȏ�͗�������Ȃ���
�o�����ł��B�͂��߂Ă��̌��ۂ�s�v�c�Ɏv�����̂�powershotA520��
LED�C���~�l�[�V�������{�J���ĎB�e�����Ƃ��ł��B
mFT�̃����Y��GF2��14/2.5��14-42mm�̃L�b�g�����Y�������L���ĂȂ�
14mm�͋A�Ȓ��Ȃ̂ō��G��Ȃ��ł��B������ƌ����Ńo�^�o�^�Ȃ̂�
10��2���ȍ~�Ɏ莝���̃V�X�e���E�����Y�ō��������Ă݂܂��B
�莝����EF�����YTokinaAT-X116, EFS18-55IS, EF135/2.8SF�Ȃ�A�_�v�^
�o�R��GF2�Ŏg���܂��B
���͌o��������A�ǂ����čŐV�����Y�͂�������P���Ă����Ă��Ȃ��̂�
�^��Ɏv���Ă��邾���ł��B�j�R���́u������ł̓{�P�̕����ɍ�肠�Ƃ�
�o�Ă��܂��܂����A�K���X���[���h�ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�v��
�^�Ȃ�A����͌��퍭�ɂ��邯�ǁAAF-S17-55/2.8�̍��̂悤�Ȃ̂�
���݂���̂ŁA���ɂ��v��������̂�������܂���B
�����ԍ��F13560872
![]() 1�_
1�_
�|���_�n����
���{�P�̕ό`�����Ȃ��̂̓t�H�[�T�[�Y�̃����b�g�̈�ł���
�Ə����Ă܂����A�O�Ɏ��͉��x�������܂������A�t�H�[�T�[�Y��
�c�Ȏ����������Y�ɂ��C������̂ł͂Ȃ��A�O�ʂ�傫�����ăC���[�W�T�[�N���̂���
�����̎������̂��̂̏��Ȃ��������o���v�ɂȂ��Ă���ƁB
�����ƁA�{�P���Y��ɂȂ邵�A�B�e�����̂��̂��V���[�v�ɂȂ�B
�\��Ńg�s�傪����ɂ���A
�����[�J�[�ɕ������Ƃ��됫�\�I�ɂ͑傫�ȈႢ���Ȃ��BE-P3�������瓖�R�}�C�N���t�H�[�T���[�Y�K�i�Ή��̃����Y�̕����D��Ă���ƌ�����A�Ƃ̂��Ƃł���
�����邢�����Y���~�����B
��M.ZUIKO�@DIGITAL�@ED12mmF2.0�Ȃ�ăt�B���^�[�a42mm������ǂ����62mm�ɂ���������Ɓ����邢�����Y�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����E�E�E���Ƃ͂����P���ł͂Ȃ��̂ł��傤����ǁI
�ƌ�������B
���[�J�[�����\�ɈႢ�͖������ƌ���������B
������L�ۂ݂ɂ��āA�g�s�𗧂Ă����_�ŁA�ʃt�H�[�T�[�Y�̃f�����b�g��̊��ŗ������Ă��Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂��B
��ʂ�t�����W�o�b�N���X���낢�댾���l�����܂����A�S�Ăɂ����Ĉ�ԏd�v�Ȃ̂�
�O�ʂ̌a���A��p�ɑ��ď\���傫�ȃ��m�ł��邱�Ƃ��A�ł��d�v�ł���A
�d�ʂ��傫�����ɗ͖��Ƃ��Ċɘa���ꂽ�`�~�߂���Ȃ�A�u��������v�傫�ȑO��
�̐v���D�G�Ȍ��ʂɂȂ�͎̂����̗����ƍēx�����Ă����܂��B
�|���_�n���́A�����Y�Ȃ�тɃ}�E���g�ɂ��āA���낢�돑���܂����A
����ȁu�펯�I�v�Ȏ��ɑ��ĂȂ��ӎ��������Ă��܂���B
�����āA�����Y�Q�A�����Y�̍\����A���ނɂ���Ă����̌��ʂ���p���傫���Ⴄ���Ƃɑ���
������A��ʌa���ǂ�������A�e���Z���������Ȃ�����ʂ�ƌ����B
�O�ʌa�́i�P���ȑO�ʌa�ł͂Ȃ����ߋ��Ƀj�R���̂V�O�|�Q�O�OF2.8��L���m���̓��l�̃Y�[�������Y�̗�ŋL�ڂ��Q�Ɓj
�p���[�̏d�v���ɑ��Ė������Č����̂́A�����Y�̂��Ƃ��S���킩���Ă��Ȃ�����ł��B
�Â����ʃ����Y�����ȍޗ���p���Ȃ��v�̂��̂Ȃ�A�����I�Ɍo���������Ă͂܂���̂����邪�A
�ꗥ�A��ʌa���ʂ̉����ʃ����Y�̌`�����ŁA�����Y�v�̑P�����������|���_�n����
�����Y�Ɋւ���͗ʂ͐����Ēm��ׂ��̃��x���ł��邱�Ƃ��ēx�`���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
���������A�������������̐l�̘b���A�����m��Ȃ��A�Z�p�I�Ȓm���������Ȃ��l��
�����������Ǝ���Ă��܂��������̒��Ɏ���đ傫�ȃ}�C�i�X������̂ƍl���Ă��܂��B
�N��������������A�u��������������v�͊ԈႢ�B
�Z�p�I�ɐ������𗧏؏o���Ȃ����̂́A���Ƃ��ĊԈႢ���ĊQ�ɂȂ�Ɖ��߂ďq�ג����Ă����܂��B
�����ԍ��F13560888
![]() 1�_
1�_
�|�����_�n����
��������
�ʃ����Y�f�t�H�[�J�X���̓��S�~��̉e�ł����A�e�͌��̗ʂ̃������̂��̂ł���ˁB
���̃����́A�ˏo������ˏo���������̒��Ɍ��ʂ̃���������Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���������������悤�ɋ��ʃ����Y�ł͂��̂悤�ȉe�͌����܂���A�ʃ����Y���̂��̂Ɍ���������Ƒz���o���܂��B
�����̂ЂƂƑz�������ʃ����Y�̌��퍭�ł����A�e�̗l�q���猩�āA����͌����s���ɂ��C�菝�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤�B
���ʃ����Y�͋��ʎM������������ɉ�]�����ă����Y���グ��̂ŁA�����Y�ʂɑ��Č����̕������͂���܂��A�ʃ����Y�ł͌����𒆐S�ɃK���X����]������]�u�Ő������킵�Ĕʂ�����Ă��邻���ł�����A���S�~�����Ɍ�������邱�ƂɂȂ�܂��B
http://www.nikon.co.jp/profile/technology/core/optical/aspherical_lenses/index.htm
��]�u��ʂ̋Ȑ��ɍ��킹�Ĉړ������鎞�ɁA�v�Z�ǂ���덷�[���ňړ������邱�Ƃ��o��������ł��傤���A���ۂɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͕s�\�ł�����A���z�I�ȋȐ����牚�ʂ̔����Ȍ덷���o�Ă��܂��ł��傤�B���ꂪ�s���ȋ��܂������錴���ɂȂ�A�ˏo������ˏo���������̒��Ɍ��̃���������Ă��܂��̂��Ƒz���o���܂��B
�K���X���[���h�̋��^�������悤�ɐ�������Ő������Ă���Ƃ���A����ʃ����Y�Ɠ����悤�Ȍ��̃�������������ł��傤�B
�����A�����Y�͑�ʐ��Y����ł��傤���A��i���Y�ɋ߂����^�͂����ƂĂ��˂��Ɏd�グ�邱�Ƃ��o����ł��傤����A��芊�炩�Ɏd�グ�邱�Ƃ��o���邾�낤�Ǝv���܂��B
����Ƃ����ЂƂA�K���X�́u�����v���s���ȋ��܂̌����ɂȂ�܂��B
�K���X���[���h�����Y�ł́A�����ɋ߂��`�Ɏd�グ�����w�K���X�������œ�����ăv���X����̂ŁA���ꂪ�����`�ɕό`����鎞��A�₦�Čł܂鎞�ɁA�����Ȗ������o���Ă��܂��ƍl����ꂻ���ł��B
�~�`�ɐ��`���ꂽ�f�ރK���X���v���X���ĕ����I�Ɍ��݂�ς��Đ��`�����邱�ƂɂȂ�̂ŁA���S�~��ɖ������o���Ă��܂����Ƃ����肦�����Ɏv���܂��B
�����ԍ��F13561015
![]() 4�_
4�_
�o���r�[�m��
>�N��������������A�u��������������v�͊ԈႢ�B
>�Z�p�I�ɐ������𗧏؏o���Ȃ����̂́A���Ƃ��ĊԈႢ���ĊQ�ɂȂ�Ɖ��߂ďq�ג����Ă����܂��B
���̂Ƃ���ł��ˁB
�ł�����o���r�[�m��́A���������w�E�����u�ԈႢ�v���Ȃ��ԈႢ�Ȃ̂��A�u�Z�p�I�ɐ������𗧏v����K�v������Ǝv���܂��B
�u�����Œ��ׂ�v�ł́u����͊ԈႢ�ł��v�ƌ��������ԈႢ�ł͂Ȃ����Ƃ��ؖ��ł��܂���B
>�����������ȂȂł͂���܂����i�j���������Ă�����E�E�E�B
>���ꂩ��A�؍퍭����^���Ȃł�����܂����i�j
>�܂��B����l�Ƃ��A���̂悭�������Ƌ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA�ԈႢ�����͎w�E���܂�����
�悭�����ׂ��������B
�����o���r�[�m��̏������݂ɊԈႢ������Ə��������ɂ��ẮA���ꂩ��d���Ŏ��Ԃ�����܂���̂ŁA��قǏ������Ă��������܂��B�\���킯����܂���B
�����ԍ��F13561044
![]() 11�_
11�_
Tranquility����A��������A�����́B
�������̕\�ʂɃG�b�`���O�ŊG��`���A���̍����G��������Ȃ��Ȃ�܂��Y��ɂɖ����グ�Ă�
���̋��Ƀ��C�g�˂�����ƁA���̗ւ̒��ɂ��̊G�������яオ���Ă���m�����n�ƌĂ��
�������邱�Ƃ��v���o���܂������A�����悤�Ȍ��ۂȂ�ł��傤���ˁB
���[�U�[���𗘗p�����z���O�����Ȃ�ȒP�ɐ����ł��錻�ۂł����ǁA���[�U�[���̂悤��
�R�q�[�����g���ł͂Ȃ����R���ł��Č��ł��錻�ۂł��̂ŁA�P���ł͂Ȃ������ł��ˁB
�����ԍ��F13562805
![]() 0�_
0�_
�Ƃ肠����35-100mm/F2��35mm�ł��B�e���Ă݂܂������ǁA����ł��F�▾�x�ɂ����
�͗l�̂悤�ȕ����ʂ鎖������݂����ł��ˁB
35-100mm/F2�̓I�����p�X�̖��ʂƂ���Ă���100mm/F2���ꡂ��Ɏ��������Ȃ��A�_��
�_�Ƃ��Ďʂ�H�ȃ����Y�ŁA�V�̎ʐ^���B���Ă���l�ɂ͋M�d�ȃ����Y�̂P�{�ł����A
�ׂ�������ƁA�����̂悤�ȃp�^�[��������܂���ˁB
�����ԍ��F13563661
![]() 1�_
1�_
Tranquility����@
��ɒf���Ă����܂��B
�q���ŏ����ꂽ���̕��́B
�{���͎O�ɕ�����Ă��܂��̂ŁA�q���ŕʂ̉��߂ɂ��Ȃ��悤�ɂ��肢���܂��B
���@����̓|���_�n���Ɍ������b�B
>�����������ȂȂł͂���܂����i�j���������Ă�����E�E�E�B
�@�����ł̊��ȂƂ̓j���[�g�������O�̊��Ȃ̂��Ƃ������Ă��܂��B
���@����͂܂ȂĂ�����ƋM�a�ւ̌��t�B
>���ꂩ��A�؍퍭����^���Ȃł�����܂����i�j
���@����́A�|���_�n���Ƃ܂ȂĂ�����ւ̌��t�B
>�܂��B����l�Ƃ��A���̂悭�������Ƌ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA�ԈႢ�����͎w�E���܂�����
�悭�����ׂ��������B
�����ԍ��F13564094
![]() 1�_
1�_
���ꂩ��A�����������ȕ�������̂ŁA�ʐ^��}�̎�����\��t���Ă����܂��B
�z���͂����Ă����ɂȂ�A����̖����悤�ɗǂ����ǂ݂��������B
�u���ʎ����Ƃ́A�{�P�I�̎��ł��ˁB�v
http://blogs.yahoo.co.jp/solunarneo/29287129.html
�g�ʎ����Ƃ�
http://www.olympus-ims.com/ja/microscope/terms/astigmatism/
���[�U�[�i�R�q�[�����g���j�ɂ�銱��
http://www.holorer.jp/Arch/What/index.html
���Ɗ��Ȃɂ���
http://www.chuo.co.jp/technology/tech_02/tech_02_04_01.html
���ʎ�������g�ʎ����ւ̕ϊ���̔�r�i�P�j
http://homepage2.nifty.com/mtnsuzuki/tele006.htm
�����Y�̋��ʎ���
http://www.enjoy.ne.jp/~k-ichikawa/iRay_LensAberration.html
�T�C�f������
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%AB%E5%8F%8E%E5%B7%AE
�œ_���O���e�X�g�̃y�[�W
532nm�̃O���[�����[�U�[�ɂ��œ_���O���Əœ_���̃e�X�g�摜�ł��B
http://homepage3.nifty.com/cz_telesco/syoutenzoutest.htm
�i�ォ��ڂ̃O���[���ƃ��b�h�̔g���ɂ��œ_�����ω�����_�ɒ��Ӂj
���̑��i�L���m�����{�L�b�Y�A�t�[�R�[�e�X�g�j
http://web.canon.jp/technology/kids/mystery/m_02_06.html
���ꂩ��A�܂ȂĂ����o���ꂽ�T�C�g�̃t�[�R�[�e�X�g�B
����̓����Y�ł͂Ȃ��A�����܂ł������u���ʂł͂Ȃ������ʂł��邱�Ƃɒ��Ӂv
�����āA�����Y�͕������ł��邱�ƁB
�܂��A�܂ȂĂ����o�����T���v���ʐ^�̃T�C�g
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503511873/SortID=11106238/ImageID=598846/
�������{�P���Ă��܂����A�_�����ł̃{�P���ʐ^�̏㉺�ʒu�Ń{�P�_�ł̒����̎Ȗ͗l���A�ʐ^�㕔�ł͉���
�ʐ^�����ł͏�ɂ���Ă���u�ꕔ�̎ȁv�����邱�Ƃɒ��ӁB
�Ƃ肠�����ȏ�ł��B
�����ԍ��F13564213
![]() 1�_
1�_
���ꂩ��lj���
�œ_���O���e�X�g�̃y�[�W
532nm�̃O���[�����[�U�[�ɂ��œ_���O���Əœ_���̃e�X�g�摜�ł��B
http://homepage3.nifty.com/cz_telesco/syoutenzoutest.htm
�i�ォ��ڂ̃O���[���ƃ��b�h�̔g���ɂ��œ_�����ω�����_�ɒ��Ӂj
�̕����B
��ԏ�̎ʐ^��
�u���{��7cmF8 2���ʕ������t���[���C�g�A�|�N���}�[�g�i�剖���L�j�v
�Ƃ���܂����A�t���[���C�g�B�������̍D�ތu�̃����Y�̂��Ƃł��B
���܂��ł�����t���Ƃ��܂��B
http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/hosi1.4d.htm
���āA�����҂����܂���B
�|���_�n���̘b�����́A�ŏ�����Ō�܂őS�����Ӗ����A�Ԉ���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł����i�j
�����ԍ��F13564238
![]() 1�_
1�_
>���āA�����҂����܂���B
�N����̉�҂��Ă���������̂ł��傤�H
�������A�ǂ����������Љ�������܂����B
�u�œ_���O���e�X�g�̃y�[�W�v
http://homepage3.nifty.com/cz_telesco/syoutenzoutest.htm
�V�����ɂ͂Ȃ��݂̃e�X�g�ł��ˁB
�����Œ��ڂ��ׂ��̓W�t���N�V���������O�i�O���[�����[�U�[�ɂ��œ_���O���j�ł͂Ȃ�
�u�i�C�t�G�b�W�e�X�g�v�Ɓu�i���e�X�g�v�̉摜�ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F13564524
![]() 1�_
1�_
���N����̉�҂��Ă���������̂ł��傤�H
�܂��A����l��
�������o���r�[�m��̏������݂ɊԈႢ������Ə��������ɂ��ẮA���ꂩ��d���Ŏ����Ԃ�����܂���̂ŁA��قǏ������Ă��������܂��B�\���킯����܂���B
���������ꂽ������ł��B
�����ԍ��F13564923
![]() 0�_
0�_
���Ƃ̂���l�́A�������Ă���̂��킩��Ȃ����瓚�����Ȃ��̂��͂킩��܂���B
�����A�܂ȂĂ�����̌��ɂ��ẮA�����؍퍭����^���ƌ����Ă����b�ɂ���
�؍퍭����^���ł͖������m�́A�v���i�������j�̌덷�ɂ��Ă̘b�ƁA
�����Y���ʂ̃A���W�����[�V�����̘b���������̂��Ƃ́A�����̖T�犴���܂����B
�ʏ팾����؍퍭�́A���������Ӗ��ł͎g���Ȃ��̂ł����A���t�̈��p�̈Ⴂ�ł����
�ꕔ��������_�͂���܂����B
���������_���͊F����ɑ��B
�E�ꏊ�͂ǂ���
�E�ǂ̂��炢�̐[���̉��ʁi���j������̂�
�E���̑��Ƃ��ăA���W�����[�V�����̂��Ƃ������Ă���̂��H
�ƃL�`���Ǝf���܂������A���O���Ƃ��������܂���B
�ǂ̂��炢�̘c�݂܂��́A����������̂��K�ɓ������郏�P�������Ǝv���܂����̂�
�d��������܂��A�A���W�����[�V�����ɂ��ĊԐړI�Ɍ����������Ƃ����͂킩��܂����̂ŁA
�Ƃ肠�����͂����܂łł��B
�������A���ꂾ���ō���̌��ۂ̐����ɂ����R�ɂ��Ȃ�Ȃ����Ƃ́A��̎�������
�L�`���Ɠǂ݉����A�z���o����͂��Ȃ̂ł����A������ǂ݊ԈႦ���
����Ȗϑz���[�h�Ō�������܂�܂��B
�������l�Ȃ̂��ǂ����A�������������������Ă��܂����A�����Ƃ��ďo���܂����B
�����Ŗ����Ă��A�|���_�n���̗l�Ɂu���l�͌o���������A���������Ĉ��������Ƃ�������A�ǂ�����������v
�ƌ������b����̓��e�ł́A�ǂ݉����Ȃ������ɂ͂Ȃ��Ă��܂��B
����܂��āA�ǂ����B
�����ԍ��F13564942
![]() 0�_
0�_
�����������̃X�����E�������͎̂���
�u�ʃ����Y�̂��܂˂��{�P�������Ȃ�ł����ǁA������ċZ�p��
�����ł��Ȃ��̂ł��傤���H�������ʃ����Y�g���Ă��郌���Y
�������Ă��܂����A�C�ɂȂ�܂��B�v
�Ə���������ł��ˁB���̃e�[�}�Ɋւ��Ă͎��͓��������߂Ă��鑤��
�������鑤�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A�����܂łɎ��̔c�����Ă�͈͂�
�������Ă����܂��B
�E���܂˂��i���邢�͂������j�ڂ��͔ʃ����Y�g�p�̃����Y��
�@�������͊ϑ����Ă�B���ʃ����Y�ł̔��Ⴊ����Ȃ�m�肽���B
�E������ł̓{�P�̕����ɍ�肠�Ƃ��o�Ă��܂��܂����A
�@�K���X���[���h�ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�ƃj�R���������Ă���B
�@�f�l�n�ł��o����̂����邵�A���S�~�ł͂Ȃ�������₵�Ă�̂������
�@���͎v���Ă��܂��B
�E�ʃ����Y�̓ʖʂ̌�����ɂ��Ă����Ђ����邪�A���ʂ͑Ή��s��
�@�Ə����Ă���ꍇ������B�ʃ����Y�ł��ʖʂ̂ݔʂ̂��̂͌�����
�@�\���Ǝv���Ă��܂��B�t�ɉ��ʂ��ʃ����Y�̂��̂͂܂������ł��Ȃ��B
�@�����
http://www.sigma-cybertech.co.jp/sct_opt/eigyou/Chemicalnews/01.htm
http://www.ikuta-sk.com/
�@�̏���ǂ�Ŕc�����Ă��镔���ł��B
�E�u�œ_���O���e�X�g�̃y�[�W�v��t�[�R�[�e�X�g�Ɏ��Ă��邩��A��������
�@�W���Ă���Ƒz�����Ă��܂��B
���Ƃ�EF 50/1.2L��Sigma50/1.4�̌��w�n�͎��Ă���Ƒf�l�ڂɂ͎v�����ǁA���܂˂��{�P�̗ʂ⓯�S�~�̔������I�H�ł̓V�O�}���_���g�c�ɂ��܂˂���B
EF50/1.2L�͂��Ԃ�f�l�n���Ǝv�����ǁA��������Ă�̂��͔c�����Ă��Ȃ��B
�����ԍ��F13565095
![]() 7�_
7�_
�o���r�[�m��̃^�}�l�M�ڂ��̌����Ɋւ���L�q
�E�؍퍭����^���������ł͂Ȃ�
�E�G�o�l�b�Z���g��̂悤�ȊT�O�̌��ۂ��N��
�E�����Y�̑��݊��ɂ��
�E���Ȃł͂Ȃ�
�E���ۘ_����ł͂Ȃ�
�E�����Y�̌��݂��֘A���Ă���
�i�ʃ����Y���W���Ă���Ƃ̋L�q�����j
�������������^�}�l�M�ڂ��̌���
�E�ʃ����Y�Ɍ��������邾�낤
�E�؍퍭����^���ɂ���ċN����s���ȋ��܂������̃����ł͂Ȃ���
�u�s���ȋ��܂������̃����v�Ƃ́A�Ⴆ�A�v�[���̒�ɉf��g�̉e�̃C���[�W�ł��B
����Ɏv�������̂ł����A�؍퍭����^���ƌĂ�ł��闝�z�Ȑ�����O�ꂽ�����ȉ��ʁi�o���r�[�m�������Ƃ���̃A���W�����[�V�����H�j���A������������̔g�ʂ̊���ŁA�f�t�H�[�J�X�����ɖ��Ẫ���������Ă���̂ł͂Ȃ����B
�܂�A���z�Ȑ�����O�ꂽ�ʕ�����ʂ���Ɖ�������ʂ���̔g�̈ʑ�������āA�����N�����Ă���̂ł͂Ȃ����H�Ƃ������Ƃł��B
�g�̈ʑ�������Ċ�����Ɣg�̋������ς��̂́A���Z2�N�ŏK���̂���?
���z�Ȑ��Ŕʃ����Y����������Ă����Ƃ��Ă��A���ʃ����Y�Ƃ͈�����f�t�H�[�J�X���̌��ʕ��z�ɂȂ肻���ł����A�����Ɗɂ₩�Ȍ��ʕω��ŁA���̂悤�ȃ^�}�l�M�͗l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�܂��A���������ꂽAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED�̂��܂˂��摜�ł����A�o���r�[�m�w�E�̂悤�ɉ�ʎ��ӕ��̃{�P���ł͎Ȗ͗l�̒��S������Ă��܂��B
����͍i��t�߂̔ʃ����Y�Ń^�}�l�M�͗l���������āA���a�H�Œ��S������Č�����Ɨ����ł���Ǝv���܂��B
�ȏ�A����܂ł��u�c���Ǝv���v�Ə������悤�ɁA���ׂĎ��̐����ł��B
���ł���Ȃ���ł���Ƃ��w�E���������A���̗��R�������Ă�����������肪�����ł��B
�����ԍ��F13566338
![]() 8�_
8�_
�����o���r�[�m��̏������݂ɊԈႢ������Ə��������ł����A
���̏������݈ȑO�ŁA�����u����͂��������v�Ǝv�����Ƃ���͈ȉ��̓_�ł��B
�u�������A�����ȃe���Z���g���b�N���ł͂Ȃ��A±15�x���x�܂łȂ�X���Ă��ǂ�
�@���Ƃ��������Ȃ�A�t�����W�o�b�N�������Ă��t�Ɍ�ʂ��������Ă���薳��
�@���Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B
�����̘b�͋��ʃ����Y�Őv�����Ȃ�ƌ��������ł���v
[13540799]
�E���ʃ����Y�ł��ʃ����Y�ł��A�����̎��̌X���ɂ��Ă̏����͓����ł��傤�B
�u�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Œ|�N���X���o�Ȃ��̂́A�v������ƌ������A�R���Z�v�g�㍂���ȃ����Y�����Ă�����Ȃ��̂ŁA�����ȃ����Y�Q�ŏ\����������l�B�ɂ킴�킴����Ȃ������Y���o���Ӗ��������Ƃ����̂����̍ő�̗��R�v
[13540799]
�EOLYMPUS�̕��ɕ������̂ł��傤���H
���̃X���b�h�����Ă��킩��Ƃ���A�����ł��傫���Ă���������~�����Ƃ������[�U�[�͂��܂��B���̂悤�Ȑ��ɓ����Ĕ������ꂽ�̂�M.ZD12mmF2.0�ł��傤�B�傫�����d�����Ȃ��ł�����ǁA�����ł��B
Panasonic��7-14/4.0�Ƃ�25/1.4�A45/2.8�}�N���A8/3.5�t�B�b�V���A�C�Ȃǂ�������|�N���X�̃����Y�Ȃ̂ł́H
�uNikon1�ɏ��Ă�i���ł���Ώ\���ƍl����Ȃ���Ƀn�C�G���h�����Y���o���K�v�������ƌ����̂����̗��R�v
[13540799]
�E����B
�u�I�����p�X�A�����ă}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A���������@�B�I�ȉ\�������A�J������g�߂ȑ��݂ɂ��A�R���p�N�g�Ŏg���₷���J��������낤�Ƃ��Đ��ɏo�����J�����ł��B�v
[13540873]
�E�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̓R���p�N�g�Ŏg���₷���Ƃ����_��������̂ł��傤���A�t�H�[�T�[�Y�́A������܂߂Ă���Ƀf�W�^�����t�̉\����Nj������J�������Ɨ������Ă��܂��B����OLYMPUS�̐��i�ł��A���i���Ⴂ�܂��B
�܂��A�u�R���p�N�g�Ŏg���₷���J��������낤�v�Ƃ��邱�Ƃ��A�@�B�I�ȉ\����Nj����邱�Ƃł��B
�u���邢�����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ŏo���ɂ����̂́A�ނ��낱����̗��R�ŁA�ʂ̐v���Â��ƁA���邢�����Y�ł͂�����̂́A�t�H�[�J�X���Â��A�{�P�~���o�Ȃ������Y�ƂȂ�A�����Y�̉��l�����Ȃ��Ă��܂����߂ł��B�v
[13540919]
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̖��邢�����Y�́A�u���邭�ăV���[�v�v�ƕ]�����ꂽ�����Y����Ȉ�ۂł����B�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ŗ��邢�����Y���o���ɂ����Ƃ������Ƃ͖����ł��傤�B
�u�e���Z�������������߂�Ȃ�A�O�ʂ��ɗ͑傫�����āA�����Y���傫�����s�ɍ��Ηǂ������ł���ƌ������Ƃł��B�v
[13541006]
�E[13535908]�ɂ��}�������܂������A���ʂ̃e���Z���g���b�N�����������߂�Ȃ�O�ʂ͕s�v�ł��B
�����ԍ��F13566342
![]() 11�_
11�_
>���������ꂽAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED�̂��܂˂��摜
�����܂���B24-70/2.8G�̔̒���ꂽAF-S 17-55/2.8�̉摜�ł��B
�O�̂��߁B
������ɂ���
>���a�H�Œ��S������Č�����Ɨ����ł���Ǝv���܂��B
�������a�H���Ǝv���܂��B������
>�؍퍭����^���ɂ���ċN����s���ȋ��܂������̃����ł͂Ȃ���
���������v���܂��B�����āA����������ł��Ȃ��̂��Ȃ��Ǝv�����킯�ł��B
���s�̍��z�ȃ����Y�ł��łĂ���̂ŁA�Z�p�Ȃ̂��A�R�X�g�Ȃ̂��A���_
�Ȃ̂��͂킩��܂��A��������낤�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F13566925
![]() 3�_
3�_
���̌�́u�H�v�Ɗ������o���r�[�m��̏������݁B
�u�Y�[���ł��Ɣʃ����Y���S���͕K�v�ɂȂ�͂��ł��B�v
[13547507]
�E�ʃ����Y0�����畡�����g�p�������̂܂ŁA���낢�날��܂����c
�u�{�P�~���D���ł͖����̂Łc�v
[13547507]
�E�u�ڂ����v�́u�ڂ������v�Ɠǂނ̂����ʂ��ȁB�ŋ߂́u�{�P�~�v�Ƃ������̂ł����H
�u�ڂ������v�̌������ʁF�� 2,720,000 ��
�u�ڂ��݁v�̌������ʁF�� 1,310,000 ��
�ӊO�Ɓu�ڂ��݁v��������ł��ˁB
�u�|���_�n���̘_�_����́A�p�[�v���t�����W�Ȃǂ̌��ۂɂ��Ă͑S�������o���Ȃ��v
[13555650]
�E�p�[�v���t�����W�͈ꌾ���b��ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ɁA�Ȃ������ł��̐��������߂�̂ł��傤�H
�u�吨�̐l���Ԉ�����m���������ƂɂȂ�܂��B�v
[13555804]
�E�{���̂��Ƃ������m�ł��ꂪ���S�z�ł�����A�T�N�b�Ɛ��������Ƃ������������̂ł́B
�В����߂̊�Ɣ閧�Ȃ�ł��傤���H
�u�t�H�[�T�[�Y�͘c�Ȏ����������Y�ɂ��C������̂ł͂Ȃ��A�O�ʂ�傫�����ăC���[�W�T�[�N���̂��ɒ����̎������̂��̂̏��Ȃ��������o���v�ɂȂ��Ă���ƁB�v
[13560888]
�E�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�̓C���[�W�T�[�N�����\�M���M���ł���B�傫���C���[�W�T�[�N���̈ꕔ���o���悤�ɂȂ��Ă��܂���B
���������A�����e���Z���g���b�N���m�ۂ��ăC���[�W�T�[�N����傫������ɂ́A�C���[�W�T�[�N���Ȃ�Ɍ�ʂ�傫�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�����ԍ��F13567512
![]() 11�_
11�_
�ނ��������悤�����ǁA����ς�C�ɂȂ�̂Ŏw�E���Ă����܂��B
�����ۂ̓��a��46.1mm�����Ȃ��ł�����A��43mm�̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[�����邱�Ƃ�
�����C�J�l�X�̂悤�ɃI���`�b�v�}�C�N�������Y���V�t�g�����Ȃ��Ǝ��p�I�ł͂Ȃ��ł���
�S������ȕK�v�Ȃ��ł���B���Ȃ��Ƃ��AA�}�E���g�����Y�͑S�����Ȃ��g�������B
A�}�E���g�̓��a����A�C���[�W�T�[�N���̒[�����܂Œ��������Ă݂Ă��������B���̒�����E�}�E���g�̓��a�ɂ��肬��G��܂���B���������v�Z�̏�ɐv����Ă܂��BFT��MFT�Ɠ����W�B
�ʂ˂��̘b�͋����[���q�����Ă܂��B�����Ă��������B
�����ԍ��F13568414
![]() 2�_
2�_
�����i�܂ȂĂ��j����A�����́B
����nikon��D70�`D2X���g���Ă�������ɂ�17-55mm/F2.8���g���Ă��܂����̂�
�`�ʂ̌X���͗������Ă������ł����AAPS-C�T�C�Y�p�ł���Ȃ���A���a�H��
���Ԋp���甭������ȂǁA�F�X�C�ɓ���Ȃ������������āA�I�����p�X�ɏ�芷
�����o�܂�����܂��B
��̑O�̃h�C�c�̃����Y�v�҂��A�u�i��̌`���Z�p�`�Ŋp�����Č��ꂵ���v��
���{�l�ɔᔻ���ꂽ���A�u��X�̓s���g���������ӏ��̉𑜓x��R���g���X�g��
�d�����Ă���A�s���ڂ��̉ӏ��ɂ͋����͂Ȃ��v�Ƃ����悤�ȈӖ��̌������
���Ă��������v���o���܂����B�{�P�͂��̌�[bokeh]�̂܂ܐ��E�W���̒P��ɂȂ�
�܂������ǁA����̃^�}�l�M�̒f�ʂ̂悤�ȎȁX�{�P�́A�����_�ł́A�܂��œ_��
�����̌��̏W�܂��i�X�|�b�g�_�C�A�O�����j��ǂ����邱�Ƃɒǂ��Ă���
���̑O��̃{�P�̃p�^�[���܂ł̓R���g���[������Ɏ����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�
���傤���B
�X�|�b�g�_�C�A�O�����͉��L��URL�ŎQ�Ƃ��Ă��������B
http://pentaxstudy.bufsiz.jp/Lensdesign/LENS_MENU1_J.htm
���Ȃ݂ɁA���͍ŏ�����
���^�}�l�M���ɂ����悤�Ȗ͗l�̃{�P�́AF1.4��薾�邢�ʃ����Y�ɑ���
��������悤�ł����ǁA�j���[�g�������O��蕡�G�Ȋ��e�̂悤�ł�����A
�Ə����Ă���A�^�}�l�M�{�P���j���[�g�������O�Ƃ͌����Ă܂��Anikon��
�Z�p�҂��u�ǂ����Ŋ����N�����ăj���[�g�������O���o�Ă���悤�ȋC�����܂����v
�Ə����قǁA���ۂƂ��Ă̓j���[�g�������O�ɑ�\����銱�e�ł���ˁB
�I�����p�X�̃{�P�ɂ̓^�}�l�M�{�P�ɋ߂����͂Ȃ��悤�Ɋ����Ă���̂ł����A
�ǂ��Ȃ�ł��傤���ˁB
�������ACANON��DO�����Y�^�ϑw�^��܌��w�f�q�̏ꍇ
���B�e�����Y�̕\�ʂ�0.001mm�P�ʂ̍a�S�~��ɂ���A�ꖇ�Ōu�����Y��
���ʃ����Y�̓������Ɏ������邱�Ƃɐ���
�Ƃ���܂����ǁA���ϑe�����x��0.00003mm�ł������ł��Ă��������ł���̂�
�����Ƒ傫�ȍa�Ȃ�e���Ȃ��Ȃ��ł��傤���ˁH
�����ԍ��F13568440
![]() 5�_
5�_
�|���_�n��
�����A�M�a�̎咣�ɑ��鐳���Ȉӌ��������Ă��܂���B
���݂ɂ���HN�͎��ł͂���܂���ˁi�j
gintaro����@
�|���_�n���́A�������Ȃ��܂��́A�����Ȃ��Ǝv���܂���B
���g�ɂƂ��ĕs���v�Ȏ�����ߋ��ɉ������߂���1�x���Ȃ��̂�����i�j
������ɂ��Ă��A����邭�炢�t�قȗ��_�́A�ߋ��Ɉ�Ă��r���Ă�������Ȃ�Ƃ�����
�悤�₭�����Âł͂��邯��ǁA�|���_�n���̍l�����̊ԈႢ�ɋC�Â��Ă�������l��
�o�Ă��Ċ������v���܂��B
�J��Ԃ��܂����A�|���_�n���͎��炪�\��t�����u�R�q�[�����g���v�ł���
�N����Ȃ��悤�Ȍ��ۘ_�ɂ��Ă̘b�ɂ��āA���炪�R�q�[�����g���̂��Ɓu����v
�m��Ȃ��������ł�����ˁB
���ɔg����������ƌ����A�u����Ȃ��́E�E�v�ƌ����ł��傤���ǁA���ꂱ��
�u���̌��v�������ƂȂǖ����ł��傤����A�o���s���͔ۂ߂܂���B
��w�łȂ�A���[�U�[�̂���Ȏ����ɂ������Ȃ��o���͒N���������Ă��ł����ǂˁB
�����J������G�������Ƃ�����Ƃ��Ȃ��Ƃ��A�����ł͔����Ȃ��y���^�b�N�X�̂Ȃ��
�ʂ������Ƃ�����Ƃ��Ȃ��Ƃ��A�{�����Ƃ��Ắu�ǂ��ʐ^���B�邽�߂Ɂv�ǂ�����̂�
�ǂ̃J�����ƃ����Y���g���̂��x�X�g�Ȃ̂�����ԋ���������Ƃ���Ȃ�ł����A
�|���_�n���̉ߋ��̍�������ƁA����Ȕ������Ȃ�Ĕ��o�������Ȃ������肪�o�Ă���
�{���̂悤�ȋc�_�Ɏ�������߂鎑�i������̂��r���^��ł��B
�ߋ��Ȃ�A�|���_�n���ɓX�R�A�ŁA�u�ǂ��v�̃{�^����������Ă��܂������A
���͂����ł������悤�Ȃ̂ŁA�����������������Âł͂���܂����A
���ʓI�ɃI�����p�X�����悭�����o�����Ԃ̂��̂��Ǝv���܂��B
�w�p�I���t�����Ȃ��v�����݂ɉ����āA�Z���X�̂Ȃ����т��t�����o���b�́A
�łɂ����Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13568607
![]() 2�_
2�_
Tranquility����
�܂��A�M�a�̐؍�E�E�E�܂߂��b�B
��̓I�ɂǂ̂��Ƃ������Ă��邩�A��ɏ������͂��ł�����������Ă���A
����ȁu���Ǝv���v�ƌ����悤�Ș_���I�ł͂Ȃ��b�����Ă��������B
�܂��͂��ꂩ��ł��ˁB
���́A�܂ȂĂ�����Ɠ������b�����Ă�����ł���B
�����Ă܂ȂĂ�����́A�ǂ����������f���ɒm�����~�����ƌ����Ă��܂����A
�M���͉����ŁA�Z�p�I�ɘ_�j���Ĕے肷��̂ł͂Ȃ��A�v�����ݓ��X�ŏ�����Ă��܂��B
�S�������āA�؍퍭���X�̎咣�������ɂ��Ă��A�{���`���ɂ���ʂ��
����ɃL�`���Ɠ����ĖႦ�Ȃ���A����C�ɂ��Ȃ�܂���B
�В��]�X�܂߂āA�����l�Ԃł�����ˁB
���̋C�ɂ����Ȃ��M�a�̌����܂߂āA�M�a�ɓ�����C�͖�����ł��B
�����ԍ��F13568619
![]() 0�_
0�_
�����i�܂ȂĂ��j�����
���́A�����g�̎���������g�ʼn���悤�Ɍ��������Ă���킯�ł͂���܂���B
����́A���|���_�ɂ���C���������Ƃ��ɒf������Ō����܂����A�������܂˂��ڂ��̘b���o���ۂɁA�����v���Ă����C���[�W�̓��e�ƌ��ۘ_���؍퍭�̘b���قȂ���e��
���߂Ă�����悤�Ɏv���܂����B
����́A���݂��l�Ԃł���A�Z�����t�����ł́A����̑z�����Ă��郂�m��
�����̗p��ȊO�̃j���A���X�œ`����ɓ������ẮA�ǂ����Ă��o�Ă��鑊�ݓI�Ȗ��ł��B
�ł�����A���������ė~�����ƌ������b�́A�܂ȂĂ�����̓I�ɂǂ��v���Ă���̂���
�L�`���ƌ`����Ă����Ȃ��ƁA�o���̃C���[�W�̂��ꂩ��b�����������悤�Ɏv�����̂�
�����Ă������ł��B
�܂��A�J�肩�����ɂȂ�܂������܂˂��ڂ��́A��̗v���łȂǐ��藧���Ă��܂���B
����肪�������̂ŁA�����f���ɂȂꂸ�ɂ��܂����A�؍퍭�Ȃ�тɂȂ��V�O�}�������̂���
�^��ɑ������ł͂���܂��A�o������e�͎������킹�Ă��܂��B
�����A�ςȘb�B
�����l�ԂȂ̂ŁA����������ꂽ�`�A�ʂ̓�l�̌���Еt���Ȃ���A���_�q����ǂ��`��
���������䂪�Ԃ��v���Ă��邾���ł��B
�䖝�����A�{���ɂ��ċ^��̉��������ꂽ���Ǝv����Ȃ�A���t���������������B
�����ԍ��F13568638
![]() 0�_
0�_
�d���������̂ň�_���������č����グ�܂��傤�B
�u�|���_�n���̘_�_����́A�p�[�v���t�����W�Ȃǂ̌��ۂɂ��Ă͑S�������o���Ȃ��v
[13555650]
�E�p�[�v���t�����W�͈ꌾ���b��ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ɁA�Ȃ������ł��̐��������߂�̂ł��傤�H
�|���_�n���̒m���ɁA���̔g�����B���R���̋����ɂ��āA�ނ��m�����������킹�Ă��Ȃ����Ƃ�
�ؖ����邽�߂ł��B
���ꂩ��A���͋M������̎���͎��ɂƂ��Ďז��ȊO�̉����̂ł�����܂���B
�����Ă���̂͂܂ȂĂ�����ł�����A���Ɏ��₷��̂ł͂Ȃ��A�܂ȂĂ�����ɑ���
�����Ă�����`�ŁA�f���ɉ��Ă��������B
�M������l�̔N�z�҂́A�����猩��A�N���̗�␅���A�Ƃ݂ɂ��ɂ�
�����I�Ȑl�̌����ɂ����v���܂���B
�i�܂ȂĂ�����ɂ͌�������͂���܂��{��Ԃł͓��Ă͂܂�܂��j
�M�a�ɑ��Ă̂����ƁA�{�������I�ɂ́A�m����������̂ɑ���
�����𐿂����̂́A�i���ł�����ˁB
�В��]�X�ȑO�ɁA������̂�������O�Ȃ�Č����ē�����K�v�Ȃ��
�㉺�W��������A�w�����߂����؍����̊W���Ȃ��`�A���`�I
�����I�Ȍ������l�b�g�ł͗D�悳���Ǝv���A�u���̋C�����킹���v�u���̋C�ɂ����Ȃ��v
�������݂����������̊ԈႢ�Ȃ�ł��B
�n�b�L���������܂�����ˁB
�l�̈ӌ��ɔ��Έӌ����������Ȃ�A���Ɠ��i�����i�ȏ�̒m�����������킹��
�����x���ł̋c�_�i���ƒm���̑�����j���o���Ȃ���A�M�u�A���h�e�C�N�ɂȂ�Ȃ���ł��B
���͊w��ɗǂ��s���܂����A���_�𗧂Ă��邩�ۂ����d�v�Ȃ�ł��B
����ɂ܂������Ă��āA������コ�́A����҂ɑ��āA���̒P�Ȃ闬�o�����Ȃ�ł��B
�����đ���͐l�ԂȂ�ł���B
�{�点����s�����ɂ��������_�ŏI���Ȃ�ł��B
���́A�|���_�n���̗l�Ȍ���������l���A�ނʋ��t�Ƃ��āA������m�炵�߂��������Ȃ̂ł��B
�|���_�n�����������Ƃ��A�ނ̓��e�Ɛ����̉ߒ��ŁA�������������������邱�Ƃ��܂Ƃ߂āA
�ނ����������b������ƌ������Ƃ́A�ނ̒m���Ɍ��@���Ă��郂�m�A�Ԉ���Ēm���Ƃ��Ă�����̂�
��������Ă��邾���ɉ߂��܂���B
�p�[�v���t�����W�Ɋւ��āA�M�a�Ɏ�������Ă��Ȃ��ɂ��ւ�炸�A
�����Ĕނ̌����܂߂āA�m��Ȃ��̂ł���Ȃ��̂��ƁA�����g��
�u�ԈႢ�𐳂��܂��v�ƌ����Ă����Ȃ���A�Z�p�I�ȉ�Ȃ��ŏ����Ă���l��
��ɂ��������ʂ莄���猩��Ɠ�l�Ƃ��|���_�n���Ɠ����i�̐l�Ɍ����܂��̂ŁA�D���ł͖�����ł��B
�ǂ����A����܂��Ď��̌���������Ă��������B
�����ԍ��F13568667
![]() 0�_
0�_
�܂ȂĂ�����
��w�E���Ă����ƁB
���L�̌��B
���a�H�͏o�Ă܂��B
�������A���܂˂��{�P�̒��S�̕����̂�������A�ꕔ�̉~�ŁA�K�N�b�Ƃ���Ă��镔��������܂��B
����́A���̓I�ȏd�Ȃ肪�A�[���i�����j�̂��ꂪ������̂��߂��猩�����̌`�ɋ߂����m�ł��B
�悤�́A���̂��܂˂��{�P�́A���̓I�Ȍ`�̉e�����Ă���ƌ������Ƃł��B
���͂߂�ǂ������̂ŁA�ʐ^���H���Ă�����w�E���Ă��܂��A������x�����������ڂ�
�����������������B
�����i�܂ȂĂ��j����@manatealog�E�E�E�@.>���������ꂽAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED�̂��܂˂��摜
�����܂���B24-70/2.8G�̔̒���ꂽAF-S 17-55/2.8�̉摜�ł��B
�O�̂��߁B
������ɂ���
>���a�H�Œ��S������Č�����Ɨ����ł���Ǝv���܂��B
�������a�H���Ǝv���܂��B������
>�؍퍭����^���ɂ���ċN����s���ȋ��܂������̃����ł͂Ȃ���
���������v���܂��B�����āA����������ł��Ȃ��̂��Ȃ��Ǝv�����킯�ł��B
���s�̍��z�ȃ����Y�ł��łĂ���̂ŁA�Z�p�Ȃ̂��A�R�X�g�Ȃ̂��A���_
�Ȃ̂��͂킩��܂��A��������낤�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F13568743
![]() 1�_
1�_
>�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̓������������Ė��邢�����Y���~����
(���K�D�K���G)����E�E�E�HF2�Ƃ�F1.8�ł͈Â��ƌ������ł���
�����ԍ��F13568779
![]() 0�_
0�_
�ōX�ɉ���������Ă����ƁB
�ʐ^�����̍���ƍ�������̔������g���Y�t���Ă����܂����A
���ĉ�]���ē\��t���Ȃ������悤�Ȃ��̂Ɍ����܂��B
�������A��Ɏw�E�����܂���͗l�́A�}�̉���̒ʂ�A�܂���͗l�Ƃ���ȊO�̕����Ƃł�
�������{�P�̂ڂ��̊O�`�`��ɔ�Ⴕ�ĂЂ���ł��镔���ƁA�܂���͗l�����̂���Ă��镔����
�킯�čl������B
����́A���̓I�Ȃ��������ԂŋN�����Ă��錻�ۂ��Ƒ����ėǂ��Ǝv���܂��B
�������A�����Y�ŗL�̌��ۂł�����܂�����A�����Y�̌^�Ԃ�[�J�[���قȂ��
�ʂ̌��ۂ����Ă܂��܂��B
�i���܂˂��{�P�̖��͈�̌��ۘ_�ŋN�����Ă���킯�ł͂Ȃ��ƌ������Ƃł�����܂��j
�����ԍ��F13568867
![]() 1�_
1�_
���ꂩ��A�܂ȂĂ��������Ă���A�V�O�}���Ƃ��܂˂��{�P�������Ƃ����w�E�B
����͂���ŕʂ̗��R������܂����A�Ƃ肠�����͍����͂����܂ŁB
�����ԍ��F13568872
![]() 1�_
1�_
���j�̒��́������o�Ă�����I����@.
��>�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̓������������Ė��邢�����Y���~����
��(���K�D�K���G)����E�E�E�HF2�Ƃ�F1.8�ł͈Â��ƌ������ł���
���炭�X���傳��́A���̃����Y�ŁA�����Y�ɂ��`�ʗ͂̍����A�����ȃ����Y��
����Ȃ�̃����Y�B�����ĉ���l�����������Y�̃{�P�~��R���g���X�g�̍����Ȃǂ�
�ǂ����ő̊������̂��Ǝv���܂��B
�i�������Ⴂ�͂���ł��傤���A�T�ˌ����������Ƃ͂킩��̂Ŗ��ł͖����Ǝv���܂��j
�P�ɖ��邢�����Y������ǂ��킯�ł͂���܂��A��L�ɂ��������Ƃ���A
�V���b�^�[���x����������A�{�P�~�������Ƃɑ��āA�C���[�W�ʂ�̉�ɂȂ��Ă��Ȃ�
�܂��́A����l�̈Ⴄ�����Y���ƁA�ʐ^�̃C���[�W������Ȃɂ��傫���Ⴄ�̂���
�����������߁A����ȑf���炵���ʐ^���B���Ă݂����Ǝv���Ă���̂��Ǝv���܂��B
F�l�Ɋւ��ẮA����I�����p�X�̔ŋc�_���ꂽ�̂Ŋ������܂����A
�{�P�~�́A�t�H�[�T�[�Y����肽���Ă����Ȃ�����̈���Ǝv���܂��B
���́A�t���T�C�Y�Z���T�̃J�������g���Ă��܂��Ă���̂ŁA���R�̊��͂���܂����A
�ʐ^���B��l�ɂƂ��āA����D�悳�������̂��A������x�ڂ��삦�Ă����
�����Ƃ킩���Ă���ۑ�ł�����Ǝv���܂��B
���ʁA�ʂ̃}�E���g�A�ʂ̃��[�J�[�̃J�������̂��A�e�N�j�b�N���܂߂�
�ʂ̕��@�ŃJ�o�[����̂��́A�{�l�̈ӋC���ݎ��悾�Ǝv���܂��B
�����A���ꂪ�킩��l�͂����ڂ����Ă���l���Ǝv���܂��B
�X���傳��́A���������_����A�ʐ^�̎����ǂ�ǂ�オ���Ă��������Ǝv���̂�
������ė~�����Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F13568919
![]() 1�_
1�_
gintaro����
���S������ȕK�v�Ȃ��ł���B���Ȃ��Ƃ��AA�}�E���g�����Y�͑S�����Ȃ��g�������B
�����ȃe���Z���g���b�N���͂Ƃ肠�����l���Ȃ��Ă��ς�300mm/F2.8�̃����Y���ɂƂ��
���ʂ���300mm���ꂽ�ʒu�ɔ��a53.6mm�̑O�ʂ�����̂Ɠ������ɂȂ�܂�����A��������
���ʂ̈ʒu�ŃC���[�W�T�[�N���̔��a21.5mm�̂Ƃ���܂Œ����������Ă݂�AF2.8�̌���
���œ_�ʂ܂ŏR��ꂸ�ɓ͂��̂ɕK�v�ȃ}�E���g�̔��a������܂��B
�o�b�N�t�����W��44mm���Ɣ��a25.5mm�͕K�v�ł����ǁA�d�e�}�E���g�̓��a��51.2mm��
����ƂƂ����Ƃ���ł��B�ƌ������ACANON�̃}�E���g��300mm/F2.8�ɍ��킹�Ă���̂���
�Ƃ����C�����܂��B
SONY�̂`�}�E���g�͌��a50.0mm�E�t�����W�o�b�N44.5mm�ł�����A������Ə������ł��ˁB
�t�����W�o�b�N18mm�̂Ƃ��낾�Ɣ��a24mm�͕K�v�ł�����A46.1mm���ƁA����܂��������
�������ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA200mm/F2�ɂ̓t�����W�o�b�N44mm����54mm�A��44.5mm����55mm�͕K�v�ł�����
�܂Ƃ��ɐv����Ɗ����̋≖���ォ��̃}�E���g�ł͏R���܂��ˁB
�`�}�E���g�̏ꍇ�A43mm�̃C���[�W�T�[�N���Ƀt�����W�o�b�N����44.5mm�̈ʒu����
�^������F2�̌����Ă�ɂ́A65.25mm�܂Œ��a��傫������K�v���������Ƃ���
���Ƃł��BF1.4���Ɩ�75mm�͕K�v�ł�����A�܂Ƃ��Ƀ��C�J���T�C�Y�̃f�W�^�����t
����낤�Ƃ���Ƒ傫���Ȃ�܂��ˁB�����T�C�Y���݂̉掿��������悤�ɂ���ׂɂ�
�K�v�Ȏ��ł�����A������ł��v�������ė~�����ł��BCANON�̂d�e�}�E���g�̏ꍇ
APS-C�i24��18mm�j�̎B���f�q���炢�܂ł�������n�j�Ȃ̂ł����c
���nikon���o���Ă���300mm/F2�Ƃ��������Y�̏ꍇ�A���̏����ȃ}�E���g�ɉ�ʎ��ӂ܂�
F2�̌������ł��邾���ʂ����Ƃ��āA�Ƃ��Ă��A�N���o�e�B�b�N�Ȑv�����Ă����̂�
�v���o���Ă��܂��܂����A�]�������Y�Ȃ̂ɁA�e���Z���g���b�N�����ǂ��Ȃ��Ȃ�āc
�Ƃ��������ł��B�I���`�b�v�}�C�N�������Y������ɃV�t�g���Ă���B���f�q�Ȃ�ނ���
�s�b�^���Ƃ����\��������܂����c
�t�H�[�T�[�Y���ƕK�v�ȃ}�E���g�̌��a��F2.8��32mm�AF2��36mm���x�ł�����]�T�ł��ˁB
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł�F2�ł���30mm����Ώ\���ł�����A��薳���ł��ˁB
�����ȃe���Z���g���b�N�����m�ۂ����ꍇ�ł��A�t�����W�o�b�N38.67mm�̃t�H�[�T�[�Y
���Ɩ�F1.5�̌�������ʂ̒[�܂Œ��p�ɓ��Ă��܂����A�t�����W�o�b�N20mm�̃}�C�N��
�t�H�[�T�[�Y�̏ꍇ�́A��F1.05�܂łn�j�Ƃ������ɂȂ�܂����ǁA�����Y�̘g�̎���
�l������A��ʂ��瑜�ʂ܂ł̋������Z�����A���̂��炢�̗]�T�͕K�v�Ȃ͂��ł��B
NEX�̏ꍇ�A�q�d�c�����C�o���ɂȂ�͂��ł�����A�X�[�p�[�R�T�̃V�l�}�d�l�̂o�k
�}�E���g�����Y�̃C���[�W�T�[�N��(APS-H)��31.4mm���J�o�[����Ηǂ��Ǝv���Ă���
�̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z���Ă���̂ł����ǂ��ł��傤���ˁB
�����ԍ��F13570013
![]() 4�_
4�_
ginganohikari����A�����́B
��M.ZUIKO�@DIGITAL�@ED12mmF2.0�Ȃ�ăt�B���^�[�a42mm������ǂ����62mm�ɂ�����
�������Ɩ��邢�����Y�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����E�E�E
���̃X���b�h�̓��e�����Ȃ肸��Ă��Ă���݂����ł����ǁA�b�����ɖ߂��āA�X���傳���
F1.4�����҂���Ă����ł��傤���H����Ƃ��AF1.2�Ƃ�F1.0�H
F1.2���ƁA�R�X�g��T�C�Y�I�ɂ����Ȃ����ł��傤���ǁA�`�e���x���Ȃ��Ă��A���\�f�J�N
�Ȃ��Ă��ǂ��Ƃ��������t���ɂȂ�܂����AF1.4�Ȃ�ł������ȋC�����܂��ˁB
12mm/F2��25mm/F1.4�̌�ʂ̈ʒu�Ƒ傫�����r���Ă���������C�Â����Ǝv���܂����A
�e���Z���g���b�N�����l������ƁA��ʂ����ʂɋ߂���߂��قǁA�傫������K�v���ł�
���܂��B���Ƀ}�E���g�̋߂��ɉ�ʎ��ӂł�F1.4�̌������m�ۂ��邾���̌�ʂ�u�����Ƃ��Ă�
���ꂾ���̑傫�����m�ۂł��Ȃ��ꍇ�A�o�b�N�t�H�[�J�X��������������K�v������܂��B
�����āA���̕��A���g���t�H�[�J�X����������K�v���o�Ă��܂�����A�O�Q�̉������Y��
�傫���Ȃ�A�S���������Ȃ�܂��B
�h�C�c�̃����Y�v�҂̏ꍇ�A���ӌ��ʂɗ]�T���������邽�߂��A���L�p�ł��O�ʂɓ����
�ʃ����Y�������Ă���f�B�X�^�S���s��21mm/F2.8�悤�ȃ����Y����������Ƃ�����܂�������
�ł������ł���ˁB
http://www.kyocera.co.jp/prdct/optical/catalog/pdf/systemcatalog_vol7.pdf�@��P10�Q��
���O�ʂ��f�J�N����Ǝ��ӌ��ʂ������Ȃ��Ƃ��E�E�E�ǂ�������܂��E�E�E�E
��ʂ��e���Z���g���b�N�����m�ۂ���̂ɏ\���ȑ傫���ɂł��Ȃ��ꍇ�́A�O�ʂ��f�J�N
���Ȃ��Ǝ��ӌ��ʂ��m�ۂ��ɂ����ł��傤�ˁB
1970�N��̘b�ł����A�L���m���d�w�I�[�g�Ƃ������t����������Ă��܂����B
�����Y�̍\���}�����Ă���������C�Â����Ǝv���܂����A�i������̌�Q�����Y��
�{�f�B�[�ɕt�����܂܁A�O�Q�݂̂���������Ƃ����w���e�R�Ȑv�ŁA50mm/F1.8��35mm/F3.5
�̃t�B���^�[�a��46mm�ł������A95mm/F3.5��62mm�A125mm/F3.5��72mm�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ�
�傫���ɂȂ��Ă��܂����B
����F125mm/F3.5�A����:95mm/F3.5�A�E��F50mm/F1.8�A�E���F35mm/F3.5
���H���`�F�b�N����Ɖ�p�ɑ��đO�ʂ̑傫���ɖ��ʂ������Ƃ������Ƃ�������܂����A
SIGMA��50mm/F1.4�̏ꍇ�A������ʂ�����1cm�f�J�N�ł�����A�O�ʂ�1cm�������ł���ł��傤
����A���ʂ������Ƃ����C�����܂��B
���Ⴆ�t�H�[�T�[�Y50mmF2.0�}�N����50mmF1.4�}�N���Ƃ����邢��60mmF1.4�}�N���Ȃ�ďo�������ȋC������B
�}�N�������Y�͑��ʂ̕��ʐ����v������܂����A�ߐڎ��̊e�����̕�͖��邭�Ȃ�Ȃ�ق�
����ɂȂ�܂�����AF2���炢�����p���E�ɋ߂��̂ł͂Ǝv���܂��B
���Ђ�F2�̃}�N�������Y���o���Ă���̂�ZEISS��TAMRON�����Ƃ����̂��A����𗠕t���Ă���
�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13570341
![]() 5�_
5�_
�B�e�ɖZ�����ċv�X�ɂ̂������琏���}�j�A�b�N�Șb�ɍs���Ă���悤�Łi�j
�Ƃ肠����
��KissX50�@2011�N03��29���@129.9×99.7×77.9mm�@��450g
��D5100�@�@2011�N04��21���@128×97×79mm�@��510g
���f�W�^�����t�̏��^�y�ʉ��́A���łɌ��E�܂ŗ��Ă���̂�������܂���B
�܂��A�j�R�L���m�͓O��I�ȏ��^�y�ʉ��ɂ͂����ĂȂ���ۂł��˂�
�j�������w�T�O���S�T�O���Ő������Ɍ����邯�ǂ��c
���͌Â��@�킾���ǂ��\�j�[�̃��Q�R�O
�i��͋@�B�I�ȘA���ł����A�`�e���[�^�[���{�f�B�ɂ���ɂ�������炸
128x97x67.5 mm�@450 g
�ƂȂ��Ă��܂�
���Q�R�O�̃N�I���e�B�łd�e�}�E���g���ƌ��\�y����ꂻ���ł���
(*´��`)�m
�܂��`�o�r�|�b�P��t���e�s�Ɠ��������^�y�ʉ��ɂ͕s���ȋK�i�Ȃ킯��
�~���[���X���o�����A���^�y�ʉ����ŗD�悵�Ă��������Ȃ����i�j
���d�}�E���g�Ƃ͌����Ă܂���ANEX�Ƀt���T�C�Y�Z���T�[���ڂ���ׂɁA�V����
�}�E���g���l������Ƃ������ł��傤���ˁH
����ȈӖ��ł͌���Ȃ��ł��傤
���ʂɂd�}�E���g�Ńt���T�C�Y�ł���Z�p�����łɎ����Ă���̂ł́H
�d�}�E���g�͂e�}�E���g�قǂ̃T�C�Y�Ȃ̂�
�e���Z���̖��������ł��鎩�M������Ƃ݂��i�j
���ʏƎ˂��Ƃ肠�������ɗL����������܂���
�t�H�g�_�C�I�[�h���ʏ�^�ɔ�ׂ�Ƃ��Ȃ�Z���T�[�̕\�ʋ߂��ɂ���܂�����ˁ�
(*´��`)�m
�����ԍ��F13570861
![]() 0�_
0�_
�o���r�[�m��
>�܂��A�M�a�̐؍�E�E�E�܂߂��b�B
��̓I�ɂǂ̂��Ƃ������Ă��邩�A��ɏ������͂��ł�����������Ă���A����ȁu���Ǝv���v�ƌ����悤�Ș_���I�ł͂Ȃ��b�����Ă��������B
>�M���͉����ŁA�Z�p�I�ɘ_�j���Ĕے肷��̂ł͂Ȃ��A�v�����ݓ��X�ŏ�����Ă��܂��B
���́A���Ȃ�ɘ_���I�ɍl�������Ƃ��A��̓I�Ɂu�����v���i��������j�v�Ə����Ă������Ȃ�ł����B
�����ɂ����[�J�[�̎҂ł��Ȃ������҂ł��Ȃ��̂ŁA�ȒP�Ȏ����Ɛ��������邵���Ȃ��̂ŁB
>���́A�܂ȂĂ�����Ɠ������b�����Ă�����ł���B
���̂��b��ǂ܂��Ă��������Ă��܂������A�����^�}�l�M�ڂ��̌����ɂ��Ă���Ȃ�ɍl���Ă��������������̂ŁA�b�̗ւɉ���点�Ă��������܂����B
�����ł̃o���r�[�m��̏������݂ł́A��������̋^���̓I�ɓ����邱�Ƃ͂܂����������A�t�ɖ₢������Ԃ����ƂƁA�|�����_�n����ւ̔ᔻ�����ǂ߂܂���ł����B
���͂��̒��ŁA�o���r�[�m���������Ƃɋ^����������_�����X���������Ƃ́A��ɏ������Ƃ���ł��i�ǂ��ł������悤��1���������������������Ă��܂��j�B
�N���������Ɍ�����������݂����āA���ꂪ�u���Ƃ��ĊԈႢ���ĊQ�ɂȂ�v�Ƃ��l���ɂȂ�Ȃ�A�T�N�b�Ɓu���������Ƃ���̓I�Ɂv���������āA������_���A�����̉����łȂ��قǃo�b�T����̂Ă������ł���B
�w��Ŕ��\�������悤�ȕ��ł�����A�킯���������Ƃł��傤�B
����������肭�ǂ����Ƃ����āi�Ⴆ�j����|�����_�n����̊ԈႢ���ؖ���������A��������܂���ɂ́A����ۂǂ��̕������ʓI���Ǝv���܂����ǁB
>�����đ���͐l�ԂȂ�ł���B
�{�点����s�����ɂ��������_�ŏI���Ȃ�ł��B
�����̌f���ɏ������݂����Ă���ҁA�������݂�ǂ݂ɗ��Ă���ҁA���ׂĐl�Ԃł��B
���R�A�㉺�W�Ȃǂ���͂�������܂���B
���̂��Ƃ������Ȃ͈̂�����܂��܂��A���Ȃ��̌l�U���I�ȏ������݂Ɂi���̑Ώۂ̋L�q���ԈႦ�Ă����Ƃ��Ă��j���Ȃ�s�����Ȏv�������Ă��܂��B
��������Ƃ̘b�Ɋ��荞��ŕs������������܂��AAF-S 17-55/2.8�̃^�}�l�M�͗l�́u�ځv������ďd�Ȃ��Č����錏�ɂ��āB������������Ƙb���Ă��܂��̂ŁB
���Y�����Y�͔ʃ����Y��1�E3�E5�Q�ɂ��ꂼ��1�����g�p���Ă��܂��B
��p���ӕ��̌�����1�Q�ڂ̉������Y�̒��S��ʂ�Ȃ��ł��傤���A3�E5�Q�ڂ̓ʃ����Y�͒��S��ʂ�ł��傤�B
��p���ӕ��̌����́A���ꂼ��i�肩��̋����ɉ����Ď߂ɂ���ă����Y���S��ʂ�A����2���̃����Y�ō��ꂽ�^�}�l�M�͗l�́u�ځv������ďd�Ȃ��ă������ڂ��ɓ��e���ꂽ���̂Ȃ̂��Ɛ������܂��B
���ɂ́A�܂��܂��^�}�l�M�͗l���ʃ����Y�i�̔ʁj�ɂ���č���Ă���Ǝv���܂��B
�o���r�[�m��ɂ��u�G�o�l�b�Z���g��̂悤�ȊT�O�̌��ہv�Ɓu�����Y�̌��݁v���֘A���Ă���Ƃ̂��ƂŁA�ʃ����Y�������Ƃ͂���܂ňꌾ��������Ă����܂��B
�����ԍ��F13572364
![]() 9�_
9�_
>SONY�̂`�}�E���g�͌��a50.0mm�E�t�����W�o�b�N44.5mm�ł�����A������Ə������ł��ˁB
���Ƃ̎咣�́uE�}�E���g�Ƀt���T�C�Y�f�q�͂��т����v�Ɠǂ߂܂������AA�}�E���g����Ƃ��̘b��������ł����H
�����������������̂́AE�}�E���g�K�i��ؕύX�Ȃ���NEX�Ƀt���T�C�Y�f�q�ς�ŁA�����}�E���g�Ƃ��đ����̃��[�U�[���s�s���Ȃ��g���Ă���A�}�E���g�����Y���S�āA���w�I�ɂ͂Ȃ�̖����Ȃ��A���̂܂g�����ˁA�}�C�N�������Y���������肷��K�v���Ȃ���ˁA�Ƃ������ƂŁA���̓_�Ɉّ��͂Ȃ��悤�ł����猋�\�ł��B
�����AA�}�E���g�t���T�C�Y���ƁA300mmF2.8���ǂ��Ƃ��A�ŁA
���t�H�[�T�[�Y���ƕK�v�ȃ}�E���g�̌��a��F2.8��32mm�AF2��36mm���x�ł�����]�T�ł��ˁB
���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł�F2�ł���30mm����Ώ\���ł�����A��薳���ł��ˁB
�͂������ɂ��������ł���B�t�H�[�T�[�Y��F2����t���T�C�YF2.8�̉悪�B����ł����H
�t�H�[�T�[�YF2�̓t���T�C�YF4�A�t���T�C�YF2.8�̓t�H�[�T�[�YF1.4�ɑΉ����܂��B
�قȂ�t�H�[�}�b�g�Ԃ̔�r�ŁA������Ƃ�����������Ӗ��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F13572382
![]() 0�_
0�_
gintaro����
��A�}�E���g�̓��a����A�C���[�W�T�[�N���̒[�����܂Œ��������Ă݂Ă��������B
�����̒�����E�}�E���g�̓��a�ɂ��肬��G��܂���B
�`�}�E���g���������ł����ǁA�t�����W�o�b�N�������ł�����A�܂��L���ł��ˁB
�������A�d�}�E���g�̓t�����W�o�b�N���Z���ł�����A�]�������Y�ʂɐv
���Ă��܂��ƁA�����̔����̓}�E���g�ɎՂ��Ă��܂����ɂȂ�܂��B
�t�H�[�T�[�Y��150mm/F2�Ɠ����悤�ȃ{�P��������̂́A���C�J���T�C�Y�̏ꍇ
300mm/F2.8��F4���i�����ꍇ�ł�����A�������{�P��~�����ꍇ�͓������A
�ނ���t�H�[�T�[�Y�̕����L���ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B
���ɂ͉�ʎ��ӂ܂ʼn~�ɋ߂��{�P�łȂ���Δ������{�P�Ƃ͎v���Ȃ����߁A���C�J��
�T�C�Y�ł͓_������F2��薾�邢�����Y���g���či��J���Ń{�P�����ĎB�e���邱�Ƃ�
�l�����܂��A���Ȃ背���Y��I�ԕK�v������悤�Ɋ����Ă��܂��B
�������{�P���~������A�����T�C�Y��I�����ǂ��Ɗ����Ă��܂��B
�������}�E���g�Ƃ��đ����̃��[�U�[���s�s���Ȃ��g���Ă���A�}�E���g�����Y���S�āA
�����w�I�ɂ͂Ȃ�̖����Ȃ��A���̂܂g�����ˁA�}�C�N�������Y���������肷��
���K�v���Ȃ����
�����A�����Ă���̂Ȃ�A����ŏ\�����Ǝv���܂��B
���̊�Ƒ傫���قȂ��Ă��邾���̘b�ł��B
�o���r�[�m��
���J��Ԃ��܂����A�|���_�n���͎��炪�\��t�����u�R�q�[�����g���v�ł���
���N����Ȃ��悤�Ȍ��ۘ_�ɂ��Ă̘b�ɂ��āA���炪�R�q�[�����g���̂��Ɓu����v
���m��Ȃ��������ł�����ˁB
�m�P�F���n���u�R�q�[�����g���v���Ɗ��Ⴂ���Ă���̂ł��傤���H
���o�[�g�E�t�b�N���m�j���[�g���n�������̂�1665�N�ŁA�j���[�g���͂��̌�A
�l�X�ȁm�P�F���n�����ĂāA���̖��Â��K���X�Ԃ̊Ԋu�ɂ���Ď����I�Ɍ��܂邱�Ƃ�
�����A1701�N�Ɂm���w�n�ł��̌������ʂ\���܂������ǁA[�R�q�[�����g���v��
1958�N��C�ET�E�^�E���Y �� A�EL�E�V���E���E �ɂ���ė��_�I�Ɏ����̉\�����w�E����
1960�N��T�EH�E���C�}�������r�[�����ɂ�郌�[�U�[���U�ŏ��߂Ď����������ł�����
�j���[�g���́u�R�q�[�����g���v�ł͂Ȃ��m�C���R�q�[�����g���n�Ŋώ@����Ă���
�킯�ŁA��L�́m�u�R�q�[�����g���v�ł����N����Ȃ��悤�Ȍ��ۘ_�n�Ƃ����̂�
���S�Ƀs���g���O��Ă��܂��ˁB
���Ȃ݂ɁA�j���[�g���͌��𗱎q���ƍl���Ă������߂ɁA�g���ɊW���������Ƃ�
�����ł��Ȃ������悤�ł��B
�����ԍ��F13572475
![]() 4�_
4�_
�|���_�n����
�������Ȃ��B
����A����ς�M���͐����B
����ă��m�������Ȃ����炢�����i�j
���m�P�F���n���u�R�q�[�����g���v���Ɗ��Ⴂ���Ă���̂ł��傤���H
���A�u�P�F���v�Ȃ�Ĉꌾ�ł������܂��������H
���A���[�U�[�ƃR�q�[�����g���́A�����ł͈Ӗ������Ƃ��Ăł���
�����Ӗ��ł͏����܂������ǁA�P�F���Ȃ�đS���ᒆ�ɖ����������Ă�������ł������H
���������āA�ƌ������|���_�n���B
LED���ƃ��[�U�[���̋�ʕt���Ȃ��ł���i�j
�l�����Z�ɖ_���ӂ������炢�̒m���ł́A��͂�t�[���G���w�̘b�͓�������ł����ˁH
�R�q�[�����g���Ǝ��͌J�肩���������Ă���̂ł����A���������Ă���̂ł����H
�Ƃ肠�����M�a���R�q�[�����g��������ς艽���m��Ȃ������ؖ��������ɂȂ����悤�Ŋ������ł��i�j
���ꂩ��A���̂����j���[�g�������O���R�q�[�����g�������ł����N����Ȃ��Ȃ��
�ꌾ�ł������܂������H
���j���[�g���́u�R�q�[�����g���v�ł͂Ȃ��m�C���R�q�[�����g���n�Ŋώ@����Ă���
���킯�ŁA��L�́m�u�R�q�[�����g���v�ł����N����Ȃ��悤�Ȍ��ۘ_�n�Ƃ����̂�
�S���t�ŁA�M�a���\��t�����T�C�g�́A�R�q�[�����g���ɂ��Ă̘b�������A
�{���ƊW�������ƂɊւ��ċL�ڂ�����̂ł���B
�M���́A���ɑ��ăs���g������Ă���Ȃ�Ə������̂ł����A�M���̕����r���ڒ�����
�T�C�g���o�����̂Ō������܂łȂ̂ł����A�ǂ��܂Œp�̏�h������炪����C���ςނ̂ł��傤�H
�����Đ���A�|���_�n���́A�R�q�[�����g���Ǝ��R���̋�ʂ����Ă��Ȃ��Ǝ��͌����Ă���̂ł��B
�P�F���̘b�������ƌ������Ƃ���A�X�Ƀ|���_�n���́A�P�F���ƃR�q�[�����g���̋�ʂ���t���Ȃ����Ƃ�
�����Ŗ����ɂȂ����킯�ł����A�ǂ��܂Řb��c�Ȃ����āA�����̖��m�����炯�o�������̂�
���͂������������̐��E�ɓ����Ă��܂��B
�����ł����ǁA���́A���[�U�[����LED�����P�F�����R�q�[�����g�������R�����S����ʂ�
�����̈Ⴂ���������Ă܂�����ˁB
���R���[�U�[�ALED�A�u�����A�d�����X�̔��������܂߂Ăł��i�j
����Ȏ����A���[�U�[���ƒP�F�����������ď������Ƃ́A�������P�F���Ȃ�Č���Ȃ������b��
�˂�����Ȃ�āA���x�̎��Ȃ��疳�m�����炯�o���Ȃ��瑼�l�̂����ɂ���Ȃ�č����Ȃ��Ǝv���܂���
�|���_�n���́A���[�U�[���̔��������͂������A�u������LED����������LED�Ɩ��̌��̔���������
�X�y�N�g�����A�Ȃ�ɂ��m��Ȃ��ł���H
2011/09/28 00:34�@[13556532�n
�����o���r�[�m��
�����Ȃ��̈��p���郊���N���s���g�O��Ȃ̂��Ƃ��Ă��C�ɂȂ�̂ł����A�j���[�g�������O��
���������������������F���ł��u����Łv�C�������ۂł��B
��http://www.keirinkan.com/kori/kori_physics/kori_physics_1_kaitei/contents/ph-1/4-bu/4-3-4-1.htm
�����Ȃ��Ƃ��A�l�K����掆�Ɉ����L�����o��������l�Ȃ�A�����L���@�̏W�������Y��
���Z�b�e�B���O���Ƃ��A�����T�C�Y�p�̃K���X���̃l�K�z���_�[�ŁA�j���[�g�������O����������
�����܂��o��������͂��ł����ǁA�������������H�͑S�����@���Ă���݂����ł��ˁB
���ꂩ��A
> �`�}�E���g���������ł����ǁA�t�����W�o�b�N�������ł�����A�܂��L���ł��ˁB
> �������A�d�}�E���g�̓t�����W�o�b�N���Z���ł�����A�]�������Y�ʂɐv
> ���Ă��܂��ƁA�����̔����̓}�E���g�ɎՂ��Ă��܂����ɂȂ�܂��B
> �t�H�[�T�[�Y��150mm/F2�Ɠ����悤�ȃ{�P��������̂́A���C�J���T�C�Y�̏ꍇ
> 300mm/F2.8��F4���i�����ꍇ�ł�����A�������{�P��~�����ꍇ�͓������A
> �ނ���t�H�[�T�[�Y�̕����L���ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B
���@���A����͂܂��ʔ������b���B
�@�ڂ��݁A�ƃ{�P�Ƃ͎��͋�ʂ��Ă����ł����ǂˁB
�@�����ł́A�ڂ��݂���Ȃ��A�n�b�L���ƃ{�P�Ƃ���܂��ˁB
>
> ���ɂ͉�ʎ��ӂ܂ʼn~�ɋ߂��{�P�łȂ���Δ������{�P�Ƃ͎v���Ȃ����߁A���C�J��
> �T�C�Y�ł͓_������F2��薾�邢�����Y���g���či��J���Ń{�P�����ĎB�e���邱�Ƃ�
> �l�����܂��A���Ȃ背���Y��I�ԕK�v������悤�Ɋ����Ă��܂��B
> �������{�P���~������A�����T�C�Y��I�����ǂ��Ɗ����Ă��܂��B
>
�@�ł������ł͔������{�P���~������A�����T�C�Y��I���������ƁH
�@��ł�
�@> �t�H�[�T�[�Y��150mm/F2�Ɠ����悤�ȃ{�P��������̂́A���C�J���T�C�Y�̏ꍇ
�@> 300mm/F2.8��F4���i�����ꍇ�ł�����A�������{�P��~�����ꍇ�͓������A
�@> �ނ���t�H�[�T�[�Y�̕����L���ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B
�@�t�H�[�T�[�Y�̕����D�ʂƌ����Ă܂���ˁB
�@
> �������}�E���g�Ƃ��đ����̃��[�U�[���s�s���Ȃ��g���Ă���A�}�E���g�����Y���S�āA
> �����w�I�ɂ͂Ȃ�̖����Ȃ��A���̂܂g�����ˁA�}�C�N�������Y���������肷��
> ���K�v���Ȃ����
>
> �����A�����Ă���̂Ȃ�A����ŏ\�����Ǝv���܂��B
> ���̊�Ƒ傫���قȂ��Ă��邾���̘b�ł��B
�@�������AF�l�́A�����Y�K�i���ς���Ă�F�l��F�l�����A
�@�C���[�W�T�[�N���B�����A�N���b�v�����l�Ȍ`�ŃC���[�W�Z���T���������ꍇ�A
�@�{�P�̋�����������ƌ����`�ɂȂ���Č��_����Ȃ������̂ł��������H
�@
�@�܂��A�܂�������S�{�ɂȂ��ĕԂ��Ă���Ǝv���܂����A���ꂾ���m�I�ƌ���ꂽ
�@�|���_�n�����A����Ȃɖʔ������e�����Ă����������̂ŁA�ꉞ�w�E���Ă݂܂�����i�j
�@
�����ԍ��F13572574
![]() 1�_
1�_
���ꂩ��A�܂ȂĂ����\��t���Ă����������A���܂˂��ڂ��̃T�C�g�̎ʐ^��
�_�����́ALED�Ɩ��̂͂��ł��B
���āALED�ƃ��[�U�[�̈Ⴂ�A�͂��܂����R���̈Ⴂ���|���_�n���ɂ͂��̂��ȁH
�u�R�q�[�����g���Ƃ́v�ŁA�l�b�g�ł�`�����ׂĂ���܂��u�t���Ă��n�v���Ă��������ˁB
�łȂ��ƁA��ɋM�a���\��t�������̃T�C�g�̂̂��Ɠ���
2011/09/28 00:34�@[13556532�n
�����o���r�[�m��
�����Ȃ��̈��p���郊���N���s���g�O��Ȃ̂��Ƃ��Ă��C�ɂȂ�̂ł����A�j���[�g�������O��
���������������������F���ł��u����Łv�C�������ۂł��B
��http://www.keirinkan.com/kori/kori_physics/kori_physics_1_kaitei/contents/ph-1/4-bu/4-3-4-1.htm
�M�a�͂ȁ`��ɂ��킩���ĂȂ��ƌ����ؖ��ɂȂ����Ⴂ�܂�����ˁB
�����ԍ��F13572634
![]() 1�_
1�_
Tranquility����@
�������A�M���̌����Ă��邱�Ƃ������Ȃ�A�M�a�����ނł��B
�����āA�M���͋Z�p���o�b�N�ɐ�������Ǝ��g�ł�����������ł͂���܂��H
������������ɁA�v�����݂ŏ����ꂽ�̂ł͑��l���܂�����ނ̂�
����I�Ȗ��Ȃ瓖���ғ��m�̘b�ŏI���܂����A�Ԉ�����b�����ɂԂ��܂���
��������������������ƌ����̂��Ԉ���Ă���ƌ����Ă���̂ł��B
���͎�|���ѓO�������ł����A�M�a�͂˂��Ȃ����Ă��Ă���悤�ȋC�����܂��B
�����ԍ��F13572650
![]() 1�_
1�_
�o���r�[�m��
On Bullshit�Ƃ����{������̂ł����A�����̂ň�ǂ������߂��܂��B
True>Lie>>>>>>>>bullshit�ł��B
�e�N�j�J���Ȃ��Ƃ̓L���b�`�A�b�v�ł��܂���
���̃o���r�[�m��̕��͂ɑ���]����bullshit�ł��B
�v���t�F�b�V���i���Ȃ�q���ɂ��킩��V���v����
���͂����肢���܂��B
���邢�P�œ_�����Y�Ō���̔ʃ����Y�����Ă��ǂ�����
�ƂĂ��d�v�ȕ������Ǝv���܂��B�{�P�\���ɂ�����邩�炱����
����a���ƍl����ƂȂ����炱�̕����͖����ł��Ȃ��ƌl�I�ɂ�
�v���Ă��܂��B
���邠���肩��_�����ڂ����Ȃ���莝���̃����Y��GF2�ŕ]������
�݂悤�Ǝv���܂��B���A����14/2.5�i��3���g�p���j������܂��B
��AF-S 17-55/2.8�̃^�}�l�M�͗l�́u�ځv������ďd�Ȃ��Č����錏
�����莝���̋@�ނŒǎ����Ă݂܂��B
�����ԍ��F13572781
![]() 9�_
9�_
�����i�܂ȂĂ��j����
���̓v���ł͂Ȃ��̂ł����S���������i�j
�v���Ǝ��͌������o���͂���܂����B
�Z�p�ƒm���͎������킹�Ă��܂����A�F���炨�����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂�
�����Ńv���ƌ�����̂ɂ́A��R������܂��B
���ꂩ��A�u�킩��₷����������v�ƌ����͕̂ʂ̈Ӗ�
���m�Ȑl�̕������̉��i���ł��̂ŁA���͕������������܂���B
���ɂƂ��Ė��Ȃ̂́A�Ԉ���Ă��邩�ǂ����ł��B
����ƁA�c�_�Ƃ����̂͒�`�t������Ϗd�v�ł��B
�܂ȂĂ�����̂��܂˂��{�P���ǂ��������̂������Ă���̂��A��`�t�����{���K�v�ł��B
�{�����Љ�Ē������̂Ŏ������Љ�܂��B
���m�̒m�Ƃ����̂�m���Ă��܂����H
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%9F%A5
����͖{�ł͂���܂���̂ŁA�����K�v�͂���܂����B
�����������ǂ��܂Œm��Ȃ����m���Ă���ƌ������̂ł��B
�������A�����S�Ă�m���Ă���Ȃ�āA�����Ă����܂��A�|���_�n����
�ǂȂ����̗l�ɁA����͂������ƌ����Ă����Ȃ���A�c�_�̍��������`�����������Ă���
���̂��������肷�����ł��B
�e���Z�����͑O�ʂȂ�Ė����Ă�����Ƃ��B
�O�ʂ́A���̃����Y�̌��̎�荞�݊܂߂āA��`�Â��ł��B
�O�ʖ����Ńe���Z����������Ȃ�Č����̂́A�y�䂪�Ȃ��Ƃ݂����ȃ��m�ł��B
���肦�܂���i�j���{�I�ɊԈ���Ă��܂��B
���́A�����̂܂ȂĂ�����̎��₪���������瓚�������m�ł��B
�����āA�����̂��܂˂��{�P�̎���̒�`�Â����B�����������߁A�����̕����L��
�����̒m�����������킹�Ă��Ȃ������𗝉����邱�Ƃ��{���o���Ȃ��Ƃ�����������ł��B
�m�����������킹�Ă��Ȃ��l�ɁA��̖���m��Ȃ��l�ɂ��������o���Ȃ��̂Ɠ����ł��B
�X�ɁA������킩��₷���������낾�Ȃ�āA�܂���Ȃ�ɂ��ꂪ�o���Ă��A
���́A�w�͂��Ă����̒m����g�ɂ�����Řb���Ă��܂�����ˁB
�܂��ɁA�w�ɉ����Ȃ�
http://mis.edu.yamaguchi-u.ac.jp/~math1/zukei/home/math25/0000/1-13.htm
�Ɠ����Ӗ��̌��t�����͂����Ă������Ȃ̂ŁA����̖����悤�ɂ��肢���܂��B
�����ԍ��F13572979
![]() 1�_
1�_
�����̂����Ƃ����Ӗ��Ńv���t�F�b�V���i���Ƃ͌����Ă܂���B
�������̋^��ɔ����Ă���_������Ȃ�Ȍ��ɑ���Ȃ�����������
�����Ē�����Ə�����܂��B�������A�o���r�[�m��̕��͂�
bullshit�Ƃ����Ӗ��œ���ł��B
���܂ȂĂ�����̂��܂˂��{�P���ǂ��������̂������Ă���̂��A��`�t�����{���K�v�ł��B
�ʃ����Y���g���Ă��郌���Y�œ_�������ڂ����ĎB�e�����ۂ�
�����{�P�̒��ɓ��S�~��̖͗l�����������Ԃ̃{�P�ƒ�`���܂��B
�����ċ^��͂ǂ����Ă�����������������Y���łĂ��Ȃ��̂��ł��B
��`�t���̗ǔۂ��܂߂Ē@���Ē�����K���ł��B
�����ԍ��F13573325
![]() 4�_
4�_
>�������̋^��ɔ����Ă���_������Ȃ�Ȍ��ɑ���Ȃ�����������
>�����Ē�����Ə�����܂��B
���܂˂��{�P�ɂ́A������ʃ����Y�ɂ���Ƃ͌����A���̑��ɂ�������������̂�����܂��B
�������A�{���́A�u�ʃ����Y���ƋN���錻�ہv�Ƃ��ē������b���f���Ă��܂��B
�V�O�}�ŋN����₷���b�ƁA�L���m���ł��N����b�B
�����āA�������e������b���X�A�ꍇ�������{���K�v�ł����A�S�Ă���������ɂȂ��Ă��܂��B
�ł��̂ŁA�ǂ̃����Y�ŋN�����Ă���b�́A�ǂ̏�Ԃł̎����Ȃ̂����`���Ȃ���Ȃ�܂���B
����āA��̂������̎���́A�ǂ̓_�̉��������Ă���̂��́u�ݖ�v�ł�����A
�����Ē����Ȃ��Ă͘b���i�܂Ȃ��̂ł��B
�����A�f���Ɏ����A�Ȃ�ƌ����悤�Ƃ��f���ɓ����Ȃ��̂́B
�P�D�����̎���̍ۂ̎���̕��͂��B�����������߁A�����������ɑ���
�@�@�P�Ɂu���̂��Ƃł͂Ȃ��v�Ɛ��Ď̂Ă����ƁB
�@�@
�Q�D���܂˂��{�P�ɑ��āA��������߂čs���n�߂��Ƃ�
�@�@�u���̌����ɂ��Ă͂킩���Ă��܂��E�E�E�v�Ɛ؍퍭�̘b���������ƁB
�@�@
���ʘ_�ł����A���܂˂��{�P�ɂ��ẮA�P���Șb�ł͂���܂���B
����ł����Ă��A�����炷��A�؍퍭�܂߂Ă����g�Ƃ��āA�����ł���m���Ă���ƌ����̂Ȃ�
�����܂ł͎��Ƃ��Ă͂킩���Ă��邪�A���܂˂��{�P�̗��R�����ꂱ�ꂱ�����������R����킩��Ȃ���
��������Ə����ĖႦ��A�����Ƒf���ɉ����Ǝv���܂��B
���ɁA�u�����ČN�v�Ƃ��Ďf���Ă��Ȃ��̂ŁA�ߓx�ɂƂ��v���܂����A
�����̓�����̋M�a�̕��͂̐S�͗ǂ��Ȃ��������Ƃ͎����ł��B
�c�_�A���_�������ꍇ�ƁA�킩��Ȃ��b�������ė~�����ƌ����ꍇ�ł́A�b���Ⴂ�܂��B
�v���Ƃ��ĂȂǂƁA���r���[�Ɏ����グ���āA��L�̗l�ɐS����������ɑ���
�n�C�����ł����Ɠ�����ł��Ȃ��̂����̎v���ł��B
�Ƃ͂����A���̂���l�Ƃ͈���āA�����ɖ��Ƃ��đΏ����Ă�����_�B
����ƁA�w���͕ʂƂ��Ē����ɂ킽���āA�{�ۑ�ɑ��Ď��g��ł���ꂽ�_�ɂ��Ă�
�������Ă���A���̕ӂ̐܂荇���Ƃ��āA���̕��Ƃ͋M�a�ɑ��Ă̓���������Ⴄ�̂�
������l�����Ă̘b�ł��B
�S�������āA�M���������Ƃ���̃v���ł������Ƃ��Ă��l�͐l�ł��B
���Ƃ��Ė`������ꕔ�s�����Ɗ����������ɑ��ẮA�����������������������B
�����ԍ��F13573623
![]() 1�_
1�_
���ʃ����Y���g���Ă��郌���Y�œ_�������ڂ����ĎB�e�����ۂ�
�������{�P�̒��ɓ��S�~��̖͗l�����������Ԃ̃{�P�ƒ�`���܂��B
�����A���ꂪ�`������o�Ă���ΐ����̎d�����ς�����Ǝv���܂����A
����ƂȂ��Ă͂��ꂾ���ł́A��`�Â��͊Â��ł��B
����A�ǂ��Ӗ��ł����A�܂ȂĂ�����̒m�����x���͍������Ƃ͗������Ă��܂��B
���̈Ӗ��A�^��̃��x���������ƍl����ƒ�`�t�������ƂȂ��Ă͊Â��̂ł��B
��̓_�ŁA�������uLED�v�d���ł���̂��A���H�̔��˂�A�t�̐�[�̐��H�̔��˂Ȃ̂�
�����Ɍ�����u�̂Ȃ���̐M���@�v�̌��Ȃ̂��A�uLED�̐M���@�̌��v�Ȃ̂�
�e�[�������v�̌��́uLED�v�Ȃ̂��A���ʂ̃����v�Ȃ̂��B
�����āA�����Y�͉���p���āi���[�J�[�A�^�ԁj����̂��A�ǂ̃����Y�̂ǂ����������܂˂��{�P�̏ꍇ�Ȃ̂��B
�B�e�ꏊ�ƁA��ʑ̂ɑ���p�x�͂ǂ��������p�x�ŎB�e�����ꍇ�Ȃ̂��B
���X�ŏꍇ�������K�v�ł��B
���܂˂��{�P�ɂ��ẮA�����Y�\���ł��ς���Ă��܂��B
����āA���x�̍����{������܂����A��̃L���m����F1.2�ł�����Ɗ����Ă���Ƃ����
���Ȃ背�x���̍������܂˂��{�P�u�����v�̘b��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
���ʃ����Y�ł����ꂪ�o��̂��o�Ȃ��̂��܂Ŏ�����f���Ă��܂����A
�����Ƃ��Ă̗��R��A�W������e�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
����āA�����������ɑ��ďꍇ�킯�����Ő������悤�Ƃ���ƁA�Ђ��[����
���̌����Ɨ��R��������Ă����Ȃ���Ȃ炸�A���̂������J�͂�������܂��B
�����_�ł́A�؍퍭���X�ɂ��Ă̘b�ɂȂ��Ă��܂��B
�{���������A�u�����؍퍭�ƌ������́v�Ɓu�܂ȂĂ�����̌����؍퍭�v�̈Ӗ�������
�Ⴄ���Ƃ��r������킩�����Ƃ������A�܂ȂĂ�����̌����؍퍭�́A�؍퍭�Ƃ͌ĂȂ����̂�
�܂ȂĂ�����̍l���Ă���u�����L���Ӗ��ł́v�؍퍭���m���Ɉꗝ����Ƃ��v���Ă��܂��B
����ɂ��ẮA�m���ɃV�O�}�ŏo�₷�����R�ɂ͓��Ă͂܂�܂����A���܂˂��{�P��
�S�Ă̌����ł͂Ȃ��̂������ł��B
�����܂��āA��������ɑ��ĉ��n�߂�Ɓu����́E�E�E�v�ƌォ��b���o���Ă���̂�
�������Ȃ��ƁA����ɂ��āA�����Ɛ������o���Đ������f�������Ǝv���Ă��܂��B
�P�Ɉ��̈ꎖ�ۂɂ�����A�����I��肾�������グ��Ȃ�ʂł����A�M�a�͍��{�I�ɂƌ���
�l���������Ă���悤�ł����A�\�Ȃ璼���Ȃ����ƍl���Ă���悤�ł��B
�����A�ŏ��ɑf���ɉ����Ă��镔��������̂ł���B
�����A���܂�ɂ��b�̌����̉����ɑ��Ē��т����Ă���̂ŁA�킩��Ȃ������ł��傤���ǁB
NC�}�V���iNC���Ձj�̐��\�ƊW������ƁB
�Ƃ肠�����A���̍����̋C���I�ɂ͂����܂łł��B
���e�͂��������B
�����ԍ��F13573668
![]() 1�_
1�_
���ꂩ��A���ۂ̗��������ꍇ�A�����g�ŎB�e�������̂Ȃ�A
�ʐ^���炢�����ސ��o������̂�����܂����A�B�e���Ԃ�B�e�����ɉ�����
�J�オ��̎ʐ^�Ȃ̂��A�t�ďH�~�̂��̎����Ȃ̂��������Ă��������B
�܂��A�Ӓn�����Ə����ꂻ���Ȃ̂ŁA�f���ɏ����Ă����A�u���莖��̏ꍇ�v
�u��C�̃`���̗ʁv�ɂ��ꕔ�W���Ă���Ƃ��낪���邩��ł��B
�܂��A��B�e��i�ꖇ�̎ʐ^�j�̖��������Ė{���̘b��i�߂�̂��A
����̃����Y�ɂ�����������̘b��i�߂�̂�
�͂��܂��A���{�I�ɖ��������������̂��ŁA��`�Â����ς��܂��B
���̑O�ɁA�܂��͂����g�ŎB�e���ꂽ����������ė~�����̂��{���ł��B
��`�Â������Ă��������ƌ����Ă��A�����ǂ����킩��Ȃ����Ƃ�����ł��傤����ˁB
�ł́A���肢���܂��B
�����ԍ��F13573805
![]() 1�_
1�_
���т��тł����B
���ꂩ��A�܂ȂĂ�����B
�M�a�́A�|���_�n���ƈ���ăR�q�[�����g���ɑ��Ă�����x�m���������Ă���Ǝv���̂ł����A
�R�q�[�����g���͂�����x�ł����A��������Ă��܂����H
LED�ƃ��[�U�[���̈Ⴂ���킩���Ă���A�������Ă�����̂Ƃ��܂��B
�Ӓn���ł͂Ȃ��A�{����������邽�߂ɕK�v�Ȃ��b������ł��B
���ƁA�{����͂܂ȂĂ����畷���Ă��܂��̂ŁA�܂ȂĂ�������m�����x�����Ⴂ�l
�|���_�n���͓��R�Ƃ��āATranquility����ɑ��Ă��u�킩��₷���v�Ɗ���������܂���B
�����܂ł��܂ȂĂ����A�[�����郌�x���ł̉Ƃ��܂����A�����ł���ˁB
�����ԍ��F13573851
![]() 1�_
1�_
�ł���ΊT�_�Ƃ���3�s���炢�ł܂Ƃ܂��Ă����Ƃ��肪�����ł��B
�匳������������A�e�����Y�̊e�_�͌ʂɑΉ��ł���Ǝv������ł��B
�R�q�[�����g���ɂ��Ă͐����ł���قǗ������Ă��܂���
���܂˂��{�P�̊ϑ��ɂ̓��[�U�[������ԂŁA����
LED��i�g���E�������v�Ȃǂ̒P�F���������Ă��āA���z����
���M�d���͂��܂˂��{�P���ϑ���������Ƃ��Ă͌���Ǝv���Ă��܂��B
�������ɂ������āA���[�U�[���͈����Ȃ�Ă��Ȃ��̂łǂ�����
�����̂��킩��Ȃ��ł��B���[�U�[�|�C���^�[�ł��ǂ����ɂ����Ċϑ�
��������̂�������Ȃ��ł����ǁA�莝�����Ȃ��ł���
�����I�ɂ�LED���C�g���ł��邾�������ɂ����āA������ڂ�����
�B��̂������������Ƃ��Ă͈�Ԃ悢�悤�Ɏv���Ă��܂��B
���ƁA�������܂˂��{�P�ɐ������̂�����Ȃ�m�肽���ł��B
���S�~��̃{�P���炢�����\��������܂��A�Ȃ�Ƃ����ۂƂ�
�Ȃ�Ƃ��Ƃ������P��ŕ\����Ȃ�A���̎��ӂ���ł��܂��B
�����ԍ��F13574359
![]() 5�_
5�_
���̕��ƈႤ�Ƃ��낪�_�Ԍ������̂�
����͑�ڂɌ��܂��B
����ɂ��Ă��O�s�ˁi�j�B���݂ɉ��L���S�Ăł͂���܂���B
�����A�b�̗��ꂩ��܂ȂĂ�����̋C�ɂ��Ă�����̂́A�ƌ������Ƃŏ����܂��B
���炭�g�ʎ����̈�ł��B�ʃ����Y�̌`�x�����ƂȂ��ċN���錻�ۂł��B
LED�̓R�q�[�����g���ł͖������m�́A�R�q�[�����g���ɋ߂�����������A���̒��i�����������ߓ_�����Ƃ��ċ��������A
���̉�܂��i�蕔���ŋN���鑼�A�����Y�R�[�g�ɂ�锽�˖h�~�������Â炭����p�x����̓��˂̏ꍇ���ꂪ�n�b�L���Əo�܂��B
http://www.olympus.co.jp/jp/lisg/bio-micro/terms/16.cfm
�ȏ�@�����܂ŁB
���܂��B
�ʃ����Y�ɂ�鐻����̖��Ƃ��āANC�}�V���Ő؍���H���s���ۂɁA�}�V�����x��
�O�D�P�ʂ����x�̐��x��������̂́A�v���x�͂�������������̂�ݒ肵�Ă��邽��
�}�V���Ƃ��ẮA�����_�ȉ��̐��x�O�̒l�͊ۂ߂ē���i�l�̌ܓ��I����j���邱�Ƃ���A
�K�i��̒i���ł͂Ȃ��A�g�ł���������B
����͎g�p����}�V�����Â��}�V�����g���Ƃ�茰���ɏo��B
�i���́A���^�̏ꍇ�������Ă��A�؍펞�̋����ւ̎c�����͂ɂ��ώ����Ă��܂����ߒi���͎c��B
�Ɏq���H�Ȃǂ̏ꍇ�́A���̌㌤������Ίɘa����邱�Ƃ����邪�A���^���H�Ƃ͈Ⴂ�A
�����H���邽�߁A���H���x�����^�����������H���Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A������̒i����
���ʂ͏o��B
�i�ʃ����Y��NC�}�V���ł������H���o���Ȃ��j
����āA�����̓}�V���̓��쐸�x�̖��Ƃ̊W�܂��́A���H�R�X�g�i���x�j�Ƃ̊W�ɂ����
�����邱�Ƃ�����B
���[�J�[���t�H���[����A�������x�M���M���Őv���A�����ł��@�B���x��́A�덷�[���ō��グ���͂��Ȃ̂�
�ʏ킱����؍퍭�Ƃ����^���Ƃ��ĂȂ��B
�J��Ԃ��܂����A�����͂��ꂾ���ł͂���܂���B
�C�ɂȂ��Ă���ł��낤�_�ɑ��Ẳ��x���ł��B
�����ԍ��F13574510
![]() 1�_
1�_
�܂��A������Ȃ��������̂�����Ȃ̂ŏ����Ă����ƁA�ʃ����Y�ŏo�₷���̂́A
�ʃ����Y��
http://www.sumita-opt.co.jp/ja/products/molding/about-aspheric-lens.html
���̃����Y�ƈ���āA����Ȍ`�ŏW�������Ă���A���ʃ����Y�������̓�����
�ꖇ�ł���Ă̂���B
�t�Ɍ����A���ʃ����Y�̐��x�Ŕʃ����Y��������ꍇ�A���̌덷������
��������ďo�Ă���Ƃ�������B
���̎ʐ^�̏ꍇ�ALED�d���̌��������ɂȂ����\��������B
�E���ł��܂˂��{�P���o�Ă��Ȃ��̂́ALED���Ƃ͌����ALED�d���̎߂���̎U�������E���Ă���\������������
���ۂƂ��Č����ɂ��������Ǝv����B
LED���̏ꍇ�A�����Y�R�[�g�������Ȃ��������́A�t�Ƀ~���[�ɂȂ��Ă��܂��ꍇ������B
�R�[�e�B���O�͂P�^�S�ɂ̔g���ł́A���˗��������Ȃ�B
http://www.cvimgkk.com/products/pdf/01-guide/cvimgkk-guide5_all.pdf
�����̃R�[�e�B���O�������ꍇ�A�߂Ɛ��ʂ���ł͌�������̃R�[�e�B���O�����ω���
���˗����قȂ�B
����́ACD��DVD�����F�Ɍ����錻�ۂƓ������́B
�����Y�R�[�g�́A�O���[����b�h������g���ɕ����������˃R�[�g�����Ă���ꍇ������
�R�q�[�����g���Ȃǂ̓���Ȍ��̏ꍇ�ł́A����炪�t�Ƀ~���[�Ƃ��ē����ꍇ������B
�����Y���Ŕ��˂��N����ƁA����͎U�����Ƃ��Č�����B
�_�����ł̃{�P�́A�����Y���ł̌��̋O�Ղɋ߂��A���ꂪ���܂˂��{�P�Ƃ��Ċώ@����Ă���ɉ߂��Ȃ��B
��̎����ŁA�g���ɂ��A�Ⴄ���ʂ��o���̂͂������N�����Ă���͂��B
�Ɏq��v���X�`�b�N�̏��ނ́A�K�����������ł͂Ȃ��B
�v���X�`�b�N��Ɏq�͒ʏ�A�����t�@�X�����A�Ǐ��I�Ɍ������u���v���ω����Ă���ꏊ������
���ꂪ�h�炬�Ƃ��Ċώ@�o����ꍇ������B
���̑��A�R�قlje�������鎖�ۂ����邪�A�Ƃ肠�����ŏ����ŁA�����͂����܂ŁB
�����ԍ��F13574657
![]() 0�_
0�_
����ƁA�|���_�n���܂߂āA�e���Z���������ۂɁA�����̐l�������Y�Ɂu���v��������
���������A���̌��͂����ɏW�܂��āE�E�E�Ɠ����Ă��邪�A���͔g�����������Ă���̂�
�{���̋����͂���ȂɊȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�R�q�[�����g���ɂȂ�Ƃ���͂����������������B
�����́A����g���Ƃ��ĂƂ炦�A�Q�����ȏ�̍������ɂ��čl������m�����������
�u�v���o���Ȃ��v
�����Y�ɊȒP�Ȑ������������āA�����}�E���g�ƃ����Y�̐v���o����̂Ȃ�A
�Ȃɂ��|���_�n�����łȂ��Ƃ��f�l�ł�����B
�ɂ��ւ�炸�A�R�q�[�����g�������������o���Ȃ��|���_�n���u���v���炠�ꂱ�ꌾ����
�ዉ�Ȑv�����[�J�[���u�P�v�I�Ɏg���v�}�E���g�ɂ���͂��������B
���[�J�[�́A�|���_�n���������قǃo�J�ł͂Ȃ��Ƃ����́A�����q�ׂĂ����܂��B
�S�Ăɂ͗��R������̂��ƁB
�����ԍ��F13574699
![]() 1�_
1�_
���o���r�[�m��@
���܂�ɂ��o�J�o�J�����̂ŁA���X����C�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł����ǁA
�^�U�f�ł����˂�l�̂��߂ɏ�������ł����܂��B
�Ƃ肠�����A�t�[���G�ϊ��Ɋւ��ẮA��啪��ł��B
FFT�iFast Fourier Transform�j�����t�[���G�ϊ��́A���R����������
�v���܂����ǁA����@�͉����������ł����H
�P�ɁA�t�[���G�W�J�Ƃ�������ꂽ�����ł����H
�����g���Ă����g�o�̂e�e�s�̉摜���t�o���Ă����܂����ǁA������
�ł��傤���B
���܂��A���܂˂��{�P�̐����Ƀj���[�g�������O���o���Ƃ��납�炵�ĊԈႢ�i�j
�����ʃ����Y������A�R�q�[�����g���̌��ۘ_�����Ȃ�A�f�l�̐������Ń����Y�̌`����
���ސ��o���邱�Ƃ�����ł��傤���A�����͕����̔g���̌��̏W�܂�ŁA�Ȃ������[�U�[�̂悤��
���R�q�[�����g���ł͂���܂���ˁi�j
2011/09/27 21:59�@[13555650]
���̃��X�œˑR[�R�q�[�����g��]���o���Ă��܂������ǁA�Ӗ��s���ł��B
http://www.keirinkan.com/kori/kori_physics/kori_physics_1_kaitei/contents/ph-1/4-bu/4-3-4-1.htm
�̃����N�ɂ́A[�j���[�g�������O]�̋L�q������A�����Ƀi�g���E������
���F���̉摜���ڂ��Ă��܂�������p�Ƃ��Ă͂ӂ��킵���Ǝv���܂���
���̎���[���̊���]�̋L�q������܂�����A�X�y�b�N���E�p�^�[����
�^�}�l�M�{�P�Ƃ͊W�Ȃ��̂ł͂Ƃ��������̈�ɂȂ�Ǝv���܂��B
���ƁA���C�g�ȂǂɎg���Ă���LED�iLight Emitting Diode�j�̔�����
�g����U���ɂ��������̂ŁA�R�q�[�����g���ł͂Ȃ��ł��B
LD(Laser Diode)��CD�v���[���[�ȂǂɎg���Ă��܂����ǁA�Ɩ��ɂ�
�s�����ł��B
�����i�܂ȂĂ��j����A�����́B
�����܂˂��{�P�̊ϑ��ɂ̓��[�U�[������ԂŁA
���[�U�[��(�R�q�[�����X���������j�͖ڂɓ���ƖԖ��Ɉ����e����^��
�܂�����A�~�߂Ă����������ǂ��ł���B(^^;;
��ԃn�b�L������͓_�����ł�����A�ԁA���A�A�A���̍��P�xLED
���œK���Ǝv���܂��B
P.S.
���o���r�[�m��
���l�̉摜������Ɉ��p����͎̂~�߂Ă����������ǂ��Ǝv���܂��B
���[�J�[�������\���Ă���}�Ȃ�n�j���Ƃ͎v���܂����c
�����ԍ��F13574997
![]() 9�_
9�_
���[�U�[���œK���Ǝv�����̂�
http://homepage3.nifty.com/cz_telesco/testkiki.htm
�����Ɋ��Ƃ������t�ƂƂ��ɂ킩��₷���摜���łĂ�������ł��B
���Ɓu����͌��w�ʂ����Ɋ��炩�Ɍ�������Ă��邱�Ƃ�\���Ă��܂��v
�Ƃ����\�������S�~�{�P���ł邫�ꂢ�ɂł郌���Y��
�s���g�ʂł͍��𑜂��Ƃ����Ӗ��Ŏ����ƍ��v���Ă��镔���ƁA�A�A
�{�P�����ł͂��肪�����Ȃ��Ȃ��Ƃ����C�����̂Q�ɂ킩��Ă��܂��B
���[�U�[�͎��ɂ͈�������Ȃ����A���������@�ނ��Ȃ��ł���
�������t���e���r�̓d��LED�ƉƂ̊O�̃A�p�[�g�̌u������
�e�X�g���ł��B
���g�ʎ����̈�ł��B�ʃ����Y�̌`�x�����ƂȂ��ċN���錻�ۂł��B
�g�ʎ����Ƃ����p��ɂ͂��߂ĂԂ���܂����B���L���b�`�A�b�v���ł��B
�Ƃ肠�����A�t�[���G�ϊ��Ɋւ��ẮA��O���ł��B
�C�m���w������啪��ł����@
�j���[�g���̌��Ƃ͂Ȃɂ��H���炢�����ǂ�ł���܂���B
GF2 14/2.5�̉摜�ƃg���~���O�摜���Ă����܂��B
�O�̃A�p�[�g�Ɖt���e���r�ł��B�ϑ��ɂ͌����ȊO�ɂ�
�����Ƃ������Ƃ����낢��t�@�N�^�[������܂��ˁB
�����ԍ��F13575528
![]() 5�_
5�_
���`�}�E���g���������ł����ǁA�t�����W�o�b�N�������ł�����A�܂��L���ł��ˁB
�������A�d�}�E���g�̓t�����W�o�b�N���Z���ł�����A�]�������Y�ʂɐv
���Ă��܂��ƁA�����̔����̓}�E���g�ɎՂ��Ă��܂����ɂȂ�܂��B
�u���ʂɁv�̈Ӗ���������܂��A��͂���������̂��Ǝv���܂��B
���ʂɍl����ATranquility��������x��������Ă�ʂ�A�t�����W�o�b�N�i���o�b�N�t�H�[�J�X�̍ŏ��l�Ɖ��肵�܂��j�͒Z���قǁA�}�E���g�a�͑傫���قǁA�����Y�v�̎��R�x�ƌ����Ӗ��ł͗L���ł��B
�Ă������A�`�}�E���g�ŕ��ʂɐv���ꂽ�����Y�����̂܂܂d�}�E���g�ŕ��ʂɎg������Ă̂̓|�����_�n��������ӂ��Ă��������Ă�̂ł���ˁH
���̈Ӗ��łd�}�E���g�͂`�}�E���g�̊��S��ʌ݊��}�E���g�ł��B�d�}�E���g���s���ȂƂ���͈������܂���B
���Ȃ݂ɁA�����l�����ŁA�d�}�E���g�Ƃl�e�s�}�E���g���ׂ�A
�t�����W�o�b�N�F�d���l�e�s
�}�E���g�a�F�d���l�e�s
�ł�����AMFT�ɗL���ȓ_�͈������܂���B
���_��AMFT�ɂł���NEX�ɂł��Ȃ����Ƃ��Ȃɂ�����܂����H�Ȃ��ł���ˁA����B
������MFT���[�U�[�ŁASONY���[�U�[�ł͂Ȃ����ǁA����͎����Ȃ���d������܂���B
���������AMFT�p�ɐv���ꂽ�����Y�͓����v��NEX�p�ɂ���܂��i�t�͖����j�B�t�@�[���A�b�v�Ńt�H�[�T�[�Y�N���b�v���[�h�lj�����A���̖����Ȃ��g���܂��BNEX7�̑f�q�̂܂�Ȃ���蔲���AE-P3�̂���Ƃ���ׂĉ�f�ł������x���\�ł�����f�q���ł��܂�����A�掿����肠��܂���B�����Y���ǂ��Ƃ��ŁAMFT�̕����K�i�Ƃ��ėD�ꂽ�Ƃ��낪����悤�ȋL�q�͊ԈႢ�ł��B
�������A�����MFT�ɗǂ��Ƃ��낪�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���i�����玩�������[�U�[�Ȃ킯�Łj�B�I�����p�X�͂����ǂ�����������ŁA�����Y�����C���i�b�v���Ă�Ɗ����܂��B
�����ԍ��F13576261
![]() 0�_
0�_
�s���z�[���Ōu�����i���j�Ɣ��M���i�E�j |
�O���i�������悻200m�`3km�j |
�O���i�������悻1km�j |
35mmF2.0���ʃ����Y |
��������
�^�}�l�M�ώ@���Ă݂܂����B
�g�p�����Y��COSINA��M�}�E���g�ANOKTON 35mm F1.2 Aspherical�i���^�j�B
������������Ƀ^�}�l�M�ɂȂ郌���Y�ł��B
�E�`�ɂ����[�U�[���u�͂���܂��A�����̃s���z�[���i��e�̃s�����^����1.5m�j�Ɖ��O�̊O�����B�e���Ĕ�r���܂����B
���ʂ͂����̒ʂ�A�����̎�ށA�F�A�����A��������܂������W�Ȃ��A�����^�}�l�M�ڂ��ɂȂ�܂��B
�O���Ń^�}�l�M�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂́A�����ɖʐς�����Ƃ���B
�����Ƃ���A�_�����ł���A����Ȃ��^�}�l�M�ɂȂ�܂��ˁB��������������Ώ������قǁA��������͗l���o��悤�ł��B
�������A�P�F���ł��R�q�[�����g���ł��Ȃ��A�܂������g���́g�́h�̎���������Ă��Ȃ������ł��B
�s���z�[���e�X�g�ł͓��œ_�����̋��ʃ����Y�ł������܂������A������ɂ̓^�}�l�M�͗l�͌����܂���ł����B
�o���r�[�m��
�������₷��ƕs�����ł��傤���c
�u�m�����x�����Ⴂ�v�������A�D�ɗ����Ȃ��Ƃ��낪�o�Ă���̂ŁA����������܂���B
>���炭�g�ʎ����̈�ł��B
��ʂȃ��X���₵�āA���ǁu�����炭�v�Ƃ̐����Ȃ�ł��傤���H
�g�ʎ����ŁA�����f�t�H�[�J�X���̌��ʃ����������o����̂ł����H
>�ʃ����Y�ɂ�鐻����̖��Ƃ��āi�����j�����_�ȉ��̐��x�O�̒l�͊ۂ߂ē���i�l�̌ܓ��I����j���邱�Ƃ���A�K�i��̒i���ł͂Ȃ��A�g�ł���������B
���ǁA�ʂ̐������x�������Ȃ�ł����H
�u�G�o�l�b�Z���g��̂悤�ȊT�O�̌��ہv�Ɓu�����Y�̌��݁v�͂ǂ��Ȃ����̂ł����H
�����ԍ��F13576343
![]() 11�_
11�_
Tranquility ����̉摜�f�[�^�Ɋւ���l�@
Tranquility����A�����l�ł��B
5,500�`6,500�x�P���r���Ǝv����u�����ƁA����3,000�x�P���r���Ǝv���锒�M����
�^�}�l�M�͗l�̃p�^�[�����A���̓���ł͂قړ����悤�Ɍ�����Ƃ������Ƃ́A�g��
�Ƃ́A����قLj��ʊW���Ȃ��悤�Ɋ������܂��B
�Q���ڂ̐ԐF���Ɋւ��ẮH���t���܂����c
�j���[�g���ŁA�j���[�g���̖��O���o�Ă���������������܂��ǁA�V�̖]������
�j���[�g�����v���������ˎ��]�������F�������瓦���ł��ȒP�ȉ������@����������
���l����ƁA�Ђ���Ƃ��āA�ʃ����Y����̔��˂��e�����Ă���̂ł͂Ƃ�������
�����藧�̂ł͂Ǝv���܂����B
�}���`�R�[�e�B���O��������O�ɂȂ��Ă��錻�݂ł́A���ˌ��̉e���͖������Ă���
�悤�ȋC�����܂����A�ǂ��Ȃ�ł��傤���ˁB
�I�����p�X��ZEISS�̃����Y�̏ꍇ�A�}���`�R�[�e�B���O�ɂ���Ĕ��˂�}����̂ł�
�Ȃ��A�z�����Ă���̂ł͂Ǝv����قǁA���ߗ����Ⴂ�̂��C�ɂȂ��Ă��܂����A
�Ђ���Ƃ��āA���̂�����̓������e�����Ă���̂ł͂Ƃ������Ă��܂��B
�����ԍ��F13576576
![]() 2�_
2�_
�|�����_�n����
�s���z�[���e�X�g�̔��M���́A���悻2500�P���r�����炢�ł��B
�ԐF���͓S���̑��Q���ł����A���ƈỄp�^�[��������Ɠ����ł��ˁB
�^�}�l�M�ڂ��Ɋւ��āA�g���͂܂������W�Ȃ��ƌ����Ă����Ǝv���܂��B
�����Y�̔ʂ���̔��˂��e�����Ă���\���ł����A�����Y�߂��ďœ_�����Ԍ��ɔ�ׂ�Δ��X������̂ł�����A������W�Ȃ��ł��傤�B
�œ_�̑O��A�œ_�����ƊO���ł́A���Ẫp�^�[�����t�]���܂��B���ʎ����̑傫�������Y�̊O�����W���ƒ������W�������]����̂Ɠ��l�ł��B�܂��A���R�ł��ˁB
�܂��A���S�~�̖��ẤA�œ_�O��̃w���R�C�h�̉��͈͓��ł́A�܂����������p�^�[���ő傫�����ς�邱�Ƃ��킩��܂����B
���ߗ��̒Ⴂ�Ƃ��������Y�́A�ǂ̂悤�ȃ����Y�ł����H
�ŋ߂̃Y�[�������Y�͍\���������ƂĂ������̂ŁA�z��������Ȃ�ɑ����ł��傤�ˁB
ZD7-14/4.0��ZD14-35/2.0��18���AZD35-100/2.0�ł�21�����g�p���Ă��܂��B����ȏɍނ��ƁA�z���̑������̂����邩������܂���B
�����A�R�[�e�B���O�͂��炵���AM.ZD12/2.0��ZERO�R�[�e�B���O�ȂǁA�O�����炾�ƃ����Y�������悤�ɂ������܂��B
�����ԍ��F13576704
![]() 2�_
2�_
ginganohikari����
���������Ăǂ����H
�����ԍ��F13576868
![]() 1�_
1�_
��������
http://homepage3.nifty.com/cz_telesco/testkiki.htm
�̃y�[�W�u���j�X�J�X180�̏œ_�O���̏ڍׁv�̊��摜�́u�W�t���N�V���������O�i��܊j�v�ŁA�]�����Ŋώ@����_�����̏œ_���Ƃ��̑O��Ō����܂��B�����Řb��̃^�}�l�M�͗l�Ƃ͈Ⴂ�܂��B
�W�t���N�V���������O�̐����̓o���r�[�m�Љ��
�u���ʎ����Ƃ́A�{�P�I�̎��ł��ˁB�v
http://blogs.yahoo.co.jp/solunarneo/29287129.html
�Ƃ�
�u�W�t���N�V���������O(��܊�)���ł���킯�v
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tomoyu/column/co018.htm
�ɂ��킵���ł����A�Ɍ��̐��\��ڎw���V�̖]�����ł́A�����O�����ꂢ�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�W�t���N�V���������O�Ƃ��œ_���O���Ƃ�����ׂ�ƓV���n�̃T�C�g�ɂ��ǂ蒅���܂��ˁj
�������A�J���������Y�͓V�̖]�����̑Ε����قǐ��x�����߂��܂���i�]�����Ƃ͈Ⴄ���\�����߂��܂��j���A�����Y���������������ɏœ_�������Z���ł�����A�W�t���N�V���������O�̌�������̂͂܂�����܂���B
��͂�o���r�[�m�Љ��
�u�œ_���O���e�X�g�̃y�[�W�v
http://homepage3.nifty.com/cz_telesco/syoutenzoutest.htm
�����܂��ƁA�O���[�����[�U�[�ɂ��œ_���O���Ɓu�i�C�t�G�b�W�^�i���e�X�g�v�̉摜������܂��B
���z�I�ɖ����ꂽ�����Y�┽�ˋ��́A�i�C�t�G�b�W�e�X�g��i���e�X�g�Ő^������Ɍ����܂��B
�i�t�[�R�[�e�X�g�������悤�ȃe�X�g�ŁA���ʋ�������Ɍ����܂��j
���̃e�X�g�Ő^������Ɍ����郌���Y�ł́A�œ_���O���̑Ώ̐����ǂ��A�����O�����ꂢ�ɐ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�u�c�A�C�XAPQ100/640 3���ʁv�ȂǁA�����ł��ˁI
����́A���ʎ������قƂ�ǖ������Ƃ������Ă��܂��B
�i�C�t�G�b�W�e�X�g��i���e�X�g�̉摜�ŁA���ʂ����S�~��ɓʉ����Č�������̂�����܂����A����͗��z�ʂ���̃Y�������邽�߂ŁA���̂悤�ȃY�����J�����̔ʃ����Y�ɂ�����̂��ƍl���Ă��܂��B
�����Y���g�p���������V�̖]�����ł��ʉ����ꂽ���̂�����悤�ł����A��͂蓯�S�~��̓ʉ���������悤�ł��B
http://homepage3.nifty.com/cz_telesco/refracter_test10-11cm.htm
�́u�c�A�C�XAS100/1000 2���ʕ������Z�~�A�|�N���}�[�g�v�ȂǁB
��ɂ������܂������A�����Y����ˏo���ꂽ�����̏œ_�t�߂̂ǂ����ɂ��Ă��^�}�l�M�ڂ��͑����ŁA�����O�̖��Õ��z�����������ł��B����́A�^�}�l�M�ڂ��̐��������̔g�̊��ł͂Ȃ��؋��ł��傤�B
���ǁA�^�}�l�M�ڂ����Ȃ����ɂ́A�ʉ����ꂽ�����Y�\�ʂ̓��S�~��̂��˂�����āA���炩�ɂ��邵���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13576992
![]() 6�_
6�_
nightbear����
�@����ɂ���
>���������Ăǂ����H
�@�������o�I�Ȍ����肩���茵���Ȏ戵���ɋc�_���[�܂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���邢�����Y���ڎw�����͈̂�̉��Ȃ̂��A�����Ă��̕K�v�����܂߂Ď�������ׂ̗l�X�ȉۑ肪��N��������Ɍ����Ċ����ȋc�_�����킳��Ă���l�q�͐��ɗ��������v���Ă���܂��B
�@�����ȋc�_�����킷�ƂȂ�ƁA
�@�@�@��`�m�ɂ���
�@�@�A��r��m�ɂ���
�@�ƌ������v�f�Ȃǂ��K�v�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�@�������Ȃ��Ɠ����v���b�g�t�H�[���ł̉�b�����藧���܂���B
�@�c�_�̐��ڂ����̂悤�ȕ����Ɍ������Ă���Ǝv���Ă���܂��B
���A�l�ł��낢��ƕ������Ă��������Ă���܂��B
�t�H�[�����ɎQ�����Ă��������Ă���F�l�ɐS���犴�Ӑ\���グ�܂��B
�����ԍ��F13577633
![]() 4�_
4�_
Tranquility����
�s���z�[���e�X�g�A�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂����B
���ł��ǎ��ł���͈͂ł��̂ł���Ă݂܂��B
������I���ɓ������ۂ��Č��ł��Ă���Ƃ������Ƃ͍��܂ł�
�o���ƍ��v���镔�����傫���ł��B
���[�U�[�Ŋϑ����e�ՂȂ͔̂g���̖��ł͂Ȃ��_�����Ƃ���
�D�G�����炾�Ɛ��������ق����悳�������Ɨ������܂����B
�ϑ��ɂ̓s���z�[���œ_����������Ă���Ă݂悤�Ǝv���܂��B
���܂܂ŃT�{���Ă��܂����B
�_�����̏��������d�v�ȃt�@�N�^�[�Ȃ炻�̕ӂɗ����Ă������
���������Y�ŏo��o�Ȃ��������̑傫���ŐU�蕪����ꂻ���ł��ˁB
>�����Y����ˏo���ꂽ�����̏œ_�t�߂̂ǂ����ɂ��Ă�
>�^�}�l�M�ڂ��͑����ŁA�����O�̖��Õ��z�����������ł��B
��铮��ŃJ������O�コ���ĎB�e�ł��Ȃ����Ǝ��s���낵�Ă����̂ł����A
�{�P�̑傫���ɔ�Ⴕ�đ����`�Ń^�}�l�M�ڂ���悤�Ɍ����܂����B
>���ǁA�^�}�l�M�ڂ����Ȃ����ɂ́A
>�ʉ����ꂽ�����Y�\�ʂ̓��S�~��̂��˂�����āA
>���炩�ɂ��邵���Ȃ��Ǝv���܂��B
��͂胆�[�U�[�Ƃ��Ă͏����Ɋ��҂��Ă�������̂��ȂƂ������܂����B
�����ԍ��F13578004
![]() 4�_
4�_
ginganohikari����
�m���ɂ��̒ʂ��ȁB
�킵�ɂ́A��߂��đS�R��������B
�����ԍ��F13578240
![]() 5�_
5�_
�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g
�c�������ł�(/�E�E)/
�����I�����p�X����n�K�L���͂��Ă��܂����B
���ɂ���A�����Ɖ���ł��Ă������ƂɈ��S���܂���(^3^)
���傳�ꂽ���A�������{�܂ŋC���ɑ҂��܂��傤�E�B�Eb
�����ԍ��F13511914�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�����ɂ����Ă܂����B
��t�����ςƂ������ƂłЂƂ܂����S�O�O
�����ԍ��F13513308
![]() 0�_
0�_
�C�t���܂���ł�����
���̉Ƃɍ���n�K�L���͂��Ă��܂����B
�y���݂ɂ��Ă����̂Œx��Ă���͎̂c�O�ł���
���̔��ʁA��t�����I�H�݂����Ȃ��̂Ȃ̂ň���S�ł��B
��͋C���ɑ҂݂̂ł���
�����ԍ��F13530198
![]() 0�_
0�_
��t�m�F�̘A�����Ȃ������̂ŕs���ł���ˁB
�����ԍ��F13533189
![]() 0�_
0�_
�����O�Ƀn�K�L���܂����B
�I�����p�X�̃L�����y�[���͒x��邱�Ƃ̕��������̂�
�C���ɂ܂��Ƃɂ��܂��B
E-5�̂Ƃ��قǂ͒x�������͂������ł��B
�����ԍ��F13533213
![]() 0�_
0�_
�ʂɘA�����Ȃ���HP�ł��l�т��ڂ��邾������C�����Ȃ�����҂��o�Ă��܂�����ˁ`�O�O
���������A���������Ƃ�鏊���ėǂ���ˁ��I�����p�X�O�O
���̂Ƃ���ɂ��n�K�L�����Ă܂����B
�����ԍ��F13550164
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g
|
|
��u�����ON,OFF�ł̈Ⴂ���ăA�b�v���܂��B
panasonic 14mm f2.5. AVCHD HD���[�h�ł��B
���̌��ۂɂ͂ǂ��������̗v�f�A�X�e�b�v������ł���Ǝv���܂��B
1 �Z���T�[���̗̂v�f ���[�����O�V���b�^�[���܂ށB
2 ���掞�̓d�q��U���ɂ��
3 �g���K�[�͎�u���A�����Y�t�H�[�J�X�̋쓮�H
��Ԃ̎匴���̓\�t�g�ɂ��d�q��U���ł��B
�����ON�ɂ���Ɖ�ʂ�����g���~���O������אU���͕����܂����傫�ȗh��A���ɍ��E�㉺�Ɍ�����������100%�p�x�ŃO�j�����ƂȂ�܂��B���ЊJ���Ȃ̂����C�Z���X���s���ł������炭���̃A���S���Y�����^�R�Ȃ̂ł��傤�B ���Ȃ݂ɉ掿���[�h��SD�����d�q��U���ON�ɂ������ł͔������x���y������܂����AAVCHD�ł͂ǂ�����x�͓����ł����B �d�q��U����OFF�ɂ����1�̗v�f���c��A�R���j���N�ɂ��Ă͂��Ȃ�y���Ƃ������A�����ł���J�b�g��������Ǝv���܂��B�������A�㉺�Ɍ������U��������GF1���E-P3�͑ϐ����Ⴍ���ۂ��o�₷�������ł��B
�I���ɂ́A���̃\�t�g���ǂ��܂�����Ă��炢�����ł��B
���i�A���P�[�g�ɂ͏����ĕԐM���Ă����܂����B
���̓����Y�ɂ�鍷������̂��H �ł��B
![]() 25�_
25�_
�����āA�L�b�g�����Y M.ZUIKO DIGITAL 14-45mm II R�ł��B
�w����낭�Ɏg�p���������Ă��܂����̂ŁA�H�t�̓X�ēX���i�����Ă݂܂����B ��ł͓d�q��U��ON, OFF�̈Ⴂ�� �R���j���N��U�������邽�ߑf�����p���ƈӐ}�I�ɏ㉺���E�ɂ��Ȃ�h�炵�Ă��܂��B�ߌ��ɗh�炵�Ă���̂ł킩��Â炢��������܂��AOFF�ł�������z�[���h���ĎB�e�����ꍇ�͌l�I�ɂ͋����郌�x���ł����B
���̕����O�X���ɂĎ�u��OFF�Ƃ��Ă�����Ǝ��͈Ⴄ��ۂ��܂����B �����A�O�X���̍�Ⴊ�d�q��U����ON�łȂ������Ƃ�����AE-P3�̌̍����l�����܂��B �s��i���ǂ����� �I�����p�X�����f���邱�Ƃł��傤���A����������ق��ĂȂ��ł��傤�B
���̑�25mm �莝���̃}�j���A�������Y���ׂ��܂������A��͂�
�d�q���ON�ŋ����U��������A�����Ă�蒷�œ_�قǃR���j���N�ɂȂ�Ղ��Ɗ����܂����B
�d�q��ׂ͍����U���͏������߂�̂ł����A�傫�ȗh��ɗ\�z�O�̏Ǐ�������N�����Ă���悤�ł��B���Ƃ����P���ė~�������̂ł��B
���A�A�l�I�ɂ͓d�q����g����悤�ɂȂ��Ă��p�i ��O.I.S�t���V�����Y�����ēd�q���OFF�ɂ�����������ł������ɍ��͍l���Ă��܂��B
�����ԍ��F13426286
![]() 16�_
16�_
���Ⴀ�肪�Ƃ��������܂����B
���̂d�o�|�R�����l�Ȋ����ł��B
����͐�����قǂ����g���Ă��܂��A��Ԃ����ĎB�e���Ă���̂ł���Ȋ����ł����B
��Ԃ�����Ă���ƈӐ}�I�ɍׂ����h�炷�ƍ����ɉ�ʂ��䂪�݂܂��B���̎���ʂ�ł��B
�ƂĂ����ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F13426399
![]() 6�_
6�_
������J���܂ł��B
�Ȃ�ł����R����
���������ł���E�E�E
�g�����ɂȂ�܂����
�����ԍ��F13427662
![]() 7�_
7�_
�m���A���R�[���ł��B
�����ԍ��F13427834
![]() 6�_
6�_
��Ԃ����Ă��Ђǂ��ł��ˁB
���̂悤�Ȃ��Ƃ��r�f�I�ł��邱�Ƃ����߂Ēm��܂����B
���O�̃R���f�W�iHX9V)�Ŏ����Ă݂܂������A�����ƃu���u���U���Ă��S����肠��܂���B
�n�[�h�I�Ȗ��ŃZ���T�[�̓ǎ摬�x������Ȃ��̂Ƃ��l�����܂��B
����2���~�O���1080/60P,60i���\�ȃR���f�W���T�u�Ɏ��������ăr�f�I���B�����ق����悢�Ǝv���܂��B�掿���ǂ��̂ɂ̓r�b�N�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13427987
![]() 4�_
4�_
�������낢�����ł��ˁI�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂����B
��Ԃ���OFF�ɂ���ƖڂɌ����ĉ��P����̂��킩�����̂ō��x�����Ă݂܂��B
��������Q�l�Ƃ��Ď�Ԃ�ON�̕��i�ł��B
��������z�[���h���ē������ƁA���܂茻�ۂ͋N���Ȃ��悤�ł��B
�ǂ̂��炢�̃X�s�[�h�ŐU��ƂՂ�Ղ邷��̂��͎����Œ͂�ł��������Ȃ��ł��ˁE�E�E
E-P3�ŗǂ����悪�B�ꂽ��E�l�|�Ƃ������Ƃł��傤����
���̌��ۂ́A�uPhoto of the Day�v�ihttp://thisistanaka.blog66.fc2.com/entry/502/�j�ł��G����Ă��܂��ˁB
�l�I�ɋC�ɂȂ�̂�E-P3���ߋ��̃f�W�J���̒��ł������ɂЂǂ��̂��H�Ƃ����_�ł��B
�t��HD�ɂȂ��Ďg���l�����������瑛����n�߂���ł��傤���H
�Ⴆ��GH-2��5D2�ł͂��̌��ۂ͋N���Ȃ��̂ł���A����@�Ƃ��Ă͑��А��i�������������ł��ˁB
�����ԍ��F13428493
![]() 6�_
6�_
����r�f�I�T�����Ƃ����G�������Ă�����A�~���[���X�@�̃��r���[���ڂ��Ă��āA���̋@��̓���ɂ��Ắu����@�̂��߂����悪�䂪��ł���v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂����B�p�i��\�j�[�@�̓���͍��]���ł������B�����͂��̋@���LUMIX�@G3�Ɩ����Ă��܂������A��������\�g�p���邽�߁AG3�ɂ��Ă悩�����Ǝv���܂��B���͓I�ȋ@��Ȃ̂ɂ�����Ǝc�O�ł��B�t�H�[�T�[�Y�@�ł̓p�i���I�����p�X�̋Z�p�𗬗p�����肵�Ă���̂ɁA�t�͂ł��Ȃ������̂ł��傤���B�i����ɂ��ăp�i�̋Z�p�����Ƃ����Ӗ��ł��j
�����ԍ��F13428569
![]() 4�_
4�_
E-P3�ł͂�����݂ŁA���̓���W�̔����R�ǂ�ł邾�낤�l�����ŋ����Ȃ���R�����Ă�̂ɂ͏킵�Ă��炢�܂����B^^
>�q�}����@
HX9V�̏ꍇ�͂��̋@��݂̂Ȃ炸�w�ǂ̈�ᓮ������D�ꂽ���搫�\�������Ă��܂��ˁB���ۛ��̃\�j�[�̐V�@��4�Z�킪�ǂ̂��炢�܂œ��搫�\���u���b�V���A�b�v���Ă����̂���������Ƃ���ł��ˁB
�����ԍ��F13428968
![]() 9�_
9�_
PL3�̔������Ă��܂����B����ɂ��́B
��U��Off�̂Ƃ��ł����A�c�݂��G�̉����ƃu���b�N�m�C�Y��AAF�̓����̕����C�ɂȂ�܂��B
�G�������̂͂����̃V�X�e�����ϊ���������Ă邹���ł��傤���B���̉掿�Ȃ���œ���B��Ӗ����S���Ȃ��ł��ˁB
AF�̓����͎��Ȏ咣������ƁA��i�ɂƂ��ăm�C�Y�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���Ƃ́A�R���j���N�̓V���b�^�[���x���W����Ǝv���܂������̕ӂ͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B
�����œ�����B�肽���Ă��낢�댟�����Ă��ł����A�Ȃ��Ȃ������@�ނ��Ȃ��ł��B�Î~��������PEN�Ɋ��҂������Ȃ��ł����ADSC-TX10������Ȃ��Ƃ����C�����Ă��܂����B�G�Ƃ��Ă͖ʔ����Ȃ���ł����B
�����ԍ��F13443764
![]() 0�_
0�_
E-P3�̃R���j���N���ۂ����[�J�[�����F�����Ă���悤�ł��ˁB
���A�Ō�p�Ɋ��҂����Ă܂��B
E-PL3��E-PM1�܂łɊԂɍ�������������ł��B
�����ԍ��F13445392
![]() 1�_
1�_
����͍����E�E�Ew
�������̎��A����@�\���ڂ��Ȃ���Ⴂ���̂ɁB
���������ˁ[�ȁB
�����ԍ��F13446561
![]() 2�_
2�_
�ꉞ�B
���i.com �̃V�X�e���ł�AVCHD�͎t���܂���B
�����mpeg2�Ȃǂ̕ϊ����K�v�ł����̂œ��R�掿�͗����܂��B�I���W�i�����T�C�Y��1/10�ȉ��ɂȂ��Ă܂��B�掿�̕]���܂ł��̃X���ł����Ƃ͑z�肵�Ă܂���ł����̂ŏ��X����Ă��܂��B
SD�J�[�h�o�R��HD�v���Y�}�e���r�ōĐ����Ă��܂����A�h��̌��ƃt���[�����[�g�ȊO��
�R���V���}�[�p�r�f�I�̃A�x���[�W���F��n�C���C�g�̔S�肪�������Y��ł���B
�����ԍ��F13450026
![]() 3�_
3�_
���Ă�[���掿�ȑO�̖�肾���ȁB
�����ԍ��F13452734
![]() 1�_
1�_
�掿�̕]���H
����ȑO�̖��ŁA�R���j���N(���łႠ��܂���)���ۂ����Ȃ��H
�����ԍ��F13452786
![]() 1�_
1�_
�Ƃ���ŁA���L����Ă��Ȃ��A�܂��͍w��������{�C�ł���Ă��Ȃ������R�����g����Ă���Ƃ�����
���̕��B�ɂƂ��ĉ������Ȃ̂ł��傤�B
����҂��\�����悤�ȕ]�_�C���ŁA�P�ɂ����肽���������Ƃ����痝��s�\�ł��B
���ɂƂ��Ă͂��̌��͌y�����ł��B �p�i�\�j�b�N��12-35mm OIS���o���為�Ў����Ă݂����ł��ˁB
�����ԍ��F13454654
![]() 3�_
3�_
�I���Ƀ\�j�[�u���́v�U�������Ă���l������悤�ł��O�O
�����ԍ��F13454848
![]() 0�_
0�_
���ʃO��������
�������p�i�̑���a�Ɋ��҂��Ă܂��B
�K����NEX�����߂�̂����邯�ǁA�܂Ƃ��ȃ����Y���Ȃ��ł����ˁO�O
�����ԍ��F13454879
![]() 2�_
2�_
�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P3 �{�f�B
E-P3�̓���Ɋւ��ẮA�w�����������Ă�����́u���e�͈́v�ł͂Ȃ��ł��傤���H
�l�����ꂱ�ꌾ���Ă��A�����l������ŗǂ�������Ǝv���܂��B
E-P3�̓���̃R���j���N���ۂɊւ��āA���[�J�[�͎d�l�A�t�@�[���A�b�v���ł̉��P�̗\��͂Ȃ��A�Ƃ̂��Ƃ������ł��B
�����Ȃ�ƁA���������ɂ��̃��f�����������Ă�����ɂƂ��Ă̋��e�͈͂ŁA���������Ηǂ��Ǝv���A���|�[�g���܂����B
����āA�Î~��݂̂��l���Ă�����Ɋւ��ẮA�܂������Ӗ��̂Ȃ����̂ł��B
�ł�����A�u���́A����͕K�v�Ȃ��v�Ƃ������́A�������ĉ������B
���惌�|�[�g�Ɋւ���
�ҏW�͈�؍s���Ă��܂���B�B�������̂����̂܂܃A�b�v���Ă��܂��B
�O�r�͎g�p���Ă��܂���B
�{�̂́AOLYMPUS PEN E-P3�ł��B
�P�A�����Y�@M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U R�@��U���@����
http://youtu.be/AaKXu0hvBKg
�Q�A�����Y�@M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8�@�@��U���@����
http://youtu.be/puDaIBJETsg
�R�A�����Y�@Panasonic LUMIX G 20mm/F1.7�@��U���@����
http://youtu.be/Js15A_B7OZU
�S�A�X���̎��@�@�����Y�@M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U R�@��U���@�Ȃ�
http://youtu.be/AID3yx0GDiU
�������f���������B
E-P3�����ׂĔے肵�Ă���킯�ł͂���܂���B
�����l�̔��f����Ǝv���܂��B����͕K�v�Ȃ��Î~�悾���Ŗ������Ă�����͂���ł����Ǝv���܂��B�����A�P�`�������ʔ����͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����A����ŐÎ~��̉��l����������̂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
���������ɍl���Ă�����ɂƂ��ẮA���f�̍ޗ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���[�J�[���u�d�l�v�Ƃ����A�u�t�@�[���A�b�v�ȂǂőΉ����Ȃ��v�A�Ƃ����̂ł���A����҂̓N�`�R�~�Ȃǂł��낢��ȏ��āA�l���邵���Ȃ��Ǝv���܂��B
����Ɋւ��ẮA�l�̔��f��A���e�͈͂�����Ǝv���܂��̂ŁA���Ă����f���������B
���̋��e�͈͂́A���S�ɃA�E�g�I�ł��B
���̑��̕��ނɂ��܂�������{�I�ɂ̓��|�[�g�ł��A���e�ɂ���Ă͕ԓ��Ȃǂ��Ȃ��ꍇ������܂��B���e�͂��������B
![]() 34�_
34�_
���蕥�����̂ɂ܂�����Ă�̂��O�O
�����ԍ��F13422205
![]() 28�_
28�_
�C�`����҂ł���I���Ƃ��Ă͂ǂ�ǂ�������Ǝv���ˁA���������̂́B
�ނ���܂�����Ȃ����炢����B
�l�K�L�����ł��Ȃ���E�\�����Ă�킯�ł��Ȃ��B
���������̂킯�킩���呛�������Ă�킯�ł��Ȃ��B
�����āA���[�U�[�ȊO�̓X���𗧂ĂĂ͂����Ȃ��Ƃ������[���Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ��B
�Ȃɂ����ȂH
���[�J�[��W�҂͍��邾�낤���A���i�Ɋ���ړ����₷���M���t�@�������͓{�邾�낤���A�I���͑S�������B
�ނ��낱��ŃI�����p�X�̃J�����̓���@�\������w�ǂ��Ȃ�A�I���͂Ƃ��Ă��������B
�������A�X���傳��݂����Ȏ��s�͂̂���q�g�����܂�����ďo�Ă���āA
��ʂɂ����Ăǂ�ǂ�����Ďw�E���Ă���邨�����ŁA�I���͘J�͂����X�N���[���B
����Ȃ̂ɋC�ɓ����Ă郁�[�J�[�́A���ڂ��Ă铮��@�\���ǂ�ǂ�ǂ��Ȃ邩���m��Ȃ����Ă���A
����Ȋׂۖ��̃n�i�V�͂Ȃ��E�����Ƃ܂��
������x�������B
����҂Ƃ��āA�������ȂH
�����ԍ��F13423247
![]() 38�_
38�_
�ӌ��Ɣᔻ����ʂ����ɁA�����Ƃ���������ƒ����A���`��������ґ����o�Ă��邪
�ǂ�ǂ�ׂ����Ǝv���B
����҂̓G�͂����������X�����Ă�X������l�łȂ��A�����Ƃ���������ƒ����A���`��������ґ�
���Ǝv���B
���ꂩ��w����������l�ɂ͎Q�l�ɂȂ�A�ǂ��X�����Ǝv���܂���B
�����ԍ��F13423507
![]() 24�_
24�_
���̐��i�̎��ۂ͂ǂ��Ȃƌ������͑����̍w���\��҂̒m�肽�����Ă��邱�Ƃł��B
�ǂ�Ȃ��Ƃł����ꂪ�����Ȃ瓊�e���邱�Ƃɉ����肠��܂���B
���郁�[�J�[��i�ɉߓx�̊���ړ����āA���̐��i�̌��_���w�E�����ƁA���̓��e�������l���l�I�ɔᔻ����̂͂悭�Ȃ����Ƃ��Ǝ����v���܂��B
�X���傳��͂��łɐ��i��������Ă��郆�[�U�[��I�����p�X�t�@���ɑ債�Ă����̋C�����ɔz������Ă���A�Ȃ����̂Ȃ����e�ł��B
�������A����ɂႭ���ۂ̓J�������Ȃ邾���������Ȃ��悤�ɂ��ĎB�e���鎖�ł��Ȃ�h����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F13423588
![]() 17�_
17�_
���i�ɑ���Ȃ�������s�����Ȗʂ��w�E����͈̂������ƂƂ͎v���܂��A
���_�������炤�����ł̓��[�J�[�ւ̃A�s�[���ɂȂ��Ă��w���҂̂��߂ɂ͂Ȃ�܂���B
�ǂ�����Ζ����ł���̂����v�Ă��H�v���A�ǂ��Ǝv�����@�͑��҂֓`���邱�Ƃ�
���[�U�[�Ƃ��Ă̍őP�̋߂ł���A���ʐ��i���ǂɌ����Ẳe���͂������Ǝv���܂��B
�w�����������鑼�҂ւ̒��ӊ��N���厖�ł����A���ۂɎg���Ă��郆�[�U�[�̒��ɂ�
�s�����������邽�߂̕��@���l���Ď��H���Ă���l����������킯�ŁA
����Ȕނ�̐������Ƃ����p�����������ق������͑����Ǝv���܂��B
�c�O�Ȃ͖̂쎟�n�̐��������Ă���������Ă��邱�Ƃł��傤���B
�����ԍ��F13423795
![]() 10�_
10�_
�ǂ������������Ƃ����ł�������̂����̗l�Ȍf���ł���
�����M������M���Ȃ����A�Q�l�ɂ�������Ȃ����A�ǂޑ�����ł́H
�{���ɖ��ȏ������݂�����Ή^�c�ґ����폜���邾�낤�����B
�����ԍ��F13424037
![]() 10�_
10�_
�W����&�����[����̈ӌ��Ɏ^���ł��B
�X���傳��̌o�����ꂽ�͈͂�������Ɠ���͎g���Ȃ��Ƃ������f�ɌX�����������Ǝv���܂���
���ۂɎg�p���Ă��郆�[�U�[���炷��ƁA���ꂽ�Ⴞ�����S�Ăł͖����A�Ⴆ�Ύ��̏ꍇ��
�p�i�̃����Y25mm f1.4. 14mm f2.5 �Ƃ̑g�ݍ��킹�œd�q��U����Off�ɂ���ƈႤ���ʂ��o�܂��B
�c���ꂽ�H���[�U�[���炷��ƁA���������ō��̂Ƃ���s��������ǂ��g�����H�ǂ̓_�����ǂ���悤���[�J�[�ɐ��������đ����C�������邩�ɋ���������̂ŁA�P�Ƀ_���ł��g�����ɂȂ�܂��������Ă��L�p�ł���܂���B�܂��A�w����������Ă��������ʂ̏���ŎQ�l�ɂȂ����ƁA�w���@����Ă��܂����Ƃ��N�����Ă��܂��Ƃ����炻����c�O�ł��B
���A�l�I�ɓ���ɂ��Č��؎��������Ă���܂��̂ŋ߂����ɃA�b�v�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13424045
![]() 15�_
15�_
���̃N�`�R�~�͑�ώQ�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ȏ��čw�������߂�ޗ��ɂ͂Ȃ�܂��B
�s���������ɂ��Ă��f���������̂ł����A
���s�����������邽�߂̕��@���l���āE�E�E�E�Ƃ���܂����A
��U����Off�ɂ��āA�Ⴄ���ʂ��łĂ��A��U�����g���Ȃ��ŁA�s���������������ƂɂȂ�̂ł��傤���H
�����Y�ȂǕς�����Ƃ�����܂����A�܂��ʂ̏o�����̂Ȃ炩�Ȃ荂�z�ɂȂ��Ă��܂��܂��H
��U����ON�ŁA���̌���i�c�C�������Y�L�b�g�j�ŁA�s���������ł�����@�͂Ȃ��̂ł��傤���H
�����ԍ��F13424117
![]() 9�_
9�_
�Î~�����B���Ă����̂ŁA�S���C���t���܂���ł������A
����ᓮ��A�S�R�_���ł��ˁB
�����I�����p�X�A�������ƒ����I
���ꂮ�炢�t�@�[���A�b�v�ʼn��Ƃ��Ȃ邾�낤�B
E-P1,2�̎��ɖ��ɂȂ��ĂȂ��������ƂȂ̂ŁA�͂撼���I
�����Ȃ������烆�[�U���݂�ȃp�i�\�j�b�N���\�j�[�ɗ���Ă��܂����I
�����Ȃ��Ă����͒m�`��Ȃ��ƁB
�����ԍ��F13424463
![]() 17�_
17�_
�l�I�ɂ͂��̓���͊��S�ɃA�E�g���B
�_�����킱���B
�J�����Ƃ��Ă͖��͓I�Ȃ��ǂˁB
�X���傳�肪�Ƃ��B
�����ԍ��F13424584
![]() 17�_
17�_
��̉�����B
�{�̎�Ԃ����I�t�ɂ��ăp�i�̃����Y����Ԃ����g���A
�^�C�����[�Ȃ��Ƃ�10���Ƀp�i����d���Y�[���t����14-42��40-175����������܂��B
����B�e�h�ɎB���Ă͂��ꂵ�����Ƃł��B
�����ԍ��F13424864
![]() 11�_
11�_
�ł��Ĕ���Ȃ��ŗǂ������ł��I�I
�A�E�g�ł��ˁB
NEX-�TN�@http://www.sony.jp/ichigan/products/NEX-5ND/
��҂��Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�X���傳�肪�Ƃ��������܂����B
������Ȃ��ł��݂܂����B
�����ԍ��F13430239
![]() 4�_
4�_
����̓A�E�g�ł��ˁc
E-P3�ɕ��C�������ɂȂ�܂������ǁAGH2���g���Ȃ���
GH3�AGF�v���҂��ɖ߂�܂��B
�����ԍ��F13430907
![]() 4�_
4�_
>t-ss����
�\�j�[�͍ő�29�������A���B�e�o���܂���̂ŁAGH2���ǂ��ł���B
���撆�̐Î~��B�e���o���܂����B
�\�j�[��60P�ɂȂ����̂ŁAGH3��60P�ɂȂ�̂͊m���ł��傤����A
���Ȃ�GH3��҂�����������͖����Ǝv���܂����c
�����ԍ��F13430979
![]() 2�_
2�_
�\�j�[�͔M�\����\�h���邽�߂Ɉ��S���u����������Ă��āA�����Œ�~������Č������炵���@�\������܂����ˁB
29�������Ȃ����������Ȃ��ƁO�O
�����ԍ��F13431252
![]() 3�_
3�_
�\�j�[�^�C�}�[�Hf^_^;)
�����ԍ��F13432824�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
>29�������Ȃ����������Ȃ��ƁO�O
�S�e���N�X�̃t���[�W�����̍��̎��Ԃ��Z����
�����ԍ��F13433894
![]() 2�_
2�_
���ꂪ�u�d�l�v�ŁA�u�t�@�[���A�b�v���ł̉��P�̗\��͂Ȃ��v�Ƃ́A�J���������ӂ�����܂���B
E-P3�̓X�^�C�����ǂ���AF������Ǝg�����̂ɂȂ肻���������̂ōw�����������Ă��܂������A
���̓�������Ċ��S�ɔM����߂܂����B
����Ȓv���I�Ȍ��ׂ��u�d�l�v�ƒf�����郁�[�J�[���ĥ��
���蓾�܂���ȁB
�X���傳��Ɋ��ӂł��B
���ʌ����������ɂ��݂܂����B
�����ԍ��F13435441
![]() 7�_
7�_
>�v�W���Y����
�d�|�o�k�Q�̘A���B�e���Ԃ͂V���i�I�j�������̂��A����ɖ��S����
�d�|�o�R�͂Q�Q���ɉ��P�i�S�e���N�X�̃t���[�W�����̍��̎��Ԃ��Z����
�ƌ���ꂻ���ł����c�j���ꂽ�̂ŁA���̌��ۂ��d�|�o�S�ł͉��P������
�v���܂���
�u�d�l�v�ƌ�������̂́A�d�|�o�R�����f���`�F���W���閘�̊Ԃ����ł���
�i�ƁA�v�������c�j
�����ԍ��F13442883
![]() 0�_
0�_
����̋@��͓���́u���܂��v�ƍl���čw���ł��ˁB
���̊����x�ł͂܂����惁�C���ɂ͒u���܂���B
�����̐悪�y���݂ł�����܂��B
�����ԍ��F13445406
![]() 1�_
1�_
�����H
�X����͂���E-P3�����Ă�́H�H
�����ԍ��F13445423
![]() 1�_
1�_
>���܂�������
>���̊����x�ł͂܂����惁�C���ɂ͒u���܂���B
���惁�C���Ȃ�A�f���Ƀp�i�������������Ǝv���܂���c
�Î~�惁�C���Ȃ�d�|�o�R�ł���
�i�f�R�̕����A��f�������āA�����x�����āA�d�u�e�����ŁA�o���A�����j�^�[��
�@�^�b�`�p�l���ŁA�A�ʑ����āA���掞�Ԗ������ŁA�����āA�P�T���d�������ł����ǁA
�@�I�����p�X�̌f���Ȃ̂Ŏ��l�c�j
�����ԍ��F13446422
![]() 3�_
3�_
�����GH2�ŎB���Ă��܂��O�O
�ł��A���������Y�����L�ł���̂ŕ֗��ł���B
�����ԍ��F13446446
![]() 1�_
1�_
youtube�ɍX�ɃR���j���N���ۂ̓��悪
�����Ă�悤�ł����ǁA������ƍ����ł��ˁB
�X���傳��̃T���v���ǂ��낶��Ȃ������ł���B
����ƁA������`������X���b�h�͎����^���ł��B
�����ԍ��F13535786
![]() 2�_
2�_
�f�W�^�����J���� > �I�����p�X > OLYMPUS PEN E-P3 �����Y�L�b�g
�݂Ȃ���A����ɂ��́B
�p�i�\�j�b�N����A�����̃����Y���o�܂����ˁI
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn110826-1/jn110826-1.html
�p���P�[�L�ƕς��Ȃ����炢�̃R���p�N�g���œd���Y�[���A�������ꂽ��Ԃ��ɉ掿�ɂ�����������ƌ���ꂽ��A�C�ɂ����ɂ͂����܂���ˁI�i����Ńp�i�\�j�b�N�́AAVCHD 2.0�Ή���GF�V���[�Y��ʋ@����o���S�ɋ��_�H�j
���ЁAE-P3�ɂ��t���Ă݂����ł����A�p�i�\�j�b�N�̃J�����ł��A�t�@�[���E�F�A�̃A�b�v�f�[�g���K�v�炵���̂ŁAE-P3�����̂܂܂ł͖����ł��傤�ˁI
�����ԍ��F13420798�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��E-P3�����̂܂܂ł͖����ł��傤�ˁI
�^�_�Ȃ炢����ˁA�Ȃɂ����傢��Ȃ��B�@�@���i�O�|�O���j�i���O�|�O�j��
�����ԍ��F13420808
![]() 11�_
11�_
������ƑO����b��ł��B�v�������ቿ�i�ŁA�w�L�т���Ύ肪�͂������B
�N�Ƌ��ɏk�݂���܂��̂ŁA�}���������ǂ����ȁ`�B
�����ԍ��F13420822
![]() 2�_
2�_
http://www.dpreview.com/previews/panasonic_x_14-42_3p5-5p6/page3.asp
�Y�[���͌��\�����傫�����H
���悾�ƊO���}�C�N���K�v�ł��傤���ˁH
���i�K�ɃY�[�����x���ς�����̂œd���Y�[���Ƃ��Ă͎g���Ղ����ł���
�ł����ʂɂ͂�͂�蓮�Y�[�����L���ł�����
���ʏd���Ȃ�I���̃����Y����U��͂Ȃ����ǂ�������Q�O�����d���Ȃ�Ȃ����悳��
�l�e�s���m�d�w���o���������łǂ�ǂ�{�̔������Ă��Ėʔ����Ȃ��Ă��܂�����
(*´��`)�m
�����ԍ��F13420845
![]() 2�_
2�_
�����������S�T���ڂŃV���v���ȕ���PEN�Ɏ��������ǂȂ��E�E�E�Ƃ������ɏ���Ȋ��z�͒u���Ƃ��āE�E�E
���M���^�ł������A�{���ɂ��̃T�C�Y�Ȃ�ł��ˁB�f���炵���B
DPReview�ɂ��i�����Y�Ƃ��Ă̍Œ���̋@�\�́jPEN�ł����Ȃ��g����悤�ł���B
��Of course this is a Micro Four Thirds lens, and can therefore be used on Olympus PEN models as well as Panasonic's own Lumix G series. Olympus owners need have no fear about whether it will work - according to Panasonic it will be fully compatible with their cameras (and we've found no problems with it in early use). To achieve full compatibility, all cameras from both makers will need their forumware updated.
�t�@�[���A�b�v�́AX�����Y�������K�Ɏg�����߂̂��̂ŁA�Ⴆ�A�t����ʂŃY�[���ʒu���m�F�ł���u�œ_�����\���v�@�\��u�X�e�b�v�Y�[���v�@�\���g����悤�ɂȂ�悤�ł��B
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn110826-1/jn110826-1.html
�p�i�����Y�p�̃t�@�[���A�b�v���I�����p�X���o���Ă����Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA���̕ӂ͓��ʃp�i���[�U�[�̓����ɂȂ肻���ł��B
�����ԍ��F13420932
![]() 2�_
2�_
GF2/GH2/GF3/G3�Ł@���̃����Y�ɑΉ����邽�߂̃t�@�[���A�b�v��
�F �t����ʂŃY�[���ʒu���m�F�ł���A�u�œ_�����\���v�@�\��lj��B
�F ���߂�ꂽ�e�œ_�����܂ŃY�[������A�u�X�e�b�v�Y�[���v�@�\��lj��B
�F �d��OFF���̃Y�[���ʒu���o����A�u�Y�[���ʒu�������[�v�@�\��lj��B
�F �d���Y�[���̑��x��I���ł���A�u�Y�[�����x�v�@�\��lj��A�ȂǁB
�@���ĂȂ��Ă��邩��A���̋@�\���g���Ȃ��̂����m�Ȃ�@m4/3s�d�l�Ȃ̂œ����Ǝv���܂�����
�@�ł��A�Y�[���ʒu�������A�X�[�����x�͗~�����ˁ`
�����ԍ��F13420936
![]() 3�_
3�_
�{����20mmF1.7�Ƃقړ����T�C�Y�Ȃ�ł��ˁB�������ȁB
�����ԍ��F13421097
![]() 2�_
2�_
guu_cyoki_paa����
��w�E�A���肪�Ƃ��������܂��I
(��)������(��)�����@�ł����E�E�E
���A�d���Y�[���W�̒lj��@�\���䖝����A�t����Ȃ����Ƃ͖��������ł��ˁB�܂��A�I�����p�X���A����14-42mm�����f���`�F���W���鎞�́A�����Ȃ����炢�̂��o���Ăق����ł��ˁI
�����ԍ��F13421126�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
http://www.imaging-resource.com/PRODS/GF3X/GF3XA.HTM
��͂�A�����}�C�N���ƃY�[���̉����E���Ă��܂��܂��˂����c
�c�O
�����ԍ��F13421424
![]() 4�_
4�_
�d���Y�[���E�E�ł����B
����AF�������A���X�|���X�̍��������]�܂�Ă��āAE-P3�ł͑������������Ă��܂��B
�B�e�҂̏u�ԓI�ȑ���f�������Ƃ����̂��A����I�ԃ|�C���g���Ǝv���܂��B
���͎蓮�Y�[���̂ق����x�X�g�̂悤�Ɏv���̂ł����A�d���Y�[�����o���Ƃ������Ƃ͂����]�ޕ�������ƌ������ƂȂ�ł��ˁB
�R���p�N�g�v�͎����^�т��悳�����ł����|�C���g�ł��ˁB
���̃����Y���܂߂āA�p�i�̍L�p��E-P3�̃f�U�C���Ƀ}�b�`���������ł����B
�p�i�̃{�f�B�ɃI����R�����Y�̓J�b�R�悭������ł���ˁB
�����ԍ��F13421933
![]() 3�_
3�_
�����A�F�Ⴂ������݂����ł��ˁI�I
http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/473/193/html/pana26.jpg.html
http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/473/193/html/pana25.jpg.html
�܂��܂��A���~���E�E�E�I
�ł��A�킴�킴�I�����p�X�̂��߂ɐF�Ⴂ��p�ӂ���͂��͂Ȃ��̂ŁANEX-7�R�̐V�^�o��̉\����I�ł��ˁB
�����ԍ��F13422100
![]() 0�_
0�_
����͂������ł��ˁB
GH2�������Ă�̂ŋC�ɂȂ�܂��O�O
�����ԍ��F13422176
![]() 2�_
2�_
�Î~��B��Ȃ�A�蓮�Y�[������ΓI�ɗ��p���₷���ł��B
�d���Y�[���͓���̂��߂ł��傤�B
����B�e��̂̐l����͓d���Y�[���͑҂��]�܂�Ă��܂����B
�����ԍ��F13422738
![]() 3�_
3�_
GF7�ɃZ�b�g�ŕt���Ă������ȗ\���B�B�B�B
�����ԍ��F13424569
![]() 2�_
2�_
���̑傫�������Ő�Η~�����Ǝv���܂����B
�掿��MZD14-42mm�UR���ǂ������甃�����������Ǝv���Ă��܂��B
�p�i�\�j�b�N��12-35mm�̖��邢�����\�����Y���o��\������A�����Y�Ŋ撣���Ă���Ă���̂͑�ϊ������ł��ˁB
�I�����p�X��12mmf2�A45mmF1.8�A�p�i��25mmF1.4�A����14-42mm���^�����Y�A�\��12-35mm����a�����Y��M4/3�������Y�̑I�����������ɗ��Ċi�i�ɑ����ė��Ă��܂��B
�������̃����Y�ŎB�����T���v�������������ł��B
�����ԍ��F13424683
![]() 3�_
3�_
http://panasonic.net/avc/lumix/systemcamera/gms/gallery/lens.html#lens_x_1442
���Q�l�܂ŁB
�����ԍ��F13424933
![]() 2�_
2�_
�@�d���Y�[�����u����Ȃǂ̋@�\�̓J�����{�f�B�Ɉˑ����Ȃ����̂ŁA�I�����p�X�uPEN�V���[�Y�v�ȂǑ��А��̃t�H�[�T�[�Y���f�W�^���J�����ɑ��������ꍇ�ł����l�ɗ��p�ł���Ƃ����B
14-42mm�͎U�������Y�ɍœK���ȁB
�����ԍ��F13425128
![]() 2�_
2�_
>�������߂���
�T���v���ʐ^�̃����N���肪�Ƃ��������܂����B
X14-42mm�Ȃ��Ȃ��掿�������ł��ˁB
X45-175���f���炵���ł��B
�ł���Ԃ����ȂƎv�����̂�25mmF1.4�ł����B
���ꂩ��M4/3�̃����Y���ɂ͂܂肽���Ǝv���܂��B(��)
�����ԍ��F13428064
![]() 2�_
2�_
���悢��p�i�̓����Y���C���A�b�v���n���NEX�����������ɂ�����܂����ˁB
���N�̑���a�����Y�ɂ����҂ł��B
�����ԍ��F13428684
![]() 2�_
2�_
�����Y�̐��\�Ƃ��Ă͂ǂ��Ȃ�ł��傤���ˁH
�f�l�l���Ƃ��ẮA�������̂ɓ������\���o����̂��ȁ`���Ďv���Ă��܂��܂��B
��ʼn̂����̂����ȂƂ�����Ďv���Ă��܂������A���̏������͎̂Ă������ł��ˁB
�蓮�ŏ������̂����Ȃ��̂ł����ˁH�H
�����ԍ��F13430380
![]() 0�_
0�_
�p�i�\�j�b�N�̓I�����p�X���ア����ɗ͂����Ă���悤�ł��ˁB
�I�����ǂ����ǂ��z���Ŋ撣���ė~�������̂ł��B
�����ԍ��F13445439
![]() 0�_
0�_
���̐��i�̍ň����i������

OLYMPUS PEN E-P3 �c�C�������Y�L�b�g
�ň����i�i�ō��j�F ���i���̓o�^������܂��� �������F2011�N 7��22��
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z2025PC�\���Q
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC�Q
-
�y�~�������̃��X�g�z2025PC�\��
-
�y���̑��z9700X wh
-
�y�~�������̃��X�g�z�~�������̃��X�g
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j