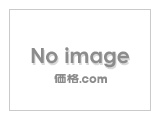
T-88CAV
�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �o�^���F2009�N 1��14��
�v�����C���A���v > CAV > T-88
���Ȃ����H�t�̉��W��T-88��V-70NW�̑g���킹�����̂Ń��|�[�g���܂��B
(���L���Ă����ł͂Ȃ��̂Ō��R�~�Ƃ��܂���)
�����I���ԍۂɉ��ɒ����ƁA����S���̃I���W�����M�Ȃ������Ɂu�L�������Ȃ̂�
������ƌ����������m��܂��E�E�E�v�ƌ����Ȃ���Ȃ��������̂ŁA���́u�m����
���̕����̍L���ł��̃T�C�Y�̃X�s�[�J�[�ł͎d������܂��v�ƍ����������Ă�����
�ł����A�������t���n�܂��Č���Ƃ��̕��������ቹ�̉����Ɉ��|����Ă��܂��A
�u���̃I���W�\����Ȃ������Ȋ炵�ĂȂ�ĉ��o���Ă₪��I�I�v�Ɠ��h��
�B���܂���ł����B�X�s�[�J�[���ǂ��̂�������܂��A��͂�d�ʋ��^��ǃA���v
�̋쓮�͂̓f�W�^���A���v�ɑ��Ĉ��|�I�ȃA�h�o���e�[�W������悤�ł��B
�e���������ŋ߂܂ł͐^��ǃA���v�Ƃ������͖̂����L����̂ł����Đ��\�ł̓f�W�^��
�A���v�ɓG��Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A���ۂ̓f�W�^���A���v�������Ă���̂̓R�X�g�E
�@�\���E�ȓd�͐��ł���A�X�s�[�J�[�̋쓮�́A���ɒ����̓f�W�^���A���v�ɏ��ڂ�
�������Ƃ�����܂����B���̎傽�錴���͑�e�ʂ̏o�̓g�����X�ɂ���悤�ł��B
�f�W�^���A���v�ł��A�i���O�d���̂��̂͐^��ǃA���v�Ɠ������d���g�����X��������
����̂ł����A�o�̓g�����X�͎����܂���BT-88���㕔�Ɏl�p�������O����܂����A
��͓d���g�����X�œ�͏o�̓g�����X���[�܂��Ă�����̂Ǝv���܂��B
�R�C���ɂ͓d�C�𗭂ߍ��ސ���������̂�(�����c�̖@��)���肵���d�͋������\�Ȃ���
�ɍ����쓮�͂����̂����m��܂���B
���Ȃݎ��͍ő�o��50W(6��)�̃f�W�^���A���v��12W(6��)�d��11.5kg�̃V���O������
�^��ǃA���v��12W(4���H)�d��26.5kg�̃v�b�V���v�������^��ǃA���v�������Ă��܂����A
�����珇�ɒ��ቹ�̌��݂������čs���܂��B
�f�l�l���ł����A�^��ǂ̑�������(�������Ƃ����₩�Ƃ�)�̓f�W�^���ōČ��ł�����
�Ȃ̂ŏo�͒i���A�i���O�����ăg�����X����������쓮�͂���̂ł͂Ȃ���
�Ǝv���܂��B
�����̋��������D�݂�(����ؑւ��o����悤�ł�)�f�W�^���A���v�̒��ቹ�ɕs��������
�l�ɓK�����A���v���Ǝv���܂��B
�f�W�^���ł͔{�̒l�i���o���Ă�T-88�̒��ቹ�ɂ͓G��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������A�^��ǃA���v�̏ꍇ�̓o�C�A�X����(DC 0.5V���x�𑪒肷��̂ɓK�����e�X�^�[
���K�v)�ƃn���o�����X����(�X�s�[�J�[�Œ�����)���K�v�ȏꍇ������̂�T-88�ɂ���
���X��[�J�[�ɖ₢���킹���ق������������m��܂���B�������̂͋����Γd�C��
�m���ȂǕK�v�Ȃ��A���ŏo������̂ł��B�܂��A�d�ʂ��d���̂ő̗̖͂������͗v����
�ł��B
���W�̃x�X�g�o�C�@���Ǝv���܂��B
���Ȃ݂�T-3-WH���Ȃ��Ȃ��̉����ŁA���������Ȃ炱��ŏ\�������m��܂���B
�����ԍ��F10493775
![]() 4�_
4�_
�ΐl����A����ɂ��́B
�����[�����|�[�g�A����J�l�ł��B
>�^��ǃA���v�Ƃ������̂�(����)���\�ł̓f�W�^���A���v�ɓG��Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A
>���ۂ̓f�W�^���A���v�������Ă���̂̓R�X�g�E�@�\���E�ȓd�͐��ł���A
>�X�s�[�J�[�̋쓮�́A���ɒ����̓f�W�^���A���v�ɏ��ڂ͖������Ƃ�����܂����B
�����[�����ӌ��ł��ˁB���������ʂ�A���̖�������G�l���M�[���ł͐^��ǃA���v������܂��ˁB�����������f�W�A������Ȃ��v������ł��B
�������ꂪ�C�R�[���A�^��ǃA���v�̓f�W�A�����u�쓮�͂ɏ����Ă���v�Ƃ�����̂��H�@�ɂ��Ă͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B��������ǂ݂ɂȂ��Ă���݂Ȃ���͂ǂ��v���܂����H
�����ԍ��F10494041
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂��B
�X���傳��̌o���B
������������Ӗ�������܂��B
�m���Ƀ��[�G���h�L�тɂ��ẮA�f�W�^���A���v�͉��тĂȂ������ł��B
���ɃE�[�n�[�̐������~�߂鑬���̓f�W�^���A���v���������Ɓc
(�~�܂��ė~�������Ɏ~�܂�j���Ӗ��s���ł���(��)
���݂Ɏ����������f�W�^���A���v�̓A�C�X�p���[�̃`�����l��500W�B����A�i���O�A���v�̓`�����l��150W�̋��ɊC�O�A���v�ł����B
���Ƃ�����A�j���[�t�H�[�X�̃f�W�^���A���v(�A�i���O�X�C�b�`���O�A���v�j�� ���Ȃ�[�����[�G���h�܂ł�����Ȃ����Ɓc
�����܂ʼn����ł�f^_^;
���������Ȉӌ����ĕ��������ł��ˁB
�����ԍ��F10494404
![]() 2�_
2�_
Dyna-udia����ɂ��́B
���[���E���t����ɂ��́B
����̓_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ�����̘b�ł��ˁB
�m���Ɏ����m�������Ԃ肵�������c�̖@�����炷��Əo�̓g�����X�͓d���̗��オ��E
�����藼���Œ�R���邱�ƂɂȂ�A���_��ꂪ�����Ȃ鐫��������̂ł��傤�ˁB
�������W�A��ɕx�m�\�t�g�̌������ɂ���I�[�f�B�I�V���b�v�ΖƂ����X�ōw������
cayin��A200-P(�艿�̔��z��14��3��~�������̂Ŕ����Ă��܂��܂����I)�͂܂��G�[�W
���O�����ł����A�n�C�X�s�[�h���^�����Ă��x���Ƃ��݂��Ƃ�����ۂ͎܂���B
����12W�̃p���[�ŏd�ʂ������ȉ��̃��f���ɔ�ׂĖ��炩�ɒ��ቹ���������Ȃ���
����̂ɓ݂��͊����Ȃ��Ƃ������Ƃ̓����b�g�ƃf�����b�g�̂����A�����b�g�̂ق���
�傫���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H�X�s�[�J�[�̃��X�|���X�ɂ���邩���m��܂�
�B
T-88�Ń��^��������ǂ��������������[���ł��B�\���I�ɂ͓����͂��ł����A�p��
�[�̈Ⴂ(T-88 45W,A200P 12W)���_���s���O�ɉe������̂������[�����̂ł��B
���������ăp���[���傫���Ǝ~�܂�ɂ����Ƃ�����̂ł��傤���H���ǂ��̃A���v��
����҂̃p���[�M�łƂ肠�����J�^���O�X�y�b�N��D�悵�Ȃ��Ɣ���Ȃ����ł�����B
�{���͉ߏ�ȃp���[�͂Ȃ��ق����ǂ����Ƃ�����̂ł́H
�N�����̕ӂ���u�߂��Ă��炦�Ȃ��ł��傤���B
�A�C�X�p���[�̃`�����l��500W���O�O���Ă�������܂���ł����B����͂���������
�W�F�t�E���[�����h�Ƃ����u�����h�̂��Ƃł����H�W�F�t�E���[�����h��Model 102 S��
�������f���͓����̏ڍׂȉ摜���������̂Ō��Č���ƁA�d���g�����X�炵���g���C�_
���g�����X�Əo�̓g�����X�炵���R�A�g�����X���ʂ��Ă��܂��B�����l�����悤�Ƀf�W
�^���E�A�i���O�ܒ��Ȃ̂��ȁH�Z�p����ł͂��̕ӂ�͐G����Ă��܂���B��Ɣ閧
�����炩�ȁB�j���[�t�H�[�X�̓z�[���y�[�W�����܂����������\���̎ʐ^�͖������A
���̕ӂ̋Z�p������F���ł����B
��ʂɒm��ꂽ���[�J�[�ł͂Ȃ��āA�O�q�̂悤�ȃ��[�J�[�̍ŐV�@����Č�����
���̂ł��B1000W�Ƃ͋����ł��B
����ɂ��Ă����܂Ŏ��͐^��ǃA���v�ƃf�W�^���A���v�̃p���[��Ɏv���Ă��܂�
�����A�ǂ�����҂͑S���ʕ��ƍl�����ق����ǂ������ł��B�^��ǃA���v�͍ő�p��
�[�͒Ⴍ�Ƃ���^�̏o�̓g�����X�̂����ŕ��������ቹ���ł܂����A�f�W�^���͂ǂ���
�Ă����SW�̃p���[���K�v�Ȃ悤�ł��B
���Ƃ��Ă̓f�W�^�����A�i���O�����ǂ����W���čs���ė~�������̂ł��B
�����ԍ��F10498785
![]() 3�_
3�_
�X���傳��ɂɂ���
�����������̂̓��[�e��(�f�W�^���A���v�j�ƃ{���_�[500SE(�A�i���O�A���v)�̗��@�p���[�A���v�ł���
�X�s�[�J�[��38�Z���`�E�[�n�[��B&W�̃m�[�`���X
�ꉞ���[�e���ƃ{���_�[�̗��@�̕�����ׂł����A�{���_�[�̂ق������[�G���h�܂ŐL�тĂ܂�����
����܂胁�J�̂ق��͏ڂ����͂Ȃ��̂ł�������
�����������ł͎����D�݂ł�����
�ꉞ�����N���Ƃ��܂�
�{���_�[�̂ق��͂�����Ƃ킩��܂���
���X�Ƀj���[�z�[�X������悩�����̂ł�������
http://www.nuforce.jp/products/p8s_01.html �j���[�z�[�X
http://www.onken-audio.co.jp/rotel%201.htm�@���[�e��RB1092
�����ԍ��F10500213
![]() 1�_
1�_
�X���傳��
�����B
�{���_�[SE���{���_�[AE�ł���m(_ _)m
�����ԍ��F10501172
![]() 1�_
1�_
���[���E���t���肪�Ƃ��������܂��B
���[�e���ƃ{���_�[�̃z�[���y�[�W�݂܂����B
���[�e���͒��g�͑S�������Ă���܂���ł������{���_�[�̓C���e�O���[�e�b�h�A���v��
���f���W�U�T�Œ��g�������Ă���܂����B����ȓd���g�����X�Ə����ȏo�̓g�����X��
�悤�Ȃ��̂��t���Ă܂��B���̃T�C�Y�̏o�̓g�����X�����[�G���h�̐L�т̎�v�Ȍ���
�Ƃ͎v���܂���ˁB
�l���Č���ƒቹ�����������o�����߂ɂ͐U�����U�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯
�ł����A���[�e���ɂ��Ă��ǂ��̃f�W�A�����[�J�[���u���̑�d���̋������厖�Ɛ���
���Ă��܂��B
�f�W�^���A���v(D��)�ƑɓI�ȑ������s��A���A���v�̎d�g�݂��r����ƁA
A���͏�Ƀo�C�A�X�d���Ƃ������̂���H�ɗ����Ă����āA�����ɐM���d���𗬂�
���Ƃɂ���đ������Ă��܂��BD���A���v�̓o�C�A�X�d���������ăp���X�M��
�����邲�Ƃɑ������Ă��܂��B
�Ⴆ��Ȃ�k����������̂�A���͏��������ăX�^�[�g���C���ɒB����̂ɑ���D����
�N���E�`���O�X�^�[�g������悤�Ȃ��̂ł��傤���B����ł�D���̂ق����y���Ɏ��͂�
��łȂ���Ώ����ڂ͂���܂���ˁB
�܂�D���������߂ɂ͉����́i�u���̓d�������\�́j���K�v�ł���A���̂��߂ɂ�
���͂ȋؗ́i��d�͔����\��(500W�Ƃ�)�j���K�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ƂĂ�������l�i�ł͂���܂��W�F�t�E���[�����h��Continuum 500(4��1000W,20kg)
���Ă݂������̂ł��B�Ȃ��f�W�A���ւ̐���ς𐁂�����Ă��ꂻ���ȋC��
���܂��B
����B&W�����ł��ˁB�O�͂Ƃɂ����d������Nj����Ă���ł����A�ŋߏ_�炩�����□��
���鉹�����߂Ă��܂��܂��B�W���Y��N���V�b�N�����������C�����邵�B
�N���ȁH
�����ԍ��F10503356
![]() 3�_
3�_
���炢�������܂��B
OPT���A�E�g�v�b�g�E�g�����X�t�@�[���o�̓g�����X�B
�R�A�̃{�����[�����傫�����d�ʂ̂���o�̓g�����X�B
�d�ʂ̂���o�̓g�����X�͒�悪�o�܂��B
�d���g�����X���傫�������悢�Ƃ������������܂��B
�Ȃ̂ŃA�i���O�A���v�͏d���قlj��������Ƃ��������ꗝ����܂��B
�������o�̓g�����X�̓R�C���Ȃ̂ŁA
���g���ɂ���Ē�R�l���ς��܂��B
NFB�ʂő������P�ł��܂����A
������������j�A�łȂ����悪�o�ɂ����Ȃ�܂��B
�l�Ԃ̎��ɕ������Ȃ����g��������ǂ��̂�������܂���B
�����������悪����ɉe�����A
�ǎ��Ȓ�����ɂȂ�̂Ń��j�A���ǂ��Ƃ���̂��A
SACD���o�Ă���̎嗬�ł͂���܂��B
��]�̂���o�̓g�����X�͍����Ƃ������_������A
�o�̓g�����X�̒�����R���ɂ����g�������̈������l����ƁA
�o�̓g�����X�͖��������ǂ��Ƃ������������܂��B
���j�A�Ȏ��g��������OTL���A�E�g�v�b�g�E�g�����X�t�@�[�E���X�B
OTL�^��ǃA���v�͍������l�C������܂��B
�قƂ�ǔ����̃A���v�ƕς��Ȃ����ł��B
DF�͈ꌅ�ɂȂ�Ƃ�邢���ɂȂ�悤�ł����A
���ꂪ�^��ǂ̉��̓����Ƃ������܂��B
Nuforce�f�W�^���A���v�̓����ʐ^�́A
�I�[�f�B�I�G���ɍڂ��Ă��܂��B
�g�����X�͏��^�ł����X�C�b�`���O�d���Ȃ̂ŁA
�����g�ϊ��p�͏��^�ő�^�Ɠ����������ł��܂��B
�����R���f���T�[���p�����Ďg�p���Ă��܂��B
��R�����Ȃ����A�ϓ��ɑ��ė����オ��̑����A
�X�s�[�h���̂��鉹��_�������̂ł��B
�������o�����X������邽�ߕK�������ǂ��Ƃ͌����܂���B
�W�F�t102�A�C�X�p���[���X�C�b�`���O�d���ł��B
�A���v�����X�C�b�`���O�����ł��B
�R���f���T�[���p�����Ă��Ȃ��������̍D�݂ł��B
�������g���C�_���g�����X���g�p�����f�W�^���A���v������܂��B
�����ԍ��F10503637
![]() 1�_
1�_
�Ґl���� �f�W�R������
���R���g���[���ɂ��Ă������������̂ł����c
�f�W�S������ɂ́A�N���[���d���̎���ʃX���Ŏf���Ă܂������c
�N���[���d���A����200V�_�E���g�����X�����ɂĒ��̐����R���g���[�����������̂Ȃ̂��c
���݂Ɏ��̃A���v�͂`���ł��B(AB������ŋߕς��܂����j
�ȑOAB���̎��ɃN���[���d�����A���v���ɃJ�}�X�ƒ����̃p���[�A�b�v�A�p���[�A���v��lj����������H�ɂ͂Ȃ����̂ł����c ��
���̃��x���Œቹ���o�ĂȂ��킯�ł͗L��܂���B(�����̃��x���܂ōs���Ă܂��B���[�G���h�܂ŐL�тĂ܂��j�B
����ɁA200V�_�E���g�����X�������̓N���[���d�������Ő����́A�o���͂����������S�ɋ��_�Ƃ͎v���܂����c�������ł���`�I�H
���݂ɕʓr�u���b�W�ɂ���p���[�A���v�̒lj��͍l���Ă͂���܂���B
�����ԍ��F10504894
![]() 1�_
1�_
�ΐl����A����͂�́B
��_�A�������肦�Ȃ����Ǝv�����X�v���܂����B
>�܂�D���������߂ɂ͉����́i�u���̓d�������\�́j���K�v�ł���A���̂��߂ɂ�
���͂ȋؗ́i��d�͔����\��(500W�Ƃ�)�j���K�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
������u���d�������\�͂Ɓu�o�́v�Ƃ́A�C�R�[���̊W(�܂�P���ɏo�͂��傫���قǏu���d�������\�͂�����)�Ƃ�����̂ł��傤���H�@
���͒m���s���̂��ߔ��R�Ƃ��܂��A���[�J�[��������ɃA�s�[�����Ă���Ƃ���ɂ��ƁA�u���d�������\�͂͏o�͂Ƃ������ނ���쓮�͂ƃC�R�[���̊W�ł���悤�Ȉ�ۂ������Ă��܂����B(�܂�K�������o�́��쓮�͂ł͂Ȃ��A�Ƃ����悤�ȕ����ł���)
�Ƃ���u�f�W�^���A���v�͋쓮�͂�����v�Ƃ悭������̂́A�o�͂Ƃ̊W�ł͂Ȃ��u���d�������\�͂��������䂦�ł͂Ȃ����H�@�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��B
�����ԍ��F10505421
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����B
���u�N���[���d���A����200V�_�E���g�����X�����ɂĒ��̐����R���g���[�����������̂Ȃ̂��c�v
�ȑO�f�W�^���A���v��ON�^OFF�����́A
�X�C�b�`���O�����f�[�^�ɕϊ����Ă�
�A�i���O�g�`�ɖ߂����Ƃ��o���Ă��܂�������A
�N���[���d���Ŕg�`���Đ������Ƃ��Ă�
���{�I�Ȑ����͕ς��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Əq�ׂ܂����B
���l��200V����~������100V�Ƃ��Ďg���Ă��A
�@��ɗ^����200V�̐����͂��̂܂c��Ǝv���܂��B
http://community.phileweb.com/mypage/entry/1292/20080207/2804/
���u200V���~�������d�����g�p����ƁA�������Ƃɂ͖߂�܂���v
�t��100V����������200V�Ƃ����ꍇ�A������100V�Ƃ������ł��B
���R�[�h���D�Ƃ̃A�i���O�v���[���[�ւ̏�M�c�B
�C���^�[�R�l�N�g��SP�P�[�u���ŁA
�����ς��Ȃ��Ƃ����^��ǃA���v����h�ł��A
�v���[���[�̃V�F�����[�h�ʼn����ς��Ƃ����܂��B
�������J�[�g���b�W��v���[���[�ɂ���Č��ς��鎖�ɔ��_�͂Ȃ��ł��傤�B
�v���[���[�����[�^�[�ɃR�C�����g�p���Ă��܂����A
���[�^�[����̎����R������@�ʼn����ɉe�����܂��B
�������A�[���A�^�[���e�[�u���Ȃǂɂ��C���g���܂��B
CD�v���[���[�ɂ��ꂾ���̏�M��������ł���ł��傤���B
�ڂɌ����Ȃ��قǂ̃��R�[�h�a��A
CD�Ȃǂ̃r�b�g�������Ă��鎖�ł͓������i�ł���Ǝv���܂��B
�㗬�̃v���[���[�ɃA�i���O�قNjC���g��Ȃ��͉̂��̂ł��傤�B
�����ɔg�`�Đ��^�N���[���d�����g�p���邱�ƂŁA
�����\�̃A���v�ł������قǁA
CD�v���[���[�̂킸���ȏ��܂ŗ]�����ƂȂ��������A
�A���v�̐��\���o�����鎖�ɂȂ�Ǝv���܂��B
��ʂ���g���������ǂ��Ȃ�A�ቹ�������o��Ƃ͂ǂ����������Ƃ����ƁA
��@���̂��̂������Ă���\�͂��o����Ƃ��������Ǝv���܂��B
�����Ƃ�����@�ɂ�������Ƃ������������܂����A
����͂��ł��o���܂��B
���߂鉹�Ƃ͊�@�̌��������Ŋ���������̂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10507799
![]() 1�_
1�_
�f�W�S��������I�ȓ��e�����������Ă��������ėL�������܂��B
���������m����m���Ă���Δ[��������ŋ@��ƕt�������Ă�����Ǝv���܂����A
���E���L����܂��B
���ׂČ����1�����~�̍����o�̓g�����X�̓����͉����ł�50Hz����70kHz�قǂ͈̔͂Ł{�|2dB
�قǂŋC�ɂ���قǂ̂��̂ł͂���܂��A�C���s�[�_���X��25kHz�ӂ肩��Q�����I�Ɉ���
���Ă����悤�ł��B�����ш�O�̉����d������Ȃ�A��������������f�W�A�����g�����ق���
�����ł���ˁB
�����ш�O�̉��������ш���̉������P����Ƃ����b�͕��������Ƃ�����܂��B���ʂɎ���
���鉹�͊�ɔ{�����d�˂��������Ȃ킯�ł����A���������{���������ɂȂ�قNJ�̂Ƃ��ɂ�
�P���ȃT�C���J�[�u��`���Ă����������G�Ŋ��炩�ȃJ�[�u��`���Ă����Ƃ������̂ł��B
�����A���̃J�[�u�̊��炩����l���F���ł���͈͂ɂ����E������킯�ŁA���ʐl�̉������E��
��N�҂�17kHz�O��Ƃ������Ƃ��l����Ƃ�������20kHz�܂ł͈̔͂ł��\���ɉ��������P�����C��
���܂��B
�قƂ�ǂ̐l�̓u���C���h�e�X�g���s���ƁE�E�E�B
�܂��A���������ш�O�̉���On/Off�ł���A���v�������Ă����̂ʼn��x���������̂ł����E�E�E�B
����ȏ�͂��̎�̋@��̃Z�[���X��W�Q����̂Ō����܂���(��)�E�E�E�B
����CD���������Ȃ��̂ŒN�ɂł��n�b�L���킩�邭�炢���ቹ�����������A�E�g�v�b�g�g�����X
�t�������ł��ˁ`�B
�ł��^�̃}�j�A�͉����ш�O�̉��̈Ⴂ������Ǝv���܂��I
���ƁA������Ƙb����т܂����ACD�v���[���[�ɂ�鉹���̕ω��͑̌��������Ƃ���܂��I
�\���N�O�̂R���̃v���[���[���ŐV�̂S���̂��̂ɕς����Ƃ���A���̉𑜓x�ƃN���A����
�啝�ɑ����܂����B����ȏ�ǂ�قǃn�b�L�����P�̗]�n������̂��z���ł��܂���B����
�����łȂ��Ɣ�r�ł��Ȃ��̂Ŕ����Ă݂Ȃ��Ɖ���Ȃ��ł��傤���E�E�E�B
�����ԍ��F10512602
![]() 2�_
2�_
���[���E���t����
�����_�E���g�����X�ƃN���[���d���͓����������Ƃ��Ȃ��̂�
�Ȃ�Ƃ������܂��A���Ƀ��[�J�[�̃E�^�C����ʂ�̌��ʂ�������
�Ƃ��Ă��m�C�Y�������Ȃ��ĉ����N���A�ɂȂ邾���ł���ˁB
�u���͂̓p���[����f�q�̉e�����傫���ł��傤���A�����͂̓A�E�g�v�b�g�g�����X
�t�̃A���v�̏ꍇ�͑O�q�̃����c�̖@���łǂ����Ă����������������͂���̂�
���傤������u���́A�����͂Ƃ��ɃX�s�[�J�[�Ƃ̌��ˍ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����A�����̖͂��������ɂȂ�Ǝv���̂ł���͂���ő厖�ɂ����ق����悢�̂ł́H
���̃A���v�ɑ��Ă����߂�͖̂��������邩�ƁB
�����ԍ��F10512605
![]() 2�_
2�_
Dyna-udia����A������B
��������قǂ̒m�����Ȃ��Đ\����܂���B
�����̈�˒[�_�c�Ƃ������ƂŁE�E�E�B
���͌��X�A���������ɃX�s�[�J�[���쓮����̂ɏ����d�͕͂��ʂ̃V�X�e���Ȃ�
�RW���x�ƕ����̂ŃA���v�̍ő�o�͂͏\�����b�g�ŏ\���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���
�̂ł����AA���A���v���^�̃A�E�g�v�b�g�g�����X�������͕̂ʂƂ��ăf�W�A����
���E�I�ɒ����ȏ�ƂȂ��100W�ȏ�̏o�͂������Ă��܂��B���[�J�[�̍����ł͂Ȃ�����
�^���Ă����̂ł����A���E���̃��[�J�[���O���ɂȂ��Ă���Ƃ��v���Ȃ��̂Ō����
�f�W�A���̑����f�q�ɂ͉������{�I�Ȗ�肪�����Ă��̂悤�ȑ�o�͂��K�v�Ȃ̂ł�
�Ȃ����Ǝv���܂����B
���ǂ̓A���v�f�q�ɓd��������Ă�������̔����̂��O�a��ԂɂȂ��ēd��������o���܂ł�
�^�C�����O�Əo�͂�100���ɂȂ�܂ł̎��Ԃ��A�x�[�X�d���̃T�|�[�g�Ɛ^��ǂ̓d�q���o��
���X�|���X�̗ǂ��ɓK��Ȃ��̂ő�U�����̐U���̗����オ�肪�݂��Ȃ��č����ł���
�̂��Ǝv���܂�(���Əo�̓g�����X���o�b�t�@�ɂȂ��Ă�̂���)�B
�d�������̎������ł��Ȃ��Č㔼�ɂւ���Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁB
���ۂ̏o�͂��RW�ōςނȂ�A���ɓI�ɂ͂��̒��x�̍ő�o�͂�����Ηǂ����ƂɂȂ�܂��B
�������A�S���V���������̂��J������̂������ɂ͖����ł��傤����D���̗��オ������P
���邽�߂ɂ͍ő�p���[���グ�鎖�����Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���̂��ߐ��E�ɂ�
��o�͂̃f�W�A�������Ă���ƁE�E�E�B
�v����ɍő�p���[���グ��Əu�������\�͂��オ��̂��Ǝv���܂��B
�Ⴆ��10W�̃A���v��3W�̏o�͂�����܂ł�1�b������Ƃ��āA100W�̃A���v��3W�̏o�͂�
��������܂łɂ�0.1�b�ōςނƂ��B
����z�����Ă��邾���Ȃ̂ł����A���ǂ̂Ƃ���A�����̂̍��{�I�Ȗ��̂��߂ɐ��E�I��
�p���[�������N���Ă���̂��Ƒz�����Ă��܂��B
�����A���������A������T-88�̌��R�~�Ȃ�Ő�`���Ƃ��܂����A
���W��T-88���Ă���L�����[�J�[��20���~��̃f�W�A�������Ƃ���A����悪
�X�J�X�J�ɕ������܂����B����20kg��̏d�ʋ��f�W�A���łȂ����T-88�̒��ቹ�̌��݂ɂ�
�K��Ȃ���Ȃ��ł��傤���ˁB��������Ɖ��i��50���~���z���܂����A����d�͂�T-88��
�卷����܂���(�����͋����[���Ƃ���ł��B���ǃf�W�A�������ቹ�̌��݂����߂�Ƒ����d��
�ɂȂ�̂ł��傤���B�W�F�t�E���[�����h��Continuum 500�ȂǑҋ@�d�͂�35W�ł����ő��2000W�ł�)�B
�܂�T-88��SN��80dB�Ńf�W�A���ɔ�ׂăN���A�ȉ����ł͂���܂���ł������A������������Đ^���
�̖����킩��₷���ėǂ���������܂���B�����A��Ƀ��[�J�[�̍ɏ����i�Ŕ��z���������߂ɑς�
���ꂸ�ɔ����Ă��܂���(T-88�̃C���p�N�g������(�X�������ĂȂ�������))A-200P�Ȃǂ͂��̓_91dB��
�f�W�A�����݂ɃN���A�ȉ����Ȃ̂ł������������͋C�͉���ɂ��������m��܂���(������Ď������ȁH)�B
�����ԍ��F10512610
![]() 3�_
3�_
�ΐl����A����ɂ��́B
>�L�����[�J�[��20���~��̃f�W�A�������Ƃ���A����悪�X�J�X�J�ɕ������܂����B
�܂��f�W�A���͂��̃X�b�L�����������ł���ˁB���Ȃǂ͂��̂ւ���܂�D�݂���Ȃ���ł����A�t�ɍ���d���œ������Ƃ��@�ׂ��A�X�s�[�h�������߂�l�ɂ̓f�W�A���͍D�܂��悤�ł��ˁB
>T-88��SN��80dB�Ńf�W�A���ɔ�ׂăN���A�ȉ����ł͂���܂���ł������A
>������������Đ^��ǂ̖����킩��₷���ėǂ���������܂���B
�͂��B�^��ǃA���v�͂����Ӗ��ł̎G���Ƃ������A���t�Łu�m�C�W�[�v�ȂƂ��낪���ɂȂ��Ă��܂���ˁB���Ƃ��G���L�M�^�[�̉����Ӑ}�I�ɘc�܂����A������f�B�X�g�[�V�����T�E���h�Ȃ́u���ꂢ�ȉ��v���D�ސl�ɂ͂��邳�������ł��傤���A�������������́u�m�C�Y�v�����y�ɐ[�݂□�킢��^����̂������ł��B
�I�[�e�B�I�̗��j��SN��̍����u���ꂢ�ȉ��v��Nj����Ă������j�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�ĊO�A���y�̖��킢�Ƃ́A����Ƃ͋t�����̐��E�ɂ������肷���Ȃ����ƍŋߎv���܂��B
�����ԍ��F10513776
![]() 4�_
4�_
Dina-udia����ɂ���
>�I�[�e�B�I�̗��j��SN��̍����u���ꂢ�ȉ��v��Nj����Ă������j�ł͂Ȃ����Ǝv���܂�
>���A�ĊO�A���y�̖��킢�Ƃ́A����Ƃ͋t�����̐��E�ɂ������肷���Ȃ����ƍŋߎv
>���܂��B
�m���ɂ��������̂��邩���m��܂���B
�ŋ߁uHi-Fi(�������Đ�)�K�������P�Ȃ炸�v�Ǝv���̂ł����A�悭���[�J�[��CD�ɍ��߂�ꂽ�\�[�X��
�����Ɉ����o�����Ƃ��ŗǂƌ����Ă��܂����A����͘^���������ł��邱�Ƃ�O��Ƃ���
���Ȃ��ł��傤���B�Ⴆ�ΐ^��ǂ�KT-88�̂悤�Ƀ\�[�X����⌃�����������邱�Ƃ�Hi-Fi
����͉�������܂����A�������Đ����̔��͂���݂����点����Ƃ��B
�^���Z�t�̈ӌ����Ă݂������̂ł��B
�f�W�A���ɂ��\�t�g���[�h�Ƃ��n�[�h���[�h������Ƃ��������B�����i�K�ł͂Ȃ��ĐM���ǂݎ���ɏ�������Ƃ�����������܂���ˁB
���ǁA�I�[�f�B�I�ɉ����Ȃ��ł��ˁB�ł��邾�����i�̈Ⴄ�@�ނ𑵂��ċC���≹�y�ɍ��킹�Ďg��������ƍō������B
�����ԍ��F10518146
![]() 3�_
3�_
����ɂ���(^_^)v
�Ґl���� �f�W�S������
�N���[���d���̃��r���[��(���̉�������߂�Ȃ��j�Č����\�������X����܂��B
�ܘ_�b�c�v���[���[(�f�W�^���O�i�j�͔[���ł��܂��B
�������ǂ̉ƒ�(��ʏZ��j�ł��N���[���d�����ʂ����邩�͋^��ł����A�g���Ă݂Ȃ��ᕪ����Ȃ������̂Ƃ���Ó��Ȑ��ł���f^_^;
(�A���v���ɂďu���́A�L��ȃs���~�b�h�o�����X���\�z�o����̂��H�j
�܁A�B�����Ȃ�̑f�p�ȋ^��łƂ��Ă����܂��B(^_^)v
����͊y�������b���肪�Ƃ��������܂����Bm(_ _)m
�����ԍ��F10520757
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����ICEpower�̏�肪�Ƃ��������܂��B
�A���v�ȊO�̗v��������Ȃ��̂�
���ȏ�̃A���v�����߂邱�Ƃ͂Ȃ������ł���
�f�W�A���ɂ����������Ă܂����B
���Ȃ݂�ICEpower��250W���f����1kHz�ȉ�(8��)�ł̓_���s���O1000�ȏ゠��܂��ˁB
4�����Ƃ������������Ă܂��B
��͂�_���s���O�t�@�N�^�[�̓f�W�A�����B
Dina-udia����
ICEpower�̃z�[���y�[�W������ʔ����ް����̂��Ă܂����B
ICEpower®250ASP�Ƃ���250W�A���v�̃R���g���[���[�̃f�[�^�V�[�g(14�y�[�W)��������
20kHz�Ńt���p���[�܂Ŗ�1.8�b�A10kHz�Ŗ�12�b�ł����B
10kHz�ȉ����̂��Ă��Ȃ��̂ł����A�قڒ����̃O���t�Ȃ̂ł��̂܂ܐ���������
f0�t�߂Ŗ�80�b�ł��B3.1W������܂�1�b�Ƃ���Ƃ��Ȃ�x���悤�ȋC�����܂��B
A���A���v�̏ڍׂȃf�[�^���Ȃ��̂łȂ�Ƃ������܂��A��͂�f�W�A����
�ቹ�����Ȃ̂����BICEpower�̓f�W�A���̒��ł͑������\�����ق��ł��傤����B
�Ȃ���250W���f���������̃f�[�^�͂̂��Ă܂���ł����B
�܂����ԈႦ�čڂ����Ƃ��H
�����ԍ��F10524050
![]() 2�_
2�_
>�ŋ߂܂ł͐^��ǃA���v�Ƃ������͖̂����L����̂ł����Đ��\�ł̓f�W�^��
>�A���v�ɓG��Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A���ۂ̓f�W�^���A���v�������Ă���̂̓R�X�g�E
>�@�\���E�ȓd�͐��ł���A�X�s�[�J�[�̋쓮�́A���ɒ����̓f�W�^���A���v�ɏ��ڂ�
>�������Ƃ�����܂����`
�����͈ȑO�̎��������ł����B
�@�ނ̐��\�𗝘_���Ă��ăX�y�b�N�◝�������ōl����ƃg�����W�X�^�[�Ȃǐ��g���ăp���[������f�W�^���A
�A�i���O�A�A���v���D��Ă���E�E�E �ƃA�^�}�̒������ŏ��s�����ߕt���Ă��܂��̂ł����A��x�ł��Nj��A���v��
�����Ă��܂�����A���̊Ԉ�����u�T�O�v��������Ă��܂��܂��ˁB
�A���v�ɂ���ĕς�鉹��` �^�C�Ă��ɗႦ��ƁA�����̂Ɂu�v���g�����A���v�Ɣ�ׂĐ^��ǃA���v����o�Ă���
`�^�C�Ă��̕����Q�{�߂��p���p���ɃA���R���l�܂����^�C�Ă��Ƃ����������ł��傤�B
���̖��x���A�Z�������g�����W�X�^�[�A���v�ł͊ȒP�ɂ͏o���Ȃ����̂�^��ǃA���v�͋���Ȃ��o���Ă��܂��B
���̂�����͖��@�ƌ����Ă�T���X�CAU-07Anniversary���낤��AU-X1111 MOS-FET���낤�����ꑾ���ł��ł��܂���B
�����ԍ��F10539378
![]() 2�_
2�_
HDMaster����ɂ��́B
�����̃��X�|���X�I�ɂ̓V���R���Ƃ��Q���}�j�E����}�̂ɂ��ēd���𗬂���
�}�̂Ȃ��œd���𗬂��^��ǂɂ͌����I�ɕs���ȋC�����܂��ˁB
�����A�����I�ɕs���ł����Ă��������͂Ȃ��̂��ƒ�����\���ȃp���[�������邩���B
ICEpower�̃��W���[���Ŏ��삵�Ă݂������̂ł��B�����i�͍����Ĕ����Ȃ��̂ŁB
�S�����W���[���Ȃ�p�\�R�����̂Ɠ�������Ȃ��ł����ˁB
�܂�����ȂɃA���v�����ĂĂ��Ӗ��Ȃ��ł����ǁB
�^��ǃA���v(�A�E�g�v�b�g�g�����X�t���̂���)���݂̃p���[�̂���f�W�A�������y���i��
�ɉ���Ă���܂łɂ͂܂����炭�����肻���ł��ˁB
���̂Ƃ���R�X�g�p�t�H�[�}���X�I�ɂ��^��ǃA���v�͔��ɗD�G�Ȃ悤�ł��B
�����ԍ��F10544238
![]() 1�_
1�_
Dyna-udia����A���[���E���t����B
���O�̃R�����g��Triode��TRV-A88SE��Cayin��A-200P�ɂ���
��^�o�̓g�����X���ڂ�A-200P�̂ق��������̌��݂������Ă��邯��ǂ�
�_���s���O�t�@�N�^�[�̈����͊����Ȃ��Ə����܂������A�X�s�[�J�[�����ւ���
������ׂĂ݂�Ƃ�͂�A-200P�͒����̌��݂����������A�}�b�^���Ƃ�������
�Ȃ��Đ�͗������ۂł��ˁB
��͂�f�W�S������̂����悤�Ƀg�����X��ςނ��Ƃɂ�闘�_�����镪�A������
����悤�ł��B
�^�A�j���Łu�B���p�͓��������������v�ƌ����Ă��܂������A�I�[�f�B�I�ɂ������
���Ă͂܂�悤�ł��B
��T�ɑ�^�g�����X���ǂ��Ƃ͌�����܂���ˁB
�����ԍ��F10548965
![]() 2�_
2�_
���͂悤 �������܂��B
�ȑOHiVi�̓��W�Œ�摤�̃p���[�𑼎Ђ̓{���A���v�ɑւ�����W�����܂����B
�������`�����f�o���g�����A�A
���̃��[�G���h���L�уS���b�Ƃ����u���͂����郁�[�J�[�̃A���v�͔j�i�Ȓl�i�̂悤�ł��B�m��500���H
�ȑO�d���g�����X�̘b�������܂������c
�O�ɂ����Ă��A���v��505u�B����ɃO���[���d���ɍ������ނƖ����� �u���͂��i�Ⴂ �܂�SN�͗ǂ���Ńv���X�ɍ�p����܂����B
(���y��������������j
�������ǂ̂���ł��́H�H�H�ł����c
���݂ɓ����̉Ƃł͎q�u���[�J�[�����̃A���v���R���Z���g(�����z���j��CV8�X�P�A���g���Ă܂��B
���܂�ڂ����Ȃ��̂ł����N���[���ȓd�������邱�Ƃɂ���ă_���s���O�t�@�N�^�[���オ�錾�����Ƃ��l������̂ł͂ƁH�H
�G���̃��r���[�̋L���ɂ͕K���������������Ă܂�
�����O���܂ł���ςł��芴�������Ƃ������Ă܂� �ꊾ�B
�܂��f�W�^���A���v�̗ǂ��A�i���O�A���v�̗ǂ��͕ʂ̃x�N�g����������܂����(^_^;)
�������̍D�݂ɂ���肻���ł��B(���͑S�̖̂��x�ł`���ɂ��܂����B
����ƃW�F�t�̃A���v�B
�������������Ȃ�܂����B(��)
�����ԍ��F10550223
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����ɂ���B
�N���[���d���A������x�͎����Ă݂����ł��B
���������ł����ǁB
�m���ɃN���[���d���̂悤�ȃ��J�j�Y�����d�����ɖ����A���v�̏ꍇ�A�d�����C���̓d����d���̕ϓ��͑������Ɋg�傳��ďo�͂���Ă��܂��C�����܂��B�����炭���̉𑜓x�������Ă��܂��ł̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̂悤�ȏ����P������
�������� �u���͂��i�Ⴂ �܂�SN�͗ǂ���Ńv���X�ɍ�p����܂����B
�Ɗ�������Ǝv���܂��B
���̉𑜓x���オ��Ƃ������Ƃ̓_���s���O�t�@�N�^�[�̌��㎞�Ɠ������ۂ��Ǝv���܂��B
�܂荂���g�����X��N���[���d���Ń_���s���O�����P�����킯�ł͂Ȃ��A���l�̌��ʂ����҂ł���Ƃ������Ƃ�������܂���B
�����A�A���v�̎�ނɂ���Ă��d���̉��P���ʂɈႢ������Ǝv���܂��B
��Ԍ��ʂ�����̂̓N���[���d���Ɠ��l�̋@�\���Ȃ��ăV���O�������ő�^�̏o�̓g�����X�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��^�C�v���Ǝv���܂��B�m�C�Y�܂Œ����ɍĐ����Ă��܂�����ł��B
�t�Ɍ��ʂ��������Ȃ̂̓N���[���d���Ɠ��l�̋@�\�𓋍ڂ��Ă��ăv�b�V���v���ő�^�̏o�̓g�����X�𓋍ڂ��Ă���^�C�v�ł͂Ȃ��ł��傤��(���������@�킪���邩�͒m��܂���)�B
���X�m�C�Y���J�b�g���Ă����ɁA�v�b�V���v���łQ�n���̃A���v�̏o�͂���܂Ƃ߂ɂ���Ƃ��ɉ𑜓x�͒ቺ���邵(���ʒቹ�͌��シ��)�A��^�̏o�̓g�����X���𑜓x���ቺ���邩��ł��B
�����炭505u�͌��サ�₷���^�C�v�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���p�̃A���v�͂���������ƃv�b�V���v���ő�^�g�����X���ڃ^�C�v�ł́H�ł���A�����������̃^�C�v�̃A���v�͐��𑜓x�ł͂Ȃ��A�ቹ�̗͋����ƃ_���Ȋ������y���ނ��̂�������܂���B�ԂŌ����A���Ԃ���Ȃ��ł��傤���ˁB
KT-88�̃V���O���Ƃ��v�b�V���v���ł����^�g�����X�̂������������B
����KT-88�̃V���O���ŏ��^�g�����X�̃��f����2A3C�̃v�b�V���v���ő�^�g�����X�̂��̂�
�C����\�[�X�ɍ��킹�Đ�ւ���ׂ��^��Ǘp�̃A���v�Z���N�^�[�𒍕����Ă��܂��܂����I(�n��)
���܂��f�W�^���A���v�̗ǂ��A�i���O�A���v�̗ǂ��͕ʂ̃x�N�g����������܂����(^_^;)
�v�b�V���v���̑�^�o�̓g�����X���f���́uHiFi�K�������P�Ȃ炸�v�̓T�^��̂悤�ȋC�����Ă��܂����B
�����ԍ��F10557038
![]() 1�_
1�_
������`
�m���ɗǂ��l����������ȂƁc
������c ���������Δ[�����܂��ˁB
�H�t���e���I���ɂđ݂��o���N���[���d��������܂��B
�^��GPC-T�{���g�A���y�A�B
1500W�^�C�v�ł�����A���v�ł��g���܂��ˁA���� ���X�ɂ���c
�m���Ƀ��b�N�X�`���ɂ͂��܂���ʂ́H�H�����ł��ˁB
���݂Ƀv���[���[�Ɏg���Β��Ԃł��[��ɕ��������G�ɂ͂Ȃ�܂��B
����ƍ���]�_�Ƃ��E�G�X�g���C�N�̒��Ɏg�����Ƙb������̃A���v�̓`���v�^�[�ł��B
D�N���X�A�i���O�A���v�ƌ������m���̃A���v�ł��ˁB525���~�B
�����ԍ��F10558334
![]() 1�_
1�_
���[���E���t������B
������肪�Ƃ��������܂��B
�H�t�̃e���I���B���̂��������Ă݂悤�Ǝv���܂��B
���܂̉��̓������ŏ\���Ȃ̂ł����A�_���؋��ł����烂��������
������������ł��B
�`���v�^�[�E�E�E�B�������ł��ˁB
�A�i���O��D�����E�E�E�W�F�t�Ƃǂ����������낤�B
�قƂ�Ǐ��N����̃{�X�L�����Ό��ł��ˁB�������܂�Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��ƁI
���[���E���t����̃}�V�����Đ^��ǂ��Ǝv���Ă���ł����ǁuL-550A�U�v���uL-590A�U�v�ł���ˁH������ăg�����W�X�^����Ȃ��ł����I�������p�������v�b�V���v���Ƃ́E�E�E�B�T�C���J�[�u�̂Ȃ��ڂ������v�b�V���v���ƑS�̂��܂�ׂ�Ȃ��ڂ₯��p�������E�E�E�܂�ׂ�Ȃ��ق����ڗ����Ȃ��ėǂ��C�����܂����A���ۂɂ�������Ȏd�l�̃}�V���ŕ�����ׂ��猩�ɂ߂��Ȃ���������܂����(���)�B
���̃}�V���͕��ʂ̃A�i���O�d���ŏo�̓g�����X����������Ȃ���SN��������E�E�E�B
�N���[���d���̈З͂����������^�C�v�����B
�^��ǂ�A���ƃg�����W�X�^��A���ŕ�����ׂĂ݂����ȁ`�B
�^��ǂƓ����ȏ�̒����̃p���[����������V���b�N���ȁ`�B
���Ƃ̓X�s�[�J�[���ȁB����ł��������Ȃ��悤�ɃX�L�����X�s�[�N�̃E�[�t�@�[�g�������C�����Ă��܂����B���W�ł��\�j�[��SS-AR1�̃X�R�[�J�[�Ɏg���Ă܂�����(���Ԃ�OEM�B����ȂȂ��ڂ̂��郆�j�b�g�̓X�L�����X�s�[�N�����Ȃ��Ǝv��)�������g�����y�b�g�̉��ł�����B�@�ނ�����ڂ������炵���E�[�t�@�[�͑u�₩�ɂȂ��Ă��܂��Ă܂������E�E�E�B
�����ԍ��F10560459
![]() 1�_
1�_
������`
���̓��b�N�X��600A�Ȃ�ł���B�B
�X�s�[�J�[��ATC�̃g�[���{�[�C�B
�v���t�B�[���ɃV�[�U�[������Ă܂��B(��)
M800A�Ƀv���Ƀ��r���\��320S�����ł������f�O���܂����B
�A���v�����ɂăe�X�g�����A�L���̂`35��艜�s����SN���D��Ă܂����B�ŏ�����v�����C���͓��ɂ���܂���ł����B(�Z�p���[�V�����̊W�Łj
�X�s�[�J�[�V�^JBL4429���Œ肵�Ă��炢�e�X�g�B
�{���_�[�Ɩ����܂������cf^_^;
�����Đ����ł����ˁB
�N���[���d������200V�_�E���A�C�\���[�V�����g�����X
���N�t�ȍ~�ł��ˁB
��������ɍw��
�A���v���ʔ����Ă����낢��v���[���[����f�W�^���@��Ɏg���܂����甃���đ������͖�������(^_^)v�v���܂��B
�����ԍ��F10563051
![]() 1�_
1�_
���[���E���t������B
�������}�V�������Ă܂��ˁI�����܂����I
M-600A�͐A���v�̒��̎コ���������邽�߂ɂS�p������×�S��SN��114dB��B�����Ă�킯�ł��ˁB�����Ԃ̃G���W���Ō����Β��S���S��̂����ĂP�U�C���Ƃ������Ƃ���ł����B����ł�����Ɠ�������114dB�Ȃ��炷�����B�����Ɋ�Ɣ閧������킯�ł��ˁB�Ԃ�������}�C�R���œd�q���䂷���ł����ǁB�_���s���O��350�����邶��Ȃ��ł����I
�����AATC�̃X�s�[�J�[�͂����Ƃ��ȕ��݂����ł����ǂ��̃N���X�Ƃ��Ȃ�Ǝ��͂�������ɂ͕�������d������܂ő�����肱�܂Ȃ��Ɠ���݂����ł��ˁ`�B�A�܂����Y�݂ł��B��J����̂�����܂����B�V�[�T�[�u���Ă����ƈ������킢�Ă��Ă����Ǝv���܂��B
���͎������̃X�s�[�J�[�ɂ��čl���Ă���ł����ǁA�����̐���A�A���v�̐��\�A���I�ɂǂꂭ�炢�̉��ʂ��o�����Ƃ��\�Ȃ̂����厖���ƋC���t���ė�ÂɂȂ��Ă����Ƃ���ł��B�H�t�̃V���b�v�̃I���W�ɋ��������ł����A�������X�s�[�J�[�͋��͂ȃA���v�ő傫�߂ȉ��ʂŖ炳�Ȃ��ƒቹ���łȂ��Ďア�A���v�͑�^�ō��\���̃X�s�[�J�[���g��Ȃ��ƒቹ���łȂ��Ƃ��B�m����PE-101A�Ŏ����Ă݂��炻�̒ʂ�ł�����B��ʓI�ȃC���[�W�Ɣ��ł���ˁB���ʂ͎ア�A���v�ł͏������X�s�[�J�[�����������Ȃ��ƍl���܂�����B
���̏ꍇ�͑剹�ʂłȂ��Ă�����̂��鉹�ƒቹ���ł�X�s�[�J�[��Njy����̂��x�X�g�Ǝv���܂��B�X�L�����X�s�[�N�͂���\���Ȃ�ŃK���K���Ȃ炳�Ȃ��Ƃ��߂����B����Beyma�̃z�[��CP350���~�b�h�Ƀn�C�̓t�H�X�e�N�X��T90�Ȃ�ŃE�[�t�@�[��Beyma�̂ق������\���ł��������Ƃ����C�����Ă��܂�����B
�Ԃ�o�C�N���ł����������鑬�x�������l���Đv����Ă��܂����A�X�s�[�J�[�������܂œǂݎ��Ȃ��ƌ��܂���ˁ`(�O�b�^��)
�����ԍ��F10565037
![]() 2�_
2�_
>�������X�s�[�J�[�͋��͂ȃA���v�ő傫�߂ȉ��ʂŖ炳�Ȃ��ƒቹ���łȂ���
>�ア�A���v�͑�^�ō��\���̃X�s�[�J�[���g��Ȃ��ƒቹ���łȂ��`
�܂��ɂ��̒ʂ�ł��ˁB
��厏�Ȃnj���ƈ����A���v��JBL���A�E�[�t�@�[30�`38cm��^�X�s�[�J�[�ɂȂ��Łu�ȊO�ɂ��h���C�u�\�͂��[���L��v
�Ȃ�ăg���`���J���ȃR�����g���I�[�f�B�I�]�_�Ƃ����X�Ə����Ă�̂������Ζڂɂ��܂����A�����ǂޓx��
���̃I�[�f�B�I�]�_�Ƃ̓X�s�[�J�[��ǂ��m��Ȃ��z���ȂƊ����Ă��܂����B
�X�s�[�J�[�����삷��Ɨǂ�����̂ł����A�ʔ̓X�ŃY���Y���ቹ�ߑ��ŗǂ��炵�Ă���̂��������鏬�^�V�X�e���R���|
�Ȃǂ̏����߂̃X�s�[�J�[���炠�ꂾ���ቹ�o���͕̂��ʂ̃o�����X�̃A���v���Ȃ��ł��܂������o���A�A���v�Ńo�X�u�[�X�g
���Ă�̂ŏ����ȃX�s�[�J�[�ł��o����ቹ�Ȃ̂������ł��܂��B
�Ȃ̂ň��������ȃV�X�e���R���|�̃A���v���g���Ă݂���ATC�ȂǓ����ɂ����E�[�t�@�[���ӊO�ɂ��h���C�u�ł��Ă��܂�
�\������܂��ˁB
�����ԍ��F10565093
![]() 1�_
1�_
�Ґl���� HD����B
��Ƃ���ł��B
���̏ꍇATC�̐��i���r���[��v���O�ɂăZ�p���[�g�łȂ点��
����L�����ڂ��Ă܂����B
���̗ǂ��ቹ�͂ǂ�������ł邩�I�ł����c
�A���v�̒����͂�����܂���
�v���X�����̈ꎟ���˂̃R���g���[�����厖���Ɓc
�����˂�}����B���f�b�h�C���ɖ͗l�ւ�����B
���܂菑���Ƃ�₱�����Ȃ�܂����炱�̕ӂɂ��Ƃ����܂����A�A�A�B(��)
���݂Ɏ��̎����Ă�X�s�[�J�[�̃E�[�n�[��17�p�B�}�O�l�b�g�R�C����38�Z���`���͂��邩�Ǝv���܂��B�U���̓s���A�p���v�ł��ˁB
���Ƃ��̃X�s�[�J�[�̓����ł��钆��~�b�h�X�R�[�J��20�Z���`���炢�̃}�O�l�b�g�R�C���ł��B
�X�s�[�J�[���ǂ�ȍގ��̐U�����g���Ηǎ��̒ቹ���ł邩�I�H���Ȃ�ɕ����Ȃ���Ƃ͎v���Ă܂����c
���̓��J�j�Y�����y�������y����������Ɓc
�����ԍ��F10565550
![]() 1�_
1�_
�ǐL
�Ґl����
�����̍L���ɂ���ăE�[�n�[�̑傫���A�{�����[���̏o������l����͂܂��������Ǝv���܂��B
�����������X�s�[�J�[�̉��s�������Ȃ��ꍇ�A(12��ȉ��̏ꍇ�j����a�͗v��Ȃ��Ƃ��c����I�[�f�B�I�V���b�v�X����
�����̏ꍇ���̂��炢�������ς������ς���������܂���B f^_^;
�����ԍ��F10566729
![]() 2�_
2�_
�H�����Ă��܂����ˁIHDMaster����B
�����������ȃV�X�e���R���|�̃A���v���g���Ă݂���ATC�ȂǓ����ɂ����E�[�t�@�[���ӊO
���ɂ��h���C�u�ł��Ă��܂��\������܂��ˁB
�����Ȃ�ł���ˁB�n�C�p���[�A���v�ł����[�p���[�A���v�ł������b�g�����g��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂����܂Ŕ@���ɑ����悹�邩�ƈ��肵�ăp���[���o�����ɂ������Ă���ƁB���̂��߂Ƀ��b�N�X�݂����ɃA���v�f�q���P�U���g���Ă݂��肵�Ă�킯�ł��ˁB
���Ƃ̓X�s�[�J�[���̎v�z���厖�ŁA85dB�ȉ����炢���ƃA���v�Ƀp���[��v�����邩������܂���ˁBBeyma�̃E�[�t�@�[��95dB�������Ń��[�p���[�̃A���v�ł����������s�����肵�ĂƂ��������������܂��B�������A���̃z�[���h���C�o�[�̃A�b�e�l�[�V���������߂�Ƃ��ɂ����Ȓ�R�l�Ŏ����Ă݂���ł����ǁA95dB���Ɩ��M�����̃z���C�g�m�C�Y�����\����������SN��̍����A���v����Ȃ��Ƃ��������B
���ƁA�X�s�[�J�[�ƃA���v�͑������厖�ł��ˁB
�@����RWay�{Triode TRV-A88SE
�APE-101A�{Cayin A-200P
�ȏ�̑g�ݍ��킹�����ւ��Ď����Ă݂���ł����A�@�̓V���O���{���^�g�����X�ŃN���A�ȉ����Ńh�����̒ቹ���͋�������������̂Łu����ōs�������ȁv�Ƃ��v���Ă�����A�A�̂ق����g�����y�b�g�̉������肪�����đO�ɏo�Ă����̂Łu�t�������W�͒����悪�������炩�ȁv�Ǝv�����̂ł����@�ƇA�̃A���v�����ւ��Č���Ƈ@�̓g�����y�b�g���O�ɏo�Ă��ĉ����͂��_���ɂȂ�(�N���A���͂�◎��)�A�ቹ�͂��͋�������͗����銴���ł����B�A�̓_���������Ĕ��ɐ�ƃN���A���������ē������̂��銴���ɂȂ�A�����Ƃ��ǂ��Ȃ�܂����B
���^�X�s�[�J�[�̓p���[�̂���A���v���ǂ��ƌ����Ă����x������悤�ł��B���܂�ቹ������ɂȂ��Ă������̂̔\�͂����E�ɒB���܂��B�܂��A�ӓ_�͍ŏ��ɇ@�Ńh���������������̂ŃA���v�̃p���[���\���Ǝv�����̂ł����A�ӊO�ɂ��������s�����Ă��܂����B��͂�p���[�s���ł������悤�ł��B��͂�RWay�ȏ�ɂȂ�Ƃ��Ȃ�̃p���[��v����悤�ł��B�܂��A�V���O���̐^��ǃA���v�ƃt�������W�̑g�ݍ��킹�͐�i�ł��ˁB���ɓ������������ăg�����y�b�g��̏����̒�����ɔ��ɒ��肪����܂��BEV�Ƃ͐����̐��E�Ȃ�Ŗʔ�����������܂����B
�X�L�����X�s�[�N���������ǃt�������W�͂��̐��E���C�y�Ɋy���߂�A�C�e�������B�����搶�݂����Ȑl������킯������܂�����B
�����ԍ��F10570274
![]() 1�_
1�_
������E�E�E���Ă������������������܂��B���[���E���t����B
�����̗ǂ��ቹ�͂ǂ�������ł邩
��C���t������ł����ǁA���ɋ߂������ɃX�s�[�J�[��u���Ə��ʂɉ������˂��Ēቹ���傫���Ȃ��ł����A����𗘗p����ƒቹ���u�J�u�J�������ɂȂ��Ď��͈����Ȃ�܂��ˁB
���ƃX�s�[�J�[�̃|�[�g�̓t�����g���ǂ��Ǝv���܂��B�ŋ߂̓��{���[�J�[�̂̓o�b�N�|�[�g�������ł����A����͔w���Ⴍ�Ȃ邵�|�[�g����x��ďo�����ŃE�[�t�@�[��500Hz���炢�܂ł̉����c�܂Ȃ��̂�HiFi�ɂ͗ǂ��Ǝv���܂��B�������A���ۂɃt�����g�|�[�g�̂��Ɏ�������Ē����Ă݂�ƃ`�F���̉��Ȃ������ǂ������������Ă���킯�ł��B�t�����g�|�[�g����̉��ɂ�200Hz�ȏ�̒��ቹ���������Ă��邽�߂��Ǝv���܂��B�o�b�N�|�[�g���Ƃ��̗̈�̉��͌�������̂ŐU������̒��ڕ��ˉ��ƍ�����Ȃ����߃}�C�N�ɂ�鑪�����Y��ȃO���t���o�Ă��܂��B
�`�F����M�^�[�A�o�C�I�����⑾�ۂȂǂ̎��ۂ̊y����ώ@���Ă݂�ƌ�����̒��ڕ��ˉ������|�[�g����̒ቹ�̂ق������炩�ɒx��ďo�Ă���̂ʼn��͘c��ł���Ǝv���܂��B�a���ۂ̔��Α�������˂����ቹ�����l���Ǝv���܂��B
�ƒf�ƕΌ��ł����A�o�b�N�|�[�g���̉���HiFi�ł����ă��A���ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傩�H�u�}�C�N���������߂̉�������Ă͂����Ȃ��v�Ȃǂƒ��q�ɂ̂��Ă݂��肵�Ă��܂�(��)�B�y��t�҂̈ӌ����Ă݂����ȁ`�B
���ǂ�ȍގ��̐U�����g���Ηǎ��̒ቹ���ł邩
�u�ቹ�͋����̕��������������Ă����̂��ȁv�Ƃ��u���̕������̂��鉹���ł邩�ȁv�Ƃ��v���̂ł����A�H�t�̃V���b�v�Łu���������Ă܂��ˁ`�U���͎��ł����H�v�ƓX��ɕ����Ă݂�ƁA�u�����A�|���v���s�����ł��B�v�ȂǂƕԂ��Ă��܂�(��)�B���ۂɂ͂��肦�Ȃ��Ǝv���܂����A���ʁE�����E�`�����ł���Αf�ނ̈Ⴂ�͉���Ȃ���������܂���B���ɓ����Ă���̂͋�C�ł�����B�܂��A�ɒ[�Ȓቹ(150Hz�ȉ�)�⍂��(15kHz�ȏ�)�ɂȂ�Ɛl�Ԃ̎��ʔ\�͂��قƂ�ǖ����Ȃ邩���m��܂���ˁB
�I�[�f�B�I��p���[���~�����ł��ˁ`�B�h���̂�B
�����ԍ��F10570310
![]() 1�_
1�_
�ΐl�����ł͉��X�ƈӖ��̖������X������l�B���P�[�u���͂������̂������̂Ƃǂ��ł�������������Ă�ꍇ�������ł�
�������̔ł͒������L�Ӌ`�Ŗʔ������e�ł��ˁB
�|�[�g�̈ʒu�ł����O���Ƃ���������ł͂Ȃ��ăX�s�[�J�[�U���łɂȂ�ׂ��߂����̂��ǂ��̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B
�ƂŃZ���^�[�b���Ɏg���Ă���a���v805�Ȃǂ͂܂��ɂ����n�ł����Ă���悤�Ȑ��i�ł��B
�|�[�g�̗��z��˂��l�߂�X�s�[�J�[���j�b�g���̂��t���[�e�B���O���t�����A���j�b�g�̎��͂ɂ����C�̏o�����ꂪ�o����
���̂��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���������̂������̗p����Ȃ����R�́B�ʏ�X�s�[�J�[���j�b�g�̎��t���Œ�̓X�s�[�J�[�L���r�l�b�g�O�ʃo�b�t���ɌŒ�
�����ꍇ���w�ǂȂ̂ŃX�s�[�J�[���j�b�g�̃t���[�����̂�U�������Ȃ��ׂɂ̓^�C���h���C�����_�̕x�m��ECLIPSE�V���[�Y
�X�s�[�J�[�̂悤�ɑO�ʃo�b�t���ɗ���Ȃ��Œ���@���K�v�ł��B
�����Ȃ�ƍ\���̕��G���ɂ��R�X�g�A�b�v���K�v�Ȃ̂ŁA��������Ȃ��Ō����O�ʃo�b�t���ɌŒ肵�|�[�g��݂��Ă���ꍇ��
�L��悤�Ɏv���܂��B
����ƃX�s�[�J�[�̐U���͒�����ł̓|���v���s�����������������܂��ˁB
Micropure�� Cz201ES�Ȃǂ����̂������{�ł��ˁB
http://blogs.yahoo.co.jp/tec_style2004/39439510.html
�Ƃ�KEF��SP���g���C�A���O�����S�ă|���v���s�������E�[�t�@�[�ł��B
�Ȃ�ƌ������������R�Ŏ��̂悤�ȍd�����o�܂���ˁB
�����ԍ��F10571022
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́`
�����̃g�[���{�[�C SCM40�͍��͒����������ł��B
���ƃI�[�f�B�I���͑S�R�����̗Y�_�C�A�g�[�����̔��I�����Ƃł���(��)
���݂ɂ����̃Z�b�e�B���O�ł����c
�����t���[�����O
�{�[�h��50�o���̃S���̖B
����ɏ㕔�ɂ`�a�`�̔��^���U�{�[�h�ɃX�s�[�J�[�X�o�C�N�E �X�o�C�N���Ă܂��B
�X�p�C�N�͐挎�t���̌��̃X�o�C�N����J1�v���_�N�c�̃R�[���ɂ��܂����B
�ꌾ�ŗD�����̂悤�Ȗ���ɕϐg�ł��ˁB
���ƃX�s�[�J�[�̊Ԃ͐l�̍l���t���Ȃ������ŋ��U������Ă܂��B����ł��ˁB(��)�B����������Ǒ�A����������Ă��܂��B
�����ł͂���܂����N���炢���玩���Ȃ�Ɂc
�Ă� �������邱�Ƃɂ���ăX�s�[�J�[�������鉹��^�Ɂc
�ŋߎv���ɂ܂����Z�b�g���ĉ����A����X�ɖ点�����f^_^;
�e�Ɋp�E�[�n�[�������(�u���͂��������A�����~�߂����j�ł��ˁB�B
�A�O���b�V�u�ȉ����ƍL��ȉ���̃R���{���[�V�����B
�����ЂƓ��肷��Ώo�������ł����c
��������ɂ� �J�͂ƒm�b���v��܂�(��)
�Ȃ��Ȃ�����e�[�}�ł��ˁB
������������X�s�[�J�[�������Ȃ��Ƒʖڂ��ȁ`��(��)
�]�k�ł����ȑO�������A�o�����ƃE�B���\���I�[�f�B�I�B
����Ȗʍ\���ł���ȉ��͔������낤�Ǝv���܂����ˁB
���Ƙb��������̕�����f^_^;
�����ԍ��F10572282
![]() 1�_
1�_
HDMaster����܂��ʔ����̈��������Ă��Ă���܂����ˁI
�x�m�ʂ��X�s�[�J�[����Ă�Ƃ͒m��܂���ł����B
���������p�\�R���p�ŃG�N���v�X���ۂ��`�̂��������Ƃ���܂��B
HiFi�����ɂ܂ŒNj�����ƃG���N���[�W���[�̉e���[���ɂȂ��ł��傤�ˁB�G���N���[�W���[���̂��̂��y��̂悤�ɖ�^�C�v�Ƃ͑ɓI�łǂ���ɂ����l������Ǝv���܂��B�����A�G���N���[�W���[���̂��̂��y��̂悤�ɂ���Ɩ{���̊y��Ɠ����Ŏ���͈͂͋����Ȃ�܂��ˁB�o�C�I�����ɂ͌������ǃR���g���o�X�ɂ͌����Ȃ��Ƃ��B
�O��̃R�����g�������������ł����ǁA�o�C�I�����n�̊y��̃|�[�g�̓X���b�g�^�ŋɗ͒����������Ȃ��悤�ɂ��Ă܂��ˁB�|�[�g����̒�����ϋɓI�ɗ��p���Ă�̂̓M�^�[�ł��ˁB���Ƙa���ۂ̔��Α�����o��ቹ�͉�͂��đO�ʂɉ�肱�ނ̂Ńo�b�N�|�[�g�Ɠ����ł���(��)�B
HiFi�̎������@�����푽�l�Ń��[�J�[�͎�_�͂��܂��Ă�̂Œ��ӂ��K�v�ł��ˁBHiFi�I�ɂ̓|�[�g�͗��p���Ȃ��̂���Ԃ��Ǝv���܂�(�����c�ނ̂�)�BB&W�̃m�[�`���X(http://www.bowers-wilkins.jp/display.aspx?cpflgs=0111&infid=1457)�݂����ɁB�������̓|�[�g�̉��͊y����ۂ��čD���ł��B�x�m�ʂ̃T�u�E�[�t�@�[�����ł��ˁB���������̖������Ȃ��Ďv���Ă���ł��B�������A���[���C�R���C�U�[�ŃX�s�[�J�[�Ƃ̈ʑ����}�b�`���O����@�\���Ȃ��Ƃ��������̃^�C���h���C�����_���䖳������(���E�̃X�s�[�J�[�̈ʑ������킹�Ă���Ȃ���)�B�����̉������������邵�A�v���A���v�ɂ��������@�\������Ε֗��ł����̂ł����B
�܂��A���͓_�����ɉ��^�I�Ȃ�ł���B���t�҂̈ʒu���͂��������Ƃ����܂����A����͐l�Ԃ��]���ʼn��ꏈ�������Ă��邾�����Ǝv���܂�(�����܂Ōv�Z�ɓ����Ηǂ���������܂���)�B���ۂ̉��t���������Ƃ������l�ɂ͋�Ԃ��������Ȃ���Ȃ��ł��傤���H���̏��L����t�������W������ڂ��̂�������܂��A����͎���RWay�̂ق����������܂��B�ォ�珇�Ƀz�[���E�c�C�[�^�[�E�E�[�t�@�[�E�|�[�g�ɂȂ��Ă���̂Ńh�����Z�b�g�̉�����ɃV���o���������ĉ��Ƀh���������銴�����悭�o�܂��B�I�̍���������Ȃ��ăc�C�[�^�[���^�ɂȂ��Ă��܂��Ă܂����A�܂���Ńr�N�^�[�̃I�u���[�N�E�I���j�A���C�����݂����Ȍ��ʂ����Ă���Ηǂ��̂ł���(��)http://www.jvc-victor.co.jp/audio_w/hifi/sx-lc33mk2/feature01.html�B�������A�N���V�b�N�̃I�[�P�X�g���̏ꍇ�͏�i�ɒቹ�y�킪���Ԃ̂ŏ㉺�t���܂ɂȂ��Ă��܂��̂ŏڂ����l�͈�a�����o���邩���B���j�b�g�̏�Ƀ|�[�g������X�s�[�J�[������܂���������̓N���V�b�N�p�����B
���ۂ̃��C�u���t�͓_��������Ȃ��ł����B�������A�O�L�̂悤�ȏ㉺�t�]���ۂ��N����Ȃ��̂Ŏ���͈͍͂L�������B
�a���v805�����ł��ˁI�P�u���[�R�[���̂������_�炩�����Œቹ�����R�ł��B�ق����I
HD�����PP�R�[���C�ɓ����Ă܂������B��������Beyma��20cmPP�R�[������悤���ȁB�T�u�E�[�t�@�[����Ȃ��Ȃ邵�E�E�E����������͏����߂̐U���̂ق����ǂ��Ƃ���������S�z���ȁ`���̐^�̂ł����Z���^�[�L���b�v�������߂̐U���łƂ��ē����Ă���邱�Ƃ����҂������I
�����ԍ��F10572747
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����B
SCM40�ł����B
�F�X������Ă�悤�ł��ˁ`�B
�����͒����|�[�g�ő����ł��Ȃ�����Ƀ|�[�g�t���̂悤�Ƀ|�[�g�̍Œዤ�U���g���ȉ��͋}����F�����ቺ����������Ȃ��ėǂ��߂������݂����ł��ˁB���ꂾ���̕���ウ�Ă��܂��̂��ܑ̂Ȃ��悤��(��)�B���͂�M-600��BTL�ڑ������������Ȃ��̂ł́H�����ɕБ������ł���Ă݂�Ƃ��������B����ł��ʖڂȂ��͂�X�s�[�J�[�̍D�݂̖�肩�ȁH
�ґ�ł����ǐ��_�����^�C�v�̃Z�b�g�Ə_�炩�^�C�v�̃Z�b�g���~�����ł���(��)�B
�����ԍ��F10572881
![]() 1�_
1�_
�Ґl����
���N���m�p���[���l���܂����B�f�W�^���A���v�̃j���[�t�H�[�X�B
���͍����ƁB
�� �{���_�[�����ċt�]���܂����ˁB
���݂Ƀm�[�`���X�I
������B��W�͈ꖡ�Ⴄ�ˁB
�w���҂ɂȂ����݂����ȃX�s�[�J�[���[�J�[�ł��B
�R���g���[�����I�݂ŏ�肢�ł��B
�S�Ẵ��f���Ƃ܂ł͂����܂��A�A(��)���l��������X�s�[�J�[���[�J�[�ł��ˁB
���̏ꍇ�ꉞ�ŏI���肵���f���@�́AB��W�ƃ_���ł����B
�s�A�m�g���I���������ɐ��ɋ߂����������̂͂`�s�b�ł����B
�x�m�ʂ̃X�s�[�J�[
��ԉ��y�ƂɈ��p�҂������݂����B �o�C�I���������`�Ŕ[�����܂����B
�����ԍ��F10573067
![]() 1�_
1�_
������
B&W804�A805�A685���l������35%�����ł����E�E�Փ������͂�߂Ă�����
http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/newpage_13.htm
�����ԍ��F10573103
![]() 0�_
0�_
�|�`�����l������B
��i�قł����B
��������HP���������Ƃ͂�������ł����A�����Č��Ă݂�Ƃ�����Ƃ��������Ƃ���i���i���Ŕ����Ă�̂͂����ł��ˁI
�悭���ɏ����������������ʼn������ς��Ƃ������Ă�X��������܂����A����Ȃ̉������璴�l�ł���B�ɏ��T�C�Y�̔��Ȃ�Ƃ��������ʂ̃T�C�Y�̔��ł͖ډB�����ꂽ�璤�����ō�������炢�ł͕�����Ȃ��ł��傤�B�i�^�ŃU�N�b�Ƃ�����番���邩�ȁB����������Ȃ�������p��������(��)�B�ؕ��������Ȃ�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F10575250
![]() 3�_
3�_
���[���E���t������B
��͓d���ł����E�E�E�B
����őʖڂȂ�X�s�[�J�[�����Ȃ��ł����ˁH(��)
�ቹ�̐�Ȃ��͂荄���̍����f�ނ���Ԃ��Ǝv���܂��B
������ăt���t�����Ă�悤�Ȏ��n�̐U���Ȃ͂�͂蒮���Ă��t���t�����Ă܂��ˁB�̐U���͂�����͍d���āA�����ƍd���̂̓A���~�Ƃ��}�O�l�V�E�����̋������ł��ˁB��͂肽��܂Ȃ����特���J�b�`������̂����B��g�����ƈʑ����킸���ɃY���e�݂��Ȃ�\������܂��ˁB
�}�O�l�V�E�����Ƒ���a�͂Ȃ����낤����A���~����a�̈ꔭ���ȁB
����Ȑ��i���������ȁH
�����ԍ��F10575325
![]() 1�_
1�_
��i�ق͈��ł���
B&W�A�ꕔ������800��600�V���[�Y�͒艿����35%�l�����ɂȂ����l�ł��B
�I�[�f�B�I�ɍĂіڊo�߂�����KEF�ӂ�Ɩ������ȁH�ƁB
�����ԍ��F10575530
![]() 0�_
0�_
���͂悤 �������܂��B
���̃}���`�E�F�C�B
�ǂ����Ă����Ȃɂ�����|������̂�����܂��ˁB
�ʑ��̃Y����Z�p���[�V������Njy����ƈꔭ�̕��ɁA�A�B
���� �X�s�[�J�[���[�J�[�͂��̃}���`�E�F�C�𑽗l����̂��H
�ȒP�Ɍ����ƒ�悪�o�Ȃ�����ƂȂ�ł��傤���ǁc�c�c
���̈����X�|���X����݂��爫�ɂ����������Ȃ���ł���ˁ`
���̒m�邩����}���E�F�C�ł��ł��ʊ����o��̂͂�͂�B��W�A�A�o�������ȁ`�B
���܂�e���[�J�[�̃}���`�E�F�C�̖{�����ĂȂ���łȂ�Ƃ��ł����A�A�A�n�C�G���h�N���X�ɂȂ邩�ȁ`��
�����w���Ȃ��R�����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��ˁB��̘b�ł�(��)�B
�挎�A�N�����v�g���̖��}���`�E�F�C�X�s�[�J�[���܂������A�A
�ǂ�����悪���Ăɕ������Ȃ������ł��ˁB���ƒ��悪�S�R����
�B
�m���ɃA���v��Macintosh���ƌ����̂�����܂������c (��)
�����ԍ��F10576033
![]() 1�_
1�_
���[���E���t������B
�R�X�g���l����Ƃǂ����Ă��}���`�ɂȂ����Ⴄ��ł��傤�ˁ`�B
�u�b�N�V�F���t�p�̃E�[�t�@�[���^���[�^��3�g���Ƃ��B
�A���~�Ȃ�������^�����̂͌���������(���Y���̖���)�����I�ɂ͎����ŕ\�ʂ̃R�[�e�B���O�ނ��Z���~�b�N�Ƃ������A�������͕\�ʂ̃R�[�e�B���O�������ăJ�`�J�`�̂�ɂȂ邩������܂���ˁBATC�Ȃ͎ʐ^�Ō������S���n���ۂ��ł��ˁB�\�t�g�Ȋ������o�����߂��ȁB
�v���ɋɒ[�ȃL���������߂�l�͗L���u�����h�̗D�����I�T�E���h�ł͖����ł��Ȃ���Ȃ��ł����ˁH�m��l���m��݂����ȃu�����h�łȂ��ƁB
Beyma(http://www.atics.co.jp/unit_beyma.html)�Ƃ����������B���̓z�[�������g���ĂȂ�
�ł����ǁA�V���b�v�̃I���W�͍d���Đ�̂��邢���������Ă����Ă܂�����B46cm���f��������łǂ����̍H�[�ō���Ă��炤�Ƃ��B���̂ւ�̓X�ɂ����Ă݂�Ƃ��������Bhttp://www.hino-audio.co.jp/01/01.html�@���͎��������͍s�������Ȃ���ł����ǖʔ������Ȃ�ō��x�s���Ă݂悤���ȁB
�N���v�g���ƃ}�b�L���g�b�V���B�ŋ߁A���ƃV���N�ɋ�������������ŋ����[���ł��B
�G�[�W���O�i�ނƕς�邩�ȁH
�����ԍ��F10577633
![]() 1�_
1�_
�O�̃R�����g�œ_�����ɉ��^�I�Ə����Ă��܂����̂ŕ⑫�����Ă��������B
�����^��Ɏv���̂́u�y��t�҂̈ʒu����Ɏ��悤�ɕ�����v�Ƃ����悤�Șb�ł��B
�_�������Ɖ��̒�ʂ��͂����肵�Ă�̂ŁA���ɂ͂ނ�����̃X�s�[�J�[�����Ă��銴�������͂����肵�܂�(��)�B
�������A�_�����̗L���ȓ_�����X����Ǝv���܂��B
�Ⴆ�c�C�[�^�[���E�[�t�@�[�ƈ�̂ɂȂ��Ă���̂Ŕ��Ɏ��t����Ƃ��̃��C�A�E�g�����R�Ȃ��ߍœK�Ȉʒu�Ƀ��j�b�g�����t�����܂����A�c�C�[�^�[���ז����Ȃ��̂Ńo�b�t�����Y��ɐU�������邱�Ƃ��ł��܂��B���̓_B&W805�͈�̉��������Ă���Ă܂��ˁB
�}���`�͒�ʊ����������A�z�[���̂悤�ȋ�Ԃ�\������̂ɂ͌����Ă���Ǝv���܂��B
�_�����̃X�s�[�J�[�͒�ʊ��������Ėڂ̑O�Ŗ��Ă��銴�������܂����A���ꎩ�̂��y��̂悤�ɖ�̂ŏ��l���Ґ��̎����y�ȂǂɌ����Ă���Ǝv���܂��B
�܂��ŏI�I�ɂ͍D�݂̖��ł��傤�B
�t�������W�ƃR�A�L�V�����Ɋւ��Ă͈꒷��Z�łǂ���Ƃ������܂��A���[�p���[�ȃA���v�Ŗ炷�Ȃ�t�������W���L���ł��傤�ˁB
�����ԍ��F10596188
![]() 1�_
1�_
������
B��W���L�̗�̃`�����}�Q�ł��H
�m���Ɋ����Ȃ������Y��ɖ点��̂͂��̒ʂ�ł��ˁB
�A�o���M�����h�⃀���h�̃n�C�G���h�X�s�[�J�[�͊m���e�p�[�c�������ʕ����Ŗ炵�Ă܂��ˁB
���̑��`�Œ��ɕ������Ă܂��B
�����ԍ��F10600215
![]() 1�_
1�_
Focal Scala Utopia�̓L���r�l�b�g���Ɨ�
http://www.ippinkan.com/focal_utopia_scala_diablo.htm
�N�H�[�h�ȂǁA�����̗A���㗝�X�̉��i�ݒ�͕s�]�炵��
�������
http://www.ippinkan.com/vienna_acoustics_the_kiss.htm
CEC�̃A�t�^�[�T�[�r�X�̓��[�킩���ł��B
�����ԍ��F10600318
![]() 0�_
0�_
������B
�A�o���M�����h�͒��x�ŋߒm�����Ƃ��낾������ł����ǁA�̂̃z�[���̃C���[�W�������ɂ��Ăăl�I�N���V�J�����ۂ��Ă����ł��ˁB�t�H�[�J���ɂ��Ă��~�b�h����Ńn�C���^���Ă����̂͋����[���B�r�N�^�[�̃I�u���[�N�I���j�A���C�Ɠ��������ʼn����Y��ɍL����̂ȁB���̂͒I�̐���̂�����������ł����ǁA������Ɗ�����(��)�B
�����h���Ēm��Ȃ�������ł����NJ����Ƀo���o���ł��ˁI����ɂ��Ă��l�i�����I���낻��}���V���������܂���B�m���ɂ��������ǂ�����Ȃ�ł������͂Q�S���������Ƃ��Ȃ�H�܂����̒��A�����i�قǗ��v�������ł�����ˁB�S���̎Ԕ����Ă��R�������ׂ���Ȃ����njܕS���̔���ΕS���ׂ���܂�����ˁB
�t�H�[�J���́u���v�̎��^���Ă̂��ʔ����B���ꂾ�ƃX�C�[�g�X�|�b�g�������Ȃ�Ȃ����ƐS�z�ɂȂ��ł����E�E�E�B
�ɂ߂�Εʑ̌^��������܂���SMC40�Ȃ͕ʑ̂̕K�v���[���ł��ˁB�X�R�[�J�[���c�C�[�^�[�Ɠ����Ō�ʂ����^�Ȃ�ŃE�[�t�@�[�̔w�����Ȃ����A���^�Ń|�[�g���������甠�̏�[�ɃE�[�t�@�[�������Ă��ă|�[�g�Ƃ̈ʒu�W���œK������K�v�����Ȃ����B��e�ς��K�v�Ȗ��^���^���[�^�Ȃ�X�s�[�J�[������˂邩�疳�ʂ��Ȃ��B���̃X�s�[�J�[�͗��_�I�ɂ��Y��Ɋ������ĂČ��������ł��ˁB�|�[�g���������ቹ�̐ꂪ�����悤�Ɋ�����\���͂���܂����A�|�[�g��t����ƃ|�[�g�̐ݒ���g���ȉ��̉����J�b�g���Đݒ���g���ȏ�ɑ����������Ă��������Ȃ�Ŗ��^�̂ق����[���ቹ�𖡂킦��͂��Ȃ�ł���ˁB�����肪���̕ӂ��ǂ��������邩���厖���ƁB���������Ƃ͂Ȃ��ł����A�ʍD�݂̖��@�̗\�������܂��B
�����ԍ��F10602037
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂��B
����́A�V�����Ŏg�p���A�����ǂ��L����܂��B
http://joshinweb.jp/audio/9212/2097146878608.html
������́A���x�����\��ł��B
http://www.anthonygallo.jp/products/strada_01.html
�����̗A���㗝�X�����i�ݒ荂�߂���
�����ԍ��F10602311
![]() 0�_
0�_
�|�`�����l������B
�|�b�h�X�s�[�J�[�ł����B�͂��߂Ēm��܂����B
�f�U�C���I�ɂ͊��̏�ɂł��u�������ł��ˁB���͌��\�傫���̂�������܂��B
�f�U�C���I�ɂ͂��Ȃ�t�@���L�[�Ȃ�ŋC�ɓ������l�͔�����������܂��lj����͂ǂ��ł����H�ȂP�u���[�Ƃ����Ə_�炩�n��z�����܂��B�c�C�[�^�[���������̂ő@�ׂȉ����ȁH�ቹ�͋����͂Ȃ����������lj�͂̂Ȃ��{�f�B�[�Őꂪ���銴���ł����ˁH
���ɂ͒l�i�����������܂����A�f�U�C�����C�ɓ��邩�ǂ����Ō��܂邩�ȁB�����ȃf�U�C�����ƕ����̓��ꊴ�����Č����l����܂���ˁB
�K�������߂Ăł����A�X�g���[�_���Ă��̃T�C�Y�ʼn����ǂ����������ł����ǂˁB5.1ch�Ƃ��Ŏg���X�y�[�X���Ȃ��Ă����ł���ˁB�����A���̃T�C�Y�Œቹ���o��̂������[���ł��B���|�[�g���肢���܂��I
�ŋ߁A�Ȑ��^�X�s�[�J�[�����Ȃ��Ă��܂����ˁB�m���ɑ��ۂ͐��E���~���`�����A�l�p�����ۂ���ςȉ��o�܂���ː�B�~���`�����c�q�݂����ɐςݏd�˂邩�A���̂����ĒB���^�ɂ��邩�B���삶�ጵ�������B�v�����f���݂����ɐp�n�̍ޗ��Ȃ���邩�ȁH�h�[�i�b�c�^��MDF��ςݏd�˂č��̂��ޗ���������B���Ȃ��ĒM�Ƃ����ۂ݂����ɍ�ꂽ��E�l���݂���(��)�B
���[�J�[����ɂ͂����������삶��s�\�Ȃ̂�����Ă��炢�����ł��ˁB�����I�ɂ͖ō��̂��ǂ������ł����ǃ��[�J�[������R�X�g�I�ɂ��Ȃ茵�������ł��ˁB
�����ԍ��F10607109
![]() 1�_
1�_
�Ґl����
�m���P�u���[�͌ł��f�ނł́H
�h�e�`���b�L�Ɏg���ĂȂ��������ȁH
���e�͐��A���́`
����Ă��炲�߂�Ȃ���f^_^;
�����ԍ��F10608993
![]() 1�_
1�_
�����̓��W�[�N�̂r�o�ł��B�������Ƃ͂���܂���
http://www.paradiserecords.net/proaudio/pages/musik.html
�����ԍ��F10610001
![]() 0�_
0�_
���[���E���t������B
�P�u���[�Ƃ��O���X�t�@�C�o�[���čd�����nj��Ǒ@�ۂ���Ȃ��ł����B
�z�n�݂����ɕ҂݂���ŐU���ɂ����ŕ҂ݕ��ɂ����ł��傤���Ǖ҂ݖڂ͓������A�e�������邩��G��Ə_�炩����ł���B���X�ł�������G���Ă݂Ă�������(��)�B�����ƈ���Ēׂ�邱�Ƃ͖����Ǝv����ŁBB&W�Ƃ��I���L���[������̓P�u���[�����Ă܂��ˁB
�P�u���[�ōd�������ĕ��������Ƃ��Ȃ��������̂ŁB�I���L���[�͎����炢�d���ł����lj����͂Ȃ����_�炩���ł��ˁB���̗v�f���W���邩�炩�ȁB
�J�[�{���Ȃʔ����ł��ˁB�f�m���݂����ɑ@�ۂ�҂ݍ��߂Ώ_�炩�������邵�A���[�J�[���v���o���Ȃ���ł����ǃE�G�b�g�J�[�{���Ŕ�ɂȂ�����͋����݂��������B
�P�u���[�̃X�s�[�J�[���~������ł����ǂ���ȂɃX�s�[�J�[�����ĂĂ��ȁ`���Ă�������������܂��ˁB���������{�[�J���̃|�b�v�X�Ȃɂ͗ǂ���Ȃ��ł��傤���B���b�N�Ƃ��W���Y���Ƃ�����Ɛ������Ȃ������B�g�Q�g�Q�������Ȃ��Ȃ��ŁB
�����ԍ��F10610998
![]() 1�_
1�_
�|�`�����l�����́B
MEG�ł����B���߂Č��܂��ˁB
����͂������I�E�[�t�@�[�̑O�ɔ��ނ��Ă���I�E�[�t�@�[�Ȃ���̉��͉�荞�݂₷����ł܂������ł����ǃX�R�[�J�[�̑O�܂Ŕ��ނ��Ă��郂�f�������邶��Ȃ��ł����I�T�C�h���J���Ă�Ώ\���Ȃ̂��ȁH
�������A�E�[�t�@�[�̑O�ɃX�R�[�J�[������Ǝw�����������シ����Ă����̂��悭�킩��Ȃ��ł��ˁB������������X�R�[�J�[�̔w�ʂ���o�鉹���E�[�t�@�[����̉��Ƒł����������ăE�[�t�@�[����킸���ɏo��~�b�h�����W�̉����L�����Z������邩��R�A�L�V�����ɂ��肪���Ȉʑ��̗��ꂪ�Ȃ��Ȃ��ăN���A�ȉ����ɂȂ�̂����B���������Ή��W�ɏo�W����Ă�FOSTEX�̎���i�̃R�A�L�V�����̓f�B�t���[�U�[���Č���������ł����ˁH�h�[�i�b�c��̔��E�[�t�@�[�̑O�ɋ���Ŏ~�߂��Ă��āA�E�[�t�@�[�ƃc�C�[�^�[�̊�����������Ƃ̂��Ƃł����B
�t�������W�Ƃ��R�A�L�V�����͒�ʊ������邹���Ŋm���ɃX�e���I���͂͂����肵�Ă܂��ˁBLR�Ɖ��z�̃Z���^�[(�u�X�s�[�J�[�ƃX�s�[�J�[�̊ԂɃI�b�T��������I�v�݂�����(�̎肪�I�b�T���̏ꍇ)�B)���͂����肵�Ă܂��B
���̏ꍇ�̓t�������W��PE-101A�Ǝ���3Way���g���Ă��ł����A���y���Ƃ���PE-101A���g�����Ƃ������ł��ˁB�ӊO�ɃG���L�M�^�[���s���܂��B�ł��A���ǃ��C�u��(��ԂŖ��Ă銴��)�̂���RWay���S�ɂȂ��Ă܂��B�RWay�Ƃ��������łȂ��z�[���̂���������܂����B
���Ȃ݂Ɏ��̂RWay�͏ォ��Beyma��CP350Ti�AFOSTEX��T90�AVictor��SX-L33MK2(�E�[�t�@�[�̂�)���g���Ă܂��B20cm���̃E�[�t�@�[�ɓ���ւ�������ł������̃��b�N�ł̓X�e���I�����Ȃ��Ȃ肻���Ȃ��16cm�������x���Ȃ��Ċ����ł��B
����ɂ��Ă�PE-101A�̐U���͍ŏ�d�q���������ł����A�S��ƒ��肪�����Ă��������Ă܂��B16cm���炢�̃E�[�t�@�[������Ă���Ȃ����ȁB
�����ԍ��F10611353
![]() 1�_
1�_
�ǂ����ł��B
�P�u���[
��v�ł����Čł����Ă��Ƃ͖����킯�ł��ˁB������܂����B
�Z���^�[��ʁB
���̎��_�ł����A�A
�~�b�h�X�R�J�[(����j�̃G�l���M�[�������X�ł́H
�悭�A���v�͒�ʂ�ʑ��̃o�����X(�Z�n���[�V�����̗D�ꂽ���i�͉��s�����͗��̐��Ȃ�Ƃ��j�B
�X�s�[�J�[�����̐���Z���^�[��ʂ𒆐S�ɍl�����ꍇ����̗D�ꂽ���i���Z���^�[��ʂɊW�����邩�ƁB�B�B
B��W��f�B�i�E �f�B�I ATC �z�[���Ō����ŋ߂�JBL4600 4429������B(JBL�͗ǂ������Ȃ���j�ł����B
�S�ă��j�^�[�オ���(�X�^�W�I�W�j�Ŏg���Ă�̂������ł��邩�ƁB�B
�A���v��X�s�[�J�[�≹����Œ�ʂ͌��܂�悤�ȁB
�������v���[���[�ɂ����̂��Ƃ��v�������悤�ȁB�B�B
�����ԍ��F10614082
![]() 1�_
1�_
���[���E���t�����́B
���~�b�h�����X
�������ɂ��������B�l�Ԃ̎�����ԕq���ȑш悾���B���m�Ȓ�`�͒m��Ȃ�����200�`5kHz���炢�܂ł��ȁB
���Ȃ͕ǂ⏰�ɓ������Ă����܂茸�����Ȃ�����������Ȃ���ł���ˁB
�Ƃ���Έ�ԕ��������킩��₷�����������X�ɂȂ�ƁB
���A���v�͒�ʂ�ʑ��̃o�����X(�Z�p���[�V�����E�E�E
�������ɋɒ[�ɃZ�p���[�V�����̈����A���v�������烂�m�����݂����ɂȂ��ė��̊��Ȃ��Ȃ�ł��傤�ˁB�ʑ�������������(��ɍ��悩�ȁH)���悪�ڂ₯�ă����W�������̂Ɠ��������̊��Ɖ��s�����ቺ���邩���B
�g�[���R���g���[����10kHz�ȏ��ቺ������ƉԂ̖����₵�����ɂȂ�܂�����ˁB
JBL4600���������ˁ`�B���Ȃ͍����Ď肪�o�Ȃ����玩�삵�Ă�悤�Ȃ���ł���(���ƃf�J�C)�B�z�[���͗ǂ��ł���A�̎�̐������������X�������B�l�̐������Ƃ����z�[���Ŋg������ďo�Ă��܂���(�z�[���͌���肳��ɋ�����ōD���������邩��)�B�������̃_�C�A�t�����Ȃ������G���L�M�^�[��n�[���j�J�����X�����ł��B�Ƃ��ɐ^��ǃA���v�ƍ��킹��Ɨ]�v�����B�~���[�W�V�������݂�Ȑ^��ǎg���Ă邹�����B
��������
�������ɃX�s�[�J�[����̒��ډ��Ɠ�������ɔ��ˉ����������Ă������ʂȂ�Ė����ł��ˁB
���v���[���[�ɂ����̂��Ƃ��v���E�E�E
�ǂ��Ȃ낤�H�T���v�����O���[�g��SN�䂪�����ŁA������x�̃O���[�h�Ȃ�卷�Ȃ��悤�ȋC�����邯�ǁB����CD�v���[���[��ウ�����̓T���v�����O���[�g���S�R�ς�����������𑜓x���啝�A�b�v���܂������ǁA����24�r�b�g���m���Ƒ�����������Ă��l�Ԃ͋C�����Ȃ��悤�ȋC������E�E�E�B
�������@���g���Ă݂����ł��B
�����ԍ��F10615502
![]() 1�_
1�_
������
�ꉞ�A�����h�݂̒艺���H�r�o�ł��B�����i�͂Ƃ�ł��Ȃ�
http://www.avcat.jp/avnews/index.html
�����ԍ��F10615566
![]() 0�_
0�_
���[���E���t����B
CD�v���[���[�ɂ��Ă̒lj��ł����A����CD�v���[���[�̐��\��DA�R���o�[�^�[�ƃA���v(CD�v���[���[��)����ԏd�v�ȋC�����܂��B�f�W�^���o�͂Ȃ�A���v�̗v�f���Ȃ����ȁB�M���ǂݎ��̌덷�Ƃ��ׂ͍������Ă킩��Ȃ����B
�A���v����̂����ŃI���L���[���ۂ��܂����薡�ɂȂ�����A�P���E�b�h�݂����Ȃ������薡�ɂȂ�̂��Ǝv���܂��B
DA�R���o�[�^�[����̃f�W�^���M�����A�i���O�M���ɕϊ�����Ƃ��ɔ����̂悢�A���v���ƒ�悪�o����Ƃ����邩���B�f�m���͒�悪�o��炵�����ǁA����������CD�v���[���[�̃A���v���v�b�V���v���I�H
�Ȃ��͂�CD�v���[���[���^��ǂ��I�H(�n��)
�����ԍ��F10616600
![]() 1�_
1�_
�|�`�����l����ǂ����B
�|�`������̂����Ă郂�f���͈ȉ��́uEPILOGUE 1&2�v�ł����H
http://www.stellavox-japan.co.jp/products/goldmund/speakers.html
�A���v���ڂƂ͂����QWay��5�S���ł���I
�t���Z�b�g��3��5�S������}���V�������������ł���I
��x�L���b�V���Łu�������グ�v���Ă݂����B�g�����N�K�v�ł��ˁA���z���ᖳ���I
�����ԍ��F10616645
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂��B
�����h�����L���Ă�]�_�Ƃ⒘���l�͒m��܂���
�A�o���M�����h�͎������₱�̕��Ȃǃ`���z��
http://www.gokudo.co.jp/
���̑�����AC2�ƃO���[���m�[�g����
http://www.ac2.jp/
http://www.green-note.net/?mode=f3
�����ԍ��F10616986
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́`
��������
�f�m���̃v���[���[�͒���悪�ł��ˁ`
���10���O���CD�v���[���[�͂ǂ̃��[�J�[������������������ł��B
���̏�~�h���N���X����e���[�J�[�̐F����ʂ̈Ⴂ����ʔ��ʏo���邩�ƁB�B
�m���f�m���̃v���[���[
�^��ǂ͖����ł���H�Ȃ��}�b�^�����o����̂��H
�g���C�I�[�h 4SE�́A�}�b�^�����͏o�Ă܂������A�A�A�B�m���^��ǁH
���݂ɂ����̂̓A�L���ł��B DP400�B
�ȑO505u���ƃ\�t�g�Ɋ���č��悪�L�c���ꍇ������ق炠��܂������c
�Z�p���[�g�ɂ���
���͏����Â������ɁB
(�𑜓x�₻�̑��Ȃ�ł��Ă�邩������Ə㗬���ʂ������ė����j�ƃA���v�������Ă�݂����Ȋ����ł��B
���ƕ\�����ςł���(��)
�����ԍ��F10618224
![]() 1�_
1�_
������ATC SCM-19�̓v�����C����DUSSUN V6i(���^�{�n)�ACDP���g���C��4SE�ł��B
�f�������̓E�C�[���A�R�[�X�e�B�b�NT3GB+ATOLL IN100SE+�v���C�}�[CD21�ł��B
T3GB��30�`22000 Hz��-3dB��-6dB�\�L���Ȃ��̂ŕs���A��y�p�͂���Ȋ������ȁB
���^�{�́�
http://www.audiorefer-d.com/cgi-local/detail_view.cgi?id=00157&category=80
�����ԍ��F10618273
![]() 0�_
0�_
�|�`���� ����ɂ���
�������^�u�b�N�V�F�t�T�C�h�v���X�̃X���ɍs���Ėʔ������p�l���������悤���ȁI�I(��)
�t������Ƃ��ł��悢���ǁc
���N����X�s�[�J�[����p�l������(�������P���������āj
����Ƃ��̃X�s�[�J�[�̎��������o��悤�Ɂc
�X�s�[�J�[����V��t�߂���_�̐����A�A(�I�[�o�[�ł���)
�F����̃R�������g�B
�̌��k��b���ǂ�������܂��B
�t������̃P�[�u���w���O�ɕ�������I�͐������ł��ˁA�𑜓x���Q�ɂȂ�܂��A�ꎞ���肷���Ċɂ߂��o�܂��B
�܃^�C�~���O�݂Ă��̃E�`�B(�N�����Ԃ͉摜�ςĂ邩���j
���݂�SCM19���߂łƂ��������܂��B
���͂Ă�����f�B�i���w���悩�Ǝv���Ă܂����B(��)
�G�[�W���O��N������܂��B
��������L�c���Ȃ��Hf^_^;
�v���[���[���g���C�Ȃ���v���A�A�A�B
�Ґl����
�]�k�Ƃ茾�ł��Bm(_ _)m
�����܂ւ�
�����ԍ��F10619076
![]() 1�_
1�_
�ǂ����ł��B
�����͂�������܂��X�T�m�E��da1.0�Ȃǂł͖�̂��C�ɂȂ�܂��B
�����e���̃w�[�Q���������|�[�g��
���{�s���ł͍��拭�߂̋@�킪���x�ǂ�(�E�P��)�̂�
�w�[�Q���͎g���܂���Ȃ�ċL�ڂ�����܂����B
����ł́A�d���̕����ŁE�E�E�E�E�E
�X����l�A�d���̕����͂�����
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2071/#10604145
���j�[�N�Ȃr�o�X�^���h�̕����͂�����
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2071/#10591060
�v���Y�}��KURO���Ԍn�͂�����(���ɂ�����)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2071/#10593393
�����ԍ��F10619177
![]() 0�_
0�_
�|�`����
�N���ɂ͂��傭���傭
PTQ �ӂ�H
�ɂ͖���
����10������PTQ�ɉ摜����t�����Ă܂��B������ʼnt���e���r�ɍ��������p�l��������ō��܂����B
����̓e�L�����B
�����_����Ɏg�����ɂ��I�X�X��
�����Ă��ǂ����ǃX�s�[�J�[����ǂ������̂ƈႤ�������̌`��ł܂����������ς��܂��B
�e�����ǂ̉����x�X�g���͎��g����Ԓm��Ƃ���ł��ˁB(���܂�Q�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ������j
�V���E�W����H�H��
�X�s�[�J�[����o�b�N�O�����h����Ԃ��Ɓc���Ƌz������Ȃ��g�U��ł��B
�Y�₱�ꂩ��Ɠd�̃}�C�i�X�C�I���������u�łǂ��ς�邩���e�[�}�Ǝv���Ă܂��B
���ƃ��X�i�[����ǎx���ł����B�B�B
����x���͂����͂��ꂩ��ł��B�V��� (��)�B
�����ԍ��F10619588
![]() 1�_
1�_
�|�`������ǂ����B
�A�o���M�����h�̃I�[���z�[����������B
�z�[���t�@���̖��ł��ˁB�T�u�E�[�t�@�[�܂Ńz�[���ł�����ˁI
�Ȃ{�엿���t���R�[�X�݂����ŁA�S���H�ׂ�͕̂s�\�B�������ĐH�ׂ���߂������ł��B���������ς��߂��ăQ���f�������Ȃ��炢�������I
�������Ă݂����B
Dussun V6i �艿24����11���I�H���J�j�Y���͓䂾���ǂ��̃X�y�b�N�ł��̉��i�͐��E���̃��[�J�[���ߖグ�܂���B�����������ł��ˁI�ق�Ƃɗ~�������ǂ���ȏ�A���v�����ĂĂ��Ӗ��Ȃ����E�E�E�B
�������A�`���C�i�p���[����ׂ��ł��ˁB����Cayin�������ł����A�����@����݂̎d�l�Œ����̒l�i�ł�����ˁB���{���[�J�[�������c���̂͐��Ђł��傤�ˁB
SMC-19�̃��J�j�J���QWay�E�[�t�@�[�ʔ����B���ʂ̓t�������W�ŗp�������@�ł�����ˁBT3GB�̃X�p�C�_�[����PP�R�[�����ʔ����B4SE�͎����������悤���ȂƎv���Ă���ł����_�炩�n�̉��ł����BCayin��CD�v���[���[��DAC���s�������A���N�X�}���͍̂������Ď肪�o�Ȃ��B
�����ς����߂��ĕԎ����o���Ȃ��B�ʔ�������I�B
��̋ɓ��������������B
�����ԍ��F10622274
![]() 1�_
1�_
���[��������(�����ƕς��ȁH�ΐl�������ƕς����A�ϊ����ɂ������E�E�E)�B
�K��Ɉ����Ӗ��̌��t�͎g������ʖڂ��ď����Ă��������A�����ӌ����D�����茾�����߂ɕϐl�ɂ͂��Ȃ��ŕΐl�ɂ����킯�ł��B
�����{�[�h�ʔ������Ȃ�Ō����Ă���������B����SX-L33MK2�̃o�b�N�|�[�g���s���Ńt�����g�|�[�g�ɉ���������ł����A���ɓ����Ƃ����ĊȈՂɉ��P������@�����������Ǝv���A�����Ă����Ηǂ������ƌ�����Ă܂��B
�|�`����d���̕��������Ă��炢�܂����B
���̂������ז������Ă��炨�����ȁB
�����g�����X�����Ă݂������ǁA�t���������N�����Ă��y�[�W�̋L��������ƃg�����X�̃C���V�����[�^�[��ς��������ʼn������ς��錏�ȂǕ����ƁA����ȃf���P�[�g�ȕ�����ꂽ��g����ǂ��o���ĘT����������邱�ƂɂȂ�͂��Ȃ����ƐS�z�ɂȂ�܂����B�����̃T�[�W������˂ăN���[���d���̈����̓���Ƃ��Ώ\�����ȁH�Ƃ��B
���������Ή��W��CD�v���[���[�ɂ��čl����������X�s�[�J�[����������ł���BViV(http://www.vivaudiolab.com/home.html)���Ă�����ł����ǁAprima��evanui���܂����B10cm�����̃t�������W�Ń}�O�l�V�E���U���Ɏ���h���ă_���p�[���X�Ŏ������̂ɕ������Ă����ł����ǁA�g�p����CD�v���[���[���W�肳��H��2���~��AV�v���[���[�Ƃ̂��ƁB����Ȃ̂ɃM�^�[�Ƃ��J�X�^�l�b�g�̃A�^�b�N��(�x���x���Ƃ��J�`�J�`���Ă����u�ԓI�ȉ�)�������Ă߂��Ⴍ����ꂪ�����ł���(�ቹ�Ɨ��̊��͑�^�}���`�ɂ͂��Ȃ��܂���)�B�W�肳����u����CD�v���[���[�ł�����Ȃɏ��ʂ����ł���v�ƌ����Ă��܂������A����ȃS�~�̂ď�ɂ�����ĂĂ����������Ȃ�CD�v���[���[�ɂ���قǂ̏��ʂ�����Ƃ͎v�������܂���ł����B���̃u�[�X�̐��\����CD�v���[���[�ł���^�}���`�E�F�C�̃X�s�[�J�[�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ȃ̂ł���Ȑ�͂���܂���ł�����B���Ȃ݂Ɏ���PE-101A�ł�����荂�z�ȃ}���`���A�^�b�N���̐�͏�ł��B��ʓI�ɑ�^�}���`�̏ꍇ��CD�v���[���[���A���v�ɗ͂���ꂽ�ق����ǂ������ł��B�l�b�g���[�N��j�b�g���m�̊��ōׂ��ȉ��͏����Ă��܂��̂ŁB���[�J�[��CD�v���[���[�̍����\���������̂ɔg�`�ɎG����������Ȃ����ƂƐ���Ă��邱�Ƃ��A�s�[�����Ă��܂����}���`�ł͐��͂܂�܂邵�A�����̂䂪�݂���������͔̂������Ȃ��ł��傤�B���[�U�[��CD�v���[���[�̏��ʕs�������������Ȃ����Ƃ�S�z���������ǂ���������܂���B�O�q��ViV��x�m�ʂ̃G�N���v�X�ӂ�A�������͉����ǎ��ȃt�������W����������ΐV���n���J����\������܂���I(�����G�N���v�X�͒��������Ƃ���܂���)�V���o���Ƃ��h������@�����Ƃ��M�^�[�̌����͂������A�J�X�^�l�b�g���̉��ɒ��ڂ��Ē����Ƃ��������B
CD�v���[���[�̏��ʂ��ő���ɔ�������ɂ̓V���O�������̃A���v�ƃt�������W�̑g�ݍ��킹����Ԃ����B���̊�����̔��͂͑���Ȃ������m��܂��E�E�E�B
���[���E���t����ɂ͎����b��������܂��{��Ȃ��ł�(��)�B
�����ԍ��F10633249
![]() 1�_
1�_
�����́B�ΐl����B
�摜��\��t���܂��B�����30mm�s�b�`�̉����p�l���i��������j
�f�B�X�v���C�̉����p�l���ł��B
�ʓr�A�v���[���[��5.5sqVVR�E�A���v��8sq4��CV�����䂪�Ƃ̓d���B
�f�B�X�v���C�̉����p�l���͂܂��v�����łƂ肠�����Q�Ԗڂɂł������̂�
�ʐ^�ŎB��܂����B
�����ԍ��F10636245
![]() 1�_
1�_
���[���E���t�����́B
���ꂪ��̉����{�[�h�ł����I
�e���r����͉����͂����Ԃ��Ďז����邩�璅�E���̋z���{�[�h���Ă�낤�Ƃ����킯�ł��ˁB���̖ؐ��z���ނƂ������Ȃ肩�Ȃ�w�͂���Ă܂���(��)�B���̕����͘a���Ȃ̂ŋz�����ʂ͍������낤�Ƃ������Ƃł����������w�͂̓T�{���Ă܂��B
���̂Rway���ݒu�Ԋu���L���ăX�e���I���ʂ����߂����Ƃ���ł����A�{�I�����Ȃ����Ƃɂ͕s�\�ł��B���߂Ă��̓w�͂ŁA�����ăn�̎��^�Ƃ������s�z�u�ɂ��Ă܂��B�����A�o�b�N�|�[�g�����t�����g�ɉ��������̂Ō��̕ǂ̉e���͍ŏ����ɗ}�����܂����B�|�[�g�ʐς��Q�{�قǂɂȂ��Ēቹ���p���[�A�b�v���܂������B�����A14.5cm�̃X�R�[�J�[���ۂ��E�[�t�@�[�ł͌y���m�͕��݂Ȃ̂ł������ɒቹ�͕͗s���B����(�T�u�E�[�t�@�[)�ő����͂��Ă܂������m�͂�20cm��C�ɂ͑����ł��ł��܂���B20cm�C�Ɋ����������Ƃ���ł����A���̃��b�N(�D��)�ł͏d�ʒ��߂œ]���K���Ƃ������ł��B�ŋߌR�����������������̂Ŏb���ُ͋k�����ōs���Ȃ��ƕx�������͒B���ł��܂����(�Ӗ��s��)�B
���������ΑO�q�̍~���g�����X�̘b���āA���̐^��ǃA���v���g�����X�̉�Ȃ̂ŐU���ɂ͎ォ�낤�Ǝv���}篑�����ł߂��̂ł����A�ǂ��Ȃ����C�͂��Ă��m�M�ł��Ȃ��̂Ŏ����ɉ��y���Ȃ���A�E�g�v�b�g�g�����X�̃P�[�X���R�c�R�c�@���Ă݂܂����B�������A���`���Ŏ�̐U�����ۖ��ɒB���Ă���̂Ƌ�ʂ����܂���ł����B�N���Ɏ�`���Ă��炤��������܂���ˁB
�����ԍ��F10638306
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́`
�e���r�̃p�l���B
�p�l�������ɂ�120�̉��ʌ`��̓��e�����M�b�V���B
�����˂𐧌�B
�V�[�X�̖Ԃ́A�J�[�y�b�g�̊���~�߂̃V�[�g�ł��I
���S�����������͏����ȋɏ����b�V���̃t�B���^�[�Đ����ł��B
�t�B���^�[�����Ȃ��Ɨ]��ɂ��𑜓x���o�����đ��������ɁB
���̃p�l����ݒu���邵�Ȃ��͒i�Ⴂ�B
���ƕǏ㕔�ɎO�������ȃp�l����ݒu���Ă܂��B
�����ԍ��F10640602
![]() 1�_
1�_
���[���E���t���� ����ׂ��I �Â�ɋÂ��Ă܂��ˁB
�ǂ̉��ʌ`��̃p�l���i�؍ޖ_�̐ݒu�j�͊m���Ɍ��ʑ傾�Ƃ͎v���܂�������Ă�l�͂��Ȃ菭�Ȃ��Ǝv���܂��B
�䌩���ꂢ�����܂����Bm|_ _|m
�����ԍ��F10640651
![]() 1�_
1�_
���[���E���t�����́B
���̑܂̒��͂���ȂɋÂ�������������ł��ˁ`�B
���V�[�X�̖Ԃ́A�J�[�y�b�g�̊���~�߂̃V�[�g�ł��I
���ꖃ���Ȃɂ����Ǝv�����B�܂����悭���銊��~�߂Ƃ́I
�Ȃ��Ȃ��̓����݂����Ŗʔ����B
HD���v���Ԃ�B
�}�����������̂��ȁH
HD����ł��Ȃ��ȁ`�Ƃ��v���Ă���ł���I
�ŋ�CD�v���[���[�̘b���Ă���t�������W�̕��������Ċm�F���Ă��Ƃ���ł��B���̊��Ƃ��d�ቹ�Ƃ���_�ɒ��ڂ��Ē���������������Ȃ��ł��ˁB������T���Ȃ��Ƃ��Ă��Ƃł����ˁB
�G�N���v�X�����������Ȃ��ė��܂����B�o�b�N���[�h�������[�����A��������^�C�v�̔��Ƌ������Ȃ��^�C�v�̔��ǂ�����ʔ����B�v�t���̏��N��Ԃł��I
�|�`����ǂ����B
���̕ǃp�[�c�͂��̒l�i���Ƃ���Ȃɐ��͏o�Ȃ���Ȃ��ł����H�z���Ɗg�U�n�������݂����ł����ǁA�o�b�N�|�[�g�̃X�s�[�J�[�������璵�˕Ԃ��n���X�s�[�J�[�̌��ɒu�������ł��ˁB�������͂���������Ȃ����ł����ǁB
����ȕǃp�[�c��������Ńz�[���^�̕���������Ă݂����ȁ`�B�����ƃX�s�[�J�[���Q�����N��ɂȂ�����������Ȃ��ł��傤���H�܂��A�Q�����N��̃X�s�[�J�[�������ق������オ��ł��傤���ǁE�E�E�B
�����ԍ��F10643061
![]() 1�_
1�_
�����́`
�f�B�X�v���C�p�l���B
�e���b�V��(���蓤�̑܁j�ŏ��̃��f���Ɏg���܂����I(�Ȃ��Ȃ��ł��j
���O���V�[�X(�҂݁j���l�����ł��B�����ǂ����Ǝv���܂����c�����獷���ʁB�����Ȏ�ޑ������獂�z�ɂȂ�܂�(��)
�A�R���o���g���Ă܂������p�l���̃{�����Č��������n�B
������ɓ������@�m�肽���ł��B
����Ȃ�ȂĂ��炨�������炠���Ă�����܂����(��)�B
�݂Ȃ���
�X�s�[�J�[�X�p�C�N�ŗǂ����i�ɓ����������ĕ��B���~�����ł��B
���F�͎��R�̂ʼn��������X�R�[���Ƃ���悤�Ȑ��i���x�X�g�����B
�}�O�l�V�E�� ���S�ȊO�Ȃ���c
���̃X�p�C�N��J1�v���̉~���`�d���R�[���ł��B
�|�`����
�s���~�b�h����p�l��
�X�s�[�J�[�ԃZ���^�[���㕔�ɐݒu�͌��ʂ��邩������܂���B���̍\���͒m�肽���ł��ˁB
�����ԍ��F10645680
![]() 1�_
1�_
���[���E���t����ǂ����B
�z���V�[�g�Ɍ��ł����I
���i�͍����N�b�V�����Ƃ��ė��p�ł������ł��ˁB�ł����ۂɎg������{��ꂻ��(��)�B
�X�p�C�N�ɂ��ďڂ����킯�ł͂Ȃ��ł����ǁA��̌��k����܂��B
�l�H�嗝�̏�ɐl�H�嗝�{�^�J�̃X�p�C�N���g������������܂����B
���͗ǂ�������̂ł����A���̐U�����~�܂�Ȃ��炵���Ĕ��̕t�щ������Ē��܂�Ȃ���ۂɂȂ�܂����B�ʑ����킹(����O��ɂ��炵��)�ɕs�ւȂ��Ƃ������āA�n���Y�̈����R���N�V�[��(2mm�����炢)�ɑウ���Ƃ��딠�̐U�������܂����悤�Œ��܂肪�o�܂����B�v�͍d���X�p�C�N�ɍd���y��ł͐U���̓����ꂪ�����Ď~�܂�Ȃ��������Ǝv���܂��B
�Ȃ̂ōd���X�p�C�N�͖�R���N���̔�r�I�_�炩���f�ނŎ�Ƃ��������B
�v�����ăX�p�C�N�𔖂��ď_�炩���f��(�S���Ƃ��R���N)�ɂ��Ă݂�ƒ��܂肪�o�邩������܂����B���݂����ɍ����X�p�C�N���n���Y�̃R���N�V�[���ɕ�����\�������邩��(��)�B
�����ԍ��F10652054
![]() 0�_
0�_
���͂悤 �������܂��B
���̃X�s�[�J�[�ł����Ƃ肠�������o�[�E�b�h50�o���̏�ɂ`�a�`�̔��}�O�l�V�E�����J�}�Z�Ă܂��B
����ɃX�p�C�N�ł��B
�X�p�C�N��C���Ƀj�b�P�����b�L�����_�˂̐��i���悤���ƁI�I
�����ԍ��F10658046
![]() 0�_
0�_
�͂��߂܂���
ROM���Ă����̂ł����_�˂̖C���C���V�����[�^�ƕ����ĎQ�サ�܂����B
�A���g����������܂��B�Ӑ}�I�ɋ���(���ɒ��)��t������^�C�v�̐��i�ł����B
���͋C�Ŗ炵�����l�����Ń��[���E���t����̈Ӑ}����������Ƃ͈Ⴄ�̂��ȂƎv���܂��B
�}�O�l�V�E���ƒ��S���D�݂ɍ���Ȃ������̂ł�����A���~��X�e�����X�������Ă݂Ă͔@���ł��傤�B
�Ƃ肠���������Ƃ������ł����
�A���~(�Ƃ������W�������~���ł���)�ł�����g�c����ESD-SR1
�X�e�����X�ł�����TAOC��PTS-N
���f�ނ��������肵�Ă銄��ɗǐS�I�ȉ��i�ł����߂ł��B
�����ԍ��F10659551
![]() 0�_
0�_
�⑫
�����g�����C���C���V�����[�^�̓��b�L�̖������f���ł��B
���b�L�t���͎g�������Ƃ�����܂���B
�����ԍ��F10659685
![]() 0�_
0�_
����ɂ���`
KEZIA����
��肪�����ł��B
�C����͂�ł����B(���Á�)
�m���ɃP�[�u����S�W�ɏ����Ă܂����ˁI
�}�O�l�V�E�����g���܂����������X�L�b�v���銴���ł��āA�A�B
��
���N�O�w�������O���[�f�[�V�������S�^�I�b�N�X�p�C�N�g���Ă܂��A�A
���Ԃɋg�c�N�̃W�����g���Ă݂Ă͂Ƃ͌����܂������ˁB
�}�O�l�V�E���ƃW����(�q��A���~�j�Ⴂ�܂����ˁI�ǂ������Ă�悤�Ŋ�
�m�荇�����ǂ��ł��ƃX�X�����܂����B
�X�R�[���Ɣ����Ă���Ă�����肪�x�X�g�ł��ˁB
�g�c�N�ɖ⍇�����Ă݂܂��`��
�E�`�̃V�X�e���ŃX�s�[�J�[�C���V���������ω��傫���ł�����
�|�`����
�|�[�J���E���C��
�V���p�����p�l��{�s���~�b�h�V�[�����O}�o�܂����ˁB����30000�ʂ��ȁI�H
�����ԍ��F10660047
![]() 0�_
0�_
�|�`�����́B
����͎�Ƀo�b�N�|�[�g���̃X�s�[�J�[�Ŕw��̕ǂ܂ł̋��������Ȃ�Ă��āA�ǂ��傫���Ēቹ���o�����鎞�ɗL���Ȃ��̂̂悤�ł��ˁB�ǂ܂ł̋������Z���ƕǂɓ��������ቹ�������̔w�ʂɂ����炸�Ƀ��X�i�[�̂ق��֒��˕Ԃ��Ă��܂��̂Ō��ʂȂ������ł��B
���͒ቹ�s���ɔY��ł��܂������A�o�b�N�|�[�g���͑傫�ȕǂ����ɂ���t�����g�|�[�g���������͂Ȓቹ����̂�������܂���ˁB����̐��i�����Ă��ċC���t���܂����B
�����A�������������͂��܂�Ȃ������ł����B
�����ԍ��F10662036
![]() 0�_
0�_
���[���E���t���� ������
�}�O�l�V�E���ƃW�������~�����\���Ă�Ǝv���܂��B
���̊��z�Ƃ��Ă�
���ʓ_�͍�����A�^���������A�������������Ƃ���B
����_��
�}�O�l�V�E���̓t�����ƍL�����đ�l�����Ȃ�܂����A
�W�������~���̓S�����Ɖ����Ă��ă����`���ȏ��ł��B
(�g�p�@�ށFSoulNote dc1.0)
�X�L�b�v���Ɋւ��Ă͑̌����������Ȃ��̂Ńm�[�R�����g��
�����ԍ��F10670461
![]() 0�_
0�_
KEZIA����
���͂悤�������܂��B
�}�O�l�V�E���t���b�Ƃ��������B
�X�L�b�v���܂ߒn�ɑ��������Ė��������ł���ˁB
����g�c�N�Ƃɓd�b����ĒS���҂���A���~�̉����܂����B
���}�O�l�V�E����肾���ǒ������܂��������ŏo�܂��ƁB�B�B
���͎����ɍw���A�b�v�̎����N���Ă��܂����B (�l�i�����[�Y�i�u���ł����ˁj
���݂ɕt���̃X�p�C�N��J1�v���̉~���`�d���R�[���ɕς����Ƃ�����D�����̂悤�ȉ�(�o�����X�����������j�ł��B
�����`���ŕs�ǂ����Ǖ�������g�b�v�N���X�̉�(�D�����j��ڎw���Ă܂��B
������
������Y���C�ł���m(_ _)m
�����ԍ��F10671999
![]() 0�_
0�_
���[���E���t���� ����ɂ���
> �}�O�l�V�E���t���b�Ƃ��������B
> �X�L�b�v���܂ߒn�ɑ��������Ė��������ł���ˁB
�����������ƂȂ�[���ł��B
�t���t�����ė���Ȃ��Ƃ��낪����Ȃ������̂Ȃ�A�W�������~���͈ꖡ�Ⴂ�܂���B
J1�̃X�p�C�N��(BA35HB)��SP�X�^���h�̐ڒn�Ɏg�p���Ă�̂ł����A������D�����ł���B
�ςȕȂ���炸�Ƀm�C�Y��啝�ɃJ�b�g���Ă����̂ŏd�Ă܂��B
�����A�`���b�g�D�����߂���Ƃ������A����Ղ肪���Ȃ�킪�ꂿ�Ⴂ�܂����ǁB
J1�g���ɂ͏d��������ĂȂ��Ƃ����\�����̂Ă���Ȃ��̂ł���^^;
���Ȃ݂Ɏg���Ă�SP��DALI��Helicon300�ŃX�^���h��FAPS�̃T�C�h�v���X�Ȃ̂ŕБ�16Kg���x�ł��B
���o���ɂ���̂����Ȃ�ŁA���łɑ��̋@�ނ��Љ�Ƃ��܂��B
CDP�FARCAM CD36T
DAC�FSoulNote dc1.0
AMP�FPASS INT-150
����CDP��AMP��NORDOST��PulsarPoints��DAC���g�c����ESD-SR1�ł��B
���͋g�c�F�͏��Ȃ߂Ȃ̂ł�(��)
�����ԍ��F10673633
![]() 0�_
0�_
KEZIA����
�\�E���m�[�g��DAC
�p�X�̃A���v
�����J�V�Z�����̉��F�H
�p�X�͎����e���I����B��W803S�ŕ����܂�������悪����̂���ǂ����o���Ă܂����ˁ`�`�B(���\�Ԃ��Ȃ����N�̂U���j
�\�E���m�[�g��DAC�B
�ŋ߂܂��o�܂�����ˁH���N���ɃN���[���d���̍�ƏI����DAC�������������ȁ`�Ďv���Ă܂� ���B
�Ȃ�Ƃ��~���[�W�b�N�o�[�h�̔�������Z�����ɂ������A�A�A�A
�����ԍ��F10678563
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
- �g�����X
- �ቹ
- �o��
- �|�[�g
- �^���
- �v���[���[
- �ǂ�
- �p���[
- ���[�J�[
- ���[��
- �E�[�t�@�[
- �f�W�^���A���v
- �U��
- �d��
- ����
- �N���[���d��
- ��^
- �A�i���O
- �K�v
- ����
- �p�l��
- ��
- ����
- ���f��
- �z�[��
- ����
- �}�O�l�V�E��
- ���
- �^�C�v
- ����
- ����
- ����
- �}���`
- �쓮
- ���P
- �𑜓x
- SP
- �v�b�V��
- �Ⴂ
- �f�W�^��
- ���\
- �N���A
- �g�p
- �d��
- �傫��
- ���^
- ��
- ���g��
- �ő�
�uCAV > T-88�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 6 | 2014/03/21 1:27:48 | |
| 13 | 2014/03/10 11:39:17 | |
| 7 | 2013/12/30 16:30:53 | |
| 3 | 2013/12/15 11:01:24 | |
| 5 | 2014/06/10 17:23:02 | |
| 28 | 2013/04/11 10:45:44 | |
| 0 | 2013/02/05 15:33:15 | |
| 7 | 2010/02/22 2:31:27 | |
| 83 | 2009/12/24 17:10:05 | |
| 0 | 2009/11/04 10:35:21 |
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�v�����C���A���v]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����z�ڂ��̂肻���̂ς�����
-
�yMy�R���N�V�����z���݂̃��C���@�\��
-
�yMy�R���N�V�����z2026�N�Ł@i7-3770S
-
�y�~�������̃��X�g�z10���ȉ�pc
-
�y�~�������̃��X�g�z10���ȉ�
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2026�N1���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2025�N12���z

�^�u���b�gPC
- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2026�N1���z

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�v�����C���A���v
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j













