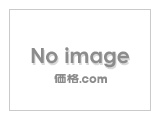
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2013年2月5日 15:33 | |
| 9 | 7 | 2010年2月22日 02:31 | |
| 87 | 83 | 2009年12月24日 17:10 | |
| 0 | 0 | 2009年11月4日 10:35 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
T−88購入しました。今までは、まったく真空管に興味がなかったオーディオファン歴30年以上の者です。
まず、重さにはビックリ!そして、筐体の作りの堅牢さ。また、トランスのでかさ!どれも、この価格や専門店では買えないような物体です。中国製真空管アンプは、ネットオークションなどでよく問題になっていますが、T−88はノイズもなくすばらしいできと思います。真空管の音を一度体験してみたい人。私みたいに、トランジスタ(石)アンプHIFIと両立したい方には、いいと思います。お店をネット等で調べれば、安く買えますしね。
CAVは、日本法人もあり、安心度が高いので購入に踏み切りました。なかなかよい買い物でした。
![]() 3点
3点
真空管アンプ購入おめでとうございます。
私も真空管アンプの購入を検討しています。
オーディオ暦30年ちょいですが、真空管には初めた頃から興味を持ってましたが、若かりし頃に自作してあまり良い音がしなかった経験と金銭面、そして扱い憎さで、敬遠していました。
でも世間では今でも真空管の音に不動の人気がありますね。
私はつい先日、真空管のCDPなるものを購入しました。
使用している部品が良いことも手伝って素晴らしい音を聞かせてくれて満足しています。
真空管の音って、艶やかでその響きと味がありますね。そして思ったよりクリヤーです。
今度は、アンプも真空管に替えようと思っていますが、悩んでいるのが、真空管が300BかKT88かEL34のどのタイプにしようかと言う事です。
どなたかそれぞれの音質のタイプの違いを教えてください。
値段的には300Bが最も高いと思います。パワーではKT88。
良く聞く音楽はポップスからジャズ、ヴォーカルまで幅広く聴きます。最近ではバイオリンなんかも。
それともうひとつ困るのが、ちょっとした事ですが、真空管アンプの殆どにヘッドフォン端子が無いことです。
夜はヘッドフォンで聞くのでこれも重要です。
ヘッドフォンアンプと言っても、アンプにラインアウトが無いので困ります。
中国製の製品ですが、実は私のCDPも中国製Cayinのものです。
値段の割りには、高級なまともな部品を使ってあります。
人件費が安いので、その分、部品代に回せるのだと思う。
日本の一流の部品、欧州の部品が使ってあります。
多分、CAVもそうだと思います。一度、中を覗いて部品を調べられたら面白いですよ。
中途半端な価格帯の日本製よりきっと良いと思います。
信頼性に関しても、ある程度高額な製品には力入れているので、通常使用では多分問題ないと思いますよ。
CAVの製品もCayinを製造している工場で作っていると聞いたこともあります。
Cayinは欧州でもその質が認められてます。
Triodeも一部の製品がその工場で作られていると聞いたこともあります。
因みに私はスピーカーも台湾製のUsherですよ。これもすごく良い音します。
書込番号:10940296
![]() 1点
1点
トライオードTRV-88SE所有してます。
ヘッドホン端子はありますね。
http://joshinweb.jp/audio/5120/4521296008267.html
他の所有アンプはDUSSUN V6iです。
http://www.audiorefer-d.com/cgi-local/detail_view.cgi?id=00157&category=80
真空管アンプでオートバイアス品はAH!があります。
http://www.bach-kougei.com/mystere/m_top.htm
書込番号:10940943
![]() 1点
1点
TRV-88SEのEL-34搭載版でTRV-35SEがありますけど、音の比較をされた事はありますか?
あれば、その印象をお聞かせください。
また300B搭載版のA300SEもありますが、こちらは?
確かに、ヘッドフォン端子がありますね。
Cayin製はどうも無くて困ってます。
書込番号:10942377
![]() 0点
0点
二匹の犬さんこんばんわ。
参考程度の話ですが、私の所有するトライオードのTRV-A88SEとCayinのA-200Pの音質を比べるとA88SEはクリアで勢いがあってやや角がある音で、A-200Pは中低音に厚みがあり、繊細で角が無い音に感じます。ドラムの音などの重低音はA-200Pのほうが柔らかい音(生音に近い音)で量感もあります。ご存知かもしれませんが、技術的にはシングルのアンプはトランスが電磁石になってしまって極低音のインピーダンスがあがってしまうために極低音のレスポンスが悪化して硬い音になってしまうようです。それでも半導体のアンプよりは柔らかい低音が出るとは思います。
プッシュプルは正相と逆相で打ち消しあうのかそういった問題はないようです。A-200Pはパラプッシュなようなので試しにA-200Pの1番と4番の玉を抜いてシングル動作させてみたのですが、クリアな音になって代わりに低音はやや硬くなりましたが、KT-88よりは柔らかい音でした。
2A3Cは繊細さに定評のあった2A3を大型化して300B並みのパワーを持たせた物だそうです。製造元の曙光電子のHPを見ても2A3Cのデータはまだ公開されていなかったのですが、曙光電子製のシングルアンプで8Wの出力を出しているので本当に300B並みのパワーを達成したようです。
KT-88は最高出力は2A3Cや300Bより上ですが、極低域の立ち上がりは後者のほうが良いために低音の評価が高いようです。半導体のアンプも最高出力は真空管より遥かに高いのですが低域ではパワーが発揮されないので硬い低音しか出ないようです。どうやら真空管は大型の物ほど低域の立ち上がりが良いようです。
EL-34は中庸との評価を聞きます。秋葉の小泉無線で試聴用に使ってるのがTRV-35SEだったような・・・。確か中庸な音がしてた気がするんですよね〜。いい加減な記憶ですみません。
私もヘッドホン端子が無いのでヘッドホン端子を自作してみようと思ってます。上手く行ったら報告します。
書込番号:10943497
![]() 2点
2点
ONKYOを好む方はTRV-35SE
DENONを好む方はTRV-88SE いい加減な主観
トライは取り扱い店が多いので試聴するのが宜しいと思います。
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
書込番号:10943730
![]() 1点
1点
300B、オークションで2万円程度の機種を購入し
改造される方もいらっしゃいますね。
2万円と言っても、見た目は10〜15万円、平行輸入の中国メーカー品です。
自作、改造に嵌るのも楽しいですね。
http://www.op316.com/tubes/tubes.htm
書込番号:10943773
![]() 0点
0点
ヘッドホン端子製作しました。
手順(L/R両方に手順を適用する)
1.ヘッドホンピンジャック(オス)→RCA変換ケーブル(L/R)のRCA端子を切断
2.切断部分を皮むきし、シールド線をよじってグランドラインとして芯線を
信号ラインとして剥く
3.芯線に10W240Ωの抵抗を直列で繋いでその先に極細のスピーカーケーブルを繋いで
端子に固定しやすくする
4.グランド側も長さ調整も兼ねてスピーカーケーブルを繋ぐ
5.むき出しのケーブルに絶縁テープを巻いて半田で先端を処理
6.ヘッドホンピンジャックコネクター(オス→オス連結用)を「1」のオス端子に
取り付けてメスにする(たぶんメス→RCA変換ケーブルは無いと思うので)
以上で完成です。
私のアンプは240Ωで7時か8時の位置で聴く感じです。T-88ならば480Ωは必要でしょうか。抵抗を並列にも接続すればもっと小さい抵抗で済むでしょうが、並列側に無駄な電流が大量に流れるのと結線がめんどくさいので止めました。音質的にはどちらが有利なんでしょうか?
私の場合はスピーカーセレクターを使っているので空いている端子をヘッドホン用としましたが、そのへんは工夫が必要ですね。
音質的には意外にも良かったですね。A-200Pを聴くと、整流管らしき小さな音がキュルキュルと聞こえてきて、まるでアンプに聴診器をあてているような感じです(聞き苦しいほどではない)。TRV-A88SEは整流管が無いせいか殆んど雑音は聴こえません。こちらのほうがヘッドホンアンプ向きでしょうか(笑)。
音質的にはスピーカーで聴くときと全く同じです。「300Bでヘッドホンを聴きたい!」みたいなわがままオヤジには面白いのではないでしょうか?
今回とは逆のアプローチで3W程度でプッシュプルのヘッドホンアンプがあれば、フルレンジ一発で都市部の一般家庭ならば事足りてしまう気もします。
書込番号:10979450
![]() 1点
1点
こないだ秋葉の音展でT-88とV-70NWの組合わせを聴いたのでレポートします。
(所有している訳ではないので口コミとしました)
私が終了間際に会場に着くと、解説担当のオヤジが自信なさそうに「広い部屋なので
ちょっと厳しいかも知れませんが・・・」と言いながら曲をかけたので、私は「確かに
この部屋の広さであのサイズのスピーカーでは仕方あるまい」と高をくくっていたの
ですが、いざ演奏が始まって見るとその分厚い中低音の音圧に圧倒されてしまい、
「あのオヤジ申し訳なさそうな顔してなんて音出してやがるんだ!!」と動揺を
隠せませんでした。スピーカーも良いのかもしれませんが、やはり重量級真空管アンプ
の駆動力はデジタルアンプに対して圧倒的なアドバンテージがあるようです。
各言う私も最近までは真空管アンプというものは味が有るものであって性能ではデジタル
アンプに敵わないと思っていましたが、実際はデジタルアンプが勝っているのはコスト・
機能性・省電力性であり、スピーカーの駆動力、特に中低域はデジタルアンプに勝目は
無いことが解りました。その主たる原因は大容量の出力トランスにあるようです。
デジタルアンプでもアナログ電源のものは真空管アンプと同じく電源トランスを持って
いるのですが、出力トランスは持ちません。T-88も後部に四角い箱が三つありますが、
一つは電源トランスで二つは出力トランスが納まっているものと思われます。
コイルには電気を溜め込む性質があるので(レンツの法則)安定した電力供給が可能なため
に高い駆動力を持つのかも知れません。
ちなみ私は最大出力50W(6Ω)のデジタルアンプと12W(6Ω)重量11.5kgのシングル増幅
真空管アンプと12W(4Ω?)重量26.5kgのプッシュプル増幅真空管アンプをもっていますが、
左から順に中低音の厚みが増して行きます。
素人考えですが、真空管の増幅特性(激しいとか穏やかとか)はデジタルで再現できそう
なので出力段をアナログ化してトランスを入れれば高い駆動力を得られるのではないか
と思います。
押しの強い音が好みで(強弱切替が出来るようです)デジタルアンプの中低音に不満がある
人に適したアンプだと思います。
デジタルでは倍の値段を出してもT-88の中低音には敵わないのではないでしょうか。
ただし、真空管アンプの場合はバイアス調整(DC 0.5V程度を測定するのに適したテスター
が必要)とハムバランス調整(スピーカーで調整可)が必要な場合があるのでT-88について
も店やメーカーに問い合わせたほうがいいかも知れません。調整自体は教われば電気の
知識など必要なく、勘で出来るものです。また、重量が重いので体力の無い方は要注意
です。
音展のベストバイ機だと思います。
ちなみにT-3-WHもなかなかの音質で、狭い部屋ならこれで十分かも知れません。
![]() 4点
4点
偏人さん、こんにちは。
興味深いレポート、ご苦労様です。
>真空管アンプというものは(中略)性能ではデジタルアンプに敵わないと思っていましたが、
>実際はデジタルアンプが勝っているのはコスト・機能性・省電力性であり、
>スピーカーの駆動力、特に中低域はデジタルアンプに勝目は無いことが解りました。
興味深いご意見ですね。おっしゃる通り、低域の躍動感やエネルギー感では真空管アンプが勝りますね。私もそこがデジアンを物足りなく思う一因です。
ただそれがイコール、真空管アンプはデジアンより「駆動力に勝っている」といえるのか? についてはどうなのでしょう。これをお読みになっているみなさんはどう思われますか?
書込番号:10494041
![]() 1点
1点
おはようございます。
スレ主さんの経験。
おっしゃった意味分かります。
確かにローエンド伸びについては、デジタルアンプは延びてなかったです。
反対にウーハーの制動を止める速さはデジタルアンプが早いかと…
(止まって欲しい時に止まる)←意味不明ですが(笑)
因みに私が聞いたデジタルアンプはアイスパワーのチャンネル500W。対するアナログアンプはチャンネル150Wの共に海外アンプでした。
私としたら、ニューフォースのデジタルアンプ(アナログスイッチングアンプ)は かなり深いローエンドまでいくんじゃないかと…
あくまで憶測ですf^_^;
私もいろんな意見を聞いて勉強したいですね。
書込番号:10494404
![]() 2点
2点
Dyna-udiaさんこんにちは。
ローンウルフさんこんにちは。
それはダンピングファクターというやつの話ですね。
確かに私が知ったかぶりしたレンツの法則からすると出力トランスは電流の立上がり・
立下り両方で抵抗を受けることになり、理論上切れが悪くなる性質があるのでしょうね。
私が音展帰りに富士ソフトの向かいにあるオーディオショップ茂木という店で購入した
cayinのA200-P(定価の半額の14万3千円だったので買ってしまいました!)はまだエージ
ング初期ですが、ハイスピードメタルを聴いても遅いとか鈍いという印象は受けません。
同じ12Wのパワーで重量が半分以下のモデルに比べて明らかに中低音が分厚くなって
いるのに鈍さは感じないということはメリットとデメリットのうち、メリットのほうが
大きいということではないでしょうか?スピーカーのレスポンスにもよるかも知れませ
んが。
T-88でメタルを聴いたらどう感じたか興味深いです。構造的には同じはずですが、パワ
ーの違い(T-88 45W,A200P 12W)がダンピングに影響するのか興味深いものです。
もしかしてパワーが大きいと止まりにくいとかあるのでしょうか?今どきのアンプは
消費者のパワー信仰でとりあえずカタログスペックを優先しないと売れなそうですから。
本当は過剰なパワーはないほうが良いこともあるのでは?
誰かその辺りを講釈してもらえないでしょうか。
アイスパワーのチャンネル500Wがググっても見つかりませんでした。それはもしかして
ジェフ・ローランドというブランドのことですか?ジェフ・ローランドのModel 102 Sと
いうモデルは内部の詳細な画像があったので見て見ると、電源トランスらしきトロイダ
ルトランスと出力トランスらしきコアトランスが写っています。私が考えたようにデジ
タル・アナログ折衷なのかな?技術解説ではその辺りは触れられていません。企業秘密
だからかな。ニューフォースはホームページを見ましたが内部構造の写真は無いし、
その辺の技術解説も皆無でした。
一般に知られたメーカーではなくて、前述のようなメーカーの最新機種を聴いて見たい
ものです。1000Wとは驚きです。
それにしても今まで私は真空管アンプとデジタルアンプのパワーを同列に思っていまし
たが、どうやら二者は全く別物と考えたほうが良いそうです。真空管アンプは最大パワ
ーは低くとも大型の出力トランスのせいで分厚い中低音がでますが、デジタルはどうし
ても数百Wのパワーが必要なようです。
私としてはデジタルもアナログも仲良く発展して行って欲しいものです。
書込番号:10498785
![]() 3点
3点
スレ主さんこんににちは
私が聞いたのはローテル(デジタルアンプ)とボルダー500SE(アナログアンプ)の両機パワーアンプですね
スピーカーは38センチウーハーのB&Wのノーチラス
一応ローテルとボルダーの両機の聞き比べですが、ボルダーのほうがローエンドまで伸びてましたね
あんまりメカのほうは詳しくはないのですが・・・・
聞いた感じでは私も好みでしたね
一応リンクを張っときます
ボルダーのほうはちょっとわかりません
お店にニューホースがあればよかったのですが・・・・
http://www.nuforce.jp/products/p8s_01.html ニューホース
http://www.onken-audio.co.jp/rotel%201.htm ローテルRB1092
書込番号:10500213
![]() 1点
1点
スレ主さん
是正。
ボルダーSE→ボルダーAEでしたm(_ _)m
書込番号:10501172
![]() 1点
1点
ローンウルフさんありがとうございます。
ローテルとボルダーのホームページみました。
ローテルは中身は全く見せてくれませんでしたがボルダーはインテグレーテッドアンプの
モデル865で中身を見せてくれました。巨大な電源トランスと小さな出力トランスの
ようなものが付いてます。あのサイズの出力トランスがローエンドの伸びの主要な原因
とは思えませんね。
考えて見ると低音域をしっかり出すためには振動板を大振幅させなければならないわけ
ですが、ローテルにしてもどこのデジアンメーカーも瞬時の大電流の供給が大事と説明
しています。
デジタルアンプ(D級)と対極的な増幅を行うA級アンプの仕組みを比較すると、
A級は常にバイアス電流というものを増幅回路に流しておいて、そこに信号電流を流す
ことによって増幅しています。D級アンプはバイアス電流が無くてパルス信号
が入るごとに増幅しています。
例えるなら徒競走をするのにA級は助走をつけてスタートラインに達するのに対してD級は
クラウチングスタートをするようなものでしょうか。これではD級のほうが遥かに実力が
上でなければ勝ち目はありませんね。
つまりD級が勝つためには加速力(瞬時の電流供給能力)が必要であり、そのためには
強力な筋力(大電力発揮能力(500Wとか))が必要になるのではないでしょうか。
とても買える値段ではありませんがジェフ・ローランドのContinuum 500(4Ω1000W,20kg)
を聴いてみたいものです。なんだかデジアンへの先入観を吹き飛ばしてくれそうな気が
します。
あとB&Wいいですね。前はとにかく硬い音を追求してたんですが、最近柔らかい音や味の
ある音を求めてしまいます。ジャズやクラシックを聴く回数が増えた気がするし。
年かな?
書込番号:10503356
![]() 3点
3点
失礼いいたします。
OPT=アウトプット・トランスファー=出力トランス。
コアのボリュームが大きい=重量のある出力トランス。
重量のある出力トランスは低域が出ます。
電源トランスも大きい方がよいという事がいえます。
なのでアナログアンプは重いほど音がいいという説も一理あります。
ただし出力トランスはコイルなので、
周波数によって抵抗値が変わります。
NFB量で多少改善できますが、
高域特性がリニアでなく高域が出にくくなります。
人間の耳に聞こえない周波数だから良いのかもしれません。
しかし超高域が可聴域に影響し、
良質な中高域になるのでリニアが良いとするのが、
SACDが出てからの主流ではあります。
定評のある出力トランスは高価という欠点があり、
出力トランスの直流抵抗分による周波数特性の悪化も考えると、
出力トランスは無い方が良いという事が言えます。
リニアな周波数特性のOTL=アウトプット・トランスファー・レス。
OTL真空管アンプは根強い人気があります。
ほとんど半導体アンプと変わらない音です。
DFは一桁になるとゆるい音になるようですが、
それが真空管の音の特徴ともいえます。
Nuforceデジタルアンプの内部写真は、
オーディオ雑誌に載っています。
トランスは小型ですがスイッチング電源なので、
高周波変換用は小型で大型と同じ働きができます。
平滑コンデンサーをパラって使用しています。
抵抗を少なくし、変動に対して立ち上がりの早い、
スピード感のある音を狙ったものです。
ただしバランスが崩れるため必ずしも良いとは言えません。
ジェフ102アイスパワーもスイッチング電源です。
アンプ部もスイッチング増幅です。
コンデンサーをパラっていない所が私の好みです。
もちろんトロイダルトランスを使用したデジタルアンプもあります。
書込番号:10503637
![]() 1点
1点
編人さん デジコンさん
低域コントロールについてお聞きしたいのですが…
デジゴンさんには、クリーン電源の事を別スレで伺ってましたが…
クリーン電源、又は200Vダウントランス導入にて低域の制動コントロールが効くものなのか…
因みに私のアンプはA級です。(AB級から最近変えました)
以前AB級の時にクリーン電源をアンプ側にカマスと中低域のパワーアップ、パワーアンプを追加した感じ?にはなったのですが… 汗
今のレベルで低音が出てないわけでは有りません。(満足のレベルまで行ってます。ローエンドまで伸びてます)。
これに、200Vダウントランスもしくはクリーン電源導入で制動力、出発力が加わったら鬼に金棒とは思いますが…いかがでしょ〜!?
因みに別途ブリッジにするパワーアンプの追加は考えてはおりません。
書込番号:10504894
![]() 1点
1点
偏人さん、こんはんは。
一点、ご教示願えないかと思いレス致しました。
>つまりD級が勝つためには加速力(瞬時の電流供給能力)が必要であり、そのためには
強力な筋力(大電力発揮能力(500Wとか))が必要になるのではないでしょうか。
いわゆる瞬時電流供給能力と「出力」とは、イコールの関係(つまり単純に出力が大きいほど瞬時電流供給能力が高い)といえるのでしょうか?
私は知識不足のため判然としませんが、メーカーがしきりにアピールしているところによると、瞬時電流供給能力は出力というよりむしろ駆動力とイコールの関係であるような印象を持っていました。(つまり必ずしも出力=駆動力ではない、というような文脈ですね)
とすれば「デジタルアンプは駆動力がある」とよく言われるのは、出力との関係ではなく瞬時電流供給能力が高いがゆえではないか? というようなことです。
書込番号:10505421
![]() 1点
1点
ローンウルフさん。
>「クリーン電源、又は200Vダウントランス導入にて低域の制動コントロールが効くものなのか…」
以前デジタルアンプがON/OFFだけの、
スイッチングしたデータに変換しても
アナログ波形に戻すことが出来てしまう事から、
クリーン電源で波形を再生したとしても
根本的な性質は変わらないのではないかと述べました。
同様に200Vから降圧して100Vとして使っても、
機器に与える200Vの性質はそのまま残ると思います。
http://community.phileweb.com/mypage/entry/1292/20080207/2804/
>「200Vより降圧した電源を使用すると、もうあとには戻れません」
逆に100Vを昇圧して200Vとした場合、性質は100Vという事です。
レコード愛好家のアナログプレーヤーへの情熱…。
インターコネクトやSPケーブルで、
音が変わらないという真空管アンプ自作派でも、
プレーヤーのシェルリードで音が変わるといいます。
もちろんカートリッジやプレーヤーによって激変する事に反論はないでしょう。
プレーヤーもモーターにコイルを使用していますが、
モーターからの磁束漏れや制御方法で音質に影響します。
もちろんアーム、ターンテーブルなどにも気を使います。
CDプレーヤーにそれだけの情熱をつぎ込んでいるでしょうか。
目に見えないほどのレコード溝や、
CDなどのビットを扱っている事では同じ性格であると思います。
上流のプレーヤーにアナログほど気を使わないのは何故でしょう。
ここに波形再生型クリーン電源を使用することで、
高性能のアンプであればあるほど、
CDプレーヤーのわずかな情報まで余すことなく増幅し、
アンプの性能を出しきる事になると思います。
定位や周波数特性が良くなり、低音が凄く出るとはどういう事かというと、
器機そのものが持っている能力を出し切るという事だと思います。
もっといい器機にすればもっといい音が聴けますが、
それはいつでも出来ます。
求める音とは器機の交換だけで完成するものでもないと思います。
書込番号:10507799
![]() 1点
1点
デジゴンさん専門的な内容をご教授していただいて有難う御座います。
こういう知識を知っていれば納得した上で機器と付き合っていけると思いますし、
世界が広がります。
調べて見ると1個数万円の高級出力トランスの特性は音圧では50Hzから70kHzほどの範囲で+−2dB
ほどで気にするほどのものではありませんが、インピーダンスは25kHz辺りから2次関数的に悪化
していくようです。可視聴帯域外の音を重視するならば、せっかくだからデジアンを使ったほうが
いいですよね。
可視聴帯域外の音が可視聴帯域内の音を改善するという話は聞いたことがあります。普通に耳に
する音は基音に倍音を重ねた合成音なわけですが、合成される倍音が高次になるほど基音のときには
単純なサインカーブを描いていた音が複雑で滑らかなカーブを描いていくというものです。
ただ、このカーブの滑らかさを人が認識できる範囲にも限界があるわけで、普通人の可視聴限界は
若年者で17kHz前後ということを考えるとそこから20kHzまでの範囲でも十分に音質が改善される気が
します。
ほとんどの人はブラインドテストを行うと・・・。
また、私も可視聴帯域外の音をOn/Offできるアンプを持っていたので何度も試したのですが・・・。
これ以上はその手の機器のセールスを妨害するので言えませんが(恐)・・・。
私はCDしか聞かないので誰にでもハッキリわかるくらい中低音が強化されるアウトプットトランス
付がいいですね〜。
でも真のマニアは可視聴帯域外の音の違いが解ると思います!
あと、ちょっと話が飛びますが、CDプレーヤーによる音質の変化は体験したことあります!
十数年前の3万のプレーヤーを最新の4万のものに変えたところ、音の解像度とクリアさが
大幅に増しました。これ以上どれほどハッキリ改善の余地があるのか想像できません。環境が
同じでないと比較できないので買ってみないと解らないでしょうが・・・。
書込番号:10512602
![]() 2点
2点
ローンウルフさん
私もダウントランスとクリーン電源は導入したことがないので
なんとも言えませんが、仮にメーカーのウタイ文句通りの効果があった
としてもノイズが無くなって音がクリアになるだけですよね。
瞬発力はパワーや増幅素子の影響が大きいでしょうし、制動力はアウトプットトランス
付のアンプの場合は前述のレンツの法則でどうしてもそういった性質はあるので
しょうしから瞬発力、制動力ともにスピーカーとの兼ね合いもあるのではないでしょうか?
ただ、制動力の無さも味になると思うのでそれはそれで大事にしたほうがよいのでは?
一台のアンプに総てを求めるのは無理があるかと。
書込番号:10512605
![]() 2点
2点
Dyna-udiaさん、こんばんわ。
教示するほどの知識がなくて申し訳ありません。
ただの井戸端論議ということで・・・。
私は元々、じっさいにスピーカーを駆動するのに消費する電力は普通のシステムなら
3W程度と聞くのでアンプの最大出力は十数ワットで十分ではないかと思っていた
のですが、A級アンプや大型のアウトプットトランスを持つものは別としてデジアンは
世界的に中級以上となると100W以上の出力を持っています。メーカーの策略ではないかと
疑っていたのですが、世界中のメーカーがグルになっているとも思えないので現代の
デジアンの増幅素子には何か根本的な問題があってそのような大出力が必要なのでは
ないかと思いました。
結局はアンプ素子に電流が流れてから内部の半導体が飽和状態になって電流が流れ出すまでの
タイムラグと出力が100%になるまでの時間が、ベース電流のサポートと真空管の電子放出の
レスポンスの良さに適わないので大振幅時の振動板の立ち上がりが鈍くなって差ができる
のだと思います(あと出力トランスがバッファになってるのかな)。
電流供給の持続ができなくて後半にへたるとは思えないので。
実際の出力が3Wで済むなら、究極的にはその程度の最大出力があれば良いことになります。
しかし、全く新しい半導体を開発するのもすぐには無理でしょうからD級の立上がりを改善
するためには最大パワーを上げる事しかなかったのではないでしょうか?そのため世界には
大出力のデジアンが溢れていると・・・。
要するに最大パワーを上げると瞬時供給能力が上がるのだと思います。
例えば10Wのアンプが3Wの出力を発揮するまでに1秒かかるとして、100Wのアンプが3Wの出力を
発揮するまでには0.1秒で済むとか。
現状から想像しているだけなのですが、結局のところ、半導体の根本的な問題のために世界的な
パワー競争が起きているのかと想像しています。
あっ、そうそう、ここはT-88の口コミなんで宣伝しときますが、
音展でT-88を聞いてから有名メーカーの20万円台のデジアンを聞いたところ、中低域が
スカスカに聞こえました。結局20kg台の重量級デジアンでなければT-88の中低音の厚みには
適わないんじゃないでしょうかね。そうすると価格は50万円を越えますし、消費電力もT-88と
大差ありません(ここは興味深いところです。結局デジアンも中低音の厚みを求めると大消費電力
になるのでしょうか。ジェフ・ローランドのContinuum 500など待機電力は35Wですが最大は2000Wです)。
まあT-88はSN比80dBでデジアンに比べてクリアな音質ではありませんでしたが、それもかえって真空管
の味がわかりやすくて良いかもしれません。私が帰りにメーカーの在庫処分品で半額だったために耐え
きれずに買ってしまった(T-88のインパクトもある(店が扱ってなかったし))A-200Pなどはその点91dBで
デジアン並みにクリアな音質なのでそういった雰囲気は解りにくいかも知れません(これって自慢かな?)。
書込番号:10512610
![]() 3点
3点
偏人さん、こんにちは。
>有名メーカーの20万円台のデジアンを聞いたところ、中低域がスカスカに聞こえました。
まあデジアンはそのスッキリ感が特徴ですよね。私などはそのへんがあんまり好みじゃないんですが、逆に高域重視で透明感とか繊細さ、スピード感を求める人にはデジアンは好まれるようですね。
>T-88はSN比80dBでデジアンに比べてクリアな音質ではありませんでしたが、
>それもかえって真空管の味がわかりやすくて良いかもしれません。
はい。真空管アンプはいい意味での雑味というか、ラフで「ノイジー」なところが味になっていますよね。たとえばエレキギターの音を意図的に歪ませた、いわゆるディストーションサウンドなんかは「きれいな音」を好む人にはうるさいだけでしょうが、こうしたある種の「ノイズ」が音楽に深みや味わいを与えるのも事実です。
オーティオの歴史はSN比の高い「きれいな音」を追求してきた歴史ではないかと思いますが、案外、音楽の味わいとは、それとは逆方向の世界にあったりするんじゃないかと最近思います。
書込番号:10513776
![]() 4点
4点
Dina-udiaさんこんにちわ
>オーティオの歴史はSN比の高い「きれいな音」を追求してきた歴史ではないかと思います
>が、案外、音楽の味わいとは、それとは逆方向の世界にあったりするんじゃないかと最近思
>います。
確かにそういうのあるかも知れません。
最近「Hi-Fi(高忠実再生)必ずしも善ならず」と思うのですが、よくメーカーがCDに込められたソースを
完璧に引き出すことが最良と言っていますが、それは録音が完璧であることを前提として
いないでしょうか。例えば真空管のKT-88のようにソースをやや激しく増幅することでHi-Fi
からは遠ざかりますが、かえって生音の迫力をよみがえらせたりとか。
録音技師の意見を聞いてみたいものです。
デジアンにもソフトモードとかハードモードがあるといいかも。増幅段階ではなくて信号読み取り後に処理するといいかもしれませんね。
結局、オーディオに王道なしですね。できるだけ性格の違う機材を揃えて気分や音楽に合わせて使い分けると最高かも。
書込番号:10518146
![]() 3点
3点
こんにちわ(^_^)v
編人さん デジゴンさん
クリーン電源のレビューで(この音を聞いたら戻れない)て言う表現が多々あります。
勿論CDプレーヤー(デジタル前段)は納得できます。
しかしどの家庭(一般住宅)でもクリーン電源効果があるかは疑問ですし、使ってみなきゃ分からないが今のところ妥当な線ですねf^_^;
(アンプ側にて瞬発力、広大なピラミッドバランスが構築出来るのか?)
ま、。自分なりの素朴な疑問でとっておきます。(^_^)v
今回は楽しいお話ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:10520757
![]() 1点
1点
ローンウルフさんICEpowerの情報ありがとうございます。
アンプ以外の要件が揃わないので
今以上のアンプを求めることはなさそうですが
デジアンにも興味がもてました。
ちなみにICEpowerは250Wモデルは1kHz以下(8Ω)ではダンピング1000以上ありますね。
4Ωだとすこし悪化してます。
やはりダンピングファクターはデジアンか。
Dina-udiaさん
ICEpowerのホームページ見たら面白いデータがのってました。
ICEpower®250ASPという250Wアンプのコントローラーのデータシート(14ページ)を見たら
20kHzでフルパワーまで約1.8秒、10kHzで約12秒でした。
10kHz以下がのっていないのですが、ほぼ直線のグラフなのでそのまま線を延ばすと
f0付近で約80秒です。3.1Wを発揮するまで1秒とするとかなり遅いような気もします。
A級アンプの詳細なデータがないのでなんとも言えませんが、やはりデジアンは
低音が苦手なのかも。ICEpowerはデジアンの中では相当性能いいほうでしょうから。
なぜか250Wモデルしかこのデータはのってませんでした。
まさか間違えて載せたとか?
書込番号:10524050
![]() 2点
2点
>最近までは真空管アンプというものは味が有るものであって性能ではデジタル
>アンプに敵わないと思っていましたが、実際はデジタルアンプが勝っているのはコスト・
>機能性・省電力性であり、スピーカーの駆動力、特に中低域はデジタルアンプに勝目は
>無いことが解りました〜
ここは以前の私も同じでした。
機材の性能を理論立てしてスペックや理屈だけで考えるとトランジスターなど石を使ってパワーを増幅するデジタル、
アナログ、アンプが優れている・・・ とアタマの中だけで勝敗を決め付けてしまうのですが、一度でも管球アンプを
聴いてしまったら、その間違った「概念」が覆されてしまいますね。
アンプによって変わる音を` タイ焼きに例えると、半導体に「石」を使ったアンプと比べて真空管アンプから出てくる
`タイ焼きの方が2倍近くパンパンにアンコが詰まったタイ焼きといった感じでしょう。
音の密度感、濃厚さがトランジスターアンプでは簡単には出せないものを真空管アンプは苦もなく出してきます。
このあたりは銘機と言われてるサンスイAU-07AnniversaryだろうがAU-X1111 MOS-FETだろうが到底太刀打ちできません。
書込番号:10539378
![]() 2点
2点
HDMasterさんこんにちは。
増幅のレスポンス的にはシリコンとかゲルマニウムを媒体にして電流を流す石は
媒体なしで電流を流す真空管には原理的に不利な気がしますね。
ただ、原理的に不利であっても石も超強力なものだと聴感上十分なパワーが得られるかも。
ICEpowerのモジュールで自作してみたいものです。完成品は高くて買えないので。
全部モジュールならパソコン作るのと同じじゃないですかね。
まあそんなにアンプもってても意味ないですけど。
真空管アンプ(アウトプットトランス付きのもの)並みのパワーのあるデジアンが普及価格帯
に下りてくるまでにはまだしばらくかかりそうですね。
今のところコストパフォーマンス的にも真空管アンプは非常に優秀なようです。
書込番号:10544238
![]() 1点
1点
Dyna-udiaさん、ローンウルフさん。
何回か前のコメントでTriodeのTRV-A88SEとCayinのA-200Pについて
大型出力トランス搭載のA-200Pのほうが中低域の厚みが増しているけれども
ダンピングファクターの悪化は感じないと書きましたが、スピーカーを入れ替えて
聞き比べてみるとやはりA-200Pは中低域の厚みが増した分、マッタリとした音に
なって切れは落ちる印象ですね。
やはりデジゴンさんのいうようにトランスを積むことによる利点もある分、損失も
あるようです。
某アニメで「錬金術は等価交換が原則」と言っていましたが、オーディオにもそれは
当てはまるようです。
一概に大型トランスが良いとは言い切れませんね。
書込番号:10548965
![]() 2点
2点
T-88ではありませんが、真空管アンプとミニSP、CDPのコンポが、10万円以下で登場するみたいでした。元々、パイオニアの方々が立ち上げているという事で音に対する強いこだわりはあるようです。初めて聴いてみましたが、CD再生はなかなか良かったです。(近くで鳴っていたQUADのシステムが聴こえてくると差を感じましたが・・・)ipodは会場が騒がしかったこともあって、コメントできませんが繋がっているのは確認しました。中国の工場で製造し、ギリギリまでコストを抑えているという事ですから手軽に真空管アンプを楽しみたい層には支持されるのでは無いでしょうか。今後の展開に期待します。
![]() 0点
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】O11D mini v2 White SL no LCD build
-
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
-
【欲しいものリスト】PC構成20251031
-
【欲しいものリスト】メインPC再構成
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
プリメインアンプ
(最近3年以内の発売・登録)














