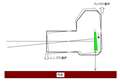PENTAX K-7 �{�f�B
���엦��100%�E�{����0.92�{�̃K���X�v���Y���t�@�C���_�[/�Ǝ��̎�u����@�\�uSR�v/HD����B�e�@�\�Ȃǂ�������f�W�^�����t�J�����B���i�̓I�[�v��
���i���̓o�^������܂��� ���i���ڃO���t
����
�ň����i(�ō�)�F
¥16,200 (3���i)
�^�C�v�F���t ��f���F1507����f(����f)/1460����f(�L����f) �B���f�q�FAPS-C/23.4mm×15.6mm/CMOS �d�ʁF670g
![]()

-
- �f�W�^�����J���� -��
- ���t�J���� -��
PENTAX K-7 �{�f�B�y���^�b�N�X
�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �������F2009�N 6��27��
���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S555�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 2010�N3��11�� 02:24 | |
| 120 | 43 | 2010�N3��11�� 02:03 | |
| 288 | 67 | 2010�N3��10�� 21:24 | |
| 46 | 6 | 2010�N3��10�� 20:41 | |
| 146 | 30 | 2010�N3��10�� 13:54 | |
| 2233 | 439 | 2010�N3��9�� 23:29 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > �y���^�b�N�X > PENTAX K-7 Limited Silver �{�f�B
�����������������ɒu���Ă���������������ł��傤�ˁB
PENTAX�ɖ₢���킹�Ă݂܂������A�L���b�V���o�b�N�̑ΏۊO�Ƃ̂��Ƃł��B
1���~�͕Ԃ�܂���̂ŁA�����ӂ��������B
![]() 5�_
5�_
���̏Z�l����@����ɂ���
�@�c�O�ł����^^;
�@CB�������Ȃ��̂́`�B
�@CB���l����ƍ�K-7�{�f�B�̎�����8���~����Ă��܂��B
�@k-7Ltd��116800�~�ƂȂ�ƁA4���~�߂��l�i���ɂȂ�܂�����B
�@�Ⴂ���A
�@�@�F
�@�@�X�N���[���}�b�g
�@�@�����K���X
�@�@�����̃o�b�`
�@��k-7�ł��Ή��ł��镨��
�@�@PENTAX Digital Camera Utility4 ver4.10
�@�@�{�̃t�@�[���E�F�A�@ver.1.03
�@�Ƃ��������ł��ˁ`�B
�@
�@CB�������̂��ɂ��ł����A���͉��i�R���̂��X�ł͂Ȃ��ł���
�@����A���X��1���ԔY��ŗ\�Ă��܂����i���j
�����ԍ��F10985407
![]() 5�_
5�_
������������i�͑A�܂����ł��B
KX�Ɋւ��Ă̓J���t���߂��Ĉ����Ă܂������B
K7�݂����Ȍ���͏��L������܂��ˁB
�X�e�L�Ȃ��Ƃł��B
�����ԍ��F10985432
![]() 3�_
3�_
�ȂA���Ǘ\�����I
�Ƃ�����ł݂�B
�����v�Ē��ł��B
�����A�R�}�E���g�̐��̓��y�҂Ȃ̂ŁA�h���ɂ̃X�y�[�X���Ȃ��̂ł����B�B�B
�����ԍ��F10985752
![]() 3�_
3�_
�����B�\��҂��ӊO�ɂ��܂��ˁB
���͒����f�W�^���_���Ȃ̂ł��߂ł��B
���̂��A200�~���ɂ��ŁA60-250���Ă��܂��܂������B�B�B^_^;
����ŁACB�Ώۃ����Y�Ŗ��w���̂��̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
���A�������������B�B�B
�����ԍ��F10985861
![]() 3�_
3�_
���̏Z�l����@����ɂ���
�@��N������67�U���g���n�߂Ē����̐�����m��n�߂āA645D���C�ɂȂ���
�@����̂ł����A�t�H�[�}�b�g���Ⴂ�܂��̂ł���͂���łƁ`�i�j
�@K20DTi�ƈႢ�������lj�����F�����łȂ��Ⴂ������A�������^�����ł��`�B
�@�܂�DA��60-250�w�����߂łƂ��������܂��`�I
�@
�@
�@
�����ԍ��F10986453
![]() 1�_
1�_
CB�Ȃ��Ă��������o��ł�����B�@
�������{�ACB�������肬���K-7���w���\�肶�Ⴊ�A�w����Ԃ��Ȃ�
��p�@���o���肷��Ɛ��_�ƐS���Ɉ��������B
�@
�S���Ō���1000��Ȃ炷���Ȃ��Ȃ��Ȃ����̂��H
�����ԍ��F10990276
![]() 1�_
1�_
���N�ɓ���A3������K-7���w�����悤�ƌv��𗧂ĂĂ܂����B
�O�����f���炵���ł����A�d���K���X�Ƃ�������V�[�g�Ƃ�����d�l�����Ȃ肻�����܂��B
�L���b�V���o�b�N���Ȃ��Ƃ��Ă��~�����Ȃ��B
�{����CB�L�����y�[����3�����܂ł�����CP+�Ńy���^�j���[�J���������\���ꂽ��A�������������₷���Ȃ邩�Ȃ��Ǝv���Ă����̂ł����c
K20D�̋�f����1000�����ŁA�����l�b�g�V���b�v�Ō������܂����A����ȂɍQ�Ă鎖�Ȃ��̂��Ȃ��Ǝv���Ȃ�������ɋC�����͂قڌł܂��Ă����Łc�I
�����ԍ��F10990757
![]() 0�_
0�_
K-7�̌�p�ł����A�����炭�ACP+�ł͂���I�ڂ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�Ǝv���܂��B
�{�[�i�X�����̃����[�X���ڕW�������͂��ł�����A6�����{�ɊԂɍ����悤�ɁA5�����{���\�A5���������Ƃ����������ł͂Ȃ��ł��傤���H
���ڋ@�\�Ȃǂ́A����̋�f���⒆���f�W�^���ŗ��p�ł������ȋ@�\������I�ڂ���邩�ƁB
�ł́A���~�h���p�ɁB�B�B^_^;
�ʐ^�Ō���y���^�b�N�X�uK-7 Limited Silver�v�i�f�W�J��WHATCH�j
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/pview/20100224_350829.html
�����ԍ��F10991096
![]() 3�_
3�_
��������!!
�ς��đς��đς�������!!
����ɑς������āu�����I���A��p�@����ɂ���v�E�E�E���@���S�t���O��
�@
��k�͂��Ă����A2��̐��ł͊�t�͂������E
�T�u�i��t�ł͂R��ڂɂȂ邯�ǥ��(^^;;
���͋@�����Ń}�C�N���t�H�[�T�C�Y�N���X�ɂ��Ȃ��Ɓu�J�����̔����|��v�ɂȂ肻����
�y���^����optio-I-10�x�[�X�ō��Ȃ��ł����ˁ`
�I�����A�p�i�ɑ������̑��uSAMSUNG�v��NX10���\������
�f�W�}�K���Ă݂��K-7���T�C�Y��r�Ŕ�ׂ��Ă��邯��
�y���^�Ȃ�I-10�̃V���o�[�f�U�C���̉�����ŃR���p�N�g�ł������m�o�������Ȃ�ł����ˁ`
�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�܂��V���o�[Limited�������肠��
�����ԍ��F11005152
![]() 2�_
2�_
Limited���Փ���������@����ɂ���
�@���y���^����optio-I-10�x�[�X�ō��Ȃ��ł����ˁ`
�@auto110�̗l�ȕ����������ł����Aauto110����4/3�̎�����Ɠ����l�ȑ傫��
�@�������Ǝv���܂��̂ŁA�f���f�q���ǂ����炩�����Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�
�@�܂��ˁB
�@�ŋ߃t�C������ist����肵����ł����ǂ��AAPS-C�@���t�C������ist�ʂ�
�@�傫���ɂȂ��Ă����Ɗ����������ƁAk-x�Ɣ�ׂĂ��܂��܂����i�j
�@�����Ƃ����܂�ς��Ȃ��ł����A�}�E���g�ʂ���w�ʉt���܂ł̌��݂�
�@�t�C������ist�̕��������̂ŁA�����ʂ̌����ɂȂ�Ƃ��������Ɓ`�B
�@
�����ԍ��F11005520
![]() 1�_
1�_
���̏Z�l����AC'mell�ɗ����Ă���@����ɂ���
>�����Ƃ����܂�ς��Ȃ��ł����A�}�E���g�ʂ���w�ʉt���܂ł̌��݂��`
NX10�̃T�C�Y���܂��ɂ��̌����A�~���[���X��K-7�̖���40mm��i�≖��SP+10mm�H�j
K-7��1400��COMS�Z���T�[�͊��������SAMSUNG���ł����A
���̂܂܃~���[���X��110���̃��g�����ŁE�E�E
OP��HELIAR�p�݂����ȉt���r���[�t�@�C���_�[�t�����ĥ��
��������Y��ULTRA�@WIDE-HELIAR�݂����ȒZ�œ_�Ƃ�FA,DA��Ltd�N���X�����
�����A����Ȃ珗�������t���[�U�[�̃T�u�@�Ƃ��Ēʗp����
��������E�E�E
�����ăV���o�[Limited��Ȃ������u��`��������Ƃ��挩���Ɛ��������f�������v��
�������g�Ɍ�����ł��饥�
�E�E�E���ȁH��
�����ԍ��F11006266
![]() 0�_
0�_
2�T�ԥ����
�Y�݂ɔY��ť����
Limited Silver�����R�������B�����`����
����ŁA���Ƃ͌������Ă��炫�߂܂��B
�������A�������ꃖ���Ԃł܂�K-7�����̂��H������⎩���̓��X
�������̂܂܂ł́u����k-7��FALtd�g�����тɔ������˂���������݂�����
���_�q���ア���Ȃ��v�ƥ����
�����āA�����Ƃ̒��ł��݂���ɂ�Ȃ��l�ȉB���ꏊ��{���Ȃ��ƁE�E�E
���ꂪ��Ԃ̓�₾�����肵�āE�E�E��
�����ԍ��F11032118
![]() 1�_
1�_
> �����āA�����Ƃ̒��ł��݂���ɂ�Ȃ��l�ȉB���ꏊ��{���Ȃ��ƁE�E�E
�}�W�b�N�ŏォ�獕�ɋU������Ƃ����̂͂ǁ[�ł���H�@^_^;
�����ԍ��F11032138
![]() 0�_
0�_
>�}�W�b�N�ŏォ�獕���U���`
����A���łɍ���K-7��K200D�ɋU�����ĉB��Ă����ł���
�ȃ����Ȃ̂ŁA���ݎ��̂���������Ȃ��ƥ��
�������ɋ≖��SP�U�ɋU�����Ă��o���o���ł����i��
�����ԍ��F11035021
![]() 0�_
0�_
Limited���Փ���������@����ɂ���
�@��NX10�̃T�C�Y���܂��ɂ��̌����A
�@�����Ȃ�ł���ˁ`�B
�@�������A�}�E���g������Ɠd�q�ړ_�ł��ׂĂ̑�������Ă���̂�
�@PK�}�E���g�̃����Y�́A�}�E���g�A�_�v�^�[����āAMF�ōs��
�@�Ή����邵���Ȃ������Ɏv���܂���^^;
�@���������A�������ꃖ���Ԃł܂�K-7�����̂��H������⎩���̓��X
�@�T�u�@���l����ƁA���C���@�Ƒւ�������������Ԃ��Ǝv���܂��̂�
�@K-7Ltd���w�����Ă��܂��̂������Ȃ����Ɓ`�i�j
�@����K-7�����łɉ��l�ɃI�[�v���ɂȂ��Ă���̂ł���A
�@�uK-7�̍��̓h���𗎂Ƃ��A�}�O�l�V���[���{�f�B�̉��n���o���Ă�������B
�@������p�������������ǂ��`�v
�@�ƌ����̂���Ȃ̂��Ǝv����������܂�^^;
�����ԍ��F11036213
![]() 0�_
0�_
��1���~�͕Ԃ�܂���̂ŁA�����ӂ��������B
���T�Ȋ����ł����I
����Ȃ�P���~����������Ηǂ����Ă��Ƃł��傤�H
���������X�ł͂����ɍň��l���������Ă��炦�����Ȃ�ł�����Ɗ����������B
�������A����ł�������B�B�B
�����ԍ��F11050737
![]() 0�_
0�_
�F����A������
�����䕪���X�N���[���}�b�g���645D�̃I�v�V�����ŏo�܂�����
�ǂ����Ȃ�K-7�p�ɂ��o���ė~���������ł��B
�y���^�t�@���݂͂�ȁH645D�Ő���オ���Ă�悤��
�������ɏՓ������o������z����Ȃ����i�O�O�G�G
�B����������T�C�Y�ł������i��
K200D�̂ɋU������̂������߂��邵
����ȑO�ɂ��܂���������
PEN�@Lit���T�u�ɔ����܂��傤���iOP���݂ł���LimtedSilver�Ƃقړ��z�������襥����j
�����ԍ��F11067387
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > �y���^�b�N�X > PENTAX K-7 �{�f�B
645�c�����Ȃ��ƕ����Ă��Ă����\���y���݂ł킭�킭�ł�
���̃V���[�Y���p������Ƃ��ď����I�ɂ͑f�q�T�C�Y��645�ɂȂ��ł��傤���H
�䐔�̏o��J�����ł͂Ȃ��̂Ń��f���`�F���W�͂����Ă���{�\���͕ς����Ȃ��Ǝv���̂ł����A�����̑f�q�T�C�Y�̑�^���i645�j�����z���Đv����Ă���̂��A����Ƃ�����̗p�����f�q�T�C�Y�ɓ��������{�f�B�ŏo�Ă���̂��H
�F����͂ǂ��v���܂����H
![]() 4�_
4�_
645�ӂ邳�����`�`�`���`�`�B
����Ǝv���܂��I
�����ԍ��F11039880
![]() 4�_
4�_
�����Y�����̃Z���T�[��p�v�������Ȃ̂ł��܂���҂ł������ɂȂ��ł��ˁB
645�t���T�C�Y��100���ȉ��Ŏ�ɓ���ɂ͂܂��܂����Ԃ��|�肻���ł���
���̂Ƃ���̓t���T�C�Y��1.7�{�Z���T�[�@�ɐ�������܂��傤�B
�����ԍ��F11040019
![]() 1�_
1�_
35�~���t���T�C�Y�ɂ͊ȒP�ɏ��Ă�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�ʂɑʖڂƂ͌����܂��A�V�X�e���������͂ƁA�ʎY���ʂ̋����͂Ȃǂ͌������ł��B
�J�����{���{�̏�p�����Y�i30�`300�~���H�j�ŕS���ȓ��i35�~���t���T�C�Y�����@���j���K�v���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11040144
![]() 3�_
3�_
645�{�f�B���⏬�������B���f�q�ł��傤���H�Ӗ��Ȃ��ł��ˁB
�≖�ɗ����Ԃ�Ε����闝���A�܂�͎B���ʂ̑傫�����~�����Ċg�債���̂ł�����B
�ςȂ��ˉ�ꎞ�����̏��i�J���Ȃ�A���Ȃ������܂��B
�����ԍ��F11040444
![]() 8�_
8�_
�{�f�B�T�C�Y�������Y(�}�E���g)���ʕ��ł�����K-7�̃{�f�B��645�̑f�q���ڂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ�
�����ԍ��F11040520
![]() 0�_
0�_
645D�̃����Y���A��pDA?�����Y�d�l�ƂȂ�A�܂��܂��Ǝ��K�i���m�B
���r���[�Ȋ��͘c�߂܂���ˁB
���ꂾ������A�������̂��ƁA35mm�t���T�C�Y�@�������̋@��K-7�ɕ��荞���i���o�������������������肻���ȋC�����܂��ˁ`���B
����645�ɍS��K�v���Ȃǂ܂����������Ǝv���܂����E�E�E�B
����Ƃ��A�ɏ����̈ꕔ���[�U�[���M�]���Ă���̂ł��傤���ˁH
645�Ƃ�������p�r�Ɍ���Ȃ��߂��f�W�J���ŗL�����قǁA���̊�{���\�ւ̂������́A�����i�Ƃ͔�ׂ悤�������قlj��[�����x���ł̕]���ɑς����鐻�i���e�łȂ���Ȃ�܂���B
������������Ӗ������ŁA�ቿ�i�H���Ƃ����헪���v�l�����Ƃ���A���r���[�Ȑ��i�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB
645�Ƃ��������ŁA���\�Ɋ��҂��Ă��܂����[�U�[���A���������̃^�[�Q�b�g�ł��傤����B
PENTAX HOYA 645�ňꂩ�����̏����ɏo�܂����ˁH�H�H
����Ƃ��A645���L��܂��B�@���x�̊�ƃC���[�W���ł��傤���H
�����ԍ��F11041419
![]() 4�_
4�_
�t�B�����̎g��Ȃ��f�W�^���ł�����A�Z���T�[�T�C�Y�̓��[�J�[������Ɍ��߂ėǂ��Ǝv���܂��B
�����������ɂ���܂��A�������Ђ��J�����ƃf�W�^���o�b�N�����R�Ɍ݊��ł��铝��K�i��
����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B���ꂪ�Ȃ���Z���T�[�T�C�Y�������ł��Ǝ��K�i����Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F11041488
![]() 1�_
1�_
645D�Ƃ����B���f�q�̋��������A�����A�T���X���ł������Ȃ���قƂ��đ����Ă����ׂ������Ǝv���܂��B
645�T�C�Y�ł̐����o�ׂ��\�ɂȂ����Ƃ������Ǝ��̂ɋ����������܂��B
���܂ł̃T�C�Y�ł͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂ̕����܂藦���Ǝv���܂����A���i�Ƃ��ďo�o����i�K�ɂ܂Ő������x�����܂��Ă������ɒ��ڂł��B
���i���\�Ƃ͕ʂ̃x�N�g���ł̘b���ł����B
���ڎB���f�q�ɂ���ϋ������Ђ���܂��B
�ǂ̂悤�ȃ��m��ς�ł��邩�H�@�@�����ÁX�ł��B
�����ԍ��F11041677
![]() 4�_
4�_
�Z���T�[�T�C�Y�͂��Ɛ����҂��Ȃ��Ƃ킩��܂���ˁB
�P�R�T�~���̃T�C�Y�̂P�D�V�{�Ɣ��\����Ă��܂����A�ʐςłP�D�V�{�Ȃ�R�_�b�N�Ȃǂ��甭������Ă��鏬�Ԃ�̃Z���T�[���Y�����܂��B����őΊp���łP�D�V�{�ƂȂ�ƂقڂU�S�T�̃t�B�����T�C�Y���Ǝw�E����Ă��܂��B���܂̂Ƃ���A���̍Ō�̐����͂ڂ����ꂽ�܂܂ł�����A�N�����ꂪ�������Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B
��{�I�ɒm���Ă���m�c�`�i�閧�ێ��_��j�Ō����܂��A�m�c�`������ł��Ȃ���Βm��܂���B
���ʂɍl����A�R�_�b�N�̎s��CCD���g�p����i����i�ł��g���Ă����j�ƍl���܂����珬�^�̑f�q�Ȃ�ł��傤�ˁB^_^;
�������A����Ȃ��Ƃ��킴�킴�ڂ������H�I�Ƃ����������ł��܂�����A�T�v���C�Y�Ńt�B�����U�S�T�ɋ߂��f�q�T�C�Y��������܂���B
�Ƃ������ƂŁA����̂��Ƃ��܂߂āA�܂��A�s���ł��B
������������l�͂��Ȃ��ł��傤�B
���T�̃��[���j���[�X�A��������PENTAX����̐������\��҂��܂��傤�B
�����ԍ��F11041966
![]() 7�_
7�_
�����Y���[�h�}�b�v������ƁA645�f�W�^���p�̐V�����Y�͑S��DFA�Ȃ̂�
�u���[�j�[645�T�C�Y�͊m�ۂ���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����l�I�ȍl���ł����A������645�t���T�C�Y�ׂ̈Ƃ�������
�≖645���[�U�[�ł��g���郌���Y�Ƃ����Ӗ�������������܂���ˁB
�����ԍ��F11041990
![]() 4�_
4�_
�≖��67�y���^�[������645����135���̃����Y���A�_�v�^�[�Ŏg�����悤��
645�f�W�^���J���������Ѓ����Y��135�������Y���g����悤�ɂ���
�t�H�}�b�g��645�f�W��35�t���T�C�Y�������Y�y�т��̎��̓s����
�ς�����Ɨǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F11042567
![]() 4�_
4�_
��ko-zo2����
�t�Ȃ̂ł́c�H
�U�V�͂U�V�̃����Y�����g���Ȃ��ł����
�t�����W�o�b�N���Ⴄ�̂ł�����܂��ł���
�U�S�T�c�Ȃ�k�u��p�łނ���ł���悤�ɂ͏o����ł��傤�����ʂɃR�X�g�����邾���Ȃ̂ł��Ȃ����Ǝv���܂��i�j
�����ԍ��F11042838
![]() 1�_
1�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
���U�V�͂U�V�̃����Y�����g���Ȃ��ł����
�����ł��ˁB
67��645�̃����Y���g���A�A�A�\���ǂ����m��܂���
��ʂ̎��ӂ��R����\���|��ł���ˁB
645�f�W�J����35�������Y�g�p�ŁA�j�R���̃t���T�C�Y�J������APS-C�̃����Y���g�����݂����Ɏ��ӂ��Â��Ȃ�ł��傤����ǂ��A
���ʓI�ɃN���b�v��35���t���T�C�Y���g���݂������Ɨǂ���ł����ˁB
645�ɂ�67�̃����Y�͎g���܂��B�≖�ł���Ă��܂����B
�����ԍ��F11044461
![]() 2�_
2�_
>645D�̃����Y���A��pDA?�����Y�d�l�ƂȂ�A�܂��܂��Ǝ��K�i���m
���Ƃ��ƃ}�E���g���Ǝ��K�i�ő��̃��[�J�Ŏg���Ȃ��̂�����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������ł��傤
�ʐϔ�Ō����t���T�C�Y��APS-C�̖�2.2�{�B
�t�H�[�T�C�Y��APS-C����1.7�{�̈Ⴂ�ɂȂ�܂��B
1.7�{�ł��\�����l�͂���ł��傤
�t����645�T�C�Y�łȂ��Ă��X�^�[�g�Ƃ��Ă͗ǂ���Ȃ����Ǝv���܂�
�}�C�N���t�H�[�T�C�Y�ɂ`�o�r-�b�A�t���T�C�Y�ƋK�i��������Ă錻��ł����璆�����K�i��������Ă��d���Ȃ��ł��傤�B
����ɃV�X�e���͊�����645�̂e�`�����Y���\���ɑΉ��o���邻���Ȃ̂ŕʂɃ[������\�z����킯�ł��Ȃ̂œ�����Ƃł͂Ȃ��ł��傤�B
�f�W�J���X�^�f�B���ɂƂ��Ă͒����͓���p�r�ƃ^�u���Č�����݂����ł��ˁB
����ɂǂ��݂Ă�645�͖����i�ł���B
�����ČR���⌤���p�r�Ȃǂł͂���܂����B
�X�^�f�B���̌��t�����A���݂����ȋɏ����̃��[�U�[���M�]�������ʁA�y���^�͂��̋ɏ����̃��[�U�[�̊�]�����ݎ����645���J�����Ă��ꂽ���[�U�[�v���̃��[�J�[�ƌ����܂��ˁB
���������炭�͔����܂��E�E�E�i��
�f�W�^����������肽���Ă��}�~����n�b�Z���ł͍������ďo���Ȃ��̂Ńy���^�b�N�X�Ɋ撣���Ă��炢�����ł��B
�����ԍ��F11045263
![]() 10�_
10�_
��ko-zo2����
���ӂ������邾���ł��ނȂ���Ȃ��̂ł�
�t�����W�o�b�N���Ⴄ�����{�I�ɃZ���T�[�̑傫���K�i�̃J�����ɃZ���T�[�̏������K�i�̃����Y��t����Ɩ��������łȂ�����߂��̕������B��Ȃ��Ȃ��ł���
�`�o�r�|���̏ꍇ�͂͂��߂���t���T�C�Y�̈ꕔ���g���~���O���Ă�K�i�Ȃ̂�
�t�����W�o�b�N�����ʂł�����Ȃ�̖����Ȃ��̂ł�
������U�V�ɂ͂U�V�̃����Y�������Ȃ���
�U�S�T�ɂ͂U�S�T�ƂU�V�̃����Y���g���邵
�R�T�����ɂ͂R�T�����ƂU�S�T�ƂU�V�̃����Y���g����̂ł�
�������͎B��Ȃ��Ă����̂Ȃ畨���I�ɂ���͓̂�����Ƃł͂Ȃ��ł��傤
�ނ���}�N����p�ɂ͂��������ł��ˁ�
��ɐڎʃ����O��t���Ă����Ԃł��i�j
�����ԍ��F11045683
![]() 0�_
0�_
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
������܂����B
�������芨�Ⴂ���Ă��܂����B
67�̃����Y��645�Ɏg�������甽���o���邩�[�Ǝv���Ă��܂����B
���݂܂���B
�������܂��ƁA�t����Ƃ���}�N����p�A���͓����ɉ��ރA�_�v�^�[����Ȃ���
�_���Ȗ�ł��ˁB
�K�����̏ꍇ��35���̃����Y��������67���������̂Ŋ��҂��Ă��܂��B
�{�f�B������Ȃɍ����Ȃ���Ηǂ��ł����ǂˁB
�o����Ή��݃A�_�v�^�[�Ńy���^�������Ǒ��Ђ�35�������Y���g����悤�ɂ��Ă����ƗL���ł��ˁB
�����ԍ��F11045798
![]() 0�_
0�_
���݃A�_�v�^�[���ƃ~���[��������̂łk�u��p�ɂȂ�܂���
���������R�T�����̃����Y�̊O�a���U�S�T�}�E���g�̓��a���傫���킯�Ȃ����i�j
����Ȃ�k�u��p�ŃZ���T�[���̂�O�ɓ������Ă��܂��ق����y�ł���
����ł����p���l�̏��Ȃ��M�~�b�N���R�X�g�����Ă킴�킴�t����Ƃ͎v���܂��c�i�j
�����ԍ��F11045836
![]() 0�_
0�_
�����������R�T�����̃����Y�̊O�a���U�S�T�}�E���g�̓��a���傫���킯�Ȃ����i�j
������Ȃ�k�u��p�ŃZ���T�[���̂�O�ɓ������Ă��܂��ق����y�ł���
������ł����p���l�̏��Ȃ��M�~�b�N���R�X�g�����Ă킴�킴�t����Ƃ͎v���܂��c�i�j
�Ȃ�قǁA�C���t���܂���ł����B
����ł��݊������m�ۂ��ė~�����ł��ˁB
�Ȃɂ��A�����̐��E�ł�����
�p�i��G1���o�ꂵ�Ă����Ƃ��̓V���b�N�ł�������
�k�u�������ǁA�F��ȃ����Y���g������Ă̂��A�A�A
�����ԍ��F11045908
![]() 0�_
0�_
�≖�⑼�Ђ̃J�����͕ʂɂ��āA645D�ƁA����DA�����Y�͓����y���^�̐��i�ł��̂ŁA�݊�����
�����ƍl�����Ă����͂��ł��B����645D�́AKAF2�i35�~���W���j�ɏ�����ł͂Ǝv���܂��B
�≖�͉ߋ��̂��Ƃł�����A�≖�����Y���g���܂����A�t�͎g���Ȃ��Ƃ��Ă��債�����Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F11045928
![]() 0�_
0�_
�U�S�T�łȂ�ł������Y���g������Ă̂͂��Ȃ薳��������̂Łc�i�j
�l�I�ɂ͑S���V�����t���T�C�Y�̃~���[���X�@���o���Ƃ������낢�Ǝv���܂���
�y���^�b�N�X�����t���T�C�Y�Ƃ��Ă͈�Ԑ�������\�����������Ɏv����ł���ˁi�j
�����ԍ��F11045930
![]() 1�_
1�_
�� KAF2�i35�~���W���j
�d�C����̘b���ł��B�������Z��300�~���ł����Ȃ�g���܂��̂ŁA
���̃����h���ܗւ܂ő���a����AF�����Y������āA�\��ė~�����Ǝv���܂��B
�ܔN�O�̃R�_�b�NCCD�͂�����Ƃł����i�ʐ�1.7�{�A�L�p1.3�{�̂�H�j�B
�����ԍ��F11045958
![]() 0�_
0�_
���͂��ڂ낰�ł����ǁA�ꉞ�����T�C�Y�̂悤�ł���
35�̃t���T�C�Y�͎s��I�ɂ݂ăy���^�ł��邪�̂̋����͖����悤�Ɋ����܂��B
�t���T�C�Y��LV���Ė��͂���܂����A������đ��Ђ��l���Ă��Ȃ����ȁ`
����ƁA35�̃t���T�C�Y�ƒ����̊ԂɊ_�������Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ȋC�������ł��B
�ł�����A�≖�̒������͏�������35�̃t�����͑傫���t�H�}�b�g�ŁA�ǂ�����o����悤�Ȃ̂��ėǂ��ł���ˁB
�����̓}�~���Ƃ��n�b�Z���Ƃ��A�y���^�͎��ۂɂ͌㔭�ł�����
��s���ЂƎv�����ĈႤ���̂̕����ǂ��Ǝv���܂����ǂˁB
���x�݂Ȃ����B
�����ԍ��F11045991
![]() 1�_
1�_
��ko-zo2����
�U�S�T�Ƃ͑S���ʂł��Ă��Ƃł����ǂ�
�U�S�T���~���[���X�ŏo���Ȃ�R�T���������Y�͊��S�Ɏg���܂����ǂ��c
�U�S�T�}�E���g�ŊԈႢ�Ȃ��̂Ń~���[�͂��邵
�ނ���k�u�e�͂܂��܂����_������̂ō̗p���Ăق����Ȃ��킯�ł���
�y���^�b�N�X�̖��͂��ăI�[���h�����Y�ŗV��Ŋy�������ėv�f�����������Ǝv����ł����
���ł͂��̕���͂��S�^�R�ɒD���Ă��܂����킯�ł����c
���̕�����ĂђD�҂��ׂ��t���T�C�Y�~���[���X�͖ʔ����I���ł�
�ߋ����猻�݂܂ł̃��C�J�ŃJ�����̂��ׂẴ����Y�Ŗ��������łāA���{���̃����Y�̉�p�ŎB���킯�ł������
���܂��烌���Y�̖R�����j�}�E���g�Ńt���T�C�Y�o�������ʔ����Ǝv���܂�
�j�}�E���g�̃t���T�C�Y���ƂU�S�T�c�̎s��Ƃ��Ԃ�܂�����
�d�|�o�P�̐����ł킩��悤�ɍŏ��̃����Y�͏����ł��Ȃ�Ƃ��Ȃ肻���ł����
���Ђ͂܂����Ȃ��Ǝv���܂���
�P��t�̃t���T�C�Y�������Ă��܂��Ă��܂�����
���Ȃ��Ƃ��m�C�b�Ɋւ��Ă͂����ł��������������Ă����ł����ˁi�j
�r�͂`�o�r�|�b�Ŕ��\���Ă��܂��܂�����
�����ԍ��F11046188
![]() 1�_
1�_
���ЂƂ̋����̖��ł���Ȃ�A���݂܂ŁA���̑��������Ȃ���o�c���Ă������ƂɂȂ�܂��ˁB
������狣���ȂǂƂ������̂́A���R���ۂƓ����悤�ɓˑR�~���ĕ����Ă�����̂ł��B
����Ȃ��ƂɋC���g���āA�����̐��i�J���p���ł́A���ʂ������Ă܂���B
���ɁA����PENTAX HOYA �����i�Ƃ��ďo���Ă���f�W�J���A�S���i�����ЂƋ�������K�i���m�����ł���B
�����ŕ����Ă���l�X�ɌC��̔����鎞��́A�Ƃ����ɏI����Ă����ł���B
�������Ă���A�܂��܂��g����ł��낤�A���̌C�����Ђ̌C�ɗ����ւ�������B
���ꂱ�����A����ł��ˁB
645�c�A�����Ǝv���܂����A�ɏ����}�j�A���������̓Ƃ�悪��ɏI��点�Ȃ��悤�肤����ł��ˁB
�Â��t�B������������ɒz���グ���APENTAX �Ƃ������͂ȃu�����h�E�C���[�W�B
���̎��ォ��t�������Ă������[�U�[�̑����́A35mm�������Y���R���L���Ă���͂��ł��B
���̎��Y�I��Y��h�点�鐻�i�\�������̂Ɍh�����Ă���̂��H�H�H
�����ɋꂵ�݂܂��ˁB
�̂̃u�����h��������Ă���悤�Ȑ헪�ɂ́A����X���܂��ˁB
�f�W�J������Ƃ��āA�V��PENTAX�u�����h�X�ƃC���[�W�헪��������̂ɁE�E�E�E�B
�����ԍ��F11046249
![]() 6�_
6�_
�f�W�J���X�^�f�B����
�c�Ǝʐ^�ق̃j�[�Y��Y��Ă��܂��H
�t�B��������������Ă����A����Ă��郁�[�J�[�ɂƂ��ău���C�_����w�Z�W�A�ό��W�̃X�^�W�I���܂߂��c�Ǝʐ^�ق͎s��Ƃ��Ă͏������Ă��A�x�[�X�Ƃ��Ă͏\�����͂̂���s�ꂾ�Ǝv���܂�
�����ԍ��F11046349
![]() 6�_
6�_
�������j�b�`�̂悤�Ɍ�����Ƃ�����ƐS�O�Ȃ�ł����B^_^;
�t�B�����̒����J�������g�p���郆�[�U�͂��������Q��ނ��āA�ЂƂ͕��i�ʐ^���B�e����v���ƃZ�~�v���i�A�}�`���A�j�ł��B�����ЂƂ̓X�^�W�I�ŁA�g�߂ȂƂ���ł͊X�̎ʐ^�فA���̂ق��Ƀ��m�̎ʐ^���B��s��Ƃ������̂�����܂��B
�ɒ[�Șb�A�e�Ђ̃J�����J�^���O�̃J�����̎ʐ^�͎��͂��̃J�����ł͂Ȃ��A�����J�����ŎB�e����Ă���P�[�X������ƕ����Ă��܂����A���܁A����o�����̃y���̋{�肠��������̃C���[�W�ʐ^�ł����A�ǂ��݂Ă��y���ŎB�e���ꂽ�ʐ^�ł͂Ȃ��A�t�B�������e�Ȃ璆���ȏ�A�f�W�^�����e�Ȃ璆���̃f�W�o�b�N���g�p����Ă���悤�Ɍ����܂��B
�����Ă�����̃J�����̎s����A�B�e�ʂƂ����_�ł͌Q���Ă����ł��B
���̎s��̓����̓J�������g�������킯�ł��A�o�b���D���Ȃ킯�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A�ΏۂƂ���ʐ^��������ƎB��邱�Ƃ����Ȃ��Ƃł��B�ʐ^�̂��Ƃ��Ƃ����Ă��鑽�l�ȕ\�����g���邱�Ƃ��K�v�Ȃ킯�ŁA���̈Ӗ��łh�r�n�T�O���犴�x�̎n�܂钆���p�̑�^�f�q�̃j�[�Y������B
�܂��A���i�ʐ^�̐��E�́A�n�C�A�}�A�Z�~�v������v����Ƃ������ł���A����ȃX�g�b�N�ʐ^�������Ȃ���A�u���������ʐ^���~�����v�Ƃ����v�]�ɂ������Ă��镪��ł�����܂��B
����A�ʐ^�E�̗ǐS�̂悤�Ȏs��ł��ˁB
���������Ӗ��ŁA�ʐ^�Ƃ̎s��ł����āA�J�����}����J�D����f�W�J���}�j�A�̎s��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F11047212
![]() 18�_
18�_
�� �c�Ǝʐ^�ق̃j�[�Y��Y��Ă��܂��H
35�~���t���T�C�Y�@�ł�3000���`4000�������������ł���B����ł������܂Œʉߓ_�ł��B
�����������������Ă��悢��{�i�ʎY�ɓ���^�C�~���O�ő�Ôg�ɂ����̂��ň��ł��B
��Ôg�͌��ł����ė~�����ł��傤���B
�����ԍ��F11048069
![]() 1�_
1�_
�����̏Z�l����
�S�����̒ʂ�ł��ˁB�J�����G���Ȃǂɍڂ��Ă���v����n�C�A�}��
���i�ʐ^�̔����ȏ�̓y���^��645��6x7�ł��邱�Ƃ������B�܂��A
���ׂĂ̎G���T�[�x�C����Ȃ�ĕs�\�ł�����A���������ň�ۂ�
�q�ׂĂ��܂����A�����Ȃ��Ƃ��@��ʂł̓y���^��645���g�b�v�ł���
���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
���̎g����B�̉�������645D������܂��Ȃ��w������̂ł͂Ȃ���
���傤���B�����ĕ]�����ǂ�������c��̐l���������X�ɍw�����Ă����B
�y���^�͎s��Ŏg���Ă���645�̐���c�����Ă���͂��Ȃ̂ŁA�������
�}�[�P�b�e�B���O������Ĕ���鐔�̖ژ_���𗧂ĂĂ���͂��ł��B
���̌��ʁA645D���o�����ƂɌ��߂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���BHOYA��
�z�����ꂽ�Ƃ��ɂ́A�����炭�����Ō���Ȍp���E���~�_������������
�Ⴂ�Ȃ��BHOYA�ɋz������Ă��炵�炭645D�̘b�肪�}�X�R�~��
���Ȃ������̂͂��̘_�����Ԃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�y�ϓI�Ȋ��҂Ƃ��ẮA35mm�t���T�C�Y�}�̐l�����̂����炩��
645D�ɏ�芷���ė~�����ł��傤���A�����_�ł͑S���������t���܂���B
���͒��B��ɂ̂߂荞��ł��܂����̂ŁA�ނ���K-7��4/3�Z���T�[��
�g�ݍ���ŁA���������Y�̏œ_������{�ɂ��ė~�����ȂƊ��҂��Ă���
�ϐl�ł��B1.4X��2X�̃R���o�[�^�[�ł�AF�������Ȃ����A�Â��Ȃ���
�}�j���A�����킹������Ȃ�܂�����B
�����ԍ��F11049049
![]() 4�_
4�_
>�c�Ǝʐ^��
���� �u���{�ʐ^�ً���v�̉�����͖�S�R�O�O�������A�Ɨ��o�c�̃X�^�W�I�Ȃǂ��܂߂�ΑS���ł��悻�Q�������͂���̂ł͂Ȃ����Ɛ�������Ă���
http://industry.fideli.com/industry/m/industry30_6_1.html
�����̓��A�ǂ̒��x����������̂��B
> ���i�ʐ^���B�e����v���ƃZ�~�v��
���� 2009�N�i1�`12���v�j�̃f�W�^���J�����̑��o���т� ���� �����Y���������t�^�C�v��991��695��
http://www.camera-info.net/cic_report/market_analysis106.html
�V�K�E���ւ��g�ɂǂ̒��x�w�������̂��B
�ȏ���l���������
�s��K�͈͂ꖜ��ɓ͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƁB
����ł́A�j�b�`�ȃ}�[�P�b�g�Ƃ���Ă��d���Ȃ������B
�Ƃ�����
�g���^ LFA����Y GTR�A�z���_ NSX�̂悤��
��ƃC���[�W�����[�h����Ŕ̂悤�ȋ@��ł͂Ȃ����ƁB
645D�� ����
�����ԍ��F11049620
![]() 0�_
0�_
> �����Y���������t�^�C�v��991��695��
�Ȃ�ł��ꏏ�ɂ���䐔�x�[�X�̃}�[�P�e�B���O�Ȃ炻���ł����A���̂����A�W������X���������炭�~���[���X�A�G���g���[�@�ŁA�������͍w������Ă���W���Y�[�������w�����Ȃ��w���قƂ�ǂł��傤�B
�}�X�ōl������}�[�P�e�B���O�͎��s���܂��B
�~���[���X�̑䐔�̑����͂قƂ�ǃv���@�̍w��������������Y�̔���グ�ɂ͂Ȃ���܂���B�������A���Ԃ͔��グ��䐔���}�[�P�e�B���O�̕]���ɂȂ���̂ŁA����₷������̋@��Ɏ��{���W�����Ă��܂��܂��B�������A����ł͐�X�ɂȂ���܂���ˁB
���B�b�c�P�O��ƃN���E���P��łǂ��炪���v���オ�邩�䑶���ł����H
�܂��Ă�A���Ӌ@��̒lj��w�����傫�Ȏ������ɂȂ���t�r�W�l�X�ň�ԑ�Ȃ̂͌��������Y�̔���グ�ł���B
�����ԍ��F11050351
![]() 12�_
12�_
PEN�̍L���ʐ^�̎B�e���i���o�Ă܂����ˁB(^.^)
http://www.digitalcamera.jp/html/HotNews/image/2010-03/04/PL1-085-L.jpg
�����̃f�W�o�b�N���ȁH
�����ԍ��F11052623
![]() 1�_
1�_
�f�q�̃T�C�Y��1.7�{�Ƃ����̂́A�ʐϔ�̈Ӗ��ɂƂ�̂����R�ł��ˁB
�ʂɂ������ڂ������R�������b�g������܂��A�����̔�Ƃ�����߂�
PENTAX���z�肵�ĂȂ��Ǝv���܂��B
35�~���p�����Y�������Ƃ��ɂ��N���b�v�@�\�Ŏg�������Ǝv���ꍇ�A
�ʐϔ䂪�傫������ƁA�t�@�C���_���̖��Ƃ�����܂����A
1.7�{���炢�́A�܂��A���������Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂��B
�����͒��B��ɂ̂߂荞��ł��܂����̂ŁA�ނ���K-7��4/3�Z���T�[��
�g�ݍ���ŁA���������Y�̏œ_������{�ɂ��ė~����
�Ȃ�Ȃ��ł��ˁB
���������Y������ȏ�A�f�q�����������郁���b�g�̓R���p�N�g�������ł��B
�����ԍ��F11056994
![]() 0�_
0�_
4000����f�ł����Ăˁ`�B
�t�F�C�Y��P40�{�ł�������?�A���Ɠ������̂ł��傤��?
�����100���ȉ��������琦�����������ȋC���c
�Ƃ肠�������i�Ȃ̉掿�Ɍ����Č�����1Ds�W�ɂ͈�������?
���Ƃ͏����I�ɐ������邩�A�挊���@��ɏI��邩�A�ł��ˁB
�����ԍ��F11057025
![]() 1�_
1�_
��gintaro����
�Ƃ肠�����R�T�����̃����Y�͂܂��t���Ȃ��ł��傤�c
����Ȗ��ʂɃR�X�g�̂����邱�Ƃ�����Ƃ͂ƂĂ��v���܂���i�j
���킳�ł̓t�F�C�Y�����̂o�S�T�{�Ɠ����b�b�c�ƂȂ��Ă����̂ł����c
����Ȃ�q�`�v�Ńt�@�C���T�C�Y���S�S�l�ɂ����Ȃ�Ȃ���ł����
������������͂R�X�O�O����f�ł���
������g���ĂP�O�O���~��̂͂Ƃ��Ă��s�\�Ƃ����v���܂���
���S�ɐV�^�̃Z���T�[�ŏo���Ă���\����
�{�C�ŃT���X�����H�i�j
�����ԍ��F11057115
![]() 1�_
1�_
> �{�C�ŃT���X�����H�i�j
���A��N��PIE�ŁA�T���X���́H�ƕ����āA�u���܂����v�Ƃ�����ق��̉����������ł����ǁB�B�B^_^;
�ǂ��ł��傤�ˁB����@��KAF39000�ʼn��i�����߂�������Ȃ������ł��������H
�����ԍ��F11057402
![]() 0�_
0�_
���i�ʂ�NG�������̂�KAF31600�ƂЂƂ܂�艺��CCD�ł����ˁB
KAF�V���[�Y�̉�͂Ȃ����ȁH
�����ԍ��F11057504
![]() 0�_
0�_
�����̏Z�l����
�ӊO�ɏ��̏Z�l����̗\�z���������ăt�W�Ƒg�ނ����ł����
�f�W�^���ɂȂ��ăR�_�b�N�Ƃ̗��ꂪ�t�]���������ł�����c
�����s��ŕ������ׂ��G�|�b�N���C�L���O�Ȏ����������Ă��邩����
�����ԍ��F11058212
![]() 1�_
1�_
�t�W�������̓t�B�������[�U�̍Ō�̉��ł�������˂��B���������Ӗ��ł́APENTAX���t�W�����Q�W�͈�v�����ł��ˁB
���т̂Ȃ��T���X����APS-C�Z���T�[�̂����ς��̊�Ƃɂ����Z�p�I�ȃp�[�g�i�[�V�b�v�͏ؖ��ς݂ł�����A�r�W�l�X�A���C�A���X�̃p�[�g�i�[�Ƃ��Ă̑f���͏\�����Ǝv���܂��B
���������f�W�^����Ώۂɂ��ăr�W�l�X�v������Ƃ���ƁA�Z�~�v����ΏۂɁA��ΓI�D�ʂȎs�ꉿ�i�̒����f�W�^����̔����āA�t�����郌���Y�r�W�l�X��A�E�g�v�b�g�r�W�l�X�Ȃǂ̃T�[�r�X�r�W�l�X�Ŗׂ���A���C�A���X�̃r�W�l�X�v���������܂��ˁB��������A���\�傫�Ȏs�ꂪ�ł��܂��B�������A�قړƐ�ŁB
�����I�ɂ͑傫�ȃZ���T�[�T�C�Y�������b�g�ɂ��āA1����f���炢�܂ʼn�f���A�b�v����ƃt���T�C�Y�e�Ђ͂��Ă����Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F11058369
![]() 3�_
3�_
�����̏Z�l����
�ł��˂���
�ق��̒����J�����̃u�����h�͂��ׂăR�_�b�N�ɍs���Ă��܂������c
�t�W���������郉�X�g�`�����X�Ƃ��Ďc�����u�����h���y���^�b�N�X�ł������
����������t�W�͏I��肩������܂���i�j
�܂��j�R���̂l�w���o����Ă��킳������܂����ǂ�
�Ƃ肠�����\���Ƃ��Ă̓t�W����ԍ������ȁH
�����ԍ��F11058517
![]() 1�_
1�_
���ۂ̃T�C�Y���ł܂����ˁB
�Ȃ�ƂȂ��A�I�������炷��ƁAKAF40000�ł����˂��B�B�B
���C�J�̌Z�킩�ȁH
���[��A���������Ȃ��B�B�B^_^;
�����ԍ��F11061401
![]() 2�_
2�_
�z�[���y�[�W�����J����Ă܂��ˁB
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/medium/645d/feature.html
���i�̓`�����v��845,800�~
�����ԍ��F11064189
![]() 1�_
1�_
���ٓI�ȉ��i�ݒ�ł��Ȃ�����
�j�`�e�S�O�O�O�O�łȂ�ł��̒l�i�ɂł����H
�������Ƃ���ˁ�
�L�^�����͂��łɂW�O�����Ă���Ă��Ƃł���
�P�c���R��c�R�w�̏o�n�߂������ł������!!!
�Ƃ肠�����t���T�C�Y�ɗ��ꂽ���i�ʐ^�B��̕��X�݂͂Ȗ߂��Ă������ł��ˁ�
���E��k�������܂�����
�����ԍ��F11064476
![]() 2�_
2�_
�����̓y���^����Ɋ撣���ė~�����ł����A���ꂶ�ጵ�����ł��ˁB
35�~�����ɏ��ĂȂ��Ǝv���܂�����i������ɉ�f������ł����j�B
�V����DFA645��55/2.8�����Y�́A35�~�������Z�i1/1.3�{�j42/2.2�����ɂȂ�܂��B
���ꂶ�ኴ�x�掿���A�{�P��35�~�����ɕ�����d�l�ɂȂ�܂��B
�܂�LPF�Ȃ��̂́A�����Y�̉𑜂��Ⴂ�i���E�j�Ǝ咣���Ă�̂ł͂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11067338
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > �y���^�b�N�X > PENTAX K-7 �{�f�B
�{���̌ߌォ�疾���ɂ����āA�b�o�{�ɓW������鐻�i�̔��\���s����̂ł��傤���A�{�������狰�낵�����炢�ɐÂ܂�Ԃ��Ă��܂��B
�f�W�J��Watch�����B�B�B
http://dc.watch.impress.co.jp/
���܂�̐Â����ɐh���ł����ɏo�Ă��Ă��܂��܂����B^_^;
![]() 11�_
11�_
����������ƁA�����\���\�����Ă��܂����B
�����ԍ��F11053163
![]() 5�_
5�_
���Z����̓N�`�R�~�ˑ��ǁH
�����̓~�j�X�J�|���X�B�e��̂��ƂŃe���V�������オ��܂��蔭�����O�I
���낦��I�[�����T���U�炵�Ă���܂��B
�����ԍ��F11053226
![]() 13�_
13�_
> ���Z����̓N�`�R�~�ˑ��ǁH
���[��B�ǁ[�ł���H
�����f�W�^�����C���X�Ȃ��ǁA������Ȃ��āB�B�B
���O���͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B^_^;
�����ԍ��F11053326
![]() 7�_
7�_
�������낢�BHOYA�̊��������肶��オ���Ă����肵�āB�B�B(^.^)
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=7741.t
100���~�̒����f�W�^���ŁA�h���Ɖ��������肵�āB^_^;
�����ԍ��F11053446
![]() 7�_
7�_
���{�{���쏊�A�j�R��G�E�y���^�b�N�X�E�\�j�[�p�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�A�_�v�^�[
�Ƃ��j���[�X���o�܂����ˁB
CP+�y���^�̃Z�~�i�[��g�[�N�V���[�̃X�P�W���[�����}�_�ł��ˁ\�B
����Ȃɒ������ނ���������ł��傤���H
�����ԍ��F11053492
![]() 2�_
2�_
�����ɋg���a�q�J�����}�����o��Ƃ��{�l�������Ă��܂��B
�����炭�A�V���i�̔��\�҂��Ƃ����Ƃ��낾�Ǝv���܂����AIR�|���V�[�ɂ�����悤�ȃj���[�X����15���i�s��I���j�ȍ~�ɔ��\�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F11053528
![]() 5�_
5�_
���������AThis is Tanaka�̓c���J�����}����1������f�i�ςł��ˁB1����f�I�j�̉\���ɂ��ĂԂ₢�Ă��܂����ˁB
��͂�A������5000����f�ł������Ă���̂��H
�����ԍ��F11053657
![]() 5�_
5�_
�����F1������f������1����f�������B�B�B^_^;
���Ă�Ȃ��B�B�B
�����ԍ��F11053824
![]() 6�_
6�_
����ɂ��́B
CP�{�ɍs�������́A645D�̊O�ώʐ^�⊴�z�����肢���܂��B�@m(__)m
�����ԍ��F11054050
![]() 3�_
3�_
�y���^���烁�[�����܂�����
�@�L����4000����f�̒�����f�Z���T�[���̗p�B
�@�B���ʐςɗ]�T�̂����^�Z���T�[�́A
�@������f�Ȃ����f�s�b�`�ɗ]�T�����邽�߁A
�@��ʑ̗̂��̊������łȂ���C�������\�������܂��B
���ɂ�����������܂����ł��B
�����Ă��l�͔����܂��ǂˁi�O�O�G�j
����ł����������Ă݂����ł��B
�����ԍ��F11054616
![]() 4�_
4�_
�����}�K�ł́A�Ō�H�܂ŏ�o���i�j�B
�������T�v���C�Y�����ˁA�y���^�b�N�X����I
�𑜓x�͂������Ȃ����ǁA��ʑ̗̂��̊��Ƃ���C���Ƃ���������ɂ́A
�_�C�i�~�b�N�����W�⍂���x�ϐ������҂��Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F11054810
![]() 2�_
2�_
���̏Z�l����A�����́B
���ɂƂ��Ē����f�W�^���͕ʐ��E�̂��b�ŁA���܂ň�X���[���Ă��܂������A
���̏Z�l����̉����Ղ�ɗU���ďo�Ă��܂����B
K-7�̂Ƃ��͎������܂������A���̏Z�l������قǂ̒����f�W�^���ɂ��傢�Ƌ������o�Ă����Ƃ���ł��B
���Ȃ�ȑO�A30���~���ڕW�ɊJ���I�Ȃ�ď����ɋ����Ƃ�����܂����A
�������ɖ����ł��傤�ˁB
�����ꂻ��Ȃ��ƂɂȂ����玄�����܂��i�j
�����ԍ��F11055410
![]() 9�_
9�_
���̂��A���O�̍X�V���S�O�O�O����f�Ȃ�ł����ǁB�B�B(T_T)
�����܂ʼn䖝�����I���Ă��Ƃł��傤���H
�����那�B�B�B
�����ԍ��F11055626
![]() 2�_
2�_
ROM�Ȑl�Ԃł����A���ĂłĂ����Ⴂ�܂����B
K10D������ɖڂ��߁AK20D�AK-7�Ǝg���A���̂���
�b�Ђ̂V�c�ɕ��C���Ă݂����̂̂�͂�y���^�b�N�X��
�D���Ȏ����ɋC�Â��Ă܂��j-7���u�Ȏ��ł����A
���x�͖��m�̗̈�̂U�S�T�c�ɋ����ÁX�ł��B
���o�����[���U���Ɋח����O�ł��̂ŁA�l�i����ł�
�������������ȏ�Ԃł��B�S�O���ŏo���ꂿ�������
�����\��ɑ����Ă����ł��ˁB�܂��Ȃ��ł��傤���ǂ��B
�܂��������ǂ�����������Ȃ��ɂ��ւ�炸������
�����Y�����ɂ��邩�ŔY��ł���܂��B
�I�z�[�c�N���ɏZ��ł���܂��̂ŁA�����Ŗ��N�s��
�m���ɂ�������ǂ�ȂɍK�����Ɩϑz���Ă܂��i�j�B
�ق�Ƃ����炷���c�B
�����ԍ��F11055673
![]() 5�_
5�_
�R�O���~�䂾������E�E�E�A�������B
�ł��A�����Y�Ȃ��ł���ˁ`�B�����s���z�[���ōs���܂����H��
�����ԍ��F11055685
![]() 4�_
4�_
�c���搶���c�C�b�^�[��645D�H�ɂ��āA���������Ԃ₢�Ă܂��ˁB
�y���^�т����̐l�Ȃ̂ŁA���ʂɖJ�߂Ă�̂͂��ĂɂȂ�Ȃ����ǁi�j�B
���Ɛ����y���߂܂����A����͏��Ǘ����������Ƃ��Ă܂��ˁB
�����ԍ��F11055785
![]() 1�_
1�_
4000����f�ƌ������́A�Z���T�[��P40+�Ƃ������Ƃł��傤���H
���̃Z���T�[���g���Ă��鑼�А��i��200���~�I�[�o�[�ł�����
100���~�ȉ��Ŕ������ꂽ��A���ꂾ���ŃT�v���C�Y�ł��ˁB
�c���搶���c�C�b�^�[�Ő�^���Ă܂��ˁB
���������J�^���O�͂��낻��͂��̂ł��傤���H
�����ԍ��F11055811
![]() 3�_
3�_
K-7����14���~�E�E1450����f/14���~������ꖜ�~��103����f�̒l�i�ł�����
4000����f�^103����f����39���~�Ƃł܂����B
PAENTAX�ɂ͊���Z�Ɗ|���Z�����o���Ȃ��l����ƐM���܂��傤�I
�����ԍ��F11055820
![]() 6�_
6�_
�ǂ��ŗ\�邩���l���Ă����˂����܂���ˁB
�܂��������ǂ��������߂Ă��Ȃ��̂Ɂi�j�B�J�[�h
�����Ȃ���`�ł��̂ŎD����p�ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂ł���
�Ɠd�X�Ζ��Ȃ̂ŐE��̎d������T�[�`���Ĕ������A�L�^������
�������c�Y�ށB�y�����̂��h���̂��A�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����i�j
�^�X�P�e�N�_�T�C
�����ԍ��F11056011
![]() 4�_
4�_
���₢��A�R�_�b�N����KAF40000�Ƃ���CCD����N���ɂЂ�����ƃ����[�X�����炵���ł��B
�T�C�Y�̓t���T�C�Y�̂Q�{�Ƃ��B�B�B
�ł��A�܂��͉��i�Ȃ�ł���B(T_T)
�Ԃ₫�A���ɃC�R�B�B�B��|��|��
�����ԍ��F11056187
![]() 4�_
4�_
����Ɏg���Ă���CCD����S�O�O�O����f�B
http://fujifilm.jp/personal/filmcamera/mediumformat/dbp/feature.html
���[�ށB�Ȃɂ��킩���B
���̗l�q����A�ؗj�������ɔ��\�ł��ˁB^_^;
�����ԍ��F11056510
![]() 3�_
3�_
��������f�Ȃ����f�s�b�`�ɗ]�T�����邽��
�t���T�C�Y�Z���T�[�ʼn�f�s�b�`�ɗ]�T������ƌ����Ȃ�
2400����f�̖ʐϔ�1.7�{����2400×1.7��4080����f
�ƂȂ�A�u��f�s�b�`�ɗ]�T������v�Ƃ͂����Ȃ��̂ŁA
�Ίp��1.7�{�̎B���f�q�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
�f�[�^��100�l�Ƃ������Ƃ�����ʐϔ�1.7�{�łȂ����Ƃ�
���炩�ł́H�i�������[�ƃp�\�R���̕��S�傫�����i�j�j
�����ԍ��F11056550
![]() 2�_
2�_
���l�`�x���o�`�o�`����
�m���ɂ����Ȃ�܂����
�Ίp���̒����̔�łP�D�V�{���ƂقڂU�S�T�t���T�C�Y�ƂȂ�Ƃ�ł��Ȃ����ɂȂ�܂���
���ꂪ�P�O�O�����Ȃ��ƂȂ�Ɛ��E�����k���܂��i�j
�����ǂ��������Ƃ���ƃZ���T�[�͂ǂ����Ȃ낤���H
�ӊO�ɃT���X���������肵�āH
�܂��A�����ƂS�O�O�O����f�ł��t���T�C�Y�ƕς��Ȃ��s�b�`�Ȃ�ƌ�������������
���ʂɖʐϔ�łP�D�V�{���Ă����Ȃ낯�ǂˁc
�����ԍ��F11056667
![]() 1�_
1�_
�R�O���ȉ��͗��ɂǂ����Ǝv���B
����ɋ߂����l�Șb���Ђ������Ă̓o��ɂȂ�l�ȋC�����܂��B
�v�͂�����u�t���T�C�Y�v�ƃ^����l�ȋ��z�ŁB
�����łȂ���A���X���̃}�[�P�e�B���O�ŁA����HP�A�����}�K�Ȃ�Ė����b���Ǝv���Ă��܂��B
�u�����鎖���\�ȋ��z�v�@���Ǝv���܂����A���̎��͐S�ꍢ��܂��ˁB�͂͂́B
�����ԍ��F11057093
![]() 7�_
7�_
�F����A������Ɨ�ÂɂȂ�܂��傤�I('-^*)/
���AD3X�̒l�i������Ĉ��l����65���~�ł���5�ʂ̗ʔ̓X�ł�78���~�ł��B
��������1�N�ȏソ���Ă�35mm�̃J����������ŁA4000����f�̃f�W�^���p�b�N��200���~����Ȃ��A�V������4000����f�̒��ՃJ������30���~�Ƃ��L�蓾�Ȃ��ł��B
K7��p�@��3���~����X�^�[�g�ƌ����Ă�悤�ȃ��m���Ǝv���܂��B
�����܂�1�����N����3200����f�ł͂Ȃ����ƌ����Ă����̂��A�\�z�O��4000����f���悹�Ă����̂ł�����100���~������\���T�v���C�ł��I
���̒��Ճ��[�J�[�͐�X���X���Ǝv���܂���B
K20D�̎���K7�̎����A���\���O�Ɉُ�Ȃ܂łɖϑz���c��݁A�W���J������K�b�J�������`�݂����Ȋ����Ńg�[���_�E�����闬�ꂪ�ڗ����܂����B
�����͈��ÂɁA�T���߂��炢�̗\�z�ɂ��Ă����āA���\���ꂽ��A�v�������萷��グ�܂��傤(�E�ցE)/
�����ԍ��F11057252
![]() 12�_
12�_
�ꎞ���f����645D�i���́j����@���R�_�b�N��KAF39000��ς��100���~���Ȃ��Ɠڍ������ߋ�������܂��B
�����100���~�����Ƃ�����ŊJ���ĊJ�n�����J�����ł�����A4000����f�ʼn�R���̉��i�ɒ��ڂ��W�܂�܂��ˁB
�Ƃ������ƂŁA100���~����Ă��T�v���C�Y�ł����ł��Ȃ��ł��B100���~���ƌ����ĊJ�����n�߂Ă܂�����B^_^;�iCF����Ȃ���SD�_�u�������j
> K7��p�@��3���~����X�^�[�g�ƌ����Ă�悤�ȃ��m���Ǝv���܂��B
���������A7D��14���~�̎���ł����玟��K-7��p��13���~�ł���킯���Ȃ��ł��傤�B���l��10���~���邩����Ȃ��Ƃ܂����ł���B3���~�͂Ȃ��ł���9���~�A8���~�Ƃ����l�t���͏\���ɂ���Ǝv���܂���B�L���m����2��D���s���`�ł��ˁB(^.^)
�܂��A���̑O�Ɏ��엦100���̋����O����13���~�ŏo����K-7���d�|���Ă����ł����ǂˁB
�����ԍ��F11057397
![]() 4�_
4�_
NG����������@��KAF31600�ƂЂƂ܂�艺��CCD�ł����ˁB
�����A�R�_�b�N��KAF�V���[�YCCD�ł͂Ȃ������H
�����ԍ��F11057510
![]() 2�_
2�_
�O�����̒����f�W�^���̉��i�̓{�b�^�N���ł��傤�B
���{���[�J�[�͍����\��ቿ�i�ŊJ������̂����ӂȂ͂��Ȃ̂Ŋ��҂������ł��B
PS3�̂悤�ɃZ��CPU���ڂł��ቿ�i�Ŕ̔��ł���̂ł�����A�������������Ǝv�������c�B
�{�f�B�̔̔����i�͈������ǁA���N�X�V�������K�v�Ƃ��c�B
�����ԍ��F11057693
![]() 1�_
1�_
���[���j���[�X�̏��͕ς��܂������A�\���̉摜�͖��邭�Ȃ�܂���ˁB
�o���ɂ��݂��H�@^_^;
�ł��AMamiya�͓��{�̉�Ђ������肵�āB�B�B
�������W���Y�[�������Ƃ����ȁB�����łɉ��Ă��邩���B
�����ԍ��F11057727
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́B
���\���̉摜�͖��邭�Ȃ�܂���ˁB
�r�~���[�ɏ����������邭�Ȃ����悤�ȁc�B
�O���b�v���������Ɍ�����悤�ȁc�B�O���b�v�Ƀ����R�������������H
���炵�܂��ˁI
�����ԍ��F11057753
![]() 1�_
1�_
�Ȃɂ��A���̂悤�Ȃ̂́A���̏Z�l����̏������݂̂悤��(��)
�ܔN���҂�����āA���҂���̂́A����܂������������܂��傤�B
���������A�t���T�C�Y���t�Ƃ́A�@���͂������\���Ⴄ�̂������ׂ邾�����B
��X���X�Ƃ��Ă���̂́A���C�J��}�~���A�n�b�Z���ł��傤�ˁB
�����̂́A�L�^�[�ȍ~�ŏ\���B������ʃ��[�U�[�ɂƂ��ẮAK-7��p�@���t���T�C�Y���t���A���ނ��ق�����肩������܂���B
�����ԍ��F11057760
![]() 4�_
4�_
����Ă݂�Ɓc
�O�����ꉞ���邭�Ȃ��Ă�݂����ł��ˁi�j
�Z���T�[�̓R�_�b�N�̉�������ׂ��ǂ����Ƌ����J�������Ƃ��H
�����̃Z���T�[���ЂƂT�O���ō���Ȃ���ٓI�ł����
��͂�T���X���H
����Ƃ��t�W�H
�����ԍ��F11058104
![]() 1�_
1�_
�U�S�T�̔��\�y���݂ł��ˁI
����ɁA�F����̐���オ����y�����ǂ܂��Ă��������Ă��܂��B
�b�l�n�r�͉��i����̓T���X�����ȂƂ��v���܂����A�ł����
�x�m�����肪������ċ������Ă��������̂ł����B
�i�x�m�̐F���D���Ȃ��̂ŁB�j
�b�͂����̂ł����A���ɂ��V�^�̔��\�����郁�[�J�̃X��
��������オ�肪�A������ꂸ�₵���ȂƎv���܂��B
�F�X�ȃ��[�J���A�����J�������o���Ă���āA��������
���̃J�������鋋���������āA�����v���o���c����
�悤�ɂȂ�����̂ł����E�E�E
�����ԍ��F11058895
![]() 6�_
6�_
> ���������A�t���T�C�Y���t�Ƃ́A�@���͂������\���Ⴄ�̂������ׂ邾�����B
���������������Ă����܂��ˁB
PENTAX�̃t�B����645��F5�AEOS1�N���X�Ɠ����̑傫���A�d���ŁA�������悢���߂Ƀt�B�[���h�J�����Ƃ��ĕ��i�ʐ^�Ƃ̎x�������������Ƃ����A�R�����g���Ă����܂��B
�������͑傫���悤�ł����A���ۂɎ��Ǝv���̂ق��A�R���p�N�g�Ńo�����X��������ł���B(^.^)
�����ԍ��F11059213
![]() 11�_
11�_
���̎����A�E�E�E�E�B
�{���̃t���b�O�V�b�v�E���f���@�ƂȂ��Ă��炢�������̂ł��ˁB
�c���́A�掿�ቺ�̏��Ȃ����k�Z�p�B
�f�W�^���S���A����A�f�W�^�����ゾ���炱���A���̕ӂɍS���Ă݂Ă��ʔ����B
�ςȏ��Ł@�P�`���Ă����肵����ʖڂł���B
�ł��APENTAX HOYA ������ȁ`���A�E�E�E�E�B�@����܂���ˁB
�����ԍ��F11059649
![]() 1�_
1�_
>�ςȏ��Ł@�P�`���Ă����肵����ʖڂł���B
�������Ă�̂́B�B�B
���@�ȁ@��
�����ԍ��F11060501
![]() 19�_
19�_
> ���������A�t���T�C�Y���t�Ƃ́A�@���͂������\���Ⴄ�̂�����
��ׂ邾�����B
���������v���܂��ȁB�J�����̓{�f�B�[�Ƀ����Y��t���Ĉꏏ�Ɏg����
������A�{�f�B�[�����̑傫���E�d�������ł͌��߂��Ȃ��B�Ƃ���
���]���𑽗p����X�|�[�c�֘A�ł́B
���̑傫���ďd���~���[�ł͕b10�R�}�͌����I�ɂ͕s�\�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F11061206
![]() 1�_
1�_
���������Ζ{���̃t���b�O�V�b�v�E���f���ƂȂ邱�Ƃ͋^���̖������B
�@
�掿�ቺ�̏��Ȃ����k�Z�p�Ȃǂǒ����f�W�^���̘b�Ƃ͒��ڊW�̖����b�������o����
�P�`���Ă�Ƃ��Ӗ��s���Ȏ��������Ă邨�������
�P�`���Ă�ȑO�ɒ����f�W�^���Ƃ͖����Ȃ���o�Ă��Ȃ��ėǂ��ł��傤�B
���x���xPENTAX�̐V���i�̃l�^��l�K�e�B�u�Șb��̂Ƃ���ɂ����o�Ă���
�������ƂɈꐶ�����ł����A�����ŋ��Ȃ�Ȃ��̂��ˁB
�S�������Đl�ԂƂ��Ēp���������B
�����ԍ��F11061314
![]() 9�_
9�_
> ���̑傫���ďd���~���[�ł͕b10�R�}�͌����I�ɂ͕s�\�ł��傤��
���܂�ɂ����������̂Ŕ������܂����B
�����Œ��]����t���ăX�|�[�c�ʐ^���B��l�͂��܂���ˁB�@(^�B^)
�ł��A�P���̕��i�ʐ^���B��̂ɕb�P�O�R�}�͕K�v�Ȃ��ł��傤�B
�b�P�R�}������Ώ\���B
���̂P�R�}�̂��߂ɉ������A�����Ԃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͉��N���������ł�����B�@�i*^_^*�j
�����ԍ��F11061366
![]() 11�_
11�_
44×33mm�̑�^CCD�Z���T�[�ƕ��������_�ŕ����������l���Ă��܂��B
�R�����łȂ�Ƃ������邩�H
�����v��𗧂Ăė����b�オ����Ƃ������̂ł��B
���Ȃ݂Ɂu44×33mm�v�Ƃ������Ƃ͑Ίp����55mm�ł���ˁH
�i�O�|�O�j
�����ԍ��F11061472
![]() 4�_
4�_
�@���̏Z�l����F
�@���͌��݁AKAF-39000��P45+���g�p���Ă��܂��B
�@Penta645D��100�����Ƃ������Ƃɂ͎����^��������܂��B���������킹�����̂悤�ɍ�����\���ꂽ�AMamiya DM40��Leaf�`�b�v��40MP�o�b�N���g�p����$21,990�i��200���j�B����ŎႵ�APenta��Kodak KAF-40000���ڂ���100�����A���̍�100���͉����ɂ���́H�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@http://www.dpreview.com/news/1003/10030801mamiyadm40.asp
�@�ł���X���X�Ƃ��Ă���̂͊C�O�f�W�o�b�N�̓��{���K�A���㗝�X�ł��傤�B
�@�܁A���������Ĕ��\��҂������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11061682
![]() 1�_
1�_
�F����A�����́B
��A�̃A�I���̐l�B���������g�������Ƃ������̂����܂�ɂ��C�^���A���Ă��Ă����炪�p���������Ȃ��Ă��܂��B
���̂U�S�T�֘A�̃X���́A���g�}�X�������̂悤�ł��ˁB
�Ƃ���ŁA�S�S×�R�R�����ƂȂ�ƁA�\�̃X�[�p�[���C�h�Y�[���́A�Q�T�|�S�T�ʂł��傤���H
�l�i���ƂĂ��C�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F11061799
![]() 5�_
5�_
��͂�P�O�O�����ɂ͐V�����b�b�c����Ȃ��Ɩ������Ǝv���̂����c
�ǂ����Ȃ�ł��傤�ˁH
�����ԍ��F11061838
![]() 0�_
0�_
���������`�o�r�|�b��t���T�C�Y����̃X�e�b�v�A�b�v���v��_���Ȃ�����̑�^�b�b�c�ł͍����x���シ���ł����c
�V�J���̂T�c�Q�Ȃ݂ɍ����x�������b�b�c���̗p���ꂽ����ٓI�ł��ˁi�j
����Ȃ獡�܂ł̒����f�W�Ƃ͂܂������Ⴄ���v�����肻���ł���
�����ԍ��F11061932
![]() 0�_
0�_
�˂��AKAF31600�ł��\�Z�I�[�o�Ȃ̂ɁA�ǂ�����Č�������������ł��傤�H
���ꂱ���A��̃R�_�b�N���T���X���̃N���X���C�Z���X�ŃT���X���������H
CCD�͊������i����Ȃ��Ƃ����������肤�邩�H
�������i���܂߂Č��J���Ă��ꂢ�I�@(T_T)
�����ԍ��F11062029
![]() 2�_
2�_
4000����f��CCD�ł��ꂾ���l�����o�����̂́A��͂胍�[�p�X�t�B���^�[���O���Ă�����ł����ˁH
���Ƃ���ƁA���C�J���O���Ă�������s����Ɣ��f�����̂ł��傤�ˁB
���[�p�X�t�B���^�[�������ƃ��A�����o�₷���ƕ����܂����A�\�t�g�őΉ�����ڏ��������Ǝv���܂��B
�n�[�h�ő���Ȃ��������\�t�g�Ńt�H���[�o����̂̓f�W�^���J�����̃����b�g�ł��B
�n�[�h�̍X�V�T�C�N����35mm��肩�Ȃ蒷���Ȃ�ł��傤�������I�Ƀt�@�[���A�b�v���Ă��炢�����Ǝv���܂����A������̃t�@�[���A�b�v��@�\�����ɑΉ��o����l�Ƀ������⏈���\�͂ɗ]�T���������Ă����Ă��炢�����ł��B
���[�p�X�t�B���^�[�������Ƃ������́A�����ׂȊG���o���鎖�ɒ�������ł��傤���畗�i�B��ɂ͍œK�ł��傤�ˁB
�����x�����҂����������悤�ł����A���Ճ��[�U�[�̕��̓x���r�A50�Ƃ��g���Ă鎖���l����ƁA�������ɐU�鎖�͂܂������ł��傤�B
�����ԘI�����̃m�C�Y���X�̕����d�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F11062587
![]() 7�_
7�_
�L�^������645D�\��J�n�B
���l�i�́c�撣�����I
�����ԍ��F11063041
![]() 4�_
4�_
http://www.dpreview.com/news/1003/10031002pentax645d.asp
dpreview���܂�����B
�\�z���i85���~�ł��B
�����ԍ��F11063123
![]() 2�_
2�_
�\�z���i�ł͂Ȃ���suggested retail price = ��]�������i�ł����B
�����ԍ��F11063129
![]() 1�_
1�_
�L�^�����ł��B�t���C���O�ł��傤���B�\�Z�I�[�o�[�ł����B�B�B
http://shop.kitamura.jp/DispPg/002022003015?sg=310a
�����ԍ��F11063139
![]() 2�_
2�_
���o�ł����ˁB�B�B
�����ԍ��F11063143
![]() 1�_
1�_
http://www.pentax.jp/japan/news/2010/201008.html
�����̃j���[�X�����[�X�����܂����B
�����ԍ��F11063154
![]() 1�_
1�_
�Z���T�[�@�ꗱ�T�C�Y�@6.0 ��m x 6.0 ��m pixel size�@����A�����ł��ˁB
��{���\�̖ϑz���A�E�E�E�E�B
���̐��i���o�Ă�����APENTAX HOYA �ɂƂ��āAAPS-C�@�́A�ʎY�i�����ł��傤�ˁB�@�����ƁB
�܂��A�b�ԘA�˂����A��������Ƃ����~���[�E�A�b�v�B�@����d�v�ł���B
�~���[�E�A�b�v���Ă��A�������甼�����ł��m�F�\�ȃt�@�C���_�[�Ȃ�A�ʔ����B
�ȂǂƁA���@�\�̖ϑz������Ă��܂��@�킩���B
�����ԍ��F11063276
![]() 1�_
1�_
����������_1200������
�܁A�܂�85���~�Ƃ������Ƃ͑��Ђ̃��f�����l����ƁA�قځu�Z���T�[��v�����Ƃ���
�j�i�v���C�X�ł�����E�E�E�@30���E50���Ƃ����l�i�����ɖ����ł���B���܂�200��
�͓�����O�̒l�i�ł�������A10�N�O��D1�̂悤�Ȕj�i�v���C�X�i�ł��B
�����ԍ��F11063295
![]() 6�_
6�_
�B���f�q�@�@Kodak�А������\CCD�C���[�W�Z���T�[�@�ł��ˁB
�������A���[�p�X�t�B���^�[���X��CCD���j�b�g�B
����́@�����I�I�I
�{���̏��������Ă��܂����I�I�I
PENTAX �́@���N�̖��E�E�E�B
�����ԍ��F11063298
![]() 3�_
3�_
>�Z���T�[�@�ꗱ�T�C�Y�@6.0 ��m x 6.0 ��m pixel size�@����A�����ł��ˁB
K-m�Ƃ��܂�ς��Ȃ��Ǝv�����ǁB���ς�炸�s���{�P�ł��ˁB
�ʎY��O��Ƃ��Ȃ�APS-C�@����郁�[�J�[���Ȃ����낤���B
�h�o�h�H�����O����_�X�g�����[�o�������APRIME2,AF���j�b�g�A-10�x�ϊ����\�Ȃ�K-7�Ƃ̋��ʍ������������܂����J���������l����Ƃ��Ԃ�645D�ŊJ�����Ă����Z�p��K-7�ɐ�s�������������ɂȂ�낤�Ȃ��B
645D�͔����܂��t���b�O�V�b�v�ɂ�鑊����ʂɂ͍�������҂��Ă܂��B
�����ԍ��F11063448
![]() 5�_
5�_
�Ȃ�Ƃ��X�^�f�B��
�����ߑ��̂Ȃ��������݂́A�A
���i.com�Ƀ��[�p�X�t�B���^�[���t���āA�X�^�f�B�����V���b�g�A�E�g�������C���ł��B
�������̓_�X�g�A���[�g�@�\�Ńy�b�^���_�g���ăS�~�����i�X�^�f�B�����j�������C���ł��B
�����ԍ��F11063475
![]() 15�_
15�_
���B�uCCD�O�ʂ�UV�EIR�J�b�g�t�B���^�[���v�i���[�o�X�t�B���^�j�͂��Ă܂��B�c�q�Q�ł͋@�\��K�v�ł�����B^_^;
KAF40000���ۂ��X�y�b�N����75���~���o�債����A�z���g������Ȃ��B�B�B^_^;
�����ŕ����܂��B�ł��A�A�x�ɊԂɍ����܂���ˁB���[��B
�������i�����������Ă���ł��������ȁH�@(^.^)
�Ƃ���ŁA�ǂ��ŃR�X�g�_�E��������ł��傤�ˁH
�����ԍ��F11063496
![]() 2�_
2�_
���N���ɐV�J�����ꂽCCD�A�ŐV�f�B�o�C�X�ł̃`�b�v�E�T�C�Y������_�B
�ȑO�̐��\��r�ŁA�����x�Ȃ�A1/3���x�ł��\���R�\���x���B
���̈Ӗ��ŁA6�ʂƂ����̂́A���قł��ˁB
�v�l���A�ǂ����Ŏ~�܂��Ă�����Ȃ�A�P�Ȃ鐔�����킹�����̖��ł��傤���E�E�E�B
���Ȃ݂ɁB�@�ł����B
�����ԍ��F11063538
![]() 2�_
2�_
�Ȃ�قǁA���i���\�ŁuCCD�O�ʂ�UV�EIR�J�b�g�t�B���^�[���v�̓��[�o�X�t�B���^�[�ɂ��炸�ƌ����Ă����ł��ˁB
���ʂ����Ȃ����Ă����ł����˂��H
�����̑�^CCD�̂����ɁA���x�̉������Q�O�O�Ƃ����̂��莝���ɔz�����Ă��������Ă��肪�����B���x��}�������ꍇ�ɂ́A���̂����\���ꂽ�P���R�[��PL���g�����Ă��Ƃł��傤�B
�O���[�v�ʼn҂��ɗ��܂��˂��B^_^;
�����ԍ��F11063547
![]() 1�_
1�_
���[�u�p�X�v�t�B���^(LPF)��UV/IR�J�b�g�t�B���^�͍��{�I�ɑS���Ⴄ���̂ł�
UV=���O�� IR=�ԊO�� LPF=�����g�J�b�g
����CCD(CMOS��)�͐ԊO�̈�ɑ��ċ������x������܂��̂�
IR�t�B���^�͖����ƑS���G�ɂȂ�܂���
PL�t�B���^�Ƃ����͕̂Ό��t�B���^�ł��茸���t�B���^�ł͂���܂���
�����ԍ��F11063658
![]() 4�_
4�_
CCD�O�ʂ�UV�EIR�J�b�g�t�B���^�[�@�́A�P�Ȃ���g���̃o���h�E�p�X�E�t�B���^�ł��B
���̃t�B���^�Ȃ�A��̃V�O�}�Ђ��̗p���Ă���t�H�r�I���̑O�ʂɂ��t���Ă��܂��ˁB
�ʏ팾���Ă���A���[�E�p�X�E�t�B���^�Ƃ͓������܂������Ⴂ�܂��B
���Ԃ�ACCD�̍\���ɍH�v���Ă�̂ł��낤�Ǝv���Ă���܂��B
�����ԍ��F11063698
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́B
�{�f�B�O�ρA�����Ԃ�i�D�ǂ��ł��ˁB
�t�B����645�ɔ�ׂĊi�i�Ɏ��������サ���悤�ł��ˁB
���{���\����J�����ɂȂ肻���ł��B
���엦98����A�S�~�����@�\�Ȃǂ͂����Ԃ�撣�����Ȃ��Ƃ����v���ł��B
�{�f�B�X�y�[�X�ɗ]�T������̂ŁA�e��X�C�b�`�������₷�����ł��ˁB
�����ԍ��F11063730
![]() 4�_
4�_
>�f�W�J���X�^�f�B����
(���[�p�X�t�B���^�[�������̂�)
>���Ԃ�ACCD�̍\���ɍH�v���Ă�̂ł��낤�Ǝv���Ă���܂��B
>2010/03/10 12:46�@[11063698]
�����ԍ��F11065285
![]() 0�_
0�_
�B���f�q�O�̃��[�p�X�t�B���^�́A��Ԏ��g���i�摜�ׂ̍�����\���w�W�j�ł̃��[�p�X�ł��B�i�ׂ����قǎ��g���������j
��f�̊Ԋu���ׂ����Ȃ́A�T���v�����O����Ɛ������L�^���ꂸ�U�F�E�m�C�Y�ɂȂ�܂��B
�t�u��ԊO���J�b�g�t�B���^�́A���Ԏ��g���i�d���g�j�ł̃t�B���^�[�ł��B
�t�u�́A���[�p�X�ł��B
�h�q�́A�n�C�p�X�i���[�J�b�g�j�ł��B
�����ԍ��F11065716
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > �y���^�b�N�X > PENTAX K-7 �{�f�B
���\�������ɂ��āA���傤�Nj߂��ɏo�����������̂ŁA�������t�H�[�����ɂ������645D�������Ă���܂����B
�L���b�`�R�s�[�́u��_�a���v�Ȃ�ł��ˁI
�j�����Ƃ����Ⴂ�܂����B
�g�тł��̗l�q���B�����̂ł����A�g�т���͎ʐ^���A�b�v�o���Ȃ���ł��ˁB�c�O�ł��B
���Ȃ݂ɁA�r�����p���t���b�g���z���Ă���܂���ł������A������Ƀr���͓\���Ă���܂����B
������Ⴊ�݂����ł��B
![]() 11�_
11�_
�����[�A���������蕶��ł��ˁI
���������Ă̔��\�ł����A�������M������̂ł��傤�B
���ꂩ��́A�^�t�Œ����掿���y���^�b�N�X�ł��ˁB
�R�x�n�̃J�����}���́A�Ȃ�Ƃ��Ă��g���Ă݂����ł��傤�ˁI
�����ԍ��F11063798
![]() 5�_
5�_
��d���_�Ƃ��ł��܂����͉̂��������ȁB
�悤���Ă݂���A�a���Łu���a�v��Ȃ����Borz
�����ԍ��F11063837
![]() 6�_
6�_
�o�d�m�s�`�w�ɂ��Ă͒����I�ȃR�s�[�ł��ˁB
�����iImageMonster�j�ł��_�ɂ͏��ĂȂ��ł��傤���Ă��Ƃł����ˁB
�����ԍ��F11063872
![]() 12�_
12�_
�܂��t�B�[���h�p�̃f�W�^���J�����Ƃ��Ă�
�ق�Ɠ����A���_�ɌN�Ղł���X�y�b�N�ł��傤����
���Ȃ����u�ߏ�Ȃ���������v�ł͂Ȃ��ł��傤�ˁB
����d���_�Ƃ��ł��܂���
���͂́A�E�P�܂����B
�ł��A�܂��ɂ����������͋C�ł��ˁB
�ŁA�u���y�d���v�ł��ˁB
�����ԍ��F11064139
![]() 3�_
3�_
��d���_�E�E�E�������Ă�Ǝv���܂���B
���Ɖ��i���_���܂���̑�����̂ł��ˁB
���̃J�����͑債�Ēl���ꂵ�Ȃ��ňێ������Ȃ��ł����H
�����g�������������H
�����ԍ��F11064153
![]() 5�_
5�_
�F���������t�����m�Ȃ�ł��ˁB
���h�̂��߂ɔ������l�̂���J�����Ȃ�ł��傤�ˁB
�����Ȃ��ł����ǁB
�����ԍ��F11065472
![]() 4�_
4�_
�f�W�^�����J���� > �y���^�b�N�X > PENTAX K-7 �{�f�B
�����Ō����Ă��d�����Ȃ���ł��傤���@PENTAX�V���i�\���T�C�g���@�����ɕ����������ł��B
�o�^���������}�K�Ŕz�M���ė������ǂ݁@�X�V���Ԃ��y���݁`�ɂ��ā@�V���i�\���T�C�g�����ɍs���Ă��@
�����}�K�ɏ�����Ă���ȏ�̏��͉��ɂ���������Ȃ��ł����@���Č������@���̂܂܁I
���݃T�C�g������Ă��邭�炢�Ȃ�@�����}�K�ɏ�����������̓I�ȕ����悹�ā@���������������ė~�������I�@
���̒��x�̓��e�̏��o���Ȃ�@�킴�킴�y�[�W���ȁI�@apple�������Ɂ@�M����ׂ����̓��܂ŁM�@�S�Ĕ閧�ɂ��ė~�������I
���\�̎��Ɂ@���z�ŁA���������X�y�b�N����Ȃ�������@�Ԃ��ꂻ���ł��I
�Ԃ��ꂳ���Ȃ��悤�ȁ@���炵�����ɂ��Ă��������i�F��ȈӖ��Łj
�ǂ������ɕ��`�ɂ��肢���܂��Bm(_ _)m
![]() 6�_
6�_
�u�����������v�Ƃ́A����̗��Ԃ��ł��傤�B
���ƂQ��Q��Γ��������ׂĕ�����܂��ˁI
44x33mm CCD�Z���T�[�͂ǂ����KODAK KAF-40000�̂悤�ł��B
2009�N11�����\�̐V���i�̂悤�ł��B
�ƂĂ��y���݂ɂȂ��Ă��܂����B
�����ԍ��F11059980
![]() 4�_
4�_
���������ŐV����m�肽���Ȃ�Agoogle���[���A���[�g���I�X�X���ł��B
http://www.google.co.jp/alerts?hl=ja&gl=jp
�^�C�v�u�j���[�X�v�A�p�x�u���̓s�x�v�ɂ��āA�L�[���[�h�uPENTAX�v���ɂ��Ă�������
�����ԍ��F11060067
![]() 2�_
2�_
�w�S�S�~���w�R�R�~���x���������̂Ɂw�U�S�T�x�Ɩ����̂́A���\�A�s���\���A�֑�L���A�ɂȂ�Ȃ��̂��낤���H�H
�L���m���V�c�̎��엦�̂悤�ɁA�ォ��w��U�S�T�x�Ə��������ď������Ȃ̂��낤���H�H
�����ԍ��F11060463
![]() 3�_
3�_
�t�F�[�Y������P40�{�̑f�q��43.9×32.9mm�Ȃ̂ł���ł��傤�ˁB
�����ԍ��F11060471
![]() 4�_
4�_
���Ɋy�Ƃ�ڂ���
�t���T�C�Y�@�ȂS��"��"�܂���"������"�ł���A����ł�"�t��"�Ɩ�����Ă���B
���h"FX"�Ȃ�Ă̂����邩�B
�����ԍ��F11060599
![]() 5�_
5�_
��hotman����@
�w�S�S�w�R�R�x�́w�U�S�T�K�i�i�T�T�w�S�Q�j�x�̂W�O���B
�w�t���T�C�Y�i�R�U�w�Q�S�j�x�̂W�O�������傤�ǁw�`�o�r�|�g�T�C�Y�i�Q�W.�W�w�P�X.�Q�j�x
�w�`�o�r�|�g�T�C�Y�x���w�t���T�C�Y�x�Ə̂�����N���[�����Ȃ��ł��傤�B
����Ɠ����ŁA�w�S�S�w�R�R�x���w�U�S�T�x�Ə̂���͖̂���������߂��ł͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F11060978
![]() 2�_
2�_
�����Ɋy�Ƃ�ڂ���
�J������Ђɐq�˂�A�u645�͌ď̂ł����ĉ��炩�̎��ۂ̐�����
�\���Ă͂���܂���v�Ƃ������Ԃ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
645�Z�~���̎��ۂ̐��@��56mm×42.5mm�ł��B60mmx45mm�̖ʐς���
10%�ȏ㍼�̂��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�v����Ɍď̂Ȃ�ł�����B
���̂Ƃ���A�R���f�W�̃Z���T�[�T�C�Y�A1/2.3�Ƃ�1/1.7�Ƃ�
�����̂��قƂ�ǂ��ׂč��̂ł��B�Ȃ����Ƃ����A�̂̎B���ǂ�
�nja���炫�����������̂܂g���Ă��邩��B���ۂ͂��̊ǂ̒��ɂ�
�nja��菬���ȎB�����������Ă���킯�ł��B
�����n�m������
����Ȃ��ƂŁA�u�����ɕ������v����������A�u�Ԃ���v���肵�Ȃ�
�ł��������ȁB�J���҂͐������s���������炭����Ȃ��̂ł͂Ȃ�
�ł����H���[�U�[�͋C���y�ł��B���������킴�邩�����Ō��߂��
������ł�����B
���͍ŋߒ��B��ɂ͂܂��Ă���̂ŁA645D�ɂ͂܂��܂��S���Ȃ�
�Ȃ��Ă��܂��A�ނ���y���^��4/3���̏����ȎB���f�q��DSLR��
����Ă���Ȃ����ȂƎv���Ă���قǁB�]�������Y�̉�p�����̕�
�����Ȃ��ď�����܂��B
�܂��A���Ɛ����B���Ԃ�J�̍ő�̊S���͒l�i�ł��傤�ˁB100��
��邩�ǂ���.....
�����ԍ��F11061095
![]() 9�_
9�_
�y���^�b�N�X645�V���[�Y�̃����Y�V�X�e�����g����f�W�^���J�����C�Ȃ̂ŁC�u645D�v��OK�ł��B
�����ԍ��F11061119
![]() 17�_
17�_
�y���^�b�N�X645�V���[�Y�̃����Y�V�X�e�����I�v�V�����i�S�����͕���܂��j����
�V�X�e�����p�����Ă���J�����Ȃ�ł��傤�B
PENTAX645DIGITAL�������܂ʼn��̂Ő������̂ƌ��܂�����Ȃ����A
�y���^�b�N�X645�V���[�Y�̃����Y�V�X�e�����I�v�V�����i�S�����͕���܂��j����
�V�X�e�����p�����Ă���J�����Ƃ��������ł��傤�B
�ʂɑf�q�T�C�Y���t�B����645�Ɠ����łȂ���Ȃ�Ȃ����R�͖����A
����͑����̒����f�W�^���Ƃ�������̂��ƁB
�@����Ƃ�����ꐶ�����T���Ă�y���\���K�v�͖����ł��傤�B
�����ԍ��F11061438
![]() 3�_
3�_
�����f�W�J���ŁA�f�q�T�C�Y���C�ɂ��Ă�����͂��Ȃ��Ǝv���܂���B
�t��645�ł���K�v���͂܂����������܂���B
35mm�̂悤�Ƀ����Y������ނ���ւ��Ďg���悤�Ȏg�����ł́A
�Ȃ��ł��傤���A��p�̌o�����炭�銴�o�ɂ��Ă���������B��
�����ł͂��܂�K�v���������܂���B
�����ԍ��F11061479
![]() 2�_
2�_
�����}�K�ɂ�
�u44×33mm��^CCD�Z���T�[���̗p��PENTAX 645D�v�Ə����Ă���̂ŁA���̂Ƃ��떼�̂�645D�ł��ˁB
�����Ɋy�Ƃ�ڂ���
�U�S�T�K�i�P�O�O���Ƃ������Ă��Ȃ��̂ŁA������Ȃ��ł����H(^_-)
�V�O�}��SD15��APS-C�ł͂Ȃ��B�B�B�Ƃ����l�����܂��B
�����ԍ��F11061514
![]() 3�_
3�_
�����ʂ�̃e�B�[�U�[�T�C�g�B
�ŁA���[�J�[�͂����645�ƌĂ�ł���́H
�����ԍ��F11061561
![]() 1�_
1�_
�@���B�X������G
�@>�����f�W�J���ŁA�f�q�T�C�Y���C�ɂ��Ă�����͂��Ȃ��Ǝv���܂���B
�@�≖���ォ��̃����Y���Y�����ꂩ������̃J�����ŗL���ɖ𗧂ĂĂ��������ƍl���Ă�����x�e�����E���[�U�[�͑����Ǝv���܂��B
�@���݁A�����f�W�E�o�b�O�̎嗬�ȃZ���T�[�E�T�C�Y�ƂȂ��Ă�����̂�48×36mm�A���ꂾ�ƃ����Y�œ_������1.1�{�ōς݂܂��B�C�ɂ��Ă�������͑����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F11061591
![]() 3�_
3�_
���߂�Ȃ����A�u�Z���T�[�T�C�Y���C�ɂ��Ă��Ȃ��v�Ƃ����̂́A���܂Œ����t�B������
�g���Ă������[�U�[����̂��b�ł͂Ȃ��A���łɃX�^�W�I���ŁA�f�W�p�b�N�����g���ɂ�
���Ă�����̊��o�ł̂��b�ł��B�i�O�O�G
�����ԍ��F11061615
![]() 3�_
3�_
�L�W�|�b�|.����@
�嗬��48×36mm�i1.1�{�j�Ƃ̂��Ƃł����A
�����f�W�E�o�b�O�̑f�q�T�C�Y���Ƃ̑�܂��ȃV�F�A�������m�ŁH
44×33mm�T�C�Y�͎嗬�łȂ��ƁH
����Ɋ����f�W�E�o�b�N��200���ȏシ��Ȃ���PENTAX��100���~�ȉ��Ŕ���������
�嗬�ɂȂ�Ȃ��Ƃ�����Ȃ��ł���ˁB
�����ԍ��F11061683
![]() 6�_
6�_
����ɂ��́B���n�m������ACanon���[�U�[�ł����AEOS5DMk2��NikonD700�́A�����������W�߂Ă��������ɁA�y���^�b�N�X�́A�����(�H)�ɂԂ�������A���`��Ƃ��܂����B
���[���ɓo�^���Ă݂�ƁA�t���T�C�Y��1.7�{�̑f�q�T�C�Y�A100MB�̃t�@�C���A�����̃��[����645�`(�H)�A�}�~��ZD�Ɠ��������Y�V�X�e���Ƒz������ƁA�����ɂ͎肪�o�Ȃ��ł����A
�ƂĂ��C�ɂȂ�j���[�X�ł��B
�f�W�^�����ŁACP�{�͔M���Ȃ肻���ł��B
Canon��1DsMk�V�A5D�^�C�v�̐V�^�ANikon��D700�̌�p�@���o���Ă������Ȋ����B
SONY�͊C�O�ŁA�m���Ă�����̂���{�ɁA�t�㗤���������B
�t���T�C�Y��4~5�@��A�V�^���o�邩�����܂���B
�����l����Ǝ�������Ȃ��B���̑O�܂ŁA5DMk2��NikonD700��������ɂȂ������̂ɁB
������̖�����o�܂��A���C�D�A�������l�t�Ŗ�����ꂸ�B����D���}�����悤�ȋC���ł��B
�����ԍ��F11061742
![]() 5�_
5�_
�@�C���_�X�g���A����F
�@�u�嗬�v�Ƃ������t���u�V�F�A�v�Ƃ������t�ɒu���������̂ł��ˁB
�@�����͊e�Ђ̃f�W�o�b�N�A�Z���T�[�T�C�Y44×33mm���i���ǂꂭ�炢�̔�����ĂāA�����S�̂̑����Ƃ̔䗦�ł����ׂɂȂ�Ƃ���������Ǝv���܂��B���\�����Ȃǂ��l������Ε�����Ղ��ł��B
�@�������o��M���̌�i�̎����͉�����������H�ł��B
�����ԍ��F11061769
![]() 3�_
3�_
�L�W�|�b�|.����
�Ȃɂ�炳���ς蕪��Ȃ��̂��ꂩ���ł��ˁB
���Ȃ��̌����嗬�̒�`������Ȃ��ł����A
�����P�ɔ�������Ă���@�퐔�������Ď嗬�Ƃ�������肽�������l�ł��ˁB
���̍l����嗬�́A
�f�W�J���S�́A�g�ъ܂߂��
�J�����t���g�т����|�I�A�����ŃR���p�N�g�f�W�AAPS-C�A135���A�����f�W
�܂�f�q�̏��������قǐ��͏o��Ƃ������Ƃł��B�i������O�ł����j
��i�̘b�͎����ł��Ȃ�ł�����܂��A����������Ă��Ȃ��@��̍����
�܂������̗\���ɑ��āh������������h�ł����H
����ł͋c�_�̗]�n�����ł��ˁB
�����ԍ��F11061864
![]() 6�_
6�_
�C���_�X�g���A����A�����f�W�ƊE��m��Ȃ������ł̂��Ȃ��̈ӌ��̓C�^�߂���B�Ȍ�X���[���܂��ˁB
�����ԍ��F11061902
![]() 3�_
3�_
48×36mm�͋≖��1/1.1��������Ȃ��̂ł����B
�ł�44×33�͂���1/1.1������f�W�o�b�N�Ɋ���Ă�l�Ȃ���Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F11061946
![]() 4�_
4�_
�����͂ǂ�����s��ɏo�Ă���ł��傤�B
�}�~����ZD�p�b�N�Ȃǂ�48×36mm�̂悤�ł��B�����DALSA�̌��s�Z���T�̑傫�������ߎ�̗l�ł��B
�t�F�C�Y������KAF39000���g�p�������̂�48×36mm�AKAF31600���g�p�������̂�44×33mm�ł��B����͓������ɕ��s�̔�����Ă��܂����B
���Ȃ݂ɁAPENTAX�̎���@���O���3000����f�̂��̂�44×33mm��KAF31600���g�p���Ă���ƌ����Ă��܂����B
���Ȃ݂ɍŐV�̃n�b�Z���u���b�h��H4��KAF40000��44×33mm�̂��̂��̗p���Ă��܂��B
Leica��S2��KAF40000�x�[�X�ƌ�����ό`�t�H�[�}�b�g�ł��ˁB
�����ЂƂ����A48×36mm�̂��̂ł��A�Z�~���i�U�S�T�j�T�C�Y�̃J���������ł͂Ȃ��A�U�V�A�U�U�̃T�C�Y�̃J�����ɂ������Z���T�[�T�C�Y�Ŏ��t�����܂�����A�c�O�Ȃ���t���T�C�Y�_�c�͒����̃f�W�o�b�N�Ɋւ��Ă͐��藧���Ȃ����ƁB
����ł����A48×36mm��44×33mm�̗�����CCD�����Y����Ă��܂��B
�n�b�Z����H4
http://www.hasselblad.jp/���i���C���A�b�v/���V�X�e��/h4d-40.aspx
�܂��APENTAX�̂U�S�T���[�U�Ɋւ��Č����A�Y�[�������Y���嗬�ɂȂ��Ă��Ă��܂�����A�L�p�Ȃ̂��]���Ȃ̂������f�t���A���Ƃ̓t�@�C���_�[�����Ȃ��犵���Ǝv���܂���B
�}���`�t�H�[�}�b�g���g���Ă�ƁA�t���T�C�Y�Ƃ��A�Ȃ�Ƃ��A�����Ă��Ȃ��̂�B
�S���Ⴄ���́B^_^;
�����ԍ��F11061984
![]() 10�_
10�_
�g�|�S�Ƃ����c
���Ƃ��Ƃg�|�P�̓t�W�Ƃ̋����J�������ǂ�
�g�|�S�ɂ̓t�W�͂܂������ւ���ĂȂ��̂��낤���H
���Ȃ݂ɒ����̂U�S�T�̃f�W�^���Ɋւ��Ă̓t�B��������̂U�S�T�J�����̃V�X�e���������p���ł���̂����疼�O�ɂU�S�T�����̂͋Ɏ��R
�ނ���Ⴄ���O������ꂽ�獬�����܂��ˁH
�}�~���i�ŐV�̂͂����Ƃ��āj�Ƃ��R���^�b�N�X�Ȃ�t�B�����o�b�N�������Ⴄ�����ł����ˁi�j
�����ԍ��F11062136
![]() 6�_
6�_
�L�W�|�b�|.����
�����f�W�ƊE��m���Ă邱�ƂƑf�q�T�C�Y�̎嗬�̘_�c�Ƃ͊W���肻���Ŏ��͖��W�ł��ˁB
���̏Z�l������������Ă���悤�ɕ����T�C�Y�Ƃ������A48×36mm��44×33mm�ɑ�ʂ����悤�ŁA
�ǂ��炪�嗬����_�c���邱�Ǝ��̂����Ӗ��ł��傤�ˁB
�Ȍ゠�Ȃ��̓X���[���܂��B
�����ԍ��F11062153
![]() 11�_
11�_
�����Ă����Ȃ��҂��̂����Ɂc
�����ԍ��F11062626
![]() 5�_
5�_
�����́u�f�W�J�����������v�ɃZ���T�[�̌��ŋL��������܂����B
�u�_���T���̃Z���T�[���g���Ă���̂ł��傤���B�v�Ƃ̃R�����g��
����܂������A���̓T���X�������Ǝv���Ă��܂����B
�@����ŁA�P�O�O���~���Ƃ��炢�B
�����A�j7�������Ƃ���Ȃ̂ł��炭�������Ȃ���ǂ�Ȏʂ肪�ł�̂�
�y���݂ɂ��Ă��������Ǝv���܂�
�����ԍ��F11062865
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂��B
�F�������Ă���͎̂��Ȃ̂Ł@���ȏ�ɋ������Ȃ��ł��������ˁi�I�j
�F�����������悤�Ɂ@�B���Ȓ�`���ǂ��Ȃ��Ǝv����ł��B
�t���T�C�Y�_�́A���I�̒��ł͂����I����Ă��܂��i�y���^�Ɋւ��Ă͂ˁI�j
�≖�����S�Ɏg��Ȃ��Ȃ��Ă���4�N�ڂɂȂ�@FA�����Y��FA50mmF1.4��FA��300mmF2.8�݂̂ɂȂ�@����DA�����i��SDM�ɓ����ŗ��܂����B
�X�ɉ�p���n�߂�APS-C�ɂ������藈�Ȃ���������ǁ@�ŋ߂ł́u�t���T�C�Y�Ɋ��Z���ā`�v���čl���Ȃ��Ă��@APS-C�ɂ�������Ƃ����݂܂����B
K-7�͏��L���Ă��܂��@ist��D,K10DGP�̉掿�ł��������Ă��܂�
�F����̌������܂��܂��ł��@�N���Ԉ���Ă���Ƃ������Ǝv���܂��B
FA�����Y�̎��Y����R������Ńt���T�C�Y��]�ޕ��A�]�܂Ȃ����͂���Ǝv���܂����A��������DA�����Y�ɃV�t�g���Ă��܂������́@�t���T�C�Y�͕ʂɖ]�܂�Ȃ��Ǝv���܂��B
���[�J�[�Ƃ��ċZ�p��i��������̂́A�厖�����@�ӂ�Γ�������Ă��܂��܂����@������Ԍ��O���Ă��邱�Ƃ́A�i�ނׂ��������A�݂�Ȃ��H���ɖ������ł��@�{�f�B�[�͏��Օi�Ǝv���Ă��܂����@�����Y���Y��������y���^������Ȃ��ŗ~�����ł��B
�N���������Ă����Ǝv���܂����@���x�̐V���i�ʼn��炩�̎�@��FA,DA�����Y���g������@�R�������炵�������Ǝv���܂��B
�ʂɃL���m���A�j�R���Ə������Ȃ��Ă��@���܂ł̃y���^�b�N�X���[�U�[�����ł����N���N�������镨����葱���Ă����@1�l�̃��[�U�[�Ƃ��Ă͖����ł��B
���ꂩ���̐��E�ł�����@������菊���F����Ⴂ�܂��ˁ@�J�������D���ȕ��A�ʐ^���D���ȕ��A�\���ɏڂ������A�����Y�`�ʂ̂������̂�����A�F���炵���ł��B���ǎ����y���^�b�N�X���D���Ȃ̂��ȁ`�i�I�j
�����ԍ��F11062927
![]() 5�_
5�_
����Ɣ��\����܂����ˁH
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100310_353556.html
�����ԍ��F11063355
![]() 2�_
2�_
>K-x�ɂ������u�R���W���i�C���{���f���v��u100 colors, 100 styles.�v�Ƃ������J���[�o���G�[�V�������f���̗\��͂Ȃ��Ƃ����B
����Ǝc�O�i�j
�����ԍ��F11063497
![]() 7�_
7�_
80���I�I
�������I�I
�����ԍ��F11063518
![]() 2�_
2�_
�o�܂����ˁI�@���`�X�b�L���I
�w�����l���Ȃ��ŗǂ����i�ŗǂ�����....�̂��ȁH
�����ԍ��F11063978
![]() 3�_
3�_
�f�W�^�����J���� > �y���^�b�N�X > PENTAX K-7 �{�f�B
K20D��K-7�̎B���f�q�V�t�g���̎�U���@�\�ɁA�悭�������Ă��܂��B
����܂ŁA�����Y����ɔ�ׂ�ƁA�Â��Ă��`�ʂ��D���ȒP�œ_�Ȃǂł���������Ă�����ȁ[�A
���Ă��炢�ɂ����A�y���^�b�N�X�̏œ_�����̓��͂��ł���A�{�f�B���̕�̗ǂ���
�������Ă��Ȃ������̂ł����A�ǂ�����U���̎d�g�݂ɂ���āA���ӂƂ���u�����ւ�
���ʂ��A���������Ⴄ�̂ł͂Ȃ����H�ƍl����悤�ɂȂ�܂����B
���������́A�L���m�����o�����n�C�u���b�gIS���ڂ̃����Y�ׂĂ������Ƃ���n�܂�܂��B
http://cweb.canon.jp/ef/technology/is-technology.html
�B�e�����ɂ����ʂ̈Ⴂ�ɂ���
http://cweb.canon.jp/ef/lineup/macro/ef100-f28l/spec.html
����ɑ��āAK20D��SR�B�W���C���Z���T�[�Ń{�f�B�̗h���ł������悤�Ɉړ��B
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/slr/k20d/feature_02.html
�����̐����C���ƐԂ����C���ɑ��Ă̑f�q�̈ړ�����A�V�t�g�u��������Ă���悤�Ɍ����܂��B
�悭�\�̂悤�Ȍ`�ŁA�{�f�B���̕�́A�t�@�C���_�Ō��߂��\�}�ƋL�^�����摜���Y����A
�Ȃ�ď������݂��ڂɂ��܂����A�����g�̓{�f�B���ƃ����Y���̕�̗������g�p���Ă�������Ƃ��āA
���]�����炢�܂ł̉�p�ŁA�ߋ����̎B�e���s���ꍇ�A�V���b�^�[�������܂ŁA
�t�@�C���_���ł̋l�߂��\�}�ƁA�L�^�����摜�̃Y�����ł����Ȃ��̂́AK-7���Ɗ����Ă��܂��B
�t�@�C���_�̎��엦�̐��m����x����`���Ă��A����{�̃Y���������قǂƊ����܂��B
�����œ_�����ʼn����̔�ʑ̂��ʂ��ꍇ�A�m���Ɋp�x�u���̗v�f���傫�����߁A�t�@�C���_��
�h���̂�������܂��A�W�����L�p��Ŏ�Ɏg�����Ƃ��������́A����܂ŕs�ւ����������Ƃ�����܂���B
�y���^�b�N�X�̃f�W�C�`�̎�U�����āA�ߋ������璆�����̃u�c�B��i�Ñ̎B�e�j�ŁA
���Ɍ��ʂ����Ă���Ɗ����鎞������܂��H
���́A�����Y���[�J�[������j�}�E���g�p�̕���������Y���o�Ă��āA��������������ł�����A
�����A�œ_�������ʑ̂܂ł̋����ŁA����ʂ̈Ⴂ���������������������A���m�点���������B
�������͑��Ћ@�p����Ă��āA���[�J�[���Ƃ̎d�g�݂̈Ⴂ�ŁA���ʂ̈Ⴂ���������Ă�������B
![]() 9�_
9�_
�����u�B���f�q�V�t�g���v�̎�U���@�\�ł��A�R�j�~�m�Ƃ́A������Ǝd�g�݂��Ⴄ�݂����ł��ˁB
�w��-7 DIGITAL�̎�Ԃ��Z�p�x
http://konicaminolta.jp/about/research/technology_report/2005/pdf/feature01_003.pdf
�iPDF�`���ł��̂ŁA�Q�Ƃ����ꍇ�͂����ӂ��������j
�y���^�b�N�X�̃W���C�����Ń{�f�B�̗h���ł����������Ƃ͈Ⴂ�A
�ǂ����p�x�u�����A����Ă���悤�ɂ������܂��B
���̃\�j�[�̃����ǂ����͉���܂��A���͂���܂ŁA�d���U�����⒴���g���[���ړ����Ȃǂ́A
�d�g�݂͈���Ă��Ă��A���ʂ͂قƂ�Ǔ����Ȃ̂��Ɗ����Ă��܂����B
�ꌾ�Ł@�{�f�B�����^ �B���f�q�V�t�g����U���@�\�@�ƌ����Ă��A�悭���ׂ�ƁA
���ӂȕ���ʂ�����Ă������ł��B
�����ԍ��F10858727
![]() 5�_
5�_
���͑��Ћ@�ł��ƁA�L���m����EOS 20D��EF-S18-55mmIS�Ƃ��������Y�̑g�ݍ��킹�ŁA
�����Y���̕�����T�d���Ŏg�p���Ă���̂ł����A�ߋ����ŏ����߂̔��p�i��G��Ȃǂ�
�B�e���Ă���ƁA�ǂ����t�@�C���_�̒��Ŋm�F�����\�}�ƁA�B�e���ꂽ�摜�͈̔͂��A
�悭�Y���Ă��邱�ƂɋC�����܂��B����I�t�ɂ���ƁA���Â��Ƃ���ł̓u���܂����A�\�}�̃Y���͊����܂���B
�����̂Ƃ���̎d�g�݂̈Ⴂ���悭����Ȃ��̂ł����A��@�\�̌����̈Ⴂ�ŁA
�����������Ƃ��N����̂ł��傤���B
���́A�]����ʼn����̔�ʑ̂��B�邱�Ƃ����Ȃ����߁A������̌o���͑��肸�A�܂��C�}�C�`�Ⴂ������܂���B
��ʂɓ����悤�Ȕ�ʑ̂��悤�ȋ����ŎB�e���Ă������ŁA�����Ƃ��Ċ��������Ƃ��A
��ŏq�ׂ��悤�ȁAK20D��K-7�̋ߋ����ł̎�U�����ʂ́A���ɍ����A�Ƃ������Ƃł����B
����́A�Â��l�e�̃����Y���g���Ă���ۂł��悭�����Ă��܂��B
���^�̃����Y�̂ق����A�J�����̌X���h�ꂪ���邽�߁A�p�x�u�����N����ɂ����A�Ƃ������Ƃ�
�W���Ă���̂�������܂���B�������������Ă���PENTAX FA35mmF2��A50mm F1.7��F2���A
�莝���B�e�ł��ASR�Ƃ̑g�ݍ��킹�ŁA���Ɏ��p�I�ȃ����Y�Ɋ������܂��B
�����͌l�I�ɂ́A�y���^�b�N�X�̃f�W�C�`�̒������Ǝv���̂ŁA�����Ƒ����̐l�ɒm���Ăق����ł��B
���^�ȒP�œ_�����������Y���C���i�b�v�̃y���^�ŁA���݂�SR�́A�����������ɂ��Ȃ��Ă���̂��ȁA�Ƃ������܂��B
���炭�l�b�g�����܂茩���Ȃ��̂ŁA��Ԏ����A�x���Ȃ��Ă��܂���������܂��A�\����܂���B
�����ԍ��F10858808
![]() 9�_
9�_
MZ-LL����@�����́B
�j�|�V�ƃj�R���̂c�V�O�O���g���Ă܂��B
���o�ŗǂ��̂Ȃ玩���̈ӌ����q�ׂ邱�Ƃ͂ł��܂��B
�ǂ�����Ⴂ�͊����܂���B
�ܘ_�{�f�B����Ԃ��ł����Ȃ��s���|�C���g�Ńs���g�����킹���܂����ˁB
�ʐ^�͂Q���Ƃ��j�Q�O�c�ɂl���S�O�O�������S�ōi��J���莝���B�e�����A�I�X�W�A�Q�n����ƃ����L�`���E����B
�ǂ�����ڂɃs���|�C���g�Ńs���g���킹���Ă܂��B
�����ԍ��F10858879
![]() 7�_
7�_
ken-san����A���������̂��������݂ƌ�ʐ^�Ǝg�p���A���肪�Ƃ��������܂��I
���͓��ɁA�]����ł̎B�e�͂悭����Ȃ����Ƃ��������߁A���m�点���������������ł��B
��������肪�Ƃ��������܂����B
�@�����o�ŗǂ��̂Ȃ玩���̈ӌ����q�ׂ邱�Ƃ͂ł��܂��B
�@���ǂ�����Ⴂ�͊����܂���B
�u���̎�ނ͎��ۂ̎莝���B�e�ł́A�n�b�L���ƕ���������̂ł͂Ȃ��炵�����߁A
�ނ���A���o�I�Ȍ�ӌ������肪�����ł��I�@���͋@�B��Z�p���ʂɂ͂������Ďア���߁A
���l��̃f�[�^�Ȃǂ����A�����������g�p���̌��A�Ȃɂ��������ł��B
����200mm�قǂ̖]����ł́A���Ƀt�@�C���_���h��č��������Ƃ͖����̂ł����A�S�O�O�����̃����Y��
��ʐ^�ŁA���ꂾ����������ʂ���Ă���Ƃ������Ƃ́A�o�����܂߂��u�r�v�����邱�Ƃ��A
�@�ނ̎d�g�݂̔����ȈႢ�Ȃǂ́A�قƂ�NJW�Ȃ��Ȃ�A�Ƃ������Ƃ�������܂���ˁB
���ɂ͂ƂĂ��B��Ȃ����ԍ����́A�f�G�Ȍ�ʐ^�A���肪�Ƃ��������܂����I
�����A���ۂɂ͏��^�̖��邢�P�œ_�Ń����Y���̕�����������Ƃ͖����̂�
�i�܂��������������Y����������Ă��Ȃ��H�j�A�قړ������ł̎g�p���̑Δ�ł͂Ȃ��̂ł��B
���o�I�ɁA�ߋ����̎B�e�����Ă���ƁAK20D��K-7�ł́A����ʂ������Ȃ��A�Ɗ����܂��B
EOS�Ŏg���Ă���IS�����Y���A�W����̃G���g���[�����Y�ł��邱�Ƃ��A�W���Ă���̂�������܂���B
���X�ƌ�ӌ��ƌ�ʐ^�A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10858947
![]() 3�_
3�_
ken-san����ւ̃��X�̒NjL�ł��B
��ʐ^�A������x�A�������Ɣq�������Ă����������̂ł����A�F�����������Y��Ȃ��Ƃ͂������A
�������łȂ��A�����Ƃ���ʂ̒��ŁA�|�C���g�ƂȂ�A������������Ɖ𑜂���A�����r�r�ł�
���u�����N���Ă��Ȃ��Ȃ��A�Ɗ����܂����B
��ʐ^�̒��ōl����A�Ԃ�E�̌s�͘e����������܂��A�����炪��������`�ʂ���Ă��邱�ƂŁA
��ʂɗՏꊴ���o�܂��ˁB�莝���B�e�ł��ƁA�\�}�̎��R�x�������A�����Ɏ�U���������ƁA
�܂��܂��B��₷���Ȃ邩������܂���ˁB��O���ł��̂ŁA�l�I�Ȋ��z�ł����܂���B
��ʐ^�ƌ�ӌ��A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10858996
![]() 3�_
3�_
���͓����Ă��鐶���́A�r���������Ƃ������āA���܂�B��Ȃ��̂ł����A�]�������Y�́A
�����ɂ��镨���傫���ʂ�A���̊��o�͂ƂĂ��D���ł��B
���܂�g��Ȃ������ɁA���̃y���^�b�N�X�̖]���Y�[���͂������������Ă��܂��B
���̔�ʑ̂́A�V�h�̃t�H�[������J�����X�ɍs�����ۂɁA�����B�肷��̂Ɏg�������
�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@K20D�ŁAJPEG 2M��1�̒��f�E�����k�̎B���ďo���ł����A
���邢�ꏊ�ł͈��k�m�C�Y�����Ȃ��A��������𑜂��Ă���܂��B
�����Y�͋v�X�Ɏg�����ADA55-200mm�ł��B
�y���^�b�N�X�̃T�C�g��J�^���O�ł̂r�q�̉���ǂ���A���u�������炵�Ă���Ă���Ɗ����܂��B
�����ԍ��F10859095
![]() 4�_
4�_
���ȃ��X���d�˂Ă��܂��܂����A�A
��̐V�h�ŎB�e�����摜�AFS�͂�����+2���炢���ƋL�����Ă��܂��B
���ƁA������������ʑ̂̂��������邩������܂��A
�t�@�C���_�̒��ő����h��č���悤�Ȃ��Ƃ́A�]����ł����������ł��B
�O�ɁA300mm��1.4�{�̃e���R����t���āA���]�Ԃɏ�����܂܁A�~�܂���
����U��Ԃ�����ԂŁA�������B�낤�Ƃ�����A�t�@�C���_���h��āA��ςł����B
�����A���ꂪ�t�@�C���_���h�����Ă��ƂȂA���āB
�ł��A�O�������āA�����ƃJ�����i���̎���������K20D�ł����j���\����A
�Ƃ��ɍ���܂���ł����B�ςȎp���̎��́A�m���ɖ]����Ńt�@�C���_�͗h��܂��ˁB
�����ԍ��F10859165
![]() 3�_
3�_
���p���������A�܂����ȃ��X�Œ����ł��B�B�B�ق�ƁA���݂܂���B
������̃X���b�h��ǂ܂�Ă���y���^���[�U�[�̕��X�́A���łɂ��C�Â����Ǝv���܂����A
�@���uDA55-200mm�v
�ł͂Ȃ��āA�uDA50-200mm�v�ł��ˁB�ԈႦ�Ă��܂��Ă��߂�Ȃ����B
�����Ă��Ȃ������ɁADA55-300mm�ƃ��C�h�[�̐�������������ɂȂ��Ă��܂��āc�B
�Ȃ̂ŁA���̉摜���̃L���v�V�������A�uDA50-200mm�@50mm���v���������ł��B
���炢�����܂����B
����ł́A���₷�݂Ȃ����B
�����ԍ��F10859206
![]() 3�_
3�_
MZ-LL����̌���ł��ˁB
�����ԍ��F10859307
![]() 15�_
15�_
>> �t�@�C���_���ł̋l�߂��\�}�ƁA�L�^�����摜�̃Y�����ł����Ȃ��̂́AK-7���Ɗ����Ă��܂��B
���Ⴂ�ł́H
�Z���T�[�V�t�g�������ƌ����I�ɂ���܂���ˁB
�����ԍ��F10859382
![]() 10�_
10�_
���Z���T�[�V�t�g�������ƌ����I�ɂ���܂���ˁB
�����͊W�Ȃ��ł��B
�����ԍ��F10859403
![]() 11�_
11�_
���A���傤�Ǔ����L�b�g�����Y�ŏ����𑵂��āA��Ԃ�̕�̌X���������Ă݂܂�����B
�Q��O�ɂ�����x�A�������`���Ă݂Ă悩�����ł��B
kuma_san_A1����A���������݂��肪�Ƃ��������܂��B
�@��MZ-LL����̌���ł��ˁB
�������ɁA�����Y����50-200mm��55mm�͂��܂�ŕ\�L���Ă��܂��܂����B���p������������ł��B
���͍Q�Ă��̂ŁA���Ⴂ�������̂ŁA�悭�Ċm�F������悤�ɂ��Ă��܂��B�d���ł��������݂ł��B
�����āA���A�z�c�̒��ŁAK-7�ɂ�18-55mm�̃L�b�g�����Y�����āA30cm�قǂ̔�ʑ̂ցA
�킴�Ƃ����ȃu���̎d���������Ȃ���A�������B�e���Ă݂܂����B
�����Y�̏����������Ă��Ȃ���Ԃł́AEOS 20D�Ƃ̈Ⴂ�͎������̂ł����A����ł́A
���m�Ȍ��ʂɂȂ�Ȃ��Ɗ���������ł��B
���_���猾���A��͂�A�y���^�b�N�X�̍��̂r�q�́A�V�t�g�������܂ރu�����A
�ł������\�͂������A�Ɗ����܂����B�������A�f�q�������̍Ō�̕����Ŏ���A�������Ă���ȏ�A
�p�x�u������ł���̂ł����A���V�����f�q���A�W���C���ň��ɕۂ����Ȃ̂ŁA
�����ȏ㉺���E�ւ̃{�f�B�̗h��i�����Y�ƃ{�f�B�̊p�x��������x����ԂŁj�ł�
����A�p�x��t���ėh�炵���ۂƔ�ׂ�ƁA�����ɍ����ł��B
�ł���A����APS�Œ����@���炢�̏d���ŁA�L�b�g�����Y�ŁAEOS�����ɒu���āA
���x���B���ׂĂ݂�A�n�b�L������Ǝv���܂���B
EOS 20D��EF-S18-55mmIS�̑g�ݍ��킹�ŁA�߂����m���B�鎞�A�t�@�C���_�̒��ł��A
�p�x���t�������̃u�����A�����Ď~�܂�̂��A�n�b�L���Ɖ���܂��B
�Ȃ�ł��A�����Ŋm���߂Ă݂���̂ł��ˁB
�����ԍ��F10859459
![]() 4�_
4�_
�ʒu�Ԃ�(�V�t�g�Ԃ�)�����o����Z���T�[�𓋍ڂ��Ă��Ȃ��V�X�e���ł��̕�ʂ����Z���邱�Ƃ��s�\�Ȃ̂ł��B
�����ԍ��F10859467
![]() 16�_
16�_
��delphian����
���������݂��肪�Ƃ��������܂��B
�@���Z���T�[�V�t�g�������ƌ����I�ɂ���܂���ˁB
���������A������̂ق��́A����܂ł����A������Ȃ����炢�Ɏ����Ă��܂����B
���ǁA�V���b�^�[���u�Ԃ܂ŁA���Ă��鑜�ɑ��āA���Ƃ��{�f�B���킸���ɗh��Ă��A
���V���Ă���Z���T�[���A�W���C���Z���T�[�ŁA���̈ʒu�Ŏ~�܂��Ă���Ă��邱�Ƃ��A
�t�@�C���_���ŋl�߂��\�}�ƁA�قړ��������A�L�^����v���ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ����܂��B
�܂����Ԃ����鎞�ɁA���炽�߂ď����܂��B
�������A������x�A��ʑ̂܂ł̋������߂��A�W���悩��70mm���x�̒��]�����炢�܂ł����A
�����Ă��Ȃ��̂ŁA���ׂĂł����Ȃ�킯�ł͖����Ǝv���܂��B
���ʂ������͂��́A���L�p��ł́A���ʂ�����₷����ʑ̂������̂ŁA�����Ă��܂���B
�������i�A�d���ł��v���C�x�[�g�ł��悭�B��A���܂�傫���Ȃ��Ώە����A�߂������ŎB��ۂɁA
���ɁA�t�@�C���_�̒��ł̊m�F�ƁA�L�^�����摜�̌덷�����Ȃ����ƂɁA��������Ă��܂��B
���ЁA�^��Ɏv������X�́AK-7�Ŏ����Ă݂Ă��������B
���엦���قڊ��S��100���ł���K-7�́A���̌덷�����Ȃ����Ƃ��A������₷���ł���B
�����ԍ��F10859468
![]() 5�_
5�_
�����V���Ă���Z���T�[���A�W���C���Z���T�[�ŁA���̈ʒu�Ŏ~�܂��Ă���Ă��邱�Ƃ��A
����̗������܂������Ԉ���Ă��܂��B
�܂��A���L�p�ł͑��ʈʒu�ɂ��K�v���(���S���[�̂ق������������K�v������)���قȂ�܂�(��^�[�Q�b�g�͊p�x�̂Ԃ�Ȃ̂�)�B
�����ԍ��F10859482
![]() 12�_
12�_
�ʒu�Z���T�[�́A���ڂ��Ă���݂����ł���B
���܂����l�����Ƃ��AK20D��SR�̍\��������A�����Y�̐^��ʂ��Ă��Ȃ��A
�����̕����ŁA���̈ʒu��ۂ����f�q���A������Ă���̂�����Ǝv���̂ł����B
�������Ēm������������A�����W�߂�ꂽ�肷��ƁA����������A��������肷��̂ł��傤���H
�����A�C���[�W�T�[�N���̒��ŁA�f�q��������͈͂̕�ł�����A
�V�t�g�u���i�ʒu�u���j�����S�ɕ�ł���̂́A�����킸���ȗh�ꂾ�����Ǝv���܂��B
�c��́A�p�x�u���̕�ł��傤�B
K-7�A�������ł���A���ۂɏ㉺���E�ɕ��s�ɏ������h����Ȃ���A�B�e���Ă݂āA
�������Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�ł��A���߂āA�����Ȃ��Ƃׂ�ꂽ�̂́Akuma_san_A1����̂������ł��B
���ׂ��菑������͑�ςł����ǁA�����������ӂ��Ă����ł���B
���̃X���b�h�𗧂Ă��̂��A���Дł������������X�����������ł����B
�C���[�W�T�[�N�����ŁA�W���C���ňʒu��ۂ��ē������邱�Ƃ��|�C���g�ł��B
���̍\�����A�J�����̃{�f�B�����O�r���ŌŒ肳��Ă��鎞�ɁA�t�̕����ʼn��p�����̂��A
���C�u�r���[�g�p���́A�ʒu�������@�\���Ǝv���܂��B�������±1mm�̒������ł��܂�����A
���Ȃ��Ƃ��A1mm�⍇�킹��2mm�́A�莝���̍ۂ̈ʒu�u���Ƃ����������ȗh��́A����Ă���Ă������ł��B
�Ƃɂ����A����������I
�����ԍ��F10859491
![]() 3�_
3�_
�L�p��̂��Ƃ��A�����Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B
������A�@�����A�����Ă݂����Ǝv���܂��B
�Ƃɂ����A�����B���Ă���悤�ȑ傫���̔�ʑ̂ŁA�u����h��̃e�X�g�����Ă݂Ă��������B
�����Y��IS�́A�p�x���t�������ɁA�{���Ƀt�@�C���_�̒��Ńu�����~�܂��Ă���̂ŁA
������A���炽�߂ăr�b�N�����܂����B�W����ł́A���i�͂��܂���ʂ������ł��Ȃ��ł��̂ŁB
����ł́A���₷�݂Ȃ����B
����ȍ~�̃��X�͏����x��܂��B
�����ԍ��F10859503
![]() 1�_
1�_
���W���C���ňʒu��ۂ���
������A�u�W���C���v�͈ʒu�Z���T�[�ł͂Ȃ��̂ł��B
�Ȃ��A�u�ʒu�𑪂��Ă���v�ɑ�������̂͑��ʂ̐���̂��߂̂��̂ňʒu�Ԃꌟ�o�̂��߂�G�Z���T�[�ł͂���܂���B
�~�m���^->�R�j�J�~�m���^->SONY�͈̂��d�A�N�`���G�[�^�[�œ��삷��̂ŁA�d���I�����̏�����(�Z���^�[����)�̌�̓t�B�[�h�t�H���[�h�Ő���ł��܂����APENTAX��SR�͑��ʂ̈ʒu��m��Z���T�[���g���ăt�B�[�h�o�b�N�Ő��䂷�邱�Ƃ��K�{�ł��B
�����ԍ��F10859511
![]() 11�_
11�_
���́[�A�AK20D��SR�̉���ŁA�W���C���Z���T�[�ƈʒu�Z���T�[�̃R���r�l�[�V�����ŕ������āA
�n�b�L�������Ă���܂����ǁc�B
�����A�W���C�����ʒu�Z���T�[�ł���Ȃ�āA�v���ĂȂ��ł���B
�W���C���̓W���C���ł��傤�B
�����ԍ��F10859518
![]() 1�_
1�_
���߂��I�������Ă��炦�Ȃ��B
SR��3�_�{�[���ɉ����t����`�̓d���쓮�Ȃ̂ŃC���[�W�Z���T�̃Z���^�����O�ʒu�A����ѕ����ʒu���u�ʒu�Z���T�[(����̓J�����̂Ԃꌟ�m�̂��߂ł͂���܂���)�v�ɂ���Ēm��K�v������܂��B
AS�͈��d�A�N�`���G�[�^�[�����C�͂œ��삷����̂Ȃ̂ŏ������ŃC���[�W�Z���T�̈ʒu���Z���^�����O������쓮�X�e�b�v���œ����𐧌�ł��邽�߃C���[�W�Z���T�ʒu��m�邽�߂̃Z���T�[���K�v����܂���B
�����͎�Ԃ��V�X�e���S�̂̎����A�v���[�`�̈Ⴂ�ɂ����̂ł��B
�����ԍ��F10859535
![]() 15�_
15�_
kuma_san_A1���A�����r�炵�I�ȏ������ݕ�������l��������A���������Ɗ���I�ɂȂ邩�A
�������́A�����̋C���������������܂Ŗ������邩�A�������Ǝv���̂ł����A�����Ƃ���
�������ݕ������Ă����������������ŁA�������̖{���������킸�ɂ��݂܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�Ƃ��ɁA�R�j�~�m�̂`�r�Ɋւ��Ē��ׂ��̂��Akuma_san_A1����̑��ЃX���ł̌����������ł������A
����܂Ŏ��͎B���f�q�V�t�g���̎�U���́A����̂��߂̋@�\�̎d�g�݂��Ⴄ�����ŁA
�قڎ����悤�Ȍ��ʂ�������̂��Ɗ����Ă��܂����B����������͌�肾�����悤�ł��B
�B���f�q�V�t�g���ƌ����Ă��A�ꌾ�ł͂�����Ȃ��̂ł��ˁB
�����ɋC�t�����̂��Akuma_san_A1����̂������ł��B���肪�Ƃ��������܂����B
����K20D�����߂Ă̎�U�����ڋ@�������̂ŁA���������āA�{�f�B���̊e�Ђ̕�̈Ⴂ���A
�̊��ł���قǂ͉����Ă��Ȃ��̂ł��B�t�Ɍ����AK20D��K-7�A���킹�ĉ����V���b�g��
�B���Ă������Ƃɂ��A�t�@�C���_�̌�������A��̌�����̋L����̊�������܂��B
�iK100D��K10D���g���Ă݂܂������A�������������������Ă��銴�����܂����j
����ƁA���̓y���^�̂r�q�̃W���C�����̐����ŁA�f�q���u���V���Ă���v�ȂǂƁA
�܂�Œ��ɕ����Ă���悤�ȏ����������Ă��܂��܂������A���ۂɂ͎O�_�̃{�[����
�x�����Ă��邱�Ƃ�⑫���Ă�������A���肪�Ƃ��������܂����B
���̕ӂ�̃C���^�r���[�����ߋ��ɓǂ�ł����̂ł����A�����o�I�Ȍ��t�ŁA�����Ă���Ƃ������Ă��܂������ł��B
�ł���A���ݓX���Ŋm�F�ł���K-7�ŁA���s�ړ��̈ʒu�u���������邱�Ƃ��A
���ۂɊm���߂Ă�����������ŁA�y���^�b�N�X�̌��݂̂r�q�Ɋւ��Ă����́A�䎞�Ԃ̂��鎞�ɂł��A
��������������ł���������Ɗ������̂ł����A�����ʼn���܂ł́A���u���Ă��������Ă��������ł��B
�[��ɂ��낢��ƌ������������A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10859640
![]() 3�_
3�_
���j��ɍŏ��ɂ������@��X���b�h�ւ̏������݂��琔���ԁA����Ǝ����������Ă������o��
�Ԉ���Ă��Ȃ����Ƃ��ؖ�������@�������܂����B
�����Ă݂�A�Ȃ�ł���Ȃ��ƂɋC�t���Ȃ������낤�A�Ǝv���Ă��܂��悤�Ȃ����ł����B
���������Ă���@�ނł́APentax K-7��K20D�ŁA���s�����̈ʒu�u���������ƕ����邱�Ƃ��A�N�ł��H����܂��B
���L���Ă���l�Ȃ�A�N�ł�����悤�Ȃ��̕��@�Ƃ́A�u���C�u�r���[�����掞�̂r�q�삳���邱�ƁI�v�ł��B
��������܂Ŋ����Ă����ʐ^�̎B�e�i�Î~��j�ł́A�Ȃ��Ȃ������悤�ɑ��̕��X��
�����Ă��炤�̂́A����ƍl���܂����B�o�b�e���[��H���̂����������̂ł����A
�O�̂��߁AK-7�œ��惂�[�h���������݂��̂ł��BAF�{�^���Ń��b�N�I���I
��������A�ق���A�㉺���E�����́A���s�ړ��̃u�����A�����Ƒł�������Ă��܂���I
�������A�C���[�W�T�[�N�����ŁA�f�q���ړ��ł��镪�����ł�����A���̃u���͏��������m�Ɍ�����ł��傤�B
�ł��A�m���ɁA�����Y��{�f�B���߂ɌX���Ȃ���Ԃł́A���s�ړ��̃u�����ȒP�ɂ͉���Ȃ��قǂɖ����Ȃ��Ă��܂��B
�F����A�䑶�m�̒ʂ�AK-7�̓���́A�d�q���ł������Y���̌��w���ł�����܂���B�r�q�ɂ���ł��B
���Ђ��A����ŎB���f�q�V�t�g���ɂ���𓋍ڂ��Ă���A�Ƃ����b���Ȃ��̂́A���̕ӂ����R������̂ł͂Ȃ����ƁB
kuma_san_A1����Ƀ����N�ŋ����Ă����������T�C�g�ł̉���̂悤�ɁA�����̃R�j�~�m�̂`�r�ł́A
���s�ړ��̈ʒu�Ԃ�A�V�t�g�Ԃ�͂��܂��ł��Ȃ��̂�������܂���B
�������A�y���^�b�N�X�̌��݂̂r�q�ł́Akuma_san_A1���������ɂȂ��Ă��闝�_��
�ǂ����͂Ƃ������A���ɕ�ł��Ă��܂��̂ł��B���͋Z�p�I�ɂ͒m�����Ȃ��̂ŁA
������Ă�����e���A�Ԉ���Ă��邩�ǂ���������Ȃ��ł����A�ے肷��C������܂���B
�ł��A���ɂ́A�c��������b���Ĕ����Ă������̖ڂƂ�����Âɕ��͂��銴�o�ƁA������
���p�i�Ȃǂ��B�e���Ă�������ł̌o��������܂��B���������B�e���d�˂Ă������Ƃɂ���āA
������������ʑ̂�\�}�l�߂Ɍ������@��Ƃ��āAK20D��K-7��I�т܂����B
�Ƃ���K-7�́A���m�Ȏ��엦�ƖL�x�ȉ摜�����@�\�ŁA����܂Ŏg���Ă����S�Ẵf�W�J���ŁA
���̎B�e���@���ʑ̂ɁA��Ԍ����Ă���@�킾�Ɗ����Ă��܂��B
�i�����Ɛi������Ǝv���̂ŁA���@����y���݂ł��j
����́A�l�I�Ȃ������s�m���Ȍ��ł����������Ƃ��A�ЂƂB
�y���^�b�N�X�́A���ۂ̋@�\��\�́A��`��������������I�B�ƂĂ�����B
�m���ɁAK-7�̓v���~�A���X���[�������A�J�^���O�ɏ�����Ă��邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ���������܂���B
�ł��A����Ȃ������Z�p����������Ă����Ȃ��ł������B�@�����ƃA�s�[����������̂ɁI
���������܂������A�����̒��Ń����������Ă������m���A�X�b�L�����Ă悩�����ł��B�����܂��B
�����ԍ��F10859641
![]() 5�_
5�_
�����܂���A�Q�̏������݂��قړ����ɓ��e���悤�Ƃ��āA���Ԃ��ԈႦ�Ă��܂��܂����B
������́A�@[10859641]��[10859640]�́A���Ԃ��t�ł��B
���ۂɕ��͂��������̂́A[10859641]�̂ق�����ł��B���炢�����܂����B
�����̊��o���O��Ă��Ȃ����Ƃ������āA����ƃX�b�L�����܂����B
�m������́A���ɔ��f�͂����킹�邱�Ƃɂ��Ȃ�̂ŁA�����g�����ӂ��悤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10859643
![]() 3�_
3�_
���s�u��(�ʒu�u��)����ʂł킩��Ƃ����̂́A�ǂꂾ���ߐڂŎB�e�{�����オ���Ă���̂ł��傤���H
���s�u��(�ʒu�u��)�͎B�e�{���ɔ�Ⴕ�đ��傷����̂ŁA�ʏ�̎B�e�̈�ł͂قƂ�ǖ����ł���ʂł���B
�����u�����v�̏������݂����҂����Ă��܂��B
�����ԍ��F10859652
![]() 16�_
16�_
�����̃��X�A���肪�Ƃ��������܂��B
�Ȃɂ��A���m�ɂ킸���ȕ��s�ړ��̗h���u�����Č��ł���@�ނ�����A
�����p���ďؖ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����́A��������ł��Ȃ�ł��Ȃ��ł�����A�䎩�g�����������������Ă���ő��v�ł��̂ŁA
�䎞�Ԃ�����܂����ɂł��A�X����K-7�ȂǂŎ����Ă݂Ă��������B
�����A�����ݒ�͂�����������ł�����A��x�ł͏�肭�s���Ȃ���������܂���ˁB
����́A���̊��o�́A����قNJԈ���Ă��Ȃ����Ƃ������ʼn������̂ł����A���̂��Ƃł́A
���ꂩ���kuma_san_A1����⑼�̕��X�̂��������݂����Ŋw�����Ă����������Ƃ����邩�Ǝv���܂��B
�܂��ʂ̃X���b�h�ł��A���������݂�q������̂��y���݂ɂ��Ă���܂��B
����́A���ۂɎB�e���Ă���������Α��̊F���܂ł����邱�Ƃł��̂ŁA���̕҂��ł��ˁB
�����ԍ��F10859662
![]() 4�_
4�_
�����f�W�^���J�����ł����p�i���B��悤�ɂȂ��āA���N�ł��傤�ǂP�O�N��قǂɂȂ�܂��B
���̑O�ɂ�35����f�@�ł��������x�ɂ͎B���Ă܂������A�����R���f�W���ォ��́A
�{�i�I�ɋL�^����悤�ɂȂ�܂����B����̕����獜���i�܂ŁA�����Ďl�̎q������v���̃A�[�`�X�g�̍�i�܂ŁB
���̕���W����Ԃ��B�e���Ă���ƁA���������\�}�̋l�߂��d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�����R���f�W�����EVF�ł́A�f���͍r�����̂́A�Ȃ�Ƃ����ꂪ�B�e���ł��o�����̂ł����A
�f�W�C�`�������ہA���엦����95���̋@�킾�������̂ŁA���̗]�������l����̂��A
�����X�g���X�ɂȂ�܂����B����܂ł̋≖�̈��t�ł́A����قǂł��Ȃ������̂ł����B
�i��掆�ւ̈����L���̃T�C�Y�ɂ���Ẵg���~���O���A�悭����Ă����������Ǝv���܂��j
���X�����܂������A��U���̏�Ԃł́A�t�@�C���_�ƎB�e�����摜�̍\�}�̈ʒu�Y�����A
�ł����Ȃ��̂�K-7���Ɗ�����A�Ƃ������ł����A�ǂ���炱����A���������Ă������ƂŁA�Ԉ���Ă��Ȃ��悤�ł��B
�r�q�̎d�g�݂��A�V���b�^�[��鐡�O�Ńt�@�C���_�Ō�����͈͂��A�I�����ɑf�q��
��U���ł������Ă����Ǝ~�܂�ʒu�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ���A����ō����Ă���悤�ł��B
�����قnj����������āA�������̏��Ō������Ƃł�����A�m�͂���܂��B
������A�m���ł͂Ȃ��A���ׂČo���Ŋ����Ă������Ƃł��B�����悤�Ȕ�ʑ̂���B���Ă��܂�����B
���̂悤�ɁA���Ƃ��āA���o���A�X�y�b�N�̏����q�����킹���m�����A�����邱�Ƃ�����Ɗ����܂��B
����͂ǂ̕���ł������ł��B�������A�Ԉ�������ɂ͎����̒��Œ�����C�����錉�����K�v�ł��B
���́A���p�u�t�Ƃ��āA���k����B�̍�i�̋L�^����ʂɎB��̂ł����A�A��ēƂ�ŁA
�B�e�����摜������ƁA����Ŋ����Ă������͂⌇�_�Ƃ́A�܂��������ۂ��邱�Ƃ�����܂��B
��������āA���x�����x��������i�����邱�ƂŁA�l�p����ʂɐ���ꂽ�A�Ⴄ�p�x��ʒu����B����
��ʑ̂��A���������ǂ����Ď����̖ڂƊ��o�ň���Č�����̂��A�Ƃ������Ƃ��A
��Ћ߂��Ă��Ȃ����A���ɂ́A������A���ꂾ�����l���ĉ߂������Ƃ�����܂��B
����Ӗ��A�������ꂵ�������������Ă��邩��A���邱�Ƃ�����̂�������܂���B
�X����Ȃ̂��������ƂɁA�������J������p���Ă̎B�e�Ŋ����Ă��邱�Ƃ��A���X�������Ă��������܂����B
���͐�Ƃ̃J�����}���ł��L���l�ł�����܂��A�u����v�Ƃ������ƂɊւ��ẮA���ȃv���ӎ��������Ă��܂��B
���ꂩ����F�X�Ɗ��Ⴂ���邱�Ƃ��A�ԈႤ���Ƃ����邩�Ǝv���܂����A�ł��邾�����ꂪ�A
�ǂ������Ԉ�����̂��A�ǂ����Ċ��Ⴂ�����̂��A�Ƃ������Ƃ��l�������Ǝv���܂��B
�A�����X�A���炢�����܂����B�����͂��ꂩ��A�������炭������o������\��ł��̂ŁA�����������݂܂���B
���������݂����������F���܁A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10859670
![]() 3�_
3�_
PENTAX��SR�Łu�ʒu�Z���T�[�v���u�������o����Ƃ͏����������̂ŁA
MZ-LL���w�E��K20D�̃y�[�W�����Ă݂܂����B
�w�uSR�v�ł́A�W���C���Z���T�[���J�����̌X�������m�B
�@�ʒu�Z���T�[�Ƃ̃R���r�l�[�V�����ɂ��A�u����CMOS�Z���T�[��K�Ȉʒu�Ɉړ������A
�@��u����ł������܂��x
������ƞB���ȕ��͂ł͂���܂����A�u�������m����̂̓W���C���Z���T�[�ŁA
�ʒu�Z���T�[��CMOS�Z���T�[���ړ������邽�߂̂��́A�̂悤�ɓǂ߂܂����B
�w��u������ƁA�{�f�B���̃W���C���Z���T�[���u���ʂƃu�����������m���܂��x�Ƃ�
�L�q������A�Ԃ�̌��m�̓W���C���Z���T�[�i�̂݁j�ōs���Ă�Ɠǂނق������R�Ǝv���܂����B
�����Akuma_san_A1����̍ŏ��̕��̏������݂Łu�������Ă��炤�v�̂́A
����͂���ō���Ǝv���܂���B
���Ȃ݂Ɏ���K-7�����Ă܂����A�V�t�g�Ԃꂪ�����Ă���Ƃ͊m�M�ł��܂���B
�Ȃ��Ȃ�A�u�����ȃV�t�g�����݂̂̃u���v���Č��ł��Ȃ�����ł��B
�u�����Y��{�f�B���߂ɌX���Ȃ���Ԃł́A���s�ړ��̃u���v���ǂ̂悤�ɍČ����ꂽ�̂����A��������܂��B
�i�莝�����ƁA�܂��������Ǝv���܂����E�E�E�j
MZ-LL����A���炭�������݂ł��Ȃ����ɏo��������悤�ł��ˁB
�����C����������A�����Ă���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10859679
![]() 10�_
10�_
Op555����A���������݂��肪�Ƃ��������܂��B
�܂��Ƃ��o�ĂȂ��ł���B�܂����ƈꎞ�Ԉȏ�͂���܂��B�g�x�x�̎��Ԃ��K�v�ł��̂ŁB
�ڂ����́A����܂��������Ă������������v���܂����A�Z���T�[�̌������ǂ��ł���A
�܂��͎��ۂ�K-7�����C�u�r���[�⓮��ŁA�L�b�g�����Y�ł��P�œ_�ł��ǂ��ł�����A
�߂���ʑ́i���{�ȏ�̃}�N���łȂ��ق����������ėǂ��Ǝv���܂��j���ʂ��Ă݂Ă��������B
�����āA�J�����������Y�Ƃ̃��C�����ł��邾�������Ȃ��悤�ɁA���E�ɗh�����Ă݂Ă������B
�p�x�ȂLjȏ�ɁA���E�̓������W���C���őł�������Ă��邱�Ƃ��ȒP�ɉ���܂���B
�������A����Ń����Y�ƃJ�������x���܂��B
�R�c�́A�C���[�W�T�[�N���̍L�����A��⓪�ŁA������x�C���[�W���āA
�f�q�����̒��œ����Ă��镝���A���o�I�ɃV���N�����āA���E��㉺�ɐU�邱�Ƃł��B
�����A���������A�܂������������ł́A�㉺�������E�̂ق����A�l�Ԃ̘r�̍\�����炩�A
�p�x���t���Ȃ��悤�ɁA�h����₷�������ł��B
���Ƃ��ƁA�V�t�g�Ԃꐬ���𑽂��܂ރu���̕�Ɋւ��ď����Ă���킯�ł�����A
���S�ȕ��s�ړ��łȂ��ėǂ��̂ł��B�ł����炩�ɕ��s�ړ��̓������A�ł�������Ă���̂��A
�����C�u�r���[�Ȃ����܂��B�܂������Ă��������B
�l�b�g��̌f���ȂǂŁA�ϋɓI�ɏ��������̒��ɂ́A�������߂���\�͂ɒ������l�������Ǝv���̂ł����A
�ǂ����������ޑO�ɁA���x�����ۂɎ����Ƃ��A�g�̂Ŋo����A�Ƃ����̂����ȕ��X�������悤�ł��ˁB
�u���̓x��������A�p�x�����Ŗ������Ƃ��A�n�b�L������͂��ł��B
�܂��́A�C���[�W�T�[�N���̑傫�����A�J�������\�����ۂɁA�W�����Ĉӎ����Ă��������B
�����đf�q�̑傫���Ɠ������B
�����ԍ��F10859710
![]() 2�_
2�_
���ۂ�LV�Ō����肵����ŏ������̂ł����ǂˁB
�����������Ȃ��悤�ɏ������̂́A���X�S�O�ł����B
MZ-LL�������ꂽ�͂킩��܂����B���ԐM���肪�Ƃ��������܂����B
MZ-LL����Ƃ͈قȂ鎩���Ȃ�̔��f�͂���܂����A
�����̊��o�_�̂Ԃ������ɂȂ�̂ōT���܂��B
�����ԍ��F10859738
![]() 9�_
9�_
�����܂������̓x�f�l�Ł@�ʔ������e�̂悤�œǂ܂��Ă��������܂������A���e�𗝉��o���܂���B�B�B
�f�l�Ȃ���ɒm���Ă���̂́A�R���f�W�͓d�q�I�ɑg�ݍ��킹�ĕ���A���̓��j�A�ɂ���ĉ����Ŏ�U��������p�r���嗬�̂悤�ł��ˁB�����ă��j�A������p���ăY�[�~���O���J���\���ł͂Ȃ��A�c�����j�A�ŃY�[�~���O�ړ�������悤�ȊJ�����i��ł���悤�ł��B�߂�T�Ђ����肪�o���悤�ȁB�B�B
���܂�����Ŏ��炵�܂����B�B�B
�����ԍ��F10859799
![]() 5�_
5�_
�l�H�I�Ɂu���s�i�c���A�����u�����v�����āA�j�|�V�̃e�X�g���������ʂ��A�A�T�q�J�����Q�O�P�O�N�P�����j���[�t�F�[�X�f�f���ɂ���܂��B����ʂ��܂����������Ȃ������ƂȂ��Ă��܂��B
��Ԃ����ʂ̐f�f�ړI�̂���̂悤�ł������A���̃e�X�^�[�́A��Ԃ����p�x�u����������̂ƒm���Ă��Ȃ������悤�ł��B
����ʂ��܂����������Ȃ������ƌ����Ă��܂����A���̗��R�Ƃ��Ď��R�Ȏ�u���Ƃ͈قȂ�U�����g���ł��邽�ߔ������Ȃ������Ȃǂ̗��R�ƍl�����悤�ł��B
���s�u���Ȃ̂ŕ���ʂ����������̂����R�ŁA�U�����g���������Ƃ����̂͊ԈႢ�Ǝv���܂��B
���̃e�X�^�[�̕��́A��Ԃ��̌�����m�炸�ɁA���̑��u��p�ӂ������̂Ǝv���܂��B
�����܂ł������ł����A�����Y����ɂ���{�f�B����ɂ���A�p���x�Z���T�[�i�W���C���j�Ńu�������o���āA�����ƃC���[�W�Z���T�[�ʂƂ𑊑ΓI�ɃV�t�g���邱�Ƃł́A�����ł��ˁB
�v��̃A�N�`�F�[�^�[�̍��₷���A�R�X�g�z�����̑��A�ׂ��ȂƂ���Ȃǂł͈Ⴂ���L��Ǝv���܂��B
��Ԃ��Ƃ͕ʂɂj�|�V�ɂ́A�摜�̌X���̕�i����������j������܂�����A�f�Z���T�[���L��Ǝv���܂����A�ʂ̌n�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10860082
![]() 18�_
18�_
�莝���ō\�}�Ƃ����엦�Ƃ��c�_����̂͏�k���Ǝv���܂���
�X���̎��͕���ʂ̈Ⴂ�Ƃ������ƂȂ̂ł����̓X���[���܂��D
�����������̂ł����C��r����Ă���̂�
>30cm�قǂ̔�ʑ̂�50mm������ŎB�e
>�B���f�q���ʕ����ł̃u���i�V�t�g�u���j���r
>�@�ނ�20D 18-55IS�@K-7, K-20 18-55
>20D 18-55IS�ɃV�t�g�u���̕�͂Ȃ�
>K-7 18-55���ƃV�t�g�u�������Ă���
>�̊����@�u���C�u�r���[�����掞�̂r�q�삳���邱�ƁI�v
�Ƃ������Ƃ�kiss X3�Ƃ��Ń��C�u�r���[�Ƃ������IS���쓮������̂�
��r����̂������悤�Ɏv���܂����D�����Y��18-5IS��100/2.8LIS��
�悳�����ł��ˁD
>EOS 20D��EF-S18-55mmIS
>�ߋ����ŏ����߂̔��p�i��G��Ȃǂ��B�e
>�t�@�C���_�̒��Ŋm�F�����\�}�ƁA�B�e���ꂽ�摜�͈̔͂�
>�悭�Y���Ă��邱�ƂɋC�����܂��B
���엦�ȊO�̃V�t�g��ɂ��Y�������o���Ă���̂ł��傤���H
�������ł��ˁD
>K-7�Ŏ����Ă݂Ă��������B
>���엦���قڊ��S��100���ł���K-7�́A
>���̌덷�����Ȃ����Ƃ��A������₷���ł���B
�Ȃ王�엦�̖��ł́H
>����I�t�ɂ���ƁA���Â��Ƃ���ł̓u���܂����A
>�\�}�̃Y���͊����܂���B
�Ԃ�Ă�ƍ\�}�𐳊m�ɔc���ł��܂���w
�x�[�X���v�����݂��Ƌc�_���Ԃ�܂��D
�����ԍ��F10860645
![]() 8�_
8�_
�ȒP�ɃC���[�W���Ă��炢�܂��傤(�l�ɂ���Ă͊ȒP�ł͂Ȃ���������܂���)�B
��Ԃ̎ԑ�����̕��i�ł��B
��Ԃ̑��s�����������ł͉����̌i�F�͂������Ɨ���A���H�e�̓d���Ȃǂ͂т��т����ōs���܂��B
���ꂪ�u���s�u���v�u�V�t�g�u���v�u�ʒu�̃u���v�ŁA�^�[�Q�b�g�ƂȂ鋗���Ńu���ʂ��Ⴂ�܂��B
�t�Ɂu�p�x�u���v�͗�Ԃł����J�[�u�𑖍s���Ă��鎞�̊O���̌i�F�Ƃ��A�J�������p���j���O������Ԃ��v�������ׂ�Ώ[���ł��傤�B
�p���j���O�ł����Β��L�p�����Y�Ńp���j���O����Ɓu������v�Ȃ̂��킩��Ǝv���܂�(�K�v��ʂ���ʎ��ӂł͕s������b)�B
�����ԍ��F10860920
![]() 8�_
8�_
���A�}篁A�����ɋA���Ă��܂����B
���_���炢���܂��ƁA���̃X���b�h�ŁA����SR�⎋��Ɋւ��ďq�ׂ����Ƃ́A
�قڂ��ׂĐ������������ƂɂȂ�܂����B
���Ѓ��[�U�[����B���A�܂����������������̂��Ƃ������Ă��āA�����A���Ă��܂��܂����B
���́A�����A�A���̓r���ɁA�y���^�b�N�X�ɒ��ږ₢���킹�āA�����ɁAK-7�Ȃǂ�SR��
���s�ړ��̃u������ɑł������A�ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ͉���܂����B
�����A�O�̂��߁A���ۂɂǂ������d�g�݂Ńu����ł������Ă���̂��A���엦�̂��Ƃ��m�肽���������߁A
�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̕��ƁA�P�P�ŁA�����Ԃ��b�����Ă��������@������������܂����B
��ϊy���������ł��B�����āA�����l���Ă������ƁA�����Ă������Ƃ��A�{���̂��Ƃ�������ł�����B
���������ŏ����Ă������Ƃ́A�����قڂ��̂܂܁A�����ł����B
�W���C���ŁA���V�����f�q���ʒu�����ɕۂ��A�{�f�B���̗h��ɑ��đł������B
���m�ɂ͏�肭�����Ȃ��ł����A�܂���������������߂āA�����A�����Ă������Ƃ������܂����A
���̊��o�┻�f�́A�܂������Ԉ���Ă��܂���ł����B�@�ق���݂�A���Ċ����ł��B
�����A�����ŁA�Ƃ�ł��Ȃ����_��W�J���Ă��������A�ǂ̂悤�ȕېg��}�邩�������̂ł��B
���x���������悤�ɁA�l�b�g��G���̏����Ȃ����킹������̋�_�����A
���̂悤�ɁA���͂Ɗ��o���ǂ��l�Ԃ��A��R�̎B�e���o�āA�����Ƃ��Ĕ��f�������Ƃ̂ق����A
�������Ƃ������Ƃ́A�悭����̂ł��B
�O�ɏ������ʂ�A���C�u�r���[�⓮��Ȃ�A�ʒu�Ԃꂪ�����Ă��邱�Ƃ��A�܂�킩��Ȃ̂ł����ǂˁB
�����A�����łƂ�ł����_��W�J���Ă����l�����̌���̂Ђǂ��⊴�o�݂̓��ɂ́A
�������肳�����܂����B������Ӎ߂̏������n�߂��ق��������Ǝv���܂��B
�͂�����ƁA�f�q�̕��s�ړ��ɂ��A�ʒu�u���i�V�t�g�Ԃ�j�̕�ł���A�����āA
�p�x�Ԃ�ɂ́A���܂蒍�ڂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ���������Ă��܂����B
���̕ӂ�́A�܂��ڂ��������܂��B
�������A�������ŁA�Ԉ�����F�����A���������Ƃ���Ƃł��v�����̂ł��傤���B
���x�����Ⴗ���܂��B
�����ԍ��F10862019
![]() 4�_
4�_
�������A�Ȃ�ł���ȍ������������l�������A��R����̂ł��傤�ˁB
��Ԃ��I���̏�ԂŁA�\�}���l�߂��āA�قڐ��m�ɔ��f�����̂��{���̂��ƂȂ̂ɁB
���ۂɎg���Ă����Ȃ��A�������͎g���Ă��Ă����o���݂��Ď����ł��Ȃ��A���������l�������A
�l�b�g��{�ōL���W�߂������Ȃ��ł́A�Ƃ�ł��Ȃ����_��W�J���āA���������Ƃ�ے肷��B
�����{���ɁA�������A�Ƃ������A�����b�ł��B
�����A�X�b�L�����܂����B���ۂɁA�����ƃz�[���f�B���O���āA�����̓��ӂȔ�ʑ̂�
�B�e����A���ꂪ�ǂ�������ނ̃u���̗v�f�������̂��A�Ƃ��A����Ƃ킩���Ă���
�͂����ƁA���͎v���Ă�����ł����A���܂����Ȃ��l�������݂����ł��ˁB
�ʃX���ōŏ��ɏ����܂����ʂ�Akuma_san_A1���Q�ƂɏЉ�ꂽ�T�C�g�̏��́A
���炭�Â����A�B���f�q�V�t�g���͉�����s�����Ă����̂ł��B����Ȃ̓ǂ߂A�������邶��Ȃ��ł����H
�킴�킴��-�V�ƁAK20D�̕�̎d�g�݂̈Ⴂ������悤�ɁA�����N���Ă������̂ɁB
K20D�̐}������A��������A�ʒu�Ԃ��ł�������ł��邱�Ƃ��A�����ɉ���̂ɂȂ��B
�������A���x�����Ⴗ����B����ȂɃK�b�J�������̂͏��߂Ăł��B
�����ԍ��F10862068
![]() 3�_
3�_
���̃X���b�h�̃g�b�v�ɖ߂�A�A
�u��U���̌��ʂ̈Ⴂ�v�́A�p�x�u��������@�\�ɑ��āA�͂����肠��悤�ł��B
�������A�Ȃ��p�x�u�����y���^���ϋɓI�ɕ���Ȃ����A�ƌ����A�≖���ォ�炿����
�J�������\���ĎB�e�ł���l�́A�قƂ�NJp�x�u�����N�����Ȃ��̂ŁA��������z�[���f�B���O���Ă�
�ǂ����Ă��o�Ă��܂��A�S���̌ۓ����炭����u���ɍ��킹��������邱�Ƃ�A
�ʒu�u�����A�W���C���Ń{�f�B�̓�����ł��������ƂŁA�B�����Ă���悤�ł��B
K-7�ɂ������ẮA�i�����́j��]�����̃u�����ł�������̂ŁA�V���b�^�[������u�ԁA
���Ƃ��A�E������ŃJ�������P�x�X�����Ƃ���ƁA�f�q�������ł��������Ύ���ɌX���A
���̏�Ԃ̂܂܁A���E��㉺�����̕��s�ړ������Ĉʒu�u�����ł����������ł��B
�t�@�C���_�Ŋm�F�����\�}���A�L�^�����摜�ɐ��m�ɔ��f����闝�R���悭����܂����B
�������A�ق�ƁA�Ȃ�ł���ȍ����ԈႢ�������A�̂����ɏ�����Ȃ�āc�B
�����ԍ��F10862093
![]() 3�_
3�_
�X���b�h�̎�|�ɂ����āA��ӌ���g�p���������������̂́A�ŏ��Ƀ��X�����������A
ken-san�����ł��ˁB�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��I
�@���ǂ�����Ⴂ�͊����܂���B
����́A�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̕�������������Ă����\���Ō����A
�u�����ƃz�[���f�B���O���ł��Ă��邩��v�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
��͂�A�u�r�v�Ȃ̂ł��ˁB
���S�ҁE����҂̕��X���A�ǂ�ȃu���̎d���ŋN�����₷�������A�g�U���U���������
�ڂ��������Ă��������܂����B�Ԃ��̐��E�́A�܂��܂��[�����ł��B
�����ԍ��F10862134
![]() 6�_
6�_
K20D�̕�@�\�̓����}������A������������Ƃ͎v���̂ł����A�����A�����Ă������Ƃ�
��肭�����邩����܂��A�������Ă������Ǝv���܂��B
�V���b�^�[���ۂɁA�ʒu�Z���T�[���A�w���W�Ƃx���W������o�����ʒu�ŁA
�B���f�q�̏ꏊ�����ɕۂ��A�{�f�B���h�ꂽ��ʒu�u�����肵�Ă��A�W���C���Z���T�[�ŁA
�f�q���A���̗h���ʒu�Ԃ��ł����������Ɉړ�����B
�����́A����Ȋ����̘b�������Ǝv���܂��B�Ƃɂ����A�o���Ȃ��Ƃ������ŏ����ꂽ
�W���C���ɂ��ʒu�u���̕���A�y���^�̂r�q�͕��ʂɂ���Ă��܂��Ă���킯�ł��B
�����āAK-7�ɂ������ẮA�i�f�q�̌����ɑ��Đ����́j��]�����̃u���܂ŁA���m���āA
�ł������悤�ɕ���Ă��܂��킯�ł����A�{���ɂ������e�N�m���W�[���l�܂��Ă���̂ł��ˁB
�Ȃ��A���������ʁA�ǂ��Ɣ�ꂪ�ł܂����B
��͂莄�ł͏�肭�����ł��܂���c�B�܂����߂āB
�����ԍ��F10862219
![]() 3�_
3�_
�������Ă݂�ƁA
�E�y���^�b�N�X�̂r�q�@���@�����ƈʒu�u��������B���������\�B
�EK-7�̂r�q�@���@��]�̃u�����ł������ĕ�B�������@�\�B
�EK-7�̎��엦�@���@�����̂����̂������d�g�݂��Ă��܂����i����͌���j
�EK-7�̃t�@�C���_�ƋL�^�摜�@���@����ς�덷�����Ȃ��͍̂����Ă���B
�ق��ɂ��AK20D��K-x�Ɋւ��Ă��A���낢��Ƌ����Ă��炢�܂����B
�l�b�g�Ō��������Ă����܂�o�Ă��Ȃ��r�q�̏ڂ����d�g�݂��A���낢��ƒm�ꂽ�̂͗ǂ������ł��B
K-7���������@�\��x�����낢��Ƌl�ߍ���ł���̂��A�悭����܂����B
�{���Ƀy���^�́A�����Ƃ��������@�\��ϋɓI�ɐ�`���Ă������̂ɂȁA���Ċ����܂����B
��Ԃ��A�ӊO�Ƃ܂���ʂɂ͓`����Ă��Ȃ����Ƃ������ł��ˁB
�V�������C���i�b�v�̗\����A���͂�����Ə����ɂ͂��̂ł����A����͂܂��閧�Ȃ̂��ȁB
�����ԍ��F10863354
![]() 4�_
4�_
����Ȃ�ł��������X���b�h�����グ���Ă����f������R�R�Ō��J���Ă�
�Ƃ����K-7���Ă���Ȃɗǂ��́H
�����Z���T�[��K20D��K-7�ŎB���ׂ����Ƃ��邯��
K-7��K20D�̔{���炢�m�C�Y�����
�����ԍ��F10863768
![]() 14�_
14�_
MZ-LL�����A�N�ɋ����Ă��낽�m��ǁA
��]�̃u����ł������ĕ�H�H�H�H�H
�������Ă��珑������ł���ւ��납?
�����ԍ��F10863881
![]() 13�_
13�_
�u�t�@�C���_�[�Ō����\�}�ƁA���ۂɎB�ꂽ��̍\�}�������Y����ɔ�ׂă{�f�B����̂ق�������Ȃ����������v
�Ƃ����咣�ŗǂ��ł��傤��?
MZ-LL����ɓ��Ă͂܂邪�ǂ����킩��܂��A
�t�@�C���_�[�����ߐM���ăz�[���f�B���O���Â��Ȃ����ꍇ�ɋN���邩���m��܂���B
�����Y����̋@�̂������Ă��Ȃ��̂ł����܂őz���ł���...�B
(1)�t�@�C���_�[�ō\�}�����߂��Ƃ��ɕ���̌��E�߂��������B
(2)�V���b�^�[������������ɕ������B
(3)���̂܂܂��ƂԂ��̂ŁA������Y�����������ɖ߂��B
(4)���ʂƂ��č\�}�������B
�Ƃ����X�g�[���[���l�����܂��B
�܂�A�z�[���f�B���O�̊Â��������ŁA����E����ǂ���̕����ł��\�}������邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10864387
![]() 2�_
2�_
�@
�����́B
MZ-LL����
���C�u�r���[�̎����������Ǝv���Ă�������Ɏ�����Ă��܂����ˁB
���C�u�r���[�ł����h��Ă���̂��m�F�����̂Ȃ番����Ǝv���̂ł����A
���̂����h��Ă���ǂ����̏u�ԂŃV���b�^�[���Ă���̂��Ǝv���Ă���̂ł����Ⴂ�܂����H
�������Ƃ���ƃt�@�C���_�[���Ǝ���ʂ������Ɉ�v���Ă���u�Ԃ��Ă킸���Ȋm�����Ǝv���Ă��܂��B
���̗���s���ł��傤���B
>> K-7�̎��엦�@���@�����̂����̂������d�g�݂��Ă��܂����i����͌���j
�����v���Ă�����@�ł����A�Z���T�[��d�C�I�Ȑ���ŌŒ�Ȃ�ړ����Ă��܂���ˁB
�Ȃ̂Ŗʓ|�ȕ����ł͂Ȃ��A�\�t�g�֒����l�̃p�����[�^��^���Ē����ł���͂����Ǝv���Ă��܂��B
���엦100%��ቿ�i�Ŏ��������̂͂��̕��@���Ǝv���Ă���̂ł����E�E�E
����̃l�^�炵���y���݂ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F10864450
![]() 2�_
2�_
���낢��Ƃ��C�������������Ă��܂��āA�\����܂���B
���������A�����ƋZ�p�I�Ȓm���Ƃ��A�H�ƕ���ɂ��ďڂ������
��肭�����ł���Ǝv���̂ł����A���ǁA���̏ꍇ�A�������g�����
�Q�l�ɂ�����Ƃ��̃��x���Ō�b���Ă��܂��Ă���̂ŁA
����̑̂ɂȂ��Ă��Ȃ��Ă��݂܂���B
�f�q�̉�]�i�X���j��́A�p�x���������ł���ȏ�A�������������ɓ�����̂͑����Ă����̂ł����A
�܂����A��Ԃ�������]�i�X���j�Ȃ���o����Ƃ́A�v���Ă����܂���ł����B
K-7�̃V���b�^�[�́A�▭�Ȋ��G�ł�����A�������ƂŌX���Ă��܂����Ƃ͖����Ǝv���̂ł����A
�����A�E������⍶������ŁA�킸���Ƀ{�f�B����]�����ɂ킸���ɌX�����ꍇ���A
�f�q�������ł������p�x�Ŕ���]�ŌX���i�������X���̌��x�͂���Ǝv���܂��j�A
�I�����A�X�����܂܁A�ʒu�u����f�q�̈ړ��őł�����������s����悤�ł��B
�Ȃ��������e�N�m���W�[�ł��ˁB���͋@�B�̂��ƁA�Ȃ�ɂ�����Ȃ��̂ł����A
�������ɁA�t�@�C���_�Ŋm�F�����摜���A���̂܂܋L�^�����̂������̂́A
���̋@�\�����ʓI�ɓ����Ă���̂��Ǝv���܂��B
�O�ɉ��x���AK-7���ƁA���m�Ȏ��엦�̃t�@�C���_�Ȃ������A�莝���ł��l�p���G���
�^���ʎB�e���A���������₷���A�Ƃ������Ƃ����������ŏ�������������܂��A
���̉�]�����̔����ȌX����������Ă���̂�������܂���B
�t�@�C���_���ŁA�G��̏�ӂ��t�@�C���_�g�ƕ��s�ɂ����ۂɁA���̕��s�̃q�b�g�����A
���̃J�������������̂ł��BK-7�A�v���������A�����̎B�e���@�Ɍ����Ă���@��̂悤�ł��B
�����ƁA���̗D�ꂽ�@�\���������J�����̖{���̔\�͂��A�����Ȑl�ɒm���Ă��炢�����ł��B
�����ԍ��F10865215
![]() 3�_
3�_
�����܂���A�������Â��L�[�{�[�h���ςȃm�[�gPC�ŏ����Ă�̂ŁA�܂��܂����͂��ςɂȂ��Ă܂��B
�@��K-7�̃V���b�^�[�́A�▭�Ȋ��G�ł�����A�������ƂŌX���Ă��܂����Ƃ͖����Ǝv���̂ł����A
�u���܂薳���Ǝv���̂ł����v�̊ԈႢ�ł��B�������ꏭ�Ȃ���A������x�́A
�V���b�^�[���ȏ�A�����ȌX����A�����Ȉʒu�Y���͋N����܂���ˁB�����܂���B
�O�ɂ����̘b�́A�ǂ����œǂC������̂ł����A�J�����̍\�����������肵�Ă���l�ł�
�N����₷���A�S���̌ۓ��i���Ԃ�ؓ��̐k�����j�ɂ����u���ɔg���H�����킹�����
���Ă���̂��A�ʔ����ł��ˁB������Ԃ��ł��A���ЂƂ͈Ⴄ�l���Ō��ʂ��l���Ă���A
�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����������Ă����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10865242
![]() 2�_
2�_
�܂����ȃ��X�ł��B
�@��K-7�A�v���������A�����̎B�e���@�Ɍ����Ă���@��̂悤�ł��B
�u�v�����ȏ�ɁA�v�̊ԈႢ�ł��B�@�����Ă���A�Ǝv���čw�������̂ł����A
���ۂɎg���Ă݂�ƁA���̂����������Ă���̂ŁA�B�邽�тɃr�b�N�����Ă܂��B
���͂��Ƃ��ƁA������ƌÂ����̂��D���Ȃ̂ŁA�≖�ł��f�W�J���ł��̂̋@������ł�
���X�g���̂ł����A��Ԃ��Ɋւ��ẮA�y���^�b�N�X�͐V�@����X�V���邽�߂ɁA
���x����ʂ����߂Ă���C�����܂��B
����Ō��������Ă������ɁA�ȑO�ɂ�������Ɠǂ�ł����AK10D���������������́A
K100D�̊J���҂̕��X�̍��k��`���̃C���^�r���[�ŁA��Ԃ��Ɋւ��āA
���낢��ƌ���Ă����l�b�g�L�����o�Ă����̂ł����A������ō�����ׂĂ������ɂЂ�������܂���ł����B
�����������ł́A��Ԃ�͂�͂�A��ʑ̂܂ł̋����ł��Ԃ�����Ⴄ����A��̌��ʂ����킹�Ē������Ă���A
�悤�Ȃ��Ƃ����Ă܂������A��͂�L�p��̂ق����A������ʂ������A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�
�b����Ă����悤�ȋC�����܂��B����ɖ߂�AURL���R�s�y�Ń������Ă܂��̂ŁA
�����N�ŏЉ���Ă������������Ǝv���܂��i���łɑ����̕����ǂ܂�Ă���L�����Ǝv���܂����j�B
�����ԍ��F10865291
![]() 2�_
2�_
��K20D�̐}������A��������A�ʒu�Ԃ��ł�������ł��邱�Ƃ��A�����ɉ���̂ɂȂ��B
���̕��͂���A�����炭�ʒu�Ԃ�i�V�t�g�Ԃ�j�̌��t�̈Ӗ����������Ă�̂��Ǝv���܂��B
���������ɑ����Ԃ��̂��V�t�g�Ԃ�E�E�ł͂Ȃ��ł��B
�J���������������ɕ��s�ړ����邱�Ƃɂ���ċN����̂��V�t�g�u���A�X�����ƂŋN����̂��p�x�Ԃ�B
���p���ꂽ�}�ɂ́u�J���������ɌX�����ꍇ�v�Ɛ���������A�p�x�Ԃ�̕�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B
�����ԍ��F10865674
![]() 13�_
13�_
�����������ʂ�A�����ʂ�A�u�}������v�Ƃ������Ƃł���B
���̉�����̂��Ƃł͂���܂���B
��[���A���̐}�ƁA���V�̐}���ׂČ��܂��傤�B
���Ɍ����BK20D�ł́A�̃��C���ƐԂ̃��C���B
�������ǂ��Ƃ��łȂ��āA���ۂɃV�t�g�u���������Ă��āA�y���^�̐l���A
�ʒu�u�������Ă���ƃn�b�L�������Ă����B
�����������������悤�Ȕ�ʑ̂��ʂ��Ă��āA�����Ă������Ƃł��B
������ƃJ�������\�����Ă��邩�炱���A���������Ƃ炵���ł��i���������܂����j�B
�p�x�A���Ă����ȈӖ�������Ǝv���܂��H
�u�p�x�u���v�̊p�x�̂��Ƃł͂Ȃ���������܂����H
����������ƁA�������Ă݂܂��傤��B
�����ԍ��F10865707
![]() 3�_
3�_
gintaro����@�̏�����Ă���ʂ�ŁA������Ďv�����Ƃ����Ƃ���ł��ˁB
�u�ʒu�u���v(�u�V�t�g�u���v�u���s�u���v)��������Ă���Ɗ��������烊���N�ȂǏЉ���̂ł����A�u��Â��v�Ɨ��܂����B
����������ė������Ăق����̂ł����A���������ł��ˁB
�����ԍ��F10865721
![]() 17�_
17�_
�����Ɍ����BK20D�ł́A�̃��C���ƐԂ̃��C���B
�u�p�x�u���v����Ȃ��ł����B
�����ԍ��F10865742
![]() 9�_
9�_
�̃��C�����ɁA�{�f�B�̂���ł������āA�ړ����Ă����ł���B
���������A��ÂɌ��܂��傤��B
�������A�p�x�u���ƈʒu�u�����A���S�ɕ�����͓̂�����A
���̊G�ł́A�C�����߂ɂ��X���Ă܂���ˁB�ł��������|�C���g�ł͂Ȃ���ł��B
���ۂɃy���^�̃J�������g�p���Ă���l�Ȃ�A�܂������ł���\���͍�����������܂��A
�f�q�̓����������ƃC���[�W���Ă���������I�@�{���Ɋ��o���݂����܂���B
�C���[�W�T�[�N�����ŁA�ʒu�Z���T�[���f�q���A��ԂɃW���C���ŁA�قڌŒ�H���āA
�{�f�B������u���œ����Ă��A���ɕ������悤�ɁA�f�q�͓����Ȃ��̂ł��B
������K-7�͌X���܂ŁA�ł���������������قǂ̋@�\������܂��B
�ǂ��l���Ă��A�ʒu�u���̕�ł��傤�B���x���������Ƃ���A�ǂȂ������A
�o���Ȃ��A�Ȃ�ď����Ă����A�f�q�̓������A�y���^��SR�ł͏o���Ă��܂���ł�����B
�{���ɁA�������ޑO�ɁA���������A�悭�m�F���܂��傤��B�������܂���B
�܂������������������݂𑱂���Ȃ�A���ʓI�ɍr�炵�I�ȍs�ׂɂȂ�Ǝv���܂��B
���肵�ĂȂ��ł�����A�����䎩�����g���Ă���@��̎�Ԃ��ƁA
�y���^�̂�������ۂɎg���Ă݂āA�Ⴂ����������A�����Ȃ������肵����A
��������ł݂Ă��������B�X���b�h�̎�|�́A�\���ł�����ˁB
�l�̎�ςł�����A���ۂɎg���Ă�����X���A�Ⴂ�������Ȃ����Ǝ��͕̂ʂɂ�����ł��B
�ł��A�͂��߂��玄�̏����Ă��邱�Ƃ��A�܂�Ŋ��Ⴂ���v�����݂̎Y���̂悤�ȏ����������Ă�����A
�b���ʂȕ����ɍs���āA���R�ł���B���������A����A�����ƁA���������������Ȃ����Ƃ��A
�o���Ɗ��o�Ō�������l�Ԃ�����A���Ă��Ƃ�m��܂��傤��B
���傤���Ȃ��ł���B���́A�q���̍�����A���������̂߂��Ⴍ����ɒb���Ă��Ă��ł�����B
����ł��A�ԈႤ���Ƃ����邵�A����Ȃ����Ƃ�����܂����ǁA�����Ă��Ȃ���ԁA
�u������Ɗ������v�Ƃ������x���ł́A�킴�킴�X���b�h�𗧂��グ���肵�Ȃ��ł���B
�����Ȃ�ɁA������x�A�����Ƃ��ĉ���܂Ŏg��������A���������̓A���ł����ǁA���̃X���𗧂Ă��̂ł��B
������A�������I�ɂ́A���̂ق����A��ΓI�ɕs���ł��A�����������Ă��邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ������̂ł��B
�ł��A���R�A�����������玩�����Ԉ���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɖ��x���l��������A�������ݒ��ɁA���ۂɎ茳��EOS 20D��K20D��K-7��u���āA������m���߂Ȃ���A�g�p���������Ă����܂����B
���́A�^��������قǁA��Ɏ������^���Ă��܂��B�����炱���A���p�ł��������d�����ł��邭�炢�A
�q�ϓI�ȏ����Ƃ����\�ł����A�����͐l���炷�����M������Ă��܂��B
�ł��A���͋��Ȃ��Ƃ��炯�ł��B�����x�����A�����@���悭����܂���B
�u�ځv�Ƃ������犴�������m���A�������l�������Ĕ��f����A���̒T���S���ُ�ɋ����̂ł��B
���������l�ԂȂ̂ł��B�ł�����ȊO�̓��Z�́A�Ƃ��ɂ���܂���B
���������ӂȕ���̓��ӂȂ��Ƃ������Ă��邾���Ȃ̂ł��B���������ꂷ����X�A�^���Ă��܂��B
�������O�̃��X�ŁA���̂��Ƃ��u�Ȃ�ł������̍l�����������Ǝv���Ă���v
�Ȃ�ď������݂��Ă���l�����܂����A����͑傫������Ă��܂��B
���́A�Œ��ꒃ�Ɏ����s�M�Ȑl�Ԃł���B
�����ԍ��F10865810
![]() 4�_
4�_
���̃��C�����ɁA�{�f�B�̂���ł������āA�ړ����Ă����ł���B
�����������A��ÂɌ��܂��傤��B
�}�́A�p�x�u���̐����ł��B
���������A�p�x�u���ƈʒu�u�����A���S�ɕ�����͓̂�����A
�����̊G�ł́A�C�����߂ɂ��X���Ă܂���ˁB�ł��������|�C���g�ł͂Ȃ���ł��B
�p�x�u���ƈʒu�u���Ƃ́A�Z���T�[�̈Ⴂ�Ŋ��S�ɕʂɌ��o����܂��B
�p���x�Z���T�[�i�W���C���j�ł́A�p�x�u���̂��o�ł��܂��B
���Ȃ݂ɁA���̃Z���T�[�́A�Z���~�b�N�U���W���C���ŃC���[�W�Z���T�[�ڕ��ׂɏo����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�p���x�ɔ�Ⴗ��d�C�M�����o�͂��A�A�N�`�F�[�^�𐧌䂷���H�ɓ��͂���܂��B
��u���̈ʒu�u���́A�n������Ƃ���ʒu�ł�����A�ʓr�̌��o��i��K�v�Ƃ��܂��B
�j�|�V�̎�Ԃ��@�\�̒��ɂ���ʒu�Z���T�[�́A�C���[�W�Z���T�[�̎��t���ɑ��Ă̓����̊�ʒu�ł��B
�����ԍ��F10866068
![]() 17�_
17�_
���͋Z�p�̒m�����Ȃ��̂ŁA��肭�����Ȃ��̂ł����A
�y���^�̃Z���T�[�́A�ʒu�Z���T�[���Ǝv���܂����A
��Ԃ̎B���f�q�̈ʒu���A�w���W�Ƃx���W������o���ċL�����āA�ʒu��ۂA
�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����������Ă����Ǝv���܂��B
��������ȏ�m�肽����A�y���^�b�N�X�ɒ��ږ₢���킹�Ă݂Ă��������B
���̒m���ł́A���m�ȉ�����ł��܂���B
�����܂ł��A���̂́A�g�p�����痈��A�ʒu�u���������Ă���A�Ƃ���
���������ɂ��ď����Ă܂��̂ŁB
�����āAK20D�̐}���A���ɂ͂ǂ��������āA�ʒu�u���̕����ɍs���Ă���悤�Ɍ����܂����B
��ԉE�ŁA�����Y�̐^�łȂ��ʒu���܂������i�ތ����ɁA�f�q���A��Ԃ�O��
�������ʒu�ɁA�Ԃ��ł������`�ňړ����Ă���̂ł�����B
�����}�����Ă��A�����Ԃ�ƔF�����Ⴄ�̂ł��ˁB
�����ԍ��F10866124
![]() 2�_
2�_
�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̌���ɂ́A���Z�����̂ɒ����ԁA��b�����Ă��������܂����B
�����A���̂��d��������ł��傤����A�v�_����������ł������AK-7��K-x�̕]����
�������Ɨ_�߂Ă������Ƃ��������������A�����炪���₵�Ă��Ȃ����Ƃ��A���낢��Ƌ����Ă��������܂����B
�{���Ɋy���������ł��B
�y���^�b�N�X���܂��܂��D���ɂȂ�܂����B
�ł���A���̂ق����b�������Ƃ��A������ƓI�ɍ���̏��i�W�J�ɂł��A
�ق�̂킸���ł��A�����ɗ��Ă�Ηǂ��̂ł����B
���̎g�p���@�́A������������ł�����A���ɗ��悤�Ȃ��Ƃ͉����Ȃ���������܂���B
�ł��A�g�p����v�]�Ȃǂ́A�ڋq�ɒ��ڊւ�镔���Ƃ��ẮA�J���w�ɓ`���邽�߂ɂ��A�ƂĂ��~�����悤�ł���B
�����A�y���^�b�N�X�̎Г��̕��X�ɒ��ډ����@�����A
�����Ȏ����̎g�p���Ȃǂ��A�`����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�ւ�ɃX�y�b�N�̐����I�Ȃ��Ƃ����
�グ�邱�Ƃ��������肷��A���Ȋ������邩������܂���ˁB
���������AK20D��K-7�̉𑜗͂�ΐF�̕\���̘͂b��ɂ��Ȃ�܂������A
��͂肻���́A�y���^�Ƃ��Ă����M�������āA���ɑ���o���Ă��邻���ł��B
�{���ɁA�̊K���A�F���������Ȃ��A���Ċ����܂�����ˁB
�Ȃ�ɂ���A���ځA��b���āA�X�b�L�����܂����B
�����ԍ��F10866191
![]() 2�_
2�_
�咣�ɑ��Ĕ��_���ꂽ���X�����x�����Ⴂ�ƒQ���Ă�����Ⴂ�܂������A
���_�������̗��_�������Ȃ��̂Ɏ�ς𐺍��ɋ邲���g�̃��x����??
�����ԍ��F10866636
![]() 20�_
20�_
���A�����̕��̎��̏������݂����ł��������Ă݂��̂ł����A�܂������ԈႦ������܂����B
2010/01/31 10:47�@[10865291]
�@�����͂��Ƃ��ƁA������ƌÂ����̂��D���Ȃ̂ŁA�≖�ł��f�W�J���ł��̂̋@������ł�
�@�����X�g���̂ł����A��Ԃ��Ɋւ��ẮA�y���^�b�N�X�͐V�@����X�V���邽�߂ɁA�y���^�b�N�X�͐V�@����X�V���邽�߂ɁA
�@�����x����ʂ����߂Ă���C�����܂��B
���̏������݂ł܂��ԈႦ�܂����B
�@����Ԃ��Ɋւ��ẮA�y���^�b�N�X�͐V�@����X�V���邽�߂ɁA���x����ʂ����߂Ă���C�����܂��B
�ł͂Ȃ��āA�u�y���^�b�N�X�͐V�@����X�V���邽�тɁA�v�ł��B
�������ꕶ���ł����A�܂�ňӖ����ς���Ă��܂��܂��ˁB����͂��Ȃ肢���Ȃ��ԈႢ�̂P���Ǝv���܂����B
����āA�������́A
�@�� ����Ԃ��Ɋւ��ẮA�y���^�b�N�X�͐V�@����X�V���邽�тɁA���x����ʂ����߂Ă���C�����܂��B
�ł��B
�Â��m�[�g�o�b�ł��̂ŁA����ƃy�[�W���J���Ă������тɁA���삪�������Ȃ��Ă��Ă��܂��܂����B
���̂������̓��������X�܂ō폜����āA���ʁA�u���A��r�炵�v�I�ȍs�ׂ�����Ă��܂��܂����B
�ł��邾���X���[�A�Ƃ����͖̂{���̂��Ƃł��ˁB�C�����܂��B
���������g�p������������ł�������������ւ́A�ʂ̃��X�́A�����������̏�Ԃ�
���������Ă��炳���Ă��������B�\����܂���B
�{���́A���ۂ̎g�p��������������̂́A�������������̂ł��B�@���Ƃ��ƁA���������X���b�h�ł����B
�����̎g�p���ƈႤ���@�Ŏ�����Ă�������A�ǂ������Ă���̂��B�B
����������������������F���܁A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10866648
![]() 3�_
3�_
�u�ڎ��Łv�u���x�����߂Ă���C�����܂��v�u������Ďv���v
����t���o�̘b�B
������Ǝ�U�����ʂ̍����͂���Ȃ�A�U�������ɔ��������鑕�u��p����
�S�����������Ŕ�r���K�v�B
�y���^�b�N�X�D���E�L���m�������Ŏ�ςŃo�C�A�X����������r�ɂ͂Ȃ��
���ؓI�������Ƃ��Ȃ�Ȃ��B
�����ċc�_������C���Ȃ��Ȃ�A�����̃u���O���ׂ��ł���B
�^�c���͉����l���Ă����������y����u���Ă���̂��낤���A�폜����悤�Ȃ�펯���^���B
�����ԍ��F10866704
![]() 26�_
26�_
MZ-LL����
���@�@���ɂ́A�c��������b���Ĕ����Ă������̖ڂƂ�����Âɕ��͂��銴�o�ƁA
�����Ԕ��p�i�Ȃǂ��B�e���Ă�������ł̌o��������܂��B���������B�e���d�˂�
�������Ƃɂ���āA������������ʑ̂�\�}�l�߂Ɍ������@��Ƃ��āAK20D��K-7
��I�т܂����B
�@���p��i���B�e����ꍇ�A�O�r�ƃ����[�Y�̎g�p�͕K�{�ł͂Ȃ��ł��傤���B
��Ԃ��̋@�\���A�c�݂̏��Ȃ��摜���ʂ������Y�A�K�ȏœ_�����̃����Y�̑I���A
�J�����̈ʒu�A���C�e�B���O�̕��@�A���p�i�Ǘ��҂̗����@���X���S���ł͂Ȃ����Ǝv
���܂��B
�@��Ԃ��̗D�ꂽ�{�f�B�̑I�����́A�����Y�̑I�����厖�ł͂Ȃ��ł��傤���B
���p�u�t������Ă���X���傳���p��i�̎B�e��ΏۂƂ��āA��Ԃ��̋@�\��
���Ę_�����Ă��邪������Ɗ�قɎv���܂����B
�@���p��i�̎B�e�Ƃ����Ă����낢��ȖړI������̂����m��܂��E�E�E
�����ԍ��F10866805
![]() 16�_
16�_
��induster����
�������A�O�r���烌���[�Y����A���낢��Ƌ�g���ĎB�e���Ă܂���B
�����ă����Y�������Ȃ�ɁA�������Ă��钆�ŁA�œK�Ǝv������̂��g�p���Ă��܂��B
�������ɂȂ邱�ƂƁA�܂������t���I�ɂȂ邩������܂��A
�����炱���A�y���^�̎�Ԃ��̕������A���ɍ����Ă���̂ł��B
�܂��A�����Y��I�Ȃ��B�������`�ʂ��D���ȃ����Y���g����B
�����āA�傫�Ȋp�x�u���͂��܂�N���Ȃ��̂ŁA�ʒu�u������ɕ����d�g�݁B
�����āA�ǂ����Ď�Ԃ�����g���邩�A�ł����A���͎��́A
�G��łȂ����̌n�̍�i�𑽂��B�邱�Ƃ������̂ł��B
�O�r�ƃ����[�Y��p�����B�e�����āA�ǂ����\�}�����܂������ȁA��
��������A�J�������O�r������O���A�����Y�����̂܂܂ŁA�B�e���܂��B
�������ɔ��Â��ꍇ�́AISO���x���グ�܂����A��������400���炢�܂łł��B
���m�Ȏ��엦�̂������ŁA�莝���ł��A�\�}���t�@�C���_�̒��ŋl�߂邱�Ƃ��ł��܂��B
�G��̎B�e�Ȃǂł́A�O�r�g�p�����O�b�ƍ����̂ł����A�����O�r�����������Ă���킯�ł͖����A
���̓��ɓˑR�A�B�e���邱�ƂɂȂ鎞������܂��B���������ۂɂ́A�l�p���G���
�莝���ł��^���ʎB�e�����ɂ��₷���AK-7���ƂĂ��֗��ł��B
�{���ɁA���̂����������̊m�����オ��܂���BK-7�ł́B
���ۂɎ莝���ŁA���p�i�Ȃ荜���i�Ȃ�A���ʂȂ藧�̍�i�Ȃ�A�B�e���Ă݂�ƁA�悭����܂��B
�{���ɂ��������p�r�Ɍ����Ă���̂ł��B�莝���B�e�Ɋւ��ẮA�p�r�ɂ���ẮA�t���T�C�Y�ȏ�Ȃ̂ł�
�Ȃ��ł��傤���B�����Ȃǂ̗��̍�i���A���̗ǂ����ʐ^������l�ɂ��`���悤�ɎB��ɂ́A
�\�}��p�x�A�����Ď��_�̈ʒu�����ɏd�v�Ȃ̂ł��B���Ȃ��Ƃ����͂��������Ă��܂��B
�B�e�ʒu���A�킸���ɈႤ�����A�����Ȃǂ̕\��A�܂���������Č����邱�Ƃ�����܂��H
�O�r�s�g�p�ɂ��Ă��A�O�r�B�e�O�ɁA�A�^�����o���ۂɂ��A�莝���B�e�͔��ɏd�v���ƁA���͊����Ă��܂��B
���ۂɍs���Ă���l�̘b�́A���������Q�l�ɂȂ�Ǝv����ł����ǂˁB�ϑz����Ȃ��ł����B
�����ԍ��F10866886
![]() 5�_
5�_
��قɌ����悤�������܂����A�ǂ��ł������̂ł��B
���ۂɎ��͑�R�B�e���Ă��āA��Ԃ��@�\��L���Ɋ��p���Ă���̂ł�����B
��̓I�ȕK�v���́A���₻��ɋ߂����Ƃ����Ă���l�ł͂Ȃ��ƁA����Ȃ��ē��R�ł��B
�����Ĕ��p�̐��E���L���ł�����A���Ƃ��������肵�Ă��鏊�œ����Ă���l�́A
�Ȃɂ������ŎB�e���Ȃ��ŁA�O��������̐�Ƃ̃J�����}���ɔC��������̂ł��B
���Ƃ��ƁA���̃X���b�h�́A�u���ʂ̈Ⴂ���ǂ������Ă��܂����H�v�Ƃ�����|�Ŏn�܂��Ă��܂�����A
���������o�I�œ��R�Ȃ̂ł��B����������Ȃ��ƁA�ǂ������玝���Ă��������Ȃ����킹�āA
����̋�_�ɋ߂��悤�ȋZ�p�_���n�܂��Ă��܂��܂��B
���̏���m������������A�܂����ɂƂ��ĎQ�l�ɂȂ�̂ł����A�������łɌ������Ă��邱��
�i�R�j�~�m�Ƃ̕����̈Ⴂ�Ȃǁj���A�����Ԉ���Ă���ƑO��ŁA���ꂱ�ꉽ�x��������Ă��A
���������������_�����߂��A�o��킯������܂���B��������Ƀ��X������邾���ł��B
���ꂼ��̊��A����A�ƊE�ȂǂŁA���������悤�Ȃ��Ƃ����Ă���ƁA�O�̐��E�̘b�ɂ�
���Ƃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂����A���Ȃ��Ƃ��A����������Ă��邱�ƂɊւ��ẮA���x�͍����Ȃ�܂��B
�������A�q�ϓI�ȕ��͂�A�P����b�B��ӂ�A���Ă������Ƃ����肦�܂��B
�ł��A���Ȃ��Ƃ����́A����܂ŏ����Ă����B�e���@�ȂǂɊւ��ẮA���݂̂Ƃ���A
�����A�Z�p�I�Ɍ��サ�A����������̃`���C�X����肭�Ȃ��Ă���C�����Ă��܂��B
������A���́A�ʐ^���B��̂��y�����ł��B
�����ꂱ�̑��x���������s���l�܂�A���̕ǂ��z����̂ɂ́A�X�Ȃ�o�����K�v�ɂȂ�ɈႢ����܂���B
����͔��p��i�̐���ɂ����Ă������ł����A���͉��x���s���l���Ă��܂����B�������Ȃ��ǂ�����܂��B
�ł��A�����������f���ŏ����ꂽ���ɂ���āA�Ȃɂ��̎Q�l�ɂȂ�����A
�V�����Z�����邫�������ɂȂ�����A���������l������悤�ȋC�����Ă���̂ł��B
�����g���A���i�R���f�����q�n�l���邱�ƂŁA�����Ԃ�������Ă��炢�܂�������B
�����������R�ł��A���܂�ɂ��Ԉ�������́A������Ɩ��f�Ȃ̂ł��B
�����ԍ��F10866956
![]() 5�_
5�_
Z-LL����
���@�@�܂��A�i��Ԃ��̗D�G��K-7�́j�����Y��I�Ȃ��B�������`�ʂ��D���ȃ����Y
���g����B
���@�@���́A���p�u�t�Ƃ��āA���k����B�̍�i�̋L�^����ʂɎB��̂ł����m10859670�n
�@�i�j���͐����̂��ߕ⑫���܂����B
�@���p�i�̎B�e�ɂ��ăR�����g�����Ă������Ă���܂��B
�@���p�i�̎B�e�̏ꍇ�A�c�Ȃ����Ȃ��A�����ȐF�̈Ⴂ�◧�̊��A�}�`���G�[�������悭
�\���ł���A�ߐڎB�e�ł��j�]���Ȃ��A�Ȃǂ̐��\�̍��������Y��I�����܂��B
��Ԃ��������ɗD�G�ł��A��L�̐��\���J�o�[���Ă���܂���B�������D���ȕ`�ʂ�
�����Y���g�����Ƃ͓�̎��ɂȂ�܂��B�L�^�Ƃ��ĎB�e����Ƃ��́A�g�����X�y�A�����g
�ȎB�e��S�����˂����܂���B
���@�@�������ɔ��Â��ꍇ�́AISO���x���グ�܂����A��������400���炢�܂łł��B
���m�Ȏ��엦�̂������ŁA�莝���ł��A�\�}���t�@�C���_�̒��ŋl�߂邱�Ƃ��ł��܂��B
���@�@�����Ȃǂ̗��̍�i���A���̗ǂ����ʐ^������l�ɂ��`���悤�ɎB��ɂ́A
�\�}��p�x�A�����Ď��_�̈ʒu�����ɏd�v�Ȃ̂ł��B���Ȃ��Ƃ����͂��������Ă��܂��B
�@MZ-LL����́A���R���₻�̏�̏Ɩ��ŎB���Ă���̂ł��傤���B���ꂾ�Ǝ��_��
�ʒu�̑I���͌������Ȃ��ł����B
���@�@�O�r�s�g�p�ɂ��Ă��A�O�r�B�e�O�ɁA�A�^�����o���ۂɂ��A�莝���B�e�͔���
�d�v���ƁA���͊����Ă��܂��B
�@�A�^�����o���Ƃ������Ⴂ�܂����A����Ȃ�p�\�R������R���g���[���ł���{�f�B�̂�
��낵���Ǝv���܂��B����ł�MZ-LL����̂����A�^���̊m�F�͂ǂ�����Ă���̂ł���
�����B
�@MZ-LL����̏������݂���A���p�u�t������Ă������p�B�e�ɂ��Ȃ葢�w���[��������
���@���@�܂��A���d���ŎB�e����Ă���Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�R�����g�����Ă���������
�����B
�����ԍ��F10867463
![]() 4�_
4�_
�X����l�̋��Ă���u�ʒu�u���̕�v�ł����A�������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�ȉ��͎��l�̈ӌ��ł����A���ۂɉ��_�������Č��܂����̂ŁA�����炭�Ԉ���Ă͂��Ȃ��Ǝv���܂��B
�ʏ�A�ߐڎB�e�Ŗ�������A�ʒu�u���͊p�x�u���Ɣ�r����Ƃقږ����ł��郌�x�����Ǝv���܂��B
�Ⴆ�A���Ȃǂ̕���ȏꏊ�ɒ�K�ƃJ������u���āA��K�ɂȂ���悤�ɃJ�����s�ɍ��E�ɐ��Z���`�������Ă��������BLV�Ō���ƕ�����₷���ł����A�ʂ鑜�͂����͂��ɂ����Y���Ȃ��͂��ł��B
���āA�J�����ɂق�̏����p�x�����������ł��A�ʂ鑜�͂��Ȃ�Y����͂��ł��B
�܂�A�}�N���B�e�Ȃǂ̋ߐڂłȂ�����A�p�x�u���ɑ��Ĉʒu�u���͂قƂ�ǖ��ɂȂ�܂���B
K-7�̓W���C���Z���T�[�Ŋp���x�����o���Ă��܂��̂ŁA���̊p�x�u���ɑ��ĕ���s�Ȃ��A�ʒu�u���͌��o���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
����ɁA�u�����Y�̌����ɑ��āv�Z���T�[���V�t�g������{�f�B����Ԃ��ł́A�ʒu�u���̕�͌����I�ɍ���Ǝv���܂��B�Ƃ����̂́A��ʑ̂Ƃ̋����ɂ���āA�Z���T�[���V�t�g������ʂ��ς���Ă��܂��܂�����ˁB
�����Ɂu�\�}�������v�ŃZ���T�[�����Ă݂Ă��������BK-7�̓Z���T�[���c�����ꂼ��1mm�����܂����A�O�q������K�ŃJ�����{�̂����E��1�o�������̂ƁA�Z���T�[�����E��1mm�����̂ł́A���̓��������S���Ⴄ�͂��ł��B��ʑ̂Ƃ̋����ɂ���Ă����Ԃ��o�邩�Ǝv���܂��B
�����炭�A�p�x�u�������邽�߂ɃZ���T�[���V�t�g���Ă���̂��A�ʒu�u�������Ă���ƌ�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�f�W�^���J�����̏ꍇ�A�Z���T�[�ʂƃ����Y�̌����͏�ɐ����łȂ���Ȃ�Ȃ��ł��̂ŁA�{�f�B����u����̏ꍇ�A�Z���T�[�͏�ɕ��s�Ɉʒu���V�t�g���ău�������Ă��܂��B�Ⴆ�A�J�������������ɌX�����ꍇ�A�����ł������悤�ɃZ���T�[�͕��s�ɁA�������ɃV�t�g����܂��B
�����ԍ��F10867767
![]() 8�_
8�_
������ɁA�u�����Y�̌����ɑ��āv�Z���T�[���V�t�g������{�f�B����Ԃ��ł́A�ʒu�u���̕�͌����I�ɍ���Ǝv���܂��B�Ƃ����̂́A��ʑ̂Ƃ̋����ɂ���āA�Z���T�[���V�t�g������ʂ��ς���Ă��܂��܂�����ˁB
�u�ʒu�u���v(�V�t�g�u��)�͊m���ɔ�ʑ̂Ƃ̈ʒu�ŕK�v��ʂ��ς��܂����A�B���{���̏オ�����}�N���̈�Ō��ʂ邱�Ƃ�����A�w�i���C�ɂ��Ȃ����ʂȂǂɂ����ẮA�t�H�[�J�X�����킹���ʒu�ɂ����ėʂ����肷�邱�ƂɂȂ�܂�(���������Ӗ��ł́u���n�̌��v�Ȃ�ł����ǂ�)�B
�ŁA����ɑ��ăZ���T�[�V�t�g�������Ƃ������Y�V�t�g�����̈Ⴂ�ɂ���āu�\�v�u�s�\�v�̍��͂Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł��傤�B
�����ԍ��F10867842
![]() 6�_
6�_
��kuma_san_A1����
��Ƃ���A�ʒu�u����̓}�N����ň��̌��ʂ�������Ǝv���܂��B�t�ɁA�}�N���ȊO�ł͂قƂ�nj��ʂ͊��҂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�{�f�B���ł������Y���ł��A�����͍���ł�����͕s�\�ł͖����Ǝv���܂��B
�����A�}�N����ɂ̂ݓ���������ŁA�t�H�[�J�X�ʒu�̌��o��A����ɔ����Z�p�J���≉�Z�����Ƃ��������l����ƁA��͂背���Y����̂ق������L���ł͂��邩�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10868049
![]() 4�_
4�_
�������A�}�N����ɂ̂ݓ���������ŁA�t�H�[�J�X�ʒu�̌��o��A����ɔ����Z�p�J���≉�Z�����Ƃ��������l����ƁA��͂背���Y����̂ق������L���ł͂��邩�Ǝv���܂��B
�t�H�[�J�X�ʒu�̌��o�̓����Y�Ƃ̒ʐM�ʼn\�ł����A���Ƃ��Ƃ̊p�x�u����ł������Y�̌J��o���ʂ�m�邱�ƂŐ��x���グ�Ă��܂��B
�l�I�Ɂu���n�̌��v(�������ŋt�ɔw�i���������Ԃ��)�ł��̂ŁA�{�f�B�[����ɓK�p����̂͂��Ȃ�ȉp�f���K�v�ɂ͎v���܂��B
�L���m���̏ꍇ�̓}�N�������Y�ɓ��ڂł�����ˁB
�L���ȏ��z��ł�������I���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10868086
![]() 6�_
6�_
���ߓǂ݂͂��܂������A�����悭�킩��܂���B�����A�ЂƂ����v�����Ƃ�����܂����B
>�������A���x�����Ⴗ����B����ȂɃK�b�J�������̂͏��߂Ăł��B
���������Ȃ�AMZ-LL��������������ł���B�l�͂���Ȏ�������MZ-LL����ɃK�b�J�����܂����B
���x�����Ⴗ����v�ƌ����̂ł���A�ǂ�ȑf�l�ɂ��A�ꔭ�ŗ����o����l�ȕ����Ȍ��t�Ńy���^�̋Z�p�̕����畷�����A�ƌ����b���������ׂ����Ǝv���܂��B���ꂪ�����̂Ɂu�������A�����������납�����A�[�������v�@�Ƃ܂Ō�����������ɍ��f���܂��B
�l�������y���^�t�@���Ƃ��āA���̐����[���������̂ɁB
�����ԍ��F10868298
![]() 25�_
25�_
�����́B�f�W��͂��납��u����t�̃R���f�W���玝���Ă܂��E�E�E
�����[���q�����܂����B
������ƃu���C�N�A����̘_�ƌ��������̑̑��B
�p�x�u���ł͂Ȃ��ăV�t�g�u���ŃJ���������ɓ������ꍇ�A���̃V�t�g�u��������ɂ͎B���f�q�̓J�����ɑ��ď�֓����ł��傤���A���ւł��傤���H
�ł���A�X����l�̂�����҂��Ă���݂Ȃ��܂̂����A�����ď����̎v�����q�ׂ����Ǝv���܂��B�݂Ȃ��܂ɋ��v�ł��闧��ł͂���܂��B
�����ԍ��F10868398
![]() 1�_
1�_
��kuma_san_A1����
�����ł��ˁA�L���m���̃}�N�������Y�ɓ��ڂƌ����͍̂����I���Ǝv���܂��B
�{�f�B����Ńt�H�[�J�X�ʒu�������Y���猟�o����Ȃ�A�Â�MF�����Y�ł͂��������ʐM���ł��܂���̂ŁA�ʒu�u����ł��Ȃ����ɂȂ�܂��ˁB
���X�b�]�R����������
�����̓����Y�𒆐S�ɁA�Z���T�[�ʂɏ㉺���E���]���đ������т܂�����A�J���������ɃV�t�g�����Ȃ�A�Z���T�[�����ɓ����A���������ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10868717
![]() 2�_
2�_
���{�f�B����Ńt�H�[�J�X�ʒu�������Y���猟�o����Ȃ�A�Â�MF�����Y�ł͂��������ʐM���ł��܂���̂ŁA�ʒu�u����ł��Ȃ����ɂȂ�܂��ˁB
���̒ʂ�ł��B
���̃X���b�h�g�b�v�ɓ\���Ă���ʐ^�Ȃǂ̏ꍇ���Y�����܂�(���������u�ʒu�u����v�͓o�ڂ���Ă��Ȃ��̂ł���)�B
�����ԍ��F10868828
![]() 3�_
3�_
���ӂ́B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10850394/
������̃X���b�h�̑����݂����ł��ˁB
�{�X���̎�|�͎B�e�摜�ŃV�t�g�u����@�\���ڂ̗L���f������Ă��ƂȂ̂ł��傤���B���Ȃ����Ǝv���܂����B
�L���m���̏ꍇ�n�C�u���b�hIS�i�ƌ����Ă����ނ����Ȃ��j�Ɣ�n�C�u���b�hIS �̎B���ׂ�����A����͌��ʂɈႢ���o��Ǝv���܂��B
�ł����A�V�t�g�u����������Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ���@��i�Ⴆ�� K10D �� K7 �Ƃ��j���B���ׂėL�ӂȍ����o���Ƃ��Ă��A���ꂪ�p�x�u������\�̈Ⴂ�Ȃ̂��A����Ƃ��V�t�g�u����������Ă��邩��Ȃ̂��͔��f�ł��Ȃ��ł��傤�A�Ƃ������Ƃł��B
�L���m���̃y�[�W�������
http://cweb.canon.jp/ef/technology/is-technology.html
�V�t�g�u�����m�͉����x�Z���T�[�Ȃ�ł���ˁB���ڂ͑��x�Ȃ킩������Ȃ�����A���炻�����Ƃ��������ł����B
�����x���ƌl�ł̌��͓�����ł��B�p�x�u�����o�����ɉ������ɗ͂������˂Ȃ�܂���B
�����ԍ��F10869272
![]() 1�_
1�_
SR���p���x�Z���T�[�̏���łȂ��A�����Y�̏œ_������B��������
�������ƂɎB���f�q�V�t�g�ʂ𐧌䂵�Ă��邱�Ƃ́A�戵��������
�g�o�ɏ�����Ă��܂��B�����Y���������擾�ł��Ȃ��Â��l�e�����Y��
�g�p����ۂ́A�œ_�������蓮���͂��邱�Ƃɂ��K�ȕ�ʂ�
���邱�Ƃ��\�ł��B���ۂ�蒷���œ_��������͂��邱�ƂŁA
��苭����ʂ�e�N�j�b�N������悤�ł��ˁB
�����ԍ��F10869362
![]() 3�_
3�_
�܂��قƂ�ǖϑz�ȃf�}���̃I���p���[�h���A�n�܂��Ă��܂����݂����ł��̂ŁA
�ł���A�����Ǝ����ŁA�y���^�̃J�������g������ł���A�����ė~�����Ǝv���܂��B
�Â��P�œ_�����Ă��AK-7�œ���Ȃ胉�C�u�r���[�Ȃ�ŁA�����A�ڂƊ��o�̗ǂ��l�Ȃ�A
�����ɉ���Ǝv���܂��B�N�ł�����Ə����Ă��܂����̂́A�ɒ[��������������܂���B
�܂����A����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��l����������Ƃ́A�l�����Ȃ������̂ŁB
�i����ʂ̐��m���́A���Ԃ�c�`�����Y���̂ق���������������܂���ˁj
�{���́A�������̃X���b�h�̒����ɂȂ��Ă��܂��܂������A���C����������������A
��ӌ����������������ւ̃��X�������Ă������������̂ł����A�܂��x��Ă��܂������Ő\����܂���B
����́A�Ԉ�������� �������_�̂悤�ɐU�肩�����A�r�炵�I�ȏ������݂�������X��
����܂ł́A�F������������ނ킯�ɂ́A�����܂���̂ŁB
�����ԍ��F10869408
![]() 2�_
2�_
���X�b�]�R����������
���������݂��肪�Ƃ��������܂��B��Z�ɉ����Ă��������܂��B
��{�A�y���^�̂r�q�́A�����܂ł����ʏ�̓����ŁA�C���[�W�T�[�N�����ȂǁA
�f�q���ړ��ł��鋗���͌����܂����A�A�A
�{�f�B���قڊ��S�ɕ��s�ʼn��ɂ킸���Ɉړ������Ƃ���A�r�q�ł͎B���f�q�́A
�i���ʓI�ȁB���w�E�x�j��ԍ��W��ŁA���̂܂܂̈ʒu�Ɏc���Ă���͂��ł��B
�{�f�B����݂�A��Ɉړ��������ƂɂȂ�܂����A�ނ���A�u�{�f�B�����ړ������v��
���߂���ق����A�y���^�̍��̎�Ԃ������̃C���[�W�ɋ߂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�f�q���A�V���b�^�[���u�ԂƁA�����ʒu�ɂ��邱�ƂŁA�ʒu�u���͕����邱�ƂɂȂ�܂��B
�������A����͂킸���Ȕ͈͂ł����A���̈ړ��i��ԏ�łقڐÎ~�j�ŕ�ł�����E�����u���́A
�摜�ɂ��u���Ƃ��ċL�^����Ă��܂��܂��B
���̌��E������A�p�x���������A�������̎��̓u�����ʐ^���B���Ă��܂��܂��B
���ׂĂ𐬌������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����܂ł����s�����点��B��������m�����オ��B�ł��B
�����s�����Ǝv���܂����A����Ȋ����ł��B
�䎩�g�̂��l��������܂�����A���������݂���������K���ł��B
�����ԍ��F10869416
![]() 4�_
4�_
�����L�X�E�f�E�K�[��������
���������݂��肪�Ƃ��������܂��B�������̕\�L�̌���A���肪�Ƃ��������܂����I
���������݂ɋC�Â��O�ɁA��ӂ��̃X���b�h�������Ă������̂ŁA
�������ŁA�f�}�A�Ȃǂ̌��t�������Ă��܂��Ă��Đ\����܂���B
���L�X�E�f�E�K�[��������̂��������݂ɑ��Ă̌��t�ł͂���܂���B
�{���ɐ\����܂���B
�����ԍ��F10869445
![]() 2�_
2�_
[10869416]�̏������܂ꂽ���삾�Ɛ���Ƀu�����Ⴂ�܂��ˁB
�����ԍ��F10869454
![]() 3�_
3�_
�����܂���A�Q�Ăď�������A�܂����t���炸�ł����B
���A�ǂݒ����܂����B
�ۂ��ƁA�C�����������Čf�������Ă��������B�r���ŁA�I�����A�Ƃ������t�����Y��Ă܂����B
���X�b�]�R����������
���������݂��肪�Ƃ��������܂��B��Z�ɉ����Ă��������܂��B
��{�A�y���^�̂r�q�ł̎B���f�q�̓���́A�����܂ł����ʏ�̓����ŁA
�C���[�W�T�[�N�����ȂǁA�f�q���ړ��ł��鋗���͌����܂����A�A�A�B
�{�f�B���قڊ��S�ɕ��s�ʼn��ɂ킸���Ɉړ������Ƃ���A�r�q�ł͎B���f�q�́A
�i���ʓI�ȁB���w�E�x�j��ԍ��W��ŁA���̂܂܂̈ʒu�Ɏc���Ă���͂��ł��B
�{�f�B������݂�A��ɔ��ړ��������ƂɂȂ�܂����A�ނ���A�f�q�ɑ��āA
�u�{�f�B���i�u����h��Łj���ړ������v��
���߂���ق����A�y���^�̍��̎�Ԃ������̃C���[�W�ɋ߂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�f�q���A�V���b�^�[���u�ԂƁA�i��ԏ�j�����ʒu�ɂ��邱�ƂŁA�ʒu�u���͕����邱�ƂɂȂ�܂��B
�������A����͂킸���Ȕ͈͂����ł����A�I�����ɂ��̈ړ��i��ԏ�łقڐÎ~�j�ŕ�ł���
���E�����u���́A�摜�ɂ��u���Ƃ��ċL�^����Ă��܂��܂��B
��������Č��E������A�p�x���������A�������̎��̓u�����ʐ^���B���Ă��܂��܂��B
���ׂĂ𐬌������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����܂ł����s�����点��A��������m�����オ��A�ł��B
�����s�����Ǝv���܂����A����Ȋ����ł��B
�䎩�g�̂��l��������܂�����A���������݂���������K���ł��B
�Čf���A���炢�����܂����B
�����ԍ��F10869492
![]() 3�_
3�_
�ʒu�u���̕�͖{���͈ȉ��̂悤�ɍs���܂��B
�O��Ƃ��Ċp�x�u���̕����ɉ��Z���܂��B
�E�ʒu�̕ψʂ́u���_�v�̓����Y�̑O����_
�E�����ɒ�������ʂ̏c�������̕ψʂ���L���_�ʒu�ɒu���ċ��߂�(�p���x�Z���T�ɂ��p�x�u����G�Z���T�ɂ��ʒu�̕ψʂ�G�Z���T-�u���_�v�Ԃ̋������牉�Z����)
�E���Ɍ��_�ʒu���u�������v��1mm���ꂽ�Ƃ���
�E��ʑ̂Ƀt�H�[�J�X�����킹�����̎B�e�{�������߂�
�E���ꂽ1mm�ɎB�e�{�����悶���������B���ʂ��u�������v�����������Ɋp�x�u���̕�ʂɉ��Z���Ĉʒu�u���̕����������
�ł�����A�p�x�u�����S���Ȃ��ꍇ�A�J�������������ɓ������ꍇ�͎B���ʂ��������ɓ������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
�����ԍ��F10869557
![]() 3�_
3�_
�F�l�A�͂��߂܂��āB
k200d��2�N���L��Ak-7���T���L��������̎҂ł��B
���̃X����ǂ݂Ȃ���A�������g���낢��������Ă�����Ă��܂��B
�����Ȃ���A�B���f�q���Ȃ����s�ړ����邾���ŁA�J�����̊p�x������
�ł��邩��[�����邽�߁AK20D�̐����}�������Ȃ�ɉ��߂��Ă݂܂����B
�i�����̊p�x�ω��̓��[����уs�b�`���O�j
fig.1
�Ώہi���F�j�𑨂��č\�������
�B���f�q�i�j�O�ʂɃs���g�������Ă���B
�����Y�̓����Ƃ��āA�B���f�q�S�ʂőΏۑS�̂̃s���g�������Ă���Ƃ���B
fig.2
�V���b�^�[�������ăJ�����̊p�x���ς���Ă��܂����B
�Ώۂ̓J��������ɂ���ƁA�����Y�ւ̓��ˊp���ω����邱�ƂɂȂ�B
�B���f�q�̊p�x���ς�邪�����Y�Ƃ̑��Έʒu���ς��Ȃ���A
�s���g������邱�Ƃ͂Ȃ��B
�����Ώۂ��B���f�q����ړ����邱�ƂɂȂ�B
fig.3
�����ŃW���C���Z���T�[�Ō��m�����p�x�ƃ����Y�̏œ_�����iDA�����Y�Ȃ玩�����m�j��
�����ĎB���f�q�s�ړ����A�Ώۂ��B���f�q�̈��ʒu�ɕۂB
fig.4
�{�f�B���V�t�g�̎�_�Ƃ���
�L�p�����Y�ł̓����Y�̒[��������˂���قǁA
���͂Ђ��ނ��߁A����͎B���f�q�̃V�t�g�ł͕�ł��Ȃ��B
�܂����ߋ����i�}�N�����j�ł́A�p�x�̕ω��őΏۂƃ����Y�̋����ω���
���ΓI�ɑ傫���Ȃ�A�s���g������킸���ɋN����B
����Ȋ����ł����Ă܂��ł��傤���H
���Ȃ݂�k-7�ł̓��[�����O�ɂ��p�x����������܂��ˁB
���̃X���ł͉�]�Ƃ������t�̈Ӗ�������ɑ�������̂ł����ˁB
�����ԍ��F10869595
![]() 8�_
8�_
wsxwsx����A���������݂Ɖ摜�̌�f���A���肪�Ƃ��������܂��B
��قǁA�������Ƃ��ׂẲ摜��q�������Ă������������v���܂��B
��Ϗ����������Ƃ�����܂��̂ŁA�܂��͂�������������Ă��������B
�@�����Ȃ݂�k-7�ł̓��[�����O�ɂ��p�x����������܂��ˁB
�@�����̃X���ł͉�]�Ƃ������t�̈Ӗ�������ɑ�������̂ł����ˁB
�����ł́A��]�Ƃ������t���g���Ă��܂����̂ł����A������������A�����
�y���^�b�N�X�̌���́A���[�����O�Ƃ����P��Őg�U���U��������āA
���������������������܂���B�u��]�v�Ƃ������t�͂����ȕ��Ɏ��Ă��܂��̂ŁA
�g����������ȁA�Ƃ��傤�NJ����Ă��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�摜�Ƃ��������݂������������e�́A�����������x�A�������Ɣq�������Ă��������܂��ˁB
�����ԍ��F10869654
![]() 2�_
2�_
wsxwsx����@�A��{�I�ȗ����͍����Ă���Ƃ����Ă悢�Ǝv���܂��B
�������ŃW���C���Z���T�[�Ō��m�����p�x�ƃ����Y�̏œ_�����iDA�����Y�Ȃ玩�����m�j��
�����ĎB���f�q�s�ړ����A�Ώۂ��B���f�q�̈��ʒu�ɕۂB
�����Y�ƒʐM�ł���Ȃ�œ_����+�����Y�̌J��o���ʁc�C���i�[�t�H�[�J�X�Ȃǂ���̂ł�萳�m�ȕ\����ڎw���Ȃ�u�����Y�̌����_����B���ʂ܂ł̋����v�𗘗p���邱�ƂŐ��x�����߂邱�Ƃ��o���܂��B
�L�p�̏ꍇ�̖��_�����̒ʂ�B
���ƁA�}�̒��Łu�����v�Ɍ��y����Ă��܂����A�C���[�W�T�[�N�������肬��Ƃ����킯�łȂ��̂ŋC�ɂ��Ȃ��ėǂ��ł��B
�����ԍ��F10869663
![]() 4�_
4�_
�J�����̓����ɑ��ăZ���T�[�����̈ʒu�ɗ��܂낤�Ƃ��铮�������Ă��A�u���̕�ɂ͂Ȃ�܂����B
�u�����̉��Œ��߂��˂��g���Ď��ȂǂɌ����W�߂�ƁA���̏�Ɍu�����̌`�̑����ʂ�܂��B���̏�ԂŒ��ዾ�����E�ɓ������ƁA�ʂ����������߂��˂ƈꏏ�ɍ��E�ɓ����܂��B
�Z���T�[�������ƂŃJ�����̈ʒu�̓�����ł����������Ǝv���̂Ȃ�A�Z���T�[�ƃ����Y���Z�b�g�œ������K�v������܂��B
�����ԍ��F10869678
![]() 4�_
4�_
��{�I�ɂ��̃X���͕��u���悤�Ǝv���Ă��܂������A
�ЂƂ^�₪�X�������̂ŏ�������ł����܂��B
�������Ȃ��̕��A[10859738]�ɂď������AK-7�̃{�f�B�����E�ɐU����LV�\�����������̈�ۂ́A�ȉ��̒ʂ�ł����B
�@1)���C�u�r���[�\���̂��߁A�������\�����x���B
�@2)CMOS�ǂݏo���̃Y���ɂ��A���E�ɐU��X�s�[�h�ɂ���ẮA��ʂ��c�ނ悤�Ɍ�����B
���̂Q�_�́A�r�q�@�\��OFF�ɂ��Ă��A���l�Ɋ����邱�Ƃ��o���܂����B
MZ-LL�����[10869416][10869492]�̏������݂�����ƁACMOS���܂ފ�Ղ����S�Ɂu���V�v���Ă��āA
�Ⴆ�J�����{�f�B���������֔����Ɉړ������ꍇ�ɂ��ACMOS�͕��V���Ă��Ă��̈ʒu�ɗ��܂葱����Ɖ��߂��Ă��܂��B
���̉��߂��ƁALV�\�����J�����̈ړ��ɑ��Ď�x��A
������������L1�r�Ɠ������ۂ���������ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
MZ-LL���ALV�\���̉������Ĉʒu�Y���̕���s���Ă���Ɓu�m�M�v�����̂��^�₾�����̂ł����A
1)�̓����������āA�������̉��߂ƌ��т��Ĕ[�����Ă���̂��낤�Ɨ\�z���鎖���ł��܂����B
���Ȃ�X�b�L�����܂����B
���Ȃ݂Ɂc�cMZ-LL����̂��̔����ɂ��ւ�炸�A
�F����͂��낢��ڂ���������Ă���Ă��܂��B
MZ-LL����A���������Ȃ��Ȃ��c�c
�܂��A�������̊��o�����������M�p�����̂��悢�ł��傤�B
���́A���̊��o�Ǝ��W��������M�p���܂��B
�����ԍ��F10869714
![]() 6�_
6�_
�X�����MZ-LL����Akuma_san_A�P����A
�[��̏������݂ɂ�������炸���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
��{�I�ɂ����Ă��āA�����͂���Ȃ薰��ɂ��܂��B
�ł́A�܂�
�����ԍ��F10869743
![]() 2�_
2�_
�܂����낢��ƂƂ�ł����_�ɂȂ��Ă��Ă��܂��Ă���悤�ł����A
�C���[�W�T�[�N�����ł̈ړ��A�Ƃ����̂��|�C���g���Ǝv���܂��H
�����āA�����C�u�r���[�Ŏ����A�ʒu�̔��u���A�h�ꂪ�A�����Ă��邱�Ƃ�����܂���B
����A��]�n�i���[�����O�j�̃u���̐����̌�A�����čL�����i�B�e�̍ۂɁA
��Ԃ����n�m�ɂ��Ă���ƁA�C���[�W�T�[�N���ɑ��āA���ӂł��鍶�E��
���ӕ��̉掿�́A�Ɠ��̃u���i���̕��������ɂ͐����ł��Ȃ��̂ł��j���o�邱�Ƃ�����A
���Ă������Ƃ��A�܂��g�U���U��ƁA���܂��܋߂��ɓ\���Ă����J�����_�[���Ȃɂ���
�傫�ȕ��i�ʐ^���g���āA������Ă��������܂����B
�L���͂��ڂ낰�ł����A�Z���A�㉺�łȂ��A���ӂł��鍶�E�̒[�̂ق��̉掿�̂��Ƃ��A
����������Ă������Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�����čL�������̏ꍇ�ɁA�f�q�����[�����O����ƁA�Ɠ��̃u����������A����������b�ł����B
�����A���́A�����̎g�p�����炱�̃X���b�h�𗧂��グ�Ă��܂�����A�����I�Ɍo�����Ă��Ȃ����Ƃ́A
�������肭�ł��Ȃ��̂ł��B���p����悭�m��܂���B
�ł��A����̌�b�̗v�_�́A�����ŏ����ȏ�A���x���m�F���Ă��܂����B
�p�x�u�������A�ǂ��炩�ƌ����A��Ɉʒu�u���i���s�u���j�����Ă���̂��ƁB
�V�t�g�Ԃ�A�Ƃ����P��͏o�Ă������ǂ����o���Ă��܂���B���Ȃ��Ƃ����͎g���Ă����̂ł����A
�Z�p�҂̌�����A���̒P����g���Ă͂��Ȃ������悤�Ɋ����܂��B�t�Ɍ����A
�ʒu�u���╽�s�ړ��A�Ƃ����P��́A���x����b�̒��ɏo�Ă��܂����B
���ƁA���C�u�r���[�ŁA�������x��ĕ\������邱�Ƃ��A���͊��Ⴂ�Ȃǂ��Ă��܂���B
��������������������ɂ��Ă��������B
�����ƁA�ʒu�̔��u���������āA�~�܂��Ă���̂ł��i���S�ɂł͂Ȃ��ł����j�B
�ڂ���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10869777
![]() 4�_
4�_
MZ-LL����
������
�l�l�ɉ�������������闧��̕��əG�z�ł͂������܂����ꌾ�B
kuma_san_A1����̔����ɏ�������݂��Ă݂Ă͂������ł��傤���H
���Ȃ��Ƃ�kuma_san_A1����̘b�ɕs�𗝂ȓ_�͊����܂��ǂ��ł��傤�H
����͂��Ă����A�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂���Ƃ��b���ꂽ�Ƃ̂��ƁB
�l�I�ɂ͔��ɋC�ɂȂ�܂��̂Ŏ��₪�������܂��B
�y���^�b�N�X��K-7�\�������̂��b�ŁA
�u��]�����̎�U���͎������Ă��Ȃ��v�ƕ������̂ł����A
���̊Ԃɂ��o�[�W�����A�b�v�ł�����Ă���̂ł��傤���H
�������C�Â��̓_�ł�����܂����炲�ԓ����肢���܂��B
�����ԍ��F10869811
![]() 6�_
6�_
�����W���āA���������̋�_�łȂ����킹��̂��A���낻��~�߂āA
���̏����Ă��邱�Ƃɔ[�������Ȃ��l�����́A���ڃy���^�b�N�X�ɁA�₢���킹���
�ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@�y���^�̐l�����̌�d���𑝂₵�Ă��܂��̂́A���������Ȃ̂ł����A
���낻�낢�������ɁA�Ԉ���������������ނ̂́A��߂ė~�����ł��B
�Ԉ���������A�����牽�x�������Ă��A����͖��f�ł�������܂���B
�X���b�h�̎�|������O��Ă��܂����A���Ȃ��Ƃ��A�����y���^��������Ă���ȏ�A
�f��`�ŏ����͎̂~�߂āA�����������Ԉ���Ă��邩������Ȃ��A�Ƃ����O��������Ȃ��ƁA
�{���ɁA�ǂ�ł���l�����܂ł��A������Ă��܂��ł��傤�B
����́A�����̖ڐ��ōl����A���������������f�Ȃ��ƂȂ̂ł����B
������A�������������Ƃ̂ق������������Ƃ����炩�ɂȂ邵�A����ȏ�A�R�̏��������A
���W�����Ȃ��Ȃ�܂��B���łɃX���b�h�̔����ȏオ�����R��f�}�Ȃ̂�������܂��A
�ł���A�����Ǝ��ۂɉ��������������A�₢���킹��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��]�����̃u���ɂ��Ăł����A�������̕�͂܂��ł��Ȃ����̂��ƍl���Ă��܂����B
�ł��A���ۂɂ�����A�g�U���U��Ő������Ă����������̂ł��B
�����āA�����Ă݂�A�^���ʎB�e�̍ۂɁA���s�␅�������ɍ����₷���ȁA��
�����Ă������Ƃ��A��Ŕ[���ł��܂����B
�������_�̂悤�ɁA�������ސl���A���̃X���b�h�ł́A���������Ԉ���Ă����肵�܂�����A
�ǂ�ł�����́A���ЁA���C�������������B�{���Ƀ^�`�������ł��B
���̐����́A���͊��o�I�ȃ��m�Ɋ�Â��Ă���̂ʼn���ɂ����Ǝv���܂����A
���̂ق��͐������ł�����A������Ȃ��悤�ɁA�C�����Ă��������B
�������ŁA�^�������܂�킯�ł͂���܂���B
�����ԍ��F10869839
![]() 6�_
6�_
��Tubby sponges����
�@�����Ȃ��Ƃ�kuma_san_A1����̘b�ɕs�𗝂ȓ_�͊����܂��ǂ��ł��傤�H
����́A�����B���f�q�V�t�g�����̎�Ԃ��ł��Akuma_san_A1�������Ă���̂́A
���Ԃ�R�j�~�m�̕����̂��Ƃ����炾�Ǝv���܂��B������A�ꌩ�A�������Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����B
�ł��A�����ŏ����Ă���̂́A�y���^�b�N�X�̂r�q�̂��ƂȂ̂ł��B
���̎d�g�݂��A�����A���ɕ����Ă����̂ł��B
��]�����̃u���Ɋւ��ẮA��L�̒ʂ�ł��B
������ÂȌ����ł��A���ۂ́A�Ԉ�����l�̈ӌ��𐳂����ƔF�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA
��Âł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���������A�l�������Ă݂Ă��������B�����v���Ⴂ�ł��B
�����ԍ��F10869860
![]() 2�_
2�_
MZ-LL���u�ǂ̂悤�Ɋ����Ă��邩�v�Ƃ��A�u�v���Ă��邱�Ɓv���������̂́A����Ӗ��u���R�v�Ȃ̂ł����A�u��Ԃ��v���ǂ̂悤�Ɏ�������邩�Ƃ����u�����I�Ȑ����v�����́A��������s�킹�Ă��������Ă��܂��B
����͌�����L�܂�̂�h���Ӗ�����ł��B
�e���f�B�A�Ɍf�ڂ���Ă���L����A���[�J�[�̍L��ɂ�������L�q�͑��X�����܂��̂ŁA���[�U�[�����Ȕ��f����K�v������܂��B
�������A�����g��������L�q���s�����Ƃ�����ł��傤�B
�������͑ӂ�Ȃ��p����ۂ������ƍl���Ă��܂��B
������Ƃ͖����ɗ������Ȃ��ŁA�u��Ԃ��v�Ȃǂ̋Z�p�̉��b��f���Ɏ�ƌ������@������܂��B
�u�e�����̗D��v�͗ǂ��b��ɂȂ�܂����A�ǂ���u�B�e�̈���g�債�Ă����v�L�p�ȃA�V�X�g�@�\�Ƃ��Ď~�߂�Ηǂ��̂ɂƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F10869886
![]() 16�_
16�_
��������ÂȌ����ł��A���ۂ́A�Ԉ�����l�̈ӌ��𐳂����ƔF�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA
����Âł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���������A�l�������Ă݂Ă��������B�����v���Ⴂ�ł��B
�\�������܂��A�ǂȂ��̂��Ƃ��w���Ă�����̂ł��傤���H
�������āA�����Ă݂�A�^���ʎB�e�̍ۂɁA���s�␅�������ɍ����₷���ȁA��
�������Ă������Ƃ��A��Ŕ[���ł��܂����B
����������̌��ʂɂ��ẴR�����g�ł��傤���H
��U���͒��ڊW�Ȃ��ł���ˁH
�����ԍ��F10869928
![]() 5�_
5�_
����̋�_���Ȃ����킹�āA�����̓s���̗ǂ��\���Ɏ����Ă����̂́A���Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���܂��B
���̘b��ŁA���̃X���b�h�̎�|����O��Ȃ����߂ɂ́A�܂����ۂɃy���^�b�N�X��K-7�ȂǂŁA
�����������ׂ��ł��B������Ȃ�ł��A���̃X���b�h�̒��ŁAkuma_san_A1�����
���܂�ɂ��ԈႦ���������������܂����B���������������A��������ł͗~�����Ȃ��ł��B
���̏������݈ȊO�ł��Akuma_san_A1��������Ă�����A�Ԉ���Ă����肵�����Ƃ��A
���������炩�ɂȂ��Ă܂��H�@�Ƃɂ����A�r�q�̂��Ƃ�m��Ȃ�����̂ł��B
������x�A�����Ȃ����ė~�����̂ł��B�������ވȏ�́B
�����ĊԈ�������Ƃ���������A�����ƒ������Ă��������B���ꂪ�ǂސl�����ɂƂ��āA
��ȏ��ɂȂ�܂��B�����ԈႢ�������ƏC������E�C�������Ă��������B
�����ԍ��F10869936
![]() 6�_
6�_
kuma_san_A1���ʃX���ŏЉ��Ă��T�C�g�ł����A�����ł������N���Ă����܂��F
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/as/as.html
�X�b�]�R����������̖��̓����ڂ��Ă܂��ˁB
�܂��A�ߐڎB�e�ȊO�ōł��傫�Ȏ�Ԃ�v�����p�x�Ԃ�ł��邱�Ƃ��A���̃y�[�W�㔼�̃O���t����킩��܂����A
�������A���̂��Ƃ́AF-47��������Ă�悤�ɁA�����̖ڂŊȒP�Ɋm���߂邱�Ƃ��ł��܂��B
CANON��SONY���A���Ђ͂��ׂĕ���������Ă��邱�̊̐S�̊p�x�Ԃ�Ɋւ��āA
���p�x�Ԃ�ɂ́A���܂蒍�ڂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ���������Ă��܂����B
���p�x�u�����y���^���ϋɓI�ɕ���Ȃ�
�Ə�����ẮA��������PENTAX�͉�����Ă�A�ƁA�s���ɂȂ���������邩������܂���ˁB
PENTAX�̖��_�̂��߂ɂ��A������x���߂Ē������Ă����܂����A
PENTAX��SR�͊p�x�Ԃ������@�\�ł��B�����T�C�g�̐������番����Ǝv���܂��B
�i��̃X���傳��̋L�q�́APENTAX�ɂƂ��Ă͂���Ӗ��A�c�ƖW�Q����̃f�}�ł�����A
�X���傳�g�ŋC�t����āA�������ꂽ��悢�Ǝv���Ă܂����B�B�j
�����ԍ��F10869969
![]() 19�_
19�_
MZ-LL����͂��Ԃ����ēǂ�ł���ł��傤���A�u��Â��v�����ł��B
�킽���̉ߋ��̏������݂̏Љ�ł�(��Ԃ��W)�B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501110810/SortID=4415761/#4419283
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501110599/SortID=3392001/#3445537
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=3432162/#3434327
��Ԃ��̊�{�͂��Ȃ�̂̃p�i�\�j�b�N�̋Z�p�҂���ɂ����̂ł�(�u�����r�[������)�B
�Z���T�[�V�t�g�����ɂ��Ă������Ƃ��̋Z�p�҂��G��Ă܂����A�����͌������܂����B
�W���C���Ńu���̊p�x�Ƃ����߁A����tan�ƂɁu�����_-�B���ʂ̋���(�������Ƀt�H�[�J�X������Ԃł͏œ_�����ɓ�����)�v���悶�������t�����ɎB���ʂ��V�t�g����̂���{�I�Ȍ����ł��B
�Z���T�[�V�t�g������XY�K�C�h���[���ƈ��d�A�N�`���G�[�^�쓮�ŃR�j�J�~�m���^�ɂ���������APENTAX�̓{�[��3�_�x���̓d���쓮�Ŏ�������܂����B
�E�R�j�J�~�m���^�̕����̓A�N�`���G�[�^�̋쓮�X�e�b�v���ňړ��������킩��܂��̂ŁA�X�e�b�v���Ő�����s���܂�
�EPENTAX�����͎B���ʂƈ�̉��������j�b�g�ɓd���쓮�V�X�e����2�_�ȏ�̈ʒu�Z���T�[(�Z���^�[�ʒu��쓮�ʒu���t�B�[�h�o�b�N���邽��)��p���Đ�����s���܂�
���d�A�N�`���G�[�^�����͋쓮�X�s�[�h�̉����ɑ���ȊJ���G�l���M�[�𒍂����悤�ł��B
�d���쓮�V�X�e���̓X�s�[�h�ʂł̕s���͂Ȃ������ł����AXY�K�C�h�ɔ����Ȃ����삪�\�Ȃ̂Łu���������ێ��v��A�t�@�C���_�[�X�N���[���ɍ��킹���B���f�q�̈ʒu���߂Ȃǂɂ����p����Ă��܂��B
���[�C���O�A�s�b�`���O�����̊p�x�u���̑��A���[�����O�����̃u���(�����̃A�i�E���X�͖����Ǝv���܂���)����������܂���B
�����ԍ��F10870027
![]() 5�_
5�_
MZ-LL����̃C���[�W���Ă���u�W���C���ň��ɕۂ����v�Ƃ����̂́ADiMAGE X1�̎�Ԃ����Y�����܂��B
�B���f�q�����ɕۂ̂ł͂Ȃ��A�u���w�n�܂ގB���ʂ܂ł̃��j�b�g�v���̂��̂��p�����䂷����̂ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00502411000/SortID=6105252/#6112402
(�����ɏЉ�̃����N��͖����Ȃ��Ă��܂�)
�����ԍ��F10870072
![]() 3�_
3�_
��gintaro����
���̃����N��̏��͌Â��A�B���f�q�V�t�g����Ԃ��Ɋւ��ẮA����s���ł��B
���x�����̂��Ƃ������܂����B�R�j�~�m�̕�����̉���ł��B
�}����ő�ω���₷������A����͂̂Ȃ��l�ɂ́A���傤�Ǘǂ��̂�������܂��A
�����A��������������Ŋ�������A���ږ₢���킹���A�y���^�̂r�q�̓���Ƃ́A�����ɑ��āA
���̊��m�̎d���⓮������������Č�����̂ł��B�y���^�́A�f�q���i���ʂ́j��ԍ��W��ŁA
�����Ȃ����Ƃɂ���āA�u����ł������Ă��邩��A�ʒu�u����̗v�f�������̂ł��B
�Ԉ���������̌������A�����������悤�ɏ�����Ă͍���܂��B
���x�������܂����A�l�b�g�ŏE���Ă����悤�ȏ����Ȃ����킹���A�ϑz�����̋�_�����A
�^�����������郌�x���܂Œb���グ���A�l�̎g�p����o���̂ق����A���i�ȓ��ɋ߂Â����Ƃ�����̂ł��B
��kuma_san_A1����
���o���ɐ��������������Ă��������łȂ��A�傫���v���Ⴂ�����Ă��镔������R�������킯������A
�����ƒ����̌`�������āA�������Ă��������B�����Č����^���Ă���l�����ɁA�Ӎ߂������ق����悢�ł��傤�B
����A���ւ̎Ӎ߂́A�������{���ɐ\����Ȃ��Ɗ����Ă���ł��܂��܂��A���Ȃ��Ƃ��A
�ǂ�ł���l�����Ɍ����ẮA�ꌾ�ł������̌���l�т��ق��������Ǝv���܂��B
�����g�́A�����ƒ��������Ă����Ȃ�A����͂��Ȃ��ł����A�܂��ʂ̕���ł�
���b�Ȃ�A�������Ă����������Ƃ����邩������܂���B
���͌����������Ē��ׂ����ŁA�����ɏ�������ł���킯�ł͂���܂���̂ŁA
���i�R����̕ʃX���̂��̃����N�L���́A�܂��ǂ�ł��܂��A���͖Z�����̂ŁA
���Ԃ��o�������ɂł��q�����܂��B
�����ԍ��F10870804
![]() 3�_
3�_
�d���Ȃ��̂ŁA�͂����菑���Ă����܂��B
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/slr/k20d/feature_02.html
�́uSR�̎d�g�݂Ɛi��(�C���[�W�})�v�ł����A
�u��Ԃ��O�v�̐}�Ɓu��Ԃ����v�̐}������ւ���Ă��܂��B
�T�|�[�g��ʂ��Ē�����i�����Ă����Ă��������B
�����ԍ��F10870833
![]() 2�_
2�_
���m�Ɍ����ƁA�J�����{�f�B���̐}������ւ���Ă���̂ł����A�Ԑ��Ɛ��͐������Ƃ����c���܂�����Ԃł��ˁB
��Ԃ����̃J�����{�f�B�ł͎B���f�q�������Ɉړ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B
�����ԍ��F10870844
![]() 2�_
2�_
�܂��܂����ז������Ă��������B
MZ-LL�����K-7��SR�@�\�Ɋւ��Ă̕��͂��A�܂��Ƃɏ���Ȃ���
�����Ȃ�̉��߂�fig.1�`4�̃C���[�W�}�ɂ��Ă݂܂����B
�i�Ԉ���Ă������e�͂��j
�܂�K-7�X�[�p�[�u�b�N�̕\�������p����A
�h�B���f�q�̏�����Z���^�[�v���[�g�A�w�ʃv���[�g��
3�_�Ŏx���{�[���ŕ��ʐ���ێ�����A���͂Œ�ʒu�ɕ����Ă���B�h
�Ƃ���܂��B
�����ŎB���f�q��
fig.1
�J�������V�t�g���ꂵ�Ă��A�B���f�q�i�j�{�Z���^�[�v���[�g�i�Ԙg�j��
�V���b�^�[�������ĂԂꂽ�u�Ԃ͂��̐�Έʒu�i�n�ʂɑ��鑊�Έʒu�j��ς��Ȃ��B
�i���ꂪ�����̖@���䂦���A�A�N�e�B�u�ɐ��䂳��Ă̂��̂��͓ǂ݉����܂���ł����B
�h�W���C���ňʒu��ۂh���W���C�����ʂł͂Ȃ��ł����E�E�E�j
fig.2
�������V���b�^�[�������ă��[�����O���Ă����̈ʒu��ς��Ȃ��B
����ɂ�
fig.3
K20D�̎�Ԃ��̃C���[�W�}�Ɋւ��ẮA�����Y�����ɉ��������ꍇ��
�J����������ɃV�t�g������N�����̂ŁA�B���f�q������܂�
��Έʒu��ۂĂA����ʂ��邱�Ƃƍ��v����B
fig.4
�����ȃV�t�g����i�ʒu����j�Ɋւ��āA�B���f�q����Έʒu��ۂĂ�
�����Ƃ̊W���ς��Ȃ��̂ŁA����ʂ�������B
�Ƃ��������̂ł��B
���̕��X�̌����Ƃ��邱�Ƃ��킩��܂����̂ŁA���̎��ɃC���[�W�}�ɂ���
�A�b�v���܂��B����܂ł��̃C���[�W�}�ɑ��邲�ӌ��͌�e�͂��E�E�E�B
�����ԍ��F10870845
![]() 7�_
7�_
�܂����t���炸�ł����B
�@�������g�́A�����ƒ��������Ă����Ȃ�A����͂��Ȃ��ł����A�܂��ʂ̕���ł�
�@�����b�Ȃ�A�������Ă����������Ƃ����邩������܂���B
�ȉ��ɒ��������Ă��������B
�@�@�����g�́A�����ƒ��������Ă����Ȃ�A����͂��Ȃ��ł����A�܂��ʂ̕���ł�
�@�@���b�⑼�Ћ@�Ɋւ��Ă̂��ƂȂ�A�������Ă����������Ƃ����邩������܂���B
���ہA�����B���f�q�V�t�g���ł��A�y���^�Ƃ͕�̎d�����Ⴄ���Ƃ́Akuma_san_A1�����
�������݂����������ŁA�����Łw��-7 DIGITAL�̎�Ԃ��Z�p�x�����ċC�Â����킯�ł����A
http://konicaminolta.jp/about/research/technology_report/2005/pdf/feature01_003.pdf
�������ꂪ������A���̓y���^�������̌��ł͒m��Ȃ����߂ɁA�B���f�q�V�t�g���́A
�\���⓮��̎d�g�݂��e�ЈႤ�����ŁA�قړ����悤�ȕ���s���̂��ƁA���Ⴂ�����܂܂������Ǝv���܂��B
������A���Ԃ����鎞�́A���V���[�Y��A�I�����p�X�Ȃǂ̎�u����Ɋւ��Ă��A���ׂčs�������ł��B
���̃X���b�h�́A�ǂ���̕���D��Ă��邩�A�Ȃ�Ă��Ƃ����ꏊ�ł͂Ȃ��A�����g���A
�ǂ��̃��[�J�[���ォ�����A�Ȃ�Ă��Ƃ����������킯�ł͂Ȃ��ł����A���ɂ����������͏����Ă��܂���B
�P���ɁA��������Ⴄ���Ƃɂ���āA���ʂ̏o�����Ⴄ�Ɗ�������̑̌���~���Ă���̂ł��B
�g�p���@���قȂ�A�l���ꂼ��̎����͈قȂ�A�Ⴂ�͊������Ȃ������A�Ǝv����������������ł��傤�B
�������A������������ӌ��͑��d�����Ă��������܂��B�����ĕ��ɂȂ�܂��B
�����Ă������������Ƃ����肪�����v���܂��B�ł��A�͂��߂��玄�̍l���̂ق������������A
�Ƃ����O��ŁA�������Ȃ��A�Ԉ�����������ꂱ��Ђ����珑���l�́A���������f�Ȃ̂ł��B
�X���b�h�̎�|������O��Ă��܂����B
�������ޑO�ɁA�Y�����Ȃ����������Ă�����A�������甭����������̋�_�ł͂Ȃ��A
���ۂɎ����̗͂ŁA�����Ƃ�����������Ă݂ė~�����̂ł��B
���̏�̂��i�Y�����Ȃ��Ƃ͌����j�������ꍇ�ł��A����������Ɠǂݎ��\�͂������l���A
��������ɗ���ɂ�����A�U�肩�������肷��A����́u�Q�v�ɂȂ�܂��B�C�����Ă��������B
�����ԍ��F10870859
![]() 4�_
4�_
MZ-LL�������C�Â��Ă����Ηǂ��̂ŁA�ʂɎӍ߂��v��܂���B
�������ʓ|�ł��傤���犨�Ⴂ�����������������Ώ[���ł��B
(���ꂾ�����̐������[�����Ă���X���b�h��ǂ�Ō������̂͂��̐l�̐ӔC�ł�����)
�����āA����炪���s����Ȃ������Ƃ��Ă��A���������ɕω��͂���܂���B
����Ȃ��Ƃō��肷��͖̂��v�ł���B
�����ԍ��F10870879
![]() 7�_
7�_
wsxwsx����A���������݂ƁA�摜�̌f���A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��I
�Ƃ��ɁAfig.2�́A�����u��]�v�Ƃ������t�ŗp�������[�����O�̕�̐}�ŁA
�y���^�b�N�X�̕����A�g�U���U��ŋ����Ă������������Ƃł��B�����āA���̃��[�����O��
��ŁA�u���ɑ��đł������悤�Ȋp�x�ɌX�����܂܂ŁA�I�����A��ԍ��W�ɗ��܂�悤�ɁA
�{�f�B�ɑ��Ĉړ����Ă��邻���ł��B���̃��[�����O�̌X����ۂ����܂܁B
�������A���̈ړ���[�����O�ł���͈͂��Ă��܂��قǃu�����傫����A
�摜�ɂ��A�u�����L�^����Ă��܂��܂���ˁB
�����āAfig.4�́A�܂��ɁA���̃X���b�h�ɂāA���������Ă������Ƃł��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��I
�������A�����Ɏ莝���ŁA�����܂Ŋ��S�ȃV�t�g�����̃u���Ƃ����̂́A�����߂����ɖ�����������܂���A
�ł��A����ɋ߂��u�����N�����ۂɁA���ۂɑ̊��ŁA���ꂪ�����Ă��邱�Ƃ�������ꂽ�̂ł��B
���́A�@�B�ɏڂ����Ȃ����߁A���������ǂ������Z�p�ł��ꂪ�s���Ă��邩������Ȃ��̂ł����A
������A������̃X���b�h�ʼn���ł����ԂɎ����Ă������߂����ɕ�����̂́A
��ςȎ��Ԃ�v���܂����A��M������܂���B
����₷���}�ŁA������Ă������������ƂɁA���ӂ������܂��B
�������A�٘_��������X���A��R����������Ǝv���܂����A�ł���A�����̍l�@�ɁA
�Ƃ��ꂸ�ɁA�ł��邾����Âɔ��f���A���ł���Ύ��ۂɎ����Ă݂Ă��������B
�����āA�ǂ����Ă�����Ȃ���A���[�J�[�ɖ₢���킹�Ă݂Ă��������B
���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10870904
![]() 4�_
4�_
���̕��X�̂Ȃ���[10868398]�̔������ꂽ���������ƂȂ��ꂽ
���Ƃ��C���[�W���Ă݂܂����B
��قǂƓ�����fig.4������ɑ������܂��B
���̏ꍇ�A�B���f�q����Έʒu��ۂ̂ł����
�B���f�q�̓J�����ɑ��ď�����ɃV�t�g���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
����fig.5�ł����A�J���������ɃV�t�g����Ƃ������Ƃ́A�J������
��ɂ��Ă݂�ƁA�B�e�Ώۂ���ɃV�t�g�����̂Ɠ����ł����
���߂���܂��B
�������J��������ɂ��Č����ꍇ�A�Ώۂ���ɓ����ƎB���f�q���
���͋t���Ȃ̂ŁA�������Ɉړ����邱�ƂɂȂ�B
������B���f�q�͉������ɓ����Ȃ��ƂԂ����ʂ͓����Ȃ��B
�����fig.4�͕����I�A�_���I�ɐ��藧�b�ł͂Ȃ��B
���܂�ɉ����Ŏ�O����ɂȂ�܂��̂ŁA�����܂łɂ������܂����A
�v�����K-7�i���͂��ߎ�Ԃ��S�ʁj�́h�p�x��h�ł����āA
�ʒu����i�V�t�g����j��ł͂Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB
������ɂ��Ă�K-7�͂����J�����ł��B�ݒ�̑��쐫��K200D�����P����܂����B
����K200D��MF�{���M�v�X�ɂ������܂������AAF�{�^���̈ʒu���悭�Ȃ菕����܂��B
����DA��300mm�����č\�����Ƃ��́AK200D�̃O���b�v�̕�������₷�����肵�܂��B
�ł́A�܂��B
�����ԍ��F10870920
![]() 6�_
6�_
�����ł��B
[10870833]�Ƃ��̎��ŏ������u�}������ւ���Ă���v�ł����A�ǂ�����Ɓu��Ԃ����v�͂����Ɖ����Ɉړ����Ă���悤�ɏ������Ƃ��Ă���݂����ł��B
�^�̐}�������Ə����Ă��Ȃ��̂Ō�����Y��ł���̂��ȁH
�����ԍ��F10870925
![]() 1�_
1�_
wsxwsx����@�A�܂��ɐ}���̒ʂ�ł��B
MZ-LL����̗���(���)���ƁA��Ԃ��������ł��܂���B
�����ԍ��F10870946
![]() 4�_
4�_
wsxwsx����A���ۂ̎g�p�������������݂��������A���肪�Ƃ��������܂��B
���́A�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̌���ɁA���̌����ŁA�͂�����ƈʒu�u���̕���ƁA
�����Ă��Ă��܂��̂ŁA�ǂ����Ă��ꂪ�ł��Ȃ��̂��́A�����ł��Ȃ��̂ł����A
���Ԃ������Đ}������Ă������������ƂɁA�{���Ɋ��ӂ������܂��B
���ɉ���₷���ł��B
���ʂ��t���ɂȂ�̂́A�≖�ł��f�W�C�`�ł������ł����A�f�q��������ԍ��W���
���܂��Ă���A�W�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����āA�C���[�W�T�[�N�����̒��ł̈ړ��i�Î~�j�ł��邱�Ƃ��|�C���g�ł��B
�����āA�y���^�̎�Ԃ��́A�O�ɂ������܂������A�S���̌ۓ��ɂ����u���Ȃǂ�����Ă��邻���ł��B
������B���Ă��Ă��A�C���[�W�T�[�N�����̑f�q��������i�~�܂��j�������قǂ�
�ʒu�u�����A�����ƕ�ł��Ă��邱�Ƃ��������܂��B
��͂�A���ۂɉ��x���m���߂邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����̋�_�ɂƂ����ƁA�^�������ɂ߂邽�߂̊��o��ڂ��炽�Ȃ��Ǝv���܂��B
���������݂ƁA�}���A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10870969
![]() 2�_
2�_
������ƍl���Ă݂܂������A�C���[�W�T�[�N�����ŁA���ړ����Ă���Ƃ������Ƃ́A
wsxwsx����Afig.5�̍l���͓��Ă͂܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����͈��̂܂܂ŁA�����Y�̂ǂ��炩���̎��ӕ��̕`�ʂ��邱�ƂɂȂ�܂����A
�C���[�W�T�[�N�����ł̈ړ��ł�����A���ӕ����ɒ[�ɗ��邱�Ƃ͂���܂���B
�R�j�~�m�̂悤�ɁA�X���Ă��ꂽ�����ɍ��킹�đf�q���ړ�����Ȃ�A���Ε����ɓ����̂�
����̂ł����A�y���^�̂r�q�́A����̕������Ⴄ�̂̓n�b�L�����Ă��܂��H
�{���ɂ킸���ȁA���Ԃ�̈ʒu�u�������ʓI�ɕ����A�Ƃ����O��ŁA�����ƍl���Ă݂Ă��������B
���́A���̔��u���̈ʒu�u�����A�����邱�Ƃɂ���āA���ɏ������Ă��܂��B
�f�q�������镪�����̕�ł�����A�m���Ɉʒu�u���ł���ʂ́A�킸���ł��B
�������A���̂悤�ɁA�ߋ����E�������B�e������ۂɁA���肵���\�����ł���l�Ԃɂ�
�i������s�B�e�������ς����܂����j�A���̈ʒu�u���̕���A��ς��肪�����̂ł��B
�����A�C�ɂȂ�܂�����A�y���^�b�N�X�ɒ��ږ₢���킹�Ă݂�̂��悢���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10870997
![]() 2�_
2�_
���̂���ނ��ɂ̂т�ˁD
��U�����ė����B��݂����Ȃ���ł���D
��ʑ̂����ɓ������牺�ɒǂ�����������͂��D
�O�r�ɌŒ肵�ė����B�胂�[�h�Ƃ�������������̂ɁD
�����ԍ��F10871060
![]() 0�_
0�_
wsxwsx����́AMZ-LL����(�ȊO�ɂ���������Ⴂ�܂����H)�̗����ƁA�����܂ޕ����̐l�̗��������ꂼ��}�����Ă��ꂽ���̂ł��B
MZ-LL����̌���͉����܂����H
�����ԍ��F10871072
![]() 4�_
4�_
LR6AA����
����U�����ė����B��݂����Ȃ���ł���D
��ʑ̂����ɓ������牺�ɒǂ�����������͂��D
�O�r�ɌŒ肵�ė����B�胂�[�h�Ƃ�������������̂ɁD
���Ƃ����K����Ȃ��C�����܂��B
�u��ʑ̂����ɓ�������(�B���ʂ�)��ɒǂ�������悢�v
�����ԍ��F10871150
![]() 1�_
1�_
�����܂���A�Ƃ��o�鏀�����ɏ������̂ŁA��������ǂ܂��Ƀ��X���Ă��܂������߁A
������Ă��邩������܂���B����A�܂��q�������Ă��������܂��B
���̓ǂ݊ԈႢ�Ȃ���������Ă��������܂��B�����܂���B
������A���ꂱ�����傤�ǁA�l�̍�i�W�̉��B�e�ɍs���܂��B�莝���ł����ʂ������Ă��܂��B
����́A�����̂��߂ɂQ����o�b�e���[���������邽�߁A����ȂǂōĊm�F���ł��܂���ł����B
�������ɎO�r�̗p�ӂ�������A���Ƃ��Ɖ��B�e�̗\��ł�����A�莝���������Ȃ�Ǝv���܂��B
����A�{�i�I�ȎB�e�ł��B
����ł́A�܂����炭�A�X����͂��Ȃ��Ȃ�܂����A�ł���A�^���ɋ߂�����
��������ł���������K���ł��B���̕�ł͂Ȃ��A�y���^�̂r�q�ɂ��Ăł��B
�����ԍ��F10871226
![]() 5�_
5�_
�ȂA���ˌ��Ă�C���ɂȂ��Ă��܂������B�B
�����Y���Ă܂���ł���(fig.4)�A�Ȃ�ăI�`������Ȃ��Ȃ��B
wsxwsx����̐}���́A���ꂾ���ŏ\���킩��₷���ł����A
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/as/as.html
�̒��́A������̐}�����킹�Č���Ɨǂ���������܂���ˁB
�����ԍ��F10871284
![]() 6�_
6�_
�����́B
[10868398]�ɂ����������������肪�Ƃ��������܂��B
�J�����������ɃV�t�g�u�����鎞�A���������B���f�q�́u���v�֓����Ǝv���܂��A���Ȃ苭���m�M�ł��B
���R�́A�Ȍ��ɂ�[10868717]F-47����̐����A���ዾ�̎����ŗe�ՂɊm���߂���@��[10869678]�݂Ȃ���̂��������Ă���܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
����̓X���傳�܂ɂ͎c�O�ȃR�g��������܂���B�X���傳�܂́u��v�̓����A���̓������������ȋC�͂��Ă��܂����B
[10858683]�e�X���b�h�́u�W���C���Z���T�[�Ń{�f�B�̗h���ł������悤�Ɉړ��v��[10859459]�u���V�����f�q���A�W���C���ň��ɕۂ����v�̕\���Ɉ�a�������ڂ��܂����B�u�Ȃ�����ȍl�����H�v�Ǝv�����炷�ƁE�E�E
�u�W���C���v�̌��t�Łu��]����R�}�v�̃\���A��ԂŎp�����ێ����悤�Ƃ���\�����v��ꂽ�̂ł͂���܂��H�@���ꂩ��u���V�����f�q���A�W���C���ň��ɕۂv�ƃC���[�W���c��̂ł́B
�����ł́u�W���C���v�͂���ł͂���܂���B�܂������Ⴄ�d�g�݂́u�p�����x�Z���T�[�v�̂��Ƃł��B�d�g�݂Ȃǂ�Web�������B
[10858727]�ŏЉ�̃R�j�J�~�m���^��-7DIGITL�����ƈႤ�Ƃ��������_�A�u�B���f�q�͒��Ԃ���A�ɂ��ʒu���߁E���䂳��Ă���v�݂����Ȏv�����݁B�u�ɂ��v����A�J�����������Ă��A�����̊����̖@���ŃJ�����̓����ɊW�Ȃ��A���炭�͂����ɗ��܂낤�Ƃ���B
(�����ł́u�ɂ��v�͎B���f�q�ɕ��s����(�����ɐ���)�ȕ��������ł��B[10858727]�ŏЉ�̃�-7DIGITL�̎�u����Z�p��fig.3�́u�����Y�{CCD���j�b�g�v�S�̂��X���ău������Ă���}�ł͂���܂���B�y���^�b�N�X�Ɠ��l�̎B���f�q�����̈ړ��ł��B�����Y���X���Ă���̂́u�����Y��[�������ւ̃u���v��`���Ă��܂��BCCD�̒��S�Ɖ������ɒ��ځA�ȉ��������B)
�����Đ�̎���̓����A�V�t�g�u�������鎞�̎B���f�q�̓������v���Ⴂ���ꂽ���ƂƑ��܂��āA�V�t�g�u���ɑ��Ă̓R����������@�ɒ��x�͎キ�Ă������n�Y�Ƃ̍l���ɂȂ����̂ł́B
���ۂɂ́A�u�ɂ��v�ł͂Ȃ��u���Ȃ�拭�v�ɓd���̗͂ňʒu�ێ��A���邢�͈ړ����䂳��Ă���Ǝ@���܂��B���J�j�Y���͈Ⴂ�܂����A�拭���̓�-7DIGITL���������l���ƁB�����̖@���ł��̏�ɗ��܂�قNJɂ�������A�p�x�u���ƃV�t�g�u�����d�Ȃ������A�V�t�g�u���̃Z���T�[�������ăR���͐���ł��Ȃ��̂ŁA�p�x�u���̐���̐��x���ۂĂȂ��Ȃ�܂��B
(�ʒu�Z���T�[�́A�B���f�q�̈ʒu�����o���邽�߂ŁA�V�t�g�u���̓����̓x���𑪂�����x�Z���T�[�ł͂Ȃ��ł��傤�B�ʒu�Z���T�[�ł��A�f�[�^�[����������ϕ�����������Ƒ��x������x�Ɍv�Z�͂ł���ł��傤���A�����K�v�Ȃ�A�킴�킴�����Ɏ�Ԃ̂�����R�����́A�f���ɉ����x�Z���T�[�𓋍ڂ���ł��傤�B"�p"�����x�Z���T�[(�W���C��)�Ƃ͕ʕ��ł��B�u�d���̗́v�Ə����Ă܂�����������@�Ŋm���߂��킯�ł͂���܂���B)
�g�p�����瓾���u�V�t�g�u���ɂ�����Ȃ�Ɍ��ʂ�����v�Ƃ̌��A�莝���ŃJ�������V�t�g�u���݂����ɓ�����������ł��A����͕I�⌨���~���S�ɂ����p�x�u�����������ꂽ���m�ł͂���܂��B�莝���Ō����ȃV�t�g�u���������N�������Ƃ���ƁA�I�⌨�̉�]�^�����L�����Z�����邽�߂Ɏ����t�ɂЂ˂�K�v�����邩�Ǝv���܂��B������Ǝ������x�̗��K�ʼn\�ł��傤���B�܂��A�p�x�u���łȂ��V�t�g�u���ł���Ɗm���߂���@�́B
(���̘_�ł́A�t�Ɂu�p�x�u���łȂ��V�t�g�u���ł���v�Ƒ�����R�g�����S�ɂ͔ے�͂ł��܂���A�O�̂���)
�������E�E�E
���Ƃ���(�}�N�������Y�łȂ�)���œ_����50mm�̃����Y��50mm�̉����`���[�u�����1:1�}�N���B�������ꍇ�A�p�x�u����̂��߂̏œ_�����l��50mm�łȂ��ă����Y�J�o���ʂ�������100mm�ƃJ�����ɋ����Ă��K�v������Ǝv���܂��B�����Ɋp�x�u�������̏ꍇ�A�l50mm�ł͕�s���ɂȂ�܂��B
��L�̂悤�ɈӐ}�I�ȃV�t�g�u�������������ꍇ�A�p�x�u���̕�s���̃u���ƃV�t�g�u�����ł��Ȃ��u���Ƃ����܂���p���āA���ʂƂ��ėǂ������Ɍ������R�g������̂�������܂���B����Ń}�N���B��(�]�������Y�łȂ��ߐڎB�e)�ŁA�u����̌���Ƃ��đ̊��ł���̂����B
�����̔]���X�̗e�ʂł́A�Ӑ}�I�ȃV�t�g�u�������������ꍇ�̃J�����̓����A�u���̏o���A�u����̌��ʂ��V�~�����[�V����(���㕪��)���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�ł��B�����ł́A�ЂƂ̉����Ƃ��Ă����グ�Ă����܂��B
�E�E�E�ȂǂȂǁA�v���Ⴂ���������R�g�͂ł��܂����A�v���Ⴂ�łȂ��R�g�𗝉����邱�Ƃ͂��Ȃ荢��ł��B���̕��X�̏������݂Əd�����鏊������܂����A����炪�����̎v���ł��B
�������A�����͋Z�p�҂ł��Ȃ��A������m���߂���J�����������蓮����m���߂��킯�ł�����܂���B���̃��m����̃y���^�b�N�X�̎����������킯�ł��Ȃ��AWeb��̋ʐ����̏��v�������R�g�ł��B�܂����m��ʐl���������`�����Ȃ��A������y���݂ɂ��Ă���̂ł�����܂���B�����A�����Ƃ͈Ⴄ�����ɂ́A�ꉞ�͎���݂��Ă݂����͂���A�����������܂��B
���̋@��A���肪�Ƃ��������܂����B
��ӓ��e���悤�Ƃ��܂������A�菇�̃~�X�����e�ł��Ă܂���ł����B�蒼�����āA�������������Ȃ�܂����A��������B
�ŏ��̎���̓����A�t�C�������t�̃t�B�����ʒu�ɔ����������������ăo���u�ŃV���b�^�[�I�[�v���A�B�e���Ŋm�F���܂����B��͂�u���v�ł��B���ꂾ���͊���̘_�łȂ��Č��\�Ȏ��ł��B
�����ԍ��F10872506
![]() 11�_
11�_
>���Ƃ����K����Ȃ��C�����܂��B
>�u��ʑ̂����ɓ�������(�B���ʂ�)��ɒǂ�������悢�v
������ƍl���Ă݂܂��D
>�t�C�������t�̃t�B�����ʒu�ɔ�����������������
>�o���u�ŃV���b�^�[�I�[�v���A�B�e���Ŋm�F
���ꂢ���ł��ˁD����Ă݂܂��D
�����ԍ��F10872676
![]() 0�_
0�_
���A�A��܂����B
�������A���惂�[�h���Â������Y��t���Ď����Ă݂܂������A�����ƈʒu�u���������Ă��܂����B
�����āA�X�b�]�R����������̏������݁A�܂������Ɠǂ�łȂ��̂ł����A
���������Ă����Ƃ͈Ⴄ�̂ŁA�����ł̏������݂Ƃ��ẮA�ԈႢ�ƂȂ�Ǝv���܂��B
���������������������̂ɁA�����Ȃ�̔ے�Ő\����܂���B
�f�q����ԍ��W��ɗ��܂�A�Ƃ������Ƃ́A�C���[�W�T�[�N�����ł���A���ꂾ����
�ʒu�u����������͂��ł��B���̃X���b�h�ŊԈ���������������ސl�̓����Ƃ��āA
���r���[�ɒm�������邱�ƂŁA�������č������Ă���悤�Ɍ����܂��B
�X�b�]�R����������́A���낢��ƍl���邱�Ƃ��ł���l�Ȃ̂�������܂��A
���ЁA�X���ɂāAK-7�惂�[�h�����C�u�r���[�Ŏ��ۂɎ����Ă݂Ă��������B
�����āA�킴�Ǝ�U����N��������̂ł͂Ȃ��i����ɂ́A���ɍ����Z�p�Ɗ��o���K�v�ł��j�A
��{�͂�������ƃz�[���h���āA�p�x�u�����N���Ȃ��悤�ɁA�܂��͎B���Ă݂�����̂ł��B
���u�������łɕ����Ă��邱�Ƃ��A�n�b�L������܂��B
�����āA�B�e�Ɋ��ꂽ��A���́A�C���[�W�T�[�N���̍L���ƁA�B���f�q�̑傫���ƈړ��ł��鋗���A
�����ĕ��ʓI�ȋ�ԍ��W�Ɏc���Ă����Ԃ��ł��邾�����m�ɑz������̂ł��B
���̂܂ܕ��s�ړ�������A�ق�̂킸���ɕ��s�u���������ŋN���Ă��邱�Ƃ����o�ł���
���̃^�C�~���O���������Ȃ����Ƃł��B���u���������ƕ����Ă��܂��B
���̂悤�Ȓb�������͂Ɗ��o���Ȃ��Ă��A������x�́A�ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ��A���邩������܂���B
����Ȃ���A���x���`�������W���Ă݂Ă��������B�ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ́A�y���^�b�N�X��
�Z�p�҂̌���Ɋm�F���Ă��܂�����A�ςɋ^�킸�A�܂����̏���������Ƃ�O��ɂ���ׂ��ł��B
�f�q���A���ʁi�w�E�x�j�̍��W��ŁA���������s�ړ��i�u���A�h��j�Ȃ�A
���̈ʒu�Ɏc���Ă���̂��A���m���q���Ȋ��o�������Ă���l�Ȃ�A�����ɗ����ł���͂��ł��B
���C�u�r���[�⓮��Ȃ�A����͂���������₷���A�Ǝ��͊������̂ł����A����Ȃ��l��
�����悤�ŁA�������������܂����B
�Ƃ��ɑ��Ѓ��[�U�[����A�����ăy���^�b�N�X���[�U�[����Ŏ��o�̖����l�́A
�܂���K-7���Ŏ����Ŏ��ۂɎ����Ă݂܂��傤�B�@�t�B�������g�����������͌����Ⴂ�ł�����A
���̃X���b�h�Ŏ����������Ă��邱�Ƃ�A�y���^�b�N�X�����狳���Ă������������Ƃ́A
�ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�ǂ��炩�ɓ����A�̂ł͂Ȃ��A�f�q����ԍ��W��ŁA�����Ȃ��̂ł��B
������A�����t�Ƃ��A�����A���[�Ȓm�����A�������Č���������Ă���悤�Ɋ����܂��B
�C���[�W�T�[�N���͈̔͂̒��ł́A�ق�̂킸���Ȉʒu�u���̕�ł��B�������A���ꂱ�����A
�J�����̃t�H�[���f�B���O�������Ƃł�����X�ɂ́A���ɗL���ȃu���̕�Ȃ̂ł��B
���̂��Ƃ��A�����Ă��炦��Ɨǂ��̂ł����B
�����āA�l�Ԃ��ǂ����Ă������Ă��܂��A�S���̌ۓ��ɍ��킹�����u������ł���
�i�������Ɏ�������ɂ͂قƂ�NjC�t���܂���ł����j�A�Ƃ���������Ă����A�y���^�̐E�l���H���I�I
�����ԍ��F10873154
![]() 2�_
2�_
�܂��A�I�����A���Č��t�����Y��܂����B
�@���f�q����ԍ��W��ɗ��܂�A�Ƃ������Ƃ́A
�ł͂Ȃ��A
�@�@�f�q���I�����ɋ�ԍ��W��ɗ��܂�A�Ƃ������Ƃ́A
������Ɂ����������Ă��������B
K-7���[�U�[����ɂ������������̂ł����A�{���ɓ����C�u�r���[���ɁA
��U����ON�ŁA�ʒu�u���̕���m�F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��傤���H
���ЁA�����������Ƃ��āA�i�ʒu�u�������𑽂��܂j���u���������Ă��邱�Ƃ��A
�����Ă���A�Ƃ����l������������A���m�点�������������ł��B
�����ԍ��F10873182
![]() 2�_
2�_
>�ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ́A�y���^�b�N�X��
>�Z�p�҂̌���Ɋm�F���Ă��܂�����A�ςɋ^�킸�A
>�܂����̏���������Ƃ�O��ɂ���ׂ��ł��B
>�ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ́A�y���^�b�N�X��
>�Z�p�҂̌���Ɋm�F���Ă��܂�����A�ςɋ^�킸�A
>�܂����̏���������Ƃ�O��ɂ���ׂ��ł��B
>�ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ́A�y���^�b�N�X��
>�Z�p�҂̌���Ɋm�F���Ă��܂�����A�ςɋ^�킸�A
>�܂����̏���������Ƃ�O��ɂ���ׂ��ł��B
>�ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ́A�y���^�b�N�X��
>�Z�p�҂̌���Ɋm�F���Ă��܂�����A�ςɋ^�킸�A
>�܂����̏���������Ƃ�O��ɂ���ׂ��ł��B
���̑O������ɋ^�₪����̂ł��D
�����ԍ��F10873240
![]() 8�_
8�_
�܂��⑫���Â��C�����Ă��܂����B
�@���f�q���I�����ɋ�ԍ��W��ɗ��܂�A�Ƃ������Ƃ́A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�f�q���I�����ɃV���b�^�[���u�ԂƓ�����ԁi���ʁj���W��ɗ��܂�A�Ƃ������Ƃ́A
���炢�����Ă������ق����A�ǂ������ł��ˁB�����A�f�l�ł�����A�p��̎g������
�Ԉ���Ă��邱�Ƃ������Ǝv���܂�����A�C�ɂȂ���́A�����Œ��ׂ���₢���킹���肵�Ă݂Ă��������B
���̌��������炱���A�V���b�^�[���u�ԁi���O�j�܂Ŕ`���Ă����t�@�C���_�̍\�}���A
���m���ŁA�L�^�����摜�ƁA��v����̂ł��B���͂�����������Ă��܂����B
�������A���̕�������Ȃ��̂ł͂�������A�B���f�q���ʒu�u����ł������镝����A
�����ɉ摜�Ƀu�����L�^����Ă��܂��܂����A�p�x�u���������o��A������̃u�����摜�ɕ\��܂��B
���s���Ȃ��A�ł͂Ȃ��A���������グ��A��A���s�����炷�A���̂��߂̎�U���@�\�ł����A
���́A���ɂ��̋@�\�ɏ������Ă��܂��B�≖����ł͎B��Ȃ������ʐ^���B��邱�Ƃ������ł��B
�����ԍ��F10873275
![]() 2�_
2�_
MZ-LL����
�����Y���O���āA�����Y�̗����烌���Y�̑������Ȃ���A�����Y�̖ʂ̐������o���āA���̐������ێ������܂܂Ń����Y��Ⴆ�Ή��ɉ��낵�Ă݂Ă��������B
�����Y�̒��̑��͉��ɓ����܂��B
����႟������O�ł��B�����Y�œ����鑜�́A�V�n�����E�����]�������E�ł��B
�ƌ������͑f�q�𑜂ɑ��āA���̈ʒu�ֈړ������鎞�ɂ́B�����Y�����ɓ����A�f�q�����ɓ����Ȃ��ƃ_���A�ƌ������ɂȂ����Ⴂ�܂��B
��������C�u�r���[�Ō���ƁA�����������Ɍ�����̂ŁA�v�킸�u��v�ƌ��������Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���f�q���ԍ��W��ɗ��܂�A�Ƃ������Ƃ́A�C���[�W�T�[�N�����ł���A
�����ꂾ���ňʒu�u����������͂��ł��B
�ƌ������Ŕ����Ǝv���܂��B�i�����܂��j
�f�q�́A�ϋɓI�ɁA�J���������������ɑ���ǂ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�X�b�]�R����������͂����`�������̂��Ǝv���܂��B
���āA
��K-7���[�U�[����ɂ������������̂ł����A�{���ɓ����C�u�r���[���ɁA
����U����ON�ŁA�ʒu�u���̕���m�F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��傤���H
�����܂���I
�ŁA��Ԃ��Ƃ��ẮA���̔��u���i���̕\�����`�g�ςȋC������j���E���Ă��܂��A��Ԃ�͉����o����A�ƌ����R���Z�v�g�Ńy���^�b�N�X�̊J���͍l���Ă���̂��Ǝv���Ă��܂��B
�����ăV���b�^�[���A�ƌ����s�ׂ͕��ʂ͂ق�̈�u�Ȃ̂ŁB
���u���̏ꍇ�A�܂�Ńt���t���Ǝ�Ԃ�����Ă�����Ă���s�v�c�Ȍ����������郉�C�u�r���[�ł����A���������u�����N����ƁA�i�Ⴆ�Α傫�ȃu���j�A�C���[�W�T�[�N�����Ă��܂��l�ȁA��L�f�q�̓������������˂Ȃ�Ȃ��Ȃ��āA����̓P�����Ɍq����̂őf�q�̓������i������j��߂Ă��܂��i�J�������j���̌��ʁA��U�x��ă��C�u�r���[�̑��������i�ʐ^�ł͎�Ԃ�Ƃ��ĕ\������Ă��܂��j�ƌ������ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�Ԉ���Ă܂����ˁH
�����ԍ��F10873455
![]() 4�_
4�_
���B
�������������Ă܂��ˁB
�f�q�̓��������͔��ł�����^^;
�����ԍ��F10873473
![]() 6�_
6�_
���ۂ������A���������݂��肪�Ƃ��������܂��B
���̍����̒��܂łɏ������݂������������X�ɂ��A�܂��͂��l�т���B
�����A�d���ő�R�̔��p��i�����Ă��āA�����������́A�ǂ����f�����̐l�l�̕��͂��ʐ^���A
�Ȃ����A�������茩���Ȃ��̂ł��B�Ȃ�Ƃ��������Ɏ��o��h�b�Ɠ����Ă����������A
�����������悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�����̎v�����Ƃ́A��R�N���Ă��邯�ǁA
�l�l�̍l���Ă��邱�Ƃ�ǂ茩���肪�قƂ�ǂł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�܂��A����A�������q�������Ă������������v���܂��B�\����܂���B
�����ł������������ł��A�Ə����Ă����Ȃ���A�����Ɠǂ߂Ȃ��Ă����܂���B
���́A�����Ȑl�ɏ�������ł����������A�f�q�̓����Ɋւ��ẮA�l�����̈Ⴂ�́A
�����Y�����X�A�C���[�W�T�[�N���ɑ��ď����]�T���������͈͂̌���f�q���ɑ����Ă���A
�Ƃ������Ƃ��l����ƁA���������o�Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ����܂����B
��������Y�ɂ���āA���̗]�T�̕��͈Ⴂ�܂����A�قƂ�ǖ������̂�����܂����B
�y���^�̂r�q�́A���̃C���[�W�T�[�N���E�v���X�i�Ƃ��̎��́j�͈̔͂ŁA�f�q�������āi���܂�āj�A
�ʒu�u�����N���Ă��鎞�́A�����Y�̌����̂ǐ^�ɂ́A�f�q�̒����͖�����ԂŁA
������Ă���̂��Ǝv���܂��B�Ԃ�̓r���ňꎞ�I�ɂǐ^�ɖ߂邱�Ƃ����邩������܂���B
�i�ǂ݂̂��A�ړ��͒����Ă��~���P�ʂ̘b�ł��傤�B�����̒����ɖ߂�����߂�Ȃ�������A���Ă̂���u����������܂��j
���̂��߁A�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̌��������������Ă�����b���A���ڂ낰�Ȃ���A
�v���o���ƁA�B���f�q�̍L���ŁA�C���[�W�T�[�N���̒[�ɋ߂��A���ӂł���A���E�̗��[���A
�����Y�̎�ނ��ʑ̂܂ł̋����A�u�����ɂ���ẮA�����ڂ₯���肷�鎞�����邩������Ȃ��A
�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����������Ă����C�����܂��B
����́A�������A���[�����O�Ԃ�ƁA�ʒu�u�������킳���āA�����ĉ����̍L���͈͂�
���i�Ȃǂ��B��ۂ́A���E�̒[�̂ڂ₯���̘b���A�J�����_�[�̂悤�Ȍi�F�̉摜�����ɁA
���J�ɐg�U���U��������āA�������Ă����������̂ł����A�n�b�L���Ǝv���o���Ȃ��̂ł��B�����܂���B
�܂��������݂������܂��B�ȉ��B
�����ԍ��F10873873
![]() 2�_
2�_
���܂��A����A�������q�������Ă������������v���܂��B�\����܂���B
�������ł������������ł��A�Ə����Ă����Ȃ���A�����Ɠǂ߂Ȃ��Ă����܂���B
�����������͖����ɏ����Ȃ������K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���ʂȌ�����d�˂鎖�ɂȂ邾���ł��B
�����ԍ��F10873909
![]() 7�_
7�_
��̃��X�̑����ł��B
���ƁA���C�u�r���[�Ɋւ��Ăł����A�m���ɁA�V���b�^�[��鎞�͈�u��������܂��A
����ł��ƁA�����Ǝ�����Ă��āA���̓��삪�n�b�L���ƈʒu�u����}�����Ă���Ɗ����鎞������܂��B
�����āA�قƂ�ǃu���Ă��Ȃ��f�����L�^����܂��B
���Ђł́A����B�e���ɎB���f�q�V�t�g���̎�U���́A����ł���@����������Ȃ�
�i�����������炠�邩������܂��A�m���s���ł����܂���j�̂́A���̃y���^�̂r�q�Ȃ�ł͂́A
�B���f�q���A�I�����ɁA�ʒu�Ԃ��ł����������ɕ��s�ړ����Ă��邱�Ƃ��A�v���Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ɗ����܂����B
�����A���̏ꍇ�ł��ƁA�u�V���b�^�[�������u�ԂɁA���W���Œ肳��v�Ƃ͍s���Ȃ��ł�����A
����̏ꍇ�́A�ŏ��̘^��X�^�[�g���ɑf�q����ԍ��W���o���A�قڐÎ~�Ŕ��u����
�ʒu�u���͂܂�����܂����A�J�������ړ������ۂ́A���̌��E���āA�܂��~�܂�ƁA
���u����ł������A���̌J��Ԃ������x���s���Ă���悤�ȓ��삾�ƁA�����܂����B
���������x���A�Â��P�œ_�œ�����B��܂������A
�B�e�X�^�[�g�@���@�Î~�ɋ߂���ԂȂ̂Ŕ��u���������Ă���B�ʒu�u���������Ă���悤���B
���@�傫�����E�Ɉړ����Ă݂�B�����ɕ���E���邵�A�傫�ȓ������Z���T�[�����m���邹�����A���ʂɈړ��ł���B
�i���������⑬���ɂ���ẮA������R���j���N��Ԃɋ߂������ɂ��Ȃ�j
���@�܂��Î~�ɋ߂���Ԃ�ۂB��͂���u���������Ă���B������ʒu�u���̂悤���B
���@�܂����E�A���x�͎����𒆐S�ɉ�]�����ő傫���������ړ��B�����ĐÎ~�B�܂����u���������Ă���B
�������A�����ړ��ł��A�������O�i�����肷��ۂ��A���u���͕����Ă���悤�ȋC�����܂��B
�����āA�������Y�[�������肷�鎞���i����͂��܂������Ă���DAL18-55mm�Ŏ����܂����j�A
���u���������Ă���C�����܂��B
����B�e�́A�{���ɑf�l�ł�����A��������ł��A������͂قڐÎ~���āA��ʑ̂�
������蓮���Ă���Ă���ق����A�܂����₷���ł��B
�Ƃł́A���ʂɐÑ̂̓���B�e�ŁA���u���Ȉʒu�u���̕�̃e�X�g�����܂������A
����͓���͂���܂���ł����B��{�͕��ʂɊp�x�u�����Ȃ��悤�ɍ\���Ă��܂��B
���������������Ƃ��A�����ł��悭�����Ă��Ȃ��A�{���ɓ��揉�S�҂̏�Ԃł�����A
�ł���A�F����ɂ́A�����Ŏ����Ă������������ł��B
����������̂́A�莝���ł��A�ɒ[�Ȉʒu�u����p�x�u�����N�����Ȃ��l�Ȃ�A
�����Y��ȓ��悪�B���A�Ɖ��߂Ċ����܂����B�r�q���āA�������ł��ˁB
�����ԍ��F10873999
![]() 1�_
1�_
���A������x�A�����̎g�p���Ŏv���o���Ă݂܂������A
���E�ւ̂������Ƃ����ړ������A������������A�㉺�̔��u���͕����Ă����C�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��B
�����A�܂��܂��J���������ē�����B�e���Ă����Ԃł́A��̌��ʂ́A���m���ŁA
�����A���u�����悭�����āA���ꂵ���h�ꂪ�Ȃ��Ă�����ȁ[�B�����[�ȁ[�B���Ċ����ł��B
����̗�Ɋւ��Ă͏����b�肪����Ă��܂����A����ʂ̎g�p����������X���b�h�Ƃ��ẮA
�d�g�݂͂悭����Ȃ��Ă��A���ʂ̊��G�́A�������鎞�͋��������Ǝv���܂��B
�܂�������A����B�e���̕�Ɋւ��Ă��A������@�����A�m���߂Ă��悤�Ǝv���܂��B
������A�����̓��C�u�r���[�⓮�撆�̈ʒu�u���̕�ɑ��Ă��A�����������̂ł����B
����ȊO�̌�b�������[�����āA�L�������������o����Ă��܂����悤�ł��B
���ƁA���A��i���������Đ����������悤�ȏ�Ԃŏ����Ă���̂́A���������Ɍ��������ƂłȂ��A
�T�ɉ������́A���x�̈Ⴂ�͂���A�d���̌�́A����Ȋ����ł��B���������ꍇ���A
�摜����q������̂��A����ɂ����Ă��������Ă��܂��B�\����܂���B
�����ԍ��F10874152
![]() 2�_
2�_
�X���傳��
���������Z�p�n�̃X���𗧂��グ��Ȃ玖�O�ɐ}�ʂƂ��N�����\���Đ������Ȃ��ƊF����[�����Ȃ���
�������ł���u����̎d�g�݂ɂ��ĕ������ĂȂ���Ȃ��ł����H
�Z�p�̕��Ƃ��b�����Ƃ������Ƃł��������̓s���̗ǂ����߂����Ă��܂��H
���ƃJ�����������Ă���Ȃ烌���Y���O������ԂŎB�e�����
�B�e���̃Z���T�[�̓�����ڎ��Ŋm�F�ł��邩�����Ă݂�
����Ńr�f�I�ɂƂ��ē��e���Ă�
�����ԍ��F10874288
![]() 16�_
16�_
�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̕���
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/slr/k-7/feature_5.html
>�����ȍ\�}�Ɛ����o���̌������B
>�\�}�������@�\�Ǝ���������@�\�B
����̐��������Ă����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł����H
�ʒu�u���i�V�t�g�u���j������̂Ȃ�c�����������ɂf�Z���T�[���K�v�ł��B
��������̉�]�u���i���[�����O�j������̂Ȃ���������̃W���C���Z���T�[���K�v�ł��B
�y���^�b�N�X�̃y�[�W�ɂ���u�\�}�������@�\�Ǝ���������@�\�v�́A���̂ǂ�����K�v�ł͂���܂���B
�l�I�ɂ́A��]�u������t���Ă���̂Ȃ瓮��B�e�Ɍ��ʂ�����Ǝv���̂ŁA���̋@��ɋ������o�Ă��܂��܂��B���ꂭ�炢�d�v�ȏ��ł��B
�ł��A������������[�J�[�� HP �ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ���ł���ˁB
���ʼnB���K�v������̂��B�����Ƒ�X�I�ɐ�`��������̂ɁB
�����ԍ��F10874413
![]() 4�_
4�_
K-7�ɓ��ڂ���Ă���C�J�����S�̂̓�������o����Z���T�[�́C
1.�s�b�`���O�ƃ��[�C���O�����̃W���C���Z���T
2.�����x�Z���T�����p�����C�d�q������
�݂̂��Ǝv���܂��B
���ʓI�ɁC�u�V�t�g�Ԃ�v�ɂ͑Ή��ł��܂���̂ŁCMZ-LL���u�V�t�g�Ԃ�Ɍ��ʗL��v�Ɗ��o�I�Ɋ������̂́C��Ԃ��̎d�g�݂ɂ����̂ł͂Ȃ��C���̗v�����Ǝv���܂��i���̂��Ƃ�ے肷�����͂���܂���j�B
2.�̃Z���T�ŁC�Z�p�I�Ɂu��]�Ԃ��v�ɑΉ��ł���̂����ɂ͂킩��܂��CK-7�Ɂu��]�Ԃ��v�͓����Ă��Ȃ��C�Ƃ����̂����\�����̐����ł����̂ŁC���݂����̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10874537
![]() 4�_
4�_
�X����l�A�����ł��ꂱ��\���グ����AK-7�Ŏ��ۂɁA�Z���T�[�̓��������m�F���������̂��őP���Ǝv���܂��B
�����Y���O���ă}�E���g����������悤�ɂ��A�\�}�������ō\�}����ɓ������Ă��������B�\�}����ɓ������ƁA�Z���T�[�͉��ɓ����܂��B
�Z���T�[�����������ƁA�����鑜�̕����͋t�ł��B
���ɁA�ǂɊ|���ꂽ�G����A���̊ۍ\�}�ŎB�e����ƍl���܂��B
�J���������ɓ����ƁA�\�}���̊G��͒�������ɃY���܂���ˁB���ꂪ�I�����ɔ�������ƁA��Ƀu�����ʐ^�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���̏�ɃY���Ă��܂����G����A���̓��̊ۍ\�}�ɖ߂��A�u����ł��������A�ƌ����܂���ˁB
�\�}�������Ō����Ȃ�A�\�}����ɓ������킯�ł�����c�܂�A�Z���T�[�͉��ɓ����܂��B
�̂ɁA���ɃJ�����������A�Z���T�[�����ɓ����Ȃ��ƕ�ł��܂���B
�Ȃ̂ŁA�X����l�̋�A
���f�q���I�����ɃV���b�^�[���u�ԂƓ�����ԁi���ʁj���W��ɗ��܂�
�́A���������Ƃ��Ă͋t�������ƍl���܂��B
���l�ɁA�����Y���O����LV���N�����A��Ԃ����̃Z���T�[�̓���������x�����������B
�����ԍ��F10874539
![]() 5�_
5�_
�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̕����������Ԃ������Đ����Ȃ����������ł����A��͂������������Ƃɂ́A�������Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤�B
�����ԍ��F10875126
![]() 19�_
19�_
�Ⴆ�A
��Ԃ��̌��ʂ������܂���?
�ĕ����ꂽ��قƂ�ǑS����Yes�Č������B
�ʒu�u����̌��ʂ������܂���?
�ĕ����ꂽ��N��Yes�Č����ւ�̂�ˁB
�݂�Ȋp�x�u�������Ă�ƔF�����Ă邩��ȁB
�������Ȃ��������������āA
���͂�w�E����ɂ��I���i��A
�w�E���ꂽ�炨�O��ǂ��܂ł��A�z��ȂĈ������邵�A
���̒��ɂ͂܂��܂�����m�邱�Ƃ��ł���悤��
(�ȉ��폜�Ώۂɂ���)
�����ԍ��F10875251
![]() 18�_
18�_
�������A�����܂ł悭���܂��AK20D�Ȃǂ̐}�������N���Ă���̂ɁA
�r�q�̓���̎d�g�݂��A�����ł��Ȃ��܂܁A�Ԉ�������ƁA���Ⴂ�������Ƃ��A
������l�B�����낼��Ɠo�ꂷ����̂ł��ˁB���낵���ł��B
��ӂ̎��̓���ł̂r�q�̎g�p���́A�����āA���̃X���b�h�̎�|�ɖ߂��āA
�ǂ����������A�ǂ��v�������A�Ƃ������Ƃ��������Ă݂܂������A�������������ƂŁA
�܂��Ԃ��āA�˂����܂��ɋ����Ȃ��l�B���A�v���Ⴂ�������n�߂�Ƃ́B�����͌������Ǝv�����̂ɁB
�F���A�����Ŋ��Ⴂ����Ă��鏑���������Ă��邱�Ƃ́A���ɂȂ��Ă��錻�ۂ���́A
���ׂĂ��Ԉ���Ă���킯�ł͂Ȃ���ł��B���ʂ�180°�Ђ�����A���Ă�Ȃ�āA������O�̂��Ƃł����B
�ł��A�r�q�̓���ɒu���������ۂɁA�ǂ��������Ɨ������Ă��Ȃ��B�ƌ������Ԉ���Ă���B
�����炵�Ă݂�A���̃X���b�h�𗧂��グ��O����A�قڐ��m�ɑ̊��ŗ������Ă�������A
���ɒP���Ȃ��Ƃł�����A�킴�킴�������������邽�߂ɁA�}�ȂǏ����K�v���Ȃ��̂ł��B
���̃X���b�h�́A�l�ɂr�q�̕����������邽�߂ɗ��Ă��킯�ł͂���܂���B
�݂Ȃ���A�����̕ω��ɂƂ��ꂷ���Ȃ̂ł��B
�����̊p�x���ς�邱�ƂŁA���̌��������������Ĉړ�����̂��A�R�j�~�m�̕������Ǝv���܂��B
�����āA���̌����̕ω�������Ӗ��u��������v�̂��A���̃y���^�b�N�X�̂r�q�̕����A
�Ƌɒ[�Ȍ�����������Ȃ�A�����l�����ق����A���̐l�B�ɂ͗������₷����������܂���B
�f�q���A�{�f�B�������Ă����̈ʒu�ɂ��邱�Ƃɂ���āA�����Y�̃C���[�W�T�[�N���̒[�̂ق���
�ړ����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����A����͂ł��܂��B
����́AK20D�̐}������A�悭���邱�Ƃ��Ǝv���̂ł����B
�{���ɁA�����炷��A�Ȃ�����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��̂��A�������������ł��Ȃ���ł��B
�����̎B�e���̑̊�������A�y���^�b�N�X�̂r�q�̉���̋L��������A�悭���܂��A
����ȂɌ���ł���l�������]���]���ƗN���ďo�Ă���̂��ƁB
���A�Ԉ���������ɋ����āA�R�j�~�m�̕����̎d�g�݂Ƃ̈Ⴂ�������܂��B�ȉ��B
�����ԍ��F10875302
![]() 2�_
2�_
�Ԉ������Ƃ��ċ�̓I�ɋ�����Akuma_san_A1���R�j�~�m�̕����Ɗ��Ⴂ���Ă��邱�Ƃ��A
�ۉ���ɂȂ��Ă��܂����߁A������Ɖ������ȁA�Ǝv�� �����Ă��܂������A�����܂�
����̏������݂��L�����Ă��锭�[�ɂȂ����l�Ȃ̂ŁA�����A����������˂Ȃ�Ȃ���������܂���B
�ȉ��A����̗�Ƃ��āA�������݂��Љ�܂��B
2010/02/01 11:10�@[10870833]�@�@kuma_san_A1����̃��X
�@���d���Ȃ��̂ŁA�͂����菑���Ă����܂��B
�@��http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/slr/k20d/feature_02.html
�@���́uSR�̎d�g�݂Ɛi��(�C���[�W�})�v�ł����A
�@���u��Ԃ��O�v�̐}�Ɓu��Ԃ����v�̐}������ւ���Ă��܂��B
�@���T�|�[�g��ʂ��Ē�����i�����Ă����Ă��������B
����������͂������Ƃ�����X�Ȃ�A��̏������݂���A����܂ł��̐l�������Ă������Ƃ́A
���̂قƂ�ǂ��A�R�j�~�m�̕������A�y���^�b�N�X�̂r�q�ɂ��A�̊��̖����܂܁A��������Ă͂߂āA
�Ƃ�ł����_��W�J���Ă������Ƃ��A�ȒP�ɉ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
K20D�̂r�q�̓���̎d���̐}�̏��Ԃ́A�Ԉ���ĂȂǂ��܂���B���Ȃ��Ƃ����́A
�����v���Ă��܂��B����Ȃ̂����ƌ���A��u�ʼn���܂��B
�O�̏������݂ŁA�����킴�Ƌɒ[�ȏ�����������
�@�����̌����̕ω�������Ӗ��u��������v�̂��A���̃y���^�b�N�X�̂r�q�̕����A
�Ƃ������t�ɓ��Ă͂߂Ă݂Ă��������B���Ƃ������A��������܂łɂ����ŏ����Ă����悤�ȁA
�@���f�q���I�����ɃV���b�^�[���u�ԂƓ�����ԁi���ʁj���W��ɗ��܂�A�Ƃ������Ƃ́A
�Ȃǂ��O��Ƃ��Ă��������i����̓y���^�b�N�X�̌���ɉ��x���A�g�U���U���������Đ����������������Ƃł��j
�����āA�R�j�~�m���g�������ɏo���Ă���A�w��-7 DIGITAL�̎�Ԃ��Z�p�x�Ƃ���
���̃X���b�h�̃g�b�v�̎��Ń����N�����L�����A�܂�����Ȃ��Ȃ��r���Ă݂Ă��������B
�{���ɂ܂�����܂��H�@���́A����Ȃ��Ə����Ȃ��Ă��A������Ǝ����Ă����̊��ŁA
�قړ��삻�̂��̂́A�������Ă������A�@�B�I�ȍ\���́A�悭����Ȃ��Ă��A����ł�
�Ȃ�̎x����Ȃ��̂ł����B��͂蒆�r���[�ɒm�������邱�Ƃ��A�������F��������邱�Ƃ�
�j�Q���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@���������A���x���l�������Ă݂Ă��������B���܂��B
�܂������܂��B
�����ԍ��F10875342
![]() 2�_
2�_
�X���傳��A���������Ȃ��Ă�����
������Z���T�[�̓������r�f�I�ɂƂ��ē��e���Ă�
��������ǂ̈ӌ�������������ڗđR
�����������Ɏg�p����v�����݂����Ō����Ɩ��f�Ȃ�
�������Ԉ�������������烁�[�J�[�ɂƂ��Ă��}�C�i�X�ł����Ȃ�
�f�����s���葽���̐l��������
�������Ă�l�Ȃ爢�ۂ��Ȉʂɂ����v��Ȃ�����
���S�҂����ĐM���Ă��܂�������z����
�����ԍ��F10875368
![]() 15�_
15�_
������������N��������A�{���͐[��ɂȂ�����ɖ����Ȃ�͂��������̂ɁA
��i�W�ł܂���ʂɎ��o������������ŁA���Ȃ�x�����Ԃ܂ŐQ�t���܂���ł����B
�b�������o�́A����Ӗ��A���n�̌��ŁA�t���b�V���o�b�N�A�Ƃ������A���n���̂悤�ɁA
���̓��Ɍ����芴�����肵����A�����Ԃ��]���ŁA���邮�邮��������Ԃ������܂��B
�{���ɁA���������Ă���悤�ȏ�Ԃɂ�������܂��B
�Ȃ��Ȃ�����Ȃ���������A���傤���Ȃ��̂ŁA�܂�K-7�̓���B�e���̂r�q�@�\�������܂����B�Q���ō�������ԂŁB
��͂�A�ʒu�u�������������܂܂����u�����A���Ɍ��ʓI�������ɕ���Ă��܂��B
����B�e���́A���[�����O�i��]�j�Ɋւ��ẮA���݂̎��_�ł́A���͕���Ă���̂��ǂ�����
�m�F���Ă��܂���B�Î~��ƈ���āA�܂����[�����O�ȌX���̊p�x�͈̔͂́A�R�c��͂߂Ă��Ȃ�����ł��B
�킴�Ɣ����Ȋp�x�i�����Y�̐���㉺�⍶�E�A�������͎߂Ȃǂɏ��������~��j�����x���t����
���ʂ������܂����B��͂�p�x�u�������𑽂��܂ރu���́A�قƂ�Ǖ�ł��Ă��Ȃ����Ƃ��A����܂����B
�����āA���惂�[�h�̓������ЂƂ������܂����i���l�����������Ɓj�B
�傫�߂̊p�x�u�����N�����ƁA�������́A�i�u���ł͂Ȃ��Ӑ}�I�Ɂj�p�x���傫���ς��ƁA
���삪�����e���|�����̂��A�w�ʉt���ŁA����₷���łĂ��܂��B�����Ŏv���܂����B
Op555����́A����łȂ����C�u�r���[�̂ق��݂����ł����A[10869714]�Ŏg�p���̂悤��
�������݂����Ă��܂����A���삪�x��邱�Ƃ��悭������Ȃ�A�p�x�u�����悭�N�����Ă���
�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A�����Ƃ����z�[���f�B���O�̋Z�p��g�ɂ���ƁA
�ʒu�u���̕���A�r�q�����ʓI�ɂ��Ă���Ă��邱�Ƃ��A�悭����Ǝv���܂��B
���Ԃ͂�����Ǝv���܂����A���ꂪ����悤�ɂȂ�̂́A�����Ɛ�̂��Ƃ�������܂��B
�S���̌ۓ��Ȃǂ��痈��A���u���̕���܂߂āA�y���^�b�N�X�̂r�q�́A�J������������
�\���邱�Ƃ��ł��āA�傫�Ȋp�x�u�����N�����ɂ����l�ɂƂ��āA�����ʓI�ȕ�ƂȂ�悤�ɁA
�l���Đv���Ă���A����������b���f���Ă��܂����B
�ł���A�F������A�����ƃz�[���f�B���O���āA�����������Ȉʒu�u�������𑽂��܂�
�u�����N�����Ă���̂��A�p�x�u�����傫���Ȃ��Ă���̂��A���炢�A�B�e���Ɋ�������悤�ɂ��܂��傤�B
�����āA���̂悤�ɁA�C���[�W�T�[�N���͈̔͂�A�B���f�q�̈ړ��̎d�����A���ŃC���[�W���Ȃ���A
�B�e����ƁA��ʑ̂�œ_�����A��ʑ̂܂ł̋����Ȃǂɂ���ẮA��U�ꂵ���炢�B�e���ł��܂��B
�Ƃ��Ɏ莝���ł̓���B�e�́A���ԂȂǂŃJ�������Œ�ł��Ȃ����Ƃ�����A���́A
�f�q�́u������ԁi���ʁj���W��ɗ��܂�v�Ƃ����C���[�W��g�̂Ɋo�������āA
�B�e���邱�ƂŁA���u����h��̏��Ȃ�������B��₷���ł��B�{���Ƀy���^�̂r�q�̓X�S�C�A�Ɖ��߂Ċ����܂����B
����ł̂r�q�̎g�p���Ɋւ��ẮA������ʃX���b�h�ł����ĂāA���������Ǝv���܂��B
����́A�Q�l�ɂ��Ă������������ȃR�c���ȁA�Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10875465
![]() 1�_
1�_
�����������A�����Ɨ������邱�ƂŁA���ʂƂ��āA��萸�x�̍����B�e���ł���Ǝv���܂��̂ŁA
�{���́A�Ԉ�����������݂ɉe������Ȃ����炢�A���̃X���b�h��ǂސl�B�ɂ͔��f�͂�g�ɕt���ė~�����Ǝv���̂ł����B
�l�l���ǂ������X�^���X�ŁA�B�e���邩�́A�܂����������Ď��R�ł�����A�����������Ƃł͂���܂���B
���̃X���ŁA���ɑ��āA�͂��߂�����A�ԈႦ�Ă���Ƃ����Ⴂ���Ƃ��A���������������݂�
���Ă����l�B�́A���߂āA���������A�̌���o����ς�A���������������ƕ����āA��������ŗ~���������ł��B
���ɗ���͂��Ⴂ���Ƃ��c�O�ł������A������ƍl����Ή��邱�Ƃ��A�Ȃ�����Ȃ��낤�H�A
�����āA�Ȃ�ł���������̏������݂̎d���̂����ɂ���̂��낤�H�@�Ɗ����܂����B
�����́A����Ȃ��l�Ɍ����āA�����y���^�b�N�X�̂r�q�̎d�g�݂�\���ɂ��āA
�����Ă����邽�߁A����ȃX���b�h�ł͂���܂���B�����Ď��͌��X����Ȃ��Ƃ�
������C���A��������Ƃ��v���Ă��Ȃ��̂ł��B
���X�A���ЂƂ̈Ⴂ�������Ă�����A�g������ł�����̌l�̎g�p�������������邽�߂ɗ��Ă��X���b�h�ł��B
����́A�g�b�v�̕��͂̌㔼������A[10858947]�̎��̃��X�Ȃǂ�ǂ�ł���������A
�����Ă��炦��Ǝv���̂ł����A�����������Ƃ��n�߂�����낤�Ƃ���C���Ȃ��A
��{�I�ɁA�C�ɐH��Ȃ����c�̗g�������Ƃ��Ă�낤�A�݂����Ȑl�B���A���������������Ă���
���̌f���ł́A����̂�������܂���ˁB
�������A�Ђǂ��S�����āA���̏������݂ɑ��āA�������t�ł��������c�b�R�~�����Ă���l�����l�����܂����A
�����A�����������݂����āA���i�R���̊Ǘ����ɍ폜���ꂽ�Ƃ��Ă��A�����ꂽ����
���̃A�J�E���g�����A�����Ɗo���Ă��܂����A�{���ɂ��傤���Ȃ��Ȃ��A�ƕ��ꂽ��ۂ�
�����Ǝ��������Ă��܂���������܂���B
���Ȃ݂ɁA���̂ق�����́A�폜�˗����o�������Ƃ͈�Ȃ��ł����A���̕��@���m��܂���B
���́A�ނ���A�؋��Ƃ��āA���̍����������݂��c���Ă���Ă���ق����A�s�����ǂ��̂ł����A
�^�c���̔��f�ɂ́A�����炪�ق���������A�c�����Ƃ���肢����̂́A����悤�Ȃ̂ŁA���߂܂��B
�ł���A���ɑ��āA���������c�b�R�~������O�ɁA�܂������ŁA�������������
�V�r�A�ȎB�e���o�����āA�Z�p�⊴�o�┻�f�͂�g�ɂ��܂��傤�B
�����ԍ��F10875513
![]() 1�_
1�_
���掞�́A��U��̎d���������ۂɁA�����Ċp�x��ʒu�u�����A���̐����������܂ނ悤�ɁA
�Ԃꂳ���Ă݂�A�Ƃ����e�N�j�b�N�A�Ƃ������R�c�Ɋւ��Ă̕⑫�ł��B
����́A����Ӗ��A�������u�t�̎d���Ő��k����B�̍�i���B�邽�߂Ɏg���\��́A
EOS 20D��EF-S18-55mmIS�̂������Ȃ̂ł����AK-7��K20D�̉���EOS20D��u���āA
�Е��̋@��̃u�������ʂ̊��o���c���Ă��邤���ɁA�����Е��������܂��B
EOS 20D��EF-S18-55mmIS�̑g�ݍ��킹�ł́A������x�܂ł̊p�x�̃u�����A�m���ɕ����A
���t�@�C���_�̒��ŁA�{���Ɏ~�܂��Ă���悤�Ɍ����܂��B
�Z�������Ɏg����p�̃J�����A�I�Ȉ��������Ă������߁A����܂łقƂ�ǁA����
�u�~�܂��Ă���悤�Ɍ�����v�A�̏�Ԃ��������Ă��Ȃ������̂ł��B
�p�r��D�݂ɂ���ẮA�����Y����IS���A�֗����Ɗ�����l�������̂��A�[���ł��܂��B
���́u�~�܂��Č�����v�A���E�̊p�x�u�����A���������̊��Ŋo���āA������K-7�ȂǂŎ����ƁA
�B�e�����摜�́A�p�x�u�������𑽂��܂ޏꍇ�A�Ƃ��ɂS�Ocm���炢�̋ߋ����ł��ƁA
�قƂ�Ǖ����܂���B�������L���m����IS�̂ق����A�p�x�u���̕���ʂ��������Ƃ�
����܂ł������Ƃ��ĉ����Ă��܂�����A�p�x�̊J�����AK-7�Ȃǂł́A���Ȃ߂ɂ��Ď�����������Ă��܂��B
�ł��A��͂�A�p�x�u���́A�ʒu�u���ɔ�ׂ�ƁA�n�b�L���ƕ����Ă���悤�ȋC�����܂���B
���Ƃ����āA�܂����������Ă��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A�����Y�̏œ_�������ʑ̂܂ł̋����ɂ���ẮA
���̋Z�p�ł́A������x �p�x�u���i�̔��u���j���N���Ă���͂��Ȃ̂ɁA�L���b�Ƃ����ʐ^���B��Ă��܂��B
������A�y���^�b�N�X�̌��������������Ă������Ƃł����A�p�x�u���Ɋւ��ẮA
���Ђ���̃����Y���̕�قǁA���ʂ͖����������邵�A���܂肻����̃u���ɂ͒��ڂ��Ă��Ȃ����A
���������{�̃z�[���f�B���O���ł��Ă���悤�ȎB�e�҂̕��X�ɂ́A�����́i�y���^�b�N�X�́j
�悤�ȁA��Ɉʒu�u��������ق����A���ʂ�����Ǝv���A�����Ăǂ�Ȑl�Ԃł��o�����ȁA
�S���̌ۓ����炭��悤�ȁA���u���ɑ��Ă��A�������ĕ�ł���悤�ɂ��Ă���B
�������A�g�p�҂ɂ���ẮA����������o�Ă��܂����Ƃ�����B
����ȁA�����̂��Ƃ�����������Ă��܂����B������肭�\���o���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA
�C�ɂȂ�l�́A�����Œ��ׂĂ݂����������B
��������L�̒ʂ�A�d���Ȃ̂ŁA�܂��A���Ă�����A���������������悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��邩������܂���B
�����͐��k���������ŁA�Ƃ��ɖZ�������e�Ȃ̂ŁA���������܂����B
�ł���A�Ԉ�����������݂��A�Ȃ�̋^�����Ȃ�������̂́A�������Ăق����ł��B
�X���b�h�̎�|���A������x�A���Ă��������B
�����ԍ��F10875708
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́B
��u����̎d�g�݂��ǂ��Ȃ��Ă���̂��͎��ɂ͕�����܂��A�\�j�[��900�̃��[�r�[�ł́A�Z���T�[�ʒu�͓�����Ԃɗ��܂��Ă���悤�ɏЉ��Ă��܂��B
���͐^�U�͕�����܂���B�Q�l�܂łɁB
�����[�r�[�̃A�h���X�i��900�̓������r�f�I�ł��Љ���N���b�N���Ă��������j
http://www.sony.jp/dslr/products/DSLR-A900/index.html
�����ԍ��F10875728
![]() 2�_
2�_
MZ-LL����A���Ȃ��������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��������Ǝv���܂��B
���ɂ�������̎B�e�o���ɗ��t�����āh�����������h�͎̂����ł��傤�B
�ł��A�h��ԏ�̈ʒu�Z���T�h�Ƃ������̂͂��̐��ɑ��݂��܂���B
�����x�Z���T�ɂĐ������邱�Ƃ����ł��܂���B
�y���^�b�N�X�̃J�����ɓ��ڂ���Ă���ƃy���^�b�N�X�̋Z�p�҂������������
�h�ʒu�Z���T�h�͉����Ɖ����̈ʒu�W���Z���X���镨�̂͂��ł��B
�܂�A�J�����̃V���V��CMOS�Ƃ̈ʒu�W���Z���X����Z���T�[�ł��B
�n�ʂƂ̈ʒu�W�����m����̂ł���A�J�����O���ɗႦ�Β����g�����v��[�U�[�����v�Ȃǂ��K�v�ƂȂ��Ă��܂��܂��B�i�������A�J�����̃V�t�g�Ԃ������ɂ͂���ł͐��x���s�\���ł܂������g���Ȃ����Ǝv���܂����B�B�j
�����������ł��Ȃ����ɂ��Ă͔ے肵�����Ȃ�C������������܂����A
�h�������S�Ă�m���Ă��āA��������ΐ������h�Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������Ƃ�F������
�i����͎��ɂ��Ă��F����ɂ��Ă������邱�Ƃł����j
�l�̈ӌ��ɂ������X���邱�Ƃ���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���ɂ́h�����ɂ͕�����Ȃ��h�Ƃ������Ƃ�����ł��傤�B
�ł����ꂪ�����ł��B
������ƌ����������
1. ���s�ړ����郌�[���ɍڂ��ĐU�������ăV�t�g�Ԃ��������B
2. �Ⴆ�ΎO�r�������Ƃ��ă����Y�����E�ɐU�������Ċp�x�Ԃ��������A
�@�@�i�ǂ������ɂ��邩�A�Ⴆ�����Y�O�ʁA�Ƃ��ɂ���Ă��ς�邩���H�j
�Ȃǂ̎������K�v�ł��傤�B
�ŁA1�ɂ��Ă̓j�R�L���m������������Ă���悤�ɁA�A�T�q�J�����Ō�����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B
�i���̎����҂��V�t�g�Ԃ�Ɗp�x�Ԃ�̕�𗝉����Ă��Ȃ��ĕ����Ȃ��Ă��������Ǝv�����Ƃ̂��Ƃł����B�B�j
�ŁA�悤�₭MZ-LL����̎���ɑ���ł����A
���l�̊��o�ɂ�����ʂɑ���ӌ��ł����A
�莝���ł͔��ׂȕ��s�ړ��Ɗp�x�ړ��𐧌�ł��Ȃ��̂ŁA�h������܂���h�ƂȂ�܂��B
�����ōl����A���l�Ƃ��Ă͏�L�ɂĕ�����悤�ɁA�W���C���Z���T�Ō��m���Ă���ȏ�͊p�x�Ԃꂵ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
��݂����ɐl���U������̂ł͂Ȃ��āA
��ÂɁA�l�Ɍ���ꂽ���Ƃ����������������Ƃ��l���Ă݂Ĕ��f���Ă���������Ƃ��ꂵ���ł��B
�����ԍ��F10875737
![]() 14�_
14�_
���낯�ނ�����A�\�j�[��900�̐��i�Љ�̃����N�A���肪�Ƃ��������܂��I
��900�͐��E���̃t���T�C�Y�̎B���f�q�V�t�g����U���@�Ƃ������ƂŁA�C�ɂ͂Ȃ��Ă��܂������A
������̃��[�r�[�͏��߂Ēm��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�̂̃R�j�~�m�̕�́A��-7�̋Z�p���ւ̃����N�ŁA������x�A���̃y���^��SR���Ⴄ���Ƃ́A
�������Ă����̂ł����A���݂̃\�j�[�̃��V���[�Y�Ɋւ��ẮA�܂������m�����Ȃ��������߁A
��̂ق��ŁA�u���̃\�j�[�̃��͉���܂��v�ƑO�u�������̂ł����A�Љ�������������N�̓����q�����āA
�����ƁA���̎d�g�݂̂��Ƃ��A�m�肽���Ȃ�܂����B
���Ԃ͂�����Ǝv���܂����A���Ȃ�ɁA��900�̂��ƂׂĂ������Ǝv���܂��B
�����āA�������ϒx���A���̉Ɓi�؉Ƃł����j�̃l�b�g���ŁA���i�������悪�A
�Ƃ��Ɏ~�܂����肹���ɍĐ��ł����̂ŁA�\�j�[�̃T�C�g�͂������e���ȁA�Ɗ����܂����B
������Ɖ𑜓x�̍����A�d�����������ƁA����Ɏ~�܂�܂��̂ŁB
�����A���ۂɃN���b�N���čĐ�����܂ł́A�����ł͌���Ȃ���Ȃ����ȁ[�A�Ȃ�ĕs���ł����B
����A���肪�Ƃ��������܂����I
���݂̎��ł́A���ꂪ���������ǂ������d�g�݂œ����Ă���͉̂���܂��A
�X�����Ŏ�������A�\�j�[�̃J�����S���̕�����l�ɁA������Ε����Ă݂����Ǝv���܂��B
��900�̃��b�N�{���ǂ߂�Ό��Ă݂܂��B
�����d���ɍs�����������˂Ȃ�Ȃ��̂ŁA����Ŏ��炢�����܂��B
�����ԍ��F10875773
![]() 3�_
3�_
������x�A���̃X���b�h��`���Ă݂Ă悩�����ł��B
core star����A���C�����������������e�Ŏn�܂�䏕���ƌ�ӌ��Ǝg�p���A���肪�Ƃ��������܂��B
���͎��Ԃ��Ȃ��ď����܂��A�������̃X���b�h�𗧂Ă�������A����čl���Ă������Ƃ�����܂��̂ŁA
����������������Ă��������B�Ȃ�ɂ���A���̃X���b�h�̎�|�Ƃ��ẮA����������
���ۂ̎g�p�����痈��A���o�I�Ȋ��z�������Ă���������A����Ŏ��͊������̂ł��B
����������Ă���l���A����ς�����������A�v������Ŏ����ꂽ���ʂ��ƁA
���܂���ɗ��������ɖ����̂ŁA���� ���������Ƃ��������Ă��������Ă܂��B
����ł́A����A���߂āA�������݂�q�������Ă������������v���܂��B
�����ԍ��F10875919
![]() 1�_
1�_
�������[�r�[�̃A�h���X�i��900�̓������r�f�I�ł��Љ���N���b�N���Ă��������j
http://www.sony.jp/dslr/products/DSLR-A900/index.html
���̃��[�r�[�ł̐�������́u�C���[�W�v��`������̂ŁA�������炠��ׂ����삩�猩��u�Ԉ���Ă���v�Ƃ������Ƃł��B
�L��ł͂悭��邱�Ƃł��B
�����ԍ��F10876062
![]() 0�_
0�_
�p�x�u���̒��S�͕��ʂ͑f�q�̑O�B
����ł�낵���ł���?
�����Y������A�f�q������A�̑g�ݍ��킹��
�f�q���[�{�f�B���͏オ���Ă邩��
�f�q�͖T�ڂɂ݂�Ε����������ŁA
�����Ɠ����Ƃ���ɗ��܂�悤�ȓ����B
����ł�낵���ł���?
�����ԍ��F10876182
![]() 0�_
0�_
����܂łɂ��܂��Ƃ����܂������A����fig.4�̃C���[�W��
�����܂��������̂ŁA�ēx���e�����Ă��������܂��B
MZ-LL���ȑO��fig.4�̃C���[�W�ŕ�����Ă���K-7��SR������
������fig.1�̃C���[�W�ł͂Ȃ��ł��傤���H
���Ȃ킿�����ȃJ�����̃V�t�g����ɑ���
�C���[�W�T�[�N���̒��i�����ȋ�ԁH�j�ł�
�����Y�͕��ʂɋ߂������Y�̕ϓ��ɂ��
���ˌ��̕ω��͖����ł��A�B���f�q�i�j����Έʒu��ۂĂ�
���Ԃ�͔������Ȃ��A�Ƃ��������̂ł��B
����̋�_�ɂȂ�܂��̂ł���ȍ~�͉����\���܂���B
�����ԍ��F10876219
![]() 1�_
1�_
�ʒu�Ԃ��ł͂Ȃ��Ċp�x�Ԃ�������A�����̕����Ƃ��Ă͂����Ȃ�킯�ł���ˁB�iSONY�̃r�f�I�j
�����ԍ��F10876307
![]() 0�_
0�_
���ʒu�Ԃ��ł͂Ȃ��Ċp�x�Ԃ�������A�����̕����Ƃ��Ă͂����Ȃ�킯�ł���ˁB�iSONY�̃r�f�I�j
�����A���̓���̓J�������p�x�u�����������̕��s�ɓ������Ă��܂��B
�ŁA�Z���T�[�̓����͐���MZ-LL���C���[�W���Ă��铮�������Ă���킯�ł��B
����ȃC���[�W���悪���邩��A�A�T�J���̃e�X�^�[���S�����ʂȃe�X�g���l�����Ⴄ��ł��ˁB
�ߋ��ɂ��u��Ԃ�N�v�Ƃ����L��p�̑�|����ȑ��u��web�ɏo�Ă��肵�܂����B
�����ԍ��F10876328
![]() 2�_
2�_
MZ-LL����
����Ȃ���A�������Ă��������܂��B
MZ-LL�����̃X���ł�������肽�����Ƃ́A�����܂Łu�g�p���v�u���o�v�ł���ƌ������Ƃł���ˁB
�܂�A�@�\�I�ɐ��������ǂ����͂Ƃ������A���o�Ƃ��Ċ���������ꂪ�������ƁB
�ƌ������Ƃł���AMZ-LL����́A��Ԃ��́u�d�g�݁v�ɂ��Č��y���ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
���o�ōςޘb�ł���A���o�����Řb������Ηǂ��A�����ɕςɎd�g�݂̘b�𗍂܂��邩�炢���Ȃ��̂ł��B
MZ-LL����́u���o�v�ɍ��킹�āA�J�����̎�Ԃ��@�\������Ă���킯�ł͂���܂����B
�����܂Ŏ�Ԃ��́A���́u�����v�Ƃ������������u�d�g�݁v�ɂ���������Ă���̂ł����āAMZ-LL��������ǂ��u���o�v�Ƃ��Ċ����悤�ƁA�������d�g�݂͂�����Ƒ��݂��Ă���̂ł��B
���̕����A����������������Ԃ��̎d�g�݂�������Ă���Ă���̂ɑ��AMZ-LL���A���o�Ɋ�Â��Ă����ے肷��̂͂��������Ǝv���܂��H
MZ-LL����̊��o��MZ-LL����ɂƂ��Đ������͓̂��R�ł����A����͂����܂Ōl�̊��o�ɉ߂��܂���B
���l�̊��o��������������ł��傤���A�����łȂ�����������ł��傤�B
���̊��o���̂�ے肷�����͂���܂��A����������Ă������̊��o�Ɋ�Â��z����̎d�g�݂��������Ǝ咣����̂́A�s���߂��ł͂Ȃ����Ǝv���܂���B
�V�t�g�Ԃ�𑪒肷��ɂ́u�����x�Z���T�[�v���K�v�Ȃ̂������ł��B�������A�y���^�b�N�X�̃J�����ɂ́u�p���x�Z���T�[�v�͂����Ă��u�����x�Z���T�[�v�͂Ȃ��݂����ł���B
���o��D�悷�邱�Ǝ��̂́A�ׂɂ������Ȃ��Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
���������o�͂����܂Ŋ��o�B�J�����͐v�ǂ���ɂ��������Ȃ����̂ł��B
�u�����̊��o���������t�B���^�[�v��ʂ����ɁAK20D��SR�̉���}��������x�ǂ����Ă��������B�ނ���MZ-LL����̎咣��ے肵���}�̂悤�Ɏv���܂����c�B
�l�b�g�Ōy���������������ł��A���͂�����ł��o�Ă��܂��̂ŁA�t�B���^�[��ʂ����Ɉ�x�����ɂȂ��Ă݂Ă͂������ł����H
30���`1���Ԃ�����A��Ԃ��̌����Ǝd�g�݂������ł���Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10876383
![]() 25�_
25�_
��delphian����
�E���Z���T�[�Ɏʂ��Ă��鑜�ł���ˁB�Z���T�[�̓������́A����ō����Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10877435
![]() 1�_
1�_
delphian����A�����́B
�������Ǝv���܂��B
�J���������ɂԂꂽ�ꍇ�A�Z���T�[����艺�ɓ��������ƂłԂ��ł������킯�ł��ˁB
MZ-LL����́A�J���������ɂԂ�Ă��Z���T�[�͋�ԓI�Ȉʒu��ۂc�����Z���T�[����ɓ��������ƂłԂ��ł������ƌ����Ă���̂Łc�@�c�O�Ȃ���Ԉ���Ă���킯�ł��B
�������A�����I�ɂ͐��������̐}���A�����x�Z���T�[�������Ȃ����ߎ����͏o���Ă��Ȃ��킯�ł����B
�ƁA�l���Ă��ăt�g�v�����̂ł����A�܂���K-7�ł͓d�q������ɉ����x�Z���T�[�𗘗p���Ă��āA���̏����V�t�g�Ԃ�ɂ����p���Ă�Ƃ��������肷���ł����ˁH
���Ƃ���ƁA�d�g�݂̌���͂����Ă��AMZ-LL����̃V�t�g�Ԃ�����Ă���Ƃ������o��A�y���^�b�N�X�̐l���畷�����Ƃ����b�Ƃ͈�v���邱�ƂɂȂ�܂����c
�����Ƃ��AK-7�Ɍ������b�ɂ͂Ȃ�܂����c
�ł��A�������`����ȃy���^�b�N�X�ł��A���ꂪ�������Ă�Ȃ炳�����ɃJ�^���O�Ȃ�ɏ����悤�ȋC�����܂����˂��B�ǂ��Ȃ�ł��傤�H
�����ԍ��F10877499
![]() 3�_
3�_
�X����l
���݂܂���A���̔����͋�Ƃ���A�X����l�̗g���������l�Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂����B
���̃X���b�h�̖{���̎�|�́A��Ԃ��̎��ۂ̎g�p���⊴�z����������̂ł����B��|����傫���O��Ă��܂��A�{���ɐ\����܂���B
�ł́A�{��ɖ߂�܂��āc
�������ۂɁA��ɒ��]���`���]���ŎB�e�����ۂɁA��Ԃ��Ŋ��������z���q�ׂ����ĉ������B
���]�������Y��p���āA��r�ŎB�e����悤�ȏꍇ�́A��Ԃ��̌��ʂ͔��ɂ��肪�����Ɗ����Ă��܂��B
�������A��Ԃꂪ������̂���ԏ�����܂����ALV�Ŏ�Ԃ���ON�Ō����̂��������Ă��܂��B
���]���͌��w�t�@�C���_�[�ł́A�ӂ�t���̂ō\�}�����߂�̂����J�ł����A��r�Ŏx���Ȃ����Ԃ�ON�ALV�Ō��Ȃ���ł��ƁA�u�����y�������̂ŏ������Ă��܂��B
���̎��Ɏ��������Ă����Ԃ��́A�����炭�p�x�u���̕�̉��b�ɂ��₩���Ă���̂��Ǝv���܂��B
��r���g�p���ĉ��i���B�e����ۂ́A�ʒu�u�������p�x�u�����������₷���Ǝv���܂��B�J�����̍�������r���x���Ă���܂����A�J�����̌X�������́A�������g�Ŏ�����ŗ}���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł�����ˁB
�ł����ASR��ON�ɂ���ƁA���̃u�����啪�y������܂��̂ŁA���ɏ������Ă��܂��B
�����ԍ��F10877609
![]() 1�_
1�_
�ォ�炴���Ɠǂ̂ł���
MZ-LL����̓V�t�g�u���ɂ����ʂ�����ƍl���Ă���
���̕��̓V�t�g�u���ɂ͌��ʂ��������Ď��ł����
���̓����Ƃ��Ă̓V�t�g�u���ɑ��ẮH�ł�
�J�����̏�ɒu���ă��C�u�r���[�A��u����I���̏�Ԃ�
���̊W��@���Ƒ����������u���܂�
�V�t�g�u���ɑΉ����Ă���Ȃ瑜�͌������Ԃꂸ�Ƀ���������
�����Ǝv���܂����Ⴂ�܂����H
�莝���ŎB�e����ƃ��������Ɨh��܂����܂��܂�����͂��܂���
������SR���ƃu���u���ƃu���Ă���̂�������܂���
����ŎB���Ă݂��̂Ł�������������
���ɃJ������u��������
http://eyevio.jp/movie/336423
�莝��SR�I��
http://eyevio.jp/movie/336424
�莝��SR�I�t
http://eyevio.jp/movie/336422
�J������K-7�A�����Y��A��200mmF2.8+FAF�A�_�v�^�[�ł�
�Q�l�ɂȂ�܂������H
�����ԍ��F10877860
![]() 6�_
6�_
MZ-LL����
�@�W���C���Z���T�[�͕ʖ��p���x�Z���T�[�ƌĂ�A�P�ʎ��ԓ�����̊p�x�̕ω���
�����o����Z���T�[�ł��B���̃Z���T�̏o�͂�ϕ�����A�ω������p�x���������
���B�ł��A�V�t�g�����ʂ�m�邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@����A�����x�Z���T�[�́A2��ϕ�����ƈړ������ʂ�������܂��B�W���C���Z��
�T�[�Ɖ����x�Z���T�[�Ƃ͂܂������قȂ���̂ł��B�����x�Z���T�[�̓y���^�b�N�X
��SR�ɂ͎g���Ă��܂���B
�@�������p�ɂɂ��ڂ���MZ-LL����́A�l�Ԃ̍��i�ɂ��Ă͂悭���������Ǝv���܂��B
�l�̓����͊߂𒆐S�Ƃ�����]�^������{�ł��B�]���āA��Ԃ�ʂ̃Z���V���O��
�W���C���Z���T�[���g���̂́A���ɂ��Ȃ������Ƃł��B�V�t�g�ł͂Ȃ���]�ɒ��ڂ���
���������B�l�Ԃ̍��i�ƈقȂ�\���̎O�r�̂Ԃ�ɂ́A���R�A��Ԃ��̋@�\�͗L��
�ł͂���܂���B
�@K7�iK100D�ȍ~�̋@��j�́A��Ԃ�̃Z���V���O�p�Ƃ��āA�W���C���Z���T�[����
�iX����Y���j�g���Ă��邾���ł��B���̑��ʒu�Z���T�[���g���Ă��܂����A���̈ʒu�Z
���T�[�́A�B���f�q�̈ړ��ʂ��Z���V���O���邽�߂̂��̂ł��B���̈ʒu�Z���T�[�̂�
�A�ŁA�B���f�q��K�ɓ��������Ƃ��o����̂ł��B�J��Ԃ��܂����A�ʒu�Z���T�[��
��Ԃ�̃Z���V���O�p�Ɏg���Ă��܂���B
�@�y���^�b�N�X�z�[���y�[�W�̐�����SR�̎d�g�݂Ɛi���̐����ɂ����āA�uSR�ł́A
�W���C���Z���T�[���J�����̌X�������m�B�ʒu�Z���T�[�Ƃ̃R���r�l�[�V�����ɂ��A
�u����CMOS�Z���T�[��K�Ȉʒu�Ɉړ������A��Ԃ��ł������܂��B�v�@�Ə����Ă�
��܂��B�����ł́A���ꂼ��̃Z���T�[�̖����肪���m�ɋL�q����Ă��Ȃ��̂ŁA
MZ-LL����̌�����������̂����m��܂���B
���@�S���̌ۓ��Ȃǂ��痈��A���u���̕[10875465]
�@�ł͂Ȃ��ł��B
���@�����A�f�l�ł�����A�p��̎g������
�Ԉ���Ă��邱�Ƃ������Ǝv���܂�����A�C�ɂȂ���́A�����Œ��ׂ���₢���킹��
�肵�Ă݂Ă��������B[10873275]
�@�������������Ă��܂��ƁA�l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����͓���ł��傤�ˁB����
���M����̂ł���A�p��̒�`�Ƃ��̎g�����ɂ͋C���g���ׂ��ł��B
���@���̐����́A���͊��o�I�ȃ��m�Ɋ�Â��Ă���̂ʼn���ɂ����Ǝv���܂����A
���̂ق��͐������ł�����A������Ȃ��悤�ɁA�C�����Ă��������B[10869839]
�@���o�Ƃ��̊��Ő^���𗝉��ł���͈͂͌����Ă��܂��B�_����ςݏd�˂Ă�����
�̊��ł��Ȃ����Ƃ������Ă���̂ł��B�_��������A�Ȃ��Č��_���o���Ă���ƁA
�l����_���̕⋭���邱�Ƃ��e�Ղł��B��������Ȃ��ƌ����w�E����Ă��A�ǂ���
�Ԉ�����̂����̂��悤���Ȃ��̂ł́B
�@MZ-LL����́A�l���w�����闧��̕��ł�����A����ȍl���������āA�F�����
�R�����g��������x�ǂ�ł������������ł��B
�@���̃X���͓ǂݒ����Ă����������l���\������܂��B
�����ԍ��F10878115
![]() 16�_
16�_
���͂��̃X���������Ɠǂ݂܂��āA���g��SR�ɑ���m�������߂邱�Ƃ��ł��܂����B
���̈Ӗ��ŃX���傳��⑼�̊F����Ɋ��ӂ��Ă���܂��B
�f�W�C�`���ŏ��ɍw������ۂ̓��@�̓z�[���y�[�W�쐬�̊W��
���L�p�̎ʐ^���K�v�ŁAfisheye�����Y�̎g�p���l�������߂ł����A
���̂Ƃ���PENTAX�̃{�f�B��SR�@�\�Ƃ��ݎ��@�\�ɖ��͂������܂����B
���̂Ƃ��A�Ȃ�CANON��NIKON�������Y��SR�����Ă���̂��A
�܂����������Đ[���l���܂���ł����B
�܂�PENTAX���{�f�B��SR����������ɂ�����A�Ȃ������Y�̏œ_������
���̃p�����[�^�ɉ�����̂��ȂǁA���g�Ő}�����ė����ł��܂����B
�g�p�������ɏ����Ă���܂����A�ߋ����B�e�Ŏ�u�����Ȃ��������Ȃ�����
�����𗝉�����Δ[���ł��܂��B
�J�����i�������Y�j�͂��̎g����̃J�����ɑ��闝���ŁA
��������@�\�������ɍ��E����铹��ł���A���̕��A
�g����͗�����[�߂�قǏ��L�����J�������g�����Ȃ���햡�𖡂킦�܂��B
�܂��J�����̋@�\�ɑ��āi���ɍ����SR�j���[�J��HP�̃C���[�W�}��
�}�j���A���{�̕\�L�݂̂ł��̖{�����Ȃ��Ȃ��ǂݎ��Ȃ��ǂ��납�A
����������悤�Ȃ��̂���A�����͍��㐳���Ăق������̂��Ƃ��v���܂����B
�i�����g���C���[�W�}�݂̂Ŕ�т�����l�ł��E�E�E�B�j
�X���傳�܂̎�|�ɂ͂�����Ȃ�������������܂��A�e�����ɂ����
��Ԃ��̌��ʂ̈Ⴂ�����������ł��܂������Ƃɂ����\���܂��B
�����ԍ��F10878187
![]() 5�_
5�_
wsxwsx����A�lj��̉摜�A���肪�Ƃ��������܂����B
����́A�������ݓ��e��������Ă����݂����Ő\����܂���B
�܂����܂������e�����݂���Ă��Ȃ��̂ŁA��ɂ��l�т܂łɁB
�i�ǂ��ŕ��͂̈Ӗ�����Ă��邩����Ȃ��������߁A�܂��悭�����Ă܂���j
�y���^�b�N�X���A��{�̎�U���̎d�g�݂��A�ʒu�u���ւ̕�ł��邱�Ƃ́A
�{���ɉ��x���m�F���Ă��܂����̂ŁA�����͐M�p���Ă��������B
�܂��ŏ��ɁA�L���m���̃n�C�u���b�gIS�̃V�t�g�u����Ƃ̔�r�ł��邱�Ƃ��A
�����ƃy���^�̋Z�p�҂̌���ɓ`���Ă���܂��B��������b���n�߂܂����B
��{�̌����́Awsxwsx����ɐ}�ɂ��Ă����������悤�ȁA�f�q���I�������i���ʂ́j���W��ŗ��܂��Ă���
�Ƃ������ƂŁA���x���������Ă��܂��̂ŁA�����͊Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
�������A��������̉��p�A�����Y�̏œ_�������ʑ̂܂ł̋�����A�p�x�Ȃǂ��܂߂���̔�������
�ւ��ẮA�������Ď��̂ق�����������Ǝv���A���܂�˂����������͂��Ă��܂���B
����ł��A������x�́A�œ_�������ʑ̂܂ł̋����ɂ��u���Ⴂ�̘b��ɂ͂Ȃ�܂����B
�����āA��������́A���̏���Ȑ����ł��B������A����̋�_�ł��B���܂ɂ͏����Ă݂܂��B
��{�̓���́A�܂��A��L�̂悤�ɁA�ʒu�u�������邽�߂ɁA�B���f�q���{�f�B�������Ă��A
���ʂ̍��W��ɗ��܂��Ă���Ƃ��������Ƃ������Ƃ����ɂ��܂��i���������Ă����̂Łj�B
�����āA�p�x�u����AK20D��SR�̐}�̂悤�ɁA�{�f�B���O�̂߂�ɌX�����ꍇ�ł��A
�ǂ����āA������x�͕��������A�}�ł�����悤�ɁA�{�f�B��ł����������ɁA
�f�q���ړ����Ă���̂��A���Ȃ�̉��߂Ƃ��ẮA������܂��B
����́A�f�q�̋�Ԃɗ��܂낤�Ƃ���ړ��́A�����̔��������A�y���^�b�N�X��SR�ł́A
�Z���T�[���A���S���Y�����i���̕ӂ�̗p��͂悭�����̂Ŕ���܂��j�A
���낢��Ɖ��Z���āA�u���̎d����x�����ɍ��킹�āA���ʂ��o��悤�A�{���������ׂ��͂��̍��W�ցA
�Ӑ}�I�ɂ��炷���ŁA�p�x�u����A�œ_�������ʑ̂܂ł̋����ł̃u�����̈Ⴂ�ɁA
�Ή����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂����B
����́A�����A�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̌�����畷�����A��{�̓���i�ʒu�u���̕�j��
���āA����ɍl�����A����̋�_�ł��B�����Ă���Ȃ�A�F���₽��ɏ����Ă�A
������������A�f�q�̈ړ��������Ƃ��A�p�x�u���ƍ��킳�����ۂɋN���肦��
�v�f���A�����ł���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ����܂����B
�Ⴆ�A�{���͐��������W��ɂ�2mm�̋����������̂��A1.5mm�ɂ�����ǂ��ł��傤���B
���ʓI�ɎB���f�q���A�u���Ɣ��Ε����ɂ킸���ɓ����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
���́A�u�t�Ƃ��Ẵe�N�j�b�N�Ƃ��āA�����āu���ʋ��t�ɂȂ�v�Ƃ������Ƃ��悭����Ă܂��B
���k����B�ɂƂ��āA���h����銮���Ȏt���ł��邱�Ƃ����A�}�k�P�Ȗʂ��B���Ȃ����ƂŁA
���������̓��ōl���Ă��炢�A�搶�ł���ԈႤ���Ƃ�����A���ďォ��̋����ɁA
�^�����������A���_�ł���X�L���킴�ƍ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�|�p�̐��E�ł́A����̂ق����A�˔\��L���₷�����Ƃ������̂ł��B
�������̃X���b�h�ł���Ă������Ƃ́A����Ƃ͑S�R�Ⴄ���A���Ɨ���������Ă��Ȃ��l�̂��ƂƂ��A
�����A�ǂ��ł������̂ł����Awsxwsx����ɂ́A�}���g���Ă������������Ƃ��A�{���Ɋ��ӂ��Ă���܂��B
������A�����A���������Ă����A�y���^�b�N�X�̊�{�I�Ȏ�U���̕�����A
���̑��̓���Ɋւ��āA�ǂ����Ă��[�����ł��Ȃ��ӏ�������܂�����A���Ԃ����鎞�ł����ł�����A
����A�y���^�b�N�X�ŁA���ځA�����Ă݂Ă��������B��������A�����Ɖ���₷���A
�����������悤�ɁA�g�U���U��������āA������Ă������邩������܂���B
����������A�����Ɨ�����[�߂邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B
����܂ŁA��������̉摜�̌�f���A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10878420
![]() 2�_
2�_
���ς�炸�A�����y���^�b�N�X����m���߂����܂ŁA�Ԉ���Ă���̂��O��ł�
�������݂������̂��A�Ȃ�ł����A���ۂ̎g�p�����A�オ���Ă����̂͊������ł��B
�y���^�b�N�X�̎��@���g���Ă̌�ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�U�b�Ƃ��ׂĂ�q�������Ă����������̂ŁA���̏������݂��I�������ŁA
�ł��邾�����x���J��Ԃ��A�ǂ܂��Ă������������Ǝv���܂��B
���ƁA�l�b�g�Œ��ׂĂ���A�Ƃ������r���[�Ȓm���Ōł܂��Ă������Ȑl�����܂����A
��ʂ�͂�����܂������A�y���^�b�N�X�̌������\�������Ƃ���Ă��Ȃ��ȏ�A
�l�̍l�@�͂��܂�Q�Ƃł��Ȃ��A�Ǝ����Ȃ�ɔ��f���܂����B
����́A�܂������ʂ̃W�������ł͂���܂����A�����g���A�l�b�g��ŁA�����̌����Ȃǂ�
�Q�Ƃɂ��ꂽ��A����Ƀ����N���ꂽ��A���X�A���l�̃u���O�Ȃǂł��[�����[��������Ă��܂�����
�l�Ԃł�����A�������ăl�b�g��A�M�p�ł��Ȃ����Ƃ��������Ƃ��A�t�̗���ł悭�m���Ă��邩��ł��B
�e���r�Ȃǂł����ۂ̔��p�i�������āA�����̌�������������o��������܂��B
�i�������A�J�����̋Z�p�̐��E�Ƃ͊W�Ȃ��ł����A�l�b�g�œ��������q�����킹�āA
�Ƃ�ł��Ȃ����_�ɓW�J����l�B�́A���̕���ł������悤�ɂ��܂��j
�l��Web�}�K�W���ȂǂŁA��U���̎d�g�݂�A����ʂ̃e�X�g������Ă����Ƃ��Ă��A
����������Ă���l�Ԃ��A������̃X���b�h�� �Ƃ�ł����_��W�J���Ă���悤�Ȑl�����ƁA
�����������x�����Ƃ�����ǂ��ł��傤�H�@���͋A���č������āA���������Ƃ������Ȃ��Ȃ�܂��B
�����A�Q�Ƃ���Ƃ�����A�y���^�b�N�X�����\��������̋Z�p���̂悤�ȋL���ł��B
���Ђ̋@�\�ƍ������Ă���l������Əd���A�Q�l�ɂȂ邩�Ǝv���A������̃X���b�h�̖`���ŁA
�R�j�~�m�̃�-7�̋Z�p���ւ̃����N�������܂����B
��ӂ͐Q�t���Ȃ������̂ŁAK10D�̃��b�N�����ASR�Ɋւ���Ƃ�����A�ǂ�ł��܂����B
�Ȃ��Ȃ��A�����ŏؖ��ɂȂ�悤�ȁA����͂���܂���B�Q�l�̂��߁AE-520�̃��b�N��
�ǂ݂܂������A����ς�ڂ������Ƃ͍ڂ��Ă��܂���B
�����̐l���A�p�x�u�������邱�Ƃ�������O�ŁA�ʒu�u���͕�ł��Ȃ��A���ď����Ă܂����ǁA
�y���^�b�N�X�̌������\�ŁA�u�����͊p�x�u������ɕ���Ă��܂��v�Ƃ����Ă����̂��A
��������ł����H�@�����Ȃ�A���̈ӌ����A���߂���ے肷��̂́A�y�����Ǝv���܂���B
�����A�F����̈ӌ����A�Ԉ���Ă���Ƃ��������́A�����g�������Ă������Ƃł��B
���ꂪ�A�R���Ƃ��A���̕����ԈႢ�Ƃ����Ⴂ���Ǝv���Ȃ�A�����Ŋm���߂�Ηǂ��̂ł�
�Ȃ��ł��傤���H�@���̏�������������߂Ă����傤���Ȃ��ł���B���͂���Ȃ���ł��B
���������X���b�h�̎�|�ɂ�����Ȃ����Ƃ��A���ɗv�����Ȃ��ł��������B
���������b���A�R�j�~�m�̎d�g�݂Ɗ��Ⴂ���Ă���l���A���낢��ƁA�Ƃ�ł����_��
�����Ă�������n�܂����̂ł͂Ȃ��ł����H�@�܂��A���̐l�̏������݂������������Ƃ��A
�����ƁA���ɂ߂邾���̊��o���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F10878592
![]() 2�_
2�_
�܂��ԈႦ�܂����B�����܂���B
�@��wsxwsx����ɂ́A�}���g���Ă������������Ƃ��A�{���Ɋ��ӂ��Ă���܂��B
�g���Ă����������Ƃ��A�ł͂Ȃ��A�u����Ă������������Ƃ��v�̃^�C�v�~�X�ł��B
���炢�����܂����B�������́A
�@��wsxwsx����ɂ́A�}������Ă������������Ƃ��A�{���Ɋ��ӂ��Ă���܂��B
�ł��B�Ȃ��\����Ȃ����Ƃ��肵�Ă��܂��Ă��܂��B���߂�Ȃ����B
�{���ɁA�}������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10878647
![]() 1�_
1�_
�œ_�������𗘗p���邱�Ƃ���u�p�x�u���̕�v�V�X�e���ł��邱�Ƃ́u�����v�ł��B
�����ԍ��F10878668
![]() 12�_
12�_
�u��Ԃ�v�Ƃ��Ďʂ��ԑ傫�ȗv�����u�p�x�u���v�Ȃ̂ł����炻����^�[�Q�b�g�ɂ���̂��܂��u���R�v�ł�(Pentax�̃T�|�[�g�Ɏ��₳��Ă�������)�B
�����ԍ��F10878867
![]() 9�_
9�_
���ʓI�ɁA�p�x�u���������Ă��A��{�̍\�����A�ʒu�u������ɕ����d�g�݁A
�����́A���x���m�F���܂������A�Z�p�҂̌�������Ăт��������O�́A��t���ɑҋ@����Ă����A
���l�̕��X�ɂ��A�Ƃɂ����A���s�����̃u���̕�A�Ƃ������Ƃ́A�����ɉ��������܂����B
�ł��A�����ł����ȃc�b�R�~�����邱�Ƃ�\�z���āA�O�̂��߁A�Z�p�҂̕�����A
���ڌ�b���f���ƁA��ϒ������ԁA��b�����Ă��������A�{���ɂ��肪���������ł��B
�����ŁA���x���A�ʒu�u���̕�����C���ŁA�p�x�u���́A��ɓ���҂̕��X�ȂǂŁA
�J��������������z�[���f�B���O�ł��Ă��Ȃ��l���A���̓����Ƃ����킹�ĂȂǂŁA
�N����₷�����Ƃł����āA�����i�y���^�b�N�X�j�ł́A�ނ���A�\�����������肵�Ă���l�ł��A
�B�e�Z�p������l�ł��A�Ȃ��Ȃ��h���Ȃ��悤�ȃu���̎d���A�Ⴆ�A�S���̌ۓ��Ȃǂ���
�N������u���Ȃǂ����m���āH�i�������āH�j����Ă��܂��B�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������܂����B
���ׂāA�g�U���U�肪���ŁA��ϒ��J�ɋ����Ă��������܂����B
�Z�p�҂̌�����A��t���̌�����A�ǂ���ɋ��Ă����������̂��͖Y��Ă��܂����̂ł����A
�����A���p�i�Ȃǂ̐^���ʎB�e�Ȃǂ̎g�p������A�ʒu�u���������Ă��邱�Ƃ��A
���������̂Ŏ��₳���Ă��������܂����A���Č�������A�u�ǂ��C�t���܂����ˁB
����́A�z�[���f�B���O����������o���Ă��邩��A�������Ǝv���܂���v���āA
�����Ă����������C�����܂��B
�ȂA���w���̎Љ�Ȍ��w�̍앶�I�ȓ��e�ɂȂ�A�����ł����������Ă���݂������ȁA
���Ċ����܂��B����������́A����������̂ŁA���܂�J��Ԃ������͂Ȃ��ł��B
��U���Ɋւ��ẮA�����Ȏd�g�݂���������A�����Ȏg�p������������͓��R���Ǝv���̂ł����A
�l�b�g��G���ŏW�߂���ƁA���[�J�[�������ɃR�����g���Ă��Ȃ����Ƃ܂ł́A
���͂��ɂ����Ǝv���܂��B������A�悭�l������A���[�J�[�ɖ₢���킹��̂́A
����ȂɈ������Ƃł͂Ȃ���������܂���ˁB
�ŏ��́A��d���̎ז�����������āA�\����Ȃ��Ȃ��A�Ƃ������������̂ł����A
���ۂɐ��i���g���Ă��郆�[�U�[�Ƃ��ẮA�g�p����v�]���̃R�����g�����Ă����̂ŁA
�b�͂͂��݂܂������A�����ł��A���x�͎��̂ق��������ɗ��Ă�����ȁA�Ƃ��v���܂����B
�����ԍ��F10879053
![]() 2�_
2�_
>�œ_�������𗘗p���邱�Ƃ���u�p�x�u���̕�v�V�X�e���ł��邱�Ƃ́u�����v�ł��B
�ʒu�Ԃ���B���f�q��̋����̎B�e�{��������Ȃ���Ε�o���܂���œ_�������Ƌ�����K�v�ł���ˁB
�����ԍ��F10879123
![]() 1�_
1�_
�y���^�b�N�X��
�œ_�����̂ݓo�^�K�v��
�B�e��������v������ւ�V�X�e����
���s�ړ��ɂ��u��(�V�t�g�u���A�ʒu�u��)��
��ł��邩�ǂ����l�����炦����Ƃ��Ⴂ�܂��H
�����ԍ��F10879201
![]() 1�_
1�_
>�B�e��������v������ւ�V�X�e����
�B�e������炢���ړ_�ő����Ă�ƕ��ʂɎv���Ă܂������ǁB
SF7�ł͏œ_�������ƎB�e�������B�e�{��������o����2���������̒��������̔䗦��ς��Ă����̂�PENTAX-F�����Y�̍������������Ă��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10879325
![]() 0�_
0�_
>���ׂāA�g�U���U�肪���ŁA��ϒ��J�ɋ����Ă��������܂����B
>�Z�p�҂̌�����A��t���̌�����A�ǂ���ɋ��Ă����������̂��͖Y��Ă��܂�����
>�ł����A
>�����A���p�i�Ȃǂ̐^���ʎB�e�Ȃǂ̎g�p������A�ʒu�u���������Ă��邱�Ƃ��A
>���������̂Ŏ��₳���Ă��������܂����A���Č�������A�u�ǂ��C�t���܂����ˁB
>����́A�z�[���f�B���O����������o���Ă��邩��A�������Ǝv���܂���v���āA
>�����Ă����������C�����܂��B
>
>
>�ȂA���w���̎Љ�Ȍ��w�̍앶�I�ȓ��e�ɂȂ�A�����ł����������Ă���݂�����
>�ȁA���Ċ����܂��B����������́A����������̂ŁA���܂�J��Ԃ������͂Ȃ��ł��B
����႟�����ł��傤�B
�ł��A�ǂ�ł�������A���̐����敾���܂���B
�����āA�u�Z�p�҂ɕ����Ă����v�@�ƌ����邻�̖{�l���A���X�Ɓu�Y��Ă��܂����v�Ƃ��u�����ĉ��������C�����܂��v�@�Ƃ����Č����Ă��ł�����D�D�D�D�D
MZ-LL����A�����̕������A�d���ŕ��ׂ������u�������Ǝv���܂��v�Ƃ��u�Y��܂����v�ƕ��ꂽ��A�u�������v�@�Ɣ[���o���܂����H
�l�͌����Ă����܂����AMZ-LL����̓`�������Ǝv���Ă��鎖�𗝉���������ł��B�����炱�����Ėl�̎v����`���Ă��܂��B
�O�ɂ������܂������A�Z�p�҂��畷���Ă����A�ƌ������̏����ȕ��͂ŗ������₷����������鎖�͕K�{���Ǝv���܂��B�c�_�͂������炾�Ǝv���̂ł����D�D�D�D�D�D
�����ԍ��F10879328
![]() 15�_
15�_
�����c���A���X�������ɁB
�y���^�̎�Ԃ��́u�S�āv�̃����Y�ɗL���ł����B
�����ԍ��F10879388
![]() 2�_
2�_
�܂������Ă���ł��ˁB
�X���傳�ŏ��Ɍ����Ă�ꂽ�A
>�t�@�C���_���ł̋l�߂��\�}�ƁA�L�^�����摜�̃Y�����ł����Ȃ��̂́AK-7���Ɗ����Ă��܂��B
�́A�������Ă���̂��Ǝv���܂��B
Nikon�́A�����[�Y�������Ƃ��Ɂu�ړ�������u��������Y�Q���u���Ɍ����̒��S�ɖ߂��i�Z���^�����O�j�A���߂ĘI���̂��߂̎�u������s���܂��B�v
�Ƃ������Ƃł�����A��ƂȂ�ʒu���A�����[�Y���ƈقȂ�ꍇ���������܂��B
�y���^�b�N�X�́A�����[�Y�O�Ɏ�Ԃ����������Ă��Ȃ�����A�����[�Y�������u�Ԃ̈ʒu����Ɏ�Ԃ����J�n����B�ƁA�������Ă��܂��B
�����A�����́A�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̘b��������Ď���ĂȂ����H�C�ɂȂ�܂��B
���w�I�ɂ́Adelphian���� �̐}�̒ʂ�A��ʑ̂ɑ��ă����Y���ړ�����ƁA���̈ʒu�͓��������ɂ���ɑ傫������邩��B
�J���������ɂԂ�Ă��Z���T�[�͋�ԓI�Ȉʒu��ۂ��ƂŁA�u����ł������͕̂s�\�ł���B
�����ԍ��F10879452
![]() 3�_
3�_
K200D�̍w�����ɂ݂�SR�̐����������ł����B
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/special/k200d/
�̃T�C�g�̎�Ԃ���SR���J�j�Y����SR ON
���̂Ƃ��͉��̋^���������܂���ł������A�������
���m�Ȃ��̂Ɏv���܂��B
���[�J�[���̂����̂悤�Ȑ����ł���������Ă��邱�Ƃ��A
���̖{���ł���Ǝv���܂��B
��_�łȂ����ۂɃJ�����̃����Y�i���H�����̂�DA21mm�j�݂̂�
�V��̌u�����Ɍ����A���Ɏ���u���Ču�����̑����ʂ��āA
���̂悤�Ƀ����Y���X���C�h������Α��̓����Y�ƈꏏ�ɓ����܂��B
���Ƃ����ꂪ�ǂ�Ȃɔ����ł��B
�i������̈ړ��ʂ͌����ɂ͓������͂Ȃ��ł��j
���̌����ʼn����̕��i���B�e���V�t�g�Ԃꂽ��A���������ǂ�Ȏʐ^�ɂȂ�̂��E�E�E�B�i���i��SR�@OFF�H�j
�����ԍ��F10879474
![]() 2�_
2�_
>�y���^�̎�Ԃ��́u�S�āv�̃����Y�ɗL���ł����B
�i�j�S�Ẵ����Y�ɗL���ł��S�Ă̋@�\���g����Ƃ͌���܂����B
���ہA���̂��C�ɓ���ł��鉽�̏��ړ_�������Ȃ��P���R�[�~���[�����Y���ᕪ���]���������g���������d�_���X�|�b�g�����ɂȂ邵�����|�C���g�����������g���܂���B
�����ԍ��F10879487
![]() 0�_
0�_
��K200D�̍w�����ɂ݂�SR�̐����������ł����B
http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/special/k200d/
�̃T�C�g�̎�Ԃ���SR���J�j�Y����SR ON
������������ł��ˁB
�ł��A�R�j�J�~�m���^���\�j�[�����l�̌���ސ��������Ă܂����B
�L��S������l�͂����Ɨ������Ă����Ȃ��ƁB
�����ԍ��F10879519
![]() 2�_
2�_
�L�̍��z�c����A
>���̏��ړ_�������Ȃ��P���R�[�~���[�����Y���ᕪ���]���������g���������d�_���X�|�b�g�����ɂȂ邵�����|�C���g�����������g���܂���B
�����]���������g����̂͂`�|�W�̂��郌���Y�����ł��̂Ő���ł���
(���鎖������ƕ����]��������X�g���{��TTL����Ȃ��g���܂����ǎ��p�I�ł͂Ȃ��̂ŕ����Ēu���܂�)
�\�j�[�݂����Ƀ`�b�v�������ƃu������g���Ȃ����Ă����Ȃ�b�͕ς���Ă��܂����ǂ�
�y���^�̓����Y�̑����Ȃǂ͊W�����Ɏ�u�����t�H�[�J�X�C���W�P�[�^�[��
�g����̂͐��������Ǝv���܂���
�����ԍ��F10879605
![]() 0�_
0�_
���̌���������́A
�B�e���̔�ʑ̂܂ł̋������������Ȃ������Y��
��Ԃ��ł���Ƃ������Ƃ�
�ʒu�u���̕�͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤��?
�p�x�u���̕�ł���Ƃ����͎̂�����ˁB
�ƁA���܂���A1����̘b�ɏ���Ă���w
�Ă��ƁB
F�ȍ~�̃����Y�ɂ��Ă�z
���z�c���͈ʒu�u���̕������ƁH
�����ԍ��F10879636
![]() 1�_
1�_
���������A�V�t�g�u���ɂ��ċC�ɂȂ����̂Ő�قǃ����Y���O���Z���T�[�̓���������������s���܂���
�J��������ɓ������ƃZ���T�[�͉��ɁA�J���������ɓ������ƃZ���T�[�͏�ɍs�������������Ă���܂���
����ăV�t�g�u���ɂ͑Ή����Ė��������ł���
���������T���ʼn������鎖�Ȃ̂ɊF����ɂȂ�ł��ˁ`��
�����ԍ��F10879654
![]() 3�_
3�_
>F�ȍ~�̃����Y�ɂ��Ă�z
>���z�c���͈ʒu�u���̕������ƁH
�@
�s���B
�m�肷��ޗ����ے肷�闝�R�����m�ɖ����̂ɔ��f�͖��Ӗ��B
�P�ɊԈႢ���ԈႢ�Ǝw�E���������ł��B
Tomato Papa����
�p�x�u�����Ȃ��̂ɎB���f�q���������Ƃ������ł����H
�����ԍ��F10879698
![]() 0�_
0�_
>�p�x�u�����Ȃ��̂ɎB���f�q���������Ƃ������ł����H
�����������ƂȂ̂��ȁH
�Z���T�[�͈��̏ꏊ�ɒ���悤�Ƃ��܂��A�J�������L�`���ƍ\������ԂȂ�
�����Y�̐悪���ɌX���Z���T�[�͉��ɁA��ɌX����Ώ�ɍs���܂���
�u���̌������ĊF�����������Ă���悤�ɃL�`���ƍ\���Ă����
�J���������Ƀ����Y�̐�[���h��ău���鎖�������ł����痝�ɂ��Ȃ��Ă�Ǝv���܂���
�����V�t�g�u���ɑΉ�����̂ł�����Z���T�[�͋t�̓��������܂����
�ړ������������Ȃ�܂����C���[�W�T�[�N���ɂ��]�T���K�v�ɂȂ�܂�
�ʏ�t�@�C���_�[��`���\��������ȃV�t�g�u���͖w�NjN����܂���
���C�u�r���[�ł�����̓����Y�������Ă���̂ŃV�t�g�u���͋N�����Ǝv���܂�
�����疳���ɃV�t�g�u���p�̓������̗p����Ӗ������܂薳���ł���
�����ԍ��F10879761
![]() 3�_
3�_
Tomato Papa����
���`��c
�p�x�u���̃Z���T�[�������ڂ��Ă��Ȃ��Ǝv���Ă����̂ł����V�t�g�����o�����Ⴄ��ł����B
�����Y���O������Ԃł͋�����Ȃ��̂ŎB�e�{�������ł����V�t�g�u���������ɓ��삵�Ȃ��͓̂��R�Ƃ�������킯�ł����B
�܂����ۃV�t�g�u�����L���Ȃ̂͂��Ȃ�B�e�{���������ꍇ�ł��傤���莝���œ��{�B�e���s����������܂�������x�̕������ł�����Ă��炦��Όl�I�ɂ͑�ςɗL���ȋ@�\�Ȃ�ł����ˁB
�����ԍ��F10879798
![]() 0�_
0�_
���͂悤�������܂��B
MZ-LL����
�����ƁA�l�b�g�Œ��ׂĂ���A�Ƃ������r���[�Ȓm���Ōł܂��Ă������Ȑl�����܂����A
����ʂ�͂�����܂������A�y���^�b�N�X�̌������\�������Ƃ���Ă��Ȃ��ȏ�A
�l�̍l�@�͂��܂�Q�Ƃł��Ȃ��A�Ǝ����Ȃ�ɔ��f���܂����B
�{���Ɍ��܂������H�l�̍l�@�H
������ƃ��[�J�[�̕��̐����Ȃǂ������Đ������Ă���T�C�g�Ƃ��ȒP�Ɍ�����܂������c�@(�y���^�b�N�X�ł͂Ȃ��ł���)
�������ŁA���x���A�ʒu�u���̕�����C���ŁA�p�x�u���́A��ɓ���҂̕��X�ȂǂŁA
���J��������������z�[���f�B���O�ł��Ă��Ȃ��l���A���̓����Ƃ����킹�ĂȂǂŁA�c(�ȉ���)
����ł́A����@�ł���K-m��K-x�̎�Ԃ��́A���̃��C���^�[�Q�b�g�ł������҂ɂƂ��Ė��ɗ����Ȃ����Ă��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB
���ƁAdelphian����̐}���ɂ��Ă͂ǂ��v���܂����H�����H
�Ђł��낳��
��Nikon�́A�����[�Y�������Ƃ��Ɂu�ړ�������u��������Y�Q���u���Ɍ����̒��S�ɖ߂��i�Z���^�����O�j�A���߂ĘI���̂��߂̎�u������s���܂��B�v
���Ƃ������Ƃł�����A��ƂȂ�ʒu���A�����[�Y���ƈقȂ�ꍇ���������܂��B
��H�t����Ȃ��ł��傤���H
�����[�Y���ɉ��߂ĘI���̂��߂̎�u������s���Ƃ������Ƃ́A�ނ����ƂȂ�ʒu�������[�Y���ɍ��킹�邽�߂̏����Ɏv���܂����B
���y���^�b�N�X�́A�����[�Y�O�Ɏ�Ԃ����������Ă��Ȃ�����A�����[�Y�������u�Ԃ̈ʒu����Ɏ�Ԃ����J�n����B�ƁA�������Ă��܂��B
�V���b�^�[�������Ńt�@�C���_�[���Ɏ�Ԃ��}�[�N���\�����ꂽ��Ԃł́A�����[�Y�O�ł���Ԃ��͌����Ă܂���B�t�@�C���_�[�Ŋm�F�͂ł��܂��ALV�Ŋm�F�ł��܂��B
Tomato Papa����
��>�p�x�u�����Ȃ��̂ɎB���f�q���������Ƃ������ł����H
��
�������������ƂȂ̂��ȁH
Tomato Papa����A�莝���ł��ꂽ��ł���ˁH
��������Ă݂܂������A�莝���ł͏�ɑO��̓������������Ă��܂��̂ŁA���S�ɃJ�������㉺���邾���̊p�x�Ԃ�̂Ȃ���Ԃ����͓̂���Ǝv���܂��B
�ŁA�㉺�����̓��������邽�߂ɁA�����ȂŎg���u�͂���v���g���Č��܂����B
���ʁc�͂���̏�M�����ĂԂ������Ă���Ă��A�Z���T�[�̓{�f�B�ƈꏏ�ɏ㉺���邾���ŕ����͂��܂���ł����B
�܂�A�V�t�g�Ԃ�ɂ͔������Ȃ������ƌ������Ƃł��B
�u�͂���v������ΊȒP�Ɏ����ł��܂��̂ŁA�����Ԃ��������Ă݂ĉ������B
�����ԍ��F10879942
![]() 5�_
5�_
�L�̍��z�c����A������ƒ����ł�
���ɂ������܂����NJ��S�Ɋp�x�u����r�����܂��ƃZ���T�[�͔������܂���
�p�x�u���̂ݗL�����Ċ����ł���
���Ƃ���A
�ܘ_�莝���ł��A���Ƃ���������D���ł����H��
�Z���T�[�̓��������邽�߂Ƀ����Y�͊O���œ_����200mm�ŃZ�b�g���܂���
>�莝���ł͏�ɑO��̓������������Ă��܂��̂ŁA���S�ɃJ�������㉺���邾���̊p�x�Ԃ�̂Ȃ���Ԃ����͓̂���Ǝv���܂��B
�����ł��ˁA�莝�����Ɣ����Ɋp�x���t���Ĕ������Ă��܂��܂���
���C�ǂ��������Ă��܂����͎̂莝���Ŕ����Ɋp�x���t���������ł���
���Ƃ������ƂŒǎ����Ă݂܂���
�����̌v��͓d�q���Ȃ̂ňႤ���@�Ŏ����܂���
�O�r�̃G���x�[�^���t���[�ɂ��J�������グ�������铮���
�J���������ɍ��E�ɐU�铮��Q��ގ����܂���
���ʂP�@�F�@�J�������グ���������ꍇ�̓Z���T�[�͔������܂���
���ʂQ�@�F�@�J���������ɍ��E�ɐU��ƌ������������܂�
�����̌���
�u��u����͊p�x�u���ɂ̂ݗL���v
�Ƃ����̂����̓����ł�
MZ-LL����A����ł����ł����H
�����ԍ��F10880351
![]() 3�_
3�_
Tomato Papa����
���ܘ_�莝���ł��A���Ƃ���������D���ł����H��
���������A�ǂ������ƌ����Ɩʓ|�������艮�ŁA�����D���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A����F�X�����Ă��܂����̂Ŋm�F��������Ƃ����Ǝv���܂��āB
���O�r�̃G���x�[�^���t���[�ɂ��J�������グ�������铮���
���J���������ɍ��E�ɐU�铮��Q��ގ����܂���
�Ȃ�قǁB���ꂾ�ƃV�t�g�Ԃ�Ɗp�x�Ԃꗼ�������܂��ˁB������̂ق����ǂ������ł��B
MZ-LL����
��L�̂悤�ɁATomato Papa����Ǝ��̎����ł́A�p�x�Ԃ�͕����Ă��V�t�g�Ԃ�͕����Ȃ��Ƃ������ʂƂȂ�܂����B
�܂��A�莝���̎����ł́A�V�t�g�Ԃꂳ��������ł������̊p�x�Ԃ���N���Ă��܂����Ƃ�������܂����B
����́A�莝���̏�ԂŁA�����̎�Ԃꂪ�V�t�g�Ԃ�Ȃ̂��A����Ƃ��p�x�Ԃ�Ȃ̂��A�蕪���Ċ������邱�Ƃ��ɂ߂č���Ƃ������Ƃ������Ă���Ǝv���܂��B
�C�����I�ɂ́AMZ-LL����̊��o�d�������Ƃ���ł͂���܂����c
���Ђ����g�Ŏ������Ă݂Ă������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10880522
![]() 3�_
3�_
�j�|�V�����Ă��܂��̂ŁA���炭�Ԃ�ɔ`���Ă݂܂�����A����͋���ׂ��X���ł��ˁB����Ȃ������S�ǁA��U�s���Ƃ����Ƃ���ł��傤���B
���t�̃{�f�B����Ԃ��́Akuma_san_A1���A�������̂悤�ɁA�Â����V���������������ŁA�R�j�J�~�m���^�A�y���^�b�N�X�A�I�����p�X�A�\�j�[�̂��������Ԃ��̌����́A�p�x�u���̕�ł��ˁB
�p���x���o�Z���T�[�̏o�͐M���ƃ����Y��_����C���[�W�Z���T�[�܂ł̋��������Ɍv�Z�����ʂ����C���[�W�Z���T�[���V�t�g���܂��B
�Ⴄ�̂́A�C���[�W�Z���T�[���t���̖ʎi���j�̎d�g�݂ƃA�N�`�F�[�^�[�̎d�g�݁A���_�̌��ߕ��Ȃǂ��Ⴄ�̂ł��ˁB
����͂���Ƃ��āA�j�|�V�������Ă���̂Ŏ��@�̓���ɂ��āA���łȂ��猩�Ă݂܂����B
��Ԃ��̓���́A�t�@�C���_�[���g���Ƃ��ƃ��C�u�r���[�̂Ƃ��ł́A���삷��^�C�~���O���Ⴂ�܂��B
�t�@�C���_�[���g���Ă���Ƃ��́A���������ăt�@�C���_�[���Ɏ�Ԃ�}�[�N���o��Ǝ�Ԃ����L���ɂȂ�܂����A�܂��V���b�^�[���܂ł́A��͓������C���[�W�Z���T�[�͓d���͂ŋ��łɈʒu�Œ肳��Ă��܂��B
���C�u�r���[�ɂ���Ɣ���������܂ł������펞��Ԃ����������Ƃ��āA�莝���Ȃǂł́A�ӂ�ӂ�Ɖ摜�������Ă��܂��B
�������Ȃ���Γ����܂���A��Ԃ��������Ă��邩�A����Ƃ��͈͂��Ă���̂��́A���R�Ƃ��܂��A�摜�������Č�����Ƃ��́A�͈͂���E���Ă���̂ł��傤�B
�V���b�^�[���ƁA���̏u�Ԃ�����Ԃ�����B�e�����Ɗ����܂��B
�莝���ł͖����ATomato Papa����Ȃǂ̕��@���ɏo�Ă����A�T�J���̑��u�̂悤�Ɋp�x�u�����Ȃ��悤�ɂ���A�ӂ�ӂ�͖����Ȃ�܂����B
����Ȃ��ƂŁA���Ɏ�������́A������̐V���Ȓm���͓����܂���ł����B
���C�u�r���[�Î~��B�e�ł́A���m�ɂ́A�O�r�g�p�i��u����͕s�g�p�j���A�����߂��܂��B
�����ԍ��F10880633
![]() 3�_
3�_
��ӌ��⌟�̌�A���肪�Ƃ��������܂��B
�v�X�ɂU���Ԉȏ� ����܂����B����ē��������ԃX�b�L�����Ă��܂��B
�����A������A�Ƃ܂��Z�����A��T�����獡�T�ɂ����ẮA�����Ԃ̏������݂����Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��̂ł����A
�x���ł��鍡���̂����ɁA�ł��邾���A������Ă�����X�ɂ����m�Ȕ��f�͂������Ē������߂̃q���g�̂悤�Ȃ��́A��
����������Ǝv���Ă��܂��i�Z�����Ȃ����́A��ʓI�Ȍ�d�������A�����̔��f�Ŏg���鎩�R�Ȏ��Ԃ������ł��j�B
�������܂��ۂɁA���ւ̔z���₨�C���������������A��ρA�������v���܂��B
���ς�炸�A���r���[�Ȓm�������ɁA�����ȓ������ʂ����������邾���̒b�����u�ځv��
�����Ă����Ȃ��̂ɂ��ւ�炸�A�^�����Ȃ������̒m���⌟���������悤�ȏ����������Ă���l��
����������悤�Ȃ̂́A�܂��܂��߂���������܂����B
�ł��A�폜���ꂽ�悤�ȏ������݂��A��ӁA�����Ō�Ɋm�F��������A�����悤�Ȃ̂ŁA�����͊������ł��B
������Ă��邱�Ƃ��A�؋��Ƃ��Ďc���Ă��ꂽ�ق����A���Ƃ��ẮA����������₷���̂ł��B
�����g���A�v�_�����Ȃ��Ɨ����ł��镝���Ă��܂��̂ƁA�ʒu�u���͕�ł��Ȃ��A
�ȂǂƏ����Ă���l�B�ɁA�������n�b�L�������邽�߂ɁA�y���^�b�N�X����ɖ₢���킹���ۂ́A
��{�I�ȁA�ʒu�u����ł������d�g�݁A�̕����𒆐S�ɁA���x�������Ă��������܂������A
���̉��p������A�l�Ԃ��莝���B�e�ŋN�������u���A��U��A�h��A�ɍœK�����Ă��邱�Ƃ���A
�C���[�W�T�[�N�����ŕ��s�ɔ��ړ����邱�Ƃɂ���āA�{�f�B���������Ă��A���W�ɗ��܂�A
�Ƃ�����{�\���ȊO�ł��A�����ƕ��G�Ȍv�Z��f�[�^�����ɁA�ׂ������삪����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��l�͐������܂��B
���x�l���Ă��A�C���[�W�T�[�N�����̔��ړ��ł���A�V���b�^�[���u�Ԃ̍��W��
�I�����ɗ��܂��A�ʒu�u���͂قڕ�ł���A���ۂɂ���͕����Ă������Ƃł����A
���̍l�����A�Ԉ���Ă���Ƃ͎v���܂���B�Z�p�I�ɂǂ��́A�̘b�����X���Ă���킯�łȂ��A
�����A������ƎB�e���Ă������ŁA�ǂ����Ă��p�x�u���݂̂̕�ł́A�Ή�������Ȃ���
�v��������̉摜�����邩��ł��B
�����āA���ۂ�EOS��IS�����Y�̑g�ݍ��킹�ł́A��ł��Ȃ��ł����A�듮��Ȃ̂�
�d�g�݂̂����Ȃ̂��A�_�����\�}����ʒu���Y���܂��B����Ȃ��SS�ŎB���Ă���ꍇ�ł��ł��B
�����Y���O���A��A���̏�ɏ悹�ėh���Ԃ�A�ȂǁA���ۂ̎莝���̎B�e��ԂƂ́A
�Ⴄ���@�ŁA�P�������悤�Ƃ��Ă��ASR�̂ق����A�����ƕ��G�Ȃ��Ƃ�����Ă̂��Ă���̂�����A
�m���߂�͓̂���Ǝv���܂��B�t�Ɏ��̂悤�ɁA���V�r�A�ŁA���̖ш�{�̌덷����
�������˂Ȃ�Ȃ��A�B�e�����S����������ق����A����ۂǁA���̕�̌��ʂ̉��b�A
�Ƃ������������@�\��\���A��������͂��ł��B
�i�����X�ɑ����܂��B�j
�����ԍ��F10880646
![]() 2�_
2�_
�i�O���X����̑����ł��B�j
����B�e���A���ɂ�����Ǝ��r�̔��u�����ł���̂��A�t�@�C���_��`���B�e�̍ۂɁA
��������J�������Œ肵�āA�p�x�u�����قƂ�NjN�����Ȃ��悤�ȍ\�����o����l������
��Ƃ́A�Ⴄ�A���S���Y���ŁA����B�e����SR�̕������ς��Ă���̂�������܂���ˁB
���������A�Z�p�҂�J���҂Ȃ�A���Ԃ�����ł��傤�B
���ԁi���W���j�łقڌŒ肵�Ă����ԁi������������͐k���A�ؓ�����͏����Ȑk�����`���j�ƁA
�������L���āA����ŕ�������悤�Ȍ`�ŃJ�������\����ꍇ�i�k����j�Ƃł́A��̎d�g�݂�
�������ŕς���̂́A�Ȃɂ����R�ȋC�����Ă��܂����B�@������B���Ă���ƁA�����܂��B
�������A�킸���Ȋ��Ԃ̏��Ȃ��o�����炭�銴�G�ł����Ȃ��A���Ȃ�̋�_�ŁA�����ɂ����߂��܂���B
���ۂɊp�x�u������ɕ���Ă���@��ƁA�y���^�b�N�X��SR�̋@��i�����ł�K20D��K-7�j�ŁA
�������A�����悤�Ȕ�ʑ̂��B���ׂ�A�����́A�����Ă�����̂�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ł���A�C���[�W�T�[�N�����ł́A�f�q�̓����╝���C���[�W���Ȃ���B�e�����ق����A
������ʂ͏o�₷���Ǝv���܂��B
��ӁA�F����̎g�p����ǂ܂��Ă��������̂��r���ɂȂ��Ă��܂��܂������A�����قǂł�
����܂��A������x�͐����������悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă������߁A����ς肿���Ƃ͓ǂ߂܂���ł����̂ŁA
������A���̃X���b�h���A�ł��邾���O�ɖ߂�Ȃ���A�q�������Ă��������܂��B�v�X�ɁB
�����āA���́A�����܂ł��u�����Ă������Ɓv���A���w���ȉ��̕��͗͂ŁA�����Ă��邾���ł��̂ŁA
����ȏ�́A���m�ȁu���v�ƂȂ邱�Ƃ��A�����ʼn���ł���Ƃ͎v���Ă��܂���B
�q���g�͂���߂Ă���͂��Ȃ̂ŁA��������́A�ǂF���A�m���߂�����Ǝv���܂��B
�l�b�g��Ō��������Ă��o�Ă��Ȃ�����ł�����A����𗊂�ɕ����𗝉����悤�Ƃ���l�ɂ́A
���������������܂���B���������������@��ɂł��A�u�ځv��b����A���Ă��Ƃ�����Ă݂�̂��A�ǂ���������܂����B
�ǂ�Ȑ��x�⌋�ʂł���A�g�p���Ɋւ��ẮA�ł��邾���Q�l�ɂ����Ă������������v���܂��B
���������݁A���肪�Ƃ��������܂����B
�������ݎ��̂́A�Z�����Ă��A�����ŏo����̂ł����A�ǂ�摜��������́A�����̂悤�ȓ���
�Ȃ��ƁA����Ǝv���̂ŁA�ł��邾�����X�𒆐S�ɂ����Ă������������ł��B
�����ԍ��F10880649
![]() 1�_
1�_
�����A���撆�ɁA�p�x�u�����N���������̂ق����A���삪�x��Ă���炷��A
�Ƃ������Ƃ͏����Ă܂���B
��͂�A�u�ځv�̒b�������Ⴄ�̂ł��ˁB���́A�����炪�u���܂�����Ă��Ȃ��v�Ɗ����܂����A
�ł��邾�����肵���������ŁA����B�e���Ă���ۂ́A����ł��A�g�̂��k���Ă���̂�����̂ɁA
����������ŁA�ł������Ă���ASR�̌��ʂ��A�n�b�L���ڎ��ł��܂��B
�������ׂ����A�����ȍ��݂ŕ����Ă��܂��B
��͂�A�c��������̃f�b�T���̕��Ƃ��A�P���̎����Ȃ̂ł��傤���B
�u�ځv��b���ĂȂ��l�����ɁA��肢�������ł��Ȃ��̂��A�炢�Ƃ���ł��B
�����ԍ��F10880665
![]() 1�_
1�_
Tomato Papa����@���Ƃ���@�������肪�Ƃ��������܂��B
����̌��ʂɂ��܂��Ă̓����Y���O���čs��ꂽ�l�ł��̂ŋ��������J���������������Ɣ��f�����Ƃ���V�t�g����s���Ȃ������̂̓V�t�g��Ƃ��Ă�����ȓ���Ƃ������ɐ���܂��B
�]���ăV�t�g��̗L���f����ޗ��ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂��B
>��H�t����Ȃ��ł��傤���H
>�����[�Y���ɉ��߂ĘI���̂��߂̎�u������s���Ƃ������Ƃ́A�ނ����ƂȂ�ʒu�������[�Y���ɍ��킹�邽�߂̏����Ɏv���܂����B
�����Y���ŏ펞�u������s���ꍇ�t�@�C���_�[�������肷��̂ƈ��������Ƀ����[�Y�̎�����j�b�g���[�̈ʒu�ɗL��ƒ����ʒu���烌���[�Y���̂ݕ���s���ꍇ�ɔ�ו���ʂ��ቺ����ꍇ���o�Ă��܂��B
�����Ńt�@�C���_�[���̈���ƃu������ʂ𗼗�������ׂɏ펞�u������s���~���[�A�b�v���Ƀu������j�b�g�𒆉��ʒu�ɖ߂��Ă��烌���[�Y���̕���s�����[�h���o���܂��������������ɃV���b�^�[�{�^�������������̃t�@�C���_�[���Ƃ̃Y�����傫���Ȃ�ꍇ���o�ė��鎖�ɂȂ�܂��B
���ꂩ�玄�͊p�x�u������s���Ă��鎖�ɋ^��������Ă���킯�ł͂���܂���B�莝����800mm����p�H���Ă܂��̂Ō��ʂ��������Ă��܂��B
�����ԍ��F10880706
![]() 1�_
1�_
�܂��A�F����̃��X�������ƓǂޑO�ɏ����Ă��܂��ċ��k�ł����c�B
���̃X���b�h�𗧂ĂĂ݂āA�������̂́A�≖���ォ��J�������D���Œ����B�e����Ă������X���A
���̒m����o���ɂ���āA�������āA���̌��ʂ��m���߂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����悤�ȋC�����Ă��܂��B
������x�A�{���ɁA�����Ȉʒu�u���������Ă��Ȃ����A�y���^�b�N�X���玄�������Ă������Ƃ��A
���Ƃ��ǂ݂Â炢���͂��Ƃ��Ă��A�q���g�Ƃ��āA����ʂ������A���̏�A
�����ĊԈႢ�łȂ����Ƃ́A����Ǝv���̂ł����B
������x�A�Ə����܂������A�C�����Ƃ��ẮA���S�A����ƁA�����Ǝ����Ă݂Ă����A
���Ċ����ł����A���ꂪ�o����悤�ɂȂ����łɂ́A�����Ɛ��x�̍����B�e���A�莝���ł��\�ɂȂ�ł��傤�B
���ƁA���C�u�r���[�́A��{�I�ɎO�r���g�p���ĎB�e�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B
���́A�~���[���オ���āA�V���b�^�[�����܂ŁA�^�C�����O����������ł́A
��U���̌��ʂ����҂ł���͈͂̃u�����A�x��SS�ł́A������ȁA�Ƃ����̂�����ł��B
������A�P���⊵��ŁA������x�̓J�o�[�͂ł���Ǝv���܂����A������͎��͒��߂Ă��܂��B
��i�W�̎B�e�Ȃǂ̎d���ł́A�O�r�ł̎B�e�������ł����B���C�u�r���[�܂Ŏ莝���ł���̂́A
�O�r���g���Ȃ��悤�Ȋp�x��A�����Ƃ��\�}���߂Ɏ��R�x���K�v�ȍۂȂǂ́A����ȎB�e�̏ꍇ���Ɗ����܂��B
���Ƃ́A������p�Ȃǂ́u��i�v�ł́A���������ςȎB�e�̎d�����ʔ��������肵�܂��̂ŁA���̎����炢�ł����ˁB
�ق�ƂɁA���ꂩ��A�F����̏������݂�q�������Ă��������܂��B
�������Ȃ��ƁA�����A�ł��܂���̂ŁA�A�����X�A���炢�����܂����B
�����ԍ��F10880746
![]() 2�_
2�_
�@���������Ȃ��ƁA�����A�ł��܂���̂ŁB�@�A�����X�A���炢�����܂����B
�̊ԈႢ�ł��B�{���ɍ����̂����ɁA�Ȃ�Ƃ��ǂ܂��Ă��������āA
�ꕔ�̌���ɂ����ł���Ԏ������Ă���������Ǝv���܂��B
�݂Ȃ��ܑS���ւ̃��X�́A�������Ǝv���܂��̂ŁA�\����܂���B
���̂��Ƃ́A���̃X���̑����i�K�ŁA�����Ă܂��̂ŁA���炢�����܂��B
���ӌ��� ���������݁A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10880764
![]() 2�_
2�_
���Ƃ���
>�V���b�^�[�������Ńt�@�C���_�[���Ɏ�Ԃ��}�[�N���\�����ꂽ��Ԃł́A�����[�Y�O�ł���Ԃ��͌����Ă܂���B�t�@�C���_�[�Ŋm�F�͂ł��܂��ALV�Ŋm�F�ł��܂��B
������������ł����B
�t�@�C���_�[�ł́A�m�F�o���Ȃ��̂ŁA�Ă����背���[�Y���������Ƃk�u���������Ǝv���Ă��܂����B
�m�炸�Ɏg���Ă��邱�Ƃ͑����ł��ˁB
���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F10880812
![]() 0�_
0�_
�L�̍��z�c����A
>���������J���������������Ɣ��f�����Ƃ���V�t�g����s���Ȃ������̂̓V�t�g��Ƃ��Ă�����ȓ���Ƃ������ɐ���܂��B
�����ł��ˁA���̉\�����L��܂�����
��������ɂ�AF�}�N�������Y�Ȃǂ�ROM���J�����ɓ`�B�����Ȃ��ƂȂ̂Ŏ����͓���ł�
�܂��A���ʂȎ����Ȃ̂Ŏ��͂��C���N���܂���A�ł������V�t�g�u����͓���Ȃ��Ǝv���܂���
�Q�l�ɂȂ邩������܂���FAF�A�_�v�^�[�g���Ɖ��i���B���Ă�PHOTOME�Ō���Ƃ��闓��macro�ƕ\������鍀�ڂ�����܂�
�ʏ�̃����Y��t������Ԃł��Ƌߋ����ł�macro�A�ߋ����ȊO�ł�Distant view�ƕ\������܂�
PHOTOME��macro�\�����ߋ����B�e�Ƃ��ăJ�������F�����Ă���Ƃ���������ς��̂��Ǝv��
�J������FAF�A�_�v�^�[���Z�b�g���������̎����������܂������㉺�ړ������Ă���͓���܂���
�ł�����}�N����ł��V�t�g�u����͊|����Ȃ��Ǝ��͍l���Ă��܂�
���Ƃ��Ƃ���̎�������J�����ɔ����Ȋp�x���t���������Ŋp�x�u������������Ă��܂����Ƃ�
�m�F���܂����̂Ŋp�x�u����݂̂��L���Ȃ̂�������Ǝv���܂�
�p�x�u���E�V�t�g�u���̕�̓Z���T�[�̓������t�ł�����Z���T�[��������������
���������邱�Ƃ͏o�������ł���
�����V�t�g�u���A�p�x�u���o���ɑΉ�������Ȃ�Z���T�[���烌���Y�܂ł��ɓ������ĕ����
�����Y���j�b�g�X�C���O�����łȂ��Ɩ����ł���
����ȏケ�̘b��͂����ł͂������Ȃ��̂�
�ʂ̋@��ɑ��ł��܂��傤��
�����ԍ��F10880941
![]() 3�_
3�_
���́A�ʒu�Ԃ�̕�����Ă邩�ǂ����Ȃ̂ł��ˁB
�ʒu�Z���T�[���������ƁA����ѕ����Ƃ���A�����Y�ƈ�̂ŃC���[�W�Z���T�[���V�t�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���A�ʒu�Ԃ�̕�́A���Ă��Ȃ��ƂȂ�܂��B
��Ԃ��̌��ʂ��ƂĂ������ł�����A�V�t�g�u�������́A�ǂ�������Ă���Ǝv���܂��B
�j�|�V�ł́A�ʓr�Ɏ��������������܂��̂ŁA�d�q������i�����x�Z���T�[�y�A�j�������Ă��܂�����A������n�m�ɂ��Ă��ĐU��ƎB�e�摜�ɌX�����܂����A����͂��̍ۂ́A���W�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10881029
![]() 1�_
1�_
>�����V�t�g�u���A�p�x�u���o���ɑΉ�������Ȃ�Z���T�[���烌���Y�܂ł��ɓ������ĕ����
>�����Y���j�b�g�X�C���O�����łȂ��Ɩ����ł���
�@
>�����Y�ƈ�̂ŃC���[�W�Z���T�[���V�t�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ�
�J�������猩��Ίp�x�u�����ʒu�u������ʑ̂̑��ΓI�Ȉʒu�ω��ɉ߂��܂��牽�̂���ȗ����ɂȂ�̂��H
>�p�x�u���E�V�t�g�u���̕�̓Z���T�[�̓������t�ł�����Z���T�[��������������
>���������邱�Ƃ͏o�������ł���
�p�x�u���ƃV�t�g�u���͕ʂ̂��Ȃ̂ŏ�ɋt�Ƃ�����Ȃ��ł��傤�B
�ނ���t�Ȃ痼�������Z������ʂ����Ȃ��Ȃ�̂Ŋy�ł��傤���ǁB
�ʏ�̃����Y�̍ŒZ�B�e�����͏œ_����10�{���x�ł����牼�Ƀ����[�Y��5mm���ʒu�u�������Ƃ��Ă��K�v�ȎB���f�q�̃V�t�g�ʂȂ��0.5mm�ɉ߂��܂���B
�B���f�q�ɖڎ����ĕK�v�ȏ������Ƃ��v���Ȃ��̂ł܂��̋@��ɁB
�����ԍ��F10881108
![]() 0�_
0�_
���݂̎��ł��A��Ԏ��������ɂł������Ȃ��Ƃ���A���X�����Ă��������܂��B
���Ԃ͑傫���ς��Ǝv���܂����A���e�͂��������B
���݂Ȃ���̂�����@�@[10869678]
�����ɂȂ��āA���߂ď������݂�q���������܂����B���X���肪�Ƃ��������܂��B
�@���u�����̉��Œ��߂��˂��g���Ď��ȂǂɌ����W�߂�ƁA
���̌��ؕ��@�H�ł��ƁA�y���^�b�N�X��SR�̎d�g�݂𗝉��ł��Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�܂��l�������Ă݂Ă��������B
���́A�ȑO�A������p�n�̓W����̊�摤�Ƃ��āA�s���z�[���J�����̍\�����������A
��Ԃ̐ݒu�Ɋւ�������Ƃ�����܂��B���ۂɂ͊��S�ȃs���z�[���ł͂Ȃ��A�����Y��p���܂����B
�i���͂��̋�ԍ�i��v������Ƃł͂���܂���̂ŁA���̃����Y���ǂ��������̂��͂悭�m��܂���j
���̍ہA�s���z�[���̑���ƂȂ�A���̃����Y�̃x�X�g�Ȉʒu���A���s�ړ������Ȃ���A
���߂��Ƃɂ��A������܂������A������̔��������C��ƂȂǂ�����Ă��܂����B
�����Y�̈ʒu���ς��ہA��Ɉړ�����A�ǂɉf���o���ꂽ��ʑ̂̍\�}�͈̔͂��A���Α���
�g���~���O�Ƃ������A�\�}�̒��g���ړ�����̂́A�{���̂��Ƃł��B�i��̂̂��Ƃł��̂ŁA�L���͂��ڂ낰�ł����j
�l�Ԃ��A�J�����̓����ɂ���悤�ȁA��Ԃ̍�i�ł����B
�ł����A�C���[�W�T�[�N�����Ɍ���܂����A�Ǒ��������������ł����������ŁA�ړ�����A
�ʒu�u���̕�͂ł��邱�ƂɂȂ�͂��ł��i�C���[�W�T�[�N�����̑�Ϗ����Ȉړ��͈͂Ɠ����ł��j�B
���x�������Ă��܂������A�����Y�����X�����Ă���C���[�W�T�[�N���͈͓̔��ł��邱�ƂƁA
�B���f�q���A�ǂ⎆�ƈ���āA��������������A����悤�ɋL�^����d�g�݂ł��邱�Ƃ��A�|�C���g���Ǝv���܂��B
���ꂪ�AK-7�̂悤�Ȏ��엦���قڊ��S�ɋ߂���100%�̋@��ł��A��U���̓��쒆�ł��A
���m���ŁA�L�^�����摜���A�t�@�C���_�̒��ōŌ�Ɋm�F�����\�}�ƁA�قڈ�v����A
�Ƃ������ʂɌq�����Ă���̂��Ǝv���܂��B����͂��ׂāA�̊��Ɩڑ��ŋC�t�������Ƃł��B
���̐����́A����ɂ����Ǝv���܂����A�ߋ��̑̌�����ł��̂ŁA�Ԉ���Ă��邩������܂��A
���߂��˂̌�b�́A�y���^�b�N�X��SR�ɂ́A���Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�܂��@�����A
���낢��Ǝ����Ă���������K���ł��B
���l�̌�������Ă��鑼�̊F����ɂ��A�ꕔ�A���̃��X�ɂāA���Ȃ�̉ɂ��������Ă��������B
�܂��A�L�����n�b�L�����Ă��܂�����A�⑫���邩�A�������邩�A�Ǝv���܂��B
�����A����SR�̎d�g�݂������m���Ă�����A�W����Ƃɂ������āA�s���S�ł��������Ă݂����Ƃł��傤�B
�����ԍ��F10881188
![]() 0�_
0�_
���L�̍��z�c����
����������Ă��邱�Ƃ̂قƂ�ǂ́A�܂������Ɠǂ�ł��Ȃ��̂ŁA�������Ă��Ȃ��̂ł����A
�Ō�́A�B���f�q�́i�����Y���O������ԂŁj���ږڎ����āA���m�Ȕ��f�͂ƂĂ��ł��Ȃ����낤�A
�Ƃ����̂́A���������Ă��܂��B
���́A�ނ���A�t�@�C���_�ł̌����ȍ\�}�̐Î~��B�e�Ȃ�A����B�e�̍ۂ̉t���Ȃ肩��̂ق����A
�ق�̂킸���ȁA�ʒu�u���������Ă��邱�Ƃ��A����₷���Ǝv���Ă��܂��B
�������A���ꂱ�����A�≖���ォ��B�e�Z�p����Ă������X�ɂ́A���Ɏ��o�Ȃ�
���ӎ��ŕ����Ă��܂��A��ς��肪�����@�\���Ǝv���̂ł��B
�y���^�b�N�X�́A��������ɂ��܂蔭�\���Ă��Ȃ��ł����A���ۂ̎g�p������A�������͉���͂��ł��B
�������Ƃ����\����A�ċz���~�߂���A�͂�����A�ȂǁA�����������@�ŁA���u����
������x�́A�h���邩������܂��A�y���^�b�N�X�̏ꍇ�A�l�Ԃ���ǂ����Ă��o�Ă��܂��悤��
���u���Ȉʒu�u�����A����Ă��邻���Ȃ̂ł��B
���̂��߂ɂ́A������������A�i���ʓI�ȁj��ԍ��W������o�����߂ɁA�������K�͂�
���u�Ȃǂ����A�ނ���A��U��̓����ɂ�荇�킹���A�v���O�����⍂�������m�ɓ���ł���
�\���i���͎��Ȃǁj���A���ۂ̌��ʂƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
������A���u���̈ʒu�u�����A�Â�MF�����Y�ł���ł���̂��Ǝv���܂��B
�����́A�����X�b�L�����Ă��邹�����A�������������ł��A�[���ł��闝���������Ă���C�����܂��B
���i�́A�u�����Ă���C�����܂��v�ł����A�Ƃ��ɐl�Ɍ����Ă�������悤�Ƃ��v��Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F10881218
![]() 0�_
0�_
�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̌���́A�����Y�̌݊������܂߂āA�≖���ォ�璷���J�������g���Ă������[�U�[���A
�������厖�ɂ��Ă��āA���A���������l�B�̎B�e���@��A�킸���ɋN����u���̓����Ȃǂ��A�����Ԃ�ƌ������������ł��B
�����āA�v��v���O�����Ȃǂɔ��f�����Ă���A�Ƌ��Ă����C�����܂��B
�i�����܂ł��A�������������ƁA�ł�����A�f��`�ł͏��������Ȃ��̂ł��j
���̍ۂɁA�≖����́A�i��̓����Ă��Ȃ��j�����傫�Ȗ]�������Y���g�p�����ۂ́A
�p�x�Ԃ���N�����ɂ����A�z�[���f�B���O�̎d�����A�g�U���U��Ő������Ă��������A
���̎������A���̃X���̍ŏ��ɁA���Ǝg�p�������������݂����������Aken-san����
�@[10858879]�@���j�Q�O�c�ɂl���S�O�O�������S�ōi��J���莝���B�e
�̂悤�Ȍ���́A�������Ƃ����t�H�[���f�B���O���o���Ă��邩�炱���A����������
�œ_�����ł��A���Ђ̃����Y���̕���g�p���Ă��A�����悤�Ɍ��ʂ��g���Ȃ���A
�u���Ă��Ȃ��ʐ^���B���̂ł͂Ȃ����A�Ə���Ɏv���܂����i�������Â��l�����Y�ł���ˁI�j�B
�������ۂ̎g�p�������������݂��������ĂȂ���A���͑傫�Ȓ��]�������Y�Ȃǂ��g���@�
�قƂ�ǂȂ����߁A�����������z�́A�����Ȃ������Ǝv���܂��B
ken-san����A�������̃X���b�h�͔`����Ă��Ȃ����Ǝv���܂����A�ēx�A�����������Ă��������B
���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10881378
![]() 0�_
0�_
�����́A�����܂ł��u�����Ă������Ɓv���A���w���ȉ��̕��͗͂ŁA�����Ă��邾��
��������ԗǂ��Ȃ��ł��B
PENTAX�������������ɂ���A������L���E���߂��A�����ɕ\������̂�MZ-LL����ł��B
���̋L������߂��Ԉ���Ă����ꍇ�͓��R�A�܂��A�����łȂ��ꍇ�ł��A
�����ɏ������ގ��_�ŁA�������ݓ��e�ɑ���S�ӔC��MZ-LL�������ׂ��ł��B
�Ƃɂ������̎咣���������ƌ����Ă����͂�������A���Ƃ�PENTAX�ɕ����A�Ȃǂ�
�J��Ԃ��̂́A���������Ǝv���܂��B
�������Ԃ����āA������킩��₷���������Ă�������Ȃ�A�����Ő������܂��傤��B
���ꂪ�A���������Ő������悤�Ǝv�����炵�ǂ���ǂ�A�m������Ȑg�U���
����ȒP�ꂪ�o�Ă����悤�ȁE�E�E�B���ȋL���Ɨ����A�ƁA�����g���F�߂��Ă܂����A
����Ŗ�����i�H�j�A�������ݓ��e���ł���߂������ꍇ�́A�������Ă��ꂽ����A
PENTAX�ɑ���Ȗ��f�������邱�ƂɂȂ�܂���ˁB
���̓_�́A�����g�ł͕s���Ɋ����Ȃ��ł����H
�L���◝�������₵����A���߂āA�u����������Ă���������Ƃ��A�ȉ��̂悤�ȕ��ʂ�
PENTAX�̐����Ƃ��Čf���ɏ����������Ǝv���̂ł����E�E�v�ƁA
���O��PENTAX�ɗ�����邭�炢�̐T�d���������Ă��ǂ��͂��Ȃ̂ɁAMZ-LL����̈�A��
�������݂́A���܂�Ɍy���Ŗ��ӔC�Ɋ����܂��B
PENTAX�ɕ����A�Ȃ̂�MZ-LL����ł��B�i�����łȂ��A���[���ŕ����Ă��������ˁB�j
�����ԍ��F10881396
![]() 16�_
16�_
���x�������Ă���悤�ɁA����̓X���b�h�̎�|�ł͂Ȃ��̂ł��B
�����g�����i�R����ROM���Ă�������ɁA�ł��Q�l�ɂȂ����̂́A
�����ɋ߂��B�e�Ȃǂł́A�l�̎g�p���ł����B
�����A�Z�p���̃E���`�N��A�����摜�������������Ă���ŁA�_���_�������悤�ȃX���b�h�́A
�ǂݔ���Ă��܂����B�����ǎ҂Ƃ��Ă��~�����̂́A���o��A���z�A���̌����痈��A
�u�`�Ǝv���v�u�`�Ɗ������v�Ƃ����A���ł��B�����āA�g�p�����J�����ƃ����Y�A������
��ʑ̂̏����A������₷���ł��B
���������Ӗ��ŁA�������������ƂƂ́A�قȂ��ӌ���g�p�����Ƃ��Ă��A��L��
ken-san����ɏ����Ă������������X�́A���ۂɃy���^�b�N�X�̋Z�p�҂̌���ɐ������Ă���ۂł��A
�C���[�W�Ƃ��āA�����ׂ��܂������A���ɏ�����܂����B����Ӗ��A�����ȃ��X�ƌ��Ⴞ�Ɗ����܂����B
���u���̈ʒu�u���������Ă���B���̏���ł��A���o���s�����Ȃ�A���@��p����
�����Ȍ����A���ۂɎ������g�łł���ł��傤���A���͂�����A���ꂼ��̕���
����Ă����Ηǂ��̂ł��B����ł�����Ȃ���A�y���^�b�N�X�ɖ₢���킹��Ηǂ��ł��傤�B
���ɂ���Ă��Ȃ��ł��낤�Ƃ����ނ̏��Ȃ̂ł�����A���ꂵ�����@�͂Ȃ��ł��傤�B
���������āA�����A�ǂ�Ȃɗ�ÂɂȂ��āA���Ԃ������ĉ�������Ƃ��Ă��A
���̏������ɕ����t���āA�{���������ɁA����̋�_�ŊԈ���������������ނ悤�Ȑl�B���A
�[������Ƃ͎v���܂���B����Ȃ��Ƃʼn����������x�̌���ł�����A���߂��珑������ł��Ȃ��͂��ł��B
�ޓ��i���̃��X�������Ă��鑊��������ł����j�́A�������G����l�b�g�ŏW�߂��������ƁA
������q�����킹�āA�s�ˌJ��āA���_�A���Ǝv���Ă������Ă���̂��A�ے肳��Ă��邩��A
�킴�킴�S�����āA��Ȃ����Ă���̂��Ǝv���܂��B���ɂ͂��������C���͉���Ȃ��ł����B
���͉������A���ۂɎ����āA���x�����߂Ă���A������̃X���b�h�𗧂��グ�܂����B
������A�͂��߂��玄�̈ӌ���������Ƃ��A�R���Ƃ��A�������ނ悤�Ȑl�B�́A
���ۂ�K-7�ŁA���x�����������̂ł��B���Ȃ��Ƃ��A���͖ڑ��ʼn����A���ꂪ�A
�����������ƁA���ɕ����Ă����̂ł�����B
�{���ɁA�Ⴂ�ȁA�Ɗ����܂��B
�����ԍ��F10881460
![]() 1�_
1�_
�����x�������Ă���悤�ɁA����̓X���b�h�̎�|�ł͂Ȃ��̂ł��B
�X���b�h�̎�|�łȂ��Ă��A���ꂱ�����x���APENTAX�̌䌾�t�Ƃ��āA�����Ȃ��Ə���������Ă�̂�MZ-LL���g�ł���B
�l�̎g�p���Ƃ��ĂȂ�Ƃ������APENTAX�̌�����Ăł���߂��������Ƃ́A
���Љ�I�A��PENTAX�I�s�ׂ�����A�܂�����Ȃ��H�ƁA���ӂ��Ă�̂ł��B
������x�BPENTAX�̐l�͐��������ƌ����Ă����Ƃ��Ă��A�����̗�����L�����Ԉ����
�����Ȃ����ƁA���̓_�́A�����g�ł͕s���Ɋ����܂��H�Ⴆ�A
�����l�̕��X�ɂ��A�Ƃɂ����A���s�����̃u���̕�A�Ƃ������Ƃ́A�����ɉ��������܂����B
����́A�ԈႢ�ł͂���܂����B
PENTAX���A�J�����̓����ɂ���Đ����鑜�̕��s�����̃u�����A���̃u����ł������`��
�f�q�s�i�c���j�ɃV�t�g���邱�Ƃŕ���܂��B���������Ӗ��łȂ�u���s�����̃u���̕�v�ł��B
�ł��A����������āuPENTAX�́i�p�x�u���łȂ��j�ʒu�u����v�Ƃ���AMZ-LL����̗����E���߂́E�E
�����ԍ��F10881625
![]() 6�_
6�_
��K-7�̂悤�Ȏ��엦���قڊ��S�ɋ߂���100%�̋@��ł��A��U���̓��쒆�ł��A
�����m���ŁA�L�^�����摜���A�t�@�C���_�̒��ōŌ�Ɋm�F�����\�}�ƁA�قڈ�v����A
���Ƃ������ʂɌq�����Ă���̂��Ǝv���܂��B����͂��ׂāA�̊��Ɩڑ��ŋC�t�������Ƃł��B
�m���ɂj�|�V�́A�L�^�����摜���A�t�@�C���_�̒��ōŌ�Ɋm�F�����\�}�ƁA�قڈ�v����m�����A�Â��@����オ���Ă��Ă���悤�ɂ킽���������܂��B
����́A�����[�Y�^�C�����O���Z�k���サ�����̂Ɖ����Ă��܂��B�V���b�^�[��������A����������܂��B
�����ԍ��F10881650
![]() 0�_
0�_
���g���C�|�b�h����
��ӌ��Ǝg�p���̂��������݁A���肪�Ƃ��������܂��B
K-7�̃t�@�C���_�Ŋm�F�����\�}�ƁA�L�^�����摜����v����m���������v���́A
���낢��ƕ������Ă���Ǝv���̂ł����A�g���C�|�b�h��������Ă���悤�ȁA
�@������́A�����[�Y�^�C�����O���Z�k���サ�����̂Ɖ����Ă��܂��B�V���b�^�[��������A����������܂��B
������A�����I�ȗv�f�̂����́A�ЂƂ��ƁA���������܂��B
�V���b�^�[���A�~���[�A�b�v���ŁA������~���[�V���b�N�A�k�������Ȃ������Ȃ��Ƃ������܂��ˁB
�����āA�V���b�^�[�{�^���́A�N���b�N���̓x�����Ȃǂ��A�J�����Ɋp�x�u�����N�����Ȃ����߂ɂ�
�i�Ƃ��ɉ�]�����̌X���i���[�����O�j�̔��u���Ȃǁj�A�l���͂���Ǝv���܂����A
�����g�́A���ɑ������悭�����Ă��܂��B�V���b�^�[���C�����悭�����̂ł��B
�i�o�N�ɂ��������Ă���A�̍��������ɏo�Ă��邩������܂��j
�������A�����g���A����܂ł̋@������A�\�}�̃Y���A�������̓Y���Ă��Ȃ����Ƃ��A
�m�F���₷���Ȃ����̂́A��͂�A�قڊ����ɋ߂����엦�ƁA�X������㉺���E�̈ʒu�Y���Ȃǂ�
�قƂ�ǂȂ��������ꂽ�i������̍��͑�������Ǝv���܂��j�t�@�C���_�̂��������ƁA�����������Ă��܂��B
�{���ɁA����{�̌덷���犴�����ɁA�t�@�C���_�m�F�����\�}�̒[�܂ŁA���m�ɋL�^����鎞�������ł��B
����́A���܂���ɂ���Ă��Ȃ��ł����A�y���^�b�N�X���g����`�ɗ͂����Ă��Ȃ��ł����A
���́A���̂悤�ȎB�e�̐l�ԂɂƂ��ẮA��ςɂ��肪�����@�\�ł���A
���ꂾ���̂��߂ɁAK-7�����l������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����v����قǂł��B
K20D���C�ɓ����āA�Q����������قǑ�R�g���Ă��Ă��܂����A���엦����95���ł��邽�߁A
�O�r�g�p���́A�\�}�ɑ��Ă̗]���̑傫�����A������x�A���m�ɗ\���ł��܂������A
�莝���ƂȂ�ƁA���������s�Ɉʒu�u���Ă���̂��A����Ƃ��t�@�C���_�Ɉʒu�Y��������̂��A
�������ɁA����{�Ƃ������x�ł́A�m���߂��܂���ł����B���O�{�Ƃ��A�ܗk�}��{�Ƃ��A
���������A���������A�̃��x���ł͉���܂����B
���撆�̂r�q�̓���Ɋւ��Ă��AK-7�̃J�^���O�ł́A�ق�̏����������Љ��Ă��܂���B
�������A���̎��r��g�̂��N�������u�������ʓI�ɕ���Ă���\�͂́A������
�傫����`���Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����H�Ɗ����܂��B
K-7�̐V�Z�p�A�������x�ȋ@�\�A���\���A�M�����ƃ{�f�B���ɋl�܂������̊������A
�����Ƃ������҂�ɁA�w�������҂̊F����ɁA�`���ė~�����ł��B
�g���Ύg���قǁA�������Z�p�������Ă���ȁA�Ɗ����Ă��܂��B�{���ɁB
���Ȃ݂ɁA���́A�≖����́A�L���m�������C���ŁA��́A�����Y�̗ǂ��R���p�N�g�@�Ƃ��A
�T�O�N�O�̌Â��֕��̃J�����Ƃ����g���Ă܂����B
������A�f�W�^������́A�y���^���[�U�[�̐V�Q�҂ł��B
�����ԍ��F10881729
![]() 0�_
0�_
�i�O�̃��X�̑����I�ȓ��e�ł��j
�����āAistDL2��K20D���w������ۂ́A���i�R���f���̏������낢��ƎQ�l�����Ă��炢�܂����B
�y���^�b�N�X�̑��쐫���̂́A���̏����O�ɔ�����Optio A30��A�����ƑO�ɒm�l����肽Optio 5z
�ł������Ă��܂������A�{�^���ނɁA�J�X�^���ݒ肪���蓖�Ă₷���ŁA�g�����肪�����Ȃ��A�Ɗ����Ă��܂����B
�t�@�C���_���U���̋@�\���AK-7�ɑ�������悤�ȋ@�킪�A���Ђ���� �����o��A
�w�����Ă݂����ȁA�Ɗ�����Ǝv���̂ł����A���́A���̋@����g�����ނ��ƂŁA
�ʂ̎d���Ŏg��EOS 20D�Ƃ̈Ⴂ��A�I�����p�X��E-1��E-500�ȂǁA�G���̌X����
���ӕ������ςŔ��f���āA�p�r���ʑ̂ɍ��킹�Ďg�������Ă܂��B
�����������ŁA����̂悤�ȁA�t�@�C���_�̈ʒu�Y�����N���ɂ������ƂƂ��A
�����Ȉʒu�u���������Ă��邱�ƂƂ��A����B�e�ł��A���Ȃ���ʓI�ɔ��u����
�ł������Ă��邱�ƂƂ��A�������Â��l�e�ł���A������x�͌����Ă��邱�Ƃ���A�����Ă����܂����B
K20D�����C���Ŏg�p���Ă���������A�ʒu�u���̗v�f�������u�����̕������Ă��邱�Ƃ́A
������x�Ŋ��o�ŋC�t���Ă��܂������A�����ł��m�����Ă�܂ł́A����܂���ł������A
�p�x�u�����Ƃ́A�u�����̈Ⴂ�Ɋւ��Ă��A�m��������܂���ł����B
�L���m���̃n�C�u���b�gIS�̋L����ǂ�AK-7������ƍw���ł��āA���ۂɎ������肷�邤���ɁA
����ƁA�n�b�L���Ɖ���悤�ɂȂ�A���������͂��낢��Ƃ���̂ł����A
���̃X���b�h�𗧂Ă��������ł��B
���[�J�[���A������ƌ��\���Ă��Ȃ����Ƃł�����A���Έӌ��͂����ē��R���Ǝv���̂ł����A
���̕����Ă������Ƃ��A���Ƃ��M�p�ł��Ȃ��Ă��A����Ƃ��Ăł������Ă݂邱�ƂŁA
���ʂƂ��āA����������A���x�̍����g�p���@�ɁA���ǂ蒅����q���g�ɂȂ邩������܂���B
�ǂ�ł���݂̂̕��X�ɂ��A�����������ƂŁA�����ɗ��Ă�Ί������ł��B
�����ԍ��F10881808
![]() 0�_
0�_
�܂��A���f�͂̂Ȃ��l���A�˂����݂�����Ȃ��ƋC�����܂Ȃ��悤�ł��̂ŁA�⑫���Ă����܂����A�A
�@������������āuPENTAX�́i�p�x�u���łȂ��j�ʒu�u����v�Ƃ���A
����Ȃ��ƁA�����ĂȂ��ł��B�p�x�u���������ł��傤���ǁA��{���ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ́A
���x���m���߂܂����B�����āA�œ_�������ʑ̂܂ł̋����ɂ���ẮA�p�x�u���Ɋւ��ẮA
�u���Ђ���̃����Y���̕�������ʂ��ア�ꍇ������܂����A�v�ƕ����A
�����āA�傫���v���]�������Y�ȂǂŁA��U���@�\�������������ォ��́A
�p�x�u�����N�����Ȃ��z�[���f�B���O�̘b�ɂȂ�܂����B
�������x�������Ă���̂́A�q���g�݂̂ł��B���̃X���b�h��ǂސl���Q������l���A
���������́A���m�ȓ����~�����Ȃ�A�����ł��낢��Ǝ����Ă݂Ă��������B
�ł��A���l�ɂƂ��ẮA�����Ă������ƂŁA�[���A�Ԉ�������̏������݂����Ă���l���A
�u�Ԉ���Ă���A������Ă���v�Ə������Ƃ͂ł���̂ł��B�v�_�͂������艟�����āA
���x���m�F���Ă��܂������A�����܂ł̎��̎��ۂ̌o��������̂ł�����B
�����ԈႢ������A�܂����S����B�e���Ċm�F���āA�������Ԉ�������Ƃ�[���ł���܂ŁA
�J��Ԃ������ł��B����������́A���������Ă������Ƃ��A�O��Ă��Ȃ��������Ƃ��A�悭����܂����B
�����A�����̓s�����ǂ��ق��ɁA�c�Ȃ��ď����̂͂�߂ė~�������̂ł��B
�����ԍ��F10881845
![]() 0�_
0�_
�����ł��B
�@���傫���v���]�������Y
�u�傫���d���]�������Y�v�̌�ϊ��ł��B�����܂���B
�����ԍ��F10881857
![]() 0�_
0�_
�����́B������܂̂��ŁE�E�E
�p�x�u����r���ăV�t�g�u��(�ʒu�u��)�������N�������@�A�l���Ă܂����B
[10879942]���Ƃ����"�͂���"���g�����@
[10880351]Tomato Papa����̃G���x�[�^�[�O�r�̃\�����㉺������@
���ӂ���̃A�C�f�A�A���肪�Ƃ��������܂��B
�m�b���i���Ďv�������̂��A����ȃe�[�u����2�{�̉~��(�~��)��Q�����ĕ��s�ɔz�u�A���̏�ɃJ������u���ē������ƁA���E�̓����̓V�t�g�u���ɂȂ肻���B�~���͊��d�r�ł��W���[�X�̊ʂł��C�C���ȁA���܂�c��ł���Ƃ܂������ȁB
���@�Ŏ�������͂ǂ����B
�X���b�h�{��� PENTAX K-7 �̎�u���h�~�@�\�ɂ��ẮE�E�E�B
�����ԍ��F10882416
![]() 0�_
0�_
���L�̍��z�c����
��[10881188]�̏������݂ł́A���������݂�����������A���̕��X�Ƃ̂��Ƃ��ʂ��ĂȂǂ́A
�S�̂�ʂ�������� �܂��ǂނ��Ƃ��ł��Ă��炸�A�䌾�t�̈ꕔ���݂̂ɑ��Ĕ�������
���X�������Ă��܂��A�\����܂���ł����B
�O�ɖ߂��āA���������݂�q�������Ă��������܂����B�M�d�Ȍ�ӌ��Ǝ��ۂ̎g�p���̌�A
���肪�Ƃ��������܂��I�@���͎����̐�啪��ȊO�ł́A��肢�\�����I�m�Ȍ��t���I�ׂȂ��̂ł����A
�L�̍��z�c����̂��������݂ł́A�����Ē����킯�ł͂Ȃ��̂ɁA��M���b��
�l�܂��Ă��銴�����܂����B���ۓI�ȕ������Ő\����܂���B
��M���b�Ƌl�܂��Ă���䂦�ɁA���x���J��Ԃ��q�������Ă����������̂ł����A
�܂��܂����̒m���ł́A�����̌o���ő̊����Ă��Ȃ������̕����Ȃǂf�ł����A
���������݂����������A���e�ɑ��āA���X�ł��Ȃ��Đ\����܂���B
�@���ʏ�̃����Y�̍ŒZ�B�e�����͏œ_����10�{���x�ł����牼�Ƀ����[�Y��5mm���ʒu�u�������Ƃ��Ă�
�@���K�v�ȎB���f�q�̃V�t�g�ʂȂ��0.5mm�ɉ߂��܂���B
������������A���̌v�Z�́A��{�I�Ȃ��ƂȂ̂�������܂��A�����B�e�̌o���Ƃ��āA
���̑f�q�̈ړ����A���Ƃ��������Ƃ��A�ʒu�u������ł���悤�Ȏ����͂���܂��B
�����Y�������Ă���C���[�W�T�[�N���̒��ŁA�f�q���{�f�B�̂킸���ȃu���ɑ��āA
���̍��W�ɗ��܂��Ă���A�Ƃ��������́A���͓���̃u���̎d���ɑ��ẮA���Ɍ��ʓI
�Ȃ̂ł͂Ȃ����H�Ə���ɐ������܂��B
�B�e���̃u�����́A�����ɂ̓n�b�L���ƕ������郂�m�ł͂Ȃ��ł��傤���A�L���m����
�u�V�t�g�Ԃꐬ���𑽂��܂ށv�Ȃ�ď��������A�f��`��������A��肢�\���̎d�����ȁA�Ȃ�Ċ����Ă��܂��B
�@���B���f�q�ɖڎ����ĕK�v�ȏ������Ƃ��v���Ȃ��̂�
�@
�{���ɁA�����Y���O������ԂŁA�f�q�̓�������Ă��A�����ꂷ���邵�A���������Ă������Ƃ�
�ے肷��ޗ��ɂȂ�Ƃ͎v���܂���B�@���ŁA���ۂ̑f�q�̓���Ɍ��Ȃ���A�L�^�����摜��
��r����Ȃǂ́A�o����P����ς��Ȃ�A�K�v�ȏ���ǂݎ�邱�Ƃ��ł��邩������܂���ˁB
��ӌ��ƌ���Ǝg�p���̂��������݁A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10882546
![]() 0�_
0�_
���X�b�]�R����������
���������A��U���̖{������A�������ꂽ�������s���ƁA�ςȌ��ʂ���߂����܂�āA
�{���Ɂu�Ƃ�ł����_�v����ʔ������Ă��܂��܂���B
�ނ���A�ʏ�̂�������ƍ\�����莝���B�e�ŁA��ʑ̂��H�v�����肵�āA���S���
�������ق����A���m�ȏ���ǂݎ���\���������Ǝv���܂��B
�������A����f���邽�߂́A���x�̍������o���K�v�ł����B
�������Ă��邱�Ƃ��A���x���w�E����̂͋C���I�Ɍ��Ȃ̂ŁA���̐l�B�ɏ����������A
�Q�Ƃɂ��Ă���������Ώ�����܂��B
�f�q�̈ړ��̕����Ɋւ��Ă��A�����Ԍ������Ă���悤�ł�����A
���̐��p������܂�g���ĂȂ��������݂ł�����
�����x�������Ă��܂������A�����Y�����X�����Ă���C���[�W�T�[�N���͈͓̔��ł��邱�ƂƁA
���B���f�q���A�ǂ⎆�ƈ���āA��������������A����悤�ɋL�^����d�g�݂ł��邱�Ƃ��A�|�C���g���Ǝv���܂��B
���̕ӂ�𗝉����Ă���������A�������y�Ȃ̂ł����B
�B���f�q���{�f�B�̈ړ���ł��������ɁA�u���܂��Ă���v�������ŁA���ړ�����̂́A
�y���^�b�N�X���T�C�g�Ȃǂōڂ��Ă���A�r�q�̓��������A�ςɒ��r���[�Ȓm������ŁA
�P���Ȃ��Ȃ��Ă��A����͂Ƃ���Ǝv����ł����ǂˁB
�܂��A���낢��ƍl���Ă݂Ă��������B
K-7�̓��惂�[�h���A�ł��邾���p�x�u�����N���ɂ����A�K�x�ɏ����������Y�Ŏ����̂��A
��ԉ���₷���Ǝv���܂��BFA35mm�����肪�ǂ��ł��傤���B50mm�̃����Y���c�݂����Ȃ��Ă悢�̂ł����B
�����ԍ��F10882636
![]() 0�_
0�_
�f�q�̈ړ��Ɋւ��Ăł����A�O�̃��X�ŏ��������Ƃ́A�����܂ł��A��{�̓���ł����āA
�p�x�u����A�œ_�������ʑ̂܂ł̋����Ȃǂ̏���������ۂ́A���Ԃ�A�����ʂ��
��{����ȊO�̗v�f���A�����Ă������ȋC�����Ă��܂��B
�^�J�����}�����A�J���҂̕��X�ւ̃C���^�r���[�ŁA��̃A���S���Y���́A
�����قǂɉ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�Ƌ��Ă���̂��A�Ȃ�ƂȂ�����܂��B
�����A�Z�p�̂ق��̐��Ƃł��Ȃ������A���̎d�g�݂𐳂����������̂́A�s�\�ɂ������ł��B
������A���������v���́A���ꂩ������Ȃ��ŗ~�����ł��B
�ʂɁA�����Ԉ���Ă���Ƃ��A���Ⴂ���Ƃ��A�S�̒��Ŏv���̂͂��܂�Ȃ��̂ł����A
���߂āA���̃X���b�h�ɏ������ވȏ�A���������A�����I�Ȑ��x�̍��������܂������ė~�����A�����v���܂��B
�����A�������āA���� ���x���������A�l�I�Ȑ����̂悤�ɁA�Ƃ�ł����_�́A�����炾���ď�����̂ł��B
�ł��A�������ɂ��������������̕��X������f���ł́A�T�������ł��B
���������Ă������Ƃ́A�������[�U�[�Ƃ��Ă̎g�p���ł��B�����āA����m�ȍ������Ȃ��A
�ǂ������玝���Ă����悤�ȏ���s�ˌJ����m���ŁA�ے肷�鏑�����݂�����l��
���܂�ɂ������̂ŁA���Ƀy���^�b�N�X����ɖ₢���킹���āA�����Ԃ̌�b�̒��ŁA
���x���A�ʒu�u���̕����{�ł��邱�Ƃ��A���������܂����B
���A�v���A�����ƁA�p�x�u����������x�́A�ǂ����ĕ�ł���̂��Ƃ������Ƃ܂ŁA
�L�`�b�ƕ����Ă���ׂ��������Ǝv���܂��B�ł��A�v�_�͍i�肽�������̂ł��B
�����āA���������ł���͈͂������������̂ŁB
K-x�̓h����g�ݗ��ĂɊւ��邱�Ƃ������Ă����������̂ł����A������́A���������A
�����A���m�����d����A�F�ʂɊW����d�������Ă܂�����A���Ƃ���Ȃ�Ɨ����ł��܂����B
����������ɗ����ł����킯�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B��ϋ����[����b�ł������A
�X���b�h�Ⴂ�ɂȂ�܂�����A�����ł͏����Ȃ��ق����悢�ł��ˁB
�����ԍ��F10882737
![]() 0�_
0�_
�����L�X�E�f�E�K�[��������
[10869362]�̂��������݂ł́A�������̌��肪�Ƃ��������܂����B
���̑O�ɏ�������ł������������X�̂ق��ւ̌�Ԏ��ł��B
�@���咣�ɑ��Ĕ��_���ꂽ���X�����x�����Ⴂ�ƒQ���Ă�����Ⴂ�܂������A
�@�����_�������̗��_�������Ȃ��̂Ɏ�ς𐺍��ɋ邲���g�̃��x����??
���́A���_�����Ŕ��_������ȂǁA�ѓ��������A�������ł���Ƃ��v���Ă��Ȃ��̂ł��B
���_�����A���ĈӖ��ł�����A���̃��x���́A�� �Ⴂ��Ȃ��ł��傤���H
�{���ɋ����Ȃ��ł����A�������ǎ҂ł�����A���������͓̂ǂݔ���̂ŁB
�ł��A�����u���o�v�Ƃ������t�ł��A���ɂƂ��Ă̂���́A���������傫�ȈӖ�������̂ł��B
������A���ꂩ����A�����̊��o�̐��x�����߂�ق��ɁA�W�����Ă��������Ǝv���܂��B
�����āA�������炠����x�A�����Ƃ��ē���ꂽ�����A���Ԃ����鎞�ɁA�����h��������܂��A
�ǂ�ł���ǂȂ����́A���������ɗ��悤�ȃ��m�ɂȂ�A�Ǝv���܂��B
����ŁA���܂�ɂ��Ԉ���Ă�����A������Ă����肷�鏑�����݂������̂ŁA
���������t���g�킹�Ă��炢�܂����B
�ʂɈ��҂ɂȂ������āA������ł��B�^���̂ق����d�v�ł��̂ŁB
�䏕���Ǝ���Ă����܂��B�������݁A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10882878
![]() 0�_
0�_
�������ɁA�������������X��ǂނ̂ƁA�������݂��R������A�ւƂւƂɂȂ�܂����B
�������d���ł��̂ŁA���낻��x�e�������Ǝv���܂��B
���C���������������̂ɁA���X�ł��Ȃ������F���܁A�\����܂���B
����܂ł̏������݂����Ă���������Ή���Ǝv���̂ł����A���������������ƂƂ����A
�������������Ȃ�A���Ԃ��Ȃ����ł��A�Z�������ł��A����Ȃɑ�ςł͂Ȃ��̂ł����A
���X��摜��q�������Ă��������āA����ɑ��Č�Ԏ�����ق����A���W���͂��A���̏ꍇ�A�K�v�Ȃ̂ł��B
�����͂��������x�݂Ȃ̂ŁA�ǂނق��𒆐S�ɁA�����Ԃɓn���āA���x���q�������Ă��������܂����B
���݁A�O�قǏ����r���̃��X������̂ł����A�^�C�~���O������A����͎����z�������Ă��������܂��B
���������͂��A�Ȃ�ł��A�b�v���Ă���̂ł͂Ȃ��A����܂ł��A�P�O��قǁA���ɑ��āA
���E����ȏ������݂������l�ւ̃��X��A�y���^�b�N�X����ŕ����Ă������Ƃ̏ڍׁA�Q�ƂɂȂ肻����
�T�C�g�̂��ƂȂǁA�������������ŏ��������̂��A�f�������A��������H�������܂܂ł��B
�������Z�����Ȃ�܂����A���낢��Ƒ�ςȂ��Ƃ��v���C�x�[�g�ł��N���Ă���̂ŁA
���ꂩ����A�����Ƃ������X�͂ł������ɂ���܂���B
�Ƃɂ����A���̊��z����́A�q���g�ł����Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���ꂼ��̕��X���A
�������玎���āA��������������A�������Ă���������K���ł��B
�ꕔ�A�ςȂ̂��o�v���Ă܂����A����ȊO�̕��X�́A�������݂��肪�Ƃ��������܂����B
�i���̏������݂��ׂĂɔS�����邽�߂��A�t�@���ł������̂ɁA�t�@���o�^�́A���Ђ�߂Ă��炢�����ł��B
���ɋC���������ł��B���͏��S�҂ł��̎d�g�݂��悭����Ȃ��̂ł����A�o�^���ی��@�\�͂���̂ł��傤���c�j
�����Y�������āA���X���폜����Ă��܂��̂́A�����������Ȃ̂ŁA�����܂��B
���炩�Ɍ�����Ă������A�r�炵�I�ȏ������݂�����l������܂�����A�ǂ����g�p�����ŁA
�������������ƂƁA�܂������Ⴄ���ƂȂǂ̌�ӌ������������Ă��A���������A��ÂɑΉ��ł���Ǝv���܂��B
����ł́A�܂��A�ǂނ��Ƃ��̂��̂��A���Ȃ��ςł��B����ł́A���炭���炢�����܂��B
���̎v�킸�����Ȃ��Ă��܂����X���b�h���A�ǂ�ł��������Ă�����X���A���肪�Ƃ��������܂��I
�����A�����̖��ɗ����܂��悤�ɁI
�����ԍ��F10883002
![]() 0�_
0�_
������A�\�̃I�����p�X�̐V�^�@�A�������\�ɂȂ��Ă��邵�I�@���x�ꂽ���I
���R�[������A�V�^���I�A�A�A�B
�X����Ȃǂ���Ă���ƁA�ǂ�ǂ����ꂵ�Ă������������܂��c�B
�����ԍ����\�������������Ă����Ǝv���Ă��A�܂��܂������T�C�N���ŁA�V���i�͏o�Ă��܂��ˁB
K-7�̊J���҂̊F������A��p�@���ǂ������X�y�b�N�ɂ��邩�A�ǂ�ȋ@�\���l�ߍ��ނ��A
�R���Z�v�g�����߂�̂��A�v����̂��A���T�[�`����̂��A��ς��Ǝv���܂��B
����������Ɠw�͂̌����̂悤�ȃJ�������Ɗ����܂��BK-7�́B�������A�p�r�ɂ���ẮA
���_������܂����A����������ł��傤����A�l�ɂ���ẮA�S�R�悭�Ȃ��J������������܂���B
�����A���܂����̗p�r�ɂ́A�����Ă����݂����ł��B
�V���i�̏������Ă���A�x�ނ��ƂɕύX���܂����B����ł͂��I
�����ԍ��F10883052
![]() 0�_
0�_
�y���^�b�N�X�́A�r�q�Ɋւ�����J����������܂����B���Q�l�܂łɁB
http://kantan.nexp.jp/kouhou.html?kh=A/2006/86/2006171286&kp=pdf
������̃y�[�W10�́A����0034����ꕔ���p���܂��ƁA
�f�W�^���J����1�Ɏ�U�ꂪ������ƁA��U��ɂ��B�e�����Y����O �̊p�x�U��ɂ��摜�̗h���ł������悤�Ɏ�U�����s����B
�c�c�c�i�����j�c�c�c
��U�ꂪ�����āAX�����p���x�Z���T201��Y�����p���x�Z���T202����������m����ƁACPU50���ϕ���H�Ƃ��ē���
�c�c�c�i�����j�c�c�c
���Ȃ킿�A��U��ɂ�����O�̊p�x�U��ʂɒǏ]����CCD3��XY�����ɋ쓮����A��U��ɂ��CCD3��̑��U�ꂪ������B
�p�x�u�������m���āA����Ă���A�Ƃ����Ӗ��Ɏ��͂Ƃ�܂��B
�����ԍ��F10883147
![]() 13�_
13�_
F-47����A�����S�R���ǂ���Ȃ����������̏��A���肪�Ƃ��������܂��I
�䎩�g�̎�ł����ׂ��������A���ӂ������܂��B
��ϋ����[�����e���������߁A�܂��̓U�b�Ɣq�������Ă��������܂����B
���̓����̕��͂��A���������ǂ��������Ƃ������Ă���̂��A�{���I�ɂ͎��͉���܂���B
�����A���ʓI�ɁA���������Ă������Ƃ╷���Ă������Ƃ��A�Ȃ�ƂȂ��ł����A
�ؖ�����Ă���悤�ȋC�����܂����B
�m���ɁA�ʒu�u���A�Ƃ������t�͖��������ł����A���A�U�b�Ɠǂ����ł́A�������܂���ł����B
�ł��A�u�U���Z���T�[�v�Ȃ�P��������܂����B�ǂ����R�����A���u���̈ʒu�u����
���ʓI�ɕ�����ŁA���ɂȂ��Ă���Z���T�[�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���������A���Ԃ����鎞�ɂł��A�������q���������܂��B
������A������x�A�ǂݒ����܂��B��O���ł����A�������������������[���ł��B
�����N�A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10883322
![]() 0�_
0�_
�����Ɋւ��āA�܂��U�b�Ɠǂݒ������Ă��������Ă܂��B
�����p�x�u�������C���ł�����A�����Ɓu�X�����m����i�Z���T�[�j�v�Ȃǂ�
�P�ꂪ�o�Ă��Ă��ǂ��C������̂ł����A���Ɂu�U���v�Ƃ����P�ꂪ�����Ȃ��ł����H
�@���J�����{�f�B�̐U�������o����U�����o�Z���T
�@����L�ړ��̂��J�����{�f�B�ɑ��āA���ɏ�L�����ƒ��������݂��ɒ�����������
�@���w �����y�тx �����ɒ����I�ɑ��Έړ������鎥�͔������u��
���̕ӂƂ���������܂����A�悭����Ȃ��̂ł����A�ǂ��ł��傤�B
�����ԍ��F10883437
![]() 0�_
0�_
�ȉ����p ----------------
�@�w �����̊p�x�U������o����w �����p���x�Z���T�i �U�����o�Z���T�j
�@�x �����̊p�x�U������o����x �����p���x�Z���T�i �U�����o�Z���T�j
���p�I�� ----------------
����̎��ł��B
�����ԍ��F10883494
![]() 7�_
7�_
���́A�����Ȃǂ̂������������Ȃ��������͂�^���ɓǂނ̂́A���߂Ăɋ߂��o���Ȃ̂ł����A
���Ȃ�ʔ����ł��ˁB�S�R�u����v����Ȃ��̂��A�V�N�ł��B
���̐�啪��A�Ƃ��������̐��E�ł́A�M��������v��������ł��邱�Ƃ��A
�u�˔\�v�ƌĂԂ��Ƃ������ł��B
�N��ɊW�Ȃ��A�������̂��ƁA�\���Ɋւ��ẮA���Ȃǂ��ƂĂ��y�Ȃ��قǂ�
�˔\�����l���A�m�l�̃A�[�`�X�g����吶��A�����̂Ƃ��̐��k����̒��ɋ����肵�܂��B
������A���́A���������l�B���A���������h���Ă��܂��B��������\�͂��������l���A
���Ƃ����_���������Ƃ��Ă��A���́A���̒�����L���悤�ȁA�w�������Ă�������ł��B
�ȂA��ꂪ������т܂����B�������ʔ����ł��I
��Љ�A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10883504
![]() 0�_
0�_
���̒��x�̓����͊ȒP�Ɍ����\�ł��B��ʂ̐l�ł���������HP����T�������\�ŁA������������܂���B
�������A���̕��͂͐R���������������Ȃ̂ŁA�����ł͂���܂���B�P�Ȃ���J�L��ł��B
�����͏o�肩��V�N�ȓ��ɏo��҂�����������ׂɓ������R���������N�����˂Ȃ�܂��A���̕��͂͏o�肩�炷�łɂT�N���o�߂��Ă��܂��B
����̂ɕ��ʁA���̎�̕��͂́A�P�ɂV�N�Ԃ̎��ЋZ�p�̖h�q�ɉ߂��܂���B
�������A�R���A�������P�͎�Ԃ��������Ă܂���ˁB
�����Y�쓮�ł͂Ȃ��A�摜�f�q���uAF�R�C���v�Łu�����Y�����ɕ��s�v�Ɂu�쓮����v���������B�Ə�����Ă��܂��B�iAF�@�Ƃ͏�����Ă��Ȃ������~�\�����j
�������Q�ŏ��߂Ď�Ԃ����o�Ă���̂ŁA���̕��͂́uAF�R�C���v�Łu�����Y�����ɕ��s�v�ɉ摜�f�q���u�쓮����v�u���v�Ŏ�Ԃ����o�����Ⴂ�܂����B�ƌ����ʒu�Â��̗l�ɓǂ߂܂��B
�y���^���F�X�Ɩh�q���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��˂��B���������@�\�̓R���^�b�N�X���t�C�����J�����Łi�t�C�����������Y�ʂɑ��đO�コ����A�ƌ������@��AF�J�������o���Ă����j���Ɏ����ς݂Ȃ̂ŁA���m�̎����A�Ƃ��āA�R���������Ă��p�������̂��ւ̎R���Ǝv���܂��B
����̂ɂ��̕��͂�MZ-LL�������������Ƃ͈Ⴄ�l�Ɋ����܂��B
������u�p�e���g�y���f�B���O�v�̗l�����܂��܂��Z���ł��ˁB�������A���������ȂA�ǂ��Ƃł�����l�ɁA�L�������̂���ʓI�ł�����A�d���Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F10883553
![]() 0�_
0�_
���ۂ������A���X���肪�Ƃ��������܂��B
��O���ł��̂ŁA���낢��ƎQ�l�ɂȂ�܂��B
�������m��Ȃ����E�̂��ƂɂȂ�ƁA�{���ɕʂ̒m�������������X�́A�����肪�����Ȃ�܂��B
���ۂ̓����Ƃ͈Ⴄ�Ƃ��Ă��A���ɓǂނ̂��ʔ����ł��B
�Â����p�̂��ƂȂǂׂĂ���ƁA�d�����A�Õ����̂悤�ȃ��m���ǂ܂Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł����A
���̖ʔ����Ɏ��Ă��܂��B
��ӌ��ƌ���A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10883615
![]() 0�_
0�_
���������A���܂藝���ł��Ă͂��܂��c�Q�l�Ƃ��ẮA�m���ɋ����[���Ǝv���܂��B
����́A�R�C�����g���āA�f���f�q����w�f�q���쓮����Z�p�ŁA�����AF�쓮���͎�Ԃ��Ɏg�p�����ꍇ�ɂ��ď�����Ă���悤�ł��B
�Ȃ̂ŁASR�ɂ����̓����͎g�p����Ă���c�Ɖ��߂��Ă܂��B
�U�����o�Z���T�́A�����炭�W���C�����[�^�[���w���Ă���Ǝv���܂��B
���l�ɁA�u��Ԃ��@�\�t���J�����v�Ɋւ�����J����������܂����̂ŁA����������Q�l�ɂȂ�܂�����B
http://kantan.nexp.jp/kouhou.html?kh=A/2006/31/2006293131&kp=pdf
6�y�[�W�A����0020������p���܂��ƁA
�J���������ɂ́A��Ԃ�����o���邽�߂̃W���C�����[�^20A �A20B���݂�����
����A�W���C�����[�^20A�A20B�́A���ꂼ��J�������s�b�`���O�A���[�C���O����Ƃ��̊p���x�����o����B
�Ƃ���܂��B�s�b�`���O�A���[�C���O�́A���̏ꍇ�J�����̍��E�㉺�̌X���ƍl������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10883708
![]() 0�_
0�_
���݂܂���A���ׂĂ݂���A����͌��J����ŁA�o��̓��e���f�ڂ���Ă��邾���ŁA��������邩�ǂ����͖��炩�ɂ���ĂȂ��݂����ł��B
�Ȃ̂ŁA���ꂪ���ۂɓ����ɂȂ��Ă��邩�ǂ����́A�킩��܂���B
�����ԍ��F10883769
![]() 0�_
0�_
F-47����A�����J�ȕ⑫�������肪�Ƃ��������܂��B
���������A���P�l�ł́A�܂��������Ȃ����ł��B
F-47���A�䎩�g�łł��邱�ƁA���Ԃ������Ē��ׂĂ������������Ƃ��A
���̂悤�Ȗ�O���ɁA�Љ�Ă����������̂��A��ϊ������̂ł��B
���̒m���Ɍq����Ƃ��ɑ�ώQ�l�ɂȂ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�{���ɁA���낢��Ȍ��t���o�Ă��āA�Q�l�ɂȂ�܂����B
�܂����߂āA�q�������Ă��������I
�����ԍ��F10883809
![]() 0�_
0�_
�����܂���A�u���J�ȁv�̊ԈႢ�ł��B���炢�����܂����B
�u���v���t���Ă��܂��ƁA�����ȈӖ��ɂƂ�Ă��܂��āA����ł��ˁB
���J���v���ȕ⑫�A���肪�Ƃ��������܂����I
����͂����o�b��܂��B����������������F����A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10883840
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����A����ɂ��́B
������ROM���Ăċ^��Ɏv�������ƂȂ�ł����A
MZ-LL����[10869416]�Ȃǂŏ�����Ă�
>�{�f�B���قڊ��S�ɕ��s�ʼn��ɂ킸���Ɉړ������Ƃ���A�r�q�ł͎B���f�q�́A
>�i���ʓI�ȁB���w�E�x�j��ԍ��W��ŁA���̂܂܂̈ʒu�Ɏc���Ă���͂��ł��B
�Ƃ������Ƃ́A�����Y�����Ɉړ����Ă��B���f�q�͂��̋�Ԉʒu�ɂƂǂ܂��ē����Ȃ����߁A�f���̓u���Ȃ��Ƃ������Ƃł���ˁB
�Ƃ��낪
[10881188]�ł�
>���̍ہA�s���z�[���̑���ƂȂ�A���̃����Y�̃x�X�g�Ȉʒu���A���s�ړ������Ȃ���A
>���߂��Ƃɂ��A������܂������A������̔��������C��ƂȂǂ�����Ă��܂����B
>�����Y�̈ʒu���ς��ہA��Ɉړ�����A�ǂɉf���o���ꂽ��ʑ̂̍\�}�͈̔͂��A���Α���
>�g���~���O�Ƃ������A�\�}�̒��g���ړ�����̂́A�{���̂��Ƃł��B
���ꂾ�ƁA�����Y���ړ�����ƕǂɉf���o���ꂽ��ʑ̂̍\�}�������A�܂�B���f�q��������ԍ��W�ɗ��܂��Ă���ƃu���Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�܂�AMZ-LL����̑̌����炷��ƁA�����Y���������Ƃ��͎B���f�q�������Ȃ��ƃu���Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
(�����������ǂ��炩�͂Ƃ�����...)
�����ԍ��F10886032
![]() 10�_
10�_
���f�B�[�G�X�V�[����
���A�A�������Ȃ̂ł����A������x�A���̑O��̃��X��ǂݒ����Ă݂Ă��������B
���낢��ƌ�����Ă��܂��B
�s���z�[���J�������A���̂܂܂r�q�ɒu�������Ă͑ʖڂł��B
�����͉��x���A���͏����Ă��܂�����A
�B���f�q�́c�@����@�Ƃ������Ă���̂��A�Q�Ƃ��āA
������x�A�����̒��ŁA���A���ɑz�����Ă݂Ă��������B
�ǂ����Ă�����Ȃ���A�����A���Ă��钆�A��Ԃ������āA
�������Ă����܂��܂��A�����Ɠǂ�ł����A����Ǝv���܂��B
�ǂ����Ă�����Ȃ���A�܂���������ł��������B
�B���f�q�́A�s���z�[���ɒu���ẮA�u�ǁv�ł͂���܂���B
�ǂɉf�鑜�́A�����Y�̎��ő�̃C���[�W�T�[�N�����̂��̂Ȃ̂ł��B
�����ʂ�u�~�`�v�ł����ˁB
�r�q�̎B���f�q�́A�����Y�̃C���[�W�T�[�N���̓����́A�鑤�̃{�f�B�̃T�[�N���̒��Łc�B
�����A�قړ����������Ⴂ�܂����B
���́A�\��A��\��A���|�p�������̕����Ă��āA���Ȃ����w�����w���x���ȉ��Ȃ̂ł����A
�Ȃ��A����Ȏ����A�������Ă����ł��傤���c�B
���������A�������āA���₷��O�ɁA�����ōl���܂��傤�B��肢���܂��B
���w�Ƃ��A���w���̎��A�ق�ƂɂR�O�_�Ƃ��������Ȃ�������ł����ǁc�B�߂����v���o�ł��c�B
�i�ł��A�Õ���Ƃ��͑f�l�̑�l�����A�����Ə�肩�����͂��ł��c�j
�ق�ƂɁA�|�p�n�̂��Ƃ�������Ȃ���ł����ǂˁB�Ȃ�Ŏ����c�B
�����A�����ł��܂�����A�ȒP�ȕ��������B
ROM���Ă������������Ƃ��̂��̂́A�������������̂ł��B���肪�Ƃ��������܂����I
�i�������A���Ⴂ���Ă��鎿��ɁA�i�C�X�I���[������A���i�R���̃A�J�E���g�o�^�҂̒���
�ꕔ�̐l�̗���͂�l�@�͂��āc�B�j
���́A��������₷������p�ӂ��Ă���܂��B����ł͂��I
�ł��A�������̗͂ŋC�t�����ق����A�����ƋC�������ǂ��ł����A�������m���ɂȂ�܂���I
�����ԍ��F10887252
![]() 0�_
0�_
�@���B���f�q�́A�s���z�[���ɒu���ẮA�u�ǁv�ł͂���܂���B
�ԈႦ�܂����B
�@���B���f�q�́A�s���z�[���ɂ����ẮA�u�ǁv�ł͂���܂���B
�����܂���A�����͓��ɖZ�����u�`�̓��ł͂Ȃ��̂ł����A����ł�����ς�ւ�ւ�ł��B
��x�A�x�݂܂��B
�����ԍ��F10887289
![]() 0�_
0�_
��������������A�≖���ォ����t���g���Ă���̂ɁA��������܂܂̐l�B���A
�����A�ǂ�ł���A�ꏏ�ɍl���Ă݂Ă��������B
�t�B�����ɒu�������Ă��邩��A�������ĉ���Ȃ������̂�������܂���ˁB
���̌��Ɋւ��ẮA���Ǝ��̌���������A�P���Ȏd�g�݂ł�����A
���ł��A����₷���������v���t���܂����B����������̂͊ȒP�ł����A
�����̓��ōl���āA�������āA�[�������ق����A���ꂩ��̐l���ɁA�����͖𗧂��Ƃ����邩������܂���B
�s���z�[���̌����f���Ă���A�V�n�������܂́A�@�ǂ̉~�@�A�@����́A�����Y�̍ő�̃C���[�W�T�[�N���B
�ǂ��ł����H�@���ƁA�q���g���A�P���Q�� �����A�N�ł������Ă��܂��܂�����A
���������Ȃ̂ŁA�����ŋC�t�����ق����ǂ��ł���I
���炭�A�����̒��r���[�ȗ������A�^���������A��������ł������X�A
�Ӎ߂��A�������A�����ɂ���Ă���������Ȃ�A�����Ă��������Ă����v�ł���B
����ł́A��낵����肢�������܂��B�E�ƕa���ȁ[�B
�����ԍ��F10887331
![]() 0�_
0�_
�@
MZ-LL����
�@��}�̊��z�������Ȃ������̂ŃJ�L�R�������܂��B
�@�����ȃV�t�g�u���̕���s���ƃ����N��̗l�ȓ���ɂȂ�Ǝv���܂����A�������ł��傤���H
�@http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/ImageID=560784/
�����ԍ��F10887353
![]() 4�_
4�_
���ƁA�u�g���~���O�Ƃ������\�}�̒��g���ړ��v�A���Ă̂́A���낢��Ɖ��߂ł��Ă��܂��܂�����A
���������������܂��A�u�\�}���ς��v�Ƃ������t�̂ق����A�V���v���ŁA����₷����������܂���B
���g���ړ��A���Ă����A���e���ړ��A�Ƃ������A�Y����Ƃ������A
���[�ށA�����͏�����������̂ŁA�s���z�[���̌����Ȃǂ��A�܂��������Ă݂Ă��������B
�ނ���A�����������v�������A�ȒP�ȍޗ���p�����A�s���z�[���̕ǂ�
�����̂ق����A�킩��₷���ł��傤�B
�ł��A����������Ă��܂����A�����ōl�����ق��������Ǝv���܂��B
�}�Ȃǂ��쐬���Ă܂ŁA�킩��₷������������C�́A���͂���܂���B
���������X���b�h�ł͂Ȃ��̂ł����A������Ă���l���A��ʔ����������̃X���ł́A
���傤�Ǘǂ��@�������܂���ˁB
�����ԍ��F10887394
![]() 0�_
0�_
������̃��X�́A�f�B�[�G�X�V�[����@�ɑ��Ăł��B
���̏������݂����p����Ă����̂ŁB
���̂ւڂ��q���g����A�����Ă���������l������Ǝv���܂��̂ŁA
�Ȃɂ��̖��ɗ��ĂȁA�Ɗ����܂��B
�ł́A�����x�݂܂��B
�����Y�̂��A�ő�̃C���[�W�T�[�N���H���A�ǂɉ~�`�ʼnf���Ă��邱�Ƃ́A
�厖�ȗv�f�Ȃ̂ŁA�Y��Ȃ��ł��������B
�����āA�B���f�q�́A�ǂł͂���܂���B�����Ɓc�@�@�B
�����ԍ��F10887415
![]() 0�_
0�_
�������������������ŁA�����̐l���������Ă����݂����Ȃ̂ŁA
���w�H�̐������d�g�݁i�f�l�̎��ł�����͈͂̂��Ƃł����j�𗝉����邽�߂�
�菕���ɂł��Ȃ�A�q���g���o�����Ă����������b�オ����Ƃ������̂ł��B
�ǂɉf���Ă���f���i�s���z�[���\���̒��ɓ���ƁA�Î~��łȂ������Ԃł��j���A
�V�n�������܁A�Ȃ�Ă̂́A�{���ɓ�����O�̊�{�I�Șb�ŁA���������Ⴂ������́A�������Ɏ��ł����܂���B
�ł��A���̃X���b�h�����Ă��āA����Ӗ��A�ʔ��������̂��A�����������܂ɂȂ邱�ƂƁA
�ʂ�͈͂��������܂̏�ԂŁA�����Y��{�f�B�����s�ɓ����A�ǂ��ς�邩�Ƃ������Ƃ��A
���낢�낲����܂��ɂ��āA������Ă���A�Ƃ����l�q�ł����B
�N�C�Y�̂悤�Ȃ��Ƃ��A�₢�����Ă����l�����������Ă���̂́A���������o�����O�Ŋ����܂����B
�������ޑO�ɁA�ł���A��[����[���A�l���Ă݂�ƁA��������Ǝv���܂��B
�����āA�Ԉ���Ă������ƂɋC�t������A�ł���A�����̏������݂����܂��傤�B
���Ɍ����Ăł͂Ȃ��Ă悢�ł�����A�ǂ�ł���l�Ɍ����āA���߂āu���炵�܂����v�Ƃ��A
�������ق����ǂ��C�����܂��B�������ȏ�A�ӔC�������ė~�����ł��B
��낵����肢�������܂��B
�����ԍ��F10888390
![]() 0�_
0�_
������܂ő������A�������]���邱�ƂƁA�f�q�̓����Ɋւ��Ẵ��X�Ƃ͕ʂɁA
�l�l�̃u���O�ł����A�p�x�u���Ƃ��ʒu�u���Ƃ������������Ƃ́A���m�ȓ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł����ǁA
�����C�u�r���[���́A�w�ʉt���ł̕���ʂ̊m�F�ɂ��āA
�uPhoto of the Day�v�ɂāAK20D�̂k�u��c���J�����}����������Ă܂��ˁB
http://thisistanaka.blog66.fc2.com/blog-entry-240.html
������A�g�p���ł����āA�ǂ��炪�������Ƃ��A���������ނ̘b�ł͂���܂��A
�����A���ɍׂ��������ŁA�莝���ł̓���ŁA���u���������Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B
��������A��i�W�̉��B�e�ɂāA����������܂����BA50mmF2��DAL18-55mm�Ƃ����A
�����Ƃ��������G���g���[�ȃ����Y�ł��B���Ƃ��ƎB�e�̗\�肪�������ł����̂ŁA
�����ɋA��ۂɃJ�o���ɓ���Ă��������Y�����ł��B�����́A�O�r����[�Y���g�p���ẮA
�{�i�I�ȎB�e�ɂȂ�\��ł��B�͂��߂�K20D�Ƃ̃R���r�̂Q��̐��ōs���܂�
�i�ʂ̑g�ݍ��킹�ŁA�Q���R����������ނ��Ƃ͂���ł������j�B
�������B�e���Ă���ԁA�����Е����A�Ⴂ�A�[�`�X�g�ɑ݂����Ǝv���܂��B
���l���g�������ɁA�ǂ�������̂��A������Ɗy���݂ł��B
�P���ɃJ������݂��o���̂́A��������Ă���̂ł����A���̏�łǂ��g���Ă���̂���
���邱�Ƃ́A���܂肱��܂ł���܂���ł����B�@�����āA�V�����ق���K-7��݂��Ă݂܂��B
�����ԍ��F10888542
![]() 0�_
0�_
�X����ǂ�Ŋ��������Ƃ����X�B
�����Y��`�����Ƃ��A���̂܂܃����Y���㉺���E�ɕ��s�ړ�������ƁA
�ڂ����Ȃ���t���܂ɂȂ������̓����Y�����������ɓ����܂��B
����͒m���◝�_�ł͂Ȃ��A�N�ł������Ɏ��؉\�Ȏ����ł��B
���̎����́A�B���f�q�����ʒu�ɕۂ��ƂŃu����h�~����Ƃ����A
MZ-LL����̘_�ɔ�������̂ł��B
�iMZ-LL����̌����Ƃ���ł���A�����Y�����Ă����͓����Ȃ��͂��ł��j
���̎����ɂ��āA�ǂȂ�����������Ă����Ǝv���̂ł����A
�c�O�Ȃ��ƂɁAMZ-LL����͖������ꂽ���C�t���Ȃ��������A���̔����������Ă���܂���B
�V�t�g�u�����p�x�u�����A����MZ-LL����̂悤�ȗD�ꂽ���o���A
���̕��̂悤�ȖL�x�Ȓm��������܂���̂ŁA�����ɂ͌��y�ł��܂��A
��L�����ɖڂ�w���Ă��邱�Ƃ��AMZ-LL����̗��_�̐M���������痎�Ƃ��A
�ꕔ�̕s�v�Ȋ���_��ł����̗v���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�ߋ��ɂ�������MZ-LL����̏������݂������Ƃ��ɂ́A
���ɗ�ÂŁA�_���I�Ȉӌ��������Ă���l���ȂƂ�����ۂ������̂ł����A
���̃X���ł͂���Ƃ͈Ⴄ��ۂ��܂��B
�Z�p�I�Șb���ɂ���AMZ-LL���������ʂ�ʼn��߂��Ė��Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B
��Ȃ��Ƃ͂ǂ�Ȏ�ނ̃u�����ǂ�����Ėh�����ł͂Ȃ��A
�������B��ʐ^�̕i������ɁA�ǂ�ȍv�������Ă���邩�A�ł�����B
�P�ɁA��U�������̈Ⴂ���݂Ȃ���͂ǂ������܂����H
�Ƃ��������̃X���ł�����Ԃ����͋N���Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ē��ł������Ȕ��_����ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�������Âɓǂݕ�����w�͂�ӂ��Ă��邱�Ƃ��A���͔��Ɏc�O�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F10888824
![]() 17�_
17�_
��ask-evo����
�����Y�⒎�ዾ��`������ԂƂ́A�Ⴂ�܂��̂ŁA
������x�A�{���Ƀs���z�[���J�����̍\�����������₷���Ǝv���܂��̂ŁA
���ׂĂ݂Ă��������B�����A������Ă�����ցA�������Ȃ������背�X���Ȃ��̂́A
�ł���A�����ŋC�t���Ăق�������ł��B
���e�����ǂ��A�B���f�q�ł͂���܂���B�������F����������Ă��܂��B
���J�ȕ��̂ŏ�������ł������������Ƃ́A���ӂ����Ă��������܂��B
�s���z�[���̋�Ԃ��킩��₷���Ǝv���܂��̂ŁA������x�A��l���������������B
�ő�̃C���[�W�T�[�N�����̂��A����邱�Ƃ́A�Ȃ�̖��ł��Ȃ��̂ł��B
�m��������ƁA�������ē���̂�������܂���B
�ǂ܂�Ă�����X�̒��ɂ́A������O�̂悤�ɗ������Ă���l������Ǝv���̂ł����B
�Ȃ����A�������݂����l�������肪�A�����̌���ɋC�t���Ȃ��B
�s�v�c�Ȍ��ۂ��N���Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F10888868
![]() 0�_
0�_
�{���̓��́A�������ł͌��܂�܂���A���ЁA�������݂̕��͋C���炭��A
����ς����܂苭���������A�����o�����q���g����A�������o���ė~�����ł��B
���ʓI�ɁA���ꂾ���̐��ɑ����ꂽ�ɂ��ւ�炸�A���������ɁA�������̊��������Ƃ��A
�M���āA��Â����������A�ߖ����ɉ����Ă���������Ǝv���܂��B
���ۂɌ��Ď��������Ƃł����A�s���z�[���\���̋�Ԃ̒��ɓ���A���̂��Ɠ��͂킩���Ă���͂��ł��B
����𐳊m�ɃC���[�W�ł���\�͂��A�������Ƃ��A���������ɂȂ���͂��ł��B
�䎩�g�̎v�����ꂽ���ؕ��@���A�����Ă݂邱�Ǝ��̂́A�Ȃɂ��������Ƃł͂���܂���B
�ł��A����ŏo�������A�{���ɐ������̂��A���x��������\����ς��āA���͂����Ȃ�܂���B
�܂������ƊE�͈Ⴂ�܂����A�����d���ł���Ă��邱�Ƃ��A�˂��l�߂�A�����J�͂��K�v�Ȃ̂ł��B
����Ӗ��A�u���o�̈Ⴂ�Ȃ̂ł��傤���Ȃ��v�Ƃ������t���A�ł��ʂ��Ȃ����E�Ȃ̂ł��B
���t�␔�l�ɏo���Ȃ��A�o�����炭�鐸�x�����߂����o�i�u�ڂ��삦�Ă���v�Ȃǂ̌��t�ł��\����܂��j���A
�������炢�̐��x�̐l�B�̊ԂŁA���L�ł��Ă��܂��A�Ƃ������E�ł��B
���́A���ǂȂǂ̏�Q�̂���q���B�̔��p����ɂ��ւ�邱�Ƃ�����̂ł����A
�ޓ��̂ق����A����ƌĂ��l�B�����A���m�Ȏ��o����F�����A�L�����Ă��邱�Ƃ��A
�����͂�����x�i������̂́A�悭����܂��B�@
�ꌩ�A�܂Ƃ������ȏ������݂�\�������Ă���l�B�̈ӌ����A�L�ۂ݂ɂ��Ȃ����Ƃ��d�v�ł��B
�ǂ�ł�������F����A���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F10888920
![]() 0�_
0�_
��ask-evo����A�f�B�[�G�X�V�[����A���̌�����Ă����Ԃŏ������F����
��قǂ̏������݂����āA�o�b�̓d���𗎂Ƃ��āA���̂T����ɂ́A�J�����D���Ȃ�
�N�ł������Ă������ȁA�����������ʂ̋@�ނŁA���������Ă����A�f�q�̕��s�u����ł������i��Ԃɗ��܂�j�������A
���������Ƃ��ؖ�����A���ؕ��@�������܂����B�����āA���̂Q����ɂ́A�ڂ̑O��
���������̂�������������O�̋@�ށA�����Y�Ȃǂ��g���āA���łɎ��ۂɊm���߂Ă���܂��B
�s���z�[���̒��ɓ��邱�Ƃ𐳊m�ɃC���[�W����A�Ƃ����̂́A���Ԃ�A��ʓI�Ȑl�ɂ́A
������Ƃ������܂����B�����āAask-evo����̌��ؕ��@�́A�����猩��ƁA
�{���Ɋ��S�ɊԈ���Ă���Ɗ��������Ƃ��A����̎����̌��ʼn���܂����B
�@�ނ�������A�P���Ŋm�F�ł��邩������܂���B
�܂��A�ȒP�ɏ����Aask-evo������������Y��`�����@�́A��Ԋׂ�₷�����Ⴂ�ł��B
����́A�����Ƃ������A�������̂��A�������g�́u��v�ɂȂ��Ă��܂��i�]�ʼn�́j�A
�J�����̎B���f�q�̎���̎d�����A���m�ɍČ�����ɂ́A����Ӗ��A�ł����ꂽ����������ł��B
�����Y�̓�����A�J�����ŎB���Ă��܂��Ă���悤�Ȃ��Ƃ��A����Ă���̂ł��B
������������m�F���邽�߂ɂ́A�s���z�[���J�����̂悤�ɁA�ǂȂǂɓ��e����Ă��鑜
�i�������˂��Ă����ԁj������K�v������܂��B�����܂ŏ����Ί��������l�͉���Ǝv���܂��B
�����A������ŏ������A�N�ł�����悤�ȁA����ӂꂽ�J�����̋@�ނ╶�[���p���āA
���ʂ̎����ŁA��������@�������ŁA�����āA�������������l�B�����ۂɎ����āA
���������̊ԈႢ�ɋC�t���āA����������ƒ���������A�ǂ�ł���l�B�ɎӍ߂ł���Ȃ�A
������A�����̒��ɂł������Ă����܂��܂���B
�����ƁA�����ł��邩�A������ɏ����Ă��������āA���̐��ɂ���ẮA�l���܂��B
ask-evo����̂悤�ȁA���J�ȏ������݂��ł�������A�u�ǂ����Ă��v�Ƃ��̕��@�����]�݂Ȃ�A
ask-evo����l�̂��߁A�����ēǂ�ł�����X�ł�����Ă݂����l�B�̂��߂ɁA�������Ă��������܂��B
���̕��@���A�{���ɁA�����̊��A�����Ŏv�����܂����B�܂��A�o�����炭�钼���Ȃ̂ł����B
�Ԉ���Ă��A�r�炵�I�ȏ������݂�����l�B�̂��߂ɂ́A�f���������͂���܂���B
������Ӎ߂��A�����Ƃł���o��̂���l����������A���̌�ɁA�錾�Ə������݂���肢�������܂��B
��낵����肢���܂��B�����A�������Đ\����܂���B�ł��A���ꂪ���Ȃ�́A�u�����߁v�ł��B
�����ԍ��F10889133
![]() 0�_
0�_
�܂���ϊ����܂����B
�@�������܂ŏ����Ί��������l�͉���Ǝv���܂��B
�u���������l�́v�ł��B�����܂���B
�@�������܂ŏ����Ί��������l�͉���Ǝv���܂��B
�ǂ�ł���l�B�̒��ɂ́A������X�������Ǝv���̂ł����c�B�Ȃ��������ސl�B���肪�A
����ȒP���Ȃ��Ƃ��c�B�J�����̍\���𐳊m�ɗ������Ă���A�ȒP�ɂł�������⌟�ؕ��@�Ȃ̂Ɂc�B
�����́A�ْ����̂���A�{�Ԃ̎B�e�ł��̂ŁA����͖����̏��������āA�����Q�����Ǝv���܂��B
���₷�݂Ȃ����B
�����ԍ��F10889142
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����
���ł���ޗ�������̂Ȃ炷���ɂł���������ʼn������B
���Ӗ��ɃX�����L�т邾���ł��B
�����͂��Ȃ��̍u�`�̏�ł͂���܂���B
���ǂ��ł����H�@���ƁA�q���g���A�P���Q�� �����A�N�ł������Ă��܂��܂�����A
�����������Ȃ̂ŁA�����ŋC�t�����ق����ǂ��ł���I
�����炭�A�����̒��r���[�ȗ������A�^���������A��������ł������X�A
���Ӎ߂��A�������A�����ɂ���Ă���������Ȃ�A�����Ă��������Ă����v�ł���B
���l�ł����H
�����͏������L����f���ł��B
�d�˂ď����܂����A���Ȃ��̎����ł��u�`�̏�ł�����܂���B
�����ԍ��F10889284
![]() 19�_
19�_
�����i���t�ł͍����j�̎B�e�̏����ŁA�r�c�J�[�h�̉摜��ۑ����ċ�ɂ����ƂȂǁA
����Ă�����A���Ȃ�x�����ԂɂȂ��Ă��܂��܂����B
�W���͂�v���鐳�m�ȎB�e�ɂāA�̗́E���_�͂������S�z�ł��B
���́A�f���ōu�`�ł��邾�Ȃ�āA��x���v�������Ƃ�����܂���B
���Ɨ����ӗ�����������Ă��Ȃ��̂ɁA�Ȃ�����ȏ������ݕ����������X��
����₷�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���B
�X���b�h�����ʂɐL�т�̂��A�S���I�ȍr�炵�̐l�B���A�������邱�Ƃ������̂ЂƂł��傤�B
�u���O���̐�`���������l�́A���ʂɐL�тĒ��ڂ���邱�ƂŁA���v�⌰���~�����邩������܂��A
���́A���̌��̎d���́A�{���ł̊����ł�����A���������������̌f���ł́A
�悭�����������ڂ���Ă��A�������v�͂���܂���B
�������g���A���i�R���f�����Q�l�ɂ��āA�����Ă������オ����������A
���Ɠ����悤�ȁA�������͋߂��A�g�p���@�����Ă�����X�́A�����ł��Q�l�ɂȂ�A
�Ƃ����v���ŁA�����Ă��܂����B���엦�Ɋւ���X���b�h�ł������ł��B
���ړI�ɂ������������݂�X���b�h�����邱�Ƃɂ���āA��������̓��[�J�[���ɂ�
�t�B�[�h�o�b�N����A���ʓI�ɖ����ɁA�����]�ނ��Ƃɋ߂��d�l�̏��i���A��������邱�ƂɂȂ�͂��ł��B
������ڂő҂��Ă���A���ꂪ��Ȏ��́u���v�v�ł��B
�����̓J�����Ɋւ���f���ł���̂ɁA���܂�ɂ����̊�{�\���������Ă��Ȃ��l���A
�y�͂��݂ɏ������݂������̂ł��B�Ȃ��\�}���ړ����Ă��A��ʑ͓̂����Ȃ��̂��A
����́A�����炷��A�����ē��R�̂��ƂȂ̂ł��B
���x�������܂����A�s���z�[���J�����̌����ɁA�����Ԃ��āA���̒��ł����r�q������Ƃ�����A
�B���f�q���ǂ��������������̂��A������A���x����Âɍl�������A���̂��Ɠ��͂łĂ���͂��ł��B
�����v���Ă���̂ł��B�ł��A�Ȃ��Ȃ����ꂪ����l�����Ȃ��B
���Ƃ������ł��A�������ވȏ�́A�ӔC������Ǝv���܂��B�Ԉ�������́A�����Ȃǂł��ǂ蒅���āA
�ǂސl�ɂ��A�����^���邵�A�{���ɖ��f�Ȃ̂ł��B�@�ԈႤ���Ƃ͒N�ɂł�����̂ł�����A
�܂��́A������x�A���̎d�g�݂��A�l���������Ƃ��Ǝv���܂��B��낵����肢�������܂��B�@�Q�܂��B
�����ԍ��F10889373
![]() 2�_
2�_
MZ-LL����
MZ-LL����́u�r�q����f�q���ꏏ�ɗh��Ă���v�ƌ��������u�����o���Ă��Ȃ��v�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��ł����H
�ƌ������ŁA����Ă݂܂����B
�t�C�����J�����ŁA�t�C�����̏ꏊ�Ƀe�b�V���������āA�����Y�̑����������Ԃɂ��āB
���R�ł����A���̃e�b�V�����J�����ɌŒ肵�Ă���̂ŃJ�����ƈꏏ�ɗh��܂��B
��͂�c�O�Ȃ��瑜�̓J�������h�������ɗh��܂��ˁB�r�q��������A�f�q�̓J�������h�������ɓ������˂Ȃ�܂���B�ƌ������A���̓����Ă��鑜�����āA�v�킸���̕����ɑf�q���������Ȃ�܂����B���Ȃ�����͂̂�������ł����D�D�D�D�D�D
�����ԍ��F10889446
![]() 5�_
5�_
���ۂ������A���͂悤�������܂��B�����̕��肪�Ƃ��������܂��B
���̎����ł́A�r�q�̎d�g�݂͌��ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�����Y�̃C���[�W�T�[�N���������ƁA�C���[�W�T�[�N���S�̂̍\�}���Y���܂����A
���g�͈ړ����Ȃ����Ƃ��A���Ẵs���z�[���J�����i���m�ɂ̓����Y�g�p�̋[���s���z�[���j�̒���
�ő̌����܂������A��ӂ��A���̎v�������A���Ȃ萳�m�ɂ�����Č��ł���Ǝv������@�ŁA
�����܂������A���ۂɂ����ł����B���̖ڂŊm�F���܂����B
�ȉ��A�g�p����������A�����̐l�������Ă������Ȕ͈͂ŏ����Ă����܂��B
�ׂ��������Ɋւ��ẮA�����͖Z�����̂ŁA���邩�����ɂł��B
����ɁA�������Â������ق������₷���̂ŁA�������Ă���̂ق��������₷���ł��B
�������邽�߁A�����Ɏ����X�ŏ����܂��B�ȉ��B
�����ԍ��F10889754
![]() 0�_
0�_
�����A��ӁA��x�A�������݂���߂āA�Q���ɖ߂����ۂɁA�����Ɏv�����āA�莝���̋@�ނ�
����Ŏ��������@�A���̕��@�������A���m�ȓ��삪�ł����┻�f�ł���ڂ�����������Ȃ�A
�����ɉ���Ǝv���܂����A�������̂́A��ɂ����Ă��������B
�ȉ��A�g�������̂�������ӏ������ŁB���ƃR�c��q���g���B
�E��ʂ̎����ŃI�b�P�[�B�����͂ł��邾���Â�����B
�E�i����蓮�ŊJ���ł���50mm�O��̂l�e�����Y
�i�œ_�����͂��܂�W�Ȃ��Ǝv���܂����A�Ƃ肠��������55mm�Ŏ����܂����j
�E���ւ������₷���y�����C�g�B�i�����g�������̂́A���܂��܈ꔭ�ł��傤�Ǘǂ����̂ł������A
�@�ł���A����ނ����O�ɗp�ӂ����ق����A�����Ɍ������̈Ⴂ��I�ׂĊy��������܂���B�j
�E�傫���̈Ⴄ�A���������Q���B�i���͂��łɓ���̊��Ō����������Ă��邽�߁A�P���̎��ł�
�@���v�Ȃ̂ł����A��̓I�Ɋm�F���Ă݂����l�́A�傫���ق��̎��͂ǂ�ȃT�C�Y�ł��悭�āA
�@�������ق��̎��́A������K-7�̔ł�����AAPS-C�T�C�Y���炢�̑傫���ɐ��Ă����Ɨǂ������B�j
�ȏ�ŁA�K�v�ȓ���͏I���ȋC�����܂��B�Y��Ă�����̂����邩������Ȃ��̂ŁA
�܂����ӂɂł��m�F���Ă݂܂��B�ȉ��́A�R�c��q���g�̂ق����B
�E���̎������@�ł́A�J�����{�f�B�́A�ނ���ז��Ȃ̂ŕK�v����܂���B�������Â����Ă��邱�ƂŁA
���z�I�Ȉ��t�J������s���z�[���J�����̏�ԂɂȂ�܂��B
�E�i���s���g���蓮�Œ����ł���Ȃ�A�ǂ̃}�E���g�̃����Y�ł����܂��܂��A
���ɑ��āA�����ɕ�������ۂɁA�t�����W�o�b�N�̒����́A�ڑ��ŗǂ��̂ŁA���̃����Y��
�������������A�ł��邾���Č����Ă��������B
�E���́A���̃����Y�̍ŒZ�B�e�����Ŏ����܂����B
�E�y�����C�g���͌Œ�A�����Y�s�ړ��ł��B
�����̏����ŁA���������ő�R�����Ă����A�y���^�̂r�q�Ɠ����悤�ɁA
�{�f�B�����s�ړ������ۂɁA�f�q�̈ʒu�����W��ɗ��܂��Ă���A
�����Y���{�f�B�Ƌ��ɕ��s�ړ����Ă��A�ő�̃C���[�W�T�[�N���i�̍\�}�j���ړ����邾���ŁA
�f�q���������͈͂�\�}����e���ς��Ȃ����Ƃ��A�ؖ��ł���͂��ł��B
�����̎B�e�̏����ɒǂ��āA���ǁA�Q���Ԃقǂ�������܂���ł������A����ł��X�b�L�����āA
�����܂�Ȃ����Ƃ͂ǂ��ł��ǂ��Ȃ��āA����ς莄�́A�����Ŋ��Ⴂ�����������݂̐l�B��
�ӔC���Ƃ���₤�����A�ǂ�ł���l�B�̖��ɗ������A�������݂����A�����v���܂����B
���m�ɃJ�����ƃ����Y�̃C���[�W���Č��ł���A����Ǝv���܂��̂ŁA����҂����Ă���܂��B
�Â��Ȃ��Ă���̂ق����A���₷���Ǝv���܂��B
�܂��A�R�c��q���g���������Ǝv���܂����A�Ƃ肠�����A�������̕ӂŁB�Ƃ��o�܂��̂ŁB
�����ԍ��F10889793
![]() 0�_
0�_
�Y��Ă܂����B�⑫���܂��B
�E�y�����C�g���Œ�A�ł����A�����Y�⎆�ƁA�����ɂȂ�悤�ɂ��Ă��������B
�E�����Y�͌X���Ȃ��悤�Ɂi�p�x���t���Ȃ��悤�Ɂj�A���m�ɂ킸���ȕ��s�ړ������Ă��������B
�����̐l���A�����悤�Ȋ����ŁA�d�g�݂�������Ă����Ǝv���̂ł����A�命���̐l�Ԃ̓����悤�ȃp�^�[����
���Ⴂ������ԈႢ�����A�������P�l�́A���m�ȍl�@�͂Ⓖ�����������l�Ԃ��A
�^�������������Ƃ́A�悭���邱�Ƃł��B�@�ł���A�ԈႦ���������݂������l�B�ɂ��A
���x���A�������ԈႦ�Ă������Ƃ����邽�߂ɁA���̂��Ȃ��������ė~�������̂ł��B
��낵����肢�������܂��B
�����ԍ��F10889812
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����A���͂悤�������܂��B
��ӂ̓l�b�g���������ɂ��Ȃ������̂ŁA���X���x��Ă����܂���B
>�B���f�q�́A�s���z�[���ɒu���ẮA�u�ǁv�ł͂���܂���B
>�ǂɉf�鑜�́A�����Y�̎��ő�̃C���[�W�T�[�N�����̂��̂Ȃ̂ł��B
>�����ʂ�u�~�`�v�ł����ˁB
[10887252]
���������Ă���͉̂f���Ă�~�`�̍\�}�ł͂Ȃ��A�Ⴆ�����S���~�`���ɉf���Ă���Ƃ��A�~�`���̍\�}�͕ς�����Ƃ��Ă��A�ǂɉf���Ă��郊���S�̈ʒu�������������Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
(�~�`���ł̃����S�̈ʒu�������������Ȃ����ł͂���܂���A�ǂɑ��Ẵ����S�̈ʒu�ł�)
>���g���ړ��A���Ă����A���e���ړ��A�Ƃ������A�Y����Ƃ������A
>���[�ށA�����͏�����������̂ŁA�s���z�[���̌����Ȃǂ��A�܂��������Ă݂Ă��������B
[10887394]
���̃��X�ł��ƁA�ǂ��炩������ƕ�����Ȃ��̂ł����B
>�����Y�̃C���[�W�T�[�N���������ƁA�C���[�W�T�[�N���S�̂̍\�}���Y���܂����A
>���g�͈ړ����Ȃ����Ƃ��A���Ẵs���z�[���J�����i���m�ɂ̓����Y�g�p�̋[���s���z�[���j�̒���
>�ő̌����܂������A��ӂ��A���̎v�������A���Ȃ萳�m�ɂ�����Č��ł���Ǝv������@�ŁA
>�����܂������A���ۂɂ����ł����B���̖ڂŊm�F���܂����B
[10889754]
�����炩��A��L�̃����S�͕ǂɑ��Ă̈ʒu�͓����Ȃ��ƌ������Ƃł���ˁB
����Ŗ{��Ȃ̂ł����A���ۂɊȈՂ̃s���z�[���J����������Đ}-1�̂悤�ȃe�X�g�����܂����B
�����f�镔���������S�����������A�s���z�[���݂̔̂����Ɉړ����܂����B
���R�A�C���[�W�T�[�N���͉��Ɉړ����m�F�B
�����S�̑������Ɉړ����܂�����B
(�C���[�W�T�[�N���Ɠ����ړ��ʂł͂���܂���̂ŁA�\�}�͕ς��܂���)
�����ԍ��F10890017
![]() 5�_
5�_
���������ǂ����������̂ł����A���ꂾ�������Ď��̏������݂͏I���ɂ������Ǝv���܂��B
�C���[�W�T�[�N���͖������č\���܂���B
��ʑ̂ƃs���z�[���Ɠ��e�ʂ�z���A�`��A�������͎�����p�ӂ��Ă��������B
�s���z�[����ʂ��ē��e����鑜�́A��ʑ̂ƃs���z�[���̉�������Ɍ������܂��B
����͓�����O�ł��ˁB
�܂�A��ʑ̂ɑ��ăs���z�[�����ړ������ꍇ�ɂ́A���e����鑜�̓s���z�[���̈ړ���肳��ɑ傫���ړ�����̂ł͂���܂��H
���ɂ�MZ-LL���������˂��Ȃ��Ă���Ƃ͎v���܂��A�O������̐ݒ肩�A���ۂ̉��߂Ɍ�肪����悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B
���������ɗ�����������ł����ǂ�(^^;
�����ԍ��F10890369
![]() 6�_
6�_
��������������₷���}��lj����܂��B
�������ۂɊm�F�ł����̂́A(2)�̏�Ԃł��B
MZ-LL�����Ă���̂́A(3)�̏�Ԃł���ˁB
(�s���z�[���̈ʒu�������Ă������S�̑����f���o����Ă����ԍ��W�ʒu�͕ς��Ȃ�)
�ł����ꂾ�ƁA�������Ȃ���Ȃ��Ǝ����ł��܂����ˁB�s���R�ł͂Ȃ��ł���?
�����ԍ��F10890421
![]() 12�_
12�_
����Ȃ���AMZ-LL����̎������@���邢�͌��ʂ̓ǂݎ����Ɍ�肪����̂ł͂Ȃ����Ɓc
���x�݂Ƀp�p�b�ƍ�����}�Ȃ̂��Y��łȂ��Đ\����܂��A��}�Ɍ�肪����悤�ł�����A��̓I�ɂ��w�E���������܂��ł��傤���B
�f�B�[�G�X�V�[����̐}�Ƃ́A�������Ⴄ�����œ������Ƃ������Ă���Ǝv���܂��̂ŁA�ꏏ�Ɍ��Ă���������Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10890583
![]() 11�_
11�_
�@
�����O���������Y�ƃX�[�p�[�̃��W�܂Ŏ��ۂɂ���Ă݂܂������A
MZ-LL����̎����Ƃ͈قȂ錋�ʂɂȂ�܂����B
�z���g�Ɏ��H���ꂽ�̂ł��傤���H
�\�����}�́@�f�B�[�G�X�V�[����A���Ƃ���Ɠ����l���̍�}�ł��B
�����ԍ��F10890634
![]() 12�_
12�_
���_�͏o���l�ł��Ȃ��c�B
�����ԍ��F10890640
![]() 3�_
3�_
�����܂���AMZ-LL����̏����ꂽ���������悤�Ǝv�����̂ł���
�܂�MZ-LL����ɂ͖��Ӗ��ƌ����郌�x���̒Ⴂ�������Ă��܂��܂���
�Ƃ肠�������ʂ�Z�߂��̂Ō��Ă�������
http://papablog2.ice-tomato.com/article/140302368.html
����K-7�̏ꍇ�V�t�g�u���ɑ���SR�͖��͂ł���
������������[�Y�����u�Ԃ��������ĂȂ��݂����ł�
MZ-LL�����K-7�͓����������Ă���薳����ł����
�Ђ���Ƃ��Ď���K-7�����Ă���̂ł����H
�����Ă��������X�������肢���܂�
�����ԍ��F10890715
![]() 13�_
13�_
SR���ǂ̂悤�ȂԂ�ɑΉ����Ă���̂��y���^�b�N�X�₢���킹�܂����B
���Ή����Ă���Ԃꁄ
�@�E�����Y��[�̏㉺���E�̂Ԃ�(�p�x�Ԃ�)
�@�E�J�����̕��s�ړ��ɂ��Ԃ�(�V�t�g�Ԃ�)
���Ή����Ă��Ȃ��Ԃꁄ
�@�E�J�����̌X��(��]����)�̂Ԃ�@(�����������SR�Ƃ͊W�Ȃ�)
�@�E�J�����̑O������̂Ԃ�
�ȏ�ł��B
�p�x�Ԃ�ƃV�t�g�Ԃ�́A�莝���B�e�łǂ��炩����݂̂��������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ̔F���̂��ƁA�����ɑΉ����Ă��邻���ł��B
�ȑO�̎��̏�������[10877499]�ŁA�d�q������p�̃Z���T�[�ŃV�t�g�Ԃ�����Ă���\���ɂ��Ă͐G��܂������A����������Ƃ̊֘A���Ȃ��悤�ł����A�V�t�g�Ԃ���ǂ̂悤�Ɍ��m���Ă���̂��͕s���ł��B
��A���S���Y���ɂ��ẮA���R�Ȃ������J�Ƃ̂��Ƃł����B
�V�t�g�Ԃ�̕�̗L���ɂ��ẮAMZ-LL����̂��������ʂ�ł����B
���Ƃ́A�V�t�g�Ԃ������Ƃ��̃Z���T�[�̓����ł����A�������MZ-LL����̂��������ʂ�ƂȂ�ł��傤���H
�����ԍ��F10891805
![]() 5�_
5�_
���X�ǂ����ɂȂ�܂����B���G�ȍ\���Ȃ�ł���
���܂�M�藧�Ɓ@�̐S��SR�������Ȃ��قǐk���܂���i�I�j
�������̕ӂ�......
�����ԍ��F10892582
![]() 2�_
2�_
���A�A��܂����B�������Ƀw�g�w�g�ł��B
�����A�g�p�@�ނ����������܂������A���Ƃ͂���������Ă���悤�Ȃ̂ŁA�����Ă����܂��B
�����Y�̃s���g�����O���ŒZ�B�e�����ɂ͂��܂����A�y�����C�g�́A�����Ƌ߂Â��Ă��������B
���̋����܂ŗ����ƁA�����̌��̓_�̂悤�ɂȂ��āA�����Ă��܂��܂��B
����͏������Ȃ����C���[�W�T�[�N���ł�����A�����Y�������A�����ē��R�ł��B
�C���[�W�T�[�N���́A�����Y�̒��S�i�����j�ɍ��킹�Ĉړ����܂��̂ŁB
����͓�����O�̂��Ƃł��B
�\�}�̒��g�i��ʑ́j�̑���ɁA���̓y�����C�g�������Ă�����ւ��g���܂����B
�y�����C�g�́A�C���[�W�T�[�N������邽�߂́u���v���̂��̂Ƃ��Ă��g���A
���̌��ւ��摜�Ɍ����Ă܂����B���i�C���[�W�T�[�N���j�͈ړ����܂����A
���̂���������ł́A�摜�Ɍ����Ă����ւ͈ړ����܂���ł����B
���s�̔��ړ��ł���A�C���[�W�T�[�N���������Ă��A�������W�Ŏ~�܂��Ă��܂��B
�����Ɖ���₷�����@������Ǝv���܂��̂ŁA�������l���Ă݂܂��B
�Ƃ肠�����A�y�����C�g�́A���ɑ��Đ����ŁA�����āA�����Ƌ߂Â��Ă݂Ă��������B
��肭���ւ������Ȃ���A�ʂȃ��C�g�ɕς��Ă݂Ă��������B
�����āA�����g���A�i�����Y��p�����j�s���z�[���\���̒��ŁA�����Y�s�Ɉړ������ہA
�\�}�͕ς��܂������A�w�ʂ̕ǂɁA�����r�q�œ��삷��B���f�q�Ɍ����Ă��A
�����`�̎���u���A���̒��Ő蔲���ꂽ�摜�͕ς��Ȃ��͂��ł��B
�����s���z�[���\���̒��ɋ����̂́A�O�̕��i�ł����B���i�͓V�n�������܂Ɏ�����
�ǂɉ~�`�ɓ��e����A�����Y�s�Ɉړ�����A���̉~�`�̒��̕��i������܂��B
�������A���̉~�`�̓����ɎB���f�q�Ɍ����Ă������`�̎���u���A���̒��̍\�}�͕ς��Ȃ��͂��ł��B
�f�B�[�G�X�V�[����ɍ���Ă����������}�ł́A������ƈႤ�悤�ȋC������̂�
������x�m���߂����Ă��������B�����S�Ȃǂ���ɂ���ƁA������Ƃ悭����Ȃ��Ȃ�̂ŁA
�i�F�����A�Ƃ����悤�Ȍ`�̂ق����A���̑̌��ɋ߂��ł��B�����͓����Ȃ̂�������܂��A
�̂Ɍ��Ă������ƂƁA����肢���������}�̓������A�Ⴄ�悤�ȋC������̂ł��B
�J���������s�ړ������ہA�����Y�����C���[�W�T�[�N�����ŁA�{�f�B�̓�����ł������`�ŁA
�B���f�q���A���̍��W�ɗ��܂��Ă���A��{�I�Ɉʒu�u����������d�g�݂͊Ԉ���Ă��Ȃ��͂��ł��B
����́A���x���m���߂Ă��܂����̂ŁB
�����A�����ƕ��G�ȓ��삪�A�œ_������B�e�����Ȃǂ̏���A����ȊO�̏���������A
�ׂ������䂪����Ă��邱�Ƃł��傤�B
K-7�̍\�}�������@�\�́A�O�r�ȂǂɌŒ肵�Ă̎B�e�̍ۂɁA�f�q����ړ������āA
�\�}������@�\���Ǝv���܂����A�����\����p�����r�q�́A���̂��傤�Njt�ŁA
�{�f�B�����s�ɔ��ړ������ۂɁA�u�\�}��ς��Ȃ��v�@�\���Ɗ����Ă��܂��B
���ꂪ�A�u��U���ł���������v���Ǝv���܂��B
���ɂ��A���낢��ƃ��X�������Ă������������̂ł����A�����x��ł���ɂ����Ă��������B
�����ԍ��F10892813
![]() 0�_
0�_
�@�����s�̔��ړ��ł���A�C���[�W�T�[�N���������Ă��A�������W�Ŏ~�܂��Ă��܂��B
�����Y�̕��s�̔��ړ��ł���A�̊ԈႢ�ł��B�@�����܂���B
�@�������Y�̕��s�̔��ړ��ł���A�C���[�W�T�[�N���������Ă��A�i���g�E��ʑ̂��j�������W�Ŏ~�܂��Ă��܂��B
�����ԍ��F10892860
![]() 0�_
0�_
MZ-LL���� ������
�������Y�̃s���g�����O���ŒZ�B�e�����ɂ͂��܂����A
���y�����C�g�́A�����Ƌ߂Â��Ă��������B
�����̋����܂ŗ����ƁA�����̌��̓_�̂悤�ɂȂ��āA�����Ă��܂��܂��B
������͏������Ȃ����C���[�W�T�[�N���ł�����A�����Y�������A�����ē��R�ł��B
���C���[�W�T�[�N���́A�����Y�̒��S�i�����j�ɍ��킹�Ĉړ����܂��̂ŁB
������͓�����O�̂��Ƃł��B
��������Ă݂܂����B���̎����ɂ��Ă�MZ-LL����͊��Ⴂ����Ă���Ɛ������܂����B
��͂肻���ł����ˁB������x�悭���l�����������B
�����ԍ��F10892955
![]() 3�_
3�_
MZ-LL����A�����́B
�ʂɃ����S����Ȃ��ĕ��i�ł������̂ł����A�������̂������Ȃ̂Ŏ����̕��i�����R�����܂�����B
�����A�C���[�W�T�[�N���ƃ����S���܂߂����i�̈ړ��́A�����ړ��ʂł͂Ȃ��̂ŁA�C���[�W�T�[�N�����̍\�}�͓��R�ς��܂��B
�܂�
>�����āA�����g���A�i�����Y��p�����j�s���z�[���\���̒��ŁA�����Y�s�Ɉړ������ہA
>�\�}�͕ς��܂������A�w�ʂ̕ǂɁA�����r�q�œ��삷��B���f�q�Ɍ����Ă��A
>�����`�̎���u���A���̒��Ő蔲���ꂽ�摜�͕ς��Ȃ��͂��ł��B
[10892813]
���̒����`�̎��̒��̉摜�͓����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂���ˁB
�����ԍ��F10893030
![]() 2�_
2�_
���A�x�݂Ȃ���A�����Y��p�������������Ă��܂������A
�y�����C�g�̑O�ɁA�e���ł���悤�ɏ����ȏ�Q����u���܂������A
�����Y�s�ɓ��������ہA��͂�A�C���[�W�T�[�N���͈ړ����Ă��A
���̉e�͓����Ȃ��ł��ˁB�ǂ��ł��傤���B
��ł��������J��Ԃ��āA���x���m���߂Č��܂��B
�����̂��̂́A�C���[�W�T�[�N������邽�߂Ɏg���Ă���̂ŁA�ł���A
�Ȃɂ���ɂȂ郂�m�������Ă��������B
���ւƏ����܂������A���m�ɂ͂k�d�c�̗֊s�̂悤�Ȋ����ł��B
�����g�́A���s�ړ��ŁA���ɂ��邻�ꂪ�A�����悤�ɂ͂ƂĂ������܂���ł����B
���f�B�[�G�X�V�[����
���X���肪�Ƃ��������܂��B�����A�s���z�[���ő����������Ƃ�����A
�����g���A�̌��������̂��A�ʏ�̂�����u�s���z�[���\���v�ł͂Ȃ��A
�����Y��p�������̂��������߁A�P���Ȍ��ł���s���z�[���Ƃ́A�f�鑜���Ⴄ�\��������܂��B
���̏ꍇ�A���������Ă����A�s���z�[���\���ׂĂ��������A�Ƃ������t���̂��A
���Ⴂ�������ƍl�����܂�����A���̕��ł��A������x�A�����Y��p���Ȃ��A
�{���́u�s���z�[���v�Ɋւ��āA���ׂ����Ă��������B��͂肻�ꂪ���̊��Ⴂ�ł�����A
�����ŁA����ȏ��������������Ƃ��A��قǎӍ߂����Ă��������܂��B
�����Y�ƃ��C�g�Ǝ���p�����A�����̌��������̂������������悤�ȁA��L�̎����ł́A
��͂��ʑ͈̂ړ����܂���ł����B�C���[�W�T�[�N���͈̔͂͂������ړ����܂����A
���g�͓����ꏊ�ɂ���܂����B
�{���̃s���z�[���́A�����̌��i�ł��o���邾���^�~�Ȃق����ǂ��悤�ł��ˁj�ŁA
�����Y�͖����̂ŁA���i�����������̂�������܂���B
�����̌������̂́A���������̂��郌���Y��p�����A�[���s���z�[���ł����B
���i�����������A�����̌��ł́A���̂܂ܕ��s�ړ����A�p�x�u���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��̂�������Ȃ��A�Ɗ����܂����B
�ǂ���ɂ���A���͎��̏����������������ł��̂ŁA������䎞�Ԃ����������B�\����܂���B
���̕��ւ̃��X�����������Ă��������B
�����ԍ��F10893172
![]() 0�_
0�_
���y�����C�g�̑O�ɁA�e���ł���悤�ɏ����ȏ�Q����u���܂������A
�������Y�s�ɓ��������ہA��͂�A�C���[�W�T�[�N���͈ړ����Ă��A
�����̉e�͓����Ȃ��ł��ˁB�ǂ��ł��傤��
���������ǂ悭���l���ɂȂ��Ă��������B
�����ԍ��F10893204
![]() 2�_
2�_
�^������A���͊��Ⴂ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂���B
���Ɛ��m�ɁA�r�q�̑f�q�����W�ɗ��܂���������z�����������ł��Ă���͂��ł��B
�^��������A������x�A���낢��Ǝ����Ă݂Ă��������B
���Ȃ��Ƃ����́A���s�ړ��œ����C���[�W�T�[�N���̒��ŁA�\�}�̕ς��Ȃ��܂ܒ����ɂ���
�f�q�̏�Ԃɖ͂����͈͂��A�m�F�ł��܂����B
�����ԍ��F10893325
![]() 0�_
0�_
���t�����W�o�b�N�̒����́A�ڑ��ŗǂ��̂ŁA
�����̃����Y�ɍ������������A�ł��邾���Č����Ă��������B
�����́A���̃����Y�̍ŒZ�B�e�����Ŏ����܂����B
�Ȃ����̂悤�ȏ����ɐݒ肷��̂ł��傤���H
���y�����C�g�́A�����Ƌ߂Â��Ă��������B
���x�ł��悭���l���ɂȂ��Ă��������B
[�C���[�W�T�[�N��]�@�ɂ��Ă��m�F���Ă��������B
�ł́A���̎����ɂ��Ẵ��X�͂�����Ō�Ƃ����Ă��������܂��B
�����ԍ��F10893362
![]() 2�_
2�_
�����Ƃ���
�y���^�b�N�X�ɒ��ڂ��₢���킹���������A���肪�Ƃ��������܂��B
�u�Ԃ�v�Ɋւ��ẮA�������������������Ƃ��A���������Ă������ƂƁA�قƂ�Ǔ����Ȃ̂ł����A
�u��]�����̃u���̕�v�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�������ڋ����Ă������������ƂƁA�����g�̐������A
���m�łȂ������\��������܂��B�����g�́A�g�U���U��ŁA�f�q���킸���ɌX���Ȃ���A
��U��E����ʒu�܂ňړ�����l�q���A���ځA�����Ă����������̂ł����A
���ꂪ�A�u��]�����̎�U���v�Ƃ����P��ł͕����ĂȂ������L��������A
��b�̒��Łi�����ȁj�X����ł������āA�r�q�̎�U���ƈꏏ�ɂȂ��āA���삷��A�Ƃ��������������C�����܂��B
����́A�K�������u��]�����i���[�����O�j�̎�U���v�Ƃ͌����Ȃ��̂�������܂���B
�����A�f�q����]�����ɌX���Ă��ړ�����A�Ƃ������́A��������ƕ������L���ƁA
�g�U��̐��������邽�߁A�N���Ɋo���Ă��܂��B�����͂܂�����J�̋Z�p�Ȃ̂�������܂���B
�����āA�u��Ԃ��v�Ƃ͌����Ȃ��̂�������܂���B
�����̎B�e�ł��A�����Đ�قǂ��AK-7�ɂāA�t�@�C���_�̏�ӂɎ���{�̌��ԂŁA
���s�ɂȂ�悤�ɁA�����̔�ʑ̂��ʂ��ƁA�莝���B�e�ł��A���̐��������A���̃J��������
���Ȃ荂���ł��B�ق�̂킸���Ȋp�x���A�ł������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ɗ����鎞������܂��B
�t�@�C���_�̎��엦�����m��������A���̌X�������������肵�Ă��邱�Ƃ��A�e���͓��R����Ǝv���̂ł����A
�����Ă������Ƃ�������x��������A�u�u���v�ɑ��Ăł͂Ȃ��Ă��A�Ȃɂ�����̕�̂悤�Ȃ��̂�
�����Ă���̂ł́A�Ɛ������Ă��܂��B�@���Ȃ��Ƃ��A������������͐������Ă��������܂����B
�������A�����͎��ɂƂ��ė\�z�O�ŕ����\��̖��������u���p�O�v�̕����ł��̂ŁA
������x�A����T������A���̋@��ł́A���x�͏ڂ������������Ă݂悤�Ǝv���܂��B
��]�����̌X���̕�Ɋւ��ẮA������̃X���b�h�ɂāA���̕\��������������
����������Ǝv���܂��̂ŁA���m�ȏ���肵�����A�⑫�������������Ă������������Ǝv���܂��B
���������݂ƌ���A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10893373
![]() 0�_
0�_
���^������
�u�C���[�W�T�[�N���v�̕����ł��ˁB�������܂����B
�����́A�������t���K�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B
�����A�y�����C�g�Ȃǂ��A���傤�Ǘǂ����m�ł���A�قڐ��m�ȃC���[�W�T�[�N����
�o���オ��Ǝv���܂��B�c�O�Ȃ���A���C�g�̍\������A�����͂قƂ�nj��݂̂������Ă��܂��܂����B
�ׂ��y�����C�g�̌��̂悤�Ȃ��̂ł��ƁA���C�g�̋����ɂ���āA�����Y�̃}�E���g���̉���
�������ɂ́A�����Ȍ��ƂȂ��Ă��܂��܂��B�������ɂ���́u�C���[�W�T�[�N�����̂��́v
�Ə����̂͐���������܂���B�C���[�W�T�[�N���̒����ł����āA���ۂɂ͖ڂɂ͌���
�����Ȃ��ł����A���̎��͂ɁA���̂قڌ����Ȃ��A�����Ƃ������̃����Y���{�������Ă���
�C���[�W�T�[�N��������͂��ł��ˁB
�����܂���A���Ă���̂ŁA���낢��ƌ��t���͂����܂����B�����Ɨ��������Ă���A
�����̂��Ƃ͏������ق����ǂ��Ǝv���܂����B
�������A�����{���A�����������Ƃ͂����������Ƃł͂Ȃ��A�C���[�W�T�[�N���̒��S��A
�O�~���ړ����Ă��A��ʑ̂̈ʒu���ς��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�����́A���̂����ŁA�m���߂��Ă���Ǝv���܂��B
�Ȃ�ɂ���A���t���炸�ł����B���������A�ł��邾��������������Ƃɋ߂��A
�����������������������Ȃ̂ł����A�������āA�s�K�ȗp����g���Ă͂����܂���ˁB
�ǂ�ł���F�l�A���炢�����܂����B�@�^������A�⑫�������邫������������Ă������肠�肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F10893418
![]() 0�_
0�_
�܂����t���炸�ł����B
�@���c�O�Ȃ���A���C�g�̍\������A�����͂قƂ�nj��݂̂������Ă��܂��܂����B
�u�����͂قƂ�nj��݂̂Ő^�����Ɍ����Ă��܂��܂����B�v�A����Ȋ����ł��傤���B
�����܂���A���̕ӂ̘b��A���̒��ŁA���͏�肭�����܂���̂ŁA�����ȍ~�Ɏ����z�������Ă��������B
�ǂ�ł���������X�ɁA���������A�Q�l�ɂȂ���A�Ƃ������Ă����āA������
���t���炸���������Ă���̂ł́A�����瑁�������������悢�̂ł́A�Ƃ����C��������ł��A
������⑫�̎��̏������݂������āA�܂��܂����Â炢�X���b�h�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB
���X�������������X�ɁA�����ƌ�Ԏ�����̂́A����ɂȂ��Ă��܂��܂����A
�����̂ւ�ւ�̏�Ԃł́A�낭�Ȃ��Ƃ����������ɖ����̂ŁA�����ŋx�܂��Ă����������Ǝv���܂��B
�����g�́A�r�q�̎d�g�݂ɋ߂��ƍl������悤�Ȏ��������Ă݂�����ł����A
�����Ɨǂ����@�ŁA�{�f�B�̕��s�ړ���ł��������Ƃ��������₷�����@�����邩�A
���߂āA�l�������Ă݂����Ǝv���܂��B�@�����܂������ɔ��Ă��܂��B���炢�����܂��B
�����ԍ��F10893455
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����
���Ƃ�����m�F���ꂽ�悤�ɁAK-7�̃u������V�t�g�u���ɂ��Ή����Ă��邱�ƁA��]�u���ɂ͑Ή����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A����܂ł̎v�����݂Ƌt�ł����̂ŏ��Ȃ��炸�V���b�N�ł����B
���ɂȂ�܂����B
����Ƃ͕ʂɁAMZ-LL�����A�F�����ꂼ��Ɏ��������āA���ʂɐH���Ⴂ���o�Ă���̂��s�v�c�ł��܂�܂���B���낢��l���Ă݂��̂ł����A
MZ-LL����̎����ł́A�y�����C�g�ƃ����Y�̊Ԃɂ��̂�u���āA�����Y�������i���s�ړ��j�Ƃ��ɁA���Ɏʂ����y�����C�g�̔����~�͓������A�u�������̂̉A�������Ȃ��B�Ƃ������Ƃł��傤���H
�e�ɏœ_�͍����Ă��܂����H�y�����C�g�����������Y�ɋ߂����邩�A���������Y�ɋ߂����āA�������Ă��Ȃ��ꍇ�́A�����Y�Ƃ��ċ@�\���Ă��Ȃ��āA����f�ʂ����ĉe�G�����Ă���悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
���̏ꍇ�AMZ-LL����̌�����悤�Ȍ��ۂɂȂ�Ǝv���܂��B
�ɒ[�Ɍ����A�傫�ȑ��ɑ��z������������ŁA���O�̖̉e���ł��Ă���̂Ɠ�����ԂŁA���̈ʒu�������ړ����Ă��A�̉e�Ɉʒu�������Ȃ��̂Ɠ������Ƃł��B
�J�����́A�e�G�ł͂Ȃ��A���������G���ʂ��܂��B����������ꍇ�A�y�����C�g�ƃ����Y�̊Ԃɒu�������̂̉e�ɏœ_�������悤�ɒ��������Ă���A�����Y�����Ă݂Ă��������B
����Ă���A���߂�Ȃ����ˁB
�Ȃ��H���Ⴄ�̂��A���̂܂܂���A�C���������̂ŁA�A�A�A
���ۂ��A�������l���Ă݂����ł��B
�����ԍ��F10893892
![]() 0�_
0�_
�V���b�N����K�v�͂���܂���ˁB
PENTAX�́u�V�t�g�u���ɂ��Ή����Ă���v�Ǝ���悤�ȉ��Ԉ���Ă��܂�����(������e�Ђ悭���邱�Ƃł�)�B
�����I�Ȕ��f���e�l�ōs���܂��傤�ˁB
�u����v�ł킩�邱�Ƃ�MZ-LL����̌�����������߂Ɏ��ۂɗᎦ���グ���Ă���F����Ɍh�ӂ�\���܂��B
MZ-LL����ɂ�����܂��ẮA���[�ƂȂ���
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10850394/#10852172
�ɂďЉ�������N���ǂݔ�����A�v�����݂�r�����āu��{�����v�Ƃ��ė�������邱�Ƃ�����Ă�݂܂���B
�u��Â��v���u���ł���v�ɂȂ���Ȃ����Ƃ��������������������ł��B
�����ԍ��F10893908
![]() 5�_
5�_
���Ƃ���A
�����y���^�ɖ₢���킹���k�Z���^�[���烁�[���ʼn����������܂����A���[���̓��e�͌��J�ł��܂���
�P�x�ڂ̖₢���킹�̎��̓V�t�g�u���ɂ̂ݑΉ����p�x�E�O��u���ɂ͑Ή����Ă��Ȃ��Ƃ������ł���
�����MZ-LL�����Ă����Ɠ������e���Ǝv���܂�
�ēx�����Ō��������ʂ��܂ߍĎ������ꂽ�Ƃ���Q�x�ڂł��Ƃ���Ɠ���
�V�t�g�E�p�x�u���ɑΉ����O��u���ɂ͑Ή����Ȃ��Ƃ������܂���
�P��ڂQ��ڂʼn��ς���Ă܂��ˁA���[�J�[�̐l�Ԃł��m��Ȃ������L��ƌ������Ƃł�
���ʂ��Ԃ��Ă��邩�͕�����܂��ēx�₢���킹�����A������ɂ���@�ނŌ��𗊂�ł��܂�
���A���Ƃ���A�g���C�|�b�h���s�����p�x�u�������S�Ɏ�菜�������ɐ���������
�u�����Č������ꍇ�A��Ԃ������삹���B���f�q�������Ȃ������͎̂����ł���
���͍���̃u����̌��Ɋւ��Ă͍Č����鎖���o���܂��̂Ŏ����̌��،��ʂ�M���܂�
�����ԍ��F10894829
![]() 5�_
5�_
���Ƃ���A
�����܂���AHN��ł��ԈႦ�Ă��܂��܂���<(_ _)>
�����ԍ��F10894837
![]() 0�_
0�_
��]�u���ɂ��āA��]���̈ʒu��ς����}�����܂����B
�����ł́A�p�x�u���i���[�p�A�s�b�`�p�̕ω��j���u��]�u���v�ƕ\�L���Ă܂��B
���[���p�̕ω��i�B���f�q�`��ʑ̊Ԃ����Ƃ����p�x�ω��j�ɂ͌��y���Ă��܂���B
���āA��]���̈ʒu�ɂ���ĎB���f�q�ړ���ʂ��ω����܂��ˁB
��]�u���F
�����Y�T�C�Y���l������ƁA�P���ڂ́i�Q�j�ƂQ���ڂ́i�R�j�i�S�j��
�ʏ픭������p�^�[���ƍl���Ă�낵���ł����ˁB
���̏ꍇ�Ɍ���A�r�q�ɂ��B���f�q�̃{�f�B�ɑ��铮���́AMZ-LL����̂��������Ƃ���A
��������̓{�f�B�̓�����ł����������ɂȂ�܂��B
�V�t�g�u���F
�R���ڂ́i�T�j�i�U�j�ʼn�]���ʒu���ɒ[�ɉ��������ꍇ�ɊY������ƍl�����܂��B
�i�Ȃ̂ŁA�����́A�V�t�g�u������]�u���̈��ƔF������]�ƃV�t�g�œ��ɋ�ʂ��܂���B�j
���̏ꍇ�A�W���C���Z���T�[�ł͊p���x�����o�ł��Ȃ��̂ŁA
���������x�Z���T�[���ŃV�t�g�u�������o�ł�����A
�r�q�ɂ��B���f�q�̓����́A�{�f�B�̓����Ɠ��������ɓ������ɂȂ�܂��B
�V�t�g�u���̋����ɂ��Ⴂ�F
���i�̏ꍇ�F
�V�t�g�u���ɂ��C���[�W�T�[�N���ړ��ʂɑ��ăC���[�W�T�[�N�����ł̔�ʑ̈ړ��ʂ͋ɒ[�ɏ������ł��B
���ɃC���[�W�T�[�N���ł̌�����x�m�R�Ƃ��āA�J������10cm�V�t�g�ړ�����ƁA
�x�m�R���ł�10cm�ړ��́A���i������Ŗw�ǖ����ł��郌�x���ł��B
�@�@��3,000m�̎R�i���c15mm�̎B���f�q�ɏ㉺�����ς��Ō������Ă���Ȃ�A
�@�@�@�R�i����10cm�V�t�g�ړ��͑f�q���0.5��m[��15mm/(3000m/0.1m�j]�ƂȂ�A
�@�@�@�c3000�s�N�Z���̎B���f�q�ł���A�f�q��̈ړ��ʂ�0.1�s�N�Z�����B
�]���āA���i�Ńu������s��Ȃ����A�s���Ă��ق�̔��ʂ̂͂��ł��B
�ߋ����`�}�N�����x���F
��ʑ̂Ńu������s���ꍇ�́A�B�e�����ɂ���ĕω����܂��B�i�������̒ʂ�ł��ˁj
�^��F
�l�I�ɂ́A���L�ɂ��Ēm�蓾�����Ƃ���ł��B
�i�P�j���[�A�s�b�`�p�̉�]���ʒu�́A�C�ӓ_�ɌŒ肵�Ă���H�^���Z�ŕω��H
�i�Q�j�r�q���V�t�g�u���ɑΉ����Ă���Ƃ���Ȃ�A
�@�@�㉺���E�̈ړ��ʂ��ǂ̂悤�Ɍ��o���Ă���̂��H
�@�@�@��������̉����x�Z���T�[���p�ł���AK-7�̂ݑΉ��ł����ˁB
�@�A�ߋ����̔�ʑ̋����ɂ���ʍœK���͎����ł��Ă���̂��H
�c�F�X�ƋC�t������鎖�����X����^���ɂȂ�܂����B
�i����Ȋ���ϑz�̓X��������������܂��A���e�͉������B�j
�����ԍ��F10894840
![]() 3�_
3�_
���@�@SR���ǂ̂悤�ȂԂ�ɑΉ����Ă���̂��y���^�b�N�X�₢���킹�܂����B
���@�@���Ή����Ă���Ԃꁄ
���@�@�@�E�����Y��[�̏㉺���E�̂Ԃ�(�p�x�Ԃ�)
���@�@�@�E�J�����̕��s�ړ��ɂ��Ԃ�(�V�t�g�Ԃ�)
�@�L���m���̎��̐�����ǂ�ł���������A�y���^�b�N�X�̐�����������
�r�����m�ł��邩��������ɂȂ�Ǝv���܂��B
http://web.canon.jp/pressrelease/2009/p2009jul22j.html
�@�B���f�q���V�t�g�����Ď�Ԃ�����܂����A��Ԃ�̃Z���V���O���A
�p���x�Z���T�[�݂̂ōs������A�V�t�g�Ԃ�����邱�Ƃ͂ł��܂���B
�����ԍ��F10895099
![]() 6�_
6�_
�F����A����ɂ��́B�@���������݂������l�@���ӌ��A���肪�Ƃ��������܂��B
���́A�������ǂ܂��Ă��������Ȃ���A�����̃��X���A�ߑO���ɂQ�������̂ł����A
�������p��⌾���ŏ����Ă��Ȃ����������X���肻���Ȃ̂ŁA�m�F������͈͂ł��Ă���A
�f�������Ă������������Ǝv���܂��B
��ӁA�o�b��钼�O�ɁATomato Papa����̃����N�ł̎����̉�����A�q���������܂����B
�Z���Ԃ̔q���ł����̂ŁA�܂���قǁA�������ƌ������Ă��������B���������L�̂܂��f�����Ă��Ȃ�
���X�̒��ŁA�����G�ꂳ���Ă����������̂ŁA�J��Ԃ����������邩�Ǝv���܂����A���炢�����܂��B
������
�Ȃ��A����������ŋɒ[�ȕ������i�����͂킴�Ƃł����j�����x�������Ă��܂��������ŁA
���C�������������Ă��܂��A�\����܂���B
�����g�́A�{���́u����̋�_�v����D���Ȃ̂ł��B���Ƃ��Ƃ��̃X���b�h�̓��e�ɂ��Ă��A
�����g���̊����Ă������ƁA�A���Ƌ߂߂̐Ñ̂��悭�B�e���悭����̂ŁA���̍ۂ�
�u�ȂA��̌��ʂ��v�������������Ȃ����H�v
�ƁA�ӂƊ������^�₩��n�܂��Ă���̂ł��B
�����ŃX���b�h�𗧂��グ��O�̒i�K�ŁA����܂ʼn��x������̋�_���ׂẮA
���ۂ̎B�e�ŁA�f�q�̓�����C���[�W�����肵�āA�����Ă݂܂����B
�����āA�����ÂA�܂��B�e�����s���闦�������Ă������̂ł��B
�����g�����������̂́A�l�̊��o��A���[�J�[�̒����ɓn��Z�p�J���̌����ł��邱�̋@�\���A
�ے肷��ۂɁA�ǂ������玝���Ă����m�����q�����킹�āA�����̓s���ɍ��킹�Ęc�߂��悤��
�������݂���ʔ������Ă��邱�Ƃł����i���ۂɂ́A�����łȂ�������������Ă����Ƃ͎v���܂��j�B
�����A����̋�_�ł��A���҂ւ̍U����ے�̂��߂ł͂Ȃ��A�����������𐳊m�ɗ������悤��
�l���邽�߂́A���������ɂȂ�Ȃ�A����ȑf�G�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�ƌl�I�ɂ͎v���Ă��܂��B
�����g�́A�q���̍�����A���̌J��Ԃ��Ő����Ă��܂��B�����Ċ��Ⴂ���ԈႢ����������R���Ă��܂����B
��قǁA���������݂������������e���A���x���q�������Ă������������v���܂��B
�܂��́A���̂����ŁA�u����̋�_�v�Ƃ��������ŁA�{���ɂ��C���������Ă��܂������Ƃ��A
�Ӎ߂����Ă��������B���߂�Ȃ����B
�����g�́A�ǂ�ł���F����̎Q�l�ɂȂ�悤�ȁA����������A�����ɂ��ǂ蒅���܂ł�
���ؕ��@�A�����ĉ����A�g�p����������A�Ǝv���܂��B
���[�J�[�̋Z�p��ے肷�邽�߂ɂ́A���̊�Ƃ̐��̌�������J���҂Ȃ݂̒m�����K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����A
�Ɗ�����������܂��B�@�����g���d�������Ă��鐢�E�Ō����A����Ŏ��ۂɍ��x�Ȍ�����
���Ă���l�B�̍l�@�����̏�ŁA�ے肷�邽�߂ɂ́i�S�̒��Ŋ����邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��Ǝv���܂��j�A
���̍������A�Ⴆ�Ζc��Ȍ��������W�߂���A���ۂɌ��n�Œ���������A�ȂǁA���ɑ�ςȍ�Ƃł��B
���Ƃ����i���̌f�����Ƃ��Ă��A���[�J�[�ɂ����邩�Ȃ�閧�̕����A���x�ȋZ�p�Ɋւ��ẮA
�ςɁA�ے肷������A�܂��́A���[�U�[�̂P�l�Ƃ��āA�̊����ĉ��b�ɂ�������̂��A
�ǂ����ȁA�Ȃ�Ċ����Ă���̂ł��i����Ȃ�̋��z���o���āA���́u���\�v���w�����Ă���킯�ł����ˁj�B
���e�ɑ��Ăł͂Ȃ��̂ɁA�������X�A���炢�����܂����B���������݂��肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10895282
![]() 0�_
0�_
TomatoPapa���Ɠ������A
�y���^�b�N�X�̃��[�U�[�T�|�[�g�̉ɂ͑S����ѐ����Ȃ��Ďv�B
���T�ɂ́u�V�t�g�u���ɑΉ����Ă܂���ł����B�v�Č���ꂻ��w
�����A���̓X����ɓ���ׂ��_������Ďv�B
�������A���̐l���ɂ���(�ȉ���
�����ԍ��F10895373
![]() 4�_
4�_
����ɂ��́B
K-7���V�t�g�u��������Ă���Ƃ̌��A�ӂ��̊p�����x�Z���T�["����"�ł͂ł��Ȃ��Ǝv���̂ł����E�E�E
"�B���f�q�ƃ{�f�B�̈ʒu�W"�����o����ʒu�Z���T�[������Ɩ������Ďv���ƁE�E�E
�V���b�^�[���������S�������ŁA�B���f�q���x�~���(��B�e���)�̈ʒu���王�엦100%���������ׂ�"�B�e���O�ʒu"�֏u���Ɉړ������Ă���Ǝv���܂��B�����őz�肵�Ă���"�B�e���O�ʒu"����킸���ɂł��Y���Ă���ƈʒu�Z���T�[�����o�������A���̃Y���͉��炩�̊O�͂Ő������ƍl�����܂��B(�ʒu����̐��x�������Ƃ̓R�R�ł͌��킸�ɁE�E�E)
����"���炩�̊O��"�̂ЂƂ͊p�x�u���A����ɂ����ЂƂV�t�g�u��������ł���Ƃ���ƁA�p�x�u���̗ʂ͊��݂̂ӂ��̊p�����x�Z���T�[�Ōv�Z�ł��܂�����A�ʒu�Z���T�[�����o�����Y���Ɗr�ׂĈႢ������A���̍��̓V�t�g�u���̉e�����Ɣ��ʂł��邩������܂���B
�܂����ۂ̘I�����n�܂��Ă���A�p�x�u���̕�����A���^�C���ɑ�����킯�ł����ǁA������v�Z�l�ƈʒu�Z���T�[�����o�������ےl���Y���Ă���A��Ɠ��l�A�V�t�g�u���Ƃ��Ĕ��ʂł��邩������܂���B���̕���f���������V�t�g�u���ɂ��Ώ��ł���̂����B
�ʒu�Z���T�[�̕���\���B���f�q�̉�f�s�b�`������������(���x��������)�A���Z���x�A�B���f�q�̈ړ��������x���\���ɑ�����A���邢�͉\��������܂���B
<�]�k>
[10872506]�ŏ������u�p�x�u���̐���̐��x���ۂĂȂ��Ȃ�܂��v�̒i���ł́u���Ȃ�拭�Ɉʒu�ێ��E�ړ����䂵�Ă���v�Ɛ������Ă��܂����A"���Ȃ�"�̒��x�������キ�Ȃ����C�����܂��B"�K�`�K�`"�Ɋ拭�ł͏�̉����͐��藧���܂���B
����ɑ�������(�`)�ň͂i���́u�킴�킴�����Ɏ�Ԃ̂�����R���v�����H���Ă���Ƃ������܂��A�ӊO�ɂ��B
�X�ɕʂɂ���炵���A�����Z���T�[(�X�Z���T�[)���ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��́A������Web�������Č��܂������A�킩��܂���ł����B����ŁA����ɂ͐G��Ȃ��ł����܂��B
���̏������݂��\���ɍl�@�������m�ł͂���܂���B�������A���̏������݂Ɠ��l�A����Ȃ�����Ȏv�����݂��܂݁A�����ł��B
�������A�V�t�g�u��������Ă���R�g�A�q�ϓI�Ɏ��ł��܂��ˁB
�X���b�h�������Ȃ�R�g�ɕs�����������Ă�����������������邱�Ƃ͗������Ă���܂��B�ȂɂƂ����e�͂��������B�ߕ��ł��S�ɉa(��)��^����R�g�ł����B
�����ԍ��F10895381
![]() 3�_
3�_
����@
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/#10894840
���^��F
�l�I�ɂ́A���L�ɂ��Ēm�蓾�����Ƃ���ł��B
�i�P�j���[�A�s�b�`�p�̉�]���ʒu�́A�C�ӓ_�ɌŒ肵�Ă���H�^���Z�ŕω��H
�i�Q�j�r�q���V�t�g�u���ɑΉ����Ă���Ƃ���Ȃ�A
�@�@�㉺���E�̈ړ��ʂ��ǂ̂悤�Ɍ��o���Ă���̂��H
�@�@�@��������̉����x�Z���T�[���p�ł���AK-7�̂ݑΉ��ł����ˁB
�@�A�ߋ����̔�ʑ̋����ɂ���ʍœK���͎����ł��Ă���̂��H
�i�Q�j�̃V�t�g�u���ɑΉ����Ă��Ȃ��O���
�i�P�j�̉�]���ʒu�͖������܂��B
��]���ʒu�ɂ��Ԃ�́u�p�x�v�ɂ��J�����́u���_�̈ʒu�v�̂���ƂȂ�킯�ł��B
�����āA�J�����́u���_�v�Ƃ́A�������ꂽ�����Y�̑O����_�ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/#10869557
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/#10870027
�����ԍ��F10895425
![]() 2�_
2�_
Tomato Papa����
���́A�������̖₢���킹�ł͂͂�����Ƃ���������ꂸ�A�p�x�Ԃ�ƃV�t�g�Ԃ��}��������ōĖ₢���킹���A����ɑ��ė����ɑΉ����Ă���Ƃ̉����炢�܂����B
�ŏ��̖₢���킹���ɁA������ӏ������ɂ��ʂɉ���������悤���肢�����̂ł����A�Ȃ��������ł̉ŁA�m�肽�����Ƃɂ�����Ɖ��������Ȃ��������Ƃ��c�O�ł��B
�ɋ^�₪����܂����̂ŁA�u�V�t�g�Ԃ�ɂ��Ă͉����x�Z���T�[���K�v�Ȃ͂������A����Ȃ��łǂ�����ăV�t�g�Ԃ�����m���Ă���̂��v�Ƃ̎|�A�ēx�₢���킹���ł��B
HN�̂��Ƃ͋C�ɂ���Ȃ��Ă悢�ł���O�O
����
���i�P�j���[�A�s�b�`�p�̉�]���ʒu�́A�C�ӓ_�ɌŒ肵�Ă���H�^���Z�ŕω��H
�����ł����A���Z�ŕω������Ă���̂��Ǝv���܂��B
�����Ă����������}��(5)�A(6)�ł��w�E����Ă���ʂ�A��]�����J��������ƌ����ꍇ�A�V�t�g�Ԃ�ɔ��ɋ߂���ԂƂȂ�܂����A���̏�Ԃł���Ή��Z�őΉ��\�Ǝv���܂��B
�y���^�b�N�X����̉̒��Ɂu�p�x�Ԃ�ƃV�t�g�Ԃ�́A�莝���B�e�łǂ��炩����݂̂��������邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ̔F����������Ă��܂����̂ŁA�����炭�}(5)�A(6)�ւ̑Ή��������āu�V�t�g�Ԃ�ɑΉ��v�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��l���Ă��܂��B
���i�Q�j�r�q���V�t�g�u���ɑΉ����Ă���Ƃ���Ȃ�A
���@�@�㉺���E�̈ړ��ʂ��ǂ̂悤�Ɍ��o���Ă���̂��H
���@�@�@��������̉����x�Z���T�[���p�ł���AK-7�̂ݑΉ��ł����ˁB
���@�A�ߋ����̔�ʑ̋����ɂ���ʍœK���͎����ł��Ă���̂��H
�����������ł́A�������SR�͓Ɨ����Ă���Ƃ̎��̂悤�ł����c�B
�����ԍ��F10895474
![]() 1�_
1�_
�@�����Ƃ����i���̌f�����Ƃ��Ă��A���[�J�[�ɂ����邩�Ȃ�閧�̕����A���x�ȋZ�p�Ɋւ��ẮA
�@���ςɁA�ے肷������A�܂��́A���[�U�[�̂P�l�Ƃ��āA�̊����ĉ��b�ɂ�������̂��A
�@���ǂ����ȁA�Ȃ�Ċ����Ă���̂ł��i����Ȃ�̋��z���o���āA���́u���\�v���w�����Ă���킯�ł����ˁj�B
�����܂���A���[10895282]�������݂̍Ō�̂ق��̂�����A������������ŁA�܂邲�ƍČf�������Ă��������B
�ȉ��B
.........
���Ƃ����i���̌f�����Ƃ��Ă��A���[�J�[�ɂ�����閧�̕����A���Ȃ蕡�G��������
���x�ȋZ�p�Ɋւ��ẮA�ςɁA�ے肷������A�܂��́A���[�U�[�̂P�l�Ƃ��āA
�̊����ĉ��b�ɂ�������̂��A�ǂ����ȁA�Ȃ�Ċ����Ă���̂ł��B
�i����Ȃ�̋��z���o���āA���́u���\�v���w�����Ă���킯�ł����ˁj
�����āA���̎��ۂ̎g�p�����������߂A���ꂩ��w�����l���Ă���l�ɂƂ��Ă��A
���݂��łɏ������Ă��郆�[�U�[�ɂƂ��Ă��A�g�p�ړI��p�r�ɍ����A�L�v�ȏ��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A
�Ɗ����Ă��܂��i�������A���ꂪ��������������͊Ԉ��������A�����Ɍ�������͓̂���Ǝv���܂��B
�u�����������v�A�u�����v�����v�A�Ƃ����̂́A�������[�U�[�Ƃ��ẮA���Ɛ^�����ȁA
�Ƃ��������A�֗��ȁA�\�����@�Ȃ̂ł͂Ȃ����ȁA�Ȃ�Ċ����Ă����肷��̂ł��B
.........
����ւ̃��X�̌`���Ƃ�Ȃ���A���ʓI�Ɏ������v�����Ƃ܂ŏ����Ă��܂��܂����B
���炢�����܂����B
�����āA�X�b�]�R����������[10891498]�Ōf������Ă���摜�Ȃ̂ł����A
�������̑O�Ɍf�������@�ނ�ޗ���p���āA�Ȃɂ��̎��������Ă��ꂽ�݂����Ȃ̂ł����A
�����������Ă��镶�͂������̂ŁA���̕��́A������������A�X�b�]�R���������A
���甽�ʋ��t�ƂȂ�ׂ��A���s�Ƃ������Ԉ�������ؕ��@���f�����Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��Ƃ��ȁA�Ɗ����܂����B
�O�ɂ������܂������A���ꂾ�����ׂ̍��y�����C�g���A�摜�Ō�����قǂ́A���ꂾ���̋�����
�����܂��ƁA�P���ɁA�C���[�W�T�[�N���̒��������A���̏����ȓ_�ŁA�����Y�̉��̖ʂ�
�f���Ă��邾���ɂȂ��Ă��܂��܂��B����ł́A���̊����Ă���d�g�݂̌��ɂ͂Ȃ�܂���B
�@�ނ������������ł́A��������p����������l���o�Ă��邩������Ȃ��ȁA�Ƃ͎v�����̂ł����A
�����������Ă��Ȃ��ȏ�A�X�b�]�R������������ɓ����邩�͉���܂��A
���Ȃ��Ƃ��A[10891498]�ł͌��ł��Ȃ��ł����A�O�ɂ��ǂ����ŏ����܂������A
�����̓��̒��ł̍l���ɍ��킹���\���ŁA�������s���ƁA����𐳂������f����\�͂������ꍇ�́A
�Ԉ�������ʂ��������������Ƃ̂悤�ɁA�f�����Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
����́A���������Ƃ͌ĂȂ��Ǝv���܂��̂ŁA�F����A�����ӂ��������B
�����A�����s���ۂ́A�܂������̗��_�Ƃ��ȑO�̑̌��Ƃ����A�^�����Ƃ���n�߂܂��B
�����������ŁA���惂�[�h��C�u�r���[���A���u���̈ʒu�u�����A���ʓI�ɕ���Ă��邱�Ƃ��A
�ƂĂ�����₷�����Ƃɂ��A�C�t���܂����B
Tomato Papa����̂悤�ɁA�O���ւ̃����N�ł��悢�̂ŁA�����Ɖ���⌋�ʕ��q�ׂ��Ă���ق����A
�ǂ�ł�����X�ɂ́A�e���Ǝv���܂��B�摜�������Ă��A���������A�Ȃ�̎������������́A����Ȃ��̂ŁB
��낵����肢���܂��B
�s���g�̈ʒu�����A�ނ���œ_�����ɒ��ӂ��āA�߂Â������Ȃ��悤�ɁA�ł��邾���A
�����Y�̉��̉~���A�L���Ȃ�悤�ɁA�߂Â�����A�������́A��肱�̎����Ɍ������^�C�v��
���C�g�Ȃ�����d���Ȃ�ɁA�����Ă݂�Ɨǂ��Ǝv���܂��B
���Ȃ��Ƃ��A�����g�������C�g�Ƃ́A���Ȃ�^�C�v���Ⴂ�܂��B�u�y�����C�g�v�A�Ə������̂������Ȃ������Ǝv���܂����B
�܂��A�ߑO���ɏ��������̂��A�f���ł��Ȃ��Ă����܂���B
���A�lj��������X�����܂������A�Z�p�_��T�|�[�g�̑Ή��̈Ⴂ�Ȃǂ��A�����̂́A
�X���b�h�Ⴂ�ł��̂ŁA�ł��邾���������������B
�����ԍ��F10895487
![]() 0�_
0�_
�ꉞ�A�戵��������133�y�[�W�́u��Ԃ��@�\�𗘗p����v����������������Ɓc
���ߋ����̎B�e�ł͎�Ԃ��������Ȃ��ꍇ������܂��̂�
�܂�A�B�e�{���ɔ�Ⴕ���u�ʒu�u���v�̉e�����傫���Ȃ邽��(�����Ă��ꂪ��̑Ώۂł͂Ȃ�����)�ł��ˁB
�u��Ԃ��v�Ƃ����u�Z�p�v�͂�����ے肵�Ă��܂��A���[�U�[�͉��b�ɂ��������Ă��邱�Ƃ͋^���]�n������܂���B
�����ԍ��F10895510
![]() 0�_
0�_
�y���^�b�N�X�̖₢���킹�ŁA�P��ł͊ȒP�ɖ��m�ȓ������o�Ȃ����Ƃ́A
��ЂƂ����g�D���l����A���R�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B
�����A�ŏ��Ɏ�t���������������A���Ȃ���Ă������X�Ȃǂ���A���̒m���◝��͂ł�����悤�ȁA
�͂�����Ƃ��������������Ȃ��������߁A�����܂��ǂ������Ă��Ȃ�������Ă�����A
�ŏ��Ɏt���Ă����������Ј��̌���̂��C�����ŁA������Z�p�҂̌�������Ăт��������܂����B
��ρA������܂����B�����āA��� �����������ł��B
���G�ȋZ�p�n�̏��́A�Ј����ׂĂ̐l�B�̊ԂŁA���L�ł���Ƃ͎v���܂���B
��������A�ނ���A����ɂ킽���āA�ł��邾�����m�ȏ��ƂȂ�悤�ɁA
�ĘA���ɂ��Ή��ł���A�y���^�b�N�X�̐�������]�������ق����ǂ��Ǝv���܂��B
�����A�B�e�̐��x���グ�Ă��������ŁA�t�@�C���_�ɑ��Ă������ł����A����������
�ׂ₩�ȑΉ��������A���X���Ћ@�����S�̃��[�U�[�ł����������A���݂̓y���^�b�N�X��
�J���������C���ɁA�����ĐM�p���Ďg�p���Ă��闝�R�Ȃ̂ł��B
�{���ɃX���b�h�Ⴂ�ł��̂ŁA�����ŁA�����������b��͍T���Ă��������܂��悤�ɂ��肢���܂��B
���́A�����̈ӌ����ؖ�������A�������Ă����������߂ɁA�u�y���^�b�N�X�ɒ��ځA�₢���킹�Ă݂Ă��������v
�Ə������킯�ł͂���܂���B�����̕��X�̌�������܂�ɂ������̂ŁA�X���b�h�̎�|����
�傫���O��Ă������Ƃ��A�����ł��H���~�߂邽�߂ł��B
������A���́A�����̌����Ă������Ƃ��A������x�A�����������A�Ƒ��̕��X����A
������������Ă��A��ÂɑΉ����Ă������ł��B�����𑝂₵���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
�����ł��A���m�ȔF����������������A������̃X���b�h�ɂāA���ۂ̎g�p������
���Ă������邱�Ƃ��A���ɂƂ��āA���Ȃ��Ƃ����̃X���b�h�ɉ����ẮA�ł��d�v�Ȃ̂ł��B
�T���Ă��������B�@�@�������ޑO�ɁA�悭�l���Ă݂Ă��������B
�����đ��҂̑��@��݂̂ŁA���ۂɃy���^�̂r�q���ڋ@��������x�̊��ԁA�g�p�����o���������l�́A
�u����K-7�������L���Ďg�p�����o���͂���܂��c�v�Ȃǂ̑O�u�����A
�����Ƃ��Ȃ��ƁA�ǂ�ł�����X�́A������Ă��܂��Ǝv���܂��B
���̃X���b�h�̃g�b�v�́A�����Ƃ������A��|�Ƃ������A�ړI���A�C�`����l�������Ă݂Ă��������B
��낵����肢���܂��B
�i���������������A�����ɒ[�ȕ�������p���Ă܂ŁA���ӂ������Ă������R�Ȃ̂ł��B�j
�����ԍ��F10895557
![]() 0�_
0�_
�@�������đ��҂̑��@��݂̂ŁA
�܂��ԈႦ�܂����B�Ӗ��͒ʂ�Ȃ����Ƃ������̂ł����A��ϊ��ł��B�������́A
�@�������đ��Ђ̑��@��݂̂ŁA
�ł��B���炢�����܂��B�ł��邾���ԈႦ�Ȃ��悤�ɁA�`�F�b�N���Ă������Ȃ̂ł����A
����ł��ԈႦ�Ă��܂��܂��B�@�l�Ԃ���Ƃ��A���x�̍��� ���Ƃ̏d�v���͏����ɂ����
�傫���͈Ⴄ�Ǝv���܂����A��{�I�ɂ́A�����ԈႢ�����Ȃ��g�D����͂��Ȃ��Ǝv���܂��B
�J�����̂悤�Ȑ����@�B�ł���A����������Ȃ���A���C�Ō듮�삵�܂����ˁB
�������A�����ł́A���̂��Ƃ����������킯�ł͂���܂���B
�u��U���̌��ʂ̈Ⴂ ���Ă���Ǝv���܂��H�v
�Ƃ����^�C�g���̃X���b�h�ŁA�������炭��A���ۂ̑̌����Ă���̂ł�����A
�������A�����A�����Ɉ��Ă��܂����Ƃ́A�����Ĉ������Ƃł͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����A
��������e�ɂ���ẮA�ǂ�ł��邱�Ƃ̎Q�l�ɂȂ�ł��傤�B
�������A���m�ȔF�����o���Ă��Ȃ��l���A��������ɏ������ݑ�����̂́A�����ėǂ����ƂƂ͎v���܂���B
�����܂ł̏������݂ŁA�ɒ[�ȕ����������Ă��܂������A���͂������Ɠǂ߂Ȃ��������ƂŁA
�������R���Ă��Ă��܂��܂����B�{���Ɏ��炢�����܂����B
�������A�u���P�l�v �� �u��������̌�������l�����v�@�Ƃ����傫�Ȑ}�����ˑR ���܂�Ă��܂��āA
�����Ă����ł͂Ȃ����X���ꕔ�A�Q�����Ă����������ɂ��ւ�炸�A�Ȃ��Ȃ��X���b�h�̎�|�ɂ́A�߂�܂���ł����B
�����玄���ł��邾�����J�ȑΉ������Ă��A�܂�ŕ������������Ă���܂���B
�����������Ă��邤���ɁA���ɑ��āu�����Ɛl�̈ӌ������ق����ǂ��v
�Ȃ�āA�������݂� �������o�Ă���n���B
���́A���Ƃ��ƁA�����ȊO�́A�l���܂̎��̌��������āA���̃X���b�h�𗧂��グ�܂����B
�{���͂����ƁA���̕��X�̕��A�������ǂ݂��������̂ł��B����͂��������̏������݂ł������Ă���������͂��ł��B
���ꂪ�A�����̒ʂ�ł��B�����畁�i�͔�r�I��Âɏ�������ł������̎��ł��A
�����āA����������邱�ƂŁA�����ŊJ���悤�A�Ƃ������@���Ƃ炴�邨���Ȃ��������Ƃ��A
�����́A�z������������K���ł��B�@�{���ɑ�ςł����B
�����ԍ��F10895608
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����A
SR�̌��ʂ�����͎̂������Ă܂���
�����Ԉ�������͐����Ȃ��Ƃł���
���Ƃ����ꂪ���[�J�[�̏o���������ł���
MZ-LL�����Ă����l���Ă����ł���H
�d�v�ȕ����̃��X�������Ă��܂��B������x�����N��\��܂���
���̌��ʂ��ǂ��l����̂���������������
http://papablog2.ice-tomato.com/article/140302368.html
�����ԍ��F10895741
![]() 6�_
6�_
�u�ǂ��v�����v�̊��o�̘b�͔ے肵�܂��A�����Ă��������Ηǂ��Ǝv���܂��B
�Ԉ�����F���ɂ��Z�p�ɑ��鏑�����݂͉����������������킯�ł��B
�����ł��Ă��Ȃ��u�C���[�W�T�[�N���v�u�p�x�u���v�u�V�t�g�u���v�Ȃǂ̌��t���g�킸�A�u��Ԃ��̌��ʁv�̘b�����o�I�ɏo���Ȃ��̂ł����H
MZ-LL����́uSR�v���uOFF�v�ɂ������ł��K�v�ȎB���f�q(���܂ރ��j�b�g)�̎��C�쓮�ɂ�鐧��̕��@�ɂ��ĉ�����ꂽ���̂��uSR�v�́u���삻�̂��́v�ƌ�����Ă�������Ⴂ�܂��B
�����ԍ��F10895759
![]() 5�_
5�_
��Tomato Papa����
�ߑO���ɏ��������͂Ōf�����Ă��Ȃ����m�ɂ́A�����A�����N���������������̉���ɐG�ꂽ������
����̂ł����A�\����܂��A�܂������A�����̕��͂��A���ۂɌf�����Ă������̂��A
���f�ɖ����Ă��܂��̂ŁA���炭���҂����������B
������������Ă������������Ƃ��̂��̂́A�������v���̂ł����A�Ȃɂ��A���͂����̃X���������Ă��āA
���ɂ��A��Ԏ����Ă��Ȃ����X�����邾���łȂ��A�܂������Ɠǂ�ł������Ȃ����X��
����������̂ł��B�܂��́A�ǂނق���D�悳���Ă��������B
�i�����ă��X���f������ۂɂ́A��������m�F��Ƃ��K�v�ł��̂Łj
����͌ߑO�������܂ŁA�����ƎB�e�ł����̂ŁA�A�����A�قƂ�NJF����̃��X��q���ł��Ȃ������̂ł��B
�������A�����̏������݂��A���t���炸�����݂悤�ȕ\������ŁA�}���ł����Ƃ͌����A�������Ȃ��Ă���r���ł��B
�������݂����������̂́A�������̂ł����A�ł���A������ɂ������悤�ȗv����
���Ȃ��ł���������Ƃ��肪�����ł��B�ǂނ����ł��A���Ȃ莞�Ԃ�������܂��̂ŁB
�i�s���������ď����Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ŁA������Ȃ��悤�Ɍ�肢���܂��j
�ƁA�����킯�ŁA�����͍u�t�̎d���ŁA�����P�l �ɑ��āA�@�吨�̕��X�A�@�Ƃ�����Ԃ́A
��r�I�A����Ă͂���̂ł����A����ł��A��̌����Ȃ��A�����������f���ŁA�r�炵�I�ȏ������݂�
�����o�v������ԁi�����m�����ł�����Ȃ�̐����폜�ΏۂƂȂ����悤�ł��B
���̃��X���A���A��łQ�قǖ����Ȃ�܂����j�ŁA������s���̂́A���Ȃ�ߍ��ł��B
�Ƃɂ����A���������ۂɑ̌��������Ƃ�A���������Ƃ��A�����̒��Ŋm�F��Ƃ��s�������ł��A
��ςȂ̂ł��B�ł���A�ǂނق��ɓO�������̂ŁA������ւ̗v���͍T���Ă���������Ƃ��肪�����ł��B
�����āA�܂����t���ςł����̂ŁA���������Ă��������B[10895608]
�@���u��U���̌��ʂ̈Ⴂ ���Ă���Ǝv���܂��H�v
�@���Ƃ����^�C�g���̃X���b�h�ŁA�������炭��A���ۂ̑̌����Ă���̂ł�����A
�@���������A�����A�����Ɉ��Ă��܂����Ƃ́A�����Ĉ������Ƃł͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����A
�@����������e�ɂ���ẮA�ǂ�ł��邱�Ƃ̎Q�l�ɂȂ�ł��傤�B
�Ō�̕��́A�ł��ԈႦ�܂����B
�@���u��������e�ɂ���ẮA�ǂ�ł��邱�Ƃ̎Q�l�ɂȂ�ł��傤�B�v
�ł͂Ȃ��A
�@���u��������e�ɂ���ẮA�ǂ�ł���l�B�̎Q�l�ɂȂ�ł��傤�B�v
�ɂ����Ă��������B
�����g�́A�����ɂ��ꂽ�b����A���������D���ł��B�������X��������Ă���A���̃X���b�h�ł́A
���́A���ɂ��ꂽ��蓹�Șb��ł̑��̕��X�̂��������݂ŁA�������ɕ������Ă��������Ă܂��B
����̔�ꂪ�A�܂������Ԏc���Ă���Ƃ͌����A�����͋x�݂ł��̂ŁA���łɒ��ɂ�
�Ǝ����ς܂��܂������A��͂������A�����������������݂�q���������ł��B
���X���̂��̂́A�����Ԓx���Ȃ�Ǝv���܂��B���炢�����܂��B
�����ԍ��F10895840
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����
�������Ă����ł͂Ȃ����X���ꕔ�A�Q�����Ă����������ɂ��ւ�炸�A�Ȃ��Ȃ��X���b�h�̎�|�ɂ́A�߂�܂���ł����B
�c�擪���ăX���̎�|����͂���Ă������̂́A�X���傳���g�̂悤�ȁc
��̂ق��ł��ǂȂ��������Ă��Ǝv�����ǁA���o�Ƃ��̊��̘b�����������Ȃ�A�܂������g���A�Z�p�I�Ȃ��b�ɐG��Ȃ�������Ǝv����B
�����ԍ��F10895861
![]() 3�_
3�_
MZ-LL����A
�B���ȕ��͂łȂ����w���Ńn�b�L�������Ă��������Č��\�ł�
�����ԍ��F10895867
![]() 1�_
1�_
�ǂނ̂���ςɂȂ�̂ŁA���l�ɑ��邱�Ƃ́A��x�A��߂Ă݂Ă��������B
�����Ƃ����������݂����Ă���������ƁA����Ɉ��������Ȃ��̂ŁA
�r�炵�I�ȏ������݂́A�ł��邾���X���[�����Ă��������Ă���̂ł����A
�Ō�ɂł��A�܂Ƃ߂āA�����ɂ��ꂪ�A�����s�ׂł��邩�́A��������Ă��������܂��B
���łɍ폜���ꂽ���X�ŁA�����t���A���l�́A�����Ɗo���Ă��܂��B
���ۂɂ́A������������m�F�ł��Ȃ��ԂɁA�������܂�č폜���ꂽ���X������̂�������܂��A
���Ȃ��Ƃ��A�L�����Ă��邱�ƂɊւ��ẮA�y�[�W�̕ۑ������Ă��܂����A
���̂ق�������A���ꂪ�ǂꂽ�������������݂̎d���ł��邩�́A�w�E�����Ă��������܂��B
���x�������܂����A���l���폜�˗��������Ƃ́A��x������܂���B
�����ɂƂ��āA�s���̈����������݂⌟�،��ʂ��������Ȃ��A�Ȃ�ċC�����͂Ȃ��̂ł��B
�ł��A�X���b�h�̎�|����O�ꂽ��A��������܂܁A�ǂ�ł���l�B�ւ̒�����Ӎ߂������A
���X���J��Ԃ��̂͂�߂Ă��������B
���łɏ������܂ꂽ�ߋ��̃��X�ɑ��āA�����������������������ꍇ�́A�����Ƃ��ꂪ�A
������Ӎ߂��Ɖ��镶�̂Ō�肢�������܂��B�l�̌��_�̎w�E�����A�܂��͎����̂��Ƃł��傤�B
�l�ɔ��Ȃ����Ȃ����Ȃ�A�܂��A������H���Ă݂Ă��������B
���l�ւ̎Ӎ߂́A�Ƃ肠�����A���́A����܂���B����Ȃ��Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��̂ł�����B
�X���b�h�̎�|�ɉ������������݂����A�̌��k����肢�������܂��B
�����A���炭�̎��Ԃ́A�������݂������܂���B���������܂��B
����𗥂��āA�������ޑO�ɁA�����������낢��ƍl���ė~�����Ǝv���܂��B
�����A�������y�������������Ȃ��āA�C�����悤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10895887
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����
�����x�������܂����A���l���폜�˗��������Ƃ́A��x������܂���B
�N�����Ȃ����폜�˗����Ă�Ɣᔻ�����q�g�����܂������H
�����l�ւ̎Ӎ߂́A�Ƃ肠�����A���́A����܂���B
���R���Ǝv�����ǁB�Ȃ����Ȃ��Ɏӂ�K�v������́H�@
�ނ���A���Ȃ������Ȃ��ɔ��_���Ă���q�g�ɑ��ď��������X�̖\���E�����̂ق�������ۂnj��ꂵ�����ǁB
�Ӎ߂��ׂ��Ȃ̂͂��Ȃ��ł��傤�B
���X���b�h�̎�|�ɉ������������݂����A�̌��k����肢�������܂��B
������������ݐh�����A���痦�悵�č���Ă��������Ƃ��ɂ��������C�Â��ė~������ˁB
���܂��牽�H���Ċ����B
���ǂނ̂���ςɂȂ�̂ŁA���l�ɑ��邱�Ƃ́A��x�A��߂Ă݂Ă��������B
���Ȃ��̒����Ń|�C���g���B���ŁA�{�|�ȊO�ɗ]�v�Ȃ��Ƃ��_���_�������A�ǂރq�g���ɂ߂ĕs���ɂ����鏑�����ɑ��A�݂�Ȑh���������Ȃ��̌�����������Ǝ��Ԃ������Ă��Ȃ��B
�킽���݂����̂��o�Ă���̂��C���Ȃ�A�܂����X�t���Ă�F����Ɋ��ӂ��āA�����̎p�������߂���ǂ��H
�����ԍ��F10895989
![]() 21�_
21�_
�x�X�X�C�}�Z���B
��kuma_san_A1�����
�����̋^��ɂ������������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B
�Ȃ�قǁ`���w�[���ł��ˁB
��]���̊�ʒu�́A�h�����Y�̑O��_�h�Œ�ł���A
�u��ʒu�ȊO�ł̉�]���ɂ��p�x�u���i�a�j�v�̏ꍇ�́A
�u��ʒu�̓��p�x�ɂ��p�x�u���i�`�j�v�Ƃ��ĕ�ʂ����Z����A�ƁB
���̍ہA�a�ł́A�`�ɑ����ʂ̍����ɂ��ẮA
������@�h�V�t�g�u���ƌ��Ȃ��A��������h�@�Ƃ������ł��ˁB
�ł���A
�a�Ɍ������ꍇ�A��]���ʒu������o����ƁA���̂ق��������I�ɂ͊y�ł��傤�ˁc
�����Ƃ����
�������ł����A���Z�ŕω������Ă���̂��Ǝv���܂��B
�����������c�Ƃ�������]�I�ϑ��ɂȂ�܂����A���Z�ŕω����Ă��Ăق����ŃX�ˁB
��u���́A�l�X�Ȏ��g���Ɨl�X�ȉ�]���ɂ�镡���U���ƍl����ƁA
���Z�������Ńu���̕ψʗʂ���g���ɂ��ĉ�͂���ł��傤���B
��]�����J�����V�X�e���̏d�S�ɂ���Ă��e������Ƃ���A
�{�f�B�ɑ������郌���Y�̏d�ʂ�A�Y�[�~���O�����A�c�ʒu�A���ʒu�A�\�����A�k�u�莝���B��c
�S�̂̏d�S���ω�����Ή�]���ʒu���s��ƂȂ邾�낤���B
���̗l�X�ȃp�^�[���ɂ��ĉ�]���ʒu���ʂɐݒ�ł���A
��萳�m�ɕ�ł���̂ł́H�ƁA�f�l�Ȃ���v���킯�ł��āB
�܂��A
�Ⴆ�J�������Ł@�h����͐S���̌ۓ��ɂ��u�����h�@�Ɣ��ʂ��Ă��炷�����ł��ˁB
���̍ہA�\�߈�ʓI�ȃq�g�̍��i�ؓ��ɂ��J�����ւ̐U���`�B�p�^�[���Ȃǂ̃p�����[�^�i�o�����j�ɂ���āA
�ۓ��u�����L�̉�]���ʒu������o���āA�����c���Ă���C�C�Ȃ��A�Ă��ȁB
�������������ł́A�������SR�͓Ɨ����Ă���Ƃ̎��̂悤�ł����c�B
�ł���ˁB�y���^�b�N�X�̉ł́u�V�t�g�u���ɑΉ����Ă���v�����Ȃ̂ŁA
�������SR�̊e�n�͓Ɨ����Ă��邯�ǁA������̃f�[�^�Q�Ƃ͉\���Ǝv���܂��āB
�����ԍ��F10896004
![]() 0�_
0�_
��Tomato Papa����
���}���̋C����������悤�ł��̂ŁA�D�悵�āA���X�����Ă��������܂��ˁB
����A��������K-7���̏�Ȃ̂��Ƃ����v�������邩�炩������܂���ˁB
�N�ł��A�����}���˂Ȃ�Ȃ��u�Ԃ́A����Ǝv���܂��̂ŁA�����͑Ή������Ă������������ł��B
�ꕔ�A�܂��f�����Ă��Ȃ����m�Əd�����Ă��܂��̂ł����A������̊m�F��Ƃ��x��Ă��܂��̂ŁA
��ɁATomato Papa����ւ̃��X�������A�������Ă��������܂��ˁB
�܂��́A�����N�ɂāA�䎩����K-7�p���������̌�A���肪�Ƃ��������܂����I
�����āA�܂������C���t���܂����̂́A����́u�莝���B�e�v�ł̎�U���̌��ł͂Ȃ��̂ŁA
���m�Ȍ��ʂ��o���̂́A�قږ������Ǝv���A�Ƃ������Ƃł��B
����́A���̃X���b�h�ʼn��x�������Ă����̂ŁA��Ԏ��̓��e���ۗ��̂悤�ȏ�ԂŁA
�������Ă������������Ƃ̌��݂̂��������̂́A�����ɋC�t���ė~������������ł��B
�y���^�b�N�X�ŁA�����A�g�U���U��������ĕ����Ă������Ƃ́A�Z���T�[�̎d�g�݂��ǂ��A
�Ƃ������A���ۂɁA�ǂ��������ɁA�ǂ�����������A�r�q������̂��A�Ƃ������Ƃł����B
�Ȃɂ��A�����A���ꂩ����莝���ŎB�e�����Ă�����ŁA���ꂪ��� �m�肽����������ł��B
�y���^�b�N�X�̊J���҂⌤���҂̕��X���A�J���������ۂɎ����ĎB�e����l�������A
���������ǂ������u�����N�����̂��A�����Ă��́u��U��v�Ƃ����B���ȑ��݂��A
�ǂ����͂��Ă����̂��A�A�����������Ƃɑ�ςȒ������Ԃ���M�������āA��������Ă������Ƃ��A
�Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă��܂����B����̖͂������̓��ł����B
���x���������A�S���̌ۓ��Ȃǂ��炭��A�ǂ����Ă��h���Ȃ��A���u���Ȃǂɂ��A
�Ή����Ă��邱�Ƃ��A���̂ЂƂł��傤���A���ꂪ�ǂꂾ�����ʂ�����̂��́A
�l�����A����Ȃ�ɂ���Ǝv���܂��B
�܂��A�������Ă������������e�Ɋւ��ẮA�����A���ŗ�Âɗ����ł��Ă��Ȃ��̂ŁA
���z�������Ȃ��̂ŁA���}���A����Ȋ����̌�Ԏ��ŁA���炳���Ă��������B
�����āATomato Papa�����K-7���̏Ⴕ�Ă���̂��ǂ����́A���l�ɂ͉��肩�˂܂��B
�i�����X�ɑ����܂��j
�����ԍ��F10896154
![]() 0�_
0�_
�i�O���X����̑����ł��j
�����ɗ�������܂��A���l���AK20D��K-7�ƒʂ��ĉ�������B�e�����āA
�r���ŒZ���Ԃł���K10D��K100D���g���Ă݂���ŁA�����Ȃ�́A�u��U��v�ɑ���
�����̎d��������܂����B��͂�A��U���@�\�́A���ۂɎ�Ŏ����Ă����A���̌��ʂ�
�m���߂���Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ��A�y���^�b�N�X�̂r�q�́A������������������Ă���͂��ł��B
������A�O�r�g�p���ɂ́A�듮���h�����߂ɁA�@�\���I�t�ɂ���Ǝv���܂����A
�����B��Ȃǂɂ��A���܂����Ή�����̂��x��Ă���̂��Ǝv���܂��B
����������������̂ł����A���p�̓W����Ȃǂł́A���ʌn�̍�i�ƁA���̌n�̍�i���A
�������ɓW������Ă��邱�Ƃ̓U���ŁA���̍ۂɁA�O�r�B�e�ƁA�莝���B�e���A
���Ȃ�p�ɂɎg�������āA��������̖������B���Ă������Ƃ�����̂ł��B
����Ȓ��ŁA�O�r�ɏ悹�ĎB���Ă��鎞�ł��A����ď����U����^���Ă��܂��āA
���u�����������鎞������܂��B�����Ď莝���ł��A��U���@�\��ON�ɂ��Ă��Ă��A
���u���i�̈ʒu�u���Ȃǁj���ł���͈͂��Đk���Ă��܂��A���u�����������邱�Ƃ�����܂��B
�����������A���x�����x���A�����悤�Ȕ�ʑ̂��B�e���Ă������ŁA�莝���ƎO�r���̃u�����̈Ⴂ��A
������U��ł��A�ʒu�u�������𑽂��܂ރu���ƁA�p�x�u�������𑽂��܂ރu���Ȃǂ́A
�����ȈႢ���A�����A�{���ɁA�Ȃ�ƂȂ��A�Ȃ̂ł����A�����Â����Ă���̂ł��B
�ł��A���́u�Ȃ�ƂȂ��v�����S��ƌJ��Ԃ��ƁA����͂܂����������ɂȂ��Ă��܂��B
���̎d�����A�{���ɐ��l�⌾�t�̐����ł́A��肭�\�������ł��Ȃ��悤�Ȏ��o�����A
�����悤�ɁA����Ōo����ς�ł����l�����̊ԂŁA���ʔF���Ƃ��āA���̌덷���������邱�Ƃ��ł���
���������o�������Ă��܂��B
��肭�͏����܂���ł������A�u��U���@�\�v�̌��Ɋւ��ẮA�l�ɐ������邽�߂ɁA
���u�Ȃǂ�p�����������Ă������������A������������A���̕��̎��Ԃ��A
�ł��邾���A�莝���ŁA�r�r�Ȃǂ̕ω���A�V���b�^�[�̉������̈Ⴂ�Ȃǂ�
�Ă������������Ȃ���A���x���J��Ԃ�����Ă݂�̂��A�ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
�������A����Ă����������悤�Ȏ������A��ɖ��ʂł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�܂��A���̎���������Ă��������ă����N�ŏЉ�Ă������������ƂŁA
�������Ă����������l�ԁE�����g���A�����ɂ��܂��I
����̃A�C�f�B�A�Ő��삵�����u�ɂāA�������Ă��������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�Ƃ��ɁA�u������v�̃I���I�t�Ȃǂ́A���،��ʂ́A�����y���^�b�N�X�ŕ����Ă������ƂŁA
�����C�}�C�`�����ł��Ă��Ȃ����Ƃ��A������₷���Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���A����������
�Ȃ肻���ȋC�����Ă���̂ł��B���̂��߁A�܂����x���A�q�������Ă��������āA
�����āA�����ł������Ă݂Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ɗ����܂����B
�Ⴄ�`�̎������@�ɂȂ邩�Ǝv���܂����A���Ȃ�ɁA�l���Ă݂����Ǝv���܂��B
�����͂���ȃ��X�ƂȂ��Ă��܂������Ƃ��A�����g�������Ă��܂��B�ł����́A����Ō�e�͂��������B
���т��т̂��������݁A���肪�Ƃ��������܂����I
�����ԍ��F10896158
![]() 1�_
1�_
�ESONY�Ȃ������ł����A�V�t�g�Ԃ����������Ă��Ȃ����[�J�[�ł́A
�p�x�Ԃ�ƃV�t�g�Ԃ�͂킴�킴��ʂ����ɁA�܂Ƃ߂ďc���������邢�͕��s�����̂Ԃ��A
�Ƃ���������ōl���A�������邱�Ƃ������悤�ł��B
���̂��߁A�p�x�Ԃ�ƃV�t�g�Ԃ�̈Ⴂ�Ɋւ��ẮA�������i�T�|�[�g�̗������j���[�Y�Ȃ̂�������܂���B
�܂����A���̈Ⴂ�ł���Ȃɂ��߂Ă�Ƃ́A��������v��Ȃ��ł��傤���ˁB�B
�u�b�`�m�n�m�́A�]���̊p�x�Ԃꂾ���łȂ��A�V���ɃV�t�g�Ԃ������Z�p���J��������
��`���A���̋Z�p�𓋍ڂ����}�N�������Y���ŋߔ������܂������A�o�d�m�s�`�w�ł́A
�Ƃ����Ɋp�x�Ԃ�A�V�t�g�Ԃꗼ���ɑΉ����Ă����Ƃ������Ƃł��傤���H�v
�ƁA����������߂ΈႤ�������Ԃ��Ă���̂ł��傤�B
�E����̏����ꂽ�悤�ɁA�p�x�Ԃ�Ɋւ��ẮA��_�̖�肪����܂��B
����_����_�Ƃ��Č����Ƃ������Ȋp�x�Ԃ�ł����Ă��A�ʂ̓_����Ƃ���Ίp�x�Ԃ�ƃV�t�g�Ԃ�̍����ł��B
�Ⴆ�A�����Y�O�ʂ̎�_����Ɋp�x�Ԃ���`���āA�J�����������̂�
�摜�f�q�̒��S����Ƃ���p�x�Ԃ�Ȃ�A����́A�p�x�Ԃ��Ƃ������́A
�p�x�Ԃ�ƃV�t�g�Ԃ�̍������A�Ƃ����̂��ނ��됳�m�Ƃ������܂��B
�o�d�m�s�`�w�́u�V�t�g�E�p�x�u���ɑΉ��v�iTomato Papa����̕\���j�Ƃ������A
���̈Ӗ��ɂƂ邱�Ƃ��ł��邩������܂���E�E�E���A
������ɂ���A����́A�V�t�g�Ԃ�Ɗp�x�Ԃ�́u�����v������A�Ƃ������ƂƂ͑S���Ⴂ�܂��ˁB
�E�o�d�m�s�`�w�@�́A���͂�������V�t�g�Ԃ����������Ă���I
�Ƃ����\�����ے�͂��܂���B
�j�V�͉����x�Z���T�[��������Ă�Ǝv���܂����A�������������x�Z���T�[���Ȃ��Ă�
�V�t�g�Ԃ����s�\�Ƃ͌����܂���B�����A
�u�����y�[�W�̐����͊p�x�Ԃ�̐����v�ł���̂͊m���ł����A�܂��A
�݂Ȃ���̌��ł́A�ǂ����A�u���s�ړ��ɑ��ẮA�f�q�������Ȃ��v�悤�ŁA
�o�d�m�s�`�w���A�A�i�E���X���Ȃ��A���ʂ��Ȃ��V�t�g�Ԃ��@�\�𓋍ڂ��Ă���
���R�Ɋւ��ẮA�悭������܂���ˁB
�����ԍ��F10896333
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����F
>���łɍ폜���ꂽ���X�ŁA�����t���A���l�́A�����Ɗo���Ă��܂��B
>���ۂɂ́A������������m�F�ł��Ȃ��ԂɁA�������܂�č폜���ꂽ���X������̂�������܂��A
>���Ȃ��Ƃ��A�L�����Ă��邱�ƂɊւ��ẮA�y�[�W�̕ۑ������Ă��܂����A
>���̂ق�������A���ꂪ�ǂꂽ�������������݂̎d���ł��邩�́A�w�E�����Ă��������܂��B
����Ȃ��Ƃ����Ă���q�}������̂ł�����A
���̐l�̏������݂������Ɠǂ�ŁA������Ɨ������邱�ƂɎ��Ԃ������Ă��������B
�u���̓��ł͂܂������ł��Ă��܂��v�ł͂Ȃ��A
�܂��A���̏�Ԃő��l�̎����A�������݂�ے肷��̂ł��Ȃ��B
���������Ȃ��ł����A����ł��B
���͓r�����珑�����݂���߂�ROM���Ă܂������AMZ-LL����ȊO�̏������݂͗L�p�Ȃ��̂������A
���̕��X�̊Ԃł́u�������v�����藧���Ă��āA���ɋ����[���ł��B
���������Ӗ��ł́A���́u�X���v�ɂ͊��ӂ��Ă��܂��B
���[�炳��F
>�N�����Ȃ����폜�˗����Ă�Ɣᔻ�����q�g�����܂������H
�ȑO�A���������������݂��������Ǝv���܂��B
�ŁA���̏������ݎ��̂��폜���ꂽ�悤�ł��B
�iMZ-LL����͕ۑ�����Ă邩������܂��ǂˁj
�܁A���̂P�s�ȊO�́A���[�炳��̏������݂ɂ͓��ӂ������܂��B
�J�����̂��Ə����ĂȂ��ł�����A������폜����܂����ˁ[�B
�����ԍ��F10896397
![]() 11�_
11�_
���A�r�炵�I�ȏ������݂�����l���A�Ȃ��Ȃ�����Ȃ��̂ŁA���ӂ����Ȃ����������݂����Ă���Ƃ���ł����B
�u���o�̈Ⴂ�v��������ɂ��āA�����̊��o���݂�������A�������Ȃ������肵���̂ɁA
�܂��̂����ȏ������݂����Ă����l���A�ēo�ꂵ�܂����ˁB�����������悤�ɁA�r�炵�I�ȏ������݂�
���Ă���l�ƁA�������Ă���̂�����A���܂�������ł͂���܂���B
�Ƃ肠�����A�܂��́A���̂����̌��_�����w�E��������A�����̊ԈႢ�⊨�Ⴂ���A
�����ł��邱�Ƃ́A���Ă݂ė~�������̂ł��B
���͂Ɍ��������v���C�h�������Ȃ��ƁA���m�ȏ������������Ƃ́A����Ǝv���܂��B
������̌f���ŏ������܂ꂽ�������̐l�́A�^�������A���Ƃ��Ԉ�������⌟�ł��A
�����B�����L�ł���A�����ł��郌�x���ŁA�c�_�H�̂悤�Ȃ��̂��A���Ă��邾����
�y�����A�Ƃ������ɂ��A�����܂����B�����Ă��ꂾ���Ńv���C�h����������Ă���悤�ɂ��B
�m�����C�ɂȂ��Ă���悤�ɂ��B
���́A�����͂Ȃ肽������܂���B�ƂĂ����ʋ��t�ɂȂ�܂����B����Ɋ��������ł��B
�ǂ�Ȍ`�ł���A���ꂾ���r�炵�I�Ȑl��A�{���́u�r�炵�v���o�v���Ă��܂����X���b�h�ɂāA
�ǂ�ł���l�B�̖��ɗ��������ȏ������x�W�܂����̂́A�ǂ������Ǝv���܂��B
���̗͂ł͂���܂��A�X����Ƃ��ẮA�����͂Ȃ�Ƃ��Ă��B�����������Ƃł́A����܂����B
�����Z�p�̂��Ƃ�����Ă����傤���Ȃ��ł����A�ԐړI�ɕ����Ă����A�y���^�b�N�X�̒����ɓn�錤���̂��Ƃ�
�������Ƃ��Ă��A�����͂������̂ŁA���̃X���b�h�𗧂��グ�Ă����̍��ɁA�����ŏo�Ă����C���^�r���[�̋L���ق� �ł��B
�܂��f�W�C�`�ɂr�q��������͂��߂�����̍������ɁA����܂ł̌o�܂ɂ��A�����G����Ă��܂��ˁB
�y���^�b�N�X���[�U�[�̊F����̑����͒m���Ă���L�����Ǝv���܂����A�����N�����Ă��������܂��B
�u�U�E�J���҃C���^�r���[�@�@PENTAX K100D�v
http://www.digi-came.com/jp/modules/interview5/index.php?id=14
������͕ʌ��ł����A�u�d�q������v�Ȃǂɂ��āB
��ʂ̐�����F�����A�����K-7
http://www.camera-pentax.jp/k-7/tanip/007/index.html
����̔�ꂪ�܂������Ă��炸�A�Ȃ��Ȃ���Ԏ�����������������܂���B
��ςȎ��Ԃ�v�������ł��B
�����ԍ��F10896565
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�ŁA���ݎc���Ă��鏑�����݂ŁA�����A���������N�Ɍ����ē{���Ă�̂��A
�w�E���Ă���̂��A����Ȃ��ӏ����������Ƃɂ��Ăł����A���łɂ��Ȃ�̃��X���폜����āA
���̕����ɁA�̂悤�ȃ��m������̂ł��B
���ۂɂ́A���̃X���b�h�ɂāA���́u�v�����邱�Ƃ��ł��܂��A�������łɉ��x���A
�܂�Ŏ����폜�˗��ڂ������̂悤�ȏ������݁i�����m�����Q�x�قǁj������Ă���̂ł��B
��������������ł��B
�����āA�܂��ɍ��A���̏������݂���A���́u�����Ȃ��v�Ɍ����Ă̌��t�ɂȂ肦��\�����A����̂ł��B
�����A�����̓s���̈����ӌ���X�ɑ��āA�������悤�ƍl���Ă���Ǝv����̂�
�������S�O�Ȃ̂ł��B���͂ނ���A�����l�̋C�����Ō����A�ǂ�ȃ��X�ł��c���Ă��ꂽ�ق���
�ǂ��ƍl���Ă��܂��B���̂ق����A�ӔC�������ď������߂�l������ł��傤�B
�Ƃ��ɁA���i����ϋɓI�ɏ������܂�Ă���l�B�ɂ́A���Ȃ𗥂��ė~�������̂ł��B
�������A�����ɂ́A�u�̂ăA�J�E���g�v�ƌĂ��悤�Ȗ��ɂāA�������t���g����
�������݂�A�����{���ɍr�炵�ȊO�̉��҂ł��Ȃ��������݂����āA�Ȃ�̐ӔC���Ƃ炸�ɁA
�����Ă����A���������l�������o�v���Ă��܂����B
�Ǘ��ґ��ł���A���i�R�����A�������폜�ΏۂƂ��āA�폜���邱�Ƃɑ��ẮA
���́A����ł͕���͌����܂���B�����āA�����g�̏������݂��A�����ĉ������t��
�g�����킯�ł͂Ȃ��Ƃ��A�r�炵�I�ȏ������݂�����l�����ƁA���X�̓��e���W���Ă��邾���ŁA
�ꏏ�ɂȂ��č폜������܂����B�@�ǂ�ł���l�B�̂��Ƃ��l����A���̍폜�����R���Ƃ͎v���܂��B
������A�������ސl�́A�܂����������������������̐l���ǂމ\��������A
���̌f���ɂāA�₽��ɐl�̗g�������Ƃ�����A���_�Ɍ����邱�Ƃ��A�������t�ŕ��J������A
�����Ȃ��Ƃ������́A�������̂��ƁA�����̂ق����Ԉ���Ă���\�������邱�Ƃɑ��ẮA
������x�A�T�d�ɏ������܂˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��厖�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����g���A��� �C�����Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B
�܂��߂Ƀ��X�����Ă��܂��܂������A���l�ɑ��Ă̏������݂́A�܂��͈�x�A��߂Ă݂Ă��������B
�����āA�l�ɍs���┽�Ȃ����Ȃ��������̂Ȃ�A�܂��͎��炪���H���āA��{�ƂȂ��
�ǂ����Ǝv���܂��B���͂悢������Ӎ߂̎d��������l����A�w�����Ă����������Ƃ������A
���ЃX���b�h�ŁA�������p�����p���Ă����ۂ��A�����ƎӍ߂ƒ������������́A
���̂��ƂŁA�������ė_�߂����X�������������������������Ⴂ�܂����B
�ǂ��s���́A�l���\��������A�����s���́A���ʋ��t�ƂȂ��āA�܂��l�ɉe����
�^���邱�Ƃ�����܂��B�@����f����̂́A�������g�ł����A�ł���u�c�b�R�~�v�Ƃ�
�ƂĂ������Ȃ��悤�ȁA�u�r�炵�I�v�ȏ������݂�����l��A�{���̍r�炵�A�Ȃǂ́A
�^�������́A���͂������Ȃ��ł��B���ʋ��t�ɂ����Ă��������܂��B�{���ɍ������X�������܂����B
���@��Ƃ́u��U���̌��ʂ̈Ⴂ�v�����ۂɑ̊��ŗ����ł��������������Ă݂����ł����A
�ǂ������g�r�g�r�Ƃ͌����A����Ǝv���܂�����A�܂����̃X���b�h��������͂Ȃ��ł����A
�������ɁA������Ӎ߂������Əo���Ȃ��l�����ɂ́A���炭�������݂��T���ė~�����A
���������C����������܂��B�����̊��Ⴂ��F�߂邱�Ƃ��A�ǂ����Ă���Ȃɕ|���̂��A
���ɂ́A�s�v�c�łȂ�܂���B��������ȃv���C�h�̂ق����d�v�Ȃ̂�������܂���ˁB
������x�A�������o�Ă����Ƃ���ŁA����܂ł����Ă����������Ƃ�Y��āA
�����������悤�Ȋ�����āA��������ł���l������̂ɂ́A���������Ă܂��B�����͔��Ȃ��Ăق������̂ł��B
�i�X���b�h�̎�|���O��āA���X�ƊԈ�������_�������Ă���l�����̂��߂ɁA�����ǂꂾ����ς��������A
���ꂷ��z���ł��Ȃ��̂ł�����A�J�����̍\���Ɋւ��āA�z���͂��s�����Ă���̂����R��������܂���j
�r�炵����܂߂āA�������������Ƃ��������Ă��������܂����B
�����ԍ��F10896579
![]() 1�_
1�_
�p�x�u���ƃV�t�g�u���ƂŁu���̂̉^���̋L�q�v���čl���Ȃ���ʖڂł���B
�����Y��_�����_�Ƃ���O������ԁB
�i�Ⴆ�j�����[�Y���̌��������� z���A���_����J������������ x�����L�сA�c������ y�����L�т�B
�J�����Ƃ������̂̉^���́A(vx,vy,vz), (��x,��y,��z) �̘Z�̃p�����[�^�[�ŕ\���ł���A�ł��B
�t�Ɍ����ƁA�Z�̃p�����[�^�[������Ȃ���Ί��S�ɂ͕\���ł��Ȃ��A�ł��B
�ӂ��̎�u����@�́A���̂��� ��x �� ��y �̓�̏���m���Ă��ł��B
���̃X���Ō����V�t�g�u�������邽�߂ɂ� vx �� vy �̓�̏���Z���T�[���K�v�ł��B
���̃Z���T�[�� z���i�����j�𒆐S�Ƃ����u���˕����i�ȒP�ɂ� x���Ay�������j�v�̉����x������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ���邩�������H�ł��傤�ˁi�����ł��傤���j�B
�y���^�b�N�X�̌����u������̂��߂̉����x�Z���T�[�v���Ă̂́A���˕����ł͂Ȃ��A�u�~�������v�̉����x�� x���ɕ��s�Ȓ�����Ɏ�������̂Ȃ̂ŁA����ł̓V�t�g�u������͓����܂���B
������̉����x�Z���T�[�ŏo����̂� ��z ����̊p�x�u����A������u��]�u����v�����ł��傤�ˁB
�y���^�b�N�X�̐l�́i�Z�p���𐳊m�ɓ`�������Ȃ�j�A
�E�ǂ̐����̉^�����H
�E�ǂ��������̉^�����H
�m�ɂ��˂Ȃ�܂���B
�u�ǂ̐����v�Ƃ́u�����x�v���u�p���x�v���H�Ƃ������Ƃł��iv �� �� ���̖����j�B
�u�ǂ��������v�Ƃ� x���Ay���Az���̂��ꂼ��̐����̂��Ƃł��i�����̑傫���̖����j�B
���������Ȃ��T�|�[�g���́u�Z�p���Ƃ��Ă͐M���ɒl���Ȃ��v�Ƃ��ׂ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F10896611
![]() 2�_
2�_
���s�̂�������A�������݂��肪�Ƃ��������܂��B
������Ă��邱�Ƃ́A���ɂ͂��܂藝���͂ł��܂��A����炪�������Ƃ��Ă��A
������������A�܂������ʂ̕��@�ŁA�ʒu�u�����ł��Ă���\��������Ƃ́A
�l�����Ȃ��ł��傤���B�ł���A���������]���������Ďc���悤�ȏ����������Ă����������ق����A
�ǂ�ł�����X���A���̐��m�ȏ���m���Ɍq����ۂ��A�𗧂��Ǝv���܂��B
�����āA�ł���A���̃X���b�h�̎�|�ɍ��킹�āA�䎩���̎g�p���������������݂���������K���ł��B
���������Ă������Ƃ́A��Ɂu�Z�p���v�ł͂Ȃ��A�u�B�e�Z�p�̏��v�Ƃ��āA�̂r�q�ɂ��Ă̂��Ƃł��B
���̃X���b�h�̎�|�I�ɂ������ł����A�����g���m�肽�����Ƃ��A����ł����A
��b�����Ă��������ۂ��A�����A���p�i�̎B�e�ɂāA���̃V�t�g�u���̔��u���̕���A
���ɖ𗧂��Ă��邱�Ɠ`���A�����������������e�N�j�b�N�ł͖����A�e�N�m���W�[�̂ق���
�Z�p����ɂ́A�m�����قƂ�ǂȂ����Ƃ��A�����Ă���܂��B
���ۂɁA���̂��߂ɁA�g�U���U������킹���������A�킴�킴���Ă��������܂����B
�������A���̂ق����A�������[�U�[�Ƃ��Ď��ۂ̐��̎g�p�����A���t�� ��͂�g�U���U��������āA
��b�����Ă��������Ă��܂��B����ȕ��ނ̎g�p�@�ł����A�����̂����ɗ��ĂA�ƁB
���s�̂��������A�����ŏ������������̐l�B�̒��ł́A����ł͔[����
�����Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�䎩���ŁA�䎩�����m�肽�����Ƃɍ��킹���A�₢���킹���A
�e�Ђɂ��Ă݂Ă��������B������̃X���b�h�ɂẮA�������������Ƃ̓X���Ⴂ�ł��邱�Ƃ́A
�䎩�o������������ŁA�ł���A�z���������āA���������݂���������K���ł��B
�����ԍ��F10896691
![]() 0�_
0�_
>�u�ǂ̐����v�Ƃ́u�����x�v���u�p���x�v���H�Ƃ������Ƃł��iv �� �� ���̖����j�B
���Ȃ݂Ƀ����Y��_�����_�Ȃ̂ŁA�����x���p���x���u���ʂɂƂ��Ă͐����x�ł���v�Ƃ͕\���ł��܂��ˁB���̕ӂ������̃|�C���g�Ȃ�ł��傤�i��X�ɂƂ��Ă��T�|�[�g�ɂƂ��Ă��j�B
�ł��A�p���x�Z���T�[�œ������͂����܂ł��p���x�B�V�t�g�u���������̂Ȃ�����x�Z���T�[���K�v�Ȃ�ł��i���˕������������o��������x�Z���T�[�j�B
�p���x�Z���T�[�œ��������V�t�g�u����ɗp������g�t���ʁh�ɂȂ����Ⴂ�܂����� �� �������������ō��ӂ������Ă��Ȃ��̂����̃X���̖��_�B
�����ԍ��F10896699
![]() 2�_
2�_
���s�̂�������A���Z�������A�ă��X���肪�Ƃ��������܂����B
���Ƃ����@�킾�Ƃ��Ă��A���ۂ̎g�p�������A����̂悤�Ȍ�ӌ����܂߂āA
���������݂���������A�����Ƃ܂��܂��A�ǂ�ł�����X�̎Q�l�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A
�Ɗ����܂����B�����g�́A�m��������܂���̂ŁA���e��ے肷�����͂���܂���B
��͂�A���̌��̒��ŁA���̗��_���A�ǂ������`�ŁA�B�e�ɁA��U���@�\�́A����ꂽ���ʂ̉摜�ɁA
�o�Ă���̂��A�����������Ƃ��������ق����A������̃X���b�h�I�ɂ́A����₷���A�Ƃ����C�����Ă��܂��B
���������݂������������Ƃ��̂��̂́A�������ł��B���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F10896746
![]() 0�_
0�_
�u�B�e�Z�p�̏��v
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503511532/SortID=5754488/#5766690
�ق��Ɂu�ʒu�̃u���v�W
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501611022/SortID=6403596/#6406736
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503511532/SortID=7058423/#7059152
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210882/SortID=7643336/#7659723
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503511532/SortID=7797270/#7797299
���̑��A�ukuma_san �ʒu�̃u���v�Ō������Ă݂܂����B
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchWord=kuma_san+%88%CA%92u%82%CC%83u%83%8C&BBSTabNo=0&Image1.x=0&Image1.y=0&PrdKey=&SortType=datedesc&SearchRange=0&PageMax=20&act=input
�����ԍ��F10896792
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����
���̊F����������Ă��邱�Ƃ͊�{�ꏏ�ł��B
�ŁA���Ƃ͌��ŁB���l���̕����o�l���ɏ悹�����Ԃ��g�����肵�Č��Ȃ����Ă܂��ˁi���ɂ͎v�����t���Ȃ������f���炵���A�C�f�A�j�B
����A���Ɂu�V�t�g�u���i�ʒu�u���j�v�ł�����B�p���x�͗^�����ɁA�����Ƒ��x�Ɖ����x��^���Ă���B
�u�莝�����L�̑��x�E�����x�ƈقȂ�i������J���������䂵�Ȃ��j�v�\���͂���܂����A�ڂ낢�O�r�g���Ă��V�t�g�Ԃ�͋N���肦�܂�����ˁi��ԂƂ��o�l���Ƃ��́A��ʎB�e�ōl�����镨�����f�����Ƃ������Ɓj�B���̐�������Ă��Ȃ�����A��͂�u�V�t�g�u���͕�����v���ȂƁB
�g�u���͕��̂̉^���Ƃ��ĕ\���ł���h�B
���̂̉^�����ČÓT�ł�����A������x�́u���ʌ���v�ʼn�b���ė~�����ł��B
�����́u����̋�_�v�ł͂Ȃ��u���o�̕\���v�ł���͂��B
�l�Ԃ̊��o�ɂ͑��҂֓`�����Ȃ����̂���������܂��B�ł��u���́g�^���h�Ƃ��ĕ\���ł��邵�A�i���ۂɕ������f���ŕ\������͓̂�����A������ƌ����āj�\������w�͂�������ė~�����Ȃ��Ǝv���܂��B
���ꂪ�P�Ɂu���̃J�����̓u���ɂ����ł��ˁv���ď������݂�������N�̔���������Ȃ������Ǝv���܂��B
����Ȃ��āu���o����u���h�~�Z�p�𐄑��v����Ȃ�A����Ȃ�̋��ʌ��ꂪ�K�v�ł��傤�A�Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F10896822
![]() 6�_
6�_
MZ-LL����
�ꐶ�������J�ȕ��͂ŏ����Ă����܂����A�������ɂ��̒��d�����@�ɂ��A�ƌ��������Ɏv���Ă��Ă��鏊�ł��B
���̃X���ł͖l�̎���ɂ��A��������������ŁA�܂Ƃ��ɓ����Ă͂�������L��������܂���B�i���Ȃ��͂�������Ȃ��A�Ǝv���Ă����邩������܂��A���������Ȃ��̂ł��B�e�L�X�g�̐��E�͑���ɂ����v��ꂽ�炨�I���ł��j
�����A�F�X�Ƌc�_���������͂������̂ł����A�������Ɋ�����̂́B
�u���Ȓ��S�v
�ƌ������t�ł��B
�l�͊m���j�|�V���w�����������MZ-LL����Ɂu��ɍ��g���Ă��������v�Ə����āA���̐������S���Ă����������l�ɋL�����Ă��܂����A���̌��t�P�܂��B
���������i�C�X�Ȍ��t��MZ-LL����ɏ������������A�S�������Ă��܂��B
�����ԍ��F10896842
![]() 9�_
9�_
>������������A�܂������ʂ̕��@�ŁA�ʒu�u�����ł��Ă���\��������Ƃ́A
>�l�����Ȃ��ł��傤���B�ł���A���������]���������Ďc���悤�ȏ����������Ă����������ق����A
>�ǂ�ł�����X���A���̐��m�ȏ���m���Ɍq����ۂ��A�𗧂��Ǝv���܂��B
�u�g�p���o�ŃV�t�g�u����𐄑��v���u���[�J�[��������n�t���������������v
���������b�̗���ɂ���̂ł���A���̓�̘b�ɐ������������Ⴂ���Ȃ����Ă��ƂȂ�ł��B
�u�܂������ʂ̕��@�ŁA�ʒu�u�����ł��Ă���\���v�����[�J�[���������Ȃ��Ⴂ���Ȃ���ł��B
���̎��_�ł̓��[�J�[�̘b�͑S���M�p����A�ł��B
�\���͍l�����܂���B
�Ⴆ���C�u�r���[�Ŕ�ʑ̂̑��ʏ�̈ړ����x�𑪂�A����Ɗp���x�Z���T�[�Ƃ̌v�Z�ʂƂ̈Ⴂ����V�t�g�u�����x���Z�o�A�Ƃ��B
�u�B���Ă݂���V�t�g�u�������Ȃ��悤�Ɋ�����ꂽ�v�A�u���[�J�[���V�t�g�u��������Ă���ƌ������v�A���̓�̏��ł͔������Ȃ�ł��B
�����ԍ��F10896879
![]() 4�_
4�_
���ۂ������A���݂̂Ȃ�����A�u�l���̕]���v�Ȃǂ͔����܂��H
MZ-LL����Ȃ�ɐ^�����Ǝv���܂����A����I�ȏ������݂͓ǂޕ��ŗ����Ηǂ��ƍl���܂��B
�s����ΏۂɊJ���ꂽ��ł��B
�������ޓ��e�ƕ\���ɂ��Ă������v���͏o���Ȃ��ƍl���܂��B
�Ȃ��A�{��ł͂���܂���̂ŁA���̃R�����g�́u�폜�v����Ă����\�ł��B�����i.com�Ǘ��̕��X
�����ԍ��F10896881
![]() 3�_
3�_
���s�̂�������A���т��т̃��X���肪�Ƃ��������܂��B
�䏕���ł��邱�Ƃ́A�d�X���m���Ă���܂��B
�������A�����������Z�p�I�ȏ������݂݂̂����������ƁA���ʓI�ɁA�O�Ɠ�����
�J��Ԃ����ƂɂȂ�܂��B����͑��Ђ̎��엦�n�̃X���b�h�ł��A���l�ł����B
���́A���o�_�����A�Z�p�_�̂ق����A�ǂ��Ƃł��Ƃ�Ă��܂����Ƃ��A�����������f���łł͑����A
�Ƃ��Ƀh�[�h�[���肵�Ă��܂����ۂ��A���������N�����Ă��邽�߁A���́A�������������̂ł��B
�Ȃ��Ȃ�A�������������A�����g�����ɗ��A�ƍl���邱�Ƃ́A���܂薳������ł��B
�i��������������A�����n�̏��ւ̃����N�́A�Õ����̂悤�ő�ϖʔ��������ł��B���肪�Ƃ��������܂����I�j
�������A�ǂ�ł�����X�⏑�����ސl�B�̒��ɂ́A��������������~�����A�Ƃ���
�l�B�������Ǝv���܂��B�@�V�K�ŁA�X���b�h�𗧂��グ��@�\��������̌f���ɂ�
����̂ł�����A����A�V���ȃX���b�h�ɂāA�����������F����ŁA�Z�p�n�̌�b��
���Ă݂�A�ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��ρA����Ǝv���܂��B�Ȃ��A���o�I�Ȃ��Ƃ��d������A���̃X���傪����Ă���X���b�h�ɂāA
���l���̐l���A�S�����ď�������ł���̂��́A�悭����܂���B
�ǂ�Ȃɂ������Z�p�I�Ȃ��Ƃ������Ĕے肵�Ă���l�����Ă��A�����g�́A�ʒu�u����
�����Ă��邱�Ƃ��A���̌��Ō��������Ƃ��ł��A��������p���Ă�����ŁA�����Ă���̂ł��B
���낢��ƌ��������Ƃ͎v���܂����A�����炷��A���̌����҂̈ꕔ��A����Ŏ��ۂ�
�r�q�̊J���Ɋւ�������X�ȊO�ŁA�����������f���ŁA�Z�p�n�̂��Ƃ�b���Ă��A
���ʓI�ɁA�����������o�邱�Ƃ͂Ȃ��Ɨ\�����Ă��܂��B
����Ƃ͕ʂɁA�����܂��܂����Ⴂ���Ă��邱�Ƃ�����Ƃ͎v���܂����A���Ƃ�����
�X���b�h�Ⴂ�Șb�肾�Ƃ��Ă��A���X��Ԃ��āA��������ł��܂����ȏ�A�������������Ɋւ��ẮA
���ꂩ��A������A��������Ȃ��Ƃ������Ă���A�Ӎ߂��Ă�������ł��B
���̂��߂ɂ��A����́A�ł���A�X���b�h�̎�|�ƈႤ�b��́A�ɗ͔����Ă���������Ə�����܂��B
���J�ɏ����Ă��������������A�ȒP�ɖ������邱�Ƃ͂ł��܂���̂ŁB
�����ԍ��F10896913
![]() 0�_
0�_
kuma_san_A1����
�l���̕]���Ȃ������Ȃ��ł��B
kuma_san_A1��������ʂ�ŁA�����ׂ����m�ł����A�l�͎c�O�Ȃ���A�u�q�g�͊���œ��������ł���v�@�ƌ����X�^���X�ł��B
�e���A�Œ���̊�������̃��C���������āA���̃��C���܂ꂽ�A���܂�Ȃ��A�Ɋւ��Ă͂��̐l�Ԃ̎��R�ȍٗʌ��ł��傤�B
���Ȃ��Ƃ������o���Ȃ����͂���������āA����ɑ��āA�F�X�Ȏ�������āA���������݂��ɐi�߂����Ǝv���ď��������͂ɑ��āA�c�O�Ȃ��痝���o���Ȃ����͂őΉ������A�Ō�ɂ�
�u�����_�����v�ƂȂ�͎̂d���Ȃ����ł��傤�B
�X���傳��ɂ͈ꌾ���������A�D���ɂ��Ηǂ��̂ł��B��
�Ǘ��l����ցB���̃R�����g�������Ă�����Č��\�ł��B
�����ԍ��F10897116
![]() 8�_
8�_
�c�A�ʂ̈Ӗ��ł����_�͏o���l�ł��Ȃ��c�B
���́A�v���t�ɂ������Ă���ʂ�u������Z�p�I�Șb�v�Ȃ�ĉ��̋����������̂ŁA�ǂ��ł��C�C�ƍ��܂Ő���s�������Ă��邾���ł������l�B
���̂��Ɖ]���A�����܂ŏڍׂ��[���Z�p�_��g�ɂ����g�R���ŁA�����̎B�e����ł͂���Șb�̓N�\�̖��ɂ������Ȃ����x�́u�r�v�ł�����Ȃ��B�i��)
�ł����A�ǂ����ăX����a�́A�����̖�̕�����Ȃ������Ɂu�ًc�v���́A�u���_�v���Ă���l�����ɑ��Ă͂܂Ƃ��Ɏ�荇��Ȃ���ł����ȁH
�������i�j�������āA�i�j�����Ă���̂�����C�Â��܂��ȁH�H
�v�͂��Ȃ��̘b�́u�]����u������_�Ɛ��������͉����ŏ��������o�I�Șb�v�ɉ߂��Ȃ��̂ł́H�i���ɑ����̕��X�͂��C�Â��ł��ȁB�j
���Ă��āA�{���Ɂu�C�^�C�v�ł��Ȃ��B�i�j
�L���m���ł����X�Ƀ_���_���ƃA�N�r�ȊO�͏o�����ɂȂ��b��W�J���Ă����łł������A�R���͐��Ɂu�ɂߕt���v�ł��Ȃ��B
�����̂����̐��E�Ɂu�����v�ł����Ă��邩�̂悤�ȓs���̂����Ή��ƁA���̓Ǝ��̘_���ɂ͂��������A�E���U���ł��Ȃ��B
�{���ł́A�u����ȃN�\�b��ł悭���R�R�܂ʼn�������������������郂�m���v�Ɗ��S���Ă��܂��܂��ȁB
���̕������̒ʂ�A�Z�p�_�����A���������ۂ̓^�_�́u���o�_�v�ɉ߂��Ȃ��u�Z�p���S�b�R�̗V�сv�͂����~�߂Ē����������m�ł��Ȃ��B
�܂��A�ꕔ�̋Z�p�_�A�\�r���������q�g�ɂ́A����ł͓s���������悤�ł����l�H(���)
�Ō�ɕ\��ɑ��Ă̎��́A���`�����u���o�I�v�Șb�Ƃ��Ă͂ł��ȁB
�Ⴂ�́A�L��ł��傤�Ȃ��B
��u������J������(���݂̂Ɍ���@)�A
�{�f�B������F�R�j�J�~�m���^��SweetDigital�A�y���^�b�N�XK10/20/7
�����Y������F�L���m��1DMK3�A5DMk2�A(�ؕ��Ƃ���)7D�A�j�R��D3/300/80
�c�����g���Ă��܂����A���͈̂��|�I�Ƀt�@�C���_�[�������肷�郌���Y�������g���Ղ��A�ߐڂł̕��i�l����i�ł́A�{�f�B�����g���Ղ��ł��ȁB
�����͂ǂ��炪�ǂ����͎��Ƃ��Ă̓����Y���̕��ɂ�◘�����ǂ��l�Ȉ�ۂł��B
���A�������ǂ��Ɖ]���̂́A���́A�͂����荷�Ƃ��Ă͕�����܂���ȁB
�v����ɏ��F�͂���Ȓ��x�̘b���Ɖ]�����ł��傤��B
�l�I�ɂ́A�{�f�B������̗p���[�J�[�ɂ͏����I�ɍ��������Y�ɂ̂݃����Y����@�\�����ڂ��āA���ÑS�Ă̔�ʑ̂ōœK�ȕ�����ŎB�e�ł���悤�ȃA�h�o���e�[�W�������Ă��ꂽ��ǂ��Ǝv���܂��Ȃ��B
�c�A�����܂���Ȃ��B���̘b��������Ƃ����Ȃ��ʂɁu�����b�v�Ɂc�B(����)
�����ԍ��F10897173
![]() 21�_
21�_
���̏������݂ɒE��������܂����B[10896565]�ł��B
�@�����́A�����͂Ȃ肽������܂���B�ƂĂ����ʋ��t�ɂȂ�܂����B����Ɋ��������ł��B
�����́u����Ɋ����������ł��B�v�ł��B
�@�����́A�����͂Ȃ肽������܂���B�ƂĂ����ʋ��t�ɂȂ�܂����B����Ɋ����������ł��B
���n���ȃI�b�T������
�����猩��A�n���ȃI�b�T������̂��̏������݂قǁA���킢�����Ȃ��炢��
�u�ɂ��v�������݂͂���܂���B
�䎩���̊��o���݂��āA�Ƃ��Ƀ��[�J�[�Ԃ̕�̈Ⴂ������Ȃ��̂Ȃ�A
����ŗǂ��ł͂Ȃ��ł����B�@�ډ������悤�ȏ������ŁA�l�Ɏ���Ȏ��������K�v���Ȃ��ł��傤�B
�O�ɂ���l�Ԃ��A�ߏォ�猩��A�ǂ�Ȍ��_�����Ďw�E�ł���̂ł��B
�����A���ꂭ�炢�͏o���܂��B
�i�Ƃ��Ɏ��̎d���ł́A���_�Ȃ�Ă����ē�����O�̃��m�̒����������āA������L���˂Ȃ�܂���j
�T���猩��A�o�������ꂼ�ꂨ���������Ƃ������Ă��邭�炢�A�N�ł�����̂ł��B
�������A���̓X����̐ӔC�Ƃ��āA�n���ȃI�b�T������⑼�́A�����������ݕ�������l���A
�s�����X�܂ŁA����ǂ݂����ɁA���Ȃ�������Ȃ��̂ł��B
�������X����Ŗ�����A����Ȃ����́A�ǂ܂Ȃ���ς݂܂��B�����̖����X���b�h�́A
���̃X�����̂�`�����Ƃ�����܂���B
�����A�ǂ�Ȃɔ]���Ŗϑz�������Ƃ��Ƃ��Ă��A���̎��͂��ǂ��āA�������͂��鐸�x��������x���邱�Ƃ́A
���̒N�ł��Ȃ��A�����g���m���Ă���̂ł��B����𗘗p���āA���������邱�Ƃ�
�����Ă������Ƃ��A�����N���̎Q�l�ɂȂ�͂��ł��B���Ȃ��Ƃ��A���̌��Ȃ̂ł�����B
�n���ȃI�b�T�������A�ꕔ�̐l�B���ׂ�₷���̂́A���҂̊������̈Ⴂ��A�\�͂�o���̈Ⴂ��
�����Ƃ��đz��ł��Ȃ����߁A����ȏ������݂𑱂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̑ʖڂȕ������炢�A���ʂɌ������āA�����͒��߂��芄������肵�āA�Ή���������̂ł��B
����Ɋ��������߂Ă͂����܂���B�����Ă��������g�������Ƃ��Ă��ʖڂł��B
�ǂ̐��E�ł��A�o�����璼�������߂��l�Ԃ̌������Ƃ́A������x�͑��d����܂��B
�l�b�g��ł���f���邱�Ƃ́A����ł����A�t�Ɍ����A���肪���������l�Ԃł��邱�Ƃ��A
�z��̒��ɁA����Ă����˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�����g���A���Ⴂ���Ă������Ƃ�A���������Ă��Ȃ����ƂɊւ��ẮA���ꂩ���
�m�F�𑱂��Ă��܂��B�@���ꂾ���������Ԉ���ď������܂ꂽ�X���b�h�̊Ǘ���Ή����A
�ǂꂾ����ςȂ��Ƃ��A����Ă����Ȃ��l�ԂɈ̂����ɏ����ė~�����͂Ȃ��ł��B
�����ԍ��F10897378
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����@
>�@�@K20D���C�ɓ����āA�Q����������قǑ�R�g���Ă��Ă��܂����A���엦��
��95���ł��邽�߁A�O�r�g�p���́A�\�}�ɑ��Ă̗]���̑傫�����A������x�A
���m�ɗ\���ł��܂������A�莝���ƂȂ�ƁA���������s�Ɉʒu�u���Ă���̂��A
����Ƃ��t�@�C���_�Ɉʒu�Y��������̂��A�������ɁA����{�Ƃ������x�ł́A
�m���߂��܂���ł����B[10881729]
�@�u���������s�Ɉʒu�u�����Ă���̂��v�Ə�����Ă��܂����A�����ł�������
�u�����p�x�u������v�ȗv�f���Ƌ^���������A���s�Ɉʒu�u���Ɣ��f���ꂽ�̂�
�����ĉ������B
�@K20D�AK7�̃u����ɂ��Ă��A�p�x�u���łȂ��ʒu�u�����傾�Ƃ���Ă���
�̂Ɠ�����T�̍���������������悤�Ɏv���܂��B
�@�p�x�u���ƃV�t�g�u���iMZ-LL����͈ʒu�u���ƕ\���j�̈Ⴂ���������ł悭��
������邱�Ƃ��܂��͏d�v�Ȃ��ƂƎv���܂��B
�@�y���^�b�N�X�i��БS�̂łȂ��L��̒S���̕��j���ߍ�肾�Ǝv���܂��B
�@�뎚�E���ɂ��Ă͂���قNjC�ɂ���邱�Ɩ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10897751
![]() 12�_
12�_
>induster����
�u���������s�Ɉʒu�u�����Ă���̂��v�Ə�����Ă��܂����A������
�������̃u�����p�x�u������v�ȗv�f���Ƌ^���������A���s�Ɉʒu�u��
�Ɣ��f���ꂽ�̂������ĉ������B
���̃X����l�͒��N�̒b���ɂ���āA�莝���ł̊p�x�u�����ł���
���x���܂łقڊ��S�ɉ��������ނ��Ƃ��ł��鎩�́u�_�̎�v��̓���
��Ă��邻���ł�f^_^;
�܂����������N�̒b���ɂ���āA�N���Ă��邱�Ƃ���������̂���
����V�t�g�u���i�ʒu�u���j���A������ƕ����Ă��邱�Ƃ��莝����
���ɂ߂��鎩�́u�_�̊�v���̓�����Ă��邻���ł�(>_<)
���̂悤�ȃh�f�l�ɂ͈ꐶ�����ł��Ȃ������������Ȃ����o�ł�(���)
�����ԍ��F10898813
![]() 4�_
4�_
������������u���̕����\�������݂̂�ȂƂ͋t�Ȃ̂�������܂���ˁB
���C�u�r���[��ʂ���ɂ���A�J�������������Ɉʒu�u��������Ɣ�ʑ͉̂�ʂ̏�����Ƀu���܂��i��u����̖����J�����j�B
���݂̂�Ȃ͎B���ʂ���ɂ��Ă��܂��B
�B���ʂ���ɂ���A�B���ʂ̉������Ƀu���܂��i��u����̖����J�����j�B
�B���ʃV�t�g����u����@�̏ꍇ�B
�J�������ʒu�u��������ƁA�B���ʂ̓J�����ɑ��ē��������ɂ��炵�܂��i�J�������������u���Ȃ�A�B���ʂ̌��̎��t���ʒu��肳��ɉ��ɂ��炷�j�B
�J�������p�x�u��������ƁA�i��]�̒��S�̓����Y��_�ł��J�����{�̂ł������ł����j�����Y��_����Ƃ��āA�p�x�u���Ƃ͋t��]�����ɎB���ʂ����炵�܂��i�J��������]�ɂ�艺�����Ɉړ�����Ȃ�A�B���ʂ̓J������ŏ�j�B
�p�x�u����̂ق�������͓���ł��ˁB�u�����S�̔F���ɂ������͐F�X���肻���B
�ǂ����Ɋ�Ȃ苤�ʔF���Ȃ�������Ȃ��ƁA��������ׂ��Ă���̂��킯���킩��Ȃ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F10898981
![]() 2�_
2�_
���T�Ԃ����Ă����_�̂łȂ��X�����n�߂��猩�鍪�����Ȃ��̂ő�G�c�ɏq�ׂ܂��B
�V�t�g�u���i���s�u���j�Ȃ�ĕ�o���Ȃ��ł��傤�H�B
�@
�����w�r����w�K����W�]���i���B�e���A�������ƃr�������h�ꂵ�܂����������V�t�g�u��
��͂���܂���ł����B
�������⋴�̒��������璬���ݕ��i���B�e���A��^�g���b�N�����ʉ߂���Əc�h�ꂵ�܂���
�c�����V�t�g�u����͂���܂���ł����B
�u���ʂ������̂�������܂��A�����x�Z���T�[�Ȃ�Ė����̂ł́E�E�E�B
�@
�X����a
���X���ꂽ���̘b�͎��ꂸ�A������p�����_��A�������X��L���Ȃ玩�g�̃u���O��
�J�݂�������Ŏ��_�W�J���Ă��������Ȃ��ł��傤���H�B�������炵���ł��B���̃X���B
�i�^Digi�������g�̃u���O�Ŏ��_���q�ׂĂ��܂���B�j
�����ԍ��F10899313
![]() 14�_
14�_
���̑����̕��ƁA�������ǂ����Ă����܂ň���āA�Ȃ��Ȃ��b�����ݍ���Ȃ����A
����Ɖ����Ă��܂����B
���������܂ŁA��ӂ͋v�X�ɂP���߂����炢�ɂ͐Q�ꂽ�̂ŁA�������ڂ��o�߂����ɁA�q����܂����B
����̐[��߂��A�����̌ߑO���������̌ߑO���ɂ����āA���l���̕��Ɍf�������������A
�����Y�̈ʒu���ς�����ۂɁA�B���f�q�ɂǂ��������Ɍ��������邩�A�Ƃ����}���A
���͂�ǂނƁA�������Ă�₱�����Ȃ�̂ŁA�摜����������x �L�����āA�����Ȃ���A�Ƃ��A
�H�����Ȃ���A�Ƃ��̍Œ��ɁA�����̐g�̂⓪�̈ʒu��ς����ۂɁA�����鐢�E���ǂ��ς�邩�A
�Ƃ������Ƃ��A���߂āA�l�������Ă݂܂����B
�����āA�C�t���܂����B���������Ă������Ƃ́A��U���ɂ��Ă��A�����Y�ƃ{�f�B�̈ʒu�̈Ⴂ�ɂ��Ă��A
���ׂāAmm�i�~���j�P�ʂ������͂���ȉ��̘b�ŁA����������ƂȂ�悤�Ȉړ��͈̔͂�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
��ӁA�Ō�ɂo�b���O�ɁA���L�X�E�f�E�K�[��������Ƃ��̏������݂�����������̂����āA
�Ȃ�ŁA�莝���ɂ��Ă��O�r�ɂ��Ă��A�ʒu�u���A�Ƃ������ʒu���ς�邱�Ƃ������̖ڂ�
����Ȃ��낤�H���ĉ��߂āA�����܂����B
���́A�G���i�Ȃǂ��O�r�ŎB��ۂ͂������A�莝���ŎB��ۂ��A�قڊ��S�ɐ^���ʂ���A
�c�݂�X�����Ȃ��A�l�p�����m���l�p���B���悤�ɕ��i����P�����Ă���܂��B
�����āA���ꂪ�ł���悤�ɂȂ����̂́A���͋≖����⍂���R���f�W��EVF��t���ł̎B�e�̎���ɁA
�O�r�B�e�ŁA�^���ʂ�^���Ղ��A�ǂ�����������A���^���ʂɋ߂Â����A�Ƃ������Ƃ��A
����g�̂Ŋo��������A�莝���ł��A�ǂ����������ɃJ������U��A�p�x�̃Y����
��ł���̂��A�Ƃ��������Ƃ���͂�A�̊��Œm���Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B
���ς�炸�A�O�u���������Ȃ��Ă��܂��܂������A�܂��A�O�r�ɂāA�傫���͓K���ł悢����A
�ǂɊG��������āA�J�������قڊ��S�ɐ^���ʂɂȂ�ʒu�܂Ŏ����čs���A�p�x�����킹�āA
�X���������������āA�^���ʎB�e���s���Ă݂Ă��������B
�����āA�O�r�̍\����A���E�����㉺�̂ق����������₷���ł��傤����A
1mm��2mm���G��ɑ��āA���s��Ԃ̂܂܁A�ォ���ɉ����Ă݂Ă��������B
�i�����X�ɑ����܂��j
�����ԍ��F10899411
![]() 0�_
0�_
�i�O�̃��X���瑱���ł��j
��X�̐��E�ł́A�����Ȃǂ̗��̌n�̍�i�ɑ��āA�G��̂��Ƃ��u���ʁv�Ɨ����ČĂԂ��Ƃ����X����܂��B
���ۂɂ́A�G��͊��S�ɂ͓��ł���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ��ɖ���Ȃǂ́A�J���o�X�̌��݂����邵�A
���G�̋�̃}�`�G�[���Ƃ��A������萷��オ���Ă���̂�����܂��B
�m���ɁA�O�r�ɌŒ肵�āA�u���ʁv��i���B�e���Ă��Ă��A�^���ʂ���Ŗ�����A
���������̍�i�̂悤�ȃ��m���ȁA�Ɗ����܂��B�Ƃ��ɉ����̓W�����i�Ȃ��B���Ă���ƁA
�J���o�X�̃w���i���݁j�̕��������������ڂɓ���܂��i�ŋ߂̉�Ƃ���吶�́A�z�����Ȃ����Ƃ������ł��j�B
�����āA�O�̃��X�̍Ō�ŏ������悤�ȁA�^���ʂɋ߂��B�e�̍ۂł��A�O�r���㉺�⍶�E�ɁA
�����╽�s�ŏ����Â������Ă����ƁA������x�̂Ƃ���ŁA���́u�w���v���ڂɂ��Ă��āA
���悻�u�^���ʎB�e�v�ƌĂׂ�悤�ȃV�����m�ł͖����Ȃ��Ă��܂��܂��B
�����A�^���ʂ�^���Ղ̎B�e�ŁA�������������̗̂v�f��������܂ŃJ�����̈ʒu��
�ړ�������̂́A���ɋH�ł��B�ނ���A�ǂ����p�x��t����Ȃ�A��45�x �I�ȁA
���̍�i�ɂƂ��āA�ł����h���̗ǂ��ʒu����B�e����ł��傤�i�������ʌn�ɑ����Ă��A
10cm���炢�̌��݂����锠���ۂ���i������܂�����A���������̂͂悭�߂ł��L�^���Ă����܂��j�B
���́A����̌ߑO���ɏ����Ă��Č��ǁA�f�����Ȃ������Q�̒������X�̂����A�Е��́A
���l���̕�������Ă���������������A����Ă����������}�ɑ��āA�������������Ƃ�
�Ⴄ�̂ŁA�œ_�����̂��ƂƂ��A�ǂ�������琳�m�Ȑ}�ɂȂ�̂��A�Ƃ��A���ꂱ��l�����̂ł����A
�l����l����قǁA�����Ώ����قǁA�������g������Ȃ����Ƃ������āA�f������ȏ�A
���������Ȃ��Ƃ͏q�ׂ�Ȃ��ł�����A�����ׂ����Ă���łȂ��ƂȁA�Ɗ����Ă��܂����B
�����ł́A�X���傾����A�������[�U�[�Ƃ��Ă̎B�e���@�A���p�i�Ȃǂ̂��Ƃ����܂菑���Ă��A
�Ȃ�̗�ɂ��Ȃ�Ȃ����ȁA�ƍl���āA���܂ł́A���܂��̓I�ɏo���܂���ł������A
���ہA�ǂ��������ɔ��������āA���������B�e���s���Ă���̂��������Ă��܂���ł����B
�ł��A�X���傾������āA���o����̌����痈��g�p���̈Ⴂ�����X���b�h�Ȃ̂�����A
�����B�e�҂Ƃ��āA��������Ԃ悭����Ă��āA���A���e�B�����邱�Ƃ��A�������ق����ǂ������̂��ƁA
���߂Ċ����܂����B���Ƃ��ƌo�����������X�^�[�g�����X���b�h�Ȃ̂ł�����B
���Ƃ��A�����ł���l���A���������Ă�����ł��B�ނ���A���̐l�̃E���`�N�ɍ��킹����A
�u���_���������Ȃ������Ɂv�A�Ȃ�āA�����ɂ��l�b�g�Z�������������Ȃ��Ƃ��ԂɎ��肷��K�v�͂Ȃ���ł��B
���⎄�ɋ߂����Ƃ����Ă���l�ɂ�������Ȃ����Ƃ��A��̓I�ɏ����Ηǂ��̂��Ǝv���܂����B
�����������f���̏펯��A�Öق̗�����A�X�����A���Ԃ̔�펯��������A���̂悤��
������Ɠ���ȋƊE�œ����l�ԂɂƂ��ẮA�����ł��Ȃ��s���p�^�[�������l����A��������A��
���낢��Ƃ������Ȃ��Ƃ�����̂ł�����A����ɗ������K�v�͂Ȃ���ł��B
�������Q�l���x�ɕ����āA�K���ɗ����Ηǂ��̂��Ɗ����܂����B
�i�����X�ɑ����܂��j
�����ԍ��F10899481
![]() 0�_
0�_
������ƒ����B
�@�������������f���̏펯��A
���̕�����
�@�������������f���̒��ŏ�������ł���l�̏펯��A
�Ɋ��������Ă��������B
�i�O�̃��X���瑱���ł��j
����ƁA��̓I�Ȉʒu�Y���̈Ⴂ�ɂ��ď����܂��B�ʒu�u���̂��Ƃ������O�ɁA
�ʒu�Y���̂ق�����A��̓I�ɐ��������ق����ǂ��ƍl��������ł��B
��͂�A�܂����ʌn�̍�i�̂ق����P���ł�����A����₷���Ǝv���܂����B
�O�r�ŁA�قڊ��S�ɋ߂��A�^���ʂɃJ�������ʒu���Ă��āA����ʑ̂̊G��̒�����
�t�@�C���_�̒������A�قڈ�v���Ă����Ԃł��B��������]�����̌X���������A
�l�p�����m���l�p�������Ă����Ԃł��B�����Y���c�Ȃ����Ȃ����m��o�ɂ����B�e�����Ŏg���܂��B
�����������ɁA�O�X���X�̍Ō�ɋ������悤�ɁA�O�r�̉_����A�ォ����1mm��2mm�A������
�ړ������Ă݂Ă��������B�ǂ��ł����H�@�킸���ɍ\�}�͕ς��܂����A��ʑ̂̊G��̒�������
�ړ��������������Y���܂����A�܂����ʐ���ۂ��Ă��邱�Ƃ͉���܂����A�u���̍�i�I�v�ɂ́A�����Ȃ��ł���ˁH
�������A���̂܂B�e���āA�L�^�����摜�����̂͂��ł��B���ʐ����ۂ���Ă����Ԃł́A
���s�␂���ɂق�̂킸���Ɉړ������ۂł��A�l�p�����m�͎l�p����ۂĂ܂��B
�������A�߂Ɋp�x���t���Ă��܂��A�����ɁA��`�c�݂�A���s�l�ӌ`���ۂ��c�݂Ȃǂ��A�����ɏo�܂��B
�����āAAdpbe Photoshop�Ȃǂ̐蔲���c�[�����g���ۂɂ́A�����������c�݂̂���摜�́A
���������ʓ|��������Ƃ����Ă���łȂ��Ɓi���ɂ͒����Ԃ�����܂��B�����Y�̘c�ȂȂǂ��V�r�A�ɏo�܂��j
�g���Â炢�ł��B�Ƃ��ɏ��ƈ���p�i���p�ق��L�̃`���V��|�X�^�[��DM�Ȃǁj��
�f�[�^��n���ۂ́A�O����Ɋm�F���܂��B
�������x�������Ă����A�B���f�q�����̕��ʂ̍��W�ɗ��܂��Ă��邱�ƂŁA���u���̈ʒu�u����
�ł�������ĕ�����A�Ƃ������Ƃ́A���������o���̒��ŁA�C�t���Ă���̂ł��B
0.5mm�Ƃ�0.8mm�Ƃ��͈̔͂ňʒu�u�����Ă��܂����ۂɁA�f�q�����ʓI�ɕ��V������ԂŁA�V���b�^�[������
�u�Ԃ���A�I�����A���܂��Ă���Ă���A�Ƃ������Ƃ́A���̂悤�ɁA�����Ƀt���[�~���O����l�ԂɂƂ��ẮA
���ɁA�Ƃ��Ă��A�������A������@�\�Ȃ̂ł��B
�Ƃ��ɁA���ؓ��́A�ǂ����Ă��k���܂�����A�莝���B�e�ŁA����������SS�ł����Ă��A
���u������m�������点�܂��B�ċz�𐮂�����A���ԂŊp�x���t���Ȃ��悤�ɌŒ肵����ȂǁA
���낢��ƌP�������Ă��܂����A����ł�����ς�A�k���鎞�͐k����̂ł��B
�Ƃ��ɁA�莝���ł̐^���ʎB�e�Ƃ����A����Ӗ��A�s�\���\�ɂ���ۂ́A
�i�������A���̓��̑̒���ʒu��p���ɂ���ẮA���s�̂ق��������Ƒ�����������܂��j
���ɋْ����Ȃ���A���ʐ����t�@�C���_�Ŋm�F���āA�����ƃV���b�^�[���܂��̂ŁA
�悭�k���Ă��܂��̂ł��B
�ł��AK-7��K20D�ƕ`�ʂ̗ǂ��P�œ_�ŎB�e����ƁA�G�̋�̃f�R�{�R�͂������A
���h��̊G���ƁA�J���o�X�̐��n�̕Җڂ܂Ńn�b�L���ƎB�e���ł��܂��B
�iRAW+�ŎB���Ă����A�V���[�v�l�X����ł��낢��I�ׂāA�{�f�B�� �����ł������ĕ֗��ł��j
����Ƃ͂܂������ʂɁA������C���X�^���[�V�����Ȃǂ́A���̌n�̍�i�ɂ��Ă�
���������G��Ă����܂��B���Ƃ��Ƃ́A�ނ��낻�����̂ق������Ȃ̂ŁB
�i�����X�ɑ����܂��B������������Ƌx�e�B�j
�����ԍ��F10899559
![]() 0�_
0�_
�O�̏������݂̕⑫�ł��B
��U���@�\ ON�̎��ł��A��������ƕ`�ʂ���A�Ƃ����Ӗ��ł́AK20D��K-7���A
�����悤�Ȋ����ŎB��܂����A�莝���ł̐^���ʎB�e�̐����̊m���A�Ƃ����Ӗ��ōl����ƁA
�t�@�C���_�̎��삪���m�Ȃ��߁AK-7�̂ق����A���s�������Ə��Ȃ��ł��B
�����̎B�e�ł������܂������A���̌n�ƕ��ʌn���������Ă���悤�ȓW����Ԃł́A
�W�����̕��͋C�Ȃǂ��L�^����ۂ́A�d�_��C�����邱�Ƃ͈Ⴆ�ǁA�B�e���@�I�ɂ͓���
�Ȃ̂ł����ǁA��_��_�̋L�^�I�ȎB�e�ɂȂ�ƁA���̌n�ƕ��ʌn�ł́A�܂�ŁA
���o���Z�p���A�C�����邱�Ƃ��A�������Ƃ��A�m�E�n�E���A����A�Ⴄ�A
�ƁA���l�͊����Ă��܂��B
�������A�Ⴂ�A�[�`�X�g�Ɂi�������������Ƃ�����y���ق��́jK-7��݂��āA
����̐��������Ȃ���A���̌n�̎B�e�̃R�c�̂悤�Ȃ��Ƃ��A�b���Ă��܂����B
���ʂɎ莝���ŎB�e����ɂ��Ă��A�O�r�ƃ����[�Y�ƃ~���[�A�b�v�ŎB�e����ɂ��Ă��A
���l�́A���̌n�̎B�e�̂ق����A�B���Ă��Ċy�������A�C���y�ł��B
�����āA�p�x���ς������A�J�����̈ʒu���ς��i���̂�����ʒu���ς��A�p�x���ς��܂����j
�ƁA���̍�i�������Ă���A�\��̂悤�ȃ��m���i�ʂɐ����n�̍�i�łȂ��Ă��j�A
�ǂ�ǂ�ω����Ă����āA�ƂĂ��y�����̂ł��B
���̌n�̎B�e�ł́A5mm���炢�ʒu���ς��ƁA�����Ă�����̂��Ⴂ�܂�����A
�ꕔ�̐l�ɍ���Ă����������A�}�̂悤�Ȋ����ŁA�i�V�n�������܂ł͂Ȃ��ł����j
�t�@�C���_��A�L�^���ꂽ�摜�ł��A�����̔�ʑ̂Ɣw�i���̕ω����m�F�ł��܂��ˁB
�ł��A����ς�y���^�b�N�X��SR�́A���̌n�̎B�e������ۂł��A�{�P���Y�킾������A
�悭�{�P���肷��A���邢�P�œ_�����Y���g���܂�����A���Ɏ莝���B�e�����₷���ł���B
�ł��邾���AISO���x�͏グ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��鎄�ɂƂ��ẮA�ǂ�Ȃɂ�������J������
�\���Ă��N����悤�ȁA���u���������邱�Ƃ́A�ƂĂ����͓I�Ȃ̂ł��B
���̕���̂��Ƃł���A������ł�������̂ł����i���ꂱ���A����܂Ōo�������������j�A
�����̏�����̃e�N�j�b�N��m�E�n�E�̕���������܂�����A������ǂ�ł���l�B�̒N����
�����Q�l�ɂ��Ă������������A�Ƃ����|���V�[������Ƃ͌����A����ł��A
���ɂ������Ȃ����Ƃ́A��R����̂ł��B
�O�ɁA���p�n�̎B�e�ɂ��āA��������ꂽ�̂ŁA�^�ʖڂɓ����Ă��܂������Ƃ��A
���̃X���b�h�ł�����܂������A������������̐l���A���́A���̗g�������Ƃ肽�������ł��邱�Ƃ��A
���X������������߁A���ꂩ��͈�� ���邱�Ƃ͂�߂܂����B
��Ԃ������āA�^�ʖڂɓ����Ă��A���肪���ۂɂ�������������Ƃ����C�������Ȃ�A
�k�J�ɏI���܂��B�Ȃ�A����̒N���ł͖����A�u�ǂ�ł���l�B�v�Ɍ����ď������ق����A�܂��}�V�ł��B
�����������A�f���ŏ����ȏ�A����Ȃǂ̂��Ƃ�̒��ŁA���X���i��ł����̂́A
���R�̂��ƂȂ̂ł����A�ɂ��ǂ�����������悤�ɁA����̎d������̏������ɂ��A
��͂�A�ǂ������A������ƁA���ۂɎd�������Ă��Ă��A�����܂��B
����ɂ���A�����ȑΉ��ⓚ�������߂Ă͂����Ȃ��A�Ɖ��߂Ďv���܂����B
�����ԍ��F10899648
![]() 0�_
0�_
MZ-LL����
���@�@�����āA���ꂪ�ł���悤�ɂȂ����̂́A���͋≖����⍂���R���f�W��
EVF��t���ł̎B�e�̎���ɁA�O�r�B�e�ŁA�^���ʂ�^���Ղ��A�ǂ�����������A
���^���ʂɋ߂Â����A�Ƃ������Ƃ��A����g�̂Ŋo��������A[10899411]
�@���w�t�@�C���_�[�ɔ�t���̗D�ʐ�������܂����H
�n���h���l�[������ސ�����Ɍ��w�t�@�C���_�[�J�����͂������������Ǝv���܂��B
���@�@�O�r�̍\����A���E�����㉺�̂ق����������₷���ł��傤����A
1mm��2mm���G��ɑ��āA���s��Ԃ̂܂܁A�ォ���ɉ����Ă݂Ă��������B
�@�u�X���C�_�[�v�i���[�J�[�ɂ��Ăѕ����낢�날��j�Ƃ������i�������ł����B
���p�����ƕ֗��ł���B
���@�@�������ɎO�r�̗p�ӂ�������A���Ƃ��Ɖ��B�e�̗\��ł�����A�莝����
�����Ȃ�Ǝv���܂��B[10871226]
���@�@��i�W�̉��B�e�ɂāA����������܂����BA50mmF2��DAL18-55mm�Ƃ����A
�����Ƃ��������G���g���[�ȃ����Y�ł��B���Ƃ��ƎB�e�̗\�肪�������ł����̂ŁA
�����ɋA��ۂɃJ�o���ɓ���Ă��������Y�����ł��B�����́A�O�r����[�Y���g�p
���ẮA�{�i�I�ȎB�e�ɂȂ�\��ł��B�͂��߂�K20D�Ƃ̃R���r�̂Q��̐��ōs��
�܂��i�ʂ̑g�ݍ��킹�ŁA�Q���R����������ނ��Ƃ͂���ł������j�B[10888542]
�@�Ɩ��@�ނ͎������܂Ȃ��̂ł����B
���@�@�������ɔ��Â��ꍇ�́AISO���x���グ�܂����A��������400���炢�܂łł��B[10866886]
�@���̏�ɂ���A�O�r����āA���̏�̏Ɩ��ŎB�e����̂ł��傤���H
�v���̃J�����}���łȂ��Ƃ���������Ă܂����A����A���p�u�t�Ƃ��Ďd���Ŕ��p��i
�̋L�^���B��Ƃ��������܂�Ă��܂��BTV�Ŕ��p����܂ł���Ă�����̎B�e�X�^�C��
�Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��B
���@�@������p�Ȃǂ́u��i�v�ł́A���������ςȎB�e�̎d�����ʔ��������肵�܂���
�ŁA���̎����炢�ł����ˁB[10880746]
�@�����Ȃ��Ă��܂��Ƃ��͂�L�^�ł͂Ȃ��ł���B�܂��A���I�ȋL�^���Ă��Ƃł��傤
���B
�@�{�B�e�������Ԃ͓����̎��ԑт̂悤�ł����A���w�҂̎G���̂Ȃ��ŎB�e���ꂽ�̂�
���傤���H����Ȃ�O�r���g���Ȃ�����Ԃ�ɂ������̂͗����ł��܂��B
����Ƃ��A����I���ゾ�����̂ł��傤���H
�@��Ԃ�ɂ��������A���p�i���L�^����B�e���@���̂��̂ɂ������������������
���A��قǐ��k����Ɋ���Ǝv���܂��B
���@�@�O�ɁA���p�n�̎B�e�ɂ��āA��������ꂽ�̂ŁA�^�ʖڂɓ����Ă��܂�������
���A���̃X���b�h�ł�����܂������A������������̐l���A���́A���̗g�������Ƃ肽
�������ł��邱�Ƃ��A���X������������߁A���ꂩ��͈�� ���邱�Ƃ͂�߂܂�
���B[10899648]
�g�������Ƃ����͂���܂���B������Ă��邱�Ƃ��A��Ԃ�̗������B�e�X�^�C��
�ł��A�ǂ̐�����猩�Ă��s���Ȃ�ł��B���̂��ߎ�������Ă���܂��B
���@�@���ꂩ��͈�� ���邱�Ƃ͂�߂܂����B
�@�Ƃ������A�X�W�̒ʂ������ł��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�����ɑ��قƂ����ǁB
�����ԍ��F10900081
![]() 12�_
12�_
���Ƃ��āA�u�c�Ȃ̏��Ȃ������Y�v�ɂ͕��ʗp�r�Ƃ��č��ꂽ�}�N�������Y���Y�����܂��B
�e�Ђ�50mm�A100mm�}�N���͊T�˘c�Ȃ����Ȃ��ł����AGANREF�Ȃǂ̕]���ł�PENTAX��50mm��100mm�̃}�N�������Y���ǂ��X�y�b�N�ł��B
�ėp�}�E���g�Ƃ��Ă�TAMRON��90mm�}�N���ASIGMA��50mm�}�N�����D�G���Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F10900307
![]() 1�_
1�_
�����Ă����̒����Ő\����܂���B
���e�Ђ�50mm�A100mm�}�N���͊T�˘c�Ȃ����Ȃ��ł����AGANREF�Ȃǂ̕]���ł�PENTAX��50mm��100mm�̃}�N�������Y���ǂ��X�y�b�N�ł��B
PENTAX�̃����Y�ɂ��Ă�APS-C�T�C�Y�ł̕]���Ȃ̂ŁA�u�e�ЂƂ��D�G�ȃX�y�b�N�v�Ƃ������_�ɂ����Ă��������B
�����ԍ��F10900324
![]() 1�_
1�_
�⑫�ł��B
[10899411]����[10899648]�܂ł̎l�̏������݂� �ׂ��ŏ������A�O�r�B�e�̂��ƂŁA
���t���炸�ȕ���������܂����B���������܂��B
�������A�O�r�B�e���͎�U���@�\�iSR�j��OFF�ɐݒ肵�Ă��������B
�i���̐ݒ�ɂ���ẮA�B�e���Ɏ����ŋ@�\���Ȃ��Ȃ�܂����B������͋C�ɂȂ�l�͒��ׂĂ݂Ă��������j
�����ԍ��F10900539
![]() 0�_
0�_
���ۂɂ܂������Ȏ����͂��Ă��Ȃ��ł����A�O�r�̏㉺��1mm��2mm�̔��ړ��ƁA
�\�}�������@�\��g�ݍ��킹��A���������Ă����ʒu�u������̑f�q�̓������A
�������₷���̂ł́A�ƍl���Ă��܂����B
�Ⴆ�A�ǂɊ|�����Ă���G��ƁA�O�r�ɏ悹���J�����ƃ����Y�ƎB���f�q���A
�قڊ��S�ɕ��s�ŁA�X������������A�����Y�̒����ɁA��ʑ̂̊G��̒��������Ă���A
���m�Ȏ���⎋�엦�̃t�@�C���_������K-7�ł��ƁA�G�悪�t�@�C���_�̐^�ɂ���͂��ł��B
�����Ń��C�u�r���[�ɐ�ւ��܂��B���̐��m�ȃt�@�C���_�̂������ŁA�덷�͂قږ����͂��ł��B
�����č\�}�������@�\�ɂāA�����āA�ق�̏�����ʑ̂̉�ʁi�\�}�j�̒��ł̈ʒu��
�ς��Ă݂܂��B����́A�G��̏㑤�̌��Ԃ��L�����܂��B���̍ہA�w�ʂ̑���{�^���́A
�u�な�i�^�C�}�[�̃A�C�R���̃{�^���j�v�����܂��B�����Č��ʓI�ɁA�\�}�̒���
�G�̈ʒu�͉�����A��̂ق��̌��Ԃ��L���Ȃ�܂��B
���̍ۂ́A�f�q�̓����́A�������ł��i���ɂ��ꂽ���Ŋm�F���Ă���܂��j�B
���̂��ꂽ��Ԃ̂܂܁A�����\�}���Ăђ����ɖ߂��Ȃ�A���������ǂ�����ł��傤�B
�P���ł��B�O�r���ق�̂킸���ɁA���ɉ���������̂ł��B
�����l���Ă���SR���쎞�́A�ʒu�u���ɂ������{����Ƃ��ẮA�B���f�q�̓�����
�Ԉ���Ă��Ȃ����Ƃ�����܂����B
�������A�����Y�̏œ_�����Ɣ�ʑ̂܂ł̎B�e�����̊W�ŁA�G�̏㕔�ɍ�������Ԃ̕��́A
�Tcm�L�������Ƃ��Ă��A���̎B���f�q�̈ړ��́A1mm�ɂ������Ȃ��ꍇ������Ǝv���܂��B
�������A���͑̊��ŁA��ʑ̑��̕��Ⓑ���̈ړ��ɑ��āA�J�����{�̂��A�ǂꂾ���킸���ɓ������������A
�o����P������A������x�͉���̂ł��B�����āA�������A���ۂɓ������Ă݂Ȃ���A���������܂��B
����́A�����Y�̏œ_������A��ʑ̂܂ł̋����ɂ���āA����A�قȂ�܂��B
���ꂪ�O�r�ł͂Ȃ��A�莝���ŁA�p�x�u���������������Ă���ƁA�f�q�͏����Ⴄ����������ƁA
���͗\�����Ă��܂��B���̕����́A�����ăy���^�b�N�X�̋Z�p�҂̌���ɂ́A�����܂���ł����B
���̓�����₭����ɂȂ邩��ł��B
���̎��̗\�z�ł́A�P���Ȉʒu�u���̍ہi�����ɂ́A�莝���ł͊��S�ȁu�ʒu�u���v�͋N����ɂ����j�́A
�����Y�̎����Ă���C���[�W�T�[�N�����Ȃ�A�����܂ł����Ă����A��{�����ŁA
�ł�������Ƃ͎v���܂��B�������A�{����mm�P�ʂ̏����Ȃ��̂Ɍ���܂��B
�p�x�u�����܂������ۂ́A�O�ɂ������܂������A�{���Ȃ�2mm�ړ����āA���̍��W�Ɍ�����˂Ȃ�Ȃ����ɁA
1.5mm�ɗ}���Ĉړ����邱�ƂŁi���ʓI�ɋt�����ɓ����̂Ƌ߂����ƂɂȂ�j�A�p�x�u����
�܂������ۂɕ����ȂǁA�������������p�����肦�������Ǝv���܂��B
���̕ӂ�́A���̊��S�Ȋ���̋�_�ł��B�������A�ʒu�u���̊�{�\�������ɂ�������A
�̊��Ƃ��ĉ����Ă��镔�������邩�炱���A�v�������ƂȂ̂ł��B
�œ_������B�e�����̏����A�������ʂɊW���Ă���ł��傤�B
���C�u�r���[���̍\�}�������@�\�A�����A�قڏ��߂Ď������̂ł����A���K����A
�W���̎B�e�̍ۂɁA�𗧂������ł��B�����͂����Ȃ�{�ԂŎ��������͖����������߁A
���܂Œʂ�ɁA�t�@�C���_�ł̎B�e�𒆐S�ɍs���܂����B��i�_�������Ȃ�����C�u�r���[��
�g���̂ł����A�ł��邾���������B���Ă������ق����A��Ƒ��Ɋ���̂ł��B
�o�b�e���[������邩�A�\���d�r�������Ă���Ƃ͂����A�s���ɂȂ�̂ŁALV�⓮��́A
�]�T�����鎞�ɂ����g���܂���BAC�A�_�v�^���g����������܂����AK20D��K-7�ł͍w�����Ă��܂���B
���̋@��ł͎����Ă���̂�����܂��B��������\���d�r���������������ƂŁA�Ή�����悤�ɂȂ�܂����B
��r�I�A�̂̃J�����ɔ�ׂāA�o�b�e���[�̎������ǂ��@��ł�����B
�i�\�}�������@�\�Ɋւ��āA���Ƃ�����Ƃ��������X�ɑ����܂��j
�����ԍ��F10900544
![]() 0�_
0�_
�\�}�������@�\�́A�O�r�ɃJ�������Œ肵����Ԃł��A�A�I���B�e���ł��Ă��܂��悤�ȁA
�������@�\�ł����A�O�̃��X�ŋ������悤�ɁA���ʂ̔�ʑ̂�^���ʂ���B��ۂȂǂ́A
�{���ɍ\�}�݂̂���ړ�����悤�Ȏg�������ł���킯�ł��B
�������A��肷����A��ʑ̂̊G��̑傫���ɂ���ẮA��������ʂŁA�ォ���A
�������́A�E�����̂ǂ��炩�́u�w���v�������Ă��܂��ł��傤�B
�f�q�̓����Ɋւ��ẮA�������x���m���߂܂������A�f�肵�ď����ɂ́A�����Ə�����
�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��A�Ɗ����܂����B�܂��ۗ������Ă��������B
�����A�y���^��SR�̍\���́A���x�������Ă����ʂ�A���u���̈ʒu�u��������ۂ́A
��{����́A�f�q���V���b�^�[�������u�Ԃ́A���W�ɗ��܂�i�{�f�B�̓�����ł������悤�Ɉړ�����j�A
�Ƃ��������ŁA��{�͂����Ă���͂��ł��B���Ƃ͂�������̉��p���삩������܂���ˁB
����ȏ�A���̋Z�p�҂ł��A�J���҂ł��Ȃ����������C�͂Ȃ��ł����A���̐�̘b�́A
���̂Ƃ���A�������m�肽���킯�ł͂Ȃ��A�@�����A�Ƃ��������ł��B
�Ȃɂ����₳��Ă��A�����邱�Ƃ́A�����ɂ͓���ł��B
.
�����ԍ��F10900592
![]() 0�_
0�_
�����́AK-7�̔ł�����A�i���m�ɂ͌�p�@�ł͂Ȃ��̂ł����j�O�@��ł���K20D���܂߂��b���
���S�ɂ��Ă��܂��B�����Ă��́A��U���̋@�\���g�p�����ۂ́A���@��⑼�̎d�g�݂Ƃ�
�g�p���̈Ⴂ�A�������͈��Ȃ����ƂȂǁA���̌����痈�銴�G��m�肽�������̂ł��B
�iSR���ڋ@��ł́A�ق���K10D��K100D��Z���Ŏg�p�o��������܂��j
�����āA�����������Ƃ�m�肽���̂́A�������ł͖����̂ł́H �Ǝv���܂����B
�O�ɂ������Ă��܂����A���́A�ǂ̕����̕���D��Ă���Ƃ��A�ǂ̃��[�J�[���ォ�����A�Ƃ��A
�����������Ƃ������C�͖ѓ��������̂ł��B����Ȃ��Ƃ������A������Ŏg�p����
���Ă����������̎g���Ă���@��́A���Ȃ���Ă��܂��ł��傤�B
�ł���A���Ћ@�p���Ă��郆�[�U�[����B�ɂ��A���������������������̂ł��B
���l���~�����@��A�����Ă݂����@��������Ȃ�A���ÃJ�����X�ɓ����āA�܂��m�F����̂́A
��-7D��SweetD�̍ɂł��B�Ȃ��Ȃ��`�����X�����m�ɂł��܂��A�����K���A
���Ȃ��Ƃ��ǂ��炩���A���肵�����Ǝv���Ă��܂��B
���Ɏ������g���Ă����ASR�����@�킾�ƁA�R���f�W�ł����AOptio A30��A40������܂��B
A30�́A�������������g���Ă����̂ŁA��x����x�A�ǂ����Ă����̃J���������Ȃ����ɁA
�G��̐^���ʎB�e����������Ƃ�����܂��B�莝���ł͂Ȃ��A��Ƃ̎O�r���肽�o��������悤�ȁA
����ς�莝���������悤�ȁB�@�Ȃ�ɂ���A���t�͕֗��ȃJ�����ł��B
�����āA���̂��B�e����ۂ́A�����Y�̕`�ʂ�I�ׂ�A�{�f�B���̕�̋@��́A
��ϕ֗����ƁA�����鎞������܂��B
���낯�ނ�����Ƀ����N���Љ�������A�O����C�ɂȂ��Ă����A��900�ɂ��A
�t�@�C���_���Y�킳�݂̂Ȃ炸�A�f�q�̓���Ɋւ��Ă��A�������o�Ă��܂����B
�ȒP�Ɍ����A�B�e�҂��A�����̗��z�ɋ߂��ʐ^���B�邽�߂ɁA�������������\������
�����Ă���鎞������A�Ƃ����b���Ǝv���̂ł����A�����g�́A�����悤�Ȕ�ʑ̂�
�����B�e���邽�߁A������x�́A�e�Њe�@��̓�����m�肽���A�Ƃ����v��������܂��B
�� ��I�ȈӖ��ŗ~�����J�����́A�܂��ʂ̘b�ł��ˁB
�����ԍ��F10900681
![]() 1�_
1�_
MZ-LL�����[10900544]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/#10900544
�菇�̗v�|�ɖ|�Ă��܂�
�E�O�r�g�p�Łu�J�����S�̂��㉺�Ɉړ��v�Ɓu�\�}�������@�\�v�𗘗p���Ċm�F���܂�
1)��ʑ̂�LV�ɂĉ�ʒ��S�ɔz�����悤�Z�b�e�B���O����
2)�\�}�������@�\�ɂĉ�ʏ㕔�̌��Ԃ��L����(���𑀍�A�B���ʂ͉������ɃV�t�g)
3)�Ăє�ʑ̂���ʒ��S�ɔz�����悤�J�����̍�����Ⴍ�ύX����
�⑫�F�ʒu�u�����B�e�{���ɔ�Ⴗ��W����A�ʏ탌���Y�ł͍ŒZ�B�e����(���1/10�t�߂̔{��)�ɂčs���Ɨǂ��ł��傤�B
�������l���Ă���SR���쎞�́A�ʒu�u���ɂ������{����Ƃ��ẮA�B���f�q�̓�����
�Ԉ���Ă��Ȃ����Ƃ�����܂����B
���̗����Ɍ������Ԉ���Ă��܂��A����܂ł�MZ-LL����̗����͊Ԉ���Ă���Ƃ������Ƃ����珑����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
2)��3)�̏������t�ɂ���ƁA
2b)�J������Ⴍ�����牺���̌��Ԃ��L������
3b)�\�}�������@�\�ɂčĂє�ʑ̂���ʒ��S�ɔz�����悤��ʏ㕔�̌��Ԃ��L����(���𑀍�A�B���ʂ͉������ɃV�t�g)
�ƂȂ�܂��̂ŁA�u�B���ʂ����̈ʒu�ɂƂǂ܂葱����悤���䂳���v�Ƃ����̂͊ԈႢ�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F10900829
![]() 14�_
14�_
�����̏������ݓ��e�Ɍ�肪�����������̒����ł��B
�R�j�J�~�m���^��AS�Ɋւ��Ă��B���ʋ쓮���䎞�Ɂu���C�ƃz�[���f�q�v�ɂ�鑜��XY���ʏ�ł́u�ʒu���o�v���s���Ă������Ƃ���������Y��Ă��܂����B
������́u�ʒu���o�v�̓J�����{�f�B�ɑ���B���f�q�̈ʒu��m�邽�߂̂��̂ŁA�u�ʒu�̃u���v�����o������̂ł͂���܂���B
�Y������͈̂ȉ��̏������݂��Ǝv���܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/#10859511
[10859511]
[10859535]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/#10870027
[10870027]
�����ԍ��F10901658
![]() 0�_
0�_
���\�}�������@�\�́A�O�r�ɃJ�������Œ肵����Ԃł��A�A�I���B�e���ł��Ă��܂��悤�ȁA
�������@�\�ł����A�O�̃��X�ŋ������悤�ɁA���ʂ̔�ʑ̂�^���ʂ���B��ۂȂǂ́A
�{���ɍ\�}�݂̂���ړ�����悤�Ȏg�������ł���킯�ł��B
�悭����p��̊��Ⴂ���Ǝv���܂����A�u������(Tilt�Ƃ�Swing)�v�ł͂Ȃ��u�V�t�g(���C�Y�Ƃ��t�H�[��)�v�̂��Ƃł��̂ŁA�o���Ă����Ɨǂ��ł��傤�B
���Ȃ݂�35mm�t�B�����t���T�C�Y�p�̃����Y���g�p����ۂɃZ���T�[�̃V�t�g�\�Ȕ͈͂Łu�V�t�g�B�e�v�ł���悤�ȗv�]�́A�R�j�J�~�m���^��PENTAX�ɂ͂����Ԃ�̂ɏo���Ă���܂��B
�����A���������A�C�f�A�̗ނ͌l����͌����ɂ͎t���Ȃ�(���Ђ̌����J������ł����������Ă���Ƃ�������)���ƂɂȂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F10902150
![]() 1�_
1�_
�u������B�e�v�͎��̊��Ⴂ�ł����ˁB
web�Ō���ƃV�t�g�������Ƃ̋L�q������܂��ˁB
�u�t������v���ƃs���g�ʂ̃R���g���[���̂悤�ł��B
�ꊴ����̓V�t�g(���C�Y�A�t�H�[��)���{���̂悤�ȋC�����܂��̂ŁA���m�ȂƂ��낪�킩��l�̎w�E��������ꂵ���v���܂��B
�Ƃ肠�����A�킽���̎v�����݂ɂ�����ł��������Ƃ��ӂ�܂��B
�����ԍ��F10902491
![]() 1�_
1�_
MZ-LL����
���@�@��X�̐��E�ł́A�����Ȃǂ̗��̌n�̍�i�ɑ��āA�G��̂��Ƃ��u���ʁv��
�����ČĂԂ��Ƃ����X����܂��B���ۂɂ́A�G��͊��S�ɂ͓��ł���킯�ł͂�
���A�Ƃ��ɖ���Ȃǂ́A�J���o�X�̌��݂����邵�A���G�̋�̃}�`�G�[���Ƃ��A����
���萷��オ���Ă���̂�����܂��B[10899481]
�@�}�`�G�[���Ƃ����Ӗ��͍ގ����ł��B�����ł͓ʉ���\������Ă���̂ŁA����
�R���e�N�X�g�Ń}�`���G�[���Ƃ����͕̂s�K�ł��B�u�G��͊��S�ɂ͓��ł����
���ł͂Ȃ��A������萷��オ��v�Ȃ�ĉ]���Ă����܂����A���ꂪ���ɂȂ����
�ł����B
���@�@�����āA�O�̃��X�̍Ō�ŏ������悤�ȁA�^���ʂɋ߂��B�e�̍ۂł��A�O�r��
�㉺�⍶�E�ɁA�����╽�s�ŏ����Â������Ă����ƁA������x�̂Ƃ���ŁA����
�u�w���v���ڂɂ��Ă��āA���悻�u�^���ʎB�e�v�ƌĂׂ�悤�ȃV�����m�ł͖���
�Ȃ��Ă��܂��܂��B[10899481]
�@�K�ȏœ_�����̃����Y�̐���ƁA��ʑ̂ƂƃJ�����̓K�ȋ������l���܂��傤�B
���@�@�����������f���̏펯��A�Öق̗�����A�X�����A���Ԃ̔�펯��������A
���̂悤�ɂ�����Ɠ���ȋƊE�œ����l�ԂɂƂ��ẮA�����ł��Ȃ��s���p�^�[����
���l����A��������A�Ƃ��낢��Ƃ������Ȃ��Ƃ�����̂ł�����A����ɗ�����
��K�v�͂Ȃ���ł��B�������Q�l���x�ɕ����āA�K���ɗ����Ηǂ��̂��Ɗ����܂����B
[10899481]
���p�̐��E���ƊE�Ƃ����̂ł����B
���@�@�l����l����قǁA�����Ώ����قǁA�������g������Ȃ����Ƃ������āA
�f������ȏ�A���������Ȃ��Ƃ͏q�ׂ�Ȃ��ł�����A�����ׂ����Ă���łȂ��ƂȁA
�Ɗ����Ă��܂����B[10899481]
�@���������ʂ肾�Ǝv���܂��B�����̍l�������ď����Ȃ��ƁA�����Ă�������
���������Ŕ[���ł��Ȃ��̂ŁA�G���h���X�̏������݂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����̍l�������ď������݂܂��傤�B
���@�@Adpbe Photoshop�Ȃǂ̐蔲���c�[�����g���ۂɂ́A�����������c�݂̂���
�摜�́A���������ʓ|��������Ƃ����Ă���łȂ��Ɓi���ɂ͒����Ԃ�����܂��B
�����Y�̘c�ȂȂǂ��V�r�A�ɏo�܂��j�g���Â炢�ł��B�Ƃ��ɏ��ƈ���p�i���p�ق�
��L�̃`���V��|�X�^�[��DM�Ȃǁj�Ƀf�[�^��n���ۂ́A�O����Ɋm�F���܂��B
[10899559]
�@Photoshop���蔲���c�[���Ȃ�ł����B�������������Ȃ��g�����ł��B�K���ɎB��
�Ă�����Photoshop�@�\�̃t�B���^�^�䂪�݂ŕ����͎̂ד��ł���B�B�e�̒i�K
����c�Ȃ�r�����Ȃ��̂ł����B
�@�J�����{�f�B�ɂ͊S��������̂悤�ł����A�����Y��Ɩ��ȂǓڒ��Ȃ��悤�ł��ˁB
�����������ɂ��|�p����э�i�B�e�̐��Ƃ̂悤�Ȍ��Ԃ�����Ȃ��ł��������B
�@MZ-LL����́A����Ȋ������������̂悤�ł��̂ŁA���������ʂł̓��j�[�N�ȍ�i
�������ɂȂ�̂�������܂���B�ł��A���������c�������̐搶���炢�ł͂Ȃ�
�ł����B
�@��i�W�Ƃ������Ⴂ�܂����A�U��T�C�Y�̃M�������[���肽�`�Ԃ��炠��܂����A
�s�u�o�������Ƃ������Ⴂ�܂����A�n�斧���̃P�[�u���e���r�Ȃ玄�ł��o���ł���
�̂ł���B�������邱�Ƃł��Ȃ�ł��Ȃ��ł��B���ߏ��̘b��ł�����B
�@�X���𗧂Ă�̂ł���A�F����ƃC���^���N�e�B�u�ȃR�~���j�P�[�V�������Ƃ�
���Ƃɓw�߂�̂��Œ���̃��[���ł͂Ȃ��ł��傤���B���̎���ɓ����Ȃ������ł�
���A���̕��̎���ɂ������Ă��Ȃ��ł���ˁB�����̒b�����ڂ�����Ȃ�ĈӌŒn
���Ȃ�Ȃ珑�����݂͂����~�߂Ă��������B���ʋ��t�Ȃ�Ă����Ԃ��Ă����܂����A
�l�i����������~�߂Ă������������ł��B
�������Ƃ��������Ē����܂������A�k10900681]�́AMZ-LL����̏I���錾�Ȃ̂���
����܂���ˁB
�����ԍ��F10902846
![]() 28�_
28�_
���̂o�I���� [10899313]
���̃��x���ɂȂ�ƁA�O�r�Ȃǂ̑��u�ɑg�ݍ��܂ꂽ�ʒu�u����@�\���K�v�ł��傤�ˁB
���̏ꍇ�̓����Y�ƎB���ʂƂ̊W�Ƃ͑S���t�ŁA�n���Œ�̍��W�n�̈ʒu���ێ����鐧��ɂȂ�܂��i�������オ��Ή��A������Ώ�ɎO�r��L�k������j�B
�Ƃ�����A�B���f�q��u����@�̈ʒu�u����������ɂ��Ă͍��ӂ�����ꂽ�悤�Ȃ̂ŗǂ�������Ȃ��ł����B
�J���������Ƀu������B���ʂ͉��I�ł��B
�����ԍ��F10904495
![]() 1�_
1�_
�Ăꂽ�悤�ŁE�E�E�i�j�B
���s�̂�������@����A�V��V���B��Ƒ��ȕ��ɑ����Ẵ��X���肪�Ƃ��������܂��B
�i�X����̃R�����g�����҂��Ă����̂ł����E�E�E�B�j
K-7�������̐g�Ƃ��đ����X���������������͂���K-7�ɖ߂鎖���F���Ă���܂��B
�������A��U�����đf���炵���ł��ˁB��500���������Y���莝���B�e���܂����œ_
�������͂�800�����Ō�ݒ肷��Ɣ��u���łقڑS�ł��܂�����ˁi���j�B
�œ_�������̐���������̂��ȂƊ����鎟��ł��B
�����ԍ��F10905034
![]() 2�_
2�_
�P���Ȏ���Ȃ̂ł����E�E�E
���̃X���őO�q�̎����ōČ�����錵���ȁu���s�u���v�̂悤�ȃu�����āA�����莝���ł͋N���܂����ˁH
�������Ă�n�ʂ����̂悤�ɓ����Ȃ�����E�E�E
�莝���ŋN���镽�s�u���́A�ׂ����p�x�u���̘A���ɂ��[�����s�ړ����A���̑傫�Ȋp�x�u���ł���͂��ł��B
���l�Ԃ̐g�̂̍\����A���s�����S�ɕۂ����ׂ����쓮�͕s�\�ł�����B
Pentax���������Ă��镽�s�u���ɗL���ł���Ƃ��������́A���Ǝ莝���u�U��v�Ɋւ��邱�ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�l�̓L���m�����[�U�[�ł����A�ʏ�̎�U���������Y�g�p�ŁA
�Ȃ�ƂȂ��u���s�u���v���u��U��v�ɕ���������o��������܂��B
�����ۂ͌����ɂ͕��s�u������Ȃ��̂��낤�Ɖ��߂��Ă��܂��B
�C���[�W�Ƃ��Ă͉~�̖ʐς����߂邽�߂̊T�O�}�Ƃ��āA
�~��W�J���ĕ��s�l�ӌ`�ƌ��Ȃ��}������܂����A���̂悤�Ȋ����ŁB�B�B
�\���I�ɂ́u�����I�ɖ����v�ȓ����ł�����A�p�x�u���������@�\�ł���͖̂����ł����A
�[���I�ɑ������ʂ�����Ƃ������Ƃ͂���̂�������܂���B
�����ԍ��F10905656
![]() 4�_
4�_
����̒��A�������������݂̍Ō�ɁA[10900681]�̕��͂��A�b�v���܂����B
���̒���ɁA�͂��߂ċC�t�����̂ł����A�����̑O�̏������݂Ƃ̊ԂɁA�Ȃ�Ƃ������A
�����A�r�炵�Ƃ��r�炵�I�Ƃ��ȑO�́A��Ȃ��A�댯�ȃ��X���A���ł��邱�Ƃ�m���āA
�������ɁA����ȏ�A�h�����Ȃ��ق��������Ɣ��f�������߁A�Ƃ肠�����l�b�g�ڑ����܂����B
���̊ԁA�����g�����ƂɏW���ł����̂ł����A����Ǝ��ȊO�̐l�ł��A�y���^�b�N�X��SR��
�ʒu�u��������Ă��邱�Ƃ��A�����ł��邽�߂́A���ؕ��@���v�����܂����B
�����A�ʔ̓X�̓X���ɂāA���Ђ̃����Y���݂̂̕�̋@��ƁA���̌��ʂ̕ω����A��ׂĂ��܂����B
�ȉ��A�ȒP�ɏ����Ǝ菇�������܂��B
�E����ōs���ꍇ�́A��ʑ̂́A�����������āA�߂��猩��Ή��s��������悤�ȕ��̂��ǂ��B
�{�I�Ƃ��A�f�X�N�g�b�vPC��➑̂Ƃ��B�X���Ȃ�APOP��J�����̏���Ă���W����ȂǁB
�E�ŒZ�B�e�����̒Z�������Y�B�����ēX���̑��Ћ@�ɕt���Ă����ȉ�p�̃Y�[�������Y�B�L�b�g�����Y�ȂǁB
K-7��K20D�݂̂⏊�����Ă��鑼�Ћ@�ōs���Ȃ�A�}�N�������Y������ƁA�Ȃ��ǂ��B
�E���C�u�r���[������@�\������@�킪�K�v�B�����Y���̕�̋@��ł́A���͍����́A
�L���m����Kiss X3�A50D�B�j�R����D90�B�p�i��GH1�B�����Ŏ�ɔ�r���܂����B
�����āA���̏�ŁA��̈Ⴂ�̌��������m�F���邽�߁AK-7�����Q������A�X����K-x�ł������܂����B
�����͂���Ȋ����ł��B�����X�ɂāA�菇�������܂��B
�����ԍ��F10908328
![]() 0�_
0�_
�܂��ŏ��ɁA����Ȃǂ̗������������ŁA��L�̂悤�ȁA���������艜�s���������ʑ̂��A
K-7�Ȃǂ�SR���ڋ@�ɂāA���C�u�r���[�����惂�[�h�ɂāA�莝���B�e�̗��K�����Ă݂Ă��������B
�������ASR��ON�ɂ��Ă����Ă��������B
����ł͎B�e���j���[�R�́u����v�̒��ɕʂɂ���܂�����A�ԈႦ�Ȃ��ł��������B
���u���������ɕ����Ă��邱�Ƃ��A���������Ȃ��l������ƁA���̌����������Ȃ��̂ŁA
�܂��́A���K�ł��B�������x�̍����B�e������ۂ̃R�c�̕������A���p���܂��B
�����Y�̏œ_�����́A�Y�[�������Y�Ȃ�A�Ƃ肠����50mm������ɍ��킹�Ă݂Ă��������B
�t�H�[�J�X�́AMF�̂ق����A�Ă��Ƃ葁���ł��B
��L�̉��s���ƒ����������ʑ́A���ɖ{�I���Ƃ��āA����ɂT�Ocm���炢�̋�������A
���惂�[�h�œd�������āA�J�������\���܂��B����Ȃ�ɂ������肵���\�����ł���l�Ȃ�A
�t�@�C���_�[��`���ۂ̂悤�ɁA���ԓ��Ŏx���Ȃ��Ă��A���܂�ڗ������u���͋N���Ȃ��͂��ł��B
�����āASR�����삵�Ă���̂ŁA���r�́A�k���̂悤�ȃu���́A�����Ă���͂��ł��B
��ρA�f������ł�����A����Ȃ��l���ƌ��������Ȃ���������܂���B
���̂��߂ɁA�R�c�A�������Ă����܂��B
���́A����ł�����A�w�ʂ̉t�������Ȃ���̎B�e�ł��B�ʂɃV���b�^�[�������Ȃ��Ă������̂ŁA
���m�ɂ́A�B�e�͂��Ă��Ȃ��ł����A�t���ɂ�SR�ɂău��������ꂽ���悪�f���Ă���͂��ł��B
�t���̍��[�ł��E�[�ł��A��ʑ̂̂ǂꂩ�̏c�̒�����p���āA����{����{�̌��Ԃ��A�t���̒[��
�ł���悤�ɁA�\�}�����߂܂��B�ׂ����Ԃ����̂́A���̂ق����A�ׂ����u��������̂�
�Ȃ��̂����A����₷������ł��B�����ƍ\�����Ă���A���u���������Ă���̂ŁA
���̎����{���̌��Ԃ́A�����{���̕���ۂ����܂܂̂͂��ł��B
50mm�̏œ_�����ŁA�����Y��[����50cm���炢�̋����Ȃ�A�܂��p�x�u���̔��u����
�䗦���A���������������Ă��邱�Ƃ������ł��傤����A���̏ł́A�K�������A
���ׂ̍����Ԃ��u���Ȃ��قǂ̕���ʂ��A�K�������A�ʒu�u������ł��Ă���Ƃ͌���܂���B
�����Y�������Ă���ŒZ�B�e�����́A��{�I�ɂ͎���ʂł���A�t�B������B���f�q����̋������Ǝv���̂ŁA
�܂������Ă��̃����Y�́A�߂Â���͂��ł��B�������Ƌ߂Â��Ȃ���AMF�ŁA�s���g�����킹�A
�~�܂��ẮA�܂������ɑ��āA�ׂ����Ԃ�����Ă����āA�����𒍖ڂ��Ă��������B
�����ƃJ�������\���Ă���A�܂������Ă���͂����Ǝv���܂��B���������E�̌l���͂���ł��傤�B
�ŒZ�B�e�����ł��ASR�Ȃ�A�܂���������Ă���̂��m�F�ł���Ǝv���܂��B
�}�N�������Y�Ȃ�A�����Ƌ߂Â���ł��傤�B
�ȏ�A�y���^�b�N�X��SR������g���Ă���l���猩��A�����������ʂ̕�̌��ʂ��Ǝv���܂��B
�ׂ����Ԃ��Y���Ȃ����炢�i���ۂɂ͕����Ă���̂ŁA�����u���Ă���͂��j�A
�莝���ł������Ƃ����\�����o����l�Ȃ�A�����������Ƃ́A������x�A�̊����Ă���͂��ł��B
�����āA���Ƃقڂ܂����������悤�Ȃ��Ƃ��A���x�́ASR��OFF�ɂ��Ă���Ă݂Ă��������B
��ʑ̂ɋ߂Â��߂Â��قǁi�B�e�{�����オ��j�A��L�ׂ̍����Ԃ��u�����Ɉێ�����̂�����Ȃ�͂��ł��B
����́A����Ă݂Ă��炦�Ή���Ǝv���̂ŁA�ڂ����͏����܂���B
�����āA���Ђ́A�����Y���́A�p�x�u����݂̂��s���A��U���@�\�Ƃ̔�r�ɂ��Ăł��B
�i�����X�ɑ����܂��j
�����ԍ��F10908330
![]() 0�_
0�_
�i�O���X����̑����ł��j
���́A���܂��܁A�����Y���̕�̋@��ł́A���C�u�r���[�⓮�悪�B��郂�m�������Ă��Ȃ��̂ŁA
���傤���Ȃ�����A�X���ɓW�����Ă���J�����ōs�킹�Ă��������܂����B
�ڂŌ���Ή��邱�Ƃł�����A�Ƃ��ɋL�^���f�B�A�Ȃǂ́A���Q���܂���ł����B
���ʂɁA�ʔ̓X�̓X���ŁA�W���@���������Ă��邾���ł�����A�X������ɋ��͂���Ȃ��Ǝv���܂��B
�O���X�ŏ������悤�ȁAK-7����SR���ڋ@�ōs�������Ƃ��A�X���œK���Ȕ�ʑ̂������āA
�����悤�ȏœ_�����A50mm���炢�Ŏ����Ă݂Ă��������B�������A��ʑ̂܂ł̋������A
�ڑ��ŗǂ�����A�������炢�Ŏn�߂܂��B���C�u�r���[�Ŏ�Ɏ����܂����B
�����Y���̕�̋@����A�����Ɗp�x�u���̔��u������ł���悤�ŁA�|�[�g���[�g�ȂǁA
�ʏ�̂悭����B�e�����ł́ASR�ƂقƂ�Ǎ����Ȃ����炢�ɁA��̐k������
������x�́A�����Ă��܂��B�����āA�Ƃ��ɏœ_�����������ꍇ��A��ʑ̂������ꍇ�Ȃǂ́A
SR�����A�p�x�������ۂ̃u�����ł��镝���A�����L�����������܂��B
���������p�x�����Ă��A����Ă���܂��B
�ł��A�ǂ�ǂ�B�e�������A�O���X�Ɠ����悤�ɁA��ʑ̂̒����𗘗p�����ׂ����Ԃ��m�F���Ȃ���A
�k�߂Ă݂܂��傤�B���{�̃}�N���B�e�܂ł����Ȃ��Ƃ��A1/5���炢�ɂȂ鋗�����炢����Ƃ��A
��́A����{���Ƃ��̌��Ԃ��ێ�����̂���ςɂȂ�����A��ʏオ�A�v���v���Ɛk���Ă����肷��̂��A
�ڗ����Ă��܂��H�@�ŒZ�B�e�����ł͂������A�s���g�͍���Ȃ��Ȃ�܂����A
�������������߂Â��Ă݂�ƁA�܂��܂��k���Ă���̂�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
������u���ł��A�ʒu�Ԃ�i�V�t�g�Ԃ�j�����𑽂��܂ނ悤�ȁA�u�������A�n�C�u���b�gIS�ȊO��
����ڃ����Y�ł́A���Ȃ��Ƃ��A�����Ƃ��ĉ���Ǝv���܂��B
�����āA���Q����K-7�i�������͓X���ɂ���K-7�ł������Ɛݒ肵�Ă���Ȃ炩�܂��܂���j�ŁA
���A�����Y���̕�@�ŁA���낻���ׂ̍����Ԃ��ێ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����A�Ƃ����悤�ȋ�������A
�����悤�ȏœ_�����ŁA�B�e���Ă݂܂��傤�B�����ƍ\���Ă���A�܂��v���v�������悤��
���ۂ��قƂ�nj��ꂸ�ɁA����{���̌��Ԃ��A���̂܂܈ێ��ł����肵�܂��B
���́A�����Ńg�b�v���牽�x�������Ă����Ƃ���A��U���̎d�g�݂̈Ⴂ�ŁA
���ʂ��o�₷���A���ʂ��Ⴄ�ꍇ������ƁA�����Ƃ��Ċ����Ă��܂��B
�y���^�b�N�X����A���ɁA�ʒu�u������ł��邱�Ƃ��A�����������ł͂Ȃ��A
�ł���A���̐l���A�̊��ł���悤�ȁA���ʂ̈Ⴂ��������@�������Ă݂����ł��B
���ƁA�X���Ŏ����ɍs���O�ɁAK-7�Ƀ^��������V�O�}�̍��{���Y�[����t���Ă݂��̂ł����A
�]�����ɂ��āA�����C�u�r���[���ɁA�킴�Ɗp�x��t����ƁAK20D�̃_�X�g�����[�o���̂悤�ȁA
�B���f�q���A������A�Ƃ��������Ă�������������������܂��ˁB
�Y�[�������O���L�p���ɂ܂킵�āA�������炢�̊p�x��t����ƁA�����������Ȃ�܂�����A
�]���̂ق����A�傫�����C�悭�A�B���f�q���ړ����Ă���悤�ȋC�����Ă��܂��B
���ʼn���A�Ƃ����̂��ʔ����ł��B
�����ԍ��F10908335
![]() 0�_
0�_
kuma_san_A1����A���낢��ƌ�����������������A���肪�Ƃ��������܂��B
����̒��A�Ȃ��X���b�h�����������ƂɂȂ��Ă��āA�h�����Ȃ��ق����ǂ����ƁA
����Ă��܂��܂����B�ǂނ̂��x���Ȃ�܂����B�\����܂���B
[10900829]�̃��X�ŏ����Ă����������A
�@��2)��3)�̏������t�ɂ���ƁA
����n�܂�����A��ς킩��₷�������ł��B�����A�����Ă������������ƂƓ���������A
����̌ߑO���ɁA���C�u�r���[�Ŏ����āA���̒��ŁA�f�q�̓������C���[�W�����ɂ��ւ�炸�A
���܂����A�[���������Ȃ��܂܂ł����B���܂��ɗǂ������Ă܂���B
�f�q�̓����Ɋւ��ẮA�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̌������A���������Ă������Ƃ��A
���̃X���b�h�ɂāA�����A���m�ɓ`���Ă��Ȃ��\�����������A���ꂩ��A
�����������Ă������Ƃ����߂Č������Ă݂܂��B
�{���̂Ƃ���́A�ʒu�u���Ɋւ��ẮA�ǂ����삵�Ă���̂��́A�y���^�b�N�X��������
���\���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����Ă������Ƃ��v�������ׂ邵���Ȃ��̂ł����A
���������Ă������Ƃ́A�e�N�m���W�[�Ƃ��Ắu�Z�p�v�ł͂Ȃ��ASR�𗘗p����ۂ́A
�u�B�e�̂ق��̋Z�p�v�ł��������Ƃ��A�����ƃn�b�L���ƁA�ŏ��ɏ����Ηǂ������̂ɁA
�Ɩ{���Ɍ�����Ă���܂��B
���������āA�u�B�e�̂ق��̋Z�p�v�ł������Ɣ��f���邱�Ƃ���A���ɂ͏o���܂���ł����B
�F���炢���������A�}��p���Ẳ����A�����Ȃǂ��A����ƐS�ɗ]�T���o���āA
�ǂ茩����A�����Ă��������Ă��邤���ɁA������������Z�p�̂��Ƃ��A
�y���^�b�N�X�ŕ����Ă����킯�ł͂Ȃ����ƂɁA�C�t���Ă��܂����B
�����܂ł��A��������܂łɂ���Ă����B�e�o������A�C�t�������Ƃ��ɂ�����A
�����Y���̕�Ƃ́A�ǂ��������ɁA���ʂ��Ⴄ�̂��A�����āA�f�q�͂ǂ�Ȋ����œ����̂��A
�����������Ƃ��A�g�U���U��������Ȃ���A������Ă��������܂����B
�����������̃v���ł�����A�����A���������m�����������Ƃ�`���Ă���܂�����A
���ɍ��킹�����������Ă����������Ǝv���܂��B
�Z�p�ғ��m�̘b�Ȃǂł́A���Ԃ�p���Ȃ��悤�ȕ\���ŁA�����������t�ŋ����Ă����������̂��Ǝv���Ă��܂��B
���ɂƂ��ẮA�܂��ނ���AK-x�̓h�����ǂ�����Ă���Ă���̂��A�F�ɂ���āA
�h��d�˕����ǂ��Ⴄ�̂��A�G�߂⎼�x�ɂ��f�ނ̏k���̂��ƂȂǁA�����������A
�u���̂Â���v�I�Ȃ��Ƃ̂ق����A���ʂɗ����ł��܂����B
���ꂩ��́A���������������A�����Ă������������Ƃ��A�ǂݒ����āA
�����̏������݂��A�������邱�Ƃ͂������A����Ȃ��Ƃ������Ă��܂������Ƃ��A
�Ӎ߂����Ă������������Ǝv���܂��B������x�A�ǂ܂��Ă��������B
���Z�������A���x���A�����ȏ��������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10908490
![]() 0�_
0�_
�y���^�b�N�X����u�ʒu�u��������Ă���v�Ɖ����Ă��A
���ۂɁA�{���ɂ��ꂪ�����Ă���̂��ǂ����A�悭����Ȃ��A�Ƃ������X�������Ǝv���܂��B
���́A���̃X���b�h�ɂāA�����̕��ɁA�킴�킴�}������Ă�����������A�����Ȏ�����
���Ă�����������A�Ƒ�ςȎ�Ԃ������āA���������Ă��������܂����B
�������ӂȂ��Ƃ́A�u��R���邱�ƂŁA�ڂ��g���Ĕ��f����v�A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B
�ł��A���̃X���b�h�̓r���ł́A�ǂ����Ď��������邱�Ƃ��A���̐l�B�ɂ������悤��
�킸���ȉ摜�̈Ⴂ�Ȃǂ��������Ă��炦�Ȃ��̂��낤�A�ƁA�Ȃ��Ȃ��u�킩��Ȃ��v
�Ƃ������Ƃɑ��ẮA��肢�������ł��܂���ł����B
�ł��t�ɁA���̃X���ő�R��������������◝�_��A�Z�p�A�}���Ɋւ��ẮA
���̕����u�킩��Ȃ��v�Ƃ����ŁA�����Ă������������X���炷��A
�u�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ�����Ȃ��̂��v�Ƃ����C�����������Ǝv���܂��B
���������A���낢��ƍl���āA���肪�ǂ����āu�킩��Ȃ��̂��v�A�Ƃ������ƂŁA
��肢������X���Ȃ�Ƃ����悤�Ǝv���̂��A��߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�ނ���A�������u�ǂ����ĉ������̂��v�Ƃ������ƂɎ�_��u���āA�������ASR�@�\��
�p���ĎB�e�������ʂ���A���ɒ��ڂ��āA�ʒu�u���������Ă��邱�ƂɋC�t�����̂��A
��������A���Ԃ��������Ă��������ق����ǂ��̂ł͂Ȃ����A�Ɗ����܂����B
����{���Ȃǂ́A�ׂ����Ԃ��킴�Ƌ邱�ƂŁA���f�̊�Ƃ���̂́A
�L���͈͂���������A�덷����u�Ŋm�F�ł���m�����グ�邽�߂ł��B
���엦��ڑ��Ōv��ۂȂǂł��A�����̌�������e�N�j�b�N�͉��p���Ă��܂��B
�f�b�T���Ȃǂ̏K��ŁA�l�͂ŎO�����̕��̂��A���ʂɂ�������Ƃ́A�ו����������厖�Ȃ̂ł����A
�S�̂����āA�`�������ĂȂ����A�s���R�łȂ����A���̕����͍����Ă��邩�A�ȂǁA
�����ȕ����ƍL�͈͂��A���݂ɉ��x���m�F�����肵�܂��B
�ł��A�ʐ^�́A�Ƃɂ����J�����C���ŁA�O��������ɐ��邱�Ƃ́A��u��
�o���Ă��܂��킯�ŁA�ނ���A�\�}��s���g��{�P�ȂǁA�u�ǂ����邩�v�̂ق���
�d�v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����A�Ȃ�čl�����肵�܂��i�{���́A�G�ł������͑厖�ȗv�f�ł��j�B�@
�ł�����̂悤�ɁA�Ԃ���̈Ⴂ���������邽�߂ɂ́A�ǂ��������A���̏����ȓ������A
�����̖ڂŊm�F���₷������̂��A�Ƃ������Ƃ��A�|�C���g�ɂȂ��Ă���Ǝv���̂ł��B
���̍ۂɁA�킴�Ɗm�F���₷�����邽�߂ɁA�ɏ��Ƃ��ɍׂƂ��́A��Ƃ���͈͂�݂��Ă��A
�������W�����Č��Ă�鎖�ɂ���āA�ق�̂킸���ȓ�������A�������Ȃ��悤�ɂ���A
�Ƃ����e�N�j�b�N���A�ʂɒN�ɏK�����킯�ł͂Ȃ��ł����A�����g���A������ڑ���
�v��ۂɂ́A�悭����Ă���̂ł��B
�������������́A�ǂݔ���Ă��������Ă��������ł��B
�����A�ʒu�u�����{���ɕ����Ă���̂��A�C�ɂȂ�������������Ⴂ�܂�����A
�O�̂R���������X�ŁA���������Ƃ��A�����Ă݂Ă��������B
���́A�����Y���̕�i�n�C�u���b�gIS�͏����j�Ɣ�ׂāA��ʑ̂ɋ߂Â����ۂ́A
���u����������E�̋������A�y���^�b�N�X��SR�́A���Ȃ荂���Ɗ����܂����B
�������ɂ��Ȃ��A�Ƃ������A�����ɋ߂Â��Ă��A��̐k�����A�t����ʂɌ���܂���B
���C�u�r���[�ł��A����ł��B�@�ł��A�������A�l���͂���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10908701
![]() 0�_
0�_
�X���b�h�̃g�b�v�ł������N���Ă��܂����A
http://cweb.canon.jp/ef/technology/is-technology.html
�L���m���̃n�C�u���b�gIS�̉�������́A���������ǂꂭ�炢�̔{������A
�V�t�g�u�������������Ȃ��Ă����̂��A�Ƃ����}�́A������x�͎Q�l�ɂȂ邩������܂���B
�u�Ԃ�v��\���P�ʂ͂Ȃ��ł�����A�P���ɓ����œ_�����Ȃ�A�{�����オ��ƁA
�E���オ��ɂȂ�A���Ă��Ƃ�\�ɂ��Ă��邾�����Ƃ͎v���܂����ǁB
���́A�Ƃɂ����A�ǂ�Ȍ����ł��������Ă̂��Ă��邩�͂悭�����̂ł����A
�u�ʒu�u���������Ă���v�ƃn�b�L��������u�Ԃ�����܂��B
����́A�O�r�ł̎B�e���A��������Ă������炱���A�������Ċ�����̂��ȁA�Ǝv���܂��B
�ߋ����ƒ������Ɋւ��ẮA���������s�����Ă��A�قڎO�r�ŎB�e�����̂Ɠ����悤��
�掿�̎ʐ^���B���悤�ɁA�P�����Ă���܂��B
�����ɂ͂�����肭�͂����ĂȂ��Ǝv���܂����A���������A����ł��A���p�ق̊��W��
�|�X�^�[�Ȃǂɂ��A��Ƃ�ʂ��āA�摜����Ă����肵�܂�����A���ƈ���ł��A
����Ȃɑ傫���Ȃ���A�ς�����ʐ^���B���Ă͂���Ǝv���܂��B
���́A�y���^�b�N�X�̃f�W�C�`�́A���p�i�͂������A�ߋ����A�������́A�Ñ̎B�e�S�ʁA
�u�c�B���A���i�B�e�ȂǂɁA���Ɍ����Ă���Ǝv���܂��B�O�r�g�p���ł��A
SR��p�����莝���B�e���ł��B�@����͂����Ƒ����̐l�ɒm���Ă��炢�����ł��B
�����ԍ��F10908797
![]() 1�_
1�_
MZ-LL����
��R�����܂����̂ŁA���낻��A���̔��I���ɂ��Ă�낵���̂ł́B
���Ȃ��̎咣�́A����������Ă��܂��̂ŁA����ȏ㏑���Ă��A�c�_���Ă��A�������Ƃ̌J��Ԃ��Ǝv���܂��B
���i.com�̃X���̎�|�ł���A����EK-7�ł�����Ƃ�������m�点�����ȂǂƁA�u�݂Ȃ���ɒm���Ăق����̂ł��v�͈قȂ�Ǝv���܂��܂��̂ŁA����ȏ�̂��Ƃ́A�u���O�ł��������������B
PEN�@SL
�����ԍ��F10911395
![]() 25�_
25�_
���̃X���b�h�����Ċ�����̂́A�f�l�����r���[�ɂ��������m�����A�����Ԃ��
�̂����ɏ����Ă���l�������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł����B
�����g���A�l�b�g�Ō����������Ă��o�Ă��Ȃ��A�y���^�b�N�X��SR���ʒu�u���������Ă��邱�ƁA
���C�t���āA�g�p���������Ă���̂ɁA���̕��⌤�������Ă����킯�ł��Ȃ��l�������A
�Ȃ�ł���Ȃɒf���ł���̂��A�s�v�c�ł����B�����������m���Ă������ׂĂł͂Ȃ��̂ɁB
�����ŏo�Ă��Ȃ����ƂɊւ��ẮA���i�R���̃A�J�E���g�������ꕔ�̐l�B�̏�A
�����ɍ������キ�Ă��������Ȃ̂����A���Ɏ����������܂����B
����ɂȂ��ď��߂ēǂ݂܂������A����̎��̏������݂̒��O�܂ŁA�����̖ڂŌ������邱�Ƃ�
�ł��Ȃ��A���o�݂̓��l�������A�ʒu�u���̕�Ȃ�Ăł��Ȃ��A�Ƃ���������ł���̂ł��ˁB
�{���ɒႷ����Ɗ����܂����B
�����āAinduster����̂悤�ɁA���p�̃v���̌�����܂������m��Ȃ��h�f�l���A
���ۂɌ���ł����Ȏd�����o�����Ă������ɑ��āA�����������ɑf�l�ۏo������
�C�t���Ȃ��悤�ȏ������݂��A�d���̋������A�g�������Ƃ邽�߂����ɁA��ʂɈ��p���āA
�S�����Ă���̂��A���ɋC���������ł��B
����l������A���̐l�Ȃ�ɂ��m��ˁ[�̂ɂ悭�̂����Ȃ��Ƃ�������ȁA���Ċ�����͂��ł��B
DTP�Ƃ��낭�ɂ�������ƂȂ������ɁA�����܂߂��ƊE�œ�����O�ɂ���Ă��邱�Ƃɑ��āA
���ō�����R�̏��œ�Ȃ�������A�悭�p���������Ȃ���ȁA�Ƃ��v���܂��B
���́A���Ȃ��Ƃ��A���{�ōō���̂�����������ŁA�d���������o�������邵�A�c���̍�����
��勳����āA����Ƃ�����w�ɓ����āA�݊w�����\���Z�̍u�t�����Ă����A
���������A�����I�Ȕ��p�n�̊w�ѕ����A�\��A��\��Ƒ����Ă�������A�Œ���̂��Ƃ͒m���Ă��܂��B
�����āA�v���Ƃ��ĕ��ʂɉ��N���������Ă���A�G����V���Ȃǂɏo��@����A
���ʂɏo�Ă��邵�A�e���r�����ĕ��ʂɑS�������ł��B�ł��A�n�斧���̉�L�⏬���Ȕ��p�قȂǂł́A
�P�[�u���e���r��n���������āA��ނ��Ă��炦�邱�Ƃ͂��肪�������A�W�q�Ɍq�������肵�܂��B
�����Ƃ��āA�ǂ��d�������Ă������A�ǂ��J�������g���Ă������A�Ȃ̂ł��B
�l�b�g�Ŏd���ꂽ���A�ǂ����ł��������悤�Ȓm�����Ђ��炩����Ă��A�{���ɑΉ��ɍ���܂��B
�ʂ̃X���b�h�ł́ADigi����Ƃ����l���A�����悤�ɑf�l�ۏo���ŏ����Ă������Ƃ�����܂������A
�悭���܂��A����Ȃ��悤�ȍ����������݂����Ă����l��������̂��A�ƃr�b�N���������܂��B
�����B���f�l�ł��邱�Ƃ��A�����Ǝ��o����ׂ��ł��B
���f������Ƃ��̎B�e��Ƃ��A�傫�ȃC�x���g�ɍs���āA���o����B���B��A�����
���q������A�����X�^�b�t�̐l�B�͗D�������Ă���邩������܂���B
�����J�������w�����鎞�́A���q����A��������܂��A�J�������g�����́A���q����ł͂Ȃ��̂ł��B
�����āA�����B�e����A�[�`�X�g�B���A�݂���L������قł���Ă���킯�łȂ��A
����L����p�قŁA�����Ƃ��āA��i�\���Ă���̂ł��B���ɃV�r�A�Ȑ��E�ł��B
����B�e�����Ă����q���A��\��ł����A������p�̐��E�ł͒N�����m���Ă���悤��
�傫�ȏ܂��Ƃ����l�ł����A�g�̂��܂Ő���ɂ̂߂荞�ނ悤�ȍ�ƂȂ�āA�U���ɂ��܂��B
�ʒu�u����̘b�݂̂Ȃ炸�A���p�̘b�ł��A�R�̏��������̂́A�{���ɂ�߂Ăق������̂ł��B
PhotoShop�̐蔲���c�[���Ȃ�āA�����̊F���w�Ƃ��Ō��Ă���A��K�͂Ȕ����قƂ�
���p�قƂ��̃|�X�^�[�Ƃ�������Ă��錻��ł��A���ʂɎg���Ă���̂ł��B
�������ݕ�����A�˂����݂���ӏ��܂ŁA���ׂĂ������ȃh�f�l�ȊO�́A���҂ł��Ȃ������ł��B
���B�e��A�^���B�e���A�J�������莝���ōs���Ȃ���A��Ƃƍ���͂ǂ�ȃR���Z�v�g���Ƃ��A
�ǂ̍�i��D�悵�ĎB���ė~�����̂��A�Ƃ��b������A��Ԃ̌��̕ω��Ƃ��A�L���Ƃ��F�Ƃ��A
���������̂����ɂ߂Ă����̂́A���ɑ厖�Ȃ��ƂȂ̂ł��B
�����獂���@�ނ��g�������āA���������Ō��ɂ߂˂A�ޓ��ɕK�v�Ƃ����ʐ^�͎B��܂���B
�낭�ȍ����̖����ے�قǁA�������m���̂Ȃ���I�悷�邱�ƂɂȂ邾���Ȃ̂Ɂc�B
���ꂾ�ȁA�Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10914099
![]() 1�_
1�_
�u���p�v�Ɋւ��ẮA���̌������������Ɗ����܂����AMZ-LL����̓J�����}��
�ł��Ȃ����A�J�����ł̋L�^����ɂ��Ă��Ȃ��̂ł��傤�B����ɂ͎�U��
�̋Z�p�I�Ȗʂɂ��Ă��A�f�l�ۏo���Ȕ����𑱂��Ă���Ǝv���̂ł����B
�Ȃɂ��AMz-LL����ɕK�v�Ȃ̂́u�����ȑԓx�v�Ɓu���l�Ƙb�������펯�v��
��������������悤�Ɋ����܂��B�����ŁADigi����̂����O���o�����Ǝ��̂��A
�M���̔�펯���ɔ��Ԃ������Ă��܂��B
Digi����̍l�����ɂ͎^���ł��Ȃ����Ƃ��قƂ�ǂł����A���̃X���b�h�ŋM����
��������ł����ł��傤���B
�M���ɕK�v�Ȃ̂́A�u�����̑ԓx�E�����݂�p�v�Ɗ�����S�̋����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10914561
![]() 38�_
38�_
����܂ŖT�ς��Ă��܂������B
���g�́u�]���v�Ƃ����͎̂����ł�����̂ł͂���܂���B
���҂�������̂Ȃ̂ł���B
����܂�MZ-LL���Ԃ����������݂ɑ��ăi�C�X�̐��͍��v�����Ȃ�ł��傤�H
�قƂ�ǂO�ɋ߂��̂ł͂Ȃ��̂ł����H
�܂�͂��ꂪ���҂���MZ-LL����ɑ���]���̌��ʂ̈�c���Ǝ��͎v���܂���B
�����ԍ��F10915165
![]() 29�_
29�_
��ԕs�v�c�Ȃ͔̂��p�i�Ƃ����B�e����̂�APS-C�̃f�W�J�����g���Ă�Ƃ���Ȃ��ǂ��B
��̃t�B�����ŁA4×5�Ƃ�6×7�Ƃ��ŎB����̂��Ǝv���Ă��B
�����̓f�W�J���ŎB�����Ⴄ����Ȃ낤���B
�����Ȕ��p�قł���i�Ȃ��T�|�W�ő݂��Ă���āA�f�[�^�ł��ꂽ���Ƃ͍��܂ň�x���o�����Ȃ��B
�傫���ėL���ŗ��h�Ȕ��p�قł͊�����APS-C���x�ŎB��悤�ɂ��Ă�̂��ȁB
���͂�|�W�ł̎����i�B�e�͉ߋ��̘b�H
��������͕ʂƂ��āAK-7�͏������Ċ拭�Ŏ��엦100%�Ŏʂ���悭�ē���������āA�ƍ��ł��o�F�̏o���̃J�������Ǝv���B
�����ԍ��F10915388
![]() 9�_
9�_
MoonAttack����A���߂�Ȃ����B�ŏ��ɖ^Digi���̖����o�����͎̂��ł��B�i2��7���J�L�RNO[10899313]�j�B
���A���̒���X��������Ɣ]���ɕ�����ł��Ă��܂����l�����ł����B�i�^�{�l����A���߂�Ȃ����j
�X����a
���p���ς�u�P���v�ȏ�ɋ�C��ǂށu�P���v������鎖��]�݂܂��B�i�����q����B������E�E�E�j���i�u���O�J�݂��E�E�E�j
�j�ā`�BROM��i�K�j�ɓO������肾�����̂Ɂ`�I�i�܁j�B
�����ԍ��F10915562
![]() 11�_
11�_
���̃X����ǂ�ŕ��������R�g�B
�@�E��u����̌����Ǝd�g��
�@�ESR�͂ƂĂ��D�ꂽ�@�\���Ƃ�������
�@�ESR�͌����ȈӖ��ł̃V�t�g�u���ɂ͑Ή����ĂȂ�����
�@�E���M�ߏ�E���ӎ��ߏ�͌��ꂵ�����̂ł��邱��
�@�E�X����ɔ�ׂ�f�W�J���X�^�f�B�������Q�Ɏv���邱��
�ȏ�B
�����ԍ��F10915983
![]() 20�_
20�_
���[���X���A�����낤�Ǝv���ēǂݎn�߂���ʔ����āA�S���ǂ�ł��܂��܂����i�ꕔ�����������j�B
���̍l���ł́ATomato papa����̌���
http://papablog2.ice-tomato.com/article/140302368.html
������I���Ǝv���܂��B
�u���O��q���������A��x�ǂ����ł͈Ӗ����悭�킩��Ȃ������̂ł����A�ǂݕԂ��Ă��邤���ɂȂ�قǂƎv���܂����B
���̎����ł́u�J�����Ɣ�ʑ̂̑��ΓI�ʒu�W�����v�Ƃ����̂��|�C���g�Ȃ�ł��ˁB
�ł��̂ŁASR�������Ă���t�ɑ��͂Ԃ�Ďʂ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���E�V�t�g�Ԃ�̃P�[�X�ł͑����Ԃ�Ă��Ȃ��̂ŁASR�͓����Ă��Ȃ��Ƃ������ʂł��ˁB
�����ԍ��F10916089
![]() 6�_
6�_
���݂̋@�B�͏����ɍ������������ɂ��̏����ɓK������������鎖�����߂��Ă���̂ŒP���Ȏ����ŒP���ɓ������o����قǒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂����ˁB
�V�t�g�u�������ɐ���Ղ����{�t�߂̎莝���B�e�ł�SR�����m�Ɏ�u�������Ă���̂͂���܂ł̎B�e�̌��ʂ��ؖ����Ă��܂��B
���ۂ̎B�e���ʂ��f�l�̛�������D�悷��̂͗����o���܂���B
�����ԍ��F10916256
![]() 3�_
3�_
�c�O�Ȍ��ʂɏI���܂����ˁB
SR�]�X�����X����̐l�Ԑ����I�悵�Ă��܂��܂���
�ȑO����X���傳��̔����A�����͂��ꂢ�ȗD���������Ȃ�����ǂ����U�P�I��
�ǂ��l���Ă��邩�̂悤�ŏ����C�ɂȂ��Ă��܂�����
����ς肻���ȂȂ��E�E
10914099�ł̏������݂͓ǂނɑς��Ȃ��悤�ȓ��e�ł���
�D�������Ƃ��������₦���ォ��ڐ��Ŏ����ȊO���������Ă���Ɗ����܂����B
�ǂ����P�ɂ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10916653
![]() 27�_
27�_
�����݂̋@�B�͏����ɍ������������ɂ��̏����ɓK������������鎖�����߂��Ă���̂ŒP���Ȏ����ŒP���ɓ������o����قǒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂����ˁB
�H
�ߋ����낤�ƌ��݂��낤�ƁA�@�B�͐l�Ԃ̐ݒ肵�������ł��������Ȃ����̂��Ǝv�����ǁH
�V�t�g�u����ے肷��������āA�p�x�u�����܂܂Ȃ������ȃV�t�g�u���Ƃ�����������ɂ͑Ή����ĂȂ����Ă��Ƃ��ؖ����Ă邾���ł���H
�V�t�g�u���̕��ے肵�Ă�q�g�������A�莝���ł�����V�t�g�u�����ۂ������̕�܂ł͔ے肵�ĂȂ���ˁH
���Ԃ��ǁA�V�t�g�u�����ے肵�Ă�q�g�����́A�u�V�t�g�u���v�Ƃ����R�g�o���u�p�x�u�����܂܂Ȃ��ꍇ�̂݁v�Ɏg���Ă�̂ɑ��āAMZ-LL������L�̍��z�c�����(�y���^�b�N�X���H)�A�u�V�t�g�u�����ۂ������v�Ƃ��������܂��Ȃ��̂ɑ��āu�V�t�g�u���v���ăR�g�o���g���Ă��܂��Ă��Ȃ����ȁB
������A�b�����ݍ���Ȃ��B
�ŁA����ɁAMZ-LL���A�����͊p�x�u���̂Ȃ��V�t�g�u�����莝���ŋN������Ȃ�Č������Ⴄ����A�]�v��₱�����Ȃ��Ă�B
�킽���ɂ́A�����v������ǁc�����l����̂��ăw�����ȁH
���V�t�g�u�������ɐ���Ղ����{�t�߂̎莝���B�e�ł�SR�����m�Ɏ�u�������Ă���̂͂���܂ł̎B�e�̌��ʂ��ؖ����Ă��܂��B
����͌�����������ˁB����Ȃ��Ƃ��ؖ����Ă�f�[�^�ł�����́H
���������A����ȋC������A�����ł����ė~�������x����Ȃ��H
�킽�����}�N���ł悭�B�邯�ǁA�ӂ��̎B�e�������Ȃ��ȁ`�Ƃ����̂��������ȁB(�P�Ƀw�^�N�\�Ȃ�����������Ȃ����ǁB)
�����ۂ̎B�e���ʂ��f�l�̛�������D�悷��̂͗����o���܂���B
�N�����ۂ̎莝���ł̎B�e���ʂ�ے肵���肵�ĂȂ��Ǝv�����ǁB
����������Ȃ��Ď������ʂ���B������̂͑f�l��������Ȃ����ǁA���������SR�������Ȃ��͎̂����ł���B
�莝����SR���������ăR�g�ƃV�t�g�u���̎������ʂƂ́A��������킯�ł��Ȃ��̂Ɂc�@�Ȃ�Łu�D��v�Ƃ����ăn�i�V�ɂȂ�̂������ł��܂���B
�����ԍ��F10916933
![]() 18�_
18�_
�L�̍��z�c���� [10916256]
���[�炳�� �̏�����Ă���Ƃ���ł���B
�����g�Łu�V�t�g�u���v���Č��t���g���Ă���̂�����A�V�t�g�u���Ƃ͂ǂ��������̂��n�l���Ă݂Ă��������B�����g�̗������B���ł͑��҂Ƙb�����ݍ����͂�������܂���B
���̌����ł́u����Ă����Ƃ��Ă��A�����ꕔ�̃V�t�g�u���ɑΉ��v�ł��ˁBTomato papa ����̃u���O
http://papablog2.ice-tomato.com/article/140302368.html
���������u�����ꕔ�̃V�t�g�u���ɑΉ����Ă��邩���H�v���Ă̂��킩��Ǝv����ł����B
����������́u�V�t�g�u����v�Ƃ����ɂ͂��܂�ɂ��e���Ȃ��̂ł��B�P�Ɋp�x�u����̌������キ�������x�̂��̂ł��B
���ǂ̂Ƃ��� ���[�炳�� �̏����ꂽ�Ƃ���
>�@�ESR�͌����ȈӖ��ł̃V�t�g�u���ɂ͑Ή����ĂȂ�����
�����������Ƃł���B���܂ł̌��ł́B
�����ԍ��F10916987
![]() 6�_
6�_
�����E�V�t�g�Ԃ�̃P�[�X�ł͑����Ԃ�Ă��Ȃ��̂ŁASR�͓����Ă��Ȃ��Ƃ������ʂł��ˁB
�⑫����ƁA�u���E�V�t�g�u���@SR�I���@������I���v�̎����ł́A
�h�����Ɓh�摜���X���Ă܂��B
�i�u���O�f�ڂ̎ʐ^�����ł͔����Ȃ̂ł����A�����摜��DL���Č���ׂ�ƕ�����܂��B�j
������������A�����x�����m���āA�f�q����]����Ă܂��ˁB
����ɁA�X������ԂłԂ�Ă܂���A
�E�����[�Y�̏u�ԁA�������ɍ��E�����̉����x���������Ă��āA��������@�\���Ă���B
�E���A�I�����́i���E�����̉����x���ω����Ă�ɂ�������炸�j�f�q�͌Œ肳���B
�܂�A������͐�����ł����āA��]�Ԃ��ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
���s�̂�������
�����������u�����ꕔ�̃V�t�g�u���ɑΉ����Ă��邩���H�v���Ă̂��킩��Ǝv����ł����B
�����́A�悭������܂���ł����B
�����ԍ��F10917405
![]() 1�_
1�_
���[�炳��
>�ߋ����낤�ƌ��݂��낤�ƁA�@�B�͐l�Ԃ̐ݒ肵�������ł��������Ȃ����̂��Ǝv�����ǁH
�@�B�͂������������̔��f�͏o���Ȃ�������ł��ꂪ�o����l�ɂȂ����̂̓}�C�N���R���s���[�^�[��Z���T�[�ނ����ڂ���Ă���̎��ł��B
>����������Ȃ��Ď������ʂ���B������̂͑f�l��������Ȃ����ǁA���������SR�������Ȃ��͎̂����ł���B
�P���Ȏ����͕������ۂɂ͒ʗp���Ă��C���e���W�F���g�Ȍ��݂̋@�B�ɂ͊P�ɒʗp���Ȃ��ł��ˁB
�]���ē��������SR�������Ȃ������̂������đS�Ă�ے肷��̂͛������ł���Ƃ������ł��B
>����͌�����������ˁB����Ȃ��Ƃ��ؖ����Ă�f�[�^�ł�����́H
���̌��Ɋ���̂ł�����f�[�^���Ȃǂ��Ă��܂��A�[�����Ă��炤�K�v���L��܂���B
���[�炳�u�����ʐ^�����B��Ȃ��ƌ����Ȃ炻��������ł��傤���A���ɂ͊W�Ȃ����ł��B
>�킽�����}�N���ł悭�B�邯�ǁA�ӂ��̎B�e�������Ȃ��ȁ`�Ƃ����̂��������ȁB
�L���m���̃V�t�g�u��������Y�ł��}�N���B�e�͎�u�����E�V���b�^�[���x���ʏ��2�{�Ə�����Ă܂�����A�V�t�g�u�������Ă��}�N���B�e�ł͎�u������ӂ��̎B�e�������Ȃ��ƌ����͓̂�����O�ȂƎv���܂����B
���̏�ŕ���Ȃ���Ύʂ��Ȃ��l�ȍו��܂ŕ`�ʂ���Ă��鎖�����̌��㏭�Ȃ��Ȃ��ƌ������ł��B
�莝����SR���������ăR�g�ƃV�t�g�u���̎������ʂƂ́A��������킯�ł��Ȃ��Ƃ����F���ł���Ȃ炻�̓_�͓��ӌ��ł��B
���s�̂�������
�V�t�g�u���̕�������ʂɂ��Ă͈ȑO���̃X���ɏ����Ă��܂��B
���ۂ̓��{�B�e�ŕK�v�ȃV�t�g�u���ʂȂ��0.01mm������̕�������Ă��邩�ǂ����̊m�F�������Ȑ��l�ł���B
���̏������Ő��m�ɓ����Ă���SR�V�X�e�����u���܂�ɂ��e���Ȃ��́v�Ƃ͎v���܂���B
�����V�t�g�u����ɑ��ĉߑ�Ȋ��҂����Ă���Ƃ����v���܂��A���ۂ̃}�N���B�e�ɂ����ăV�t�g�������܂ގ�u���ɑ��Đ��m�ɕ���s���Ă���A����ȏ�K�v�Ȏ��ł�����܂����B
�����ԍ��F10917512
![]() 5�_
5�_
�m�肷��ɂ��ے肷��ɂ����m�ȍޗ��̂Ȃ���
���f����͖̂��Ӗ������Ă͂�����͍��z�c����������ȁH
�V�t�g�u������m�肷��ޗ����������̌o���Ɗ��o�ŁH
�X����Ƒ卷�Ȃ����_�ł������܂��ˁBw
�����ԍ��F10917564
![]() 9�_
9�_
�|���R�E�r�A���R����
>�V�t�g�u������m�肷��ޗ����������̌o���Ɗ��o�ŁH
�m�肷��ޗ��͎����ŎB�e�����摜�ł��B
�u���Ă邩�ǂ����A����Ⴀ����܂����B
�X�`�����J�Ȏ����⛛�������m���Ȕ��f�ޗ����Ǝv���܂����ˁB
�����ԍ��F10917802
![]() 5�_
5�_
�����̏�ŕ���Ȃ���Ύʂ��Ȃ��l�ȍו��܂ŕ`�ʂ���Ă��鎖�����̌��㏭�Ȃ��Ȃ��ƌ������ł��B
������O�ł���ˁB
�ߐڎB�e�ł��p�x�u���̉e���͏������Ȃ�܂���APENTAX�ł�CANON�ł��A
�}�N���ŕ���ʂ��Ȃ��Ȃ�킯����Ȃ��ł��B�i���ΓI�ɒቺ���邾���B�j
�������A�V�t�g�Ԃ��Ƃ����̂́A���ʂ̒��͔����ȂƁA����Ȃ�Ȃ�����A
���݂���p�x�u����̌��ʂƕ������āA���ꂪ�������ɂ���A�Ƃ����̂́A
�ǂ̂悤�ɂ��Ď����ł���̂ł��傤���B
�i�X���̓�������w�E����Ă����|�C���g�ł��B�j
�X���傳��Ȃ݂Ɍ������܂��ꂽ���o���������Ȃ�b�͕ʂł����E�E
�����ԍ��F10917838
![]() 6�_
6�_
�܂��A�����Ă��āA�c�_���I�J���g�ɂȂ��Ă���̂ŁA1���B
��ςɐ\����܂���B�����ł��̂ŁA���Ԃ̂�����̂݁B
�V�t�g�u����ɑ��郁���ł��B�u���̌������l�������̂ŁA�y���^�b�N�X�J�����̋@�\�ɂ��Ă̋c�_�ł͂���܂���B���̍H�w�I�m���ŏ����Ă��܂��B
��U��́A�����Y�����̊p�x���ς��u�i�����j�p�x�u���v�A�����Y�����𒆐S�Ƃ���u��]�u���v�A�J�����������Y�����ƒ��p�����i�㉺�E���E�j�ɓ����u�ʒu�u���i�V�t�g�u���j�v�y�уJ�������O��ɓ����u�O��u���v�ɂȂ�܂��B�i���͉̂��ł��j
�V�t�g�u���̓J���������������̕ψʉe���݂̂ł��B�P������������P�����B�p�x�u���͔�ʑ̂Ƃ̋����Ńu���ʂ��ς��܂��BK-7�̍��[�������Y���S�ʒu����V�����Ƃ���ƁA��ʑ̂��V���̈ʒu�ł́A�u�����P�O�O�{�i�P�����łP�O�����j�B�O��u���͔�ʑ̂Ƃ̋������ς�邾���Ȃ̂ŁA��ʊE�[�x���ł́A�u���͖����ł��܂��B��]�u���́A��܂��ɂ͎���̂P�ӂ̑傫���ƃJ�����̂P�ӂ̑傫���̔�Ō��܂�܂��B�c�Q�D�T��×���S���i�W�������Y�łV�����炢�j�̏ꍇ�́A�[�Ŏ��ۂ̓����̖�Q�O�{�̃u���ɂȂ�܂��B�P�����̓����ʼn摜���S�̓u���Ȃ��A���ӂłQ�������炢�̃u���ł��B
�P���ȏ�ł́A�p�x�u��������]�u�������V�t�g�u�����O�ぁ�O�B
�}�N���ł͊p�x�u�������V�t�g�u������]�u���B�O��u���̓s������ɂȂ�܂��B
���ɂP�����̃J�����̃u���̉e���͎��̂悤�ɂȂ�܂��B
�B�e�����V�O�����@�p�x�u���P�O�����A�V�t�g�u���P����
�B�e�����P�D�S���@�p�x�u���Q�O�����A�V�t�g�u���P����
�B�e�����R���@�@�@�p�x�u���S�O�����A�V�t�g�u���P����
�X�y�b�N�ł́A�ő�SEV�iSS�łP�^�P�U�j�̕���\�Ə����Ă���܂��B
�p�x�u�����P�^�P�U�ɂȂ�Ȃ�A�B�e�����P�D�P�Q���̏ꍇ�ɁA�P�����̓������P�U�����̃u���ƂȂ�A���̊p�x�u�����P�����B�V�t�g�u���Ɠ����ʁB����́A��U���������Ă��Ȃ��Ƃ�����łȂ��A�ň��Ō��ʂ������ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B�����A�V�t�g�u���Ɗp�x�u�����t�����ł���A�ł������āA�u���O�̃P�[�X������܂��B
�T�U�����̋����ł́A�P�����̓����̌����ł͊p�x�u�����W�����A���ɂO�D�T�����ɂȂ�܂��B�V�t�g�u���P�����Ƃ���A�V�t�g�u���̕����傫���Ȃ�܂��B�������A��Ȃ��ł������ꍇ�̍ő�W�{�P�������A�ő�P�D�T�����ɂȂ����Ɨ����ł��܂��B
��ʓI�ȎB�e�ł͊p�x�u����݂̂ŏ\���ŁA�Q���ȏ�ł̓V�t�g�u�����S�������ł��Ȃ��Ǝv���܂��B��ʂɂP���ł�����Ȃ��Ǝv���܂��B�V�t�g�u������{���ɕK�v�Ȃ̂́A�B�e�{���O�D�Q�ȏ�̃}�N���B�e�����ƍl�����܂��B
��ʓI�ɂ́A�J�������Ɏ��߂���ړ��Ɋւ���Z���T�[�́A���ʌ��m���ł���W���C���n�Z���T�[�Ɖ����x�Z���T�[�ł��B
�S�����̉�]�����m����ɂ́A�����Y�̌��������Ƃ���ɒ��p�������������Q�̃W���C��������A���m�ł��܂��B���������W���C���̌��m�l����A���E���̉�]�E�㉺���̉�]�����m���āA���p�̃W���C������A�J�����̌������������Ƃ����]�����m���܂��B�p�x�u���Ή������Ȃ�A�W���C���P�B
���s�ړ��ɂ��ẮA�J�������œ����ړ��ڌ��m�ł���Z���T�[�͑��݂��܂���B�K�����I�̊����̖@���B�������A����ɑΉ��\�Ȃ͉̂����x�Z���T�[�ł��B�������A�����x�Z���T�[�P�Ƃł́A���J�������ǂ̂悤�ȕ��s�ړ������Ă��邩���m�ł��܂���B�d�Ԃ̓����x�ړ��͔���Ȃ��B�V���b�^�[�����������_�̔�ʑ̂̈ړ��́A�V���b�^�[���������_�́u�������x�v�Ɓu�����x�v���猈�܂�̂ŁA�����x�̏��݂̂ł̓V�t�g�u����͂ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�iSS�������ꍇ�́A�������x�����ł�OK�ł��j
�������A�i�Ⴆ�j�B�e�҂̓J���������܂��ێ����Đ��b�̎��ԕ��ςł͈ړ����Ă��Ȃ��i�U�����Ă���j�Ɖ��肷��A�ߋ��̉����x�̋L�����ɂ��u�����x�̕ω�������Ȃǂ���v�Z����錻�݂̑��x�v�Ɓu�v�����̉����x�v����A�V�t�g���m�͂ł��Ȃ����Ƃ͂���܂���B�l�Ԃ��R�����U��q�ގ��Ɖ��肵�Čv�Z�B
�����ȉ����x�����m����K�v������܂��B�L���m����HP�ɂ́A�u�����Y�ɉ����x�Z���T�[�v�Ƃ���܂��̂ŁA�����炭���̌����ɋ߂����Ƃ����Ă���Ɛ��肳��܂��B���x�ǂ�����邽�߂ɂ́A�d�͂̂P�^�P�O�O���x�̌��m���x���K�v�Ǝv���܂��̂ŁA���̉����x�Z���T�[�́A�ႦK-7�̐����V�������x�Z���T�[�ł����Ă��A�����V�̂��̂��������x�̂��̂Ǝv���܂��B
��ԏ�ňړ�����J�����̃V�t�g�u����́A���̕���@�̎��ԕ��ϓI�ɃJ�������ړ����Ȃ��Ƃ̑O��ɔ����܂�����A�@�\���܂���B�i������ƌ����āA�O���X�̎������@���Ԉ���Ă���K-7�ɃV�t�g�u���������Ƃ̈Ӗ��ł͂���܂���j
�V�t�g�u�������鑼�̕��@�́A�B�e�O��CCD��摜�̕����_�ł̈ړ������Ƒ��x���\�t�g�I�Ɍv�����āA�ُ�_����菜���A�p�x�Z���T�[�̏��������āA�V�t�g�u�����v�Z������@���l�����܂��B�i��ѕ��͂��߂ł����j�������A�O���X�̈ړ���Ԃ̎����Ō��ʂ��Ȃ������̂ŁA����͍̗p���Ă��Ȃ��͂��B
�l�I�ɂ́A�y���^�b�N�X��K-7�ɃV�t�g������Ă���Ƃ͎v���܂���B����Ȑ�`���ʂ��傫�����Ƃ�HP��p���t�ɋL�ڂ��Ȃ����A�X���傳��̎�����HP��SR�����}�����Ă��A���́u�Q�T�N�̃G���W�j�A�o���v���炢���āA���s�ړ��u���ɑΉ����Ă���悤�ɂ͌����܂���B
�V�t�g�u���́A�����Ɍ���u���ł��傤���A�����Ƃ��ẮA�T�O�����}�N����P�O�O�����}�N�����g���āA�L�̖т̂P�{�P�{���ʂ��������A�P�^�R�O���x����SS�����ł��Ȃ��ꍇ�Ȃǂ������ʂ͂���܂���B�L���m����HP�ɂ��}�N�������Y�p�Ə����Ă���܂��B
�H�w�����@�Z�p��
�����ԍ��F10917885
![]() 11�_
11�_
gintaro���ɓ��ӁB
���z�c��
������F��Ԃ��������Ă錾���̂Ɉ٘_�͖����B
�����ł킩��̂�
�u�V�t�g�u���Ɍ��ʂ��Ȃ��ꍇ������B�v
�Ă��ƁB
���Ȃ��̎ʐ^�ł��Ȃ����킩��̂�
�u��Ԃ��������Ă�v
�Ă��ƁB
�������ĒN�����˂Ă��H
(���͂��˂Ă��w)
�����ԍ��F10917947
![]() 5�_
5�_
�L�̍��z�c����
��>�ߋ����낤�ƌ��݂��낤�ƁA�@�B�͐l�Ԃ̐ݒ肵�������ł��������Ȃ����̂��Ǝv�����ǁH
���@�B�͂������������̔��f�͏o���Ȃ�������ł��ꂪ�o����l�ɂȂ����̂̓}�C�N���R���s���[�^�[��Z���T�[�ނ����ڂ���Ă���̎��ł��B
�}�C�R����Z���T�[�́A���X�l�Ԃ��蓮�ł���Ă����������f��P�Ɍ����肵�Ă�ɉ߂��Ȃ��́B
�����𐧌䂷��A���S���Y���^���Ă�̂͐l�ԂȂ́B�킩��H
�u�@�B�͐l�Ԃ̐ݒ肵�������ł��������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ́A���ɂ��ς���ĂȂ��̂�B
�����A����ȊO�̓����������B����́u�̏�v���Ă����́B
�܂����A�}�C�R����Z���T�[�����������@�B������ɔ��f���Ă����Ȃ�Ďv���ĂȂ���ˁH
���P���Ȏ����͕������ۂɂ͒ʗp���Ă��C���e���W�F���g�Ȍ��݂̋@�B�ɂ͊P�ɒʗp���Ȃ��ł��ˁB
�Ƃ������Ƃ́A�u�C���e���W�F���g�Ȍ��݂̋@�B�v�̓���́A�u�������ہv�ł͂Ȃ��Ƃ��������킯�ˁB�I�h���L�ł��B
���]���ē��������SR�������Ȃ������̂������đS�Ă�ے肷��̂͛������ł���Ƃ������ł��B
�����ƃq�g�̏����Ă邱�Ɠǂ�ŗ~������ˁB
�O�ɂ����������ǁA��������ł̓����ے肵�Ă��邾���ŁA���ׂĂ̔ے�ȂǒN�����ĂȂ���B
�����̌��Ɋ���̂ł�����f�[�^���Ȃǂ��Ă��܂��A�[�����Ă��炤�K�v���L��܂���B
�u�ؖ����Ă��܂��v���Ēf�����Ă��̂͂��Ȃ�����B
��>�킽�����}�N���ł悭�B�邯�ǁA�ӂ��̎B�e�������Ȃ��ȁ`�Ƃ����̂��������ȁB
���L���m���̃V�t�g�u��������Y�ł��}�N���B�e�͎�u�����E�V���b�^�[���x���ʏ��2�{�Ə�����Ă܂�����A�V�t�g�u�������Ă��}�N���B�e�ł͎�u������ӂ��̎B�e�������Ȃ��ƌ����͓̂�����O�ȂƎv���܂����B
�͂��B����͂킽���̎����ƈ�v����ˁB
�����̏�ŕ���Ȃ���Ύʂ��Ȃ��l�ȍו��܂ŕ`�ʂ���Ă��鎖�����̌��㏭�Ȃ��Ȃ��ƌ������ł��B
���Ȃ��̑̌��ł͂��������ăR�g�ˁB������Ȃ��A����ŁB
�������V�t�g�u����ɑ��ĉߑ�Ȋ��҂����Ă���Ƃ����v���܂��A���ۂ̃}�N���B�e�ɂ����ăV�t�g�������܂ގ�u���ɑ��Đ��m�ɕ���s���Ă���A����ȏ�K�v�Ȏ��ł�����܂����B
������A�����ȈӖ��ł�(�����������)�V�t�g�u�����ł��Ȃ����Ă����ŁA����ȊO�̎�u����̌�����ے肵�Ă�킯����Ȃ����ĂB
�킩��Ȃ����ȁ`�H
�����ԍ��F10918065
![]() 10�_
10�_
�悤����ɁA�o���Ƃ������Ɗ��o�����Řb���Ă��āA�����ɓ��Ă͂߂��ꍇ�̌����Ȃ�ł���B
�ŁA�������o���Ƃ��ȒP�Ȏ����i�v�f�̏ؖ��j�����Ŕ��������Ǝv���Ă���̂Ń^�`�������B
�p�x�u����@�\�ŁA�l�Ԃ��莝���ōs���V�t�g����U�������ꍇ�A����Ȃ�̃A���S���Y�����K�v�ł��B
��������ʓI�ɍs���Ȃ�A���̃A���S���Y���̃m�E�n�E�́i�������x���̊v�V���Ȃ���j�܂����J����܂���B
Pentax�Ƃ��ẮA����Ɋւ��Ă����M�����邯�ǁA��ԎւȂ̂ő傫��搂��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B
���ǂ̂Ƃ���A�ʐ^�J��������ł͎�U���Z�p�Ɋւ��Ĉ�Ԃ̃m�E�n�E������L���m�����A
�O�r�Œ�̍��{���}�N���B�e�ł��N����u�ꕔ�́v�u���ɑΉ����ׂ��V�t�g�u������̗p���������ŁA
�{���̂Ƃ���̓}�N�������Y�Ɋp�x�u����@�\�����邾���ł��債�����Ƃ������A
�莝���ł̑唼�̃}�N���B�e���̃u����}�����鐦���i���Ȃ킯�ł��B
100mm�}�N����160mm�����̃}�N���Ƃ��Ďg����v�f���Ȃ���Γ��ڂ���Ȃ����������ł��ˁB
���_�ł����A�莝���Łu�V�t�g�u���v���N����Ƃ����̂��F����̊ԈႢ�����A
���o�I�ȁu�[���V�t�g�u���v�́i���[�J�[���Ƃ̌����͂Ƃ������j���Ɋp�x�u����@�\�ŕ����Ă��܂��B
�������đo���Ƃ��c�_�⌟�����Â���ƁA�P���ɑ�����������������ǂ����̘b�ɂȂ�܂��ˁB
�����ԍ��F10918097
![]() 3�_
3�_
�A�L���Z����
�����_�ł����A�莝���Łu�V�t�g�u���v���N����Ƃ����̂��F����̊ԈႢ�����A
�����o�I�ȁu�[���V�t�g�u���v�́i���[�J�[���Ƃ̌����͂Ƃ������j���Ɋp�x�u����@�\�ŕ����Ă��܂��B
����H�A����܂ł̗��ꂩ�炨������錋�_�͂��łɑ����̕����F���ς݂Ǝv���Ă����ǁc
�������̂��ȁH
�����ԍ��F10918161
![]() 5�_
5�_
��[��炳��
������
2010/02/08 10:13�@[10905656]
���_�̏������݈ȑO�ɁA�X���b�h���ɂ��̂悤�ȔF���̒�����悤�ł�����|�C���^�ł������������B
�܂��A���S���Y���̌��ł����A
�����������G�ł������قǁA���G�ȏ�����S�đ��肵�������łȂ��ƌ��ɂȂ�܂���B
�ł��̂Łu�ȒP�Ȏ��������ł́`�v�Ƃ����b���o�Ă���悤�Ɏv���܂����������ł����H
�����ԍ��F10918197
![]() 1�_
1�_
gintaro����
�w���͗L��܂����ւ̃��X�Ƃ��Ĕ��f���܂��B
>���݂���p�x�u����̌��ʂƕ������āA���ꂪ�������ɂ���
����Ȏ��N�������܂������H
�����������̂͊p�x�u���ƃV�t�g�u�������݂�������ł��u�������m�ɕ����Ă���Ƃ������ł��B
�B�e�{���������Ȃ�ƃV�t�g�u���̉e�����傫���Ȃ�Ƃ����͈̂ȑO�w�E�������ł����A�V�t�g�u�����N���肤��Ńu���Ă��Ȃ��摜��������Ό��ʂƂ��ăV�t�g�u��������ł̃u����ɐ��������Ƃ������ɂȂ�ł��傤�B
�莝���̓��{�B�e�ŃV�t�g�u�����Ȃ��͂ނ�����I�ł��B
���[�炳��
���ł��X�C�b�`���������Ί댯�ȏł����삵�Ă��܂��@�B�Ȃǂ�����ł�����܂����ˁB
>�Ƃ������Ƃ́A�u�C���e���W�F���g�Ȍ��݂̋@�B�v�̓���́A�u�������ہv�ł͂Ȃ��Ƃ��������킯�ˁB�I�h���L�ł��B
�C���e���W�F���g�Ȍ��݂̋@�B�̓���́A�P���ȁu�������ہv�ł͂Ȃ��ƌ������ł��B�����Ȃ�ł��ȉ�����̂ɂ̓I�h���L�ł��B
>������A�����ȈӖ��ł�(�����������)�V�t�g�u�����ł��Ȃ����Ă����ŁA
���̓���̏����̓V�t�g�u������s���ׂ������ł��������^��ł��B���݂̋@�B�ł͌듮��ƂȂ�������ł͓��삵�Ȃ��������߂��܂�����B
������x�����܂������ʂƂ��ĉ摜�̃u�����}�����Ă��邢��ȊO�K�v�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F10918245
![]() 4�_
4�_
�L�̍��z�c����
���V�t�g�u�������ɐ���Ղ����{�t�߂̎莝���B�e�ł�SR�����m�Ɏ�u�������Ă���̂͂���܂ł̎B�e�̌��ʂ��ؖ����Ă��܂��B
���̕��͂ƑO��̕�������A�L�̍��z�c����́u�r�q���V�t�g�Ԃ������Ă�v��
�咣���Ă�ƂƂ�܂������A�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁH
�u���{�t�߂ł��r�q�͌��ʂ�����v�Ƃ����A���ꂾ���̎咣�ł�����A�S���٘_����܂���B
�ł��A���̂��Ƃ͍ŏ����炾����ے肵�Ă܂��ATomato Papa����̎����Ƃ��Ȃ�̊W������܂���ˁB
������A�Ȃ��ˑR�咣���������̂��͂킩��܂��A�����܂߁A�݂Ȃ���
���ɂ��Ă�̂́A�r�q���V�t�g�Ԃ�����邩�ǂ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10919604
![]() 5�_
5�_
�݂Ȃ���
�{���ɁA�����~�߂܂��傤��B
MZ-LL����̎�̂Ђ�̏�ŗx���Ă��܂��Ă��܂��B�܂��Ɏv���ڂ��Ǝv���܂��B
�{���ɕ��u���鎖�B���ꂪ��Ԃ̐J�߂ł��B
�����ԍ��F10919633
![]() 9�_
9�_
pen SL�ł��B
��قǏ�������Ȃ��������e�ł��B
��قǂ̃��X�ɂ������u�^���V�t�g�u���v�Ƃ����������Ȃ�A�\�@�e�Ђɂ́A�莝�����̊p�x�u�����N����ۂ̑̂̓������x�[�X�ɁA�o���l�I�ɁA�p�x�u���l����CCD��̕������߂�ۂɁu���ϓI�ȃV�t�g�u�����l���ɓ��ꂽ�p�x�u����̃A���S���Y���v�����݂���Ǝv���܂��B�i�e�Ђ̔���J�̐���萔�j�]���āA�u����̂��܂����肪��Ђ��Ƃɂ���Ǝv���܂��B
�Ⴆ�A��ɕI�����ʼn�]���Ă���̂ŁA�u�R�O�����̔��a�̉�]�Ŋp�x�u�����N���Ă���Ƃ̑O��ŁACCD�ψʕ����v�Z����v�Ȃǂ̍l�����Ƃ��B
�������A����͐��m�ɂ́u�p�x�u������@�̒��ŁA������@�Ƃ��Ċp�x�u�����CCD�ʒu����ɃV�t�g�u���̗v�f�����������v�ł���Ǝv���܂��B
�h������V�t�g�u����ƌ����ɂ́A���t�̒�`��A�d��Ȗ�肪����Ǝv���܂��B�h
�����炭�AK-7�ɂ͉����x�Z���T�[�͓��ڂ���Ă��Ȃ��ƍl�����邽�߁A�p�x�u����̐���̍ۂɁA��ʓI�ɋN����₷���V�t�g�u���̗v�f�����ꂽ�A�Ƃ̂��Ƃł���A���R���̂悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă���Ǝv���܂��B
�ȏ�A�⑫�ł��B
�����ԍ��F10919766
![]() 4�_
4�_
gintaro���� [10917405]
�����܂���B���� [10916987] �̋L�q�͊ԈႦ�܂����B
>�P�Ɋp�x�u����̌������キ�������x�̂��̂ł��B
���ꂪ�ԈႢ�i���Ⴂ�j�ŁA�������́uSR �͉��i���t�����Ƀu������̂ɂȂ�܂��v�ł��B
�������A�uSR ���p���x�Z���T�[�݂̂ŃV�t�g�u��������Ă���ꍇ�v�ł��B
�p���x�Z���T�[�݂̂ł��ꕔ�̃V�t�g�u���͊��m�ł��܂��B�V�t�g�u���Ƃ͉����H �p�x�u���Ƃ͉����H ���l���Ă݂Ă��������B���ƒ����I�ɐ����ł�����̂ł��B
�����ԍ��F10920230
![]() 0�_
0�_
pen SL����
>�e�Ђɂ́A�莝�����̊p�x�u�����N����ۂ̑̂̓������x�[�X�ɁA�o���l�I�ɁA�p�x�u���l����CCD��̕������߂�ۂɁu���ϓI�ȃV�t�g�u�����l���ɓ��ꂽ�p�x�u����̃A���S���Y���v�����݂���Ǝv���܂��B�i�e�Ђ̔���J�̐���萔�j�]���āA�u����̂��܂����肪��Ђ��Ƃɂ���Ǝv���܂��B
���ɂ͂��ꂪ�������ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��܂��A
���܂ł̘_�c�̒��ŁA�����Ƃ��[���̍s�������ł��B
����Ȃ�A�p�x�Ԃ�����V�t�g�Ԃꂪ�D�ʂɓ����̈�ŁA
�u�V�t�g�Ԃ�Ɍ����Ă���v�Ɓu������v���Ƃ��A
���̂悤�ȋ@�\�͓��ڂ���Ă��Ȃ��Ƃ����u�Z�p�I�ӌ��v�A�u�������ʁv��
�Ƃ��ɗ����ł���悤�ȋC�����܂��B
����ɁA�\�����A�ċz�ۓ��̃y�[�X�Ȃǂ̌l���ɂ��A
�u���ϓI�ȃV�t�g�u���v����O�ꂽ�P�[�X�ł́A
�V�t�g�Ԃ�ɂ͌����Ă��Ȃ��Ɗ����邱�Ƃ����肦�܂���ˁB
�i����������͕K�������\�����������Ƃ����b�ł͂Ȃ��ł��ˁj
�������ǂ����͂킩��܂��A�����I�ɂ͂���Ŕ[�������܂�����
���肪�Ƃ��������܂���(^^)
�����ԍ��F10920491
![]() 3�_
3�_
[10920230] �̎��ȃ��X�B
>�p���x�Z���T�[�݂̂ł��ꕔ�̃V�t�g�u���͊��m�ł��܂��B
�����^���鏑�����ł����̂ŏ����Ă����܂��B
�V�t�g�u���͊��m�ł��܂���B���������[�U�[�̎B�e�̕Ȃ����߂�������ł��Ȃ����Ƃ��Ȃ��A���x�ł��B
�J�����{�f�B�������č\����l�̓V�t�g�u�����Ղ��ł��傤�B���������l��p�̃A���S���Y���͑g�߂܂��B�����������Y�������č\����l�ɂ͑Ή��ł��܂���B
�V�t�g�u���i�O����܂ވʒu�Ԃ�j�Ƃ́u�����Y��_�̕ψʃx�N�g���i�̎��Ԕ����j�v�̂��Ƃł��B
�i��������̉�]�u���ȊO�́j�p�x�u���Ƃ́u�B�e��̌����s�ړ������B�e�O�̃����Y��_�ɍ��킹��B���̎��̎B�e�O��̌����́i�x�N�g���Ƃ��Ắj�Ȃ��p�i�̎��Ԕ����j�v�̂��Ƃł��B���Ԕ����i���x�j�Ȃ�ŁA��������̉�]�u������`�ł��܂��B
�����������Đ\����܂��A�p���x�Z���T�[�����ł͈ʒu�Ԃ�͂킩��܂���B
�K���ɐ����A���S���Y����g�ނ��Ƃ͏o���܂��i�Ⴆ�V���b�^�[�{�^���������{�f�B�͉��Ƀu����A�Ȃǁj�B��������������\������l�ɂ͋t���ʂɂȂ�܂��B����Ȃ��͎̂�Ԃ��Ƃ͌Ăׂ܂���ˁB
�����ԍ��F10920609
![]() 0�_
0�_
�V�t�g�u������l�����ꍇ�A����s�����ۂ��̓J�����}������ʑ̂�ǂ��Ĉӎ��I�ɃJ�������ړ��������ꍇ�ƃJ�����}�����{���̓J�����𐧎~���������̂ɂԂꂽ���܂����ꍇ���J�����������m�ɔ��f�o���Ȃ���Εs�Ǖi���x���̕�����s��������Ȃ������}�V�ȏꍇ�����Ȃ��炸�l������Ƃ������ł��B�]����G�Z���T�[�̎�Ȗ����͕���s���ׂ����ۂ��̔��f�Ɛ��m�ȕ���s����͈͂̌���ł���Ǝv���܂��B�V�t�g�u������K�v�ł���L���Ȕ͈͂͂��Ȃ苷���ƍl������̂Ō̈ӂɃu�������铮��ŃL�����Z�����ꂽ�Ƃ��Ă��Ԉ�������f�Ƃ͌����Ȃ��ƌ������ł��B
>���̕��͂ƑO��̕�������A�L�̍��z�c����́u�r�q���V�t�g�Ԃ������Ă�v��
>�咣���Ă�ƂƂ�܂������A�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁH
�ʏ�莝���œ��{�t�߂ŎB�e����Γ��R�V�t�g�u�����������Ă��܂��B
���̏������ŎB�e�����摜�Ƀu�����������Ă��Ȃ���V�t�g�u���������Ă��邩�A�V�t�g�u���̕���s�v�ł��邩�̂ǂ��炩�ł���J����������𐳊m�ɔ��f�����Ƃ������ł��B
pen SL����
�y���^�b�N�X�̌��J��������������ƃu����������Y���ōs�����B���f�q�ōs�����̌����i�K����ʒu�Z���T�[���ɗ��p����A�C�f�A�������܂��B�ʒu�Z���T�[��K-7�ł͐�����ɂ����p����܂����J�����̎p�����d�͂̕����Ŕ��f���Ă�����G�Z���T�[�̈��ł��ˁB
�����ԍ��F10920710
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������
���V�t�g�u���Ƃ͉����H �p�x�u���Ƃ͉����H ���l���Ă݂Ă��������B
�Ƃ����h��ɓ����������Ă�ԂɁA���������\���ꂽ�悤�ł��B
�V�t�g�Ԃ�Ɗp�x�Ԃ�̒�`�Ɋւ��ẮA�����̗����ł������������Ă����Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁA�����[10894840]�̐}��������₷���ł����A�ϑ����ꂽ�p���x�������ł��A
�ǂ�����]�̎��ƍl���ĕ���邩�ɂ���āA�K�v�ȑf�q�̃V�t�g�ʂ͕ς��܂���ˁB
�ŁA�p�x�Ԃ�́u��`�v�ɂ����ẮA�����Y��_����Ƃ���̂��W���I�Ȃ悤�ł����A
���ۂɂ́A�J���������̓_����Ƃ����p�x�Ԃ�̕���s���Ă�Ƃ͌���܂���ˁB
�莝���B�e�ɂ����ċN����₷���̂́i����������ƎB�e�҂��́H�j�ʂ̓_�����Ƃ���
�p�x�Ԃ�̂悤�ȋC�����邵�A���̕ӂ̓��[�J�[�ɂ���Ă��Ⴄ�̂�������܂���B
���������Ӗ��ł́A�����ɂ́A�r�q�������̂͏����Ȋp�x�Ԃ�ł��Ȃ��i�ƌ����Ȃ����Ȃ��j�B
���s�̂�������������肽���������Ƃ��A���������b�ƊW����̂��Ȃ�
�l���Ă����Ƃ���ł����A�Ƃ肠�����A
���p���x�Z���T�[�����ł͈ʒu�Ԃ�͂킩��܂���B
�Ƃ����̂́A�����̗����Ƃ������܂����A���S���܂����B
�����ԍ��F10920792
![]() 1�_
1�_
pen SL����
����A�ʔ����ǂ܂��Ă��������܂����B
��_�����A�m�F�������_������܂����̂ŁA���������Ԃ���܂�����E�E
����ԏ�ňړ�����J�����̃V�t�g�u����́A���̕���@�̎��ԕ��ϓI�ɃJ�������ړ����Ȃ��Ƃ̑O��ɔ����܂�����A�@�\���܂���B
�u�@�\���܂���v�́u�������@�\���܂���v�Ƃ����Ӗ��ł��傤���H
����Ƃ��A�����ʂ�u�@�\���܂���v�ł��傤���H
�u���ԕ��ϓI�ɃJ�������ړ����Ȃ��v�Ƃ����̂́A����������邽�߂̏����ł����A
�e�u�Ԃɂ����ăJ�����͂����m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
���������āAK7���V�t�g�Ԃ������Ȃ�A���̎����ł́A�f�q�͉����x�ɔ�������
���炩�̓���������͂��ł����A���̓u���ĂȂ��B
�Ƃ������Ƃ́A�f�q�������ĂȂ��A�V�t�g�Ԃ����s���ĂȂ��Ƃ������Ƃ�
��������A�ƍl���Ă��̂ł����A���̗����͊Ԉ���Ă܂����H
���Apen SL����̕⑫�̏������݂�ǂޑO�ɁA��d��������e���ЂƂ�̃��X��
���炾��Ə����Ă��܂��܂������A
���ɁA�ȉ��̂��w�E�͏d�v���Ǝv���܂��B
���������A����͐��m�ɂ́u�p�x�u������@�̒��ŁA������@�Ƃ��Ċp�x�u�����CCD�ʒu����ɃV�t�g�u���̗v�f�����������v�ł���Ǝv���܂��B
���h������V�t�g�u����ƌ����ɂ́A���t�̒�`��A�d��Ȗ�肪����Ǝv���܂��B�h
������[10896333]�ɂ����āA�u�p�x�Ԃ��Ƃ������́A�p�x�Ԃ�ƃV�t�g�Ԃ�̍������v
�Ƃ����\�������܂������A
�E�Q�̂Ԃꂪ������̊����ō����������̂�����
�E�Q�̂Ԃ�����ꂼ���Ɨ��ɕ����
�́A�S�R�Ⴄ�A�Ƃ������Ƃł���ˁB
����킵���ł����A��������������ɂ���Ƌc�_�͉i���ɂ���Ⴄ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10920943
![]() 1�_
1�_
gintaro����
���̃X���ł��̂͏��X�C��������̂ł����A�����������Ƃ��Ȃ���b�ɂȂ�낤�A���Ă��ƂŁB
>�p�x�Ԃ�́u��`�v�ɂ����ẮA�����Y��_����Ƃ���̂��W���I�Ȃ悤�ł���
�����Y��_����Ƃ���͎̂ʐ^�B�e������ł��ˁB
�n��ŎB�e����̂Ȃ���W�n�͒n��Œ�B�����Y��_�̑��x�x�N�g���͈ʒu�Ԃ�A�����Y��_�𒆐S�Ƃ����p���x�x�N�g���͊p�x�u���B���ꂼ��O�����Ȃ̂ŕϐ��͎O���̌v�Z�B�����ĘZ�̕ϐ��͑S�Ď��Ԃ̊��B����őS�āu�J�����u���v�͕\���ł��܂��B
Tomato papa���� �̃u���O
http://papablog2.ice-tomato.com/article/140302368.html
�́u�e�X�g�R�v�͈ʒu�u���������A�Ƃ������Ƃ������������������Łi�������ʒu�Ԃ�����Ă���Ƃ͓��ꌾ���������j�B
�Ƃ���ŁA�ǂ����Ɋ����n��ݒ肵�Ă����́i�J�����j�̉~�^���̒��S�_�����̓��ɂ���Ƃ͌���܂���ˁB�����ĉ�]���S����ł���Ƃ�����܂���B��]���S���������邩������Ȃ��i���z�n�ɑ��Ēn���͎��]�ƌ��]�̓������j�B
����ł������n�i���W�n�j����ݒ肷��A�g�C�ӈ�_�̃u���h�́i���̓_�́j���x�Ɓi���̓_�̎���́j�p���x�ŕ\�����Ƃ��ł���A�Ƃ������Ƃ��d�v�ł��i�g�C�ӈ�_�h�Ȃ̂ŁA�����Y��_�Ɍ��炸�A�B���ʃu���ł��A�V���[��̃X�g���{���S�̃u���ł��\�j�B�J�����Ƃ��ėL���Ȃ̂̓����Y��_�Ƃ������Ƃł��B
�i���ۂ̃W���C���Z���T�[�������܂ł̐��x�����邩�͋^��ł����j�B���ʕt�߂ɃW���C���Z���T�[��u�����ꍇ�́u�B���ʎ���̊p���x�v��̂ł��傤���A���̏ꍇ�����Y��_����̋���������܂��B���������̏ꍇ�͗��҂��Ƃ��Ɍ�����ɂ��邽�߁A�����Y��_����̊p�x�u���Ɠ���ɂȂ�̂ł��i�����������Y��_�̈ʒu�Ԃ�͋N���肤�邵�A����͊��m�ł��Ȃ��B�B���ʈʒu���Œ�Ƃ����O��̌��Ȃ�v�Z�ł���Ƃ��������j�B
���Ɓu�d�q������v�ł����B
�j�R���� D3 �́u�p���x�Z���T�[�v�A���R�[�̃f�W�J���� K-7 �́u�����x�Z���T�[�v�炵���ł��ˁB
�i���ɏ����܂������j�����x�Z���T�[�̐�����̏ꍇ�A�B���ʏ�́g���S�~�����h�̉����x�Z���T�[�̂��߁A�u��������̉�]�u���v�͊��m�ł��Ă��u�ʒu�u���v�͊��m�ł��܂���i���˕����A���邢�͑O������̉����x�Z���T�[���K�v�j�B
������\��������̂́i��������ɏ����܂������j�u�ʒu���̂��̂̌��o�v�ł��ˁB�t�H�[�J�X�|�C���g�ŎB�e������m��A���C�u�r���[�摜�̃s�N�Z���̃u�������i�p�x�u�����L�����Z�������ꍇ�́j�ʒu�u���ʂ�m�邭�炢�ł��傤�B���Ȃ�����\���͒Ⴂ�Ǝv���܂��B
�l�I�ɂ͈ʒu�u���������Y��B���f�q�ŕ����͔̂��ł��ˁB�p�x�u���̂��ƂȂ����l���Ă��Ȃ�����i���i���t�����Ƀu����ꍇ�����邵�A��s���ɂȂ�ꍇ������j�B
���Ȃ烊�R�[GXR �̂悤�Ɂu�����Y�B���f�q��̌^�v�Ƃ��āA�J�����{�f�B�ɑ��ē����悤�ɂ��ׂ��ł��B
�̂̃R�j�J�~�m���^�� DiMAGE X1 �͈�̌^�̎�u����������炵���ł����ǂˁB�ʒu�u��������Ƃ͕����Ă܂��B
�����ԍ��F10920946
![]() 1�_
1�_
gintaro����
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�����x�Z���T�[�́A�J�����̈ړ����x���ω����邱�Ƃ����m������̂ł��B
�����x�Z���T�[�̍쓮��������l���āA�������i����ꍇ�ƐÎ~�̏ꍇ����ʂł��܂���B�����ړ����Ă����ԏ�ł́A�J�������Î~���Ă���ƔF�������ł��܂���B�]���āA�u�@�\���Ȃ��v���������A�u�������@�\���Ȃ��v�͊ԈႢ�ł��B
�U���́A�U��q�̓������l���Ă��炦�����̂ł����A�U��q�̈ʒu�E���x�E�����x�i���x�ω����j�������W�ɂ���܂��B�]���āA�P���ȐU��q�ł���A�����x�̕ω��Ǝ����𑪒�ł���A�ʒu�Ƒ��x���r�I���m�Ɍv�Z�ł��܂��B
�l�Ԃɂ͊߂����������āA�ۓ���̂̃u���ȂǑ̑S�̂̓���������A�U�������G�ł��B�����A�����O�ɏ��������@�ő��x���m����Ȃ�A���O�ɑ�R�̐l�̐U���𑪂��āA�ǂ̂悤�Ȏ����̐U���i���ʂ͐���ނ̎����̐U�������킳�������́i�����j�j�����邩�A�l�ɂ���ĕω��͂Ȃ��������O�������āA���͂��������x�̎��ԕω��̃p�^�[������A�U����͌v�Z�������A�V�t�g���x���v�Z����̂���ʓI���Ǝv���܂��B
���ƁA�\����̖��Ƃ��āA�R�����g�����������܂����B���́A�J������Ђ��ǂ̂悤�Ȓ����i�`���[�j���O�j�����Ă��邩�s���ł��̂ŁA�u�������āv�̕\�������Ă��܂��B
�\���I�ɂ͎w�E�̒ʂ�A�u�������āv����萳�����Ƃ͎v���܂����APENTAX�����̂悤�ɍl���Ă��邩�s���ł����̂ŁA�u�����v�Ƃ̂����܂��ȕ\���Ƃ��āA�F�X�Ȍv�Z���@�����邱�Ƃ������\���Ƃ��Ă��܂��B
�O�ɂ������܂������A��ʂ̎B�e�ł́A�p�x�u������U��̂قƂ�ǂł��邽�߁A������U���̐���n��v����Ƃ�����A
�܂��A�p�x�u���𒆐S��CCD�ړ�����������āA���C�����ځi�`���[�j���O�j�̂P�Ƃ��āA�ʒu����̏C�����������܂��B���C�����Ƃ��ẮACCD�쓮�p��H�̓d���̗����オ�葬�x�A�d���l��CCD�̉����x�̊W�i���j�A�ł���Ζ�肪����܂��j�A�V���b�^�[���x�̉e���A���̑���CCD�ړ�����ɂ������C�����ƁA�l�Ԃ̕Ȃɂ�����鍀�̏C���������܂��B
�i���͐���E�v���O�������ł͂���܂��A���Y�ݔ��̋@�\�v�Ȃǂ����Ă��܂��B�A���S���Y�����������A������@�̎d�l�����o�����ł��j
���̐���v�ł���Agintaro����̎w�E�̂悤�ɁA�u�������v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
���ɁAK-7�������x�Z���T�[�ɂ��V�t�g�u��������Ă��Ȃ��Ƃ���A��U���Ƃ��āA�p�x�u����𒆐S�Ƃ��āA�V�t�g�u���Ȃǂ̐l�Ԃ̕Ȃ�������X�̏C���������邱�ƂŐ��x�A�b�v���Ă���\���������Ǝv���܂��B�i�O�̃��X�ɁuCCD����n�Ɛ����V�͕ʌn��v�Ƃ���܂��̂ŁA�����炭�����x�Z���T�[���u������Ɏg���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��j��������̂�����C�����邱�Ƃ́A�V�t�g�u���C���Ƃ͌����܂���B������ł��B
�����Ō��������̂́A�V�t�g�u���Ή��͑��̍��ڂƕ���Ő���̏C�����ڂ̂P�ł���ƍl������̂ŁA����������Ă��|�V�̓V�t�g�u������Ă���Ɠ��X�ƌ����̂͌����߂����ƁB
pen SL
�����ԍ��F10921970
![]() 1�_
1�_
gintaro����@�Ԏ����P�Y��Ă��܂����B
�������������m�ɂ킩��Ȃ��ł��̂ŁA���m�ȓ������킩��܂��A�����̏����ł����A�����x�Z���T�[�ł̐���������Ȃ��Ă��Ȃ����A����\�ȃp�^�[���ł̓����ɂȂ��Ă��Ȃ����̂ǂ��炩�Ǝv���܂��B
�P�O�O���̊m�M�͂Ȃ��ł����A�l�I�ɂ́u�Ȃ��v�̕����Ǝv���܂��B
pen SL
�����ԍ��F10922097
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������
K-7�̓d�q������͈��̏㉺�p���z����ƃL�����Z�������̂őO��̏d�͕��������m���Ă���Ǝv���܂��B
pen SL����
�V�t�g�u���Ή��͑��̍��ڂƕ���Ő���̏C�����ڂ̂P�ł���ƍl������̂ŁA����������ăV�t�g�u������Ă���Ɠ��X�ƌ����̂͌����߂��ƌ������ł��ˁB
����͎�Ɋp�x�u�����o���s���W���C���Z���T�[���ɉ����x�Z���T�[�����C�����ڂƂ��ĉ������Ă��V�t�g�u������Ă���Ɠ��X�ƌ����̂͌����߂��ƌ������ł��傤���B
�����ԍ��F10922443
![]() 1�_
1�_
ask-evo����
���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
���̋L�ڂ́u�����J������Ђ̋Z�p�҂������炱������v�̈Ӗ��ł��B�J������Ж��̎�U���̗D���邱�Ƃ���A���̈ӌ��ł��̂ŁB���̂悤�Ȑ���̓n�[�h�̗D�G���ɉ����āA����\�t�g�̎��ł��D�o�܂��B
���̂悤�ȃm�E�n�E�͕��ʊ�Ɣ閧�ł��B
���j
�������A�����炭�u���ϓI�Ȑl�Ԃ̕Ȃ�D�荞����v�ł���A�V�t�g�u�����������Ƃ̈Ӗ��ł��̂ŁB
�����ԍ��F10922451
![]() 1�_
1�_
�ǂ��̃}�j�A�b�N�Ȑ��E�ł��A���葤�łȂ����[�U�[�B���A�����B�̌��ɓ͂��͈͂̏��݂̂ŁA
�\����Z�p�̂��Ƃ̒��ōl���āA�ǂ�ǂ�Ƙc�Ȃ����āA�I�J���g�߂�������\�b��
���L���Ċy���ށA�Ƃ������ۂ͂悭����b�ł��B
�����A���̊J���҂⌤���҂������A�������Ԃ������Ďϋl�߁A���ǂ���������d�˂�
�@�\��\���A���܂�ȒP�ɋZ�p�I�Ȍ��_�Ɏ����Ă����Ȃ��ق����A���ʓI�ɂ͎��̐������m����
���邽�߂ɂ͗ǂ��̂ł͂Ȃ����A�Ɗ����܂��B
�i�䖼�O��������ƁA��������ł��܂����ꂪ����܂����珑���܂��j���Ȃǂł�
�ƂĂ������Ȃ��悤�ȁA��Â������I�Ȍ�w�E���ӌ��A�l�@��ǂ݂₷�����͂ŁA
�����Ă�������������̂��������݂��A��ϊ��ӂ��Ă���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
������x�A�r�q�̓���̒��ӎ�����A�L���m�����n�C�u���b�g�h�r�ʼn�����Ă��邱�Ƃ��A
�ǂ��ǂ�ł݂�A�Ȃ�ƂȂ��l���邫�������́A�o�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����A�{���ɃL���m�����f�W�C�`�ŏ��߂ăV�t�g�u���̕�������ł����Ƃ���Ȃ�A
�u�V�t�g�u������ł���̂́A�L���m�������ł��B�����Y����ł���h�r�����ł��v
���Đ����X�ɗD�ʐ��������悤�ɏ����Ă������āA�s�v�c�ł͂Ȃ��ł��傤�B
����������������A����܂ł����Ă����̂ł�����B
�u�n�C�u���b�g�v�Ȃ�Č��t���g��Ȃ��Ă��A�y���^�b�N�X�̂r�q�́A���Ƃ��Ɨ����̃u����
�Ή����Ă����̂��Ǝv���܂��B���ꂾ���́A����������₷���b���Ɗ����܂����B
�����āA���̎g�p���̈Ⴂ���A�������[�U�[�Ƃ��Ă̌l�I�Ȏ����Ȃǂ��A
������̃X���b�h�ł́A�����Ă��܂����B
�Ȃ̂Ŕ�r�I�p�x�u�����N����₷���A�]����̃����Y�̎B�e�Łu�Ⴂ�������Ȃ��v�Ə����ꂽ�����
�䊴�z�́A�����Ƃ��Șb���Ɗ����܂��B���������Y�ł��u�������Ȃ���������Ƃ����t�H�[���f�B���O��
����Ă���̂ł��傤�B�@�����������������Y�Ŏ莝���ŎB�e����A�u����m���͉��{�������Ȃ�Ǝv���܂��B
�i���́A�߁E�������̐Ñ̂���̎B�e�ł�����A���̔�ʑ̂�B�e���@�Ɋւ��ẮA�ƂĂ����m�ł��j
���x���������͂��ł��B�y���^�b�N�X�ł́A�r�q�ŁA���[�U�[�����ۂɎ莝���ŎB�e����ۂɁA
�ǂ�Ȃɍ\�����������肵���l�ł��A�ǂ����Ă��N�����Ă��܂��悤�Ȕ��u���ɂ��Ή����Ă���A
�ƕ����ė������āB�����āA�ʒu�u���ɑΉ����Ă��邱�Ƃ��A���x���m���߂Ă��܂����B
���͂悭�Ȃ��������ݕ������Ă��܂������A�����Ă�������������Ă��镔�������邩�Ǝv���܂��B
�����n�b�L��������̂́A�r�q�ɂ��Ă��A�t�@�C���_�̎���ɂ��Ă��A�l�Ԃ̓��̂⎋�o��
���킹�āA�`���[�j���O������Ă���A�v��v���O����������Ă���̂ł��B
������A�����듮�삪�����āA�C���⒲�����˗�����Ƃ��Ă��A������m���߂�̂́A
�l�Ԃ̖ڂ�v��Ŏ�ɍs���Ă��āA�v���퓙�͂���ȊȒP�Ɏg���킯�ł͂Ȃ��A�ƕ����Ă��܂��B
���ۂɁA���̃J�����̎��삪�������Ɉꖇ�A���̖ш�{�قǂ̌덷���������ۂɁA���������肢���鎞��
�r�b�̌�����A�䎩�g�̖ڂő��肵�Ă���āA���Ɠ������A�{���ɉ������Ɉꖇ�A�͂��Ȍ덷�����邱�Ƃ��A
�m���߂Ă��������A�C���𐳎��ɂ��肢���邱�ƂɂȂ�܂����i����������������@�̈ꕔ�������Ă��܂����j�B
�߂��Ă����J�����̎���́A�i����ł́j�قڊ����Ɋ����Ă��܂��B���ɉ��K�ł��B
�i�����܂��j
�����ԍ��F10922869
![]() 0�_
0�_
��L�Ƒ����Ė������e�ł����A�������������Ă����܂��B
����̖邩��[��ɂ����āA���ۂɂ����ȃ����Y�łr�q�������Ă������ƂƂ��A
����܂łl�e���܂߂�ƂT�O�{�ȏ�i�����^�Ԃ��������܂ށj�̃����Y�������āA
�������d���Ŏg���ۂɌ����Ă��镨��I��ł������ƁA�Ȃǒ����ʼn��������Ă��܂����B
�ł��A�[��܂Ŗ������������A�f���͂��܂���ł����B
���̂悤�ɁA���X�Ǝ����̍l����g�p���Ȃǂ��������ސl�Ԃ́A�������悩�瓊�e���Ă����
���Ă��Ċ�����l�����邩������܂��A���Ȃ�ɁA���ۂɃA�b�v���郌�X��摜�́A�I��ł���̂ł��B
���́A���Ƃ��ƁA���������҂ɂȂ��Ăł��A��������R�B�e�����o�����犴�������Ƃ́A
����قNJԈ���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ������Ă�������ł��B
������A�F���l�I�Ɏ������ӋC�ȓz���Ƃ��A�l�i���c��ł��邾�Ƃ��A�v�����Ƃ��̂��̂́A
�܂��������܂��܂���B�ǂ���낤���A�l�̎��R�Ȃ̂ł�����B
�ł��A������ŏ������ވȏ�́A�X���b�h�̎�|��A���i�R���f���̎�ȃ��[�����m�F���āA
���X���f�����ė~�����A�Ɗ����Ă��܂��B
���x�����炩�ȁu�r�炵�v�Ɓu�r�炵�I�v�ȏ������݂�����y���o���������̃X���b�h�ł����A
��ÂɌ��Ă���l�Ȃ�A�����ɋC�Â��Ǝv���܂����A�i�ȉ��A�����܂ł������ł��j
�ޓ��́A�����̃A�J�E���g�������āA���������������X�ɁA�����Ɂu�i�C�X�I���[�v���s���A
�����h�̉��o�̂��肩�Ȃɂ�����܂��A�p�����������Ƃ�����Ă���悤�Ɍ����܂����B
�����āA����A���Ɋ�Ȃ��������݂������A���Ƀt�@���o�^���Ă܂ŁA�S�����čr�炵�Ă���
�l�́A�Ȃ��������Ă��܂��܂������i������A�N�Z�X�֎~�Ƃ�����ł��傤���H�j�A
���x�͂����A����ɑ���悤�ɁA�ʂ̃t�@���o�^�����Ă܂ŁA���̃X���b�h�ł��S������
�ǂ������čr�炷�l���A�o�Ă��܂����B
���x�������܂������A�������ł͐^���͓����o���܂���B
����ɗx�炳�ꂽ�l�����́A���ЁA�[�����Ȃ��ė~�������̂ł��B
�������������Ƃ��������Ƃ��Ԉ���Ă���Ƃ��A���ꂼ��̐l���A�����̎B�e�̌��̒�����A
���������Ă���������A����ł����̂ł��B
�����ԍ��F10922921
![]() 1�_
1�_
�L�̍��z�c����
����̓����ł��B
���ɁAK-7�ŁA�����x�Z���T�[����������Ă��āA���̏��Ƃ��ƂɁA�p�x�u����ƃV�t�g�u�����������������������Ȃ��Ă���A�ǂ��炪�召���͖��łȂ��A�u�V�t�g�u������s���Ă���v�ƌ����Ă����Ǝv���܂��B
���t�̖��Ȃ̂ŁA��ΐ����͂Ȃ��Ǝv���܂����A�Z���T�[�Ō��m�������Ő��䂵�Ă���A���ꂪ�����Ȑ���ł����Ă����䂵�Ă���̂����Ă����Ȃ��Ǝv���܂��B
pen SL
�����ԍ��F10923899
![]() 1�_
1�_
pen SL����
��{�I�ɂ̓��[�J�[�i�L��j�����Ă��铮��T�O�}�́i�ȗ����ɍۂ��Ắj���������������{�̗v���Ɏv���܂��B
�܂����ۂ̐��i�́i���̓���̑P�������͕ʂƂ��āj���G�ȗv���i�Ƃ��̐���j������ł��鎖�ւ̔F���s�����ł��B
�Ⴆ�u�����Ȋp�x�u���v�Ɓu�����ȃV�t�g�u���v���������Ă�����A��U���͐��藧���܂����ˁH
���^�t�̓��삪�K�v�ɂȂ�ꍇ�A���R�ǂ���Ƀv���C�I���e�B���������̓A���S���Y���Ō��߂܂��B
���������Ƃ��낪���i�Ƃ��ďo�ׂ���镨�́u�_���ł����ė�������Ȃ��v�̂��Ǝv���Ă��܂��B
������̓p���_�C���̒u�����A�u���ꏊ���قȂ�Ƃ����Ӗ��ł��B
���������b�ƁA���̃X���b�h�ŕp�ɂɌ����肳��Ă��钧������Ƃ́A�v���̊O�������̂�����ȂƊ����܂��B
�����ԍ��F10925202
![]() 5�_
5�_
�A�L���Z����
�䗝�����肪�Ƃ��������܂��B�����ꂽ���ƂƎ��̍l���́A�ƂĂ��߂��ł��B
��U���̗ǂ������́A�n�[�h�̐��\�Ɛ���\�t�g�̃}�b�`���O�̌��ʂŌ��܂�Ǝv���܂��B
����\�t�g�ł́A�o����̃u�����ڂ̂����A�ǂ��D�悵�ČW�������蓖�Ă邩�p�{�i�o�Z���T�[�̐��x�Ɛ��䐸�x�̐������i�����̏ꍇ������܂��j�p�{�o�l�Ԃ̕ȂȂǂ�D�荞�߂邩�p�Ȃǂ̓_���傫���e�����܂��B���ʁA���[�J�[���̎�U���̂��܂����肪�ł�͂��ł��B
�����ɏ�����Ă�������AK-�V�͎�U�����ǂ��Ǝv���Ă���Ȃ�A����́AK-7�̎�U���́u�����́v���������ƂɂȂ�܂��B�V�t�g�u������Ă��邩��A�����[�J�[���ǂ��Ƃ̌��_�͏o�܂���B�Z���T�[�������Ɣ�����Ă��Ȃ���A�⏕�I���ڂł���ˁB
K-7�̃J�����̎�U���ł́A�u����̍l�����̗D�G�����m�ۂ��邽�߂ɁA�u�ő�̗v���ł���p�x�u������x�[�X�ɁA�F�X���钲�����ڂ̒��ŁA�p�x�u���̌X������V�t�g�u���𐄒肵�āA�������Ɏg���Ă���i�\��������j�v�Ƃ̈Ӗ������̗����ł��B
�䗝�����Ă�������������o�܂����̂ŁA���͈̔��ނ����Ă��������܂��B
�����ԍ��F10926146
![]() 7�_
7�_
��pen SL����
���x�������Ă���悤�ɁA�ǂ���̕����Ƃ��A�����������Ƃ��Ă���킯�ł�
�q�ׂĂ���킯�ł��Ȃ��̂ɁA���r���[�Ȓm���ŁA�Ԉ�������Ƃ�f��`�ŏ������̂́A���ɖ��f�ł��B
���������X���b�h�Ⴂ�ł��B��x�Ƃ����������b��́A�������܂Ȃ��ł��������B
�����̊��o�݂̓��������Ȃ̂ɁA���������������˂�����ƂŁA�v���C�h���ێ�����p�́A
���ɎS�߂Ɍ����܂����B
�ǂ�ȋZ�p�Ƃ��̘b�����˂���Ă��A�������f�l�̎��o���疳���Ȃ�A�����Ɍ��E�͂���ł��傤�B
�O�Ɏ������������Ƃ́A��͂蓖�����Ă���悤�ł��ˁB
���Ƃ��Ԉ�������Ƃ�A�^�����牓�����Ƃł��A���������̃��x���ŗ����ł���͈͂ŁA
���◝�_�����L���邾���ŁA�������Ă���l�����������A���āB
�����B�̖����̂��߂ɁA��|���Ⴄ���Ƃ��A���̃X���b�h�ʼn��x���������܂Ȃ��ŗ~�����ł��B
�����ɂǂꂾ���̔�炪���邩�A���o���������_�ŁA�q�ϐ��������Ȃ��̂ł��B
���̃X���b�h�ɏ������܂��A�����悤�ȗ���͂̐l�����ŁA�V���ȃX���b�h�𗧂ĂāA
���Ȗ����Ń��X�������Ă���Ηǂ�������ł��B�@�{���ɖ��f�ł����B
�����ԍ��F10926567
![]() 2�_
2�_
pen SL����
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B
�������x�Z���T�[�̍쓮��������l���āA�������i����ꍇ�ƐÎ~�̏ꍇ����ʂł��܂���B�����ړ����Ă����ԏ�ł́A�J�������Î~���Ă���ƔF�������ł��܂���B�]���āA�u�@�\���Ȃ��v���������A�u�������@�\���Ȃ��v�͊ԈႢ�ł��B
���X�A���̕��Ō�����Ă����Ƃ��낪�������悤�ł��B
����ԏ�ňړ�����J�����̃V�t�g�u����́A���̕���@�̎��ԕ��ϓI�ɃJ�������ړ����Ȃ��Ƃ̑O��ɔ����܂�����A�@�\���܂���B�i������ƌ����āA�O���X�̎������@���Ԉ���Ă���K-7�ɃV�t�g�u���������Ƃ̈Ӗ��ł͂���܂���j
�ɂ����āA�����́u��ԁv�Ƃ́A��ʓI�ȁu�����x�^�������ԁv�������̂ł��ˁB
Tomato Papa����̎����̑�Ԃ̂��Ƃ��w���̂��Ǝv���Ă܂����B�i������͖��炩�ɓ����^���ł͂Ȃ��B�j
����ԂƂ点�Ă��܂��܂����B
�p�x�Ԃ��ɃV�t�g�Ԃ��̗v�f���������錏�̉�������肪�Ƃ��������܂��B
�������A�p���x�Z���T�̌��o�l�Ɋ�Â�����ł���ȏ�́A���F��
�h�����ȃV�t�g�Ԃ�ɑ��Ă͌��ʃ[���h
�ł��傤����A�ǂ������\�����K���Ȃ̂��͎����悭�킩��܂��A
���b�́i�������������܂������j�킩��₷�������[�������ł��B
���������A�p���x�Z���T�Ō��o���ꂽ�l�i�p���x�̂P�����̐����j����A
���ۂ̃J�����̓����𐄑�����̂ɁA�l�Ԃ̂���������ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ�
�͓̂��R�Ǝv���܂��B
����������́A�~�^���̎����ǂ��ɉ��肷�邩�A�Ƃ������ł��傤����A
���[�J�[�Ƃ��āA�V�t�g�Ԃ�Ƃ̍������Ƃ��A�V�t�g�Ԃꐬ���������Ƃ�����
�ӎ��͂Ȃ����낤�Ƃ��v���܂��i���ł��j�B
���ۂ̃A���S���Y�����ǂ��������̂Ȃ̂��͋�������܂��ˁB
�i�]�v�Ȃ��Ƃ����Ă������Ȃ��̂ŁA�������G�Ȃ��̂ł��Ȃ��̂ł́A�ƌl�I�ɂ͑z�����܂����B�j
�����ԍ��F10926591
![]() 2�_
2�_
���ۂɋߋ����ŁA��̌��ʂ��o�Ă��邱�Ƃ͂������̂��ƁA
�y���^�b�N�X����A�u�ʒu�u�������Ă���v�Ƃ���������̂ɁA
�Ȃ��A���܂��ɁA�����ꒃ�Ȃ��Ƃ��A���̃X���b�h�݂̂Ȃ炸�A���X���b�h�ł������Ă����̂ł��傤�B
�y���^�b�N�X�Ŏ��ۂɎ�Ԃ��@�\�̊J���Ɍg������킯�ł��Ȃ��l�Ԃ��A
�����̒m�������◝�_�������ɁA�̂����ɔے肵�Ă悢�Ǝv���Ă�̂ł��傤���B
�ǂꂾ���������Ȃ��Ƃ����Ă��邩�A���o�������l�Ԃ��A�Ԉ���������T���U�炵�Ă����B
������A�����̌f��������ƌ����A���ӔC�����܂��B
���{�I�ɁA�����̊��o���݂����̂ł��邱�Ƃ��A���o�ł��Ȃ��̂����ł����A
������A���r���[�Ȓm���ŕ����B�������̂��A���͂̔����Ă��Ȃ��v���C�h�ɂ����݂������̂��A
�ǂ���ɂ���A���ɂ݂��߂ȍs�ׂł��B
����Ȃ��ƂŁA���̃X���b�h���g���̂́A��߂Ă��������B
�Ԉ���Ă���������L���āA������^���҂������Ă��A����͊Ԉ�����܂ܕς�邱�Ƃ͂���܂���B
�����B�����̕������Ă����킯�ł��Ȃ��A���ۂɊJ���Ɍg����Ă����킯�ł��Ȃ��̂ɁA
�悭�����܂ł����Ƃ��炵��������ȁA�Ɗ����܂��B�@�܂��͎��͂����邱�Ƃ���n�߂�����̂ɁB
�X���b�h�Ⴂ�̘b��𑱂��Ȃ��ł��������B�����B�̔����Ȃ݂Ă��������B
�����ԍ��F10926717
![]() 2�_
2�_
>�y���^�b�N�X����A�u�ʒu�u�������Ă���v�Ƃ���������̂ɁA
���Â��ˁA������x�y���^�ɕ����Ă݂�
�Ⴄ�������Ԃ��Ă����
�����ԍ��F10926748
![]() 16�_
16�_
gintaro����
�I���ɂ�������ł����A���l�тł��B����́A���̌��t���炸�Ō�������܂��āA�\����܂���ł����B
�������ē���ł���ˁB�`�e�����P������Ƒ傫�Ȍ���ɂȂ����肵�܂��B�Θb���Ƃ����ɒ����ł����ł����B
����ł́A�ʂ̔ŁB
�����ԍ��F10926795
![]() 1�_
1�_
MZ-LL�l
�M�a�́A�����g����ΓI�ɐ��������̂悤�ɏ����Ă������Ⴂ�A�M�a�ƈႤ�ӌ����q�ׂ��Ă������ډ����Ă�������Ⴂ�܂���
��قǂ��̂����Ȃ̂ł��傤�ˁB
�������B�����̕������Ă����킯�ł��Ȃ��A���ۂɊJ���Ɍg����Ă����킯�ł��Ȃ��̂ɁA
���悭�����܂ł����Ƃ��炵��������ȁA�Ɗ����܂��B�@�܂��͎��͂����邱�Ƃ���n�߂�����̂ɁB
�M�a�́A���̕������ꂽ�̂ł��傤���H�@�J���Ɍg��ꂽ�̂ł��傤���H
���͂�����Ƃ́A���̎��͂����邱�ƂȂ̂ł��傤�H
���ꂾ�������g�Ɏ��M�̂���M�a�̎��́A���Дq�������Ă������������ł��B
�����ԍ��F10926867
![]() 32�_
32�_
���s�̂�������
�ڂ���������肪�Ƃ��������܂��B
�����_�Ƃ����̂́A���b�ǂ݂Ȃ���A���ꂪ���R���낤�Ɣ[���͂��܂����B
�������x�Z���T�[�̐�����̏ꍇ�A�B���ʏ�́g���S�~�����h�̉����x�Z���T�[�̂��߁A�u��������̉�]�u���v�͊��m�ł��Ă��u�ʒu�u���v�͊��m�ł��܂���
�i���˕����A���邢�͑O������̉����x�Z���T�[���K�v�j�B
�u���S�~�����̉����x�v�B�p���x�ł͂Ȃ��ĉ����x�ł��傤���H
Tomato Papa����̃e�X�g�P�ł́A���E�����̉����x���������ĂȂ��ł����A
������@�\�̂��߂Ǝv����摜�̌X���������܂��B
�ł�����A���E�����̉����x�͂Ȃ�炩�̌`�Ō��m����Ă�̂ł���ˁH
��������\��������̂́i��������ɏ����܂������j�u�ʒu���̂��̂̌��o�v�ł��ˁB�t�H�[�J�X�|�C���g�ŎB�e������m��A���C�u�r���[�摜�̃s�N�Z���̃u�������i�p�x�u�����L�����Z�������ꍇ�́j�ʒu�u���ʂ�m�邭�炢�ł��傤�B���Ȃ�����\���͒Ⴂ�Ǝv���܂��B
�ǂ������`�ł���A�f�q����f�[�^���̂��̂𗘗p������Z�p���ł���Ƃ悢�Ǝv���܂�
�����x�Z���T���p���x�Z���T���K�v�Ȃ��Ȃ邩�珬�����ł��܂��ˁB
�ꕔ�̉�f��I�����ɍ����ŕ�����ǂݏo���A�Ԃ�ʂ��Z�o�A�f�q���V�t�g�B
�̂���̉�f�����ʼn摜�f�[�^���B
�E�E�Ȃ�Ă̂͂���܂��ˁH�b�l�n�r�Ȃ�B
�L�̍��z�c����
�x���X�ƂȂ�\����܂���B
���ʏ�莝���œ��{�t�߂ŎB�e����Γ��R�V�t�g�u�����������Ă��܂��B
���̏������ŎB�e�����摜�Ƀu�����������Ă��Ȃ���V�t�g�u���������Ă��邩�A�V�t�g�u���̕���s�v�ł��邩�̂ǂ��炩�ł���J����������𐳊m�ɔ��f�����Ƃ������ł��B
���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B�����āA
�V�t�g�u��������ꂽ�̂�
�V�t�g�u���̕���s�v�ł������A�܂�A�V�t�g�u�����N���Ȃ������̂�
�́A�B�e���ʂ����Ă���ʂł��܂���ˁB
��n�m�łԂ�邱�Ƃ����邵�A��n�e�e�łԂ�Ȃ����Ƃ�����B
���������オ�����A�Ƃ��������ł́A�P�Ɋp�x�Ԃ��̌��ʂ�������Ȃ��B
������A�V�t�g�Ԃ��̌��ʂ���������͍̂���ł͂Ȃ����Ƃ����̂������������Ƃł����B
�s�\�Ƃ͌����܂���B
�Ⴆ�A�ʏ�B�e�ƋߐڎB�e�Ő��������قƂ�Ǖς��Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ�
�V�t�g�Ԃꂪ�����Ă�ƌ��������ɂȂ肤��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10926893
![]() 3�_
3�_
MZ-LL����
pen SL����̂��ӌ��́A�����܂ň�ʍH�w�I�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B
���̏�ŁAK-7�ɓW�J����Ă���Ƃ���A�Ƃ����u�l�@�v�ł���A�u�V�t�g�Ԃ�Ɍ����Ă���v�Ƃ����ӌ����A�u�V�t�g�Ԃ��͓��ڂ���Ă��Ȃ��v�Ƃ����ӌ����A�ǂ�����ے肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ނ��뗼�҂��Ƃ��ɍm��ł�����ɉ���I�ȁu�ӌ��v�Ɏv���܂����B
(�l�I�Ȏv���͎�����Ă��邩���m��܂��A���͂͑��_�Ƃ��Ē����I�ŋq�ϓI�ł�)
�����玄�͂��̃X���ŗB��i�C�X���������Ă��������܂����B
���������Z�p�I�Ș_�c����|�Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂ł���A���͍��̂Ƃ���ł��D�ꂽ�u�ӌ��v�Ɋ����Ă��܂��B(����ł��č����͋Z�p�I�ōl�@���Ȋw�I�ŁA�Ȃ���������ے肵�Ă��܂���)
��x�A�F�ዾ���O���ēǂݒ����Ē��������Ǝv���܂��B
�[���ł��邩�ǂ����͂Ƃ������A�����܂Ŕ������e�ł͖����悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F10929053
![]() 15�_
15�_
��Ԃ�̂����u�V�t�g�u�������v�������Ă��邩�ǂ����ɂ��Ă�(�����̃J�b�g���T���v���Ƃ��Ĕ��f���K�v�ł���)�A50mm���{�}�N�������Y��No.10�̃N���[�Y�A�b�v�����Y��g�ݍ��킹��
�E�����Y�̋���������ɃN���[�Y�A�b�v�����Y�����Ń}�N���B�e
�E�N���[�Y�A�b�v�����Y���O���ď�Ɠ����{���ɋ߂��Ȃ�悤�}�N���B�e
���莝���ŃT���v��������āA�D�ʂȍ�������Δ��f�\���Ǝv���܂��B
�ȏ�A���@�_�݂̂̒ł����B
�����ԍ��F10929131
![]() 2�_
2�_
��ask-evo����
�䏕�����肪�Ƃ��������܂��B����������Ă��邱�Ƃ́A�ʏ�̐����̒��ł��Ă͂߂�A
�܂��������̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
�͂��߂��狑�ۂ����A�F�ዾ���������ɁA����̘b���Ă��邱�Ƃ������ƕ����Ă݂�B
����͎��������u�t�̎d��������ۂɂ́A�S�����Ă��邱�Ƃł��B
���̃X���b�h�ł́A�����u��C��ǂ�ł��Ȃ��v�ȂǂƁA�����Ă����y���A����ł����A�ƌ��������
�o�v�����̂ł����A�����g�͂���܂ł̐l���o����A��̋�C��ǂ�ł���ɍ��킹�邱�Ƃ�
�����邱�Ƃɂ���āA�悢��i�����Ă���l��A�ǂ��������o���Ă���l���A�������Ƃ��Ȃ��̂ł��B
�u��C��ǂ߂Ȃ��l�v��u��C��ǂ�ł��Ă����u��Y�ꂸ�ɐ�����l�v�Ȃǂ̂ق����A
�\�͂����Ă��邱�Ƃ������Ƒ����A�Ƃ������Ɋ����Ă��܂��B
�����͂����̏������̌f����������܂��A�ǂ�Ȏ��ł��A���̒��̐S�\���́A
�ł��邾���h��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�����A�����ʂ̔ł܂��X����̗���ŁA���̃X���b�h�ɂ����鎄�̂悤�ȏ������݂�����l�Ԃ��A
���̐l�ƈꏏ�ɂȂ��āA���_��U�肩�����āA����Ă������Ĕے肵����A�ǂ��ł��傤���B
���낢��Ǝv�����͂���܂����A�����Ƃ��炵�����Ƃ������l�ɁA�����ɗ����ꂸ�ɁA
���������̃X���b�h�𗧂��グ���ۂ́A��|��ړI�Ȃǂ�Y�ꂸ�ɁA�������g�̗����l����
���Ă������тɁA���x���A�m�F���Ȃ����A���S�ɋA���Ă����܂��B
���������Ӗ��ł��A�܂�pen SL������Ă������Ƃ́A��|����O����ɁA�����̍l�����A
�������������Ƃ̂悤�ɏ����Ă��鎞�_�ŁA���ȊO�̉����ł��Ȃ��̂ł��B
pen SL����̈ӌ���l�������āA�^��������[��������A�ǂސl�̎��R�ł��B
����ROM���Ă��邾���̗���Ȃ�A�Ȃ�قǁA�ƍl������������܂���B
�������A��L�̂悤�ɁA���Ȃӂ�܂��ł��邱�Ƃ́A���Ɋ����Ă��܂��B
���x�������Ă����ʂ�A�ʂ̃X���b�h�����痧���グ�āA�s���悢�Ǝv���܂��B
�����g�́A�₦�������ł������ł��B���Ћ@�̗ǂ����悭�m���Ă��܂����B
�����A�ŏ������������������x�́A�����̒��ł��Ă����āA�r�炵��r�炵�I�ȏ������݁A�����āA
����̂悤�ɁA��|�Ƃ͉��x���Ⴄ�ƒ��ӂ��Ă���ɂ��ւ�炸�A�������Ƃ��J��Ԃ����l���A
������ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ��A�ƍl���܂����B
�{���͂����ƌl�I�Ɏv�����Ƃ��A���������Ƃ�����܂����A�܂����������������݂�
����^�C�~���O�ł͂Ȃ��ƍl���Ă��܂��B�����͂��낢��Ƃ��Ă���܂��B
�䏕���Ƃ��C�����A���ӂ������܂��B�@�v���C�x�[�g�݂̂Ȃ炸�A������ŏ������ޏ�ł�
�Q�l�ɂ����Ă��������܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10931426
![]() 1�_
1�_
>�͂��߂��狑�ۂ����A�F�ዾ���������ɁA����̘b���Ă��邱�Ƃ������ƕ����Ă݂�B
>����͎��������u�t�̎d��������ۂɂ́A�S�����Ă��邱�Ƃł��B
>���̃X���b�h�ł́A�����u��C��ǂ�ł��Ȃ��v�ȂǂƁA�����Ă����y���A����ł����A�ƌ��������
>�o�v�����̂ł����A�����g�͂���܂ł̐l���o����A��̋�C��ǂ�ł���ɍ��킹�邱�Ƃ�
>�����邱�Ƃɂ���āA�悢��i�����Ă���l��A�ǂ��������o���Ă���l���A�������Ƃ��Ȃ��̂ł��B
�����X���傳�X���͂��߂Œ������摜���݂�
�X���傳��̃X�y�b�N������܂����D
���͂͌|�p�I���Ǝv���܂��D���ꂩ������i���Ă��������D
�����ԍ��F10931863
![]() 10�_
10�_
[10929131]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/#10929131
�̈Ă��ȉ��̂悤�ɏC�������ĂɕύX���܂��B
��Ԃ�̂����u�V�t�g�u�������v�������Ă��邩�ǂ����ɂ��Ă�(�����̃J�b�g���T���v���Ƃ��Ĕ��f���K�v�ł���)�A50mm���{�}�N�������Y�ƁA100mm�̃����Y��No.10�̃N���[�Y�A�b�v�����Y��g�ݍ��킹�����̂��g����
a) 100mm�����Y�̃t�H�[�J�X������������ɃN���[�Y�A�b�v�����YNo.10�����Ń}�N���B�e
No.10�͏œ_����100mm�Ȃ̂œ��{�B�e�ɂȂ�܂��B
�p�x�u���̃u���p�x�Ƃ��瑜�ʏ�̃V�t�g�ʂ����߂邽�߂�tan�Ƃɏ悸��̂̓����Y�̌J��o���ʂ�0�Ȃ̂ŁA�œ_�����ł���u100mm�v�ɂȂ�܂��B
b) 50mm�}�N�������Y�{�܂ŌJ��o���ă}�N���B�e
�p�x�u���̃u���p�x�Ƃ��瑜�ʏ�̃V�t�g�ʂ����߂邽�߂�tan�Ƃɏ悸��̂̓����Y�̌J��o���ʂ�50mm�ŁA�œ_������50mm�Ȃ̂ŁA���킹�āu100mm�v�ɂȂ�܂��B
������Ԃ�ɂ�����V�t�g�u������(�����Y�̑O����_=���_�̈ʒu�̂���)���u�����݁v�ȂǂőΉ����Ă���Ƃ��āA�ua)�v�̏ꍇ�͖������Ƀt�H�[�J�X���Ă���̂Łu���{��=0�v�Ƃ݂Ȃ��̂ŁA�V�t�g�u�������̕���s��Ȃ��͂��ł��B
�t�Ɂub)�v�̏ꍇ�́u�����݁v�ɂ������̃`���[�j���O�̗L���ɂ�鍷���ώ@�ł��邩������܂���ˁB
�莝���ŃT���v��������āA�L�ׂȍ�������Δ��f�\���Ǝv���܂��B
�ꉞ�A�����̗���ł͌����݂ɂ��u�V�t�g�u�������̕�v�́u��������v�̂������I���Ǝv���̂ŁA�A���S���Y���ƌ��������������`���[�j���O��C���ꂽ��u��������v�悤�Z�b�e�B���O���܂��B
�����ԍ��F10932069
![]() 1�_
1�_
���ސ錾�����܂������A���܂�̔����ɂP���������܂��B�C���d�������̂ł����A���X�Ƒ����A������O�̃��X��ǂ݂܂����B��������ǁB
MZ-LL����
�o�������������u�ʒu�u��������Ă���v�ƌ����Ă���Ƃ̓��e���ēx�m�F���Ă��������B
�O�ɂ��A�����܂������A��ʓI�ȕ����@�������Ƃɍl����ƁA�J�����ɉ����x�Z���T�[���ݒu����Ă��Ȃ���A���s�ړ��̃V�t�g�u���i�ʒu�u���̕\���͋Z�p�I�ɂ��������Ǝv���܂��j�������Ă��܂����A���ڂ���Ă��Ȃ���A�V�t�g�u���Ή��͂���Ă��Ȃ��ƂȂ�܂��B
2010/01/30/05:20 [10859641]�ɏ����Ă���u���C�u�r���[�����掞��SR���쓮�����邱�Ɓv�̕��@�ł́A�ǂ̋����ŎB�e�����̂ł��傤���B���̂悤�ȕ��@�ŃV�t�g�u�����m�F�ł���B�e�{����0.4�`0�D5�{�ȏ�Ǝv���܂����A���̏����ɓ����Ă��܂����H
�O�̕��̃��X�ɂ��Akuma san A1�����AOp555�����������Ă���悤�ɁASR�́u�ʒu�Z���T�[�v�Ƃ́ACCD�iCMOS�j�Z���T�[�̈ʒu����肷�邽�߂̂��̂ł��BPentax��SR�͓d���I��CCD�T���T�[���쓮������̂Ȃ̂ŁA�@�B�I�ɓ��������̂ƈႢ�A�J�����̑��̕��i�Ƀ����Y�����ɒ��p�̖ʂł͌Œ肳��Ă���킯�ł͂���܂���B�����Ȃ��ł́ACCD�Z���T�[�ʒu�������炸�ACCD�Z���T�[�̓����𐧌�ł��Ȃ��̂ŁA�Z���T�[�ʒu�ׂ�K�v������܂��B
�O�ɂ������܂������A���̕����w�E���Ă���悤�ɁA��ʂɁu�J�����ʒu�v�𑪒肷��Z���T�[�͓��ڂ���Ă��܂���B�ʒu�Z���T�[�ł�����A�����g�Ȃǂɂ��A�O���̌Œ肳�ꂽ�_�Ƃ̂���肪�K�v�ł��B�i�����g�Ȃǂł�����P�����P�ʂ̈ʒu����͋Z�p�I�ɕs�\�ł����jK-7�@K-x�ɂ����̂悤�ȃZ���T�[�͓��ڂ���Ă��܂���B�]���āA�����x�Z���T�[����U�ꐧ��Ɏg���Ă��邩���c�_�̃|�C���g�ɂȂ�܂��B
������x�APENTAX�Ɂu��U���p�̉����x�Z���T�[�����ڂ���Ă��邩�v���m�F����Ă���A�F�X�ȂƂ���Ŕ����������������Ǝv���܂���B
���̂Q�Ԗڂ̃��X�ɐ錾�����悤�ɁA��ʍH�w�I�ɍl�@����Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�Z�p�I�ɕ��ՓI�Ȃ��ƈȊO�ŁAPENTAX�ł̐v���e�͕s���ȕ����́u��ʓI�ɂ́v�u�����v����v�Ƃ��Ƃ���ď����Ă������ł��B�܂��A���l�̕����A�u�p�x�u���ȊO�ɃV�t�g�u��������Ă���Ɗ�������v�Ƃ̈ӌ��ɂ́A�����x�Z���T�[���ݒu����Ă��Ȃ���A�����PENTAX�̐���`���[�j���O�ŃV�t�g�u����̗v�f�i���̂܂܂̕\�����ǂ����͕ʂƂ��āj���������Ă���\��������ƌ����Ă���킯�ł��B������m�F���ꂽ��B
�R�����g
�����́A���̒m�����ł����A�㉺�𑪒肷������x�Z���T�[�ƃu�����v����������x�Z���T�[�����p���邱�Ƃ͓�����ȋC�����܂��B�d�͂͂PG�i980cm/s2�j�ł����A���ʂɃJ��������������\������ԂŋN��������x�͂��̂P�^�P�O�ȉ��A�����炭�P�^�P�O�O���x�ƍl�����邽�߂ł��B���������̉����x�����肵�Ȃ�������܂���B
MZ-LL����ɁA�����ӌ�������A�l�i�ے�ł͂Ȃ��A�^�₩�c�_���ł��锽�؈ӌ��������Ă��������B���Ȃ��́A���̂��Ƃ�m��Ȃ����A�ǂ̂悤�Ɍ��s���Ă���̂��ǂ������킩��Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F10932991
![]() 21�_
21�_
���x�������܂����A�X���b�h�̎�|����O��Ă��邱�Ƃ��A���łɔ��Ȃ̂ł��B
���ꂪ����Ȃ��ŏ�������ł���̂́A���łɐ��_�ł��Ȃ�ł��Ȃ��̂ł��B
���x�������܂����A�����̒��r���[�Ȓm���ŁA���ꂱ�ꏑ�������Ȃ�A
�ʂ̃X���b�h�����痧�ĂāA�s���悢�ł��傤�B
SR�̋@�\���A���ۂɂǂꂾ���g���Ă���̂ł����H
���Ȃ��Ƃ����́A�ߋ����ʼn��������B�e���Ă���̂ł��B
�����������A�����Ƃ��낢��Ȕ�ʑ̂Ŏ����Ă��܂����A��قǂ��A���ƂȂ肻����
�ʐ^���B���Ă��܂����B
�܂����������Ă���Ⴂ�̂��Ƃ��A���x��������Ă͍���̂ł��B
�������A�����Ƃ킫�܂����������݂��o���Ȃ��l�́A�ǂ�ȂɁu���_�ۂ��v���Ƃ������Ă��A
�������u�i�Ƃ����قǂ��������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����j��Y��ȂĂ��Ȃ��ȏ�A
���ɖ��f�Ȃ̂ł��B
���x�������܂����A���ۂɁAK-7���ŁASR�̋@�\�������ĕ��Ă��������B
���̏�ŁA���ƈقȂ銴�z���������Ȃ�A����ł��܂�Ȃ��̂ł��B
�X�^�[�g���Ⴄ�̂ł��B���ꂭ�炢����܂��傤�B�����Ƃ��炵�����Ƃ������̂Ȃ�B
�����ԍ��F10933294
![]() 3�_
3�_
����ɂ��́BMZ-LL����
�L���ȏ������Ă���Ɗ����ēǂ�ł���̂ł����A
�E���Ƃ��������ƂȂ�c�O�Ɏv���܂��B���Ȃ��܂ߊF�����
�������ɂ͂ƂĂ������������Ă��܂��B
���X�������݂Ȃ����
���]�Ȑ܂͂���܂����A�X���傳��̓����̖ړI�́A��Ԃ�
���{�f�B���Ȃ̂������Y���Ȃ̂�����2��ނ��u�����Ă���l�v
���ǂ̂悤�Ȍ��ʂ������Ă���̂����X���~�����B�����Ƒg�ݍ��킹
���Ǝv���܂��B
�܂��A���Ћ@���u�����Ă���v�l��K-7�Ɣ�r���āA���ʂ̈Ⴂ��
����������X���~�����B
�Ƃ��������Ǝv���܂��B����Ď��́u�����Ă��Ȃ��v�̂ŃX������
�ł����A���܂�ɂ��s�тȊ����ł����̂ł����X���Ă��܂��܂����B
���L�́A�X���b�h�擪�́u�v�]�v�̈��p�ł��B
���́A�����Y���[�J�[������j�}�E���g�p�̕���������Y���o�Ă��āA
��������������ł�����A�����A�œ_�������ʑ̂܂ł̋����ŁA�
���ʂ̈Ⴂ���������������������A���m�点���������B
�������͑��Ћ@�p����Ă��āA���[�J�[���Ƃ̎d�g�݂̈Ⴂ�ŁA
���ʂ̈Ⴂ���������Ă�������B
�����ԍ��F10933502
![]() 3�_
3�_
����ł́A�{���ɍŌ�̈ꌾ�B
�u�B�e�������̊��o�E�ʐ^�̂ł��v�̔Ƃ̂��Ƃł�����A�������̒m����������U���̂��Ƃ̘b������������n�߂�ׂ��ł͂Ȃ��̂ł��傤���B�i�Z�p�ɑa���Ə�����Ă��܂���ˁj
�B�e�̊��o��e�N�j�b�N�ɂ��āAMZ-LL����̃��x�����]�X���Ă���l�͂��Ȃ��Ǝv���܂��B
����܂ŁA��R�̕��́AMZ-L����̋Z�p�I�Ȍ�����������Ă����悤�ƁA�܂��A�ǂl������������������Ȃ��悤�ɂƁA�ꐶ�����ɐ������Ă����Ǝv���܂��B���Ɍ��킹��A�ƂĂ��e�Ȑl�����Ǝv���܂��B������ǂȂ����S�ʔے肳���킯�ł��ˁB
���ꂩ��A���̎���ɂ������Ă��������܂����B���C�u�r���[�B�e���̎B�e�{���͂ǂ̂��炢�ł����H
���j�O�̕����Ɉꕔ�ԈႦ������܂����A�Q�i�ڂ́u�ݒu����Ă��Ȃ���v�́u�ݒu����Ă���v�̊ԈႦ�ł��B
�����ԍ��F10933528
![]() 11�_
11�_
yle.ely����A���C�������肪�Ƃ��������܂��B
���傤�ǁA���A���ۂ̍��������āA�X���b�h�̎�|�ɖ߂����������݂��s���Ƃ���ł����B
��ρA������܂��B
������̃X���b�h���E���ƂȂ��������̂ЂƂ́A���̋ɘ_���܂������ق��������ݕ��ɂ���A
�Ǝ����g�������Ă���܂��B�����āA���Ƃ��������������ƂƂ͈���Ă��A�ǂ�ł�����X�ɂƂ��āA
���ɎQ�l�ɂȂ�悤�Ȍ�ӌ������������Ă��邱�Ƃ��A�������Ă���܂��B
�\�z���͂邩�ɒ����āA�����Ȃ��Ă��܂������̃X���b�h�ł����A������x�A���ۂ̎g�p����
��Â������|�[�g���A�����g���A�܂��s���Ă݂����Ǝv���܂��B
���C�����ƌ�ӌ��A�����ăX���b�h�g�b�v�̗v�_�̈��p�A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10933540
![]() 0�_
0�_
���܂�ɂ��X���b�h�̎�|�𗝉����Ă��Ȃ��������݂������̂ŁA�������������āA�������e��ς��Ă݂܂��B
����������T�ԂقǍl���Ă����̂́ASR��IS�Ȃǂ̎�U���@�\�́A�Ȃɂ������āA
�������́A�ǂ��ɒ��ڂ��āA�u�O�r�̑���v�Ƃ��邩�A���́A���ꂼ��̃��[�U�[���A
���C���̔�ʑ̂⎩���̎B�e�X�^�C���ɍ��킹�āA�܂������قȂ銴���������Ă��邾�낤�ȁA�ƌ������Ƃł��B
�����ł́A�܂��A�ǂ�ȕ�����ł������͓����̈Ⴂ�͂���ǁA�����ƕ���Ă����A
�Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��܂��B�����āA���l�́A�K�������u�O�r�̑���Ƃ��āv�݂̗̂��R�ŁA
SR�@�\���D��Ŏg���Ă���킯�ł͂���܂���i���łɂ����͉��x�������Ă��܂��j�B
�����ɂ����ʑ̂�]����ő傫���B�e�������l�ɂƂ��ẮA�t�@�C���_���ŁA
�_���̔�ʑ̂����肷��A�����Y���̕�̂ق����A�u�O�r�̑�p�v�Ɗ����邱�Ƃ�������������܂���B
�������A�p�x�u�������܂�傫���N����Ȃ��ߋ����⒆�����ŁA�����ɍ\�}���l�߂��肷��ۂ́A
�ނ���A�t�@�C���_�����A�V���b�^�[���u�Ԃ܂ŁA�������N���������ȃu����
�����Ɣ��f���Ă���Ă���ق����A�ǂ��Ɗ����鎞������̂ł��B
�B�e��A�L�^���ꂽ�摜������ƁA���ɂ́A������̂ق����u�O�r�I�v�Ȍ��ʂ������܂��B
�ߋ����ł����u�������Ă����A�Ƃ������Ƃ́A���r���[�Ȍ`�ŁA�O�r��p��������A
�莝����SR�@�\�Ő����B�e���邱�Ƃɂ���āA���ʓI�ɁA�u�œK�łȂ��p�����������O�r�v
�����A�u���̂قƂ�ǖ����A�ǂ��ʐ^���c���邱�Ƃ��A���X����A�Ɗ����Ă��܂��B
���������O�r�������Ă��ASS�ɂ���ẮA�����[�Y��~���[�A�b�v���g�킸�ɁA
���ʂɎw�ŃV���b�^�[���ƁA���u��������邱�Ƃ��A���X����Ǝv���܂��B
�������A�O�r�̍���A��ʑ̂܂ł̋����A�œ_�����ȂǁA���G�ȏ��������ݍ����܂��B
������SR�ŋߋ����ŁA�ᑬSS�ŁA�莝���ŎB�e����ƁA�܂�Łu�z���t���悤�Ɂv�A�s�^�b�ƃu�����~�܂��Ă���
�ʐ^���B��鎞������܂��B��������\��̎B�e�łȂ��Ă��A�Q��Ƃ��R��Ƃ��A�V���b�^�[��
�邾���ŁA�����������ʂ��o��̂ł��BSR���I�t�ɂ��Ă��A�莝���ŎB��Ȃ��킯�ł͂���܂��A
�m�����O�b�Ɖ�����̂ŁA���\����v����Ƃ�������܂��B
�����X�ɂāA��̓I�ɁA�ǂ�ȎB�e�̎d���ō��������A���������ĉ���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10933545
![]() 1�_
1�_
�@
pen SL����
�@���̃X���͕����Ă����܂��傤�B
�@���A���Ԃ������č�}�܂ł����̂Ɋ��z���璸���܂���ł����B
�@�����X����̑Ή��ɂ͕���Ă��܂��B
�����ԍ��F10933598
![]() 28�_
28�_
delphian����
�͂�
�����ԍ��F10933680
![]() 24�_
24�_
�i�O�̃��X����̑����ł��j
����ł�SR�ŁA�ʒu�u�������������u���������Ă��邱�Ƃ��m���߂邽�߂ɁA
���{�܂ł͍s���Ȃ��ߋ����B�e�����x���s���Ă��܂����B���傤��K�}�E���g�̃}�N�������Y�́A
�������O�Ɏ�����Ă��邽�߁A�ȈՃ}�N���n�̃����Y�����A�茳�ɂȂ����߂ł��B
�i���̂��Ƃ́A�܂��A�b�v���Ă��Ȃ����͂ŏ������̂ł����A��ŕ⑫���܂��j
���傤�ǃt�B���^�[�a52mm�̃N���[�Y�A�b�v�����Y���o�Ă����̂ł����ANo.3�̂��߁A
�]���n�̃����Y�łȂ��ƁA�B�e�{���͂قƂ�Ǒ����܂���B���傤���Ȃ��̂ŁA�茳�ɂ�����̂ŁA
52mm�a�̖]�������Y�ł��ƁADA55-200mm���ڂɓ��������߁A����ōs���܂����B
����́ASS�Əœ_�����Ɋւ��āA�ǂ��炩�ƌ����Β��ڂ��Ă݂܂����B
�������A�ʒu�u���̔��u���̕�������Ă���̂ŁA������x�̎B�e�����Ɣ{���́A
�m�ۂ�����ԁA�Ƃ����̂͑�O��ł��B
���́A���i�A���Â��ߋ����ł��ASS�͂��������A1/13�b�ȏ�ŎB��悤�ɂ��Ă��܂��B
1/13�b�Ȃ�A0.3�{���炢�̔{���ł��A��������m�����A����Ȃ�ɍ�������ł��B
1/10�ȉ��ɂȂ�ƁA�œ_������B�e�����ɂ���ẮA���s�̂ق������������邱�Ƃ�����܂��B
�i����ł�SR��ON�ɂ��Ă���A�Ȃ�Ƃ��u�g����v�ʐ^���B���̂́A���ɂ��肪�����ł��j
���̂Q���̉摜�́ASS 1/6�b�ł��BM���[�h�ŎB�e���܂����B
�ŏ��A�\�����B�e���āA���̂����������A�u���Ă��Ȃ��Ɣ��f�ł��邩�A�Ȃǂ��A
�G���Ȃǂōs���Ă��錟���܂˂āA������Ƃ���Ă݂��̂ł����A�������A
SR��ON�̂ق����A���s�͏��Ȃ����Ƃ�������O�Ȃ̂ŁA���@��Ƃ̔�r�Ȃ�Ƃ������A
�P����ON��OFF�̈Ⴂ�Ȃ�A�ނ���A���ۂɎ����̎B�e�X�^�C���ɋ߂��A���Ȃ��������A
���x����p����ς��Ȃ���A�B��ق����ǂ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂����B
����́A��������SR��ON��OFF�łR���ÂA�����Č����ɂ��邽�߁A���ON�ŎB�e������A
�������́A�t��OFF�����ɂR���B������A���݂Ɏ����܂����B
�����ł́A�����Y�̏œ_������100mm�̈ʒu�ɂ��킹������ł����A95mm�A�������悤�ł��B
�i��J���ł������܂������A�N���[�Y�A�b�v�����Y���g���Ă��邱�Ƃ��炩�A���܂�����
�掿���������߁A�����i��܂����B
�i������ƐȂ𗣂�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����߁A����̂����̉���́A�����X�ɑ����܂��j
�����ԍ��F10933743
![]() 1�_
1�_
��ɃA�b�v�����摜�ł����A2M������JPEG�B���Ă����A�Ȃ̂ł����A
�ǂ����A�A�b�v����ۂɁA�Ĉ��k�������邹�����A����PC�Ō�������A
�����ƃV���[�v�����Ⴂ�ł��B���܁A���炽�߂ċC�t���܂����B
�Ƃ��ɁA�E�̉摜�́A�܂�ňႢ�܂��B
�ނ���A�{�f�B���Ő�o���āA�����������ق����A�ǂ������ł��̂ŁB
�B���Ă����ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł����A��قǁA�ăA�b�v���܂��B
����ł́A���ɂȂ�܂���B
���}���A�����Ōf�������Ă��������܂��B
�����ԍ��F10933799
![]() 1�_
1�_
������̌f���́A�摜�Ɋւ��Ē���1024�s�N�Z������Ɣ䗦��ۂ����܂܃��T�C�Y���H����܂��B
�܂�JPEG���k��12�i�K��10���x�iFine���x�j�Ɉ��k��������܂��B
�ł��̂ŁA�u���Ȃǂ̊m�F�ł���A���̃J�����̍ő�T�C�Y�EJPEG/Fine�掿�ŎB���ďo�����s���A
�s�N�Z�����{�̂܂܃��T�C�Y�����A1024×1024�s�N�Z���Ő�o���ē\��t����̂��m���ł��B
�����ԍ��F10936519
![]() 5�_
5�_
�A�L���Z����A�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B
�l�b�g������PC�ƁA�摜�ҏW�n�̃A�v���������Ă���PC�Ƃ��Ă���̂ŁA
�J�����{�f�B���ł��邱�Ƃ����ɂ��悤�Ǝv���Ă����̂ł����A����A�A�b�v����
�摜�����Ȃ���A���Ƃ��Ďg���Â炢�掿�ɍĈ��k����Ă��܂��Ȃ�A�f�[�^�𐮂��悤�Ǝv���܂��B
�Ƃ肠��������́A�{�f�B�̂ق��Ńg���~���O���܂����B�܂��A�f���̎����ł��B
�i�ȉ��́A���X�łȂ��A�ʂ̘b��ł��B���炢�����܂��j
........
�����A�Â����ő傫���d���̂ł����A�uKenko ZOOM CLOSE-UP LENS�v�Ȃ���̂�
�����Ă��邱�Ƃ��v���o���AK20D��K-7�ɕt���Ă݂܂����B
���܂��܃t�B���^�[�a��52mm�ŁA0.45���`0.07���̋�����������Ă���A0.07���i7cm�j���ɂ���ƁA
���Ȃ�߂Â��܂��B�����Y��[����́A�Qcm�Ƃ��̋����ł��s���g�������܂����B
�����āA���������ŁA���̌Â��uZOOM CLOSE-UP LENS�v�ŁA200�����炢�͎����B��
�����Ǝv���̂ł����A���{�ȏ�H�̃}�N����������ƎB���Ă�����A���o�����������Ȃ��Ă��܂����B
�����āA�����Y�̌`���d���A�����̃o�����X�ɂ���āA�p�x�Ԃ��ʒu�Ԃ��
�o����x�������A���Ԃ���܂߂āA�����Ԃ�Ⴄ���ƂɁA���߂ċC�t���܂����B
�œ_�������ƁA��������100mm�ӂ�����ɁA�ߋ����B�e�ł��p�x�u�������������Ă���C�����܂��B
�����āA�]���Y�[���ł��ƁA�S���������A���������Ă��郌���Y�́A����قǏd���Ȃ����߁A
�e���[�ŁA�ŒZ�B�e�����i�ȈՃ}�N���j�ŎB���Ă���ƁA�ׂ��Ȋp�x�Ԃꂪ�A���ɋN���₷�����ɂ��C�t���܂��B
�L���m�����A100mm�̃}�N�������Y���n�C�u���b�gIS�ɂ����̂́A�Ȃ��Ȃ����ɂ��Ȃ��Ă���Ȃ��A
�Ɖ��߂ĊS���Ă��܂��܂����B
50mm�����Y�ŁA��L�́uZOOM CLOSE-UP LENS�v��t���A���{����قǂ̋�����
�B���Ă��Ă��A�o�����X�������������ASR�I�t�ł����A�������Ɉꖇ�A�u���̏��Ȃ��A
���������Y��Ȏʐ^���B���̂ŁA�����܂����B
�œ_������50mm�ł��邱�ƂƁA��͂�d���Ƒ傫���̃o�����X���ǂ��̂��Ǝv���܂��B
�z�[���h�����₷���ł��B������̕Ɖ摜�́A�܂�����ɂł��B
�����ԍ��F10937068
![]() 1�_
1�_
������̉摜�́A[10933743]�̂Q���́A���ꂼ��g���~���O�������̂ł��B
�����̂��Ƃ��������Ǝv���Ă����̂ɁA�Y��Ă��܂����B
�g�p�J�����́AK-7�B�g�p�����Y�́ADA50-200mm �{ �N���[�Y�A�b�v�����Y No.3�B
50-200mm�A�Ƃ����Y�[����́A�œ_�����̕ω��ŁA�Ԃ���̈Ⴂ��������ɂ́A
�Ȃ��Ȃ����傤�Ǘǂ��͈͂��ȁA�Ɗ����܂����B
���������āA�N���[�Y�A�b�v�����Y��t���鎖�ŁA�����Y�ƃ{�f�B�̒ʐM���A�{���ɐ�����
�������Ƃ�ł��邩�́A�^��ł����B�ł���A�����Ƃ����}�N�������Y���g�����ق���
��萳�m�Ȍ��ʂ��o��悤�ȋC�����Ă��܂��B
�����āA����̂́A�u���v�Ƃ����قǑ傰���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�����g�́A�P�Ɂu�����Ă݂��v�A
�����̂���ł��B����̋ߐڈ�ł́ASR��ON����OFF���̈Ⴂ���A�g�̂Ŋo��������������ł��B
���i�́A�莝���B�e�̍ۂ́A�킴�킴SR��OFF�ɂ͂��Ă��܂���B
�u���ʂ������v�Ɗ����Ă����̂́A����܂Ŏg���Ă�����̓������Ă��Ȃ��J�����Ɣ�ׂĂ̂��Ƃł��B
50mm����200mm�̊ԂŁA�œ_������ς���ON����OFF���ŁA�ŏ��͂��ꂼ��T���Â��炢�A
�����čŏI�I�ɂ́A�R���ÂB���Č��܂����B�i�����Y��[����j20cm�O�キ�炢�̎B�e�����ł��B
50mm�͒ᑬSS�ł��A�u���Â炭�A80mm���炢�ł��A���i����悭�g���Ă���œ_�����Ȃ������A
�������͍��������ł��B�����āA95mm�Ƃ�105mm�Ƃ����A��ԑ��������܂����B
135mm��200mm�ł������܂������A�ߋ����ł��p�x�Ԃꐬ�����傫���Ȃ��Ă����̂�����܂��B
��p�͂��̂܂܂ŋ������k�܂��ĎB�e�{�����オ�邾���Ȃ̂ƁA�œ_���������킹�ďオ��̂ł́A
���������u�������Ⴄ�ȁA�Ɗ����܂����B
80mm��95mm�i100mm�̂��肾�����j�ł��A���������u�����͕ω����܂��B
SS��1/13�b����1/6�b���炢���A��Ɏg���܂����B95mm��1/6�b���ƁA�Ԃꂽ�ۂ̋O�Ղ�����₷���ł��B
���ɂ��^��������28-300mm�̍ŒZ�B�e�����i�ő�B�e�{���P�F2.9�j�ł������܂����B
���ς�炸�A���X���܂����B���������܂����B�����v���܂����B���̃I���p���[�h�ł����A
���̏������݂����Ă݂āA���炭����₵�Ă���A���������ǂ������ȕ\�������肻���Ȃ�A�p�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10937537
![]() 1�_
1�_
�u�����Y�̏d����傫���ɂ���ău���₷����u���̌X�����Ⴄ�v�Ƃ����̂��A�����Y�V�t�g���̍ő�̒����ł��B
���̌X���̋����X�|�[�c�E�{���]�������Y���[�U�[�̑����L���m����j�R�����̗p�������R�̈�ł�����܂��B
�t�ɁA�y�ʂ̃����Y�ł������قǁA�{�f�B�o�����X��V���b�^�[�E�~���[�V���b�N�̗v�f�����ΓI�ɑ����܂��B
���̏ꍇ�A�{�f�B���ƂɃA���S���Y�����œK���ł���B�e�f�q�V�t�g���ɃA�h�o���e�[�W�����܂�܂��B
�]�k�ł����A�ȏ�̗��R�ŁA�{�f�B�{�̂̎��ʂ��V���b�^�[�E�~���[�V���b�N���z��������x�グ�A
�g�p�����Y�������̃o�����X���œK�����A�����������ʂ�ێ��ł���z�[���h�����m�ۂł���u���͌������܂��B
����͎�U���@�\�ȑO�̖��ł����A�o�b�e���[�O���b�v�Ȃǂ́u���v�����Ŏ����ł��܂����A
�S���ėp�v���[�g�i�X�e�|�j�Ȃǂ𗬗p����A�K�v�Œ���̏d���ɗ��ߌ��ʂ邱�Ƃ��ł��܂��B
����������p���ōl����A�悭�c�_����Ă��鑨�����ɂȂ�ł��傤���A��Ƃ��ĂȂ炻���������Ƃł��B
���œ_�{�ߐڎB�e�i�������莝���j���ɐ������ȁu�u���v�Ō��ʂ̗D���܂�b�ł͂���܂���B
���p���ƌ��ʓ������������Ęb���n�߂�ƁA�ȒP�Ɍ����Ă���v�_�������Ă��Ȃ��Ȃ�܂��B
�V���b�^�[�E�~���[�V���b�N�������Ȃ���i�����Y�V���b�^�[�@�F������R���f�W�Ȃ�j�A
�����Y�V�t�g���{�X���[�V���b�^�[�ł��̒��x�͎B���Ƃ����T���v�����B
���������A�ꔭ��OK�i�S���S���j�Ƃ����b�ł͂���܂���B
���ƁA����쌟�ł���Ȃ�A�ő�T�C�Y����̃s�N�Z�����{��o���łȂ��Ɖ摜�ɈӖ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10937557
![]() 6�_
6�_
MZ-LL����
�@�܂������Ă����̂ł��ˁB
�@�u���z�������珸��A���ɒ��ށv����͐������m�o�ł���A���̊��o�Ŕ��f�������A
�V�����͋^�����Ȃ��悤�Ɏv���܂��B���o�����ł͕����̖{���������Ă��Ȃ����Ƃ���
��Ƃ����F���͕K�v���Ǝv���܂��B
�@MZ-LL����́A�u�����v�����āAPENTAX�̎�Ԃ��@�\SR���A��ɃV�t�g�u����
�����Ă���Ɣ��f���ꂽ�̂ł��傤���B
�@�����g�A���́u�����v�����������������Ƃ���������Ă܂����i[10908701]���j�A
����ɖ��炩�ɂȂ�܂���B�ʐ^���f�������̂����́u�����v�������邽�߂��Ǝv����
���B
�@���炭�AMZ-LL����͖{���ɁA���Ƃ����́u�����v���F����ɐ����������̂ł��傤�B
�����ȕ����Ǝv���܂����A�s���ȕ��������ʂɏ��ł��B
�@���́u�����v�������悤��MZ-LL����͕��S���A�ǂ�ǂ����܂�Ă��܂����A
�������ł����������e�ɔ[���ł��Ȃ��A�ł��F����Ɏ����̐M���邱�Ƃ��������
���������B����ŃG���h���X�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�ł����́u�����v�m�o���������A�����������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��BSR�́A
��ɃV�t�g�u������Ɣ��f�����̂́A�����̒m�o������������ł͂Ȃ��A�u������v
�ƍl���Č���ƁA���̃X���̕s�v�c�����������Ă��܂��BMZ-LL����́A���̓`����
�ɂȂ��Ă��܂����悤�ł��B
�@������~�߂�̂́APENTAX����̐����ł����A�����ɏo�Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
PENTAX�z�[���y�[�W��SR�Ɋւ���������s���Ăł��B�����ꖾ���ȓ��e�ɂȂ邱�Ƃ�
���҂��܂��傤�B
�@SR���A��ɃV�t�g�u������Ȃ�Ă��Ƃ́A�`��������e�Ƃ��Ă̓X�W�������ł�
�ˁBMZ-LL��������������̂悤�ł��̂ŁAMZ-LL������F������A�{���̂��̃X��
�̖ړI�łȂ����ƈȊO���������܂Ȃ��̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10938937
![]() 14�_
14�_
���������ɂ�����߂Ă���܂��H
�u���Ȃ�����Ȃ��v�Ȃ�Ĉ̂����Ȃ��ƌ����Ă܂����A
��Ԕ��Ȃ��ĂȂ��̂�MZ-LL����{�l�ł��傤�B
�����ԍ��F10939545
![]() 24�_
24�_
�����g���A�y���^�b�N�X����u�ʒu�u�������Ă���v�ƕ����Ă���A
�����͉��x���m���߂Ă���̂ɂ����ς�炸�A�����ꒃ�Ȃ��Ƃ������Ă����l���܂����܂����A
���ɖ��f�ł��B���r���[�Ȓm�����A�����Ƃ��炵�������̂͂�߂Ă��������B
�����āA���̊�{�̈ʒu�u����ƁA�l�Ԃ̐S���̌ۓ������ݏo���u���Ȃǂ�����Ă���A
�Ƃ�����b�́A��������ƕ����Ă��܂��B����Ȗϑz���J��L����̂͂�߂Ă��������B
�i�S�̒��ʼn����v�����Ə���ł����A�����ŏ������܂��͖̂��f�ł��j
��U���̊J�������A���������ǂ�ȃA���S���Y���Ŕ��������Ă��邩�ȂǁA
����ȊȒP�ɁA�O���̑f�l���A���������f���Ő��m�ȓ������o����Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����̖����ے�ł́A�����b�̌J��Ԃ��ɂȂ�A�����Q�l�ɂ͂Ȃ�܂���B
���x�������܂����A�܂��͎����̎��͂�t���Ă���A�����ے肷�邽�߂̓�Ȃ����邾���ł͂Ȃ��A
�����̎g�p����p�����@�ނȂǂ��n�b�L���������A�������݂����Ă��������B
��啪��̘b������ɂ́A���܂�ɂ��o�����s�����Ă���悤�Ɏv���܂��B
�i���p�̘b�́A���������肷����̂ŁA���������Ȃ��ق����ǂ��ł��傤�j
�������ǂꂾ�����g���������Ƃ������Ă���̂��A���߂Ď����ŔF���ł���悤�ɂȂ��Ă��������B
���������ˉĂ��邾���ŁA���܂�ɂ������炢�ł��B
����B�e�Ȃ�A��r�I�A���ʂ̈Ⴂ������₷���Ǝv���̂ŁA��ʑ̂܂ł̋�����
�߂Â��Ă݂�ȂǂŎ����Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤���B�@���̍ۂ́A�����Ȍ��ԂȂǂ́A
�����̖ڂŊm�F���₷���͈͂�����Ă��ƁA�������₷���͂��ł��B
�����ԍ��F10942535
![]() 1�_
1�_
�A�L���Z����ACanon PowerShot G10�ł̋ߐڎB�e�̍�Ⴀ�肪�Ƃ��������܂��B
�莝���ŃX���[�V���b�^�[�ł��ˁB�Y��ɎB��Ă���Ȃ��A�Ɗ����܂����B
�����A������PowerShot G�V���[�Y�ł́A�A�_�v�^�`���[�u�o�R�ŁA�N���[�Y�A�b�v�����Y����
�������A�}�N���B�e�̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă��܂����B�������A�����͎�U���@�\��
�i�V�ł������A�����Y�����邩�����̂ŁA�{�P���悭�o���L��������܂��B
�����g�́A�����Y���ƃ{�f�B���ɂ��A���ꂼ�꒷���������Ă��܂����A�����{�f�B���ł��A
�y���^�b�N�X��SR�̂悤�ȁA�\���� ���M�����Ȃ��A�����ԓ��삵�����Ă����܂�d�͂�
����Ȃ��ȂǁA���ꂼ�����������A���ʓI�Ɏg����V�[�����قȂ邱�Ƃ���A
���p���̍�������ʂɂ��A���ق�����Ɗ����Ă��܂��B
����ł�SR���@�\����̂́A���ɗǂ����Ƃ��Ɗ����Ă��܂����A�\�j�[�̃��V���[�Y��
�I�����p�X�̕����Ȃǂɂ��A���ꂼ��\����̈Ⴂ��v���O��������A���ӂȂ���
���Ȃ��Ƃ��A�����Â���Ă���̂��낤�ƁA�\�z���Ă��܂��B
�����Y���̕�́A�����Ŏ����Ă���͈̂��ނ݂̂Ȃ̂ŁA���͓X���Ŏ��������x�ł����A
�p�i�\�j�b�N��GH-1�̂悤�ȃv���X�`�b�L�[�Ȍy���@��ł��A�����Y���̕���A
�Ȃ��Ȃ��ǂ������ŋ@�\���Ă��āA���撆�̊p�x�Ԃ�̔��u�����A���ʓI�ɕ���Ă���̂������܂����B
�e�ЁA�͂����Ă���@�\�̂ЂƂŁA���������Ă���ł��傤����A�O���̐l�Ԃɂ́A
�S�e������悤�Ȃ��Ƃ͖����Ǝv���܂����A���ۂ̎g�p���������邱�Ƃ��A����
��ԁA���A���e�B�̂�����Ǝv���Ă��܂��B
��U��̎d���́A�t�@�C���_�ȏ�Ɍl��������܂�����A�l�̈ӌ��⊴�z�́A
�{���ɁA�Q�l���x�A�ɂ����Ȃ�Ȃ���������܂���B�������A���ꂱ���������m�肽�����Ƃł��B
���ƌ�ӌ��A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10942539
![]() 1�_
1�_
A50mm F1.7 + ZOOM CLOSE-UP LENS |
���̉摜�̌��T�C�Y���� �����������g���~���O |
�uKenko ZOOM CLOSE-UP LENS�v |
����̐[��A����O�ɁA�����X���[�V���b�^�[�H������Ă݂悤�ƁA�v���āA
���d�ɂ��A�B�e�{����������Ԃ̂܂܁A2�b�`0.6�b�ʼn������B���Ă݂܂����B
�摜�́A1.6�b�̎��̂��̂ł��B�ő�𑜓x�ŎB���āA�����`�̂́A���̂܂ܒ������g���~���O�������̂ł��B
���u��������C�����邵�A�Â��uZOOM CLOSE-UP LENS�v�̉𑜗͂��Ă��銴�������邵�A
�s���g�������ƍ����Ă��Ȃ��C�����܂����A�������B�e���Ă��A�悭�Ă����������̃��x����
�ʐ^�����B��܂���ł����B���������ASR��ON�ł��B
�����ƃu�����̂�����܂����ASR��ON�ł́A�u���������点�܂����A
���̎B�e�����Ɣ{���ƒx��SS���ƁA���ʂ͊��S�ł͖����A�J�����̍\������������Ƃł�������A�ȒP�ɕ���E���܂����B
0.5�{���炢�̂ق����A���܂�^���ɎB��Ȃ��Ă��ASR�̌��ʂ��y�ɑ̊��ł��܂����B
���͍���A����ȊO�ł��A�uZOOM CLOSE-UP LENS�v�ɂē��{�t�߂̔{���ł̎B�e���A���S������Ă�����A
�����Y�̑傫����d���ƁA�J�����{�̂̃o�����X���A��U��ɂƂĂ��W���Ă��邱�Ƃ��A
�܂����߂Đg�̂Ŋo���܂����B
��L�̂悤�Ȓʏ�̎d���ł͎莝���ł͍s��Ȃ��悤�ȁA�x��SS�������܂������A
���\�����B���Ă���ƁA�g�̂���肭�I�����ɑ傫�ȃu�����N�����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����̂������܂����B
�����āA���̒���ɁA����܂ʼn��x���g���Ă��āu�u�����炢�v�Ɗ����Ă����A���^�Ōy�������Y�ɕς�����A
���x�́A����܂Ō������Ƃ��Ȃ����炢�A�u����A�����Ă��܂��܂����B
SR�@�\��OFF�ɂ��Ă����̂��A�ƍQ�ĂĊm�F�����Ƃ���AON�ŁA�������ߋ����ƌ����Ă��A
�}�N����ł͖�����ԂŁA�ł��B����ȂɃu�����̂͏��߂Ăł����B
�g�̂��A�uZOOM CLOSE-UP LENS�v��t���������d���ɁA�ꎞ�I�Ɋ���Ă��܂��������Ȃ̂�������܂���B
�Ȃɂ��J�������\���Ă��āA���������Ȃ������ɂȂ�܂����B�y������Ƙr�����f�����̂����B
�g�p�����Y�́APentax A50mm F1.7�@�Ɓ@Ricoh RIKENON 50mm F2�A����ɁuKenko ZOOM CLOSE-UP LENS�v�ł��B
�uKenko ZOOM CLOSE-UP LENS�v�́A�t�B���^�[�a 52mm�ł��̂ŁAA50mm F1.7�ɂ́A
�X�e�b�v�A�b�v�����O���Ԃɂ��܂��܂����B
���l�̊��z�Ƃ��ẮARIKENON 50mm F2�̂ق����A���́uZOOM CLOSE-UP LENS�v�Ƒ�����
�ǂ��悤�Ɋ����܂����B������ŋ������摜�́AA50mm F1.7�̂ق��ł��B
1.6�b�O���SS�ł̎B�e�A����������Ɨǂ���ԂŁA���̃����Y�ł������Ă݂����Ǝv���܂��B
SR�̍��ƂȂ�悤�ȁA�ǂ��ʐ^�ł��Ȃ����A�B�e�����������Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A
�ł��邾���A�������B�������̂́A���h�炸�ɐ����Ɍf���������ł��B
�E�[�́uKenko ZOOM CLOSE-UP LENS�v�̉摜�́A���������A�B��܂����B
�����ԍ��F10942972
![]() 1�_
1�_
����ȃL�����b�t�̘b�͒N�����������Ȃ���
����������������u���ɂ��Ď����Ă��Ȃ��́H
�ǂ�ȃu���ɑ��ėL�����ǂ������������Ă�
������������Ă�Ȃ�ȒP�ɏo���邾��H
�o���Ȃ��Ȃ炱���ɏ�������l��l�Ɏӂ��Ă�
�����ԍ��F10943130
![]() 14�_
14�_
MZ-LL����
�X���b�h�̎�|���т����Ƃ��Ă���������̂́A��Ɉ�т��Ă��āA
��������̍����A���̗D�G�����������������̂ł��邱�Ƃ͏\����
�����ł��܂��B���̂�����͂ƂĂ����S����̂ł����ASR���D�G�ł���
�Ƃ���u�ʒu�u������Ă���v�Ƃ������_�ɑ��āA���ꂾ�������̐l��
���_�E�������ĉ������Ă܂��B�������A�����̔��_�ɂ͂قƂ�lj�
�����A�m��I�Ȉӌ���������ɂ������J�ȃ��X��Ԃ��A����͂��܂�ɂ�
���炫��܂�Ȃ��A�t�ق��Ǝv���܂��B
�����Ɠǂ��Ƃ����܂Ƃ߂�ƁA
MZ-LL����̎咣
�P�DSR�͈ʒu�u��������Ă��邩��D�G�ł���
�Q�D�ʒu�u����́A�y���^�̐l���畷��������^���ł���
�R�D�ʒu�u����̌����́A�����̖@���̂悤�ɁA�f�q�����̏�ɂƂǂ܂낤�Ƃ�����̂ł���
�S�D�ʒu�u����́A�J�������P���ȕ��s�ړ������������ł͂��߂ŁA�莝���ŕ��s�ړ������������łȂ��Ɠ��삵�Ȃ�
�P�E�Q�ɂ��ẮA������ؖ����邱�Ƃ����ɓ���ł����A�����ے肷��؋��͒N���������킹�Ă��܂���B
�Ȃ̂ŁA���e�Ƃ��Ă͎������Ă��\��Ȃ��Ǝv���܂��B
�R�ɂ��ẮA�L�u�̕��������ĉ��������悤�Ɂu�f�q�����̏�ɗ��܂��Ă͕���ł��Ȃ��v���Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B
�S�ɂ��ẮA�S���_����������Ă��炸�A�u�莝������Ȃ��ƃ_�����v�Ƃ̂P�_����ŁA�N���[�����Ă��Ȃ����e���Ǝv���܂��B
���Ȃ��Ƃ��A�p�x�u���̕�ƈʒu�Y���̕���~�b�N�X�œ��삵�Ȃ��ƁA�ʒu�Y���������Ȃ��Ƃ��������ɑ��āA���ꂪ������O�ł��邱�Ƃ̂悤�ɏ�����Ă��A�N���[���͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
���ʂ������̂��ǂ��������f���t���Ȃ������A��Ԃ������ďグ��������A��L�R�E�S�ɑ��Ă̌��������b���Ă����ق����A������ǂ�ł���
���ׂĂ̐l�ɗL�p���Ǝv���܂��B
�y���^�@�����L���Ă��Ȃ��l���A�y���^�����@�ƂȂ�̂ł���A���[�J�[�ł�������ɔ��\���Ă��Ȃ��u�ʒu�u����v�ɂ��āA���ׂĂ̘b�ɒ��낪�����悤�A�܂Ƃ߂Ē��������Ɗ肢�܂��B
�y���^���[�U�𑝂₷���߂ɂ��u���ۂɎ����āA�����Č���̂��悢�v�Ƃ����ӔC�����Ƃ��Ƃ�铊�������́A���̗v�f�ł��B
�����̐l���^������_�����A���H���R�ƌ���āA���߂āu�G���ĂȂ����ǁA�����Č��鉿�l�����肻�����v�Ƒ����̐l�����f���邩�Ǝv���܂��B
MZ-LL����قǂ̒m���ƋZ�\���������̕��ɁA��������̂��b����͍̂K���Ȃ��Ƃł����A�ǂ�ł�����X���A�Ō�̔��f���������߂̌���I�ȍޗ��܂Ŏ����Ē�����ƁA�������v���܂��B
�X�������肢�������܂��B
�����ԍ��F10943451
![]() 9�_
9�_
��������������
>�R�D�ʒu�u����̌����́A�����̖@���̂悤�ɁA�f�q�����̏�ɂƂǂ܂낤�Ƃ�����̂ł���
����ɂ��Ă͂����g�̍l���͉��܂����悤�ł���B
K-7 �̃��C�u�r���[�ł͎�u�������Ȃ��悤�Ɋ����܂����A����͉��ƂȂ��摜�����̖��̂悤�ȁi�Ⴆ�Ε\���t���[�����[�g�����Ȃ��Ƃ��j�BSONY �� ��550 �̃��C�u�r���[������܂�u���Ȃ��悤�Ɍ����܂����B
����L���m���̃��C�u�r���[�͏����̃u���ł��q���ɕ\�����銴�������܂��iIS �� ON �ŃV���b�^�[�{�^�����������j�B
�����ԍ��F10943517
![]() 0�_
0�_
���s�̂������� ����
���w�E���肪�Ƃ��������܂��B
�r���A�W���͂���ēǂ�ł����ӏ����������̂ŁA���̓_�������Ă�����������܂���B
ML-ZZ����ɑ��Ă��A���̓_�͂��l�ѐ\���グ�܂��B
�\���t���[�����[�g���Ⴄ�i�b�ԃR�}�������Ȃ��j���߁A���������������邩������Ȃ��A�Ƃ����͎̂��̊��o�I�ɂ��r���S�ȋC�����܂��ˁB
���́u���o�v��厖�ɂ���Ă���MZ-LL����̎咣���A������x�^���ł��镔��������܂����A���X�]���Ȃ��Ƃ��������ɂȂ肷���Ă��܂����悤�ł��ˁB
�����ԍ��F10943560
![]() 3�_
3�_
�܁A�ق�Ƃɉ��܂����̂��͒肩�ł͂���܂��A[10900544] ������ł��B
���C�u�r���[�� HDMI �Ȃǂ�ʂ��ĊO���o�͂ł���̂ł���A������x�d�l���킩��̂�������܂���ˁB
KissX2 �� USB ��ʂ��ĊO���o�͂ł��܂����A20fps ���x�ł��ˁB����ł� 20fps �Ȃ̂ɂ�������炸�ߐڎB�e�̃��C�u�r���[�͂��������u���܂��B
���C�u�r���[�͖ڈ����x���Ďv�������������悤�ȁB
�����ԍ��F10943601
![]() 0�_
0�_
���܁A�ق�Ƃɉ��܂����̂��͒肩�ł͂���܂��A[10900544] ������ł��B
[10908490]�ł́H
�c�O�Ȃ���܂��[���ł��Ă��Ȃ��ƌ��Ă��܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=10858683/#10908490
�����܂����A�[���������Ȃ��܂܂ł����B���܂��ɗǂ������Ă܂���B
PENTAX�́u�v�����PENTAX�̋Z�p�̐l(���畷�����Ƃ���)�́u�����v�ɊԈႢ��������(���ASR�́u�Z���T�[����v�̐������u�ʒu�u���̕�v�̐�����MZ-LL���������)�\�����l���Ăق������̂ł��B
���̕����ƁAPENTAX�̃T�|�[�g��ʂ��ĊԈ���Ă��镔���𐳂��������AMZ-LL����̌���������̂ɋߓ���������܂���B
�����ԍ��F10945771
![]() 4�_
4�_
�X���b�h�}�X�^�[����ԋ���Ă���͎̂����̎咣���u���Ă��܂����ƁB
�u���̌����ƂȂ郌�X�͂��Ƃ��Ƃ������Ă��܂��c
�����N���t�H�[�X��������̂���I
�����ԍ��F10946122
![]() 9�_
9�_
���s�̂������� ����
������ł� 20fps �Ȃ̂ɂ�������炸�ߐڎB�e�̃��C�u�r���[�͂��������u���܂��B
����͎�Ԃ����ғ����ł����\�Ԃ��Ƃ������Ƃł��傤���H
�R�}�������郌�[�g����Ԃ�郌�[�g�@�̏ꍇ�A�u���͏��Ȃ�������ł��傤���A
�R�}�������郌�[�g����Ԃ�郌�[�g�@�͋t�Ƀu���͑傫�������邩���m��܂���ˁB
����Ԃ�郌�[�g����Ԃ��U���^���Ƃ��čl�����ꍇ�ł��B
�i������Ɩ��������邩������܂��B�j
������ɂ��Ă���̋��オ�͂�����킩��悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������ł��ˁB
kuma_san_A1����
��PENTAX�́u�v�����PENTAX�̋Z�p�̐l(���畷�����Ƃ���)�́u�����v�ɊԈႢ��������(���ASR�́u�Z���T�[����v�̐������u�ʒu�u���̕�v�̐�����MZ-LL���������)�\�����l���Ăق������̂ł��B
���{�l�������O�̃X���ŁA��₱��ɋ߂����Ȃ̕ق��q�ׂĂ炵���悤�ł����A
�S�̂�ǂݒ����Ă݂�Ƃ̂��Ƃł����̂ŁA�����҂��Ă݂܂��傤�B
�Ƃ͂������̂́A�ǂݒ������͍��A�b�v�̕����D�悾�����悤�ť��B
�����ɂ����āAPENTAX�ɏƉ�Ă݂����Ǝv���܂��B
�������������̏�ŁAPENTAX�̕������b���ꂽ�Ƃ������e��������Ă��܂��̂ŁA�����ǂ�X�ɂ́A���₷�錠�����炢�͂���܂���ˁB
�����ԍ��F10948805
![]() 5�_
5�_
����������������
�ȂX�g�[���[������ɍ���āA�킯���킩��Ƃ������̂͂�߂Ă��������B
���x�������Ă���ʂ�A���́A�y���^�b�N�X��SR�������D�G���Ƃ��A��������������ł́A
�܂����������A���Ƃ��� �ǂ��̃��[�J�[���D���Ƃ��́A���������Ȃ��̂ł��B
���傤�Ǘǂ���ɁA�g����Ⴂ���A���Ď�`�ł��B
�����Y���{�f�B���A�Ƃɂ��������̖ڂł��낢��Ǝ����Ă���A�p�r�ɍ��킹�ėp����A�������������ł��B
���A�ϋɓI�Ɏ�����@�킪�AK20D��K-7���ƌ��������ł��iK-7�́AAPS�@�̒��ł́A
�l�I�ɂ́A���ɔ��p�i�Ȃǂ̐Ñ̎B�e�Ɍ����Ă���Ɗ����Ă��܂��j�B
�����āA�ʒu�u�����ǂ��������ɕ����Ă��邩�A�Ƃ������ƂŁA�����y���^�b�N�X�ŕ����Ă������Ƃ́A
���ǁA������肭�����ł��Ȃ��̂ł�����ɗ͂��g���Ă��Ȃ��̂ł����A�����p���Ă���P��̈ꕔ�A
X���W��Y���W�A���̈ʒu�Ɍ������A�ł������A�S���̌ۓ��̃u�����A�z�[���f�B���O��
�V�b�J���o���Ă���l�����A�ȂǂȂǁA�͂ł��邾�������Ă����܂܂Ŏg���Ă������ł��B
�ʒu�u���������Ă��邱�Ƃ́A���x���m���߂����A����XY���W�ɑf�q���������b���A
���ꂪ�A���������ǂ������������͉���Ȃ��Ă��A�����������������Ă������������Ƃ͊o���Ă��܂��B
�O���̑f�l���A���������f�ГI�ȏ��ŁA���������U���邾�����ʂȂ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�����g���A������A�����Ƃ��ɁA�|�p����̂��Ƃ����l���Đ����Ă��܂����A���̌����҂������A
���������A�����悤�Ȍ�������������Ȃ���A�����ÂV�����Z�p�ݏo������A�������肵�Ă���̂ł��傤�B
�i���e���ʂ̋ƊE�ŗ��n�̌����҂�����Ă��܂��B���ɂ͔ނ�����������������Ă���̂��A�S������܂���j
�������[�U�[�Ƃ��āA�������o����͈͂ŁA���낢�뎎���Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����\����A���S���Y���Ȃǂ̋Z�p�I�Ȑ��m�ȓ������A�O���̑f�l�ɒH�蒅����Ƃ́A�ƂĂ��v���Ȃ��̂ł��B
���r���[�Ȓm���̐l�B�́A�o����[���ɗ]�T�������ƁA�����������l�̊ԈႢ���w�E����ق��ɁA
�͂��g���̂��Ǝv���܂��B�@�{���ɁA�����Ɖ��̂ق��܂Œm�肽���ƍl���Ă���l�Ԃ́A
�ق����Ă����Ă��A�X�Ȃ鍂�݂�ڎw������A���[���܂Ő����čs���ł��傤�B
���́A�Ƃɂ����A��U���@�\���g���̂��D���ŁA���b���Ă��āA���ꂩ����ł��邾�������̋@����A
�����čs�������ƍl���Ă��܂��B���̐l�B�̎��ۂ̎g�p���������ł�����A�������������̎Q�l�ɂȂ�̂ł��B
���l���g���āA����ȃX�g�[���[�ݏo���̂́A���Ԃ̖��ʂ����A�܂������̌o���𑝂₵����A
���o���Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ɑ��l�����������A�����ƒ������Ԃ������āA�����Ȕ\�͂����߂��肵�Ă���A�Ƃ������Ƃ��A
���߂Đ����ł���悤�ɂȂ�A�ЂƂ̌��ۂւ́u�F���v���A�����ȒP�ɋ��L�ł��Ȃ��A
�������́A���x�ȃ��x���ŋ��L�ł��邱�Ƃ�����A�Ȃ�Ă��Ƃ�����̂ł́A�Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10953470
![]() 1�_
1�_
[10942972]�̏������݂ŁA���m�ɂ͎��ۂɎ����Ă��Ȃ����Ƃ��A�������悤�Ȉʒu��
�ԈႦ�ď����Ă��܂������߁A�����ƕ⑫�������Ă��������B
10�s�ڂ��炢�̕��͂ł��B�ȉ��B
�@��0.5�{���炢�̂ق����A���܂�^���ɎB��Ȃ��Ă��ASR�̌��ʂ��y�ɑ̊��ł��܂����B
����́A�u�B�e�{����������Ԃ̂܂܁A2�b�`0.6�b�ʼn������B���Ă݂܂����B�v�̐�����
����̒��ɏ����Ă��܂����̂��A�~�X�ł����B���ۂɁu0.5�{���炢�v�̔{���Ŏ����Ă����̂́A
SS���A1/6�b�`1/13�b�̊Ԃł̎B�e�ł��B
�P�b����悤��SS�ł́A�莝����SR��ON�̏�ԂŁA�u���������点�Ă��A�O�r����[�Y��
�~���[�A�b�v���ƓI�m�ɗp�����B�e���̂悤�ȁA�u�������u�����܂߂āA�قډ���Ȃ����炢�܂ŁA
�z���t���悤�Ɏ~�܂��Ă���悤�Ȏʐ^�܂ł́A���\�����B�e�������ł́A�n�b�L����
���郂�m�́A�B��܂���ł����B
�}�N����ł��ASS��1/10�b�O��܂łȂ�ASR���쒆�ɂ�����x�̊m���ŁA�O�r�g�p����
���F�Ȃ���������悤�ȁA�u��������ꂽ�ʐ^���B���ȁA�ƍ��܂ł������Ă��܂������A
����̂P�b����悤��SS�ł̎B�e�ł́A�����͂܂��n�b�L�����Ă͂��Ȃ����̂́A
���S�ȕ�͂���Ă��Ȃ������ł��B�����Y�̂�����������܂��A�~���[�V���b�N�̂�����������܂���B
K-7�ł́A�~���[�A�b�v��Q�b�^�C�}�[�̎B�e�̍ۂ́ASR�͎����I��OFF�ɂ���Ă��܂��d�l�ł�����A
������AK20D������ł��ASS1.6�b�Ƃ��ŁASR�삳���āA�ł���Ȃ�Q�b�^�C�}�[��
�~���[�A�b�v�ł̎B�e���s���āA�����Ă݂����Ǝv���܂��B
�Ȃ��SS��1.6�b�ő�R�B�������ƌ����A2�b�ȏゾ�Ƃ��炢�炵�Ă��邯�ǁA
�Ȃ���1.6�b�܂łȂ�A�W�b�Ƃ��Ă���̂��A����Ȃɋꂶ��Ȃ���������ł��B
���x�������܂����A���惂�[�h������₷������A�ʒu�Ԃ�i�V�t�g�Ԃ�j�����������Ȃ�炵���A
0.1�{�`���{���炢�̎B�e�����ɋ߂Â��āA�^��Ɏv���l�����ꂼ�ꎎ���Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̏�ŁA���ƈ�������z���������Ȃ�A����͂���A�ł��B�ʂɕ��Ȃ��Ă��ǂ��ł��傤�B
�܂��́A�����̎肪���A���u���Ƃ������A�Ղ�Ղ�k����悤�ȃu���������Ă��邱�Ƃ��A
��������悤�ɂȂ�܂��傤�B�l�������x�̍�������Ƃ͎v���܂����A���͗L���ɋ@�\���Ă���A�Ɗ����܂��B
�p�i��GH1�Ȃǂ́A�����Y���̕�̋@��ł��A������x�̋���������A�Ղ�Ղ�u����
�����Ă���̂��A����܂�����A�Ȃɂ�SR�������\�ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�����āA���̂Ղ�Ղ�u���̕���A�ʒu�u������̂��́A�ƌ����Ă���킯�ł�����܂���B
�����ԍ��F10953472
![]() 1�_
1�_
�`������ے��C�����x�ŏ[���u�f�l�v�ɂ������ł��܂��恄��Ԃ��̌���
�����ԍ��F10953544
![]() 13�_
13�_
kuma_san_A1����́A�����ȂƂ���ŁA�y���^�b�N�X��SR�́A�ʒu�u������ł��Ȃ��A
���Ă����ς�����������Ă��邩������Ȃ�����A��ɂ͈����Ȃ��̂�������܂��A
���ȊO�̐l���A�u�ʒu�u�������Ă���v�Ɖ�����Ă���̂ɁA���܂ł��A
���������Ă�������A�܂��́A�����Ŏ����Ηǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����������Ă��Ă��A���ۂ̕��G���ׂ�������ɑΉ�����̂ɁA�f�q�����W��ɃW�b�Ƃ��Ă���
���ƂŁA��ł���悤�ȃu�����������肷�邩������Ȃ��A�Ƃ��A�m���ɂ͂����A
���̔����Ɍq����悤�ȁA�]����݂��Ă����Ȃ��ƁA���Ȗ����ŏI���Ǝv���܂��B
�l�̂��Ƃ��A�܂������̊��o�����Ƃ��厖�ł��傤�B
�����ԍ��F10953574
![]() 1�_
1�_
kuma_san_A1����́AMZ-LL��������S�R�J�����Ɋւ���m���������Ă�����Ǝv���܂���B
�����̌������Ƃ�ے肷��l�ɑf�l���̌����Č������s�ׂ���߂�ׂ����Ǝv���܂��B
����ɁA��������MZ-LL���������������̂����킩��Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F10953697
![]() 17�_
17�_
MZ-LL����
�����́B�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
���ȂX�g�[���[������ɍ���āA�킯���킩��Ƃ������̂͂�߂Ă��������B
���̃X�g�[���[��MZ-LL����̐��E�ł��B
������Ɠǂݔ���������܂������A���͊ȒP�ɂ܂Ƃ߂������ō���Ă͂��Ȃ��ł��B
���̃X�g�[���[���킯�킩���A�Ƃ������Ƃł����ł����H
�����x�������Ă���ʂ�A���́A�y���^�b�N�X��SR�������D�G���Ƃ��A��������������ł�
�����AMZ-LL����SR"����"���D�G�ƌ������A�Ƃ͏����Ă܂���B
���O���̑f�l���A���������f�ГI�ȏ��ŁA���������U���邾�����ʂȂ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�ł�MZ-LL��������낻��U����̂���߂āA�����ő��̂�������̐l�������Y���ɂ��Ȃ����Ƃ�Ɋ肢�܂��B
�����r���[�Ȓm���̐l�B�́A�o����[���ɗ]�T�������ƁA�����������l�̊ԈႢ���w�E����ق��ɁA�͂��g���̂��Ǝv���܂��B
���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
MZ-LL��������r���[�Ȓm���ŁA�����ɏ�������ł�������Ⴂ�܂�����ˁB
���{���ɁA�����Ɖ��̂ق��܂Œm�肽���ƍl���Ă���l�Ԃ́A�ق����Ă����Ă��A�X�Ȃ鍂�݂�ڎw������A���[���܂Ő����čs���ł��傤�B
���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B���͈Ⴂ�܂����B
MZ-LL������A�������������l�ł�������ł��܂ł������ĂȂ��ł��傤�ˁB
�Ō�ɂȂ�܂����A�X���̎�|�d���āAK-7�̎�Ԃ��̊��z�������Ă݂܂��B
�{�f�B����Ԃ��Ƃ��āA���Ѓt���b�O�V�b�v�@�Ɣ�ׂĂ����F�Ȃ��Ǝv���܂��B
�����āAMZ-LL����Ɠ������A�͂�����ƈʒu�Ԃ����Ă��邩�ǂ����͂킩��܂���ł����B
����ł́A�ǂ������ז����܂����B
�����ԍ��F10953709
![]() 12�_
12�_
>�����������Ă��Ă��A���ۂ̕��G���ׂ�������ɑΉ�����̂ɁA�f�q�����W��ɃW�b�Ƃ��Ă���
>���ƂŁA��ł���悤�ȃu�����������肷�邩������Ȃ��A�Ƃ��A�m���ɂ͂����A
>���̔����Ɍq����悤�ȁA�]����݂��Ă����Ȃ��ƁA���Ȗ����ŏI���Ǝv���܂��B
����A���������ނ̂��̂ł͂Ȃ��ł��B
�������ɋ`������ł͓�����Ǝv���܂����E�E�E�B
�B���f�q��u����̏ꍇ�͊ȒP�ɋL�q�ł��܂��B
�i�O��u���������j�V�t�g�u���́u�J�����̈ړ����������ɎB���f�q���i�J�����ɑ��āj�������v�B
�p�x�u���́u�p�x�u���Ƃ͔��Ε����̊p�x�֎B���f�q���i�J�����ɑ��āj�������v�B
���̓�ł��B
�u�p�x�ɕ���������v���Ă̂��`������ł͖����Ǝv���܂��B
���ʓI�ɍ��W��ɂ����Ƃ��Ă��邱�Ƃ����邩������܂���ˁB�ł�����͌��ʂł����Ď�u����̌����ł͂���܂���B
�����ԍ��F10953851
![]() 4�_
4�_
[10953472]�̏������݂ւ̎��ȃ��X�ł��B
�@��K-7�ł́A�~���[�A�b�v��Q�b�^�C�}�[�̎B�e�̍ۂ́ASR�͎����I��OFF�ɂ���Ă��܂��d�l�ł�����A
�@��������AK20D������ł��ASS1.6�b�Ƃ��ŁASR�삳���āA�ł���Ȃ�Q�b�^�C�}�[��
�@���~���[�A�b�v�ł̎B�e���s���āA�����Ă݂����Ǝv���܂��B
K20D�ŁA�~���[�V���b�N���N�����Ȃ��悤�ɂ��āASR���g���Ă݂悤�Ǝv���A
SR�X�C�b�`��ON���ɃX���C�h�����܂܁A�Q�b�^�C�}�[�ŎB�e���Ă݂܂������A
��͂�A������SR��OFF�ɂȂ��Ă��܂��悤�ł��B
�y���^�b�N�X�̃T�C�g��J�^���O���U�b�ƌ�������ł́ASR�Ń~���[�V���b�N�ɂ��u����
����Ă���A�ȂǂƂ́A�Ƃ��ɏ����Ă��Ȃ��݂����ł�����A���ۂ̏��͕s���ł��B
�����g�́ASS��1/10�b�O�キ�炢�܂łŎg���̂��A�ǂ����ȁA�ƌl�I�ɂ͊����Ă��܂��B
���̕ӂ�ȊO�ł��A�e�ЁA���낢��ƕ�ɑ��Ă̏d�_�Ƃ��Ă���ӏ��͈���Ă���݂����ŁA
�y���^�b�N�X��SR�́A�������݂��ƁA�u�ʏ�̎莝���B�e�v�ɂ��Ɠ������Ă���C�����܂��B
�iSR�́j���撆�������ԋ쓮�ł�����A�ߋ����B�e�ɂ����ʂ������Ƃ�����ۂ��l�I�ɂ͎����܂������A
�I�����p�X�́AI.S.2�AI.S.3���[�h�ŁA�����B��ɑΉ����Ă�����A�Ǝ��ۂɂ́A�܂����͂�����
�����Ă��Ȃ��Ă��A���ꂼ��ɓ���������ȁA�Ƃ͎v���܂��B
�i�I�����p�X�̕���A�ߋ����ł����ʂ��������́A�܂���x�������Ă��Ȃ��̂ŁA����܂���j
�J���w�̍l������A���[�U�[�̗v�]�Ȃǂɍ��킹�āA�i�����Ă���Ǝv���܂����A
�쓮�����̈Ⴂ�Ȃǂ�����A������@�\���������^�C�~���O�Ȃǂ��A���R�Ȃ���
�قȂ��Ă���̂ŁA�u�����łȂ��v�Ƃ������Ƃ́A�ǂ����Ƃ��ȁA�Ɖ��߂Ċ����܂��B
�������[�J�[�̃J�����ł��A�쓮������A���ʂ̒i��������Ă����肷�邩��A
�����́A�����̕K�v�Ƃ��鐫�\��A�D�݂ɍ��킹�āA�I�ׂ�̂́A�ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10958121
![]() 0�_
0�_
�i�l���ł͂Ȃ��A�����������Ă������Ƃ̕⑫�Ƃ��āj
�m��������A�Ƃ������x���ŁA����I�Ɍ������Ă���킯�łȂ����O�̂��Ƃ��{���ɉ���Ȃ�A
�ɒ[�ȏ�����������A��勳����A���������A�ُ�Ȓ��̏�M����Ɗw���A�K�v�Ȃ��ł��傤�B
�����������Ă��Ă��A�ʒu�u���������Ă��邱�Ƃ��A����Ȃ������̂Ȃ�A
������x�A�����Ȃ����悢�̂��Ǝv���܂��B
����������܂Œm���Ă������ƂɁA���x�ȋZ�p���Ђ��ς�悹�āA�P�������ĉ��߂�����̂ł͂Ȃ��A
�{���ɋ���������Ȃ�A�����̕��������k���Ȑ��E�ɁA�g�𓊂���A�����������ɋ߂Â���ł��傤�B
�����������f���ŁA�Z�p�I�Șb���A���������Ă��A�������o�ɂ������R���A�����B���m���Ă��邱�Ƃ��A
���̐��E�́A�ق�̒f�ГI�ȏ��ł����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�O���ɒu���Ă��Ȃ����Ƃ��A�����̂ЂƂ��Ǝv���܂��B
���́A�������g�����x���ŁA�B�e�̋Z�p�A�����ē����錋�ʂƂ��Ẳ摜�̒��ŁA
�u��U���̌��ʂ̈Ⴂ ���Ă���Ǝv���܂��H�v
�Ƃ�����̃X���b�h�ŁA�l�ɂ����˂Ă��܂����B
�܂��́A���Ƃ����Ћ@�ł��A�������g���Ă���@�ށA�J��������Y�Ȃǂ������āA
���������ǂ������g�����ŁA�ǂ��������ɁA�ǂ����������A
�Œ�ł��A���ꂪ�����ƁA���ɂ̓C���[�W�����炢���A�������N���܂���B
�l�̗g��������邽�߁A�ЂƂ̌��t�����p����������A�������ǂꂾ���̂��Ƃ�
�{���ɒm���Ă���̂��A�܂��́A�₢�����ׂ��ł��傤�B
���́A������̃X���b�h�ŁA�����������ɒm���Ă��邱�Ƃ����������A���߂ĉ���܂����B
�������A���������ӂȂ��ƂɊւ��ẮA�܂��܂��u�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ��ڂŔ��f�ł��Ȃ��̂��낤�v�A
�Ƃ����ɊJ���������܂����B
�t�@�C���_�̎��엦�ɂ��Ă��A�����LV�ł̂Ղ�Ղ�u���������Ă��邱�Ƃ��A
���̌��邱�Ƃ̌P���̉��p�ŁA�u�������v��������A�ʏ�̎��͂�����l�ł���A
����قǓ�����Ƃł́A�Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł����A�\�N����\�N�������đ̓��������Ƃ�
��������̂́A��ςȂ��Ƃ��Ɗ����܂��B
�Ȃ�ɂ���A�����Ƃ͈Ⴄ�\�͂��������l�Ԃ�����A�����āA���������ʂɉ��邱�Ƃ�
�����邱�Ƃ��A������������Ă�����Ȃ��l�Ԃ�����A�Ƃ������Ƃ��A�m������ŏ�������ŗ~�����ł��B
�����ԍ��F10958318
![]() 1�_
1�_
���������������ł��ˁB
�p�x�u���ƈʒu�u�����m���ɂ킯�āA�l�Ԃ��J�����ɗ^���邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł����H
�}�N����ł͂��܂�A��U���͌������ア�悤�Ɋ����܂����B
����͑��Ѓ��[�J�̎�U���ł��ꏏ�ł��B
���l�ƑΘb����C���Ȃ��Ȃ�A�����Ȃ����B
�����ԍ��F10958347
![]() 13�_
13�_
���V�̓X����̂������m�����o�������邯�ǂȂ�
���[�J�[�ɂ��m�F�������ʒu�u���̕�͖�����
�܂��A�A�z�ɉ��������Ă����ʂ��Ă��Ƃ��킩������
�����ԍ��F10958414
![]() 23�_
23�_
[10958318]
���Ȃ�ɂ���A�����Ƃ͈Ⴄ�\�͂��������l�Ԃ�����A�����āA���������ʂɉ��邱�Ƃ�
�����邱�Ƃ��A������������Ă�����Ȃ��l�Ԃ�����A�Ƃ������Ƃ��A�m������ŏ�������ŗ~�����ł��B
�u���l�̐����𗝉��������̂Ȃ��l�vor�u���l�̐����𗝉��ł��Ȃ��l�v
�ł̓R�~���j�P�[�V���������藧���܂���ˁB
���J���ꂽ�f����ł́A���������l��O��ɂł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10958994
![]() 20�_
20�_
MZ-LL����
���@�����������f���ŁA�Z�p�I�Șb���A���������Ă��A�������o�ɂ������R���A
���@�����B���m���Ă��邱�Ƃ��A���̐��E�́A�ق�̒f�ГI�ȏ��ł����Ȃ��A
���@�Ƃ������Ƃ�O���ɒu���Ă��Ȃ����Ƃ��A�����̂ЂƂ��Ǝv���܂��B
���@[10958318]
�@MZ-LL����́A�Z�p�I�Șb�����̃X���ł��܂������B�Z�p�I�ȃR�~���j�P�[�V����
�͐��藧���܂���ł����BMZ-LL���A�_���I�ɂ��܊��ł��F�����Ă��Ȃ��i�{�l
�͖{�C�Ŋ������Ǝv���Ă���j�uSR�̎�Ԃ��͎�ɃV�t�g�u�������Ă���v
�ɁA��������Ă��邾���ł��傤�B�����͏o�Ă��܂���BMZ-LL�������ł��Ȃ�
�����ł��B
�@���������A��u����̌����𗝉�����Ȃ�A����Ȃɑ傰���ɍ\���Ȃ��Ă悢
�ł��B���i������̂͂���Ȃ�ɑ�ς��Ǝv���܂����B
�@MZ-LL����́A��_���̖�̕�����Ȃ����������˂܂��ˁB�����Ă������Ă��b��
�܂Ƃ܂炸���f���J��Ԃ��B���X�����̍���Ȃ����Ƃ��咣���Ă��邩��A������
����͂����Ȃ��B������̉ʂẮA�����͈̂��Ǝ���������n���B���ꂾ����
�X���͒������Ȃ�܂��B
���@���ɂ́A�c��������b���Ĕ����Ă������̖ڂƂ�����Âɕ��͂��銴�o�ƁA
���@�����Ԕ��p�i�Ȃǂ��B�e���Ă�������ł̌o��������܂��B[10859641]
���@�c��������̃f�b�T���̕��Ƃ��A�P���̎����Ȃ̂ł��傤���B
���@�u�ځv��b���ĂȂ��l�����ɁA��肢�������ł��Ȃ��̂��A�炢�Ƃ���ł��B
���@[10880665]
���@���́A���Ȃ��Ƃ��A���{�ōō���̂�����������ŁA�d���������o�������邵�A
���@�c���̍������勳����āA����Ƃ�����w�ɓ����āA�݊w�����\���Z
���@�̍u�t�����Ă����A���������A�����I�Ȕ��p�n�̊w�ѕ����A�\��A��\��Ƒ���
���@�Ă�������A�Œ���̂��Ƃ͒m���Ă��܂��B[10914099]
�@MZ-LL����A����Ȃ��ƌJ��Ԃ������Ēp���������Ȃ��ł����B�@�ǂޕ����p������
���Ȃ�܂��B
�@�f���ł́A�����b�͉��̈Ӗ��������܂���B�������ޓ��e�ɉ��l���t���̂ł��B
�c���̂��납��b�����ڂ������Ă���Ȃ�āA�ǂ��ł��ǂ��̂ł��B���m�ł���B
���@�Ȃ�ɂ���A�����Ƃ͈Ⴄ�\�͂��������l�Ԃ�����A[10958318]
�@���₨��A�ʒu�u�����̓`���t���_�ɂȂ�܂������B
���@���������ʂɉ��邱�Ƃ⊴���邱�Ƃ��A������������Ă�����Ȃ��l�Ԃ�����A
���@�Ƃ������Ƃ��A�m������ŏ�������ŗ~�����ł�[10958318]
�@���������v���̂ł�����A����I���_���_���I���������˂Ȃ��ŁA�����ɁA����
�͓���ė����ł��܂���ƌ����悢�̂ł��B
�@MZ-LL����́A�_���I�Ȏv�l�͓��ӂłȂ�����A�����Ɗ��o�I�ɃJ�������y���߂�
�悢�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10961596
![]() 32�_
32�_
�ŋ߂̍r�炵�͂��낢��Ǝ肪����ł���̂ŁA�폜�����̂�����Ȃ��̂��A
����Ȃ���Ԃŏ������ނ̂́A���낢��Ɩʓ|�������ł��B
���x�������܂����A�X���b�h�̎�|�����x�������Ă������ĂȂ����_�ŁA�����ɔ�������A
��������C���Ȃ����Ƃ��A�����Ȃ̂����A���̃X���b�h�𗧂ĂāA�����B���C�ɂȂ邱�Ƃ��A
�D���Ȃ悤�ɏ����悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̃X���b�h�́A�������x�����Ă���������܂��A���ۂ̎g�p������邽�߂ɁA
���Ă��킯�ŁA�������������������A���X�ƌJ��Ԃ���Ă��A�^���ɓǂ߂Ȃ��̂ł��B
�ǂ�ł���l�B��Q�����Ă���l�B�̒��ɂ́A�g�p�������A���r���[�Ȓm�����q�����킹�āA
���˂���܂킵�āA�y���ނ̂��D���Ȑl���A����Ȃ�ɂ���Ǝv���܂����A�ʂɂ��̃X���b�h��
���K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̃X���b�h�ł��A���͋�������������ǂݔ���܂��B�ł������ł͂��������킯�ɂ������Ȃ��̂ł��B
����A�����ŁAEOS 20D��K-7�Ƃō��킹��1650�����炢�B�e���܂������A���ł��g�����тɁA
�V���Ȕ�����A�R�c�A�������Â����Ă��܂��B
���̃X���b�h�̍ŏ��ɁA�l���S�O�O�������S�̍i��J���ł̍��������Ă�������������̂悤�ɁA
�����g�������Ƃ����������Y�ŁA�B�������Ƃ��Ȃ��悤�Ȕ�ʑ̂ŁA�䎩�g�̎g�p����
��������ł��������ƁA���Ƃ����Ɗ��z�⊴���Ă��邱�Ƃ͈���Ă��A�����g���ǂ�ł���l�̒��ŁA
���p�𒆐S�ɍl���Ă���l�ɂƂ��Ă��A�Q�l�ɂȂ邱�Ƃ������Ǝv���܂��B
���ۂɁA���̓y���^�b�N�X�Ō�b���f���ۂɂ��A�u�i�≖����́j�]�������Y�ł��A��U�ꂵ�Â炢�\�����v
�̎����Ă���ۂɁA��������������A�v�������ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B
K-7�ŘA�ʂ�hi�����߂Ďg���Ă݂܂������A�������炠�����ŕ֗����Ǝv���܂����B
�����������������Ă���l�Ԃ��B���Ă��āA�g�[�^���Ő������閇���𑝂₹��̂�����A
���̋@�\����ɁA�J������I�Ԑl������̂��A�������[���ł��܂��B
��U�����A�e�� ����̎d�g�݂�����Ă��Ă��A���ʂ̈Ⴂ���n�b�L������u�Ԃ́A
���Ȃ���������܂���B�������A���ۂ̌o������A�����������ɂ���Ȋ����ŕ���ꂽ�A
���ʂ��������A�����̊m�����オ�����A�Ə����ł����W�܂�A���Ȃ��Ƃ��u�Q�l���x�v�ɂ́A
�Ȃ�ƍl���Ă��܂��B�ł��A���̎Q�l���x�̑��҂̕��A�����Ŗ𗧂@����邩������Ȃ��B
��U��A�Ƃ����̂͞B���ȕ��ŁA�n�b�L��������͓̂�����̂�������܂��A
�g�p�����Y��{�f�B�A�B�e�҂Ƃ̑�����u����v����ẮA�p�x�u�����N���Â炢�g�ݍ��킹��
����A�Ɗ����Ă��܂��B�����Y�̒�����d���ȂǁA�d�l�\���画�f�ł���ޗ������邯��ǁA
���ۂɎg���Ă݂�ƁA�v���������������肭��A�Ȃ�Ă��Ƃ��悭����܂��B
�����Ŏg���Ď�����̂���Ԃ����ǁA�l�̑̌��k�ɂ��A�������\�����Ȃ��������Ƃ�
�C�t�����Ă����悤�ȁA�����������܂܂�Ă��邱�Ƃ������ł��傤�B
�܂��́A��������U���@�\���ǂ��������@�ނŗp���āA�ǂ�ȕ��Ɋ������̂��A
������������Ƃ���A�����ł͂��ׂ����Ǝv���܂����A���ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ�A�����ł͏������܂��ɁA
�ʂ̃X���b�h�ɂāA�����B�����ڂ���b����A�f���̃��[�����ŁA�D���Ȃ悤�ɋ��L����Ηǂ��Ǝv���܂��B
�i�������A�����Ŏ����̑̌��������A��������Ă������A�ƌ����킯�ł͂���܂���B����͓��R�j
���o�I�Șb�łȂ��A���Ɍ����I�Șb�ł��B
�����ԍ��F10967558
![]() 3�_
3�_
���̃X�����グ�鎖���������������i��
MZ-LL����
�y�j���B�ɂȂ̂ł�����ƗV��ł݂܂����B
�ƌ����̂����̃X���A�������ݐ��S�Q�T�@�ɑ��ăi�C�X���P�X�Q�U�@�Ƌ��낵�����ł��B
���̒���MZ-LL�������i�C�X�����m�F���āAMZ-LL����ȊO�ɓ������i�C�X�Ƃ̐����r���āA���̍������R�̍����A�K�R�̍��Ȃ̂��ׂĂ݂����Ȃ�������ł��B
�S�������ݐ��@�@�@�@�@ �S�Q�T���@�i�C�X���@�P�X�Q�U��
MZ-LL����̏������ݐ��@�P�U�R���@�i�C�X���@�@�P�T�Q��
��MZ-LL����̏������ݐ��Q�U�Q���@�i�C�X���@�P�V�V�S��
MZ-LL����̂P�������ݕӂ�̕��σi�C�X���@�@�O�D�X�R��
��MZ-LL����̂P�������ݕӂ�̕��σi�C�X���@�U�D�V�V��
��L�̍����ԓ��Ō��肵�Ă݂܂����B
���l���R�D�T��
���̒l�́A�������̃X����������x���ĂāA�������e�ŋc�_�����Ƃ���ƁA�P�O�O��c�_���āA�������̂R�D�T���o�Ă��Ȃ������A�������ŋN�����Ă��܂��B
���̍��͋��R�Ƃ͌����܂���B�K�R�I�ɋN���������ƌ��킴��܂���B���̐������ł��B
�Ȃ��A����ȍ����N�������̂��H�@���̌����͂����ł͍l�@���܂��B
�����ԍ��F10970827
![]() 18�_
18�_
���炭�Z�������Ă���ԂɁA���̊Ԃɂ��AK-7�̌���V���o�[���f�������\���ꂽ�悤�ł��ˁB
���́A�y���^�b�N�X�Ŏ�U���@�\�̂��Ƃ�A���̂��Ƃ������Ă������������ɁA
K-7����������������A����F�̃��f�����o��\��A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��A������Ƃ�����b�����������܂����B
�����A�v�X�ɋx�݂������̂ŁA���߂Ă��̃X���b�h�́A�����̏������݂𒆐S�ɁA
�ŏ�����A�Z���ԂŃU�b�Ƃł͂���܂����A�ǂ�ł݂܂����B
��͂�A�����Ă���SR�̎d�g�݂Ɋւ��ẮA�����B�e�Z�p�Ƃ��Ă̌��ʂ𒆐S��
�u�˂Ă�������������A�{���ɏ�肭�����ł��Ă͂��Ȃ��Ǝv���܂����B
�����A�����Ă����P��́A�ł��邾�������Ŏg��������ł��B���Ƃ������P����g���Ă��A
�I�m�ɗp���ĂȂ���A�����ɂ͂Ȃ�܂��A�Z�p�I�Ȃ��ƂɊւ��ẮA�����������������Ƃ�����A
�w�͂��Ă܂ŁA�����̐l�ɓ`�������Ƃ͎v���܂���B
�i����������ア���Ƃ́A���̃X���b�h�̂��������̒i�K�ŁA�����Ă��܂��B[10858947]���j
���炭�����Ƃ��ɖZ���������̂ŁASR�̍�����̂悤�ȃl�^���A���͂ЂƂ�����܂���B
�����v�����܂�����A�����Â��ɂȂ������Ƃł����A������̃X���ł܂����������Ă������������Ǝv���܂��B
�����ۂ������
���ۂ�����A�����Ȑl�Ɍ����Ă��܂����B
���x�������Ă���ʂ�A�������ł́A�^�����������m�����A�����Ă��Ȃ��ƁA����
����܂ł̐����̒��ŁA���x���������Ă��܂��B
�߁E����j�����Ă��A�����Ƃ͂����܂��A����͂悭���邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
K-7���������ł��傤����A�����Y�Ƃ̑g�ݍ��킹�ŁASR�̎g�p���ł������Ă���������Ɗ����������̂ł����B
�i�Ⴆ�b�Ƃ��āj�Ύ���ɐd�𓊂������̂��D���Ȑl�́A�C�y�ł����ł��ˁB
�����ԍ��F10994568
![]() 2�_
2�_
>>���ۂ������
�i�j�Ȃ�Ă��ďグ�ė~�����Ȃ��ł��B���f�ł��B
>>MZ-LL����
�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂ƈ�Έ�Řb�������Ė{���Ȃ�ł����H
����ȂɉɂȋZ�p�҂������ł��傤���H
�����ԍ��F10995276
![]() 2�_
2�_
���Z�p�I�Ȗ��ɂ���
�p�x�u���ւ̑Ή����L
�V�t�g�u���ւ̑Ή�����
���u��U��v��@�\�Ƃ��Ă̓���ɂ���
�p�x�u���I�u��U��v�ւ̑Ή����L
�V�t�g�u���I�u��U��v�ւ̑Ή����L
�����������ʂł����Ă�����s�v�c���Ȃ��Ǝv���܂��B
�]���āA�y���^�b�N�X�̋Z�p�҂�
�u�w��U���@�\�Ɋւ��Ắx�V�t�g�u���ɂ��Ή������Ă���v
�Ɛ������Ă��s�v�c�ł͂���܂���B
�O�u��U��ŋN����u���Ɋւ��āv�ƓK�p�͈͂����肳��Ă��邩��ł��B
�����āu��U���@�\�v�́u��U��v������@�\�ł�����A
�u�@�B�I�ɍ쐬���ꂽ�u���v���ł��Ȃ��Ă��ʂɖ��ł͂���܂���B
��U�����S�Ẵu����}�����Ȃ���Εs�Ǖi�ł���Ƃ����̂Ȃ�A
�O�r�Œ莞�ł���U��ON�őS����肪�����Ȃ��͂��ł��B
���̂悤�ɁA����ƓK�p�͈͓��m�ɂ��Ȃ��ŁA�Z�p�I�Ȃ��Ƃ��c�_����̂�
�_���I�ƌ������͒P���Ɋ���I�ȗv�f���旧�悤�Ɏv���܂��B
���̒��ɂ͍ŏ������~�ȉ��̎B�e�f�q�s�b�`�͖��Ӗ��ł���Ɛ邤���̋Z�p�҂����܂��B
���̐l�ɂƂ��āA�ŏ������u�~�v�́A�^�l�p�ȂP��f�ŏ[���\���\�ł����āA
���̒��́u���v�͑S�čŏ������~�̒��a�ɉ������u����v�Ő��藧���A
���̒��Ԃ̍��W�i�Ⴆ�A���̃s�b�`�̔��������㉺���E�ɂ����Ƃ��j�ɏœ_���邱�Ƃ͖����ƍl���Ă���킯�ł��B
�����Ȃ��Ƃ��l�ɂ́A�^�l�p�̊K���t�h�b�g�ʼn~��\������ɂ͍Œ�R×�R�h�b�g���K�v�Ɏv���܂����E�E�E
���̃��x���ł��Z�p������킯�ł�����A�ǂ��炩������ȏ�ɐق��Ă��A
�S�̎��������悤�Ɍ�������̂Ȃ̂��ȂƎv���܂��B
�X����̌����Ă邱�ƂŁA�ЂƂ������Ă���Ǝv�����Ƃ́A
�ŏ��ɊϔO�I�ɋZ�p���Ȃǂ�M�����ނƁA���ۂɂ��̓��삪�ǂ��K�p����邩���������͓݂͂�Ƃ������Ƃł��B
����͗B���_�҂��u��ցv�ɊY������悤�ȑ̌������Ă��A���������鎖���ł��Ȃ��̂Ɏ��Ă��܂��B
��������A���ۂɂ͖c��ȕ����@���̑g�ݍ��킹�̌��ʂł���Ǝ���鎖���̂͏o����͂��Ȃ̂ł����E�E�E
�ЂƂ܂��ł����A�y���^�b�N�X���̐����Ɋւ��ċ^���������Ȃ�A
�������g�Ńy���^�b�N�X�̃T�[�r�X�Ɋm�F����悢���Ƃł��B
����ŃX���呤�̐������ꗂ�����̂Ȃ�A���̓��e�����悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����I�ȉ�����]��ł���Ƃ������́A����I�ɑ�����h���������Ă��邾���̂悤�ɒ[����͌����܂��B
�����ԍ��F10997340
![]() 4�_
4�_
MZ-LL����
���̃X�����グ�鎖�ɒ�R������܂����A���Ȃ�オ���Ă܂����B
�����x�������Ă���ʂ�A�������ł́A�^�����������m�����A�����Ă��Ȃ��ƁA
�܂����������ł���B
�Ȃ���������Ă��܂����������݂ɏ����Ă��܂������A�������̐��l������������ł͂���܂���B�P�ɐ��l�̍����������������ł��B�������������ŁA���_�͒N�ɂ��o���Ȃ��A�ƌ����l���ł��B�i����͎��ہA�����������m�ł��j
���R�̍����A�K�R�̍����B���ꂾ�������������Ă��܂���B�����Ă��̍��͋��R�o���Ƃ͌����Ȃ��A�ƕ\�������ɉ߂��܂���B
�����������̐��l���������Ă���A�Ɗ������̂Ȃ�A����͊��������Ȃ��̒��ɂ��̓���������Ǝv���܂��B�̂Ɂu�Ȃ��A����ȍ����N�������̂��H�@���̌����͂����ł͍l�@���܂��B�v�Ə����Ă���̂ł��B
SR�̎g�p���A�ł����A�֗��ȋ@�\���Ǝv���Ă��܂��B
�V�t�g�u���ł��p�x�u���ł��A�u�����}������̂Ȃ�Ȃ�ł������̂ł��B
�����ԍ��F10998261
![]() 3�_
3�_
�f�W�^���t�H�g�R�����̓��W�L��
�w������l�ɂ͕����Ȃ��f�W�^�����t�̋^��P�T�O�x
045�F�Ȃ��}�N���B�e���͎�u����������Â炢�́H
�i�}�N���̈�ł͊p�x�u�����V�t�g�u���̉e�����傫���Ȃ邱�Ƃ�A�L���m����
�n�C�u���b�h�h�r�Ɋւ�������̌�Ŋe�Ђ���̌����j
�u�{�f�B����U���ł��A���s�ړ����o�p�Ƃ��ĉ����x�Z���T�[��ʓr���ڂ����
���l�̂��Ƃ��\�ł���ƌ�����ł��܂����A���ʂƂ��Ă̓}�N���̈�Ɍ��肳���̂ŁA
�R�X�g�p�t�H�[�}���X���Ⴂ�ƍl���Ă��܂��B�܂��A�}�N���̈�ɂ����ẮA����������
�u���ɑ���j�[�Y�̂ق��������ƔF�����Ă���A�����𑍍��I�ɉ������Ă����̂�
����̉ۑ�ł��B�i�y���^�b�N�X�j�v
�����ԍ��F11007053
![]() 23�_
23�_
�Ȍ�̌�y����
PENTAX�ɁASR�ɂ��Ă̎�������[�����Ă݂��Ƃ���A
��͂�u���s�ړ����o�͂��Ă���܂���v�Ɖ����炦�܂����B
������
MZ-LL����̊����Ă���uSR�̕�́A�ʒu�u���ɂ����ʂ�����悤���v�́A
���܂���SR�̕�@�\�ɁA���������u�v��Ӑ}���Ȃ��������ʁv��
�������̂����m��Ȃ��Ƃ����_�́A�S�ʓI�ɔے肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B
�������Ȃ���A���̌�MZ-LL�����̃R�����g�����Ȃ��Ȃ����̂�
�ނ̒��̌��_����Ă���̂����m��܂���ˁB
�������A���������̃u���ɑ����Ƃ����͓̂�����ł��ˁB
���엦�����̋Z�p���p�ʼn\�����m��܂��A���엦���ς��Ƃ���
�_�ő���������̂ɂȂ��Ă��܂����ƁB
����́A�ʒu�u���̕�ŏ������Ă���Ƃ����A���̖тP�{��
�t���[�~���O������R���g���[���ł���MZ-LL����ɂƂ��ẮA
�܂����������Ȃ���Ƃ������Ƃɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
������ƒE�����܂����A�R��������̌������A�^������ȂQ�������ʂ�
�B���f�q�Ŏ�ȏ�A�����ȂԂ��Ƃ����͎̂����s�\�Ȃ�ł���ˁB
�B���f�q���̂��A�����Y�̉�p�ɍ��킹�Ęp�Ȃ����`��łȂ����襥�B
�Ƃ������Ƃł��̃X�������ɏI�������m��܂���B
�ւ�����F�l�A�S�g�Ƃ��ɂ���ꂳ�܂ł����I�i�j
�����ԍ��F11039971
![]() 10�_
10�_
�Ō�ɁAMZ-LL���S�Ă̐l�ɔ������Ă��܂��������݂��ēx���p�����Ē����܂��B
MZ-LL����ɂ́A���߂Ă������̂������ɂȂ�ꂽ���e���ᖡ���Ē����A
���������B��Ƒ����т����̂��A����܂ł̏����݂��������߂�̂��A
����x�l���Ē�����K���ł��B
> ���_���炢���܂��ƁA���̃X���b�h�ŁA����SR�⎋��Ɋւ��ďq�ׂ����Ƃ́A
> �قڂ��ׂĐ������������ƂɂȂ�܂����B
> ���Ѓ��[�U�[����B���A�܂����������������̂��Ƃ������Ă��āA�����A���Ă��܂��܂����B
>
> ���́A�����A�A���̓r���ɁA�y���^�b�N�X�ɒ��ږ₢���킹�āA�����ɁAK-7�Ȃǂ�SR��
> ���s�ړ��̃u������ɑł������A�ʒu�u���̕�ł��邱�Ƃ͉���܂����B
> �����A�O�̂��߁A���ۂɂǂ������d�g�݂Ńu����ł������Ă���̂��A���엦�̂��Ƃ��m�肽���������߁A
> �y���^�b�N�X�̋Z�p�҂̕��ƁA�P�P�ŁA�����Ԃ��b�����Ă��������@������������܂����B
>
> ��ϊy���������ł��B�����āA�����l���Ă������ƁA�����Ă������Ƃ��A�{���̂��Ƃ�������ł�����B
>
> ���������ŏ����Ă������Ƃ́A�����قڂ��̂܂܁A�����ł����B
> �W���C���ŁA���V�����f�q���ʒu�����ɕۂ��A�{�f�B���̗h��ɑ��đł������B
> ���m�ɂ͏�肭�����Ȃ��ł����A�܂���������������߂āA�����A�����Ă������Ƃ������܂����A
> ���̊��o�┻�f�́A�܂������Ԉ���Ă��܂���ł����B�@�ق���݂�A���Ċ����ł��B
>
> �����A�����ŁA�Ƃ�ł��Ȃ����_��W�J���Ă��������A�ǂ̂悤�ȕېg��}�邩�������̂ł��B
>
> ���x���������悤�ɁA�l�b�g��G���̏����Ȃ����킹������̋�_�����A
> ���̂悤�ɁA���͂Ɗ��o���ǂ��l�Ԃ��A��R�̎B�e���o�āA�����Ƃ��Ĕ��f�������Ƃ̂ق����A
> �������Ƃ������Ƃ́A�悭����̂ł��B
>
> �O�ɏ������ʂ�A���C�u�r���[�⓮��Ȃ�A�ʒu�Ԃꂪ�����Ă��邱�Ƃ��A�܂�킩��Ȃ̂ł����ǂˁB
>
> �����A�����łƂ�ł����_��W�J���Ă����l�����̌���̂Ђǂ��⊴�o�݂̓��ɂ́A
> �������肳�����܂����B������Ӎ߂̏������n�߂��ق��������Ǝv���܂��B
>
> �͂�����ƁA�f�q�̕��s�ړ��ɂ��A�ʒu�u���i�V�t�g�Ԃ�j�̕�ł���A�����āA
> �p�x�Ԃ�ɂ́A���܂蒍�ڂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ���������Ă��܂����B
> ���̕ӂ�́A�܂��ڂ��������܂��B
>
> �������A�������ŁA�Ԉ�����F�����A���������Ƃ���Ƃł��v�����̂ł��傤���B
> ���x�����Ⴗ���܂��B
�����ԍ��F11040047
![]() 17�_
17�_
���̃X���b�h���ڂ��Ă��܂����B
���ǃ^�C�g���́u��U���̌��ʂ̈Ⴂ���Ă���Ǝv���܂��H�v
�ɂ��ẮA�ǂ��Ȃ̂ł��傤���H
�Ȍ�̌�y����Љ�̂������f�W�^���t�H�g�R�����̓��W�L��
�w������l�ɂ͕����Ȃ��f�W�^�����t�̋^��P�T�O�x
045�F�Ȃ��}�N���B�e���͎�u����������Â炢�́H
���n�ǂ��܂����BPentax�Z�p�҂́u���������v�́A�V�t�g�U��ɂ�
�Ή����Ė����Ɠǂݎ��܂����B
�]�k�ł����X���傳��͂ǂ��̂悤�ȑԓx���Ƃ��邩�A������P��
����Ƃ������Ă����̂ł����A�l�Ԑ����Љ�I�펯������Ă����
�v���܂��B
�b��߂��āA
�������A�Ή����Ă��邩�ǂ����͖��ł͖����A���ʂ��L�邩��
���Ȃ�ł���ˁB�悭�ԂŃV���V�[��{���\���v�A�Ȏԗ��͐����
���Ƃ�����̂Ɠ����ŁA���䂪�����Ԃ��D��Ă����ł͖����A
��ΐ��\���C�ɂȂ�킯�ł��i�Ⴆ�������[���`�F���W���j�B
�����Y����U��@�\�t���̃����Y���I���ł���悤�ɂȂ��Ă���
�w���̂Ƃ��͊m���ȏ����Ə�����܂��E�E�E�B
�i�r�f�I�ł����ŋߍw������CanoniVIS HF M31 Powerd IS�͂ƂĂ�
�ǂ�������U���ł����B�]��300mm�����̂Ƃ��̐Î~���r
�ł��B�j
�����ԍ��F11042604
![]() 0�_
0�_
yle.ely����
> �������A�Ή����Ă��邩�ǂ����͖��ł͖����A���ʂ��L�邩��
> ���Ȃ�ł���ˁB
> �����Y����U��@�\�t���̃����Y���I���ł���悤�ɂȂ��Ă���
> �w���̂Ƃ��͊m���ȏ����Ə�����܂��E�E�E�B
�X���傳��̏��Ƃ��ẮA�X���傳��̂悤�Ȋ����ȃz�[���f�B���O��
�ł�����ŁA�p�x�u���ł͂Ȃ��ʒu�u���������Ȃ��ɂ����āASR�̕��
���̕���@�����D�G���A�Ƃ������Ƃł��ˁB
�܂��ʂ̐l�ɂ͑S���Q�l�ɂ͂Ȃ�܂���B
�X����|�ɉ����Ă����Ɗ��z�������Ă�������A���������u�ǂ��v�`
�u���܂�ς��Ȃ��v�u�킩��Ȃ��v�Ƃ����ӌ��̂悤�ł��B
��Ԃ��̌��ʂɂ��ẮA�l�Ԃ̊��o�Ƃ��Ĕ����ȗD�������̂�
����ƂƎv���܂����A�܂�͗L�v�ȏ������Ƃ����̂����Ȃ�
�̂ł͂Ȃ��ł��傤�����B
�P�i���̕�ƂT�i���̕�́A���炩�ɈႢ������Ǝv���܂����A
������ȑO�ɁA�J�^���O���l�ł��������������������ł��ˁB
�����ԍ��F11048580
![]() 1�_
1�_
��������ƏC���ł�
> �X���傳��̂悤�Ȋ����ȃz�[���f�B���O���ł�����ŁA�p�x�u���ł͂Ȃ�
> �ʒu�u���������Ȃ��ɂ����āASR�̕��
> �X���傳��̂悤�Ȋ����ȃz�[���f�B���O���ł�����ŁA�p�x�u���ł͂Ȃ�
> �ʒu�u���������Ȃ��A���������P�{���x���̃u���ɂ����āASR�̕��
�����ԍ��F11048594
![]() 1�_
1�_
��������������
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�ߓǂ݂ł����Ɠǂ̂ł����A������ƊԈ��������
���������ȁE�E�E�B
---
�X���傳��̏��Ƃ��ẮA�X���傳��̂悤�Ȋ����ȃz�[���f�B���O��
�ł�����ŁA�p�x�u���ł͂Ȃ��ʒu�u���������Ȃ��A���������P�{���x��
�̃u���ɂ����āASR�̕�����̕���@�����D�G���A�Ƃ������Ƃł��ˁB
---
���́A�S�����ł͎��s�ł��܂���B�������ߌi�ł���ˁB�}�N���ƌ����Ă��ǂ�
�ł���ˁB����{�̐U��i0.5mm���炢�H�j�Ȃ�āA�����܂���E�E�E�B
�ǂ�������܂����B���̓��e�ł͎������҂��Ă����ʓI�ȕ�̘b�ł͂Ȃ��A
�~�N���̐��E�̘b�ł��ˁB�������`�c�O�B�ꉞIS�̘b���o�Ă����̂ŁA���Ƃ�
�������������r�f�I�̘b���������ǁA���Ӗ��ȃR�����g�ł����E�E�E(^^;)
�����ԍ��F11051162
![]() 0�_
0�_
yle.ely����
���������A���Ӗ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��ł���B
�����͑����̐l���݂Ă���悤�ł����AK-7��X�`���J�����Ƃ������ƂƂ�
�W�Ȃ��Ɂu��Ԃ��v�Ƃ����L�[���[�h�œǂސl���������Ƃł��傤�B
Powerd IS�ɂ��Ă͎������ׂĂ݂��̂ł����A�r�f�I�J�������@�
�o�Ă�����(���ۍ��̉�ꂻ��������)�A�܂���Ƀ`�F�b�N���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
���icom�ł�Powerd IS�̓��W�ڂ��Ă܂����ǁA�m���ɋ��͂����ł��B
�Ƃ������킯�ŁA���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͗L�v�ȏ��ł��B
���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F11051286
![]() 0�_
0�_
�V�t�g�u���ƃ��[�������̃u���̕���s���u5����u����v�̃f�W�J�������i������܂����B
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_0367.html
�������A�ǂ�������́u���}���`�t���[���Z�p�v��p�����A�����Ȃ�Γd�q����u����̂悤�ł��B
���A���B�e�����������̉摜��p���āA1���̍����摜������Z�p�B
���w���̎�u����͏]���ʂ�u�p�������v�Ɓu�e�B���g�����v�̊p�x�u�����Ƃ������Ƃł��傤�B
�����܂ł��Ȃ�u�R���e�B�j���A�XAF�v�Ƒg�ݍ��킹�āu6����u����v���ď̂����Ⴆ�����̂ɁA���Ď��Ȃ͎v���܂��B
�����ԍ��F11061369
![]() 1�_
1�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z����p�\�R��2025
-
�y���̑��zAMD �x�A�{�[��
-
�yMy�R���N�V�����z���C���@����
-
�yMy�R���N�V�����z���ꔃ�����Ⴈ������〜
-
�y�~�������̃��X�g�z����Mini-ITX�@����PC�P�[�X�ɍ��ꂻ��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h
- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j