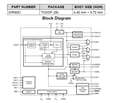HAP-Z1ES
1TB HDD����������n�C���]�Ή��I�[�f�B�I�v���[���[
�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� ���i���ڃO���t
HAP-Z1ESSONY
�ň����i(�ō�)�F�V���b�v���̔����i���f�ڂ���܂ł��҂��������� �������F2013�N10��26��
���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S183�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 755 | 200 | 2018�N5��13�� 22:27 | |
| 2 | 2 | 2018�N5��4�� 20:50 | |
| 853 | 200 | 2018�N4��30�� 14:14 | |
| 908 | 200 | 2018�N4��15�� 19:13 | |
| 3 | 20 | 2018�N4��15�� 15:53 | |
| 21 | 14 | 2018�N4��10�� 14:01 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
HAP-Z1ES�������ɂ��w�����悤�ƍl���Ă���҂ł����A�w���ɓ������āA�O�t��BD�h���C�u�������ɍw�����ׂ��������Ă��܂��B
�Ƃ����̂́A�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���L�q���l�b�g��ɎU������邩��ł��B�������ꂪ�{���Ȃ�A�gCD���ڃ��b�s���O�h�̂��߂̊O�t���h���C�u���w�����܂��B
�������A���̈���Łu�o�C�i������v����Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N����Đ����āA���Œ����Ă킩��قlj������قȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��v�Ƃ���ӌ�������܂��B���������炪�{���Ȃ�A�����dBpoweramp����PC���b�s���O���ɍs�����߂̃\�t�g���w�����܂��B
�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H
���������܂�����A���̌��ʁA�ǂ���̉������ǂ��������A���邢�͕ς��Ȃ����������A�����Ă������������Ƒ����܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21724280/�iPart 1�j
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21754288/�iPart 2�j
����̑����ł��B
![]() 4�_
4�_
Symbolist_K����A�����l�ł��B
�W�b�^�Ɋւ��闝���͐[�܂����ł��傤���H
�W�b�^�����҂��ƍl����l���������A���ۂɏ��������g�ɐ����g�W�b�^��t�����������Ă݂��
�r�u���[�g�ł���A���y��S�n�悭����v�f�ł���͂��Ȃ�ȁB
����ŁA�O�X���̍Ō�̕��ŁA
���̕ӂŁA�p�C�������y��wav�t�@�C����1/f��炬��t������ȒP�ȕ��@���Љ�Ă��ꂽ��A
���������ǁB
�Ə������B���y��wav�t�@�C������1/f��炬�𒊏o����c�[����������l�̃T�C�g�ɁA�ȉ��̐���������B
http://mahoroba.logical-arts.jp/archives/80
�����ԍ��F21789328
![]() 3�_
3�_
�݂Ȃ��܁A�����́B
Symbolist_K����́A�O�X��[21789161]��
>�����Ƙ_����K�Ƀp���t���[�Y���Ă���Ȃ�Ƃ������A�������ɓs���̂������߂ł����������Ă��Ȃ��̂Łu���p�v�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
�����āA�O�X���ȂǂŘb���o�� AIT Labo �̃J�N�^������v���o���܂����i�����u���O�F�@http://aitlabo.net/blog/?c=003�@�j�B
�O�X���ȂǂŎQ�Ƃ��ꂽ��������̘_���@http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf�@�́A�����������u�N���b�N�W�b�^�[�͎����㉹���ɉe����^���Ă��Ȃ��v�Ƃ�����|���Ǝv���܂����A������J�N�^�����p����Ă���͕̂s���A�Ӗ����킩���Ă��Ȃ���Ȃ��́A�Ƃ���^���܂����A����͒u���Ă����āA��L�u���O���́u�����ω����m���v�̍���
>�u��������w�����_�WVol.7 No.2, pp.79-92�i2004�j
>�f�B�W�^���E�I�[�f�B�I�@��ɂ�����T���v�����O�E�W�b�^�[�̏��l���Ƃ��̗v���v�@�@�ɂ�
>�u�����̕ω��ׂĂ��邪�A�������ʂɂ��ē��v�I������s�������ʁA�U��80ps�̃W�b�^�[�̗L�����A�팱�҂͗L�Ӎ�����ŕ����������v�ƌ����L�ڂ�����A
�Ƃ����L�q������܂��B����́A�_�����p�̂������Ƃ��Ċ��S�Ƀ��[���ᔽ�ł��B�{�X���̎Q���҂ł�������ɈӖ����킩��Ǝv���܂����A��L�u80ps�v�͓��{TI�Ԗx����̕ł���A��������̘_���͂���ɋ^�`��悷�闧�ꂾ����ł��B�u��c�����v�Ƃ������t������قǂ҂����肭��b���Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B��������L��������͘_���ւ̃����N�������Ă��炸�A�ǎ҂Ƃ��Ă͊��S�Ƀ~�X���[�h���鑼�Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
�u���̐v�҂�DAC�������Ȃ��Ă���v�Ȃ�Ė��n�҂����܂������A���͂ƂĂ����������C�ɂ͂Ȃ�܂���i�l�̊��z�ł��j�B���ꂩ��A��L�L�q�̑O��
>�W�b�^�[�������ɉe�����錟�m���́A�]�����e���琄������Ɩ�60ps�ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B
�Ƃ����L�q������A�{�X���ł����グ���Ă��܂������A��L�u�����v�̍��������ɂ͌������܂���ł����B�N���킩��܂����H
�����ԍ��F21789960
![]() 5�_
5�_
�p�C������
>�������ݔԍ�[21780079]�̃O���t�ł��傤���B
���̃O���t�ł��B
>�Ȃ̂ŁA�܂��͕ۑ��ꏊ�̈Ⴂ�Ƃ������A�W�b�^�[�ɑ�������ϒ��m�C�Y�������������ŁA�~���������A10ns�̃W�b�^�[�������郉���_���ϒ��m�C�Y���������Ƃ��ɁA�ǂ̒��x�A�����ɈႢ���o��̂����`�F�b�N���邽�߂ɍ�����̂��A�������ݔԍ��i21785503�j�̉����ɂȂ��Ă܂��B 
�@������̉����̇A�V���p���ƇB�V���p��+10ns���炢�̃����_���W�b�^�[�����̕ϒ��i�W���Y���y�j�Œ�����ׂ���悤�ɂȂ��Ă��܂����A��������ׂĂ���ƁA�s�A�m�̘a���̎c�������̋������̈Ⴂ�ʼn����̈Ⴂ���킩��悤�ȋC�������̂ł����A�ȏ��������_���Đ��ɂ��āA�u���C���h��ԂŐ�ւ��Ă��邤���ɁA�Ⴂ���킩���ĂȂ����ƂɋC�Â��܂����B 
�@�����������d�˂邤���ɍ����̂悤�ȏ�ԂɊׂ��Ă����̂������ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B 
�@�Z�C�E�`����Ȃ�A�A�ƇB�̈Ⴂ�͂����ɕ�������̂Ȃ̂ł��傤���B
�������ݔԍ��i21785503�j�̉����A�ƇB�̈Ⴂ
������܂���ł���××
DELA N1A��HDD��SSD�Ɋ����������̍��͂����Ƒ傫���āA�Î⊴�����������������̂ł����A������y���ɏ��������̗l�Ɋ����܂����B
�����ԍ��F21790583�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
��tohoho3����
�@�Ƃ肠����1/f��炬�肷��\�t�g������܂��B
https://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se406812.html
�@��炬��͌N�Ƃ����t���[�\�t�g���g����1/f�̎��g�������ɋ߂��M���Ńe�X�g���Ă݂܂����B�m�R�M���g�̐M�������傤��1/���̎��g�������ɂȂ��Ă���̂ŁA�M�����o�͂��āA��炬��������Ă݂܂����BwolframAlpha�ł̉����o�͂��ł��Ȃ������̂ŁAwavegene�ŏo�͂��Ă܂��B
�@���y�M����CD������wav�t�@�C���ŁA�h���b�v����Δ��肵�Ă���܂��B
�����ԍ��F21790591
![]() 4�_
4�_
��Symbolist_K����
������ƁA���̈��p�̓A�E�g����Ȃ��ł����B
��ǂ�ȉ��Ƃ������A�s�����x�����Ǝv���܂��B
�ȉ��ASymbolist_K����̏�������
>������̋L�q�ɂ���
http://www.ezto.info/stpress/2016/09/597.html
������̋L�q�̌��_��
����������ƁA�ŏI�I��DAC�`�b�v�ɓ��͂���uI2S��MCK�ABCK�ALRCK�̕i���������Ƃ��d�v�v�Ȃ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ�
�ł���A�A�������Ƃ��āA�Â��}���`�r�b�g�^DAC���g���悤�ȏꍇ�́A
��USB DDC�ADAC�iDAI�ADAC�`�b�v�j�S�Ă��X���[�u�i�Ǐ]���[�h�j�̃N���b�N�œ���
����̂ŁA
���ŏ㗬��USB�z�X�g�iPC�j���o�͂���USB�V�X�e���N���b�N�i�}�[�J�[�M���j�̕i������ѓ`���i���A�X�Ɋe�X�e�[�W�̃N���b�N�Ǐ]���\��W�b�^�[�����Ɉˑ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�Ƃ���܂��B
�ȉ�����
��������ƁA�ŏI�I��DAC�`�b�v�ɓ��͂���uI2S��MCK�ABCK�ALRCK�̕i���������Ƃ��d�v�v�Ȃ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����AUSB DDC�ADAC�iDAI�ADAC�`�b�v�j�S�Ă��X���[�u�i�Ǐ]���[�h�j�̃N���b�N�œ��삵���Ƃ���ƁA�ŏ㗬��USB�z�X�g�iPC�j���o�͂���USB�V�X�e���N���b�N�i�}�[�J�[�M���j�̕i������ѓ`���i���A�X�Ɋe�X�e�[�W�̃N���b�N�Ǐ]���\��W�b�^�[�����Ɉˑ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�܂��AUSB DDC���A�V���N���i�X���[�h�œ��삳�����Ƃ��Ă�S/PDIF�ȍ~�̐M���i���͒ʏ�������܂���B
���������AMinerva2000����̏������݂̎�|���u�N���b�N�W�b�^�[�͎����㉹���ɉe����^���Ă��Ȃ��v�Ƃ����_���ɑ��锽�Ȃ̂�����A�u�e��������v�Ƃ����u���O�����p�������_�Ŗ{���������Ă��܂���B
�������⎖�������Ă܂ŁA�c�_�ɏ��Ƃ��Ƃ��Ă܂���?
�����ԍ��F21790595�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
���l�̓Z�C�E�`����
�@�킴�킴�ǂ����ł��B
�@���̉����͕ʉ��y���m�C�Y����ɓ��ꂽ�̂ŁA�ϒ��ƌ����Ă��A�P�Ȃ�m�C�Y�Ɠ����ŁA�W�b�^�[�̂悤�ȏ����Ɉˑ����Ĕ�������m�C�Y�Ƃ͈Ⴄ�̂ŁA�����ȃz���C�g�m�C�Y�̂悤�ɒ������Ȃ���́A�e�����Ȃ��悤�ȏ�Ԃ��ƍl�����܂��B�Ȃ̂Ŏ��ۂɃW�b�^�[������������Ԃ��ʓI�Ɋm�F�ł��鉹������͂�K�v�Ȃ̂��Ȃƍl���Ă܂��B����ł͎v�����܂���B
�����ԍ��F21790610
![]() 3�_
3�_
�l�̓Z�C�E�`����
�S���̌�ǂł��B�ᔻ������O�ɋc�_���悭�ǂ�ł��������B�ǂ����炻��Ȕᔻ���o�Ă���̂ł����B����Minerva2000����̘_����ᔻ�����A�̓��e�̗����ǂ��������Ō���Ă��������B
�����������AMinerva2000����̏������݂̎�|���u�N���b�N�W�b�^�[�͎����㉹���ɉe����^���Ă��Ȃ��v�Ƃ����_���ɑ��锽�Ȃ̂�����A�u�e��������v�Ƃ����u���O�����p�������_�Ŗ{���������Ă��܂���B
�S�����̈��p�̈Ӑ}���킩���Ă���������Ȃ��B
�uMinerva2000����̏������݂̎�|���w�N���b�N�W�b�^�[�͎����㉹���ɉe����^���Ă��Ȃ��x�Ƃ����_���ɑ��锽�Ȃ̂�����v�Ƃ������́u�������݁v�͂������������ԍ����Ԃ̏������݂��w���Ă���̂ł����H
�������̓���̏������݂Ŕᔻ���Ă���̂́A�p�C������i [21787124] �j���u�����Ŗ��ɂȂ��Ă���̂́A���葤�̊O���N���b�N�ł͂Ȃ��A��M����DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g�����Ƃ��ɔ�������W�b�^�ɂ��ċc�_���Ă���̂Ō����Ⴂ�̓��e�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�v�Ə����ꂽ�̂ɑ��āAMinerva2000����i [21787256] �j���u�����Ⴂ�̓��e�ɂȂ��Ă͂���܂���BS/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A�`������Ă����N���b�N���g�p���܂��B�v�Ɣ��_���ꂽ����Minerva2000����̓���̌��������ł��B�i����́A���̏����ԍ� [21788258] �̘_���̕⋭�ł��B������͓ǂ܂�܂������H�j
������A��������ɑ��čĔ��_����ɂ́A�uS/PDIF�ł����Ă��A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v�Ƃ������Ƃ������悢�����ł��B
http://www.ezto.info/stpress/2016/09/597.html
�̌�����
����������ƁA�ŏI�I��DAC�`�b�v�ɓ��͂���uI2S��MCK�ABCK�ALRCK�̕i���������Ƃ��d�v�v�Ȃ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����AUSB DDC�ADAC�iDAI�ADAC�`�b�v�j�S�Ă��X���[�u�i�Ǐ]���[�h�j�̃N���b�N�œ��삵���Ƃ���ƁA�ŏ㗬��USB�z�X�g�iPC�j���o�͂���USB�V�X�e���N���b�N�i�}�[�J�[�M���j�̕i������ѓ`���i���A�X�Ɋe�X�e�[�W�̃N���b�N�Ǐ]���\��W�b�^�[�����Ɉˑ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�܂��AUSB DDC���A�V���N���i�X���[�h�œ��삳�����Ƃ��Ă�S/PDIF�ȍ~�̐M���i���͒ʏ�������܂���B
�́A�u��������ƁA�ŏI�I��DAC�`�b�v�ɓ��͂���uI2S��MCK�ABCK�ALRCK�̕i���������Ƃ��d�v�v�Ȃ��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��v�̕����ɉ����āA�uS/PDIF�ł����Ă��A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ������Ă���ł͂Ȃ��ł����B
�����āA����ȉ��́u�̂ł����AUSB DDC�ADAC�iDAI�ADAC�`�b�v�j�S�Ă��X���[�u�i�Ǐ]���[�h�j�̃N���b�N�œ��삵���Ƃ���ƁA�ŏ㗬��USB�z�X�g�iPC�j���o�͂���USB�V�X�e���N���b�N�i�}�[�J�[�M���j�̕i������ѓ`���i���A�X�Ɋe�X�e�[�W�̃N���b�N�Ǐ]���\��W�b�^�[�����Ɉˑ����邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��AUSB DDC���A�V���N���i�X���[�h�œ��삳�����Ƃ��Ă�S/PDIF�ȍ~�̐M���i���͒ʏ�������܂���B�v�̕����́A�Â��}���`�r�b�g��DAC���g�����肵�āuUSB DDC�ADAC�iDAI�ADAC�`�b�v�j�S�Ă��X���[�u�i�Ǐ]���[�h�j�̃N���b�N�œ��삵���v�ꍇ�ɑ���A�������ŊԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�����āA���Ƃ����̏ꍇ�ł������Ƃ��Ă��A�uS/PDIF�ł����Ă��A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���ƂɈႢ�͂���܂���B
�����ԍ��F21790731
![]() 7�_
7�_
�����̂���ȑO�̋L�q���ǂ̂ł����H
���Ō��DAC���u������S/PDIF���V�[�o�[〜DAC�`�b�v�Ԃ�I2S��Ԃł��B
I2S�Ɋ܂܂��MCK�i���DAC�`�b�v�̃V�X�e���N���b�N�j�ABCK�iPCM�f�[�^�̊e�r�b�g�^�C�~���O�N���b�N�j�ALRCK�i�T���v�����O���g���ƍ��E�̃`���l���w��N���b�N�j�̊e�N���b�N�̎g�����i�T�E���h�ɑ���e���x�����j�́ADAC�`�b�v�ɂ���đ傫���قȂ�܂��B
DAC��IC�`�b�v�̓A�i���O�M���ɕϊ�����Ō�̑f�q�ł����A�`�b�v�ɂ���ē����\���i��H�\���j���傫���قȂ邽�߂ł��B
�Ẫ}���`�r�b�g�^DAC�̓T���v�����O���g���̎����ŃT���v���z�[���h�����ւ��邱�Ƃŏo�͂܂��̂ŁA�N���b�N�̃^�C�~���O�Ƃ��Ă�LRCK�̕i�����d�v�ł��B
BCK��PCM�e�r�b�g��High/Low�肷��g���K�[�Ƃ��ċ@�\����悭�A�I�[�o�[�T���v�����O��f�W�^���t�B���^�[�Ȃǂ̕t���@�\���Ȃ����MCK�͂��������s�v�ł��B
�I�[�o�[�T���v�����O�@�\��f�W�^���t�B���^�[�𓋍ڂ��Ă�����A�������g����DAC�̏ꍇ�́A��荂�����g���œ��삷�邽��BCK��MCK����{/�������ė��p���܂��̂ŁABCK�AMCK�̐��m�����d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�܂�DAC�`�b�v�ɂ���Ă�SRC�i�T���v�����O���[�g�R���o�[�^�[�j�𓋍ڂ��Ă��āABCK�ALRCK�ADATA��3�_�Z�b�g�Ƃ͔���MCK����͂����MCK�̃N���b�N���g���ɍ��킹�ăT���v�����O���[�g��ϊ�����DAC�`�b�v�ȑO�Ŕ�������W�b�^�[�̉e����r������B�Ƃ������@�\��������̂�����܂��B
���̏ꍇMCK�̕i�����ƂĂ��d�v�ɂȂ��Ă��܂����A�ׂ���������BCK�ALRCK��SRC��PLL������y�����������W�b�^�[���������ł���̂�BCK�ALRCK��������x�ȏ�̕i���͕K�v�ł��B
�X�ɁA���͂��ꂽMCK����BCK�ALRCK���A�o�͂ł���DAC�`�b�v������ADAC�`�b�v�����������N���b�N�ɍ��킹�ăf�[�^���o�͂��Ă��炦��ADAC�`�b�v�ɓ��͂���MCK�̕i���ɒ��͂���悢���ƂɂȂ�܂��B
���͂��̋L�q�ƁAEDN�͍̉��_���́u���݂̃I�[�f�B�I�pDAC�f�o�C�X��ϊ������̊ϓ_�Ō���ƁA���̂قƂ�ǂ̓����ϒ��������̗p���Ă���v�Ƃ��������Ă�g�ݍ��킹�āA���M���̃W�b�^�[�̉e����������x�傫���Â��}���`�r�b�g��DAC�ł����Ă��uS/PDIF���A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���ƂɈႢ�͂Ȃ����A���݂̃����ϒ�������DAC�ł͑��M���̃W�b�^�[�̉e���͑啔���r���ł���̂ŁA�Ȃ�����uS/PDIF���A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ��悭�킩��A�Ƃ����̂ł��B
����ŁA�uS/PDIF���A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��������̂ł����H
�܂����̂��� [21789055] �̏������݂́A���O�� [21788683] �̏������݂��Ă����⋭������̂ł���A�����ł͎���
�����������̂�������
����S/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A�`������Ă����N���b�N���g�p���܂��B
�������̂ł���B�u�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�v���uDAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����v�Ƃ����̂͊��S�Ȍ��ł͂Ȃ��ł����A�Ԗx�_���ɏƂ炵�Ă��B�ǂ����āu�`���H�o�R�̃N���b�N�̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v���Ƃɂ���āA�u�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N��DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ��ے�ł���̂ł����H �_�����j�]���Ă��܂��B
�Əq�ׂĂ��܂��B
���̗��ꂩ����A���́uS/PDIF���A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ������悢�������Ƃ��킩��ɂȂ�܂��H
�������Ď��͂��́u���p�v�𐳓��ɗp���āA�uS/PDIF���A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă͂��܂��H�i���̂��ƂɁA���M���̃N���b�N�̉e����W�b�^�[�����݂��邱�Ƃ͊W�Ȃ��̂ł���j
����̂ǂ����u��ǂ�ȉ��Ƃ������A�s�����x���v�Ȃ̂ł����H
�u�{���������Ă��Ȃ��v�̂͂ǂ���ł����H
�l�̓Z�C�E�`�����A�u�������⎖�������Ă܂Łv�s����Minerva2000�����i�삳��Ă��܂����A���̈Ӑ}�͉��ł����H
�����ԍ��F21790735
![]() 7�_
7�_
�p�C������A�L��������܂��B
��{�g���g�������ɒႭ�A�U���������Ȃ̂�����g��wav�t�@�C�����쐬���āA���y��wav�t�@�C���ɉ��Z����A
1/f�h�炬���lj������̂��ȁH���邢�͎��ԕ��ς�1�ɂȂ�悤�Ȃ̂�����g���쐬���ď�Z����̂��ȁH
���Ԃ�����Ύ����Ă݂܂��B
�����ԍ��F21790849
![]() 3�_
3�_
�Ƃ肠�����AWavegene��0.1Hz�̎O�p�g���쐬���āi�̂�����g���Ɣg�`�̕s�A���_�ő傫�ȃm�C�Y������̂Łj�A
�t���X�P�[����-6dB�̐U���ɂ��āA���y�t�@�C���ɉ��Z�������̂�ɂ��Ă݂��B
https://www.youtube.com/watch?v=86ZUeweqZBE&feature=youtu.be
�t���X�P�[����-6dB�͂��Ȃ�傫�Ȃ�炬�����ǁA�قƂ�nj��̉����̉����Ȃ�Ȃ��ȁB
�����ԍ��F21791101
![]() 3�_
3�_
tohoho3����A�����l�ł��B
�O�X���ł́A���낢��Ƃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂����B
�u1/f��炬�v�͖ʔ����ł��ˁB
http://mahoroba.logical-arts.jp/archives/80
���Љ�̂�����̕��̃u���O�͑�ϋ����[���A�p���p���Ǝ蓖���莟��ǂ�ł݂܂����B
�i�����A���̃y�[�W�ɓ\���Ă����ď��������̑Βk�ɔ�Ԃ͂��̃����N�������ƁA�ؓ������܂̃y�[�W�ɔ�����̂ŁA�n�b�N����Ă���悤�ł����j
�u���y�̂�炬�̐��̂Ƃ́A���g���ƐU���̂�炬�������̂ł��v
�Ƃ������ƂŁA�l�X�ȉ��y���u1/f��炬�v�̊ϓ_���番�͂��Ă���y�[�W�����Ɏh���I�ł����B
�ihttp://mahoroba.logical-arts.jp/archives/86�j
�x�[�g�[���F���́w�����x�̑��y�͂́u��r�I�N���̏��Ȃ��ȂȂ̂Ńɂ͂����Ƒ傫�߂ɂȂ�Ɨ\�z���܂������A�ӊO�Ȍ��ʂł����B�������˂�͌����܂����A�S�̓I�ɂ͂ق�1/f��炬�ɂȂ��Ă��܂��B�������ɖ��Ȃƌ����邾���̂��Ƃ͂���܂��B�v
�V���p���́w�p�Y�x�́u���̖��̒ʂ���ɗE�s�ȋȂŋN���ɕx��ł��܂��B�X�y�N�g���͂قڒ������z�ɂȂ��Ă���A�ɂ�1�ɋ߂��l�������Ă��܂��B�������̓V���p���̖��Ȃł��B�v
���t�}�j�m�t�̃s�A�m���t�ȑ�Q�Ԃ̑��y�͂́u�܂�ʼnf�批�y���v�킹��Ô��ȃ����f�B�[�Œm���Ă��܂��B�ɂ͎�傫�߂ł����A�X�y�N�g���̕��z�͂�������Ȃ����ɂ��ꂢ�Ȓ����ɂȂ��Ă��܂��B������\��1/f��炬�ƌ����Ă悢�Ǝv���܂��B�v
�u���b�N�i�[�̌����ȑ�W�Ԃ̑�l�y�͂́u�厩�R���v�킹��s��Ȍ����ȂŒm����u���b�N�i�[�̍ō�����ł��B���ł����̑�l�y�͂ɂ��ׂẴG�b�Z���X���l�܂��Ă���悤�Ɏv���܂��B�X�y�N�g���͔��ɂ��ꂢ�Ȓ������z�������Ă��܂����A�ɂ͎�傫�߂ɂȂ��Ă��܂��B�m���ɖ��������Ƃ���������������܂���B������0.05Hz������g���̌X���������ɂ��̂ŁA�S�̓I�Ɍ����1/f��炬�ɋ߂��̂�������܂���B�v
�ǂ����u�N���ɕx�ށv�A�u�s��ȁv�A�u�厩�R���v�킹��v�悤�ȉ��y�Ɂu1/f��炬�v������悤�ł��B
���̕���������u��炬�A�i���C�U�[�v�Ƃ����\�t�g������܂��ˁB
http://mahoroba.logical-arts.jp/archives/1299
���Ȃ݂ɁA��������݂����D���Ȃ̂ł����H
�����ԍ��F21792031
![]() 3�_
3�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
AIT Labo�p�c����́A�����̍��DAC�̉����u�����Ȃ��v�����ł���B
�ނ́u���_�I�ɐ������A�v���[�`�Ő������v���Ă���A���i�̎��͉����ɂ͑傫�ȉe���͂Ȃ��v�Ƃ����g���O�h��DAC�����A�����̐v�ɐ��Ȏ��M������̂Łu�����Ȃ��Ă��悢�v�炵���ł��B
���ۂ̉��́u���������v�Łu�_�o���v�������ŁA�uAIT�̓I�[�f�B�I���i����Ȃ��čH�Ɛ��i�v�Ƃ����]������܂����B�������A�ނ́g���O�h�ɐS�����Ă���l�ɂ́u���������ȉ��������œ����ʂ��������Ǝv���邵�A�_�o���ȉ����@�ׂŏ_�炩���Ɗ�������v�����ł��B
�ihttps://2ch.live/cache/view/pav/1481457684�j
�܂��A�Q�����˂�ŏE�����b�Ȃ̂ŁA����ł����B
�{���Ɂu�����̐v�ɐ��Ȏ��M������v���䂦�Ɂu�����Ă��Ȃ��v�̂��Ƃ�����A����܂蔃�������͂Ȃ��ł��ˁB
�����āA���́u�v�v�̗��_�I���t�������u���O�ɁA�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̂��w�E�́A���̂悤�ȁu��c�����v�Ș_�����p������悤�Ȏv�l�Ȃ̂ł�����B����Łu�����Ȃ��Ă��悢�v�ƌ����Ă��B
�u�_�����p�v�ƌ����A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̏������݂Ɏg�t���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��l�ɁA�Ƃ�ł��Ȃ����e������āA���R�Ƃ��܂����B
���͂����Əo�T�����āA���p���ꎚ���ς����肹���A�����킩��₷�悤�ɕ������������ĉ���������Ȃ�����p������A�u�s���v�ƌ����Č��t�������܂�����B
���̐l�͑O�X���ŖY��悤�ɂ��������Ȃ�����̐������u�ϑz�v�ƌ��߂����l�ł����A��قǁu�f�W�^���P�[�u���̈Ⴂ�ʼn������ς��v���Ƃ������̂����D���炵���AMinerva2000����̗�́u���P�[�u���ɂ�錟�v���C�ɓ����Ă��܂��āA�u���̌��ɂ���ē�������̘_�������ł��邱�Ƃ��킩��v�Ƃ���Minerva2000����̎咣��M���邠�܂�A�uMinerva2000����̏������݂̎�|���w�N���b�N�W�b�^�[�͎����㉹���ɉe����^���Ă��Ȃ��x�Ƃ����_���ɑ��锽�Ȃ̂�����A�w�e��������x�Ƃ����u���O�����p�������_�Ŗ{���������Ă��܂���B�v�ȂǂƑS�������Ⴂ�̂�������x���̎w�e�����Ă����̂ł����A�Ȃɂ��ǂ��u�s���v�Ȃ̂��H �����炭�u�s���v�̈Ӗ������킩���Ă��Ȃ��悤�ł��B
�u���P�[�u���ɂ�錟�v�Łu��������̘_�������ł��邱�Ƃ��킩��v�Ȃ�ĕ��т��̂ł���ˁB���҂ɂ͘_���I�֘A������Ȃ��̂ɁB����Ɂu���P�[�u���ɂ�錟�v�Łu��������̘_�������ł��邱�Ƃ��킩��v�Ƃ����u�����v��ᔻ����̂������Ȃ��̂Ȃ�A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����ɑ��Ă�������������ׂ��Ȃ̂ɁA���ɍ~�肩�����Ă��Ă������f�ł���(��)
�����ԍ��F21792129
![]() 4�_
4�_
�Z�C�E�`����A����ɂ��́B�i�u�l�́v������ƕ����ǂ݂ɂ����̂ŁA�Z�C�E�`����Ŏ��炵�܂��j
�Z�C�E�`����ɂ₳�����������������ł��BSymbolist_K����͋߂��낿����ƃR�����ł���(��)�A���͑��v�ł��B�Z�C�E�`����͂����ς�X�}�[�g�t�H���T�C�g���珑�����܂�Ă���̂ŁA��ʂ̕��͂���Ղ��ė�������ނ̂���������m��܂���ˁBSymbolist_K����̒�����PC�ł����\��V�ł�(��)�B�ȉ�Symbolist_K����Ƃ�����Ƃ��Ԃ邩���m��܂��B�Z�C�E�`�����
>�u�e��������v�Ƃ����u���O�����p�������_�Ŗ{���������Ă��܂���B
��Symbolist_K�����ᔻ����Ă���킯�ł����AMinerva2000�����[21787256]��
>S/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A
�Ə�����Ă��܂��B����������́A���Ȃ��Ƃ��������g����DAC�ł͂������Ɍ��ł��B���̂��Ƃ́A���������u�w�e��������x�Ƃ����u���O�v������킩��܂�����A�Z�C�E�`����̏�L�ᔻ�͓�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�E�E�E�Ƃ������̈ӌ��ɂ��āA�Z�C�E�`����͂ǂ����l���ł��傤���H���̔��f�Ɍ�肪����Αf���ɂ��������܂����A�t�ɂ������Ɍ�肪����i�Ǝv���悤�ɂȂ����j�Ȃ�A���̂悤�Ɍ����Ă���������ƍK���ł��B�łȂ��ƁA�Z�C�E�`����Ƃ́u���������l�v�ł���A�Ɣ��f������܂���B
�܂��A[21788867]�ŏ������悤�ɁA�����Minerva2000����ɂ���Đ������ꂽ���ʂȋc�_�Ȃ̂ŁA����l�̋M�d�ȘJ�͂͂��Г��{�o�ς̂��߂Ɍ��ݓI�Ɏg���Ă������������Ɗ肤����ł��B
�����ԍ��F21792201
![]() 6�_
6�_
��Symbolist_K����
���āA�N�C�Y�ł��B
DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�͂ǂ��ɂ����Ăǂ��ɂȂ����Ă���Ǝv���܂����H
S/PDIF���V�[�o�[--I2S--DAC�`�b�v
�̍\���ŁA
�P�DDAC�`�b�v�̒��ɂ����āADAC�ɂȂ����Ă���B
�Q�DS/PDIF���V�[�o�[�̒��ɂ����āA���̓����̂ǂ����ɂȂ����Ă���B
�R�DDAC�`�b�v�̊O�ɂ����āADAC�`�b�v�ɂȂ����Ă���B
�S�DS/PDIF���V�[�o�[�̊O�ɂ����āAS/PDIF���V�[�o�[�ɂȂ����Ă���B
�T�DI2S�̋߂��ɂ����āAI2S���番�ĂȂ����Ă���B
�������̃u���O�ɂ́uI2S�Ɋ܂܂��MCK�i���DAC�`�b�v�̃V�X�e���N���b�N�j�v�Ƃ����L�q�͂���܂����A�uDAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�v�Ƃ̋L�q�������A�������ǂ��ɂ����Ăǂ��ɂȂ����Ă��邩�̋L�q������܂���B
�uI2S�Ɋ܂܂��MCK�v��S/PDIF�o�R�ŋ��������N���b�N���x�[�X�Ƃ̉��߂����サ�Ă��܂��B�Ƃ����̂̓u���O�ɂ͉��L�̋L�q�����邩��ł��B
--------------------------------------------
S/PDIF���V�[�o�[�iDAI�j�̓v���A���u���M���𒊏o����PLL��H�ŃT���v�����O���g�����Č����A��������DAC�ɓn��I2S��LRCK�ABCK�AMCK�Ȃǂ����܂��B
--------------------------------------------
�v���A���u���M���𒊏o����PLL��H�ŃT���v�����O���g�����Č����A��������DAC�ɓn��I2S��MCK������̂ł���AMCK��S/PDIF�o�R�ŋ��������N���b�N���x�[�X�Ƃ����l����ꂸ�ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�\�̏o�Ԃ͂���܂���B
�v���A���u���M�����o��PLL�̈Ӗ����������Ă�����́A�N���b�N�W�F�l���[�^�͖��W�Ƃ���������܂��B���ꂪ��b�m���������ƌ���Ɍ�����d�˂Ă��܂��A�Ǝ������������Ă��闝�R�ł��B
���̃u���O���e�ł́uS/PDIF�ł�DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���̂��I�I�v�Ǝ咣����鍪���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�Ƃ��������̃u���O�ɂ��A���̎咣�����������Ƃ����t�����܂����B
�����ƃf�W�^���I�[�f�C�I�Z�p�ɑa���f�l�̏������c�t�ȃu���O��T���Ă��������B�łȂ��Ƃ��܂ł����Ă����_�ł��Ȃ��ǂ��납�A���̎咣�𗠕t���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂���B
�����Ƃ��A�ǂ̃u���O���c�t�Ŏg���āA�ǂ̃u���O���g���Ȃ��܂Ƃ��ȃu���O���A�̔��f������̂悤�Ƀ~�X���āA��s���ɑ����Ă��܂��̂��A�炢�Ƃ���ł����B
���Ȃ݂ɂ��̃u���O�ł����u�����I�ȃ^�C�~���O�̕ϓ��i�����I�ȃW�b�^�[�j�͂��̎��g���ŃA�i���O�o�͂�ϒ����Ă���̂Ɠ����ŁA���E�t���b�^�[�Ǝ����悤�Ȃ��̂ł��v�Ƃ��āA������ƊԈ���Ă���Ƃ��������܂��̂ŁA�S����^�ɎĂ͂����܂���B
PS;�����ĐX�������A�Ƃ��������������Y�o�b�Ɩ{�������S�ɔc�����ď������݂��ł���l�̓Z�C�E�`����̂悤�ȕ��������Ƃ͋�����������Ɠ����Ɋ����������܂����B
�����炭�Z�C�E�`����̐����������ł����A�}�t���߂����Ă��܂��l���قƂ�ǂł��傤�ˁB
�����ԍ��F21792428
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����A
>���Ȃ݂ɁA��������݂����D���Ȃ̂ł����H
��������݂̂��̋Ȃ����D�����ȁB�K���ɑI�����������ŁA�p�C������Љ�́u��炬��͂���v
�g���āA�O�p�g��炬�����Z����O�̌��̃t�@�C��������͂��Ă݂���A�u��炬�ߏ�v����
�������̂ŁA�I�����������������B�ꉞ�A�O�p�g��炬�̉��Z�ł�炬�̐��l�͑����Ă邯�ǁB
�����ԍ��F21792445
![]() 3�_
3�_
�l�̓Z�C�E�`����
����Ԃ�ꔄ�����Ƃ���͂��̖Y��悤�ɂ��������Ȃ������D�����̂ŁA�Ȃ��������������h�����̂�����̂ł����A�����҂��X����Ƃ��Ă͂ǂ����Ă�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B�i�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����Ɏw�E�����܂Ŗl�̓Z�C�E�`�����X�}�[�g�t�H�����炱����̃X���b�h�ɃA�N�Z�X����Ă��邱�ƂɋC�����܂���ł������A���Ƃ��X�}�[�g�t�H������A�N�Z�X���Ă��邩��Ƃ����āA�X���b�h�ɎQ�����Ă���ȏ�͂����������ɂ��ė~�����͂���܂���B�j
�l�̓Z�C�E�`����́A���́u���p�v���u�s�����x���v�Łu�A�E�g�v�ł���Ƃ�������Ӗ�����������e������܂����B�������A���́u���p�̎d���v�ɋ^�`������̂Ȃ�A�܂����ɂ��̐^�ӂ�₤�āA���̋^���ɑÓ��������邩�m�F����ׂ��ł͂���܂��H ������̂��ɁA�^�ɑÓ����Ǝv���ď��߂āA���̂悤�Ȉ�厖���ƌ����悤�ȋ������q�̋��e������̂��Ƃ������̂ł͂���܂��H ������A�����Ȃ�A�܂����������̈Ⴄ�Ƃ���Ɉˋ����Ȃ��炵�������̍������������ɁA�����u�s���v�A�u�A�E�g�v�ƌ����y�Ԃ̂͏�O���킵�Ă���Ǝv���܂��B�Ȃ��Ȃ�A�����ɂ͂����������̔F�����Ԉ���Ă�����ǂ��Ȃ�̂��Ƃ����\������،����Ă��邩��ł��B�u�X���b�h�̍�@�v�Ƃ��ẮA���Ȃ��̕����A�E�g�ł͂���܂��H
������ƍl���Ă݂Ă��������B�Ⴆ�A���̃X���b�h�͍���n�܂�������ł��̂ŁA�O�X���̓��e��m�炸�ɂ��̃X���b�h����ǂݎn�߂�l�X�����邩������܂���B����A���̃X���b�h�́A���̋@��Ɋւ���u�N�`�R�~�v�̃X���b�h���X�g�̍ŏ�i�ɂ���܂��̂ŁA�����������X�͕��ʂɂ���������ł��傤�B���̕��X���A�O�X���̓��e��m�炸�ɖl�̓Z�C�E�`����̏������݂̂��̋������q�̋��e��ǂ�ŁA�X����̎��ɑ��Ă����̂Ȃ��Ό��������Ă��܂��A�h�����āA�Q������͂����������̃X�����狎���Ă��܂����Ƃ�����A�l�̓Z�C�E�`����̐ӔC�͏d��ł͂���܂��H �����āA�������l�̓Z�C�E�`���Ԉ���Ă����Ȃ�A���̐ӔC���ǂ���邨����Ȃ̂ł����H
�J��Ԃ��܂����A���Ƃ�Minerva2000����̂Ƃ��鏑�����݂̎�|���u�N���b�N�W�b�^�[�͎����㉹���ɉe����^���Ă��Ȃ��v�Ƃ����_���ɑ��锽�ł������Ƃ��Ă��A���̑O�X���� [21789055] �̏������݂͂���Ƃ͒��ڊW�͂Ȃ��̂ł���B
���� [21789055] �́AMinerva2000���� [21787256] �ɉ����āuS/PDIF�ł́A�I�[�f�B�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A�`������Ă����N���b�N���g�p���܂��B�v�ƌ���ꂽ���Ƃɑ��Ă̔��_�ł��B
�܂����͂��ł�Minerva2000����� [21787256] �ɂ� [21788258] �Ō��t��s�����Ĕ��_���Ă���̂ł����A����ɑ��āAMinerva2000���� [21788379] �Łu��������ɂ�������Ԃɗ�����ƁA�����������̌���������e�ؐS�͎����Ă��܂��܂��B�v�Ɩ�O���������u��_�����ADIR�ł�PLL�ł��`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���B�v�ƌ����ꌾ�Ŏ��̒����� [21788258] ��ے肳�ꂽ���̌��t�ɑ��Ă̔��_�ł��B
����䂦�A���́uS/PDIF�ł��A�I�[�f�B�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ������悩���������Ȃ̂ł��B����ɂ����Minerva2000����́uS/PDIF�ł́A�I�[�f�B�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A�`������Ă����N���b�N���g�p���܂��B�v���ł��܂����A���̔����ɑ���Minerva2000����́uDIR�ł�PLL�ł��`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���B�v�Ƃ����Ĕ��_�����_�Ƃ��ĈӖ��������Ȃ����Ƃ�������̂ł��B�u�I�[�f�B�I�Đ��N���b�N��DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃɑ��āu�`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���i�������ĒǏ]���Ă���j�A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ͊W�Ȃ�����ł��B�Ƃ����̂��A�u�X���[�u�Ƃ��āi�Ǐ]���[�h�ŁjDAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ́uDAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃɑ��Ȃ�Ȃ�����ł��B
���̂��߂Ɏ���
http://www.ezto.info/stpress/2016/09/597.html
�̃u���O�̋L�q���g�킹�Ă����������̂ŁA���������Ӑ}�����m�ɂȂ�悤�Ɍ��������������Ă�������������}�݂��̌��������p���܂������A�������͈̂ꎚ���ς��Ă��܂���B�܂��}�����������������āu��c�����v�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ́A���p�̒��O�̌��������ׂēǂ�ł���������Ζ������Ǝv���܂��B�܂�A���̃u���O�̋L�q�ɂ���āA�uS/PDIF�ł��A�I�[�f�B�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v�Ƃ������Ƃ͌�������̂ł��B����͌Â��}���`�r�b�g�^��DAC���X���[�u�i�Ǐ]���[�h�j�̃N���b�N�œ��삵���Ƃ��Ă��A���݂̃����ϒ�������DAC�����M���̃W�b�^�[�̉e����啔���������Ă��Ă��A�������ƂȂ̂ł��B�u�Ǐ]���[�h��DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v�Ƃ��ɑ��M���̃W�b�^�[�����ꏭ�Ȃ���`�B����Ă��܂����Ƃ́A���̍ۂǂ��ł������̂ł��B���̃u���O�̋L�q�ɂ���āA���Ȃ��Ƃ��uS/PDIF�ł��A�I�[�f�B�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���Ă���v���Ƃ͊m�F�ł��邵�A���Ƃ���A���̂��߂ɂ������̈��p�ɂ�������������܂��B
����ɑ��āA���̈��p�̂ǂ����Ȃ��u�s���v�Ȃ̂��A�S�������������Đ������邱�Ƃ��Ȃ��A�������߂��āu�A�E�g�v�Ɛ鍐����Ȃ�āA�ǂ��l���Ă��s���߂����Ƃ͎v���܂��H
�悭�l���Ă݂āA�����������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21792457
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����
������
>�uMinerva2000����̏������݂̎�|���w�N���b�N�W�b�^�[�͎����㉹���ɉe����^���Ă��Ȃ��x�Ƃ����_���ɑ��锽�Ȃ̂�����v�Ƃ������́u�������݁v�͂������������ԍ����Ԃ̏������݂��w���Ă���̂ł����H 
�����ԍ��F21786361 �ł��B
�����炪�o���_�ɂȂ��āA�p�C������̏������݂�����܂��B
������肾�Ǝv���Ă���̂́A�X���傳�ȉ��̕���}���������ƂŁA�M�҂̈Ӑ}�Ƌt�̈Ӗ����������悤�Ƃ����_�ł��B
>�A�������Ƃ��āA�Â��}���`�r�b�g�^DAC���g���悤�ȏꍇ�́A
���̕��͂����ނ��ƂŁA�ȉ��̕��͂����݂�DAC�ł͓��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ����~�X���[�h��U�����̗l�ɂȂ��Ă��܂��B
>�X�Ɋe�X�e�[�W�̃N���b�N�Ǐ]���\��W�b�^�[�����Ɉˑ����邱�ƂɂȂ�܂��B 
�܂��AUSB DDC���A�V���N���i�X���[�h�œ��삳�����Ƃ��Ă�S/PDIF�ȍ~�̐M���i���͒ʏ�������܂���B 
�������A�����̈ȉ��̕\���͊m���ɂ�����ƕς�������Ȃ��ł��ˁB
>I2S�Ɋ܂܂��MCK�i���DAC�`�b�v�̃V�X�e���N���b�N�j
���m�ɂ́uSPDIF�M�����̃N���b�N����������DIR(PLL)�Ő������ꂽ�N���b�N�M���v�Ƃ���Ȋ����ɂȂ�Ǝv���܂��B
SPDIF�̏ꍇ�A����葤(���̏ꍇDDC)�Ɠ���������K�v������̂ŁA�ʏ��DAC���̃N���b�N���g�p�ł��܂���B
���ۂɎ����g�p���Ă���DAC(TEAC UD505�Aor UD503)�ɂ͍ŋߍ��ꂽ�����DAC�`�b�v�����ڂ���Ă��܂��B
�܂��A�O���N���b�N(DAC�����̃N���b�N�ɑウ��)���g����̂ł����A���ł���USB�ɑ��Ă͗L���ł��A���������Ȃ���Ȃ�Ȃ�SPDIF�ɑ��Ă͎g�p�ł��܂���B
ESOTERIC��DAC�ł����SPDIF�ł��O���N���b�N���g����̂ł����A���̍ۂɂ͑���葤�ɂ������ɊO���N���b�N�����ē���������K�v������܂��B
SPDIF����Ŏg�p���邱�Ƃ��o����Ƃ͎v���܂����A�嗬�͓����̃^�C�v���Ǝv���܂��B
Minerva2000����̏������݂͐������Ǝv���܂��B
>Minerva2000�����i�삳��Ă��܂����A���̈Ӑ}�͉��ł����H 
Minerva2000�����i�삵�����Ƃ��������A�X���b�h����̃u���O�̈��p���ǂ��Ȃ��̂Œ����������Ƃ����v���������ł��B
��O�҂����ꓙ�̏������݂�ǂƂ��Ɏӂ��ė������Ă��܂�����h�������Ƃ����Ӑ}�ł��B
�X���傳��̂����W���m�Ƃ����T�O�ɂ��ʂ��邩�ƁB
�ܘ_�AMinerva2000����̏�����Ă��鎖�́A���̑̌��ƍ��v���܂����A��������w�̘_���͍��{�I�ɉ������Ԉ���Ă���Ǝv���܂��̂ŁA���̈ӌ����������݂����Ƃ����ӎv������܂����B
�����ԍ��F21792459�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
������
>S/PDIF�ł́A�I�[�f�C�I�Đ��N���b�N�́ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^���g���̂ł͖����A
�Ə�����Ă��܂��B����������́A���Ȃ��Ƃ��������g����DAC�ł͂������Ɍ��ł��B
����́A������o�T�͗L��܂���?
���̎g�p���Ă���DAC�������̂͂��ł����ASPDIF�͓������ō쓮���܂��̂ŁADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�͎g���Ă��܂���B
�����ԍ��F21792489�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�l�̓Z�C�E�`����
>����́A������o�T�͗L��܂���?
>���̎g�p���Ă���DAC�������̂͂��ł����ASPDIF�͓������ō쓮���܂��̂ŁADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�͎g���Ă��܂���B
���̃u���O��
>�������g����DAC�̏ꍇ�́A��荂�����g���œ��삷�邽��BCK��MCK����{/�������ė��p���܂�
�Ƃ���܂��B�Ƃ������Ƃ́uBCK��MCK����{/�����v���邽�߂̃N���b�N�W�F�l���[�^�[���K�v�ł��ˁB�Ƃ������A��������MCK������N���b�N�W�F�l���[�^�[���K�v�ł��ˁB�������ł��傤���B�Ȃ�����́A�uSPDIF�͓������ō쓮���܂��v�Ɩ������܂���B
�����ԍ��F21792616
![]() 4�_
4�_
Minerva2000����
�O�X���ł͂P�O��قǖ₢�|���Ă�����ɂ������ɂȂ炸�A�����u��_�����ADIR�ł�PLL�ł��`���H�o�R�̃N���b�N���x�[�X�ɂ��Ă���A���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���B�v�Ƃ����ꌾ�ŕЂÂ��Ă����ł͂Ȃ��ł����B
�u���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���B�v�Ƃ������W�Ȍ��q�œ����Ă����āA���F�������Ȃ��Ă���Ƃ܂����炽�Ȍ��p��M���Ă���Ƃ͂ǂ��܂Ō��疳�p�Ȃ̂ł����B
�ł́u���̃W�b�^�[���犮�S�ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂���B�v�_�̌��t�Ƃ��������͂ǂ����邨����ł����H ����ɑ��Ă͂�͂薳���Ȃ̂ł����H
���uI2S�Ɋ܂܂��MCK�v��S/PDIF�o�R�ŋ��������N���b�N���x�[�X�Ƃ̉��߂����サ�Ă��܂��B�Ƃ����̂̓u���O�ɂ͉��L�̋L�q�����邩��ł��B
--------------------------------------------
S/PDIF���V�[�o�[�iDAI�j�̓v���A���u���M���𒊏o����PLL��H�ŃT���v�����O���g�����Č����A��������DAC�ɓn��I2S��LRCK�ABCK�AMCK�Ȃǂ����܂��B
�������A�uI2S�Ɋ܂܂��MCK�v��S/PDIF�o�R�ŋ��������N���b�N���x�[�X�Ƃ̉��߂͕��サ�Ă��܂���B�Ȃ��Ȃ�A���́u���L�̋L�q�v�́uUSB DDC�`DAC���uS/PDIF���V�[�o�[�iDAI�j��S/PDIF��ԁv�̘b������ł��B���̋�Ԃ́uS/PDIF��ԁv�Ȃ̂ŁuS/PDIF�o�R�ŋ��������N���b�N���x�[�X�v�Ȃ̂͂�����܂��ł��B
�����ƂȂ��Ă���̂́uDAC���u������S/PDIF���V�[�o�[?DAC�`�b�v�Ԃ�I2S��ԁv�ł���B��������炸���̂���ւ�����肢�ł��ˁB�uI2S�Ɋ܂܂��MCK�v�́uI2S��ԁv�Ɏg�p�����Ɍ��܂��Ă��܂��B
���v���A���u���M���𒊏o����PLL��H�ŃT���v�����O���g�����Č����A��������DAC�ɓn��I2S��MCK������̂ł���AMCK��S/PDIF�o�R�ŋ��������N���b�N���x�[�X�Ƃ����l����ꂸ�ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�\�̏o�Ԃ͂���܂���B
�uI2S��ԁv�̘b���uS/PDIF��ԁv�̘b�ɂ���ւ��Ă����āA�uMCK��S/PDIF�o�R�ŋ��������N���b�N���x�[�X�Ƃ����l����ꂸ�ADAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�\�̏o�Ԃ͂���܂���v�ƌ����Ă݂��Ƃ���Ŗ��Ӗ��ł���B
DAC�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�͂ǂ��ɂ���̂��A�ɂ��Ă͂��łɑO����� [21788263] �̐}�Ŏ����Ă��܂��B��ɂ�����x�A�b�v���܂������̐}��TI�А��́uDIR9001�v�̃u���b�N�}�ł����ADAI�̓����ɂ��邱�Ƃ���������Ă��܂��B���������gPreamble Detector�h���������v���A���u����PLL�ɑ����A�gClock Decoder�h�A�gDivider�h���o��SCK�i�f�W�^���t�@�C���^�[���̍��x�ȕϊ������p�̍����N���b�N�j�ABCK�ALRCK�Ƃ��ďo�͂����DAC�`�b�v�ɑ����邱�Ƃ͖����ł��B�����āAMCK�̓u���O���̂Ɂu���DAC�`�b�v�̃V�X�e���N���b�N�v�Ə����Ă���ł͂Ȃ��ł����B
SCK�ABCK�ALRCK��DAI�Ő�������AMCK��DAC�`�b�v�Ő��������B����������DAC�iDAI�{DAC�`�b�v�j�����̃N���b�N�W�F�l���[�^�\�̏o�Ԃ͂������܂���B
�u�Ƃ��������̃u���O�ɂ��A���̎咣�����������Ƃ����t�����܂����v�Ƃ́A�u���P�[�u���̌��ɂ悢�A��������̘_���̌�肪���t�����܂����v�̂����̂Ɠ������炢�̖��Ӗ����ł��ˁB
�����ԍ��F21792689
![]() 5�_
5�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
�����͐V�^��iPad���w���\��Ȃ̂ł����AiOS�A�v����OS�̐����ɂ�艹�y�t�@�C���̃R�s�[�ɑΉ��o���Ȃ��Ǝf���Ă��܂��B�@HDD Audio Remote�ɂ��Ă�Android�̃X�}�z���瑀�삷�邱�Ƃɂ��Ă��܂����AiPad�ł̓t�@�C���]���ȊO�̑���(�d����ON OFF/�Đ� ��~etc)�͉\�Ȃ̂ł��傤��? iPHONE��iPad�𗘗p����Ă�����������܂�����A��������낵���肢�܂��B
![]() 0�_
0�_
���r�[�O��chan����
����ɂ���B
����͐V�^ipad��ios11���Ɠ��삷��̂��A�Ƃ�������ł��傤���H
�����g�p���Ă���ipad��2017�N�t���f��(ios10)�ł����A�d��on�Aoff�A�Đ��A��~�����ʂɂł��܂��ˁB
�V�^�͎����ĂȂ��̂łȂ�Ƃ��c
�Q�l�ɂȂ�Ȃ�����݂܂���B
�����ԍ��F21799049�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 1�_
1�_
���Ł`�ނ�����
������B�@�w���\���iPad�͂R�������̑�6���� 9.7�^�ł��B
���Ƃ����������ȕ��͋C�ł��ˁB�@���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F21799993
![]() 1�_
1�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
HAP-Z1ES�������ɂ��w�����悤�ƍl���Ă���҂ł����A�w���ɓ������āA�O�t��BD�h���C�u�������ɍw�����ׂ��������Ă��܂��B
�Ƃ����̂́A�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���L�q���l�b�g��ɎU������邩��ł��B�������ꂪ�{���Ȃ�A�gCD���ڃ��b�s���O�h�̂��߂̊O�t���h���C�u���w�����܂��B
�������A���̈���Łu�o�C�i������v����Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N����Đ����āA���Œ����Ă킩��قlj������قȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��v�Ƃ���ӌ�������܂��B���������炪�{���Ȃ�A�����dBpoweramp����PC���b�s���O���ɍs�����߂̃\�t�g���w�����܂��B
�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H
���������܂�����A���̌��ʁA�ǂ���̉������ǂ��������A���邢�͕ς��Ȃ����������A�����Ă������������Ƒ����܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21724280/
����̑����ł��B
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����@�@�����͂ł��B
�w�����ł������˂��܂����A�gCD���ڃ��b�s���O�h��HAP-Z1ES��ɍ�����t�@�C���̍Đ��ƁA����CD��PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��Ƃ����ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂����܂����H�x
��L�́A�o���܂���B
�ƌ����̂��A�����Ȃ�]�����悤�ɂ��A�㏑������Ă��܂��̂ł��B
��ɂo�b�]���Ń��b�s���O���ꂽ�Ȃ������ԂŁA�O�t���h���C�u�Ń��b�s���O���悤�Ƃ���ƁA���ɂ��̋Ȃ͂���܂��B
�㏑�����܂����H�ƕ����Ă��܂��B
���Ȃ��c���Ȃ킿���b�s���O���~�ł��B
�o�b�]�����́A�����Ă��Ȃ��̂ŁA�㏑�����Ă���̂��A���ĂȂ��̂��s���ł����H
�����ԍ��F21754329
![]() 4�_
4�_
�V�����X���ɂȂ����̂ŁA���̋@�킪���������Ƀf�[�^�]����LAN�o�R�ɍi�������R���l���Ă݂�Ƃ��������ł�
CD���b�s���O�͌�t���̋@�\�ł������
���Ԃ�ł����A�ڋq�������]�낤�Ǝv���܂�
�����ԍ��F21754564�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�Â����̑�D������A�����́B
���PC���b�s���O�����t�@�C����]�����Ă��ꂪHAP-Z1ES��ɂ����ԂŁA�gCD���ڃ��b�s���O�h�����悤�Ƃ���ƁA�u���ɂ��̋Ȃ͂���܂��B�㏑�����܂����H�v�ƕ����Ă���̂ŁA�Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES��ɋ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��ˁB
����ł́A���Ԃ��t�ɂ���悢�̂ł͂Ȃ��ł����H
��ɁgCD���ڃ��b�s���O�h������B���ꂩ��APC���b�s���O�����t�@�C����]������B���̂Ƃ��A�]����HAP Music Transfer���g���A�����炭���ڃ��b�s���O�̃t�@�C�����㏑������Ă��܂��ł��傤�B
�ł��AExplorer����́AHAP-Z1ES�͒P�Ȃ�O�t���n�[�h�f�B�X�N�Ɍ�����̂ł���ˁB�Ȃ�APC���b�s���O�����t�@�C���̖��O��ύX�������Explorer�ŃR�s�[����A�Q�̃t�@�C����HAP-Z1ES��ɋ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
����łł������ȋC�����܂����A�i���͂܂������Ă��Ȃ��̂ŁA�m�F�ł��܂��j�ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F21754696
![]() 5�_
5�_
���́u�O�t���n�[�h�f�B�X�N�v�Ƃ����̂́u�l�b�g���[�N�n�[�h�f�B�X�N�v�̊ԈႢ�ł����B
�Ƃɂ����AExplorer�ɂ��PC����HAP-Z1ES�Ƀh���b�O&�h���b�v�ŃR�s�[�ł���͂��ł��F
http://helpguide.sony.net/ha/hapz1es/v1/ja/contents/TP0000774183.html
�����ԍ��F21754743
![]() 5�_
5�_
��Symbolist_K����
�F����̋c�_�������[���ǂ܂��Ă�����Ă��܂��B
�����ɂ��o�����̂ŁA����Ă݂܂������A�����̎��ł͔��ʕs�\�ł���(��;)
1, �uIO-Data DVR-UA24EZ2A�v���q���Œ��ڃ��b�s���O�B
2, Windows10 ��PC��ŁuHAP Music Transfe�v���g��HAP-Z1ES�ɓ]��
�����Ȃ�ʃt�H���_�ɓ���܂����̂ŁA�u���ɐ�ւ��邱�Ƃ͂ł��܂���B
��������
HAP-Z1ES �� �o�����X�P�[�u�� �� STAX SRS-4170
�ł��B
���X���쐫�̌��オ���ړI�ŁuHAP-Z1ES�v���w�������̂ŁA����قlj����]�X��Nj�����C�͂Ȃ��̂������ȂƂ���ł͂���܂��B���݂܂���A���������O�삩��̈ӌ��ƌ������ƂŁc�c
�����ԍ��F21754758
![]() 10�_
10�_
Symbolist_K����A�O�X���̃R�[�f�B�l�[�^�[�������l�ł����B
�O�X���̊p�c����̃u���O�ǂ�ł��炢�����Ə����Ă����̂ŁA���p���Ƃ����B
���͐��P�O�N�O���́A�I�[�f�B�I�@��v���d���Ƃ��Ă��܂����B���̎��̓I�[�f�B�I�v�͗��_�����܂薳���A�_�l�̂悤�ȉ�������҂Ǝg�p���i���x�z���Ă���悤�Ɋ����A�r�f�I�v�ɓ]���܂����B���̌㑪���J�����o�āA���܂����̐��E�ɊW���Ă݂�Ƃ܂��ȑO�̂悤�ȏ�����悤�Ɏv���܂��B
���i�A�����������I�ɐi�����Ă��܂�����A�]���𖾁A�����ł��Ȃ��������ł����Ă��e�ՂɑΉ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�t�ɐv�\�͂͑މ����Ă��邽�߁A���ҍ��킹�Đi������~���Ă���悤�ɂ��v���܂��B
�m���ɐ��ɏn�m�������́A���̓��ɂ��Ă͏ڂ����ǂ̂悤�Ȏ��ɂ��������܂��A�����O���ƑS���������Ȃ��ƌ������Ƃ������Ȃ��ė��Ă��܂��B
������̓`�B�̓C���^�[�l�b�g�̔��B�ɂ���āA����I�Ɍ��サ�܂����B����ɂ���ĒN�ł����ƂƓ��l�ȏ�����肷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂������A���̐^�U�f����\�͂͏]���̂܂܁i�ނ���ቺ�j�̂��߁A���Ɍ�������f�����邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B���ߑ��H
�T���v�����O���[�g�̍������������̂ł͂Ȃ��A�ł��������݂���CD�������ɗǂ������ōĐ��ł��邩���d�v�ƍl���Ă��܂��B���̃f�o�C�X�Z�p��p�����384kHz24b���x�̐M�������͗e�ՂɎ����ł��܂��������Đ��p�Ƃ��Ă͂��܂�Ӗ�������܂���B
���̂P�N�I�[�f�B�I�v���Čo�����܂������A�����������d�������ƃV�~�����[�V��������p���ĉ�͂���A�ȑO�s���ł����������A���ł�������x�𖾂ł���̂ł͂Ȃ����ƍĔF�����Ă��܂��B
DAC�v�ɓ������Ă͖w�ǂ̉�H���V�~�����[�V�����ł���͂��A���茋�ʂƍ��v������悤�ɂ��Ă��܂��B
����ǂނƁA���̐v�҂�DAC�������Ȃ��Ă��邯�ǁADAC�ɐ��\�����o�����ȁB
�����ԍ��F21754811
![]() 8�_
8�_
Symbolist_K����A�����́B
�����A�h�肪�o���i���j�BSymbolist_K����[21754278]
>�����̂ŁA�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�ǂ�œ��e�������܂�ŋ����Ă��������B
��������ǂ�ǂ����āE�E�E�ǂ������Ȉ���(��)�H
�Ƃ���Łu�X�e���I�T�E���h���̊p�c��Y���v�ƁuATI Labo�̊p�c����v�͈Ⴄ�l�Ȃ�ł����ˁB�����قNjC���t���܂����B�ȉ��A�����܂ł��l�̊��z�Ƃ��f�肵�Ă����܂��B
�܂��u�ǂ�ǂ����̂P�i�@����j�v�̕����́A�c�`�b����Ȃ��Ă`�c�b�Ȃ�ł��ˁB���̓������[�v���ɂc�`�b������A�Ƃ�������Ȃ̂ŁA�u�Ȃ�ł��̕����H�v�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B���̕������瓾����{�X���Ɋ֘A������́A�u�N���b�N�W�b�^�[�łr�m�q�i�r�m��j����������v�Ƃ����A������O�̎����ł�������܂���B��������O�ꂽ�������m�C�Y�ł�����ˁB
���Ɂu�ǂ�ǂ����̂Q�i��������j�v�́A�p�c����̃u���O�ł́uSPDIF�̏ꍇ����JITTER�́v�Ƃ����������烊���N����Ă���ɂ��ւ�炸�ASPDIF�Ƃ͂Ȃ��W�Ȃ��A�O�L�����ɑ����uPLL��LOOP�t�B���^�[�Ő��������v���T�|�[�g���邾���̈Ӗ���������܂���B�����������O�̎����ŁA��͂�A�u�Ȃ�ł��̕����H�v�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B
�uPLL��LOOP�t�B���^�[�Ő��������v�ƃW�b�^�[�̍��搬�������������킯�ł����A�u���O�ł́u�ʂ͂킸���ł������M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��v�ƁA���_����Ă��܂��B���́A����͂Ȃ��Ȃ��Ɏ�O�݂��Ș_�����Ǝv���܂��B
���̌f���Ŕ��_����@��^�����Ă��Ȃ��i�Ǝv����j�p�c�����ᔻ���邱�Ƃɂ͐T�d�ł���ׂ��Ǝv���܂����A���Ƃ��Ă͎����������������Ȃ��A�ƌ��_���Ă����܂��B�E�l���ȂЂƂȂ̂����m��܂��A��O�݂��͂�����ƁB
�����A�������̂Q�͂������낢�ł��B
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf
�A�u�X�g�����p�����
>�W�b�^�[�����ʂ��ē���ꂽ�ő�̃W�b�^�[
>�����U���́A�W�b�^�[���g��2 Hz�ȏ�ɂ����āA2ns����������B�]���̎��g���ϓ����m�����̌��ʂƔ�
>�r����ƁA���̒��x�̃W�b�^�[�������ɗ^����e����҂����m���邱�Ƃ͍���ł���Ɨ\�z�����B
�Ƃ̂��Ƃł����A��̐Ԗx�������p����Ă���
>����ŁA�Ԗx��m�P�n�́A�f�B�W�^���C���^�t�F�[
>�X��̃r�b�g�X�g���[���ɃW�b�^�[�������āA������
>�̉����̕ω��ׂĂ��邪�A�������ʂɂ��ē��v
>�I������s�������ʁA�U��80ps�̃W�b�^�[�̗L�����A
>�팱�҂͗L�Ӎ�����ŕ������������Ƃ�������Ă�
>��B
�ƁA�y���u�ς��E�ς��Ȃ��v�_���Ȋ����ł��B�����A�������̂�
>����n�̃m
>�C�Y���x�������i�ʂȃf�B�W�^���@��ɂ����ēT�^�I
>��-130dBFS�^Hz�ȉ��ł���ꍇ�A�����M����p����
>�W�b�^�[�U�����m���͐�ps�`��10ps���x�ł���B
�Ƃ����L�q�ł��B�����Ƃ͌�����ps�`��10ps�͋����ׂ������ł��B�l�Ԃ̌��m���Ƃ��Ă̓X�S�����Ăɂ킩�ɂ͐M���������̂ł����A����ɂ͕����i�����j��������Ă��Ȃ����Ƃ����̂悤�ȋ^���������܂��B����́ASymbolist_K����ɒ��҂ɕ����Ă��炤�����Ȃ��悤�ȁE�E�E�h��Ԃ�(��)�B
�����ԍ��F21755054
![]() 8�_
8�_
�s�����g�����R����A�����́B
���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�������ɂ��o�����̂ŁA����Ă݂܂������A�����̎��ł͔��ʕs�\�ł���(��;)
���ۂɒ�����ׂĂ݂Ă̋M�d�Ȃ����z����������A���ӂ������܂��B
�s�����g�����R����́u��ʂł��Ȃ��h�v�̂R�l�ڂɂȂ�܂����I
�Ƃ���ŁA�]����HAP Music Transfer���g���Ă��A�gCD���ڃ��b�s���O�h�����t�@�C���Ƃ͕ʂ̃t�H���_�ɓ������̃t�@�C�����㏑�����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��ˁB
���Â����̑�D������
HAP-Z1ES�Ƀt�H���_������������Ă����āAPC���b�s���O�����t�@�C�����gCD���ڃ��b�s���O�h�����t�@�C���Ƃ͕ʂ̃t�H���_�ɓ]������Α��v�������ł���I
�����ԍ��F21755344
![]() 5�_
5�_
MAX���O�Y����
�u���̋@�킪���������Ƀf�[�^�]����LAN�o�R�ɍi�������R�v�́A�����炭�́A���ł�PC�I�[�f�B�I�^�t�@�C���I�[�f�B�I�炭����Ă���WAV��AIFF��FLAC��ALAC��DSD��DSF�̃t�@�C����PC�ɂ��ߍ���ł���l���^�[�Q�b�g�ɂ�������BPC����͑O��Ƃ��āB
�������A���̌�AHAP-Z1ES�������ǂ��ƕ������āAPC����ɂ��܂芬�\�łȂ����X�������悤�ɂȂ����̂ł��傤�B�\�j�[�ɂ��A�u�wCD���b�s���O�ɂ͂ǂ�ȃ\�t�g���g�������̂��x�w�p�\�R�����g��Ȃ���CD���b�s���O������@�͂Ȃ��̂��x�Ƃ������₢���킹�����[�U�[���瑽����ꂽ�̂ŁA�p�\�R�����X�ŊO�t���h���C�u���璼�ڃ��b�s���O�ł���@�\��lj�����A�b�v�O���[�h�ɓ��ݐ����v�����ł���B
�����ԍ��F21755347
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
�O�X���ł͑����̏������݂��肪�Ƃ��������܂����B
���T���v�����O���[�g�̍������������̂ł͂Ȃ��A�ł��������݂���CD�������ɗǂ������ōĐ��ł��邩���d�v�ƍl���Ă��܂��B���̃f�o�C�X�Z�p��p�����384kHz24b���x�̐M�������͗e�ՂɎ����ł��܂��������Đ��p�Ƃ��Ă͂��܂�Ӗ�������܂���B
�p�c�����CD�X�y�b�N�i44.1kHz/16bit�j�ł����Ă�DAC����ŏ\���������ɂ��邱�Ƃ��ł��A���Ȃ��Ƃ�384kHz/24bit�͈Ӗ����Ȃ��A�Ƃ�������Ȃ̂ł��ˁB�ł́A384kHz/24bit�͈Ӗ����Ȃ��Ƃ��āA�ǂ��܂łȂ�Ӗ�������Ƃ��l���Ȃ̂ł��傤�ˁH 192kHz/24bit�܂ŁH ����Ƃ�96kHz/24bit�ŏ\���H �ł��A�̗p����ES9018��384kHz/32bit�܂ŁAES9038PRO��768kHz/32bit�܂őΉ����Ă��ł���ˁB
���Ȃ݂�ES9038PRO ���̗p����OPPO Sonica DAC��SOULNOTE D-1�AAK4497���̗p����TEAC NT-505�́A768kHz/32bit���Đ��ł��邱�Ƃ��ւ��Ă��܂��ˁB����ȉ����A�����Ă܂��ǁB
AIT-DAC-zn2�i347,800�~�j�́A���i�I�ɂ�SOULNOTE D-1�Ƃ��������ł����A���h���͈����ł��ˁB
����ɔ�ׂ��烁���R��Dela�ł����������悭�����܂��BHAP-Z1ES��N-70AE�Ȃ�Ăނ��Ⴍ���Ⴉ���������ł���˂�
�Ȃ�ƂȂ��A�����@����Ē����Ă݂�H�w�������܂���B�i�����܂ŁA��Ȃ̂́u���v�ł����j
�����ԍ��F21755350
![]() 5�_
5�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�ق�Ƃ��ɘ_����ǂ�ł����܂�ŏЉ�ĉ������āA���肪�Ƃ��������܂����I
���Ȃ݂ɁA�X�e���I�T�E���h���̊p�c��Y���́u�̂��v���ŁAAIT Labo�̊p�c����i���̖��O�͕s���j�́u�������v����Ǝv���܂��i�v���t�B�[���Ɂu���O�Fkkt�v�Ƃ���̂ŁBDAIGO���I���j�B
AIT Labo�p�c����͎�O���X���݂Ȃ�ł����B�_���̎g��������c�����I�Ȃ�ł��ˁB�u�ʂ͂킸���ł������M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��v�������킩��Ȃ����A��ɖ��ɂȂ��Ă����u�{�������v�Ƃ̊֘A���悭�킩��܂���ˁB���ꂩ��A���܂�l�̂��Ƃ͌����܂��A�₽��ƂЂ炪�Ȃ̔����������ł��ˁB
���āA�u�ǂ�ǂ����̂P�i�@����j�v�͓ǂ܂Ȃ��Ă�������ł��ˁI �悩�����ł�(��)
�ł��A�u�ǂ�ǂ����̂Q�i��������j�v�͖ʔ�����ł��ˁB�ł́A�����p���p�����Ɠǂ�ł݂܂��B
��������I�[�f�B�I�}�j�A�̈ꕔ�ɂ́AAC�d���̎��ɍS��X����������B�������A���̉Ȋw�I�����͖R�����A�v���O��P�[�u�������i���Ȃ��̂Ɍ����������Ƃɂ��v���\�ȓd�C�I�e���≹���I�e���́A���܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�ȂA�u�I�[�f�B�I�}�j�A�v���f�B�X���Ă܂��ˁB
�����肳�ꂽ�W�b�^�[�́A�]���̌����œ���ꂽ���g���ϒ��ɑ��錟�m���i�����Ƃ����x�̍����ϒ����g���RHz�ɂ����āA�W�b�^�[�U���Ɋ��Z����Ɩ�S�`10ns�m13�n�j�ȉ��ł������B����ď]���̒��o�I�m������́A���肳�ꂽ�W�b�^�[�́A�����I�ɂ͖��̂Ȃ��ʂł���ƍl������B
���ߔN�ł́A�b����m14�C15�n���A�f�B�W�^���̈�ɂ����ĉ��y�M���ɐl�H�I�ȍL�ш掞�Ԃ�炬�������āA���̌��m���𑪒肵�Ă���B���̌��ʁA�ł����x�̍����팱�҂���уT���v���Ȃ̏ꍇ�ł��A�����l�ŕ\�����W�b�^�[�̌��m����500ns���x�ł������B
������ŁA�Ԗx��m�P�n�́A�f�B�W�^���C���^�t�F�[�X��̃r�b�g�X�g���[���ɃW�b�^�[�������āA������̉����̕ω��ׂĂ��邪�A�������ʂɂ��ē��v�I������s�������ʁA�U��80ps�̃W�b�^�[�̗L�����A�팱�҂͗L�Ӎ�����ŕ������������Ƃ�������Ă���B�������ނ�̎����ł́A���ۂɍĐ������A�i���O�����M���ɂǂ̒��x�̃W�b�^�[���܂܂�Ă����̂������m�Ɍ�����Ă��炸�A�����ɂ͂������̉������{�����I�[�f�B�I�@�킪�g�p����Ă��邽�߁A��ʐ��̂��錋�ʂł��邩�ǂ����ɂ��ċ^�₪�������B
���m���̑��茋�ʂ́A80ps�`4ns�`10ns�`500ns�܂ŁA�܂��܂��i��ԉ��͈�ԏ�̖�P�����̂P�I�j�Ȃ�ł��ˁB���̒��ŁA���̐Ԗx���́u80ps���v�͋^���Ă܂��ˁI
���āA���q�˂�
������n�̃m�C�Y���x�������i�ʂȃf�B�W�^���@��ɂ����ēT�^�I��-130dBFS�^Hz�ȉ��ł���ꍇ�A�����M����p�����W�b�^�[�U�����m���͐�ps�`��10ps���x�ł���B����p���y�M���͉ߋ��̑���m�V�n�Ɠ�����RWC-MDB2001No.2�m10�n��p�����B���̏ꍇ�̃W�b�^�[�U�����m���͂Rns�m�V�n�ł���
�Ƃ����L�q�ł����A�u�S�D�l�@�v�̍ŏ��̕�����
�����y�M���𑪒�M���Ƃ����ꍇ�ɂ́A���o���ł���Rns�ȏ�̃W�b�^�[�͑���ł��Ȃ������B
�Ƃ�����߂������ł���B������A����@��̑���u���o���v�̊ԈႢ�Ȃ�Ȃ����Ǝv����ł����B
�����炭�A�@��ɂ��W�b�^�[�U���́u���o���v���A�����ł͐�ps�`��10ps�A���y�ł͂Rns�����Ęb�Ȃ�Ȃ��ł����H �l�Ԃɂ��u���m���v�ł͂Ȃ��B�Ⴄ���ȁH
�����ԍ��F21755354
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����@���͂悤�������܂��B
�ʃt�H���_�E�E�E�ł����H�@���́A�䂪�Ƃ�USBDAC�̋@�\������CD�v���[���[��2�䂠��܂���
�v���[���[�ŁA�f�B�X�N���g���Ắu���v�Đ��ƁA�m�[�gPC�Ƀ��b�s���O����USB�ڑ��@iTunes�ł̍Đ��Ł@�u���v����̂��ȁH
2�䋤�Ɏ����Ĕ���Ȃ��H�@�͌o���ςł����AHAP-Z1ES�̍w���ړI���A���ɂ̂��[����Đ����̍\�z�Ȃ̂�
�s�����g�����R����Ɠ����ӌ��ŁA����قǒNjy����C�����͕����Ă��܂���̂ŁA���̕ӂ�ň������炸�ł��B
�����ԍ��F21755449
![]() 4�_
4�_
�Y�ꂳ�ʔ����Ƃ����̂ŁA
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Jitter.pdf
��ǂ݂��������A�u��͐M���v���ĉ�����Ƃ����Ƃ���ō��܂����B
�O�O��ƁA
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/emm180.pdf
�ɉ��������ȁB
�悭�킩��ǁA���ԗ̈�̑���M���i���g����_c�̏��������gAsin(��_ct)��t��Jsin��_jt�Ƃ��ăW�b�^��t���A���Ȃ킿�A
Asin(��_c(t+Jsin��_jt)�j����q���x���g�ϊ��ʼn�͐M���̋������������߂�ƁA��͐M���̎��������Ƌ��������̔��arctan
�ł���A����M��Asin(��_c(t+Jsin��_jt)�̏u���ʑ��p��(t)����_c(t+Jsin��_jt)�����܂�B�]���āA�W�b�^�g�`Jsin��_jt���A
����M�����狁�߂���B������t�[���G�ϊ��������̂��W�b�^�X�y�N�g�������H
�����ԍ��F21755773
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����A����ɂ��́B
����ɂ��Ă��A�s��Ȏ���X���ł���ˁB�Ƃ��ƂƔ����Ē����Ă݂��E�E�E���ē˂����݂�12�l���炢���畷�����Ă������ł�(��)�BDAIGO����A����Ȃ��ăJ�N�^����̌��A���肪�Ƃ��������܂����B
>���m���̑��茋�ʂ́A80ps�`4ns�`10ns�`500ns�܂ŁA�܂��܂��i��ԉ��͈�ԏ�̖�P�����̂P�I�j�Ȃ�ł��ˁB���̒��ŁA���̐Ԗx���́u80ps���v�͋^���Ă܂��ˁI
�܂��A�Ԗx���i���炭���{TI�j���f�B�X���Ă���ۂ����ҁi��������j�̌��ł͂���܂����ǂˁB����ɂ��Ă��A�O�X���̕č��_���ɂ�錟�m���i10ns�`300ns�j��肸���Ԃ�Ⴂ������̂́A���{�l�Ȃ�ł͂̑@�ׂȒ��o�E�E�E�Ƃ������Ƃł͑����Ȃ��ł�(��)�B
�_���ɂ���悤�ɌÂ������̐M�����ɂ͒��ӂ���K�v�����肻���ł����A�܂��A�_���Ɂu�����Ƃ����x�̍����ϒ����g���RHz�ɂ����āv�Ƃ���������������܂��B��s�������ǂ߂Ȃ��̂Ő����ł����A����̓W�b�^�[�̈���E�������RHz�ŌJ��Ԃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����B���ꂾ�ƕč��_���̂悤�Ȃ`�a�w�@���͂��Ȃ茟�m���������肻���ł��ˁB����Ȃ킯�Łu���m���͂��ꂱ��v�ƌy�X�ɂ͌����Ȃ��Ɨ������ׂ��ł��傤�B
�������A�N���b�N����IC�̃x���_�[�����А��i��i�삷��_���������̂͗����ł���Ƃ��āA����ɉʊ��ɗ�����������w�̌����͊�Ƃ���̉����͓���ꂻ�����Ȃ��A�Ȃ�̓��ɂȂ�̂��A�ЂƎ��Ȃ���S�z�ɂȂ�܂��B����Ȍf���ł���ȒP�ɍ�i���j�B
>������A����@��̑���u���o���v�̊ԈႢ�Ȃ�Ȃ����Ǝv����ł����B
Symbolist_K����́u�u���_���v�������ł����A�̂͂�����ĎZ�����ł��Ȃ��j�q�̂��ƂƎv���Ă��܂����B���̌㑽���̐l���o�����o�āA�ŋ߂ł͍��������̕�����܂������A�����܂�������\�͂�L����ЂƂ����ۂ���̂ɂ͐S��I�h���L�܂��Btohoho3���������Ă����悤�ɁASymbolist_K�����������H
��k�͂Ƃ������A���͎������������悤�ɓǂ�ł��āA���������A����Ȃ��ău���_����Symbolist_K����ɐ�ɂ���������Ăق�����������ł��B���m�ɂ́A����@�펩�̂̓s�R�b�𑪒�ł��܂����A��A�̕]���t���[�S�̂Ƃ��āA�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21755976
![]() 7�_
7�_
�����ł��B
>����̓W�b�^�[�̈���E�������RHz�ŌJ��Ԃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����B
�́A�Ⴂ�����ł��B����������ƃW�b�^�[�i�ʑ��j���̂��RHz�ŕϒ������悤�ł��B����Ȃɂ�����肵���W�b�^�[�܂ōl���Ă���Ƃ̓C���[�W���Ă��܂���ł����B
������ɂ��Ă��A���ꂾ���������h�����Ă�����A���^�C���ň�a���������₷���Ƃ������ƂŁA�L���ɗ���`�a�w�ɔ�ׂ�Ƃ����Ԍ��m����������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21756099
![]() 5�_
5�_
�Â����̑�D������A���͂悤�������܂��B
�u���b�s���O���@�͈Ⴄ���o�C�i���͓����Q�t�@�C����HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɋ�����������ōĐ������r����v���Ƃ͂���Ă��Ȃ��̂ł��ˁB
�Ƃ������Ƃ́A�O�X���ɏ������܂ꂽ�A
�����`���ƁA���ۂɒ��������̂̌o���Ƃ��āA���̑ʎ�(������)�ł́A�����ς蕪����܂���(�͂͂́I)
��
���ʐ^�ɕt���܂����l�ȁA�O�t���h���C�u�c����́A���܂��܃m�[�gPC�p�ɊO�t���h���C�u�������Ă���
���̂Ŏg���Ă܂����A�f�B�X�N�g�b�vPC�Ń��b�s���O�����f�[�^��LAN�o�R�œ]�������Ă܂����A�u���v
���Ȃ�Ă����ς�ł��B
�Ƃ����̂́APC���b�s���O�ō�������鉹�y�̃f�[�^�̍Đ���CD���ڃ��b�s���O�ō�����ʂ̉��y�̃f�[�^�̍Đ��Ƃ��r���Ă̘b�������킯�ł����B
����ł��A�uPC�]���ƊO�t���h���C�u�ł̃��b�s���O�ł́w���x�v������Ȃ������ƌ����Ă���̂ŁA�����悤�ȋȁi�Ⴆ�Γ����̎�̕ʂ̉̂Ƃ��j���r���Ă̂��b�������̂ł���ˁB
�ł���A�܂��u�T�v�I�ł͂���܂����A���̃X���ł͌Â����̑�D����������������u��ʂł��Ȃ��h�v�̂��P�l�ɐ��������Ă��������܂��B
�����ԍ��F21757752
![]() 5�_
5�_
tohoho3����
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/emm180.pdf
�́A���ɂ͓�����ēǂ߂܂���B
�u�t�[���G�X�y�N�g���v�Ƃ��u�q���x���g�ϊ��v�Ƃ������ς�ł�^^;
�����ԍ��F21757753
![]() 3�_
3�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���_�߂ɂ������肠�肪�Ƃ��������܂��B
���[�ƁA���́u�u���P���_���v�ł��B�u���P�W���v�Ȃ�ʁu�u�P�_���v�B�u���w�n�v�Ȃ�ʁu������n�v��
�ŋ߁u���P�W���v�����Ă͂₳��Ă���̂ŁA���̑ɂɈʒu���邱�Ƃ��������Ă݂܂����B
�u�u���_���v�Ə̂���ƁA�ȂA�H��܂��Ƃ����肵�Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ����������܂�(��)
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����́u���P�W���v�ł���ˁH
�u���n���q�����T�[�r�XRikejo�v�i�Ȃ�ăT�C�g������܂����j�ɂ��A
�����P�_���i���n�j�q�j�ƃu�P�_���i���n�j�q�j�̘b�ƂȂ�܂����B���ǁA���P�W�������P�_���ƌ��������肷��̂́A���ǂ͏o��ꏊ���Ȃ�����ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�u�P�_���ƃ��P�W���́A���݂��ɔ�����Ƃ������������ƂłȂ��āA���ǂ͒m��Ȃ��܂܂ɏI���Ƃ��������ł��傤���BT����̑�w�ł́A���H�n�̊w���́A���̊w���Ɗu������Ă��������ŁA���̂悤�ȑ�w�͑����ł���ˁB
http://www.rikejo.jp/unclassified/article/1199.html
�������ł��˂�����
���āA
���܂��A�Ԗx���i���炭���{TI�j���f�B�X���Ă���ۂ����ҁi��������j�̌��ł͂���܂����ǂˁB����ɂ��Ă��A�O�X���̕č��_���ɂ�錟�m���i10ns�`300ns�j��肸���Ԃ�Ⴂ������̂́A���{�l�Ȃ�ł͂̑@�ׂȒ��o�E�E�E�Ƃ������Ƃł͑����Ȃ��ł�(��)�B
������������ƃW�b�^�[�i�ʑ��j���̂��RHz�ŕϒ������悤�ł��B����Ȃɂ�����肵���W�b�^�[�܂ōl���Ă���Ƃ̓C���[�W���Ă��܂���ł����B
������ɂ��Ă��A���ꂾ���������h�����Ă�����A���^�C���ň�a���������₷���Ƃ������ƂŁA�L���ɗ���`�a�w�ɔ�ׂ�Ƃ����Ԍ��m����������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
������Ȃ킯�Łu���m���͂��ꂱ��v�ƌy�X�ɂ͌����Ȃ��Ɨ������ׂ��ł��傤�B
�Ȃ�قǁB�����ɂ���Č��m���̒l�͂��Ȃ�㉺����̂ł��ˁB�����ē��{�s�h�̐Ԗx���́A�Ӑ}�I�Ɍ��m��������������ɂ��Ă����Ƃ������Ƃł����B
���������A�N���b�N����IC�̃x���_�[�����А��i��i�삷��_���������̂͗����ł���Ƃ��āA����ɉʊ��ɗ�����������w�̌����͊�Ƃ���̉����͓���ꂻ�����Ȃ��A�Ȃ�̓��ɂȂ�̂�
��������w�́u���w�̐��_�v��ǂ�ł݂܂����F
http://www.tuis.ac.jp/university/spirit/
�u�����_�Ƒ�w�̑n�ݎҁA�|�{���g�͕����E�O���E�_�����E���M��b���C���ߑ�����D�ꂽ�����Ƃł���ƂƂ��ɁA���p�I�ȉ��p�Z�p�ɗ͂𒍂��u���w�v�̏d�v�����������Ȋw�҂ł�����܂����B
�@��������w�ł́A�|�{���_�W�I�Ɍp�����A�����������ĐV�����������l�ވ琬�����w�̐��_�Ƃ��A���̋��痝�O���u������w��`�v�Ƃ��Ă���̂ł��B�v
�ܗŊs�ɗ��Ă������čŌ�܂ŎF���R�ɒ�R�����|�{���g�́u�|�{���_�v���p�����Ă���Ȃ�A����Ȋ�Ƃɂ��ׂ��������悤�Ș_���������Ȃ�āu�^������Ɓv���ĂƂ��낶��Ȃ��ł��傤����
�����ԍ��F21757756
![]() 6�_
6�_
>���ɂ͓�����ēǂ߂܂���B
�����Ǝ��Ԃ�����A
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/eMM_back/backcontents.htm
�́u��b����̎��g�����́i�P�j�v����ǂ߂ASymbolist_K�������痝���ł���͂��B
�����ԍ��F21757794
![]() 5�_
5�_
Symbolist_K����A����ɂ��́B
>���_�߂ɂ������肠�肪�Ƃ��������܂��B
�u��k�v���ď���������(��)�B�u�u�P�_���v�ł����ˁi������ƒp���������j�B���͉��吶�ł����A���y������Ă���l�Ő��w�ɂ߂��ይ���l���ĈĊO�����ł���i�s�^�S���X�Ƃ��j�B
>�Ȃ�قǁB�����ɂ���Č��m���̒l�͂��Ȃ�㉺����̂ł��ˁB�����ē��{�s�h�̐Ԗx���́A�Ӑ}�I�Ɍ��m��������������ɂ��Ă����Ƃ������Ƃł����B
�݂Ȃ���ɂ킩��Â炩�����Ǝv���̂ŁA�킩��₷�������܂��B�u10ns�̃W�b�^�[�v�ƌ������ꍇ�A���Ԏ������̐U����10ns�ł��邱�Ƃ͂킩��܂����A���ꂪ�ǂ�ȋK�����Ŕ������Ă���̂������܂���B�Ƃ������A�O�X���Łu�����_���E�W�b�^�[�v�Ƃ����ꂪ�������悤�ɁA�L�����g���������܂ނ̂����ۂƎv���܂��B
�l�Ԃ̌��m���̎���������ꍇ�ɂ͐��䂳�ꂽ�W�b�^�[���킴�Ɖ�����K�v������܂����A�����Ƃ��P���Ȃ͈̂����g���̃W�b�^�[�ł��傤�B���ۂƂ͂�������Ă��܂����A�ނ��댟�m�͂��₷�����ł��i��������̘_���ɂ�����������Ă��܂��j�B
����ɁA���_���ɂ����̎��g����3Hz�̂Ƃ��ɂ����Ƃ��킩��₷���Ƃ̂��Ƃł��B������������3Hz�̃r�u���[�g���������ĕ�������Ƃ������Ƃł��B�����������3Hz�����肪�킩��₷�����ȋC�����܂��ˁB�����Ă��̂Ƃ��̌��m���́A�W�b�^�[�U�����Z��4ns�`10ns�Ƃ̂��Ƃł��B
�v����ɁA���Ԃ��炩������A�����Č��m���₷��������T���āA�悤�₭4ns�`10ns�ł���Ƃ������Ƃł��B���Ă݂�Ɠ��{�s�h�́u80ps���v�́A���̌��������K�v�͂���܂��傤���A�Ȃ�炩�̖��������肻�����Ǝv���ق������R���Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁA�J�N�^����́u���M���ɂ���čL�悪�ʂ̉��ɂȂ��Ă��܂��v�Ƃ����b�́A�Ⴆ��3Hz�̂悤�Ȓ��W�b�^�[�őS�́i�L��j�Ƀr�u���[�g���������Ă��܂��v�Ƃ������Ӑ}�Ȃ̂����m��܂���B�������A��������̘_�������p����̂́A�������ɂ͋t���ʂ��Ƃ��킩�肾�����̂ł��傤���ˁE�E�E�B
>��������w�́u���w�̐��_�v��ǂ�ł݂܂����F
���Ȃ��Ƃ��A�_���ɂ͌����҂Ƃ��Ă����������������܂��B
�����ԍ��F21758877
![]() 6�_
6�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
HAP-Z1ES�̍w�����������Ă���҂ł��B���A�w���ɓ������āAUSB�O�t��DVD/BD�h���C�u�������ɍw�����ׂ����ǂ����Ŗ����Ă��܂��B
�Ƃ����܂��̂��A�uHAP-Z1ES�ɒ��ڂȂ����h���C�u����́gCD���ڃ��b�s���O�h�̉������炵���v�Ƃ���L�q���l�b�g��ɎU������邩��ł��B�Ⴆ�A
https://www.phileweb.com/review/article/201511/16/1850_3.html
�ɂ��A�u�i�]���̂����Ń��b�s���O�������̂Ɣ�r���āj����HAP-Z1ES��CD���b�s���O�����W���j�E�~�b�`�F���wMingus�x��WAV�t�@�C���̉����������ǂ��B���̓����x���オ��A�I�[�v���`���[�j���O�̃M�^�[��W���R�E�p�g���A�X�̃����@�[���̌������x�[�X�̋������N�₩���B�W���j�E�~�b�`�F���̔����Ȑ��g�����N���ɂȂ�A���y�S�̂̃��A���e�B�[���������v���ƂȂ�v�Ɗp�c��Y���͏q�ׂĂ����܂��B
�܂��A���̃T�C�g�̃u���O�̕��́A
http://emuzu-2.cocolog-nifty.com/blog/2016/01/hap-z1eshap-s1c.html
�gCD���ڃ��b�s���O�h�̉��̗D�ʐ����m�M���āA����܂ł��łɑ�����CD�����b�s���O���Ă������ɂ�������炸�A���̂��ׂĂ��gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O���������Ƃɂ��āA���݃��b�s���O���ł��邻���ł��B
�������A�͂����Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ����肦��̂ł��傤���H PC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C�����A�gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O�����t�@�C�����A�����A�Ⴆ��WAV�t�@�C���Ȃ�A�����o�C�i���\�f�[�^�ł����āA�����o�C�i���\�f�[�^�̉����ς��Ƃ������Ƃ����肦��̂ł��傤���H
�������̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ƃ�����A�o�C�i���\�f�[�^�Ƃ��ĈقȂ�f�[�^���gCD���ڃ��b�s���O�h�͍��o���Ă���Ƃ����l����ꂸ�A�Ƃ������Ƃ́ASony�̃\�t�g�ɂ����ǂ�ꂽ�gCD���ڃ��b�s���O�h�́A���������ǂ��Ȃ�H�v��������ꂽ���b�s���O�ł���̂ł��傤���H�i����Ȃ�A���̃t�@�C����PC�ɖ߂��Ă݂ĕ��ʂ̃��b�s���O�t�@�C���ƃf�[�^�I�ɔ�r���Ă݂�킩��͂��ł����B�j
�����ŁA�������˂��܂����APC�Ń��b�s���O����HAP-Z1ES�ɓ]�������t�@�C���̍Đ��ƁA����CD���gCD���ڃ��b�s���O�h�Ń��b�s���O�����t�@�C���̍Đ��Ƃ����ŘA���I�ɔ�r���ꂽ���Ƃ̂�����͂����܂��ł��傤���H
���������܂�����A����A���̌��ʂ��A�u�������ɁgCD���ڃ��b�s���O�h�̕��������ǂ������v�Ƃ��A�u����A�Ⴂ���킩��Ȃ������v�Ƃ��A�u����A�t��PC���b�s���O�̕��������ǂ������v�ȂǂƋ����Ă�����������K�r�ł��B
����́A���ꂩ�玄��HAP-Z1ES�̍w���ƂƂ��ɍ\�z���悤�ƍl���Ă���V�X�e���S�̂Ɋւ����ł��̂ŁA�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B
![]() 8�_
8�_
���Ⴆ��WAV�t�@�C���Ȃ�A�����o�C�i���\�f�[�^�ł����āA�����o�C�i���\�f�[�^�̉����ς��Ƃ������Ƃ����肦��̂ł��傤���H
�@�f�W�^���M���́A���̔g�`�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�Q�i�@�̐��l�f�[�^�ł��B�f�o�C�X��ς��ă��b�s���O�����f�[�^�ł����Ă��A�o�C�i������v���Ă���ꍇ�́A���l�̓]���~�X�͂Ȃ��̂œ����f�[�^�ɂȂ�܂��B
�@���Ƃ��A���̃f�[�^��10000��J��Ԃ��ăR�s�[���Ă��A�ŏ��ƍŌ�̃o�C�i������v���Ă���A�f�[�^�̗i�G���[�j�͐����ĂȂ��̂ŁA���b�s���O�����o�C�i������v���Ă���2�̃f�[�^���A�����o�H�i�ڑ��j�Ɠ����I�[�f�B�I�@��ōĐ������ꍇ�́A�������ɂȂ�܂��B
�@�������o�C�i������v���Ă��Ă��A�I�[�f�B�I�ɂ̓v���V�[�{���ʂ�����̂ʼn����������Ē�������ꍇ������܂����A���̏ꍇ�́A�����Ă�{�l���C�ɓ�����������@������`���C�X����A���_�I�X�g���X�����Ȃ��Ȃ�A�ǂ����ʼn��y���y���߂�Ǝv���܂��B
�@�o�C�i������v���Ă��邩�ǂ����́Awav�t�@�C���̃f�[�^�����݂̂̔�r���K�v�ɂȂ�̂ŁAwav��p�̃o�C�i���`�F�b�N�v���O����������܂��B�\�t�g����WaveCompare�@for Windows�Ń_�E�����[�h��́A
http://efu.jp.net/soft/wc/wc.html
�@�g���Ă݂�ƂƂĂ��֗��ł��B����������CD��ǂݍ��݂������Ȃ���CDR�Ȃǂ���A�h���C�u��A���b�s���O�\�t�g��ς��ĕ������b�s���O���Ă݂āA���̃\�t�g�Ŕ�r���āA���S��v����ACD�h���C�u�ɂ��G���[�������͈�ؖ����ŁA���m�ɒ��o����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�����ԍ��F21724353
![]() 15�_
15�_
�p�C������
���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B
wav��p�̃o�C�i���`�F�b�N�v���O�����͕֗������ł��ˁB���x�g���Ă݂܂��B
�ł����A���͂܂�HAP-Z1ES�������Ă��Ȃ��̂ŁA�gCD���ڃ��b�s���O�h�œ���ꂽ�t�@�C����PC���b�s���O�œ���ꂽ�t�@�C�����r���邱�Ƃ��ł��܂���B
�����ACD��̃f�[�^�ƃr�b�g�p�[�t�F�N�g���ǂ����Ō����A�gCD���ڃ��b�s���O�h�����A�o�C�i���`�F�b�N�v���O�����Ȃ�AdBpoweramp�Ȃ�AEAC�Ȃ�A���낢��g����PC�ł̃��b�s���O�̕�����萳�m�����ł���ˁB
���������o�C�i������v���Ă��Ă��A�I�[�f�B�I�ɂ̓v���V�[�{���ʂ�����̂ʼn����������Ē�������ꍇ������܂����A���̏ꍇ�́A�����Ă�{�l���C�ɓ�����������@������`���C�X����A���_�I�X�g���X�����Ȃ��Ȃ�A�ǂ����ʼn��y���y���߂�Ǝv���܂��B
�Ƃ������Ƃ́A�p�C������́A��Ɉ��p�����p�c��Y���Ȃǂ́ASony������IO-Data DVR-UA24EZ2A��I�肵�āgCD���ڃ��b�s���O�h�����邱�ƂɋC�����ǂ��Ȃ��Ă��܂��āA���̐��_��ԂŒ������̂ŗǂ����ɕ��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ȃ̂ł��ˁB
�p�c��Y���̓X�e���I�T�E���h���̎��M�w�ɂ��āACD�̘^���ɂ��g����Ă���l�ł����A�����������Ƃ���A�u�W���j�E�~�b�`�F���̔����Ȑ��g�����N���ɂȂ�A���y�S�̂̃��A���e�B�[���������v���ƂȂ�v�Ȃ�āA�悭����Ȃ��Ƃ����������̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�ނ̑��̕]�_��ǂނƁA����Ȃɂ��������Ȑl�ł��Ȃ������Ȃ̂ł����B
�ł��A�gCD���ڃ��b�s���O�h���R���g���[������Sony�̃\�t�g�ɉ��炩�̗D�ꂽ�d�g�݂�����\�����̂Ă���܂���B
�ǂȂ����A���ۂɎ��Ŕ�r���ꂽ���͂�������Ⴂ�܂��H
�����ԍ��F21724406
![]() 7�_
7�_
���������b�ŃX���傪�o�C�i������v���Ă����特�͕ς��Ȃ��Ƃ����l���̎�����Ȃ̂ŁA�ԐM����l�͂��Ȃ��Ǝv���܂���
�o�Ă����������@���̂���Ȃ�ł��傤����ˏ�
�����ԍ��F21724412�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
MAX���O�Y����
����͌���ł��B
���́u�o�C�i������v���Ă����特�͕ς��Ȃ��Ƃ����l���̎�����v�ł͂���܂��A����Ƃ͈Ⴄ�l���̐l��@�����������܂���B
��ŁA�p�c��Y���̌������Ƃ������������琳������������Ȃ��Ƃ����^�O��悵�Ă���ł͂���܂��B
�o�C�i���]�X�́A������Ƃ������������������Ă��邱�Ƃ��q�ׂ��܂łŁA�{���͂悭�킩���Ă��炸�A�ނ��뎄�͎����̎��ɕ����������̂���̌����ƂƂ炦��̂ŁA���ɑ��錻���̑O�ł͊ϔO�◝�_�͂����Ɏ̂Ă܂��B
�����A���ۂɎ��Œ����āgCD���ڃ��b�s���O�h�̕��������ǂ��Ƃ�����������ق炢��������Ȃ�A���͂���ɒǐ����āA�O�t��DVD�h���C�u���āgCD���ڃ��b�s���O�h���������ł��B
���Œ����ėǂ��Ȃ�A�o�C�i�����ǂ��Ƃ��͂ǂ��ł��悢���A����ł����o�C�i������v���Ă���̂ɉ������ǂ��ƂȂ����Ƃ�����A�����������Ƃ�����ȂƎv���āA���ۂɉ����ǂ��������܂���B
�����ԍ��F21724421
![]() 9�_
9�_
��Symbolist_K����
0,1�̃f�W�^���f�[�^�ŋL�^����Ă���A�ƌ����Ă����S�ȋ�`�g�ŋL�^����Ă���̂ł͖����A�݂����A�i���O�I�Ȕg�`�ŋL�^����Ă��܂��B�݂��Ă��Ă�0,1��ǂ݈Ⴆ�邱�Ƃ͂���܂��A���݂̓肩���̒��x�������ɉe����^���܂��B
���ڃ��b�s���O�͂��݂̓肩���̒��x�����Ȃ��A�������ɂȂ�̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21724512
![]() 11�_
11�_
�h���C�u��\�t�g�̐��\�ɂ����E����邻���ł��ˁB
���������f�[�^��Ō��Ă��u����̓E�\�ŁA����������悤�ɂ��������ŁA���ۂ͂���ȒP������Ȃ��v�Ɛ��Ƃ��������Ă܂�����B
�����ԍ��F21724833�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 9�_
9�_
Minerva2000����
���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B
�Ȃ�قǁA�L�^���ꂽ0,1�f�[�^�̋�`�g�݂̓���̒��x���A�����ɉe����^����̂ł��ˁB
�����āA�����炭���ڃ��b�s���O������Ƃ���Sony�̃\�t�g���D�G�ł���Ƃ������Ƃł��ˁB
�������܂��ƁAPC���b�s���O����Ȃ�A���b�s���O�\�t�g�͑I�ԕK�v������܂��ˁB
�����m�����AdBpoweramp����Ԑ��m�Ȃ悤�ł��B
�i��������dBpoweramp��EAC�̌��ʂ��r���đO�҂̏������Ƃ��Ă��܂��B
http://www.dbpoweramp.com/secure-ripper.htm�j
���ڃ��b�s���O����Ƃ���Sony�̃\�t�g v.s. dBpoweramp�Ȃ�A�ǂ��炪���D�G�Ȃ̂��Ƃ������ɂȂ�܂��ˁB�ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F21725337
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����
��CD���ڃ��b�s���O�h���R���g���[������Sony�̃\�t�g�ɉ��炩�̗D�ꂽ�d�g�݂�����\�����̂Ă���܂���B
�@���Ⴂ���Ă���悤�Ȃ̂Ő������܂��B���b�s���O�̖ړI�́ACD�ɏ������܂ꂽ���l���A�ς��邱�ƂȂ����o���̂��ړI�ł��B���ʂȎd�g�݂͂���܂���B���m�ɓǂݎ��邩�ǂ����́A�h���C�u�̐��\�ɂ����܂����A�ǂݎ��Ȃ��f�[�^���������ꍇ�͕⊮��������A���̏ꍇ�̓o�C�i������v���Ȃ��̂ʼn��������邱�ƂɂȂ�܂��B�o�C�i������v�����ꍇ�͗͂���܂���B
�o�C�i������v���������ʼn����ς�邩�ǂ����̎����ł��B�_�E�����[�h��́A
https://yahoo.jp/box/zYGHd9
�@�t�@�C�����e�͎���3�����B�i��������o�C�i�����S��v�t�@�C���j
test01
test02
test03
�@�����̕ҏW���e�̎菇�ł��B
�@test01���R�s�[����test02���쐬�A�o�C�i����v�̊m�F�ς݁B
�A���y�G�f�B�^�iAudacity�j��test01��test02��W�J���āAtest01������30sec�`60sec�̋�Ԃ�test02�����̓��ꕔ���Ɠ���ւ���test03�ŕۑ��B�i�o�C�i����v�̊m�F�ς݁j
���������e�X�g���@
�@test03�̉�����30�b��60�b�̈ʒu�ʼn���������ւ��܂����A�Ⴂ���������邩�ǂ������|�C���g�ł��B
�@����͒N�������Ă��킩��Ȃ��̂����ʂł��B�o�C�i����v�Ƃ͓��������ł��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B��̓����������I�ɐ�\�肵�Ă��A�f�[�^�͌������Ɠ����ł��B
�����ԍ��F21725352
![]() 16�_
16�_
S_DDS����
���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B
�����ł����A�ł̓o�C�i���`�F�b�N�Ȃǂ��܂肵�Ă��Ӗ��͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
�h���C�u�̐��\�ɂ����E�����Ȃ�A���ڃ��b�s���O����ɂ��Ă��ASony��Q&A�̉̃y�[�W�Ő�������h���C�u�̂�����DVR-UT24EZ���g�����ALDR-PUC8U3T���g�����ABRXL-16U3V���g�����ł������ς���Ă���\��������܂��ˁB�i����ɂ��Ă��A����Sony��Q&A�̉́u2016�N4�����݁v�ƂȂ��Ă��āA�����Q�N���O�̂��̂Ȃ̂ɁA�X�V����Ȃ��̂ł��傤���H�j
�ƂȂ�ƁA�u��ԗǂ��h���C�u���g�������ڃ��b�s���O�vv.s.�u��ԗǂ��h���C�u��dBpoweramp���g����PC���b�s���O�v�̏����ƂȂ�܂��ˁB
�ǂ��炪���ǂ����ɂȂ�̂ł��傤���H
�u����Ȃ��́A��������HAP-Z1ES�ƊO�t���h���C�u���āA�����Ŏ����Ă݂�v�ƌ���ꂻ���ł����A�����������Ă݂����������܂�����A�ǂ����������������܂��B���肢�������܂��B
�����ԍ��F21725374
![]() 7�_
7�_
�p�C������
�⑫���������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B
������HAP-Z1ES�ɑg�ݍ��܂�Ă���Sony�̃��b�s���O�\�t�g�ɗD�ꂽ�d�g�݂�����Ƃ���A����͉�����t����������C�������肷����̂ł͂Ȃ��i����Ȃ��Ƃ�������ނ���ɂȂ�j�ACD�ɏ������܂ꂽ���l��ς��邱�ƂȂ����m�Ɏ��o���\�͂ł���Ƃ������Ƃł��ˁB
�v����ɁA�u���b�s���O�\�t�g�̗D�G���Ƃ͂��̐��m���ł���v�Ƃ������Ƃł��ˁB
Sony�̃\�t�g v.s. dBpoweramp�̑Ό��ɂ��Ă��A���̐��m���̏����ł���Ƃ������Ƃł��ˁB
�����āA��萳�m�ȕ������Ȃ��A�����ǂ��͂��ł���ƁB
�u�o�C�i������v���������ʼn����ς�邩�ǂ����̎����v�A�����Ă��������܂����B
test03��30�b��60�b�̈ʒu�ʼn���������ւ�邱�Ƃ́A���ł͑S���킩��܂���ł����B
�����ԍ��F21725406
![]() 7�_
7�_
���u�o�C�i������v���������ʼn����ς�邩�ǂ����̎����v�A�����Ă��������܂����B
test03��30�b��60�b�̈ʒu�ʼn���������ւ�邱�Ƃ́A���ł͑S���킩��܂���ł����B
�@�������łȂ��A���̃f�[�^���w�̌������ŕ����I�ɕ��͂��Ă�����Ă��Ⴂ�͂킩��܂���B�S�������f�[�^���m���r���Ă���̂Ɠ����ł�����B
�����ԍ��F21725487
![]() 8�_
8�_
�p�C������
���̔g�`���炵�đS����v����Ƃ������Ƃł��ˁB
�����o�C�i���͓������̂ŁA������Đ����u�ɂ����ďo�鉹�̔g�`�������ł���B��������ŋ�ʂł���͂����Ȃ��A�����Ȃ̂�����ƁB
�������܂��Ƃ�͂�ACD�ɏ������܂ꂽ���l��ς��邱�ƂȂ��Ȃ�ׂ����m�Ɏ��o�����Ƃ̂ł���������A���ǂ����b�s���O�ł���A���ǂ����̌��ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
����́uHAP-Z1ES�{Sony�̃\�t�g�v�Ȃ̂��͂��܂��uPC�{dBpoweramp�v�Ȃ̂��H
�g���h���C�u�̖�������܂����B
�����ԍ��F21725553
![]() 7�_
7�_
��Symbolist_K����
CD�̃��b�s���O�ł̓h���C�u�ɂ���Ă��A�\�t�g�ɂ���Ă��������ς��܂��B
����͂O�C�P�̃f�[�^�������������Ă��Ȃ����特�����ς��̂ł͂���܂���B
�ǂ̃h���C�u�ł��\�t�g�ł��A��قǏ�������CD�Ŗ�������A���L��C2�G���[�͂܂��������܂���BC1�G���[�Ȃ犮�S�ɒ�������܂��̂ŁA�O�C�P�̃f�[�^�͐��m�ɓ����܂��B
---------------------------------------
CD�ł́A�o�[�X�g�G���[�ɑΉ����邽�߁A���̃f�[�^�ɒ����p���[�h�\������������t���A������̃t���[���ɕ��U���Ă���B���̎��̃��[�h�\������������C2�����Ƃ����B
���ۂ�CD��ǂݎ���ăt���[�����̌��������s�Ȃ����A�����Œ����ł��Ȃ����Ƃ�C1�G���[�Ƃ����B���U���ꂽ�f�[�^�����̏����ɖ߂����A���̎��ɂ�C1�G���[�̃f�[�^�̍s����͊m�F�ł��Ă���̂ŁA�����C2�����Œ�������B
C2�����ł�224�r�b�g��32�r�b�g�܂ł̃G���[������ł��邪�A���������ł�����������Ȃ��ꍇ��C2�G���[�ƌĂԁB
CD-DA(���yCD)�̏ꍇ�AC2�G���[�����������ꍇ�͑O��̐���ȃf�[�^�̕��ϒl���Ƃ铙�̕��@�ɂ��A�������邱�Ƃŕ�Ԃ���B
���̂��߁A�����͗��邪�A�h�����čĐ��͂ł���B
---------------------------------------
�Ȃ����b�s���O�̃h���C�u��\�t�g�ʼn������ς�邩�́A���\�j�[�̂����Ȃ܂鎁�̉�����Q�l�ɂȂ�܂��B
[111212]
�y�Ȃ��R�s�[���邽�тɉ������ς��̂͂Ȃ��ł����B
http://kanaimaru.com/AVQA/0f.htm
���O�Ԍo�R�Ń_�E�����[�h����ƁA��L�̃l�b�g���[�N��ʂ����Ƃɂ��W�b�^�[�����_�����O�������āA���̈Ⴂ���قƂ�Ǖ�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F21725618
![]()
![]() 8�_
8�_
�����̔g�`���炵�đS����v����Ƃ������Ƃł��ˁB
�@�o�C�i������v�������ꉹ�����Đ������Ƃ��Ă��A���̔g�`�͈�v���邱�Ƃ͂���܂���B
�@�����Ɍ����ƁA�T���v�����O���ꂽ�f�W�^���f�[�^�́A����K���ɏ]���č��ꂽ���U�f�[�^�i���l�����ꂽ�f�[�^�j�Ȃ̂ŁA���ꎩ�͉̂��̔g�`�ł͂���܂���B���̃f�[�^���T���v�����O�̋K�������ƂɁADAC��ʂ���D/A�ϊ����Ă͂��߂ĉ��̃A�i���O�g�`�̐M���ɂȂ�܂��B�A�i���O�����ꂽ�d���M���́A��H��\������f�q�ɂ��e�����āA�K�������܂��B
�@�T���v�����O�f�[�^���ꏏ�ł��A�A�i���O�����ꂽ���y�M���ɂ́A�K���m�C�Y��c���̂�܂��B
�@���̃m�C�Y��c�̓^�C�����C���Ŋm�F����Ǝ��Ԏ��Ń����_���ɔ������A�������ω����Ă���A����̂��̂͂���܂���B
�@�Ȃ̂ŁADAC����o�͂��ꂽ���y�g�`+�m�C�Y+�c�̍Đ����́A�����������J��Ԃ��čĐ������Ƃ��Ă��A�����ɂ͓������ɂ͂Ȃ�܂���B�܂�A�o�C�i������v���Ă��鉹�����A10��A���ōĐ������ꍇ�A���̓s�x������m�C�Y��c�������ɉ���邽�߁A�����I�ɂ͂��ׂĈ�������ɂȂ�܂��B
�@������ׂ�ꍇ�́A�f�W�^���ƃA�i���O�̐����𗝉�������ŁA�������Ę_����Ƃ킩��₷���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21725622
![]() 12�_
12�_
�p�C������
���݂܂���A�u�����I�ɕ��́v�Ƃ����̂�g�`�̂��Ƃ��Ɗ��Ⴂ���Ă��܂����B
��DAC����o�͂��ꂽ���y�g�`+�m�C�Y+�c�̍Đ����́A�����������J��Ԃ��čĐ������Ƃ��Ă��A�����ɂ͓������ɂ͂Ȃ�܂���B�܂�A�o�C�i������v���Ă��鉹�����A10��A���ōĐ������ꍇ�A���̓s�x������m�C�Y��c�������ɉ���邽�߁A�����I�ɂ͂��ׂĈ�������ɂȂ�܂��B
�Ȃ�قǁB�ł��A�������ɂȂ�Ȃ��Ƃ��Ă��A���Ƃ��ėD������悤�ȗL�Ӎ��͐������A����10��A���ōĐ������Ƃ��ɁA�Ⴆ�u�W�Ԗڂ���ԉ����ǂ������v�Ȃ�Ă��Ƃɂ͕��ʂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���ˁB�������Ȃ���A�u�W�Ԗڂ���ԉ����ǂ������v�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�\���͂O�ł͂Ȃ��A�ɂ߂ċH�Ȃ���Ȃ��Ă��܂����Ƃ��������肷��̂��A�i���O�̕s�v�c���Ȃ̂ł��傤���H
�Ƃ���ŁA�p�C������AMinerva2000���Љ�ꂽ���Ȃ��܂邳��̉�ǂ܂�܂������H
�p�C������́A
���f�W�^���M���́A���̔g�`�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�Q�i�@�̐��l�f�[�^�ł��B�f�o�C�X��ς��ă��b�s���O�����f�[�^�ł����Ă��A�o�C�i������v���Ă���ꍇ�́A���l�̓]���~�X�͂Ȃ��̂œ����f�[�^�ɂȂ�܂��B���Ƃ��A���̃f�[�^��10000��J��Ԃ��ăR�s�[���Ă��A�ŏ��ƍŌ�̃o�C�i������v���Ă���A�f�[�^�̗i�G���[�j�͐����ĂȂ��̂ŁA���b�s���O�����o�C�i������v���Ă���Q�̃f�[�^���A�����o�H�i�ڑ��j�Ɠ����I�[�f�B�I�@��ōĐ������ꍇ�́A�������ɂȂ�܂��B
�ƌ����܂������A���Ȃ��܂邳��ɂ��ΈႤ���ɂȂ邻���ł��B�f�W�^���f�[�^�������ł��A�����Ă��ꂪ�����n�[�h�f�B�X�N��ɂ������Ƃ��Ă��A�X�g���[�W��ɂ��邻�̂�����ɂ���ĉ����ς�邻���ŁA
�����ǁA�p�P�b�g�ɂ炷���Ƃ�key�Ƃ���A���̃��x���ɃN�Z���������Ƃ͉\�Ȃ�ł��B�����킢�f�W�^���f�[�^(PCM�̌X�̒l)�͕ω����܂���̂ŁA�������ێ������킳�����ĂA���ɖ߂����@�͂���̂ł��B
�Ƃ̂��Ƃł����A�ǂ��v���܂����H
�����ԍ��F21726319
![]() 7�_
7�_
Minerva2000����
�F�X�Ƃ��������肪�Ƃ��������܂��B
C1�G���[�͒����\�Ȃ̂Ŗ��Ȃ����AC2�G���[�͒����s�\����ԑΏۂȂ̂ŗ̌����Ƃ������Ƃł��ˁB
���ǂ̃h���C�u�ł��\�t�g�ł��A��قǏ�������CD�Ŗ�������A���L��C2�G���[�͂܂��������܂���BC1�G���[�Ȃ犮�S�ɒ�������܂��̂ŁA�O�C�P�̃f�[�^�͐��m�ɓ����܂��B
�������A��Ɉ��p���܂���Illustrate�̌��ɂ��܂��ƁA
http://www.dbpoweramp.com/secure-ripper.htm
C2�G���[�͂�����x�p�ɂɋN�����Ă��āAdBpoweramp��EAC�ŁgC2 error pointer�h���I���ɂ��Ă����ƁAC2�G���[���N�������ӏ���������x���b�s���O���Č��ʂ��r����B�����āAC2���m���ƂȂ�A�h���C�u��CIRC�ɕ�Ԃ�����Ȃ�AAccurateRip�������Ă���Ȃ肷��悤�ł��B
���Ȃ݂ɁA������̃u���O�̂炩������ɂ��A
http://erijapan.blog93.fc2.com/blog-entry-51.html
iTunes�́gC2 Error Info�h�̏����g���Ă��Ȃ������ŁAiTunes�ł͏ꍇ�ɂ���Ă͂��Ȃ�s���m�ȃ��b�s���O�ɂȂ�悤�ł��ˁB
http://ch.nicovideo.jp/rgb/blomaga/ar1170756
����ȃT�C�g�������܂����B���̕��̓p�C��������Љ�ꂽWaveCompare for Windows���g���Ĕ�r����Ă��܂����AiTunes�Ń��b�s���O�������ʂ́A�I���W�i����wav�Ƃ̓o�C�i���\�I�Ɂu���Ȃ�Ⴄ�v���̂ɂȂ邻���ł��I
���������āA��͂�\�t�g�ɗD��͂���悤�ł��B�idBpoweramp��EAC����iTunes�j
�܂��A��̂炩������H���A
���\�t�g���ł́uCIRC�G���[�����v�͂��Ă��Ȃ��̂ł�����ARipping�i���̗v�͂���ς�u�h���C�u���\�v�Ȃ̂ł��B�h���C�u�̓ǂݎ�萫�\���Ⴏ��\�t�g�������x�ǂ�ł��_���Ȃ��̂̓_���ł��傤�BC1��C2�̃G���[���������CIRC�ɂ��K��Ȃ̂ō��͖������߁A�v�͌��w�I�Ȑ��\�ɂȂ�Ǝv���܂��B
��͂�h���C�u�ɂ��D��͂���悤�ł��ˁB
�炩������̂܂Ƃ߂����ɗ��Ǝv���̂ň��p���܂��ƁA�h���C�u�ƃ\�t�g�̑g�ݍ��킹�łS�̃p�^�[��������悤�ł��F
��
�E�Z�L���A���b�p�[�F����h���C�u��p�E�E�E��\��uPlexTools Professional�v
�@����m������h���C�u�ƈ�S���̂ł���Ă�̂œ���͕ۏ���邪����h���C�u�ł����g���Ȃ��B
�E�Z�L���A���b�p�[�F�ėp�h���C�u�p�E�E�E��\��uEAC�v
�@������ă\�t�g�E�F�A�ł���Ă邩�����h���C�u�ȊO�ł��@�\���邪�ۏ̌���ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�h���C�u�̃t�@�[���ɂǂ�ȃo�O�����邩����������Ȃ��B
�E�Z�L���A�Ƃ͌����ĂȂ����b�p�[�F�ėp�h���C�u�p�E�E�E��\��F�uiTunes�v
�@������u�G���[�����v��ON�ɂ���Ƃ�����Ƃ���邯�ǁA�Z�L���A���b�p�[�قǂ͂����Ȃ��i��ʓI���p�ł̗�����D�悵�Ă���Ǝv����j�B�܂��A���[�h�L���b�V���@�\������h���C�u���ƒ��߂��Ⴄ�B
�E���b�s���O���x����@�\�t���h���C�u�E�E�E��\��uPureRead�V���[�Y���ڃh���C�u�v
�@�h���C�u�̃t�@�[���E�F�A�ŏ��u�B������p���[�e�B���e�B�Ő���ł���B�t�@�[�����x���Ȃ̂�PC����I/F�K�肵�Ă��Ȃ��悤�ȏ����g�������l�ȃ��g���C�ł���B
��ɋ�����Illustrate�̃y�[�W�ł��A�Â�Plextor�̃h���C�u���AMatsushita��NEC�̃h���C�u���D��Ă���ƌ�����Ă��܂��B���Ȃ��܂邳����A�u�Â��v���N��TEAC�̃h���C�u���������悢�̂͗L���ł��v�ƌ����Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F21726328
![]() 7�_
7�_
���Ȃ��܂邳��́u[111212]�y�Ȃ��R�s�[���邽�тɉ������ς��̂͂Ȃ��ł����B�v�ɑ���́A�����[���ł��B
���f�W�^������1��0��������܂��A���ۂ̋L�^�͂ӂɂ�ӂɂ�ȃA�i���O�̔g�`�ŏo���Ă��܂��B�ǂݏo���Ƃ��ɁA������x�ȏ�̓d����1�A������x�ȉ���0�Ƃ��邾���ł��B�ӂɂ�ӂɂ�Ƃ́A1�ƋL�^�������̂́AHDD��ł�1�ł͂Ȃ��āA����O�a�l��1�Ƃ�����A0.7�`1.0���炢�ɋL�^����Ă���Ƃ������Ƃł��B0�ƋL�^�������̂�0�`0.3���炢�ł��傤���B�����0.5���炢�ŏォ�����Ŕ��肷��A�����Ƃ��Ă͂��Ƃɖ߂�܂��B
�����Minerva2000����̂��w�E�̂��ƂƏd�Ȃ�܂��ˁB
���Ƃ��낪�A����0����1�A1����0�֔��]����^�C�~���O�́A���̃A�i���O�̓ǂݏo�����g�`���ア�ƁA�O���O���Ǝ��ԓI�ɑO��ɗh��܂��B�h��Ă��ǂݏo���^�C�~���O�܂łɂ͕K�����肵�܂��̂�(�����Ȃ�悤�ɃT�[�{�n�����삵�Ă��܂�)��͂萔���͊ԈႢ�܂���B�Ƃ��낪�g�`�����]����Ƃ��ɂ͓d���ɃX�p�C�N�m�C�Y������܂��B�g�`���O���O���h��Ă���ƁA���]�m�C�Y���o��^�C�~���O���O���O���ɂȂ�܂��B���ꂪ��������DA�ϊ��̃N���b�N��h�炷�Ɖ������Q���܂��B�܂��R�s�[���͌��ɔ�ׂ�Ɨh�ꂪ�����Ȃ�̂ŁA�������ς���čs��(��ʓI�ɂ͗��čs��)�̂ł��B
�����������̂Ȃ�ł��傤���I
���̎w�E���d�v�ł��F
����ʓI�Ƀf�W�^���f�[�^���������悢�̂́ACD����̃��b�s���O�ł͓ǂݏo��������ł��B�h���C�u���Ƃ��Ɏw�ߗp�Ɏg�������C���Y��ȃN���b�N��HDD�ɂ��͋����L�^����邩��ł��B�Ƃ��낪������R�s�[����Ƃ��́A�f�[�^��ǂݏo�����Ƃ��̃m�C�Y���L�^�����g�`�ɍ��Ղ��c���̂ŁA�������ς��̂ł��B
���ꂪ��������A�������Ɂu�gCD���ڃ��b�s���O�h�̉���PC���b�s���O�̉��ɗD��v�Ƃ����p�c��Y�������̎咣���������ꍇ�ɂ́A���̗��R�Ƃ��Ĉȉ��̉�������������܂��F
�u�gCD���ڃ��b�s���O�h�́ACD����ǂݏo���ꂽ�f�[�^���AHAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɁA���C���Y��ȃN���b�N�Œ��ڗ͋����L�^�����̂ʼn����ǂ��BPC���b�s���O�́A�f�[�^��HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɂQ���I�ɃR�s�[�����̂ŗ��B�v
�����������Ƃ����蓾��ȂƂ����C�����ɂȂ��Ă��܂��B
�������A���̋L�q���C�ɂȂ�܂��F
�������������Ȃ��Ă��܂����ꍇ�A������@������܂��B����̓l�b�g���[�N��ʂ����Ƃł��B�l�b�g���[�N�̓p�P�b�g�ʐM�Ȃ̂ŁA�A���g�`����x�����̌ł܂�Ƀo���o���ɂȂ�܂��B�܂��l�b�g���[�N�͒ʏ�ǂݏo�������N���b�N�������Ă��܂��̂ŁAHDD�ɏ������ނƂ��Ƀt���b�V���ȃN���b�N���g���܂��B
�Ƃ���APC���b�s���O�ł��A���̃f�[�^���iUSB�ڑ��ł͂Ȃ��jLAN��ʂ���HAP-Z1ES�̃n�[�h�f�B�X�N�ɏ������܂��̂ł���A�t���b�V���ɏ������܂��̂ł���ł����̂ł͂Ȃ����H
����ɁA��xWAN���o�R����Ɗ��S�Ƀt���b�V���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��ˁB
�܂��܂��A���ڃ��b�s���O��PC���b�s���O�A�ǂ���̕����D��Ă���̂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�����ԍ��F21726337
![]() 7�_
7�_
���Ȃ��܂鎁�̓\�j�[�ɍݐЂ��Ă���v���̋Z�p�҂Ȃ̂ŁA�g���Ă���@�ނ�P�[�u���ނ̃��x������ʃs�[�v���Ƃ͈Ⴄ�Ǝv���܂��B
����͂��Ȃ��܂鎁�̃z�[���y�[�W�ɂ��Ƃ���ǂ���ɏ����Ă���܂��B�ׂ��ȃA�N�Z�T���[�ɂ����Ă��������ᖡ���������Z���N�g���Ďg���Ă����
����ɔ�ׂĂł����A�]�_�Ƃ̊p�c���͍��x�ł͂��邯�ǃA�}�`���A���x���̈���Ȃ��������ł̔��f�Ȃ̂ŁA���Ȃ��܂鎁�ƈӌ����H���Ⴂ�̂��d�����Ȃ����Ǝv���܂�
�ȒP�ɏ����ƁA�����]���Ɏg���ׂ�LAN��H�Ɏg���Ă��郋�[�^�[��X�C�b�`���O�n�u��LAN�P�[�u���̎����Ⴄ�낤�Ƃ������Ƃł���
�����ԍ��F21726484�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��Symbolist_K����
C2�G���[�����o���Ȃ������G���[��C2�G���[�ƌĂт܂��B����܂�EAC�ő��ʂ�CD�����b�s���O���Ă��܂������AC2�G���[�����͈ꖇ��CD��10����x�N���������Ƃ͂���܂����AC2�G���[�̌o���͖����ł��B�܂�0�A1�̃f�[�^�͊����Ƀ��b�s���O�o���Ă��܂����B
����C2�G���[��10��N������WAV�t�@�C�����Đ����Ă��A�ǂ��Ő��`��Ԃ������͒N��������Ȃ��ł��傤�B�܂艹���͕ς��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
1�A2m�̃C�[�T�l�b�g�P�[�u����ʂ������炢�ł̓W�b�^�[�����_�����O�͏o���܂���B�N���E�h�ւ̃A�b�v���[�h�ƃ_�E�����[�h���s���K�v������܂��B
�����ԍ��F21726506
![]() 10�_
10�_
��Symbolist_K����
������ȃT�C�g�������܂����B���̕��̓p�C��������Љ�ꂽWaveCompare for Windows���g���Ĕ�r����Ă��܂����AiTunes�Ń��b�s���O�������ʂ́A�I���W�i����wav�Ƃ̓o�C�i���\�I�Ɂu���Ȃ�Ⴄ�v���̂ɂȂ邻���ł��I
�@
�@����͑z���ł����A�������b�s���O��������̓o�C�i�����S��v�Œ��o���Ă邯�ǁAitunes�ŕۑ�������Ƃ��ɁA���������i�m�C�Y�V�F�C�r���O�j�����������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B
�@�A�b�v�}�̇C�͉��y�G�f�B�^���g���ĕۑ�����Ƃ��ɁA�f�B�U�����O�������I���ɂ��ăm�C�Y�V�F�[�r���O�������ĕۑ������ꍇ��FFT�i�����t�[���G�ϊ��O���t�j�ɂȂ�܂��B
�@���̏���������ƒ��o�ɕq���Ȓ�����ɑ��݂���m�C�Y�t���A�������邱�Ƃ��ł���̂ŁA�N���A�ȉ����ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B�o�C�i���͓��R��v���Ȃ��̂ŕ����I�ɂ͗ɂȂ�܂����A���o�I�ɂ̓N���A�ȉ����ɂȂ�܂��B
�@�Ȃ̂ł����ۑ����邾���̃\�t�g�Ɣ�ׂ�ƁA���Ԃ�ǂ����i�N���A�ȉ��j�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������̗\�z�������Ă���̂Ȃ�A�������l�ԍH�w���n�m���Ă���A�b�v���Ƃ��������ł��B
�@
�����ԍ��F21727215
![]() 10�_
10�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
HAP-Z1ES�AWINDOWS�P�O�m�[�gPC���ɓ�������LAN���C���^�[�l�b�g�ڑ����Ă��܂��B
HAP MUSIC�@TRANSFAR�ŃR�s�[�ׂ̈ɐڑ����悤�Ƃ���ƁuIP�A�h���X���قȂ邽�ߐڑ��ł��܂���v
�ƂȂ�܂��B
���ׂ��HAP��PC��IP�A�h���X�̉��ꌅ���Ⴂ�܂��B
����LAN���[�^�[����x���Z�b�g������AHAP�@MUSIC�@TRANSFAR���C���X�g�[�����Ȃ������肵�Ă��_���ł����B
�X�}�z�Ƃ͖���LAN�Őڑ��ł��Ă��܂��B
�����������@�������m�Ȃ�����ĉ������B
![]() 1�_
1�_
��ABEBIREX����
HAP��PC��IP�A�h���X�̉��ꌅ�������Ⴄ�͖̂��Ȃ��ł��B
�{�@�̃��Z�b�g�͎�����܂������H
�����ԍ��F21748248
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�{�̂̏����������܂������������ł��Ă��Ȃ��悤�ł��B
���y�f�[�^���c���Ă���A�A�b�v�f�[�g�����ꂽ�܂܂ł��B
���Âōw����������Ȃ̂ł����̏�ł��傤���H
�̏�ł���Εԕi�̓s��������܂��̂Œm���̂��邩���̕ԐM���X�������肢���܂��B
�����ԍ��F21749174
![]() 0�_
0�_
�{�̂ŃA���o���͈���폜�ł��܂����B
�A���A�n�[�h�f�B�X�N�̍ăX�L�����A�H��o���ݒ�����܂��Ă����y�f�[�^�̓N���[���ɂȂ�܂���B
�Q�O�P�R�N���ł����A�A�b�v�f�[�g���ŐV�̂܂܂ŃI�[�f�B�I�ݒ������������܂���B
�̏Ⴉ�Ǝv���ƐS�z�ł��B
�ǂȂ����m���̂�����X�������肢���܂��B
�����ԍ��F21749270
![]() 0�_
0�_
�{�̂ŃA���o���̍폜�͏o�����̂ł����A������������܂����y�f�[�^���P�O�Ȃɖ߂��Ă܂����B
�������ݒ蓙�̏��������o���Ă܂���B
�̏Ⴉ�ǂ������f���Ē��������Ǝv���܂��B
�ǂȂ����X�������肢���܂��B
�����ԍ��F21749450
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
�̏�̉\��������̂Ń\�j�[�ɑ��k����Ă͂������ł��傤�B
�����ԍ��F21749799
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
���͂悤�������܂��B
��͂�̏�ł��傤���H
���t�I�N�Ōl�o�i�҂��璆�Õi���w����������Ȃ̂ł��Ȃ�c�O�ł��B
�Ƃ肠�����ʖڌ��ŕԕi�����肢���Ă݂܂��B
�t���s��̃��R�[���̑Ώۏ��i�ɂ��Ȃ��Ă��܂��̂ōŏI�I�ɂ�SONY�̂����b�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21749815
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
�H��o���ɖ߂��Ă��t�@�[���E�F�A�͖߂�܂���B
�܂��T���v���Ȃ͓�������ԂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F21749823
![]() 1�_
1�_
��mctoru����
�t�@�[���E�F�A�͏������ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��ˁB�����Ă���Ȃ��ǂ��݂���T���v���ł����B
�Ƃ肠�����̏�ł͂Ȃ������ł��B
���肪�Ƃ������܂��B
���Ƃ͖���LAN�ڑ����o����Ηǂ��̂ł����B
�����ԍ��F21750589
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
���[�^�[�Ɩ{�@�����Z�b�g���Ă��������Ȃ���Ȃ��̂��A�̏Ⴞ�Ǝv�����̂ł����B
���������ăt�@�[���E�G�A���߂�Ȃ�������A�T���v���������Ȃ��͕̂��ʂł��B
�����ԍ��F21750646
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
������������t�@�[���E�F�A�͖߂���́A�T���v���f�[�^�͑O�̎�����̃f�[�^���Ǝv���Ă܂����B
���̊��Ⴂ�ł����f���|�����܂����B
���肪�Ƃ��������܂��B
����LAN�ڑ��Ȃ̂ł����A�G�N�X�v���[���[��HAP-Z1es�̉��y�f�[�^���p�\�R���ɃR�s�[���邱�Ƃ͂ł��܂����B
�ԈႢ�Ȃ��q�����Ă��܂��B
�Ȃ�Hap Music Transfer����f�[�^�̃R�s�[���o���Ȃ��̂��s�v�c�ł��B
�����ԍ��F21750778
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
���L���Q�Ƃ��������B
http://helpguide.sony.net/ha/haps1/v1/ja/contents/TP0000165239.html
�����ԍ��F21750820
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�ǂ܂��Ē����܂����B
�w���v�K�C�h�̂Ƃ���h���b�O&�h���b�v�ʼn��y�t�@�C�����R�s�[���悤�ɂ��A�mHAP���Q�Ɓn����G�N�X�v���[���[���J���Ă���܂���B
���ڃG�N�X�v���[���[���J���܂��ƁAPC�́h�l�b�g���[�N�̏ꏊ�h�̂Ƃ����HAP-Z1ES��VAIIO�i�����L��PC�j������܂��B
HAP-Z1ES���特�y�f�[�^��PC�ɃR�s�[�ł��܂������̋t�͏o���܂���B
���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F21750878
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
���L���Q�Ƃ��������B
https://www.sony.jp/audio/update/?nccharset=ACDE0384&searchWord=Hap
�����ԍ��F21750952
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�{�̃A�b�v�f�[�g�͍ŐV�ł��B
���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F21751188
![]() 0�_
0�_
�ƂȂ�ƁA��͂�\�j�[�ɑ��k�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21751709
![]()
![]() 1�_
1�_
��Minerva2000����
���r���O�Ɏ�������Ń��f������L��LAN�Őڑ��A�E�C���X�\�t�g�̈ꎞ���f������Ă݂܂������ʖڂł����B
�X�}�z����̃R�s�[�͂Ƃ肠�����ł��܂�������̃A���o������ɕʂ�Ă�����]�v�ȕ��܂ŃR�s�[�����肵�đʖڂł����B
�Ƃ肠���������͔�ꂽ�̂ł��̕ӂŎ~�߂Ƃ��܂��B
�܂������F�X����Ă݂܂��B
�Ō�͕ԕi���\�j�[�ɑ��k�ɂȂ肻���ł��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21751835
![]() 0�_
0�_
PC�����������܂����疳��HAP-Z1ES�Ɩ���LAN�Ōq����܂����B
PC�Ƃ̑����̖��ł��傤���H
PC��VAIO�Ȃ̂�SONY���m�ő����������Ƃ����̂��ǂ����ƁB
����Ɖ����v���܂����B
�F�l���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21753752
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
��������ėǂ������ł��ˁB
�Q�l�܂łɋ����Ē��������̂ł����APC�̏������Ƃ͋�̓I�ɂ͉������ꂽ�̂ł��傤���H
�܂���HDD�̃t�H�[�}�b�g��OS�̓��꒼���͂���Ă��܂����ˁB
�P�ɃV���b�g�_�E���ƍċN���ł��傤���H
�����ԍ��F21753815
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
windows10�Łu�ݒ�v�́u�X�V�ƃZ�L�����e�B�v�ɂ���u�v����A�u����PC��������Ԃɖ߂��v���N�����u�l�p�t�@�C����ێ�����v��
���������܂����B
�E�B���X�\�t�g����K�v�������\�j�[��VAIO�A�v���܂őS�������܂����B
����ł���ƌq����܂����B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21753854
![]() 0�_
0�_
��ABEBIREX����
�����܂ł���܂������B
�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21753857
![]() 0�_
0�_
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[ > SONY > HAP-Z1ES
�{�@�̃f�W�^���o�͋@�\�lj������p���ĊO��DAC���g�����ƍl���Ă��܂����A�Ȃ��Ȃ��������m��������܂���B��]�̓w�b�h�t�H���A���v�Ȃǂ̗]�v�ȋ@�\�Ȃ��̏����ȃI�[�f�B�IDAC�ŁA�������HAP-Z1���鉹�����҂������̂ɂȂ�܂��B����Ƃ�����܂��ł����AUSB�ڑ��̃h���C�o�[�̃C���X�g�[���ȂǗv���Ȃ����m���K�{�ł��B�悸�͂��낢���~�����̂ŁA�u�Ȃɂ�������HAP-Z1���鉹�Ƃ������H�v�Ȃ�Ă����c�b�R�~�͔����ł��肢���܂��B���i�тƂ��Ă͐V�i��30���~���x�ȉ��ł��肢���܂��B�����̊��̓A�L��C2420���A�L��A-30���_���̃w���R��400MK2�ł��B��낵�����肢���܂��B
![]() 5�_
5�_
��996s68����
��USB�ڑ��̃h���C�o�[�̃C���X�g�[���ȂǗv���Ȃ����m���K�{�ł��B
���݂܂���B���̕ӂ͂��X�����[�J�[�ɖ₢���킹�Ē��������̂ł����A�A�L���t�F�[�Y�ӂ肪����ł͂Ȃ��ł��傤���H
https://www.accuphase.co.jp/model/dc-37.html
http://review.kakaku.com/review/K0000699509/#tab
�����ԍ��F21493375
![]() 0�_
0�_
����SONY��USB-DAC/�w�b�h�z���A���v�� TA-ZH1ES���ǂ��̂ł͂Ǝv��܂��BDSD���Đ��ł���悤�ł��B
�u�@https://www.phileweb.com/review/article/201611/04/2278_2.html�@�v
���̓A�����b�N��AL-9628D��ڑ����ĕ����Ă��܂����{�̂ɂ͂Ȃ����y��������܂��̂ŗ����܂���B
�����̃V�X�e���\���ɂ��˂�܂�������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21494976
![]() 0�_
0�_
��music art����
������SONY��USB-DAC/�w�b�h�z���A���v�� TA-ZH1ES���ǂ��̂ł͂Ǝv��܂��BDSD���Đ��ł���悤�ł��B
�����ł���ˁB�������Ƃ͎v���܂�������SONY�̉����낤���A�������Ă�������Ƃ���w�b�h�t�H���A���v���t���Ă��Ȃ�������DAC����]�Ȃ̂�TA-ZH�͑ΏۊO�ɂ��Ă܂����B
�����̓A�����b�N��AL-9628D��ڑ����ĕ����Ă��܂����{�̂ɂ͂Ȃ����y��������܂��̂ŗ����܂���B
�A�����b�N��AL-962D�̂ق������C�ɂȂ�܂����Bmusic art�����HAP-Z1�Ɏg���Ă���̂ł��傤���H �Ƃ������Ƃ�HAP-Z1��USB�Ŗ��Ȃ��ڑ��o���Ă�Ƃ������Ƃł���ˁH ������ƒ��ׂĂ݂����ł��B
�����ԍ��F21495082
![]() 3�_
3�_
��996s68����
�l�b�g�Ō������Ă������ȏ��USB DAC��ڑ����Ă����قƂ�nj�����܂���B
�Ή����Ă���R�[�f�b�N�����ƂȂ��Ă͌���肷��̂ƁAZ1ES��USB�o�͂̎�����p�g�����X�|�[�g��PC�ɔ�ׂč��ЂƂȂ̂����R���Ǝv���܂��B
30���ȓ����ƕ]���̗ǂ�SOULNOTE D-1�����߂����̂ł����AZ1ES�Ɛڑ��ł��邩�O�O���Ă�������܂���ł����B
�w�b�h�z���A���v���t���Ă��܂����A�����������������TEAC UD-505���ڑ��ł���Ηǂ������ł��B
���̓l�b�g�Őڑ��̎��т̂�����Sonica DAC���w�����܂������A�������C���������D�݂ɍ���Ȃ��Ƃ����l�����܂��B�d���P�[�u����USB�P�[�u���A�o�����X�P�[�u������I�ׂΎ�_���J�o�[�����Z1ES�����t���̗ǂ��Z���߂Ȋ����ł��B
����DSD�Đ��ŋȊԂɎ�m�C�Y������܂��B
�����ԍ��F21495572
![]()
![]() 1�_
1�_
��mctoru����
�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��I
���l�b�g�Ō������Ă������ȏ��USB DAC��ڑ����Ă����قƂ�nj�����܂���B
�����Ȃ�ł��B�Ȃ��Ȃ�������Ȃ���ł��B���̂Ƃ����̓I��Z1ES�Ƃ̐ڑ����l�b�g�Ō�����ꂽ�̂�OPPO��MEITNER��MA1�����B
OPPO�͉��i�I�ɂ��育�낾���A�O�]���i�G���͂������������ǁE�E�j���ǂ������̂ň�Ԍ�₾�������ǁA��ʃ��[�U�[�Ɏ��@���L�܂�ɂ�āu����قǂł��E�E�v�ɂȂ��Ă��Ă���̂ł�����Ƒ����݂��Ă܂����B
SOULNOTE���D���ȃ��[�J�[�Ȃ̂ŋC�ɂ��Ă܂������A��͂�ڑ�������̂��l�b�N�ł��BUSB�ڑ��ɐ�p�\�t�g�̃C���X�g�[�����K�v���ǂ����̓��[�J�[�ɕ��������Ă���邯�ǁAZ1ES�Ɛڑ��\���ǂ����͎��ۂɎg�������[�U�[�łȂ��Ƃ킩��Ȃ��̂ł����ŕ��������Ȃ���ł���ˁ`�B���܂�������ł��B
���Ȃ݂ɁA�O�q��MEITNER��MA1�͌q���������т̓l�b�g�ɂ����ł����A�I�[�i�[����ɂ��Ɓu��Ȗڂ̏o�������v�Ƃ����Ǐo��Ƃ̂��Ƃ����A��������100���~�I�[�o�[��DAC�Ȃ̂Ŗ��O�ł��i�j
�������������������TEAC UD-505���ڑ��ł���Ηǂ������ł��B
�V���i���o��̂ł����H�f�U�C�����ς��Ȃ�A�����ȁ`�B�ǁ`�ɂ�TEAC�̃f�U�C����������Ȃ��E�E�i�j
������DSD�Đ��ŋȊԂɎ�m�C�Y������܂��B
����A�����ł��B�ǂ�Ȋ������悯����������ڂ��������Ă��������BOPPO�͂܂����ɓ����Ă���̂ŁB
�Ƃ���ŁAMEITNER��MA1�̃I�[�i�[��������Ă���̂ł����AZ1ES�̋��N2���̖{�̃\�t�g�̃o�[�W�����A�b�v�ŁA�f�W�^���o�͂̉��ʂ��啝�Ƀ_�E�����āA�����{�����[�����グ�Ȃ��ƒ������Ȃ��Ǐo�Ă���Ƃ̂��ƁB�\�j�[���̂�����͊m�F�ς݂����ǁA����DAC�ȊO�ł̏Ǐ�Ȃ̂őΉ����邩�ǂ�������Ƃ̂��Ƃł��BOPPO�ł͂���ȏǏ�Ȃ��ł��傤���H�X�y�V�������[�h�Ńo�[�W�����߂�����Ή�������炵�����ǁA������ʔ����Ȃ����E�E�B
��낵���A�h�o�C�X�肢�܂��B
�����ԍ��F21495900
![]() 2�_
2�_
��996s68����
��������DSD�Đ��ŋȊԂɎ�m�C�Y������܂��B
������A�����ł��B�ǂ�Ȋ������悯����������ڂ��������Ă��������BOPPO�͂܂����ɓ����Ă���̂ŁB
�傫�ȉ��ł͂���܂��A�v�`�b�Ƃ����m�C�Y�ł��B
����͕ʂ�DAC�ł��ł܂��B
���Ƃ���ŁAMEITNER��MA1�̃I�[�i�[��������Ă���̂ł����AZ1ES�̋��N2���̖{�̃\�t�g�̃o�[�W�����A�b�v�ŁA�f�W�^���o�͂̉��ʂ�
���啝�Ƀ_�E�����āA�����{�����[�����グ�Ȃ��ƒ������Ȃ��Ǐo�Ă���Ƃ̂��ƁB�\�j�[���̂�����͊m�F�ς݂����ǁA����DAC�ȊO�ł̏Ǐ�
���Ȃ̂őΉ����邩�ǂ�������Ƃ̂��Ƃł��BOPPO�ł͂���ȏǏ�Ȃ��ł��傤���H
���ʂ͖�肠��܂���B
�����ԍ��F21498359
![]() 1�_
1�_
���傫�ȉ��ł͂���܂��A�v�`�b�Ƃ����m�C�Y�ł��B
������͕ʂ�DAC�ł��ł܂�
mctoru�����Ă��܂����A�䂪�Ƃ�DAC�ł������Ǐ�ł��B
�䂪�Ƃ̏ꍇ�ACD�v���C���[���瓯���P�[�u���Ōq����DSD�ϊ�����ƋȊԂŃv�`�ƃm�C�Y���������܂��ˁiPCM�ϊ��ł͖��Ȃ��j�B
���R�Ƃ��ẮA�ȊԂ̖������x���ƃg���b�N���̖������x���������傫���ƃv�`�ƃm�C�Y����������炵���A�������Z�������背�x���̍������Ȃ������̓m�C�Y�����Ȃ��Ɛ����܂����B
mctoru����Ɠ������R��������܂��A�䂪�Ƃł͂���Ȋ����ł��B
�����ԍ��F21499560
![]() 2�_
2�_
���ς�炸�l�b�g��ł͏��ʕs���ł����A�C�O����DAC��2���i�Ɍ��i��܂����B���Ɋ��ɔp�Ő��i�ł����A�������Ђ���HAP-Z1�Ƃ̐ڑ����\���낤�Ƃ̉���������̂ŁA���Ƃ͎荠�Ȓ��Â̏o����҂��Ƃɂ��܂����B�����ł���������Ē����܂��B�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F21525173�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
�����Ƃ����u�����h��DAC���������܂������ǂ������ł���B�������������Ȃ��Ɩܑ̂Ȃ����炢�̏o���h���ł��B
�J���҂̕��Ƃ���肵�Ă܂����A�C�ODAC�̂��Ƃ��悭��������Ă���A���܂Œ��������ł̓R�X�p�͍ō��Ȃ��̂��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F21535791�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������_��������
��肪�Ƃ��������܂��B���P�AAUSE�A���̃u�����h�m��܂���ł����B
�z�[���y�[�W���ɍs���܂������A���`��`�̍D���ł��i�j ���������́u�j�I�C�v�����܂��B
�����A�z�[���y�[�W����@��݂��o���\������ł݂܂����B�����ԗ���̂��킩��Ȃ����ǁA������ƃ��N���N�ł��B
����͎̂�Ē����Ă݂ėǂ�������ǂ����悤�H���Ă������ƁB�����Ē��ÂȂo�Ă����ɂȂ����A�V�i�����͂Ȃ����E�E�Ȃ�āB
�����ԍ��F21536051
![]() 0�_
0�_
PS AUDIO��DAC���AHAP-Z1ES�Ɛڑ��o����݂����ł��ˁB
�������A�ŐV�t�H�[���ł͍쓮�o���Ȃ��݂����ł��B
��������������Ă݂���A�@���ł��傤���H
http://review.kakaku.com/review/K0000721148/ReviewCD=1099660/?lid=kaden_pricemenu_2073_newreview#1099660
�����ԍ��F21550772
![]() 0�_
0�_
���\��Y����
�^�C�����[�ȏ�肪�Ƃ��������܂��B
�Ƃ����̂��A����PS AUDIO��NUWAVE DSD����Ԃ̌��ɂ��Ă��̂ł��B
�P�Ȃ�DAC�Ȃ̂ɋ���ȃg���C�_���d���𓋍ڂ��Ă���A�J�̕]���������@��Ȃ̂ŁB
�������@��Ƃ͈Ⴂ�܂����A�������[�J�[�Ȃ̂ŁAZ1ES���ŐV�t�@�[���ɂ���Ǝg���Ȃ��Ƃ����\���������ȂƁB
���`��E�E�������Ⴂ�܂����B
�����ԍ��F21551986�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���\��Y����
PS AUDIO��NUWAVE DAC�����܂����B�ŏ���DSD�Ή���NUWAVE DSD���l���Ă����ǁA��������HAP-Z1�Ƀl�C�e�B�u��DSD�t�@�C���������݂�3�Ȃ��������Ă��Ȃ����A������嗬�͒���CD�̃��b�s���O�ɂȂ肻���Ȃ̂ŁE�E�B
�����ȏ�Ƀf�[�^�T�C�Y�̃f�J�CDSD�t�@�C�����_�E�����[�h���Ă��A���ɂ͒����������Ȃ��킯�����i�j
�ŁA��������NUWAVE DAC�ł����A��͂�HAP-Z1�̍ŐV�̃t�@�[���E�F�A�ł͔F�����Ă��ꂸ�A�ЂƂO�̃t�@�[���E�F�A�Ƀo�[�W�����_�E�����Ȃ��ƃ_���ł����B
������Ɖ��������ǁA���F�͉\�ǂ���̂������ł��B�N���A�����ǃc�����ۂ������Ƌ��ɉ��ꂪ�O�b�Ɖ��ɍL�������������V�N�ł��B
�����HAP-Z1�̉��l���܂��L�������݂����ł��B
�����ԍ��F21589768�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
SOULNOTE�̂c-1�́A���Ȃ��g���܂��B
���ɉ����ς݃X���ł����A�֑��ŏ������܂��Ē����܂��B
�����ԍ��F21741268
![]() 6�_
6�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z�C���z��
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
-
�y�~�������̃��X�g�z���C���A�b�v�O���[�hv4.22
-
�y�~�������̃��X�g�zNEW PC
-
�yMy�R���N�V�����z���炠��U20��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
�i�Ɠd�j
�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�v���[���[
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j