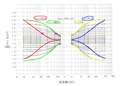A-S301(B) [�u���b�N]
- �ő�192kHz/24bit�Ή��̌�/�����f�W�^���������͂����A�I�[�f�B�I�@��͂������A�e���r��Q�[���@�Ȃǂ����������ł���A�n�C���]�Ή��v�����C���A���v�B
- �p���[�A���v���́A��i�o��60W×2�̃V���O���v�b�V���v���\�����̗p�B��e�ʃp���[�T�v���C�Ƃ̑�����ʂɂ��A�]�T�������Ă�����X�s�[�J�[��炷�B
- �g�[��/���E�h�l�X/�o�����X�̊e�R���g���[���ƌ�i�o�b�t�@�[�A���v���o�C�p�X���A�S���͂ɂ����鉹���������������u�s���A�_�C���N�g�X�C�b�`�v�𓋍ځB
A-S301(B) [�u���b�N]���}�n
�ň����i(�ō�)�F¥34,020
(�O�T��F�}0 ![]() )
�������F2015�N 8����{
)
�������F2015�N 8����{
���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S41�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2023�N1��8�� 20:38 | |
| 12 | 9 | 2023�N1��8�� 16:22 | |
| 56 | 15 | 2023�N1��3�� 19:54 | |
| 2 | 2 | 2022�N12��13�� 11:37 | |
| 6 | 8 | 2022�N10��21�� 20:30 | |
| 18 | 4 | 2022�N3��2�� 16:14 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301
�I�[�f�B�I���S�҂ł��B
���߂Ė{�i�I�ȃA���v���w�����C�ɓ����Ă���܂��B
���₪�������܂��B
�EDAC���瓯���f�W�^����������
�EBlu-ray���R�[�_�[������f�W�^����������
���̂Q�n�����g�p���A�A���v��������悤�Ȃ��ƂɂȂ�A�����r��A�d���̃p���[�����v���_�ł��錻�ۂ͕p�����܂��B
����͉����v���ł��傤���H
��Ȃǂ������܂����炲���������������������܂��B
��낵�����肢�������܂��B
![]() 2�_
2�_
��kakouad����
�܂��A�戵������P12�́u�̏Ⴉ�ȁH�Ǝv������v��ǂ�Ń`�F�b�N���Ă��������B
�`�F�b�N���Ė�肪�Ȃ��A�f�W�^�����͂����ŋN���錻�ۂȂ�A�����Ɉُ킪����Ƃ������Ƃł��B
���̎w���ʂ�ɂ��邵���Ȃ��ł��傤�B
�u�{�@�����̉�H�Ɉُ킪����B �@�d���v���O���āA�������グ�X�܂��͍Ŋ��̃��}�n�̔��X�ɂ��₢���킹���������B�v
����������Ȃ�A�ۏ؊��Ԓ��ł��傤����A�����������ق����ǂ��ł��B
�����ԍ��F25086215
![]() 2�_
2�_
�����̃R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�}�j���A���̖{�y�[�W�͊m�F���Ă���܂��B
���R�[�h�v���[���[����̃t�H�m���͂ł͂��̂悤�Ȍ��ۂ͑S���N���܂���B
�f�W�^�����݂͂̂ł̌��ۂł��B
�����̌̏�̉\���������̂ł��傤���B
���łɕۏ؊��ԊO�Ȃ̂ł����A���[�J�[�ɑ��k���邱�Ƃ������������܂��B
�����ԍ��F25086225�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2023/01/07 10:45�i1�N�ȏ�O�j
�����̂Q�n�����g�p���A�A���v��������悤�Ȃ��ƂɂȂ�A�����r��A
���d���̃p���[�����v���_�ł��錻�ۂ͕p�����܂��B
������͉����v���ł��傤���H
��ʓI��PCM�M���̃r�b�g�[�x��T���v�����O���[�g���Ή����Ă���͈͂ɂ��邩�B�H�ł��ˁB
�������̂P�T�y�[�W�ɏ����Ă���M���`���ł����B�H
�����ԍ��F25086277
![]() 1�_
1�_
���������肪�Ƃ��������܂��B
���̓_�͔F�����Ă���܂���ł����B
���ꂩ��m�F�����Ă݂܂��B
�O�ɐi�߂����ł��ꂵ���ł��B
�����ԍ��F25086337�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���������肪�Ƃ��������܂����B
���X�ׂ������ۂ��m�F���Ă����܂����Ƃ���A�Q�ځi�X�s�[�J�[B�j�ɐڑ����Ă���X�s�[�J�[�uEdifier ED-R1280T�v�������̂悤���Ɛ��@����܂����B
���̃X�s�[�J�[�Ƃ̐ڑ����I�t�ɂ���Ɩ��̌��ۂ��N����܂���B
���̌�uEdifier ED-R1280T�v�ւ̓��͂�AUX����PC�ɕς����Ƃ���A���͉��������悤�ł��B
A-S301����X�s�[�J�[�ւ̏o�̖͂�肾�����Ƃ��������ł�낵���ł��傤���B
�I�[�f�B�I�̐��E�͂킩��Ȃ����Ƃ������ĉ����[���ł��B
�ł��������y�����̂ł��ˁB
�����ԍ��F25088189
![]() 0�_
0�_
��kakouad����
ED-R1280T�̓A���v�����X�s�[�J�[�ł����A������X�s�[�J�[�[�q�ɐڑ����Ă����̂ł��傤���B
�����ԍ��F25088374
![]() 1�_
1�_
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
���݁AED-R1280T���́ARCA�i2RCA�I�X�j�o�́i����AUX����PC�ɕύX�j�ŁAA-S301�̃X�s�[�J�[B�Ƀo�i�i�[�q�Őڑ����Ă���܂��B
�P�[�u����ONKODO Blue y524 RCA -�o�i�i×2 �X�s�[�J�[�P�[�u�� 2�{�Z�b�g���g�p���Ă���܂��B
������{�I�A���{�I�ȊԈႢ�����Ă���̂ł��傤���B
���p������������ł��B
���ƓK�Ȑڑ����@�̂�����������܂�����K���ł��B
��낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F25088472
![]() 2�_
2�_
��kakouad����
���C�����͂̍ő�d����2V���x�ł����A�X�s�[�J�[�[�q�̏o�͓d����20V�ȏ�ɂȂ�܂��B
���͑��̋@������ꂪ����̂ŁA�ʏ�͂��������ڑ����@�͍s���܂���B
�A���v��REC OUT�[�q����ڑ����āA�X�s�[�J�[�̃{�����[���ʼn��ʒ�������̂����ʂł��B
�ǂ����Ă��A���v�̃{�����[�����g���������́A���̂悤�ȃA�_�v�^�[���g���܂��B
https://www.amazon.co.jp/dp/B07S7W67ZB/
�����ԍ��F25088584
![]() 2�_
2�_
���������肪�Ƃ��������܂��B
�A���v�iA-S301�j��REC OUT�[�q����RCA�i2RCA�I�X�j�Őڑ����āA�Z�J���h�X�s�[�J�[�iED-R1280T�j��AUX�[�q��RCA�i2RCA�I�X�j�ƌq���ŃX�s�[�J�[�̃{�����[���ʼn��ʒ�������Ƃ������Ƃł�낵���ł��傤���B
�������̂悤�ɂ��Ă������̂ł����A�A���v�iA-S301�j�̃{�����[���ƘA�����Ȃ��̂ŁA����̂悤�Ȑڑ������݂��o�܂��������܂����B
���������I�Ɍ��サ���悤�Ɋ����܂����i�p�j�B
�����ԍ��F25088621
![]() 1�_
1�_
�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301
�����́A�����R������A�S�X�s�[�J�ڑ��\�ƁA
���߂�@�\�̓h���s�V���ŁA�傫�����e�F�ł���̂ł����A
�M�̂�����₷�����b�N�ɓ����̂ŁA���M��}�������̂ł��B
�{�@�́A�f�W�^���A���v�ł����H
![]() 1�_
1�_
�����@��́A���i�d�͂��قڂ��̂܂ܔ��M�ɂȂ��
�l���ėǂ��Ǝv���܂��B
�Ȃ̂ŁA�g���Ƃ��̓��b�N�̔��i����H�j�������邩�A
���b�N�w�ʂ��u�`�����Ƃ��B
�{�@�́A�f�W�^���M�����͂ł��邯�ǁA�����f�W�^���A���v�ł͂Ȃ��B
�f�W�^���A���v�Ƃ�
https://www.phileweb.com/magazine/audio-course/archives/2007/12/20.html
�����ԍ��F25044144�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B
�����ʉғ��ł��A�d�������ł���Ȃ�̔��M������Ƃ������Ƃł��ˁB
�����ԍ��F25044245
![]() 0�_
0�_
�����ʉғ��ł��A�d�������ł���Ȃ�̔��M������Ƃ������Ƃł��ˁB
�����ł��ˁB��i��190W�܂ł͂����Ȃ��ɂ��Ă��A
�M�������Ȃ���A����Ȃ�ɔM���Ȃ�ł��傤�B
�ҋ@�d�͂�0.5W����
�����ԍ��F25044541�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��shuhei58����
A-S301�𖧕��Ďg������ǂ��Ȃ邩�͕�����܂��A
A-S801 �� A-S2100 ���J�����b�N�Ŏg���Ă������ł́A
���ʂ̃X�s�[�J�[�j�A�t�B�[���h�����ʈȉ���A-S801�͂܂������₦���܂܁A
�\���Ⴂ�X�s�[�J�[�ő剹�ʂ�A-S2100���ƒg�����Ȃ�A
�Ƃ��������ł��ˁB
���ƁA�J���ݒu��PMA-390�i����j�A���ʂ̃X�s�[�J�[�ŏ����ʂ��₦���܂܂ł��B
A���̈悪��قǍL���Ȃ������AB���A���v�͉��x���オ��Ȃ����̂�������ۂł��B
���C���V�X�e���Ŏg���Ă�p���[�A���v�iSchiit Vidar�BA���쓮�̈�͖�1W�܂Łj�͑剹�ʁi�����j���ƐG��邩�ǂ����܂ŔM���Ȃ�܂����A��-�����ʂ��Ƃ��������ق�̂�ʂ邢�������炢�ł��B
���ł͎g�������Ƃ͂Ȃ��̂ň������炸�B
�����ԍ��F25044637
![]() 1�_
1�_
���[�J�[�Ƃ��Ă͍ň��̎����l���ā@���L�̗l�Ɏ���ɍڂ��Ă��܂��B�@�`�|�r�R�O�P����V���
• ���ʂ��̈��������Ƃ���ւ͉�����
�܂Ȃ�
�@������ɔM��������A�ЁE�̏�E��
����̌����ɂȂ�܂��B
�{���i�̎��͂ɏ�30cm�A���E20cm�A
�w��20cm�ȏ�̃X�y�[�X���m�ۂ���
���������B
�f�W�^���A���v�ł͂Ȃ��̂Ŕ��M���܂��B�@�`���ł͂Ȃ��̂Ń{�����[�����オ���Ă��Ȃ���@����قǂ̔��M�͂��܂���B�@�@�{�����[�����グ��Ώグ��قǔ��M�ʂ͑����܂��B
�܂��|�@��ʘ_�Ƃ��Ăł����@��͊J����@�O��͕���ʂ����߂ɃI�[�v���ɂ���B�@�@����͕K�{�ł���B�@�@�Z���ɏI��点�����Ȃ���c�B
�����ԍ��F25044641
![]() 1�_
1�_
A-S301�̃��[�U�[�ł��B�{�@�̓A�i���O�A���v�ł����A���̎g�p���ł͈ȑO���p���Ă����A���v�Ɣ�r���āA���M���ƂĂ����Ȃ��ċ����Ă��܂��B
�傫��➑̂̒��Ƀp�[�c�ނ��R���p�N�g�ɂ܂Ƃ܂��Ă��邱�Ƃ��A���M�����Ȃ��v���̈��������܂���B
�����ԍ��F25044850
![]() 3�_
3�_
���x���߂̃��b�N�ŁA��20�N H/K �̗����ł� HK600 ���g���Ă��܂������A����̏Ⴕ�܂����B�d������邾���ł���Ȃ�ɔM���āA�Ă͓��Ɍ��������̂ł��B���ƁA�Đ������APC��TV�����C���ƂȂ�A���y�ԑg�≹�y�����Ƃ��Ɏ�y�Ƀ����R���� SW ON�Ƃ����̂���]�ł����B
�}���V�����Ȃ̂ŁA�p���[�͂ǂ݂̂��o���Ȃ��̂ŁA�����D��ł��ˁB
�ʏ��AMP��蔭�M�����Ȃ߂Ƃ������ƂȂ̂ŁA���������������Ă݂܂��B
�����ԍ��F25044921
![]() 0�_
0�_
�����A���ׂ��Ċ��\���Ă��܂��B
�Ƃ̊����ƁASP�̌������ǂ����߂��A�قƂ�ǔ��M���Ă��܂���B
�����A���f�W�^���ڑ������܂������Ȃ��ĉE���������܂������A15�N���̌��P�[�u����NG
�������悤�ŁA�V�������Ƃ�������ł��B
�������f���ł����ł��B
➑̂́A������Ə��a�ȃV���o�[�ɂ��܂������A������ӊO�ɗǂ��ł��B
�����ԍ��F25059019
![]() 1�_
1�_
��shuhei58����
�x���X�ł����A���Ђ̃l�b�g���[�N�A���vR-N803���g���Ă���܂��B�Q�O�P�X�N�w���łقږ����f�X�N�g�b�v�I�[�f�B�I�Ŏg���Ă���܂��BR-N803��A-S801�Ƀl�b�g���[�N�@�\��t�����悤�Ȑ��i�Ǝv���Ă���������������Ǝv���܂��i�����ʐ^�ō\�������Ă܂��j�B
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n803/
ADK����̃I�[�f�B�I���b�N�ɒu���Ă���O�㍶�E�͗]�T�ɋĂ܂����A�V���ɓ��Ђ�BD�v���[���[��u���Ă܂��B
BD�v���[���[��CD�v���[���[�Ƃ��Ă��܂ɕ����܂��B�������BD�����܁[�[�[�Ɍ��܂��B
����ȏ�Ԃł����A���ɕs��͂Ȃ��g���Ă���܂��B
�m���ɓV�����ӂ����`�ł����A����ł�2�������x�̌��Ԃ͋Ă���܂��̂ő��v���ȂƎv���Ă���܂��B
���b�N�̓R���ł��B
https://www.asahiwood.co.jp/products/adk/item/detail/?id=6659854139562&product_type=2&collection=37&sub_collection=
��������PC�̎������܂��Ă��̌o���܂��āA�f�J���d�͕���➑̂ɍ����R-N803���w�����܂����B
�ƂĂ����K�Ɏg���Ă��܂��B
�\�[�X�͎��MacBookPro��USBDAC��ڑ����Ă�������RCA�A�i���O�P�[�u���ŃA���v�ɓ��͂��Ă܂��B
�����ԍ��F25088168
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301(B) [�u���b�N]
�����b�ɂȂ�܂��B
�g���R���̃X�y�b�N������ƁA�ቹ����
Boost/Cut 20Hz:±10dB, �^�[���I�[�o�[���g��:400Hz
�Ə����Ă���܂��B
�����20Hz�𒆐S�ɑ�������Ƃ��������ł��傤���H
�܂��A�^�[���I�[�o�[���g��:400Hz�Ƃ͉����Ӗ����Ă���̂ł��傤���H
��낵�����肢���܂��B
![]() 2�_
2�_
�������܂ɂ��낳�� ����ɂ���
�ȑO�����ڂɂ����������Ƃ�����悤�ȋC�����܂��B
http://smonaka.web.fc2.com/soft/amp/model-15/tone2/index.htm
������̃O���t�S�ő�ŏ��̑g�ݍ��킹�@�ɂ̓u���[�̃��C���ƃO���[���̃��C���̌�����_�����}�n�ł�400HZ,
�}�ł͍Œ�悪10Hz�ł����A���}�n��20Hz��
�}�̃N���X���Ă郌�x����-20db�ł�������̍ő��l��14db�ł����A���}�n��20db
��挸�������ɂ�-�P�Qdb�ł����A���}�n��-20db�ƁB
�g�[���R���̓O���C�R�ƈႢ�A�A���I�ɕω������邱�Ƃ��o���܂��B���Œ���g���͂���܂������S���g���͂���܂���B
�O���t6�}�͒��̃J�[�u�ł��B
�����ԍ��F25079429
![]()
![]() 0�_
0�_
�킟�A�Ȃ�����b�ł��ˁB
�������}�n��R-N803�����Ă܂��B������̃X�y�b�N�ł́A����ȕ��ɏ����Ă���܂��B�Q�l�ɂȂ邩�ȁH
�g�[���R���g���[������
Bass�F±10dB�i�ϕ� 20Hz�j�A330Hz�i�^�[���I�[�o�[���g���j
Treble�F±10dB�i�ϕ� 20kHz�j�A3.0kHz�i�^�[���I�[�o�[���g���j
����ɏ�ʃ��f���ł͂���Ȋ����ł��B
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/a-s3200/specs.html#product-tabs
Bass�F�ϕ�:50Hz/±9dB, �^�[���I�[�o�[���g��:350Hz
Treble�F�ϕ�:20kHz/±9dB, �^�[���I�[�o�[���g��:3.5kHz
�܂��A���ɂ̓`���v���J���v���Ȑ��E�ł��B
�����ԍ��F25079532
![]()
![]() 5�_
5�_
�u�ϕ��v�Ƃ������t����ł���
�����̎R�̃s�[�N�����̎��g���Ƃ����Ӗ��ł���ˁH
�����ԍ��F25079572
![]() 0�_
0�_
�ϕ��ɂ͈Ӗ��������Ǝv���܂��ˁA��̓��x���i�傫���j�ł��A���}�n��20db�ł��A������̓N���X�I�[�o�[����20Hz�܂ł̎��g���̕��ł��B
�������̎R�̃s�[�N�����̎��g���Ƃ����Ӗ��ł���ˁH
�c���̓��x���ŁA���������g���ł��ˁB
�����ԍ��F25079610
![]() 1�_
1�_
�����܂ɂ��낳��A����ɂ��́B
�}��\��܂����B���̐}�ɂ� Bass/Treble �����̓���������Ă��܂��B
���̏ꍇ���Ɖϕ� ±15dB �ł��B�ς�����ő啝�Ƃ������Ƃł��B
http://kouyamamoto.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/2_6c91.html
Bass�̏ꍇ�́u�^�[���I�[�o�[���g���ȉ���boost(�܂���cut)����v�Ƃ����̂����O�ŁA�u�����̎R�̃s�[�N�v�Ƃ����̂͂�����ƈ���āA�u20Hz �ő���������� ±10dB �ς��܂��v�Ƃ������Ƃ��ƁB
# �Ȃ��A���g���̕��� dB �ŕ\�킷���Ƃ͂���܂���̂ŁA���ԈႢ�Ȃ��悤�B
�����ԍ��F25079621
![]()
![]() 6�_
6�_
�������܂ɂ��낳��
�����ł�
�����}�n��20db��10db�ł����B
�����ԍ��F25079629
![]() 0�_
0�_
�F���܁A���肪�Ƃ��������܂���
�l���~�����X�y�b�N�́A50Hz��±10dB�ʂŁA�^�[���I�[�o�[���g����100Hz�ʂ��Ɨ������܂���
�������������g���R�����Ă����ł����ˁH
�O���C�R��p���C�R�ł��傤���ˁH
�����ԍ��F25079700�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����܂ɂ��낳��A�����́B
�����ς݂ɂȂ��Ă邯�ǃf�^�����������̂ŁB
������������
>�Œ���g���͂���܂������S���g���͂���܂���
�S���̃f�^�����ł��B
�g�[���R���g���[���̊�{�I�Ȓ��S���g����1kHz�ł��B
TREBLE��1kHz�`20kHz��
BASS��20Hz�`1kHz���B
���S�_��1kHz�͑�������܂��A1kHz�ɋ߂��قǑ������͏������Ȃ�܂��B
�܂�u�������v�Ƃ̓g�[���R���g���[���ł͑�������Ȃ�1kHz�ɑ��āA
������Ă�����g���i�����̏ꍇ�͗��[�ɂȂ�20Hz��20kHz�j��
�ǂ̂��炢��������邩�Ƃ����l�ł��B
����̍\�����l����ƁA1kHz�Ƃ����̂͂��Ȃ��Ȃ̂ł����A
���������g�[���R���g���[���̖{���̖ړI�́A1kHz���S�Ƃ������Ƃ���l���āA
���R�[�h�Đ��̏ꍇ�́ARIAA�C�R���C�U�[�ɑ����̈Ӗ������邩��ł��傤�B
�ł�����A�g�[���R���g���[���œ���̉����C�ӂɑ����ł���悤�Ȏd�g�݂ł͂Ȃ��̂ł��B
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
>Bass�̏ꍇ�́u�^�[���I�[�o�[���g���ȉ���boost(�܂���cut)����v�Ƃ����̂����O��
������Ⴂ�܂��B
�g�[���R���g���[���̎d�g�ݏ�A����̎��g���ȏ�܂��͈ȉ����A
�Ƃ������Ƃ͏o���܂���B
�ɂ₩�ɁA�ቹ��20Hz�`1kHz�A������1kHz�`20kHz���ς��܂��B
�Ƃ������ƂŁA�^�[���I�[�o�[���g���Ƃ́A�Ϗo����@��̃J�[�u���݂�ƁA
1kHz(0dB)�ɑ��āA�ō��ψʒu�ɂ���3dB�ς�����g���������悤�ł��B
>�l���~�����X�y�b�N�́A50Hz��±10dB�ʂŁA�^�[���I�[�o�[���g����100Hz�ʂ��Ɨ������܂���
�f�^�����Ȑ����������̂ŁA�g�[���R���g���[���̖{���ɂ��āA
�܂����������ł��Ă��Ȃ��悤�ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ̓g�[���R���g���[���ł͖����ł��B
�킩��ɂ����Ǝv���̂ŁA����A���v�̃g�[���R���g���[���̕ω��}�ł��B
20Hz�A20kHz�Ł{�|10dB�̒������o����悤�ɂȂ��Ă��āA
�^�[���I�[�o�[���g���́A
�ቹ��125Hz�A500Hz�A������2.5kHz��8kHz�Ɛ�ւ����܂��B
�ቹ��
500Hz�ݒ�̏ꍇ�̍ō��l�{�|10dB�ݒ�l��A
125Hz�ݒ�̏ꍇ�̍ō��l�{�|10dB�ݒ�l��ԂłȂ����Ă���܂��B
�F�̓h���Ă��Ȃ��������́A500Hz�ݒ�̏ꍇ�̉ϒl�ł��B
������
2.5kHz�ݒ�̏ꍇ�̍ō��l�{�|10dB�ݒ�l�����A
8kHz�ݒ�̏ꍇ�̍ō��l�{�|10dB�ݒ�l��łȂ����Ă���܂��B
�F�̓h���Ă��Ȃ��������́A2.5kHz�ݒ�̏ꍇ�̉ϒl�ł��B
�܂��A�{�|3dB�̂Ƃ���ɐ������āA�ቹ�̑������̌�_�ɑȉ~�ŐF��t���Ă���܂��B
���������ł����A�^�[���I�[�o�[���g�����{�|3dB�n�_�ߕӂ��Ƃ������Ƃ��킩��ł��傤�B
������݂�Ƃ킩��Ǝv���܂����A
�^�[���I�[�o�[���g����Ⴍ�i�������͍����j����ƁA�Ԑ�����̂悤�ȕω��ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA
�^�[���I�[�o�[���g���ƁA�������������g�����߂Â���͖̂������Ƃ킩��Ǝv���܂��B
50Hz�̑�����+-10dB�ɑ��ċ߂��̂́A�^�[���I�[�o�[���g��500�g���̂ق��ł����A
50Hz�`1kHz�����Ȃ葝������Ă��܂��킯�ł��B
����̎��g���悾�����������ꍇ�́A
�O���t�B�b�N�C�R���C�U�[��p�����g���b�N�C�R���C�U�[���g�������Ȃ��ł��傤�B
DEQ2496�i�����i�Ȃ�A�L���t�F�[�Y��DG-68)�̂悤�ȁA
�}�C�N�Ŏ��������ł�����̂̂ق����֗������Ƃ͎v���܂��B
BEHRINGER ( �x�����K�[ ) / DEQ2496
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19062/
DIGITAL VOICING EQUALIZER DG-68
https://www.accuphase.co.jp/model/dg-68.html
�����ԍ��F25079911
![]() 10�_
10�_
�������܂����A���肪�Ƃ��������܂���
�����ԍ��F25079971
![]() 0�_
0�_
blackbird1212����
�����A�����́u�����̌������Ƃ̓f�^�������v�̂��b�Ȃ̂ŁA�ꉞ�B
>>Bass�̏ꍇ�́u�^�[���I�[�o�[���g���ȉ���boost(�܂���cut)����v�Ƃ����̂����O��
>������Ⴂ�܂��B
>�g�[���R���g���[���̎d�g�ݏ�A����̎��g���ȏ�܂��͈ȉ����A
>�Ƃ������Ƃ͏o���܂���B
>�ɂ₩�ɁA�ቹ��20Hz�`1kHz�A������1kHz�`20kHz���ς��܂��B
���ӓI�ȉ��߂ł��B���Ƃ��u�g�[���R���g���[���@�^�[���I�[�o�[���g���v�ŃO�O���ăg�b�v�Ƀq�b�g����T�C�g�ihttp://www.audiosharing.com/people/segawa/audio_abc/abc_08_1.htm�j�ɂ́A
>�^�[���I�[�o�[�Ƃ́i�����j�R���g���[�����ׂ�����Ɖ���̋��E�̂��Ƃ������Č����킯�ł��B���m�ɂ̓^�[���I�[�o�[���g���iTurn-over Frequency�j�Ƃ����܂��B
�Ƃ�������������܂����A�u���E�v�ƌ����Ă��A����̎��g���œˑR���g���������ς��킯�͂Ȃ��͓̂�����O�ŁA����͎�����Ɍf�ڂ����}�ł������ł���͂��ł��B�t�ɁA
>1kHz(0dB)�ɑ��āA�ō��ψʒu�ɂ���3dB�ς�����g���������悤�ł��B
�Ə�������ɂ́A�����������܂��傤�B���肻���Ȓ�`���Ƃ͎v���܂����A��ʓI�ɒʗp����b���ǂ����A�F����̎Q�l�ɂȂ�ł��傤�B
# �X���傳��͂��ԐM�s�v�ł��B
�����ԍ��F25080006
![]() 3�_
3�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B
>���ӓI�ȉ��߂ł��B���Ƃ��u�g�[���R���g���[���@�^�[���I�[�o�[���g���v�ŃO�O���ăg�b�v�Ƀq�b�g����T�C�g
>�ihttp://www.audiosharing.com/people/segawa/audio_abc/abc_08_1.htm�j�ɂ́A
>�^�[���I�[�o�[�Ƃ́i�����j�R���g���[�����ׂ�����Ɖ���̋��E�̂��Ƃ������Č����킯�ł��B
>���m�ɂ̓^�[���I�[�o�[���g���iTurn-over Frequency�j�Ƃ����܂��B
�����̋L�q�ł����A�͂�����ƁA
>����͂��Ƃ��A�^�[���I�[�o�[���R�O�O�w���c�ɍ��킹�� BASS �̃c�}�~���A
>�R�O�OHz�ȉ��̒ቹ�������邱�Ƃ��ł��A�T��Hz�ɂ��킹�� TREBLE �̃c�}�~���ƁA
>�T��Hz�ȏ�̍����������ł���A�Ƃ����Ӗ��ŁA
>���̏ꍇ�A�R�O�OHz����T��Hz�܂ł̊Ԃ̎��g���́A����ω����܂���B
����ȃf�^�����Ȃ��Ə����Ă��郊���N��������܂��Ă��˂��B
�܂�A������ǂ�ŁA
>Bass�̏ꍇ�́u�^�[���I�[�o�[���g���ȉ���boost(�܂���cut)����v�Ƃ����̂����O��
�������������ǁA�ԈႢ���w�E����āA���ȕٌ���n�߂Ă���Ƃ����v���܂���B
>�Ƃ�������������܂����A�u���E�v�ƌ����Ă��A
>����̎��g���œˑR���g���������ς��킯�͂Ȃ��͓̂�����O�ŁA
>����͎�����Ɍf�ڂ����}�ł������ł���͂��ł��B
���������A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̓��e�œ\��t�����}�ɂ́A
�^�[���I�[�o�[���g���̋L�ڂ������킯�ł����A
�^�[���I�[�o�[���g����ؑւ��ꍇ�̕ω����L�ڂ���Ă��Ȃ��킯�ł��B
�����āA�\��t���������N��ɂ��^�[���I�[�o�[���g���̐������Ȃ��킯�ł��B
�ł��̂ŁA�^�[���I�[�o�[���g�����ւ����ꍇ�ɁA���Ƃ��A
>�R�O�OHz����T��Hz�܂ł̊Ԃ̎��g���́A����ω����܂���
�Ƃ������Ƃ�ے肷��悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��Ȃ��킯�ł��B
����ŗ�������ƌ����܂��Ă������Ƃ��������悤���Ȃ��ł��B
�ł�����A�X���傳���
>�l���~�����X�y�b�N�́A50Hz��±10dB�ʂŁA�^�[���I�[�o�[���g����100Hz�ʂ��Ɨ������܂���
���̂悤�ȕԎ����������킯�ł��B
����͏����ꂽ���Ƃɑ��鐳���ȉ��߂ł����Ă܂��������ӂȂǔ��o���Ȃ��ł��B
�����ԍ��F25080098
![]() 12�_
12�_
�F���܁A���c�_�Q�l�ɂȂ�܂�
�F����̋c�_�ŁA�����炭�l�̓g���R���̐������������ł��Ă���Ǝv���܂�
���v�ł�
�����ԍ��F25080226�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
blackbird1212����ɔ��_���܂��B�i�����܂ɂ��낳��A�ǂ������݂܂���B�j
>>���̏ꍇ�A�R�O�OHz����T��Hz�܂ł̊Ԃ̎��g���́A����ω����܂���B
>
>����ȃf�^�����Ȃ��Ə����Ă��郊���N��������܂��Ă��˂��B
���Y�T�C�g�ł́A��̂ق���
�u���[�J�[�̔��\�ɂ��A�R�O�OHz���^�[���I�[�o�[���g���ł���A�ƂȂ��Ă��܂��B���������ۂɂ͐}�̂悤�ɂP��Hz�t�߂���ω����Ă���v
���Ƃ���A���҂͂��̓_�𐳂����F�����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B��L�u����v�͂������ɓK�Ƃ͎v���܂��A���̈�_�����œ��Y�T�C�g�S�̂�ᔻ����̂͑Ó��ł͂���܂���B
>���������A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̓��e�œ\��t�����}�ɂ́A
>�^�[���I�[�o�[���g���̋L�ڂ������킯�ł����A
�����������Ⴂ�܂����A�M�a��
>1kHz(0dB)�ɑ��āA�ō��ψʒu�ɂ���3dB�ς�����g���������悤�ł��B
�ɂ��āA���ꂪ����̐��i�ɂ��Ĉ�ʓI�ɒʗp���鍪���͌��ǎ�����Ă��܂���ˁH�u�����悤�ł��v���炷��ƁA�͂��ȍޗ�����̐����ɂ����Ȃ��̂ł́H���Ȃ݂ɁA�u�f�^�����v�������Ă���Ƃ��ꂽ�O�L�T�C�g������ɓǂނƁA
�u�g�[���R���g���[���ő�_�̎��ۂ̓������݂āA�{�i�܂��́|�j�RdB�̂Ƃ��낪�A�ق�Ƃ��̃^�[���I�[�o�[���g�����A�ƌ����Ă悢�̂ł��B�v
�Ƃ���܂��B������u�f�^�����v�ł����H
���� 3dB �Ń^�[���I�[�o�[���g�����`���闬�V������̂͒m���Ă��܂������A���ꂪ����̐��i�ɂ��Ĉ�ʓI�ɒʗp���邩�ǂ����肩�łȂ��̂ŁA�ŏ��̓��e�ł͂����Ē��ۓI�ȕ\����p���܂����B�ׂ��Ȍ��܂Łu�f�^�����v�ƕ]����Ȃ�A�M�a��
>���S�_��1kHz�͑�������܂���
���u�f�^�����v�ł��傤�B1kHz���u����v��������Ȃ��͂�������܂���B�u��������Ȃ��v�����������܂����H
�����ԍ��F25080369
![]() 2�_
2�_
�@�@�@���@�@�������������Ԃ��͗ǂ��̂ł����H
�����ԍ��F25080379
![]() 7�_
7�_
�����N��\��Ȃ�A���̓��e�ɂ��ӔC�������Ă������������ł��B
�����̎咣�̗��t���Ƃ��ē\���Ă����Ȃ���A���F�������Ȃ�ƁA�u���������Ă���킯�ł͂���܂���v�Ƃ������ē�����̂͌��ꂵ���ł��B
�����ԍ��F25081153
![]() 8�_
8�_
�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301
SONY��333esx�U�̒��ÂƂقړ������i�Ȃ��ǁA�ǁ[������B
333�ƂĂ��������悭�ăC�J�ɂ��B�������������Ȃ���
���X40�N�O�̃A���v�Ɏ���o���̂͂ǂ��Ȃ̂�����B�����ς݃N���[�j���O�ϕs��Ȃ��炵�����ǁB
�������炱������YAMAHA�����ׂ�������B
���҂̕��X�A�h�o�C�X���ӌ����肢�������܂��B
�����ԍ��F25048380�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2022/12/11 14:03�i1�N�ȏ�O�j
�����̓��e�ɂ����܂��B���[�`���[�u�̑n���̊قƂ����`�����l����ESX�̃I�[�p�z�[���̖͗l���A�b�v���[�h����Ă���̂ŎQ�l���x�Ɍ��Ă݂��炢���ł��傤�B���̂��炢�̎�������Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ă������Ƃł��B�ړ_�����܂�h�z������x�ł͂��߂����Ă������Ƃł��B
�����ԍ��F25048501
![]() 2�_
2�_
���肪�Ƃ�������n���̊�
�������낢���
�����ԍ��F25051375�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301
�I�[�f�B�I�}�j�A�̕������炲�����������B
���݁A�ȉ��̍\���œ��͉����\�����Ă܂����A�����̎��ł͂��͂�D��͂킩��܂���B
�������A�����I�H�Ɍ����ǂ���̓��͕��@���D��Ă���̂ł��傤���B���������������ꂽ��������Β�����ׂ̊��z�����������������B
�@PC�i192PCM�o�́j��USB�[�q�ڑ���DAC�itopping D10s�j�����f�W�^���P�[�u���ioptical�j��A301���X�s�[�J�[
�APC�i384DSD�o�́j��USB�[�q�ڑ���DAC�itopping D10s�j��RCA�P�[�u����A301���X�s�[�J�[
![]() 1�_
1�_
������V�V�V�V�V����
384DSD�Ƃ����\�L���C�ɂȂ�܂����B
1bit DSD �i�t�@�C���t�H�[�}�b�g�@*.dsf�@*.dsdiff �Ȃǁj�ɂ�
�T���v�����O���g���̈Ⴂ��
�E2.8224MHz�i=DSD64�j
�E5.6448MHz�i=DSD128�j
�E11.2896MHz�i=DSD256�j
�Ȃǂ��L��̂͑����Ă܂���
�X���傳��͂��̏��384DSD�i�����炭������t�@�C���ł��傤���c�j��{���ɍĐ�����ċ���̂��ȁH
�����������Ƃ���
��ʓI�ɓ���ł���̂ł��傤���H����ł���Ƃ��Ă�
���g����DAC�ł͋Ȃ��`���̂悤�ȋC�����܂����B
�����ԍ��F24955519
![]() 2�_
2�_
������V�V�V�V�V����
����ɂ���
�@��Topping��DDC�Ƃ��Ďg�p�ŁAA301��DAC�ƃA���v�����g�p�ł��B
�A��Topping��DAC�ŁAA301�̓A���v���g�p�ł��B
PC�̓m�C�Y�������Ƃ������ƂŃm�C�Y�Ȃ���Ă��邩�ʼn������ς��Ǝv���܂��B
DAC�������œd���̎����d�v�Ƃ����Ă��܂��̂ŁA
���̕ӂ��s���ł����A����Ă��Ȃ��ꍇ�́A���������͓���悤�Ɏv���܂��B
�����܂ł������ł����A���炵�܂����B
�����ԍ��F24956278
![]() 1�_
1�_
������V�V�V�V�V����
�܂��͉����ƂȂ�PCM��DSD�̗D��Ɠ`��������RCA�A�i���O�ڑ��ƌ��f�W�^���̗D��̂Q�̖��ɂȂ�Ǝv���܂��B
�f�[�^�̏��ʂƂ��Ă�DSD�̕����D��Ă���ƌ����܂��ˁB�ڑ������ł�DSD���A�i���O�ɕϊ����Ă��瑗��̂ʼn����ɍS��Ȃ�P�[�u�����̑��ɗ]���Ȕ�p��������\����ł��ˁB���ڑ��Ȃ�@�ނ��Ή����Ă����192kHz�̂܂ܓ`���o���܂��B(������192kHz�A����96kHz�܂ł̋@�ނ��L��܂�)
����DSD�ł�PCM�ł��l�C�e�B���Ș^���f�[�^�Ȃ̂��H�ƌ������ł��˂��`(��)�ɒ[�Șb�A16bit/44.1kHz�̃f�[�^��ϊ��������������m��܂���B
����16bit/44.1kHz�̃f�[�^��192kHz�ɃA�b�v�T���v�����O������DSD2.8MHz�ɕϊ����Ē��������L��܂����ADSD�̕����m�C�Y�������Ȃ������ł��ˁB
�l�I�ɂ́A�܂���16bit/44.1kHz�̃f�[�^���������ōĐ��o����V�X�e�����\�����Ă��特���̃O���[�h�A�b�v��}��ׂ����Ǝv���܂��B
��������PC���̂��m�C�Y���ł�����ˁBPC�{�̂̃m�C�Y��AUSB�ɂ��m�C�Y�t�B���^�[���K�v�����m��܂���B
���ƈ�����USB�m�C�Y�t�B���^�[�́u�R�g���F�[�� �^�b�s���O�K�[�h�A�_�v�^�EUSB�p�@TGA-USB-AAP�vAmazon�Ŗ�3000�~�ł��B
�����g���Ă܂����A���Ђ̍����ȃI�[�f�B�I�pUSB�m�C�Y�t�B���^�[�Ƒ��F�Ȃ����\�ł��B(��)
�����ԍ��F24959656�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�Ȃ�قǁA�A�����ς�킩��܂����
PC����DSD�o�͂�I������ƁA�g�b�s����384DSD�ƕ\������邱�Ƃ���A���̂悤�ɋL�ڂ��܂����B
�m���s���ł��݂܂���B����͋M�a�̃J�e�S�������Ō����Ƃ���̂ǂ�ɊY��������̂Ȃ̂ł��傤���B
�����ԍ��F24959734�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G�X�v���b�\����ւ̕ԐM�Ƃ��ċL�ڂ��܂���
�����ԍ��F24959736�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����V�V�V�V�V����A�����́B
�P���ɁA
>�@PC�i192PCM�o�́j��USB�[�q�ڑ���DAC�itopping D10s�j�����f�W�^���P�[�u���ioptical�j��A301���X�s�[�J�[
A-S301��DAC���\�ɂ���ĉ�����������܂�
>�APC�i384DSD�o�́j��USB�[�q�ڑ���DAC�itopping D10s�j��RCA�P�[�u����A301���X�s�[�J�[
D10s��DAC���\�ɂ���ĉ�����������܂�
����2�̈Ⴂ���ׂ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
DAC�`�b�v�̐��\�́AD10s�̕�����ł��B
�d�����́AA-S301�̕�����ł��B
DAC�`�b�v�ȍ~�̃A�i���O�o�b�t�@�ɂ��ẮA
A-S301�̎d�l���킩��Ȃ��̂Ŕ�r�s�\�ł��B
D10s��OP�A���v�����\�ł��B
S/PDIF�i����/���f�W�^���j�ł̐ڑ����ƁA
�����192k/24bit�ɐ�������DSD�̃l�C�e�B�u�Đ����o���Ȃ��ł��B
�Ƃ����悤�ɁA���f�W�^���ڑ��̂ق������傫���g���ɂ����̂ŁA
�����I�ɈႢ���Ȃ��Ɗ����Ă���̂ł�����A
�g������̗ǂ�D10s����̃A�i���O�ڑ��ŗǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���G�X�v���b�\SEVEN����
>384DSD�Ƃ����\�L���C�ɂȂ�܂����B
����́ADSD128��48kHz�n���DoP�o�͂̂��Ƃł��B
�{���ADSD��44.1kHz�n��Ȃ̂ŁADoP�iPCM�U���j�o�͂��ƁA
DSD64��PCM176.4k�ADSD128��PCM352.8k�o�͂ɂȂ�̂ł����A
PCM��DSD�ϊ�����Ƃ��ɁA����PCM�t�@�C�����A
44.1k/88.2k/176.4k�ł͂Ȃ�48k/96k/192k�������ꍇ�A
PCM��DSD�ϊ�������DoP�o�͂���ƁA
DSD64��PCM192k�ADSD128��PCM384k�ŏo�͂����Ƃ������Ƃł��B
>�g�b�s����384DSD�ƕ\������邱�Ƃ���
����D10���Ɓu384�@PCM�v�ƕ\������܂��B
�m�C�Y��ɂ��ẮA��p�Ό��ʂ�����ł��B
1���قǂ�DAC�ɐ���~������Ӗ������邩�ǂ����Ƃ������ƂɂȂ�܂����A
USB�P�[�u�����ǂ����̂��g�����������͗ǂ��Ȃ�܂��B
����Ȃ��Ƃ����Ă���ƁA������1���~���Ă��܂��܂��B
����V�V�V�V�V���ǂ��܂Ŗ]�ނ��ŕς�邵�A
���ۂ�PC�ƂȂ��Ă݂Ȃ��ƌ��ʂ̂قǂ͂킩��Ȃ��̂ŁA
��̓I�ɐ��i���Љ��͓̂���ł��B
�����ԍ��F24959864
![]() 0�_
0�_
��blackbird1212����
������肪�Ƃ��������܂��B
��������
���߂āA�X���傳�g�p��DAC�̎d�l�\������
�uDSD64-DSD256�i�l�C�e�B�u�j�@�ȊO�Ɂ@DSD128�iDop�j�̃��[�h������
���̍ۂɂ́A�U���Ɏg���Ă���PCM�̎��g���R�W�S���g�����\�������Ă���v�@�̂�
�Ɨ����ł��܂����B
������V�V�V�V�V����
������͋M�a�̃J�e�S�������Ō����Ƃ���̂ǂ�ɊY��������̂Ȃ̂ł��傤���B
�ʂɎ����J�e�S���������Ă�ᖳ���̂ł�����ǂ��A
�����́@��L�@�u�v�@�̒��ɏ������ʂ�ł��ˁB
���������A�����I�H�Ɍ����ǂ���̓��͕��@���D��Ă���̂ł��傤���B
�܂��A�I�[�f�B�I�I�ɂ́@�����������^��������邾�낤��
�������@�艺���邱�ƂɁ@����Ȃ�̈Ӗ�������̂ł��傤���A
���y�����y�Ƃ��Ď�������A���D����c�Ƃ����ϓ_���炷��Ƃ��܂�K�v�̖����c�_
�_�o�𒍂��ׂ��|�C���g���ᖳ���悤�ȋC�����܂��ˁB
�����āA���y�W�������E���t�`�ԁE����ߒ��̈Ⴂ�Ȃǂ�
PCM��DSD�́A���ꂼ�ꑶ�݂��Ă����ł��傤�B
�I�[�P�X�g���Ƃ��A�W���Y�̃r�b�O�o���h���̈ꔭ�^��ŗǂ��o����SACD����
�u���̃_�C�i�~�N�X�Ƒ@�ׂ������ї��i=�g���h��f�i�Ƃ�����j����Ԃ͂P�U�r�b�gCD�����Ζ�������c�v�Ǝv�������
�d�C�y���̂�������ADTM�̔��W�`�̂悤�ȗl����悵�Ă���J�|�b�v��b�N�Ȃǂ�
����DSD(1bit)�ɍS��K�v�������킯�ł���ˁB
���X�i�[��l��l��
�D���ȉ��y������A�����Ղ��L��Ǝv����
����ȑO�ɃA�[�e�B�X�g��R�[�h��Ђɂ�
�e�X�̓s����D���D�����L�锤�Ȃ̂�
���̎���ɍ��킹
�F����s���ɂ���Ďg�������Ă���c�ŗǂ��̂ł́H
�Ƃ͂���
�X���傳�I�[�f�B�I�I�����ŁA
�Ȃ�ׂ������Ȕ�r�����āA�ǂ��炩����ɌR�z���グ��Ƃ��������o���Ȃ����Ȃ��ł��傤�B
����ɂ�
�X���傳��̂悤�ɁA��̋@���DDC�^DAC�Ƃ��Ďg�������Ă��܂���������Ȕ�r�ɂȂ�Ȃ��̂�
���Ȃ����}�nA�V���[�Y�ł�
A-S801�Ȃǂ̂悤�Ɉ���PCM��DSD����@����g���Ĕ�r���Ă݂���ǂ��Ǝv���܂��B
�i���ǂ��悤�ł���
���y�����I�ɂ͂��܂�Ӗ��͖������Ƒ����܂��B����������̏o���ł���
�A���v�^�X�s�[�J�[
���̓���������̋@��̂T�{���炢�̋��z�̃��m�܂ōL����
�V���b�v�Ŏ������܂���c�ƐF�X�����Ă��Ċy�����Ȃ�Ǝv���܂��B�j
�����ԍ��F24961167
![]() 0�_
0�_
A-S301�̓_�C�i�~�b�N�����W�ɗ]�T�����Ȃ��̂ŁB�X�C�b�`���O���M�����[�^��߁B�Ȃ̂Ō����͂̂ق����R�������[�h�m�C�Y�̉e�����Ȃ��̂ŃX�b�L���������ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F24974706
![]() 0�_
0�_
�v�����C���A���v > ���}�n > A-S301
�����i�L�`����
����ɂ���
�V���i�́A���̎����܂��o�Ă��Ȃ��ł��傤�ˁB
�����̂͂S���Ɂ@�߂肻���ȉ\�����ɂ��܂������A��p�@���o���Ƃ��Ă�
���i�͂Q�O�����炢�A�b�v���ā@�o�Ă������ł��ˁB�o�ė����Ƃ��Ă��A�傫�ȕύX�_��
�l���ɂ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24612353
![]()
![]() 5�_
5�_
2022/02/21 18:33�i1�N�ȏ�O�j
���Ẵp�C�I�j�A���G���g���[�N���X�̃v�����C���A���v��̔����Ă�������������܂������C��p�@���f�����o�����Ƃ͂Ȃ������Ă䂫�܂����B
��p�@���o�邩�łȂ����̓��}�n�̎��v���悾�낤�Ǝv���܂��B�f�m���̃v�����C���A���v�̈�Ԓቿ�i�@(���̐^�����̏����ȋ@��ł͂Ȃ��@��)�ʂłȂ��ƁA�̎Z������Ȃ���Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
S301�����قǐԎ��Ȃ�Ό�p�@���o�����Ƃ��Ȃ������Ă䂭�^���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24612742
![]()
![]() 6�_
6�_
����ɂ���
����AV�A���v�Ƃ̕����Ȃ�ł����
�����ʂő��p�r�̃A���v����ɓ���̂ŁA���̃N���X
�������������͂������ɂ����Ă��܂�
301�̓s���A���f���Ŕ��ɗǂ��A���v�ł����A
���[�J�[�Ƃ��ďo�����Ƃ�Y�݂܂�
���͑�^�e���r�ƍ��킹�Ďg�����v�������A���X�s���A���f�����o���ɂ���
�X�s�[�J�[�ŎO���A�A���v�ŎO���ACDP�ŎO��
�v10���ʂ̃s���A���f���̓G���g���[�ɂ͐����ė~�������i�я��i�Ȃ̂ł���
���Ƀ��}�n�ɂ͊撣���Ăق���
�����ԍ��F24626999�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 7�_
7�_
���͂炽����P�O�O�O�_����
������ς茆��RS-1506U 38-2T������
���I���t�F�[�u���^�[�{����
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F24628855
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�v�����C���A���v]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
-
�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�v�����C���A���v
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j
![A-S301(B) [�u���b�N] ���i�摜](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000795760.jpg)