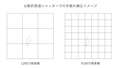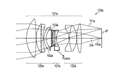���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S29128�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 49 | 52 | 2025�N5��27�� 19:22 | |
| 30 | 9 | 2025�N5��20�� 04:40 | |
| 64 | 8 | 2025�N5��23�� 12:28 | |
| 4 | 12 | 2025�N5��21�� 18:41 | |
| 41 | 9 | 2025�N5��21�� 22:17 | |
| 59 | 7 | 2025�N6��4�� 22:04 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DC-S1M2ES �{�f�B
S5II�Ɖ����Ⴄ�낤�Ǝv���āA�ȒP�ɒ��ׂ����ʁA���Ȃ�Ⴄ�悤�ł��B
�E��荂���ȃv���Z�b�T�[���̗p���Ă���AAF���\��^��@�\������
�E���S�Ȗh�o�E�h�H���\������A-10���܂ł̑ϊ����\
�E576���h�b�g��OLED EVF�𓋍ڂ��A���t���b�V�����[�g�͍ő�120fps�A�x����0.005�b�����Ɣ��Ɋ��炩�ȕ\�����\
�ES5II�͎�U���͍ő�6.5�i�������AS1IIE�ł͍ő�8�i���Ɍ���
�ES5II�͘A�ʂ�AFC���J�V���b�^�[����7�R�}/�b���������AS1IIE�͑��x�D�惂�[�h�i12bit�j�� 10�R�}/�b���\�ɂȂ����B
�EUHS-II SD�J�[�h�X���b�g��XQD/CFexpress�X���b�g���e1���
![]() 10�_
10�_
�����Ȃ̂ł����A���̒l�i���o���Ȃ�Z6III�̕����c�݂����Ȃ�AF���ǂ��A�ƂȂ��ŁA���̎B��Ȃ��Ȃ�S5II�ʼn��̖����Ȃ��ł��B
S5II���[�U�[�����������邩�ƌ����Ă��A15���~�Ŕ����ĉʂ����Ēlj���20���~�����l�������邩�ł��ˁB
�����ԍ��F26181593�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
����S1RM2���p�X�����̂ŁA��������������Ȃ̂ł���AF���ǂ��܂ʼn��P���Ă��邩����Ȃ̂ł���ˁB
���搫�\��S5M2�ł��\���Ȃ̂ƁA���[�����O�V���b�^�[���x�����҂��Ă������ł͂Ȃ������̂�S1M2�ɖ��͂������Ȃ��̂ŁA�����炪�ŗL�͌��ł��B
��f���I�ɂ͂��傤�Ǘǂ��̂ł����A������ƍ����߂���C������̂ł���ˁB
�X�`�����[�U�[�͂���ς�S1RM2�Ȃ̂��ȁB
���������Y��ōw������̂������߂܂��B
�����ԍ��F26181660�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��taka0730����
����EVF���悭�Ȃ��ă`���g�t���ł�
�ׂ����Ƃ����S1��MK2�V���[�Y���瑽�d�I�o���ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ƁA�F���������ς���Ă܂�
�ϑw�Ŗ����̂ŘA�ʋ@�\�͗����Ă܂�����AS5M2��S1MK2E�̍��͏��Ȃ��̂Ŕ����ȏ��ŁA�ϋɓI�ɔ��������ł��ƃ��J�V���b�^�[�̘A�ʑ��x�̈Ⴂ����Ԃł����ˁB
�����ԍ��F26181726�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�t�����j�^�[���o���A���O������o���`���ɂȂ����̂͑傫���ł��ˁB
�����ԍ��F26181736
![]() 3�_
3�_
��taka0730����
����ɂ��́B
��S5II�Ɖ����Ⴄ�낤�Ǝv���āA�ȒP�ɒ��ׂ����ʁA���Ȃ�Ⴄ�悤�ł��B
S5M2W �_�u�������Y�L�b�g�̃R�X�p���ǂ�����̂ŁA
�`�e�֘A�ł��Ȃ�̐i�����݂��Ȃ��ƌ��݂�
���i���̔[�����������ɂ�����������܂���B
�����ԍ��F26181889
![]() 4�_
4�_
AF���\�͂����炭S1RII�Ɠ������Ǝv���܂����A
�������ɂ͂��܂����̂悤�ł��B
https://www.youtube.com/watch?v=aLO3UmwEEes
�����ԍ��F26181909
![]() 0�_
0�_
��taka0730����
S1RII�ł܂����̒��S�̎B�e�i�X�|�[�c�A���j�������Ă��܂��AR1�A��1II�Ɣ�r���ĂW�|���X�|�����炢�̐��x�ł��B
�C�}�C�`�Ƃ����Ă��A���Ȃ�n�C���x���̃C�}�C�`���Ǝv���̂ł����B
�m���ɒǔ�AF�̓_���ł����A�ǔ��łȂ�AF�͕��ʂɗǂ��ł��B
���Љ��Youtube���܂������A�P�ʂ͗ǂ��ĘA�ʂ��E�E�E�ƌ����Ă��܂����A�悭����ƘA�ʂ̏ꍇ�A���̖тƂ���S�̂��u�����悤�Ɍ����܂��B�R���̓V���b�^�[�V���b�N���Ǝv���܂��B���J�̏ꍇ�A�Q���ڈȍ~�̓u���܂��BS1R�̂悤�ȐÉ��V���b�^�[�ł͂Ȃ��̂ŁB
�����ԍ��F26181978
![]() 2�_
2�_
���������ɂ͂��܂���
��S1M2�Ɣ�ׂĂ݂����ł��A�ϑw�Z���T�[�̃J�����Ɣ�ׂ��瑼�Ђ̃J���������l����
�{���R�ł�����Ă��܂������v���Z�b�T�[�̕ύX�͑傫���ł��A�A�[�o���X�|�[�c�Ńu���C�N�_���X������Ȃ�����AS5M2��AF�Ɍ��C�������Ă�Ȃ�A�������Ă������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26181980
![]() 1�_
1�_
�V���b�^�[�u���͕���1/60�`1/200�b���炢�ŏo��ƔF�����Ă���̂ł����A����YouTube�ł�1/4000�b���炢�ŎB���Ă��܂��B
����ł��o��̂Ȃ�A���\ �A�ʎ��ɃV���b�^�[�V���b�N���傫���̂ł��傤���H
�~�܂��Ă���Ƃ����1/800�b���炢�ŎB���Ă��܂����A�u���͂Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F26182006
![]() 0�_
0�_
�ő�B�e�R�}���ARAW+JPE200�R�}�ȏ�ŃX�g�b�v�o�͂Ȃ����x���x���Ȃ�܂łɂȂ�����ł��ˁBGUHS-�U�AU3�J�[�h���g�p�����ꍇ�Ə����Ă���܂����Acfexpress type b���g������A�o�b�e���[���Ȃ��Ȃ邩�Acfexpress type b�̗e�ʂ����ς��ɂȂ�܂Œx���Ȃ炸�ɂ��ނ�ł����ˁH
�����ԍ��F26182331�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
S1M2�̓_�C�i�~�b�N�����W�u�[�X�g������ς�D��Ă���Ƃ̌��،��ʂ��悤�₭�m�F�o���܂����B
GH7�Ȃǂ̂悤�ɐÎ~��ł͎g���Ȃ����Ȃ̂��c�O�ł����A�Ï��ł̓���B�e�ɂ̓����b�g���L�肻���ł��B
�����4K60p���N���b�v�ł��ǂ��̂ł����A�Ï��ł̍����x�B�e�������̂ŁA����ς�掿�ʂł̊�{���\�̍�����S1M2�̕��ł����ˁB
4K60p�Ńn�C�u���b�h�Y�[�����֗��Ɏg���邵�AS1M2�ɂ��Ă����̂������ȋC�����ė����B
�A�[�o���X�|�[�c�͒ʏ�̓�AF�ƕʐݒ�̂悤�ł����A���̃��[�h�ł��A�Î~���Ă���l�̓��ɂ��K�`�s����������̂ł��傤���B
�p�r�ɂ���Đݒ�ύX���K�v�����A�l���F��AF���D��Ă��邱�Ƃ���]�ł��B
S1RM2�ŘA�ʎ��̃V���b�^�[�V���b�N�͍���f������ڗ��̂ł��傤���B
S5M2�ł͋C�ɂȂ������Ƃ������ł��B
�����ԍ��F26182473�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Q�O�����̒j����
�����͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��BS1II�́ASH�A�ʂ�180�R�}�i�Q�b������Ɓj�Ńo�b�t�@�t���ɂȂ�A�o�b�t�@�N���A��CFexpress�J�[�h��33�b�ASD�J�[�h��49�b�̃N���A���Ԃ��K�v�̂悤�ł��B
�܂�ꐢ��O�̑��ЃJ�����̋����o�X�K�i�Ō��x�ł��B����CFexpress�œ���̏������݂̓N���A�ł����悤�ł����A�X�`���̏ꍇ�͎����o�b�t�@���t���ɂ��Ă��珑�����݂��n�܂銴���ł��ˁB�i�����͏�������ł���̂ł��傤���ǁj
���ꂾ���������i�ɂ���̂�������A�����͐V�K�i�ɂȂ�Ȃ������̂��Ǝc�O�Ɏv���܂����A�X�`�����[�U�[�����Ă��Ȃ��������܂��B
S1II�Ő��̔�э��݂��v���A�ʂŎB��ꍇ�A��э��ݎ��Ƀo�b�t�@�g�����Ă��܂��ƁA���ʂ���オ���ė��鎞�͂����B��܂���B70�R�}�����łȂ��A20�R�}30�R�}�̐ݒ肪����ƃo�b�t�@�ɋ��o��̂ł����B�ނ���S1M2ES�̕����R�O�R�}�b�Ȃ̂ŋ������ėL���ł��B�������c�݂܂����B
�����ԍ��F26182474
![]() 2�_
2�_
��longing����
��S1RM2�ŘA�ʎ��̃V���b�^�[�V���b�N�͍���f������ڗ��̂ł��傤���B
��S5M2�ł͋C�ɂȂ������Ƃ������ł��B
���͓����Ă���l���̓A�X���[�g�����B��Ȃ��̂ł����AS1RM2�ł�S5M2�ł���S�̂������V���b�^�[�ŃL���̂Ȃ��ʐ^���B�������Ƃ�����܂���B�d�q�V���b�^�[�ł����Ƃ�Ȃ����߁A���J�V���b�^�[�A�ʂ��Ə펞�J�������U�����Ă����Ԃ䂦�A�\���Ƃ��Ă���̂��Ǝv��������ł��B
������ɂ��Ă����J�V���b�^�[�őS�R�}���s���g�����Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��̂ŁAYoutuber�̕��͊����ăo�`�s���łȂ������ʐ^�����o���Č��y���Ă���̂��A�����͕s���ł��ˁB
�����ԍ��F26182502
![]() 0�_
0�_
��kosuke_chi����
�u���J�̏ꍇ�A�Q���ڈȍ~�̓u���܂��B�v
�Ƃ����̂́AS1RII�ł̎��̌��ł͂Ȃ��A����Ȃ�z���Ȃ̂ł��傤���H
�����ԍ��F26182519
![]() 1�_
1�_
��taka0730����
�����܂���A�����͈�ʘ_�����܂��������Ƃ��Ă��������B�u���J�̏ꍇ�A�Q���ڈȍ~�̓u���邩������܂���v
�V���b�^�[�V���b�N�́A�斋���J�����U���Ő�������̂ł����A1/250�b��1/320�b�ȏゾ�Ɛ斋�������Ɠ����Ɍ㖋���ǂ�������̂ŁA�斋���J���ĐU�����N�������ɂ͘I���̂قƂ�ǂ��������Ă��邽�߁A�P�ʂł̓u���������܂���B
�������A�A�ʂ̏ꍇ�ɂ́A�㖋�̖߂�ł��U�����N���Ă��܂��̂ŁA�Q���ڈȍ~�̓u����\��������̂ł͂Ƃ��������ł��B�����Y�ɂ���Ă���������́A�����Ȃ����̂�����̂ŁA��T�ɂ͌����܂���B
�����ԍ��F26182538
![]() 0�_
0�_
�����J�V���b�^�[�őS�R�}���s���g�����Ȃ��Ȃ�
����f�@�ł��̂Ŕ�ʑ̃u�����Ă��邾���ł��傤�B
�쒹�B�e��SS1/4000�ŎB�e���Ă����ƃs�������Ă��i�オ���Ă܂����A�V���b�^�[�u������SS�̑��x�ł͖����ł��B
����������S1M2��3�@��͐��m���S���Ⴄ�@��ł��̂�S1R�̍���f�@�̃��r���[�łǂ��̂����̂����̂͐\����Ȃ��̂ł����A�Ӗ������ł�
�����ԍ��F26182817�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Q�O�����̒j����
LUMIXG9M2�AS5M2����ς�炸�d�q�V�b�^�[���͘A�ʖ����ɕς�炸��3�b���炢�Ńo�b�t�@�����t�ƂȂ�ACFexpress�J�[�h��33�b�ASD�J�[�h��49�b�̃N���A���Ԃ��K�v�ƂȂ�A�v���A�ʂ͂����������ԁA�����������o�܂��A���[�U�[��SSD�g���ăN���A���ԏグ��Ȃǂ��Ă܂��̂�S1M2�V���[�Y����������
�J�������̃{�g���l�b�N�ɂ��Ă̓��[�J�[���F���͂��Ă��邯�ǁA�N���A�𑁂�����Ƒ��̋@�\�ɂ������肪�o��̂Ńo�[�W�����A�b�v�͕ۗ��ɂȂ��Ă邻���ł�
�d�q�V�b�^�[�̘A�ʖ������R�i�K���炢�ɂ��邱�Ƃ͌������Ă邻���ł�
�����ԍ��F26182829�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������89����
S5II�Ƃ̈Ⴂ�̓_�ł́A�O�tSSD���g����悤�ɂȂ�Ƃ��������b�g������܂����ˁB
�Ƃ���ŁA8GB���x�̃o�b�t�@���������N���A����̂ɂR�R�b�Ƃ������Ƃ́ACFexpress�ւ̓����������ݑ��x�͑��250MB/s���Ǝv���܂��B
���Ђ�1,000MB/s���炢�̃C���[�W�Ȃ̂ł����A�O�tSSD�̎����l�͐��\�̂P�^�S���x�����Ȃ�Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA1,000MB/s��SSD���g���Ă������ăN���A�������Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�������Ȃǂ���܂��ł��傤��?
�����ԍ��F26183059
![]() 0�_
0�_
�ēx�m�F�����Ƃ���A����Ŏw�E���Ă���摜��1/2000�ł��ˁB
�i��͕s���ł����A���������{�P�Ă���̂ŊJ��F1.8�ł��傤���B
���̃V���b�^�[���x���Ɣ�ʑ̃u���A���J�V���b�^�[�̃V���b�N�u�����l���ɂ����ł��B
�������Ȃ���A���X��ʏ�ɓ����Ȃ����p����B�e���X�^�[�g���Ă��܂��B
���̏����ł́A�A�ʂŐU��������u�Ԃɓ��𑨂��āA�u���Ƀt�H�[�J�X�����ł�����K�v���L��܂��B
�b��10�R�}��6���ڂ̃V���b�g����摜�̍��ŏ��w�E���Ă���̂ŁA1/10�b�P�ʂł̃s���g���x�̎w�E�ł��B
�ǔ�AF�Ƃ��Ⴄ�����ł����AF1.8�Ń{�P�ʂ����������傫����A4500����f�̍��𑜓x�ŃK�`�s���ɂȂ�̂��ȁH�Ƃ͎v���܂��ˁB
�E�ڂɍ��ł��Ă���Ǝw�E���Ă��܂����A���ڂ͉e�ɂȂ��Ă����A���ڏ�Ԃœ��������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
����������������O�ɁA���̘̂A�ʂł͍ŏ�����\�j�[�ɂ͋y�Ȃ��Ǝw�E���Ă���A�����҂�AF�������Ƃ������Ƃ���ەt������Ő������Ă��܂��B
���ۂɃ\�j�[�ɂ͋y�Ȃ����Ƃ��m���Ȃ̂��Ƃ��Ă��A�\�j�[�Ȃ瓯�����ŃK�`�s���ɂȂ邱�Ƃ��ؖ�������ł͂���܂��A���Ȃ舫���ȃ��r���[�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F26183097�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
S1R�A�͓��悾�Ɣ�ʑ̂̃s���g���O�����Ƃ͖����̂�
�\�j�[�L���m�����������Д�r�ł������قǍ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�j�R���t�W�������AF�͗D��Ă���킯�ł͂���܂���B
����f�@���u�����₷���͓̂s�s�`���ł���B
����̂ł���Γ������ɏo���@��Ŏ�u����̒i�����ς��͂��ł���B
R6��R5�A��7c2�ƃ�7RV�A����o��S1�A��S1R�A�̎�u������\�͕ς��܂���B
����f�@���u���Ղ��͍̂���������������E�\�ł��B
AF���\�̓\�j�[�L���m���ȊO�h���O���ł��̂�
AF�ɂ������Ȃ�2�Ђ���I������ׂ��ł��傤�B
�����ԍ��F26183432�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��hunayan����
������f�@���u���Ղ��͍̂���������������E�\�ł��B
�ӏ܂����悾������A�Î~��ł�
�ŏI�ӏܔ{�����ς��Ȃ���A
�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�i������������͎��R�Ɍ�����̂ɁH
�u����t���������肷�炷��킯�ł����j
����f�@�Ńs�N�Z�����{�m�F����ꍇ
���f�@�����ӏܔ{�����オ��܂��̂�
�s���g���U��A��ʑ̃u���Ȃǂ�
�B�e���̑e�������₷���Ȃ�܂��B
�����̓t�B�����̃v�����g�����Ă��܂������A
�t���[�~���O��u�Ԃ̐�����ǂ��ʐ^��
�Z��͋��e�͈͂ł���L���ɂ͑ς��Ȃ�
�i������Ɗ���Č�����Ǝ��͎ʂ肪�Â��j
�J�b�g������܂������ǂˁB
����f�@�ł̃g���~���O�𑽗p�������ɂ�
�i���B�e�Ƃ������̃v���̑I��̃A�b�v�Ƃ��H�j
�������Ȃ��A�Ƃ͌����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F26183462
![]() 0�_
0�_
���Ƃт��Ⴑ����
��f���ɂ����̐���Œ��f�A����f�̊������Ǝv���܂����A
�����2000-2400��������͉�f���͏��Ȃ��A
4000�����z����Δ�r�I������f���ɂȂ�Ǝv���܂��B
����f�̓u�����ڗ����Ղ��̂ł͂���A����f�͖ڗ����ɂ����A
���ɂ������Ƃ��Ă��A���ǃu���鎞�̓u���Ă���킯�ł��B
���̓{�f�B����u��������̃N���X�ł��ƕK���t���Ă���A
�u����f�@���u���Ղ��v�͂��Ȃ�`�[�����Ă�Ǝv���܂����A
2400����f��4400�A4500����f�Ńu���̖ڗ����Ղ��̕����ǂ̒��x���Ȃ�Đ��l���o���܂����ˁB
���ہA����2400����f�@��4200���A5000����f�@�����N�����p���Ă��܂������A
�摜���u���Ă����ʐ^�̊����ɍ������������Ƃ͂���܂���B
�����āA�V�^�@�킪�o��ƃ{�f�B����u����̃e�X�g��
YouTube�ōs�Ȃ�ꂽ�肵�܂����A
�V���b�^�[�X�s�[�h�̉��b�܂Ŏ~�߂��邩�Ȃ�ăe�X�g�����Ă��A
����f�@�ƍ���f�@�Ō��ʂ͉����ς��Ȃ��̂ł��B
�����]�X�ȑO�ɁA���g�p��܂������l����K�v���Ȃ��u����f�@�̓u���Ղ��v����
������Ȃ����Ƃ��̏�Ȃ��ł��B
���Ȃ��Ƃ��J�������w������ۂ̌��������ɂ���K�v�̓[���ł��B
�����ԍ��F26183504�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��hunayan����
���Ƃт��Ⴑ����
��U��Ɣ�ʑ̃u���ł͏��X�Ⴄ�Ǝv���܂��B
�����܂Ŏ����ł����A����f�@�Ń{�f�B����U���������@��̓��C�JM11���炢���Ǝv���܂����A�{�f�B����U���⋦����U���̏ꍇ�A���{�`�F�b�N���Ă����E�܂ŃV���[�v�Ō��E����ƈ�C�ɔj�]���銴���ł��B
�����͐Î~�����B�鎞�͎�U�ꂷ��悤��SS�ł͎B��܂��A����f�@�E���f�@�ǂ�������E�ƂȂ�SS�͓����ŁAhunayan����ɓ��ӂł��B
����A��ʑ̃u���̏ꍇ�͕ʂŁA���̔��Ă�X�|�[�c�I��{�Ō���ƃu���Ă��邱�Ƃ�����܂����AWEB�p��30����f�ɏk��������ASNS�p�ɏk������Ǝ~�܂��Ă��邩�̂悤�ɃV���[�v�ɂȂ�܂��B���l��4500����f��2400����f�ɏk������Ə����u�����y�������̂ŁA�����͂Ƃт��Ⴑ����̌�����Ƃ���ł��B
>���Ȃ��Ƃ��J�������w������ۂ̌��������ɂ���K�v�̓[���ł��B
�͂��B2400����f�ɏk������Δ�ʑ̃u���������Ȃ̂ŁA�u�����C�ɂ��Ē��f�@�ɂ���Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�Â��Ƃ���ł�AF���x�͒��f�@�̕�����ʓI�ɂ͗ǂ����������܂��B
�����ԍ��F26183542
![]() 0�_
0�_
������f�@���u�����₷���E�E�E
�ꕔ�̎B�e�Ώۂł͎����ƍl���Ă܂��A��f�����オ���ĉ摜�s�b�`���ׂ����Ȃ��Ă܂�����A���{�Ō���@������X�|�[�c��i�ł̓V�r�A�ɂȂ��Ă��Ă܂��B
����f�̃~���[���X�@�Ńg���~���O�O��ŎB�e����悤�ȎB����ł̓Z���T�[�̐��\���オ���Ă��Ă܂��̂ŁA�Z���T�[�T�C�Y���炢�܂�SS���グ�������ʑ̃u�����}�����܂��B
���������܂ł��������O��ł��̂ŁA�Î~��ɂ��Ă͖{�̂̎�Ԃ������͂ɂȂ��Ă܂��̂ł��̌���ł͖����Ǝv���܂�
�����ԍ��F26183705�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��hunayan����
������f�̓u�����ڗ����Ղ��̂ł͂���A����f�͖ڗ����ɂ����A
�����ɂ������Ƃ��Ă��A���ǃu���鎞�̓u���Ă���킯�ł��B
�������A�ǂ�������l�Ƀu���Ă���킯�ł����A
�g��{�����傫���Ɩڗ����₷���͎̂����ł���B
�����Ȃ��Ƃ��J�������w������ۂ̌��������ɂ���K�v�̓[���ł��B
�J�����w���̍ۂɍ���f������I�Ȃ��A
�ȂǂƂ͌����Ă��܂��E�E�B
���ێ����͍���f�@�̕��������̂ŁB
�Z���T�[�ǂݏo�����x������f�@�ŁA
���[�����O�V���b�^�[�i�d�q�V���b�^�[�j��
���p�ȉ��̑��x�Ȃ�I�����ʂ�������A
�Ƃ����͎̂����̏ꍇ�͂���܂����ǂ��B
������̂ł���Γ������ɏo���@��Ŏ�u����̒i�����ς��͂��ł���B
�ӏܔ{���������Ŏ�U�����J�̐��\�������Ȃ�A
���f�@�ƍ���f�@�œ�����i���ɂȂ�͓̂��R�ł��B
��kosuke_chi����
������f�@�E���f�@�ǂ�������E�ƂȂ�SS�͓����ŁA
������ӏܔ{���������Ȃ�A�Ƃ������Ƃł��B
�����̏ꍇ�͎�U��͓��{�m�F����̂�
�i��f���ɂ��g��{���������̂Łj�A
������ƈ�ۂ��قȂ�܂��ˁB
���u�����C�ɂ��Ē��f�@�ɂ���Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����͂��������b�͂��Ă��Ȃ��̂ł����E�E�B
�����A��ɏq�ׂ��悤�ɓd�q�V���b�^�[��
���p�ȉ��ɂȂ�悤�ȍ���f�@�̏ꍇ��
�I������ۂɂ�͂�C�ɂȂ�܂��ˁB
�i�����̏ꍇ1/30�b���x���@��j
�����ԍ��F26184123
![]() 1�_
1�_
�����v���Ȃ�A���ʏƎ˂ɂ���ϑw�^�ɂ��捂��f�@����������Ă������
����f�@�̓u���Ղ��Ɛ�������Ηǂ������ł���B
���͋C�ɂ���K�v�͂Ȃ��Əq�ׂ܂��B
���Y���͉����ς��܂��A�ꏏ�ł�����B
���ƍ���f�@�͂�������\�����ق����ǂ��Ƃ����l�����܂����ǁA
�{���ɂ�����Ȃ��b���ł��B
��������\���Ȃ��ƃu��������A�ݒ�ł���A����f�@������f�@�������ł��B
�������ōw�������҂�f�킷�悤�Ȃ��Ƃ����͐������܂���
�B
�����ԍ��F26184174�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���Ƃт��Ⴑ����
�Ƃт��Ⴑ����̏ꍇ�́A�����������Ƃł�낵���̂ł́B
�l�ɂ���ċZ�ʁA�g�p���郌���Y�A��ʑ́A���������܂��������قȂ�܂��̂ŁA��T�ɂ͌����Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁB
���͑S�Ă̎ʐ^�{�`�F�b�N���܂��i�g���摜�\�t�g�������N���b�N�œ��{�ɂȂ�̂Łj�B�Î~���̏ꍇ�͎O�r�ŎB�����ʐ^�Ɠ�������Ƃ��Ă��܂��B
�����܂Ŏ��̏ꍇ�͂Ƃ������Ƃł��肢�������܂��B
���u�����C�ɂ��Ē��f�@�ɂ���Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�������͂��������b�͂��Ă��Ȃ��̂ł����E�E�B
�͂��Bhunayan����ւ̃R�����g�ł��B
�����ԍ��F26184209
![]() 0�_
0�_
��hunayan����
����������\���Ȃ��ƃu��������A�ݒ�ł���A����f�@������f�@�������ł��B
���x���\���グ�܂����A�g�嗦�ɂ��
���ꂪ�ڗ����ǂ����A�Ƃ����b�ł��B
�g�傷��ׂ������������Ă���̂�
������O�̘b�ł���B
�ŏI�m�F���Ⴆ�g���~���O�Ȃ��ŁA
�����Î~��̃��j�^�[�ł�
�t���X�N���[���ӏܓ������
���R�ς��܂���B
�������v���Ȃ�A
�����g�̎g�����ŋC�ɂȂ�Ȃ�����A
���ꂪ�^���A�Ƃ����̂͂�◐�\��
�c�_�Ɏv���܂��ˁB�v���A�v��Ȃ�
�Ƃ����b�ł͂���܂���B
���������ōw�������҂�f�킷�悤�Ȃ��Ƃ����͐������܂���
�N������f�@���ȂȂǂƔ������Ă��܂��E�E�B
S1RII������ĂȂ��͍̂���f������ł͂Ȃ�
AF�̖��ŁA���f�ł��낤������f�ł��낤��
���ړI�ɂ͊W�Ȃ��Ǝv���̂ł����E�E�B
�����ԍ��F26184212
![]() 0�_
0�_
S1R2�͎��̏�������̂ŁA
����ĂȂ��Ƃ����킯�ł͖��������ł����B
�F�X�A�����ƒ��ׂĂ���̂ق����ǂ��ł��傤�B
���͒���f�@�A����f�@�p���ė������܂����B
�ʂɒ��ׂ��킯�ł͂���܂���B
���������B���āA����A�����������Ǝv�����킯�ł��B
����܂ł͎�������f�@�̓u���Ղ��Ǝv���Ă܂����B
�����������Ǝv���č���f�@���u���Ղ����R�ׂ�ƁA
����f�@�͈Â��ʂ�̂ŁA���f�@���V���b�^�[�X�s�[�h��������K�v���o�Ă���̂�
�u���Ղ������ł��B
�����āA�g�嗦�̘b�͌�t���ł���B
�����炨�������ł��B
�����ԍ��F26184230�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��hunayan����
������f�@�͈Â��ʂ�̂ŁA���f�@���V���b�^�[�X�s�[�h��������K�v���o�Ă���̂�
�����܂���A�����́A����f�@�͎������Â����Ńm�C�Y���o�₷���̂ŁAISO���x��Ⴍ�}���A���X���[�V���b�^�[�ɂ��邱�ƂŃu���₷���A�Ƃ������Ƃł�낵���ł��傤��?
�����ԍ��F26184272
![]() 0�_
0�_
��hunayan����
�������āA�g�嗦�̘b�͌�t���ł���B
�������炨�������ł��B
�ŏ��̃��X����A���L�̂悤�ɐ\���グ�Ă��܂��B
���ŏI�ӏܔ{�����ς��Ȃ���A
���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������Ƃ����y���Ă���̂ŁA
����������������Ƃ悢�̂ł����B
������f�@�͈Â��ʂ�̂ŁA���f�@���V���b�^�[�X�s�[�h��������K�v���o�Ă���̂�
���u���Ղ������ł��B
����͍���f�@�Őݒ�\�Ȃ��肬���
�����xISO�̈悩�Ȃɂ��̘b�ł��傤���B
�ʏ�ISO�ݒ�̈�ŏ�L�̘b���{���Ȃ�A
�Ⴆ�Γ���ISO�W�O�O�A����F�l�ō���f�@����
�Â��ʂ��Ă��܂����߁A�V���b�^�[���x��
���f�@��蒷������i���I�o���ς��j�A
�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���������Ȃ��ł����H
�����̏ꍇ�͒��f�@�ƍ���f�@��
�I�o�l���Ӑ}�I�ɕς�����͂��Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F26184281
![]() 2�_
2�_
��u���������J�����ɂ����āA�u���Ղ��͉�f���ɉe�����Ȃ��Ǝv���܂��B
��u����������Ȃ��Ȃ�̂́A��u������j�b�g�̉ғ��̈���đ傫���u�����Ƃ��݂̂ł��B
���ʒu��ʂō���������24mm�ł����A��ʓ��ő���1mm�u�����炩�Ȃ�̃u���u���Ȃ̂ŁA�ʏ�͕�̍ۂɎ��ۂɓ������Ă���ʂ͔����ʂŁA�������ɓ������[�^�[���g�p���Ă��܂��B
��u������j�b�g�͍����ɁA�����������ɒǏ]����̂ŁA����f�@�ł����肵���掿��������̂ł��傤�B
����ɑ��Ĕ�ʑ̃u���͗}����ꖳ���̂ŁA����f�@���u���ɂ��掿�ւ̉e�����ڗ����Ղ��̂ł��傤�B
�s���{�P�����l�ŁA�s�N�Z���s�b�`������������f�@�́A�_�����������f�s�b�`�����傫���Ȃ�ƃs���{�P��ԂɂȂ�̂ŁA����f�@���ł���ΐ��\�ɃV�r�A�ł��B
�����ԍ��F26184335�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��{�I�ɂ͒���f������f���Z���T�[�T�C�Y�������Ȃ�����͓����ł��B
�s���{�P���A��ʑ̃u���������ł��B
�u�������{�P��������ł��B
�����ς��܂���B
�ł��̂ŋC�ɂ���K�v�͂���܂���B
�ς��悤�ɔ�������Ă���������܂����A���v�ł���?
���ۂɎB���Č���ׂĂ݂��ق����ǂ��ł���B
����f�@���Â��ʂ�A�͈ȑO�����Ă����b����
���̍l���ł͂���܂���B
��f�s�b�`�����������炾�����ł��B
���̍l���ł͂���܂���B
�����čŋ߂̓Z���T�[�̐��\���ǂ��Ȃ����̂ŁA���͖����Ȃ����A
���̂��ߊg�嗦���̔�ʑ̃u�����̂ɗ��R���ύX�ɂȂ����悤�ł��B
���ꂪ��t���ł��B
����[���Ȃ��b�ł���B
�����ԍ��F26184512�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>���x���\���グ�܂����A�g�嗦�ɂ��
���ꂪ�ڗ����ǂ����A�Ƃ����b�ł��B
�g�傷��ׂ������������Ă���̂�
������O�̘b�ł���B
�ŏI�m�F���Ⴆ�g���~���O�Ȃ��ŁA
�����Î~��̃��j�^�[�ł�
�t���X�N���[���ӏܓ������
���R�ς��܂���B
�܂��B�e��������Ƃ��@��ɂ���āA�܂���ς�����b�ł͂��邯��ǂ��g�嗦�̈Ⴂ�Ő�������͔̂@���Ȃ��̂��ƁB
�Ƃ����̂́A2400����f�̃J�����̏ꍇ�͌��X�̕`�ʌ��E�ɉ����ă��[�p�X�t�B���^�[�̃}�C�i�X�e��������AJPEG�G���W���ɂ���Ă��ꂪ(�����ڏ�)�قڏ���������x�ɂ̓V���[�v�l�X�▾�Č��ʂ��������Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA�g�債�Ă���ƕ�������x�̔��u���ł�����̃V���[�v�����͈̔͂Ŗ�����Ă��܂��ꍇ�������ƍl�����܂��B
������4500��6000���̃��[�p�X���X�@��̓V���[�v�̐ݒ肪���������Ⴂ�܂����A�V���[�v��������O�̉摜�������Ⴂ�܂��BRAW�ŃV���[�v�ݒ�̐��l��S�������ɂ�������Ȃ���r�ł���Ƃ��������Ȃ��ł��傤�B
�Ȃ̂Ŋg�傷��ׂ�������e���ڗ����Ղ��Ȃ�A�Ƃ����Ă��A���܂�q�ϐ����Ȃ��Ď����Ƃ��ꗂ�����悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F26186470�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��longing����
����u���������J�����ɂ����āA�u���Ղ��͉�f���ɉe�����Ȃ��Ǝv���܂��B
��hunayan����
����{�I�ɂ͒���f������f���Z���T�[�T�C�Y�������Ȃ�����͓����ł��B
���J����SP����
���܂���ς�����b�ł͂��邯��ǂ��g�嗦�̈Ⴂ�Ő�������͔̂@���Ȃ��̂��ƁB
������̎�U�����J�Ő��\�������ꍇ�A
�u�Z���T�[��ŕ�ł����U��̐�Ηʁv��
�����ł���ˁH
�i��F��7CII�ƃ�7CR�Ƃ��AR6��R5�Ƃ��j
��U���̓Z���T�[��̂Ƃ����f��
���B���ׂ��������ꂽ���̂�{���̈ʒu��
�߂���Ƃɑ��Ȃ�܂���B�iIBIS�AOIS�A
�O�r�g�p�A��������\����A���ړI�͓����ł��j
���S�ɂ���ׂ��N�_���炸���ꍇ�A���̂����
���m���Ė{���̈ʒu�ɖ߂����Ƃ���킯�ł����A
2400����f�ł͂��͈̔͂Ɏ��܂�u���ł����Ă�
6100����f�ł́u�ƂȂ�̉�f���ł��Ȃ��ق�
�I�����Ă��܂��܂ł̃u���v�ɂȂ�܂���ł��傤���B
�i�}1�A�}2�j
�אډ�f�ɓ���͂��̌����{���̉�f�i���S���j
�ɂ�����ł��傤����A�I�o�s���͂Ȃ��ł��傤���A
�e�F�̐F�����͖��炩�Ɉ����Ȃ�܂��B
�i���m�N���ł��P�F�Ƃ��������ŕ������킭��Ȃ�܂��j
�摜�����ő����̂��܂����͂ł���Ǝv���܂����A
�אډ�f�̘I�����ڗ��A���邢�͂�葽���Ȃ�
�قǂ̋O�ՂɂȂ�Ɖ摜��̓u���A�Ƃ��Ďc��܂��B
�i��ςł���t���ł�����܂���j
�|�[�g���[�g��SK����̂悤�ɐ�ΓI�ȉ𑜓x��
�����܂ŏd�v������Ȃ��A�܂��̓e���r�ȂǂŁA
�ӏ܃T�C�Y�����܂��Ă���ꍇ�͍���f��
���f��������قǕς��͂Ȃ��A�Ƃ���
���ӌ�������������������Ƃ͎v���܂��B
��������f�@���[�U�[�Ȃ�2400����f�ł�
������Ȃ����i�̑�L���≓���̒���
�����Ȃǂ̃g���~���O���������������ʂ�
����������Ǝv���܂��B
�i2400����f�Ŏg���ӏ܃T�C�Y�ȏ�Ɂj
�g�傷��̂̓i���Z���X�A�Ƃ����̂�
�ĉf�ʂ̍D�݂̃t���t���[���ł̎B�e��
��r�I�e�ՂȎB�e�W�������i�|�[�g���[�g��
�X�i�b�v�Ȃǁj�ł̘b���ȂƊ����Ă��܂��܂��B
���j�}�̐����ŁA�{����2400����6100����f��
��f�s�b�`�͖{��1.59�{�̈Ⴂ�Ȃ̂ł����A
��}���ʓ|�Ȃ���3vs5�}�X�ő�p�i1.67�{�j
���Ă��܂��B
�����ԍ��F26188927
![]() 0�_
0�_
��hunayan����
������f�@�͈Â��ʂ�̂ŁA���f�@���V���b�^�[�X�s�[�h��������K�v���o�Ă���̂�
����f�͒ኴ�x�ŁA�Ƃ����b���Ȃ�̂��Ƃ�
�ǂ�������Ȃ������̂ł����A�������
�t�W���J��������̐����̂��Ƃł��傤���B
�E����f�J�����ŎB�e���郁���b�g�E�f�����b�g
�u�f�����b�g
��u���Ɏア
��f���̑����J�����ŎB�e����Ƃ������Ƃ́A��f1������̎���ʂ����Ȃ��Ȃ�܂��B
�Â��Ƃ���Ńm�C�Y�����₷���̂Ɠ������V���b�^�[���x�������Ȃ�A
��u�����N���₷���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�������A�ߔN�̍���f�J�����͉摜�����G���W���̑啝�Ȑi����
�{�f�B����u������ڂ̐��i�������Ă��Ă���A���P����Ă��܂��B�v
�E�ʐ^�E����̎B����E�n�E�c�[�i2025.01.05�j
�J�����̉�f���͑������������H�掿�Ƃ̊W�ƍ���f�̃����b�g�E�f�����b�g�����
https://www.fujiya-camera.co.jp/blog/detail/info/20200820/
����f�@�̍����x�h�r�n�m�C�Y������邽�߂�
�V���b�^�[���x��������A�Ƃ����B�e�@��
�u���₷���Ȃ�̂͂܂��A����͓��R�ł����A
������͒��f�@�ƍ���f�@���g���ۂ�
�u�^�p��ł̃u���₷���v�̈Ⴂ�̐����ł��B
���F�X�A�����ƒ��ׂĂ���̂ق����ǂ��ł��傤�B
�����̏ꍇ�ł����A��������̓L�^������
�u����͂��������ʁv�̂��߁A
���h�o�V��}�b�v�A�t�W���������
�ɂ����邩�Ŕ��f���Ă��܂��B
�����قǂ�S1RII�̂`�e�̘b�������܂������A
�����A�ʂł��Ă����[�����O���傫�����Ƃ�A
���ڂ��ꂽ����@�\�����̘^��\���Ԃ�
�t�@���A�t�B���t���Ȃ̂ɂ����̂Ȃ�
��1II�9III�������͒Z���A�Ƃ����_����
��ÂɎs��ɔ��f����Ă���̂��Ǝv���܂��B
�����Ȃ�ɒ��ׂĂ͂������Ȃ̂ł����E�E�B
�����ԍ��F26188948
![]() 0�_
0�_
>���S�ɂ���ׂ��N�_���炸���ꍇ�A���̂����
���m���Ė{���̈ʒu�ɖ߂����Ƃ���킯�ł����A
2400����f�ł͂��͈̔͂Ɏ��܂�u���ł����Ă�
6100����f�ł́u�ƂȂ�̉�f���ł��Ȃ��ق�
�I�����Ă��܂��܂ł̃u���v�ɂȂ�܂���ł��傤���B
�i�}1�A�}2�j
�}���̂��͕̂�����Ղ��̂ł����A����͎�Ԃ�Ƃ�����胁�J�V���b�^�[�Ȃǂ���̔��U���ɂ��u���Ɏv���܂��B
���ۂ�6000����4500����f�́A�u���s�ʐ^�Ƃ����قǂł͂Ȃ��͂��ȃu���v�̓��{�摜���茳�ɉ���������܂����H���̉摜�́A2����3�s�N�Z���̒P�ʂŃu���Ă��܂��ł��傤���H
�����z�肵�Ă���͂��Ȏ�Ԃ�́A�Ⴆ�ΘI�����Ԃ̂���9���ʂ͂قڕ����Ă���A�c���1�����Y���Ă���(���ʁA�֊s�̃R���g���X�g�ቺ)�悤�ȃC���[�W�ł��B���Ȃ��G�c�ł����B
>�אډ�f�ɓ���͂��̌����{���̉�f�i���S���j
�ɂ�����ł��傤����A�I�o�s���͂Ȃ��ł��傤���A
�e�F�̐F�����͖��炩�Ɉ����Ȃ�܂��B
�i���m�N���ł��P�F�Ƃ��������ŕ������킭��Ȃ�܂��j
���ɂ������Ƃ��Ă��A
���[�p�X�t�B���^�[�ɂ��(��Ԃ�ȑO��)�F�����̈������}�C�i�X30�_�A�}�Ɏ����ꂽ�悤�ȃu���ɂ��(���[�p�X���X����f�@)�̃}�C�i�X������20�_�Ȃ�A����f�@�̂ق�����Ԃ�Ɏア�Ƃ͒f��ł��Ȃ��C�����܂��B
����f�ł�����[�p�X���X�ł͂Ȃ��Ă��A�����ʂ̔������[�p�X�ɏo����킯�Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F26189334�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
���}���̂��͕̂�����Ղ��̂ł����A����͎�Ԃ�Ƃ�����胁�J�V���b�^�[�Ȃǂ���̔��U���ɂ��u���Ɏv���܂��B
���������悤�Ƀu���̓~���[�A�b�v��
�V���b�^�[�斋�̓��B�Ռ��ł��N���܂��B
�������A�~���[���X���d�q�V���b�^�[�Ɠ���
����B�e�ł���U��͋N����̂ł��B
�����Â��_���ł����A�X�`���Ɠ����
��U��v���Ɋւ���_���ł��B
�E���w����U���͂ǂ��܂ʼn\���H
��U��v���ƎB�e�摜�̍��𑜓x���B
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/62/4/62_4_500/_pdf
�������z�肵�Ă���͂��Ȏ�Ԃ�́A�Ⴆ�ΘI�����Ԃ̂���9���ʂ͂قڕ����Ă���A�c���1�����Y���Ă���
9�������̉�f�́i���[�p�X�܂މ摜������
���܂�����j��͈͂ɓ����Ă���A�ł��ˁB
���̂킸���Ǝv����U�ꂪ�A���b���̎�U���
���]���̂悤�ȕ����p�x�̏����������Y�ł�
���ɂȂ�Ȃ��ł��傤���B���̎�U����
���E�l�ɋ߂��悤�ȏ����ł͕�����Ղ�����
�v���̂ł����B
�����W���Ȃ��Ȃ�A���b���ł������]���ł�
�Î~�̔�ʑ̂ɂ�����AF�����܂��Ă����
��U��i�Ǝv�����掿�ቺ�j�͋N���Ȃ������ł����A
�����g�̃J�����ł͂������ł��傤���B
�Z�Z�b�莝���B�e�\�I�Ƃ��������݂Ă�
���ƂȂ��Â��i�莝�����͂������ǂ��ł����j�A
�摜���g�傷��ƒ��S�����炫����Ƃ�
�𑜂��Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂����ƌ������܂��B
�����[�p�X�t�B���^�[�ɂ��(��Ԃ�ȑO��)�F�����̈������}�C�i�X30�_
���_�ʐ^�p�Ƀ��[�p�X����苎�����J������
���[�p�X�̂Ȃ��j�R��D800E��D800�����A
�i�i�Ƀu���₷���Ȃǂ̎��Ⴊ����̂ł��傤���B
�i�����͕��������Ƃ�����܂��j
�����ԍ��F26189374
![]() 0�_
0�_
�Ƃт��Ⴑ����
���Ԃ̓s��������_���͓ǂ߂Ȃ��ł��B
�����̂킸���Ǝv����U�ꂪ�A���b���̎�U���
���]���̂悤�ȕ����p�x�̏����������Y�ł�
���ɂȂ�Ȃ��ł��傤���B���̎�U����
���E�l�ɋ߂��悤�ȏ����ł͕�����Ղ�����
�v���̂ł����B
�����W���Ȃ��Ȃ�A���b���ł������]���ł�
�Î~�̔�ʑ̂ɂ�����AF�����܂��Ă����
��U��i�Ǝv�����掿�ቺ�j�͋N���Ȃ������ł����A
�����g�̃J�����ł͂������ł��傤���B
������ƕԐM�̈Ӗ���������Ȃ��ł��B
���́A�u���ɂȂ�Ȃ��v�u�W���Ȃ��v�Ƃ����Ӑ}��
�u�I�����Ԃ̂���9���ʂ͂قڕ����Ă���A�c���1�����Y���Ă���v�Ƃ��������������킯�ł͂Ȃ��B
�ǂ��炩�ƌ����ƁA���肬��NG(�\�Ȃ�B�蒼������)�̏ꍇ���C���[�W���Ă��܂��B
>�Z�Z�b�莝���B�e�\�I�Ƃ��������݂Ă�
���ƂȂ��Â��i�莝�����͂������ǂ��ł����j�A
�摜���g�傷��ƒ��S�����炫����Ƃ�
�𑜂��Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂����ƌ������܂��B
���͎莝�����b�A�̂悤�ȎB�e�͂��Ȃ��h�ł��B
�����_�ʐ^�p�Ƀ��[�p�X����苎�����J������
���[�p�X�̂Ȃ��j�R��D800E��D800�����A
�i�i�Ƀu���₷���Ȃǂ̎��Ⴊ����̂ł��傤���B
�i�����͕��������Ƃ�����܂��j
���[��B������Ӗ���������Ȃ��B
���́A�ǂ��炪�i�i�ɂԂ�₷���A�Ƃ����悤�Șb�͑S�����Ă��܂���B
���[�p�X�t�B���^�[��K�v�Ƃ�����f�̃J�����́A��Ԃꂷ�邵�Ȃ��ȑO(����\�ɂ�炸)�ɑS�Ă̎ʐ^���ڂ₯�܂��B(A)
��ɂƂт��Ⴑ���}�Ŏ����ꂽ���u��(���f�@�ł͎��F������Ȃ�u��)��z�肷��Ȃ�A����f�̃J�����͎�Ԃ���E�t�߂ł��F�����������Ȃ�ڂ₯��Ƃ��܂��B(B)
B��90�_�̎���70�_�̎��ł炯�闦�͒��f�@��菭�������ł��傤�B����������������āA����f�̃J�������u���₷���Ƃ͌����Ȃ����A���̋t���R��Ƃ����b�ł��B
�u�����L�^���Ă��܂����A��ʑ̂������ɋL�^�ł���킯�ŁA���̑��E���镔����������Ă��܂��B�ܘ_�A���炩�Ƀu�����ڗ��ꍇ�̘b�ł͂���܂���B
�����ԍ��F26189428�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
���ǂ��炩�ƌ����ƁA���肬��NG(�\�Ȃ�B�蒼������)�̏ꍇ���C���[�W���Ă��܂��B
����B�e�����Ńu�����A�Ǝv������B�蒼���킯�ł���ˁH
���̃_�����A�Ƃ��锻�f�������f�@�ł͏オ��킯�ł����B
�����͎莝�����b�A�̂悤�ȎB�e�͂��Ȃ��h�ł��B
�|�[�g���[�g�����B�e����Ȃ��Ȃ��
���R���b�I�������@����܂��Ȃ��ł��傤���A
�����獂��f�����f����U��ɂ͊W�Ȃ�
�Ƃ�����̂ł��傤���B
�����g�̂�������ꂽ�B�e�͈́A�ΏہA
�ӏܖ@�ł̂����f�ɂȂ�܂���ł��傤���B
�����[�p�X�t�B���^�[��K�v�Ƃ�����f�̃J�����́A
����Ԃꂷ�邵�Ȃ��ȑO(����\�ɂ�炸)�ɑS�Ă̎ʐ^���ڂ₯�܂��B(A)
���[�p�X�@�ł͂����������ׂĎʐ^���ڂ₯�邩��A
���f�@�̓u���Ɋ��e�A����f�@�̓��[�p�X����������
��U��ɃV�r�A�A�Ƃ������l���ł��傤���B
�������܂��ƁA���f�@�ɂ͎�U����
�ʂɗL���Ă��Ȃ��Ă��ǂ���ł����ˁH
�����[��B������Ӗ���������Ȃ��B
���[�p�X�̗L���Ńu���̔��f���ς��A�Ƃ�������ׁ̈A
�������[�J�[�A����f�A�����\�����[�p�X�t�B���^�[��
�L�������m�ȋ@����Ƃ��ďグ���̂ł����A
���̈Ⴂ�͂킩��Ȃ��̂ł��傤���B
�������܂��ƁA���[�p�X�̗L����
���܂�W���Ȃ���������܂���ˁB
���u�����L�^���Ă��܂����A��ʑ̂������ɋL�^�ł���킯�ŁA���̑��E���镔����������Ă��܂��B
�u�����L�^���Ă��܂�����A�����Ɏʂ邱�Ƃ͂���܂���B
����Ƃ�����f�@�̓u�����L�^���₷�����ǂ��A
���ӂ��ĎB�e����A�����Ɏʂ����Ƃ��o����A
�Ƃ����Ӗ��ł��傤���B
��������������Ղ���Ƃ���1200����f��6100����f
�i��f�s�b�`����2.25�{�j�ł͂������ł��傤���B
�i�}3�C4�j
��U���\�͂������ꍇ�A���[�p�X�]�X�ȑO��
����f�@�̕����ǂ����Ă��u���ɃV�r�A�ɂȂ肻���ł����B
���F��}��3�F7�i2.33�{�j�̂��ߎ��ۂƂ͈قȂ�A
�u���̋O�Ղ�������������K���ȃC���[�W�ł��B
�����ԍ��F26189522
![]() 0�_
0�_
>����B�e�����Ńu�����A�Ǝv������B�蒼���킯�ł���ˁH
���̃_�����A�Ƃ��锻�f�������f�@�ł͏オ��킯�ł����B
6000���M���M���̃f�B�e�[���ŁA�Ƃ������͐T�d�ɎB�e���܂��B2400���ł����l�ł��B
���|�[�g���[�g�����B�e����Ȃ��Ȃ��
���R���b�I�������@����܂��Ȃ��ł��傤���A
�����獂��f�����f����U��ɂ͊W�Ȃ�
�Ƃ�����̂ł��傤���B
�����g�̂�������ꂽ�B�e�͈́A�ΏہA
�ӏܖ@�ł̂����f�ɂȂ�܂���ł��傤���B
�|�[�g���[�g���A���̎B�e�W�������̕��������ł��B�������i�ł͂����ďڂ������M���Ă��܂���B
��Ԃ�����̎B�e���p�ɂɂ��Ă��܂��B
�����[�p�X�t�B���^�[��K�v�Ƃ�����f�̃J�����́A
����Ԃꂷ�邵�Ȃ��ȑO(����\�ɂ�炸)�ɑS�Ă̎ʐ^���ڂ₯�܂��B(A)
���[�p�X�@�ł͂����������ׂĎʐ^���ڂ₯�邩��A
���f�@�̓u���Ɋ��e�A����f�@�̓��[�p�X����������
��U��ɃV�r�A�A�Ƃ������l���ł��傤���B
�������܂��ƁA���f�@�ɂ͎�U����
�ʂɗL���Ă��Ȃ��Ă��ǂ���ł����ˁH
�Ⴂ�܂��B�ǂ��炪�V�r�A�ƒf�肷��Ӗ��������A�Ƃ����b�����Ă��܂��B
��Ԃ��͕K�v�ł��B��ɐ}�ł��߂��ꂽ�A�u2400���ł͂قږ����ł��邪����f�ł͎��F�ł�������ȃu���v�ɑ��錩���́A��Ԃ�������Ȃ�ɗL���ɍ�p������(�������́A�œ_������2�{�ʂ�SS�͊m��)�ł̘b�Ȃ̂ŁB
���u�����L�^���Ă��܂����A��ʑ̂������ɋL�^�ł���킯�ŁA���̑��E���镔����������Ă��܂��B
�u�����L�^���Ă��܂�����A�����Ɏʂ邱�Ƃ͂���܂���B
����Ƃ�����f�@�̓u�����L�^���₷�����ǂ��A
���ӂ��ĎB�e����A�����Ɏʂ����Ƃ��o����A
�Ƃ����Ӗ��ł��傤���B
���ׂȃu���A�ł���A���Ȃ�̒��x�����Ɏʂ��Ă��܂��B�v�́A��������2400���@�̃��[�p�X�L�摜�����V���[�v������K�ɂ��Ă���荂���_�̎ʐ^�ɂȂ�ƁB
2400���Ŋg�債�Ăقڎ��F�ł��Ȃ����x���̔��u���A��Ԃ������������������Ŋ��S�ɂ͕������Ă��Ȃ��̈�̉摜�ł��B
�������A��ɒ��f�@���L���Ƃ͂���������͏o��ł��傤�B
>��������������Ղ���Ƃ���1200����f��6100����f
�i��f�s�b�`����2.25�{�j�ł͂������ł��傤���B
�i�}3�C4�j
��U���\�͂������ꍇ�A���[�p�X�]�X�ȑO��
����f�@�̕����ǂ����Ă��u���ɃV�r�A�ɂȂ肻���ł����B
1200���A500���A�Ƃǂ�ǂ炵�Ă�����
��Ԃ�����������Ŏc��悤�Ȕ��u���A�͈̔͊O�ɂȂ�Ǝv���܂��B���͂��Ԃ�����v��Ȃ��ƁB
�����������u������x�ȏ�ɃV���[�v�Ȏʐ^���B��K�v������(�V���[�v�ł���قǍ����_)�v�Ƃ����O��Ŏ��͘_���Ă���̂ŁA500����f�@�͎�Ԃ�ɋ������H�A�͎�|���̂��̂�����Ă��܂��B
D800��D800E�Ɋւ��ẮA��҂�I�т܂��B���ɎB���ďo��JPEG���g�債�Ĕ��u�������F�ł��Ă��A�œK�ȃV���[�v������D800��(�S��������Ԃꂾ����)�摜��菭�������_�ɂȂ�₷���Ƃ����l���ł��B�������A���B�蒼���ΎB���ďo����90�_�ɂ��o���܂��B
�����ԍ��F26189631�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
����f�Ńu�����ڗ����₷���A�ڗ����ɂ�����
���RAW�����V���[�v�l�X�����ł��܂�������悢�A
�͂��ꂱ���ʌ��ɂȂ�܂���B
�����ԍ��F26189831
![]() 0�_
0�_
>����f�Ńu�����ڗ����₷���A�ڗ����ɂ�����
���RAW�����V���[�v�l�X�����ł��܂�������悢�A
���̏ꍇ�A2400���@�ł��\���Ɋg�債�Ă悭����A�܂��������ׂ̍��Ȕ�ʑ̂ł���Δ��u���͊m�F�ł���i�֊s���̋͂��ȃR���g���X�g�̒ቺ�j�Ƃ����z��ł��B
������u�X��C�ɂ��Ȃ��i�������Ȃ��j�v�Ƃ����̂́A�����܂Ŏ�ςƗp�r�̖��ł���A�u���RAW�����V���[�v�l�X�����ŌӖ������v�Ӗ����Ȃ��i�S�����P����Ȃ��j�킯�ł͂���܂���B
���炽�߂Đ�������ƁA���Ƀ��[�p�X�L��2400���@�̍ō��掿����2100���Ɖ��肵��
�@�ǂ�ȂɁi�莝���Łj�撣���Ă����2100���̉掿���������Ȃ���U��ɃV�r�A�ȏ����Ŗ����̂悤�ɎB�e���鎖���m�肵�Ă���B
�A�ǂ�ȂɎ�U��ɃV�r�A�ȏ����ł����Ă��A��ɖ�5600�������̉掿�ŎB��Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�B�肽���j�Ɗm�肵�Ă���B
�@�̃P�[�X�ł́A���R2400���̒��f�@���ł��傤�B
�A�̃P�[�X�ł́A��͂�掿�̍Œ�l�������̂�6000����f�@�킴��܂���B
����f�@�̕�����U��Ɏア�A�Ƃ����������Ȋw�I�ɊԈႢ���Ƃ����b�ł͂Ȃ��A�@�ޑI��������ł��́u�̕�����U��Ɏア�v��������قڈӖ����Ȃ��Ȃ��Ƃ������ł��B
�Ƃ����̂́A���ɇ@�̂悤�ȎB�e�����ɔN�ɋ����I�ɉ��x������Ƃ��Ă��A6000���@�ŎB����2400���@��茋�ʂ������Ȃ�킯�ł͂���܂���B�����āA�@�̏������T�T�ł���ƕ������Ă���i���Ɩ��B�e�̃��C���j�Ȃ�A��͂�命���̐l�͖��킸2400���@��I�Ԃł��傤�B
���������A2400���ł͎��F������ō���f�ɂȂ�Ɩڗ��悤�ȃu���A���ĕp�ɂɔ�������悤�Ɋ����܂���B������͎�ςł�
�����ԍ��F26190056
![]() 0�_
0�_
�NjL�B
���f�@�ɂ����āA�ŏ����烍�[�p�X�t�B���^�[�ɂ��u�S�Ẳ摜���ڂ₯��v�O��ōœK��(�ƃ��[�J�[���l����)�V���[�v���������Ă���Ȃ�A
����f�@�ɂ����Ď�Ԃ�ɃV�r�A�ȏ�ʂł̎B�e�ōŏ�����u�S�Ẳ摜���͂��ɔ��u�����邩���m��Ȃ��v�O��̃V���[�v�ݒ��^���鎖�͓��ʃA���t�F�A�ł͂Ȃ��Ƃ̔��z�ł��B
����Ă鎖�̈Ӑ}�͓����Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F26190080�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
������f�@�̕�����U��Ɏア�A�Ƃ����������Ȋw�I�ɊԈႢ���Ƃ����b�ł͂Ȃ��A
�אڂ����f���u���ɂ��I������₷���A
�Ƃ������Ƃ͂����������������Ƃ������Ƃł��ˁB
���̗אڕ��̉�f�̘I�������C������Ȃ�
�i������ɂ��������u����Ȃ�j�{������ׂ���f��
�I���ʂ���ł��傤����A�摜�����������
���Ă��A�u�������ׂ���f������ς���āv
���܂��܂�����ˁB���u���ǂ��납�A���S��
�u���摜�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���@�ޑI��������ł��́u�̕�����U��Ɏア�v��������قڈӖ����Ȃ��Ȃ��Ƃ������ł��B
�����͂Ԃ�₷�����獂��f�@��I�Ȃ��悤�ɁA
���Ƃ͈ꌾ�������Ă��܂����B
�������hunayan����̌�咣�Ȃ̂ŁA
�����Ⴂ�Ȃ���Ȃ��悤���肢���܂��B
�����̋@�ނ����C���͍���f�@�ł��B
�p���������b�ł��������͎�U�ꂵ�₷���A
�~���[���X�ɂȂ��ă~���[�V���b�N���Ȃ��Ȃ�
�d�q�V���b�^�[�ɂȂ�A�����Y���\���オ��
�t�B��������͂������A���t�������
����f�@�ō��掿���������
�����Ă��Ă�����̂́A�����B���
�\���ɐ��\�������o���Ȃ��Ȃ�
�����Ȃ���B�e���Ă��܂��B
������Jpeg�B�e�h�Ȃ̂ŁA���s�ʐ^��
���̌��RAW�����ŃV���[�v�l�X��
������Ƃ�����Α��v�A�Ƃ���
���z�͂Ȃ���ł���ˁB
�����ԍ��F26190167
![]() 0�_
0�_
>���̗אڕ��̉�f�̘I�������C������Ȃ�
�i������ɂ��������u����Ȃ�j�{������ׂ���f��
�I���ʂ���ł��傤����A�摜�����������
���Ă��A�u�������ׂ���f������ς���āv
���܂��܂�����ˁB���u���ǂ��납�A���S��
�u���摜�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
���̘_�|�����߂Ċ��ݍӂ��ƁA
�܂���Ԃ��@�\�̔\�͂ƃ����Y���\(�����̉𑜗�)��ISO�̑ϐ����Ɖ��肵�āA
�����2000����f�̉𑜓x����������x�̎�u��
������4000�������̃u��
6000�������̃u��
����Ɉꉭ�����̃u��
�����邾���ŁA�J��������f���ɂ��u��Ԃ�ɋ������ǂ����v��_����K�v�͂Ȃ��Ƃ����b�B(��Ԃ��@�\�̐��\���������ǂ����́A������Ӗ�������)
���̂Ȃ�A�P���Ɂ��̂悤��(��f�̘I���Ɋւ���)�����ɏI�n����Ȃ�A����́u���掿�Ȏʐ^���B�e����̂͒�掿�Ȏʐ^���B�������v�Ƃ�����ʘ_�������Ă���̂Ƒ卷���Ȃ��Ȃ邩��ł��B
�����ĉ��Ɉꉭ��f�̃J�����œx�X5000���̎ʐ^�����B��Ȃ��̂��u�ܑ̖����v�ƍl���邩�ǂ����́A�����܂Ŗ{�l�̎�ς�p�r�̖��B
����f�ȃJ��������Ԃ�Ɏア�A���邢�̓u���₷���킯�ł͂Ȃ��B
��{�I�ɂ͂ǂ�ȏ����ł��A����f�ł���قǍ��掿�ɂȂ�\��������(��ɏq�ׂ��悤�����Y���\��ISO���ł���Ȃ�)�ƍl����̂��K�Ɏv���܂��B
���Ƃ́A�����Ɏg�p���郌���Y��ISO���Ԃ����\�Ƃ̌��ˍ����ł��ˁB
��₱�����̂ł��̕ӂŁB
�����ԍ��F26190402�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
S1R2�̓}�b�v�J�����ƃt�W���J�����͍��������ł��ˁB
�Ӗ��s���Ȑ}�����������Ă��A
�u���̍��͔������܂���A���ꂾ���ł��B
��u����̐��\���ς��܂���B
���[�J�[�̎d�l�����S�Ăł��B
�떂�����Ă����ʂł���B
�����ԍ��F26190434�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
�������2000����f�̉𑜓x����������x�̎�u��
��������4000�������̃u��
��6000�������̃u��
������Ɉꉭ�����̃u��
�������邾���ŁA
������e�i300dpi)�̎w�E�T�C�Y��
500����f��A5�A200����f��A3�A
4000����f��A2���x�ł��ˁB
�E�f�W�J���̉�f���ƈ���\�ȃT�C�Y��K�ȉ𑜓x���ڂ������
https://www.photografan.com/basic-knowledge/print-degital-camera-resolution/
��f���ɂ�苖�e�ł���g�嗦�i���ł���̈����������j��
��������AA2���x�̑傫���i594×420mm�j���x�Ȃ��
�u���ʂ́iA4�ƕς��Ȃ��j�����Ŋg��ӏ܁v
���邱�ƂɂȂ�܂���B
�𑜓x�𗎂Ƃ���4000����f�N���X��A0����ł��āA
�����܂łȂ�Ə�������Ă݂���͂���ł��傤���ǁB
�����g���G���AA4���x�܂ł����L���Ȃ�����
�ς��Ȃ��i�킩��Ȃ��j�͕ʂƂ��Ăł���
�i��ς̖��j�B
��hunayan����
���Ӗ��s���Ȑ}�����������Ă��A
���������i�ނƂ悢�ł����B
��S1R2�̓}�b�v�J�����ƃt�W���J�����͍��������ł��ˁB
�������R�����g�������͂ǂ��炩��
�{�f�B�݂̂����������̂ł����A
�����Ă݂܂��ƁA
�}�b�v�ł̓����Y�L�b�g�ɂ���A�{�f�B�ɂȂ��A
�t�W���J�����ł̓����Y�L�b�g�ɂ���A�{�f�B�Ɏc��͂�
�ł��ˁB
�l�o�̑������j���ɍɂ����������āA
���j�������Ƀ��[�J�[�����[���ꂽ�̂ł��傤���B
���Ƃ���ƁA�����܂ł͕i�s���ł��Ȃ��悤�ȁH
�C�����܂��ˁB
������x����Ă���Ȃ�A����͂���ł��ꂵ���ł��B
�p�iHD��1���l���X�g����s�̎Z����̌����������邻���ŁA
�G���^�[�e�C�������g���R�~���j�P�[�V�������ɂ�
�撣���Ē����Ȃ��ƁAOMDS�̈�{���Ŗ@�ł�
M4/3�V�X�e���i���[�U�[�ł��j���S���Ƃ���܂���̂ŁB
�����ԍ��F26191590
![]() 0�_
0�_
�Ȃ�����̘b�ɁH���ۂɁA2400���Ŋg�債�ĕ�����Ȃ��͂��ȃu���A������5000���Ŋg�債�Ĕ��ʂł���ʐ^���L��������������Ȕ�r�摜�Ȃ�܂�������܂��B
>�����2000����f�̉𑜓x����������x�̎�u��
������4000�������̃u��
6000�������̃u��
����Ɉꉭ�����̃u��
1����f�@�̂ق���(�𑜓x���t���ɔ����������Ȃ�)��Ԃ�Ɍ������A���ꂾ���Ȃ�N�ł��ŏ�����m���Ă��鎖�ł��B1000���̎ʐ^������Ɍ��܂��Ă܂��B
�����A���������Ă��@�ޑI��ɂ͂قږ��ɗ����Ȃ��Ƃ����b�����Ă��܂��B���̓_�͉��x�������Ă܂���ˁB
�Ⴆ��3000����2400���@�Ŏ�Ԃꂪ�������č���A�Ȃ�ă��r���[��(���ʂ̗p�r�̃��[�U�[�Ȃ�)���i�ł��قƂ�nj������܂���B
5000��6000���Ŕ��u�����C�ɂȂ�Ȃ�AISO����i�グ�邩�i�����i�J���邩�A�����i���ς��邩�A�ł��������̏�ʂ͑Ή��ł��܂��B��7R�X�̉��i���r���[�ł���Ԃ��@�\�̐��\UP�͕]������Ă��邵�A�m�C�Y�������\�t�g�̐i������Ώ��̗]�n������ł��傤�B
�܂�����f�@�͉��i������Ȃ�ł�����A�ǂ̃��[�J�[�������@��萫�\���ǂ���Ԃ��𓋍ڂ���X��������܂��B
�Ƃт��Ⴑ������f�@�̎�Ԃ�ō���@������Ȃ�A����͋�̓I�ɂǂ̂悤�Ȕ�ʑ̂Ɨp�r�Ȃ̂ł��傤���H���_�I�ɗאڂ����f���ǂ��̂����̂́A�ŏ����玄���f�l�Ȃ�ɔc�����Ă��܂��B
���̏ꍇ�́A�Â������̐Õ������肵��(�֎q�ɍ����ǂɊ�肩���铙)�\����50����100mm�ŎB�e�������莝��1/10�ȉ���F5.6�Ő���B���(�Œ�1��OK�J�b�g���m��)���ɖ��͂���܂���BISO��3���Ŏ��܂�܂��B���̎�̔�ʑ͎̂B�蒼�����\�Ȏ����������A4���Ă����b�ł��B
�|�[�g���[�g�ł͔�ʑ̃u�����C�ɂ���SS�����߂܂������Ԃ�͂��܂�W�Ȃ��ł��B�X�|�[�c�⓮���������ł���ˁB���i�����̉e��������܂��B
���Ȃ�Â���i��A�A�A���������O�r�Ȃ��ŗǂ��ʐ^�B��܂����ˁH����f�@�̂ق�����Ԃ��̐��\�͗ǂ������肷�邪�A�A�A����͂ނ��덂���x�ϐ��̖�肩�ƁB
��ʘ_�Ƃ��āA2400���J�����̂ق������t�ɎB��镔���͂���ł��傤��
�u����f�̎�Ԃ���C�ɂ��Ă���v���[�U�[�́A������������f�ɂ��掿�ʂ̉��b�ɊS�������čw�����ɓ���Ă���킯�ŁA�uISO��SS�グ��ʂȂ狻���Ȃ��v�Ƃ͊ȒP�ɂȂ�Ȃ��ł���B
��̓I�ɂǂ�ȎB�e�����łȂɂ��B��̂��A����Łu��Ԃ�ɍ���v�x�����͑S�R�ς���Ă��܂�����A���̓_���������������B
�����ԍ��F26191755�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�NjL�B
>���̏ꍇ�́A�Â������̐Õ������肵��(�֎q�ɍ����ǂɊ�肩���铙)�\����50����100mm�ŎB�e�������莝��1/10�ȉ���F5.6�Ő���B���(�Œ�1��OK�J�b�g���m��)���ɖ��͂���܂���BISO��3���Ŏ��܂�܂��B
���Ȃ݂ɂ��̏�����NG�J�b�g�́A�u2400����3300���ŎB�e���Ă��Ă��Ԃꂪ���ʂł����ł��낤�v�ʐ^�̕�����⑽���̂ł��B
�ƂȂ�ƁA�ᑬSS���Ƀ�7R�X��(�Ⴆ��7�W�ɔ�ׂ�)��Ԃ�Ɏア�A�ƒf��ł��Ȃ��C�����܂��B
�����ԍ��F26191786�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ȒP�Ƀe�X�g���Ă݂����ǁA
������SS1/3�AISO800�A135mm�Ń�7R5��6100����M�T�C�Y2600���̔�r����A�҂�����~�܂�̂�5����1�����x�łǂ�����ς��Ȃ��B
�̐�������1/6�b�ł��A�قƂ�Ǔ���(5����)�ł��B
�ŏ�����2600���̃Z���T�[���Ƒ����Ⴄ�̂����B
�����ԍ��F26191836�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J����SP����
���Ȃ�����̘b�ɁH
35�~���i�t���T�C�Y�j���ł����
�g�嗦���ς���r�I�g�߂�
�Ꭶ�Ƃ��Ăł��B
�ӏ܁i���邢�͓��e�j�t�H�[�}�b�g��
���܂��Ă�����X�ɂ͊W�Ȃ��b�ł��傤���B
���Ƃт��Ⴑ������f�@�̎�Ԃ�ō���@������Ȃ�A
���݂͂��قǍ����Ă��Ȃ��̂ł����A
���C���@����7RIII�ɂ������Ƀs���g��
�u���i��ʑ̃u���A��u���j��
�V�r�A���ȁA�Ɗ���������ł��B
�����ԍ��F26192261
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > �j�R�� > Z5II �{�f�B
Z�}�E���g�V���[�Y�̏o�n�߂̍��̃J�����̓��X�|���X�������s���_����ł������AZ9�o���̃J�����͂��Ȃ�ǂ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B
AF���\�̌���͂��Ƃ��A�������芴�������Ȃ�L�r�L�r�Ɠ����l�ɂȂ������ƂłƂĂ��C�����ǂ��B���l�ɂȂ�܂����B
�A�ʐ��\�⍂�x��AF���\��v���������̂��B��̂Ŗ�����Γ��ɕs���_�������A���[�Y�i�u���ʼn��ł����������B��ĂĂ��܂�Z5�U�͎��ɂ̓s�b�^���ȃJ�����ł��B
Z5�U��24-120F4�̃R���r�Ȃ�Α啔���̐l�͖����o����̂łȂ��ł��傤���B
�����A�j�R���͓������̂��B�e�����������AF��A�ʐ��\�d���̒��f�@�A�����炭���Ă�D5��D500�̗l�Ȑ�������\�̃J�������o���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26181363�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 11�_
11�_
�������炢�̃j�R�ꂳ��
D500�̗l�Ȑ�������\�̃J�������o���Ǝv���܂��B
����͗ǂ��J�����ł����B
���ł����X���p���Ă�������������܂��B
�����ԍ��F26181551
![]() 4�_
4�_
�������炢�̃j�R�ꂳ��
����ɂ��́B
�������A�j�R���͓������̂��B�e�����������AF��A�ʐ��\�d���̒��f�@
�ŋ߂̃j�R���͔����ڎw���Ă���悤�ŁA
�L���m��R1�̔���s���łǂ��l���邩�ł��傤���B
Z9II�͏o�����ł����A�ǂ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F26181908
![]() 1�_
1�_
���́AZ�}�E���g�w����Z7�U����ł����B���X���i��A���U���X�i�b�v���S�ł�����AAF���V���O���|�C���g���C���Ŗ������Ă���܂����B���̌�j�R���́AZ9�𓊓����Ĉȍ~AF�̐��\�́A����I�Ɍ��サ�܂����ˁB���̌㎄�́AZ8�AZf�ɔ����ւ��A�j�R���ŐV��AF�i3D�g���b�L���O�A��ʑ̔F����)���A���낢�뎎���Ă��܂��B����Z5�U�A�j�R���ŐV��AF���\�������A����ɂ����߂₷�����i�ݒ�A����́A�V�K�ɁA�j�R���t���T�C�Y����������Ă����
���łɃj�R�����������ŁA�lj��w������������Ă�����A�{���I�X�X���ł���ˁB
���͎����w���A�˂���Ă܂�!!�B
�����ԍ��F26182008�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���Ƃт��Ⴑ����
���������L���m����R1�A���ƓI�ɐ������Ă��ł��悤��?�B���́A�����낵���j�c�`�ȕ���̏��i�Ƃ݂Ă��܂��B�����炭�听�������j�R���̃t���b�O�V�b�v�@Z9�Ƃ́A�̔������炵�Ĕ�ׂ悤���Ȃ����x���ł��悤�B�j�R����D6��߂�ƌ����Ă���ȏ�A�������̕���i���f�����A�ʋ@�j�ɂ͌�������Ă���ł��悤�BZ9�o��ȍ~�A���f�����A�ʔŁA���т��щ\�ɂ̂ڂ�܂����A�Ȃ��[�Ƀ\�j�[���S�������C���Ȃ��ȏ�A�j�R���P�Ƃł́A�ǂ����悤���Ȃ��B
�����ԍ��F26182239�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����~���y�I���W����
���Ȃ��[�Ƀ\�j�[���S�������C���Ȃ��ȏ�A�j�R���P�Ƃł́A�ǂ����悤���Ȃ��B
�j�R���ɂ��C�i�������̔����Ǝx�����̌_��j��
���邩�ǂ����Ȃ̂ł́A�Ǝv���Ă��܂����B
�j�R���͒��f�A�ʋ@����肽���̂�
�\�j�[�Z�~�R���_�N�^����肽�����Ă��Ȃ��A
�Ƃ����b������̂ł��傤���B
���܂�ɏ����b�g�i���z�j���Ƃ�肽���Ȃ��A
�͂��邩������܂��B
�����������L���m����R1�A���ƓI�ɐ������Ă��ł��悤��?
�t���b�O�V�b�vD6�̎d����������ɁA
R1�̔���s�������AD6�̔̔����ڂ�
�v�킵���Ȃ������̂�������܂���B
�����ԍ��F26182383
![]() 3�_
3�_
�J���̗e�Ղ����炷��A����e����ł���2400����f�N���X�ō����A�ʋ@��v���������ǂ��Ǝv���܂����A����f�A�ʋ@�̕���]��ł�����������ƃj�R���͍l���Ă���̂ł��傤�ˁB
�ł��A���͈Ï��ɋ�����PC�̕��S���y���A�掿�����������̒��f�@�̕����g���Ղ��Ǝv���܂��B
���������l���̕������������ɂ��ėv�]��������ƃj�R���͏o���Ă����Ǝv���܂��B
���̒m�l�ɂ�����f�͈Ï��Ɏキ��������ςȂ̂Œ��f�@���ǂ��ƌ����Ă���l�͑����ł��B
�v�͎��v�������߂�Ɣ��f�����ꍇ�͔�������ł��傤�B
�̔��䐔��D6���U���Ȃ������̂́A���x�~���[���X�@���}���ɐ��\���グ�Ă������ɉ����ă����Y�Ȃǂ̎��Ӌ@�킪���t�@���݂ɏ[�����Ă��������ł�����A�w�����S�O�����̂��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26184026�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�������炢�̃j�R�ꂳ��
�������̒���24M��f���W���ɂȂ����l�ł��B
�����ł�iPhone16e�ł���48M��f������fusion24MP�B�e�d�l�Ȃ�ł���B
fusion�B�e�Ƃ͗אڂ����f�̎B�e���m�C�Y����菜���Ĉ��菬�����摜�ɂ��č��掿�B�e����Z�p�ł��B
�����ԍ��F26184046
![]() 1�_
1�_
�������炢�̃j�R�ꂳ��
�����܂���A�v��ʔ��M���Ă��܂������ȂƔ��Ȃ��Ă��܂��B�j�R����Z9�AZ8�ŁA�]�O�̐����������߂��ƌ��Ă��܂��B�v���Έ��t��D5�AD6�́A��ʌ����łȂ��A�n�C�A�}�����ɂ́A850���낤�ƁA�v���Ă��܂��܂����B
����850�́A��q�b�g���A����������N�҂��Ă���Ɠ��肵�܂����B
�����Z9�U�̔��\���ɁA�]���̔��W�^�v���X�A2400����f�N���X�����A�ʃ��@�[�W�����Ƃ��A�܂����̃O���[�o���V���b�^�[���ڂȂ�Ă̂��A�������\���ꂽ�肵����A�ō��ł���ˁB
�����ԍ��F26184351�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�j�R���́A���X�ƂĂ��Ȃ��������܂���ˁB
D5���o�����ɗ\�z�����Ȃ����������A�ʋ@D500�������ɔ������ꂽ���̏Ռ��͖Y����܂���B
D500�͓����̃��C�o���Ђ̍����A�ʋ@��������ʂň�C�ɒǂ������A���j�Ɏc�閼�@�ƂȂ�܂����B
�܂��A���̌�o��D850���A�~���[���X�S�����̍��ł��ʗp����掿��L���AAF�������̍���f�@�̒��ł͍ō��N���X�ŁA�����J�����Ƃ��Ď��͍��ł����p���Ă��܂��B
�Ƃɂ����A�������ꂽZ5�U�̏o��������ƁA����j�R���͉�������Ă��ꂻ���ȋC�����Ă��ł���ˁB
���̊�����������x���肢���܂��j�R������B
�����ԍ��F26184435�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�f�W�^�����J���� > �j�R�� > D200 �{�f�B
�j�R���t�@���̊F�l
�@�����́B���@D200�Ɂ@�\�L�����Y�����ĉԎB��Ȃǂ��y����ŗ��܂����B
�@���̃X���b�h���J���O�Ɏ��́A�����O�ɂ����e�݂̂������̃X���b�h�@
�@�@�@�w �`�e NIKKOR 70�`300G�@�����x�@2025/03/14 07:40
�@�@�@https://bbs.kakaku.com/bbs/00501610928/SortID=26109499/#tab
�Ɋ����Ē��������ƍl���̂ł����A�X���^�C���e�ƈقȂ郌���Y�Ȃ̂œ��e���~�ߕʃX���ɂ��܂����B
�݂������@
�@�����M�d�ȃR�����g��Ղ��Ă���܂��B��L�̎���ŕʃX���ɂ��܂������A���������ƍl���Ē����A�����̂悤�ɂ��ӌ��Ȃ肨�������������B
�@�M�X���ł�shuu2����Ƃ̂�����q�����A�ǂ���ɂ��ꗝ����Ȃ������܂����B
�@���͂ǂ�ȃJ�����ł���A��U��ɂ�����Ȃ��Ȃ�������Ȃ��Ŏ茳�ɒu���Ď��X�ł�������Ƃ����h�ł��B�����Y���R��ł��B
����@D200��85mm�����Ă݂悤���Ǝv���������w�i������܂��BSony�ł̃X���ɋv�X��o�����܂�����A�M�S�ɃX���b�h��W�J�ێ�����Ă�����X����l���A���]����85mm�����Y�őf�G�ȍ��𓊍e�Ȃ����Ă���ꂽ�̂Ɋ�������āA�����g��Ȃ��܂ܕ��u���Ă���85mm�����Y���v���o�������̂ł��B
�@����܂ł����ƃR���f�W�ȂǂŖ쒹��ǂ������Ă��Ă���Ԓ������̒��̉Ԃƕ��ƌ��͑a���ɂ��Ă����̂ł����A�̗͂��l����Ƃ��낻��@�|�ւ����������ȂƎv�����Ƃ�����A�ŋ߂͒Z���œ_�����̃����Y�ł̒P�ʂ��y����ł�����܂��B
�@�Â��@��ł������̂������肵���j�R���̋����@��D200���v�X��ɂ��Ă݂āA�B�e���̃t�B�[�����O�̗ǂ��ɍ��꒼���ď��ł��B
�����Y85mm�͎����͎g�����Ȃ��Ȃ��܂ܖh���ɂɎ��߂Ă��܂����B�Ƃɂ����B���Ă݂Ȃ��Ǝn�܂�Ȃ��ƍl�������Ƃ������o�������R�̈�ł��B
�@�����AAF�@NIKKOR�@85mm�͎B�e�����̐��������A�ԂȂǂɎv����ߕt���ĎB�邱�Ƃ͊����܂���B����ł��߂Â���AF�@NIKKOR�@50mm�������o���Ă���܂��B�ǂ����D200���Ər�q�����m��AF���\�ł��̂ŁA���͂Ɏ��M�̂Ȃ����ɂ͉��K�ȃJ�����V�X�e���ƂȂ��Ă���܂����B
�j�R���t�@���̊F�l
�@�ł́@�A���ňꋓ�ɃA�b�v���[�h���܂��B
![]() 17�_
17�_
�j�R���t�@���̊F�l
�@D200/85mm�n�ł̘A���ł��B
�@2���ڂ�3���ڂ̐Ԃ��o���̉Ԃ́A�I�o�����+0.67EV���Ă������Ƃ�����̂�������܂��A�܂��̓K���ɖ��邢�����œ���Ō����Ԃ��Č�����Ă��炸�A���邭�����I�����W�|�������F�ɎB��Ă��܂����i�B�e����WB�F�܂�j
�@RAW�t�@�C���𗘗p���āA�I�o���A���_�[���ɖ߂��A���@�Ԍn�̃g�[���������M���Ă��܂��B�ꖇ�ڂ̃I�����W�F�̃o����4���ڂ̔��o���͂���Ȃ�Č�����Ă܂����B
�����ԍ��F26180617
![]() 12�_
12�_
D200/50mm�ʼnԂ��|1 |
D200/50mm�ʼnԂ��|2 |
D200/50mm�ʼnԂ��|3�@���a�W�o���x�̏����ȉ����Ԃ��������� |
D200/50mm�ʼnԂ��|4�@�n�i�A�u�����Ă���Ԃ���Ԃւƈڂ��Ă��܂����B |
�j�R���t�@���̊F�l
�@�U�铹�[�̎B�e�Ώۂ̉Ԃ��������Ȃ���85�o�����Y�ł͎��܂肪�����������̂ŁA���߂Â���50�o�����Y�ɑ������Ȃ����܂����B
�@����AF�@NIKKOR 50�o�W�������Y�́AMF����ɂ͏����t�H�[�J�X�����O�ɃK�^�����Ă��܂����A�B����y�Ȃ̂ő�D���ȃ����Y�̈�ł��B
�����ԍ��F26180627
![]() 11�_
11�_
���V�V���`���E�U�����D������
���A������Ƃ͂킩��Ȃ��̂ł����A
�uD200/85mm�ʼnԂ��|4�v��q�����đf���炵���Ǝv���܂����̂ŏ������݂����Ă��������܂����B
85mm�����ł���ˁB�I
��ϐS�n�̂悢�ʐ^�����肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F26180940
![]() 3�_
3�_
80����90�N��̃I�[�g�t�H�[�J�X�̑���a85mm�A�~�m���^��AF 85/1.4 G(D)�ƃj�R����AF Nikkor 85/1.4D IF���g�������Ƃ�����܂����A�قȂ�L�����N�^�[�Ŋy���������ł��ˁB
�j�b�R�[���͋C�ɓ����ĂĂ܂������Ă܂����A�~�m���^�̕��̓\�j�[�̋@�ނ���C�Ɏ�������ɓ����Ă��܂��܂���
�����ԍ��F26180958�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
D200/85mm�ʼnԂ��|9 |
D200/85mm�ʼnԂ��|10 |
D200/50mm�ʼnԂ��|5 |
D200/50mm�ʼnԂ��|6�@�������X�J�V�������E�E�E�Ԃ̐F��������ƂĂ��������� |
D2��������
�@�������������܂��B
�����@��̃X���ɉ������R�����g���c���đՂ����ӂ��Ă܂��B
D200�́A�J������������i�����������Ɓj������̒m�Ȃ���A���Ȃ��Ȃ�g���ĖႦ����������Ǝ�n���ŏ����đՂ������̂ł��B��������Əd�����A�����Ə[�����̂���CCD����̃J�����ŋC�ɓ����Ă܂��B
�@CCD����̃J�������j�R���@��ł�D40�i2��j�AD3000�𖢂��ɉ������Ă��܂����A����D200�͂����̌Z�M���I���݂ȋC�����܂��B�������������͋C�̊G��^���Ă���܂��̂ŁA�������������ł����P�œ_�����Y�Q�ƍ��킹�đ厖�ɖh���ɂ̃��C���I�ő�ɂ��Ă܂��B
seaflanker����
�@�������������܂��B
���i�R���ʐ^�X���̕Ћ��̓��X���ɖڂ�ʂ��đՂ����肪�Ƃ��������܂��B
�@���~�m���^��AF 85/1.4 G(D)�ƃj�R����AF Nikkor 85/1.4D IF���g�������Ƃ�����܂����A�قȂ�L�����N�^�[�Ŋy���������ł��ˁB
����������ł����A�~�m���^��85mm���Ƃ���ɑO��̃{�P���_�炩���Ȃ�̂ł��傤���B
�@���̐���̃����Y��J�����́A�������J�Ŕ@���ɂ��������w���i�Ƃ������̂������B���S�ł��̂Ŗ����Ɍ��݂ł��B���A�l�œ���ւ����f�̗������Ȃ��܂܂Ȃ��Ƃ�����A����h���ɂ݂���͂߂ɂȂ�܂����B�D���Ȏʐ^�B��̂��ƂȂ̂ʼnƑ��͖ق��ď��F�ł�(^0^)
�@D200���܂߂đ����̋@��Ɏ��X�d�C��ʂ��Ėڊo�߂����Ă܂����A���\�Ƃ��āA�t�@�C���_���Ƃ����Č�����ł�����̃{�P�����������o�����Ė���Ă܂�(^0^)�@�@
�����ԍ��F26181336
![]() 7�_
7�_
2025/05/17 17:09�i5�����ȏ�O�j
���܂���Ai-AF����̃����Y���j�R���ň�ԃJ�b�R�ǂ��Ǝv���Ă܂���
�g��Ȃ��̂�300/4�����Ă��肵�܂��i�j
�����ԍ��F26181807
![]() 3�_
3�_
��cpu�����Y�@105�o |
��cpu�����Y�@135�o |
��cpu�����Y�@200�o |
��cpu�����Y�@50�o�@���̃t�@�C���̂ݍi��l�ƎB�e�������قȂ�܂� |
�j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
>���܂���Ai-AF����̃����Y���j�R���ň�ԃJ�b�R�ǂ��Ǝv���Ă܂���
�m���ɁA���I�Ń��J�j�b�N�������������Ă����Ai-AF����̃����Y�́A�J�����ɂ���ƒ��܂肪�����Ċi�D�����ł��ˁB
�@�f�̗�������Ȃ��Ƃ������Ai�����Y���܂߂�NIKKOR�����Y�͋������̂����L�������Ă��܂��B���a����i�ƈꊇ��ɂ��Ă��܂��Ɩ��f�ȕ���������Ǝv���܂����j�̏K���ʼn��ł��ܑ̂Ȃ��v���Ă��܂��Ă��邩��Ȃ�ł����A���A�ł����̃����Y���e��Ă���鋌����̃J����������������H�ڂɂȂ��Ă܂��B
�@NIKKOR�����Y�͐F�X�ȕϑJ�������č��Ɏ����Ă��܂����ǁA��Ai�AAi�A��Ai�A���ƍ\���ɂ܂�郌���Y�̃W�����������G�B
�������肵��D200�ł����A������̃����Y�̂��ׂĂ��e��Ă����킯�ł��Ȃ��A�����炪�������ȁ`�Ɗ�����Ƃ���ł��B
�����ԍ��F26182726
![]() 4�_
4�_
�������肵���ǂ��J�����ł��ˁB�����̃t���b�O�V�b�v��D2X�V���[�Y��50���~�������悤�ł������̃J������20���~���Ŕ������ƋL�����Ă��܂��B�V�i�Ŕ����������Ȃ��J�����̈�ł����A���ł��[���g���܂��BCCD�ƌ��������ǂ������グ���܂����ARAW�B�肪�w�ǂ̖l�ɂ͂��܂�W����܂���B��������A���܂�b��ɂȂ�Ȃ��ł����t�@�C���_�[��.�N���A�őf���炵���ł��B�v�X�Ɏ����o���܂������A�l�͖w�ǂ����Ԃ̃l�C�`���[�t�H�g�Ȃ̂ō����x����薳���ł��ˁB�ނ���]�v�ȕ����t���Ė����̂ŁA�ݒ���K�w���Ďg���₷���ł��B�܂��܂��g����J�����ł��B
�t�����l��t���Ȃ��Ɛ��i�Ƃ��Ă̖��͂������ƍl����l���������A20�N�O�̃J�����ł��[���B��邱�Ƃ��ĔF�������Ă����J�����ł��ˁB���̐̃J�����͑ϋv������ōō��̎���ł����B���[�J���g�������Ȃ��@�\�ڂ�����A�J�����Ƃ��Ă̊�{���\��A�ϋv�����l���Ē����g����J����������ė~�����ł��ˁB������4�`5�N�ŏC���s�\�ɂȂ�̂́A�̔����i���l����ƁA��������Ƃ͔����Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F26187804
![]() 5�_
5�_
�f�W�^�����J���� > �V�O�} > SIGMA sd Quattro �{�f�B
�����ߘa7�N5��15��(2025.5.15)�ASIGMA����FOVEON�W�̓��������J����܂����ˁB
�ǂݏo�����[�h�̓����ł����ǁA�����N�������ł��ˁB
�k�}�E���g��35mm���ƂȂ�ƁAFOVEON�����ʂ̃x�C���[�Z���T�[���e���Z���g���b�N�������ɂȂ�\�����Ƃ������ƂŁA������ƐS�z�ł��B
��Ԃ����A���͂�K���Ƃ��������ł�����A���Ƃ����ė~�����ł��B
![]() 2�_
2�_
�����o�肳��Ă��Ȃ��O���o��́H
�Ǝv���Č������Ă݂܂���(^^;
���u���E�U�|��Ń\�R�\�R�c���ł��܂�
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=jp_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=&AP=&PR=JP&PD=2005-2025&PA=SIGMA+CORP&IN=&CPC=&IC=&Submit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
��
2005�N�ȍ~�ɂ��Ă���̂ŁAEspacenet��500���̐���ȓ��ŏo�͂ł��܂�(^^)
��2025/5/15����
�����ԍ��F26180161�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
3�w�Ƃ����\����A���o�I�ɂ̓����Y�̃e���Z���g���b�N���������͉̂��ƂȂ������ł��܂��B
�Ƃ���ƁA�g�b�v���炪�u�Z���T�[���Ŕz�����A�����Y���̃e���Z���g���b�N���͈�؍l�����ĂȂ��v�Ƃ������C�JM�����Y�݂����Ȃ̂�Foveon���Ǝg���̂͌��������ł���
�x�C���[�Z���T�[�@�ɂ��Ă���O�̃K���X���������ƈӐ}�������\���炩�����ꂽ������邵...
�����ԍ��F26180475�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��seaflanker����
�ȑO����́A����f�q���́u�}�C�N�������Y�v���A
seaflanker����̌��O�����ւ̑��i�̂P���Ǝv���܂����A
���̑O�ɂ���ԊO���J�b�g�t�B���^�[�Ȃǂ̂Ƃ̑��ւ��C�ɂȂ��Ă��܂�(^^;
�����ԍ��F26180557�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
��ԍŏ��ɕ\�������@US2025130410 (A1)�@��500mm/F5.6�̓����ł��ˁB
���{�ł́@2025-071886�@�ł��ˁB
���̎���FOVEON�Ɋւ�������@2014-068053�@�͊O���ł͂܂����J����Ă��Ȃ���ł��傤�ˁB
��seaflanker����
�����肪�Ƃ��A���E����
�I���`�b�v�}�C�N�������Y�����ӂɋ߂Â��ɂ�ď����������ɃV�t�g���邱�ƂŁA�ߓ��ˌ��������ł�������荞�����Ƃ����܂��܂����w�͂����Ă���t�H�[�}�b�g�������ł����ǁA�������̂��߂ɂȂ��Ă���킯�ł�����A�ׂ̑f�q�ɘR��Ă��܂��N���X�g�[�N�͖����ł��܂���A��ʎ��ӂ̉𑜓x�ƃR���g���X�g�͌����I�ɗ������Ⴂ�܂���ˁB
�X�ɁA�����Y�ɂ���Ď߂ɂȂ�m�x���قȂ�킯�ł�����A��p���قȂ�L�p�����Y����]�������Y�܂œ������ˊp�ɓ��ꂷ��̂͂܂��s�\�ł��傤�ˁB
SONY��FE�}�E���g�����Y���ƕ��ʂɐv����e���Z���g���b�N�����B��Ă��܂��]���n�̃����Y�ł��A�킴�킴�}�E���g�t�߂ɉ������Y��z�u���Ď߂ɂ�������Ă܂��ˁB
�ԊO���J�b�g�t�B���^�[�Ȃǂ̌��݂Ɋւ��ẮAFE�}�E���g���k�}�E���g���}�C�N���t�H�[�T�[�Y��蔖���ł���B
���̕��A�z�R����S�~���ʂ荞�݈����Ȃ�܂����c
�����ԍ��F26180702
![]() 0�_
0�_
���|������ǃ_�n����
�t�H�[�T�[�Y�̓e���Z���g���b�N�̗v�������C�J�����͊ɂ��ł��傤����[�̉掿�͂����܂ŃV�r�A�ɍl����K�v���Ȃ�����ł��傤�Ȃ�
https://s.kakaku.com/bbs/K0001569665/SortID=25737767/
�ʃX���Ŏ����Ă݂܂������A����24MP�N���X��2012�N��Leica M��2023�N��Nikon Zf�ƁA10�N�ȏ�̔N�㍷������{�f�B���A�����W�t�@�C���_�[�p��ZEISS Biogon 2/35 ZM�Ŕ�r�����Ƃ���A���̃r�I�S���̂悤�Ȍ�ʂ��傫�����ɂ���o�ĂĎˏo�������ɂ���悤�ȃ����Y���ƁAZf�ł̎g�p���Ƌ��̑傫���s���g�ʒu���傫���Y���đ��ʘp�Ȃ̂悤�ɂȂ��Ă��܂��悤�ł��B
�����AFSI��BSI�̈Ⴂ�Ń��C�JM�̕��̓}�[���^���o��V�[���͂���܂���
�I���`�b�v�}�C�N�������Y���ł����A�Z���T�[�O�̃J�o�[�K���X��ԊO�J�b�g�t�B���^�[�̍��͂��Ȃ肠��悤�ł��ˁB�j�R���͂̃C���^�r���[����́A��͂�Z���T�[�O�̃J�o�[�K���X�͔����ȉz�������Ƃ͂Ȃ���������������x�͏オ�邻���ł��B
���C�J�͂��̕����R�X�g�ɔ��f���Ă����̂Ȃ�����������Ă�̂Ő��藧��ł��傤�B
���C�JM�n�̓��C�JSL�n���������A�����W�t�@�C���_�[�����Y���g���Ȃ�M�̕��������Ɠ����Ă܂���
�����ԍ��F26180953�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
CANON 135mm/F2 |
SIGMA�v��75mm/F1.8 ��ʂ͓ʃ����Y |
NIKON��Plena ��ʂ͉������Y |
CANON�̐��i�����ꂽ����136mm/F1.8�@��ʂ͉������Y |
��seaflanker����
���t�H�[�T�[�Y�̓e���Z���g���b�N�̗v�������C�J�����͊ɂ��ł��傤����[�̉掿�͂����܂ŃV�r�A�ɍl����K�v���Ȃ�����ł��傤�Ȃ�
�^�t�ł���B
�t�H�[�T�[�Y�̕����X�ɃV�r�A�ł������ǁA�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Ȃ�e���Z���g���b�N����Nj����Đv����Ă��܂���B
�p�i�����^�������������悤�ŏ����������Ⴂ�܂������ǁA�����t�H�[�T�[�Y�Ɠ����}�E���g���a��������F0.95�̃����Y���`�e�Ή�������ꂽ�ł��傤�ˁB
CANON����135mm/F2�̑�ϋ����[���������o�Ă��܂����ǁA�������i���ł���Ȃ�NIKON��135mm/F1.8 S Plena�����S�ɂ����Ⴄ���x���ł��ˁB
�O�ʂ̒��a��83.10mm��Plena���10mm���x�����傫���Ȃ��ł����ǁA��ʂ̒��a��63.39mm�Ɩ�43.2mm�̃C���[�W�T�[�N���ɑ��\���ȑ傫�����m�ۂł��Ă��܂��B
�ő�̍���Plena�̌�ʂ��������Y�ŏ����ȃ}�E���g���a�����ʎ��ӂɌ������L����v�ɂȂ��Ă���̂ɑ��ACANON�̕��̓t�H�[�T�[�Y��}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ɠ����悤�ɓʃ����Y�ŎB���f�q�ɑ��ĉ\�Ȍ���^�������ɂȂ�悤�ɐv����Ă��܂��B
�����}�E���g���a�̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂Q�{��80mm���炢�͕K�v�ł��傤�ˁB
���j�R���͂̃C���^�r���[����́A��͂�Z���T�[�O�̃J�o�[�K���X�͔����ȉz�������Ƃ͂Ȃ���������������x�͏オ�邻���ł�
��ʎ��ӂɌ������Č������߂Ƀt�B���^�[��ʉ߂����邱�Ƃ��l����A�������Ȃ��Ƒʖڂł��傤�ˁB
2002�N2���ɔ������ꂽ���Z���ECONTAX�́uN DIGITAL�v�̏ꍇ�A629����f�ł������烂�A�������ׂ̈ɂ����͂ȃ��[�p�X�t�B���^�[���K�v�ł�������A�ʏ�̑f�ނł͌����Ȃ肷���A���ɍ����ȁu�������܃j�I�u�_���`�E���v���g�p������Ȃ������킯�ŁACONTAX�قǂ������|�����Ȃ����[�J�[�ɂƂ��Ă͎�����肾�����ł��傤�ˁB
https://av.watch.impress.co.jp/docs/20011115/kyocera.htm
�����e���Z���g���b�N�������\���Ȃ�t�H�[�T�[�Y�̂悤�Ɍ����Ă����Ȃ��悤�ł��B
�����ԍ��F26181134
![]() 0�_
0�_
���|������ǃ_�n����
�����ŏ��������͓ǂݕԂ��āA�Ӗ��s���ł�����
>FE�}�E���g���k�}�E���g���}�C�N���t�H�[�T�[�Y��蔖���ł���B
�ɑ���
>�����e���Z���g���b�N�������\���Ȃ�t�H�[�T�[�Y�̂悤�Ɍ����Ă����Ȃ��悤�ł��B
���܂��Ɏ��������������������Ƃł�
�L���m���̓����A��ʂ̒��a��63.39mm�Ƃ̂��Ƃ�����RF�}�E���g�̓��a54mm�Ȃ̂Ō������ł��ˏ�
��p�v�̃����Y��������Ȃ���邩�H
N�f�W���ׂ�ڂ��ɍ��������̂̓��C�J���Z���T�[�����E�����Ă̂����邯�ǁALPF���������Ă����̂�����Ƃ͕����܂����B
�L���m����1DX�n��GD LPF���R�X�g��������ĕ����܂���
���Ȃ݂Ƀ��C�JM�͂߂�����S�~�ڗ����܂�w
�Y�}����M 28/5.6�ȂJ����F5.6������A�J���ł��S�~�����邱�Ƃ�������...
�A�|�Y�~�N�����݂����Ȓ������\�����̃T�C�Y�Ŏ����ł���̂��e���Z���g���b�N�Ƃ��������Ă邩��Ȃ̂���
�����ԍ��F26181145�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
(���b�����ɃX�~�}�Z��)
���|������ǃ_�n����
���X�A���肪�Ƃ��������܂�(^^
��FOVEON�Ɋւ�������@2014-068053�@�͊O���ł͂܂����J����Ă��Ȃ���ł��傤�ˁB
��
���{�ւ̏o��݂̂ł����B
�p�e���g�t�@�~���[���X�g: JP2014068053 (A)
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadocPatentFamily?CC=JP&NR=2014068053A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20140417&DB=EPODOC&locale=jp_EP
����{�I�ɁA2014�N(���{)���J�ŁA���܂��ɊO���Ō��J����Ȃ����Ƃ͂���܂���B
(�����ɂȂ��Ă��邩�A�Ȃ�Ȃ��������́A�ʂƂ��āB���ẴT�u�}���������̌��́A���L�Q��)
�D�挠�咣���Ԃ��l������ƁA��{�I�ɍŏ��̏o�肩��P�N�ȓ��ɊO���o�肪�s���A
PCT�o��o�R�̏ꍇ�ł��A�e���ڍs(�č��Ȃ�)�́A�ŏ��̏o�肩�� 30����(2�N��)�ȓ��Ȃ̂ŁA
���s�̒x�����������Ƃ��Ă��A��i���ւ̊O���o��̏ꍇ�́A
�ŏ��̏o�肩�� �x���Ă� �R�N�ȓ��Ɂu���J�̊m�F���\�v�ɂȂ�A
����Ō��J�������ł��Ȃ��˓��Y���֏o�肳��Ă��Ȃ��A
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���č��́A���ẴT�u�}���������́A�����ł͊�{�I�ɂ���܂���B
�������A�����I�ȃT�u�}���������p�~�u�ȑO�v�ɕč��o�肳�ꂽ�ꍇ�́A���Y�����@�����ȑO���K�p���ꑱ���邩������܂���(^^;
�Ȃ��A���{(�D�挠)�ˉE�L�̂����ꂩ�̊O���o��(PCT�A�āA���A�ƁA��)������̂́A�����_��11���̂݁B
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=jp_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=WO+US+EP+DR+CN&AP=&PR=JP&PD=&PA=%22SIGMA+CORP%22&IN=&CPC=&IC=&Submit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
�������� Espacenet�ł͌��������̐��傫���̂ŁA���Ѓm�C�Y������Ȃ����x�̃e�L�g�[�Ȕ͈͂ɂ��Ă���A��L�ł͊O��(��)�ւ̒��ڏo�肪�R�������ł��̂ŁA
��胁�[�J�[�֘A�ł̌��������Ƃ��Ă͕s�K�ɂȂ�ꍇ�������Ȃ�܂�(^^;
��PCT�o�莞�_�͓��{��̂܂o��ł���̂ŁAPCT�o�莞�_�ł͔�p�ȊO�͓��{�����o��Ɣ�ׂđ卷����܂���̂ŁB
�����ԍ��F26181420�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
�I���`�b�v�}�C�N�������Y=�W����
IR�t�B���^�[�A�J�o�[�K���X���X=���ʘp�ȁA���ʎ���etc
���ȁH�I���`�b�v�}�C�N�������Y����O�ɃJ�o�[�K���X���͂����āA������ʂ������ɋ��܂��Ď������傫���Ȃ�����Ƃ��B
������܂߂���p�v�̃����Y�Ȃ�ǂ����ǁA���̓o���l�b�gL�}�E���g�ŁA���C�J��SL�n�͑��Ђ�L�}�E���g�J�������J�o�[�K���X�͔����Ɠ����Ă��āA�Ƃ����
�V�O�}�A�p�i�\�j�b�N�A���C�J�J�����̂��ꂼ��L�}�E���g��p�v�̃����Y�ł����ӕ��̉掿�͈قȂ郁�[�J�[�ԂŃC�R�[���ɂȂ�Ȃ���������Ȃ��ł�
�����ԍ��F26181827�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��seaflanker����
���X�A���肪�Ƃ��������܂�(^^)
�����t�B���^�[�Ȃǂ́A�I���`�b�v�}�C�N�������Y�́u�O�ɂ��郂�m�v���C�ɂȂ��Ă�������ǂ��A
�����������ݍ��ނƁAseaflanker��������Ă���悤�Ȏ��Ɋ֘A����킯�ł���(^^)
���̓��ߕ����̎��Ȃ���A�֘A���[�J�[�Ԃ̑Ή��͏c����̂悤�Ȋ��������܂���(^^;
�����ԍ��F26183373�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
SA�}�E���g��SD Quattro�A�o���l�b�gL�}�E���g��S5II�ȂőO���猩��ƁA�}�E���g�̓��a�ɑ���SA�}�E���g�͂܂��l���͗]�T���肻���Ȃ�ł����
L�}�E���g�̓}�E���g���a��SA���傫�����ǂ���ȏ�ɃZ���T�[���傫���̂ŁA�}�E���g�����̌��\�M���M���܂ŃZ���T�[�̒[�����Ă܂��B
L�}�E���g�Ƃ�������ł�Foveon�̐v�͓�����ł��˂�
�����ԍ��F26185725�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��seaflanker����
�}�E���g���a���傫���ƌ�ʂ�傫���o����Ƃ������Ƃł�����A�}�E���g���a�͏d�v�ł��B
�e���Z���g���b�N�����d�������ꍇ�A��ʂ̒��a�ƌ�ʂ���B���f�q�܂ł̋���(�o�b�N�t�H�[�J�X)�ƃC���[�W�T�[�N�����d�v�ȗv�f�ɂȂ�܂��B
�ȒP�Ȍv�Z���ƁA�o�b�N�t�H�[�J�X���e�l�Ŋ��������l�ɃC���[�W�T�[�N���𑫂������l����ʂ̒��a���������Ȃ���n�j�Ƃ������Ƃł��B
��̓I�ɂ����ƁA����35mm���p��F1.0�̃����Y�̌�ʂ��}�E���g�ʂɂ���A�}�E���g�ʂ���B���f�q�܂ł̋���(�t�����W�o�b�N)20mm���Ƃ���ƁA��ʂ̒��a��20mm÷1�ɃC���[�W�T�[�N��43.2mm�𑫂���63.2mm�����OK�Ƃ������Ƃł��B
���Ȃ݂�F1�̃����Y�̌����̍ŊO���̊p�x�͖�26�x34���ŁA�B���f�q�̓��ˊp��30�x�z���邠���肩�犴�x���������邱�Ƃ��l������ƁA����a�����Y�قǃe���Z���g���b�N������ɂȂ��Ă���悤�ł��B
�I���`�b�v�}�C�N�������Y�����ӂɋ߂Â��ɂ�ď����������ɃV�t�g���Ă��ׂ̃Z���ɘR��邾���ł��ˁB
��ʒ��S��F1�Ŏ��ӂ�F4���Ȃ������Y���āA���Â��i���Z���X���Ǝv���܂��B
m4/3�@�@�@�@�@�@17.3×13mm�@�@21.6mm
APS-C_SD15�@�@ 20.7×13.8mm�@24.9mm
APS-C_CANON�@22.3×14.9mm�@26.8mm
APS-C�@�@�@�@�@ 23.5×15.6mm�@28.4mm
APS-H�@�@�@�@�@ 26.7×17.9mm�@32.1mm
35mm���@�@�@�@ 36×24mm�@�@�@43.2mm
���C�JL/T�}�E���g�̏ꍇ�A�t�����W�o�b�N��20mm�ł�����AF1.4�̃����Y�Ή��ł��}�E���g�ʂ�67.5mm�̌�ʂ��]�܂�����ł����ǁA�y�}�E���g�ł��q�e�}�E���g�ł��ʖڂł��ˁB
�����Y�\���}�����Ă��A�C���[�W�T�[�N�����傫�Ȍ�ʂ��̗p����35mm���̃����Y���ĊF���ł�����AFOVEON�ɂ������ʂȒ�����a�}�E���g�ƒ������\�����Y��p�ӂ���̂͑�ςł����ǁA�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͊J�����_�ŁA���������Ă���̂�SIGMA�ɂ�FOVEON�̃����b�g���ő�������邽�߂ɂ��撣���ė~�����ł��B
���Ȃ�OMDS�Ƒg��Ń}�C�N���t�H�[�T�[�YFOVEON�@�����i�����Ă��ꂽ��Ƃ��v���܂��B
SD15�܂ł�2,640×1,760�s�N�Z��(×3)�̖�464����f(×3)�ł����ǁA�����FOVEON�Ђ��Z���_�[��2,640×2,640�s�N�Z��(×3)�̖�697����f(×3)�����`�ŊJ�����A�����2:3�ɃJ�b�g�����ׂ������ł��B
���̎B���f�q��21.9×15.3mm�ɂ��čX�ɍ���f�����}���`�A�X�y�N�g������A15.3×15.3mm�̐����`����21.9×11.6mm��Cinema(17:9)�ɑ�������摜�f�[�^�������܂�����A�ō����Ǝv���̂ł����ǂ��ł��傤���ˁB
�R���̉f������p�e���r�J�����̏ꍇ�ARGB�f�[�^����舵���܂�����A����n�͒��o���Ńt����RGB/YCbCr��4:4:4�ŊO���L�^����悤�ɏo����ō��ł��傤�ˁB
�e���r�X�^�W�I���̉f���`����^�惌�x����4:2:2��e���r�����ADVD/Blu-ray�^�惌�x����4:2:0���ƁA�N���G�[�^�[�ɂ͌����Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F26186130
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > �j�R�� > Z5II �{�f�B
��䗷�s�ɍs���Ă��܂����B
1���ځA31,000��
2���ځA21,000��
�T�Q��1�����̃E�H�[�L���O�����Ă��܂����������ɑS�g�ؓ��ɂł��B
�ʐ^�̑O��2����NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
�㔼��2����NIKKOR Z 50mm f/1.8 S�@�ƂȂ�܂��B
��r���邽�߂Ɏ����悤�ȃA���O���ɂ��܂����B�w�O�Ȃ̂ŎO�r�͎g�킸AUTO���[�h�ł̎B�e�ł��B
A���[�h��F�l��1.8�ɌŒ肵���摜������܂����AISO�����������ł���������ƈÂ��ł��ˁBAUTO����2.8�Ƃ�4�ɂȂ���ISO�����̕��オ��܂����A���邭�Ă������̕����D�����Ǝv���܂����B�iISO���グ��Ɩ��ɗ��q�������܂����܂������C�ɂȂ�Ȃ����x���ŋ����ł��BZ5�ł͖��̗��q�ɗ��_���Ă܂����̂ŁA��i���O�r�g�p����ł����������̋Z�p�̖͂�肩���j
���āA���r���[�ɂ������܂�����AUTO���[�h��AF-A�G���A��AF-S�Ȃǂɕς��āA�I�[�g�G���AAF����V���O���|�C���gAF�Ȃǂɕς�����ŁA�B�e���[�h�_�C��������x�ύX���AAUTO���[�h�ɖ߂���AF-A�@�I�[�g�G���AAF�ɖ߂��Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B
�d�l�Ȃ̂��o�O�Ȃ̂��A�J�������Ă�����������Ȃ̂��A����Ƃ��ݒ肪����̂��c�i��J�Œ��ׂ�C�͂Ȃ��j
���i���Ƃ��܂��ẮAAUTO�ŎB����A���[�h�ŎB���āA�ړ����Ă܂�AUTO�ł��ĎB��������Ă���̂ŁA����ύX����̂��ʓ|���Ǝv���܂����B
![]() 3�_
3�_
��AUTO���[�h�ɖ߂���AF-A�@�I�[�g�G���AAF�ɖ߂��Ă���
�t���I�[�g���[�h����AF��AF-A,�I�[�g�G���A�Ɏ����Őݒ肳�邩��A���ꂪ���킾����B
�����ԍ��F26180211
![]() 7�_
7�_
�����_�����q����
����ɂ���
��AUTO���[�h��AF-A�G���A��AF-S�Ȃǂɕς��āA�I�[�g�G���AAF����V���O���|�C���gAF�Ȃǂɕς�����ŁA�B�e���[�h�_�C��������x�ύX���AAUTO���[�h�ɖ߂���AF-A�@�I�[�g�G���AAF�ɖ߂��Ă���
����Nikon��Z50�U�������Ȃ̂ŁA�R����Nikon�̎d�l�Ȃ�ł��傤��
�����ԍ��F26180217
![]() 3�_
3�_
���R����Nikon�̎d�l
�j�R���Ɍ��炸�t���I�[�g���[�h�ł͓��R������B
���S�Ҍ����̃��[�h������w�ǑS�Ă̍��ڂ̓J�����C���̃I�[�g�ɂȂ邪��B
�����ԍ��F26180224
![]() 6�_
6�_
�����_�����q����
����ɂ��́B
��AUTO���[�h�ɖ߂���AF-A�@�I�[�g�G���AAF�ɖ߂��Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B
AUTO���[�h�͏��߂Ă̕����Ƃ肠����
����ɂ��Ƃ��Α�̎ʂ�A�Ƃ������[�h
�ł��̂ŁAAF��I�o�ݒ�܂߁A���ׂ�
�J�����ɏ]���I�[�g�ȃ��[�h�ɂȂ�̂�
�s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
AF��I�o�ݒ�i�Ƃ����̕ێ��j��
�C�ɂ����悤�ȎB�e�҂̃X�L���́A
����AUTO�͑��Ƃ��Ă���͂��A
�Ƃ����l�����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F26180244
![]() 5�_
5�_
�������ǂ��g���ݒ��U1-U3�ɓo�^���Ă����Ηǂ��ł��B
���̂��߂̃��[�U�[���[�h�ł��B
�����ԍ��F26180343�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
���T�C�����X�X�Y�L����
�Ƃɂ���J�����Ŏ���������Nikon�APENTAX�̓J�����C���̃I�[�g�ɂȂ邯��
GF5�AG5�AGX7mk2�Ȃǂ�LUMIX��AF-S�Ȃǂɂ��Ă�ƃI�[�g�ł�AF-S�ɂȂ�̂�
�u���R�v�ł͖����A���[�J�[��@��ɂ���Ďd�l���Ⴄ�̂�������܂����
�����ԍ��F26180864
![]() 1�_
1�_
�����_�����q����
�j�R���̏ꍇ�͂�����������ł��B
AUTO���[�h�̓J�����C���̃t���I�[�g���Ǝv���Η������₷�����Ǝv���܂��B
�I�o�����ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�s���g���킹�������ʒu���^�b�`���邱�ƂŃ^�b�`�����ʒu�Ńs���g���킹���s���A�w�𗣂��ƃV���b�^�[�����d�l�Ȃ̂łƂ����ɎB�肽���ꍇ�͂��̕��@���������Ǝv���܂��B
�������A��ʍ��[�ɂ���w�̃A�C�R�����^�b�`���āu�^�b�`�V���b�^�[�v�ɂ��Ă����K�v������܂��B
�����ԍ��F26183073
![]() 3�_
3�_
2025/05/20 02:50�i5�����ȏ�O�j
��Z5�ł͖��̗��q�ɗ��_���Ă܂����̂�
�����x�m�C�Y�ጸ���u���߁v�ɐݒ肷��Ή����ł��������H
�����ԍ��F26184410
![]() 3�_
3�_
�ԐM���x��܂����B
�݂Ȃ��肪�Ƃ��������܂����B
�����ɁuAUTO���[�h�v�̑��݈Ӌ`���͂��Ⴆ�Ă����悤�ł��B
U�Ɋ��蓖�Ă邱�Ƃɂ��܂����B
���L���O�I�u�u�����_�[�Y����
�������x�m�C�Y�ጸ���u���߁v�ɐݒ肷��Ή����ł��������H
���̎ʐ^���B�����̂͂܂��������S�҂̍��ŁA��i�B�e�ɂȂ��O�r���K�v�Ȃ̂������悭�������Ă��܂���ł����B
�����x�m�C�Y�ጸ�̐ݒ肪���邱�Ƃ�m�����̂́A�y5�U��Youtube�ł�����ˁB
�������A�K����芵���ł���Ă������Q�ł��ˁB
�����ԍ��F26186332
![]() 4�_
4�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-3 �{�f�B
OM-3�̓O���b�v���Ȃ����Ƃ�O��Ƃ��Đv����܂����B
�܂�A���ꂪ�{���̎p�ƌ������Ƃł��B
�������A����������X�̓J�X�^�}�C�Y�Ƃ������̉��ɂ��̃o�����X����������Ȃ�Ƃ�������܂��B���ꂪ��Ƃ������̂ł��B
iwood���̃O���b�v����ɓ��ꂽ�̂ŁAOM3�ɃO���b�v���K�v���ǂ������n�Ō������邱�Ƃɂ��܂����B
���ʂ͉摜�̕\�ɓY�t���܂��B
�ꌾ�ł܂Ƃ߂�Ȃ�AOM3�ɃO���b�v�͂���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
���ʂɗ���ŎB�e�������A�O���b�v�͉��̖��ɂ������Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B
�������Ў�Ő������̃K���}���̂悤�ɃX�i�b�v������A�E��ɃJ�������Ԃ牺���ĕ����X�^�C���̎B�e�҂ɂ͗L���ł��B
�܂��A�O���[�u��t�����܂B�e����Ƃ����L���ɍ�p���܂����B
����EM5MK2�ł܂��ɂ��̂悤�ȎB�e���D��ł��܂������AOM3�ł͂������Ȃ����Ƃ�I�т܂����B
�u����Ŏ����Ă�������B���Ă���v�Ƃ����v�̍l�����������邩��ł��B
�ނ��A�O���b�v��t�������ЂƂ͖�肠��܂���B�f�����b�g�͂����͂��ł��B
������������邱�Ƃ�����܂��B
�O���b�v���Ȃ����Ƃ����̃J�����̃E�B�[�N�|�C���g�ƂȂ邱�Ƃ́A���܂�Ȃ����낤�Ƃ������Ƃł��B
���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͂����������Ƃł��B
![]() 16�_
16�_
�E�E�E����A�uED 100-400mm F5.0-6.3�v�ł���Ă݁H�i�j�@�@�v��Ǝv����B
�����ԍ��F26180113
![]() 12�_
12�_
��Albern����
> OM-3�̓O���b�v���Ȃ����Ƃ�O��Ƃ��Đv����܂����B
�܂�A���ꂪ�{���̎p�ƌ������Ƃł��B
�z���͐l���ꂼ��ł��B
�����̂��{���ł��ǂ��Ǝv���܂����A���p�I�ɎЊO��
�𒅂���̂������Ղ��B��₷���Ɍq���邩�Ǝv���܂��B
OM-3�̓t�B��������̃m���O���b�v�ȃJ�����f�U�C��
�ł����A�������̎��ゾ���ă��C���_�[��[�h���I��
�@�\�g���ɂ͂Ȃ�܂����O���b�v�I�ȕ��𒅂��Ă܂���
����A�����������{���Ƃ������Ȃ��Ă��ǂ�����
�Ǝv���܂��B
���Ǝ����Ղ��̊ϓ_���猾���A�t�B�������ォ�����
���n�߁A��^�����Ă����ł�����v��Ȃ���ł������A
OM-3�̓��g�����̊�����傫������f�U�C���v�f�Ȃ�
�v���܂��B
�l�I�ɂ̓O���b�v���������J�����Ȃ̂ŁA�d���Ȃ���
�{���]�|�ƌĂ�Ă��A�o�b�e���[���[�����˂����[�h��
���ۂ��S�c�����J�b�R�ǂ����ȂƎv���܂��B
�����ԍ��F26180119
![]() 8�_
8�_
��Albern����
����ɂ��́B
���ꌾ�ł܂Ƃ߂�Ȃ�AOM3�ɃO���b�v�͂���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�V�X�e���̃��C���A�܂��͂����䂾���̏��L�ŁA
�]����12-100�̂悤�ȏd�������Y���g���ꍇ�A
�i�����ڂ͕ʂƂ��܂��āj�O���b�v���������ق���
�g���悢�ꍇ�����邩�ȂƎv���܂��B
�X�i�b�v�ȂǂōL�p����W���̒P�œ_��
�y���Y�[����{�t���Ă̎B�e�Ȃ�A
�����������ځi����ꂽ�ځH�j�D���
�O���b�v�͕t���Ȃ����낤�ȂƎv���܂��B
�����Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͂����������Ƃł��B
����͐l���ꂼ��ł����A
���������ʂ肾�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26180235
![]() 3�_
3�_
��Albern����
���������Ў�Ő������̃K���}���̂悤�ɃX�i�b�v������A�E��ɃJ�������Ԃ牺���ĕ����X�^�C���̎B�e�҂ɂ͗L���ł��B
�܂��A�O���[�u��t�����܂B�e����Ƃ����L���ɍ�p���܂����B
�����ł��ˁB�d�������Y�����ł�������ƁA
�J�����̂ق��̉E��w��������Ƃ���̃��o�[�Ȃ�A�V�{�炪�_���[�W�₷���ł��B
�܂��X�g���b�v���I�ԂƂ����Ƃ��������܂��ˁB
�������|���̑��ʃX�g���b�v��X�g�X�g���b�v�̓A�E�g�B
�̂Ȃ���̂����ċ����ӂ�ɃJ�������������܂�X�g���b�v�łȂ��ƁA
�J�����������グ��̂ɗ���͓���Ƃ��v���܂��B
�����ԍ��F26180476
![]() 1�_
1�_
PENTAX LX HABA ��144.5mm�ł�����500mm�N���X�ł�OK�ł��� |
100-400mm/F4-6.3���x�Ȃ�]�T�H |
�����Y�̕��ŕێ������150-400mm/F4.5�ł����v |
��Albern����
�Y�[�~���O��O��ɂ���ƁA����Ń����Y��͂ނ��ƂɂȂ�܂����A�T�[�h�p�[�e�B�[�̃O���b�v��t���郁���b�g�͂Ȃ������ł���ˁB
12-100mm/F4�N���X�Ȃ�Y�[�~���O�����Ȃ���ΕЎ�ł��B�e�͉\�ł����c
���]��(�Y�[��)�����Y��t�����ꍇ�́A�����Y�̕����������ǂ������ȋC�����܂����AOM-3�̏ꍇ�A�{�f�B�[�̕���������x����̂ŁA���\��������ێ��ł��銴���ł��B
�����ԍ��F26180776
![]() 3�_
3�_
������I���������邩��V�X�e���ł��āc�g���₷���悤�Ɋy���炢���Ǝv���܂��B
���ꂪ�{���̎p�����i�j
�����ԍ��F26181059�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 11�_
11�_
�O���b�v
OM�X�g�A�ł� �̔�����Ă��܂��̂ŁA���D�݂ŁA
���邢�͑��������Y�ɂ���ėՋ@���ςɂŁA�ǂ��̂���Ȃ��ł��傤���B
Leofoto LPO-OM-3 �O���b�v�t��L�^�v���[�g
\ 15,840�~ (�ō�)�`\ 14256(�ō��j
https://jp.omsystem.com/outdoor/product/om3grip.html
UN OM-3 �E�b�h�O���b�v
�� 14800 (�ō�)�`\ �P3320(�ō��j
https://jp.omsystem.com/outdoor/product/un_om3grip.html
�����ԍ��F26200397
![]() 5�_
5�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
-
�yMy�R���N�V�����z����\��
-
�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X
-
�y�~�������̃��X�g�z2025PC�\���Q
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j