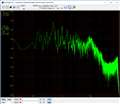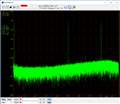このページのスレッド一覧(全6474スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2017年12月17日 19:25 | |
| 3 | 3 | 2017年12月16日 08:12 | |
| 1 | 3 | 2017年12月15日 00:43 | |
| 1 | 5 | 2017年12月8日 16:34 | |
| 16 | 6 | 2017年12月8日 14:08 | |
| 5 | 9 | 2017年12月6日 08:56 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX
バージョン1.17を使用しているんですがsonic radar proが動作しません
ゲームリストには表示されているんですが、ゲーム(R6S)を起動してもレーダーが表示されないんです
他のバージョンも試したのですが同様です。
また、ショートカットキーの出来ないので困ってます。
studioの方は問題なくいごきます。
同事象の方、解決方法ご存知の方いませんか?
書込番号:20629953 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 4点
4点
改善に繋がるかは分かりませんが
自分も同じ症状でした
初めにproを購入したのですが主様の症状に加え
コントロールボックスも利かず一度初期不良で返品し
再度DLXを購入しました
ですが症状の改善には繋がりませんでした
商品自体の不具合でなければもしやと思い
以前MBの故障で使ってたz170からz270に換装したことがありその際に日常生活に時間もなかったので
osをクリーンインストールせずに上からz370のドライバーなどをインストールしていたのでその関係でドライバーが干渉してるのを疑いosのクリーンインストールを実施したのですが
それでBOXの起動不具合 レーダーが立ち上がらない動作不良については改善しました
参考になれば幸いです
ちなみに再生デバイスがstrix raidではなくUSBデバイスなどになっていると
レーダー自体は表示されないみたいですよ
書込番号:21439822 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5
先日こちらの商品を購入して早速blasterx acoustic engineを公式よりダウンロードしインストールしましたが、
イコライザーのタブを開こうとすると
「保護されているメモリに読み取りまたは書き込み操作を行おうとしました。他のメモリが壊れていることが考えられます。」
と警告が出てソフトが落ちてしまいます。
ホームページにあるバージョン「BlasterX Acoustic Engine Pro ソフトウエアパック (69.10 MB) 2 Mar 17」は以上の症状ですが、
もう一つある「BlasterX Acoustic Engine Pro ソフトウエアパック (Windows用) (67.81 MB) 20 Oct 17」は、
警告がも何も出ずにそのままソフトが落ちてしまい、そもそも他のタブを押そうとするとも一定の確率でソフトが落ちてしまいます。
同じ様な症状の方は、解決策を知る方はおりませんでしょうか?よろしくお願いします。
*PCスペック
windows10 pro(最新バージョン)
cpu: i7 4790k
mem: 16gb
ssd: 128gb
gpu: gtx1060
![]() 0点
0点
ドライバーインストール時にウイルス対策ソフトがブロックしてしまっている可能性もあります。
停止させるなり一時的にアンインストールするなりして試してみるべきでしょう。
それから英字の大文字小文字には意味があります。
特に単位の大文字小文字は致命的な違いになることがあります。
16gbでは16グラムビットという謎単位になります。
書込番号:21429756
![]()
![]() 3点
3点
アドバイスありがとうございます。
アンチウイルス関連のソフトをオフにした状態でインストールしてみましたが症状は変わりませんでした。
別のPCにソフトをインストールしてG5を繋いで見るとしっかりイコライザーも調整できたことより、
おそらく現在使っているPCになにか問題があるのかもしれません。
根本的な解決にはなりませんでしたがとりあえずこの状態でしばらく使用してみることにしました。ありがとうございました。
また、大文字小文字の話もありがとうございます。確かに読み方も変わってしまいますので、今後は気をつけてみます。
書込番号:21432840
![]() 0点
0点
アンチウィルスソフトで、インストールされたディレクトリをスキャン対象外に指定してみては?
ソフトにより、実行プログラム自体を指定して除外しなければいけなかったりしますが、改善する事もあります。
書込番号:21435549 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX
半年ほど前にこちらのカードを購入し、一時は正常に動作をしていたのですが
PCの再起動やスリープをかけるとSTRIX RAID DLXが認識されない不具合が起こるようになりました。
しばらくそのままの状態で放置すると、カチっと音がしたと同時にSTRIX RAID DLXが認識され問題なく動作するのですが
再び再起動やスリープをかけると認識されません。
放置して認識されるまでの時間はまちまちで、認識されないこともあります。
別なPCI-Eスロットに挿しても症状は変わりません。
ドライバの再インストールも試しましたがこちらも変化ありません。(公式の最新版)
カードの中でオレンジ色のランプが点灯しているので通電はされているようです。
ハードウェアの問題なのかソフトウェアの問題なのか原因がつかめず困っています。
![]() 0点
0点
環境は
OS:Windows10 64bit
CPU:4790K
M/B: ASUS MAXIMUS VIII RANGER
Mem: 16GB
GPU: ASUS GTX1080
電源ユニット: Seasonic SS-860XP2 PLATINUM 860W
宜しくお願い致します。
書込番号:21430779
![]() 0点
0点
これに限らず内蔵型のサウンドカードって結構相性とかシビアで、最初問題なくても使ってるうちに不具合が出ることはわりとよくあること。
とりあえず潰しておくべき点として、Windows10の大型アップデート際にサウンド周りの不具合が出るケースが多いのだけれど、その際は上書きだと治らないことがあるので、ドライバーを一削除(アンインストール)してから再度インストールをすると直ることがあるので、まずは試されてみては?
それと上記のケースが当てはまる場合は最新版のインストールメディアを作ってOSのクリーンインストールするのも方法かもしれない。
後このサウンドカードはコントローラーICにC-Media 6632AXを採用しているが、このチップはUSB-DAC用のチップで接続インターフェースはUSBになっており、それを内部でPCI-Eから変換チップ経由して接続をしている関係で、へんな相性とかがあったりするんで、そのあたりの可能性も否定は出来ないし...。
その他、一応確認だけれどもコールドブートからの起動で正常に動いていれば、ハードの故障出ない可能性が高いので、スリープって不具合結構出ることがあるのでスリープを使わないようにするなどの使用方法を含めた対処もありかと...。
自分が気付いた点はこのあたりですね。
知り合いもこのカード使ってる人が1人いますけど、その人もマイクが変な挙動してて困っていたような...。
書込番号:21431665
![]() 1点
1点
>くら〜くで〜るさん
返信ありがとうございます。
OSクリーンインストール、ドライバの再インストールを試しましが改善されませんでした。
コールドブートからでも認識されないのでハードウェア側の問題が濃厚になって来ました。
購入時のレシートを紛失してしまい、ASUSはレシート等がないと有料修理も受け入れてくれません。
まれに認識する事があるのですが、PCの電源を10分以上落としてしまうと再び認識されず完全にお手上げ状態です。
念のため、次のWindowsアップデートまで待ってみて、それでも改善されない場合は処分するしかないですかね?・・・
書込番号:21432721 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 0点
0点
サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus
これはコントロールボックスがついていますが、知らずに使っていたのですが、これは音量を上げる・下げることのみですか?
これにつないだことにより、音質が上がるとか そういったことはないですよね?
![]() 0点
0点
あと、AMAZONでレビューなどを見ようとしたのですが、
Asus Xonar Phoebus Solo Carte son interne と Xonar Phoebusがあったのですが、
あれはコントロールボックスがあるか ないか の違いでしょうか。
価格も大きく変わっていたので、コントロールボックスに何か仕組みがあるのでしょうか。
書込番号:21409191
![]() 0点
0点
このシリーズはもうだいぶ前に終了しているハズです。
コントロールボックスは手元でボリュームをコントロールするだけでしょう。
Soloはコントローラーやゲームを除いたモデルのようですが、日本では出なかったんじゃないですか。
Amazonで出ているのは並行輸入版で、異常な高値をつけている業者がいるので注意が必要です。8万なんてあり得ない価格ですから。
書込番号:21410346
![]()
![]() 0点
0点
返信ありがとうございます。
廃版なのはわかるのですが・・・って感じです。
コントローラーやゲームを除いたものとは、コントローラーはわかるのですが、ゲームを除いたとは どのようなことでしょう。
アマゾンの価格は高くなっていますね・・・
書込番号:21410413
![]() 0点
0点
ゲームはゲームです。
市販のPCゲーム(当然ASUSが作ったものではない)が同梱されていました。
タイトルは調べるのも面倒ですし...
書込番号:21414985
![]() 0点
0点
>uPD70116さん
ゲームってあの製品+ゲームがどれか貰えるという。
自分はそれは求めていないので、大丈夫そうです。
回答ありがとうございます。
書込番号:21415542 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD
来年10年目、ONKYOがサウンドカードを作り始めてから20年目という節目となり今更ながらこの製品の素晴らしさを語らせていただきたい。
まず私の環境からご紹介
●私の環境●
○PC環境
windows10 pro 64bit
i7-6900k 32GB
ROG STRIX X99 GAMING
○デジタル部
SanDisk SSD Extreme PRO 960GB---デジタル音源(FLAC)---AIMP4.5(WASAPI envy24 デジタル出力 96khz)---SE-200PCI LTD(玄人志向 PCI-PCIEX1によりPCIEに変換)---Cable Matters TOSLINKオプティカルケーブル---TEAC UD501
○プリメインアンプ
TEAC UD501(RCA出力より)---BELDEN 8412 RCA 赤白ライン---DENON PMA390RE----TEAC LS-H265-B
○パワーアンプ
DENON PMA390RE(プリアウトより)----BELDEN 8412 RCA 赤白ライン---ONKYO M-506R(OH済み)---CORAL X-V(OH済み)
-------------------------------------
以上である。
X-Vはミドルハイを絞ってウファーとして使っている。非常に引き締まった低音で心地よい。
さて、この構成だと本製品はUD501との光出力のために使われているので客観的に見て性能を活かせていない、もっと安価なPCIE-S/PDIF、強いてはオンボード出力でいいのではないかと感じる方も多いかと思う。
私もそれが気になりクリエイティブ社のZxRや同社300PCI ASUSのSTRIX RAID DLXを差し替えてサウンドテストしたところ明らかな違いが出た。
クリエイティブ社のZxR に関しては耳に刺さるような高域が始終出っぱなしでとても「ずっと聞いていたい」と感じる音ではなかった。
近年のサウンドボードはオーディオよりもゲーミング方面を意識しているため「よりノイズレスに、よりハイファイに」という思考で設計されていることが伺えた。
300 PCIに関してはチップがクリエイティブ社の物を使用しているがさすがにONKYO、その点が大幅に改善されているように思えた。しかしながら本商品と比べると音場が狭くなってしまい平べったい音、よく言えばモニターヘッドフォン的な音になっているように思えた(こちらは音の好みが分かれるかと思う)
ASUS社に関してもやはりゲーミングを意識しているためクリエイティブ社と同等の傾向があり音楽を長時間楽しむ設計ではないとかんじた。
そして本製品は主観であるが音のキレ、解像度、音場の広さ、ノイズレス、音圧、どれをとってもバランスがよく「ずっと聞いて居たい音」であった。どんな音源も魅力的に響かせてくれる安心感がある。特に顕著に違いが出るのが中域にジューシーさである。ギターの歪みの粒立ちが明らかに違う。クラシックなどでは透き通り綺麗にフェードしていく広域が目立つ(特にピアノ)。
以上を踏まえてS/PDIF出力で音質に違いが出るということはクロックのジッターの影響が濃厚かと思うがここまで音質に差が出るものなのだろうか。
PCI200 LTDのクロック回路には±10ppmの超高精度の水晶発振子やほかにはない東信工業株式会社と共同開発したハイグレードオーディオコンデンサーや導電性高分子アルミ固体電解コンデンサの採用などがありそれらも音質に大きく影響していると感じる。
つまり一概に「デジタル出力なのだから音は同じだろう」「オプティカルの音の違いはジッターによるものだけである」とは言えないのではないか。みなさんの意見をもしよろしければお聞かせ願いたい。
--------------------------------------------------
ところで私がなぜ96khz出力でオプティカル接続を選択したかという話だが、
まず周波数についてだがこちらは192khz出力すると高周波域が雑音となって音が濁って聞こえるためである。特にCD音源などは44.1khzからアップコンバートされるため192khzまでの高周波域は空データが流れることとなり耳鳴りのような雑音が入りやすいと言える。
私の耳に合うのは96khzであった。
次にオプティカル接続についてだが、実際にオーディオ評論家の意見を垣間見るとシングルのオプティカルよりも同軸のコアキシャル出力やUSBDACによるUSB接続のほうが音質が良いというのが一般的になっているかとおもう。
UD501はそもそもUSBDACであるためUSB接続を前提に設計されている。しかし私があえてUSB接続を使わない理由は音源を再生時かならずポップノイズが生じてしまうためである。小音での使用やヘッドフォンやイヤフォンでの使用であれば気にならない、気付かないレベルかもしれないが、私のようにスピーカーにてそれなりの音量で聴く場合これがかなりストレスになる。USBケーブルも高品位なものをいくつも試し、電源もオヤイデのノイズ処理されたものを使い、USBポートもASRock,Intel,Renesasコントローラーのものを比較したが改善がなかった。USBというデバイス上ノイズを受けてしまうのかもしれない。
そしてUSB接続の音質は少々ノイジーに聞こえてしまった。
こうなるとUD501を使用する上で選択肢として挙がるのはコアキシャル入力かオプティカル入力である。
コアキシャル出力に対応しているサウンドカードとしては300PCIEやaimのSC808やASUSのEssenceシリーズなどがある。
そこで300PCIを所持しているので同設定でオプティカル出力とコアキシャル出力で音に違いが出るのかサウンドテストしてみた。
その結果違いが全くわからなかった。そもそもジッターが発生する仕組みとして私の場合PCからDACまでの非常に短い区間をデジタル接続しているためジッターによる音の違いなど人間に観測できるレベルをはるかに凌駕しているといえる。
したがって音の傾向はデジタル、アナログ共に出力形式によらずサウンドカードの作りに依存しているのではないか、という私の推測は濃厚になった。
---------------------------------------------------------------------
![]() 4点
4点
(入りきらなかったので追加です)
2018年、10年目を迎える本商品であるが未だに一部のオーディオファンから絶大な人気があると言える。
2017/12現在中古平均価格5000円前後。この価格でこのクウォリティは信じがたいコストパフォーマンスだ。
この製品のメインチップであるVIAは最近までwindows10/8に対応していなかったためドライバトラブルが多かった。
しかし2015年AUDIOTRACK社から対応ドライバが公開されたためこれから購入する方もこちらを参照して欲しい。
http://audiotrack.co.kr/en/drivers/1368
また公式からもwindows8対応のドライバが公開された。私の環境ではwindows10でも使用できた。日本語対応しているので日本語がいい方はこちらも参照して欲しい
http://www.jp.onkyo.com/support/pcaudio/download/se200pci.htm
Deckを起動し、右側の周波数を選択しようとすると「システムは再生/録音状態です」と出ると思うが、いちど再生デバイス欄の該当デバイスを無効にすると選択できるようになる。その後再生デバイスを有効にし、プロパティのサポートされている形式欄にて周波数が選択できる。
さらに、このサウンドカードは古いためPCIにしか対応していないが最近のマザーはPCIスロットが搭載されていない。
そのためこのサウンドカードを諦める方もいるかもしれないが玄人志向から以下の商品がでているので確認して欲しい。
http://www.kuroutoshikou.com/product/interface/converter_board/pci-pciex1/
私の環境で正常に動作しているので参考にしてもらいたい。
ただし変換カードの高さ分上にズレるのでRCA出力を使う方はミドルタワーPCケースだと使えない可能性がある。
固定方法などを画像をアップロードするので参考にして欲しい
----------------------------------------------------------------------------------------------
そろそろ部品の寿命を迎え始める頃でもある本商品。
今後どのように修理、改造していけばよいのかみなさんのおすすめするカスタマイズ方法なども是非この場でお聞かせ願いたい。
長くなってしまったが日本の技術を凝縮したようなこの素晴らしい芸術品をこれからも使い続けられたらうれしい。
書込番号:21412588
![]() 3点
3点
少なくともクリエイティブメディア系(SE-300PCIEも含む)の製品はデジタルの時点で加工がされているので比較は無意味です。
USB接続のDDCやDAC、HDMI接続のAVシステムとの比較をした方がいいでしょう。
余程過酷な環境にない限り電解コンデンサーの容量抜けもないでしょうし、何等かの理由で使えなくなるまでそのまま使い続ければいいと思いますよ。
書込番号:21412655
![]() 4点
4点
>USB接続のDDCやDAC、HDMI接続のAVシステムとの比較をした方がいいでしょう。
比較して当機とは、さよならいたしました。
書込番号:21412713
![]() 2点
2点
ご指摘ご意見ありがとうございます。
少し書き方が分かりずらかったかもしれません。
私の本製品の使用法はあくまでもUD501へ接続するための手段でありこの製品がメインではないということが第一にあります。
PCからDACまでなるべく新鮮な情報を送るための手段にすぎませんがケーブルによって音質が変化するようにどのような接続をするかによって音質が変わるのではないかと考えています。より新鮮にDACへ情報を送るために選んだ手段が本製品となります。
そのため音の性質はDACであるUD501に大きく依存していることは承知しております。
USB DACやプリアンプ パワーアンプなどに関しましては別で比較を行い個人的に好みのものを選んでいます。
そちらに関しては比較を行ったのがずいぶん前ですのでここ数年で直接USB接続やHDMI接続可能なプリメインアンプやオプティカルやコアキシャル入力端子を装備したアンプが増えたため恐らくもっと好いものが作られていてお二方は更なる高みへ行っておられるのでしょう・・・
私が所持しているアンプは記述以外にもluxmanやmarantzなどがありますがどれも古いので「デジタル音源はアンプとは別のDACで変換するもの」という概念が染み付いてしまっています。
今後の選択肢としてデジタル入力のついたプリメインアンプというのも視野に入れようと思います。
ちなみにUSB接続は記述の通りポップノイズなどのマザーボードのノイズを拾ってしまいやすい点で選べませんでした。
musa47さんの現在の環境など差し支えなければ教えて頂けませんか?
書込番号:21413423
![]() 1点
1点
>つまり一概に「デジタル出力なのだから音は同じだろう」「オプティカルの音の違いは
>ジッターによるものだけである」とは言えないのではないか。
同感です
でも、まだ解明してないのでジッターのせいだけって事にしとこう、みたいな
>「デジタル音源はアンプとは別のDACで変換するもの」という概念が染み付いてしまっています。
同じように染みついてます。
私は、SE-200のアナログ出力→アンプ からスタートして
現在は、PC(USB)→DDC→DAC→アンプ と、とても面倒な構成になってしまいました。
書込番号:21415099
![]() 1点
1点
ご返信ありがとうございます。
なるほどDDCですか、いわばわたしの使い方でいうところの本製品のデジタル回路部分を特化させたような製品でしょうか
初めて知りました。DDCはUSB接続が多いようですがポップノイズなどはどうですか?
大変参考になりました。
書込番号:21415306
![]() 1点
1点
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2
お世話になります。
レコードを録音したくて上記製品と組み合わせて使っております。
これまでは何も考えず「環境設定」でサンプリング周波数を96kHz、ビット数を24bitにして録音しておりました。
しかし、よく見ると「環境設定」で384kHzまで、ビット数で32bit(float)まで設定できるようで、試しに192kHz/24bitで
録音してみて、foobar2000で再生したところきちんと192kHz/24bitと表示されました。もっとも私のあほ耳では違い
はわかりませんでしたが。
さて、これは192kHz/24bitに対応している、ということなのでしょうか。最大384kHz/32bitまでいける、ということで
よろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
![]() 0点
0点
>さて、これは192kHz/24bitに対応している、ということなのでしょうか。最大384kHz/32bitまでいける、ということでよろしいでしょうか。
たぶん対応してると思います。対応してるかどうかを調べる方法としては、wavespectraというフリーソフトで、drop再生するとアップ図のように周波数特性が表示されるのでサンプリング周波数が384KHzなら、周波数特性が20Hz〜192KHzの帯域で表示されるはずです。
では音質はどうかというと、こちらのサイトにアナログレコード信号の歪みについての考察があります。
http://fixerhpa.blog.fc2.com/blog-entry-217.html
アナログ録音の場合、高音質といわれたDENONのPCMシリーズのマスターの音でさえ、高音の上限は23KHzまででそれ以上はカットされてます。ではなぜアナログレコードの周波数特性を見ると200Hz位まで信号が検出されるのかという疑問が残りますが、これはレコードの溝の波形を円形針や楕円形針でトレースすするときに発生する高調波歪が音楽信号と一緒に出力されていまうのが原因です。
なので物理的にサンプリング周波数を上げてレコードから再録音して、高音の上限を伸ばしたとしても、歪み音とファイル容量が増えるだけであまりメリットは無いと思います。
ただしオーディオは感覚の世界。音色の好みは人それぞれなので、高調波歪が追加された音でも、メリハリがきいてい良い音だと感じれば、それはそれで試してみる価値はあると思いますが、音質の変化を感じないのなら、無駄にファイル容量が増えるだけなのでやめておいたほうが無難です。
書込番号:21408506
![]() 1点
1点
訂正があります。
誤り アナログレコードの周波数特性を見ると200Hz位まで信号が検出されるのかという疑問が残りますが
訂正 アナログレコードの周波数特性を見ると200KHz位まで信号が検出されるのかという疑問が残りますが
200Hz→200KHzに訂正。
書込番号:21408514
![]() 0点
0点
>吉田"Tricky"勝さん
お使いのOSは何でしょう?Winsows10ですか?
DigiOnSound X Expressとの組み合わせで使用している時、コントロールパネル→サウンド→録音タブで当機(SB-DM-PHDR2)のプロパティの詳細タブで24bit/192Khzや32bit/・・・が選択できるようになってるでしょうか?
ここで24bit/192kHzが選択できてるようですと24bit/192kHzでの録音もできてることになります。
しかしそこは当機のドライバーによるハードの設定ですので、私の推測としては24bit/96kHz以上の設定はできないままになっているのではないかと思います。
記載の環境設定とはソフト側のDigiOnSound X Expressのものだと思います。そこは録音時のフォーマットの設定ですので実際の入力信号に関係なくソフトの機能として32bit云々まで設定できるようになっているのではないかと思います。
したがって、24bit/96kHzの音を24bit/192kHzのフォーマットで録音している可能性が高いと思います。
サウンドのプロパティは初期設定の16bit/44.1kHzのまま変更せずに録音ソフトの設定だけを24bitにしてハイレゾ録音している気になっている人を時々見かけます(笑)
録音ソフトのフォーマットを24bit/192kHzに設定して録音すると実際の入力情報とは関係なく、例えば無音状態を1分間録音しても録音されたファイルのフォーマットは24bit/192kHであり、当然foobar2000では24bit/192kHzと認識し、ファイル容量は普通の音楽を1分間録音した時と同じになります。
分かりやすく言うと軽トラ1台分の荷物を10トントラックで運んでいるようなものです。
ついでで申し訳ないのですがfoobar2000について最近気づいて気になっていることがあります。
先月、仕様上〜60kHzまで再生可能とされるスピーカーを入手したのでどこまで測定できるか試そうと思って10〜60kHzのスィープファイルを作成してfoobar2000で再生してみたんですが、40kHz以上になると出力レベルが0になる=40kHz以上は出力されていないみたいなのです!。
今までヘッドフォンのF特を何回か測定してきましたが、ずっと40kHzまでのファイルしか使用してなかったので気づきませんでした。
なのでここ数年の私の持論「24bit/48kHzと96kHzの違いは感じるが96kHzと192kHzの違いは感じない」が根底から崩れています(笑)40kHz以上が出力されていなかったのだから96kHz設定と192kH設定で出てくる音は同じで元々違ってなかったのです。
まだ時間がなくてfoobar2000で40kHz以上の音を出す方法があるのかどうかも調べられてないのでスレチですがご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
>パイルさん
ハイパーソニックを研究した人(チーム)によると音源に50kHz付近の信号を強調して入れると音量が大きく聴こえ脳内麻薬的成分により快感を感じる(α波が増す)ハイパーソニック効果が見られるというような話を何処かで読んだ記憶があります。なのでノイズでも歪でもなんでも50kHz付近の成分だったら良いみたいですよ。
ただ、わざわざ「50kHz付近」と言ってるところがミソで、96kHz/24bitじゃ50kHzにちょっと足らないから192kHzが必要と思わせるためのどこかのビジネス的陰謀とも思えます(笑)
とりあえず96kHzが再生可能なソフトとハードと音源を用意して自分で試してみるのが良いのですが、なかなか難しいですね。
書込番号:21408775
![]()
![]() 1点
1点
一点訂正と説明不足なところがあります。
1. 時々見かけたのはハイレゾ録音じゃなくてハイレゾ再生の方です。サウンド機器のプロパティを初期値の44.1kHz/16bitのままfoobar2000やその他の再生ソフトで24bitのハイレゾ音源を聴いて全く違いがわからないと言っていた知人が2人いました。
2. ハイパーソニック現象は全員が感じるわけではないそうです。何人かで実験した中でそう感じた人の割合が多かったということでしょう。特に音の聴こえ方、感じ方は個人差が大きいので人それぞれです。
書込番号:21408913
![]() 1点
1点
こちらではマザーボード(オンボード)のヘッドホンアウト(192KHz24bit)を使ってサンプリング周波数192KHzの音源で80KHzの音声信号を出力してオシロスコープで確認してみました。
wavegene直接出力、WindowsMediaPlayer、Foobar2000で試したところいずれも50KHz以上の音が出力されているのが確認できました。アップ図参照。
マザーのライン入力を通すと、録音デバイスでサンプリング周波数192KHzに設定できても、50KHz以上はカットされて出力できませんでした。それとPCケースの前面のヘッドホン出力端子で測定すると、この場合も50KHz以上はカットされて出力できませんでした。
なのでFoobar2000の仕様ではなく、サンプリング周波数が192KHzに設定できても、出力、入力(A/D変換)のどこかで50KHz以上がカットされているものと推測できます。なのでスレ主さんの場合384KHzで録音できるということなので、その録音音源をwavespectraで再生してみると、50KHz以上の音楽信号が含まれているかどうかの確認ができると思います。
書込番号:21409023
![]() 0点
0点
訂正です。
誤 : マザーのライン入力を通すと、録音デバイスでサンプリング周波数192KHzに設定できても、50KHz以上はカットされて出力できませ
んでした。
正 : PCケースの前面出力からとっていたため50KHz以上が確認できなかったようです。80KHzがちゃんと出力される背面PHONE出力から配線して録音状態にすると、アップ図のように80KHzの信号も確認できました。なのでこちらのマザーの場合は、LPレコードの音声を、サンプリンス周波数192KHz(20Hz〜96KHzの帯域)で録音できることになります。
書込番号:21409110
![]() 0点
0点
>パイルさん
ということはfoobar2000で40kHz以上の出力が可能ということなのですね?
私の問題はソフトだけの話で、とりあえず先ほどWaveGeneで40kHzと63kHzのファイル(もちろん24bit/192kHzで)を作ってfoobar2000で再生してみたんですが、40kHzはピークメーター、VUメーターとも上がる=出力されているのですが、63kHzでは全く上がりません。
パイルさんのfoobar2000で出力ができているので、おそらく私のfoobar2000のDSPか何かの設定に問題があるのだと思います。
それが分かれば24bit/192kHzの音源を聴けることになると思うと楽しみなのですが、なかなか調べる時間が・・・^^;
もし見当がつくようでしたら教えてください。
e-omkyoでDLした24bit/192kHzの音源はたくさんありますし、一応手持ちのヘッドフォンではSONY MDR-1A(BIが100kHzまで出るという仕様になってるはずで、ヘッドフォンアンプはASUS Xonar U7、ラトックス REX-KEB02AK、FX-AUDIO DAC-X4Jとあるのでなんとかなるでしょう(笑)
書込番号:21409305
![]() 0点
0点
Foobar2000は、普段使わないのでデフォルトのままで再生してます。オンボのDACのサンプリングが192KHzになっているので、帯域が96KHzまで出力されているようです。
windows10を使ってますが、メディアプレーヤーとfoobar2000では、ともにサンプリング周波数384KHzの音源も再生できてしまいますが、DACの設定の上限は192KHz-24bitなので、ダウンコンバートされて出力されるため、帯域はサンプリング192KHz=20Hz〜96KHzで出力されます。なのでこちらの実験では、再生周波数の上限は再生プレーヤーではなく、DACとその設定に依存するようです。
書込番号:21409712
![]() 2点
2点
皆様、早速のお返事ありがとうございます。感謝でございます。
>パイルさん
> なので物理的にサンプリング周波数を上げてレコードから再録音して、高音の上限を伸ばしたとしても、歪み音とファイル容量が
> 増えるだけであまりメリットは無いと思います。
> ただしオーディオは感覚の世界。音色の好みは人それぞれなので、高調波歪が追加された音でも、メリハリがきいてい良い音だと
>感じれば、それはそれで試してみる価値はあると思いますが、音質の変化を感じないのなら、無駄にファイル容量が増えるだけなの
>でやめておいたほうが無難です。
なるほど。おっしゃるとおり仮にいい音になったとしても、私のあほ耳では「そんな気もする」程度の認識でその割にはファイルサイズがでかいのはどうなのか、と思っておりました。大変参考になりました。ありがとうございました。
>o-sunshineさん
私の使用しているOSはWindows7です。さっそくコンパネで設定を確認してみたところおっしゃるとおり96kHz/24bitまでしか設定できないようになっておりました。
> 分かりやすく言うと軽トラ1台分の荷物を10トントラックで運んでいるようなものです。
よくわかりました。どうもありがとうございました。
書込番号:21410065
![]() 0点
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】windows11に対応で購入
-
【その他】原神用?
-
【欲しいものリスト】自作PC
-
【欲しいものリスト】200V脱衣所暖房
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
サウンドカード・ユニット
(最近3年以内の発売・登録)