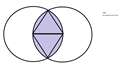���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S446�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2014�N5��11�� 09:08 | |
| 2 | 2 | 2013�N12��3�� 23:31 | |
| 0 | 3 | 2013�N11��25�� 19:37 | |
| 4 | 1 | 2013�N12��2�� 05:50 | |
| 1 | 4 | 2014�N3��14�� 22:19 | |
| 3 | 4 | 2013�N10��14�� 08:15 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�܂��͂��߂ɒf���Ă����܂������̎����Ă���̂�
���^�C�v(�����c�[�g��)��TL880�ł��̂ŁA���s�͂ǂ���������܂���B
�ȑO����80mm�ɂ��Ă͂����Ԃ�Â��̂ŏW���͂ɋ^�������Ă����̂ł���
STL750�̃��R�[��(�ŋߒm��܂���)�ɔ����A���X�Ȃ��番���������ׂĂ݂܂����B
�܂��A���_�ł����A�Ռ��ɎՂ��L���a�͌��̂�80mm������܂���B
���쒆�S�̋ɋ����͈͈�_�݂̂��A�������ς�����66mm(����68.1��)�������Ƃ���ł��傤�B
������ӕ��Ɏ����Ă͂��̍X��60.9��(���̌��a��41.4��)��������܂���B
�����ɐ������ɂ��邽�߂̋�(*�v���Y���ł͂Ȃ�)4���ƃ����Y�̓��ߗ��������̂ŁA
�����͂����ƈ����ł��B
�������ďڍׂׂ��Ƃ���A��ɑΕ������Y�Ɉ�ԋ߂��Ռ��������Ղ��Ă��܂���
�h���[�`���[�u���k�߂�ƃh���[�`���[�u�̐�[(�Ε���)���A
�����o���ƃh���[�`���[�u���̎Ռ��ƃh���[�`���[�u��[(�ڊᑤ)��
�����Ղ莋�삪�Â��Ȃ�܂��B
�g�p����ۂ̓o���[�����Y�͘_�O�ŁA�V���v���Y�����g�p���Ȃ�����
�h���[�`���[�u�̈����o���ʂ����Ԃ��炢�̂��ߎ�ł����������ǂ��Ǝv���܂��B
������x�̃P�����͕�����܂����A���a80mm���ł���̈悪�S�����݂��܂���B
�h���[�`���[�u����������Ԋ����Ȃ��ʒu��68mm������Ƃł��B
��������L�̈ʒu�ł̓s���g���o�܂���B����͖��炩�Ȑv�~�X�ł��B
�h���[�`���[�u��[�̐ؒf�ƎՌ����a�̒����Ń}�V�ɂȂ肻���Ȃ̂�
������b�オ����Ƃ������܂����c
���̑��A���|�[�g�������̂Łc
�O�r�̓O���O��(��ɋ����ڑ��������_��̎���������݂܂�)�A
�r�̒����Œ�l�W�͎������őϋv���ɓ�L��(����܂���)�B
�㉺�����l�W�̌Œ蕔�����������Ŋ���܂����B
�l�i�Ȃ�ƌ��������ł����A�j���[�g�������O�����邱�Ƃ�
�L���a66mm�����ŋ����̖��������A�ؐ��̖͗l(2�{)�A�y���̗ւ������邱�ƂȂǂ���
�����Y�͂���ȂɈ����͂Ȃ��悤�ł��B�܂��R�[�e�B���O�͔��ˌ����Ԏ����ۂ��̂�
���m�R�[�e�B���O�̂悤�ł����B������O���B�B
�����h���E�Ռ������͈ꉞ�{����Ă��܂������r���[�Ȋ����ł��B
���邢�Ώۂ�����Ɣ����ۂ��Ȃ�܂��B
����80mm��搂��Ă���ȏ�A����̒��S�����ł�75mm���炢�͂��g���Ăق����ł��ˁB
![]() 4�_
4�_
�v�Z�Ԉ���Ă܂����B
×�@������ӕ��Ɏ����Ă͂��̍X��60.9��(���̌��a��41.4��)��������܂���B
���@������ӕ��Ɏ����Ă͂��̍X��39.1��(���̌��a��26.6��)��������܂���B
�ڊᕔ���猩���鎋����ӕ�(���a20mm�t��)�͓Y�t�摜�̎��ɓh����������
���삵���L���ł͂���܂���B
15mm�a�t�߂Ŗ�66��(���̌��a���45��)�ł��B�c�ϕ����ʓ|�Ȃ̂Ōv�Z���Ă��܂��B�B
�Ռ������A�h���[�`���[�u������������31.7mm�a�̃A�C�s�[�X����荞��
�������悢��������܂���ˁB
�����ԍ��F16916592
![]() 3�_
3�_
���̌�c���͎̂����Ǝv���������Ă݂܂����B
�E���Ռ���(�ƌĂԂ̂��m��܂��A��ԑΕ����̎Ռ���)������10�`15cm�قLjړ�
�E�h���[�`���[�u���̎Ռ������A�قُ���(�c��2mm�ق�)
�E�����~���[�@-�@�h���[�`���[�u�Ԃ̎Ռ������A���S�ɏ���
�E�h���[�`���[�u�Ɛ����~���[�̐ڍ����̓�����Z�����A���a���L����
��L�̉�����
�h���[�`���[�u�i�[��68mm�A
�h���[�`���[�u��1/3�J��o����74mm
�h���[�`���[�u��1/2�ȏ�J��o����75�`76mm*
�܂ʼn��P����܂����B
*�����Y��������̊W��75�Ȃ���76mm�ȏ�͖����Ȃ悤�ł��B
�h���[�`���[�u�i�[���̃P�����͎c�����܂܂ł����A
�ʏ�̓h���[�`���[�u��1/3���x�ȏ�J��o������ԂŎg�p����̂�
�ؒf���Ă����܂���ʂ������Ȃ��Ǝv�����̂܂܂Ƃ��܂����B
�܂��A�Ռ������ɔ������������������߁A�����Y�̃R�o�������h��A
�����~���[�����ǂɃe�B�b�V����\�荕���h��܂���
(���̂܂܂��ƃ~���[���ӂ̎������Ŕ��˂��܂�)�B
�ق��ɂ��F�X�����Ă���ӏ�������̂ŋC�x�ߒ��x�ł����蒼�������܂����B
�������̒��ӓ_�Ƃ��Ă�
�@�����������̂Ń����Y�̌���(��]������)��O�ʁE��ʂ̔z�u�Ȃǂ�
�K���T�����������B
�c�T���Ă��̂܂ܑg��ł��S���e�[�v�̌Ђ̌��݂̕��ŃY���܂��B
���������A�����炸��Ă��܂������B�B
�A�ꉞ�����������Ȃ���Ă���̂Ńh���[�`���[�u���̎Ռ������Ƃ���
�{��(�}�X�L���O)���K�v�ł��B
�B���Ռ��𒆂։������ޕ��@�ł̉����́A
�Ε������Y���ɐV���ɎՌ��������ꖇ�lj����������ǂ��Ǝv���܂��B
���ՎՌ��̓��a�𒆐S�������炳���^�~�ɍ���̂ł����
�ʒu��ς����ɍ�����ق����ǂ��ł��B
�C���[�J�[�̕ۏ��Ȃ��Ȃ�̂ʼn����͎��ȐӔC�ɂĂ��肢���܂��B
������A���ۂɐ�������Ƃ��Ȃ薾�邭�Ȃ�܂������A
���͑��ς�炸�p�b�Ƃ��Ȃ��̂Ō��ݒ������ł��B
�ȈՌ��������A�C�s�[�X�Ō����������A
�j���[�g�������O�Ń����Y�̐c�o���������s���܂�����
���ʂ����܂����Ȃ̂őO�ʂƌ�ʂƂ�
����������Ă���̂ł��傤���ˁB
�����̂Ƃ���͂��܂�ڂ����Ȃ��̂�
�����Œn���ɒ������邵���Ȃ��悤�ł��B
�����@�\���Ȃ����߂ǂ��Ȃ邱�Ƃ��B�B
�����ԍ��F16956379
![]() 2�_
2�_
���̌�A�����~���[�����������AVixen��31.7mm�̓V���v���Y����
�������܂�����ԂŖ������˂�����ł݂܂����B
�����~���[�̕��A���H��������Ȃ��Ȃ邽��
�Ƃ肠�����V���v���Y��x2��ʂ��Ă��܂��B
�ؐ��̎ȓ�{�ȊO�Ɏ�������Ƃ����悤�Ȑ�������悤�ȂȂ��悤�ȁc�B
��Ԕ��͔S���Ă݂܂����������ł����B
�y���͍��x���Ⴂ��A�V��Ɍb�܂ꂸ������ƌ����Ă��܂���
A��B�̐F���Ⴄ���Ƃ͎��ʂł����悤�ȁB�B
������J�b�V�[�j�̊Ԍ����������Ƃ͌����Ȃ��ł���
���̕ӂ肪���̑Ε������Y�̌��E�ł��傤���B
Vixen��80mmF11�A�N���ł͂��������͂����茩���܂�
(������������Ɍb�܂ꂸ�B��r�̂��ߓV���~���[2�ʂ��Ă܂��B)�B
TL880�͏W���́A���ȊO�̓m���R�[�g��60mmF15�A�N��
(�h�����đ�Ԕ��������܂�)�ɂ��犮�s���Ă��܂��B
�ڊᕔ���p�̖ڐ��͕t���Ă���̂ł������i���̌̂̕���
�悭������@��A���l�i�������̂ł킴�킴��������̂��Ȃ��ƁB�B
���͐����~���[����24.5mm�A�C�s�[�X�ɖ߂��Ă��܂��������������肵�Ȃ�
�����̓~���[�ƕt���̓V���v���Y���łقڌ��܂�̂悤�ł��B
�����ԍ��F17289762
![]() 1�_
1�_
�ŏI��
�E�Ε������Y�`���Ռ��܂ł̋�������
�E�t�[�h
�E�����Y������
�E�h���[�`���[�u���̖��h����(���̂��ꕔ�������h��������)
�ɐA�ю���\��܂����B
�����Y���O�������łɂ�����x�����Y�̐c�o�����s�����Ƃ���
�ؐ��̑�Ԕ����h�����Č����郌�x���ɂȂ�܂����B
����\�ł�Vixen��80mmF11�A�N���ɂ��ƈ���Ƃ������Ƃ���ł��B
���̏�Ԃł����60mmF15�A�N����薾�炩�ɂ悭�����܂��B
Vixen��70mmF12�A�N�����TL880(80mmF10)������悤�Ɋ����܂����B
�F������60mmF15�ɋy�т܂���80mmF11��舳�|�I�ɏ��Ȃ��ł��B
�������肵���������ŁA��͂背���Y���̂͂��������D�G�Ȃ悤�ł��B
�����A���̎��̂̃����Y�͒��N�����Y�Z���Ɏ߂��爳������Ă���������
��ό`���Ă���悤�Ȃ̂Ŋ��S�Ȃ��̂��Ƃ����������Ɍ�����̂�������܂���B
���^TL880(���������d�l)�̃_���ȓ_���܂Ƃ߂��
�E�傫�Ȍ��_
1.�Ռ��̈ʒu�A�傫�����s�K��
2.�ڊᕔ�ɓ�������Ă���4���̃~���[�̕i��������
�E�����Ȍ��_
1.�����̃Y��(�����A�����Y�Z���̉��H�A���t�����x������)
2.�V���v���Y���̕i�������̉����炢
3.�����h�����ꕔ�ȗ�����Ă���
�ˑ�̓O���O���Ə����܂�����
������e���i�Ɣ�ׂ�Ƃ������肵�Ă��܂��B
�uPORTA�o�ܑ�Ɣ�r����Ɨh�ꂪ�傫���v�ɒ������Ă����܂��B
�����ԍ��F17503164
![]() 1�_
1�_
�V�̖]���� > �r�N�Z�� > �~�j�|���^ A70Lf
�܂������̏��S�҂ł��B
�f����_��������ώ@������
�~�j�|���^A70Lf���w�����悤�Ǝv���Ă����̂ł����A
�~�U�[��TL-880�ƒl�i���߂��̂ŁA��������C�ɂȂ�܂����B
���S�҂ɂ͂ǂ������ǂ��ł��傤���H
�������̉��i�т��Ǝ肪�o�܂��A
���i������������Ƃ������o�[�W�����A�b�v���l���Ă��܂���B
��������낵�����˂������܂��B
![]() 0�_
0�_
���̌��a�N���X���ƌ���ؐ��Ȃǂ͏\���y���߂܂����A���_�ƂȂ�Ƃ�����ƈÂ��Ă�قnj��Q�̖�������Y��ȏ��łȂ��Ɠ�����Ǝv���܂��B
���i�I�ɂ����܂łƂ������Ƃł���Α��ɂ�
http://scopetown.jp/prod_st_atlas_1.html
����������Ă��邩�Ǝv���܂����A����ؐ��ƌ�����ꂪ�ł��悭�����邩������܂���B
�g������Ƃ��Ă̓~�j�|���^�������Ǝv���܂��B
�~�U�[���̂��̂̓l�b�g��̎ʐ^��t���i�Ȃǂ�������肿����Ƃǂ��Ȃ̂��ȂƂ����C�����܂��B
�]�����͊�{�I�ɂ͓|�����Ƃ����đΏۂ��t���܂Ɍ����܂��B
�o�ዾ��ό��n�ɐ����Ă���n�㕗�i�߂邽�߂̖]�����Ȃǂ͂����Ƀv���Y����~���[�����Đ������A�܂�t���܂ł͂Ȃ�������悤�ɂ��Ă���킯�ł����A���Ԃ̒n�㕗�i�ɔ�ׂĂ͂邩�ɈÂ��V�̂�����ꍇ�͂���͌��ʂ�����̂ł��܂�D�܂������Ƃł͂Ȃ��A�����̕����ɂ��������肵���R�[�e�B���O���{����Ă��Ȃ��Ɨ����˂ȂNjN�����ăR���g���X�g���Ⴍ�Ȃ����肵�܂��̂ŁA���ʍŏ����炻�̂悤�Ȏd�l�ɂȂ��Ă���]�����Ƃ����̂͂Ȃ��A�ǂ����Ă��Ƃ����ꍇ�͌ォ�琳���v���Y���Ƃ����I�v�V�����i�����ƂɂȂ�܂��B
�V�̂������ǒn�㕗�i���������炢�������ȂǂƂ����ꍇ��TL-880�ł�������������܂��A�����łȂ��Ȃ瑼�̓����I�ꂽ���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F16910876
![]()
![]() 2�_
2�_
�ڂ����������肪�Ƃ��������܂��B
�u�����Ō�����́H���b�L�[�v���炢�Ɏv���Ă��܂���(^^�U
���͏��S�҂Ɛ\���܂������A
�\���N�O�ɍw�������{�[�O�̂P�Q�T���a�̖]����������܂��B
�����m�炸�ɎO�����炢�Ŕ������̂ł����A
�u�������u�̖����O���O������O�r�v
�u�h���[�`���[�u����ł̂��ăs���g���킹�v
�ŋ�J���Ėʓ|�ɂȂ�A�����ɕ��u���Ă��܂��܂����B
���x�͂����Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�������߂���I�Ԏ��ɂ��܂��B
���肪�Ƃ��������܂���m(__)m
�����ԍ��F16912801
![]() 0�_
0�_
�V�̖]���� > �P���R�[ > �X�J�C�G�N�X�v���[���[ SE-GT102M
�]�����̐ڊᕔ�ɃJ�������q���̂ł͂Ȃ��P�̂Ƃ��čڂ������Ƃ������Ƃł��傤���B
���̃V�X�e���͂��̂悤�ɂ͏o���Ă��Ȃ��̂ł��̂܂g���Ƃ����͖̂����Ȃ悤�ł��ˁB
�������O���Ă��̃A���~�]�ڍ����Ƃ����Ƃ���ɕʓr�v���[�g�Ȃǔ����ĕt����J���������ڂ��邱�Ƃ͏o���܂����A������t�����܂܂ł��t�@�C���_�[���O���ē��������̃A���~�]�ڍ����ɉ����H�v���邱�Ƃōڂ��邱�Ƃ��o���邩������܂��A����͐ԓ��V�ł͂Ȃ��̂ł�郁���b�g�͂Ȃɂ������Ǝv���܂����B
�����ԍ��F16829988
![]()
![]() 0�_
0�_
�Z�b�g�i�A�I�v�V�����Ƃ��ɉ_������邽�߂̐ݒ�͂Ȃ��ł��ˁB
�s�̂�115mm�̋����o���h�łP�^�S�C���`�̃l�W�̖��ߍ��݂̂�����̂�T���Ă݂܂������A�c�O�Ȃ��猩���邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�ǂ����Ă��Ƃ����̂Ȃ�A�s�̕i�Ƀl�W��ʂ���悤�����J���Ď��삷����@�����Ȃ������ł��B
�����A�����܂ł��ĉ_������t���ăJ�������ڂ����Ƃ��Ă��A�ˑ䂪�o�ܑ�ł����玩�������ɂ͎g����Ƃ��Ă��A�����ǔ��@�\���g���Ă̒����ԎB�e�͂ł��܂���B
�����ԍ��F16830018
![]()
![]() 0�_
0�_
�L��������܂����B�ԓ��V�Ƃ͈Ⴂ�܂�����ˁE�E�E�B���̕���T���܂��B
�����ԍ��F16880022
![]() 0�_
0�_
�V�̖]���� > �P���R�[ > SKY WALKER New SW-III PC
���[�^�[���t���ӏ����ASYNTA��EQ3�p�Ɏ��Ă����̂ŁASeben��M4���[�^�[���Ă݂܂����B
SebenEQ3�Ƃ͍��E�̎��t���ʒu�����Ȃ̂ŁA�N���b�`�̃r�X�ƃX�v�����O�̃r�X�̈ʒu��ύX����K�v������܂������A�����Ɏ�t���������܂����B�N���b�`��������Ɠ��삷�邵�A1���ԓ������Ă݂܂������A���E���ւ����̂ŁA�씼�����[�h�ɂ��Ȃ��Ƃ����܂��ǁA������1���ԕ��̉�]�����Ă��܂��B
���i�I�j�����ōH��ł��Ȃ��l�́A�^�����Ȃ��ł��������B���s���Ă��ӔC�����܂���B
SW3�ɂ�T�����O���t�����Ȃ��̂ŁA���̂܂܂ł́A���œ_�B�e�͓���ł����A�ԓ��V�̃}�E���g�͈�ʓI�ȃA���a�Ȃ̂ŁA�J�������ڂ���͓̂���Ȃ�����A����B�e�͏\���ł������ł��B
�]�����̒��œ_�B�e�̂��߁A1.25�C���`����T�����O�ւ̕ϊ��A�_�v�^��T���Ă݂悤�Ǝv���܂��B
![]() 2�_
2�_
Hndl����
���̌�A����ʐ^�͂������ɂȂ�ꂽ�ł��傤���H
���Ђ��̌�̃��|�[�g�����肢���܂��B
���̋��z�̐ԓ��V�Ŏ����ǔ��ł���̂Ȃ�A�|�����G�������y���߂����B
�O�r�Z�߂Ɏg���ăJ�������ڏ悹�Ă��܂��K�^�K�^���Ȃ��Ȃ�Ȃ����ȁH
�ȂǁA�����������������Ă݂����ł��B
�������ꂽ���[�^�[�́A����ł��傤���H
Quartz-controlled R.A. Motor Drive M4 with Hand Controller
For SEBEN telescopes with EQ3 or EQ2 mount
Important: Only suitable for telescopes bought since January 2012
���҂����Ă��܂��B
�����ԍ��F16905667
![]() 2�_
2�_
�V�̂̎B�e�̂��߂ɖ]�����̍w�����l���Ă���܂��B
���t���w�����Ă��猎��V�ђ��x�ɎB��悤�ɂȂ�A�œ_�����̒��������Y���w�����Ă��炫����ƎB�e�������Ǝv���悤�ɂȂ��Ă��܂����B
���́Asigma150-500��pentax k-5�ŎB�e���Ă���A35mm���Z��700mm�{�g���~���O�ŎB�e���Ă���܂��B
�Ăɂ͔�r�I���̉e�������Ȃ��Ǝv���܂��y���̎R���ɑ؍݂��܂��̂ŁA���̎��ɑ��̓V�̂��B�e�A�ώ@���ł���Ƃ��v���Ă���܂��B
�����Ȃ�ɂ����ׂĂ݂��̂ł����A�ڊ���Y�H�̔{���ȂǂŌ�����傫�����ς��ȂǑS���`���v���J���v���Ŏ��₳���Ă�������������ł��B
��낵����A�h�o�C�X����������Ǝv���܂��B��낵�����肢�������܂��B
![]() 0�_
0�_
�J���������Y�ɂ������10�~���O��̒��L�p�����Y����500�~���I�[�o�[�̒��]���܂ł���悤�ɁA���邳��F1�N���X�̑���a�̖��邢���̂���F4�ȂǏ��X�Â߂̂��̂܂ł���悤�ɁA�]�����ɂ��ړI�ɂ���ĐF�X����A�c�O�Ȃ���1�{�łȂ�ł��d����Ƃ������̂͂���܂���̂ŁA���߂Ăǂ̂悤�ȑΏۂ��B�肽�����̓l�b�g�ł����Ȏʐ^����������Ă��̂悤�Ȃ��炢��������Ƃ�����ł����B
����Ƃ��\�Z�������Ă���R�����g�������Ƃ��炢�₷���Ȃ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F16734577
![]() 0�_
0�_
���R�Ƃ����Ő\����܂��C�{�̂�PENTAX�����g���ł�����C
PENTAX���g���t�B�[���h�X�R�[�v���o���Ă��܂����C�B�e�p�̃A�^�b�`�����g
���o�Ă���Ǝv���܂��B
���Ȃ��Ƃ�500mm��蒷�������Y�i���̕��Â��ł��傤���ǁj�͂���܂��B
AF�͏o���Ȃ��Ǝv���܂����ǂˁB
�����ԍ��F16735572
![]() 0�_
0�_
�ԐM��ϒx���Ȃ�܂��Đ\����܂���B
>takuron.n����A���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
���莝���̋@�ނŎB�e�ł�����E�������A�b�v���[�h�����摜�ł��āA���ȏ�ɑN���Ɍ��Ȃǂ��B�e�ł���Ǝv���Ă���܂��B
�܂��A���̋@�ނő��̓V�̂��B�e�ł�������Ǝv���Ă�����x�ŁA�܂����m�ɃR�����B�肽���I�Ƃ����̂͌���N���ɎB�肽���A���炢�����������܂���B
�܂��\�Z�̕�������I��Ŕ����悢�̂��S�������炸���Ă������܂����炻�����ɂ�����x�ȏ�ł���Β��������肵�čw���ł���Ǝv���Ă���܂��āA���m�ɗ\�Z�̓R�����炢�A�Ƃ������̂͂���܂���B
�ǂ̃N���X�̕��Ƃ��̎���̂��̂����낦��Ηǂ��̂��S���������Ă��炸�A���̂悤�Ȋ����ł��B�\����܂���B
>���[���[����A���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�t�B�[���h�X�R�[�v�Ƃ������̂�S���m�炸�I�����ɂ�������Ă���܂���ł����c�B
�t�B�[���h�X�R�[�v���g�����ꍇ�A�V�̖]������p����ꍇ������y�ɎB�e�ł�����̂Ȃ̂ł��傤���c�H
���낢��ȕ����ώ@�ł��邩�A�Ƃ����Ă�Ŕėp�����R������ΓV�̖]�����ɂ��Ă����āA�����I�ɂȂɂ��ώ@���������̂����������������Ǝv���Ă���܂��B
�������Ő\����܂���c�B
�����ԍ��F16775999
![]() 1�_
1�_
K-5�Ō��̒��œ_�B�e������Ȃ�A�œ_����1300mm���x���҂�����ł��B
vixen��VC200L�Ƀ��f���[�T�[��t������A20cm��F6�j���[�g���Ȃǂ���ɓ���₷���Ǝv���܂��B
�L�������K�X���_�ɂ�8�p����10�p��500�����O��̋��ܖ]�������n�O��͂ɂ�1500mm����2000mm�̃V���~�J�Z��b�`�[�N���A�`���Ȃǂ��K���Ă���Ǝv���܂��B
�ˑ�͍�����EM200��r�N�Z����SXP�N���X�ȏ�̂������肵�����̂������߂ł��B
������ɂ��Ă����߂̓x�e�����ƈꏏ�ɎB�e�ɍs���̂��������Ǝv���܂��B
�B�e���Ă�����̃u���O��t�F�C�X�u�b�N�̓V�̎ʐ^�W�̏����̂����Ə��������܂��B
���œ_�ł̎B�e�ɂ͐ڊ���Y�̔{���͊W����܂���̂ŁA�]�����̏œ_�����̂܂܂ł��B
�����ԍ��F17303456
![]() 0�_
0�_
�V�̖]���� > �r�N�Z�� > �|���^II A80Mf
���̖]�����ő��z�̊ώ@���l���Ă���̂ł����A�ǂ̂悤�Ȍ����t�B���^�[���g�p����Ηǂ��ł��傤���H
80mm�a�ȏ�̌����t�B���^�[�ł���Ή��ł������̂ł��傤���H
�����A���S�҂̂��߁A�ڂ��������肢���܂��B
![]() 0�_
0�_
��Ԉ��オ��̓A�X�g���\�[���[�t�B���^�[�ᎋ�pND-5�i10���{�����j�ł��B
http://www.kkohki.com/Baader/astrosolar.html
�����]�����̐�ɍ����悤�Ɏ��삵�Ă��Ԃ��܂��B
�����ԍ��F16702065
![]() 0�_
0�_
�ł����S�ȕ��@�ő��z�̍��_���ϑ��������A�Ƃ��ł���Α��z���e�������߂��܂��B
�|���^II�`�W�O�l���Ȃ��p�̂��̂����z���e�`�Z�b�g�̖��̂Ńr�N�Z������o�Ă��܂��B
���z���e�ł��g�������ۂ̊ϑ����@���A�X�g���A�[�c�̃z�[���y�[�W�ŏЉ��Ă��܂��B
http://www.astroarts.co.jp/alacarte/tips/solar_projection/index-j.shtml
�t�B���^�[�ȂǂŒ��ڊᎋ����ꍇ�͍אS�̒��ӂ��K�v������܂��B���f����ƕ����ʂ�ڋʏĂ��ɂȂ郊�X�N������܂��B
���ƁA�t�@�C���_�[���댯�ł��B��������`���Ɠ����悤�Ɏ����̋��ꂪ����܂��B���Z�̕����ő��z�ϑ����Ă����Ƃ��́A�t�@�C���_�[�͈��S�̂��ߊO���āA�����̉e���ŏ��i�^�~�j�ɂȂ�悤�ɓ������đ��z�����Ă��܂����B
�����ԍ��F16702226
![]() 0�_
0�_
���z�ڌ���ꍇ�́A���������łȂ��A���O���J�b�g����ł��B
�������ō����Ă����O���œ������Ɩڂ��ׂ��댯������܂��B
�t�B���^�[�̎d�l����������m�F���Ă��������B
�����ԍ��F16702896
![]() 3�_
3�_
���肪�Ƃ��������܂��B
�݂Ȃ���̂��ӌ����Q�l�ɁA�A�X�g���\�[���[�t�B���^�[��t���ăf�W�J���Ŋώ@���Ă݂܂��B
��肭�����Ȃ���A���e���w���������Ǝv���܂��B
�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F16704064
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�V�̖]����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
-
�yMy�R���N�V�����z����\��
-
�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�V�̖]����
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j