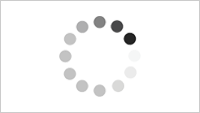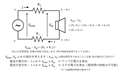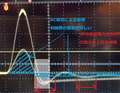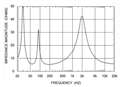���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S1909�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 40 | 9 | 2019�N10��12�� 23:02 | |
| 154 | 46 | 2019�N10��15�� 18:55 | |
| 56 | 13 | 2019�N10��12�� 16:10 | |
| 349 | 200 | 2020�N3��12�� 23:41 | |
| 193 | 65 | 2019�N10��6�� 21:55 | |
| 44 | 16 | 2019�N9��27�� 20:43 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
���v���Ԃ�Ɏ��⎸�炵�܂��B
�}�����c��M-CR611���g�p���Ă��ĐV�����A���v���w�����悤�ƌ������Ȃ̂ł����APMA-1600NE��2500NE���Ŗ����Ă��܂��B���݁A�X�s�[�J�[��B&W607���g�p���Ă��܂��B���̃N���X�̃X�s�[�J�[�ł́A�ǂ���̃A���v���K���Ă���̂ł��傤���H�X�s�[�J�[�̃|�e���V���������܂�c�����Ă��Ȃ��̂Łc
�����A�ǂ�����K���Ă��Ȃ���A���̃X�s�[�J�[�ɍ������A���v�������Ă������������ł��B
���͒���悪�s���Ɗ����Ă���̂ŁA����悪�L�тĂ���悤�ȃA���v����]���Ă��܂��B
�����ԍ��F22982536�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���ė����t����
�u�T�E�R�E�Q�̖@���v�Ƃ������̂����邻���ł��B
�I�[�f�B�I�@��̉��i�o�����X�ŁA�X�s�[�J�[5���A�A���v3���A�v���[���[2�����ǂ��Ƃ������̂ł��B
���ꂩ�炷���1600NE�ŏ\���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����܂Ŗڈ��Ȃ̂ŁA�ł���Ύ������Ĕ��f���邱�Ƃ������߂��܂��B
�����d���Ȃ�ADENON�̑I���ŗǂ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F22982554
![]() 5�_
5�_
�����Ă��čw���ł���Ȃ�Ώ�ʋ@����Ă������ǂ��Ǝv���܂��B
�]�T�����Ė炵�܂��傤�B
���R�A�X�����Ȃ��O��ł��B
���[�J�[�Ⴄ�Ɩ����̂ł��傤���B
�����ԍ��F22982561
![]()
![]() 4�_
4�_
�����[�J�[��1�O���[�h�Ⴂ�Ȃ̂ŁA�\�Z�ɉ����đI������Ηǂ��Ǝv���܂��B
��X�X�s�[�J�[�̃O���[�h�A�b�v������ۂɗD�ʂɂȂ�̂�2500NE�ł��傤���B
�ቹ�̓X�s�[�J�[���̂��̂̃T�C�Y�Ɋ��Ƃ��낪�傫���̂ŁA�A���v�Ɋ��҂���̂ɂ͌��x���L��Ǝv���܂��B
�f�m���őI������Ă���̂ŗL��A���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22982721�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 4�_
4�_
�����X�s�[�J�[�ł��v���Ă���ȏ�Ƀ|�e���V�������L��悤�ȋC�����܂��B
(�����X�s�[�J�[�̂ق����������|�e���V���������ł���)
�����A���v���������Ă��������Ȃ�ɃX�s�[�J�[�͉����Ă����Ǝv���܂��B
��ɏ����ʂł��������Ȃ����ďꍇ�͉��̃f�e�B�[���������ɂ����̂ň����A���v�ł��������Ȃ��Ďv���܂��B
���i��肿����Ɖ��ʂ��グ�ĉ��̃f�e�B�[�������������Ȃ獂���A���v�ɂ��Ƃ����ق������Ďv���܂��B
�����ԍ��F22982931�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 5�_
5�_
���ė����t���� ����ɂ���
�������̗�������V�X�e���A���V�X�e���Ɏg���Ă��܂��B
���߂�2500NE���܂��āA�悩�����̂ő������������܂����A����ȑO�̓}�b�L���g�b�V������ցAROTEL����֎g���Ă܂����B
�ǂ�����X�s�[�J�[�̓t���A�^�C�v�����C���ł����A�R���p�N�g�^�C�v�ł������܂��B
���[�t�F�f�[����Diamond�Q�Q�T��2500NE�Ŗ炵�����̋����͑N���Ɋo���Ă��܂��A��u���j�^�[�I�[�f�B�ISilver200���ƕ����Ⴆ�܂����A�����Ƌ����܂����B��O�I�ȃR���p�N�g�X�s�[�J�[�������i�l�ɂƂ��Ắj�X�s�[�J�[�̉��ɕ��������̂ł��B
�A���v�������Ƃ����܂ł悭�Ȃ邱�Ƃ�̌����܂����A1600NE�ł͂����܂ł̈Ⴂ�͂̂���܂��A�O�̃A���v���𑜓x���ƂĂ��悭�Ȃ�܂����B
2500NE���������߂��܂��B
�����ԍ��F22983026
![]() 1�_
1�_
�ė����t����A����ɂ���
PMA-2500NE�A1600NE�ǂ�����t�F�A�ŕ����Ă��܂��B
1600�͓���p�̃C���[�W�ł������A�k�P���悭�ĉ��y�������������Ă���A����[���ŏ㋉�@�Ƃ͈قȂ鉹���B
�J�W���A���ɂ��������y����1600�Ƃ����L�������m�����Ă���Ǝv���܂����B
�i����Ȃ炠���ăX�}�[�g��1600��I�Ԑl������Ƃ������܂��j
2500�̓X�s�[�J�[���d�ʋ���B��W802�ŐU���邩�Ǝv���܂������A���ʂ��グ�Ă���荞�ݕs���̓r�ꂽ������ቹ�̑�g���݂͂�ꂸ�쓮�������Ă銴�������N�̉��W�ł̓g�b�v���x���̉����o�Ă܂����B
�i�t�F�A�Ȃ̂Ƀf���I���͉��Z�b�e�B���O�̓��O���Əo���̎����i�Ⴂ�A�^���X�^�W�I�̋Ǝ҂���H�j
�����ԍ��F22800893
B��W�̉𑜓x�͏o���ɂ��݂��Ȃ��A�㋉�͉��ʂƉ��K���傫���Ȃ��Ă�����ہA2500�ł��悳���o��Ǝv���܂����A�o�����X�I�ɂ������߂�1600�B�i�����ȃ��f������C�ɑ����ĔR���s���ł͂Ȃ��A��������I�[�f�B�I�̃X�e�b�v�A�b�v���y���ނ̂͂������ł��傤���H�j
�����ԍ��F22983511
![]() 5�_
5�_
���ė����t����
�\�ł����炨�X�œ����X�s�[�J�[�ŃA���v�����ς��Ē�����ׂĂ݂��炢���Ǝv���܂��B
���h�o�V�Ƃ��Ȃ�C�y�ɔ�r�����ł��܂��B�i���̏ꍇ�͂Ȃ�ׂ������Ŕ����Ƃ����̂��O��Łj
�S�̗̂\�Z�����܂��Ă���ꍇ�̋@��̗\�Z�z���̖ڈ��͂悭�����Ă��ăR�X�p���猾�����炻���Ȃ̂�������܂��A�R�X�p������Έ����X�s�[�J�[�ł��A���v�ł��̂������ς��ƌl�I�ɂ͊����Ă��܂��B
���̓��}�n�ł���������ׂ����Ƃ�����܂��A�����A���v�ɂȂ�ɂ�ė]�T�A���芴�A�ՐΊ��A�X�P�[��������R�悭�Ȃ��Ă����Ǝ��͊����܂����B
�X���Ńy�A4���N���X�̃X�s�[�J�[�� A-S301, A-S801, A-S2100�ƒ�����ׂ����z�ƁA�����Tannoy Mercury 7.1�i�y�A4�����炢�j��DAC�͕ς����ɃA���v��A-S801����A-S2100�ɕς������i���C���V�X�e���̂�������j����̊��z�ł��B
DENON�ł̓N���X�Ⴂ�̒�����ׂ��������Ƃ��Ȃ��ł����A�����悤�ȈႢ������̂ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B
�����A�S�̂̃o�����X���厖�ŁA�A���v�ɂ��Ⴂ���������Ⴄ�Ǝv�����A�債�����łȂ��Ǝv�����͐l������ꂼ��ł����ADAC��P�[�u���A�Z�b�e�B���O�ɂ���Ă��ቹ�̊����������ԕς��ƌl�I�ɂ͊����Ă���̂ŁA�ǂ��ɂ����𓊓�����̂��������͓���Ƃ���ł��ˁB
�ł��v�����C���Ȃ�20���N���X�ɂ���Ɩ{�i�I�ȃI�[�f�B�I�炵�����ɂȂ�Ȃ��ƌl�I�ɂ͎v���Ă���̂Ŕ�����Ȃ炻�̃N���X�ȏオ�I�X�X���ł��ˁB
�����������@��ł̓_���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����������������Z�b�e�B���O��g�ݍ��킹�̕�����قǑ厖�Ȃ̂ł����͂��낢�뎎�������Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F22983582
![]() 6�_
6�_
���ė����t����
�f�m���̃A���v�̌X���͒ቹ���ł邱�Ƃ��Ǝv���Ă܂��B��ʓI�ɂ̓s���~�b�h�^�Ƃ��������ł��B
�\�Z�ɍ��킹�Ă��w�����ǂ��Ǝv���܂��B
�������A���v�]�̒��ቹ�̏[�����A���v�w���Ŗ����ł�����̂Ȃ̂��́A�������ꂽ�ق����ǂ��Ǝv���܂��B
�X�s�[�J�[�͔��̑傫�����傫�����E���܂��̂ŁA�g�[���{�[�C�^�C�v�̂悤�Ȓ��ቹ�Ȃ̂��A�u�b�N�V�F���t�^�C�v�ŃA���v�Œ��ቹ���[��������̂��ǂ����́A��������āA�ǂ���̒��ቹ�̉�����ڎw���̂��ŁA�傫�ȈႢ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22983714
![]() 6�_
6�_
���ė����t����
�ቹ�����߂�Denon���l���Ă���l�ł����A���̃I�X�X���́B
YAMAHA s801
ATOLL 50
���̂Q�@�킪�o�����X(��������ቹ�܂�)���ǂ��A�y�������y��������I�X�X���̃A���v�ł��B
denon�͎���706s2�ƍ��킹�Ă܂������A������Ɖ��F�ƃo�����X�����ȉ��ł����B(���ɂƂ��čd�����ł���)
�I�X�X�����������Ȃ̂ŁA�����͂��Ă݂ĉ������B
���Ȃ݂ɁAATOLL��B&W��600�V���[�Y�Ƃ̑����͎��̒��ł͈�Ԃł��B�ۓ����Ɖ��s�����X�S���ł��B
�����ԍ��F22984489�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
����������Ȃ��A�����Ԕ��Ȃ��X�s�[�J�[��T���Ă��܂��B
�����̏����I�ɂ͎��������̓j�A�t�B�[���h�A�ǂ܂ł̋����͖�40cm�B���͑傫���͂Ȃ��̂ł����A��̂Ђ�T�C�Y����Ȃ��Ă����͖�20cm�܂ő��v�ł��B
�d����������PC���g���̂ő��Œ����Ԓ����Ă����Ȃ����ƁA�l�̐��⒆�������Ăɒ����ĉ����u������Ȃ��v���ƁA���{�����[���I�ɂ͏����߁`�����炢�ŋߏ����f�ȑ剹�ʂ͗L�蓾�܂���B
�W���Y�A�N���V�J���A�|�b�v�X�A���b�N�Ȃ�ł������܂��B
���批�y�ӏ܂��炢��DTM�Ȃǂ����Ȃ��ł��B
�w�����̋������邿����Ɠ��̈ʒu��ς���ƒ�ʂƂ����̂ł��傤�����y�����ꂽ�肷��^�C�v��ቹ�������ł�͍̂D�݂ł͂Ȃ��ł��B
�\�Z�͂��̂悤�ȃX�s�[�J�[��2������8���܂łɑ�������̂ł��ꂭ�炢�ŁB
���̓A���v�����̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�ŋC�ɓ����Ă��鏇�Ԃ�Edifier S880DB�AJBL 305P MKII�ł����O�҂͂�����Ȃ��悤�ł����A�����Ԃɂ͕s�����Ō�҂͏���������炵���ǂ�����w���ɂ͎����Ă��܂���B
�Ƃɂ����u����������Ȃ��v�A���ɒ������N���A�ȋ@������߂Ă���܂��B
![]() 3�_
3�_
���`����������
����ɂ��́B
�t�������W�X�s�[�J�[�ŃE�b�h�R�[���X�s�[�J�[�́u�r�N�^�[�̃E�b�h�R�[���v���v�������т܂����B
�������Ă݂ĉ������B
��ʂ��ǂ����t�������W�X�s�[�J�[
���Ȃ��A�����[�����E�b�h�R�[���X�s�[�J�[
�R���p�N�g��PC�I�[�f�B�I�ɂ��ǂ��Ǝv���ē��e���܂����B�i��������������ĉ������B�j
���炵�܂����B
�����ԍ��F22973786
![]() 6�_
6�_
���͌l�̍D�݂ɍ��E����܂��B�Ƃ���X�s�[�J�[���w���������Ɏ����̕�����
�W������Ă��鏈�Ƃ͑S���Ⴄ�����o��̂����ʂł��B
�����̍D�݂ɍ����l�ɁA�ݒu�ꏊ�A�ݒ肷��̂��X�������ƁB���̕����X�s�[�J�[�ɂ��������킭�Ǝv���܂��B
�ݒu�ꏊ�A�ݒ�Ȃǂł܂�ň���ĕ�������ꍇ���L��܂��B�����̕����ŕ����ƌ������͂��̕����̉����Ǝv���Ă��������B
�����̎���M���ă`�������W����̂��ʔ����B�������ǂ�ȉ��̌X�������߂Ă���̂���������܂��B
�����ԍ��F22973793
![]() 6�_
6�_
���`���������� ����ɂ���
�R���p�N�g�^�C�v�͔��̑傫���Ɍ��E�����邽�߂��A������^�C�v���������܂����A���̒��ł��������߂�
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000778152_K0000793812&pd_ctg=2044
�ł��B
����ł�������Ȃ�e�[�u����X�^���h�Ƃ̊ԂփX�y�[�T�[�ł��傤���B
�X�ɂ̓o�X���t�|�[�g���ǂ��Ƃ��B
�������Ȃ����Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F22973813
![]() 1�_
1�_
���Ȃ�߂��j�A�Ȃ̂�DAC�Ƃ��A���v�g�킸�ɃX�s�[�J�[����������PC�p�̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�������̂ł���ˁB
�Ⴆ��GX-550HD�͂ǂ��ł��傤���H�t�����g�o�X���t�ŕi���ɒ�]����ONKYO�Œቹ�]���ɂ��Ă������̂ł����炸�ɒ��������B
�����ԍ��F22973861
![]() 3�_
3�_
���`����������
https://kakaku.com/item/K0000833784/
�������߂��܂��B
���̃X�s�[�J�[�́A�Ɠd�̔��X�Ŏ�����������ł́A�T�C�Y�̊��ɂ͒ቹ���L���ŁA������������ɏo�Ă��܂��̂ŁA���Ȃ��Ǝv���܂��B
���݂ɁA�f�W�^���A���v�Ȃ̂ŏ���d�͂����Ȃ߂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22973880
![]() 5�_
5�_
���`����������
�����́B
�n�m�j�x�n�̕��������ł��ˁB
�g�p���Ă���킯�ł͂Ȃ��ł����A
�N���v�g����KS-1HQM �Ȃǂ��ł��傤���ˁB
�����ԍ��F22973882
![]() 5�_
5�_
���`����������
�X�s�[�J�[�͍ގ��ʼn������Ȃ�ς���Ă��܂��̂ŁA�����Ԏg�p����Ȃ�A�P�@��ɍŒ�R�O���ʂ͎������ĉ������B
�����Ȃ��܂�ŗ��������Ȃ��ƁA�{���̐��\���A���f�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�Ⴆ�A�A���~�n��SP���Ɛꖡ�͗ǂ��ł����A����Ƃ�������܂��̂ŁB
�j�A�t�B�[���h�ł�����X�s�[�J�[�̍ގ������f�̈�v�f�Ƃ��Ē��ڂ��Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F22973891
![]() 5�_
5�_
�������{���i���ȁB
�Z�������l���������C���i�b�v�B
�I���L���[��t�H�X�B
�܁A��Ԃ�SHOP�ŕ����Č���H���������ˁA
�����ԍ��F22973892�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�`����������A������
������������Ȃ��A�������N���A
�E�b�h�R�[���̃t�������W�����씠�ɓ��ꂽ�炢�����ł��傤���H
ParcAudio 10cm�t�������W DCU-F121W
�E�b�h�̓}�C���h�����A�l�b�g���[�N�Ȃ��̂ŃN���A�ł��B�]�����\�Z�Œ��f�W�A�����ґ�DENON��DAC�t���v�����C������������
�����ԍ��F22974052�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
�V�X�e���g�[�^����8���܂łȂ̂��A�X�s�[�J�[������8���̗\�Z�Ȃ̂��E�E�E�E�E�ǂ����H
�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�̏ꍇ�ɂ́A�X�s�[�J�[�{�A���v���Z�b�g�ɂȂ��Ă�킯�ł����A�p�b�V�u�X�s�[�J�[�͕ʂɃA���v���K�v�ł��B
�Ȃ̂ƁAPC���特�y�M�����ǂ�����Ď��o���̂��E�E�E�E�E�E�ł��ˁB
����ƁA305P MKII������������Ƃ̂��Ƃł����A�ǂ������������ŕ����ꂽ�̂ł��傤���H
������E�E�E�E�Ƃ����̂��A�ǂ������A��Ԃ��w���Ă���̂��悭�킩��Ȃ��̂łȂ�Ƃ��ł��E�E�E�E�E�E�E�E
�����ԍ��F22974139
![]() 5�_
5�_
�R�����g�ɂ������@����P�Â��ׂĂ��܂����A�o�͂�PC�̃}�U�{����ADAC�A�A���v�Ȃǂ̓A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�̂��g�����Ǝv���Ă��܂��B
���y�ӏ܂��ړI�Ƃ��܂����A�h���}��A�j����������ɂ���킯�ł͂Ȃ��Ƃ͂������W�I�Ƃ��j���[�X�ȂŒj���̐����ڂ₯���肷��̂͌��ł��ˁB
���Ăɒ����ɂ͒������[�����Ă��邱�Ƃ��厖�Ȃ�ł��傤���H
�����̋@���I����͐����������Ă܂����Ƃ������Ƃ�����̂ł����H
�����ԍ��F22974561
![]() 0�_
0�_
���y����X�^�W�I�A�X���[�����j�^�[�X�s�[�J�[�i�A���v�����X�s�[�J�[�j
https://www.ikebe-gakki.com/ec/srDispCategoryTreeLink/doSearchCategory/11073c00000/04-05/3/1?sonotaBrandFlg=1
USB�A���f�W�^�����͕t�������邩��
�A�i���O���͐ڑ��R�l�N�^�`��͊m�F�K�v
�I�[�f�B�I�V���b�v�ł��ꕔ��舵������
ADAM�AFOCAL�͍����̂�EVE Audio��������
�����ԍ��F22974791
![]() 5�_
5�_
���͂悤�������܂��B
����������Ȃ������k�P���ǂ��A�X�s�[�J�[�̉����ꂪ�ǂ��B�ł���A�X�s�[�J�[����̓K�x�ȋ������K�v�ɂȂ�̂��ȂƎv���܂��B
����Ƃ�����Ƃ����̉��̂�����(?)������܂���Ɖ���������Ɋ�������A�������Ē����Ԃ̃��X�j���O�͔����������肷��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�A�N�e�B�u���j�^�[�ł����A
https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/hs_series/index.html
MSP�V���[�Y���ǂ������ł����A�R�`�������ɋ�������ƋX�������Ǝv���܂���B
�����ԍ��F22974932�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
KS-1HQM��DAC�����ŃN�I���e�B���������Ȃ�ł����A�ǂ����̂قǁu�����ʒu�̍L���v��u������ꂵ�Ȃ��v�Ƃ��������Ƒ������邱�Ƃ��뜜���܂��B
�P�̂�USB-DAC�i�o�X�d���̈����Ȃ��̂ŏ\���j�����ނ��Ƃŏ��^�̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�̑I�������L����i�e���r�p�̈������̂ł��ǎ��Ȃ��̂͑����j�̂ŁA�����������@����������Ă͂ǂ��ł��傤���B�����d���Ȃ珬�a�̃t�������W���ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22975379�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�R�����g�������������X�A���肪�Ƃ��������܂��B
�ǂ��I�炢���̂��킩�炸�����ł����A��ʓI�Ɏ��R�Ȍ`�Œ����悪�L���ł���ƒ�����ꂪ���ɂ����̂ł��傤���H
������̂͂܂��G�[�W���O�O��������X�s�[�J�[�ŗL�̖�肾�����蔻�f������ł��ˁB
�����ԍ��F22975480
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂Ɂ@�X���傳��́A������ꂵ����������̂ł��傤���H
���́A�������̃N���A�ȉ��ŕ�����ꂷ��Ƃ������܂�����A���\���������������o����Ă邩��
�����ԍ��F22975628
![]() 2�_
2�_
���`����������
>��ʓI�Ɏ��R�Ȍ`�Œ����悪�L���ł���ƒ�����ꂪ���ɂ����̂ł��傤���H
���邩���Ȃ����́A�̂̌��N��ԂɈ�ԍ��E����܂�����A�X�s�[�J�[�I�тŔY�ނ����A���N�Ǘ��̕������ɏd�v���Ǝv���܂��B
�����������߂����X�s�[�J�[�́A���������Ď��̎�ςŗǂ������Ǝv���Ă�����̂ł����A���ɂ́A���������Ƃ��Ȃ��X�s�[�J�[��i�߂ė�����A��������_�C�ʼn����t���Ă����������悤�Ȃ̂ŁA�X�s�[�J�[�I�т́A���ۂɓX���ŕ�����ׂ�̂���Ԃ��Ǝv���܂���B
����ƁA���͎��������������A�P�[�u���̈Ⴂ��G�[�W���O�̈Ⴂ�ɂ�鉹�̈Ⴂ�͊m���ɂ͕�����ׂ��Ȃ��ł����A�X���Œ����ԓW�����Ă���X�s�[�J�[�́A�G�[�W���O���o���Ă�����̂ƍl���Ă����̂ł͂Ȃ��ł����B
�����ԍ��F22975629
![]() 4�_
4�_
��:���������Ƃ��Ȃ��X�s�[�J�[��i�߂ė�����A
��:���������Ƃ��Ȃ��X�s�[�J�[���������߂���A
�����ԍ��F22975637
![]() 2�_
2�_
���`����������
�u�������v�̗v�f�͂��ꂼ�ꂾ�Ǝv���܂��B����̑ш悪�����������A�𑜓x���������č�ƂɏW���ł��Ȃ�������A�����̉��̗�����肪�s�߂�����ȂǁB�܂��A���\�Z���������Ȃ̂őI���̕����L�����܂��B�������̒����Ȃꂽ�������Ɠd�X�ȂǂɎ����čs���ėl�X�����Ă݂āA�ڑ����@��ݒu�X�y�[�X�Ȃǂ��l�����Č��߂�̂��������Ǝv���܂��B
���Ȃ݂Ɏ��̎������iPC�j�A�t�B�[���h�j���ƁA
�X�s�[�J�[�F���}�nNX-50�i�A���v�����j�EUSB-DAC�F�t�H�X�e�N�XHP-A4�@�ł����A
�����撆�S�ŏ��ʂ͍T���߂Ȃ���A���Ȃ�N���A�Ń{�[�J���Ȃǐ��X�����������o��̂�PC�j�A�t�B�[���h�ɂ͏\���ł��B���������u�����Ɗ���ɔ��˂��ċC����������w�����������̂ŁA�����ȃX�s�[�J�[�X�^���h�ɍڂ��Ď������Ɍ����Ă��܂��B
���͋C��I�[�f�B�I�I���������߂�Ȃ���������傫�߂̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[���A�X�y�[�X�ɗ]�T������g���������߂�Ȃ�DAC�����A���v�{�p�b�V�u�X�s�[�J�[�ȂǁA���l���̂��\�Z�ŐF�X�I���ł���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22975795
![]() 2�_
2�_
���`����������
�����N���v�g����E�߂܂��B
�ꎞ���g�p���Ă܂����B�꒮�̉��l����ł��B
�ӊO�ƃe���r�̗��[�ɒu���Ă��ǂ��ł���B
KS1-HQM
�����ԍ��F22975849�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�������ɂ��āA�ȑO�̓��[�J�[���f�X�N�g�b�vPC�ɕt�����Ă�����r�I�����ȏ��^�X�s�[�J�[��15�N���炢�g���Ă��ĉ��K�ł����B
���̌�ɔ������X�s�[�J�[���^�C�g���ʂ�ɍň��������̂ŃX�������Ă����Ă��������܂����B
�������N���A�ɂȂ�Ɣ��₷���Ȃ�Ƃ����̂͏����ł��������������Ƃ�����̂ł��ˁB�B
�w�����������@����ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����̂��Ƃ������܂��B
���������߂�Ɛv��ǂ����Ă��w�����������Ȃ�X��������̂ł��傤���H
������Ƒ̂����Ƒ傫���������ω�����̂��X�g���X�ł��B
���}�nGX100HD�AFostex��PM3~4�����肪���̂�����o�����X�������̂ł��傤���H
�j���[�X�Ƃ��h���}�Ől�̐������ĂŎw�����������Ȃ��A�ቹ��ȊO�͂���Ȃ�ȏ�Ƃ������悤�ȃX�s�[�J�[�͂Ȃ����̂ł��傤���ˁB
�����ԍ��F22976479
![]() 1�_
1�_
���`����������
�A���v���K�v�ȁA���̃W�������̃X�s�[�J�[�ŗ\�Z��
8���~�܂ł�PC�T�C�h�Ȃ�AELAC BS302
�͂ǂ��ł��傤���B
�����͎������Ė����̂Œ�����ꂷ�邩�͕s���ł����A�j�A�t�B�[���h�ŃI�[���W�������̋Ȃ��̂ɂ͖��Ăȉ��ŗǂ������ł����B
�����������̃A���v��DENON DRA-100�ł�����
�\�Z�Ɏ��߂�Ȃ�A���v��PMA-30��KENWOOD KA-NA7�ɂȂ�̂��ȁB
�\�Z��������ł��I�[�o�[���Ă悢�Ȃ�A�G��NetAudio No35�ɂ��A���W�̋L��������
KEF LSX��KRIPTON KS-9Multi+�̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[���l�i�����̉��̂悤�Ŕ��ɗǂ������ł��傤�ˁB
�����ԍ��F22976682�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�₵�����͂��Ȃ������D�݂̐l������̂�
���������Ƃ������Ă��Ȃ��Ă�
�����������߂�̂��ʏ�
�y��X���܂ޔ̔��X���߂��ɂȂ��̂�
�����͖����Ȃ疳����
�����ԍ��F22976833
![]() 3�_
3�_
�߂������ŏ����ȉ��ʂŒ����̂Ȃ� JBL Pebbles �͂ǂ��ł��傤���B
https://kakaku.com/item/K0000565941/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
���͂��̃X�s�[�J�[���g���Ă��܂����A���̉𑜊��ɋ����܂����B
�킸��5000�~�̃X�s�[�J�[�Ƃ͎v���Ȃ��N���A�ȉ��ł��B
�ł��ABGM�I�ɒ����ɂ́A�����ƃE�H�[���ȉ����̂ق��������̂�������܂��B�B�B�B
PC�ƃf�W�^�����������炩������܂��A�Ƃɂ����܂�̂Ȃ����ݓn�������ł��B
���܂܂ł́ABOSE��Companion2���g���Ă����̂ł����A��������ቹ�������ăN���A���������������ł��B
�����A�ŏ��͏����V�����V���������������C�ɂȂ����̂ł����A�G�[�W���O���i�̂��A�܂��͎������ꂽ�̂��A���͂��̓��������ƂĂ��S�n�悢�ł��B
���̂�����͊F���ł��B�ቹ�͒Ⴂ�ق��͏o�܂��A���ቹ���K�x�ɏo�ĐS�n�悢�ł��B
�����܂ł��f�X�N�g�b�v�ŏ��`�����ʂŒ������Ƃ�O��Ƀo�����X�����Ă��܂��̂ŁA�剹�ʂɂ����獂���������Ă��邳���Ȃ�܂��B
�T�C�Y���������Ďז��ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�������̂��鉹���D���Ȃ炨�����߂ł��B
�����ԍ��F22976934
![]() 3�_
3�_
��taka0730����
�w�����͂ǂ��ł����H
�ƂĂ��L���ǂ̊p�x���璮���Ă������ł��傤���H
�����ԍ��F22977074
![]() 1�_
1�_
���`����������
������ꂵ�Ȃ����ƁA�w�����������߂̂悤�ł��̂ŁA�҂�����̃��[�t�F�f�[���@�_�C�������h10.1������܂��B
https://kakaku.com/item/K0000124787/
�摜�̃`�F�X�^�[�̗��[�̃R���p�N�g�ȓz�ł��A����͍ŏ��ݒu�������̉��͋����܂����A�����̂����������������ɍL����܂����B
�������ǂ��ŕ����Ă���肭��������̂ł��B
�����A�E�[�n�[�̃Z���^�[�֎�t����Ă鉹�������Y�����̓��������Ă邩�Ǝv���܂��B
�W���Y�Ȃ̔��͂͑傫�ȃX�s�[�J�[�ŕ����A�����{�[�J����N���V�b�N�͂����ς�10.1�̏o�Ԃł��B
�܂��A���̂�����͊����܂���B
�����ԍ��F22977277
![]() 1�_
1�_
���ǂ̊p�x���璮���Ă������ł��傤���H
�u�ǂ����v�̍��ڂ̈ꕔ�ł��鉹����ʂ�𑜊��Ƃ����������͕K�v�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł����ˁB��ʓI�Ɂu�������v�Ǝv����X�s�[�J�[�Ƀj�A�t�B�[���h�ł����]�ނ͓̂���Ǝv���܂��A���������Α傫���p�x���ς��̂ŁB
�����Ȃ��Ă���ƁA�����������̂����v�������т܂���B
MONITORAUDIO�@i-deck�@�F�@http://www.hifijapan.co.jp/i-deck.htm
i-deck��3.5mm�A�i���O���͉\�ł��B���̏ꍇ�ʓrDAC���K�v�ł�i-deck100��iPod���ڂ��Ē����܂������A�_�炩�������ɖ�܂��B���R�Ȃ��特���͒�ʂ��܂���B
���Ƃ́A�e���r�p�̃T�E���h�o�[���ǂ��Ǝv���܂��B�w�������L������Ă���͂��Ȃ̂ŁB�l�̐��������₷���ł��傤�B
https://kakaku.com/kaden/home-soundbar-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec301=2
������ɂ��Ă��킴�킴���X�j���O�|�C���g�����炵�Ď������Ă���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���Ђ������ŐF�X�����ɍs����邱�Ƃ������߂��܂��B
�����ԍ��F22977302
![]() 4�_
4�_
�X���傳��A�Ԕ����Ȉ��͖������Ă��������ˁB
�w�������C�ɂ���Ȃ�A����Ȃ̂͂������H
SONY LSPX-S1
https://www.sony.jp/active-speaker/products/LSPX-S1/index.html
360�x�ǂ��ł������ł��B
�����ԍ��F22977384
![]() 5�_
5�_
������������
���҂�����̃��[�t�F�f�[���@�_�C�������h10.1������܂��B
����̓p�b�V�u�X�s�[�J�[�ł���B
�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�ł͂���܂���B
�X���傳��̗v�]�𗝉����悤�Ƃ������A���S�҃}�[�N���t���������N�`�R�~���e�������Ȃ��ăI�I�J�~���N�Ƃ������Ƃ�m���Ă��Ȃ�����҂�_���ł����Ă���̂��o���o���ł��B
�����ԍ��F22977397
![]() 11�_
11�_
�����Y��܂������ADiamond10.1�ɂ̓A���v�������Ă܂���̂Ńv�����C���A���v�Ȃǂ̃A���v���K�v�ł��B
https://kakaku.com/item/K0000376679/?lid=20190108pricemenu_hot
��x�A���v���Ă����A����X�s�[�J�[�I�тɂ����ŏo���A�����̒����炨�I�тł��܂��B
�X�s�[�J�[�P�[�u����OFC(���_�f���j�̂��̂�200�~/M���x�̂��̂ł����ł��傤�B
�����ԍ��F22977412
![]() 1�_
1�_
�`���������� ��
�h���̓A���v�����̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�h
�Ə�����Ă���̂ɁA���[�t�F�f�[���@�_�C�������h10.1���āA�A���v�����ł͂Ȃ����A���Âō\��Ȃ��Ȃ炢���m�炸�A���Y�����i��E�߂Ăǂ�����낤�E�E�E (��)
�����ԍ��F22977434
![]() 7�_
7�_
���`����������
�_�C�\�[�̂R�O�O�~�X�s�[�J�[�͂������B
�ቹ�͏o�Ȃ��̂ł�����܂���B
�����ʂȂ�N���A�ȉ��ł��B
�����ԍ��F22977437
![]() 7�_
7�_
�`����������
���l�̂��Ȃ����d�������ł̗��p�́Akinpa68�����߂̃X�s�[�J�[��������A���l�̂��邨�d�������Ȃ�A�R�s�X�^�X�t�O�����߂̃l�b�O�X�s�[�J�[���ǂ��̂ł́H
�g�p���ʼn��K�����ς��ł��傤���A������x�Ë����K�v���ƁB
���������Ƀl�b�g�Ń|�`�́A�M�����u���ł��B
�����ԍ��F22977489�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�w�����Ƃ����Ă��A�t�������W1�{�̃X�s�[�J�[�͂ǂ���������炢���Ǝv���܂����E�E�E�B
https://review.kakaku.com/review/K0000565942/ReviewCD=1221402/ImageID=476825/
���̃X�s�[�J�[�́A������̉摜�̂悤�� ���j�b�g����50�x��������ĕt���Ă��܂��B
���A�l�b�g���O�ʂɂ���̂ŁA�w�����͂���Ȃɉs���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22977510
![]() 3�_
3�_
���`����������A����ɂ���B
������������Ȃ��A�����Ԕ��Ȃ��X�s�[�J�[��T���Ă��܂��B
�ω����𓊂������Ă��������܂����ABOSE�̓_���ł����H
�Ⴆ�ACompanion 20 multimedia speaker system �Ȃǂ͂������ł��傤���B
https://kakaku.com/item/K0000277477/
�ƌ����Ă݂͂����̂̏���BOSE�T�E���h�Ȃ̂ōD�������͂��邩�Ǝv���܂����O�O�G
������������
�����ۂ������ł��B�r�炵�͂�߂܂��傤�B�����̌f�����p���[���Ɉᔽ���Ă��܂��B
�������ݔԍ�22973813��22973861��22977277��22977412
���X���b�h�̎�|�ɔ����܂��B�X���b�h�̎�|�Ɩ��W�Șb��͂��T�����������B
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=AR001
�����s���������������f���Ō��܂��傤�B
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR005
���N�`�R�~�f���͗l�X�ȕ������p����R�~���j�e�B�T�C�g�ł��B���ۂɏ�������ł���l���������ł͂Ȃ��A�����̐l���{�����Ă��邱�Ƃ�Y��Ȃ��悤���肢���܂��B���g�̓��e�ɂ͐ӔC�������܂��傤�B
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR008
�����ԍ��F22977516
![]() 12�_
12�_
���`����������
����setting�O���active(powered)�Ƃ������Ƃ�Audioengine���i���s�b�N�A�b�v���Ă݂܂������A�ǂ�Ȃ��̂ł��傤��?
https://www.pcmag.com/roundup/303628/the-best-computer-speakers
https://www.amazon.com/Audioengine-Active-2-Way-Speakers-Black/dp/B005OA3BSY?th=1
https://www.amazon.com/dp/B01K5LI1Y0/ref=emc_b_5_t
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81%E3%80%91Audioengine-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3-A5-%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%BC/dp/B07HNLD5GX?th=1
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81%E3%80%91Audioengine-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3-A2%EF%BC%8B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-Bluetooth-aptX%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%BB24bit/dp/B07RWHTDYX?ref_=ast_bbp_dp
�����ԍ��F22978857
![]() 2�_
2�_
�����̂��ӌ��A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B
�S�Ă̕��ɕԎ��ł��Ȃ��Đ\����Ȃ��ł��B
�����������ӌ������ɒ��ׂ܂����Ƃ���I�[�f�B�I�G���W����A2+��JBL Pebbles���ł��t�B�b�g����悤�ő����ƍl���Ă��܂��B
���R�Ƃ��܂��Ă͏��^�ł��邱�ƁA�i����Pebbles�͉��u�������Ȃ��j�A�N���A�ȃT�E���h�A���r���[�ł̕]���������B
���O����_��A2+�͎w���������Ȃ苷���炵���ݒu��̐��������ƁAPebbles�͓���DAC���ᐫ�\�Ŋ��҂ł��Ȃ����Ƃƃz���C�g�m�C�Y������炵�����ƁB
���҂͉��i������܂����A�ꉞ�\�Z���ł��B
���R�s�X�^�X�t�O����
KS-1HQM�͈�Ë@�탁�[�J�[�H���A��T�C�Y���傫���A����������炵���A�����i�̊���Ƀt�������W�Ɛ����ǂ���ۂ͂���܂���B�܂��T�E���h�o�[�A�l�b�N�^�Ȃǂ������̊��ł͍����Ă܂���B
�O��DAC���痬���ƃ`�[�v�ȃX�s�[�J�[�ł����Ȃ艹�����ǂ��Ȃ邱�Ƃ�����悤�ł��ˁB����DAC�̓����͂܂��m�����Ȃ��̂őz�肵�Ă��܂���B
��taka0730����
�w�����̓��C�o�����i�Ɣ�ׂ�ƌ��\�L�߂Ȃ悤�ł��ˁB
Pebbles�ɂ��Ĉ�_�����Y�ꂽ�̂ł����j���[�X�A�h���}�A����Ȃ̂ŒႢ�j���̐��̓N���A�ɒ������܂����H
���]�ː�R�i���R�i������
Bose��M2���T�C�Y�I�ɂ͋C�ɓ������̂ł����A�A���А��i���ʂʼn���������A������Ă���A���L�̋�������Ƃ����]���������c�O�Ȃ�����O�Ƃ��Ă��܂��B
���ɂ�FostexPm3n�Ƃ��]���̍����̂�����܂����A�ǂ������܂����Ȋ����ł����B
�����ԍ��F22979950
![]() 0�_
0�_
Pebbles�͂��������f�W�^���M�������̃X�s�[�J�[�Ȃ̂Ńm�C�Y�ɋ����\���ł��B
�{�����[�������Ȃ�グ�Ă݂܂������A�m�C�Y�͊F���ł����B
�f���h���}�͂��܂茩�܂��A��������ϖ��ĂȂ̂Œj���̐������Ȃ��Ǝv���܂��B
BOSE��Companioin2�i�U�^�j�͎����Ă��܂����A������̓A�i���O���͂̉������ǂ���ΐM�����Ȃ��������ɂȂ�܂��B
�ł�PC�̃A�i���O�o�͉͂��������܂�悭�Ȃ��̂ŁA�{���̎��͔͂����ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
CD�v���[���[�����đ剹�ʂŖ炵���炷�炵���������܂��B
�����ԍ��F22980198
![]() 3�_
3�_
��taka0730����
���肪�Ƃ��������܂��B
�f�X�N�g�b�vPC�Œ�A���`�����ʂŃj�A�t�B�[���h���X�j���O�Ȃ�A2+�͐��\�����ė]��������Pebbles�ŏ\���ł��傤���H
�ቹ�d���A�剹�ʂ݂����ȏ����Ȃ�ς���Ă���悤�ł����E�E�A������͂Q���~�ȏ㍂���̂Ǝw�����������APebbles�͂��̓_�A�h�o���e�[�W����܂���ˁB
���ʂ����`���ł������������قǂ����Ⴄ���E�Ɋ�����Ƃ����Ȃ�ʂł����A�A�i�����̎��Ŕ��ʂ����^��j
�����ԍ��F22980804
![]() 0�_
0�_
A2+�Ƃ����̂͂悭�m��܂���ł����BAudioengine�Ƃ����̂́A�ǂ��̍��̃��[�J�[�ł��傤���B
�����̂ŁA����Ȃ�ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����A���`�����ʂł͂ǂ������]���ɂȂ邩�킩��܂���B
�����̂ōŏ��� Pebbles���āA�����C�ɓ���Ȃ������烁���J���Ŕ����āAA2+���Ă݂Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F22981244
![]() 2�_
2�_
��taka0730����
��A2+�@Audioengine
�č��̃��[�J�[�ł��ˁB���{�̃��r���[���̏��Ȃ��ł����������Ŋ֘A�܂�����Ă���A�}�]������3���̃��r���[���荂�]���ł��B
���\����DAC�������Ă�悤�ł��B�e�L�T�X�C���X�c�������c�̂Ȃ����ȁE�E
�j�A�Ȃ�\�͎��ė]�������ł��������悤�Ƀy�u���X����͂��߂Ă݂�ׂ��ł����ˁB
�M�d�Ȃ��ӌ����ӂ������܂��B
�����ԍ��F22981271
![]() 0�_
0�_
JBL Pebbles�w����A�����Ԏ������܂������A�N���V�b�N�Ȃǂ̑��d���t�≹�����j���̐��͈����Ȃ��̂ł����A�|�b�v�X�Ȃǂō����A�{�[�J�����O�ɂłȂ��Ƃ��������ɕ���ł銴���ł������Ă���̂ł���ˁB�{�[�J���������Ƃ�������N���A�ɂ��������Ǝv���Ă�USB�ڑ��Ȃ̂ŃC�R���C�U�[�̍��������ɂ�������̂��Ȃ��̂ł��B
�G�C�W���O�ɂ����P�����̂ł��傤���H
���^�ʼn��u���ł���͍̂��]���Ȃ̂ł����A���܂̂Ƃ���͎c�O�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B
����ȊO���ƃI�[�f�B�I�G���W����A2+�Ɋ��҂��邵���Ȃ����ȁE�E�B
�����ԍ��F22989426
![]() 0�_
0�_
�G�C�W���O�ŃK�T�K�T���������͎���Ǝv���܂����A��{�I�ȃL�����N�^�[�͓����ł��B
�����d���̃o�����X�Ȃ̂ŁA�����{�[�J���͑O�ɏo�Ă��܂��B
���u���ł͂Ȃ��A�{���͏c�u���Ŏg���X�s�[�J�[���Ǝv���܂��B
���͕ǂ̂Ȃ����̊��̏�ɒu���Ă��܂��̂ŁA������̓[���ł��B
�ǂɋ߂Â���ƒቹ�������Ȃ��āA���������悤�ɂȂ邩������܂���B
�����ԍ��F22989483
![]() 1�_
1�_
��taka0730����
���ߋ����A�c�u������������Ă����ł����A�ڂ₯�邱�����ł���ˁB�C�R���C�U�[�ŕύX���Ă܂����ˁH
�ƂȂ�ƃG�C�W���O�ŕς��̂ł��傤���ˁB
�����ԍ��F22989520
![]() 0�_
0�_
PC�p�X�s�[�J�[��V���������̂ł����A�����̊����Ƃǂ��������^�C�v���K���Ă���̂��A�h�o�C�X���肢���܂��B
�E�X�s�[�J�[�Ǝ����̋����͍ŒZ��70cm�B
�E�X�s�[�J�[�u�����͉���110c���A���s��70cm�B�����̑S��A���s���̔�����i30cm�j�܂ł��X�s�[�J�[�ݒu�\��B
�E���Ɛ��ʂ̕ǂƂ̋�����20cm�i�Ԋu�͋��邪�A��ʒu�Ƃ������j
�E���Ɖ��̕ǁi�Жʁj�͖��ځB�i�Œ�j
�E6��Ԃ̋��i�Œ�j
�E�������y�Đ��݂̂̒ʏ�p�r�B���y�W�������͑��푽�l�B���ʂ͏��`���A���p�x�B�i�剹�ʂ͑S���s�g�p�j
�E�I���{�[�h�̃��C���A�E�g�ŏo�́B�i�T�E���h�J�[�h�AUSB DAC�A���[�q���͗\�薳���j
�E�\�Z��6���~�ȓ��ŁA�O�ρA���쐫�͕s��B
�����Ƃ��Ă͂����܂ł������Ȃ��ł����A�ቹ�`�����܂ł������肵�Ă��Ď��R�Ȃ��̂��ǂ��A
���^��bose companion2�̂悤�ȋ������t�����Ă���i�炵���j�̂͂�����ƁE�E�B
��͏������˂�Ƃ����܂����A��17-20cm���炢�̃u�b�N�V�F���t�^�͋ߋ������ƕs�����ł����H
�����MACKIE CR�V���[�Y�݂����ȃ��A�o�X���t�^�C�v�͂����Ă̂ق��Ȃ̂ł��傤���H�i�ቹ���ǂɔ��˂��ē����Ƃ��j
��12cm�ȉ����œK�Ƃ��Ă������ɓ���肻���ō����i�т͐�q�̋���łƂ�����ɂ������肫�܂���B
![]() 10�_
10�_
��JABOON����
���R�Ȃ��̂ƌ���ꂽ���_�ŁE�E�E�̔����猋�\�o���Ă܂��̂Ń��t�I�N�ł����|���܂��B
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000443921/#tab
�悭�E�߂܂����A�R���ł��ˁB
�\�Z�I�[�o�[�ł��̂ʼn��ʋ@���
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000415558/#tab
������ł��B
�����ԍ��F22969230
![]() 7�_
7�_
��JABOON���� ����ɂ���
���l�̃X����A�����ď������܂�Ă��܂����A�����̗L�v�ȉ��������܂�Ă�ɂ��ւ�炸���u����Ă��܂��B
�����̃��[��������肢�����������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22969357
![]() 2�_
2�_
EVE Audio�̃��j�^�[�X�s�[�J
https://shopping.yahoo.co.jp/search?first=1&dnow=&dtype=&tab_ex=commerce&sc_i=shp_pc_store_searchBox&cid=&p=EVE+Audio
�����ԍ��F22969418
![]() 7�_
7�_
������������
�����l�̃X����A�����ď������܂�Ă��܂����A�����̗L�v�ȉ��������܂�Ă�ɂ��ւ�炸���u����Ă��܂��B
�X���傳��͕��u�Ȃǂ��������ƕԐM���Ă��邵����̌��t���q�ׂĂ��܂��B
�����|����͂�߂������ǂ��ł��ˁB
�������̃��[��������肢�����������Ǝv���܂��B
���[���ᔽ�̏�K�҂����l�Ƀ��[�������ȂǂƐ����Ƃ������̃l�^�������ł����H
�O�b�h�A���T�[�N���N�����Ă����̂����ݏo������Ăđ��ӂ����������ł���B
���l�ɑ��ă��[��������O�ɂ܂��͂����g�����̌������Ȃ݂�ׂ��ł��傤�B
��JABOON����
�����́B
�O�b�h�A���T�[���~���������̃��[���ᔽ��K�҂̌������Ƃ͋C�ɂ���K�v�͖����ł���B
�^�₪��������܂����e���ĉ������ˁB
�ꉞ�A�����̉^�c�����
�u����X���b�h�ł́A�O�b�h�A���T�[�̑I���ƁA�^���g���u���̌����͉��������̂��Ȃǂ̌��ʕ�����ƁA���㓯���^����������l�̎Q�l�ɂ��Ȃ�܂��̂ŁA���Ќ��ʕ����Ă��������B�v
�Ƃ������肢��������݂����ł����ǂˁi�������O�b�h�A���T�[��I���ɉ����ς݂̏��������Ă��\���܂����j�B
�����ԍ��F22969831
![]() 14�_
14�_
���\�Z��6���~�ȓ��ŁA�O�ρA���쐫�͕s��B
�����Ƃ��Ă͂����܂ł������Ȃ��ł����A�ቹ�`�����܂ł������肵�Ă��Ď��R�Ȃ��̂��ǂ�
�S����������莩�R�ɖ炷�A�A�A
B&W800�N���X�̐��\�ŏ��^�ȕ��A�A�A
\6���Ō�����Ȃ玄���~�����B
�����̃X�s�[�J�[�͒ቹ�Đ������ł��A�₤�ׂɍH�v������̂ł����A�X�s�[�J�[�I�т͂����ɂ�閡�t�����A�ے�I�ɑ����邩�m��I�ɑ����邩�ł����Ȃ��Ǝv���܂��B
�h�������̂Ȃ���Ă��Ȃ������ŁA�o�C�I�����ʂɒe�����Ȃ�ߏ����f�ȉ��ʂɂȂ�܂��B
���R�ȉ��Ƃ������t�����ߎ��悾�Ǝv���܂����A�����Ŋy��̉���{���Ɏ��R(���m)�ɖ炷�@�킪����Ȃ�A��Ɋׂ�o�傪�K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
���R�ȉ��ɒ�������悤�ȂƉ��߂���Ȃ�A�����������ƂȂ�A������͎����ȊO�ɔ��f���鎖������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���t�������I�ȉ��ƍl���A���ҕ]���ɘf�킳���O�Ɏ��@�ɐG��Ă݂鎖�����E�߂��܂��B
�ӊO�Ƌr�F���ꂽ�������͓I�Ɗ�������A��ʂ������C�����܂��B
�ǂ����Ă����������ǂ��Ȃ��A�����ɂ������Ȃ����A��������ƒቹ���獂���܂Ŗ���̂��ǂ��Ƃ������ꍇ�́A�w�b�h�z����C���z���Ȃǂ̕�������]�ɋ߂����i�Ɏv���܂��B
���̎���������O�ɉ�������o����Ɨǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F22970321�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
������������
��Έ���܂ޑ�O�Ҍ����̏��ł�����̂�
��̔N��͂ǂ��ł��������A�Ⴂ�z��͏��a���͉��y�i���W�I�j������
�����ԍ��F22970394
![]() 2�_
2�_
��JABOON����
�����d���Ȃ̂���y���d���Ȃ̂��悭������Ȃ��̂ł����A���l�ɂ��ꂱ�ꕷ����育���g�Ŏ��ۂɗ\�Z�͈͓̔��̃X�s�[�J�[��F�X�����Ă݂Ă͂ǂ��ł����H
�Ⴆ�A���A�o�X���t�Ȃ牽�ł��ǂ��狗�����Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł�����܂���B���ɏ��ʂ̏��^�̕��Ȃ�10cm��20cm���炢�����Ώ\���ȕ�������Ǝv���܂��B
�܂��A�ቹ�ƌ����Ă�40Hz���炢�ɂȂ�Ɖ��Ƃ��Ă͖w�Ǖ������܂��A����ʂ̒ቹ���o�Ă���ƃ��C�u�����Ȃǂ̋�C���݂����Ȋ��������\�������Ǝv���܂��B
�������ł������ɂȂ��Ă�����̂ł͂���܂��H
���������߂�Ƃ����������炠���Ă�����܂���B�@
������傫���͐獷���ʂȂ̂ŁA�����g�ŐF�X�����Ă݂�̂��ǂ��Ǝv���܂��B���l���ǂ��Ɖ]�����������ɂ͗ǂ��v���Ȃ������m��܂����B
�����ԍ��F22971105�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��JABOON����
���̕������������ʂ育�����ŐF�X�����Ă݂�̂���ԂȂ�ł����c�A�j�A�t�B�[���h�ł͔�r�I���a�̏��������j�b�g�̕����𑜊���ቹ�̃X�s�[�h�����m�ۂł���悤�Ɏv���܂��B
B&W��M-1�Ȃǂ��ł��傤���H�����ڂ͍D����������Ǝv���܂����A�𑜊����ٗl�ɍ�����������B&W�̐��i�ł��邱�Ƃ��������܂��B�i�T�u�E�[�t�@�[�͂��D�݂ŁB�\�[�X�̗ǂ����������炯�o���܂��̂ŁA���ɑ��ݓ���邱�ƂɂȂ邩������܂���B�j�u���y��������ƒ��������v�p�r�ɂ͌����Ȃ���������܂��B
�����ԍ��F22971374
![]() 2�_
2�_
��JABOON����
����ɂ��́A�����o�X���t�i��둤�Ɍ����Ă��郂�f���j�̏ꍇ�́A
�ǂɗ����˂�������̂�ݒu�����͂��������ǂ��Ǝv���܂��B
�قƂ�Ǘv�]�ʂ�̊��Ŏg�p���Ă��܂��B
�p�\�R�����̉��ʂ͍ő�ɂ��Ă����A�A���v���Œ�������Ɨǂ��Ǝv���B
FYNE AUDIO F300
https://kakaku.com/item/K0001139492/
DENON PMA-600NE
https://kakaku.com/item/K0001182074/
6��8��~�{�X�s�[�J�[�P�[�u��7��~�i�T���V���C���j�ƂȂ�A�\�Z�I�[�o�[�ł��B
PMA-600NE ��3���~�W���X�g�Ŕ������̂ŁA���z7���~�|����܂����B
�傫���T�C�Y�قlj��̏œ_������Ă����̂ŁA4�C���`��5�C���`��ڈ��ɂ��������ǂ��Ǝv���B
�A�N�e�B�u�^�X�s�[�J�[�ł́AEVE AUDIO SC204 �Ȃ�A6��8��~�ŁA�\�Z�I�[�o�[�B
���̃T�C�Y�ł͊����ȃ��t�@�����X�Ƃ��Ďg���郂�j�^�[�X�s�[�J�[�A�S�ш��DSP�Ńt���b�g�ցB
�p���[���傫���̂ő����ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��_����_�ł��B
����2�̃p�^�[�����ō������Ƃ��đz�肵����A�@�\������Ă����A
�\�Z���Ɏ��܂�܂��B�������������K�v�Ȃ��Ȃ�APMA-600NE�łȂ��A
DENON PMA-390RE(SP)
https://kakaku.com/item/K0000376679/
����őO�̍\������15,000�~�������čl������A5��3��~�{�X�s�[�J�[�P�[�u��7��~�ŗ\�Z���B
Bluetooth���͂������Ȃ�̂ŁA�X�}�z�̃��W�I�A�v���������ꍇ�́A���̍\���͒��~�B
�����ԍ��F22971615
![]() 2�_
2�_
��JABOON����
�����͕���17cm�̃N���v�V����R-15M���f�X�N�ɒu���Ďg���Ă܂����A���\�ȑ��݊�������܂��B
�ł���A���̏�ɂ͏��^�̂��̂�I��ő���Ȃ��ቹ���T�u�E�[�t�@�[�ŕ₤�̂���Ԃ����ł��B
�ݒu�ŏd�v�Ȃ͍̂����ł��B���̏ォ��E�[�t�@�[�܂ł̋�����25cm�ȏ�Ƃ�Ȃ��Ɗ��̖ʂ��甽�˂������ƒ��ډ���
�����ĉ��������܂��B���̂��Ƃ͏��ɒu���ꍇ�̒��ӂƓ����ŁA���̂����Ȃ�|���u�����Ă������Ƃɂ�
�Ȃ�܂���B
�X�s�[�J�[���傫���Ƃ���ȍ����ɂł��Ȃ��̂ŁA�X�s�[�J�[���̏�ɂ̂��A����ɏ㉺�t���ɒu�����ƂɂȂ�܂��B
���̂����育���ӂ���������Ǝv���܂��B
�I���{�[�h�̃��C���A�E�g�Ƃ����ƁA�A���v�����^�ɂȂ�ł��傤���B
���̂����߂�ONKYO GX-R3X (2004�N)�ɂȂ�܂��B�����I����Ă܂����A�܂�����͉\�ł��B
�ʔ������ƂɃT�u�E�[�t�@�[�[�q���t���Ă܂��B
�����ԍ��F22972305
![]() 2�_
2�_
�⑫�Ƃ��āA����𓊍e���܂��B
�v�_
�ǂƃX�s�[�J�[�̊Ԃɉ��𗐔��˂���悤�Ȃ��̂�u���i�܂��͍��j
�Ǎۂ̃X�s�[�J�[�͉����o�ɂ����̂ŁA2�����O�ɏo��
USB-DAC���ґ�Ȃ̂ŁA�����܂ł͕K�v�Ȃ�
�����ԍ��F22972348
![]() 1�_
1�_
��JABOON����
���̎g�����Ȃ�A�t���b�g��]�Ƃ������ƂȂ�Ȃ����特�y����p�̃p���[�h���j�^�[�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�Ⴆ�Ή��L�ɂ���悤�ȃ��C���i�b�v�ł��B��ɋ����Ă���}�b�L�[������܂����A���ɂ����j�^�[�ɂ͂�����ŗL���ȃ��[�J�[����������܂��B
https://www.soundhouse.co.jp/search/index?s_category_cd=1106&i_type=c
�t�����g�o�X���t�^�C�v������܂���B
�^���m�C�Ȃ͉��y�ӏ܂ł��]�����ǂ������肷��悤�ł��B
�y�A�Ŕ̔�����Ă�����̂������悤�ł����A�y�A�Ə����Ă��Ȃ����̂�1�{�̒l�i�Ȃ̂ŋC��t���Ă��������B
�Ȃ��A�Ɩ��p��RCA���͂ł͂Ȃ����Ƃ������̂ŁA�ڑ��ɂ͕ϊ��P�[�u�����K�v�ɂȂ邱�Ƃ������Ǝv���܂����A��������T�E���h�n�E�X�Ŏ�ɓ���܂��B
�X�s�[�J�[�ɂ���ē��͒[�q�͈قȂ�܂����AYAMAHA, Tannoy, JBL, Mackie, Presonus �Ȃǂ̗����@��ł�����Phone���́i6.3mm���m�����v���O�j������̂ŁA�Ⴆ�Ή��L�̂悤�ȃP�[�u���������PC�̃��C���A�E�g���獶�E�̋Ɩ��p�p���[�h�X�s�[�J�[�Ɍq����@�킪�������ł��B
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/25906/
�d��SW�͊e�X�s�[�J�[�̗��ɂ����Ėʓ|�Ȃ̂Ń����R���t���d���^�b�v������ƕ֗��ł��ˁB
https://www.amazon.co.jp/�T�����T�v���C-�茳�X�C�b�`�t�������~�߃^�b�v-4��-RoHS�Ή�-TAP-5433N/dp/B000KN8R2U
�����ԍ��F22972663
![]() 2�_
2�_
2019/10/12 16:10�i1�N�ȏ�O�j
�������g���Ă�����̂ł����ǁB�����������肵�����ł��B
DAC�FS.M.S.L Sanskrit 10th
��10,530-�@Amazon
USB�P�[�u���FAnker Powerline(1.8m x 2�{)
��999-�@Amazon
�X�s�[�J�[�FTASCAM VL-S3
��7.905- Amazon
RCA�P�[�u���F���K�~ 2534(1.0m x ���E)
��2000�~���炢�H
�X�s�[�J�[�X�^���h�F�L�N�^�j MO-SPS
��5,097- Amazon
�C���V�����[�^�[�F�R�{�����H�| �S���X�y�[�T�[ GS8
��714�] Amazon
���v3���~��Ȃ̂ŗ\�Z��6���Ȃ珬�^�̃T�u�E�[�t�@�[�Ƃ������Ɨǂ������ł��ˁB����Ƃ��͒ቹ�����⋭�����������͂���܂����B����SN��̗ǂ�DAC�͐�ɉ����������ǂ��ł���B���Ɏh���鉹���o�錴���̓m�C�Y�Ƙc�݂ł�����B
�����ԍ��F22983670
![]() 1�_
1�_
���N�A�p�C�I�j�A��4�c�P�[�u���i2sq×4�j��Б�2m�Ŏg�p���Ă��܂����B
20�N�ȏ�O�ɍw���������̂Ȃ̂ŁA�^�Ԃ͖Y��܂������A�P�[�u���ɂ́uOFC STAR QUAD SPEAKER CABLE PIONEER MADE IN JAPAN�v�ƈ���Ă��܂��B
���̓x�A�������C�A�E�g�ύX�����Ƃ���A�Б���2m�ł͕s�����鎖�ԂƂȂ�A�V���ɃX�s�[�J�P�[�u���̍w�����K�v�ƂȂ�܂����B
���p�̃P�[�u���ɓ��ɕs���͂Ȃ��̂ł����A���ɔp�ԂƂȂ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA���P�[�u�������������������������e���܂����B
���p�P�[�u���́A��R�i���m�ɂ̓C���s�[�_���X�j�~�j�}���ŁA�܂�A���������ŒZ�łƂ����l���Ɋ�Â��đI�т܂����B
���l�̍l���ŁA���L3���i�����ɂ��Ă���܂��B
�E�x���f��8477�F�@AWG12�i3.5sq�j×2
�E���K�~3103�F�@AWG12×2
�E�J���i4S11�F�@2sq×4
��L3���i�ɂ��A���g�p����Ă�����̃R�����g������������K���ł��B
�܂��A��L3���i�ȊO�ł����߂̃P�[�u��������܂�����A���������������B
���i�I�ɂ�1000�~/m�قǂ�ڈ��ɂ��肢�������܂��B
���p�̃V�X�e���́A�p���[�A���v�̓A�L���t�F�[�YP-360 ��P-4500�ɓ���ւ����Ƃ���ŁA�X�s�[�J��JBL2235H�A2426J�{2370A�A�p�C�I�j�APT-R7III���g�p��������V�X�e���ł��B
�܂��A�ڑ��̓o�i�i�v���O��Y�v���O�͎g�p�����A�S�����A���v����уX�s�[�J�̒[�q�ɑ}�������ߕt���Ă��܂��B
![]() 5�_
5�_
��bebez����
����ɂ��́B
�����ȃV�X�e�������L����Ă���悤�ŁA�����܂�������ł������܂��B
���L�͂��Ă���܂��A�x���f���ӂ�͕]�����ǂ��Ɗ����܂��B
�ǂ����ʂ��o��Ƃ����ł��ˁB�����X�^�[�P�[�u���Ȃ�Ă̂����݂���悤�ł����B�B�B
�����ԍ��F22962428
![]() 4�_
4�_
��bebez���� ����ɂ���
�������̒���Belden8477�͎g���Ă��܂��A���̓N���A�ő��������Ƀp���[��������A�X�s�[�J�[JBL 4318���O�C�O�C�炵�Ă���܂��B
�摜�̉E���̏��Ɏʂ��Ă��܂��A�O���[�̔핢�̂�ł��A�o�C���C�A�����O�Œ������p��8470(�����j�ł��B
�������o�i�i��Y�͎g�p�����A�����߂ł��i�َ�����̐M���ʉ߂��������߂ł��j�B
�A���v�̓}�b�L���g�b�V���̃v�����C���ł��B
���K�~�A�J�i�����]���͍����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22962483
![]()
![]() 2�_
2�_
��bebez����
����ɂ��́B
���͂����ƒႢ���x���Ȃ�ł����A�]�m�g�[���̐��F�̃P�[�u���g�p���Ă��܂��B
�P�O�O�O�~�^���Ƃ������Ƃɔ������ē��e���܂����B
2200����1500�~���炢�ŁA1500��900�~���炢�ł��B�i�A�}�]���Ȃǒʔ̂̉��i�ł��j
�P���łȂ��āA�F�X�Ȑ����g�ݍ��킹�āA�n�C�u���b�g�ȉ�����ڎw���Ă���^�C�v�ł��B
�]�m�g�[���Ō������Ă݂ĉ������B
�P�O�O�O�~�łȂ��ĂP�O�O�O�O�~�ł�����X���[���ĉ������A���炵�܂����B
�����ԍ��F22962484
![]() 4�_
4�_
���h�b�h�R���b�c����
�����̂��ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�S�������Ă��������āA�������v���܂��B
������������
�����A�h�o�C�X�������������肪�Ƃ��������܂��B
�x���f��8477�����g���Ƃ̂��ƁA��ώQ�l�ɂȂ�܂��B
�ʌ��ł����A�ȑO�A�h�o�C�X�������������Z�J���h�X�s�[�J�p�̃A���v�ł����AA-50DA���w�����܂����B
�Ȃ��Ȃ��̋쓮�����͂ŁA���S���Ă���܂��B
�ʓr�A���r���[�ɓ��e�������Ǝv���Ă��܂��B
��cantake����
���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
���A����20�N�قǃI�[�f�B�I�����x�݂��Ă����̂ŁA�P�[�u���̒m���̓[���ɋ߂���Ԃł��B
�����Ō������Ă݂��Ƃ���A�^����ɏo�Ă����̂������߂���������2200���ł����B
�]�����ǂ��悤�ł��ˁB
���i�I�ɂ͎˒����ł����A2sq×4��5500�����Ƃ�����ƍ������邩�ȂƎv���Ă���Ƃ���ł��B
�V���b�v�ł̃P�[�u���̎����Ƃ����̂͂��܂茻���I�łȂ��̂ŁA�X�y�b�N�����R�~������ł��B
�u�����P�[�u�����ŒZ�Łv�Ƃ����̂́A�����Ɍ̒����S�j���ɉe������Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22962600
![]() 1�_
1�_
��bebez����
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
�����Z�J���h��A-50DA���g���Ă܂��B�P�[�u�������S�҂Ȃ�ł����A�e����̏��x�Ƃ��ޗ��ɂ���ĉ��i���Ⴄ�悤�ł��B
����Ӗ��ʼnߌ��Ȕ̔��X�u�v���P�[�u���v�����HP�Ȃ��P�[�u���ɂ��ĐF�X�����Ă����Ėʔ����ł��B
���炵�܂����B
�����ԍ��F22962653
![]() 4�_
4�_
���X�s�[�J��JBL2235H�A2426J�{2370A�A�p�C�I�j�APT-R7III���g�p��������V�X�e���ł��B
�E�[�n�[BOX�̃T�C�Y�͂ǂꂮ�炢�E�E�E�E�}���`���Ȃ���ł����E�E�E�E�ƁA����Ƃ͈Ⴄ�����ɋ����ÁX�ł��B
�܂��A����͒u���Ƃ��āB
���ɂ����Ă���X�s�[�J�[�P�[�u���͂ǂ���u��ԁv�Ȃ̂ŁA�ǂ�ł��ǂ��Ǝv���܂��B
�l�I�Ȏ�Ō����A�x���f���͈�ʓI�ɂ͕Ȃ��Ȃ��Ƃ��A�t���b�g�Ƃ����Ă���̂ł����A������Ƌ^��B
�J�i���́A��Ԓ��̒�Ԃł����A�P�[�u���\�����ǂ��ł����A���Ă݂�ƒl�i����͍l�����Ȃ��o���̗ǂ��������܂����A��݂�����������܂��B
���K�~�́A������Ɖ����אg���Ȃ��Ǝv���Ƃ���͂����ł����A�𑜓x�������B
������ƃ}�C�i�[�ł����A�J�i���̂SS11�ƂقƂ�nj����������Ȃ��̂ł����A����d����T�SS11�Ƃ����P�[�u���������߁B
�قڂقځA�J�i���Ɠ����Ȃ�ł����A����܂肪�������Ȃ��Ƃ����C�����܂��B
�P�[�u���́A���������̑���������u�����v�Ȃ�Ȃ�ł�������Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂��B
����Ȃ�A������Ƃ������t���Ƃ��������̃V�t�g�͂�����ł��ł��܂�����A�𑜓x�d���Ń��K�~���ȂƂ͎v���܂��B
�����ԍ��F22962697
![]() 5�_
5�_
bebez����A�����́B
������ꂽ���ł́A���i�������Ƃ������R�ŃJ�i���������߂��܂��B�u���������ŒZ�Łv�Ƃ����l�������͐������ɂ͐������ł����A�����������x�Ȃ�z�[���Z���^�[�̈����ł����イ�Ԃ�Ȉʂł��B
���R�Ȃ���A�̔��X�Ȃǂ̋ƊE�W�҂͏�����s���̂悢���Ƃ��������܂��A�u�����͎����ǂ��v�Ǝ��F����}�j�A�������Ƃ��炵�����Ƃ������̂ł��B�J�J�N�Ō���ꂽ�}�j�A�̈ӌ������́u�X�s�[�J�[�P�[�u���ʼn��͕ς��̂��v�Ō������Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B�Ȋw�I�ɂ́A�ʏ�̊��ł���q�g��������������قǂɉ����ς�邱�Ƃ͂���܂���B
�����ԍ��F22962834
![]() 17�_
17�_
��cantake����
A-50DAi�����ł���ˁB�R�X�p�͍ō����Ǝv���܂��B
��قǃ��r���[�𓊍e�������Ȃ̂ŁA�����Ԃ�����Ό��Ă���Ă��������B
��Foolish-Heart����
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�ƂĂ��X�b�Ɠ����ė���R�����g�ł��B
���ɁA�u�P�[�u���́A���������̑���������u�����v�Ȃ�Ȃ�ł�������Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂��B�v�Ƃ����̂͋����ł��܂��ˁB
�����͂����Ă��A�S���̏_�炩���Ƃ��͐ڐG��R����ɉe��������̂ŁA�����ɂ͑����̗D��͂���Ǝv������ł��B
����X�s�[�J�ł����A2235H�͓��e�ʖ�150L�̃��A�_�N�g�o�X���t�ɓ���Ă��܂��B
�o�b�t����21mm����2���d�˂ŁA4507�Ȃǂ��͂͂邩�Ɋ��ɂł��Ă邩�Ǝv���܂��B
���삵�������͋����łƂĂ��}���`�Ɏ���o����ɂ͂���܂���ł����B
���̑���ƌ����Ă͉��ł����A�l�b�g���[�N�͎��Ԃ��|���Ă��Ȃ�Â������ɂ�������ł��B���ꂪ�y���݂ł�����܂����B
�����ԍ��F22962880
![]() 3�_
3�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�S�����̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
�����p�C�I�j�A��0.75����×4�Ŗ炵�����Ƃ�����܂����A�����ȂƂ���2sq×4�Ƃ̈Ⴂ�͕�����܂���ł����B
�ʂ̃V�X�e���ł����A����ԍ�60�~/m�i20�N�ȏ�O�̉��i�j�̃P�[�u�����g�������Ƃ�����܂����A���ɖ������������Ƃ͂���܂���B
�u�����āA�I�[�f�B�I�����ŁA�����ǂ��ƌ����Ă���v�C���̖�肩������܂���ˁB���Ƃ͌����ځB
���w�E�̒ʂ�A���̒��ł̓J�i�������Ɉ�ԍ����Ă��邩������܂���B
�����ԍ��F22962938
![]() 2�_
2�_
�ǂ����B
�X�s�[�J�[�P�[�u���I�с@�y�������^^
�������̓x���f���h�Ȃ̂ŃR�������܂���B
�E�x���f��8477�F�@AWG12�i3.5sq�j×2
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����������Ƃ͕����邯�ǁA��������B
�`���b�g�͋�C�ǂ��������Ǝv��
���Ȃ����X����a���������Ă���P�[�u�����Ă݂Ċy����ł݂ẮH
�����ԍ��F22962978
![]() 6�_
6�_
���ɕ��F�̉��
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�x���f���ƃJ�i�����������Ē�����ׂĂ݂�̂�������������܂���ˁB
�������͕�����Ȃ��悤�ȋC�����邯�ǁA�����������̂���Ȃ����B
35�N�O��S-955III���ĕt���ŕt���Ă����̂��p�C�I�j�A��0.75sq×4�B
���̌�A�����p�C�I�j�A��2sq×4�ɑւ��Ĉȗ��A���C���V�X�e���̃P�[�u���͈�ؕύX�Ȃ��ł����B
���`���[�j���O�͑S�ăX�s�[�J�ł���Ă������̂ŁB
�P�[�u�����Ⴛ�����͕ς���Ǝv���A�`�������W����̂��ꋻ���ƁB
�b���͕ς��܂����A�ȑO�̎���Ƀp�C�I�j�A��D���A���v�����߂Ă��ꂽ�̂͒ɕ��F�̉��ł����ˁB
A-50DA�����܂����B���\�C�ɓ����Ă܂��B
�����ԍ��F22963148
![]() 2�_
2�_
�ɕ��F�̉��A�����́B
>�����������Ƃ͕����邯�ǁA��������B
�}�j�A�̂�����Ƃ��Ă�������肽�����Ƃ͂킩��܂����A��l���z���g�̂��Ƃ������Ȃ��̂��L���`�����C�ł��B
bebez����A�����́B
��قǂ͖��̖����b�����Ă��܂��A�S�ꂵ���ł��B�S�ꂵ�����łɁE�E�E�w�������̂̓J�i�������ɂ���A�x���f���̕��ʼn����܂ɂ��Ԃ������グ��A�Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ����ł͂Ȃ�����(��)�B�x���f���ȏ�ɐS�L���ɂȂ邩���B
�����ԍ��F22963238
![]() 15�_
15�_
��bebez����
mogami��3103(2�c)��3104(4�c)���I�X�X�����Ă����܂��B
�𑜓x���\���ŁA�������������F�ł��B
�J�i����x���f�����ǂ��ł���B
zonotone��SAEC���ǂ��ł��B
�����A�l�ɏ��߂�Ȃ��ԕȂ̖���mogami���I�X�X�����܂��B
�����ԍ��F22963249�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 1�_
1�_
���̂������]�k�Ȃ�ł����E�E�E�E�E�E�E�E
�l�����ƍH��p�ɋC�ɓ����Ă���t�H�X�e�N�X��SFC�W�R�ƂP�O�R�Ƃ����P�[�u���B
����A����X�s�[�J�[�̓����P�[�u���Ƃ��A�@�ނ̓����z���ɂ�����ł�����ǁA�ǂ�����Ɗ��G�����K�~�ɂɂĂ��ł���ˁB
���ނ��Ƃ��̎艞�����A���K�~�̃P�[�u��������Ƃ��ɂ��������Ă���B
�d�l���݂�ƁA�� 0.32��OFC����19�{�c�ɔQ��Ƃ����āA���K�~�̃P�[�u���Ƃ͐��̑������Ⴄ��ł����ǁA���̃P�[�u�����҂ݕ����H�v���Ă����āA�f�ʂ��ψ�ɂȂ�悤�ɂQ��ނ̕҂ݍ��݂�g�ݍ��킹�Ă��܂��B
�Ȃ̂ŁA�ꉞ�A�t�H�X�̃X�s�[�J�[�P�[�u���������߂ɂ��Ă��܂���
���c�̃m����������ł���˂�
�N���t�g�I�[�f�B�I�����悤�ɂȂ��Ă���́A���ނƂ����������A��Ɛ����d������悤�ɂȂ�A���������̔z���̓��K�~���g���Ă��܂��A���R���A���K�~�̔z���܂͏����ł߂Ȃ�ł����A�疌���X�p�b�Ɛ�Ăނ��₷����ł���B
�����āA������ƌł߂Ȃ̂ŁA���c����Ƃ��ɐ�ɋȂ��Ă����ƁA���炭�͂��̋Ȃ����`�̂܂܂ɂȂ�̂ō�Ƃ��₷���B
���������z���ނʼn��������̂��A�����Ȃ��̂��͂����������Ȃ�ł����E�E�E�E�E�E�Ȋw�I�ɂ݂�ƕς��Ȃ��͂��E�E�E�E�E�E����������Ɛ��̖��ŁA���c������Ƃ��A�����߂�Ƃ���������Ƃ�����ƁA���̍�Ƃ́u�d�オ��v�ɓ��R�Ⴂ���łĂ��āA����͉Ȋw�I�ɂ݂āA���\���A�I�[�f�B�I�̏ꍇ�ɂ͉����̍����ł邱�Ƃ͊ԈႢ�ł͖����Ǝv���Ă��܂��B���A���ꂪ�{���Ɏ��ŕ�������̂��͉Ȋw�I�ȍ����������܂��A�ړ_�Ƃ����̂͑��̕����ɔ�ׂĘc�݂̃I�[�_�[���傫�������ł�����A���蓾�Ȃ������Ȃ��̂��Ȃ�
�Ƃ������ƂŁA�l�́A�P�[�u���ɂ�鉹���̍��͂���ƌ�������ɗ����Ă��āA���A���ۂɁA�`���[���̎��ɕ����̃P�[�u�����g�������Ă��܂��B
�����A�X�s�[�J�[�P�[�u���́A�u���߂̓����Ȃ炢��Ȃ��ł����v�ƌ����Ȃ���A���́AMIT�̃~�h���O���[�h�ȏ����p���Ă��܂��B
�����ԍ��F22963327
![]() 3�_
3�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���̖����b�ł͂Ȃ��A�����܂߂قƂ�ǂ̐l�ɂƂ��Ă͐^���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂���B
�����A�P�[�u���̕����ɂ���ĉ�������Ă���Ƃ����̂��^���ŁA���[�J�̊J���i�̉����`�F�b�N����悤�ȃX�y�V�����X�g�́A���E�ŕ���������Ă���ƈꔭ�ŕ����邻���ł��B
�܂��A���������Ɉ��܂����A�@�B�I�ɑ��肷��ΑS�����������̃R���f���T�ł��A�핢�̐F�̈Ⴂ�ʼn��ɍ����o�邻���ł��B
�I�[�f�B�I�Ɍ��炸�A����◝���ł͐���������Ȃ����Ƃ��Č��\����܂���ˁB
��msyk828����
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�Q�l�ɂ����Ă��������܂��B
��Foolish-Heart����
�����C���Ŏg���Ă���X�s�[�J�̃l�b�g���[�N�́A�S���͎͂g�킸�A�S�ăJ�V���Őڑ����Ă��܂��B
�d���̖����͊o���Ă��܂��A�I�[�f�B�I�p�̑����ĉ��H���₷�����̂��g���Ă��܂����B
�������A����قǍ��z�ł͂Ȃ����̂ł��B
�͂��X�ɂ����̂́A�͂͌o���i���x�T�C�N���j�ŃN���b�N���������s��̌����ɂȂ邩��ł��B
�����ԍ��F22963417
![]() 2�_
2�_
���͂��X�ɂ����̂́A�͂͌o���i���x�T�C�N���j�ŃN���b�N���������s��̌����ɂȂ邩��ł��B
�X�s�[�J�[�̃l�b�g���[�N�͔��c�����u�����߁v�̕����ǂ��Ɩl���������Ă����ł����A�����ȃu�b�N�V�F���t�Ńc�C�[�^�[�ɃR���f���T�����������x���Ɓu���c�̕����y�v�ƁA��������Ĕ��c�����Ⴂ�܂��B
�{�C�Ń`���[������̂Ȃ�A�l�b�g���[�N�͊O�ɏo���āA�������܂�����Ƃ�����Ƃ����A���̂܂܃G���N���[�W���[�ɂ͔[�߂Ȃ��ł��˂�
�l�́A���Ƃ̕��łS�R�S�R�������Ă���̂ł����A�E�[�n�[�����藣�����}���`������Ă��܂��B
���낻��AMID-LO�����̃l�b�g���[�N���č\�z���Ȃ�����Ȃ��Ǝv���E�E�E�E�E�S�R�S�R�͎�z���̂����߂Ȃ̂ŊȒP�Ƀp�[�c���Ƃ�͂����܂����A�X�y�[�X���L���̂ő�e�ʂ̃��m��������܂��B
�ŋ߂́A�����h���t��EVO�V���[�Y�����C�ɓ���ŁA����EVO-OIL�̌n�����D��Ŏg���܂��B
�ނ��Ⴍ���ፂ���̂ł����AEVO-OIL��gold/silver�͂����ł���A�����h�炵���𑜓x�̍����ƁA����ł��ăs�[�L�[�ł͂Ȃ��A������ƃE�H�[�~�[�ŁA�������V���L�[�ȉ������܂��B���ʂ�EVO-Oil�ŗe�ʂ��҂��ŁA���߂̂P���gold/silver������Ɨǂ������ł��B
�ŋ߂̓R�C�Y�~�����ł���ɓ���悤�ɂȂ����̂ł����A�ȑO�͊C�O�ʔ̂Ŕ����Ă��܂����B
��R���A�����h�̒�R�����ł���B�f�[���������Ƃ������̂ł����A�f�[���͂Ȃ�ƂȂ��A�����J���ł���ˁA�����h�ɂ���Ƃ�����ƃ��[���s�A���e�C�X�g�i�����ł��t���Z�{���Ǝv���Ă��܂����j�ɂȂ�܂��B
�z�[���V�X�e���̒���͎��ɂ�������э���ł���̂ŁA���������p�[�c�̃u�����h�ōD�݂Ɏ����čs���̂��y�����ł���ˁI�I
�������e�ʂŃp���g������ɂ́A�e�t�����R���f���T�⓺���X�`�R���i�ŋ߁A���Ȃ�ɂ������Ă���j�A�}�C�J�Ȃ��g���܂��B
�e�t�����R���f���T�́A�C�O�ʔ̂Ō�����ƃK�o�b�Ɣ�����߂Ă��܂��B�ŋ߁A�ψ����Ⴂ���m�͂悭�łĂ���̂ł����A���ψ��̃��m�͂Ȃ��Ȃ��o�Ă��܂���B
�g������̗ǂ��A0.01�ʂ̃e�t�����́u����قǁv�ɂ�����Ă��܂���
�}�C�J�͐F�X�����Ă��܂����A�l�͍D���ł悭�g���܂��BOP�A���v��v���A���v�̈ʑ��⏞�ɂ�SE�R���f���T���g������ACR�����͂��܂��Ƀ}�C�J���Ă܂��B�i�ǂ����Ă��Z���R���̉����C�ɓ���Ȃ��j�@�ŋ߂́A�Q���ȉ�������PPS���o�Ă����̂ō����PPS�𑽗p���邩���B
�����ƁA�����̓P�[�u���̘b���ł����˂�
������Ǝv�����̂ł����A�x���f���̘b�肪�o��ƁA�E�~�w�r�Ƃ����˂��ˌn�̘b��͂悭�ł�̂ł����A�l�I�ɂ̓X�^�W�I�W�P�S�Ƃ�1810A���ďo�Ă��Ȃ��ł���ˁE�E�E�E�E������̕����f���ł����Ƃ��������ǂȂ��Ǝv���Ă����肵�܂��B
���ɂ���^�V���b�v�̎��肪��������Ȃ낤�Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͑S�R�v���Ă��܂����i�n�[�g
�����ԍ��F22963711
![]() 2�_
2�_
��bebez����
�x���f���ƃJ�i���͗��p�������Ƃ���܂��B
���̓J�i���̕����D�������B
���́ASTP��LAN�P�[�u��0.5mm×4p�̂�4�{1�g
�ɂ����P�[�u���𗘗p���Ă܂��B���̑�����1�{4mm�ɂȂ�̂��ȁB�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̗ǂ��ƃ����O�P�[�u����莩��Ȃ̂Œ��������R�ɍ���̂��C�ɓ����Ă܂��B
�J�i��4S8G�N���X�ȏ�̉��Ŗ銴���͂��Ă��܂��B
�����ԍ��F22963892�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 4�_
4�_
��Foolish-Heart����
�����[�����b���肪�Ƃ��������܂��B
4343�͊����i�ł���Ȃ���A�����ł����邱�Ƃ��ł��āA�����̐l�ɂƂ��Ă͍ō��̂�������ł��ˁB
�������A4Way����Ȃ�����̂͑����ȍ��C������̂ł͂Ȃ��ł����H
���̏ꍇ�́A2Way�Œ������āA�A�h�I����ST���悹�Ă���̂ŁA�܂��A�肪�͂��Ƃ������Ƃ���ł��B
NW�͓Ɨ�����Box�ɓ���Ă܂��̂Ő���͏��Ȃ��A�g�ݗ��Ă͔�r�I�e�Ղł����B
NW�|���j�b�g�Ԃ͊e�X�p�C�I�j�A��4�c�P�[�u���Őڑ����Ă���̂ŁA�X�s�[�J�P�[�u���Б�2m�ƌ����Ă��A������3m���炢�ɂȂ��Ă��܂��B
JBL���j�b�g�őg�ޑO��FOSTEX�̃��j�b�g�����C���Ŏg���Ă��܂��āA�����FOSTEX�}�Ȃ̂ŁA�R���f���T�͑S��FOSTEX�̂��̂��g���Ă��܂��B
�g�ݗ��Ă��̂�20�N�ȏ�O�Ȃ̂ŁA�R���f���T�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƋC�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����A���ɔp�ԂƂȂ��Ă���A���C�A�E�g��A�ȒP�Ɍ����ł��Ȃ��̂ŁA���͂��̂܂g���Ă��܂��B
�S�ăt�B�����R���Ȃ̂ŁA�܂����v���ȂƂ͎v���Ă��܂����A����ւ����猀�I�ɗǂ��Ȃ邩���Ȃǖϑz�����Ă��܂��B
�R���f���T�̗i�e�ʂʂ��j�͋ɂ߂Ċɂ₩�Ȃ̂ŁA�����������Ă��܂��Ă邩������܂���B
��fmnonno����
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
LAN�P�[�u��4�{�g���ł����B
�F����A�Ǝ��̕��@�Ŋy����ł����܂��ˁB
���́A���܂ŁA���܂�P�[�u���ɍS�������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�ǂ������킯���A�ƂĂ��e�ߊ��������܂��B
�I�[�f�B�I�͒��������łȂ��A�����Ȃ�̕��@�ʼn���������̂���햡�ł���ˁB
���āA��^�A�x�ɂ͍H���\������āA�d�����Ȃ���Ɏ��g��ł������Ƃ��v���o���܂����B
�Ƃ���ŁA�SS11G�iOFC�j��蔄�肵�Ă���Ƃ���������m�ł���A�����Ă���������ƍK���ł��B
�X�^���_�[�g�̂SS11��蔄�肵�Ă���V���b�v�͂����������܂������A�SS11G�͂�����ƌ��������͈͂ł͌������܂���ł����B
�����ԍ��F22963982
![]() 1�_
1�_
��bebez����
4S11�ł����Ǝv���܂��������S�c�̂Q�p���͒[����������ςȂ̂�4S8�ł������Ǝv���܂��B
�d���͑����Z�����������ł������ۂɂ̓A���v���̒�R�̊W�ŁA�P���[�g��������0.5�X�P�A��葾�����Ă����ʁi�_���s���O�t�@�N�^�[�j�͂��܂�ς��܂���B�R���[�g���Ȃ�1.5�X�P�A����Ώ\���ł��B
�d���̒�R��������Ǝ��ɖ��ɂȂ�̂��ڐG��R�ł��B���ꂪ�d���̒�R�ɕC�G���邭�炢�Ȃ̂Ŗ����ł��܂���B
�[���Ƀo�i�i�i�͂t���j���邩�A�������b�L�����[�q�����ĐڐG��R�������邱�Ƃ̂��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B
���Ȃ݂Ɏ��͒Z���z����4S6�A�����z����4S8�����p���Ă܂��B
�����ԍ��F22963983
![]() 5�_
5�_
��bebez����
����ɂ��́B
�X�s�[�J�[�P�[�u���ł͂Ȃ��̂ł����A�q�b�`�P�[�u���ŁA���K�~�͎g�������Ƃ�����܂��B
�V�X�e���\����������p���[�n�������̂ŁA�p�b�g�����ɂ́A�ǂ���ۂ������̂ł����A
�����Ԃ͔����o���܂����B
�q�b�`�Ƃr�o�ł́A�X���͈Ⴄ��ł��傤���ˁB
���Ȃ݂ɁA�e�N�j�J�͂r�o�P�[�u�������Ă܂������ǁA���������ł��B
�ӊO�Ɠd�C������̃L���u�^�C���P�[�u�����f���ȉ��ł����B
�����ԍ��F22963989
![]() 2�_
2�_
���n���ق���
�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B
�J�i���̓R�X�p�����Ȃ�ǂ������ł��ˁB
���܂ŁA�P�[�u���Ɋւ��Ă͐[���l�����ɁA��͏������˂�Ƃ����������Łu�����Z���v�ł���Ă��܂����B
�o���I�ɂ́A3m���x�ł���A1.5sq�ł�������Ȃ��Ƃ������o�������Ă��܂��B
���l�I�Ȃ����������������܂����̂ŁA���₳���Ă��������B
�J�i���̂SS11���Ɏ��ƁA��R��9m��/m�ŁA3m����27m���ɂȂ�܂��B
�_���s���O�t�@�N�_700�̃A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�͖�11m���ł��B
����A�X�s�[�J�̃C���s�[�_���X��8���ł��B
���l�I�Ɍ���ƁA�P�[�u���̒�R�̓A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�ɑ��Ă͖����ł��Ȃ��I�[�_�[�ŁA�X�s�[�J�̃C���s�[�_���X�ɑ��Ă͔��X������̂Ƃ������Ƃ��ł��邩�Ǝv���܂��B
�A���v��NFB���|�����Ă���̂ŁA�P�[�u���̉e���𐔒l�I�ɍl����ꍇ�́A�X�s�[�J�̃C���s�[�_���X����ɂ�������Ƃ������Ƃł��傤���H
�P�[�u���̒�R���[�q�ڑ��̐ڐG��R�ɒ��ӂ��K�v�Ƃ����̂͑S�������ł��B
5.1����������Ă������́A��Ɏ��֗̕�������A�P�[�u���̐�[�ɂ̓o�i�i�[�q�����t���Ă��܂������A2ch�V�X�e���͐S����[�q�ɒ��ڒ��ߕt������@������Ă��܂��B
���_�I���t���͂���܂��A���o�I�ɂ͐ڐG�ʐς��҂��āA�[�q�̊ɂ݂Ȃǂɑ��Ă����o�X�g�Ȋm�����̍����ڑ��@���Ǝv���Ă��܂��B
�J�ł͍����ȃo�i�i�[�q��Y�[�q�������Ă��܂����A�H�H�H�Ǝv���Ă��鎟��ł��B
���h�b�h�R���b�c����
�ēx�̏������݂��肪�Ƃ��������܂��B
AT�̓I�[�f�B�I�A�N�Z�T���[���[�J�Ƃ��āA�ƂĂ�����݂�����܂��B
���C���V�X�e���̓A�L���t�F�[�Y�̃P�[�u�����g���Ă��܂����A����ȊO��RCA��f�W�^���P�[�u���̂قƂ�ǂ�AT�ł��B
�����AT��SP�P�[�u���ׂ��̂ł����A�������̂��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���ɂ͋����܂���ł����B
�L���u�^�C���A�ƂĂ��������������ł��B
�̒����N�v����5.5sq�̃L���u�^�C�����g���Ă����ƋL�����Ă��܂��B
�����ԍ��F22964113
![]() 1�_
1�_
�u���������ŒZ�Łv�Ƃ��A�u�P�[�u���ʼn��͕ς��Ȃ��v�Ƃ��A�P�[�u���̘b��ɂȂ�ƕK���N���ďo��o�L�ڂ���ł��ˁB
�����ƒ����̓o�����X���厖�ł��B
���͕ς��Ȃ��ƌ����Ă�l�́A���@�Ȃɍs���Ď��|�����Ă�������ق���������Ȃ��ł����ˁB
�����ԍ��F22964147
![]() 7�_
7�_
��bebez����
�_���s���O�t�@�N�^�[�͂���Ȋ����̎��ł��B
DF��Rsp�^(R0�{R1�{Rc)
�@Rsp:�X�s�[�J�̌��̃C���s�[�_���X
�@R0:�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X
�@R1:�X�s�[�J�[�P�[�u���̃C���s�[�_���X�i������)
�@Rc:�[�q�ƃP�[�u���̊Ԃ̐ڐG��R
Rc�͗��d�����Ǝ_���⓱�ׂ̂̒�ɂ����݂Ȃǂň��肵�܂���B
�������b�L�����[�q�Œ��ߕt���g���N��������Ƃ���ΐ��~���I�[���ȉ��Œ������艻���܂��B
�[�q��v���O�̓I�[�f�B�I�p�ł͂Ȃ�JIS�K�i�i��d���e�ʂ����L���ꂽ���́i�T�g�[�p�[�c TJ-560�Ȃǁj�̂������߂ł��B
�����ԍ��F22964188
![]() 3�_
3�_
���n���ق���
�����̂����肪�Ƃ��������܂��B
�����ł��ˁA�P�[�u���͉����ōl����ׂ��ł����B
�ŋ߂͒����i10���~���x�j�ȏ�̃A���v�ł���A�_���s���O�t�@�N�^300�ȏ�Ƃ����̂͒���������܂���B
���ɁA�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^��500�Ƃ����R0=16m���ƂȂ�܂��B
�����ŁA4S8�i15m��/m�j��3m�g���Ɖ�����R1=90m���ł��B
�ڐG��RRc=��m���Ƃ���ƁA�V�X�e���S�̂̃_���s���O�t�@�N�^�̓P�[�u���̒�R���x�z�I�Ƃ������ƂɂȂ邩�Ǝv���܂��B
���̂悤�ȗ����ł�낵���ł��傤���H
�ʂ̌����ł����A�_���s���O�t�@�N�^200�̃A���v+�P�[�u��1,5m(R0+R1=85m���j�̕����A�_���s���O�t�@�N�^500�̃A���v+�P�[�u��3m�iR0+R1=106m���j���V�X�e���S�̂̃_���s���O�t�@�N�^�͑傫���Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����l����ƁA�P�[�u�����n���ɂł��܂���ˁB�i���݂܂���A���^�₪�o�Ă��܂������̂Łj
�����ԍ��F22964257
![]() 1�_
1�_
���n���ق���
�����̎_���ɂ͒��ӂ��Ă��܂��B
�ڎ��ł����A����I�Ƀ`�F�b�N���āA�ϐF��������ꍇ�ɂ͐�[�����V�������̂��o���悤�ɂ��Ă��܂��B
���̂����������āA2m�������͂��̃P�[�u�����Z���Ȃ��āA����̎���ɂȂ���������ł��B
�i�������A���C�A�E�g�ύX���傽��v���ł����ǁj
�����ԍ��F22964286
![]() 2�_
2�_
��bebez����
����ɂ��́B
�Ⴄ��������܂��A�Ԉ���Ă��炷�݂܂���B
�_���s���O�t�@�N�^�[���āA�X�s�[�J�[�̖��ʂȐU����}����\�͐��l����Ȃ������ł��傤���B
������A�����͂������悤�ȋC�����܂����ǁB
���Ȃ݂Ɏ��̃A���v�́A�P�T�O��������܂��ǁE�E�E(;´�t�M)�g�z�z
�����ԍ��F22964297
![]() 1�_
1�_
��bebez����
�P�[�u����20�N�ʎg���܂��ƘI�o������������Ȃ��핢���̂����݂Ȃǂ���܂��H�₪�����Ȃ肭���݂ɂȂ��Ă������������낵�����Ǝv���܂��B
�M���������͓̂��̂̕\�ʂƕ����Ă܂��̂ŁB
�_���s���O�t�@�N�^�[�̓A���v�̏o�̓C���s�[�_���X����������Ă��܂��̂ŁA�����͂Ƌ��ɋ쓮�͂��e������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22964394
![]() 1�_
1�_
bebez����A����ɂ��́B
�_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ����̂́A�܂����̂Ȃ��b�ŋ��k�ł����A�ƊE���̃Z�[���X�g�[�N�̂��߂ɕ҂ݏo���ꂽ���l�������A�������}�j�A�œd�C�H�w�I�ɗ������Ă���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�Ȋw�I�ɂ�10�`��10���������ȏ�͖��Ӗ��ł����A�t�ɏ���������Ƃ����ĉ��������Ƃ������Ƃł��Ȃ��ł��B
������ƃ}�j�A�b�N�Œ����ł����A�̋c�_�������Ƃ�����܂��ł�낵����B
�c�e�l�ɂ��āI�I�I
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15682249/#tab
�c�e�l�ɂ��ćA
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15745542/#tab
�����ԍ��F22964541
![]() 9�_
9�_
�J�i���SS11G�͂܂������Ă��邨�X�͂Ȃ��ł���ˁB
�g���J�Ƃ���B�d�@���̃J�i�������X�ɕ����Ă݂�̂���낵�����Ǝv���܂��B
�J�i���̉c�ƂɁu�戵�X�v�������Ă��܂��Ă����������B
���i�R���ł́A����������W�̓_���ł����A���[���ōw�����āA�]���������I�[�N�V�������ŏo���Ƃ��AFacebook��mixi����SNS�Łu�I�[�f�B�I�v�W�̃t�H�[����������̂ŁA�����������ŔЕz�⋤���w��������������̂��A�����Ǝv���܂��B
��Ԃ͂�����܂����ǁE�E�E�E�E�E�E�E�E
�X�s�[�J�[�P�[�u�����������m�͏d���������ɂ����̂Œʔ̂Ō�����ꂽ��A�ʔ̂Ŕ����������Ƃ��v���Ă��܂��B
�l�A�H�t���܂Ŏ��]�Ԃōs���鏊�ɏZ��ł��܂����A�P�[�u�����l��������Ƃ��ɂ͒ʔ̂�������Ă܂���
�P�[�u�������łȂ��A�ŋ߂́A�p�[�c�ނ͂܂Ƃߔ����ɂ��āA�e�X�́u���������v���z�܂Ŕ�������������Ă܂���B
�ȉ��]�k
DF�̘b���ɂȂ��Ă��܂����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�l�͂��܂�C�ɂ��Ă��܂���B
�����ĂˁAD���A���v���Đ��Ԃł́u�쓮�͂������v�Ƃ����Ă���̂ł����AD���A���v����DF�𑪒�ł��Ȃ��ł���E�E�E�E�E�E�E�E
�����ԍ��F22964627
![]() 2�_
2�_
��bebez����
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
��Foolish-Heart����
����ɂ���
�_���s���O�t�@�N�^�[���������������Ƃ����Č������������āA�i�V�O�O���������Ȃ��j
���̂P�T�O�����Ďv���ċC�ɂ͂Ȃ��Ă���ł����ǁB
�ς����Ă��������ƁB���܂�W�Ȃ��A�C�ɂ��Ȃ��Ă����݂����ł��ˁE
(´���M) ί�@�@
�����ԍ��F22964675
![]() 1�_
1�_
��bebez����
>�ʂ̌����ł����A�_���s���O�t�@�N�^200�̃A���v+�P�[�u��1,5m(R0+R1=85m���j�̕����A�_���s���O�t�@�N�^500�̃A���v+�P�[�u��3m�iR0+R1=106m���j���V�X�e���S�̂̃_���s���O�t�@�N�^�͑傫���Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����䂤���Ƃ���Ȃ��ł����B�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�����ɑ傫���i���Ȃ킿�A�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X���~���I�[���ȉ��̔��ɏ����Ȓl�j�Ƃ��Ă��A�P�[�u�����g�̒�R��ڐG��R�A�l�b�g���[�N�̃R�C���̒�����R�̍��v�����\�~���I�[���ł���A�n���ق���̎����_���s���O�t�@�N�^���v�Z���鎮�̕���̒l�́A�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�̒l�i�A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�̒l�j�ɂ͂قƂ�Ljˑ����Ȃ��Ȃ�̂ŁA���܂�ɑ傫��DF�l�͈Ӗ����Ȃ��B
�����ԍ��F22964713
![]() 5�_
5�_
������������
2�����قǑO�ɁA���̃P�[�u���i�p�C�I�j�A��0.75����×4�j�̔핢���܂������A�����ڂɂ̓s�J�s�J�̐V�i���l�ł����B
���̃P�[�u����20�N�ȏ�O�ɍw���������̂ł��B
���h�b�h�R���b�c����
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
2235H�̓A�L���t�F�[�Y�ȊO�̎莝���̃A���v�ł͒��̒��肪�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����܂��点�܂���ł����B
����͐����́A�܂�_���s���O�t�@�N�^�̖�肩������Ȃ��Ǝv���A�Z�J���h�X�s�[�J�p�̃A���v�I�т̍ۂɒ��ڂ��܂����B
���ǁAD���A���v�iA-50DA�j�ɂ����̂ŁA���������悤�ȁA�����łȂ��悤�ȁB
���̂悤�Ȕw�i���������̂ŁA�u�_���s���O�t�@�N�^�v�Ƃ����t���[�Y�ɉߏ�ɔ������Ă��܂�����������܂���B
��Foolish-Heart����
���������A�߂��̃I�[�f�B�I�V���b�v��B&W�̎����ɍs���Ă��܂����B
800D3�̓Y�S�C�ł��ˁB�e���[�J�����t�@�����X�ɂ��邾���̂��Ƃ͂���Ǝv���܂��B
804D3�����Ȃ�ǂ������ł��B���i�E�T�C�Y�Ƃ��A�lj��œ����Ȃ�R���Ǝv���܂����B�i���i�͂�����ƍ����H�j
����ɑ��āA700�V���[�Y�́E�E�E�@��r�Ώۂ����������̂ł��傤�B
�����̌�ŃP�[�u�������Ǝv�����̂ł����A�x���f���͎戵�͂�����̂�8477�͂Ȃ��A���K�~�ƃJ�i���͎戵�Ȃ��Ƃ̂��ƂŎc�O�B
��ʂ�A�ʔ̂Ŕ����̂������I�ł��ˁB
�����ԍ��F22964729
![]() 1�_
1�_
���h�b�h�R���b�c����
�v���o�����̂ŒNjL���܂��B
28�N�O��P360���w�������̂ł����A�_���s���O�t�@�N�^��300�ł����B
�������̃A�L���t�F�[�Y�̃g�b�v���f����M-1000�ł����A�J�^���O�����܂��ƃ_���s���O�t�@�N�^��200�ł��B
���������Ƃ͂���܂��AM-1000�̋쓮�����͂�P360���y���ɏゾ�Ǝv���̂ŁA�_���s���O�t�@�N�^�ŋ쓮�����͂�_����͓̂K�ł͂Ȃ��悤�ɂ��v���܂��B
�����ԍ��F22964751
![]() 2�_
2�_
��bebez����
����ɂ��́B
���肪�Ƃ��������܂��B
�d�� 27.4kg Accuphase P-360�@ ��370,000
�d�ʁ@29.2 kg�@�@�o�|�S�T�O�O �@�@�艿�s��
�ǂ��A���v�ł��ˁB�����^�т���ς����ł����E�E�E�E
�_���s���O�t�@�N�^�[�ɂ��ẮA�_����@�m��������܂���B
�ł��莝���̃A���v�ł����v�݂����ł��B�@
�����ԍ��F22964762
![]() 2�_
2�_
���h�b�h�R���b�c����
���肪�Ƃ��������܂��B
�����̓X�s�[�J���S�łƂ����X�^�C���Ŏ��g��ł��܂����̂ŁA�A���v�ɂ͐F�t�������Ȃ��������肵�����̂��Ƃ������ƂŁA�A�L�����A�L���łȂ��܂����B
�ŏ��̃A�L���iC-260+P-360�j��27�N�ȏ�m�[�g���u���ŁA�܂��܂��g�������ł������A�N����l���č��N����ւ��܂����B
���܂�A�ϋv�M�����ɂ��Ę_�����邱�Ƃ�����܂��A���̓_�ɂ����Ă̓A�L���͍ō����Ǝv���܂��B
20�N�A30�N�m�[�g���u���Ŏg����A���������������ł��Ȃ����ȂƎv���Ă��鎟��ł��B
�����ԍ��F22964773
![]() 1�_
1�_
�_���s���O�t�@�N�^�[�̌��A�̂̒����X���������N���������Ȃ̂͗��\�ł����B���̌������ȉ��ɂ܂Ƃ߂܂��ibebez����͂������Ă��˂��ɕԐM�����Ă�������A���肪�Ƃ��������܂��B����͎��̃~�X�ł��̂ŁA�y�������Ă��������B�B�j�B
---
�Ȋw�I�ɂ́A�u�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X���A���v�̓�����R�Ŋ���v�Ƃ����s�ׂɂ��܂�Ӗ������o���܂���B
�܂��ADF���傫�����Ƃ̒萫�I�Ȍ��ʂ͎��̒ʂ�ł��B�A���v���̃C���s�[�_���X�������邱�ƂŁA�X�s�[�J�[�ɂ����镪�������܂�܂��BDF�l�����߂邱�Ƃɂ��i�A���v�̃C���s�[�_���X�������邱�Ƃɂ��j�A����I�ɃX�s�[�J�[�ւ̕������m�ۂ���邱�Ƃ���X�s�[�J�[�ւ̃h���C�u�͂��グ����ʂ�����Ƃ���Ă��܂��B
�ł͒�ʓI�ɂ͂ǂ��ł��傤���H�X�s�[�J�[�̒�i�C���s�[�_���X��6���Ƃ����Ƃ��ADF=50�̃V�X�e���ł̓A���v�i�{�P�[�u���j�̒�R��0.12���ADF=100�̃V�X�e���ł�0.06���ł��B�A���v�̏o�͓d�����ǂꂾ���̌����ŃX�s�[�J�[�ɓ`�B����邩�Ƃ����ƁA�O�҂ł� 6/6.12�A��҂ł� 6/6.06 �ŁA���҂̍��� 20�Elog(6.12/6.06) = 0.086dB �ł��B
���̎����Ƃ���́A�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�����g���ɂ���ĉ���6���`���܂ŕϓ������Ƃ��āA���V�X�e����f���ɁA�ő� 0.086dB �̍����o�邩������Ȃ��Ƃ������Ƃł��BDF=500�̃V�X�e����DF=1000�̃V�X�e���Ƃ̍��Ȃ�A�ő�ł� 0.0087dB �ł��B���̂悤�ɁADF�Ƃ������l�́A�Ȋw�I�ɂ͂��܂�Ӗ�������Ƃ͎v���܂���B
����A���l��͂ǂ��܂ł�DF�������V�X�e�������邱�Ƃ��~�\�ŁA���[�J�[�ɂƂ��Ă͎��ɓs���̗ǂ��w�W�Ȃ킯�ł��B�F�X�Șb�𑍍�����ƁADF�Ƃ́A�A���v���[�J�[���Z�[���X�g�[�N�̂��߂ɂЂ˂�o���A�P�[�u����������ɏ������`�Ő��̒��ɗ��z���Ă����̂��낤�ƍl���Ă��܂��BNFB�𑽂�������DF=1000�̃A���v���ł���ƁA�ɑ��P�[�u���łȂ���A�P�[�u����������X�|�C������v�Z�ɂȂ�c�Ƃ��������@�ł��B
��L��f���ɂ��Đ������܂������A�����鐧���ɂ��Ă��������ƂŁA�����I�ɂ́i���q�g�������������邩�ǂ����Ƃ����_�ł́jDF�͂���������10������イ�Ԃ�ł����āA�^��ǃA���v�������Α��̃V�X�e���Ŏ����ł��Ă���b�ł��傤����ADF���l������Ӗ��͂Ȃ��A�Ƃ����̂��^���ł��傤�B
�����ԍ��F22964848
![]() 7�_
7�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���J�Ȃ��������肪�Ƃ��������܂��B
���וϓ��A��ɃE�[�t�@�ɔ�������t�N�d���ɑ���ϐ����A���v�̋쓮�����͂ɒ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
���̈�̖ڈ����_���s���O�t�@�N�^���Ǝv�����̂ł����A�P�[�u���̒�R���݂Œ�`�����Ƃ���ƁA������Ǝ�ς���Ă��܂��ˁB
���̃A���v�͏o�͒i��NFB���|���Ă���̂ŁA���וϓ��ɑ���ϐ���NFB���\�ɂ��Ȃ�ˑ����邩�Ǝv���܂��B
�����ANFB�̓X�s�[�J�̒[�q����|���Ă����ł͂Ȃ��A�A���v�����̓���Ȃ̂ŁA�P�[�u�����݂Œ�`�����_���s���O�t�@�N�^�ƕ��וϓ��ɑ���ϐ��A���Ȃ킿�쓮�����͂Ƃ́A�����Ԃł͂Ȃ����̂̑��Ԃ͒m�ꂽ���̂Ɨ������܂����B
��DF�͂���������10������イ�Ԃ�ł�����
���ꂪ�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22964951
![]() 3�_
3�_
��bebez����
�i�C�X�N���b�N�ł��B
�����ԍ��F22965191
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ� ����
�����́B
�ŋ߁A�����閈�ɉȊw�I�ɂ͂Ȃ�̈Ӗ����Ⴂ�������Ə�����Ă��܂����A
�_���s���O�t�@�N�^�[�݂̂̈Ⴂ��������ׁADF800�̃p���[�A���v��
2��ނ̒�R��}�����ċ[���I��DF 1��DF 100�̏�Ԃ����A
��r�����Ɣg�`���v�������v���O�ł����A
http://nojima-audiosquare.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
������S���̉R�Ńv���V�[�{�ł����H�B
�X���傳��ɂ����Ė���Ċ��z���f�������ł��B
���A�P�[�u���ɕt���Ă��Ȋw�I�ɂ͂Ȃ�̈Ⴂ���Ȃ��A�v���V�[�{���ʂł���A
���o�ɉ߂��Ȃ��Ǝ咣����Ă��܂����A�v���V�[�{���ʂ��̂��̂�������100%��
���ʂ������ł͂Ȃ����A�����O�̖K�v�Ȏ��ԂɎ���A�g�̂ɗǂ��Ȃ��A
�H�E�����K����f���������⎞�Ԍo�߂ɂ�鎩�R�����̌��ʁA
�����u���ɂ���v���l������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
�ƂĂ��悭������Ă���͓̂`����Ă��܂����A
�ǂ�ȃV�X�e����A�N�Z�T���[�ŁA�ǂ�Ȋ�������Ńe�X�g�����Ċm�F�����̂��H�A
�Ɩ����ƃX���[����鏊������ƁA�E�L�y�f�B�A�ɏ����Ă��鎖�Ƒ�������A
�Ƃ������_���̗l�ł��ˁB�L�x�Ȍo���ɗ��ł����ꂽ���_�Ȃ�A�[�����Ղ��̂ł���...
�n�D�������ɂ���Ė��킢�����鎖�́A���̌l�̐^���ł���A
���E�̐^���ƃC�R�[���łȂ���Ȃ�Ȃ���ł͖����Ǝv���܂��B
���ۂɍw�����āA����ނ��̐��i���������o���k���A
�v���V�[�{�ɂ��v�����݂ƒf���A
���ꂪ�o���ɖR�������_��̎������ň�R�����̂́A�@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����B
��������B���������炵�ĉ҂��������ōw�����A�u���ʂ�����v�Ƒ̌���������
���f�����̂�����A���́u�R�v���Ƃ͎v��Ȃ��B���̐l�������Ŋm���Ɋ������A
���̐l�́u�^���v�ł���u���z�v���ƐM���܂��B
�����ĂƂ��A���̂Ȃ��b�Ɓu���v�Ǝ��o�������
���́u���v���ĉ��̂͑�l�C�Ȃ����A�u���v�Ƃ������̂ł��B
���ӂ͂Ȃ��A�Ӗ����鏊�̎��o�͂Ȃ��l�ł����A
���̐l�����ۂɍw���̏�A�����Ċ�������(���z)�ɑ���
�u�v���V�[�{�ɂ��v�����݁v�u���o�v�ƌ������̂́A
�u�R���v�u�Ⴂ���Ȃ�����������ʂ��������Ȏ��̂����ɑ喇�͂����ăo�J���ȁv��
���J���Ă���̂Ɠ��`�ł���B
�䎩�g�́u�ӌ��v�▾�炩�ɊԈ�������ւ̎w�E�͌��\�ł����A
���ۂɎg�p���Ă���l�́u���z�v���u�v���V�[�{=�R�v�Ɣے肷��̂͒����Ȃ����A
������a�����o���܂��B
�����̑��݈Ӌ`���̂��̂�ے肷�鎖������A��ԉɂ����ĎQ�����Ȃ��Ă�...
���̌o���ł́A�I�[�f�B�I�A�N�Z�T���[�̗ނ́u�z���g�Ɍ��ʂ���́H�v��
�^���̖ڂ������Ē����l�ɐS�|���Ă��܂����A���ʂ́u������Ȃ����v
�u�ǂ��Ȃ����l�ȋC�����镨�v�u����͒����Ε����镨�v�܂ŁA�F�X����܂����B
�ܘ_�A�d������╔���̉��������A�@��̑g�ݍ��킹���̊���
���X�傫���قȂ�̂ł�����A���ʂ������Ȃ������ے肵�Ȃ����A
�����܂ł����I�Ȍ����ɉ߂��Ȃ��B
�v���V�[�{���ʂ��咣�������A�傫�Ȍ��ʂ�����Ȃ�A10���~�ʂ̋@��ŁA
100���N���X�̉��Ɋ�����v���V�[�{�����ɂ����ĉ������B
����ȃv���V�[�{�ɂ������Ă݂����I�B(��)
�����ԍ��F22965205
![]() 6�_
6�_
�����X�̃V���b�v�͐F�Ɠ������Ⴄ�����Ŗ��͓����炵���ł��B
�v���V�[�{��������ł��ˁB
�����ԍ��F22965224�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��bebez����
�J�i�� 4S11G��3000m����̓����i�̎��Y�炵���蔄�肵�Ă����Ƃ�����A�ŋ߂͌�����Ȃ��ł��B
4S11��4S8G�Ȃ�Amazon �ł������Ă܂��ˁB���t�I�N�Ō������Ă��A4S11����������Ȃ��ł��B
LAN�P�[�u���͂܂����肵�₷���ł����A���H�͖ʓ|�ł��B�ł����͋C�ɓ����ė��p���Ă܂��B��x�����Ă݂�̂��ǂ������B
�����ԍ��F22965239�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��bebez����
����Ȋ����ŁA���Ƀo�i�i�v���O��t���Ă܂��B
�����ԍ��F22965257�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ٔ����ō̗p�����̂͌܊��Ō����Ύ��o�̈�v�B(�؋��ʐ^)
���≹������͂�قǂ���Ȃ�����̗p����Ȃ��B
���o(�f��)�ȊO�̌܊��o�͊e�X�̋C��������łǂ��ɂ��Ȃ肤��B
�܂��Ă�n�D�i�c�_�ɒl���Ȃ��ł���B
�X�s�[�J�[�P�[�u���H
�����Ď����ĂˁB���ŏI�B
�����ԍ��F22965306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
bebez����A������
4S11�͍��悪������̂ŁA4S8������ł��B
�����悪�L�c�C��������4S8G�ł����A2426��R7�Ȃ�G�Ȃ��������Ǝv���܂��B
2235�͂��Ƃ͂����Ⴏ�C���Ȃ̂ŁA�}���`�ɂ��ăA���v�����̕��������������Ă܂Ƃ܂�Ղ��Ǝv���܂��B
R7��97dB/W�Ŕ\���Ⴍ�A���肪�z�[�����ƐZ���͂Ȃ��̂Ŗ�s���ł́H���ʂɃz�[���c�C�[�^�[�ɂ���R7��16kHz�ȏ�Ŗ��t�����x�ɂȂ��̂��悢�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22965505�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���I�̉��������m����A�����́B
>�[���I��DF 1��DF 100�̏�Ԃ����A
>��r�����Ɣg�`���v�������v���O�ł����A
DF�� 1 �� 100 �ƂȂ�A�q�g�������Ă������킩��Ǝv���܂���B
>�ǂ�ȃV�X�e����A�N�Z�T���[�ŁA�ǂ�Ȋ�������Ńe�X�g�����Ċm�F�����̂��H�A
>�Ɩ����ƃX���[����鏊������ƁA�E�L�y�f�B�A�ɏ����Ă��鎖�Ƒ�������A
>�Ƃ������_���̗l�ł��ˁB
����܂��������H���́u�P�[�u���̍���������ɂ̓q�g�̊��o�͌덷���傫������v�Ƃ������咣�����܂��B��������Ǝ����g�����������ʂ́i�ς�����ɂ���ς��Ȃ������ɂ���j�����ɂȂ�ɂ����̂ŁA�������̎咣�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�܂��A�����镨���������Ƃ͕s�\�ł�����A�Ȋw�ōl���邱�ƂɂȂ�܂��B
���ꂩ��AWiki ��_���ɂ��Ă���킯�ł͂���܂����B���X�́u�ς�����I�v�Ƌ��Ԑl�ׂ̗Łu�������ȁ`�v�Ǝv�����̂����������ŁA�����Ōv�Z����悤�ɂȂ�������ł��B���������◝���͏����̂��ǂނ̂��ʓ|�Ȃ̂ŁAWiki �����p�ł���Ε֗��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
>���́u���v���ĉ��̂͑�l�C�Ȃ����A�u���v�Ƃ������̂ł��B
����͂킩��̂ŁA�G�k�X���≏�����Ԃ��悤�Ȃ��Ƃ͂��܂��A���J���ꂽ����X���Ńz���g�̂��Ƃ������l����l�����Ȃ��̂̓L���`�����C�ł��B���������Ȃ��Ƃ����������������̂ŁA���ǂ��̌��t��q���āu�Ȋw�҂Ɏ����X����v�Ƃ����̂��{���ł���(��)�A���������u���̌l�̐^���v��\�����邱�Ƃ����R�ł����A�ǂl�͍D���Ȃق���M���邾���ł��傤�B
# �ƁA����ȕ��Ɍ��̂����Ȃ�ł���ˁB�B
�����ԍ��F22965533
![]() 12�_
12�_
�����I�̉��������m����
����ɂ��́B
�Y�t����������URL�q�����܂����B
�@100Hz�p���X�M�����ăp���X��5ms�̋�`�g���Ă��ƁH
�@�ǂ��̓d���𑪒肵�Ă���́H�@�X�s�[�J�[�q�[�H
�ȂǁA���^�₪�łĂ��Ă��܂��܂����B
�K���A�I�[�f�B�I�X�N�G�A����͓���݂�����̂ŁA���x�������Ă��炨�����Ǝv���܂��B
��fmnonno����
��肪�Ƃ��������܂��B
���g���Ă���̂�OFC�Ȃ̂ŁAG�ɂ�����Ɩڂ��s���܂������A�܂���4S11���ȂƎv���Ă��܂��B
�����[���E���t����
�P�[�u���Ɋւ���m�����قƂ�ǂȂ������̂Ŏ��₵�܂������A
�F����̃R�����g�ŁA���ɋ�����3���i�͂��������ԂŊԈႦ�̖����i�ł��邱�Ƃ�������܂����B
���ɂƂ��ẮA����͑傫�Ȏ��n�Ȃ̂ł��B
���������͂��������ʂ�ł��ˁB
�������ɂ悵����
2235H�͐���������Ƃ����̂͂��������ʂ�B
���������Ƃ͂���܂��Am0��155g������̂ŋt�N���傫���̂��Ǝv���܂��B
2235H +2426J��2Way����{�Ƃ��Ă���̂ŁA2426J�̍���̓J�b�g�����APT-R�VIII�̓A�h�I����ST�Ƃ��Ė��t���Ɏg���Ă��܂��B
�J�b�g�I�t�̓q�A�����O�Ō��߂܂������Afc=10��Hz�i-3dB�j�A2���A��=0.7�AMid�ɑ��ċt�����x�X�g�ł����B
�����ԍ��F22965632
![]() 4�_
4�_
bebez����A�����́B
���uOFC�v�Ȃ�A��������̂܂܈ێ����āA
MOGAMI 3103�ŗǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
Belden�͒�Ԃ�8460/8470/9497�Ńe�X�g�����܂������A
�ǂ����X�Y���b�L�ƁA�����ɂ��Ă͑����������̉e�����A
����ɕȂ������悪�ׂ��Ȃ�X���ł��B
8477�͑��������͉�������邩������܂��A����͂ǂ��ł��傤���H
�܂��A�Ȃɂ��D���D��Ńr���H���p�̃P�[�u�����g�����Ƃ��Ȃ����Ǝv���܂��B
CANARE�́A4S8/4S8G/4S11/4S11G/4S12F�������܂������A
4S11/4S12F�͂��܂������Ȃ��A�Ƃ��������ł��܂͎g���ĂȂ��ł��B
4S8���ʁi40m)�ɂ�������Ƃ����̂�����܂����B
MOGAMI��3103�ł͂Ȃ�3104���g���Ă��܂��B
8sq�Ȃ�ŁA�o�i�i���K�{�ɂȂ�̂ł����ȒP�ɐl�ɂ͊��߂��܂��B
���̒��ł́A3103���B��OFC���g���Ă���P�[�u���ł�����A
����𐄏����܂��B
���܂�����Ƒg�ݑւ����Ȃ̂ŁA3104�͂��炭�g���ĂȂ��ł����A
��X�́A2215B+2450J(or2440)+2405(or2420)�̒��Ɏg���\��ł��B
���������ł��̂ŁAJBL�̓}���`��ڎw�����炢�����ł��傤���H
�����ԍ��F22965703
![]() 3�_
3�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ� ����
�����́B
��DF�͂���������10������イ�Ԃ�ł����āA�^��ǃA���v�������Α��̃V�X�e����
�����ł��Ă���b�ł��傤����ADF���l������Ӗ��͂Ȃ��A�Ƃ����̂��^���ł��傤�B
��DF�� 1 �� 100 �ƂȂ�A�q�g�������Ă������킩��Ǝv���܂���B
���̃u���O�́ADF 1��DF 100���r����Ƃ������A
�v�ʂ��DF 800�Ɣ�ׂāADF 1�̎���DF 100�̎����r�����������z���Ǝv���̂ŁA
������Ă��鎖�ɐ��������Ȃ��l�Ɋ�����̂ł����B
DF 1��DF 100�A�ǂ���̎������z�ɂ��A
���X�g���[�g�ڑ��ɔ��
�Ə�����Ă���̂ŁB
�uDF�͂���������10������イ�Ԃ�v�ł͂Ȃ�����A
DF 800�ɂ����Ӗ��������������Ǝv���̂ł����A�@���ł��傤�H�B
���A
���A���v���[�J�[���Z�[���X�g�[�N�̂��߂ɂЂ˂�o���A
�P�[�u����������ɏ������`�Ő��̒��ɗ��z���Ă����̂��낤�ƍl���Ă��܂��B
���̏������݂�����ƁA���̃u���O�̔�r�����̊��z�͉R���Ƃ������ł����H�B
PS
������܂��������H
�K�E�d���l�̗l�ȃn���l�̕��ɉ��x������Ă��܂�����B
�����ԍ��F22965747
![]() 3�_
3�_
��blackbird1212����
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
���ۂɎg�p���ꂽ��ł̃R�����g�͑�ώQ�l�ɂȂ�܂��B
JBL�͍��Ȃ̂ŁA����ێ��̂���ł��B
���[�J���̖{�i�I�ȃX�s�[�J��93�N��DS-2000Z�����̂��Ō�Ȃ̂ŁA�v�X�Ƀ��[�J�������邱�Ƃ��l�����ł��B
���́A�����AB&W�����@�킩�������Ă����̂ł����A���i�E�T�C�Y�I�Ɏ˒����ɂ���804D3�͂��Ȃ�C�ɓ���܂����B
����Ȃ���800D3������ł��A�\�����͂̂��鉹�����Ă���܂����B
�������A���̉����o���Ƃ���JBL�����|���܂����A�g�[�^���̖��͂Ƃ����_�ł͍b���t����Ƃ����������ł��B
�o����A�����Z�b�g�����Ă��A���ǂ��C�ɓ����1�Z�b�g�����g��Ȃ��Ƃ����̂������ł����A
����JBL��804D3�Ȃ�A�C����\�[�X�ɂ���Ďg�������āA�{�y���߂�悤�ȋC�����Ă��܂��B
�Ƃ͌����A�����������ł͂Ȃ��̂ŁA�T�d�̏�ɂ��T�d�ɂƎ��������߂Ă���Ƃ���ł��B
����������������ŁA������Ƌ����C���Ȃ̂ŁA����Ƃ͖��W�Ȃ��Ƃ����炾�珑���Ă��܂��܂��������e�͂��B
�����ԍ��F22965791
![]() 2�_
2�_
���I����
�܂��܂��A�����łP��
https://www.youtube.com/watch?v=56Hvoqgdlfk&list=RDMM56Hvoqgdlfk&start_radio=1
�Ӗ��[�ȉ̎��ł����A�Ȃ�ƂȂ��P�[�u���̘b���Ƃ��ADF�̘b�����ł邽�тɖl�͂��̋Ȃ͎v���o�����肵�܂��B
���̃v�����X�l�̋Ȃ��J���@�[�����O���[�v������̂ł����ADead Or Alive�Ȃ�B
���[�_�[�̃s�[�g�E�o�[���Y����́A���ʂɂ����������̂ɁA�����̗e�p�ɂ������R���v���b�N�X�������āA�߂���߂���q�b�g�\���O���o���āA��������ɂȂ����̂ɁA���̂��������ׂĔ��e���`�ɂ����݁A����Ɏ؋��܂ł��āE�E�E�E�E��p�̎��s�Ŋ�͂߂��Ⴍ����A�g�̂�����Ń{���{���ɂȂ�A�Ō�͑������o���������Ȃ��āE�E�E�E�E�E�Ȑl������݂܂��B����Ȕނ��A���̋Ȃ��J���@�[���Ă����킯�ł��B
���Ȃ݂ɁA�v�����X�l�ƃs�[�g�͓����N�Ƃ������܂��t���E�E�E�E�E�E
�Ȃɂ��A�I�[�f�B�I�}�j�A�ɒʂ��鏊������悤�ȋC�������������ł���ˁB
�I�[�f�B�I���ێq��K�I�ɉȊw�Ō��̂��܂�Ȃ����A���Ƃ����āA�����ɋN�������ۂ��Ȋw�I�Ȍ��������ɃI�J���g�ŕЂÂ���̂��Ȃ��˂�
�܂��A�K�x�Ɋy���߂��炢��Ȃ��̂��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁADF���P�O�ȉ��̃A���v���Ă̂���R�����Ăł��ˁA�^��ǃA���v�i�V���O���h���C�u�j�͑�����DF���P�O�ȉ��ł��B
���āA��悪�ǂ��̂Ƃ����Ƃł��ˁA�^��ǃA���v�͈ӊO�ɒ�悪�ł�悤�Ȋ����ŁE�E�E�E�E�������A�o�͂͂P��
�����ŁA�g���f�����_�����܂�܂���
�^��Ǐo�͂R�{��
����Ȃ�A�A���v��Ԃ��h�����炢��ˁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E
����ɁADF���Ⴗ���āA���̐��䂪�o���Ă��Ȃ�����A�E�[�n�[�Ɂu�����Ă��[���v�Ŏ����ɖ��Ă邩����Ƃ�������抴�����邾���B�o�͂��A���������A��ʉƒ�ʼn��������̂Ȃ�A�PW��������������̏ꍇ�͉��ʓI�ɖ�肪��������A�������ꂾ���Ȃ�ł���ˁE�E�E�E�E�E
�������ȁADF�ꌅ�̃A���v�����ɁA�^��ǂ̃A���R�����R�{�ɂȂ����Ƃ��Ă��A�������������ɂ��Ȃ�A�o�͂�����قǑ傫���킯����ˁ[�ׂȁA����Ȃ�A�^��ǂP�O�O�{�����炢�̐�����^�����Ƃ��v���킯�ł��E�E�E�E�E�E���A�܂��A����Ȃ��Ƃ�^�ʖڂɘ_���Ă�������ʔ����Ȃ��̂ŁA���������̂́u���ԓ��v�Łu�����n������ˁ[�́A�Ȃ]�_�ƋC��肵�ĂĂ����v�Ƃ���Ă��������ł���B
�m���Ƃ��Ă̓A���ł��A�u�����h�x���Ȃ�ď����Ȃ炵�Ă�Ⴂ��v�ł��B�i���A�ł��A�����Ă��l�͐�͂̋@�e�ŗ��Ƃ����Ƃ������r���X�[�c���Ƃ��Ă͍ň��̕s���_�Ȏ��ɕ����Ă��ŁE�E�E�E�E�E�j
�Ƃ����s��ȑO�u�������āA�{��
�Ȃ̂ŁA�l�͐l�ɂ́u�X�s�[�J�[�P�[�u���́A���߂̓����Ȃ炢��Ȃ��ł����v�Ƃ����R�����g��f���A�����ł͔�Ȋw�I�Ȏ��������āAMIT�̃P�[�u�����g���Ă����肷��킯�ł��B
�����A����X�s�[�J�[������Ă��āA�t�������W�P���ŁA���j�b�g����^�[�~�i���ɂȂ��Z�������P�[�u���́A��������Ɗm���ɉ����ς��̂ŁA�ϋɓI�Ƀ`���[�����ɃP�[�u���ō��킹�Ă��܂��B����́A�Ȋw�ł͏ؖ��ł��Ȃ���Ȃ����Ȃ��E�E�E�E�E�E�E���ۂɁA�o������X�s�[�J�[�G���W�j�A�̐l�B���A�^�[�~�i���̏d�v���͂������̂��ƁA�����z���͊O���P�[�u�������e�����傫���悤�ȋC������ƌ����Ă��܂����B�����P�[�u���̏ꍇ�ɂ́A���̖̂�肾���łȂ��A�U���ɂ��e���������ł����ǂˁB
�Ƃ������ƂŁA�l�̑̌���悩�����`���[���Ƃ��ẮA�����P�[�u�����_���v���Ă݂Ă��������E�E�E�E�ł���
���ꂾ�A���I����A���F����R�₵�āA�����뎯�ɖڊo�߂�ƁA���̕ӂ̂��Ƃ��킩��̂�������܂���ˁB
�����ԍ��F22965926
![]() 3�_
3�_
��bebez����
���͂悤�������܂��B
�ڎw���P�[�u���̕������́A�����Ă��܂����ł��傤���H
�v���̕��́A�{�����[������x�������ꂽ�Ƃ������Ƃł����A
�C������͂�������قǂ������ł��傤���H
������Ɗ�蓹�Ȏ���ł����A�\����܂���B
�����ԍ��F22965960
![]() 0�_
0�_
���h�b�h�R���b�c����
���͂悤�������܂��B
���̓��e�ɊS�������Ă��������A�������v���܂��B
����������������܂����̂ŁA���������܂��B
C-260�̃{�����[��������1���~������Ƃ������ƋL�����Ă��܂��B
�{�����[���̓v���A���v�̎�v�p�[�c�Ȃ̂ŁA�Z�p���܂߂Ē艿��1�����x�͊o�債�Ă����̂ł����A���̈����ɂ͋����܂����B
�������ꂽ�{�����[���͑��슴�����サ�Ă���A�ȍ~�A��K�����łȂ��������Ƃ���A�ϋv�������サ�����Ǖi�������Ǝv���܂��B
�{�����[�������ɍ��킹�āA�����Ń����[���u�������ナ���[�v�Ɍ������Ă���܂����B
���̎��ł́A����������������邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A�T�[�r�X���f���炵���Ɗ����܂����B
C-260��P-360���w������27�N���g���܂������A�C���ɏo�����̂͂���1���ł��B
�i�w�������P-360�̏����̊J�ɕs������������Ă��炢�܂����̂ŁA�����Ɍ�����2��ł��B�j
�A�L���t�F�[�Y�͐��\���ǂ��ł����A�ϋv�M��������уT�[�r�X�̓s�J�C�`�Ǝv���܂��B
�܊p�̋@��Ȃ̂ŁA������ƒ����Ȃ邩������܂��A�ŋ߂������A�L���t�F�[�Y�̐_�Ή����Љ�܂��B
���N�A20�N�Ԃ��CDP��DP-430�ɍX�V���܂����B
�w������ɁATV�i������A���N�w���j�������f�W�^�����͂����Ƃ���A�r�b�g���\���ɕs���ȓ�������܂����B
�����ɏǏ���A�L���t�F�[�Y��TV���[�J�ɘA�����܂������ATV���[�J�́u���̌댟�o���낤�v�Ƃ̉B
����A�L���t�F�[�Y�́ADP-430 �̕ʂ̌̂ƁA���o���@���قȂ��ʋ@���DP-560���Q�Ō���m�F�ɗ��Ă���܂����B
������TV�ƕ�����CDP���g���������̌��ʁA�\������TV���̖��ł��邱�Ƃ͖��炩�ɂȂ�܂������ATV���[�J�͂Ȃ��Ȃ����А��i�̕s��ł��邱�Ƃ�F�߂܂���ł����B
�ŏI�I�ɂ́A�A�L���t�F�[�Y����TV���[�J��DP-430��݂��o���Ă��炢�ATV���̖��ł��鋤�ʔF���������܂����B
���̌�ATV���[�J�ő�\�t�g���쐬��TV�ɃC���X�g�[�����Ă��炢�܂������A�A�L���t�F�[�Y����̎x�����Ȃ���ΈÏʂɂ̂肠���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
��\�t�g�́A����A���C���K�p�������Ƃ̂��Ƃł����B
���А��i�ɂ͑S���Ȃ��Ƃ������܂ł���Ă����Ƃ����̂́A�_�Ή��Ƃ��������悤���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F22966407
![]() 5�_
5�_
��bebez����
��O�I�Șb�ł����A
���N��7���ɁAWIREWORLD Luna(4�c) �X�s�[�J�[�P�[�u�����ɏ�����1���[�g�����Ŕ��艿1200�~���ō�108�~�������̂ŁA�v�킸20���[�g�����A4�c�𑩂˂�1�{�̃P�[�u���ɂ��āA�v���X�A�}�C�i�X��2�{�ɂ��Ďg������A����������ł��傤���A�𑜊��̍������ꂢ�ȉ��ɂȂ����̂ɂ͊��������̂ƁA���i�����܂�ɂ����������̂ŁA�ʂ̕����ɂ�����I�[�f�B�I�ɂ��g�����ƁA��������ɁA�܂������ɍs���܂����B
�P�[�u���ʼn��͕ς��Ȃ����A�u���[�V�{���ʂ��Ƃ����������܂����A�I�[�f�B�I�̋@��ɂ���ẮA�P�[�u�����������邾���ł��������シ�邱�Ƃ́A�̌��������̂łȂ��ƁA���̈Ⴂ�Ƃ����ʂ͕�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�����A����͂��܂��܌����Ŕ������̂Ō����͂��܂������A1���[�g�������萔��~�̂��̂ɂ͂Ȃ��Ȃ���͏o���܂���ˁB
�����ԍ��F22966411
![]() 4�_
4�_
�l�b�g���[�N�̃R�C�����E�[�n�[�̎�O�ɂ��邱�Ƃ������ł����ASP�P�[�u�������ł̒�惌�x���̕ω��͑傫���A���ɕs����ȕ��ł����郌�x���ł��傤�B
������₷�����邽�߁A����0.75�X�P�A��3.5�X�P�A�i�ł���Γ��ꃁ�[�J�[�j����芷���Ď�������A�o����u���C���h�ŁB
1 �E�[�n�[��30cm
2�@�P�[�u�������Б�5M
3 �A���v8���~�ȏ�̃v�����C�������̓��C���A���v
���̈Ⴂ�͉Ȋw�I�ɂ��ؖ��o����Ǝv���܂��B
�������A�R���|�ŃA���v�ASP���g�ݍ��킳��ăP�[�u������1M���x�Ȃ番����Ȃ��\��������܂��B
�����ԍ��F22966426
![]() 1�_
1�_
�������������݂Ȃ����
���̎���ɑ��A�����̗L�v�ȏ��E�R�����g�����������A���肪�Ƃ��������܂����B
�����A�I�[�f�B�I���͈ꉞ40�N���ł����A�P�[�u���Ɋւ��Ă͂��Ԃ̑f�l�ł��B
�����i�Z���j�A�]���������Ȃ����̂Ƃ����w�j��3���i�����ɂ��܂������A�u����ł����̂��ȁv�Ƃ����^�₪���莿�₢�����܂����B
�݂Ȃ��炢���������R�����g�ŁA���ɋ�����3���i�͒�ԂŊԈႦ�̂Ȃ��i�ł��邱�Ƃ��ǂ�����܂����B
����́A�S���m���̂Ȃ����̂ɂƂ��ẮA���\�傫�Ȑ��ʂł��B
�܂��A�������I���̂��S���������Ă̂��̂ł͂Ȃ������Ƃ������ƂŁA������ƈ��g�����Ă��܂��B
GA��t���������͑����������̂ł����A���̌��Ɋ�Â�����ɃX�g���[�g�ɉ������������̒�����I���Ă��������܂����B
Foolish-Heart�����blackbird1212����ɂ͂������̃V�X�e���̏Љ�����������y�����q�������Ă��������܂����B
����E��ʂ��āA���������ғ��m�̃R�~���j�P�[�V�������}���̂͐S�n�̗ǂ����̂ł��B
�I�[�f�B�I��40�N���Ƃ����Ă�����20�N�͋x�~��ԂŁA�I�[�f�B�I�G�������قƂ�Ō��Ă��Ȃ��̂ŁA���S�҂ɋ߂����ʂ��������܂��B
�]���āA�܂������I�Ȏ�������邱�Ƃ����낤���Ǝv���܂����A�t�������Ă���Ă��������B��낵���B
���A�{��̃P�[�u���Ɋւ��Ăł����A�܂��́A��ԃ��[�R�X�g�ȃJ�i�����g���Ă݂悤���Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B
�����ԍ��F22966467
![]() 2�_
2�_
��hironhi����
108�~�ł����B����͖���ԍ��d�����ł��ˁB
�����܂������b���ł��B
������������
���̎������@�͗��ɓK���Ă�Ǝv���܂��B
���I�̉��������m���\��ꂽ�I�[�f�B�I�X�N�G�A�̎����́A���̕��@���ɒ[�ɂ������̂��Ǝv���܂��B
����������Ɓu�P�[�u���̑f�l�������ق����v�ƈꑛ���ɂȂ邩������܂��A���͈ȉ��̂悤�ɍl���Ă���܂��B
�P�D�������������Ō����A�P�[�u���i�ڐG��R�܂ށj�̒�R�i���m�ɂ̓C���s�[�_���X�j�̓[���ɋ߂������ǂ��B�܂�A�����Z���ł��B
�Q�D�A���A�e�A���v���[�J�̓X�s�[�J�ɃP�[�u���łȂ��ōŏI���m�F�i�����j���s���Ă���̂ŁA���Ƃ��Ă͉��m�F���̃��C�A�E�g�ɋ߂������ǂ��Ȃ�ꍇ�͂���B
�@�@�Ⴆ�A�A�L���t�F�[�Y��800D3�Œ������Ă���̂ŁA800D3�i�܂���800�V���[�Y�j���A�L���t�F�[�Y�Ŗ炷�̂ł���A�P�[�u�����܂߃A�L���t�F�[�Y�������̃��C�A�E�g�ɋ߂Â���Ɨǂ����ʂ���\���������B
�R�D�u���������ׂ����̕����ǂ������o��v�A�u�P�[�u�����͂�����x���������悢�v�A�u�����ƒ����̃o�����X������v�Ƃ����̂͊ԈႦ�Ƃ͌����Ȃ����A����̓P�[�u���̃C���s�[�_���X�ɂ���Ċɂ��Ȃ�����悪�ʊ��𑝂����ʂƂȂ�A���ꂪ�����l�̍D�݂ɍ����Ă���Ƃ������Ƃł���B�P�[�u���Ń`���[�j���O����Ƃ����̂́A�A���v�̏o�͔g�`��ω������čD�݂ɋ߂Â���Ƃ������Ƃł���B
�S�D�P�[�u�����A�����A��R���قړ���ł������ɂ���ĉ��ɍ����o��̂́A���V�e�ʂƋ͂��ł͂��邪�P�[�u����L�����̈Ⴂ�ɂ��Ƃ��낪�傫���B�v����ł͑���ł��Ȃ����x���̍��ł����Ă��A�������������l�͂���B
�T�D�z���̕����ɂ���ĉ����ς��Ƃ����̂͗����ł͐��������Ȃ����A���Y����Ɍ��炸�A�v�������銴�������X�y�V�����X�g�͌�������B�i����́A���̌�����ł��B�j
���̏ꍇ�́A�X�s�[�J���ʼn��`���[�j���O���s���̂ŁA�����Z���������Ǝv���Ă��܂��B
���[�J���̃X�s�[�J���g���ꍇ�́A�܂�������ƈ���Ă��邩�ȂƂ��v���܂����A�����܂Œ����������鎩�M�͐�������܂���B
�����ԍ��F22966546
![]() 1�_
1�_
���̃X���ʼn��Ă���n���ق���̃z�[���y�[�W�����Ă�����A
https://souzouno-yakata.com/audio/2002/05/09/2144/
���������B�P�[�u���ɂ��ẮA������Q�l�ɂ��������Ȃ����ȁB
�X���傳�A�v����ō����Ȃ��Ă��m�o�\�Ƃ����Ă��邪�A�v����ő��肵�Ă���T�C�g�͂���B
http://archimago.blogspot.com/2015/06/measurements-speaker-cables-wires.html#more
15�N�g�����P�[�u���Ȃǂ�3�q����11�t�B�[�g�ɂ������҂��t�����P���V���^�C���Ɠǂ�ł���P�[�u���ƃJ�i����4�t�B�[�g��4S11�P�[�u�����r���Ă��邪�A���g�������̑�����A���ԗ̈�̃C���p���X����������قƂ�Ǔ����ł���B
�����ԍ��F22966699
![]() 3�_
3�_
���I�̉��������m����A������ƖZ�����Ēx���Ȃ�܂����B
>���̏������݂�����ƁA���̃u���O�̔�r�����̊��z�͉R���Ƃ������ł����H�B
��̓��e�́A���͂܂��߂Ƀu���O�������ɓ����Ă��܂��܂����i���݂܂���j�B"DF 1" �̂ق��͒u���Ƃ��� "DF 100" �̂ق��ł����A�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�� 0.01���B������ 0.1�� �̒�R����ꂽ�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�X�s�[�J�[�� 8�� �Ƃ����
DF = 8 / ( 0.01 + 0.1 ) = 72.7
�ƂȂ�܂��ˁB����� "DF 100" �Ə̂���̂͂��������A�o�E�g�Ȑl�X�E�E�E�C���ȗ\�������܂��B����͂܂������Ƃ��āA�C�ɂȂ����̂́A�X�g���[�g�ڑ��� 0.1�� �}���ƂŔg�`�̐U�������Ȃ�Ⴄ���Ƃł��B�������� 2/3 �ɂȂ��Ă��܂��ˁB
�u�g�`�̍������Ⴂ�̂́A��R�ŐM���������������߁v�Ə����Ă���܂����A������ƍl���Ă݂Ă��������B�X�s�[�J�[�̕����̓X�g���[�g�ڑ��� 8/8.01 �ŁA0.1�� �lj��� 8/8.11 �ł�����A���҂̔�� 8.01/8.11 = 0.988 �ƂȂ�͂��ł��i���Z���Ă݂Ă��������j�B
�Ȃɂ��̊ԈႢ�Ȃ̂��Ӑ}�I�Ȃ̂��͂킩��܂��A���̎����͂߂���߂���I�J�V�C�ł��BDF=2 ���炢����Ȃ��ł��傤���B���_�A�����̊��z���M����ɒl���܂���B�̔��X�̃e�L�g�[�ȑ���͂܂܂���܂����A�����܂Ńq�h�C�̂͏��߂Č��܂����B
�����ԍ��F22966864
![]() 6�_
6�_
��bebez����
�����́B���[�J�[�_�Ή��̘b���肪�Ƃ��������܂��B
�������悢��A���v�̎�芷�������ɂȂ��Ă��Ă���܂��̂ŁA
�߁X�����ɏo�����悤�Ǝv���Ă͂���̂ł����A�Ȃɂ��A25�N�Ԃ肭�炢�ɂȂ���̂ŁA
���X���������܂���B���b�N�X�}�������ɋ����Ă����̂ł����A�_�Ή��̘b�ɂ��
�A�L���ɂ��S�������Ă���܂��B30�N�����ĂA�����Ō�̃A���v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
��l�����Ă��������܂��B
���P�[�u���Ɋւ��Ăł����A����b���o�Ă��Ă���܂����A���ɂƂ��Ă̓`���v���J���v���ł������܂��B
�o�������ŁAbebez����̂��C�ɓ���̉����o�Ă��邱�Ƃ��F���Ă���܂��B
�����ԍ��F22967148
![]() 1�_
1�_
�t�[����A�����́B
�]�f�B�A�b�N�u���C�u��m��Ȃ����炩~(��)
�ʂɘ_���������͖����̂ŁA
���F����R�₵�Ă��������A�������߂��Z���ĂȂ������B(��)
�Y�� ����͐��I�Ȓm�����������Ȃ̂ŁA�^��Ɏv���Ă��������Ă݂���������ł��B
���̕���_�j���邾���̒m���͎������킹�Ă��Ȃ��̂�...
�P�[�u���ʼn����ς��A�ς��Ȃ��̗ނ͎��X�_���ɂȂ��Ă��邻���ł����A
�ω����A�̌��������̂���l�́u�ς��v�_�҂��낤���A
�̌��̖����l�́u�ς��Ȃ��v�_�ҁB
�i���ɕ��s�����낤���A����ŗǂ��Ǝv���܂����A�o��������ł́u���z�v�́A
�l�̐^���Ő��E�̐^���ƃC�R�[���łȂ��Ă����������A��x�͏����Ă������ƍl��������ł��B
�܂��[������������ƌ��������A�s�����ƌ����������R���ȁA�ƁB
�Ȋw�ɂ����������ȏ�������A�������ۂ��N�����Ă���̂�
�H�ׂđ̒��Ɉُ킪�Ȃ���u���y�v�A�H�ׂđ̒��Ɉُ킪����u���s�v�B
�Ȃ��Ȃ�...
���Y��悤�ɂ��������Ȃ� ����
�����́B
���Z�������A����Ԃ���点�܂����B
�u�_���s���O�E�t�@�N�^�[800�͕ۏؒl�ŁA���ۂɂ͂���ȏゾ�����ł��B�v
�Ə�����Ă���̂ŁA
�Ȃ̂�DF 850�ʂƉ��肵�āA8��(0.0094+0.1)=79.25�B��DF 80�B
��DF�͂���������10������イ�Ԃ�ł����āA�^��ǃA���v�������Α��̃V�X�e����
�����ł��Ă���b�ł��傤����ADF���l������Ӗ��͂Ȃ��A�Ƃ����̂��^���ł��傤�B
�Ƃ�����̂ɁADF 20�̍��ɁA�������^���������̂ł����H�B
8��(0.0094+0.1)=79.25�A��0.1���̒�R�}���������̂��A
�����̎����͂߂���߂���I�J�V�C�ł��BDF=2 ���炢
�Ƃ�����Ȃ�A10���̒�R��}�������A8��÷10��=0.8��DF�́H�B
���n�̎����x�̒m���ł́A�A�L���̐l�Ԃ��ւ���Ă��錟�ɓ��ɃI�J�V�C�������o���܂���B
��bebez ����
�����́B
�ǂ����b���܂����B���ʁA���X���������Ă���Ȃ��ł���...
���A�L���A�Ƃ��������ł��ˁB
�l���������Ȃ��͈̂ɒB����Ȃ���ł��ˁB
�����ԍ��F22967313
![]() 1�_
1�_
�����I��������ȁH
���Z�����
���݂��g���̃P�[�u����
�^�[�~�i�����t���A���[�^�[�蔄�荂���P�[�u��15�a�q���ŃX�s�[�J�[���Ɏ��t����
�o���͍����P�[�u���̎��������Ȃ�o�܂��B
���ɓd��������}�C�i�X���A�Е��ł����ʗL��܂��B
������15�a�̍����P�[�u�����q�������ł��B
�����̃X�s�[�J�[�̓g���C���C�X�s�[�J�[�^�[�~�i���A
�A�R���o�̕���A�_�v�^�[�^�[�~�i�����g�����ݔ̔�����ĂȂ�PCOCCA��
15�a�g���Ă܂��B
�������ނ̃����A�����������Ăȉ��ɕω��B���Ȃ�̌��ʂł������オ��B(��)
�X�s�[�J�[�����z����������y�ł��ˁA(��)
�o�C���C�ɂ��됳�����q�������Ă����ċt�N�d�͋N�����Ȃ��B
����Ȃ����B
�����̓X�s�[�J�[�P�[�u���ʼn����ς�����X�s�[�J�[�P�[�u���Řc�݉����N�����Ȃ����g�݂ł��ˁB
�����ԍ��F22967569�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���I�̉��������m����A�����́B
������ɂ��������邱�Ƃ͍\��Ȃ��̂ł����A���I�̉��������m����̂��咣�₲����́A�_���I�ɐ�������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�ȉ����̎����������A������ɂ��������܂��B
>��DF�͂���������10������イ�Ԃ�
�i�����j
>�Ƃ�����̂ɁADF 20�̍��ɁA�������^���������̂ł����H�B
�u��10����DF�l�ɈӖ����Ȃ��v�Ƃ����͎̂��̌��ŁADF���Ȋw�I�ɗ������Ă���l�݂̂��m���Ă���b�ł��B�ł��A���������l�X�͒m��܂����ˁH DF 100 �� 800 �������悤�Ƃ��Ă���ʂł�����B
�Ȋw�I�ɗ������Ă��Ȃ��ނ炪 DF=72.7 �� 100 �Ɋۂ߂Ă��܂����ƂɁA�����^���������̂͂�����������܂����ˁB
�ŁA�ۂ߂��������܂�ɃA�o�E�g�Ȃ̂Łu�A�o�E�g�Ȑl�X�Ȃ̂ł͂Ȃ����v�Ɗ뜜�����킯�ł����A�Ȃ��u�A�o�E�g�v���C�ɂ��邩�Ƃ����ƁA�����I�[�f�B�I���͒����A�ǂ�ȍ��ׂȂ��Ƃ����i�����j���Ƃ��܂��Ƃ���Ɛ_�o�����茸�炷�@�ׂȎ���Ǝv���Ă��邩��ł��B
�|���Ĕނ炪�A0.1dB���x��������������ɒ���ł��鎖�Ԃ�F�����A�����̏������ł��Ă���Ƃ͎v���Ȃ��A�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��i��ۂȂ̂ň٘_�������Ă�����܂��j�B���ہA�ނ�̓I�V���̔g�`���x�����u�I�J�V�C�v�ƋC�Â����Ƃ��ł��܂���ł����B
>�����̎����͂߂���߂���I�J�V�C�ł��BDF=2 ���炢
>
>�Ƃ�����Ȃ�A10���̒�R��}�������A8��÷10��=0.8��DF�́H�B
���̂�����Ɏ��������邱�Ƃɂǂ̂悤�ȈӖ�������̂ł��傤���H������̂��ʓ|�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����ɈӖ����킩��Ȃ��̂ł��B
�����A�������₳���Ƃ������Ƃ́A��L�uDF=2 ���炢�v�̗��R�𗝉�����Ă��܂���ˁH���̐�̓��e�́ADF�̒�`��m���Ă���Ε��n�̂����ł��v�Z�ł���悤�ɏ����Ă��܂��̂ŁA������Ƃ����g�ōl���Ă݂Ă��������i�~�Q�ł�����������܂��j�B�Ȋw�́i���Ăقǂ���Ȃ����ǁj�A�ь��������薡���ɂ����ق��������ł���B����]�Ȃ�ł���͈͂ł��������܂��B
>���n�̎����x�̒m���ł́A�A�L���̐l�Ԃ��ւ���Ă��錟�ɓ��ɃI�J�V�C�������o���܂���B
�O�q�̒ʂ�A���n�ł��������傤�Ԃł��B�����u�A�L���̐l�Ԃ��ւ���Ă��錟�Ɂv�̘_���I�Ӗ����킩��܂���B�u�A�L���̐l�Ԃ��ւ���Ă���̂�����I�J�V�C�͂����Ȃ��v�ƕ������܂����A������������ς������댯�ł��B���I�̉��������m����͐���ςɍ��E����₷���l�A��������܂���B
���̎����ɃA�L���t�F�[�Y�̃G���W�j�A���Q�����Ă����̂��Ƃ���ƁA���̓��Ђւ̐M���͒n�ɗ����܂��B���ۂ́u�A�L���t�F�[�Y�̒�āv�ɂ����Ȃ��悤�ł��ˁB���������ׂ��������ɂ��C��z�肽���ł��B
�����ԍ��F22967895
![]() 6�_
6�_
�����[���E���t����
��bebez����
�����́B
���̂P�T�Z���`�̘b�́A�Q�T�N�O�قǁA�X�e���I�T�E���h�Ƃ����{�ɋL�ڂ���Ă��āA�F�l���������Ă��܂����B
�F�l�͖������Ă܂����B
�K�\�����ɏ����n�C�I�N�����銴���ł��傤���B
�Ⴄ���ȁB�a�o���a�R(^^�U�B�B�B�B��ʤ���ڲ
�����ԍ��F22967911
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ� ����
�����́B
�u��10����DF�l�ɈӖ����Ȃ��v
����͐�10���z������100�A500�A1000�ł��낤��
�u�Ȃ��ς��Ȃ��v�u�Ӗ����Ȃ��v�Ƃ̎咣������Ă����ł�����A
��80��100�ɌJ��グ��(��20)�̈Ⴂ��
���^���������̂͂�����������܂�����
��������ꂽ��A�������ݍ����Ă��܂����b�ɂȂ�Ȃ��ł��B
��10��1000���ς��Ȃ��̂ɁA��20�̌J��グ�ɋ^��������鎖��
�u�咣�ɐ��������Ȃ��v�u���������v�Ɗ�����������ʂł��B
�ۂ߂���DF 100�ɂ���̂�0.08���̒�R���g�����A0.1����10���̒�R���g������
������Ղ����炾�Ɨ��������̂ŁB�v�͋ɒ[��DF��ς��鎖�ʼn��ւ̉e����
���������Ղ�����ړI���Ǝ@���܂����B��ʓI�ȉ��߂���...
���u�A�L���t�F�[�Y�̒�āv�ɂ����Ȃ��悤�ł��ˁB
����͌��ؑO�Ɍ��̕��@�ƖړI���A�L���̐l�Ԃɑ��k���Ă��邩��A
�u��āv�o����̂ł���A���̏�ɗ�������Ă��Ȃ��Ă��A
���R�A���̌��ʂ��u���O�ɍڂ��鋖���A�L���������Ă��邾�낤���A
���e�ƌ��ʂ�c�����Ă���Ȃ�ԈႢ������Ύw�E����Ă���A�Ɨސ������߂��܂����B
���[�J�[��搂������S�ĉL�ۂ݂ɂ��鎖�͔@���Ȃ��̂��Ǝv���܂����A
DF���グ������ŐV���i��W�J���Ă��郁�[�J�[�ƁA
DF�����\�������Ȃ����[�J�[������A�v���ł����������������̂ɁA
�f�l�̎��ɂ͉Ȋw�I�ɂǂ��炪�������̂��H�A�͕����肩�˂܂��B
�P�[�u���ɕt���ẮA�����܂ł��ς�鎖��̌����Ă��鎖���_���Ȃ̂ŁB
�Y�� ����Ȃ疾���ɉ�����Ă����Ǝv�����̂ł����A
�lj�͂̒i�K�Œʂ��Ȃ��̂́A�c�O�ł����B
���A
�������I�[�f�B�I���͒����A
���̃X���̘b�Ő\����Ȃ��ł����A
�Ȃ�A��������̓I�ɂǂ�ȋ@���P�[�u���Łu�ς��Ȃ��v�ƌ������̂��H�A
����Ă��X���[�����̂��H�B�����Ε����قNj^�₪�N���Ă��邾���Ȃ̂ŕs�тł��ˁB
�����ԍ��F22968066
![]() 5�_
5�_
�傳��
�K�\�������n�C�I�N�ɕς��B
�X���[�Y�ȗ����オ��B
�G�����y�����Ă��Ƃ��ȁB
�P�[�u������
�����P�[�u���ɑ��������Ŋy�ł��B
�����z�ɂ��D�������A�A
�P�[�u���������āA��̓��y(�I�[�f�B�I�S��)
�Ȃ�Β����
���ʂȓ��y�قNJy�������m�͂Ȃ��B
����Ă���Ȃ���ł��B(��)
�����ԍ��F22968324�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��bebez����
�����[���E���t����
���͂悤�������܂��B
���[���E���t����A�������ł��ˁB���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F22968382
![]() 2�_
2�_
�����[���E���t����
���͂悤�������܂��B
�P�[�u�����p�p�̏Љ�A���肪�Ƃ��������܂��B
�u�I�[�f�B�I�͓��y�v�@�܂��ɂ��̒ʂ�I
���́A�P�[�u���ɂ͖��ڒ��������̂ŏ��S�ғI�Ȏ�������܂������A���y�Ƃ����Ӗ��ł́A���Ȃ�̎U�������Ă��܂����B
�Y�t�����ʐ^�͎���X�s�[�J�́i�����j17��ڂ�18��ڂł��B
10cm�t�������W����n�߁A�����S�j���v�̃X����a��D-55�A�����D-55��1.3�{�T�C�Y�̋���SW�����܂����B�i3���ځj
�ݐς���A�G�x���X�g�͖����ł�S-9900�Ȃ�肪�͂����炢�̎����𓊓����Ă��܂��B
�ł����A�\�z�A�o���b�N�ł̎����A�v�A����A�����Ƃ����ߒ����\���Ɋy���̂ŁA�����Ė��ʋ����g�����Ƃ͎v���Ă���܂���B
�����āA���ꂾ�������|���Č����̂��Ȃ�ł����A�@���Ɉ������������o�����Ƃ����̂��A���y�̈���Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F22968527
![]() 3�_
3�_
��bebez����
�ǂ����ł��B
����������
�ł���ˁB
������́@�����ł�����B�ǂ����Ɋ�����Ύ��R�Ƃ������ɂȂ��Ă�������ł��B
�Ȃ���Ďv���Ă���܂����E�E�E
�����ԍ��F22968539
![]() 1�_
1�_
bebez����͎���Ƃ͎v���Ȃ����ꂢ�ȃX�s�[�J����Ă܂��ˁB�摜�������Ă݂���A
https://okwave.jp/qa/q9636057.html
�ŁA�_���s���O�t�@�N�^�̋c�_���Ă܂��ˁB�����ł�sirasak����̐������킩��₷�������B
�����ԍ��F22968645
![]() 1�_
1�_
��tohoho3����
�܂��ɓ��y�ł��B
���C���Ɏg���Ă���̂�JBL�Ȃ̂ł����A�ŋߎ��Ԃ��ł����̂ŁA�v�X��FW-208N×2�̃Z�J���h���炵�Ă݂����Ȃ�A���̃A���v�I��̂��߁A�F����̒m���o����q���܂����B
���̎���X�s�[�J�̂قƂ�ǂ́A�l�ɏ����Ă��܂��܂������A���̃Z�J���h�ɂ͈���������A���N�A�Ƌ�x�i�i�H�j�Ƃ��Ă���܂����B
���ʓI�ɂ�A-50DA��I�т܂������A���̉ߒ��Ń_���s���O�t�@�N�^�ɒ��ڂ�������ł��B
A-50DA�͎��̊�]�ɍ��v�����A���v�ł����A�Z�J���h�V�X�e�����ǂ��ɐݒu���邩���A���͍��ő�̉ۑ�ƂȂ��Ă���܂��B
���̒i�K�ɂȂ�ƁA�ő�̏�Q�̓J�~�T���ł��B
�����ԍ��F22968707
![]() 1�_
1�_
bebez����A����ɂ��́B
>�ő�̏�Q�̓J�~�T���ł��B
�ł�����A�x���f����ʼn����܂ɒa�����̂��Ԃ������グ���炢�������ƁA����͌��\�{�C�ŏ������̂ł��B�I�[�f�B�I������Ă��邨������́A�H�ׂ������Ȃ��Ԃɂ������g���Ƃ������z���܂������Ȃ��Ǝv���܂����A�����͊�Ԃ��̂ł���B
�����ԍ��F22968808
![]() 7�_
7�_
���I�̉��������m����A�����́B
���Љ�̎����͂r�o�P�[�u���ɊW����d�v�Șb�Ȃ̂ŁA���������Ă��������܂��i�����ɂ��Ă͌�̓��e�ʼn���������܂��j�B�c�_�����ݍ���Ȃ��ƁA�Ƃ����lj�͉]�X�Ƃ����b�ɂȂ�܂����A��ÂɌ��A��������w�͂����܂��傤�B���̑�����̓��I����̓lj�͂�_���ɖ�肪����悤�Ɍ�����̂ł����A���̑��ɖ�肪�����̓I���w�E���������B�P�����܂��B
>��10��1000���ς��Ȃ��̂ɁA��20�̌J��グ�ɋ^��������鎖��
>�u�咣�ɐ��������Ȃ��v�u���������v�Ɗ�����������ʂł��B
�u��10��1000���ς��Ȃ��v���A�����̐l�X�͒m��܂���B�m��Ȃ��̂ɌJ��グ����u���������A�o�E�g�v�ƌ����Ă��������Ȃ��ł��傤�i�킩��܂��H�j�B���������u���������A�o�E�g�v�͎��̈�ۂɂ����܂���A����Łu��b�ɂȂ�Ȃ��v�ƂȂ�͉̂ߏ蔽���ł��B
>���R�A���̌��ʂ��u���O�ɍڂ��鋖���A�L���������Ă��邾�낤���A
>���e�ƌ��ʂ�c�����Ă���Ȃ�ԈႢ������Ύw�E����Ă���A�Ɨސ������߂��܂����B
�v����Ɂu�A�L���̐l�Ԃ��ւ���Ă���̂�����I�J�V�C�͂����Ȃ��v�Ƃ��l���Ȃ̂ł���ˁH���͕��n�̂����ɂ��킩��_���Ō���Ă��܂��B�����̔��������ƃA�L���̌�Ќ��ň�R����Ă͂��ꂱ����b�ɂȂ�܂���B�����g�Ōv�Z���m���߁C���z������������ƍK���ł��B
>DF�����\�������Ȃ����[�J�[������A�v���ł����������������̂ɁA
>�f�l�̎��ɂ͉Ȋw�I�ɂǂ��炪�������̂��H�A�͕����肩�˂܂��B
>�P�[�u���ɕt���ẮA�����܂ł��ς�鎖��̌����Ă��鎖���_���Ȃ̂ŁB
>�Y�� ����Ȃ疾���ɉ�����Ă����Ǝv�����̂ł����A
�u�����ɉ�����Ă����v�Ȃ�āA�z���g�͎v���ĂȂ��ł���H(��)
DF�ɂ��Ă͌X�l�ŁA�܂��X�s�[�J�[�ɂ���Č������������̂����R�ł��B�������A�ɒ[�ɍ���DF�𐁒����郁�[�J�[�͎x���ł��܂���BDF�����J���Ȃ��ق��������ł��܂��ˁB
>��������̓I�ɂǂ�ȋ@���P�[�u���Łu�ς��Ȃ��v�ƌ������̂��H�A
>����Ă��X���[�����̂��H�B
����ɂ��Ă� 22965533 �ʼnς݂ł��B�������₪�J��Ԃ��ꂽ��X���[����Ǝv���܂����炲�������������B����A���I���ȒP�Ȍv�Z���炳��Ȃ����R�͉��ł����H22966864 �ł��肢�������Z�͂��Ă����������ł��傤���H
�����ԍ��F22969840
![]() 5�_
5�_
�݂Ȃ��܁A�����́B����DF�����ɋ������邩���ɂ́A��ǂ������߂��܂��B
���I�̉��������m���Љ�̃u���O
http://nojima-audiosquare.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
�̎������ʂ��I�J�V�C���Ƃ� 22966864 �ňꕔ������܂������A���I����10���}���̃P�[�X�ɂ��Ēlj����₪����܂����̂ŁA�}����R�l����ʉ����ĉ�����܂��i���w���x�̐��w�ƃI�[���̖@���̒m�������肵�܂��j�B�ȒP�̂��߃A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�� 0 �Ƃ��܂����A��߂���܂���B
�A���v�̏o�͓d���� Vout�A�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�� Rs�A�}�������R�� Ra �Ƃ���ƁADF�y�уX�s�[�J�[�ɂ�����d�� Vs �͂��ꂼ�ꎟ�̂悤�ɂȂ�܂��B
DF = Rs / Ra
Vs = Vout × Rs / ( Rs + Ra )
�u���O�̃I�V���̔g�`�� Vs �Ǝv���܂��i���ɍl�����܂���j�B�}����R Ra �ɂ���ē��R Vs ���������܂����A�X�g���[�g�ڑ� ( Vs = Vout ) ����Ƃ������Βl��
Vs / Vout = Rs / ( Rs + Ra ) �� ��
�ƂȂ�܂��i"Vs / Vout" �͌��Â炢�̂Ń��Ƃ����܂��j�B�����ό`���ADF�ɂ��ĉ����܂��B
�� = Rs / ( Rs + Ra ) = 1 / ( 1 + Ra / Rs ) = 1 / ( 1 + 1 / DF )
�� DF = �� / ( 1 - �� )
���C�Â��ł��傤���HDF�̓��݂̂���v�Z�ł���̂ł��BRa = 0.1�� ( DF �� 80 ) �Ƃ��������ł́A22966864 �ŏ������悤�ɃI�V���g�`�� �� �� 2/3 �Ɠǂ߂�̂ŁA
DF �� 2
�ƂȂ�܂��i�O�̓��e��"DF=2���炢"�Ə����܂����j�B�܂�u���O���咣���� DF �� 80 �͂��蓾�܂���B�������Ɩʓ|�ł����A�v�̓X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X��8������̂ɁA��������0.1����}�����ĐU����2/3�ɂ܂Ō���̂̓I�J�V�C�̂ł��B���n�̂����ł����ϓI�ɂ킩��̂ł́H
���܂菑�������͂Ȃ��ł����A�{���� 4�� ��}������ DF=2 �Ȃ̂� "DF100" �ƋU��ADF�̌��\��s���ɐ�`�i�ȉ����j�B
���I�����������悤�ɁA�������A�L���t�F�[�Y�����̎������ʂ�c�����Ă���Ȃ�A���Ђ̃Z���X�i�Ƃ������p���j���^�킴��܂���B
�Ȃ��A10����}�������Ƃ��������ɂ��Ă͊e�������ꂽ���B����̎�������ƂŁA�������ǂ��ɂ���̂������[���ł���ł��傤�B
�����ԍ��F22969907
![]() 5�_
5�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���I����Ƃ̋c�_�Ɍ������ނ���͂Ȃ��ł����A���߂邾���̒m��������܂��A���ꂾ���͌����܂��B
4sq�i9m��/m�j�̃P�[�u����5.5m�����Ɖ�����0.1���ɂȂ�܂��B
���ɂ͌v���g�`������\���Ă���̂�������s���Ƃ��Ȃ��̂ł����A���Ƌ������ւ�����g�`���Ƃ���ƁA
�A�L����DF=800�̍����A���v�́A�P�[�u����5.5m�����������ŁA�傫�������ς��Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
5.5m�Ȃ�āA�傫�߂̕����ŃZ���^���b�N�ȊO�̃��C�A�E�g��������A���ʂɎg�������ł��傤�B
���肦�Ȃ��Ǝv���܂����ǂˁB
����ƁA�߂ɓǂ̂Ō����Ƃ��Ă邩������܂��A�ǂ�ȃX�s�[�J���g�����̂������Ă���܂��������H
13cm�E�[�t�@��38cm�E�[�t�@����m0�͈ꌅ�ȏ�Ⴄ���A�t�N������DF��_���Ă����܂�Ӗ����Ȃ��悤�ɂ��v���܂��B
�����Z�p�I�ɋ^������Ƃ��[������܂œ˂��l�߂����Ȃ��Ă��܂����Ȃ̂ŁA
���x�A�I�[�f�B�I�X�N�G�A�ɍs�������ɐu���Ă݂����ł��B
�����ԍ��F22970106
![]() 3�_
3�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����A�����́B
�����ԍ��F22966864
>�u�g�`�̍������Ⴂ�̂́A��R�ŐM���������������߁v�Ə����Ă���܂���
����́ADF=1�̕��̐����ŁADF=100�̐����ɂ͏����ĂȂ��ł��B
>�X�g���[�g�ڑ��� 0.1�� �}���ƂŔg�`�̐U�������Ȃ�Ⴄ���Ƃł��B�������� 2/3 �ɂȂ��Ă��܂��ˁB
��ʂ̃X�P�[�����A�X�g���[�g��DF=1�͓����ł����A
�ʐ^���������ł�DF=100�ł͈���Ă���悤�ł����A
����ʼn�ʂɉf���Ă���g�����ׂ�͈̂Ⴄ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A
�ǂ����ǂ���r���āu2/3�v�Ȃ̂ł��傤���H
�Ȃ��X�P�[�����Ⴄ�̂��͂킩�肩�˂܂����B
��ʍ������uCH1 500mV�v�ƁuCH1 1.00V�v
��ʉE�オ�u��:690mV�@@:720mV�v�Ɓu��:1.38V�@@:1.44V�v
�ʐ^���������ł́A��ʕ\���ɂ��̂悤�ȈႢ������̂ł����A
>�g�`�̐U�������Ȃ�Ⴄ���Ƃł��B�������� 2/3 �ɂȂ��Ă��܂��ˁB
�Ƃ����悤�ɁA�Ȃ���r���邱�Ƃ��\�Ȃ̂��A���������肢�������܂��B
�������A���̕\���̈Ⴂ���l��������ŏ�����Ă����ł���ˁB
�����ԍ��F22970214
![]() 2�_
2�_
bebez����A�����́B
>4sq�i9m��/m�j�̃P�[�u����5.5m�����Ɖ�����0.1���ɂȂ�܂�
4sq���ƁA0�D005��/m���Ǝv���܂��B�iMOGAMI 3103�i��3.96sq)�̃J�^���O�f�ڒl�j
�ł��̂ŁA0.005x5.5x2=0.055���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22970408
![]() 0�_
0�_
��blackbird1212����
���w�E���肪�Ƃ��������܂��B�����ł��ˁB�ԈႦ���悤�ł��B
�J�i����4S11�̃J�^���O���݂��̂ł����A9m��/m��1�{���̒�R�ł��ˁB
�{�|�e�X��2�{�g���Ɗm����4.5m���ɂȂ�܂��B
�����A2sq��5m�g���Ƃق�0.1���ɂȂ�܂��̂ŁA�{���I�ɂ͋^��͑傫���ς��܂���B
�����ԍ��F22970532
![]() 2�_
2�_
blackbird1212����A����ɂ��́B
>��ʂ̃X�P�[�����A�X�g���[�g��DF=1�͓����ł����A
>�ʐ^���������ł�DF=100�ł͈���Ă���悤�ł����A
������A�ق�Ƃ��B����͎��炵�܂����B�ʐ^���������̂Ō����ڂŔ��f���܂����i�N���b�N����Ƒ傫���Ȃ��ł��ˁj�B����"10��"�̂ق��͂��قǂ��������Ȃ��̂� "0.1��" �̂ق��ɂ͂Ȃɂ��Ӑ}�����肻�����ȂƁB�u"0.1��"�̂Ƃ������v�X�P�[�����Ⴄ�Ƃ́A�܂��܂��@�ׂ�������܂���B
�ŁA��������ƁA�X�g���[�g�ڑ����� "0.1��" ��}�������ق����U�����Ȃ�傫���Ƃ������ƂɂȂ�i��j�A����ł� 22969907 �Ȃǂ̌v�Z�̑O���藧�����܂���BDF=2 ���͎������܂��B�݂Ȃ��܁A�����������܂����B
���ǁu"0.1��"�̂Ƃ������v�v�������ɈႢ������Ƃ������Ƃł��ˁB������ǂ����邩�݂͂Ȃ��܂̎��R�ł����B
�����ԍ��F22971396
![]() 0�_
0�_
bebez����A����ɂ��́B
>�����A2sq��5m�g���Ƃق�0.1���ɂȂ�܂��̂ŁA�{���I�ɂ͋^��͑傫���ς��܂���B
�u���O�̔g�`���M���ɑ���̂��A�����������������ł���̂��ɂ��Ď��͋^��Ǝv���܂����A����͂��Ă����A��L�v�Z�ŁA��ׂ�ׂ��̓P�[�u���Ԃ̍��ł�����A����ɏ������Ȃ�܂��ˁi�{���I�ł͂Ȃ���������܂��j�B
�����ԍ��F22971409
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���w�E�̌��͂��̒ʂ肩������܂��A���̎�����0���ƌ����P�[�u�����g���Ă��邾�낤��������ȂƂ���ł��ˁB
�����Č����Ȃ�A2sq�ŃP�[�u������5m�Ⴄ�ƁA1�ڂ�3�ڂ̔g�`�̍��ɑ������鍷���o��Ƃ������Ƃ��ƁB
�����ԍ��F22971473
![]() 3�_
3�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���v���Ԃ�ł��B
DF��Vs / Vout�̓d����݂̂Ɉˑ�����`�ɂ��ĕ\�����ꂽ�Ƃ���́A������₷�����������Ǝv���܂����B
�����A���̎�̓d�C�v�Z�Ɋ���Ă��Ȃ����n�Ȃǂ̕��ɂ͏�L�̈Ӑ}�������ł��Ȃ���A�v�Z�ߒ����܂߂ăn�[�h���͏��������̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B
DF�̃u���O��q�����Ă݂܂������A0.1����R�}���̃X�P�[���͊m���ɕς����Ă���悤�ŁA���R�͂Ƃ������A�����������X�̃u���O�ł�����A�M���M�������b���ł͂Ȃ��āA���͋C���������ēǂ�ł݂ĉ��������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�ˁA�A�B
�A�L���t�F�[�Y���S���Ă���1,000�Ȃǂ�DF�l�ɂ��ẮA�P�[�u����[�q�ڑ����̃C���s�[�_���X���x�z�I�ɂȂ���ŁA���l���̂ɂ͎����Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���Ă��闧��ł��B
�A���v���łǂ̂悤�ɒ�C���s�[�_���X����}���Ă��P�[�u����[�q�̌����̃R���f�B�V�����ȂǑS�̂̌n�Ō�����y�����E����Ă��܂��܂��B
����ŃA���v�̏o�͒[�q���O�܂ł̕i����S���A���v���[�J�[�ɂƂ��āA�H�Ɛ��i�Ƃ��Ắu�����\�ȃA���v�Ƃ͉����v�ɉ�����ׂ��A�i�����ʓI�Ȏw�W�Ƃ��Čf����A�L���t�F�[�Y�̂悤�ȃ��[�J�[�̎p���͌l�I�ɂ͍����]�����Ă��܂��B
NFB��DF�l�͜��ӓI�ɑ���ł���ł��傤���A������̉��������ɂ��Đ��l�����ɒ��ڂ�DF���グ��s�ׂ̓A�L���t�F�[�Y�̐��i�J���̗��O���炵�Ă͂��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F22972438
![]() 5�_
5�_
�̂�ۂ�A���v���Ԃ�ł��B�������ƂȂł��ˁi���p������������j�B
>���n�Ȃǂ̕��ɂ͏�L�̈Ӑ}�������ł��Ȃ���A�v�Z�ߒ����܂߂ăn�[�h���͏��������̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B
�����v���܂��B�ł��f�{�͂���͂��Ȃ̂ŁA�����̓w�͂��A�Ƃ������Ƃ���ł��i������DC���x���̋c�_�Ɏ��߂Ă��܂��j�B��ς���邾�����Ƃ����̐��|���_�ł����A�q�ϐ���������Ċϑ��̐��x���オ��̂͗ǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B
>�����������X�̃u���O�ł�����A�M���M�������b���ł͂Ȃ��āA���͋C���������ēǂ�ł݂ĉ��������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�ˁA�A�B
�ł��A������u�L���v�ł�����A���R�̑����ʂ̍�����@���l����͂��ł��B�ӂƎv���܂������A�����M���O�̎��g������100Hz�Ȃ̂ŁA���ꂪ�X�s�[�J�[�� fo �ł��傤���i���O�����j�B������100Hz�̔��g�����g�`�̋쓮�p���X�����Ԃ��Ă���̂́A���������M���M���l�߂Ă���悤�ɂ��B
�Ō�ɁA�A�L���t�F�[�Y�̂܂��߂Ȏp���͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂����ADF�𐁒������ƈ����Ă��܂��܂��B���������悤�Ȃ��Ƃ�����܂����A�����ɉ߂��܂��ADF�����߂邽�߂�NFB���������Ƃ����畉�ג�R�̉e���͎₷���Ȃ�̂ŁA���g�p��Ԃł�DF150�̃A���v�̂ق����_���s���O���ǂ��A�����m��܂���i�܂��~�N���Șb�ł����j�B
�����ԍ��F22973471
![]() 2�_
2�_
���I�̉��������m����̏Љ�̃u���O
http://nojima-audiosquare.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
�̐^�������Ă݂��B
�A���v�ƃX�s�[�J�̊Ԃ̒ʏ�̃P�[�u���̊Ԃ�10m�ׂ̍��P�[�u���i��0.1���j��}�������ꍇ��60W�̔��M�d���i��15���j��}�������ꍇ���r�����B
https://www.youtube.com/watch?v=vJaSrQIESaI
https://www.youtube.com/watch?v=jpFn2NssECc
WaveGene��WaveSpectra�Ƃ����t���[�\�t�g��ADC�Ƃ��ẴI�[�f�B�I�E�C���^�t�F�[�X������ΊȒP�ł���̂ŁA�����̂���l�͎����Ŏ������Ă݂�Ƃ����B
�����ԍ��F22974028
![]() 0�_
0�_
��tohoho3����
�����́B
�����[���������ǂ����ł��B
����������̂ŁA���������₳���Ă��������B
�P�j���͉͂�Hz�̋�`�g�ł����H
�Q�j��R�}���Ȃ��ł��E������ɂȂ��Ă���̂�AC�J�b�v�����O���Čv�����邩��ł����H
�R�j�u���O�̃f�[�^�͒�R�Ȃ��ł������オ�肩��Ȃ܂��Ă��܂����Atohoho3����̎����ł̓V���[�v�ɗ����オ���Ă���悤�Ɍ����܂��B����͎��Ԏ��X�P�[���̈Ⴂ�ł��������Ă��邾���ł��傤���H
�f�C�u�O���[�V���� MIGRATION �ł��ˁB
GRP���[�x���炵�����C�h�����W�Ș^���ł���ˁB
�����I�[�f�B�I�`�F�b�N�ɂ��܂Ɏg���܂��B
�ł��A�f�C�u�O���[�V���Ȃ� HOMAGE TO Duke �̕����ǂ��g�����ȁB
�����ԍ��F22974150
![]() 1�_
1�_
�d���i��15���j�ʼn��ʂ� -9dB �Ƃ������Ƃ炵���̂ŁA�X�s�[�J�[�� 8.25���B
"0.1��" �̂ق��� -0.6dB ���Ƃ���ƁA��L 8.25�� ���g���Ď��ۂ� 0.6���̌v�Z�ł��B
"0.6dB" �̐��x���グ��͓̂���ł��傤���A�ڐG��R�Ƃ��A�������l���Ă��Ȃ��Ƃ��A���v�ł��傤���B
�����ԍ��F22974245
![]() 0�_
0�_
���т��т��݂܂���B�z���g��0.1���ɂȂ��Ă��邩�́A�T�C���g�ifo �t�߂͂͂����āj�ŋ쓮���ĐU���ቺ�𑪂�����ł����ˁB���łɊm�F�ςȂ炲�߂�Ȃ����B
�����ԍ��F22974328
![]() 0�_
0�_
��bebez����
1)50Hz�̋�`�g�ł��B
2)�ǂ��Ȃ�ł����ˁBRubix22�Ƃ����I�[�f�B�I�E�C���^�t�F�[�X��ADC�Ƃ��Ďg�p���Ă邾�������A���͂�AC�����ɂȂ��Ă�̂��ȁH
3)����ł́A���Ԏ��̒P�ʂ͌��ɂ����ł���ms�ł��B
���ꂩ��A����Icecream Screen Recorder�Ř^�����ꂽ���́iVorbis Audio�Ƃ����R�[�f�b�N��196kbps�j�����̂܂g���Ă���̂ŁA���܂�悭�Ȃ����A����ł���r����ƈႢ�͏o�Ă���Ǝv���B
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
0.1���Ƃ����̂́A�莝����2��~�̒��ؐ��f�W�^���e�X�^�[�ł̌v���ŁA���R�ł͂��Ȃ�ӂ��������A�V���[�g�����Ƃ��̍������̂��̂��炢���ȂƋL�ڂ������̂Ȃ̂ŁA0.6�I�[�����Ƃ��Ă��Ȃ����Ȃ��Ǝv���B
>�T�C���g�ifo �t�߂͂͂����āj�ŋ쓮���ĐU���ቺ�𑪂�����ł����ˁB
���m�ȑ���ɂ́A�d���l�Ɠd���~���̒l���K�v�ł���ˁB�ȂȒP�ɓ�������@����������ĉ������B
�����ԍ��F22974373
![]() 0�_
0�_
tohoho3���ցB
0.1������ɂ��Ă��鎞�ɑf�l�̐ݔ��œd���x�ǂ�����̂̓����ł�����A��ɏ������悤��WaveGene�ŃT�C���g���o���đ���̂��ǂ��Ǝv���܂��B������0.1���ł���� -0.1dB ���炢�ɂȂ�͂��B�܂��A���̑��莩�̂����\�@�ׂł����B
�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X��m��K�v������܂����A��̎��̌v�Z�i��8���j�̓X�y�b�N�Ƌ߂��ł����H����Ȃ� 8�� �Ƃ���悢�Ǝv���܂��B�d���i15���j�͉��x�Œ�R�l���ς��܂����A���̎������x�Ȃ�v�Z�͍����Ă���̂ł͂Ȃ����ƁB
�����ԍ��F22974442
![]() 0�_
0�_
��tohoho3����
�����肪�Ƃ��������܂��B
�I�[�f�B�I�X�N�G�A�̎�����100Hz�p���X�M���Ə����Ă���̂ŏ����͑����Ⴂ�܂����A�����オ��̔g�`�͂��Ȃ�Ⴂ�܂��ˁB
�v�������Ⴄ�H�@����Ƃ����ׁi�X�s�[�J�j�̈Ⴂ�ɂ����́H
�itohoho3������I�[�f�B�I�X�N�G�A�̎����̏ڍׂ͂������Ȃ��ł��傤����A�͕s�v�ł��B�P�Ȃ�Ԃ₫�ł��B�j
�����ԍ��F22974467
![]() 1�_
1�_
bebez����A��������o���ł����B
�u�����オ��̔g�`�͂��Ȃ�Ⴄ�v���́A�I�[�f�B�I�X�N�G�A��tohoho3����ƂŁA�쓮�i����j�Ɏg�����g�`���Ⴄ�A�Ƃ����P���ȗ��R�ł��B�v���ӏ��͓����ŁA�X�s�[�J�[�̈Ⴂ�͊W���܂���B���͂������I�[�f�B�I�X�N�G�A�̎��������Ă��܂��A�ԈႢ����܂���B
tohoho3���g���Ă���̂́A���̌��t�������₦�u�J��Ԃ����g��50Hz�̋�`�g�v�ł��B����������̂��ȒP������ł��傤�B
�I�[�f�B�I�X�N�G�A���g���Ă���̂́A�T�C���g�̏㔼���݂����Ȕg�`�ł���ˁB�悭����Ɓu100Hz�̐����g�̈ꕔ�i80%�ʁj�v�̂悤�ł��B�J��Ԃ����g���͕s���ŁA�u100Hz�p���X�M���v�ƌĂԂ̂͂�����Ƃ��������ł��B�Â����g�`�Ȃ̂ŁA�A�L���t�F�[�Y�̎w��ł��傤�B
tohoho3����������悤�Ȕg�`�����Z�p�Ɗ��͂���͂��ł����A�����ʓ|�����ł��E�E�E�B
�����ԍ��F22974714
![]() 0�_
0�_
��bebez����
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���͂悤���������܂��B
���Ǐo���̑傫�ȈႢ�͂ǂ����������̂Ȃ�ł��傤���B
�����ԍ��F22974924
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���I�[�f�B�I�X�N�G�A���g���Ă���̂́A�T�C���g�̏㔼���݂����Ȕg�`�ł���ˁB
�������Ƃ���ƁA���������܂��ˁB
�p���X�M������`�g�Ƃ�������ς��������̂łƂĂ��C���������������̂ł����A���Ȃ�X�b�L�����܂����B
�u���O�ɂ͓��͐M���Ɋւ��Ắu�p���X�M���v�Ƃ����L�ڂ���ĂȂ��Ǝv���܂����A�Y�ꂳ��͓��͐M���͒������̌v���g�`�ƊT�ˑ����ƍl����ꂽ�̂ł��傤���H
�������̌v���g�`�ɂ��A���_�[�V���[�g���o�Ă���悤�Ɍ�����̂͋C�Ɋ|����܂����A�����AC�J�b�v�����O�Ōv���������ʂƍl����̂��Ó��ł����ˁB
���h�b�h�R���b�c����
���͂悤�������܂��B���A�����ł��ˁB
���͒�R�}���̎����������ł�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA������ɂ͓������܂���B
������̂́A4sq�E2m�̃P�[�u�����g�����ꍇ�ƁA��������1.5sq�E3m���g�����ꍇ�ŁA���m�ȉ��ɍ��͊������Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F22974993
![]() 1�_
1�_
������ƕ��͂��������������̂Œ������܂��B
���m�ȉ��ɍ��́@���@���m�ȉ��̍��� or ���ɖ��m�ȍ���
�����ԍ��F22975005
![]() 1�_
1�_
��bebez����
���͂悤�������܂��B
���m�ȓ����ł������܂��B
���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F22975010
![]() 0�_
0�_
bebez����A����ɂ��́B
>�Y�ꂳ��͓��͐M���͒������̌v���g�`�ƊT�ˑ����ƍl����ꂽ�̂ł��傤���H
������̐��m�ȈӐ}���킩��܂��A�A���v�ł�������͐M���Əo�͐M���i���X�g���[�g�ڑ����̌v���M���j���T�ˑ����ɂȂ�͓̂��R�ł���ˁB���m�ȑ����ɂȂ�Ȃ������͂���������܂����A�ȉ��̘b���C�ɂ���Ă���̂��ȂƎv���܂����B
>�������̌v���g�`�ɂ��A���_�[�V���[�g���o�Ă���悤�Ɍ�����̂͋C�Ɋ|����܂����A
����̓A���v�̏o�͂����ۂ����Ȃ��Ă���̂��Ǝv���܂��B�J��Ԃ����g�����i�s���Ȃ���j���ɒႢ���Ƃ͖��炩�ł��B���ʂ̃A���v�if�����[���܂ŐL�тĂ��Ȃ��A���v�j�́A�[���ł͂Ȃ����d�����ԕێ��ł��܂���̂ŁBtohoho����̋�`�g���_��������ɂȂ��Ă���̂������b���Ǝv���܂��B�܂�A
>�����AC�J�b�v�����O�Ōv���������ʂƍl����̂��Ó��ł����ˁB
�Ƃ������z�͉s���Ǝv���܂��B���ۂ́A�v���ł͂Ȃ��A���v�̏o�͉�H���`�b�J�b�v�����O�ɂȂ��Ă���Ɖ��߂ł��邩�ƁB
�܂�A0.1���lj����̂킸���ȃA���_�[�V���[�g�̑������C�ɂ���̂ł���A����ȑO�ɑS�R�����g�`�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ǝv���̂ł����A�B�B
�h�b�h�R���b�c����̂�����̈Ӗ����킩��܂��Abebez����̂��Ŕ[�����ꂽ�Ɨ������Ă����܂��B
�����ԍ��F22975320
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����肪�Ƃ��������܂��B
���̂������Ŕ[���ł��B
�A���_�[�V���[�g�̂悤�Ɍ�����̂́A�A���v��DC���J�b�g���Ă���Ɨ�������������[�Y�i�u���ł��ˁB
�������A�v���n��AC�J�b�v�����O�Ƃ����\�����c��܂����B
��������̐��m�ȈӐ}���킩��܂���
�\����������Ă���Ǝv���܂����E�E�E
�����ԍ��F22975349
![]() 1�_
1�_
�����F�@�v���n���v���n�i������ƃ~�X�^�C�v�������ł��ˁj
�����ԍ��F22975355
![]() 1�_
1�_
bebez����A����ɂ��́B
�I�[�f�B�I�X�N�G�A�̂́A�ʐ^�������
�C���p���X��������p�́A�����V���b�g�̃p���X�g�ł��傤�B
�J��Ԃ��g�`�ł͂Ȃ��̂ŁA���g�����v���ł��Ȃ��̂ł��傤�B
�L�����Č�����̂́A�킩��₷���悤�Ɏ��Ԏ����L���Ă��邩��ŁA
�X�s�[�J�[���ׂɐڑ����Ă��邩��A�g�`�������݂��Ă���̂�������܂���B
>�������̌v���g�`�ɂ��A���_�[�V���[�g���o�Ă���悤�Ɍ�����
�����������邽�߂Ƀ����V���b�g�̃p���X�g���g���Ă���킯�ŁA
�J��Ԃ��g�`��������Atohoho3����̉摜�̂悤�ɁA
���̕��������邱�Ƃ͏o���Ȃ��ł��B
�����Ƃ����Ă��A�X�s�[�J�[�ɂȂ��ł���A���_�[�V���[�g�͑����o��ł��傤�B
tohoho3����̂͋�`�g�ł����A
�f���[�e�B�[��1:1�̃p���X�g����`�g�ƌĂԂ̂ŁA
�ǂ�����p���X�g�Ƃ����p���X�g�ł��B
�����Ɏ�������̂����g����������������̂��ƁA
�J��Ԃ��̂��A�����V���b�g�Ȃ̂��̈Ⴂ�ł��B
�����ԍ��F22975655
![]() 0�_
0�_
��blackbird1212����
����ɂ��́B
���͐M���́A�P���̔��g�������ꂽ�����g�i�\�������������́H�ł��j�ƍl����̂��������肫�܂��B
�����A�����ɉ߂��Ȃ��̂ŁA�I�[�f�B�I�X�N�G�A�Œ��ڐu���Ă݂����ł��B
�����Ɏ��������肢���Ă���̂ŁB
�܂��A�A���_�[�V���[�g�Ɍ�����̂́A�A���v��DC�������J�b�g���Ă���̂��x�z�I�v���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���܂ŃI�[�f�B�I���H�w�I�ɍl�������Ƃ����܂�Ȃ������̂ŁA����DC�A���v�̃C���[�W�Ō��Ă���܂������A
�Y�ꂳ��̉���ŁA�I�[�f�B�I�A���v��DC�������J�b�g���Ă��邱�Ƃ��v������������ł��B
�������A�����Ƃ͂�����10m���͂���ł��傤����A���w�E�̂悤�ɁA���וϓ��ɂ��A���_�[�V���[�g����͂���Ǝv���܂��B
����ɂ��Ă��A���ڐu���Ă��܂��B
�����ԍ��F22975730
![]() 1�_
1�_
bebez����A����ɂ��́B
�ꉞ�����Ă����܂����A
�����V���b�g�̃p���X�g�́A���_�ɕ���Ȏ��Ԃ������̂ŁA
���ɍL����ƁA�摜�̂悤�Ȕg�`�Ɍ����邾���ŁA
�����g�ł͑S���Ȃ��ł��B
�u�C���p���X�����v�ʼn摜�������Ă݂Ă��������B
�I�[�f�B�I�Ɍ��炸�C���p���X�����̔g�`�́A
������������Ȍ`�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F22975764
![]() 0�_
0�_
bebez����Ablackbird1212����A����ɂ��́B
�A���v���c�b���J�b�g����Ƃ������Ƃ́A�C�ӂ́A������x�������Ԃŏo�͓d����ϕ�������[���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B����͐��̃p���X��������Ă���̂ŁA���̒���͕��d�ʂ��������Ȃ��Ɩ��ߍ��킹�ł��܂���B���ꂪ�A���_�[�V���[�g�Ɍ�����Ƃ������Ƃł��B�����V���b�g�ł��J��Ԃ��ł��A��҂̎�����������x������Ό��ʂ͓����Ȃ̂ŋC�ɂ��Ȃ��Ă悢�ł��B
�܂��A�����0.1���̒�R�̉e�����`���悤�Ƃ������ł�����A�X�g���[�g�ڑ����ɃP�[�u�����̒�R����10m��������Ƃ͎v���܂���B�v��������Ⴍ���Ă���͂��ł��B���̏Ȃ�A�L���̃A���v�̓X�s�[�J�[���قڊ��S�ɐ��䂷��ł��傤�i�����ׂɂ��Ă��g�`�͂قƂ�Ǖς��Ȃ��Ǝv���܂��j�B��ŏ������悤�ɃX�s�[�J�[�͈ĊO���^�Ǝv���܂��B�P�[�u�����ɒZ�ɂ��邽�߂ɂ��A�f�X�N�g�b�v�X�P�[���̎����ƌ��܂��i���X�ŕ����āA���ʂ��������苳���Ă��������j�B
�Ȃ��u�C���p���X�����v�͎��������Ă��܂����A����̃P�[�X�Ŏ����o���K�R���͂Ȃ��Ǝv���܂���B
�u���g�������ꂽ�����g�v�ł����A�悭����ƎR�̐���܂Ŋ܂�ł���A��ŏ������悤��100Hz�����g�̏㕔80%�A���炢�Ȋ����ł��B�u�����g����Ȃ��ăK�E�V�A�����v�Ƃ����l�����邩���m��܂��A��������ƃu���O�́u100Hz�̃p���X�M���v�Ƃ���������"100Hz"�̍��Ղ����S���ł��Ă��܂��̂ŁA�g�`����҂͋��炭100Hz�����g���������̂��낤�Ɓi�ǂ��ł��A���̐����j�B�����A������̂͑����A�L���t�F�[�Y�̃G���W�j�A�Ȃ̂ŁA���A�o�E�g�����ȁi����I�j���X�̐l�ɕ����Ă킩�邩�ȁE�E�E�B
����ɂ��Ă��A���ǂ��͊��������Ƃ��̔g�`���o�b����o�Ă���n���ŁA�̂́A�o�J�����Ďg���Â炢�r�f�͂��������Ȃ�����I�E�E�E���Ēm�荇���̂����������Ă܂����B
�����ԍ��F22976042
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���ϕ�������[���ɂȂ�Ƃ������Ƃł�
�����d�ʂ��������Ȃ��Ɩ��ߍ��킹�ł��܂���
���̒ʂ�A���ɂ��܂��������Ǝv���܂��B
�u�f�X�N�g�b�v�X�P�[���̎����v�͂ǂ��ł����ˁH
�z���n�̉e�����~�j�}���ɂ���Ȃ炻�̑I��������܂����ADF�̉��l������������Ȃ畉�וϓ��̑傫������a�E�[�t�@���ڂ̃X�s�[�J���g���������Ⴂ�͌����ɏo��̂ŁA�������������a���g���܂��B
������ɂ��Ă��A�����ɐu���Ă��܂��B
�A�L���t�F�[�Y���Z�p�T�|�[�g���Ă���̂͊m�F�ς݂Ȃ̂ŁA�I�[�f�B�I�X�N�G�A����ŃX�b�L���Ƃ����������Ȃ��Ƃ��A�A�L���t�F�[�Y�������ȉ���������Ǝv���܂��B
���̃X���̓r���ɐ_�Ή��ɂ��ď����܂������A�A�L���t�F�[�Y�Ƃ����̂͂���������Ђł�����B
�����ԍ��F22976231
![]() 1�_
1�_
>�������������a���g���܂��B
���ʂ����v���܂���ˁH
�Ƃ��낪�I�E�E�E���đ���@���ăn�X���ƒp���������̂ł��̂ւ��(��)�B
�����ԍ��F22976513
![]() 0�_
0�_
�f���[�e�B�[��ς̋�`�g��WaveGene�ł��Q�[�g���삵�Ĕ����\�݂��������ǂ��܂������\������Ȃ������̂ŁA��amazon�Ŕ�����1���~���炢��DDS�M��������Ŕ��������āi����ł��f���[�e�B�[�䂪�������Ƃ��͓��������܂��Ƃ�Ȃ��j�A�ׂ�10m�P�[�u�����X�s�[�J�P�[�u���ɒlj������ꍇ�̉����𑪒肵�Ă݂��B
https://www.youtube.com/watch?v=IUEUy6e9DQo
�p���X���I������I�t�ɂȂ�����A��炢�����U�����Ă��Ȃ��̂ŁA10m�P�[�u����lj����Ă����̃V�X�e���ł̓I�[�o�[�_���s���O��ԂƂ������ƂȂ̂��ȁH
�܂��A�����30�b�����肩��f���[�e�B�[���ς��Ă��邪�A�Y�ꂳ���
>�c�b���J�b�g����Ƃ������Ƃ́A�C�ӂ́A������x�������Ԃŏo�͓d����ϕ�������[���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
���悭�킩��Ǝv��
�����ԍ��F22977855
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
��tohoho3����
��x�N���[�Y������ł������A�Y�ꂳ��̉����tohoho3����̎������ʂ͑�ώQ�l�ɂȂ�܂����B
���XDF�ɂ͊S������܂������A���Ȃ藝�����[�܂�܂����B
DF�̃X���Ƃ��ė��Ă��̂ł���A�������GA��t�������Ă������������Ƃ���ł����A���ɃN���[�Y������Ȃ̂ł��e�͂��B
�����I�̉��������m����
�I�[�f�B�I�X�N�G�A�̃u���O��\���Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B
�_���ł͂Ȃ��̂ŁA�����K�v�ȏ�����Ă��萄��������Ȃ��_������܂������i�����ł��A�����ɁA���͔g�`�ɂ��Ă͌�����������Ă��܂��j�A�c�_�̂��������Ƃ��đ�������������Ǝv���܂��B
�K���A�I�[�f�B�I�X�N�G�A����Ƃ��A�L���t�F�[�Y����Ƃ��ʎ�������̂ŁA�^��_���N���A�ɂ��A�A���v��DF����уP�[�u���̉e���ɂ��ė�����[�߂����ł��B
�����ԍ��F22977925
![]() 1�_
1�_
bebez����Atohoho3����A�����́B
>��炢�����U�����Ă��Ȃ��̂ŁA10m�P�[�u����lj����Ă����̃V�X�e���ł̓I�[�o�[�_���s���O��ԂƂ������ƂȂ̂��ȁH
�P��U�����Ă���炵�����萧���s���ł��傤(��)�B
GA���W�߂�Ƃǂ�Ȃ������Ƃ�����̂��m��܂��A�u�P�[�u���͈����ł����v���Ęb���肵�Ă��邹�����A�Ȃ��Ȃ��W�܂�܂���(��)�B
�A���_�[�V���[�g�̌��͎����^�₾�����̂ł����Atohoho���̔g�`�����Ă킩��܂����B���͂悭��������̂ŁA���낢��肪���������Ċy�����ł���B
���ꂩ��Abebez����́A�ߔN�̃I�[�f�B�I�ł͋H�L�̉Ȋw�I�Z���X���������Ɗ����܂��B�`�b�J�b�v�����O�̌��������ł����A�P�[�u���Ƃ����ƃJ�i�����x���f�����A�Ȃ�Ƃ����b�L���A�Ƃ����b�ɂȂ����A��sq��m�Ƃ����ق��͂܂�����܂���(��)�B�̔��X��[�J�[����b�������āu���ʂ̐l�v�ɂȂ�܂���悤�ɁB�B
�����ԍ��F22978184
![]() 0�_
0�_
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
DF����������Ɖߏ�ȓd���������|����}�����ꂽ�������Ȃ��ቹ�ɂȂ�����ASP�ɂ����Ƃ͎v���܂����A�K��DF�l�����݂���̂�������܂���ˁB
���̂悤�Ȃ��Ƃ��l����ƁA��������DF�̃A���v�ɑ��A�ׂ������P�[�u���������Ē����Ȃ�Ă��Ƃ��A���Ȃ̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B
�����������~�N���̂��b�ł��A�A�B
tohoho3����
���v���Ԃ�ł��B
�����c�b���J�b�g����Ƃ������Ƃ́A�C�ӂ́A������x�������Ԃŏo�͓d����ϕ�������[���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
�z���g�A�����N��̎����A�v���X�ƃ}�C�i�X�̖ʐς������Ƀo�����X���Ă����ł�(*^-^*)
������₷�������ł��B
��bebez����
�ʔ����X�������肪�Ƃ��������܂����B
���X���A���炢�����܂����B
�����ԍ��F22978304
![]() 0�_
0�_
�̂�ۂ�A���v���Ԃ�ł��B
�쐬�������悪�����ɗ��Ăĉ����ł��B
��ŁA
>��炢�����U�����Ă��Ȃ��̂ŁA10m�P�[�u����lj����Ă����̃V�X�e���ł̓I�[�o�[�_���s���O��ԂƂ������ƂȂ̂��ȁH
�Ə��������ǁA�{�����[����傫������ƁA2��U�����Ă�̂ŁA�A���_�[�_���s���O�ł��ˁB���̓�����\���Ƃ��܂��B
https://www.youtube.com/watch?v=pbL-Yhf97mg
��������āA�����Ŏ��������l�́A�{�����[����傫������ƁA��`�g�ɂ͑傫�ȍ����g�������܂܂�Ă���̂ŁA�c�C�[�^��
�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������B
�����ԍ��F22979189
![]() 1�_
1�_
bebez����A������
���J�b�g�I�t�́Afc=10��Hz�i-3dB�j�A
��2���A��=0.7�AMid�ɑ��ċt�����x�X�g
���g����U���Čv�Z����ƈʑ��������ł���߂ɂȂ�̂ŁA�ĂŒ������Ă܂�����0.84��-4.5dB���悭�g���Ă܂�����(35�N�ʑO)�A���̂���3�f�q�^��-22dB/oct�ŃX�p�b�Ɛ��萔���������̂Ő�ւ��܂���(25�N�ʑO)�B15�N�ʑO����̓}���`�Ńl�b�g���[�N�p�~�ł��B
�z�[���͌����I�ȃT�C�Y���ƃN���X������ɂȂ�܂����A�X���[�g����J���ɂ����Ĉʑ���]���傫���A�Ȃ��ߕt�߂ŏ����܂��B������ɃX�p�b�Ɛ��ĂȂ��B�O���I�͂���ł��悩�����̂ł����A���ǂ��̓T���E���h�S���ŃX�s�[�J�[�Ԃ̈ʑ�����̓T�ums�Ńf�B���C����펯�ł��B(�����t���łȂ���ق��ł悩������G�c�Ȏ��オ�Ȃ�����)
B&W�݂����ɒ�������̂������_���Ȑv�̃X�s�[�J�[�ɑ��A���X�i�[�܂ŋ�����3�`4m�����Ȃ��̂�1�{�̃X�s�[�J�[�̒��Ń_�C���t������40�`50cm�����܂��Ă���z�[���͌����I�ɂ����A�z�[�����ƃX�^�W�I�ł���Ă���}���`�쓮�ňʑ��̓f�B���C�ǂ����݂��}�X�g�ł͂Ȃ����Ɗ����Ă܂��B
�����ԍ��F22982104�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����I�̉��������m����
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
��blackbird1212����
���I�̉��������m���\���Ă����������I�[�f�B�I�X�N�G�A��DF�̎����ɂ��Đu���Ă��܂����B
�\�ߎ�������ʂŏo���Ă������̂ŁA���ʂł̉ƂȂ�܂����B
���炭�A�A�L���t�F�[�Y�̋Z�p�̕��������ꂽ���̂��Ǝv���܂����A���炩�ȊԈႦ��I�O��ȉ��܂܂�Ă��܂����̂ŁA�N���A�ɂȂ��������̂ݕ��܂��B
�P�j���ׁF�@B&W802D�A�E�[�t�@�F20cm×2
�Q�j�P�[�u���F�@�����F3m�A�����F���O���܂���
�R�j���͔g�`�F�@100Hz�����g�̔��g�����g�`��P���œ���
���A��R�[���ł��g�`�̗����オ�肪�Q�Ă��邱�Ƃɂ��āA�u���ׂ̉e���ł��傤���H�v�Ǝ��₵�܂������A�u���ۂ̉�H���V�~�����[�g���Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��v�Ƃ̉B
�܂��A��R0.1���Ńs�[�N�d������R�[���̖�1.3�{�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��Ă����₵�܂������A�u�x�z�I�v���͂킩��܂���v�Ƃ̂��ƁB
�{���́A���������t�H���[���Ă��������Ǝv���܂��B
�ȏ�A���܂ŁB
��blackbird1212����
�ʂ̃X���Ŏ��₵�����y�f�[�^�t�@�C���̌��A�����肪�Ƃ��������܂����B�i200�z���ł�����������߂܂���ł����j
�����ԍ��F23008645
![]() 1�_
1�_
bebez����A����ɂ��́B
�����肪�Ƃ��������܂��B��^�X�s�[�J�[�ł�����(��)�B10���}�����̃����M���O���g����100Hz�� f0 �ƌ����̂ł����A�����P���ł͂Ȃ��̂ł��ˁBNFB������ł���̂ł��傤���i����������tohoho����12��������Ȕg�`�ł����j�B
���āA�u��R�[���ł��g�`�̗����オ�肪�Q�Ă��邱�Ƃɂ��āv�ł����A����͓Y�t�}�̔��ە����ɂ����Ĕg�`�����ɓʁi�Q�����W�������j�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���ˁH���x�������܂������A����g�`�͐��m�ɂ́u100Hz�����g�̔��g�����g�v�Ƃ͍l�����܂���B
�p���X������8ms�i��100Hz�̂P������80%�j����܂����A�s�[�N����ŏ��l�܂ł̎��Ԃ�4ms�ȏ゠��܂��B�s�[�N�ƍŏ��l�̎����͖��炩�ɋ쓮�g�`�ɂ���Č��܂��Ă���Ǝv���܂�����A100Hz�����g�̈ꕔ���g���Ă���Ȃ�A���g�����g�`�ł͂Ȃ��A������̏㕔��80%�Ɛ��肳��܂��B
�҂͎����̃R���_�N�^�[�Ƃ͕ʐl�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F23009934
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
����ɂ��́B
���܂萄���ŏ����̂���낵���Ȃ��Ǝv���A����������ƁA��������ʂ̓A�L���t�F�[�Y�̋Z�p�̕�����I�[�f�B�I�X�N�G�A�̕��ɑ���ꂽ���ʂ̃R�s�[�ŁA�Ⴆ�A�u���O���܂����v�Ȃǂ̕�������ꏏ�Ɏ������s���������Ǝv���܂��B
�����A�S����10���̎�������܂������A�I���˂���4���i��3���ƌv�����ʁj�݂̂ŁA��́A�����Ă���Ă�̂��ȁH�Ǝv�킹����e�ł����B
�]�k�ɂȂ�܂����A��-�A�L���t�F�[�Y-TV���[�J�Ԃʼn����܂ł�2�����߂��v����CDP�̃r�b�g���\���s��̎��ɂ́A�A�L���t�F�[�Y�̋Z�p�w�͎�����̕�������ŁA������肩�Ȃ萳�m�ɕs������𐄒肵�Ă���A�m���ȋZ�p�������Ă����邱�Ƃ��Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă��܂����B
����ɔ�ׂ�ƁA����́i�蔲����������܂��j����2�N����3�N���̃C���[�W�Ȃ̂ŁA�q�A�����O���Ȃ���w�����Ă����Ȃ��Ɠ��ꖾ���ȉɂ͓��B���Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂��B
�܂��A�Z�p�҂Ƃ����Ă��獷���ʂŁA�v������S������J���Z�p�҂ƁA�̔��X�ɋZ�p����������c�ƋZ�p�҂Ƃł́A�Z�p�Ɋւ��闝��x�ɑ傫�ȃM���b�v�����邱�Ƃ͎��m�̎����ł����B
�Y�ꂳ����Ŏ����ꂽ�����̋����ɂ��Đ��m�ɗ������邽�߂ɂ̓V�X�e���̃_�C�i�~�N�X�E�`�B���Ƃ��������Ƃɂ�����x���ʂ��Ă���K�v������܂����A�����Ҏ��g�A����B���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����������Z�p�҂͌��\�����ł��B
����ǂ��납�A���ʂƏd�ʂ̈Ⴂ�𗝉����Ă��Ȃ��i�Y��Ă��܂����j���H�n�o�g�҂��E�E�E���S�ȉ���
����ȏ㏑���ƋC�̓łȂ̂ł��̂��炢�Ŏ~�߂܂����A�t�H���[�͌p�����čs�������Ǝv���Ă��܂��B���m�ɂȂ�Ȃ��ƃX�b�L�����Ȃ��Ƃ��������������i�Ȃ̂��̂ŁB
���A���͔g�`�ɂ��Ăł����A���͓����u�p���X�M���v�Ƃ������[�h�ł�������P����`�g���C���[�W���Ă��܂��A���̃f�[�^�͈�̉��҂Ȃ̂��H�@�ƍ��f���܂������A�Y�ꂳ��̐����g�̈ꕔ�Ƃ����l�@�œ��S�������܂����B
�Y�ꂳ��80�����炢�ƌ����Ă�����̂́A�����オ��i����j���Ă̂��Ƃ��Ɨ������Ă��܂������A���̓l�b�g���[�N��LCR�܂��͋t�N�̉e���ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B
�P�[�u��3m�i�����͎��O�Ƃ̂��Ɓj�ł�����A�����ƌ����A��10m���i�S�X�P�����肵�ĂR�Om���j�͂���̂ŁA�A���v�̏o�͒[�ƃX�s�[�J�[�ő����̍����o��͕̂s�v�c�ł͂���܂���B
�����A80���Ȃ̂�50���Ȃ̂��������Ř_�����Ă����Ӗ��Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�����y���f�B���O�ɂ��Ă͂ǂ��ł��傤���B
�����ԍ��F23010118
![]() 1�_
1�_
bebez����A�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
bebez�������ւ�����Ȃ����ł��邱�Ƃ��`����Ă��āA���k���Ă��܂��܂��B�����A�s�v�c�Ȍ��ۂ�����ƂȂɂ��N�����Ă���̂��C�ɂȂ��Ė���Ȃ����i�Ȃ̂ŁA����ʂ��Ƃ������Ă��܂��܂��B�S�e�𖾂̈ꏕ�ɂȂ�Ƃ͎v���Ă��܂����A����ɏ����Ă��邱�Ƃł��̂ŁA���ɂ��ԐM�₲�m�F�����߂���̂ł͂���܂���B�G�k�Ǝv���������������B
>�܂��A�Z�p�҂Ƃ����Ă��獷���ʂ�
��Ӂi�h�N�^�[�w���j�B�ꕔ�̃G�[�X�̗͂ʼn���Ă���̂����ʂ����m��܂���B���ǂ��̂��Ƃł�����A�A�i���O�̃Z���X�̂���l�͏��Ȃ������B�Z�p�������\�z����Ă���bebez����͗]�v���������邩���m��܂���B����Ɓu���O���܂����v�́Abebez�����O�����킯�ł͂Ȃ������̂ł���(��)�B
>���ʂƏd�ʂ̈Ⴂ�𗝉����Ă��Ȃ��i�Y��Ă��܂����j���H�n�o�g��
����A����͂Ȃɂ���������܂��������B���͂��������ʂ̘b����D���ł��B��̌ÓT�_�Ƃ��B
>���̓l�b�g���[�N��LCR�܂��͋t�N�̉e���ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B
�_���E�_�j���悤�Ǝv���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŕԐM�͕s�v�ł����A�����͎��M������̂ł��������������Ă��������ƁA��R�[���̔g�`�ɂ��ẮA����������g�`���̂��̂������Ă���ƍl���܂��i�c�b�J�b�g�ɂ��A���_�[�V���[�g�������j�B
�R�[�����Î~��Ԃ��瓮���o���ۂɁADF1000�̃A���v�o�͂��t�N�d�͂œ݂�̂͂��������Ǝv���܂����A�����Ȃ�炩�̊��ʂŔg�`���݂��Ă���̂Ȃ�A���U���̐M�����Ђǂ��c��ł��܂������ł��B
�܂��A�p���X�̊J�n�E�I�����̔����s�\�_�́A����d�����̂����̎����ɋ}�s�ȕω������Ȃ���ΐ������Ȃ��Ǝv���܂��B���g�����g�Ȃ�{���̃p���X����5ms�ł����A���ꂪ8ms�ɉ��т�悤�ȃ��J�j�Y���͑z���ł��܂���B�����u80%�v�݂����ȋÂ����g�`��������{�l�Ȃ�u���g�����v�Ƃ͌���Ȃ��悤�ȋC�����܂����A�������ʓ|�Ȃ̂Ō�҂������Ă���̂����m��܂���ˁB
>�����ƌ����A��10m���i�S�X�P�����肵�ĂR�Om���j�͂���̂ŁA�A���v�̏o�͒[�ƃX�s�[�J�[�ő����̍����o��͕̂s�v�c�ł͂���܂���B
�g�������̂悤�Șb�ł����A���̂R�Om���͏���R�Ȃ̂ŁA�A���v�̏o�͒[�ƃX�s�[�J�[�̓��͒[�Ƃœd���g�`�͐����������A������0.1dB�����̍��ł�����A����덷���x���œ����ƌ��Ă悢�ł��傤�B���́A0.1��+30m��=130m�� �ł����炩�A���_�[�V���[�g��������̂ł���A�����i30m���̂݁j�ł������Ȃɂ������鋰�ꂪ���邱�Ƃ��Ǝv���܂��i���L�����ʂƂ��Ă��܂����j�B���ۂ͂ۂ����肵���A���_�[�V���[�g�����������Ȃ̂��s�v�c�ł��B
�����ԍ��F23010610
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�ȉ��A�G�k�ł��B
�ŋߗ��H�n�w���̃��x�������������Ƃ����܂����A����͍��Ɏn�܂������ł͂���܂���B
���H�n�V�l����������܂��A
�@Q�F�N�̑̏d�́H�@A�F60�L���ł�
�@Q�F����ł͌N�̎��ʂ́H�@A�F60�L���H�H
�@Q�F���Ⴀ�A�d�ʂƎ��ʂ͓����Ȃ́H
�܂��A��͈̂���������܂����A�����ŒP�ʌn�̈Ⴂ�ɋC�t���Έꎟ�������i
�����i����Ȃ���A�Y�ꂳ�����Ȃ������j
�@Q�GSI�P�ʌn�ŁA�g���N�̒P�ʂ́H�@A�FNm�ł�
�@Q�F�G�l���M�[�̒P�ʂ́H�@�G�l���M�[���d���ʁ���×����������Nm�ɂȂ��ˁB�@A�F�͂�
�@Q�F���Ⴀ�A�g���N���ăG�l���M�[�Ȃ́H
���呲�ł��A�܂����̖₢�ɂ͈ꔭ�œ������܂���B
���炵�܂����B
�Y�ꂳ��̂��ӌ��A�ނ��ȂƂ��������܂��B�i��������f�[�^��������80�������������悤�ȁj
�t�ɂ����łȂ��Ƃ��������悤�Ɏv���܂��B
���̕���́A���ăX�s�[�J�l�b�g���[�N��F���v�Z���炢�͂��܂������A�����E�v���E�V�~�����[�V�����Ȃǂ͑S����������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�y�n��������܂���B
�����A�A���v��DC���J�b�g���Ă��邱�Ƃ��瓪��������Ă������炢�ł�����B
�]���āA�萫�I�Șb�����ł��Ȃ��̂ł����A�܂�������Ɠ������ď������q�ׂ邩������܂���B
�����́A���ꂩ��[��ɘ^�悵�Ă�����F1�̃v���N�e�B�X�����܂��B����ł́B
�����ԍ��F23010734
![]() 1�_
1�_
�Y��悤�ɂ���͉i���̉��吶�ł����H
������
�����ԍ��F23011202
![]() 0�_
0�_
bebez����A�G�k�����i�I���j�o�X�`���j�ł��B
F1�ł����B�鎭�Ŋς����Ƃ�����܂��B�Ƃ�����蒮�����ƌ����ׂ��ł��傤���B���̔��͂͌���Ȃ�ł́B���A�����e�J�����̃R�[�X�𑖂������Ƃ������ł���I�E�E�E�ό��o�X�łł���(��)�B���[�M�A�ł̃w�A�s���̗����オ�肪�C�₵�����Ȃ��炢�̂낭�āB
�����ł����A����ɕ����ʂ蓚����Ȃ�u�g���N�ƃG�l���M�[�Ƃ͈قȂ���̂ł��v�ƂȂ�ł��傤���A���ꂾ�ƕs���i�ł��傤����E�E�E�Ȃɂ����Ђ��t����Ȃ�u�g���N�Ɋp�x���|����Ǝd���i�G�l���M�[�j�ɂȂ�܂����A�p�x�͖������ʂȂ̂ŁA�g���N�ƃG�l���M�[�̒P�ʁi�����j�������Ő������܂��v���炢�ł��傤���B�B
�����オ��g�`�ɂ��Ă̋c�_�́A�ҁi�����̃I�y���[�^�[�Ɛ���j�̃��x���𐄂��ʂ낤�Ƃ����Ӑ}�ł��B���Ƃ������ƃI�y���[�^�[���͔��g�����g�`�ƍl���Ă���悤�Ȃ̂ŁA�g�`�̃f�U�C�i�[���Ƃ͕ʐl�ł���Ƃ����̂����̗���ł��i���������݂����ł��ˁj�B
�������A�������s�����A�v���ł�����I�y���[�^�[�����u�V�~�����[�g���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��v�ƌ����Ă���̂ɁA���������Ă����Ȃ��f�l�i���j���u����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă��킩��v�ƌ����Ă���̂́A�����Ԃ�ȑ匾�s��Ɍ����܂���(��)�B
�����ԍ��F23011864
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
����ɂ��́B
�c�O�Ȃ���F1�J�[�͈�l���Ȃ̂ŏ�������Ƃ�����܂��A���J�������삳��i���{�ꑬ���j�j�Ƃ͂�����Ɩʎ��������āA�����[�J�[�ɓ��悳���Ă���������Ƃ�����܂��B
�W�F�b�g�R�[�X�^�[���͔��͂���܂����ˁB�����r�Ɋo���̂��鎄�ł����X70�`80km/h������Ƃ̂Ƃ�����J�b���ŁA�i�ȉ���b�j
���u�����L���o�Ă܂����H�v�@���@���J������u�l��̓X�s�[�h���[�^�͂��܂茩�Ȃ�����˂��B140�L�����炢����Ȃ����ȁB�v
���삳��̎��L�Ԃɂ��悹�Ă��炢�܂����B���傤�ǃ}�b�`�̋��K��S�����|�\�E�f�r���[���ʂ������Ⓒ���i�H�j�������̂ł����A���삳��H���u�i�Ԏ������j���������Ă��݂܂���˂��v�@���@���i�S�̒��Łj�u�R�m�����E�I�v�@
��]�^���n�ł́A�G�l���M�[���g���N×�p�x�@�����ł��B�������܂����B
��̓��͔g�`�ł����A�����ɐ\���グ��Ɖ����̃X�P�[����2.5ms/div�Ǝv������Ō��Ă��܂������A�Y�ꂳ��̎w�E�Ŋm�F�����Ƃ���m����4ms/div�ł����̂ŁA100Hz�����g�̔����ł͐������܂���ˁB
�������A���̂���ȓ���Ȕg�`��p�����̂ł��傤�H
4ms�̐����g���̔g�`����肽���Ȃ�62.5Hz�̐����g�g������������킯�ŁA�S���K�R��������܂���B
�������m�M�ɕς��邽�߂ɂ́A���S�ł��闝�R�t�����K�v�ł��B�����ŁE�E�E
�u���O�̋L�ړ��e����щ�����A�����`�[���̋Z�p���x����������x�����ʂ邱�Ƃ͂ł��܂��B
�蔲�����A���������̂���Ă��邱�Ƃ����͗ǂ������ĂȂ����@�̂ǂ��炩�łȂ��Ƃ��̉ɂ͂Ȃ�܂���B
���������Ȃ̂ł����A�����ʂ����ނ�̗͗ʂƐ����g80%�̓���g�`�Ƃ͂ǂ�����Ό��т��̂ł��傤���H
���炭�����́A
�@�ނ��100Hz�����g�̔��g�����g�`����͂�����肾����
�@�������A�M��������i�����f�W�^���j�̑���~�X�ɂ��DC�i�[���j���x�����I�t�Z�b�g���Ă��܂���
�@����ɋC�t�����������s���A���ʂ����邱�ƂȂ��u���O�̍ڂ��Ă��܂���
�@�{�l�����́A�����Ɍ��ɋC�t���Ă��Ȃ�
�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B����Ȃ瓾�S�������̂ł́B
���̎�̌��͌��\�w�p�_���̐��E�ł�������̂ł��B
�ȑO�A������D���̖^���勳���̘_����100%���蓾�Ȃ��ƒf���ł���V�~�����[�V�������ʂ��ڂ��Ă����̂ŁA���J�Ɏ��₵���Ƃ���A�ŏ��͂��̂��̌����Ă܂������A�Ō�́u�V�~�����[�V�����͊w���ɂ�点���̂ŊԈ���Ă�����������܂���v�Ɠ��𐂂ꂽ�Ȃ�Ă��Ƃ�����܂����B
�܂��A������Ɖ����ɂ���Ă��܂��܂����ˁB
�{���ɂ��Ă͂܂�����������̂ł����A�����Ȃ�܂����̂ŁA�Ƃ肠���������܂łŁB
�����ԍ��F23012111
![]() 2�_
2�_
bebez����A�����́B
���̓��[�^�[�X�|�[�c�ɂ͑a���̂ł����A���삳��͂킩��܂��B�ނ���u�������̂ق��v�����������������̂ł�(��)�B
�����̐l�X�͂ǂ����A�o�E�g�Ȋ����Ȃ̂ŁA���̓L�[�p�[�\�����ʂɂ��āA�g�`���V�~�����[�V�����Ō��ʓI�Ȃ��̂��l�����̂��낤�Ǝv���܂������A���������悤�Ɍ���̃~�X��������ƁA�܂��Ȃ�ł�����Ȃ̂ŁA�ے肷��͓̂���ł��B
�M��������ł����A�ǂ��ł����ˁB���܂� PC �� USB DAC ������A�^����ꂽ�������Ƃ��ďo�����Ƃ��ł��܂��B���Ƃ��u�㕔80%�v�̔g�`�ł����
max( -0.6 , sin (2��×100t) )
�Ə��������ł��i�c�b�����͂Ȃ�Ƃł��Ȃ�ł��傤�j�B���ꂾ�Ɖו����y�����ԈႢ���Ȃ������ł��B�Ȃ��p���X����8ms�ɂ���ɂ́u�㕔90%�v�̂ق����߂��A�v�͕����̃s�[�N��������ƃg���~���O����C���[�W�ł��B
�����_�ł͂���ȏ�̉����͓�����ł����A����ʉ����Ǝv����b���܂߂āA�������ĎG�k�����Ă���Ɨ������[�܂�܂��B
���Ƃ��A0.1���Ŏ�I�[�o�[�V���[�g�������Ă��܂����A�A���v�Ƃr�o�̊Ԃɂ͏���R��������܂���A��ɏq�ׂ��悤�ɃA���v�̏o�͒[�������Ȃ��Ă���͂��ł��B�����M���O�̎������r�o�̌ŗL�U���ł͂Ȃ��ƂȂ�A�����Ă���̂̓A���v�̂m�e�a�����i�̐ق��j���Ǝv���܂��B�����l����ƁA���������A�L���̕q�r�G���W�j�A�ł������Ȃ�A����g�`�͗\�߃V�~�����[�V�����Ō��肷��Ƃ���ł����B
�����������̎������ǂ��ǂނ��H�Ƃ����͎̂��͓���ł��B�{�[���ƌ��Ă���Ɓu�c�e��100���ᑫ��Ȃ��ȁA����ς�1,000�̃A�L�����B�v�ƂȂ邩���m��܂���B�������A���v�̔̑��Ȃ�A��10m���̕��ʂ̃P�[�u�����Œ肵�āA���Ђ̒�c�e�A���v�Ɣ�r���ׂ����Ǝv���܂��B�����Ă��̏ꍇ�A�A�L�������Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23012883
![]() 0�_
0�_
�����G�k�ł��B
�ߑ��ɂȂ��Ă��܂��܂������A�������i���ar[m]�j�Ɋ����t�����āA���̐�ɒ��͂�F[N]�̑傫���łԂ牺�����Ă��邨���肪�������Ƃ��āA���ɑ���[rad]�̊p�x�����������ꍇ�̎d��W[J]��
W��F×r�Ɓ@�Ȃ̂ŁA
�@��Fr��
�@��T��[J]
�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̂��������悤�Ɋp�x���͖̂������Ȃ̂Ńg���NT[N�Em]�͊m���ɃG�l���M�[�̒P�ʂƓ����ɂȂ�܂���ˁB
�����A��]�̂�d�C�Ɨ��߂Ă��b����Ȃ�A�Ⴆ�Γd���@�i�d�C�Ƃ������d�@�W�ł��傤��^^;�j�Ȃǂ̗��_�������ꍇ�A��{�I�ɂ̓g���N�͎��g���𗍂߂��p���x��[rad/s]�i��2��f�j��p����T��P/��[N�Em]�̕����A���́i�������b�g�j��@�B�I�o�͂�������Ŏ��p�I�ł��B
�p���G���Ȃǂ̓d�q�H�w�͐��ł͖����ł����A�P�ʂ��݂�ƁA������x�͕����ʂƂĊ��o�I�ɗ����ł��镔��������A�P�ʂ��đ�Ǝv���Ă��܂��B
���i.com�̃T�C�g���܂߃l�b�g�ł��A�������Ƒ啶���̋�ʂȂNJ܂߁A�P�ʂ̏������ЂƂ���A��悻�Ȋw�ɐڂ����o�����������Ă��܂��悤�ɂ������܂��B
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�r�o�̌ŗL�U���������M���O�̎����Ɉ�v����̂ł͂Ƃ����Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̗\�z�ɁA�����Ȃ�قǂƎv���Ȃ���q�ǂ��Ă����̂ł����A���ʂ͈ӊO�ɂ��傫��SP�ł̎����������̂ł��ˁA�A�B
�܂�10[��]���̃P�[�u���͎��ۂɂ͂܂��Ȃ��Ȃ��ł����ANFB�ɂ���ă����M���O�̎������ω����Ă��܂��Ȃ�A�P�[�u�����������Ƃ��ɂ́A�~�N���I�ɂ�SP����o�鉹���A���v�ɂ���ĕω����܂��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂������ł���^^;
���Ƃ������܂��A���_�q����͂Ȃ�ׂ��Z�߂̒����̃P�[�u�����ǂ��̂��ȁ[�Ǝv���Ă��܂��܂����A�A�B
�����ԍ��F23013228
![]() 0�_
0�_
�Ȃm���ԂɉȊw�I�Șb�ɂȂ��Ă܂��ˁB
http://www.tonestack.net/articles/speaker-building/speaker-cables-facts-and-myths.html
������ƁA�S���Ƃ��̌��̃C���s�[�_���X�̒Ⴂ�X�s�[�J�ł́A���ۂ̃C���s�[�_���X�́A���U��l�b�g���[�N��H�̉e���ł�������������Ȃ�悤�Ȏ��g���ˑ���������̂ŁA10m���炢�̒����čׂ��P�[�u�����g�p����ꍇ�́A���̒�R�ƁA���g���ˑ��̃X�s�[�J���̂̃C���s�[�_���X�ɂ��d���f�o�C�_���`������āA���g���ˑ��̐U������������₷���Ȃ�i���F���ς��j�Ə����Ă���ȁB
�����ԍ��F23013338
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���͂悤�������܂��B
�����b�ł����B����Ȃ�����Ƃ���܂���B
�T���f�B�G�S�ɍs�������ɁA�g�b�v�K���̎B�e�Ɏg�����~���}�[�̊C�R��n��K�˂āA�i�ߊ��a�i4�{���j�̈ē���F-14��A-4�ɒ��������Ă��������A���Z�N���u�Ńr�[��������ƁA�ƂĂ��C���v���b�V�u�ȑ̌������܂����B
���ł���Ԉ�ۂɎc���Ă���̂́A���Z�N���u�Ō����������R���̏������Z�ŁA�f�悳�Ȃ���ɃJ�b�R�ǂ��������Ƃł����ˁB
���āA�{��ɓ���܂����A���Ԃ��𖾂����ɂ͂܂����Ԃ��|���肻���Ȃ̂ŁA�����������𑱂��܂��傤�B
���f�肵�Ă����܂����A�����ł̂�����ʂ��āA�Y�ꂳ��͂��Ȃ�̊w�����������ŁA���_�����łȂ��f�[�^������ځA�f�[�^�����ۂɂȂ��铴�@�͂��������̕��Ƃ������Ă���܂��B
�܂��A���w�I�Z���X�ɉ����ẮA�����D�ꂽ���̂��������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���Ă���܂��B
���̏�ŁA�����āA�Y�ꂳ��̌����Ɉ٘_�����������Ă��������܂��B
���_�������𑱂���ɂ́A�F���̋��L���͌������܂���̂ŁB
�܂��ŏ��ɁA����������Ă��炢�܂��B
��̕œI���˂���10����4���Ə����܂������A10��5���̌��ł����B�lj���1���ɂ��āA�ȉ���Q&A�����̂܂܋L�ڂ��܂��B
���A�����P�͒����A�����Q��10���}���A�����R��0.1���}���������܂��B
Q�F�A���v�̏o�͒[�q�̓d���͌v���i�܂��́A���j�^�j����܂������H�@�����Q�A�����R�ł��A���v�̏o�͒[�q�̓d���͎����P�Ƃقړ���ł��傤���H
A�F�͂��A�ǂ̎����ł������ɂȂ����Ǝv���܂��B
�����̓A���v�̏o�͒[�q�d���ƁA�v�����ł���X�s�[�J�̒[�q�d���̊W�ɂ��������q�ׂ����Ă��������܂��B
�����A����̖Y�ꂳ��̃R�����g�́A�A���v�ƃX�s�[�J�Ԃɑ}�����ꂽ�P�[�u�����R��͏���R�ł��邩��A�����ʂ̓d���̓Q�C�����ς�邾���ő����ɂȂ�Ǝ咣����Ă���悤�ɓǂݎ��܂��B
�܂��A�u�����������v�ƌ����\���́u�������v�́u�����Ɍ��Ă��v�Ƃ������Ƃ���������Ă���Ɖ��߂��܂����B
��L�����̏�ő����܂����A�����Ɍ�肪������w�E���������B
���A�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�͌����ɂ͒�R�Ƃ̓x�N�g���̕������Ⴄ�Ǝv���܂����A�c�_���ȒP�ɂ��邽�߁A�o�̓C���s�[�_���X�͒�R�ɒu����������Ƃ����Ă��炢�܂��B
���āA���ׂ��X�s�[�J�ł͂Ȃ��Ⴆ��8���̏���R�̏ꍇ�́A�Y�ꂳ��̎咣�ʂ�A�����ʂ̓d���g�`�̓Q�C�����ς�邾���ŁA�����������ɂȂ�܂��B
�������A���ۂɎg�p�������ׂ̓_�C�i�~�N�X��L����X�s�[�J�ł��B
����g��Ɍ��肵�ĕ��ׂ̓����𐔎����i���`�ߎ��j�����ꍇ�A���炭�A4���i�o�l�}�X��LCR�j�܂���2���iLCR���j�ŕ\����邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���̕��ׂ̃_�C�i�~�N�X�ɂ���āA��R��}�������ꍇ�ɂ̓X�s�[�J�[�q�[�ɕϓ��i�U���I�U�镑���j����������킯�ł��B
����A�A���v�̏o�͒[�ɂ͋���NFB���|�����Ă���̂Łi�����ꂪ�A�L���t�F�[�Y����̎����H�j�A�ϓ��͑啝�ɒጸ����A��Ɏ������A�L������̉ʂ�A�A���v�̏o�͒[�ł́A�����̏ꍇ����R��}�������ꍇ���A�����ڂɂ͂قƂ�Ǎ����Ȃ��g�`���ϑ�����邱�ƂɂȂ�܂��B
���z�I�ɁA�iDF=800�̃A���v�j���i�C���s�[�_���X=0�EDF=���̃A���v��0.01���̏o�͒�R���Ȃ������́j�ƍl����A�e�Ղɂ��������������邩�Ǝv���܂��B
�]���āA�A���v�ƃX�s�[�J�̊Ԃɑ��݂���̂�����R�ł����Ă��A�����ʂ̓d���g�`�͐����������ɂ͂Ȃ�܂���B
�����������ɂȂ�̂́A�A���v�|�X�s�[�J�Ԃ̒�R�l���[���̏ꍇ�݂̂Ƃ������ƂɂȂ낤���Ǝv���܂��B
�������A���x���͂����āA�����i���z30m���j�̏ꍇ�́A�����ڂł͕�����Ȃ����炢�̈Ⴂ�ɂȂ�Ǝv�����A�����łȂ������̂ł����A�X�N�G�A����̎������ʂ��ՂƂ���ƁA�K�����������Ƃ͌����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�{���͂��̂܂ܕ��u�ł��Ȃ��ȂƎv���Ă��鎟��ł��B
���͂������炪�j�S�Ȃ̂ł����A�����������Ȃ��Ă��܂����̂ł��̕ӂŁB���ꂩ��AF1���L�V�RGP�����i�^��j�����܂��B
�����ԍ��F23013605
![]() 1�_
1�_
bebez����A����ɂ��́B
�܂����٘_�̌��́A�܂������̎��̊��Ⴂ�ł����B�܂��Ƃɐ\����܂���ł����B10���}���ŃA���v�o�͂��r���킯���Ȃ��ł��ˁB�u�ł͂ǂ�����ׂ����v�́A�l�������Ă݂܂��B�Ƃ����
>A�F�͂��A�ǂ̎����ł������ɂȂ����Ǝv���܂��B
�ɂ��āA0.1���̎��������d�����傫�����Ƃ͌������Ă���͂��ł���ˁB
�̂�ۂ�
>NFB�ɂ���ă����M���O�̎������ω����Ă��܂��Ȃ�
��L���Ⴂ���������̂ŁuNFB�����Ă���v���͍l�������K�v�����邩������܂���B�}����R�ɂ�炸100Hz���炢�ŐU�����闝�R�͓�ł����ANFB�̕Ȃł���\���͎c���Ă��āA����g�`��100Hz�ɑI���R�ƃ����N���邩���m��Ȃ��Ǝv���܂��iNFB�̕���p���ɂ��Ă�bebez�����|�I�ɂ��ڂ����͂��j�B
tohoho3����
�O�̎����� WolframAlpha �ɂ��g�`�������Ȃ��g��Ȃ��̂��낤�H�Ǝv���Ă����̂ł����A�ǂ����L�������Ă��܂����݂����ł��ˁB
�����ԍ��F23013842
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B�悤�₭F1�����I���܂����B
�������ʂɂ��ẮA���Ȃ�F���̋��L�����i�Ǝv���܂��B
�ȉ��A������ɉ��܂��B
>A�F�͂��A�ǂ̎����ł������ɂȂ����Ǝv���܂��B
����́A����1�A�Q�A�R�ɂ�����A���v�o�͒[�d���̎���ɑ���Ȃ̂ŁA���͂���܂���B
�����A�v���ł���A�u�����ɂ͋ɂ킸���ȍ��͏o�Ă���͂��ł����A���̍��͎g�p�@�ނŊϑ��ł��郌�x���̂��̂ł͂������܂���B�v�Ɖ��ė~���������Ǝv���܂��B
0.1����R�̑}���Ńs�[�N�d��1.3�{�ɂȂ錏�ɂ��ẮA�ʂ�2�ʂ�Ŏ��₵�܂������A��������S���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���ł����B
�ł����A�A�L������̖��_������̂ŁA�����ɉ��N�����Ƃ͍T�������Ǝv���܂��B
��������͐����ł��B
�C�t���Ă������H�@�ɂ��ẮA���炭�C�t���Ă��Ȃ������Ǝv���܂��B
�u���O������ƁADF�ʼn����ς���ł���@�Ƃ������Ƃ�PR����̂���ړI�ł����āA�v���f�[�^�͂���𑽏��i�����������邽�߂̃I�}�P�Ƃ������������܂��B
������A�u���O���������l�i�X�N�G�A�j���A��������`�����l�i�A�L���j���f�[�^���������茩�čl�@����A������Ƃ������Ƃ͂���Ă��Ȃ����A�����A��������\�͂��������킹�Ă��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�Ƃ͂����Ă��A���̏�Ƀf�[�^�����J�����킯�ł�����A�^��ɂ͐^���ɉ��Ă������������Ƃ����̂����̃X�^���X�ł��B
�܂��A�M���̃A�L���t�F�[�Y�ł�����A�����ꂷ������Ƃ�������������̂Ǝv���Ă��܂��B
�i����������ƁA�{���̃v�����o�ꂵ�čĎ����ɂȂ����肷�邩���j
���܂ŖY�ꂳ��Ƌc�_���Ă������͐M���`���A���v�o�͒[�̓d���g�`�́A���͂���قǑ債�����Ƃł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�ł����A�܂��������͂����肳���Ȃ��Ƙb����ɐi�܂Ȃ��Ǝv�������������ɂ��t���������������܂����B
�j�S�́u0.1����R�̑}���Ńs�[�N�d����1.3�{�ɂȂ�v�̈�_�ɐs����Ƃ����̂��{���ł����A���̑����͎���ȍ~�Ƃ������ƂŁB
�����ԍ��F23013999
![]() 1�_
1�_
�Y�ꂳ��A
�{�����BIE11�ł͂Ȃ��������������Ă݂��Ȃ����Achrome���ƃ��A���^�C���ʼn������łȂ��Ȃ��Ă�ȁBWolfram���P�`����������ȁB
�����ԍ��F23014011
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
SP�[�q�ł̓d���̓P�[�u������SP�̋������܂ރC���s�[�_���X�Ƃ̕����Ȃ̂ŁA�P�[�u����������R�ł��A�A���v�[�q���̓d���g�`�Ƒ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��_�͂������Ƃ��Ă��A����͕ʂɂ���NFB�̉e���̉\���̂��ƁA���m���܂����B
�܂����������Ȃǂ�����܂����炨������������(*^-^*)
���ƁASP�̌ŗL�U���ƃ����M���O�̎����Ƃ���v���Ă��Ȃ��\���Ƃ��āA�P�Ɉ���g�`�ɂ��i�ߓn�O�́j��������SP�̋t�N�d�͂ɂ���ă����M���O�����̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B
�A���v�ƃP�[�u�����܂߂��n�ō���DF�̊��Ȃ�ASP���猩���A���v���͉��z�I�ɃV���[�g�ɋ߂���Ԃ̒�C���s�[�ƌ�����̂ŁA����DF�̏ꍇ�A�A���v���ŋt�N�d�͂̉e�������ݍ��݁A�����M���O�̔g�`������ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ́A����HP�̎����ŕ��͋C�Ƃ��Ă͓`����Ă��܂����B
��tohoho3����
�����N��̂��Љ�A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F23014167
![]() 0�_
0�_
bebez����A�����肪�Ƃ��������܂��B
�܂��G�k�ł��Bbebez���Ⴂ����������߂�(��)�̂Ɏg�������ȁH�l�^���B
���ׂ�킩���Ă��܂��܂����A�ʐڂō��i���闝�H�n�̎�҂͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƁB
���ꎟ�����i�����|�����H�j
�d���ɂƂ܂����X�Y�����n�ʂɗ��Ƃ��e�́A�������{�P�Ă����ˁH�@�Ȃ�ŁH�i�`�R����j
�������i�u�P�ʁv�Ȃ���Łj
�u�X�s���v�ɂ��āA�Ⴆ�Γd�q�� ±1/2 ���ďK����ˁH�@�Ȃ�ł����P�ʂ��t���Ȃ��́H
���u�����͍H�w�n�Ȃ̂ŗʎq�͊w�͕s�ē��ł��v�͕s���i�B
���āAbebez����́u����1�A�Q�A�R�ŃA���v�o�͓͂����v�Ƃ�����M����Ƃ������Ƃł��傤���B���́A����͂��蓾�Ȃ��i0.1�����̓A���v�o�͂��炵��1.3�{�̂͂��j�Ǝv���܂��i�����łȂ��ƃG�l���M�[�ۑ����S�ۂ���Ȃ����ł��j�B�ꉞ���̉\�������ۂ���������B
>�u���O������ƁADF�ʼn����ς���ł���@�Ƃ������Ƃ�PR����̂���ړI�ł����āA
PR�����炵�傤���Ȃ��ł����ADF1000�̃A���v��0.1����}�������u�`�����DF100�v�������o���̂͂��邢�ł��B���X���X��DF100�̃A���v���g���ׂ����ƁB�قڃX�s�[�J�[���͂���NFB���|����̂ł��Ȃ�ǂ��͂��E�E�E�Ƃ������Ƃ͍L���ɂ͖����ł����ˁB�ł��u�M���̃A�L���t�F�[�Y�v���邽�߂ɂ́A���������Ă������������ł��B
�̂�ۂ�
>�P�Ɉ���g�`�ɂ��i�ߓn�O�́j��������SP�̋t�N�d�͂ɂ���ă����M���O�����̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B
��E�\������������Ȃ̂ŏ��������Ō����܂����A������āA�쓮�p���X���I�����A��x�R�[�����Î~��������A�ߋ�100Hz�ŋ쓮����Ă������Ƃ����҂����L�����Ă���K�v������܂���ˁB�R�[����l�b�g���[�N�ɂ��̔\�͖͂��������Ȃ̂�NFB������ł���Ƃ����v���Ȃ��̂ł����ANFB�ɂ��Ă��u�L���v�͓���悤�ȁB
�����ԍ��F23014464
![]() 0�_
0�_
�u�X�s���v�Ȃ�Ă���������Ƃ������Ă��܂��ˁB
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/49977?page=3
�Ƃ�
https://www.kyoto-su.ac.jp/project/st/st04_04.html
�Ƃ��ǂނƁA�ʎq�͊w�̍��ǂɊւ�邱�ƂŁA�����Ƃ��߂��ʎq�R���s���[�^�ɂ��W���Ă�ȁB
�����ԍ��F23014630
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�������ɂ��Ă͓lj�͕s�����A���̐S��������Ȃ������̂Ńp�X�����Ă��炢�܂��B
���u����1�A�Q�A�R�ŃA���v�o�͓͂����v�Ƃ�����M����Ƃ������Ƃł��傤���B
Yes�ł��B�M���̃A�L���t�F�[�Y�̃A���v�ł�����B�i��k�ł��j
�������A�Y�ꂳ�l�A������0.1���̒�R��1.3�{�͂��肦�Ȃ��Ǝv���Ă܂���B
���̖������ǂ��������A���ꂪ���������̐_���ł���ˁB
����ǂ��ĕR�����Ă�������ł����A���܂�v�킹�Ԃ�Ȃ̂���낵���Ȃ��̂ŁA������Ƃ����B
���̐����ł����A
�@����0.1���̃f�[�^�͋��U���\��Ă���A���̂��߃s�[�N��1.3�{�ɂȂ��Ă���
�A���͐M���𐳌��g�̔����Ǝv������ł����̂Ɠ��l�ɁA�}��������R���E�E�E�����~�X�H�E�E�E
�Ƃ������Ƃ���ł��B
�ؖ��͖����ł����A�_���I�ɉ����̊m���炵���������Ă݂����Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B
���������͕����Ă��܂�����������܂��A����}�����t�������Ă���Ă��������B
�����X���X��DF100�̃A���v���g���ׂ����ƁB
���̃u���O�̎���́u���v�ł����āA���[�J�Ⴂ����DF�̉e���Ƃ��������̉��̈Ⴂ���ł��Ȃ��̂ŁA��R�}���Ƃ������@��I�������̂ł��傤�B�i�u���O�ɂ�����Ȃ��Ə����Ă��������Ɓj
���͉��A�f�[�^�v���̓f�[�^�v���ŕ������Ă���Ă����Ηǂ������̂ł����A�f�[�^�͂�͂�I�}�P�Ƃ������A�N�Z�T���[�Ȃ�ł���B
�܊p1000W�i8���j�EDF=200��M-1000�Ƃ������h�ȃA���v������̂�����A�����DF=1000�̍ŐV�@���r���Ă����Ηǂ������̂ł͂Ǝv��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB
DF���Ⴄ�A���v���m�Ŕ�r�������������~�X�̃��X�N�������邵�B
�����A�������x�̍��������łȂ��ƁADF=1000��DF=200�̍��m�ɏo�����Ƃ͏o���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�����ԍ��F23014662
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���������A���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
�Ⴆ�A10���̒�R��t�����P�[�u���̏ꍇ�ADF�l���Ⴍ�d���I�Ȑ����������ɂ�����Ԃ̍ۂɁA�쓮�p���X���I�����U������̈ʒu�ɖ߂��Ă����Ƃ��ɁA�U�������ʂ������Ă��܂��̂ŁA�҂�����~�܂炸�A�˂̗l�Ɋ����őĐ��ŐU������Ƃ������Ƃ�����̂��ȂƑz�����Ă݂��̂ł����A�������Ȃ��̂ł��傤���B
�����ԍ��F23014785
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���͂悤�������܂��B
����ł͎����b�̑�3�e�Ƃ��������Ƃ���ł����A���܂葱���ƌ��������A�e�W���C�A���g�n��vs�~���}�X�J���X�f�܂ők��̂��ǂ����Ǝv���̂ŁA�b���͕��܂��B
�X�N�G�A�����DF�����ɂ��āA�����ł̋c�_��ʂ��ė�����[�߂Ă��܂������A�j�S�ɓ���O�ɁA�����͂�����ƈႤ�b�����悤�Ǝv���܂��B
�Ⴄ�ƌ����Ă��A���ǂ͖{��ɂȂ������Ȃ̂ŁA�N���]���́u�]�v�Ǝ���Ă���������낵�����Ǝv���܂��B
�l�b�g�ŃP�[�u���ɂ��ĐF�X���ׂĂ����Ƃ���A���L�y�[�W�ɍs�����܂����B
https://item.rakuten.co.jp/procable-shop/belden8477_3002/
�����ɂ́A�v���p�I�[�f�B�I�P�[�u���̂��X�uProCable�v����������P�[�u���̒����Ƒ����̊W���L�ڂ���Ă��܂��B
��̓I�����l�́A2m�FAWG18�A3m�FAWG16�A5-7m�FAWG14�A9-12m�FAWG12�ł��B
��R�l�Ɋ��Z����ƁA�������0.1���O��ɂȂ�܂��B
�A���v�ƃX�s�[�J�̑g�ݍ��킹�ɂ���ẮA0.1�����炢����邱�ƂŁA���������������ɂ߁A���̗ʊ��𑝂��Ƃ��������ɂȂ�ꍇ������Ƃ͎v���܂��B
�������A����́A�ʁi�A���v�@��A�X�s�[�J�@��A�l�̍D�݁j�̓��ى��ł��B
��������̗��_�I���t������������ʐ��̂���œK���̂��Ƃ�PR����ȂnjӎU�L����Ђ��ȂƂ͎v���܂����A����͂��Ă����A�����ŏd�v�Ȃ̂́A0.1���P�[�u������ʓI�Ɏg�p�����͈͓��ɂ���Ƃ����_�ł��B
����ɂ��Ă��A�x���f��8477�iAWG12�j3m�蔄��̃y�[�W�ɁA�uAWG12��9�`12m���K���g�p�͈́v�Ƃ��u3m�O���8470�iAWG16�j���v�ȂNjL�ڂ���̂��āA���̏��i�͔���Ȃ������ǂ�����Č����Ă�悤�Ɋ����܂��H�@�ȂA������Ɗ��m�B
�b���͕ς��܂����ADF�ɂ��ăl�b�g�������܂��ƁA�uDF=20�`40���ǂ��v�Ƃ��uDF=100�ŏ\���v�ȂǂƂ����L�����悭�������܂��B
�A���v��DF=800�A�P�[�u��0.1�����ƃg�[�^����DF=73�i�ڐG��R������Ƃ����������ɂȂ�j�A�A���v��DF=200�A�P�[�u��0.1���Ńg�[�^��DF=57�Ȃ̂ŁADF�̊ϓ_������A0.1���̃P�[�u���Ƃ����̂͏\�����p�͈͓�����ƌ����܂��B
�����̌��_�F�@0.1���̒�R��L����P�[�u���͏\�����p�͈͓��ɂ���A0.1���̓P�[�u���̃v�������̂����Ђ̐����l�ɂ��Ȃ��Ă���
�{���͂����܂łƂ����Ă��������܂����A�����ɂ͐������������҂��I�ł��邩�Ǝv���܂��B����ł́A�ǂ�������B
�����ԍ��F23015314
![]() 2�_
2�_
��bebez����
DF�ʼn����ς��Ƃ����b�͌��ǂ̂Ƃ���
�X�s�[�J�[��Q���㏸���Ă���ɂ���Ă����̉ߓn���������邽�߂ł����玮�ł�����
Q��Q0c(1�{1�^DF)�@�@Q0c�̓X�s�[�J�[�V�X�e����Q
��Q�̏㏸�܂ōl���܂��B
�K�vDF�̓X�s�[�J�[��Q���P�[�u������ꂽ�����p�[�Z���g���邩�H
�Ƃ������ƂŔ��肵�āA�����Ⴆ�R�������Ȃ�OK�Ƃ��܂��ƁA
��ʓI��Q0c�̂Ƃ�DF�������ȉ��ɂ��ׂ���
���̂��߂ɂ̓X�s�[�J�[�̒�R�������������I�[���ɂ�������A���Č��_���o�Ă��܂��B
�v���P����̐����͂��������s���ł����A���_�͂Ȃ����A���������傫���͊Ԉ���Ă��Ȃ��悤�ł��B
�����ԍ��F23015401
![]() 2�_
2�_
×�@���̂��߂ɂ̓X�s�[�J�[�̒�R��
�Z�@���̂��߂ɂ̓X�s�[�J�[�P�[�u���̒�R��
���݂܂���
�����ԍ��F23015404
![]() 0�_
0�_
���n���ق���
�R�����g�������������e�͖ނ����Ǝv���܂��B
�P�[�u���̒�R0.1���͏\�����p�͈͓��Ƃ������Ƃɂ��Ă͑S���٘_�͂���܂���B
�����x�X�g���ƌ����Ƃ���̓P�[�X�o�C�P�[�X�ŁA�����̎g�p���Ă���2235H�Ȃǂł͂�����Ɣ����������x���ł��B
���́A�I�[�f�B�I�X�N�G�A����̃u���O�Ɍf�ڂ���Ă���0.1����R��}�������ۂ̎������ʂł��B
�p���X���͂ɑ��ăX�s�[�J�[�̃s�[�N�d����1.3�{�قǂɂȂ��Ă���AQ�̕ω���3���Ȃ�Ă��Ⴀ��܂���B
�����ŁA���ł���Ȃ��Ƃ��N����̂����l�@���Ă���Ƃ���ł��B
�����ɂ͍l�@���ʂ��I�ł��邩�Ǝv���܂��̂ŁA���Ԃ�����Ό��Ă���Ă��������B
�]�k�ł����A�f�m����PMA-390AE��2235H�ɂȂ������Ƃ�����܂����A�ቹ�����������u�J�u�J�ɂȂ��Ă��܂����������̂ł͂���܂���ł����B
����DF���s�����Ă���̂��낤�Ǝv���Ă����Ƃ���A�ǂ����̋L���Ɍv���l�Ƃ���DF=39�Əo�Ă��܂����B�iAE���������́H�j
2235H�̏ꍇ�́A�Œ�ł�DF=100�͗~�����悤�ȋC�����Ă��܂��B
�������A390�����^�E���^�X�s�[�J�Ȃ���Ȃ��쓮�ł��܂��B���́A���}�n��NS-515F���Ȃ��ł��܂��B
�����ԍ��F23015484
![]() 1�_
1�_
���n���ق���
�����������܂��B
�����Ċm�F�����Ƃ���A���̌���PMA-390��DF�́u�n���̊ى��y��y���v��HP�Ɍf�ڂ���Ă���A���̒l��32�ł����B
�@��͖����ɉ����t���Ȃ��������f���̂悤�ł����B
�܂��AJBL�Ƒ�������낵���ƌ�����}�b�L����DF���ӊO�Ə������̂́A������Ƃ��������ł����B
�Ƃ���ŁA�n���ق���́u�n���̊ى��y��y���v�̊W�҂ł��傤���H
�����ԍ��F23015528
![]() 1�_
1�_
bebez����A�̂�ۂ�Atohoho3����A����ɂ��́B������ƒx���Ȃ�܂����B
�Y�Y���̖��͎v�l�͂�₤���́B�X�s���͐V���̉Ȋw���ɂ������ł����A�P�ʂ����ɂ͌����̐[��������܂��B�̏d�Ǝ��ʂ̈Ⴂ�ʂ͌����ė~�����̂Ɠ������Ƃł��B����tohoho�����w�E�̒ʂ�A�����ÓT���������ł͂���Ă����܂���B
���Ė{��B���̓��e�ł�bebez����̐����ɑ���٘_�������܂��B0.1���}�����Abebez����̓X�s�[�J�[���͂��A���v�o�͂��1.3�{�ɑ傫���Ȃ�Ǝ咣����Ă��܂��ˁH���ꂪ�N����ɂ́A�A���v�̏o�͓d���ɑ��ēd�����t�����ɗ����K�v������܂��B�܂�A�X�s�[�J�[���d�͂������A�A���v������������悤�Ȋ��D�ł��B
0.1���}�����ƒ������̔g�`���d�˂ĉ�͂���Ƃ킩��̂ł����A�O�҂͑��莞�ԑS��Ŗ�1.3�{�ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ������Ƃ́A���̊��ԑS��ŃX�s�[�J�[���d�͂������Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��Bbebez���Ȃ�Ƃ�������낤�ƁA����͂��蓾�܂���B��R�l�����ł�����肱�̎���͕ς��Ȃ��ł��傤�B
�܂�0.1���}�����A�A���v�o�͎��̂�1.3�{�ɂȂ��Ă���Ƃ����l����ꂸ�A�A�L���t�F�[�Y�́u����1�A�Q�A�R�ŃA���v�o�͓͂����v�Ƃ����͌��ƒf������܂���B
�̂�ۂ炲���₪����܂����̂ŁA��R�}�����̔g�`�̋�����������܂��B
�p���X������A��{�I�ɂ��̒ʂ�ɋ쓮����܂��B�u�d���ƃR�[���̈ʒu���P�F�P�Ή�����v�ƌ����킩��₷���ł��傤���B
�s�[�N�t�߂ł̓R�[���̑��x���[���ɋ߂����ߋt�N�d�͂������ŁA�A���v�͊y�ł��B�����Ƀs�[�N�l��1.3�{�ɂȂ�悤�ȃ��J�j�Y���͑��݂��܂���B�Ȃ��X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�ɔ�ׂ�0.1���͏������̂ŁA�قƂ�lje���͂���܂���B
�������p���X�I�����A�d�����ˑR�t���b�g�ɂȂ邽�߃R�[���ɋ}������������܂����A�����̂��ߒ����ɂ͎~�܂�܂���B�������̓A���_�[�V���[�g����������Ƌ��͂�NFB�ɂ���Ď~�܂�̂ł����A0.1���̉e����NFB�s�����������A���������ɉ�邽�߃����M���O���N����܂��iNFB���傫���A���v�قlje�����傫���͂��ł��j�B
�A���v���ڑ�����Ă��Ȃ�������M���O�̓X�s�[�J�[�̌ŗL�U���Ɉ�v����͂��ł����ANFB���}���������Ƃ��錋�ʁA���Z���ŗL�U�����������Ă�����̂ƍl���܂��B���ꂪ��100Hz�ł����A�쓮�g�`��100Hz�ł��������Ƃƈ��ʊW�͂���܂���B���܂��܈�v�������A�����̃L�[�p�[�\�����Ӑ}�I�Ɉ�v���������ł��B
�{���͂���ȂƂ���ŁB�B���Abebez����A�n���ق���ɂ��Ă͓����̃A�C�R���̉E�ɂ��邨�ƃA�C�R�����N���b�N����킩�邩�ƁB
�����ԍ��F23016136
![]() 0�_
0�_
�X�s�[�J�[�P�[�u���̃X���b�h�Ǝv���ēǂ�ł������A�N��肪�u�����b�ƒm���̂Ђ��炩��������v�X���ɂȂ��Ă��Ă�ˁB
�����ԍ��F23016236
![]() 5�_
5�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����́B
�A�L������̉Ƃ���Ӗ������ɂȂ��Ă��܂��܂����A���I�ȋ��������t�Ő����E��������͔̂��ɓ���A���_�I�ɐ�������������ɂ͐������i���f�����O�j������ŃV�~�����[�V�������s���̂��ł��L���ł���ƍl���܂��B
�i�A���A�����Ŏ��ʂƏd�ʂ̒l���ԈႦ�ē���Ă��܂��Ƃ������Ă̌��ʂ��o��̂ŁA�����������~�X�͗v���ӂł��B�j
�X�s�[�J�͎��g���т�����A�o�l�}�X��LCR�ŋߎ��ł���Ƃ͎v���̂ł����A�c�O�Ȃ���A�X�s�[�J���܂ރI�[�f�B�I���i�Ɋւ��Ă̓X�s�[�J�̃l�b�g���[�N�v�Z�������A��͓I�A�v���[�`�Ō��������o�����Ȃ��̂ŁA����͌��ۂ��琄������Ƃ����A�v���[�`��1.3�{�����l�@���Ă��܂��B
�����܂łɂ͐����������Ȃ̂ŁA�������҂����������B
��_�����Y�ꂳ��Ɋm�F����������������܂��B
�u�����̓X�s�[�J�[�̓d���̓��ɔ�Ⴗ��v�ƍl���Ă��܂����A����͐������ł��傤���H
�����ԍ��F23016276
![]() 1�_
1�_
��bebez����
���͑n���̊ى��y��y���̊W�ҁA�Ƃ�����获�M�����{�l�ł��B
�����Ŏ�����HP��URL�����̔ɏ����ƗU�����Ă�݂����Ȃ̂ŁA�ł��邾�������Ă܂�
�i���̕����\���Ă��������镪�͍\��Ȃ��ł��j
�����ԍ��F23016448
![]() 2�_
2�_
���n���ق���
���ԐM�A���肪�Ƃ��������܂��B
�S������ϖ����Ō������đn���ق���HP���ڂɎ~�܂�܂����̂ŁA�����Ƒ�R�𗧂��M����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B
����A�F�X�Q�l�ɂ����Ă������������Ǝv���܂��B�����b�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F23016538
![]() 2�_
2�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�lj����܂��B
�Y�ꂳ��́A��������0.1���}�����ŃA���v�̃{�����[���̈ʒu������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƌ肽���̂��Ǝv���܂��B
�m���ɁA���̎������x�����ƗL�蓾��b�ł͂���܂��B
�܂��A��������0.1���}�����̃f�[�^���قڑ����ł���A���̉\���������ƌ����܂����A�������ڂ����͓̂��͒�~��̎���ł��B
DC�J�b�g�ɂ��A���_�[�V���[�g�i�w�p�I�ɂ̓A���_�[�V���[�g�Ƃ͌���Ȃ��H�j�������������Ă݂�ƁA0.1���̃f�[�^�́A���Ɉ�R�͖��m�ɏo�Ă���A�͂��ł����X�ɏ�Ɉ�R���邱�Ƃ��ł��܂��B
���傤�ǁA�n���ق���DF��Q�̊W������Ă��������܂����̂Ŋ��p�����Ă��������܂����A
Q��Q0c(1�{1�^DF)
�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁADF=73�Ȃ�Q��1���������ω����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
Q���P�����������������ł́A������0.1���}���̎���ɂ��ꂾ���̍���������킯���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂����肢��������Ǝv���܂��B
�]���āA�P�Ɂu�{�����[���̈ʒu������Ă����v�ŕЂÂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B
�ǂȂ��������Ă����C���p���X�����ł���A���̍��͂����ƌ����Ɍ��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B
���͔g�`�������g�̈ꕔ�Ȃ̂ŁA���ΓI�Ɉ�R�ڂ��傫���Ȃ��Ă��܂��A�e�[���̐U�����ڗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A0.1���}�����̃f�[�^�͂悭����ƌ��\�U�����c���Ă���̂ł��m�F����������Ǝv���܂��B
�܂��A���́A�A�L���t�F�[�Y�́u����1�A�Q�A�R�ŃA���v�o�͓͂����v�Ƃ����͐M����Ƃ������������Ă���܂����A��x����Ƃ��A�u0.1���}�����A�X�s�[�J�[���͂��A���v�o�͂��1.3�{�ɑ傫���Ȃ�v�ȂǂƎ咣�������Ƃ͂���܂���̂ŁA����Ȃ��悤�ɁB
�A���v�̏o�͂������Ȃ̂ɁA���X0.1���̒�R��}�����邾���Ńs�[�N�d����1.3�{�ɂȂ�Ƃ������蓾�Ȃ����ۂ������������Ƃ����̂�����ł��B
�����ԍ��F23016589
![]() 1�_
1�_
bebez����A���Ԃ����Ȃ��̂Ŋm�F�Ƃ��肢�ł��B
>���́A�A�L���t�F�[�Y�́u����1�A�Q�A�R�ŃA���v�o�͓͂����v�Ƃ����͐M����Ƃ������������Ă���܂����A��x����Ƃ��A�u0.1���}�����A�X�s�[�J�[���͂��A���v�o�͂��1.3�{�ɑ傫���Ȃ�v�ȂǂƎ咣�������Ƃ͂���܂���̂ŁA����Ȃ��悤�ɁB
�ł͂ǂ��咣����Ă���̂ł��傤�H�z������Ɂu�s�[�N�d����1.3�{�ɂȂ�Ǝ咣���Ă���̂ł����āA�S�̂�1.3�{�ɂȂ�Ƃ͎咣���Ă��Ȃ��v���Ǝv���܂����A����ł悢�ł��傤���H�Ⴄ�ꍇ�͂ǂ��������咣�Ȃ̂��A����̗]�n�̂Ȃ����t�Ŏe�ׂ܂ŋ����Ă��������B
��L�O��ŏ����܂����A����ɂ��Ă͎�����̓��e��
>0.1���}�����ƒ������̔g�`���d�˂ĉ�͂���Ƃ킩��̂ł����A�O�҂͑��莞�ԑS��Ŗ�1.3�{�ɂȂ��Ă��܂��B
�Ə����Ă���̂𗝉�����Ă��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B����̐}��Y�t���܂��B����́A�Q�̔g�`�̃[�����x���ƃs�[�N�l�������悤�ɏd�˂����̂ł��i�҂�����d�˂�Ƃ킩��Â炢�̂Ŏ��Ԏ����������炵�Ă��܂��j�B
��̃A���_�[�V���[�g�������A�S�̂���v���Ă��邱�Ƃ��킩��ł��傤�B�܂�A�s�[�N�l��1.3�{�ɂȂ��Ă��邾���ł͂Ȃ��A�S�̂�1.3�{�ɂȂ��Ă��܂��B�A���_�[�V���[�g�̃��J�j�Y���͒u���Ă����Ƃ��āA0.1���}���������{�����[���������͓��͐M�����グ�Ă����ƍl����̂��ɂ߂Ď��R���Ƃ͎v���܂��H�����łȂ��Ƃ���������������̓��e�ɏ����܂����B
���̑��Aweb�Œ��ׂ�Ηǂ��������A��̎��̓��e���悭�ǂ߂킩��b������Ǝv���܂��B�������������b�������ƑΉ������˂܂��B�܂��A���炩�ɊԈ�����O��Ɋ�Â����b�A���Ƃ��Ώ�L�A�L���̉����������Ƃ�O��Ƃ������b�����l�ł��i�A�L���̉��������Ȃ����Ƃ̗��R�͐�̓��e�ŏ\�ɏ����܂����̂ŁA�܂�����ɔ��_���Ă��������j�B
�������T�d�Ɏ��̓��e�����ǂ݂ɂȂ�A���̑��̓��������v�ɂ��z���������������A�����e�̏C���Ȃ�����肢�ł���ƍK���ł��B
�����ԍ��F23016881
![]() 1�_
1�_
bebez����
�ꕔ�A��������邱�Ƃ��킩�����C�����܂��B0.1�����ɃA���_�[�V���[�g������̂�
>�P�Ɂu�{�����[���̈ʒu������Ă����v�ŕЂÂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B
�Ƃ������Ƃł���ˁH����͂��̒ʂ�ł��B
���������Ă���͈̂ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃł��B�i�Ƃ������A���͂�^���悤�̂Ȃ������ƍl���Ă��܂����j
�E0.1�����ɃX�s�[�J�[���͔g�`���u�����ނˑS�̂Ƃ��āv��������1.3�{�ɂȂ��Ă���̂́A�A���v�o�͂�1.3�{�ɂȂ��Ă��邩��ł���B�����łȂ��ƃX�s�[�J�[���G�l���M�[���Y�����Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��A���蓾�Ȃ��B�܂�A�L���͕̉����@���ɔ�����B
�E�A���_�[�V���[�g���N�����Ă���̂́A0.1���̉e���ŏu�ԓI��NFB�s���������Ă��邩��ł���i����͈ꉞ�A�������x���j�B
�v�́u1.3�{�v�Ɓu�A���_�[�V���[�g�v�͕ʂ̘b�Ƃ������Ƃł��B����œ`���Ƃ悢�̂ł����B����āA
>�A���v�̏o�͂������Ȃ̂ɁA���X0.1���̒�R��}�����邾���Ńs�[�N�d����1.3�{�ɂȂ�Ƃ������蓾�Ȃ����ۂ������������Ƃ����̂�����ł��B
�Ƃ����͓̂k�J�ł�������܂���B�����@���ɔ�����O���u���͖̂��Ӗ��ł��B�u���蓾�Ȃ��v�͓̂��R�ł��B
�����ԍ��F23016996
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���͂悤�������܂��B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�u0.1���̑}���Ńs�[�N�d����1.3�{�ɂȂ�v�Ƃ������蓾�Ȃ��b���ɂ߂ď��Ȃ���琄�����Ă���킯�ŁA�^���̓A�L�����^���Ɍ������������A���邢�͍Ď������Ȃ����薾�炩�ɂȂ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�������A����ɂ͎��Ԃ��|����̂ŁA���炭�������������y�������Ƃ����R���Z���T�X���ł��ꂢ��Ǝv������ł����̂ł����A�Y�ꂳ��̃X�^���X�͏���������悤�ł��ˁB
������Y�ꂳ�ɐ\���グ��ANFB�̐��\�������Ă��̂悤�ȃA���_�[�V���[�g����������Ƃ������Ƃ͒f���ĂȂ��ƒf�������Ă��������܂��B
���āA���͐��������Ƃ��Ċy����ł������肾�����̂ŁA�\���ʂ芮���҂��������܂����B����������������������B���Ȃ蒷���ł��B
�����A�u�����̓X�s�[�J�[�̓d���̓��ɔ�Ⴗ��v��O��ɐ������܂����̂ŁA���̑O��Ɍ�肪�������ꍇ�ɂ́A���Z�b�g���čl�������K�v������܂��B�i�ɂ߂ď����I�Ȃ̂ł����A���͂�����Ǝ��M���Ȃ��̂ł��B�j
�����ԍ��F23017139
![]() 1�_
1�_
����ł́A�n�߂܂��B
�Y�t�����O���t���g���Đ�����i�߂܂����A���̃O���t�i�ȉ��A�O���tA�j�͑n���ق����HP�i���LURL�j������p�����Ă���������̂ł��B
https://souzouno-yakata.com/audio/2002/05/09/2144/
HP�ɍs���ƁA�X�ɏo�T��������Ă��܂����A�匳�͒P�s�{�̂悤�ł��B
���l�̃f�[�^�����p����ꍇ�́A���̐M�ߐ��̊m�F�͕s���ł����A�O���tA�͒P�s�{����̈��p�ł��邱�ƁA�f�[�^���̂����o�Ƀt�B�b�g���邱�ƁA�����āA����̑n���ق���Ƃ̂�����Ƃ�������肩��A���p����ɒl������̂Ɣ��f���܂����B
����́A�O���tA�ƃI�[�f�B�I�X�N�G�A����̃u���O�Ɍf�ڂ����R�̎������ʂ�p���Ęb��i�߂܂��B
�j�S��0.1���}�����̎����f�[�^�ł����A���̃f�[�^�̏ڍׂȍl�@�ɓ���O�ɁA�R�̃f�[�^�̑��ΊW�ɂ��ĐG��Ă����܂��B
�����̃f�[�^����Ƃ��āA0.1���}�����̓s�[�N�d�������������A10���}�����͌��������ł���A�ꌩ�X�������݂ɂ��������܂����A����͖�肠��܂���B
�����f�[�^����ǂ߂�s�[�N�d���́A������2.2V�A0.1����2.9V�A10����1.6V�ł����A��R�}���ɂ��Q�C��������������ƁA�e�X�A2.2V�A2.9V�A3.6V�ƂȂ�܂��B
����́A��R�l�𑝂₷���Ƃŋ��U���ۂ������o��Ƃ����X���������Ă��܂��B
�܂��A�s�[�N�d���̑��������f�V�x�����Z����ƁA�e�X�A0dB�A+2.4dB�A+4.3dB�ƂȂ�܂��B
���ɁA�u��R0.1���̃P�[�u���͎��p�͈͓��ɂ���v�Ƃ����O��̌��_��O����0.1���}�����̃f�[�^�����Ă݂܂��B
�c�O�Ȃ���A���́A�X�s�[�J�[�̓d���ϓ��Ɖ��̕ω��̑��ւɂ��đS�����o���������킹�Ă��Ȃ��̂ŁA�u���O�̎������@�ɂ�����s�[�N�d���̕ω������ɗ^����e�����C���[�W���邱�Ƃ��ł��܂���B
�������A�����̋Z�p����E�H�ƕ���ɂ����ẮA�p���X�����̃s�[�N1.3�{�Ƃ����悤�ȕω��͖����ł��Ȃ��傫�ȕω��Ƃ��đ�������ꍇ�������A����ɂ���Ắu�s��v�Ƃ��Ĉ����郌�x���ł��B
���p�͈͓��ɂ���P�[�u���Ɠ����̒�R���g���Ă��̂悤�ȕω�����������Ƃ����̂́A�ɂ킩�ɐM���邱�Ƃ͂ł��܂���B
�܂�A�������Ԉ���Ă���ƍl����̂��Ó��ł��B
����ł́A������ʓI�Ɍ��Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B
�O���tA��DF�ɂ��X�s�[�J�̎��g�������̕ω���\�������̂ł��B
�u���O�̎����Ƃ͈قȂ�X�s�[�J�ׂƂ��Ă���̂ŁA�����ȈӖ��ł͒�ʓI�ɕ]������c�[���Ƃ��Ă͕s�K�ł����A�u�R�E�F�C�V�X�e���v�Ƃ̋L�ڂ�����̂ő���a�̃E�[�t�@�𓋍ڂ��Ă���Ɛ�������A�I�[�_�[��������Ƃ����Ӗ��ɂ����Ă͏\�����p�ł���ƍl�����܂��B
�O���tA�̒���g��ɒ��ڂ���ƁA40Hz�t�߂�DF�̉e�����ł��傫���o�Ă��܂��B
DF=���ɑ��āADF=10�ł�+1dB�ADF=3��+3dB�ADF=1��+6dB���炢�Ɠǂݎ��܂��B
�L�ڂ͂���܂��A���̕���\�̃O���t��ł�DF=100��DF=���Əd�Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���āA���̃O���tA�̃f�[�^�ƁA�u���O�̎����f�[�^���r���Ă݂܂��B
�������A���҂̊Ԃɂ͌v�����@�̈Ⴂ�͂��邵�A�O���tA�ōł����x�̍���40Hz�̒l�ƃp���X���͎��̃s�[�N�d���̒l���r����̂͑������\�ł����A�����܂ŁA�I�[�_�[����������Ƃ������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��̂ŁA���̂܂ܐi�߂܂��B
�O���tA�ł́ADF=10�ł��S��ɓn���Ċ�ɑ����X1dB���x�̍������o�Ă��܂��A�v�Z��قڈꌅ���DF=73��L����u���O0.1���}���̃f�[�^��+2.4dB�ƂȂ��Ă��܂��B
�ǂ��炩�ɉ�������̌�肪����ƍl����̂��Ó��ł��B
�������A�ǂ��炪���������ƌ����A����͎����ł��B
���ɁA�O���tA��DF=1�ƃu���O��10���}���iDF=0.8�j���r���܂��B
�O�҂�+6dB�A��҂�+4.3dB�ł�����A�����������̑����X�̈Ⴂ���l������A�����ɂ͖��������o�����Ƃ͂ł��܂���B
�ނ���A�F�X�ȏ����̈Ⴂ�����钆�ŁA���������ǂ���v�������Ă���ƕ]���ł��邩�Ǝv���܂��B
�O���tA�Ƃ̔�r�ɂ��A10���}���̎����͐������s���A0.1���}���̎����ɂ͉�������̌�肪����Ƃ����\�������܂�܂����B
�����ŁA�u0.1���}�������̍ۂɈꌅ�Ⴄ��R��}�����Ă��܂����v�Ƃ�����_�ȉ����𗧂ĂĂ݂܂����B
1���Ȃ̂�2���Ȃ̂��A����͂������ɐ����ł��܂��A�Ƃ肠����1���Ɖ��肵�ăO���tA�̃f�[�^�Ɣ�r���Ă݂܂��B
1���ƂȂ�ƃQ�C���̒ቺ�������ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���߂ăs�[�N�d���̏㏸�����v�Z����ƁA��̒����ɑ��Ė�1.5�{�A+3.4dB�ƂȂ�܂��B
�܂��A�v�Z���DF�͖�8�ł��B
�O���tA�ł́ADF=10��+1dB�ADF=3��+3dB�ł�����A�I�[�_�[�Ƃ��Ă͋߂��Ȃ����ƌ����܂��B
���l���킹������Ȃ�A1���łȂ�3���Ɖ��肵�������ǂ���������܂��A����͂����܂ŃI�[�_�[�������邽�߂̃��t�����Ȃ̂ŁA����͂������܂���B
1���Ƃ����̂�4sq�P�[�u��100m�ɑ�������̂ŁA�����I�ɂ̓u���O�f�ڂ̃f�[�^�������܂��B
�܂��A�}��������R�l���Ԉ���Ă����Ƃ���A�u0.1���܂���DF=100���x�ł���A�����܂���DF=800�Ƃ̍��͔����ł���A�D�݂ɂ���đI���ł�����e�ł���v�Ƃ������܂ł̏펯�i�H�j�����邱�Ƃ�����܂���B
���_�F�@0.1���̒�R���}���������肪�ꌅ�Ⴄ��R���}�����Ď������Ă��܂����Ɖ��肷��ƁA�s���ȃu���O�f�ڃf�[�^����������
�ȏ�Ő��������͊����Ƃ����Ă��������܂����A�s�v�c�Ȍ��ۂɑ����������ɂ́A�܂����̌����𐄒肵�A�����������Ă����������Ƃ����̂��g���u���V���[�e�B���O�̊�{�ł��̂ŁA���̊�{�ɏ]���A�I�[�f�B�I�X�N�G�A�l����уA�L���t�F�[�Y�l�̋��͂̉��A�{�������̉𖾂��s���Ă��������ł��邱�Ƃ�t�����������Ă��������܂��B
���炭���t���������������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F23017149
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
��lj����܂��ˁB
�Y�ꂳ��̃R�����g��q������ƁA�A���v�̏o�͒[�̓d��������ł�������d�́i���Ԃ��|����G�l���M�[�j������ł���Ǝv���Ă���悤�Ɋ�����̂ł����A�Ⴂ�܂����H
���ׂ����i�Ⴆ�ΌŒ��R�j�̏ꍇ�ɂ͓d�͓͂d���̓��ɔ�Ⴗ�邩�炻�̒ʂ�ł��B
���������וϓ��i���̏ꍇ�̓X�s�[�J�̋t�N���傽��ϓ��v�f�j������ꍇ�ɂ́A�o�͒[�̓d��������l�Ɉ�v������悤�ɓd�́i�܂��͓d���j�̋����ʂ�����̂�NFB�ł�����A�A���v�̏o�͒[�̓d��������ł����Ă������d�͂������Ƃ͌����܂���B
�]���āA�����P�C�Q�C�R�ŃA���v�̏o�͒[�̓d��������i�����ɂ͋͂��ȍ�������A���̍���NFB�̐��\�Ɉˑ����܂��j�ł������Ƃ��Ă��A�d�͋����ʂ͓���ł͂���܂���B
�܂��A0.1���Ƃ����������Ă��ǂ��悤�Ȓ�R�l�ōl����Ƃǂ����Ă��u���蓾�Ȃ��v����s���Ă��܂��̂ŁA�i�����ƒf���͂ł��܂��j��x1���Ȃ�3���Ȃ�̒�R���Ԉ���ē���Ă��܂����ƍl���Ă���������Γ��S���s���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����ł��Ȃ����A�Y�ꂳ�{�����[�������咣�����̂ł���́A����ȏ�c�_���Ă����s���̂܂܂Ȃ̂ŁA��U�y���f�B���O�Ƃ��܂��H
�����ԍ��F23017196
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�X�ɂ�����B
���u�s�[�N�d����1.3�{�ɂȂ�Ǝ咣���Ă���̂ł����āA�S�̂�1.3�{�ɂȂ�Ƃ͎咣���Ă��Ȃ��v���Ǝv���܂����A����ł悢�ł��傤���H�Ⴄ�ꍇ�͂ǂ��������咣�Ȃ̂��A����̗]�n�̂Ȃ����t�Ŏe�ׂ܂ŋ����Ă��������B
��ɓ��e�����������������҂Łu����̗]�n�̂Ȃ����t�Ŏe�ׂ܂Łv��������ł����A���������X�g���[�g�ɉ��܂��ˁB
No�ł��B
�s�[�N��1.3�{�Ȃ�S�̂��T��1.3�{�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�]���āA�����̖@���ɑ���ƁA�A���v����̓d�͋����ʂ�[��1.7�{�{�}����R�̓d�͏��]�ɂȂ��Ă���Ɛ������܂��B
�d�˂Đ\���グ�܂����A����0.1���̎�����0.1���ł͂Ȃ������Ƒ傫����R���g���čs��ꂽ�@�Ƃ����̂��������ʂł��B
�����ԍ��F23017276
![]() 1�_
1�_
�w�Z�̐��k�S�����猙����^�C�v�ł���B
�����ԍ��F23017394
![]() 2�_
2�_
���t�@�C�u�}�C���Y����
�����ł��ˁB�s���葽�����ڂɂł����ł���肷��ɂ́A�K���Ɍ�������������܂���ˁB
�����ԍ��F23017475
![]() 1�_
1�_
bebez����A�d�v�Ȗ��������Ă�����܂��̂ŁA���₳���Ă��������B
>�A���v�̏o�͂������Ȃ̂ɁA���X0.1���̒�R��}�����邾���Ńs�[�N�d����1.3�{�ɂȂ�Ƃ������蓾�Ȃ����ۂ������������i23016589�j
>�s�[�N��1.3�{�Ȃ�S�̂��T��1.3�{�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�i23017276�j
��L�Q�̂�������
>���́A�A�L���t�F�[�Y�́u����1�A�Q�A�R�ŃA���v�o�͓͂����v�Ƃ����͐M����Ƃ������������Ă���܂����A��x����Ƃ��A�u0.1���}�����A�X�s�[�J�[���͂��A���v�o�͂��1.3�{�ɑ傫���Ȃ�v�ȂǂƎ咣�������Ƃ͂���܂���̂ŁA����Ȃ��悤�ɁB(23016589)
�Ƃ������������������Ă���悤�Ɏ��ɂ͎v���܂��B����Ă��܂��Ɂi��L�R�ڂ́j�������̐��m�ȈӖ����킩��܂���B���萔�ł��������Ă��������B
����A���� 23016881 �Ōf�ڂ����}����A0.1���}�����̃X�s�[�J�[���͂̊T�ˑS�̂��A�������̂����1.3�{�ɂȂ��Ă���̂͋q�ϓI�����ł��B����͂����������������ł��傤���H
�Ƃ������Ƃ́A�����u����1�A�Q�A�R�ŃA���v�o�͓͂����v�������ł���A�u0.1���}�����A�X�s�[�J�[���͂̊T�ˑS�̂��A���v�o�͂��1.3�{�ɑ傫���Ȃ��Ă���v���ƂɂȂ�̂ł����B�����_��������肢���܂��B
�����ԍ��F23017646
![]() 1�_
1�_
bebez������Y�ꂳ����c�_���肶��ʔ����Ȃ��낤�B�O�ɂ����������ǁAWaveGene��WaveSpectra�Ƃ����t���[�\�t�g��ADC�Ƃ��ẴI�[�f�B�I�E�C���^�t�F�[�X������ΊȒP�Ɏ����ł���̂ŁA�V��ł݂��炢���̂ɁB�Ƃ������ƂŁA�A���v�ɂ��_���s���O�̈Ⴂ���r���Ă݂��B
https://www.youtube.com/watch?v=Dg272YPywlg
�����ԍ��F23017745
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�Y�ꂳ����������Ǝv���܂����A���̃��x���̃e�N�j�J���ȋc�_���A���������ōs�������Ɋ����Ă���܂��B
�i�Y�ꂳ��̓x�e�����̂悤�Ȃ̂ŁA�����łȂ������j
���Ď���ւ̉ł����A
�u���O�Ō���0.1���ƌ����Ă�������́A���炭�A1����2����3���̒�R��}�����Ď��{���ꂽ�̂ł͂Ȃ����@�Ɛ\���グ�Ă��܂��B
�����ł���ADF�͂��Ȃ艺����̂ŋ��U���o�āA���U�ɂ��X�s�[�J�[�̃s�[�N�d�����A���v�̏o�͒[�q�̓d�����傫���Ȃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ����A�e�[���ɐU�����c�邱�Ƃ����������Ǝv���Ă��܂��B
�����������̂��肾�����̂ŁA�������܂킵�ȁi�v�킹�Ԃ�ȁj�\�����������ƂŖ��������������Ă��܂�����������܂���B
���́i�����Y�ꂳ����������Ǝv���܂����j�A����͈͓̔��ł���P�[�u���̉e���Ȃǔ��X������̂Ƃ����X�^���X�Ȃ̂ŁA�����A0.1���ł��̂悤�ȕω�������Ƃ���ƁA���{�I�ɍl�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B
�]���āA�������u���O�̃f�[�^�Ƃ͂����A�����R�̃f�[�^�Ɋւ��Ă͓��S���s���܂ŃA�L���t�F�[�Y����ɐ��������߂Ă�������ł��B
�̔��X��ʂ��ƒx�X�Ƃ��Đi�܂Ȃ��悤�ȋC������̂ŁA���̓A�L������̕i���ۏؕ��ɒ��ړ����Ă݂悤���Ƃ��v���Ă���Ƃ���ł��B
�����ԍ��F23017872
![]() 2�_
2�_
bebez����
���͐�̓��e�ŁAbebez����ɂQ�̎���ƂP�̖₢���������܂������A������ɂ���������܂���ł����B�����Ŏ���P�ɍi��܂��̂ŁA���肦�Ȃ��ł��傤���B���Ȃ킿���L�ł��B
>���� 23016881 �Ōf�ڂ����}����A0.1���}�����̃X�s�[�J�[���͂̊T�ˑS�̂��A�������̂����1.3�{�ɂȂ��Ă���̂͋q�ϓI�����ł��B����͂����������������ł��傤���H
���t�̂��Ƃ�ɂē���_���������������Ă��������B�O�̂��ߐ����������܂��B�}�������Ƃ���́A�u0.1���}�����̔g�`�̓d������萔�{�������́v�Ɓu�������̔g�`�v���A��̃A���_�[�V���[�g�����������قڈ�v����Ƃ������Ƃł��i�������0V�̈ʒu�Ǝ��Ԏ��̃X�P�[���͍��킹�Ă��܂��j�B�s�[�N�d����1.3�{�ł�������A�S�̂�1.3�{�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���邢�͎��̐}������K�v���Ȃ��āA0.1���̔g�`�ƒ������̔g�`���A�d������L�k������Έ�v�������Ȃ��Ƃ͂킩��ł��傤�B
����������������̂́A���������ɏd�v������ł��B�����܂ł��������Ă������Ȃ��Ƃ���A�Ȃ�炩�̗��R�ł������ۂ��ꂽ���̂��ȂƗ������A����ȏ�͍T���܂��B
�������Abebez���{���S���ꂽ���̂ł���A��L�𗝉�����邱�Ƃ͏d�v�ł��B���i������ł����������ł��j�����邱�Ƃ�����Ă���܂��B
�����ԍ��F23018113
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
����ɂ��������܂��B
��0.1���}�����̃X�s�[�J�[���͂̊T�ˑS�̂��A�������̂����1.3�{�ɂȂ��Ă���̂͋q�ϓI�����ł��B����͂����������������ł��傤���H
�ԈႦ�Ȃ��A�s�[�N�����łȂ��S�̂�1.3�{�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͗������Ă���܂��B
�����A�����R�̃f�[�^�́A0.1���}���Ə̂��Ă��邾���ŁA�����Ƒ傫����R��}�����čs���������̌��ʂ��Ɛ������Ă��܂��B
����ɉ�����ƁA���łɐ\���グ�����Ƃł����A
�����P�i�����j�Ǝ����R�i0.1���Ə̂��Ă���j�ɉ����āA�A���v�̏o�͓d���͓���ł��A�A���v�����ׂɋ������Ă���d�͎͂����R�̕����傫���A
�����R�̋����d�́�����1�̋����d�͂�1.69�{�{�}����R�̓d�͏��
�ƍl���Ă��܂��B�i1.69=1.3×1.3�j
�t�Ɉ���₳���Ă��������B
�����Q�i10����R�}���j�̏ꍇ�ł����A�A���v�̏o�͒[�̓d���͎����P�Ƃقړ���Ƃ������Ƃ͋��ʔF���ɂȂ��Ă������Ǝv���܂��B
����ł́A�����Q�ɉ����ăA���v���畉�ׁi��R�{�X�s�[�J�j�ɋ��������d�͂͂ǂ��Ȃ�Ƃ��l���ł����H
�����ԍ��F23018231
![]() 1�_
1�_
bebez����A�����肪�Ƃ��������܂����B�悩�����ł��B
�����Ă̋c�_�W�J�͌�ɂ��āA�����ⓙ�ɉ��܂��B
>�����A�����R�̃f�[�^�́A0.1���}���Ə̂��Ă��邾���ŁA�����Ƒ傫����R��}�����čs���������̌��ʂ��Ɛ������Ă��܂��B
�͂��B����͉��܂߂Ă������Ȃ��Ƃ����X����̂ŁA�������̉\����r�����܂���B
>�����P�i�����j�Ǝ����R�i0.1���Ə̂��Ă���j�ɉ����āA�A���v�̏o�͓d���͓���ł��A�A���v�����ׂɋ������Ă���d�͎͂����R�̕����傫���A
���̓A���v�̏o�͓d���͓���ł͂��蓾�Ȃ��i�����ł͂Ȃ��Ȋw�I�A���j�Ƃ̗���ł��B����ɂ��Ă͌�̓��e�Ő����������܂��B�u�A���v�����ׂɋ������Ă���d�͎͂����R�̕����傫���v�͓��ӂł��B
>�����Q�ɉ����ăA���v���畉�ׁi��R�{�X�s�[�J�j�ɋ��������d�͂͂ǂ��Ȃ�Ƃ��l���ł����H
�ǂ̒��x�̐��x�����߂��Ă���̂��킩��܂��A�P���ɂ́A���ג�R�� 10��+8�� �ɑ�������̂ŁA�A���v����������S�d�͂͒������� 8/18 �{�ɒቺ����Ǝv���܂��B�����M���O���Ă���e���ɂ��Ă͂悭�l���Ȃ��Ƃ킩��܂���B
�����ԍ��F23018295
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���Ȃ����Ɨ���Ȃ��ꎟ�Ő����ł���̂������܂ł��ȂƎv���A���߂Ď��������A���A�L���t�F�[�Y�ɑ������Ƃ���ł��B
�������玿���ƍ��킹�ĖY�ꂳ��ɂ����肵�Ă��ǂ��ł����A�Ȃɂ����܂��A�����@��������m�点���������B
�������̒��ɂ͐F�X�ƕ��@�����邩�Ǝv���܂����A���̎�ɂ͑a�����̂ŁB
���̂悤�ȃT�C�g�ł́A���Ă��ꂸ�Ƀ`���`�������Ă����m�ɂ�����̂ŁA���̐�͕ʂ̕��@�������������낵���Ǝv���܂��B
�Y�ꂳ��Ƃ͋��ʔF���ɗ��Ă������ƁA�������s���̕���������܂����A�A�L���t�F�[�Y�ɍĎ��₷��ɂ������ẮA�����ł̂���肪�����𗧂����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23018362
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���Ԏ��A�x���Ȃ�܂����B
�U���̋����̊m�F������܂������A�U���͑��x�������Ċ�_�ɖ߂������ۂɁu�쓮�p���X���I�����A��x�R�[�����Î~��������v�Ƃ̗Ⴆ���C�ɂȂ�A�₢���������Ē����܂����B
�����J�Ȃ������A���肪�Ƃ��������܂��B
�쓮�g�`�̎��g���ƃ����M���O�ł̎��g���͓����ɂȂ�K�R�����Ȃ����ƁA���m���܂����B
�l���݂܂��ƁA�쓮�p���X�I����́A�U���ɑ��x���^�����Ă��邾���ŁA���̑��͉���쓮�p���X�̉e�����邱�Ƃ��Ȃ��̂ŁA���̏u�Ԃ���ŗL�U���Ɉڍs���邱�ƁA���������ʂ�ł��B
�g�`1.3�{�̌��A���Ή�����ꂳ�܂ł�^^;
�����̃X�����q�����܂������A�Y��悤�ɂ��������Ȃ�����̂��b�͗��H���R�Ɋ����܂����B
�����ԍ��F23018413
![]() 1�_
1�_
bebez����A�����́B
�����ӂ��肪�Ƃ��������܂��B�����������̂ւ�͑a�����̂ŁE�E�E�B
���āA�u�A���v�̏o�͓d���͓���ł͂��蓾�Ȃ��v���ł����A���̍����� 23016136 ��
>0.1���}�����Abebez����̓X�s�[�J�[���͂��A���v�o�͂��1.3�{�ɑ傫���Ȃ�Ǝ咣����Ă��܂��ˁH���ꂪ�N����ɂ́A�A���v�̏o�͓d���ɑ��ēd�����t�����ɗ����K�v������܂��B�܂�A�X�s�[�J�[���d�͂������A�A���v������������悤�Ȋ��D�ł��B
�Ə����܂����B�����������ȑf�����Ă��������������Ȃ������Ǝv���܂��̂ŁA�����̐}�����܂����B�A���v�o�� Vamp �ƃX�s�[�J�[���� Vsp �Ƃ��ׂ��ہA��R���}�����ꂽ�畁�ʂɍl���� |Vamp| > |Vsp| �ƂȂ�̂ł����Abebez����͒�R�l�ɂ���Ắ@|Vamp| < |Vsp| �ƂȂ蓾��A�Ƃ��l�����Ǝv���܂��B
�}�̐����������Ƃ���́A|Vamp| < |Vsp| ���N�������ꍇ�A�X�s�[�J�[���d�͂����邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃł��B����̓����M���O���Ȃǂ̒Z���ԋN����̂ł���Ζ��Ȃ��̂ł����A��ɂ������������悤�Ɂu�قڂ�����1.3�{�v�͂��蓾�Ȃ��̂ł��B
����́u�ʏ�0.1���v�̃P�[�X�ł́A�A���_�[�V���[�g���Ă���Z���Ԃ����A|Vamp| < |Vsp| ���N�����Ă��܂��B
�̂�ۂ�A�����́B
�̂�ۂ�ɂ͂���������������Ǝv���Ă���܂����B�悩�����ł��B�ԐM���肪�Ƃ��������܂����B
�����M���O�̎��g���ł����A�c�e�̋c�_�ŕK�����p����鍲�����厁�̌Á`���f�[�^�ibebez����� 23017149 �ň��p����Ă��܂��j�����܂��ƁA�c�e���傫���Ȃ�قǃs�[�N�������g���փY���Ă������Ƃ��킩��Ǝv���܂��B����͂m�e�a������ł���̂ł͂Ȃ����ƁB�i�Ȃ��A���̃f�[�^�͉��L�ɓ\��ꂽ�̂��ŏ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��j
http://www38.tok2.com/home/shigaarch/OldBBS/DFandftoku.html
���ƁA�O���炿����ƋC�ɂȂ��Ă����̂ł����A
�X�����X���b�h(thread)�̗�
���X�����X�|���X(response)
�Ȃ̂ŁA������ƊԈ���Ă��邩���B�B
�����ԍ��F23018576
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�}����ʼn�������������肪�Ƃ��������܂��B
�����ɂ͓��̐������ł��Ȃ��̂ŁA�������Ԃ�����čl���Ă݂܂��B
���_������ƁA�l���Ă��������������ƁA��������Ă��������������Ƃ�����܂��B
����F
�������A|Vamp| < |Vsp|�ɂȂ�̂̓E�[�t�@�̃R�[�����������ƂŔ�������t�N�d�͂ɂ��ƍl���Ă��܂����A
�ǂ����ĒZ���Ԃł���N�����Ă����Ȃ��āA�����ԁi�قڂ����Ɓj���Ƃ��蓾�Ȃ��̂ł����H
�����ԁi�قڂ����Ɓj�Ƃ����Ă��A���̏ꍇ��8ms���x�ŁA���ۂɂ���8ms�ԁA�R�[���͈�����ɓ����Ă���Ǝv���܂����B
�܂��A�A���_�[�V���[�g/�����M���O�Ƌ��Ă���͓̂��͒�~��̐U���̂��Ƃ��Ǝv���܂����i����Ă����炲�w�E���������j�A
10���}���̏ꍇ�ɂ́A���͒�~��A��12ms�����i�Б�6ms�j�Ŕ����Ƃ͌����Ȃ����x���ŕϓ����Ă��܂��B
����͋N�����Ă����Ȃ��Ƃ������e�Ȃ̂ł��傤���H
�l�����������������F
�r���ł��\���グ���悤�ɁA0.1���̑}���ł�Q��1%�������ς��܂���B
���̕ω��͎��Ԉ�f�[�^�Ɍ����ɕ\��郌�x���ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A0.1���}�����̃f�[�^�ɂ̓e�[���ɖ��m�ȐU���������܂��B
���̂悤�ȐU���́AQ���啝�i10%�I�[�_�j�ɕω����Ȃ����蔭�����Ȃ��Ǝv���܂����A���̃e�[���̐U���ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɂ��l���ł����H
����������������������F
8���̏���R�ׂƂ����ꍇ�ƁA�C���s�[�_���X8����802D�N���X�̑�^�X�s�[�J�ׂƂ����ꍇ���r���āA�A���v�̏o�͒[�q�d��������̏ꍇ�A�A���v�����ׂɋ�������d�͂͂ǂ̒��x�Ⴄ�������m�ł����H
�덷�͈́H�A�����H�A��10���H�A����ȏ�H
�ȏ�A��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F23018814
![]() 1�_
1�_
��������܂��B
�u�R�[����������ɓ������Ă���v�Ə����܂������A�m���Ɉʒu�͈�����ł����A���̏ꍇ�͑��x�Ō���̂��Ó��Ȃ̂ŁA������Ƃ����̂͂��܂�K�ȕ\���ł͂���܂���ł����B
�����ԍ��F23018833
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂��B
�Z�p���̔߂������ŁA�C�ɂȂ��đ����ڂ��o�߂Ă��܂��܂����B
�܂����S�ɗ����ł����킯�ł͂���܂��A�Y�ꂳ�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ͂��Ȃ蕪�������C�����܂��B
�m���ɁA���ɑ}�����ꂽ��R���傫���ċ��U���o�Ă���Ƃ��Ă��A�}�����ꂽ�̂͏���R�Ȃ̂ŁA���͓d���i�A���v�̏o�͒[�d���j���o�͓d���i�X�s�[�J�̒[�q�d���j������Ƃ����̂͂�������a��������܂��ˁB
�u���蓾�Ȃ��v�łȂ��u��������a��������v�Ə��������R�́A������₵���e�[���̐U�������Ƃ̐�����������s���Ƃ��Ă��Ȃ�����ł��B
���͐M���i�M�������킩��A���v�ɓ��͂����M���j���[���ɖ߂��Ă���̓��삾���ōl����ƁA�A���v��DC�J�b�g�ɂ�蔭�����Q�ߓI�Ƀ[���ɖ߂郉�C���i���܂��\�����@�͂���܂��ˁH�j���ێ�����悤���䂵�A�X�s�[�J�[�ɂ͂��̓d������ɋt�N�d������悹����Č����Ă���Ƃ������ƂŁA�����a���͂���܂���B
�����A���͐M���̓[�����v���X���[���ł����A�V�X�e���͕ʂɗ̈������ē��삵�Ă���킯�łȂ��A���I�ɓ��삵�Ă���̂ŁA���͐M���v���X�̗̈�ł�NG�A���͐M���[���̗̈�ł�OK�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��͂��ł��B
����̂������ɂ������A�Z���ԁA�����ԁi�قڂ����Ɓj�ł͒��ۓI�߂��āA�\���Ȑ����Ƃ͌����܂���B���ɍ�����₵�Ă���܂��̂ŁA���S�̂��������������҂��܂��B
�܂��A�{�����[�����͂��Ȃ�L�͂ł����A����ł͉ߓn�����̌����ȕω��͐����ł��܂���B���̂Ƃ��뗼�����Ƃ��Ắu�}�������R�l���ԈႦ�A�{�����[�����������Ă��܂����v�����l�����܂��A���ɂ������Ƃ���ƁA�_�u���Ńq���[�}���G���[�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��A�u���O�Ƃ͂������������ɂ���I�ƌ��������Ȃ�܂��ˁB
�����ԍ��F23019102
![]() 1�_
1�_
bebez����A����ɂ��́B
>�������A|Vamp| < |Vsp|�ɂȂ�̂̓E�[�t�@�̃R�[�����������ƂŔ�������t�N�d�͂ɂ��ƍl���Ă��܂����A
>�ǂ����ĒZ���Ԃł���N�����Ă����Ȃ��āA�����ԁi�قڂ����Ɓj���Ƃ��蓾�Ȃ��̂ł����H
|Vamp| < |Vsp| ���������Ă���u�Ԃ̓X�s�[�J�[���d�͋������ɂȂ��Ă��܂��B�u�ԓI�Ȃ炢���ł����A�ŏI�I�Ɂi�d�͐ϕ��g�[�^���Łj�������ƂȂ�A�Ȃɂ��Ȃ�������G�l���M�[���������邱�ƂɂȂ��č���܂��B
>10���}���̏ꍇ�ɂ́A���͒�~��A��12ms�����i�Б�6ms�j�Ŕ����Ƃ͌����Ȃ����x���ŕϓ����Ă��܂��B
>����͋N�����Ă����Ȃ��Ƃ������e�Ȃ̂ł��傤���H
��������10�����̔g�`���d�˂��}��Y�t���܂��B����͎����I�ɁA10������ Vamp �� Vsp �����Ă���̂͂����ł��ˁB�ڍא����͏ȗ����܂����A�����ŃX�s�[�J�[�����d�͋������ɂȂ��Ă���̂́A�}�ŖԂ����������ԑт����ł�����A��肠��܂���B
�֑��ł����A10�����̃s�[�N�d���͒������� 8/22 ���炢�ŁA��̌v�Z 8��/18�� �ɋ߂����̂̂�⏬�����ł��B�����M���O�����ŃA���v���lj��œd�͋������Ă���̂ŁA����͍����܂��B
>���̂悤�ȐU���́AQ���啝�i10%�I�[�_�j�ɕω����Ȃ����蔭�����Ȃ��Ǝv���܂����A���̃e�[���̐U���ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɂ��l���ł����H
"0.1��"��M����O��ł����A��ɏq�ׂ��悤�ɁA��R���W�Q����NFB�s���ɂȂ��Ă��邽�߂ƍl���܂��B�����ɗD�G�ȃA�L���t�F�[�Y�̃A���v�ƌ����ǂ��A����FB���Ȃ��[�q�̋��������S�ɐ��䂷�邱�Ƃ͕s�\�ł��B�p�l�̘b�͑n���ق���̋L����ǂ�ł���܂��ANFB�̋����܂ł͐D�荞��ł��Ȃ������m��܂���B�Ȃ��A��ɂ��Љ���������厁�̃f�[�^�ł����A�n���ق���̂��̂Ɨǂ����Ă�����̂̕ʕ��ł����i���݂܂���j�B
>8���̏���R�ׂƂ����ꍇ�ƁA�C���s�[�_���X8����802D�N���X�̑�^�X�s�[�J�ׂƂ����ꍇ���r���āA�A���v�̏o�͒[�q�d��������̏ꍇ�A�A���v�����ׂɋ�������d�͂͂ǂ̒��x�Ⴄ�������m�ł����H
�����܂���̂Œ��ς��܂ޗ����ōl����ƁA�U�����ۂ̃G�l���M�[���x�͊�{�[���Ǝv���܂��̂ŁA�قڕς��Ȃ��Ǝv���܂��B���������ʂȓd������������\��������A���̍ۂ͒�R�����ɂ�鑹�����������܂��B���̒��x�͐U���̒��x����ł����A���ʂ͖����ł��郌�x���ł͂Ȃ����ƁB
����ň�ʂ肨���������Ǝv���܂��B�̂肵��̕����͂Ȃ�ׂ������g�ōl���Ă���������ƍK���ł��B
�����ԍ��F23019639
![]() 0�_
0�_
���݂܂���A��L�Ō�̂ق��́u�قڕς��Ȃ��Ǝv���܂��v�ł����A�X�s�[�J�[�̌ŗL�U�����t�߂ł̓C���s�[�_���X����i����傫���㏸����̂ŁA�A���v����������d�͂͂���ɔ���Ⴕ�Č�������ł��傤�B
�����ԍ��F23019660
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�ڂ����������A�������܂��B
����ɂ��Ă��A�f�[�^�����܂����H����e�N���������ł��ˁB�i�ŋ߂���A������O�H�j
�Y�ꂳ��̂��咣�͊T�˗����ł������Ǝv���܂��B
���萔�ł����A������[�߂邽�߂ɍX�ɋ����Ă��������B
�Y�ꂳ��́A�n�b�`���O���|�����̈���X�s�[�J������A���v���ɓd�͂����������̈�Ɛ�������܂����B
�m���ɁA�Y�t�̐}�ł�|Vsp|>|Vamp|�͂��̗̈悾���ł��B
�����ŁADC�A���v�����z���Ă��������B
DC�A���v�ł���A���͐M�����[���ɂȂ�ƁAVamp�͑��₩�Ƀ[���ɂȂ�܂��B
����AVsp�͐����s�����́A�[���𒆐S�Ɂ{�|�ɐU��܂��B
��������ƁA���͐M�����[���ɂȂ����ȍ~�͂����ƃn�b�`���O���|���邱�ƂɂȂ�܂��B�@�������܂łŁA�������Ⴂ�͂���܂����H
DC���J�b�g�����I�[�f�B�I�A���v���ƃn�b�`���O�̈悪����I�ŁADC�A���v���Ƃ��ꂪ�����ƍL����Ƃ����̂͂ǂ�������������̂ł��傤���H
�X�ɁA�����Ă��Ďv�����̂ł����A10���}���͈ꉞDF=1�i0.8�j��_�����ݒ�ł����A�����DF��������ƁA����U���̂悤�ɒ����ԐU���������悤�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
���̂悤�Ȍn���@�\�̂Ȃ�DC�A���v�ŋ쓮����ƁA�X�s�[�J�����d���A���v��������z�����鎞�Ԃ������������ƂɂȂ�AVanp�̓��̐ϕ��l��Vsp�̓��̐ϕ��l�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
��ǓI�ɍl����ƁA�X�s�[�J�ɃG�l���M�[��^����̂̓A���v�݂̂ŁA�X�s�[�J�̓A���v����^����ꂽ�G�l���M�[�ȏ�̂��͕̂��o�ł��Ȃ��̂ŁA�ǂ����Ɋ��Ⴂ������Ǝv���̂ł����A��������ɂȂ���w�E���������B
�����܂ł��A�ŏ��̂��ɑ���Ď���ł��B
�ߓn�����ɂ��ẮANFB���\�ɂ��Ƃ̂������ł����A����͂�����ƈႤ�Ǝv���܂��B
�A���v��DF�Ƃ����̂�NFB�R�~�Œ�`�E���肳���̂ŁA�����ŁANFB���\���X�Ɏ����o���Đ����Â���͖̂���������Ǝv���܂��B
�}��������R���ԈႦ�Ȃ�0.1���������Ƃ�����A�����ł̐��x�E����\�̌v���ł́A�������ƂقƂ�nj����������Ȃ��g�`�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����A����͐��|���_�ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA�Ď���͂������܂���B
�Ō�ɁA��R���ׂ̏ꍇ�ƃX�s�[�J���ׂ̏ꍇ�̓d�͋����ʂ̈Ⴂ�ɂ��Ăł����A�f�p�ȋ^��ɋ߂������̂ŁA�������Ȃ���Ό��\�ł��B
�X�s�[�J���ׂ̏ꍇ�͋t�N�d�͂��A���v���z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�C���[�W�I�ɂ͌��\������悤�ȋC������̂ł����A���̃I�[�_���S��������Ȃ��̂ŁA�������ł���Ǝv�����₵�܂����B
������̎���Ɏ��Ԃ������Ē��J�ɂ������������肪�Ƃ��������܂����B
�Ď���ɂ��܂��ẮA�����������Ⴂ���Ă���̂��Ǝv���܂����A�����Ȃ�������������̂ł���ΐ��肢���܂��B
��������l����A�����ʼn����ł��邩������܂��B
�����ԍ��F23019762
![]() 1�_
1�_
bebez����A�����́B
>DC���J�b�g�����I�[�f�B�I�A���v���ƃn�b�`���O�̈悪����I�ŁADC�A���v���Ƃ��ꂪ�����ƍL����Ƃ����̂͂ǂ�������������̂ł��傤���H
�C�ɂ��ׂ����ۂł͂Ȃ��ł��傤�B�c�b�A���v�Ƃc�b�J�b�g�A���v�Ƃ̊Ԃɖ{���I�Ⴂ������킯�ł͂Ȃ��A��҂̒����E��0Hz�ɋ߂Â��������Ԋ|���̈悪�L���邾���̂��Ƃł��B�Ƃ���ŖԂ����̈ʒu��������ƃA�o�E�g�ł����B�܂��������B
>���̂悤�Ȍn���@�\�̂Ȃ�DC�A���v�ŋ쓮����ƁA�X�s�[�J�����d���A���v��������z�����鎞�Ԃ������������ƂɂȂ�AVanp�̓��̐ϕ��l��Vsp�̓��̐ϕ��l�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
�u�@�\�v�̈Ӗ��Ƃ�����肽���Ӑ}�������ł��Ȃ��̂ł����A�p���X�I����̐U���̘b�ł���ˁH�p���X���I�����Ă���̂ł����� Vamp �̓[���Œ�ł��B���������āuVanp�̓��̐ϕ��l��Vsp�̓��̐ϕ��l�������v�܂����A����͉ߋ��ɃA���v���X�s�[�J�[�ɋ��������d�͂̈ꕔ���X�s�[�J�[�̐U���G�l���M�[�Ƃ��Ďc���Ă��������̂��ƂŁA�Ȃ��s�v�c�͂���܂���B
>�X�s�[�J���ׂ̏ꍇ�͋t�N�d�͂��A���v���z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�C���[�W�I�ɂ͌��\������悤�ȋC������̂ł����A���̃I�[�_���S��������Ȃ��̂ŁA
�����̐l��������Ă���Ǝv���̂ł����A�_���s���O�Ƃ����̂̓X�s�[�J�[�̃G�l���M�[���A���v���z�����錻�ۂł�����A�A���v�̏���d�͂͌���̂ł��B�����Ƃ������Ȃ̂̓E�[�t�@�[�̌ŗL�U���ŁA��ɏq�ׂ��悤�ɂ����ł̓C���s�[�_���X�����{�`10�{�ȏ�ɑ����A����ɔ���Ⴕ�ď���d�͂͌������܂��B
NFB�ɂ��Ă͂��������ʂ蕽�s���Ȃ̂ł���ŏI���ɂ��܂����ADF1000�̃A���v��0.1���������̂ƁA���XDF100�Őv���ꂽ�A���v�ƂŁA�u�ߓn�����́v��҂��D���̂����R���Ǝv���܂��i�A�L���̋��@��⑼�ЂƂ̑Ό������Ă݂����ł��j�B�Ȃ��A�}�̃e�N�ɂ��ẮA������ƍ��x�����i�����H�j�B
���ƁA�]�k�ł����A��ʂ̐l�́u�X�s�[�J�[�v�A�d�C�n�̐l�́u�X�s�[�J�v�A�@�B�n�̐l�͂���ɉ����āu�G�l���M�v�Ə����K��������悤�ȁB���Ă݂��bebez�����(��)�B
�����ԍ��F23020000
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�܂��܂��A��������肪�Ƃ��������܂��B
�Y�ꂳ��̉�����Q�l�ɁA�����Ȃ�ɗ�����[�߂����Ǝv���܂��B
����ʂ̐l�́u�X�s�[�J�[�v�A�d�C�n�̐l�́u�X�s�[�J�v�A�@�B�n�̐l�͂���ɉ����āu�G�l���M�v
�����Ȃ�ł����B��ʂ̐l�́E�E�͊m���ɂ����ł����A�d�C�n�A�@�B�n�Ȃ̂ł����B
���́A3�����ȏ�͊�{�[�͕t���Ȃ��Ƌ��炳��Ă����̂ł����A�G�l���M�[�����͈�ѐ��̖����ɂ��傢�ƈ����|����Ȃ���[�����Ă��܂��̂ł���ˁB
�G�k���łɒP�ʌn�ɂ��Ă������
���鎞�A��Ђ�SI�P�ʂɓ��ꂵ�܂��傤�Ƃ����������n�܂�A���Z�\�Ƃ������J�[�h���z��ꂽ�̂ł����A
���������ƂɁA���̃J�[�h�ɂ́@1Hz��1/sec�@�Ə�����Ă�����ł��ˁB
�����ŁA����͊Ԉ���Ƃ�Ǝ��͂ɒ��ӊ��N�������Ƃ���A��l�̎�҂��������Ƃ��Ď��ꂸ�A
1/sec��rad/sec������E�E�E�Ɖ~�ʂ̊G�܂ŕ`���Đ������Ă�����̂ł����A���Ǔk�J�ɏI���܂����B
���̓��A��k�D���̐�y�Ɂu���o�v�Ƃ�����������t�����Ă��܂����B
���炭���t�����������������肪�Ƃ��������܂����B
���\�A���ɂȂ����Ƃ������A�Ⴆ�Ă������������܂��B
����A�A�L������Ɏ������o�����̂ŁA�i�W������A�܂��A���܂��ˁB
���x�́A����Ȃ�̋�ʂ��Ă���̂ŁA�O��قǍ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A
����3�N�O�̎����Ȃ̂ŁA�蔲���łȂ��Ƃ��u���O���܂����v�Ƃ����̂͂��邩������܂���B
�����ԍ��F23020075
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ��܁A�����́B�c�_�����������̂ŁA�����ɑ���^�`���Ă܂Ƃ߂Ă����܂��B
�܂��A�X�g���[�g�ڑ��Ƃ����u�����P�v�ƁA0.1���}���Ƃ����u�����R�v�ɂ��āADF�̌��̒l�I�Ȃ��̂͂��ꂼ�� "1,000" "100" �Ɠǂ߂܂����Abebez����̖₢���킹����3m�̃P�[�u�����g�p����Ă����R�ł��i�����͕s���j�B���̒�R�ɂ���bebez����̉��v�Z "30m��" ��q����ƁA���ۂ� DF �͂��ꂼ��
DF1 = 8 / ( 0.01 + 0.03 ) = 200 �i���� 1,000�j
DF3 = 8 / ( 0.01 + 0.03 +0.1) = 57 �i���� 100�j
�ƂȂ�܂��i�Ȃ��Ȃ��j�B�d�C�������������Ƃ̂���l�͂킩��Ǝv���܂����A��10m���̊�R���t���Ȃ��悤�ɂ���ɂ��z�����K�v�ŁA�{�������ɑ@�ׂȎ����Ȃ̂ł����A�P�[�u���̑������s���ł͐^��DF���s���E�E�E�Ƃ������A�P�[�u����R����������Ă������_�ŃZ���X���^���܂��i�l�̊��z�ł��j�B
���ɁA�u�����R�v�̔g�`�̐U�����A�u�����P�v�Ɩ{�� 1% ���x���������Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA���ۂ͖� 4/3 (�� 1.3) �{�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����Ƃ���܂����B23016136 �ȂǂŐ��������悤�ɁA�A���v�̏o�͂��u�����P�v��4/3�{�ɂȂ��Ă��Ȃ��ƉȊw�I�Ȑ��������܂���B
�u���O�ɂ�10����}�������u�����Q�v�ɂ��āu�g�`�̍������Ⴂ�̂́A��R�ŐM���������������߁v�Ƃ���܂�����A0.1���Ƃ͂�����R��}�����ĐU����4/3�{�ɑ������炨���������Ƃɂ͓��R�C�Â��͂��ł��B�܂��A�u�����P�C�Q�v�̐ݒ�̂܂ܐU����4/3�{�ɂȂ�����I�V���̃����W���I�[�o�[���Ă��܂��܂�����A�Ή����K�v�ł��B
���ʂȂ�A���v�o�͂��m�F���đO�̎����̃��x���ɖ߂��ł��傤�B�Ƃ��낪�u�����R�v�ł̓I�V���̓d�������W�̂ق����ύX����Ă��܂��B���R�ɕς��킯������܂���A�Ӑ}�I�ȕύX�̂͂��ł��B
����łȂɂ��N�����Ă����̂��Ƃ����ƁA�܂��O���Ƃ�����u�����P�C�Q�v���s������A���C���Ƃ�����u�����R�v���s�����Ƃ���A�v�����悤�ȍ����o�Ȃ������̂ŁA�A���v�̃{�����[�����グ���A�ƍl����̂����R���Ǝv���܂��B���̉e�����ǂ̒��x���͂킩��܂��A���炵�Ă��̎����̐M�����ɂ͋^�����������܂���B
�܂��Abebez����̖₢���킹�ɑ��u����1�A�Q�A�R�ŃA���v�o�͓͂����v�Ƃ�����|�̉����������Ƃ��s���ł��B��q�̎���炵�āA�q�ϓI�����ƉȊw�I�ɖ������邱�Ƃ𗝉����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���邩��ł��B
�{���͂���ȂƂ���ŁB
�����ԍ��F23020472
![]() 1�_
1�_
�����������Ɩ{��ł��B
0.1���}���Ƃ����u�����R�v�ŃA���v�̏o�͐U���������Ă��邱�Ƃɋ^���̗]�n�͂���܂��A����ł��̃A���_�[�V���[�g���������邩�Ƃ����Ƌ^��ł��B���ۂ�0.1�����傫�������Ƃ���bebez����̂��ӌ��͂����Ƃ��ŁANFB�]�X�����͂邩�ɊW�R���������b�ł��B�����́A��R�A�P���~�X�A���̑��B
���̏ꍇ�̌���̏́A0.1����}���������肪�\�z�ȏ�ɐU���������Ă��܂��܂��B����ł͂Ȃɂ��Ɠs���������̂Ń{�����[�����グ���A�ł��傤���B���������Ɛl�ł���ΐU���������P�ƍ��킹��ł��傤�B��������������������܂��i�ȑ{���̏����j�B
�����������͈ȏ�ŏI���Ƃ��āA�u�����R�v�̃A���_�[�V���[�g���o���ɂǂ�ȉe����^����̂����l���܂��B
��Ƃ͂������m�ȃA���_�[�V���[�g�����������bebez�����h�����̂��킩��܂����A100Hz�̐�������5%(0.5dB)�����Ă��邾���A�̂悤�Ɍ����܂��B0.5dB�Ƃ����ƈ�ʂɂ̓u���C���h�ł͔��ʂ��������Ƃ����̈悾�Ǝv���܂��B�������A���l�̔g�`���A�����ČJ��Ԃ��ꂽ�ꍇ��0.5dB�Ƃ������Ƃł��B
���������g�p����Ă���g�`�́A�U���̉^�����ɋ}������������悤�A�������ɒ[�ɔ�Ώ́A�������s�\�_���܂ނ悤�Ȑl�H�I�Ȃ��̂ł��B���ۂ̉��y�M���ł���Ȃ��Ƃ͂܂��Ȃ��Ǝv���܂����A����100Hz�t�߂�f����0.5dB����オ�����Ƃ��Ă��A���������ł���Ƃ͎v���܂���B
�Ȃ����A����͑}����R����130m���i���邢�͂���ȏ�j�A���� DF60 ���x�̃P�[�X�ł��B�����̃I�[�f�B�I�t�@���̊��͋��炭��10m���A���̐�10m���̂܂��ŃP�[�u�����������ꍇ�ɂ��̍��������������邩�ƍl����A�����͖��炩���Ǝv���܂��B
�悤�₭�X���b�h�^�C�g���̘b�ɖ߂�܂����B�ЂƂ܂�����ŏI���ł��B
�����ԍ��F23021287
![]() 1�_
1�_
�Q�l�ɁA�X�s�[�J�̃E�[�n�[���|���|���@�����Ƃɂ��t�N�d�͂̉e���𑪒肵�Ă݂��B
https://www.youtube.com/watch?v=Xd-civfX6GU
0:00 �` 0:15�F�A���v���I�t�ɂ�����Ԃł̃X�s�[�J�^�[�~�i���ł̑���
0:16 �` 0:33�F�A���v���I���ɂ�����Ԃł̃X�s�[�J�^�[�~�i���ł̑���
0:34 �` 0:48�F�A���v���I���ɂ�����Ԃł̃X�s�[�J�^�[�~�i���ł̑���i���ԗ̈�̏c����10�{�Ɋg��j
���ԗ̈�Ō������A�A���v�ɂ��قڐ�������Ă���i���ԗ̈�̏c����10�{�Ɋg�債�Ă悤�₭�킩�郌�x���j�B���g���̈�Ō���Ǝ�U�������邱�Ƃ͂킩��B
�����ԍ��F23021395
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
����ɂ��́B
��������������������A���肪�Ƃ��������܂��B
�W�R���A����͖@���̐��E�ŗǂ��g����p��ł��ˁB
0.5dB�̉e���ɂ��Ă͑S�����ӂł��B
�X�s�[�J�H�����Ƃ��Ă����o����A���j�b�g�̉������x���̂���ɂ͌��\��J�������܂����B
���̌o�����i���j�ł́A���E����1.5dB����Ɩ��m�ɕ�����A1dB�͔����A0.5dB�͕�����Ȃ��Ƃ����������ł��B
����͊��x�̍�������̘b���ł����A����͂����ƒႢ���g���Ȃ̂ŁA���X0.5dB�̉e���͏������Ȃ�Ƃ����̂������܂��B
�l�ɂ���ẮA���̒��肪�o���Ƃ��������Ƃ����Ƃ��������j���A���X�̕ω��ɂ͂Ȃ邩������܂���B
���́A���̎����R�̃f�[�^���ǂ����邩�ł��B
�Y�ꂳ��́A�ŏ��̃s�[�N�i���j�ƃA���_�[�V���[�g�ʁi��̑Q�ߐ���艺�j���r����5%�Ɠǂ܂ꂽ�̂��Ǝv���܂����A
�����Ŕ�r���ׂ��͎����P�Ǝ����R�̃A���_�[�V���[�g�ʂ̕ω��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����P�̓A���_�[�V���[�g���[���Ȃ̂Ŕ䗦�ŋc�_����͓̂K�ł͂���܂���B
��������̓I�[�f�B�I�H�w�̗̈�ɂȂ�̂ŁA�����f��I�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��̂ł����A���炭�����ł̑�\�l��Q�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����R�̃f�[�^���炱��Q�l�i�܂��́A���̕ω��j����̓I�ɓǂނ��Ƃ͂ł��܂��A1%��2%�̕ω��ł͐��������Ȃ��Ƃ������Ƃ����͌����܂��B
Q�l���o��A�����Ɗe���g���ɂ����鉹�����x���̕ω������l�Ƃ��ďo�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����ƁA���h�Ƌ��܂������A���̕ω��]�X�ȑO�ɁA������0.1���ł��ꂾ���������A���v�Ȃǎg�������Ȃ��Ƃ������������ł��ˁB
���N�A�A�L�������DF=700���ւ�A���v���w�����܂����̂ŁA����ł͍���̂ł��I
�u���O�ł́A�����R�̉��̕ω��ɂ��Č���Ă��܂����A���ꂪ���X0.5dB�̍��������Ƃ���ƁA�������ꂽ���X�͂ƂĂ��D�ꂽ���������Ă�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
�܊p���߂Ă����������̂ɁA�܂������Ԃ��悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�[���ł��Ȃ����Ƃ͕����Ă����Ȃ��Ƃ����̂��Z�p���̐��ł��̂ŁA�������̂قǂ��B
�����ԍ��F23021433
![]() 1�_
1�_
��tohoho3����
����ɂ��́B
�f�[�^�̒��肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F23021448
![]() 1�_
1�_
http://www.taiyoinc.jp/products/cardas/speaker/crosslink_sp/index.html
���̃P�[�u���̑㗝�X�ɃV���b�v�o�R�Œ�R�l��₢���킹����A����J�Ƃ������Ԃ��Ă��܂����B
�C���_�N�^���X��L���p�V�^���X�͌��J���Ă���̂ɁA�̐S�̒�R�l����J���Ė��d�s�v�c�B
�����ԍ��F23021455
![]() 1�_
1�_
bebez����A�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
��ÂȂ��ӌ��͂܂��������S�Ȃ��Ƃł��B�P�[�u���X���ł͂Ȃ��Ȃ������Ȃ�Ȃ�Ȃ����̂ŁB�A���_�[�V���[�g�̉e����0.5dB�ƌ���̂́A�g�`���t�[���G�ϊ������炻���Ȃ邾�낤�Ƃ������Ƃł��B�����s�\�_�t�߂̋������Ⴄ�̂ō����g�����ɈႢ�͏o��ł��傤���A���Ȃ��Ƃ����ۂ̉��y�ł͖����ł���̂ł͂Ȃ����ƁB
�Ƃ���łp�l�̘b��n���ق���̂g�o�Ɍ��ɍs���܂������A������P�s�{����̈��p�Ƃ������Ƃō������킩��܂���ł����B�ł��A�Ȃ��o������Ȃ��Ǝv������A�́u�Y��_���s���O�t�@�N�^�[�v��҂ݏo���Ă������Ƃ��v���o���܂����B���Ԃ����Ƃł��傤�B
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15682249/#15719909
��������tohoho�����o�ꂵ�Ă��܂�(��)�B�p�l�̊��o�͗������Ă���̂ŁA0.1���ł��̃f�[�^�ɂ́A������a������̂ł��E�E�E�B
�����ԍ��F23021860
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�A�L���t�F�[�Y����ɂ́A�u���߂Ɍ��ς����Ă�Q�̕ω��͂Q�������Ȃ��̂ɁA�����R�̂悤�ɂȂ�̂͂��������Ȃ����H�v�@�ƃX�g���[�g�Ɏ��₵�܂����̂ŁA�^���Ɍ�������������A�[���ł������������̂Ǝv���܂��B
�Y�ꂳ��͂����ɂȂ�����������܂��A���̃X���̓r���ŃA�L���t�F�[�Y�̐_�Ή��ɂ��ď����Ă���܂��B
���̎��̎��̃X�^���X�i��Ɍ떂�����������Ȃ����ȓz�j���悭�������̕��������Ȃ̂ŁA�������������ȓ����͂��Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23021963
![]() 1�_
1�_
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15682249/#15719909
����2���ɂ͂̂�ۂ������ȁB�_���s���O�t�@�N�^���o�Ă���ƃX���������Ȃ�ȁi�j�B���ꂾ�����̊T�O�͕������Ƃ������Ƃ��B
�����ԍ��F23022045
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����́B
���͂��܂����o���Ă��Ȃ��ł����A������������Ă���������10�����ƒ����̂Ƃ��̏d�˂��O���t�̖Ԋ|�������i|Vamp| < |Vsp|�j�ɂ��܂��āA��������Ƙb���i��ł��܂�����������܂��i��
���������̋@��Ȃ̂ʼn����N�����Ă���̂��F��������Ă����狳���Ă��������B
�X�s�[�J�[���f���o���t�N�d�͂́A�����I�ɁA
V��vBl[V]�iv�F�{�C�X�R�C���̑��x�AB�F�������x�A���F�{�C�X�R�C���̐����j
�ł���ˁB
���̋t�N�d�͂́A�쓮�g�`�̎��ԑтɂ��A�������蓭���A�ނ��낖���傫�Ȏ��Ԃł́A��������̓d�͂�ԋp���Ă���͂��ł����A�����A���v����̓d�͂̎����H�ɕԋp���ǂ��t���Ȃ��Ƃ����C���[�W�������܂����i|Vamp| > |Vsp|�j�B
�Ԋ|�������̓{�C�X�R�C���̑��x���������A���̕��A�t�N�d�͂̑傫�����������͂��ł��B����ł����ΓI�ɃA���v�̓d�͋����ʂɏ��������ԑсi|Vamp| < |Vsp|�j�������Ƃ������Ƃŗǂ��ł��傤���B
��tohoho3����
�E�[�t�@�[�̋t�N�d�͂̃����N��A�q�����܂����B
�t�N�d�͂̉e���ɂ��ăA���v��OFF��ON�Ƃ̈Ⴂ�A���o�I�ɕ�����₷�������ł��B
�����ԍ��F23022175
![]() 1�_
1�_
�̂�ۂ�A�����́B
��̖Ԃ��������̍��G�b�W�������Y���Ă����̂ŁA�C���ł�Y�t���܂��B�̂�ۂ�̂悤�ɁA���������g�`�����Ċe�u�ԂɂȂɂ��N�����Ă���̂��ɋ^��Ɏ�����邩���́A�����ւ�Z���X���ǂ���A����ɂ��ꂪ���܂��Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B
|Vamp| < |Vsp| �݂����ȏ��������͒��ϐ���D�悵�����̂ŁA�̂�ۂ�����ł���A�X�s�[�J�[����������d�͂͑f����
Psp = Vsp (-I) = Vsp ( Vsp -Vamp ) / ( R+ + R- )
�Ə������ق����킩��₷���ł��傤�B�ŁA������Ƃ�₱�����ł����A������u�t�N�d�́v�͓d�͂ł͂Ȃ��d���Ȃ̂ŁA�{�C�X�R�C���������炪����ċt�d���������Ă��A�A���v���̓d����������A�d�͂Ƃ��Ă͎؋��ɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ƃ������Ƃ͂��̋t�̃p�^�[��������܂��B
������}���Ă����A�e�u�ԂɂȂɂ��N�����Ă���̂��A�̂�ۂ�Ȃ���Ȃ����������ł��傤�B
�����ԍ��F23022334
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
����ɂ��́B
�}���C�����ĉ�����A�܂������ƂĂ�������₷���������ĉ�����A���肪�Ƃ��������܂����B
�X�s�[�J�[�̓d�͂����邩�ɂ��āA������Vsp�iVsp -Vamp�j�̐�������m���ɔ��f�ł��āA��w������₷���ł��B
�EVsp�iVsp -Vamp�j�������X�s�[�J�[�̓d�͂�����
�EVsp�iVsp -Vamp�j�������A���v�̓d�͂�����
�i���ʁA�Ԋ|��������ŊO�̍��E�̗̈�ł͕��A�Ԋ|�����E���̓[���A�Ԋ|���̈�͐��B�j
�A���v�ƃX�s�[�J�[�Ƃł͑��݂ɓd�͂̉���������A�d�͂̎��x�i�����ł͂���܂��A�A�j�Ƃ��āA���ʂƂ��Ă��̂悤�ɂȂ����Ƒ����Ă��܂����A���ɃX�s�[�J�[�̓d�͂�����|�C���g�͋����������܂����B
�����ԍ��F23022964
![]() 1�_
1�_
���܂����������ĂȂ����ǁA�Y�ꎁ�̉摜�ɕt�������Ă݂��B
�摜�ɂ́A�uSP�̋t�N�d�͂�AMP�̓d�͂�����̈�v�Ə��������ǁA�������́A
�����g�̔��g���̈�ŊO�͂�^������i�A���v���d�͂�����������j�A���̔��g���̈�ȍ~�́A
�A���v�͓d�͂��������Ă��Ȃ��̂ŁA�X�s�[�J�̃R�[�����̌����U���ɂ��t�N�d�͂̕ω���
�\���Ă���̂ł́H
�����ԍ��F23023025
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��܁A����ɂ��́B
���̃u���O�͍폜���ꂽ�悤�ł��ˁB
�M���̃A�L���t�F�[�Y�u�����h�̂��߂ɂ͎~�ނȂ��A�Ƃ�����蓖�R�ł��傤���B
�����ԍ��F23032170
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���݂Ȃ���
�����́B
�z���g�ł��ˁA�A�u���O�̋L���̍폜�͏����т�����ł��B
�폜���������⑫�����Ȃǂŕ���Ă��ǂ������̂��ȁ[�Ƃ��v���܂������A�A�L���t�F�[�Y�Ƃ̊W�ɂ��z���i�u�x�H�j�����̂ł��傤����^^;
�����ԍ��F23033605
![]() 1�_
1�_
�̂�ۂ�
���������B�u���O�̎����� 23020472 23021287 �ł܂Ƃ߂��悤�ɁA���Ȃ肨�e���ł��BDF800�̎���������Ă���̂ɒ���3m���̃P�[�u���̒�R����������u�����͎��O�v�̗R�B�܂��A���v�̏o�͓d����I�V���̓d�������W�ύX�͈Ӑ}�I�Ȃ��̂Ɖ�������܂���B�ƂĂ��⑫�����őΉ��ł��郌�x���ł͂���܂���B
���������̎������哱�����͔̂̔��X�ł͂Ȃ��A�A�L���t�F�[�Y�̎Ј��ł������͗l�ł��B�ƂȂ�Δ̔��X�̜u�x�ł͂Ȃ��A�A�L���t�F�[�Y���A��@�Ǘ���L���̍폜���w�������ƌ��ĊԈႢ�Ȃ��ł��傤�B���}�ȉ�Ђł���A�L�����ɊW�������Ƃ���Ŗ������ƂȂ肻���ȂƂ���ł����B
�����ԍ��F23034276
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�ȉ���DF�����Ɋւ���A�L���t�F�[�Y�̉̊T�v�������܂��B
�P�D���͔g�`�ɂ���
�e�X�g�pCD�̃��C�Y�h�E�R�T�C���M�����g�����Ƃ̂��ƁB�i�Y�t�j
�]���āA�p���X����50ms�ł�80ms�ł��Ȃ�100ms�������B
�Y�t�����́u���U���v�͐������́u�U���v���Ǝv�����}�t���߂Ȃ̂ŁA����͂ǂ��ł��������ƁB
�Q�D���͐M����~��A�v���f�[�^���A���_�[�V���[�g���Ă���悤�Ɍ����錏
�I�X���X�R�[�v��AC�����œ��͂��Ă��邽�߂Ƃ̂��ƁB
�A���v��DC�J�b�g�̎��萔�́A�I�V����AC�����̎��萔��10�{�قǑ傫�����߁A��v���ł͂Ȃ��B
�i�ŏ��̉ŁA�X�s�[�J��LC�̉e�����ȂNjY�����������̂ōĎ��₵�܂����j
�R�D0.1���̃f�[�^�������ɑ��Q�C��1.3�{�ŐU���I�ɂȂ��Ă��錏�i���ꂪ�j�S�j
�Q�C���ɂ��āF
�{�����[���������Ȃ��玎���������߂Ƃ̂��ƁB
�܂�A�Q�C���ɂ��ẮA�c�_���鉿�l�͑S���Ȃ��B
�ߓn�����ɂ��āF
�O�X���ɃA�L���t�F�[�Y�Г��Ŏ��{�����\�������̌��ʂ��J�����Ă���܂����B
�f�[�^��4�ŁA�����A0.1���A1���A10���B
������0.1���͔��ɋ߂��g�`�ł���A�����������0.1���ł͂قƂ�Ǖω����Ȃ��ƌ��_�t���Ă��܂��B�i����̓��[�Y�i�u���Ȍ����A��`������Ƌ͂��ȈႢ�͊m�F�ł���j
�u���O�f�[�^�́A0.1���̃f�[�^�������ŁA�����̃f�[�^�͖�����Ԃ�CDP�̏o�͔g�`���ԈႦ�Čf�ڂ����Ƃ̌����B
�ȏオ�̊T�v�ł����A�����̃f�[�^���ԈႦ���Ƃ���A�L���t�F�[�Y�̍l�@�́A���肩���E������̐��{���ق��v���N����������̂ł����B
�\�������̃f�[�^������ƁA���U���g���̓u���O������1/2�ȉ��A�����͂��Ȃ舫���Ȃ��Ă��܂��B
���ꂪ802�i20cm×2�j�ŁA�u���O�����Ŏg�����X�s�[�J�͖Y�ꂳ��̍l�@�ʂ蕉�ׂƂ��Ă͗y���Ɍy�����̂������悤�ɂ��v���܂��B
�V���ɊJ������������4�̗\�������̃f�[�^�ƁA������Ă��܂����u���O��3�̃f�[�^������ׁA�����āA������1���̎��������\�肾�������Ƃ��l������A0.1���̂���f�ڂ����f�[�^��1���̃f�[�^�������Ƃ����^���͍��܂�܂��B
���̂悤�ɉ�����u���ƁA���ׂẴf�[�^����������Ȃ������ł���̂ŁA������t�B�[�h�o�b�N���܂������A����ɑ��Ă͉��̃��X�|���X������܂���ł����B
�����A���̃��X�|���X���Ȃ������Ƃ����̂͊ԈႦ�ŁA�u����l�@���܂������Ɋւ��܂��āA���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B����\���グ�܂��B�v�Ƃ̃��[�������������܂����B
�����ԍ��F23230538
![]() 2�_
2�_
�_�u���Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F23230557
![]() 1�_
1�_
bebez����A��肪�Ƃ��������܂��B
bebez����͎Ⴂ����Ɏ茵��������قǂقǂɁA�ƌ��������Ǝv���Ă��܂������A���̓��ق����Ă��܂��Ɗm���ɏ����������������Ȃ�܂��ˁB�_�Ή��ŗL���ȉ�Ђɂ��Ă͂Ȃ�Ƃ��s�v�c�ł��B
�ɂ��Ă��A�����V���b�g�p���X���`�b�J�b�v�����O�ő���܂����ˁE�E�E�i���������C�ɂ��Ă��Ȃ������������ł��ˁj�B���������ĐV���������ł����l�̃A���_�[�V���[�g������܂����H�����Ă���Ίw�K���ʂ����������ƂɂȂ�܂����B
����ƃA�L���t�F�[�Y�́u0.1���̃f�[�^�������v�Ƃ����������������Ƃ���ƁA�V���������ł�0.1���̌��ʂƋ߂����͂��ł���ˁB�ł����������
>0.1���̂���f�ڂ����f�[�^��1���̃f�[�^�������Ƃ����^���͍��܂�܂��B
�Ƃ���bebez����̐���ƍ���Ȃ��̂ŁA���̕ӂ��悭�킩��܂���ł����B
�����ԍ��F23233133
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�������������悤�Ȃ̂ŁB
�V���ɒ���������4�̃f�[�^�́u�V���������v�̃f�[�^�ł͂Ȃ��A�u���O�����̑O�X���ɃA�L���t�F�[�Y�Г��Ŏ��{�����\�������̃f�[�^�ł��B
�]���āA�v���̓u���O�����Ɠ���AC�J�b�v�����O�ł��B
3�N�O�̎����f�[�^�������ƊǗ�����c���Ă����͕̂]���ɒl����Ǝv���܂��B
�u���O�����ɔ�ח\�������̕������ׂ͂��Ȃ�d�������悤�ŁA�i�d���F���a��Am0��j
����10���}���̃f�[�^���ׂ�ƁA���U���g���̓u���O90Hz�ɑ��\��40Hz�ŁA�������\�������̕������Ȃ舫���Ȃ��Ă��܂��B
����ɑ��āA��������0.1���̃f�[�^������ׂ�ƁA�����U���̗l�q�i�s�[�N�l����юR�J�̐��j���t�]���Ă�����낪�����܂���B
���ׂ̓����Ⴂ�����āA�u���O������0.1���̌����̗l�q���\��������0.1����1���̂ǂ���ɋ߂����Ƃ����A�p�b�g���ɂ�0.1���̕����߂������邩������܂���B
�������A����͍H�w�I�m����Z���X�������l�̌����ł����āA���ɂ�1���̃f�[�^�ɂ��������Ȃ��̂ł����A�ؖ����邽�߂ɂ̓u���O�����̃Z�b�e�B���O�ōĎ�������邵���Ȃ��̂ŁA�㖡�͂悭����܂��A�����܂łƂ��܂����B
���A�V����������ǂ��ł������f�[�^�Ƃ����̂́ACDP�̏o�͔g�`�A�܂�A���C�Y�h�E�R�T�C���M���ł��B
���Ԏ���ς���2�ʂ�A�e�Ŏ���Ă����������̂ł��傤���A�قǂ�ƈӖ��̂Ȃ��f�[�^�ł����B
�����ԍ��F23233278
![]() 1�_
1�_
bebez����A������肪�Ƃ��������܂��B�����������Ƃł������B
����3�N�O�̎����f�[�^�Ȃ�c���Ă��Ă������ʂ��Ǝv���܂�������͂Ƃ������A�\�������̌��ʂ�m���Ă��Č��̃u���O����u���Ă������Ƃ������ł��B�Ȃ��Ȃ�A���I�̉��������m����̂悤�Ȃ�����
>���n�̎����x�̒m���ł́A�A�L���̐l�Ԃ��ւ���Ă��錟�ɓ��ɃI�J�V�C�������o���܂���B
>���R�A���̌��ʂ��u���O�ɍڂ��鋖���A�L���������Ă��邾�낤���A
>���e�ƌ��ʂ�c�����Ă���Ȃ�ԈႢ������Ύw�E����Ă���A�Ɨސ������߂��܂����B
�ƌ�����邾�낤���Ƃ�e�Ղɗ\���ł��邩��ł��B
>�������A����͍H�w�I�m����Z���X�������l�̌����ł����āA
�Ȃ�قǁB��������肽�����Ƃ��`����Ă��܂��E�E�E
�����ԍ��F23233434
![]() 0�_
0�_
bebez����A����ɂ��́B
�V�~�����[�V�������Ă݂܂����B
�P�D��{�I�ɐU���̐U�������k�b�ő�ցB
�Q�D������R�W���B
�R�D�U���̎��g��(90Hz)�ƌ����̎��萔���A10���̑���ƍ����悤�ɓK�X�����B
�ȏ�̐ݒ�ő}����R�P���̏ꍇ���V�~�����[�g���Ă݂�ƁA�A�L���t�F�[�Y�� "0.1��" �Ǝ咣���Ă���������ʂƂقڃh���s�V���ň�v���܂��Bbebez���ȑO����咣����Ă����ʂ�ł��B
�����ԍ��F23237252
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
�����́B
�V�~�����[�V�����܂ł��Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B
LCR�Ń��f�����ł���̂ł��ˁB���ɂȂ�܂����B
��H�n�{�o�l�}�X�ŋߎ�������̂Ǝv���Ă��܂����B
�M�ߐ��̂���f�[�^�i10���j�Ń��f�����O���āA�V�~�����[�V�����Ō�����Ƃ����̂́A�܂��Ƀg���u���V���[�e�B���O�̂���{�ł��ˁB
�f���ɁA���S���Ă��܂��B
�A�L���t�F�[�Y�����̔����ł������Ɍ������Ă����ƁA���i�H�j�A�L���M��҂Ƃ��Ă͎��Ɏc�O�ł����A�p���Ƃ������͎�ɔ\�̖͂�肾�Ǝv���̂ŁA�v��������܂���B
�����ԍ��F23237347
![]() 1�_
1�_
�W�O�̏������݂Ɍ�肪�������̂ŁA�ꉞ�A�������Ă����܂��B
��F�@�]���āA�p���X����50ms�ł�80ms�ł��Ȃ�100ms�������B
���F�@�]���āA�p���X����5ms�ł�8ms�ł��Ȃ�10ms�������B
�����ԍ��F23237396
![]() 1�_
1�_
bebez����
�o�l�n�́u�ʒu�G�l���M�[ �� �^���G�l���M�[�v�̌������u�d��(C)�̃G�l���M�[ �� ����(L)�̃G�l���M�[�v�̌����Ƃ��܂��Ή����܂���ˁB������R�i0.5��)��L�ƃV���[�Y�ɓ���܂������A���ׂĂ݂�ƁA�p���œ����ق������ʂ����m��܂���i�p�����[�^������Ό��ʂɈႢ�͂Ȃ������ł����j�B
>�p���Ƃ������͎��
�����V���b�g�p���X���`�b�J�b�v�����O�ő����Ă����̂͏Ռ��ł������A�u�V������������C�Y�h�E�R�T�C���M���v���A���������āH
�����ԍ��F23237797
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���͂悤�������܂��B
�������ɁA���͐M����DC�Ŏ���Ă��܂������A�{���̃A�L���͂��e���Ƃ��������悤������܂���B
�\�������̋��U���g����40Hz�Ȃ̂ŁA�ŏ��̉�802D�Ƃ����̂͋��炭�\�������Ɏg�������ׂł���A�u���O�����͂����ƌy�����ׁi16cm�u�b�N�V�F���t���炢�j���g���Ď��{�������̂Ɛ����ł��܂��B
���ɂ������Ƃ���ƁA�ŏ��̎���10��̓��A�������́A�v�����ʂ݂̂ŁA�����������̂��P�[�u���Ɋւ��ĉi����3m�A�������O�j�ŁA���̑�8��ɑ��Ă͊ԈႦ�܂��͓����ɂȂ��ĂȂ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�B��̐����Ǝv��ꂽ�v�����ʂɂ��Ă��A�����̃f�[�^�͈Ⴄ���ʂ��v�������̂��Ǝ咣���Ă���̂ŁA�S�łƂ����Ă������ł��B
�Y�ꂳ��͎��̕��͂ł̐����݂̂Ō����Ƃ���Ƃ���𗝉����Ă��������܂������A�A�L���ɂ͐}���g���ăA���_�\�V���[�g�ʂ�R�J�̐��ȂǏڂ����������č����グ���̂ɁA�����������ꂽ�`�ł��B
�܂��A1���̃f�[�^��0.1���̃f�[�^���Ǝ咣���A������0.1���Ƒ����ƌ����Ă���̂ŁA���̃A���_�[�V���[�g����ѐU������������1���̏�Ԃ����Ђ̃A���v�̑f�̐��\�ƌ����Ă���킯�ŁA������Ď��Ђ̐��i���Ȃ߂Ă�����Ă��ƂɋC�t���Ȃ����̂ł����ˁH
DF��ɂ��āA�����PR����ړI�Ŏ������s���Ă����Ȃ���A���ʓI�ɂ͕��Ђ̃A���v�͕��וϓ��Ɏア�ł����Č����Ă���悤�Ȃ��̂ł��������鑼����܂���B
���́u��Ђ̃A���v�̐��\�͂����Ɨǂ��ł���v���ċ����č����グ�Ă���킯�ł����āA����ɑĂ��̜��疳��ȑԓx�ł�����A�A�L���̍D���x�����Ȃ艺����܂����ˁB
�����ԍ��F23238277
![]() 1�_
1�_
bebez����A�����́B
�V�~�����[�V�����܂ŌJ��o���Ęb���}�j�A�b�N�ɂȂ��Ă��܂��܂������A���_�ɖ߂�A
�u�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X���W���̂Ƃ��ɁA�������[�v���ɓ���A���v�̃C���s�[�_���X��0.1��(DF=80)�ł���̂�0.01��(DF=800)�ł���̂ƂňႤ��ł����H�v
�Ƃ������Ƃł��B��R�����āA�A�L���t�F�[�Y���g��B&W802�Ƃ����啨���g�����\�������Łu0.1���ł͂قƂ�Ǖω����Ȃ��v�ƌ����Ă���킯�ł�����A���_�͖��炩�ł��傤�B
�����炭���l�͂܂��߂ɂ��̊��������̂��Ǝv���܂��i��Ђ̗���I�ɂ͂���Ă͂����Ȃ������Ƃ͒m�炸�Ɂj�B�ŁA���肩�������瓚�قɂȂ炴��Ȃ������A�Ƒz�����܂��B�������A�u0.1����}�������v�ƃu���O�ɏ����Ă���A�ǂނق��͋^���܂����ˁE�E�E�B
�����ԍ��F23239465
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
���肩���E��������A�L������������闧��̕s�����͓���̂��̂ł����A���肩���E������͊m�M�ƁA�A�L���͔\�͕s���Ƃ����Ⴂ�͂���̂ŁA�������ɂ͂��Ȃ�̈Ⴂ�͂���܂��B
���āA802D3��F����705S2�̃C���s�[�_���X�̃f�[�^������܂����̂œY�t���܂����B
802D3��40Hz�ɃC���s�[�_���X�̃s�[�N������A705S2��90Hz�ɂ���܂��B
�p���X�����̋��U���g�����C���s�[�_���X�̃s�[�N���g���ߖT�ɂȂ�Ƃ���ƁA�\�������̕��ׂ�802D3�N���X�A�u���O������705S2�N���X�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�ŏ��Ƀu���O�����̕��ׂ�₢���킹�����̉��ɂ́A�u���a�F20cm�A�i�菑���Łj802D�v�ƋL�ڂ���Ă��܂�����A�r�߂�ꂽ���̂ł��B
�ł����A�u���O���k���ȃf�[�^�Ɛ������l�@�ō\������Ă����Ƃ�����A���̂܂܃X���[����Ƃ���ł������A�s�v�c�ȓ_�����X�������̂Ő[�@�肷�邱�ƂɂȂ������߁A���ʓI��DF�Ɋւ��闝�������Ȃ�[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B
�Ȃ̂ŁA����͂���ŗǂ������ƑO�����ɑ����邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B
�A�L���̓��ӂ͓����܂���ł������A�A�L�������2�x�ڂ̉���������i�K�ŁA���̃f�[�^�͒�R�l�Ⴂ�ł��邱�Ƃ͂قڊԈႦ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A�Y�ꂳ��̃V�~�����[�V�����Łu�قځv�����X�b�L�����܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F23239946
![]() 1�_
1�_
bebez����A�f�[�^���肪�Ƃ��������܂��B
705S2�͌v�����悤��90Hz�ł��ˁBbebez����A����ǂ����ł��B����ƁA���ǂ��͒�i�C���s�[�_���X��������R�Ƃ����펯���ʗp���Ȃ��̂ł����B�Ƃ������ƂŁA�C���s�[�_���X�̋ɏ��l����R�Ƃ��ăV�~�����[�V�����������܂����i���ʂ͑卷����܂��j�B
����ƁA"10��"�̃f�[�^����`�b�J�b�v�����O�̎��萔���킩��̂ŁA���̏ꍇ�̃V�~�����[�V���������Ă݂܂����B�Ƃ�������������f�[�^���`�b�J�b�v�����O�Ȃ̂ŁA���̏�Ԃō��킹���݂����܂����B�`�b�J�b�v�����O�͂b�q�̃n�C�p�X�t�B���^�[�ł����}�����܂���B
802D3�𐄑������V�~�����[�V���������Ă݂܂������Af0=40Hz�Ƃ�������ł͂k�b�̐ς����킩��Ȃ��̂ŁA�k�b��90/40�{�ɂ��܂����B�{���́A�������d���Ȃ����ꍇ�͂k�A�_���s���O�������Ȃ����ꍇ�͂b�ɉe������͂��ł����ˁB�������b���琄������ɁA�\�������̌��ʂƂ͂��܂��������Ă��Ȃ������ł��ˁB
�����ԍ��F23240326
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
����ɂ��́B
�A�L���t�F�[�Y�̗\���������ʂ͋��U���g����40Hz �ɉ������������ł͂Ȃ��A���������Ȃ舫���Ȃ��Ă��܂��B
�����ł����������U���������܂��B
�A���v�̃C���s�[�_���X0.01�������ł͍l�����Ȃ��̂ŁA���炭�P�[�u���̃C���s�[�_���X�̉e�����o�Ă���Ǝv���܂��B
�\�������̃f�[�^���f�ڂł���̂���ԗǂ��̂ł����A�������Ɏ��̈ꑶ�ł͂ł��Ȃ��̂ŁA�A�L���t�F�[�Y�Ɍf�ڂ̉ۂ�₢���킹�Ă݂悤���Ǝv���܂��B
���邢�́A�ʂł���A�Y�ꂳ��ɒ��ډ��𑗂邱�Ƃ͖��Ȃ��Ǝv���܂����A�������@���������Ă��������B
���A�A�L���t�F�[�Y�ɖ₢���킹��ۂɁA�u���O�����̕��ׂ�705S2�Ɖ��u�������ꍇ�̃V�~�����[�V�������ʂ𑗂��Ă���낵���ł��傤���H�i�ԓ���낵���I�j
�A�L���Ƃ̖{���ł̂����͂�������̂ň�U�ł���܂������A��R����ԈႦ�𗠕t����V�~�����[�V�������ʂ��������������̂ŁA������킵�Ă݂悤���Ƃ����C�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F23240432
![]() 1�_
1�_
bebez����A�����́B
802D3�̃V�~�����[�V�����Ń����M���O�̑傫���߂��邱�Ƃ͉\�ł����A���Ȃ̂�
>�����ł����������U���������܂��B
>�u���O������0.1���̌����̗l�q���\��������0.1����1���̂ǂ���ɋ߂����Ƃ����A�p�b�g���ɂ�0.1���̕����߂������邩������܂���B
�Ƃ����_�ł��B���܂̃V�~�����[�V�����ł͒����ł͓��R�����M���O�͏o�܂��A�P�[�u���̒�R�ɂ��Ă��A�펯�I�ɂ͂���������10�����ł���ˁB0.1���}���łقƂ�Ǎ����Ȃ��킯�ł����琔10�������������Ƃ���ŕς��͂���܂���B
�u���O��"0.1��"�͎��͂P���ł��邱�Ƃ��m���Ȃ̂ŁA���ꂪ�\��������0.1���Ɓu�p�b�g���߂��v�ƂȂ�ƁA�V�~�����[�V�����ŗ\�������̌��ʂ��Č����邱�Ƃ͕s�\�ł��B�܂�A���v����1���߂��̒�R������K�v������̂ł��B�ł��A���ꂾ�ƃA���v�̂c�e���W�ɂȂ��Ă��܂��܂���ˁB�Ȃ̂ŁA�����\�������̃f�[�^�����Ă��^��͎c���Ă��܂��킯�ł��B
�ł͂Ȃɂ��N�����Ă���̂��E�E�E�͐������邵������܂��A�Ⴆ��802D3�̂悤�ȑ啨�ł͂Ȃ�炩�̔���`�Ȍ��ۂ��N�����Ă��Ă��܂̃V�~�����[�V�����ł͎�ɕ����Ȃ��̂����m��܂���B
���A�\�������́u�����v�͎��͂̓E�\�ł���A�ƍl����̂��V���v���ł��B�u�u���O��"0.1��"�͎����ł���v�Ƃ�������Ɛ��������邽�߂����m��܂���B��������������Ƃ��������ʂ�u���Ђ̃A���v�͕��וϓ��Ɏア�ł��v�ƂȂ��Ă��܂��܂��B��̃E�\����蔲�����Ƃ���Ƃ������Ȃ��ƂɂȂ�̂́A�܂��Ɂu���肩��������v�ł��B
�Ȃ������f�ڂ����V�~�����[�V�������ʂ��H�́A���łɌ��J�������̂ł������������m�I���Y�ł�����܂���̂ŁA���������悤�Ȃ����p�͂����R�ɂǂ����B����ɖ{�X�����o���Ă���̂��ǂ����m��܂��A�ꉞ�o���Ă��Ȃ��̂Łu�^���v���悢�ł��傤���B
200���X���߂Â��Ă��܂����B����������ƘA���p�ɉ�������邩���m��܂���B���A���܂ŁB
�����ԍ��F23240826
![]() 0�_
0�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�v�X�ɃA�L���t�F�[�Y�����Y�܂��Ă����܂����ˁB
���̃V�~�����[�V�������f���Œ����ł͐U���͔������Ȃ��͕̂�����܂��B
�����A�P�[�u�������������0.05����0.1�����炢�Ȃ�LC�̋��U����������A�����̐U���͏o��悤�ɂ��v���܂��B
������0.1���̃f�[�^���߂��̂ŁA�G�C���Ő�������A���̒����F�P�[�u�����X��0.1���A����0.1���F���̒����v���X0.1����R��0.2�����ĂƂ�����Ȃ����ƁB
�A�L���t�F�[�Y�̋�����ꎟ��A�\�������̃f�[�^���A�b�v���܂��B
�r�r�b�ă_�����Č����ė��邩������܂��ǁB
����ł́A�A�L���̉҂��Ƃ������ƂŁB
�����ԍ��F23240883
![]() 1�_
1�_
���Y��悤�ɂ��������Ȃ�����
����ɂ��́B
�{���A�A�L���t�F�[�Y�������܂����B
��R�l�Ⴂ��F�߂�Ǝ�����e�ł����A�ȉ��ɁA�̕������̂��̂�Y�t���܂��B
�y�A�L���t�F�[�Y�̉z
���߂āA�u���O���́u100Hz�p���X�M��0.1����R�}���v�̎ʐ^���A�u100Hz�p���X�M���v�̎ʐ^�ƐU�������킹�Ĕg�`��r���s���܂����B
�����̗\�������̔g�`�Ɣ�r����ƁA�����l�̌����Ă���1���̒�R��}�������Ƃ��̔g�`�̕����߂��Ɣ��f�ł��܂����B
���A��R����ԈႦ���m�M�ł��闠�t���ƂȂ����\�������̃f�[�^�Ɋւ��ẮA�u���ڑ��邱�Ƃ͖��Ȃ����A�C���^�[�l�b�g�f���ւ̌f�ڂ͎~�߂ė~�����v�Ƃ̂��Ƃł����B
��������������A�ꎞ�I�ȃt���[���[���A�h���X��ݒ肵���m�点��������A���点�Ă��������܂��B
�����ԍ��F23274849
![]() 1�_
1�_
bebez����A���A�����肪�Ƃ��������܂����B�������Ă��Ēx���Ȃ�܂����B
�����A�A�L���t�F�[�Y�̉����m�ɗ����ł��܂���ł����B�ɂ́u�g�`�v���S�o�ꂵ�܂��ˁF
�P�D�u���O���́u100Hz�p���X�M��0.1����R�}���v�̎ʐ^
�Q�D�u100Hz�p���X�M���v�̎ʐ^
�R�D�����̗\�������̔g�`
�S�D�����l�̌����Ă���1���̒�R��}�������Ƃ��̔g�`
�����łS�D�̋�̓I�Ӗ����킩��Ȃ��̂ł����A
�T�D�\��������1���̒�R��}�������Ƃ��̔g�`
�Ő������ł��傤���H�i���̃V�~�����[�V�����͊W�Ȃ��ł���ˁH�j�@���̑O��ʼn��߂���ƁA�A�L���t�F�[�Y�̉�
�U�D�\��������0.1���̒�R��}�������Ƃ��̔g�`
�����A��L�T�D�̂ق����A��L�P�D�ɋ߂��A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂������A����ł悢�ł��傤���H
�����Ƃ��\�������ƃu���O�Ƃŕ��ׂ̏d�����܂�ňႤ�̂ŁA�����ڂǂ����̔g�`���߂��������̂��ǂ����Ǝv���܂����E�E�E
�u���O�̂ق������^�r�o�Ǝv����̂ŁA�u���O��"0.1��"�́u���ۂ͏��Ȃ��Ƃ�1���v�Ƃ͌��������ł��ˁB
��낵����A�����͉����ł��肢���܂��B�i���e�ҏ��F���ł��B��قǍ��������ŁA������g���邩�킩��܂���B�j
���āA�b�����ݓ����ė����ł���ǎ҂͂��Ȃ��Ǝv���܂����A�Ō�̃��X�Ƃ������Ƃŏ���Ȃ��猋�_���܂Ƃ߂܂��B�A�L���t�F�[�Y���g�̕Ƃ��āAB&W802�Ƃ����啨���g����������
>������0.1���͔��ɋ߂��g�`�ł���A�����������0.1���ł͂قƂ�Ǖω����Ȃ��ƌ��_�t���Ă��܂��B
�Ƃ̂��Ƃł����i23230538�j�B��ʓI�Ȋ��ł̓X�s�[�J�[�P�[�u���̉�����R�͂���������10�����x�ł�����A�i�ڐG��R���P�A�������j�X�s�[�J�[�P�[�u���Ńq�g��������������o���̍��͔������Ȃ��ƍl���Ă悢�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F23281041
![]() 1�_
1�_
�Ⴆ�u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[�ƃf�X�N�g�b�vPC�ƒ��ڐڑ�����ꍇ�ɁAUSB DAC�o�R����[�q�A�w�b�h�z���[�q��������܂����A�w�b�h�z���[�q�͏����ʂł����Ă������͂��Ȃ舫���Ȃ�̂ł��傤���H
�܂�������USB DAC�o�R����[�q�ɂ����ɗႦ�ΐ����~�N���X��PC�p�X�s�[�J�[�ł��f�X�N�g�b�v�p�r�Ȃ�\���ł��傤���H
�S�����m�Ȃ��̂Ō�w��̂قǂ�낵�����肢���܂��B
![]() 2�_
2�_
��JABOON����
�������Ă��钆�ň�Ԉ����ł��B
pc�p�X�s�[�J�[�ŏ\�����H���B���Ȏ�ςŌ��߂���̂ł�����Ȃ�Ƃ������܂���B
�����ō��������߂�ׂ̋��z�͕����Ȃ肠��܂���B
�܂��A2. 3���̂��̂Ŗ����o���邩�����܂��H
�����ԍ��F22959690�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��JABOON����
�܂����炵�܂��B�܂���{�I�Ȃ��Ƃ𗝉����ĉ������B
DAC���f�W�^�����A�i���O�����M���ɕϊ����镔�i�E�@��ł�
PC�̃w�b�h�t�H���[�q����A�i���O�����ŏo�͂��遁PC����DAC���g�p����Ƃ������Ƃł�
USB�A���A�����A�u���[�g�D�[�X�@�\�Ȃǂ́APC����f�W�^���M�����o�͂��遁�O����DAC���g�p����K�v������Ƃ������Ƃł�
��ʓI��PC�͉����ړI�łȂ��̂ŁA�O����DAC���g�p�̕����������ǂ��Ȃ�Ƃ������ƂŊO�t��DAC���g�p�����ł���
�f�W�^���M����DAC���A�i���O�M�����i�A���v�j���X�s�[�J�[
�Ƃ�������ɂȂ�܂��B
�@��̑I��́A�\�Z�Ƃ����p�X�y�[�X�A�f�U�C���Ȃǂ����Ă��āA�I��ŗǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22959703
![]() 4�_
4�_
��JABOON����
���́A
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000954783/#22942008
�Ƃ����A���v�ƃX�s�[�J�[�ŁAPC���̕��ʂ�DAC����1.5m�̃A�i���O�P�[�u���Ńf�W�^���A���v�ɂȂ��ł��܂����A���������������A�S�R�������Ă��܂��B
�����Ƃ������ł����A1m���x�̃A�i���O�P�[�u���̐M�����m���ɕ�����������l�͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
AP20d���̗p�����̂́A���i�ƐM�����𗼗����鎖���l�����̂ƁA�T�u�E�[�n�[���g�p����ׂɂ́A�v���A�E�g���������ق����ǂ���������ł��B
�����ԍ��F22959757
![]() 4�_
4�_
��JABOON���� ����ɂ���
PC�̃C�A�z���W���b�N����A���v�t���X�s�[�J�[��炷�ꍇ�́APC����DAC���g�����ƂɂȂ�܂����APC����DAC�̓R�X�g�D���
�̗p����Ă�ƍl�����A�u�����v�ɂ͍l������ĂȂ������̂���ʓI�Ȍ����ł��B
������PC���̓f�W�^���M���ŏ�������Ă邱�Ƃ���A�A�i���O�M���ł��鉹�y�Ƃ͑������܂��B
�����ŁA���y�M�����f�W�^���̂܂�USB����Ŏ��o���A�O�t���̉����I�ɍl�����ꂽDAC���g���ăA�i���O�M���ɒ������Ƃ�
��������ł����n�C���]�Đ����\�ƂȂ�̂ł��B�`���̎��ɃA���v�����̃X�s�[�J�[���Ȃ����A�v�����C���i���邢�̓R���|�j�o�R�ŃX�s�[�J�[��炷���Ƃō������Đ����o���܂��A�l�b�g�����ɂ����܂����A����CD�v�����[��CD���Đ������荂�����ł̍Đ����o���܂��B
�ł�����A�u������PC���ŃA�i���O�ɂ�����A�O�t��DAC���ȒP�ō������v�ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F22959800
![]() 1�_
1�_
�Ӗ����킩��܂���A�A�A
PC�����ƃf�W�^���M���ŏ������ꂽ��A�i���O�M���ł��鉹�y�Ƒ�������H
�������A�ƁA�����ŁA�A���C�}�C�`�q����Ȃ��ł��ˁBPC���̓f�W�^����������Ă��邩��ǂ��̂ł���B
�w�b�h�z���[�q�͈�U�{�����[����H�ʂ��āA����ɊO���̃{�����[����H�ʂ��Ă��܂��ׁA���̘c�݂��ǂ����Ă��o�܂��B
�Ȍ��ɂ����ƃA�i���O�͍ŒZ�Ŗ��ʂȉ�H�͒ʂ��Ȃ������L���ł��B
�����PC���ڂ�DAC�Ɉ����{�����[���A�A������I�[�f�B�I�@��ɒʂ��Ɣ߂������ɂȂ�܂��B
�����̑����͂�߂�ׂ��ł��B
�����ԍ��F22959903�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 13�_
13�_
������������
>�ł�����A�u������PC���ŃA�i���O�ɂ�����A�O�t��DAC���ȒP�ō������v�ƂȂ�܂��B
���ؖ��ł���q�ϓI�Ȑ��l�f�[�^��ł��܂����B
��cantake����
>�����PC���ڂ�DAC�Ɉ����{�����[���A
�Ƃ����̂́APC���ڂ�DAC�̎��ɁA�A�i���O�A���v������Ƃ����悤�ɑ������܂����B
����͖{���ł����B
�����T�E���h�f�o�C�X�̐v�҂Ȃ�A�{�����[���̓\�t�g�I�ɕύX����Ǝv���܂�����ǂ��B
�����ԍ��F22959957
![]() 8�_
8�_
�ȑO���牽�x�������Ă��܂����A�X���傳��ȊO�̕�����̂��q�˂ɂ͉��Ă��܂���B
�������A�f�[�^�Ȃǒ��ёO�ɏo���܂��B
�����ԍ��F22959976
![]() 1�_
1�_
��JABOON����
�����ƂȂ�f�[�^��v�����Ă��A�f�[�^���o���Ȃ��l�������鎖�͐M�p���Ȃ��ق�������Ǝv���܂���B
���A
>�����Ƃ������ł����A1m���x�̃A�i���O�P�[�u���̐M�����m���ɕ�����������l�͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�Ƃ����̂́A���l�̊��o�Ő\���グ�Ă��邾���ł��̂ŁA�P�Ȃ��ӌ��Ƃ��ĕ����Ă���������K���ł��B
�����ԍ��F22959986
![]() 8�_
8�_
�F�l���肪�Ƃ��������܂��B�ƂĂ����ɂȂ��Ă��܂��B
�f�X�N�g�b�vPC�ő傫�ȉ��ʂ��o���Ȃ������Ȃ�2�`4�����炢��PC�p�X�s�[�J�[�i�[�q�̓w�b�h�z���H�j�̓I�[�o�[�X�y�b�N�C���ł����ˁB�T�E���h�̓I���{�[�h�A�X�s�[�J�[��15�N���炢�O��NEC�f�X�N�g�b�vPC�̕��T�������炢�̕t���X�s�[�J�[�i�A���v�����j�g���Ă܂����A���ʂł�������ƃm�C�Y������L�l�B
�������̂͒ʏ퉹�ʂȂ���Ȃ���Ԃł��B
������������
���Ƃɂ����ɂȐl����
�X����ł����A��������܂��̂ŋc�_���Ă��\���܂����B
�����ԍ��F22959996
![]() 1�_
1�_
��JABOON����
>�X���傳��ȊO�̕�����̂��q�˂ɂ͉��Ă��܂���B
>�������A�f�[�^�Ȃǒ��ёO�ɏo���܂��B
�Ƃ̎��ŁA��������������̂ŁAJABOON����̂ق��Ńf�[�^�𗢂�������ɂ��肢���Ă��������Ȃ��ł��傤���B
>�f�X�N�g�b�vPC�ő傫�ȉ��ʂ��o���Ȃ������Ȃ�2�`4�����炢��PC�p�X�s�[�J�[�i�[�q�̓w�b�h�z���H�j�̓I�[�o�[�X�y�b�N�C���ł����ˁB
�ɂ��Ăł����A���Z���ɂ��Ǝv���܂��B
���ŋߑ傫�Ȗ��ɂȂ����悤�Ȉ��A�p�[�g�ł���A�Չ����������̂�1���~���x��PC�p�X�s�[�J�[�����g���Ȃ��Ǝv���܂����A�������肵���ꌬ�Ƃł���A�X�s�[�J�[��A���v�ɂ��~�����鉿�l�͏\������Ǝv���܂��B
���A2�`4�����炢��PC�p�X�s�[�J�[�Ƃ����̂́A2�`4�����炢�̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�̎����Ǝv���܂����A����Ȃ�̋��Z���ŁA�\�Z�����܂肩���Ȃ��悤�ɂ���̂ł���A��̉ɂȂ�Ǝv���܂��B
���݂ɁA����Ȃ�̋��Z���ɏZ��ł��邯��ǂ��A�������������́A
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000954783/#22942008
�Ƃ����ɂȂ�܂����B
�������ŋ߁A���������ƖL���ɂ������Ȃ�A�����T�u�E�[�n�[���������lj����邩�ǂ����Y��ł���Ƃ���ł��B
�����ԍ��F22960032
![]() 5�_
5�_
��JABOON����
�����C�ɂ���Ȃ�w�b�h�z���͂�߂܂��傤�B
�I�[�f�B�I�J�[�h�Ƀ��C���A�E�g������Ȃ��������g���܂��B
�Ō�̎�i�ł���B�����o�邾���B�B�B
�����ԍ��F22960050�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�F�l�A��ώ��炵�܂����B
�w�b�h�z���[�q�ł͂Ȃ����C���A�E�g�ł����B�S�����m�Ȃ��̂œ������̂Ɗ��Ⴂ���Ă܂����B
�u���C�� �A�E�g�|�[�g
�t�����g �i �X�e���I �j �X�s�[�J�[��ڑ����邽�߂̃|�[�g�ł��B �v
�����̒[�q�̂��Ƃł��B�܂��Ƃɐ\����Ȃ��B
���C���A�E�g�ƌ��AUSB�@DAC�Ƃ̉����̈Ⴂ�͒m��܂��A�卷�Ȃ��ƍl���Ă����̂ł��傤���H
�����ԍ��F22960069
![]() 0�_
0�_
��JABOON����
����͗L��܂��B
�������茾���Ă��܂���DAC�̐��\����ł��B
�f�W�^����l���킩��A�i���O�ɕϊ����鑕�u�̐��\����Ƃ������Ƃł��B
�p�\�R���̃��C���A�E�g�@�܂�@DAC
�Ɛ����u����DAC
�R�X�g�����l���Ă���������܂��B
���̉����ɍ��������Ȃ�ΒN�������Ȑ����u�������܂���B
�������A�p�\�R���̃��C���A�E�g�o�R�ł��]���������̂������Ε��ʂɖ�܂��B
�����Ŗ������邩�A�X�ɔ�p���|���č��𑜓x�A�N���A�ȉ������߂邩�̓X���傳��ł��B
��ʎg������l����ƃR�X�p�̔��Ɉ������E���҂��Ă܂��B���A����Ŗ����Ƒʖڂ��ƍl����w�����ɐ��i����R�o�Ă�����x�l���Ă����Ηǂ��Ǝv���܂��B
�����镔���������ɂ���̂Ŏ����ɋ������ɏo��Ǝ���o���Ă��܂��̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22960129�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
��JABOON����
>���C���A�E�g�ƌ��AUSB�@DAC�Ƃ̉����̈Ⴂ�͒m��܂��A�卷�Ȃ��ƍl���Ă����̂ł��傤���H
���͑卷�͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A��������������̂ŁA�X������AJABOON����̂ق��ł�����̃f�[�^�𗢂�������ɂ��肢���Ă��������Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F22960132
![]() 5�_
5�_
��JABOON����
���ƂȂ��Ă͗]�k�ɂȂ邩������Ȃ��ł����A����AP20d�̃����̃��C���C����TV����Ƃ��āA�t�����g�̃��C���C����PC���Ń{�����[���R���g���[������ׂɁA������PC�̃w�b�h�t�H���o�͂���ڑ����Ă��܂��B
PC�̃��C���A�E�g��AP20d�̃��C���C���Ɍq���ŊȒP�Ɋm�F���܂������A���̎��������������A�����̈Ⴂ���m�F�ł��܂���ł����B
���͋Z�p���i�����āA��R�X�g��DAC�ł�����Ȃ�ɉ����o���悤�ɂȂ��Ă��Ă���悤�Ȃ̂ŁA���̒m�ꂽ���[�J�[��PC�ł���A���C���A�E�g�ɂǂ̂悤�ȋ@��ɂȂ��ł��A���ʂ͑S�����͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A���̏ꍇ�ɖ�肪�������Ƃ����b�����͕��������Ƃ�������������܂���B
�������A�f�W�^���A���v�̃_���s���O�t�@�N�^�[�ɂ��Ă͂����炩�_�c������悤�ł����A���ɂ͏ڂ������Ƃ͗ǂ�������܂���B
��ʘ_�I�ɁA�f�[�^���o�����ɖ�m���Ō���Ă�����������������̂܂܉L�ۂ݂ɂ��Ă��܂����ꍇ�A�]�v�ȏo��Ɨ]�v�ȘJ�͂��x�o���邱�Ƃ����邩������Ȃ��̂ŁA���̓_�ɏ\�����C��t�����������B
�܂��A�f�[�^���o���Ă��A���͘_�c�ɂ�����Ȃ����̂ł���ꍇ������܂��̂ŁA���̓_���\�����C��t�����������B
�����ԍ��F22960201
![]() 3�_
3�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
�����͓���ł���ˁB
���̍���������@��łȂ��ƒ�����킩��܂���B
�f�[�^�����������ĉ������Ƃ��������Ȃ��B
�o�P�c�ŃR�b�v��t�̐��𑪂�͓̂���B�����B
�����獇���ĂȂ��@��Ŕ�r���Ă����͕�����܂���B����Ȃ�̋@��Œǂ����܂Ȃ��Ǝ����o���܂���B
�����炱������o���Ȃ��Ȃ���̕����ǂ��ł��B
�����ԍ��F22960231�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��kockys����
���ɃI�[�f�B�I�̏ꍇ�́A�D�݂Ƃ����v�f���傫���ł���ˁB
�����猴���𒉎��ɍĐ��o�����Ƃ��Ă��A���ɒ�������̏ꍇ�́A�l�ɂ���Ă͘c���������ق����D�܂����ƍl����ꍇ�����肤�邩������܂���B
���݂ɁA�Z�p�I�ɂ��f�[�^�I�ɂ��A�܂��҂̌o�����悭������Ȃ��ꍇ�́A����l�̐������ł�����x���f����Ƃ����̂����肩������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�������ʘ_�ł����A�Ⴆ�A�R�����l�̂����������A�R�����Ȃ��l�̂����������ق����ԈႢ�����Ȃ��Ƃ������͂��邩������܂���B
�u�I�I�J�~���N�v�̘b������̂őS�ے�͂��܂��B
�����ԍ��F22960288
![]() 6�_
6�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
���������v���܂��B
�t�Ƀf�[�^���o���ƌ�����Ƃł��܂���Ƃ��������Ȃ��ł��B�B�g�`�o���Ă����̂��ꂪ�f�[�^�ɂȂ�̂������o���܂���B���ɂ͂ł��B
�ł�����A�f�[�^�Ȃǒ��ёO�ƌ�����l������Ɣ��ɋ����������ł��B
�����ԍ��F22960454�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
��kockys����
>�f�[�^�Ȃǒ��ёO�ƌ�����l������Ɣ��ɋ����������ł��B
���������ł��B
�����ԍ��F22960474
![]() 6�_
6�_
��JABOON����
����ɂ��́B�����ꕔ��PC�ɂ�ONKYO�̉����{�[�h��PC�X�s�[�J�[��GX-70AX��SW-10A��t���Ă���҂ł��B2010�N�����܂łȂ�PC�p�Ƃ��Ă͍������x�����ɑ����邩�ȂƎv���܂��B
�ŋ߂�PC�̃T�E���h�{�[�h�́A���i.com�݂�Ƃ��Ȃ�ǂ����̕����o�Ă�悤�ł��ˁB
��̓I�Ȑ��i�������Ă��̐��i�̃w�b�h�z���[�q�ŋ�̓I�ȃw�b�h�z���Œ����Ƃǂ����B
��USB-DAC���i��������
�I�[�f�B�IOUT�[�q�����̓I�ȃA���v�ւŃX�s�[�J�[�Œ����Ƃǂ����Ƃ��B
�̕��������₷���̂ŁA������₷���������邩���ł��B
���i���B���ł��ƁA�w���̗\�Z�����鍂���Ȃ��̂͂�����ł��łĂ��邵�A�_����ɂ��Ȃ��Ă悭�킩��Ȃ��܂܂̏ꍇ�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F22960701�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�܂��X���傳��@���q�˂̌��_�ɋA���Ă݂����Ǝv���܂��B
��������USB DAC�o�R����[�q�ɂ����ɗႦ�ΐ����~�N���X��PC�p�X�s�[�J�[�ł��f�X�N�g�b�v�p�r�Ȃ�\���ł��傤���H
����͈���ɂǂ��炪�������H�͓̉���ł��A�܂��f�X�N�g�b�v�p�r�Ƃ́A�X�s�[�J�[�Ɛڋ߂��ĕ����Ɨ������܂���
����ƁA���ʂ�����قǑ傫���Ȃ��Ƒz���ł��܂��A������j�A�t�B�[���h�ł̒���ƂȂ�܂���ˁB
���̏ꍇ�A�������̔��ˉ��Ƃ��A�o�b�N�̕ǂƂ��̉e�����ɂ����A�X�s�[�J�[�̐��̉������֒B����Ɨ����ł��܂��B
���̉��Ȃ炻�ꂾ���ɑN�x�̍����������߂���Ǝv���܂����������ł��傤�B
�X�s�[�J�[�͂��������̂ł����z�Ȃ��̂ł��A���̏o���ł��A�o�������Ƀ��X�i�[�֑i����e���͑傫�Ȃ��̂�����܂����A
�����ł���f�W�^���M������A�i���O�M���֕ϊ����镔�����s�s���������āA���������Ă����点�������̍�����
�X�s�[�J�[�����܂��Đ����Ă���Ȃ���ł��B
���̂��߁A�܂��ǎ���DAC���K�v�Ə����Ă��܂��A�����͂���ŏo���オ���ł��A
���Ƃ̓A���v�ƃX�s�[�J�[�ł��A����͏��S�҂̕��������Ă킩��₷���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22960867
![]() 1�_
1�_
��JABOON����
���̊��́APC�̃X�s�[�J�[�Ȃ̂�PC�X�s�[�J�[�̂Ƃ���łǂꂩ����ؐ��i��I������čēx���₳�ꂽ�ق����ǂ������B
https://s.kakaku.com/pc/pc-speaker/ranking_0170/?lid=sp_pricemenu_ranking_0170
�����̃X�s�[�J�[�̓s���A�ȃI�[�f�B�I�̃}�j�A�̑��A�I�ȂƂ��낪����̂ŁA����]�̊��Ƃ͍���Ȃ����Ƃ������Ȃ��č����ŏI��邩������܂���̂ŁB
PC�X�s�[�J�[�̂Ƃ���ŁA��������āA
��͂�A�I�[�f�B�I�p�̃X�s�[�J�[���C�ɂȂ�Ȃ�PC�X�s�[�J�[�̂Ƃ���łł��ӌ��Ȃǂ��Q�l�ɂ���ēx�A�����Ŏ��₳���Ɨǂ��������ꂹ��B
��A���͎������M�������f�͏o���Ȃ��̂��Ƃ���O��ł��B
�ЂƂ̈ӌ��́A���̐l�̊��Ɗ��z�ł����ċ͂��ȎQ�l�����Ȃ�Ȃ����ł��鎖��Y��Ȃ��ł��������B
PC�X�s�[�J�[�ł��������邩���Ȃ����͂����܂Ŏ��M�̔��f�ł��B
�����ԍ��F22961081�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��JABOON����
>�T�E���h�̓I���{�[�h�A�X�s�[�J�[��15�N���炢�O��NEC�f�X�N�g�b�vPC�̕��T�������炢��
>�t���X�s�[�J�[�i�A���v�����j�g���Ă܂����A���ʂł�������ƃm�C�Y������L�l�B
PC�̃w�b�h�z���[�q����Ȃ��ł������I�ɖ��Ȃ��A�Ƃ����̂�PC�̃w�b�h�z���[�q�̎����ǂ�����ł��B
PC�ɂ���ẮA�w�b�h�z���[�q�Ɂu�W�[�v�Ȃǂƃm�C�Y������Ă���ꍇ������܂��B���̂悤��PC�́A�w�b�h�z���[�q�̉������]�X����ȑO�̖��ł��B���Ԃ�AJABOON����̃f�X�N�g�b�vPC�̃w�b�h�z���[�q���m�C�Y������Ă���̂ŁA���������߂�Ȃ�g��Ȃ������ǂ��ł��B
�Ȃ��A���̈���PC�X�s�[�J�[���ƁAPC�X�s�[�J�[���m�C�Y���o���Ă���ꍇ������̂ŁAPC�̃w�b�h�z���i���C���A�E�g�j�[�q�ɒ��ڃw�b�h�z���������āA�u�W�[�v�i�����ȉ��ł����j�ƕ������邩�����Ă݂Ă��������B
PC�X�s�[�J�[���畷������m�C�Y���A�u�W�[�v�Ȃ�PC�Ɍ���������A�u�u�[���v����PC�X�s�[�J�[�Ɍ���������ꍇ�������ł��B
>�w�b�h�z���[�q�ł͂Ȃ����C���A�E�g�ł����B
�f�X�N�g�b�vPC�Ȃ�w�b�h�z���[�q�ƃ��C���A�E�g�[�q���ʁX�ɂ���̂�������܂��A�m�[�gPC�Ȃ�[�q��1�����Ȃ��w�b�h�z�������C���A�E�g�����p�ł��BPC�̏ꍇ�A�w�b�h�z���ł����C���A�E�g�ł��p�r�͓����ł��i���C���A�E�g�Ƀw�b�h�z���͂Ȃ��Ȃ��łƒ��L������Ȃ�w�b�h�z���͂Ȃ��܂��j�B
>���C���A�E�g�ƌ��AUSB�@DAC�Ƃ̉����̈Ⴂ�͒m��܂��A�卷�Ȃ��ƍl���Ă����̂ł��傤���H
���͂���܂����A�卷�Ɗ����邩�ǂ����́A���̐l�������ł��B
�����A�m�C�Y���u�W�[�v�Ə���Ă���Ȃ�A���C���A�E�g�̓I�[�f�B�I�I�ɂ͎g�����ɂȂ�܂���B
���̏ꍇ�ł��A����USB�Őڑ�������u�W�[�v�͏��܂���̂ŁAJABOON����̃f�X�N�g�b�vPC���I�[�f�B�I���u�ŕ����Ȃ�A���ꂵ���Ȃ��ł��傤�B
���ƁA�b������܂����A15�N�O�̃f�X�N�g�b�vPC�͏������āA�ŋ߂̃m�[�gPC�ɔ����ւ����Ă͂ǂ��ł��傤���H�@�����͑������A�ȃX�y�[�X�ɂȂ邵�A�ȃG�l�ŁA�ړ����ł��܂��B�t�@���̑������������i�@��ɂ���Ă̓t�@�����X�j�ł��B�I�[�f�B�I���u�Ƃ̐ڑ���USB�iUSB DAC���ڃR���|���ʓrUSB DAC���K�v�j�ɂȂ�܂����ABluetooth�Ŕ�����Ƃ��ł��܂��B�R���|�ɂ���ẮAWi-Fi�o�R�ōĐ����邱�Ƃ��ł��܂��B���C�����X�ōĐ��ł���Ȃ�A�m�[�gPC���x�b�h�̏�Ɏ����Ă��ē�������A���̓R���|����Đ�����A�Ƃ������Ƃ��ł��܂��B
�����ԍ��F22961697
![]() 1�_
1�_
��JABOON����
����ɂ��́B�ēx���炵�܂��B
PC����̃A�i���O�����o�͂́A��{�I�ɗǂ��Ȃ��ł��B�ǂ���ΒN�������̂悤�ɂ��Ă��܂��B
�i�唼�̕��́A��{�I�ɗǂ��Ȃ��ȁ[�Ǝv���Ă邩��Ȃ�ł��B�j
�f�W�^���M����PC�܂ł͗ǂ����̂����Ă��܂��̂ŁAPC����f�W�^���o�͂����āA�O���@��ŗǂ�����ڎw���ĉ������B
�O���@��ł��A�����܂ł����i�ł�����A���i���������ǂ��p�[�c�g�p�@����{�ł�����A���\�Z�ɂ��킹�đI�肷�邩
�A�V���ȃX���ŁA���ꂾ�Ǝv�����i�̎�������ꂽ��ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22962265
![]() 4�_
4�_
��JABOON����
>�i�唼�̕��́A��{�I�ɗǂ��Ȃ��ȁ[�Ǝv���Ă邩��Ȃ�ł��B�j
�؋��ƂȂ�f�[�^�͂���܂����B
�܂��A�̂ƍ��ł͈���Ă��Ă���Ƃ������͂���܂��B
�����ԍ��F22962295
![]() 4�_
4�_
��JABOON����
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001161722/SortID=22962371/#tab
�Ƃ����̂������܂����B
���݂ɁA���̃m�[�gPC�̃T�E���h�f�o�C�X�̓��}�n���ŁA�f�X�N�g�b�v��Realtek���ł��B���̎�������������������܂��A���ɂ͂����̉����̈Ⴂ�������邱�Ƃ͏o���܂���B
�����ԍ��F22962388
![]() 2�_
2�_
�X���傳��A�ς݂܂���A���肵�܂��B
�w�b�h�t�H���[�q��
PC���̃A���v����X�s�[�J�[�p�o�͂��Ē�R�Ō��������āA�w�b�h�t�H���[�q�ɏo�͂����Ă��āA
�w�b�h�t�H���A���v�̂悤�Ȑ�p�̉�H��PC���ɂ͖����Ǝv���܂��B
�X�s�[�J�[�ƃC���t�H���Ȃǂ́A�\���ォ��C���s�[�_���X�i��R�l�j���������̂ŁA���̂悤�ɂ��Ă���Ɨ������Ă��܂��B
�v�����C���A���v�ł������Ȃ��̈ȊO�̓w�b�h�t�H����p��H��g��ł��܂���B
kockys���������������Ă�悤�ɁA������H���ʂ����Ƃ́A�����������ł��B
�N���l���Ă��A�A���v�ő������{�����[�����͒�R�Ō������A���v�ő����@�Ȃǂ𑽂��J��Ԃ��̂͗ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B
������̏ꍇ�ł́A�o���_�ƂȂ�PC���̃A���v�i������H�j�́A���z�I�ɂ��������ǂ��Ȃ��N���X�̕��i�Ɛ������܂��̂�
���̂悤�ȁA�v�����瓊�e�������̂ł��B
�����ԍ��F22962403
![]() 2�_
2�_
��cantake����
>kockys���������������Ă�悤�ɁA������H���ʂ����Ƃ́A�����������ł��B
���C���A�E�g����Ƃ�A���̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������͂Ȃ��̂ł��傤���B
�����ԍ��F22962429
![]() 1�_
1�_
�lj��Ŏ��炵�܂��B
�����f�W�^���M����PC�̈����ق�̈ꕔ�ŁAPC�ɂ͖c��Ȑ��m�ȃf�[�^���m���ɓ͂��Ă܂��B
PC�͗p�r����I�[�f�B�I�p�ɂ͐��삳��Ă��܂���B
PC�I�[�f�B�I������Ă���́A�ł��邾���ǂ������Œ��������̂ŁA�����f�[�^�����O���Ɏ��o���āA
DAC�Ƃ��A���v�ASP�ȂǐF�X�ȋ@����w�����ꂽ�肵�Ă���̂��������Ǝv���܂��B
���炵�܂����B
�����ԍ��F22962437
![]() 1�_
1�_
����Ȋ����ł��傤���H�I�[�f�B�I�{�[�h�̃N�I���e�B�ɂ����܂����B
××�i�_�O�j�@��PC�̃w�b�h�t�H���i�C���z���j�[�q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�A���v�@���@�X�s�[�J�[
���i���������j�@��PC�̃I�[�f�B�I�{�[�h��RCA�i���C���j�o�́@�@�@�@�@�@�@�@ ���@����~�̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[
�Z�i�܂��������j��PC����f�W�^���o�́@���@����~��DAC�̃��C���o�́@���@����~�̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[
�������l�����ꂽ�A�i���O�ϊ����������g���̂��̂ł��B���̉���������X�s�[�J�[������Ă��Ӗ�������܂���B
�ŋ߂͉��ʂ����߂Ȃ��Ȃ�����A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�ł��𑜊��̂���A�����������������܂��B
�ቹ�̗ʊ��≹�ʂ����߂�Ƃ���Ȃ�̉��i�̂��̂��K�v�ł��傤���ǁB
�����ԍ��F22962448
![]() 2�_
2�_
���R�s�X�^�X�t�O����
>××�i�_�O�j�@��PC�̃w�b�h�t�H���i�C���z���j�[�q
PC�̃��C���A�E�g�[�q�͂ǂ��ł����B
���݂ɁA���܂���PC�̃w�b�h�t�H���i�C���z���j�[�q��PC�̃��C���A�E�g�[�q�ɐ�ւ��ĕ�����ׂĂ��܂����A���̎��������������A�m���ȈႢ�������邱�Ƃ��o���܂���B
�����ԍ��F22962457
![]() 1�_
1�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
���܂�ڂ������Ƃ́A�悭�킩��܂��ACD�v���[���[���烉�C���A�E�g�Ńv�����C���A���v�ɓ��͂��Ă���̂����ʂł��B
�ł����烉�C���A�E�g�͉����������Ƃ������Ƃł͂���܂���B
�ǂ̂悤�ȕi����DAC���烉�C���A�E�g����Ă��邩�ŁA�P�[�X�o�C�P�[�X�̂悤�ȋC�����܂��B
�ŋ߂�PC�̓f�W�^���Z�p���i�����Ĉ����ɂȂ����̂�DAC���D�G�Ȃ��̂ɂȂ��Ă�悤�ł��B
�����ԍ��F22962467
![]() 2�_
2�_
���̗����ł��B������炲�w�E���B�B
���C���A�E�g��DA�ϊ���̒�i�o�͑����ł��B�{�����[��������Ă���ꍇ�͍ő�l�����ł��B
�{�����[�����E�Ɉ�t�ɔP������ԁB
�����Ńw�b�h�z���[�q���v���A���v�����Ƃ��Ďg���p���[�A���v�ɒ�������B�܂�A�{�����[����pc���Œ�������Ȃ���������̃{�����[��������Β����鉹���łĂ��܂��B
�ň��Ȃ̂̓p�\�R�����Ń{�����[�����i���ĉ������������čX�ɃA���v���̃{�����[���ő���������g�����ł��B�����c�݂܂��B
���C���A�E�g���Ȃ��ꍇ�ɂ͎d���Ȃ��̂Ńw�b�h�z���[�q�������ő�ɂ��ăA���v�ɓ���Ă�����Œ������܂��B������A�p�\�R�����ŕςɑ�������ĂȂ��O��ł��B
�܂��A�{�����[������ʂ��͎̂��߂��ق����ǂ��ł��傤���A�A�A
�p�\�R���͐̂̓m�C�Y�ڂ��Ă܂����B
��L�̎g�����̓I�[�f�B�I�@��̃Z�p���[�g�ڑ��̊�{�I�Ȍq�������Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F22962475�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��cantake����
���ŋ߂�PC�́`DAC���D�G�Ȃ��̂ɂȂ��Ă�悤�ł�
������������܂���B
���Ƃɂ����ɂȐl����
PC�̃I�[�f�B�I�{�[�h�iDAC&���C���o�́j�̔\�͎���ł��傤�B
���̎�ςł����APC�́u�w�b�h�t�H���[�q�v�͒ቹ�̗ʊ����o�����萺���₷�������肷�邽�߂ɁA�A�i���O�ϊ���ɃA���v�œ������������Ă�����̂������悤�Ɋ����܂��B���̏��L����PC�i���C���o�͕͂t���Ă��܂���j�ł́A���������y����\�t�g�ɕt���Ă���USB-DAC�i����~�H�j��PC�Ɍq���ł��̃��C���iRCA�j�o�͂���o���������A�w�b�h�t�H���o�͂�葊���𑜊��̂���N���A�ȉ����o�܂��B
�����ԍ��F22962496
![]() 1�_
1�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
�����܂���A�M�a����������PC�̃w�b�h�t�H���o�͂������D�G�ȉ\��������܂��̂ŁA��̂͒m���̏��Ȃ����̎�ςƂ��������������B
�����ԍ��F22962514
![]() 2�_
2�_
��cantake����
>�ł����烉�C���A�E�g�͉����������Ƃ������Ƃł͂���܂���B
���肪�Ƃ��������܂����B
��kockys����
>��L�̎g�����̓I�[�f�B�I�@��̃Z�p���[�g�ڑ��̊�{�I�Ȍq�������Ǝv���Ă܂��B
����͓��ӂ��܂��B
�������A���ۂɕ������ۂ̉����ƈ��S���ɖ�肪������A��{�ʂ�łȂ��Ă��悢�Ǝv���Ă��܂��B
�����l����͎̂�������������܂��B
���R�s�X�^�X�t�O����
>�w�b�h�t�H���o�͂�葊���𑜊��̂���N���A�ȉ����o�܂��B
�f���炵���@�ނƑf���炵�����͂�������Ă�������A�܂����ł��B
�����ԍ��F22962519
![]() 2�_
2�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
���̃m�[�gPC�̃w�b�h�t�H���o�͂��V���{����ł��傤�B�@�ނ��������Ȗ����ł��B��ŏ�����������USB-DAC��EDIROL��UA-1G�Ƃ�����ł��B���i�g���̓t�H�X�e�N�XHP-A4�ƃ��}�nNX-50�i�w�������v3���~���x�j�ł�����A�����͏��܂��B
�����ԍ��F22962552
![]() 2�_
2�_
���R�s�X�^�X�t�O����
������������A�X�s�[�J�[��LC�l�b�g���[�N�������Ȃ��t�������W���j�b�g�̃X�s�[�J�[�����獷��������悤�ɂȂ����̂�����Ȃ��ł��ˁB
���݂ɁAPC�X�s�[�J�[�̃A���v�̉�H�͊ȑf�Ȃ̂ŁA�c�l��}��Ƒ傫���l�ɂȂ����Ƃ��Ă��A�ߓn�������f��������@�ׂȉ����Č��o����̂�������܂���ˁB
�����ԍ��F22962591
![]() 2�_
2�_
���R�s�X�^�X�t�O��������₷���}�[�N�ŏ�����܂������A���������⑫�����Ă��������܂��B
CD�̉�����ɂ��܂��A�ǂ�ȃn�C���x����CD�v�����[���i�������R�X�g�D��ō��ꂽPC�����x���C�v���jCD�̋K�i�ȏ�̉����o�����Ƃ͕s�\�ł��iSACD�͕ʂł��j�B
�Ƃ��낪�n�C���]�͂���6.5�{���̏��ʂ������A�_�C�i�~�b�N�����W��CD��96db����120db�֊g�傳��܂��B
������₷���T�C�g���\�j�[�ADENON,�@�E�L�y�f�A�Ȃǂɂ���܂��̂ŁA�n�C���]�Ō������Ă��������B
CD��16bit/44.1Khz�̋K�i�ɑ��A�n�C���]��214bit/192Khz�ȂǕ��ʂɏo���Ă��܂��܂��A
������Đ����邽�߂ɂ́APC����USB�P�[�u���Łi���⓯�����\�ł����APC�̏o�͂����A���ꍇ�������jDAC�ցA�����ŃA�i���O�M���ɕϊ�����A���v�t��SP, �R���|�A�v�����C���A���v�ւȂ���čĐ�����܂��B
CD�̃M�U�M�U�������Ȃ邱�ƂŘc����������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22962618
![]() 0�_
0�_
������������
>CD�̃M�U�M�U�������Ȃ邱�ƂŘc����������Ǝv���܂��B
�X�s�[�J�[�̃R�C����LC�l�b�g���[�N���ŃM�U�M�U�����܂��B
�Ƃ������A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%98%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%97%E9%9B%91%E9%9F%B3
���������������B
�����ԍ��F22962630
![]() 4�_
4�_
�����ł�
��214bit/192Khz��24bit/192Khz �ł��B
�����ԍ��F22962636
![]() 0�_
0�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
�ȑO������Ă����A���v�̓p���[�A���v���Ə�����Ă��܂����{�����[���͂ǂ���Œ�������̂ł����H
�A���v���̃{�����[����ʂ��Ė����̂��ȁH�Ǝv���܂����B
���̎�̘b�A�������g���Ă���@��ł̌o�������ɂȂ�̂ňӌ����ς���Ă��܂��ˁB���ۉ��i���ł�����3���Ⴄ�@��̌o���Ō���Ă���B�B�B
���Ƃ͒������̈Ⴂ�����邩�Ǝv���܂��B
�{�[�J�����ꍇ�l�̐��Ɉӎ������������ł��B���ꂾ�ƋC�Â��Ȃ���������܂���B�ŏ��ɋ@��̉��������ɍ����L�т�Ȃ��B�ቹ�o�߂��B�_�炩�����ōD�݁B�Ȃǂ���Ǝv���܂��B
�{�[�J���̌��Ŗ��Ă���y��̃Z�p���[�V�����Ɉӎ���u���Ē����Ă݂��肵�Ă܂����H
�����c�q�ɂȂ��Ă���Ȃ�Č������肵�܂��B�S�̓I�ɃZ�p���[�V�������ǂ��ƗՏꊴ���ǂ��Ȃƃn�b�Ƃ����肵�܂��B��������������������o���łȂ��Ə㗬�̈Ⴂ��������Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22962649�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��kockys����
>�{�����[���͂ǂ���Œ�������̂ł����H
TV��AP20���̃{�����[���ŁAPC��PC�Œ������Ă��܂��B
>��������������������o���łȂ��Ə㗬�̈Ⴂ��������Ȃ��Ǝv���܂��B
���������ʂ肩������Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F22962715
![]() 2�_
2�_
��JABOON����
PC�̉����{�[�h�̉��������Ƃ�����������
��ʓI�ȏ��Ɨ��_������PC�̉����{�[�h�͑ʖڂȉ����������Ɣ��f���Ă��܂��Ă��邩������܂���ˁB
PC���A���ł�PC�̃{�[�h�̍�莟��ł��B
ESS�̍����\�ȉ����`�b�v���ڂ����Q�[��PC�Ȃǂ�����܂����B
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1156091.html
���Q�l�ɂȂ邩�ƁB
�����ԍ��F22962908�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
���ɂ������i�Ǝ����Ŏv���Ă���j�l�́APC�ɃA�i���O�M���̃n���h�����O�������邱�Ƃ�������܂��BPC�̃A�i���O�o�́i�w�b�h�z���[�q��RCA�o�͒[�q�j���D�G�Ȃ̂ł���A�O��DAC���g���K�v�͂���܂���B�����܂Łu���Ȗ����v�̐��E�ł�����B
�����ԍ��F22962936
![]() 2�_
2�_
���R�s�X�^�X�t�O����
���͎��̓I�[�f�B�I�ɂ͌��\���Ɨ����Ă��āA����܂ŁA������̃X�s�[�J�[��A���v���̍w�����Ă������߁A�X�s�[�J�[��A���v�̈Ⴂ�ɂ�鉹���̍��͂�����x�͊����鎖���o����Ǝv���Ă��܂��B
�������A�ŋ߂�PC�{�̂̃I���{�[�h�f�o�C�X�́A����Ȃ�̃��x���ɒB���Ă���Ɗ����Ă��邽�߁A�F����Ɗ��o�̃M���b�v������̂�������Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F22962995
![]() 2�_
2�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
�p�\�R���ł��I�[�f�B�I�pPC������܂����C�O�����I�[�f�B�I�ł����g�̓p�\�R���Ȃ�Ă��̂�����܂�����p�[�c���悾�Ƃ͎v���܂��B
������ƌÂ��b������ƁB�B
PC-98����AX68000����̐l�B
DOS/V����̐l�B
�T�E���h�u���X�^�[���Ȋ����o��������m���Ă�l�B
:
:
�S���Â��ł����ˁB�B�B
https://www.oliospec.com/shopdetail/000000003521/ct147/page1/order/
����ȃI�[�f�B�I����PC�Ȃ�S�R���肾�Ǝv���܂��B
�ŋ߁H�H���\�O����I���L���[�u�����h�ƃR���{���������ǂ����Ƃ��A�s�[������PC������܂��B
������x�I�[�f�B�I�ӎ����Ă���l���I��PC�Ƃ����łȂ��ꍇ�ł͋��R���̗ǂ�PC��I��łȂ��Ƃǂ��Ȃ�̂��ȂƂ��v���܂��B
�A���A��p�̃I�[�f�B�I�@��Ƃ͈Ⴄ����������̂������B�B
�����I�[�f�B�I�̕���͕����ă_���Ȃ�v�����ď㋉�@�s���Ă݂悤�Ŕ[��������̂ɍs���������̂ňႢ����������̊������B���ɃP�[�u���A�d���܂��͍Ō�̍Ō�E�E�E���Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F22963169
![]() 1�_
1�_
�F����
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1167962.html
�����Ă������������̂ł����A�f�X�N�g�b�vPC�̃I���{�[�h�T�E���h�f�o�C�X�̃f�[�^������ƁA�Ȃ��Ȃ��������Ă���Ǝv���܂��B
�Â����o�C��PC�̓_���_���������ł����B
�����ԍ��F22963557
![]() 1�_
1�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
��ώ��炵�܂����B�ŋ߂�PC�̐��\�ɂ͑a���̂Łc�i���r�W�l�XPC�Ȃ��̂Łc�j�B����ւ�Q�l�ɂȂ�܂��B
PC�Ƃ����Ă��I�[�f�B�I��p��H�������Ă��邩���Ȃ����őS���Ⴄ�̂ł��傤�B
����ł���͂�PC�Ƃ͓d���������Ƃ����DA�ϊ����āA�A�i���O��H��PC�̊O�ɂ�������c�Ǝv���܂��B���̕�������R�X�g�ʼn���ǂ��ł���̂ł͂Ȃ����ƁB�l�b�g���[�N�v���[���[������ɋ߂���Ȃ��ł��傤���B
����A�ŋ߃��}�X�^�[���ꂽBlu-specCD���w�����A1983�N���̓���������LP���R�[�h�ƕ�����ׂĂ݂܂����BCD���̃f�W�^���f�[�^�̗ǂ����������R����Ǝv���܂����A���|�I�ɃA�i���O���R�[�h�̊y��̉𑜊��E���F�̍Č����̕�����ł����B�u�n�C���]�Ή��v�����\�̂悤�ɂ��Ă͂₳��Ă��܂����A���͂����������ł��B
�����ԍ��F22963640
![]() 1�_
1�_
���R�s�X�^�X�t�O����
>PC�Ƃ����Ă��I�[�f�B�I��p��H�������Ă��邩���Ȃ����őS���Ⴄ�̂ł��傤�B
>����ł���͂�PC�Ƃ͓d���������Ƃ����DA�ϊ����āA�A�i���O��H��PC�̊O�ɂ�������c�Ǝv���܂��B
�_���f�[�^����ۂɕ��������̊��o���d�������ق��������Ǝv���܂���B
�����ԍ��F22963659
![]() 2�_
2�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
����PC�̃A�i���O�o�͂́i�O�o��Ŏd���pPC�̃C���z�����g�p����ȊO�́j����10�N�ȏ�g�p���Ă��܂���B�����ĉƂ�PC��USB�ŊO��DAC�i2�䂠��j�Ɍq���ł��܂��B�ł��̂Ő\����܂���PC�����I�[�f�B�I�f�o�C�X�iDAC�j�̕K�v�����������A�������Ȃ��̂ł��B���ɑ��Ă̎�n�D�ł�����A�f�[�^�ɂ�����������܂���B
�����ԍ��F22963701
![]() 2�_
2�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
�����N�挩�܂����B�e�ɂ݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��B����ς肻���Ȃ�܂���ˁB�B
�ǂ��I�[�f�B�IIF�ς�ł�Ȃ炻�������g���܂��Ɠǂ݂܂����B
����������Ă�悤�ɒ����Ă݂ĉߕs���Ȃ���Ηǂ��B������Ēʏ�̃I�[�f�B�I�@��I�т̎������Ă݂܂��傤�Ɠ����ł��ˁB
�����ԍ��F22963779
![]() 0�_
0�_
�F����
��:�Â����o�C��PC�̓_���_���������ł����B
��:�V�������o�C��PC�̓_���_���������ł����B
��kockys����
���́A����܂ō������Ɨ����ē�����Ԃ̎��n�́A�u�ߕs���Ȃ���Ηǂ��B�v�Ƃ������������̂�������Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F22963950
![]() 1�_
1�_
���Ƃɂ����ɂȐl����
�����x�͌��ǂ��̐l�����f���邵���Ȃ��ł�����ˁB
���ꂾ����I�[�f�B�I�̃I�X�X������ł��B�i�j
���͖����o���Ȃ��Ȃ�����N���グ�Ă݂悤�����P�ł��B
�����ԍ��F22963976�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��JABOON����
���͂悤�������܂��B
�^�C���h���C���Ȃ�Đ̂����Ă܂������ǁB
���\�������ł����B
���͂ǂ���������ł��傤�B�������܂���B
�����ԍ��F22964002
![]() 0�_
0�_
���h�b�h�R���b�c����
�u�^�C���h���C�����_�v�Ƃ����̂́A�܂��Ƃ��ȗ��_�Ȃ̂ł��傤���ˁB
�F����
�m���Ă�l�͒m���Ă���Ǝv���܂����A���̐́A�x�����E���c�C�[�^�[�Ƃ������̂������āA�������̉��ɖ������ꂽ�l�Ԃ̈�l�ł��B
���}�n��NS1000M�̓x�����E���c�C�[�^�[�ł����A���É�����ɂ����Ă���ꍇ�������̂ŁA�������É�����Ŏ����\�Ȃ�A����Ƃ������Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F22964805
![]() 1�_
1�_
�^�C���h���C���̓f���\�[�e���̃C�N���v�X�X�s�[�J�[���܂�����܂��H
�����ԍ��F22964822�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���h�b�h�R���b�c����
�C�N���v�X�̖��O�ŁA�o��܂���B
�䂪�Ƃ�PC������1PC�Ƀe�N�j�N�X�̃A���v�o�R��
https://s.kakaku.com/bbs/K0000330895/
���Ă܂��B
�����ԍ��F22967410�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��fmnonno����
�����́B�C�N���v�X�̃��[�J�[�T�C�g���Ă݂܂������ǁA���̓J�[�i�r��A�h���C�u���R�[�_�[����Ȃ�ł��ˁB
�x�m�ʃe�����Đ̎ԍڗp�̂`�l���W�I���قƂ�ǃV�F�A���߂Ă܂���ł������ˁH
�C�N���v�X�̃R���ł̉摜�͏�����Ă܂��ˁB�ŋ߂����̃T�C�g�̉摜�ŏ�����Ă�����̂������ł��ˁB
�҂����Ȃ���ł��傤���ˁB
���Ȃ݂Ɏ����g���Ă����̂́A2���~���炢�������ł��B
��JABOON����
���݂܂���A���ז����Ă܂��B
�����ԍ��F22967433
![]() 2�_
2�_
��JABOON����
�p�\�R���̃I�[�f�B�I�����l�B�̊��o
�i���N2���~�ȉ��j�T�E���h�J�[�h�܂���Creative�ŏ\���Ǝv���l
�i���N5���~���x�j�w�b�h�z�����S�� DA-310USB �Ȃǃw�b�h�z���A���v������
�i���N10���~���x�j���^�X�s�[�J�[�ɒ�Ԃ̃A���v PMA-600NE ��g�ݍ��킹��
�i���N20���~���x�j�����X�s�[�J�[�⍂���w�b�h�z�� HD 800 S �Ȃ�
���ʂ͈���������n�߂�20�N�o��10���~����20���~���|����̂����ʂɁB
�Ȃ��ł����H
�u���ɖO���Ă��܂�����v�A���ɖO���Ă��܂��̂ō������֏�芷����B
��������3�N����8�N���x�ŖO���Ă���̂ŁA�����Ǝg���镨�ƍl����Ǝ��s���܂��B
Creative�Ŗ����̐l�͂��܂��B
���܂ŁA�ǂ̂悤�ȃI�[�f�B�I������Ă��Ă��邩�ɂ��A
�����������߂��A�ς���Ă��܂��B
Creative�R�[�X�̏ꍇ�́A
�w�b�h�z���Ȃ�ō�5���~���炢��ڈ��ɁA�X�s�[�J�[��3���~�ʂ�ڈ��ɃA�N�e�B�u�^
����20�ォ��30��O���܂ŁACreative�Ŗ����ł����B
�ŏ��̓G���R���̈���PC�X�s�[�J�[�ʼn䖝�ł���̂ł��B
����BOSE�Ȃǂ�5���~PC�X�s�[�J�[�ցB�O���Ă�����A���̃X�e�[�W�ցB
Denon DA-310USB�ƃR�X�p�̗ǂ��A�N�e�B�u�^�X�s�[�J�[
TANNOY Reveal 402 �Ȃǂ̑g�ݍ��킹
DA-310USB�̃��C���o�͂�4�N�o�ƖO���Ă���̂Ō��E5�N�ƍl����B
�w�b�h�z���o�͂͏����ȉ��ʂŖ��Ăł����A�����A���v��m��Ƃ����O����B
Denon PMA-600NE�ƃR�X�p�̗ǂ��X�s�[�J�[�̑g�ݍ��킹�B
���f�W�^���o�H�ŕs�����Ȃ��ꍇ�́A�p�\�R�����ڂ̌��f�W�^���o�͂�
���f�W�^���ɕs�������Ȃ� TOPPING D10 �� USB-DDC �Ƃ��Ďg���A
�����f�W�^�����͂ɂ���BUSB-DDC�̈����͉̂��i�R���ɂȂ��B
�Â��ȉ��ʂŁA��i�ɕ�����X�s�[�J�[�قǍ����ȌX����
���́A30��㔼����10���~�R�[�X�A40��㔼����20���~�R�[�X�ցB
�i���� PMA-600NE + FYNE AUDIO F300 + USB-DDC or USB-DAC�j
�ŏ����獂�z��PC�I�[�f�B�I���n�߂���A�ቿ�i�͈ێ��ł��Ȃ��B
���̓_��z�肵�āA�������Ă݂ĉ������B
�����ȉ��ʂʼn����������Ȃ�̂́A�������m�قǁB
�R�X�p���ǂ��ł��ƌ����Ă��鐻�i�́A�����ȉ��ʂł������͗ǂ��B
�����ԍ��F22970255
![]() 2�_
2�_
��hiro.coolverse.jp���� ����ɂ���
��̓I�ɂȂ��Ȃ���肭������Ă܂��ˁA�i�C�X�N���b�N���܂����B
���ɖO����͎̂����i���������ʂ��ƌ��߂āA���̂��J���̂��߂ɔ����ւ��Ă��܂��B
�I�[�f�I���Ȃ�Č������������܂����A����͂����Ӗ��ɉ��߂��Ă��܂��B
�s���_�����炩�ɂ���A��芷���ʼn��P�ł������̊�т̕����傫������ł��B
�����ԍ��F22970725
![]() 1�_
1�_
hiro.coolverse.jp���� ��
���ŏ����獂�z��PC�I�[�f�B�I���n�߂���A�ቿ�i�͈ێ��ł��Ȃ��B
�@�@�@���̓_��z�肵�āA�������Ă݂ĉ������B
���Ɏ�̒i�K�������ɕ\������Ă܂��B
���̎��͐F��Ȏ�ɋ��ʂ��邱�Ƃł��ˁO�O
�����ɂȂ�܂����@���������̂��̃X���̑O�̃��X
PC�p�X�s�[�J�[�I��https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22969178/#tab
�����l�̃X����A�����ď������܂�Ă��܂����A�����̗L�v�ȉ��������܂�Ă�ɂ��ւ�炸���u����Ă��܂��B
�@�����̃��[��������肢�����������Ǝv���܂��B
�����āA2019/10/05 20:22�����ԍ��F22969831
���̃��X�ɑ��]�ː�R�i���R�i������
���X���傳��͕��u�Ȃǂ��������ƕԐM���Ă��邵����̌��t���q�ׂĂ��܂��B
�@�����|����͂�߂������ǂ��ł��ˁB
�����[���ᔽ�̏�K�҂����l�Ƀ��[�������ȂǂƐ����Ƃ������̃l�^�������ł����H
�O�b�h�A���T�[�N���N�����Ă����̂����ݏo������Ăđ��ӂ����������ł���B
���l�ɑ��ă��[��������O�ɂ܂��͂����g�����̌������Ȃ݂�ׂ��ł��傤�B
�ᔻ�����獡�x�͖J�ߏグ�ŃO�b�h�A���T�[�N���N���ł����E�E�E�E
����Ȏ��������ɂ��L��̂Ȃ�A���Y���X�ɎӍ߂��ׂ��ł���`�`
�����̃X���Ƃ͕ʂɎӍ߂��ׂ��X������}���ƗL��ł��傤���I�I�I
�����ԍ��F22970865
![]() 14�_
14�_
���i�C�X�N���b�N���܂����B
�������悭���P�l�Ԃ����肨��̃i�C�X�N���b�N�Ԃ������炤���߂̏퓅��i���ˁB
���ӂ����������Ȃ�Ȃ��B
�����ԍ��F22970903
![]() 11�_
11�_
���]�ː�R�i���R�i������
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1167962.html
����Ă��r�N�Ƃ����Ȃ����R�����������悤�ȋC�����܂����B
�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F22970955
![]() 4�_
4�_
��������u�i�C�X����Ƃ��܂����v�Ə������ނ̂͒p���������B
�t�@���o�^�җ~�����ɕЂ��[�Ƀt�@���o�^���܂���l���p���������B
�����ԍ��F22972360�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
�A���v���ւ���̂ŃP�[�u������|���悤�ƌ������Ȃ̂ł����A���������o�C���C���ڑ����̂𗝉�������Ă��Ȃ��̂ł����������肢���܂��B���� �Y�t�ʐ^�̂悤�Ȑڑ��ŃW�����p�[�����g�p��2�c�̃P�[�u�����g�p���Ă���̂̓V���O�����C���ڑ��Ȃ̂ł����H1�{��4�c�̃P�[�u�����w�����X�s�[�J�[���͂��ꂼ��4�ڑ��A�A���v����4�c����荇�킹2�c�Ƃ��q����ƃo�C���C���ƂȂ�̂ł����H�X�s�[�J�[�͒��Âōw���������ɃW�����p�[�v���[�g�͕t������Ă��炸�W�����p�[�P�[�u�����t������Ԃł����B
�����l�����ʐ^�̂悤�Ȑڑ������Ă��܂����A�v���[�g���P�[�u���������͓����Ȃ̂ł��傤���H
�X�s�[�J�[�FB&W685/DM603S3 �A���v�F���}�nRX-A1080�@�P�[�u�����̓]�m�g�[�� 6NSP-G5500�i4�c�j��6NSP-��2200�i2�c�j�Ō������ł�
![]() 7�_
7�_
��niconicopon����
�Y�t�ʐ^�̐ڑ��ŃW�����p�[�����g�p��2�c�̃P�[�u�����g�p���Ă���̂̓V���O�����C���ڑ��ł��B
1�{��4�c�̃P�[�u�����w�����X�s�[�J�[���͂��ꂼ��4�ڑ��A�A���v����4�c����荇�킹2�c�Ƃ��q����ƃo�C���C���ڑ��ɂȂ�܂��B
�v���[�g���P�[�u���������͓����ł��B
�����ԍ��F22948253
![]() 5�_
5�_
��Minerva2000����
�ԓ����肪�Ƃ��������܂��B��͂�V���O�����C���������̂ł��ˁB�������ݓ�������Ƃ悭�o�C���C���̕����ǂ��Ȃ����ƕ����܂��̂�4�c���߂̍w�����l���܂��B�A���v�����ԉ����X�s�[�J�[�܂�9���[�g�����ł����A1�̃X�s�[�J�[��2�c��2�{���ƃP�[�u�����炯�ɂȂ�̂�4�c1�{���������ł����A���܂荂���ł͂Ȃ��������߂͂���܂����H�������l���ꂼ��ł��傤���i�j�f��ӏ܂������ł��B�����ł���������ׁA�b�E�e�k�E�e�q���o�C���C���i4�c�j�A�r�q�E�r�k���V���O�����C���i2�c�j�����肩�ȁH�Ƃ��l���Ă��܂�
�܂��A�x���O�E�o�i�i�v���O�̒[�q�͂������������I�ɂ͗ǂ��̂ł��傤���H�������\�K�v�ɂȂ�܂����E�E��
�����ԍ��F22948307
![]() 1�_
1�_
��niconicopon����
����ɂ��́B
�ʐ^�����܂��ƁA������Ă�̂̓V���O�����C���\�������|���iHi+�ALo-�j�̂悤�ł��ˁB
�o�C���C���[�͕Б�SP������Q�c×�Q�{�ƂS�c×�P�{�ł������ł����A�R�[�h�̒f�ʐς͈���Ă��܂��B
���ʂ͐l���ꂼ��ŁA���������Ⴄ�Ǝv���܂��B
SP�R�[�h�����Ȃ荂�����̂���F�X����悤�ł����A������x�ŏ\���Ǝv���Ă܂��B
����I�ȉ�����������߂�Ȃ�A��͂��SP�̃O���[�h�A�b�v�i���s�̂Q�{���炢�j���ߓ��Ǝv���܂��B
��ʓI�ɁA�R�[�h�ɂ̓A���v��SP��ς���قǂ̌��ʂ͊��҂��Ȃ������ǂ��ł��B
�����ԍ��F22948310
![]() 3�_
3�_
�ǂ����B
cantake����Ɠ��ӌ��ł��B
�����ǁA�A�N�Z�T���[�Ƃ��Ċy���ނ̂ł�����b�͕ʂ���
�V�X�e���͌����ڂ̑厖�₩��ˁi��
�����ԍ��F22948424
![]() 2�_
2�_
�m���ɃP�[�u����肻�̑��̃O���[�h�A�b�v�ł���(��)�B����͗\�Z�̓s����X�s�[�J�[�͒��߂ăP�[�u���I�т�
�y����ł݂܂��B�ڑ��̃����������������܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F22948499
![]() 1�_
1�_
��niconicopon����
�b�E�e�k�E�e�q���o�C���C���i4�c�j�A�r�q�E�r�k���V���O�����C���i2�c�j��OK�ł��B
�x���O�E�o�i�i�v���O�̒[�q�͂������������I�ɂ͗ǂ����Ƃ�����܂��B
������̈�i�ق�HP���Q�l�ɂȂ����Ă��������B
https://www.ippinkan.com/cojp/howto/page_1.htm
���̓X�s�[�J�[�P�[�u���ɂ����āA�����X���[�u�ō����X�s�[�J�[�P�[�u�����p�������Ă��܂��B
�����ԍ��F22948565
![]() 4�_
4�_
niconicopon����A����ɂ��́B
>�P�[�u����肻�̑��̃O���[�h�A�b�v�ł���
�Ƃ��������̂͂��̒ʂ�ł����A�����������m�ɂ����ƁA�o�C���C�������O���܂߁A�ʏ�͈̔͂łr�o�P�[�u�����������Ă��A�o���̍��̓q�g��������������悤�ȑ傫���ɂ͂Ȃ�܂���B�����܂ł������D�荞���ƂȂ̊y���݁A���炢�ɍl����̂������ł��B
�������̔��X��ƊE�W�̂g�o�ł͖��̂���b���肪�x��܂����A�C�����̖��ʼn����ς�����Ɗ������l�����r���[���������Ƃ�����܂��B
�������ڐG���̖��ʼn������邱�Ƃ͂���܂��B�x���O�E�o�i�i�v���O�̘b���悭�o��b��ł����A��������ڑ�����Ă���ǂ�ł��i�����̒��ڑ��ł��j���͓����ł���B
���ƁA�g�������ŋ��k�ł����A�`���ł��������悤�Ɂu�P�[�u������|�v���Ă��܂��Ɖ����o�܂���̂ŁA�u��V�v�������ł��ˁB
�����ԍ��F22948634
![]() 6�_
6�_
�z�[���Z���^�[�ł�100�~���x�Ŕ����Ă���VVF2.0�ɃX�s�[�J�[�P�[�u����ւ���A���͂����ƕς��܂��B
���̎����Ɏ���50�N�O�ɋC�t���܂����B
�o�C���C�������O�ڑ��͓��ł̎��p�V�ĂŁA�������ꂽ�̂ő����̃X�s�[�J�[���[�J�[���R�X�g�A�b�v�ɂȂ�̂ɁA����p�̒[�q���̗p���Ă��܂��B
�����ԍ��F22948704
![]() 1�_
1�_
9�����K�v�Ȃ̂ŗL��A�o�C���C���ڑ������A�V���O���ڑ��ŗǎ��ȃW�����p�[�P�[�u����p�ӂ��������ǂ��Ǝv���܂��B
�Ⴆ��4�c�́u6NSP-G5500�v���w������Ă�2�c�̃o�C���C���ڑ���4�c�̃V���O���ڑ����r����Ă݂������ǂ��Ǝv���܂��B
������4�c�̃V���O���ڑ����ǂ���A�Ⴆ�Ή��L�̂悤�ȃW�����p�[�P�[�u����p�ӂ���邱�Ƃ������߂��܂��B
���W�F�N�g LJ-GEN-JP4
�t���e�b�N JUMPER-B
�����ԍ��F22949335�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
niconicopon����A������
���o�C���C���ڑ����̂𗝉�������Ă��Ȃ�
SP�[�q�̃y�A�ŏ㑤�������p�A�������ቹ�p�ł��B
�ቹ�pSP�͋t�N�d�͂��傫���A���v�ɒ����ŋz�������������悭�A
������SP�̓t�B���^�[�������Ă��܂����t�N�d�͂ŕψʂ��Ă���P�[�u���Ƀf���P�[�g�ȍ����M�����悹�ē��͂�����A���v�[�q�����p�P�[�u���ő������������ϒ����Ȃ��ł��B
���ʂ͒ቹ�̎���A�����̉𑜊��̉��P�B
�����͕����邱�ƂȂ̂œd���I�ɂ�1�{��4�c�P�[�u���̕������A2�{�̃P�[�u��1�{�Â��悢�������A�ቹ�Ő�p�A���v�ɂ���o�C�A���v���X�Ɍ��ʓI�ł��B
���P�[�u���̓]�m�g�[�� 6NSP-G5500�i4�c�j��
��6NSP-��2200�i2�c�j�Ō�����
B&W685�͂�����ƃh���V������B&W�̒��ł͉��y�̊y�����ɐU���������B�]�m�͑������Œቹ�����߃��b�L���̃u�����h�ō��������߂�̂Ŕ����ĉ����X�s�[�J�[���Ƃ������薾�Ăɂ悭�Ȃ����悤�ɕ������܂����h���V�����Ƃ��Ԃ�̂�B&W�͍��𑜂Ȃ̂ŁA���t�������ǂ��������������ɕ������邩������܂���ˁB
�o�����X�I�ɂ͑f���ł������߂́A�J�i��4S6(�ቹ������߂����Ȃ�4S8)��1���SP�ɍ����A�ቹ��2�{�g���ł��B
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/21331/
�����ԍ��F22949443�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��niconicopon����
����ɂ��́B�ʐ^�̓V���O�����C���[�ڑ��ł��ˁB
���̂Ƃ���ł́A���݃o�C���C�������O���Ă�X�s�[�J�[�̓A���v��A+B�o�͂ɂ�
���Ƃ�Cat5eSTP��LAN�P�[�u�����������̂�4�{1�g�̌v8�{�œ��Ƀo�i�i�v���O��t�������𗘗p���Ă܂��B
�s�̂̃P�[�u���Ȃ炩�Ȃ�̐��������U�����܂������A�J�i��4S8G�̓R�X�g�p�t�H�[�}���X�������f���ŗǂ��̂ł��C�ɓ���ł����B
�����ԍ��F22949611�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��niconicopon����
RX-A1080��5.1ch�\���Ȃ�2ch�]��̂Ńt�����g�̃o�C�A���v�쓮���o���܂���B�X�s�[�J�[�[�q������Ă���̂�4�c�P�[�u���ł͓���ł��ˁB
�f��d���Ȃ�t�����g�v���[���X���g�b�v�X�s�[�J�[��ݒu����5.1.2�\���ɂ���̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�����O���[�h�A�b�v������̂ł���AMX-A5000�V���[�Y�̓��������ʓI���Ǝv���܂��B(�\�Z�ƒu���ꏊ���K�v�ł���)
���}�n��AV�A���v�͒ቹ������Ȃ��Ƃ��쓮�͂��ア�Ƃ��]����鎖�������ł��B����RX-A3070�̉�������ƃA�g���X�\���ׂ̈ɊO���A���v�������܂���������MX-A5000�������܂����B�A���v�̏o�͂͒�i���5W�����������̔��ł������̃����n���������čX�ɉ����O�ɏo��悤�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F22949616�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�F���肪�Ƃ��������܂��B�F��ȓ�����������ɂȂ�܂��B�o�C�A���v�͍l���Ă��炸�A�A�g���X5.1.2�ׁ̈ADALI��ALTECO C1���w���\��ł��B�J�i��4�r8�͈����ŗǂ������ł��ˁB���ƃx���f��8470���l�b�g������ƕ]�������ł��ˁB�b�E�e�k�E�e�q�iB&W603S3�j�̓]�m�g�[����5500�Ńo�C���C���ɂ��Ăr�q�E�r�k�iB&W685�j�͔z������������̂ň����ȃP�[�u���ŃV���O�����C���ɂ������Ǝv���܂��B�����Ń]�m�g�[��6NSP-2200�E�J�i���E�x���f���ŃV���O�����C���ڑ�����Ȃ�ǂꂪ�ǂ��ł��傤���H���̑��R�X�p�̗ǂ��P�[�u���ł������߂���܂����H
������A�J�i����4�c�Ȃ̂ŃV���O�����o�C���C���ڑ��ɂ��������ǂ��̂ł��傤���H
�X�s�[�J�[���Â����O���[�h���Ⴂ��������܂��A�P�[�u���ŏ����ł��ς��Ȃ�撣���Ă��炢�����̂�(��)
�����ԍ��F22950205
![]() 1�_
1�_
niconicopon����A����ɂ���
�J�i����4�c�ł����A�Ό�����2�c���悶���ăc�C�X�g�y�A�ɂ��v���X�A�}�C�i�X��2�y�A�Ŏg���܂��B
�v���P�[�u���Ȃ̂ŁA�X�^�W�I�⏬�K�̓X�e�[�W�ŊO���m�C�Y������Ȃ��v�ł��B
�]�m�������Ȃ�]�m�g�[�����͂����肷��5500�ȏオ�悢�Ǝv���܂��B(�X�s�[�J�[�ɂ���Ă̓]�m�������߂邱�Ƃ�����܂��B)
�����ԍ��F22950637�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
niconicopon����A������
�t�����g��5500�ŃT���E���h�̓V���O���ɂ��邯�lj����悢���H�̎���ł��˃X������Ă��݂܂���
�T���E���h���͘e���Ȃ̂Ƌ����L�т�̂�4S8�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22951278�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�ʐ^�̐ڑ���Ԃ̓V���O���ł��ˁB�@�@�o�C���C���ƂȂ�Ɓ@���i���������j�ƒ�i�������j�ɂ��ꂼ��ڑ�����ā@�W�����p�[���������̓W�����p�[�v���[�g��������Ԃ������܂��B
�ʐ^�@�Q��
�`�P�O�W�O�͂T�D�P�����ł���o�C�A���v�o�C���C�������O�i�A���v���ł��o�C���C���j���o���܂���
�ʐ^�A�Q��
�S�c�P�[�u���g���ā@�A���v���́{�|�ɂQ�c�Â���ā@�X�s�[�J�[���łP�c�ɂ�����ĕ��@�ł���ˁB
�ʐ^�B�Q��
���̏ꍇ�A���ʂ̃P�[�u�����ƃX�s�[�J�[�������Ȃ�ׂ��Ȃ��Ďd�����@�A���v�������������Ȃ�P�[�X���唼�ł��ˁB�@�@��⋭���ł����Q�{�P�[�u����p����̂��x�X�g�ł����ˁB�@�A���v���ɓ��邩�ƁA�����ƃR�X�g���|�����ςł��ˁB
�T�D�P�������Ɓ@�X�s�[�J�[�̃R�X�g�͊|����܂����@�o�C�A���v���o����̂Ō��ʂ͖]�߂܂����@�X�s�[�J�[�P�[�u���ɂ��o�C���C�������O�͖��Ӗ����ȁH�@�@�P�[�u���Ɠ����f�ނŃW�����p�[�P�[�u�������ڑ����������ǂ��ł��傤�ˁB
����ƁE�E�E�@�@�ʐ^���B���Ē����@�l�q��������̂͗ǂ����Ȃ̂ł����@�R�������Ȃ��Ȃ̂ł���ˁB�@�@�i�Q�l�ʐ^�̓l�b�g�̉摜��������̓Y�t�ł��j�@�@�@����ł����@�����ł��ˁI�@�@�����]�X�����O�ɑ|�����܂���I�@�P�[�u���ɚ��A�X�s�[�J�[�ɚ��A�Œ�ł��ˁB�@���߂Ďʂ������炢���͏����܂��傤��B�@�@�i�j
���ꂽ�x���O���v��܂���ˁB�@���ڃP�[�u����}���Ē��߂ĉ������B
�����ԍ��F22951529
![]() 3�_
3�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�X�s�[�J�[]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z����Mini-ITX�@����PC�P�[�X�ɍ��ꂻ��
-
�y�~�������̃��X�g�zCore Ultra 3 205�o���炱�̂��炢�őg�݂���
-
�y�~�������̃��X�g�z�O���{�Ȃ�
-
�y�~�������̃��X�g�z���ʼn���VR�Q�[�������K��
-
�y����E�A�h�o�C�X�z�\��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
�i�Ɠd�j
�X�s�[�J�[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j