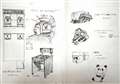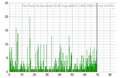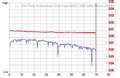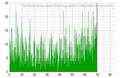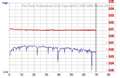���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S109�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 83 | 151 | 2008�N11��15�� 21:51 | |
| 23 | 161 | 2008�N8��31�� 19:39 | |
| 41 | 32 | 2008�N5��30�� 00:22 | |
| 62 | 156 | 2011�N7��3�� 15:35 | |
| 0 | 0 | 2007�N10��8�� 08:39 | |
| 0 | 3 | 2007�N9��16�� 11:01 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�V���[�Y��O�e�ł��B����̃X���b�h�i�@http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7748266/�@�j�ł͉������̃I�[�f�B�I���i���u�����h�ʂɐU��Ԃ�u��ڕҁv�A���ڂ̃X���b�h�i�@http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7920820/�@�j�ł́u���ꂩ��̃I�[�f�B�I�͂ǂ�����ׂ����v�ȂǂƂ������s�����ő�ȑ�ڂ��f�����u�W�]�ҁv�ƓW�J���Ă��܂������A�Đ��ő������̃p�[�g3�ł́u�G�k�ҁv�Ƃ��āA����҂ɓ�����`�̑��̃g�s�b�N�ł͏�������Ȃ��I�[�f�B�I�Ɋւ���D������Ȏl���R�b���}�b�^���Ɨ��������Ői�߂����Ǝv���܂�(^^)�B
�@�̘b�⎩���b�A���[�J�[��f�B�[���[�Ɋւ��Ă̕]����s���_�A�l�I�ɂ͎��s�k�Ȃ������U�炩�����Ǝv���Ă��܂��B
�@����ł́A��낵�����肢���܂� �|�� ALL�B
![]() 1�_
1�_
�@�܂��ŏ��̃l�^�́A�I�[�f�B�I�@��̐������������ɃV�t�g���Ă��邱�Ƃɂ��āB����������Y���������Ă��郁�[�J�[������܂����A�������_�𒆍��ɒu���Ă���I�[�f�B�I���[�J�[�͒������͂���܂���B���Ȃ݂ɁA���̎g���Ă���KEF��iQ�V���[�Y�͒������B�ȑO���L���Ă����������[�J�[�̃A���v��CD�v���[���[��Made in China�ł����B
�@�܂��A�����g�Ɍ����ẮA�ǂ��ō���悤�ƑS���C�ɂ��܂���B�����C�ɓ������Ń��V�ł��B���������A�ǂ̍��̍H��ō��ꂽ���ɂ��ĕK�v�ȏ�ɐ_�o���ɂȂ�̂͂������Ȃ��Ƃł��B���Ƃ���A�Ƃ������i�͖��炩��B�Ƃ������i��艹���ǂ����AA�͒������ł���̂ɑ�B�͓��{���Ȃ̂ŁA������B��I�ԁE�E�E�E�Ȃ�Ă��Ƃ͔n�����Ă��܂��B
�@��X�̐����ɂƂ���Made in China�͕s���ɂȂ��Ă��܂��B�ߗ��i�ł����j�N���݂����ȗ����i�����ł͂Ȃ��A���������L���ȃu�����h�̐��i�������ō���Ă��܂��B���������o�ό����I�Ɍ����A�R�X�g�̈����Ƃ���ɐ������_���W������͓̂��R�̘b�ł��B
�@�������A�s���A�E�I�[�f�B�I���i�Ƃ����̂̓u�����h���̈ߗ��i��������Ӗ�����������킯�ł��B�����������i��P�Ɂu�R�X�g���Ⴂ����v�Ƃ������R�Œ����̍H��ō�点�ėǂ��̂��Ƃ����̂��A�����ȋ^��ł͂���܂��B�܂��A���̔w�i�ɂ͏���҂̊Ԃɒ����������{�����邢�͉��B���Ɣ�ׂăO���[�h��������Ƃ����u����v�����݂��Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B
�@TRIODE�Ƃ����A�^��ǃA���v�Œm������{�̃��[�J�[������܂����A���i�͒������ł��邱�Ƃ��������Ă��܂��B���Ђ̐��i�Ɏg���Ă���p�[�c�ނ�����Έ�ڗđR�ŁA���{�Ő��Y����Ƃ��̉��i�ł͐���܂���B���Ђ́u�ґ�ȑf�ނ��g�������i���A�����Œ��邽�߂ɒ����ō�点�Ă���v�Ƃ����|���V�[�������Ă���悤�ŁA����������������͊Ԉ���Ă͂��܂���B���̎p���ɔ[�����郊�X�i�[�́A�w�����ɋ�����Ηǂ������̘b�ł��B
�@���āA�ʂ̃X���b�h�ő��ʂɋ������Ă���VICTOR�̃X�s�[�J�[�̘b�͎��Ɋ��S���܂���B���Ђ̍����X�s�[�J�[�́A�����ɂ��u���{�̃G���W�j�A���O�����߂���i�v�݂�����搂�������f���Ă���炵���ł����A���ۂ͒������ł��B���̔�������������Ƃ���ƁA���\�ɋ߂��ł��ˁB�����Ƃ��ȑO����VICTOR�̃X�s�[�J�[�͒����ō���Ă��邱�Ƃ́A�I�[�f�B�I�t�F�A�̐ȏ�œ��Ђ̊��������X�Əq�ׂĂ��܂����B�Ȃ�G���h���[�U�[�ɂ����L�����m���ׂ��ł��傤�B
�@�{���̂Ƃ���A�I�[�f�B�I���i�������ő勓���Đ�������邱�Ǝ��́A�o�ς݂̍���̊ϓ_���炠�܂�����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�m����TRIODE�̂悤�ɒ������ł��邱�Ƃ��ŏ����疾�����ď������Ă��镪�ɂ̓}�[�P�e�B���O�ʂł͖��Ȃ��ł��傤�B�������A�����@��̍��肪�����ɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�������I�ɂ͍D�܂����͂���܂���B���͐l�����̃��[�g���i�s���Ɂj�Ⴂ�̂ōH��𒆍��ɒu�����Ƃ̍��������O�ʂɏo�Ă��܂����A�בփ��[�g�Ȃ�āg�����h�ł��B����������P�ނ�����Ȃ����Ԃɒǂ����܂�邩������Ȃ��B���̎��ɂȂ��ă��[�J�[�����������Ă��x���̂ł��B
�@�����āA�����ł����Y�Ƃ̋������O����Ă�������A�s���A�E�I�[�f�B�I�@��̂悤�Ɏ���̍������i���炢�����ō��ׂ����Ǝv���܂��B�����Ȃ��ƋZ�p�̌p���͏o���܂���B�Z�p�Ƃ����̂͐v�i�K�����ɂ���̂ł͂���܂���B����҂ɏo���Ēp���������Ȃ������́u�d�グ�v�����h�ȋZ�p�ł��B���������Ē����ł̐����͐l���R�X�g�ʂŕ��������L���ȕ��ޒ��B�͏o����ɂ���A�d�グ�͓��{���̓G�ł͂���܂���B������A���~���C�̃��H�����[�����g���Ă��悤�ƁA������V�R�ؓ˂��d�グ���낤�ƁA�����ȃ^�b�`��t�B�[�����O���͂��傹��u�������v�Ȃ̂ł��B
�@������[�G���h�@�܂Ŋ܂߂Ă��ׂĎ������Y�ɂ���Ƃ͌����܂���B�ł��A�����i�ȏ�̐��i�͒����Ɋۓ��������ɁA�����ŐӔC�������Đ������ė~�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8281757
![]() 1�_
1�_
���E�������
�ǂ��^�C�~���O�̐V�X���ł��B�X�N���[�����ʓ|�ɂȂ��Ă��Ă��܂�������B
���`�A���ݎ���JBL�̃X�s�[�J�[��4��ގ����Ă���܂��B�܂�S3100�ł�������̓A�����J��
�ł��B�Z���^�[�X�s�[�J�[��HC1000���A�����J���ł��B�T���E���h�o�b�N��S3500���g���Ă�
�܂�������͓��{���Ɩ��łɂ���܂��B�s���A�I�[�f�B�I�p�Ƃ��Ďg���Ă���S4000�ł����A
����͒������ł��B���������AJBL�̃X�[�p�[�g�D�C�^�[���g���Ă��܂����A�������������
���B���Ȃ݂�S4000���X�[�p�[�g�D�C�[�^�[���ƂĂ��Y��Ɏd�オ���Ă��܂��B
�ŋ߁A�r�N�^�[�̃X�s�[�J�[SX-M3���܂������A�����ɒ������ł��B
�������Y�����ǂ��ł��낤�ƋC�ɂ��܂��A���ƊǗ����A�����J/���{�ł���Ȃ�A��
����������t���܂��B���̋ߐ�������ɐi�o���Ă���܂����A�ނ�͌���ꂽ���Ȃ�Β���
�ɍ�邻���ł��B�����A�u������ƍl���č���āv�ƂȂ�Ə����\�͂������邻���ł��B
�E�E���Ȃ݂ɍ��N��AV�A���v���ւ��܂�����(���}�n)�A�O�@��DSP-Z9�͓��{���ł����B��
���č��x��DSP-Z11�́u�}���[�V�A���v�ł��B�\�j�[��AV�A���v�̃t���b�O�V�b�v�@���}���[
�V�A���ł��B
�E�E�E���NHK�̔ԑg�ł���Ă��܂������A�������ŋ߂͐l����������Ȃ蒆������������o
����A�Ƃ����̂��I���炵���ł��ˁB��ɋ������}���[�V�A�A�x�g�i���ӂ肪���̐i�o��ɂ�
���Ă��Ă���l�ł��B�E�E�E�u�������{�v�͂ǂ��ɍs���Ă��܂����̂ł��傤���E�B
���́A�ɋ߂��������S�z�ł��B
�����ԍ��F8283666
![]() 0�_
0�_
�y�͂��߂Ɂz
�@���B�͎s��ɏo����Ă���S�ẴI�[�f�B�I�@��ɂ��čw�����Ď���Ŏg�����Ƃ͂ł��܂���B�������A���ۂɂ͎���Œ����Ԏg���Ă݂Ȃ���Ηǂ������͐�ɔ���܂���B�������I�[�f�B�I�̈�Ԃ̖��_�ł��B�@��w���͂قƂ�ǃo�N�`�ɋ߂��s�ׂł���A�ʎZ����Ε������ςȂ��A���̏ꍇ�A�����ɕ���������ł��܂��B
�@���u��A�N�Z�T���[�����ꂱ��ς��ĉ��̕ω����̂��y���ނ悤�ȁA�����������I�[�f�B�I�̊y���݂��낤���Ǝv���܂����A�{���e�͂����瑤�̚n�D�ɂ͐G��܂���B�u���y����i�Ƃ��ẴI�[�f�B�I�v�ł���A�u���̗��z������������Œ�o���Ă���l�v��ΏۂƂ����ӌ��ł��B
�y�����Ԃ��Ȃ��I�[�f�B�I�z
�\�j�[�̃f�W�^���A���v�s�`�|�c�q�Pa���w�����ĂR�N�A�X�s�[�J�P�[�u���̑I��Ɏ�Ԏ��A���̃|�e���V�����̔������o���Ȃ���������������܂��B��ʘ_�Ƃ��ĂP�O�O���~�̃A���v�ɂ͑����č����ȃP�[�u���ł��傤���A���ꂱ��ύX�����������A0.6�o�̓��P���i�ʏ̃`���C���P�[�u���A�V�O�~�^���j���ŗǂ̌��ʂł����B�R�N�ԂłQ�O���~�]���
�r�o�P�[�u���Ƃ��̔��i�Ƀ��_�g�����܂����B���Ɨ��Ƃ��Ă͑Ó���������܂��A���Ԃ̖��ʂ͉����ł�����݂���܂���B�X�ɒNj�����x�X�g�}�b�`�P�[�u���͂��邩������܂��A����ȏ���H��f�r���悤�ȋ��s�͂������Ȃ��ƐɎv���܂��B�R�N�Ԃɂ��킽����s�̈���Ƃ��Ď����M�̖��w�E���m������A����͔ے�ł��܂���B�o����
���o���Ɗw�₪����ΓK�ȑΏ����u���ɏo�����͂��ł����A���[�g�������萔���~�̃P�[�u�����V�O�~�̂��̂ցA�o�C���C���[���V���O�����C���[�ցA�A�R���o��Y���O���P�O�~�̔ėp�i�ցA������w��I�ɐ�������i�������j�ƌ����Ă��A�ӂ�肪���Ȃ����A�Ȃɂ����S��Ƃ��Ĕ[���ł��Ȃ��B�����̕��X�͓����悤�Ȃ��o�������邩�Ǝv��
�܂��B�o�J�Șb���ł����A�������h�ȃP�[�u���Ń`���C���P�[�u���Ɠ��������o�������B��Ȃ����Ƃł����A�����v�����̂������ł��B
�@�������b�͂���ŏI���܂���B�P�[�u�����x�̘b���Ȃ�l����ے肳�ꂽ�悤�ȃV���b�N�͂���܂��Asonic impact 5066�f�W�^���A���v�i�������i�W�O�O�O�~�j�̉����Ɏ���A���ƃI�[�f�B�I�Ɋւ������A�N���M�p�o���Ȃ��Ȃ�܂����B���̓W���Y����ɒ����܂���JBL S4800��N�X�Ɖ̂킹���̂�TA-DR1a�ł͂Ȃ� sonic impact 5066�������̂ł��B
�y�K�������s�A�I�[�f�B�I�z
�@����������Ȃ����͂����ł����s���d�˂܂����Bsonic impact �ɕt�����Ă����̂̓X�C�b�`���O��AC�A�^�v�^�[�������̂ŁA�l������ō��̃p�[�c��p���ăf�B�X�N���[�g�ň��艻�d���삵�������܂����B���ʁA�t��sonic impact�͐��ʂ������AS4800�͉̂�Ȃ��Ȃ�܂����B���̌��ہA��Âɍl����Γ�����O�̂��ƁA�������ڂ̑O�Ɍ��ۂƂ��ē˂������Ȃ���Δ[���ł��Ȃ��������B�@�Ԉ���Ă���A�����Ȃ����Ƃ��A�Ƃ̔F���������Ă��s�����}���ł��Ȃ��A���̐S����ԁE���̍s���p�^�[���͖��ł̃W�����L�[��A�A���\�s�E�l�ƂƊ�{�I���_�\���ɂ����ĕς��Ȃ��A�܂�ނ�Ƌ��ʂ���DNA���̂��̂���Ȃ����Ɓc�A�V���b�N�ł����B
�y���_�z
���̎�����ߖڂƂ��Ď��͖ڂ��o�߂܂����B���y���y���ނ��߂ɂ͍����i���i�o�J�ȒP��ł����j�s�����ƐM���Ă��܂������A���ꂪ�ԈႢ�ł��邱�Ƃ��B���_�Ƃ��ẮA�@��͌y���A�������A��������I�Ԃ��ƂŁA�]�͉����Ŏ��̎�������J������āu���y�v���ɍs�����Ƃ��c�B���ꂪ�킩�����̂ł��B
�y�����Ԃ����I�[�f�B�I�z
�@sonic impact �̋��P��TA-DR1a����TA-F501�@��ύX���鐄�i�͂ɂȂ�܂����B�isonic impact ���g��Ȃ������̂̓����R���Ɠ��͌n���̕s�������R�j�������낢���̂�TA-DR1a�ł͕K�v�s���Ɏv��ꂽTAOC�̃��b�N�͍��ł͂ǂ����ł������Ǝv���邵�A���[�J�̃}�X�^�[�ׁ[�V�����Ƃ����v���Ȃ�VRDS���J�����蕥���A�������L���Ă����X�s�[�J�Ȃǂ��S�Ď�����Đg�y�ɂȂ�܂����B�������r�S�W�O�O�����͑��肪������Ȃ��̂ł��̂܂܂ɂ��Ă��܂��B�ŁA�o���͂Ƃ����ƁA���������傫���𑜓x���ቺ����ʂ��Â��ł����A���������ɂ͔����Ƃ������C�̗ǂ�������A�Ȃɂ����Ԃɂ�����ĔY�ނ��Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ċ炪�����炩�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�@��蕥�������Ń\�t�g���R�O�O�����炢�]���ɔ�����̂����\�ȍK���ł��B�@
�y�Ō�Ɂz
�@�I�[�f�B�I�������Ƃ��Ē蒅���Ȃ����R�͖��m�ł��B�܂����������̂Ȃ��l�����U��Ԃ点�A�����~�܂点�鉹�A�������������C�̗ǂ������{���ɗǂ����ł���B���������������F�������������[�U���ߋ��ɂ͂������܂����B�Ƃ��낪���݂ł͍I�݂ȕ��̂��g�����Ȃ��A�����ɂ͂�������Ȃ��ˋ�̉���J�߂�����]�_�ƃ}�W�b�N�Ƀ��[�J�����[�U�����������Ă��܂��Ă��܂��B�H���A��ʂ��A�������A�𑜓x���A��C�����A�C�z���A���X�B����Ȃ��̉��y�̗ǂ������̃G�b�Z���X�Ƃ͑S�����W�ł�����]�ł��邱�ƂɋC�Â��Ă��Ȃ��B����ł̓I�[�f�B�I�����̒蒅�͂��납�A�َ��̂��́A�~���̍����ϐl�̎�Ƃ��āA�܂��܂��ޗ��֗��������ł��B
�@�������������i�Ƃ��ẮA���̌��C���i��̂͂P�ɂ��Q�ɂ��X�s�[�J�̔\���ł��邱�ƁA�����Đl�̐S��a�܂���̂͋������Ȃ����R�Ȓ��ł��邱�ƁA���̂Q�_�ɂ��āu���������Ɓv�Ƃ��ĔF�m���邱�Ƃł��B����Ĕ\���K�������{���A�X�Tdb�ɖ����Ȃ��X�s�[�J�̔̔��֎~�y�сA�R�[�����̒��a�K��������ׂ��Ǝv���܂��B�i�\���̗��z�͂P�O
�Odb�ȏ�j����ɂ���ăA���v�͑啝�Ȑv�ύX�i�o�͂̒ጸ�j���\�ƂȂ�͂��ŁA�o�͒ጸ�͂�����Ӗ��ō��i���ቿ�i�̎����ɍv������͂��ł��B���\���X�s�[�J�{���o�̓A���v�̉��A�������ׂ��ڕW�����m�ɂȂ���Ƃ͊ȒP�ł��傤�B�f�W�^���̓A�i���O��肠����_�ň��|�I�ɗD��Ă���̂ł�����B
�����ԍ��F8291667
![]() 9�_
9�_
�@130theater����A����ɂ��́B
�@�ǂ����ē��{�̑���Ƃ��������͂��ߊC�O�ɐ��Y���_��u��������̂��B�������Ⴂ�בփ��[�g�ƃR�X�g�ʂ̗L����������܂����A����ȊO�ɐŋ���Ƃ����v��������悤�ł��B���s�Ő��ł͊�Ƃ̊C�O�q��Ђ����������v�͐e��Ђ̍����̎����ƍ��Z�����z�ʂŖ@�l�ł������炵���ł��B������C�O�̗��v�������ɖ߂��Ȃ��ł����A���̕��܂�܂�C�O�̒Ⴂ�ŗ����K�p�����킯�ŁA40%�Ƃ������{�����̍����@�l�ŗ����瓦�����̂ł��B������̂܂܂ł͎����͓��{�����ɂ͓����Ă��܂���A���Ƃ�������ׂ��Ă����������͂��납�����ɂ����f����܂���B�����́u���Ƃ̊����i����ђ���j�����͍D�i�C�B���ď����̓h�c�{��ԁv�̈���Ƃ��Ȃ��Ă���̂ł��傤�B
�@���́u�i�ڐ�́j�ׂ��̂��߂Ȃ�Ή�������Ă������v�Ƃ������������ʂ�悤�ɂȂ����̂́A�������̒|�������ɂ��o�ϐ���̂����ł��傤�B�s�Ǎ������������̍����ƌ��Ȃ��A�����ł������̎ア��Ƃׂ͒��ׂ����E�E�E�E�Ƃ����A�z�ȃX�^���X����l�����������ʁA��Ƃ͒������I�Ȃ��Ƃ��l���Đݔ���l�ނɓ���������A�Z���I�Ȓ����ׂ̖��������ł��傫�����āu�s�Ǎ��v��������邱�Ƃ������悤�ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B������������ۂ͖c�傾���ǒ����͂قƂ�Ǐグ�Ȃ��B�����ł��R�X�g�̈����������Ő��Y�B�o�����X�V�[�g�������ł���������ΐ،��݂̂悤�ɒׂ���Ă��܂��E�E�E�E�Ƃ̋����ϔO�Ɏ����Ă���̂�������܂���B
�@�W�T�C�g�ɂ��A���{��Ƃ̊C�O���Y���͊؍���GDP�����傫���Ƃ��B���̕��A�{���Ȃ���{��GDP�ɐςݏグ����ׂ��o�ϊ������������Ă���Ƃ������Ƃł��B���Ƃ������Ő��Y���Ă����Γ��{�͕s�i�C�Ȃǁu�ǂ��������v�ł������ł��傤�B������ɂ���A���������������ٗp�����������Ă܂ŊC�O�Ŗׂ������v�ɑ���u�{�������ׂ��ŋ��v�܂Ŏ̏ۂ��A��ʏ����ɑ������ł̐��グ�𐭕{�ɗv�����Ă���悤�ȓ��{�o�c�A�̊��������o�[�ɂ́A�v�킸�u���v�Ƃ̃��b�e����\�肽���Ȃ�܂��B
���\�j�[��AV�A���v�̃t���b�O�V�b�v�@��
���}���[�V�A���ł��B
�@�����ł����B�q�h���ł��ˁB���y�i�Ȃ�Ƃ������A�n�C�G���h�@���炢�����̍��ō��Ȃ��̂ł��傤���BSONY�̑n���ҒB�̍������z�͂ǂ��֍s���Ă��܂����̂��B����ȂɊC�O���Y�ɍS�����Ȃ�A�J�^���O�ɓ��X�Ɓu�}���[�V�A���I�v�Ƒ发���A�u�����Ő��Y�����ꍇ�ɔ�ׂĂ��ꂾ�������\�I�v�Ƃ����f�[�^���炢�ڂ��Ăق������̂ł��B�{���Ɂu�������{�v�̍��オ��Ԃ܂�܂��ȁB
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�����ԍ��F8292406
![]() 1�_
1�_
�@inouesp����A����ɂ��́B�͂̂��������������݁A�L���������܂��B
�@�u���y���y���ނ��߂ɂ͍����i���s�����Ƃ����̂́A�ԈႢ�ł���v�Ƃ������t�́A�����悭�s���f�B�[���[�̓X��������悭�����܂��B�������͊m���Ɏ����ǂ����ǁA���̃p�t�H�[�}���X�͖{���ɒl�i�Ɍ����������̂Ȃ̂��A�����������[�U�[���g�����Ȃ���̂��A�������������Ƃ��ɂ��āu����������v�Ƃ�����������������Ȃ��V���b�v����G���́u�����Ă悵�v���Ǝv���܂��B���Ɂu100���~�ȉ��̃V�X�e���ł͉��y���y���ނɒl���Ȃ��v�ƌ����������^�x�e�����]�_�Ƃɂ͎E�ӂ��o���Ă��܂��܂����i���j�B
�@�����āA��X�I�[�f�B�I�t�@�����ׂ�₷���p�^�[���Ɂu�\�����𐂂��v�Ƃ��������Ȃ�����܂��B�𑜓x�E���x���E�c���E��ʊ�etc.�Ȃǂ́A�f�l����̈�ʓ��킩��͊��S�ɘ��������p������˂���Ă��܂������ł��B���̈Ӗ��ŁA�O�̃X���b�h�ł��q�ׂ܂������A�w�^�Ȕ\��������ؒʗp���Ȃ��������[�U�[����̏����ɁA�I�[�f�B�I���[�J�[�͐�ւ���ׂ��ł��B
�@�\���ɂ��łł����A���j�b�g�̍\�����̂Ƃ͈Ⴄ�悤�ɂȂ��Ă����Ƃ͂����A�ŋ߂͒�\���E��C���s�[�_���X�̃X�s�[�J�[����������Ǝv���܂��B�u���\���X�s�[�J�{���o�̓A���v�v�Ƃ����\������ʉ�����A���[�J�[�̔n�������u�X�y�b�N���֎�����}�[�P�e�B���O�v���Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�����g���Ă���SOULNOTE��sa1.0��10W×2��������܂��A�K�i�ʂō��v����X�s�[�J�[��I�ׂΉ��ʖʂʼn������͂���܂���B����ȃt�b�g���[�N�̌y�����i����������o�Ă��ė~�����ł��B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�����ԍ��F8292416
![]() 0�_
0�_
�@�v�X�Ɂu�������̃I�[�f�B�I�@��v�ɂ��ď����Ă݂܂��B����̃l�^��NIKKO�ł��B���K�d�@��1935�N�ɑn������A��ɑD����q��@�Ɏg����z�d�ՂȂǂ���|���Ă��������ł��B���݂��d�핔�i�A���Ƀu���[�J�[�Ɋւ��Ă͋ƊE�̑��ł��B���̃��[�J�[�͐̃I�[�f�B�I���i������Ă������Ƃ�����܂��B
�@�����[�X���Ă����̂̓A���v�ނŁA���R�{���Ɩ����������`�ł̓W�J�������̂ł��傤�B�Z�p���[�g�A���v���܂߂ă��C���i�b�v�͑����Ă����悤�ł��B
�@�������A���͓��Ђ̐��i�������Ƃ��Ȃ���A�������������Ƃ�����܂���B����ł��C�ɂȂ郁�[�J�[�Ƃ��ċL���Ɏc�����̂́A�v�����C���A���v��A-300��AM/FM�`���[�i�[��T-300�̑��݂ł��B70�N�O���ɔ������ꂽ���i�ŁA��������͒��������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�I�[�f�B�I�G���ɍڂ��Ă����L���ƁA���[�J�[��������J�^���O�͂��������C���p�N�g���傫�������ł��B
�@A-300��29,800�~�Ƃ����G���g���[�N���X�Ȃ���A��i�o�͂�26W×2������A���@���t���T�C�Y�ł����B�����ׂ��͓��o�͒[�q�̑����B�m�����̃J�^���O�ɂ́u���̉��i�т̐��i�����߂�悤�ȃI�[�f�B�I���S�҂ɂƂ��ẮA������K���݂��Ă��܂��悤�ȃ��A�p�l���v�Ƃ������悤��搂����傪�ڂ��Ă����悤�ł����i�j�A�m���ɓ���N���X�̃I�[�f�B�V�X�e���̒��j�ɂȂ�悤�ȋ@�\���ւ��Ă��܂����B�`���[�i�[��T-300�͒艿2���~�قǂł������A������t���T�C�Y�Ō������͑��Џ㋉�N���X�ƃ^�����悤�Ȃ��̂������悤�ł��B
�@A-300�̐�厏�ł̕]���́A���̃R�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����͂��Ƃ��A���Y�i�ł͒������u�_�炩���i�̂������v����ۓI�ł���E�E�E�E�Ƃ������̂������݂����ł��B���̃��[�J�[�Ƃ͈Ⴄ�Ǝ�����ł��o���Ӗ��ł͂��́u���h�H���v�͓��R�ł����A���݂����������F���������A���v�����݂��Ȃ������ɁA��x�͒����Ă݂��������Ǝv���܂��B���������A�����S�j�����̐��i���^���Ă����炵���ł��B
�@���K�d�@��1987�N�ɉ����@��̐��Y����P�ނ��Ă��܂����A�s���A�E�I�[�f�B�I�̕\���䂩��͂����肸���ƑO�ɑޏꂵ�Ă����݂����ł��B�g�����X�̃��[�J�[�ł�����SANSUI���ꐢ���r�����悤�ɁA�u���[�J�[�̍���ł�����NIKKO�����ł��I�[�f�B�I�@�����葱���Ă���A�Ǝ��̒n�ʂ�z���Ă����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8296511
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
���E�������A�V�X���̐V���ȓW�J���y���݂ɂ��Ă��܂��B
�g�ݗ��Ă̂݊C�O�Ƃ��������i�͗��Ƃ܂��Ȃ��قLj��Ă��܂��ˁB
�J���͒����̖ʂ�����܂����A�łƂ̊W��������l�ł��B
�Y�ƗU�v�ٗp�m�ۂ̐���ł��傤���A�����i�i�g�ݗ��ēr���Ȃǁj���H�͔�ېłƂ��鍑�����邻���ł��ˁB
FENDER�̃M�^�[��x�[�X�ȂǃG���g���[���i�т̊y��Ȃǂ̓��L�V�R�ʼn��H����P�[�X�������Ă��܂����B
�I�[�f�B�I�Ɋւ��Ē��߂Ă݂�Ƒ�p�ƒ������X�s�[�J�[�E���j�b�g�̐������_�ƂȂ��ċv�����ł��B
JBL��SCAN-SPEAK���͂��߃��W���[�ǂ���͂������Ă���2�̍��Ő������Ă��܂��B
���̓m�E�n�E���p���i�ƃR�s�[�i�t�F�C�N�j���i������2�̍����o���Ɏs��Ɉ��Ă��܂������Ƃł��傤�B
SCAN-SPEAK��OEM���[�J�[�iUSHER-AUDIO)���قړ��ӏ��̃m�E�n�E���p�i�����А��i�Ƃ��Ĕ̔����Ă��܂����A
DYNAUDIO�̓t�F�C�N���i���J�[�E�I�[�f�B�I�s��Ɉ��X�s�[�J�[�E���j�b�g�̔����Ƃ�����߂�v���ɂ����Ȃ�܂����B
��p�ƒ����́i���ď�������݂��j��@�R�s�[�ɑ���ӎ��������S���قȂ�܂����A
���앨�⌠�����ɂ����Ă��@���I���r�_���炵�ĕʎ������ʐ��E�Ȃ̂ŁA
����A�I�[�f�B�I�@��̖ʂł��l�X�Ȗ�肪�����邩������܂���ˁB
inouesp����A�͂��߂܂��āB
����͂⎨���ɂ��Ƃ����̂��A�䂪�g�Ɋ����邨�b����ŋ����[���q���v���܂����B
���X�Tdb�ɖ����Ȃ��X�s�[�J�̔̔��֎~�y�сA�R�[�����̒��a�K��������ׂ��Ǝv���܂��B
���i�\���̗��z�͂P�O�Odb�ȏ�j����ɂ���ăA���v�͑啝�Ȑv�ύX�i�o�͂̒ጸ�j���\�ƂȂ�͂��ŁA
���o�͒ጸ�͂�����Ӗ��ō��i���ቿ�i�̎����ɍv������͂��ł��B
���ʗ�������Ȃ��[���ɓ������X�s�[�J�[�M�@�̂��Ƃ��A���v�Ŗ炵�Ă���܂��i�ꊾ�j
������G�l���M�[�����l���鎞�A�����̃I�[�f�B�I�@��͒P�Ȃ�Q�ɂ����Ȃ��Ă���܂���B
���ő�����˂邪���Ƃ������̃u�b�N�V�F���t�́A�F�A���̊���Ɋ܂܂�Ă��܂��܂��ˁB
���̏��L�@��͂܂��Ɍ�@�x�̋��i����E�E�E
���܂����������̂Ȃ��l�����U��Ԃ点�A�����~�܂点�鉹�A�������������C�̗ǂ������{���ɗǂ����ł���B
�����������������F�������������[�U���ߋ��ɂ͂������܂����B
�v�X��6�C���`1���̃t�����g�E���[�h�z�[����^��ǃA���v�Ŗ炵���N�̉p���o���h���@�����܂����B
�ƂĂ����X�����z�������܂��������W�I��ꖂ���Ē����Ă��������v���o�������ƂĂ��y���������ł��ˁB
�����ɂ��߂��߂��������h���̋�C�≔�F�̋�̈�ۂ������āu����͈Ⴄ�v�Ƃ�����a���������܂����B
����ɖ߂蓯���A���o�����Â�KEF�Ŗ炵�����āA�u�X�R�[���I�v�Ɖ��������邱�Ƃ��K�������ǂ��Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂����B
inouesp����̒H�蒅���ꂽ�l�����Ƃ͂����Ԃ�قȂ邩������܂��A
�A�[�e�B�X�g���A���o�����쎞�ɗ��z�Ƃ��čl�������F����ɏ����ł��߂Â��č�i�����\�������E�E�E
���z�ƌ����̃M���b�v���傫�߂��܂����A���ꂪ���̃I�[�f�B�I�ɑ��錴���I�ȑz���ł��B
�^�C�v�̈قȂ�I�[�f�B�I�����������p�ӂ��邱�ƂŎ����g�̗~���������Ƃ��Ă��܂��B
�����ԍ��F8301844
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ��߂܂��āB��������Q�������Ă��������Ă������ł��傤���H
�u���v�Ɋւ��āA�������\����̘b�ł��B
������ÃI�[�f�B�I�@��������Ă��邨�X��Luxman SQ38FD���@�����܂����B
�Ȃ���́A�ƁB�Ƃ�ł��Ȃ��Ռ������̂������Ȋ��z�ł��B
�Ȃ�ĉ��̂��鉹�Ȃ낤�A�ǂ����Ă���Ȃɔ]�݂��ɐ��ݓ����Ă���̂��낤�Ƃ��������ق�Ă��܂��܂����B
���炭���Ă���C�������̂ł����A���̂悤�ȉ��A�̂͂����Ƒ����p�x�ŕ����Ă����悤�Ɏv���܂��B�e���I�[�f�B�I�D�����������߁A���ӋC�ɂ��c���̍����獂���I�[�f�B�I�̉��ɂ͐e����ł����f���Ȃ̂ł����A���������Ώ��������ɕ������I�[�f�B�I�̉��͂���Ȃ������ȁA�ƋL�����h�����̂ł��i�������SQ38FD�Ƃ����ӂ�[���A���v�ł���ˁj�B
������̃I�[�f�B�I�X�ɍs�����Ƃ��̂��Ƃł����A�ǂ������܂�S�ɂ������肭�鉹��t�ł鐻�i���Ȃ������̂���ۂɎc���Ă��܂��B�ꉹ�ꉹ�̉������M�X�M�X�ƝP��o����A�s���������o����悤�Ȏ咣�̋������������u���C�̂Ȃ��v���B��肭�g�����Ȃ��Đ\����Ȃ��̂ł����A��L�̂悤�Ȉ�ۂ��Ă��܂��܂����B
�����v���Ɂi�����܂œƒf�ƕΌ��ł����j�A���̂Ƃ���̃I�[�f�B�I���i�̖ڎw���Ă�����̂́A���y�Đ��ł͂Ȃ������Ƃɂ������������Ƃ������ƂɕΈڂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�̐S���������Ȃ��̂ł��B
�Ⴆ���Ă̑�I�y���̎�Ƃ����̂́A�ǂ������Ă݂�Ƃ��قlj̏��Z�p�ɒ����Ă���킯�ł͂���܂���B�剉�t�Ƃ��R��ł��B�Ƃ��낪�A���݊���̎�≉�t�Ƃ���قNJ���������̂�����܂��B����݂͂�Ȃ��K�����������悤�ȋZ�p��O�ɏo�����y�ł͂Ȃ��A���̉��t�Ƃ̐l�Ԗ������݈��Ă�������ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
����A�̐S���鉹�y��t�ł鐻�i���o�Ă��邱�Ƃ����҂������ł��B
�����ԍ��F8304194
![]() 5�_
5�_
�@���v���Ԃ�ł��B�V�X���ł��Ă���ł��ˁA�ŋߎd�����Z�����Č��Ă��܂���ł����B
�@�ŋ߂͖{���ɒ������͂��߃A�W�A�̍��X�̐��i�������܂����ˁB���̍��X�̔��W���l����Ɨǂ����ƂȂ̂ł����A���{�̍�����l����Ɣ����ȋC�����܂��B�o����Γ��{�̊�Ƃ������̐��Y���_�ƊC�O�̐��Y���_�̏Z�ݕ�����������Ƃ��Ăق����ł��ˁB
�@inouesp����͂��߂܂��āA���Ȃ�M�̂��������������݂ł��ˁB���܂ł̌o���������܂ł�����̂�������܂��A�����f��I�߂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�m���Ɍ��C�̗ǂ����i�o�`�I�H�ȉ��j���D�܂�������������Ⴂ�܂����A�����łȂ����������Ǝv���܂��B
���Ȃ��Ƃ����͈Ⴂ�܂��B���Ȃ݂ɁA���̎g���Ă���V�X�e���́AAMP musical fidelity��A3.5CR CD ��A3.5CDP SP HARBETH��Monitor30���g���Ă��܂��B�܂��܂����z�̉��i���ɂƂ��Ắj�Ƃ܂ł͍s���܂��A����Ȃ�ɂ͖������Ă��܂��B
����ƁAS4800��SONY��TA DR1a�Ŗ炵����Ȃ��ƌ������Ƃł����A�������Ȃ��̍D���ȉ��F�ł͂Ȃ������ƌ��������ł͂Ȃ��ł��傤���H�ȑOS4600��TA DR1a�ɂĎ��������o�����猾���Ə\���炵�����Ă���Ǝv���܂��B����TA DR1a�͊m���Ɍ��C�̗ǂ����ƌ�����艐��������A�i���O�I�ȉ��������ƋL�����Ă��܂��B
����ƍŋ߂̃X�s�[�J�[�͔\���̒Ⴂ���f�����m���ɑ������ł������\���̃X�s�[�J�[���������݂��܂��B���ꂼ��̃��[�U�[�����ꂼ��̎g�p�ړI�╷�����A�D�݂̉��ȂǂŁA�I�ׂ�ƌ������Ƃ̂ق����������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�������\���̃X�s�[�J�[�������̐��̒��ɑ��݂��Ȃ���ǂ����Ă��傫�ȃE�[�t�@�[���g��Ȃ���ΖL���ň������܂����ቹ�Ȃǂ̂��߂܂���B���̂悤�ȃX�s�[�J�[��������Ɛݒu�ł�����̕��͂����̂ł����A���̓��{�ɂ��̂悤�ȕ������������Ȃ�l����̂ł��傤���H
���͉��y���̂ɂ���Ȃɓ���l����K�v�͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��A�l���ꂼ��D�݂��Ⴄ���A������z�Ƃ��鉹���Ⴄ���A�����l�ł��N�ƂƂ��ɕω����Ă䂭���̂Ǝv���Ă��܂��B�I�[�f�B�I�@��͂���ɋ߂����邽�߂̎�i�ł����Đ������s�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�����o���邾����̕����ɏW������̂ł͂Ȃ����̍L���I�����̂Ȃ�����l�̎��R�Ȉӎv�őI�ׂ�悤�ɐF�X�Ȑ��i������Ηǂ��Ǝv���܂��B
�@
�����ԍ��F8308302
![]() 1�_
1�_
�����̌����Ȃ���c�_�ɂȂ�܂���̂ŁA�F�l�Ƌc�_�������͂���܂���B����������ɗ͂����߂ē��e���܂��B�P�U�Z���`�V���O���R�[���P���Œቹ�̗ʂƎ��łr�S�W�O�O����X�s�[�J�����̒��ɑ��݂���A�i���̃��C���V�X�e���ł��j���Ƃ��Љ���Ē����܂��āA�Ō�̓��e�Ƃ����Ē����܂��B
�@���ăE�G�X�^�[�����ڎw�������͌Ǎ��ŋC�������̂ł������A��������������܂ŕ������������Ƃ��A�ʂ����ėǂ������̂��H�@�^��ł��B�E�G�X�^�[�����ڎw��������ʂ̃A�v���[�`�Ŏ�������B�����l�����K���[�W���[�J�̘b�ł��B
�y�w��̂Ȃ����E�@Part1�A�����Ƌt���z
�X�s�[�J�[�V�X�e���i�Ȍ�r�o�ƌĂԁj�̃R�[�����͓ǂ�Ŏ��̔@�������͂���ɗނ�����̂��ł���A���ꂪ���y�������ɉ����Ă��邩�N���킩���Ă��Ȃ����A�������悤�Ƃ����Ȃ��B�I�[�f�B�I�ƊE�����ނ̈�r�����ǂ�A�f�W�^���v���[���̃w�b�h�z�������ɂԂ�����҂����ɕs���ǂȂ̂��A�G�W�\������̂܂܂�SP����葱���Ă���I�[�f�B�I�ƊE�ɂ��̐ӔC�̈�[������B
���Ƃ��}���V�����ȂǁA���͗��֘R���B�������R���N���[�g�ł����͓��߂��Ă��܂��̂ɁA�R�[�����ǂ�قlj��߂��邩�A�N�ɂł��e�Ղɑz���ł���ł��낤�B���̓R�[�����̂̉����ߗ��ɂ���B
�r�o���j�b�g�͑��Ɏ��t�����Ă��āA�R�[�������͔��̒��ł���B���̖�ڂ͗l�X�����A�R�[�����ʂ�������ꂽ���t���̉��́A������z���ނ����낤�Ƃ����̒��ŋ����A���˕Ԃ�A�c���̓R�[�����߂��đO�֔�яo���Ă���B�܂�A���̏ꍇ��X�̒������͐����̉��Ƌt���̎c�����Ƃ������������ł���B�������A�r�o�Ƃ��ė��_�I�ɐ������\���Ƃ����̂́A�R�[������O�ʂɓ��˂����u�����v�����̂ݒ��o�������̂͂��ł���B�u�R�[���͋t�����߂����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�A�Ƃ������Ƃ����j�b�g�Ƃ��Ă̍Œ�����ƒm��ׂ��ł���̂ɁA�����̂r�o�͂��̏d�v�ȓ��������Đv����Ă���B���Ƃ����@�ƌĂ��SP�������ɔ����ɒ������悤�ƁA�u�t���Ɛ����������������v�ł���A�Ƃ��������͒N���ے�ł��Ȃ��ł��낤�B�����������ɂ͂��������r�o�œ����͘_�c���ꌈ�肳���B�N���ǂ��l���Ă��w��̃J�P�����Ȃ��\���ł���̂ɁA�w�E�����P������ɂ����l�q�͂Ȃ��A�ُ���ُ�ƍl�����A�w�₪�w��Ƃ��đ��݂��Ȃ����E�A���ꂪ����I�[�f�B�I�r�o�ł���B������ł��x���Ȃ��BSP�ɗv������镨���I�v���́u�܂��R�[�����̖̂h�����v�ƒm��ׂ��ł���B
�y�w��̂Ȃ����E�@Part2�E�R�[���̕����U���z
�@�g�^������Œ@���Ɓu�o���o���v�Ƒ傫�Ȃ�����B����̓g�^�����̂ɍ������Ȃ��ׂ̋��U������������B�g�^�������̂Ȃ�u�R�c�v�Ɩ邾�����B���̃R�[���̓g�^���Ɠ����ŋ��U���A�䂪�ށA������U���Ɖ]���B������O�ł��邪�A�䂪�R�[�����琳�������g�����˂����킯���Ȃ��B�r�o���j�b�g�͒��S�Ƀ{�C�X�R�C��������A�O�������ăR�[���ʐρi���ʁj�������`�䂦�A���������𑝂��Ă��g�^�����ۂ�������邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�ޗ��͊w�Ƃ��āu�R�[���f�ʒ��S���f�ʂ������O���������\���v�łȂ���Ή����œ����{�C�X�R�C���ɃR�[���S�̂�Ǐ]�����邱�Ƃ͕s�\�ł���B�X�y�[�X�V���g�����i�ōޗ��͊w������Α��ė��Ȃ̂ɁA�I�[�f�B�I�̐��E�ł͕��R�Ƃ��������Ƃ���ɁA����I�[�f�B�I�̕������������B
�y�w��I�ɐ������r�o�z
�@�@�ȏ�Q�̃|�C���g�ɒ��ڂ����R�[�������͂���B
�@�@http://homepage3.nifty.com/kisystem/ki.html
�@ �����~�������̃R�[���ɃN�����߂������{���A�����ߗ��R���ȉ���B�������B�i���̃R�[����
�̓��ߗ���80���ȏ�j�X�ɃG�b�W���ɂ͘R�ꂽ���ˁA�z�������ݸނ������B
�A�R�[���f�ʂ𒆐S���Q�����C�O����0.3mm�Ƃ��A����ɕ��ˏ�Ƀt�����W��lj��A�l�������炢�ł��S���ό`���Ȃ��������m�ۂ����B����������ŐU���������V�~�����[�V�����ɂ����Ă��A�R�[���͑S���ό`���Ȃ��B��������g���ɐ��m�ɃR�[���S�̂��Ǐ]����ׁA�r�o�P�{�Ń��C�h�����W��B���B�E�[�n�[���c�C�[�^���s�v�A��ԁE�������炷�l�b�g���[�N�����R�s�v�ƂȂ����B����O�̂��Ƃ���O�Ɏ��s����́A�\���͋Ɍ��܂ŃV���v���ɂȂ邱�Ƃ̏ؖ��ƂȂ����B���ꂱ���������̌��������ɒ����ȗB��̂r�o�̒a���ł���B�A���A�R�[�������ʂ͑��Δ�r�łP�O�{�ȏ�ƂȂ�A�A���v�̕��S�͑������B
�y���������E�����������u�E�������l���z
�w��Ƃ��Đ������Ȃ��r�o�͉��Ă���A���������Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B�����ĉ�ꂽ�r�o�ɐ������A���v���Ȃ������ꂽ�����o��B������܂��ł���B�������ꂽ�r�o�ɉ�ꂽ�A���v���Ȃ��œ��v�I��@�Ńo�����X�����A���̌��ʂɈ���J����̂����̃I�[�f�B�I���B���̋������s�ׂ̖ʔ�����ے肷��킯�ł͂Ȃ����A�����Ɋw�₪�Ȃ�����܂�ɂ��c�t�ł��������ł���B�I�[�f�B�I�}�j�A�Ɉ��|�I�ɒj�������̂́A���̐��_�N��̒Ⴓ�ƁA����łR�����I��ԑz���͂��D��Ă��邱�Ƃ����R�Ƃ�����A������ł��x���Ȃ��A�܂��w��Ƃ��Đ��������u�őt�ł�A���������ł���Ƌ����Č��������Ƃ��ł��悤�B�B
�����ԍ��F8310425
![]() 3�_
3�_
�F����A�����́B
inouesp����@
�������̌����Ȃ���c�_�ɂȂ�܂���̂ŁA�F�l�Ƌc�_�������͂���܂���B
������������ɗ͂����߂ē��e���܂��B�P�U�Z���`�V���O���R�[���P���Œቹ�̗ʂƎ��łr�S�W�O�O����X�s�[�J�����̒��ɑ��݂���A
���i���̃��C���V�X�e���ł��j���Ƃ��Љ���Ē����܂��āA�Ō�̓��e�Ƃ����Ē����܂��B
�ǂ����ɑ������͂����炭�����܂ߊF����Ǝ��̍l�������������Ǝv���܂����A�܂������ے肷����������܂���B
�Ō�̓��e�ȂǂƋ炸�A�F�X�Ƃ��b�����Ē����܂���ł��傤���B
�o���Ɋ�Â��c�_�Ƃ܂ł͐\���܂��A�Q�l�ɂȂ�����h���ɂȂ�b��͂���Ǝv���܂��̂ŁB
�b�肪���������Ƃ̊��҂����߂āA�Ⴆ�E�E�E
�����Ƃ����@�ƌĂ��SP�������ɔ����ɒ������悤�ƁA
���u�t���Ɛ����������������v�ł���A�Ƃ��������͒N���ے�ł��Ȃ��ł��낤
�p�b�V�u�̃R�[���^�U���Ղ̃_�C�i�~�b�N�^�X�s�[�J�[�E���j�b�g�ɂ����Ă͂��w�E�̒ʂ�Ǝv���܂��B
�����������̂̌^�����قȂ�Ǝ���ς���Ă��܂��B
�Ód�t�B������R���f���T�[�^���{�����g�p�����A�N�e�B���^�X�s�[�J�[�ł͑O��ɂ��ꂼ�ꐳ���Ŕ���������̂�����܂��B
���@�ł����ł�����܂��AMartin �k�������� ASCENT�Ƃ����X�s�[�J�[�����C���Ɏg���Ă���܂��B
�����̎g�p�@�̓R�[���E�E�[�t�@�[�Ƃ̃n�C�u���b�g�ł������Ђ̃��C���i�b�v�ɂ͐Ód�t�B�����݂̂̃X�s�[�J�[������܂��B
http://www.us.martinlogan.com/speaker_intro/clx.html
APPGE��QUAD�̃R���f���T�[�^�X�s�[�J�[�����X���Ɛ\���グ�Ďx�Ⴊ�Ȃ��Ǝv���܂����A
�����̂��čl����ƃ_�C�i�~�b�N�^�X�s�[�J�[����������A�R�[�X�e�B�b�N�y��ɂ��߂��Ɠ��̕\�������܂��B
QUAD�͌��s�i�����K�ɗA������Ă���܂��̂ŁA�@�����܂�����A��x�A�������Ă݂ĉ������B
�I�[�f�B�I�t�@���삯�o������A�͂��߂܂��āB
�������v���Ɂi�����܂œƒf�ƕΌ��ł����j�A���̂Ƃ���̃I�[�f�B�I���i�̖ڎw���Ă�����̂́A
�����y�Đ��ł͂Ȃ������Ƃɂ������������Ƃ������ƂɕΈڂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���̐S���������Ȃ��̂ł��B
�������[�J�[����ɂ͎茵�����w�E�ł����A�X�y�b�N��J�^���O�E�f�[�^�ւ̕Ώd�X���͐@���Ȃ��ł��ˁB
���w�E�̒ʂ肾�Ǝv���܂����A�����ǂ����ʼne������Ă��܂��Ă��鎩�o�Ǐ���܂��B
inouesp����̐�̂��b�ɂ�����܂������A�����ʂɉ𑜓x�ɒ�ʁE�E�E
�u����艹�y���y���ނ��̂ł��傤�I�v�Ƃ��������������Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F8311648
![]() 1�_
1�_
inouesp�����́A�����x���Ȃ��̌������������ƌ����̂������Ă݂����ł��ˁB�����Ƒf���炵�����Ȃ̂ł��傤�B
���͉��y�����Ƃ₻�̂��߂̋@��I�т��w��ɂ������͂���܂���A�I�[�f�B�I�@��ɑ��Ă̒m���������܂ł���܂���A����Ȃ�ɐF�X�ȕ��i���y�W�̎d�������Ă������@��̊J�������Ă�����j�Ƃ��b�����Ă�����������F�X�ȋ@������������肵�܂������A������inouesp����̌o����m���ɂ͂Ƃ��Ă����Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�������y���y�������������Ƃ����v���͕����Ă��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ō���̂��߂Ɏ���Ȃ̂ł����@
�P�@�Ȃ��R�N�O��inouesp�����sony��TA DR1a���w�������̂ł��傤���H�iTA DR1a�̂ǂ������Ƃ��낪���ɂ����čw�������̂��j
�Q�@sonic inpact��TA DR1a�̈Ⴂ�͂ǂ�ȈႢ�Ȃ̂��H�i�ǂ����ǂ��D��Ă��āA�ǂ����ǂ�����Ă���̂��j
�R�@TA DR1a�̖{���̔����̃|�e���V�������o���Ȃ������Ƌ��Ă܂����A�Ȃ������v����̂��H�i�ǂ�����100%�̉������̂��A���������Ȃ炻�̂Ƃ��̃A�N�Z�T���[�ނ́H�j
�S�@���[�g�������萔���~�̃P�[�u�����V�O�~�̂��̂ցA�o�C���C���[���V���O�����C���[�ցA�A�R���o��Y���O���P�O�~�̔ėp�i�ւƂ���܂����{���ɐ������H�i���w�Ȃ��ߕ�����Ȃ��̂ł����Ȃɂ��Ȋw�I�ȍ���������̂ł��傤���A�o���邾���킩��₷�������Ă������������ł��B�j
�T�@�Ȃ�TAF501�ɕς����̂��H�i�ق��ɂ������ȃf�W�A���͑��X����܂������sonic impact�ƌ����A���v�̉����{���ɑf���炵���Ȃ班�����炢�ς킵���Ă�����������̂ł́H�j
�U�@�����̂Ȃ��l�������~�܂点�鉹�͖{���Ɍ��C�̗ǂ��������ł��傤���H�i���������傫���𑜓x���ቺ����ʂ��Â��ł����A���������ɂ͔����Ƃ������C�̗ǂ�������E�E�E�������������������Ăق��̉��͊ԈႢ�Ȃ́H�j
�V�@�f�W�^���̓A�i���O��肠����_�ň��|�I�ɗD��Ă���̂ł�����B��������Ԃ����̂悤�Œm��Ȃ��̂ł����ǂ����ǂ����|�I�ɂ�����Ă���̂ł����H���̍��܂ŕ����Ă����f�W�^���A���v�͊m����CP�ɗD�ꂽ���̂�쓮�͂ɗD�ꂽ���͑��X����܂������A�i���O�A���v��������_�ŁA���|����A���v�ɂ͂߂��荇���Ă��܂���B���Ȃ݂ɂǂ̗l�ȃA���v�Ȃ̂ł��傤���H
�W�@���C���V�X�e���Ŏg���Ă���X�s�[�J�[�̔\���ȂǏڂ����X�y�b�N�o����Ύg�p�A���v�Ȃǂ������Ă��������Ȃ��ł��傤���H
�ȏ㎄��inouesp����̏������݂����ė����Ɏv�����^��������Ă݂܂����B
�f���ƌ����̂͂��݂��̈ӌ�����̌���������ꏊ�ł������I�Ɏ����̈ӌ�����M�����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B������������I�ɂ��Ȃ��̈ӌ������M�����l�̈ӌ��⎿��ȂǕ����C��������C���Ȃ��ƌ����̂Ȃ�z�[���y�[�W�Ȃ�u���O�Ȃ�l�I�ɍ���Ă�����ł��Ă��������Ȃ��ł��傤���H�ς킵���Ƃ͎v���܂����A�����̎���ɓ����Ă�����������Ɛɖ]�݂܂��B
�����ԍ��F8311813
![]() 1�_
1�_
�G�k�Ƃ������Ƃł��̂ŏ��X���ז������Ă������������Ǝv���܂��B
�s�K�ł�����w�E����������Α��X�ɑގU�����Ă��������܂��i��
>�������[�J�[����ɂ͎茵�����w�E�ł����A�X�y�b�N��J�^���O�E�f�[�^�ւ̕Ώd�X���͐@���Ȃ��ł��ˁB
����́A���{�̃��[�J�[�i�Z�p�ҁj�Ƃ��������A��ʓ��{�l�ɑ��������鐫�i�H�̂悤�Ȃ���
�ɋN����������傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����̌f���̎���ł��ǂ������܂����A���ۂɉ����ȑO�ɃX�y�b�N�������Ȃ���
���邩��Ƃ��A����ȉ�H������Ƃ��A���������\��������Ƃ��������e�����\����܂��ˁB
���[�J�[�͂��̂悤�ȃ��[�U�[�̍w���S�𑨂���悤�ȁi�����j���i����邱�Ƃ��d��
���Ă���̂ł͂Ǝv���܂��̂ŁA��T�Ƀ��[�J�[�̐ӔC�Ƃ͎v���܂���ˁB
�X�y�b�N�╔�i�A��H�蕶��ɂ���̂͗ǔۂ͕ʂɂ��Ă���Ӗ��A���{�������Ǝv���܂��B
���ۂ̂Ƃ���A���������ăX�y�b�N���H�\���Ă���l�Ȃǂ��Ȃ��ł����A�t��
���������d�l�����特���ǂ��Ɖ]���l�͌��\�����Ǝv���܂��B
>�����ʂɉ𑜓x�ɒ�ʁE�E�E�u����艹�y���y���ނ��̂ł��傤�I�v�Ƃ��������������Ă��܂���
�l�I�Ɏv�����Ƃ�����܂��B
���X�������܂����AHi-Fi�n�i���̌��t�̈Ӗ��𐳂����������Ă���l���ǂꂾ�����邩
������܂��j�̉������y���ɖR�����A���I�ȉ��F�����y���������ƌ������ӌ��ł��B
�I�[�f�B�I�@��Ɠ��̉��F���������������^�ɉ��y���������̂ł��傤���H
���̏ꍇ�A���̉��t�̉��Ƃ͏��Ȃ��炸�Ⴄ���ƌ������Ƃł���ˁB
�ł�Hi-Fi�n�i�����iCD�ɋL�^���ꂽ���j�����Đ��j�͖{���ɉ��y�����Ⴂ�̂ł��傤���H
�l�I�Ɏv���̂͂ǂ��炩�ƌ����AHi-Fi�n�̕��������ɂ͋߂����ł���Ǝv���܂���
�Ⴄ�ł��傤���H
���ꂪ�ԈႢ�łȂ��Ƃ���ƁA�����ɂ��߂��������y�����Ⴍ�A�Ɠ��̉��F����������
�������y���������Ƃ������Ƃ͌��̉��t�̉��y����ے肷�邱�ƂɂȂ�A��������Ǝv���܂����B
Hi-Fi�n�̉����D�ށi���������ł����j�l���A���y���i�y���ށj�ۂɈ�X�ׂ������Ƃ�
�C�ɂ��Ȃ��番�͓I�ɒ������Ȃǂ���܂��AHi-Fi�n�̉����D�܂Ȃ��l�͏���Ɂi�ے�I��
�Ӗ������߂āj���̂悤�Ɍ����܂��B
���͓I�ɒ������͂���܂����A����͊�@���w������Ƃ��ɁA���C�ɓ���̊�@��I�肷��
���߂ɔ�r��������ꍇ�������Ǝv���܂��B
�ŏI�I�ɂ͒����Ăǂꂪ�ł��C�����ǂ����A�������I���ł��B
�����āA�����ɂƂ��ċC�����ǂ����͂ǂ�ȉ����Ƃ������ł����A���̋C�����ǂ��������
�����ŕ\������Ƃ����Ȃ�Ƃ������Ƃ��A�Ɖ]�����Ƃ������`�������ł��B
���ʁA�𑜓x�A������ʂȂǂ̌��t�́A�����܂ł��̂悤�ȏꏊ�ł��̊�@�̉�����
�`����ꍇ�Ɏg�����̂ł���A�����̃V�X�e���ʼn��y�����ɂ��̂悤�ȕ����͑S���C��
���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
�u����艹�y���y���ނ��̂ł��傤�I�v�́A�����܂Ŕے�I�Ȑl�����̈Ӗ������߂Č�����
����ɉ߂����A�D��Œ����Ă���l�ɂƂ��Ắu���y���y����ł���v�̂ł��B
�l�I�ȍD�݂Ŏ���̈قȂ�l��ے肷��悤�ȕ������͑��l��s�����ɂ����鎖������
�Ɖ]�����Ƃ����Y��Ȃ��B
Hi-Hi�n�ł��낤���A�����łȂ��낤���l�̍D�݂Œ����Ă���̂ł�����A�ǂ��炪���y��
������Ƃ��Ȃ��Ƃ��̋c�_���Ԃ��s�K���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8311970
![]() 2�_
2�_
�h���L�[�R���Ojr ����@����ɂ���
���₢���킹�̌��A�\���グ�܂��B
��inouesp�����́A�����x���Ȃ��̌������������ƌ����̂������Ă݂����ł��ˁB�����Ƒf���炵�����Ȃ̂ł��傤�B
�@�������A���ʂ̉��ł��B�����������퐶�������Ď��ɂ���A�����������肱��������A�@������A�f�ނƑf�ނ����������������R�ɏo�鉹�A�܂��̓��C�u��f��قȂǂ�PA�̉��Ȃǂł���A�ߓx�ɑ@�ׂłȂ����A�����Ȃ�����s���ȉ����܂܂�܂��B
�����͉��y�����Ƃ₻�̂��߂̋@��I�т��w��ɂ������͂���܂���A�������y���y�������������Ƃ����v���͕����Ă��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�@���u���y���y�������������Ƃ����v���v�ɏ��������͂Ȃ��Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ����͂��̂悤�l�������Ƃ͂���܂���B
���P�@�Ȃ��R�N�O��inouesp�����sony��TA DR1a���w�������̂ł��傤���H�iTA DR1a�̂ǂ������Ƃ��낪���ɂ����čw�������̂��j
�@���u�X�s�[�J��炷DAC�v�Ƃ�����厏�L���ɐG������ċ����{�ʂōw�����܂����B
���Q�@sonic inpact��TA DR1a�̈Ⴂ�͂ǂ�ȈႢ�Ȃ̂��H�i�ǂ����ǂ��D��Ă��āA�ǂ����ǂ�����Ă���̂��j
�@���D���A���Ƃ����̂́A���҂̑��Δ�r�ł��ˁH���Δ�r���Ă����̍s���̂ɈӖ�������܂���̂ŁA�\����܂��A����������r��web�������E���Ă��������A���݂܂���B�����ɑ��Ă̐�Δ�r�Ƃ����Ӗ��Ȃ�A�I�[�f�B�I�̉���TA DR1a�A���R�E�ɂ���i������Ƃ����Ȃ��j����sonic inpact�ł��B
���R�@TA DR1a�̖{���̔����̃|�e���V�������o���Ȃ������Ƌ��Ă܂����A�Ȃ������v����̂��H
�@�����Ƃ��Ƒf���̗ǂ��A���v�������̂ɁA���̑f���̗ǂ����킩��Ȃ���������ł��B�u�����v�Ƃ����̂́u���t�̂���v�ł��B
�i�ǂ�����100%�̉������̂��A���������Ȃ炻�̂Ƃ��̃A�N�Z�T���[�ނ́H�j
�@��������̈Ӗ����킩��܂���̂ŁA�ł��܂���B
���S�@���[�g�������萔���~�̃P�[�u�����V�O�~�̂��̂ցA�o�C���C���[���V���O�����C���[�ցA�A�R���o��Y���O���P�O�~�̔ėp�i�ւƂ���܂����{���ɐ������H�i���w�Ȃ��ߕ�����Ȃ��̂ł����Ȃɂ��Ȋw�I�ȍ���������̂ł��傤���A�o���邾���킩��₷�������Ă������������ł��B�j
�@���b�c�̃s�b�N�A�b�v����A�r�o�̏o���܂ŁA���̂̑������͂��������ǂꂭ�炢����̂ł��傤���H�r�o�̃{�C�X�R�C���܂Ŋ܂߂�Ƃ����ƂP�O�O���[�g���ȏ゠��̂ł͂Ȃ����H�Ǝv���܂��B�i�z���ł��j
���̒��łr�o�P�[�u���͂����������ł��B�����ς��āA���̏o�����ǂ��A�����Ɣ�r���邻�̍s���̂��Ȋw�I�ł͂���܂���B�ǂ���卷�͂Ȃ��A�����l����̂��Ȋw�I�ł���Ǝv���܂��B�������I���Ƃ��Ă͂͂��̂r�o�̉����߁i�J���j�Ɏg�p���ꂽ�P�[�u���ނ��g�����Ƃł��傤���B�u�r�o�̉����߂ɃA�R���o��Y���O�͎g��Ȃ����낤�v�����l���܂����B
���T�@�Ȃ�TAF501�ɕς����̂��H�i�ق��ɂ������ȃf�W�A���͑��X����܂������sonic impact�ƌ����A���v�̉����{���ɑf���炵���Ȃ班�����炢�ς킵���Ă�����������̂ł́H�j
�@���f�W�^�����̓A���v�v�ł��邱�Ƃ����R�ƁA�����R�����~���������̂����R�ł��B�u�Ȃ��v�Ƃ����P����g�p���ĒNjy���Ă����ƁA�����͒N�ł��ł��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA����P��ł�����ׂ�肢�܂��B
���U�@�����̂Ȃ��l�������~�܂点�鉹�͖{���Ɍ��C�̗ǂ��������ł��傤���H�i���������傫���𑜓x���ቺ����ʂ��Â��ł����A���������ɂ͔����Ƃ������C�̗ǂ�������E�E�E�������������������Ăق��̉��͊ԈႢ�Ȃ́H�j
�@�����C�̂Ȃ��A�����Ƃ��Ă��Ȃ��s���⌾���������蕷�����肵���Ƃ��A�y�����Ȃ�Ƃ͎v���܂���B�y�����Ȃ邩�ǂ�������Ƃ���Ύ��͂��ꂪ�������ƐM���܂��B
���V�@�f�W�^���̓A�i���O��肠����_�ň��|�I�ɗD��Ă���̂ł�����B��������Ԃ����̂悤�Œm��Ȃ��̂ł����ǂ����ǂ����|�I�ɂ�����Ă���̂ł����H���̍��܂ŕ����Ă����f�W�^���A���v�͊m����CP�ɗD�ꂽ���̂�쓮�͂ɗD�ꂽ���͑��X����܂������A�i���O�A���v��������_�ŁA���|����A���v�ɂ͂߂��荇���Ă��܂���B���Ȃ݂ɂǂ̗l�ȃA���v�Ȃ̂ł��傤���H
�@����ʘ_��\���グ�Ă���܂��B�f�W�^���́u�`���ƏC���v�ɂ���
�A�i���O��舳�|�I�ɗD��Ă��܂��̂ŁA�����Ő��\���ǂ��A�y�ʂȂ��̂��o����B���������Ӗ��̕��͂ł��B
���W�@���C���V�X�e���Ŏg���Ă���X�s�[�J�[�̔\���ȂǏڂ����X�y�b�N�o����Ύg�p�A���v�Ȃǂ������Ă��������Ȃ��ł��傤���H
�@���\���͋ɒ[�ɒႭ�A���炭85�����ȉ��B�A���v��3�i�����|�S�i�g�����X����EL34�^��ǁB���̓C���s�[�_���X����A������R���[���ɋ߂Â��邱�ƂŁA�r�o�̃C���s�[�_���X�ɊW�Ȃ��S��őш悪�m�ۂł���悤�ɐ�p�v���ꂽ���̂ł��B
�ȏ㎄��inouesp����̏������݂����ė����Ɏv�����^��������Ă݂܂����B
�f���ƌ����̂͂��݂��̈ӌ�����̌���������ꏊ�ł������I�Ɏ����̈ӌ�����M�����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B������������I�ɂ��Ȃ��̈ӌ������M�����l�̈ӌ��⎿��ȂǕ����C��������C���Ȃ��ƌ����̂Ȃ�z�[���y�[�W�Ȃ�u���O�Ȃ�l�I�ɍ���Ă�����ł��Ă��������Ȃ��ł��傤���H�ς킵���Ƃ͎v���܂����A�����̎���ɓ����Ă�����������Ɛɖ]�݂܂��B
��������������������Đ\����܂���B���͂Ŏv����`���邱�Ƃ͑�ϓ���A���Ɍ���݁A�����������Ƃ��ɂ͑�ϔ��܂��̂ŁA����ɂĂ����ي肢�܂��B
�@�@���I�[�f�B�I�Ƃ��������ɂǂ��Ղ�����ĂR�T�N�A���̂Ȃ��Ŗ�X�Ƃ��Ă������Ƃ��ł������ƂŋC�������y�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�F�l�ɂ�����܂��Ă͂���w�́u���y�̌���v�����F��\���グ�܂��B
�����ԍ��F8312108
![]() 3�_
3�_
redfodera����@����ɂ��́B
����ł����A�v���t�B�[����q�������Ē����܂����B
���̒��ɂ͎����悤�Ȏ�̃I���W����������悤�ŁB���ꂵ���v���܂��B
����Martin �k�������� ASCENT�ɂ��ẮA���O���炢�����m��܂���ł����B�������A�U�N�O�ɂ���}�j�A�̂���֖K�₵�A�A�|�W�[�Ƃ����R���f���T�[�r�o���R���Ԃ��炢�������Ē��������Ƃ�����A�r�o�̑��݂�S�����������Ȃ��i�r�o���Ȃ��I�j���̂������܂��Ɋ��������Ƃ�����܂��B�m���ɐ��U�����ɂ���A�����������Ǝv�킹����̂ł����B
Martin �k�������� ASCENT�ɂ��ẮA�C�ɂȂ�܂��B��������ȏ�@��ɂ����������܂��A�Ƃ��ŋߌ��S��������Ȃ̂ɁA�C��������炢�ł��܂��i���}�j
�����ԍ��F8312160
![]() 1�_
1�_
inouesp����v���Ȃ��ԓ����肪�Ƃ�������܂��B�����͕s���葽���̕��X���W�܂�f���ł��A���������ق��Ȃǂƌ��킸���ꂩ����ǂ�ǂ�ӌ�����̌����⎞�ɂ͔M���c�_�̂��Ƃ�����܂��傤�B���t�̂���ɂ�����Ȃǂ�����Ƃ͎v���܂�������Ȃ��ƋC�ɂ��Ă��Ă��d�����Ȃ����Ƃł����A���݂���100%�����������邱�ƂȂǂȂ��ł�����A�����ł�������������ׂɂ��ǂ�ǂ�ӌ��̌��������Ă����܂��傤�A��������w�ׂ邱�Ƃ������͂���Ǝv���܂���B���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
wakamatu181����͂��߂܂��ā@������́A���{�̃��[�J�[�i�Z�p�ҁj�Ƃ��������A��ʓ��{�l�ɑ��������鐫�i�H�̂悤�Ȃ��̂ɋN����������傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤��
���������v���܂��B���{�l�قǃJ�^���O�X�y�b�N�ɂ������i�����܂߂āj���������������ł���ˁB�����������낻��ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�Ƃ͎v���܂��B���{�Ƃ��������Z�p�ʂ�o�ϖʂł͏\����i���ɂȂ��Ă��܂����A���낻��J�^���O�X�y�b�N�����ɂ�����炸���̂��̖̂{���������Əd�������{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�[�̂悤�Ȃ��̂����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������ɗ��Ă���Ǝv���܂��B�����Z�p�͂�X�y�b�N�A�R�X�g�����ɂ�������Ă����A�K���߂������ق��̍��ɍ��̓��{�̒n�ʂ�D���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���̂��߂ɂ���X���܂ߓ��{�l�������ƈӎ����v����K�v������悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F8313130
![]() 2�_
2�_
wakamatsu181����@
���u����艹�y���y���ނ��̂ł��傤�I�v�́A�����܂Ŕے�I�Ȑl�����̈Ӗ������߂Č����Ă���ɉ߂����A
���D��Œ����Ă���l�ɂƂ��Ắu���y���y����ł���v�̂ł��B
���l�I�ȍD�݂Ŏ���̈قȂ�l��ے肷��悤�ȕ������͑��l��s�����ɂ����鎖������Ɖ]�����Ƃ����Y��Ȃ��B
��̃��X�ł͎����ŋ߃I�[�f�B�I�@����w������ۂɃX�y�b�N���H�ȂǂɕΌ����Ă������Ƃ����}�I�ɕ\���������̂ł��B
���t�����肸wakamatsu181������͂��ߊF����ɕs���ȑz���������Ă��܂��܂������Ƃ��l�т������܂��B
�I�[�f�B�I�@��̍Đ����ɂ܂�鉹�y���i����Ɠ��`�H�j�ɂ��Ă��b������܂������A
������ɂ��Ď��Ȃ�̍l�������q�ׂ����Ē����܂��B
�O���ł��l�ѐ\���グ�����Ƃ��ƁA�藣���Ă�������K���ł��B
��Hi-Fi�n�i�����iCD�ɋL�^���ꂽ���j�����Đ��j�͖{���ɉ��y�����Ⴂ�̂ł��傤���H
���i�����j�����ɂ��߂��������y�����Ⴍ�A�Ɠ��̉��F�����������������y���������Ƃ������Ƃ�
�����̉��t�̉��y����ے肷�邱�ƂɂȂ�A��������Ǝv���܂����B
�l�I�ɃI�[�f�B�I�@��̍Đ����ɂ�����X���ʼn��y���������Ⴂ�Ƃ�����ʂ◝���͂��Ă���܂���B
�����𒉎��ɍČ����悤�Ƃ�����̂�����A�v�T�C�h�̗��_�Ɉˋ��������������@�������A
���̋@��ōĐ�����Ƃ��̋@��Ȃ�ɉ��炩�̉���������Ƃ����A�������ꂾ�����Ǝv���܂��B
�����܂ߊe�l���ꂼ��̎����D�݂ɂ��������i��T���A�w�����A�g�p���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�܂��ǂ���ōĐ���������Ƃ����Ă��A�[�e�B�X�g�≉�t�҂̍�i��ے肷����̂ł��Ȃ��ƍl���܂��B
�A�[�e�B�X�g�≉�t�ƁA����T�C�h�����z�Ƃ��Ėڎw�������Ƃ�������Ă�������Ƃ����Ĕے肵�����ƂɂȂ�̂ł��傤���H
���m������AM���W�I�Œ����Ă��g�ѓd�b�ň��k���ꂽ�t�@�C���Œ����Ă����l�ł��B
���y������ʂ�́A�A�[�e�B�X�g�≉�t�ҁA�Ђ��Ă͍�i�ɑ��ėp������ׂ����t�ł����āA
�Đ�����Đ��@��̎�ނ�O���[�h�Ƃ́A�����A���W�ł���Ɨ������Ă���܂��B
�s���ȑԓx�ƎƂ��܂�����A�ȂɂƂ����e�͉������B
�����ԍ��F8314056
![]() 5�_
5�_
�F����A����ɂ��́B
�A���X�������������B
inouesp����@
������ł����A�v���t�B�[����q�������Ē����܂����B
�����̒��ɂ͎����悤�Ȏ�̃I���W����������悤�ŁB���ꂵ���v���܂��B
�����������k�ł��B
�ς��҂ł����A����Ƃ��X�������肢�v���܂��B
���A�|�W�[�Ƃ����R���f���T�[�r�o���R���Ԃ��炢�������Ē��������Ƃ�����A
���r�o�̑��݂�S�����������Ȃ��i�r�o���Ȃ��I�j���̂������܂��Ɋ��������Ƃ�����܂��B
Apgee���������ɂȂ��܂������I
���炭������`�̃p�[�e�[�V�����̗l�ȃV���o�[�E�t�B������CALIPER�ł͂Ȃ����Ɛ��@���܂��B
������ڍ��ꂵ�܂������A���F�A��̓͂��ʍ���̉E�E�E��ނȂ�Martin �k���������ɂȂ�܂����i��j
CALIPER�͋C���Ă̗D�����A���v�삾�Ƒ��|�����܂���A���Ȃ�̃h���t�@�������������ł��B
Martin �k�������������݂̓G���h�[�T�[������܂���̂Ōl�A�����邵���V�i�͍w���ł��܂���B
���[�J�[��HP���ς�ƁA�V���i���R���X�^���g�Ƀ��C���A�b�v���Ă��āA�����ւ���`�����X���Ȃ����v�Ē��ł��B
�t�������W1���I������Ƒ���Ƃ���Ŏ�����Ă��܂����낤���ƁA����Ƃ͂Ȃ��ɗ����ł��܂��B
�v�����f�����o�łȂ���Ď���X�s�[�J�[���A���X�A�쐬���Ă܂��B
�����w�{�Ȑv������Ƃ������{�I�Ȍ�����I�グ���Ă��A�l�b�g���[�N�ʼn��̑N�x�������Ȃ�܂�����E�E�E
�h���L�[�R���O�i������A���v���Ԃ�ł��B
�M�������ɁA��������͂����߂Ĕq�ǂ������܂����B
��musical fidelity��A3.5CR CD ��A3.5CDP SP HARBETH��Monitor30���g���Ă��܂��B
���������܂Ƃ߂��Z�b�g�A�b�v�ł��ˁB
���ǂ��F���ƖF���ȋ����Ȃ̂ɃV���[�v������߂��o�����z���ł��܂��B
A3.5�̓f�U�C�����G�x�Ōl�I�Ɏg���Ă݂����Ǝv�����v�����C���ł��B
�Ɩ��𗎂Ƃ��������Œ����������H�[�J���͊i�ʂȂ̂ł͂Ȃ����ƁE�E�E
�@�����܂�����A����A�C���v�������肢���܂��B
�����ԍ��F8314264
![]() 1�_
1�_
�@���炭���Ȃ������ɏ������ݐ����L�тĂ��܂��ȁB�������ɑS���Ƀ��X����̂̓L�c���ł�����(^^;)�A�o�������t�H���[���܂��B�܂��Aredfodera����A����ɂ��́B
�@�m��Windows95���o�n�߂����������ł��傤���A�x�m�ʂ��p�\�R���̕��ނ̒��B�您��ѐ������_���p�Ɉڂ������Ƃ��������ƋL�����Ă��܂��B���̍ۂɍw���S���̊������e���r�̃C���^�r���[�Łu9���ȏ���C�O����d����邱�Ƃɐ��������B����Ŕ̔����i�������Ȃ��ċ����͂��t���đ�ׂ����v�݂����Ȃ��Ƃ��В���ŏq�ׂĂ������Ƃ��v���o���܂��B���������[�̔̔�����ł́A�����s�ǂ����܂�ɂ������Ȃ������߁A�f�B�[���[�����[�U�[����������Ă��܂����B���ɑ�ʂɎd�����K�v�̂������@�l���[�U�[�͑�ςł����B���Ȃ݂Ɏ��̋ߐ�������ŁA����ȗ����Ђ̐��i���ʂɍw�����邱�Ƃ͂���܂���B
�@����ɕx�m�ʂ͑��Ђɐ�삯�Ē����́u�N��v��u���ʎ�`�v�����܂����B������̗p���������́u�O���[�o���X�^���_�[�h�ɑΉ�����A�V�����ٗp�`�Ԃ��I�v�Ƃ����Ƃ��̂����ɐ������Ă������̂ł����A���ʂƂ��ď]�ƈ��͈�N�P�ʂ̖ڐ�̂��Ƃ����l���Ȃ��d���������Ȃ��Ȃ�A�����ᗎ�������܂����B
�@�O���[�o�����Ƃ����̂́A�Z���I�ȗ��v������Nj�������@�_�̂��Ƃ炵���A����܂ł̐l�ނ�Z�p�̏��p��厖�ɂ��Ă������{���o�c�Ƃ͑��e��Ȃ����̂ł��B�x�m�ʂƂ������ʋ��t������Ȃ���A���܂��ɓ��{�̃��[�J�[�́u�ڐ�ׂ̖��v��u�ڐ�̊����v�ɍS�D���A�������I���B�W�����������������R�X�g�̒ጸ����Ɍ䎷�S�̂悤�ł��B
�@�I�[�f�B�I�ɂ��Ă��R��ŁA������v�Ɗ����i�����͖{���ł��Ƃ����Ă��A�C�O�ł̐��Y����ׂ̍��ȃm�E�n�E�܂ł͓`���ł��܂���B�Ђ���Ƃ���ƁA��������E�v�������̂����i�Ƃ��Č������Ȃ����A���邢�͏��i�Ƃ��Ċ������Ă��v�҂����҂��郌�x���ɋy�Ȃ��P�[�X���o�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�E�E�E�E����A��X���m��Ȃ������ŁA���łɂ���Ȃ��Ƃ͋N�����Ă���̂�������܂���B
���V�X���̐V���ȓW�J���y���݂ɂ��Ă��܂��B
�@�����炱���A�X�������肢���܂�(^^)�B
�����ԍ��F8315909
![]() 1�_
1�_
�@�I�[�f�B�I�t�@���삯�o������@���߂܂��āB
�@LUXMAN��SQ38�A���Ȃ�̂ɒ������L��������܂��B�܂�₩�ʼn��₩�A���ꂼLUX�Ƃ����T�E���h�ł����ˁB���ƑO�ɂ������܂������A�����ʂ��Ă������Z�̉��y���ɒ������Ă����Z�p���[�g�A���v��LUXMAN�̊Nj����ł����B�X�s�[�J�[��DIATONE�̃X�^�W�I���j�^�[�ł������A�Ƃ��������������Ƃ���Ă���DIATONE�����Ƀ}�b�^���ƃh���C�����Ă������Ƃ��v���o���܂��B
�@���݂̃I�[�f�B�I�̃g�����h�����x����M�C�����𑜓x�E�X�s�[�h���ɐU���Ă����̂́ACD���o�ꂵ�Ă��炶��Ȃ��ł��傤���B�A�i���O�Ɠ��̃g���[�X���̃m�C�Y��c�݂��������ꂽ���̃C���p�N�g�����܂�ɂ��傫���A���ꂩ��́g�\�[�X�ɓ����Ă��鉹���o���邾���Č���������h�Ƃ����������ɂ��[���ƍs���Ă���悤�ȋC�����܂��B
�@�������𑜓x����ʂ͍����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���ꂾ���ł͉��y�����Ȃ��Ƃ��������������ē��R�ł��B�ŋ߂̃A�i���O���R�[�h�̕������A����Ɗ֘A���Ă���Ǝv���܂��B
�@JBL��PARAGON�Ƃ����@�킪����܂����B�Ƃ����̐̂ɐ������I���܂������A���B���e�[�W�̃X�s�[�J�[�̑㖼���Ƃ��č��ł��m���Ă��܂��B���N�J�Â��ꂽ�I�[�f�B�I�t�F�A�ŏ��߂Ă��̉��ɐڂ��邱�Ƃ��o���܂����B�n�b�L�������āA�Â��W���Y�����点�܂���B�N���V�b�N��|�b�v�X�ł̓_���Ȃ̂ł��B�Â��W���Y�ȊO�̉��y�͎t���܂���B�ł��A���̌Â��W���Y�̍Č��\�͂ɂ͐�������܂����B�����M����ł��B�����Ɍ����ʂ��Ă��܂��BPARAGON�͂��̊�ԂȌ`�炵�Ă��A�I�[�f�B�I�@��Ƃ������g�y��h�̕��͋C��Y�킹�Ă��܂��B�𑜓x�͌��݂̃G���g���[�N���X�̋@��ɂ��y�т܂��ǁA���y���y���݂��ɂ����ẮA���Ђ̍��̍ŏ㋉�@EVEREST������ł��B
�@�����������u�L�@�I�ȃT�E���h�v��~��������͍��ł������Ǝv���܂��B���낢��Ƙb��ɂȂ��Ă���uProCable�v�̐����V�X�e�����A���Ԃ̌X�����Ƒz�����܂��B�����炱���@����邱�Ƃ������ɂ���A�M�S�ȃt�@�����t���Ă���̂ł��傤�B
�@���������A�̘̂^���͑f���炵�����̂�����܂����B50�N��E60�N��̃W���Y�̃f�B�X�N���ƁA�ǂ����Ă���Ȃɐ��X�����T�E���h���^���̂��낤���Ɗ��S���܂����A�N���V�b�N�����āA���Ƃ���DECCA�̉��N�̘^���͍������Ă��S�R�Â�����܂���B�ׂ��ȕ��������ɂ�鐧��z���A������ɔ���悤�ȃG���W�j�A�̎�r�����m�������Ă����̂ł��傤�B
�@�Ƃ�����A�X��Ŗ��Ă��āu�����A����͊y���������I�v�ƒN�����U����������������V�X�e���̓o���]�݂����Ƃ���ł��B�������A�����܂ł��u�}�X�^�[�e�[�v�̉��ɋ߂Â���悤�Ȑ��U�@�̃T�E���h�E�f�U�C���̗���グ�v�͕s�����Ǝv���܂��B���܌�������F�t�������Ղ�́u��̐X�����ʁv�ł����Ȃ������o�����i�ł͍���܂����̂ˁB
�@�ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�����ԍ��F8315923
![]() 0�_
0�_
�@�h���L�[�R���OJr.����Ainouesp����Awakamatsu181����A�������ݗL���������܂��B�u�܂Ƃ߃��X�v�Ő\����܂���B
�@�O�ɂ������܂������A���{�l�͐����Ɏア�ł��B�X�y�b�N��J�^���O�E�f�[�^����ɋC�ɂ��܂��B�����ǁA�f�B�[���[�����[�U�[�Ɛڂ���ۂɁu�I�[�f�B�I�͐�������Ȃ��I�@�����ăi���{�̃V�X�e���ł��I�v�Ɨ͐���������b�E�E�E�E�ł��Ȃ��̂��h���Ƃ���ł��B
�@���[�[���N�����c�̎�Ɏ҂������Ă܂������A�l�b�g�ʔ̂̕��y�Ɠ����Ƀ��[�J�[�ƃf�B�[���[�ƃ��[�U�[�Ƃ̋������傫���Ă��܂����悤�ł��B�݂��Ƀ\�b�|�������A���l�Ɋւ���������ь����Ă���B����ɃI�[�f�B�I�s���ɂ��s���A�E�I�[�f�B�I�@��ɐڂ������Ă��߂��ɒu���Ă���X���Ȃ��E�E�E�E�Ƃ�����Ԃɒu���ꂽ����҂������Ȃ����Ƃ�������������ɔ��Ԃ��|���܂��B�����Ƃ������Ŏ����ł���ꏊ�Ƌ@��Ȃ���A���[�U�[�̋����̓J�^���O�f�[�^�Ɖ��i�����Ɍ��������Ȃ��ł��傤�B
�@�O�̃X���b�h�ł������܂������A����ȃX�y�b�N�����`��ł��j�邽�߂ɁA���[�J�[���f�B�[���[���w�͂��ׂ��ł��傤�B�N��葊��̏����Ȃ�߂āA�@����Ђ������Ēn���ɂ��o�����u�s���A�E�I�[�f�B�I�͂���Ȃɂ��f���炵���v�Ƃ������Ƃ��A�s�[�����邽�߂ɁA���̍����x���ł̉c�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A��������Ȃ��Ƃ��̋ƊE�ɂ͖����͂Ȃ��ł��B
�h���L�[�R���OJr.����H��
���Z�p�͂�X�y�b�N�A�R�X�g�����ɂ��������
�������A�K���߂������ق��̍��ɍ��̓��{��
���n�ʂ�D���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@�܂��������̒ʂ�ł��B���݂͗lj݂��쒀����Ƃ̗Ⴆ������܂��B�������[�J�[�����肪�u�X�y�b�N�U���v�������Ă���������������čs�����\�������Ă���܂��B�������[�J�[���O���[�o�����]�X�Ƃ������R�Ő������_���C�O�Ɋۓ������Ă��ẮA�V�b�y�Ԃ���H�炤���Ƃ��o�傷�ׂ��ł��傤�B
�@����Ƃ��X�������肢���܂��B
�����ԍ��F8315948
![]() 0�_
0�_
�F���ӂ�
redfodera���ӂ́A
��musical fidelity��A3.5CR CD ��A3.5CDP SP HARBETH��Monitor30���g���Ă��܂��B
���݂܂��������ԈႦ�ɂ������܂����BA3.5�ł͂Ȃ�A3,2CR(�v���ƃp���[�j�@A3,2CDP�ł����B�������܂��B���̃V�X�e���ɂȂ����̂͂T�N�ʑO�̂��Ƃł��B�{����JBL�̃X�s�[�J�[�����Ǝv���߂��̃I�[�f�B�I�V���b�v�ɍs�����̂ł������܂��܂����ł��̃V�X�e���Ńf�������Ă��Ĉ�ڍ���Ȃ�ʈ꒮���ꂵ�Ă��܂��܂����B���̓��͌��lj������킸�ɋA��܂����B�����̎��ɂƂ��Ă͌����Ĉ����������ł͂Ȃ������̂ł����ǂ����Ă����̉����Y���ꂸ���Ljꃕ����ɍw�����Ă��܂��܂����B���܂Ŏg���Ă̊��z�͂ƂĂ��������Ă��܂��B�w�������̓A�N�Z�T���[�ނȂǂ���؎g�p���Ă��Ȃ������̂ł�������ł��\�������ł��鉹�ł����B���݂̓P�[�u���Ȃǂ͏o���邾���Ȃ̏��Ȃ������g�p���Ă��܂��i�A���v��X�s�[�J�[���ǂ��Ӗ��ŕȂ�����̂Łj�B���̕���redfodera����̋�悤�ɓK�x�ɉ����̂艷���݂�����A��������邭�Ȃ�߂����Ƃ����������ł��B�����N�������D�މ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ōD�������������ꂻ���ł����c���͌����ɂ͂܂�܂����B���̃V�X�e���ɂ��Ă���{�[�J�����̂����Ƃ������܂����B���ɏ����{�[�J���͗ǂ��ł��ˁB�_�C�A�i�N���[���Ȃǂ��Ă���Ɩ{���ɐS�n�ǂ��ł��B������͂�p�����̋@��Ȃ̂ŃA���v�̓��o�͒[�q�Ȃǂ͓��{���̋@��ɔ�וn��ł��B���g�[���R���g���[�������E�o�����X������Ă��܂���B
�ȏ㎄�̋@��̃C���v���ł����B
����F����̃C���v�����ǂ�ǂe���ĉ������B
�����ԍ��F8316215
![]() 1�_
1�_
�F����A������
�钆�ɖڂ��o�ߍ��������̂ŐQ���܂���B
���E�������
�V�E�������̃I�[�f�B�I�@��ƍ���̓W�]���A�G�k�@�Ɉ��z���ł��ˁA��������̗��q������܂��悤�ɁB
130theater����
���\�j�[��AV�A���v�̃t���b�O�V�b�v�@���}���[�V�A���ł��B
������ƃr�b�N���ł��ˁA�O���[�o����ƂƂ͌����{���ɕ��Â���Z�p�̋����S�z�ɂȂ�܂��B
�I�[�f�B�I�t�@���삯�o������A�n�߂܂���
���̂���̐S���鉹�y��t�ł鐻�i�����������đI�Ԃ̂ɍ��邮�炢�ǂ����i�𑽐����[�J�[�����
�o���Ăق����ł���ˁA���������育�뉿�i��(��])
inouesp����A�n�߂܂���
�����y���y���ނ��߂ɂ͍����i���i�o�J�ȒP��ł����j�s�����ƐM���Ă��܂������A���ꂪ�ԈႢ�ł��邱�Ƃ�
����������I�[�f�B�I�G���ɃA���v�̏Љ�ň��|�I�ȗʊ��Ǝ��������ē��������A�����ȗ����Ԃ�ɋ������ꂽ��
�A���v�̔�]���Ȃ����Ă���]�_�Ƃ���̋L���̉���4.800.000�~�Ə����Ă���܂����B
���͒l�i�ɋ������̂ł����A�]�_�Ƃ���Ƌ�����������Ă܂����E�E�E
wakamatsu181����A�n�߂܂���
Hi-Fi�n�̔M�����X�ǂ݂܂����B�v���Ԃ�ɉł���Ɗ��G������̃R���T�[�g�ɍs���A�Ⴂ���̉̐��ɕς��Ȃ�
�n�b�L�������̎��A�ȊԂ̘b���y���߁A����A�蔏�q�A�|�����A�y��������A�y�������Ԃł����B
���ʁA�𑜓x�A������ʂȂǂ̌��t���͊F���ł����A����I�[�f�B�I�@������t�Ō����\���Ƃ��ɂ͕K�v�ł���
�X�̎������Ⴂ�܂��B
���������̌��t���Ȃ�������ǂ��A�����̕\�������ł͉v�X����Ȃ���Ԃŋ@��I��ɂ͗L�͂ȏ�Ǝv���܂��B
redfodera����
�������ʂɉ𑜓x�ɒ�ʁE�E�E�u����艹�y���y���ނ��̂ł��傤�I�v�Ƃ��������������Ă��܂���
�����t�����肸wakamatsu181������͂��ߊF����ɕs���ȑz���������Ă��܂��܂������Ƃ��l�т������܂��B
�s���ȑz���H���X�̕��ʂ�ǂތ���wakamatsu181����Ɠ����Ӗ������Ǝ�����̂ł����Aredfodera����ɂł�
�Ȃ���ʘ_�Ƃ��ẮA�����ʂɉ𑜓x�ɒ�ʁE�E�E�̂��b�ł͂Ȃ������̂ł�����
�h���L�[�R���O�i������
��musical fidelity��A3.5CR CD ��A3.5CDP SP HARBETH��Monitor30���g���Ă��܂��B
����ڍ���Ȃ�ʈ꒮���ꂵ�Ă��܂��܂����B
�����̃V�X�e���ɂ��Ă���{�[�J�����̂����Ƃ������܂����B
SHM-CD�⍡��̋@��A���̒m��Ȃ�������ł��B�������y���߂�̂��ŗǂł��ˁB
�����ԍ��F8317010
![]() 0�_
0�_
�@�Ⴂ������ԉ�����A����ɂ��́B
�@�I�[�f�B�I�G���̎��M�҂̊F����́u�������قǗǂ������v�Ƃ���Ƀn�C�G���h���i�������グ�܂����A��������[�U�[��������g�����Ȃ��邩�ǂ����ɂ͊S�͂Ȃ��̂ł��傤���ˁB��x�ŗǂ�����u���̋@��͊m���ɗǂ����ǂ���Ȃ�̊�����Ȃ��ƕ�̎�������B�g�����Ȃ��ɋC��a�ނ��́A���̃��f�����Ă��̕�CD�𑵂��������K���ɂȂ��v�Ƃ��������]�_�Ƃ̃t���[�Y��ڂɂ��������̂ł��i�j�B
�@���G���̓L�����A�����ł��ˁB�s�v�c�Ȃ��̂ŁA���̓I�ɔN���d�˂�X�s�[�h����́u���v�Ƃ������̂͊����u���Ă������݂����ł��B�g�V������Ă��Ⴂ���Ɛ��̕ς��Ȃ��V���K�[�������������܂���ˁB�E�E�E�E���A�ǂ������Ƃ����Ǝ��͊��G�����͖��̗ǔ��̕����D���ł�����(^^;)�B�n���ȕ��͋C�ő����Ă����Ƃ͎v���܂����E�E�E�E�B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�@�b�͕ς���āA70�N��㔼��NHK����e���r�Łu�Z�\�u���@�I�[�f�B�I����v�Ƃ����ԑg�����f����Ă������Ƃ��v���o���܂����B76�N����������J�n����A���T���j���ƉΗj���̌ߌ�6������30���Ԃ̃I���G�A�����������ł��B
�@���͉��������Ƃ�����܂����A�g����@�ނ̃u�����h�������ׂăe�[�v�ōǂ���Ă����̂ɂ͋�������̂ł��BNHK�Ƃ��Ă̗���ł��傤�ˁB�u�𑜓x���A����̃g�����W�F���g���E�E�E�v�Ƃ������}�j�A�b�N�ȓ��e�ł͂Ȃ������ł����A�G���h���[�U�[�̃��x���ɍ��킹�������ʂ�́u�g�����Ȃ��v�ɏœ_�����킹�Ă����悤�ł��B���Ɉ�ۓI�������̂́A�A�i���O�E�J�[�g���b�W�̑����̎d�������ؒ��J�ɏЉ�Ă������Ƃł��B�u�A�[���̍������E�E�E�I�[�o�[�n���O�������E�E�E�C���T�C�h�t�H�[�X�L�����Z���[���E�E�E�v�Ƃ������e�v�f��������Ă��܂������ACD�����m��Ȃ��Ⴂ���y�t�@����������u�Ȃ�Ėʓ|�������I�v�Ǝv���ł��傤�ȁB�ł��A�����͂��̒m�����K�����邱�Ƃ͕��ʂ̂��Ƃ������̂ł��i�ԑg�̎Ⴂ�����A�V�X�^���g��������O�̂悤�ɃA�i���O�v���[���[�̒��߂�����Ă����̂ł��j�B
�@������ɂ��Ă��A�s���A�E�I�[�f�B�I���Љ�I�ɍL���F�m���ꂽ���h�Ȏ�ł��������オ���݂������Ƃ͊m���ł��B������x�A����ȏɂȂ�Ȃ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��܂����E�E�E�E(^^)�B
�����ԍ��F8330224
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ����́B
���E�������
�V���X���肪�Ƃ��������܂��B
�����S�҂̖l�ɂƂ��Ă̓n�C���x���Ȃ��b�������Ă����̂ŗl�q���f���Ă��܂������A
�������Ǝ���̃X�s�[�J�[�X�^���h�����������̂ł��̕������Ă��������B
�������������Ȃ̂œV��ɌX������A���C��SP��u���Ă�ʒu�łT�O�Omm����X�^���h�ł�
SP���V��ɓ������Ă��܂��܂��B���������̍����ɍ��킹��ɂ͊����i�ł͂��傤�ǂ���
�T�C�Y�A�����̕����Ȃ����z�������ł��B
�����Ŏ��삷�邱�Ƃɂ��܂����B
���͖؍ށB�V�A��͂Umm�ƂXmm�̓S���g�p���܂����B���d�ʂ͖�Tkg
�����S������\12,000����v�Z��������ł����A���������T���܂����Ēm�荇���̂Ƃ���ň����d����邱�Ƃ��ł��A�����܂ł̑����v�ł���\8,000�ōς݂܂����B
�����̃Z�b�e�B���O���o�����Ƃʼn������͂����肵���̂ƁA���X�s�[�J�[�ɔ��C�X�`���[����
�u���b�N���d�˂Ă��̏��SP��u���Ă����̂���A�܂����Ȃ�ɂ������肵���X�^���h�ɏ悹��
���Ƃɂ���āA�ቹ������������܂�܂����B
��`�A�A�����Ō����̂��Ȃ�ł����l�̓I�[�f�B�I���y���߂Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8330635
![]() 0�_
0�_
�����܂���
�V���X���V�X���̊ԈႢ�ł����B
�����ԍ��F8330652
![]() 0�_
0�_
����28��������@
������A�u���[�Ƃ͐����F�ł��ˁB�������̕ǎ��H���u���[�Ȃ�ł��ˁI�I�B���̕����͓���
���������̂ł����A�v���W�F�N�^�[�������Ƃ����͂蔽�˂��C�ɂȂ�̂ł��B�����z��
���n������w�����A��e�̂�����Ƒ傫�ȕ��œV��\�����Ƃ���悪�ƂĂ����܂��Ă���
�̂ł��ˁB�E�E���Ǖǎ������œ\��ւ��Ă��܂��܂����B������6������ɂ����`�œ����
�t����12��v���X2���14��Ȃ̂łł����A�����̕����ł��̂őS�����ł͋C���œ����Ă���
�����ꂪ�������ׁA�X�N���[�����̖�5����3�����ɁA�c��͔����܂܂ł��B�����̉E���̓N��
�[�[�b�g�Ŗ̐F�Ȃ̂ŃJ�[�e�����[�������t�������J�[�e�������t���A�v���W�F�N�^�[
���g�����ɂ̓N���[�[�b�g�̑O�֍����J�[�e���������o���A�X�N���[�����͐^�����ɂȂ��
���B�����V���b�^�[�J�˂�����ג��Ԃł��A�قڊ��S�ȈÈłɂȂ�܂��B
�V�A��͓S�Ƃ������ł����A���~�͍l���ɓ���܂���ł������H�B�����X�s�[�J�[�X�^��
�h�̓r�N�^�[�̃X�^���h���g���Ă��܂����A�X�s�[�J�[�̑傫���ƍ���Ȃ��ׁA�V��18mm��
�̃A���~��lj����Ă���܂��B
�E�E�|�ށA�A���~�ނȂǂ̓z�[���Z���^�[�Ȃǂɂ������Ă��܂����A���ł����ɉ����Ă�
��f�މ�������܂��̂ł�����Ŕ�����2����1����5����1�ōw���o���܂��B(�́A�ԂɃp
���[�A���v��t����ׁA5mm×50mm�̃A���~��~�����ăz�[���Z���^�[�������܂������A
���̗l�ȏ��ł�1����1000�~�ʂ��Ă��܂����B��S����(�A���~/�^�J/��)���̓X�ʼn��i��
������800�~�Ƃ̎��ł����B������ƈ����Ǝv���܂���������͒��(�m��4m)1�{�̒l�i�ł�
���B�܂�4m��800�~�E�E�E�Ԃɏ��Ȃ��̂Ŕ����ɃJ�b�g���Ă��炢�܂����B
�E�E�E���̗l�Ȃ��X�́u�^�E���y�[�W�v�Ɍf�ڂ���Ă��܂��̂ŁA���i�Ƃ����������Ă��炦
�邩�\�ߊm�F���Ă���s���Ɨǂ��Ǝv���܂��B
������A�i���j�~�X�~ FA�p���J�j�J���W�����i�Ƃ�����Ђ�����܂����A�����ɂ͂��낢
��ȍH��p�ł������i������܂��B�S�Ȃ�SS400�Ƃ�����������܂����ēݍނ�����S�Ƃ�
�Ă͗D��Ă��܂��B���H�ς݂ł������̐��x�������x�ł��B
http://fa.misumi.jp/index.jsp?contents=/product/plate/index.html
���m�F�ł����A���̏ꍇ�H��Ζ��ł��̂Ŏ�ɓ������̂ł�����ʂ̕���Ώۂɔ����Ă�
��邩�ǂ���������܂���B
�����ԍ��F8331044
![]() 1�_
1�_
130theater����
��������A�u���[�Ƃ͐����F�ł��ˁB�������̕ǎ��H���u���[�Ȃ�ł��ˁI�I�B
�R�o���g�u���[�Ƃ��}�����u���[�Ƃ��̔Z���ڂ̃u���[�ł��ˁB
���łɃ\�t�@�[�������F�ł��i�j
���X�u���[���D���Ƃ����̂�����܂����A��p���ő����Ȃ����i�̐����ɂ��W�Ȃ�
�����Ȃ̂ŁA�Â�����ׂɍ����l���܂������A���������Ȃ̂Ŏv�����Ă��̐F��
���Ă݂܂����B�Ƃ��Ă��C�ɓ����Ă��܂��B
���V�A��͓S�Ƃ������ł����A���~�͍l���ɓ���܂���ł������H
�ꉞ�͍l���Ă݂��̂ł����A����Ȃ�̌��݂ŏd�ʂ��o���ɂ͐g�߂�ss400�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�~�X�~���������܂���A���肪�Ƃ��������܂��B
�S�H���W�����J�����m�荇���Ɍ��ς��肵�Ă�����Ă����̂ł����A�����ł�����������
�ׂɉ��T�Ԃ������Ĉ������������܂����B�S�݂̂łQ�U�O�O�~�ōς݂܂����B
130theater����̃A���~�P�Wmm���������ł��˂��i���j
�����ԍ��F8331863
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ���@������
���E�������A���v���Ԃ�ł��B
��3�e�̐V�����X���A���g���Z���ł��ˁB
inouesp����̃\�j�[�̃f�W�^���A���v����ւ��b�ȂǁA
130theater����ł͂Ȃ��ł����i������j�ł���B
�O��̃X���́A�`���b�g���肻�тꂽ�̂ŁA�y�����ǂ܂��Ă��������Ă��܂����B
����͑��߂Ɂi�����Ȃ����H�j�䈥�A�ɎQ��܂����B
�X�������肢���܂��B
�Ă���28��������ASP�X�^���h�������߂łƂ��������܂��B
���^SP�̓X�^���h�̉e���������o��Ƃ����܂����A
�����؍ނł���Ηǂ����������A���y�͊y���߂����ł��B
���Ɏ���i�ł�����A�������N����2�{�y���߂܂��ˁB
�����ԍ��F8335916
![]() 0�_
0�_
�F����@����ɂ��́I
���E�������@�V�X�������グ���߂łƂ��������܂��I
���e���i�X�Z���Ȃ肠��Ӗ��A�N�w�I�ɂȂ�P�זE�ŏ����m�\���x���̒Ⴂ���ɂƂ��ēǂނ̂Ő���t�ł�(>_<)�E�E�E���Ȃ�Ƃ��Q���������Ǝv���Ă܂��̂ŋX�������肢�v���܂��B
�Ă���28��������@�r�o�X�^���h�A�F���N�₩�Ɋ�������܂����ˁA���߂łƂ��������܂��I
���͎��̓��C���r�o�̂h�p�X�ɕς�蓯���j�d�e�̂p�P�y���E�������@�̃T�u�r�o�̂h�p�R�̑O�g�œ������a�̃��j�b�g���g�����u�b�N�V�F���t�̂r�o�ł��B�z���g���n�߂Ă���A���R�r�o�X�^���h���g���܂��B
���̎����̑N�₩�ȃX�^���h����ɓ������킯�ł��A�C�C�i�[�I�܂��Ď���ł��ˁA���x����������Ă݂����[(^^)
���A�}�f�̂r�o�X�^���h�ł������C���r�o���u�b�N�V�F���t�ɕς��ăg�[���{�[�C�^�Ƃ͈Ⴄ���Ȃ�̗ǂ��𖡂���Ă��܂��B
�����ԍ��F8337346
![]() 0�_
0�_
�@�Ă���28��������A����ɂ��́B
�@�������A�I���W�i���̃X�s�[�J�[�u����ł��ˁB�������u���[�Ƃ́E�E�E�E�������X�B�^�T�C�g��YAMAHA��NS-1000M���u���[�ɓh�����������Ƃ������|�[�g���ڂ��Ă܂������A����ɕC�G����u�����v�i�H�j���Ǝv���܂��B
�@���͎�悪���s��p�Ȃ̂ŁA�H��̂��܂��l�͑��h�����Ⴂ�܂��B
�@�ӂƎv�����̂ł����A�s�̂̃X�s�[�J�[�X�^���h�����������u�V�ѐS�v���K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B����ؖځA���邢�͋����F���̂܂�܂�����ł͖ʔ�������܂���B�܂��A����̓X�^���h�Ɍ��炸�I�[�f�B�I�@��S�ʂɌ����邱�ƂȂ�ł����ǂˁB
�@audio-style����Asatoakichan����A����ɂ��́I�@�������ݗL���������܂��B���ꂩ����u�Z���v�X���b�h�^�c�ɓw�߂܂��̂ŁA�X�������肢���܂�(^^)�B
�����ԍ��F8339681
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ����́B
audio-style����
���肪�Ƃ��������܂�
�@
�����Ɏ���i�ł�����A�������N����2�{�y���߂܂��ˁB
�����Ȃ�ł��A�I�[�f�B�I�S�̓I�ɂ����������̂�ڎw���Ă���̂�
��������Ȃ薞�����Ă��܂��B
�܂��܂��E�[�t�@�[�{�b�N�X��A���ɂ��������Ƃ���������̂�
���̖ڕW�����߂ď������y���݂܂��i�O�O
satoakichan����
���肪�Ƃ��������܂��B
�����̎����̑N�₩�ȃX�^���h����ɓ������킯�ł��A�C�C�i�[�I�܂��Ď���ł��ˁA���x����������Ă݂����[(^^)
���Ѝ���Ă݂Ă��������A�y���������ł���i�O�O
��Ђō���Ă����̂ŁA�d���I����Ă���P�O���Ƃ��A����Ɉ�x�h�肾���悵�Ă������Ƃ�
���x�݂ɒ��̖؍ނ��Ă݂���Ƃ��A�͂����茾���ĉ������ɉ�Ђ֍s���Ă�����������Ȃ�
��Ԃł��i�j
���E�������@
���肪�Ƃ��������܂��B
���s�̂̃X�s�[�J�[�X�^���h�����������u�V�ѐS�v���K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ł���˂��A�ꐶ�����u�b�N�V�F���t�Ƃ����Ǐd�����X�s�[�J�[�������グ���܂܊撣���Ă�
���݂Ȃ�ł�����ˁA�咣�����Ă����Ȃ���I
����ɂ����̏ꍇ�X�N���[����������ƃX�s�[�J�[���X�B��Ă��܂��̂ŁA���������F�Ŗ`��
�ł����̂������ł����ǂˁB
����ł�����ς�͍D���ł��i�j
�����ԍ��F8339889
![]() 0�_
0�_
�F����@������
���E�������
�����A�ǂ������Ƃ����Ǝ��͊��G�����͖��̗ǔ��̕����D���ł�����(^^;)�B�n���ȕ��͋C�ő����Ă����Ƃ͎v���܂����E�E�E�E�B
�ނނ��`�ǔ��h�ł����E�E�E�o�g���u���ł��ˁ`(��)
��������ɂ��Ă��A�s���A�E�I�[�f�B�I���Љ�I�ɍL���F�m���ꂽ���h�Ȏ�ł��������オ���݂������Ƃ͊m���ł��B
��������x�A����ȏɂȂ�Ȃ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��܂����E�E�E�E(^^)�B
�X�̂��q����B�͔��Ɍ��I�Ȑl�����������ŋ߂ł̓I�[���u���L�̓S�l28���A�E�肪�����Ă��邯�ǁA�����̔���
�t���Ă��镨���I�[�N�V�����ɏo�i����A�Q���������n�`�}�L��������������ɕ����ė��Ƃ��Ȃ������Ɩ�ꎞ�ԃO�`��
�����܂����B���ɂ͑����̔N�z�̕����Q�����ꂽ�Ƃ̎��ł��B
�t���Ă��锠�����炵����i�ŁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��Ă�������������ł��B�Y��Ȕ��̂ق����ǂ��̂ł͂Ȃ��̂ł�����
�����Ƃ���͏�̉��A�X��ɕ��ׂ��Đ����ɓ������Đ▭�ɏĂ��Ă��镨������Ƃ̎��I�I
�փF�`�`�E�z�H�`�`�E�t�D���`�`���炢�̕Ԏ������o���܂���ł����B
���̕����炠�̎�͉����Ɛq�˂��I�[�f�B�I�Ƃ��f��ӏ܂Ƃ�����ł��Ɠ������
����͍����Ȏ��˂ƌ����܂�����(���)
����28��������@������
�����̃I�[���u���L�̓S�l28���A�������E�肪�����Ă��镨��10���~���������ł��B�����l�C�ł����
�������Ƃ��n�����Ƃ��B��ƂƂ��̌��t�ɉs���������܂��B
�������B���Ă��肻����(��)�X�s�[�J�[�X�^���h�̃R�o���g�u���[���������Ă��܂����Ԃ̓h�����o����̂ł͂Ǝv���܂��B
�����~�����ł������������E�E�E
satoakichan����@������
�����͎��̓��C���r�o�̂h�p�X�ɕς�蓯���j�d�e�̂p�P
���y���E�������̃T�u�r�o�̂h�p�R�̑O�g�œ������a�̃��j�b�g���g�����u�b�N�V�F���t�̂r�o�ł��B�z
�����g���n�߂Ă���A���R�r�o�X�^���h���g���܂��B
�I�[�f�B�ɋ������o�Ă������q�ɂk�t�w�l�`�m�̃A���v�Ƃh�p�X�������Ă�����A�������܍č\�z���ł��B
���q����͋@���̂������Ⴆ�Ȃ��̂ŁA���[�������W���[�܂�������ł��B(��)
�����ԍ��F8340085
![]() 0�_
0�_
inouesp����@
�͂��߂܂��āAkojirou_sasaki�Ɛ\���܂��B
��ϙG�z�ł����Ainouesp�����܂��܂Ȃ��Ƃɏo����A�����A�������A��������ꂽ���b�A�o�܂�ǂ܂��Ē�������ŁA�ǂ�������悤�ȋC���������܂��B�����Ȃ���ǂ܂��Ē����܂����B
�����̂��Ƃ�\���A50��̃}�j�A�ł����A30�N�ȏ�O�AJBL��D-130��075���o�b�N���[�h�z�[���Ŗ炵�Ă���Ƃ��Ɂu�]�엝�_�v�ɏo��P�[�u�������ׂă��K�~�ɕς����v���o������܂��B����10�N�قǃI�[�f�B�I���牓�������Ă����̂ł����A�I�[�N�V�����Ŏ�ɓ��ꂽ�����~�j�R���|���v���̂ق��C�����ǂ���̂ŁA�������Ȃ����̂����������ɁA�̓��[���ɐ������Ă����u�I�[�f�B�I�}�j�A�a���́v���������n�߂��悤�ł��B
���́AiPod��PC�ɔk��WAV�t�@�C�������A�G���N�g���{�C�X��38�Z���`��炵�Ă��܂��B���ł�SP�P�[�u���̓��K�~�ł����A�x���f����m�C�g���b�N�̃R�l�N�^�[���g���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�\�����������Ȃ�܂����B
inouesp����̋�悤�ȃX�s�[�J�[�R�[���ɗv�������������u���x�͋����A���������������͑傫���A���������R�[�������߂���̂��v�ƕ����M���Ă��܂����B�f�l�Ȃ���A�f���ɋ^��Ɏv���Ă����̂́A�����Ėʐς̍L���G�b�W��������A��ʂ̋t���������O�ʂɉ����o�����̂ɁA���ŊF�����C�Ɏv���Ă���̂��A�Ƃ������Ƃł����B
�����āA�y���R�[�������ǂ�����đ�ʂ̋t�������Ɛ���āi�����āj����̂��܂ł͎v������܂���ł����B
�ł��̂ŁAinouesp����́u�Ɣ��v�ɂ͐[���Ӗ��������Ƃ��Ă������ł��B
����Ȃ��肢�ł����A�ʏ�̃X�s�[�J�[�Ƃ̈Ⴂ���R�g�o�œ`���Ă��������܂��B���̊����𑼐l�ɃR�g�o�œ`�������͕S�����m�ł��B�Ȃ�Ƃ����肢�ł���K���ł��B�R�~���j�P�[�V�����͑����i�\���ҁj�̓w�͂Ǝ�̓w�́A�o���Ȃ��ɐ��A���Ȃ����̂̂悤�ł��B
�����āA�������ݍ���Ő}�X�����\���A�ǂ����łǂȂ����ɕ������Ă��炢�����B�N���������Ă�������Ȃ����̂��낤���A�Ƃ����ϑz�ɍL�����Ă���܂��B
�����A�����s�̐��c�J��Ƃ����Ƃ���ɏZ��ł���܂��B�ߐ�͍]����ł��B�������m�荇���̕��œ����ɂ��Z���̕����������������炨�m�点������K���ł��B
����Ƃ��X�������肢�\���グ�܂��B
�������A�����_�c���y�����Q�������Ē������Ǝv���Ă���܂��B
�{�R�[�i�[�Q���̊F�l�A�Ȍエ���m��u�����������܂��悤�ɁA�X�������肢�\�������܂��B
�����ԍ��F8340357
![]() 1�_
1�_
���E�������
�I�[�f�B�I�E�}�j�A�ƌĂ��l�����͉̗w�ȂȂǂ͗]�蒮���܂���ˁB�����̂͂����ł���
���A���̎q�ƕt�������l�ɂȂ�Ƃ���Ȏ��������Ă���ꂸ�A�����l�ɂȂ�܂����B�����
�Ɖ��̂����������Ⴂ�܂��B(����A���݂ɍs���ăJ���I�P������X�i�b�N�ɍs�������A����
��S���m��Ȃ��Ƃ��̏�ɋ����܂������ˁB)����Ȏ��ł����A�̗w�ȂƌĂ��W����
���̉̎�ł����G���͐̂���D���ł����B�����̔����������̊m�������������肵�Ă��āA
������L���̂����܂��̎�ł��ˁB�E�E�E�ޏ���CD�����������L���Ă��܂����A��N{PRAHA
Deluxe Edition}�Ƃ����`�F�R�E �t�B���n�[���j�[�nj��y�c�Ƃ̃R���{���[�V�������! �h�{
���U�[�N�z�[���ɂĎ��^���ꂽ���G���̑�\��12��!���������Ղ��w�����܂����B���ɂ͐�
���ȂNJ����������~�n�̋��n���������܂��B
���̕��삾�ƁA�z�{�����̂����܂��̂ő�D���ł��B�R���T�[�g�֍s���ĕ����Ă��Q�Q�Ɖ̂�
���͖��_�ł��B�S�b�����̍Ō�̕��̉̂��D���ł��B
�E�E���A��ԍD���ȉ̎�̓Z���[�k�E�f�B�I���ł��B3���ɂ͓����h�[�������ɍs���܂����B
����28��������@
�I�[�f�B�I�@��̃u���[�ƌ����AJBL�̃��j�^�[�V���[�Y�̃o�b�t���ʂ��u���[�ł��ˁB��
�̃u���[�����������ŗǂ����Ɏv���Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F8340513
![]() 0�_
0�_
kojirou_sasaki�l
�@inouesp�ł��B
�@�����₠�肪�Ƃ��������܂��B
�@������̌��A�\���グ��ƂƂ��ɁA�u�����v�����Ē����܂�
�@���̃X�s�[�J�̐������̂̓C�m�E�G�j�h�X�s�[�J�ƌĂт܂�
�@�����ăC�m�E�G�X�s�[�J�ƌĂ�ł��܂��BKI�͊J���ҁ@
�@�́@��㌒�O���̃C�j�V�����ł��B
��50��̃}�j�A�ł����A30�N�ȏ�O�AJBL��D-130��075���o�b�N���[�h�z�[���Ŗ炵�Ă���Ƃ��Ɂu�]�엝�_�v�ɏo��P�[�u�������ׂă��K�~�ɕς����v���o������܂��B
���]��O�Y�̓C�m�E�G�X�s�[�J�𐢂ɍL�߂��l�ŃV���b�v�ɂ����X���Ă��܂��A�I�[�f�B�I�A�N�Z�T���[�̎�ނł��B�́@��㌒�O����
�{���Ă��܂����ˁB�I�[���̖@����m������]�_�Ƃ���Ƃ��
�����āB
�����́AiPod��PC�ɔk��WAV�t�@�C�������A�G���N�g���{�C�X��38�Z���`��炵�Ă��܂��B���ł�SP�P�[�u���̓��K�~�ł����A�x���f����m�C�g���b�N�̃R�l�N�^�[���g���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�������̓v���P�[�u���h�ł��傤���H�@�A���v�̓N���E���Ƒz�����܂��B
�@
���ʏ�̃X�s�[�J�[�Ƃ̈Ⴂ���R�g�o�œ`���Ă��������܂��B���̊����𑼐l�ɃR�g�o�œ`�������͕S�����m�ł��B�Ȃ�Ƃ����肢�ł���K���ł��B�R�~���j�P�[�V�����͑����i�\���ҁj�̓w�͂Ǝ�̓w�́A�o���Ȃ��ɐ��A���Ȃ����̂̂悤�ł��B
���y�����z�ŗL�̉����͂���܂���B���e��Ȃ��t�̉��A���Ƃ���
�@�@���₩�ŏ������܂��̉��ƁA�d���ŕ������V���o���̉��A�����@�@���ɖ��Ă���Ƃ��A���̊y�킪���ގ��ŗL�̋����𒉎��Ɂ@�@�@�\�����܂��B�n�[�׃X�ƃA���e�b�N�U�O�S���������K�v��
�@�����Ė��Ă���Ă���A�ƌ������\�����ɒ[�ł͂���܂���B
�����ш恄�I�[�f�B�I�e�X�g�b�c�ł͉��͂R�OHZ�A���1.5�g�y
�@�܂Ŋm�F���܂����B�����ł́A���܂ŕ������ǂ̃X�[�p�[�E�[�t�@�[�@���Ⴂ�����o�Ă��܂��B����ɂ����Ă̓c�C�[�^�̂悤��
�@�u�V���A�V���v�I�ȉ��͑S���Ȃ��A�����������i�ςȕ\���ł����j
�@�ł��B����a�̃z�[���r�o�̒���������ԋ߂��C���[�W�ł��B
�����������X�s�[�J���犮�S�ɉ��͗���āA�X�s�[�J��
�@�@�@������̊Ԃɗ��̓I�ȑ������т܂��B�N���V�b�N�̍����Ȃǂ�
�@�@�@�X�s�[�J�̌������i�ǂ̌������j���璮�����������
�@�@�@���ł��܂��B
�����_�C�i�~�b�N�����W�������Ƃ����ӂƂ��镪��ł�
�@�@�@���ʂɂ���Ē�����̑ш�o�����X���ς�邱�Ƃ͂���܂���
�@�@�@�[��ɉ�̖��悤�Ȏ㉹�ŕ����Ă�
�@�@�@�u�s�A�j�V�����͋����v���ł��B
�@�@�@
�������̐c���Ƃɂ����������ŁA�����x���������ł��B
�@�@�@���ʂ��グ�����A�����͑傫���Ȃ炸�A���̂܂ܑO�֑O��
�@�@�@�Ɣ�т܂��B������`���̂ł͂Ȃ��A�R�[���̃s�X�g���^��
�@�@�@�ʼn����o������C�̔g�������̂܂ܑ̂ɓ͂��܂��B
�@�@�@���g�����畆�́u�ɂ��v�Ɗ�����Ƃ�������܂��B
�����r�m���u��X�͉��̖��Ă��Ȃ��Î╔�����ɌX����v
�@�@�@����̓A�L���t�F�[�Y�̎В��i��H�j�̌��t�ł���
�@�@�@���̂܂܃C�m�E�G�r�o�ɓK�p�ł��܂��B�D�ꂽ�^���ł����
�@�@�@���Ԏ��̃Y���Ȃ��ɊԐډ��͋����܂��B�l�b�g���[�N�������Ȃ�
�@�@�@�V���O���r�o�ŁA�������U�����Ȃ��R�[���ł̂�
�@�@�@�`�����ł�
�������_���C�m�E�G�r�o�����I�[�f�B�I�����F�l������
�@�@�]���́A�u����̓I�[�f�B�I����Ȃ��A�ڋ����v�ƌ����܂��B
�@�@���̈Ӗ��͓d�C���i���o��������Ȃ��āA�����Ⴄ�G�l���M�[
�@�@���Ƃ��Ό��q�͂Ƃ��A���������ْ[����Ɋ�����������
�@�@�ł���ƁB�������܂����B
�@�@
�����āA�������ݍ���Ő}�X�����\���A�ǂ����łǂȂ����ɕ������Ă��炢�����B�N���������Ă�������Ȃ����̂��낤���A�Ƃ����ϑz�ɍL�����Ă���܂��B
�����A�����s�̐��c�J��Ƃ����Ƃ���ɏZ��ł���܂��B�ߐ�͍]����ł��B�������m�荇���̕��œ����ɂ��Z���̕����������������炨�m�点������K���ł��B
���V���b�v���͉��L�ł�
�@�@�@http://www.ryohindendo.jp/shopbrand/007/O/
�@�@�@�X�s�[�J�͂P�T�O�Z�b�g�������ɏo�Ă���܂���
�@�@�@���ꂪ�쓮�o����A���v�͐�p�A���v�ɂȂ�܂��B
�@�@�@�s�̂̃A���v�ł͐�ɋ쓮�ł��܂���̂ŁA
�@�@�@�K���C�m�E�G�d�C�X�̃I���W�i���A���v
�@�@�@�R�i�����A�S�i�g�����X�����A���A�ҁAEL34�v�b�V��
�@�@�@�Ŗ炵�����Ŕ��f���Ă��������B
���ڂ������ɂ��Ă͂�����֘A���肢�܂�
t890570@hotmail.co.jp
�i���̌l���[���ł��j
�@�@�@
�����ԍ��F8341061
![]() 0�_
0�_
�F����ɂ���
����[�F���ꂼ��̃I�[�f�B�I���C�t�i����Ă��܂��ˁB����ɂ��Ă��Ⴂ������ԉ�����̂��q���A�܂����`
inouesp����X�s�[�J�[�̖��O��������ł��ˁAinouesp����̃��r���[�����Ď������̃X�s�[�J�[���Ă݂����Ȃ�܂����B�d���̊W�ō��͊��ɋ���̂ł��ɂȂ邩�͔���܂����x�����ɍs���@�����ΐ������Ă݂����Ǝv���܂��B
�F����ɐG�����ꂽ�Ƃ�����ł��Ȃ��̂ł��������V�X�e���̉��e�Ƃ܂ł͍s���܂���PC�̉�����������悤�Ƒ���DAC�F���ł��A���������߂̕��Ȃǂ���ΐ��Љ�����B
�����ԍ��F8342225
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
�Ƃ�������̉������̂��߂ɃI�[�f�B�I�̃Z�b�g�A�b�v��炵�܂������̌��������͂��߂܂����B
�V�x�@����X�s�[�J�[���j�b�g�Ȃǂ̑��ɃA�N�Z�T���[�ނ̑�������������Ă���A
�U�����ĈӖ����������̂������⎩������Ȃ�������A�x���߂����Ă���܂��i��j
�h���L�[�R���O�i������
�C���v���L���������܂����B
�ŋ߂�HARBETH��LS5/12A�Ɗi�����Ă܂��̂ŁA�g�����ȂǂƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂����B
��PC�̉�����������悤�Ƒ���DAC�F���ł��A���������߂̕��Ȃǂ���ΐ��Љ�����B
USB�Ōq���̂ł��傤���A�͂��܂��{�[�h�̃f�W�^��I�^O�Ōq���̂ł��傤���E�E�E
PC�Ƃ̘A�g�ł���DTM���Ŏg����n�[�t���b�N�E�T�C�Y��DAC����̕����I�����������Ȃ�܂��ˁB
���i�Ɣ\�͂��܂��܂��Ȃ̂ŁA�y�퉮�����DJ�n�̃c�[���������V���b�v�Ń`�F�b�N����邱�Ƃ������߂��܂��B
�f�W�^��I�^O�Ōq���ꍇ�͐M����AES/EBS���������Ƃ������Ȃ�܂�����P�[�u�����V�K�ɕK�v�ɂȂ����肵�܂��B
�����i�̒��ɂ������̂��@SYMETRIX Lucid DA9624�@�ł��B
�i��DAC�ł���CD�̃}�X�^�����O�ł��g��������ʼn��Ƃ��Ȃ郌�x���ɂ���܂����B
�j���[�g�����ŃN�Z���Ȃ��g���₷���āA���ÂȂ狰�炭2���~�O��œ���ł��閣�͂�����܂��B
http://www.mixwave.co.jp/audio/lucid.html
�I�[�f�B�I�Ƃ̕��p����CEC�̂c�`�T�R�ɃN�I���e�B�����i�̃o�����X���Ƃ�Ă��čŋ߂͐l�C���W�����Ă���l�ł��B
����A��������@�����܂������D�G�Ȑ��i�ł��̂ŁA���F�E���������D�݂ɍ��������߂ł��܂��B
http://www.cec-web.co.jp/products/da/da53/da53.html
����28��������A�t�@���^�X�e�B�b�N�I�I�I
�d�オ���������f���炵������Ȃ��ł����I
������ƑO�̃X���ł͂����Ԃ�ȃR�����g�ł������O�����e����Ă܂����ˁH�@����Ȃ��i�j
�J�X�^�������Ӌ`���\���ɂ���܂���B
�����̂Ȃ���ăX�s�[�J�[�ł͂��b�ɂȂ�܂���E�E�E�ƂĂ��ʐ^�Ɏ��߂�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ����B
kojirou_sasaki����A�͂��߂܂��āB
���̓��[���ɐ������Ă����u�I�[�f�B�I�}�j�A�a���́v���������n�߂��悤�ł��B
���A��Ȃ����A�ŁA��낵���ł��傤���B
���͓�������N�̓r���A�J�[�I�[�f�B�I��SP���j�b�g������AV���̏����ōĂєM�����Ă��܂��܂����B
�ŋ߂͓d���a�Ɠd���a�܂ŕ������Ă��܂��A���Ȃ����܂������ł��Ȃ��Ȃ��Ď��͂����f���Ă���܂��i��j
inouesp����A����ɂ��́B
���n�[�׃X�ƃA���e�b�N�U�O�S���������K�v�ɉ����Ė��Ă���Ă���A�ƌ������\�����ɒ[�ł͂���܂���B
�A�e��炵�����邩�̂��̕\������z�����������ł��h�L�h�L�����Ⴂ�܂��B
��x�A�q���������X�s�[�J�[�ł��B
�Ⴂ������ԉ�����A
���I�[�f�B�ɋ������o�Ă������q�ɂk�t�w�l�`�m�̃A���v�Ƃh�p�X�������Ă�����i�����j
���q�����DNA�ɂ��u���y��D���I�v�̓v�����g����Ă���Ǝv���܂�����A�ԈႢ�Ȃ��o��������Ă܂��ˁi�j
�ȑO�Aaudio-style����ɂ����q����Ɖ��y�̌�炢�̂��b���f���S�̉��܂�z���������Ē����܂������A
�e�q�œ���������L�ł�����āA�ƂĂ��f���炵���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8342793
![]() 1�_
1�_
�h���L�[�R���OJr����
�@
dac�����T���Ƃ̂��ƁB
�������ꂪ�b�o����Ԃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
dac�͂��̃p�[�c�\�����画�f���ĂT���~���鏤�i��
�I�J���g�A�Ǝ��͎v���܂�
�@
http://audiotrak.jp/product/?audiotrak=DR.DAC%202
�����ԍ��F8344683
![]() 1�_
1�_
inouesp�l
kojirou_sasaki�ł������܂��B
�����J�Ȃ��Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B
���ƂȂ��j�h�X�s�[�J�[�̃C���[�W���N���Ă��܂����i�z���g�����H�j����{���ł��B
�e�X�g�b�c�̍������́i�c�C�[�^�̂悤�ȁu�V���A�V���v�I�ȉ��͑S���Ȃ��A�����������j�A�����ɑ����̊y�킪���Ă��A�ގ��ŗL�̋����𒉎��ɕ\���A�܂��A���F�B�́u����̓I�[�f�B�I����Ȃ��A�ڋ����v���\���|�����Ⴄ�G�l���M�[���Ƃ��Ό��q�͂Ƃ��A���������ْ[����Ɋ������������|
�����Ă邩�ǂ����͕ʂƂ��āA�C�}�W�l�[�V�����c��݂܂��ł���B�C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��E�E�E
����͐����ł��ˁB�����Ə��߂ĕ�������u�����H�v�u���Ȃ́H�v�Ǝ��Ԃ��ǂ��~�߂邩��������̂ɂP�O�����炢�͊|���肻���Ȋ����ł��ˁB�C�C�ł��˂��A�����������̂���A�������������ʂ��Ă邩��������Ȃ������S�B�����l�i���āA�ʂ̐S�̏������K�v���ȂƎv���܂����B
���Љ�����̔��X���ّ�̂��ߏ��Ƃ������Ƃ�������܂����B
�����A�ǂ������甃���Ă��邩�I�Ƒ��f�ł��Ȃ��̂��䂪�Ƃ̎���ł��āA�Ɠ�����u�N���}��I�[�f�B�I�Ɋ��|�����Ǝv���Ă�I�v�Ƃ����|�`���č����҂��Ă���܂��̂Łi����ځj�B�`�����X�i�Ɠ��̊�F�j�����āA����̔��X����ƘA�����Ƃ��Ă݂����Ǝv���܂��B�w���͂��Ȃ��ɂȂ�Ǝv���܂����E�E�E
���āA�I�[�f�B�I�̊y���݂͐F�X�����Ċy�����ł��ˁB
�䂪�Ƃ̃A���v��inouesp���@���̂Ƃ���I�b�q�n�v�m�ł��I�A�ƌ��������Ƃ���ł����A�����̓I�[�N�V������3,000�~���Ŕ�����ONKYO�~�j�R���|�̃A���v���i13W�{13W�j�Ȃ�ł��B�_���s���O�t�@�N�^�[�Ƃ��s���ł����A����ł��\�������Ⴄ��ł��B�܂�CROWN�ɂ���ǂ����������ɗǂ��Ȃ邩�͌��������Ă��܂��i�悤�ȋC�����ɂȂ��Ă邾���j�B
�����̓X�s�[�J�[�iEV forcei�j�����ɓ|���Ă��O���ɌX���āu���E�v���͂��Ă݂悤���ƈ�����S�\�S�\����Ă���܂����B���ꂾ���ł��A���̖��ēx���ς��A�ܘ_��ʊ����C�����傫���ς��A�u�͂͂��A���̕ω��������̎��Ŋm�F�����Ƃ��I�[�f�B�I�̊y���݂��v�ƌ�����悤�ȓƂ茾���̂��܂��Ȃ���y����ł���܂����B�����͊��G���Ƒ�і��q�Ə��c�a���A����Ƀp�t�B�[�A�f�[�u�u���[�x�b�N�A�W���b�N�E���[�V�F�A�E�B�[���t�B���̃x�[�g�[�x���ł����B����������ƒ��͕������ꂽ�Ȃ��������A�Z�b�e�B���O��ς����������x�A�Ńh�b�`���ǂ������H���[��߂����A�Ƃ��Ƃ��A���ꂪ��ς����NJy�����̂ł��ˁB
redfodera����@
�͂��߂܂��āA����A�����߂�܂����I�ł���
�����͓�������N�̓r���A�J�[�I�[�f�B�I��SP���j�b�g������AV���̏�����
���ĂєM�����Ă��܂��܂����B
���ŋ߂͓d���a�Ɠd���a�܂ŕ������Ă��܂��A���Ȃ����܂������ł��Ȃ�
���Ȃ��Ď��͂����f���Ă���܂��i��j
���̌Â�����̎��a�́u�d���a�v�ł����B���߂Ă̔��ǂ����a51�N��52�N�������̂ŁA�����Â��^�̃E�B���X�ł��ˁB�ŋߐ��̒��ɂ͍��x�ȃE�B���X����R����悤�ł����A���̏ꍇ�A�������ɍR�̂��ł����������d�lj��͂����ɍς�ł��܂��B
�d�����C�ɂȂ��ł����A100V�ǃR���Z���g�ƃG�A�R���R���Z���g�̃A�[�X���g���ĕ��ʂ̃P�[�u���łȂ��Ă��܂��B
���͂������ǂ�ǂ�d�lj�����댯��������܂��ˁB���̏ꍇ�A�K���s�K�����͂��s�������Ƃ��K�x�ȃu���[�L�ɂȂ��Ă���܂��ł��B
�݂Ȃ���
�N���}�̂��D���ȕ��������悤�ł��̂ŁA�����ŏ���Ă����N���}�̂��Љ�Ɓi����Ȃ��Ƃ��Ă��C�C�́H�j�����Ă������������ƁE�E�E
���݂܂���A�Ɠ����A���Ă������̂ł�����A�܂����x�Ƃ������ƂŁA�͂��A���炢�����܂��B
�����ԍ��F8345123
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ����́B
[�Ⴂ������ԉ�����]
�@
�������̃I�[���u���L�̓S�l28���A�������E�肪�����Ă��镨��10���~���������ł��B�����l�C�ł����
�܂�����݂����ȕۑ���Ԃ����K�x�Ȃ�����������ĂƂ���Ȃ�ł��傤���E�E�E
�l�̏ꍇ�Â�����̓S�l28���͍D���ł����A�A���e�B�[�N�ɂ͋����Ȃ��̂ł���ɂP�O���~
�͏o���܂���i�j
���Ԃ̓h�����o����̂ł͂Ǝv���܂��B
���Z���ォ��P�ԁA�w�����b�g�Ɛ��X�̕����I���W�i���h�����Ă��܂����̂ŁA��x������
�����ݔ��ŎԂ̓h�������Ă݂�����]�͂���܂��I
�P�X���炢�̎��ɗF�l��KP61�̃t�F���_�[���ʃX�v���[�œh�������͔ߎS�Ȏd�オ�肾�����̂�
�����܂ł�����܂���i��j
�������~�����ł������������E�E�E
�����ł���`�j�̔閧��n�I�ȑ��݂ł��B
�ď����ē~����(~~;
�܂��A�~�̓A���v��PJ���g�߂Ă���܂����A�ď���G�A�R�������������܂���
�������u�Ԃ̓T�E�i���������ł��B
[redfodera����]
���J�߂����������肪�Ƃ��������܂�(^^;
��������ƑO�̃X���ł͂����Ԃ�ȃR�����g�ł������O�����e����Ă܂����ˁH�@����Ȃ��i�j
�����̂Ȃ���ăX�s�[�J�[�ł͂��b�ɂȂ�܂���E�E�E�ƂĂ��ʐ^�Ɏ��߂�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ����B
����`�K�x�ɉ�f�̍r���ʐ^�͓s������낵���ł��i�j
�����̓s�A�m�h���̂悤�Ƀc���b�c���Ɏd�グ�悤�Ǝv���Ă���ł����ǂˁA�Ë������ςȂ���
�������ɓV�͂Ȃ��Ȃ��ȉ������Ă܂����A���͂��Ō���Ɩؖڂ��ςɂłĂ��������ł���B
����ɂ���ȂɌ��������Ƌt�ɖl�̎ʐ^���p���������Ȃ��Ă��܂��i���j
[inouesp����Akojirou_sasaki����]
�͂��߂܂��āB
������������SP�ł���ˁA�l�������������܂����B
���ł������ł���Ƃ������������ł����ǂˁB��x�͕����Ă݂����ł��B
[�h���L�[�R���O�i������]
DAC�����̂�������Ƃ����ł��ˁB
�����͍��̂Ƃ���͕K�v�ȕ�����Ȃ��̂Œ��ׂ��肵�����Ƃ��Ȃ��̂ł����A
��A�䂭�䂭��PC��itunes�ɓ����Ă�Ȃ��̂������Ȃ��Ȃ�Ďv������
���Ă��܂��B
����Ȏ��ɕK�v�ȕ��Ȃ�ł���ˁADAC���āH
�ق�Ƃɂ����͂����Ȃ��Ƃŕ��ɂȂ邱�Ƃ������Ă��肪�����ł��B
���E�������ɂ����ӂł��ˁB�@
�����ԍ��F8345783
![]() 0�_
0�_
�F���ӂ�
redfodera����inouesp����f�������L�������܂��B���������DAC�ƌ����Ă��s������L���܂ŐF�X����̂łǂ̈ʂ̕����ǂ��̂������Ă��܂����B�Ƃ肠����������̂����߂��Ă���@������C���ɖ����ɂł����F���Ă��悤�Ǝv���܂��B���ɂ����ꂪ�ǂ���Ƃ������̂���������Ă��������B
���ŋ߂�HARBETH��LS5/12A�Ɗi�����Ă܂��̂�
�Ō��BBC���j�^�[�ł��ˁA�ǂ�ǂ�i�����ĉ������i�O�O�j/�B
�^��ǂɋ���ŔZ���ɑt�ł�̂��������A�𑜓x���d�������j�^�[���C�N�ɓO����̂��ʔ����Ǝv���܂��B�Z�b�e�B���O�����܂�܂����琥��C���v����낵�����肢���܂��B
�Ă���Q�W��������DAC�Ƃ̓f�W�^���M�����A�i���O�M���ɕϊ�������̂ŁAPC�̃I�[�f�B�I�{�[�h��CD��MD��Ipod�Ȃǂ̃v���[���[�Ȃǂɂ����ڂ���Ă��܂��B����PC�̃A�i���O�o�͂͂��܂萫�\���ǂ��Ȃ��̂Ńf�W�^���̂܂o�͂�����DAC����ăA���v�ɑ��낤�ƌ������Ƃł��B
�����ԍ��F8346441
![]() 0�_
0�_
�F����A�������������܂��B
�h���L�[�R���O�i������
DAC�A���C�ɏ������̂�������Ɨǂ��ł��ˁB
�{���A�撣���ĉ������B
���Ō��BBC���j�^�[�ł��ˁA�ǂ�ǂ�i�����ĉ�����
�X�s�[�J�[�E���r���[�̃��N�G�X�g���肪�Ƃ��������܂����B
�ߋ���KEF��LS3/5A���f�����g�������Ƃ�����̂Ōy���C�����œ������܂������ALS3/5A�͂��Ȃ�̓�ł��B
����6����81.5dB�ɂȂ��Ă܂������s�\���͂���ɒႢ�l��Musical Fidelity��A1�𑲓|�����Ă���܂����i�ꊾ�j
���̃X�s�[�J�[�p��Audio-Analogue�̃��m�����E�p���[�A���v�B�����̂ł�����Ńh���C�u�E�e�X�g���ł��B
http://www.audioanalogue.com/eng/donizetti.php
�܂��܂��ϋl�߂�O�ł��̉����X�����������[�ł���Ƃ���܂Ŏg���Ă��܂��A�g���C�A�����Ă錻��́E�E�E
CD�v���C���[��Sony XA50ES�Ńo���A�u���E���H�����[���Ńp���[�A���v�ɒ��ɑ����Ă��܂����A
Musical Fidelity��A1���v���A���v�Ƃ��Ďg�p���邩�A�V�K�Ƀv���A���v��T�����v�Ē��ł��B
������ɂ��Ă��ŋߒ��ÂŒ��B����DAC�ACamelot Technology��Arther�A CI Audio DAC-1�Ŗ炻���Ǝv���Ă܂��B
���Õi�̒��B�ɖ^�l�b�g�I�[�N�V�����A���p���܂���ł��i��j
�A���v�̃^�[�~�i���E�|�X�g���������̂�CANALE��4S8G���X�s�[�J�[���Ńp�������������o�C���C�������O���Ă܂��B
�����̃^�[�~�i���E�|�X�g�ƃS�����́AWBT�̃^�[�~�i���ƃX�e�����X�̃X�p�C�N���ɂ��ꂼ�ꊷ���������ł��B
���Ƀ^�[�~�i���E�|�X�g�͏�������ɉؚ��ł�����g����SP�P�[�u���̑I�����𑝂₷��ł������͕K�{�ł��B
�X�^���h��NHT��M6�p�i�ؐ��j�ŕ\�ʐς̍L�����̂��g�p���ĉ��z�����̃o�b�t�����ʂ�_���Ă��܂��B
�ʑ�������̂��A���u�������������ƈʑ��Y���̉e���ŋC�����̈�����������܂��B
��͂�����̍Č����ɏd�����������X�s�[�J�[�Ȃ̂Ō��̓����Ȃǂ͂悭������܂����A
���j�^�[�Ƃ��Ă���Ӗ��\�[�X�ɑ��ėe�͂��Ȃ��̂Ń��b�v�E�m�C�Y�Ȃǂ������ł��B
���y���y���ވȑO�ɁA�\�[�X�ɑΛ���������l�ȃv���b�V���[�����������Ă���܂��B
�����ԍ��F8346889
![]() 1�_
1�_
�A���X�A�������������B
�������̌^�Ԃ̒����ł��B
���ߋ���KEF��LS3/5A���f�����g�������Ƃ�����̂Ōy���C�����œ������܂������ALS3/5A�͂��Ȃ�̓�ł��B
�i��jLS3/5A�͂��Ȃ�̓�ł��B���i���jLS5/12A�͂��Ȃ�̓�ł��B
�����ԍ��F8346906
![]() 0�_
0�_
��قǁA�����P�[�u���̐M�҂ɂȂ����F�l���A��܂����B���܂ł̑��u�͑S�Ď̂ĂāA�����P�[�u����F�ɐ��܂����F�l�ł��B�����������̂�����ċC��������N���E���c�S�T�𒍕����Ă��܂����i���j
�@���̔ނ�MACBOOK���A���̉��̂��炵���ɋV���ăG�\�e���b�NDV-30�p�����Ƃ̂��ƁB����Ȃɗǂ��Ȃ琥�����āA�Ƃ��肢����MACBOOK�������Ă��Ă��炢�܂����BMACBOOK�̎g�����́����P�[�u�������ǂ�������n�[�h�f�B�X�N�ɃR�s�[���ꂽ�f�[�^����̍Đ��ŁA�ّ�ł̌o�H��MACBOOK�w�b�h�z���o�͂���SATRI�v���i����j���p���[�A���v���C�m�E�G�r�o�ƂȂ�܂��B����Ŕ�r�Ώۂb�c�o�̓t�B���b�v�X�b�c�l�P�Q�g�����X�|�[�g�ŁA�T�[�{�E�f�R�[�_���ɂ��̂��̓Ɨ��d����^�������̎��M��ŁATDA1541 ����DAC�ƃZ�b�g�Ŏg�p���Ă��܂��B��r�ׂ̈ɂg�c�����̂b�c�Ղ������Ă��Ă��炢�y�����y����������ƂȂ�܂����B
�@���ʁAMACBOOK�̉��͐��ɕt�щ����܂Ƃ����āi�����炭�W�b�^�[���j�c���S���Ȃ��t�j�����ŁA�Q���ƒ����Ă����Ȃ��ɂ܂������̂ł����i���̎��ɂ͂��������܂����j�A�Ƃ��낪�A�F�l�̎��ɂ͂b�c�l�P�Q�g�����X�|�[�g�̓����W���ɒ[�ɋ��������k���łȂ��A�f�[�^�̑唼���������������A�b�ɂȂ�Ȃ��B�Ƃ̂��ƁB
�@���������āA�����܂Ŋ��������Ⴄ�Ɓc�|�����̂�����܂��B�Ƃ����킯�ŁA�Ђ���Ƃ��Ď������Ԉ���Ă��邩������Ȃ��ƌ������|�ɏP���ꎞ�I�Ƀp�j�b�N��Q�ɂȂ�܂������A���͂����ԗ��������Ă��܂����B�ł��ǂ��������������Ȃ̂��́A���̂Ƃ���͂ǂ������������A�ƌ������͂���܂���B���ꂪ�I�[�f�B�I�ł��B
�����ԍ��F8347874
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ���@�@����ɂ���
inouesp����A�͂��߂܂���
>�@���������āA�����܂Ŋ��������Ⴄ�Ɓc�|�����̂�����܂��B�Ƃ����킯�ŁA�Ђ���Ƃ��Ď������Ԉ���Ă��邩������Ȃ��ƌ������|�ɏP���ꎞ�I�Ƀp�j�b�N��Q�ɂȂ�܂������A���͂����ԗ��������Ă��܂����B�ł��ǂ��������������Ȃ̂��́A���̂Ƃ���͂ǂ������������A�ƌ������͂���܂���B���ꂪ�I�[�f�B�I�ł��B
��Ƃ���ł��ˁB
inouesp����̃A���v�ASP�̃��X��ǂ܂��Ă��������Ă���ƁA
�ЂƂɂ���ẮAinouesp����Ɠ����悤�ȏɊׂ�������邩������܂����ˁB
�����A���ɂǂꂪ���������́A�Ȃ��Ǝv���܂���B
�v�́A�����͂ǂ�ȉ����D���������ŗǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����A�����͂���ȉ����D�����Ǝv������ł��鎖������܂�����A
�����ȉ����Ă݂�̂́A�y���݂̕����L����Ӗ��ł͕K�v���Ƃ͎v���Ă��܂��B
�����ԍ��F8348145
![]() 1�_
1�_
�F����ɂ��́B�܂����ז������Ă��������܂��B
���X�s�[�J�[���ɋC�ɂȂ�܂��B
�V���O���R�[���̑f���̗ǂ��͒�]�̂���Ƃ���ł����A�㉺������̂�
�ʂ���ł��B
���̃X�s�[�J�[���{���Ƀ��C�h�����W�ł���A�V���O���R�[���̏펯��j��
�����\�X�s�[�J�[�ł��̂Ő���~�����ł��B
�����A47��������lens��AMM���{ AM105i�A�}���`�E�G�C�Ɣ�r���������W����
��������ł�����A���m�点������Ɗ������ł��B
lens�̉��ɂ�Ⴢ�܂������A��͂�㉺�̃����W���̕s�����Ђ�������A�w��
�ɂ͎���܂���ł����B
���҂𗠐�Ȃ��̂ł���A���Ƃ��Ă������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8349599
![]() 0�_
0�_
wakamatsu181����
�@inouesp�ł��B�Љ������͍Ō�܂ł�������t�H���[�����Ē����܂�
�@
���āA�����W�ɂ��Ăł����A�R���֒����Ȃ��A���͂S�OHZ�Ȃ�y�X�Đ��͈͂ł��B�R�O�g�y�ł��o�Ă��܂����A�ّ�̕����̍L���ł͉��Ƃ��Ă͕�����A�ۖ�����������U���������͂��܂��B��͂P�T�jHZ�܂ł͕�����邱�Ƃ��o���܂����A����ȏ�͎��̎��̂������A�������܂���B�ߋ���JBL S143, S4800 ,�I���L���ED-77MRX�Ȃǂƕ��p���Ă��܂������A�ш�ɂ��Ĉ��r�o�ɕs�������������Ƃ͂���܂���B���̏T������BOSE��AM5�U�ƈ�����ׂĎg���Ă��܂����A���炩��BOSE���i���E�����W�ł��B
���r�o�̈�Ԃ̖��̓A���v�ŁA�����̋쓮�͂ł͋쓮���ł��Ȃ����Ƃł��B���Ȃ݂ɃN���E���̂c�S�T�A�\�j�[TA-DR1�ł́A�O�҂��d�b�̂悤�Ȓ��i���E�����W���A��҂̓{�����[���Ƃ����Ԕ����ȉ��ɂȂ�܂����B�N������ML�Ȃǂ̃A���v�ł���Ђ���Ƃ�����邩������܂��A�����Ă��܂���̂łȂ�Ƃ������܂���B��Ίm���Ȃ͈̂��f���L�X�̐^��ǃA���v�ł��B
�������c�J�̂��X�ɂ��̃A���v������Ζ�肠��܂���B
�����A�����ȊO�Ő���Ƃ������Ƃł���A��L�A�h���X�֘A���˂����܂��B
�����ԍ��F8349928
![]() 0�_
0�_
inouesp�l
�@�����́Akojirou_sasaki�ł��B
�����P�[�u���M�҂̂��F�l��inouesp����̕�����ׂ̂��b�A�����ɐ\���グ�āA�������|���b�ł����B
�D�݂̍����\�����̂��Ƃ͎v���Ă��܂������A�����܂ňႤ�Ƃ́E�E�E
��������F�X�l������ł��܂��܂����B�i�܂����_�̂悤�Ȃ��̂͏o�Ă��܂��j
�����̊������^�킵���Ǝv������p�j�b�N�ɂȂ�̂������ł��܂��B
���������|���������ƂƎv���܂��B
�M�d�Ȃ��b���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F8350728
![]() 0�_
0�_
[�h���L�[�R���O�i������]
�@
��DAC�Ƃ̓f�W�^���M�����A�i���O�M���ɕϊ�������̂ŁA�E�E�E
�f�W�^���|�A�i���O�|�R���o�[�^�[�@�ł����(^^
���͖l���v���Ԃ�ɃI�[�f�B�I�M���Ԃ�Ԃ��Ă����̂�PC����ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B
�ꉞ�V�A�^�[���[���Ƃ������I�[�f�B�I���[���Ȃ鉮���������͐��N�O���炠�����̂ł����A
�@����قƂ�Ǐ\���N�O�̕��̂܂܂ŁA�O���[�h�A�b�v�����قƂ�ǂ���C�����������̂ł����A���i�g���Ă���PC��itunes�ɓ����Ă���Ȃ����r���O��BGM�ׂ̈ɁA���W�J�Z�����
�uPC�X�s�[�J�[�ł�������Ƃ�������Ă݂邩�v�ƒ��ׂ͂��߁A
�uPC�X�s�[�J�[��{�[�h�ƌ����I���L���[�����A�I���L���[�ƌ��������I�����
�f�W�^���A���v������̂����v�u�A���v�ƌ����V�A�^�[���[����AV�A���v��HD�����Ή���
�������Ȃ��v
�uAV�A���v�ƌ����E�E�E�v
�ƌ������̂����i�h�b�g�R���̔ŁA�����ł����ȕ��ɏo��A���̂��̏�ɂ�����
�Ƃ�������ł��B
�ق�Ƃ݂Ȃ���ɂ͂Ƃ��Ă����ӂ��Ă���܂��B���̏�����肵�Ă���\�������܂��B
������PC�X�s�[�J�[�͌��ǂ������̂��ŁA���C���̃I�[�f�B�I�ɂƂ��Ղ�̏�Ԃł��i�j
�ł��̂ł䂭�䂭��PC�ƃ��C���̃I�[�f�B�I�������N���āE�E�E�݂����Ȑ�̖ڕW������킯�ł��B
�����̃v���[���[��PS3�Ȃ̂ŁALAN�o�R��PC�ƃ����N���鎖���\�Ȃ̂ŁA���ꂩ���
�������莞�Ԃ������Ă����Ȏ��ɒ��肵�Ă�������ł��B
�����ɂȂ��Ă��܂��܂���(^^;
�����ԍ��F8350833
![]() 0�_
0�_
�F���ӂ́A������DAC�����߂Ċy��X��d��X�A�I�[�f�B�I�V���b�v�ȂǐF�X����ė��܂����B�ŏ���PC�̉���������Ȃ�̉����ŕ�����Ώ\�����Ǝv���Ă����̂ł����A�r������~���o�Ă��Ăǂ����Ȃ�CD�Ƃ��q���ł�荂�����ɂȂ�悤�ȕ��̂ق����悢�̂ł́H����Ǝ�芸�����荠�ȉ��i�̕��Ŏ����Ă���ȂǓ��̒��ōl�������낱��ς�茋�lj������߂��ɋA�邱�ƂɂȂ�܂����B�A�H�̓r�����傤�ǃI�[�f�B�I���Ԃ̕��i���y�j���炨�d�b�������������̓^����b���ƁA�����ǂ������獡�g���Ă��Ȃ�DAC������݂�̂Ŏ����Ɏg���Ă݂�H�Ɗ������\���o������A���D�ӂɊÂ��鎖�ɐ���܂����B
���肵���@���inouesp����ɂ��Љ��������DR.DAC2�ƃC���t���m�C�YDAC1��ESOTERIC��D-05�ƌ������Ȃ艿�i�̈قȂ�R�@��ł��B���ꂩ�炶�����莎�������č��̎����ɖ{���ɕK�v�Ȃ��̂�I�т����Ǝv���܂��B
������6����81.5dB�ɂȂ��Ă܂������s�\���͂���ɒႢ�l��Musical Fidelity��A1�𑲓|�����Ă���܂����i�ꊾ�j
A1�ł��߂ł����`A1�͊m����W���͒Ⴂ�ł����X�s�[�J�[�̋쓮�͂͂��Ȃ�̕����ƋL�����Ă��܂��B��͂�Dynaudio�̃��j�b�g���g���Ă��邩��ł����ˁH�ł������������Ƃ�����Z�b�e�B���O�����܂���Ȃ���҂ł������ł��ˁi�O�O�j�B���������܂�����ŐV����A1���o�Ă���炵���ł��ˁA�{�����E����Z���N�^�[�����[�^���[����X�C�b�`�ɂȂ��Ă��܂����B���������Ă݂����ł��B
�����������āA�����܂Ŋ��������Ⴄ�Ɓc�|�����̂�����܂��B�c
�{���ɂ��̂Ƃ���ł��ˁB�l�ɂ�蓯���ꏊ�œ��������Ă��l���ꂼ�ꊴ������������薔�����l�ł������Ⴆ�܂��������ۂ����������X����Ǝv���܂��B����Ƃ���͌l�I�Ȏ��̈ӌ��ł����AMacBook�̉����͊m���ɓ����i�т�Winpc�ɔ�ׂ�Ηǂ��Ǝv���܂��B�����I���L���E��PC�̗l�ɉ��y�Đ��ɓ�������PC�ł͂Ȃ��̂ł����܂ł̔\�͂͂Ȃ��Ǝv���܂��B�m��MacBook�ɂ̓f�W�^���i�I�v�e�B�J���j�o�͂�����Ǝv���܂��̂ł�����ŕ����Ɩ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������A�����͂���ȉ����D�����Ǝv������ł��鎖������܂�����A
�����ȉ����Ă݂�̂́A�y���݂̕����L����Ӗ��ł͕K�v���Ƃ͎v���Ă��܂��B
���̂Ƃ���ł��ˁA�ȑO�̎��͐^��ǂ̉��ƌ����Ƃ��������݂̂���m�X�^���W�b�N�ȉ����Ə���Ɏv������ł�������������܂����B����������Ƃ��ǎ��Ȑ^��ǃA���v�̉����Ė{���ɋ����A���܂ł̍l�����ԈႢ�ł��邱�Ƃ�m��܂����B���ꂩ����F�X�ȉ����y���݂̕����L���čs�������ł��B
���V���O���R�[���̑f���̗ǂ��͒�]�̂���Ƃ���ł����A�㉺������̂�
�ʂ���ł��B
�����Ȃ�ł���ˁ`�B�ǂ�ȂɗD�G�ȃN���X�I�[�o�[�ł��낤�Ɠ������j�b�g�ł��낤�Ǝ��R���ł̓V���O���ɂ͓G��Ȃ��ł����c���̏ヌ���W�ł������Ȃ��Ȃ�킴�킴���𑝂₷�K�v���Ȃ��ł����A���[���Ă݂��`���B
�����ԍ��F8351062
![]() 0�_
0�_
inouesp����@
�lj���肪�Ƃ��������܂��B
�����W�͍L�����A���v��I�Ԃ̂ł��ˁB
���̎苭���̓R���t�B�T���ł��傤���H�i��
�A���v��ւ���ƂȂ�Ə��X�l���Ă��܂��܂����A�Ƃɂ����@���������
�����������Ǝv���܂��B
�炵��ƌ����Aredfodera����
�����́B
HARBETH LS5/12A�Ƃ������Ƃ͋��R���^�[1.1���n�̃E�[�t�@�[�ł��傤���B
��Ȃ��ėL���ȃ��j�b�g�ł�������i�j�A���̃N���X�̃A�i���O�A���v�ł�
�������ł��傤�ˁB
���̈Ⴂ�łǂ��Ȃ邩�͕�����܂��A�T��DYNAUDIO�̃X�s�[�J�[�̓A���v��
�I�ԌX���������ł��B
�����ԍ��F8351529
![]() 1�_
1�_
inouesp����
�͂��߂݂Ȃ���
�����́Akojirou_sasaki�ł��B
�ȉ��A�����ς炢�̋Y���ƕ��������Ă�������K���ł��B
�̂������ł������A���ł��u�ǂ����v��n��̂́u�l�v�Ƃ����̂��I�[�f�B�I�̐��E�̓����Ǝv���܂��B����������ŁA�I�[�f�B�I�t�F�A�Ƃ��L�����i�̓�����m��`�����X�́A���ׂđ�萻�i���[�J�[�̃r�W�l�X�x�[�X�i��甄��邩�j�Ői�߂��Ă��܂��B
�����Ŏv�������u�ϑz�v�ł��B�ǂ����̉��ɖh���u�[�X�i�h���Ԏd��j��݉c���āA�l�⏬��Ƃ��o�W����Ƃ����̂͂ǂ��ł��傤�B
�C�m�E�G�X�s�[�J�[�u�[�X����A�r�`�s�q�h��H�̃A���v���x�[�X����A�v���P�[�u���̌��E�u�[�X����A�r�����̎���A���v�R�[�i�[��b�c�g�����X�|�[�^�[�{�c�`�b�R�[�i�[�A����r�o�R�[�i�[�A���X�E�E�E
�ŋ߃I�[�f�B�I�G����ǂ�ł��܂���B���ׂăl�b�g�̏��Ŕ��f�i�E�������j���Ă��܂��B�C���^�[�l�b�g�̏o���ɂ���āA�̂ɔ�ׂ���y���ɔ��z�̎��R�x���������悤�Ɏv���܂��B
�I�t�������ł����A�l�b�g�ɓ���݂̏��Ȃ��l���������߂�悤�ȁu�W���E������v�Ȃ�������A�����Ȃ��A�Ǝv���܂����B
�����Ƃ��ꂩ�瑝���čs����ł��傤�ˁB
���݂܂���A�Ƃ茾�ł����B
�����ԍ��F8351749
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�h���L�[�R���O�i������Awakamatsu181����A
LS5/12A�ւ̂������L���������܂��B
��HARBETH LS5/12A�Ƃ������Ƃ͋��R���^�[1.1���n�̃E�[�t�@�[�ł��傤���B
Contour�Ŏg�p���Ă������킩��܂��A15W7508BBC�E�[�t�@�[��D-260BBC�c�B�[�^�[�̑g�����̗l�ł��B
http://audio-database.com/HARBETH/speaker/ls5_12a-e.html
����Ȃ��ėL���ȃ��j�b�g�ł�������i�j�A���̃N���X�̃A�i���O�A���v�ł͌������ł��傤�ˁB
�������A����ς�i��j
�A���㗝�X�̂��D�ӂ�YBA�̃g�b�v���C����3���������肵�Ă�����Ŗ炵�Ă���܂������A
�C�M���X�̂Ƃ���X�^�W�I�̏Љ����LS5/12A�Ƃ̑g�����Ⴊ������Audio-Analogue���[�Ă܂����B
Martin �k���������Ɏg���Ă���KRELL�iKSL�{KST�j���Ɖ������Ȃ��������̗l�ɐU��Ă����̂ł����A
������Ɉڐ݂��悤�ɂ����x��Martin �k�����������h���C�u�ł�����̂������Ȃ��Ă��܂����̂��Y�݂̃^�l�ł��B
�ʐ^�ƏЉ�����ʼn��͑S���������M�����u�����܂�����Audio-Analogue�Ƃ̑g�����������͍D�݂ł��B
�����n�ɑ������Ȃ��ƌ����̂��A���w�E�̃E�[�t�@�[���쓮�ł��ĂȂ���ۂ��������Ȃ��͊����܂��B
�A���v2����X�s�[�J�[1��ɐU�蓖�ăo�C�A���v�^�o�C���C�A�����O���ă��m�����E�\�t�g�Ńg���C�A�����Ă��܂��B
�o�C�A���v�^�o�C���C�A�����O�̌��ʎ���ŁAAudio-Analogue���������i�܂ʼn������Ă܂����璲�B���邩�l���܂��B
inouesp����@
�����������āA�����܂Ŋ��������Ⴄ�Ɓc�|�����̂�����܂��B
���ǂ��������������Ȃ̂��́A���̂Ƃ���͂ǂ������������A�ƌ������͂���܂���B���ꂪ�I�[�f�B�I�ł��B
�����E�E�E�����l�l�̊����Ƀ_���[�W��^���Ă��܂��^�C�v�����ł��i�ꊾ�j
inouesp������͂��߂�����ɏO�Q���ꂽ�N�`�R�~�X�g�̊F����ɂ͖ڎw�����Ƀ��B�W�������������Ȃ̂��Ǝv���܂��B
���̏ꍇ�͂��̕ӂ�̈ӎ����łނ���@��i���ɃX�s�[�J�[�j�̃L�����N�^�[�ɍ��ꂿ�Ⴄ�Ƃ��낪����܂��āA
���̃L�����N�^�[���y���߂�g������Z�b�g�A�b�v���l����Ă������ł����A
���ʓI�ɃA�N�̋����@����葵�����ɂȂ��ĊF�l����������u�����ȉ��v�Ŗ炵�Ă���Ǝv���Ă��܂��i��j
�����r�o�̈�Ԃ̖��̓A���v�ŁA�����̋쓮�͂ł͋쓮���ł��Ȃ����Ƃł��B
���s��KRELL���Ƒ����̑啨���g��Ȃ��Ƌ쓮������Ȃ���������܂���B
�~�h���E�N���X�܂ł̓g���N���̂ĕʂ̃x�N�g����ǂ��Ă܂�����A���N�O��KST�ӂ�̕����K�������ł��B
����Apgee��1��82dB��炵���g���N�͉e����߂Ă��Ė��ɏ�i�ɂȂ��Ă��܂��B
�ނ���ŋ߂̓J�i�_��Classe�@Audio�̕����A�L��ő@�ׂȃ����W�Ɨ͋��������˔����Ă��菬�o�͂ł��g���N������܂��B
���͍�N�ɃG���h�[�T�[���ς���Ă���G���g���[���~�h���E�N���X������Ȃ��Ȃ����̂ʼn��i���E�E�E���߂��܂��i���j
http://www.classeaudio.jp/index.html
�����ԍ��F8353274
![]() 1�_
1�_
redfodera����A����ɂ��́B
DYNAUDIO����y�ɖ炷�Ȃ�20�`30���N���X�̃f�W�^���A���v�ł��傤�B
50�����x�̃A�i���O�A���v�ł��Ƌ쓮���邾���ŁA�Ȃ��Ȃ�DYNAUDIO�̓����܂�
�����o����A���v�͏��Ȃ��ł��ˁB����̓v���[���[�ɂ������邱�Ƃł����B
�����͐���A�X�s�[�J�[��������܂Ŋ撣���Ă������������Ǝv���܂��i��
��r�I�����A�i���O�A���v�ł�����SOULNOTE��ma1.0���x�X�g��������܂���B
���Ɏv�����̂�SOULNOTE sa1.0���v���ɂ��āA�p���[��PRIMARE A32������ł��B
����ȊO�ł���100���N���X�܂ōs���Ă��܂��悤�ȁB
���Q�l�܂ŁB
��コ��̃X�s�[�J�[�̓R���t�B�T�N���X�Ƃ���ƁAFM��X�y�N�g�����܂ōs���Ȃ���
�_���Ȃ̂�������܂���ˁi��
������da1.0�ł������������B
�����ԍ��F8354379
![]() 1�_
1�_
wakamatsu181����A����ɂ��́B
��50�����x�̃A�i���O�A���v�ł��Ƌ쓮���邾���ŁA
���Ȃ��Ȃ�DYNAUDIO�̓����܂ň����o����A���v�͏��Ȃ��ł��ˁB
��͂�g�c������I�Ȕ��z���K�v�Ȃ�ł��傤���˂��B
����ƑO�ɑ��̃N�`�R�~�X�g�̕���������l�̃A�h�o�C�X���܂����B
DYNAUDIO�͎ԍځASP���j�b�g�AMA���j�^�[�Ǝg���Ă����̂ł����A����̂͂�����Ƌ����Ă܂��B
��DYNAUDIO����y�ɖ炷�Ȃ�20�`30���N���X�̃f�W�^���A���v�ł��傤�B
���͍���ADYNAUDIO�̃V���[���[���Ƀq���g�T���ɍs���Ă��܂����B
�����Ē��������H���A�uDYNAUDIO�̃��j�b�g���������X�s�[�J�[�ł����w�̂ւ��Ȃ���v�A�Ƃ̎��B
DYNAUDIO�{�Ƃ��������V���O���E���C�������O�łȂ����A�o�C�A���v�^�o�C���C�������O�ł̐ڑ��ƁA
�ʑ��ʂŃc�C�����m�����m�����̃p���[�A���v�Ńh���C�u����̂͐����݂����ł����A
���������̍Č������������ɂ͂���Ȃ�ɓ������K�v�ȗl�Łi���j�E�E�E
Nuforce��CI AUDIO��D�N���X�E���m�����E�p���[�A���v�����肪�ĊO���������A�Ƃ̂�Ȃ����b�ł����B
�����ԍ��F8354627
![]() 0�_
0�_
�@����ɂ��́@->ALL�B �A�x���ɉ��o���Ă����ԂɁA���Ȃ�̐��̏������݂������ăr�b�N�����Ă��܂��B�ƂĂ��S���Ƀ��X�͏o���܂��A�����܂�Ńt�H���[�������Ǝv���܂��B
kojirou_sasaki����H��
���̓��[���ɐ������Ă����u�I�[�f�B�I
���}�j�A�a���́v���������n�߂��悤�ł��B
�@���̕a���̂Ɉ�x�`�����Ƃ�قǂ̂��Ƃ��Ȃ��Ɓu�����v�������܂���B�Ǐo�Ȃ��Ȃ����Ǝv���Ă��A�ӂƂ������q�ɁE�E�E�E�����A���C�Ȃ������I�[�f�B�I�V���b�v�̃V���[�E�C���h�E�A���R���X�Ŗڂɂ����I�[�f�B�I�G���A���ӎ��Ƀq�b�g�����Ă��܂����I�[�f�B�I�֘A�̃z�[���y�[�Wetc. �����������d�Ȃ�ƈ�C�ɏǏ��݉����܂��B�����A�����Ȃ�����ł�H���ΎM�܂łƂ��������ŎQ��܂��傤�i���j�B
-> 130theater����
�@���G���Ɓu���O�g���I�v�͓����N�ł��ˁB�����u���O�g���I�v�̒��ōD���������͉̂��ƐX���q�ł��B�ʂɃ��b�N�X�ʂł͉��Ƃ��v���܂���ł������A�̏��͂ɂ͈��|����Ă��܂����B���������}�C�P���E�W���N�\����}�h���i��v�����X���u���O�g���I�v�Ɠ����ł��ˁB���̐���͂��������l�ނ������ł��B
�@inouesp����́u�����P�[�u���̐M�҂ɂȂ�����F�l�v�̘b�A�Ȃ��Ȃ������[�������ł��B�u�������������������̃T�E���h�Ȃ̂����I�v�Ǝv������ł��܂��ƁA���̎�������؎���Ȃ��Ȃ�E�E�E�E�Ƃ����u���|���[�v�v�������J���đ҂��Ă���E�E�E�E�ȂǂƎv���Ɖ���炨�K�̂����肪���]���]�������܂��B�ł��܂��A����Ӗ��u�M�ҁv�ɂȂ���Ă��Ƃ͓��ʂ̃s���A�l�X������킵�Ă���Ƃ������܂��B���Ȃu���߂����悤�Ȍ����v�ɐڂ���Ɠ�����^���Ă����鐫�i�Ȃ̂ŁE�E�E�E�܂�������Ȃ��牘�ꂫ�����l�������ł�����̂ł��i�j�����j�B
�@�b�͕ς��܂����A�u�邵�̎蒟�v�Ƃ����G��������܂�����ˁi���ł����s����Ă��܂����j�B����̃I�[�f�B�I���i�ł��o���Ȃ����̂��Ǝv�������Ƃ����������܂��B
�@���̎G���̔��蕨�͊e�폤�i�e�X�g�ł��B���Ȃ�̌��i�ȍ���ŗe�͂���܂���ł����B����́A��̑�����̍L�����t���Ȃ��Ƃ����X�^���X�ɂ��\��Ă��܂��B�������u�邵�̎蒟�v�̃I�[�f�B�I�ł��ł�����A���̃I�[�f�B�I�G���Ɍ�������e��a�Ȕ������̍^���Ƃ͈�����悷���̂ɂȂ�ł��傤�B����ǂ��납�A���F�ɑ����]�͂܂������Ȃ���u�����̎��Ŋm���߂�v�݂����Ȏp���ŕЕt������͂��ł��B���̑���g������ɑ��鐸���͉s�����̂ɂȂ�ł��傤�B���Ƃ��u�A���v�̃X�s�[�J�[�[�q�̑傫���Ƒ������v�u�^CD�v���[���[�̓��쉹�ƃ����R���̑��쐫�v�u�A���v�̔��M�v�uRCA�[�q�̌��a�v�u�d�グ�̍I�فv�u�c�}�~�ނ̕i���v�Ƃ��������̂��O��I�ɒ��ׂ��A����҃T�C�h�ɗ��������|�[�g�����҂ł���Ǝv���܂��B
�@�E�E�E�E�܂��A����Ȃ��Ƃ͖����Ɍ��܂��Ă��܂����A�����������̎G���͐́u���R�[�h�Љ�v���[�����Ă��܂����B���ɂ́u�q���ɒ������錻�㉹�y�v�݂����ȓˏo���������������悤�ɋL�����Ă��܂�(^^)�B
�����ԍ��F8361711
![]() 1�_
1�_
�F���ӂ́A
������Ȗ�Ȏ�Ă�dac�̕�����ׂ����Ă���܂����A�Ȃ��Ȃ��ʔ����ł��ˁ`
���i�����̈Ⴂ���͂�����o��Ƃ��������A����ȂɈ��Ȃ��Ƃ������������E�E�E
�Ƃ肠�������x�̓��j�܂Ŏ�Ă���̂ŐF�X�ȑg�ݍ��킹�Ŏ������Ă݂܂��B
redfodera����A��ςȂ��ƂɂȂ��Ă��܂����ˁA���̎g���Ă��郂�j�^�[�R�O���ꉞBBC���j�^�[��LS5/9�̃��v���C�X���ł���HARBETH�̃X�s�[�J�[�́A�S�ʓI�ɂ���ȂɃA���v��I�Ԃق��ł͂Ȃ��̂Łi��������͕ς��܂����c�j���������܂Ŗ炵�ɂ��������Ƃ͎v���Ă����܂���ł����B����������̂ł���ΐ���CHORD�̃A���v�������Ă݂Ă��������A�ȑODynaudio�̃X�s�[�J�[����������炵�Ă��܂������A������LS5/12A�������Ă����H�Ǝv���܂��̂ő����͈����Ȃ��Ǝv���܂��B�m���ɂQ�O�`�R�O�ʂ̃f�W�A���̂ق��������葁����CP�͍����Ƃ͎v���܂����E�E�E�l�I�ɂ̓A�i���O�h�Ȃ̂�redfodera����ɂ͐�����Ă��炢�����ȁi�����̂Ȃ����x�Ɂj�Ǝv���Ă���܂��B
��������v���Ԃ�ł��B���̎Ⴂ���̃A�C�h���ƌ����Ώ����q����⒆�R���䂳�X�����ɂ�N���u�Ȃǂł��B���y�I�ɂ̓��x�b�J�ɂ͂��Ȃ�͂܂�܂����B���̌�o���h�u�[�����o��zeep��cream�Ȃǂ��悭�����悤�ɂȂ�܂����B���̌�q���a��i�������ɋ����������N���V�b�N���l�ɂȂ������������̓A�}�f�E�X�ƌ����f������Ă���ł��B���͓��ɃW�������ɂ�����炸�����D���ȉ��y�����̂Ƃ��̋C���ŕ����Ă��܂��B
�����ԍ��F8367467
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�h���L�[�R���O�i������
��������Ȗ�Ȏ�Ă�dac�̕�����ׂ����Ă���܂����A�Ȃ��Ȃ��ʔ����ł��ˁ`
���C�����A�悭�킩��܂��B
�����i�ƈ�̌^CDP�܂Ŋ܂߂�ƌ���7��DAC���茳�ɂ���܂����ǖ�����܂�ňႢ�܂�����B
����3�����ŐV����荬����3�����B���Ă��܂��o���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A��Ȃ�����߂����Ǝv���Ă܂��B
��HARBETH�̃X�s�[�J�[�́A�S�ʓI�ɂ���ȂɃA���v��I�Ԃق��ł͂Ȃ��̂Łi��������͕ς��܂����c�j
�����������܂Ŗ炵�ɂ��������Ƃ͎v���Ă����܂���ł����B
���l�I�ɂ̓A�i���O�h�Ȃ̂�redfodera����ɂ͐�����Ă��炢�����ȁi�����̂Ȃ����x�Ɂj�Ǝv���Ă���܂��B
���C�����L���������܂��B
LS5/12A�͉������Ė��J���̃f�b�h�X�g�b�N���i���œ���ł��邱�ƂɂȂ�A�����y���C�����œ���������ł��B
�����g���Ă݂�������̘A���ł��āA����ȓ���Ƃ͑S���\�z���Ă܂���ł����i���j
Audio-Analogue�ŕ�����Ȃ��������Ă��܂������ɁA�炷�@����_�E���O���[�h���Ă��܂������Ƃ�����܂��B
�q����YBA�̃g�b�v���C���ɂ���A������KRELL�ɂ���A�l�i�����ōl���Ă������ɂ���3�{�ȏ�̂��̂ł�����B
�{���A�قǂقǂɖ�u���i�����v�ł���͂��Ȃ̂ɁA�����炪�ߓx�̊��҂����Ă�l�Ɏv���܂��B
�܂����݂́A�o�C�A���v�ŗl�q���݂Ă���Œ��ł����A���_��扄���ɂ��ď�����ÂɂȂ�K�v�������Ă܂��B
�u���s����������I�v�ŔM���Ȃ��ē˂�����A�������L����̂��A��ԁA�����I���Ɏv���܂��̂ŁE�E�E
���Ԃ��|���Ă������撣���Ă݂܂��B
�����ԍ��F8368561
![]() 0�_
0�_
redfodera����
>�{���A�قǂقǂɖ�u���i�����v�ł���͂��Ȃ̂ɁA�����炪�ߓx�̊��҂����Ă�l�Ɏv���܂��B
��DYNAUDIO�́A�قǂقǂ̃A���v�ł͂قǂقǂɖ�Ȃ��Ƃ��낪��ƌ���ꂽ���Ȃł��B
��������������B
�Q�l�ł����A�����ɏo��SOULNOTE�̃p���[�A���v�����Ȃ�̋쓮�͂�����Ƃ̐��]�̂悤�ł��B
�����ԍ��F8373557
![]() 0�_
0�_
���E�������
�u��炵�̎蒠�v�̈��p�A�����Ȃ���̍����ڐ��ł̂��ӌ��A�Q�l�ɂȂ�܂��B���͏�X�v���Ă���̂ł����A�u�I�[�f�B�I�@��͂��Ȃ��ɂƂ��đ厖�Ȃ��̂̉��ԖڂɂȂ�̂��v�ƌ����₢�ւ̉Ƃ��āA10�N�O�Ȃ�T�{�̎w�ɓ��邭�炢�̑厖�Ȃ��́A�������̂ł����ŋ߂ł͎葫�̎w�̑����ɂ�����Ȃ��Ȃ�܂����B�������Ȃ��Ȃ����Ƃ������A�������E�l�����̕ω��ɂ����̂ł��B�����������Ӗ��ő��u���厖�Ȃ̂́A�b�c��R�[�h�Ȃǂ́u�|�p�v�ł���A�ۗL���������������ƂŎ����̐l���Ɋ��Y���Ă����ՂƂ����̂͂��������̂Ȃ����́A�厖�ȃ��m�Ƃ��ĔF�����Ă��܂��B
�@
�@���_�̏o�Ȃ��I�[�f�B�I�k�`���y�����ł����A������ł�����ƃR�[�q�[�u���[�N�Ƃ��āA�ڐ���������ƈႤ�ӌ����Љ�Ă����܂��B���͂��̕��̃t�@���ł��B
http://www.op316.com/tubes/tips/tips19.htm
http://www.op316.com/tubes/tips/tips15.htm
http://www2.famille.ne.jp/~teddy/tubes/moso.htm
http://www2.famille.ne.jp/~teddy/honneb/honneb3.htm
�����ԍ��F8374606
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
wakamatsu181����A����ɂ��́B
����DYNAUDIO�́A�قǂقǂ̃A���v�ł͂قǂقǂɖ�Ȃ��Ƃ��낪��ƌ���ꂽ���Ȃł��B
�K�`���[���I
�V���b�L���O�Ȃ��b�A���肪�Ƃ��������܂��i���j
��O����X�s�[�J�[��������O�ɁA������̈ӎ�������Ă܂���܂����B
��Ȃ��炦�炢���̂����������Ă��܂������ƂɁA����Ɠ��u���ӑR��̂ƂȂ������G�ȐS���ł��B
inouesp����@
�ʔ����Ƃ������A���ɃO�T�b�I�Ƃ��S�����s�b�I�ƕs���������������Ȃ��b�̃I���p���[�h�ł��ˁB
���̏ꍇ�͎v�������鎖�Ă��ƂĂ������āA�v�킸�[�������}���邱�Ƃ�����B
���̎�̃l�^������قǑ�����������Ă��邾�����q�ǂ��鉿�l������T�C�g�ł��B
�����ԍ��F8380620
![]() 1�_
1�_
�^�ʖڂȂ��肢�ł��B
����ȃN�\�d���X���͑��̔ł���Ă��炦�܂��B
�{���ɖ��f���Ă��܂��B
�ڐА�̓X�s�[�J�[�������ł��B
�������ɂ͕ʂ̃N�\�d���X��������̂ł���ƈꏏ�ɂ���Ă��炦���낵�����Ǝv���܂��B
��������ǂꂾ�����f�������ł���Ǝv���܂��B
���낻�낱�̃X�����I��点�ăX�s�[�J�[�ŐV�K�ɃX�����Ă��Ă��������B
���肢���܂��B
�{���ɂ��肢���܂��I�I�I
�����ԍ��F8381187
![]() 0�_
0�_
���B���p�t����@
��r�I�����d���X���Ƃ͎v���܂��E�E�E
�d���Ɗ�����Ȃ�ւ��Ȃ�������b�ł͂Ȃ��ł��傤���B
My�y�[�W�₨�C�ɓ���̍��ڂ��ǂ��ݒ肳��Ă邩�͕�����܂��A�Ⴆ��
�X�V���ɂ��Ă����Ė����ʂɂ���̂��E�U���Ă������Ă���̂ł��傩�H
�d���y���͂��̃X���ɏ����������Ǝv��Ȃ��Ɗ����Ȃ������Ǝv����ł����ǂ˂��A
���܂肻�̂ւ�̐ݒ�ŏڂ����Ȃ��̂ƁA���������C�ɓ���ɐݒ肵�Ă��鍀�ڂ�
�������ւ���Ă��Ȃ��X���ɑ��Ă��d���Ƃ����������Ƃ��Ȃ��g�Ȃ̂ŁA
�����Ԉ���Ă���̂Ȃ�t�ɋ����ĉ������B
�����ԍ��F8381746
![]() 2�_
2�_
���߂�Ȃ����A������ƌ����߂�����������܂���B
�X�s�[�J�[�̂��̖��_�o�X���ɈȑO����ނ����Ă����̂ʼnߕq�ɂȂ�܂����B
60���X���x�ł͂�����Əd�����x�ł��B
�ł�50���X���x�ŐV�X���𗧂��グ�Ă��炦��Ώ�����͎̂����ł��B
�����ƑO����X�s�[�J�[�͊J���Ă܂���B
���M�����L���O�Ō����700���X�ɂȂ��Ă���̂ŊJ���̂�����ł��傤�B
���̓p�[�g�Q�ɂȂ��Ă܂����p�[�g�P�̂��납��J���Â炭�Ȃ��ăX�s�[�J�[�����Ȃ��Ȃ�܂����B
���_�o�ɂ��قǂ�����܂��B
�Q�����Ă���l�̓X�����L�т�Ɗy������������܂������̂Ȃ��l�Ԃɂ͖��f�疜�ȊO�̉����̂ł�����܂���B
�J�e�S���[�S�������n�����߂ɂ͍X�V���ŊJ���Ȃ��ƌ���Ȃ��̂œ���̃X���������Ȃ��Ƃ����I�����ł��܂���B
�����珑�����݂���A���Ȃ��͊W�Ȃ��ł��B
���̐l�Ƃ��̓T�N�T�N�����̂�������܂��A�X���傳��͒x���l�̂��Ƃ��l���Ă���������Ə�����܂��B
�����ԍ��F8385285
![]() 0�_
0�_
���ꂩ�炱�̃X���̓��e��CDP�ɖ��W�Ȃ��Ƃ̓X��������m���Ă���͂��ł��̂ŁA�W�Ȃ��̂Ȃ�V�X���Ɉڍs����ꍇ�͐���X�s�[�J�[�ł��肢���܂��B
���̃N�\�X�������݂���ȏ�͎��̓X�s�[�J�[�͌���Ȃ��̂Ő�����œ��킹�Ă��������B
�����ԍ��F8385414
![]() 0�_
0�_
�B���p�t����
�������Ȃ��ɕs�����Ȏv�����������̂Ȃ炷�݂܂���B
���������̃X���ɑ���s���ł͂Ȃ��ق��̃X���̕s���������ł���������Ă�������������Ă��܂��܂��B
��700���X�ɂȂ��Ă���̂ŊJ���̂�����ł��傤�B
�����̓p�[�g�Q�ɂȂ��Ă܂����p�[�g�P�̂��납��J���Â炭�Ȃ��ăX�s�[�J�[���Ȃ���
����܂����B
�m����700�ȏ�X�����L�тĂ���Ɗ��ɂ���ẮA���Ȃ�d����������X�g���X�������邱�Ƃ����邩������܂���B�{���ɘB���p�t�������Ă���̂ł�����A������̃X���ł�����Ƃ��̂��Ƃ����`�������ق����ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H����ł����P����Ȃ��Ȃ牿�i.com�ɂ����k����Ă͂������ł��傤���H
���Q�����Ă���l�̓X�����L�т�Ɗy������������܂������̂Ȃ��l�Ԃɂ͖��f�疜�ȊO
���̉����̂ł�����܂���B
���J�e�S���[�S�������n�����߂ɂ͍X�V���ŊJ���Ȃ��ƌ���Ȃ��̂œ���̃X��������
���Ȃ��Ƃ����I�����ł��܂���B
�������珑�����݂���A���Ȃ��͊W�Ȃ��ł��B
���݂܂��S�҂Ȃ̂Ŕ���Ȃ��̂ł��������̂Ȃ��X���͔���ēǂ߂悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���̂��߂ɃX���̍ŏ��ɍŌ�̃y�[�W�ɔ���{�^��������Ǝv���Ă��܂����B
�����̐l�Ƃ��̓T�N�T�N�����̂�������܂��A�X���傳��͒x���l�̂��Ƃ��l���Ă���
��������Ə�����܂��B
���̃X���̃X����ł��錳�������͂�����ƍl���Ă���Ǝv���܂���B������펯�I�Ȕ͈͓��ł���150�O��ŃX�����X�V���Ă��܂��B�B���p�t�����50�`60�ōX�V���ƌ������Ƃł�������ł͓����X�����葝���������ĔS�̂��g���ɂ����Ȃ�Ƃ������܂��B����Ɏ������̃X���̂��Ƃ�m�����͈̂ȑO�̃X����100�ȏ�L�тĂ�������ł��B�������狻������������܂�ROM�����������̂ɎQ�������Ă��������悤�ɂȂ�܂����B���������l������Ƃ������Ƃ�B���p�t������������Ăق����ł��B
��CDP�ɖ��W�Ȃ��Ƃ̓X��������m���Ă���͂��ł��̂ŁA�W�Ȃ��̂Ȃ�V�X���Ɉڍs��
����ꍇ�͐���X�s�[�J�[�ł��肢���܂��B
�m����CDP�����̘b��ł͂Ȃ��ł����A�܂��������W�̘b��������Ă���킯�ł͂���܂���A�{���̓I�[�f�B�I�@��S�ʂ̌f��������Ηǂ��̂ł����c�O�Ȃ��炠��܂���B
���Ȃ��̏������݂����Ă���Ƃ����P�Ɏ����ɋ����̂Ȃ��b�������X���͂��ׂăN�\�X���Ŏ����̋����̂���X���͗ǃX���ł��̗ǃX���������̊��ł̓T�N�T�N����Ȃ��̂ł悻�ł���Ă���ƌ������Ɏ�������Ȉӌ��ɕ�������̂ł����B���Ȃ��ɂƂ��Ă͋����̂Ȃ��b��ł����Ă��X�����L�тĂ���ƌ������Ƃ͂��ꂾ�������������Ă���l������ƌ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F8387217
![]() 1�_
1�_
���B���p�t��said
������ȃN�\�d���X���͑��̔ł���Ă��炦�܂��B
�@�f��B���łɁu�Ă���28�����v����Ɓu�h���L�[�R���OJr.�v���I�m�ȃ��X������Ă��܂����A���߂Ď��̌����������Ă������B�A�i�^�̈ӌ����C�ɂȂ�Ȃ����R�͈ȉ���3���B
(1)���͂������������_��70���x�̃��X���ł́u�d���v�Ƃ͎v��Ȃ��B
�ʂ̉��i.com�̌f���ł��������ݐ�����C�O�S�ɂȂ�X���b�h�͑��݂��邪�A�u�h���L�[�R���OJr.�v����̌�ӌ��ɂ�����悤�ɁA���̓��X��150���x�Ő�グ�Ă���B�������A�A�i�^�́u�N�\�d���v�ƌ����Ȃ��炷�ł�3�A�[�e�B�N�����A�b�v���Ă���X���b�h�́u�d�ʑ����v�ɉגS���Ă���B�܂�͑ԓx�ɐ������������Ȃ��B
(2)�u���\�̃R�[�i�[�ł��v�Ƃ����������ɂ͍��������Ȃ��B
�X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�Œ���X�������邩��A�����X���͑S�������ł��Ƃ��������͒ʗp���Ȃ��B�Ȃ�u�X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�̓ǎҁv�͂ǂ��Ȃ��Ă������̂��H�@�X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�Œ���X����W�J���Ă���ҒB�ɑ��Ă͉��������Ă��Ȃ������ɁA�ʂ̃R�[�i�[�̑S���W�̂Ȃ��X���b�h�ɔ��߂������Ƃ������̂͋؈Ⴂ�Ƃ������̂��B
(3)���������A����Ȃ��Ƃ̓{�[�h�Ǘ������ǂɌ����ׂ����B
�{���Ɂu�����X���͖��f�疜�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��v�Ǝv���̂Ȃ�A���i.com�̎����ǂɐ\����������B�������������X���Ɂu�������邼�A�R��!�v�Ƃ������������݂����Ă��A�v��ʃo�g�����Ăэ��ނ����ŁA�����ł��������X�����܂��܂��u�d���v�Ȃ�\�����������낤�B
����ɁA�e�g�s��ɂ͈�Q���҂ɉ߂��Ȃ��A�i�^�̎咣�ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��`���͂Ȃ��B�������ɏ]���K�v������̂́A���肪�{�[�h�Ǘ��҂̏ꍇ�������B����āA�{�[�h�Ǘ��҂̑����瓮���Ă����Ȃ��Ǝ��Ԃ̎��E�͕s�\�ł���A����𑣂��s���������{�ł���B���Y�X���b�h�ɋ��̏������݂����Ă����ʂ��B
�@���Ɓu�N�\�v���̉����̂Ƃ��������̑P�������ɂ��ẮA�����ł͖ڂ��Ԃ낤(^^;)�B
�@�Ȃ��A�X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�̒���X���b�h�ɂ��Ă͎��������ɂ͎v���Ă��Ȃ��B���̒��q�Ńp�[�g3�܂ŗ����グ��悤�Ȃ�A�����ǂɐ\������\��ł���B�ȏ�A���M����B
�����ԍ��F8390559
![]() 2�_
2�_
> ���݂܂��S�҂Ȃ̂Ŕ���Ȃ��̂ł��������̂Ȃ��X���͔���ēǂ߂悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���̂��߂ɃX���̍ŏ��ɍŌ�̃y�[�W�ɔ���{�^��������Ǝv���Ă��܂����B
�X���̍ŏ��Ɂu�X���b�h�̍Ō�ցv�Ƃ��������N������̂͋C�Â��܂���ł����B�����Ă���Ă��肪�Ƃ��B�������ǂݔ���͓̂��R�ł�������ȑO�Ƀy�[�W���J�����Ǝ��̂�����ł����炻��ȑO�̖��ł��B
> ���̃X���̃X����ł��錳�������͂�����ƍl���Ă���Ǝv���܂���B������펯�I�Ȕ͈͓��ł���150�O��ŃX�����X�V���Ă��܂��B�B���p�t�����50�`60�ōX�V���ƌ������Ƃł�������ł͓����X�����葝���������ĔS�̂��g���ɂ����Ȃ�Ƃ������܂��B
150�O�オ�펯�I���Ƃ͎v���܂���B����ł͊ԈႢ�Ȃ��d���ł��B�����X���������Ă����R�ɗ����Ă����܂�����g���ɂ����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����O��̖������킩��ɂ����Ȃ�Ƃ������ƂȂ�Ήi���ɃX����L���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����ɂ���Ȓ����X���ɎQ�����Ă���l�͌p���I�ɓǂ�ł���ł��傤����g���ɂ����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B�g���ɂ����Ƃ����Ӗ��ł͔��d���Ȃ�ق����g���ɂ����̂ł���B�ł�����50�`60���K���Ǝv���܂��B
> �m����CDP�����̘b��ł͂Ȃ��ł����A�܂��������W�̘b��������Ă���킯�ł͂���܂���A�{���̓I�[�f�B�I�@��S�ʂ̌f��������Ηǂ��̂ł����c�O�Ȃ��炠��܂���B
���e��CDP�ɊW�Ȃ��Ƃ������Ƃ̓X��������m���Ă��܂��B�I�[�f�B�I�Ƃ����J�e�S���[�͂Ȃ��̂ł����𗘗p�����̂��Ǝv���܂����W�Ȃ��̂ł���u�Ɠd�v�Ƃ������̃J�e�S���[�ɓ��e����̂��K���Ǝv���܂��B
> ���Ȃ��̏������݂����Ă���Ƃ����P�Ɏ����ɋ����̂Ȃ��b�������X���͂��ׂăN�\�X���Ŏ����̋����̂���X���͗ǃX���ł��̗ǃX���������̊��ł̓T�N�T�N����Ȃ��̂ł悻�ł���Ă���ƌ������Ɏ�������Ȉӌ��ɕ�������̂ł����B���Ȃ��ɂƂ��Ă͋����̂Ȃ��b��ł����Ă��X�����L�тĂ���ƌ������Ƃ͂��ꂾ�������������Ă���l������ƌ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H
�ʂɋ����̂Ȃ��X������Ă���킯�ł͂���܂���B�d�����Ƃɕs���������Ă��邾���ł��B�X�����L�тāA����������l���������Ă������R�ɂ���Ă��炦��Ό��\�B�������X��50�`60�ɂȂ�����V�X���𗧂��グ�ė~�����Ƃ����Ă���̂ł��B���Ȃ����d���X�����u�X�����L�тĂ���ƌ������Ƃ͂��ꂾ�������������Ă���l������ƌ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H�v�ƍm�肷��̂ł������700���̃��X�����Ă���X�����m��Ȃ���Ƃ������Ƃł��B������̃X���ł��������̂܂ܑ����Ă����Ώd���Ďg���ɂ����Ȃ�̂Łu�^�ʖڂȂ��肢�v�����������ł��B������ɂ͉��̌���������܂���ˁB
�X���傪�u�f��v�Ƃ����ԓx�ł�����d������܂��X����̖{�����_�Ԍ����悤�ȋC�����܂��B
�����ԍ��F8392774
![]() 1�_
1�_
>�@�A�i�^�́u�N�\�d���v�ƌ����Ȃ��炷�ł�3�A�[�e�B�N�����A�b�v���Ă���X���b�h�́u�d�ʑ����v�ɉגS���Ă���B�܂�͑ԓx�ɐ������������Ȃ��B
�ނ��Ⴍ����ł��ȁB�s���������Ă����������ȂƂ������ł����B
> �X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�Œ���X�������邩��A�����X���͑S�������ł��Ƃ��������͒ʗp���Ȃ��B
���Ⴀ�Ȃ�CDP�̔Ȃ̂��B�����g�Ŗ`����CDP�ƊW�Ȃ��ƔF�߂Ă���������B�W�Ȃ��̂Ȃ�u�Ɠd�v�̃J�e�S���[�ł��悢�ł��傤�B
> �Ȃ�u�X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�̓ǎҁv�͂ǂ��Ȃ��Ă������̂��H
���̔̐��퉻�������]��ł����l�ł���B
> �X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�Œ���X����W�J���Ă���ҒB�ɑ��Ă͉��������Ă��Ȃ������ɁA�ʂ̃R�[�i�[�̑S���W�̂Ȃ��X���b�h�ɔ��߂������Ƃ������̂͋؈Ⴂ�Ƃ������̂��B
���͌����Ă���B���������̏C�����Ȃ���Ȃ��̂ł�����߂Ă���B���̃X���ɂނ����Ă���͎̂��������A����Ƃ͊W�Ȃ����̃X�������̂܂ܑ�����Ώd���ĊJ���̂�����ɂȂ�̂ł��̑O�Ɂu���肢�v�����������ł���B
> �e�g�s��ɂ͈�Q���҂ɉ߂��Ȃ��A�i�^�̎咣�ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��`���͂Ȃ��B
���̂Ƃ���Ȃ̂Łu���肢�v�������̂ł���B�u�f��v�Ƃ������Ƃ����R�̑I�����̈���B
> ���Y�X���b�h�ɋ��̏������݂����Ă����ʂ��B
���ʂȂ悤�ł��ˁB
> ���M����B
�v���o���܂������ȑO�ɂ�����̂悤�Ȋ����œ��e���Ă��܂����ˁB������v���o���ׂ��ł����B�����������Ȗ��ʂȂ��Ƃ����Ȃ��ōς��낤�ɁB
���������悤�ɂ���ȏ㏑���Ă����ʂȂ悤�ł����A���������悤�ɗ]�v�ɏd���Ȃ��Ă��܂��̂ł����ŏI���ɂ��܂��B
�����ԍ��F8392871
![]() 4�_
4�_
��l�̈ӌ��������̏�ʼn������悤�Ƃ��Ă����ʂ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F8393798
![]() 1�_
1�_
���`�������߂Ă���l�ł����A����PC���ł͉��ɂ����Ȃ��̂Łu�����悵���v�ł�����
���B(�ł����̗l�ȂƂ���Łu�N�Z�v�Ƃ������͂�߂Ă��������B)
����A�A�L���t�F�[�Y�̎�����ɍs���ė��܂����B�A�L����DG-48�Ƃ����u�f�W�^���E���H��
�V���O�E�C�R���C�U�[�v������̎�����Ŏg�p�@��̓v����C-2810�A�p���[��M-6000×2�ASA
-CD�v���[���[��DP-700�A����ɃN���[���d�����u��PS-1210�������܂��B�X�s�[�J�[��JBL
��S-9800SE�Őڑ��P�[�u���ނ��A�L���t�F�[�Y�̗l�ł����B(�X�s�[�J�[�̓o�C���C���[�Ń�
�[�J�[�͕s���Ȃ���n�ڋ@�Ɏg���P�[�u���̗l�ɑ������ł����B)���̑g�ݍ��킹���Ƃقڃn
�C�G���h�ŕs���������g�ݍ��킹���Ǝv���܂��B(���z�I�ɂ͒P���v�Z800�`900���~�ʂł�
�ˁB)�Ȃ��u�t�̕��̓A�L���t�F�[�Y�̂��̐��i�̊J��������Ă�����ю��ŁA2����10����
�炢�̎��ԁA�F�X��SA-CD(CD)�ՂłƂĂ��M�S�ɐ������Ă��������܂����B
�I�[�f�B�I�}�j�A�A������㋉�ƂȂ�ƃg�[���R���g���[���Ƃ����̗l�ȃC�R���C�U�[�̗l
�ȕ�����݂�����͎̂ד��Ƃ����l��������܂��ˁB����������n�܂�O�͂���Ȃ��̕s
�v���ȁI�Ǝv���Ă���܂������ADG-48�͂���ȊT�O�����̂ł����B�J���҂̕����ڂ̑O
�Ŏ��ۂɉ����Ȃ���ADG-48�ʼn����o����̂��F�X����Ă����Ƃނ���K���i�̗l�ȋC
�����Ă��܂����B�Ⴆ�ǂ�ȕ����ɂ���ݔg�Ƃ����������݂��A����̕�͂ƂĂ����
�Ȃ̂ł����A������g���Ɣ�r�I�ȒP�ɕ�o����̂ł��B�܂��AL/R�̃X�s�[�J�[�ݒu��
���ɂ���Ƃ����͈̂�ʉƒ�ł͂قڕs�\�Ȃ̂ł����A����DG-48�͕���Ă�����
�ł��B
�����A�������݂����鎖�ɂ�艹���̗������Ă͉����Ȃ�܂��A���܂Ń_���ȕ�
�������鎖�ɂ������m���Ɍ��サ�܂��B�E�E�E���y���y���ނɂ͒��������ɗ�
��̂��ǂ��̂ł����A���_�ƃf�[�^�Ɋ�Â��ăI�[�f�B�I�I�ɒ�������̂͂��肾�Ǝv����
���B�Ȃ��Ȃ�Ύ��ۂɉ��y���͉̂������̉��Ő����t�Ȃ炢���m�炸�A���ۂɉ��y��
�y���ނ̂̓I�[�f�B�I���u���g���Ċy���ނ̂ł�����I�I�B
���ɂƂ��Ă͍ő�̖���78���~�Ƃ������i�ł��B(��������₵�Ă݂܂������A�����ȃn�C
�G���h�̕��̗v��������ɂ͑Ë��͏o�����A�p�[�c���������i���ȕ������I���Ďg����
����ނ���������炢�H�Ƃ̎��ł����B���������m��܂���A������g�����Ƃɂ��A����
���܂߂��I�[�f�B�I���̔\�͂�100���߂������ł��鎖�ɂȂ�̂ł�����I�I�B)
�����ԍ��F8396714
![]() 1�_
1�_
130theater����
����ɂ��́B�����A�f�W�^���E���H���V���O�E�C�R���C�U�[DG-48�ɋ�������N�`�ł��B�j���e���h�[DS����ɂ͓�����O�i!?�j�̃X�^�C���X�y�����C�ɂȂ�܂��B�Ƃ���ŁA������Ƃ͂��Ă����A���̋@����g�����Ƃɂ��A�ɒ[�Șb�A�Ⴆ�u�X�s�[�J�[��������̕z�c�̊ԂɁA�͂���Łv�ݒu���Ă��i�u�b�N�V�F���t�Ȃ�ʉ�����V�F���t�E�j�A���̃X�s�[�J�[�̖{���̎��͂�����Ȃ�Ɉ����o����A�ƍl���Ă������̂Ȃ̂ł��傤���H
�����ԍ��F8397481
![]() 0�_
0�_
���B���p�t��said
���s���������Ă����������ȂƂ������ł����B
�@����Ȃ��Ƃ͒N�������Ă܂���B�ӌ����q�ׂ�̂́u���R�v�B���������肪���̈ӌ���ۂނ��ǂ������u���R�v�B�������ꂾ���ł��B
���u�Ɠd�v�̃J�e�S���[�ł��悢�ł��傤�B
�@�Ȃ�u�Ɠd�̃R�[�i�[�̓ǎҁv�͂ǂ��Ȃ��Ă������̂��H
���i�X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�́j���퉻�������]��ł����l�ł���B
�@���Ɠ������̂��̂��B�������̃X���b�h���X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�Ɉڂ�����A�A�i�^�̌����u�N�\�d���v�X���b�h�������Č��ʓI�ɂ��̃{�[�h�̓ǎ҂�����ł͂Ȃ��ł����B�X�s�[�J�[�̃R�[�i�[�̓ǎ҂ɖ��f���|����悤�Ȃ��Ƃ��u�����v���Ă��邭���Ɂu���퉻��]�ށv�Ƃ͂������������b�X���B���悤�ɁA�A�i�^�̕��͂ɂ͋̒ʂ����Ƃ��낪���o���Ȃ��ł��ˁB
�����͌����Ă���B���������̏C����
���Ȃ���Ȃ��̂ł�����߂Ă���B
�@�ł̓{�[�h�Ǘ������ǂɂ͌������̂��H
���u�f��v�Ƃ������Ƃ����R�̑I�����̈���B
�@������f���Ă��܂��B
������ȏ㏑���Ă����ʂȂ悤�ł�
���i�����j�����ŏI���ɂ��܂��B
�@�ł́u�A�i�^�͓�x�Ƃ��̃X���b�h�Ɍ���Ȃ��v�Ɨ��������B�����l�B���x�́i�ʃX���b�h�ł́j�u���ݓI�ȁv�������݂����҂��������̂ł��B�ȏ�B
�����ԍ��F8399792
![]() 0�_
0�_
�@inouesp���Љ�ꂽ�T�C�g��ǂ�ł݂܂������A���Ȃ�����_������^��Ɏv���_������܂����B�܂��́u���̃A���v�v�}�j���A�� / �G�w�ҁv�̒��ɂ���u���I���ɑ��鑍���͂��Ȃ��ƁA�ǂ����̃A���v��I�[�f�B�I�V�X�e���Ȃǐ�ɍ��Ȃ��v�Ƃ����͎̂������ӌ��ł����A���̌�ɂ���u�ǂ��������Ȍ`���ł��Ă���l�́A�����������邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ̂�����́A����̗���ł͂����łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v���܂����A��ʃ��X�i�[�̃��x���ł͓��Ă͂܂�܂���B�����������[�U�[�̒��Ɂu�ǂ��������Ȍ`���ł��Ă���ҁv�͂��������ǂꂾ������̂ł��傤���B
�@������u���͂������������D���Ȃ̂��I�v�Ǝv���Ă��Ă��A�������J��Ԃ��Ă����Ǝ��́u�S�R�e�C�X�g�̈Ⴄ���v���D�����������Ƃ�������P�[�X�����X����܂��B�N��Ƌ��ɉ��̚n�D���ς�邱�Ƃ��������͂���܂���B������D�݂̉���������ɂ͂��̃T�C�g�̎�Ɏ҂��l�K�e�B���ɑ����Ă���u���낢��Ƃ������ĉ����ς�邽�тɈ���J���邱�Ɓv���J��Ԃ������Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��A�I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��Ă͂�����y�����̂ł����ǂ�(^^;)�B
�@���Ɓu�Z�p�v�l�E�_���v�l�̊낤���v�Ƃ����̂͂悭������܂��B�I�[�f�B�I�@��͋Z�p�I�Ȑ�������˂��l�߂ĊJ���������̂ł�����A�Z�p��_���͖����ł��܂���B�������A�ߓx�ɂ���Ɏ����Ă��܂��ƑO�i�߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�I�[�f�B�I���i�̐v�E�J���ɂ����āu����������A�����Ȃ��āA��������Ɍq������͂����v�Ƃ������Ƃ���ɒʗp����Ȃ��J�͂��Ȃ��̂ł��B������n�[�h�����Z�p�I�ȎY���ł��A��������l�Ԃ̎��͌l��������A���������̚n�D�͈�肵�Ă��܂���B�Z�p�͑�ł����A����ȏ�Ƀq�A�����O���d�����ė~�����Ǝv���܂��B�O�ɂ������܂������A�ǂ������{�̑�胁�[�J�[�͂��̓_���a���悤�Ɏv���܂��i���ɃX�s�[�J�[�̊J���Ɋւ��āj�B
�@�|���h���L�[�R���OJr.����
�@���́A�����q�́u���}�g�i�f�V�R���ω��v��12�C���`�V���O���������Ă��܂��i���j�B7���ȏ������A�r���Łu���v��璆������n�[�h���b�N���̃M�^�[�E���t��炪�}�������Ƃ�������ł����A�����͍ō����x���ł��B���j�����q�N���u�E�E�E�E�m�������o�[��30�l���炢�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ƂĂ����O�Ȃ�Ċo�����܂���ł����i�����o�[�̒��ɂ͍��ł��|�\�E�Ŋ��Ă���҂�����悤�ł����� ^^;�j�B���x�b�J�̈�A�̃f�B�X�N�̓f�W�^���^���ł�����ˁBCBS�\�j�[���ł����{�̃|�b�v�X�̘^���ɋC�������Ă��������ł��B
�@�u�A�}�f�E�X�v�͌���ł����B���e�����邱�ƂȂ��特�y�ē̃l���B���E�}���i�[�̑��݂��傫�������Ǝv���܂��B�N���V�b�N���y���l�^�ɂ����f��ł̓o�b�n�̓�Ԗڂ̍ȃA���i�E�}�O�_���[�i�̖ڂ��猩�����n���E�Z�o�X�`�����E�o�b�n�̐��U��`���u�A���i�E�}�O�_���[�i�E�o�b�n�̓��L�v����ۓI�ł����B�o�b�n�ɕ����Ă����̂������ȃL�[�{�[�h�t�Ҍ��w���҂̃O�X�^�t�E���I���n���g���Ƃ����̂������ł����B17���I�̓V�ˉ��y�ƃ}�����E�}���ƁA���̎t�̂���܂��V�ˍ�ȉƃT���g�E�R�����u�Ƃ̊�����`�����l�ԃh���}�u�߂��舧�����v���f���炵���f��ł��B�E�E�E�E�f��̘b�ɂȂ�Ǝ~�܂�Ȃ��̂ŁA�����܂łɂ��Ă����܂��i�j�B
�����ԍ��F8399807
![]() 0�_
0�_
�X�o��20000����@�͂��߂܂��āB
>�Ⴆ�u�X�s�[�J�[��������̕z�c�̊ԂɁA�͂���Łv�ݒu���Ă��E�E�E
����͂������ɖ����ł��傤�B��̌��E�Ƃ����������锤�ł��B���g�ɂ��Ă������̍\
��/�T�C�Y����ǂ����Ă���_�ƂȂ�ӏ������݂��Ă��܂��A���̗l�ȂƂ���͊��S�ȕ��
�o���Ȃ������ł��B�����A���̏ꏊ���e�X�g�g�[���𗬂����ɂ�蕪����܂�����A������
���������|�C���g�ł������Ȃ���̃|�C���g�����炷���̑łĂ܂��B
���̃C�R���C�U�[�͎����D�݂̉������o����A�Ƃ����̂�����ł��̃X�^�C���X�y���Ŕg
�`�����R�ɕω������鎖���o���܂��B���̃C�R���C�U�[�̎g�����͂܂��t���b�g�ɂ��āA��
���鏊��������牺���鏊�����A���܂�ɒ[�ȕω��͂����Ȃ����X�ׂ��Ȏg������������
�Ă���܂����B���ɋ����[���@��ł��B�E�E�E�������A78���~�o��o����Ƃ��Ă��X�s�[�J
�[���悩���m��܂���B30�`40���~�ӂ�̉��i�ł������瑊���Y�ނ����m��܂���ˁB
�����ԍ��F8402638
![]() 0�_
0�_
����`�`�A�F�l���v�Ԃ�ł��I
���݃{���}���V������4.5��E�o���ׂ������P���������T���ɖz�����Ă���܂����B
�u���������l�s�H�v�ƐM�����Ȃ��悤�ȏꏊ�ɁA���ɑł��Ă��̕���������
�������ɂ͈����z���\��Ō�����܂��B
������������14����A���C���̃I�[�f�B�I���[���͕ό`�W����͂���Ǝv���܂��B
�����A�����̂��錚���̕~�n���Βi�ŏオ��悤�ȏꏊ�Ȃ̂ŁA4344�̎��e���E�E�E�B
�����������ɂ͐܂��݂̒�q�����Ȃ��̂Ŗ����I�����֗���4344�̏����ɈÉ_���E�E�B
�����������ăl�b�g���̐�ւ��ȂǂŎb���͉��M�s�ʂɂȂ銴���ł��B
�������{�ȍ~�A�I�[�f�B�I�EAV�W�̐ݒu���������������ɍĂт��ז����܂��B
���[���悤�A��������A�ƃv�����͎��X�ƕ����т܂��B
�����������̓A�i���O���R�[�h��DVD�ELD�����p�ɂW��͉t���{�u���[���C��HD�Đ��B
��܂��ȃv�����͂���Ȋ����ł��B
�����ԍ��F8412335
![]() 0�_
0�_
130theater����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B�������ɁA�u�z�c�̊ԁv�͖����ł���ˁE�E�B
�ɒ[�ȗ�ł��������Ă��܂��܂����B70���~��Ƃ����̂́A���ꂾ����
�݂���ƂĂ������ł����A����ŁA�I�[�f�B�I���[�������Ƃ��A
��������A�Ƃ��A�͂��܂��I�[�f�B�I�p�Ƀ������[�����I
�Ƃ��ɔ�ׂ�A�������ƁE�E�B���̋@�B�̕�\�͂��A�ǂ̒��x�܂ŃC�P��̂��A
���ڂ��Ă���܂��B
�����ԍ��F8413831
![]() 0�_
0�_
�X�o��20000����@
���������u�ݏo�@�v�����邩�炲����Ŏ����̋@��Ŏ����Ă݂ĉ������Ƃ̎��ł����B��
�ߏ��ɃA�L���t�F�[�Y�������Ă��āA���ӂɂ���Ă���V���b�v�͂������܂��H�B
�ݏo�@����āA�����̕����̈����ӏ��𑪒肵�Ē����Ԃ��Ă��ǂ��ł���A�Ȃ�Ď�����
��������Ă��܂����B����������Ă���u�X�e���I�E�T�E���h�v���ɂ��傤�ǂ��̋@�̓��W
���g�܂�Ă���A�Ƃ̎��ł��B
�E�E�E���̏ꍇ�͎�������J���Ă���邨�X�ɂ͎�����͍s���܂������̓X�Ŕ������͗]��
����܂���B�F�l���F�X�����Ă���̂Ŕނƈꏏ�ɍs�������ŁE�E�B���̎�����̍Ō��8��
���Ƀv���[���g������A�L���t�F�[�Y������SACD/CD�Ղ�5���A3���ɃX�e���I�E�T�E���h����
���炦��A�Ƃ����W�����P��������A���ƗF�l��l�����ď����c��SACD/CD���Q�b�g���܂����B
�����ԍ��F8417966
![]() 0�_
0�_
���E�������
�������ɂ��������Ƃ���A�u�ǂ����̎��Ȍ`���v�͍�����L��遂肩������܂���ˁB��������d�m�����L�x�ł������ɉz�������Ƃ͂���܂���B�A�}�`�F�A�̍���ł����A�@��ύX��A�N�Z�T���[�ύX�ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ���Q���R�P�{�̌����ŋ~�ρA�Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
��������X���[�U�[�ɂ͉�������ȂƂ��낪����܂��̂ŁA�����������u���ǁv���菕�����Ă����̂��`���[�j���O�V���b�v���Ǝv���܂��B�`���[�j���O�V���b�v�̋Z�p�E�Z�\���l�X�ł����A��H�}�Ȃ��ŃA���v�△���@�̈���͑g�ݗ��Ă��邭�炢�̍����g��d�m���ƁA�����ĉ�H�}�ƍ\���p�[�c������Ύ��ۂɒ����Ȃ��Ă��A�ǂ�ȉ����o��̂��킩�邭�炢�̏n���Ƌ��{���K�v�ƍl���܂��B�X�I���W�i�����i�����̂ł͂Ȃ��A�������@����q�̚n�D�ɍ��킹�ĉ��ǂ��Ă����̂��x�X�g�ł��B�P�X�W�O�N��ɂ͂����������X�����Ȃ����ǂ���܂������A�I�[�f�B�I�̐��ނƂƂ��ɐ��͌������i��p�҂����Ȃ��Ƃ����̂�����ł����j���ł͉������ȃA�N�Z�T���[�̔���\�ʓI����������s���X�������݂��邱�Ƃ͒Q���킵������ł��B
�@���Ęb�͕ς��܂����A�u������тƁv�Ƃ����M��̂P��ʂŁA�`�F���t�҂�ڎw������l���̐e���o�c���Ă����i���X�i�o�[�H�j�̃I�[�f�B�I���u���ʂ�܂����A�A�i���O�v���[�����e�N�j�N�X�̂r�k�P�Q�O�O�A�J�[�g���b�W�����Q�V�O�b�A�A���v�͕s���ł������A�X�s�[�J�͂i�a�k�̃����T�[�P�O�P�i���Ԃ�j�������Ǝv���܂��B�����Ǝʂ����k�o���R�[�h���J�T�h�V���̃V���[�}���������肵�āA�X�^�b�t�̃I�[�f�B�I�Ɖ��y�ւ̐[�����w�������܂����B�@�ߔN�H�ɂ݂�T��ȉf��ł����B
�����ԍ��F8423717
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ����́B
[�l�I���W����]
�����z�����߂łƂ��������܂��B
�������������̓A�i���O���R�[�h��DVD�ELD�����p�ɁE�E�E
�P�S��������ł����I�H
�L���͑S�R�������܂����������������Ԃ������Ċ������ł��B
�Ă̏����͔��[�Ȃ��ł����A���y�ɐZ��ɂ͂Ƃ��Ă�������Ԃ��Ǝv���܂��B
�܂��ݒu��̂��b�������Ă��������ˁB
�����ԍ��F8432196
![]() 0�_
0�_
�@130theater����A�X�o��20000����A����ɂ��́B
�@ACCUPHASE��DG-48���t�B�[�`���[�����V�X�e���͐�̃I�[�f�B�I�t�F�A�Ŏ����������Ƃ�����܂��B�Ȃ��Ȃ��ʔ����Ǝv���܂����BACCUPHASE�͐����h�̃I�[�f�B�I���[�J�[���Ƃ����F��������܂����A�ӊO�ƋZ�p�D�ʂŃg����������Ă����Ă��܂��B�����������Ȃ̂ň�ʃ��[�U�[�iACCUPHASE���i�̃Z�O�����g�ɂ͖����̃G���h���[�U�[�j�ɂ͒m���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��BDG-48�̋@�\����������ƁA����@�̃��[�U�[�����ŘM�肻���ȃV�����m���Ǝv���܂��B
�@�������A�����Ȃ�i�O�ɂ������܂������j���t�F�A�Ń��[�[���N�����c�̎�Ɏ҂���Ă��Ă����u�Z�b�e�B���O��O�ꂵ�ċl�߂Ă������Ɓv�̕����ʔ��������Ǝv�����́A�A�i�N���Ń��[�g���̃I�[�f�B�I�t�@���Ȃ̂ł��傤���i�j�B
�@ACCUPHASE�Ƃ����A�ŋ߂�����Ƌ������̂����Ђ����C���P�[�u�����o���Ă��邱�Ƃł��B�����u�����h�̈�p���߂铯�ЂȂ̂ŁA���������P�[�u�����n�C�G���h���Ǝv������A�т����肷��قLj����̂ł��i���������u�����h�ł�ESOTERIC�Ƃ͑�Ⴂ�j�BACCUPHASE�Ƃ��Ắu�P�[�u���Ȃ�āA���̒��x�ŏ\���v���ƌ����Ă���̂�������܂���B�d���a���҂ɂƂ��Ă͂��������C���p�N�g�̂��鎖������Ȃ��ł��傤���B
�@�|���l�I���W����
�@������������14��Ƃ̓X�S�C�����ˁB��������^�X�s�[�J�[�̔����Ƀn�[�h�������������l�q�ŁA�䌒�������F�肵�܂��B���܂��������������ɂ̓��|�[�g���Ă��������Ɗ������ł��B
�@�|��inouesp����
�@80�N��ɂ́u�����V���b�v�v�����������̂ł����H�@�����͒n���ݏZ���������Ƃ������ē����͂���ȓX�͂܂������m��܂���ł����B�����Ƃɂ��Ă���X�����邱�Ƃ�m�����̂͂������N�ł��B�ȑO���̂����̈�ɑ����^�Ƃ���A�X�����炢���Ȃ�u���Ў莝���̋@��������Ă��ĉ������B�K�b�c�����������Ē����܂��I�v�Ɣ����ĖʐH�炢�܂����B�܂��A�X���Ŏ��������A���v�ނ𗊂݂����Ȃ��̂ɕ������n�߁A�u��������������ƁA�����������ɂȂ�v�Ƃ������u�߂����X�Ƒ����A�@���ގv�����������̂ł��B�܂��A�u�����v�����ʓI�Ŗʔ����ł��傤���ǁA�u�܂��͉������ł��������肫�v�Ƃ������X�^���X�����͊��ق��ĖႢ�������̂ł��B���Ȃ݂ɁA���̓X�͂��ꂩ��1�N��ɒׂ�܂���(-_-;)�B
�@�u������тƁv�͂܂��ςĂ��܂���B�]�����ǂ��̂ł�����̓`�F�b�N���܂��B�E�E�E�E�ł��A���̉f��̊ēE��c�m��Y�̓s���N�f��o�g�ŁA�{���͂����i�ȃR���f�B�ƃG�Q�c�Ȃ��T�C�R�E�T�X�y���X�����ӂȂ̂ł��B����Ȕނ��u�����v�݂����Ȉ����ʼnf����B���Ă���̂́A������Ƃނ��y���C�����Ă܂����E�E�E�E�i�j�B
�����ԍ��F8432566
![]() 0�_
0�_
���E�������
���J�Ŕ�������Ղ�̂����肪�Ƃ��������܂����B���̓s���N�f����̊ē̍�����f��ɉ��x�����x���܂��܂����B�i������j�Ƃ��������ɂ��Ă��������܂����B�����͎��̗���Ƃ���ł͂Ȃ������ƁA�����ɔ��Ȃ��Ă��܂��B
���āu�I�[�f�B�I�@��̍���̓W�]�v�ł����A���E�������A���Ȃ��̂悤�ȑ��́u�g�E�V���v���킩�������Ȉӌ��������A�擱���Ă��邤���͂���^���Âł��ˁB��H�̓��쌴�����������Ȃ��ʼn����]�X���邱�Ƃ́A�f��ē̑f����m�炸�ɂ��̉f��Ɋ���������߂͐[���ł��傤�B
�@�ł͂���ŁA�F��������悤�B���悤�Ȃ�B����������������`�����l���ł��������܂��傤�B
�@�@
�����ԍ��F8433117
![]() 2�_
2�_
�F���͂悤������܂��B
130theater����DG48�Ȃ��Ȃ������[�����i�ł��ˁA�m���Ƀ��[���A�R�[�X�e�B�b�N�ɑ��z�̗\�Z���|�����肱����̕����ǂ��̂�������Ȃ��ł��ˁB���ɑ傫�ȃX�s�[�J�[������ۂɂ͂��͂��������ł��ˁB���̎��ɂ̓`���ƃI�[�o�[�X�y�b�N�Ȋ��������܂����A�@�������Ќ��ʂ�̌����Ă݂����ł��B�������̏ꍇ���������@����g���Ƃ���������߂��Ă��܂��ċt���ʂɂȂ��Ă��܂����Ƃ����X����̂ŗv���ӂȂ̂ł����c���������̉Ƃ����Ă�Ƃ��i���邩�ǂ����킩��܂��j�ɂ́A����V�X�e���Ɏ�����Ă݂����ł��ˁB
�l�I���W���v���Ԃ�ł��A�������ĂȂ����ȁH�����z�����߂łƂ�������܂��B�����������琥��V���ł̃Z�b�e�B���O�̋�J�b�≹�̕ω��ȂǐF�X���������������B
inouesp����ʂɌ�����������������Ȃƌ����Ă���킯�ł͂Ȃ��Ǝv���܂���B���������̎v�������Ƃ��������������Ǝv���܂��Binouesp������������Ȃ��Ȃǂƌ��킸�������̎v�������Ƃ⊴�������Ƃ��ǂ�ǂ��Ă��������B�ȑOinouesp����̏Љ�Ă��ꂽ���̏��������Ɉӌ��̈قȂ�l�Ƃǂ�ȂɌ��t�����킵�Ă��Ӗ����Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��������������͎��͔��ł��B�����悤�Ȉӌ��̐l�⓯���悤�Ȋ����̐l�����ŋc�_���Ă����̒������Řb�͐���オ�邩������܂�����͐���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���͂��������l�����ō�������̂́i�I�[�f�B�I�@��Ɋւ�炸�j�{���ɗǂ����i�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B��������B�����Ŋy���ނ̂ł������ŗǂ��Ǝv���܂����A����Ȃ�Ɏ����B�̒��ł͖����̏o���镨���o���邩������܂��A���ꂪ���������ł��萳�������ɂȂ�̂ł��傤���H����𗝉��ł��Ȃ��l�⊴���̈Ⴄ�l�͊Ԉ�����{���̗ǂ���m��Ȃ��l�Ȃ̂ł��傤���H���͂����͎v���܂���B�����ƈӌ����`�A�����̈Ⴄ�l�Ƙb����c�_�����A���݂��������Ă������ƂŐV�������������I�Ȕ��z�����܂�Ă���Ǝv���܂��B�m���ɓV�˂ƌĂ��l��J���X�}�ƌĂ��l�����܂������ׂĂ��̐l�̃I���W�i���ƌ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B���̐l�ɉe����^�����l�͂����Ƃ�������͂��ł��B
���ƃI�[�f�B�I�@��̍������m�����Ȃ��̂Ɍ��̂͂��������ƌ����܂��������ł��傤���H���Ȃ��͐��m���̂Ȃ����̂Ɋւ��Ă͈�؉������Ȃ��̂ł����H�Ⴆ�ΎԂȂǁH
�m���ɃI�[�f�B�I�@���Ȃ炻���ł��傤�����[�U�[�̂قƂ�ǂ����̂悤�Ȓm���Ȃǎ����Ă��܂����������m�����Ȃ��Ǝg���Ȃ����i�Ȃǂ���܂���B
�M���c�_�͑劽�}�ł��������̔l�荇���͔n���n�������̂ł�߂܂��傤�B
����������тƂ�����i�͌��Ă��Ȃ��ł����s���N�f��o�g�̊ēɂ��f���炵���ē͑�������Ǝv���܂��B
���ꂩ��́A�����ƗL�Ӌ`�Ȉӌ������̏�ɂȂ邱�Ƃ�]�݂܂��B
�����ԍ��F8433815
![]() 0�_
0�_
�@����̐M���ɋÂ�ł܂��Ă���l�����́A�����ł��䎩���̈ӌ��ƈႤ������ڂɂ���ƁA�����瑊�肪���Ղȕ������ɏI�n���Ă��悤�ƁA���C�Łu�N�\�v���́u�g�E�V���v���́u�����������Ȍ���@���ȁv���̂Ƃ������\����f���̂ł��ˁB�܂��A����ȃP�[�X�͉��x���ڂɂ��Ă��܂����獡��������܂��ǁB
�@inouesp����͂��������Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����i�{���͂܂���������ŖႢ�����̂ł����ǂˁj�A�ꉞ���X�͂��Ă����܂��Binouesp����̕��͂̒��ň�Ԉ�ۓI�������̂́u��H�̓��쌴�����������Ȃ��ʼn����]�X����ȁv�Ƃ�������߂ł��B���͂���ɑ��Ă͂܂������^���ł��܂���B�h���L�[�R���OJr.�����������Ă��܂����A���m���������Ă��Ȃ��Ǝg���Ȃ��Ɠd���i�Ȃǂ���܂���Binouesp�������Ă�̂́u�e���r���f�錴����m��Ȃ��Ńe���r�̉掿�ɂ��Ă��ꂱ��q�ׂ�ȁI�v�Ƃ����̂Ɠ������Ƃł��B�������Ɠd�X�̓X���œX����������������������N���[���̗��ł���B
�@���̓��[�J�[�̃G���W�j�A��ꕔ�̃f�B�[���[��R�A�ȃI�[�f�B�I�}�j�A�́u���_�������炸�ɉ��ɂ��Ă��ꂱ�ꌾ���ȁI�v�Ƃ������ԓx�i���ӎ��I�����ӎ��I���Ɋւ�炸�j�������A�I�[�f�B�I�𐊑ނ����Ă��錴���̈���Ǝv���܂��B�Z�p�I�Ȃ��Ƃ𗝉����Ă��鉹�y�t�@���Ȃ�āA�ق�̈ꈬ��ł��B�Z�p�ɑa������҂��̂ĂĂ��܂��ẮA���̋ƊE�ɖ����͂���܂���B
�@���[�J�[�̃J�^���O��I�[�f�B�I�G���̏��i�Љ�L���Ȃ�����ƁA�ǂ����ċZ�p�I�Ȃ��Ƃ���`�I�Ɍ���Ă��܂��̂��ƈÑR�Ƃ����C���ɂȂ�܂��B�i���g�J��H���ǂ��̂Ƃ��A�J���g�J���u���ǂ������Ƃ��A����Ȃ��Ƃ��C�ɂ��ĉ��y���Ă���l�ԂȂ�ċɏ����ł��傤�ɁB����ł��āA�̐S�ȉ��ɂ��Ă͒��ۓI�Ȕ������ɏI�n���Ă��āA�����l�ԂɂƂ��Ă͂܂�ŎQ�l�ɂȂ�܂���B���Ƃ��J�^���O�Ɂu�_�炩���ĉ��̂��鉹�I�@�N���V�b�N�t�@���ɂ҂�����I�v�Ƃ��u���C�����I�@���b�N��W���Y�Ȃ�܂����Ƃ��I�v�Ƃ������ꕶ����ɗ���A�ǂꂾ������҂ɑ��ăA�s�[���ł��邱�Ƃł��傤���B
�@���̓��[�J�[���f�B�[���[���u�Z�p�I�Ȃ��Ƃ͉���������Ȃ�����ҁv������厖�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B����ƁA�����V���b�v�̋����ɂ͔��ł��B�O�ɑ����^�����V���b�v���ׂꂽ���Ƃ������܂������A�t�Ɍ����u���ׂ�邩������Ȃ��V���b�v�Ǝ������͎̂^���ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B���̃T�C�g�ł͋g�c�����i�ق̉����i�����߂鏑����͂����������܂����A����͋g�c�����i�ق��S���I�ɒm���A��厏�ɂ��L���f�ڂ��e���Ă���u�M�p�̂�����Ǝҁv�Ƃ̕]�����m�肵�Ă��邩��ł��B�����m��Ȃ��L�ۖ��ۂ̉������Ǝ������̂̓����e�i���X���l����Ɠ���ł͂���܂���Binouesp����͉����V���b�v�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��Q���̂悤�ł����A�������������̈˗��Ȃ�ď����̃}�j�A�̂��邱�Ƃł͂Ȃ��̂ł��傤���B��ʃs�[�v���Ƃ͉��̂Ȃ����E�ł����A�����������[�J�[���������肵�����̂�����Ă���A�����Ȃs�v�ł��B
�@�Ƃ������A���ꂩ��͋Z�p�I�Ȃ��Ƃ͑O�ʂɏo�����A�����̂��̂�g������Ƃ��������[�U�[�C���^�[�t�F�[�X���d���������������ɂȂ�Ǝv���܂����A�������Ȃ���I�[�f�B�I�̕����Ȃ�Ċo���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8436973
![]() 1�_
1�_
�@���āA�Ђ���Ƃ����inouesp����̓s���N�f����͂��߂Ƃ��鐬�l�f��ƃA�_���g�r�f�I�Ƃ̋�ʂ��t���Ă��Ȃ��̂�������܂��A�A�i�^�����ƌ������Ƒ�c�m��Y�ē��s���N�f��o�g���Ƃ��������͕ς����܂��A���Ԃ�{�l�����̂��Ƃ�p�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��͂��ł��B����ǂ��납�A���܂Ŕނ��������B������ʉf��̒��ŁA�s���N����̏������N�H���e�B�̂��͈̂�{����Ƃ�����܂���B�u�s���V���[�Y�v�����ʔ������R���f�B��ނ͈�ʉf��ŎB�������Ƃ͂Ȃ����A�u�^���̐���v�����|���T�X�y���X�h���}��ނ͈�ʉf��ō�������Ƃ͂Ȃ��̂ł��B�u������тƁv�́A�ނ́u�s���N������鏉�̎d���v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B
�@�u�f�X�m�[�g�v�ł�����݂̋��q�C��ē��A�u�g�E�L���E�\�i�^�v���J���k���ۉf��Ղŕ]�����ꂽ���ē��A�u�r�[�E�o�b�v�E�n�C�X�N�[���v�V���[�Y�̌́E�ߐ{���V�ē��A�u�֎O�\�Y�v�������C�N���Ęb����Ăːl�E�X�c�F���ē��A�uShall we �_���X�H�v�̎��h���s�ē��A�u�����v�Ȃǂ̕��w��i�̉f�扻�ł͒�]�̂��鍪�g���Y�ē��A���̑����{�f��̑����Ŋ��Ă���X�^�b�t�̑��������}���|���m��s���N�f��̏o�g�҂ł��B���l�f����o�J�ɂ��邱�Ƃ́A���{�f�悻�̂��̂��o�J�ɂ���̂ƈꏏ�ł��B
�@�u�X���b�h�Ƃ͊W�̂Ȃ��b������ȁI�v�ƌ�����S�����i�T�C�Ǝӂ邵������܂��A�f��t�@���Ƃ��ď������ɂ͂����܂���ł����B�ł͂܂��B
�����ԍ��F8436994
![]() 0�_
0�_
inouesp���ӂ͂������̃X���͌��Ă��Ȃ��̂ł��傤���H�������Ă����琥�X���������������ł��Binouesp����͉�H�}�Ǝg�p�p�[�c��������̂��̂��Ȃ��Ă������킩��̂��ǂ��Z�p�҂��Ƃ���������Ă��܂������{���ɂ����Ȃ̂ł��傤���H���͂����͎v���܂���B�{���Ɉꗬ�̋Z�p�҂͉�H�}�Ǝg�p�p�[�c�������Ȃ̂ɂȂ�����ȉ����o����̂��낤�Ǝv�킹����̂����ۂɍ��l���Ǝv���܂��B�m���ɂ�����x�̒m����o�����ނƂȂ�ƂȂ��o���オ��̉����킩��悤�ɂȂ�ł��傤�B�����������ŏI����Ă��܂��Ƃ��̐�̗̈�ɂ͂��ǂ蒅���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�Ⴂ���悭�Ԃ̃G���W���̃I�[�o�[�z�[���Ȃǂ����Ă����̂ł����������i���悤�ɑg�݂��Ă����S�҂̍��ƂȂ�Ă������Ƃł̓G���W���̏o�������Ȃ�Ⴂ�܂��A�����Ƃ��܂��l���g�G���W���͂����ƈႢ�܂��B���������i�Ƃ����Ă������ׂ�����ׂ�Ɠ������ȂǂقƂ�ǂ���܂���B�����g�ݗ��Ă�̂ł͂Ȃ������̕��i�̃o�����X�Ȃǂ����܂��Ƃ�Ȃ���g�ݗ��ĂĂ����Ƃ����g�ݗ��Ă������̃G���W���Ɣ�ׂ�Ɣn�͂�o�͓����Ȃǂ����サ�܂�������ȏ�ɃG���W���̃t�B�[�����O���܂�ŕʕ��ɂȂ�܂��B�I�[�f�B�I�@��������������Ǝv���܂��B�����������Ƃ̌J��Ԃ����{���̌o���ł��肻�ꂪ�n���̋Z�ł���A�^�̒m���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H����𗝉������s���Ȃ��Ǝ����̑z���͈͓̔��̉��������܂��z����₷�鉹�͉i���Ɏ�ɓ���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�����܂������ӋC�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F8438497
![]() 0�_
0�_
�@�كu���O�ɂ������܂������A�ŋ߂܂��X�s�[�J�[�P�[�u����V�����܂����BQED��SILVER MICRO�Ƃ����A���������ȕ��ł��B���̓��t�@�����X�Ƃ���Belden��8460���g���Ă��܂����A���܂�ɉ��̏o�����Ⴄ�̂ŋ���������ł��B
�@���Y�����č��Ɖ��B�Ƃ����Ⴂ�͂���܂����A��������Ɩ��p�Ɩ����p�Ƃ̉��̃A�v���[�`���قȂ�Ƃ������Ƃł��傤�BBelden�̓h���C�ȃ��j�^�[���AQED�̓E�F�b�g�Ȕ������ł��B�l���Ă݂���́g�������h�Ƃ������t���N�Z�����Ǝv���܂��B
�@�I�[�f�B�I�t�@�C���ɂƂ��ĉi���̘_���̃e�[�}�̈�����̃��j�^�[�� vs �������Ƃ�������Ǝv���܂��B�I�[�f�B�I�̖ړI�������i�}�X�^�[�e�[�v�̉��j�������ɒ����ɍČ����邩�Ƃ������ƂȂ�A���j�^�[���ȊO�̃A�v���[�`���@�͂��蓾�܂���B�Ƃ��낪���̒��ɂ͔�������g��Ƃ��鐻�i�����X����܂��B�����Đ��H���������I�[�f�B�I�̖ڎw���Ƃ���ł͂Ȃ����Ƃ͊m���ł��B
�@�l���Ă݂�u���̃X�s�[�J�[�͏_�炩���ĉ��₩�ŁA�N���V�b�N�����v�Ƃ�����������I�J�V�C�̂ł��B���@�C�I�����̓Ƒt��ڂ̑O�Œ����A�ƂĂ��u�_�炩�����v�ł͂��蓾�܂���B�n�[�h�Œ��B�I�ȃT�E���h�ł��B�������I�[�f�B�I�t�@���Ɍ��炸���y�t�@���̊Ԃł́u�\�t�g�ʼn��₩�ȉ����N���V�b�N�Ɍ����v�Ƃ����R���Z���T�X���o���オ���Ă���̂ł��B����́A�I�[�f�B�I�Ƃ������̂������Ƃ͕ʂ̃R���Z�v�g�ɂ�萬�藧���Ă���Ƃ����v���܂���B
�@�����l������j�^�[���Ƃ����̂��A������g�����h�̒��̈�Ȃ̂�������܂���B�v����Ɍ��������H���ɂƂ��ꂸ�Ɏ����̍D���ȉ���Nj����Ă����̂��s���A�E�I�[�f�B�I�̊y���݂Ȃ̂ł��傤�B
�@���Ƃ����ăI�[�f�B�I�̐��E�ɂ͉𑜓x�Ƃ�����\�Ƃ��A�ш�o�����X�Ƃ��X�s�[�h���Ƃ������A���ՓI�i�Ǝv���Ă���j�w�W������܂��B����炪�����Ă���ƒ����Â炢���ɂȂ�P�[�X�������̂��m���ŁA������g�������C�ɓ���A�ǂ�ȉ��ł��ǂ��h�Ƃ͌����Ă��A�I�[�f�B�I�I�w�W�̃|�C���g���������Ă��Ȃ��炵�������Ă��郆�[�U�[��������ƁA�I�[�f�B�I�t�@���Ƃ��Ắg������Ƒ҂����I�h�ƂȂ��Ă��܂��܂��B
�@���ՓI�i�Ǝv���Ă���j�w�W�Ɓg�����h�Ɓg�����̍D���ȉ��h�Ƃ������Ȃ錓�ˍ������`�����Ă���̂��A�l���Ă��悭������܂���B����������̂́A�I�[�f�B�I�Ƃ����̂͂������̏ꏊ�Ɂg��ΓI�ȗǂ����h�Ƃ����̂������āA�F����Ɉ꒼���Ɍ������Ď��s���낵�Ă���̂ł͂Ȃ��A�e�l�������Ă���g�ǂ����h�̊T�O���X�Ƀn�b�L���ƌ��ɂ߂Ă䂭��Ɓi��j�Ȃ̂ł��傤�B
�@�E�E�E�E�Ƃ�����A�P�[�u����������v��ʂ��ƂɎv����y���Ă��܂��܂���(^^;)�B
�����ԍ��F8441978
![]() 0�_
0�_
��inouesp�ł��B���������֗���\�肪�Ȃ����̂�ID�폜���܂����B�������A���܂�ɂ����̌��t�̐^�ӂ���������Ă��Ȃ̂ŁA�lj��������s���܂��B
�@���āA��H�i�@��j�̓��쌴���𗝉����Ă��Ȃ��l�́A���ɂ��Ĉӌ����q�ׂĂ����Ȃ����H������YES�ł��B���i�R���̂悤�ȕ��L���ǎ҂������A�l�̔������ǎ҂̍w���Ɋւ����̃��f�B�A�Łu�]�_�ƂԂ����v�ԓx�ňӌ����q�ׂ�Ȃ�A�����̔����ɑS�ӔC���o��ł���Ă��炢�����B���_�̎��R�Ƃ́A�ǂ�Ȕ��������Ă��ǂ�����ǂ��A�����ɐӔC������l�݂̂ɔF�߂�ꂽ�����ł��B�����ĐӔC�����鎑�i�́u�v���v�u�D�݁v�u�����v�ł͂Ȃ��w��ɗ��ł����ꂽ�ؖ����i��ʓI�Ɂj����邱�Ƃ��Œ�����A������O�ł��B
����inoue�X�s�[�J���ɂƂ��āA���̒��̑唼�̃X�s�[�J���u�����w�ɑ����āv�Ԉ���Ă���Ǝw�E���܂����B���͎��ۂɂ�����w�����A�R�O�N�Ԏg���A�����Ɍo�ϓI�ɋ���������O�̃X�s�[�J���E�I�b�`���ė��܂������A�ш�E���F�ɂ��āA�ǂ��inoue���邱�Ƃ͏o���Ȃ������B�O�ɂ������܂������A�_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�Łu�����̉��v���������Ƃ���������inoue�ӊO�ɑI�����͂Ȃ��A�X�s�[�J�ȑO�̋@��A�A���v��CDP�Ȃǂ́u�����̉��v�������āA���̗ǂ��������n�߂Ĕ��f�ł���̂ł��B������������ł����H�X�s�[�J�Ƃ������Ɉ�ԋ߂��@�킪�u�����Ƌt���̉��v���������Ă����ԂŁA�ǂ����ď㗬�̃A���v��b�c�o���ǂ��Ɣ��f�ł���̂ł����H�@���Ƃ����K���ǂ����킩��܂��A����Ȃ��߂��˂ŁA�����[�f���炵���i�F�ł��ˁI�ƌ����̂Ǝ����Ƃ��Ăǂ����Ⴄ�̂ł��傤���H�@���̈ӌ����Ԉ���Ă���Ƃ����̂Ȃ�A�X�s�[�J�̂���ׂ��p���u�w��ɑ����āv��Ă��Ă��炢�����B�@������̘b�͂���ȍ~�̘b�ɂȂ�܂��B�u�����̉��v�ł������l�b�g���[�N�������Ȃ��u�ʑ�����̂Ȃ����v�Ŕ��f����ƁA�P�[�u����\���p�[�c�̉��X���͍��̃I�[�f�B�I�T�O�ł͑z�����ł��Ȃ��قnj��ς��A�ǂ������������ɂȂ�܂��B��������̌������Ȃ�u�g�E�V���v�Ƃ��������͓P�܂��傤�B�����ɂ���L���ȃI�[�f�B�I�V���b�v���D�ӓI�ɂ݂Ă�����������������悤�ł����A�\����܂���A�����Ȃ��������Ă��Ă���͂�Ǒf�l�̈�ɑ����܂��B
�@�Â��f��̘b�ŋ��k�ł����A�X�^�[�g���b�N�u�̋��ւ̒������v�Ń~�X�^�[�X�|�b�N�������܂�
�u�����̌����Ȃ���c�_�͐������Ȃ��v
���̌��t�̈Ӗ��͐[���B��ʘ_��펯�����ȂNJW�Ȃ��B�f�B�i�E�f�B�I�ł�KEF�ł��^���m�C�ł�FOSTEX�ł�JBL�ł����ł������A�����̂ǂꂩ��inoue�𗼕��������ԏ��L���āA���̌����Ă��玄�Ɉӌ����Ă��炢�����B�����������Ƃ͈ȏ�ł��B
�@�o�r�A�h���L�[�R���OJr����B�Ԃɂ��ẮA�I�[�f�B�I�������ƈӌ����������Ƃ���������܂����A�b���������̂Ŏ~�߂܂��B�����ł��Ȃ��������킯�ł͂���܂��A�ЂƂ���ł��B���͓���I�ɉ^�]����ɂ����āA���[���[�����g���P��ł��Ԃ��Ȃ����ʓI�ɓ������i�~�߂�j�^�]�Z�p���ŗǂōō����Ǝv���A�S�����Ă��܂����A�@�h���L�[�R���OJr����͂ǂ̂悤�Ȏw�j�ʼn^�]���Ȃ����Ă��܂����H
�����ԍ��F8442134
![]() 0�_
0�_
��inouesp����
>��H�i�@��j�̓��쌴���𗝉����Ă��Ȃ��l�́A���ɂ��Ĉӌ����q�ׂĂ����Ȃ����H������YES�ł��B
���`��A�����܂Ō�����ƁA�������Ȃ��H�Ǝv���Ă��܂��܂��B���Ƃ͕������ۂł͂���
�܂����������Ƃ��ĔF������̂͐l�Ԃ̐S��/�������傫���ւ���Ă���Ǝv���܂��B���Ƃ�
�������ۂł͂Ȃ��S�����ۂ��Ǝv���܂��B�Ⴆ�s�A�m���D���ȕ��̓s�A�m�̉�����������
�Ă���ƁA���̋Ȃ��낤�Ƃ��ǂ����t�����Ă���Ȃ��Ƃ������܂����A�L���C�ȕ��ɂƂ���
�͂����̑����ȊO�̉����ł��Ȃ��Ɗ����܂��B�E�E�E�t�ɗႦ��F-1�̃G�L�]�[�X�g�m�[�g��
��������]���Y��ɉ���Ă��鎞�̉��Ȃǂ��A�悭�\�v���m���̂��Ă���l���Ƃ����A����
�W�̕��͗Ⴆ���肵�܂��B���Ԉ�ʂł́u�����v���Ɗ�������������Ƃ͎v���܂����E�E�E�B
�܂�A������(�I�[�f�B�I�̏ꍇ�͉��y�̉����ȁH)�����̊������ǂ����������H�Ƃ�
���ӌ��͔������Ă�������m�炸�Ƃ��ǂ��Ǝv���܂��B����������̂Ɍ���/���_�͓��ɗv��
�܂���B�����A�ǂ������������_�I���t��������A�Ȃ�������������Ă͂���Ǝv��
�܂����E�E�B���̗��_��(���_�ƌ����ɂ͑傰���ł����E�E�E)���g���������t���b�g�������Ƃ��A
S/N�䂪�ǂ������A�c�݂����Ȃ������Ƃ������x���ŗǂ��Ǝv���܂��B
�X�s�[�J�[����̉��̏o���ł����A�M�a�̂����߃X�s�[�J�[�ƋɈꕔ�̃X�s�[�J�[��������
�S�ă_���Ȃ̂ł��ˁB�E�E�E�Ȃ�Ίy��͂ǂ�ȉ��̏o�������Ă���̂ł��傤���H�B�ʑ�
����ȂǂȂ��̂ł��傤���H�B�y�킩��o�鉹�S�Ă��y��̉��Ǝv���̂ł����E�E���Ƃ���
��ɘc�݂��܂܂�Ă��Ă��E�E�E�H�H�H�B
�~�X�^�[�X�|�b�N�Ƃ��ӌ����m���ɂ��ӌ������������ȋ�inouesp����ł����A�~�X�^�[�X�|
�b�N���J�[�N�D���ɗ��_�ł͍l�����Ȃ��l�Ԃ̊�����������Ă��܂����ˁH�B
�����ԍ��F8442834
![]() 3�_
3�_
��inouesp����
�����āA��H�i�@��j�̓��쌴���𗝉����Ă��Ȃ��l�́A���ɂ��Ĉӌ����q�ׂĂ����Ȃ����H������YES�ł��B���i�R���̂悤�ȕ��L���ǎ҂������A�l�̔������ǎ҂̍w���Ɋւ����̃��f�B�A�Łu�]�_�ƂԂ����v�ԓx�ňӌ����q�ׂ�Ȃ�A�����̔����ɑS�ӔC���o��ł���Ă��炢�����B���_�̎��R�Ƃ́A�ǂ�Ȕ��������Ă��ǂ�����ǂ��A�����ɐӔC������l�݂̂ɔF�߂�ꂽ�����ł��B�����ĐӔC�����鎑�i�́u�v���v�u�D�݁v�u�����v�ł͂Ȃ��w��ɗ��ł����ꂽ�ؖ����i��ʓI�Ɂj����邱�Ƃ��Œ�����A
�悭���̂悤�Ȃ��Ƃ������܂��ˁA����ł͍��܂ł��Ȃ������i�R���ɏ��������e�����ׂēǂݕԂ��Ă݂Ă��������B�ƂĂ��ӔC�������ď������݂����Ă���Ƃ͎v���܂���B���������̒m���Ă��邱�Ƃ݂̂��������ƐM�����݂������葼�l�ɂ��]�킹�悤�Ƃ��Ă��邾���ł͂Ȃ��ł����H����Ƃ����l���Ⴄ�ӌ���������������ȂƂ���ɂ͗��Ȃ��Ǝ̂đ䎌���͂�������̂̂��邱�Ƃ����Ȃ��̐ӔC�̎����Ȃ̂ł����H
������Ă���悤�ł����A�ʂɈ��ki�X�s�[�J�[��ᔻ���Ă�����������܂���B����������ɂȂ�ꂽ��コ���ᔻ���Ă���킯�ł�����܂���B�ނ��뎄�͈�コ��h���܂��B�����Ƃ��̃X�s�[�J�[�i�Ƃ��Đ��̒��ɐ��ݏo�����߂ɂ͂��Ȃ�̎��ԂƘJ�͂��g�������Ƃł��傤�B���s����̓��X���������Ǝv���܂��B�����������̐M�O���т��A������ƌ`������̂Ƃ��Ă��̐��ɂ̂��������Ƃ͋Z�p�҂Ƃ��đf���炵�����Ƃ��Ǝv���܂��B
����������Ƃ��Ȃ��̂�������Ȍ�����l�����������ԓx�͕ʂ̖��ł��B
���Ȃ��ɂ͐M�O��M���Ƃ������̂͂Ȃ��̂ł��傤���H
�ŏ��ɂ��̃X���ɏ������݂����Ă����Ƃ��ɂ͂�������\���̃X�s�[�J�[�͐��̒����疳���Ȃ�悢�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂�����ˁB��������Ȃ�M�̓������������݂������Ǝv���܂��B���̏������݂��炷����Ȃ��̎�����inoueKI�X�s�[�J�[�͂��̐��ɍ݂��Ă͂����Ȃ����̂Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H
���̂Ƃ��́A�m��JBL��S4800������݂̂���Ȃ��X�s�[�J�[���ƌ����Ă����Ǝv���܂��B
���ꂪ���̊Ԃɂ������ɂ��y�Ȃ��X�s�[�J�[�ɂȂ�Ō�ɂ͐������Ȃ��X�s�[�J�[�ɐ��艺����܂����B���Ȃ��́A���̂悤�Ȗ������锭���ɂǂ̂悤�ȐӔC���Ƃ�̂ł��傤���H�i�w��ɗ��ł����ꂽ�ӔC��������˂������܂��B�j
�킽���́A���icom�̌f���ɐ��Ƃ̈ӌ��Ȃǂ��������Ă��܂���B����Ȃ��Ƃ�胆�[�U�[������̗����Ȉӌ���A�h�o�C�X�����҂��Ă��܂��B�ׂɂ��̏��i����^���Ă��\���܂��t�ɂ����݂��Ɍ����Ă��\��Ȃ��Ǝv���܂��B�����̈ӌ����Q�l�ɂ��邩���Ȃ����͓ǂݎ�̔��f�ł͂Ȃ��ł��傤���H�f���̋K��ɂ����m���̂Ȃ����͏������݂��Ȃ��ʼn������Ȃǂǂ��ɂ������Ă���܂���B
�܂����Ȃ��͑��l�̂��Ƃ��g�E�V���Ă�肵�Ă��܂������Ȃ��͂���Ȃɐ��m��������̂ł��傤���H�������݂�������葼�l�̈ӌ��◝�_���������p���Ă��邾���ɂ��������Ȃ��̂ł����A���ꂪ���m���Ȃ̂ł����H�i�������Ȃ��Ǝ��̗��_�Ȃ�m���Ȃ肪����̂Ȃ琥���Ă������������ł��B�j
�g�c���Ƃ����V���b�v�����͍s���������w���������Ƃ��Ȃ��̂ŕ]���ł��Ȃ��̂ł������Ȃ��͑f�l�̈���o�Ȃ��ƒf�����Ă��܂����ǂ������Ƃ��낪�ǂ��f�l�̈���o�Ȃ��̂�������Ƌ����Ă��������B�ǂ�������łǂ̂悤�ɔ��f�����̂��H
���ɂ��Ȃ��̈ӌ������ׂĐ������Ƃ��č����̒��ɐ���������X�s�[�J�[�͂��ׂĐ������Ȃ����������Ă���̂ł���ˁB����ł͂��̃X�s�[�J�[�p�ɍ��ꂽ�A���v��CD�v���[���[���A�����̋@����g�p������ꂽCD�Ȃǂ̃\�t�g�������������o���@�B�ŕ������ꍇ�������Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł����H
���Ȃ��́A�M�O�������Đ��i�i����̍�i�ł͂Ȃ��j���ꂩ��i�l�̈������}�ʂȂǂ��g�킸�j��萢�̒��ɑ���o�������Ƃ��݂�̂ł��傤���H�i�ʂɉ����@��łȂ��Ă����܂��܂���j�����o��������̂Ȃ�ǂ�Ȃɗ��_�I�ɂ�����Ă��Ă��K�������ŗǂ̂��̂ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��ƌ������Ƃ�����͂��ł��B�����Ƃ͂���ȂɊȒP�Ȃ��Ƃł͂���܂���Bkef��jbl��tannoy��fostex��dynaudio��������M�O�������ĕ��������Ă����Ђł��B���Ȃ��͂����̃X�s�[�J�[���ō��̑g�ݍ��킹�ŕ�����ׂ����Ƃ�����̂ł����H���X�s�[�J�[�͂��Ȃ��̂��g���̃A���v���ō��̑g�ݍ��킹�Ȃ̂ł���ˁA����Ƃ��肠�킹�̋@��Ŕ�ׂ�ꂽ�X�s�[�J�[�͓��������ł͂Ȃ��̂ł́H�����������ɏ�������������Ƃ͎v���܂��B
�Ō�Ɏ��ւ̎���ɂ��������܂��B�킽���́A�^�]����Ƃ��ɂ���Ȃ�����Ȃ������C�ɂ��ĉ^�]�Ȃǂ��܂���B�����ĉ����グ��Ƃ�����o���邾�����ՂŎ��͂̏f�ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��炢�ł��B�Ȃ����Ȃ��͎Ԃ̋����ω��̃��[�����ɂ������̂��Ӗ����킩��܂���B�X���[�Y�ȉ^�]��S������Ȃ牡�����ւ̋����ω��������C�ɂ��Ă��Ӗ����Ȃ��ł���B�����Ƒ厖�Ȃ��Ƃ͂�������܂��B
�����ԍ��F8445411
![]() 2�_
2�_
�@marantzcd67�i��inouesp�j����A����ɂ��́B�O��u�{���͂܂���������ŖႢ�����v�Ƃ͏��������̂́A���́u�܂��A���Ԃ�߂��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��ȃ@�v�Ɠ��S�v���Ă����̂ŁA���Ȃ��́u�ēo��v�͑z��O�ł��B���̈ӋC�����͔����܂��̂ŁA���������g�s��Ƃ��đ���������Ă��������܂��B
����H�i�@��j�̓��쌴���𗝉����Ă��Ȃ�
���l�́A���ɂ��Ĉӌ����q�ׂĂ����Ȃ�
���i�����j���_�̎��R�Ƃ́A�ǂ�Ȕ�������
���Ă��ǂ�����ǂ��A�����ɐӔC������l
���݂̂ɔF�߂�ꂽ�����ł�
�@���Ȃ��͊Ԉ���Ă��܂��B���̗��R���A�[�I�ɏq�ׂ܂��傤�B�܂��A���Ȃ��́u�����ɐӔC������҂������m�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����̂��^�����Ɖ��肵�܂��B�Ȃ�ΑO�Ɏ����������悤�Ɂu�e���r���f�錴����m��Ȃ��Ńe���r�̉掿�ɂ��Ă��ꂱ��q�ׂ�ȁI�v�Ƃ����ӌ������ʂ邱�ƂɂȂ�܂��B�ɒ[�Șb�A�����w�҂�{�W�҂������ǂ�����Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ邵�A�G�R�m�~�X�g�����o�Ϗ�ɂ��Č��y���Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�A�싅�I�肵���싅������Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃɂ��Ȃ�܂��B�������������Ƃ������B�����u���_���E�v�ł��B
�@���Ȃ����u���_���E�v����D�����Ƃ����̂Ȃ�A�����������Ē��������B���������l�ԂƂ͋�����u�������̂ŁA�����������Ȃ�����������X�Ɂu���u���[�h�v�Ɉڍs���܂��B
�@����ƁA���Ȃ��̌����u�ӔC�v�Ƃ͂����������ł����H�@�����͂��߁A���̃{�[�h�Łi���邢�͑��̃{�[�h�ł��j�I�[�f�B�I�ɂ��Ă��ꂱ�ꌾ���Ă���҂͂����������܂����A������������u�ӔC�v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ��������̂ł��傤���B������₷���������ĉ������B
�@���łɁA�f��W�҂ł��Ȃ��̂Ƀs���N�f����u�y���v�����悤�Ȕ������������Ȃ��́A�ǂ��u�ӔC�v�����̂����������ĉ������B
���i�����w�ɐ��ʂ��Ă��Ȃ��ʼn��ɂ���
���ӌ����q�ׂ�̂́j����Ȃ��߂��˂ŁA
�������[�f���炵���i�F�ł��ˁI�ƌ�����
���Ǝ����Ƃ��Ăǂ����Ⴄ�̂ł��傤���H
�@�������A�u�����Ƃ��Ắv�����Ⴂ�܂��B���K�l������������Ȃ����́A�Ώە����n�b�L���F���ł��邩�ǂ����Ƃ������u���m�Ȏw�W�v�Ɋ�Â��Č��肳��܂��B�������t���[���̃t�B�b�g����u�n�b�L�����v�̍D�������i�H�j�Ȃǂ̌l�I�ŞB���ȃt�@�N�^�[�������ł��܂��A���`�I�ɂ́u�n�b�L���ƌ����邱�Ɓv���ŏd�v�ۑ�ł��B
�@���ăI�[�f�B�I�V�X�e������o�Ă��鉹�̑P�������ɂ��āu���m�Ȏw�W�v�Ȃ�Ă���܂���B�m���ɉ𑜓x�Ƃ�����\�Ƃ����ʂƂ��A�����ʂɊւ���u�q�ϓI�w�W�ɋ߂������v�͑��݂���̂�������܂���B���������̒��ɂ͉𑜓x�̍��������D���ł͂Ȃ��l�����܂��B�t���b�g�ȉ������h���V�����ȃT�E���h���S�n�悢�Ɗ����郊�X�i�[�����Ă��܂��B���Ƃ��ΑO�ɂ������܂������AJBL�̉��N�̖���PARAGON�͒�����̉𑜓x�E����Ɍ��s�@��ɂ͋y�Ԃׂ�������܂���B������PARAGON�Ŗ炷�Â��W���Y�͖����ꒃ�y�����ł��B���̂��ƂɊւ��Ă͓��Ђ̍��̍ŏ㋉�@EVEREST������ł��B
�@�����炭�̓X�y�b�N�ɂ����č��̐��i����������PARAGON���ǂ����Ċy������������̂��A���Ȃ��́u�����I�Ɂv�����ł���̂ł����H
���ǂ��inoue���邱�Ƃ͏o���Ȃ������B
�@�Ƃ肠�����A���̂��Ƃ��咣���Ă��邠�Ȃ��ɑ��A�u�ӔC�v������Ă��炤�悤�ɗv�����܂��B�܂����u�ł��Ȃ��v�Ȃ�Č����܂����ˁB�����Ƃ��A���͂��́u�ӔC�v�Ƃ�炪�ǂ��������̂��m��܂���B�������Ȃ�����P���čl���Ă݂�ƁA���Ƃ����Ȃ���inoue�X�s�[�J�[�Ƃ��̎��������Â��āA������inoue�X�s�[�J�[�����А��i���D��Ă��邩���A�s�[��������Ă̂��u�ӔC�v�̎����̈���Ǝv���܂����A�ǂ��ł��傤���B
�@������ɂ���A�A�J�E���^�r���e�B����������Ɖʂ����Ȃ��҂͌y�̂���Ă�����ׂ��Ȃ̂ŁA���҂ɑ��āu�ӔC�̎��Ȃ��z�͉]�X�v�ƌ����O�ɁA�䎩��������̔����ɑ��u�ӔC�v���ʂ����ׂ����ƍl���܂��B��낵���ǂ����B
�@�������������A�u�����w�ɑ����āv�ǂ��̂����̂ƋL���Ă܂����A���R���Ȃ��͕����w�̊w�ʂ��炢�͎���Ă����ł���ˁB���܂łǂ�Ȏ��т��グ���̂��A����������Ă��炦��Ί������ł��B
�����ԍ��F8445823
![]() 0�_
0�_
inouesp2����
>�Жڂ̉�
http://homepage3.nifty.com/ja8mrx/katamenosaru.htm
�M�a�̎��Ȃ̂ł��傤���H�B�@
�����ԍ��F8446307
![]() 1�_
1�_
�F����A������
������������A������ƃM�X�M�X���Ă�c
���b���u���x�v�߂��Ă��Ă����܂���(^^�U
�����ƁA�y�������b�����������ł��B
�Ⴆ��DG-48�݂����ȗD�G�ȃC�R���C�U�[�ŁA�ŗL�̍Đ���Ԃ̉�������������Ƃ����̂͗��ɂ��Ȃ������͓I�ȍl�������Ǝv���܂��B
�Ȃ̂ŁA�����Ƃ��̕��ʂ̂��Ƃ�m�肽���ł��B
��͂�DG-48�I�Ȃ��Ƃ��ł���@��́A���������̂ɂȂ��Ă��܂��̂ł��傤���c
�����ԍ��F8446399
![]() 0�_
0�_
inouesp�Q���Ȃ��͑傫�Ȋ��Ⴂ�����Ă��܂��B���x�ł������܂����킽���͕ʂ�KI�X�s�[�J�[���Ԉ���Ă���Ƃ����Ă���̂ł͂���܂���B���ۂɉ������������Ƃ̂Ȃ��������Ƃ������X�s�[�J�[��z�������Ŕᔻ������������܂���B���Ƃ����č��̏�Ԃł͂��Ȃ��̌��t�����ׂĐM���邱�Ƃ��o���܂���B
���͏��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̎���ɓ����܂������Ȃ������ꂾ���̑匩��������̂�����ςȗႦ�ł͂��炩�����ɂ�����Ɠ����Ă������������ł��B
�����ԍ��F8446418
![]() 1�_
1�_
�������̑����ł��B
�F����A�Ƃ����ɂ����m�Ȃ̂�������܂��A�ŋ߃T�E���h�T�C�G���X������ЂƂ�����Ђ́u�T�E���h�V���L�b�g�v�Ƃ������i���C�ɂ����Ă���������܂���B�i��ɃJ�[�I�[�f�B�I�p�ɔ̔�����Ă���悤�ł��B�j
�����A�V���L���Ƃ���i�j�̂ł����A�T�C�g���̃f���Ȃǂ��Ă݂�ƁA���̑_�����ǂ�������܂����B������SP�Ȃǂ̒��ቹ�⒴�����ʂ̃O���C�R���10dB�ȏ㎝���グ�A����͂��̂܂܂ɂ�����́u�G���n���T�[�v�u����ȃp���C�R�H�v�̂悤�Ȃ��̂̂悤�ł��B�������Ńf���������܂��B�ɂ������珬���߂�PC�ɂȂ��Œ����Ă݂Ă��������܂��B
http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/controller/index.html
���́A��������Ǝv���Ă���KENWOOD�̏�����SP�iLS-SE7�j��PC�`�~�j�R���|�o�R�ŁA�����Ă݂܂����B
���ʁA�r�b�N�����܂����B���t�I�N��6000�~�Ŕ������~�j�R���|�iKENWOOD��ONKYO�j����A�M�����Ȃ����̋�C���┗�͂�����A�����Ɍ����ĉ��y��EV���y���ނ��Ƃ��ł����̂ł����B�u���܂ʼn��������v�A����܂ł�EV Force-i�i38�Z���`�E�[�n�[�{�z�[���h���C�o�[�j�������炩�Ɋy���������̂ł��B
�����[���h���V�����C���Ȃ̂ł����A�y�����Ȃ��Ă��āA���܂ŎU�X�����s������CD��V���Ȋ��o�Ŋy���߂����ȗ\�������Ă��܂��B�i���Ȃ݂ɍ��A���Õi���I�[�N�V�����œ��D���ł��jKENWOOD LS-SE7���ăX�s�[�J�[�A5���b�g�����̏����Ȕ���12cm�E�[�n�[�ƃh�[���c�C�[�^�Ȃ̂ł����A��́u�y�����v�ɂ́A���̏����Ȉ����X�s�[�J�[�̌��E�������o���ꂽ�悤�ȁu�������v�������ɂ������悤�Ɏv���܂��B
�F����́u�s���A�I�[�f�B�I�v�̕�������A������ƃX���Ⴂ�ł������ˁB
���Ƃ����炷�݂܂���B�����Ă��������܂��B
�ǂ����A���́u�s���A�I�[�f�B�I���v�łȂ������̂�������܂���ˁB�i������N�\���ł��ˁB�ł��������[��j
�����ԍ��F8446535
![]() 0�_
0�_
kojirou sasaki�����܂���ςȋ�C�ɂȂ�����Ă܂����ǂ��܂�C�ɂ��Ȃ��ʼn������B
�ł����accuphase����ɂ���Ă�����ď����ቿ�i�ł��o���ĖႢ�����ł���ˁB�O���C�R�����Ȃ瑼�Ђ�����������o�Ă��܂�����ʃ��[�U�[�ɂ͂Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ��ł��B
DG48�͑���������܂œ���Ȃ������ꑪ�肩�����炷�ׂĈ��Řd����֗��ȃA�C�e�����Ǝv���܂��B�s���A�Ƃ��s���A����Ȃ��Ƃ�����Ȃ̋C�ɂ������y���y���݂܂���[�B
�����ԍ��F8446847
![]() 0�_
0�_
�h���L�[�R���O�i������
���肪�Ƃ��������܂��B�C�ɂ������y���y���ނƂ������܂��傤�B
�����ɐS�䂩��A���Ƃ����オ��̕��@�͂Ȃ����ƍ�ӂ���l�b�g��f�r���T�������Ă܂����B�����Č����܂����B
�܂����������Ă��܂��A�܂��A�I�[�f�B�I�\�[�X�����̂悤��PC��HDD�ɂ��Ă��������ɂȂ��Ă��܂��܂���"Frieve Audio M-Class"�Ƃ����D�ꂽ�\�t�g(3000�~)������܂��B
http://www.frieve.com/frieveaudio/
����p�}�C�N��PC�ɂȂ���ƁA���̃\�t�g�̎�������`��@�\�łقڃt���b�g�ɂł���悤�ł��B
�C�R���C�U�A���T���v�����O�ȂǑS�Ă̓���������64bit���������_�ōs���Ƃ����X�O�����m�ł��B��������p�̃}�C�N�����瑦�������ă��|�[�g�������Ǝv���܂��B
���I�[�f�B�I�h���C�o��"ASIO4all"(����)���g���Ƃ��Ȃ荂�i���ȉ��������܂��B��O�̏�Ԃł͎����ς݂ł����A���Ȃ�C�C�ł��B
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/02/29/asio4all.html
�����ԍ��F8447631
![]() 0�_
0�_
�F������
9�����Z���ňȑO�̂悤�ȖZ�����ł͂Ȃ��ł����A�d�����Z��������Ɨ��������܂����B
���炭���������̊ԂɐF�X�Ƃ������悤�ł����A�F�����܂��傤�I
�q����l�ɃI�[�f�B�I�@��������Ă�����A�����~�����Ȃ����̂ŋg�c������̋g�c�����CR-D2XR�𒍕�
�X�s�[�J�[���~�����ł��ƌ����Ɨ\�Z�͂ƕ�����A�\�Z�͖����ł��Ƒ���(��)
�ł̓p�C�I�j�A�̃t�������W�ꔭ��S-101SE�͂ǂ��ł����ƌ����A�Ⴂ��FOSTEX�̃��j�b�g�Ŏ��삵���̂�
�v���o���A�܂��t�������W�̃X�s�[�J�[�Œ����Ă݂悤�Ǝv�������A���̕����ɂ���܂����܂��J�����Ă��܂���B
�l�b�g�ł͍������̃X�s�[�J�[���A�b�v����Ă��܂����B
��قǂ܂Ŏc���Ă���V�X�e���ʼnf�批�y���[�r�[�q�b�g���Ă��܂����B�������Ԃ�����
���[�����o�[(�e�B�t�@�j�[�Œ��H��)�I�[�h���[���Y�킾�����I
���̓��L�V�R��
�G���h�E�N���W�b�g�E���h���[(�U�E���L�V�J��)
���̓e�L�T�X��
�p���A�e�L�T�X(�p���A�e�L�T�X)
���͐��E�����
�A���E���h�E�U�E���[���h(80���Ԑ��E���)��ύD���������I
���͉F����
2001�N�F���̗�
�X�^�[�E�H�[�Y
�X�^�[�g���b�N
���͖��m�̐��E��
ET
�o�b�N�E�g�D�E�U�E�t�B�`���[
�Ō�ɑg��(���m�Ƃ̑���)
���Ԃ����߂Ē����̂���ϊy�������̂Ń����b�N�X���܂����B�����͔���Ђ肳��̃W���Y�ƃX�E�B�O�W���Y�����I
kojirou_sasaki�����PC�W�̃��X�Ŏv���o�����̂͌��݂�PC�͖�1�N���O�Ɏ��삵�����ł��낻��CPU��ς������̂ł���
�܂��������E�E�E(��)
�����b�N�X������߂���ł����A�y�������y���ăX�g���[�g�E�I�u�E�t�@�C���[�I�I(�s��)
�����ԍ��F8450978
![]() 0�_
0�_
�h���L�[�R���O�i������@
>�ł����accuphase����ɂ���Ă�����ď����ቿ�i�ł��o���ĖႢ�����ł���ˁB�O���C�R�����Ȃ瑼�Ђ�����������o�Ă��܂�����ʃ��[�U�[�ɂ͂Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ��ł��B
�����ቿ�i�ɁE�E�E�܂��ɂ��̒ʂ�ł��ˁI�B80���~�͂������ɍ����I�I�B�g���Ă���v��
���C�����A�L���t�F�[�Y��E-550�Ŗ�60���~�A�����80���~�̃C�R���C�U�[�ł͉��i�o�����X
��������ƈ����C�����܂��B���z��40���~���x��������I�I�Ɛ��`���v���܂��B
�����Ƃ������Ɏ������ĊJ���҂����������Ă�������҂Ƃ��Ă�80���~���Ó��Ȋ�������
�܂��B��������H��AV�A���v�ɐ���}������������݂��邻���ł��B
kojirou_sasaki����@
�u�T�E���h�V���L�b�g�v�E�E�E���O���炵�ĉ������Ȑ��i�ł��ˁB���݂͐̂���m���Ă���
������Ƃ͋C�ɂȂ�̂ł����E�E�E�B�{���ł͂Ȃ��l�ȋC�����܂��B�����a�̃X�s�[�J�[��
�͗L�������m��܂���B���̏ꍇ�A38cm�E�[�t�@�[��JBL��S3100�A25cm×2��S4000�AS3500
HC1000�A�s���A��AV�p�ɃX�[�p�[�g�D�C�[�^�[���E�E�E����Ƀp�C�I�j�A�̃����g�X�s�[�J
�[S-A4SPT-VP�A��X���ɍw�������r�N�^�[�̃}�O�l�V�E���U����SX-M3�����L���Ă��܂���
E-550�Ŗ炷��S-A4SPT-VP�ł�����������z���ł��Ȃ��ቹ���o�܂��BSX-M3�͂قƂ�ǖ�
�炵�Ă��Ȃ��̂ʼn����d�����������āA����Ӗ����z�̃X�s�[�J�[�U���ގ��̃}�O�l�V�E
���̗ǂ��͂܂��������Ă��܂���B
�Ԃ̃I�[�f�B�I�͐̂�CD�`�F���W���[��CD���Ă��܂������A���͂�HDD�̎���ł��ˁB�J
�[�i�r�{�̂�30GB��HDD��i-Pod��30GB�^�C�v�p���Ă��܂��B���݂����Ƃ��������y��
���̂͂�������PC�̃L�[�{�[�h���͂��Ȃ��炷��PC�̃X�s�[�J�[�ł��B����Ȗ�ł���PC�p
�X�s�[�J�[���I���L���[��GX-100HD���w�����܂����B
�����ԍ��F8451526
![]() 0�_
0�_
�F���ӂ�
�ŋ߂��̃X���̂����Ŏ����I�[�f�B�I�@����ɃX�s�[�J�[�ɂ��ĐF�X�l���������܂����B�͂����Đ�������������Ȃ����Ƃ������͎̂��ۂɂ���̂ł��傤���H
���_�I�ɐ��������ƌ������̂͑��݂��邩������܂���������ۂɃI�[�f�B�I�V�X�e���ōČ����邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��傤���H
�Ⴆ�ΈȑOinouesp����̓R�[���̉��̓��ߐ��������厖���Ɨ͐�����Ă��܂����B�m���ɃX�s�[�J�[���X�s�[�J�[�R�[���̑O�ʂ���o�����݂̂����o���Ȃ��̂Ȃ炻�������m��܂���A�������X�s�[�J�[�̉��ƌ������̂̓X�s�[�J�[�R�[���̑O�ʂ���o�鉹�݂̂ł͂���܂���B
�G���N���[�W���[�̖�������܂����o�X���t�|�[�g�̗L���₻�̈ʒu�ɂ���Ă����͗l�X�ɕω����܂��B�܂��R�[���̍ގ���傫���d�ʂȂǂɂ���Ă��ω����܂��B�ǂ�����ԑ厖�Ȃ̂��͎��ɂ͂킩��܂���A�����Č����Ȃ炷�ׂẴo�����X�̗ǂ����̂ł��傤���H
�^�C���h���C���̃X�s�[�J�[�Ȃǂ��Ǝ��̗��_�Ɋ������Ă��܂������̉����������đ��̉����������Ȃ��Ƃ��v���܂���B
���̒��ɂ͗l�X�ȃX�s�[�J�[�����肻�ꂼ�ꂪ�Ǝ��̌��Ȃ藝�O�Ȃ�������č���Ă��܂��A�ǂ��炪�������Ăǂ��炪�������Ȃ��ȂǒN�ɂ����f�ł��܂���B
���ǎ����̍D�݂�g�p����\�Z�ɍ��킹�Ď����őI��ł������Ƃ����o���Ȃ��Ǝv���܂��B
�悭�I�[�f�B�I�}�j�A���i�����܂߁j�ׂ�₷���̂����l�̑g�V�X�e���������̍D�݂ƍ���Ȃ�����Ƃ����Ĕᔻ�I�Ȉӌ�����������A�����̃A�h�o�C�X�ɏ]��Ȃ���������ƌ����ċ}�ɑ���ɑ��Ĕᔻ�I�ɂȂ����肷�邱�Ƃł��B�����̈ӌ������R�Ɍ������Ƃ͑厖�Ȃ��ƂŒN�������������Ǝv���܂��B�������l�ɂ����̈ӌ�����������̂͊ԈႢ�ł��B�D���Ȃ��̂����炱���]�v�ɔM���Ȃ�̂ł��傤������Ȃ��Ƃ��J��Ԃ��Ă��Ă͂܂Ƃ��Ȑl�̓I�[�f�B�I�ƌ��������ǂ�ǂ�Ă����Ă��܂����������ƕ��I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����ƋC�y�ɃI�[�f�B�I�≹�y�̘b���o����悤�ɂ݂�Ȃŗǎ��������Đ���グ�Ă����܂��傤�B
�����ԍ��F8456448
![]() 2�_
2�_
�h���L�[�R���O�i������ɂ���
���͂����Đ�������������Ȃ����Ƃ������͎̂��ۂɂ���̂ł��傤���H
���͂��̉���
�D�݁A�D�݂łȂ��E�y�����A�y�����Ȃ��E�����₷���A�����ɂ����E�D�݂̃W�������A�D�݂łȂ��W����������
�����ɑ��Đ����������������Ȃ������Ǝv���܂��̂ŁA���̐l�ɑ��Ă͐������Ȃ���������Ǝv���܂��B
�����̂��q����̎Ԃ̃R���|�̃C�R���C�U�[�ݒ�͖w�Ǔ������͖̂������L��CD�EMD�����S���Ⴂ�܂��B
�Ƃ̃I�[�f�B�I�@�������W���������ɂ͗ǂ������̃W�������ł̓_���ƌ������Ƃ��L��ł��傤��
������Ō��߂�Ηǂ����Ǝv���܂��������̍D���ȉ������X�ω����A�W���������V���Ȕ���������܂��B
���͎Ԃɂ̓p�C�I�j�A�A����ł̓I���L���[�Ƃ��߂ĉ��͂悭������h���V�����̉����D���Ő��m�ɂ�
�h���E�V���L�ł��B
���\�N����Œʂ��Ă��܂��������q����̉����@�������V���b�v�Œ�������A�ʔ̓X�Œ�������
���Ă���ƐV���Ȕ���������܂����B
�F�l���KEF�̃X�s�[�J�[�����Ƃ��ɂ̓X�s�[�h���͖����̂ł������ɒ����₷�����ɂ��̂ɂ���������������
�㋉��4�h�A�[�Z�_���ɏ���Ă��銴�������܂����B
�V���b�v��Dynaudio�̃X�s�[�J�[�������ɂ͔��Ɍ����炵���ǂ����őS�̂ɍL���銴����
�I�[�v���J�[�ɏ���Ă��銴���ł����B
���q����̎����ELAC�̉������Ƃ��ɂ͔��ɂ������肵�����ŃJ�`�b�g�������܂���������
�h�C�c�n�̑����̂������肵���Ԃɏ���Ă��銴���ł����B
�ǂ�������g�A���ȉ��ł͂Ȃ������̍D���ȉ����ǂ�Ȃ̂�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�ǂ����D���ȉ��Ǝv���Ă��������A�����Ȃ�Ă������Ɗ��Ⴂ�Ă����̂ł͂Ȃ����Ɛ��N�O�Ɏv��
�ŋ߂ł͐F�X�ȉ����ɍs�����蒮�����肵�Ă��܂��B
�������g���̂悤�ȏ�Ԃł��̂ŁA�D���ȉ��T���͉i���ɑ����Ǝv���܂����@��ނ͈����̂����肪����
���̍��͉͂i�v�ɂ͑����܂���B
�����ԍ��F8457781
![]() 0�_
0�_
�@�f��u������тƁv���ςĂ��܂����B�Ȃ��Ȃ��ʔ��������ł��ˁB�f��̒��Ŏg���Ă���I�[�f�B�I�@��̃X�s�[�J�[��JBL�ł������Amarantzcd67�i��inouesp�j���������Ă����̂Ƃ͈���āA�����T�[101�͂ǂ��ɂ��o�Ă��܂���ł�����(^^;)�B��l���̏Z���i���E�i���X�j�ɒu���Ă���̂́i�����炭�́j4318�A�В���ɂ������̂́i�n�b�L���Ɗm�F�͏o���܂���ł������jARRAY BG�V���[�Y�ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B�E�E�E�E�������AJBL�̓W���Y�������Ƃ̕]���͌��R�Ƃ��đ��݂��邵�A���l��JBL�ŃN���V�b�N�����Ƃ͎v��Ȃ����A�ʂ����Ă��̉f��ɂӂ��킵���I�肾�����̂��Ƃ����^��͊����܂��i�܂��A�قƂ�ǂ̊ϋq�ɂƂ��Ă͂ǂ��ł������b�ł��� ^^;�j�B
�@���āA�f��t�B�����̐������͑傫�������ē����܂��B����̓R�_�b�N�ƕx�m�t�C�����ł��B���R�̎��Ȃ���撲���Ⴂ�܂��B�����������\�ȋ敪�������Ă��܂��A�R�_�b�N���g�F�n�ŕx�m�����F�n�ł��B���Ăł̓R�_�b�N�������ƕ��������Ƃ�����܂����A�x�m�̐F�����D�ލ�Ƃ����Ȃ��Ȃ��悤�ŁA���Ƃ��u���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�v�V���[�Y�͕x�m�t�C�����ŎB���Ă��܂��B
�@�x�m�̉撲�͍ŏ����犦�F�n��_�������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�掿�̉𑜓x�����̉�ЂȂ�ɕ��������ʂ���l�߂Ă��������ʁA���̂悤�ȃ^�b�`�ɂȂ����̂ł��傤�i�������A���ۂ̂Ƃ���͒m��܂��� ^^;�j�B�悭�l���Ă݂�A���̂��Ƃ̓I�[�f�B�I�@��A���ɃX�s�[�J�[�v�̃A�v���[�`�ɂ��ʂ�����̂��Ǝv�����肵�܂��B�x�m�̉撲�ɂ͕��������d���Ō��_��ׂ��Ă䂭���Y�X�s�[�J�[�̊J�����@�Ǝ����Ƃ��낪����悤�ȋC�����܂��B
�@�������A��ۂ̐��E�ł���f���͕x�m�̌����ЂƂ̃��@���G�[�V�����Ƃ��đ������܂��B��Ƃ̈Ӑ}����Ƃ���ɂ��A�t�B�����͑I�������ꍇ�������ł��傤�B�t�B�����̎�ނ͉f���\���́u������v�Ƃ��Ă̒n�ʂɂ��܂��B
�@���Ē��ۂ̐��E�ł���I�[�f�B�I�́A�@��̌��ƃ��X�i�[�Ƃ̑������S�Ăł��B�����@�킪�f���́u������v�Ƃ��ċ@�\����AV�Ƃ͈Ⴂ�A�@��̃R���Z�v�g�����m�������܂��B��������������Nj�����Ηǂ��킯�ł͂Ȃ��Ƃ���ɁA�I�[�f�B�I�̖ʔ���������Ǝv���܂��B
�|�� kojirou_sasaki����
�@�����܂���B�u�T�E���h�V���L�b�g�v�Ƃ������i�������ŏ��Ă��܂��܂����B���ƂȂ��u�P�������v�Ƃ��u�n�b�L���v�Ƃ���������̖��O���v���o���܂��B�I�[�f�B�I�@������̃l�[�~���O�̃R���Z�v�g���̗p����Ɩʔ����E�E�E�E�Ǝv�����肵��(^^;)�B���Ƃ��u�}�b�^���v�Ƃ��u�N�b�L���v�Ƃ��u�h���V���J1���v�݂����Ȗ��O�̃X�s�[�J�[������A�E�P�邩������܂���i���E�P�邩���I ^^;�j�B
�|�� �Ⴂ������ԉ�����
�@S-101SE�͋����L��܂��ˁA�ŋ߁u�g�c���v�ɂ͑����^��ł��Ȃ��̂Łi���������A���͕������ݏZ�ł����ǁj�A�߁X�����ɍs�������Ǝv���܂��B�f�批�y�̘b�ɂȂ�Ǝ����~�܂�܂���B���������A�^�f�B�[���[�̓X���ŁuJBL�̃X�s�[�J�[�Ō����Ȃ��ƃn���E�b�h�̉f�批�y�݂����Ɋ����Ă��܂��v�ƌ�������E�P�܂����i���j�B��������9���̒��Ԋ����Z���I����Ă��炸�A���ς�炸�̖Z�����ł��B�������ƕЕt���đ��߂ɋA����y�ӏO���Ƃ��������Ƃ���ł��B
�����ԍ��F8466935
![]() 0�_
0�_
�F�l�A�����������Ă���܂��B
�����z�����ǂ��ɂ���i�������ĉו��̐������X�����I���܂����B
����������悤�ɁA�����������ւ̃A�v���[�`���A���~���̒�q�����Ȃ��A4344�͖ܘ_
���̑��A�A�i���O�p�@�ނ�������ďオ��̂�����ƂƂ����L�l�ł��B
�I�[�v�����[�����Q��A���R�[�h����W�O�O���A���̑��A���v�A�r�f�I�A���b�N�A�e�[�v��
��́A���\��オ�艺�肵���ł��傤���H
���A�Ń��^�{�Ȃ����������͂ւ����悤�ł��B
���ǁA��������SP�͂��荇�킹��BOSE�����A���C����AV�W���\���@��͉��̕ω���
����܂���B
�����o������ɂȂ����̂ɁA4344�������Ȃ��̂͑S���c�O�ł�����ނ����܂���B
�����������Ԃ������ăZ�b�e�B���O�����������܂�����ʐ^�ȂǓY���āu���|�[�g�v����
����ł���܂��̂ŁE�E�E�E�B
����[�������u���X���~�v�ƌ��_�H�����킳��Ă��܂��ˁ`�B
�����ԍ��F8467343
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���A������
���t�I�N�ŁA�T�E���h�������ƁA����Ȃ������A�u�T�E���h�V���L�b�g�v�������Ⴂ�܂����B�����͂��܂����B
����ɂ��Ă���k�݂����Ȃ��̏��i���A�ǂ��ɂ��Ȃ��̂��I�Ǝv���A�������Z�b�e�B���O���āA�܂��͏��^SP�ŏ����g���Ă݂܂����B
���_�������A�Ȃ��Ȃ��ǂ��ł��B
���ʂ̃g�[���R���g���[����Bass�ATreble�̎��g���т�肸���ƊO���̎��g����ω������Ă銴���Ƃ������A�ł��O���C�R�Œ����ƒ�������u�[�X�g����̂Ƃ��Ⴄ�s�v�c�Ȋ����Ȃ̂ł��B���m�Ƀh���V�����C���ɂȂ�̂ł����A���̓h���V�����͍D���ł͂Ȃ��̂ɁA�R�C�c�͌��ȉ��ł͂Ȃ��̂ł��B
�܂����������āA���܂��\���ł��Ȃ��̂ł����A�Ⴆ���炭�����Ă�����ʂ�OFF�ɂ���Ɓu�������T�~�V�[�C�v�u�c�}���i�[�C�v���Ɋ����Ă��܂��܂��B�v�͔h��ȉ��A�����n���̂��鉹�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤���B���̂�10���ł���Ɋ����ƁA�����ƒ����Ă������܂ł̉����c�}���i��������Ƃ����A�����ɕω�������ȃ��^�N�V�̊������A�����Ă����A�Ȃ̂����E�E�E
�܂�130theater����̋�悤�Ɂu�{���ł͂Ȃ��C���v���܂����A�����g���{���ł͂Ȃ��悤�ȋC������̂�(��)�A�������������ł��B
�֗��Ȃ̂́u���ʁv�u�V���L�b�g�l�X(��)�v�u�ቹ�d���|�����d���v��A�����Ď茳�ő��삷�鏬���ȃR���g���[�����t���Ă��邱�Ƃł��B�����\�[�X�ɂ���āA���邢�͋C���ɂ���ĉ��̌X����ω���������̂́i�s���A�I�[�f�B�I�ɂ����Ă͎ד���������܂��j�Ƃ��Ă��֗��ł��B�܂����̎��ɂ͉����̗͔��ɏ��Ȃ���ۂł����B
��ɂ��`�������o�b�I�[�f�B�I�̉���������\�t�g�Ɏg���A����p�R���f���T�[�}�C�N�Ɠd���i�~�L�T�[�j�����������̂ŁA������ɂǂ��Ȃ邩���܂߂āA���炽�߂Ă��m�点�������Ǝv���܂��B
�T�E���h�V���L�b�g�̎����͂�����i�������H�j
http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/controller/index.html
�ł͂ł�
�����ԍ��F8468852
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
kojirou_sasaki����
��ѓ���ł��˂��A�u�T�E���h�V���L�b�g�v�B
���������Ă���܂��B
�ԓ��̐U����[�h�m�C�Y�Ƃ̌��ˍ����Ō��ʂ��̊��ł���A�J�[�I�f�B�I�炵�����i�Ƃ������܂��ˁB
�G�t�F�N�^�[�Ƃ����ׂ��A�C�e���Łu�n�[���j�N�X�E�G�N�T�C�^�[�v�u�\�j�b�N�E�}�L�V�}�C�U�[�v�Ə̂���܂��B
�����ɔ{�����������Z�������ĉ��Ɩ��ēx�����߃n�b�L���E�N�b�L�������Ă���܂��B
���l�̌��ʂ����uBBE�v�Ƃ����G�t�F�N�^�[������A
Pioneer�̎ԍڃ��j�b�g�̑������@�\�Ƃ��ē��ڂ��Ă��܂��B
�z�[�����[�X�ł��ȉ��ʍĐ����ɃX�s�[�J�[�̃o�����X������Ă��鎞�͌����U�ʂł���B
�Ⴂ������ԉ�����
�X�s�[�J�[�̌X���ƎԎ�̃C���[�W�t���ɂ͂������ԉ�����Ɗ��S���Ă���܂��B
�{���ɕ�����₷���āu�m���ɁI�v�ƕG��@���Ă��܂��܂����B
���p�C�I�j�A�̃t�������W�ꔭ��S-101SE�͂ǂ��ł����ƌ����A
�r�N�^�[�̃E�b�h�R�[���E�X�s�[�J�[�E�L�b�g�̖����Ȑl�C��
�^��ǃA���v�E�L�b�g�ȂǂȂ�DIY�A�C�e���������܂������A
SP���j�b�g���������������ċv����Pioneer�ł�����
����SP���j�b�g�������Ǝv���܂��B
�j���[�g�����ŃX���[�Y�Ȓ�ʂ��ƂĂ��S�n�悳�����ł��ˁB
�Z�b�g���ꂽ��A����A���r���[�����肢�v���܂��B
�l�I���W����A
���v�Ԃ�ł��B
�����C�����ň��S���܂����B
�܂��M���������݂��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F8469579
![]() 0�_
0�_
�Ⴂ������ԉ�����
�����́A�O�̂����e�Ɋ������Ȃ���A���e��Y��Ă���܂����B
��KEF�F�㋉�̂S�h�A�Z�_��
��Dynaudio�F�I�[�v���J�[
��ELAC�F�h�C�c�n�̑����̂������肵����
�f���炵���g���ł��ˁB
�������ǂ��̒ቹ���ǂ��̂Ƃ������Ȃǂ��A�i���肪�N���}�D���Ȃ�j����Ɋm���ɓ`���܂��ˁB
�Ƃ���ŁA�ْ����Ȃ��������q�ł���t�����X�Ԃ��v�킹��X�s�[�J�[�ƌ�������A�����v�����܂����H�i�V�g���G����v�W���[�Ȃǂ̃t�������A�t���t���A�Ƃ��Ƀl�o�������Ȃ�Ȃ��璼�i���̍����t�����X�Ԃ���D���Ȃ��̂ł�����j
����BGM�p��SP�Ƃ������ƂɂȂ�܂����ˁE�E�E
�����ԍ��F8469754
![]() 0�_
0�_
�F����A���͂悤�������܂��B
130theater����
�����o�b�X�s�[�J�[�̂f�w�[100�g�c������������g�p���Ă��܂��B��ϋC�ɓ����Ă��܂��B
���E�������
�䂪�ƂŃP�������̈Ӗ����ʂ����͉̂ł����ł����B(�j
�l�I���W����
�����������̃��|�[�g��ϊy���݂ɑ҂��Ă��܂̂ł�낵�����肢���܂��B
redfodera����
�p�C�I�j�AS-101SE�Z�b�g��Ɏ��Ȃ�̊��z�����X�v���܂��B
kojirou_sasaki����
�T�E���h�V���L�b�g�A�o�b�I�[�f�B�I�y�������ł���
���ْ����Ȃ��������q�ł���t�����X�Ԃ��v�킹��X�s�[�J�[�ƌ�������A�����v�����܂����H
������BGM�p��SP�Ƃ������ƂɂȂ�܂����ˁE�E�E
�V�g���G���ƌ����Ό�y���V�g���G�����X�����Ă��܂��̂ʼn�������܂������Ɠ��̏��S�n�ŗǂ��Ӗ��ł�
�����Ӗ��ł��n�C�h���͖{���Ɍ��I�ł��B
�f�m���̂r�b�|�b�w303�A���Y�ł������[���b�p�ԓI��
�\�t�g�œK�x�ȏd�ʊ��A�o�����X���ǂ��ӂ���Ȃ���(���i���̗ǂ���)
���b�N��(�n�[�h���s)�ɂ͑������������Ȋ����ŁA�������������ł����B
���j�^�[�n�ł͂Ȃ��A���Ȃ����S�n(�����S�n)�̊����ŁA��t�����X���]�[�g�d�l�Ԃ���
���̒��������ł̎��Ŕ͈͂������Đ\����Ȃ��ł��B
�����ԍ��F8471298
![]() 0�_
0�_
�F����@���͂悤�������܂��I
�L�q���e�����I���Z���Ȃ��Ă����̂œ��荞�߂��₵���������ăW�b�g���߂Ă��܂�����(^^)
�����Ɂi�Ⴂ������ԉ�����j�̖����A�V�g�̐��I�I�I
�@��KEF�F�㋉�̂S�h�A�Z�_��
�I�[�䂪�Ƃ�KEF���[�A���[�V����͂����邼�I�@�E���H�ł�KEF�ƌ����Ă��s������L���܂ł������B
����͍������A�ł������ŋC�����܂����B�S�h�A�Z�_���͏㋉���肶��Ȃ��A�X�^���_�[�h�̃^�C�v�����Ă���I�����K�i����͂���邯�NJ��ق��Ă��������ˁB
���X�ł����r�o�Ɋւ��ݒu�Ƃ����̂����ɑ厖�ƌ��������������Ă��鍡�����̍��ł��B
�ʐ^������Y�t���Ă��܂��܂����i�|�j��ɂȂ�̂��ȁH�S�z�ł����j�B
�ȑO�͂`�u��ɐݒu���Ă��܂����A�T�E���h100�C���`�X�N���[���̈׃��C���r�o�����Ȃ艜�܂��Ă���E�ǂɂقڂ���������Ԃł����B���R���e����A���E�o�����X�A���ꊴ�A�t�щ�etc�E�E�E�B������100�C���`���߂r�o���30cm�O�i�A���R�X�N���[���͂r�o�̏�Ɉ���������g�p�s�ɂȂ�܂������B
�ł����̑O�i�̂������Ń��C���r�o�����������S��w�Ǖʕ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ʂɕϐg���܂����B2ch�Đ��ł��[���T�����h��������A������good�ɁA�ԓI�ɂ�1000����1500�ʂɂ͂Ȃ������ȁH�Ǝv���Ă܂��B
�����܂���E�����Ă��܂��܂������A���ȕϑJ�̘b�ɂ��Ă��܂��܂����A���߂�Ȃ����I
�o�l�I���W����p���v���Ԃ�ł��A�V�����߂łƂ��������܂��A��������╬�o�I�ł��l�I���W����̓ːi�͂ł����Ɨǂ������Ɍ������ƐM���Ă܂���[�A�����|�[�g�y���݂ɑ҂��Ă��܂��B�ꌾ���̋��Z�n�����q�ׂ̗̉��l�ł�(^_^)�A�ł́B
�����ԍ��F8471610
![]() 0�_
0�_
�җ��ڑO�ɁA�����z���͍������܂��B���A�D���ȉ��y�A�I�[�f�B�I�̂��߂Ȃ�
�܂��܂��u�����v�Ȏ��͌����Ă͂����܂���B
���̂��т̈����z���Ŏd���I�ɂ͒ʋ��d�Ԃł͂����Ȃ邽�߁u���v�Ƃ���
���̖����u���|�u�v�ƌ���������̎Ԃ��w�����܂����B
�K���A�V���ɂ͂R�䕪���炢�̒��ԃX�y�[�X������A�Ė����ނ��ڂ����̃|���R�c�Ԃ�
�u�V�[�g�v�����Ă��܂��B
�Ԃƌ����A�I�[�f�B�I�@��ƌ������̎����Ă��镨�͂ǂ����𗧂�������ŁA
��Ɖ䂪�g�����݂܂��B
�����������͍��̂Ƃ���u���u�v��Ԃł��̂Łu�A�i���O��p���[���v�ւ̓���
���������m��܂���B
�\�z�I�ɂ̓r�f�I�ELD�����Â��v���W�F�N�^�[�Ńh���r�[�T���E���h�Đ��Ȃ̂ł��E�E�E�E�B
�悸�́uHD�p�V�X�e���v�̗����グ���}����鏈�ł��B
�����ԍ��F8471827
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���A�����́B
�Ⴂ������ԉ�����
�u�f�m����SC-CX303�v�Ő́A�����40�N�߂��̂��v���o���܂����B303�Ƃǂ����u�����v�����ʂ��Ă���̂ł��傤���B�������Z3�N���A���a48�N(1973�N)���ł��B���̍��̎��ɂƂ���JBL��A���e�b�N�͍���̉ԉ߂��Č�����������܂���ł����B�����ɓo�ꂵ���̂�JMTEC�Ƃ����A���e�b�N�̘a���R�s�[�ł��B�����Ď��ɂ́A���̍��t�B���b�v�X��u���E���Ƃ��������B���[�J�[������̓I�ł����BSC-CX303�͒��������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�V���v���ȃf�U�C�����烈�[���b�p�I�Ȃ��̂������A���̍����v���o�����̂ł����B
�ʐ^�͂��̍��~�����Ă���ɓ�����Ȃ�����̂��̂�`�������̂ł��B�������炢�͎��ƒ��ɕ`�����悤�ɂ��v���܂��B�v���A���̍��͗~�����Ƃ����u�v���v���s���A�ł����B�����m�炸�ɔY�܂��ɂ����u����āv�����̂ł�����c
�ςȊG��UP�����Ē����܂������A�X���b�h�^�C�g�����u�V�E�������́c�v�Ȃ̂Łu�������v�Ƃ������ƂŃR�W�c�P�����Ē����܂����B
�����ԍ��F8473219
![]() 0�_
0�_
satoakichan����
���v���Ԃ�ł��A���̊ԂɃZ�b�e�B���O���P��Ɛi�s���������̂ł���
���S�h�A�Z�_���͏㋉���肶��Ȃ��A�X�^���_�[�h�̃^�C�v�����Ă���I�����K�i����͂���邯�NJ��ق��Ă��������ˁB
�㋉�̌��t���㎿�ɕύX���܂��傤���ˁA��������ǂ̃^�C�v�ł��㎿�ł����(�j
���E�������
���f��t�B�����̐������͑傫�������ē����܂��B����̓R�_�b�N�ƕx�m�t�C�����ł��B
�����Ȃ�ł����S���m��܂���ł����B�����ē������قȂ�g����������Ă��鎖���A���ɂȂ�܂����B
�������Ԋ����Z���I��点�A������肵�Ă��������B
kojirou_sasaki����
�������40�N�߂��̂��v���o���܂����B303�Ƃǂ����u�����v�����ʂ��Ă���̂ł��傤���B
���������Z3�N���A���a48�N(1973�N)���ł��B
���͂܂����܂�Ă��܂���B(�R�j�M�d�Ȏv������̂���X�P�b�`�q�����܂����B
����`�܂���܂����B�G����������Y��ŁA�܂������������̃I�[�f�B�I�@��ł��ˁA�悭�c���Ă܂���
���̍��Z���̎��͊m���Ԃ̃X�P�b�`�ł������c���Ă��܂���B���i����ɂ��Ă��������B(���Q�j
�����ԍ��F8474731
![]() 0�_
0�_
�F���ӂ�
���������
�f��̃t�B���������̗l�ȓ���������̂ł��ˁA�ȑO�J�����D���̗F�l�Ƀt�B�����ɍS��l�������ƕ������̂��v���o���܂����B���͍ŋ߈ȑO�ɔ�f��قɍs���ĉf����ς邱�Ƃ��߂����菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�w���̍��̓��[�h�V���E�͖ܘ_�P�ُ�f�̂��̂⋌��Ȃǂ��ǂ��͂������Ċςɍs���Ă����̂Ɂc���������ŋ߂͎O�{����I�[���i�C�g�Ȃǂ������ł��ˏ����₵���ł��B
�l�I���W����
���z�������l�ł����B����ɂ��Ă����R�[�h800���͐����ł��ˁB���C�ɓ���Ȃǂ��Љ�����B
satoakichan����
�Z�b�e�B���O�I���s�����悤�ł��ˁA�����ƒ�̎���Ȃǂɂ��Ȃ��Ȃ������ȃZ�b�e�B���O�Ƃ܂ł͍s���܂����X���s������J��Ԃ��Ă��܂��B�ŋ߂͉����ɂ͋@�ނ̗ǂ�����������܂����Z�b�e�B���O�̗ǂ������̂ق����e�����傫���̂��ȁ[�Ɗ����Ă��܂��B���g���̃X�s�[�J�[��KEF��iQ9�ł���ˁBKEF�̓������\���Ɏ������f���炵���X�s�[�J�[���Ǝv���܂���B
kojirou sasaki����
�f���炵���C���X�g�ł��˂��̍��̏����ȋC�������M���������܂��B�����w���̍��悭���ƒ��ȂǂɃm�[�g�ȂǂɍD���Ȃ��̂⓲��̂��̂Ȃǂ������U�炵�Ă��܂����B���̂͂����̗������ł����c���Ȃ݂Ɏ���s48�N���܂�ł��B
�����͎B�蒙�߂��e���r�ԑg���ςĂ����̂ł����A�F����͖����z�����Ƃ����ԑg�������m�ł����H�Q�X�g�̂��������Љ���薢�����J�������m������Љ��Ƃ����ԑg�ł�������9/26�������ɁA�I�[�f�B�I�P�[�u���ւ̂������Ƃ������Ƃō������T���Q�X�g�ŏo�Ă����̂ł��B�X�^�W�I��B&W��800D�ƃN���b�Z��CD�v���[���[�ƃA���v���������݊e��P�[�u����ς��A���̈Ⴂ���������T���M������Ă��܂����B���̏o���ҒB�͂��܂艹�̕ω��������Ă��Ȃ������悤�ł������̃V�X�e������o�Ă��鉹�ɂ͊�������Ă����݂����ł��B���������T����͎���Ƀ}�C�d�������ĂĂ���炵���ł��B
�|�\�l�̒��ɂ̓^����������͂��߂��Ȃ�I�[�f�B�I�ɍS���Ă�����������̂ł��Ђ����������X�ł����]��������ׂ�I�[�f�B�I�k�`�A�����̂������Ȃǂ����ԑg������Ζʔ����ȂƎv���܂����B��������I�[�f�B�I�[��̕��͖ܘ_�����̂Ȃ����������̓I�[�f�B�I�ɋ����������I�[�f�B�I�Ƃ�����������Ǝs��������̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B
�����ԍ��F8487603
![]() 0�_
0�_
kojirou_sasaki����@
�T�e����M-14LE�͍��o��MC�^�J�[�g���b�W�ŏ����A�g�p���Ă��܂����B�m���j������MC�^��
����Ȃ���o���܂�����ˁH�BMC�^�͏����g�����X���K�v�ł��������ł������炿����Ɠ�
��ł����B�I�v�V�����Ő������|�����R�H�������܂������A�����������Ȃ��������Ɋ���
���ǎg���܂���ł����B�V���A�[�^�C�v�V���g���܂����B���Ɏ����g�����J�[�g���b�W�̓e
�N�j�J��AT-15Sa�A�O���[�X��F-8E�A�p�C�I�j�A��PC-1000�U�A�e�N�j�N�X��EPC-205CMK�U�A
EPC-205CMK�V�A�Ōオ�e�N�j�J��MC�^�J�[�g���b�WAT-33�ł��B
�e�J�[�g���b�W���^�Ԃ��グ��ƐF�X�v���o���܂��B�e�N�j�J��AT-15Sa�͂��~�j�̃��C���R
���^�N�g�������Ǝv���܂��B�����VM�^�Ƃ������Ă��܂����ˁB�p�C�I�j�A��PC-1000�U�̓�
�j�^�[����ɓ��I���Ă��炢�܂����B����������Ő�[�ŁA�s���A�{�����̃e�[�p�[�J���`
���o�[�������ƋL�����Ă��܂��B�e�N�j�N�X���T�}���E���R�o���g���ʼn����̎��ʂ���
�߂ď������A�g���b�L���O�\�͍͂ō��ł����B�܂��{�͎̂����Ă���̂ł����A�����j�͂�
�����ɖ����悤�ł��B�@
���R�[�h�v���[���[�̓p�C�I�j�A��PL-1800�����`�Ǝ����Ă��܂��B�N�H�[�c���b�N���o�鏭
���O�̐��i���ƋL�����Ă��܂��B����3�`4�N�͎g���Ă��Ȃ��̂ł����A���̑O�X�C�b�`���
�ꂽ����܂����B�^�[���e�[�u���̎��͂ɑ��x�m�F�p�̖͗l�H���t���Ă���̂ł����A��
�����͂����肵�Ȃ��̂ł��B�E�E�E�����͌u�������͓̂d�����g�����̂܂܂ł������A����
�C���o�[�^�[���̌u�����Ȃ̂ł��˂��B���g�����S���Ⴂ�܂����番����Ȃ����P�ł��B��
�p�̃����v���t���Ă���̂ŁA��]���͒����o���܂����E�E�B����ł��ˁB
�����ԍ��F8487911
![]() 0�_
0�_
�F����@���͂悤�������܂��I
���E�������@�́@�f��t�B�����̘b�@��ώQ�l�ɂȂ�܂����B������
�@����������������Nj�����Ηǂ��킯�ł͂Ȃ��Ƃ���ɁA�I�[�f�B�I�̖ʔ���������Ǝv���܂��B
�@
�S�����̒ʂ肾�Ǝv���܂��A�������I�[�f�B�I�݂̂Ȃ炸�A�`�u�Ɋւ��Ă��[�����w���������ł��ˁI
�A�܂����ł�(^^)
�h���L�[�R���O�i�������
�@���ŋ߂͉����ɂ͋@�ނ̗ǂ�����������܂����Z�b�e�B���O�̗ǂ������̂ق����e�����傫���̂��ȁ[�Ɓ@�@�@�����Ă��܂�
�����Ȃ�ł���[�I�ܘ_�@��̐��\������܂����A�Z�b�e�C���O�̗ǂ������őS���̕ʕ��ɋ߂��ς���Ă��܂���������̊����܂����B�ܘ_��������ׂ̈ɏ��X�̏���i�A�N�Z�T���[�A�d�����j������܂����A�Z�b�e�C���O�̕ω�����ԑ傫���悤�ȋC�����܂��B
�������͎B�蒙�߂��e���r�ԑg���ςĂ����̂ł����A�F����͖����z�����Ƃ����ԑg�������m�ł����H
�n�C�A�m���Ă܂����A�ƌ����̂����̔ԑg�̏Љ���@I LOVE YOU BMW����@�ƌ��������@[8415148]�@�ōs���Ă���i���̃X���b�h�̏ォ��R���̂Q�ʂ̏��ł��B�j�@�����ԑg�̗����Ɂi���R�͏����Ă���܂�^^;�j���܂����B���̎��v�����̂��@�h���L�[�R���O�i�������
���|�\�l�̒��ɂ̓^����������͂��߂��Ȃ�I�[�f�B�I�ɍS���Ă���������E�E�E�E��������E�E�E�E�����̓I�[�f�B�I�ɋ����������I�[�f�B�I�Ƃ�����������Ǝs��������̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B
�Ɠ����A�����ł��I�I�I
�����ԍ��F8489306
![]() 0�_
0�_
�F����A������
���Ⴂ������ԉ�����
���h���L�[�R���O�i������
�܂Ƃ߃��X�Ŏ��炵�܂��B
�ٍ�X�P�b�`�ŎႢ���̏�M�ɂ������������݂����ŁA�ƂĂ��������C�����ł��B���肪�Ƃ��������܂��B
�ł�����F����̉������摜���q���������ł��B�̂̃X�e���I�Z�b�g�̎ʐ^�Ƃ�����ĂȂ��ł����H
��130theater����
�T�e��M-14�g���Ă炵����ł��ˁB
�u�J���`���o�[�v�A�������������ł��B
���u�R���v���C�A���X�v�ƌ����u�@�ߏ���v�̂��Ƃł����A�����́u�J���`���o�[�̏_�炩���v�̂��Ƃł�����ˁB
���̎g�����J�[�g���b�W�͑債�����Ƃ���܂���ASHURE�̍����i�ɓ���Ȃ���A�I�[�f�B�I�e�N�j�J�̈���AT-3�A�����i������SHURE M7/N21D(���y�i)�A��l�ɂȂ��Ă���O���[�X�ƃX�^���g�����������ȁB
�v���[���[(�^�[���e�[�u��)�́A�ŏ��̓N���X�^���J�[�g���b�W�̂���LP�Ղ��͂ݏo��25cm�v���[���[�A���ɃZ���~�b�N�J�[�g���b�W��CR-11�i�N���X�^���J�[�g���b�W��Z���~�b�N�J�[�g���b�W�͕��ג�R���P�l���ʍ������Ȃ��ƁA���ʂ̂l�l�Ɠ����悤�ɂq�h�`�`�Ȑ��ŃC�R���C�W���O����Ă��܂��čQ�Ă����Ƃ�����܂����B�j�A���Ɉ�����30cm�����h���C�u���i�����v���i���O���č�����u����A�����̌����h���C�u(�����ăP�[�X�͍��l��)�v�Ŋy���݂܂����B����ɕt�����g�[���A�[���̓I�[�f�B�I�e�N�j�J��AT-1005�U�ł����B
���w�A���Z����̃I�[�f�B�I�͔Y�݂̂Ȃ��A�y���������̎�ł����B�������ɉɂ������̂ł��傤�B���w1�N���獂�Z3�N�܂ł̂�����6�N�ԂɗႦ�X�s�[�J�[�́A����(�܂�1�{���S�~)×4�{�A�R�[����×10�{�A�t�H�X�^�[(������FOSTEX����Ȃ�����)×10�{�A�O�H×2�{�A�p�C�I�j�A×2�{�A�v28�{�g���܂����B�O�H�̓_�C���g�[���̒N�ł��m���Ă�P-610�ł����B�܂��A�X�s�[�J�[�}�g���b�N�X��4ch���ǂ����y����ł��܂����B
�I�[�f�B�I�t�F�A�Ŏ���A���v�̎��g�������𑪂��Ă����Ƃ����b�ɂ��āA�w�Z���Y���x�݂��āA����^��ǃ��C���A���v(6BM8PP)�����Q�������Ƃ�����܂����B���R�ł����]�_�Ə����̑O�Łu�g�����W�X�^�A���v�Ɛ^��ǃA���v�͂ǂ��Ⴄ���v�̑�ނɂ���āA���\�l���̊F����̑O�Ŗ炵�����Ƃ����������ǁA�h�L�h�L���Ȃ������I�Ȏ���͉���������������Ȃ��āA�p�����������Ǖ��������悤�Ȋ炵�悤�Ƃ�����A�����{���{���ł����B�]�_�Ɛ搶�́u�ق�^��ǂ͒�悪�L���ł���ˁA����̓_���s���O�t�@�N�^�[���Ⴂ����Ȃ�ł���v�ȂǂƋ�A����ȗ��_���s���O�t�@�N�^�[�ƕ����ƕ��G�ȐS���ɂȂ�܂��B
���̌�20���߂��āA�H�t���̃_�C�i�~�b�N�I�[�f�B�I�Ƃ������X�ɕ���ł�JBL D-130(�F�����m��38cm�t�������W)�̒��x�̗ǂ�����×�Q��4���~���炢�ŏՓ��������Ă���A���K�I�ɂ����_�I�ɂ��I�[�f�B�I�̖{�i�I�ȋꂵ�݁��y���݂��n�܂����̂ł����B�����������̂��Ƃ����ŋ��k�ł��B
�����ԍ��F8491738
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
���̃I�[�f�B�I�̌��_��[SONY�V��]�ł����B���E�ŏ��߂ăg�����W�X�^���g���A�P�O�d�r4�{�Ŗ点��g�у��W�I�Ƃ��āA��̓��@���@�ɁA�e�����w�����܂����B���̌�A�����Ɛ肵�A���̂��̂ɂȂ�܂����B
���N��Ɍ̏Ⴕ�āA�ܔ��c��SONY�Ɏ������ݏC�������܂������A�Ή����������ǂ��g�����W�X�^���S�Č������Ă������ł����B���ł��d�r������Ɖ��͏o�܂��B
TC-350�A�F����A�����m�ł��傤���H����͍Đ���p�̃e�[�v�R�_�[�ł��B������w�������̂͏��a38�N����ł������A�\�t�g�̓��R�[�h��Ђ�SONY��TDK���������Ă��܂����B�_�r���O�Z�p���]�蔭�B���Ă��Ȃ������������̓C�}�C�`�ł����B�����ς�ALP��FM��������^�������e�[�v���Đ����Ă��܂����B
kojirou_sasaki����
kojirou_sasaki����͐F�X�ȃJ�[�g���b�W���������Ȃ̂ł��ˁB���̓I���g�t�H����[�k�t��]�J�[�g���b�W���~���������̂ł����A�����A�V���~�ȏ�����Ă��܂����̂ŁA�z�́m�G���p�C��]�ƌ����J�[�g���b�W�ɂ��܂����B�����j��7�`8�N�O�ɏH�t���Ŕ����Ă��܂����B
�v���[���[��SONY��PS6750�ł��B���̓{�����[�����グ�ĉ��t����ق��ł�����A���R�[�h�̃X�N���b�`���ɂ͉䖝�ł����A���ł̓v���Ɍq���ł��܂���B���Ґ��̎����y�Ȃǂ�CD�ɂȂ��āA�z�b�Ƃ����قǂł��B
�����ԍ��F8494014
![]() 0�_
0�_
�@����ɂ��́@�|�� ALL�B�����l�^���v�����Ȃ��܂܃X���b�h���i��ł䂭�̂��{�[�b�ƒ��߂Ă��邾���̃w�^���ȃX����ł��i���j�B
�@�t�B�����ɂ��Ăł����A���̓f�W�J���S���Ő̂Ȃ���̃t�B�������J�����͏����h�ɂȂ��Ă܂���܂����B����ł��A�f��̐��E�ł̓f�W�J�������t�B�����B��̕������|�I�ɉ掿���ǂ��ł��B�t�b�ƍ��v���o���܂������A�ƒ�p�J�����p�̃t�B�����ɐ́u������J���[�v�Ƃ����̂�����܂����ȁB��Ɂu�R�j�J�J���[�v�ɂȂ�܂������A�u������J���[�v�̍��͕x�m�t�C�����Ɠ������Y�Ȃ���A�x�m�Ƃ͑S���F��������Ă��܂����B���̖��̒ʂ�u������F�v�̂悤�ȐԂ��ۂ���ŁA�ꕔ�ɍ������t�@�����������̂ł��B
�@���͂ƌ����A������Ɖ��o����ۂ̓f�W�J���ƃt�B�����J�����̗����������Ă������Ƃɂ��Ă��܂��i�܂��A���������ł��� ^^;�j�B
�|�� kojirou_sasaki����
�@��悪�s��p�Ŏq���̍�����G���K�������m�ɂȂ�Ȃ����������炷��A�C���X�g��������l�͑��h���Ă��܂��܂��BBRAUN�͍��ł͓d�C�V�F�[�o�[�Œm���Ă��郁�[�J�[�ł����A�̂̓X�s�[�J�[���o���Ă��܂�����ˁB���͂Ƃ��Ƃ��������Ƃ��o�����ɏI���܂����B�����̓h�C�c���X�s�[�J�[��BRAUN���炢�����m���Ă��܂���ł������A���ł�ELAC��ALR/JORDAN�Ȃǂ̓ƃu�����h�������������{�ɓ����Ă��Ă���A�u���̊�������܂��B
�@�T�e���̃J�[�g���b�W�A���������o�͌^MC�ł����ˁB���������A70�N�㖖�̃x�X�g�d��̃��W�ICM�ɂ��������̂�����܂����E�E�E�E�i���[�J���ȃl�^�ł����܂���j
�u�}�b�L���g�b�V���̃A���v�E�E�E�E�J�[�g���b�W�̓V���A�A�I���g�t�H���A�T�e���𑵂��E�E�E�E�X�s�[�J�[�͂������W���������I�v�i���F�W�������Ƃ�JBL�̂��Ƃł��j
�@������v������邵������܂��A�����͉��y�t�@���ɂƂ��ē���̃u�����h���������Ƃ͊m���ł��B
�|�� �h���L�[�R���OJr.����
�@�����z�����Ƃ����ԑg�͒m��܂��A�L���l���I�[�f�B�I�V�X�e�������f�B�A�ŏЉ�邱�Ƃ͑傢�Ɍ��\���Ǝv���܂��B�u���X�v�Ȃǂ̃h���}�ɂ��I�[�f�B�I�V�X�e�����ǂ�ǂ���Ƃ��ēo�ꂳ���āA��l���ɃE���`�N�̂ЂƂł�����Ăق����ł��B���������e�����Ɂu���@�I�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�Ƃ��������ԑg������܂����A���B���e�[�W�̃I�[�f�B�I�@��̓��W���炢����ė~�����ł��ˁB
�@�^�����Ƃ����A���[���Ɛ́A�����V���l���������ɐ��l���̃Q�X�g�Ƃ��ďo�����Ƃ�����܂��B����[�A�e���r�ł͐���Ȃ��ߌ��ȃl�^�̘A���ŁA�悭���܂��s���ǂ����������̂��ƁA���ɂȂ��Ă͎v���܂����E�E�E�E�i���j�B
�����ԍ��F8498346
![]() 0�_
0�_
�|�� satoakichan����
��AV�Ɋւ��Ă��[�����w���������ł��ˁI
�@���������A�A�_���g�W�ɂ��Ă͂�����ƃE���T�C�E�E�E�E���āA�Ⴂ�܂��i���j�B�I�[�f�B�I�ɂ��Ă͈̂����Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ��鎄�ł����A���B�W���A���@��ɂ��Ă͂܂������̃h�f�l�ł��B�u�u���[���C���ĒN�̂��Ƃł����H�v�ƌ����������c�܂���قǂł͂Ȃ��ɂ���i�j�A���ꂩ������Ȃ����Ȃ�Ȃ����Ƃ͎R�قǗL�肻���ł��B�������A�f��͑�D���Ȃ̂ŁA�����z�[���V�A�^�[�����Ă��܂�����A�}�j�A�b�N�ȃ\�t�g�̃R���N�V�����ɑ��肻���ŁA���X�|���ł�(^^;)�B
�@���āA�V���ŕ�������Ă���l�I���W����̕��͂�q�ǂ��Ďv���o�����̂��A�I�[�f�B�I�@��̏d�ʂɂ��Ăł��B����A��{30kg�ȏ゠����Ƃ̃X�s�[�J�[���A�����s�݂̎��ɗ��e�����œ������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����������A��J���Ĉړ����������̂̌��̂Ƃ���ɒu���̂͒f�O������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A���ǎ����s���܂Ő��T�ԃw���ȂƂ���ɕ��u���ꂽ�܂܂������Ƃ������Ԃ��u�����܂����B
�@�����ȃI�[�f�B�I�@��͏d�ʂ������Ȃ��̂ł��B�̂́u�A���v���X�s�[�J�[���d����Ώd���قǂ����v�Ƃ����������I�[�f�B�I�G���ȂǂŔ��ʂ�A598�I�[�f�B�I����ɂ́u�d�ʋ����v�݂����Ȃ��Ƃ����s���Ă������̂ł����A���₱��̓i���Z���X���Ǝv���܂��B���[�J�[���I�[�f�B�I�̕�����_���Ă���̂Ȃ�A�d���Ĉ����ɂ������͈̂�ʃs�[�v���͌h�����邱�Ƃ�m���������ǂ��ł��B��������Ɠd�i�ł��①�ɂ����@�������d���ł��B�ł��A�����͈�x�ݒu����ƈ����z�����������Ă������������̂ł͂���܂���B���ăZ�b�e�B���O�����d�v�ۑ�Ƃ�������I�[�f�B�I�ł́A�X�s�[�J�[�Ȃ͓������̂�������O���Ƃ������܂��B�������A���\�L��������@��͍��N��w�͂������A���ꂩ��^�[�Q�b�g�ɂ��ׂ��������[�U�[�ɂ͈����ɂ������̂ł��B
�@���R�A�d�ʂ𑝂����Ƃɂ�郁���b�g������ł��傤�B���������R���Z�v�g�̐��i�͖����Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�ł��A����Ȃ炻��ʼn������d�����ė~�����ł��B�d���X�s�[�J�[�ɂ͎���肮�炢�t���Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����������70�N��㔼����80�N�O��ɂ����āA���̋Ɩ��p���b�N�ɑ��������邽�߂̃n���h�����t�����A���v�ނ���������Ă��܂����B���Ă��ꂪ�ǂ��Ȃ��������Ԃ��Ȃ��s�ꂩ������܂������A���������^�C�v�̐��i����������ėǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����������܂��B
�����ԍ��F8510587
![]() 0�_
0�_
���E�������
>�d���X�s�[�J�[�ɂ͎���肮�炢�t���Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�E���g���E�X�[�p�[�ő�^���ł��B���̋@��͑����d���Ă���|����(����)������܂���
�玝���グ�ړ��͉\�Ȃ̂ł��A�X�s�[�J�[�̓m�b�y���{�[�ő傫���d���Ă����������
���Ă��Ċ���̂ł���ˁI�I�B�^�[�~�i�����㕔�ɂ�������Ɏ���|���āA�Ȃ�Ď�����
���\�Ȃ̂ł�������������ɂ���Ǝ�|����ɂ͂Ȃ�܂���B��قǁA�c�B�[�^�[�Ɏ���
������Ŏ����グ�Ă��܂����Ƃӂƍl�����肵�܂��B
����ƍ��������̃s���E�E�E����JBL�X�s�[�J�[�ɂ͒�ʂɃX�p�C�N�s������������Ă����
�ł����A�X�s�[�J�[�������グ�Ȃ��ƃs���̃l�W����炸�����o���Ȃ��̂ł��B���߂Ă���
�s����2�ʕ�������X�p�i������Ηǂ��̂ł����˂��B�E�E�E�E�p�C�I�j�A�̃X�s�[�J�[�ł�
��S-1EX�͍����������O�ɒ���o���A�ݒu��ɒ����o���܂��ˁA���ꂾ���ł��~�����Ǝv��
����X�s�[�J�[�ł��B(�d����60Kg���ł����E�E�E)
�T�u�E�[�t�@�[�ɂ̓I���L���[�̃Z�v�^�[SW-1���g���Ă��܂����A�d������45Kg������̂�
������o���Ă����ɃL���X�^�[�����Ă��܂��܂����B�T�u�E�[�t�@�[�̈ʒu�͐F�X������
�v�f������ׁA�L���X�^�[��t���܂����B�������ቹ������������ȂɋC�ɂȂ炸�֗��ł��B
�����ԍ��F8511158
![]() 0�_
0�_
�d��SP�͊m���Ɉ����ɍ���܂��ˁB
�@
�@SP707�����肩��ł��傤���H�����ς�F�l�̓S�H���ŃA���O���ƃL���X�^�[�Ő�p��
�@��Ԃ�����Ďg�p���Ă���܂��B
�@�L���X�^�[�͑O�Q����Q�̂ǂ��炩�ł��Ȃ�y�ɓ������܂��B
�@�o���ł͂S�t����Ɖ����ݒu���s����ɂȂ�܂��B
�@��b�̃t���[������s�̂̑�Ԃ̎����̂悤�ȕ���t���Ă���܂��̂Ŏ���
�@�y�ł��B
�@�p�����O��4344�ɂ��Ă���100kg�ł������l�ł̈ړ��A�������ȂǕs�\�ɋ߂��ł��B
�@���͂���قǁu�����h�v�ł͂Ȃ��̂ŏ��ɒ��u���A�X�p�C�N���܂��A��ԏ悹�̐ݒu�@
�@��I��A���킸��ԗ��p�ł�����B���ꂱ���u���j�^�[SP�v�̎g�����ł��B
�@JBL�̈�A�̃V���[�Y���u�Ƌ�v�Ƃ��Ă��́u����v�Ƃ��Ă̎d�グ�ł����A��a����
�@�]�肠��܂���B
�@
�@�ŋ߂́u�Ƌ�v�d�グ�̍���SP�͂���������ɂ͂����Ȃ����������ł��ˁB
�@�@���ɂ������ɂ������ȃt�H�����̕���A�f��ŐG��Ɠ{��ꂻ���ȕ��Ȃ�
�@���ɂ͒l�i�����i���̂����t���������邱�Ƃ̖������i���Ɗ����܂��B
�����ԍ��F8512979
![]() 0�_
0�_
�@130theater����A�l�I���W����A���X�L���������܂��B
�@���������A�Ɩ��p�̃X�s�[�J�[�ɂ͎���肪�t���Ă�����̂������悤�ł��B�������d�����Ă���̂œ��R�ł����ǁA�����p���Ɩ��p�̗ǂ��Ƃ�������K���ď��i�W�J�����Ă��炢�������̂ł��ˁB
�@���āA����92�N�ɂ��܂��ܓ����ɒ����؍݂��Ă����܁A�r�܂̃T���V���C���r���ōs���Ă������{�I�[�f�B�I�t�F�A�ɑ����^���Ƃ�����܂��B�܂��������͓̂��ꗿ������Ă������Ƃł��ˁB�܂��A���ŋL�O�i��牽�������������Ⴆ��̂Ń��g�͎��̂ł����A�����ł������̂ł͂Ȃ����Ǝv�������̂ł��B�܂��A���ꗿ������Ă��q�͏W�߂���Ƃ������Ƃ́A�����͂܂��I�[�f�B�I�͈�ʂɔF�m���ꂽ�l�C�̂����������Ƃ������Ƃł��傤�B
�@���̃t�F�A�̖ڋʂ̓J�Z�b�g�e�[�v�ɑ���2�̎����チ�f�B�A�̏Љ�ł����B�ЂƂ�MD�A�܂�~�j�f�B�X�N�ł��B����͍��ł����[�U�[������悤�ł����APC�̃o�b�N�A�b�v�p�Ƃ��Ă��g���Ă����̂Œm���Ă���l�͑����ł��傤�B�ŁA�����ЂƂ�dcc�Ƃ������̂ł����B
�@dcc�Ƃ̓f�W�^���R���p�N�g�J�Z�b�g�̗��ŁA�t�B���b�v�X�Ə����d�킪�����ŊJ�������K�i�ł��B�����ʂ�A�f�W�^���Ř^���ł���J�Z�b�g�e�[�v�ł����B�f�W�^�ł���e�[�v���f�B�A�Ƃ��Ă�DAT���L���ł������Adcc�̈�Ԃ̃E���́udcc�f�b�L�ł͏]���̃J�Z�b�g�e�[�v���g����v�Ƃ������̂ł����B����ɂ���ăJ�Z�b�g�e�[�v�̃��[�U�[��dcc�Ɏ�荞�����Ƃ�����킾�����悤�ł��B
�@�������A��ڌ���Ȃ肱��̓_���ȋK�i���Ǝv���܂����ˁB�f�W�^�\�Ƃ����Ă��A���傹��e�[�v�ł��B�A�N�Z�X�̊ȕ��ł�MD�̓G�ł͂���܂���B�����SONY���̏o����L�J�Z�b�g���v���o���悤�Ȉ��ՂȃR���Z�v�g�ł��B�ʔ����̂�dcc���J�������̂��u�����g��Ɓv�ł����������ŁAMD��SONY�̎�ɂ����̂��������Ƃł��B���̍��܂ł�SONY���撣���Ă��܂����B
�@dcc�͂������鐷��オ����Ȃ��A2000�N�ɂ͏I���B�e�[�v���������h�C�c��BASF�݂̂Ƃ����₵���ł����B��͂�V�������f�B�A�����y���邩�ǂ����́A�����������[�U�[�C���^�[�t�F�[�X�̃A�h�o���X���������̂ł��傤�BSACD������オ��Ȃ��̂����̂������Ǝv���܂��B
�@�Ō�ɘb�͕ς��܂����A�x�m�ʃe����HP�Ńf�U�C�i�[�̃R�V�m�q���R��ECLIPSE TD���g���Ă��邱�Ƃ��ڂ��Ă��܂����B�L���l�ɂ͂ǂ�ǂ�I�[�f�B�I�@����g���Ă�����āA�������ʃs�[�v���ɏЉ�Ăق������̂ł��B
�����ԍ��F8533369
![]() 0�_
0�_
�F����A������
���E�������
���L���l�ɂ͂ǂ�ǂ�I�[�f�B�I�@����g���Ă�����āA�������ʃs�[�v���ɏЉ�Ăق������̂ł��B
�������T���I�[�f�B�I�}�j�A�œd���a�炵���ł���H�t���ɂĈ�l�ŃR�[�h�F����邻���ł��B
�莝���̃u�b�N�V�F���t�Ŏ��������Ŏ���h���C�u�����܂����B���������łǂ�������`�`�I
�h���C�u�R�[�X�͒����`�Ń��C���̂`�u�V�X�e���A�Q�����V�X�e���̃��b�N�Ƃo�b�����������ݒu�ňړ��s�̏�Ԃł��̂�
�c�̑����ɃX�s�[�J�[�X�^���h��ݒu���ăX�s�[�J�[�����ւ��h���C�u�J�n�ł��B
���A�����̓t���[�����O�ł����z�[���Z���^�[�ŏ����3/4�͏��̂�������d�l�ł��B
�A���v�͋g�c������̂b�c��̌^�R���|�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�EONKYO�X�e�����X�r�{�R���f���T�[�t[CR-D2XR]
�X�s�[�J�[�͕����ł́E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�EPIONEER�t�������W�X�s�[�J�[[S-101SE]
�X�s�[�J�[�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�EPIONEER�s���A�����g�X�s�[�J�[[S-A4SPT-VP]
�X�s�[�J�[�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�EMONITOR AUDIO[SILVER RS1]
�X�s�[�J�[�X�^���h�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�EDYNAUDIO�����X�^���h[�^�C�v4]
�V�ƃX�s�[�J�[�̊ԂɃI�[�f�B�I�X�p�C�_�[�V�[�g�E�EPACIFIC AUDIO[ASP-001]
�d���͐^��ǃA�C�\���[�V�����g�����X�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�m�O�` [PMC-1000EZ]
�\�t�g�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�N���b�V�b�N�E�W���Y�E�|�b�v�X�E�̗w�ȁE�{�T�m�o�E���b�N
�ȏ�̊��Ŏ������J�n�����̂ł������肪�����A�X�g�b�v���Ă��܂��܂����B
�s���A�����g�X�s�[�J�[[S-A4SPT-VP]�ł����X�̂��q����Ǝ��̎莝���̎ԗp�i�ƕ��X�����������̂ł����A���q�����
�Z���^�[�X�s�[�J�[�Ƃ��Ă̗p�r��1�{�ł����B�����`�u�V�X�e���ŃZ���^�[�g�p�ł����̂ŁA���i�R���ň��l�̂��X��
�₢���킹�����1�{�ł������ł��鎖���m�F��1�{�lj��A�Е��̓G�[�W���O���i�ݕЕ��͐V�i�œ����X�s�[�J�[��
�v���Ȃ��قlj����Ⴂ�A�����ăR�[���̓������S���Ⴄ�E�E�E������R�A�I�I
�ꎞ���f��2���ԃG�[�W���O�b�c��1�{���������I�Ɋ��炵�^�]���J�n�A���E�����Ƃ͌����܂��A�ǂ��ɂ��������Ԃ�
�Ȃ����̂ōĊJ���܂����B
�I�[�f�B�I�I�\���͂����ς�_���ʼn������̂悤�Ɏԉ��I�\���ƒ����I�\���ɂȂ�܂����������̒���낵���ł��B
[CR-D2XR]
40�v�ł������s�Ԏ��1.500cc�N���X�O��̊����Œʏ푖�s�A�������s���\�ŕs�����͂��܂芴���܂���B
�X�s�[�h�����L��^�[�{�A�X�[�p�[�`���[�W���̃h�[���Ɨ���X�s�[�h���ł͂Ȃ��c�C���J��24�I�ȃX���[�Y�ȃX�s�[�h����
�������\�t�g�ȏ��S�n�ł͂Ȃ��H�ʂ���������E���H�ʏ�Ԃ�������S�n�Ɋ����܂����B
�@�@�@�I�[���V�[�Y�����s�\�ȍ��Y���^�X�|�[�c�Ԃ̕��͋C
[S-101SE]
���s�Ԏ�̎Ԃł͂Ȃ��V�[�g�ʒu����r�I�ɍ����ԗ��d�ʂ��y���A�y���ȎԂŌ��I�ŏ���ꂵ�܂��g���N��
��������I�ȎԂł͂Ȃ��ł��B
�������\�N�O�ɏ���Ă����Ԃ��v���o���A����`�E�E�E���������I�W���Y�E�|�b�v�X�E�̗w�ȁE�{�T�m�o���A�y���ł����B
�@�@�@���ш�(�̖̂��O�ŏo�Ă��܂�)
[S-A4SPT-VP]
���ɏ��^�Ȃ̂ɏ��S�n�͂��������̏d�ʊ�������̂͂Ȃ��ł��傤���ˁE�E�E
�����A�n���h���̃L�����A���ɉ��K�ȏ��S�n�Ńu���[�L���\(���̐ؖ�)�Ńz�C�������b�N���Ď~�܂�̂ł͂Ȃ�
�`�a�r�t���ŋ}���Ɏ~�܂炸���ɃX���[�Y�ɒ�~���銴���ŁA�e�\�t�g�����j�I�m�g�j�����y�c�� [�ĕP]�S26�ȑS��
�����Ă��܂��A���^�ł�����Ԃ���Ǝ�������ς�����藎�����܂��B����`�E�E�E�������̂ɂ悤�撣��́I
�@�@�@�����\�ȏ��^�̃~�j�o���ł��l�ł��i
[SILVER RS1]
�I�[�v���J�[�܂ł̊J�����������ł����A�X�b�L���E�N�b�L���ŎԂ̃T�����[�t�S�J�Ŕ��ɑu�₩�Ő��m�Ȉ��
�{�f�B�[�����������傫���Ȃ�ቹ�����̕��܂ŗǂ��o�܂��B
���ɐ��݂������������O�ɏo�āADYNAUDIO�̍L����̂��鎋�E���ǂ��I�[�v���J�[�Ɖ����Ⴄ�̂��I
�����悤�Ɋ����܂����h���C�u����G�߂��S���Ⴄ�悤�Ɏv���܂��B
DYNAUDIO�͒g�����t�A���͏��Ẵh���C�u�AMONITOR AUDIO�͐��݂����������H��̃h���C�u�I
���邢�{�T�m�o�܂ł��@�ׂȏH�̊����������̂ɂ͂���Ӗ�����(��)�g�ݍ��킷�A���v�ňႤ�Ǝv���܂������Ɍ����J�ł��B
�@�@�@�T�����[�t�S�J�ŏH�̃h���C�u
�X�s�[�J�[�R�[�h�͍���̓x���f���ł������A���x�̓R�[�h��ς��ĕʂ̃h���C�u�R�[�X�𑖂낤���Ǝv�Ē��ł��B
5���~�O���ONKYO��̌^�R���|�Œ��Â�MONITOR AUDIO�ō��E���̈ႤPIONEER�s���A�����g��PIONEER
�̖̂��O�ŏo�Ă��܂��t�������W���A����Ȃɂ͍����Ȃ��@��ŋG�ߊ�����������������y�������Ԃł����B
�����ԍ��F8547784
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�v���Ԃ�ɂ��ז��v�������܂��B
kojirou_sasaki����@
�����Ȃ�Ă��̂ł͂���܂���ˁB
��厏�̑}�G���A���[�J�[�̃p���t�̃C���[�W�E�C���X�g�̗l�ł��B
�̂̃X�C���O�W���[�i���Ȃǂ͂������e���ɃA�[�e�B�X�g��I�[�f�B�I�@�퓙��
�X�}�[�g�ȑ}�G���g���Ă����̂��v���o���܂����B
�ĊO�A������̐��E�ɐi�܂ꂽ���Ȃ̂����Ǝv���Ă��܂��܂����B
�Ⴂ������ԉ�����
�����O�h���C�u�A�����l�ł������܂��B<(_ _)>
���Ȃ݂ɂǂ̕ӂ�܂ő����܂����H
�������Ⴂ������ԉ�����A������O��ɗ�炸���ꂼ�ꂪ�C���[�W�̂��₷�����ƁA���₷�����ƁB
�����̂Ȃ���ĕ]�_�ƒ����r���[�ł͏����͂��납���b�ɂ���Ȃ�Ȃ��ł��B
�ǂ����Ō|����g�ɂ��Ȃ��Ɓi���j�E�E�E
[S-101SE]�̃��N�G�X�g�ɂ������������������ł��B
�����I�̖̂��O�ŏo�Ă��Ă��Ԃ��g���N�^�[�ł͂Ȃ���ł��ˁH�H�H
�ƌ������́A�����ꂪ�ǂ��čׂ������Ƃ͂����Ⴎ���ጾ��Ȃ��C���̗ǂ��j�O���Ă��Ƃł��ˁi�j
���ĉ��̂�������E�E�E
���E�������
�Ƃ���X���ł́A��ρA�����v���܂����B
�������l�тɎf���܂����B
�����������ď펯�l�Ԃ��Ă��܂��܂��������E�������̂��b�̒ʂ�̓^���ł����ˁB
�X���傳���[�U���C�̓łŐ\����Ȃ��A�Ō�͓����������̔O�ɂ����܂����B
�[�����Ȃ��Ă���܂��B
�����ԍ��F8566701
![]() 0�_
0�_
�|�� �Ⴂ������ԉ�����
�@���������ʔ������r���[�A�L���������܂��B�uMONITOR AUDIO�͐��݂����������H��̃h���C�u�I�v�Ȃ�Đ▭�ł��B�I�[�f�B�I�G���̕]�_�������������u�V�ѐS�v���~�����ł��ˁB���ۓI�ȓ��e�̒L������ł͖O���Ă��܂��܂��B���Đ���A�g�c���ɂ�CR-D2XR���������Ă܂���܂����B���̓m�[�}����CR-D2�͒��������Ƃ��Ȃ��̂ł����ACR-D2XR���̂͂��Ȃ�̃X�O�����m���Ǝv���܂����B���߂̃X�s�[�J�[�ł��炵�Ă��܂��邵�A���ʂ̉��y�t�@���Ȃ����ŏ\���ł��傤�B
�@�\�ɂ��ƁA�g�c�����Đ̂̓n�C�G���h�w�������������ł��i���͏ڂ����͒m��܂��� ^^;�j�B���ꂪ���̓X���ɂȂ��Ă��珎������̏����Ɏ������ڂ��������ŁA���ʓI�ɂ��ꂪ����t���Ă���悤�ł��ˁB�����iQ30���W������Ă����̂ɂ͏����r�b�N���B�X�^�b�t�H���u�]���ɂȂ��Ă���V���[�Y������A��@�킮�炢����Ƃ��Ȃ��Ƃˁv�Ƃ̂��Ƃł������ACR-D2XR�Ƃ̃R���{���[�V���������������C�P�Ă܂����B�����AiQ30�͑O���iQ3�Ɣ�ׂ�ƑS��Ƀ^�C�g�œ��ɍ��悪�L�тĂ���̂ŁA�����ɃN�Z�̂���A���v��P�[�u���ƍ��킹��̂͐�֕����Ǝv�������̂ł��B
�|�� redfodera����
�@����A���͑S�R�C�ɂ��Ă܂���A���Ȃ����C�ɂ����K�v�͂Ȃ��ł�(^^)�B�^�X���̓{�[�h�Ǘ��҂ɂ���āu�ҏW�v����Ă��܂��܂������A�������������W�J�ɂȂ�ƃg�s�傳����˘f��ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂��Ƃ��v���Ǝ�����������ł��܂��܂��B
�@�ŁA���̃X���Ŗ\��Ă���jazzland_old�Ƃ�������m�̏������݂�ǂ�Ŏv���o�������Ƃ�����܂��B���̓I�[�f�B�I���͖��ʂɒ����̂ł����A���x���n�C�G���h���[�U�[�i�Ǝ��̂�����X�j�̂���ɍs�������Ƃ�����܂��B�ǂ�����ʃs�[�v���ɂ͉��̂Ȃ������ȋ@�ނ��u���Ă���܂������A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�ʂőÓ��Ȃ̂��͕�����Ȃ��܂ł��A�u�Ⴄ���E�v�̉����o�Ă��Ċ������Ă��܂��܂����B
�@�ł��A���ɂ�2�l�����A�q�h�������o���V�X�e���̃��[�U�[�����܂����B�{�l�B�͍ō����Ǝv���Ă���̂ł��傤���A����ш�ɂ������ȋ�����������A�ƂĂ��������Ԓ����Ă����܂���B�����āA����2�l�̏Z���ɂ͋��ʓ_������̂ł��ˁB�������A�Z�܂��̘Ȃ܂����u����āv����̂ł��B�����@�����ׂ����X�j���O���[�������͈ꉞ�̍ق𐮂��Ă���̂ł����A����ȊO�͎���ꂪ�s���͂��Ă��Ȃ��Ƃ������A1�l�͖��ȑ����z�����Ă����肵�āA�ƂĂ��Z�݂����Ƃ͎v���Ȃ��Ԏ��ł��i�������A���̏�́u�Ȃ��Ȃ��̉��ł��ˁv�ƎЌ����߂��q�ׂāA���X�ɗ�������܂����� ^^;�j�B
�@�I�[�f�B�I�����ɂ̂߂荞�݁A����ȊO�̑̍قɂ܂������C������Ȃ��}�j�A������A�N�����āu�����v�܂��B�����āA���͂Ƃ̌��ˍ����Őg�̏�ɍ������m�[�}���ȓW�J��S�|���Ȃ��ƁA�ǂ����������Ă��܂��ł��傤�B���̈Ӗ��ł����[�J�[��f�B�[���[�͍��܂ł̌ڋq���u���Z�b�g�v���邮�炢�̑�_�ȃ}�[�P�e�B���O���̗p���������ǂ��Ɗ����鎟��ł��B
�����ԍ��F8567891
![]() 0�_
0�_
���E�������
���S�����L���������܂��B
�ҏW�O�̏I�Ր�ł͂������Ƀ��[�U����̕�������������ɂ������Ă��܂��܂����B
�^������肩�͂ǂ��ł��悢�̂ł������̃n�C�G���h���A
�u���ꂩ��v���y���݂ɂ���Ă������̂킭�킭����悤�ȋC�������킢���ł��낤���Ƃ������܂���B
�N�ɂ��܂��ăX���傳���[�U����͕��������������낤�Ǝv���ƐȂ��Ȃ�܂����B
���̃X���b�h�ł��l�т����肨�b�����肷��@�����܂��悢�̂ł����A
���E�������̗l�ɂǂ����ł���ł���Ȃ�܂������A�������́c
�����ԍ��F8568898
![]() 0�_
0�_
�F������
���E�������
�g�c����iQ30���ꂽ�̂ł���iQ30�܂������������Ȃ��^�Ԃ�0���t���������ł������͐����Ⴄ�悤�Œ����Ă݂����ł��B
�g�c���̓X������͏����h�ł���
�В�����A�X������A��C����A�d�b�ł���3�l�̕��Ƙb���܂������A���ꂼ����I�ő�σo�����X���ǂ��̂ł͂Ǝv���܂��B
redfodera����
�Ԃ��g���N�^�[�ł����I���S�ɃI�b�T���̐��E�ł���(��)�v���g���N�^�[�͂Ȃ��Ԃ������̂ł����ˁE�E�E
redfodera����̌|���́A�a�m�I�ŕ��m�肻���Č��C�ȃg���N�^�[�I����L�����N�^�[���Ǝv���܂��B
���E�������Ɖ������Ńo�g���������̂ł����H
�����o�g�����܂��傤���I���E�������͊��G�����͖��̗ǔ��̕����D���ł����Ƃ̎��ł����A���͎o����̕���
�ǂ��Ǝv���̂ł��Ώ���܂���(���)
�����ԍ��F8575558
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�Ⴂ������ԉ�����@
�����E�������Ɖ������Ńo�g���������̂ł����H
KEF IQ-3�Ŏ��̃n�C�G���h�̂��Ղ�D����������1��قǁB
��قǂ���O������Ŋi�����Ȃ�ł��B
�����E�������͊��G�����͖��̗ǔ��̕����D���ł����Ƃ̎��ł����A
�����͎o����̕����ǂ��Ǝv���̂ł��Ώ���܂���(���)
���Ŋ��o�����ȁA���Q�l�Ƃ��I
�m����2�l�Ƃ��̂͏��ł����ǁE�E�E
��������f�R�A�Ζ�3�o���ł���I�I�I
�̂͂��Ă����A�����o���G�e�B���I
�^�q����A�悤������A�֎q����A����̎��ʔŁu�L���b�c�E�A�C�v�͎���͂���3�l�ł��肢���܂��B
���v���g���N�^�[�͂Ȃ��Ԃ������̂ł����ˁE�E�E
�m���ɖʗd�ȁE�E�E�N�{�^�ɓ��e���Ď��₵�Ă݂˂B
�����ԍ��F8575684
![]() 0�_
0�_
��������q�n�l���Ă܂������i�ŏ��̃g�s����j
�y�������Ȃ̂ŎQ���}�����Ă�������^^;
�b�c�o�@�@�@�F�@�s�d�`�b�@�@�b�c�o�S�O�O
�c�u�c�@�@�@�F�@���Ł@�@�@�@�r�c�|�T�O�O�O
�`�l�o�@�@�@�F�@�n�m�j�x�n�@�W�P�V�q�w�Q
�s�t�m�d�q�@:�@�@�s�n�q�h�n�@�j�s�|�W�O
�r�o�@�F�@INFINITY�@�@REFERENCE�@�P�O
�q�b�`�P�[�u���͂͂r�`�d�b�̂P�W�O�R
�r�o�P�[�u���͂r�`�d�b�̂r�o�j�W�O�O�Ċ���^^;
�ŋ߃A���v�̒��q�������Ȃ�
�I�N�Ł�̂P�r�b�g�A���v�̃~�j�R���|��ɓ��ꂻ��Ɍq���ł��Ԃł��i���j
�ӊO�Ɖ����ǂ��ăr�b�N���Ȃ�ł�����(��)
���n�R�I�[�f�B�I�Ȃ�ł�����( i�ti )
�b�ς��܂��āu�Ԃ��g���N�^�[�v
�C�Z�L�E�N�{�^�E�����}�[�e�АԂ������C�����܂�
�����}�[�́i�m���j���ш�����
�u�R����j�̐Ԃ��g���N�^�`��v�Ƃ��̂��Ă����ƁE�E�E
�������Ɂu�N�{�^�T�i�G�v����Ă���
�g���N�^�[�����k�ϋ@�������Ă��������t���ĉ��z�������肗
�S�~���X���݂܂���m(__)m
�����ԍ��F8579716
![]() 0�_
0�_
�@�Ⴂ������ԉ�����Aredfodera����A����ɂ��́B���̐́A����̓z��Ɂg���G���̐���TANNOY���Ƃ���ƁA���̗ǔ��̉̐���QUAD���낤�B�I����QUAD�̕����D�����h�Ȃǂƌ���������b�Ȏ�����Ԃ��ꂽ�g�s��ł��i���j�B
�@���ǔ��̃f�r���[��u�Ԃƍ��v�́A80�N��̗w�V�[�����\���閼�Ȃł���Ƃ̔F���͌��݂��h�邢�ł��܂���B3rd�V���O���́u���Ȃ��F�̃}�m���v�́A�h�����X�ƃx�[�X�݂̂��N���[�Y�A�b�v�������t�������Ƃ��Ă͎a�V���������Ƃ��o���Ă��܂��B���������A80�N��NHK�g���̍���ɏo�ꂵ���ۂɂ͎o�̍G�����o�Ă��āA�o�������\���o��Ƃ����̂́A�����Ɏ���܂ōg���j�ケ�̈�����ł��B
�@���āA���ݎo���Ŋ��Ă���|�\�l�̒��ň�ԋC�ɂȂ��Ă���̂��s����a�q�Ǝ����q�ł��ˁi�̎肶��Ȃ����� ^^;�j�B��ʂɂ�NHK��̓h���}�u�ĕP�v�ɂ��o�Ă�������q�̕����L���ŁA�ޏ��͉f��uBlue�v�Ń��X�N�����ۉf��Ղ̎剉���D�܂�����Ă���قlj��Z�͂ɂ͒�]������̂ł����A�����ۛ��ɂ��Ă���͎̂o�̎��a�q�̕��ł��B��x�������ΖY����Ȃ��@�̂ȗe�e�ƃA�N�̋������݊��͉f��t�@���Ƃ��Č������܂���B���Ɂu���a�̗w��S�W�v��u�R���Z���g�v�ł͂��̃G�L�Z���g���b�N�Ȍ����S�ʊJ�Ԃ��Ă���A�܂��ɋ��C�̐��E�Ɉ꒼���ł��i���j�B
����������f�R�A�Ζ�3�o���ł���
�@���̐́A�^�q�͖^�啨�̎�ƌ������Ă������Ƃ�����܂����ˁB�������̎��͂ɂ͔ޏ��̃t�@���������������āA�����ɃV���b�N�������������������悤�ŁE�E�E�E�i�j�B
�@arusqul ����A����ɂ��́B���g���̃X�s�[�J�[��INFINITY�ł����B���Ђ͕č��ł͑僁�W���[�ł����A���{�ł͉�X�I�[�f�B�I�t�@���ɂ������܂�m���Ă��Ȃ��̂��⊶�ł�(^^;)�B����ς�AJBL�݂����ɋƖ��p�͏o���Ă��炸�A�����p��{���Ȃ̂������Ȃ̂ł��傤���B
�@���̐́A�S���{�I�[�f�B�I�t�F�A��INFINITY�̃n�C�G���h�@���g���Ắu�ቹ�u���u�����v�i��j���J�Â���Ă����̂��o���Ă��܂��B�L���]�_�Ƃ���𑵂��Ă̊y�����i�H�j���ł������A���ቹ������ɘR��܂���ŁA���̃u�[�X�ł͂Ђキ�����̂ł͂ƐS�z���Ă��܂��܂����B����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�@�g���N�^�[�E�E�E�E���̐́i�܂����� ^^;�j�A�J�Łu�i���`���b�e��������v���b��ɂȂ������A�^���W�I�ԑg�Łu�R����Ƀ����}�[���������ڌ��v�Ƃ����l�^������Ă��܂����B���ł��A�Ԓ��œˑR�u����A����ς胄���}�[�������ȁI�v�Ƌ���ő���o�������ŁA���ɃC���p�N�g���������Ƃ��E�E�E�E�i�Ȃ����j�B
�@�E�E�E�E�b�ς���āA�ŋ߂܂�RCA�P�[�u�����Ă��܂��܂����BOYAIDE��ACROSS 750 RR�ł��B���i�̓G���g���[�N���X�Ȃ���A����͗ǂ��ł��B���ɉ��s�����̉��o�͗v�`�F�b�N�ł��B�Ɩ��p�̃t���b�g�H���Ƃ͈Ⴄ�e�C�X�g�ł����A�N�Z�̏��Ȃ��悤�ȍI���Ȗ��t��������Ă���A���̉��i�т̖����p�P�[�u���Ƃ��Ă�CHORD��CRIMSON�ƕ���Ńx�X�g�o�C�ł��傤�B
�����ԍ��F8591337
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
���E�������A�Ⴂ������ԉ�����
���o���ւ̑R�p�ɖڂۗ̕{����̐��ʐ^���t�o���܂��I
�c�F����A�I�[�f�B�I�̘b����E�����Ă��݂܂���(^^�U
����`�����ڂŏo�������C�x���g2���ł̎ʐ^�ł��B
4���̈ɐ��ł̃C�x���g�͎o���R�l�������\��ł������A
�c�O�Ȃ���悤�����h���}�̎B�e�ŃL�����Z��(^^�U
�����ꖇ�͂P�O�����{�̑��ł̃C�x���g����B
�܂�Œǂ������݂����ł����A
���Q�l�̏����������ɂ͓x�X���d���ł����b�ɂȂ��Ă���܂����A
�d���ɂ��������E�����p�ȃC�x���g�̃T�|�[�g�ł���(^^�U
���E�������
�P�[�u���ނł��ŋ߂̓f�W�^���E�P�[�u�����}�C�E�u�[���ł��B
�Z�p���[�g�̂b�c�o�����ƒ��Âc�`�b�����������肵���W�ŐF�X�ƏW�߂Ă��܂��܂����B
�^�l�b�g�E�I�[�N�V�����ł͐l�C�̂Ȃ��W�������Ȃ̂Ŕ��i���i���ň�������܂��B
����RCA�v���O�ōŋߖʔ������̂����i�I�[�N�V�����i�j���܂����B
Eichmann�i�A�C�N�}��or�A�C�q�}���j�̒ʏ̃o���b�g�ƌĂ����̂ŁA
���̂ǂ���V�F�����������ȏ�ɐړ_���s���|�C���g�ł��B
http://www.interu.co.jp/Eichmann/BulletPlug.html
���������ɂ��Ȃ����I�Ƃ����艿�ݒ�̏���R�l�N�^�̕�����肵���̂ŁA
�n�C�X�s�[�h�E�^�C�v��S/A LAB��MWT�̐ؔ��i��͂�I�[�N�V�����i�j�Ƒg�����܂����B
���D���z�Y��6,900�~�{�����Ǝ��O���H��ޗ�����l����ƂȂ��Ȃ����i�ʂȃP�[�u���ł��B
��X�m�̂��Ƃ����x���Ɠ����x�ɏ��X�т�����B
���݁A��������Classse'�̃v���A���v�{AudioAnalogue�̃��m�����E���C���̒��p�Ɏg�p�\��ł��B
����Ō��Ă�HARBETH��LS5/9a�����Ғʂ�苿���Ă����Ό�̎��Ȃ̂ł���(^_^)
arusqul ����A�͂��߂܂���
INFINITY�͂��g���̃X�s�[�J�[�̍��܂ł͂ƂĂ��ǎ��Ȑ��i�ł����ˁB
���{���p����Ă����INFINITY�̐��i�͎c�O�Ȃ��猩��肵�܂����A
�ߔN�͂ǂ����J�[�I�[�f�B�I����ɏd���������Ă���悤�Ŏc�O�ł��B
INFINITY�͂ǂ̐��i���s�A�m�̖肪�ƂĂ��f���炵�������ł��ˁB
�������N�x�ē~�{�[�i�X�{�������͂����đ�^�t���A�^�C�v�����߂ē��������̂�INFINITY�ł����B
REFERENCE 10�̏���@�͓����̃K�[���t�����h�ɖ�����w���������v���o������܂�(^^�U
�E���^���E�G�b�W���ɂ݂₷���̂��Y�݂̎�ł��������v���C�X����܂����H
�����܂��Ȃ�ӊO�ɊȒP�Ȃ̂ŕ�C�L�b�g�Ńg���C����邱�Ƃ������߂��܂��B
�����ԍ��F8594373
![]() 0�_
0�_
�����ɒE�����Ă���Ƃ���ŁA�ɂ߂��I
�̎�o���ƌ������̑o���́u�U�E�s�[�i�b�c�v�Ɓu�R�}�h���o���v�ł��傤�B
���̉��y���ƁA����͈̗͂��ɒ[���́A���[�ł͂���܂��ǂˁB
����ƔԊO�Łu���������E���������v�m���Ă���l�͖w�ǂ��Ȃ��u�o���r�[�Y�v���Ă̂́H
�D����JAZZ�E�ł́u�A���h�����[�V�X�^�[�Y�v�u�}�b�N�O�A�C�A�[�V�X�^�[�Y�v���X�B
����[�A���ז����܂ł����I
�����ԍ��F8595255
![]() 0�_
0�_
�����E�������
�����ł���infinity�������Ƃ�����������
�u�ԁH�����v�Ƃ������܂�������
�ꕔ�̃I�[�f�B�I�}�j�A�����m��Ȃ���ł��傤��^^;
�m�荇���̃}�j�A�ł����^�u�b�N�V�F���t�^�o���ă��m�m��Ȃ������o�܂��E�E
�͓��������́H�Ƃ������܂�������E�E�E
�q�b�`�P�[�u���Ƃ������̂�������ς��Ă݂����ł���
�旧���̂�(��)
��redfodera����
��(�P���P;)��������!���������������������[�U�[�ł���
�������ޏ��ɖ�������킹������(��)
�����i�X�T�N���j�X���Ŏ������đ����������r�o�ł�^^;
�s�A�m�L���C�ł��ˁ`�吼���q�E�R���m��E�e�r��́i�~�[�n�[�j�����Ă܂�
���R���̃T�C�Y�ł����牺�̕��܂ŏo�Ă܂���
�^�C�g�Ȓቹ�i���Ȃ�ł͂ł����ˁH�j
�����{�[�J�����G����Ċ����ŁE�E�E������ƃL���s�L���s���Ă܂�����(��)
������Ə̂��Ēm�l��̃A�L���t�F�[�Y�̃A���v�Ƃb�c�Ŗ炵�Ă݂���(��)
�S�F�R�F�R�̔䗦�ŃV�X�e���g�߂Ƃ��悭�����܂�������
�A���v��������Ɣ\�͏o���Ȃ����ȂƂ��v���܂���
�ʎ��Ȃ̂ŁE�E�E���̉��i�сE�T�C�Y�ő���ɂȂ�̂��������Ă܂���^^;
�����̂��������Ă��旧���̂��Ȃ��ł�����(��)
�Q�N�ʑO�ɃE���^���G�b�W�������ʂĂ܂���(��)
�f�m�����{�ɖ₢���킹����P�{�R���ʂ��ƌ����
�i�I�C�I�C�E�E�E�V�i�ς��邶��Ȃ��ł��������j
�X�L�����Ȃ��������̂ŁA�m�荇���ɒ���ւ������܂���(��)
�ȒP��������ł���^�O�G
infinity�Ђ��čŋߕ����Ȃ��ȂƎv���Ă���
�n�[�}����舵���ӂ肩��v�҂������������
���Ă̗ǂ��������ς�炵���ł��E�E�E�c�O
���l�I���W����
�R�}�h���o����������E���������ӂ�͂킩��܂����E�E�E
�o���r�[�Y���āE�E�E�H�H�ł�
��˂��Ȃ���Ȃ̂��������C�����܂��������ς�ł�(��)
�����ԍ��F8598224
![]() 0�_
0�_
�F����A�������������܂��B
�l�I���W����
������������!
�|�\�o���͈ĊO�Ƒ�������������l�ł������X�g�A�b�v���ꂽ���X�͑o�q�n�H
�R�}�h���o����TV�ł݂��L�����Ȃ��ł��ˁA���ɂ́B
�s�[�i�b�c�́u���̃t�[�K�v�����u���X���`��A���X���`��v�̃C���[�W�����|�I(^^�U
���������E���������A ��イ�����×�Q�R�[���X�A ��イ����s���čK���H�ׁ[������CM�͂荞�܂�Ă܂��B
�o���r�[�Y���ĒN?�ǂ��̕�???
�m�y���ł̓m�[�����Y���������o���������L�����c
arusqul ����
��������!���������������������[�U�[�ł���
�����������IRS��GAMMA���i���ŏ�������Ă��ďZ�����Ȃ݂��w�����܂����B
�W��P���[���ɂ��т������Ă���܂������A�قƂ�ǃI�u�W�F�ł�����B
�����ȉ��ʂŖ点���͍̂w����R�N�قnjo���Ĉ����z���Ă���ł���(^^�U
���������ޏ��ɖ�������킹������(��)
����u�]�ł���������Ƃɂ͂ɃO�����h�s�A�m�������������ňꏏ�Ƀo���h�����Ă܂����B
�m�y����D���Ȗ��ŃI�[�f�B�I�ɂ͊��S���Ȃ������킯�ł��Ȃ��A
KENWOOD�̂T�X�W�A���v��CDP��TEAC��W���o�[�X�f�b�L���g���Ă܂����ˁB
�R�N���炢�O���ȁc���R�A�V�h�Ō������܂������A
�R�l�̂��q����A��đ̌^���ӂ��悩�ȗ��h�ȁu������v�ɂȂ��Ă܂����i���j
�������Ă����炱��ȏ�Ԃ������̂��Ɓc
���܂�̕ς���Ɂu�����Ȃ��Đ����I�v�Ɠ��S�z�b�Ƃ��܂����B
�������g�̕ϖe�Ԃ��I�ɏグ������Șb�ł���(^^�U
�����ԍ��F8598606
![]() 0�_
0�_
�F������
arusqul����
�n�߂܂��Ă�낵�����肢�v���܂��B
���C�Z�L�E�N�{�^�E�����}�[�e�АԂ������C�����܂�
�ŋ߂ł̓��C�o����Ђ��Ԃ�������A�������͐��ƌ��������ł������̓����͉E�ɕ킦�������̂ł���
�V���[�v�̂P�r�b�g�R���|�ǂ����̂悤�Ŋy����ł��������B�����V���[�v�I(���C���ł̂ڂ��C���ł�)
�������ł���infinity�������Ƃ������������u�ԁH�����v�Ƃ������܂�������
�����A�ԉ����o�ŎԂ��Ǝv���ď��S�n�͂ǂ��ł����ƕ����Ă��������m��܂���B
���E�������
�����āA���ݎo���Ŋ��Ă���|�\�l�̒��ň�ԋC�ɂȂ��Ă���̂��s����a�q�Ǝ����q�ł��ˁi�̎肶��Ȃ����� ^^;�j�B
�h���C�u�R�[�X���Ⴄ�ƌ������E�E�E�����R�[�X�������܂��ˁI�a���ł��ˁ`���������͊��G����TANNOY�h�ł�(��)
OYAIDE��ACROSS 750 RR�̌��ł��������~�����Ȃ��Ă��܂����B
�l�I���W����
�U�E�s�[�i�b�c/�R�}�h���o��/���������E��������
���X��/�O����/�C���f�B�A�����b�N�Ɠ��̒��ɏ��Ԃɕ����̂ł����A�o���r�[�Y�Ŏ~�܂��Ă��܂��܂����B
���҂ł�����܂����ˁE�E�E�܂����o���r��2�C�ƌ����I�`�ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł����E�E�E
redfodera����
����������f�R�A�Ζ�3�o���ł���
�ւ��`������ˁ`�`�I(�܂����C���ł̂ڂ��C���ł�)�������Ζ�3�o�������G���ł��i��j
���l����̎ʐ^�A�b�v���肪�Ƃ��������܂��B�ڂۗ̕{�ɂȂ�܂����B
redfodera����͗ǂ��d���ł��ˁA�Y��Ȑl�Ǝd�����o���ėǂ����y���Ď��Ȃ͖����A�S�̉���ł��̂Łi��j
�����ԍ��F8602372
![]() 0�_
0�_
�������Ɂu�o���r�[�Y�v�͂��m��ɂȂ�Ȃ�������ł��ˁI
������Ƃ����v���̎�ł������q�b�g�͖����A���͂������̖��������s�����ł����B
������������u�����v�͉��l�ֈ����z���O�̎��Ƃ�������Ă�����Ƃ���ł����B
��x���s�������Ƃ�����܂���B�����Ȓ��ؗ����X�ł��B
��̂ɂ������A�ߏ��́u�i�V���v�ƌ����X�ɍD���ȃ��j���[������܂����B
�L�q�Ɉ߂�t���ėg�������ɁA�J���[���������Ă���̂ł����A���̎q���̍���
���Ȃ�́u���y���v�ł����B
����͂�A�\����Ȃ�����ł��B
�I�[�f�B�I�Ƃ͊W�Ȃ��b����ŁE�E�E�E�E�E�E�B
�����ԍ��F8603810
![]() 1�_
1�_
�|���l�I���W����
�@�o���r�[�Y�͎����m��܂���ł����B���₠�A�o�q�̐��E�͐[�����X�i�Ȃ���� ^^;�j�B�������������[�Y���Ă̂����܂����ȁB
�@�o�q�Ƃ����A70�N��㔼�Ɉꐢ���r�����A�����J�̃R�M�����o���h�A�����i�E�F�C�Y�iThe Runaways�j�̃��[�h���H�[�J���������V�F���[�E�J�[���[�ƁA���̑o�q�̖��}���[�E�J�[���[���v���o�����[�g���̃��b�N�t�@���̎��ł��B
�@���āAOYAIDE��ACROSS 750 RR�̎g�p���ł����A�����͉��s�������悭�o�邱�ƁB��ʂ��n�b�L���Ƃ��Ă���悤�Ȉ�ہE�E�E�E�Ƃ������A�Ɠ��́u���t���v�ɂ�薳����Ƀn�b�L���Ƃ������Ƃ��������ł��B�����ɂ��V�f�ނ��A�s�[������悤�ȓW�J�ŁA�I�[�f�B�I�t�@���D�݂̉��ł��B���ɍŐV�̗D�G�^���ɐ^�����B���ʁA�Â��W���Y�̘^���͐��������ĕ�����Ȃ���ʂ��B�Ƃ�����ACP�͍����ł��ˁB�g������̖ʂł͌ł��Ď��h���̂���_�ł����E�E�E�E(^^;)�B
�����ԍ��F8606769
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
���̃I�[�f�B�I�V�X�e����AV�ɏ������悤�Ƃ��Ă��܂��B�X�s�[�J�[�Ԃ�2.8m����܂����A���̊Ԃ������Ȃ��₵�����APDP�̉f�������\�A�Y��ɂȂ������Ƃ�������6�N�قǑO��50�C���`��PDP�����܂����B�����͗]����҂��Ă��Ȃ������̂ł����ATV��BD���R�̃A�i���O�������s���A�̃v���Ɍq�������ł��\�R�\�R�̉����Ŋy���߂܂����B
���̉����������Ɨǂ���������TV��R�̃f�W�^��������DAC��ʂ��ăs���A�̃v���Ɍq���ł݂܂����B����͉�����I�т܂����Ȃ�̍������ł��B���ʂ��グ��ƃs���A��CD�Đ��Ƒ��F����܂���B����ł��{�[�J����W���Y�̓V�����V�������������s�����c��܂��B
��N�قǑO�ɗF�l����AV�A���v�����������A���̃v�����p���[�A���v�Ɍq���}���`�`�����l�����f���t���ōĐ�����悤�ɂȂ�܂����B�d���P�[�u����^�b�v�A�{�[�h�I�т̋�J�͂���܂������A�s���A�Ƒ��F�Ȃ������o��悤�ɂȂ�܂����B�ŋ߂͂��ꂪ�嗬�ɂȂ����܂��B
�����ԍ��F8620065
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�䂪�Ƃ̓��}�n��AV�A���vDSP-Z11�ɔ����ւ��Ă���A���̃A���v�̐����H��11.2ch�ɂ���ׂ�
�T���E���h�p�X�s�[�J�[�̒lj������܂����B���ǃT���E���h�p�ł͂Ȃ��s���A�p���Ă�
�܂�(�r�N�^�[SX-M3�ł�)���܂ł̃s���A�p�Ŏg���Ă����p�C�I�j�AS-A4SPT-VP���e���r�ɁA
�e���r�Ɏg���Ă����r�N�^�[��SX-LC3���T���E���h�p�ɂ܂킵�܂����B(���̃X�s�[�J�[��
���X�f�m����AV�A���v���g���Ă������T���E���h�p�Ƃ��Ĕ��������̂ł��B�ǎ��t���̋�
��̎��t���Ղ��c���Ă��܂��B)
�����č���0.2ch�ɂ���ׂ�ECLIPSE��TD725sw���w�����鎖�ɂ��܂����B�����A���܂Ŏg����
����0.1ch�̓I���L���[��Scepter-SW1�Ȃ̂ł����A�R���Z�v�g�����Ȃ�قȂ�܂�����ʂ�
���Ăǂ�ȉ��ɂȂ�̂����X�s���ł��B(25cm���j�b�g×2���Ƃ����\���Ƒ��d�ʂ͎��Ă���
�̂ł����E�E�E�B)
�����ԍ��F8620271
![]() 0�_
0�_
�@�掿�ɂ�����肳��A130theater����A����ɂ��́B
�@AV�V�X�e���̏[���Ɋ撣���Ă�����悤�ł����AAV�ɑa���̂ŋC�̗��������X��Ԃ��Ȃ����������܂��i���j�B���͔N��100��ȏ�͉f��قɒʂ��Ă���܂����A����̎҂͂���Ȃɉf��D���̎����}�g����AV�V�X�e���ЂƂ����Ă��Ȃ����Ƃɑ��ċ����݂����ł��B���R�A�f��َ�̂̊ӏ܂ɂȂ�ƁA���A���^�C���Ŋώn�߂����������Â���i�ɂ��Ă͑a���Ȃ�܂��B������u���N�̖���v�ƌ�������̂ɂ��Ă͎����ł����R�Ƃ���قǖ��m�ł��i���o�C�o�����J���ꂽ���̂������j�B�܂��ŋ߂́u�ߋ��̌���������݂̑ʍ�I�v�Ƃ����X�^���X�ŊJ�������Ă͂���܂����E�E�E�E�i�j�B
�@���āA�̊y�������Ă����m�荇������u�I�[�f�B�I�ɋÂ���������ɐ������ڂ���������i�}�V�����v�ƌ���ꂽ���Ƃ�����܂��B���̌��t�̗��ɂ́u�ǂ��t�����������ăI�[�f�B�I����͐��̉��Ȃ�ďo�Ă��Ȃ���I�v�Ƃ����f�肪���������Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�@�u�I�[�f�B�I����͐����͏o�Ȃ��v�E�E�E�E����͐̂���I�[�f�B�I�t�@���ɑ���ɗ�Ȉꌾ�ł��葱���܂����B����͂��̒ʂ�Ȃ̂ł��B���������}�C�N�Ő������E�������_�ŁA����͎����̉��ł͂Ȃ��Ȃ�̂ł����瓖�R�ł��B���������Č��Ă����Ă��܂��I�[�f�B�I�t�@�����������������ƕ����Ă��܂��B
�@�������A�������������y�ł͂Ȃ����Ƃ��m���ł��B���͂�����̒m�荇���Ɂu������������悤�ɐS�|���Ă��A�����_�ŃJ��������x�[���̉��t�͒����Ȃ��B�r���E�G���@���X�̃R���T�[�g�ɂ��s���Ȃ��B�W���j�X�E�W���v�����̉̐��������Ȃ��B���̊����𖡂키���߂ɃI�[�f�B�I�͂���v�ƌ����Ԃ������̂ł��B�������A�̐l����ނ����~���[�W�V�����̉��t�����߂����ɃI�[�f�B�I�͂���̂ł͂Ȃ��̂ł��B�����A���y�\�t�g�Ƃ��ċL�^���ꂽ�M���́A���̃~���[�W�V�����́u���̎��_�ł́v�x�X�g�ɋ߂��p�t�H�[�}���X�����߂��Ă���̂��Ǝv���܂��B����������ŃI�[�f�B�I�ɂ���čČ�����̂��A���h�ȉ��y�̊y���ݕ��ł��B
�@�u��i�فv�̃����}�K�Ɉȉ��̂悤�Ȉꕶ������܂���
�b�I�[�f�B�I�́u�����ʐ^�v�ł����Ă͂Ȃ�܂���B
�b����́u�G��v�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@�������Ė����Ǝv���܂��B���y�\�t�g�̃}�X�^�[�e�[�v�̉����ɋߕt���悤�ɃV�X�e�������グ�Ă������Ƃ́A�����́u�����������Œ����ė~�����v�Ƃ����Ӑ}�����ݎ��Ӗ��ő�ł��B�ł��A�X�^�W�I�̉�����ʉƒ�ŏo�����Ƃ͕s�\�ɋ߂��̂������B������x�̒�����́u�i�𑜓x�Ȃǂ́j�����v�����N���A�ł���A���Ƃ̓��X�i�[���ǂ��u�G��v��`���������R�ł��B���́u���R�x�v�������I�[�f�B�I�̑�햡�Ȃ̂��Ǝv���܂��B���̈Ӗ��Łu���ꂪ�ŏI���I�v�Ƃ��u���́i�n�C�G���h�j���u�����������̂��̂��I�v�Ƃ������������Ȃ��̕������́A���̓I�[�f�B�I�̖{������Y�������̂ł��邱�Ƃ��m���Ȃ̂ł��傤�B
�����ԍ��F8625911
![]() 0�_
0�_
�N�����D������ɉ���ȁu�G��v��`�������Ƃ̓^�����I�[�f�B�I���s�̑�ʐ��Y�ɂȂ���A�I�[�f�B�I�����̕����ɂȂ������̂ł��B
�@���{��̕���ƃI�[�f�B�I�����̕���̍\�}�͎��Ă���Ƃ������܂��H�@�u����������v�u����C���������v�@���̌����͌��݂ł͕��@�I�Ɍ��Ƃ͂����܂���B����������́u�����v�ł����Ēf���āu�i���v�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@�D������ɊG���`���A���肭���ȊG���|�p�Ƃ��Đ��������悤�Ɩz�����鈫�ӂɒN���C�Â��Ȃ����Ƃ����ł��B����������ɖڂ��o�܂��ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B�I�[�f�B�I�����̖����ׂ̈ɁB
�����ԍ��F8632487
![]() 0�_
0�_
�@�_�q�̏o���Ȃ��l�̏������݂Ƀ��X����͉̂��ł����A�̂Ēu���ɂ͐ɂ����l�^�����Ă���Ǝv���܂����̂ŁA�����ăt�H���[���Ă����܂��B
���D������ɉ���ȁu�G��v��`�������Ƃ̓^�����I�[
���f�B�I�����̐��ނɁ`
�@�I�[�f�B�I�S�����̕������݂���ꡂ��Ɂu�N�����D������ȊG���`���Ă����v���̂ł��B���̔w�i�ɂ́u�D������ɕ`����v�����́u��ށv�����̒��ɑ������݂��Ă������Ƃ��������܂��B���͊G���`�����ɂ����̓�����������肳��Ă��܂��B������uCROWN�̃A���v�ƋƖ��p�X�s�[�J�[���ŏI���I�v�Ƃ��u�C�m�E�GSP�����������̂��̂��I�v�Ƃ����������Ă��A����Ȃ̂͐����Ȃ��Ȃ����u��ށv�̈�ɉ߂��܂���B
�@�O�ɂ������܂������A�I�[�f�B�I�͒��ۂ̐��E�ł��B�����ǂ��ĉ��������̂��A���̉��l�ς̓��X�i�[�̐���������ƌ����ėǂ��ł��傤�B���̒��Łu���ꂪ�ŏI���I�v�ƒf������͈̂��J���g�Ǝ����悤�ȂƂ��낪����܂��i�j�B�J���g�̒�`�͂���������܂����A��Ԃ̓����́u���̊u��v���Ǝv���܂��B����e�Ղɒf�₳���Ȃ����߂ɂ́A���͂ɐ₦������\�ȃf�[�^�����Ă��邱�Ƃ��d�v�ł��B�Ƃ��낪�����̃I�[�f�B�I�E�͂����ł͂���܂���B
�@�܂��A�n�C�G���h�@����Ƃ������Ђ����������ł���ꕔ�̋������}�j�A�͕ʂɂ��āA�u�ǂ����������v�Ǝv���Ă����ʂ̉��y�t�@�����Ɠd�X�ɍs���Ă��s���A�E�I�[�f�B�I�@��Ȃ�Ēu���Ă��Ȃ��B����������ɃI�[�f�B�I����Ƃ��Ă���҂Ȃ��Ȃ��B�������Ԃ����ĉƓd�`�F�[���̋��_�V���b�v�ɏo�|���Ă��A�W�����Ă���u�����h�͂�������DENON��MARANTZ��ONKYO�ق������B�������A���[�J�[�h���̔̔������E���E�����Ă��ē���̏��i��������߂�n���B����ł��Ɠd�X�ɒu���Ă��鐻�i���C�ɓ���������ǁA��������Ȃ�������Ë����邩�s���A�E�I�[�f�B�I���̂��̂���߂邵���Ȃ��B����ƂĉƓd�X�ȊO�̐��X�Ȃ�ʃs�[�v������͉��������̂ł��B
�@�����ɂ����Ă��āu���ꂪ�ŏI�I�@���̐��i�̓{�������̂�����I�v�ƌ��߂������̏�肢�Ǝ҂��o�Ă���A���ɔ�ׂ�����������Ă��Ȃ����[�U�[�͂Ȃт��Ă��܂��̂��A��������ʂ��Ƃ�������܂���B���Ȃ��Ƃ��A����ɃI�[�f�B�I�Ɋւ���u���ۓI�ȏ��v�������]�����Ă���A���ꂪ�ŏI���ǂ����N�ł������͕t���̂ł��B����ɂ́A�l�b�g���̕��y���u�J���g���ǂ��v�i�j�̉��s�ɔ��Ԃ��|���܂��B
�@�l���Ă݂�A�Ђ���Ƃ��Ă��́u���i.com�v�����Č��ʓI�Ɂu�J���g���ǂ��v�ɂȂ��Ă���̂�������܂���B�����ł����I�[�f�B�I�V���b�v���������A��ʏ���҂��Ȃ��Ȃ����@�ɐG��邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��������A���̌f���ŏ�A�������u���ꂪ�ǂ��ł���v�Ə����Ă��܂�����A�u�ł��A�ŏI�I�Ɍ��߂�̂͌䎩���̎��łˁv�ƒA���������Ă��A���̈ӌ����L�ۂ݂ɂ��Ď����������Ɂi�ʔ̂ȂǂŁj�w�����Ă��܂����l��������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u���[�U�[�����x�����L���O�v�̏�ʂ�����Ƃ����āA�����������ɔ����̂͊��̍���Ȃ����ł݂����Ȃ��̂ł��B�ł��A�L��������̃I�[�f�B�I�G���̕]���ł͂Ȃ��A�Ȃ܂��g�p�҂̃C���v���b�V�����ł��邾���Ɂu���ꂪ�C�C�͂��I�v�Ƃ��������싷��I�Ȕ������̈ꏕ�ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƁA����������A�̈�l�Ƃ��Ă͓��S�x��������̂�����܂��B
�@�b�x��B�u�ŏI�v���́u���ꂪ���������v���́u���_�I�ɐ����������������g�I�[�f�B�I�̌��߂āI�h�v���̂Ƃ������A����ȓ����Ȃ��̌��߂������s���Ȃ����߂ɂ��A��ʂ̉��y�D���̎��͂ɃI�[�f�B�I�́u���v�L�����z������������[�J�[���f�B�[���[�������ė~�������̂ł��B
�����ԍ��F8636963
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@������
130theater����
���悢��11.2ch�ł����I�ƕ��ʂ͂����ŋ����Ƃ���ł����A
��ɂ����Ƌ������A�A�A�A�A
ECLIPSE��TD725�A����͗ǂ��A�z���g�ɗǂ��ł��ˁB
�T�u�E�E�[�t�@�[�ł���قǐ[���A�Â��ɒቹ������@��͖����ł��傤�B
�ቹ�ŃN���A�[�Ƃ����̂��ςł����A���̒ቹ�ɛƂ�Ɣ����o���܂���ˁB
�~�����I�I�I
���E�������
>���Ƃ̓��X�i�[���ǂ��u�G��v��`���������R�ł��B���́u���R�x�v�������I�[�f�B�I�̑�햡�Ȃ̂��Ǝv���܂��B
���肭���ȊG��`���܂����Ă܂��B�i�j
�ŋ߁A�����A�L���t�F�[�Y��ALC-10�Ƃ����G���g���[�N���X��XLR�P�[�u�����܂����B
�w�����AACROSS 750 RR��XLR�łƔY�̂ł����A
�A�L���t�F�[�Y�̐V�^�C�v�P�[�u���͋v���Ԃ�Ȃ̂ŃA�L���ɂ��Ă��܂��܂����B
�����A�b�v�e���|�ɂ͒������܂����A�����̏��Ȃ��i�`�������Ȋ����ŁA�Ȃ��Ȃ��̏o���ł��B
�ȑO�̃A�L���t�F�[�Y��7N�̃P�[�u�������ǂ������ł���B
������������C�u�^���̔���̉��ɁA
����������̌��݂�����������悤�ȉ��ɂȂ��ė~�������炢�ł��B
���E��������g����ACROSS 750 RR��CP���������ł����A
�ŋ߂��̃N���X�̃I�[�f�B�I�P�[�u���́A10�N���O�ɂ͍l�����Ȃ����A�����ǂ��Ȃ�܂����B
�f�ނ��܂߂ăP�[�u����肪��肭�Ȃ�����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F8636964
![]() 0�_
0�_
�����큃�`�k�k
��130theater����
ECLIPSE��TD725sw�E�E�E���Đ����ł��ˁ���
������ĂS�O���ʂ̃T�u�E�[�n�[���������ƁE�E�E
�A��������������Έꎮ���������܂���
�i���̃V�X�e�����T�Z�b�g�ʔ�������(��)
�^�C���h���C���ƌ�����
�x�n�r�g�h�h�X�^�̃X�s�[�J�[�����삵�Ă���l�����Ȃ肢��������悤��
����Ă݂悤���ȁH�Ƃ��v���Ă܂��B
�����E�������
���肭���ȁu�G��v����Ȃ����肭���ȁu�G���L�v�悢�Ă܂�(��)
�n���̑�^�Ɠd�ʔ̓X�ɂ̓s���A�E�I�[�f�B�I�v�́u�q�v�̎�������܂���(��)
����̂̓p�i�E�f�m���E�n�m�j�x�n�E�\�j�[�E�P���E�b�h��
���W�J�Z���E�~�j�R�������E�E�E
�p�C�I�j�A�̃��j�o�[�T���v���C���[�i�c�u�|�U�P�O�`�u�j����
�u���Ă܂���ł����E�E�E�����P���ʂ܂ł̂c�u�c�v���C���[�����ł�^^;
�a�c�͂����ς�����܂������ǂ�
�����ԍ��F8637574
![]() 0�_
0�_
audio-style����Aarusqul ����@
�����́A�����ECLIPSE��TD725sw�̓A�o�b�N���l�X�̊��ɏ������܂����B���̋Ζ�
��̉�Ђ��������痈���̋Ɛт��Ԏ��Ƃ����钆�A�����̕��䂩���э~��܂����B
ECLIPSE��TD�V���[�Y�͂ǂ����l�����ǂ��̃V���b�v�ł��u�艿�̔��v�Ŗ����炵���A36��
�����̖������A�{�[�i�X���p�Ƃ��������ōw�����z��10���̋����t���Ƃ������ł����B��
������36��ł��ˁA7��~/���Ŏc�肪�{�[�i�X6��ł��B�����ł����������鏊���Ȃ�������
4���~�̒l����������A�X�s�[�J�[��AV�A���v�̗l��1�`2�N�ŌÂ��Ȃ鎖���Ȃ��܂�3�N����
���͂����o�����Ⴄ����ƌ��ӂ��܂����B
��{�I�ɋ���/�萔�����|���锃�����͂��܂���B�ԂƉƂ͂���ȃ��P�ɂ����Ȃ��̂Ŕ����
�������Ă��܂����E�E�E�B
�A�o�b�N�̒S���҂̕��ɁAECLIPSE��TD725sw�ƃI���L���[��Scepter-SW1�̑g�ݍ��킹�̉���
�z���ŗǂ�����ǂ�Ȋ����ɂȂ肻�����q�˂��Ƃ���AScepter-SW1���n�C�X�s�[�h��搂���
�r�v�ł��邪��͂�R���Z�v�g���Ⴄ�ATD725sw���ꔭ�Ŗ炵�������ǂ������H�I�Ƃ̎���
�����B���炭�S����T���Ă����Ɠ����V�X�e���Ŏg���Ă�����͋��Ȃ��Ǝv���܂��̂�
����������ɂȂ�܂��B(�A���vDSP-Z11�A�X�s�[�J�[JBL��S3100�CHC1000��)
�_����������Scepter-SW1�̓V�X�e��2�ɁA�V�X�e��2�̃��}�n�̃T�u�E�[�t�@�[YST-SW525��
�����ł��BScepter-SW1�ł��Ƃ�h�邪���ቹ���o�܂�����V�X�e��2�ɂ͍���Ȃ��\����
����܂����E�E�E��s���ƂȂ邩���H�ł��B
�����ԍ��F8637695
![]() 0�_
0�_
�@�G�����厏����̏��ɉ����āA���ł̓l�b�g��Ŏ��₷��ΒN���������Ă���܂��B����I���}���C���^�[�l�b�g�ȑO�ƈȌ�ł͊i�i�̈Ⴂ������܂��B�������l�b�g�ォ��̏�����͎�y�ł����w��������܂��B���̎�̏��i���̉��i�R���̂悤�ȁj�́A����̐l�����������Ɉӌ����邽�߂ɂǂ����Ă��ŗL�J���[���o�Ă��܂����Ƃ͔ۂ߂܂���A�������������Ȃ�əł���l�͖�肪�Ȃ��̂ł����A���S�҂�Ɖu�̂Ȃ��l�͐M���̂��������ȕ��̈ӌ����L�ۂ݂ɂ��Ă��܂����Ƃ�����킯�ŁA�\������������ށi�l�j�̖��������I�Ȉӌ��������Ă��܂���������Ȃ��B������莋���Ă��܂��B�����甽�Έӌ��͏�ɕK�v�Ǝv���Ă��܂��B
�ŏ��̘b��͓d���P�[�u���ł��B���͂����v���܂��B
�u�d���P�[�u����ւ��Ă����y�̉��߂��ς��قǂ̉��ω��͂Ȃ��v
�u�d���P�[�u����ς��邱�Ǝ��̂��Ӗ��̂Ȃ��s�ׁv�@
���̃I�[�f�B�I�펯����͈�E�����ӌ���������܂��A�u�ς��Ȃ��ƐM����v�ς��Ȃ��̂ł��B�����v�������͎��̂悤�Ȃ��Ƃł��B�Ƃ̉����z���͂��̂܂܁A�I�[�f�B�I�����A�@��̓d���\�P�b�g����d���g�����X�܂ł̔z���͂��̂܂܂ŁA�킸���P�`�Q���̓��̂�ւ��������ʼn������ς��A���܂Œ����Ȃ��悤�ȍ����b�c���������Ɂc�Ȃ�킯���Ȃ��B�Ǝv���̂ł��B�����炻���]�Ɍ����������邱�Ƃ����ʂȏo������Ȃ��錍�Ǝv���Ă��܂��B
�Ⴄ����Љ�܂��傤�B
�u�˂��̒��t���g���N�܂ŊǗ����ĉ��`���[�j���O�����܂����v�A�Ƃ����b�c�v���[��������Ƃ��܂��傤�B�i���ۂɂ���܂����j�@���̂悤�ȑ�Ȑ��i�͑��A�d���P�[�u���͒E�����ł��ˁB�������ς���p�[�c�Ƃ��ēd���P�[�u��������̂Ȃ�A���[�J�͂Ȃ�����P�[�u���̌����������Ă͂����Ȃ��Ǝv���̂ł����A�������ςł��ˁB�������Ȃ��Ɣ���Ȃ��������̂͗������܂����A�ς�遁�ǂ��Ȃ�ƒN���������������ƂŁA�m�����R�����l��U���E�擱�E���]�������Ƃ����̂悤�Ȗ����������i�̉��s���������Ԃ��������ƂɂȂ����Ǝv���̂ł��B
�X�s�[�J-�[�u���Ɋւ��ẮA�d���P�[�u���قǂ̃I�J���g���͂Ȃ��Ǝv���܂����A�Ó��ȉ��i�̂��̂�I�Ԃ̂��������Ǝv���܂��B��ɉ��i�o�����X���l�����đI�ׂA�V�X�e���S�̂̉������̂��ƃo�����X�����Ă���A�����������̂��Ǝv���܂��B�P�[�u���͂����܂ŃP�[�u���B���̐��ł��B�P�O�O�~�^��������̂͗v���ӂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8640256
![]() 0�_
0�_
�����́�ALL
inouesp�U����@
>���ʂȏo������Ȃ��錍�Ǝv���Ă��܂��B
���̔��ɂ�����ʓI�ȏo���m�肽���āA�����܂ߏ����W�߂��莿������肷��̂��ȂƎv���܂��B
�������d�˂Ď����̎��Ō��ʂ��o���E�E�E�٘_�͂���܂��C�ɂȂ镨���e�X�g�ł��Ȃ��ꍇ�͂ǂ����܂��傤�H
�s���Ŏ��Ԃ�����Ύ����ł���l����ł͂���܂���B
�g�߂ȓX�܂Ń`�F�b�N�ł��鐻�i���������������Ȃ����͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂���B
��O�҂̊ԐړI�ȏ��𗊂�ɂ��ĉp�f���邵���Ȃ��P�[�X�A�����炭��ΐ��͂��̕��������ł��傤�B
�����A�h�o�C�X�Ȃ�R�����g���Ό����邱�Ƃ������ł����A�O��I�Ȍ����͂��Ă��Ȃ�����ł��B
���ʁA����ւ��ɂ��ω��ɕБ���������܂܂ɂȂ肪���Ȃ̂͏��X���L��ł��ˁB
�����ԍ��F8641949
![]() 0�_
0�_
�|��audio-style����
�@ACCUPHASE�̃P�[�u���́A���Ђ̃A���v�̃L�����N�^�[�ɒʂ�����̂�����悤�ł��ˁB�@�탁�[�J�[���P�[�u�����o���Ƃ��́A�@��Ǝ����悤�ȃJ���[�ɂȂ邱�Ƃ������̂��Ǝv���܂��i��FDENON�̃X�s�[�J�[�P�[�u���Ƃ��j�B���[�J�[���Ƃ��Ắu�Ⴄ�L�����N�^�[�ŃA���v�ނ̃o�����X��⊮���Ă�낤�v�Ƃ͎v��Ȃ��̂ł��傤���B�܂�̓��[�U�[���l����悤�ȁu�P�[�u���ŋ@��̎�_���J�o�[���悤�v�Ȃ�Ă��Ƃ́A�u�t�����P���nj�Q�̈����O�v�Ȃ�Ă��Ƃ����蓾�܂��ȁi���j�B
�|��arusqul ����
�@�ŋ߁A�����̃A���P�[�g�Łu�i�C�������Ȃ�����A�^����ɍw�����T������̂́H�v�Ƃ����ݖ�ŁA��ʂ́u�����J�����v�ɑ����āu�I�[�f�B�I�v����ʂɗ��Ă��܂����B��������ʃs�[�u�������̃A���P�[�g�ł�����A�����Ō����u�I�[�f�B�I�v�Ƃ̓s���A�E�I�[�f�B�I�ł͂Ȃ��~�j�R���|�̗ނ��Ǝv���̂ł����A���ꂾ���u���y���v�Ƃ����s�ׂ͉䂪���ł͌y�������Ă���̂ł��ˁB���Ȃ݂Ɂu�i�C�������Ă����������Ɠd�v�̈�ʂ̓e���r�ł����B���Ȃ�e���r�͖����Ă��ǂ����ǁA�I�[�f�B�I���Ȃ������琶���Ă����܂��ǂˁi�j�B���Ăœ����A���P�[�g���������Ⴄ���ʂɂȂ�̂�������܂���B
�|��130theater����
�@ECLIPSE�͓��{�̃��[�J�[�łٍ͈ʂ�����Ă��܂��ˁB��s�I�ȃG���W�j�A��i���Ă��邻���ŁA�܂����ꂪ���i������Ă��܂��Е����������Ă���Ǝv���܂��B���ꂪ�̂Ȃ���̃I�[�f�B�I��僁�[�J�[�ł͊����̘g���Ȃ��Ȃ��j��Ȃ��X��������̂�������܂���B
�@���āA�ŋߌl�I�Ɋ��҂��Ă�����̂�SHARP��1�r�b�g�E�f�W�^���A���v����|���Ă����Z�p�҂������グ���u�����h�uN MODE�v�ł��B���i���育��ŁA�o������ł�10���~��̃A���v�ނ́u�䕗�̖ځv�ɂȂ肻���ȗ\�������܂��B�^�u�g�c���v�ł͎���i���W�����Ƃ̂��Ƃł����A�s���ɂ�葫���^�ׂ����ɂ���܂���B�c�O�ł��B�܂��A12���ɐ����ɓX���ɕ��Ԃ炵���̂ŁA����Ƃ������Ă݂����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8642651
![]() 0�_
0�_
�����E�������
>�ŋߌl�I�Ɋ��҂��Ă�����̂�SHARP��1�r�b�g�E�f�W�^���A���v��
>��|���Ă����Z�p�҂������グ���u�����h�uN MODE�v�ł��B
>���i���育��ŁA�o������ł�10���~��̃A���v�ނ́u�䕗�̖ځv��
>�Ȃ肻���ȗ\�������܂��B
���V���[�v�̕z������ł���
�P�r�b�g�̂c�A���v���o��̂��Ǝv���Ă���ł����Lj�����݂����ł���(��)
SHARP SM-SX10�͌y�������Ă��܂��Ƃ̋g�c������̃��r���[�Ȃ̂�
���ꎩ�������҂��Ă܂�^^;
�\���P�R�D�X���łP�Q���P�O���\��炵���ł����王���������Ƃ��ł���
�n���Œu���Ă���Ƃ��Ȃ�Ė������낤�ȁE�E�E��^^;
�����ԍ��F8643895
![]() 0�_
0�_
�|��redfodera����
�@�Ƃ��ǂ��v���̂ł����A���̒��Ɂu����v�����݁v�����݂���ꕔ�̐l�X�́A�����玎�����Ă��Q�l�ɂȂ�Ȃ��P�[�X�����X����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ƃ��u�Z�b�e�B���O�ł͐�Ή��͕ς��Ȃ��v�ƌ����l�Ɏ��͕��������Ă��܂����A�uCD�v���[���[�͂ǂ�������ꏏ�ł���v�Ƃ̎��_�X�Ɣ�I����l�ɂ��o��܂����B�u�v�����疽�����v�ł͂Ȃ��ł����A�S�ɋ����O�����������������̂Ȃ̂�������܂���B
�@�����̏o������ɂ������҂́u�����h�v�ɂȂ��Ă���̂�������܂��A����ł������̃{�[�h�ł́u�o���邱�ƂȂ�A���@�ɐG��ĉ������v�ƃA�h�o�C�X���邱�ƂɐS�|�������ł��B�܂��u�I�[�f�B�I�Ȃ�Č����ڂ���I�v�Ɗ���锃����������ł��傤���ǁA����Ȃ�Ώ��X�����̃`�F�b�N���d�v�ۑ�ł����ǂ�(^^;)�B
�|��arusqul����
�@�uN MODE�v�̓W�J�͊y���݂ł����A�t�Ɍ����Α�胁�[�J�[�ɂ̓I�[�f�B�I���̊���ł���ꂪ���ꂾ�����Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤�B����ɂ��Ă�CDP�͂���ς�SACD�Ή��ł͂Ȃ������ł��ˁB�ŋ߂͏]���̃v���[���[�őΉ��ł���n�C�X�y�b�N��CD�\�t�g���o����Ă����̂ŁA������SACD�ɍ��킹�邱�Ƃ͂Ȃ��ƒf�肵���̂�������܂���B�Ƃɂ����A���@�̎����͊y���݂ł��B
�|��inouesp��
�@�u�ŏ��̘b��͓d���P�[�u���ł��v�Ƃ̂��Ƃ����A�c�O�Ȃ���{�X���b�h�́u�l�I�ł����v�ł���150�A�[�e�B�N���ɒB���Ă��܂����B����āA����ɂĈ�x�u���߁v�āA����i�C���������� ^^;�j�V�X���b�h�Ɉڍs���܂��B
�@�������A�M�a������Ɂu�d���P�[�u���ʼn��͕ς��킯���Ȃ������咣����X���v��ʂɗ����グ��͎̂��R�ł��B��낵��������h�E�]�B�܂��A�d���P�[�u����ւ��悤���A�ǂ�ȃn�C�G���h�V�X�e���ɃO���[�h�A�b�v���悤���A�u���܂Œ����Ȃ��悤�ȍ���CD���������ɂȂ�v�Ƃ����̂͗L�蓾�Ȃ��Ǝv���܂����ˁi���j�B�����������X�i�[�����P�[�u���ύX���炢�ł���ȁu�z����₷�錃�ρv�Ȃ]��ł��Ȃ��ł��傤�ȁB���傹��A�N�Z�T���[�i�������j�����B
�@�E�E�E�E����ł́A�F����A����ɂĂ��̃X���b�h�́u���J���v�ɂ������Ǝv���܂��B�����l�ł���(^^)�B
�����ԍ��F8645479
![]() 2�_
2�_
�O�̃X���b�h�i�@http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7748266/�@�j�����X����150�ɒB���A���X�u�d���v�Ȃ��Ă����̂ł����ɐV�X���b�h�𗧂Ăāu�d�蒼���v�Ƃ������܂��B�O��͉������̃I�[�f�B�I���i���u�����h�ʂɐU��Ԃ�u��ڕҁv�Ƃ����ׂ��W�J�Ő̘b������オ��܂����B��������ł�������F����ɂ͉��߂Č��\���グ�܂��B
�@���̃p�[�g2�̓g�s��Ƃ��Ắu�W�]�ҁv�Ƃ��Ęb��i�߂܂��B�O�̃X���b�h�̖`���ɂ��q�ׂ��ʂ�A���ꂩ��̃I�[�f�B�I�͂ǂ�����ׂ����A�ǂ�ȏ��i����������ė~�������E�E�E�E�Ƃ������A�����������s�����ő�ȕ����Ŏ��Ƃ��Ă͕��͂������U�炩���Ă����������Ǝv���܂��B�ŁA���́u�ǂ�����ׂ����v�Ƃ����̂́A�Ηz�������s���A�E�I�[�f�B�I���ǂ�������痧�Ē����邩�Ƃ������Ƃ����C���ɂ��܂��B�������X�I�[�f�B�I�t�@�����u���̋@��͂����A���̑��u�̓T�C�R�[���v�ƌ������Ƃ���ŁA�s��S�̂��傫���Ȃ蓯�D�̎m�������Ȃ����Ƃɂ́A�C�}�C�`�ʔ����Ȃ��ł���E�E�E�E�B
�@�������A���u��ڕҁv���u�W�]�ҁv���ƁA�����C�ɂȂ��Ďd��������ɂȂ��Ă���̂͂��̃{�[�h�̈�Q���҂ɉ߂��Ȃ��s�сE���̏���ȏ��Ƃɉ߂��܂���B���������������̃I�[�f�B�I���i�ɂ��Ă̏������݂�v���o�b�����}���܂��B�܂����݂̃I�[�f�B�I���i�E���[�J�[�E�����ăf�B�[���[�Ɋւ��Ă̕s���_�Ȃ��u�`�����Ă��炦��Θb���e�ނ�������܂���(��)�B����ɂ��A���̌f���Ɏ���̃X���b�h�𗧂ĂĂ���悤�ȏ��S�҂̊F����ɑ��ĎQ�l�ɂł��Ȃ�i�Ȃ�̂��H ^^;�j�K���ł��B
�@����ł́A��낵�����肢���܂� �|�� ALL�B
![]() 0�_
0�_
�@�O��̃g�s�b�N�Łu��ڕҁv�̍Ō��B&O�������Ă�������Ƃ������Ƃł��Ȃ��̂ł����A�܂��̓f�U�C�����܂߂��u�O���v�̖ʂŃs���A�E�I�[�f�B�I�̍���݂̍����T��܂��B
�@�C�O���[�J�[�ł͋@��̃f�U�C���͂�����x����グ���Ă���Ƃ͎v���܂��B������ɂ̓_�T���O���̂��̂�����܂����A���Ȃ��Ƃ����炩�̃|���V�[�͊������܂��B���āA�唼�̍������[�J�[�͎��i�ł��B
�@��������Ƃ����f�U�C���|���V�[�����������s�̓��{�̃��[�J�[�Ƃ����AACCUPHASE�����v�������т܂���B�n�Ǝ����猻�݂܂ŁA����قǃf�U�C���̈�ѐ����ێ����Ă��郁�[�J�[�͑��ɂȂ��Ǝv���܂��B���ƁA�����Ă������LUXMAN���炢�ł����ˁBESOTERIC���f�U�C���ł͌������Ă���Ƃ͎v���܂��B
�@�������AACCUPHASE��LUXMAN��ESOTERIC���A���S�҂��N�w��܂��Ă⏗�����C�y�Ɏ���o���鏤�i�ł͂���܂���B�Ɠd�ʔ̓X�̃I�[�f�B�I�R�[�i�[�́g�����~�h�݂����Ȏ������ɂ����̋@�킪�������Ă��Ă��A��ʃs�[�v���͖ڂɗ��߂܂��A���Ƃ��ڂɂ����Ƃ��Ă��g�������h�Ƃ�������ςɂ�莩���Ƃ͊W�̂Ȃ����i���Ǝv���Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����Ɉ������ƂɁA����ACCUPHASE�ɂ������āg�f�U�C���|���V�[�������Ă���h���Ǝ��͕̂]���ł��Ă����̃f�U�C������ΓI�ɗD��Ă��邩�ǂ����́A��ʏ���҂ɂƂ��Ă͕ʂ̖��Ȃ̂ł��B�l�I�ɂ́AACCUPHASE�̃f�U�C���͊C�O�u�����h�ɝh�R�ł�����̂ł���Ƃ͎v���܂���B�����܂Łg���Y�ɂ��Ă̓}�V�h�Ƃ������x���ł��B
�@�ł��A�{����ACCUPHASE�̂悤�ȍ����ƌ�����u�����h�̃f�U�C���̂��ƂȂǂ��ł������̂ł��B�����̐��i���w�́A������x�I�[�f�B�I����Ƃ��Ěn��ł������[�U�[����ł���A��ʏ���҂Ƃ͈Ⴂ�܂��B���́A���ʂ̉��y�t�@�����u�~�j�R���|��肿����Ɨǂ����Œ��������v�Ǝv�����Ƃ��ɁA�������[�J�[������ɑΉ������u���L�~�����f�U�C�������������i�v��p�ӂ��Ă���Ă���̂��ǂ����ł��B�͂����茾���āA��œI�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�s���A�E�I�[�f�B�I�̃G���g���[�N���X�̐��i�A���Ƃ���DENON��MARANTZ�AONKYO���̉��̃N���X�̃A���v�ށA��ʏ���҂��~������ł��傤���H�@���͂܂����������v���܂���B�ÐF���R�Ƃ����A�����c�}�~������ł��邾���̊O���B����f�U�C���ʂœ˂��l�߂��`�Ղ�����܂���B�������A�Z���������悤�ȃt���T�C�Y�B���ɔƍߓI�Ȃ܂łɑ傫�����s���B���������u�s���A�E�I�[�f�B�I�Ɏ����߂悤�Ǝv������A�f�U�C���̂��Ƃ͍l����ȁI�v�ƌ�������ł��B
�@���S�҂�����o���₷�����i�Z�O�����g�̐��i�ɂ����A�f�U�C���i�y�уT�C�Y�j�ɋC�������ׂ��ł��B���Ȃ��Ƃ��A�~�j�R���|�����ׂ̗ɒu���Ă���A��ʃs�[�v���Ɂu���������~�����I�v�Ǝv�킹�邮�炢�̊O���I�ȃA�h�o���e�[�W��t�^���Ă��炢�������̂ł��B�����ȃf�U�C�i�[���N�p���Ă��ǂ��Ǝv���܂��B���̂��߂ɉ��i�����������Ȃ����Ƃ��Ă��A���ꂾ���̏��i���l������Ə���҂Ɏv�킹��Ώ\���y�C����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F7921006
![]() 1�_
1�_
������������܂��B
�@�����A���̂悤�ȁu�ȁ`����āv�I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��Ă̓w�r�[�Ȃ���ł��B
�@�ŋ߂̓n�C�r�W�����E�t���e���r�̔���s������`���Ă�������������悵�Ă͂��܂���
�@��悤�Ɂu�s���A�I�[�f�B�I�v�Ƃ͎��Ĕ�Ȃ���̂ł͂���܂��B
�@���̊�����ɁA�Ɠd�ƃI�[�f�B�I�@��̊_�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ͗ǂ��̂ł����A���̌f����
�@�̗��p�����Ă���͂茻���͂��Ȃ茵�����Ɗ����܂��B
�@�����̏���҂��u�����āE�u���āE�����v�ƌ������ꂱ���①�ɂƓ������o�ł���l��
�@�ƂĂ��������Ƃɋ����A�����ɂ́u��v�ƌ�����肩�u���p�i�v�Ƃ��Ẳ��l����
�@�l�����Ă��Ȃ��l�����|�I�Ȃ̂��Ǝv���܂��B
�@ipod�𒆐S�Ɂu�����������y�v�����R�̂��̐��̒��A������x�����ɗ]�T(�o�ϓI�ɂ�
�@���_�I�ɂ�)���Ȃ��ƉƂł�������Ɖ��y������~���Ȃ��̂ł��傤���H
�@�������͍D���ȎԂɒu�������čl���Ă��܂��܂��B
�@�n���s�s�ł͈�l�Ɉ��̊��Ōy�����Ԃ����݂��Ă��܂��B
�@�o�ϓI�A��I�ɂ���ȏ�̎Ԃ�]�܂����ɂ͉^�]�������A���L�������ƌ����~����
�@����܂��ˁB
�@���Y�E�O���Ԃ��܂߂��̑I�����͂��Ȃ肠��܂����A�Ԃɂ͂��ꂼ��́u���݊��v��
�@����A�y�����Ԃ������Ȃ��l�ɂ��x���c��N���E���͂킩��܂��B
�@�I�[�f�B�I�͔@���ȕ��ł��傤�H
�@���y���e���r�̗̉w�ԑg���Ԃ̃��W�I�ł��������Ȃ��l�ɃI�[�f�B�I�@�킪�ǂꂾ��
�@�́u���݊��v�����邩�Ƃ����Ƒ����ɋ^��Ɏv���܂��B
�@�n�C�r�W���������Ń��[�J�[���͂������Ƃ���Ɂu�̔��헪�v���u�`�����A����҂�
�@���邾�������Ă��܂��B�^�����g�̃C���[�W�Ŕ���グ���ς��ƌ������Ƃ����Ă�
�@���݂̏���҂̎��m��܂��B
�@�m���ɁA�u�f�W�^���v�̂������ō����\�E�������E���掿���A�i���O����Ƃ͔�ׂ�
�@�����ł��Ȃ��قǎs�����邱�Ƃɐ���������܂��B
�@���ЂƂ̊i���������ƂŔ���グ�������悤�Ƃ���͎̂��R�̐���s���ł����A
�@����҂̍����������Ă��邱�Ƃ��傫�Ȏ����ł��B
�@���E�������́����S�҂�����o���₷�����i�Z�O�����g�̐��i�E�E�E�E��
�@�̌�����͂�l�b�N�ɂȂ�̂ł��傤�ˁB
�@���S�Ҍ̂ɁA���Ⴂ�E���������E�������|���Ɏ肪�o�Ă��܂��ł��傤���ˁB
�@���s�E�h���E�H�v�Ƃ��낢��Ȍo�������炱���u������v�҂ɂȂ�̂ł��傤���B
�@�u����Љ�v�͂܂������ł��傤����A���̐����ʌ����ƃ}�j�A�����̕ǂ͍�������
�@�Ȃ�悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B
�@�u�Ⴂ�̂킩��j�́����I�v���Ƃ���CM�����s���Ă���O�\�N�߂����Ȃ�܂���
�@�����I�ɈႢ�̂킩��l�͈���ɑ����Ă͂��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�@�u�������v���ۂ͐l�̎g�����A�S�Ăɘj��ƍl���Ă��܂��܂��B
�@�命�����߂�u���Y�K���v�����̕����ǂ�ǂ��Ă����̂́u�����v�����F����
�@�l�B�́u�R���Z���T�X�v�Ȃ̂����m��܂���ˁB
�@���͊җ��ڑO�ɂ��āu���[�L���O�v�A�v�ǂ��납�����������낤�����̍��ł����I
�@
�����ԍ��F7921278
![]() 0�_
0�_
�@�l�I���W����A����ɂ��́B�O�̃X���b�h�ł͂����b�ɂȂ�܂����B
�@�I�[�f�B�I�]�_�Ƃ̐��쉫�F���uAV�͋�ۂ̐��E�ł���A�s���A�E�I�[�f�B�I�͒��ۂ̐��E�ł���B���Ă���悤�őS���قȂ���̂��v�݂����Ȃ��Ƃ������Ă��悤�Ɏv���܂����A���̒ʂ肾�Ǝv���܂��BAV�͉Ƒ������Ċy���߂܂����A�s���A�E�I�[�f�B�I�͎����ň�l�V�X�e���ɑΛ����邱�Ƃ���{�̃X�^�C���ɂȂ�܂��BAV�̓G���^�e�C�������g�ł����A�s���A�E�I�[�f�B�I�͗L��Ӗ������I�ȁg��h�ɂȂ�܂��B���ۂ̐��E�ɗV�ԁg��h�Ƃ��Ẵs���A�E�I�[�f�B�I�����ނ��Ă��邱�Ƃ́A���ꂾ�������́g��h�ɐZ��]�T���Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B
�@80�N��Ɂu598�̃X�s�[�J�[��798�̃A���v�v�ŃI�[�f�B�I���y����ł����A�������͂ɉ��l�����܂����A�ނ�̓I�[�f�B�I���犮�S�ɑ������Ă��܂��B�I�[�f�B�I���u�ɋÂ�ǂ��납�A�������Ɖ��y�����Ԃ�����ꂸ�A�c�ƂƋx���o�̘A���ŋA�����V�H���ăt����������̓x�b�h�ɒ��s�̂悤�ł��B�������80�N��̃I�[�f�B�I�S�����ゾ���ċߐl�͖Z���������̂ł����A�����͌����ĈÂ��Ȃ��Ƃ����S���I�]�T���炩�A�d���Ǝ�Ƃ𗼗����Ă���҂����������悤�ȋC�����܂��B���͓����g�Z�����h�Ƃ����Ă��A��̌����Ȃ��̒��Ŗڐ�̂��Ƃ����Ȃ��̂ɐ���t�ŁA��ǂ���ł͂Ȃ��悤�Ɍ����܂��B
�@�s���A�E�I�[�f�B�I�̐��ނ́A�܂�Ƃ���o�u������ȗ��̓��{�o�ς̒���������Ȃ̂ł��傤�B����ƁA�Ђ���Ƃ�������{�l�͌��ǁi���̓I�Ɂj���y���D���ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����E�E�E�E�Ƃ��������ƂɎv��������܂��i����ɂ��Ă͌���܂����y�������Ǝv���܂��j�B
���u�������v���ۂ͐l�̎g�����A�S�Ăɘj��ƍl���Ă��܂��܂��B
�@�����ł��ˁB�N���}�����Ĕ����̂͌y�����Ԃƍ����Ԃ���B��ʃs�[�v���̍w���͂������A�������S�~�V���b�v�ƃ��j�N���ōς܂��Ă��܂��悤�ɂȂ�Β������I�ɂ͏k���ύt�̃h�c�{�Ƀn�}���Ă��܂��̂ł����A���E�����E�����E���o�σ}�N���̂��Ƃ͉����l���Ă��܂���B���������̂ł��B
�@�����Ȃ�h�C�������������݂ɂȂ��Ă��܂��ăX�C�}�Z�����A����Ƃ��X�������肢���܂�(^^;)�B
�����ԍ��F7923987
![]() 1�_
1�_
����`���x�͏d���ł��B
�s���A�E�I�[�f�B�I�̐��ށE�E�E����͂�����x���������Ȃ��������m��܂���B��X��(����)�I�[�f�B�I(���o�ł��ˁH)�ɋ��������������́A�r�W���A��(���鎖�����o�ł��ˁH)�Ȃ�ĉf��قɍs���Ȃ��Ă̓_���ł����B�e���r�͑�^�ƌ����Ă�20�C���`����Α�^�ƌ�������x�ʼn掿������Ȃ�ł����B�Ƃ������̓I�[�f�B�I��ӓ|�ɂȂ�͕̂K�R�ƌ����ΕK�R���Ǝv���܂��B���̕ӂ�̑̌������߂����ꂽ���́A���ł��s���A�E�I�[�f�B�I�ɂ��͂����Ă���Ǝv���܂��B
�ł��A����͐i�ݑ����ċߔN�̖{����50�^�O��̑���(37�^�ł͖{���ɏ����������܂��B)�e���r���E�E���ꂪ���掿�ň����Ɏ�ɓ��鎞��ł�����`�u���嗬�ɂȂ����͕̂K�R�Ȏ����Ǝv���܂��B(���Ɏ����n�C�r�W�����e���r�͉���8��E�E���A���^��6����w�����܂����B�v���W�F�N�^�[���O��2��ADLP��1��A��D-ILA��4��ڂł��B)����ɋL�^�}�̂��u���[���C����������A��������Ƃ���ɓ�����z�ł�����f���ƗZ�������`�u����������K�v������܂��B
(���͏��߂ă��}�n��AV�A���v�������A�����s���A�E�I�[�f�B�I�A���v�͗v��Ȃ��Ǝv���A�F�l�Ɉ����ŏ������܂������A���̃A���v�ŕ����s���A�E�I�[�f�B�I�̉��̈����ɜ��R�Ƃ��Ă����ɗF�l��蔃���߂��܂����B�Ȍ�A�s���A��AV�ł̓A���v�ƃX�s�[�J�[�͊��S�ʌn���ɂ��Ă��܂��B�����Ƃ��ASACD�}���`/DVD�I�[�f�B�I�}���`�̓}���`�`�����l���A���v���ڂ�AV�A���v�ɗ���Ȃ�������Ȃ��̂Ńv���[���[�͋��ʂł��B)
����Ȋ��ɂȂ����̂ł����獡����͂`�u�ł���A�s���A�E�I�[�f�B�I�͈ꕔ�̕��̗̈�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�e���r�t���̃X�s�[�J�[������Ȃ�ł͂���܂����A�̂���r�ׂ�Ƒ����u�ǂ����v�ɂȂ������̂��Ǝv���܂��B�܂��A����Ȃ��ʂ̕��Ȃ炱��ŏ\���Ǝv���͓̂��R�ł��傤�B(���Ƃ������͉̂f���������ƁA����Ȃ�̉����ł���Εs���������Ȃ��Ȃ�܂��B��ɏ������݂����l�ɁAAV�A���v�ʼnf�����Ȃ���E�E�E�Ⴆ�I�[�P�X�g���̉��t�ł��r�f�I�Ō��Ȃ��畷����AV�A���v�ł��s���͏o�Ă��܂���ł����B)
�����ԍ��F7924926
![]() 0�_
0�_
�@�O�̃X���b�h��Technics�i�����d��j��70�N�㖖�ɏo�����u�R���T�C�X�E�R���|�v�̃V���[�Y�ɂ��ď����G��܂������A���������R���Z�v�g�̐��i�����͑��݂��Ȃ��̂͏���҂ɂƂ��ĕs�K�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�u�R���T�C�X�E�R���|�v��SU-C01��SE-C01�̃Z�p���[�g�A���v�𒆐S�ɂ����V�X�e���ŁA������30cm�̃R���p�N�g�T�C�Y�Ȃ��玿���͂��Ȃ�̃n�C���x���B�f�U�C�����̂͏]���@��P������̂ł����A���������@�̒��Ńc�}�~�ނ����ɂ��܂����C�A�E�g����A�S�̓I�ȃC���[�W�Ƃ��Ă͍����@�̕��͋C�������o���Ă��܂����B���i�̓v���E���C�����킹��115,000�~�ŁA�v���[���[��A���v���܂߂��20���~�͗D�ɒ����܂�����A����ONKYO��INTEC�V���[�Y��荂���ł�����肩�A�����̕����E���^�������l����Ɨ��h�ȃ~�h���N���X�̃s���A�E�I�[�f�B�I�E�V�X�e���ɂȂ�܂��B���������̂��~�j�R���|�����ׂ̗ɂ���C�Ȃ��u���Ă���A���Ƃ������Ȃ��Ă��u�����͗~�������̂��v�Ǝv���Ⴂ���[�U�[�͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����Č��݂̓f�W�^���A���v�̋Z�p���i��ł��܂�����A���l�̃R���Z�v�g�ł����Ƌ쓮�͂̍����V�X�e������邱�Ƃ��\�ł��傤�B
�@�R���p�N�g�T�C�Y�̃A���v�ނŎv���o���܂������A2006�N��DENON��PMA-CX3�Ƃ������U��̃A���v��o�������Ƃ�����܂��B���͂�����G���̃O���r�A�Ō����Ƃ��A�u�R���T�C�X�E�R���|�v�̌���łƂ̈�ۂ������܂����B����Ƃ����������������̐��i�����ɏo��悤�ɂȂ����̂��Ǝv���A���҂��ăV���b�v�Ŏ����ɐڂ����̂ł����E�E�E�E�B���ʂ͗��_�ł����B�c�}�~�ނ͌����ڂ͗ǂ��̂ł����A�t�B�[�����O���ň��ł��B�f�ނɃJ�l�������Ă���悤�ŁA�悭����ƍC�����Ă��Ȃ��B���ɉ��s����35cm��ƁA�t���T�C�Y�̃R���|�Ɠ����������̂ɂ͕���܂����i���Ȃ݂Ɂu�R���T�C�X�E�R���|�v�͂�����10cm���������j�B�������A���ɂ��Ă̓R�����g���݂���悤�ȃ��x���B���̃��[�J�[�Ƀf�U�C����p�b�P�[�W���O�����҂��Ă��d�����Ȃ����Ƃ��m�F���邾���ɏI���܂����B
�@�u�R���T�C�X�E�R���|�v���A�I�[�f�B�I��僁�[�J�[�ł͂Ȃ������d��Ƃ����Ɠd���[�J�[����̒�Ă������悤�ɁA�a�V�ȃR���Z�v�g�̐��i�͊����̐���肩��͏o�Ă��Ȃ��̂�������܂���B
�����ԍ��F7925407
![]() 0�_
0�_
���E������� �A 130theater���� �A����ɂ��́B
���s���A�E�I�[�f�B�I�̐��ށE�E�E����͂�����x���������Ȃ��������m��܂���B
���������ʂ�ł��ˁB���y��������C�����͐S�̖��ɒʂ��܂�������ɂȂ����킵�����Ǝv���܂��B��U���Ɍ����ƁA���ꂪ�Z�����Ă����[�H�t������]�ȂNjN����Ȃ����������m��܂���B�܂��N�ɂł��`�����X�����閲�Ɗ�]�����Ă鐢�̒����\�z����K�v������܂��B�����g�A�����g�݂Ɠ�ɕ��������ł͂Ȃ�����҂ł���҂ł��A��肪���̂���d���̓`�����X�����A������ł�����Ǝv���܂��B�����ƍ��E�̂��̕��̍l��������ł��ˁB
���y��[���y�Ö@]�ƌ������t������ʂ�A�l�Ԃ̌��N�����E���܂��B�l�ɂ͊F�A�Ɖu�@�\������A���ꂪ���y�Ɩ��ڂɊW���Ă��邻���ł��B[���B]�ɂ͖Ɖu�זE��[�i�ߓ�]�����@�\������܂����A����������������ɂ͓���̉��g���W���邻���ł��B�����郿�g����鎖�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B[�i�ߓ�]�͉��\���̍זE�̒��������I��钴�ߓ������̐��E�ł��B����[�i�ߓ�]�����זE�����ȂƎw�߂��o���Ί��͊������Ă��܂��킯�ł��B�����A��҂��������������҂ɁA�����A30���ԁA���[�c�@���g�̋��t�Ȃ��������N��ɂ͊��͊������Ă��܂����Ⴊ����܂��B
����ɂ��܂��Ă��A�@���ɉ��y�𑽂������āA�����̑̂ɍ�����[�i�ߓ�]�����`�����X��^���鎖�ɂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̃s���A�V�X�e���̓p���[�A���v�̓�̓��͂��s���A��AV�ɕ����邱�Ƃɐ������܂����B�s���A�͈ȑO�ƑS�������Ɏg���܂����AAV�̓T�u�E�[�t�@�[�����ł����������͂Œ����܂��B������ 130theater���� �����������ʂ�A�܂��܂��ł��B
�����ԍ��F7926395
![]() 0�_
0�_
�@130theater����A����ɂ��́B���������b�ɂȂ��Ă܂�(^^)�B
�@AV�̋������s���A�E�I�[�f�B�I�������̂������Ƃ͊m���ł����A80�N��ɂ�AV�ɋÂ��Ă���z�͋Â��Ă܂����B���̍��ɑS���{�I�[�f�B�I�t�F�A��AV���i�̓W�����ڗ��悤�ɂȂ��Ă���ƁA�]�_�ƘA���͂������āu�R���������t�F�A��AV�@��̃f���Ȃ�āE�E�E�I�v�ƃC���Ȋ�������悤�ł����AAV�t�@�����������ł����ƃI�[�f�B�I�t�@���������Ƃ����A����Ӗ����z�I�Ȏ��ゾ�������ȂƎv���܂��B
�@AV���O�[�b�Ƒ䓪���Ă����̂́ADVD�̓o�ꂪ����I�������Ɗ����܂��B����܂ł̃r�f�I�e�[�v��茀�I�ɑ��삪�ȒP�ŁA���[�U�[�f�B�X�N�Ɣ�ׂĂ����I�ɉ掿���ǂ��B�������A�n�[�h�͂��Ƃ��\�t�g�����i�����������B�]���͂�����Ƃ���AV�V�X�e���ł��������������������̂��A�s���A�E�I�[�f�B�I�V�X�e�����������ɂȂ��Ă���B�Ȃ��������AV�ɗ���Ă䂭�̂͗��̓��R�ł��B
�@�������A���O���ł͂ǂ��Ȃ�ł��傤���B�C�O�ł�AV�V�X�e���̗����͓`������̂ɁA�V�����I�[�f�B�I���[�J�[�͎��X�ƏЉ��邵�A���{�݂����Ƀs���A�E�I�[�f�B�I���ǂ����悤���Ȃ��قǎΗz�������Ƃ����b�͕����܂���B�ȑO�m�荇���̉��l���̎Ⴂ���Đl�Ɂu�A�p�[�g�ň�l��炵���n�߂�Ƃ��A�e���r�ƃX�e���I�A�ǂ������瑵���邩�H�v�ƕ�������A�S���X�e���I���Ɠ����܂����B���{�l��������t�̉ɂȂ�ł��傤���ǁA���y�ɑ��銴�����Ⴄ�̂��Ǝv��������ł��B
�@������ɂ���A�������[�J�[���������Ă���c������Ǝv���镜�Ò��I�[�f�B�I�͕ʂɂ��āA������p���I�Ƀ[�l���������s���A�E�I�[�f�B�I���ێ����Ă����ɂ�AV�Ƃ̋����͕s���ɂȂ�Ǝv���܂��B�L��Ƃ���AV�A���v�ł̉����݂̂̃p�t�H�[�}���X�͌���肪���܂����A�����́u���S�s���A�E�I�[�f�B�I�E���[�h�v�݂����Ȃ��̂Ɉ��Ő�ւ���悤�ȋ@�\���t���Ă���̂�������܂���i�܂��A���݂������悤�Ȃ��̂͂���悤�ł����A�����ƓO�ꂵ�����̂��o�Ă����Ȃ����Ǝv�����肵�܂� ^^;�j�B
�@�掿�ɂ�����肳��A����ɂ��́B
�@�{�[�h�̎�|�Ƃ͊W�Ȃ��̂ł����A��́u�H�t�������v�A�J�ł͂��u�I�^�N����������v�Ƃ��u�Q�[�}�[����������v�Ƃ��u�e�̈�ĕ�����������v�Ƃ������Ă��܂��B�ł��A�I�^�N�ŋÂ萫�Őe�ƃ\�������킸�A���i���˂��Ȃ������z�Ȃ�Đ̂��炢����ł������Ǝv����ł��B�ł��A�]���܂ł͂����\�������Ȃ������́u�J�^�M�̐����v��e�ՂɎ�ɂ��邱�Ƃ��o������ł���ˁB�����ƈ��肵���d��������A�l���݂̃R�~���j�P�[�V�������͐����܂��B�������A�^�T�C�g�ɂ��̔Ɛl�̋ߐ�́i���܂�z����ꂽ���̂ł͂Ȃ��j�����ڏq����Ă��܂����A���Ј��̐g���ł����l��������s����ȏ�ł́A�S�̎ア�҂͂����ɌǗ����Ă��܂��܂��B������̔Ɛl�̏��Ƃ͋ɌY�ɒl���܂����A�w�i�ƂȂ���D�]�����Ȃ���A�����悤�Ȏ����͂��ꂩ������₽�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�b�x��(^^;)�B
���@���ɉ��y�𑽂������āA�����̑̂ɍ�����
��[�i�ߓ�]�����`�����X��^���鎖�ɂ����
���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����ł��ˁB�Ō�܂Łu����[���A�f����Ė{���ɂ������̂ł��ˁv�ƌ��������Ă���������S���Ȃ�܂������A��X���u����[�A���y���Ė{���ɂ������̂ł��ˁv�Ǝv���A�����Ă����������̂ł��B
�����ԍ��F7927789
![]() 0�_
0�_
�@�p�[�g1�̑����݂����ȏ������݂ŋ��k�ł����ABOSE�ɂ��ď����Ă݂܂��B���Ђ̓}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�̋����A�}�[�EG�E�{�[�Y�𒆐S�Ƃ���`�[���ɂ��1964�N�Ɋw���ɐݗ�����Ă��܂��B���{�@�l���o�����̂�84�N�ł����A���ꂩ�琔�N���o���Ȃ������ɍ����ł̒n�ʂ��m�����Ă��܂��B
�@�e�N�m���W�[�ʂł́A11.5cm�t�������W�h���C�o�[���͂��߂Ƃ���V�@���̃��j�b�g�ƃG���N���[�W���[�\���ŁA�R���p�N�g�ȊO���Ɏ�����Ȃ��ቹ�Đ��͂Ɖ���Č����蕨�ɂ��Ă��܂��i����͊F����䑶�m�̒ʂ� ^^;�j�B�������A�ǂ����������g���H���ꂽ���h�ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��A�s���A�E�I�[�f�B�I�̃t�@���ɂ͌h�������X���ɂ���܂��B������x�p�b�ƒ����������͂����̂ł����A�F�t���̔Z���ɂ����O�������Ă��܂��W�J���Ǝv���܂��B�܂��AAV�p�ɂ͂����̂�������܂���B
�@BOSE���䂪���ł��Z���ԂŎs�������̂̓f�U�C���ɂ��Ƃ��낪�傫���Ǝv���܂��B���͌����ď㎿�ł͂���܂���B�d�グ�Ɋւ��Ă͍��Y�i�̕��������ł��B�������A���Ƃ��C�������X�^�C�����O����ʏ���҂̍w���~��������܂��B�������ABOSE�͂���Ȃɍ����i�͏o���Ă��Ȃ������ɁA�������������Ă��܂���B�������[�J�[�̃~�j�R���|�݂����Ɂu�l�i�̊��ɋ@�\���L�x�v�Ƃ�����������͂��Ă��Ȃ��̂ł��B�����܂Łg���h���Z�[���X�|�C���g�ɂ��Ă��܂��B�����炻�ꂪ�I�[�f�B�I�}�j�A���炷��ΐF�t���ߑ��̃T�E���h�ł��낤�ƁA�ϋɓI�Ɂg���̗ǂ��h�荞�ގp���́A�]�����ׂ��ł��B
�@BOSE���i�͂������Ɠd�ʔ̓X�ł������Ă��܂����A�z�[���Z���^�[��f�p�[�g�ɏ��i���Ă���̂��|�C���g�������ł��B�I�V�����ȉƋ�ƈꏏ�ɂ��Ă���a���̂Ȃ��O���B�ʂ����č������[�J�[�̃s���A�E�I�[�f�B�I�̃G���g���[�N���X�̏��i�ŁA�X�^�C���b�V���ȉƋ�ނƁg���ȁh�ł�����̂����݂���̂ł��傤���B
�@BOSE�̔�����͌��K���ׂ��Ƃ��낪�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7927799
![]() 0�_
0�_
���E�������C�݂Ȃ���C���͂悤�������܂��B
�O�X���́C�ƂĂ������[�����e�ł���ƂƂ��ɁC�y�����q�������Ē����܂����B
���E�������̌o���̐[���C�L���̊m�����ɂ͋�������ł����C���݂̂Ȃ���̂��b���C�ƂĂ��y�����ǂ܂��Ē����܂����B
���āCBOSE�̂��b���o�܂������C�������߂�BOSE�������̂́C80�N��O���̍��C�Ɩ��p�X�s�[�J�[�ł���802�Ƃ����@��ł����B�傫���̓~�J�������炢�ŁC����FRP���C11.5cm�t�������W��8���������̂ł��B�����CPA�ƊE�ő�q�b�g�C���̌����́C�y���ĉ����ɗD��C�p���[���������܂��܂��ŁC�g�����肪�ǂ��B���^PA�p�X�s�[�J�[�Ƃ����V�����W��������������X�s�[�J�[�ł����B
�����BOSE���C�R���V���}�[�s��ł��C�]���̂�����݂ɂƂ���Ȃ��R���Z�v�g�����C�V�F�A���L���Ă������̂́C�C�m�x�C�^�[�I���z���o���郁�[�J�[�̏����Ƃ�����ł��傤�B
�Ɩ��p�������[�J�[�̃R���V���}�[�s��ւ̎Q���ɑ��āC�����ƐϋɓI�ɂ���Ζʔ����̂ł́C�Ǝ��͎v���Ă��܂��B�Ⴆ�C�X�^�W�I�ȂǂŌ��ݎg���Ă�Ɩ��p�X�s�[�J�[�́C�قƂ�ǂ��p���[�h�E�^�C�v�B�X�s�[�J�[�E�v���Z�b�T�[�ƌĂ��C�R���C�U�[�C�A���C�����g�E�f�B���C�C�`�����l���E�f�B�o�C�_�[�Ȃǂ���̂ƂȂ������̂�ʂ�C�}���`�E�p���[�E�A���v���o�R���ăX�s�[�J�[���h���C�u�����Ă��܂��B���[�J�[�̃G���W�j�A���C���̃X�s�[�J�[�̍œK�ȃp�t�H�[�}���X���ł���悤�C�p�����[�^�̃Z�b�e�B���O�����Ă���܂�����C�e�Ղɑf���炵���T�E���h�����邱�Ƃ��\�ł��B
���݁C�����p�̃p���[�h�E�X�s�[�J�[�Ƃ����C�T�u�E�E�[�t�@�̂݁B�p���[�h�E�X�s�[�J�[������CCD�v���[���[�ƃv���A���v��̌^�ȂǁC���i�̏��^�����\�ɂȂ�C�f�U�C���̎��R�x�������Ȃ�̂ł́H�Ǝv���܂��B
�܂��܂��C�l�I�ɂ��낢��ȓW�]�͂���܂����C�����Ȃ肻���ł��̂ŁC���ꂭ�炢�ɁB
���E�������C�܂������[�����b�����҂��Ă���܂��B
�����ԍ��F7929452
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
���������A������̐V�W�J�������݂ɂ��Ă��܂��B
�������i�Ɍ����Č����~�j�R���|��n�C�R���|�Ȃǂ̃Z�b�g���菤�i�́A
�X���ł̎��o���ʂ������Ŕ̔����тɑ傫���e�����邱�Ƃ����[�J�[�����m���Ă���̂ł��傤�B
�f�U�C�������ɓ����Đ��i�����Ă邾�낤�Ɛ����ł���A�C�e��������܂��B
�Ƃ͌����A�Z���I�Ȉ��݂��͂т����Ă���l�Ń��[�J�[���g�̎���i�߂Ă��銴���ł͂���܂����c�B
�����A�P�i�R���|�Ƃ��Ȃ�ƏG�x�ȃf�U�C���⒘���ȍH�ƃf�U�C�i�[�̗p�Ŕ̔����т��L�т鐢�E�ł��Ȃ��A
�ǂ������Ή����܂߂��H�Ɛ��i�Ƃ��Ă̊�{���\�D��u�����o�ĂȂ�ځv�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B
598�I�[�f�B�I�̍��̉��I�ȁu�E�����E�v�̕�������͂����Ԃ�ς�����ȂƎv���܂����A
�C���_�X�g���A���E�f�U�C���I�ȗv�f�͂܂��܂���i���ł���ˁB
�Ȃ��ɂ̓G�L�Z���g���b�N�Ȃ��̂�����ːF�����Ȑ��i���K�������������ǂ����͂킩��܂���
�C�O���i�̒��ɂ͖��炩�ɑ��`���Ƃ��ăf�U�C������Ă�����̂��U������܂��B
�g���Ă��Ȃ����̘Ȃ܂��i���̑�ȗv�f�Ƃ��ĕ߂炦�Ă���͂��ł��B
�����Ƃ������Ƃōl����~�b�h�Z���`�����[�E���_��/�C�[���Y�͈ӎ����ė~�����ȁA���l�I�Ȋ��z�ł��B
���āu�Ƌ�v�e���r��X�e���I�̂��������̂ł����獡���̉Ƌ���������Ă��炢�����Ǝv���܂��B
��BOSE���䂪���ł��Z���ԂŎs�������̂̓f�U�C���ɂ��Ƃ��낪�傫���Ǝv���܂��B
���X�^�C���b�V���ȉƋ�ނƁg���ȁh�ł�����̂����݂���̂ł��傤���B
BOSE��B&O�͎��Ԃ������Ē��J�Ƀu�����h�E�C���[�W������Ă��܂����B
�����̃��[�J�[�́u�A���v�́c�v�u�f�b�L�́c�v�Ƃ��������ӂȋ@����A�s�[�����Ă��܂������A
�ޓ��͌ʂ̐��i�����ނ���u�����h�Ƃ��Ắu���E�ρv���A�s�[�����Ă��܂����B
�Q�Ђ̑��݂͓�����598�I�[�f�B�I�ւ̃A���`�e�[�[�̂悤�ɉf��A���Ȃǂ͂܂�܂Ɛ헪�ɏ悹��ꂽ���ł��B
�ŋ߂̃z�[���V�A�^�[�n�G���̃O���r�A�́A���ɂ͔ޓ���20�N�O����Ӑ}���Ă������̗̂l�ɉf��܂��B
�����ɂ���̂́u���y�Ƃ��ɂ���L���Ȑ����v���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7930341
![]() 0�_
0�_
�@�W�����A�o�[����A����ɂ��́B
�@�����A�Ɩ��p�@��̃s���A�E�I�[�f�B�I�ւ̉��p�͌����ɒl����ۑ肾�Ǝv���܂��B�u�Ɩ��p�͂���Ȃɂ������ĉ����ǂ��B���������p�Ȃ�ăI�J���g���I�v�Ƃ���搂�����Řb���U��܂����̂͂��������l�b�g�ʔ̋ƎҁuProCable�v�ł����A�������̎�Ɏ҂̌������Ƃ͔������������ɂ���A���Ȃ��Ƃ��P�[�u���W�̓R�X�g�p�t�H�[�}���X�ʂł́i���F�̍D�������͂���ɂ���j�Ɩ��p�̗D�ʐ��͔[���ł���Ƃ��낾�Ǝv���܂��B
�@�������A���̎�Ɏ҂̕������ʂ�ɃA���v��X�s�[�J�[���Ɩ��p�Ōł߂�Ƃ������Ƃ́A��ʏ���҂ɂ͂ƂĂ�������邱�Ƃł͂���܂���B�g�����肪�������܂����A�f�U�C���Ɏ����Ă͈�ʉƒ�̋��Ԃɒu����悤�ȊO���ł͂���܂���B
�@�ł��A�L��悤�ɋƖ��p�̕��@�_���������������p�[�l�����E�I�[�f�B�I�@��̊J���͉\���Ɗ����܂��B�p���[�h�E�X�s�[�J�[��CD�v���[���[���v���A���v��̌^�̃��V�[�o�[�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ȃ�āA���悤�ɂ���Ă͎s��ŕ]������Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ��u�X�s�[�J�[�P�[�u���̔疌���i�c�����Ȃ��Łj�����v�ȂǂƂ������f�l����i���ɏ����j�ɂׂ͉̏d����Ƃ������t����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���ƁA���̒��ɂ̓��b�N��HIPHOP���D�ރ��X�i�[���������Ƃ���A�u�R���T�[�g���Œ����锗�͂̃T�E���h���ƒ�ŁI�v�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�ŁAPA�p���u�̃e�C�X�g�������ꂽ�V�X�e����o���ƃE�P�邩������܂���B������������i�ӎ��I�E���ӎ��I�ɌW��炸�j�u�s���A�E�I�[�f�B�I�̓N���V�b�N��W���Y�̂��߂ɂ���v�Ƃ̍l���������Ă���Ǝv���܂��B�ł��A��葽���̎��v�������߂�����ŏ��i�J�������邱�Ƃ̓}�[�P�e�B���O�̊�{�ł��傤�B�̂́A���b�N�t�@�������ɓ��������悤�ȃs���A�E�I�[�f�B�I�@�킪���������̂ł��i���̂ւ�ɂ��Ă͐܂����ď��������Ǝv���܂��j�B�ł́A����Ƃ��X�������肢���܂�(^_^)�B
�@redfodera����A����ɂ��́B
�@�����ł��ˁA�O�̃X���b�h�ł��G��܂������A�������[�J�[�ɂ��u�f�U�C�������ɓ����Đ��i�����Ă邾�낤�Ɛ����ł���A�C�e���v�́A���̍��_������������Ă���Ǝv���܂��B�P�ɏ����������̂�����Ă݂܂����Ƃ������x���ł��傤�B�L��悤�ɁA����҂́u���E�ρv�������鏤�i�ɋ������o����̂��Ǝv���܂��B���Ƀs���A�E�I�[�f�B�I�@��́u���p�i�v�ł͂Ȃ��u��v�̗̈�ɑ�������̂ł��B�����������I�ȁu��v�ł͂Ȃ��A�N�ɂł��e���߂镔����������Ă�����ׂ��u��v�łȂ��Ă͂Ȃ�܂���B�I�V�����ȃC���e���A�ɂ������Ƃ����������́u��v�Ɠ���Ɉ���Ȃ��ƁA��ʃs�[�v���́u������v���猩�����Ȃ��ł��傤�B�u�P�i�̃X�y�b�N�E���\�ɋC�������}�j�A�v�����̔�����ł́A�ƂĂ����[�U�[�̐�����L�����Ȃ��Ɗ����܂��B
�@���Ƒ�Ȃ̂��u�����h�C���[�W�ł��ˁB������ONKYO��DENON���s���A�E�I�[�f�B�I�@����o���Ă���Ƃ����Ă��A�����͓����Ɉ����~�j�R���|����|���Ă���̂ł�����A�u�����h�̃A�s�[���x�͂قƂ�ǂ���܂���BBOSE�݂����Ɂu�����͍��Ȃ��v�Ƃ����|���V�[�������Ă����̃u�����h���l���Ǝv���܂��B�������AONKYO�́u�����v����DENON�́u�d���v�ł�����A������V�܂ł��ϋɓI��CI�������炢����K�v�͂���ł��傤�BTEAC��ESOTERIC�Ɩ��ł����悤�ɁASONY���ꎞ��ESPRIT�Ƃ����������o�����悤�ɁA���i���Ԃ����ۂÂ�����悤�ȃu�����h�̌`�����]�܂��Ƃ���ł��B
�@�u�Ƌ�v�e���r��X�e���I�A�̂͂�����������܂����ˁB���̓o�u������ɂ��������̂��������邩�Ɗ��҂��Ă����̂ł����A598�I�[�f�B�I�̏d�����剻�ɔ��Ԃ��|���邾���ɏI����Ă��܂��܂����B���̂ւ�A�ǂ������[�J�[�ƃ��[�U�[�Ƃ̃{�^���̊|���Ⴂ�������ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B
�������ɂ���̂́u���y�Ƌ��ɂ���L���Ȑ����v
�@���������u�����v���܂邲�ƃR���T���e�B���O���Ă����悤�Ȕ���������߂��Ă���̂�������܂���B�ł́A����Ƃ��X�������肢���܂�(^o^)�B
�����ԍ��F7932448
![]() 0�_
0�_
�F����A������������܂��B
�@
���E�������B
�@�ȑO�������̔ł��G�ꂽ�̂ł����A���{�Ƃ����y��܂�u�_�k�����v�͍����Â��ł���
�@���y�̋����A�⏬�ȏZ��A�Εׂȍ������A�����v�l�A�W�O�_��`�A���X��X���ӎ��E���ӎ�
�@�̓��ɑ���l���ɂ����̗l�Țn�D���炽�Ȃ����R������Ǝv���܂��B
�@���ʂ��C�ɂ����D���ȂƂ��ɉ��y���y���߂�u�I�[�f�B�I�E���[���v�uAV�E���[���v
�@������Ɏ��Ă�����ǂꂾ������ł��傤�H
�@���݁A���݂̃}���V�����ɏZ�܂��Ă܂����A��ʓI�ɍL�߂̊Ԏ��ł�������ł�����
�@�̗l�Ȋy���ݕ��͂܂��o���܂���B
�@���ߏ��ւ̔z����h�������R�ɏo���Ȃ��Z���ł͗ǎ��I�ɕ�炷�ɂ̓I�[�f�B�I��
�@���̎���甽�Љ�I�ȕ��ɂȂ鎖�����蓾�܂�����ˁB
�@�f�U�C���E���\�I�ɗD�ꂽ������낤�Ƃ�����̑Ώۂ͂ق�̈ꈬ��̐l�ɂȂ�܂��B
�@598�H���������I�ɔ��ꂽ�̂��u���{�v�ƌ����}�[�P�b�g�̐^�̎p�������������̂��H
�@���̔̊e����ʂ̏������ݓ��e�����Ă��]��ɒ�x���Ȏ��̌J��Ԃ��ł��B
�@�u�N���C�}�[�v���Ƃ����y��舕����錻��A���[�J�[���u�łɂ���ɂ��v�Ȃ�Ȃ����i
�@����葱����͑����悤�ȋC�����܂��B
�@
�@�u�v���p�@��v���g�����Ƃ͈ȑO����A�n�C�I�[�f�B�I�}�j�A�ɂƂ��Ă͈��S��ł���
�@����̃I�[�f�B�I�̍ŏI�ڕW�ł������Ǝv���܂��B
�@�����A�u�����g�v�Ə̂���l��ɂ͉��V�����ɏZ�݁A�D�ꂽ�f�U�C���̉Ƌ�Ɉ͂܂�
�@���̒��x�i�̈ꕔ�Ƃ��āu�V�A�^�[�E�V�X�e���v���C���[�W�A�b�v�̂��߂Ɏ��ʂ�
�@���킵�Ă��܂��B
�@���̗l�ȃI�[�f�B�I�EAV�X�^�C��������ł́u����v�Ȃ̂ł��傤�B
�@�����̉Ƌ�Ƃ��ăf�U�C�i�[���`���C�X����I�[�f�B�I�@���������ł��傤���H
�@���̂悤�ȌÂ��l�Ԃɂ͉ʂ����Ă�����u��̃I�[�f�B�I�v���H�ƔY�ޏ��ł��B
�@�����ɂ��A�掿�ɂ��S��̂Ȃ��ڂ���������ł��傤���ǂ�͂肻��́u�Ƌ�E���p�i�v
�@�̗ނƂ����v���܂���B
�@�f�U�C���E�����E�g�����肪�A�Ƌ�Ƃ��Ĕ����l�ɂ��A�I�[�f�B�I�t�@�C���ɂ�����
�@�o���鐻�i���o�ꂷ����͔@���ȕ��ł��傤�H���͂��̖ڂŌ��邱�Ƃ������悤��
�@�C���������܂��B
�@���I�Ș_�_�͂���̑ʕ��A�������������B
�����ԍ��F7933902
![]() 0�_
0�_
�F����A�������������܂��B
�l�I���W����
�������̉Ƌ�Ƃ��ăf�U�C�i�[���`���C�X����I�[�f�B�I�@���������ł��傤���H
�����������݂ɐi��ł���l����������������l�ł��ˁB
���z�v��t�H�[������肪����u�C���X�g�[���[�v�Ȃ�v�����i�[�^�A�h�o�C�U�[�������܂����B
����yAV�Z�b�g�A�b�v�́i��p���܂߁j���ɂ̌`�Ȃ̂ł��傤�B
�����܂ŗ���ƃI�[�f�B�I�ł���ł����ł��Ȃ��ĒP�Ȃ�n�E�W���O�E�v�����ł��B
�Ɠd�ƊE�Ɓi���t�H�[���j���z�ƊE�A�Ђ��Ă͕s���Y�̔��ƊE�̐V��̃r�W�l�X�ł�������܂���B
�P�������̋c�_�������܂����A�v�͔���邽�߂̕t�����l�̐����ł�������܂���B
�����ԍ��F7933975
![]() 0�_
0�_
redfodera����A������������܂��B
�@�I�[�f�B�I���Ԃ��d�C���g���A�Ζ��R�����g�����ƂŐ��藧����ł��B
�@�x���c�ŖO������Ȃ��l���}�C�o�b�n���̂́u�Ԏ�v�ł͖����ƍl���Ă܂��B
�@�ǂ̗l�ɉ҂������͕ʂƂ��Ă����ɕ������킹�������疜�~�̃I�[�f�B�I�Z�b�g��
�@����������ƌ����āu�I�[�f�B�I��v�ł������Ǝv���܂��B
�@�n�R�l�̂Ђ��݂ł����A�u�x�̏ے��v�Ƃ��Ă̋���Ƃ��Ắu��v�̈���B
�@�������y���ނ��Ƃɑ��l�����o���K�v�͑S���Ȃ��ł����A�ꌩ�h��Ɍ����邻�̗l��
�@���ۂ��u���ꂩ��v�ƌ����l�B�ɗ^����u���z���v�Ƃ��Ă͐r���u�����v�ɉ߂��܂��B
�@redfodera����Ǝ��̐����l�͗��ɒ[�Ƃ������܂����u�����v�Ƃ��Ă̊G�����̏�����
�@PC���j�^�[�̎��ʂ���ł��A�������邱�Ƃ��o����Ǝv���܂��B
�@���L�ł��銴�o�������̓��ɃC���[�W�ł��Ȃ����́u凋C�O�v������悤�ŁA�R���ł��B
�@�~�J�̒��x�݁A��������PC���`�F�b�N��itunes�̃N���V�b�N��BGM�Ɏ��ɂ̎��Ԃł��B
�����ԍ��F7934039
![]() 0�_
0�_
�@�l�I���W����Aredfodera����A����ɂ��́B
�@���͂Ƃ��ǂ��v���̂ł����A�̂�598�I�[�f�B�I�H���̗����͂����������������̂ł��傤���B�I�[�f�B�I�Ƃ����̂́u��v�ł������A������ɂ���u�e�l�̍D�݁v�Ɏ��ʂ��Ă䂭���̂��Ƃ͎v���܂����A����ɂ��Ă͑���葤���u�e�l�̍D�݁v�������悤�ȉ��I�Ȑ��i�������Ă��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B�����悤�ȃT�C�Y�œ����悤�ȊO���B�A���v�ނ͍���F�ŃX�s�[�J�[�͏d�ʋ����ɖ������Ă��܂����B�f�U�C���ʂł͉����i���͂���܂���B����ł��������͉��̋^����������قږ��N�i���܂�Ӗ����Ȃ��j���f���`�F���W����鐻�i�����Ă������̂ł��B
�@�O�ɂ��Ă�598�I�[�f�B�I�̃��[�U�[�ŁA���̓I�[�f�B�I���痣�ꂽ�m�l�B�̂��Ƃ������܂������A���������Δނ�͂��܂�s�̉��y�\�t�g�̏��L���͑傫������܂���ł����B�艿�x�[�X�ő��z30���~�߂����̃V�X�e���𑵂��Ă��Ȃ���ACD�i�܂���LP�j���S�����Ȃ������ł�����ˁB���̑���ƌ����Ă͉��ł����A�J�Z�b�g�e�[�v�̖{�������͂₽�瑽�������ł��B�������̓����^���X�����Ă������̂��_�r���O�������̂����S�ł����A�\�t�g�ɑ��Ă͂��܂�����|�������Ȃ��Ƃ����p�����~�G�~�G�ł����B
�@�������͎��̒m�荇���̘b�ł����A�Ђ���Ƃ����瑽����598�I�[�f�B�I�̃��[�U�[�������悤�ȏ������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����肵�܂��B�܂�A���y���D���ł��܂�Ȃ�������ǂ����Œ������߃I�[�f�B�I�Ɏ����߂��Ƃ������A598�I�[�f�B�I�Ƃ������̂����s���Ă��邩�炿����Ɣ����Ă݂��E�E�E�E�Ƃ������������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂����i�C�͈����Ȃ��A�J�^�M�̋ߐl�Ȃ�Ύ��R�Ɏg������͂��������������Ƃ���������p�����̂�������܂���B
�@���āA�u�����̉Ƌ�Ƃ��ăf�U�C�i�[���`���C�X����I�[�f�B�I�@��v�ł����A���͂��̂ւ�͊�����čl���Ă��܂��āA���ꂪ�~�j�R���|���邢��AV�A���v�Ŗ炷2ch�X�e���I�̉������㎿�Ȃ�A�f�U�C�i�[�哱�̃I�[�f�B�I�V�X�e���ł����Ă����������������s��ɑ傢�Ɏ������Ό�����}�V���ƍl���܂��B
�@������598�I�[�f�B�I���P�Ȃ�n�����������Ƃ��Ă��A�Ƃ肠�����ꎞ���̃g�����h���`�������Ƃ������Ƃ́A�����̃��[�U�[�������̃V�X�R�����͊m���ɉ����ǂ����Ƃ�F�߂�����ɑ��Ȃ�܂���B�����_�ł̓f�U�C���D��̋@�킪�u���s���m�v�ł��낤�Ɖ��ł��낤�ƁA�܂��͈�ʃs�[�v���Ɂu�~�j�R���|�����㎿�̃T�E���h���E�����݂���v�Ƃ������Ƃ�m�炵�߂邱�Ƃ���ł͂Ȃ����Ƌ��l���鎟��ł���܂��B
�@�܂��A�I�[�f�B�I�Ƃ����u��v�̕����ɂ́A�����ɓn�鏊���̑��ʂ��A�b�v�����邱�Ƃ��s���ł����i����͂ǂ̎�ɂ��Ă��ꏏ�ł��j�A���̘b��˂����ނƃ{�[�h�̎�|����͑�n�Y���ɂȂ�̂Ŏ��߂Ƃ��܂����ǁE�E�E�E(^^;)�B
�����ԍ��F7940205
![]() 0�_
0�_
�@�i�{���͑ʃl�^�Ŏ��炢�����܂� ^^;�j
�@70�N��㔼��DIATONE��F1�Ƃ����X�s�[�J�[���������Ƃ�����܂��B���Ђɂ͒������o�X���t�^�B��Ҍ����ɍ�����Ƃ���搂�����ŁA�f�U�C���͊p�`�̃o�X���t�|�[�g�����������ATV�A�j���̍��̃��{���v���N��������P�����������Ղ�̂��̂ł����B�艿��1�{47,000�~�Ȃ���A25kg�Ƃ����d�ʋ��B30cm�̃E�[�t�@�[�𓋍ڂ����A�܂��Ɂu�R�P�����v�Ƃ����`�e���s�b�^���̐��i�ł����B���͂Ƃ����A�@�ׂ��ȂNJF���ŁA�����W�������A�����Ђ�����O�֏o��h���V�����^�̃A�v���[�`�B���b�N�ȊO�͒����������Ȃ��A���̓O��Ԃ�ɂ͏��Ă��܂��܂����B
�@70�N��O����VICTOR��JA-S1�Ƃ����A���v�������[�X���Ă��܂����B���i��\39,500�ŃG���g���[�N���X�Ȃ̂ł����A���͂���܂��u�n�[�h���b�N�ȊO�͌��ցv�Ǝv�킹�钴�h���V�����B���ʂ�𑜓x���ǂ��̂Ȃ�Ă܂�ŊW�Ȃ��A���[�b�ƃK�i�����Ă�悤�Ȑ����̗ǂ���������ۂɎc�������i�ł����B
�@�I�[�f�B�I���Ηz�������������炱���A�����̂悤�Ȑ��i���o������ʔ����Ǝv���܂��B�܂�A���b�N��HIPHOP�Ɂu���S�Ɂv���������悤�ȃs���A�E�I�[�f�B�I�V�X�e���ł��B�~�j�R���|�Ƃ͎����̈Ⴄ�A��p�@��炵�����̓������h���V�����Ԃ���I����A���čs������҂͂������������Ǝv���܂��B���̂���̍s���Ă��A�N���V�b�N��W���Y��胍�b�N��HIPHOP�̕������X�i�[�̐�ΐ��͈��|�I�ɑ����ł�����B
�@PA�p�̋Ɩ��p�@��𑵂�����ꂱ���u���C���Œ������v�ɋ߂��Ȃ�̂�������܂��A�O�ɂ��������Ƃ���A��ʉƒ�ɓ����ɂ͖���������܂��BDIATONE��F1�݂����ȃR���Z�v�g�̐��i������A���b�N�t�@���͔�т��̂ł͂Ȃ����Ǝא����܂��B�������A���݂ł��I�[���}�C�e�B�ɖ点��悤�ȃL���b�`�t���[�Y���f���Ă��Ȃ���A����J-POP���������Ȃ��悤�ȍ������i�͑��݂��܂����A��������J�������āu���b�N��p�I�v�Ƒ啗�C�~���L���������A�s�[���x�͍����Ǝv���܂��ˁB
�@���ƑS�R�W�͂Ȃ��̂ł����AJA-S1���͂��ߐ̂̃X�e���I�ɂ́u�}�C�N�~�L�V���O��H�v�Ȃ���̂��t���Ă��܂����B�u�̎�ƃf���G�b�g�ł���v�Ƃ����G�ꍞ�݂ŁE�E�E�E�B������āA���ۂɂ�������Ċy���l�͂����̂ł��傤���B���̒m�l�Ȃǂ̓G���L�M�^�[��ڑ����ė��K�p�Ɏg���Ă����悤�ł����E�E�E�E�i�j�B
�����ԍ��F7940216
![]() 0�_
0�_
���E�������@
>PA�p�̋Ɩ��p�@��𑵂�����ꂱ���u���C���Œ������v�ɋ߂��Ȃ�̂�������܂���
���N3���A�Z���[�k�E�f�B�I���������h�[����9�N�Ԃ�̓��{���������܂����B���͂��̔ޏ���
��t�@���ł���ׁA1�����čs���ė��܂����B�ޏ��͂������v�����̃v���Ŏ��ɂ�������Ō�
�܂őS�͂ʼn̂��Ă���܂����B�E�E�E�Z���[�k�E�f�B�I���̃X�e�[�W�ɂ͊������܂������A��
��͂o�`���u�ł��B�����炭�u�G���N�g���{�C�X�v�̃X�s�[�J�[���Ǝv���̂ł������������I
�܂�����Hi-Fi����Ȃ��ł��B�ꏊ�������h�[���Ŗ{���u���y�����v��������ł͖����ł�
�ˁB��͂�O���ɃX�e�[�W�������Ċϋq�Ȃ����镁�ʂ̉��Ō������Ă��炢�������̂ł��B
(�����Ƃ����{�����͓����E��㍇�킹�ĂS�X�e�[�W�����ł�����4�`5���l�����ꂪ�K�v��
�����l�ł��B)
���̃X�s�[�J�[(�A���v�͕s��)�̈�S�������́A�����������Ă���������鎖����������
���Ƃł��B���ꂾ���͗��h���Ǝv���܂����B
���̌����̓Z���[�k�����ʼn̂��Ă���p������ꂽ�I�A�Ƃ������l�͏\���ł������������
�����130�C���`�X�N���[���Ńu���[���C�Ŕ�������Ă���Z���[�k�E�f�B�I���̃��C�u�X�e
�[�W�̃\�t�g������AV���u�Ō�������200���ǂ������m��܂���B
�E�E�E�����I�[�f�B�I���u�ɋ��߂鉹�́A���y��𑽐l���ʼn��t���Ă��鉹�ł��B(�܂�I
�[�P�X�g�������t���Ă��鉹�ł��B)�@�_�炩���g�����A�ł��N�����[�Ō��݂�����E�E�E�E
�z���g����ł��ˁB�ܘ_�A���̊y��̉����l�Ԃ̐���Hi-Fi�łȂ�������܂��E�E�B
PA���u���g�����y�́A��{�I�ɂ́u�d�C�ϊ��v��������܂�����Ƃ̃I�[�f�B�I���u�ł�����
�����o�邩���m��܂���B(���̗l�Ɏ���̑��u���g���������ǂ��I�I�Ƃق������肵�܂��B)
PA���u���g��Ȃ��A�R�[�X�e�b�N�Ȋy�킾���ł̉��t---��\�I�Ȃ��̂Ƃ���ƃW���Y�ƃN��
�b�V�b�N�̉��t��ł����A���ɉ��t�y��̑����N���b�V�b�N�̃I�[�P�X�g���͓��ł��B
�����ԍ��F7941338
![]() 1�_
1�_
�@130theater����A����ɂ��́B
�@�h�[���̂悤�ȏꏊ�ʼn��y�����Ƃ͎v���܂��A�r�b�O�l�[���ɂȂ��Ă���Ɗϋq���������҂����߂ǂ����Ă����������f�J���ꏊ�ł�邵���Ȃ��̂ł��傤���B���ꂩ��ĂɂȂ�ƃt�W�E���b�N�E�t�F�X�e�B���@�����͂��߂Ƃ��Ė�O�R���T�[�g�������Ȃ�܂����A����ς艹���ǂ��̂ƌ������u�D���ȃ~���[�W�V�����Ŋς�ꂽ�I�v�Ƃ��u����̃V���K�[�Ɠ����ꏊ�ɂ���ꂽ�I�v�Ƃ��������b�g���傫���̂��Ǝv���܂��B���������A�^�x�e�����̃��b�N�]�_�Ƃ��u�R���T�[�g�ɍs���Ă����邾���B�ƂŃf�B�X�N��ǍD�ȃV�X�e���Œ����Ă�������ǂ��v�Əq�ׂĂ����悤�ȋL��������܂����A�g�V����Ă���ƁA�ǂ������̃Z���t�ɏd�݂������Ă��܂��������̍��ł��i���j�B
�@�G���N�g���{�C�X��PA�X�s�[�J�[�͗ǂ��Ȃ������ł����B�R���T�[�g���Ƃ͈Ⴂ�܂����A���̏Z��ł���X�̒��ň�ԉ����ǂ��Ǝv����f��قŎg���Ă���X�s�[�J�[���G���{�C�ł����B�����Ƃ����̌���͌����S�̂ʼn����ɂ͔��ɋC�������Ă���r���̒��ɂ���A�T�E���h�ɂ��r���Ƃ��ẴR���Z�v�g���o�����ƕ��S���Ă���悤�ŁA�ʔ����Ɗ����܂����B�ʏ�̃V�l�}�E�R���v���b�N�X�Ƃ͂�����ƈقȂ�A�v���[�`�ł��ˁB
�@�I�[�P�X�g���̍Đ��͖{���ɓ���ł��B�E�E�E�E�Ƃ������A�^�����̂��e�Ղł͂Ȃ��ł��ˁB�^��背�[�x���̂悤�Ƀ}�C�N���S�̂悤�ɗ��Ăă~�L�V���O���܂�����@������ADENON��BIS�Ƃ��������[�x���݂����Ƀ}�C�N�̐����ŏ����ɂ��ă����|�C���g���Ɏd�グ�悤�Ƃ����s����������܂��B������ɂ���Đ����u�ɂ͑����ȕ���\���K�v�ł��B�������A�X�P�[�������o���ɂ̓X�s�[�J�[�̃T�C�Y���W���Ă��܂��B
�@�Z���[�k�E�f�B�I���̃��C�u�X�e�[�W�̃u���[���C�f�B�X�N�A����s�����I�[�f�B�I�t�F�A�Ńf������Ă��܂������A���E�摜�Ƃ������ł�����̂ł����B������S�����Ă������[�J�[�̃X�^�b�t���ޏ��̑�t�@���̂悤�ŁA��͂蓌���h�[���ł̃R���T�[�g�ɉƑ�3�l�ōs���������ł����A�q�����������Ďn�܂��Ă����ɖ��������܂����Ƃ��ŁA���̕��̃`�P�b�g�オ���ʂɂȂ����ƃ{�����Ă���܂����i�j�B
�����ԍ��F7944209
![]() 0�_
0�_
�@����4���ɑ����^�I�[�f�B�I�t�F�A�́u�n�C�G���h�v�Ƃ����t���[�Y�����ɕt���C�x���g�ŁA���̖��̒ʂ�e�Ђ̃n�C�G���h�@���������W������Ă��܂������A�W�܂��Ă����͓̂��R�����̃I�[�f�B�I�}�j�A����ł��B���Ȃ������Ă����̂͂����̂ł����A���ʁu����ł����̂��v�Ƃ��v���܂����B
�@�����Ȃ��}�j�A��ɂ�������A���i�̓~�j�R���|��W�J�Z��g�уv���[���[�ʼn��y���Ă����N�w�ɑ��Ă����A�s�[������悤�ȍÂ�����D�悵�ĊJ���ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���Ƃ��A���̎��͂̎Ⴂ�A���́AiPod���~�j�R���|�S�ʂɐڑ��\�ł��邱�Ǝ��̂�m��܂���BiPod���X�s�[�J�[�Œ����ɂ́uiPod�ڑ��Ή��I�v�Ɩ��ł����ꕔ�̋@��łȂ��ƃ_�����Ǝv���Ă���悤�ł��BiPod�̃C���z���W���b�N�����p�P�[�u����ʂ��āA���邢��Dock�̃��C���o�͂���RCA�P�[�u������ă~�j�R���|�̓��͒[�q�ցE�E�E�E�ȂǂƂ����u�|���v�ɂ͂܂����������̂悤�ł��B��x�����莝���́u�~�j�W���b�N->RCA�[�q�P�[�u���v���g����iPod���~�j�R���|�Ɍq���ʼn����o���Ă�����Ƃ���A�ڂ��ċ����Ă��܂����i���j�B
�@iPod�Ȃǂ̌g�уv���[���[����ǂꂾ���̃p�t�H�[�}���X�������o���邩��������A���ɂ��~�j�R���|�Ɨ����Ńs���A�E�I�[�f�B�I�V�X�e���Ƃ̒�����ׂ��������A�R���|�ɕt�����Ă���P�[�u���Ǝs�̃P�[�u���Ƃ̐��\�̈Ⴂ�𖾂炩�ɂ�����E�E�E�E�Ƃ������A�Ⴂ���X�i�[�ɂ��g�߂Ɋ������镪�삩��ςݏグ��C�x���g�������Ă������Ǝv���܂��B�u�n�C�G���h�v�Ȃ�ʁu���[�G���h�I�[�f�B�I�t�F�A�v�i�j�݂����Ȃ̂��J������A������ʔ����ł��傤�B
�@�������A���[�J�[���f�B�[���[���u�s���A�E�I�[�f�B�I�ƌg�уv���[���[�Ȃǂ̂���y�����@��Ƃ͕ʂ̎����̘b���v�Ǝv������ł���t�V������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ł́A�s��̔��W�͌����߂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7944219
![]() 2�_
2�_
�@�{����DENON�ɂ��ďq�ׂĂ݂܂��E�E�E�E�ȂǂƏ����Ɓu�L�T�}�͑O�̃X���b�h�ŁgDENON�ɂ��Ă͊S�͂Ȃ��h�Ƃ����Ƃ������Ă�����Ȃ����I�v�ȂǂƂ����˂����݂����邱�Ƃ̓X�O�ɗ\�z���t���܂����i���j�A�O��Ƃ̓X���b�h�̎�|�������Ⴄ�Ƃ������Ƃł����ي肢�����Ǝv���܂��B
�@1910�N�ɔ����������{�~���@����i�̂��̓��{�R�����r�A���j��1963�N�ɓ��{�d�C�����i���j���z�����������ۂɁA���̃u�����h�ł�����DENON�i�f���I���j�������p���A���Ђ̃I�[�f�B�I���i�̏��W�Ƃ������̂ł��B�䏳�m�̂悤�ɁA2001�N�ɓ��{�R�����r�A���番������A�i���j�f�m���Ə̂��Ă��܂��B
�@�l�I��DENON�̐��i�͍��܂ŃA���v2��A�J�Z�b�g�f�b�L1����g�p���Ă��āA���̃T�u�E�V�X�e���̃`���[�i�[��DENON���ł��B���łɌ����ƃ��C���E�V�X�e���̃��b�N�ɂ�DENON�̃}�[�N�������Ă��܂��B�������A���������������Ă���̂�DENON���̂ɂ͂قƂ�ǎv������͂���܂���B�l���Ă݂�ADENON�̐��i�����Ƃ��͂�������u����DENON���i���f���炵���C�ɓ������I�v�Ƃ��������w�����@�͑S�R����܂���ł����B�u�O�̋@�킪�Â��Ȃ����̂ŐV�����̂ɍX���������B�������A��]���i�тɂ͓��i�C�ɓ��������i�͂Ȃ��B�Ƃ肠����DENON�Ȃ�Ώ��Ȃ��Ƃ��C���ȉ��͏o�Ȃ�����A���ꔃ���Ƃ����v�Ƃ��������ɓI�ȗ��R�őI�ɉ߂��܂���B
�@����DENON�ɑ��Ē����ԕ����Ă���C���[�W�́u����v�̈ꌾ�ł����B�Ƃ肽�ĂĖ��͂͂Ȃ����A����ƂĔj�]����悤�ȓW�J�͂Ȃ��Ƃ����A�g���^�̎Ԃ��Z�C�R�[�̎��v�̂悤�ȁ|�|�|�Ƃ͂����Ă��g���^��Z�C�R�[�݂����ɃN�H���e�B�̊m�����ɗ��ł����ꂽ���̂ł͂܂������Ȃ��A�����܂ʼn��̖ʂł����|�|�|����������ۂł����B
�@�������A���ꂪ�ς���Ă����̂�2001�N�ɎЖ����u�f�m���v�ɂ��������肩�炾�Ǝv���܂��B����܂ł�����̐L�т͂��������ɁA�s���~�b�h�o�����X����̂Ƃ����K�x�ȃ����W���̒��ł̒����₷�����A�s�[�����Ă����Ƃ��낪����܂������A�ߔN�͂��̒��ቹ��̂̕��������ɒ[�ɔ�剻���A���������܂����W�J�ɂȂ��Ă��܂��i���F���������Ă���̂̓A���v��CD�v���[���[�ɂ��Ăł��B���Ђ̃X�s�[�J�[�Ɋւ��Ă͐̂��炸���Ƌ����͂���܂���j�B���ʁA�𑜓x�╪��\�͐����ƌ���֒ǂ�����Ă��܂��B�������A���������������D�ރ��[�U�[�����Ȃ��Ȃ����Ƃ͏��m���Ă��܂����A�𑜓x����ʂ����u�Z�����F�v��D�悳����������́A�������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�@����ł��A�A���v�Ō�����PMA-390�APMA-1500�ACDP�Ȃ��DCD-755�Ƃ������G���g���[�N���X�̐��i�́u���ɂ��܂�I�������Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł̑��݉��l�͂���܂��B���Ȃ��Ƃ������d���̃o�����X�́AMARANTZ�̂悤�ɍ���ɃN�Z�̂��鉹����̐��i�ɔ�ׁA�͂邩�ɔėp���������ł��B�������u�����N���X�ł̃A���v�ނ̃I�X�X���́H�v�Ɩ����A����DENON���i�𐄂��̂ɂ�Ԃ����ł͂���܂���B�܂��Ɂu����v�ł��B�������A10���~���郂�f���Ɋւ��ẮA�R�����g���������͂Ȃ��̂ł��B
�@DENON��MARANTZ�݂����ȁu�Z���F�t���v�̃A���v�ނ��肪�ڗ��̂͌����Ċ��}����邱�Ƃł͂���܂���B
�����ԍ��F7949698
![]() 0�_
0�_
�@����̓I�[�f�B�I�G���ɂ��ď����Ă݂܂��B�͎̂����悭�w�ǂ��Ă��܂������ǁA�ʔ����̂̓I�[�f�B�I���Ηz���������݂��G���̐����̂��̂͌��݂����܂�ς���Ă��Ȃ��_�ł��B�V�܂́ustereo�v����n�C�G���h�w���́ustereo sound�v���A�u�I�[�f�B�I�E�A�N�Z�T���[�v���Ȃǂ͍������X�̒I�̏�ł悭�������܂��B�������A�ς�����̂͂��̓��e�ł��B
�@�̂͌��̂���]�_�Ƃ���𑵂��A���Ɉߒ����ʕ������Ŏ��ʂ���킹�Ă������̂ł��B������[�J�[���������ރn�C�G���h�@���]���͂��܂����A����ł���ɔw�����������̂悤�ȁu�v�A�E�I�[�f�B�I�H���v���݂����j�[�N�Ȋ����U�����ꂽ�悤�ɋL�����Ă��܂��B70�N��㔼�́ustereo�v�����������A20���~�ő�����I�[�f�B�I�Ƒ肵�āA�g�ݍ��킹�̃��@���G�[�V������O��I�ɋl�߂����W��g�݁A�傢�ɍw���̎Q�l�ɂȂ������Ƃ��o���Ă��܂��B
�@�Ƃ��낪���̓q�h�����̂ł��B�ǂ��l���Ă���ʃs�[�v��������o�������ɂȂ����z�@���J�߂��₷�L������B�������i���]�����Ă��邩�Ǝv���A�����Ă���X�|���T�[�̏��i�ł��B����Ɗ̐S�̕]�_�������ۓI�Ȕ�����傪���S�ŁA�����Ƃ��w���̍ۂ̃A�h�o�C�X�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B
�@�I�[�f�B�I���D�҂������Ă��邽�ߍL���ŌЌ��𗽂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������X�|���T�[�̈ӌ��ɂ͐�t�炦�܂���B�܂��Ɂu�n��������A������Εn���v��n�ōs���悤�Ȋ����ł��B�L�����ڂ����Ȃ��K���[�W���[�J�[�̐��i�ȂA�����特���ǂ��Ă���ΏЉ��Ȃ��B���ʓI�ɁA����҂̖ڐ��ɍ��킹�����ʍ�肪����Ă��܂���B
�@����ƁA�͎̂Ⴂ���X�i�[���s���A�E�I�[�f�B�I�̐��E�ɃR���^�N�g��������̂Ƃ��āuFM�G���v�Ȃ�Ă��̂�����܂����B�G�A�`�F�b�N����̂ɉ��y�\�t�g�𑵂��Ă������[�U�[��������������ł�����A�܂��̓J�Z�b�g�f�b�L�̃��r���[����n�܂�A���X�ɑ��̃p�[�c���Љ�Ă䂭�Ƃ��������čs�����͎��Ɂu���S�v�ł����ˁB�������A�ڂ̋ʂ���яo��悤�ȍ��z���i�ȂЉ�Ă��܂���ł����B����Ӗ��A�Ⴂ���y�t�@���ɂƂ��Ă͏����̗ǂ������������̂�������܂���B
�����ԍ��F7954312
![]() 1�_
1�_
������������܂��B
�@�f�W�^����̕��̕����ł��傤�ˁB
�@�������N�A��҂́u�ԗ���v���������Ă��邻���ł��B
�@���̎Ⴂ���A�܂��~�������̕M���Ɏ��Ɨp�Ԃ��������ł����A���̈ڂ낢�͑僁�[�J�[��
�@�u�}�[�P�b�g�E���T�[�`�v�ł��͂ނ��Ƃ͏o���Ȃ��ƌ������ƂȂ̂ł��傤�ˁB
�@�����g�A�I�[�f�B�I�Ɍ����Č����ƁuWalkman�v���䓪���Ă������Ɏ�N�w�̃I�[�f�B�I
�@�����������x�\�����邱�Ƃ��o���܂����B
�@PC�E�l�b�g�Eipod�ށE�g�т������܂ŐZ������Ƃ͑z���ł��܂���ł������B
�@�A�i���O�ł������̂́u���s����v�����[�J�[�E�]�_�ƁE���[�U�[�̎O�҂ŋ��L�ł���
�@����������葽�������̂ł́H�ȂǂƂ��l���܂��B
�@�u�������E�����E�C�y�v�̃L�[���[�h�œ������i�������A�u�����v���鎖���o���镨
�@�����L���邱�ƂɁu�Ӌ`�v�����鎞��ł�����ˁB
�@���\���~�̎��{�����Ɂu������Ȃ��v���ʂ����܂Ƃ��A�I�[�f�B�I�ɍs�����A
�@�����Ă������~�A�R���N�V�������u�_�E�����[�h�v�A�����͈�@�R�s�[���邾����
�@�\�t�g�́A�u�{�v�ł��邱�Ƃ����Œ������L���邱�Ƃ��l���ɂ͓���Ă��Ȃ��B
�@�u�\�t�g�v�u�n�[�h�v���ʂʼn��y�ƊE�̐��ނ�������Ă��炾���Ԍo���܂��B
�@���E�������̋�u��ʃs�[�v���v�ւ̃I�[�f�B�I�̐�s���͂��Ȃ�É_��������
�@�Â����������ĂȂ�܂���B
�@�ǂ����i����������I�[�f�B�I���[�U�[�̒�グ���o���Ȃ��̂��A�I�[�f�B�I�Ƃ�
�@�������ꂽ�l�B���������߁A�ǂ����i�����Ȃ��̂��u���Ɨ��v�ł��ˁB
�����ԍ��F7955647
![]() 2�_
2�_
�@�l�I���W����A����ɂ��́B
�@���{�l���Ă̂́A���͉��y���D������Ȃ��̂ł��B
�@�������A���̌f���Ƀ}�W���ȍw���̑��k�̃X���b�h�𗧂Ă�l�����̑�����A����ɑ��ăt�H���[�����A�����i�^�������� ^^;�j�̖ʁX�͉��y���D���ł��܂�Ȃ����Ƃ͕�����܂��B�����Ď��ۂɊy�����ɂ��Ă���l�X�A���y�ƊE�œ����Ă���ҒB�͉��y�Ɏv�����ꂪ�Ȃ��Ƃ���Ă����܂���B�������A����ȊO�́A���̒��̈��|�I�����h�͉��y��\���I�ɒ������Ƃ��Ȃ��l�����ł��B
�@�كu���O�ɂ������܂������A�ȑO�uJ�|�b�v�Ƃ͉����^���剻���鉹�y�Y�Ɓv�Ƃ����{��ǂ��Ƃ�����܂��i���҂͌������V���ЋL�҂Ō��t���[�W���[�i���X�g�̉G��z�O���j�B���̒���J-POP��CM��h���}�Ƃ̃^�C�A�b�v�ɂ�苻�����Ă������Ƃ��Ƃ��w�E����Ă��܂��B���݂͂��ꂪ�A�j���̎��̂�P�[�^�C�̒������Ȃǂɕς���������ŁA���ׂĂ��g���d�����h�Ȃ̂��Ƃ̃j���A���X�ŏ�����Ă��܂��B������CM��h���}�̃^�C�A�b�v���Ȃ���A�����̐l������CD��Ȃ����A�y�Ȃ̃_�E�����[�h�����Ȃ��ł��傤�B�g�����ʼn��y��T���y���݁h�Ƃ͉������A�Ђ�����e���r������̈���I�ȏ��ɓ���Z��BCD���̂��g�������D��������h�ł͂Ȃ��g�݂�Ȓ����Ă��邩��h�Ƃ����P�Ȃ�g�����ъ��o�h�ɂ��Ƃ��낪�傫���悤�Ɏv���܂��B
�@���������\���I�ɉ��y���Ă���͂��̃I�[�f�B�I�t�@���ɑ��Ă��A�S���ʔ����̂Ȃ����i�i���ɃX�s�[�J�[�j�����ł��Ȃ����[�J�[�����X�Ə������Ă����鍑�̏Z���ɁA���y�D���������Ƃ͎v���܂���ˁB���̂��Ƃ�[�I�Ɏ����̂��A�䂪���ɂ͉��ĂƔ�r���ă��W�I�ǂ���i���Ƃ��ċɒ[�ɏ��Ȃ����Ƃ��������܂��B���ɖ������W�I�ǂ͋��ɂ��t���Ȃ��g�[�N�Ɠ����悤�ȋȂ����������A����ɑ��Ē���҂��傫���ق��������Ƃ����b�������܂���B
�@�����̐l�ɂƂ��ĉ��y���u�v������̑Ώہv�ł͂Ȃ��ȏ�A���y���ꎩ�̂����̃��x���Ɍ��������悤�Ȏ����ɗ���������������܂���B�q�b�g�`���[�g����킹�Ă��鑽����J-POP�̊y�Ȃ��ς��f�����Ȃ����Օi�Ƃ��ẴN�H���e�B�����������킹�Ă��Ȃ������͗h�炬�悤���Ȃ��̂ł��B
���u�������E�����E�C�y�v�̃L�[���[�h�œ���
�����i�������A�u�����v���鎖���o���镨��
�����L���邱�ƂɁu�Ӌ`�v�����鎞��ł�
�@�ǂ���炻�̂悤�ł��B�v���C�x�[�g�ȗ]�ɂ��̗̈�ɂ��u�����шӎ��v���͂т����Ă��܂��B�����Ă���͒i�X�ƌ����ɂȂ��Ă����悤�ŁA�I�[�f�B�I�Ɍ��炸���蕪��ɑ��Ěn�D�����҂��u�I�^�N�v�������Čh������X���́A�Ȃ��Ȃ������Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�@�E�E�E�E�ł��A�����������ߊϓI�Ȃ��Ƃ���������Ă��d��������܂���B�I�[�f�B�I�̑����ɂ́u���y�͑f���炵���v�Ƃ���������O�̖���������ƕ��Չ�������悤�ɓw�͂��Ă��炢�������̂ł��B
�����ԍ��F7958448
![]() 0�_
0�_
���E�������A�͂��߂܂��āA�����́B
�O�҂���A�����[���q�������Ē����Ă���܂��B
�ƂĂ����ɂȂ�܂��B�L�Ӌ`�ȃX���b�h��L���������܂��B
�v�킸���Â�DIATONE���w�����A���̒m�V��̌����Ă��܂������ł���܂��B
��Ⴂ�����m�ŁA��������Q�������ĉ������B
�����́u�ǂ�����ׂ����v�Ƃ����̂́A�Ηz�������s���A�E�I�[�f�B�I���ǂ�������痧�Ē����邩�Ƃ������Ƃ����C���ɂ��܂��B
�����{�l���Ă̂́A���͉��y���D������Ȃ��̂ł��B
���I�[�f�B�I�̑����ɂ́u���y�͑f���炵���v�Ƃ���������O�̖���������ƕ��Չ�������悤�ɓw�͂��Ă��炢�������̂ł��B
�g���y�h�̊y���ݕ��́A�ЂƂ��ꂼ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�u���y�́A�ӏ܂�����A����ق����y�����B�v�Ƃ������o�̕����A��蕁�ՓI�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�I�[�f�B�I�ӏ܂Ƃ����`�ɌŎ����Ċy���ޕK�v�͖����킯�ŁA�ӂƂ������ɕ@�̂��ł���A�J���I�P�Ő���オ������A�Z�b�V�������y����A���t��Řr�O���I������c�B
�܂��A���郁���f�B���ƁA�L�����Ăъo�܂���āA�y����������߂���������c�B
�s���A�E�I�[�f�B�I���y����ł���l�����A�s�A�m��o�C�I������e�i�[�T�b�N�X��̂�_���X�⎍������y����ł���q�g�̕������|�I�ɑ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������n���āA�e�ʒ��Ő��𐔂��Ă��A�s���A�E�I�[�f�B�I����ɂ��Ă���͎̂����炢�ŁA�s�A�m�̐搶�i������o���v���j�P�l��M���ɁA�s�A�m��e���ЂƂT�l�i�����q���R�l�j�A�o�C�I������e���ЂƂQ�l�A�g�����y�b�g�𐁂��ЂƂP�l�A�I�y�����̂��ЂƂP�l�A����P�l�i�̐l�j�A�J���I�P���D���Ȑl���̑��吨�A�Ƃ�����ł��B
�u���y�͑f���炵���B�v�Ƃ���������O�̂��Ƃ́A����ς蓖����O�ŁA���܂��疽��Ƃ��čĔF��������̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�������ł��傤���B
�s���A�E�I�[�f�B�I�Ƃ����Ă��A���ɂ̖ړI���A���F�A�u���l�̉��������t���A����ōČ����A�ӏ܂���B�v�Ƃ����C���E�h�A�ȁA�{���I�ȈӖ��ŃN���G�C�e�B�u�Ƃ͌�������̂ł�����A������ӂ̏����킫�܂��Ă��Ȃ��ƁA���܂ł����Ă��}�C�i�[�Ȏ�ŏI����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�u�s���A�E�I�[�f�B�I�͑f���炵���B�v�Ƃ����}�C�i�[�Ȗ���ɂ��Ȃ����q�g�̐���@���ɑ��₹�邩�H�������A���̃X���b�h�̎��ł͂Ȃ����Ƃ������_���m�F�������Ǝv���܂����B
�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`
�s���A�E�I�[�f�B�I�����̂��߂ɁA�����₩�Ȃ���A�ƂĂ��厖�Ǝv���銈�����s���Ă��܂��B
����ς�A�q�������ɉ��y�̊y������`���邱�ƁA�����ʼn���̂��A�v���̉��t���i����Łj�����̂��y�������A�Ƃ����킯�ł��B�����̃I�[�f�B�I�ōD���ȃ\�t�g���K���K���炵�Ă܂��B
�䂪�q�R�l�ɑَ��̎����炵�����������Ă��܂��̂ŁA������͗��h�ȃI�[�f�B�I�}�j�A���v���[���[�Ɉ�ɈႢ����܂���B�c�����̐e�o�J�ł��݂܂���c
�R�l�̃E�`�Q�l�́A�W���Y��������ƃm���m���ł��B
�P�l�́A�s�A�m�Ńo�C�G���n�߂Ă��܂��B
�����A�����A����v���܂����B
�����ԍ��F7961854
![]() 0�_
0�_
�@��H�̓e����A����ɂ��́B�������݂��肪�Ƃ��������܂�(^^)�B
���g���y�h�̊y���ݕ��́A�ЂƂ��ꂼ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@����͕�����̂ł���B�ł����{�̏ꍇ�A���y�̊y���ݕ��́g�l���ꂼ��h�ł���͂��Ȃ̂ɁA�ǂ����ăq�b�g�`���[�g�ł͓����悤�ȋȁA������CM�Ŏg��ꂽ�i���o�[��e���r�ԑg�̎��̂Ȃ����𗘂����Ă���̂ł��傤���B�Ȃ��Ƀ��W�I�ǂ̐������̐�i���Ɣ�ׂċɒ[�ɏ��Ȃ��A����������悤�ȋȂƑދ��ȃg�[�N���藬���Ă���̂ɒN�����������Ȃ��̂ł��傤���B
�@���u�X�[�p�[�J�[�v�̍쎌�E�M�^�[�S���̂����킽��~�������o�G���^�e�C�����g����Łu������J-POP�͐��������ƒN�̋Ȃ��킩��Ȃ��B���̏�Ⴄ�����B�������ŃT�r���艽��������Ă���Ƃ��̂������y�������ɂȂ�v�Əq�ׂĂ��������ł����A����������܂��B
�@�e���̉��y�l���̐��Ƒ��l���ɑ��銄���ɂ��Ẵf�[�^�͌������܂��A���܂ɉ��Ăɑ����^��ł݂�ƁA���{�Ɣ�ׂĎv������������ĉ��y�ɐڂ��Ă���w���������ƂŊ����܂��B���Ƃ��y��ɐG���Ă͂��Ȃ��Ƃ��A�N�������y�ɑ��Ĉ�ƌ�����悤�Ȉ�ۂ��܂��B���Ȃ��Ƃ��A�����J�ł́gCM�\���O���肪�q�b�g�`���[�g�̏�A�h�Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B
�@�y�퉉�t����Ƃ��Ă���ҁA�����c�ɓ����Ă���ҁA�����̐l�����͂�����y��S���爤���Ă���͂��ł��B�ł��A���������l�����̑Α��l���̔䗦�Ƃ��Ă͓��{�͉ʂ����đ����̂ł��傤���B���̎��͂����n���Ă��A���y���g��h�Ƃ��Ă���҂͊��S�ȏ����h�ł��B�قƂ�ǂ̎҂͉��y�Ȃ�Ă��������ɁA�}�[�W������S���t�Ȃɋ����Ă���̂ł��B
���@�̂��ł���A�J���I�P�Ő���オ������A
�@��Ȃ���w���ȕ\���ŋ��k�ł����A�@�̂�J���I�P�́g�I�Ȃ��́h���Ɗ����܂��B�ǂ����Œ������Ȃ�䍂��Ă��邾���ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ōD���ȋȂ�T���Ƃ����g�\���I�ȑԓx�h�Ƃ͂�����ƈႤ�Ǝv���Ă܂����A������A�}�`���A�ł��A������x�̋Z�I�I�Ȑ��ʂ����߂���y�퉉�t�⍇���Ƃ͎������قȂ�܂��B
�@���͓��{�l�̒��Ŗ{���Ɂu���y�͑f���炵���v�Ǝv���Ă���҂͂���Ȃɑ����Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�������A���y�������Ȑl�͂��܂肢�Ȃ��ł��傤���A�L���C�ȃ����f�B������Ă���ΒN�����u���������ȁv�Ǝv���ł��傤�B�ł��A���ꂩ�����������ݏo���āA�����Ŋy�����ɂ�����A�����Ɨǂ��Ȃ�D���ȃ~���[�W�V������T������Ƃ������\���I�ȗ̈�܂ōs���҂͂ǂꂾ�����邩�E�E�E�E�B�ɒ[�Șb�ACM��e���r�ԑg�ɃV���O���J�b�g��O��Ƃ����y�Ȃ��g��ꂸ�A�S��BGM�I�Ȍ��ʉ���C���X�g�D�������^���Ȃ��肾������ACD�̔���グ�͌������A�y�Ȃ̃_�E�����[�h���₵�����̂ɂȂ�Ɨ\�z���܂��B
�@���͉��y�ɑ��Ĕ\���I�ȃX�^���X�����҂𑝂₷���Ƃ��s���A�E�I�[�f�B�I��������g�����h���Ǝv���܂��B�������A���y�t�@�����S���s���A�E�I�[�f�B�I�ɍs���͂�������܂���B�y�퉉�t�Ŗ�������w�������ł��傤�B�I�[�f�B�I�V�X�e���ɋÂ�̂́A���̈ꕔ�ɉ߂��܂���B�������g�s���A�E�I�[�f�B�I�\���R�h�͊m���ɑ����܂��B
�@�̂͂��̂��Ƃ����[�J�[���i�ӎ��I�Ȃ̂����ӎ��I�Ȃ̂��͕s���ł��� ^^;�j�������Ă����悤�ŁA���Ƃ���Lo-D�u�����h�Ŋ撣���Ă��������͕p�ɂɃ��R�[�h�R���T�[�g����Â��Ă��܂����B����ɖ��@���W�I�ǂ̉��y���ԑg�̃X�|���T�[�ɂ��Ȃ��Ă��܂����B���ł͎��Ȃ̃u�����hAurex���������N���V�b�N�R���T�[�g���X�I�ɓW�J���Ă��܂������A�O�H��DIATONE�̖��O�����ɕt����FM���y�ԑg�����Ă���܂����B�y�탁�[�J�[�ł�����YAMAHA�̓w�͂͌����܂ł�����܂���B
�@�Ƃ��낪���������{����s���Ă����͉̂Ɠd���[�J�[�Ȃǂ́u�V�܂̃I�[�f�B�I��僁�[�J�[�ȊO�̊�Ɓv�ł��B�̂Ȃ���̃I�[�f�B�I��僁�[�J�[�͂��̂ւ������Ă��Ȃ������ƌ����A�ڋq�̐�����L����w�͂�ӂ��Ă��܂����B�Y�ƍ\���̕ω��ɂ��Ɠd���[�J�[���I�[�f�B�I����P�ނ������݁A���̃c�P����C�ɉ���Ă����Ƃ��v���܂��B������ł��x���͂���܂���B�e�������[�J�[�͉��y�C�x���g�����������Â��A���y���ԑg�̃X�|���T�[�ɂȂ�A�@����g����CD�V���b�v���Łg�c�Ɓh������A�w�Z�̉��y�̎��Ƃɔ�ѓ��肵�ăV�X�e���̃f�����������Ɓi������͖����� ^^;�j�A�Ȃ�ӂ�\��ʁg�z�������i�H�j�h�ɋ���ŗ~�������̂ł�(^o^)�B
�����ԍ��F7966619
![]() 0�_
0�_
�@����̓f�B�[���[�ɂ��ďq�ׂ܂��B�ʋΌo�H�̓r���ɉƓd�ʔ̓X������A�悭�I�[�f�B�I�R�[�i�[��`���܂��B�������܂ɂł����A���̓X�ł̂�����Ƃ����i�I�[�f�B�I���i�ȊO�́j�������̐܂�Ɏ��������Ă��炤���Ƃ�����܂��B���Ƃ�莎�����̈����ʔ̓X�̂��Ƃł�����A�e���i�́u�^�̎��́v�Ȃ�Ă̂͌����܂���B�����悻�̉��F���`�F�b�N����ɗ��߂Ă���̂ł����A����������o���Ă���X���̃Z���t�́A���e�̔����Ƃ������炠��܂���B���u���̃u�����h�͌��������H���v���́u���̐��i�́����Ƃ����W�������͐�Ζ点�Ȃ��v���́u���̃A���v��××�Ƃ�����H�����爳�|�I�ɑ���艹���ǂ��v���́A�u�߂��������܂��B����Ȃ��Ƃ́A�������������̂��Ƃ͕�����܂��B�����������₵���Ƃ����������Ă��������̂ł��B�E�E�E�E���Ƃ����āA������̎���ɂ܂Ƃ��ɓ����Ă��ꂽ���Ƃ͂���܂���B���Ƃ��u�A�i�^�����߂Ă��遛���Ƃ������[�J�[��××��H�Ƃ������̂ƁA�ʂ̃��[�J�[�́�����H�Ƃ̈Ⴂ�́H�v�Ɛq�˂Ă݂���A�r�[�Ɍ��Ă����Ă��܂��B��{�I�ȏ��i�m���̂Ȃ��҂��A���C�Ŕ����ɗ������Ă���B���̐_�o�ɂ͗��������������̂�����܂��B
�@�ꕔ�����E�̓I�ɂȂ��Ă���u���[�J�[�h���̔����v�ɂ������܂��B����̃��[�J�[���菧�߂�̂́A���ʓI�Ɍڋq�̏��i�I��͈͂����߁A�s���v�ɓ����\��������̂ł����A�X���͈ӂɉ�Ȃ��悤�ł��B
�@�Ɠd�ʔ̓X�̃��x���͕��������A�ł͐��V���b�v�Ȃ炢���̂��E�E�E�E�Ƃ����ƁA��������S�ł͂���܂���B��Ԃ̓�_�͕~�����������Ƃł��B�Ɠd�ʔ̓X�Ȃ�Α��̉Ɠd���i�F������łɃI�[�f�B�I�����ւ��s���܂����A���X�͕����ʂ�I�[�f�B�I���i�����u���Ă��炸�A����̂ɗE�C���v��܂��B�������������ȋ@�킪�������W�����Ă���̂��O���猩�����肵�āA�n�C�G���h���[�U�[�ł��Ȃ���ʐl�͉��E���Ă��܂��ł��傤�B����Ɉ������Ƃɐ��X�͗ǂ����������|���V�[�������Ă��܂��B���̃|���V�[�Ƌq�̍D�݂����Ă�������̂ł����A�܂�ō���Ȃ��ꍇ�͓X�ɂ��邱�Ǝ��̂���ɂɂȂ�܂��B
�@���܂��玎�������������i�\���������Ɠd�ʔ̓X�Ɋ��҂��Ă��d�����Ȃ��ł����ǁA���Ȃ��Ƃ����X�͂����ƕ~����Ⴍ����w�͂����Ă������ł��傤�B�܂��A�H�t������{���̂悤�ȁu�d�C�X�v�ɂ�����V���b�v�ɗ���q�͍ŏ�����ړI�����邩�炻��ł����̂�������܂��A����ȊO�̒n��ɓX���\���Ă���f�B�[���[�́A�ꌩ����̋q��߂܂��邽�߂ɍH�v����]�n�͂�����ł�����Ǝv����ł����ǂˁB�u�ǂȂ��ł����C�y�ɂ����艺�����B�ǂ����y�����Ă܂��v�Ƃ��������ĊŔЂƂp�ӂ��邾���Ő����Ⴄ��Ȃ��ł��傤���B
�@���ƁA�������u�����C���Ȃ��Ȃ玎������ȁv�ƌ�������̑ԓx�i���ۂɌ��ɏo���P�[�X������܂��� ^^;�j�͘_�O�ł��ˁB�u��₩���劽�}�I�v�Ƃ�������g�Ȏp���������Ȃ���A�ڋq�J��͓���ł��傤�B
�����ԍ��F7966633
![]() 0�_
0�_
���E�������C�݂Ȃ���C�ƂĂ��y���݂ɔq�����Ă���܂��B
���āC���E�������́u���̓��{�ɂ́C�{���̉��y�D�������Ȃ��B�v�Ƃ��������ӌ��C�ƂĂ������镔���������ł��B
���y���D���ōD���ł��܂�Ȃ����炱���C�������Œ��������Ƃ����C�P���Ȕ��z�ł͂���܂����C�������͂�������������ŁC���̎���ɂ������͂Ȃ��ł����C����ȗF�l�͂��܂��B
�������Ȃ���C�s���A�E�I�[�f�B�I����Ƃ���Ă�n�C�G���h�@�탆�[�U�[�̕��ł����Ă��C���y���̂́C���܂蒮���Ă����Ȃ������C���̉ߋ����v���o���Ă����l��������Ⴂ�܂����B
������ł����C���܂ŋ@��ɂ����Ă������z�͐��疜�I�E�B���\���̃��S���~�̃X�s�[�J�[���傫�����X�j���O�E���[���ɒ������Ă���܂����B�@�Ȃ̂ɁC�\�t�g�Ƃ����CLP�CCD���킹�Đ��S�����x�B�V����SACD�Ղ���Ȃ��Ɣ���Ȃ��Ƃ��B
��̉����邽�߂̋@��Ȃ̂��ƁC�����^��������܂��B
������C���̗F�l�̒���8000��(�������Ǝv���܂�)�ȏ�̃\�t�g���������̕��Ȃ̂ɁC�I�[�f�B�I�́C���L�@���70�`80�����x�̂��́B����ł�����ɂ��ז�����ƁC�Z�b�e�B���O����������ϋl�߂āC�f���炵�����Ŗ炵�Ă�������Ⴂ�܂��B���ɂ��Ă��߂��Ⴍ���Ꭸ�̂������ŁC
�u�ŋ߁C�X�s�[�J�[�̃Z�b�e�B���O�����ς�����𑜓x���A�b�v���ĂˁB�ق�C�r�b�O�o���h�̃T�b�N�X���C������4�l�̂Ƃ���5�l�̂Ƃ��̈Ⴂ���킩��ł���B�v
�r�b�O�o���h�̒��ŁC�T�b�N�X��4�l��5�l�����C������������I�[�f�B�I�E�}�j�A�̕����Ăǂꂭ�炢�C����������ł��傤���H
���̂悤�ȕ����C�{���̉��y�D�����I�[�f�B�I�D���ȂȂ��Ɗ��S������ꂽ����ł��B
�n�C�G���h�@��̕��Ƃ͂��������ł������C������̕��Ƃ́C���y���I�[�f�B�I���ԂƂ��āC�������ǂ��������������Ē����Ă鎄�ł��B
�����ԍ��F7967779
![]() 0�_
0�_
���E�������A���J�ɑΉ����ĉ������܂��āA�L���������܂��B
�ƂĂ������A�h������܂��B
�����܂ɉ��Ăɑ����^��ł݂�ƁA���{�Ɣ�ׂĎv������������ĉ��y�ɐڂ��Ă���w���������ƂŊ����܂��B
���y���Ă���u���y�̋N���v�̖�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�N���V�b�N���W���Y�����b�N���A���{�l�ɂƂ��Ă͑S�ėA���i�ł��B
�g�̂̒�����A�����̒����玩�R�����������̂ł͂Ȃ��A�w���́A�w�Ԃׂ����́A�Ƃ����Ƃ��낪���Ă̈�ʃs�[�v���Ƃ̈Ⴂ�����m��܂���B
�t�ɁA���{�l�قǁA���E���̉��y���C�y�ɑ�ʂɗA�����āA����Ȃ�Ɋy����ł��܂��������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�@���A�N�w�ɍ��������e�����h���̉��y���A���܂�[���l�����ɁA�ǂ�~�ɋz�����A�ǂ�ǂ����Ă����ۂł��B
�b�͏�������܂����A���̏Z��ł���X�ɂ́A��Ă���d���ɗ��Ă�����X�����\�����āA���l���̂T���ʂ��߂Ă��܂��B���ڂ̂�����������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�s���m�ȏ���m��܂��A�ނ�̑����́A���e���ȉ��y�����W�J�Z�ŃK���K���A�ł��B
�����𗣂�ĎR���̏���ɐ��V�тɍs���A��̂����炬�Ⓓ�̖��������\�c�Ǝv������A���e���ȉ��y���K���K���炵���S�Ƒ����炢�̒c�̗l���������`�Ƃ������Ƃ�����������܂���B�����܂��A�Î�Ȕ_�������I�̃J�[�j�o���i�H�j��Ԃł��B
�g�̂Ƀ��e���ȉ��y���g�ݍ��܂ꂽ�ނ�ɁA���{�l�̍D�ށg�Î�Ƃ������y�h���y���ދC�͖ѓ������킯�ł����A�ǂ�����A���y���y����ł��邱�Ƃ����͊m���ł��傤�B�����Č����A���{�l�̓V�`���G�[�V�����ɉ����āA�Î�A�N���V�b�N�A�W���Y�A���e���ȉ��y�A���b�N�����[���A���́A�Ɖ��ł��L��ł����A��Ă̕��X�͎��������̉��y��{���ȂƂ��낪�Ⴄ�Ǝv���܂��B
�`�E�`�E�`�E�`�E�`
�s���A�E�I�[�f�B�I���Ȃ����y���Ȃ��̂��H
���̌�y�ɔ�ׂāAC/P���ǂ��Ȃ����炾�Ǝv���܂��B
�e���[�J�[��f�B�[���[�̕z�������ɖ��͂��Ȃ����Ƃ��������ł����A��ʂ̋��K���o���炷��ƁA�Ƃɂ������������ۂł��B���y���i�т̏��i�͉��ɖ��͂��Ȃ����A���ɖ��͂��o�Ă��鉿�i�т͂��łɈ�ʐl�͒N�����Ȃ��Ȃ�����Ԃ��Ǝv���̂ł��B
�����O�ɂȂ�܂����A����G���ŁA��i���Ŏ��Ɨp�Ԃɂǂꂭ�炢�̃R�X�g�������邩�̔�r������܂����B���Ăł͔N���̂Q�O�����������ϓI���Ƃ����܂��B�N���P�O�O�O���~�Ȃ�Q�O�O���~�̎ԁA�N���S�O�O���~�Ȃ�W�O���~�A�Ƃ�����ł��B���L���Ă���Ԃ��炨���悻�̔N���������ł��邭�炢�A�������肵���g�������̕�炵�����Ă��邻���ł��B
���{�ł́A���ς��Ƃ�ƔN���̂Q�T�������ŁA���E�I�Ɍ��Ă��ԍD���ȍ������Ƃ����]���ł����B���ĂŔN���̂Q�T�������̎Ԃ��Ƃ��Ȃ�̎ԍD���A�R�O�������ɂȂ�Ɗ��S�ȃ}�j�A�A�Ƃ����]���ɂȂ邻���ł��B�ނ�ɂ��Ă݂�A���{�ł͒������Ȃ����Ƃł����A�o�C�g�N���P�O�O���~���炸�̊w�����R�O�O���~�̃X�|�[�c�J�[�����A�Ȃ�Č����̂̓N���[�W�[�Ȃ��ƂȂ̂ł��B
�I�[�f�B�I�@��ɁA�N���̉��������������邩�H
���{�ł́A�P�`�����������Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B�P�O���������ނ̂́A�N���[�W�[�Ȃ��Ƃł��傤�B�N���T�O�O���~�ŁA�T�`�P�T���~�Ƃ����Ƃ���ł��B�܂Ƃ��Ɏ��g�ށi�s���A�E�I�[�f�B�I���n�߂�j�ƁA���������X�s�[�J�[�P�{���炢���������܂���AiPod��R���|�A���W�J�Z�ŏ[���A�ƂȂ�̂��d���Ȃ��킯�ł��B
�����@�B��iPod���P�|�R���~�ŁA�����ȃ��x���ʼn��y���y���ނ��Ƃ��ł���̂ɁA�s���A�E�I�[�f�B�I�Ƃ�����ɍs���Ƒ��̃P�[�u���i�d���j���P�\�R���~������̂ł́A��ʃs�[�v���i�E�`�ɂ�����܂�������b�j���猩��ƁA��������킳���悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B
�g�[�^���T�|�Q�O���~�̃s���A�E�I�[�f�B�I�V�X�e���ŁA�����̃n�C�G���h���R�U�炷�ʂ́g���̃N�I���e�B�h�����������i���܂�����ĕ��y������A�Ƃ������K���o����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�i�^ProCable�́AiPod�{�N���E��D45�{EV FORCE i������́A���i�т̃R���Z�v�g�Ƃ��Ă͂����Z�������Ă���Ǝv���܂��B�j
�����ԍ��F7967881
![]() 0�_
0�_
�{���ɋC�ɂ����������Ȃ��\�t�g���A�ō��̉��Ŗ炷�h�B
�Ƃ肠�����\�t�g�����������āA�Ƃ肠�����������OK�h�B
�ǂ����������̂�����Ȃ����ǁA�\�t�g���ِ��ɗႦ��Ζʔ����ł��ˁB
������ɂ��Ă��A���̃X���A��ʃs�[�v���ɕ������Ă���̂́A
����������݂��A�Ȃ��`�������b�i�H�j�������ˁB
�����ԍ��F7969017
![]() 1�_
1�_
�@�|�� bztaka��
�@�u��ʃs�[�v���ɕ������Ă���̂́v�Ƃ��邪�A�A�i�^�����́u��ʃs�[�v���v�̃����^���e�B�Ƃ����\���Ă��鍪���ɂ��ďq�ׂė~�����E�E�E�E�Ɠ˂����݂����Ƃ��낾���A����͂��Ă����E�E�E�E�i�j�B
�@���̕��������u�����b�v�ɕ������邩�ǂ������Ă̂́A�l�̏���Ȃ̂ŁA����Ȃ��Ƃ͋����͂Ȃ��B�������A�u�����Ƃ���v������Ղ��Ȃ��ƕ����͌����Ă��Ȃ����Ă̂͌��R���鎖���B����̓I�[�f�B�I�Ȃ�Ă�����̈�ɑ���E���`�N�����ł͂Ȃ��A�r�W�l�X����ł����������l����Ƃ������l�B�ڂ̑O�̃`�}�`�}�������Ƃ����ꊴ�o�ł��Ȃ��Ă䂭�̂��A�����厖�����A�u�����Ƃ���v��������Ȃ��ƑS�̑��͔c���ł��Ȃ��������������o���Ȃ��B
�@�܂��A�Ƃ肠�����A����Ƃ��X����(^0^)�B���Ȃ݂ɁA���́u��������̃\�t�g���ō��̉��Ŗ炵�����h�v�ł��B
�����ԍ��F7971399
![]() 0�_
0�_
�@�W�����A�o�[����A����ɂ��́B
�@�V�X�e���ɐ��疜�~�|���Ă���̂ɐ��S���̃\�t�g���������Ă��Ȃ��l�i������V����SACD����j�Ƃ����̂́A�C���ł��ˁB����70�`80�����x�̑��u���Z�b�e�B���O�ʂŊ����Ɏg�����Ȃ��A8�疇���̃\�t�g���y����ł���l�A�D���ł��B���������������Ƃ��F�B�ɂȂ肽���ł��B�l���Ă݂�Ύ����ŏI�I�ɂ̓I�[�f�B�I�V�X�e���ɂ���Ȃɋ��𒍂����߂܂���i��̓I�[�f�B�I�����ł͂Ȃ��ł����� ^^;�j�B���������̃��x���̃V�X�e���ɗ��������Ǝv���܂����A����ł�100%�߂��̎��͂�������悤�Ȏg�����Ȃ��ɐ�O�������Ǝv���܂��B�����Ă������A�\�t�g�̗ʁE���Ƃ��[�����������ł��B
�@���������ΑO�ɍs�����I�[�f�B�I�t�F�A�ŁA���[�[���N�����c�̎�Ɏ҂��Z�b�e�B���O�̏d�v���ɂ��ĔM�S�Ƀ��N�`���[���Ă���܂������A�f�B�[���[�ɂ͂����܂ł̃t�H���[���K�v���Ǝv���܂��B�u�����͔������炻���ŃI�V�}�C�ł͂Ȃ��B�����Ă���̃A�t�^�[�T�[�r�X�������Ƒ�ȂI�v�Ƃ����̂͋ߔN�ς��^�f��̎�l���̃Z���t�ł����A���̒ʂ肩�Ǝv���܂��B���[�U�[�����i���Ƀl�b�g�ʔ̂����y����悤�ɂȂ��Ă���j����������ۂɒl�i�������C�ɂ���悤�ɂȂ��āA���鑤�Ɣ�����Ƃ��ʂ̕����������Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B���̂ւ�����Ƃ����Ԃ��D�]���ė~�������̂ł��B�ł́A���ꂩ����X�������肢���܂��B
�@��H�̓e����A����ɂ��́B
�@�ŋ߁A�����[�����Ƃɑ������܂����B�E��̓����Ǝ����̊Ǘ��E����܂������������Ƃ��ꂽ�̂ł��B����́u�p�\�R����CD-ROM���ǂݍ��߂Ȃ��B�ǂ���������̂��v�Ƃ������Ƃł��B���̃f�B�X�N�����Ă��ǂݍ��ݕs�\�ɂȂ�悤�ȃL�Y���t���Ă���킯�ł͂���܂���B����PC�łُ͈�Ȃ��ǂ߂܂��B�Ȃ�Ƃ������ƂŔނ�̎g�p�����Ă�����A���ƃf�B�X�N���t���܂ɓ���Ă���̂ł��i���j�B�u�������̖ʂ����ɂ��Ȃ���ǂ߂܂����B���y�pCD�v���[���[�Ƃ��������ꏏ������v�ƌ������Ƃ���A���Ɓu���y�pCD�v���[���[�Ȃg�������Ƃ��Ȃ��B���y�Ȃ�Đ̃J�Z�b�g�e�[�v�ʼn̗w�Ȃ�������ƒ����Ă������炢���v�Ƃ����A�����ׂ��������Ԃ��Ă��܂����B��l�͌����ĔN���ł͂Ȃ��i40��ł��j�A������x�̒n�ʂ�����������}�g���ȏ펯�l�ł��B����ł��ނ�͉��y��\���I�ɒ��������Ƃ��Ȃ��̂ł��B
�@�ʂɂ��̓�l�����ʂƂ����킯�ł��Ȃ���ł��傤���ǁA�r�W�l�X�̌���Łu��́H�v�ƕ�����đ��肪�u���y�ӏ܂ł��ior�y�퉉�t�ł��j�v�Ɠ����ēr�[�ɏꂪ�C�܂����Ȃ����Ƃ�����ʂɑ��������Ƃ����b���A�l���畷�������Ƃ�����܂��B���ł��u��́H�v�ƕ����ꂽ��S���t�̃n���f����̂��u�펯�v�ł���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��Ƃ��i�ÑR�j�B���y�Ɍ��炸�A���{�ł͐l�Ɍ������ėǂ���Ƃ悭�Ȃ��������̂́A�ǂ���玖���̂悤�ł��B
�@�b�x��A�I�[�f�B�I�@��Ɋ|������z�́A�N��500���~�Ƃ���5�`15���~�Ƃ������ƂȂ�Ε���10���~�����x�Ƃ������Ƃł��傤���B�Ȃ��DENON��PMA-390AE��DCD-755AE�A�����ăX�s�[�J�[��MONITOR AUDIO��BronzeBR1��TANNOY��MERCURY F1 Custom�����킹���10���~�Ŕ����Ă��܂��܂��B������A�����炭�͂قƂ�ǂ̐����~�̃~�j�R���|��傫��������N�H���e�B�̃T�E���h���y���߂܂��B���[�U�[���w������O���[�h�A�b�v���v�������߂�\��������܂�����A���i�̑����ɂƂ��Ă̓I�C�V�C�����ł��B�ǂ����Ă��������G���g���[�N���X�̃V�X�e�������߂�悤�ȃ}�[�P�e�B���O���ǂ��̃f�B�[���[�ł����Ȃ��̂ł��傤���B�������O�ɂ��������Ƃ���f�U�C���ʂł͑f�l����́u�����āv���܂���������܂��A���̗ǂ�������O�ʂɏo���ĔM�ӂ����߂Ĕ��荞�߂A�S����������҂����Ȃ��Ȃ��Ǝv����ł����˂��E�E�E�E�B
�@ProCable�ɂ��ẮA�܂����ď������݂����Ǝv���܂��B�ł́A���ꂩ����X�������肢���܂��B
�����ԍ��F7971424
![]() 0�_
0�_
�h�b�L�I�I
���͑��u�ɐ��S������ꍇ�ɂ���Ă͐��疜�|���邪�A���̃\�t�g�͋ɋ͂��E�E�B���͂Ђ��
�Ƃ����炻�������m��܂���B�������ŋ߂͂��̃I�[�f�B�I�E�r�W���A���@����u���������v
��ԂɂȂ��Ă��܂��B�f�m����BD�v���[���[�A���}�n��AV�A���v�����̂ł����{�i�I�ɂ�
��x���炵�Ă��܂���B1.2m��35000�~�̃����X�^�[��HDMI�P�[�u�������̂ł����A��
�̃P�[�u���Ƃ̍������邩�������Ă��܂���B���̂Ƃ���A����35000�~�̃P�[�u���ƃe�N
�j�J��1���~�̃P�[�u���Ƃ̈Ⴂ��������܂���B�܂��A���S�ɐڑ����Ă��܂���E�E�B
�ŋ߂悭������̂ł����E�E�E�E
>8�疇���̃\�t�g���E�E�E
�����I�ɂ͂��̐������n�����Ă��܂��H�B�Ƃ����̂́E�E1���̃\�t�g�̉��t���Ԃ�70��
�Ƃ��܂��傤�B(CD/SACD��70�����x�̎��^�A���ɂ͉f�擙�̃\�t�g�������Ă����ƒ����Ȃ邩
���m��܂��E�E)70���|����8,000����560,000����9,300���ԁB����2���Ԃ�����̎�����
�[�Ă��Ƃ���4,650��������܂��B�����365���Ŋ����12.7�N�|����܂��B���L���Ă���\�t
�g����ł��ꂾ���|����܂�����A�V�K�ɔ����Ă����̎������A���邢�͂��C�ɓ���͓�
���\�t�g��������E�E�ƍl����Ƌ��炭100�N�ȏ�|����܂��ˁB�\�t�g�̐�8,000���E�E�E��
���i�ɂȂ�̂�80���ȏ�ɂ��Ȃ��Ă��܂��E�E�E�B
����BD���R�[�_�[2�䓙�𑵂��A�^�悵��BD�Ɏc���Ă��܂������̐��A����200���ȏ�E�E�̘^
����S-VHS�AD-VHS���L��܂���SACD��CD�����疇������܂��A�S�č��킹�����ł�
1000�\�t�g�ȏ�͗L��Ǝv���܂��B�N���50���߂����̌㉽�N�����ł��邱�Ƃ��E�E�B
���͂⎄�́u�����Ȃ��\�t�g�v�ł��������i�ɂȂ����܂��B
�ŋ߂悭�����܂��A����ȏ�\�t�g������^�悵���肵�Ăǂ�����ƁE�E�E�B
�����ԍ��F7972481
![]() 0�_
0�_
���E�������A�݂Ȃ���A���͂悤�������܂��B
���ǂ����Ă��������G���g���[�N���X�̃V�X�e�������߂�悤�ȃ}�[�P�e�B���O���ǂ��̃f�B�[���[�ł����Ȃ��̂ł��傤���B
���Â̐̂̃A���ԁi�A�����J�̎ԁj�r�W�l�X�Ƃ����̂́A�c�ƃ}���P�l������N�ɂP�`�Q�䔄��A�[������Ă������Ƃ������Ƃ������Ƃ�����܂��B�������ƂĂ��傫���A�����������v���������̂Ő��藧���Ă����̂ł��傤�B�̏Ⴊ���ŁA�����e�i���X��p������グ�ɒ������܂����B
�G���g���[�N���X�̃V�X�e�����A�L�b�`���ƃZ�b�e�B���O������p�̃X�y�[�X�Œ������āA�s���A�E�I�[�f�B�I���n�߂邩������Ȃ��l�����ɂǂ�ǂ荞�ނ��Ƃ��A�ł���{�I����ȃr�W�l�X�̂�肩���ł͂Ȃ��ł��傤���B
��ӂ��L���Ȃ��ƁA������A���ԃr�W�l�X�̂悤�ɂȂ�Ȃ��Ƃ�����܂���i�����A�Ȃ��Ă���H�j�B
���ɃN���C�W�[�ȉ�X�}�j�A�́A�ق��Ƃ��Ă��A�\�t�g��@�ނ����X�����܂�����A�c�Ƃ���K�v�͂Ȃ��ł��傤�i��
�`�E�`�E�`�E�`�E�`
���r�W�l�X�̌���Łu��́H�v�ƕ�����đ��肪�u���y�ӏ܂ł��ior�y�퉉�t�ł��j�v�Ɠ����ēr�[�ɏꂪ�C�܂����Ȃ����Ƃ�����ʂɑ��������Ƃ����b
���̏�ɋ����킹���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���Ƃ������܂��A�r�W�l�X�̌���ł́A���߂��Ă��铚����������x���܂��Ă��邱�Ƃ������ł�����A�b�̗�����̋�C��ǂ�ł��Ȃ��������������m��܂���B�S���t��S�����Ȃ��Ă��A�b�̗��ꎟ��œK���i�K�j�ɓ�����ׂ��Ƃ���ŁA�܂��߂Ɏ����̎���i�u����Ă����Ȃ��̂Ɂj�����Ă��܂����A�Ƃ������Ƃ����蓾�邩�Ǝv���܂����c�B
�K���ɓ����ċt�ɓ˂����܂�Ăڂ낪�o�邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�ǂ������ǂ����ł��傤���B
�����A�u�S���t�����Ȃ��B�v�Ƃ������ƂŁA������邱�Ƃ������Ȃ̂́A�����ł��ˁB
�`�E�`�E�`�E�`�E�`
> 8000��(�������Ǝv���܂�)�ȏ�̃\�t�g���������̕��c
���́A���y�\�t�g�̍w���́A�{�̍w���Ɠ����悤�Ȋ��o�ł��B
���x�����Ă��V��������������悤�Ȃ��́A�F�����Ȃ����̂�T���Ă��܂��B
CD���o�������玞�X�w�����A���݁A�����Q�O�O�����炸�ŁA�ǂ������\�t�g�͂��������Q�O�����炢�ł��B�����\�t�g�����S��A�������̂́A�����A�����ƒ����Ă��܂��B
�����x�Ɏ����̒��ɉ������݂�����A���������Ȃ�������A�F�X�ł����A���낢��ȏ�ʂŒ��������Ƃ����ꂱ��v���o����邱�Ƃ��y���݂̈�ł��B
�\�t�g���W�O�O�O���A�Ƃ������́A������R���N�^�[�Ȃ̂�������܂���ˁB�����Ȃ��ƋC���ς܂Ȃ��A�݂����ȁB����Ƃ��A������T�������ĂȂ��Ȃ�������Ȃ��A�T���Ă�����̂������̒��ɂ��邱�ƁA�ɋC�Â��Ă��Ȃ����Ȃ̂����m��܂���B
����ȕ����g�߂ɂ�����A���ЂƂ����F�����ɂȂ��āA�\�t�g��F�X�݂��Ē��������Ǝv���܂��i��
�����ԍ��F7972772
![]() 0�_
0�_
�@130theater����A��H�̓e����A����ɂ��́B
�@����8�疇���̃\�t�g��ۗL���Ă���l�ł����A���Ԃ�{�l�Ƃ��Ắu��������W�߂Ă�낤�v�Ǝv���Ă����킯�ł͂Ȃ��u���̊Ԃɂ����܂��Ă��܂����v�Ƃ������o�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ƃ��A�N���V�b�N�ł͗L���ȋȂ��肻�ꂼ����ނ̉��t�������W�߂Ă����Ă��A2�S����3�S���͂����ɂ��܂�܂��B�����̃W���������L���Ȃ����Ă����Ă��A�e�W��������100���قǂ͗e�ՂɏW�܂�ł��傤�B
������ȏ�\�t�g������^�悵���肵�Ăǂ�����
�@��낵����Ȃ��ł��傤��(^^)�B�u�\�t�g8�疇���L�v�������ď펞�����̂͐��\�����Ǝv���܂��B�������A�Ȃ�Ύc���7��9�S���ȏ�̃f�B�X�N�͖��ʂ��Ƃ����ƁE�E�E�E�����ł��Ȃ��ł��B�ނƂ��Ă�8�疇�̃\�t�g�̒����猵�I���ꂽ���\���Ȃ̂ł��B�܂�́u�I���̕����L���Ă��������v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B�����炭�͔����Ĉ����������ł��Ƃ͐��U�����Ȃ��f�B�X�N�����Ă���Ǝv���܂��B
�@���̉��y�\�t�g�̃R���N�V�����͐疇���炸�ł����A�����^�[���e�[�u���̏�ɍڂ�̂͂���ς萔�\���ł��B�����Ĉ�������Ă��Ȃ��f�B�X�N�����邵�A2,3�N�Ɉ���Đ����Ȃ�CD������܂��B������Ƃ����Ă������������悤�Ƃ͎v���܂���B������̋C����n�D�̕ω��ɂ���āA������炪�����ՂɂȂ邩������܂���(^^;)�B
�@�ǂ����̌f���ŁA2�疜�~�̃V�X�e����ۗL���Ă��āA�����Ă���\�t�g�͐��\�����Ƃ������Ƃ����̂��Ă���l���������܂����B��������y�\�t�g�͐����ŁA���Ƃ͑�C�̉��Ȃǂ̍Đ��̓�������i���^���̌��ʉ��݂����Ȃ̂����Ƃ��E�E�E�E�B������܂��A�ЂƂ́u��v���Ƃ͎v���܂����E�E�E�E�i���j�B
�@���āA���͐l����u��́H�v�ƕ����ꂽ��u�͌�ł��v�Ɠ�����悤�ɂ��Ă��܂��B�m���Ɉꉞ�L�i�҂ł͂���̂ł����A�ŋ߂͂قƂ�Ǒł��Ă��Ȃ����A��������قǁu��D���I�v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B�ł��ΊO�I�Ɍ�������̂ɂ͂����Ă����́u��v���Ǝv���܂��B���ɃS���t���̃}�[�W�������̂ɂ܂������������Ȃ��g�Ƃ��ẮA��̘b��ɂȂ����Ƃ��u���Ă��ڂ��H�킳��Ȃ������̃l�^���Ǝv���܂��B�u��̓I�[�f�B�I�ł��v�Ɠ�����̂́A���ɐe�����l�ɑ��Ă����ł��ˁi�j�B�}�C�i�[�Ȏ�ł��邱�Ƃ͊m���ł�����B
���G���g���[�N���X�̃V�X�e�����A�L�b�`����
���Z�b�e�B���O������p�̃X�y�[�X�Œ������āA
���s���A�E�I�[�f�B�I���n�߂邩������Ȃ��l
�������ɂǂ�ǂ荞�ނ��Ƃ��A�ł���{�I
������ȃr�W�l�X�̂�肩��
�@���̒ʂ�ł��B�c�㑊��́u�����i�����v�Ȃ�āA�Z�R���ł��B�S�߂ł��B������͎��������Ȃ�ڋq�i����I�j��z�肵�Ă��Ă���ׂ�ł��B�I�[�f�B�I���[�J�[�͂����Ɩ{�C���o���ĐV�K�ڋq���J�Ăق����ł���(^o^)�B
�����ԍ��F7973105
![]() 0�_
0�_
�@�{���͎����ς��āA�ŋߊς��f��̘b�ȂǁE�E�E�E�B�A�����J�f��u��Ղ̃V���t�H�j�[�v���ς܂����i����: AUGUST RUSH �ē�:�J�[�X�e���E�V�F���_���j�B���e�Ɛ����ʂꂽ�t���f�B�E�n�C���A�����鏭�N���A�����ׂ����y�̍˔\�Ŏ��͂𖣗����Ă����Ƃ����X�g�[���[�B���������Ęb�͐����ƌ�s����`�Ȃ̂ł����A��l�������t����V�[�����܂ތ����ł̉��y�̈������͑���ۂނقǑf���炵���B
�@�����𐁂��n�镗�����V���t�H�j�[�ƂȂ��Ď�l���̎��ɓ͂����|�I�ȃt�@�[�X�g�V�[�����͂��߁A�X���ߐs���������鉹���s��ȋ����ȂƂȂ��ʂ����삷���ʁA���ꂼ��ʂ̏ꏊ�ʼn��t������e�̑t�ł�`�F���ƕ��e�̈����G���L�M�^�[�Ƃ��▭�̃n�[���j�[���`�����邭����ȂǁA�܂��Ɂu���y�̉f�����v�����ʂ̋��S�͂Ɋ������Ă��܂��܂����B
�@���āA���{�ł��������f�悪���邩�Ƃ����ƁE�E�E�E���Ԃ�s�\�ł��B�ł��A�{���͕s�\�ł͂Ȃ��̂�������܂���B�D�G�ȃX�^�b�t�͂����Ƒ��݂��Ă��܂�����B�������A�{��ɂ́g���{�l�ɂ͍���͂����Ȃ��h�Ǝv�킹�邾���̐����͂�����̂ł��B���Ȃ��Ƃ��g���܂��A�ǂ��ɂł����y�͍~�蒍���h�Ƃ����R���Z�v�g�́A�Ȃ��Ȃ��v���t�����̂ł͂���܂���B���{�ɂ��V�ˉ��y�Ƃ���l���ɂ����f���h���}�͂���������܂��B�ł��A�ǂ����g�\�����h�����Ȃ̂ł��B���̉f��̂悤�ȁA���퐶���̂����ׂɋ��Q����悤�ȉ��y�̃����_�[�����h���T���Ă���Ƃ����▭�Ȑ}���Ƃ͕ʂ́A�����ʂ����̐l�������́g�����h�f�����E���W�J����݂̂ł��B
�@���y�ɑ��Ă��������A�v���[�`���ł��鉢�Đl�ƁA�����ł͂Ȃ����{�l�Ƃł́A�I�[�f�B�I�ɑ���F�����Ⴄ�̂����R���Ǝv�킴��܂���B���ɁA���邢���F�̊C�O���X�s�[�J�[�Ɩ��邳�̕s�����鍑�Y�X�s�[�J�[�Ƃ́g�����h���l����ƁA�Ȃ�����ł��B
�����ԍ��F7981173
![]() 0�_
0�_
���E�������@
WOWOW�̃h���}��CSI�A�N���~�i���}�C���h�A�~�f�B�A���A�R�[���h�P�[�X���悭���Ă��܂��B
���̕���̓��e�͓��{�ł͍l�����Ȃ��X�g�[���[�ŊS�������鎖������ł��B��͂�f
��̓A�����J�ł��傤���˂��H�H�I�I�B
�����ԍ��F7982006
![]() 0�_
0�_
�@�|�� 130theater����
�@�C�O���e���r�h���}�͂قƂ�nj��܂��ǁi�E�E�E�E�Ƃ������A���Y���܂߂ăe���r�h���}�͂��܂茩�܂��� ^^;�j�A�f��͍ŋ߃A�����J�����ʔ����ł��ˁB9.11���������e���ڍs�A���ۏ�l�^��Љ������������i���������A���������ꂼ����͂̂���X�^�b�t��L���o�D���������ĎQ�����Ă��邽�߁A�������̂���f�悪�ڗ����܂��B90�N��܂ł͉��B��A�W�A�̉f��Ɏ��I�ɑ卷��t�����Ē�����Ă����̂��E�\�̂悤�ł��B
�@���ē��{�f��̓_���ł��B���ɋߔN�e���r�h���}�̏Ă�������L���}���K�̉f�扻�Ȃǂ̈��ՂȊ�悪���ʂ�A���ꂪ�܂��q�b�g���Ă��܂����������ŁA���ł͑e�������ł��B�~�j�V�A�^�[�n�ɂ͗ǂ����̂�����܂����A��ʑ�O�̖ڂɐG�ꂻ���ȃ��W���[�Ȍ���ŏ�f�����M��̃��x���͒n�ɗ����Ă��܂��B
�@�I�[�f�B�I�@�킪�o�ꂷ��f��ł́A���`�f��̌���u�C���t�@�i���E�A�t�F�A�v���܂��v�������т܂��B�剉�̃A���f�B�E���E�ƃg�j�[�E���I�����I�[�f�B�I�V���b�v�Ō�荇���V�[��������܂����A�o�b�N�ɕ��ԃn�C�G���h�@�킪��ʂ�グ�Ă��܂����B���̉f��̓n���E�b�h�Łu�f�B�p�[�e�b�h�v�Ƃ��ă����C�N����A�J�f�~�[�܂܂Ŏ���Ă��܂��܂������i�ł��A�o���͍��`�ł̑����ɂ��y�т܂���ł����j�A������ɃI�[�f�B�I���i���g�����Ƃ͓��P����Ă��܂��B��l���̕����ɂ̓}�b�L���g�b�V���̃A���v�ނ��������A�w�b�h�t�H���̓[���n�C�U�[�ł����B�q���C����B&O�̃V�X�e�������p���Ă����悤�ł���(^^;)�B
�����ԍ��F7982719
![]() 0�_
0�_
JBL�E�}�b�L���EJAZZ�ƁA�A�����J��ӓ|�̎��Ƃ��Ă͉f����e���r�������ł��B
130theater����Ƒ����ɂ��Ԃ�̂ł����ACSI�e�V���[�Y�A�N���~�i���}�C���h�A
�R�[���h�P�[�X�̂R�{�́u�ƍߕ��v�Ƃ��Ă��V���ȃX�^�C�����m�����܂����ˁB
���{�́u�Y�����v�ɂ��@���ɂ��͕�ƌ�������́A���ς�炸�̂��̂Ɨ����C���B
����Ȓ��Łu���_�v�͑S�Ҍ��Ă���܂���������J���ꂽ�u����f��v�ɂ͂�������I
�ς��f��ق̖��ł��傤���H�f���������A�������������ł����B
�n�C�r�W�����łŕ��f�����e���r�V���[�Y���䂪�ƂŊς�����S�R�ǂ��̂ł��B
�ςȂƂ���ʼnt���e���r�EAV���i�̗D�G�����������܂����B
�����������ԂɊς��A�u�C���f�B�[�W���[���Y�v�͗ǂ������ł��B
�X�g�[���[�͂Ƃɂ����A�җ�߂����g�E�t�H�[�h�̌��C�Ȃ��Ƃ�����I
�ނ��͂����ԎႢ�����u��L���v�Ȃ��Ă��邱�Ƃɜ��R�Ƃ��܂����B
�����ԍ��F7982877
![]() 0�_
0�_
�@�|�� �l�I���W����
�@�u���_�v�̓q�h�������ł����i���͖����ł��� ^^;�j�B���̎��͂̕]�������N�Ȃ��̂ł͂���܂���B����ł���q�b�g���Ă���Ƃ������ƂŁA�������葤�́g���̒��x�ő�ʓ����ł���Ƃ́A���{�̊ϋq���ă`���������h�ƁA�ق�����ł��邱�Ƃł��傤�i�ÑR�j�B����������N�ς��u�g�d�q�n�v�����ɂ�����Ȃ��f��ł����B�e���r�ԑg�́g�g�p�h�Řb�萫���m�ۂ��A�L���^�N�剉�ŌŒ�t�@���������A�r�{�Ɖ��o�̓e�L�g�[�ɂ���Ă���A���Ƃ͌��ʂ͂�����x�t���Ă���͂��Ƃ����A�ϋq���o�J�ɂ����ԓx���~�G�~�G�ȃV���V���ł����ˁB
�@�ӂƁA�ǂ����g�����h�ɂ���������Ȃ����{�l�̓����𗘗p���āA�I�[�f�B�I�˂����e���r�Ńo���o�����������̂ł͂Ȃ����E�E�E�E�ȂǂƎv���Ă��܂��܂��B���Ƃ��A�h���}�̏�����Ƃ��ăI�[�f�B�I�@����Y�����ƕ��ׁA�剉�̃L���^�N���N���Ɂg�Ԃ����Ⴏ�A�~�j�R���|�Ŗ������Ă���I���i���āA���������āA���łɓ��������������h�Ƃ��������Z���t�ł��f������Ζ��S���ƁE�E�E�E�i���j�B
�@�u�C���f�B�E�W���[���Y�v�͎����ς�\��ł��B
�����ԍ��F7983372
![]() 0�_
0�_
���E�������A�݂Ȃ���A�����́B
�l�I���W����A�ȑO�AAV�A���v�̃X���Œg�������b�L���������܂����B
�f��̘b�Ƃ������ƂŁA�g���h�ɂ܂��A�������̘b��������ĉ������B
�L���Șb�Ȃ̂ŁA�F��������������܂��A�{��A�j���Ɂu���̂̂��P�v�Ƃ����̂�����܂��B���y�I�ɂ��A�n�C���x���ȍ�i���Ǝv���܂����A�������ł��傤���B
�e���Ŏ��ʉ���s�����Ƃ��̃G�s�\�[�h�ł����A�t�����X�ŏ�f�����Ƃ��́A�u���������R��`�����������f��B�v�Ƃ��čD�]�ŁA��f���̊ϏO�̔��������{�l�Ǝ��Ă��������ł��B
�A�����J�i�Ƃ����Ă��L���ł����j�ŏ�f�����Ƃ��A�X�̒��ŃA�V�^�J�i��l���̂ЂƂ�j���A�V�V�_�i�V�J�̂悤�Ȏp�̐_�b�j�ƃj�A�~�X����V�[���ŁA�u�Î�v���\�b���炢����̂ł����A���b�o�߂������炢�̂Ƃ���ŁA�ϏO�̂Ȃ�����u�������u���̏Ⴕ�Ă���B�����o�Ă��Ȃ��B�v�Ƃ��������w�E������A������������������ł��B
�u�Î�v���u�@��̌̏�v�Ǝw�E�����q�g���A�ǂ�ȉ������҂��Ă����̂��܂ł͌��y������܂���ł������A�ƂĂ������[���G�s�\�[�h���Ǝv���܂��B
�u�X�̒��Ő_�b�Ƒ����v�c�ǂ�ȉ��y�A�ǂ�ȉ����ӂ��킵���̂ł��傤���H
�c���͂���ς�A�u�Î�v�h�ł��B
�Ƃ���ŁA�f��Ɩ��̕t�����͉̂��ł���D���ŁA������Ȃ����炢�݂Ă��܂��B
�u��Ղ̃V���t�H�j�[�v�A�����A���T���ɂł������^�����đ��ʁi�Ƃ����Ă�52�C���`�t���ł����c�j�T���E���h�ł݂Ă݂܂��B
�ƂĂ��y���݂ł��B
���߂ł́A���L���q���Ƃ݂܂����B
�u�s�A�m�̐X�v�i�A�j���j�c�T�O�_
�u�p�C���[�c�E�I�u�E�J���r�A���E���[���h�E�G���h�v�c�Q�O�_
�ǂ�����A�����߂͂ł��܂���B
�����ԍ��F7984278
![]() 0�_
0�_
�@�|�� ��H�̓e����
�@�u���̂̂��P�v�ł����B�{��x�ē̍�i�Ŗʔ��������̂́A���������u�����̑�}�ցv�܂ł������ƁA�l�I�ɂ͎v���܂��B�u�g�̓v�ȍ~�͂�����ƁE�E�E�E(^^;)�B
�@�f��̒��ɂ�����g�Î�h�Ŏv���o���̂́A�h�O�}95�iDogme95�j�ƌĂ��f��^���ł��B����́A�f��삷����10�̏d�v�ȃ��[�������߂āA����ɑ����č쌀���s���Ƃ����X�g�C�b�N�ȃ��[�������g�ŁA95�N�Ɏn�߂�ꂽ���̉^���ɏ������č��ꂽ�f��͑S���E��80�{���܂��B����10�̃��[���̒��Ɂu�f���ƊW�̂Ȃ��Ƃ���ō��ꂽ���i���ʉ��Ȃǁj���̂��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����̂�����A������f�批�y�̎g�p�֎~��搂��Ă������������܂��B
�@�������A�h�O�}95�̃X�^�C���ɂ���č��ꂽ�f��͂قƂ�ǂ����[���b�p���A�W�A�̂��̂���B�A�����J�f��ł̓}�C�i�[�ȍ�i���{�ɗ��܂�܂��B����ς�قƂ�ǂ̃A�����J�l�̊ϋq�͐₦�����y�����Ă��Ȃ��ƕs���ɂȂ�̂ł��傤���i�j�B�Y�قȃA�����J���̃X�s�[�J�[�̉��F�ƁA�ǂ����ʂ�����̂�����悤�ȁE�E�E�E�i�� �������L�����X�� ^^;�j�B
�@�u��Ղ̃V���t�H�j�[�v�͓��{�ł͂܂��r�f�I������Ă��܂���B�E�E�E�E�Ƃ������A����ꂽ����ł�����A�ǂ����Ă��ς�����Ήf��قɁE�E�E�E�Ƃ������Ƃł��B�u�s�A�m�̐X�v�Ɓu�p�C���[�c�E�I�u�E�J���r�A���E���[���h�E�G���h�v�͊ςĂ��܂���B�u�p�C���[�c�E�I�u�E�J���r�A���v�͑���ڂ��ςāA���܂�̖ʔ����Ȃ��ɐ�債���̂ŁA���ڈȍ~�̓p�X�ł����B�ł��܂��A�q���C�����̃L�[���E�i�C�g���C�͗ǂ��ł��ˁB�ޏ��Ɍ��炸�A�C�M���X�̏��D�͎��㌀���悭�������܂��B
�����ԍ��F7987594
![]() 0�_
0�_
���E�������A�݂Ȃ���A�����́B
�u���̂̂��P�v���C�ɏ����܂���ł������B���炵�܂����B
���́A�u�J���I�X�g���v�Ɓu�i�E�V�J�v�͎�����ł��C�ɓ���A�u���s���^�v�͂܂��܂��ŁA�����܂łł��B
���Ƃ́A�Đ��Ō��Ă��܂����A�ǂ�ǂ��i�̃��x�����ቺ���Ă����i���Ր��������Ȃ��āA���ʂ��y���Ȃ��Ă����j�̂��A�t�ɋ����[���Ǝv���Ă��܂��B
�u���̂̂��P�v�́A�f��{�̂͂Ƃ������A���C�L���O�̃r�f�I�iDVD�j���ƂĂ��ʔ����̂ŁA�������ł�����A������̓I�X�X���ł��B�f��{�̂��10�{���炢�ʔ����Ǝv���܂��B
�Ȃ��A�{��A�j�����܂�Ȃ��Ȃ����̂����A��������ƕ`����Ă���H�Ǝv���܂��B
�����炪�{�҂ƌ����Ă��ǂ��A�G��ȃh�L�������^���[�f��A�Ƃ��Đ����Ă����܂��B
�����{�f��̓_���ł��B���ɋߔN�e���r�h���}�̏Ă�������L���}���K�̉f�扻�Ȃǂ̈��ՂȊ�悪���ʂ�A���ꂪ�܂��q�b�g���Ă��܂����������ŁA���ł͑e�������ł��B�~�j�V�A�^�[�n�ɂ͗ǂ����̂�����܂����A��ʑ�O�̖ڂɐG�ꂻ���ȃ��W���[�Ȍ���ŏ�f�����M��̃��x���͒n�ɗ����Ă��܂��B
�ǂ����āA����ȕ��ɂȂ��Ă��܂����̂ł��傤���c�H�@�ی����x�̕��Q�ł��傤���H
�s���A�E�I�[�f�B�I�̎Ηz���ƁA�ǂ����łȂ����Ă���̂����m��܂���B
���X�N�����Ȃ�����̑Ë��_�̒Ⴓ���A���̂܂܌������Ă���C�����ĂȂ�܂���B
�u��Ղ̃V���t�H�j�[�v�́A�悭���ׂ������ɃR�����g���Ă��܂��A���炵�܂����B�f��قɏo������̂��N�ɂP�|�Q��ŁA���܂Ɏ��Ԃ��o�����Ƃ��ɏo�����āA�����ł���Ă�����̂��ς���x�A�f��Ƃ��������^���A�ł����̂Łc�B�m���ɁA�����^�����̒I�ł͌������Ȃ������ȁH�Ƃ͎v���Ă����̂ł����B���N���炢�҂��܂��B
�u�p�C���[�c�`�v�́A�u���ǂ���̂Ȃ������ԉf��v�̑�\��ł����B���́A�P���Ԃ��炢�̂Ƃ���ŐQ�Ă��܂��A���R�ɖڂ��o�߂āA�܂�����Ă��܂����i�j�Ȃ͊��Ɍ����t���ĉƎ����n�߂Ă��āA�q�������Ɓu���̉f��A���I���̂��Ȃ��B�����I���Ȃ����Ȃ��B�v�Ƃ����L�l�ł����B�ǂ����Ŋς��悤�ȃV�[���̌J��Ԃ�����ŁA�ƂĂ��ދ��ł����B�܂��A���̃R���f�B�Ƃ��Ă݂�A�f�B�Y�j�[�炵���H���t���Ǝv���܂��B����ȉ��߂ł́A�t���b�V���E�S�[�h���i80�_�j�{�}�b�h�E�}�b�N�X�R�i�T���_�[�E�h�[���H�j�i10�_�j��D�̏�ō��̃����C�N���������H
�L�[���E�i�C�g���C�Ƃ����A��قǒm�l�i20�㏗���j����A�u���Ȃ��v���I�X�X���Ƃ̏�������܂����B�f��قŋ����܂������Ƃ̂��ƁB���Q�l�܂łɁB
�����ԍ��F7988406
![]() 0�_
0�_
�@�|�� ��H�̓e����
�@�u���̂̂��P�v�̃��C�L���O�r�f�I�͖ʔ������ł��ˁB�@�������Ќ��Ă݂����Ǝv���܂��B���͋{��x���Q�������f��̒��ň�ԍD���Ȃ̂́u����x������v�Ȃ̂ł��B�{��͐���S���ŁA�ḗu�ΐ���̕�v�Ȃǂ̍����M���S�������A���̊�Ԃ�ɂ��B��̎��ʉf��A�������h�L�������^���[�ł��B�������r�f�I������Ă���̂��ǂ���������܂���̂ŁA�u���Ќ��ĉ������v�ƌ����Ȃ��̂��h���Ƃ���ł�(^^;)�B
�@�ŋ߁A�m��̌��ꕕ���i�ł����������{�ꐁ���ւ��ł̏�f���������Ǝv���܂��H�@�ȑO�̓A�j���[�V�����Ȃǂ̎q�������̔ԑg�Ɍ����Ă����̂ł����A���͎q�������ł͂Ȃ��ʏ�̌�y�f��ɂ��ڗ����Ă��܂����B���̔w�i�ɂ��Ė^�f��W�҂���u����́A�ŋ߂̎Ⴂ�ϋq�̒��Ɏ����̊�����ǂ߂Ȃ��҂������Ă������炾�v�Ƃ����R�����g��Ⴂ�A���R�Ƃ��܂����B�����ĉ��ł��A�o��l���͑O�����ăe���r�h���}�▟��ŏЉ��X�g�[���[�͕�����₷�������I�Z���t���R�̂悤�ɏo�Ă��Ȃ��Ɠ��e�������ł��Ȃ��ϋq��������������Ƃ̂��ƁB�Ђ���Ƃ��āu��Ƃ苳��v��u�i���Љ�v�̉e���ł��傤���B���ƂȂ��C���Ȋ������܂��B
���s���A�E�I�[�f�B�I�̎Ηz���ƁA�ǂ����łȂ����Ă���̂����`
�@�����A�m����_�͂Ȃ��̂ł����A����ȕ��Ɏv���Ă��܂��܂��B�����ɂ̂߂荞��Ŋy���ނ��Ƃ��������āu�݂�ȉ��y��DAP��~�j�R���|�ōς܂��Ă��邩�玩�����������悤�v�Ƃ��������ŏI����Ă��܂��̂́A�u�݂�ȃe���r�h���}��l�C����ɏ��������f�����ςĂ��邩�玩�����������悤�v�Ƃ����s�����ƒʂ���悤�ȋC�����܂��B
�@�u���Ȃ��v�͌���ŊςĂ��܂��B�f���炵���f���̔������f��ł������A�쌀�ɋÂ肷���̊�������A�]������������i���Ǝv���܂����B�L�[���E�i�C�g���C�o����̒��ł́A�����_�ł̃x�X�g�́u�v���C�h�ƕΌ��v�ł��傤���B�܂��A�܂�20��O���̎Ⴓ�ł����獡�����\��͑����Ă���ł��傤(^^)�B
�����ԍ��F7993623
![]() 0�_
0�_
���߂܂��āA�I�[�f�B�I�ɋ����������n�߂����Ƃ��Ă͎Q�l�ɂȂ�܂��B
�d���P�[�u����X�s�[�J�[�P�[�u���ōŏ��͂��܂艹�͕ς��Ȃ��Ǝv���Ă�������ǁA�ς��Ă݂Č��\�ς�����Ă��܂��B
�d���^�b�v�����ł��B
�ŏ��ACD�v���C���[�̌�����ipod�ŏI���_�̋L����PROCABLE�����m�����̂ł����A�ߌ��Ȕ����ƃn�b�L�������M�O�Ŋy�����q�����܂����B
�f�l�ł��H�ƌ����L�����������̂͐l�ɒ��ӂ��������߂̐�`�̂��߂��ƁA���͂�ǂ�Ŋ����܂����B
�����͂��̋Ǝ҂���܂��w�����Ă��܂��A�l�i�ƋL����ǂނƂ������������Ȃ�S���ɂȂ�̂͐����J���X�}�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8008329
![]() 0�_
0�_
�@�ˑR�ł����A�I�[�f�B�I�ƊE�͂����Ə����ɃA�s�[������悤�ȃ}�[�P�e�B���O�����肵�������ǂ��Ǝv���܂��B
�@���͏����̕��������ǂ��Ǝv���܂��B�p�b�ƒ����������Łu�����A�ǂ����v���邢�́u�P�b�A�܂�Ȃ����v�ȂǂƑ��f�ł��Ă��܂��̂́A�����ł��i�m�łƂ����f�[�^�͂���܂��A�̌��セ���v���܂��j�B��Y�̕��́u���[��A���̍����̉��ƒ��̕���\���ǂ����炱������v�Ƃ������\�����������܂��B�����āA���̔\�����͑����Ƀ��J��X�y�b�N�ɉe������܂��B����ɁA�N�G�̓������I�[�f�B�I�}�j�A�قǁA���̌X���͌������Ǝv���܂��B
�@���J�j�Y�����i��O�ʂɏo������������́A�܂��Y��z�肵���Z�[���X���傫�Ȍ��ʂ������߂Ȃ��̂́A��ʏ���҂�ɂ���ƊE�Ȃ�ǂ��ł��ꏏ����Ȃ��ł��傤���B�����w���^�[�Q�b�g�Ƃ��Ď�荞�߂Ȃ�����A���邢�͖�Y�̔w��ɍT����u���z�̂Ђ��������Ă��鉜�������v�ɗ��������߂Ȃ������́A�悪�����Ă��܂��B���āi���x�ł������܂����j�c��̂�������̏����Ȃ�Ďv��������������ł��B����Ȃ̂ɂ͑����Ƃ������t���ď������̂��鏗���Ώۂ̃}�[�P�e�B���O�ɑS�ʈڍs���ׂ��ł��ˁB
�@�������u��������������f�U�C����������������v�Ƃ����̂͑�ԈႢ�ł��B�ȑO�AAV�@��̐��T�C�g�uphileweb�v�ɂ�����u�����̃��C�t�X�^�C���ɂƂ��ẮA���y��f��A�����Ă��̍Đ��@��v�Ƃ����������W�L���ɂ������Ă���܂������A�����������@��ɋ��߂�̂͑��ɉ��̗ǂ��ł��B�f�U�C���͂�����N���A������ł̘b�B�����ċ@��̃T�C�Y��g��������d�v�ȃ|�C���g�ł��B��Y�̃I�[�f�B�I�t�@�������ĉ��̗ǂ��͍ŗD�掖���ł��傤���ǁA�O�q�̂悤�Ƀ��J��X�y�b�N�ɂ��f�o�C�X���������Ă��܂��ꍇ�������ł��B
�@�������[�U�[��Ώۂɂ������i�J���́A�I�[�f�B�I�@��S�̂̎��I�A�b�v�ɂ��q����܂��B�����̓��J��X�y�b�N�ɂ�����ςȂقƂ�ǂ���܂��A�����炭�����ɉ��ƃf�U�C���Ǝg������ɂ���ď��i��I�����܂��B����ɂ���ċZ�p�ʂ̔\�����Ŕ��낤�Ƃ������i�́i�n�C�G���h�@�������āj�쒀����A�g�p�ҏd���̎p���ɕς��ł��傤�B
�@�����G���ɂ����X�ƍL�����ڂ����鏤�i�����A�����Ď��ۂɏ����G���ő�X�I�ɃA�s�[�����Ăق����ł��B
�����ԍ��F8021455
![]() 1�_
1�_
���E�������A�����́B
�@�@�����͏����̕��������ǂ��Ǝv���܂��B�p�b�ƒ����������Łu�����A�ǂ����v���邢�́u�P�b�A�܂�Ȃ����v�ȂǂƑ��f�ł��Ă��܂��̂́A�����ł��i�m�łƂ����f�[�^�͂���܂��A�̌��セ���v���܂��j�B
�@�������ӂł��B�p���[�A���v��ւ�����A������[�����A�����ǂ��Ȃ�����ˁB���܂ł̉��́A���邳�������ŁA�`�b�g���ǂ��Ȃ�����]�ƌ����̂ł��B����ȗ��A�I�[�f�B�I�ɂ͑S���S�̖����l�Ԃł����A���X�A�����Œ����Ă��܂��B�l���Ă݂�ƕ����ł́A����Ȃ�ɔ����ł����A�����Ɖ��̖{����������̂����m��܂���ˁB�Ȃ�قǁA�s�A�m��l�Ԃ̐��Ȃǂ�SP�̖T�����ׂ̕����Œ����Ă��������{���̉������Ă���C�����܂��B
�����ԍ��F8024252
![]() 1�_
1�_
���E�������@�����́I
�ǂ������A�Ƃ������z�b�g���Ă܂�(^^)
���̓I�[�f�B�I�̉����ɂ��Ď����ł͑S�����f���ł��Ȃ��Ȃ鎞�A������ύX�������ɃJ�~�T���ɕ����Ă��������т��сA����܂����B
�Ⴆ�v���[���[�ɂ�鉹���̒�����ׂ̍ہA���̎��Ɏ����ł͂�����̕��������͂����Ɛ���ϔO�������ĉ��o�������āA�J�~�T���ɕ����܂��B�����������͂��Ǝv���Ă�����ɌR�z����������̂ƁA���M�������ĕ����܂����J�~�T���̓����͋t�̕����w�w���A�������̕�������������I�@�G�b�H�K�[���I�I
��������ÂɂȂ莞�Ԃ�u���Ē����ƃJ�~�T���̔��f�̕�������������(>_<)
�������̓��J��X�y�b�N�ɂ�����ςȂقƂ�ǂ���܂���
�S�����̒ʂ�ł��ˁI
�������������@��ɋ��߂�̂͑��ɉ��̗ǂ��ł��B�f�U�C���͂�����N���A������ł̘b�B�����ċ@��̃T�C�Y��g��������d�v�ȃ|�C���g�ł�
�ȑO����J�~�T���Ɏw�E����Ă��܂����A�y�����������āA�g������̗ǂ������ȁA�����Ė����ł͂Ȃ��I�[�f�B�I���i���Ē��X�Ȃ��ˁ[�z
���̒��łP�_����������CLASSIK MOVIE Di�ƌ���DVD�v���[���[������AV�Z���^�[�ɂ��Ă͂���ŐF�Ⴂ����������̂ɁE�E�E�A�Ƃ��Ȃ�ǂ��_���̂��̂�����܂������B
��Ƃ��菗�������ɑ�X�I�ɃA�s�[���ł��镨���J�����ė~�����ł��ˁI
�Ђ��Ă͂��ꂪ������ĉ�X��A�ɂ����b������I�H��������܂����(^^)
�����ԍ��F8025454
![]() 1�_
1�_
�@�掿�ɂ�����肳��Asatoakichan����A���X�L���������܂����B
�@�ȑO�A�������I�[�f�B�I�V���b�v�ɃE�`�̉Ō��A��čs�����Ƃ���A�^�Ђ̃X�s�[�J�[�ƃA���v�Ƃ̑g�ݍ��킹�i���ƂĂ����z�Ŕ����Ȃ��j�����Ȃ�C�ɓ������悤�ŁA�����u���[���ƁA�܂��͒��̕���\���`�F�b�N���āA����Ɖ��ꂪ�E�E�E�E�v�Ȃ�Ă����u�\�����̐��E�v�ɐZ�荞��ł���Ԃɔޏ��́u���邢�A���C�A���H�[�J�������X�����Ċy��̉����L���C�I�v�Əu���ɗǂ��Ƃ�������������悤�ł��B�����āA����܂��^�n�C�G���h�G�������̍����@�̑g�ݍ��킹�́u�Â��A�d���A����������Ŋy�킪����ł���I�v�Ƒ����p���B������́u���[�ށA����͈ꌩ�Â����������͉����̑��������T�}�ɂȂ��Ă��āE�E�E�E���[�A�ł�����ς�t�b�g���[�N���������ȃ@�v��畏����Ă��鎞�Ԃ������������������肵�܂����i���j�B
�@�I�[�f�B�I�@���I�ԍۂɂ́A�o����J�~���A�Ɛg�҂Ȃ�Ώ��F�B��A��čs���������ǂ��̂ł͂Ȃ����E�E�E�E�ƃ}�W�Ŏv���܂��B
�������������āA�g������̗ǂ������ȁA������
�������ł͂Ȃ��I�[�f�B�I���i���Ē��X�Ȃ�
�@�����Ȃ�ł��B�t�Ɍ����u�����ǂ��āA�g�����肪�\�����Ȃ��A�Ȃ��������ł͂Ȃ��I�[�f�B�I���i�v���ǂ�ǂ���Ώ����ɂ��E�P�Ă��̋ƊE�ɂ������˂����ނ��Ƃł��傤�B
�@�O�ɂ������܂������u���������Ƀf�U�C����������������v�Ƃ������@�͋S��ł��B���������u�������[�U�[�������т����ԓx�v�ł͎��s���܂��ˁB���������߂�͕̂i���̗ǂ��Ǝg������A�����ăf�U�C���A���Ƃ̓R�X�g�p�t�H�[�}���X�ł��B�Ԉ���Ă��A�ǂ����̃A�p�����n�����u�����h�̃��C�Z���X���擾���ăA���v��X�s�[�J�[�Ƀ��B�g���Ƃ��O�b�`�Ȃǂ̏��W���������Ă͂����܂���i�j�B����Ȃ̂́u�s�G�[���E�J���_����̃I�W�T���p�C���v�Ɠ����x�̒Ⴂ�]�������Ȃ��ł��傤�B
�@�J���w�ɂ����Ə������X�I�ɋN�p���Ă������Ǝv���܂��B
�@���ꂩ��A�f�B�[���[�ɂ������X�^�b�t���K�v���Ǝv���܂��B�Ɠd�ʔ̓X�̃I�[�f�B�I�����ɋC������ȃI�b�T�����藧���Ă����̂ł́A�����q�������܂����(^^)�B
�����ԍ��F8035159
![]() 1�_
1�_
���E�������
���A�ӂƋC���t���܂����B�s���A�I�[�f�B�I��AV�̊W�͎Ԃɒu����������̂ł͂Ȃ����ƁI�B�́A�I�[�f�B�I�ƌ����s���A�I�[�f�B�I����(AV�A���v�Ȃ�Ă���܂���ł�������E�E)�B�@�Ԃƌ����Z�_��(�X�|�[�c�J�[�܂�)�Ń~�j�o���Ȃ�Ă���܂���ł����B(���p�Ԃ�1BOX�o���͂���܂������E�E)�@�Ƃ��낪���̓Z�_���~�j�o���̔䗦�̓~�j�o���̏����H�B�~�j�o���͐l�����������悹����A�Z�_���͎Ԃ̖{���̑���E�~�܂�E�Ȃ���̋@�\�͗y���Ƀ~�j�o�����D��Ă��܂��B
���̐��̒��̉��l�ς��ς��Ă��܂����B�{���̎Ԃ̊�{�őI�ԕ��͏��Ȃ��E�E�I�[�f�B�I�����̗ǂ��Ƃ�����{�����ł̓_���ŁA�~�j�o���I�v�f���K�v�E�E�E���������̓��͐��\�����葽�l����ꂽ��A�ו����悹���ďꍇ�ɂ���Ă͎ԓ��Ő������Ƃ��E�E�Ƃ������@�\���v�������l�ɂȂ��Ă��܂����B
AV�A���v�͂܂��Ƀ~�j�o���ł���e��T���E���h�t�H�[�}�b�g���Đ��ł��āA�ܘ_2ch�̃s���A�I�[�f�B�I�����������̍Đ��͂n�j�ƂȂ��Ă��܂����B��͂肱�ꂩ���AV(�~�j�o��)���嗬�A�s���A�I�[�f�B�I(�Z�_���E�X�|�[�c�J�[)���嗬�ɂȂ鎖�͂Ȃ��ł��傤�B
���͂ǂ��炩�Ƃ����u�s���A�E�I�[�f�B�I�h�v�A�������Ȃ���~�j�o�����F�߁A�s���A�E�I�[�f�B�I��AV�̗����g���ł��B�~�j�o�����E�E�E�e�Ђ�AV�A���v���t���b�O�V�b�v�@�ɂȂ��2ch�Đ������\�����܂��B���}�nDSP-Z11���g���Ă��܂����A�����2ch�I�[�f�B�I�����\�����܂��B�@
�����ԍ��F8036168
![]() 0�_
0�_
130theater����A�����́B
�@�����ԂƃA���v�̔�r�_�ɂ͑S���^���ł��B
�@�l�I�Ȋ��o�Ƃ��Ă͗����E�q�������ł����̂łPBOX�Ԃ����L�������Ƃ������̂�
�@���p�����Ԏ�(�X�|�[�c�Z�_���n)�ł��嗬���s���A����AV�n�ɂȂ��Ă���Ɗ����܂��B
�@����GTR�ł�AM���W�I�����I�v�V�����ł������A32-GTR�ł�FM�X�e���I�͓��R�B
�@�Q���32-GTR�ɂ�nakamichi�̃w�b�h��BOSE��SP�Ȃǂ���������̂ł��B
�@33-GTR�͎ԂɎ��]���܂������A���ɃX�e���ICD�͕W���ŁH���Ă��܂������A34-GTR
�@�ɂ̓T���E���h�A���v������DVD�J�[�i�r�܂ł�����悤�ɂȂ�܂�������ˁB
�@�ŐV��GTR�ł�(CD���AM/FM�d�q�`���[�i�[���W�I�A11�X�s�[�J�[�AMP3/WMA�Đ��@�\�j
�@HDD�i�r�͂��ꂱ���p�\�R���ɂ�����悤�Ȑ��\�ł�����B
�@32GTR��͌Â�ALFA�ɏ���Ă��܂����ACD�����t���Ă���܂���B
�@���̔ł��b���Ă��܂����A�u�G�[�W���O�v���i�ނƎ��̂悤�Ȑl�Ԃ͂ǂ����V������
�@�ɂ��Ă������Ƃ��A�Â����˂�������Ă��܂��悤�ł��B
�@�s���A�p�@����|���R�c�A�Ԃ��l�Ԃ��ł���͂���ŗǂ��o�����X�Ȃ̂����m��܂���B
�����ԍ��F8037995
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
���E�������
���������[�U�[��Ώۂɂ������i�J���́A�I�[�f�B�I�@��S�̂̎��I�A�b�v�ɂ��q����܂��B
�������̓��J��X�y�b�N�ɂ�����ςȂقƂ�ǂ���܂��A�����炭�����ɉ��ƃf�U�C���Ǝg������ɂ���ď��i��I�����܂��B
������ɂ���ċZ�p�ʂ̔\�����Ŕ��낤�Ƃ������i�́i�n�C�G���h�@�������āj�쒀����A�g�p�ҏd���̎p���ɕς��ł��傤�B
�����w�̕��������I�ŃX�g���[�g�ł������A���X�g�������Ԃ�A���[�J�[���ɂ͌������J�����ɂȂ�ł��傤�B
�d�����A���y�D���ȏ�������̐E��ł����I�[�f�B�I���Ƃ��Ȃ�Ɗe�l���Ȃ荷������܂��B
���͂̊�ɂ��炳�ꏗ���Ƃ��Ă̓���Ƃ̃o�����X���Ƃ�̂͑�ςȗl�ŁA��ɂ���v���ł����X�̗l�ɂ͂����܂��A
���ʁAC/P�܂߂Đ��i��I�Ԍ����͋����ׂ����̂�����܂��ĎQ�l�ɂ����Ă��炤���Ƃ����X����܂��B
���鏗���͍w�����@���l���Ă܂��āA�������@�̓I�[�N�V�����Ŕ��i��T���Ă��烁�[�J�[OH���A
�X�s�[�J�[�͓X���������Ă����ē���������Ă���l�A�����āA2�N�z���ő�����AV�Z�b�g�ɂ͋������܂����B
MYRYAD��AV�v��+5ch�p���[�A���v�ATEAC�̃��j�o�[�T���E�v���C���[�ɁADYNAUDIO�̃X�s�[�J�[�ł��B
Musical-FidelityA3.5�V���[�Y�̃v�����C���{CDP��KEF�̐��XQ��炵�Ă��鏗�������܂��B
��L�̂ӂ���͓Ɛg�ł������O�I�ł����A�唼�̏����͂��������n�C�E�R���|�Ń~�j�R���|�{iPod���قƂ�ǂł��B
�ޏ������ɋ��ʂ���̂́u�����I�v�u�ז��I�v�ƁA�����[���ł��B
�t�@�b�V�����A���s�A�H�����嗬�ł��傤���A�Ȃ��ɂ͒�����痂����������܂��B
����Ȕޏ�������U���������I�[�f�B�I���i�E�E�E���Ȃ������������܂��B
130theater����@�A����ɂ��́B
�����A�ӂƋC���t���܂����B�s���A�I�[�f�B�I��AV�̊W�͎Ԃɒu����������̂ł͂Ȃ����ƁI�B
��AV�A���v�͂܂��Ƀ~�j�o���ł���e��T���E���h�t�H�[�}�b�g���Đ��ł��āA�ܘ_2ch�̃s���A�I�[�f�B�I�����������̍Đ��͂n�j�ƂȂ��Ă��܂����B
����͂肱�ꂩ���AV(�~�j�o��)���嗬�A�s���A�I�[�f�B�I(�Z�_���E�X�|�[�c�J�[)���嗬�ɂȂ鎖�͂Ȃ��ł��傤�B
�f���炵���\�����Δ�ł��B�[���ł��܂��I�ł��܂��I�i�j
�N���y���ނ̂��E�E�E�{�l�̈�l�̂���Ƒ��F���y���ނl�̂̐����̂��̂��ω����Ă�̂��Ǝv���܂��B
�f���Ƃ����傫�Ȍ�y�W�������̒����@��Ƃ��āA��������x������n�C�G���h�܂ł���ɉ��i�тƏ��i�Q�͍L���肻���ł��ˁB
SUV���Ⴀ��܂��u���[�e�B���e�B�v���܂��ɃL�[���[�h�ŁA�Ԉ���Ă��u�R���p�`�v�ł͂���܂���B
�u�R���p�`�v�Ƃ����\�����̂��炵�ă��[�J�[���i�����܂߁j�}�j�A���@���ɂ��̎�̐��i���y���݂Ă������f���܂��B
�l�I���W����
���@�s���A�p�@����|���R�c�A�Ԃ��l�Ԃ��ł���͂���ŗǂ��o�����X�Ȃ̂����m��܂���B
�I�[�f�B�I�������Ԃ��u���b�N�{�b�N�X�����i�݉߂��ĘM���ėV�Ԗʔ����������Ă��܂��܂����B
�����Ԃ̕��͂��y���ݗl�ɌÂ�VOLVO�ŗV��ł܂����n�C�e�N�Ԃ�肱����̕��������������Ă܂��B
�I�[�f�B�I�́E�E�E�|���R�c�ւ̎v������Ɠ����ɖO���Ȃ��~���u�ǂ����Œ��������v������̂ŐV�������̂ɂ��ڈڂ肵�Ă��܂��܂��B
�ߑ��̂Ȃ��̂��A�����ɂ������炵��(^^�U
�����ԍ��F8044343
![]() 0�_
0�_
redfodera����A�����́B
�@���́A�Ԃ�VOLVO��850�ł��傤���H����T-5R�̃G�X�e�[�g�������ǂ����Y����
�@������܂����B�����A�V�Ԃ̎��͂�͂荂�������ł��ˁB
�@�M�^�[�e���̍��A�y��ԂƂ���144�̃|���R�c�ɏ���Ă܂����B
�@�Ԍ���p���݂̂ŏ���܂������A���ꂩ��U���L������܂������H
�@�g���b�N���̊�䂳�͎��D�݁A�d���n�����܂����������ȊO�͖ڗ������g���u����
�@���������ł��ˁB
�@���p��ALFA�����Ȃ�̃|���R�c�ł��B
�@�Ԃ��I�[�e�B�I�Ɠ����ŁA�F�l�E�m�l�̂�������⒆�Â���ł��B
�@�B��V�ԂŔ��������Ƃ̂���̂�32GTR�݂̂ł��B
�@���ݎs��ɏo����Ă���V�ԁE�I�[�f�B�I�V���i�Ƃ��ɁA�u����́I�v�Ǝv�킹�镨��
�@�����ł��ˁ`�B
�����ԍ��F8047800
![]() 0�_
0�_
�l�I���W����A����ɂ��́B
�F����A�E�������Ⴂ�܂���������������<(_ _)>
���Ԃ�VOLVO��850�ł��傤���H
92�N���̍ŏ�����854�i�Z�_���j��5�C��NA20�o���u�̋��S�ł�(^^�U
�s�j���t�@���[�i�v���̂��̂̃��f���Ń}�C�i�[�`�F���W��Ƀo�J���ꂷ��O�̌��^�C�v�ł��B
�v���t�B�[�����̎ʐ^���Â��̂ŕ������ł����t�����g�E�r���[���قȂ�܂��B
15�N�����ł���12��km�ɓ͂��ĂȂ�854�Ȃ�āA�Ђ��������240���[�U�ɏ��Ă܂��B
http://kuruma-guide.jp/850/
5�C��NA20�o���u�̓|���V�F�̐v�����G���W���ŗʎY��VOLVO���ЂƂ������ƂɂȂ��Ă��܂����A
���͍ŏ�����1500�q�����V���b�c�g�K���g�����ł��ă|���V�F���J�X�^���ŃG���W����g�ݏグ�Ă܂����B
�s�j���t�@���[�i�[�{�|���V�F�̃R���{���[�V�����͂��ꂵ���Ȃ��ȋ��S�Ȃ̂ň�������܂����B
���M�^�[�e���̍��A�y��ԂƂ���144�̃|���R�c�ɏ���Ă܂����B
�����p��ALFA�����Ȃ�̃|���R�c�ł��B
�a���I144�����g���ł������B�y��Ԃ��ĂƂ�������т�܂��˂��B
�ł��l�I���W�����Vow!Vow!���邳��ALFA�̕��������������ȋC�����܂��B�����ł����c
�����ݎs��ɏo����Ă���V�ԁE�I�[�f�B�I�V���i�Ƃ��ɁA
���u����́I�v�Ǝv�킹�镨�͖����ł��ˁ`�B
�Ԃ͌��Ȃ��悤�ɂ��Ă܂����A�I�[�f�B�I�͖ڈڂ肵�܂��A���ɏ������̂́c(^^�U
NuForce�́uicon�v��PC�p�ɔ������Ⴂ�܂����I������WADIA�́uiTransport�v�ƈꏏ�ɁI�I
North Star Design�̃Z�p���[�gCDP�̎x���������ꂩ��Ȃ̂Ɂc�ǂ����܂��傤�i��j
�����ԍ��F8048142
![]() 0�_
0�_
�@130theater����A�l�I���W����A����ɂ��́B�u�s���A�I�[�f�B�I��AV�̊W�͎Ԃɒu����������I�v�Ƃ����̂́A�a�V�Ȍ������Ǝv���܂��B�E�E�E�E���A�܂��Ƃɐ\����Ȃ��̂ł����ǁA�P���Ɂu�u����������v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł͂Ɗ����Ă��܂��i���߂�Ȃ����j�B
�@���͂��܂�N���}�ɋ������Ȃ��̂ŁA�������s���g�O��̂��Ƃ������Ă��狰�k�ł����A�~�j�o���̍w���w���Ė{���Ƀ~�j�o�����ΓI�ɕK�v�Ƃ��Ă���̂��낤���ƁA�^��Ɏv�����Ƃ�����܂��B�ߏ��̎�v�w�Ȃ�Ďq�������炸�����q�������\����Ȃ��Ƃ����̂ɁA�ł������~�j�o�����ŋߍw�����܂����B�ނ�H���u��͏������˂���Č�������Ȃ��ł������[�B�C�U�Ƃ������ɂ̓N���}�ɂ͂���������Ă�������ו���ς߂�������S�ł��悧�[�v�Ƃ̂��Ƃł����A���́u�C�U�Ƃ������v��������Ă��邩�肩�ł͂Ȃ��̂ɁA�킴�킴�Ԍɓ���ɂ���Ԃ��|�����^�Ԃ����Ă̂́u�������ȁ[�v�Ɗ����Ă��܂��̂ł��B
�@4�l�܂ł̉Ƒ��Ȃ�Z�_����5�h�A�ŏ\�����Ǝv�����A�E�`�����̔��f�ɂ��5�h�A�n�b�`�o�b�N�����Ɨp�ԂƂ��Ă���܂����A�ו���l����ڈ�t�l�ߍ��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃɒ��ʂ��č��������Ƃ͈�x������܂���B
�@����AV�ƃ~�j�o���Ƃ̑���_�́AAV���Ƒ������Ċy���߂�Ɠ����ɓƐg�҂ł��\���Ɏ��v������̂ɑ��A�~�j�o���͉Ƒ����o�̃C�x���g�ɂ͗L�v�����Ƃ�҂̃h���C�o�[�ɂƂ��Ă͊��S�Ɏ��ė]���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�펞��������̉ו���ςޕK�v�̂���g�p�҂������A�Ɛg�h���C�o�[�ɂ̓~�j�o���͕s�����ł��B
�@����ƁA�l�C�x�Ɍ���Ίm����AV���~�j�o�����s��̕]���͗ǂ��ł��B�������AAV���~�j�o���Ȃ�s���A�E�I�[�f�B�I�͍����\�Z�_����X�|�[�c�J�[�A�~�j�R���|�͌y�����Ԃɑ�������Ƃ��āA�J���[����v���~�I�݂����ȁu�̂Ȃ���̑�O�ԁv�ɑ���������̂�AV�ƊE�ɂ͈�т������i�W�J�������܂���B�m���ɈȑO�قǁu��O�ԁv�ɑ���j�[�Y�͑����͂Ȃ����̂́A�J���[���̔���グ�����͈ˑR�Ƃ��ĕ���܂���B�����āA�t�B�b�g�⃔�B�b�c�̂悤�Ȍy�����Ԃ������傫�������悤�ȏ��^�Ԃ��悭����Ă���ƕ����܂��B
�@�����ăI�[�f�B�I���N���}�ɂ��Ƃ���A���͂��́u��O�Ԃ⏬�^�Ԃ̃��[�U�[�v�ɑ�������Z�O�����g�����C���E�^�[�Q�b�g�ɂ���ׂ����ƍl���܂��B�܂�A�N���}�͕K�v�����y�����Ԃł͑��肪������Ȃ��A�~�j�o���ł͈�l�ŏ�鎞�Ɏ����ʓ|���A���Ƃ����č����Z�_�����قǂ̗\�Z�͂Ȃ����A�X�|�[�c�J�[�͈���������E�E�E�E�Ƃ���������҂ł��B�����AV����уI�[�f�B�I���i�̎g�p�҂ɓ��Ă͂߂�ƁA���y��ǂ����Œ����������~�j�R���|�ł͕͗s���AAV�V�X�e���Łi���y�ӏ��Ɂj�}�g���ȉ����o�����Ƃ���ƍ��z���i���K�v���A�������n�C�G���h�̃s���A�E�I�[�f�B�I�@��͎肪�o�Ȃ��A�Z�p�ʂł̒m�����K�v�Ƃ����}�j�A�������i����Ɣ�肽���E�E�E�E�Ƃ��������[�U�[�ł��B
�@��̓I�ɂ́i�O���猾���Ă���悤�ȁj����Ȃɍ����Ȃ��ď����ɂ���Z���X�̗ǂ��O���Ǝg���₷���T�C�Y������A�������~�j�R���|���͊i�i�ɉ��̗ǂ��V�X�e�����]�܂�܂����A�d�v�Ȃ̂́u������v�ł��傤�B���̂���̌����Ă����̓s���A�E�I�[�f�B�I����AV���s�����Ă��܂�����A�e�ƒ�̃��C���E�V�X�e����AV�ł��B�������T�u�E�V�X�e���Ƃ��ĂȂ�s���A�E�I�[�f�B�I�����荞�ޗ]�n������܂��B�Ƒ��Ŋy���ނ��߂�AV�V�X�e�����u���Ă���ꏊ�͂����Ă����Ԃł����A������Q���ł͉����Ɍ��肵���@�킪�K�v�ɂȂ�P�[�X������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Œ������߂̏��U��ō����\���n�C�Z���X�Ȑ��i�Ȃ�A���Z�͂���Ǝv���܂��B
�@�܂��A�������N���}�̎s��ɗႦ��u�N���}���^�]���������[�U�[�v���Ȃ���Θb�ɂȂ�Ȃ��̂Ɠ������A�I�[�f�B�I�ɂ��Ă��u�ǂ����ʼn��y���y���݂�������ҁv�����Ȃ��Ɖ����n�܂�܂���B����ɂ��Ă��e���[�J�[�͍H�v���Â炵�ė~�����ł��B
�����ԍ��F8049660
![]() 0�_
0�_
�@redfodera����A����ɂ��́B
�������w�̕��������I�ŃX�g���[�g�ł���
�����A���X�g�������Ԃ�A���[�J�[���ɂ�
���������J�����ɂȂ�ł��傤�B
�@���ꂪ����ׂ��p���Ǝv���܂��B���Ԃ̍����I�[�f�B�I���[�J�[�̊J���w�͎s�ꂪ�k�����ċ�J���Ă���Ǝv���܂��B�ł��A�ǂ��̋ƊE�ł��u�������͂���Ȃɋ�J���Ă���I�v�Ƃ��ڂ��Ă��邾���ł͐M�p����܂���B���́u��J�v��������̕����Ȃ�Ή����Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�������Ȃ��Ȃ����̂Ȃ���̃I�[�f�B�I�t�@���ɖ�������荞�ނ��߂́u��J�v�Ȃ�A��͌����Ă��܂��B�����܂ł��L�͈͂ȏ���҂̐S�𑨂��邽�߂́u��J�v�łȂ���u�k�J�v�ɏI��邾���ł��B
���唼�̏����͂��������n�C�E�R���|�Ń~
���j�R���|�{iPod���قƂ�ǂł��B
�@���̎��͂������ł��B�ł��A�ޏ������̓s���A�E�I�[�f�B�I�̉��������Ƃ�����܂���B���̂��܂�㓙�łȂ��V�X�e���ł��������Ă��ƁA�����ł��v������������ĉ��y���Ă���҂ł���A���Ȃ��Ƃ��~�j�R���|���͂����ƃO���[�h�̍������ɁA�K�������������܂��B
�@�������u�����I�v�u�ז��I�v�ƈ�ɕt�����P�[�X������ł��傤�B�O�ɂ��������Ƃ���A���{�l�ɂ͖{���̉��y�D���͑����͂���܂���B�ł��A���ۂɃV�X�e���̉��ɐڂ���A�s���A�E�I�[�f�B�I�̑��݊��Ɉ�ڒu���悤�ɂȂ鏗���͐���܂��B���܂Łu�����ɃI�[�f�B�I�͕�����Ȃ���v�Ƃ���Ƀ}�j�A�b�N�Ȗ�Y�����Ƀx�N�g���������Ă������[�J�[��f�B�[���[�̎p�������ł����������ł��傤�B
�@�Ƃɂ����A�c����͂��ߐ̋C���̃I�[�f�B�I�t�@���͌������ł��B���[�J�[���f�B�[���[�����i���Ă������Ŏs��J���ӂ��Ă���A�����́u��̃I�[�f�B�I�v�͉䂪��������ł���ł��傤�B�I�[�f�B�I�����S�ɁuAV�̏]�����v�ɂȂ��Ă��܂��u�����v�������ł��扄�����邽�߂Ɂi�j�A�C���t����]�����Ă������悤�ȋC�����܂��B
�@North Star Design�̋@��̃f�U�C���͍D���ł��B���̂��炢�̃��x���̊O�����A���Y�i�ɂ����҂������Ƃ���ł�(^^)�B
�����ԍ��F8049678
![]() 0�_
0�_
���E�������A�����́B
�����܂Łu�����ɃI�[�f�B�I�͕�����Ȃ���v�Ƃ���Ƀ}�j�A�b�N�Ȗ�Y�����Ƀx�N�g���������Ă���
�����[�J�[��f�B�[���[�̎p�������ł����������ł��傤�B
�����ł��B
���܂�C�z������Ƃ����Ԃ�s�ꂪ����������ł��傤�ˁB
���E���������A�h�o�C�X����Ă܂������A�����O��Moniter Audio�w���ŃX���𗧂Ă������̕����o���Ă�����Ⴂ�܂����H
�ǂ������j�o�[�T���E�v���C���[�̏����s�ǂ炵���̂ł����A���[�U�E�T�|�[�g�̑Ή����F�����Ȃ������l�ł��B
�������������܂܂���ƁA��������������ɂ��鏗���̃I�[�f�B�I�E�t�@���������Ă���܂���ˁB
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8039064/
�����ԍ��F8050224
![]() 0�_
0�_
���E�������A������������܂��B
�@�ǂ��ɂ��A�u�ȁ`����āEaudiofan�v�Ȏ҂ł�����A�����ɒE�������Ă��܂��܂��B
�@�\���������܂���B
�@�uaudio�ƎԔ�r�_�v�u�����ւ�audio���i�W�J�_�v�����Ƃ����[�J�[�̐l�ɓǂ܂�����
�@����ȔM���b�ɂȂ��Ă��܂��ˁB
�@�G���W�j�A�[�Ƃ���audio���i�J���Ɍg����Ă��鏗���̕���m���Ă��܂��B
�@���̕��́A�d���Ƃ���audio�����Ƃ͂����Ă��A����قlj��y�ɋ�������������
�@�Ȃ�ł��B
�@�ޏ��̎�́u�g���C�A�X�����v�Ȃ�ł����A���]�ԉ^�т�T�|�[�g�����邽�߂�
�@���o����邱�Ƃ�����܂��B
�@�ޏ��H���A�uaudio��v�Ȃ�Ĕn���݂����I�������ł��B
�@��͂菗���́A�����I
�����ԍ��F8050984
![]() 0�_
0�_
�@redfodera����A�l�I���W����A����ɂ��́B���̃X���b�h�ł͂ǂ�ȒE����OK�ł��i�j�B�����뎄���ߋ��ɂ������̃{�[�h��������֎~������H������u�E����Y�v�ł�����i���� ^^;�j�B
�@���[�U�[�T�|�[�g�͌ڋq�Ή��̊�{�ł����A�ŋ߂́i�ǂ��̈�ʏ���Ҍ����̋ƊE�ł��j���̓I�Ƀ��x���������Ă��Ă���Ǝv���͎̂������ł��傤���B�ڐ�̔���グ�⊔������ɋC������A�������甄����ςȂ��ŁA�J�l�ɂȂ�Ȃ��A�t�^�[�T�[�r�X�͌�B���}�j�A�ւ̑Ή�����肪�N���[�Y�A�b�v����A�A�t�^�[�t�H���[�̏[���ɂ��D�njڋq���͂�����Œ������I�ȗ��v���m�ۂ��悤�Ƃ������S�ȃ}�[�P�e�B���O�͉e����߂Ă����悤�Ɋ����܂��B
�@�����^���Ɠd�ʔ̓X�̕s�K�ȑΉ��ɕ������������Ƃ�����܂��B�u����������̃e���r�����������H�@�����E�`�̗����x����Ȃ����āA���q���ǂ����ɂԂ�����Ȃ����X���H�v�Ƃ����Z���t�ɂ́A������炿���ǂ��ē��C�ł��ƂȂ���������Ȏ��ł��i�� ���炱��� ^^;�j�A�傢�ɋC�����Q���܂��B
�@�E�E�E�E����͂��Ă����A�������[�U�[�̊J��ɂ́A�]���^�̉Ɠd�ʔ̓X�ł̓W�J�����f�p�[�g��t�@�b�V�����r���ɂ����鋒�_��肪��ł͂Ȃ����E�E�E�E�Ǝv����������܂��B
���G���W�j�A�[�Ƃ���audio���i�J���Ɍg�����
�����鏗����m���Ă��܂��B���̕��́A�d���Ƃ�
����audio�����Ƃ͂����Ă��A����قlj��y
���ɋ��������������Ȃ�ł��B�i�����j�uaudio
����v�Ȃ�Ĕn���݂����I�������ł��B
�@�����A�����q�h���ł��ˁB�܂��A�������߂鎖�Ə��̐��i�E�T�[�r�X���C�ɓ���Ȃ��]�ƈ���������������E�E�E�E�Ȃ�Ă��Ƃ͂悭����b�B�������ċߐ�̏��i�E�T�[�r�X�����ׂėD��Ă���Ƃ͎v�����Ⴂ�܂���B���ɂ́u�����Ⴑ��Ⴀ�B�悭����Ȃ��̔���o����ȁB�ӔC�ҏo�Ă��[���I�v�ƌ��������Ȃ�悤�Ȃ��̂�����܂��B�ł�����͎��������i�J���Z�N�V�����ɑ����Ă��Ȃ����疳�ӔC�ȃO�`�����ڂ���̂��Ǝv���܂��B�J������ɂ���A���́A�i���Ƃ��Ë���]�V�Ȃ�����悤�Ɓj���Ȃ��Ƃ������̔[������悤�ȏ��i�����������悤�Ƃ��Ă���͂��ł��B���āA���̏����J���҂͍ň��ł��B�Ⴆ�Č����A�����������ȗ����l�⌚�z�ɋ����̂Ȃ���H�݂����Ȃ���ł��傤�B
�@���Ԃ̃��[�J�[�́u�����̊������厖���v�ȂǂƂ����X���[�K���ŁA�P�Ɂu�J������ɏ��q��u���Ƃ��I�v�Ƃ������ڂ����̐l�������Ă���̂��Ƒz�����܂��B���ꂶ����{�̃I�[�f�B�I���_���ɂȂ�͂��ł��B���Ƃ���SOULNOTE��[�[���N�����c�̃X�^�b�t�́A���y���D���ōD���ł��܂�Ȃ��l�q����Ɏ��悤�ɕ�����܂��B���������u�O�x�̔т�艹�y���D���v�Ƃ����ʎq���W�߂Ȃ��ƁA����҂����S������@��͏o�����A�i���ɊC�O���[�J�[�̌�o��q���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�g���C�A�X�����D���̔ޏ��́A���ЂƂ��c�Ƃ̑����֔z�u�]�����Ă��炢�A�̗͏����̖铢�����삯�ˌ��Z�[���X��簐i���Ă��炢�������̂ł��B
�����ԍ��F8053320
![]() 0�_
0�_
���E�������A������������܂��B
�@���������s���������ł����E�E�E�A�����܂�audio�������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A����
�@�P�[�u���I�^�N�E���l�I�^�N�E�����I�^�N�Ƃ����ނ́uaudio�}�j�A�v��
�@�u�n���݂����I�v�Ə��Ă���킯�ł��āE�E�E�E�E�B
�@�ޏ����g�}�j�A�ł͂Ȃ��ł����A��͂葊���̋@��Ń��[�~���Ȃǂ��Ă���炵���H
�@�]���X�̑���Ȃ������t�̑���Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F8055528
![]() 0�_
0�_
�@�l�I���W����A�ǂ��������������ŏ����������悤�ł��i���j�B
�@�ł��A�P�[�u���}�j�A�␔�l����}�j�A�ɂ͍��������̂ł����ǁA������˂��l�߂邱�Ƃ̓I�[�f�B�I�̑�햡���Ǝv���܂��B�@�퓯�m�́u�����v�͑����̏ꍇ�Ȋw�I�ȗ��t�����قƂ�ǎ��Ȃ�����ł�����A���ꂾ�����[�U�[�̊��ƌo�������m�������܂��B�傢�ɂ�����肽���Ǝv���܂�(^^)�B
�@����ɂ��Ă��A���[�~���ł����B���ɂƂ��Ẵ��[�~���ƌ����A�r��R���ł��B�Ԉ���Ă����C�J�R���ł͂���܂���i���j�B�^�I�[�f�B�I�t�F�A�ɂ����ăA���@���M�����h�̃n�C�G���h�X�s�[�J�[�ōr��R���̉��N�̃q�b�g�Ȃ�炵�Ă���̂������Ƃ�����܂����A�D�ꂽ���y�\�t�g�ł��邱�Ƃ��Ċm�F���܂����B�E�E�E�E�ł��A���F�́g���s�́h�ł��B������̔ޏ����A�J���X�^�b�t�ɉ����ɂӂ��킵�����y�̎�������ė~�����Ǝv���܂��B
�@�Ƃ���ŁA�i�ʃX���b�h�ɂ������܂������j���{�̃|�b�v�X�̃f�B�X�N�̉����̓q�h���ł��ȁB80�N��ɂ͑f���炵�����̂�����܂������A���⒜���̈�r�ł��B����A�E�`�̉Ō䂪�u�h���J�������������v�Ƃ����̂Ń����^���V���b�v����CD����Ă��܂������A���܂�̉��̈�����5���ƒ����Ă����܂���ł����B���������AMISIA�̃f�B�X�N���ꖇ�����Ă���̂ł����A���H�[�J���̒�ʂ��s���R�ɂ܂�Ȃ��A�������Ԓ����Ȃ�CD�ł��B�h���J���̃��H�[�J���ɂ��Ă�MISIA�ɂ��Ă������ĉ͉̂���ł͂Ȃ��̂ɁA����Ȓ�x���̉����ł�����ʃ��X�i�[�ɓ`���Ȃ��̂́A���y�\�t�g�̍��肪�~���[�W�V�������y�����Ă���Ƃ����v���܂���B���Â�J-POP�̓s���A�E�I�[�f�B�I�Ƃ͉������W���������Ɗ����܂��B
�����ԍ��F8058838
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ����́B
�l���I�[�f�B�I�ɋ������������͖̂�22�N�O�A���w3�N���̎��ł����B
�N���X�ŁA���Z�Ɏ�����R���|���Ă��炦��Ƃ����b�ł�������
�ŁASONY��LIBERTY �@PIONEER�̃v���C�x�[�g�@KENWOOD��ROXY
PANASONIC��SC-D�V���[�Y�B��Ԑl�C��SONY�ł����B
�Ȃ�Ƃ����o�J�Ȃ��獂�Z�ɓ��w�����߂��l���I�̂�ROXY-CD3�ł����B
�I�v�V�����ŃO���C�R�ƃX�[�p�[�E�[�t�@�[�͂��N�ʂƏ������ŁA�g�[�^��
15���~���炢�������Ǝv���܂��B����܂Ń��W�J�Z���������ĂȂ������l��
�~�j�R���|�Ȃ���A
���߂Ă̐�p�@�̉��Ɋ��������̂��o���Ă��܂��B
�F�l�������Ă���LIBERTY�̓����R���t���ŁA�{�����[���܂Ń����R���œ���
�̂����āu�����`�I�I�v�Ȃ�Č����Ă��悤�Ɏv���܂��B
���ꂱ�ꎞ�������A�����w���̑��q�►�����͈ꉞ�ɉ��y�ɋ���������
�����܂����������܂ŃA�[�e�B�X�g�D��ŁA������Ȃ��A�̂�����������
�����݂����ł��B���͂Ƃ������j������ȏ�Ԃł��B��X�̎���͐悸�}�V�[���B
���C�ɓ���̃}�V�[�������邩��CD���B�Ȃ��������Ⴂ�܂��B
���q�►�B�A���܂��ɂ͌g�т̃`���J�`���J�������Ŗ炷�n���ł��B
�u����ȉ��y�͉��y����Ȃ��I�v�Ƃ���������ł��܂��܂��B
�v�́A��y�ɂǂ��ł��Ȃ�ł����y���Ă��܂������A�I�[�f�B�I����Ƃ�����
�l���������}�V�[���łƂ����T�O��ǂ�����Ă��܂��Ă���̂�������܂���B
���Ƃ͉f�������ӂ�Ă���̂������̂ЂƂ��Ǝv���܂��B�ڂ���̏�����Ɛl��
������̏���낻���ɂȂ�܂��B���͗c���p�̊G�{���Ă�DVD���t���Ă��܂��B
���e���f���d���ł��B
�l��̗c���̍��A�G�{�ɕt���̂̓\�m�V�[�g�ł����B�i�ÁI�j
���͂��ꂪ�悩�����ƍ��ł͎v���܂��B�f�����Ȃ����A�G�{�̓����Ȃ��G�����߂Ȃ���
�����������܂��ĕ����Ă��܂����B�L���ł͓���Ō��Ă������̂悤�ȍ��o�܂ŋN�����܂��B
16�C���`�̃u���E���ǂ̃��j�^�[�ł��A7�C���`�̎Ԃ̃��j�^�[�ł��A������������ďW������A
�������u���悯��Ήf��قɂ͈����͊����Ȃ��͂��ł��B
�ʏ�̃e���r�����ɉ����͋��߂܂��A�f�����������̂͂Ƃ��Ă����������Ǝv���܂����A
��͂肹�߂Ď����̍D���ȃA�[�e�B�X�g�̋Ȃ��炢�́A�������ŕ����Ăق����Ǝv���������̂���ł��B
���l��MISIA��D���Ń��C�u���A�N�s���Ă��܂����A��͂���̉����́A�����n�C�p���[��
�����邾���BBD���o�Ă��܂����ADVD�̉������ň��������̂ŁA���҂ł����ɍw���ɓ��ݐ�܂���B
J-POP�Ȃ͍ŋ߂̂ł������قǁA�����ɂ͊��҂ł��܂���B
�Ђ��傤�ɒ��X�Ə����Ă����܂���ł����B
�����ԍ��F8059495
![]() 0�_
0�_
�@�Ă���28��������A����ɂ��́B
����X�̎���͐悸�}�V�[���B���C�ɓ����
���}�V�[�������邩��CD���B
�@�����Ə�̐���ł��鎄�́i���j�A�X�e���I���~�����������R�́A�Ƃɂ������R�[�h������������������ł��B���ɁA�䂪�Ƃ̓X�e���I���Ȃ��̂ɂȂ������R�[�h��100���ȏ�����݂��Ă���A����͎������w���̍����畃�e���u�����X�e���I���͂�������A���R�[�h�����ɑ����Ƃ��v�݂����ȈӖ��s���̃m���Ŕ����W�߂����̂ł����A�Ƃɂ����u���̃��R�[�h�ɂ͂ǂ��������������Ă���̂��낤���v�Ƌ����ÁX�ł����B�ŁA���ۂɃI�[�f�B�I�V�X�e�����Ƃɂ���Ă����̂́A�Ă���28��������Ɠ������������Z�ɓ����Ă���ł��i�j�BDIATONE�̃X�s�[�J�[��TRIO�i����KENWOOD�j�̃A���v�ɂ��V�X�e���ŁA���߂Ă��̃L�����ǂ��O�ɏo�鉹�ɐڂ����Ƃ��͊����������̂ł����B
�@���āA�u�A�[�e�B�X�g�D��ŁA������Ȃ��A�̂����������ł����v�Ƃ����̂́A��ʂ̎Ⴂ���X�i�[�ɂƂ��āA�����̂�����قǕς��Ȃ��p�����Ǝv���܂��B�����뎄�����������������������̑����͂����ł�������(^^;)�B�������A���̍��ƌ��݂Ƃ�����I�ɈႤ�_�́A���y�\�t�g�̃T�E���h�̎��ł��ˁB�̗̂̉w�Ȃ́A������W�J�Z�ł������܂����ǁA�Đ����u�ɃJ�l����������ꂾ���㎿�ȃp�t�H�[�}���X���I���Ă���܂����B�A�R�[�X�e�B�b�N�������S�ŁA�̎�̐����������悤�ȃ~�b�N�X�_�E�����{����Ă������̂ł��B�n�C�G���h�V�X�e���ʼn��̂⃀�[�h�̗w���y���ރI�[�f�B�I�t�@���������������܂����B�Ƃ��낪����J-POP�́A���������Ș^�������ʂ��Ă��邽�߁A�����I�[�f�B�I�V�X�e���ōĐ�����Ƃ������ăA�����ڗ����A�ƂĂ������Ă����܂���B���Ɉ��k�����S���̌��݂́A���k���Ă�����قǕς��Ȃ����邽�߂��A�ŏ�����X�J�X�J�̉����������Ă��܂���B����͎Ⴂ���y�t�@���ɂƂ��ĕs�K�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�\�m�V�[�g�I�@���������ł��ˁB�c���̍��ɎG���̕t�^�ɕt���Ă��܂����B�ƂɃX�e���I���Ȃ������̂ŁA�ׂ̉Ƃɍs���Ē������Ă�����Ă��܂����i��j�B�e���r�̃q�[���[���́u�ԊO�ҁv�݂����ȓ��e�Ȃ���A�f�����Ȃ������ɘb���r�����m�ŁA���쌠�������悤�ȕ����̃V���[�Y�̓o��l�������藐���Ƃ����A���Ƃ��X�S�����̂��������Ƃ��o���Ă��܂��B���ł������Ă����猋�\�Ȓl�Ŕ���邩������܂����(^^)�B
�@�L��悤�ɁA����ς�z���͂���ł���B�O�ɂ������܂������AAV�́u��ہv�A���ăI�[�f�B�I�́u���ہv�ł��B���ۓI�ȊT�O�𗝉����邱�Ƃ������̔��B�ɍv������̂��ƁA�G�z�Ȃ���v���Ă��܂��������̍��ł��B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�����ԍ��F8067554
![]() 0�_
0�_
���E�������
�ˑR�̊��荞�݂ɂ��ւ�炸�A���e���肾������Ȃ��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
TORIO�̃X�s�[�J�[�ꎞ�����L���Ă��܂����B�^�͂킩��Ȃ���ł����A800MM×600MM���炢��
�傫�Ȃ����̔����Ċ����̌Â����ł����B
�C�ɓ����Ďg���Ă�����ł����A�V�����ƈ��z���̃^�C�~���O�Ŕp���ƂȂ��Ă��܂��܂����B
�����8�N���炢�O�ł��傤���B
���u�A�[�e�B�X�g�D��ŁA������Ȃ��A�̂����������ł����v�Ƃ����̂́A��ʂ̎Ⴂ���X�i�[�ɂƂ��āA�����̂�����قǕς��Ȃ��p�����Ǝv���܂��B
�m���Ɏ���̑������~�j�R���|�����L���Ă�������ł����A�����ǂ������ƌ����Ă�҂�
���Ȃ�������������܂���B�l���g�D���ł͂���܂������A���Z���w����ROXY�̃X�s�[�J�[
���ŋ߂܂Ń��C��SP�Ƃ��Ďg���Ă��܂�������A�I�[�f�B�I���[�J�[�ɂƂ��Ă�
���ȁi�Ȃ��Ȃ������ւ��Ȃ��j���[�U�[�Ȃ�ł�����ˁi�j
30��㔼�ɂȂ��Ă���Ə��ƌ�����Ƃ���̓�����ɁA����Ղ��Ƒ�����ꂽ�����ł��B
�\�m�V�[�g���Ă����̂͗c�����A�e���̉Ƌ�́u�X�e���I�v�ł����B
�G�{�ƃ��R�[�h���ꏏ�ɂȂ����V���[�Y�̕��������Ă�����Ă��܂����B
�悭����ɐG���ăv���[���[�̐j��܂��ē{��ꂽ����ł��B
���̂������R�[�h�v���[���[�ƃX�s�[�J�[����̂ɂȂ�����������݂����Ȃ��
�^����ꂽ�̂͂����܂ł�����܂���i�O�O�j
���܂��C���ǂ߂Ȃ��A�������Ēm�����Ȃ��P�Ȃ�f�V���o����Y�ł����A�A�A
���܂�Ђǂ����͌�w�����������B
�����炱������Ƃ���낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F8070568
![]() 0�_
0�_
������Ə��ƌ�����Ƃ���̓�����ɁA
������Ղ��Ƒ�����ꂽ�����ł��B
�@�ق�̏o���S�Łu����Ղ��Ɓv����Z���ƁA���̒�����肪�o�Ă��Ă��̂܂܃Y�u�Y�u�ƈ������܂�Ă��܂����Ƃ�����܂�����A��p�S��(^^;)�B���ɂ����낢�날��܂��āA���������U�������̂́u�P�[�u�����v�ł����A�ŋ߂́u�d�����v�Ƃ��u�I�[�N�V�������Õi���v�u�C���V�����[�^�[���v�Ƃ������V��̎��n�т��o�����Ă���悤�ł��B����Ƀx�e�����̃I�[�f�B�I�}�j�A�ɂ͍����u�A�i���O���v�Ƀn�}���Đg���������Ȃ��Ȃ��Ă���荇��������݂����ł��B���R�[�h�j���Ƃ��ɐ��\���~�A�v���[���[�{�̂Ɏ����Ắu����ς�Œ�200���~�͏o���Ȃ��Ƃˁv�Ƃ����Z���t�����C�Ŕ�ь�����Ȃ����ł��B�̂̃A�i���O����ł�5���~�ȏ�̃J�[�g���b�W�͍����i�ł������A���̃f�W�^������ɂ����ă}�j�A�b�N�ȏ��ɒЂ��낤�Ƃ����l�����ɑ��ẮA�h���C�ȁu���������v�������͂�����A�@��̍��~�܂�͎d�����Ȃ��悤�ł��i���j�B
�@�b�͕ς���āA�O�Ɂu���{�l�͖{���ɉ��y���D���Ȃ̂��H�v�Ƃ����l�^�U������܂������A����ɂ��Ďv�������邱�Ƃ�����܂��B�ŋ߂̊w�Z�̉��y���Ƃɂ�����u�ӏ܂̎��ԁv�Ŏg���Ă���I�[�f�B�I�@��̃��x�����āA�ʂ����Ăǂ̂��炢�Ȃ̂ł��傤���B�]�Z�̎q���i���w���j�̘b�ɂ��ƁA�~�j�R���|�ɖт̐������悤�ȃV�X�e���Ńh���V�����̉�������Ă���Ƃ��B���t�̕����u�ӏ܂̎��ԁv�́u�x���̎��ԁv�炵���A�������o�čs���Ĉꕞ���Ă��邩�A���邢���ґz�i������H�j�ɂӂ����Ă��邩�ŁA�M�S�ɋȂ̖ʔ����⒮�����������邱�Ƃ͂��܂�Ȃ������ł��B
�@�O�ɂ������܂������A�����̒ʂ��Ă������Z�̉��y���ɂ͐��S���~�̃V�X�e�����u���Ă���A�nj��y�Ȃ��j�]�����点�銆���̗ǂ������o�Ă��܂����B���t���g���I�[�f�B�I�t�@���ŁA���k�ɑ��āu���y���Ȃ��ɃI�[�f�B�I���u�ɂ��Â�Ȃ��ƁA�^�̊����͖��킦�Ȃ����I�v�Əq�ׂĂ������̂ł��B���̋��t�͐l�ԓI�ɂ͌����ȃ^�C�v�ł������i�j�A���̓_�����͑傢�ɕ]���������Ǝv���Ă��܂��B
�@���y�̋��t�ɂ̓I�[�f�B�I�ɂ����ʂ����l�ނ��N�p���ė~�����Ǝv���܂�(^^)�B
�����ԍ��F8078910
![]() 0�_
0�_
�F����ɂ��́B�R�R�~���g�Ɛ\���܂��B��1�e����y�����q�������Ă��������Ă���܂������A�I�[�f�B�I�X�ɍs�������Ƃ��Ȃ��l�ɂƂ��Ă͑�2�e�͂��낢��ƍl���������邱�Ƃ�����������Ă��܂����B
�̕������������I�[�f�B�I�Ƀn�}���Ă����������������炵���A���͕�����p����DIATONE��DS-30B���p���Ŗ炵�Ă��܂��B
�l�͌��ݍ��Z���ł��āA�w�Z�ɂ���I�[�f�B�I�@��Ƃ������ƂŎv�킸�������݂����Ă��܂��܂����B
�l�̒ʂ��Ă��鍂�Z�ł�SP��BOSE��464Westborough�AAMP��DENON��PMA-2000�V�ACDP�ɂ�SONY��MXD-D5C���q���Ŗ炵�Ă���܂��B����ɁA���A����������o��悤�ɂ�Lo-D�̑傫��3WAY(�^�ԕs��)���u���Ă���܂��B
�搶�Ɂu�����̊w�Z�̃I�[�f�B�I���Ă�����ł���ˁv�ƌ����ƁA�u�ׂ̊w�Z�ɂ̓y�A��80����SP���u���Ă����v�Ƌ����Ă���܂����B
�F�B�̒ʂ��Ă������1�̊w�Z��DIATONE������悤�ł�(������^�ԕs���A�����܂���)�B
���Ȃ��Ƃ������̒n��̍��Z3�Z�ł͌��E�������̂��������悤�ȁu�~�j�R���|�ɖт̐������悤�ȃV�X�e���v�ł͂Ȃ����h�ȃI�[�f�B�I�@�킪�u���Ă���܂�(BOSE���s���A�Ȃ�ČĂׂ邩!�Ȃ�ăc�b�R�~�͂Ȃ��ł���)�B�������A�ȑO�ʂ��Ă������w�Z�̃V�X�e���͊m���ɗǂ��Ȃ������ł��ˁB
�����̊w�Z�̐搶���u�ӏ܂̎��ԁv�́u�x���̎��ԁv�ł悭���k���ق����炩���ɂ��Ă͑��̕����֍s�����肵�Ă��܂��B
��قǂ������܂������l�͍��Z���ł��āA���̂悤�Ȍf���ւ̏������݂�3��قǂňӖ��̒ʂ��Ȃ����͂����邩������܂���B���̂Ƃ��͑��߂Ɍ��Ă��������B
����ł͂�낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F8079480
![]() 0�_
0�_
���E�������A�����́B
���̏��w�Z����ɂ͏���I�[�P�X�g��������A�u���Ɏq���������W�߂Ē����������̂ł��B�q���Ȃ���ɂ��A���̉��̔������ɂ͊������܂����B���́A�ǂ�Ȃɓc�ɂɍs���Ă������͑����Ă��܂��̂ŁA�q���̍����琶�̖{���̉�������`�����X������Ă��K�v�������܂��B�����ȂȂ苳��ψ���ϋɓI�ɉ��������ׂ��Ǝv���܂��B�����ɉ��y�́A�ǂ����Ă��K�v�ł����A�A�[�`�X�g�̐����ۏ�ɂ��q����܂��B
��������I�[�P�X�g�����Ă��Ȃ���I�[�f�B�I�t�@���ɂ͂Ȃ�Ȃ������ł��傤�B�����́A�܂��X�e���I�͂Ȃ��A�F�A���m�ł����B�������}�j�A��40cm�X�s�[�J�[��炵�Ă��܂����B����̑��ۂ̉��͖{���ȏ�ŁA�I�[�f�B�I�̑f���炵���Ɋ����������͎�����^�X�s�[�J�[�����L�������Ǝv�������̂ł��B���Ȃ݂Ɍ��݂̎��̃X�s�[�J�[��38cm�ł��B
�����ԍ��F8079489
![]() 0�_
0�_
���E�������
�����́B
���ق�̏o���S�Łu����Ղ��Ɓv����Z���ƁA���̒�����肪�o�Ă��Ă��̂܂܃Y�u�Y�u�ƈ������܂�Ă��܂����Ƃ�����܂�����A��p�S��(^^;)�B
���������肪�Ƃ��������܂��B����n�R�䂦�A�����ȒP�ɂ͏��ɂ͂܂�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��i��j
�����������Ȃ��悤�ɂƍ��A�S��ł���X�s�[�J�[�X�^���h�����쒆�ł��B
�؍ނƓS���g������Ȃ̂ł����A�W�������Ă݂�Ό��ǂ́A���������i���Ă��܂�
�悤�ȉH�ڂɂȂ��Ă���܂��B�������@�I�ɂ��傤�ǂ������̂������i�ɂ͂Ȃ��̂ŁA
����͂��Ă���܂���B�������莞�Ԃ������Ă�������������ł��B
�Ȃ��Ȗ����̐��E�ł�����B�i�O�O�G
�掿�ɂ�����肳��
�����́B
�����̏��w�Z����ɂ͏���I�[�P�X�g��������A�u���Ɏq���������W�߂Ē����������̂ł��B
�l�����w���̎��ɂ���܂����I���ӋC�ɂ��������āA���t��ɏo���҂̕��Ɉ��������
��������̂��o���Ă��܂��B
�����̃V�X�e���ł͓���I�P���Ȃ炷���Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�܂����̌��̎q����A���
�v���Ԃ�ɃI�P�̐����t�ł������ɍs�������Ȃ��Ǝv���Ă����Ƃ��ł����B
�����L���[�b�Ē��ߕt���Ȃ��甲���Ă����悤�ȃo�C�I�����̉���A�����������Ȃ�قǂ�
�V���o���̋������B���Ȃ��Ƃ���Ŕ]�݂���˂������Ă����悤�ȃy�b�g�̉��B
�ݑ܂��{�����Ē@���ꂽ���̂悤�ȃo�X�̉��A
���S�̂̋�C�������ɏ������悤�Ȏ��ɒ��ڕ������Ȃ��d�ቹ�B
��`���܂��\���ł��܂��A
����͎q�������Ɉ�x�͌o�������Ă����Ȃ�������Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�����ԍ��F8083208
![]() 0�_
0�_
�@�R�R�~���g����A����ɂ��́B�������ݗL���������܂��B
�@�ŋ߂̍��Z�ł�BOSE�̃V�X�e���������p�Ƃ��Ēu���Ă���̂ł����B�̂͊w�Z�ɂ���X�e���I�͍��Y�@�����ł����ˁi�܂��A�A������Ă����C�O�u�����h�����قǑ����͂Ȃ������Ƃ������R������܂��� ^^;�j�B�����ʂ��Ă������Z�̉��y���ɂ������X�s�[�J�[��DIATONE�ł����B������A�����Ǘp�̃X�^�W�I���j�^�[�ŁALUXMAN�̐^��ǎ��Z�p���[�g�A���v�ŋ쓮���A�A�i���O�E�v���[���[��Technics�̃^�[���e�[�u���ƃA�[��������L���r�l�b�g�ɑ����������̂��g���Ă��܂����B�J�[�g���b�W�͐���ނ������悤�ł����A���̒��̂ЂƂ��i���͖����jSATIN�ł����B������l����ƁA�悭���܂��\�Z�����肽���̂��Ǝv���܂��B
�@���������A���̐E��̌�y�i30���炢�j�̘b�ł́A�ނ̏o�g���Z�̎����p�X�e���I�́i�������炷��Ɓj���\�N�O�̃|���R�c�������炵���ł����A���t���܂��������C���Ȃ����������ł��B�����������y�̎��Ԃ́u���Ǝ��ԁv�ł͂Ȃ��u���R���ԁv���邢�́u���K���ԁv�������Ƃ��B���t���g�������ɗ������Ƃ��قƂ�ǂȂ������Ƃ����b�B��������O�ɂ́u���K���ԁv�ɂȂ�͓̂��R�Ƃ��āA����ȊO�͐��k���D���ȃ��R�[�h�i�������A�N���V�b�N�ł͂Ȃ����s�́j������Ɏ����Ă��ČÂ����u�Ŗ炵�Ċy����ł����Ƃ����E�E�E�E�B����͂�A�q�h���Ƃ��������������ł��B
�@DS-30B��DIATONE�ł͒������o�X���t�^�ŁA���������\���B�炵�₷���@�킾�Ǝv���܂��B�艿�͈��\42,000�Ȃ���30cm�E�[�n�[���ځA������20kg�Ƃ����d�ʂ́A������͍l�����Ȃ���i�ł��B�E�[�n�[���w�^���Ă��Ȃ���܂��܂��g����Ǝv���܂��B��ɂ��ĉ������B�Ƃ͂����A��x�͐��X�Ƃ��I�[�f�B�I�t�F�A�Ȃɑ����^��ł݂�̂��y�����ł��B�����l�ƈꏏ�ɔ`���Ă݂���A���y�k�`�Ő���オ�邩������܂���(^^)�B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�@�掿�ɂ�����肳��A����ɂ��́B
�@���̎q������ɂ���w�̃I�[�P�X�g�����w�Z�ɗ������Ƃ�����܂��B�u���̋����X�e�[�W�ł͎����nj��y�c���x�̕Ґ������W�J�ł��܂��A����ł����͂̂��鉹�ɐ��k�S�����|����Ă��܂��܂����B���������C�x���g�͕p�ɂɂ���ė~�����ł��ˁB
�@����ƁA�ȑO�e���r�̃j���[�X�ŏЉ��Ă��܂������A�W���Y�̃s�A�m�g���I���Ă��w�Z�����邻���ł��B�W���Y�Ȃ�āA��l�ł�������ɂ����̂Ɏq���Ȃ珮�X�E�E�E�E�Ƃ����뜜�́A���t���n�܂��Ă݂�Ɗ��S�ɐ������ł��܂����Ƃ��B�܂��͂��̊w�Z�̍Z�̂��W���Y�ɃA�����W�B�e���r�̃A�j�����̂�4�r�[�g�ŃV�u�����߁A���y�̋��ȏ��ɍڂ��Ă��镶���ȏ��̂̓n�C�e���|�̃X�g���[�g�A�w�b�h�Œ�������B���k�����t���������ŁA�����ɐ���オ�����l�q������Ă��܂����B����ȍÂ����A������w�Z�ł���ė~�����ł��B
�@�c���̍��̉��y�̌��́A�{���ɋM�d�ł��B���ȏȊW�҂��ϋɓI�Ɏ{���łׂ��ł��B
�����݂̎��̃X�s�[�J�[��38cm�ł��B
�@�������̒��x�̃X�s�[�J�[��������͑��������ł��B��͂�ቹ�̍Č��͂̓E�[�n�[�̌��a�͑傫�����m�������܂��B�E�E�E�E�Ȃ�Ă��Ƃ��v���Ă���ƁA���̊Ԃɂ��uProCable�v�����V�X�e���ɍs�������Ă��܂��悤�ȃI�`���l�����A�Y�݂��s���Ȃ��������̍��ł��i���j�B
�����ԍ��F8083501
![]() 0�_
0�_
�Ă���28��������A����ɂ��́B
�Ă���28��������̂悤�ȍl�����̐e�䂳�����ł���A�f���炵�����̒��ɂȂ�Ǝv���܂��B����A���q�l���R���T�[�g�ɘA��čs���Ă���ĉ������B�N���V�b�N�́A�������܂��Ē����C���[�W������܂����A���N�A�������ۃz�[������5���̘A�x�ɊJ�Â����N���V�b�N���y�̍ՓT[�M���̓�]�͗c��������o���܂����A�z�[���ŐԂ�������Ă�����������܂���B5���Ԃ̃X�e�[�W��400������A�����̂��̂���A�L���̂��̂܂ŁA\2000�~���炢�ł��B������ł��Ɨ��N�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�H�ɂ͖��N�A�W���Y�̍ՓT������悤�ł��B
���͂����ŃI�[�f�B�I�̉����`�F�b�N���Ă��܂��B���N�͂����ŁA�X�g���r���X�L�[��[�t�̍ՓT]��呾�ۂƃe�B���p�j�[�̎��ߋ���6m�Œ����p���[�A���v���ւ��鎖�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�P�[�u�������A���A���̃`���[�j���O�͑S�āA�����̉�����ɂ��Ă��܂��B���̓z�[�����Ƃ̉���Đ����ۑ�ł��B
http://www.lfj.jp/lfj_2008/
�����ԍ��F8085621
![]() 0�_
0�_
���E������J�Ȃ��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
�͂����茾���܂��Ƃ��̉��y�̐搶�͂Ђǂ��ł��ˁB�����̊w�Z�̐搶�̏ꍇ�͊ӏ܂Ƃ���1���ԃr�f�I�Ƃ�����������܂������A���i�͎��Ƃ����Ă���܂�����B���͐i�����ĉ��y�̎��Ƃ���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł����B�������A�l�͐��t�y���ɓ����Ă��ăt�@�S�b�g�Ƃ����y�������Ă���̂ŁA�搶�Ƃ͂܂��t������������܂��B�D�����搶�ł���B�搶�ɂ���č�������̂ł��ˁB
����DS-30B�A���Ȃ�ւ����Ă��ł���ˁc�B�e���]�Α��ŋ����ƂɏZ��ł������Ƃ��������ׂɁA���u(�k�C��������~�́|20���ȏ�ɂȂ�Ƃ���)�ɐ��N�ԕ��u���Ă������Ƃ�����܂��B���̂������͕�����܂��A�Ƃɂ���p�\�R���pSP��SoundSticks�U��肩�Ȃ������������܂��B�X�P�[�����͂���̂ł����A�𑜓x�Ⴗ���A��ɂ����ɂ��L�тĂ��Ȃ��c���X�s��������܂��B�܂��A�����g���Ă����Ƃ��������ƁA�_�炩��(���g���ȁH)�����D�݂Ȃ̂ł����Ǝg���Ă��܂��B
���̓N���V�b�N�̘b��̂悤�ł��ˁB�l�͑O�L�̒ʂ�t�@�S�b�g������Ă���̂Ńt�@�S�b�g�̎����y�␁�t�y�o���h���悭�����ɂ������肵�܂��B����Ƃ��w�Z�ɖ{�i�I�ȃI�P�ɗ��Ă��炢�����ł��ˁB����ɂ���āA�N���V�b�N�͌��ꂵ�����̂���Ȃ��Ƃ����F���������ė~�����ł����A�Ȃɂ�蓯�N��̃I�[�f�B�I�D��������Ă����Ȃ��Ƃ��v���܂��B
������ƑO�ɓ��{�l�͉��y���D���ł͂Ȃ��ƌ������b���o�Ă��܂������A�l�������v���܂��B�l�̒m���Ă��钆�Ŗ{���ɉ��y�̍D���Ȑl�͓����N���X��2�l���邾���ŁA���̉��y���D�����ƌ����Ă���l�����͖{���͂����ł��Ȃ��������Ƃ�������ۂ��܂����B
�������������炵�܂����B���܂��C�̓ǂ߂Ă��Ȃ��悤�ł�����K���ɗ����Ă���Ă����\�ł�(��)
�����ԍ��F8086985
![]() 0�_
0�_
�掿�ɂ�����肳��
������B
������A���q�l���R���T�[�g�ɘA��čs���Ă���ĉ������B
�������Ă�肽���q���B�͂܂��T�ƂS�Ȃ̂ŁA�s����R���T�[�g�ɂ͌��肳��܂���
�Ȃ�Ƃ��K���Ȃ̂����U���ĘA��čs���Ă�肽���Ǝv���Ă��܂��B
���̎q�������͉f�悪�D���ŁA�u�p�C���[�c�I�u�J���r�A���v��u�n���[�|�b�^�[�v
���̑��V����킸�ǂ����Ă���܂��B����ŁA���N��������f�B�Y�j�[�I���N���V�b�N��
�u�p�C���[�c�I�u�J���r�A���v�̑g�Ȃ��v���O�����ɓ����Ă��āA����������Ă�肽��������ł����A
�m�����̂����N�ɓ����Ă���ł����B��̂܂�ł��B
�N���V�b�N�Ƃ����Ɗm���ɕ~�����������ł����A�f�批�y�Ȃ玩�R�Ǝ���Ă��ꂻ���Ȃ̂ŁB�l���g���f�批�y�D���ł����B
�������Ȃ̂ŁA�����߂����������R���T�[�g�͂�����ƍs���ɂ����ł����A
���ɂ��t�F�X�e�B�o���z�[�����ł悭����Ă��܂��̂ŁA���ꂩ�璲�����ĘA��čs������
�Ǝv���܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�R�R�~���g����
�����́B
�����܂��C�̓ǂ߂Ă��Ȃ��悤�ł�����K���ɗ����Ă���Ă����\�ł�(��)
���v����Ȃ��ł����H�l�\�H��ڑO�ɂ����Ƌ�C�ǂ߂Ȃ��l�Ԃ������ɂ��܂�����[�O�O;
���͗͂����Ėl���D��ĂđA�܂�������ł��B
���ꂩ�����낵���ł��B
�����ԍ��F8087681
![]() 0�_
0�_
�R�R�~���g����A�����́B
���t�@�S�b�g������Ă���̂Ńt�@�S�b�g�̎����y�␁�t�y�o���h���悭�����ɂ������肵�܂��B
�����t�@�S�b�g�͑�D���ł��B��������t�ł���Ƃ͑A�܂����ł��B���[�c�@���g�̃t�@�S�b�g���t�Ȃ͗ǂ������܂��B����A�I�s�j�I�����[�_�[�Ƃ��āA���������ˁB�����̓��{��w�������ɂȂ邩���m��܂���B
�Ă���28��������A�����́B
�ǂ������l�������āA���q�l�����͍K���ł��B�₳�����e�v���́A���q�l�Ɉ���A�ԈႢ����܂���ˁB
�����ԍ��F8088037
![]() 0�_
0�_
���E�������ɂ��́I
�Ă���28��������@�����ăR�R�~���g����@�͂��߂܂��āB
�Ă���28��������@�̂����O�ŔN�̂������A�������̂̃A�j���S�l�Q�W����A�z���Ă��܂��܂���(^^)�@�����m�ł����H�@���E��������
��������Ə��ƌ�����Ƃ���̓�����ɁA
������Ղ��Ƒ�����ꂽ�����ł��B
���́w������ՂƁx�����Ȃ肭���҂ŔF�����Ă����ł����̂܂ɂ��O�E�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă鎩���Ɍ�ŋC�����܂��B
���Ȃ��Ȗ����̐��E�ł�����B�i�O�O�G
���ɓD���I�H��������܂����(��)�@�撣��܂��傤�H(^o^)
�R�R�~���g����@DS-30B�����g���Ƃ̎��A���͈ꎞ�����_�C�A�g�[����DS-35B�U�ƌ����̂��g���Ă܂����B���^�ł���������̂����ቹ�ō��ł��o���Ă܂��B
�N���V�b�N�̘b��Ƃ͂��Ȃ肩������Ă��܂��܂���
���l�͑O�L�̒ʂ�t�@�S�b�g������Ă���̂Ńt�@�S�b�g�̎����y�␁�t�y�o���h���悭�����ɂ������肵�܂��B
���̌��R�~�ɃI���W�o���h�����݁H�H�H���܂��B
�l�I���W���N�l�H�Ł@
���E�������́u�L�[�{�[�h�v�Aredfodera����̃x�[�X�A�l�I���W����̃M�^�[�A���̑���(�h�����ƌ����ɂ͘r�O���H)�@�ł��̂ł����ɎQ����������Ȃ�ѐF�̕ς�����A�����ĐV�������y���ł���̂ł͂Ȃ����H�ƈ�l����ɑz�����Ă��܂��܂���(>_<)
�����܂���A�N���S���l���Ă��܂���ł����I
����28���������
������͎q�������Ɉ�x�͌o�������Ă����Ȃ�������Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
���̒ʂ�ł��ˁA�I�P�ł͂���܂����t�y�̃R���N�[���Ɏq����A��čs������������܂������A���i���������̖����q���B���W�b�g��������A�����Đ����A�C�C�i�[�Ɗ����̎p�𖢂��o���Ă��܂��B
�����ԍ��F8089366
![]() 0�_
0�_
�@�|������28��������
�@�X�^���h���䐻�쒆�Ƃ̂��ƂŁA��悪���s��p�Ȏ��ɂ͉��̂Ȃ����E�őA�܂�������ł��B�X�s�[�J�[�X�^���h�̓I�[�f�B�I�V�X�e���ɂ����đ�ȃA�C�e���Ȃ̂ł����A�ӊO�ƃX�s�[�J�[�ƃW���X�g�t�B�b�g�̃T�C�Y�̒u������āA�T���̂ɋ�J���܂��ˁB�����T�u�E�V�X�e���Ŏg���Ă���iQ3���w�������Ƃ����K���Ȑ��@�̃X�^���h�������ĔY��ł����Ƃ���A�f�B�[���[����u�����̂������v��B&W�u�����h�́i�����ȁj�������̒u��������߂Ă��炢�A����������g�p���Ă���̂ł����A���ꂪ���̌�A�b�Ƃ����Ԃɔ�����~�ɂȂ�A�R���p�N�g�^�X�s�[�J�[�̃��[�U�[�ɂƂ��đI�������������݂����ŗ��_�������Ƃ��o���Ă��܂��B
�@�������܂��A�I�[�P�X�g�����͂��߁A�N���V�b�N�̐����t�ɂ����đt�ł���T�E���h�͑N��ŘN�X�Ƃ��ăC���p�N�g�������ł���ˁB�I�[�f�B�I�̐��E�ł͂悭�u�N���V�b�N�����ɂ́A�����}�b�^���Ə_�炩�������А��̃X�s�[�J�[���K���Ă���v�Ƃ����Ƃ��]�_�Ƃ�}�j�A�͌����Ă�悤�ł����A�\�t�g�ő�l�����T�E���h���N���V�b�N�ɓK���Ă���Ƃ́A�K�����������܂���B�ނ���O�֏o��ꍞ�݉s���圤�ȉ��̕����A�N���V�b�N���y�̐^����`���Ă���邱�Ƃ�����܂��B���ɁA�}�C���h�ȃT�E���h�Ń��b�N�̃��H�[�J������肭�\�����Ă���P�[�X���������肵�āA�I�[�f�B�I�V�X�e���Ɂu���������v�Ƃ����J�e�S���[�����͓K���ł͂Ȃ��Ɗ����Ă��鍡�����̍��ł��B�E�E�E�E�Ƃ͌����A���͂��̌f���ł́u���̃X�s�[�J�[�̓N���V�b�N�ɂ͍����܂���v�Ȃǂƕ��C�ŏq�ׂĂ���A��Ȃ��疵���̑����������o���Ă��鎟��ł�(^^;)�B
�@�|���掿�ɂ�����肳��
�@�������ۃt�H�[�����ɂ͍s�������Ƃ��Ȃ��ł��B�����̃R���T�[�g�z�[���ő����^���Ƃ�����̂́A�T���g���[�z�[���ƃI�[�`���[�h�z�[�����炢�ł��i���Ƃ͂m�g�j�z�[���j�B������s���ݏZ�ł͂Ȃ����̂ŁA�Ȃ��Ȃ��o�����܂���B�@�����Έ�x�͍s���������̂ł��B
�@�����t�ɐG��āA���g�̃I�[�f�B�I�V�X�e�����������Ƃ����̂��悭����p�^�[���ł��ˁB�����A�̃A�����J�̖^�L���I�[�P�X�g���Œ������Ƃ��A���̖��邭�����Ɋ������܂������A�����ɂ��̍��f�B�[���[��I�[�f�B�I�G���������グ�Ă����^���Y�A���v�E�u�����h�Ɍ����t���邫�������ɂȂ�܂����B�u���̃I�[�P�X�g���́A���̃A���v���炷�悤�ȏd���ē݂����͏o���Ȃ��B����͉����g�U���h���Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��I�v�ƍ��_���s���܂����B�ł��u�I�[�f�B�I�Ɛ����Ƃ͈Ⴄ�B�I�[�f�B�I�Ő����Ƃ͕ʂ́g�D�݂̉��h���o���Ăǂ��������I�v�Ƃ����ӌ������邱�Ƃ����m���Ă��܂��B��́A�����悤�ȋc�_�i�����h���������h�j���č��Ń}�b�L���g�b�V���Ƌ��}�����c�Ƃ̊ԂŌ��킳�ꂽ�����ł����A�I�[�f�B�I�E�̉i���̘_���ƌ����ׂ����̂ł��傤�B
�@�|���R�R�~���g����
�@�t�@�S�b�g�͐��������Ƃ͂������A�G�������Ƃ�����܂���(^^;)�B������Ƃ����̂͑A�܂�������ł��B���Â��A�Ⴂ����ɉ�����y�퉉�t�����m�ɂ��Ă����Ηǂ������Ǝv���܂��B�܂��A�ᑢ�̍��͌����Ƃ��Ƀo�^�o�^���Ă��āA�ƂĂ�����ȗ]�T�͂Ȃ�������ł����ǂˁi���j�B��N��i���܂��܂���̘b�ł����j�́A���}�n���y�����̃V�j�A�R�[�X�ɂł��ʂ������Ǝv���Ă��܂��B
�@�u�{���ɉ��y�̍D���Ȑl�͓����N���X��2�l�v�ł����B���[��A���̍��Z����ɂ����͂ɉ��y�D���͏��Ȃ������ł����ǁA����ł��N���X��10�l�߂��͂��܂����B���ꂩ��o���h�u�[����牽�����o�āA�y�����ɂ���Ⴂ�O���������Ǝv���Ă����̂ł����A�܂��܂����y�t�@���͏����h�Ȃ̂ł��ˁB����́A�e�I�[�f�B�I���[�J�[�͖{���Ɋ�@���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B����ꂽ�I�[�f�B�I�s��Ńp�C�̒D�����������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��ł��傤�B�����Ǝs��S�̂��g�傳����悤�Ȏ{�K�v���Ǝv���܂��B�Ђ���Ƃ�����I�[�f�B�I���[�J�[�́u���y�̌����Ȑl�Ȃ�Ă��Ȃ��͂��v�ƍ����������Ă���̂�������܂���B�u���y�������Ȑl�͂����͂��Ȃ����ǁA�D���Ȑl���͂��������Ȃ��v�Ƃ������������������ǂ��Ǝv���܂��B
����C�̓ǂ߂Ă��Ȃ��悤�ł�����
���K���ɗ����Ă���Ă����\
�@�������A�f���āu�K���ɗ����v����͂��܂���(^O^)�B����Ƃ��X�������肢���܂��B
�@�|��satoakichan����
�@���̃L�[�{�[�h�̘r�Ȃ�Ă܂������債�����̂ł͂Ȃ����A��꒷���Ԋy��ɐG���Ă��܂���E�E�E�E�Ƃ͌������A�s�A�m��I���K���Ȃ��Ă���Ƃ��̊Ԃɂ��w�������Ă��āA�܂��Ɂu�O�q�̍��S�܂Łv���Ȃ��Ɗ�������܂����i���Ӗ����Ⴂ�܂����H ^^;�j�B
�@�L��悤�ɁA�q���͂����Ƃ������y�̌���������ΕK�������������Ǝv���܂��B�����Ƃ����Ƌ@���^����ׂ��ł��ˁB
�����ɓD���I�H��������܂���ˁi�j
�@���́A�������Z��ł���ꏊ�̋߂��Ɂu�A�i���O���X�v�����邱�Ƃ��ŋߔ������܂����B�z�[���y�[�W�����Ă݂�ƁA���ɔZ���}�j�A�̕��X���u�ڋq�v�Ƃ��ďЉ��Ă���A�����^�Ԃ̂��S�O���Ă���܂��i���j�B�ł����A����Łu�D���v�ɗ����Ă��܂���悤�Ȍo�ϓI�g���ɂȂ肽���Ƃ��v���Ă���܂�����A�l�ԂƂ͎��ɏ���Ȃ��̂ł�(^_^;)�B
�����ԍ��F8090830
![]() 0�_
0�_
satoakichan����
�͂��߂܂��ā@�ł��ˁA������͈���I�ɂ����Ɣq�������Ă��������Ă����̂�
�����グ�Ă��܂����B
���Ă���28��������@�̂����O�ŔN�̂������A�������̂̃A�j���S�l�Q�W����A�z���Ă��܂��܂���(^^)�@�����m�ł����H
�������ł��I(^^)�l���q���̂���e���r�ł���Ă����̂̓����C�N���ꂽ�A�j���ł������A
����10�N�͓��ɌÂ��ق�����D���ł��B�g����1000mm���̃t�B�M���A�Ƃ����܂����A���v���_�N�V�������F�̖͌^�������Ă��܂����A���N�OPS2�p�̃\�t�g�œS�l�Q�W�����o���̂����܂������A�{�������̓S�l28���F�H��PSP����ɂ���܂����B
�}�j�A�܂ł͂����܂��A�����Ŗ�����28�ɂ��Ă������炢��
�t���[�N�ł��B�i�j
�l�̃j�b�N�l�[���͒��쌠�ɃX���X���Ȃ̂ł��傤���H
�D���A�A�A�}���O���[�u�ɂ��܂�Ȃ��璾�܂��オ�炸�ł����܂��傤/~~
�掿�ɂ�����肳��
�����́B
���X�^���h���䐻�쒆�Ƃ̂��ƂŁA��悪���s��p�Ȏ��ɂ͉��̂Ȃ����E�őA�܂�������ł��B
�����i���Ă��܂��Ό��ǂ͈�������������Ȃ���ł����A�����u������ق��������I�v
�Ƃ���������Ă��܂��āA�A�A
�����I���ꂪ���Ƃ������ƂȂ�ł��ˁH
�W���Y�����́E�E�E�ƌ�����ꉞJBL���g���Ă��܂����A�܂��W���Y���̉���
�点�Ă��܂���B������ƂÂ�������ăg�[�^���o�����X���Ƃ����Ȃ�ł���
���̓}�h���i��z�C�b�g�j�[�A������ɏƏ��������Ă�݂����ŁA���������ȃ\�t�g
���Ă͖��������A�Ō�Ɍ������̂悤�Ƀ}�h���i���ď��ɂ��Ƃ����̂��J��Ԃ���
���܂��B
�����ԍ��F8091549
![]() 0�_
0�_
�ŏ������֏����������Ǝv�������A�u����ȎႢ�z�ɕԎ������̂��Ȃ��v�Ǝv���Ă܂������A�F�l�̗D�������Ԏ��ŕs���͐������ł��܂��܂����B��������Ƃ��Ԏ��������ĉ�����Ȃ�Ċ��ӊ����ł��B
�t�@�S�b�g�Ƃ����y��A���t�y�o���h�ł̓}�C�i�[�ł����A�N���V�b�N�ł͂�����Ƃ���1�p�[�g�Ȃ�ł���ˁB���ɉ掿�ɂ�����肳��̓t�@�S�b�g���D�݂̂悤�ŁB�l�͐l�̐��Ɏ����悤�Ȋi���������F����D���ł��B
>satoakichan����
�I���W�o���h�ł����B��A�C�R�����珟��ɐ�������Ɩl�̂ӂ����肭�炢�N���̂悤�ł��ˁB���E�������ɂ̓s�A�m������Ē����āAredfodera����̃x�[�X�̓R���g���o�X�֎����ւ��ł��\�ł��傤���A�l�I���W����̃M�^�[��satoakichan����ɂ̓h����������Ă���������A�Ȃ���ăW���Y�o���h���o�����Ȃ��ł��傤���B�l�́c�����ł��ˁA���ǂ͖���������A�T�b�N�X������܂��I�Ƃ������āA����͂�ϑz���߂��Ă��܂��܂���(����)
���E�������
�����N���X�Ƀo���h������Ă���l�͐��l���܂��B�x�ݎ��Ԃɂ����ƃC���z���ʼn��y���Ă���l�����l�����܂��B�ł��A�����܂łȂ�ł���ˁB�������y�ɑ��銴�o�����܂ЂƂ���Ă��Ȃ��悤�ȁB�����ԑO�̌@��N�����ɂȂ�܂����A���E�������̂�����������u���͓��{�l�̒��Ŗ{���Ɂu���y�͑f���炵���v�Ǝv���Ă���҂͂���Ȃɑ����Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�v���Ǝv���܂��B
�u���ꂩ�����������ݏo���āA�����Ŋy�����ɂ�����c(��)�v�̕����͖{���ɂ��̂Ƃ��肾�Ǝv���Ă��܂��܂����B
����Љ��������1�l���A�����J�̃��b�N�ɋ���������炵���A�o�C�g�����Ă͒��߂������Ń��R�[�h��CD���ʂɍw�����Ă���悤�ł��B���̗F�B�ɁA�l���ȑO�������C���z��(ATH-EM�XD)��݂��Ă������Ƃ��늴�����Ă��܂����B�����͔M���I�ȃI�[�f�B�I�}�j�A�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B
���Z��������ȑ�_�ɕ������a���Ă��܂��Ă����̂��ȁc�c(��⊾)
�����ԍ��F8091676
![]() 0�_
0�_
����28��������@
���߂܂��āA130�C���`�̃T�E���h�X�N���[���ʼnf��/���y���y����ł���130theater�Ɛ\����
���B(�Ƃ͌����Ă��v���W�F�N�^�[���A���v�����S�ɐݒu�͏I����Ă��Ȃ��āA���z����Ԃ�
�����E�E�E�B)
>�l���q���̂���e���r�ł���Ă����̂̓����C�N���ꂽ�A�j���ł������A����10�N�͓��Ɍ�
���ق�����D���ł��B
�Â��ł��ȁA�Â�������܂���B�S�l28���́u���ʔŁv��m���Ă���܂��B�f��u��-���{�b
�g�v�̗l�ɓS�l28�����g�͐l�H�m�\�͖����đS�ă����R������ɂ��쓮�ł����B�����A��s
�����܂������炻��Ȃ�̍��x�Ȏ��Ȑ���@�\�͓��ڂ��Ă����͂��ł��ˁB�Ƃ���œS�l��1
������27���͂ǂ��Ȃ��Ă����̂ł��傤���H�B�S�l29�����邢�͓S�l28��-�U�Ȃǂ͏o�܂���
�ł����ˁB
���̗l�ȕ������݂���Ƃ���ƁA�S�W���͊C�݂ɋߕt���ƁA�����Ȃ�p�������܂����E�E�E�E
�Ƃ������͂����܂ł͂��Ⴊ�ނ��邢�͕����Ă����̂ł��傤���˂��H�B
���{�̃S�W���͐H���̃V�[��������܂���B��������Ƃ��̗��h�Ȏ��͕s�v�Ƃ������ɂȂ��
���āE�E�S�W�����o������Ǝ��q�������/�W�F�b�g�@�ōU�����܂����A�����w�I�ɂ͗Ⴆ��
�V���i�K�X�N�W���ӂ�ł��ƃ~�T�C���̃T�C�h���C���_�[�Łu�����v�������ł��B
����ɖ@���I�ɂ͎��q��������������čU���ł���̂́u�g�D�������R�����U�����Ă�����
���v�������ł����A�ʂ����ăS�W���͑g�D�������R���Ȃ̂��H�Ƃ�����肪����܂��B������
��ƍU���͏o���Ȃ��E�E�E�S�W���o���͊�{�I��1�C���琔�C�E�E�E���Ƃ���Ɛ�ł̊�@��
�m���鐶���ƂȂ��čU���ǂ��납�A�ނ��냏�V���g�����ŕی삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɂ�
���Ă��܂������ł��B�E�E�E
���E�������@����̓I�[�f�B�I�̘b������傫����E���Ă��܂��܂����B���݂܂���B
�����ԍ��F8092521
![]() 0�_
0�_
130theater����
����ɂ��́B
�͂��߂܂��Ăł͂���܂���B�J�[�I�[�f�B�I�p�E�E�E�̔ň�x
�A�h�o�C�X���������Ă���܂��A���̐߂͂��肪�Ƃ��������܂����B�i�O�O
�S�l���P��������ǂ��������Q���`�Q�V���͎��s�����Ƃ�����܂����A
�Q�V���͓G�Ƃ��ē������肵�Ă܂��ˁB�����Ɍ����Ɛ��S�l�͂Q�X��
�ɂȂ�悤�ȋC�����܂����A��̃X�g�[���[�ł͂Q�X���ɂ����郍�{�b�g
������悤�ł��B�ڂ����͕�����܂���B
���ʔł������������Ƃ���܂��B
��ԃn�[�g��߂܂�Ă���͍̂���ē̔����A�j���u�S�l�Q�W���v�ł����˂��B
���N�����̑O���A���ʔŋy�ыߑ�œS�l�Q�W�����f�扻����܂����ˁB
����ɒ����Ƃ͂����܂��A���܂��ߑ�I�Ƀ����C�N����Ă����i�ł��B
�l�I�ɂ�PS2�p�\�t�g�̓S�l�Q�W�����A����A����ēłƂ��܂��Č�����Ă���
���j�I�ɂ��Z��Ȃ���y���߂��i�ŋC�ɓ����Ă��܂��B
�S���X���̓��e�ƈقȂ�̂ł��ꂭ�炢�ɂ��Ă����܂�
���炵�܂����B
�����ԍ��F8094026
![]() 0�_
0�_
�@�|���R�R�~���g����
�@�������Z���̍��́i�����H�j���b�N�t�@���ł������A�ǂ��̃N���X�ɂ�5,6�l�͂������b�N�D���̊Ԃł͊m�łƂ����g�h���h������܂����i�j�B�ő吨�͂͂������g�u���e�B�b�V���E�n�[�h���b�N�h�h�ŁA�f�B�[�v�E�p�[�v����b�h�E�c�F�b�y�����̂悤�ȑ僁�W���[���͂��߁A���[���C�A�E�q�[�v�Ƃ��E�B�b�V���{�[���E�A�b�V���̂悤�ȍS��H�����܂߁A���X�E���`�N�𐂂�Ă������̂ł��B���ɑ��������̂����Ԃ�R�R�~���g����̗F�B�������Ă���ł��낤�g�A�����J���E�n�[�h���b�N�h�h�ŁA�N�ł��m���Ă�G�A���X�~�X��L�b�X�A�܂��̓O�����h�E�t�@���N�Ƃ��u���[�E�I�C�X�^�[�E�J���g�Ȃ̒ʍD�݂܂ŁA����܂��E���`�N�̗��ł����B���ی�ł͊e�N���X�̃��b�N�������ǂ����W�܂��āg�c�_�h�ɖ�����ꂽ���Ƃ��������悤�ł��B�Ȃ��A���́g�p���N�^�j���[�E�F�C���h�h�Ƃ����㏬�h���������̂ŁA�j�Q����Ă��܂����i���j�B���ɂ��g�T�U���E���b�N�h�h�Ƃ��g�v���O���b�V���E���b�N�h�h�Ȃ�Ă̂�����܂����Ȃ��B
�@�悭�g�\��̍��ɂ悭���y���Ă����z���A��l�ɂȂ�Ɖ�������h�Ȃ�Č����Ă��܂������A�Ⴂ����ɖ{�C�ʼn��y�ɐڂ��Ă���A���ɂȂ낤�Ɓg��������h�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B����A���\�N�Ԃ�ɍ��Z�̌��������i���͖^�L����Ƃ̊Ǘ��E�j�Ɠd�b�Řb���܂������A���b�N�}�j�A�ł������ނ́A���ł��c��ȃ��R�[�h�̃R���N�V�����ƁA�����ł͂Ȃ����ǂ悭�������ꂽ�I�[�f�B�I�V�X�e�����ێ����Ă���Ƃ̂��ƂŁA������Ɗ����������܂����B
�����Z��������ȑ�_�ɕ������a���Ă��܂��Ă����̂���
�@������ł��i�����ς� ^^;�j�B����Ƃ��X�������B
�@�E�E�E�E���āA�u�S�l28���v�̘b���o�Ă��܂����A�����������ɍŏ��́u���ʔŁv�͒m��܂���B�̂̂s�u�A�j���ł͂悭���Ă����L��������܂��B�ߔN�ɂ��[��g�ŕ��f���ꂽ�V���[�Y������A�D�]�݂����������݂����ł��ˁB���N�O�Ɏ��ʔʼnf�悪���J����܂������A���܂�̕]���̈����ɐH�w�������܂���ł����B�����D���ȑ���D���o�Ă����̂ł�����ƋC�ɂ͂Ȃ�܂������E�E�E�E�i�j�B
�@���ۖ��Ƃ��ăS�W�����o�Ă��Ă��e�ՂɎ��q���͏o���ł��Ȃ��ł��傤�B���������Ό���Łu�@���x�@�p�g���C�o�[�v�̃p�[�g3�ŁA���b���o�������ۂɂ܂������̂͏����̌x�@���Ƃ������Ƃ�������Ă��܂��B�������ł͎��������Ȃ��̂ŁA����SAT�Ȃǂ̓��ꕔ���������̂ł��傤�B�ŏI�I�Ɏ��q�����o������Ƃ��Ă��A����܂łɂ͔ώG�Ȏ葱�����K�v�ŁA���̊Ԃɔ�Q�͊g�債�Ă䂭���Ƃ��\�z����܂��B�E�E�E�E������ɂ���A��������Ƃ�����@�Ǘ����K�v�����Ă��Ƃł��傤�i�v��������b���E���ł� ^^;�j�B
�����ԍ��F8099533
![]() 0�_
0�_
�@�ȑO�u���ău�����h�̃X�s�[�J�[�͉������邢�v�Ƃ������Ƃ��q�ׂ܂������A�ł͂ǂ����āu���邢�v�̂��A���̗��R���l���Ă݂܂����B
�@����^�f�B�[���[�ŁA�X������u���Đ��̃X�s�[�J�[�͒���d�����ˁv�Ƃ����b���܂����B�Ȃ�قǁA�������܂Œ������C�O�u�����h�̃X�s�[�J�[�͉��F�͂��܂��܂Ȃ���A���悪�������肵�Ă��邱�Ƃ͋��ʂ��Ă��܂��B�Ȃ�Β���Ƃ͉����Ƃ����ƁA����̓��H�[�J���̑ш�ł��B�܂�͐l�̐�����肭�Đ����悤�ƕ��S���Ă�����A���R�ƒ��悪�Z���Ȃ����Ƃ������Ƃł��傤�i���F����d���Ƃ����̂́A�������ɋ�����������Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�Đ��̏[�����̂��Ƃł��j�B
�@���H�[�J���́A���t�҂ɂƂ��Ĉ�ԏd���������|�C���g�ł������ł͂Ȃ��A����ɂƂ��Ă�������ɂƂ��Ă��A�ł��Č����̃N�H���e�B��������ӏ��ł�����܂��B���H�[�J�����f����悤�ɂ���ɂ́A�������邭�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�Â��A�C�Ȑ���A���������ȉ̂������҂Ȃ��܂���B���ĂŃV�b�J���ƓW�J�����Ȃ���A���X�i�[�̃n�[�g�ɂ͓͂��܂���B
�@�v����ɁA�C�O�u�����h�̃G���W�j�A�����́A�ł�������₷���u�l�̐��v�Ƃ����f�ނ���O�ꂵ���q�A�����O�Œǂ�����ł���Ƃ������Ƃł��傤�B���č��Y�X�s�[�J�[�̑������Â��������o���Ȃ��̂́A���肪���y�\�[�X��������f�[�^�̕��ɋC������Ă�����Ă��Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�m���ɓ��{�l�́u���l�v���D���ł��B���̌f���ł��u���̃A���v�́������b�g�����ǁA���̃A���v��××���b�g������A�������̕����ǂ��̂ł́H�v�Ƃ����t���[�Y�����ڂɂ����悤�Ɏv���܂��B���������ΐ́u�v���X100CC�̗]�T�v�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�Ń��C�o���Ђ��o���������Ԏ������܂����ˁi��������100CC�̈Ⴂ���A����̑P�����������肷���ΓI�ȗv�f�ɂ͂Ȃ�Ȃ��͂��ł����E�E�E�E�j�B���́u���l�����v�̍s���������悪�A80�N�㖖�́u598�푈�v�Ȃ̂�������܂���B�X�y�b�N������C�ɂ��郆�[�U�[��ɂ��Ă�����A�i�C�������Ȃ�ƈ�C�Ɍڋq�������n���ɂȂ����Ƃ������Ƃł��傤�B
�@���x�������Ă邱�Ƃł����A���{�̃��[�J�[�̓X�y�b�N�����͎~�߂āA���y���d���̃X�^���X�ɓ]�����ė~�����ł��ˁB�܂��A���l�B�́u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���y���͍ŗD�掖�����I�v�Ǝv���Ă���̂�������܂��A��`������G���ł̎��グ�����Z�p�ʂ��������ɗ��āA�̐S�̉�����ɂ��Ă̌��y�͌�ɂȂ��Ă���P�[�X�������̂͊m���ł��B
�����ԍ��F8104598
![]() 0�_
0�_
���E�������ɂ���
�����X�s�[�J�[���T�u�V�X�e���Ɏg�p���Ă���ƌ������ŁA�M���̃X���ɂ͒��ڂ��Ă���܂��B�i�Q�l�ɒl������ł��ˁB�j
CDP�AAMP�̃��[�J�[�����Ǔ������[�J�[�̕��ƂȂ�܂����B
�Ƃ���ł��̃V�X�e���A���t�y���T�N�ԕ����ł���Ă��閖���ɕ���������ŁA����Ȃ����ƕ��������A�����̃~�j�R���|�̕����g���₷�̂ł���Ȃ��Ƃ������茾���A�ǂ����Ă��ȂƎv���Ă������A���̃X�������čl���Ă��܂��܂����B
�ޏ��̉��y���C�t�͎�Ɍg�тŃ_�E�����[�h�����Ȃ�������̂悤�ŁA���ɋC�ɓ������A�[�e�B�X�g��CD�w���̃p�^�[���ł��B�i�ŋ߂̎Ⴂ�l�̑�\�҂ł��ˁj
�܂�A�����Ɏ���ăs�A�I�[�f�B�I�͖{�l��needs�ɖ����ƌ��������Ɨ������܂����B
���̊肤���́A�~�j�R���|�ł����[�J�[�͉��Ɋւ��Ă͌����đË����Ȃ��������̐��i����Ă����ė~�������ł��B
���̒��ŁA�P�i�̃I�f�B�I�ɋ������o�Ă���l���o�Ă���̂ł͂Ǝv���̂ł����H
���݂̃I�f�B�I�X�̑Ή��ɂ���肪����܂��B
�n�C�G���h����̏���10���~�ʂ̕i���̘b�����Ă��鎞�ɁA�n�C�G���h�̂��q�����X���Ă������ł����A�X���͂�����̕��ɍs���Ă��܂�1���Ԕ��҂��Ă��߂��ė��Ȃ��ŁA������߂Ă��̓��͋A��������Q��L��܂��B�i����ԂȂ��X�����������̂ł��j
���X�Œm���̖������X�����ł��B
���ݎg�p���Ă���AMP�ŃX�s�J�[�����Q���Ď������C�ɓ������̂ŁA�������[�J�[�̏o�͂̏�����AMP�ł��قړ��������A���F���o��ƌ����X���̌��t��M���w���A�͂���AMP�ł������A���������������Ƃ͂قlj����A�P�����̒������ʼn����Ɏ���܂����B
�Ō�ɐ�T�ʂ̐��X��`�������ɓ��{�̃��[�J�[�̔����O�̐��i�̎������s���Ă��܂����B
�n�C�G���h�̉��͂��Ă��܂������A�l�I�ɋ����͗N���܂���ł����B
���̃��[�J�[�ŋߔp�ՂɂȂ����i�h���`�F�j�ƌ������L���Ȑ��i����Ă����̂Ɏc�O�ł��B
���E�������@�L�Ӌ`�Ȃ��b���̂��݂ɂ��Ă���܂��B--�ł�50��̎��̐������o���Ă�
���܂����A�O�O�O�O�O�O�ł�
�����ԍ��F8107208
![]() 0�_
0�_
�@���Ȃ��₶����A����ɂ��́B�ٕ���ǂ�ł��������L���������܂��B
�@�m���Ɂu�~�j�R���|�ł����Ɋւ��Ă͌����đË����Ȃ����i�v�̓o��͑傢�ɖ]�܂��Ƃ���ł��B���������[�U�[�����u���̗ǂ����i�v��K�v�Ƃ��Ă��炸�A�ȕ���@�\�̕����d�����Ă���P�[�X�����X����A�Z���I�ɂ͊e���[�J�[�����̗ǂ���O�ʂɏo���Ĕ��荞�ނ��Ƃ̓��X�L�[���Ǝv���Ă���̂�������܂���B�܂��A���̒��ō\�����v�H�����g�����h�ɂȂ��Ă���́A�o�c�ґ����ڐ�̗��v��Nj����邱�Ƃ��厖�ŁA�������I�Ȃ��Ƃ��l����̂̓^�u�[���Ƃ�������������̂ŁA�Ȃ��Ȃ�����Ƃ���ł��B
�@�ŁA����ǂT�����i�T���f�[�������������ȁH�j��LUXMAN�̂��Ƃ��Љ��Ă��܂����B���̉�Ђ͑S�������y�D���ŁA�S�����A���v�̐v���炢���Ȃ��Ă��܂��قǂ̃X�L���������Ă���Ƃ̂��ƂŁA���̑�胁�[�J�[�Ƃ͈Ⴄ�Е��ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł��B�ӂƍl�����̂ł����ALUXMAN�i���邢��ACCUPHASE�j�݂����ȉ�Ђ����~�j�R���|����|���Ă݂�̂��ʔ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���BDENON��KENWOOD�Ȃǂ̐��i�Ƃ͈ꖡ�����Ⴄ���̂��o���オ��Ɨ\�z���܂��B�������H��̉ғ����~�j�R���|�����ɐV���Ƀ��C�������̂̓R�X�g��������܂�����A��{���f���͑��̃��[�J�[�����OEM�ɂ��āA�������[�J�[�Ƃ��Ď�������ēƎ��u�����h�Ŕ���o���Ƃ��������E�P�邩������܂���B���Ƃ��u�g�c���v��ONKYO��CD���V�[�o�[���������ĉ������ヂ�f���Ƃ��Ĕ����Ă���̂Ɠ����悤�ȕ��@�_�ł���(^^)�B
�@�I�[�f�B�I�X�̑Ή��͉��Ƃ����ė~�����ł��B�^���X�ł́u��������Ƃ��́A�����E����Ȃ��Ɋւ�炸�A���З\������ĉ������v��搂��Ă���Ƃ��������悤�ł��B������ɂ���A���[�U�[�̗�����l������������]�܂�܂��ˁB
�@�����^�Ђ̐V��X�s�[�J�[�̓_���ł������B�G���W�j�A���C�O������������Ă��邮�炢�̎v�������{����u���Ȃ��ƁA��胁�[�J�[�ł͌��L��X�s�[�J�[�͐��܂�Ȃ��ł��傤�ȁB���������̂ł��B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�����ԍ��F8110108
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
������ƒ����Ȃ��Ă��܂��܂������A��낵�������炨�t�����������B
�R�R�~���g����A�͂��߂܂��āB
�I�W����ő�ς��Ǝv���܂����A�ǂ�����낵�����肢���܂�m�i.�@.)m
�����E�������ɂ̓s�A�m������Ē����āA
��redfodera����̃x�[�X�̓R���g���o�X�֎����ւ��ł��\�ł��傤���A
���l�I���W����̃M�^�[��satoakichan����ɂ̓h����������Ă���������A
���Ȃ���ăW���Y�o���h���o�����Ȃ��ł��傤���B
�R���g���o�X�i�A�b�v���C�g���ē����͌Ă�ł܂����j�ƃ`�F���ɂ̓g���C�������Ƃ������ł����s�b�`���Ƃꂸ���܂��܂����B
�{�[�C���O�����r�̃p�C�v���̂�����Ő�l�ȉ������o�������܂��E�E�E���[�E���[�E�}�ւ̓��̂�͑S�����������ł���(^^;)
�o���h�Ɋւ��Ă͎��ƕl�I���W�����ނƃR�~�b�N�E�o���h�����āu����v�\����ł����߂ł��܂���i��j
�u�킹��v�R�~�b�N�E�o���h�ɂȂ��Ȃ���Ŋ撣�����Ⴂ�܂����A���B�W���A���n�̃o���h������������ł���B
�R�R�~���g����A�r�[�g���Y���������̑O���Ƀh���t�^�[�Y�I���o�����b�������Ƃ͂���܂��H
�N���C�W�[�E�L���b�c�Ƃ��ǂ��X�C���O������Θr�Ɋo���̂���B�l�v���C���[���肾������ł��B
���Ȃ݂ɍŋ߂̌|�l����́u����v�Ƃ͑�Ⴂ�ŁA�ނ�́u�킹��v���Ƃ��ł���ꗬ�|�l�����ł����B
���t�@�S�b�g�Ƃ����y��A���t�y�o���h�ł̓}�C�i�[�ł����A�N���V�b�N�ł͂�����Ƃ���1�p�[�g�Ȃ�ł���ˁB
���ɂ͌Ăі��Ƃ��ăo�X�[���̕������Ȃ��݂�����܂����t�@�S�b�g�̉��F�͑�D���ł���B
�G���L�E�x�[�X�i���Ƀt���b�g���X�j�̃g���[�j���O�p�̃G�N�Z�T�C�Y�Ń`�F���ƃt�@�S�b�g�̃p�[�g���悭�R�s�[���܂����B
�m���H���~�q����̓t�@�S�b�g�t�҂ł����ˁB������ƑO�Ƀ��W���[����o����Ă�CD���ŋߒ����@�����܂����B
����28��������
���Ɖ��y�Ɋւ��Ă͐e�䂳��̉e���͂������傫���Ǝv����ł��B
�����������͈�������ς��Ǝv���܂����A���̉��y�ɐG���@��𑽂�����Ă����ĉ������B
���y�Ƃ����f���炵�����E�ƂƂ��Ɍ����̉��ł̃}�i�[��TPO�Ȃǂ����q�������̎��_�ŗ��������Ǝv���܂��B
���q����ɂƂ��ăv���X�ɂȂ邱�Ƃ��R�قǂ���͂��ł�����B
�������������Ȃ��悤�ɂƍ��A�S��ł���X�s�[�J�[�X�^���h�����쒆�ł��B
���W�������Ă݂�Ό��ǂ́A���������i���Ă��܂��悤�ȉH�ڂɂȂ��Ă���܂��B
�J�[�I�f�B�I�o���̂������DIY�͊��Ɛg�߂ł���ˁB
�����v�����f�����o�Ŏ���́u�Ȃ���ăX�s�[�J�[�v���A���X�A�쐬���܂����A
�Ă���28��������Ɠ��l�ɏȗ\�Z�ǂ��납�����@����ق�SP���j�b�g��p�[�c�ɎU�����Ă��܂��B
�X�s�[�J�[�͖炵�ĂȂ�ڂȂ̂ŁA�������������Ďd�������܂ꂽSP���j�b�g�قǖ��Ӗ��ʼn��z�Ȃ��̂͂���܂���(^^;)
satoakichan����@
�����̌��R�~�ɃI���W�o���h�����݁H�H�H���܂��B
�悹�Ȃ��������I�H�o���h�W�͂������m�����Ă��܂��܂�����(^^;)
�E�E�E�ƌ����Ă��A�y������t���ă��C���C�������Ƃ͖Y��悤�ɂ��Y����Ȃ��ʔ���������܂��ˁB
�ǂ��ł��傤�A�v������NHK�̃I���W�o���h�S�����̒n��\�I�փG���g���[���ĎQ��E�E�E
�����E�E�E
�����ԍ��F8110508
![]() 0�_
0�_
�A���X�Ő\����܂���B
���Ȃ��₶����A�͂��߂܂��āB
KEF IQ-3�ł̂��b�A�y�����q�����܂����B
���~�j�R���|�ł����[�J�[�͉��Ɋւ��Ă͌����đË����Ȃ��������̐��i����Ă����ė~�������ł��B
�����̒��ŁA�P�i�̃I�f�B�I�ɋ������o�Ă���l���o�Ă���̂ł͂Ǝv���̂ł����H
�ȃR�X�g�̒��Ńn�C���x���̐��i�������̂��E�E�E�C�O�̃��[�J�[�͏G�łĂ���Ɗ��������鐻�i�������C�����܂��B
�T�C�Y�I�ɂ̓t���R���|�i18�C���`�j�ł����A�l�I��TANGENT�AARCAM �ACREEK�͌������Ă���Ǝv���܂��B
����TANGENT�́AHiFi50�V�X�e���Ƃ����G���g���[�E�N���X�̃v�����C��+CD�v���C���[�Ŋ�]�������i94.500�~�A
�l�C�̃R���p�N�g2Way��EVO��g�ݍ��킹�Ă�132,300�~�ł����������10���~�O��ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����~�j�R���|��10���~�͍����@�̕��ނł��傤���A��r���ď����ɂȂ�@�킪�ʂ����Ăǂ̂��炢���݂���̂��^��ł��B
�A���㗝�XURL
http://www.porcaro-line.co.jp/hifi.htm
�v�͖{���A�����͋��炭�A�W�A���ł��傤���A������@�ŕC�G���鐻�i������Ȃ��������[�J�[�ɂ́H�H�H�ł��ˁB
���E����������߂̘b����o����Ă��܂����A�܂��Ɋ�ƂȂ�u���Ɗ����v�������e�Ђ��������łȂ��l�ł��B
���E�������́u���{�l�͉��y���D���ł͂Ȃ��v��n�ōs���l�ȁA�ƂĂ��c�O�Ƃ������₵���b�ł��ˁB
�����݂̃I�[�f�B�I�X�̑Ή��ɂ���肪����܂��B
���q���������Ă��Ă͂₳��銨�Ⴂ�����i�����l�A�I�[�f�B�I���V���b�v�������Ƃ��낪�m���ɑ����Ă܂��ˁB
���Ɍ����u���V�v�Ȃ�V���b�v�Ǝ��̕s�����̗l�ȈÖق̝|��U��Ƃ���ɂ́A�����A�����Ă��܂��܂��B
�O��_�I�Ȍ��n������ł��傤���A�j�[�Y�������q�A�����O����\�͂͂��납�b���p�����玝�����킹�Ă��Ȃ��E�E�E
�V���b�v�Ǝ��̌��͑��d�������Ǝv���܂����A�������������Ⴂ�≡���ȑԓx�ł̓}�[�P�b�g����Ƃ��͂�������܂���ˁB
���E�������
���i�̔�]���珗�������I�[�f�B�I���i�J���ւ̒͂������̂��ƁA�����Ԃ���q�[���[�����b����ƁA
CD����DVD���݂ɉ��͈͂����C�h�����W���������̃X���͑�D���I�ł��B
���Ȃ݂Ɏ���PC�̉��ɂ́A�]�t�B�A���}���A�n�J�C�_�[�ɃO�t�ƁA�H�߃t�B�M���A���ߑ��Ȃ��������Ă���F����Ɠ��ނł�(^^;)
�X�y�b�N��f�ސ푈�͍����Ɏn�܂������Ƃł͂���܂��A�u���������č����ꂸ�v�Ȑ��i���m���ɑ��߂��܂��ˁB
���y���ӏ܂��邽�߂̋@��ł���Ȃ���A���͑����̗l�ȃI�[�f�B�I���i�Ƃ́E�E�E���܂�Ɏ₵���Ǝv���܂��B
�t���I�ɍl����ƁA�����܂߃��[�U��������Ă��Ȃ������n���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ȃ̂�������܂���B
�R�R�~���g����̗l�Ɂu���y�ɑ���h�Ӂv�����������Ă����������Ȃ��̂��A�܂��߂��������ł����E�E�E
�����ƂƓ����l�ɁA�I�l�A�x�������l���܂����߂Ȃ킯�ł�����B������ƕ��G�ł��B
�����ԍ��F8110519
![]() 0�_
0�_
�F�l�A�����������Ă���܂��B
�@�F�l������������4344�̏������l�����閈���A����łȂ��Ă����ꂵ��������
�@��w�A���ꂵ���d�����X�ɂȂ��Ă���܂��B
�@����S�āu�g����o����K�v�ł���܂��ĒN�ɂ�����������Ȃ���ŁE�E�E�E�B
�@�u�o���h�v�ł����H�댯�ȋ����ł��ˁI
�@4344���̈������ŕ����̐��������Ă��Ĉ����z���ו��̒�����}���`�g���b�N���R
�@�~���[�W�b�NBOX���X���y�p�@�ނ��o�����Ă��܂��܂����B
�@�E�������E�E�E�E�A������ȁ`�B�Q�Ă��������N�������ŁE�E�E�E�B
�����ԍ��F8112004
![]() 0�_
0�_
���E�������@
�@>�v����ɁA�C�O�u�����h�̃G���W�j�A�����́A�ł�������₷���u�l�̐��v�Ƃ����f�ނ�
>��O�ꂵ���q�A�����O�Œǂ�����ł���Ƃ������Ƃł��傤�B���č��Y�X�s�[�J�[�̑���
>���Â��������o���Ȃ��̂́A���肪���y�\�[�X��������f�[�^�̕��ɋC������Ă���
>���Ă��Ƃ��Ǝv���܂��B
�C�O�u�����h�ł��A�����J�n�ƃ��[���b�p�n������A���[���b�p�ł��C�M���X�A�h�C�c�A�t��
���X�A�C�^���A�ƍŋ߂ł͐F�X�ȊC�O���[�J�[������܂��ˁB���̃V�X�e���P�̓s���A�A�`�u
����JBL�����C���ł��B�E�E�E�ł��ŋ߂ł͍��Y�̃��[�J�[�E�E�E�ƌ����Ă��C�����Ă���
���[�J�[�̓p�C�I�j�A�ƃr�N�^�[���Ǝv���܂����p�C�I�j�A��S-1EX�ł����A����������
�܂����B(�����ƌ����Ă��������F�X����܂����AS-1EX�̎�����Ȃ̂Őݒu��ԁA�g�p�@�퓙
�����I�ɂ͐\�����Ȃ����ł����B)���̃X�s�[�J�[�́u���Y�v�Ƃ��Ă͈ٗl�ɍ����Ȃ̂ł�
�����Ȃ蔄��Ă��܂��ˁBS-1EX�̊J���W�҂��u�t�̎�����ł����̂ŐF�X�b�����܂�
�����A����̊J���X�^�b�t�̔����͊O�l�������ł��B
�ܘ_�A���y���]�X�͕����Έꔭ�ŕ�����܂�����A��͂�Z�p�I�ȉ���ɂȂ�܂��B�U����
�f�ނ̃}�O�l�V�E���̓X�s�[�J�[�p�f�ނƂ��Ă͐F�X�ǂ������������Ă���Ƃ��A�o�b�t����
�������E�h���Ă��ĉ����𑵂��铙�F�X�ȍH�v�����邻���ł��B���̃X�s�[�J�[�͎��ɁA����
��100���~�L�����Ƃ����炱�ꂪ��ԗ~�����X�s�[�J�[�ł��B
�E�E�E�E���̑f�ނ̃}�O�l�V�E���ɉ�R�������N���Ă��܂����B�ŁA�}�O�l�V�E�����g����
�r�N�^�[��SX-M3���w�����܂����B�܂��[�i����Ă��܂��A���̕����Ŗ炵����ǂ��
���ɂȂ�̂��y���݂ł��B
�����ԍ��F8115224
![]() 0�_
0�_
�@�|��redfodera����
�@�R�~�b�N�o���h�Ƃ����Ύv���o�����̂��ʐ�J���e�b�g��a���܃L���O�X�Ƃ������A���̎�̘A���i���j�B�ł����A�ނ�̉��t�͕͂���Ȃ����̂�����܂����B���������Γ삱����������u������P�v���u���C�N����O�͂����o���h�������Ƃ��E�E�E�E�B�o���h�ł͂Ȃ����ǃN�[���t�@�C�u���g�������j�b�g�h�Ƃ��ăC�C���o���Ă܂����ˁ[�B�����܂����́g���k�h�����Ȃ�̂��̂ł��B�m���Ȏ��͂͏��̐^�����������o�����Ă��Ƃł��傤��(^^)�B
�@�ŋ߂́g�����u�[���h�Ƃ��Ō|�l���e���r�ɏo�܂����Ă��܂����A����ς�g����h�P�[�X�������悤�Ɏv���܂��B80�N�㏉���̖��˃u�[�����f�i�Ƃ����܂����ǁA���̃u�[���͒Z���ԂŏI���܂����B�悭�g�s�i�C�␢���s�����Ƃ��������s��h�ƌ����܂����A80�N��O���̒ᐬ����������ɉ����������Ƃ����˃u�[���̑����I���̔w�i�ɂ���̂�������܂���B���č��́g����ꂽ10�N�h�ɑ����s�������[���Ɣ��������A�o���͌����Ȃ���Ԃł��B�g�����u�[���h���_���_���ƒ����ԑ����Ă��邱�Ƃ��������肵�āE�E�E�E�B
�@TANGENT�͎����C�ɂȂ��Ă���̂ł����A���܂������ł����ɂ��܂��B�����Ă���X�͑����͂Ȃ��̂ł����A�����������i�����~�j�R���|�����ׂ̗ɕ��ׂāA�T�E���h�ʂł̍��ʉ������[�U�[�Ɍ������ė~�����ł��ˁB
�����͈͂����C�h�����W���������̃X���͑�D���ł�
�@���肪�Ƃ��������܂��B����܂��܂��g�E���h�̓x���������߂��W�J�����蓾�܂��̂ŁA�����҉������i�E�E�E�E���āA�����Ȃ�ƃ{�[�h�����ǂɂ��X���b�h�����̌䍹�����E�E�E�E ^^;�j�B
�@�|���l�I���W����
�@JBL��4344�Ƃ����A38cm���a�E�[�n�[���ڂ̏d����104kg������֎拉�̃��j�^�[�ł���ˁB���͈ȑO40kg�̃X�s�[�J�[�����L���Ă��܂������A����ł��ړ�������̂ɓ�V���܂����B�����_�ŏd�ʋ��̃X�s�[�J�[��ۗL����͍̂��ɂ̑O�t�ȂƂȂ邱�ƕK���Ȃ̂��S�O���Ă���܂��B���ꂮ����䎩������Ă��������B
�@�u�o���h�v�Ŏv���o���܂������A�f��u�u���[�X�E�u���U�[�Y�v�Ŏ�l���B���u�o���h�v�Ƃ������t���ƁA�܂�Ő_��⼌��̂��Ƃ������A��ʂɂ�����������悤�ȉ��o��������Ă��ď킹�܂������A���̌��t�ɂ͊m���ɋz���͂�����܂��E�E�E�E�Ǝv���͉̂��y�}�j�A�̉�X�����Ȃ�ł��傤���B��E���y�t�@�����吨���߂鎄�̎��͂́A����ς�S���t�ƃ}�[�W�����ƒނ肵����Ƃ͔F�߂Ȃ����g�������͋C�����Ă���܂��i�j�B
�@�|��130theater����
�@�}�O�l�V�E���U���Ƃ����AESOTERIC��MG-10��MG-20���^����ɓ��ɕ����т܂��B���Y�i�ɂ͒������g�����Ċy�������h���o���A���ɒ��̃X�s�[�h���ɂ͈��|����܂��B�܂��Ɂg���̂悤�ɐ��������Ă䂭�ቹ�h �ł��B�J���w�̘b�ɂ��Ɓg���j�b�g�̑ϋv���͖��m���h���Ƃ������Ƃł������i�������� ^^;�j�A���̉��ɂ͑��݊�������܂��B
�@�������[�J�[�̃g�����h���f�[�^�d���Ȃ�A�������̂��ƕ�������������˂��l�߂ĐV���Ȓn�����L�����@�_������̂�������܂���BTechnics�́g�ӔN�h�̍�i���܂��ɂ����ł����B���y�\�[�X�̃q�A�����O�ŃT�E���h�f�U�C�����l�߂��Ƃ͎v���Ȃ����Ȃ��ǁA�����ɂ������I�N�H���e�B���������Ȑ����Ȏ����ɓ��B���Ă��āA����͂���Œ�������������܂����B�I�[�f�B�I�u�����h�Ƃ��Ă�Technics�����ł����̂́A�ƂĂ��c�O�Ȃ��Ƃł��B
�@�o������[�i���SX-M3�̃C���v�����肢���܂��B�y���݂ɂ��Ă��܂�(^^)�B
�����ԍ��F8116800
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
130theater����@
�����̑f�ނ̃}�O�l�V�E���ɉ�R�������N���Ă��܂����B
���ŁA�}�O�l�V�E�����g�����r�N�^�[��SX-M3���w�����܂����B
�ǂ��ł��ˁ`�B�y���݂ł��ˁ`�B
�Ȃ܂����炵�Ĉꗬ�̕��͋C�������o���Ă�Ǝv���܂��B
130theater����̊��ł�����\�́{���őt�łĂ����̂ł��傤�B
�����������[���y���݂ɂ��Ă��܂��B
FOSTEX�̃C�^���A�����b�h�̃X�s�[�J�[��Tweeter���s���A�E�}�O�l�V�E���������l�ȁc
NHK�̐V���j�^�[�ɍ̗p���ꂽ�^�Ԃ���}�O�l�V�E���������L��������܂��B
�ǂ����}�e���A���Ƃ��Ă��{�̗l�ł��ˁB
�l�I���W����
���F�l������������4344�̏������l�����閈��
���œ���ɂȂ�̂ł��傤���B
���m�����m�����Ɉ�����肽������͂����ς�����������ł��傤���A
��������͕̂l�I���W���A��ԁA�E�тȂ��̂ł��傤����(TT)�c���G�ł��ˁB
���E�������
���O�̋����������X�݂͂ȁu�̗w�{�V���[�v���|���Ƃ��Ă�����Əo������ł��ˁB
���I�ɂ͉��R�z�b�g�u���U�[�X�i�R�R�~���g��������j�������Ē��������I
�u�̂�����r�u���t�H���v�Ɓu���b�v�{�o�P�c���x�[�X�v�͗��j�I�����A���Ƃ������ł��B
�iMJQ?�Łj�������Ă����~���g�E�W���N�\���Ɂu�̂�����r�u���t�H���v�������Ă܂����I
�������낤��NHK�̔ԑg��(^^�U�c
���������t�����L�[�䂳��A�n�i������A�W���[�W�������̃h�����E�o�g����NHK�Ŋς܂����B
����͂₨�O���Ƃ��I���I���B�ƂĂ��y�������ɁA�C�����ǂ������Ƀv���C���Ă܂����B
��������炪�ق���јr��g��ŚX�����Ⴂ�܂����B
NHK���Ȃ��Ȃ��ʔ����������Ă������̂��Ɗ��S�������̂ł��B
����ɗ]�k���c�A�j���u�}�b�n�IGo!Go!Go!�v�̃I�[�v�j���O�A���L���ɂ���܂��ł��傤���H
�^�U�̂قǂ͊m���ł͂���܂��^�C�g���E�o�b�N�̃}�[�`���O�E���[���̓t�����L�[����̋q�����Ƃ��c
�̂������ł������f��̒��œ犘�t���C�p���ƋY���t�����L�[���D���ł���(^^�U
�h�������@���Ă���Ă���̂��ȁH������ƋC�ɂȂ�CD�ł��B
http://www.hmv.co.jp/product/detail/1382761
��TANGENT�͎����C�ɂȂ��Ă���̂ł����A���܂������ł����ɂ��܂��B
���Ɠd�ʔ̂̒��܂����|�C���g��EVO���������NuForce��icon�Œ����Ă܂��B
���̉��i�ŗ��ʂ����Ă��郁�[�J�[�Ƒ㗝�X�ɏ^�肽���ł��B
���ꂾ���y�������y�����Ă���Ă��̉��i�Ȃ�喞���ł��B
�ƂĂ��[���������i���Ǝv���܂��̂ŋ@�����܂������x�`�F�b�N���Ă݂ĉ������B
���������戵�X��������Ɩʔ����̂ł����A�㗝�X�̉c�Ɨ͂�����Ȃ��̂�������܂���˂��B
�����ԍ��F8117899
![]() 0�_
0�_
�@�{���́A�^���V���b�v�̃I�[�i�[���畷�����b���Љ�܂��B���̓X�̏�A����u35���~�̓d���P�[�u���������璮���ɗ����v�Ƃ̐\���o���A���S�u���������ǂ��Ŕ������B�E�`�͂���ȃo�J�����P�[�u���Ȃ��߂Ȃ����v�Ǝv�����i�j�����{�ʂŃ��[�U�[�K�₵���I�[�i�[�́A���̃P�[�u���́g���́i�H�j�h�ɑ�w�������Ƃ̂��ƁB
�@����܂Ŏg���Ă���5���~�̓d�P�[���炻��35���~�P�[�u���ɕt���ւ����r�[�A�������M���[�b�ƍi��ꂽ���X�N�G�A�ȓW�J�ɕϐg�B�E�E�E�E�����lj�����M���M���[�b�Ƌ����Ȃ�A���Ƃ��₵���T�E���h�ɐ���ʂĂĂ��܂��������ł��B���[�U�[�H���u���[��i���j�B���A������35���~���ˁB�����̒��܂��͐����v�B�I�[�i�[�H���u���A�����ł��ˁB����ς�35���~�B���̕ω��̓x�����͂��Ȃ���̂��Ǝv���܂���B����v�B���[�U�[�H���u����H�@��������35���~������ˁE�E�E�E35���~����������E�E�E�E35���~�����A�͂͂͂́i�E�́j�v�B�ȉ��A��l�Ƃ������i���j�B
�@�P�[�u�����Ă̂͑����̏ꍇ�������ł��Ȃ����A�w������̂̓o�N�`�݂����ȂƂ��낪����܂��B�t�Ɍ����A���[�U�[�����i�̃N�H���e�B���m�F�ł��Ȃ��̂ŁA��Ȑ�`�����Ŕ�����邱�Ƃ��\���Ƃ������Ƃł��B�܂��uProCable�v�������Ă���悤�Ȉ����ȋƖ��p��������܂�����������܂����A��O���킵�����i�̐��i���u����́A�쌱���炽���v�݂����Ȏ����グ�������郁�[�J�[�ƁA���̐K�n�ɏ��I�[�f�B�I�G����]�_�ƁA�����ăR�������x����Ĕ������߂Ă��܂��}�j�A������ڂ̓�����ɂ���A��ʃs�[�v���̓h�������ł��傤�ȁB
�@���������Ȗؔ��ɓ����Ĕ����Ă���P�[�u���A�є�̃R�[�e�B���O���{����Ă���P�[�u���A���h�z�[�X�݂����ɑ����P�[�u��etc.�@���ʂɉ��y���y���ނ̂ł���A����Ȃ̂��K�v�ł���͂����Ȃ��̂ł��B
�@����ƁA�ʂ̃V���b�v�̓X�����畷�������Ƃł����A�����̖^�L���}�j�A���������P�[�u���̔��Ǝ҂́A�A�����J���̈����ȋƖ��p�P�[�u����O���̒P���ő�ʂɔ����A����Ɏ��Ђ̃��S�ƃP�[�u���J�o�[��t����1���[�g��������1���~�ȏ�Ŕ����Ă��邻���ł��B�܂��A�{�����ǂ����͕�����܂��A���蓾�Ȃ��b�ł͂Ȃ��ł��傤�B������č��̍����P�[�u�����[�J�[���g�p���Ă�����ނ�����Belden�����Ƃ����͎̂����݂����ł�����ˁB
�@��ʐl���炷��A���̒��ɂ̓I�[�f�B�I�}�j�A�Ƃ����l�킪���č������ȃA���v��X�s�[�J�[���Ă���E�E�E�E�Ƃ��������͉��Ƃ��������Ǝv���܂��B������ނ炪�g���Ă���A���v���X�s�[�J�[�����邩��ɍ������ł��B�������A�����̓d���ɐ��\���~�i�w�^����ΕS���P�ʁj���������ނƂ����̂́E�E�E�E�ǂ��l���Ă�����Ȑ��E�Ƃ͎v���Ȃ��ł��傤�B�슴���@�Ɠ����x���ł��B���������I�J���g���ʂ̃e�C�X�g�����Ă䂭���Ƃ��A����̃I�[�f�B�I�E�ɂƂ��đ厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8118047
![]() 0�_
0�_
redfodera����
�����́A���v���Ԃ�ł��B
�x���X�ł����܂���B
���X�s�[�J�[�͖炵�ĂȂ�ڂȂ̂ŁA�������������Ďd�������܂ꂽSP���j�b�g�قǖ��Ӗ��ʼn��z�Ȃ��̂͂���܂���(^^;)
�m���Ɏ��ۂɉ��͏o�ĂȂ���������܂��Aredfodera����̃C���[�W�̒��ɂ��Ȃ�
��������t�łĂ���͂��ł��̂ŁA���̃��j�b�g�����X�ɕ��܂܂ɂȂ��Ă������
�K���Ȃ̂�������Ȃ��ł���(^^
�o���h�����A�����ł��˂�
�l���ꉞ���Z�̎��o���h��g�o���͂���܂��BEB�S���ł����B
���܂��ɉ������Ƀt�F���i���f�X�������Ă��܂��B
�����̃R�s�[�Ƃ����Ή�����BO��WY,ZIGGY,�W�����X�J�Ƃ������Ƃ���ł��傤���H
�l�B��REDWORRIERS,THE BLUEHEARTS�ɂ�������Ă��܂����B
���C�u�o���������Ȃ��܂I����Ă��܂��܂������A�����v���o�ł��ˁB
�����ԍ��F8118920
![]() 0�_
0�_
�F����A���v���Ԃ�(??)�ł��B�y���͕����A�h��E�E�E�Ƃ��낢�날���ĖZ�����ł��ˁG
>>�r�[�g���Y���������̑O���Ƀh���t�^�[�Y�I���o��
����m���Ă܂���!�̂�U��Ԃ�e���r�ԑg�������Ō����o��������܂��B���̂Ƃ��͉���r���������茩�܂���ł����ˁB���x���Ă݂悤���Ǝv���܂��B
���ƁA�u���R�z�b�g�u���U�[�X�v���x�m�F���Ă݂܂��ˁB
�܂��b�肪���낢��ƍ������Đ\����Ȃ��̂ł����A�T���ɎD�y�̃I�[�f�B�I���X��㉮�ɍs���Ă��܂����B�j�F�B1�l�ƎD�y�����낢�댩�Ȃ����Ƃ������ƂŁA���������Ȃ�Ǝv���F�B�ɖ����������Ĉ��������Ă����̂ł��B
�܂��A�F�l�����������悤�ɁA�Ƃɂ�������ɂ���!�Ɠd�ʔ̓X�Ƃ͒������Ɠ��̕��͋C�������o���Ă��܂����B�����Ă�����1�K�ɂ�KEF��iQ3���B����!�Ǝv�����߂Ă���ƁA�X�����u��̊K�ɂ�����܂���v�ƌ���ꂽ�̂œ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
��̊K�ɍs���قǍ����ȋ@�ނ���������ƁB10���~���SP�̂Ƃ���Ŗl�̍D���ȃh���J���������܂���(�N���V�b�N�Ƃ�����Ȃ��đ�ώ���)�B�A���v�Ƃ����낢��ς��Ē����Ă݂܂������A�ْ��ł���܂�悭������܂���ł����B�X������������C���Ȃ��Ȃƕ������Ă���̂��A�������l�s�V�B���̌�AJBL�̃G�x���X�g��B&W�̂ł������̓��X�߂ē�����悤�ɋA���čs���܂����B
���������Ⴂ�̂������̂ɁA�X��������ϋɓI�ɘb�������Ă���邱�Ƃ��Ȃ��A������������ł����B
���x��10���~���炢�����Č����Č����т炩���Ȃ��王�����Ă��悤����(���)�B
�����ԍ��F8119088
![]() 0�_
0�_
�R�R�~���g����@
�V���b�v�̓X�����������̂ł��B�����|���������ǂ��̂��A�ق��Ă����Ď��R�ɂ��Ă���
���̂��ǂ����E�E�E�BDD66000���Ď���������̂����đ�s�s�̃V���b�v����Ȃ��Ɠ����
�ł�����A���߂邾���ł͂Ȃ��h���J���ł��\���܂���A�炵�Ă��炦�Ηǂ������ł��ˁB
(DD66000�̓A�L���t�F�[�Y�̃Z�p���[�g�A���v�A�G�\��CD/SACD�v���[���[�Ŏ�������������
��܂����A���i���l����ƍw������C�ɂ͂Ȃ�܂���E�E�E�B�ܘ_�A�����ƌ��������
���܂����E�E�E�B�]�����đ��̃X�s�[�J�[���܂��B300���~�����Ȃ�p�C�I�j�A��TAD�̕�
���ǂ������H�H�B)
�ǂ�ȃV���b�v���q���Ƃ��Ⴂ�l�����ɂ��Ă͂����܂���ˁB���̎��Ɉ���ꂽ�L�����c��
�܂��B����DD66000���y�`�������邨�������ɂȂ��Ă����̃V���b�v����͔����܂���B
�����Ⴂ���A��y�ɕt���ĎԂ̃f�B�[���[�ɍs���܂�����(�ƂĂ��Ԃ�������҂ɂ͌����Ȃ�
�����n�Y)���̎��̑Ή��������ǂ��A15�N���炢��ł��������̃f�B�[���[��1�䔃���܂����B
���E�������
���̒n���̃V���b�v�Ŏ�����J�����̂ŁA���X�Q������̂ł������܂łŗǂ��Ȃ��A�Ɗ�
�����̂̓p�C�I�j�A��S-1EX�ł��B�ቹ�̃X�s�[�h���f���炵���e�y��̒�ʂ������A�x����
�E��/�}�O�l�V�E���Ƃ����������U���Ȃ̂ōd�������ȁH�Ƃ�������ς�ǂ��Ӗ��ŗ���
��Տꊴ���ӂ�鉹�y��t�łĂ���܂��B
JBL�̐V����S-4600��LUXMAN��C-600f/M-600A�A�G�\��X-05�Ƃ����g�ݍ��킹�Œ����܂������A
������ǂ������ł��ˁB�N���b�V�b�N���ǂ������ł��B�����A�Ђ���Ƃ�����A����X�s�[�J�[���Ƃ�����S-1EX�Ɖ��i���߂��ł�������������ł��B�E�E�E���̃A���v�̓A�L���̃A
���v(E-550)�Ȃ̂ł���LUXMAN�ł��ǂ��������ȁH�Ǝv���܂����B(���ہA�w���������܂�
���B)�N���b�V�b�N���Ȃ�LUXMAN�̕����ǂ������H�H�B
�A�o���M�����h�̃X�s�[�J�[�͈��ٗl�Ȋ��������܂���nano�͗ǂ������ł��ˁB�����A���i
���������čw�����Ƃ��Ă�10�Ԗڂ��炢�ł��B���̓z�[���^�X�s�[�J�[���D���ł��B
�N�H�[�h�̃R���f���T�[�X�s�[�J�[�͒�������Y��ȉ��Ȃ̂ł����A�ቹ�������ς�A�^���m
�C�̃O�����G�A���ǂ������ł������A���i���l����Ƒ��̋@�킪���ɂȂ�܂��E�E�E�B����
���A������Autograph�@mini���܂�����������������̂ɗǂ����o���Ă��܂����B�ł���
�͂艿�i���y�A��30���~������̂ł͔����C�ɂ͂Ȃ�܂���B
����Autograph�@mini���炢�̑傫���Ȃ獑�Y�ɂ��E�E�E�Ńp�C�I�j�A��S-A4SPT-VP����
�����B�_����HELICON 400 MK2�������܂��������̊����ɂ͋����܂���ł����B
�p�C�I�j�A�̃J�^���O�ɍڂ��Ă����̂ł����A1976�N�Ɍ�JBL�̃`�[�t�G���W�j�A�ŕ��В���
�Ŗ��߂��o�[�g�E���J���V�[�����p�C�I�j�A�ɓ����Ă���̂ł��ˁBTAD�����̕����ł�����
���Ƃ̎��ł��BS-1EX�ȂǗǂ��X�s�[�J�[���o���킯�ł��ˁB
�����ԍ��F8119534
![]() 0�_
0�_
�F�l�A������������܂��B
�@�����A�u�R�T�x�v�ȂǂƂ������������܂��B�F�l�@���ł����H
�@���ꂵ���b��́u4344�v�ł����A�ړ��ɂ͂���قǎ�Ԃ�������܂���B
�@�O���͖^�X�^�W�I�̃��j�^�[�@�ł��āA�k�A���O�����̊��ȃL���X�^�[�ɏ����
�@����܂��āA�����̂͌y���̂ł��B
�@�R���N���A�����͌������ɒu�����Ƃ��O��ł��̂Ŏ��O���̂͂��Ȃ�ʓ|�ł���
�@���^SP�̂悤�Ɉʒu��CM�P�ʂŎϋl�߂���A�p�x�����߂���͒v���܂���B
�@���ƂȂ��ݒu���ĂQ�|�R�ȕ����āu����Ȃ���ȁ`�I�v�Ŏ��̏ꍇ��THE END�B
�@�}�b�L����A���v�W�����̃p���[�A���v�ނ������l�ȑ�Ԃɏ悹�Ă���܂��̂�
�@���i�ȕ��Ɍ��킹��Ɖ��������I�ƌ����Ă��܂��悤�ȁE�E�E�E�B
�@�u�e�L�g�[�v�Ȑ��i������ƂƂ��Ɂu���������v�ɂȂ����܂��B
�����ԍ��F8124349
![]() 0�_
0�_
�@�|��redfodera����
�@�t�����L�[��Ƃ����A�ߓ��^�F�剉�̉f��u�����ĂԒj�v�ŃL���X�g�̃h�����w�������Ă��܂����ˁB�E�E�E�E�܂��A�������鑤�́g���ʁh�͂ǂ̒��x�ł������̂��́A���͉f����ςĂ��Ȃ��̂ŕ�����܂��i���j�B�W�Ȃ��ł����ǁA80�N�㔼�܂ł͖M��ł́g���̂���f��h�̃I���p���[�h�ł����Ȃ��B���������A�������̃h���~���O���Ȃ��Ȃ��̂��̂ł����B�o���G�e�B�ԑg�Ŕނ��a���ۂ�@���V�[�����������̂ł����A���̓����Ƃ������Y���̊m�����Ƃ����A���S�������܂����B
�@�u�}�b�n�IGo!Go!Go!�v�̃I�[�v�j���O�͂�����Ɗo���Ă��Ȃ��ł��B�����������̃A�j���̃n���E�b�h���ʔŁu�X�s�[�h�E���[�T�[�v�����ς܂����B�o���́E�E�E�E�ς����Ƃ��������悤�ȃV�����m�ł����ˁB�e�ɏd�ʋ��̃L���X�g��z���Ă���̂ɁA���ɂ��������Ȃ��B�č��ō��]�������̂������܂��B
��FOSTEX�̃C�^���A�����b�h�̃X�s�[�J�[
�@���{�̑�胁�[�J�[�����ʂȃJ���[�����O�Ƀg���C���ė~�����Ǝv���܂��B�V���o�[�⍕�������Ȃ��ł����A�����ƃ��@���G�[�V�������]�܂�܂��B�E�E�E�E�Ƃ͂����Ă���Ԋ��S���Ȃ��̂́g�E�ւȂ炦�h�ł��ˁB598����̍���F�Ƃ��A10���N�O�̓V�����p���S�[���h�̉Ԑ���Ȃ�Ă̂�����܂����B�S�[���h�n�Ŏ������̂�ACCUPHASE���炢�������̂ŁA���̉�ꉻ�Ԃ�͂�����ƒɁX���������ł��B
�@�|������28��������
�@�t�F���i���f�X�A���̊w������ɂ������Ă���z�������������܂����BGRECO�Ƃ�ARIA PRO2�Ȃ�Ă̂�����܂����ˁB�M�u�\����t�F���_�[�̏��L�҂͂܂��܂����Ȃ��A����̓I�ł����B�R�s�[�̑Ώۂ�BO��WY��W�����X�J�Ƃ́A����ς萢��̈Ⴂ�����������܂��Ȃ��B��X�̎���͑��f�B�[�v�E�p�[�v�����c�F�b�y�����ł����B�y��̏�肢�z�̓��b�N�����N���X�I�[�o�[�i���Ō����t���[�W�����j�ɑ����Ă܂����B�m�荇����Stuff�̃R�s�[�o���h����Ă��z�����܂������A���̃o�J�e�N�Ԃ�ɊF����ڒu���Ă������̂ł��B
�@�|���l�I���W����
�@�}�b�L���͂悭�����������Ƃ͂���܂����A�A���v�W���͒��������Ƃ�����܂���B�s�����̃f�B�[���[�ɓW���͂��Ă���̂ł����A��������Ă���Ƃ���ɔ����킹�����P�[�X���Ȃ��̂��c�O�ł��BJBL�̃X�s�[�J�[�i���ɑ�^�j���āA��r�I�Z�b�e�B���O�ɑ�g���Ǝv���Ă܂��B����݂̒��Ãf�B�X�N�X�ł�4343�����ɖ�����Ȓu����������Ă��܂����A�I�[�f�B�I�ɋ����̂Ȃ��l�ł��g�����I�h�Ǝv���悤�ȓX�����ʔ��Q�̉��Ŗ��Ă��܂��B���ׂĂ�CD�V���b�v�͂����Ɨǂ��I�[�f�B�I�����ė~�����ł���(^^)�B
�@�|��130theater����
�@AVANTGARDE ACOUSTIC�͗ǂ��ł��ˁB���x�ƂȂ��������Ă��܂����A���قȗe�e�Ɏ�����ʖ��邭�m�[�u���ʼn��₩�ȉ��B���Ƀ��H�[�J���̐��X�����ɂ̓n�b�Ƃ��܂��B�����������ł��B�����A�߂��Ⴍ���ፂ���B����G���ɂ��̃u�����h�̃X�s�[�J�[����������X�g�������Љ��Ă��܂������A�����X�܂��ƈ������������Ă��q���h���������Ă��܂��̂ŁA�L���X�y�[�X�̊m�ۂɓw�߂��Ƃ��B
�@�I�[�f�B�I�t�F�A�ň�ۂɎc�����X�s�[�J�[��THIEL������܂��B�č����ł����AJBL�̂悤�Ȑ��C�݃T�E���h�Ƃ�AR�̂悤�ȃC�[�X�g�E�R�[�X�g�̉��Ƃ��Ⴄ�A������B���Ƃ�������悷�A���邭���Ɠ��̃L���`�C�C�W�J�������Ă��܂��B���������̂̓n�C�G���h�@�ł����A���Ђɂ͈�ʃs�[�v���ɂ�����o���鉿�i�т̂��̂�����܂��̂ŁA�@�����Ύ��@�ɐڂ��Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�|���R�R�~���g����
�@���V���b�v�͕~�������������ł����B�{���́A�ǂ�ȗ��q�������Ă�����Ȃ�ɑΉ�����̂��q�����Ȃ̂ł����A�ǂ����������Ă��Ȃ��X������悤�ł��ˁB
�@�@�����ǂ��s���X�́u���{��A������Ȃ��X�v�Ǝ��̂��Ă���ʂ�i���j�A�K�c�K�c���Ă��Ȃ��Ƃ��낪�C�ɓ����Ă܂��B�����Ƃ��A���̓X�͖ق��Ă��Ă������悤�ȏ�M�͂������Ă���̂ł����ǂˁE�E�E�E�B���̊��z���ƁA�q���y������X�́A�I���W�i���e�B�̂Ȃ��Ƃ��낪�����ł��B�������[�J�[�i����ׂĂ��邾���ł́A����ς�u����グ�����`�v��������s���Ă��܂��̂ł��傤�B
�@���x�̓I�[�f�B�I�t�F�A�Ȃɍs���Ă݂���ǂ��ł��傤���B��������Ă��N���������͌����܂���B�܂��A�V���b�v�ł����Ȃ��鎎������ʔ����ł��B
�����ԍ��F8125238
![]() 0�_
0�_
���E�������A�F����A�����́B
�F����̃R�����g�����Ɋy�������̎Ⴂ�����v�������Ă��܂��B
�`�u5.1�`�����l�����́AONKYO�̏����̃A���v�̍�����ō����݂�ONKYO�ł��B
2�N�قǑO�Ɉ��z���������̂ł����A�ו��̐����ŏ����i�ʂ��Ă����Ƃ����
�Ȃ��!�I�[�v�����[���f�b�L���o�Ă��܂����B
���܂�̉��������ɁA�肪�~�܂肵�炭���߂Ă��܂����B
��������!�����ȃI�[�v�����[���ɂ͎肪�o���A�{�[�i�X�ň�Ԉ�������������
�v���o���ۑ���Ԃ����������Ȃ��Ă��A����͎̂ĂȂ��Ŏ����Ă�����
���ꂩ��Ⴂ�Ƃ��ɒ����Ă����A���ŁA�e�l�ŗ���Ă����Ȃ���������
���������Ȃ��āA��A��Ƌ@������������Ȃ�ɃZ�b�e�B���O������
�s���A�E�I�[�f�B�I��s���A�E�I�[�f�B�I��A�ƓƂ茾�������Ă�����
�ł���Ƀs���A�E�I�[�f�B�I�ƌ����Ă����������s���A�łȂ��Ƃˁ`�`�E�E�E
�E�E�E�������فE�E�E�V���P����3�H���炢�����ɔ��ł��܂����B
���������ȂŁA���݂̘^����Ԃ̗ǂ�CD���l�b�g�ŒT���A�����Ă����Ƃ����
���q�ɂ���͉��H�ƕ�����A�̗w�ȂƓ������
�̗w�Ȃ��ĉ��H�ƕԎ����A���Ă����B
��k���Ǝv�����̂ł����������Ɛ^���Ȋ�����Ă���̂ŁA�̗w�Ȃ�m���̂���
�����ƁA���ꉽ�H�E�E�E�E
�E�E�E�������فE�E�E�V���P����4�H���炢�����ɔ��ł��܂����B
���̂͂ƕ�����
���̂̓W�F�����̂��Ă���Ƃ̕Ԏ�
���̉��̉̎�͂ƕ����Ɩق荞��ł��܂����E�E�E
�E�E�E�������فE�E�E�V���P����5�H���炢�����ɔ��ł��܂����B
�͂��`!�@����M���b�v���g�ɂ��݂�B���_���q�̃|�[���X�^�[�̓p�[�v���^�E����
������! ���ݐ����̐����A�₯�Ɏ₵���B
���߂Ă̓��e�ŃO�`���Ă��܂��܂����B�\�������܂���B
�����ԍ��F8127989
![]() 0�_
0�_
�@�Ⴂ������ԉ�����A����ɂ��́B�s���A�E�I�[�f�B�I�͍D���ł����A�S�̒��͂܂������s���A�ł͂Ȃ��g�s��ł��i�����j�B
�@�����ł����A�����̎Ⴂ�O�́u�̗w�ȁv�Ƃ����p����m��Ȃ��̂ł����B�u�̗w�Ȃ��ĉ��H�v�Ƃ��������˂�����ꂽ�ۂ́A�I�[�f�B�I�t�@���Ƃ��Ắu�̗w�ȂƂ́A���{�̃|�b�v�X�̒��ŁA�^���̗ǂ��f�B�X�N�Ɏ��߂��Ă���y�Ȃ̂��ƁB���ɘ^�����������̂�J-POP�Ƃ����̂���v�Ɨ�R�Ɠ����������̂ł��E�E�E�E���āA�t�H���[�ɂȂ��ĂȂ����X���B
�����̂̓W�F�����̂��Ă���Ƃ̕Ԏ�
�@���߂āu�X�삫�悵���̂��Ă�v�Ƃ̕Ԏ����~���������Ƃ���ł���(^^;)�B
�@�ܗ^�|�Ɣ��_���q�Ƃ����荇���Ă������A�u�j���[�~���[�W�b�N�E�̂T�E�W�푈�v�ƌ����Ă��܂����B�������u�{�ƂT�E�W�푈�v�Ƃ͌ܖЂ낵�Ɣ���I�̂��ƁE�E�E�E�Ȃ�Ă��Ƃ�m��w�����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��傤�B���_���q�́u�p�[�v���^�E���v���āA�����͔ޏ��̍쎌��ȂƂ����G�ꍞ�݂������̂ł����A����i���f�]�p�j���o���Ă���̓N���W�b�g�ɖ{���̍�Ȏ҂ł���C�O�~���[�W�V�����̖��O���L�����悤�ɂȂ����Ƃ����E�E�E�E���Ƃ��u�̘b�v�ɐ���ʂĂ܂����B�����̌o�̂͑������̂ł��B
�@�V���P���Ƃ����̂�����ł����ˁB�́A�^�ԑg�ŏ������v���u�V���P���̉́v�Ƃ����̂�����Ă܂������E�E�E�E���[�A������������������̘b�ł��i���j�B
�������Ȃ��Ă��A����͎̂ĂȂ��Ŏ����Ă�����
�@�I�[�v�����[���͎g�������Ƃ͂���܂��A�{���v�X�ɃJ�Z�b�g�f�b�L�����Ă݂��Ƃ���A�C�W�F�N�g�@�\�ɃK�^�����Ă��܂����B10�炢�����Ă���ƃt�^���J���A�̎蕨�̃��R�[�h����R�s�[�����e�[�v���Z�b�g���Ē����܂����B���[�t�@�C�ȉ��ł����A�s�v�c�Ɖ�����̂���z�b�Ƃ���悤�ȃT�E���h�ł��BiPod��PC���������ǁA�ꍇ�ɂ���Ắu�ǂ����R�s�[�����v�Ɗ�������悤�Ȓ�𑜓x�̉����̂Ă��������̂�����܂��B�����A�����͖��S�ł͂Ȃ��ɂ���A���̃f�b�L��ۗL�������邱�Ƃ����߂܂����B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂�(^^)�B
�����ԍ��F8131727
![]() 0�_
0�_
�F����A�������������܂��B
���E�������
�������̓d���ɐ��\���~�i�w�^����ΕS���P�ʁj���������ނƂ����̂́E�E�E�E
���ǂ��l���Ă�����Ȑ��E�Ƃ͎v���Ȃ��ł��傤�B
���܂܂ł����瓊���i���m�ɂ͎U���ł��j���܂������H�ƁA�����ƁE�E�E����������̂��S�O���܂��ˁB
���܂荂�z�ȃP�[�u���ނɂ͎���o�����Ă���ł͂Ȃ��͂��̎��ł��A�����ƐF�ڂł݂���z�ł��傤�ˁB
���[�����Ď��삷��悤�ɂȂ��Ă���͂���Ƃ������Ȃ�܂������A2���~�����A�C�e���͂���Ȃ�ɁE�E�E
���̏ꍇ�͒P����10���~�������̂͂���܂���SP�P�[�u���ŏ����@����݂�1�_����܂����B
�w������Ƀ��j�^�[PC�̍ł�����SP�P�[�u���im/����6,000�~�j��6m�y�A�̒��Õi���A
�u�ꐶ���m�v�Ǝv���Ȃ��Ȃ��̃o�C�g�ォ��2���~�Ŕ������͂��Ȃ̂ɁE�E�E���ǁA�����玟�ւƁi��j
�ŋ߁A���s�ɂȂ����P�[�u���ނ̃��b�N�{�����n���Ă܂����A���i�̒l�i�����邱�ƂȂ���A
���̎�̃��b�N�{���N1��ŐV�łŔz�{�����Ƃ������Ƃ��炵�āA�����ɋꂵ�ޕ��͑吨����������ł��傤��(^^;)
�����{�̑�胁�[�J�[�����ʂȃJ���[�����O�Ƀg���C���ė~�����Ǝv���܂��B
�ŋ�icon�i�p�X�e���E���b�h�j�̂�����TANGENT��EVO�i��͂�p�X�e���E���b�h�j�����������Ă��܂������A
�ߋ���ۂ��Ƃ͂����J���t���Ȃ��̂̓A�N�Z���g�ɂȂ��Ă���͂���Ŋy���߂܂��B
�ꎞ���A�A�R�[�X�e�B�b�N�E���{�̃{�������A�s�A�m�E�u���b�N�ƃ��B���B�b�h�E�J���[�i�o�b�t���̈ꕔ�j�̑g�ݍ��킹�ŁA
���I�ɂƂĂ��h�������b�N�X�ɉf��X�s�[�J�[�̃N�I���e�B�Ƃ��ǂ��G������ꂽ���̂ł��B
�o�[�Y�E�A�C��t�B�M���[�h�A�^�C�K�[�E�X�g���C�v�E�E�E���C�v���̉��ϔ���̓V�[�X���[���h����ؖڂȂ̂ŁA
�ŋ߂͑O�q��FOSTEX�̑��ɂ��₽�獑���O��킸�ڗ��l�ɂȂ��Ă��܂����ˁB���̃g�����h�Ȃ̂����E�E�E
���⋰�炭�l�I���W�����Gibson�̃I�[���h�E���X�|�[���̃Z���^�[�E�u�b�N�}�b�`���ŏ��ɃC���[�W�����Ⴂ�܂����A
�ނ����V�J���A��X�v���[�X�ł��傤�����@�C�I�������ł͂��Ȃ���j�̂��鐧���@�Ȃ�ł��B
�X�s�[�J�[���y��Ɍ����Ă邱�Ƃւ̈ӌ��͗l�X�ł��傤�����b�N�X�I�ɂ͊��}�������ł��ˁB
����28��������@
���l���ꉞ���Z�̎��o���h��g�o���͂���܂��BEB�S���ł����B
�Ă���28����������G���L�E�x�[�X��������ł����I
�����y�툤�D�҂����Ă���Ċ������ł��I
���̕��͒��w������Ƀo���h�E�p�[�g�ŋ��x�[�X�����Ȃ��A�a�X�A�e���͂��߂������ς��ߋ�������܂���(^^;)
�Ⴂ������ԉ�����@�A�͂��߂܂��āB
�̂������炢���Ȃ�_�E�i�[(^^;)�ł����A���C�����Ă܂���܂��傤�I
���ו��̐����ŏ����i�ʂ��Ă����Ƃ���ɂȂ��!�I�[�v�����[���f�b�L���o�Ă��܂����B
������̔ɂ̓I�[�v�����[���Ɉ�ƌ��������̃J�L�R�~�X�g������l��������Ⴂ�܂��B
�y�������b��������Ǝv���܂���E�E�E�ƁA����ɐU���Ă��܂��܂������A�X�������肢�������܂�<(_ _)>
�����ԍ��F8132658
![]() 0�_
0�_
�F�l������������܂��B
�@redfodera����́u����ɐU���Ă��܂��܂������E�E�v�Ɍ����ɒނ��ė��܂����B
�@���͌�����TEAC��2TR38�@��4TR�@���g�p���Ă��܂��B
�@CD�^�J�Z�b�g���S���ƌ���ꏉ�߂Ă����FM�G�A�`�F�b�N�̓I�[�v�����[���ł������A
�@�V�O�N�ォ��W�O�N��㔼�ɂ����Ẵ��C�u�ՁE�X�^�W�I�^���łȂǃ��R�[�h��e�[�v��
�@�Ȃ��Ă��Ȃ�JAZZ�l�^�����Ȃ�̗ʁA���L���Ă��܂��B
�@���y�Ɍg����Ă��������ɘ^���X�^�W�I���ɗF�l���o���A����ȊW�ŏ�q��4344��
�@���L�V�R���̃��o�[�u���j�b�g���̃X�^�W�I�@������Ȃ��ɓ���܂����B
�@AMPEX��8TR�}�X�^�[���R�[�_�[����肷��@����������̂ł����A�������̎��ł�
�@�e��S�~�����ڂɌ����Ă����̂ŁA�f�O�������Ƃ�����܂����B
�@���ԂƓ����ł��̑��ݎ��̂��������Ƃ������A����тƂ������Ɂu�X�g�C�b�N�v��
�@�ʂ��o�Ă��Ă��܂��̂͂�͂�a�C�ł��傤�ˁB
�@�G�A�`�F�b�N�e�[�v��CD�����鎖�Ɏ�𒅂������̂ł����A���̑O�ɕЂÂ��˂Ȃ�Ȃ�
�@�����R�ς݂Ō�����܂��B
�@�V�����I�[�f�B�I�@��͑��̊F����ɂ��C���ŁA���̏ꍇ��AV�W�������V�@����g�p���B
�@�u�|���R�c�E�A�i���O�E�e��S�~�v�����̃I�[�f�B�I�̎O������ł��B
�@
�����ԍ��F8132826
![]() 0�_
0�_
�F���͂悤�������܂��A���ɒ�����30���z���A�䓙�A��l�ɂ͊����܂�(>_<)
�l�I���W�����
��redfodera����́u����ɐU���Ă��܂��܂������E�E�v�Ɍ����ɒނ��ė��܂����B
���̒ނ�ꂽ�K���ɗ��܂��Ĉꏏ�ɂ������Ă��܂��܂����I
�y�|���R�c�E�A�i���O�E�e��S�~�v�����̃I�[�f�B�I�̎O������ł��B�z
�A�i���O�������S�Ă���̒��~�j�ŃX�^�C�������ł��B
�I�[�v�����[���͂S�g���V�����[���Ł@���e�l�G�A�`�F�b�N�p�Ŏg���܂����ˁB
���͂���܂��i�a�k�S�R�P�Q��������Ԏg�p�ł����B
redfodera����@���͂悤�������܂��I
�Ă���28��������@���X�Q��̂d�a�@�C���[����͂����ł��A���͔{���A�ԈႢ�Ȃ�
���ǂ��ł��傤�A�v������NHK�̃I���W�o���h�S�����̒n��\�I�փG���g���[���ĎQ��E�E�E
�����E�E�E
���̑����̑��҂Ƃ��āE�E�E�@�@�@�@�@�@�X�ɑ����H�E�E�E
�Ⴂ������ԉ�����@�͂��߂܂��āI
�����߂Ă̓��e�ŃO�`���Ă��܂��܂����B�\�������܂���B
���������@��̘b�A�M���O�����ĕ��h�̌��������l�̈ꌾ�A���X�y�����ł���A���ꂩ��������ăO�`����(�H)�@��������(^^)�B
�@
�����ԍ��F8133142
![]() 0�_
0�_
satoakichan����A���v���Ԃ�ł��B
�@�A���R�O�x�z���̏����̒��A��������Ă����}�b�L���ƃA���v�W�����p���[��_��
�@�ׁ̈A�ʓd�������܂����B
�@����ڂ��E�C���hAC�݂̂̋��������́A�ق�̂R�O���ʓd���������łR�T�x��
�@���̓d�C�X�g�[�u���̓d�͏���Ƀu���[�J�[����т܂����I
�@��CH�m�C�Y���o�Ă����}�b�L���͉��̂��m�C�Y���o�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��āH�H�H�̘A���B
�@�f�W�^���łȂ��u�s��͒@���Β���H�v�I�A�A�i���O���z�ł��傤���A�s�v�c�ł��B
�@��͂茻�p�̃A�L�����͒ቹ�̃h���C�u�Ɂu����̒�����v���f���Ȋ��z�ł��B
�@�A���v�W���̓A���v���̂̓��쉹���ȑO��葝���Ă���悤�Ɋ����܂����B
�@�ƌ����̂��A���p��5300�Ȃǂ̐V�^�A���v�̐Ïl�������߂Ď�������ƌ������̗l�ŁB
�@���̗��A���v�͓~�܂Łu�Ė��v��ԂɁB
�@�u�I���W�o���h�v�͖{���ɗ����ł��ˁB
�@��肢�E����ƌ������A�u�y�����v���y�����邱�Ƃ��厖�ł��ˁB
�@���t��̑u�����̓X�|�[�c�Ɠ����l�Ȋ��o�������炵�܂��B
�@�u�Z�\�̎�K���v�ł͂Ȃ��u�Z�\�̂����炢�v�̓I�W���ɂ͂�茒�S�ȓ��X�̗Ƃ����H
�@
�����ԍ��F8133334
![]() 0�_
0�_
�l�I���W����
TEAC�̃T���p�`�c�[�g���@�͎����g���܂���A-7030GSL�Ƃ����^�Ԃł����B���̑��ɃI�[�v��
���[���@��19cm/4�g���@7�����[���@SONY�@TC-6030A
http://www.audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/tc-6360a.html
TEAC��19cm/4�g���@7�����[���@A-4300
http://www.audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/player/a-4300.html
AKAI��19cm/4�g���@10�����[����GX-630D
http://www.obsoletemedia.com/tapedecks/akaigx630d.htm
�̌v4����g���܂����BA-7030GSL�͔��������X�ɂ������Ⴂ�܂������A���̋@��͂ǂ�������
���o��������܂���B
�I�[�v�����[����10���e�[�v�̓\�j�[�̎����^����������38�p�`2�g���̃~���[�W�b�N�e�[
�v�E�E�E���쉫�F���́u�{�q�E�B�Y�x�[�[���h���t�@�[�v(�X�R�b�`208�g�p�}�X�^�[��
��)��2�N���炢�O�܂Ŏ����Ă��܂������A�s�����̃V���b�v�̕��ɃI�[�v�����[����������
�����������̂��A���̕��ɂ������Ⴂ�܂����B7�����[���Ɉ�t���������[�_�[�e�[�v
���ǂ����ɂ������n�Y�ł����E�E�E�B
�J�Z�b�g�E�f�b�L�̓p�C�I�j�A�̑�ꍆ�@��T-3300����n�܂�Ō��AKAI��GX-R99
http://k-nisi.hp.infoseek.co.jp/gx-r99.htm
�܂�12�`13�䂭�炢�g���܂����B
����5cm×8cm×1.5cm�ʂ̃f�W�^���I�[�f�B�I�v���[���[��30GB�e��(���ʂ̕��ł����珊�L��
��CD�͑S�Ę^���\)���畷���̂ł�����B10�����[���̎g�p�����̈������E�E�E���v���ƌ�
���ǂ�����ł����B
�����ԍ��F8133580
![]() 0�_
0�_
�F����A�������������܂��B
�������܂�����̋C���́E�E�E���������Ŗ��f�ł��ˁB
130theater����A�l�I���W����A
�����ȐU��ɂ��t�����������A�܂����o�܂������A�L���������܂�<(_ _)>
satoakichan����܂ł��o�܂�������Ƃ́E�E�E���ӁI
�掿�ɂ�����肳������炭���o�܂�������̂ł͂Ȃ����ƁE�E�E���҂��Ă���܂��B
���͏E���Ă��������Ŏg������m��܂�����O�Ƃ��āA���E������I�[�v�����̌��͈ӊO�H�ł����B
����ɂ��Ă��A130theater������͂��߁A�F����A�ؗ�Ȃ鈤�̕������߂��܂�(^^;)
�l�I���W����
����CH�m�C�Y���o�Ă����}�b�L���͉��̂��m�C�Y���o�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��āH�H�H�̘A���B
���f�W�^���łȂ��u�s��͒@���Β���H�v�I�A�A�i���O���z�ł��傤���A�s�v�c�ł��B
����HARBETH�����|������Musical-Fidelity�̃v�����C���ő̌����܂������A
������Ɩ���������ƃV���L�b�I�Ƃ�����̗̂l�ł���A�A�i���O�@��́E�E�E���ċ��������܂����ˁB
�����ԍ��F8133776
![]() 0�_
0�_
130theater����Aredfodera����A�����́B
�@���p�I�[�v���ȊO�Ŏg��������SONY��TC-5950�APIONEER��RT�A���X�w�ǂ�AUTOREVERSE�@
�@����ł����B
�@NAGRA�EREVOX�ȂǗ~�������͐�����Ȃ�����܂������A�@���������́E�E�E�E�B
�@�J�Z�b�g��TEAC��W-790R�Ƃ�����r�I�V�����������p���Ă��܂��B
�@�^��ǂ̃��W�I�E�e���r�͌̏�́u�@���v�ƌ����̂����܂��Ȃ��H�ł����ˁB
�@�\�P�b�g����O�ꂻ���ɂȂ��Ă���̂�@���ƌ��̈ʒu�Ɏh�������肷��H
�@���a�O�\�N��́u�펯�v�������I�ĂȎ��́uClear-Red-Lie�v�ł��B
�����ԍ��F8134260
![]() 0�_
0�_
redfodera����A���E�������A�����́B
�����A�������������Ă��܂��B��������AV�͈ꎞ�I�ɂ��x�݂ł��B�����o���ׂɂ̓p���[�A���v�͕K�{�ł����AA���ׁ̈A���M�͔��[�ł͂���܂���B�����PDP��500W�AAV�A���v�A420W�������A�G�A�R������ꂽ����E�ł��B�����ς瑋���J����CD���t�ɓO���Ă���܂��B
�I�[�v�����[����SONY��TC-7960�������Ă��܂����B�I�[�g���o�[�X���Ђ����Ĉ���ʍs�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�w�b�h���A���v�����C�ł������A�e�[�v���I���ƃ��[�����˂��ւ��Ċ����߂������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B[�ɓ��䂩��]��[���w�̎v���o]�Ȃlj��������čĐ����Ă��܂������A����ł͂ǂ����悤���Ȃ��������ă����[���������Ă�����ɉĂ��܂��܂����B�I�[�f�B�I�X�̕��ɍ����グ�܂�������J���Ă���Ǝv���܂��B(5�`6�N�O�̘b�ł�)
TC-7960���8�N���炢�ȑO�ɔ������ꂽ�Đ��@�\�݂̂�SONY-STEREO-350�������m�ł��傤���H����͍\�����P���Ȃ����ɍ��ł������o�܂��B���[����7���܂łŁA�ɓ��䂩���10���͂�����܂���B�������[�^�[�̃S���S�����́A�������Ɏ����o���Ȃ��ƒ����Ă����܂���B�ł����X�A�̂Ă��Ȃ��̂ł��ˁB
�����ԍ��F8134726
![]() 0�_
0�_
�@�e�[�v�I�[�f�B�I�̘b�Ő���オ���Ă���悤�ł��ˁB�����ō���͋v�X�u�������̃I�[�f�B�I�v�V���[�Y�Ƃ���TDK�ɂ��ď����Ă݂܂��傤���B�����܂ł��Ȃ��A���C�e�[�v�̑��u�����h�ł����B
�@TDK���Ɠ����d�C���w�H�Ɗ�����Ђ�1935�N�ɐݗ�����Ă��܂��BTDK�̃u�����h���͑n�ݓ�������g���Ă����悤�ł��i�펞���������j�B���Ƃ��Ƃ̓\�t�g�t�F���C�g�̍H�Ɖ���ژ_�x���`���[��ƂƂ��ďo�����Ă��܂������A���C�^���e�[�v���Ƃ�1953�N����Q�����A�I�[�f�B�I�t�@���̒m��Ƃ���ɂȂ��������ł��B�Ȃ��A83�N�ɎЖ���TDK������ЂƂ��Ă��܂��B
�@���̐�����u�J�Z�b�g����v�ł��鎄���炷��ATDK�Ƃ����J�Z�b�g�e�[�v���^����Ɏv�������т܂��B1966�N�ɓ��{�ŏ��߂ăJ�Z�b�g�e�[�v�����i�������̂����ЂŁA���̂������i���ɂ͒N������ڒu�����ƂɂȂ�܂��B���{�ŃJ�Z�b�g�e�[�v�����Ă����͓̂����}�N�Z����x�m�t�C�����iAXIA�j�ASONY�ADENON�A�Z�F�X���[�G���iScotch�j�Ȃǐ��Ђ�����܂������A����TDK����ԐM�����Ă��܂����B�Ƃɂ�����肪���S�Ńg���u�������Ȃ������ł��B����SD�Ƃ��������̓N���[���|�W�V�����p�e�[�v���o��O�܂ł͉��y�p�J�Z�b�g�e�[�v�̑㖼���ɂȂ��Ă����悤�ł��B
�@�Ȃ��B��ԕi���ʂŃ_���������J�Z�b�g�e�[�v��SONY�ł����B�e�[�v���s���Ƀs���`���[���[�Ɋ����t������A���邢�͐ꂽ��Ƃ������s�ˎ��̉��Ƒ����������ƁBSONY���u������̃J�Z�b�g�e�[�v�v�Ƃ��Ė蕨����ŊJ�������t�F���N���[���|�W�V�����p�e�[�v��TDK���͊��S�ɖ��������̂́ATDK���e�[�v���[�J�[�Ƃ��Ă�SONY���o�J�ɂ��Ă���������������܂���i�j�B
�@�N���[���|�W�V�����p�e�[�v��SA�A���^���|�W�V�����p�e�[�v��MA�ɂ͐����Ƃ����b�ɂȂ����悤�ȋL��������܂��B���Ɗm��MA-R�E�E�E�E�������ł��傤���A���d�ʋ��̃P�[�X�𓋍ڂ������^���|�W�V�����p�e�[�v�ɂ͋�������܂����B�������j���o�ł����B
�@���݂͓��Ђ�Blu-ray Disc���ӂȂǂ������ċL�^���f�B�A�̐��������������Ă���A�Y�Ɨp�d�q���i�̊J���Ɏ厲���ڂ��Ă���悤�ł����A�����̃I�[�f�B�I�t�@���y�т��Ẵ��W�J�Z���p�҂ɂƂ��ĖY����Ȃ��u�������̃u�����h�v�̈�ł��B
�����ԍ��F8139127
![]() 0�_
0�_
�F����A������
�o�Ă����I�[�v�����[���̓A�J�C�̂f�w-77�ł��B
satoakichan����A�l�I���W����A���l�ɂe�l�G�A�`�F�b�N�p�ł����B
�����̓n�[�h�����͓I�ł������A�\�t�g���ǂ��e�l�ԑg����������y���߂܂����B
���������������̂͋@��Ɠ����ɂ��̓����̎���w�i�ŁA�����̋�������Ƃ�
�ё�i�n���_�C�j�����Ă����̂ŁA�{�[�i�X�ł������Ȃ��ē���������
���[�������W���[�ł����B
�����͈�T�ԂłȂ��Ȃ�A���̌�͂ǂ����Ă����̂��H��ł��B
���E�������A�܂�����ƌ�����P�ꂪ�E�E�E
130theater����4��ł����I�����ł��ˁA�A�܂���������ł��B
�掿�ɂ�����肳���
[�ɓ��䂩��]��[���w�̎v���o]�Ȃlj��������čĐ����Ă��܂���
�����������܂��Ĉɓ��䂩�肳��̂b�c�~�����Ȃ�܂����B
�����̍��얞�j���A�܂����ȁ`�`�E�E�E
redfodera����̓��e�͉��������C�����ς��ł��ˁI
�A���i�~���`�ł�����ł܂����ˁI�A���i�~���`�͎���ł͂Ȃ��ł����
�����V�l�z�[���A���{�ݓ��Ńo���h�̃��H�[�J�������ĉ��y�������Ă��܂��B
�w�^�N�\�Ȃ̂ł����A���������芅�тł��N���̕��ɂ�
��肢�A�w�^�N�\�͊W���Ȃ��悤�ł��B
����A�n�Ӑ^�m�q����̂b�c�i�C����̃��b�Z�[�W�j�������ቹ�������Ă��邩��
�����Ă݁[�ȂƁA���q�Ɩ��ɒ��������Ƃ���
���ɂ��܂�S���Ȃ����q�́A�������ቹ��ȁ`�@�����o������ȁ`�Ƃ̃R�����g�I
���̓��[�[�I�������I�������g���Ă���o�`�̃X�s�[�J�[�����F�X�ȉ�����������I
�������X�S�C�ˁI
���Œ����Ă����ł��ቹ�ɂ��F�X�����āA���܂�ቹ�ƐL�т�ቹ���悭���������
�E�[�[�E�����j���E�E�E�E�E�E�E
��]�����z���j���w�{�������ł����B�ق�܂ɕ������[�[�[�[����ׂ������w�I�I
���E�������J�Z�b�g�e�[�v�̂��b������܂������A�I�[�v�����[��������
�����w�Ƀe�[�v�̃��[���̘b�����āE�E�E
�܂��������Ȃ��Ǝv���܂����A��������g�h���ł��B�~�߂Ă����܂��B
�����ԍ��F8139248
![]() 0�_
0�_
���E�������
�@SONY�e�[�v�̕i���͂���ȂɈ��������ł����B�I�[�v�����[���̎���̓e�[�v�̕i���ł͗]�荷�������悤�Ɋ����܂����B���[�J�[�́mSONY][TDK][Scotch]�̎O�Ђ����[�x�m�t�B����]�������������m��܂���B���������Θ^���A�����̌J��Ԃ��ň�ԍŏ��Ƀ��������ɂȂ����̂�SONY��������܂���B�ł������ɑR���A�����������L��������܂���B
���̌�A�J�Z�b�g���o�ꂵ�܂������A�I�[�v�����[���̃N�I���e�B�����������̂őS���S������܂���ł����B�e�[�v���V�i�킸�A�w�ǂ������ǂ̂�������ł��B���̖����ł���[Scotch]���啔���������L��������܂��B
�����ԍ��F8139762
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ����́B
redfodera����
satoakichan����
���Ă���28����������G���L�E�x�[�X��������ł����I
���Q��̂d�a�@�C���[����͂����ł��A���͔{���A�ԈႢ�Ȃ�
�ڂ��̂d�a�o���Ȃ�đS�R�����Ė����悤�Ȃ���ł�����A
��k�ł��o���h���E�E�E�Ȃ�Ęb�́A��߂܂��傤�ˁi�O�O
�낭�Ɋy�����ǂ߂܂��A�`���b�p�[�Ȃ�Ė��̂܂����ł�������B
���x�̓I�[�v�����[���̘b������オ���Ă܂��˂��B
�������Ƀ��A���Ɏg�����o���͖����̂ł����A
���w�Z���炢�̎��ɉƂɂ������悤�ȋC�͂��܂��B
���[�J�[�Ƃ��͊o���Ă��܂��A���������Ă��Ȃ��e�[�v��
�Đ������芪���߂�����Ƃ����������ɂ��Ă��܂����B
�L���ɂ͂�����c���Ă��镨�Ƃ����A�p����K�p�̃v���C���[�ŁA
�P�ꂲ�ƂɃJ�[�h������N���W�b�g�J�[�h�̃X�L���i�[�̂悤��
�a�ɃJ�[�h������ƃ��[���[�ő����Ȃ��炨��{�̒P�ꂪ�X�s�[�J�[
���痬���B�Ƃ������̂ŁA�J�[�h�̒��ɂ͎����̐���^���ł��镨��
�����Ă��āA�J�[�h�ꖇ������\���b�̘^�����ł��܂����B
���ꂪ�ڂ��̘^���@�̂͂���ł��B
�F��ȉ���^�������Ă͖炵�Ă�����ł��܂����B
�p��̕���肻���������C���ł����i��j
���������Ɍ����˂������A�i�V���i�����̃��W�J�Z���Ă���܂����B
���ꂪ�l�̃I�[�f�B�I�@�̂͂���ł��B
���̌�KENWOOD��ROXY�ւƌq�����Ă����킯�ł��B
�Ƃ���ł悭�ڂɂ���598�I�[�f�B�I�Ƃ͉��Ȃ�ł���H
�p�������Ȃ���I�[�f�B�I������Ă銄�ɂ͒m��Ȃ��������ɑ����ł��B
�ǂ������������������B�i�Ȃ�ƂȂ��z���͂��̂ł����E�E�E�j
�����܂���܂���l�����Ă��ĒE�����݂ł��B
�����ԍ��F8139867
![]() 0�_
0�_
����28��������@
598�I�[�f�B�I�Ƃ͒艿59,800�~�̃X�s�[�J�[�̎����Ǝv���܂��B�����A��̃X�s�[�J�[��
�w�j�Ƃ��Ċe�Ђ��59,800�~�̃X�s�[�J�[���F�X�o�Ă��܂����B���͓����e�N�j�N�X��SB-
7000�Ƃ����X�s�[�J�[���g���Ă����̂ł���(�艿90,000�~)�~�b�h�����W�p�̃X�s�[�J�[�̑O
�ɓ\���Ă������X�|���W���{���{���ɂȂ�A���̃X�s�[�J�[�����낻�딃���ւ��������ǂ���
�Ȃ��A�Ǝv���܂����B
�����Ŗڂɕt�����̂��e��59,800�~�ŐF�X�ȋZ�p���l�ߍ���(�Ǝv����)�X�s�[�J�[�Q�ŁA
���͂��̒�����s���A�E�N���X�J�[�{���t�@�C�o�[��U���Ɏg�����I���L���[��D-77X�Ƃ�
���X�s�[�J�[���܂����B
http://www.audio-heritage.jp/ONKYO/speaker/d-77x.html
���i���猩��ƃJ�^���O�f�[�^�I�ɂ͐����ł���I�H�B���߂Ē��������ɂ͐ꖡ�s���ቹ�A
����������Ƀf�W�^������̉��ł������肷�����肵�Ă���͗ǂ��I�Ǝv���܂����B
���A����������Ɖ������S�R����Ȃ��E�E�i�ʂ������Ƃ��������̊����ɋ����Ȃ��̂ł��B��
���āA���̃X�s�[�J�[�͏������ă_�C���g�[����DS-1000C�Ƃ����X�s�[�J�[���܂����B
http://www.audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-1000c.html
�E�[�t�@�[�̌��a��22cm�Ə��a�ȈׁA�ቹ��S�z���܂�����2���ׂ̈��S����肠��܂����
�����B�ܘ_����������i�ʂŗǂ��X�s�[�J�[�Ə��荇���܂����B���̃X�s�[�J�[�͒����g����
�����B�E�E�E���AV�p�œ������_�C�g�[����DS-700Z�Ƃ����X�s�[�J�[(69,800�~)���܂�
�������̃X�s�[�J�[�̓_���E����ɂ���DS-700Z�ƊO�ς͂قړ����ł���DS-1000ZA(13���~)
�Ƃ����X�s�[�J�[���܂������A����͂n�j�ł��B(�T���E���h�p�ł��������ł��B)
http://www.audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-1000za.html
���̎����玩���ł͉��i�I��10���~���z���Ȃ��ƃX�s�[�J�[�̓_�����ƍl���Ă���܂����B
�������A�p�C�I�j�A�̃s���A�����g�X�s�[�J�[ S-A4SPT-VP�A�r�N�^�[�̃E�b�h�R�[���X�s�[
�J�[SX-WD8 �̓y�A��10���~�ł������i�ʂŗǂ����ł��B�܂����ɍs���Ă��Ȃ��̂ł����A
���ݒ������̃r�^�[��SX-M3��10���~���܂����������Ă����Ǝv���܂��B���낻�낱��
�X�s�[�J�[��10���~���Ƃ����l����ς��鎞�����m��܂���B(�A���v���쓮�͂̂���A���v
���g��Ȃ��ƃ_����������܂��E�E�E�H�H�B)
�����ԍ��F8140774
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���ɂ��́B
130theater����
�킩��₷������肪�Ƃ��������܂��B
��598�I�[�f�B�I�Ƃ͒艿59,800�~�̃X�s�[�J�[�̎����Ǝv���܂��B
�Ȃ�ƂȂ��N��I��80�`90�N������̍����ۂ��I�[�f�B�I���C���[�W���Ă܂������A
���i�̂�����Ƃ͎v���܂���ł����B
�䂪������܂����B�i�O�O�j
���X�s�[�J�[��10���~���Ƃ����l����ς��鎞�����m��܂���B
�l�̃��C���X�s�[�J�[�����傤�ǃy�A�łP�O���~��JBL A-60�ł��B
http://www.harman-japan.co.jp/product/jblhome/aseries.html
�l�b�g��ł��悭�U������4305��4307������ŃV���b�v�֍s���܂������A
A-60�̉����ďՓ��������Ă��܂��܂����B
���X�g���Ă���ROXY CD3�̃Z�b�g���X�s�[�J�[����ł�����A�ǂ���Ă�
�ǂ������ē��R��������܂��A�؍ނ̎��������悭���j�b�g���V�����Ƃ�
�X���̑E�߂������Č��f���܂����B
���̂Ƃ���[���������Ă��܂��B
�����ԍ��F8142036
![]() 0�_
0�_
�@�|���Ⴂ������ԉ�����
�@�����ł���B�����w�̎��̗ǂ��ɂ͖�Y�����畉���ł��B�́A���̕�e���A�i���O�v���[���[�̃^�[���e�[�u���̏�ɕ~���V�[�g�̍ގ��ɂ�鉹�̕ω����Y�o���w�E�������Ƃ����������A�]�o�Ȃ�ă��R�[�h�̍����ՂƊO�ՂƂ̉��̈Ⴂ����̓I�ɐ������Ă܂�������ˁB���Ă̏��F�B�̈�l�͎���DIATONE�̃X�s�[�J�[����Ɏ��S���Ă������Ɂg���{���͉������邭�Ȃ��B�O�����̕��������炵���ǂ��h�ƌ����Ă܂����B���́g���ꂾ����V���[�g�͍���ȁB�X�s�[�J�[�Ȃ�ĉ𑜓x���S�ĂȂ�I�h�ȂǂƂ����Z���t�ʼn����Ă������̂ł��B������l����ƁA���̕���100%�̃h�f�l�ł����i�����j�B
�@���x�ł����������ł����A�I�[�f�B�I���[�J�[�͏������^�[�Q�b�g�ɂ��ׂ��ł��B�����ǂ��R�X�g�p�t�H�[�}���X�ɕq���ŁA�ܑ̂Ԃ����Z�p�I�\������I�J���g���݂�����͈�ؒʗp���Ȃ��A�{���̈Ӗ��ł̗D�njڋq���l������悤�ȓw�͂�����A�ƊE�S�̂̃��x�����オ��ł��傤�B
�@�ȑO�̓G�A�`�F�b�N����ɒl����悤�ȃ��W�I�ԑg���ڔ������ł����ˁBFM�����łȂ�AM�ɂ����������̂���v���O����������܂����BNHK��AM�����ŏT���̐[��ɂ���Ă����u���̃n�[���j�[�v��A�������X�|���T�[�ɂȂ��Ă����u�~���[�W�b�N�E�C���E�n�C�t�H�j�b�N�v�Ȃ́A���v���o���Ă����x�������������ł��B�ł����݂́E�E�E�E�i�܁j�B�Ƃɂ����A������Ȃ��g�[�N�ƕς��f���̂��Ȃ��I�ȂŋM�d��FM�̓d�g��Q��Ȃ��łق����ł��B
�@�|���掿�ɂ�����肳��
�@�I�[�v�����[���͂悭�m��܂��ASONY�̃J�Z�b�g�e�[�v�̕i���͍ň��ł����B�e�[�v��S�������߂��Ɠ��R�~�܂�͂��ł����A�����Ńe�[�v���u�`�b�Ɛꂽ���Ƃ����������܂����B�����⎼�C�ɂ��ɒ[�Ɏキ�A�����Ƀ��J����ԂɂȂ������̂ł��B�����̂̐������Ƀ������������������A����т�����������܂���ł����B����ł���N�̓Z���~�b�N�X���P�[�X�̈ꕔ�ɍ̗p�������f�������A�ӗ~�I�ȂƂ�����������悤�ł��B�m���ɂ��̐��i�Ɍ����Ă͈����Ȃ������ł��B�ł��A�w���ȏL���i�H�j�������ĕp�p����ɂ͎����Ă���܂���i���j�B
�@�W�̂Ȃ��b�ł����A�u���[�X�E�X�v�����O�X�e�B�[���́u�l�u���X�J�v�Ƃ����A���o���̃}�X�^�[�e�[�v�́A�J�Z�b�g�e�[�v���Ƃ����b�ł��B�ނ��C���������Ƃ��Ƀe�B�A�b�N�̃e���R�Ř^���������̂ŁA���̃e�[�v�̓|�P�b�g�ɓ�����ςȂ��������Ƃ��B�������]���ȃ~�L�V���O�ߒ�������o�Ă��Ȃ��������A���͗ǂ��ł��B
�@�|������28��������A130theater����
�@598�̃X�s�[�J�[�ɂ�798�̃A���v��ڑ�����E�E�E�E�Ƃ����A������l����Ɩ��d�s�v�c�ȕs���������ʂ��Ă�������ł����B�d�ʋ��̃X�s�[�J�[��798���x�̃A���v�ł͋쓮������Ȃ��Ǝv���Ă܂������A���鑤�������������܂�^�������Ă��Ȃ��悤�ł����B
�@�I�[�f�B�I�W�̌f���ȂǂŁu�o�u������O���598�I�[�f�B�I�͍�����͍l�����Ȃ��قǂ̕��ʓ����^������A�I�[�N�V�����ł����������v�݂����ȏ������݂����܂Ɍ������܂����A����͐������͂Ȃ��ł��B���͂��̍������u���ʂƉ��̗ǂ��͔�Ⴕ�Ȃ��v�Ƃ������肪�n�b�L����������ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B
�@���������ł��������[�J�[�͕����������d�����Ă���A598����́u����&�X�y�b�N�����`�v�̌��e�͊��S�ɂ͏����Ă��܂���B�����E�p�������ɂ��̋ƊE�͎��̃X�e�[�W�Ɉڍs�ł���̂ł́E�E�E�E�Ɗ����Ă��܂��B
�����ԍ��F8144235
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
������A���Ƃ���̓e�[�v�f�b�L���p�������܂����B
SONY��55ESX�ł������A�g���[�̃X�v�����O���܂�ĊJ�����S�蓮���ɂȂ��Ă���͒u���ł�����
�v�X�ɒʓd������^�ĂƂ��ɃA�W�}�X������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���i���p�Ƃ��Ė^�I�[�N�V������ʂ��ė������Ă����܂������A
���D�҂���̎茳�ō��̍Đ�����Ă���邾���ł��n�b�s�[�G���h�ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B
�掿�ɂ�����肳��
�I�[�v�����[���b�A���o�܂������L���������܂�<(_ _)>
���e�[�v���V�i�킸�A�w�ǂ������ǂ̂�������ł��B
�����̖����ł���[Scotch]���啔���������L��������܂��B
�i���[�V�����^��ł�Scotch�̃p���P�[�L�����|�I�Ȉ��芴���������ƕ����܂����B
�u�W�F�b�g�X�g���[���v�ł��Ȃ��ݖ��i���[�^�[��������B�炳������^��Scotch�̃p���P�[�L���w�肳��Ă����Ƃ��E�E�E
�v�����I�[�f�B�I�ł͖��O���܂���BASF��AGFA���I�[�v�����[���ł͑傫�ȃV�F�A�������������ł��ˁB
���E�������
��SONY���u������̃J�Z�b�g�e�[�v�v�Ƃ��Ė蕨����ŊJ�������t�F���N���[���|�W�V�����p�e�[�v��TDK���͊��S�ɖ��������̂́A
��TDK���e�[�v���[�J�[�Ƃ��Ă�SONY���o�J�ɂ��Ă���������������܂���i�j�B
�����͎���TDK�ł����������z�ɗD����AD����p���Ă��܂����B
���Z�̕����Ճo���h�̐��^LIVE�����v���o�Ɏc���Ă���܂����E�E�E�e�[�v��SONY��TYPE�V�ADUAD�ł�(^^;)
�}�X�^�[�e�[�v�����̕]����M���āu�L�O���ׂ�LIVE�v�����^���܂������v���C�o�b�N����x�ɐԖʂł����B
�W���I�ȃ��^�����������Ȕ������Łu�ꐶ�̋L�O���ׂ��p�v���c��܂����B
����ԕi���ʂŃ_���������J�Z�b�g�e�[�v��SONY�ł����B
DAT�͈ĊO�ǂ����i�����������ł���B�ʏ́uPro�@DAT Plus�v�APDP�V���[�Y�͎d���ł��悭�g�p���܂����B
�������L�̃f�b�L���E�H�[�N�}���Ƒ������ǂ���������������A���݂��f�b�h�E�X�g�b�N���茳��10�{�قǎc���Ă��܂��B
���ɂ̓X�^�W�I�W�҂̊Ԃł͉e�ԁ^���ԓI�ȑ��݂�������KAO�i�ԉ��j�ł��ˁB
�}�X�^�[�pCD-R�i���Ƃ���P�ނ��Ă��܂��j�Ƃ��ǂ��x���҂����������̂���ۓI�ł����B
�Ⴂ������ԉ�����@
��redfodera����̓��e�͉��������C�����ς��ł��ˁI
���������J�����C�Ȃ�ł��B������̏������𗬂ŊF����ɖ����Ē����Ă���܂��B�@
���߂Ċ��ӁI���ӁI�ł������܂�<(_ _)>
�����ԍ��F8144788
![]() 0�_
0�_
���E�������̃e�[�v�̂��b�Ŏv���o�����������X�����Ă��������B
�����߂Ă�����Ђ��p�C�I�j�A�����w��Ń����T���J�E�{�[�C�̃J�[�R���|���X�I��
����o���Ă������ł��B
�����w��ł��̂ŎЈ��ɂ͌����߂��Ŕ������̂ł����A����ł����i�ݒ肪����
���̋����ł͈�x�ɔ����Ȃ��āA�J�Z�b�g�f�b�L�E�C�R���C�U�[�E�A���v�E�X�s�[�J�[��
���Ԃɂ��낦��̂�����Ƃł����B
8�g���S���̎��ɁA���̃R���|�͌��Ⴂ�ɗǂ����ő�ς悭����܂����B
����Ȏ��p�C�I�j�A�̉c�ƒS�����������L��S�����������v���o���܂��A�s�꒲����
����ꎞ�Ɏ��͉��i�ݒ肪��������ƃN���[������܂����B
���̕��́A�\����Ȃ������ȑԓx�͌������L�b�p��!
�Ԓ��ł̎g�p�ł��̂ŁA�M��ƐU����ɖc��Ȏ��{�����ĊJ�����܂����̂�
������x�̉��i�̏�悹�͎d��������܂���B
�z�[���I�[�f�B�I�ȏ�ɂ������|�����Ă��܂��B�U����ł͐��E�̃g�b�v�ł��B
�Ƃ̕Ԏ��Ɏ��́A�Ȃ�قǁE�E���ꂾ���̕Ԏ������o���܂���ł����B
���E�������͍ŋ߂̓��{�̃I�[�f�B�I��Ƃ�J���A�S�z���Ă����܂���
���̓����̃p�C�I�j�A����͌��C�ŁA���I�ŁA���������J�ŁA���|���Ă܂����B
�p�C�I�j�A�̃C�R���C�U�[��G��܂������������ŁA���̑ш�͂���ȉ��ƌ����̂�
���X�ł����A����悤�ɂȂ�܂����B
�g�p���Ă����e�[�v�́A�قƂ�ǂs�c�j�ŃN���[���|�W�V�����p�e�[�v�͕p�ɂɎg��
���^���|�W�V�����p�e�[�v�Ƃl�`�[�q�́A�����Đ��{�Â��������Ă��Ȃ������ł��B
�r�n�m�x�̃e�[�v�̉����͂ǂ���������?�L�����肩�ł͂���܂���ς悭
���܂��ĉ��M�Ŋ����Ȃ����́A�悭����Ă��܂����B
�I�[�f�B�I���[�J�[����!
���̉��鏗����p�I�[�f�B�I�ł͐��E��ł��Ƃ�
�u�b�N�V�F���Œ����t���I�[�P�X�g���ł͐��E��ł��Ƃ�
�������畔���Ɏ����^�ׂ�R���|�̉����ł͐��E��ł��Ƃ�
���ł��ǂ�����A���̓����̂悤�ɐ��E�̃g�b�v�ł��ƌ������炢���C���o���[�[�[����!!
�����ԍ��F8144934
![]() 0�_
0�_
�@�|��redfodera����
�@DUAD�ɂ��Ă�SONY�͔��荞�݂ɋC�����������Ă����̂͊m���Ȃ悤�ł��B�������A�f�B�[���[�̑ԓx�͗��₩���������Ƃ��o���Ă܂��B�u�t�F���N���[���H�@�����SONY�̃X�^���h�v���C�B�����ɏ����邳�v�ƒf�����Ă����X���������������܂����ˁi�����A���̒ʂ�ɂȂ�܂����� ^^;�j�B
�@KAO�i�ԉ��j�̃��f�B�A�͗ǂ������Ǝv���܂��B�c�O�Ȃ���J�Z�b�g�e�[�v�͔������Ă���܂���ł������APC�W�̔}�̂Ƃ��Ă��Ȃ肨���b�ɂȂ�܂����B���Ђ��L�^���f�B�A�Ɏ���o���������́u�ԉ����āE�E�E�E�g���Ă邤���ɖA���o�Ă����Ȃ��́H�v�ƌ����Ă��z�����͂Ɍ��\���܂����ȁi���j�B10�N�ȏ�O�ɂȂ�܂����A���ɂ���ԉ��̕����Z���^�[�����w�������Ƃ�����܂��B�g���Ă���@�ނ�]�ƈ��̑ԓx���画�f����ƁA���Ȃ�̗D�NJ�ƂƂ̈�ۂ������̂ł��B
�@�|���Ⴂ������ԉ�����
�@�����T���E�J�[�{�[�C�Ƃ͉��������ł��ˁB87�N�Ɍ��݂́u�J���b�c�F���A�v�Ƀu�����h�ύX���Ă��܂��ȁBPIONEER�͊m���o�u���ɏ����A�肪�������Ƃ��A�啝�ȃ��X�g�������s���ĂȂ������ł����ˁB�������A���̂����肩��ӗ~�I�Ȑ��i�����Ȃ��Ȃ����悤�Ɋ�����͎̂������ł��傤���B�����I�[�f�B�I�u�����h��Exclusive���X�I�ɕ��������Ăق����ł��B
�@�ŋ߂ł��v���Y�}�p�l���̎��А��Y�����~�ɒǂ����܂�܂����B�͂����āA�L�@EL�̕���ł͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B
�����E�̃g�b�v�ł��ƌ������炢���C���o��
�@�����ł��ˁB�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�c�㑊��̏����ł���������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�s��̊g���}��Ȃ��Ƃ��̋ƊE�ɖ����͂Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F8149490
![]() 0�_
0�_
�@����̓o�C���C�������O�ɂ��ď����Ă݂܂��B�E�[�t�@�[���N�����d�C�I�ȏ�Q�i�t�N�d�́j���o���邾���쒀���悤�Ƃ����A���̐ڑ������ɑΉ������X�s�[�J�[���o���悤�ɂȂ����̂́A����10�N�Ԃ��炢�ł��傤���B
�@���āA�o�C���C�������O�Ή��X�s�[�J�[�ɂ̓V���O���ł��q����悤�ɃW�����p�[�P�[�u���i���邢�́A�W�����p�[�v���[�g�j���t���Ă��܂��B�E�E�E�E�ł��A�l���Ă݂����̓I�J�V�C�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�X�s�[�J�[�̍���̓o�C���C�������O�ɑΉ������邱�Ƃ���������̎�i�ł���Ƃ̈Ӑ}�ł��̕������̗p�����͂��ł��B������A�V���O���ڑ��ł������o��悤�ɃW�����p�[�P�[�u����t����Ƃ����̂́A�������������Ă��܂��B
�@���炩���߃n�b�L�������܂����A���͂��̃o�C���C�������O�Ƃ������̂��匙���ł��B�P�ɃP�[�u�����2�{���킹�悤�Ƃ����ƊE�̉A�d�ł���Ƃ����v���܂��i���j�B���������A�o�C���C�������O�ƃV���O�����C�������O�Ƃł́A����Ȃɉ����Ⴄ���̂Ȃ̂ł��傤���B�������X�s�[�J�[��A���v�A�P�[�u���ɂ���Ď���͈Ⴂ�܂����A���̂Ƃ���u�o�C���C�������O�ڑ��̕�����ΓI�ɃV���O�����C�������O��艹���ǂ��v�Ƃ����P�[�X�ɑ����������Ƃ�����܂���B
�@�u�o�C���C�������O�ƃV���O�����C�������O�A�ǂ������ǂ����́A���ۂ���Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��v�Ƃ����ŁA����I�Ɂu�o�C���C�������O�Ή����g�����h�ł���v�Ƃ̕���������������������X�s�[�J�[�̍���̎p���Ɋւ��ẮA�����ȋC���ɂȂ�܂���ˁB
�@�������A�����̃A���v�̓o�C���C�������O�ɑΉ����Ă��܂���B�o�C���C�������O�ڑ��ɂ�������Ή������邽�߂ɂ́A�A���v�ɂ�2�n���̃X�s�[�J�[�[�q���K�v�ł���͂��ł��B�������A�ꕔ��������2ch�X�e���I�A���v�ɂ�1�n���̃X�s�[�J�[�[�q�����t���Ă��܂���B�o�C���C�������O�ڑ������邽�߂ɂ͈�̒[�q�ɃX�s�[�J�[�P�[�u���̐c����2�{�˂����܂Ȃ��Ƃ����܂���B�������A���R�c���ׂ̍��P�[�u������Ȃ���2�{������܂���B�A���v�ƃX�s�[�J�[�Ƃ̋������傫�����ߑ����c���̃X�s�[�J�[�P�[�u�����g�p����ꍇ�͕s���ł��B
�@�ł�Y���O��o�i�i�v���O���g�������ł͂Ȃ����E�E�E�E�Ƃ����ӌ�������܂��傤���AY���O��o�i�i�v���O���g���ƁA�ړ_�������镪���������܂��B��������Y���O��o�i�i�v���O�͕p�ɂɃX�s�[�J�[�P�[�u������������K�v�̂��郆�[�U�����̃c�[���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�n�C�G���h�@�������āA�o�C���C�������O�Ή��X�s�[�J�[�͕s�v���Ǝv���܂��B�[�q��2�n���ȏ�t���Ă���X�s�[�J�[�́A�o�C���C�������O�Ή��ł͂Ȃ��o�C�A���v�Ή��Ɩ��łĂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F8150300
![]() 0�_
0�_
���E�������A�����́B
���̓o�C���C�������O�ڑ��A��D���l�Ԃł��B�p���[�A���v�̐����\�͂ɂ����Ǝv���܂����A���̐ꂪ�S���Ⴂ�܂��B�Ⴆ�Α呾�ۂ̉���[����]�ɂȂ肪���ł����A�{���̑��ۂ̉��ɂȂ�܂��B�V���O���ł��ƈꌩ�A�h��ɒ��͏o�܂����A�{���̒��ł͂���܂���B�x�̂����Ŋ��ł��܂������A���̃X�g���r���X�L�[��[�t�̍ՓT]��呾�ۂ̎��ߋ���6m�Œ����A�U��̒��Ǝ������܂����B�{���͗\�z�ȏ�ɐꂪ�ǂ��ł��B
�����ԍ��F8151035
![]() 0�_
0�_
�F����A���ӂ́B
�o�C���C�������O�c
��肭�������Ȃ��Ɖ��F��X�s�[�h�����o���o���ɂȂ�P�[�X������̂ŁA
�K�������K�{�Ƃ͊����܂��A�g�����Ȃ��̓�Փx���オ��Ƃ������ʂ͔ے肵�܂��A
���͎g�p���@�̑I�������L����Ƃ����Ӗ��ōm��h�ł��B
�g�����Ȃ��Z�ʂ������ɂ��邩��Ƃ������R�ł͂Ȃ��Ĉȉ��̂Q�Ƀ����b�g�������Ă܂��B
�o���I�ɔ\���̒Ⴂ�X�s�[�J�[�̏ꍇ�̓o�C���C�������O���������h���C�u���Ղ��Ǝv���܂��B
���߂Ďg�p�����̂�KEF��LS3/5A�i11��82.5dB�j�ł������u���肪�����v�Ǝv���܂������A
�ŋ߁A�i������HARBETH��LS5/12A�i6��81.5dB�j�ł����l�ł��B
DYNAUDIO�̗l��SP���j�b�g�̗��������D�G�ȋ@��ł͂��܂�W�Ȃ��̂ł��傤���A
�X�s�[�J�[�̓����l�b�g���[�N�̃t�B���^�[�����G�ɂȂ��Ă��鐻�i�ł́A
�R���f���T�[���R�Ȃ̂ǂ̒[�q�����V���O�����C���[�����o�R���鐔�����点��Ƃ����A
���_�q����i�����Ƀv���V�[�{�I�ł����j�A�o�C���C�������O�\�Ȑ��i�̕������S�ł��܂��B
�����ԍ��F8151512
![]() 0�_
0�_
�u���M�E�쌻�ہv���X�A���낢��`������Ȃ��d���Ƃ��v���O�Ƃ����ւ��i��ւ�
����ꑱ���Ă��܂����ˁB
���͂��̕ӂׂ̍������ق�CP�I�Ȍ��n���炵�����������ł��܂��ǁA
���ƁAJAZZ�Ɋւ��Ă͗L�������lj��肭���ȃv���C���[�̉��͂ǂ���������������ւ��Ă�
�ǂ��ɂ�������̂ł͂���܂���B
�N���V�b�N�̂悤�ɖ��L�ƌ�����y��͂���܂���̂ŁA���F���v���C���[�̗͗ʁA
�Z���X�E�����ăA�h���u�\�͂Ɍ����s������Ă��܂��܂��B
���̂悤�ɋȂ���Ȃ�ɂ����t���鑤�ʼn��y���Ă���ƁA���X�i�[�Ƃ��Ă̎����
�T�C�h�v���C���[�̎��ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA�I�[�f�B�I�Đ��ɋ��߂鉹�����F�l�Ƃ�
���Ȃ�قȂ�̂����m��܂���B
������̃{�����M�^�[�ł��u�w�ɗ�⊾�����ꗎ����v�l�ȉ��t������l�����܂����A
�����ȃM�^�[�E�A���v�E�G�t�F�N�^�[�Ȃǃ��S���������y��ł�����ڂ����t����
�o���Ȃ��L���v��������킯�ł��B
�u�w�ɗ�⊾�����ꗎ����v�l�ȉ��Ȃ�ł��傤�ˁA�����I�[�f�B�I�ɋ��߂�̂́B
�ł�����A�P�[�u���P�{�W���~�Ƃ��A�o�C���C�������O�E�o�C�A���v�E�}���`���V���O����
���̘_���E���s�E�u�a�E�����_�o�����NjC���ȃ��[�u�ɂ͉ᒠ�̊O�����ߍ���ł��܂����B
����͂Ǝv�����@�B�E�������Ď茳�ɗ����@�B�A�Ӗ����Ȃ��̂Ă��Ȃ��@�B�A
����ȋ@�B�ƂƂ��Ɂu���y�v���Ă��邾���ōK���Ȃ̂ł�����A���b�L�[�Ȏ҂ł��B
����ɂ��Ă��A�e��S�~���܂����������ŁE�E�E�E�E�B
����A���y�W�̐�y����������A��i�̃t�F���_�[�A���v�E���R�[�h���Ȃ�̗ʁE
�I�[�f�B�I�ꎮ���X�B
�����ł��镨�͂���Ȃ�Ɏ��s���������̂ł������̋@��ɕ�������炸�|���R�c����B
�����ԍ��F8157517
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���ɂ��́B
�l���l�I���W����̈ӌ��ɂ�����߂��ł��ˁB
�����y������t���鑤�ł͂Ȃ��̂ŁA���߂鉹����
�قȂ邩������܂��B
�ԓ��ł����Ⴆ���܂��A�ǂ�Ȃɍ�������������Ă��A
�ǂ�Ȃɍ����Ⴆ��GTR�Ȃɏ���Ă��A�u�����GTR���ȁ`�v
�Č�������A�u�����n�`���N�Ȃ̂ɂ�����܂��I�͂��`�I�v
���Č�����ق����C���������ł��B
�l�̃I�[�f�B�I��������Ȋ����ł��B
�u�G���g���[�N���X��AV�A���v����Ȃ̂ɁA���\���������Ă�ˁv�݂����ȁB
�V���O�����C���[�A�o�C���C���[�A�o�C�A���v
�l�̓u���C���h�e�X�g����Ă��������������邱�Ƃ͂ł��܂���B
�ŋ߂̃X�s�[�J�[���o�C���C���Ή��Ȃ̂́A
��肢�����Ŗ点�܂�����Ă����̂ł͂Ȃ���
���[�U�[�̃j�[�Y�ɏ����ł����������邽�߂̕t�����l�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F8158340
![]() 0�_
0�_
���C���[���[���h�ɃS�[���h�G�N���v�X�X�s�[�J�[�P�[�u���@GES5-2�^GEB5-2�Ƃ����P�[�u��
������܂��Bhttp://www.electori.co.jp/ampzilla.html
�g�p���̂��uOCC��v��ƌ����Γd�C��R����ԏ����ȕ����ł�����A�d�C�I�ɗ����̂Ȃ痝
�_�I�ɂ͍ō������m��܂���B��x�g���Ă݂����Ǝv���Ă��܂����A�o�C���C���[��3m����
���̎g���Ă���A���v�ƃX�s�[�J�[�قړ��z�I�Ƃ����������I�H�X�s�[�J�[�P�[�u���̂�����
���ӋC�Ŏg���C�������܂��H�H�B(���̒l�i���o���̂Ȃ�p�C�I�j�A��S-1EX���܂��B)
���̒n��̃V���b�v��8���̎����10���ɊJ����܂��B�g�p�@��́��X�s�[�J�[��Zingali�@
TWENTY 1.12�@��SACD�v���[���[��ESOTERIC�@X-01D2�@���v���A���v��McIntosh�@C46
���p���[�A���v��AMPZILLA�@ampzilla2000�Ƃ����g�ݍ��킹�ł��B�G�\�ƃ}�b�L���̃A���v��
����������(���������E�E)����܂����S�W���ł͂Ȃ��A���v�W���ƃC�^���A�W���K���Ђ̃E�b
�h�z�[���X�s�[�J�[�uTWENTY1.12�v�͒�������������܂���B���������ǂ�ȉ�������̂ł�
�傤���H�B
�����ԍ��F8159030
![]() 0�_
0�_
���C���[���[���h�̃X�s�[�J�[�P�[�u����ULR���ԈႦ�܂����B
http://www.naspec.co.jp/wire/ww-speaker.html�@�@�ł����B
�����ԍ��F8159276
![]() 0�_
0�_
�F����A������
�ȑO�ɁA���[�Ԃ�ɂ���̃T�C�g��
http://6819.teacup.com/cablesha/shop
�o�C���C����p�R�[�h�EODYSSEY��Bi-Wire�����������A�͂������̒��ɂ�
�I�[�i�[���烁�����Y�����
�����R�[�h�ŃW�����p�[�P�[�u�����쐬�������������Ă��܂����B
�E�E�E�H�H�o�C���C���ŃW�����p�[�P�[�u���E�E�E�H�H
�����ɂ͒ʏ�̃o�C���C���ڑ����@��+/-��2�{���˂ăV���O���ڑ����������F�ł��B
�������̂قǁA�ł͗ǂ����y�ӏ܂��Ə����Ă���܂����B
�ł����A�o�C���C���ڑ��X�s�[�J�[�Ƀo�C���C����p�R�[�h��ڑ�������ǂ�ȉ���
�v���Ē��������̂ŁA�V���O���ڑ�����ӎv�͂Ȃ��A���R�o�C���C���ڑ��ł����B
�ӂƎv���o��4�{��2�{�ɑ��˃V���O���ڑ��ƃW�����p�[�P�[�u����t���ĉ��o�������
���y�I�\���͏���y���̂悤�ɂ͎|���o���܂��A�p���[�ƃX�s�[�h���͏�����܂�
���̑���ォ�牺�܂Ŏ��Ɉꉹ�E�ꉹ�A�@�ׂł��E�E�E���A���ł��E�E�E
�o�C���C���ڑ��X�s�[�J�[�Ƀo�C���C����p�R�[�h���V���O���ɖ߂��ڑ�����
������Ă�̂ƌ���ꂻ���ł����A�o�Ă��鉹�͐l�ɂ���Ă�
������A���₱����ƕ������Ǝv���܂��B
�ԉ��ӂ��Ɍ����ƁA2�l�ł�4�l�ł��y�����h���C�u�����Ă��������A�ł�����
�����ԍ��F8159766
![]() 0�_
0�_
�@�o�C���C�������O�ɂ��ă��X�L���������܂����B�|��ALL�B
�@�ŁA���Ƃ��Ύ��������Ă���E�G�X�^���E�G���N�g���b�N�̃X�s�[�J�[�P�[�u���ł͖��炩�ɃV���O���ڑ��̕��������ǂ��킯�ł��B���Ƀo�C���C�������O�ڑ��ɂ��Ȃ��ƃ_���ȃP�[�u��������B�����āA���܂�ς��Ȃ��P�[�u��������܂��B���Ԃ�A�X�s�[�J�[�P�[�u���̒������傫���W�����Ă���̂ł��傤�B���Ȃ��Ƃ��u�����Ȃ�P�[�X�ɂ����Ă��A�o�C���C�������O�̕�����ΓI�ɗD��Ă���v�Ƃ�������͐������Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�����Ďg������̖ʂ��猾���A�o�C���C�������O�̓P�[�u���オ2�{������܂��B����Ȃ�̃P�[�u���������Ă��ăo�C���C�������O�Ōq�������[�U�[������Ƃ��āA���̔{�̒l�i�̃P�[�u�����g���ăV���O���Őڑ������ꍇ�A�ʂ����Ăǂ����������ǂ��Ȃ�̂��E�E�E�E�B���̋t�̃P�[�X���l�����܂��B�܂�A���������Ȓl�i�̃P�[�u�����V���O���Ōq���Œ����Ă��郊�X�i�[�ɂƂ��āA���̔��z�̃P�[�u�����g���ăo�C���C�������O�ڑ��������ƁA�ǂ��炪�N�H���e�B����Ȃ̂��E�E�E�E�ƔY�ނ��Ƃ����Ă���܂��傤�B
�@�����o�C���C�������O�ɑ��Ė����ɂȂ�Ȃ��̂́A���̂悤�Ɏg�p�҂ɗ]�v�ȑF����^�S�ËS�������t���邱�ƂɂȂ邩��ł��B�������A�W�����p�[�P�[�u���i���邢�́A�W�����p�[�v���[�g�j�̕t�^�Ƃ����A�X�s�[�J�[�̍�����ڑ����@�����[�U�[�Ɋۓ������Ă��܂��悤�Ȏ{��C�Ŏ��s���Ă���B�������t���i�̃W�����p�[�P�[�u���i���邢�́A�W�����p�[�v���[�g�j�͂ƂĂ����������ł��B���̍s�����̃f�B�[���[�����S�Ƀo�C���C�������O�������Ă��āA�X���́u�o�C���C�������O�ɂ��ĉ����ǂ��Ȃ����Ɗ����邨�q����͏��Ȃ��Ȃ����A�S�ẴP�[�X�ɂ����āA����͕t���̃W�����p�[�P�[�u�����O�������Ƃɂ����ʂ��o���ɉ߂��Ȃ��v�ƒf�����Ă��܂��B
�@�܂��A�O�ɂ������܂������A�A���v�����o�C���C�������O�ɑS�R�Ή����Ă��܂���B�X�s�[�J�[�[�q��2�n�����������A���v�͏����ł��B�����Č����APANASONIC��XR-55�i���������ȁH ^^;�j�݂����Ɉ��ŋ^���o�C�A���v�ڑ����\�ȋ@��Ȃǂ��s��ɑ����o���Ȃ�����A�o�C���C�������O�Ή��X�s�[�J�[�����������������Ӌ`�͑��݂��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�������A�P�[�u���̐ڑ���ɂ��Ă��A����₱���Ǝ��s���낷��̂��I�[�f�B�I�t�@���Ƃ������̂ł��B�������A�V���O���ڑ��Ɋւ��Ă��ቹ���Ɍq���̂��������Ɍq���̂��A�͂��܂��u�^�X�L�����v�ɂ���̂��A�疌�������āu���h�������v�Ɍq����̂��E�E�E�E�o�C���C�������O�ɂ��Ă��A2�{�Ƃ������P�[�u�����g�p�������������ǂ��Ƃ͌���܂���A�����p�͂ǂ̃P�[�u���Œቹ�p�͂������̃P�[�u���̕����ǂ��̂ł͂Ȃ����E�E�E�E�Ƃ����悤�ȁA��������I����������A����͒P�Ȃ�u�I�[�f�B�I�t�@���̊y���݁v�̘g����E���āA�����ς킵���������Ǝv���܂��B
�@�����āA���̔ς킵���͏��S�҂ɂƂ��ďd�ׂɂȂ邱�Ƃ͑z���ɓ����܂���B�������X�����̃{�[�h�Łu�ŏ��̓V���O���ڑ��ŃI�b�P�[�ł���v�ƃA�h�o�C�X���悤�Ƃ��A�{�l�ɂƂ��ẮA�o�C���C�������O�ڑ����\�ł���̂ɂ�������Ă��Ȃ��E�E�E�E�Ƃ����悤�Ȍ��O������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�@�X�s�[�J�[�̃��[�J�[���A�₽��u�d���a���ҁv�����������ȃo�C���C�������O�ڑ��ɂ��āA���������������Ă��炢�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8164593
![]() 0�_
0�_
�F����A������
���E�������PANASONIC��SA-XR55�̂��b�ŁA�l�b�g��ŗǂ����������]����
�`�u�A���v�E�r�`-�w�q55
�g�����X�p���[�A���v�E�N���E���c-45
�r�n�m�x�@�r�`�b�c�v���[���[�E�r�b�c-�w501
�Ɩ��p�^�X�J���b�c�E�b�c-01�t
���A���̕����ɂ���܂��B
�Ȃ����邩�ƌ����܂��ƁA���̂Ƃ���̂��q�l�ɃI�[�f�B�I��̕������������
�X�s�[�J�[�̐ڑ����@���l�ɁA���z�ȃI�[�f�B�I�Z�b�g�����L���Ă��Ă�
��L�̋@�킪�A�ǂ�ȉ��H�Ɣ����Ē����āA�g���āA������ׂ�����B
�����āA�[���������A�������肵�����A�����̃Z�b�g�Ɠ������炢�̉����o��
����������ƌ������R���ŁA�i���̒l�i�ŏ����Ă��炢�܂����B
���Ƃ��Ƃn�m�j�x�n�̂`�u�A���v��2ch�v�����C���A���v�Ƃ��Ăk�t�w�l�`�m�̃A���v��
���L���Ă��܂����̂ŏ�L�̋@�킪����莄�̕����َ͈�i���Z���ԂɂȂ��Ă��܂�(��)
�̂����݂��A�����ȋ@������z�@����A�d���a�Ɋ����ǁA�����ɑ���͉i�v�ɑ���(��)
�ł͖����Ȃ��Ă��܂����̂ŁA���₷�݂Ȃ����B
�����ԍ��F8165593
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
���E�������
���t���i�̃W�����p�[�P�[�u���i���邢�́A�W�����p�[�v���[�g�j�͂ƂĂ����������ł��B
�R�X�g�I�Ɍ����������鐻�i�ł͂������ɓ��Ă͂܂�Ǝv���܂������i�ɂ�肯��ł��傤�B
KEF��LS3/5A�ł̓W�����p�[�E�P�[�u���ɂ�QED�́uGENESIS�v���t���ł������A
Martin Logan�ł�CARDAS�̃W�����p�[�E�v���[�g���t�����Ă��܂����B
�@��ɕt���̓d���P�[�u���ɂ������邱�Ƃł����z�����Ă��郁�[�J�[��i�Ƃ����̂����Ȃ��炸�L��܂��B
����Ȃ�̔�p�̐��i���w������I�[�f�B�I�E�t�@���ɂ͂��܂�Ӗ��̂Ȃ��C������������A
�����@�╁�y�@�ɂ����t���i�ɃR�X�g���[�Ăė~�����Ƃ���ł����E�E�E
���[�U�̎��_�⋫���Ȃǂɔ@���Ƀ��[�J�[���݊��Ȃ̂��}�炸���I�����Ă��镔���ł��ˁB
�����ԍ��F8169476
![]() 0�_
0�_
�@�|���Ⴂ������ԉ�����
�@���������ƁASA-XR55��D-45�͋C�ɂȂ�܂��B����݂̃f�B�[���[�̘b�ɂ��ƁuSA-XR55�͒l�i�̂��ɂ͗ǂ��B�ł��ቹ�͂قƂ�Ǐo�Ȃ��v�Ƃ̂��Ƃł����A�����Ă݂Ȃ���Ε�����܂���BD-45�́uProCable�v���������Ă��鐻�i�ł����A���̋Ǝ҂̖ڎw�����Ƃ����̂������t���Ă��܂�����D-45�̃T�E���h���z���͏o���܂��B�ł��A����ς��x�͒����Ă݂����ł��ˁB���͂ɏ��L�҂����Ȃ��̂��h���Ƃ���ł��B������Ƃ����āu�����ɔ����Ă݂悤�v�Ƃ͎v���܂���B�O�ɂ������܂������A�uProCable�v�ɂ͎�������J���Ă��炢�����ł��B
�@�I�[�f�B�I�@��i�A�N�Z�T���[�ނ������j�Ƃ����̂́u�����Ƃ��āA�����قǎ����ǂ��v�Ƃ̗������������[�J�[�ƃ��[�U�[�Ƃ̊Ԃɑ��݂��Ă���̂��Ƃ͎v���܂��B���A����ł�D-45�Ȃǂ��l�b�g��Łu�����̍ŏI�I�v�݂����Ȏ��グ���������ƁA���S�҂͂������x�e�����܂ł����傢�ɋ����������̂́A�����������́u�O���[�h�A�b�v�������̂Ȃ����ς߁I�v�݂����ȍ\�}�ɂ��O�������Ă�������������̂ł͂Ȃ����Ǝא����Ă��܂��܂��B
�@�|��redfodera����
�@QED��CARDAS�̕t���W�����p�[�E�v���[�g������̂͒m��܂���ł����i���A�ǂ��������܂���j�B�����������@�͈Ⴂ�܂��ˁE�E�E�E�ƁA��u�v���܂������A���̃u�����h���̃W�����p�[�ނŃX�s�[�J�[�̃o�����X������Ă���̂Ȃ�A�C���^�[�t�F�C�X���V���O���ڑ���p�ɂ��Ă�������Ȃ����A�o�C���C�������O�Ή��ɂ���K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����E�E�E�E�Ƃ������Ă��܂��܂�(^^;)�B
�������@�╁�y�@�ɂ����t���i�ɃR�X�g���[�Ăė~����
�@���̒ʂ�ł��ˁB������I�[�f�B�I�@��͎�����������i���Ƃ����Ă��A���ɗ����Ȃ��t���i�ȂS�Q�����Ĉꗘ�����ł��B�������u���Ⴀ�A�G���g���[�@���P�[�u���ނ͕ʔ���ɂ���v�Ƃ��v���܂���B���S�҂ɂƂ��ĕ~���������Ȃ邾���ł��傤�B�����܂ł��ǐS�I�ȕt���i��Y���邱�Ƃ��@��̑����Ƃ��Ă���ׂ��p���Ǝv���܂��B
�@�b�͑S�R�����܂����A�O�Ɂu���S�Ҍ����̃I�[�f�B�I�E�t�F�A������Ăق����v�Ə����܂������ǁA���ۂɂ��������̂�����݂����ł��ˁB
http://www.my-musicstyle.com/
�u�}�j�A���̐V�������y�C�x���g�v�Ɩ��ł������̍Â��A���Ў�s���ȊO�ɂ����L���W�J���Ă��炢�������̂ł��B
�����ԍ��F8175297
![]() 0�_
0�_
�@����͈ꎞ���b��ɂȂ����AGOLDMUND��SACD�v���[���[�i�艿140���~�j�̒��g���A�Ȃ�Ǝ���1���~��PIONEER��DVD�v���[���[�ƂقƂ�Ǔ����������Ƃ����l�^�ɂ��ď����Ă݂܂��B
�@���̃v���[���[��GOLDMUND��EIDOS 20A�ŁA�f�W�^����ՂƓd���n��PIONEER�̃��j�o�[�T���v���[���[DV-600AV�̗��p���������Ƃ������B�f���Ă����܂����A���А��i�̕��i�𗬗p���Ď��Ђ̏��i�Ɏd���ďグ��Ƃ������Ǝ��̂Ɉًc��������킯�ł͂���܂���B����Ȃ��Ƃ͈ȑO������풃�ю��������Ɨ\�z���܂��B���������̃P�[�X����莋���ꂽ�̂́A���҂̋��z�ɂ��܂�ɂ��������������߂ł��B
�@����EIDOS 20A��DV-600AV�����������Ƃ�����܂���B�������A���҂̉����ɂ͂��Ȃ�O���[�h���Ⴄ�Ƒz�����܂��B�����Ă�GOLDMUND�ł�����A�Ɠ��̃n�C�X�s�[�h�ŃV���L�[�ȃT�E���h�X���͂��̋@�����������ƃJ�o�[���Ă���̂ł��傤�B������DV-600AV�̊�Ղ��g���Ă���Ƃ͂����Ă��A�d����A�i���O�i��EIDOS 20A�Ǝ��̂��̂��Ǝv���܂��B�����̃��j�o�[�T���v���[���[�Ƃ͎������Ⴄ�T�E���h���o�Ă���̂ł��傤�B���̉��ɔ[������A�喇140���~���Ď�ɓ����}�j�A�����Ă����������Ȃ��ł��B�܂�͎��v���Ƌ����������ӂ�������b�B
�@�ł��A��{����������1���~�̃v���[���[�ƈꏏ�ŁA������d���ƃL���r�l�b�g�Ɏ���������Ƃ͂����A�ǂ����ǂ������140���~�Ŕ���o����̂��A�傢�ɋ^��ł��BGOLDMUND����������p�B�u�����h�ŁA�A���㗝�X�̎�蕪�����Ȃ�傫�������Ƃ��Ă��A140���~�̓{�b�^�N���ł��傤�B������30���~���炢�̒l�t�������Ă����Ȃ�A���Ƃ���H������1���~�̃v���[���[�ƂقƂ�Ǔ������낤�ƁA����������q�͂��܂肢�Ȃ��͂��B����ǂ��납�u���̉��i��GOLDMUND�T�E���h���y���߂�v�Ƃ����G�ꍞ�݂ŕ]���ɂȂ�A�u�����h�C���[�W�͏オ�����\��������܂��B�E�E�E�E�܂�GOLDMUND�ɂƂ��āA140���~��1���~���u�ꏏ�̋��z�v�Ȃ̂�������Ȃ��̂Łi���j�A�����ł��傤���ǁE�E�E�E�B
�@���āAPIONEER�ɂƂ��Ă������������Ƃ́u����1���~�̃v���[���[�̊�{��H�ł��A�g���悤�ɂ���Ă̓n�C�G���h�@�ɓ]�p�ł���v�Ƃ������Ƃł��B�Ȃ��DV-600AV���x�[�X�ɂ���GOLDMUND��EIDOS 20A���������\�ł�����ꡂ��Ɉ�����CD�v���[���[���J�����ׂ��ł��傤�B
�����ԍ��F8180244
![]() 0�_
0�_
140���~�̃v���C���[�ƂP���~�̃v���C���[�����g�������Ȃ�ăV���b�N�ł��E�E
�I�[�f�B�I���ڂ�������̎����ƒm���āA���������o������������ɓ���Ƃ����̂͊Â��l���Ȃ̂����B
�������Ƃ����āA�����ŏI���L�ۂ݂ɂ���̂����܂�ɂ��ʔ�������܂���B
��͂�l�b�g�̕]����u�����h�ɘf�킳��Ȃ��悤�A�����̍D�݂⎨�̊�����
�������莝���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂����B
140���~�̃v���C���[�̃��[�J�[�͂P���~�̒��g�ő啝�ȗ��v��������Ȃ�����Ǒ�ȐM���������܂����B�ڐ�ׂ̖����������ڂŌ����傫�ȗ��v���̂Ă�Ȃ�ċ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8181804
![]() 0�_
0�_
���E�������A���͂悤�������܂�
��SA-XR55��D-45�͋C�ɂȂ�܂��B�ł��A����ς��x�͒����Ă݂����ł��ˁB
�������Œ�����Ɨǂ��ł���
�l�b�g���SA-XR55������a�i�a�k��^���m�C�C�Ŗ炵�Ă��铙�̃R�����g����������܂���
�����̓X�̂��q����A������ł��ǂ�����SA-XR55����������Ă���ƌ����A�ǂ������̂ł�����
�q�˂�ƁA���̕��̃I�[�f�B�I�V�X�e���Ŏ莝���̃A���v�ƒ�����ׂ𐔐l�̗F�l�Ƃ��Ă����Ƃ���
��l�̗F�l��5���~���SA-XR55�̕����ǂ����ƌ����o���������ł��B
���̕��̃V�X�e���͂��������̍��z�@�킼�낢�ŁA�@��͗���������Ă��Ȃ��̂ł��̏�ł�
�����܂��A�莝���̐��{�̃A���v����l�ɂ���ǂ��ƌ���ꂽ�̂��V���b�N�ł����������Ȃ�
�Ƃ̎��ň�������Ă��܂����B
����Ɏ����A��^�X�J��CD-01U��SA-XR55��iQ9��RCA�P�[�u���̓x���f��88760��
�W���Y�A�f�批�y�A�p�C�v�I���K���n�A�M�^�[�n���A���Ԃɒ����܂����B
�A���v�ݒ��2�`�����l���ꍇ��5.1�`�����l���̂��܂��Ă���A���v���f���A���A���v�쓮�o���܂��B
���͔��Ƀt���b�g�ʼn������������グ���悤�Ȋ����ł͂Ȃ��A�ւ�ȕt�щ����Ȃ�����
��\���X�s�[�J�[�ł��o���o�������o�����ł��B
�ቹ�́A���E����������݂̃f�B�[���[���A�ቹ�͂قƂ�Ǐo�Ȃ��Ƃ̎��ł���
iQ9�ł͕��ʂɏo�Ă��܂����A�ʊ����㎿�̒ቹ�͏o�Ȃ��ƌ������ł��傤����
5���~��ŏ㎿�̒ቹ���o�����ςł����l�b�g��̃R�����g�A�����̂��q����̃R�����g
�����Ď���Œ����������ł́A�قƂ�ǂ̃X�s�[�J�[���𑜓x�ł��Ȃ��A�w�^�ȉ��ł��Ȃ�
�����背�x���Œ�����5���~��̂`�u�A���v�ƌ������z�ł��B
�p�i�\�j�b�N���̔����@���Ԉ�����̂ł��傤���ˁA�f�U�C��������������ƃX�b�L������
�`�u�A���v����Ȃ��v�����C���A���v�Ƃ��Ĕ̔��A�t�����l��5.1�`�����l�����t���Ă���
5���~��̃f�W�^���A���v�Ƃ��Ĕ���o�J���ꂵ���̂ł�(��)
�Ԃŕ\������Ƒ�ώg������̗ǂ����^�̃~�j�o���ł��育�뉿�i�ƌ��������ł��B
���Ƀg�����X�p���[�A���v�E�N���E���c-45�ł����^�X�J��CD-01U�ƃx���f��88760����iQ9�ł�
���ł����A�r�b�N���̉����o�Ă��܂��B
����̓A���Ԃ̃I�[�v���J�[�ł��B
��E���E�����V���[�v�ŃX�s�[�J�[����u���ȉ����h���h���O�ɏo�Ă��Ĕ����Ă��܂��B
�Ԃł��A���ԃt�@���͑��������܂����A���������n���̉����D���Ȑl�ɂ͂��܂�Ȃ������Ǝv���܂��B
�k���n�̑@�ׂȉ���Ƃ��ʊ��Ȃ��L����̂��鉹�ł͂Ȃ������I�ȉ��ł��B
�A���Ԃ̃I�[�v���J�[�ƌ������̂́A�A���Ԃł��̂ōׂ����͑����A�������R�[�i�[��
�Ȃ����A�L���t���[�E�F�C��u���ɑ���̂ɓK���Ă��邱��Ȋ��z�ł��B
GOLDMUND��PIONEER�̂��b������܂������A���H�X�̒u���G���̒��ɏ��N�}�K�W���̖���ŊO�Ȉ�̌��t
�u�|�p�̂悤�ɑt�łĂ���Z�p���A�Z�p������ǂ����߂Ă͎�ɓ���Ȃ��^�̋Z�p��g�ɂ��āv
���N�T���f�[�̖���ŏ����O�Ȉ�̎�p����̌��t
�u������̂͏����ł�����A��������������Ȃ�20�N��30�N��̖������v
GOLDMUND����A�I�[�f�B�I���[�J�[����A���N�}�K�W���E���N�T���f�[��ǂ�ł܂����ˁE�E�E
�����ԍ��F8182597
![]() 0�_
0�_
�@����������A����ɂ��́B���͂���GOLDMUND�̌���������āu���Ђ̐��i�͗A�����~����I�v�Ƃ����v���܂����B140���~�̒l�t�������鐻�i�����ۂɁA��H�Ԃ������ЊJ�����悤�Ƃ��Ȃ��p���Ƃ����̂́A�����������Ȃ̂��ƁE�E�E�E�B����Ƃ��u����➑̂̒��ɂ̓X�C�X�̐����ȋ�C���l�܂��Ă��邩��A���̕������̂��v�Ƃł���������ł��傤���ˁi�j�B
�@����������EIDOS 20A�̃p�l�����O������A���̓X�J�X�J�炵���ł��ˁB�ʂɁu���g���M�b�V���l�܂��ē����z�������R�Ƃ��Ă����ԁv�������̗ǂ��Ɍq����킯�ł��Ȃ��ł��傤���A�������ǂ���Ύd�グ�͖��Ȃ��E�E�E�E�Ɗ�����قǁA���̐��i�͈����͂Ȃ��ł��B
�������̍D�݂⎨�̊�������������
�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂����B
�@�܂��������̒ʂ�ł��B�u����������I�v�Ƃ����̂��u�i�����j�ŏI��I�Ԃׂ��I�v�Ƃ����̂��A���傹��͊O��̈ӌ��ɉ߂��Ȃ��̂ł��B���ɂ́u���ɑË��͋֕������v�Ƃ����G�ꍞ�݂ŕs�K�v�ɍ������i���q�ɏ��߂�f�B�[���[������悤�ł����A�́E�����S�j�������Ă��悤�Ɂu�������̃V�X�e����[�������őI�Ԃ��Ɓv�Ƃ����̂��d�v���Ǝv���������̍��ł��B
�@�Ⴂ������ԉ�����A����ɂ��́BSA-XR55������Ȃɕ]�����ǂ��̂Ȃ�A�O���̎����������ƍ��߂ăv�����C���A���v�Ƃ��Ĕ���o�������ƁA�����v���܂��B�������A�Ɠd���[�J�[���P���I�ɃA���v������������\���͒Ⴂ�̂ŁA�x���`���[�I�Ȏq��Ђ�����Ă����ɔC����肪����܂��B���邢��OEM�Ƃ��đ��Ђɋ�������Ƃ��E�E�E�E�B���������AGOLDMUND�ɂ����p��������ʔ�����������܂���B�ŏI�I�ɂ�500���~���炢�̒l�t���ɂȂ����肵�āE�E�E�E�i�����j�B
�@D-45�͂���ς�u���������i舒B�ȁj���v�ł������B���ƂȂ��z�����t���܂��B�O�ɂ������܂������AD-45�̂悤�ȋƖ��p�@��̃e�C�X�g�����������悤�Ȗ����@���~�����Ƃ���ł��B�ǂ����̃I�[�f�B�I���[�J�[��D-45���x�[�X�ɂ��ĉƓd�X�ł�������悤�Ȑ��i������Ă��炦�Ȃ����Ǝv���Ă��܂��܂��B
�@�ŁAEIDOS 20A�ɑ���X�e���I�T�E���h���̔�]�́u�Â��ȉ���ɂӂ��悩�ł������P�����F�������яオ��v�u�S�[���h�����h�̉��n��͏�肢�v�Ƃ��������̂����������ł��B���˂Ă���v���Ă܂����A���̎G���̎��M�Ґw�̊Ԃɂ́u�R�X�g�p�t�H�[�}���X�v�Ƃ����T�O�͑��݂��Ȃ��̂ł��傤�B��x�AGOLDMUND�Ɠ����i�т̍��Y�A���v�ނƂ̒�����ׂ�����Ă݂����ł���(^^)�B
�����ԍ��F8184113
![]() 0�_
0�_
�͂��߂܂��āA���߂Ă̏������݂Ȃ̂Ŏ��炪�������炷���܂���B�F����͖{���ɃI�[�f�B�I�t�@���𑝂₵�����̂ł����H���̃X�������Ă���Ƃ����̃}�j�A�̎�������Ȍ������������Ă��邾���̂悤�Ɏv���܂��B
�F����悭�s���A�I�[�f�B�I�ƌ����܂����A�s���A�Ƃ͉��Ȃ�ł��傤���HJpop�͉��y�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H�����Ɋ������Ȃ��Ȃ玄�̓s���A�I�[�f�B�I�͗v��܂���B�m���ɍŋ߂�Jpop�͘^���̍ۂɉ������H���ꂽ���̂��قƂ�ǂł����������������̂����ɕ������Ă����I�[�f�B�I�Ƃ��Ẳ��l������Ǝ��͎v���܂��B�N���V�b�N��W���Y�̖��Ղ��������ꂢ�ɕ�������@�B�ȂǃI�[�f�B�I�@��Ƃ��Ă͕s�Ǖi�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H
�F���Y�@��́A�X�y�b�N�╨�ʂɗ��肷���ʼn����܂�Ȃ��ƌ����Ȃ���GOLDMUND�̏ꍇ�͉����������ɍ�������v�����肾�ƌ����̂͂��������̂ł́H������R�X�g���|���Ă��܂�Ȃ��������o���Ȃ��@�B���A�R�X�g���|�����ɂ��炵�������o���@�B�̂ق��������̂ł́H
���������I�[�f�B�I�@��́A�@�B�Ƃ��Ẳ��l��肻������o�Ă��鉹�ɉ��l������Ǝv���̂ł��̉����Ď����ɂƂ��Ă��ꂾ���̉��l������Ǝv���Δ����������A���l���Ȃ��Ǝv���Δ���Ȃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���܂��܂��̃X�����݂��ēǂ�l�̊��z�ł��B�C���̊Q�����炷�݂܂���B
�����ԍ��F8186004
![]() 4�_
4�_
�h���L�[�R���O�i������
���߂܂��āA�h���L�[�R���O�i������
>�F����͖{���ɃI�[�f�B�I�t�@���𑝂₵�����̂ł����H���̃X�������Ă���Ƃ����̃}�j�A�̎�������Ȍ������������Ă��邾���̂悤�Ɏv���܂��B
��������A�M�a�̋�ʂ�ł������܂��B��������Ȍ������������Ă��邾���ł������܂��B
�I�[�f�B�I�t�@���ƌĂ�Ȃ��A���邢�͎��o����Ă��Ȃ����͂����������̗l�ȏ��ɖڂ���
���܂���B������ǂ�Ńt�@����������Ƃ́A�]��v���܂���B( ���E�������A���݂܂�
��A�����ł��B)
>�F����悭�s���A�I�[�f�B�I�ƌ����܂����A�s���A�Ƃ͉��Ȃ�ł��傤���H
���I�H�ɂ̓I�[�f�B�I�E�r�W���A���ɑ��ăr�W���A�����܂܂Ȃ����A����ɋ��`�ōl�����
�̂Ȃ����2ch�X�e���I���s���A�I�[�f�B�I���ȁH�Ǝv���܂��B�T���E���h���܂܂Ȃ������m
��܂��A�r�W���A���̂Ȃ�SACD�}���`/DVD�I�[�f�B�I������܂��̂ŕ�����������ł�
�ˁB���̓r�W���A�����Ȃ���s���A�Ɋ܂�ł��ǂ����ȁH�Ƃ��v���܂��B�ł��}���`�`����
�l�����y�͒ʏ�AV�A���v�ł����Đ��o���Ȃ��̂ŁE�E�E�E�B
>Jpop�͉��y�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H�����Ɋ������Ȃ��Ȃ玄�̓s���A�I�[�f�B�I�͗v��܂���B�m���ɍŋ߂�Jpop�͘^���̍ۂɉ������H���ꂽ���̂��قƂ�ǂł����������������̂����ɕ������Ă����I�[�f�B�I�Ƃ��Ẳ��l������Ǝ��͎v���܂��B
>�N���V�b�N��W���Y�̖��Ղ��������ꂢ�ɕ�������@�B�ȂǃI�[�f�B�I�@��Ƃ��Ă͕s�Ǖi�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H
J-Pop���y�ƃs���A�I�[�f�B�I�͂��̗l�ȊW�ł͂Ȃ��A�I�[�f�B�I�͎�i�ŖړI�͉��y��
��(���y�Ƃ͌����Ȃ������ꍇ���L��܂����E�E�B)���ł��B���y���Ƃ����ړI�ׂ̈�
�̓s���A�ł�AV�ł��ǂ���ł��ǂ����P�ł��BJ-Pop���ܘ_���y�ł��B���̓A�L����E-550��
JBL��S4000�Ƃ����g�ݍ��킹�Łu���́v���������܂��I�I�B
�N���b�V�b�N/�W���Y�Ƒ���J-Pop�����y�̈Ⴂ�́A�����ł���y��̈Ⴂ�ł��傤�B�A�R�[�X
�e�b�N�Ȋy��ʼn��t������̂���̂Ȃ̂��W���Y�^�N���b�V�b�N�ŁA�d�C(�d�q)������镨��J-Pop���̂��̑�����吨���߂�c��̉��y�ł��B
�I�[�f�B�I�̂��������̎n�܂�́A�����̉��t��@���ɘ^��/�L�^/�Đ����邩�ɂ������Ă�
���Ǝv���܂��B�I�[�P�X�g���̂��̃o�C�I�����̃N���A�[�ł���Ȃ��牷�������̂��鉹�A
�W���Y�̂��̃x�[�X�̋����E�E�E�A�R�[�X�e�b�N�Ȋy��ł��邪�́A�����ɍĐ�����̂͂Ƃ�
������ł��ˁB(Hi-Fi��High-Fidelity�̗��œ��{���͍������x�ł��傤���B)
���̓_�A�d�C(�d�q)���g�������y�͋ɘ_�������Γ����l�ȑ��u���g���A�ƒ�ł����l�Ȑ���
�@����g���Γ������Œ��������o���܂��ˁB�ꍇ�ɂ���Ă͐��쎞�����H���ł���������
�o���܂��B�E�E�E���̓Z���[�k�E�f�B�I������D���ō��N�����h�[���ōs��ꂽ�R���T�[�g��
�s���Ă��܂����B�����A�I�[�f�B�I�I�ɂ͉����͐����o�Ęc�݂ȂǏo�Ȃ��̂ł����A��ꎩ��
�̍\��������܂������͈��������ł��ˁB����ł͉䂪130�C���`�X�N���[�����g����theater
�ŃZ���[�k�E�f�B�I���̃R���T�[�g��BD�\�t�g���ӏ܂��������]���܂��ł��B�����A�����h�[
���ł͐��Ŗڂ̑O�ŃZ���[�k�E�f�B�I�����̂��Ă���Ƃ�������������܂����A�ƒ�ł͂����܂Ńo�[�`�����ł�����E�E�E�B
>�F���Y�@��́A�X�y�b�N�╨�ʂɗ��肷���ʼn����܂�Ȃ��ƌ����Ȃ���GOLDMUND�̏ꍇ�͉����������ɍ�������v�����肾�ƌ����̂͂��������̂ł́H
GOLDMUND�̔�r�ʐ^�͎������܂����B�p�C�I�j�A��1���~�Ŕ����Ă���Ƃ����v���[���[�̊�
�Ղɂ�������ł����B�����Ƃ���Ύ��������܂���B�������������Ƃ����GOLDMUND���v���`
�i���C�̂܂݂��g���Ă��Ă��p�C�I�j�A��I�т܂��B�����AGOLDMUND�̐��i�͑S�ė]��ɍ�
���A����Ď�������Ώۂɂ��ʏ�͂Ȃ�܂���B�����ł���ꏊ(�V���b�v)�����Ȃ��̂Łu��
���������E�E�E�v�Ƃ������͏\�����肦�܂��B
>������R�X�g���|���Ă��܂�Ȃ��������o���Ȃ��@�B���A�R�X�g���|�����ɂ��炵�������o���@�B�̂ق��������̂ł́H
���������I�[�f�B�I�@��́A�@�B�Ƃ��Ẳ��l��肻������o�Ă��鉹�ɉ��l������Ǝv���̂ł��̉����Ď����ɂƂ��Ă��ꂾ���̉��l������Ǝv���Δ����������A���l���Ȃ��Ǝv���Δ���Ȃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
������M�a�̋�ʂ�ł������܂��B�R�X�g�p�t�H�[�}���X�Ƃ��������厖�ł��ˁB��������
���猻���Ƃ��Ă͉��l�̂�����͍̂����ł���A�Ƃ����̂������ł��B���l������Ǝv���Ă�
�����Ȃ�����������܂��B�E�E�E�̃R�[�q�[��CM�Łu�Ⴂ��������l�́E�E�E�v�Ƃ������̂�
����܂������A�Ⴂ��������Ȃ���Ή��ł��ǂ����P�ł����A����Ӗ����z���������Ȃ��ė�
���̂ł�����K���ł�����܂��B�������A�������A�Ⴂ�������鎖�͑傰���Ɍ������[��
���키�����o����̂ł��B�l�����̂��̂��K���ɂȂ邩���m��܂���B
���̎��͎������ւ����̑S�Ăɂ����Ă����v���܂��H�B���l�����o���Ύ�ɓ��ꂽ����
�v�����A���l�����o���Ȃ���Εs�K�v�Ȃ����ł��B�E�E�E�E�I�[�f�B�I�@��̉��l�E�E�E����
�͕�������l���̌o����ς�ł����ƕ�����l�ɂȂ�܂��B(������Ȃ���������܂���)
>���܂��܂��̃X�����݂��ēǂ�l�̊��z�ł��B�C���̊Q�����炷�݂܂���B
���̎��͎Љ�S�̂ɂ����đ厖�Ȏ��ł��B��Ԋ댯�Ȃ̂́u�S����v�v�E�E�E�������ꂪ�Ԉ�
����������j�łɌ������܂��B���{�ł��ߋ��ɂ���܂����ˁA�����m�푈�E�E����͊ԈႢ
���I�ƌ����Ă����l���������獡������܂��B�����O�Ɂu����������́E�E�E�v�Ƃ����f��
������܂������A�����Ƒ����̐l���u����͊ԈႢ���I�v�ƌ����Ă���E�E�E�E�B
�����ԍ��F8187518
![]() 1�_
1�_
���߂܂��āA�h���L�[�R���O�i������
���̃X���̑�ڂ�[�������̃I�[�f�B�I�@��ƍ���̓W�]]�ŋ@��A�W�������A���[�J�[��
�g�s�傳��͓���͂��Ă��܂���B
�����̃X�������Ă���Ƃ����̃}�j�A�̎�������Ȍ������������Ă��邾���̂悤�Ɏv���܂��B
�e�l�̃I�[�f�B�I����@��ɑ��銴�z���A���R�ɔ�������X���Ǝv���܂��̂�
���R�A���X�}�j�A�b�N�Ȃ�Ǝv���܂��B
���F����͖{���ɃI�[�f�B�I�t�@���𑝂₵�����̂ł����H
��Jpop�͉��y�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
���N���V�b�N��W���Y�̖��Ղ��������ꂢ�ɕ�������@�B�ȂǃI�[�f�B�I�@��Ƃ��Ă͕s�Ǖi�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H
���@�B�Ƃ��Ẳ��l��肻������o�Ă��鉹�ɉ��l������Ǝv���̂�
�����̉����Ď����ɂƂ��Ă��ꂾ���̉��l������Ǝv���Δ���������
�����l���Ȃ��Ǝv���Δ���Ȃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��L�̌���
���E�������A�����̏Z�l����B�́A���̃X���̎����Jpop�������A�W���Y�������A�N���V�b�N��
���������Ƃ̎���ɑ�R�̉A�A�h�o�C�X���Ȃ����Ă��܂��̂ŁA�I�[�f�B�I�t�@���𑝂������Ȃ���
�v���Ă���̂Ȃ��Jpop�ɂ́A���ꂪ�ǂ��̂ł͂ƌ����A�h�o�C�X������ł��傤���H
���A�ŏI�I�ɂ͎����̎��Œ����Č��߂Ă��������A���������Ă����������A��������Ă܂��B
���̃X������x�Q�Ƃ��Ă��������B
GOLDMUND�̌��́A130theater����̃��X������A���Ȃ�̒NjL�ł��B
�قړ��l�̕��i���ƌ����̂��{���ŁA���������x����������!PIONEER��1���~�EGOLDMUND��140���~�ł�
���ꂱ���I�[�f�B�I�t�@��������Ă����ƌ�����|�̔������Ǝv���܂��B
���E�������
����x�AGOLDMUND�Ɠ����i�т̍��Y�A���v�ނƂ̒�����ׂ�����Ă݂����ł���
�F�ŁA�������ŁA������ב���肽���ł��ˁ`�h���L�[�R���O�i����������ꏏ��
�h���L�[�R���O�i������ɁA����ȃ}�j�A�b�N�ȃI�b�T���B�Ƃł͌���ƌ���ꂻ���ł�(��)
�����ԍ��F8187956
![]() 1�_
1�_
130theater����A�Ⴂ������ԉ�����A���Ԏ����肪�Ƃ�������܂��B
���݂܂��̃X�����������ď���Ȉ�ۂ��������̂͌��܂��B
���̒m�荇���̃I�[�f�B�I�}�j�A�̕��̒���J-POP��ROCK��F�߂Ȃ���������̂ł������Ȃ��Ă��܂��܂����B�m���ɃN���V�b�N��W���Y���f���炵�����y�ł����AJ-POP�₻�̑��̉��y�ɂ��f���炵�����̂͑�R����܂���ˁB�����������܂��܂ȉ��y�i�^����ԂȂǂ��܂߁j���y�����������Ă���邩�ǂ��������Ȃ�̃I�[�f�B�I�@��I�т̊�ł��B�ƌ����Ă��旧���̂��E�E�E�Ȃ̂ł����B
GOLDMUND�ɂ��ẮA�����P�O�O���~�ȏ�̉��l������Ƃ͎v���Ă͂��܂���B�������̉���{���ɋC�ɓ����Ďg���Ă���������邩������Ȃ��̂ɗA����~�͑�U�����ȂƎv���܂����B
����Ƀn�C�G���h�I�[�f�B�I�ƌĂ��@��̒��ɂ͂����ƃ{�b�^����Ă��镨������̂ł͂Ȃ����ȁ[�H�Ƃ��v�����肵�܂��B�����Ƃ������ǁE�E�E
�܂��܂����n�ȏ��S�҂ł����A���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
�@
�����ԍ��F8189187
![]() 1�_
1�_
�h���L�[�R���O�i������A�͂��߂܂��āB
�����A���́A���y���F����ɂ����Đ��Ƃ郌�R�[�h��Ђ̃X�^�b�t�ł��B
���Ȃ݂Ɋ��E�c�ƃT�C�h�ł�������ɂ��A���X�A�W�邱�Ƃ�����܂��B
��Jpop�͉��y�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
�܂�����Ȃ����y�ł��B
���y�t�@����A�[�e�B�X�g�̃t�@���ɂƂ��Ă͏����ȃ��W�I�ł���g�ѓd�b�ł���Đ����u�͖₢�܂���B
�����A�������W�I�ʼn��y���D���ɂȂ�A�[�e�B�X�g�ɂȂ肽���Ċy�����ɂ��A�C�����Ή��y�ɌW�邱�ƂƂɂ��Ă��܂����B
�����������I�[�f�B�I�@��́A�@�B�Ƃ��Ẳ��l��肻������o�Ă��鉹�ɉ��l������Ǝv���̂�
�����̉����Ď����ɂƂ��Ă��ꂾ���̉��l������Ǝv���Δ����������A
�����l���Ȃ��Ǝv���Δ���Ȃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�A�[�e�B�X�g����i�Ƃ��ĐS���𒍂������̂��A�ނ炪�ڎw�������ɏ����ł��߂Â��đ̊��������E�E�E
���̃I�[�f�B�I�@��ւ̌����I�ȗ~���͂����ɂ���܂��B
�u�����ł��鉹�y�v�Əo������ǂ������傫�ȕ�����ڂ�������܂���ˁB
���傫�����[�����������߂邤���ɁA�����g�̓\�t�g��I�[�f�B�I�֎��R�Ƃ������g���悤�ɂȂ�܂����B
�\�t�g����鑤�̐l�ԂƂ��āu�����ł��鉹�y�v�������Ă��邩������Ȃ����ƂɊ뜜���A
���l������j�[�Y�ƃ��f�B�A�̃v���b�g�z�[���Ɍ˘f���Ă���̂��A�܂������ł��B
���X�A�����ł����A�I�[�f�B�I�͐H����H�ו��Ə������Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B
350�~�̋����ł����͖�������܂����A�Ђ���Ƃ�����500�~�̋����͂��������o���������Ă���邩������܂���B
�l�I�ɂ́A�~�j�R���|�ƃI�[�f�B�I�����@�̍��͂��̂��炢�����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B
�����@�╁�y�@�قǃ��[�J�[�ɐ_�o���g���ė~�����Ǝv���̂́A���l��F�߂Ă��炦�邾���̃��x���ɂȂ��ƁA
�܂���p���S���銴�����Ȃ��ƁA���y�t�@�����I�[�f�B�I�E�t�@���������Ă͂���Ȃ��ł�����E�E�E
10���~����l�Ȑ��i�͎�Ǝ���̗̈�ł��B
�������g�̂����������ƍ��v������́A���L���Đ����邱�Ƃɑウ���т������������E�ł��ˁB
���Ȃ݂�3���~�̋�����H�ׂ����Ƃ͎v���܂��i��j
��������R�X�g���|���Ă��܂�Ȃ��������o���Ȃ��@�B���A
���R�X�g���|�����ɂ��炵�������o���@�B�̂ق��������̂ł́H
���ӌ��������Ƃ��ł��B
���Y�̏����@�A���y�@�ɂ����ڎw���ė~�����������ł��B
�X��A�����g�����t�ł����u�����@�^���y�@�v�Ƃ������t���炵�ĕs�K�ł��ˁB
������Ɣw�L�т��Ĕ����Ă��������ȂƎv���Ă��炦�鉿�i�сi2���~����5���~�O��H�j�E�E�E�̐��i�ɂ��ẮA
�ɘ_����ƃI�[�f�B�I�E�}�j�A���ӎ����Đ��i���J�����Ă����܂�Ӗ����Ȃ��Ɗ����Ă܂��B
���E�������̃R�����g�ɂ��A�x�X�A�o�ꂵ�܂����A�u���������v�̍����n�[�h�����邱�Ƃ����z�ł��傤�B
�C�O���i�ɂ́A���̖ʂŏ��ɐ��i������Ă�����̂������l�Ɋ����Ă܂��B
���m���ɍŋ߂�Jpop�͘^���̍ۂɉ������H���ꂽ���̂��قƂ�ǂł���
���������������̂����ɕ������Ă����I�[�f�B�I�Ƃ��Ẳ��l������Ǝ��͎v���܂��B
�l�I�Ȋ��z�ł����E�E�E�I�[�f�B�I�E�t�@���ƃI�[�f�B�I�E�}�j�A�ł͐����Ǝ���قȂ�Ǝv���܂��B
�T�ڂ���͎����}�j�A�̕��ނɉf�邩������܂��A�����ł͉��y�t�@���䂦�̃I�[�f�B�I�D�����Ǝv���Ă܂�(^^;)
�I�[�f�B�I�E�}�j�A�̍Đ����u�Łu���v���y���߂邩�ǂ����̓P�[�X�i�^�C�g���j�ɂ��܂��ˁB
���u�̐��\�������o���l�ȃ\�t�g�����߂Ă���������Ȃ��炸��������Ⴂ�܂�����B
�����ԍ��F8189877
![]() 1�_
1�_
�F�l�A������������܂��B
�@�����璆�Ƀj�L�r������߂Ă������A�r�[�g���Y�����Ɍ���A�u�e�P�e�P�e�P�v��
�@�G���L�u�[������҂̐g���S���D���Ă��܂����B
�@���̗����̉��y���u�s�ǂ̕��v�u�ᑭ�E����v�ƌ��߂��Ă����̂͏����A��l����
�@�ł͂Ȃ��A���N�y�̎�҂ɂ�����������ł���܂��B
�@�w�Z�Ȃǂ̋���W�҂͓��R�ł����A�����̐����Ȃ��I�[�f�B�I�E���y���Ȃǂł�
�@�u�N�\�~�\�v�ȕ]�_������Ă����̂��v���o���܂��B
�@�u�N���V�b�N�v�݂̂����y�ŁA����������Ȃ��l�Ԃ�̎�����l�B�͍����̂��������B
�@�̗w�ȁE���b�N�EJAZZ�Ȃǂ͑ޔp�I�E���I�E��ؐl�̕��ƐS��l����l���v���E�A�}
�@��킸�u�䂱���͉��y�t�@���v�Ƃ̂����Ă�����ł��B
�@���y�̍D�݂�A�g�ɂ��Ă��镞����i�Ől�Ԃ̋M�˂f����l�����܂��B
�@���̐l�Ȃ�̂킩��₷�����l��ł�����ǂ��ł��ǂ��킯�ł����A���͋C�ɂ��܂���B
�@J-pop���JAZZ�̕����u�㓙�v�Ƃ��A�I�y���������Ȃ̕�����I�Ŏ���ǂ��Ƃ�
�@���������z�ɂ͌��킹�Ă����悢�̂ł��B
�@���y���āu�������v�����Ă������ɂȂ�Ȃ�[���ł����A�m�������Ԃ�̃w�{���y
�@���D�ƒB�́u���u�v���C�v�Ɍ���܂��B
�@
�����ԍ��F8190045
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��͂悤�������܂��A�l�I���W���łĂ����̂Ŏ��������悹�Ă��������@(���x�ł���(^^))
�h���L�[�R���O�i������@�͂��߂܂��āI������X�������肢�������܂��B
�������璆�Ƀj�L�r������߂Ă������A�r�[�g���Y�����Ɍ���A�u�e�P�e�P�e�P�v��
�@�G���L�u�[������҂̐g���S���D���Ă��܂����B
�����ɂ����Ă����܂˂��D���ł��ꂪ�����ăo���h��g�݃r�[�g���Y���e�P�e�P�e�P�ɖv�����Ă��܂����B�����������t�@(���ɂ��L�����I)�@����ł��B
���Z�̕����Ղɏo�����悤�Ɗw�Z�ɐ\���������G���L�o���h�Ȃǂ͉��y�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ鑛���ŕs�ǂ̂��邱�Ƃ��I�I�I�@�@�E�[���H
�������ނ̈�r�����ǂ��Ă���NHK�̍g���̍���ɓ�����q�b�g�����Ă����O���[�v�T�E���h����͂肻�̂悤�Ȏ���H�ŏo���ł��Ȃ�������������܂��B����ȗ��g���͌��Ă܂���B
����ł����y���D���ŃI�[�f�B�I���Â��ł���YMO�A�������`�A���݂��t���[�W�����n���D���Œ����Ă��܂��B�����̍D���ȋȂ������őI�V�X�e���Œ�����сA����͐l�����ƌ������ƊW����܂���ˁB�E�ƁA�g���ɋM�G�������̂Ɠ����ʼn��y�ɂ��㉺�A�M�G�Ȃǖ����ƍl���Ă��܂��A�ǂ��������̋C�ɓ��������̂Ŋy����ł��������������A���H����Ă���������̃X���b�h�ɑ������݂��܂���I
�����ԍ��F8190166
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
�l�I���W����
���m�������Ԃ�̃w�{���y���D�ƒB�́u���u�v���C�v�Ɍ���܂��B
�h�L�b!!!(^^�U�ꊾ�c
�����Ȃ���l�I���W����̃��b�Z�[�W�͔M���ł��B
�w�{���y���D�Ƃ̓����ɂ͊����܂��ł��A�n�C�c
satoakichan����
�������̍D���ȋȂ������őI�V�X�e���Œ�����сA����͐l�����ƌ������ƊW����܂���ˁB
��ł���Ȃ���|���V�[�ł�����킯�ł���ˁB
�������������ł��B
�ߑ����Ȃ��Č��Â����ɂ͋�������܂���(^^�U
���͂��������ĐF�X�Ə����Ă��܂��܂������A
����l�̏�M�Ƃ������S�ӋC�ɏ�����̂͂���܂���ˁB
���y�ɑ���h�ӂɊ������Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F8191095
![]() 0�_
0�_
�������������Ƃ����̂Ɂu���ꂵ���v�Y�ꌾ�Ȃǐ\����܂���B
satoakichan����A
�@�\�N��̂Ȃǂƌ���ꂽ�͉̂����̂��Ƃł��傤���H�����I�߂����O�̂��ƂȂ�
�@�Ⴂ���ɂ́u�H�H�H�v�̘A���ł��傤�ˁB
redfodera����
�@������܂����E�E�E�E�E�B
�@���y�E�y��E�I�[�f�B�I���i�E�ԓ��X�A���w�̐[���A�����̋����͎��ɂ͐^���ł��܂���B
�@�m���ƈ���̓G���W���ƃ^�C���݂����ȊW�ł��B
�@���̂悤�Ɂu�[��v�͎������킹�Ă��A�Ԍ��̋��������̐l�Ԃ͑ʖڂł��B
�@���ʂ܂łR���́u�i�v�A�uJAZZ�EJBL�EJAPANESE�v��ʂ������ł�����B
�@
�@
�����ԍ��F8191197
![]() 0�_
0�_
���ꂵ���Y�ꌾ�ɁA�ǂ�������������悤�Ȃނ��ꂵ�������Ő\����܂���@(�S�ꂩ��ł��I)
�ǂ����N�ւ��d�Ȃ��Ă����TPO������F�����Y��܂�(�ȒP�Ɍ����ƃ{�P�Ǐ�̎n�܂�ƌ��������ł��I)
�ɂ�������炸�@�uredfodera����v��
����ł���Ȃ���|���V�[�ł�����킯�ł���ˁB�@�������������ł��B
�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��I�ł�
���ߑ����Ȃ��Č��Â����ɂ͋�������܂���(^^�U
�Ƃ�ł��Ȃ��ł���[�I�@�u�l�I���W����v�����Ă܂�
���@���y�E�y��E�I�[�f�B�I���i�E�ԓ��X�A���w�̐[���A�����̋����͎��ɂ͐^���ł��܂���B�@�m���ƈ���̓G���W���ƃ^�C���݂����ȊW�ł��B
�S�����̒ʂ�ňًc������܂���A���ȂǑ召�̌Ã^�C����50cc�N���X�̃~�j�G���W�������������킹�Ă��܂���ł��B
�u�l�I���W����v��
���\�N��̂Ȃǂƌ���ꂽ�͉̂����̂��Ƃł��傤���H�����I�߂����O�̂��ƂȂ�
�@�Ⴂ���ɂ́u�H�H�H�v�̘A���ł��傤�ˁB
�n�C�m���ɂł����I�P�O�N�������I���v�Z���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ˁI�H
��L�Q�i�ڂ�()�̗��R�ɂ��Ǝv���܂��̂łǂ����A�u�h���L�[�R���O�i������v���������������ˁA�ł�(^^)
�����ԍ��F8191291
![]() 0�_
0�_
�l�I���W����Asatoakichan����A�����́B
�L���������܂�<(_ _)>
���J�ߒ����Č��h�ł����A���Ȃ�Ƃꂭ�����ł��B
��y�Ƀ��C�V�����߂��܂�(^^�U
���E�������
�F�X�Ȃ��ӌ����������̕��ƌ𗬂ł���X��������Ē������ӂ��Ă��܂�<(_ _)>
�O�X������ǂݕԂ��Ă݂�ƁA�F����̎��_�₨�b�����ꂼ��ɋ����[���A
�܂������̍��Z�������\�𐔂�����܂Łc�ړ_�����y�ƃI�[�f�B�I�ł���ȂɍL�����ł��ˁB
����珟��ɒ����߂ۂ����Ă��܂��܂������c
�F�D�_�͂��Ƃ��٘_���_objection�Ȍ����������肪�A�܂��܂��������Ƃ����҂��Ă���܂��B
�����ԍ��F8195568
![]() 0�_
0�_
�@����ɂ��� ->ALL
�@�ق��2���قǃA�N�Z�X���Ȃ������Ɏv��ʓW�J�ɂȂ��Ă��ċ����܂����B�h���L�[�R���OJr.����̏������݂ɑ��Ď������X����O�ɊF���I�m�ȃt�H���[������Ă���̂ŁA���܂��玄�����Ⴕ���o�Ă��Ă��u�ؕ��̏o���x��v�ɂȂ��Ă��܂��܂����i�劾�j�A�Ƃ肠�����͎v�����Ƃ��q�ׂĂ݂����Ǝv���܂��i���o�̏������݂̈ꕔ�Čf�ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��� ^^;�j�B
�@�܂��uJ-POP�͉��y�ł͂Ȃ��̂��H�v���Ă��Ƃł����A���y�ɂ͈Ⴂ����܂���B�������Y�܂������ƂɁA��ԑ���������Ă���W�������ɂ�������炸�A������g�I�[�f�B�I�f���h���Ȃ����y�Ȃ̂ł��B���ɘ^���������A���W�J�Z��~�j�R���|�Ŗ炵���Ƃ��Ɉ�ԗǂ���������悤�ȃC�R���C�W���O���{���Ă��܂����A���k���Ă���a�����o���Ȃ��悤�Ɂg���̐��h�Ƃ��Ă͍ŏ�����X�J�X�J�ł��B�s���A�E�I�[�f�B�I�̑��ݗ��R�Ƃ��Ắu�𑜓x�E���ʂ��o���������m�ۂ��āA�\�[�X�𒉎��ɉ��ɔ��f����v�Ƃ����s���������R�Ƒ��݂��Ă��܂��̂ŁAJ-POP�̃f�B�X�N��ǂ����u�Œ����قǘ^���̃A�����ڗ��͎̂d�����Ȃ����Ƃł��B
�@�̗̂̉w�Ȃ�j���[�~���[�W�b�N�͂�������Ȃ������ł��B�����ƃ��H�[�J���̎������������悤�Ș^���E�A�����W���{����Ă��܂����B����80�N��̖M�y�|�b�v�X�̃��R�[�f�B���O�����͐��E�L���������Ǝv���܂��B
�@�������A���݂͍����ȍĐ����u�����L����w�����������������A�͂��܂��䂪���ɂ͖{���̉��y�t�@�������܂肢�Ȃ����Ƃ����肩�猩��������Ă��܂����̂��A�^�����e�������ɂȂ�u�Ƃɂ�������������B���傹��͏��Օi���v�݂����ȕ���������U���Ĕ��ʂ��Ă��܂��Ă���̂����Ǝv���܂��B
�@�������A���́uJ-POP�͉��������B������s���A�E�I�[�f�B�I�ɂ͓K���Ȃ��B���ʂƂ��Đ�����J-POP�̒�����̓s���A�E�I�[�f�B�I�Ƃ͑������邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ����\�}���I�[�f�B�I���[�J�[���f�B�[���[�����u���Ă���͖̂��ł��B�]���́u�A�R�[�X�e�B�b�N�����̒Nj����I�[�f�B�I�̑�햡�v�Ƃ����������Ƃ͕ʂɁAJ-POP�ł��ǂ�����������悤�ȃs���A�E�I�[�f�B�I�V�X�e���𑗂�肪�l�Ă���K�v������Ǝv���܂��B
�@�ȑO�������܂������A�̂̓��[�J�[���Ⴂ���[�U�[�����Ɂu���b�N��p�v�݂����ȃI�[�f�B�I�E�R���|�[�l���g�����Ă��܂����B���ł������������@�_�͂����Ă����Ǝv���܂��BJ-POP���点��s���A�E�I�[�f�B�I�V�X�e���𐢂ɖ₤�ׂ��ł��傤�B���̃q���g�ɂȂ�̂�CROWN��D-45�݂����ȋƖ��p�V�X�e�����Ǝv���܂��B�|�b�v�X�ɂƂ��Ắu�����v��PA����o��T�E���h�Ȃ�A�����Ŏg����@����x�[�X�ɂ��Ė����p�Ƃ��đg�ݏグ������̂ł��B��������Ƃ͍l���������̂Ȃ��A����ł��ă~�j�R���|�Ƃ͈�����悷�N�H���e�B�̃V�X�e����o���ĎႢ���X�i�[�ɃA�s�[�����A�ڋq�w���������Ă����Ȃ���Γ��{�̃s���A�E�I�[�f�B�I�͏k���X�p�C�����ɗ������ނ��肾�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8195678
![]() 0�_
0�_
�@GOLDMUND�ɂ��Ăł����A���͉��߂ē��Ђ̎{��͋U�����ƌ��������ł��B���Ƃ��Č����Ȃ�A300�~�̃J�b�v���[�����̖˂ƃX�[�v�𗬗p���āA�u���₭�v�ɏ����㓙�ȐH�ނ��g���ĐV��̃X�p�C�X��U�肩���A�L�c�Ă̗e��ɓ����3���~�Ŕ���悤�Ȃ��̂ł��傤�B������ꕔ�̐H�ʂɃE�P���ǂ��Ă��u���傹���300�~�̃J�b�v�ˁv�Ƃ����u�햾�����v���t���ĉ��悤�ȏ��i�͔�����������܂��A��ꂻ��ȋƎ҂͐M�p�����ł��傤�B
��GOLDMUND�̏ꍇ�͉����������Ɂ`
�@EIDOS 20A�͒��������Ƃ͂���܂��A���Ђ̑��̐��i�͉��x���������Ă��܂��B�Ɠ��̐����ȉ����ŔM�S�ȃt�@��������̂������܂����A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����ł��B���̉��ł��̒l�i�E���̊O���̎����ł͂���܂�ł��B
�@�������A�}�j�A�ƌĂ��l�X�̓R�X�g�x�O���ŏ����ł����̗ǂ�����ǂ����߂܂��B���R�A���Ƃ����Y70���~��CD�v���[���[����₩��O����140���~��EIDOS 20A���w������ۂɂ́A70���~��CDP���2�{�͉����ǂ��E�E�E�E�Ǝv���킯�ł͂Ȃ��A�ق�̏����̍��ł�140���~�̋@���I�Ԃ킯�ł��B�ł����ꂪ����1���~�̈����̊�Ղ��X�I�ɗ��p���Ă������Ƃ���������A������}�j�A�Ƃ����Ă��S���₩�ł͂Ȃ��ł��傤�B���̋@��̕��i�𗬗p���Ă���̂Ȃ�A�����N�H���e�B��30���~�قǂŏo����̂ł͂Ȃ����A�܂�140���~�Ŕ���̂Ȃ�����Ɨǂ����Ɏd�グ���Ȃ������̂��E�E�E�E�Ƃ����^�S�ËS��厖�Ȍڋq�ɕ������Ă��܂������ƂŁA���̋Ǝ҂̎p���͋^�킵�����̂ɂȂ�܂��B���͏��Ȃ��Ƃ�EIDOS 20A�̗A�����炢�͌����킹�������ǂ��Ǝv���܂��B
�@�������A�O�ɂ������܂������A�{���ɔ������ׂ���PIONEER���͂��߂Ƃ��鍑�����[�J�[�ł��傤�B�����̂Ƃ��̃G���g���[�@��̕��i���g���ă{�b�^�N���̏��i��o����Ă��܂������Ƃɑ��āu������������������ƈ����ėǂ���������Ă��I�v�ƋC���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@����Ɓu�F����͖{���ɃI�[�f�B�I�t�@���𑝂₵�����̂��H�v�Ƃ����^��ɂ��Ăł����A�����܂߂ĒN�����u���₵�����v�Ǝv���Ă�͂��ł��B�����łȂ���Όf���ŃA�h�o�C�X�Ȃ��܂���B�ł����ꂪ���[�J�[��f�B�[���[�ɓ͂����ǂ����͕ʖ��B��X�̑����͋ƊE�W�҂ł͂Ȃ��s��̃I�[�f�B�I�t�@���E���y�t�@���ɉ߂��܂���̂ŁE�E�E�E(^^;)�B�ł��A������Ƃ����Ă����ł��ꂱ�ꌾ�����Ƃ����Ӗ����Ƃ͎v���܂���B���_���ł��܂����A���I�[�f�B�I���l�^�Ɍ�荇�����Ǝ��̂��y�����ł�����B
�@�Ȃ��A�������͂̉��y�D���ɗǎ��ȃI�[�f�B�I�̕K�v����M���i���Ă��܂��B�܂��A����������P�[�X�����܂ɂ���܂����i�j���� ^^;�j�B
�����ԍ��F8195685
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ����́B
����ɂ���ɖl�݂����Ȏ҂���鎖�͍��X�Ȃ��̂ł����A�i����y�����S�Č���ĉ������Ă��܂��j
�U��Ԃ��Ă݂�Ɩl������������J-POP��ᔻ���Ă����悤�ȋC�����ď����ӔC�������邵�����ł���܂��B����������\����܂���ł����B
���ꂾ���͌��킹�Ă��������AJ-POP�͗�L�Ƃ������y�ł���l���g��Ԓ����Ă���̂�J-POP�ł��B�����唼�̃\�t�g�̘^����Ԃ��̂ƕς���Ă��Ă��āA���������̂ɕ����Ɋ����Ȃ��ƌ��������̂ł��傤���A�c�O���ł����ς��Ȃ�ł��B
�D���ȃA�[�e�B�X�g��CD�͂������ł����Ăق����A���̊�]�����ڂɏo�Ă��܂��܂����B
�W�O�`�X�O�N��A���x�b�J��CD�Ȃ͂����������������Ȃ�ł����E�E�E�B
�����ԍ��F8196602
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
���E�������̋ߔN��Jpop�ɑ��錵�������w�E�́A����葤�̐l�ԂƂ��Ď����ƂĂ��ɂ��ł��B
���������Ȃ������R�E�E�E���炭�ЂƂӂ��̗v���ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A���Ȃ�Ɏv�������Ԏ�Ȏ���Ƃ��ẮE�E�E
1�j�@���̓I�Ȑ���\�Z�́i����Ӗ��ł͉ߓx�Ƃ��v����j�팸�ƍ��������i����
2�j�A�[�e�B�X�g���g�̃v���x�[�g���Ő��삵���f�ނ𑽂����p����悤�ɂȂ�������
�����������Ă��炦�Ȃ��̂ŃA�[�e�B�X�g�����ٓ��ŁE�E�E���^���Ƃ��Ă͂��܂芽�}�ł��Ȃ��T�C�N���ȋC�����܂��B
�v���E�v���̉�������ɂȂ��Ă��܂��Ƒ����̖�������Ă��܂����낤���Ƃ͏\���ɗ\���ł��܂��B
��i�Ƃ͂��Ȃ킿���i�Ȃ킯�ŁA�N�I���e�B���ێ��ł��Ȃ��Ƃ���ƊE�����悵�ď��������Ď���i�߂܂��E�E�E
�ł���������̂̓��[�U����ł�����A�c�O�ł����A��������ē��R�ł��B
����Ƙ^���̃v���t�F�b�V���i���ŁA���X�A���������A�W�����A�o�[����͈قȂ邲�ӌ�����������������܂���B
�܂����t�ƂƂ��ĕl�I���W����M���R�����g���������E�E�E
������A�����ɂȂ��Ă�������Ⴂ�܂��ł��傤���H
����̎��_���s������ŋ����[�����b���f����ƍK���ł��B
�����ԍ��F8196694
![]() 0�_
0�_
���ӂ́A���������B���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
����͋ɘ_��������܂��A�킽���̓I�[�f�B�I�́A�K�������s���A�ȕK�v�͖����Ǝv���܂��B�𑜓x����ʂȂǂ́A������̐����i�l�ɂ���ĈقȂ�j����Ώ\���ŁA�����Ɖ��̐[�݂�A���x���A�F���y���ނ��̂������Ă��ǂ��Ƃ������܂��B�ŋ߂́A���܂�ɂ��A�L�����[�g�Ńn�C�X�s�[�h�ȉ��̋@�����A���ɍ��Y�̏��H�����@�B�ԂɗႦ��ƃX�|�[�c�J�[�ł����낢��ȃ^�C�v������܂���ˁB�����������������Ƃ߂����[�V���O�J�[�A�Œ���̑���������lj������X�|�[�c�J�[�A�������s�̓��ӂȑ�r�C�ʎԂ���R�[�i�[�����O�����ӂȃ��C�g�E�G�C�g�A�F�X�Ȃ��̂�����܂��B�\���N�O�Ƀ}�c�_�̃��[�h�X�^�[�����E�I�ɑ嗬�s���܂����B
�n�C�p���[�ȃG���W����ς�ł���킯�ł��Ȃ��A�{�f�B�[����������Ȃɍ����Ȃ���ΓI�Ȑ��\�́A�������ɂ��X�|�[�c�J�[�ƌĂׂ郌�x���ł͂���܂���ł����B�������^�]����y�����i���E�͒Ⴂ�ł����j�͏\���X�|�[�c�J�[�Ƃ��Ă̊�����Ă��܂����B
���{�̃I�[�f�B�I���[�J�[�́A�����Ɩ`���Ăق����ł��B�����ƕȂ̂���i����������ቹ����������̂ł͂Ȃ��j���I�ȉ��A�y��������ڎw���Ăق����ł��B��������Ύ��R�ƃI�[�f�B�I�t�@���������Ă���̂ł́H�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8197210
![]() 0�_
0�_
�h���L�[�R���O�i������
>����͋ɘ_��������܂��A�킽���̓I�[�f�B�I�́A�K�������s���A�ȕK�v�͖����Ǝv���܂��B�𑜓x����ʂȂǂ́A������̐����i�l�ɂ���ĈقȂ�j����Ώ\���ŁA�����Ɖ��̐[�݂�A���x���A�F���y���ނ��̂������Ă��ǂ��Ƃ������܂��B
�ꗝ����܂��ˁB�u������̐����v�E�E�E����͓���ł��˂��B���ɂ͂�͂肠��ׂ���
���B�������ɂɋ��߂�̂̓I�[�P�X�g���̐����t�̍Đ��ł��傤���H(���Ɍ��y��)�B���̒��A
�R�X�g�Ƃ��Z�p�I�A���_�I��肪�o�Ă��܂�������E�͂���܂����E�E�E�B
�G��Ŕ�r����Ɨǂ������m��܂���B�G�̋���g�����G�Ɠd�q�I�ɏ�����(�����)�f�B�X
�v���B�ɕ\�����ꂽ�G�Ƃ̈Ⴂ�ł��傤���H�B�s���A�I�[�f�B�I�͂����܂ŊG�̋�ŏ������G
��d�q�f�B�X�v���B�œ����l�Ɍ�����l�ɂ���A������͌����Ȃ��Ďn�߂���f�B�X�v���B
�ɕ\������A�Ƃ����������ł��ˁB
>�E�E�E�\���N�O�Ƀ}�c�_�̃��[�h�X�^�[�����E�I�ɑ嗬�s���܂����B
�n�C�p���[�ȃG���W����ς�ł���킯�ł��Ȃ��A�{�f�B�[����������Ȃɍ����Ȃ���ΓI�Ȑ��\�́A�������ɂ��X�|�[�c�J�[�ƌĂׂ郌�x���ł͂���܂���ł����B�������^�]����y�����i���E�͒Ⴂ�ł����j�͏\���X�|�[�c�J�[�Ƃ��Ă̊�����Ă��܂����B
�ʔ����Ⴆ�ł��ˁB�X�|�[�c�J�[����Ȃ��(��������ړI�ɓ����H�H)���ɂ�F-1�ł��傤
���A�}�c�_���[�h�X�^�[�ł̓L�~�E���C�R�l���͖������Ȃ��ł��傤�ˁB�����Ƃ�F-1�h���C
�o�[�ł͂Ȃ���X�ɂ�F-1�͈�������܂��E�E�E�B�ɘ_���Ă��܂���F-1�����������݂���
���[�h�X�^�[������Ɨǂ��Ǝv���܂��B�}�c�_���[�h�X�^�[�����ɂł͂܂�܂���B(����
�Ԃ̓V�r�b�N�^�C�vR�ł����A���[�h�X�^�[��葬���Ǝv���Ă��܂��H�H�H�B)
>���{�̃I�[�f�B�I���[�J�[�́A�����Ɩ`���Ăق����ł��B�����ƕȂ̂���i����������ቹ����������̂ł͂Ȃ��j���I�ȉ��A�y��������ڎw���Ăق����ł��B��������Ύ��R�ƃI�[�f�B�I�t�@���������Ă���̂ł́H�Ǝv���܂��B
�܂��܂�����l���ł��ˁB�ǂ����Ƃ͈�ʓI�ɘc�݂��Ȃ��A���g���������t���b�g�Ȏ��A��
�x�������ǂ������X�ƌ����Ă��܂��B(�܂��v���͑�R����܂���)�e���[�J�[�͂܂����̗l
�Ȏ������߂Ă��锤�ł��B���ꂪ��{�ɂȂ��Ɓu�����̕ςȉ��v���o��I�[�f�B�I�@��ɂȂ�
�Ă��܂��܂��E�E�E�B�h���L�[�R���O�i������͋��炭�E�E�E�Ⴆ�����ł����J�c�I������
�ă}�O��������A�A�W���T���}������E�E�ǂ̋�����Ԕ����������H�Ȃ�ċc�_�͕s�тł�
�ˁB���̖��́u���v�ł͂Ȃ��u�Ⴂ�v�ł�����B
�I�[�f�B�I�ɂ���������߂Ă�����̂ł��傤���H�B
�y�킪�����I�U�������Ă��ꂪ��C�ɓ`���A�������̎��ɓ��B�A�ۖ���U�������������ۂ�
�F�m���܂��B�����Đ_�o�זE����]�ɓ��B�E�E�E�E�������̐S�Ȃ̂ł����A�l�Ԃ�������
�͂��́u�������ہv�ł͂Ȃ��A�u�S�����ہv�ł��B�����ɉ��Ƃ����������ۂ�S�����ۂɕϊ�
���邩�I�Ƃ����̂͂��̐l�̊����ł��B���̊����������Ɩ����Ȃ��Ă͂����܂���ˁB
�����ԍ��F8197367
![]() 0�_
0�_
���قف`�`���I����オ���Ă܂���܂����ˁ`�B
�@j-pop�Ȃ�W�������ɂǂ̗l�Ȑl�����āA�ǂ̗l�ȉ��y�����Ă���̂��F�ڕ�����Ȃ�
�@�I���W�ł����A������ď����A�u�j���`�~���`�W�b�N�v�ƌ���ꂽ�W�������̌��`
�@�Ȃ̂ł��傤���H���̒��͂W�O�N��O���Ōł܂��Ă��܂��Ă���̂ŁE�E�E�E�B
�@�Ԃ�Ⴆ�ɂ���ƑS����������o�Ȃ��t�F���[���Ƃ��A�����{���M�[�j�A������F1
�@�֖��s���Ă��܂��Ǝʐ^�Ō������Ǐ�������Ƃ��A�^�]�������Ƃ��Ȃ��ƌ������z�̘b
�@�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁ`�B
�@�����ɗႦ��Ƃ���ƁA�ŋ߃e���r�ʼn��������Ă��o�����Ă���u�����^�����g�v��
�@���Ă��܂��|�ƁA�ՌÒ�������ȂōI��������ď킹�ĖႤ�|�Ƃ́u���v�ʂ�
�@����̂����m��܂���B
�@���̐̂́u�j���[�~���[�W�b�N�v�ƌ���ꂽ���y���A���y���]�X���l����O�ɔp���
�@�������I��������ɂ͂Ƃɂ����V�Ȃ��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����h��������܂����B
�@�������猻���ō��������ɂ���l�̐��͂ق�̈ꈬ��ł���ˁB
�@�����ŐV�Ȃ̃A�C�f�A�������ƊO���Ȃ��u�p�N��v�l�ȉ̎�܂ŏo��n���B
�@�����̋Ȃ��t�@���w�͐�ɕ��������Ȃ�JAZZ�̋Ȃ�������A�������s�̃t���[�W����
�@�n�̋Ȃ�������Ɣ��_�Ƃ��y�������Ƃ������ɂ��Ƃ܂�����܂���B
�@�v����ɂ͂��S�A���s�̂��낤��j-pop���낤���u����ĂȂ�ځH�v�̕�����ł��B
�@�̎Z�x�O������킯���Ȃ��A���̕ӂ����ݓI�ɌŒ�q�̂���N���V�b�N�EJAZZ�Ƃ͈Ⴄ�H
�@�����E�s���A�[�x�E�N�I���e�B�[���̊ϓ_�Ŏ��̓I�[�f�B�I�ɂ��Ă��A�Ԃɂ��Ă�
�@�V���i�E�����\�ȕ�����ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��̂ʼn��Ƃ������܂��B
�@�Ⴂ�ƌ������Ƃ��܂��A�u�s���A�[�v���̕��Ȃ̂ł�����O��̌���ȂNjC�ɂ���
�@�����̍D���ȕ��A�D���ȉ��ő�R���y���̂���Ԃ���Ȃ��ł����H
�@�����l�߂Ă����ƁA���̂܂܂ł͔[���ł��Ȃ������������邩�A�����܂ł��ς��Ȃ�
�@����������̂��H�Ŏ����Ɠ��͑O�ɂ�����̂ł��B
�@�啪�A�x���ŗ�ɂȂ��Ă��܂����B
�@���オ��낵���悤�ŁI
�����ԍ��F8197544
![]() 0�_
0�_
�F����ɂ��́B
�����܂��Ƃ���������ɂ��������ł��ˁB�������F-1�̂悤�ɏ����ɃX�s�[�h��Nj����郂�f���A�I�[�f�B�I�̏ꍇ�́A�����𒉎��ɍČ����郂�f�����A��ɕK�v���Ǝv���܂��B
�������ׂẴX�|�[�c�J�[���X�s�[�h�̒Nj��݂̂ɑ�������A���[�h�X�^�[�̂悤�ȃJ�e�S���[�́A�a�����܂���ł����B�V�r�b�N�^�C�v�q�͐��܂ꂽ�����m��܂��c��
�I�[�f�B�I�@����Ƃ��Ƃ�X�y�b�N��Nj����郂�f�������łȂ���������h�����郂�f���������Ă��ǂ��Ǝv���܂��B���ɉ��Ɋւ��Ă͓��������Ă�����l�͐��ݐ��������ƌ�������l�͍������L�����ƌ�������A�����������l�ɂ��܂��܂��ł��B�����炭���ɂ̉��ƌ������̂���l��l�Ⴄ�Ƃ������܂��B�Ⴆ�I�[�P�X�g���̐����t�ł����Ԃ���ŕ��������l������A�������̐Ȃŕ��������l�����܂��B���������t�ł������ꏊ�ɂ���ĕ������Ă��鉹�́A���Ȃ�ς���Ă��܂��܂��B�����琳�������iCD�ɔ[�߂��Ă���j�����ׂĂ̐l�ɂƂ��ėǂ����ł͂Ȃ��͂��ł��B
���������ŕ����Ă������̃A�[�e�B�X�g�̕�������������������B�ƌ����̂��[���͂ł���̂ł����A���͕����l���A�S�n�ǂ��Ɗ����鉹�ōD���ȃA�[�e�B�X�g�̋Ȃ��ق����A���͓I�ɕ������y�����Ƃ������܂��B������l�ɂ���Ĉ���Ă���Ǝv���܂��B
�C�O�̃I�[�f�B�I���[�J�[�ɂ́A���̃��[�J�[�̉��Ƃ����̂��������Z������Ǝv���܂��B�������A�L�����[�g�Ńn�C�X�s�[�h�ȉ����o�����[�J�[�������ł����A�Z���ŃX���[�ȕ�����Z���Ȃ̂Ƀn�C�X�s�[�h��������A�L�����[�g�ȉ��Ȃ̂ɃX���[��������F�X�ȉ��F������Ǝv���܂��B����ɑ��ē��{�̃��[�J�[�͉��̈Ⴂ�͂���̂ł��������܂ł̌��������悤�Ɋ����܂��i�ŋ߂̋@��͓��Ɂj�t�ɋ@�B�Ƃ��Ă̑���͂������ǂ��Ǝv���̂ł����c�B
�ǂ����Ă���ʂ̐l���I�[�f�B�I�@����ꍇ�A�܂��s�����̓I�[�f�B�I�V���b�v�ł͂Ȃ��Ɠd�ʔ̓X�ł��傤�B��������قǑ傫�ȓs�s�̑傫�ȓX�܂łȂ��ƍ��Y�̏������@���炢�����u���ĂȂ��Ǝv���܂��B���̒��Ɏ����̋C�ɓ���@�킪����Ηǂ��̂ł����A������Ό��ǃ~�j�R���|�ł�����ƂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�t�ɂ��̃N���X�ɖ��͓I�ȋ@�킪�F�X����I�[�f�B�I�≹�y�������Ɗy���ސl���ӂ���Ƃ������܂��B
�b�͕ς��܂����F����́ASHM-CD�Ƃ�����������������܂����H���������Ă����琥�|�[�g�����肢���܂��B
�����ԍ��F8198210
![]() 0�_
0�_
�@���͂悤�������܂��@->ALL�B
�@�����牓�o���邽�ߎ��Ԃ��Ȃ��W��(^^;)�ASHM-CD�ɂ��Ă������X���܂��B1,000�~�́u������׃f�B�X�N�v���o�Ă��܂��ˁB�������e�̒ʏ�CD��SHM-CD�Ƃ��Z�b�g�ɂȂ������̂ł��B�N���V�b�N�ƃ��b�N�ƃW���Y�������[�X����Ă��܂����A�������肵���̂̓��b�N�łł��B
�@���������āA����ȂɃr�b�N������悤�ȍ��͌����܂���B�������A�X�̉��̃L���Ƃ��A����̍L���Ɏ�̍��ق��F�߂��܂��B�����ȋ@��Œ�����ׂ�Ƃ����ƌ����ȈႢ�����邱�Ƃ������邩������܂���B�������V���b�v�Ɏ��Q���ăn�C�G���h�@�Ń`�F�b�N�������v���܂��B
�@�������A�ŋߏo�����[�����O�E�X�g�[���Y�̃��C���Ղ�SHM-CD�d�l�͊m���ɉ����ǂ��ł��B�ʏ�CD�łƒ�����ׂĂ͂���܂��ASHM-CD�͗ǂ������Ȃ������������悤�ȋK�i���Ƃ����̂͌����邩������܂���B
�����ԍ��F8201336
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��͂悤�������܂��B
�h���L�[�R���O�i������
���I�[�f�B�I�@����Ƃ��Ƃ�X�y�b�N��Nj����郂�f�������łȂ���������h�����郂�f���������Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
�l�̃R���Z�v�g�͂��������ł��B�s���A�u���̃I�[�f�B�I�t�@���ɈႢ�͂���܂��A
�����̎呕�u��AV�A���v�ł����A���C���X�s�[�J�[��2�{��10���~���́A�~�j�R���|������
���ɖт��������悤�ȃu�b�N�V�F���t�^�ł��B���\�����S���̃X�s�[�J�[��@��ɓ����
����܂����A����������ɓ����Ă������w�����悤�Ƃ͎v���܂���B
�����Ɉ����������̂����邩�A�����ƖڕW�����Ăď����Â�������Ă����邩�A
�ӊO�������邩�A�����Ď����D�݂̉��ł��邩�ł��B
�p���[�A���v��E�[�t�@�[�͉Ƃɓ]�����Ă����J�[�I�[�f�B�I�p��]�p�����̂���L�̃R���Z�v�g�̂ЂƂł��B
�{���̃I�[�f�B�I�}�j�A�̕����猩������̃V�X�e���Ȃ͏��Ă��܂��悤�ȕ�����
����܂���B�������l�͋C�ɂ��܂���B�����Ȃ�̃R���Z�v�g�������āA��������s���Ă���
�����̔w��ɂ����������Ŋy���߂Ă��܂�����B
���������ăs���A�Ƃ��邩�A�l�͑��u�����̑��̂ł͂Ȃ���肢�����ŕ��������ȂƎv�����u�Ԃ�����s���A�I�[�f�B�I�ƌ�����̂ł͂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8201546
![]() 0�_
0�_
�A���X�����܂���B
���E�������
SHM-CD�@�T���v���łR���A�}�]���Œ������Ă��܂��܂����B
���b�N�ƃN���V�b�N�ƃW���Y
�y���݂ł��i�j
�����ԍ��F8201639
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�h���L�[�R���O�i�������SHM-CD�ւ̃t���ɏ���ăA�i���O�E���R�[�h�̍�����̈�����4�^�C�g���Œ�����ׂ��Ă݂܂����B
���Ƃ��Ɠ��e���^�����D�G��4���Ȃ̂�LP�^CD�^SHM-CD�ł̔�r�����͂ƂĂ��y���߂܂����B
Sting �@�uThe Dream Of Blue Turtles �v�u...Nothing Like The Sun�v
Steely Dan �uAija �v�uGaucho�v
Steely Dan��CD�����ꂽ����̍��̕��ƃ��}�X�^�[CD�ASting�͔���������CD�ł����B
�Â�CD�́i����N���C�ɂ��Ȃ��j�}�X�^�����O�̃v���Z�X���ނŁu...Nothing Like The Sun�v������AAD�ɂȂ�܂��B
�u...Nothing Like The Sun�v�͓����ł����Ȃ�����DDD�ŁA���}�X�^�[�̕K�v�����������Ȃ����x���ŋ����܂����B
�A�i���O�E���R�[�h��Sting�͏��ł̍����ŁASteely Dan�͗����V���[�Y�ɂȂ��Ă���̍����łł��B
�y�U�����ꂼ������ɈႤ�̂ŒP���ȍb���͂����܂��ƁA
�܂��@�ނɂ��Ă͒����Ȃ�̂Ŋ������܂����A�������������B
�v������+�~�h���̌����ŃA�i���O�E���R�[�h�̏����I�A�ɂ������Ƃ���ł����E�E�ESHM-CD�A�������^�����ꂪ�ǂ��ł��B
���������������Ă���̂��A�����̈ʒu�W��G�t�F�N�g��[���i���邢�̓G�t�F�N�g�j�E�G�R�[��������₷���ł����A
�����Ɖ��s���������ĂЂƂ܂��T�[�r�X�E�G���A���L���Ȃ�����ۂ��܂��B
���Ă�24K-CD�ƈ���Ă��l�i���W���I�Ȃ̂����}�ł��B
�����ԍ��F8204608
![]() 0�_
0�_
�F���ӂ́A
����������肪�Ƃ�������܂��B���������T���v���\�܂����B
���\���C���i�b�v���[�����Ă�݂����ł��ˁB
�����ԍ��F8204678
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́@�~�x�݂��I��茎�j����d���ł��B
�l�I���W����
�����̂悤�Ɂu�[��v�͎������킹�Ă��A�Ԍ��̋��������̐l�Ԃ͑ʖڂł��B
�ŋ߂���Ȍ��t�͂Ђ��������ɂ����A��`�E�E�E���Q�I�Ԍ��������Ă������Ƒ�ςȉ��s��������̂ł͂Ǝv���܂��B
satoakichan����
�������̍D���ȋȂ������őI�V�X�e���Œ�����сA����͐l�����ƌ������ƊW����܂���ˁB
�������ŁA�n�C�I�ƌ����Ă��܂��܂����B�i�j
130theater����
���}�c�_���[�h�X�^�[�����ɂł͂܂�܂���B(���̎Ԃ̓V�r�b�N�^�C�vR�ł����A���[�h�X�^�[��葬���Ǝv���Ă��܂��H�H�H�B)
���[�h�X�^�[�̏����I�[�f�B�I�̓r�b�N�����邮�炢�ǂ����ŁA�����̎Ԃɕt�����Ƃ���ǂ����͂���̂ł������[�h�X�^�[�Œ���
���ƈ���Ă��܂����B
�Ȃ��ɂƎv�����̂ł����A������ԁA�����ʒu���▭�ɃZ�b�e�B���O���Ẳ��ő��̎Ԃł͓������͕����Ȃ��Ǝ����Ȃ�̏���Ȍ��_�A����������������ɓ��ꂽ�̂ɑ�σV���b�N�ł����B
redfodera����
���̓I�[�f�B�I�ƊE�ł͂Ȃ��ԋƊE�ŁA�Ԃ̐��Y���偨�C�����偨�̔����哙�̌o�߂ŁA���Ԃʂ܂Ŏԉ��ł��B
�e�Ɏ�ɐE��t������ꐶ���v������A���v������ƌ����A�����M���Đ��Y����𗣂�C�������
���������X�ɗǂ��d�����A�����������Ă���Ƃ̒��������������A�����Ă��ǂ��d���A���������̎d����U�蕪���Ă���Ă��܂�����
���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɖw�ǂ̒��������������ɁA�ȑO�̂悤�ȏ��X�����Ă��ǂ��d�����ƌ��������͖����Ȃ�C������𗣂�܂����B
�����͐E�l�̎�d������@�B�����i���ƁA��ʃ��[�U�[����̒������ω��������ł��B
�ǂ��d���������l�͑������Ă�Jpop��b�N���͌g�т�PC�ł��������_�E�����[�h�����L��Ώ����ɂȂ�A����ʃ��[�U�[���g�ѓd�b���Ń_�E�����[�h�����Ȃ��C���z���Œ����Ė����Ȃ�ΒN�������Ǝ��Ԃ������ėǂ��^���̂b�c�����܂���B
���[�U�[��Jpop��b�N�����ǂ��^���̂b�c��������Ȃ��ƂȂ�A���葤���l����ł��傤�������Ȃ��Ă��Ȃ��̂ł́E�E�E
�I�[�f�B�I�ƊE�������o�������悤�Ȏ����N�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB
����28��������
�����������ăs���A�Ƃ��邩�A�l�͑��u�����̑��̂ł͂Ȃ���肢�����ŕ��������ȂƎv�����u�Ԃ�����s���A�I�[�f�B�I��
��������̂ł͂Ǝv���܂��B
���͂`�u�A���v�ŏo���邾���f��ق̂悤�ȉ��ꊴ������̕����ő̊��������A2�`�����l���ł͏o���邾���ǂ�����������
�v���Ă��܂��B
�f����ςɍs���Ă̊��z�̓X�g�[���[�̘b�A��l���̘b�A���͂̉��ꊴ�̘b���ŁA�������ቹ�������ˁ`�Ƃ������ʂ鍂���������ˁ`�Ƃ̔�]�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�w���R�v�^�[����ԏ�ʂł͘c�̈���������ق��������炵���A�����́A��̗ǂ����ł̓��W�R���ւ�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�`�u5.1�`�����l���ł̓s���A�ȉ��Œ��������̂ł͂Ȃ��A�s���A�ȉ����̊��������̂Łu�s���A����v�����Ԃɓ���Ă��������i�j
�ł��̂�2�`�����l���͂`�u�A���v���g�p�����v�����C���A���v�Ńt�����g�X�s�[�J�[�����L���ăZ���N�^�[�Ő�ւ��Ă��܂��B
�������ŋ߂̂`�u�A���v��2�`�����l�����̉����͏����̂`�u�A���v���i�i�ɗǂ��������Ă��܂��B
�h���L�[�R���O�i������Љ��SHM-CD�͑S���m��܂���ł����B�����������҂ł�����܂����ˁE�E�E
�����ԍ��F8216423
![]() 0�_
0�_
�Ⴂ������ԉ�����A��X���ɂ��ӂł��B
�@���͎��������́u�ԉ�(�^�N�V�[�̉^�����)�v�ł��āA���N�ő��\���N�ڂ��}���܂����B
�@�I�}���}���낭�ɐH���Ȃ��O���~���[�W�V�����Ɍ�������I���W�̏������p���܂���
�@���o�u������̗]�g�ł�������|�Y�I�I���W�͐Q������E�ł���ɓ������A�Ƃ��Ԃ�
�@�S�Ĕ��蕥���ƌ����U�X�ȁu��N�v�ł����ˁB
�@���͔��\���z�����o�o�A�Ɓu��q�ƒ�v�ƌ������u�V�V���v�����O�̖����ł��B
�@���܂���炿�����������������̂��߂Ă��̋~���ƌ����u���y�v�ƌ����킯�ł��āB
�@�O�����ۂ������j�L�r�ʂ̍�����B��t�������Ă���̂����y�ƎԂł�����B
�@�����Ƃ��u�Ό��v�̋ɒn�̂悤�ȕt���������ł�����]���ʓI�ł͂���Ⴕ�܂���B
�@�F����ɂ͂�����ۂ����Q�l�ɂȂ�悤�Ȏ��͂���܂��A�^���b�̈�ɂ͂���
�@�Ƃ荇�_���Ă��܂��B
�@
�@
�@
�����ԍ��F8216473
![]() 0�_
0�_
�@����ɂ��́@->ALL�B�~�x�݂��I���A��������o�ł��B�x�߂�̂͗ǂ��Ƃ��āA�������Ȃ��Ɖ����o���܂���ȁi���j�B
�@���āA�h���L�[�R���OJr.����̏������݂ɂ���u���{�̃��[�J�[�͉��̈Ⴂ�͂��邪�A���������v�Ƃ����͎̂����ł��傤�B����͂����炭�u���̗L���v�Ƃ������A���{�̃��[�J�[�ƃ��[�U�[�̗������ׂ��Ă���u�z�肵�Ă���@��̎g�����̉�ꐫ�v�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�s���A�E�I�[�f�B�I��������e�R���|�[�l���g���Ƃɔ������낦�đΛ����Ē����AAV�V�X�e���������狏�Ԃɒu���ĉƑ��Ŋy���ށADAP�Ȃ��J-POP�Ȃǂ���y�ɊO�o��Œ��������E�E�E�E�Ƃ������X�e���I�^�C�v�̎g�p�@��������������l���Ă��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B���Ă�598�I�[�f�B�I�Ȃ�Ă��̍ł�����̂ŁA����F�̏d������@�����ׂĒ��B�I�����ǐF�C�̂Ȃ����Ɍ��������Ƃ��������Ƃ��A���̋^��������ꂸ�ɕ��Չ����Ă��܂��Ă��܂����B
�@���̓_�A�i���x�ł������܂����jBOSE�̃��[�U�[�ւ̃A�v���[�`�͍I�݂ł��ˁB���W�J�Z�݂����ȋ@�B�ŃN���V�b�N���ł��鉹���Œ�����A���邢��AV�V�X�e���ł����y��������E�E�E�E�Ƃ������A�]���̃I�[�f�B�I�}�j�A���炷��C���M�����[�Ȃ��Ƃ��^�ʖڂɃA�s�[�����Ă��āA����Ȃ�̎��т������Ă���̂ł�����B����w���������Y�t�H��9�����i���͎G���͂قƂ�ǔ����܂��A���̎G���̊H���܍�̑S�����ڂ��Ă��鍆�����͕K���w�����Ă��܂��j��BOSE�̍L�����ڂ��Ă��܂����B���̃I�[�f�B�I���[�J�[���������������G���ɍL�����ڂ��Ă���̂ɂ��ڂɊ|���������Ƃ�����܂���B���{�̃��[�J�[���u��`�̓I�[�f�B�I�G���ɍڂ��Ă�������B��ʂ̎G���ɍڂ��Ă��N���ǂ܂Ȃ��v�Ǝv���Ă���Ƃ���A�Ӗ��ȊO�̉����ł��Ȃ��ł��傤�B����ȃ��[�U�[�ɑ���Œ�ϔO���v���̋@�����������[�X���Ă��錴���̈�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��܂��B
����28��������said
����肢�����Œ��������ȂƎv�����u�Ԃ����
���s���A�I�[�f�B�I�ƌ�����̂ł͂Ǝv���܂��B
�@�܂��������̒ʂ�ł��B���[�J�[���f�B�[���[���u���ǂ����Œ��������Ǝv���Ă��郆�[�U�[�v�𑝂₷�w�͂����ׂ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F8218378
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ��͂悤�������܂��B
SHM-CD�u���b�N�ŕ�����ׂ�̌��T���v���[�v����͂���������
�����Ă݂܂����B�i�W���Y�ƃN���V�b�N��9�������Ȃ̂ŗ\�j
���ʓI�ɂ͂����̃V�X�e���ł͈Ⴂ���������܂���A����������
�����Ȃ��Ƃ������܂����i��j
��Ԏ��ɂ��������̐L�тɈႢ���������܂����B
�s���I�ƒe���ꂽ�A�R�M�̌��̉��̓����x���Ⴄ�悤�ȋC�����܂��B
�Ɩl�̏ꍇ�͂���Ȓ��x�̃��r���[�ł��A�\����܂���B
�ʏ�CD�ƂQ���g�݂ł��̒l�i�͂ق�Ƃ��肪�����ł��ˁA�y���߂܂��B
�N���V�b�N�ƃW���Y���͂��̂��y���݂ł��B
�Ⴂ������ԉ�����
���s���A�ȉ����̊��������̂Łu�s���A����v�����Ԃɓ���Ă��������i�j
�����������Ԃł��i�j
�f��ق̉�������ʒu�������Ẳ���ł�����ˁ`�A�����͂܂��`�r�B���������̂�
�o���邾���ʘH�̍ۂŁA������ɋ߂��Ƃ���őI��ł��܂��܂�����B
���u���������v�Č����邩�q���q������ł��B
�Ȃ��Ȃ������ȏ����ʼnf��͌���܂��A���ʂ������i�肬�݂ȏꍇ������܂��̂ŁA
�ƂŌ���f��̂ق������������Ӗ��ł͉f��ق��悢�Ǝ������Ă���܂��i�j
AV�A���v��HDMI�A�h���r�[�f�W�^���ADTS���̐��̗��ꂩ��P�O���N�g�p�������}�n��
AVX1000����\�j�[��DA3200�ɏ�芷���܂������A�QCH�̎��̉����ł͂܂��܂��̂Ă�����
�ł͂���܂���ł�����B�z�[���p�ł̓v�����C���͎g�p�������Ƃ�����܂���̂�
AV�A���v�̃v�����̑f���̑P�������͔��f�����˂܂����A�l�I�ɂ͂Ȃ���肠��܂���i�j
���Ԃ̂ق����̔�����P�O�N�������A���Ԃ�V�Ԃōw������悤�ȕς��҂ł�����A
�Ԃ��I�[�f�B�I���S�Ăɂ����Đl�Ə����Ⴄ���Ƃ���D���Ȑl�Ԃł���܂��B
�����ԍ��F8221503
![]() 0�_
0�_
�l�I���W����
�����͎��������́u�ԉ�(�^�N�V�[�̉^�����)�v�ł��āA���N�ő��\���N�ڂ��}���܂����B
�I�[�f�B�I�Ƃ��܂�W�Ȃ��b�ł��e�͂̒�
�����O�Ɍ�����p�߂�ׂɁA�~�����Ԃ͎��Ă܂���ł������^�N�V�[��Ђ̐�������̗F�B����
���p����u���[�o�[�h�����邩�炱��ɏ��ƘA�������茩�ɍs���Ƒ��s�����͊m��50���j���ł����B
�������邩��V�K�Ō������Đ����͉�����邩�畔�i�ゾ���o���Ƃ̎��ł����B
�F�B�H���A���������������Ă��邩����v�A�܂��܂�����ƌ����܂��̂ŏ�邱�ƂɌ��߂��̂ł���
�O���ɁZ�Z�Z�^�N�V�[�Ə����Ă���܂��B���ɊX�p�Ŏ���グ��ꂽ�獢��܂��̂ŁA�ǂ����傤����
�Y��ł����Ƃ���A���x�͓h�����K���̗F�B������K�ɑS�h�����������̂œh���ゾ���o���Ă���
���̑���d�オ��ɑ��ẴN���[���͖����Ƃ̏����Ńu���E���F�ɑS�h�����Ă��炢�܂����B
�������[�̃h�A�[���^�]�ȉ��̃��o�[�ŊJ���܂��̂ő��̗F�l�ɑ傤���ŁA�F�l�B�̗]���Ă���
���i�A�X�s�[�J�[�����A����ʊԂɎ��t���Ă���A�e�l���������Œ����āA���������������N�̎Ԃ��E�E�E
����4�N�O�����Ă��܂����B�R�����v���p���ł��̂ŗF�B����K�X�������͐�_���ƌ�����
�n���̃v���p���X�^���h�̏ꏊ�͊o���Ă����̂ł����A���{���ɉ��o�����Ƃ��̓X�^���h�̏ꏊ���킩�炸
�M���҂��̃^�N�V�[�̉^�]�肳��ɃX�^���h�̏ꏊ���܂��ƁA�ց[�I�v���p���ɏ�����I
�r�b�N������A�F����e�ɃX�^���h�̏ꏊ�������Ē��������������v���o����݂�����܂����B
�����ԍ��F8223015
![]() 0�_
0�_
�@������ ->ALL�B�������݁A���肪�Ƃ��������܂��B
�@���̂���̌����Ȃ��瑱���Ă������̃X���b�h�ł����A�������ݐ������������Ȃ��̂ɂȂ�A���낻��u�d���v�Ȃ��Ă܂���܂����B�g�s��Ƃ��ĉ����u�܂Ƃ߁v�݂����Ȃ��Ƃ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ƃ͎v����(^^;)�A�����ň�x�u���߁v�����Ǝv���܂��B
�@�����ŏ����A�[�e�B�N���X�V���x�܂��Ă��������A����A��ꕔ�́u���Õҁv��́u�W�]�ҁv�ɑ�����O�e�A���t���āu�G�k�ҁv�i�ȂႻ���j�̃X�����ĂɗՂ݂����Ǝv���܂��B�X�������肢�������܂��B
�����ԍ��F8231827
![]() 0�_
0�_
�@���������b�ɂȂ��Ă��܂��A�F����B
�@�O���������A�ȉ��̂Ƃ���Ɂu�V�E�������̃I�[�f�B�I�@��ƍ���̓W�]�v�Ƒ肵�āu���ҁv��ʂɗ��Ă����Ă��������܂����B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8281742/
�@��낵�����肢�v���܂�(^^)�B
�����ԍ��F8281749
![]() 0�_
0�_
�����A���i.com����ł͏��̃K���X��CD�̃��|�[�g�ł����ˁH^^
����Ƃ����|�[�g�ł��܂��B
�c�ƁA���|�[�g�̑O�ɂ܂��A����CD������������������ ��ԑ��Y���� �ɐ[�����\���グ�܂��B
��ԑ��Y����̂��A�ł��̗l�ȏ������݂��ł��܂����B
��ϋM�d�ȕi�����������������L��������܂����B
���āA�{��ł��ˁB
�uExtreme Hard Glass CD�v�ƌ����炵���ł����A98700�~�Ƃ����n���������i�Ŕ�������܂����B
�܂��A�ォ��20���Ȃ�Ă��̂��o�܂������炻��Ɣ�ׂ�}�V�����m��܂��c�B
�����J�ɒʏ��CD�ƃK���X��CD�Ƃ��Z�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B
����͗��҂̔�r�ׂ̈ł��ˁB
�u�ف[��A�����Ⴄ�ł���H�v�Ɛ�`��������ł��ˁ`(��)�B
���ۂɔ�r���Ă��o�C�i�����x���ň�v����̂ŁA�M�����x���ōw���҂��o�������l�Ȑ^���͂��Ă��Ȃ��l�ł�(��)�B
���݂ɗ]�k�ł����AWindowsMediaPlayer�ōĐ��������A���f�B�A���Ȃ��ł����̂ŁA�N��CDDB�ɏ����ĂȂ��݂����ł�(��)�B
������A���A�ȕ��Ȃ�ł��ˁc�B
(��������PC�̃h���C�u�ʼnl�����Ȃ��H^^; )
�Ƃ肠�����A�����ʂƓ����A�����ɂ��ĊȒP�ɏ����Ă݂����Ǝv���܂��B
(���߂�Ȃ����A�S�R�ȒP����Ȃ��Ȃ���������c(�ꊾ)�B�S����3����������ގ��Ɂcorz )
�@�@�@��2�`3�y�[�W�ڂ͏d�������e�����m��Ȃ��̂Œ���!!
�E�����
��Ɏ������u�ԁA�u�d�����v�c�ƌ����������ł����B
��ԑ��Y����ɁuCD�K�i���H���Č������M���M���H�v���Ċ����̎����Ă��܂��܂����ˁc�B
����33g�ł�����ق�܂ɃM���M���ł���c�B
�������A������炢��ۂ�����܂����B
�Â����h�C�c��CD�̓G�b�W�������Ă��āA���������镨�ł����A����Ǝ�����ۂ��܂����B
�E����
�m���ɉ����ׂ����ł��B���x�͊m���ɍ�������܂��B
�������������������̂̓m�C�Y������������������ł��傤�B
�܂��A���������ۂ��ł��ˁB
�̂̋����ˑw��CD-R�����CD��f�i�Ƃ����܂��c���A�����ˑw�̕��̕����ۂ��Ǝv���܂��B
�d�������D���ȕ��ɂ͌����Ȃ��ł��ˁB
�����c
![]() 3�_
3�_
�����ł��B
�E����
������͕ςȂ�ł���ˁB
CD�̓����𑪒肷�鎞�ɁA�K���X���̕��Ɉ�a�����c�B
�g���b�N�ւ̃A�N�Z�X���Ԃ������̂ł��B
���̎��_�ł��Ȃ茙�ȗ\�������܂����c^^;
(��������O�ɔ������Ă����̂͂��������������� ��ԑ��Y���� �����Ō��Ă��܂�)
�Ƃ肠�����A���茋�ʂ̉摜��Y�t���Ă����܂��B
����2���ʏ�ՁA�E��2���K���X��CD�̕��ł��B
�ȉ��̒l��C1�G���[�̐��������Ă��܂��B
���AC2�ACU�G���[��1������܂���ł����B
(����Βv���I�ł����c^^; )
CD�̃f�[�^��(����)
MSF 69:09:25
LBA 311200
�ʏ�Ղ�C1�G���[�̐�
Avg / Sec 0.5
Max / Sec 20.0
Total 1973.0
�K���X��CD��C1�G���[�̐�
Avg / Sec 2.8
Max / Sec 22.0
Total 11433.0
���ʓI�̓G���[���[�g�Ɋւ��Ă͈��|�I�ɒʏ�Ղ̕����ǂ��ł��B
�ł��A������͑��Ɣ�ׂ�Əd�v�ł͂���܂���B
�����A���̍��͍����ł����c^^;
(�ł��A������C1�G���[�ʂȂ�ǂ��ɂł��Ȃ�܂�)
Beta(�Ԑ�)������ƃK���X���̕���������A0.00�̃��C�����痣��Ă���̂�����܂��B
����̓K���X���̕��������I�ɂ͕s���Ȏ��������Ă��܂��B
�������A���K���X���A����ɂ͋�����ł����ˁB
�悭����ƁA�����ƊO���̍������Ȃ���ł��B
�ʏ�Ղ�����ƁA���X�ɉ������Ă���̂�����܂��B
����͓����ƊO���œ������Ⴄ���������Ă��܂��B
���̓_�ɂ����Ă̓K���X���̕����ǂ������ł��B
Jitter(��)�͂��̃O���t�����ł͎c�O�Ȃ����r���ł��܂���B
���i.com����́uPremium2�v�̃��r���[�ł��L�ڂ��Ă��܂����A���̃O���t�͑��Βl�ɂ�鑪�茋�ʂȂ̂ŁA�Ⴄ�Փ��m�ł͔�r�ł��܂���B
�����A���̃O���t����������ƃK���X���̕������R�Ȃ̂�����܂��B
��͂�A������̃O���t���K���X��CD�̕������O�����̓����������������������Ă��܂��B
���ꂾ���ł͍���̂ŁA�W�b�^�[���[�^�[���g������Βl������s���܂������A�卷�͂���܂���ł����B
�C�����A�K���X���̕����Ⴂ�̂ŁAJitter�Ɋւ��Ă̓K���X���̕����ǂ��ƌ����܂��B
�Ƃ���ŁA����Bata��Jitter�͏������܂�Ă���f�[�^�Ɉˑ����Ă���A�f�[�^���ω�����ƍ����o�܂��B
�]���āA���ꂼ��̋Ȑ������Ă���̂̓f�[�^���������A���Ȃ莗�Ă��邩��c�ƌ����܂��B
(���ۂɓ������������͖`���ŋL�ڂ��Ă��܂���)
����ł́A�f�[�^�̔z�u���ς������ǂ��Ȃ�˂�H���Ď����l����킯�ł��B
�����ŁA�ȏ���S�ċt�ɂ���CD-R���쐬���Ĕ�r���鎖�ɂ��܂����B
���̃O���t�̌��ʂ��Ղ̕����I�����ɂ����̂Ŗ����̂ł���A�Ȑ��̌`����G�c�ɂ͍��E�t�ɂȂ�͂��ł��B
(����������ƌ����ƁA�Ȃ��Ƃɐ�\�肷��قړ����Ȑ����ł���͂�)
�t�ɁA���������̉e�����傫����A�Ȑ��̌`�����E�t�ɂȂ炸�Ⴄ���ɂȂ�����A���Ǝ��Ă����肵�܂��B
(���Ǝ�����Ď��͔Ղ̓��������Ă�����Ď��ɂ��Ȃ�܂���)
�����ɂ͑��z�U�d����CD-R�̑I�ʕi�𐔖��A���p���܂����B
����̗ǂ����̓��b�g�������Ȃ��c�ƌ������ł��B
�c�ƌ����Ă����܂�͂����ďĂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�D�G�Ȍ��ʂɂȂ邩�͕ʖ��ł���^^;
�ł��A���Ȃ��Ƃ����̔�r�͂��Ղ��ł��B
(�F��ȈӖ��ŃR�X�g���L�c�C�̂ŋ����Ăˁc^^; )
���āA���ʂ����\���グ�܂��ƁA�����ƊO���ŋɒ[�ȍ��͌����܂���ł����B
�]���āA��ɓY�t�����O���t�̓����ƊO���̍��̓f�[�^�ɂ�镨�Ƃ͍l����A�����I�ȓ����ւ̈ˑ��x�̕����������Ǝv���܂��B
�܂Ƃ߂�Ƃ���Ȋ����ł��B
�E�K���X��CD�͓����ƊO���̕��������̍������Ȃ�
�ECD�̓ǂݎ��G���[������
�EJitter�͋͂��ɏ��Ȃ��Ȃ�A���萫�������ǂ��Ȃ�
�X�ɑ����c
�����ԍ��F7825825
![]() 2�_
2�_
�����ł��B
�E�����A���]��
�ʏ�Ղ�CD�͏�Ԃ������ł��B
��ʓI��CD�Ɣ�ׂē���������ȉ��ł��傤�B
�ю����Ă���͕̂��ʂł��̂ŁA����������ɐÓd�C�̏����A�}�C�i�X�C�I���̏Ǝ˂����čēx�Đ����Ă݂܂����B
���ʁA���ρc^^;
���Č������A���̗��x�ȊO�̓K���X��CD���ǂ������I���ăI�`��^^;
(���̕ӂ�̊��z�͂�ԑ��Y����Ɋ��ҁ�)
�܂��A��ʓI��CD�����ꂾ���Ő����ω�����̂ł����A���̕ω��ʂ��傫�����ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B
�قȁA�K���X��CD�͂ǂȂ���˂���Ď��ɁB
�Ód�C�ɂ͗��ɋ����݂����ŁA����ɑ���ω��͏�������ۂł��B
�������A�C�ɂȂ����̂��ю��ł��B
�ʏ�Ղ�CD���ł͖����ɂ���A�ω������Ȃ��炸����̂ł��B
�������Ă��瑽���̎��Ԃ��o�߂��Ă��܂�����A��c�ł���Ζڂ��҂�̂ł����A���̍��͂��ꂾ���Ƃ͎v���Ȃ�!!
�����炭�A�������Ď茳�ɓ͂������_��100%�̃R���f�B�V�����ł͂Ȃ��c�ƌ��������ł��傤���B
�S��Ȃ炻�����������肵�ė~�����c�Ǝv���Ă��܂��܂����B
��{�I�Ɏ��Y�ł�����A������������`�����X�͖����͂��ŁA�������ʎY�Ƃ͑S�R�Ⴄ�͂��ł��B
�������A����ł��ю����Ă���c�ƌ����͖̂��A�����Ǝv���܂��B
�����Ȃ�A�V�D���o���Ă̎����ɋ�s�ł��������낵����A���ɐ܂�ڂ��������C��(��)�B
���������A���ɗ��Ă邼!!�c���Ċ�����^^;
CD�͒��߂Ă���̂ŁA����ł��ǂ��Ǝv���܂����A98700�~���20���~���o���āA���̌��ʂ��Ɨ]��ɖ��c�ł��B
�����͊����Ɏd�グ�ė~���������ł��ˁB
(�������ӌ����Ǝv���܂����A���ꂾ���̋��z�𐿋�����Ȃ炻��Ɍ������d����������I�ƌ��������ł�^^; )
����Ƃ����ЂƂA�C�ɂȂ����̂��G���[���[�g�ł��ˁB
���܂�ɂ��G���[�������̂ŁA�Z�p�I�ɖ����n�ƌ������A�����x���Ⴂ�ƌ������c�B
�ǂ����݂�����Ȃ���ۂ�����܂��B
�v���[���[�Ƃ̑������c�Ƃ��v���܂����̂ŁA��������A���ɂ̓K���X�������Y�𓋍ڂ����@��œǂݍ���������̂ł����A���܂�ω��͂���܂���ł����B
�K���X��CD�����̂ł���A�����Ɨ��荞�ޕK�v�����肻���ł��B
CD�̃e�X�g���f�B�A�ɂ��K���X�����g����������̂ł�����A������ɍ��킹�������ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���c�B
����ɂ���A���̃K���X��CD���ʂȂ�_�C���N�g�J�b�e�B���O��SACD�̕����K���ɂȂ��Ǝv���܂��B
����ȋ����邩�[!!���ĕ���SHM-CD�ŗǂ����Ɓc^^;
�܂��A�K���X��CD�Ƃ������z���͈̂�T�Ɉ������Ƃ͌����܂��A���Ȃ��Ƃ�1st���f���ł��邱��CD�͍��i�_�c�Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B
����CD-R�ʼn��������ڎw���ďĂ���������܂����A���ɃK���X��CD�ɂ͏���������č~�Q����\��ł����B
�������A�c�O�Ȃ��炱��ł͍~�Q�ł��܂���B
���̂܂܂ł͏I��点�Ȃ�����Ɋ肢�܂��B
�Ƃ肠�����A�����_�ł�98700�~�̉��l�͂���܂���I(�c�Ǝv��^^; )
�E�Ō�Ɂc
20���~�̃K���X��CD�͋Z�p�I�ɂǂ��Ȃ̂�?!
�C�ɂȂ�܂��ˁ`�B
�c�ƌ������ŁA�N���݂��ĉ�����(��)�B
���ꂩ�����Ă��ĉ������B�@�������܂������c^^;
�ȏ�A�����ʕ�(�Y���H)�ɂ��t���������������L��������܂���m(_ _)m
�����ԍ��F7825843
![]() 4�_
4�_
�v���N��D��!!����@���v���Ԃ�ł�
�����l�ł�
�M�d�ȃ��|�[�g�L��������܂�
�����́A���̃X���Ŋ�������Ȃ̂ŁA�S�R���C�ł����i��
���Ȃ݂ɁA
�h����������ɐÓd�C�̏����A�}�C�i�X�C�I���̏Ǝˁh
���Ăǂ�����Ă���̂ł����H
SFC�@SK-EX
���Ăǂ��Ȃ�ł�����
����ɂ��Ă��A������M�A�����v���܂�
�����ԍ��F7826069
![]() 1�_
1�_
�K���X����CD�͌������Ƃ��G�������Ƃ�����܂��A���ʂ͒ʏ�̂��̂ɔ�ׂĂǂ��Ȃ̂ł��傤���H
�Ə����̂��A��̂̌o���ł����A�\�j�[��CD�v���[���[�ŃV���O��CD(8cm CD)���Đ��������Ƃ��ɁA�m�C�Y���N���������Ƃ�����܂����B���������AFM���W�I�̎�M�����������ŁA�Ȃ͕������邯�ǁA�Ƃ���ǂ���ŃU�[�U�[�ƃm�C�Y������悤�Ȋ����ł����B(�{�����[�����ƂĂ�����������ƕ�����Ȃ��Ȃ�ʂ̌y���m�C�Y�B)
�����A���\���قǔY�̂ł����A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ�����CD�v���[���[���V���O��CD�ɑΉ����Ă��Ȃ����������ł���(�V���O��CD���o���Ă̍��ł����B)�B12cm�ɂ���A�^�b�`�����g��t����Ɛ���ɍĐ��ł��܂����B
�A�^�b�`�����g�́A�f�B�X�N�C����F�������邽�߂̔��˖������邱�ƂƁA�f�B�X�N�̎��ʂ𑝂₷���߁A�Ƃ���2�̋@�\�����Ȃ��͂��ł����A�m�C�Y�͌��ǂ̓f�B�X�N�̎��ʂ����ɋN��������̂ł��傤�B�X�s���h�����[�^�[�̃h���C�u���y���V���O��CD�ɑΉ����Ă��Ȃ������ŁA�ǂݎ��G���[���N���Ă����悤�ł��B
�K���X���ł͋t�ɏd�����Ė��ɂȂ��Ă���A�Ƃ����\���͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F7826089
![]() 1�_
1�_
�� ��Ɏ������u�ԁA�u�d�����v�c�ƌ����������ł����B
�� ��ԑ��Y����ɁuCD�K�i���H���Č������M���M���H�v���Ċ����̎����Ă��܂��܂����ˁc�B
�� ����33g�ł�����ق�܂ɃM���M���ł���c�B
���݂܂���B���ʂɂ��ẮA���łɏ�����Ă���܂����ˁB
�����ԍ��F7826121
![]() 1�_
1�_
������A������^^
�����Ȃ�ł��B
�����܂���A���߂��ēǂނ̂���ςł����(��)�B
�V���O���̌��͏d�����y�߂��ău�����o�铙�̗v�����Ǝv���܂��B
���ہA�d�߂���Ƃ��y�߂���Ƃ��������������Ńm�C�Y�≹��т��N����\���͂���܂��B
����ƐV�i�̋@��ł͋N�����ł����A�@��̗��i��ł���ƏǏ���铙�̎�������܂��B
�܂��A������̗�̑Ή����Ă��Ȃ��c�Ƃ����͎̂d�������ł����c�B
�����ԍ��F7826219
![]() 1�_
1�_
�v���N��D��!!����A�͂��߂܂��āB
�����ACD�̃f���v���P�[�V�����Ɏd���Ŋւ���Ă����̂ł����A
�K���XCD�̉\�͕����Ǎw�����ꂽ���͏��߂Ăł��B
�ŁA�ЂƂC�ɂȂ��Ă���̂ł����c
���茳�́u�K���XCD�v�A�ʎY�p�̃X�^���p�[�̃K���X�E�}�X�^�[�ȋC�����܂��B
���m�Ɍ����ƃK���X�E�}�X�^�[�����m�ɍ쐬����Ă��邩�e�X�g�Ɏg�����̕��ł͂Ȃ����Ɓc
���ɔq���ł������������̂ł����A�ڕ���33g�ƃG���[���[�g����Ђ���Ƃ�����Ǝv���A
���z�Ȃ��������ł�����A�����̗\�����O��Ă��邱�Ƃ��F��܂��B
�O�̂��߁u�K���X�E�}�X�^�[�v�u�X�^���p�[�v�Ȃ���̂��ȒP�ɐ������܂��Ɓc
���݂�CD�̐������@��i������́j�}�X�^�����O��@������������̂ł����A
80�N��㔼����嗬���߂��ł��I�[�\�h�b�N�X�Ȑ������@���X�^���p�[�ɂ��ˏo���`�ł��B
�X�^���p�[��CD��ʎY����ۂ̃|���J�[�{�l�[�g�m�����ˏo���^�p�̋��^�ł��B
�ˏo���Ďʂ����W�ŁA�s�b�g�͐��i�̋t�A�܂艚�^�ɂȂ��Ă܂��B
�X�^���p�[�삷��ۂ̌����܂��Ɂu�K���X�E�}�X�^�[�v�ł��B
�X�^���p�[�Ƀs�b�g�����ނ��߂ɐ��i���l�A�s�b�g�͓ʂɂȂ��Ă��܂��B
���Ȃ݂ɃX�^���p�[���̂͑ϗp���x������̂ŃK���X�}�X�^�[�ŕK�v�ɉ����čĐ��삵�܂��B
�K���X�E�}�X�^�[���s�b�g���ɉ��炩�̃o�b�N�R�[�g�i���i���ƃA���~�����j����Ή����o���܂��B
���Ȃ݂�CD��ʎY�����ۂ̍H�Ɛ��i�Ƃ��Ă̐��i�`�F�b�N���ڂ�20���܂����A
���ɂ��莝���̃K���XCD���K���X�E�}�X�^�[���̂��̂��ƁA���Ƃ��Ƃ��`�F�b�N���ڂ�NG���ł܂��B
�H�Ɛ��i�Ƃ��Ẵ`�F�b�N���ڂ́u�������ǂ��v�����������͕ۏ�����̂ł͂���܂��A
�c�O�Ȃ���u�H�Ɛ��i�̃N�I���e�B�͎������킹�Ȃ��v�ƌ��������Ă��܂��ėǂ����Ǝv���܂��B
��]���͐��i�������Ȃ��Ǝv���܂����A�����܂ł��X�^���p�[�Ƀs�b�g�����ނ��߂̕��ł�����A
���[�U�[���̕Ό����ɔ����ǂݏo���G���[��W�b�^�[�͐��i�����\����ł��B
�]�k�������ł����A
CD�́u�s�s�`���v�Ɗ����郂�m�i���ɉ������P�A�N�Z�T���[�j�͂������������ł��ˁB
CD�������̐��i�`�F�b�N���ڂ̃f�[�^���u�����v�Ƌ����Ɍ��т���X��������܂����A
�`�F�b�N���ڂƉ����ɖ��m�Ȉ��ʊW�����鍀�ڂ̕������Ȃ��Ƃ��m��u���������B
���Q�l�܂ŁB
�����ԍ��F7828354
![]() 3�_
3�_
redfodera����A�����́B
���߂܂��āB
�R�����g���������L��������܂��B
redfodera����̗l�ȕ��ɏ�������ł��������������ł��������b�オ����܂���
�K���X�}�X�^�[�ƃX�^���p�[�̘b�͒m���Ă��܂������A�����������������������̂ŁA���f�ł��܂���ł����B
���������\���͊m����0�ł͖����ł��ˁB
�ڎ����f�ł��Ȃ������ɂ������肵���R�����g���ł��܂���(��)�B
>���z�Ȃ��������ł�����A�����̗\�����O��Ă��邱�Ƃ��F��܂��B
�����A�\�z�ʂ肾�Ǝv���܂���H^^;
�������\���^�I�ł�������A�V���b�N�Ȃ�Ă�����ۂ���������܂���(��)�B
(�������҂�����ǁA�댯�ȓ����̕��������ł�����ˁc^^; )
���Z����(���Ԃ���Ȃ��c^^; )�ł��Ԃ����Ă��܂��܂����̂ŁA������̂��o���҂������Ǝv���܂����A������������A�g��ʐ^���A�b�v���Ă���邩���m��܂���B
(�ˁ[��ԑ��Y����H(/ ^^)/ ���Ă���H�w�����Ă������H(��) )
�ʐ^�ł����f�ł��܂����ˁH
�]�k&�����ɂ��Ăł����A�����������ڂƉ����Ƃ̑����ɂ͋^�₪����܂��B
�����ɓ����Ɖ����ɂ��Ă̑����ɂ��Ă̘_�����͌�����������܂��A����m�Ɍ�����Ƃ�����܂��c�B
�܂��A�A�N�Z�T���ɂ��Ă͑S���ʖڂł͂Ȃ��ł����A�ʖڂȂ̂����X����̂ŕ|���ł��ˁc�B
�����ԍ��F7830716
![]() 1�_
1�_
�v���N��D��!!����A����ɂ��́B
���ʐ^�ł����f�ł��܂����ˁH
�y���Ɂu����������v�ƃR�����g���܂������������܂��B
���L�̗��R�Ŗڎ��ł͊m�F�ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B�\����܂���B
�K���XCD�ɂ��������̍��ł���Ă���Ȃ�ʐ^�ł����f�ł���\��������܂��B
���i�ԍ��i�^�C�g��No.�j�̑��Ɍ����ی��ړI�Ƃ��Đ������i�H��j����肷�鎯�ʃR�[�h���`���Â��Ă��Ă܂��B
���炭�A�W�A���Ⓦ�������Ɨ\�z���܂����A�ӎ��I�Ɏ��ʃR�[�h�Ȃǂ��B�������肷�郂�m������܂����A
�i��ʕ��ރR�[�h�Ȃǂ��Ȃ��āj���ʃR�[�h�̈ꕔ�����ł���Ă��Ȃ��P�[�X���l�����܂��B
�v���N��D��!!����́A���āu�K���XCD�v��NEC�������Ă������Ƃ������m�ł��傤���H
10�N�ȏ�O�ɂȂ�܂����A���̍ۂ͕����ɋZ�p�����̈ꕔ���Y�����Ă��܂����B
����A��������2�Ђ���̕����̓��[�t���b�g�I�Ȃ��̂Ŏc�O�Ȃ���Z�p���������\����Ă��܂���B
����2�Ђ̂��̂�NEC�ƋZ�p�I�ɊW�����邩������܂���̂�NEC�̃K���XCD�ɂ��Ă͐G��܂��A
�l�I�ɂ́A�D�ꂽ�i����W�Ԃ��鍂�z���i�ł�����u��Ɣ閧�v�Ńu���C���h����͔̂@���Ȃ��̂��Ɗ����܂��B
���[�J�[�ƃf�B�X�g���r���[�^�[�Ƃ�����ƃX�^���X�̈Ⴂ�Ȃ̂��ȂƂ��v���܂����A
������ƋZ�p��������Δ[�����čw��������������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������������ڂƉ����Ƃ̑����ɂ͋^�₪����܂��B
�K���XCD���炿����ƒE�����܂����A��낵�������炨�t�������������B
�u��������A�̃f�[�^�l��������������S/N����dB������v�Ƃ�������̐��ɊF������҂���܂����A
���\�Ȍ����������܂��ƁA���f�B�A�́u�f�[�^�⊮�@�\�v�������čĐ����ɂ͖��m�ȕs��Ō��o���Ȃ����Ƃ������ł��B
�܂��A����`�F�b�N�O���[�h�����ΐ��i�ƔF�肷��u�H�Ɛ��i�v�Ƃ��Ă̐�����̎���w�i�ɂ���܂��B
���ăt�B���b�v�X��DAC�p�̃`�b�v�ŃO���[�h�ʂ̐��i������܂����B������ɂ��Ă݂܂��傤�B
����͐��i�Ƃ��Đ��\��ۏ���ۂ̃N�I���e�B�Ɛ�����́u�����܂�v�̊W���̂܂܂ł��B
�`�F�b�N�O���[�hS�j���ł�������������Ƃ��ĉ���5�i�K�z�肵�Ă݂܂��B
�O���[�hC�j�����i�Ƃ��Ẵ{�[�_�[���C���ł��B
�`�F�b�N�O���[�h���������Ȃ�ɂ�āA������N���A���鐻�i�̔䗦�͒ቺ���Ă����܂��B
S)�@�g���v���E�N���E��
A)�@�_�u���E�N���E��
B)�@�V���O���E�N���E��
C)�@�������i�i
D)�@�����s�K��
�{���A�O���[�hC�j����̂��̂͑S�Đ��i�Ƃ��Ă̔F��ł�����̂ł����AC�j��S�j���ʂ����ē����ł��傤���H
���i�����Z�����Ƃ����ړI�̂��̂ł����A�t�B���b�v�X�͌����Ȋ�Ƃł����琫�\�ʂɋ�ʂ��v���~�A�����̔����܂����B
CD�̗ʎY�ł�REDBOOK���K�肷��`�F�b�N���ڂ��N���A�����C�j��S�j���S�������Ɣ��f���Ă��܂��B
�f�[�^�⊮�@�\�ƁA�����܂��Ȑl�Ԃ̒����ɏ������Ă���A�ƌ����ׂ����Ƃ�������܂���B
�����ԍ��F7831399
![]() 2�_
2�_
redfodera�����
�ʐ^�ł͔���Ȃ��\��������܂����c�B
����A�܂��d�������ł��B
�s�b�g�ƃ����h��������킯����Ȃ��ł���(��)�B
(�́A�����������@���Ȃ����l�����Ȃ��c�B�l�ł͂�����Ɓc)
NEC����̒����K���XCD�͑ϗp�N�������Ȃ蒷�������L�����c^^;
���ǎ��p�����ꂸ�ɏI��������̋Z�p�ł����ˁB
>�u��������A�̃f�[�^�l��������������S/N����dB������v�Ƃ�������̐���
>�F������҂���܂����A���\�Ȍ����������܂��ƁA���f�B�A�́u�f�[�^�⊮�@�\�v��
>�����čĐ����ɂ͖��m�ȕs��Ō��o���Ȃ����Ƃ������ł��B
�����ł��ˁB
��ʓI�Ɍ������J���܂���c�B
�f�[�^�⊮�@�\�����[�_�[���̐��\�@���ɂ���Ă����������o�Ă��܂��܂����c�B
DAC�`�b�v�̏ڍׂȏ��A�L��������܂��B
���i���x���ő�R�̕����I�ʂ���Ă���͈̂ӎ����Ă��܂������A��Ƒ��̗���ł̋�̓I�ȗ�͏��߂ĕ����܂����B
(�o�[�u���E�������OP�A���v�̗l�Ɍ^�ԂŔ���Ɨǂ��̂ł����c)
���̗l�ȒE���ł���Α劽�}�ł���
REDBOOK���ċK�i�Ƃ��Ă͒��ߕt�����Â��C�����܂��ˁc�B
���i�ȏ�̕����傫���Ǝv���܂��B
CCCD�̗l�ɒv���I�ȈႢ����������A�����ł��Ȃ��c�Ȃ�Ď��͖����C�������ł���ˁB
�ߋ��Ɋ���̃v���XCD-DA�ŐV�i�ɂ��ւ�炸�A�G���[�����o����Ⴊ�������肵�܂����B
���������̂ł����Ȃ����S���t���Ă��܂���ł�����Q���Ă��܂��܂���c�B
>CD�̗ʎY�ł�REDBOOK���K�肷��`�F�b�N���ڂ��N���A�����C�j��S�j���S�������Ɣ��f���Ă��܂��B
>�f�[�^�⊮�@�\�ƁA�����܂��Ȑl�Ԃ̒����ɏ������Ă���A�ƌ����ׂ����Ƃ�������܂���B
�����ł��ˁB
�l�Ԃ̎����獷���ʂŃX�y�b�N�����܂�ɈႤ��ł���ˁB
���o������REDBOOK�̗�Ɠ����x���ł���B
2��ނ̉��𐔉����āA����������{�^���������Ȃ�Č������@�͔n�����Ă��܂��B
�ł��A���ꂾ���ĕ��ʂɒ��o����������l�ԂƂ��Ă̍Œ���̃X�y�b�N�̓N���A���Ă�����Ĕ��f�Ȃ�ł��傤�ˁB
���y���l�ԂƂ��ẴX�y�b�N���������Ă���킯�ł͂Ȃ��ł�����A����ŗǂ��̂ł��傤���c�B
�ł��A���ꂪ�l�Ԃ̎��̞B�����̔F�m�x�������錴���ɂȂ��Ă���Ǝ��͎v���܂��B
(CD�̉��̍�������c�Ƃ����F�m�x���Ⴂ�̂������l�Ȍ������Ǝv���Ă��܂��c)
�����ԍ��F7831968
![]() 2�_
2�_
�v���N��D��!!����A����ɂ��́B
��DAC�`�b�v�̏ڍׂȏ��A�L��������܂��B
�����i���x���ő�R�̕����I�ʂ���Ă���͈̂ӎ����Ă��܂������A
����Ƒ��̗���ł̋�̓I�ȗ�͏��߂ĕ����܂����B
��(�o�[�u���E�������OP�A���v�̗l�Ɍ^�ԂŔ���Ɨǂ��̂ł����c)
16bit�̃`�b�v�ŁuTDA1541A�v�ł��B
���̕W���K�i�i���܂߂�4�O���[�h�̐��i������܂����B
�g���v���E�N���E����R1
�_�u���E�N���E����S2
�V���O���E�N���E����S1
���ۂɃ`�b�v�̕\�ʂɉ����}�[�N���O���[�h�̐������v�����g���Ă��܂����B
�R��ނ��r�����ʐ^��������܂���ł�����WEB�Ō�������Ƒ����̏�����܂��B
����DAC�p�Ɍ��݂��_�u���E�N���E�����炢�܂ł͓���ł���l�ł��B
���ߋ��Ɋ���̃v���XCD-DA�ŐV�i�ɂ��ւ�炸�A�G���[�����o����Ⴊ�������肵�܂����B
���f�[�^�⊮�@�\�����[�_�[���̐��\�@���ɂ���Ă����������o�Ă��܂��܂����c�B
���Ɂu�����v�Ō�����Ă��܂����A����������CD�Ōo�����Ă܂��B
�����̂ɂȂ��TOC����ǂ݂ɂ����Ȃ��̂Ńf�[�^��E�⊮�����������̂ł͂���܂���B
�f�[�^�⊮�\�̗͂D��ׂĔ�r���悤�Ƃ����C�͑S������܂��c
�v���C���[���̃`�b�v�Z�b�g�Ńs�b�g�̓Ǒ֏�������V���v���Ȃ��̂ƁA
�\�t�g�E�G�A��Ǝ��A���S���Y���ŏ�������̂ł͉��炩�̍��������Ă��s�v�c����܂���ˁB
��REDBOOK���ċK�i�Ƃ��Ă͒��ߕt�����Â��C�����܂��ˁc�B
���ꂱ����U���Ȏ����ɂȂ��Ă��܂����k�ł����c
���́A�N�w�Ƃ������X�^���X�̈Ⴂ�Ɨ�������悤�ɐS�|���Ă��܂��B
�u��`�͂��邪�K������킯�ł͂Ȃ��v���̂䂦�g����߂�Ǝ����߂��h�����܂������A
�s���S���K�����ėאڂ��郁�f�B�A�̋K�i�iCD-ROM�Ȃǁj�Ȃǂ����܂�Ă��ꂽ�Ɗ����܂��B
CD-DA�Ɍ����Ă݂Ă��c
�A�[�e�B�X�g��쑤��16bit�ւ̃_�E���R���o�[�g�ł����16bit���t���Ɏg����悤�ɂȂ�A
���y���I�[�f�B�I�E�t�@���͍����T���v�����O�E���[�g�ւ̃��T���v�����O�Ƃ������b������܂����B
��ƊԂ̑��S���������^���f�B�A�K�i�Ƃ̍ł��傫�ȍ��ق́u�K���ƌ��v�ɑ���N�w�v�������Ǝv���܂��B
�b��߂��܂��ƁAREDBOOK�g����߂́u�K���XCD�v���ǂ��Ǝv���܂��B
�����ē��X�ƃ��[�U�ɏ���`���Ă����c�ł����B
�c�̂����Ȍ����Ő\����܂���<(_ _)>
�����ԍ��F7832714
![]() 2�_
2�_
redfodera�����
>16bit�̃`�b�v�ŁuTDA1541A�v�ł��B
���[�A�����L���ȃ`�b�v�ł���^^
�m���Ɏ�ނ�����܂����ˁ`�B
���i�̑I�ʂ̍ۂɌ����L��������܂��B
(DAC�̎���̎��Ɏg�����������āc���Ǒ��̕��ɕ��C���c^^; )
>���Ɂu�����v�Ō�����Ă��܂����A����������CD�Ōo�����Ă܂��B
>�����̂ɂȂ��TOC����ǂ݂ɂ����Ȃ��̂Ńf�[�^��E�⊮�����������̂ł͂���܂���B
����c�B
��͂�o�����Ă����łł������B
���̏ꍇ�A�h���C�u����R����̂ŁA���ꂼ�ꓯ���Ղ��Ĕ�r���鎖���ł�����ł��B
�킴�Ə���t������A�y���ŗ����������肵��CD-R�⌳�X�f���̈����Ɣ����Ă���CD��I��ŁA�F�X�ȃh���C�u���g���ă��b�s���O�����ł��B
���ʁA�ʖڂȂ̂͂Ƃ��Ƃ�ʖڂŁA�ǂݍ��ݔ\�͂̍��ق����Ȃ�o�Ă��܂��B
�h���C�u�Ɍ��炸�A�v���[���[�ɂ�C1�G���[�̌��o�ƒ����\�͂��������̂��������肵�āA���ׂ�Ɩʔ����ł��B
>�u��`�͂��邪�K������킯�ł͂Ȃ��v���̂䂦�g����߂�Ǝ����߂��h�����܂������A
>�s���S���K�����ėאڂ��郁�f�B�A�̋K�i�iCD-ROM�Ȃǁj�Ȃǂ����܂�Ă��ꂽ�Ɗ����܂��B
�m���ɁA���F�{����R����܂�����ˁ`�B
����Part ?�݂����Ƀo�[�W������������肷����̂܂ŏo�ė��邩�琫���������ł��B
�܂��ACD-ROM�K�i�͒����@�\�����Ȃ苭�͂ł�����܂Ƃ����Ǝv���܂����ACD-DA�K�i�ɂ͑S�R�����܂���ˁcorz
����A��ϖʔ������b���ł��ėǂ������ł��`��
�����ԍ��F7832844
![]() 1�_
1�_
�v���N��D��!!����A
�����炱���A�����J�ɗL���������܂��B
���m���ɁA���F�{����R����܂�����ˁ`�B
������Part ?�݂����Ƀo�[�W������������肷����̂܂ŏo�ė��邩�琫���������ł��B
���w���f�B�A�S�ʂɓn���ĂƂĂ����ڂ����ł��ˁB
���͊����c�Ƃ̕��ʂȂ̂ŋZ�p���̂��̂́u�������b�̎��藝�_�v����̕��n�ł��B
���h���C�u�Ɍ��炸�A�v���[���[�ɂ�C1�G���[�̌��o�ƒ����\�͂��������̂��������肵�āA���ׂ�Ɩʔ����ł��B
���_�����ł͂Ȃ��F�X�Ǝ��H����Ă��邱�Ƃɂ��h�����܂����B
�d���ŌW����Ă���҂�����ڂ����ł͋�������ł��ˁA���Ȃ�����ł��B
������A��ϖʔ������b���ł��ėǂ������ł��`��
�����炱���A�ƂĂ��L�Ӌ`�ȋ@������ӂ��Ă܂��B
�܂��F�X�Ƃ��b����i�ǂ߂�H�j�@����y���݂ɂ��Ă���܂��B
�����ԍ��F7833033
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ���@�@������(^-^)/
�v���N��D��!!����A���v���Ԃ�ł��B
�}�j�A�b�N�ȃ^�C�g���ɖ�����āA�`���ɂ��܂������`(^-^)/
����A����J���܂ł��B���\�A�ǂ݉�������܂�����B
�E�E�����K���X��CD�͂ǂ�ȉ����A�����Ă݂����ł��ˁB
redfodera����
�X�^���o�[�Ȃ�Č��t�A���߂Ēm��܂�����A���ɂȂ�܂��ˁB(^-^)/
���łɃt�B���b�v�X��DAC�ɂ����������Ⴂ�܂����B
�g�p����DAC�̓}�����c��PJ�ED1�ŁATDA1541AS2�_�u���N���E�����ڂł��B
�i��F�\�E���m�[�g�̗�ؓN���j�������ł���B
�ł��A�g���v���N���E���͒m��Ȃ������E�E�E(^_^;)
�����ԍ��F7838644
![]() 1�_
1�_
�F����A�����́`�B
redfodera�����
���w���f�B�A�Ɋւ��Ă͎�N�Ȃ��������Ȃ�ɒ����g���Ă���̂�^^;
���_�����Ǝ��H�I�����[�Ƃ̋��Ԃł��܂����A�R���g���[���ł�����ǂ��ȁc�Ǝv���āA���X�c�ł͂Ȃ����簐i���Ă���܂�(��)�B
���X�ł���Ȃ�ǂ���ǂ������c�B
�܂��A����(��ʓI�ł͂Ȃ�)�ςȎ����菑���Ă���̂ŁA����ȏ������݂ŗǂ����ɔ`���ĉ������ˁ_(^o^)�^
audio-style�����
�}�j�A�b�N����^^;
���́A���͂͂́cf^_^;
�J��A���̗��ĂĂ�X�����đS�ʓI�ɂ���Ȋ����ȗl�ȋC���c(�ꊾ)�B
�ǂ݉�����������Č����Ă��������ėǂ������ł���
���e�����e�ł����A���������܂�����A���ۖ��ǂ���̕��ɓǂ�ł��������邩�^��ł������c�B
��q�����c�ƌ����킯�ɂ͍s���܂���ˁc�B
�X�^���p�[�͊m���Ɉ�ʓI�ɂ͐g�߂łȂ������m��܂���ˁB
CD-R�g�����ƁA���Ȃ�g�߂������肵�܂���^^;
>���łɃt�B���b�v�X��DAC�ɂ����������Ⴂ�܂����B
���������A����ς肻���ł���ˁ`�B
�����g���v�����Č����ĊG���o�ė��Ȃ������ł�^^
�����ԍ��F7839046
![]() 1�_
1�_
�F����A�����́B
audio-style����
�����łɃt�B���b�v�X��DAC�ɂ����������Ⴂ�܂����B
���ł��A�g���v���N���E���͒m��Ȃ������E�E�E(^_^;)
TDA1541A�ƃt�B���b�v�X�̃X�C���O�A�[���E�h���C�u���J�̃R���r�͗��s��܂����ˁB
TDA1541A�̑I�ʕi�ł̓_�u���E�N���E���̔F�m�x����ԍ����̂�������܂���B
�u�{���ɑI�ʕi�H�v�Ƃ������炢�̗p�����@�������������ۂ�����܂��B
�g���v���E�N���E���̗p�@��ŋL���ɂ���̂́A����4�@�킵������܂���B
�t�B���b�v�XLHH-2000�ƃX�`���[�_�[�^���{�b�N�X�̃t���b�O�V�b�v������3�@�킮�炢�ł��B
����ɂ̓_�u���E�N���E���̒P����6�{���炢�̂��l�i�������Ƃ��E�E�E
��DAC�̓}�����c��PJ�ED1�ŁATDA1541AS2�_�u���N���E�����ڂł��B
TDA1541A�V���[�Y�͂ǂ����M�Ɏア�悤�Ȃ̂ł��C�����������B
�i�J�~�`���ԍڗp�P��DAC�ɍ̗p���Ă܂������g���u���̑������t�H�[�����Řb��ɂȂ��Ă܂����B
�v���N��D��!!����@
���܂��A����(��ʓI�ł͂Ȃ�)�ςȎ����菑���Ă���̂ŁA
�ǂ����āA�ǂ����āB�u�ρv�ł͂���܂����B
�v���N��D��!!���u�w���v���ƁA���́E�E�E�ς��҂́A�w���^�C�A�w���N�c�ɂȂ����Ⴂ�܂��B
������ȏ������݂ŗǂ����ɔ`���ĉ������ˁ_(^o^)�^
AV�́u���v�ł����ˁH
�q�����܂������F����y�������ł����ˁB
audio-style����₱�̃T�C�g�Œm�荇�������X����A�h�o�C�X�����炢�Ȃ�����A
�x����Ȃ�����͂���ƃV�A�^�[���̏��������Ă���Ƃ���Ȃ�ł��B
�F����̃V�X�e����m�E�n�E���Q�l�ɂ����Ē����܂��̂ŁA�܂��X�������肢�v���܂��B
�����ԍ��F7843288
![]() 2�_
2�_
�F����A�����́`�B
redfodera�����
���ALHH-2000�̓g���v���N���E���������c^^;
���䌳�Â��c�B
>�ǂ����āA�ǂ����āB�u�ρv�ł͂���܂����B
>�v���N��D��!!���u�w���v���ƁA���́E�E�E�ς��҂́A
>�w���^�C�A�w���N�c�ɂȂ����Ⴂ�܂��B
�����^^;
�����Q�����Ⴂ�܂��ˁ`�B
�ł��A���������Ă���������Ɗ������ł��B
�ŏ��̍��͕ςɓ˂�����ŗ���������������̂Łc�B
����ς�m���x���Ⴂ���͑ʖڂȂ�ł�����^^;
(�O�͂Ђ�����Ə������݂��Ă����̂Łc)
>AV�́u���v�ł����ˁH
���������ł����A����̃X���ŐF�X�Ə����Ă��܂��̂Łc�B
�d���֘A����A�~�Պ֘A����A�I�[�f�B�I�A�N�Z�T���֘A etc�c
�ꕔ�������݂ł͌��\�f�B�[�v�ȓ��e�ɂȂ��Ă��܂���`�B
�c�c�A��H
����ς�A��������ĕ��ׂĂ݂�ƁA���C���@��̂ł͂Ȃ����Ӌ@��⏬����A���Ɋւ��鏑�����݂������ł���^^;
�����ԍ��F7846700
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ���@�@����ɂ���(^-^)/
redfodera����
��TDA1541A�V���[�Y�͂ǂ����M�Ɏア�悤�Ȃ̂ł��C�����������B
�܂��܂��M�d�ȏ��A�L��������܂��B
�T���͓d���̓�����ςȂ���Ԃ������̂ŁA�M��ɂ͋C�����Ă͂��܂������A
���߂āA���M���₷���ꏊ�ɕύX�ł��B(^-^)/
�v���N��D��!!����@
�ȑO�A�v���N��D��!!���A���Ă�ꂽ������CD�̃X�����������Ǝv���܂����A
�ŋ�CD�ȊO�Ƀn�[�h�f�X�N�ɘ^�������������A�����ǂ��ƕ����܂��B
CDP�Ɣ�r���āA�n�[�h�f�X�N�̍Đ��͔@���Ȃ��̂Ȃ�ł��傤�H
BW200�iBD���R�[�_�[�j�̃n�[�h�f�X�N��CD���R�s�[�������A�����͖��������ł��E�E
�����ԍ��F7849111
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
�v���N��D��!!����@
�����������ł����A����̃X���ŐF�X�Ə����Ă��܂��̂Łc�B
���d���֘A����A�~�Պ֘A����A�I�[�f�B�I�A�N�Z�T���֘A etc�c
���ꕔ�������݂ł͌��\�f�B�[�v�ȓ��e�ɂȂ��Ă��܂���`�B
������CD�̕���q�����܂����B
������ɂ����ז����ď��������Ē����܂������A���[���[�����ł�(^^�U
�����܂ߎd���W�̐l�Ԃ��������Əڂ������������X�^���X�Ɍh�����Ă��܂��B
�����ALHH-2000�̓g���v���N���E���������c^^;
�����䌳�Â��c�B
�d����ɂ����Ă悭�g���܂������A���̍��͎����F�����Ă܂���ł����B
�������p��Ɍ̏Ⴕ�Ĕp������鎞�Ɉ�����邩�Y��ł����A
�i�{������́j�I�[�o�[�z�[����p�Œ��ÊO�Ԃ�������l�i�I�������̂Œ��߂܂���(>_<)
�������t�B���b�v�X�{�Ђɖ����Œi�ԋp�H�j�����͂��ł��B
�l����o�u���Șb�ł���A����ȑ㕨�̌������p�Ȃ�āc
���Ȃ疳�����Ăł���������āA�Ɛl�̋t�ɐG���Ă�͂��ł�(^^�U
audio-style����@
���T���͓d���̓�����ςȂ���Ԃ������̂ŁA�M��ɂ͋C�����Ă͂��܂������A
�����߂āA���M���₷���ꏊ�ɕύX�ł��B(^-^)/
�ԓ����Ɖď�͐��܂������x�ɂȂ�܂����牮���g�p�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��ߍ��Ȋ��ł����A
�����f�B�A����CDP���g���Ă�����̃u���O�̋@��Љ�ł����l�̘b���łĂ��܂����B
A�N���X�E�A���v�̋߂��Ȃ�Ă̂͋��炭�_�O�Ȃ̂ł��傤���A
���f��G�A���b�N���̔M�͈ȊO�ɓ����܂�����̂ˁB��ɂȂ����ĉ������B
���悢��A�����A�@�ނ��͂��܂��B���c
�w������AV�v���A���v�������j�^�[�œ͂��@�ނ̕����C�ɂȂ��Ă܂�(^^�U
�Z�b�g�A�b�v���ė��������܂�����A�ʔł��Љ���Ē����܂��B
�����ԍ��F7849509
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́`�B
audio-style�����
HDD�������ɂ���ꍇ�ɂ��Ă͎�������m�F���܂������A���͌����Ĉ����Ƃ͌����܂���B
���������Ƃ���ڂ�CD�v���[���[���HDD����̍Đ��̕��������ǂ���������܂��B
�����Ƃ����ɓI�ɓ˂��l�߂��ꍇ�A�ǂ��炪�ǂ����͂�����Ɣ���܂���B
�����A���ɂ����߂��ꍇ�A��ʋK�i��HDD�ł͂�����Ɩ�������܂��̂ŁA������͓����HDD�ɂȂ�Ǝv���܂��B
���ꂾ���ŃR�X�g�����ˏオ�邾���Ɏ��p�I�ł͂Ȃ��ł��c�B
�ǂ������͂�����x���܂��Ă��܂����A�ŋ߂̕������猾���ƍ����������߂�͓̂���Ȃ��Ă��Ă��܂��B
�傫�ȉe������p�����[�^�Ƃ��āA��]�����������܂��B
���݁A��ʓI��HDD�̉�]����7200prm�ł����A�ȑO��5400rpm��4200rpm��������܂����B
�x��HDD�̕����ǂ��ꍇ��������ۂ�����܂��B
�܂��A��]���̈��艻�ׁ̈A�d���i��������܂����AHDD�̌Œ�̎d����PC�Ƃ��Ăł͂Ȃ��AAudio�Ƃ��Ă̑Ώ������������ǂ��ł��B
(�U����}������A�C���V�����[�^���g������c)
���ƁA���M��������̂ŁA�����@���Ɍ����ǂ����������c������܂��B
�����HDD��Disk�̓������ƊO�����œ����f�[�^���x���قȂ�܂��B
(CAV�����Ŋp���x���ƌ����܂�)
�����CD�Ƃ͈قȂ�܂��ˁB
(�������CLV�����A�����x���ł�)
���ׁ̈AHDD�͓��O���œǂݍ��ݓ����̕ω����傫���ł��B
(�����ɂ���e�����o���)
�P���ɊO�����̕����L�^���x���Ⴂ�ׁA�L���ȉ\���������̂ł����A�O�����̕�����]�̂ł���ȏ�A�u�����������͂��Ȃ̂ň�T�ɂǂ��炪�ǂ��Ƃ͌�����ł��B
���A�Â�HDD�Ŏ����������͓����̕����ǂ������L��������܂��B
(���R�[�h�Ƃ͋t�̌��ʂł���)
����͋L�^���x�����u���̉e���̕����傫��(�H)�̂��ȁc�Ǝv���Ă��܂��B
���������ACAV�����̓X�s���h�����[�^�[�̑��x�����ɕۂ����ł���̂ŁA���̓_�Ɋւ��Ă�CD�v���[���[�����m���ɗL���Ȃ�ł��B
�܂��A����ɂ��u����CD�v���[���[��菭�Ȃ��čςމ\���������ł��B
���ׁ̈A���������̗ǍD�ȕ����������O�����ɃA�N�Z�X���Ĉ�����������́A�����L�^���x�������Ă��������ɃA�N�Z�X���������A�����I�ȕi�ʂ������Ȃ�c�̂��ȁH�Ȃ�čl�@�����Ă��܂��B
����PC��Audio�������N�����Ă���̂ŁAPC�ɂ͍���������_�����Đ���p�̃p�[�e�B�V������݂��Ă��܂��B
�����ԍ��F7853211
![]() 0�_
0�_
redfodera�����
���낻��@�ނƋY��Ă��鍠�ł����ˁH(/ ^^)/
>������ɂ����ז����ď��������Ē����܂������A���[���[�����ł�(^^�U
>�����܂ߎd���W�̐l�Ԃ��������Əڂ������������X�^���X�Ɍh�����Ă��܂��B
���������Ă���������Ɗ������ł��B
�ł��A����ʂ��Ă��M���������Ȃ���ł���ˁc�B
���Ƃ��Ă����ŊȒP�ɐM�����������ł�����A��ʐl�Ƃ����͔̂��ɏd���n���f�B�L���b�v������Ǝv���܂��B
���Ȃ��Ƃ��A���͐^���������ʘ_�ƈقȂ����ӌ���������������܂�����A����ʂ̃X�^���X�Ŏ������s���A�������܂Ȃ��ƒ��X�M���ĖႦ�܂���^^;
�{���͌l�z�[���y�[�W�ł������������������肾�����̂ł����A�ȂT�C�g����鎞�Ԃ����Ȃ��ācorz
����܁ALHH-2000���������p�����ł����H^^;
����Ⴈ��ł���B
�����Ȃ�����������ǂ��㕨�ł��ˁ`�B
OH�ɏo���̂͑�ςł����ǁc�B
�����ԍ��F7853213
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@������
�v���N��D��!!����
�킩��₷���A�L��������܂��B(^-^)/
��������Ɠǂ܂��Ă��������܂������A
HDD�̓����Ƃ������̂��A�w�ǒm��Ȃ��������ɉ��߂ċC�����܂����B
SD�J�[�h��CD��������荞�ވׂɁAHDD�iBW200�j��CD���f�W�^���R�s�[���Ă��܂������A
HDD�̎�荞��CD�������ADAC�ōĐ�����Ǝv�������ǂ������ł����A
�����ŁAHDD�̉������A�C�ɂȂ����Ƃ����P���Ȕ��z�ł��B
����HDD�̓d��������ł߂āA�I�[�f�B�I�I�Ȋ��o�ŐF�X�Ǝ����Ă݂܂��B
��PC�ɂ͍���������_�����Đ���p�̃p�[�e�B�V������݂��Ă��܂��B
�ǂ�Ȃ̂��Ȃ��H
�����ԍ��F7855495
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�v���N��D��!!����
�����낻��@�ނƋY��Ă��鍠�ł����ˁH(/ ^^)/
�������I10���ɉו����͂��ĖO�����ɍ��܂Ŋi�����Ă܂����B
����ƌ������Ԃ��͂点�Ē�����������CD�͉̔��߂ď������܂��B
AV���̃Z�b�g�A�b�v�����������܂ŁA���X�A�����ԉ������B
audio-style���������HDD�͂��Ȃ�Q�l�ɂȂ�܂����B
�M�d�Ȍ��ؕ��肪�Ƃ������܂��B
�{�`������HDD�ɓ�����ςȂ��͂��܂肵�܂��A
�ҏW���ɂ�Pro-Tools���g���܂�����G���W�j�A�A���Ɉ�x�`�F�b�N�����܂��B
�����e�ʂ��傫���̂ŁA���炭�ǂ��Ȃ��Ɨ\�z����RAID���Ă��ł���B
�����ԍ��F7856025
![]() 1�_
1�_
audio-style�����
�Đ���p�̃p�[�e�B�V�����Ɋւ��ẮA�ȒP�Ȏ��ŁA��������O�����Ƃ���ȊO�ɊȒP�ɋ敪�������Ă��܂��̂ł��B
���O�̉��ꂩ�̕��������ǂ��͂��Ȃ̂ŁA�܂���3�̃p�[�e�B�V�����ɕ����܂��B
(2�ڂ̃p�[�e�B�V�����ɑ唼�������܂�)
����ŁA��U�u���C���h�e�X�g�����āA���O�̂ǂ��炪�ǂ������m�F���܂��B
����WAVE�t�@�C����u���A�Đ�����Δ��ʂł���Ǝv���܂��B
�����������A�V���Ƀt�H�[�}�b�g���āA�ǂ��Ɗ��������ɕK�v�ȃp�[�e�B�V���������܂��B
���AHDD�͊O������ɓǂݏ������܂�����A�ŏ��ɍ�����p�[�e�B�V�����͊O���ɑ������܂��B
(�ǂݏ����������̂ŁA�p�ɂɎg���f�[�^��u���ꏊ�Ƃ��Ă͊m���ɗL���ɂȂ�̈�ł�)
�Ⴆ�A500GB��HDD�œ����̕����ǂ��Ɗ�������A������AV��p�ɂ��܂��B
AV�p��50GB���K�v�ȏꍇ�A�ŏ��̃p�[�e�B�V�����ɑ唼�����蓖�āA��������f�[�^�p�ɂ��A�c���AV��p�Ƃ��đ��p�[�e�B�V�����Ƃ��܂��B
���Ƃ͑��p�[�e�B�V���������p���A���p�[�e�B�V�����̓f�[�^�ۑ��p�ɂ��铙�A�p�ɂɃA�N�Z�X���Ȃ��l�ɉ^�p����Ηǂ��ł��B
(�����I�ɓ���HDD�ɑ��āA������2�ȏ�̓ǂݏ����̖��߂��s���Ȃ��l�ɂ��܂�)
���������A�t�@�C�����V�[�P���V�����ɓǂݍ��ގ����ł��܂��̂ŁA�����I�ɂ͔��ɗL���ɂȂ�܂��B
���AAV��p�p�[�e�B�V�����̓f�t���O�����ėǂ���Ԃ�ۂƗǂ��ł��B
�O����ɂ���ꍇ��HDD�̑I�肩�����̂ő�ςł����A�ᑬHDD���g���āA��L�菇�݁A�ǂ��������Đ���p�Ƃ��ė��p���܂��B
�ȑO��2�̓�������HDD��p�ӂ��A��L�̎������Ă��܂����B
�����āA�c�̈��WAVE�t�@�C����ۑ����Ă����A�Đ��������t�@�C���Q��K�v�ɉ����čĐ���p�p�[�e�B�V�����Ɉړ����Ă��܂����B
���̎��̗�j
HDD1P1 - C: 40GB(OS�p)
HDD1P2 - D: �c��(�ʏ�^�p)
HDD2P1 - E: �F�X
HDD3P1 - F: �e�ʎ��O WAVE�t�@�C���u����P
HDD3P2 - G: �c�� ����p�P
HDD4P1 - H: �e�ʎ��O WAVE�t�@�C���u����Q
HDD4P2 - I: �c�� ����p�Q
F:�ɂ���t�@�C�����Đ��������ꍇ��I:�ɃR�s�[���čĐ����AH:�ɂ���t�@�C�����Đ��������ꍇ��G:�ɃR�s�[���čĐ����Ă��܂����B
�܂��A�ґ�ɂ܂�Ȃ��g���������m��܂���ˁc^^;
����ƁA����̋L�q[7853211]��1�ӏ��C�����Ă����܂��B
(2/3�ʂ̉ӏ�)
>�P���ɊO�����̕����L�^���x���Ⴂ�ׁA
���ꂾ�Ɛ��m�ȋL�q�ł͂Ȃ��ł��B
�������́u�P���ɊO�����̕����ǂݏ����������ׁA�v�ł�^^;
�����ԍ��F7856060
![]() 1�_
1�_
redfodera�����
�������ƁB
�����I�����烌�X���c�B
>����ƌ������Ԃ��͂点�Ē�����������CD�͉̔��߂ď������܂��B
����ς�Ԃ������c^^;
�v���̌���ł�RAID0���ł��d���Ȃ��Ǝv���܂��B
��{�I��RAID0���͗ǂ���ۂ�����܂���B
����ς�o���o���ɋL�^����̂͑ʖڂł��ˁc�B
�ł��A�v���̌��ꂾ�Ɠ����HDD���g�p���Ă��܂��H
�ŋ߂͂��������b���Ȃ��̂ŁA�ň��A�����HDD���Ȃ��Ȃ��Ă���̂����c�ƐS�z���Ă���̂ł����c�B
HDD�̋K�i����������l�ł�������ĉ�����m(_ _)m
(���Ȃ��Ƃ��A�ȑO��AV���^�p�r�̓���ȓ��������HDD����������ł�)
�����ԍ��F7856092
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@������(^-^)/
�v���N��D��!!����
�܂��܂��ڂ����������肪�Ƃ��������܂��Bm(_ _)m
�������Ƀv���N��D��!!����ł���
���x���ǂݕԂ��āA�����͗����ł��܂������A���ɂ͓�����܂����B
��������PC�̕������Ă���AHDD�̃p�[�e�B�V���������ɒ��킵�Ă݂܂��B
�������A�v���N��D��!!����̐����́A�ۑ��łł���B(^-^)/
redfodera����
����������AV�A���v�A�������߂łƂ��������܂��B(^-^)/
������AV�A���v�̃X���͗L��܂����A
�C�O����AV�A���v�̃X���͖w��ǖ��������悤�Ɏv���܂��B
���YABV�A���v�ƈ���āA
�ǂ̂悤�ȉ���Ɖ��F���W�J�����̂��A�������|�[�g�y���݂ł��ˁB
�����ԍ��F7859933
![]() 1�_
1�_
�@�F������������܂��I
�@���S�ɏo�x���ԂŌ�����܂����A�������̓x�̃N�����P�̃L�����A��
����܂���ԑ��Y�ł�(^_^;)
���Ăт��|����Ȃ���Ȃ��Ȃ��o��o�����\���������܂���B
�@��ʂ͌����܂������A�����܂Ńv���N���{�ɂ��ז����Ă��܂��܂����B
�@���̌f���ɂ̓K���X���b�c�ƃ|���J�b�c�̎�����̈�ۂ����������
���܂������A�v���N���|�܂����߂ăJ�L�R�������Ɓc
�@�����A���������r�p�|���J�b�c�̓N�I���e�B���Ⴂ�Ȃƌ�����ۂ�
�����Ă���܂����B�M�����x���ŃN�I���e�B�[���Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ�����
�^�����ʂł��B�܂��A���̌��Ɋւ��܂��Ă̓v���N���|���ɗL��܂��悤��
����͂Ȃ�����������܂������c
�@��L�̂悤�Ȋ��o���o�����A���̃|���J���ɔ�׃K���X���b�c�͂ƌ�����
���ł̕������̍��͂͂�����Ɗ������܂����B
�@�ȒP�ȏ������ł����A���̖��x���͐�ΓI�ɃK���X���b�c�̕����ǂ���
�����Ă���܂��B�i���܂������͂Ɍ����܂����c�j
�@�������Ȃ���A���܂ɗD�G�ɓ��������Ƃ��́hWoooo�I�h�I�Ȋ�����ɂ�
�قlj�����ۂł��B
�@���̉��̍D�݂́A�������Y��ȁA�k�����̂��鉹�ł����k�����Ƃ���
���������A�K���X���͂���͂���łŗǂ����ȂƁc
�@�܁A���ʓI�ɉ������������ɍ����������i�������j���Ƀz�b�Ƃ�������ł��i��
�@���āA���̓x�̃v���N���{�ɂẲ�U��Ř^�����������撣���č�������ł�
�Ȃ����낤�ƌ������ʂɁc
�@����̓K���X�f�B�X�N�̗ǔۂɒ��ڊW�̂��鎖�ł͂Ȃ��ł����A�|���J��
�b�c�̂���ꂳ�������Ă�邾���Ŏ��D�݂̂b�c�ɁI�m���ɁA���̖��x����
�K���X�����ǂ��Ǝv���܂����A�]���ɂ������ǂ�`��Ƃ����h�݂������h������
��R����A�����n���E��ʊ��̂��邻�������̃f�B�X�N�ɁI�i�@
�v���N���|���ɂ��L��܂����A����������ɐÓd�C�̏����A�}�C�i�X�C�I���̏Ǝ˂ŁA
�w�{�Ǝv���Ă����b�c���ϐg�I�I�{���ɕϐg����ɂ���������܂��i��
�@���āA���āA�����Ȃ�Ύ��̂ւڎ��ł̗��f�X�N�̏������ȒP�ɏ����o���܂���
�@�K���X���b�c�@�@�k�����@�������肪�}�C���h�i�̂ɉ��ʂ�������������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĎG�������Ȃ��H�I�����I�ɂ͕�����Ȃ��i��
�@�|���J���b�c�@�@�����n�����i������ʊ��j�������A�����f�B�X�N�ɂ͎v���Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Ŏ����ȉ��H�����̎G��������͂���Ŏ��͍D���i��
�@���āA���āA���āA�ʂ����ăK���X���̂b�c�͖{���ɒl�ł��̗L�镨���ƌ���
����ɂ͕ԓ��ɍ���܂�(^_^;)�@
�@���Ȃ��Ƃ����̈Ⴂ�͗L��܂����B�i�@�������A���܂�ɂ����z���c
�@���ꂾ���̋��z���|����Ȃ�A�ʏ�̃f�B�X�N�Ŋ撣���Ă�����������o�����[
�t�H�[�A�}�l�[�H
�@�ƁA�܂��v���Ȃ���A�J�������̂Q�O���̕��͂ǂ����ȁH�Ɩ��d�ȋ^���������
���܂��͎̂������c
�@
�@�v���N����
�@�܂��̓��|�グ�����l�ł��B����قǂ̃��|���オ��������b�g�Ƃ���
���h�ł��i��
�@���`�A����ƃK���X���b�c�̓ǂݎ��ʂ̎ʐ^���A�b�v�����낵����
�ł��傤���H�ő傪�f���ŃA�b�v�v���܂��傤�i�@�Ƃ����Ƃ���ł���������
�O�o�̂��߁A�T���܂ł��e�͂��I
�@����ƁA�@�]�k�ł����A�I�N�_���B�A�ƃt�@�C���v�������_�C���N�g�J�b�g
�b�c�|�q�Ȃ���̂�݂����ł���i��
�@���`�A�܂��A�܂��A�J�L�R���������Ƃ�����̂ł����A���Ԃ������Ă���܂��̂�
�i���̎��Ԃ��Ⴂ�I�I�j�ЂƂ܂����E���c
�����ԍ��F7860739
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
audio-style�����
�ۑ��ł��Ȃ�Ă���ȁcf^_^;
�ŏ��͉��ł�����ł�����ˁc^^;
�ł��APC�͕i���ʂł̓{���{���ł�����A�����ꂷ��Ɛ����ς��܂���B
➑̂̕⋭������A�d���i���̌���A�A�[�X�d�ʂ̒ቺ�c���ȂǁB
Audio�@��̗l�Ɉ����A���ꂾ��Audio�ɋ߂��Ȃ�̂Ŗʔ����ł��B
�����HDD�ł͂Ȃ��ASSD��t���b�V������������肭�g���Ɖ����ʂł��Ȃ�D�ʂɂȂ�\��������܂��B
���ہA�������}�̂����CD-R���Ă��̂ƁAHDD����ǂݍ����CD-R�ɏ������ނ̂Ƃł͕i�ʂ��ς���Ă��܂��܂��B
�ܘ_�A���̓������Ɉ�U�S�Ẵf�[�^��u�������ǂ��ł��B
(��]�̂���Ȃ��̂͂���ς�ǂ���ł��ˁBCD-R���͏h���I�ɉ�]������܂��c^^; )
�����ԍ��F7860824
![]() 0�_
0�_
��ԑ��Y�����
�L�^�[!!�@�I�[�i�[�A�x��������(��)�B
����A�����炱�������}�̉�����&�i�������ŎM�������Ē��ɂȂ肻���������̂��\����Ȃ��c�B
���|�[�g���Á[��!!�Ƃ�����ꂽ��ǂ����悤���Ǝv���Ă��܂����c(��)�B
���������A�F����A���ʐ^���������Ďd��������ł���A������(/ ^^)/
>����ƁA�@�]�k�ł����A�I�N�_���B�A�ƃt�@�C���v�������_�C���N�g�J�b�g
>�b�c�|�q�Ȃ���̂�݂����ł���i��
�m���Ă܂����ǁA���͂�����Ƌ^���̖ڂ��c�B
����A�܂Ƃ���CD-R����鎖�Ȃ�Ăقږ����Ȃ̂ŁB
10�N�O�ł����ɒx���̂Ɂc�B
���z�U�d�������ʂ��l�����ĊJ������Ƃ͎v���܂��ARICOH�����TDK����͂�߂���������B
CD-R���ꂩ��J������̂͂����Ɩ����Șb�Ȃ̂ŁA�ǂ����𗊂炴��Ȃ��͂��B
�]���āA�ʒu�t���Ƃ��Ắu���݁A�X�^�W�I�^���ō���Ă���}�X�^�[CD-R�v���x�̃��x�����Ǝv���Ă��܂��B
(���x�͍��������m��܂��c)
���̃��x���ł���ʂ�CD���͗ǂ��Ǝv���܂����ǁA�̂�CD-R�����̃h���C�u�ŏĂ������̂̑�햡�͓����Ȃ���ł���ˁc�B
�ō���搂�ꂽ���z�U�d��63�������ˑw���f�B�A�́uCD-R63Q�v��uCDQ-63A�v�A�uCDQ-63BN�v�A�uCDR-63/570P�v�A�O�䓌�����w����63�����f�B�A�͊��ɃX�^�W�I�ɂ��w�ǖ�����Ȃ��ł��傤���c�B
�����uCD-R63Q�v�͑��݂��������m��Ȃ��ʂł����B(�����A�ŏ���CD-R����Ȃ��H)
����Ȃ���Ȃ��l������ƁA�ݒ艿�i�����������ňނ��܂�orz
�������������͖ܘ_������ł����ǂˁB
�N�������āc(��)�B
�����ԍ��F7860840
![]() 2�_
2�_
�F����A���͂悤�������܂��B
�v���N��D��!!����@
������ς�Ԃ������c^^;
�T���ɂ͏������܂��̂ŁA���������ҁI
��ԑ��Y����A�͂��߂܂���
������������ɐÓd�C�̏����A�}�C�i�X�C�I���̏Ǝ˂ŁA
���w�{�Ǝv���Ă����b�c���ϐg�I�I�{���ɕϐg����ɂ���������܂��i��
�������u���Ă܂��ˁB
�ю��͐������̃`�F�b�N���ڂɂ���܂���B
�����Ƃ̒��ړI�Ȉ��ʊW�ɗ��t�����Ȃ���ł����A
���܂萔�l�������Ɠǂݎ��G���[�l�������l���ω��i�K��������������킯�ł͂���܂��j���܂��B
audio-style����
������������AV�A���v�A�������߂łƂ��������܂��B(^-^)/
���ǂ̂悤�ȉ���Ɖ��F���W�J�����̂��A�������|�[�g�y���݂ł��ˁB
���肪�Ƃ��������܂��B
�q���������Ō@�艺���͂��̏T������ł��B
�Z�b�g�A�b�v�������������炲�Љ�����Ǝv���܂����A
��r�@�������Ă��Ȃ���������ׂ��鎨���������킹�Ă��Ȃ��̂��S�z�ł��ˁB
���������v���Z�b�g�Ŏ����t�H�[�}�b�g�����Ɨd���������ɑ��肻���ł����c(^^�U
�����ԍ��F7864679
![]() 2�_
2�_
�F����A����ɂ��́B
redfodera�����
>�T���ɂ͏������܂��̂ŁA���������ҁI
�����A�T�����y���݂ɂ��Ă��܂���^^
�ю��ɂ��Ă̓s�b�N�A�b�v�ւ̉e��������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�s�b�N�A�b�v�̊ԋ߂őю���������������]����c�ƍl����ƌ��\���Ȃ��̂��c^^;
�e�����F���Ƃ͎v���܂���B
�]���āA�������邩�������邩�̉��ꂩ���s���ƁA�s�b�N�A�b�v�ւ̈��e�������ۂ�����̂ƍl���Ă���܂��B
>���������v���Z�b�g�Ŏ����t�H�[�}�b�g�����Ɨd���������ɑ��肻���ł����c(^^�U
���̃t�H�[�}�b�g���ĕ|���ł���^^;
�C���v�����y���݂ɂ��Ă��܂���!!
�����ԍ��F7869478
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ���@������(^-^)/
��ԑ��Y����A�͂��߂܂���
���C�ɃK���XCD�̓������킩��܂��ˁA���肪�Ƃ��������܂��Bm(_ _)m
���́A�Y�ꂽ���Ƀ|���JCD�̏������s���Ă��܂����A
�}�C�i�X�C�I���̏Ǝ˂͂��Ă��܂���E�E�E
�|�J���X�G�b�g�ł������ł����H�i�����܂���(^_^;)�j
�������D���ȋȂ��������K���XCD���A1���͏��L���Ă݂����ł��ˁB(^-^)/
�����ԍ��F7872286
![]() 0�_
0�_
����ȃX���b�h�𗧂ĂĂ��܂��Đ\����Ȃ����X�@�|���`�k�k�B
�@�����Ă��鑕�u�͑S�R�債�����ł͂Ȃ����̂́A���͖��ʂɃI�[�f�B�I�������͒����̂ŁA������������������邱�Ƃ��o�������i�̑����͂������������ł��B�����͌Â����i���l�b�g�I�[�N�V�����ŏo���悤�ɂȂ�A�����̋@����g���Ă݂����Ǝv���Ă���Ⴂ���[�U�[�����Ȃ��Ȃ��Ɨ\�z���܂��B����āA������Ƃł��Q�l�ɂȂ�Ǝv���A�Ȃ��Ȃ��̒m���𗅗�g�s�b�N���A�G�z�Ȃ������Ă݂�����ł��B
�@�������A���̌f�����������������͂Ȃ��A���������@����g�p����Ă�����A�܂��͉ߋ��Ɏg���Ă������̗L�Ӌ`�ȃ��X��Ⴆ��K���ł��B
�@�ŁA�ǂ����Ċ�����CD�v���[���[�̃R�[�i�[�Ȃ̂��E�E�E�E�Ƃ����ƁA�ʂɈӖ��͂���܂���i���j�B�P�ɑ��̃J�e�S���[�ɔ�ׂăX���b�h�������Ȃ�����A�͂���R�̓��킢��낵�����Ă��ɉ߂��܂���(^^;)�B
�@����ƁA�̂�U��Ԃ����ł͂Ȃ��A���ꂩ��̃I�[�f�B�I�͂ǂ�����ׂ����A�ǂ�ȏ��i����������ė~�������E�E�E�E�Ƃ������A����������ȁi���j�����ɂ������čs����Ζʔ������Ǝv���܂��B
![]() 0�_
0�_
�@������CD�v���[���[�֘A�̃{�[�h�Ȃ̂ŁA�܂��͎����̂�CD�v���[���[�ɂ��ď����Ă݂܂��B
�@CD�v���[���[���s��ɏo������̂�82�N����ł��B�����ŏ��ɐڂ����̂́A���́g��ꐢ��h�̋@��̈�ł���ANEC��CD-803�Ƃ����v���[���[�ł��B�艿��\215,000�ŁA���ł͂܂����ڂɂ�����Ȃ��gCD���c�ɓ���ă��[�f�B���O��������h�ł����B���̕����́g�����ڂ̓����h�́A�f�B�X�N����]����l�q���O�ʂ���m�F�ł��邱�Ƃł��B�����ɂ��gCD�����t���Ă���h�Ƃ��������͋C�����[�U�[�ɖ����킹�������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���́g�c��������h�́g��ꐢ��h�̐��i�̑����ɍ̗p����Ă��܂������A�g���h����͌��݂̂悤�ȃg���C�����嗬�ɂȂ�܂��B
�@����CD�v���[���[�͂��ꂱ���蕨����Ŕ���o���ꂽ���̂ł����ACD-803�����ۂɒ�������ۂ́E�E�E�E�g���ł������H�@�R���́h�Ƃ��������x���ł����B�����Ď��̊��̂Ȃ��T�E���h�ŁA����܂ł̃A�i���O���R�[�h�̉��ɔ�ׂ���啝�ɗ�����N�H���e�B�B���Ȃ݂ɂ��̌�ɕʂ́g��ꐢ��h��CD�v���[���[���������������܂������A�ǂ�������悤�Ȃ��̂ł����B�g�A�i���O���R�[�h�ɑ���CD�̃����b�g�́AA�ʂ�B�ʂ̋�ʂ��Ȃ��r���łЂ�����Ԃ��K�v���Ȃ����Ƃ������h�Ƃ����V�j�J���ȋC���ɂȂ������Ƃ��o���Ă��܂��B
�@�������V�����t�H�[�}�b�g�̓C�m�x�[�V�����������A�g���h�ɂȂ�Ə\���Ɋӏ܂ɑς�����@�킪���X�Ɣ�������A�ߑ��̂Ȃ����͂���܂ł̃l�K�e�B���Ȍ�����Y�ꂽ���̂悤�ɁACD�v���[���[�̓����ɑO�����ɂȂ������̂ł��i�j�B
�@���܂ʼn��䂩��CD�v���[���[���g���Ă��܂������ACD�v���[���[�͉�]���J�ł��邽�߂��o�N���傫���ł��ˁB�l�b�g�I�[�N�V�����ł̌Â��@��̒��B�͐T�d�ɑΏ����������ǂ��ł��B
�@����ɂ��Ă��ANEC���s���A�E�I�[�f�B�I�@������Ă������Ƃ́A���ɂȂ��Ă͍l�����Ȃ����Ƃł��BNEC�Ɍ��炸�A�͉̂Ɠd���[�J�[��������O�̂悤�Ƀs���A�E�I�[�f�B�I����ɎQ�悵�Ă��܂����B���̂ւ�̘b�͂܂�����B
�����ԍ��F7748276
![]() 1�_
1�_
�@�g���h�ɓ����Ĕ�r�I�܂Ƃ��ȉ����y���߂�悤��CD�v���[���[�ł����A���ς�炸���i�̓I�[�f�B�I�}�j�A�ȊO�̃��[�U�[������o������̂ł͂���܂���ł����B�m����Ԉ����@��iSONY��YAMAHA����o�Ă����Ǝv���܂��j�ł����Ă�10���~�̒l�D���t���Ă����Ǝv���܂��i�������A��肪�`���`�ł����j�B���̏�Ԃ����ς����̂�85�N�ł��B
�@SONY�Ƌ���CD�̊J�����ł�������PHILIPS�Ђ�MARANTZ�u�����h�ł��̔N�ɔ�������CD-34�́A\59,800�Ƃ����A�����Ƃ��Ă͉���I�Ȓቿ�i�ł����B�������A����32cm�̃R���p�N�g�^�Ȃ���7kg�Ƃ����d�ʋ��B�A���~�_�C�L���X�g���̃V���[�V�ō��������\�����Ȃ��B����ɂ͓������Ђ����ӂƂ��Ă����X�C���O�A�[�����J�j�Y���𓋍ڂ��Ă��܂����B�����A�����W���͒��X�Ȃ��畂�����Ƃ���̂Ȃ������₷�����̂������ƋL�����Ă��܂��B
�@���RCD-34�͔����I�ɔ���A�e�Ђ�����ɒǐ����Ĉ����Ȑ��i�𓊓�������Ȃ��������߁ACD�v���[���[���̂̎Љ�I�F�m�x�͑傢�ɍ��܂�܂����B�������Ȃ���CD�\�t�g���̂͂܂������i����CD�Y���Ă������[�J�[�͐��E��6�Ђ�������܂���ł����B���Ȃ݂ɂ��̂���4�Ђ����{��Ƃł��j�A������3,200�~�Ȃ�Έ������A�A���Ղ̃N���V�b�N�Ɏ����Ă�4,200�~�Ƃ����o�J�����l�i�t�������Ă������[�x��������ACD��LP���̒l�i�ɂȂ��čL�͈͂ɕ��y����ɂ͂��Ɛ��N��v�������̂ł��B
�@�b�ς���āA���݂ł̓I�[�f�B�I�}�j�A��CD�g�����X�|�[�g��DAC�Ƃ�ʁX�ɑ����邱�ƂȂǒ��������Ƃł͂���܂��ACD�v���[���[���t�����ɂ͖����i���x���ł̂���Ȍ`���ł̍Đ����@�͑��݂��Ȃ������E�E�E�E�Ǝv������A���͈Ⴄ��ł���ˁB84�N�ɂ��łɃg�����X�|�[�g����DAC���Ƃ����������Z�p���[�g�^�̃v���[���[����������Ă��܂��BLo-D��DAD-001�Ƃ������i������ł��i�艿\600,000 ���Y�j�BLo-D�͓������쏊�̃I�[�f�B�I�u�����h�ŁA����܂ł������̓J�Z�b�g�f�b�L���ňӗ~�I�ȏ��i�W�J�����Ă���ACD�u���[���[�Ɋւ��Ă��g��ꐢ��h�̍�����Q�����Ď��т�����Ă��܂������ADAD-001�͐��E���̃Z�p���[�g�^�v���[���[�Ƃ��ċr���𗁂т܂����B�f�U�C�����f���炵���A�T�E���h�Ɋւ��Ă̓f�W�^���L�����ɗ͔p�������x���̂�����̂ŁA���𑜓x�����O�ʂɏo��������CD�v���[���[�̉�����Ɉ�𓊂����`�ɂȂ����ƌ����܂��傤�B
�����ԍ��F7753004
![]() 0�_
0�_
�@�b����A���v�Ɉڂ��܂��B���ł��l�b�g�I�[�N�V�����Ől�C�������A���p�҂̑����u�����h��SANSUI������܂��B�R���d�C�͌��X�̓g�����X�̃��[�J�[�������炵���A���͂ȓd���𓋍ڂ����d������ȍ�肪��ۓI�ł������A���ƌ����Ă������ڂ̓����͂��̃u���b�N�t�F�C�X�ɂ���܂����B80�N�㔼�ɂ̓A���v�ނ̃u���b�N�d�グ�����s��A�L���ێq���^�������̖ʍ\���������@�킪�s��ɂ��ӂ�܂������ASANSUI�͂��̂����Ɛ̂��獕���J���[�����O���̗p���Ă��܂����B
�@�I�[�f�B�I�S�����ɂ͊e�Ђ͐ϋɓI�ɐ��i�𓊓����܂������ASANSUI�͓��ɔM�S�ŁA�قږ��N���f���`�F���W�����Ă������̂ł��B������������l����ƁA�������������Ă��ꂽ���[�U�[�̐��i�������ɋ����ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ����Ă���A�������I�ɂ͓K�ȃ}�[�P�e�B���O�������̂��ǂ����^��̎c��Ƃ���ł��B
�@�ŁA�̐S�̉��͂ǂ����������Ƃ����ƁA�������͍D���ł͂Ȃ������ł��B�������ʂ�̏d�ʊ�����T�E���h�ł������A��������ς���ΈÂ��ēݏd�ȉ��ł��B�����̔����E�L�т͂܂���������܂���B���y�N���X�ł�ONKYO�ɁA�����O���[�h�ł�ACCUPHASE�ɁA�����ɂ����Ċ��S�ɕ����Ă����Ǝv���܂��B�������A���͈Â��Ă��n�͂͂���̂ŁA�Ƃɂ����O�ʂɏo��p���t���ȃT�E���h���D�ޑw�i���{�̃I�[�f�B�I�t�@���ɂ͑����j�ɂ͕��L��������܂����B
�@�ǂ����������u�����h�Ƃ��Ă̋����u���v�͂������̂ŁASANSUI�̉������A���^�C���Œm��Ȃ����[�U�[�������_�Ŏ������o���Ȃ��̂Ƀl�b�g�I�[�N�V�������œ��肷�邱�Ƃ́A�����������X�L�[���Ǝv���܂��B�܂��u���ȐӔC�v�ł���Ă��������ƌ��������Ȃ��ł���(-_-;)�B
�@�����SANSUI��90�N��ɓ����Ă���̃��f���́i�u���b�N�d�グ���ꕔ����߂āj���F�����A�L�����[�g�ȕ����ɂ��U��悤�ɂȂ�܂������A�܂��Ȃ��s�ꂩ��P�ނ��܂����B�y���Z���̃g�����h�ɏ��Ȃ��������߂Ƃ��A���{��������ꂽ�Ƃ����낢��ƌ����Ă��܂����A���āg�O��I�[�f�B�I���[�J�[�h�̈�p���߂��ƊE�̗Y�̑ޏ�́A���݂ɂ������I�[�f�B�I�s�����ے�����悤�ȏo�����������悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F7753008
![]() 0�_
0�_
���������b�ł��ˁB��������Ă��������B���̍ŏ���CDP��CD803�ł��B
���̌�903�ACD10��NEC���������̂���Ȃ��ł����ACD-34�̊��炩�������܂���
�[���ł����Ƀt�B���b�v�X�͉䂪�Ƃɓ��炸�I����Ă��܂��܂����B
�l�I�ɂ�CD903�ȍ~�ɗD�ꂽCDP�͂ق�̐���𐔂���݂̂ł��B
���̂�����Ɏ���̃I�[�f�B�I���Ԃ́A�ő̑f�q�̉\���Ɏv�����͂��Ă��܂����B
1984�N�����ł�����Â��b�ł��ˁB�P���K�������[��2���~�ȏサ�Ă�����ł��B
���A����ƌő̑f�q�ɂȂ����̂ɁA������4�M�K3000�~����ɁA�s�t���k��
�嗬�Ƃ����̂͑S���[���������Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B
CPU���x�������܂ő����Ȃ��āA��e�ʃ������������܂ň����Ȃ��Ă�
MP3������Ƃ������Ƃ́A�����Ƃ����I�[�f�B�I���@��̖����l��
���ꂾ�������Ȃ����Ƃ������Ƃł��傤�B
�܂��́A�����A����ɁA��낵���ł��B
�����ԍ��F7753373
![]() 0�_
0�_
�@�W�[�����X����A����ɂ��́B
�@NEC�̃I�[�f�B�I���i�ɂ́A���b��̃u�����h�uSOULNOTE�v�̃`�[�t�G���W�j�A�E��ؓN���Q�悵�Ă������Ƃ�����܂����ȁB��胁�[�J�[�ł͂��̌��Ɨ͗ʂ͎g�����Ȃ��Ȃ�������Ȃ����E�E�E�E�Ȃ�Ďv���Ă��܂��܂��B
��������4�M�K3000�~����ɁA�s�t���k��
���嗬�Ƃ����̂͑S���[���������Ȃ��`
�@�����ł��B�����[���ł��܂���B���k�����������������Ƃ̂Ȃ��Ⴂ�w�́A�{���ɉ��y���D���Ȃ�ł��傤���B���N�A�m�荇���̎Ⴂ�z�Ɂg�V����CD�v���[���[��������h�ƌ�������A�g���ǂ�CD�v���[���[�Ȃ�ČÂ����X�ˁB���݂̓_�E�����[�h���嗬�ł���B�I�����������N��CD�V���b�v�Ȃs�������ƂȂ��ł��h�ƕԂ���ĕ����܂����B
�@�܂��A���y�̑���葤���g���k�ŏ\���h�݂����ȃX�J�X�J�̉��������ł��Ă��Ȃ����Ƃ����ł��傤���B���Ăł́A�������l�b�g����̃_�E�����[�h������ł����A�s���A�E�I�[�f�B�I�̃u�����h�����X�o�Ă��Ă��邠����A�����Ɖ��y���Ă���w�������̂��Ȃ��Ɗ��S�������܂��B���{�������Ȃ�悤�ɁA�ƊE�����l���~�����ł��ˁB
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢�������܂��B
�����ԍ��F7755279
![]() 2�_
2�_
�@�͉̂Ɠd���[�J�[���I�[�f�B�I�ɎQ�����Ă������Ƃ͑O�̏������݂ł��q�ׂ܂������A���ł���O�ł͂���܂���ł����B70�N�㔼��Aurex�i�I�[���b�N�X�j�Ƃ����u�����h�𗧂��グ�A�ƊE�ɐi�o�B�����Ƃ��A���ł͂�����ȑO�ɂ��I�[�f�B�I���i�������Ă��܂����B60�N�ォ��uIC�{�X�g���v�Ƃ��������ŃZ�p���[�g�^�C�v�̐����u���^�X�e���I���o���Ă������A�P�i�R���|�[�l���g���������Ă��܂����B�m���A73�N�������4���~���x�̃A���v�������[�X�����悤�ɋL�����Ă��܂��B�K�b�V���Ƃ���➑̂ɃA���~���C�̃c�}�~�ނƁA���y�i�N���X�Ƃ͎v���Ȃ����ʂ���������Ă��܂����B
�@�ŁA�C���������ăI�[�f�B�I�ɖ{�i�I�ɎQ�悵���̂͂悩�����̂ł����AAurex�͓����قƂ�Ǖ]���ɂȂ�Ȃ������悤�ł��B���ł͔����̂ł̓g�b�v���[�J�[�����A�g���Ă��镔�i���ǎ��ł������ɂ�������炸�A�o�Ă��鉹�͓����̂Ȃ����̂œX���ł͂܂�ŃA�s�[���o���܂���ł����B
�@���ꂪ��ϊv�𐋂����̂�70�N�㖖�ɔ��\���ꂽ�v���A���v��SY-88�ƃ��C���A���v��SC-88�ł��B����SY-88�̃��f���`�F���W��SY-��88II�������������Ƃ�����܂����A�����Ԃ鍂���������������������Ȃ���A���炩�Ƀq�A�����O�ʼn�����˂��l�߂Ă������Ǝv���鐶�X�����T�E���h�i�������A�t���b�g�w���j�́A�S�ꊴ���������܂����B�m���A�`���̃I�[�f�B�I�]�_�ƁE�����S�j�̃��t�@�����X�E�V�X�e���ɂ�SY-88�͓�������Ă����Ǝv���܂��i�������A�g�p�҂ɂ�����������Ă͂��܂������j�B
�@���ƁA��ۓI�������̂��ƊE���̃f�U�^���E�V���Z�T�C�U�[�`���[�i�[��ST-910�ł��B�d���X�C�b�`�ȊO�̃c�}�~�������A���ׂă^�b�`�p�l���ő��삷��Ƃ����A�����ׂ������u���̐��i�ł����B�J�Z�b�g�f�b�L�̕���ł��ӗ~�I�ŁA�s�[�N���[�^�[�Ƀv���Y�}�E�f�B�X�v���C���g�p������A�J�Z�b�g�̃z�[���h���@�ɓƎ��́u�蓮���v���̗p������ƁA��肽������̊�������܂����B
�@�������AAurex���i�͍̎Z�x�O���̍\���ł��������߂��A80�N��܂łŃu�����h�͏��ŁB���ł����̌�s���A�E�I�[�f�B�I�Ɏ����߂Ă��܂���B�ł��A�����i�̒��Õ����̏o��������A���肵�Ă݂�̂��ʔ�����������܂���B����SY-88�̃V���[�Y�͗v�`�F�b�N�ł��B���N�O�ɒ��ÃV���b�v�̓X����SY-��88�������܂����B�c�O�Ȃ���u����ς݁v�̎D���\���Ă��܂������A�X�̃X�^�b�t�̘b���Ɓu���������q�̓t�H�m�E�C�R���C�U�[����Ɏg���������v�Ƃ̂��ƁB����������SY-88�ɂ�MC�^�J�[�g���b�W�Ή��̗��h�ȃw�b�h�A���v����������Ă��܂����B
�@Aurex�̎����I�ȏ��Ō���A���ł͂��炭�����̂Ƃ���Ŏ�Â���N���V�b�N�̃R���T�[�g��Aurex�̖��O��t���Ă��܂����B�Ȃ��AAurex�̃G���W�j�A�̒��ɂ�ACCUPHASE�ɈڐЂ����҂�����炵���ł��i����͂悭�m��܂��� ^^;�j�B
�����ԍ��F7762401
![]() 1�_
1�_
�@87�N�ɔ������ꂽCD�v���[���[��CD-M2�Ƃ����@�킪����܂��B���������̂�MICRO�i�}�C�N���j�Ƃ������[�J�[�ł����BMICRO�͓��{�̃��[�J�[�ł����A�A�i���O�v���[���[�̕���ł͑��Ђƈ�����悷�郌�x�����ւ��Ă��܂����B
�@70�N�㏉�߂���A�A�i���O�v���[���[�̋쓮�����͒ᑬ��]���[�^�[�Ƀ^�[���e�[�u���̃Z���^�[�X�s���h��������A������_�C���N�g�E�h���C���iDD�j���嗬�ɂȂ��Ă��܂������AMICRO��DD�ɂ͂��܂�S�D�����]���̃x���g�h���C�������̃v���[���[�����s���Ĕ������Ă��܂����B����ɂ̓n�C�G���h�N���X�ɂ̓S���x���g�̑���Ɏ��Ń��[�^�[�ƃ^�[���e�[�u�����q�������h���C���̐��i�������B�����ڂ����W���ł������A���͒n�ɑ����t�����悤�Ȉ��芴������A��������僁�[�J�[���Ɗ��S�������̂ł��B
�@CD-M2��MICRO�̃A�i���O�v���[���[�����̃m�E�n�E����������Ă���A���ɐU����ɂ͖��S�̎�i���u�����Ă��܂����B������10cm�̃X�����^�C�v�Ȃ���A�d����22kg������A���̂��Ȃ�̕������L���r�l�b�g��⋭����������p�l������߂Ă��܂����B�s�b�N�A�b�v������PHILIPS�Ђɂ��X�C���O�A�[���E���J�j�Y�����̗p�B�l�I���z�ł����A�X�C���O�A�[��������CD�v���[���[�͉��ɉ��x��������A�g�F�n�̃T�E���h����ۓI�������悤�Ɏv���܂��B
�@CD-M2�͂��Ă̒m�l�����L���Ă��Ē������Ă���������Ƃ�����܂����A�E�b�h�p�l���t���̍��������ӂ�郋�b�N�X�ɂӂ��킵���A�������̊��炩�ȓW�J�ł��������Ƃ��v���o���܂��B�������A���łɋN�������ɃK�^�����Ă��āA�㕔�p�l�������O���āu�蓮�v�ŃX�^�[�g�����Ȃ��Ɠ����܂���BCD�v���[���[�̎����͒Z�����Ƃ��ĔF����������ł��B
�����ԍ��F7764309
![]() 1�_
1�_
�@��ԍŏ��Ɏ�����ɓ��ꂽCD�v���[���[��ONKYO��Integra C-700�Ƃ����@��ł����B80�N�㔼�ɔ������ꂽ���i���Ǝv���܂����A�h��ȐF�t���͂Ȃ����̂̒��f�Ńo�����X�̗ǂ��v���[���[���������Ƃ��o���Ă��܂��B
�@82�N��CD�v���[���[���s��ɏo���悤�ɂȂ��������A�悭�f�B�[���[��[�U�[�̊ԂŌ����Ă������ƂɁgCD�v���[���[�̓f�W�^���M���������Ă���̂ŁA�v���[���[�ɂ�鉹�̈Ⴂ�͑��݂��Ȃ��h�Ƃ����g����h������܂����B�Ƃ��낪���ۂ͋@��ɂ�鉹�F�̈Ⴂ�͗�R�Ƃ��Ă���A�����������s�b�N�A�b�v���i���g���Ă��Ă����[�J�[�ɂ���ĉ��̏o�����قȂ�Ƃ������������炩�ɂȂ�ɏ]���āACD�v���[���[�����I�����ɒl����R���|�[�l���g���Ƃ����F�����L����悤�ɂȂ�܂����B
�@���T�C�g�ȂǂłƂ��ǂ��g�s���A�E�I�[�f�B�I�̐��ނ������炵���̂�CD�v���[���[�̓o�ꂾ�I�h�݂����Ȉ�߂�ڂɂ��܂����A����͊ԈႢ�ł��B�Ȃ��Ȃ�ACD�v���[���[�����y����80�N�㒆����́A�I�[�f�B�I�̑S������ł�����������ł��B�����ăs���A�E�I�[�f�B�I�����O�ɂȂ����̂́A���̌o�ς��s���ɂȂ������Ɠ������ł�������A���̂��Ƃ͂Ȃ��A�I�[�f�B�I�����ۂ̌o�σ}�N���ƃV���N������Y�Ƃ̂ЂƂ̃Z�N�V�����ɉ߂��Ȃ������̂ł��B
�@���āA�Ƃ����̐̂ɑ���ꂽ�Ǝv���Ă����gCD�v���[���[�̓f�W�^���M���������Ă���̂ŁA�ǂ���ꏏ�h�Ƃ����i���M�ɋ߂��j�����́A�s�v�c�Ȃ��Ƃɍ����ꕔ�Ő����c���Ă���悤�ł��B�Ɠd�ʔ̓X�ł́gCD�v���[���[�͂ǂ��I��ł��A�o�Ă��鉹�͓����h�ƁA���X�ƌ����Ă���X���ɉ��x���������܂������A�e��f���ł��gCD�v���[���[�͋@�킲�Ƃ̉��̍��͖������ėǂ����x���Ȃ̂ŁA�������̂ŏ\���h�Ƃ������Ӗ��̂��Ƃ𐁒����Ă���҂������悤�ɋL�����Ă��܂��B�܂��A���������Ă��l�̎��R�ł͂���܂����A�E�\�͍���܂��ˁB���ɉƓd�X�̓X�����킴�킴����ȃf�^�������I����Ƃ����̂́A���i�m���̂Ȃ�������G�����Ă���悤�Ŏ����Ă��܂��܂�(^^)�B
�@CD�v���[���[�́g���̓�����h�Ȃ̂ł����A�A�i���O����ɂ͓������g���̓�����h�ł��������R�[�h�v���[���[�Ɏ���I�[�f�B�I�t�@���͂��Ȃ������悤�ɁACD�v���[���[�̑I�����\���ᖡ���K�v�Ȏ����ł���̂́A�����܂ł��Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F7770613
![]() 1�_
1�_
���E�������
������N�x�͒��́u�撷�v������Ă��܂����B���̍s���Ɏ�o����đ�ςł����B
�I�[�f�B�I���͎������ʂɒ������ނ��Ǝv���܂��B�܂����̐̂͗ǂ������H�I�̘b��ɓ��鎞
�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�̂͂����ł��ˁB
http://www.audio-heritage.jp/
�������g���܂��ˁB
http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/index.html
�����ŏ��ɔ�����CD�v���[���[��SONY��CDP-502ES�ł����B���̎��́E�E�E�v���o���܂���B
�Ȍ㐔�䔃���ւ��č���SACD/CD�v���[���[��SCD-XA9000ES�ł��B����G�\��X-05����������
�@��܂��������̃v���[���[���ǂ��ł��˂��B����CD�v���[���[�ɓ�������z�Ƃ��Ă�
���̕ӂ肪����ł��B�����ADVD�I�[�f�B�I��SACD�}���`�������܂�������������Ƃ�����
SA-60�����m��܂���B�E�E�E���݂̍ŗD��̓f�m����BD�v���[���[��DVD-3800BD�ŁA�܂���
���w���\��ł��B
�����g�p���Ă����ԌÂ��I�[�f�B�I�@��̓p�C�I�j�A�̃��R�[�h�v���[���[��PL-1800��
���B���R�[�h�v���[���[��5�`6�䔃���ւ��܂����BPL-1800�̓N�H�[�c�E���b�N���o�邿���
�ƑO�̐��i�������Ǝv���܂��B�Ƃ͌����Ă�����3�N���炢�g���Ă��܂��E�E�B
�����ԍ��F7773482
![]() 1�_
1�_
�@130theater����A����ɂ��́BPL-1800�Ƃ͉��������ł��ˁB�m��PIONEER�ɂ͂��̉���PL-1200�i���������ȁA���M����܂��� ^^;�j�Ƃ����@�킪����ATechnics��SL-1200�Ƌ������Ă܂�����ˁBPL-1800�̃A�[���̓J�[�{���t�@�C�o�[���ł������ǁA����PIONEER�͂��̑f�ނɋÂ��Ă��āA�X�s�[�J�[�̃R�[���ɂ��悭�g���Ă������Ƃ��v���o���܂��B
�@SONY��CD�v���[���[�͎g���Ă������Ƃ�����܂��BCDP-557ES�Ƃ������@�킾�����Ǝv���܂����A�Ƃɂ������ʓ����^�ŁA�������������B���������炱�̒l�i�ł͍��Ȃ��ł��傤�BSONY��SACD�̊��U����ł������ǁA����ɂ��Ă͎p�����y�э��������̂ɂ͋C�ɂȂ�܂����B�{�C�ŕ��y�����悤�Ǝv������A�����ȁgSACD��p�v���[���[�h�𑽐��������āA�\�t�g���V����S��SACD�ł������[�X������悤�Ȑϋɐ����~���������Ƃ���ł��B
�@�f�B�[���[�̘b�ɂ��ƁA�u���[���C�f�B�X�N�̃t�H�[�}�b�g���������������㉹�y���f�B�A���o���邩������Ȃ��E�E�E�E�Ƃ̂��Ƃł����A�ǂ��Ȃ��ł��傤���˂��B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�����ԍ��F7775433
![]() 1�_
1�_
�@�{����DIATONE�i�_�C���g�[���j�ɂ��ď����Ă݂܂��BDIATONE�͎O�H�d�@�̃I�[�f�B�I�E�u�����h�ŁA���ɒm���Ă����̂��X�s�[�J�[�ł��B1947�N�ɎO�H�d�@��NHK�Ƌ����J���������j�b�gP-62F�����̌����Ƃ��A1958�N�Ƀ����[�X���ꂽ�����Ǘp���j�^�[2S-305�ɂ��A���̖��͑傫���m����悤�ɂȂ�܂����B
�@�����p�ł���Ƀx�X�g�o�C�̏�ʂ��߁A70�N��ɔ��\���ꂽDS-251����т���mk2�́A�I�[�f�B�I����p�X�s�[�J�[�̑㖼���Ƃ��Ĕ���ɔ��ꂽ���̂ł��B
�@�����ŋ��k�ł����A���Y�X�s�[�J�[�ŗB��M�p���Ă����̂�DIATONE�̐��i�ł����B���Z���̎��Ɏ�ɓ��ꂽ�ŏ��̃I�[�f�B�I�Z�b�g�̃X�s�[�J�[��DIATONE�i�������A���А��i�Ƃ̓O��I�Ȓ�����ׂɂ�茈�肵�܂����j�B����ȗ��A2�N�Ԃ���ONKYO�̃X�s�[�J�[���g���Ă��������������A�����Ɖ䂪�Ƃ̃��C���X�s�[�J�[��DIATONE�ł��B
�@DIATONE�X�s�[�J�[�̓����́A�܂������B�������Ȃ����Ƃł��B�ォ�牺�܂Ńs�V�b�Əo�āA���������ɃN���A�B����ɍ���̈ꕔ�ɔ����ȉ�������A���ꂪ�����������q��ɂȂ��ă��X�i�[�ɍ~�肩�����Ă���悤�Ȗ��͓I�ȓW�J�������܂����BDIATONE�̃T�E���h�Ɋ����ƁA���̍������[�J�[�̃X�s�[�J�[�Ȃ�āA�������邭�Ē��������̂ł͂Ȃ������ł��B
�@����������ȗ������ɂ߂�DIATONE���A99�N�ɂ͏��ł��܂����B���x�������Ȃ̂ɎO�H�d�@���P�ނ����̂́A���̌�̃I�[�f�B�I�s����������ł����Ƃ������Ă��܂����A�^���͕�����܂���B�Ȃ��ߔN�A��@�킾��DIATONE�u�����h�̃X�s�[�J�[���������܂������A��{100���~�Ƃ��������i�ł܂Ƃ��Ɏ������o���Ȃ��Ƃ�������Ȑ��i�ɂ��A�������ėǂ����Ǝv���܂��B
�@�ŁA�����������_��DIATONE���t�����C���i�b�v�ŕ������Ă����Ƃ��āA���ꂪ�̂̂悤�Ƀx�X�g�Z���[�ɂȂ�̂��Ƃ����ƁA�傢�ɋ^��ł��B�ǂ����ĈȑO��DIATONE���悭���ꂽ���Ƃ����ƁA���ɑI�Ԃ��̂��Ȃ��������炾�Ǝv���܂��B�����ł́g��l�����h�ŁA�̂��畁�y���Ă����C�O���́g�W���Y�𐨂��悭�点��JBL�h�Ɓg�N���V�b�N���܂�����ƒ�������TANNOY�h���炢�����Ȃ������̂ŁA���𑜓x�ŃI�[���}�C�e�B�ɒ������Ƃ��������̃��X�i�[��DIATONE�ɍs�������͎̂����̗��ł����B����ǂ��ADIATONE�Ɠ���������𗽂��𑜓x�������A���������������Ċy���������o���C�O�u�����h�������������Ă��Ă��錻��ł́A������J���o�b�N���Ă��d���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�@�l�b�g�I�[�N�V�����ł�DIATONE�̐��i�͂悭�o�i����Ă��܂����A�قƂ�ǂ�DIATONE�̃X�s�[�J�[�͖��^�ł��邽�߂��A�n�C�p���[���Ԃ�����ő剹�ʍĐ����Ȃ��Ɛ^���͔������Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B���킹��A���v�̓I�[�N�V�����ł̗��D���i�ł͂Ȃ��A���̒艿����ɂ��Ă���Ɍ��������N���X�̂��̂�I�Ԃׂ��ł��傤�B
�����ԍ��F7775440
![]() 2�_
2�_
�@�O��DIATONE�ɂ��ď����܂������A�{���͓������Â�����̃X�s�[�J�[���[�J�[�ł���A���݂��L�x�ȃ��C���i�b�v��i���Ă���ONKYO�Ɋւ��ďq�ׂ܂��B
�@���̃T�C�g�ł�ONKYO�̃X�s�[�J�[�͐l�C������A�f���ł̍w�����k�ɂ��������X���b�h�����Ă��Ă��܂����A���l�Ƃ��Ă͂����Ƃ��ǂ��Ƃ͎v���܂���B���R�͉����Â�����ł��B
�@�O�̃A�[�e�B�N���Łu2�N�Ԃ���ONKYO�̃X�s�[�J�[���g�����v�Ə����܂������A�킸��2�N�Ŏ�������̂͂��̈ßT�ȃT�E���h�ɑς����Ȃ���������ł��B�������͕��������̗ǂ��Ɏ䂩��āA�����Ă��������Ă���DIATONE���炿����ƖѐF��ς��悤�Ƃ��āA�����āu舒B�ł͂Ȃ��Ƃ��낪�C�ɂȂ邪�A�G�[�W���O�ʼn��Ƃ��Ȃ邾�낤�v�Ɠ���ł̍w���ł����B���ʂ͎��s�B����ς�y���C�����őI��ł̓_���̂悤�ł��B
�@�������ONKYO�̐��i�͎����g���Ă����X�s�[�J�[�Ƃ͕ʂ̑f�ށE�ʂ̋K�i�ō\������Ă��܂����A��͂薾�邳���S�R����Ă��܂���B�Â������o��Ƃ����̂́A�v�҂����y���y����ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ�������̂ł��B���Ԃ�v�Җ{�l�́u����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�I���͉��y����D�����I�v�ƌ�������̂�������܂��A���y�̒������̃x�N�g�������y���D�҂ƕʂ̕��ʂ������Ă���Ƃ����v���Ȃ��ł��B
�@�ł͂Ȃ�ONKYO�̃X�s�[�J�[�͐l�C������̂��B��ɂ͂���͕i�����̖��ł��傤�B�s���A�E�I�[�f�B�I�̃R�[�i�[�̂���Ɠd�ʔ̓X�͋ɏ����ɂȂ��Ă��܂������A�~�j�R���|�̔����͂����Ă��̃V���b�v�ɂ͂���܂��B�����ő傫���ڗ��̂�ONKYO���i�ł��B�܂�͋q�Ƃ��Ă͉����@������Ƃ���ƁA���R��ONKYO���i������������Ȃ���ԂɂȂ��Ă���킯�ł��B
�@������̗v���́AONKYO�̃X�s�[�J�[�͈�ʃs�[�v������ԍD�މ��y�ɍ��킹�ă`���[�j���O����Ă��邱�Ƃł��B�����܂ł��Ȃ��A���̉��y�W�������Ƃ�J-POP�̂��Ƃł��BJ-POP�́A�F�C�s�݂̃h���V�����ʼn��s�����Ȃ��\�ʓI�Ș^���ɂ́A���F�ɋC��z�邱�ƂȂ��������B�I�ɉ����o�����Ƃ�g��Ƃ���ONKYO�̃X�s�[�J�[�̓W���X�g�t�B�b�g�ł��B���ăN���V�b�N��W���Y�A���ă|�b�v�X��ONKYO�̃X�s�[�J�[�Œ����Ă��u���́v�܂������y��������܂���B
�@���ƍŋ߂�ONKYO�̃X�s�[�J�[�Ɋւ��ċC�ɂȂ邱�Ƃ́A�ٗl�Ȃ܂ł̔\���̒Ⴓ�ł��B�����܂ł��Ȃ����Ђ̃f�W�^���A���v�ŋ��͂ɋ쓮���邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���̂ł����A�q���A���v�����肵�Ă���̂́A���Ђ̃X�s�[�J�[���~�j�R���|�̉�������ō���Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���Ǝv���܂��B
�@�̂�DIATONE�̃X�s�[�J�[�́A���������ł����B���Đ��i�ɔ�ׂ�Ζ��邳�͂܂�ő���܂��A����ł����Y�̒��ł͍ł��������邩�����ł��B���ꂪ����DIATONE���i���g�������Ă������R�̈�ł��������̂ł����A����ONKYO�Ɍ��炸�A���Y�X�s�[�J�[�́i�ꕔ�������āj�قƂ�LjÂ�������ł��B���͕ʂɔ����i��^�̃X�^���X������Ă���킯�ł͂Ȃ��ł����A���ƃX�s�[�J�[�Ɍ����Ă͊C�O�u�����h�ɖڂ��s���͎̂d�����Ȃ���Ԃł��B
�@���낢��ꌾ��悵�Ă��܂������AONKYO�̃A���v��CD�v���[���[�͍����]�����Ă��܂��B�F�t���̏��Ȃ��t���b�g�w���ŁA�q���X�s�[�J�[�̓�����ǂ��o���Ă���܂��B�ł��A10���~���A-1VL�����u�ŏ㋉�@��v�Ƃ����͎̂₵������B�I�[�f�B�I�t�@�����[������悤�ȏ�ʃ��f���i�Z�p���[�g�A���v�Ƃ��j���o���ė~�������̂ł��B�X�s�[�J�[���̂�GRAND SCEPTER�̂悤�ȍ����@�������[�X���Ă��܂������A���ł͌���e������܂���B�܂��A����Ȃ̂Ɍ������������~�j�R���|���S�ɐ��i����ׂ邱�Ƃ́A����Ӗ������o�c��������܂��ǁE�E�E�E�B
�����ԍ��F7780384
![]() 1�_
1�_
���E�������
ONKYO�̃X�s�[�J�[�ł����E�B�g������������܂��B�����e�N�j�N�X��SB7000(�e�N�j�N�X�V)���g���Ă��܂������A�g�D�C�[�^�[�̑O�ɓ\���Ă������X�|���W��������ƐG��ƃ{���{�����Ă��Ă��܂��A�������낻�납�Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B�����œo�ꂵ���̂�ONKYO��D-77�Ƃ����S�L���E�p�[(59800�~)�V���[�Y�̃X�s�[�J�[�ł��B�N��ȃf�W�^���T�E���h��搂��A�s���A�N���X�J�[�{���t�@�C�o�[���g�����V�X�e���ł����B�[�i�������ۂ̓N���A�[�Ŗ����A�e�N�j�N�X�V�Ƃ͐����̉��ł����B�Ƃ��낪1�����Ԃ��炢�o����������ǂ������[���������Ƃ������A���̐S�ɑi������̂��Ȃ̂ł��B2�����o�������ɔ����ւ��Ă��܂��܂����B���̃X�s�[�J�[�̓_�C���g�[����DS-1000C�Ƃ����P�u���[�A���~�b�h�t�@�C�o�[��22cm�E�[�t�@�[2���s���A�{�����̃~�b�h�����W/�g�D�C�[�^�[�̃X�s�[�J�[�ł��B���̃X�s�[�J�[�͕s���͑S���Ȃ��A���`�Ǝg���܂����B���ƃ_�C�g�[���̏o��ł����B
�����ԍ��F7782103
![]() 0�_
0�_
�@130theater����A����ɂ��́BSB7000�����������@��ł��B�����ӗ~�I�ȏ��i�W�J�����Ă���Technics�̒��ł��A�Ƃ�킯��i�����ڗ����i�ł����ˁB���j�A�t�F�C�Y�����ƌĂꂽ���j�b�g�z�u���@�́A���̌�̃X�s�[�J�[�̃X�^�C���ɉe����^�������̂ł��B
�@���͎��̎g���Ă���ONKYO�̃X�s�[�J�[��D-7�̃V���[�Y�̈�ł����B���͊m���ɑO�ɏo�܂����A�L��ʂ艜�s���̓[���ł��B�Ƃɂ�������\�����ɂ��Ă͉����l�����Ă��Ȃ��d�l�ł����B�����Ă��̈Â����F�A�悭2�N�Ԃ����L���Ă������̂��Ǝv���܂��B
�@DIATONE�͍Ō�����f���ɂȂ�ƁA����̉����}�����ăt���b�g�ȓW�J�ɂȂ��Ă��܂����i�v�҂��ς���������ł��j�B���̏��L���Ă���X�s�[�J�[�����̍Ō���̃V���[�Y�ŁA�̂Ȃ����DIATONE�T�E���h��m��҂ɂƂ��Ă͂�����ƕ�����Ȃ�������A�����ւ���\�肵�Ă��܂��B���Ԃ�C�O�u�����h�̐��i��I�Ԃ��ƂɂȂ�Ǝv���܂����A������胁�[�J�[���^�ɉ��y�D���ȃG���W�j�A���N�p���āA�����Ċy�����X�s�[�J�[������Ă��炢�����ƁA�����v���܂��B
�����ԍ��F7784699
![]() 0�_
0�_
���E�������
�_�C���g�[���̃X�s�[�J�[�̓s���A�p�Ɏg���Ă��܂������AAV�p��DS-700Z�Ƃ���65,000�~�艿�̃X�s�[�J�[���܂����B�������̃X�s�[�J�[��AV�ŕ������ɂ͕s���͗]�薳�������̂ł����A�f�������Ŏg���Ɖ����ɏW������ׂ��A�ǂ�����������肸�s���ł����B���̌�ADS-1000ZA�Ƃ���130,000�~�艿�̃X�s�[�J�[���m��35���������炢�Ŕ����Ă����̂Ŕ����܂����B���̃X�s�[�J�[��DS-700Z�Ƒ傫���͂قڈꏏ�A�����������Ă��܂����ʕ��łƂĂ��C�ɓ���܂����B�s���A��DS-1000C��AV��DS-1000ZA���A�Ƃ��������đO����4��̃_�C���g�[���X�s�[�J�[������ł��܂����B(���A�T���E���h�p��DS-700Z���܂����B)���̌�A�O�H���_�C���g�[����P�ނ��Ă��܂��ƂĂ��c�O�ł��B
���̌�̓_�C�g�[���̑I�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�̂��瓲�ꂾ����JBL�Ɉڍs���܂����B�����Ƃ�JBL�Ƃ����Ă��X�^�W�I���j�^�[�n�ł͂Ȃ��A�R���V���[�}�[�p�̓��Ɂu�r�v���t�����f���ł��B�����Ƃ��ŏ���JBL��VSA-2100�Ƃ������f���ł����B����������ɂ��ADS-1000ZA�̓��A�T���E���h�ɉ܂����B
�����ԍ��F7786033
![]() 1�_
1�_
�@Technics7�̘b���o���̂ŁA�{����Technics�i�e�N�j�N�X�j�ɂ��ď����Ă݂܂��BTechnics�͏����d��̃I�[�f�B�I�E�u�����h�ŁA���݂�DJ�@��ɂ��̖����c���݂̂ł����A�I�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ��Ă����Ȃ�̎��т��グ�Ă��܂��B
�@��Ԃ̌��т�70�N�㏉���Ƀ_�C���N�g�E�h���C�������̃^�[���e�[�u�����J���������Ƃł��B����܂ł̓��[�^�[�ƃe�[�u�����S���x���g�Ōq�����x���g�h���C��������A��]�^���`�B�p�̃J���i�H�j����݂������A�C�h���[�h���C���������嗬�ł������A���]���[�^�[�̊J���ɂ�胂�[�^�[�̎����e�[�u���̃Z���^�[�X�s���h���ɒ��������邱�Ƃɐ������܂����B��]������}���A���肵���쓮���\�ɂȂ������Ƃɂ��A���̕����͂܂������ԂɍL�܂�܂����B�Ȃ��AHIPHOP�~���[�W�b�N�Ŏg�p����X�N���b�`�́A���̃_�C���N�g�E�h���C�������̃^�[���e�[�u�������ɂ͐��܂�Ȃ������ƌ����Ă��܂��B
�@�J�Z�b�g�f�b�L�̓��̓��[�^�[�ɍŏ���LED���g�p�����̂�Technics�ł����A�O�q�̃��j�A�t�F�C�Y�^�X�s�[�J�[��A�N���XAA�ƌĂꂽ�Ǝ��̃A���v����K�i�A��N�ɂ͐U���Ɏ���t���������X�s�[�J�[��A����ȕ��ʌ^���j�b�g�ȂǁA���̐�i���͐�僁�[�J�[�ȏ�ł����B
�@�������A���l��Technics�̉��ɒ����ԓ���߂��A���������͐������Ǐ����̂Ȃ������Ǝv���Ă܂����B�Ƃ��낪90�N��ɔ��\���ꂽ���C���i�b�v�́A����������˂��l�߂���ɓ��B�����悤�Ȑ�������܂鉹���E���\������Ă���A�傢�Ɋ��S�������̂ł��B�悤�₭���Ђ̐��i�̓������������n�߂����A�I�[�f�B�I�E�u�����h�Ƃ��Ă�Technics�͏I�����Ă��܂��܂��B���Ɏc�O�Ȃ��Ƃł��B
�@Technics����僁�[�J�[�𗽂��Z�p�I�A�h�o���X���̂́A����Ȏ����������Ɠd���[�J�[�ɂ�鎖�Ƃł���������ɑ��Ȃ�܂���B�������A�Z�p�ʂŗD�ʂɗ����Ă��I�[�f�B�I���Ă̂͏o�Ă��鉹�����ׂĂł�����A�e�N�m���W�[�����T�E���h�ɔ��f�����Ƃ͌���܂��A�V�����Z�p�I��Ă�������������Ƃ�����Ă��ꂽ���Ǝ��̂͗L�����Ƃł��B
�@�s���A�E�I�[�f�B�I�ׂ͖���W�������ł͂Ȃ��Ȃ��Ă܂����A����x���Ɠd�̎Q����]�݂����E�E�E�E�Ǝv���Ă��A�Ж����u�p�i�\�j�b�N�v�ƕς��A�ڐ�̗��v��Nj�����O���[�o����ƂɒE�炵�悤�Ƃ��铯�ЂɊ��҂��Ă��A�d�����Ȃ��悤�ȋC�����܂��i�ÑR�j�B
�����ԍ��F7787091
![]() 0�_
0�_
-> 130theater����
�@DIATONE��4���V���[�Y�Ɖ��̃N���X�̃X�s�[�J�[�͊m���ɃO���[�h���Ⴂ�܂����ˁB5���̃V���[�Y������܂������A4���ȏ�͓��Ђ��ςݏグ�Ă�����^�u�b�N�V�F���t�́g�����h�݂����ȂƂ��낪�������悤�ł��B
�@���������X�^�W�I���j�^�[�^��2S-305�́A�����ʂ��Ă������Z�̉��y���ɂ���܂����i���F�ŏ��ɔ������ꂽ58�N���ł͂Ȃ��A�����ƌ�N�ɍ��ꂽ���f���ł����� ^^;�j�BLUXMAN�̐^��ǎ��A���v�ŋ쓮���Ă���A�����ꉹ�̗ǂ��X�e���I�̂��鉹�y���Ƃ��Ă�����Ƃ����b��ɂȂ������̂ł��B
�@DIATONE�̓Z�p���[�g�A���v���o���Ă��āA�������v���ƃ��C���ʁX�̋@��Ȃ̂ł����A�o�������̃��{���ăv�����C���A���v�݂����Ȍ`�ł��g����Ƃ��������Ȑ��i�ł����B�A�i���O�v���[���[���A���R�[�h���c�ɃZ�b�e�B���O���郆�j�[�N�Ȃ��̂����Ă������Ƃ��v���o����܂��B
�����ԍ��F7789901
![]() 0�_
0�_
���E�������
�e�N�j�N�X�ƌ����A���R�[�h�p�̃J�[�g���b�W�ł���Ă��r���܂�����ˁH�I�B�T�}���E���E�R�o���g�����g����EPC-205C-�U�Ƃ����J�[�g���b�W���g���Ă��܂����B�V���g���܂����B���ł��{�͎̂����Ă���̂ł����A�c�O�Ȃ�������j�����ɂ���܂���B�V�̓{�����̃p�C�v���J���`���o�[�Ɏg���Ă��ē����̍Ő�[�Z�p�������v���܂��B
����Ƀe�N�j�N�X���i�̓t���I�[�g�̃��R�[�h�v���[���[��SL-1300���g���Ă��܂����B�v���o���܂����A����ƃp�C�I�j�A��PL-1800�p���Ă��܂����B
������A�e�N�j�N�X�̓A���v�ł����������o���܂����ˁB10000�ԃV���[�Y�̓e�N�j�N�X�����͂������ĊJ���������i�ł����A�����̎��ɂ͑S���肪�ł����߂邾���ł������A���̊J���Z�p���g�����Ƃ���SU-9600�Ƃ����A���v(�v��)����������A������܂����B�p���[�A���v�̓A�L���t�F�[�Y(�ŏ��̓P���\�j�b�N)�̑�ꍆ�@��P-300�����Ɏg���Ă���(�v���̓p�C�I�j�A��SA-100�Ƃ����v�����C���A���v�̃v�����g�p)�e�N�j�N�X��SU-9600�ƃy�A�ɂ��܂����B
�����̋�����7�`8���~�������ł��傤���H�A�v���ƃp���[��40.5���~�Ƃ������i�͐����w�L�т��������̂��Ǝv���܂��B
�E�E�E�e�N�j�N�X���i�͂�����E�E�`���[�i�[�ł��B������FM���d�v�ȉ��y�\�[�X�ŏd�����Ă��܂����B�p�C�I�j�A�̃`���[�i�[����e�N�j�N�X��ST-3500�Ƃ����`���[�i�[�ɔ����ւ��܂����B�Ȃ��Ȃ��ǂ����������L��������܂��B
�e�N�j�N�X�E�E���Ղ�����Ɛ����ӗ~�I�Ȑ��i���o���Ă��܂����ˁB
�����ԍ��F7791566
![]() 0�_
0�_
-> 130theater����
�@���������ATechnics�̓J�[�g���b�W�̕���ł����т��グ�Ă��܂����B�_�C���N�g�E�h���C���̖{�Ƃł����������Ƃ���A�C�����������Ă����̂ł��傤�B
�@�����Technics�Ŏv���o�����̂́A70�N�㖖�ɏo�Ă����u�R���T�C�X�E�R���|�v�̃V���[�Y�ł��BLP���R�[�h�Ɠ����T�C�Y�̃A���v�ނŁA���������ɍ��������ł��B���i�������͂Ȃ������ł����ǁA�����Ĉ����ł͂Ȃ��B�Ⴂ�T�����[�}�����w�L�т��ē͂����x�B���A�p�[�g�ɒu���ƕ����Ă��܂��܂����A���������}���V�����ɓ�������ƃC���e���A�ʂŃt�B�b�g����悤�ȃX�^�C���b�V���ȃf�U�C�����v�`�F�b�N�ł����B
�@�����̃I�[�f�B�I�s����Ŕj����ɂ́A���������u�R���T�C�X�E�R���|�v�̂悤�ȃR���Z�v�g�����������i���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���܂ł��d������ȃt���T�C�Y�̃A���v�ނ��������Ă���e���[�J�[�́A���낻��}�[�P�b�g���L���邽�߂Ɏa�V�Ȑ��i�𓊓����Ăق����ł��ˁB
�@FM���d�v�ȉ��y�\�[�X�ł����ȁB�������A���͉��y���������蒮������ԑg�����Ȃ��Ȃ��Ď₵������B�܂��g�[�N��AM�ɂ܂����āAFM�Ȃ�ł͂̃v���O�������ɕ��S���Ăق������̂ł����E�E�E�E�B
�����ԍ��F7792096
![]() 1�_
1�_
�@�����TRIO/KENWOOD�ɂ��ďq�ׂĂ݂܂��B�́A�O��I�[�f�B�I���[�J�[�ƌ����Ă����A���̒��̈��TRIO�ł����i���Ƃ̓��PIONEER��SANSUI�ł��j�B�n����1946�N�A�Ж���TRIO�Ƃ����̂�60�N�ł��B�����@��̐��삩��n�܂�A��N�I�[�f�B�I�ƊE�ɎQ�����Ă��܂��B
�@�����I�[�f�B�I�ɋ������������̂�70�N��㔼�ł����A���̍�����TRIO�̓��W���[�ȃu�����h�ł����B�����ŏ��Ɏ�ɓ��ꂽ�A���v��TRIO�ŁA�N���A�Ńt�b�g���[�N�̌y�������i�������A�͊�������j�͎Ⴂ�w�𒆐S�ɐl�C���W�߂Ă��܂����B��ԋ����[�������̂��A�Z�p���[�g�A���v��L-07C��L-07M�̑g�ݍ��킹�ł��i77�N�����j�B
�@L-07M�̓��m�����̃p���[�A���v�ŁA���E�̃X�s�[�J�[�̂����߂��ɒu�����Ƃ�O��Ƃ��Ă��܂����B�����ăR���g���[���A���v��L-07C�̓��X�i�[�̎茳�ɔz�u���A�v���ƃ��C���̊Ԃ����P�[�u���Ō��ԂƂ����g���������߂Ă��܂����B���̍��́u�X�s�[�J�[�R�[�h��1m�ȉ��̒����ɗ}����ׂ����I�v�Ƃ̍l�����L���F�m����Ă���A���̐��i�����̃R���Z�v�g�ɓY���ĊJ�����ꂽ�悤�ł��B�Ȃ�v���ƃ��C���̊ԂŃ��C���P�[�u���������ėǂ��̂��Ƃ����˂����݂����邩�Ǝv���܂����A���̍��͒�������������܂Ƃ��Ȗ����p�X�s�[�J�[�P�[�u�������݂����A�܂�����̍�ƌ����ėǂ�������������܂���B�������Ȃ���A�p���[�A���v�����X�s�[�J�[�̒��߂ɒu���Ƃ������C�A�E�g�́A���b�N�ɋ��Ȃ����ɂ͕֗����������ȂƁA���͎v���܂��i�j�B
�@�Ȃ��AL-07C��L-07M�ɑ����̗ǂ������X�s�[�J�[�́A����ƌĂꂽYAMAHA��NS-1000M�ł����B���̂������I�[�f�B�I�G�����f�B�[���[���A����ɂ��̑g�ݍ��킹�𐄏����Ă������̂ł��B
�@TRIO�͂��Ƃ��Ƃ͖����@�탁�[�J�[���������ă`���[�i�[�̕i���͐���ŁA�����̖���ݏo���܂����B����ɃA�i���O�v���[���[���d�ʋ��𓊓����A�X�s�[�J�[�����т����ACD�v���[���[�̊J���ɂ��ӗ~�I�ł����B86�N�ɂȂ�ƎЖ����u������ЃP���E�b�h�v�ɕύX�BKENWOOD��TRIO�̗A�o�i�����u�����h�ł������ATRIO�Ƃ������O�������ł͗ǂ��C���[�W��������Ă��Ȃ����Ƃ����o�����炵���A���W�ꂷ��Ɏ������炵���ł��i����҂ɑ��钲���ł́ATRIO�Ƃ����g���I���˂�A�z������Ƃ�����������ꂽ�̂��A���Ȃ�V���b�N�������Ƃ��E�E�E�E�j�B
�@�ߔN�I�[�f�B�I�̐��ފ��ɓ���AKENWOOD�̓J�[�I�[�f�B�I�̕���ŌЌ��𗽂����ƂɂȂ�A���Ƃ̓~�j�R���|���炢�ŁA�s���A�E�I�[�f�B�I�̕���ɂ̓J���o�b�N������Ă��܂���B2006�N�ɑn��60���N���L�O���āuTRIO�v�u�����h���i���ꎞ�I�ɔ�������܂������A������Ŗ{�i�I�ȕ�����]�݂����Ƃ���ł��B�S�����̉��F�����t�@�C���������i�𓊓�����A����DENON��MARANTZ�Ȃ͊y�ɏR�U�点��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7792103
![]() 1�_
1�_
���E�������
����́A�I�[�f�B�I��O�Ƃ̃g���I�ł����I�B���̌��݂����L���Ă���ł��Â��@��̓��R�[�h�v���[���[�Ƌ���FM�`���[�i�[������܂��B�Y�o���I�u�g���I�v��FM�`���[�i�[�̓����̍����@��KT-9700�ł��B�`���[�i�[�Ƃ��Ă͈ٗl�ɍ��z�����������o���Ă��܂��B���̕��A�]�������������A�V���Z�T�C�U�[�`���[�i�[����������܂������A������̃g���I�̃`���[�i�[�ɂ��܂����BFM�A���e�i���V�f�q�̑傫�ȕ������Ă܂����B�����̓T���p�`�c�[�g����TEAC�̃I�[�v�����[���̃f�b�L�������Ă��āANHK-FM��N���́u�����t�v������^��������������܂����B���j�A�t�F�[�Y�̃e�N�j�N�X�V�Ƌ��ɂ��̐��X�����̉��Ɋ������܂����B
�E�E�E����ł����̖��ʂɒ����I�[�f�B�I���ł�FM�`���[�i�[��3�䂵�������ւ��Ă���܂���B��̃e�N�j�N�X�̃`���[�i�[�Ƃ��̑O�̃p�C�I�j�A�̃`���[�i�[TX-60��3�䂾���ł��B�܂��AKT-9700���甃���ւ��Ă��Ȃ��̂ł����Ȃ�܂����E�E�E�B
�����w�������g���I�̐��i�͐U��Ԃ�Ƃ������������܂���B�Ж����P���E�b�h�ɕς��ďo�����Ō�̍����v�����C���A���v�́uL-A1�v�ł��B�A���v�̓p�C�I�j�A���e�N�j�N�X/�A�L���t�F�[�Y���I���L���[���T���X�C���P���E�b�h�Ɣ����ւ��܂����B���̃A���v�͑S���s���Ȃ��A�����g���܂����B�����A���̃A���v�͌̏���Ȃ����ɂ��s�������I�ł����������g�����Ƃ������R�����Ŕ����ւ��Ă��܂��A�L���t�F�[�Y��E-407�ɔ����ւ��A�����Č��݂͓������A�L���t�F�[�Y��E-550�ł��B
�����ԍ��F7793098
![]() 0�_
0�_
-> 130theater����
�@TRIO/KENWOOD�̃`���[�i�[�͊m���Ƀn�C�E�N�H���e�B�ł����B�����ŏ����������`���[�i�[�́i�A���v�ƍ��킹�����i�ł����� ^^;�jTRIO�ł����B��N�K�^������ONKYO�̃`���[�i�[�ɔ����ւ��܂������A��M���\��TRIO�̕��������Ă��܂����ˁB70�N���TRIO��KENWOOD���`�ŗA�o���Ă������i�̒��ŁA�n�C�G���h�̒������i���������悤�ȋL��������܂����A����قǗ͂������Ă����݂����ł��B
�@FM�̃A���e�i�̓e���r�̂��������^�ŁA5�f�q�ȏ�̂��̂������Ɏ��t�����炯�������ڗ����܂������i�j�A�}�j�A�̓A���e�i�Ƀ��[�^�[�����t���āA��M�ǂɂ���Č�����ς���Ƃ����悤�ȑ�|����Ȃ��Ƃ�����Ă������̂ł��B�������A�O�ɂ��q�ׂ܂������A���͂����܂ł��Ď�M���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȃv���O���������Ȃ��̂��c�O�ł��B�A�����J�ł�FM�����������Ήf��́g������h�ɂȂ�قǎ����ʂ��[�����Ă��邵�A���[���b�p���ǂ̐��̓A�����J�قǂł͂Ȃ����̂̏o�͂��傫���A��M��Ԃ̗ǂ��Ƃ���Ȃ�Ίe���̕�������x�ɓ���Ƃ��B��i���ł͓��{������FM��i���ɐ���ʂĂĂ���悤�ł��B
�@���������ΐ̂�FM�G����4������������ł���ˁB���ł��uFM fan�v�͒����S�j�̐h���̃I�[�f�B�I�E���r���[���ڂ��Ă��Ă悭�ǂ��̂ł��B
�����ԍ��F7798588
![]() 0�_
0�_
�@�{���͂���KENWOOD��10���Ɏ��{��������VICTOR�ɂ��ďq�ׂĂ݂܂��B���{�r�N�^�[�̗��j�͎��ɌÂ��A1927�N�ɕč��r�N�^�[�g�[�L���O�}�V���Ђ̓��{�@�l�Ƃ��Đݗ�����Ă��܂��B���Ȃ�̎��т���������Ђł������A���܂��Ȃ������d��̎q��ЂɂȂ��Ă��܂��B�r�N�^�[�̔����ɏ��o���������K�V���́A���������Z�p�͂̂����Ƃ��č����{�̂܂܂ł��ẮA���{�̓d�@�Y�ƑS�̂ɂƂ��ă}�C�i�X�ł���Ɣ��f���A���z�̃r�N�^�[�̕��������Ė������ĎP���Ɏ��߂��Ƃ����܂��B���̍��̎��{�Ƃ́A�����̂Ƃ���̍̎Z�͂������ł����A���S�̂̌o�σ}�N��������ɓ��ꂽ�u�̍����l�ނ��������������悤�ŁA���ׂ�������簐i���č����n�������҂��]�ƈ����܂������ᒆ�ɂȂ��o�c�҂��f�J��������Ă��錻�݂̏Ƃ͈���Ă����݂����ł��B
�@VICTOR�͌����_�ŃX�s�[�J�[���t�����C���Ŏ��А��Y���Ă��鐔���Ȃ����̈�ł��B���Ђ̋O�Ղ��X�s�[�J�[�����ɂ͌��܂���B���ɗL���Ȃ̂�70�N��O���ɔ������ꂽSX-3���͂��߂Ƃ����A�̃V���[�Y�ł��B���Ɛ��̃R�[�������g�p���A�G���N���[�W���[�͔��؎d�グ�B�f�U�C���ʂő傫�ȃA�h�o���e�[�W�܂����B
�@�������ASX-3�̌n���ɘA�Ȃ�X�s�[�J�[������������������Ƃ����鎄�ɂƂ��āA�܂������D�݂ɍ���Ȃ����ł����B�Ƃɂ����_�炩������̂ł��B�_�炩�������Ȃ炢���̂ł����A����̌��ʂ��������A����\���T�b�p���ŁABGM�ɂ����g���������Ȃ��A�v����Ƀ{�P�����������̂ł��B���Ȃ��Ƃ�DIATONE�̓G�ł͂���܂���ł����B
�@�ǂ����ē�����SX�V���[�Y�����ꂽ���Ƃ����ƁA�����炭�͍��Y�ɂ͒��������[���b�p�����̃T�E���h�W�J�ł��������Ƃ��傫���Ǝv���܂��B�L��̂Ɍ����Ă��܂��A��������������TANNOY�Ƃ�SPENDOR�̂悤�ȉ��B�u�����h�i���Ȃ��w���A����ŃK�}�������E�E�E�E�Ƃ����b����Ȃ���ł��傤���B�������SX�V���[�Y��TANNOY���Ƃ͉����Ⴂ�܂��B�ł��A�}�b�^���Ƃ������͋C�����͓����ł��B�C���������ł����B���Ƃ����A����ȃ��X�i�[�̐Ȃ��C�������\����Ă���E�E�E�E�Ǝv�������̂ł��i�I�[�i�[�̕��X�A�ǂ����X�C�}�Z���j�B�Ȃ��A70�N�㖖�����Zero�V���[�Y�̃X�s�[�J�[�͒��������Ƃ�����܂���B
�@���݂�VICTOR�̃X�s�[�J�[���D������Ȃ��ł��B���[�b�ƑO�ʂɏo�鉹�ł����A�[�݂͂Ȃ��ł��B�����ONKYO�Ɠ������AJ-POP���������Ȃ��Ǝv���Ă܂��B�������E�b�h�R�[���̃V���[�Y�͕ʂł��B���Y�ɂ͒��������x���̂��鉹�ŁA�����Ė��邭�͂Ȃ����̂́A�������̂��Ȃ����炩�ȓW�J�ł��B
�@����VICTOR�̃��C���i�b�v�̒��ŁA�ӊO�ƈ�ۂɎc���Ă���̂��A���v�ł��B70�N�㖖�ɏo��A-X�̃V���[�Y�́A�X�[�p�[A�ƌĂꂽ���o�̓m���X�C�b�`���O�������̗p���Ă��܂������A�T�E���h�́u���𑜓x�Ȃ̂ɉ��x��������v�Ƃ����X�O�����m�ŁA������SANSUI��PIONEER�̃A���v�Ɣ�ׂĂ������ŏ����Ă��܂����B�f�U�C��������I�ł������A���܂�s��ɂ͎�����Ȃ������悤�ł��B����90�N��ɓ����Ă����AX-S9�Ȃ��������ł����ˁB
�@�J�Z�b�g�f�b�L�������������^���e�[�v�ɑΉ��������A93�N�ɔ��\�����Z�p���[�g�^CD�v���[���[��XL-Z1000A�{ZP-DA1000A�͊ԈႢ�Ȃ�����ł����B�Â�������т̂������A�i���O�v���[���[����̏[���Ԃ�������܂ł�����܂���B
�@���ł̓X�s�[�J�[�ȊO�Ƀ��N�ȃs���A�E�I�[�f�B�I�̐��i���o���Ă��Ȃ�VICTOR�ł����AKENWOOD�Ƃ̍������@�ɁA�����̐��������߂��ė~�����Ǝv���܂����E�E�E�E�i�������ȃ@ ^^;�j�B
�����ԍ��F7798593
![]() 2�_
2�_
�@����͋C����ς��āA�P�[�u���ɂ��ďq�ׂĂ݂܂��B�u�P�[�u���̖����ʼn����ς��v�ƌ����o�����̂�80�N��ɂȂ��Ă��炾�Ǝv���܂��B������̂����ƑO����P�[�u���̉��ɗ^����e���̓}�j�A��]�_�Ƃ̊ԂŎ�荹������Ă����悤�ł����A�����܂ł���́u�P�[�u���̒����v�Ɋւ���c�_�̂悤�ł����B���_�Ƃ��Ắu�P�[�u���́A�Z����ΒZ���قǗǂ��v�Ƃ��������̂������Ǝv���܂��B�P�[�u�����q����Γd�C�I��R��������̂͒N�ł��m���Ă܂�����A���̒�R�����Ȃ��قǓd�C�M���̃��X���������ƍl����͓̂��R�ŁA������Z�������x�^�[���E�E�E�E�Ƃ����ؓ��Ɏ����Ă����͎̂����̗��ł����B
�@�}�j�A��]�_�Ƃ̋����̑Ώۂ��u�P�[�u���̒����v����u�P�[�u���̍ގ��E�\���v�ւƈڂ����̂́A�c���̍ގ���OFC���̗p����n�߂������肶��Ȃ��ł��傤���BOFC�Ƃ�Oxygen-Free Copper�̗��ŁA�_�������܂܂Ȃ�99.995���ȏ�̍����x���̂��Ƃł��B�P�[�u���̐c���̑f�ނł��铺���̂̓����I�Ȓ�R���A�_��������ߏo�����Ƃɂ���Č��������߂�Ƃ������R���Z�v�g�i���ۂ����Ȃ̂��͒m��܂��ǁj�́A�I�[�f�B�I�ƊE�ɂƂ��Ă܂��Ɂu�ڂ���v�������Ǝv���܂��B
�@OFC�͂��̌�Hi-OFC�i�n�C�N���X���_�f���j�ALC-OFC�i���`�������_�f���j�APC-OCC�i�P�������x���_�f���j�Ƃ��������i�����@�[�W�����ݏo���A�܂��ގ��̏��x�����߂�����Ƃ����A�v���[�`��6N�Ƃ�8N�Ƃ����������_�ȉ��̐��l�������悤�ȏ��i������܂����B�����n�߂čw�������s�̂̃X�s�[�J�[�P�[�u���́ALC-OFC�ŏo����AUDIO-TECHNICA���̂��̂ł����i�^�Ԏ��O�j�B80�N�㔼�̂��Ƃ������Ǝv���܂��B
�@��������܂ŃX�s�[�J�[�P�[�u���Ƃ��Ďg���Ă����͓̂d�����ł����B�X�s�[�J�[�ɕt�����Ă����P�[�u���͒�����1.5m�����Ȃ��A�Ѓ`�����l��5m�߂��������K�v���������䂪�Ƃł͎g�����ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�߂��̓d�퉮�̑q�ɂɓ]�����Ă����R���Z���g�̌Â����������������炢�A����ŃX�s�[�J�[���q���Ă��܂����B�܂��Ɂu���������o�邾���v�̏�Ԃ������킯�ł��BAUDIO-TECHNICA���̃P�[�u���ɑւ����̂́A�P�Ɂu��������ǂ��������v�Ǝv���������ŁA�����ɑ��Ă͂܂��������҂��Ă��܂���ł����B
�@�Ƃ��낪�A�V�����P�[�u�����������ĉ����o���Ă݂�ƁA�v�킸�u�A�b�I�v�Ɛ����グ���قǁA�N�x�̍����T�E���h����яo���Ă��܂����B�܂�ŃA���v��ւ����قǂ̌��ʂł��B�u�P�[�u���ʼn��͕ς��v�Ƃ������Ƃ��m�M������u�ł����B
�@�������A����AUDIO-TECHNICA���̃P�[�u�������̍d�����C�ɂȂ��Đ��N��ɂ͕ʂ̃��[�J�[�̃P�[�u���Ɏ��ւ��܂��B���z�͑O�̃P�[�u����3�{�𓊓����A�m���ɉ��̏o�����X���[�Y�ɂȂ��Ē����₷���͂Ȃ����̂ł����A�N�H���e�B���̂͂���قǏオ�����悤�ɂ͎v���܂���B���̌���������̓X���s�̕i�I�[�f�B�I�p�P�[�u���������Ă݂��Ƃ���A���ʂ͎����悤�Ȃ��̂ł��B�v����Ɂu�P�[�u���ʼn��͕ς�邪�A������x�̃��x������ɂ͂Ȃ��Ȃ����B�����A�ߓx�̊��҂͋֕��v�Ƃ������_�ɍs���������킯�ł��B����ɁA���n�C�G���h�P�[�u���́A�Ƃт���̔������Ƃ͎���d�̌ӎU�L���W�J�i�y��̎�ނ�����Ă���悤�Ȗ���j�ɐڂ���ɋy�сA�u�P�[�u���̑I���ŏo���邱�Ɓv�́u���E�v�����ɂ߂邱�Ƃ��厖���Ƃ��v�������̂ł��B
�@�b�͕ς��܂����A���́u�P�[�u���ʼn��͕ς��v�Ƃ����I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��č���펯�ȑO�̎����ɂȂ���������A������ے肷��l���������Ȃ��炸���܂��B�u�P�[�u���ʼn����ς�邱�Ƃ́A�Ȋw�I�ɉ𖾂���Ă��Ȃ��B�����特�͕ς��Ȃ��v�Ƃ��������̂��ނ�̌������̂悤�ł��B�����āu�P�[�u���ʼn����ς��Ɗ�����̂́A�v���V�[�{���B�����ς��Ǝv���Ă���z�́A�܂������ς�闝�R�𗝘_�I�ɏq�ׂ�v�Ə�݊|���܂��B���������l�����ɋ��ʂ��Č�����̂́A�����ł̓I�[�f�B�I�p�P�[�u���̒�����ׂȂ�������Ƃ��Ȃ����Ƃł��B�����āA�s��ɑ����̃P�[�u���̎�ނ����݂��鎖���ɁA�ڂ�w���Ă��邱�Ƃł��i�����ς��Ȃ��̂Ȃ�A����ȂɃP�[�u���̎�ނ������킯���Ȃ��j�B�ʂ̌��t�Ŕނ��g����Ɓu������`�ҁv���Ă��ƂɂȂ�̂ł��傤���B���Ȃ��Ƃ���Ƃ��ăI�[�f�B�I�������Ȃގ��i������̂��ǂ����A�^��̎c��Ƃ���ł͂���܂��B
�����ԍ��F7802878
![]() 1�_
1�_
���E�������A�͂��߂܂��āB
���E�������̂����͂��������̔ł��u�Ȃ�قǁv��A�����Ȃ���q�����Ă��܂����B
���͍��Y�I�[�f�B�I598����ł����炻��ȑO�̋@�ނ͂����̗��j���K�C�h���Ă�����Ă��銴�o�ł��B
���炭���ꂩ��b��ɏ��ł��낤��Ƃ��ƂĂ��y���݂ł��B
SONY�APIONIEEA�ATEAC�AAKAI�AALPINE/LUXMAN�ANAKAMICHI�ACORMBIA�ASANYO(OTTO)�ACORAL�AFOSTEX �E�E�E
HITACHI(Lo-D)�́A���X�A�b��ɋ��܂��Ă��܂��ˁB�P�[�u���̂��b�����������Ǝ��͂ǂ��炩�ȁH
�����g�̓I�[�f�B�I�D���ƌ�����艹�y�D���ŁA��w���ƌ�̓��R�[�h��Ђ�CD����֍s���Ă��܂��܂����B
�������Ď����̂����z��ɂ߂邱�ƂȂ�598�I�[�f�B�I���炢���Ȃ�W�����v���đ����̍��z�@��ɐG��Ă��܂��܂����B
�A�܂����Ƃ�������������������Ⴂ�܂����A����͂���Ӗ��ƂĂ��s�K���c���Ȃ��Ƃł��B
�d����ł̓t�B���b�v�XLHH-2000��X�`���[�_�[/���{�b�N�XA730���g������ł�KENWOOD��DP-990D�ł�����E�E�E
CD�v���C���[�Ɍ��������Ƃł͂���܂���ł������A���y���y�������ɂ��@�ނ̗����͖��߂��������̂�����܂����B
���ǁA�w�L�т����č����������ɑ���Ƃ������z�ɎЉ�l��N���śƂ��Ă��܂��܂���(^_^;)
����Ȃ���ȂŒ��ԃX�e�b�v���Ȃ����E�������̏Љ��Ă���@�ނ͌��Č��ʐU��ł�������A
������������������K�C�h�ŋ^�����[�U�[�̌��������Ē����Ă���l�ł�����܂��B
���u�P�[�u���̖����ʼn����ς��v�ƌ����o�����̂�80�N��ɂȂ��Ă��炾�Ǝv���܂��B
���Ƃ̔��[�͋��炭�^���X�^�W�I�ł̃P�[�u���I���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�G���W�j�A�i���Ȃ݂Ɏ��̓G���W�j�A�ł͂���܂���j�ɂƂ��Ă͓�����O�̂��Ƃł����A
���^�Ώۂɍ��킹�ă}�C�N��I�Ԃ��ƂƃR���\�[���p�ɃP�[�u����I�Ԃ��Ƃ͓��`�ɓ����������̂ł��B
XLR�P�[�u���͂��Ƃ��d���P�[�u����N���[���d���ɂ��Ă��^�����ꂩ��R���V���[�}�ւ̃t�B�[�h�o�b�N�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�~�L�V���O�E�R���\�[����ch����S/N��120dB���炢����܂�����w�b�h�t�H���Ń��j�^�[����ƁA
�d����P�[�u�����E���m�C�Y�͂������蒮�����Ă��܂��܂��̂ł�����ŏ����ɗ}�����i�Ƃ��ăP�[�u���I�����d�v�ł��B
�����f�ސ푈�̍��YOFC��ԏ��͂�����KANARE�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
SONY�̐M�Z���X�^�W�I����������ۂɁA���ł͓�����O�̖Ȏ��̐U���z���̂Ŋ�����OFC�P�[�u�����A
�o�σ��b�g��3km���J�X�^���E�I�[�_�[���Č������̓����z���ȂǂɎg�p�����Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B
130theater����A�����������Ă���܂��B
�����݂̍ŗD��̓f�m����BD�v���[���[��DVD-3800BD�ŁA�܂��Ȃ��w���\��ł��B
���ς�炸�V�X�e�������ɗ]�O������܂���ˁB�A�܂�������ł��B
��������AV�v���A���v��25���ɓ͂��܂��̂ŁA����ƃV�A�^�[���G���g���[�ɑ������܂��B
�{�l��AV���ɓ���ނ܂ł͏��������@�ł��傱���傱�ƌ����������Ǝv���܂��B
�܂������̐܂ɃA�h�o�C�X�����肢�v���܂��B
�����ԍ��F7804725
![]() 1�_
1�_
���E�������C���v���Ԃ�ł��B
�v�X�ɂ������`���Ă݂���C�ƂĂ������[���X���𗧂ĂĂ���ꂽ�̂ŁC�����A�Ɏf���܂����B
����`�C�z���g���������@��̂��b�C�ƂĂ��y�����q�������Ē����܂����B
���́C�f���ɂ�����l���I�[�f�B�I�D���C��������Ɋ������ꂽ�l�������悤�ŁC���S�����Ƃ��ɂ́C4�`�����l���E�X�e���I���䂪�Ƃɂ���܂���(�Â�!)�BVU���[�^�[�t���̃A���v��SONY���������悤�ȋL��������܂����C�������^�Ԃ܂ł͊o���Ă���܂���B
���Z���ɂȂ������ɉ䂪�Ƃɗ���YAMAHA NS-1000M�́C����������������āC�Z�J���h�E�V�X�e���Ƃ��Ė炵�Ă���܂��B���̃X�s�[�J�[�C�E�[�t�@�̃G�b�W���L�����o�X���Ȃ̂ŁC���ɑϋv���������悤�ł��B
���݂̍��𑜓x�E���C�h�����W��SP�Q�Ɣ�ׂ�ƁC��͂薳��������܂����C�x�����E���Ɠ���Mid�EHi�̏o���͂ƂĂ��C�����ǂ����̂ł��B
���ƌÂ��@��ł��ƁC�Љ�l�ɂȂ��ē��肵���}�C�N����BL-111�́C������ł������ł����CTASCAM��BR-20T�Ƃ����I�[�v�����܂������܂���B
�P�[�u���̘b���łĂ��܂������C���E��������������悤�Ɋm���ɉ��͕ς��܂��ˁB
����20�N���O�ɂȂ�ł��傤���C�����X�^�[�E�P�[�u�����o�ꂵ���Ƃ��́C���̒��Ԃ����ł��b��ɂȂ�܂����B�����ŁC�������g���C���g�������ׂ���CHi��6dB�ȏ�㏸���Ă��ł���B
�ǂ���ʼn����ς��͂��ł��B���Ȃ݂ɁC�����ƊE�W���̃J�i����0.5dB�ȓ��̃t���b�g�ȓ����C�x���f���͌^�Ԃɂ���ď������ق�����C���K�~�̓t���b�g�u���ł����B
���N�O�ɂ��C�I�[�f�B�I�D���̗F�l�炩���������ȃP�[�u�������Ȃ�̖{���C���l�ɒ��ׂĂ݂��̂ł����C��͂�����ɐF�t�����Ă�P�[�u�����U������܂����B
����͎��̎����ł����C������x�ǎ��ȃP�[�u���ȏ�ɂȂ�ƁC���̕ω��͂��邪�C���������P����邩�ǂ����͂킩��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�����C�P�[�u���E���[�J�[�͔���K�v�����炩�C�P�[�u�������������Ƃ��C���X�i�[�Ɂu�����I�����ς�����I�v�Ǝv�킹��K�v������܂���ˁB
�Ȃ̂ŁC���̂悤�ȉ��̐F�t�����d���Ȃ��̂�������܂���ˁB
���̐F�t�����̂́C���Ƃ͎��͎v���܂���B�p�b�V�u�E�C�R���C�U�[�̂悤�ȋC�����Ŏg���Ζ��ɗ����Ƃ�����܂����B�v�́C�g�������C�C�����ǂ����ɂȂ邩�ǂ�����������悢�̂ł�����B
redfodera��������Ă�悤�ɁC80�N��ɃJ�i�����ƊE�W���ɂȂ��Ă�����C�ƊE���ɂ��P�[�u���_�҂�����Ă͏����C�Ƃ����̂��J��Ԃ��Ă���悤�ł����C�J�i�������ɑւ��Ƃ������Ƃ͂���܂���B
�Ɩ��p�Ƃ������e�ł́C�R�X�g�Ό��ʂ��ŏd�v�����邩��ł��傤�B
������������̃��X�C��ώ��炢�����܂����B
�܂��C���E�������̂��낢��ȃI�[�f�B�I�̂��b�C�y���݂ɂ��Ă���܂��̂ŁC��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F7805190
![]() 2�_
2�_
�@redfodera����A����ɂ��́B���܂łقƂ�ǒn���ݏZ�Łi��s���ւ̏o�����ȊO�́j�����I�[�f�B�I���i����������ɂ��W�����I�[�f�B�I�t�F�A�ȊO�ł͂Ȃ��Ȃ�������������炷��A�����̍��z�@��ɐG��Ă���ꂽ������͑A�܂�������ł��B������STUDER/REVOX�̐��i�ȂA���͌������Ƃ�����܂���E�E�E�E(^^;)�B
�@�Ɩ��p�p�[�c�Ƃ����A���ł����������݂̒���Belden��CANARE��MOGAMI�Ƃ������t���[�Y���悭����Ă��鎄�ł����A�����̐��i�̊T�v��m��A�܂����ۂɎg���n�߂��̂́A�ق��3�N������ƑO����ł��B��������̚ʗ_�J�Ȃ��������uProCable�v�̃T�C�g�����Ă���ł��B����܂ł́u�Ɩ��p�Ɩ����p�Ƃ͑S���ʂ̎����ɑ����鐻�i�Q�v���Ǝv���Ă����̂�����A��Ȃ��炨�ڏo�x������ł��B�܂��uProCable�v�̎�Ɏ҂̌����Ă��邱�Ƃ͔�������������������Ǝv���Ă܂����A���Ȃ��Ƃ��Ɩ��p���i�̃R�X�g�p�t�H�[�}���X��m�炵�߂����Ǝ��͕̂]�����ׂ����Ɗ����Ă܂��B
�@�d���̏d�v���ȂA�I�[�f�B�I�S������80�N��ɂ����y���Ă���]�_�Ƃ����������������悤�ɋL�����Ă��܂��B������u�}�C�d����}�C�ψ���B�����特���ς�邩������Ȃ��ˁv�Ƃ������A���Ώ�k�݂����ȓW�J�ɏI�n���Ă����悤�ł��B���ꂪ�����͎G���ł����W��g�ނ悤�ɂȂ��Ă��āA�܂��܂��I�[�f�B�I�ɂ͖��J��̕��삪�����ƒɊ����܂��B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�@�W�����A�o�[����A���v���Ԃ�ł��B���̏f�����I�[�f�B�I�}�j�A�ł����iPIONEER�̔M�S�ȃt�@���������悤�ł��j�B4�`�����l���E�X�e���I�͉��������ł��ˁB�q���̍��A�e���r�ł��p�ɂ�CM������Ă����̂��v���o���܂��B���Ō����T���E���h�̂͂���ł����A������3�������Ă������݊������F�����������Ƃ����y�̖W���ɂȂ����Ƃ�����������܂��B����������FM�ł�4�`�����l���E�X�e���I����������Ă������Ƃ�����܂����B
�@����ς�P�[�u���ɂ����F���͕ς��̂ł��ˁBCANARE��MOGAMI���t���b�g���Ƃ����̂͒�����ł������Ă܂������A�����t���b�g�ł����̏o�����Ⴄ�Ƃ��낪�ʔ����ł��BBelden�̓t���b�g�ł͂Ȃ��A�ŏ��������Ƃ��g����ŋƖ��p���H�h�Ƌ����܂����B�ł��悭�����Ă݂�ƁA��������ш�̋�������������Ƃ͌����Ă������p�́g���t���h�Ƃ̓A�v���[�`���Ⴄ�悤�Ɏv���܂��B�Ɩ��p�ł̓C�M���X��VITAL���ʔ����Ǝv���܂����B����悪�ӂ�����Ƃ��Ă��܂����ABelden�̒��ቹ�Ƃ͈قȂ萷��オ������\�t�g�ŁA�\�[�X�ɂ���Ă͌��ʓI�ł��B
�@����ɂ��Ă��A�^�V���b�v�Łg�����h�����������P�[�u���ɂ͎Q��܂����B���@�C�I���������B�I���̉��ɂȂ�قǂ́g�����h�ł����̂ŁE�E�E�E�i���j�B�d���a�ɜ늳�����l�͂��������̂���ł����˂��B
�@����ł́A���ꂩ����X�������肢���܂��B
�����ԍ��F7807686
![]() 0�_
0�_
�@�͉̂Ɠd���[�J�[���s���A�E�I�[�f�B�I����ɎQ�����Ă������Ƃ͑O�ɂ������܂������A�������쏊��Lo-D�i���[�f�B�[�j�Ƃ����u�����h�ő����̏��i��W�J���Ă��܂����BLo-D�̈Ӗ��́u���[�E�f�B�X�g�[�V�����v�A�܂�u��c���v�̂��Ƃł��B
�@Lo-D�͂��������Â����ォ�瑶�݂��Ă����炵���A60�N��ɂ́u�M���U�[�h�G�b�W�v�ƌĂ��R�[���^���j�b�g�̍\���������������i�𓊓����A�D�]�Ă����悤�ł��B�u�M���U�[�h�G�b�W�v�Ƃ̓R�[���̒[�̕����Ƀq�_�i�M���U�[�j�������A��U�����̒�c���ƒቹ�̐L�т�_�������J�j�Y���̂��ƂŁA���݂��A���p�C���̃J�[�I�[�f�B�I�̃X�s�[�J�[�ɂ��̋Z�p���̗p����Ă��邻���ł��B
�@�l�I��Lo-D�Ŏv���o���̂́A�J�Z�b�g�f�b�L�ł��B�m��3���[�^�[�����������ꂽ�͓̂��Ђ��ŏ��ł͂Ȃ������ł��傤���B���ɃX���[�Y�ȃI�y���[�e�B���O�ʼn����ǍD�B����܂ŃG�A�`�F�b�N�p�i��I�[�v�����[���f�b�L�̑�p�i�ƌ����Čy�������Ă����J�Z�b�g�f�b�L�̒n�ʂ������グ���̂͊ԈႢ����܂���B�ȑO�Љ��CD�v���[���[��DAD-001����ۓI�ł��B
�@�X�s�[�J�[�Ɋւ��Ă̓R�[�����̃M���U�[�h�G�b�W�̃V���[�Y�ɂ͐ڂ������Ƃ͂���܂��A70�N�㖖����̃��^���R�[�����ڂ̃V�X�e���ɂ͂��炭�C���p�N�g���܂����BHS-430�Ƃ�HS-530�Ƃ������^�Ԃ��t���Ă����悤�ȋL��������܂����A����܂Ŏ��̃E�[�t�@�[���j�b�g�����������Ƃ��Ȃ������I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��ẮA�����ʂ��F�ɋP�����^���b�N�ȐU���i����������a�j��i�������b�N�X�ɂ͋������ꂽ���̂ł��B�����������Ă݂�ƁA���^���炵���L���L�����������o��̂ł͂Ȃ����Ƃ����\�z�͑傫���O��A�L�т₩�Ō��ʂ��̗ǂ��T�E���h���o�Ă����̂��r�b�N���ł����B����ɂ�HS-10000��HS-1500�Ƃ������n�C�G���h�@����������A���̕���œƎ��̒n�ʂ�z������������܂��B
�@�A���v�ł͉��ƌ����Ă��p���[�A���v��HMA-9500MKII�ł��B�p���[MOS FET���̗p�����d�ʋ��ł������A�y�A�ɂȂ�R���g���[���A���v��HCA-9000�ƍ��킹������AAurex��SY-88�V���[�Y�Ƃ̃R���s�Ō���邱�Ƃ̑��������̂́A���N�̖��I�[�f�B�I�]�_�ƁE�����S�j������HMA-9500MKII��SY-88�Ƃ̃��C���i�b�v�����t�@�����X�Ƃ��Ă������炾�Ǝv���܂��B
�@Lo-D��80�N�㔼�ɍ����I�[�f�B�I����P�ނ��Ă��܂��B�������ɍ̎Z�x�O���̐��i�����葱����������ɏI���������ł�Aurex�Ƃ͈Ⴂ�A����ȂɃR�X�g�����̉^�c�����Ă��Ȃ������悤�Ɍ�����Lo-D���ǂ����ăo�u���̓����E�����҂����ɑނ������Ƃ����ƁA�����͎q��ЂƂ��ē��{�R�����r�A������Ă������Ƃ��傫���̂ł͂Ȃ������ł��傤���B���{�R�����r�A�̃I�[�f�B�I�u�����h�͌��킸�ƒm�ꂽDENON�ŁA�ƊE�ł̓r�b�O�l�[���̘V�܂ł��B���т��グ�Ă���q��Ђ����݂���̂ɁA�e��Ђ��킴�킴����ƃo�b�e�B���O����悤�Ȏ��ƓW�J������K�v�͂Ȃ��Ƃ̔��f���������̂�������܂���B
�@�ʔ����̂�Lo-D�u�����h�͂��̌���p�����Ďg���A���S�ɖ����Ȃ����͍̂��N�ł������Ƃ������Ƃł��B�����̓���X�ł��鏬�K�͓X�ܗp�ɋ����������W�J�Z��~�j�R���|��Lo-D�̖������\���Ă����Ƃ��E�E�E�E�B�������A�����Ƃ��Ă͓���X�����̈����ȃI�[�f�B�I���i�̐����͎~�߂Ă��Ȃ��炵���ADENON���O���[�v����O�ꂽ���A������ԍ炩���Ă������悤�ȋC�͂��܂��B
�����ԍ��F7807698
![]() 0�_
0�_
���E�������@
���v���Ԃ�ł��A�����X���𗧂Ă��܂����ˁB(^-^)/
�����������i�����o�Ă���ƁA�������v���o���܂���B
���͂ǂ̐��i���łĂ���̂��A�y���݂ł��B
������A�Ȃ��`���A�X���𑱂��Ă��������Bm(_ _)m
�W�����A�o�[����
�{���ɁA���v���Ԃ�ł��B
�P�[�u���̘b�͑�ρA�Q�l�ɂȂ�܂����B
�܂��A���X����o���Ă���������B(^-^)/
�����ԍ��F7809008
![]() 0�_
0�_
���E�������
������A���b���i��ł��܂��ˁB�E�E������Ɩ߂��ăr�N�^�[�Ƃ̏o����E�E�E�B
�����I�[�f�B�I�ɋ����������n�߂����̓p�C�I�j�A/�g���I/�T���X�C���I�[�f�B�I��O�Ƃƌ����Ă����Ǝv���܂��B�I�[�f�B�I���i���Ƃ��Ă����̃��[�J�[�����炪����I�т܂����B�J�Z�b�g�f�b�L���p�C�I�j�A�̑�ꍆ�@��T-3300���܂����B�J�Z�b�g�f�b�L�͂��̌㐏�������ւ��܂����B�E�E�E���̒��Ƀr�N�^�[�̃J�Z�b�g�f�b�L������܂��B�m���^�Ԃ�KD-669S�������Ǝv���̂ł����E�E(�I�[�f�B�I�̑��Ղɍڂ��Ă��܂���B)�艿119,000�̍����@�łQ���[�^�[�ő���{�^���̓t�F�U�[�^�b�`(���̌��t�͂����g���܂���ˁB)�ő��슴�͗ǂ������ł������A�������ɍ����܂���ł����B���ꂪ�����ăI�[�f�B�I������̓r�N�^�[�̑I�����͂Ȃ��Ȃ�܂����B�������オ�r�W���A�����䓪���Ă��āAVHS�f�b�L�����̂ł�������̓r�N�^�[���܂����B���ׂɂ����12�`13�䂭�炢�͔����ւ��܂����B���̒��ł͎O�H����2�`3��ł�����̓r�N�^�[�ł��B(D-VHS�@�œ��Ő����܂������A���g�̓r�N�^�[��OEM�ł����B)
���݂�W-VHS�@��HR-W5�����AD-VHS�@��HM-DHX2��2��Ƃ����̐��ł��B�����Ƃ��AW5��MUSE�f�R�[�_�[�͏��������׃n�C�r�W�����ł͂��͂〈���܂���BD-VHS���u���[���C������͂قƂ�Ǐo�Ԃ��Ȃ��Ȃ�܂����B�����AD-VHS�̃n�C�r�W�����^�悵���e�[�v��200�{�߂�����̂ł܂������𑱂������Ă��܂��B
AV�A���v�͎��̓��}�n�}�ł����r���f�m���̃A���v�������A�����ʒu���E�ɐݒu����Ƃ������A�A�o�b�N�Ńr�N�^�[��SL-LC3�Ƃ����^�x��̃X�s�[�J�[�����z�ł����̂ŁA���ׂ̈ɔ����܂����B�ǂ����T���E���h�p�����炻�������̃X�s�[�J�[�ŗǂ��Ǝv���w�������̂ł����A���邢���F�ōD���ȉ��ł����B�f�m�����烄�}�n�ɔ����ւ����ׁA���̃X�s�[�J�[�͕s�v�ɂȂ�e���r�̃X�s�[�J�[�Ƃ��Ďg���Ă��܂��B�������Ȃ��烄�}�n��Z11�ɔ����ւ������ɂ�蓯���ʒu�ɃX�s�[�J�[���~�����l�ŕ��������Ȃ�������܂���B
���̃X�s�[�J�[���ӂɔ����ėǂ������ׁA�T�u�V�X�e���p�ɃE�b�h�R�[����SX-WD8���܂����B���̃X�s�[�J�[�͂ƂĂ��C�ɓ����Ă��܂��B����A�J�i���^�̃C���z�����r�N�^�[���܂����B���E���Ƃ����E�b�h�̃_�C���t�����̗p�Ƃ������i�ł��B��������X�̒ቹ�Ǝ��̍������������Ă���܂��B(2�T�ԂقǑO����s���s���Ȃ̂ł����E�E�E�B)
���Ƃ̓v���W�F�N�^�[���r�N�^�[��HD-1�ł��B
�����ԍ��F7809089
![]() 0�_
0�_
�@audio-style����A���v���Ԃ�ł��B��������ĉߋ���U��Ԃ��Ă݂�ƁA�͍̂������[�J�[�����ŏ\��������قǂ̃��C���i�b�v�ƁA�������x������v�Ƃ��đ����̃I�[�f�B�I�t�@�������݂��Ă������ƂɁA������Ȃ��犴������܂��B
��������A�Ȃ��`���A�X���𑱂��Ă��������B
�@�����ł��ˁA���܂�X���b�h���u�d���v�Ȃ�̂����ł�����A���Ԃ�A�[�e�B�N��70�قǂŁu��ڕҁv�̃l�^���s����Ǝv���܂��̂Łi�j�A���ꂩ��u�W�]�ҁv�ւƈڍs�\��ł��i���j�B����ł́A����Ƃ���낵�����肢���܂��B
�@130theater����A����ɂ��́BVICTOR�̃J�Z�b�g�f�b�L�́A�m���w�b�h�ɃZ���A���C�iSA�j���g�p����Ă��܂����ˁB�ʏ�̃p�[�}���C���u�⋭�v���đϋv�������߂����̂������Ǝv���܂����A���[�J�[���ł́g�t�F���C�g�ɕC�G����h�Ȃ�Č����Ă��悤�ɋL�����Ă��܂��B
�@���������Ύ��̏��L���Ă���J�Z�b�g�f�b�L��PIONEER���ł����BT-1100S�Ƃ����@��ł����A�Ƃ���ǂ���K�^�����Ă���悤�ŁA�������J�Z�b�g�e�[�v���̂��̂��g��Ȃ��Ȃ�A���͓d���X�C�b�`��������������Ă���܂��B
�@����AV�W�͊��S�ɑa���ł��B�N�ɕS��ȏ���f��قɑ����^�Ԃقǂ̉f��t�@���ł����A����ʼnf������悤�Ƃ����C�ɂȂ�܂���B�ł��A������̓g�V����ĊO�o����̂������ɂȂ��Ă��鎞���������K���������܂��̂ŁA���N��̎��Ƃ̑����z�i���邢�͐V�z�j���@�ɁAAV���u���l�������Ǝv���Ă��܂�(^^;)�B
�����ԍ��F7811929
![]() 0�_
0�_
�@�{���͎O�m�d�@�̃I�[�f�B�I���i�ɂ��ď����܂��B�ŋߒm�����̂ł����A�O�m�d�@�̑n�n�҂͏����K�V���̋`�킾������ł��ˁB1947�N�ɏ����d��̎q��ЂƂ��đn���B�O�m�d�@�Ƃ��ēƎ��H������ݎn�߂�̂�1950�N�������Ƃ������Ƃł��B���̉�Ђ͐���@�⊣�d�r�ł��Ȃ�̎��т��グ�Ă���A�e���r�ł��m����ԍŏ��Ƀ��C�����X�����R�����̗p�����̂����Ђł͂Ȃ������ł��傤���B
�@�O�m�d�@�̃I�[�f�B�I�u�����h��OTTO�i�I�b�g�[�j�Ƃ����܂����B�Ɠd���[�J�[���I�[�f�B�I�@�����|����ꍇ�A��ƃ��[�J�[�ł͏o���Ȃ���i�Z�p��i���Ďs��ɎQ������̂��킾�����炵���AOTTO���X�s�[�J�[�̕���Łu�|�[���X���^���R�[���v�Ƃ����a�V�Ȓ�Ă����Ă��܂��B����͕ʂ̖����u���A���^���R�[���v�Ƃ������A���ƃj�b�P���f�ނA��ɂ������̂�\�ʑf�ނƂ��Ďg���A����ƃA���~���Ƃ��n�C�u���b�h������Ƃ����Ǝ��̍\���������i�ŁA70�N�㖖�ɂ͂��̃��j�b�g�𓋍ڂ�����A�̃��C���i�b�v�𑵂��Ă��܂��B
�@�������A���͂����̃X�s�[�J�[�������Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�ڂ����R�����g�͔��������Ǝv���܂��B�l�I��OTTO�u�����h�ň�Ԉ�ۂɎc���Ă���̂��A78�N�ɔ��\���ꂽ�A�i���O�v���[���[��TP-L1�ł��B
�@�ꌩ�A�������ʂ̃_�C���N�g�E�h���C�������̃v���[���[�Ȃ̂ł����A���̋@��̐����Ƃ���͋쓮�����Ƀ��j�A���[�^�[���̗p���Ă������Ƃł��B�^�[���e�[�u�����̂��̂����[�^�[�}�O�l�b�g�Ƃ��ă��[�^�[�̈ꕔ�Ƃ��ċ@�\����Ƃ����A���ɂ͒N���^�����o���Ȃ��Ǎ��̐��i�ł����B�˂��d�グ�̍����L���r�l�b�g�������āA���ꂪ6���~��Ŕ������Ƃ����̂́A������l����ƐM�����܂���i�������A�J�[�g���b�W�t���ł��j�B
�@����ɁA���̍\���̓Z���^�[�X�s���h���̑ϕ��ׂɗD���Ƃ������ƂŃ}�j�A��]�_�Ƃ̕]�����ĂсA���[�^�[�ƃ^�[���e�[�u���͉����i��I���W�i���@��̐�D�̊�{�p�[�c�ɂȂ����悤�ł��B���ɖ^�I�[�f�B�I�G���ɍڂ��Ă��������i�́A�R���N���[�g���̋���L���r�l�b�g��TP-L1�̃^�[���e�[�u�������t���A���[�^�[�̎厲�����ɉ���������Ƌ��ɁA�����ɏd�ʋ��̋�����4����������Ƃ��������ꒃ�Ȃ��̂ł����i���j�B
�@OTTO�u�����h��80�N��O���ɂ͑��X�ɏ�������A���̌�SANYO�u�����h��80�N�㔼�Ɉ�{20���~��̃X�s�[�J�[��P���I�ɔ����������̂́A���̌�̓I�[�f�B�I�@�퐻���̘b�͕����܂���B���������O�m�d�@�Ƃ�����Ǝ��̂��o�c��Ԃ̉�������ЂƂ��Ēm����悤�ɂȂ�i���ɁA���̈�����������̕����Ԃ�͏T�����l�^�ɂ��Ȃ�܂��� ^^;�j�A�g�V�K�����V�Z�p�ɂ͂悭�����߂邪�A�P�ނ���̂������h�Ƃ����Е��ł́A�����͊낤����������܂���B
�����ԍ��F7811936
![]() 0�_
0�_
�����OTTO�ł��ˁA���A����������܂����B�J�Z�b�g�f�b�L��RD-4600�Ƃ����^�Ԃ������悤�ȁH�H�H�B�����2or3���[�^�[�œ�����VU���[�^�[���|�b�v�A�b�v����@�\���t���Ă��܂����B�h���r�[�̃L�����u���[�V�����@�\���t���Ă����Ǝv���܂��B
���C�ȉ��ŏ��X�r�������͂��܂������A���邭�C�ɓ����Ă��܂����BOTTO�̓A���v�Ɂu��ΐ����v�Ƃ���CM�R�s�[���L��܂���ł������H�B�u���i�Ƃ͌Ă��A���͂��i�ƌĂт����v�̃t���[�Y���o���Ă��܂��B
�P�[�u���E�E�E�d���P�[�u���ɂ͂�����Ɖ��^�I�ł��B�R���Z���g����@��܂ł̋͂��ȋ����̃P�[�u�����������������I�Ƙ_�c���Ă��܂����A�i���Z���X�Ɗ����܂��B�R���Z���g����u���[�J�[�܂ł̔z���P�[�u���̕����y���ɒ����A�����Ɏ��t���Ȃ���(�{�H�ゾ�ƕt�����Ȃ��̂������ł����E�E�E)20�����~���x�̋@���2���~������l�ȃP�[�u���ɕς���͕̂ςȘb���ł��B�����˂��l�߂�Ƃ��̎���2���u���[�J�[���烁�C���u���[�J�[�A�d�C���[�^�[�A�����ݐ��A�d���̓d���A�g�����X�E�E�E�ϓd���A�������d���A���d���̔��d�@�̃R�C���̍ގ�����Ȃ��ƁE�E�E�B�����I�Ɋ֗^���鎖�͑S���o���Ȃ��̂ł�����i���Z���X�ł��ˁB(���N���O��Hi-Vi���������Ǝv���܂����A�d�C���[�^�[�����������特���ǂ��Ȃ����A�Ȃ�ċL����ǂ�������܂��B)
�V�z�̃`�����X�Ɋ֗^�o����Ƃ����炱�̓d�C���[�^�[�ӂ肩��ł��傤���H�B�Ƃ��Ȃ�Ƃ������Ă��鎄�ł����A�Ƃ�V�z�������͈ꉞ�A���̕�����AV�@����q���R���Z���g�͎w�肵�āA�����̃R���Z���g�͒ʏ�g����P�[�u�������葾�����ŁA�u���[�J�[����p�ɂ��Ă��炢�܂����B
�����l����ƁA���Z�n�悪���\�d�v�ȗv�f�ł͂Ȃ��ł��傤���H�B�Ⴆ�H��n�тɂ���ƁA�l�����ꂽ���ɂ���Ƃł͂��Ȃ�d�����͈Ⴄ�Ǝv���܂��B�����Ƃ�������ς��鎖�͊ȒP�ɂ͏o���܂���ǂ����悤���Ȃ����ł͂���܂����E�E�E�B�Ȃ��A���Ƃ̓\�[���[�ɂ�鎩�Ɣ��d�����Ă��܂��B�I�V���X�R�[�v�Œ��ԂƔ��d���Ă��Ȃ���Ƃ̓d���g�`�ׂĂ݂܂������A�����Ƃ��Y��Ȑ����g�ł����B
�����A�����ɗ]�T���o������u�d���R���f�B�V���i�[�v���~�����Ǝv���܂��B�d���R���f�B�V���i�[�̃R���Z���g���ł͂ƂĂ�����܂���A���䔃��Ȃ��ƁE�E�E����Ƀ^�b�v��t���ăR���Z���g���𑝂₷�͎̂ד��ł��傤���˂��H�H�B
�����ԍ��F7812999
![]() 0�_
0�_
�@130theater����d���P�[�u���̘b���o�܂����̂ŁA����͂���ɂ��ď����Ă݂܂��B�d���P�[�u�����������邱�Ƃɂ���ĉ����ς��ƌ����n�߁A�s�̕i���o������̂́A�X�s�[�J�[�P�[�u�����́g�f�ދ����h��������ɐV�����A90�N��ɓ����Ă��炾�Ǝv���܂��B����܂łǂ����Ă��܂����Ȃ��������Ƃ����ƁA�����̃A���v�ނł͓d���P�[�u���̌������o���Ȃ���������ł͂Ȃ��ł��傤���B���ł̓��[�G���h�@��~�j�R���|�p�������đ������\�ɂȂ�A��̑O�Ƃ͊u���̊�������܂��B
�@�����V�X�e���̓d���P�[�u����ւ��Ă݂��̂́A3�N�߂��O�ł��B���������͂�͂�uProCable�v�ɍڂ��Ă�����Ȍ���ł����i�j�B�����l�b�g�ʔ̕i���u������Ǝ����Ă݂邩�B�������_���ł��p�\�R���p�ɓ]�p����������E�E�E�E�v�Ƃ��������ň�{���B�����̂ł����i���F���̎��̒��B��́uProCable�v�ł͂���܂���ł������� ^^;�j�A�ڊo�܂������ʂ�����ăr�b�N�����܂����B���ꂩ��X���s�̕i�̓d�P�[���w��������A�m�l��ł��m�F������A����݂̃V���b�v�ł������̋@��Łg�����h�݂����Ȃ��Ƃ����s���܂����B���ʁA����ς艹�͕ς��̂ł��ˁB�������A�X���s�̕i�ł͑喇�i4,5���~�ȏ�j��@���Ȃ�����N�Ȃ��̂���ɓ���Ȃ��̂ɑ��A�l�b�g�ʔ̕i�͂��炭�R�X�g�p�t�H�[�}���X���������Ă��Ƃ��������A����͖ʔ����Ɗ���������ł��B�X�s�[�J�[�P�[�u����RCA�P�[�u�����I�[�f�B�I�p�Ƃ��Ċ��E�J�����ꂽ���i���F�m����Ă���̂ɑ��A�d���P�[�u���͕����ʂ�̓d���p�[�c�ɉ߂��Ȃ����Ƃ���A�����ƒ����H�Ƃ݂����ȃ��x���ł�����\�ł���_�����������\�}�ݏo���Ă���̂�������܂���B
�@�������t�Ɍ����A����܂ŃA���v�ނɕt�����Ă����d���P�[�u���������ɒ�x���̂��̂ł����������������Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B����MARANTZ��DENON�̐��i�i���Ɉ����N���X�j�ɂ������Ă���d���P�[�u���̓{�����ł��B�����u�����h�Ƃ��Ēʂ��Ă���ACCUPHASE�ɂ��Ă��A�t���i�̃P�[�u���ł͕�����܂���i���F������ƑO�̃��f���ł̘b�BACCUPHASE�̌��s���i�ɂ��Ă͖��m�F�j�B�ӊO�ɂ�ONKYO�͂܂��܂��BSOULNOTE�͕t���P�[�u�����g�����Ƃ�O��ɉ���������Ă���悤�ŁA�s�̕i�ƃ^�����悤�ȃN�H���e�B�̂��̂��t���Ă���݂����ł����A����ł��s�̃P�[�u���ɑւ��邱�Ƃɂ�郁���b�g�͊F���ł͂���܂���B�Ђ���Ƃ�����u�d���P�[�u���͕ʔ���v�Ƃ����A���v�ނ�����o�Ă���\�����E�E�E�E(^^;)�B
�@���d������e�ƒ�̃R���Z���g�܂Ŗc��ȓ`���H�����݂��A���̍Ō�̐����[�g�������ւ��Ă��d�����Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂������A���ۂɕt���ւ��Č��ʂ��������̂�����d��������܂���i������v���O��ւ��邾���ł���������Ă���̂ł�����j�B�����ς�邱�ƂɊւ���Z�p�I�Ȕw�i�͕�����܂��A���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́u�ς�闝�R�v�ł͂Ȃ��u�ς�����Ƃ��������v�ł��B
�@������ɂ���A�ꎞ���d�����̃m�C�Y�ɔY�܂��ꂽ���Ƃ�����g�Ƃ��ẮA�I�[�f�B�I�t�@�����Ƃ�V�z����ۂ͓d������������ł߂������ǂ��̂͊m�����Ǝv���܂��B�m�荇���̓d�퉮���u�P��200V�̕��������ǂ��v�Ƃ����uProCable�v�̎�Ɏ҂ƈꏏ�̂��Ƃ������Ă����̂ŁA200V�ƃ_�E���g�����X�̓������������鉿�l������̂�������܂���B�u�d���R���f�B�V���i�[�v��u�N���[���d�����u�v������������܂�(^^)�B
�����ԍ��F7816172
![]() 0�_
0�_
�@����̓h�C�c�̃��[�J�[�ł���ELAC�ɂ��ď����Ă݂܂��B���Ђ����������̂�1926�N�ŁA������U�{�[�g�Ȃɐςސ����p�̃\�i�[�Ȃǂ��肪���Ă��������ł����A�I�[�f�B�I�ƊE�ɎQ������̂͐�シ����1945�N�ł��B
�@���ł���ELAC�͓Ǝ��̍\���ƃ��b�N�X�����X�s�[�J�[�̍���Ƃ����]�����m�肵�Ă��܂����A�Â�����̃I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��ẮAELAC�̓A�i���O�p�J�[�g���b�W�̑�\�I���[�J�[�ł����B���Ȃ�ELAC�����i�J�[�g���b�W�ɋL����Ă��������ł���jElectro Acoustic�Ƃ����Ăі��̕����������藈�܂��B1957�N��MM�^�J�[�g���b�W�̐����E�̔��ɏ��o���A���̃N�H���e�B�̍�����MM�^�Ƃ��Ă̓A�����J��SHURE�Ɛl�C����Ă����قǂł��B
�@�����g��Electro Acoustic�̃J�[�g���b�W���g�p�������Ƃ͂���܂��A�m�荇�������p���Ă��Ď��������Ă���������Ƃ�����܂��BSTS-455E�Ƃ����@��ŁA���i������Ȃɍ����Ȃ������̂ł����A�o�Ă��鉹�͊��炩�Ń����W���L���A�Ɠ��̉����ۂ������͓I�ł����B��������SHURE��V-15�V���[�Y���g���Ă��܂������ASHURE�̊y�V�I�Ŋ��������F�Ƃ͑�Ⴂ�́A���B���J�[�g���b�W�̎������ɚX�������̂ł��B
�@��N�A55�V���[�Y�����O���[�h�̍���ESG-792E�Ƃ������i���f�B�[���[�Ŏ����������Ƃ�����܂����A455E�������ʂ��傫�����������킢�̂��鉹�F�Ƀ}�W�ŗ~�����Ǝv���܂����B���������̎���Ortofon�̃J�[�g���b�W�̉��Ƀn�}���Ă����̂�792E�̍w���ɂ͎���܂���ł������ǁE�E�E�E�B
�@ELAC��97�N�ɃJ�[�g���b�W�̐�������P�ނ��Ă��܂��B�A�i���O����͌o�c�ʂŃy�C���Ȃ��Ƃ̔��f���炾�Ǝv���܂����A�A�i���O�����͂��̌���ł��邱�Ƃ͂Ȃ��A�ߔN�܂��V���ȃt�@�����l�����Ă��܂��B����̗Y�ł���SHURE�͍����撣���Ă��邱�Ƃ����A����x�J�[�g���b�W�J���ɃJ���o�b�N���Ă������悤�ȋC�����܂��B
�@�Ȃ��AELAC�̃X�s�[�J�[�ɂ��Ăł����A�̂́g�����AElectro Acoustic�̓X�s�[�J�[������Ă�́H�h�Ƃ��������ŁA���S�Ɂg�J�[�g���b�W���[�J�[�̗]�Z�h�Ƃ����v���Ă��܂���ł������A���݂͍L���m��ꂽ�X�s�[�J�[�u�����h�ɂȂ�܂����B���̐��k�ł��܂����邢���F�́A�������ɃX�s�[�J�[���X������ۂ̗L�͌��ł�(^^)�B
�����ԍ��F7819277
![]() 0�_
0�_
�� �����ς�邱�ƂɊւ���Z�p�I�Ȕw�i�͕�����܂��A���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́u�ς�闝�R�v�ł͂Ȃ��u�ς�����Ƃ��������v�ł��B
���Ƃ��Ίw�p�_���ɁA
�u�����Ɂ�������p������ƁA�����Ƃ������ʂɂȂ����B�v
�Ə����Ċw��\����Ă���悤�Ȃ��̂ł��B
���̔��\�̎��^�����ŁA���O���u�����͂ǂ���������@����g���ē������茋�ʂȂ̂ł����H�v�Ɣ��\�҂Ɏ��₵�Ă��A�u���̖ڂŌ��đ��肵�܂����B���̎��ŕ����đ��肵�܂����B�v�Ɠ������Ԃ��Ă���B
�u����@��̑�����E�ȉ��̔����Ȍ��ʂ�����ł��傤���H���Ƃ�����A���R�A�u���C���h�e�X�g�Ȃǂ͂��ꂽ�̂ł��傤�ˁH�v�Ǝ��₵�Ă��A����ɑ��铚���͂Ȃ��B
�u�Ȃ������Ƃ������ʂɂȂ�̂ł����H�ǂ�ȉ����𗧂Ă��܂������H�v�Ǝ��₵�Ă��A�u���͕�����Ȃ��B�Ƃɂ������ĕ����Ă������茋�ʂ��̂��B�v�Ɠ�������B
����ɂ́u���̘_����ᔻ�����̂Ȃ�A���Ȃ����������g���đ��肷�ׂ����B��������Ύ��Ɠ������ʂ�������͂����B���� ���g���ē��l�̑��茋�ʂ\���Ă��錤���҂͎��ȊO�ɂ���������B������A���̑��茋�ʂ��������͂����B����A����҂͎��̘_����ᔻ���邭���ɁA����Ҏ��g�� ���� ���g��������͂��Ă��Ȃ��B�v�Ƌ�B
���������_�����\�̎d���́A���̒��ɂ͂����炭�Ȃ��ł��傤�B�_���̘_���̕s��������E�w�E���Ă���̂ɁA����ɑ�����Ȃ��܂܁A�u���̘_�����s���Ȃ�A���Ȃ��̘_���������B�v�̂悤�Ȏ咣������Ă��܂��B
�� �@�b�͕ς��܂����A���́u�P�[�u���ʼn��͕ς��v�Ƃ����I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��č���펯�ȑO�̎����ɂȂ���������A������ے肷��l���������Ȃ��炸���܂��B�u�P�[�u���ʼn����ς�邱�Ƃ́A�Ȋw�I�ɉ𖾂���Ă��Ȃ��B�����特�͕ς��Ȃ��v�Ƃ��������̂��ނ�̌������̂悤�ł��B
�����咣����̂́u�Ȋw�I�ɉ𖾂���Ă��Ȃ��B�����特�͕ς��Ȃ��v�ł͂���܂���B�u�����ς�錴�����Ȋw�I�ɉ𖾂��Ă��������v�ł�����܂���B
�u�����ς�鎖�����Ȋw�I�ɉ𖾂��Ă��������v�ł��B
���Ȃ킿�A���̎咣�́A�uUFO�����݂��邱�Ƃ��A�Ȋw�I�ɔ[���̍s�����������Ă��������v�ł͂���܂���B�uUFO�������Ƃ������Ƃ��A���ꂪ�����s�@�̌��ԈႢ�łȂ��Ƃ������Ƃ��܂߂āA�Ȋw�I�ɔ[���̍s�����������Ă��������v�ł��B
�� �����āu�P�[�u���ʼn����ς��Ɗ�����̂́A�v���V�[�{���B�����ς��Ǝv���Ă���z�́A�܂������ς�闝�R�𗝘_�I�ɏq�ׂ�v�Ə�݊|���܂��B
���́A�u���R���q�ׂ�v�A�Ƃ܂ł͌����܂���B
�u���Ȃ����q�ׂ��Ă��邱��(�d���P�[�u���ʼn����啝�ɕς��Ƃ������_)�̑O�����(�����ς��Ƃ�������)�����������Ƃ𗝘_�I�ɏq�ׂ��܂����H�v�ƌ������������ł��B�u�q�ׂĂ��������v�܂ł͋��߂܂���B�u���_�I�ɂ͏q�ׂ��Ȃ��̂ł���ˁH�v�Ɗm�F�����������ł��B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�O�̂��߂ɏ����܂����A�����⌴�����m�F�������킯�ł͂���܂���B�O��������m�F�����������ł��B
�����ԍ��F7820193
![]() 0�_
0�_
�@������A�H�����Ă��܂������B�Ђ���Ƃ��āu�G�T���T�����v�Ƃ����`�ɂȂ����������ł����ˁi�j�B�����͎������Ă��X���ł�����A������ƕt�������Ă��܂�(^^;)�B
�����R�A�u���C���h�e�X�g�Ȃǂ͂��ꂽ�̂ł��傤�ˁH
�@���́u�u���C���h�e�X�g�������̂��H�v�Ƃ�����߂́A�u�P�[�u���ے�h�v���т̌���̂悤�ɉ������Ă�L���b�`�t���[�Y�̂悤�ł��B����́u�P�[�u���ے�h�v�̓��̒��Ɂu�u���C���h�e�X�g��������P�[�u���̈Ⴂ�Ȃǐ�Ε�����Ȃ��v�Ƃ����u����v�����т�t���Ă��邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���āA���͂Ƃ����ƁA�n�C�A�^�F�l������܂߂��I�[�f�B�I�D��3�l���Ă�ŁA�]���̂���Ńu���C���h�e�X�g�ɎQ���������Ƃ�����܂��B6��ނ̃X�s�[�J�[�P�[�u����p�ӂ��A8��̎��������܂����B�����A2����Ȃ������āH�@����2��́u�P�[�u����t���ւ��Ȃ������v�Ƃ����p�^�[���ł�����̂ł��B�ŁA���ۂǂ��Ȃ������Ƃ����ƁA����4��u�P�[�u����ւ����v���Ƃ�������܂����B2��́u�P�[�u����ւ��Ȃ������v���Ƃ�������܂����B���Ƃ�2��͕�����܂���ł����B�����Ƃ��A6�{�̂���2�{�͓������[�J�[�̋߂����i�т̂��̂������̂ŁA���̂�����������܂���ȁi�j�B���Ƃ̘A���������悤�Ȍ��ʂł����B
�@�E�E�E�E�ŁA����Ȃ��Ƃ������Ɓu�P�[�u���ے�h�v�́u���̃u���C���h�e�X�g�̓��e�������Ɛ��i�ɋ�����I�@�@�ނ́H�@�u���C���h�̕��@��?�v�Ȃǂƃ��L�ɂȂ��Č����Ă���̂�������܂��A����ȏd���̋������悤�Ȕn���炵������ɂ͓�����C�͂���܂���B��X�ɂƂ��āu�P�[�u���ʼn����ς��̂��ǂ����v�����u�ǂ̃P�[�u����I�ׂV�X�e���ɓK�����邩�v�Ƃ������Ƃ���Ȃ̂ŁA���̎��̘b��͑��X�ɂ������̕��Ɉڂ�܂������ˁB
�����������_�����\�̎d���́A���̒��ɂ͂����炭�Ȃ�
�@�����牽�ł����H�@�������I�[�f�B�I�t�@���͕��ʁu�_���v�Ȃ�ď����܂��ǁB
���u�����ς�鎖�����Ȋw�I�ɉ𖾂��Ă��������v�ł��B
�@����́u�P�[�u���ʼn����ς��v�Ǝv���Ă���命���̃I�[�f�B�I�t�@���̎d���ł͂���܂���B�J��Ԃ��܂����A�I�[�f�B�I�t�@���ɂ́u�_���������˂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����m���}�͂���܂���B�Ȋw�I�Ȑ������~�����̂Ȃ�A�ǂ������[�J�[�ɖ₢���킹�ĉ������B���Ԃ�Z�p�I�ȉ�����ł��傤�i���Ȃ��������𗝉��ł��邩�ǂ����͕ʖ��ł��� ^^;�j�B
���uUFO�������Ƃ������Ƃ��A���ꂪ�����s�@�̌��Ԉ�
�����łȂ��Ƃ������Ƃ��܂߂āA�Ȋw�I�ɔ[���̍s������
���������������v
�@�u�P�[�u���ے�h�v�́u�P�[�u���ʼn����ς��Ƃ��������v���uUFO�����݂���Ƃ��������v�Ƃ������I�J���g����Ɠ��ꎋ���A�P�[�u���̈Ⴂ���܂����������������Ȃ������𐳓�������X��������̂�������܂���B���Ȃ݂Ɂu�J�^�M�̐l�Ԃ̒��ŁAUFO�����ۂɌ��Ă����F�m�����҂̊����v�Ɓu�I�[�f�B�I�t�@���̒��ŁA�P�[�u���ɂ�鉹�̕ω���F�߂��l�Ԃ̊����v�Ƃ͂ǂ������傫���̂ł��傤���ˁB���Ԃ��҂����|�I���Ǝv���܂����B
���u���_�I�ɂ͏q�ׂ��Ȃ��̂ł���ˁH�v�Ɗm�F
�������������ł��B
�@���͕��n�Ȃ̂ŁA���_�I�Ȃ��Ƃɂ͖����ł��B������u�q�ׂ��܂���v�B�����ė��_�I�ɏq�ׂ�K�v�������o���܂���B�O�ɂ������܂������A���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́u�ǂ����ĉ����ς��̂��v�ł͂Ȃ��u�ς�����Ƃ����i���ɂƂ��Ắj�����v�ł��B���̓P�[�u���ɂ�鉹�̕ω��́i�����Ă��̏ꍇ�j���������ł��B�܂��A�P�[�u���ɂ���ĉ����ς�邱�Ƃ�F�߂�I�[�f�B�I�t�@���͂������܂��B���̏؋����A���̐��قǂ̃P�[�u���̖����ł��B�����������ς��Ȃ��̂Ȃ�A�I�[�f�B�I�P�[�u���͏����ɂȂ�܂���B�������v���V�[�{��������A���Ƃ��ꎞ�̌���ŃP�[�u���肳�����肵�Ă��A��Β��������܂���B
���O��������m�F�����������ł��B
�@���̎���͈Ӗ�������܂���B�t�Ɏ����玿�₵�܂��B���Ȃ��̓P�[�u���̒�����ׂ��������Ƃ�����܂����H
�@�����Ă��������ł��B�A���v�̋@��ɂ���Ăǂ����āu���F�v���ς��̂ł����H�@�Ȋw�I�ɐ������ĉ������B�܂����u�A���v�ɂ���ĉ��͕ς��Ȃ��v�Ȃ�Č����܂����ˁB�m���ʂ̃X���b�h�Łu�i�v���[���[��P�[�u���ɃJ�l������Ȃ�j�A���v�ɗ\�Z�𓊓����܂��傤�v�݂����Ȃ��ƌ����Ă܂�������ˁB�ł́A��낵���ǂ����B
�����ԍ��F7820693
![]() 2�_
2�_
�� �@���āA���͂Ƃ����ƁA�n�C�A�^�F�l������܂߂��I�[�f�B�I�D��3�l���Ă�ŁA�]���̂���Ńu���C���h�e�X�g�ɎQ���������Ƃ�����܂��B6��ނ̃X�s�[�J�[�P�[�u����p�ӂ��A8��̎��������܂����B
���E�������Ƌc�_���邽�тɎv���̂ł����A���E�������͓d���P�[�u���ƃX�s�[�J�[�P�[�u�������܂薾�m�ɕ����Ă���������Ȃ��悤�Ɋ����܂��B
���E������A���҂��ǂ��������Ă���̂��͒m��܂��A���͓d���P�[�u���ƃX�s�[�J�[�P�[�u���͂قƂ�LjႤ���̂��ƍl���Ă��܂��B���Ȃ��Ƃ����҂��������傭���ɂ��ċc�_�������͎��͂���܂���B�����A�u�H�����āv����͓̂d���P�[�u���̌��ɂ��Ă݂̂ł��B���̓_�ɂ��Ă͂͂����肳���Ă��������B
�����ԍ��F7820775
![]() 0�_
0�_
���E������Ō�ɏ����ꂽ [7820693] �̒��́u�P�[�u���v���u�d���P�[�u���v�ɒu�������ēǂ�ł��ǂ��̂��A����Ƃ��u�X�s�[�J�[�P�[�u���v�Ɓu�d���P�[�u���v�����݂��Ă̎咣�Ȃ̂�������Ȃ��̂ŁA���̂Ƃ��� [7820693] �ɑ���Z�p�I�ȃR�����g�͊�{�I�ɂ��܂���B([7820693] ���ǂ��ǂ߂Ηǂ��̂��̂�������̂�҂��Ă��܂��B)
�ȉ��́A����ȊO�̓_�ɂ��ď����܂��B
�����u���_�I�ɂ͏q�ׂ��Ȃ��̂ł���ˁH�v�Ɗm�F
���������������ł��B
��
���@���͕��n�Ȃ̂ŁA���_�I�Ȃ��Ƃɂ͖����ł��B������u�q�ׂ��܂���v�B
���E�������Ƌc�_���邽�тɎv���̂ł����A��������ł��B�c�_�̋���ł��B
�� �����ė��_�I�ɏq�ׂ�K�v�������o���܂���B�O�ɂ������܂������A���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́u�ǂ����ĉ����ς��̂��v�ł͂Ȃ��u�ς�����Ƃ����i���ɂƂ��Ắj�����v�ł��B
�u���_�I�v�܂ł͋��߂܂��A���Ȃ��Ƃ��u�_���I�v�ɂ͏q�ׂĂق������̂ł��B
�����̔F����ǂ̂悤�ɂȂ��ꂽ�̂���_���I�ɏq�ׂ邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����́A���n�����n���ǂ����ɊW����܂���B(�Ȃ����n�E���n�Ə������̂́A���E��������n�]�X�Ə����ꂽ����ł��B)
�� ���̓P�[�u���ɂ�鉹�̕ω��́i�����Ă��̏ꍇ�j���������ł��B
(�X�s�[�J�[�P�[�u�����d���P�[�u����������܂��A)�u����v�����Ȃ̂ł��ˁH
�� �܂��A�P�[�u���ɂ���ĉ����ς�邱�Ƃ�F�߂�I�[�f�B�I�t�@���͂������܂��B���̏؋����A���̐��قǂ̃P�[�u���̖����ł��B�����������ς��Ȃ��̂Ȃ�A�I�[�f�B�I�P�[�u���͏����ɂȂ�܂���B
�J�ɂ��ӂ�鎩���Ԃ̔R����P�O�b�Y�Ȃǂ̑��݂͂ǂ̂悤�ɂ��l���Ȃ̂ł��傤���H�Ȃ��A����͗e�Ղɑ��肪�ł��܂��̂ŁA���P���ʂ��Ȃ�����������Z���^�[�Ȃǂɂ��}�~�͂������܂��B����A�I�[�f�B�I�̐��E�́A���肪�ł��Ȃ�����ł��邽�߂��̂悤�ȗ}�~�͂�����҂ł��܂���B
�� �������v���V�[�{��������A���Ƃ��ꎞ�̌���ŃP�[�u���肳�����肵�Ă��A��Β��������܂���B
A���������i���A�������v���V�[�{��������u���Ȃ�������������́A�v���V�[�{�ł͂Ȃ��̂ł����H�v�ƌ����l�����܂ɂ͏o�Ă���ł��傤�B
�ł���������ꂽ����A����́u���ꂪ�v���V�[�{�Ȃ킯�͂Ȃ��B���͂���Ɍ��ʂ����邱�Ƃ��������Ă�����肾�B���O�͂�����g�������Ƃ��Ȃ��̂ɂȂ�����Ȃ��Ƃ�������B�v�ƃ��L�ɂȂ��Ĕ��_���܂��B���������̔��_�����_�I�ł͂Ȃ��B����Ȓ��q�ł́A�|���āA�u���Ȃ�������������́A�v���V�[�{�ł͂Ȃ��̂ł����H�v�ƌ����Ă����l���炢�Ȃ��Ȃ�킯�ł��B
����ɂ́AA����͌f����u���O�Łu���̕i�͗ǂ����̂��v�ƃG�o���W�F���X�g�Ƃ��Č��`���܂���B����Ɋ������ꂽ�l���A���A��O��A����ɂȂ�܂��B���̒��͂���̌J��Ԃ��ł��B
�����ԍ��F7823211
![]() 3�_
3�_
�����E�������Ƌc�_���邽�тɎv���̂ł����A
���i�����j�c�_�̋���ł��B
�@�c�_�H�@�u���v����͂������������L���Ă��ł��傤���ˁB�n�b�L�������āA���Ȃ��͍��̂Ƃ���u�c�_�v�̃e�[�u���ɕt�����i��������܂���B���Ȃ��������Ă���̂́u�I���͔[���ł��Ȃ��B������I����[��������B���������I�v�Ƃ����A���ɓƂ�悪��ȁu�Ԃ₫�v�ł����Ȃ��̂ł��B����Ȃ̂ɑ��Ắu����ɂ��Ȃ��v�Ƃ����I���������݂��܂����ǁA����͂��Ă����āE�E�E�E(^^;)�B
�@���Ȃ��̂悤�ȁACD�v���[���[�̉��̈Ⴂ�����N�ɕ�����Ȃ��l�ɁA�P�[�u���]�X�ɂ��āA�ǂ����ǂ�����Ĕ[���������邩�A���������m�肽�����̂ł��i�j�B
�@����ɂԂ₭�O�ɁA�܂��͂������̎���ɓ����ĉ������B
(����1)���Ȃ��̓P�[�u���̒�����ׂ��������Ƃ�����܂����H
(����2)�A���v�̋@��ɂ���Ăǂ����āu���F�v���ς��̂ł����H
�@�u�c�_�v�Ƃ����������̂Ȃ�A�y�I���₩�ɓ����邱�Ƃł��ˁB����(1)�̉̓C�G�X���m�[��������܂���A�X�O�Ƀ��X�ł���͂��ł��B
�������u�H�����āv����͓̂d���P�[�u���̌��ɂ��Ă̂�
�@����H�@����͖ʗd�ȁB���Ȃ������p���Ă��鎄�̏������݂́A�u�P�[�u���S�ʁv�A���ɃX�s�[�J�[�P�[�u���Ɋւ��ď������A�[�e�B�N���̕��͂��܂܂�Ă��܂��ˁB�b�͓d�P�[�Ȃ̂����̑��Ȃ̂��A�ŏ��Ɂu�b��v������������Ȃ������̂͂��Ȃ��̗����x�Ȃ̂ɁA������u�d���P�[�u���̌��ɂ��Ă̂݁v�Ȃ�ďؕ��̏o���x��݂����Ȏ��������Ă������邾���ł��B����Ƃ��A�������́u�X�s�[�J�[�P�[�u���̃u���C���h�e�X�g�͎��s�ρv�Ƃ̈ꕶ�����āA�X�s�[�J�[�P�[�u���̌��Řb���˂����ނ̂̓��o�C�Ǝv���āA����Ăāu�b��v��ς����̂ł��傤���i�܂����� ^^;�j�B
���d���P�[�u���ƃX�s�[�J�[�P�[�u���͂قƂ�LjႤ
�����̂��ƍl���Ă��܂��B
�@���Ȃ����u�Ⴄ�v�ƌ����Ă�̂́A�������u�@�\�̈Ⴂ�v�ł͂Ȃ��u���ɗ^����e���x�̈Ⴂ�v�̂��Ƃł��傤�A�Ȃ�E�E
(����3)���Ȃ��̓X�s�[�J�[�P�[�u���ł͉��͕ς��Ǝv���Ă�̂ł����H�@�����Ă��̗��R�͉��ł����H�@����������Ŋm�F���܂������H
�������̔F����ǂ̂悤�ɂȂ��ꂽ�̂���_���I��
���q�ׂ邱�Ƃ��ł��邩�ǂ���
�@(����4)���Ȃ��̌����A���̏ꍇ�́u�_���I�v�ȕُؕ��@�Ƃ͂����Ȃ���̂ł��傤���B����Ƃ����N�`���[���Ă��������������̂ł��B
���x�ł������܂����A�����d�P�[�ʼn����ς��Ǝv���Ă����ȗ��R�́A�����Ŏ����ĉ��̕ω���F�߂�����ɑ��Ȃ�܂���B
���i�����Ԃ̔R����P�O�b�Y�Ȃǂ́j�e�Ղɑ��肪
���ł��܂��̂ŁA���P���ʂ��Ȃ�����������Z��
���^�[�Ȃǂɂ��}�~�͂������܂��B����A�I�[�f
���B�I�̐��E�́A���肪�ł��Ȃ�����ł��邽�߂�
���̂悤�ȗ}�~�͂�����҂ł��܂���B
�@�����牽�Ȃ�ł����H�@�I�[�f�B�I�̐��E�́A���肪�ł��Ȃ�����ł��邩��A�}�~�͂Ƃ�炪�����Ȃ��E�E�E�E���āA���ꂪ�ǂ������܂������H�@���̂��Ƃ��u�����̃P�[�u�����o����Ă���̂��A�P�[�u���ʼn����ς�邱�Ƃ��F�m����Ă���I�؋��ł���v�Ƃ������Ƃ̉��甽�ɂȂ��Ă��܂��ǁB�@�@�����ƃ}�W���ɂ���Ă��������ˁB
���f����u���O�Łu���̕i�͗ǂ����̂��v�ƃG�o
�����W�F���X�g�Ƃ��Č��`���܂���B����Ɋ�����
���ꂽ�l���A���A��O��A����ɂȂ�܂��B����
�����͂���̌J��Ԃ��ł��B
�@���Ȃ����A�u���̕i�͗ǂ����̂��v�ƃ{�[�h�ŏ����A�˂邱�Ƃő��҂��u�����v�����Ƃ��ǂ��Ƃ������A����ȃl�K�e�B���Ȍ��������o���Ȃ��̂́A���l���Â����Ă���؋��ł͂Ȃ��̂ł����H�@�����Ŏ��₵�Ă���Q���҂��A�ǂ����̉������Ȓʔ̃T�C�g�́u���q�l�̐��v�݂����ɁA�l����ȒP�Ɂu�����v�����قǑ��l�̈ӌ����L�ۂ݂ɂ��Ă�Ƃł��v���Ă�ł����H�@�l�̈ӌ��͈ӌ��Ƃ��ĕ����A���߂�͎̂����Ŏ����Ȃ艽�Ȃ肵�āA�����̔[������͈͂ŏ��i�ɑ���]�������߂Ă���l���命�����Ǝv���Ă��܂������ǁA�Ⴄ��ł����ˁB
�@���l����́u���̏��i�͗ǂ��v�Ƃ����A�h�o�C�X������邱�Ƃ��u�����v�Ƃ����Ƃ��ے�I�ȈӖ��ł����������Ȃ��̂Ȃ�A���Ȃ������̃{�[�h�ɋ������Ă��闝�R�͂Ȃ��A�܂����̃{�[�h�ł̂��Ȃ��̑��݉��l�͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B����ł������̂ł��傤���B
�@������ɂ���A���Ȃ����F�m�ł���u���̒��v�Ƃ��́A�ǂ̒��x�̍L���Ȃ̂��u���ɗ�����v�Ƃ����C�����ĂȂ�܂���B
�@�܂��A�Ƃɂ��������Ŏ�����4�̎���ɓ����ĉ������B�b�͂��ꂩ��ł��B
�����ԍ��F7825253
![]() 1�_
1�_
�@�����AKAI�ɂ��ďq�ׂĂ݂܂��B�Ԉ�d�@��1946�N�ɐݗ�����Ă���A�����͏��^���[�^�[�̐����ӂƂ��Ă��������ł��B1954�N�Ƀe�[�v���R�[�_�[���J�����Ă���A�e�[�v�f�b�L�ނ���Ɏ�|����悤�ɂȂ�A60�N�ォ��70�N��ɂ����ăI�[�f�B�I�t�@���̑傫�ȐM���đS������z���܂����B
�@�����ŏ��Ɏ�ɓ��ꂽ�J�Z�b�g�f�b�L��AKAI�̂��̂ł����B70�N�㖖�̂��Ƃ������Ǝv���܂��B�^�Ԃ͎��O���܂������A�������̃��[�J�[�Œ�����ׂ��������ʁA���Ђ̂��̂����|�I�ɒ�����̃����W���L�������̂ŁA���킸�w���ł��B
�@AKAI�̃f�b�L�̓����́A���ƌ����Ă��w�b�h�Ƀt�F���C�g���̗p���Ă������Ƃł��B�ʏ�̃p�[�}���C�ɔ�ׂčd�x��ϋv���ɗD��A�܂���������̐L�т��͂��߂Ƃ��đ��ЂƂ̃A�h�o���e�[�W�邾���̃N�H���e�B���ێ����Ă��܂����B���̉��Ɋ���Ă��܂��Ƒ��Ђ̃��f���͉��ƂȂ��X�s�[�h���Ɍ�����悤�ȋC���������̂ł��B
�@�Ƃ͂����Ă��A����AKAI�̃f�b�L�����̂͂��̍ŏ��̈�䂾���ł��B���Ƃ͂Ȃ����A�����ւ���^�C�~���O�ɂȂ��AKAI�̓K���ȉ��i�т̂��̂��o�Ă��Ȃ�������A���邢�͑��쐫���C�}�C�`��������ƁA���Ǖʂ̃��[�J�[�̂��̂���X���̃��X�j���O���[���ɒ������邱�ƂɂȂ����̂ł��i�j�B
�@87�N�ɂ͐e��Ђ̎O�H�d�@�ƒ�g���AA&D�Ƃ����u�����h�𗧂��グ�Ă��܂��BA&D��A�͐Ԉ�d�@�̂��Ƃł����AD��DIATONE�������Ă��܂��i�]�k�ł����A�O�H�d�@���������Ă����g�ѓd�b�̌^�Ԃɂ��uD�v���t���Ă��܂������A��͂肻�̗R����DIATONE�炵���ł��j�BA&D�u�����h�ł́A�J�Z�b�g�f�b�L���͂���CD�v���[���[��`���[�i�[�Ȃǂ�W�J���܂����B����A&D�̏����CD�v���[���[�������������Ƃ�����܂��B�^�f�B�[���[�ŃA���v���������Ă�����A���傤��AKAI�̃X�^�b�t���o�����Ăق�ق�̃v���[���[���g�Ƃɂ��������Ă���������h�Ƃ��������Ŏ�������ł����̂ŁA�f�B�[���[�̃X�^�b�t�������Ẵ~�j������Ƒ��������̂ł��B�����ɂ�AKAI�炵�������̃L���̗ǂ��A�����ď��ʂ��傫���A�m���Ȑ��i�ł����B�������A����^�b�`�����܂�����������Ă��炸�A�f�U�C�������}�������̂Łg����ᔄ��Ȃ��ȁh�Ǝv�����Ƃ���A�Ă̒肻�̒ʂ�ɂȂ�܂����i�ÑR�j�B
�@A&D���s���ŁA�����ЂƂ̒��ł������y�핔����p�b�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A�Ԉ�d�@��2000�N�ɖ����Đ��@��\�����Ď�����I�[�f�B�I�ƊE������ł��܂��B�S�����ɂ͓��؈ꕔ�����ʂ���������̑ޏ�͎��Ɏc�O�������Ǝv���܂��B
�@AKAI�̔s���́ACD����ɏ�肭�K���o���Ȃ��������Ƃ��傫���Ǝv���܂��B�����ЂƂ̃e�[�v�f�b�L�̃��[�J�[�ł�����TEAC����������CD�v���[���[�ɑ��Ď��g�݁A�V�Z�p�����O�ŊJ�����A��N�ɂ�ESOTERIC�u�����h�ō����I�[�f�B�I���i�̒n�ʂ�z�����̂Ƃ͑ΏƓI�ł����B�e��Ђ��I�[�f�B�I�ɑ��ċy�э��ɂȂ�O�H�d�@�������̂��s�^�ł�������������܂����(-_-;)�B
�����ԍ��F7825278
![]() 1�_
1�_
�� �@�c�_�H�@�u���v����͂������������L���Ă��ł��傤���ˁB�n�b�L�������āA���Ȃ��͍��̂Ƃ���u�c�_�v�̃e�[�u���ɕt�����i��������܂���B���Ȃ��������Ă���̂́u�I���͔[���ł��Ȃ��B������I����[��������B���������I�v�Ƃ����A���ɓƂ�悪��ȁu�Ԃ₫�v�ł����Ȃ��̂ł��B
(�u�Ԃ₫�v�ł͂Ȃ��ł����A)�����ł���B���͘_�����\���ŁA���\�҂ɑ��A�u�I���͂��Ȃ������\�����_�|�̓W�J�ɔ[���ł��Ȃ��B���Ȃ������������́A�ǂ����Ă������ƌ�����̂ł����H���̐����͋q�ϓI���ƌ�����̂ł����H�������₵���I����[��������B���������I�v�ƌ����Ă���킯�ł��B
����ɑ��� ���E�������̓����́A
�� �@���͕��n�Ȃ̂ŁA���_�I�Ȃ��Ƃɂ͖����ł��B������u�q�ׂ��܂���v�B
�ł����B
����ɂ́A
�� ����Ȃ̂ɑ��Ắu����ɂ��Ȃ��v�Ƃ����I���������݂��܂����ǁA����͂��Ă����āE�E�E�E(^^;)�B
�ł����B
�� (����1)���Ȃ��̓P�[�u���̒�����ׂ��������Ƃ�����܂����H
�����ł��u�P�[�u���v�ƂЂƂ�����ɂ���Ă��܂����A�Ȃ�̃P�[�u���ł����H�����Ŏ�������ɉ��߂���ƁA�u�ʗd�v���ƌ���ꂻ���Ȃ̂ŁA�P�[�u���̎�ނ������Ă��������B
�� (����2)�A���v�̋@��ɂ���Ăǂ����āu���F�v���ς��̂ł����H
�ǂ����ăA���v�̘b�ɂȂ����̂�������܂��A�����܂��ƁA�A���v�̋@�킪�Ⴄ����B��H�v���Ⴄ����B�g�p����Ă��镔�i���Ⴄ����B
�� �������u�H�����āv����͓̂d���P�[�u���̌��ɂ��Ă̂�
��
�� �@����H�@����͖ʗd�ȁB���Ȃ������p���Ă��鎄�̏������݂́A�u�P�[�u���S�ʁv�A���ɃX�s�[�J�[�P�[�u���Ɋւ��ď������A�[�e�B�N���̕��͂��܂܂�Ă��܂��ˁB
���E�������̂����e�ł��� [7816172] �̖`���ŁA
�� �@130theater����d���P�[�u���̘b���o�܂����̂ŁA����͂���ɂ��ď����Ă݂܂��B
�Ə�����Ă��܂��B���́A���̒��́A
�� �@���d������e�ƒ�̃R���Z���g�܂Ŗc��ȓ`���H�����݂��A���̍Ō�̐����[�g�������ւ��Ă��d�����Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂������A���ۂɕt���ւ��Č��ʂ��������̂�����d��������܂���i������v���O��ւ��邾���ł���������Ă���̂ł�����j�B�����ς�邱�ƂɊւ���Z�p�I�Ȕw�i�͕�����܂��A���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́u�ς�闝�R�v�ł͂Ȃ��u�ς�����Ƃ��������v�ł��B
�̒�����A�Ō��1�s�����p�����̂ł����B�u�X�s�[�J�[�P�[�u���v�͎h�g�̃c�}���x�ɂ����o�ꂵ�Ă��Ȃ��Ǝv���܂���B
�� �@���Ȃ����u�Ⴄ�v�ƌ����Ă�̂́A�������u�@�\�̈Ⴂ�v�ł͂Ȃ��u���ɗ^����e���x�̈Ⴂ�v�̂��Ƃł��傤�A�Ȃ�E�E
�������A�u�@�\�̈Ⴂ�v������܂��B�Ȃ��u���ɗ^����e���x�̈Ⴂ�v������܂��B
�� (����3)���Ȃ��̓X�s�[�J�[�P�[�u���ł͉��͕ς��Ǝv���Ă�̂ł����H�@�����Ă��̗��R�͉��ł����H�@����������Ŋm�F���܂������H
�E�ς�邩�ς��Ȃ����̓�ґ���Ȃ�A�ς��Ǝv���Ă��܂��B���������x���ł��B�X�y�b�N�����ʂ��Ă���Εω��͏��Ȃ��킯�ł�����B
�E���R�͂��낢��l�����܂����A������R�l���قȂ�A�C���_�N�^���X��L���p�V�^���X���قȂ�A�Ȃǂł��B�l�����邾���ł���A���̓��̂������͎��ۂɂ͖���������e�������Ȃ��̂�������܂��B
�E�����Ŋm�F���܂����B�m�F�́A����(���̂̒f�ʐ�)�Ⓑ�����قȂ���̂ł����Ȃ��܂����B�Ȃ��A���[�J�[X�̐��iY�ƃ��[�J�[P�̐��iQ�̂悤�Ȕ�r�͎��͂����Ȃ��܂���B�܂��A���͕ʒi�u�X�s�[�J�[�P�[�u���ɂ���ĉ����傫���ς��v�Ƃ��Ƃ���咣����C�́A���̂Ƃ���Ȃ��̂ŁA����͂��Ă��܂���B�l����u�X�s�[�J�[�P�[�u���ʼn��͕ς��܂����B���R�͑�����������ł̌��ʂ́����ł�����B�v�ƌ���ꂽ��u�Ӂ`��A�����Ȃ̂��B������������Ȃ��ˁB�v�ŏI��邩������܂���B���ǂ͒��x���Ƃ����ʂ�����܂�����B
�� �@(����4)���Ȃ��̌����A���̏ꍇ�́u�_���I�v�ȕُؕ��@�Ƃ͂����Ȃ���̂ł��傤���B����Ƃ����N�`���[���Ă��������������̂ł��B
�q�ϓI�ȑ���ł��B����@��ő���ł���Ȃ炻������B�@��ő���ł��Ȃ��̂Ȃ�A���Ƃ������̃u���C���h�e�X�g�ł��B�������A�I�[�f�B�I�͎�ł�����u�u���C���h�e�X�g���Ă��������v�Ƌ����������͂���܂���B
�� �@�����牽�Ȃ�ł����H�@�I�[�f�B�I�̐��E�́A���肪�ł��Ȃ�����ł��邩��A�}�~�͂Ƃ�炪�����Ȃ��E�E�E�E���āA���ꂪ�ǂ������܂������H�@���̂��Ƃ��u�����̃P�[�u�����o����Ă���̂��A�P�[�u���ʼn����ς�邱�Ƃ��F�m����Ă���I�؋��ł���v�Ƃ������Ƃ̉��甽�ɂȂ��Ă��܂��ǁB�@�@�����ƃ}�W���ɂ���Ă��������ˁB
���ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ����̂ł�����A�����������E��������������u�I�؋��v���؋��ł͂Ȃ��ł��傤�B���̏؋��̍����́u�����o����Ă��邩��F�m����Ă���͂����v�Ȃ̂ł�����B���̗��_�ōs���A�u�����o����Ă���R����P�O�b�Y�͔F�m����Ă���͂����v��ے�ł��Ȃ��ł��傤�B
�܂��A�R����P�O�b�Y�́u�F�m�v����Ă��܂��ˁB��������̐l�X�������Ă��܂�����B���E��������������u�P�[�u���v�́u�F�m�v�����������Ӗ��ł����H
(�f���̕����������ɂЂ�������̂ŁA���֑����܂��B)
�����ԍ��F7825915
![]() 0�_
0�_
�� �@���Ȃ����A�u���̕i�͗ǂ����̂��v�ƃ{�[�h�ŏ����A�˂邱�Ƃő��҂��u�����v�����Ƃ��ǂ��Ƃ������A����ȃl�K�e�B���Ȍ��������o���Ȃ��̂́A���l���Â����Ă���؋��ł͂Ȃ��̂ł����H�@�����Ŏ��₵�Ă���Q���҂��A�ǂ����̉������Ȓʔ̃T�C�g�́u���q�l�̐��v�݂����ɁA�l����ȒP�Ɂu�����v�����قǑ��l�̈ӌ����L�ۂ݂ɂ��Ă�Ƃł��v���Ă�ł����H�@�l�̈ӌ��͈ӌ��Ƃ��ĕ����A���߂�͎̂����Ŏ����Ȃ艽�Ȃ肵�āA�����̔[������͈͂ŏ��i�ɑ���]�������߂Ă���l���命�����Ǝv���Ă��܂������ǁA�Ⴄ��ł����ˁB
�����Ȃ�ł����H���Ƃ��A���̌f���ł��A�����e�Җ��͕����܂����A
[7807686]�ł́A
�� �@�Ɩ��p�p�[�c�Ƃ����A���ł����������݂̒���Belden��CANARE��MOGAMI�Ƃ������t���[�Y���悭����Ă��鎄�ł����A�����̐��i�̊T�v��m��A�܂����ۂɎg���n�߂��̂́A�ق��3�N������ƑO����ł��B��������̚ʗ_�J�Ȃ��������uProCable�v�̃T�C�g�����Ă���ł��B����܂ł́u�Ɩ��p�Ɩ����p�Ƃ͑S���ʂ̎����ɑ����鐻�i�Q�v���Ǝv���Ă����̂�����A��Ȃ��炨�ڏo�x������ł��B�܂��uProCable�v�̎�Ɏ҂̌����Ă��邱�Ƃ͔�������������������Ǝv���Ă܂����A���Ȃ��Ƃ��Ɩ��p���i�̃R�X�g�p�t�H�[�}���X��m�炵�߂����Ǝ��͕̂]�����ׂ����Ɗ����Ă܂��B
�Ə�����A
[7816172] �ł́A
���@�����V�X�e���̓d���P�[�u����ւ��Ă݂��̂́A3�N�߂��O�ł��B���������͂�͂�uProCable�v�ɍڂ��Ă�����Ȍ���ł����i�j�B�����l�b�g�ʔ̕i���u������Ǝ����Ă݂邩�B�������_���ł��p�\�R���p�ɓ]�p����������E�E�E�E�v�Ƃ��������ň�{���B�����̂ł����i���F���̎��̒��B��́uProCable�v�ł͂���܂���ł������� ^^;�j�A�ڊo�܂������ʂ�����ăr�b�N�����܂����B
�Ə����ꂽ��������������Ⴂ�܂����B
����Ƃ��u�{�[�h�v�Ɓu�z�[���y�[�W�v�͈Ⴄ�ƌ�����̂ł��傤���H
�� �@���l����́u���̏��i�͗ǂ��v�Ƃ����A�h�o�C�X������邱�Ƃ��u�����v�Ƃ����Ƃ��ے�I�ȈӖ��ł����������Ȃ��̂Ȃ�A���Ȃ������̃{�[�h�ɋ������Ă��闝�R�͂Ȃ��A�܂����̃{�[�h�ł̂��Ȃ��̑��݉��l�͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B����ł������̂ł��傤���B
�w���l����́u���̏��i�͗ǂ��v�Ƃ����A�h�o�C�X������邱�Ɓx��ے肵���炢���Ȃ��̂ł��傤���H�^���������Ă͂����Ȃ��̂ł��傤���H(���������u�ے�v�́A�l�̈ӌ��ɑ��āA�u����͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����͎��́������ƍl���邩��ł��B�v�̂悤�ɔے�̍����������Ă����Ȃ��ے�ł��B�l�̘b���͂Ȃ��畷���Ȃ��A�t���Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B)
���͈ȑO�ɂ��J�J�N�R���̌f���̂ǂ����̓��e�ŏ�������������܂��A�f���ւ̓��e�Ƃ��ẮA
(1)���i�͗ǂ��Ƃ������Ƃւ̎^��
(2)���i�͗ǂ��Ƃ������Ƃւ̔ے�
(3)���i�͈����Ƃ������Ƃւ̎^��
(4)���i�͈����Ƃ������Ƃւ̔ے�
��4�p�^�[���̂ǂ�����݂��č\��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F7825925
![]() 1�_
1�_
���E�������
������Ƃ̃P�[�u���_���H�͎~�߂ɂ��܂��H�B���҂�����b�������Ă����_�͏o�Ȃ��Ǝv���܂��B�I�[�f�B�I�̐��E�́A�܂��܂����_�ŕ����o���Ȃ��ʂ�����������ł��B���������A���Ƃ������͍ŏI�I�ɂ͕������ۂł͂Ȃ��u�S�����ہv�Ȃ̂ł�����I�I�B
�s�A�j�X�g���e���s�A�m�̉��͂��̃s�A�j�X�g�ɂƂ��Ă͑f�G�ȉ��y�ł����A���y�ɊS���������ɂƂ��Ă̓^�_�̑����ł�������܂���B����ȑO�ɁA�Ⴆ�Ίw�Z�ł̎��Ƃ��v���Ԃ��Ă݂�ƁA�ʔ����b�A����������b�͐搶�����т�U�����������I�ɉ��Ƃ��Ĕ������Ă��A�ʔ����Ȃ������������b���ł��Ɓu�������������܂������H�B�v�Ƃ����l�ɕ����I�ɂ͊m���ɋ�C��U�������ĉ���������ꂽ�n�Y�Ȃ̂ɁA�l�ɂ���Ă͑S���������Ă��܂���B
����ȓd���P�[�u�����^�h�̎��ł����A����2�T�Ԃœd���P�[�u���W��2���~�قǏo��Ă��܂��܂����B���ɃA���v��SACD�v���[���[�ADVD�v���[���[�̓d���P�[�u���͌������Ă���̂ł����A�@�푤�̃R�l�N�^�[�Ƌ@��Ƃ̐ڑ����ア�����ŃI���C�f�̃R�l�N�^�[�ɕt���ւ��悤�Ǝv���A�R�l�N�^�[�������w���ł��B(OFC��LC-OFC���A���邢��PCOCC���Ɠ��̌����i�K�ł̌q�������ɂ���̂ɁA�R���Z���g�Ȃ�č�������Ńo�l�̗͂ŃN�����v���Ă��邾���I�Ȃ�āE�E�����Ƃ��R���Z���g�ƃv���O�̓l�W�~�߁A���c�t���ȂǏo���܂���A���߂Ċ�������苭�����Ƃ����l���ł��B)
���āAAKAI�ł����I�I�B���`�`�A����AKAI��10���e�[�v��������I�[�v�����[���̃f�b�L���g���Ă��܂����BGX-630D�Ƃ����^�Ԃ������Ǝv���܂��B19cm/sec.��4�g���ł��B�����ł��ˁA�w�b�h���O���X���N���X�^����搂��Ă��܂����ˁB�w�b�h�͉i�v�ۏł͂Ȃ������ł����H�B
�I�[�v�����[���͍ŏ���SONY��7�����[����19cm-4�g���@�A����TEAC��38cm-2�g���@��A-7030GSL�ł����B����������TEAC��A-4300��7�����[��19cm-4�g���@�ł����B���̎��ATEAC�����Ղ��قƂ�ǖ����Ƃ����w�b�h���g���Ă��܂������AA-7030GSL���̏Ⴕ�ďC�����e���u�w�b�h�����v�I�I�B����ɂ͔[�����������җ�ɍR�c�I�I�A�C���オ���z�ɂȂ��������v���o���܂����B�E�E�E�����TEAC�������ɂȂ�܂����B(�ŋ߁A�G�\��SACD/CD�v���[���[�̎�����������āA���\�ǂ����ŋC�ɓ����Ă��܂��Ă��܂��BTEAC���i�͔���Ȃ��Ƃ����|���V�[���G�\�����炢�����ȁH�ƕ��ꂩ�����Ă��܂��B)�@
����Ȏ�������AGX-630D���܂����B(630D�̌�Ƀv�����t���܂���38-2�g���@�ł��B)����͌̏�m�炸�A��ϋC�ɓ���܂����B
AKAI�̃f�b�L�̓J�Z�b�g�������܂����B�J�Z�b�g�f�b�L�̓p�C�I�j�A��T-3300����n�܂艄��11�`12�䂭�炢�����ւ��Ă��܂������A�Ō�̃J�Z�b�g�f�b�L��AKAI��GX-R99�ł����B
http://k-nisi.hp.infoseek.co.jp/gx-r99.htm
�I�[�g�L�����u���[�V�����Ńe�[�v�̐��\�����肵�A�K�Ș^�����x���������Ă����Ƃ������ł��I�[�g���o�[�X�ł������ϋC�ɓ���܂����BAKAI���ǂ����[�J�[�ł����B
�����ԍ��F7826239
![]() 0�_
0�_
���E�������@���͂悤�������܂��I
�����ւ���������b���y�����q�������Ă��������Ă��܂��B
CD�v���[���@���⍜���i�̕��ނ̃\�j�[CDP-555ESD�𖢂��Ɏg�p���ł�(�劾�I)
�A���v�ł̓T���X�C��907���ꎞ�g���Ă��莄���g�Ƃ��Ă͂��Ȃ�C�ɓ��������̈�ł����B
�����č���̓A�J�C�̃f�b�L�̘b�ł��ˁB
130theater����10�����[���̂�����GX-630D�����g���ɂȂ��Ă��̎��A�A�܂����ł��I
�����ǂ����Ă��\�Z�����炸7�����[���ł�����GX-77�ƌ����̂��w�����ăg���I(���P���E�b�h)��FM�`���[�i�[KT�|8300�ŃG�A�`�F�b�N�Ŋy����ł��������v���o���Ă܂��B
7���e�[�v�ɃA���~��(�H)�̃e�[�v��\�肻�̕����ŃV���[�g���N�������o�[�X����
7���ł������Ԃ̘^�����ł���ƌ��������ł͉���I�I�H�ȃA�C�f�A���i�ł����B
���݂ł͕s���̂�������@��̃O���[�hUP���܂܂Ȃ炸�����L�@����啪�Â��Ȃ��Ă��Ă��܂��B
�����ōs�����̂�SP�P�[�u���A�d���P�[�u���A�R���Z���g�^�b�v���̌�����Ƃł����B
�����g�ł͌��ʂ͊m���ɂ������Ǝ������Ă��܂��B
�l���ꂼ�ꊴ�o���S���Ⴂ�܂��ˁA�����������̓I�ɕ\���镨�̊J�������҂��܂��傤�I
�����ԍ��F7827210
![]() 0�_
0�_
������H��
�����P�[�u���̒�����ׂ��������Ƃ́H
���Ȃ�̃P�[�u���ł����H
�@�u����Ŏ����Ԃ��ȁv�ƌ��������Ƃ���ł����A�����ł͓d���P�[�u���Ƃ������Ƃɂ��Ă����܂��傤�B�ł́A��낵���B
�����͘_�����\���Ł`
�@�قƂ�ǂ̃I�[�f�B�I�t�@���́u�_���̂����������v�ɂ͂��܂���̂ŁA���Ȃ��́u�_�����ǂ����I�v�Ƃ����������ɂ͉���u���́v�͂���܂���B�����ł���Ȃ��Ƃ������̂�KY�ł����Ȃ��ł��傤�B
���A���v�̋@�킪�Ⴄ����B��H�v���Ⴄ����
���g�p����Ă��镔�i���Ⴄ����B
�@��H�╔�i���Ⴄ�ƁA�ǂ����ăA���v�̉��͈Ⴄ�̂ł��傤���B�����ċ�̓I�ɂǂ��������i�E��H���g���ƁA�ǂ������ς��̂ł����H�@�_���I�ɐ������ĉ������B�����������ł��Ȃ��ƂȂ�ƁA���Ȃ��́u�A���v�ɗ\�Z�𓊓�����v�Ƃ̃Z���t�͋Y�ꌾ���Ǝv���Ă��d���L��܂���B
���Ō��1�s�����p�����̂ł����B�u�X�s�[�J�[
���P�[�u���v�͎h�g�̃c�}���x�ɂ����`
�@���܂���u������v�ł����B�������l�ł��ˁB
�� (�X�s�[�J�[�P�[�u���ł́j�ς��Ǝv���Ă��܂��B
�����������x���ł��B�X�y�b�N�����ʂ��Ă���Ε�
�����͏��Ȃ��킯�ł�����B�i�����j��R�l���قȂ�A
���C���_�N�^���X��L���p�V�^���X���قȂ�Ȃǁ`
�@�d���P�[�u���ł�������c���̐����قȂ邳�܂��܂Ȑ��ނ��o����Ă��܂����A���R�A���ꂼ���R�l��C���_�N�^���X�����Ⴄ�Ǝv���܂��B���̎����������āu�d���P�[�u���ł����͕ς���Ă��������͂Ȃ��v�Ƃ������_�ɂ��Ȃ����Ȃ��B���Ȃ��̂��A���ɕs�v�c�ł��B����Ƃ��A���Ȃ��͓d���P�[�u���̐��ނ̒�R�l�͂��ׂĈꏏ�ł���Ǝv���Ă�ł����H
�����͕ʒi�u�X�s�[�J�[�P�[�u���ɂ���ĉ����傫��
���ς��v�Ƃ��Ƃ���咣����C�́A���̂Ƃ���Ȃ�
���̂ŁA����͂��Ă��܂���B
�@�_�������ł��ˁB�ǂ����đ��肵�Ȃ��̂ł����H�@���Ȃ��́u�X�s�[�J�[�P�[�u���ɂ���ĉ����傫���ς��Ǝ咣����C�͂Ȃ��v�Ƃ����ԓx���̂��̂��P�Ȃ�u�v�����݁v���Ƃ����\���͂Ȃ��̂ł����H�@���ՂȎv�����݂�r�����邽�߂Ɂu���肵��v�ƌ����Ă�Ȃ�������ł����H�@�l�ɂ́u�q�ϓI�Ș_�������߂�v�ƌ����Ă����Ȃ���A�����ł́u�咣����C�͂Ȃ��v�ȂǂƂ����l�I�Ȋ��z�Ɋ�Â����悤�Ȍ�s����`���ӂ肩����������A���Ɠ����̋ɂ݂ł��B
���@��ő���ł��Ȃ��̂Ȃ�A���Ƃ�������
���u���C���h�e�X�g�ł��B
�@���Ƃ��Ύ����u�d���P�[�u���ɂ��āA���������u���C���h�e�X�g�����܂����v�Ə����ƁA���Ȃ��͂����M����̂ł����H�@�l�b�g��ł͉��ł��f�b�`�グ�����ł����ǂˁB�_�������Ƃ肷���Ƃ͈Ⴂ�A��X�́u�����̎Q���ҁv�ł�������܂���B�{�[�h�ł̏������݂Ȃ�āA�����Ƃ��u�q�ϓI�ȑ���v�ɂ̓R�~�b�g���Ȃ��̂ł���B���̃f�[�^���~�����̂Ȃ�A�����ł�邵���Ȃ��ł��傤�B�Ƃ��ƂƂ���Ă��������B
���u�����o����Ă���R����P�O�b�Y�͔F�m�����
������͂����v��ے�ł��Ȃ��ł��傤�B
�@�I�[�f�B�I�p�P�[�u���ƔR����P�O�b�Y�͓����p�r�Ȃ�ł����H�i�j�@�����������Ȃ��̕����������������̂́u�I�[�f�B�I�̐��E�́A���肪�ł��Ȃ�����ł���v�Ƃ������Ƃ������Ŗ������Ă��邱�Ƃł��B�u���肪�ł��Ȃ�����ł���v���Ƃ�F�߂Ă��Ȃ���l�ɂ́u�i�R����P�O�b�Y�Ɠ����悤�Ɂj�q�ϓI�ȑ�������߂�v�݂����Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ���B���̂ւ���ǂ��u�����v�������ł��傤���B
�@���Ƃ��ACANARE��4E6S��MOGAMI��NEGLEX2534�́A�\�����ꏏ�A�c���̍ގ�������OFC�AF�����ꏏ�ł��B�Ȃ����ɓ����v���O��t���āA�����������邩�Ƃ����ƁA����͑�ԈႢ�B�S�R���������Ⴂ�܂��B�ǂ����ĈႤ�̂��͕�����܂��A���Ԃ�قƂ�ǂ̃��[�U�[�ɂƂ��āu�Ⴄ���R�v�Ȃ�ďd�v�ł͂Ȃ��ł��傤�B�u�Ⴄ�Ƃ��������v�������厖�Ȃ̂ł��B�����Ă��́u�Ⴄ�x�����v�Ɗe���[�U�[�Ƃ��ǂ��܂荇����t���邩�Ƃ����̂��A��Ƃ��ẴI�[�f�B�I�ɑ���t���������ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����Ȃ����̂ő����͕ʂ̃A�[�e�B�N���Ƃ��ăA�b�v���܂��B
�����ԍ��F7830003
![]() 0�_
0�_
�������҂��u�����v�����Ƃ��ǂ��Ƃ������`
�������Ȃ�ł����H
�@���炸��ƈ��p����Ă��܂����A���Ȃ��̈Ӑ}���s���ł��B���������������������̂ł��傤���B�悩����������肢�܂��B
�@���Ȃ݂ɁA���́uProCable�v�̏������݂ɋ����������A�������̏��i���Ď����Ă݂܂������A���ʂ̂��������i�������������Ȃ����i������܂����B�uProCable�v�݂����ȋƎ҂ɑ���ԓx�͐��X��X�ł��B������ɂ���A�����Ă����Ȃ��̂Ɂu���͕ς��Ȃ��v�ƌ�������悤�Ȍ�����`�ғI�ȑԓx�Ƃ͋����͒u���������̂ł��B
���w���l����́u���̏��i�͗ǂ��v�Ƃ����A�h�o
���C�X������邱�Ɓx��ے肵���炢���Ȃ�
���̂ł��傤���H�^���������Ă͂����Ȃ��̂ł��傤���H
�@�������u���l����̃A�h�o�C�X�ɂ͐�Ύ^�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ə����܂����H�@�����Ă����Ȃ����Ƃ�����ɒf�肵�Ȃ��ʼn������B�i�ēx�����܂����j�����Ŏ��₵�Ă���l�����́A���l�̈ӌ��͈ӌ��Ƃ��ĕ����A���߂�͎̂����Ŏ����Ȃ艽�Ȃ肵�āA�����̔[������͈͂ŏ��i�ɑ���]�������߂Ă���l���命�����Ǝv���܂��B��X��������u�����Ƃ������i�͗ǂ����v�ƃA�h�o�C�X�����Ƃ���ŁA���̖{�l�����@�ɐڂ��čD�݂���Ȃ������炻��܂łł��B���Ȃ��́u�A�h�o�C�X������A�N�ł�����ɖ������Ŏ^������X���ɂ���v�݂����ȏ���Ȏv�����݂Ƃ͖����̂Ƃ���Ő��̒��͓����Ă��܂��B����Ƃ��A���܂��܂��Ȃ��̎��͂ɂ͂���ȁu�e��Z�[���X�g�[�N�ɂĂ��߂�ɉe������悤�Ȕ]�V�C�Ȑl�v���葶�݂���̂ł��傤���B
�@���낢�돑���Ă��܂������A���݂������u���v���g���u�I�[�f�B�I�̐��E�́A���肪�ł��Ȃ�����ł���v�Ƃ��u�I�[�f�B�I�͎�ł�����v�Ƃ������Ƃ������Ă�悤�ɁA�ǂ����̏o���̈������n�̐l�Ԃ��u�q�ϓI�ȃf�[�^���Ȃ�����A���͕ς��Ȃ��I�v�ƌ������낤���A�������{�l���u�ς�����v�Ɗ������̂Ȃ�A�O��̈ӌ��͖��p�ł��B�����Ă��܂��܁A�u�ς�����v�Ɗ����Ă��́u�ς�����v�x�����I�[�f�B�I�V�X�e���������Ŗ����ł��Ȃ��ƍl���Ă���I�[�f�B�I�t�@�����吨���߂Ă�����Ă̂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�������A�u���v���g���u�I����[�������邽�߁A�N������l���o���I�v�ƈ�l�ŃV���v���q�R�[������������̂͌l�̎��R�ł��B�������A���ꂮ����u�d�P�[�ł͉��͂قƂ�Ǖς��Ȃ��v�Ƃ��uCD�v���[���[�͈����ŏ\���v�݂����Ȍ��k�𐂂ꗬ���āA�����̎���ҁi���ɏ��S�ҁj�����������Ȃ��悤�Ɋ肢�������̂ł��B
�@���ƁA�ǂ����u���v����́A���y�����ƂɊ���Ă��Ȃ��悤�Ɋ����邯�ǁA�C�̂������ȁB�������������Ă��āA���y��p�\�t�g�͂ǂ̂��炢�����Ă���̂ł��傤����(^^)�B
�����ԍ��F7830018
![]() 0�_
0�_
130theater����A����ɂ��́B
��������Ƃ̃P�[�u���_���H�͎~�߂ɂ��܂��H
�@�ʂɎ��͔ނƁu�_���v���Ă������͂���܂���B���������ނ́u�_���v�̃X�^�[�g���C���ɂ���t���Ă��܂���̂ŁE�E�E�E�B�˂��������Ă����̂͐���Ƃ͂����A���܂��������̂����ł�����A�قǂقǂɂ��Ă����܂��B�ǂ��������܂���ł����B
�@���āA�c�O�Ȃ��玄�̓I�[�v�����[���Ƃ������̂��g�������Ƃ�����܂���B�I�[�f�B�I�}�j�A�̐e�ʂ�f�B�[���[���牽�x���g�����Ƃ����߂��A�ł������ɂ͂��������傪����ȋ@���u���X�y�[�X���Ȃ��A�S�O���Ă��邤���ɖ����p�I�[�v���f�b�L�͎s�ꂩ��قƂ�ǎp�������Ă��܂��܂����B����ƁADAT�Ƃ����̂��o�܂����ˁB�^���@�ނƂ��ăn�C���x���Ȃ̂œ����������������Ƃ�����܂������A�͂����Ĕ����Ă���͈�̉���^����������̂��낤���E�E�E�E�ƍl���Ă��邤���ɁA����������Ă��܂��܂����B
�@���v���o���܂������A�̃G���J�Z�b�g�Ƃ����̂�����܂����ȁB�e�[�v�̉���ǂ����悤�ƃJ�Z�b�g�e�[�v�̕���傫������Ƃ����A���܂�ɂ����B�I�ȕ��@�ł������A�����o������SONY�ȊO�͂ǂ����ǐ����Ȃ������̂��K�i�ʂ̒ǂ����ݕs��������킵�Ă����Ǝv���܂��B
�@TEAC�̃e�[�v�f�b�L�̓J�Z�b�g�������������Ƃ͂���܂��A�������܂薣�͂̂��鐻�i�Ƃ͎v���܂���ł����B�ł�����ESOTERIC�u�����h�Œn�ʂ�z���Ă���̂́A�Ђ���Ƃ�����TANNOY�̗A���㗝�X������Ă������������邩��ł͂Ȃ����Ǝv����������܂��B���Ă�SANSUI��JBL�̗A����S�����A�A���v��JBL�̍����X�s�[�J�[��ΏۂɃ��t�@�C�����J��Ԃ������ʁA�s��ŕ]�������悤�Ȑ��i�������[�X���邱�Ƃ��\�ɂȂ������Ƃ��v���o���܂��BAKAI���L���ȊC�O�u�����h�ƒ�g���Ă���A�����c�铹���J�����̂�������܂���B
�@satoakichan����A����ɂ��́B
�@SONY��CD�v���[���[�͗ǂ����̂��Ǝv���܂���B������CD�̊J�����̂ЂƂ�������܂��B�������A�ߔN�͕s���ł��ˁBSACD���Ă���̂͂����̂ł����A�����Ɩ{�i�I�Ɏ��g��ŗ~���������ł��BSONY�͓V�˓I�Ȏ�r�������Ă����n�Ǝ҂����̎��オ�I����Ă���́A�o�c�̍���������Ă��Ȃ��悤�Ȋ������܂��B���܂����ǃI�[�f�B�I�̕���ł̊�������Ă݂������̂ł��B�Ȃ��ASONY�ɂ��Ă͋߁X���̃X���b�h�ł����グ�����Ǝv���܂��B
�@�b�͕ς��܂����A�ŋ߉��B�̖^�L���u�����h�̕S���\���~�̃v���[���[�̒��g��PIONEER�̈����v���[���[�̗��p�ł��������Ƃ��������ĕ��c�������Ă��܂��B�ł������璆�g�����[�G���h�@�̃p�[�c���낤�ƁA���̃v���[���[���������ĕS���\���~�̉��l������T�E���h���o���Ɗm�M����Δ����l������ł��傤�B�ނ��낻��ȃp�[�c���n�C�G���h�@�ɂ܂Ń��t�@�C���������[�J�[�̋Z�p�͂�_�߂�ׂ��Ȃ̂�������܂���B�܂��A�A���v��X�s�[�J�[�͎������o����̂ōD�݂ł͂Ȃ����i��͂܂���邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��̂�������܂��A�P�[�u�����͂��߂Ƃ���A�N�Z�T���[�ނ͎������o���Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��̓o�N�`�ł��ˁB�d���a�ɂȂ�Ȃ����x�Ɍ����ɂ�鉹�̕ω����y���݂̂��A�I�[�f�B�I�̑�햡���Ǝv���܂��B
�@����ł́A����Ƃ��X�������肢���܂��B
�����ԍ��F7830046
![]() 2�_
2�_
�ʂ̂��Ƃ������ƒ����Ȃ�̂ŁA���{�I�Ȃ��Ƃ��ЂƂƂ肠���ď����܂��B
���́A���E�������̂��w�E�ɂ��āA���̂悤�ɓ����܂����B
�� �� �������u�H�����āv����͓̂d���P�[�u���̌��ɂ��Ă̂�
�� ��
�� �� �@����H�@����͖ʗd�ȁB���Ȃ������p���Ă��鎄�̏������݂́A�u�P�[�u���S�ʁv�A���ɃX�s�[�J�[�P�[�u���Ɋւ��ď������A�[�e�B�N���̕��͂��܂܂�Ă��܂��ˁB
��
�� ���E�������̂����e�ł��� [7816172] �̖`���ŁA
��
�� �� �@130theater����d���P�[�u���̘b���o�܂����̂ŁA����͂���ɂ��ď����Ă݂܂��B
��
�� �Ə�����Ă��܂��B���́A���̒��́A
��
�� �� �@���d������e�ƒ�̃R���Z���g�܂Ŗc��ȓ`���H�����݂��A���̍Ō�̐����[�g�������ւ��Ă��d�����Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂������A���ۂɕt���ւ��Č��ʂ��������̂�����d��������܂���i������v���O��ւ��邾���ł���������Ă���̂ł�����j�B�����ς�邱�ƂɊւ���Z�p�I�Ȕw�i�͕�����܂��A���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́u�ς�闝�R�v�ł͂Ȃ��u�ς�����Ƃ��������v�ł��B
��
�� �̒�����A�Ō��1�s�����p�����̂ł����B�u�X�s�[�J�[�P�[�u���v�͎h�g�̃c�}���x�ɂ����o�ꂵ�Ă��Ȃ��Ǝv���܂���B
����ɑ��āA
�� ���Ō��1�s�����p�����̂ł����B�u�X�s�[�J�[
�� ���P�[�u���v�͎h�g�̃c�}���x�ɂ����`
��
�� �@���܂���u������v�ł����B�������l�ł��ˁB
�̂悤�Ɂu������v���ƕЕt������̂͐S�O�ł��B�c�_�ɂ����āA����ɑ��锽�_�͂Ȃ�炩�́u������v�ł��B
���Ȃ��́A���̔��_�ɑ��Ĕ��_���q�ׂ��A���A�q�ׂȂ����R�������Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��͎��̔��_���瓦�����A�Ƒ����Ă�낵���̂ł��ˁH���̔��_��F�߂��̂ł��ˁH
����Ȃ��Ƃ͌��������͂Ȃ��̂ł����A�������_���q�ׂĂ��A���Ȃ��͂��Ȃ��ɂƂ��ēs���̈������Ƃ́u������v�ŕЕt���Ă��܂��B���̂�������͂��Ă���B���������̂ł��B��������̃y�[�X�������Ǝv���ƃQ���i������̂ŁA���A���̎w�E�����܂����B
�����ԍ��F7830325
![]() 0�_
0�_
������H��
���u������v���ƕЕt������̂͐S�O�ł��B
�@�����ǂ����U���ƁA���Ȃ��̍ŏ��̏������݂ɂ́u���v������܂���B���炩�ɂ��Ȃ��̗����x�ł���H�@�u�����A�������肵�Ă܂����B�d�P�[�̘b�ł��v�Ƃł������������̂��A���܂ł��S�l�Ă��邠����͌��Ă��Ēɂ����̂�����܂��B����Ƃ��u�_���\�����v�Ƃ��ł́A�����̃~�X�͐�ɔF�߂��ɁA�J�����邱�Ƃ��̗v�Ȃ̂ł��傤���B�ʏ�̃r�W�l�X�̌���Ƃ͈Ⴄ�悤�ł��ˁB
���c�_�ɂ����āA����ɑ��锽�_�͂Ȃ�炩�́u������v�ł��B
�@�����������Ε�����܂����A�u�c�_�v�Ƃ́A�݂��̈ӌ����q�ׂĘ_���������ƁA�u������v�Ƃ͎����̐ӔC��邽�߂ɁA�����ȊO�̂��̂Ɏ����̍s���E�l�����̌��������߂邱�Ƃł��B
�@�J��Ԃ��܂����A���Ȃ��̏������݂́A����c�_�������Ȃ����x���ɒB���Ă��܂���B�u�_�������v�����̘_�����܂������Ȃ�����ł��B���Ȃ����q�ׂĂ���̂͂��ׂĒP�Ȃ�u������v�ł��B
�����Ȃ��́A���̔��_�ɑ��Ĕ��_���q�ׂ��A
�����A�q�ׂȂ����R�������Ȃ��B
�@���_�H�@�����������̂��Ƃł��傤���B���肪���_�����邽�߂ɂ́A�܂����Ȃ��́u���_�v���I���ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂Ƃ��날�Ȃ��̕��͎͂����т��Ă��Ȃ��u�Ԃ₫�v���U���ł��邾���ŁA����̒ʂ����_���W�J��������Ă��܂���B
�@������Łu���Ȃ��̎��_�v���ӏ������Ńs�V�b�Ƃ܂Ƃ߂ĉ������B
�@��������Ȃ��ƁA���͂��̃X���b�h�ł͍��゠�Ȃ����܂����������E�E�E�E�Ƃ܂ł͂����Ȃ��ɂ��Ă��A�u�P�Ȃ��₩���v���炢�ŗ��߂邱�Ƃɂ��܂��B
����������̃y�[�X�������Ǝv���ƃQ���i��
������̂ŁA���A���̎w�E�����܂����B
�@�Q���i������̂Ȃ�A��߂���ǂ��ł����H�@�N�����Ȃ��Ɂu�����ŃP�[�u���]�X�ɂ��ăN�_�������ė~�����v�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��ł��傤����B
�����ԍ��F7831130
![]() 3�_
3�_
�P�[�u���c���ɂ͂悭����Ȃ���ł����ǁA����
�ς��Ƃ����̌��͂��Ă������ł��B�����A
�ے�h��HP�Ȃ��ς��肷��ƁA����͒�����R��
�ڐG��R�̈Ⴂ���Ă��邾���c�Ƃ�������Ă���
���ɔ[���������܂����B���̏��x�Ȃǂ��킸����
�����̈Ⴂ�Ły���z�ɂ���邽�ߖ��Ӗ��ł���Ƃ�
������Ă��܂��B���ɂ��Ă݂�����̔ے�hHP��
�������Ŏ���������������ꂽ�͎̂����ł��B
�ے�hHP�����ĉ���ē������_��
1.�m�C�Y��͑厖�ł���̂ŊO��͂��������C��
�@�g���������B�������U���ȂW�Ȃ����A����
�@�A�N�Z�T���[�͔������肵�Ȃ��悤�ɁI���Ċ����@�ŁB
2.���̃P�[�u�����̂����x�ɂ�����炸�A������
�@���ꂭ�炢�ł�����A�Ǝv������̂�
3.�ړ_�̎����͏d�v�ŁA�����A��������ڑ�
�@����Ă��邱�Ƃ��Ƃ��Ă��d�v�B
4.���ǃI�[�f�B�I�͎�̕��A�q�����q������
�@�P�[�u�����͂�����Ƒ��߂̂������肵������
�@�t���Ă��������h�����悢�i�j�B
���炢�Ȃ���ł�����(^_^;)�B���͔�r�I�ے�h
HP�i�̐���҂���B�j�Ɋ��ӂ��Ă܂��B����������
�P�[�u����ړ_���ꂢ�ɕۂ��Ă�������ڑ��I�I
���ꂾ���l���Ă�Ⴂ�����I�Ǝv�킹�Ă���܂���
����B
�����ԍ��F7831484
![]() 2�_
2�_
�c�_�̑O��ɂ������A���{�I�Ȃ��Ƃ���_���������܂��B
�� ���c�_�ɂ����āA����ɑ��锽�_�͂Ȃ�炩�́u������v�ł��B
��
�� �@�����������Ε�����܂����A�u�c�_�v�Ƃ́A�݂��̈ӌ����q�ׂĘ_���������ƁA�u������v�Ƃ͎����̐ӔC��邽�߂ɁA�����ȊO�̂��̂Ɏ����̍s���E�l�����̌��������߂邱�Ƃł��B
���Ȃ��������������Ε�����Ƃ��������̂ŁA�����������܂����B�u�c�_�v�͂���Ō��\�ł��傤�B
���������̎����́u������v�̍��ڂɂ́A���̂悤�ȈӖ��͏����Ă���܂���B
http://dictionary.msn.co.jp/result.aspx?j=%e5%9b%bd%e8%aa%9e&keyword=%e8%a8%80%e3%81%84%e8%a8%b3&startcount=0&matchtype=startwith¤titem=00806800
���}�̂̍L���������ׂ܂������A���l�ł����B
���Ȃ����咣�����u�����̐ӔC��邽�߂ɁA�����ȊO�̂��̂Ɏ����̍s���E�l�����̌��������߂邱�Ɓv�̍����������Ă��������B
�u�����������Ε�����v�Ƃ�����������̂͂��Ȃ��̂ق��ł�����A���Ȃ������̍����������Ȃ�������A�����O������Ƃ������Ȃ��̎咣�͊ԈႢ���ƍl���܂��B
�ȉ��́A���E�������ւ̃R�����g�ł͂���܂���B
���͎����̉�����Ƃ肠���Ă��܂����A�ʂɎ��͌��t�̗g�������Ƃ�悤�Ȃ��Ƃ͂������͂���܂���B�������A���肪�u�����ł́����́������v�Ǝ咣����̂ŁA����ɔ��_���邽�߂ɂ́A���́u�����ł́����́����ł͂Ȃ��v�ƌ���Ȃ���Δ��_�ł��܂���B���������āA�����̉�����Ƃ肠������܂���B
�܂��A���͕��i�͂��̂悤�Ȍ��t�̉��V�͂��܂��A����������܂���B�������A�Ȃ����邩�Ƃ����A���肪����������Ȃ��悤�Ȏ�������Ă��邩��ł��B�����Ȃ���A�u�������Ȃ���ł���H���Ⴀ���Ȃ����Ԉ���Ă��܂��ˁB�v�Ƃ���Ă��܂��܂��B�����Ƃ������Ă��u�����̌�����ł��ˁB�v�Ƃ���Ă��܂��܂����A�������A�����Ȃ�������ŏI����Ă��܂��ł��傤�B������A���₢��ł����A���̂悤�Ȍ��t�̉��V�ł������Ă��邾���ł��B
�����ԍ��F7831888
![]() 1�_
1�_
�@������A����ȏd���̋���˂��悤�Ȃ��Ƃ�����āA�b���⏬�������悤�Ƃ��Ă����ʂł��B��������ׂ�̂͌��\�ł�����A�������Ɓu���Ȃ��̎��_�v���ӏ������Ńs�V�b�Ƃ܂Ƃ߂ĉ������B�����Ȃ��Ɓu�������v�Ǝv���܂���B���͗e�͂��܂���ˁB
�|�|�|�|�|
�@���ꂾ���D�����茾���Ă��Ȃ���A�������_�L����ƌ�������S�O���āA�܂��P�`�������邱�Ƃ�D�悵�Ă��܂��悤�ȁu�������Y�v�͕����Ă����āA���X�̃^�C�g���ɏ��������������݂𑱂��܂��B
�@����̃l�^��JBL�ł��BJBL�̓J���t�H���j�A�B�m�[�X���b�W�ɖ{�Ђ�u���A�����炭�͉䂪���̃I�[�f�B�I�t�@���̊Ԃōł��悭�m��ꂽ�C�O�X�s�[�J�[���[�J�[�ł��B������1946�N�ŁAALTEC�̃G���W�j�A�ł������W�F�[���X�EB�E�����V���O�ɂ��ݗ�����Ă��܂��B
�@������ԍŏ��ɒ�����JBL�̐��i��L26 Decade�ł��B73�N�ɔ�������A���i��1��\68,900�ƌ����Ĉ����͂Ȃ������̂ł����A�}�j�A�̊Ԃł́u����JBL���i��10���~�ȉ��Ŏ�ɓ���I�v�Ƃ��������ő�ςȘb��ɂȂ��������ł��B�����ڂ����͔̂������牽�N���o���Ă���ł����A����܂ō��Y�X�s�[�J�[�������������Ƃ̂Ȃ��������ɂƂ��ẮA������Ƃ����J���`���[�E�V���b�N�ł����B�Ƃɂ����������邢��ł���ˁB�u���ɖ��邢���Â����Ȃ����낤�B�S��ɂ킽���ĉ��y�M�����ߕs�������s���n�点��A����ŗǂ��v�Ƃ������̍l�����͊��S�ɑł��ӂ���܂����B���̒��ɂ́u���F�v�Ƃ����T�O�����݂��邱�Ƃ��A���̎��m��������ł��B
�@���ꂩ�炢�낢���JBL�̐��i���Ă݂܂����B43**�Ƃ����^�Ԃ̕t�������j�^�[�V���[�Y�����S�ł��B�����p�ł�Olympus��L101 Lancer�Ȃ̃f�U�C���̏㎿���Ɋ��S���܂����B�����č��N�ɂȂ��ď��߂�Paragon�����Ƃ��o���܂����B����̓I�[�f�B�I�p�X�s�[�J�[�Ƃ������A���͂�u�y��v�ł��ˁB50�N��ɓo�ꂵ�A80�N��㔼�ɐ����͏I����Ă��āA�����W��𑜓x�͌��s�̃X�s�[�J�[��肸���Ɨ����̂́A�Â��W���Y�𖾂邭�y������������Ƃ������ƂɊւ��Ă͑��̒ǐ��������Ȃ����݊����ւ��Ă��܂��B
�@���āA�����_�Ŏ���JBL�̌��s�X�s�[�J�[������C�����邩�Ƃ����ƁE�E�E�E����͂�����ƁE�E�E�E(^^;)�B�g�V��������������A�����������������ljA�e�̏��Ȃ�������͒�����ꂷ��悤�ɂȂ�܂����B���ɃN���V�b�N��炷�Ƃ��ɂ͈�a��������܂��B�{���n���E�G�X�g�R�[�X�g���Ƃ������Ƃł��Ȃ��ł��傤���A�h�C�c�E�I�[�X�g���A�n�̏d���Ȍ����Ȃ��n���E�b�h�̉f�批�y�݂����ɒ������邱�Ƃ����X������̂ŁE�E�E�E�i���j�B���B�u�����h�̕������ɍ����悤�ɂȂ��Ă��܂����������̍��ł��B
�@�b�ɂ��A�A�����J�ł�JBL�͂���قǔ���Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB���B�ł́i�����p�́j���S�ɗ������A�悭����Ă���͓̂��{���͂��߂Ƃ���A�W�A�炵���ł��B�{���A�����J�ň�Ԕ���Ă���X�s�[�J�[��INFINITY���Ƃ����\���܂����A�m����JBL�̉��F�͌��I�Ȃ̂ŁA�D�������͕������Ƃ͎v���܂��B�Ƃ͂����AONKYO�̂悤�ȍ��Y�X�s�[�J�[�ɂ����ڂ������Ƃ̂Ȃ����S�҂ɂƂ��āA��x�͒����Ă��炢�����u�����h�ł��邱�Ƃ͊m���ł��B
�@���āA���������Ƃ��������̃l�b�g�ʔ̋ƎҁuProCable�v�ł́A�����O����JBL��PA�p�X�s�[�J�[��Ɏ����グ�Ă��܂��B���ł��u�X�s�[�J�[�̍ŏI�v���Ƃ̂��Ƃł��i�j�B���Ƃ��Ă͂����珧�߂��Ă��������o���Ȃ����i���C�͂܂���������܂��A�Ђ���Ƃ���ƁA���b�N�n�̃T�E���h���ۂɌ����ẮAPA����o�鉹���u�����v�ƌ��Ȃ��APA�p�X�s�[�J�[���z�[���I�[�f�B�I�Ɏg�����@�����蓾��̂�������܂���B
�����ԍ��F7831922
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́I
JBL�̘b���o�Ă����̂ŏ��������Q�������Ă��������B
���E�������̘b�ɂ��o�Ă���43**�V���[�Y�Ŗ�20���N�߂��O�ɂȂ�܂���
�X�^�W�I���j�^�[��4311�̉ƒ�Ł@(4311�̓E�[�n�[����ɂ��Ă���)�@�Ƃ��ďo�Ă���
4312��JBL�Ƃ��čŏ��ɍw������SP�ł����B
�m���艿30�����~���ē����̎��Ƃ��Ă͒�����SP�ł����B����̑O�̓_�C�A�g�[��DS-35B�@MK�U
�A���v���T���X�CAUD907G Extra�Ŕ����ւ��ړI���J���b�g�����J���t�H���j�A�T�E���h��
��������Ă̎��ł����B
���̃R���r�ł��Ȃ�̊ԃ��b�N�n�ł������y�����̂ł����B
���������N��ɂȂ�ɂ�C�[�W�[���X�j���O���悤�ɂȂ�n�߂��猳�E�������@���l����SP�ł͏����������E�E�E�B
���̌�S���^�C�v�̈Ⴄ�n�[�x�XHL�R���p�N�g�ɐ�ւ��A���݂͍X�Ɉ�����KEF��IQ9�Ƃ��̃V���[�Y�n�@(�b���摖���Ă��܂��܂�����)�@�Ń}���`����ɂȂ��Ă��܂��B
����������U��Ԃ��čl����������4312�ɂ͂܂����Ȃ̑u�����A�������͍��̊��ł�
�������킦�Ȃ��Ɠ��̂��̂�����܂����B
�����ԍ��F7832164
![]() 0�_
0�_
�� �@������A����ȏd���̋���˂��悤�Ȃ��Ƃ�����āA�b���⏬�������悤�Ƃ��Ă����ʂł��B��������ׂ�̂͌��\�ł�����A�������Ɓu���Ȃ��̎��_�v���ӏ������Ńs�V�b�Ƃ܂Ƃ߂ĉ������B�����Ȃ��Ɓu�������v�Ǝv���܂���B���͗e�͂��܂���ˁB
���́A���Ȃ��ɕ�����₷�����邽�߂ɁA��U�A�_�_���i��A�u������v�]�X�ɑ��āA���Ȃ��Ɏ��₵�Ă��܂��B����قǕ�����₷������͂���܂���B����قǘb���i���Ď��₵�Ă���̂ɁA���Ȃ��͂���̂Ȃɂ��u���ʁv���Ƃ��������̂ł����H
���₳��Ă���̂Ɏ����ɓs���̈������Ƃɂ��Ă͓������A�t�ɁA�V���ɂ�����"�e��"�Ȃ����₷��悤�ȁA��������Ȃ����ɑ��ďq�ׂ鎝�_�́A���͂����ɂ��������킹�Ă���܂���B
�J��Ԃ��܂����A���́A�ȑO�Ɏ������₵�����Ƃɑ����҂��Ă��܂��B
�� �@���ꂾ���D�����茾���Ă��Ȃ���A�������_�L����ƌ�������S�O���āA�܂��P�`�������邱�Ƃ�D�悵�Ă��܂��悤�ȁu�������Y�v�͕����Ă����āA���X�̃^�C�g���ɏ��������������݂𑱂��܂��B
���Ȃ��������u�������Y�v�Ƃ́A�u�����̐ӔC��邽�߂ɁA�����ȊO�̂��̂Ɏ����̍s���E�l�����̌��������߂��Y�v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��傤���H�����������Ƃ�����Ђǂ����܂��B���̂��߂ɂ����Ёu������v�]�X�ɂ��Ẳ����߂܂��B
�Ȃ��A�ȑO����A���E�������̂����e���A�q�����Ă���ƁA���E�������́A�u24���Ԍo��������v���߂�A��A�u�l�����Ă��X���Ɋ��荞�ނ͎̂ז�������v���߂�Ƃ������`���������̂悤�ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7204223/
����́A�u�X���̃^�C�g������O��Ă��邩��v���߂�A�Ƃ����Z��҂ݏo���ꂽ�悤�ł��B
�ȉ��A���E�������ւ̃R�����g�ł͂���܂���B
�J�J�N�R���̌f���̃V�X�e����A�Ȃɂ��g�����������X���͍폜�����\��������܂��B�X���ۂ��Ƃł͂Ȃ��A�g�������铊�e�������폜����邱�Ƃ������悤�ł����A�X���ۂ��Ƃ��폜�����\���������������炠�邩������܂���B
�������݂����ꂽ�����́A�K�v�Ǝv����ꍇ�͂Ȃ�炩�̕��@�ŃX���𑁂߂ɕۑ�����邱�Ƃ������߂��܂��B
�����҂̈�l�ł��鎄�������̂��������܂����̂ł����A�Ȃ�䂫��A�������˂Ȃ炸�A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F7832509
![]() 1�_
1�_
�Z�������������Ƃ��������������͖��������H
�������A�L�����A��@�ɂ������I�[�I�^�ɉ��������Ă����ʂ����B���̌�m�Ɋ|����Δނ̎u�ꁗ���Ύ������āu�ǂ����̏o���̈������n�̐l�ԁv���Ă��ƂɂȂ����܂���(w�B
�����ԍ��F7835254
![]() 2�_
2�_
������said
����������Ȃ����ɑ��ďq�ׂ鎝�_�́A���͂����ɂ��������킹�Ă���܂���B
�@�����ł��B�ł́A�u�͂��߂��玝�_�Ȃ�ĂȂ����ǁA�������ƂȂ������Ă݂������v�Ƃ������Ƃł�낵���̂ł��傤�ȁB�ƂĂ��u�_��������肷���v�Ƃ��ɐg��u�������Ƃ�����炵�����̃Z���t�Ƃ͎v���܂��A�܂��ƂɎc�O�Ȃ���A�u�����錾�v�Ɖ��߂����Ă��������܂��B�����l�ł����B
�@�ł��܂��A���̂����́u���v���u�I�[�f�B�I�̐��E�́A���肪�ł��Ȃ�����ł���v�Ƃ����ꕶ���A�b�v�������_�ŏI�����Ă����ł��ˁB���̈ӌ���\�������ȏ�A����܂ł̋q�ϓI�ȑ��肪�d�v�]�X�Ƃ������u���v����̕������́A���ׂĘb�̚��O�ɉ����o����Ă��܂��̂ł�����B�܂�͂���܂ł́u���v����̌��������u�ꂪ�������v��ԂɂȂ�킯�ŁA���Ȃ�������ȏア���猾�t��A�˂Ă��_�������������o������ł��B
�@�����āu�q�ϓI�ȑ��肪�d�v�I�v�Ƃ����X�^���X�ɑ������W�J���A���̃{�[�h�ł�邱�Ƃ͕s�\�ł��B�ӔC�������Ȃ��u�����v�̃����o�[���W�܂��ɂ����āA�N�����u�u���C���h�e�X�g���������v�ƌ������Ƃ���ŁA���̍�������M���Ȃ���Ȃ�Ȃ������͑��݂��܂���B����ȋq�ϓI�ȃf�[�^���d�v������悤�ȃl�^�́A���ꂱ���u�_��������肷��悤�ȃX�e�[�W�v���A���Ȃ��Ƃ������ғ��m���g���𖾂����ӔC�̏��݂��n�b�L���������A�{�[�h��ł͂Ȃ��I�t���C���ȏ�ōs���ׂ��ł��傤�B���̓_�ł����̂����́u���v����ɂƂ��Ă͏��߂���s���ȃQ�[���������̂ł��B
�@���ƁA�u���߂�A�Ƃ����Z��҂ݏo���ꂽ�悤�ł��v�݂����ɁA�ߋ��Ɏ������Ȃ��Ƃ̖ⓚ�𒆒f�������Ƃɑ��ĝ��������悤�Ȍ��������₽�炵�Ă��܂����A���̔��ʁu���₢��ł����A���̂悤�Ȍ��t�̉��V�ł������Ă��邾���ł��v�Ƃ��u��������̃y�[�X�������Ǝv���ƃQ���i������v�Ƃ��������ɁA�䎩���ł́u���߂�C�}���}���v�ł���ԓx���B���Ȃ�����������܂����B�ʂẮu�Ȃɂ��g�����������X���͍폜�����\��������v�݂����ɁA���Ԃ̎��E���{�[�h�����ǂɊۓ������Ă��܂��j���A���X��Y�킹���ԓx�ɂ́A�^�������o�܂��B���������ŏ��ɓ˂��������Ă����̂͂��Ȃ��ł���H�@�����ƍ��������ė~���������ł��B
�K�b�f���I����H��
���Z�������������Ƃ��������������͖��������H
�@�Q�ĂȂ���ȁB������������ȂɃq�}���Ⴀ��܂���B�X�O�ɂ͖����ł����A���X�͏o���邾���Ԃ��܂��B
���L�����A��@�ɂ������I�[�I�^�ɉ��������Ă����ʂ����B
�@�\����Ȃ��̂ł����A���́u�@�Ɋ|����قǂ̃L�����A�v�Ȃ�Ď������킹�Ă��܂���B�`���Ɂu�I�[�f�B�I���͖��ʂɒ����v�Ə������ʂ�A���܂��ɃA���v�̑g�ݗ��Ă͂��납�X�s�[�J�[�̎��삳����������Ƃ̂Ȃ��s��p�ȓz�ł��B���������������@��̐�ΐ������͑����̂ŁA���̂ւ�̒m���������A�˂Ă���ɉ߂��܂���B
�@�ł��܂��A�s�{�ӂȂ���u�{�[�h��ł̔P�荇���v�Ɋւ���u�L�����A�i�H�j�v�́A���͐ς�ł��邩������܂���ˁi�j�B�ߋ��ɂ����āi�ʂ̃T�C�g�ł̘b�ł����j�d�q��c���ł̃����`���₨�ӂ������߂��Čf������@���o���ꂽ�P�[�X����x���x�ł͂���܂���i�j�����j�B����ł́A����Ƃ���낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F7837245
![]() 1�_
1�_
�@�Z������A����ɂ��́B�m���ɃP�[�u���̍ގ��́u���x�v��搂�����ɂ������i�ɂ̓��N�Ȃ��̂��Ȃ������ł��ˁB�u�킸���Ȏ����̈Ⴂ�Ŏ̏ۂ����ƌ�����v�f�v�ȂǁA���[�U�[�ɂƂ��ĉ��̖��ɂ������܂���B�������A�u���x�v���������邽�߂��₽��n�C�オ��̐F�t�������Ă���P�[�u�����������肵�āA���̕���́u�������v����ۂÂ��܂��B
�@���\�N�O�ɔ������ꂽWE�Ƃ�Belden�̃��B���e�[�W�P�[�u�������ł��ʗp����Ƃ�������Ă��A�ʂ����ăI�[�f�B�I�P�[�u�����́A�i�����Ă���̂��낤���Ƌ^��Ɏv���܂��B
�@�P�[�u���ɑ��鎄�̃X�^���X�́u�������Ă͂����Ȃ����A�ߓx�Ȋ��҂��֕��v�Ƃ��������̂ł��B�����牽�ł��t���i�̃P�[�u���ł̓V���{�C�̂Ŏs�̕i����������ǂ��̂ł����A������Ƃ����ăP�[�u��������Ă��A5���~�̃X�s�[�J�[����100���~�N���X�̉��͏o�Ă��܂���B���[�^�[�����萔�\���~������X�s�[�J�[�P�[�u���ȂǁA�ǂ����ǂ�������Ȕ��l���o�Ă���̂��s�v�c�ł��B�ǂ����̃T�C�g�Łu�X�s�[�J�[�P�[�u���̓��[�^�[�������~�O��̂��́iRCA�P�[�u���Ȃ��1���~�O��j����ԃR�X�g�p�t�H�[�}���X�������v�Ə�����Ă����悤�ȋL��������܂����A�n�C�G���h�V�X�e���͕ʂ�������܂��ǁA���ʂ̃V�X�e���Ȃ���̒��x�̂��̂ŏ\�����ȂƎv�����肵�܂��B
���ړ_�̎����͏d�v
�@����͌����܂��B�ړ_�N���[�i�[�ł̃����e�ʼn������t���b�V�����ꂽ�̂�̌��������Ƃ͉��x������܂��B�P�[�u�����I�[�f�B�I�@��̈ꕔ�ł�����u�g�����Ȃ��v���K�v���Ă��Ƃł��傤�B
�@�P�[�u���ɂ��Ă͐܂����Ă܂��G�ꂽ���Ǝv���܂��B
�@satoakichan����A����ɂ��́B
�@���������A4311��4312�̓E�[�n�[����ɂ��Ă��܂����ˁB�u�ቹ���j�b�g�͈ʒu�����łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ӎ��I�Ȑ���ς𗠐�悤�ȃ��C�A�E�g�ŁA�ŏ������Ƃ��̓C���p�N�g�����������ł��BSANSUI��JBL�̗A���㗝�X������Ă����W��A����ς�}�b�`���O�͗ǂ������ł��ˁB�]�k�ł����ASANSUI���X�s�[�J�[���o���Ă������Ƃ��v���o���܂����B�҂ݖڊi�q�̃T�����l�b�g����ۓI��������A�̃V���[�Y������܂������A����JBL�Ƃ͂܂������Ⴄ�u�܂�����n�v�������͖̂ʔ����Ɗ��������̂ł��B
�@�n�C�G���h�@��EVEREST�������������Ƃ�����܂����ǁA���j���o�݂����ȉ��Ȃ���A�N���V�b�N�𗎂������Ē����ɂ͌����Ȃ��C�����܂��B�����̂́u�n�[�x�X��SPENDOR��KEF�Ȃ�Ă����p�����X�s�[�J�[�͖����Ē����Ȃ����I�v�Ǝv���Ă����̂��A���͖��邭�g���݂̂��鉢�B�u�����h���i�Ɏ䂩��Ă���̂����珟��Ȃ��̂ł��ȁi�j�B����ł́A���ꂩ����X�������肢���܂��B
�����ԍ��F7837261
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@�@������(^-^)/
���]�k�ł����ASANSUI���X�s�[�J�[���o���Ă������Ƃ��v���o���܂����B�҂ݖڊi�q�̃T�����l�b�g����ۓI��������A�̃V���[�Y
�����ł��B
�҂ݖڊi�q��SP��13cm�E�[�t�@�[��SP-K1�i�H�j�����̂���ۂɎc���Ă��܂��B
�܂�10���N�O�̓T���X�C��SPENDOR�̑㗝�X�����Ă��܂����B
�E�E�����T���X�C�}�ł����̂ŁA�}�����ł�(^-^)/
�����ԍ��F7838559
![]() 0�_
0�_
�T���X�C�ł����I�B�T���X�C�̃X�s�[�J�[�͊i�q�̃T�����l�b�g(�T�����l�b�g�ł͂Ȃ����g���ȁH)���m���Ɉ�ۂ���܂����A������E�E�E�̂̓X�s�[�J�[2��ƒ����ɃA���v�^���V�[�o�[/���R�[�h�v���[���[�̃��j�b�g���g�ݍ��킳�ꂽ�u�Z�p���[�g�X�e���I�v�Ə̂��Ċe���[�J�[���������Ă��܂����ˁB���̃��[�J�[�̓^�_�̔Ŏl�p�ɑg���ő����\�����Ă��܂������A�T���X�C(�R��)�̓X�p�C�N�Ƃ͌����܂��_�Ŏx���Ă����L��������܂��B
�T���X�C�̐��i�̓v�����C���A���v��AU-��907���g���܂����B���̃A���v�͗ǂ������ł��ˁB
�����ԍ��F7839124
![]() 0�_
0�_
�� ������said
�� ����������Ȃ����ɑ��ďq�ׂ鎝�_�́A���͂����ɂ��������킹�Ă���܂���B
��
�� �@�����ł��B�ł́A�u�͂��߂��玝�_�Ȃ�ĂȂ����ǁA�������ƂȂ������Ă݂������v�Ƃ������Ƃł�낵���̂ł��傤�ȁB
�u�ł��傤�ȁv�Ƃ́A����͎���ł����H
�������₾�Ƃ�����A�O�ɂ��������悤�ɁA�����ƈȑO�Ɏ��₳�ꂽ���Ƃɂ��܂��ɓ����Ȃ��ł���l���V���ɂ��鎿��ɂ͓����܂���B
��������łȂ��Ƃ�����A���͉ߋ��� [7820193] �̑O���Ŏ��_�ɂ��Ă�"���_"�������Ă���܂��B
�� �ƂĂ��u�_��������肷���v�Ƃ��ɐg��u�������Ƃ�����炵�����̃Z���t�Ƃ͎v���܂��A�܂��ƂɎc�O�Ȃ���A�u�����錾�v�Ɖ��߂����Ă��������܂��B�����l�ł����B
�u�I���v����Ȃ��āu�����v�ł����B���₤�����ԈႦ��Ƃ���ł����B�u�I���v�Ə����ꂽ�̂Ȃ玄���Ђ���Ƃ�����ق��Ă�����������܂���B
�͌�E�����͒m��܂��A�u�����v���ĕ������ق����������t����Ȃ��ł����B���Ȃ��͂����g�̗��ꂪ��������ł͂Ȃ��悤�ł��ˁB
���Ƃ��Ώ�����������A�������Ȃ��Ɂu����v�ƌ������̂ł��B����ɑ��Ă��Ȃ��͎����̔Ԃ����Ă���̂ɁA��������ɁA�u�قق��A����ł����B���Ȃ�������ł��ˁB����Ȏ��ł悤�ł͂��Ȃ��̕����͌��܂��������R�ł��ˁB�����ł��ˁB�����ꂳ��B�v�ƌ����Ă���悤�Ȃ��̂ł��B�S���t�������玩����1���[�g���̃p�b�g���c���Ă����Ȃ���A�u�I�b�P�[�ˁB�v�ƌ����ă{�[�����E���グ��悤�Ȃ��̂ł��B
���͓������܂���B���͂��Ȃ��̔Ԃł��B���Ȃ���������āE�ł��Ă��������B�����ƃp�b�g���Ă��������B
�� �@�ł��܂��A���̂����́u���v���u�I�[�f�B�I�̐��E�́A���肪�ł��Ȃ�����ł���v�Ƃ����ꕶ���A�b�v�������_�ŏI�����Ă����ł��ˁB���̈ӌ���\�������ȏ�A����܂ł̋q�ϓI�ȑ��肪�d�v�]�X�Ƃ������u���v����̕������́A���ׂĘb�̚��O�ɉ����o����Ă��܂��̂ł�����B�܂�͂���܂ł́u���v����̌��������u�ꂪ�������v��ԂɂȂ�킯�ŁA���Ȃ�������ȏア���猾�t��A�˂Ă��_�������������o������ł��B
�����u���肪�ł��Ȃ��v�ƌ������̂́A�u����@��ł͑��肪�ł��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ������ł��B�Ȃ��A����͂��Əo���̌�����ł͂���܂���B���͉ߋ��ɂ��̃X���� [7820193] �� [7825915] �ŁA����@�킠�邢�̓u���C���h�e�X�g�ɂ��Č��y���Ă��܂��B
�� �@�����āu�q�ϓI�ȑ��肪�d�v�I�v�Ƃ����X�^���X�ɑ������W�J���A���̃{�[�h�ł�邱�Ƃ͕s�\�ł��B�ӔC�������Ȃ��u�����v�̃����o�[���W�܂��ɂ����āA�N�����u�u���C���h�e�X�g���������v�ƌ������Ƃ���ŁA���̍�������M���Ȃ���Ȃ�Ȃ������͑��݂��܂���B����ȋq�ϓI�ȃf�[�^���d�v������悤�ȃl�^�́A���ꂱ���u�_��������肷��悤�ȃX�e�[�W�v���A���Ȃ��Ƃ������ғ��m���g���𖾂����ӔC�̏��݂��n�b�L���������A�{�[�h��ł͂Ȃ��I�t���C���ȏ�ōs���ׂ��ł��傤�B���̓_�ł����̂����́u���v����ɂƂ��Ă͏��߂���s���ȃQ�[���������̂ł��B
���̎咣�����ɂ͗ǂ������ł��܂���ł����B
�܂��A�u�����v�ł͂ł��Ȃ����R��������܂���B�Ƃ��Ɂu�ӔC�������Ȃ��u�����v�v�Ə�����Ă��܂����A�u�����v�Ƃ́A���̌f���ł̃j�b�N�l�[��������Ɋ܂܂��̂ł��傤���H���Ȃ킿�A���E�������́u�����v�Ȃ̂ł����H
�����������Ƃ�����A���E�������͂����g�̂����e�ɐӔC���������ɎQ������Ă���Ƃ������Ƃł����H
�܂��A�u�{�[�h��v�Ɓu�I�t���C���ȏ�v�̂������ŁA�Ȃɂ��Ⴄ�ƌ��������̂���������܂���B�ӔC�����邩�Ȃ����Ƃ����Ⴂ�����ł͂Ȃ��A����ɂ͐g���𖾂������Ƃ܂ŕK�v�ƌ�����̂ł��傤���H
(�Ȃ��A�����j�b�N�l�[���͓����ł͂Ȃ��Ƃ��������̂ł�����A���Ȃ����咣����{�[�h�ƃI�t���C���̈Ⴂ�́A�g���𖾂������������Ȃ��������ɂȂ�܂��ˁB)
���ɂ́A�Ȃ��A����ɍۂ��Đg���𖾂����K�v������̂���������܂���B���������āA���߂�����ɏ����Ă���A���ɂƂ��ĕs���A�̂悤�Ɍ����鍪����������܂���B
�����ԍ��F7839304
![]() 0�_
0�_
���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B�P�[�u���ɂ͐F�X��
����悤�ł����A�a������100���~���炢��������
���Ă������`10�����~�̃P�[�u���Ȃǁy���Ƃ��Ă�
���l�z�������Ȃ��̂Ŏ��Ȃ甃���܂���ˁi�j�B
�P�[�u���ɑ���X�^���X�����������悤�Ȃ��̂�
���͕ς��Ƃ͎v���Ă܂����i���������ꂪ��R��
�Ⴂ���Ă邾�����Ƃ��Ă��j�A���ɂƂ��Ă�
�h���X�A�b�v�݂����Ȃ��̂ł��B
����ɂ��Ă�ELAC�����ዾ�ɂ��Ȃ��܂������I�I
���A���̃��[�J�[��S���m�炸�A���R�����ō����
�\�b�R�[�������̂ł����A����ł����̑O�ɉ��i��
���ׂ��炠�܂菑�����݂��Ȃ��A�E�z�B�}�C�i�[��
SP�Ȃ̂��H�w�������珮�̂��Ɗ������I�I�x�Ƃ�
�v���Ĕ�������G���ł͂��Ȃ�]���̍�������SP
�������悤�ŁA���ꂪ��ԃK�b�N���ł����i�j�B
�L���Ŏ����オ��Ƃ낭�Ȏ����Ȃ��̂ŁB
�ł����͋C�ɓ����Ă܂��B
�����ԍ��F7839857
![]() 0�_
0�_
�|�� audio-style����
�@����������SANSUI�̃X�s�[�J�[��SP-XI��SP-XII�ł������A�\�t�g�h�[�����g�p���Ă����������A�_�炩�߂̉��ł����ȁBJBL�̃��j�b�g���g����SP-LE8T�Ƃ����̂�����܂������A�Ƃ��Ƃ��������ɏI���܂����B�ǂ�ȃT�E���h�������̂����ł�����������܂��BSPENDOR�̑㗝�X�����Ă�����ł����B����͒m��܂���ł����B
�|�� 30theater����
�@���������ASANSUI�̓Z�p���[�g�A���v�ɂ����́u�y�P�y�P�i�q�i�� ^^;�j�v���̗p���Ă��܂����B����������SANSUI��QS�Ƃ���4�`�����l���E�X�e���I�̋K�i���Ă��Ă��܂����ˁBSONY��SQ�ƕ���킵���ł����ǁi�j�A�ʏ��2�`�����l���E�X�e���I�̎c�������i�H�j�������I�Ɉ�������o���ă��A�X�s�[�J�[�Ŗ炷�Ƃ������@�������悤�ɋL�����Ă��܂��B�ʃX���b�h�ł������܂������A�s���N�E�t���C�h�̖��Ձu�_�[�N�T�C�h�E�I�u�E�U�E���[���v��QS�V�X�e���Ń��R�[�f�B���O���ꂽ�Ƃ����̂́A�Â�����̃��b�N�t�@���ɂƂ��Ă͗L���Șb�ł��B
�|�� �Z������
�@�s�����̃f�B�[���[�̓X�����u�����V�X�e�������̃n�C�G���h�P�[�u���Ƃ�RCA�P�[�u���ł�3���~�A�X�s�[�J�[�P�[�u���ł̓��[�^�[������5��~���炢�����x�ł��傤�B���\���~�̃P�[�u���Ȃ�āA�I�J���g�ł��v�ƌ����Ă܂������A�����ł����BELAC�̃X�s�[�J�[���āA�̍ŏ��ɒ������Ƃ��́u������A�w���������V�r�A�B���X�j���O�|�C���g�����肳�ꂻ���v�Ǝv�����̂ł����A�ŋ߂̐��i�͂���قǂł��Ȃ��悤�ł��ˁB���J�j�J���ȃf�U�C���͍D���������������ł��傤���ǁA���͍D���x�������ł��B
�@����ł́A����Ƃ���낵�����肢���܂��@�|�� ALL�B
�����ԍ��F7841371
![]() 0�_
0�_
�@�{����SHARP�ɂ��ď����Ă݂܂��傤�B���͑��ɋ����\�����胁�[�J�[�ł����A1912�N�ɑn�Ƃ������ɂ͓����ŏ������Ă���ł��ˁB�����̓V���[�v�y���V��������Ă��āA���̌ꌹ�ƂȂ����̂͗L���Șb�B�֓���k�ЂōH�ꂪ��Ђ��A���ɋ��_���ڂ�����ɓd�C���i�̊J���ɖ{�i�I�Ɏ��g�炵���ł��B
�@SHARP�̃I�[�f�B�I���i��OPTONICA�i�I�v�g�j�J�j�Ƃ����u�����h���t���Ă��܂����B�ł��A����OPTONICA�̒P�i�s���A�E�I�[�f�B�I���i����x�����������Ƃ�����܂���B70�N�㖖�ɂ�CP-3820�Ƃ�CP-3830�Ƃ������K�E�X�Ђ̃��j�b�g�����O�̃G���N���[�W���[�Ɏ��߂��n�C�G���h�̃X�^�W�I���j�^�[�p��^�X�s�[�J�[�V�X�e�����o���Ă���A����Ƃ������Ă݂��������̂ł����A���̊�]������Ȃ�������OPTONICA�u�����h�͏I����Ă��܂��܂����B
�@�ŁA�B�ꎨ�ɂ��邱�Ƃ��o����OPTONICA���i�́A�����q���̍��ɗ��s����4�`�����l�������̃Z�p���[�g�E�X�e���I�����ł����B4�`�����l���͍��̃T���E���h�̂͂���ł������A�e��僁�[�J�[�������̐��i�𓊓����钆�ASHARP������ɕ֏悵���i�D�ł��B�Ƃɂ����т����肵���̂́A�f�J�����Ƃł����B➑̂����̃��[�J�[��������傫���B�����āA30cm�E�[�n�[������ɗh��Ă������Ƃ��o���Ă��܂��B������l����ƁA���������̉��ʂŃE�[�n�[�����ꂾ���h���͂����Ȃ��̂ł����A�㔭�ł�������E��僁�[�J�[��SHARP�Ƃ��ẮA�����ڂ̃n�f���ŃA�s�[�����邵���Ȃ������̂ł��傤�B���������Βl�i�����Ђ�肩�Ȃ���������ł��B
�@���ł�SHARP�Ƃ����Ήt�����͂��߂Ƃ��鍂���Z�p�Ńu�����h�C���[�W�͊m�����Ă��܂����A����N�ォ���̐l�ԂɂƂ��āASHARP�́u�����낤�A�����낤�v�̑�\�ł����B�Ɠd�i�͏����Ⓦ�ŁA�����Ȃǂ��ꗬ�ŁASHARP�͎O�������B�d�q�����W�Ȃ�ē��{�ł�SHARP�����c�݂����Ȃ��̂ŁA�䂪�Ƃł��g�������Ƃ�����܂����A�Ƃɂ����̏�̑����ɂ͕��������̂ł��B���̍��͋ߏ��̓d�퉮���uSHARP���i�͈������ǁA�̏�̑������o�傷�邱�Ƃ��ˁv�Ɩ������Ă��܂����B����������ۂ��c���Ă�����̂�����A������uSHARP�̃e���r�͐��E�̋T�R�u�����h�v�Ƃ����Ƃ������悤�ƁA���݂ł���������̂͂��߂���Ă��܂��܂��i�j�B
�@�����SHARP���s���A�E�I�[�f�B�I�ɓd�����A�����̂�2001�N�BSM-SX200�Ƃ���1�r�b�g�f�W�^���A���v�������̂ɂ͋����܂����B���i����1,575,000�Ƃ����n�C�G���h�B��p�@���SM-SX300���܂߂ĉ��x���������܂������A���k�ȓW�J�Œ��������̂��鉹�ł����B����ELAC�̃X�s�[�J�[�Ƃ̃R���{���[�V�����͑f���炵�������ł��B�������ASM-SX10�̐����I���������Ă��̕��삩��ēP�ނ����݂����ł��B���A�̖ڏ��͕t���Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����A������x�߂��Ă��邱�Ƃ����҂��������̂ł��B
�����ԍ��F7841378
![]() 0�_
0�_
���E�������@ �����́I
�@
����̓V���[�v�ł��ˁA�ł����@[7841371]�@�ŃT���X�CQS�̘b���o�Ă܂����B
���͂��̃T���X�C�̃v���b�Z�b�T�[QS-D�P�O�O�O�ƌ��������̂��ŋߕ��������čĂюg�p���Ă��܂��B
�f�X�N���[�g�A�}���`�`�����l���͐�p��H�ɂ��C���Đ��ł����A�ʏ�QCH�̃T�����h�Đ��ɂ͂��̋@����g���Ē����Ă܂��BAV�A���v�ɂ��T�����h�Ƃ͑S���Ⴄ���ł��[���ʗp���鉹���A���ꊴ���Đ��ł��܂��B
���s���N�E�t���C�h�̖��Ձu�_�[�N�T�C�h�E�I�u�E�U�E���[���v��QS�V�X�e���Ń��R�[�f�B���O���ꂽ�Ƃ����̂́A�Â�����̃��b�N�t�@���ɂƂ��Ă͗L���Șb�ł��B
�S�������ĂǑf�l�Œm��܂���ł����I���ł�������̂ł��傤���ˁ[�H
QS�V�X�e���^���Ȃ琳�K�f�R�[�h�ōĐ��ł���̂ł����E�E�E�B
�b�������ɂ��炳���Ă����܂���ł����AQS�̕������������̂Ŏv�킸�������Ă��܂��܂����I
�����ԍ��F7841539
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@�@������(^-^)/
130theater����
�����̃��[�J�[�̓^�_�̔Ŏl�p�ɑg���ő����\�����Ă��܂������A�T���X�C(�R��)�̓X�p�C�N�Ƃ͌����܂��_�Ŏx���Ă����L��������܂��B
���I�ڂ̂��ǂ��낪�V���[�v�ł��ˁB(^-^)/
satoakichan����
���S�������ĂǑf�l�Œm��܂���ł����I���ł�������̂ł��傤���ˁ[�H
QS�V�X�e���^���Ȃ琳�K�f�R�[�h�ōĐ��ł���̂ł����E�E�E�B
�v�킸�A���܂�����ł������R�[�h��T���܂����B
�����I4ch���R�[�h�E�E�E�ȁE�ȁE�Ȃ�Ɖ����`���̃��C�u�R���T�[�g(^_^;)
�E�E�E�t�@���ł�����������ł����ǁE�E�E
���ł�4chQM�����ƂȂ��Ă��܂����B
�����ԍ��F7842695
![]() 0�_
0�_
�Z������@
���C���[���[���h�̃X�s�[�J�[�P�[�u���́u�S�[���h�G�N���v�X�X�s�[�J�[�P�[�u���v�̓o�C���C���[�^�C�v�̂R���Ł�1,228,500�ł��B���ł�����g���邨����100����123���~�������炱�ꔃ���܂��B����̗l�ł�����O������X�v�[���ɂł����H�����āE�E�E�E�B����ɂ��Ă�100���~�����ăI�[�f�B�I�D���Ȃ�X�s�[�J�[�P�[�u����123���~�����H����̂ł��傤���˂��H�H�B(�r���E�Q�C�c���ƃC���h�̕��ƃh�o�C�̉��l�ł�����123���~�Ȃ�Ĉ�������ł��B)
���E�������
�V���[�v�ł����E�E�E�B�������ɃV���[�v�̃s���A�I�[�f�B�I���i�ɂ͐G��͓����܂���ł����B�����A�Ƃɂ�32��37�^�̃A�N�I�X������܂��B�ŏ��ɔ�����HDD/DVD���R�[�_�[���V���[�v�ł����B���`�ƌ�́E�E�g�т��V���[�v�ł��B�t�������Q���Y��I�I�B���Ƃɂ���V���[�v���i�ň�ԍ����̂́u���z�����d�V�X�e���v�ł��ˁB�n�����g���h�~�ɓ��Ƃ͍v�����Ă��܂��B�E�E�E�V���[�v�E�E���₢��u����d�@���v�̐�@�������Ŏg���Ă��܂��B�ꉞ�S�@�\����ł��B(�����NHK�̃N���[�Y�A�b�v����Łu���Â��d�����i�v�Ƃ������e�ŕ������Ă��܂����ˁB���v�ł��傤���H�A����d�@�̐�@�́H�H�B)
�����ԍ��F7842994
![]() 0�_
0�_
���E�������A���߂܂��āB
�@�l�I���W�Ɛ\���܂��āA�ė��N���炢�Ɂu�Ԃ������v�𒅂�N�ɂȂ�܂��B
�@�������̃I�[�f�B�I���i�̂��b�Ƌ��ɎR��-JBL�̘b���o�Ă���܂��Ă��Ăт��Ȃ��̂�
�@���ז������Ă��������܂��B
�@�R������JBL-SP���g�����߂Ă���40�N�߂�JBL�̉��������Ă��܂��B
�@�������ɂȂ��Ă����uSP-XI��SP-XII�v�͎��̋L���ł͎R�����ƌ������ƂŁA
�@JBL�́@���j�b�g���g����SP�V�X�e���ł͖��������悤�Ɏv���܂��B
�@���̑O�ɂ�SP-10�ESP-50�ESP-70�ESP-150����SP���o���Ă��܂����B
�@JBL���j�b�g���g�����V�X�e���́ASP-LE8T�ESP-505J�ESP707-J�ESP2115�Ȃǂ̑O���A
�@���̌��SP-G3000��M���ɂ���c�C���E�[�t�@�[��3WAY�@������܂����B
�@�����g�p�����̂͑O���^�R�@��ł����ASP-LE8T��20CM�̃V���O��SP�V�X�e���A
�@SP505-J��D123+LE-20T��2WAY�o�X���t�ASP707-J��D130�{LE175�̃o�b�N���[�f�b�h�z�[��
�@�V�X�e�����̗p����2WAY�ł����B
�@��ԋC�ɓ����Ă����̂�SP505-J�̃c�C�[�^�[��075�ɕύX�����V�X�e���ł����B
�@30CM��D123���t�������W�̂܂g�p���Ē�����O�V�T�ƃN���X���������͍D�݂ł����B
�@38CM��D130�̒ቹ�ɕ����͂��܂������A�V�X�e���Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂��SP505-J�̕���
�@���ł��Y����Ȃ��ł��B
�@���A�\�����Ă��܂��܂������������������B
�@���ꂩ����y�������b�A�y���݂ɂ��Ă���܂��B
�����ԍ��F7843167
![]() 0�_
0�_
���͂悤�������܂��I
audio-style����@�Ɉꌾ�@(���ӂ̋C����������(^^;)
���v�킸�A���܂�����ł������R�[�h��T���܂����B
�����I4ch���R�[�h�E�E�E�ȁE�ȁE�Ȃ�Ɖ����`���̃��C�u�R���T�[�g(^_^;)
�E�E�E�t�@���ł�����������ł����ǁE�E�E
���ł�4chQM�����ƂȂ��Ă��܂����B
���萔�������A�T�������������肪�Ƃ��������܂����B
������4ch�A�e�Њe�l�Ŋe�X�̈Ӓn�̓˂����肠���ŁA�w�ǐZ�����������Ă����Ă��܂��܂����ˁI
�ł�4ch���R�[�h���������ɂȂ��Ă�I���w�̐[���������܂����A������X�������肢�������܂��B
�����ԍ��F7843439
![]() 0�_
0�_
�F�l�A������������܂��Bsatoakichan����A���߂܂��āB
�@�uQS�Sch�v�ɍĂє��������ĖႢ�܂��B
�@��L�̎R��-JBLSP���g���Ď����uQS-1�v�ƌ����v���Z�b�T�[���g���ĂSch����
�@���܂����B�t�����g��SP505�{AU9500�A���A��SP-LE8T�{AU777�ł����B
�@74'���������ł��傤���H�܂��Sch�f�B�X�N���[�g�̃��R�[�h�͖������������A
�@�������������͂����肵�܂��A�R���N�V�����ɂ́u�^���Sch�v�̃f�����R�[�h��
�@�����ƁA�I�[�v���e�[�v�����{�������Ǝv���܂��B
�@��ɒ������̂�JAZZ�́u���C�u�Ձv���V���~���[�g�Sch�ɂčĐ����A���A���т�
�@���E����A�b�����A�O���X�̉��A����Ȃǂ����Ȃ胊�A���ɕ������邱�Ƃɋ���
�@��т܂������A���ƒ����ɔM����߂Ă��܂��܂����B
�@�u�@�B�D���v�������ăp�C�I�j�A�̂Sch�A���v�uQA-80�v�Ƃ�����ɓ���܂�����
�@�̂Ă�ɂ͔E�тȂ��uQS-1�v���X���݂ł��u�[�˂̔�₵�v�ɂȂ��Ă���܂��B
�@YAMAHA��DSP���o��ɂ͂܂��T�N�قǂ���ADolby�EDTS�ƌ����e�N�m���W�[�̐i����
�@������I�Ɂu�T���E���h�v���s�����A�u��{���v��AV�ƌ����V�W��������
�@���W�ɂ͋�����������ł��B
�@�����֗��āu���̒m�V�v�ƌ������u���̒m�V�v��2CH�Đ�����������Ă��邱�Ƃ�
�@�u����͌J��Ԃ��v�ƌ�����ۂɁA�����ʂł��B
�@
�@
�@
�����ԍ��F7844137
![]() 0�_
0�_
���E�������Aaudio-style����A130theater����A�l�I���W����A�����́B
�@�@�@���E�������A�͂��߂܂��āB���̓I�[�f�B�I��͖�50�N�ƒ����̂ł������E�������̂悤�ɏڂ�������܂���BCD���o����܂ŁASONY�̃I�[�v�����[����1120F�Œ������y���݂܂����B1120F�͖����Ɍ��݂ł����ASONY��CDP���C���s�\�ɂȂ�}�����c��SA14���w�������̂��ĂуI�[�f�B�I�ɖڊo�߂���|���ł����B
�@�V���[�v���b��ɂȂ�܂����̂ŁA�ꌾ�B���������낤�����낤�̃C���[�W�ł������ŋ߂̃V���[�v���������܂����B�S�����̐���@��5�`6�N�ԁA�̏���Ȃ��g���Ă��܂����ABD���R��HD100��BD�h���C�o�[�̕s���������2CH�Đ��͍��ł���������ԗǂ��ł��B
�@������Ƀv���V�{�[�ł͂Ȃ����ƁA���w�E���ꂽ�̂ŁA[NHK�Z��]�ɍs����[��]�̃��J�j�Y�����m���߂Ă��܂����B�����z�������ʂ�AAAC���k�d���ł��𓀂̐ݒ��AAC�ɐݒ肷���[�h���r�[�f�W�^��]�ɂȂ�PCM�ɐݒ肷���PCM�̔k�ɂȂ邻���ł��B1bit�Đ��Z�p���W���Ă��邩�͕�����܂��A������BD���R�ł́A������2CH�Đ��̉��ł̓g�b�v�ł��B
�@�܂��A�_�E���~�b�N�X�ƌ����̂��Ȏ҂ł��BSONY��BD���R�AX90��5.1CH�AAAC�Đ��́A�ƂĂ��ǂ��̂ł����ABD��5.1CH��2CH�����݂��Ă���ƁA2CH�Đ��ɂȂ����r�[�A�������K�N�Ɨ����܂��B����̓~�b�N�X�ł͂Ȃ��A�`�����l���J�b�g�̂悤�Ȉ�ۂ��܂��B
�����ԍ��F7844944
![]() 0�_
0�_
QS�̘b�ɍĂє����I�F�����܂���B
�l�I���W����@�����炱���͂��߂܂��āA�X�������肢�������܂��B
����L�̎R��-JBLSP���g���Ď����uQS-1�v�ƌ����v���Z�b�T�[���g���ĂSch����
�@���܂����B
���̌��̖��@�ƌ���ꂽQS-1���������̎��A�����ł��ˁI�I�I
����QS-D1000�͂���QS-1�̌�A�h���r�[�T�����h���͂��n�߂����ɁA�T���X�C���o�������̂ł����B�@�������m���Ƃ͎v���܂������ꌾ�������킳���Ă��������܂����B
�������֗��āu���̒m�V�v�ƌ������u���̒m�V�v��2CH�Đ�����������Ă��邱�Ƃ�
�@�u����͌J��Ԃ��v�ƌ�����ۂɁA�����ʂł��B
�@
�m���ɂ��̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
���̏ꍇ���y�̃}���`�Đ����D���Ȃ�ł��A�����Ă���QS-D1000���g�����T�����h�Đ���
���X�̂Ă������ASP�}�g���N�X�Đ����l�A���ł������Ă܂���I(�ܘ_2ch�Đ��������Ă܂���(^^))
�����ԍ��F7845091
![]() 0�_
0�_
�|�� satoakichan����
�@�s���N�E�t���C�h�́u�_�[�N�T�C�h�E�I�u�E�U�E���[���i���C�j�v��SACD�}���`�ł��o�Ă��Ď����������Ƃ�����܂��B�L���ȃL���b�V�����W�X�^�[�̉��⎞�v�̉����O�����I�ɒ�ʂ��āA����ς�債�����̂��Ǝv���܂����B���̃f�B�X�N�̃G���W�j�A�������A�����E�p�[�\���Y�͌�Ɏ���̃v���W�F�N�g�����A�D�G�^���Ղ�A�����Ă��܂����ȁB
�@SANSUI��QS��RM�i���M�����[�E�}�g���b�N�X�j�����̈�ł������A4�`�����l���E�X�e���I�̖����ɂ́A����RM��SONY��SQ�A������VICTOR��CD-4�ƁA�݊����̂Ȃ�3�̋K�i�̃f�R�[�_�[���ׂĂ���������Z�p���[�g�X�e���I�Ȃ�Ă̂���������Ă���܂����B�������A4�`�����l�����I�������̂�CD-4�̃I�[�v�����[���e�[�v�ɂ��e�`�����l���́u�L�`�b�Ƃ��������v�Ƃ͈Ⴄ���R�[�h�Ղł́u������̕����v�����C�����������Ƃ�����̂ł��傤�B�ł����̂������Ń��R�[�h�J�[�g���b�W�͊i�i�̐i���𐋂����悤�Ȃ̂ŁA�܂��ǂ������̂ł͂Ȃ��ł��傤��(^^)�B
�|�� audio-style����
�@�������A�����`�����X���B�u���̓z��v�u�������v�u���D�_�v��3�A���͓����K�L�傾�������������C���p�N�g���܂����B���w�Z�̋����ɂ������d�q�I���K���łӂ����āu���̓z��v�̃����f�B��e���Ă����Ƃ���搶�Ɍ�����L���ɗ������ꂽ���Ƃ������������i�����j�B
�@�������̗̂̉w�Ȃ̃f�B�X�N���ĉ����ǂ���ł���ˁB����80�N��ɂ̓s�[�N���}���Ă����Ǝv���܂��BCD�����ɏo�����Ŋe���R�[�h��Ђ��C�����������Ă����̂ł��傤�BCBS�\�j�[�Ȃ�ăf�W�^���^���A���ŁA�V�X�e���̃`�F�b�N�p�Ɏg���Ă����I�[�f�B�I�]�_�Ƃ��������炢�ł�����ˁB������J-POP�̒�x���̘^���Ƃ͑�Ⴂ�ł��B
�|�� 130theater����@
�@WireWorld�̃P�[�u�����Ďg�������Ƃ��u�����v�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�ǂF�Ȃ̂��m���߂����C�����܂��B�����́u�����v�炵���ł��ˁB
�@SHARP�Ƃ����A2002�N���ɁuAuvi�v�ƌĂ��~�j�R���|���o���Ă������Ƃ������āi���ł�����܂����A�ʕ��ł��傤�j�A���ꂪ1�r�b�g�f�W�^���V�X�e�����ڂ̗D�ꕨ���������Ƃ��v���o���܂��BCD���ォ��X���b�g�C�������Ƃ�������ȍ\���ł������A�����������߂̃X�s�[�J�[�ł��\���炵�Ă���܂����B�������������ʼn��̗ǂ��V�X�e�������y����Ǝ�҂̎����삦�Ă��āAJ-POP�̃N�H���e�B���オ�邩�ȁE�E�E�E�Ȃ�Ďv���Ă�����A�オ�����Ȃ������ł��ˁB�c�O�B
�|�� �l�I���W����
�@SANSUI�̃t�@�����č��ł������̂ł��ˁB�O�q�̂悤�Ɏ���SANSUI�̃T�E���h�͋��ł����A�Ȃ������C���E�V�X�e���̃`���[�i�[������SANSUI���ł��i�j�B���x���c�}�~�ɃK�^�������̂ł����A���b�N�X�������Ȃ��̂ŏ�������̂ɔE�тȂ��A�C�����d�˂Ďg���Ă���܂��B
�@SANSUI�̐��i�ŗB��u�{���ɗ~�����v�Ǝv�����̂����R�[�h�v���C���[��SR-929�ł��B77�N���̐��i���Ǝv���܂����A8���~��Ƃ������i�Ɏ�����ʏd���ȃs�A�m�p�d�����ʎd�グ�̃L���r�l�b�g�ŁA�����������Ղ�B������������VICTOR�́A����܂��ؖڋ��ʎd�グ�̃v���[���[����ɓ��ꂽ���肾�����̂ŁA�w���ɂ͎���܂���ł����BSANSUI�̓f�U�C���Ƀ|���V�[������Ƃ���͑傢�ɕ]���ł���Ǝv���܂��B
�@����2CH�Đ�����������Ă��邱�Ƃɂ͊����ʂł��B�u�l�Ԃ̎��͓�Ȃ̂�����A�X�s�[�J�[��2��ŏ\�����I�v�Ƃ͖^�f�B�[���[�̃X�^�b�t�̃Z���t�ł����A�X�e���I�t�H�j�b�N�Đ���2CH�ɐs����̂�������܂���ˁB
�|�� �掿�ɂ�����肳��
�@SONY�̃I�[�v�����[���ł����B�O�ɂ��������悤�Ɏ��̓I�[�v���f�b�L�͎g�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�m�l����͂�SONY�̃I�[�v�����[�����g���Ă��āA���܃f�b�L��S���Ń}�C�N�X�^���h�Ў�Ɂu���^��v�ɑ����^��ł������Ƃ��v���o���܂��B���^�Ƃ�����SONY�ɃJ�Z�b�g�E�f���X�P�Ƃ����̂�����܂�����(^^;)�B
�@����AV�ɂ͑a���ł����A���Ȃ�̉f��t�@�����Ƃ������Ƃ�����A��������Â�o���Ǝ~�܂�Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����ƍ�����뜜���Ă���܂��i�j�B�ǂ��t�������Ă��z�[���V�A�^�[�ł͉f�ʃt�B�����̃N�H���e�B�ɂ͓G���͂����Ȃ��̂ł����ADLP�v���W�F�N�^�[�Ȃǔ[���ł���悤�Ȏ��̂��̂��o�Ă��Ă���悤�ŁA����̓W�J���y���݂ł��B
�@����ł́A����Ƃ���낵�����肢���܂��@�|�� ALL�B
�����ԍ��F7846196
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@�@����ɂ���(^-^)/
satoakichan����
���ł�4ch���R�[�h���������ɂȂ��Ă�I���w�̐[���������܂����A������X�������肢�������܂��B
���Ⴀ�A�e�����Ⴄ���Ⴀ�Ȃ��ł����B(^_^;)
�����炱������Ƃ��X�������肢�������܂��Bm(_ _)m
�����A�莝���̃��R�[�h�ł̓|�b�v�E�g�b�v�X�̃}�~�[�E�u���[���A
�T���E���h���ʂ������A�F�l��SP�}�g���b�N�X�Đ������鎄�̒�Ԃł����B(^-^)/
�����ԍ��F7849246
![]() 0�_
0�_
�@����̃l�^��SONY�ł��B���{���\����G���N�g���j�N�X�@�탁�[�J�[�ł���A�s���A�E�I�[�f�B�I���i�������������Ă��Ȃ���A�̂Ȃ���̃I�[�f�B�I�}�j�A�̊Ԃł͋����قǕ]���͒Ⴂ�炵���ł��B
�@�����ŏ��ɐڂ���SONY�̃s���A�E�I�[�f�B�I���i�́ATA-1150D�Ƃ����A���v�ł����B70�N�㔼�ɔ������ꂽ�ƕ����܂����A\59,800�Ƃ����l�i�Ƃ͎v���ʍ�������Y�킹�A�X���C�h���̃��H�����[�����͂��߁A�ЂƂ̃c�}�~�ɍ��E�ʁX�̃g�[���R���g���[�����u��i�d�ˁv�ɂȂ������̂ȂǁA���쐫�����j�[�N�ł����B�������A���������o���Ă݂�Ə����̑S���Ȃ��K�T�c�ȓW�J�Œ��������Ă����܂���B�����̓I�[�f�B�I�}�j�A�̏f���H���uSONY���Ă̂́A�������������B�X�y�b�N�f�[�^�����ǂ��A���y�͂������̂��B����Ȃ͔̂�������_�������v�Ƃ̂���(^^;)�B
�@�����SONY���I�[�f�B�I�t�@���̎��ڂ��W�߂��̂��A�o�u�����Ƀ����[�X���ꂽ��A�̐��i�Q�ł��B����TA-F***�Ɩ��ł��ꂽ�A���v�́A���̏����O�Ɍy�ʁE�������蕨�ɂ����p���X�d���Ȃ���̂𓋍ڂ����A���v�����݊�������Ȃ����������̂ɑ��ASANSUI���r�b�N���̕��ʓ����^�ŁA�̎Z������̂��ǂ����뜜���邮�炢�̏d�ʊ���Y�킹�Ă��܂����B�������i�̂�������Ƃ����m���Ȃ��̂ŁA�쓮�͂����Ȃ肠�����悤�ɋL�����Ă��܂��B�������ɔ������ꂽCD�v���[���[�����������ȉ�����ő��ЂƂ͈�����悵�Ă��܂����B
�@�������o�u������т��̗]�C���������SONY�̓s���A�E�I�[�f�B�I�ɑ��Ċ��S�ɋy�э��ɂȂ�A���̂܂܍����Ɏ����Ă��܂��B�������ASONY�̃J�^���O�ɂ�TA-DR1a��SS-AR1�̂悤�ȍ����i���ڂ��Ă��܂����A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̖ʂł͏������ǂ��Ƃ͎v���܂��A�����Ă��y��������܂���B����������SS-X90ED�Ƃ����X�s�[�J�[���J�^���O�Ɏc���Ă��܂����A���炩�Ɍ������̓��[���b�p�̖^�А��i�̃p�N���ŁA����Ă��Ēp���������Ȃ��̂��낤���Ǝv���܂��B
�@�l�I�ɂ�SONY���i�ň�Ԉ�ۂɎc���Ă���̂��A�i���O����ł��B�x���g�h���C�����ォ�琸�x�̍������i���o���Ă����悤�ł����A�������̂�80�N���딭�\���ꂽPS-B80�ł��B�g�[���A�[����d�q���䂷��Ƃ����g�o�C�I�g���[�T�[�h�Ȃ�@�\���������t���I�[�g�v���[���[�ŁA�����Ƃ��Ă͐�i�Z�p�ł����������ł͂Ȃ��ASONY�ȊO�̃��[�J�[�ł͂����炭�v���t���Ȃ��R���Z�v�g�ɂ��ϋl�߂�ꂽ���f���������Ǝv���܂��B����������SONY�̓A�i���O�J�[�g���b�W������Ă�����ł���ˁB�\�j�[�T�E���h�e�b�N�E�E�E�E�Ƃ����Ƃ���������Ђ܂Őݗ����A�����[�J�[�ƃ^�����Ă��܂����BCD�̊J�����ł����������Ђ��A���͂���܂ŃA�i���O�Ɏ��S���Ă����Ƃ��������͍�����l����Ɩʔ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7850388
![]() 0�_
0�_
���E�������A���ӂ́B
�@�u���ʍH�v�Ƃ��āA�ʐM�@�E�����̃��[�J�[�Ƃ��Ĕ�������SONY�ł����Z�\�N�̔N����
�@�ς��܂����ˁB
�@���̔F���Ƃ��Ắu�I�[�f�B�I���[�J�[�v�ƌ������A�u�f���@�탁�[�J�[�v�Ƃ��Ă�
�@SONY���{���̎p�ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�@�e�[�v�f�b�L�E�r�f�I�f�b�L�ETR�e���r���X�A�u���{���v�u���E���v�ƌ������i�̊J��
�@�̔��ŁuSONY�v�̖���m�炵�߂܂����B
�@�I�[�f�B�I�Ɏ����߂��̂�1965�N�ATA-1120�Ƃ���ALL-TR�A���v�̔�������ł��B
�@���̃A���v���@�ɁuES�V���[�Y�v���������ƂɂȂ�܂����B
�@�������̂悤�ɁA�uTR�A���v�͉��������v�u�^��ǃA���v�͉����_�炩���v���Ƃ���
�@���������n�߂����������̃A���v�������悤�Ɏv���܂��B
�@����SONY�̃A���v��SP�������������Ƃ͂���܂���B
�@JBL��SP�Ƃ͂ƂĂ������̗ǂ���ɂ͂Ȃ肻�����Ȃ��ł�����ˁB
�@�u�f���@��v��SONY�ɐM����u���悤�ɂȂ����̂́AEDV-9000�ƃv���t�B�[��KX-27HF1
�@PVM���j�^�[�V���[�Y���炾�Ǝv���܂��B
�@BETA���p�������ASONY�����Ƃɐ�O����悤�ɂȂ��Ă���͌���ׂ���������܂���
�@�ł������A�Ђ��Ȏ�����DVD���R�EAV�A���v�EBD���R��SONY�̕������茳�ɖ߂�܂����B
�@EDV-9000�̏�ɂ���BDZ-X90������ׂ�Ɓu��\�N�v�̎��Ԃ̗����[�������܂��B
�����ԍ��F7850777
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@�@������(^-^)/
��SONY���I�[�f�B�I�t�@���̎��ڂ��W�߂��̂��A�o�u�����Ƀ����[�X���ꂽ��A�̐��i�Q�ł��B����TA-F***�Ɩ��ł��ꂽ�A���v��
10�N�قǃI�[�f�B�I�A�u�����N���オ�L��A
������A�ŏ��ɍw�������A���v��TA-F333ESX�i798�j�A�v���o�̃A���v�ł��B
�X�y�C���̏������A�W�u�����^���̊���C���[�W�������łȃV���[�V�𓋍ځA
�W�u�����^���V���[�V�[���b��̃q�b�g��ł����B
�����ԍ��F7851111
![]() 0�_
0�_
���E�������A���ӂ́B
�@ ���͑��SONY�t�@���ł��B���a50�N���A1120F��10�C���`�A�I�[�v�����[���ALP�v���[���[��SONY�Ōł�SP�̓e�N�j�N�X7�ł��BMC�J�[�g���b�W�͂ƂĂ������Ŕ������AMM���I���g�t�H���̃V�F���^�ɂ����������̂ł����A������7���~�����܂����̂ŁA�z�̃G���p�C�A�ƌ����J�[�g���b�W���w�������L��������܂��B
�@������LP���R�[�h�������ŗ]�蔃�����AFM�̃G�A�[�`�F�b�N����ȃR���N�V�����ł��B�\���b�h�X�e�[�g�̉��͍d���ĕ]���������A��������������̂�1120F�̃V���[�Y�ł��B�����10�N�قǑO�܂ł͌����ŁA���ł����C�ł��BB&W801N�Ɍq���܂�����A���������͂ł��B���������̃s���A�A���v�ƈ��������܂���B
�����ԍ��F7851137
![]() 0�_
0�_
SONY�ł��ˁB
SONY���i�͍��Z���̎��A���W�I���܂��������ꂪSONY�ł����B������SONY�̃g�����W�X�^�[�͉i�v�ۏ���Ȃ������ł����H�B�E�E���̏��L���Ă��鐻�i�̓I�[�v�����[���f�b�L��TC-6360A�ƃJ�Z�b�g�f���X�P�A���ɍŋ߂ł�CD�E�H�[�N�}���A���g���Ă���p�\�R��(�����v���E�X)�̑O��VAIO�ł����B(�g�p��3�N�ڂ��炢��HDD���̏�E�E�E5�N�ۏŃ^�_�ł������E�E)CD�E�H�[�N�}���̑���̃|�[�^�u���f�W�^���I�[�f�B�I��SONY�ł͂Ȃ��P���E�b�h�ƃV�O�l�I�Ƃ����؍��̐��i��I-Pod�ł��B�C���i�[�C���z����SONY���܂������E�E�B(����A�r�N�^�[�̃E�b�h�̐U�����g�����C���i�[�C���z�����܂������A����Ȃ��Ȃ��ǂ��ł���I�I�B)
�e���r�͓��ŁA�����A�p�i�A�p�C�I�j�A�A�T�����[�A�V���[�v�ƐF�X�����܂�����SONY�͔����܂���ł����ˁB�������A�O�ǂ���ۼު�����SONY��������2�䔃���܂����BCD�v���[���[�͍���SCD-XA9000ES������4��(�r���p�C�I�j�A��1��w��)SONY�ł��B��������8mmHi-8�f�b�L��3�䔃���܂����B���݁A�܂����L���Ă��܂����e�[�v������ł��܂��܂��̂Ŏg���Ă���܂���BHi-8�̃e�[�v�̓��^���e�[�v�ł����ˁH�A��͂�_�����Ă��Ȃ������̂��g���Ă��Ȃ��ׂ��A�Â�Hi-8�e�[�v�͂��Ƃ��Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
BD���R�[�_�[��SONY�ł͂Ȃ��p�i�ɂ��܂����BBD���f�B�A��SONY���������w�����Ă��܂��B
�����ԍ��F7851150
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
����SONY�ł��ˁB
���炭���̐��オSONY����̉e�����ł��������N�ゾ�Ǝv���܂��B
�����Ȃ��WORKMAN����Ƃł��\���܂��傤���B
���E�������
���s���A�E�I�[�f�B�I���i�������������Ă��Ȃ���A
���̂Ȃ���̃I�[�f�B�I�}�j�A�̊Ԃł͋����قǕ]���͒Ⴂ�炵���ł��B
�Ǝ��Z�p�ɂ͂�������Ƃ��Ƃ͎v���܂����A�J���[�������Ƃ������H������Ȃ��������邱�Ƃ͂���܂��ˁB
�J�����g�E�p���X��DAC�i1bit�^�C�v�j��CDP-XA50ES�����݂��g���Ă��܂��B
�f�W�^���E�t�B���^�[��9��������Ďg������͗ǂ��̂ł����A�ǂ����������肵�������ł��ˁB
�����������͖������Ă����͂��ł����A������Ȃ��āA���ǁAWADIA�̌Â�DAC�Ɍq���ł܂��B
���ʁA598�I�[�f�B�I����ɂ́u333�v�u555�v�u777�v�̃]���ڂ̋@��͐g�߂ł���܂����f�ł�����܂����B
�l�I���W����
�����̔F���Ƃ��Ắu�I�[�f�B�I���[�J�[�v�ƌ������A
���u�f���@�탁�[�J�[�v�Ƃ��Ă�SONY���{���̎p�ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
���̑��Ȉ�ۂ́u����������̂��D���v�u�����ɉ���v�ł����A�u���v�̑��݂���͊m���ɋ�����ۂ��܂���ˁB
�F����A�Y��Ă�Ƃ͎v���܂��ASONY��PHILIPS�ƂƂ���CD�t�H�[�}�b�g�̃��C���E���C�Z���T�[�ł���A
���Ђ͐��E���w�̃e�N�j�J���E�G���h�[�T�[�ł�����܂��B
�d���Ŋւ��l�ɂȂ��Ă悭������܂������ASONY���ւ��Ȃ���������w���f�B�A�͂����܂ŕ��y���Ȃ������ƒf���ł��܂��B
����CD�Ɍ����Č����ΗʎY�p�̋@���ݔ��Ȃǂ̃C���t���ɂ����鑤�ʂ�SONY�����Ɉ����Ď��p�����Ă��܂����B
��X�̎茳�ɂ���CD-DA�̋��炭2����1����SONY��PCM-1630�Ƃ����}�X�^�[���R�[�_�[�Ń}�X�^�����O����Ă��܂��B
���ł����}�X�^�����O�̎�@�͐F�X����܂���1980�N��̌㔼���猻�݂܂Ŏ嗬�̍��������Ă��܂���B
��p��3�^4�C���`�E�f�W�^���E�e�[�v�����p�P�Ƃ��Ďg�p���܂����A����o�[�W��������CD�h���C�u���������܂����B
16bit�ł͂���ȏ��]�߂Ȃ����x���Ƃ������Ă܂����A���ۂɃw�b�h�t�H���Œ����Ɛ����������܂��B
Hi-bit���^���ă_�E���R���o�[�g����ۂ����̃��R�[�_�[�p16bit�ɗ��Ƃ��܂��B
�܂����̃��R�[�_�[����h�������Z�p�ŃI�[�f�B�I�E�t�@�C���ɂȂ��݂̐[�����m��������ł��B
��\�I�Ȕh���Z�p�̑�\�I�Ȃ��̂�������ƁE�E�E
1�jA/D��D/A�R���o�[�^�[�̒P�ƃ��j�b�g���i�P��DAC�̔��z���̂��́j
2�j�X�g���[�g�E�A�[���̃h���C�u�E���J�i�A���v�X�d�C��SONY�������Ńp�e���g���擾���Ă܂��j
3�j���R�[�_�[�ƃR���o�[�^�[��A������TOS-LINK�P�[�u���i���I-LINK�̌��^�j
4�j�����z���Ŏg�p���Ă��鏃��R�[�gOFC�i���j�^�[PC����p�ɊJ�����܂����j
�Ȃ����ꂾ���̋Ɩ��@������ăR���V���[�}�̃I�[�f�B�I�@�킪���܂ЂƂȂ̂��E�E�E
�ő�����ӎ���������Ȓ��f�v�l�̓��[�J�[�̗����ʒu�̐�������̂Ȃ̂��Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F7851533
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
�A���X�ł��݂܂���B
�����ӏ�����ł��B
�������Ȃ��WORKMAN����Ƃł��\���܂��傤���B
�u��ƕ�������̃`�F�[���X�v����ɂȂ��Ă܂��B���p���������B
WALKMAN����ɒ��������Ē����܂��B
�^�ă^�C�v�ŏI�@��TCD-D100�ƍĐ���p��WMD-DT1�A2���DAT-WALKMAN���܂������ł��B
�������iPod���g���Ă��܂����A�d���W��DAT�͂܂��܂������������Ă܂����������܂���B
�����g�͈��k�f�[�^�ɒ�R������A������MD���h�����Ă��܂������A
�ŋ߂̃V���R���E�I�[�f�B�I��g�ѓd�b�̈��k�f�[�^�ɂ�鉹�y�Đ��̗������݂�ɂ��A
SONY��MD���}�[�P�b�g�̉��n�Ƃ��Ĉ��k�f�[�^��F�m�����������͑傫�������l�Ɏv���܂��B
���Ȃ݂�68�nMAC����̓Ń����S�}�䂦iPod�o��シ���Ɋח��E�E�EMD�ւ̒�R���͉��������̂ł��傤���H
�����ԍ��F7853656
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́I
�\�j�[�ɂ��Ă͑O�q�̒ʂ�CD555ESD�𖢂��Ɏg�p���ł��B
VHS�@vs �x�[�^�ŕ������\�j�[�����ɑł��ďo�����i��Hi8�ł����ˁB
�I�[�f�B�I����́A����܂�������Hi8���g�������[�r�[���w�����܂����B
V700�ƌ����^�Ԃ������Ǝv���܂��B�������I�[�g�t�H�[�J�X�̐��x���C�}�C�`
�����I�b�g�b�g�t�H�[�J�X�Ɲ�������X�ɏ��^��705�Ƃ����̂ɋ@��ς��܂����B
���̌�~�jDV��900���o�Č��݃n�C�s�W�����^�C�v��HC3�Ƃ����̂��g���Ă܂��B
�܂莩���Ƃ��Ă̓\�j�[�ɑ��I�[�f�B�I�Ƃ������AV�W�A�f���̃C���[�W�����Ă��܂����̂�������܂���B
����ł��E�H�[�N�}���^�C�v��ipod�͔��킸NW-A�^�C�v���Ē����Ă݂܂����B
ipod���͍������Ɏ��ɂ͒������Ă܂��B
redfodera�����
���ő�����ӎ���������Ȓ��f�v�l�̓��[�J�[�̗����ʒu�̐�������̂Ȃ̂��Ǝv���Ă܂��B
���������v���܂��B���[�U�[�ׂ̍��ȗv���ɑ����̃\�j�[�̎p���͘����I�H�Ƃ������C�z��̌��@���U������Ă���悤�ŁA�����c�O�ȋC����������܂��B
�����ԍ��F7853852
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�@���������ł��B
�@������SONY�̃A���v��SP�������������Ƃ͂���܂���B��
�@�ȂǂƁA�����������܂���������3200&5300�ƂQ������邶��Ȃ��ł����I
�@�����Ɍ����A�v���t�B�[���ɂ͕t���̐�pSP������܂������AVAIO�ɂ��E�E�B
�@SONY�̌��̌��̓W�����N�Ŏ�ɓ��ꂽ�u�[���}�C�쓮�f���X�P�EM-1�v��
�@�u����r�f�I�f�b�L�ECV-2000�v�������悤�Ɏv���܂��B
�@TC-2850SD�u�J�Z�b�g�E�f���X�P�v���茳�ɂ������悤�ȋL�����E�E�E�E�B
�@���́A�u�H�킸�����v�Ȃ����ŁACD���茳�ɗ����̂�80�N��㔼�H���������B
�@�V�������ɂȂ��Ȃ��A�肪�o�Ȃ����a�҂ł���܂��B
�@D-VHS�EDAT�EMD�Eipod�n�ƑS�������Ȗ������߂����Ă���܂��B
�@redfodera����A
�@�u�B��g��O�v�t�@���H���ƁE�E�E�E�E�B
�����ԍ��F7853964
![]() 0�_
0�_
�@����ɂ��́@�|��ALL�B����ς�SONY�̎��������Ɣ������傫���ł���(^^)�B
�@�O���Y�ꂽ�̂ł����ASONY�̌��s�����p�I�[�f�B�I���i�ŗB��]���ł�����̂��q�ׂĂ��܂���ł����B����̓w�b�h�t�H���ł��BAUDIO-TECHNICA�ƕ���ʼn䂪���̓��u�����h�ƌ����܂��BSONY�̃w�b�h�t�H���͉ߋ����g���Ă��܂������A��������ǂ���ۂ����L��܂���BiPod�p�̃C���z����SONY���B���܂������A�����ł���p�t�H�[�}���X���Ǝv���܂��B
�@SONY���ǂ����ăI�[�f�B�I�}�j�A����̕]�������܂�F�����Ȃ��̂��Ƃ����ƁA�ǂ����������Z�p�D��̎Е������邩�炶��Ȃ����Ǝv�����肵�܂��i�m�荇����SONY�W�҂͂��Ȃ��̂ŁA�f���͏o���܂��� ^^;�j�B���Ƃ���CD�̍l�Č��ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��ł����ACD�v���[���[�𐢂ɍL���F�m�������͈̂����PHILIPS=MARANTZ���C���ł����B���̓I�[�v�����[���e�[�v�̂��Ƃ͂قƂ�ǒm��܂��A�J�Z�b�g�e�[�v�ɂ͂����b�ɂȂ����g���猾�킹�Ă��炤�ƁASONY�̃J�Z�b�g�f�b�L����͖����ł��鉹���o�Ă��܂���ł����B�e�[�v���̂��̂��ATDK��x�m�t�C�����Ɣ�ׂ�ƍ��̐��x�Ɍ����܂����B�������Z�p�ʂł͐ϋɓI�ŁA�Z���~�b�N�X��➑̂Ɏg�p�����J�Z�b�g�e�[�v�Ƃ��������Ă����悤�ł����A���������t�F���N���[���E�|�W�V�����iType3�j���l�Ă����̂�SONY����Ȃ������ł����ˁBDENON��Scotch���Z���Ԓǐ������̂������ASONY�̓Ƃ葊�o�ɏI����Ă��܂��B
�@���Ђ�CDP-557ESD�Ƃ�����CD�v���[���[���g���Ă��܂������A���͗ǂ��������Ǖ������̂����܂�̑��@�\�Ԃ�ł����B�����_���E�v���C�Ƃ��V���b�t���E�v���C�Ƃ��A�f�B�X�v���C�ɔC�ӂ̕�����������Ƃ��A���������]�v�ȋ@�\���Ȃ��ăT�E���h�ʂ�˂��l�߂�����ƃR�X�g�p�t�H�[�}���X�̍������i���o����͂����Ǝv�������̂ł��B�v����Ɂu��i�Z�p�����ꂾ���ς�ł���v�u����ȋ@�\���l�Ă��Ă���v�Ƃ����Z�p�ʂ̃A�s�[������s���āA�{���̈Ӗ��ł̃��[�U�[�C���^�[�t�F�[�X�Ƃ������A�����������̂����܂�T�|�[�g���Ă��Ȃ��_���C�ɂȂ�܂��B�m����WALKMAN�͈ꐢ���r���܂������AiPod��DAP�̎�͂̍�����������D��ꂽ�̂��A���̂����������̂����E�E�E�E�B
�@�g�\�j�[�^�C�}�[�h�Ƃ������t�����邻���ł��ˁB�i���ʂ����S�ł͂Ȃ������悤�ł��B
�@���R�[�h��ЂƂ��Ă��ꂾ���̎��т������Ă���̂ɁA�ǂ����ĉ��y�\�t�g���y������������@��̐����Ɋւ��Ă͑��Ђɒx�������Ă����̂��A�l���Ă݂�ƕs�v�c�ł��ˁB������v���Ԃ��ƁA�o�u�����̗����Ԃ�́g�P�Ȃ���R�h�������̂ł��傤��(-_-;)�B
�����ԍ��F7854298
![]() 0�_
0�_
���E������ӂ́B
�@���Ȃ�O�ɂȂ�܂����A���̏f����SONY�ɂ���܂����B
�@�f�U�C�������ɂ����ނ̘b�͗]��Q�l�ɂ͂Ȃ�܂��A�F����̋邱�Ƃ����
�@�������Ă���Ǝv���܂��B
�@�Z�p�w�͗D�G�ȕ������������悤�ł����A���i�̕�������ǂ������������߂Ă����̂�
�@�u����ғ����v�ł͂Ȃ��A�ꕔ�̌o�c�g�b�v�̈ӌ��������悤�ł��B
�@�o�u�����ȍ~�́A���y�ƊE�A�f��ƊE�A�s���Y�A���ہA���Z���X�u���ׂ��v�ɑ������̂��A
�@�u�i�R���b�p�v�̌̂������̂ł��傤�B
�@�x�d�Ȃ�o�c�w�̌�ւ���Ў��̂́u�����v��Ԃ�����킵�Ă͂��܂��ˁB
�@�B��Ƒ����u����v�ɂȂ��Ă��܂������ɋC�Â��Ă��Ȃ��̂Ȃ�A�u���̉��l�v�B
�@�����@������̂悤�Ȏp���ō�葱�����疾����SONY�͖����Ȃ�ł��傤�ˁB
�@
�����ԍ��F7854433
![]() 0�_
0�_
���E������ӂ́B
�@ SONY�̃I�[�v�����[���̉��͂���Ȃ�ɗǂ������o�Ă����Ǝv���܂��BLP���R�[�h�͈�x�j�𗎂Ƃ������ŁA���i�͘^���������̂��Ă��܂����B���X�A�����`�F�b�N�ׁ̈A�e�[�v��LP�����t���Ă������̗͖w�ǂȂ������L��������܂��B�I�[�v�����[���͓����̉��i��30���~���z���Ă��܂������A��������SONY�Ǝv�������̂ł��B
�@���̌�CD�v���[���[����������LP�̃X�N���b�`�m�C�Y����J������āA�ق��Ƃ������̂ł��B�E�I�[�N�}�����R���|�Ɍq���ł��Ȃ�̉����������L��������܂��B�f�W�^���M���͗��Ȃ��̂ŁA�����v���[���[�ł����z�̂��̂Ɖ����I�ɂ́A�����ς��Ȃ��Ɛ�`���Ă����̂�SONY�ł͂Ȃ������ł��傤���B�܂Ƃ��ɐM�������͉��ẴR���|���15�N�͒x�������Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F7854970
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
satoakichan����A�͂��߂܂��āB
�����[�U�[�ׂ̍��ȗv���ɑ����̃\�j�[�̎p���͘����I�H
���Ƃ������C�z��̌��@���U������Ă���悤�ŁA�����c�O�ȋC����������܂��B
�u����Ȃ���ł����ł���H�v�I�Ƀm�����y���Ȃ��Ă����ۂ�����܂��ˁB
�u�˂��l�߂�v�u�O�ꂷ��v�Ƃ����p����������SONY���i�������Ă��Ă���̂�������܂���ˁB
���E�������@
������ς�SONY�̎��������Ɣ������傫���ł���
CM�ł͂���܂��u����ς�SONY�v�uSONY������v�Ƃ����炪���ݓI�Ɉӎ����Ă��܂���Ƃ�����ł��傤���B
�I�[�f�B�I�Ɍ��炸�����̋@���Z�p�ŁA�����������Ȃ��炸���b���Ă������Ƃ̏ؖ��ł�����܂���ˁB
SONY���i�ɂ͉��i�Ɋւ�炸�����炪�ŏ����獂�����x����]��ł��܂��Ă���C�����܂����A
���Ƃ���x�Ɂu�������v�ɂ���Ă��܂��n���f�B�L���b�v������A���X�A���z�ł�����܂��B
���ǂ����������Z�p�D��̎Е������邩�炶��Ȃ����Ǝv�����肵�܂�
���[�J�[�Ƃ��ċZ�p�ɂ������Ƃ������ƂɈق���������͂��������炢�Ȃ��Ǝv���܂����A
�G���h���[�U�����u����ς�SONY�v�uSONY������v�ƈӎ����Ă��܂��̂Ɠ��l�ɁA
����SONY���́u�V�Ȃ�n�����J���̂͏��SONY�v�Ƃ����������̂悤�Ȃ��̂�����̂�������܂���B
SONY�̓��ӕ��삾�����i����^�j���j�^�[TV�ƃ|�[�^�u���E�v���C���[�ő傫�Ȓx����Ƃ��Ă��܂��܂������A
���܂łƓ����悤�ȁu���E�ρv�Ŋ����Ԃ���}��̂��A�͂��܂������ʂ̕��@�_�Œ��ނ̂����ڂ��Ă܂��B
�����ł����A�����̃R���V���[�}�E�I�[�f�B�I�Ɋւ��Ă̓j�b�`�}�[�P�b�g�Ɗ�����Ă��āA
�V�A�^�[�E�V�X�e����n�C�R���|�n�ւ̃t�B�[�h�o�b�N��ړI�Ƃ����e�X�g�E�t�B�[���h�ɂ��Ă��ۂ��܂��B
���Y��D�N���X�E�A���v�Ȃǂ͂܂��ɐV�Z�p�̌����J���ߒ��̌o�ߕł͂Ȃ��ł��傤���B
SONY��AV�@��͉��B��USA�œƎ���悵�Ă��邱�Ƃ͂����m���Ǝv���܂����A
���ẴX�s�[�J�[�E���C���i�b�v�uLA VOICE�v�̗l�ɋt�㗤�ŎQ�킵�Ă����Ƃނ���ʔ����̂ł����A
�ǂ�����i����^�j���j�^�[TV������ڎw�����V�A�^�[�E�V�X�e�����S�Ŋ��҂ł��Ȃ��ł��ˁB
http://www.sony.co.uk/
http://www.sony.com/index.php
�l�I���W����
���u�B��g��O�v�t�@���H���ƁE�E�E�E�E�B
�i�C�X�˂����݁I
�B����Ȃɂ���O�����D���ł���B
���o���������ς�����������A�V���K�[�E�\���O�E���C�^�[�A�����f�B�E���C�J�[���Ǝv���Ă܂��B
����ԑg�̃��n�[�T�����i�ł����Ȃ�BOSA���M�^�[��e���Ă��̂����āu�j���b�v�Ƃ����Ⴂ�܂����B
�����ԍ��F7855819
![]() 1�_
1�_
�l�I���W����H��
�����i�̕�������ǂ������������߂Ă����̂�
���u����ғ����v�ł͂Ȃ��A�ꕔ�̌o�c�g�b�v
���̈ӌ��������悤�ł��B
�@�������A�ߓx�Ɍڋq�ɛZ�т������҂Ɍ}���������̃}�[�P�e�B���O�͊�ƂƂ��đ��̎n�܂�ł����A���Ƃ����Ďs����y�����Ĉꕔ�̌o�c�g�b�v���ƒf�ňӌ����S����������Ƃ����̂�������̂ł��ˁB�a�V�ȋZ�p��T�[�r�X�A���邢�͐V���Ȑi�o���O�ʂɏo���̂͂������ǁA�n�ɑ����t���������Ȍo�c�헪���ɂ��Ă��������̂��肪��s���Ă��܂��ƁA��������̂͊�Ǝ��g�ł���̂͂������̂��ƁA�傫�Ȗ��f����̂͏���҂��Ƃ������Ƃ��̂ɖ����ė~�����ł��B
�@���̑z���ł����ASONY���ɂ́g�ӔC�̏��݂m�ɂ���X�L�[���h���Ȃ����A�܂��͂����Ă��ɂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB�܂�SONY��������Ȃ��A����ȉ�Ђ͂ǂ̋ƊE�ɂ����݂���݂����ŁA���̗L����Ƃ����̈ꗬ��Ƃ����́E�E�E�E�Ȃ�Ă��Ƃ��������͂Ȃ��̂ł����ǁi�������A��̓I�Ȋ�Ɩ��͂����ł͏o���܂��� ^^;�j�B
�掿�ɂ�����肳��H��
���f�W�^���M���͗��Ȃ��̂ŁA�����v���[���[
���ł����z�̂��̂Ɖ����I�ɂ́A�����ς��Ȃ���
����`���Ă����̂�SONY�ł͂Ȃ������ł��傤���B
�@���[�A�����������ƌ����Ă��悤�ȋL��������܂��B�����炱���APHILIPS=MARANTZ���C���ɗ����Ńv���[���[�̎s��Ō���������̂ł��傤�BSONY�������v���[���[�ōŏ��ɓ��������̂�MARANTZ��CD-34�̂悤�ȃs���A�E�I�[�f�B�I���i�ł͂Ȃ��A�E�H�[�N�}����CD�v���[���[�łł��������Ƃ͏ے��I�ł��B�܂�͌`��@�\�����𐮂�������Ǝv���Ă��āg���ӂ̋Z�p��CD�v���[���[������Ȃɏ��^�����܂����h�Ƃ������ڂ�������s�A�e�N�m���W�[��@�\�������p���x���ł̕i����g�p�����x�����߂鑽���̏���҂̈ӌ��͂��܂�ᒆ�ɂȂ��悤�ł��B
�@�I�[�f�B�I�Ƃ͊W�Ȃ��ł����AVHS�̒a����ǂ������X�����ḗu�z�͂܂�����v�i2002�N�j�Ƃ����f��ŁA��ɑޏ�ɒǂ����܂��x�[�^�}�b�N�X��i����SONY�̔s�����Î�����Ă��邱�Ƃ��v���o���܂����BSONY�͋Z�p�Ώd�ɂ�莋��������҂����ʎY�Ȃ̕��������Ă�����ł��ˁB����B����鏼���K�V�������̍\�}����������VHS�̋N�p�����f�����悤�ȕ`����������Ă��܂��B
redfodera����H��
���u����ς�SONY�v�uSONY������v�Ƃ����炪���ݓI
���Ɉӎ����Ă��܂���Ƃ�����ł��傤���B�I�[�f�B
���I�Ɍ��炸�����̋@���Z�p�ŁA�����������Ȃ���
�������b���Ă������Ƃ̏ؖ��ł�����܂���ˁB
�@�����ł��ˁA�o�c�w������ɓ˂������Ƃ��Ă̂͂��قǂ͒������͂Ȃ��̂ł����i�j�ASONY�̏ꍇ�g�d�����˂��Ȃ��h�ł͍ς܂���Ȃ��قNjZ�p�͂ƎЉ�I�e���͂�����܂��i���ɋƖ��p�@��Ȃǁj�B�����Ȃ������ʏ���҃��x���Ƃ��ẮuSONY�̖����p�I�[�f�B�I�@��͐V�Z�p�̌����J���ߒ��̌o�ߕv�ɉ߂��Ȃ��Ɗ�����āA�u�ǂ��Z�p�v���́u�ǂ����v�����߂�s���A�E�I�[�f�B�I�Ƃ͕ʂ̎����ɑ�������̂��ƒB�ς��������ǂ��̂�������܂���B
�@��CEO�̃n���[�h�E�X�g�����K�[�̓G���N�g���j�N�X����ɂ����y����ɂ����̂Ȃ��A�e���r���o�g�̐l�ł���ˁB�����SONY�Ƃ��Ă͒�������������O���ɏ悹���R�����r�A�f��Ȃǂ̈�����ʂ��āA�܂��܂��G���^�e�C�������g�n�Ɏ厲���ڂ��̂�������܂���B
�����ԍ��F7859402
![]() 0�_
0�_
�@ACCUPHASE�i�A�L���t�F�[�Y�j�ɂ��ď����Ă݂܂��B1972�N��TRIO�i����KENWOOD�j����X�s���A�E�g�������[�J�[�ł��邱�Ƃ̓I�[�f�B�I�t�@���Ȃ�ΒN�ł��m���Ă���Ǝv���܂��B�n�Ǝ��̃u�����h���̓P���\�j�b�N�Ə̂��Ă��܂����BACCUPHASE�ɎЖ��ύX�����̂�82�N�ł��B
�@�������C���V�X�e���Ƃ��Ďg���Ă���A���v��ACCUPHASE�ł��B���Ђ̃��f�����ŏ��Ɏ�ɓ��ꂽ�̂�88�N�̂��ƂŁAE-305�Ƃ����@��ł����B�����g���Ă���DIATONE��DS-2000�Ƃ����X�s�[�J�[����肭�点��A���v��T���Ă���A�s���������悪���̃A���v�ł����B����SANSUI��LAXMAN�̃A���v���������܂������AACCUPHASE�̃T�E���h�ʂł̃A�s�[���x�͈��|�I�ŁA�g���Y�A���v�̍ŏI�͂��ꂾ�I�h�Ǝv�������̂ł��i�j�B�Ȃ��A���̍ۂɔ������ꂽ����̓��Ђ̃Z�p���[�g�A���v�i�Z�b�g��130���~�j���������̂ł����A�����g�A���v��130���~��������z�Ȃ��邩��B�N�������h�Ǝɍ\���Ă����Ƃ���A���������o�Ă݂�Ɓg�������A���̉���130���~�́A���������E�E�E�E�h�Ɗ������Ă��܂��܂����i���j�B
�@���̃��[�J�[�̃T�E���h�ʂ̓����́A���̃u�����h���ʂ�iaccurate��phase�̍�����j�A�Ƃɂ����A�L�����[�g�ɐs���܂��B�ォ�牺�܂ŃL�b�`���Əo�āA�B�����͌�������܂���B���ɍ���̍Ⴆ�Ⴆ�Ƃ����L�т͖��͂ł��B�܂��A���R�Ƃ��������z�u�͔����������������܂��B�̂̐��i�̕��i���X�g�b�N����Ă���A���ł��I�[�o�[�z�[���ɉ����Ă����̂��L���Ǝv���܂��B�����̐��i�̓_���{�[���ł͂Ȃ��ؔ��ɓ����ďo�ׂ���Ă����Ƃ����\�������܂������A�{���Ȃ̂ł��傤���E�E�E�E(^^;)�B
�@���Ђ̓f�U�C���Ƀ|���V�[�����邱�Ƃł��m���A���̈�т����p���̓u���b�N�t�F�C�X�ŗL��������SANSUI�ȏ�ł��B��������Ԉ����A���v�ł����[�^�[��t���Ă��܂����A���������߂ē��������t�@�C������R�X�g�p�t�H�[�}���X�̖ʂŗL�����Ǝv���܂����A�Œ�t�@���͂���������Ȃ��̂ł��傤���B
�@E-305��10�N�ȏ�g�p���A���͓���ACCUPHASE�̕ʂ̐��i���g���Ă��܂����A��������Ɛ��N�ōX���̗\��ł��B���������͊C�O���i�����������Ă��Ă���A���Y�ł�ESOTERIC���͂���SOULNOTE��ALLION�݂����ȋ����[���V�i���[�J�[�����݂��邱�Ƃ���A���̃A���v��ACCUPHASE�ɂȂ邩�ǂ����͕�����܂���B�ł����ς�炸�L�͌��̈�ɂȂ邱�Ƃ͊m���ł��傤�B
�����ԍ��F7861173
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́I
���x��ACCUPHASE�ł��ˁB ���E�������@��305���X�^�[�g�Ƃ̎��I
���͎���305V�ŃX�^�[�g�A���݂��������ł��B
���ォ�牺�܂ŃL�b�`���Əo�āA�B�����͌�������܂���B���ɍ���̍Ⴆ�Ⴆ�Ƃ����L�т͖��͂ł��B
�����ɂ��Ă͂��̒ʂ�ł��A�����Ď���ACCUPHASE��I���R�ɂ����������
����͓����̌̒����S�j������SP�}�g���N�X���g����A���v�Ƃ������őI�т܂����B
SP�}�g���N�X�͂����m�̒ʂ�o�����X�A���v���͎g�������Ȃ�A���v��I�т܂��B
���R�T���X�C�̓A�E�g�A�����f�m��390���g�p���Ă܂������A�����I�ɁH
�����Ŗڂ������̂�����305V�ł������A���̂��T�����h���ʂ̓f�m���̕�����I�H
SP�}�g���N�X�ɔM�����Ă������������āA�b���͂�������ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�ł����������N�t�����g�d���̑厖�����ĔF���A2�����A�}���`�̃��C���A���v�Ƃ��Ċ��Ă��܂��B���낻��O���[�hUP���l���Ă��܂��������ǂ��I�сA�ǂ����悤�����̒��ŃO���O�����킩��܂���I�ł����̎�������Ԋy�����̂ł��傤���H
���E�������@���lACCUPHASE���L�͌��ł��鎖�ɂ͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7861413
![]() 0�_
0�_
���E�������C�݂Ȃ���C����ɂ��́B
���̂悤�ȋ����[���X���𑱂��Ă�����C���E�������C�f���炵���Ɗ��S����ƂƂ��ɁC�����y�����q�������Ē����Ă܂��B
SONY�̂��b���������Ă���܂������C�ȑO�́C�ǂ̃X�^�W�I�ɍs���Ă��C3348�Ȃǂ�PCM���R�[�_�[���������Ă���C���ꂪ�W���ɂȂ��Ă���܂����B�Ƃ��낪�C����^����DAW���Ɉڍs���Ă��܂��B
SONY�́C�����������V�������ɍ������i��肪�o���Ȃ������̂��C���N�O����C�Ɩ��p�����@�킩����P�ނ��邱�ƂɂȂ����悤�ł��B�Ƃ͂����Ă��C�����̐��i�͂��̂܂܂ŁC�V�����V���i���J�������ɁC�t�F�C�h�A�E�g�����悤�Ƃ��������̂悤�ł��B
�����ł����C�A�L���t�F�[�Y�́CC-280�Ƃ������̂悤�ȃv���������g���Ă���܂��B�W�����N�i�ł��������@���\���N�O�Ɍ����C�R�c�R�c�ƏC�����čĐ������Ă��܂����B
���̃��[�J�[�́C���̍D�������͕ʂɂ��āC�ǂ̐��i�ɂ��C�|���V�[�������āC�Z�p�ҍ����������鐻�i�Q���Ǝv���Ă��܂��B�ǂ����̃n�C�G���h�E���[�J�[�̂悤�ɁC����OEM���i�ɁC�@�O�ȍ����l�i��t����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł����B
�I�[�f�B�I�̃��[�J�[��̔��X�Ȃǂ́C�������E������������Ǝ��͎v���̂ł��B���������̍��ł��鐸��t�̃T�[�r�X���ڋq�ɒ���B����Ȏp�����������郁�[�J�[�ł����ė~�������̂ł��B
���������C�p���[�E�A���v�̓A���N������DC-300�����ݎg���Ă���܂����C���C�A�L����PRO-30�ɕύX���邩�Y��ł���Ƃ���ł��B
�����ԍ��F7861615
![]() 0�_
0�_
���E�������A �W�����A�o�[���� �A�����́B
�@�W�����A�o�[����A���v���U��ł��B���̐߂͑�ςɂ����b�ɂȂ�܂����B���̌�v���ɂ����������������������̂ł����B�����A���������A�{�[�J����^������Ƃ��Ƀ}�C�N�Ƀ}�X�N���˂���͉̂��̂ł��傤���H�ł����B
�@�A�L���t�F�[�Y�̕]���̗ǂ����͐̂��畷���Ă���܂������A9�N�O�Ƀf�U�C����LUX�Ɍ��߂Ă��܂��܂����B���Y�ł̓A�L���t�F�[�Y�ɑR���郁�[�J�[�Ǝv���܂����A����҂ɑ���p�����A�L���t�F�[�Y�Ɏ��Ă���Ǝv���܂��B�̏��g���u���ɒ��ʂ��Ă��Ȃ��̂ŕ�����܂��A9�N�ԁA���N�A�В����ŔN�����̂ł��B�ŏ��͌y���l���Ă��܂������A���ꂪ���|���ŏ�ʋ@��̍w�����l����悤�ɂȂ�A���N��5����M800A���w�����Ă��܂��܂����B
�@SONY�@�̂Ƃ����猴���̒Nj������Ă��܂������ALUX�AM7f�̉��́A����ɂ͂�����Ȃ����ł������A�S�n�ǂ������܂��B������L�肩�Ȃ��Ǝv�������̂ł��B����Ȏ���M800A�������̂��̂ł����A���̉��̈Ⴂ�ɂ͜��R�Ƃ��܂����B�������A���Q�őS���Ⴄ����ł��B�t�����g����͏�ɕ����������o�Ă��܂����A���Œ����Ă����������������܂łƑS���Ⴄ�A���܂ł̂́A���邳�������ŁA�`�b�Ƃ��ǂ��Ȃ������ƌ����̂ł��B
�@�S�n�ǂ�������Ɖ��F�͌떂�������̂ł��ˁB�����s�A�m�̃\�t�g�����t���܂��Ă��O�Œ����ƈȑO�̂��̂� �R���|�̉��AM800A�͖{�����Ƃɂ���悤�ɒ������܂��B���X�A�I�[�f�C�I�̉����`�F�b�N���邽�߂ɐ��R���T�[�g�ɍs���܂��BCD�̃\�[�X�ɂ��˂�܂����A�s�A�m�Ə��Ґ��̉��̓N���A�����݂����ł��B
�����ԍ��F7862296
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@������(^-^)/
���̃A�L���t�F�[�Y�Ƃ̂������́ADP70V����n�܂�܂����B
����̃��[�J�[�ŁA�Ƃɂ����g���Ă݂����A���ꂾ���̗��R�ł��B
�������g�A���v��130���~��������z�Ȃ��邩��B�N�������h�Ǝɍ\���Ă����Ƃ���A
���������o�Ă݂�Ɓg�������A���̉���130���~�́A���������E�E�E�E�h�Ɗ������Ă��܂��܂����i���j�B
C-280L��P�]500�̑g�ݍ��킹�ł��傤���H
����C-280V��P-500L���g�p���Ă��܂����B
�����A�e�G���̃��t�@�����X�Ɏg���Ă���A
���t�@�����X�̉�����ɂ������āA���̈��@�ƂȂ�܂����B
�g���āA���i�ȏ�̉��ɑ喞���B
�܂��A�G���L���̐M�ߐ���₤�����\�ɂȂ�A
�I�[�f�B�I���y���ޏ�ŁA�������w���Ă�������悤�Ɏv���܂��B
DP70V����n�܂����A�L���t�F�[�Y�Ƃ̂������A����E-408�ƌ`�͕ς���Ă��A
���̎�����A���̖T��Ƀ��t�@�����X�Ƃ��đ��݂��Ă��܂��B
�����ԍ��F7863470
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
���E�������Asatoakichan����@
���ォ�牺�܂ŃL�b�`���Əo�āA�B�����͌�������܂���B
�u��邢�E�Â��E�Z���v�̎O�d��+���{���D���Ȏ���̂�����ACCUPHASE�̐��i�Ƃ͂ǂ������肪����Ȃ���ł��B
���E�������̋@�މ��߂ɏ��ƁA����SANSUI��KEF�̑g�ݍ��킹��U��o���ɂ��Ă��邱�Ƃɉ����āA
�_�C�|�[���n�X�s�[�J�[�̌��ɃX�e�[�W��`���^�C�v�������I�Ƀt�B�b�g���邩�炾�Ǝv���܂����A
�U��Ԃ�ƍ��Y�X�s�[�J�[������ăL�����̗����������X�s�[�J�[������g���Ă��܂����B
Martin Logan�AInfinity BOSE�̖k�ē��C�݂ƁAKEF�ADynaudio�A�ŋ߂ł�PIEGA�Ȃǂ̉��B���m�ł��B
ACCUPHASE���ƃ��j�A�߂��Ď��ɃZ���V�e�B���ɂȂ�ǂ����Ă���肭�t�B�b�g���܂���B
�����R�Ƃ��������z�u�͔����������������܂��B
�����ɍ���Ȃ��Ȃǂƌ����Ȃ���A����ACCUPHASE���g���Ă�������������܂��B
�������Ɩ��p19�C���`�E���b�N�E�^�C�v�ň�ԏ��^�̃p���[�A���v���G���L�E�x�[�X�p�Ƃ��Ăł����E�E�E
�g�p�p�x�����Ȃ����z�Ȃ̂�Infinity��IRS-Delta�Ƃ����t���ASP���K�c���Ɩ炷���ɓ]�p���Ă܂����B
�I�[�f�B�I���i�̗l���k�����͂���܂���ł������ASR�p�r�Ƃ��Ă͈ٗ�̃��C�h�����W�Łu�Â��v�A���v�ł����B
�����ӂ̃g�����X�����V�����g���[�ł͂Ȃ��ă_�u���E�g�����X�̃c�C���E���m��Threshold�̃R�s�[�ƌ����Ă܂����B
�W�����A�o�[����A
���iACCUPHASE�́j�ǂ̐��i�ɂ��C�|���V�[�������āC�Z�p�ҍ����������鐻�i�Q���Ǝv���Ă��܂��B
���CANARE�̂��b�ł̓t�H���[�����L���������܂����B
�m���Ɉӏ����܂߈�т����|���V�[���������܂��ˁB
������^����DAW���Ɉڍs���Ă��܂��B
��SONY�́C�����������V�������ɍ������i��肪�o���Ȃ������̂��C
�����N�O����C�Ɩ��p�����@�킩����P�ނ��邱�ƂɂȂ����悤�ł��B
�ق�3�N�قNJ��E�Ґ����痣��Ă��ď��ʂőa���Ȃ��Ă܂����BSONY���t�F�[�h�A�E�g�ł����E�E
�E�c�O
�������ŗ��ނ�DAW�����T���߂ɂ�������̂ŊO���ꂽ�̂����E�E�E������ƕs���ɂȂ��Ă��܂����B
�����������C�p���[�E�A���v�̓A���N������DC-300�����ݎg���Ă���܂����C
�A���N�����I�v�X�ɖ��O���܂����B
�����ԍ��F7863949
![]() 1�_
1�_
�A�L���t�F�[�Y�Ȃ玄����ԌÂ������H�ł��B���E������n�ݓ����̎����������݂���
�Ă��܂����A�P���\�j�b�N���t���Z�킪�����グ�A�����͊e�n���Ŏ�������J�Â��Ă����A��
�v���܂��B���͂��̏t���Z�킪�������鎎����ɍs���܂�������I�I�B�P���\�j�b�N�̑��
���@��C-200��P-300�œ����̌X�����قȂ��\�I�X�s�[�J�[�R���炵�܂����B�{�C�X�E�I
�u�E�V�A�^�[�̃A���e�b�N�`-�V�A�u�b�N�V�F���t���S���^��AR��3a�A�X�^�W�I���j�^�[�X
�s�[�J�[�̑�\��JBL��43**(�^�Ԏ��O)�ł��B����ch������100W���鍑�Y�A���v�͂قƂ�
�ǖ����A(20�`20KHz�o�͂ɂ�����)P-300��150W/ch�̃p���[�ł����B
������̃X�s�[�J�[�����̓�����\���A�����ȁ`�Ɗ����������o���Ă��܂��B����JBL�̃X�s
�[�J�[�̑f���炵�����I�I�E�E���̎�������JBL�̏o��Łu������JBL�̃X�s�[�J�[���v��
�v�������̂ł��B�����̋�����6�`7���~�ʂ�JBL��1�{50���~�ȏサ�Ă����Ǝv���܂����A����
�̋����ł͔�����n�Y���Ȃ�(����͍��ł��A�ł����E�E�E)���ɖ��̃X�s�[�J�[�ł����B
�������̎��g���Ă����A���v�̓p�C�I�j�A��SA-100�Ƃ����v�����C���ł͍ō���ł������A�p
���[��47W/ch���x�ł����B�������150W�̈З͂�r���C�ɓ��肱��P-300���w�����܂����B(��
�͖ł͂Ȃ����ʂ̒i�{�[���ł������E�E�E)�����g���Ă����X�s�[�J�[�͓������p�C�I�j�A
��CS-E900�Ƃ����X�s�[�J�[�ł������܂��ቹ�����̃X�s�[�J�[����܂�����Ȃɏo���̂��I�I
�Ƃт����肵�܂����B
���̎�����A�I�[�f�B�I�̓p���[�A���v���I�Ǝv���l�ɂȂ�܂����B(��Ƀv���A���v������
�܂������AC-200�ł͂Ȃ��e�N�j�N�X��SU-9600�Ƃ�������1���ԃV���[�Y�ŗ͂��o�����A���v
�̋Z�p���g���āA���i�͗}�����Ƃ����v���A���v�ł��B���̃A���v�̓t�H�m���e���͂��i�i��
�傫���A�u���b�N�p�l���Ŏ������t�����e�N�j�N�X�����̃A���v�ł����B)
�����A�Ȍ�̓Z�p���[�g�A���v�͏ꏊ����邵�A�����Ȃ̂ŃA�L���t�F�[�Y�𗣂�v�����C��
�ɂ��܂����B(�p�C�I�j�A��M-22�Ƃ���A���̃p���[�A���v���g���܂����B)�I���L���[A-820GTR�A
�T���X�CAu-��907�A�P���E�b�hLA-1�Ƒ����ĂуA�L���t�F�[�Y��E-407���w�����܂����B������
��2�N�O��3�N�g����17���~�ʼn����AE-550�����݂��ꂪ���̃s���A�p�̃A���v�ɂȂ���
���܂��B
�����ԍ��F7864021
![]() 0�_
0�_
�A�L���͊����i�ƌ��������Ŏ�ɓ��ꂽP-300�Ɏn�܂茻�݂�P-3000�Ɏ����Ă���܂��B
P-300����ɓ��ꂽ���́A�v����YAMAHA��C-1�E���C����B-2�Ƃ������ꖔ�A�u��ڍ���v
�R���r���g���Ă���܂������A������SP������4320�����ǂ��ɂ��I���点�܂���ł����B
���C����P-300�ɕς��Ă��̉��̕ς��悤�ɋ������L��������܂��B
���̌��P-300��B-1�Ń}���`�A���v�Ŏb���炵��������܂������AB-1�͂ǂ��ɂ�
�䂵�������A���v�������悤�Ɏv���܂����B
�����ɂ��A�A�L���̃v���Ƃ͉������������g�ݍ��킹�̉��������Ƃ�����܂���B
�F�l���E-405��E-407�͕��������Ƃ�����̂ł����A�ނ�SP��TANNOY��ӓ|�B
���Q����JAZZ�̃��R�[�h���Đ�������A��g�����Ԃ݂ɂȂ����悤�Ɋ����܂����B
�ނ̈����Ԃł���A�����t�`�F���Ȃ����ĖႢSP�]�X���A���v�̃m�C�Y�̖�����
�������������̂ł��B
�s���A2CH�Ƃ͌����܂���5300�v����P-3000�ŕ����A�A�i���O���R�[�h���Ȃ��Ȃ��ł��B
2CH��AV���Z�p���[�g�o���Ȃ�����ł�P-3000�̖����͑傫���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7864365
![]() 0�_
0�_
�|�� satoakichan����
�@�����S�j��SP�}�g���N�X�𐄏����Ă��܂����ˁB�T���E���h��H���̉����̂�ʂ����Ƃɂ�艹�����邱�Ƃ�������閭�Ăł������A�L��悤�Ɏg����A���v�����肳��܂��B�������͎���̕~�n�Ɂu���M�v�ƌĂ��AV���[��������Ă��܂������A�@��͍����ȊC�O���Ȃǂ����܂�g�킸�A�X�s�[�J�[�����R����ŁA�����ɃR�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����V�X�e�����\�z���Ă����悤�ɕ����Ă��܂��B���͂��̂悤�Ȍ��I�ȕ]�_�Ƃ����Ȃ��Ȃ����͎̂₵������ł��B
�@����E-305��DS-2000�Ƃ������C���i�b�v�Œ����Ă�����7�N�Ԃ́A�I�[�f�B�I�ɂ��܂�S��Ȃ����������ɓ�����܂��B���̑g�ݍ��킹�Ŗ������Ă�����ł��ˁi�j�B�����ς特�y�\�t�g�ɂ������g���Ă����悤�Ɏv���܂��B����Ӗ��A�Ăт��������������K�������Ǝv���Ă܂��B
�|�� �W�����A�o�[����
�@����ɂ��́B�����ł����ASONY�͋Ɩ��p�����@�킩�����������̂ł����B�Ȃ���悢��SONY�̃I�[�f�B�I���i�͌������������ǂ��悤�ł��ˁB����SONY�̓G���^�e�C�������g�n��A�Ђ���Ƃ�������Z�n�Ȃ����C���Ɂu�O���[�o����Ɓv�Ƃ���ڎw���̂ł��傤��(-_-;)�B
�@ACCUPHASE�͉䂪���̃I�[�f�B�I���[�J�[�ł͒������u�����h�C���[�W�̒蒅���ɐ���������Ƃ��Ǝv���܂��BACCUPHASE���i���āA�w�������Ƃ��ɂ͕ۏ؏����t���Ă��Ȃ���ł���ˁB�������ꂽ�[�i�ʒm���݂����Ȃ��̂����[�J�[�ɗX�����āA�͂��߂ĕۏ؏��������Ă��܂��B���łɁA���̐������疈��N��͂��܂��i�j�B�ڋq�������ƃt�H���[���悤�Ƃ����p�������]���Ɍq�������̂ł��傤�B�����ƃ��C�h�E�C���E�W���p���ł���̂�������������ŁA���ꂪ�������������ɂȂ�����A������i���͓����ł����[�U�[�̓\�b�|�������ł��傤��(^^:)�B
�|�� �掿�ɂ�����肳��
�@����LUXMAN�̃T�E���h�͋��Ŏg�������Ƃ͂Ȃ��̂ł����AACCUPHASE�Ƌ��Ƀu�����h���l���m�����Ă���̂́A���ꑊ���̊�Ɠw�͂����������炾�Ƒz�����܂��BPIONEER��MARANTZ��������u�E�`�͍����@����o���Ă��邼�I�v�ƃu�`�グ�Ă��A���܂��g�u�����h�i�h���蓾�Ȃ��̂́A�I�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ��Ẵ}�[�P�e�B���O�̋l�߂�����Ȃ����炾�Ǝv���܂��B����ǂ�������������ꂽ�t�@���������x����g�I�[�f�B�I�h�Ƃ�����̂��߂̋@����������Ă���̂ł�����A���L�~�����u�����h�C���[�W�͑���Ǝv���܂��B
�|�� audio-style����
�@ACCUPHASE�̋@��͂悭�I�[�f�B�I�G���̃e�X�g�p�Ƃ��Ďg���Ă���܂����ȁB���̂悤�ɃI�[�f�B�I�����O�ɂȂ�ȑO�́A�G���̋L���ɂ������炩�͐M�ߐ����������悤�Ɏv���܂��B�悭�Q�l�ɂ��Ă��܂����i���͂�����ƁE�E�E�E ^^;�j�B���������AACCUPHASE�̃A���v�ނ͖^�j���[�X�ԑg�̃Z�b�g�i�C���e���A�H�j�Ƃ��Ďg��ꂽ���Ƃ�����A�I�[�f�B�I�t�@���Ƃ��Ă͂т����肵�����̂ł��i�قƂ�ǂ̎����҂͂��ꂪ���Ȃ̂�������Ȃ������ł��傤�ȁj�B
�|�� redfodera����
�@ACCUPHASE�̃T�E���h�����ɍ���Ȃ��I�[�f�B�I�t�@�����������邱�Ƃ͕�����܂��B����SANSUI�Ƃ͐����̃e�C�X�g�Ȃ̂ŁA���������D���Ȑl�ɂ͂������͎����ł��傤�ȁB���������A���߂�ACCUPHASE�̃A���v�����������Ƃ���DIATONE�ŁA���Ƃ�ONKYO��PIONEER�Ƒ����A�������JBL�ł����x�ƂȂ������Ă݂܂������A���B�u�����h�̃X�s�[�J�[�ƍ��킹�����̉��ɂ͐ڂ��Ă��܂���ł����B���ꂪ���̑O�̃I�[�f�B�I�t�F�A�ŏ��߂ă��[���b�p���ƌq�������̉����������邱�Ƃ��o���܂����B�쓮�����̂�Sonus faber�ł��B���邭���������������A�ӊO�ɂ������ǂ������ł��ˁB
�@����������SONY��100���~�̖��w�����^�X�s�[�J�[���o���݂����ł����A�Z�p�͐������Ɍ����邯�ǁE�E�E�E����ς�Ɩ��p�����@��ɂ���y�э��ɂȂ������Ђ̐��i�ɂ͐H�w�������܂���ȃ@�B
�|�� 130theater����
�@ACCUPHASE��JBL�͑����ǂ��ł��ˁB����̃I�[�f�B�I�t�F�A�ł�EVEREST�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ŏ������܂������AACCUPHASE���������ƍ����ȊC�O���A���v�Ƃ̃R���r�����L�т₩�ɖ��Ă��܂����BACCUPHASE���i�͍����ȃC���[�W������܂����A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͍����A����Ӗ��g���������h�Ȃ̂�������܂���B
�@�W�Ȃ��b�Ȃ̂ł����AACCUPHASE�̃A���v�ŃX�s�[�J�[�[�q��A��B��2�n��������̂́A�Ȃ����uB�v�̕��������ǂ��Ƃ����u�`���v�����邻���ł��i�j�B�q�}�������璮����ׂĂ݂悤�Ǝv���������̍��ł��B
�|�� �l�I���W����
�@ACCUPHASE��TANNOY�Ƃ̑g�ݍ��킹�͒��������Ƃ��Ȃ��ł��Ȃ��B�ǂ��������ɂȂ�̂�������Ƌ���������܂��B����������YAMAHA���̂̓Z�p���[�g�A���v������Ă�����ł���ˁBYAMAHA�̓V���L�[�z���C�g�̃f�U�C���Œm����g���}�n�E�r���[�e�B�[�h�̃T�E���h�̈�ۂ����邩�Ǝv���ANS-1000M�Ƃ�GT-2000�Ƃ������n���̎��������ȃC���[�W������A������Ɩʔ������[�J�[�ł��B�����ꓯ�Ђɂ��Ă͂��̃X���b�h�ł����y���Ă݂����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7867676
![]() 0�_
0�_
���E�������A���ӂ́B
�@���̗F�l�̒��ł����̐l�́u�ς��ҁv�Œʂ��Ă��܂�����A�I�[�f�B�I�E�́u����v
�@�ȂǁA�u���v�Ƃ��v��Ȃ���m�Ȃ̂ł��B
�@���̐́A�u�O��̐_��v�Ƃ���ꂽ�uTANNOY-�VLZ�{SQ-38FD�{ORTOFON�ESPU-GT�v�����
�@TANNOY�ɂǂ��Ղ�ƐZ�����Ă���ASP���̂͒i�X�ƃO���[�h�A�b�v���܂������A����ȍ~
�@�A���v�Ɋւ��ẮA�t�������̂���I�[�f�B�I�X�̌����Ȃ�Ń��[�J�[���^�����A
�@�Œ��ꒃ�ȑg�ݍ��킹�Ō���(�ŋ߂�DENON�{GRF���������H�j�Ɏ����Ă��܂��B
�@�����������Ƃ��́A���N�^���M�����[����������SP�ƃA�L���ł����B
�@�ނ̃R���N�V�����͔������N���V�b�N�A�c�肪����Ђ�ƌ����u�ϑ���v�ł��āB
�@JAZZ�D���̎��ɂƁA����Ђ�̉̂��X�^���_�[�hJAZZ�������x�Ɂu῝�v��
�@�������̂ł��B
�@�Ƃ͌������̂́A���̔ނ���}�b�L���Ȃǂ��i���ŏ���Ă���̂łˁE�E�E�B
�@YAMAHA�͎��X�A���ȕ���̔����܂���ˁBB-2�̍������������ŎO�p���^�̃p���[�A���v
�@B-4��������B-5���������o���Ă��܂����BGT�V���[�Y�͂���Ȃ�ɐl�C������܂����ˁB
�@���͂��́u���b�N�v�͂��Ȃ�d���L��������܂��B
�@�茳�ɂ́uSR-100X�v�}�g���b�N�X�E�T���E���h�v���Z�b�T�[������܂��B
�@�v�����C���Ɍq���ŁA���A�����o�͂ƃ��A�p���[�A���v������������A���ł��B
�@PA�p�̃p���[�Ƃ��~�L�T�[�Ƃ�YAMAHA���i�̓I�[�f�B�I�ȊO�ł����Ȃ�茳�ɂ���܂��B
�����ԍ��F7868166
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
���E�������
>�쓮�����̂�Sonus faber�ł��B���邭���������������A�ӊO�ɂ������ǂ������ł��ˁB
���B�n�Ƃ��Ĉ�Z�߂ɂ���ɂ͊e���e�ЂŌX�����܂��܂��ł��ˁB
VIFA��SCAN-SPEAK���̓���SP���j�b�g���g���Ă��Ă����Ȃ����Ă܂��B
�`�����I��\�i�X�́i���B���m�̒��ł́j���Ǝ��x�̒Ⴂ������Ȃ��ł��傤���B
�������ǂ������Ȃ̂������ł��܂��B
���^���E�R�[���̃~�b�h�o�X���E�[�n�[���̗p���ăX�s�[�h�w���̂��郁�[�J�[�����v�ł��傤�B
Highland�AMonitor Audio�AAR-Jordan�AELAC������͂���������������܂���B
25���Ƀt�����X���̃n�[�h�i�w���i�����j�^�[�i�j���h�J�b�Ɠ͂��܂����B
�ꕔ�̋@����q���������̃Z�b�g�A�b�v�ȑO�Ȃ̂ő��]����ɂ͎���܂��A
�������[�J�[�i���̈ꊇ������\�ł����j�Ɩ��炩�Ɏw��������Ⴄ�̂͂����ɗ����ł��܂��B
�C�O���i�̑����͂���Ӗ��ƂĂ�������₷���u�����v������܂��ˁB
���̏ꍇ�͔����ȍ��قւ̊��x���Ⴍ�A������₷���u�����v�łȂ��Ɣ��ʏo���Ȃ�����A
ACCUPHASE�̗l�ɑ@�ׂȕ`�������������݂���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂�(^^�U
�����ԍ��F7870409
![]() 1�_
1�_
�@�{����TAOC���͂��߂Ƃ���X�s�[�J�[�u����̘b�����܂��B�m��70�N�ギ�炢�܂ł́u�X�s�[�J�[�̒u����ɂ̓R���N���[�g�u���b�N����ԁv�Ƃ���������������Ǝv���܂��B���̍��̓I�[�f�B�I�t�@���̉Ƃɍs���ƁA�����ȃX�s�[�J�[�̉��ɁA���Ԃɂ͕s�ނ荇���Ȗ����ȃu���b�N���~���Ă��������̂ł��B
�@70�N�㔼�ɃI�[�f�B�I�Z�b�g����ɓ��ꂽ�����������ɘR�ꂸ�A�@�킪�[�������O�̓u���b�N���ǂ����ɗ����Ă��Ȃ����T���Ă��܂����i�� �����Ɣ�����I ^^;�j�B����Ƌ߂��̍H������̘e�Ɂi���Ԃ�j�̂ĂĂ������R���N���[�g�u���b�N�����d���傫�߂̃R���N���[�g�̃����K���B���������Ƃ֎����ċA��A�D����Ƃ��Ēu����̑���ɂ��Ă��܂����B
�@�O�ɒZ����ONKYO�̃X�s�[�J�[���g���Ă������Ƃ������܂������A����ɂ��X�s�[�J�[�u����ɊS�����܂����̂͂��傤�ǂ��̍��ł��B����܂Ŏg���Ă������^��DIATONE�Ƃ͈Ⴂ�A�o�X���t�^��ONKYO�̃X�s�[�J�[�͒�悪���Ȃ�ɂ�Œ������܂����B�G���ɂ́u�ቹ�̐����͂𑝂��ɂ̓X�^���h���������ׂ����v�Ə�����Ă������Ƃ�����A���߂Ďs�̂̒u����B���邱�Ƃɂ����̂ł��B�����Ŗڂɕt�����̂��������S�E�A���~�̒����E�@�B���H�̃��[�J�[�ł������A�C�V�����u��TAOC�u�����h�Ń����[�X��������̒u����ł����B���ʂ͈��|�I�ł����ˁB�ቹ���܂�ŕʕ��B�v���A���F���C�ɓ���Ȃ�����ONKYO�̃X�s�[�J�[��2�N���䂪�Ƃɒ��������̂́A���̒u��������������ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B
�@���̌�A�f�B�[���[�ł����ȃX�^���h���u�����v�����Ă��炢�܂������A���ł��ʔ����Ǝv�����̂́A���탁�[�J�[���o���Ă����Z���~�b�N���̒u����ł��B����̌��ʂ����ǂ��Ȃ��ł��ˁB���ăE�b�h�u���b�N�͉����E�H�[���ɂȂ�悤�Ȉ�ۂ��܂��B
�@�l���Ă݂�ƁA�X�s�[�J�[�X�^���h�̓T�C�Y���������Δ��i�v�I�Ɏg����A�C�e���ł��B���������ɋy�ڂ��e���͂��Ȃ�傫���B�G���̍L����J�^���O�ł̓X�s�[�J�[�X�^���h�����g��Ȃ������ꒃ�ȃZ�b�e�B���O�̎ʐ^�����ʂ��Ă��邵�A���S�҂݂̂Ȃ���́u�X�s�[�J�[�ɂ͒u���䂪����́H�v�ƍl���������������������܂���B�ł��A�X�^���h�̎g�p��O��Ƃ����w���v����q�ɂ͏��߂�悤�A�f�B�[���[�i���ɉƓd�ʔ̓X�j�ɂ͖]�݂����ł��ˁB
�����ԍ��F7871866
![]() 0�_
0�_
���E�������A���ӂ́B
�@ �����R���N���[�g�u���b�N���g���Ă�����l�ł��B�]��̂������Ȃ̂ŕ\�ʂɘa�����������\��A�N�����h���ʼn��ς������̂ł��B�ቹ���ǂ��o��Ɗ��ł��܂����B�e���[�N�̒��m�[�J�b�g�Ղ����t����ƁA���̑呾�ۂ̉��̓I�[�f�B�I�D���̓�K�ɋ����e�����������ɐU���ő̂����ɕ����ƕ�����������قǂł��B���炩�ɒ��ߏ�C���ƃu�[�~���O�ɂ͋�J�������܂����B�X�s�[�J�[�u����͍����Ĕ����܂���ł����B
�����ԍ��F7872105
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@������(^-^)/
5�i�A�c�^���b�N��PJ�̒u����ɁA���^SP�̃X�^���h�A�t���A�^SP�̃A���_�[�{�[�h�A
�`�cK�̃��b�N���ɃI�[�f�B�I�{�[�h�A�ی^�A�l�p�A�n�C�u���b�h�^�C�v�̊e��C���V�����[�^�[�A�@
�@�@�@�@�@�@
�^�I�b�N����A�����b�ɂȂ��Ă��܂��Bm(_ _)m
�����ԍ��F7872312
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���A���ӂ́B
�@�u�R���N���E�u���b�N�v�͈��l�ʼn����łł���ɓ������̂�60�N�㔼����A�g���
�@�n�߂��悤�ɋL�����܂��B
�@����JBL�ɒH�蒅���O�ɁA�p�C�I�j�A��PIM-16�Ƃ��i�V���i���́u�Q���R�c�v���Ƃ���
�@�u���J�j�J��2WAY�v�Ə̂���16-20CM�̈������{�b�N�X�ɓ��ꂽ����SP�ł����B
�@�������ɘR�ꂸ�A�u���b�N�̉��ς݁E�c�ς݁E�Q�i�d�˓��X�����܂������A
�@�u�{���{���v�Ƃ��ڂꗎ���邩����N�Y�ɂ͎���Ă��܂����B
�@SPLE-8T�𒆌ÂŎ�ɂ����Ƃ��A�I�[�i�[������SP�X�^���h���ꏏ�ɂ��ĖႢ�܂����B
�@�p�C�v���̊ۈ֎q�̍��ʂ�����Ă��̕����Ɍ���t�����悤�ȕ��ł����B
�@���̍l�����Ȃ��A���̂܂g���Ă���܂������ቹ�s���C���E������̂�JBL�g�[����
�@����LE-8T�Ŗ�����ꂽ�悤�ȋC�����܂��B
�@���^�o�X���t��SP-505j�͂�͂莩��̎����֎q����SP�X�^���h�ɏ悹�Ă��܂����B
�@�S�{���̃L���X�^�[�t���֎q����w��������O���A���ʂ̃A���R������
�@�X�`�[�����̍��ʂ�SP���悹��͔̂��ɍD�s���ł����B
�@���̌�́u�H��ՃI�[�f�B�I���[���v�ł����̂ŁA�ቹ�s���ɋ�������܂����B
�@�R���N���ł��������̏��ł�4320�͑S���ቹ���o�Ȃ��̂ŁA�X�^�W�I�d�l�̃X�^���h��
�@�ォ��lj��ݒu���܂����B
�@4344�w����͎O���̊p�ނŊ�b�g�����A��ɕď��̍���t���āu�u����v�ƌ�����
�@�ȈՃX�e�[�W�����삵�R���N�����u�����肵�܂����B
�@���̎��̉����ǂ��������ǂ����́H�肩�ł͂���܂������̒��́u���ꂪJBL�I�v��
�@�����̉��ł��邱�ƂɊԈႢ�Ȃ��l�ł��B
�@����Ȍo�܂ł��̂ŁATAOC���i�Ɍ��炸SP�p�̒u����E�X�^���h���̂ق��ΐ��i����
�@�g�������Ƃ��w�ǂ���܂���B
�@���݂�YAMAHA��GT���b�N�����������O�~�̏���SP�̊Ԃɒu���Ă��邾���ł��B
�@�X�^���h�ʼn����剻������̂͂�͂�u�b�N�V�F���t�^�ɑ����l�Ɋ����܂���
�@�@���ł��傤���H
�@�ŋ߂̉��B�n��SP�͂��̕ӂ��V�r�A�ȗl��JBL-JAZZ�̑�G�c�ȃX�^�C���Ƃ͂��Ȃ�
�@�������Ⴄ�悤�Ɏv���܂��B
�@
�����ԍ��F7872599
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
�P�[�u���Ȃǂ��y���ɕω���e�����o�₷���̂��X�^���h��b�N�ł��ˁB
TAOC�͂����b�ɂȂ������Ƃ�����܂��A���i�͊��S�������郂�m�������ł��ˁB
���^���E�}�e���A���̊�Ƃł͂���܂����A���X�A�@�B������ł���ˁB
�I�[�f�B�I�E�A�N�Z�T���[�i�o���邢�������ǂ�Ȃ��̂������̂��ƂĂ��C�ɂȂ�܂��B
��Њ����ɋ���ȃI�[�f�B�I�E�}�j�A�����炵���̂ł��傤���H
�܂����������ăX�s�[�J�[�ł̃I�[�f�B�I�@��s��ւ̎Q�����E�f�������Ǝv���܂��B
���������U�X�y�V�����X�g�ISP���j�b�g���������A���ɖ��Ă���̂͂��܂��܂������A
Dynaudio��Esoter��Scan-Speak��Riveriter����V���ʂ������o�����ȁA�Ɗ����鉹�F�ł����B
2Way��FC3000�͑O�q��ACCUPHASE�Ń`���[�j���O���Ă��邩������܂���B�������߂��܂�����B
Dynaudio�����j�b�g�������Ƃ���߂Ă��܂������ߎc�O�Ȃ��琻�����~�ɂȂ�܂������A
�X���ɍɂ����邠�����Ɉ�x�`�F�b�N���Ă݂ĉ������B
�l�I�ɁA���B�X�s�[�J�[����̃t�@�������ق点��G�|�b�N���C�L���O�Ȑ��i�Ǝv���Ă܂��B
�X�^���h�����b�N����E�����Ă��܂��܂������A�ߔN�A�V���u�����h�̎s��Q�����ڗ����܂��B
�Q���u�����h�̋@��͈ӗ~�I�Ȑ��i�������̂Ŋ��}�������Ƃ���ł��B
���Ԃ��Ə]�����[�J�[��u�����h�̐��i���蔖�ŁA�s��Ƀ`�����X����ƌ���������Ă���̂��Ǝv���܂��B
���E�������
���X�s�[�J�[�̒u����ɂ̓R���N���[�g�u���b�N�����
���̐���ł�����܂����Ɏc���Ă��܂������A���ɉ����Ȃ������̂ł��傤���H
598�X�s�[�J�[�S��������e���[�J�[�Ƃ���p�X�^���h��p�ӂ��n�߂��l�ȋC�����܂��B
�ǂ��TAOC��TARGET AUDIO�̃R�s�[�Ɍ����܂������E�E�E
���Ȃ݂Ɏ��̏ꍇ�͎��o�͉������D�揇�ʂ������Ȃ��Ă܂�(^^�U
��B&O�̖��f�U�C�i�[���������R�u�E�W�F���Z���̑�t�@���ŏ�������SP�X�^���h�܂ŐF�X�Ǝg���Ă��܂��B
http://www.jacobjensen.com/
�t���ASP�����߂ē��������̂�Infinity��IRS-Delta�Ől���嗝�{�[�h���z�[���Z���^�[�Œ��B���܂����B
Martin Logan�ɐ芷����ۂ�CORIAN�{�[�h�̏�ɃJ�[�{���E�O���t�@�C�g�E�{�[�h���d�˂�l�ɂ��܂����B
�u�b�N�V�F���t��KEF����������TARGET AUDIO�ł������R�u�E�W�F���Z���E���f�����X�g���Ă��܂��B
���b�N�̓��R�u�E�W�F���Z���̃f�U�C���ł͂���܂���B&O�̃f�U�C���E�t�@�j�`���[�n�̂��̂��g���Ă��܂��B
�l�I���W����@
���X�^���h�ʼn����剻������̂͂�͂�u�b�N�V�F���t�^�ɑ����l�Ɋ����܂����@���ł��傤���H
���R�͂���������Ǝv���܂����A�u�b�N�V�F���t��ԍ�SP�Ŏ���𑽂��肪�����o�����犴���邱�Ƃ́E�E�E
1�j�t���ASP���G���N���[�W���[�̗e�ρ^�̐ρF�G�l���M�[�ʂ̔䗦���������ƁB
2�j�o�b�t�����������ē_�����ɋ߂���܌��ʂ��傫�����ƁB
3�j�ǖʂ�ϋɓI�ɉ��z������o�b�t���Ƃ��ė��p���悤�Ƃ��邩�ۂ��ōĐ����̕ω����傫�����ƁB
4�j�t���ASP�ȏ�Ƀo�X���t�̋��U��ϋɓI�ɗ��p���悤�Ƃ��邽�ߐU�����₷�����ƁBetc.
������������^�C�v��U�����������艟�������ރ^�C�v�ȂǁA�X�^���h�����X����܂����A
�����I�ɏ������u�b�N�V�F���قǐU����^���₷���Ď₷���̂ōĐ����̕ω����傫���Ȃ�A�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F7874784
![]() 1�_
1�_
redfodera����A���ӂ́B
�@�uBang & Olufsen�v�����D���I�ƌ������Ƃł��l�����܂��悭�킩��悤�ȁE�E�E�E�B
�@BeoCom 2000�ƌ����d�b�@��Beosystem2500�����������Ă������g���Ă��܂����B
�@������͉����H��Ճ��[���E���Z�܂��}���V�����ł����炨�����ȕ���u���悤��
�@�S���E������͉����Ƃ���֗��Ă��܂��܂����B
�@�u�b�N�V�F���t�̍\���ォ�炭��C�ނ��������H���������^SP���牓������̂����B
�@�ƌ�����肩�A��͂�JBL�̑�g�����������ƌ������Ƃł��傤�ˁB
�����ԍ��F7875055
![]() 0�_
0�_
�|�� �l�I���W����
�@�m������Ђ�̔ӔN�߂��̃A���o����PCM�f�W�^���^���������Ǝv���܂��B�I�[�f�B�I�G���ɂ��D�G�^���ՂƂ��ďЉ��Ă����悤�ȋL��������܂��B
�@�����̎g���Ă���ONKYO�̃X�s�[�J�[�͍���D-77�V���[�Y�Ɠ��n���̐��i�ł�������A�u�b�N�V�F���t�^�Ƃ͂����Ă����Ȃ�̑�^�ł����B�Ƃ͂����A���R����t���A�^�Ƃ͈Ⴂ�A�u����ɂ�鉹�̈Ⴂ�͌����ł����ˁBYAMAHA�̎O�p�`�p���[�A���v��B-6�ł����B�d�ʂ�9kg�����Ȃ��̂Ƀn�C�p���[�����o�����̂́A����ȓd�����g�p���Ă��������炵���ł��BSONY�̃p���X�d���Ǝ����悤�ȕ����������Ƃ��B���Ђł̂��̋K�i�͂�����肾�����炵���A���������̂܂ܓ˂��l�߂Ă����Ζʔ����W�J�ɂȂ����̂ł͂Ǝv�����肵�܂��B
�|�� redfodera����
�@�������݂�q�����Ďv���o�����̂ł����ATAOC�̓X�s�[�J�[���o���Ă��āA���̃��j�b�g�͑����͉��B���ł��B�����i�̃��j�b�g���g���Ă���̂�����A���������T�E���h�����Y���ꂵ�����̂��Ǝv������A�F�C�F���̃X�g���[�g�ȓW�J�̓T�^�I���{���X�s�[�J�[�̉��������̂ɂ͜��R�Ƃ��܂����B���������ΐ̂�VICTOR�̃X�s�[�J�[���R�[�����̓h�C�c���Ȃ��特�͂����Ђ������̏��a���i�Ӗ��s�� ^^;�j���������A�X�s�[�J�[���Ƃ����̂̓��j�b�g�͂ǂ�����G���N���[�W���[�̎d�グ�ƃ`���[�j���O�����m�������̂��ƁA������O�̂��ƂɎv��������܂��B
���]�����[�J�[��u�����h�̐��i���蔖�ŁA
���s��Ƀ`�����X����ƌ���������Ă���
�@����͌����܂��ˁB���ƊE�ŃI�[�f�B�I�S������̌������l�ނ����āA���ꂪ�����̍��Y���u�����h�̈�{���q�ȓW�J�Ɂg�I������������������Ə�肭����h�Ǝv���ď��o���Ă���̂�������܂���B�������A�C���^�[�l�b�g�̕��y��PR�������e�ՂɂȂ������Ƃ��傫���Ǝv���܂��i�͍̂����J�l�o���ĎG���ɍL�����ڂ��邵������܂���ł������� ^^;�j�B���ƁAB&O�ɂ��Ă͎���������y�������Ǝv���Ă܂��B
�|�� �掿�ɂ�����肳��
�@�����R���N���[�g���̃����K�͂��܂�ɂ��E���i�Ȃ̂ŁA�ǂ��ɂ��������ȁE�E�E�E�Ǝv���Ă�����A������w�Z����A��Ă݂�ƃ����K������ŃL���C�ɃR�[�e�B���O����Ă��܂����B���܂�̖����ȃ��b�N�X�Ɂu�Ƃ̔��ςɑ傫���x�Ⴊ�o��I�v�Ǝv������e�̎d�Ƃł����i���j�B�ŏ��͖ʐH�炢�܂������A���ʓI�ɂ͊��ӂł�(^_^)�B�e���[�N���[�x���Ƃ����A�L���Ȃ̂͗�̑�C�̉��ł��ˁB����LP�������Ă��܂����A�Ֆʂ̍a�߂Ă��邾���Ŗ����ꒃ�Ȓ�悪�_�Ԍ����܂��B
�|�� audio-style����
�@TAOC�̐��i�����ׂẴP�[�X�Ŗ��\���Ƃ͎v���܂��A���̕���ɐ�ւ�t�������Ƃ͑傫���Ǝv���܂��B�́A�^�]�_�Ƃ�TAOC�̃u���b�N�^�̒u������g�����h�������|�[�g���G���ɍڂ��Ă��܂������A���ʂ��ǂ��Ȃ����̂��͖Y��܂����i�j�B���������Εʂ̃��[�J�[��RASK�{�[�h�Ƃ����̂�����܂����ˁB���͎��������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�f�B�[���[�̘b�ɂ��Ƃ����������ʂ��傫���Ƃ̂��Ƃł����B
�����ԍ��F7875648
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@�@������(^-^)/
�����ŏ��̓u���b�N�A�����K���g���Ă��܂������A
�ׂ��������o��̂ŁA�S�ʃt�F���g��\��t���Ďg�p���Ă��܂����B
���X�N�̔��g�p���܂������A���������|���|�������ă`���b�g����܂����B(^_^;)
���X�N�͉��H�i���ǂ��ł��ˁB
��TAOC�̐��i�����ׂẴP�[�X�Ŗ��\���Ƃ͎v���܂���
��Ƃ���ł��ˁB
�ȑO�AATC��SCM100���g�p���Ă��܂������A�ׂ������p�C�v�̃X�^���h���t���ł��B
�^�I�b�N�̃X�^���h�Ɍ�������ƁA�I�[�f�B�I�I�ɂ͖����ł����A���������₽���E�E
�}篁C�Ƌ����ɓ����ŁiSCM100�A���s����45cm������̂Łj�A
���̃u���b�N������Ă��������܂������A���y�ɉ����݂������p�[�t�F�N�g�ł����B
�E�E�E���������AATC100�͖ؔ��ɓ����ĉ䂪�Ƃɂ���Ă��܂����E�E�E
�����ԍ��F7876198
![]() 0�_
0�_
�r�N�^�[�̃r�f�I�f�b�L���̏Ⴕ�Ă��܂��܂����BD-VHS�@��HM-DHX2�ł����A�e�[�v�G���h��
�J�`�����Ɖ������āA�A�����[�f�B���O���Ă��e�[�v���o�Ă��܂���B�����ŃJ�o�[��������
����ł���e�[�v����Ă��o�Ă��܂���B�E�E�E���XVHS�e�[�v���A�Ȃ̂ł���D-VHS�@�̈�
�u���[���B�����O�̊��Ԃ͂����BS�f�W�^���n�C�r�W������^�悵�Ă���AD-VHS�e�[�v��200
���ʂ���̂ŏC���ɏo���܂����B�E�E�E���i�オ1000�~���炢�ő��z7800�~�ł����BHM-DHX2
�͍��v3�䔃���܂����B1��͏������܂������A�����b�������Ŋ撣���Ă��炢�܂��B�ł�����
HM-DHX2�͍��܂Ŏg����VCR�ł͍ł����ۂ�(��������)�}���[�V�A����VCR�ł��B�掿�͈�ԗ�
�������m��܂��E�E�E�B
���A�����ւ��������̂ɃX�s�[�J�[������܂��B�����̓p�C�I�j�A��S-1EX�ł��B������
�ɂ��s���p�C�I�j�A�̕�����Z�p�������A���Ȃ�ӗ~�I�ȃX�s�[�J�[�̗l�ł��B�p�C�I�j
�A�����{���Ȃ̂ł����A���͊J���X�^�b�t�̔����͊O���l�������ł��B�ꌩ����ƃ��j�b�g��
���a���������̂ő傫�������Ȃ��̂ł����A60Kg�ȏ���L��A�߂��Ō���Ƒ傫�ȃX�s�[�J�[
�V�X�e���ł��B�������邱�ƂȂ���A���́u�r���v�̍��������@�\���ǂ��ł��ˁB�ݒu������
�̂܂܂̏�Ԃŏォ�璲���o����̂��ǂ��ł��ˁB�K�^���͑�G�ł�����B����JBL�̃X�s
�[�J�[�̓X�s�[�J�[�̒�ʂɃl�W�����Ă��肱���ɃX�p�C�N���˂����ݒ������܂����A�X�s
�[�J�[�̉����ł����璲���͂ƂĂ�����̂ł��B
�����Ń��j�^�[�I�[�f�B�I��PL300���ǂ��ł��˂��A����AJBL��S4600�̎�����ɍs����
�������A������Ȃ��Ȃ��I�I�BJBL��DD66000�̎��������܂��������i���l����Ƒ��̑I������
�o�Ă����Ⴂ�܂��B�p�C�I�j�A��TAD���������炢�̉��i�ł����ˁH�ADD66000���Ȃ�p�C
�I�j�A�̕����ǂ������H�Ǝv���܂��B(�����͂��Ă��Ȃ��̂ł����E�E)�\�i�X�̃N�����i�ł�
�������H������ǂ��E�E�E�B�X�s�[�J�[���w������ɓ�����h�����I�E�E�Z���^�[�X�s�[�J�[
����Ȃ�����2�{����Ȃ��Ƃ����Ȃ����ł��B��L�̃G�x���X�g��TAD���������X�s�[�J�[��1
�{�����Ȃ牽�Ƃ��Ȃ肻���ł����A2�{�ƂȂ�ƁE�E�E�r�N�^�[�̐V�X�s�[�J�[�͂�����Ɗ�
�҂����Ⴂ�܂��B���{�̃��[�J�[�Ŋ���ɍ����ȃX�s�[�J�[�����Ă���̂̓p�C�I�j�A��
�r�N�^�[���炢��������܂���ˁB
���̃r�N�^�[����V�^�X�s�[�J�[����������܂����A�U�����}�O�l�V�E���B�p�C�I�j�A��S-
1EX���}�O�l�V�E���ł��B�}�O�l�V�E���͉����I�ɓ������ǂ������Ŏg����l�ł��B(�y����
��v�œK�x�ȓ�������������E�E�E)�J�[�{���t�@�C�o�[�A�P�u���[�A�p���v�A�`�^���A�A��
�~�A�z�E�f(�{����)�A���A�W�������~���A���A�x�����E���A�E�b�h�A�|���}�[���W�����X�E�E
�F�X�g���Ă��܂��ˁB���������̂ł��傤���H�B
�����ԍ��F7876585
![]() 0�_
0�_
���͂悤�������܂��I
130theater����@�͂��߂܂��āA�r�N�^�[D-VHS�����g���Ƃ̎��B
���������g���Ă܂���A�Â��@���DH35000�ł�����x�C�����܂����������Ɍ��݂ł��B
�u���b�N�̒u������������ł��ˁA10���N�O�̎��ł��������X�e���I���ŕ]�_�Ƃ̋��q�p�j�����u���b�N���g���ċ��q���u���b�N�u����Ƃ����̂��ꎞ�]���ɂȂ�A�����ꎞ���킵�悤�Ƃ��܂������������I�ǂȂ������ꂽ���͂��܂����H
���݂̓g�[���{�[�C�`��SP�̈גu����Ƃ������A�~����Ƃ��Đl���嗝�̕����g���Ă܂��B
�����ԍ��F7876979
![]() 0�_
0�_
satoakichan����@����ɂ���
DH35000����HDMI�[�q���t����HM-DHX2�ɔ����ւ��܂����BDH30000��OEM�̓��ł�A-HD2000�ōw
�����A�����HM-DHX2�ɔ����ւ��܂����B���̕ӂ�̋@��ł��ƍ�������t�ł����ˁB
�E�E�E�v����VHS��VHS��Hi-Fi���o�Ĕ����ւ��AS-VHS���o�Ĕ����ւ��AW-VHS���o�Ĕ�����
���A������D-VHS���o�Ĕ����ւ��E�EHDMI���t���Ĕ����ւ��ƐF�X�����܂����B�ŏ��ɔ�����
�@��̓r�N�^�[�̃e�[�v���ォ��o�����ꂷ��^�C�v�ł����B�v���o�Ɏc���Ă���͎̂O�H��
V6000�Ƃ����f�b�L��V35(�����^�Ԏ��O)�������Ǝv���܂����A�ǂ��f�b�L�ł����B
�r�N�^�[�ł�HR-755(������^�Ԃ́H�H)���Œ�w�b�h�̉������X�e���I�ł����BX3�X�s���b
�g�AX7����ۂɎc���Ă���f�b�L�ł����BX5�������܂������̏�̘A���ł����B����Ɖ�����
PCM�^���o����Z1���ǂ������ł��˂��BPCM�^������S-VHS�e�[�v�͍��ł������c���Ă��܂�
���A���͂⒮���@�킪����܂���B
�E�EW-VHS��W5�ɂ͋ꂢ�v���o���E�E�E���鎞��ʂɃm�C�Y���`���`���E�E�N���[�j���O�e�[
�v���g���Ă��_���Ŏ����ŃJ�o�[���J���ĖȖ_�ʼn�]�w�b�h���S�V�S�V�E�E�E�Ȗ_�̑@�ۂ�
�������݂����ȕ��������������ĕt���Ă��܂����B�����낤�Ǝv���A���ʂ�ɂ��čĐ���
�Ă݂�ƌ����Ƀm�C�Y�͏o�Ȃ��Ȃ�܂����B���̑���Hi-Fi�������o�Ȃ��̂ł��B��������
�̃S�~��Hi-Fi�����w�b�h�̃R�C���������ł����B���̋@��͊e��w�b�h��10���炢��]�w
�b�h�ɑg�ݍ��܂�Ă���̂ł����A���̃w�b�h�����̌����͏o���Ȃ�(�H��Ō������őg�ށH)
�̂ŃA�b�V�[�����ƂȂ�܂��A�����Ēn���̃T�[�r�X�Z���^�[�ł͂Ȃ��A�L�[�ƂȂ�T�[�r�X
�Z���^�[�ɑ���̂�1�������炢�|����܂��A�Ƃ̎��ł����B
���ǂ���Ȃɑ҂Ă��AW5���l�i�������Ă�����������������w�����܂����B�m��18���~����
���Ǝv���܂��B(�艿��35���~�H)�@�C���͖�6���~���x�|����܂����B6���~�Ƃ����Ƃ������
�����f�b�L��1�䔃���邭�炢�ł��ˁBHM-DHX2��69,000�~�Ŕ����܂�������E�E�E�B���P�͉�
�]�w�b�h�͖Ȗ_�ł̑|���͌��ւł��B�N���[�j���O�e�[�v�����ɂ��܂��傤�B�I�[�f�B�I�e�N
�j�J�̃N���[�j���O�e�[�v�������߂ł��B����D-VHS�p�̃N���[�j���O�e�[�v�ƕz�́H�N���[
�j���O�e�[�v���g���Ă��܂��B
�����ԍ��F7878464
![]() 0�_
0�_
130theater����A����ɂ��́B
�@�@130theater������^��@�ɂ͋�J���ꂽ�̂ł��ˁB�����̏ᒆ�̘^��@����䂠��܂��BNEC�����E�ŏ��߂Ă�DVD�@�Ɛ�`���Ă���GigaStation�@MV10000�ł��B3�N�قǑO�ɃX�C�b�`������Ȃ��Ȃ�C���ɏo�����̂ł���4���~�قǂ�����Ƃ̎��B����ł��X�C�b�`�̓���Ȃ�����������܂����̂ŁA�����C���ň������܂����B�������A���̂����A�p�l���̏Ɩ��͏����A�^����Đ����o���Ȃ���ԂɂȂ�A�`���[�i�[�̋@�\�����ɂȂ��Ă��܂��܂����B�r�f�I�J�����̃J�b�g�ҏW�ɏd�Ă����̂ł����B�p�����悤���A�C�����ĉߋ��̉f�����Y���_�r���O���ď����悤���A�������Ƃ��Ă��A���̑��ʂɑΉ����Ȃ��������Ă��܂��B(�C���˗����Ă��@�蕔�i�ۑ����Ԃ��߂��Ă���̂ŁA�f���邩���m��܂���)
�����ԍ��F7878631
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�@�u���R�[�_�[�v��VHS�EBETA�Ƃ��̏�E�C���Ȃǂ̌o��������܂���B
�@���L�@���BETAx1�EED-BETAx1�ES-VHSx2�ł����S�Ċ����ł��B
�@BETA���I�����}���AW-VHS�ED-VHS�ƈڍs���鎞���͏o�x��Ƌ��ɁA�����ω����傫����
�@�u�I�[�f�B�I�v�Ƃ̊W���H���ɂȂ��Ă��܂����B
�@���ꂩ��Q�O�N�߂����o�Ƃ���͂���A�ǂ��v���o�ł͂���܂����B
�����ԍ��F7878757
![]() 0�_
0�_
�@�{���̃l�^��CRYSLER�i�N���C�X���[�j�ł��B�N���C�X���[�Ƃ����Ă��č��̎����ԃ��[�J�[�̂��Ƃł͂���܂���i�����CHRYSLER�j�B70�N��ɂ͉Ɠd�ʔ̓X�̃I�[�f�B�I�R�[�i�[�ɂ��悭�����������{�̃X�s�[�J�[���[�J�[�ł��B�����Ƃ��A���Ђ̃X�s�[�J�[���g�������Ƃ͂Ȃ��A���������̂�2��݂̂ł��i�������A��������ƒ������킯�ł͂Ȃ��A�`���b�Ƃł� ^^;�j�B�Ȃ̂ɁA�Ȃ�����ۂɎc���Ă����ł���ˁB
�@�ŏ��ɒ������̂�CE-1�Ƃ������V���[�Y�̑�^�̃u�b�N�V�F���t�ł��B���̍��i70�N��㔼�j�ɔ������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�����[�X�͂����ƑO�ŁA���̓X�ɂ͒����ԃX�g�b�N����Ă��������̘b�ł����BDIATONE�ق����̍��Y���[�J�[�ɔ�ׂĕ��������͗ǂ��Ƃ͎v���܂���ł������A�O�֏o�ċ����̂Ȃ�����͌���������܂���ł����B�ʔ��������̂����̃f�U�C���ł��B�T�����l�b�g��������ł���ˁB���̃��j�b�g���͂�����Ɠ����Č����܂��B�������A�l�b�g���O�������Ƒ����������̃p�t�H�[�}���X���܂������ꏏ�ł����B����ɋ����[�������̂��A�o�b�t���ʂɎ��g�������������O���t���������Ă������Ƃł��B�A�b�e�l�[�^�[���t�����O�ʂ́A�܂��JBL������̕č����̃X�^�W�I���j�^�[���v�킹�A���Ƀo�^�L�����킢������܂����B
�@2��ڂɒ������̂�Perfect�V���[�Y�Ƃ������A�T�����l�b�g�Ȃ��̋�F�̃o�b�t�����a�V�Ȑ��i�ł����B���́uCE�V���[�Y�ɔ�ׂč��悪�L�т����ȁv�Ǝv�����x�ł��قLj�ۂɂ͎c��܂���ł������A���̃f�U�C���͎��ɍC�����Ă��܂����B
�@80�N��ɓ�����CRYSLER�͕��ʃ��j�b�g�������������^�X�s�[�J�[���o�����悤�ł����A���͒��������Ƃ�����܂���B���̂����A�u�����h���̂����ł��Ă��܂����悤�ł��B���������Ă悭���̂̕�����Ȃ����[�J�[�ł������A�I�[�f�B�I�����������̉������̃u�����h�ł��������Ƃ͊m���ł��B���Ƀf�U�C���̃R���Z�v�g�͌����_�ŕ������Ă��s��Ɏ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7879017
![]() 0�_
0�_
�N���C�X���[�ł��ˁB���A�g������������܂��B�^�Ԃ͊m��CE-2aII�������Ǝv���̂ł����E�E�E�B�F�l�������Ă��܂��āA���̎����̓p�C�I�j�A��CS-R70�Ƃ��������ƍ����̃��j�b�g���z�[���^�C�v�̃X�s�[�J�[���g���Ă��܂����B���̃X�s�[�J�[�ƌ������܂����B
���́E�E�E��ۂɎc���Ă��Ȃ��ł��˂��B���E������������݂���Ă���l�ɁA�T�����l�b�g���������̃X�s�[�J�[�������܂����B����ƃR�[���G�b�W�ł������ʂ͓ʑ��ł����A����͉��������l�ȋL��������܂��B
���E������u�������̃I�[�f�B�I�@��ƍ���̓W�]�v�Ƃ�����ڂŃX���b�h�𗧂��グ�Ă���Ď����g�̉������̃I�[�f�B�I�@����v���o���Ă��܂����A���������Έ��̋@��̏������ǂ������̂��]��o���Ă��܂���B�ŋ߂̃A���v��(5�`6�N�O�܂�)�����ɏo���Ď��̃A���v���ė����L��������̂ł����A�N���C�X���[�̃X�s�[�J�[�͂ǂ�������������Ȃ��H�H�B
�����ԍ��F7881305
![]() 0�_
0�_
���̍Ō�̓��e([7839304])����10���Ԍo���܂������A���̎���ɑ���A���E�������̔��_�͂���܂���ł����B
����ɂ��A���E������A�����ɓs���̈������Ƃ͖������A�����̓��e�ɐӔC�������Ȃ������ł��邱�Ƃ������ɕ�����܂����B
����ɁA���ꂾ���ł͂Ȃ��A���E����������ꂽ [7825253] �́A
�� �@���l����́u���̏��i�͗ǂ��v�Ƃ����A�h�o�C�X������邱�Ƃ��u�����v�Ƃ����Ƃ��ے�I�ȈӖ��ł����������Ȃ��̂Ȃ�A���Ȃ������̃{�[�h�ɋ������Ă��闝�R�͂Ȃ��A�܂����̃{�[�h�ł̂��Ȃ��̑��݉��l�͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B����ł������̂ł��傤���B
�Ƃ������������邩����A���E�������́A�l�̔��_���t���Ȃ������ł͂Ȃ��A�f����Ŏ����̋C�ɓ���Ȃ�����������ȁE�f������o�čs���A�Ƃ������A�f������Q���҂�r�˂���v�z���������ł��B
�Ȃ��A���̂��̏������݂͍����̂Ȃ���排����̂������ł͂���܂���B
���E������A����ɉ��Ȃ��Ƃ��������A����сA�u���Ȃ������̃{�[�h�ɋ������Ă��闝�R�͂Ȃ��v�E�u���̃{�[�h�ł̂��Ȃ��̑��݉��l�͂Ȃ��v�Ƃ��������������������A�q�ϓI�ɉ��߂������ʂł��B
�����ԍ��F7882290
![]() 1�_
1�_
�F����A����ɂ��́B
CRYSLER�i�N���C�X���[�j�Ƃ������O�������Ƃ�����܂���ł����B
�T�[�t�B��������^�I�[�N�V�����ɏo�Ă܂���CRYSLER�c
�o�i����Ă�����̂��������͂�ƌ������u�Ƌ�v�ł���(^^�U
�R��̐_��ɑ����Ɠd�Ƃ��ăX�e���I�����Ă͂₳�ꂽ�����ɂ͗l�X�ȃ��[�J�[�������������ł����A
�v����CRYSLER�����������ʒu�̃��[�J�[�������̂ł��傤���H
GUYATONE��ELK�Ȃǂ��Ă̊y�탁�[�J�[�⌻�݂̋��Z�������������Ă��������ł����c
���Ȃ݂ɋ��Z���͗A�o�p��CDP���g���Ă������Ƃ��v���o���܂����I
SP���j�b�g���̂�FOSTER��Ɠd���[�J�[�ȊO�ɂ����C�[�l�Ƃ����Y���[�J�[�����Ȃ肠��A
���m�ɂ���Ă͉��N��ALTEC��JBL�ɍ������āATELEFUNKEN�AEMI�AJENSEN�̗l�ɁA
���B���e�[�W�������ăI�[�N�V�����Ŕ��蔃������Ă���l�ł��B
CRYSLER�������������j�̂P�y�[�W���ʂ郁�[�J�[�Ɏv���܂����B
130theater����@
���N���C�X���[�ł��ˁB���A�g������������܂��B
���R�[���G�b�W�ł������ʂ͓ʑ��ł����A����͉��������l�ȋL��������܂��B
130theater������͂��ߊF����؋�����̖Ҏ҂ł����̂ˁB�h�����Ă܂��B
���Ȃ݂ɉ��^�̃G�b�W�̓R�[���̐U����������Qts�I�ɂ͗��z���Ƃ����������܂��B
���^�G�b�W�͑ϓ��͂��傫���ł��Ȃ���ɑ���a��������A�ߔN�̓o�X���t�嗬�Ő�������܂������A
�ቹ�K���ɃL���������Ē��̖��ēx�������Ȃ�ƌ����Ă܂��B
���Ȃ݂�130theater����w������������Ă���p�C�I�j�A��S-1EX���͂��߁A
TAD�������̗p���Ă���R���Q�[�V�����E�G�b�W�͉��^�G�b�W�̒�扞�����ɉ����A
���ϓ��͉��Ƒ���a�����\�ɂ�������̉��ǔłƈʒu�Â����Ă���l�ł��B
�l�I���W����@
���uBang & Olufsen�v�����D���I�ƌ������Ƃł��l�����܂��悭�킩��悤�ȁE�E�E�E�B
�J�b�R�ƌ����ڂ��C�ɂ���^�C�v�Ȃ�ł��B
�ڂɓ����Ă�����̂��Y��ȕ����������ȂƁc(^^�U
Beocom�͖����Ɏg�p���Ă܂����AB��O�̋@�\���݂����Ȃ��̂ɂ͋����䂩��܂��B
�V�N�O�ɉ�Ђ̎���������������Ƃ��������R�����āA
�u����������Ȃ����炨�q�l�̖ڂɐG��鉞�ڎ��̓f�U�C����̂̔��i��u�����v��
�\�肵�Ă���JBL+Macintosh���������ɂ܂킵Beosystem�ɂ��Ă��܂��܂����B
����ȗ��A�����R�𖡕��ɂ�������d�����₷�����ɋC�Â��A���傭���傭���R�𗊂�ł܂��B
�����ԍ��F7882476
![]() 1�_
1�_
������������܂��B
�@�N���C�X���[�ł����I�B
�@130theater����̋�ASP�͌������Ƃ͂���̂ł��������͕̂��������Ƃ������悤�ȁH
�@P-610A�Ɏn�܂�A16�`20CM�̃V���O���R�[��������BOX�ŕ����Ă������ゾ�������A
�@����JBL���ɓU���Ă������m���ł͂���܂��B
�@���̑O��H��Coral�Ƃ���SP��ƃ��[�J�[�́uCX-50�v�������������QWAY���g���Ă܂����B
�@���Ȃ�傫�߂̃��j�b�g30?38CM�̕��܂ŃV���[�Y�ł���܂����B
�@TANNOY�Ɠ����Ń{�C�X�R�C�������L�����R�[���{�z�[���̃��j�b�g�C�ɓ����ċ����悤��
�@�L��������܂��B
redfodera����
�@�a���n���i��I�͕̂ʂꂽ�ł���ł����B
�@�u�s�f�v���O�Ō����͂����̂ł����A�Q�N��THE-END�B
�@�Ⴂ�ł���́A�Ȃ��Ȃ��u���_�����ڗ����v�������悤�Ɏv���܂��B
�@���E����ȓS�̉�̖ڗ������I�[�f�B�I���i��V�������Ɏ������ނ��Ƃ�f�ŁI
�@���ۂ���܂�������ˁB
�@���̂Q�N�O�オ���̐l���ň�ԁu���������v�Ɉ͂܂�Ă��������ł����B
�@�����A�u�ł���v�͕ʂł��B
�����ԍ��F7882548
![]() 0�_
0�_
�@������ցB
�@�܂������̂ł����H�@���ꂪ���̃X���b�h�ɂ����āA�A�i�^�ɑ���Ō�̏������݂ɂ������Ǝv���̂ŁA�悭�����Ȃ����B
�@���́A���g�̌����������ƁE��`�咣���ؓ����Ăė��o���Ȃ��悤�Ȗ��n�Ȍ�m�Ƃ͂܂Ƃ��Șb�����������鉿�l�����o���܂���B�O��̃A�[�e�B�N���ŃA�i�^�ɂ̓n�b�L���\���グ���͂��ł��B�A�i�^�́u���������v�̂ł��B�̖̂���̎�l���̃Z���t�����Ȃ�u���O�͂�������ł���v�ł��B
�@����̓A�i�^�ɑ����排����Ƒ����Ă��܂��������܂��܂���B�ꍇ�ɂ���Ă̓A�i�^���{�[�h�����ǂɋ������Ă��̏������y�т��̃X���b�h�̏����𗊂�ł��A���������ɋC�ɂ��܂���B�ǂ�������Ă��������B�����Ȃ�����A�ĂуX���b�h�𗧂��グ�ă��O���A�b�v�������݂̂ł��i�������A�A�i�^�����������݂͏Ȃ�����łˁj�B
�@������������ё��̎Q���҂ɑ�������ė~����������A�A�i�^�̓A�i�^�́u�I�[�f�B�I�P�[�u���Ɋւ��Ďv�����Ɓv���u�_���I�Ɂv�u������₷���v�u�o����Θ_�_���ӏ������Łv�L�q�����g�s�b�N��ʂɗ����グ�āA�F�ɖ₤���Ƃł��i���������A�˂��������Ă����̂̓A�i�^�̕��ł�����A�o���Ȃ��Ƃ͌��킹�܂���j�B���ꂪ���X����ɒl����Ǝv�����Ȃ�A���͑�������Ă����܂����A���̎Q���҂���̃��X���t���ł��傤�B�t�Ɍ����A�A�i�^�����O�̕ʃg�s�b�N�ɘb���ڂ��Ȃ��ŁA���܂ł����̃X���b�h�ŃO�_�O�_����Ă����A�َE������Ă��Ƃł��B
�@�ȏ�B��낵���B
�����ԍ��F7883313
![]() 1�_
1�_
�@AIWA�i�A�C���j�ɂ��ď����Ă݂܂��傤�B�n����1951�N�ł����炯�������Â��ł��B�A�C��������Ђ𖼏�����̂�1959�N�B���{�ŏ��߂ăJ�Z�b�g�e�[�v���R�[�_�[�\�������ƂŁA���̕���ł̐擱���ɂȂ�܂��B
�@����AIWA�ɑ���C���[�W�͉��Ƃ����Ă����W�J�Z�ł��B���܂ʼn��䂩�̃��W�J�Z���g���Ă��܂������AAIWA�̃��W�J�Z�͈��|�I�ɉ����ǂ������ł��BSONY�⏼���̃��W�J�Z���X�����ʂ�_�����悤�ȍ��拭���^�������̂ɑ��AAIWA�͒��ɏd�S��u�����s���~�b�h�o�����X�̉�����ł����B���̂����������₷���O�������܂���B���ɃN���V�b�N��炷�ƈ��S���ăn�}��܂����B
�@�J�Z�b�g�f�b�L�ł����т�����Ă��܂������A���̈�ۂɎc���Ă�����̂�70�N�㔼�ɔ��\���ꂽ�艿5���~�قǂ̃��f���ł��i�^�Ԃ͎��O�j�B�]���ʂ��1���[�^�[���ł����A����L�[�̊��G�������قǃX���[�Y�ŁA�d�����Ȃ��܂��_�炩�����邱�Ƃ��Ȃ��A�▭�ȃ^�C�~���O�œ����Ă���܂����B1���[�^�[���ł������܂ŏo����̂��Ɗ��S�������̂ł��B
�@�o�u������AIWA�̓~�h���N���X�̃s���A�E�I�[�f�B�I���i����ɎQ�����Ă��܂��B���ꂪEXCELIA�i�G�N�Z���A�j�Ƃ����u�����h�ł��B�ł��A�����Ȑ��i�ł��������Ƃ͔F�߂����܂�ɂ��v���̃f�U�C���͎s��ւ̃A�s�[���x�Ɍ����A�������Ă��܂���B
�@AIWA��2002�N��SONY�̎q��ЂƂȂ�����A���U���Ă��܂��B���Y���_���C�O�ɒu����R�X�g����_�������̂́A���ǁu�����낤�A�����낤�v�̐��i�W�J�����o���Ȃ������̂������Ƃ������Ă��܂����AAKAI�Ɠ��l�f�W�^������ɏ���Ȃ������̂��傫�������̂ł��傤�B�ł�����EXCELIA���s�����������Ƃ����������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�V�i�u�����h�Ȃ����炵���A�f�U�C�����܂߂đ��̘V�ܐ�僁�[�J�[�Ƃ͂܂������Ⴄ�R���Z�v�g���ϋl�߂�K�v������܂����B������s��Ɉ�ۂÂ��Ď��т�������f�W�^������ł��l�ނ��W�܂�A������ۂ�����������܂���B
�����ԍ��F7883346
![]() 0�_
0�_
���E�������A���ӂ́B
�@AIWA�Ŏv���o���̂́A�u�}�C�N���t�H���v�ł��ˁB
�@�w���o���h������Ă������A���K�Ɏg���Ă����̂�AKAI�̃e�[�v�f�b�L�ƖႢ����
�@AIWA�̃}�C�N�ł����B
�@�S�l�Ґ��̃o���h�ōŒ�R�{�A�펞�T�|�U�{�̃}�C�N���~�L�T�[��ʂ���2CH�X�e���I��
�@���Ę^�����Ă��܂������A���̓��̂Q�{��AIWA�ł����B
�@���̌�́u�e���r�f�I�v�H���Ȃɂ�14�D�ʂ̃e���r��e�����g���Ă����L�����B
�@SONY�ɋz�����ꂽ�̂ł����H�m��܂���ł����B
�����ԍ��F7883913
![]() 0�_
0�_
�|�� 130theater����
�@�������A�܂���CRYSLER���[�U�[�͂��̃{�[�h�ł͂���������Ȃ����낤�Ǝv���Ă�����A�g���Ă܂������B�{���ɉ��͈�ۂ͔����ł��B��������ȉ��ł��������Ƃ͊m���Ȃ悤�ŁA�����̃I�[�f�B�I�G���ŕ]�_�Ƃ��悭���߂Ă����悤�ȋL��������܂��B����ƁA�������j�b�g���z�[���^�������������A�J�^���O���������₽��\���͍����������Ƃ��o���Ă��܂��B
�@�����g��Ȃ��Ȃ����@��͐̂͂悭�����ɏo���Ă܂����ȁB�ŋ߂ł͒��É��Ɏ����čs������m�l�ɏ������肵�Ă��܂��B���������Ζ^���Ɠd�X�̓X���ɐ́u�E�`�͉����Ȃ�Ă���ĂȂ���B�����A���\�ł͂���Ă���āH�@���q����A�E�\�͊��ق��Ă�B�Â��̂����Ƃ������������玿���ɂł������Ă�����H�@��������ƃE�`�͒l������1���܂ł�����ˁv�ƌ���ꂽ���Ƃ�����܂��B���̉Ɠd�ʔ̓X�͂������ɍ��͐��Ԃ̑�����x�̒l�����͂���Ă���悤�ł����A�X���̑ԓx�͐̂̂܂܂ł��B�����Е����Ă̂͗e�Ղɐ����Ȃ����̂ł��ˁB
�|�� redfodera����
�@CRYSLER�̓Z�p���[�g�X�e���I�͏o���Ă��Ȃ������悤�ł����A������ɂ��냌�g���ȃf�U�C���ł����iPerfect�V���[�Y�͋t�ɒ����_���ł������j�B���ł̓l�b�g��ɂ����܂���͎c���Ă��܂��A�{���Ɂu��̃��[�J�[�v�ł��B��������GUYATONE�Ƃ����̂�����܂����ˁB��x�͒����Ă݂��������̂ł����A���̊Ԃɂ������Ă��܂����B
�@���^�̃G�b�W�Ŏv���o�����̂ł����A70�N�㔼��ONKYO����x�������^�̃h�[���^���j�b�g�𓋍ڂ����X�s�[�J�[��o�������Ƃ�����܂����B���̌�b���Ȃ��Ƃ��������ƁA���ʂ͗ǂ��Ȃ������̂ł��傤�i���^�̃h�[���^���̂͑��ɍ̗p���Ă��郁�[�J�[������悤�ɕ����Ă͂���܂��j�B
�|�� �l�I���W����
�@AIWA�̓}�C�N���t�H�����o���Ă����̂ł����B�m��܂���ł����B����������AIWA�̃��W�J�Z�̕t�������}�C�N�́A�����[�J�[�̃��W�J�Z�̓����}�C�N��芴�x����ǂ��������Ƃ��v���o���܂����B
�@CORAL�ɂ��Ă��������Ǝv���Ă����̂ł����A�l�I�ɂ��܂��ۂ��c���Ă��Ȃ��̂Œf�O���܂����i�����܂���j�BCORAL��70�N�㏉�߂ɏo���Ƃ����o�b�N���[�h�z�[���^�̃X�s�[�J�[���������Ƃ�����܂��B���͒����Ă��܂��A�]�_�Ƃ̘b�ɂ��Ɓu���D���ɂ͂����Ă����v�������Ƃ��B�����������S�j�́u�o�b�N���[�h�z�[���^�����o�����X�̗ǂ��G���N���[�W���[���I�v�Ǝ咣���Ď���X�s�[�J�[�ɂ��̎�@��ϋɓI�Ɏ�����Ă����悤�ł��B�Ȃ��ACORAL��X�V���[�Y�Ƃ�DX�V���[�Y�Ƃ��͒����Ă͂���܂����A���̍��̎��ɂƂ��ē��M���ׂ����̂͂Ȃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B
�@����ɂ��Ă��A��x�ŗǂ�����uB&O�̃V�X�e�����������Ɓv�ɏZ�݂������̂ł���܂��i�j�B
�����ԍ��F7883981
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
AIWA�͎������W�I�ƃ��m�����̃��W�J�Z�ł����b�ɂȂ�܂���m(_ _)m
���W�I��FEN�Ɛ[��������A���W�J�Z��FM���J�Z�b�g�ɗ��Ƃ��Ă܂����B
���W�����[�E�X�e���I���䂪�Ƃɗ���܂Ń��R�[�h�����Ƃ��ł��܂���ł�������A
AIWA�̂������Œ��w�Z3�N�Ԃ̗m�y���n�߂̒ʐM�������u�ł����l�Ȃ��̂ł��B
���W�����[�E�X�e���I���Ђ���Ƃ�����AIWA�����������E�E�E
���E�������
�����^�̃h�[���^���̂͑��ɍ̗p���Ă��郁�[�J�[������悤�ɕ����Ă͂���܂�
�t�h�[���E�c�B�[�^�[�͑����̃��[�J�[���������Đ������܂������A���炭�ł��L���Ȃ̂�FOCAL�i���j�ł��傤�B
���Ќn��ł��g���Ă��܂��������j�b�g���������Ă܂����̂ō̗p���Ă����u�����h�����i�͑����͂��ł��B
������ƑO�̃��f���܂�Acustik-Lab�uBolero�v�����F���t�h�[���E�c�B�[�^�[���̗p���Ă܂����B
�����audio-style����A��p�B�������͂��ł����E�E�E���z��@���ɁH
���Ȃ݂ɓ����A���^�G�b�W�̔�r�I�ŋ߂̐v�ɂȂ�SP���j�b�g��1�y�A�������߂Ă���܂����B
EU�e���̃u�����h�Ƀ��j�b�g�������Ă���AUDAX�i���j�Ƃ������[�J�[�̃��m�ł��B
�|�Y�̗J���ڂɂ��������[�J�[�ł����A�}篁A�������ꂽ�̂�m��Q�ĂĒ��B���܂����B
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=120&products_id=101
�ʐ^�ł͂�����ƕ������ł�������̉��^���o�[�E�G�b�W�ŐU���͂��Ȃ菬�����ł��B
�t���[�������łŃG�l���M�[����������~�߂�悤�ɂŏo���Ă܂��B
��N����A���̎n�܂���QUAD��2Way�V���[�Y�̃g�b�v�E���f��������SP���j�b�g���̗p���Ă܂����A
����Ȃ�ɐl�C�ɂȂ肻���Ȃ̂ɉ��̂��g�b�v�E���f�������͐��K�A���̑Ώۂ���O����Ă܂��B�ʗd�ȁE�E�E
������ɂ��Ă��A��x�ŗǂ�����uB&O�̃V�X�e�����������Ɓv�ɏZ�݂������̂ł���܂��i�j�B
�I�u�W�F�݂����Ȃ��̂ł����A�ʂɍ\����K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E
�ނ���p�����������Ȃ��O���X�E�g�b�v��CD�g���C�̃C���[�W��^�����~�j�R���|���e�Џo���Ă܂����ˁB
http://www.marantz.jp/ce/products/life/personalcd/cr201/index.html
http://www.teac.co.jp/audio/teac/cdx10i/index.html
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/view/B9F6C0901ED7ED454925730E000F13A7?OpenDocument
http://www.nakamichi.co.jp/audio/ss-5/SS51.htm
�����ԍ��F7885591
![]() 1�_
1�_
�@YAMAHA�ɂ��ď����܂��B�y�탁�[�J�[�Ƃ��Ă̑n���͂��Ȃ�Â���1888�N�ɂȂ�܂��B�I�[�f�B�I�@������n�߂��̂͂��Ȃ̂̓n�b�L���Ƃ͕�����܂���B������ɂ��Ă��y��ƃs���A�E�I�[�f�B�I�@��Ƃ𗼕���|���郁�[�J�[�͒������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ɂ̓I�[�X�g���A��Bosendorfer���炢�����v�����܂���i�܂��A�����m��Ȃ������ŁA���ɂ�����̂�������܂��� ^^;�j�B
�@YAMAHA�̃I�[�f�B�I�@��ōŏ��Ɉ�ۂɎc�����̂́ANS-690�Ƃ����X�s�[�J�[�ł��B73�N�ɔ������ꂽ�Ƃ������Ƃł����A�����ڂɂ����̂͂��ꂩ�琔�N�o�������ł��B���̃G���N���[�W���[�Ƀ\�t�g�h�[���𓋍ڂ���3�E�F�C�B�S�c�S�c�������b�N�X�����𗘂�����I�[�f�B�I���i�̒��ɂ����āA���̗D���ȊO���ٍ͈ʂ�����Ă��܂����B�����g���}�n�E�r���[�e�B�[�h�Ƃ����G�ꍞ�ݒʂ�̔������B���ꂩ��Ԃ��Ȃ����nj^��NS-690II���������Ƃ��o���܂������A���̕�����������w���t�@�C�����ꂽ�悤�Ȋ��z�������܂����B
�@NS-690�Ɠ������ɔ��\���ꂽ�̂��A���v��CA-1000�ł��B������܂��z���C�g�d�グ�̃A���~�p�l������ۓI�ȏ�i�ȃ��b�N�X�ŁA��������ɏ���������̂ł����B�ŋߏo��A-S2000�͂��̃V���[�Y�̕����łƂ̈ʒu�Â��ł��傤�i�������A���g�͈Ⴂ�܂����j�B
�@������YAMAHA�́g���}�n�E�r���[�e�B�[�h�̃��C���i�b�v���葵���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�Ɩ��p���i�̗�������ގ��������ȃe�C�X�g�̃��f���������[�X���Ă��܂����B���̑�\��NS-1000M�ł��B���Ɂg�Z�����j�h�ƌĂꂽ����F�̑�^���j�^�[�X�s�[�J�[�͐����ƒ������Ԃɂ킽���č���A�u����v�ƌ���ꂽ���̂ł��B�܂��A���^���j�^�[��NS-10M�͊e���̃X�^�W�I�ł��L�͈͂Ɏg��ꂽ�悤�ł��B���̑��A�Z�p���[�g�A���v�⍂��CD�v���[���[�A����ɂ͒P���̃X�s�[�J�[���j�b�g����|���A�I�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ��Ă̑S������YAMAHA�̓t�����C���Ő��i�𑵂��Ă��܂����B
�@�����g�͂ǂ����Ƃ����A�g���}�n�E�r���[�e�B�[�h�͎������J��Ԃ������ɖO�������Ă��܂��ANS-1000M��NS-10M��������ł̓t���b�g�߂��Ă��܂�ʔ����Ƃ͎v���܂���ł����i�I�[�i�[�̕��X�A�ǂ��������܂���j�B���Ђ̐��i���w�������͈̂��݂̂ł��B����̓A�i���O�v���[���[��GT-2000�ł��B�܂���CD���s�������l��������80�N��㔼�Ƃ��������ŁA���Ƃ��Ă��g�A�i���O�v���[���[�̓����́A���ꂪ�Ō�I�h�ƌ�����Ŕ����܂����B28kg�Ƃ����d�ʂɂ�������炸�A���i��138,000�~�ƃ��[�Y�i�u���B��������炱�̉��i�ł͐�Ώo���܂���B�{�@��ɂ͑����̃I�v�V����������܂������A�����܂����B�����̂�DC�p���[�T�v���C��YOP-1�ł��B�m�[�}���d�l�ł̓v���[���[�{�̂̒�~�X�C�b�`�������Ă��^�[���e�[�u���͊����ʼn�葱���A��Ŏ~�߂邱�Ƃ���������イ�������̂ł����i�j�AYOP-1�p����Ǝ葁����~���Ă���܂����B����ɂ킸���ł������̖��x���������̂��v��ʌ��ʂł����B�z�����f�B�X�N�E�X�^�r���C�U�[��YDS-1����ɓ���܂������A����ɂ͖ڊo�܂����������オ����܂����B�������c�O�Ȃ���S���̕������{���{���ɂȂ�A���ł͉����̉��Ɏd�����Ă��܂��B���ɂ��C�����^�[���e�[�u����A���J�[�u���b�N�Ȃǂ̒��W���A�N�Z�T���[�����݂��Ă��܂������A�ݒu�X�y�[�X�Ə��̋��x�̊W�ōw����f�O���܂����B
�@GT-2000�ɂ͕ʔ���ŃX�g���[�g�A�[�����t�����܂������A�^�]�_�Ƃ��l�Ă����u���A���E�X�g���[�g�A�[���v�i�H�j�̂悤�Ȃ��̂����i������܂����B�������A�����A�[���̃N�H���e�B�ɂ�����ƕs���������Ă��āA�Ȃ����X�g���[�g�A�[���̓J�[�g���b�W�����̍ۂ̎g�����肪�����Ǝv���Ă��������������̂́ASAEC��GT-2000�p�Ɍ��蔭������WE-407/GT�Ƃ����@��ł��B����SAEC�̓P�[�u����d���p�[�c�̃��[�J�[�ł����A���̍��͍����L���̃g�[���A�[���̍���Ƃ��Ēm���Ă��܂����BWE-407/GT�̓������ʂ͈��|�I�ŁA�𑜓x�����S�Ƀ��������N�オ��܂����B�A�[���ł����������ς��̂��Ƃт����肵�����̂ł��B
�@�c��p�i�H�j�Ǝv����g���}�n�E�r���[�e�B�[�h�̕��������\�ł����A�A�i���O����������Ă��鍡�AGT-2000�V���[�Y�����A���j���[�A���������Ăق����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7888794
![]() 0�_
0�_
���E�������
���}�n�ł��ˁA���͎��̎o����̂ł����u���{�y��v�ɋ߂Ă��܂����B���̍��A�o���Ј������Ń��W�����[�X�e���I�����̂ł����A���ꂪ���̃I�[�f�B�I�̎n�܂肩���m��܂���B�J�[�g���b�W��MM�^�Ƃ�IM�^�Ƃ����X�y�b�N�\�ɏ�����Ă��āA���̎����낤�H�ƒ��n�߂��������肩��I�[�f�B�I���̎n�܂肩���m��܂���B
���̃X�e���I�̓��R�[�h�v���[���[�ƃ`���[�i�[�ƃA���v����̂ŁA�s�A�m�̌`���������A�X�`���[���H�̂��Ȃ��^�̐U���̃X�s�[�J�[�ł����B�ł��t���[�G�b�W���Ȃ��U�����傫���́A�G���N���[�W���[���]��v��Ȃ��Ƃ������v���ƕςȃX�s�[�J�[�ł����B
NS-690�͂��̕ςȌ`�̐U�����~�߂āA���߂ă��}�n�̃X�s�[�J�[���F�߂�ꂽ�X�s�[�J�[�ł͂Ȃ��������ȁH�Ǝv���܂��B�Z��NS-690�U�����Ǝv���܂��B
���͂���NS-1000M�ƃe�N�j�N�X��SB-7000�̂ǂ���������\�Y�݁A���������Ȃ肵�܂������e�N�j�N�X��SB-7000(�e�N�j�N�X�V)�ɂ��܂����BNS-1000M�̓T�����l�b�g���Ȃ������ƍ����̃X�s�[�J�[���x�����E���ł����ˁB�x�����E���Ȃ�f�ނ��n�߂Ă�������m��܂����B
AV�A���v��AVX-2200DSP���w�������̂����߂Ƃ��āA���}�n��AV�v�����C���̍ō��o��x�ɔ����ւ��܂����BDSP-A3090�E�EDSP-A1�E�EDSP-AX1�Ƃ���DSP-AZ1�ɂȂ������A���i�������Ȃ肱�̎��̓p�C�I�j�A��VSA-AX10�ɂ��܂������A�ǂ������ɂ͍��킸1�N�Ńf�m����AVC-A1SR-k�ɔ����ւ��܂����B�������A�f�m�������ꏈ�������}�n�ɓG�킸DSP-Z9���������ꂽ�̂Ŕ����ւ��܂����B
�E�E�E�����č��N�A�u���[���C�̃t�H�[�}�b�g�ɑΉ�����DSP-Z11(B)���������ꂽ�̂ōĂє����ւ��܂����B���̑��̃��}�n���i�̓Z���^�[�X�s�[�J�[��1���܂����B�V�X�e��2��NS-225�Ƃ����X�s�[�J�[���܂������A���������ɂ̓_����3�����Ŕ����ւ��A�r�N�^�[�̃E�b�h�R�[���X�s�[�J�[�ɂ��Ă��܂��܂����B���̃V�X�e��2�̃T�u�E�[�t�@�[�����}�n��YST-SW515���܂������A������͕s���Ȃ��Ŏg���Ă��܂��B
�����ԍ��F7889915
![]() 0�_
0�_
������������܂��B
�@����1967�N7�� �̃��C�g�~���[�W�b�N�R���e�X�g(�|�v�R���̑O�g)���ɂł�����
�@YAMAHA�Ƃ̕t���������n�܂�܂����B
�@130theater����̋�(���A�X�`���[������SP�j�����̋L���ł�YAMAHA�I�[�f�B�I���i
�@��ꍆ��NS�X�s�[�J�[�������Ǝv���܂��B
�@���o���܂̂������ɂȂ����V�X�e���X�e���I�͂��̖����uNS�X�e���I�V�X�e���v
�@�ƌ������O�������Ǝv���܂��B
�@����̃��}�n�{�X�ɏ����Ă������̂��o���Ă��܂��B
�@���̍��̂��X�ɂ͍����I�[�f�B�I�́u�������v���E���̕��ɂ���܂��ĊC�O����
�@�A���v��SP���������悤�Ɏv���܂��B
�@�ŏ���YAMAHA���i�����̂�CA-1000�ł����B
�@���ł����L���Ă��܂����A��CH�m�C�Y������܂܂́u�W�����N�v��Ԃł��B
�@���̔������Ɏ̂Ă邱�Ƃ��o���Ȃ��ł��܂��B
�@NS-10��DTM�p�̃��j�^�[�Ƃ��Ē����g���Ă��܂������A�F�l�ɏ��n���Ă���A
�@YAMAHA���i��V�K�w���͂��Ă��܂���B
�@DTM�p�A���v�ɐ��艺�����Ă��܂����ADSP-3090�����݂ł����������T����CT-700�����H
�@FM�`���[�i�[������͂��ł����E�E�E�E�E�E�E�B
�@GT-2000���~���������̂ł����A���̓����͊��Ƀ}�C�N���̎��h���C�u�H�̃v���[���[��
�@����܂��āA�������ɂ�THORENS�������ɂ���܂���ł����ˁB
�@Z-11����������������A5300�͔���Ȃ������̂ł����B
�@YAMAHA��DSP�͍D���Ȃ�ł��B���A�p���[���ɂ����s��������܂��āB
�@Z-11�̃v���A���v�����̂ݔ����Ă���Ȃ����ȁ`�H
�����ԍ��F7890549
![]() 0�_
0�_
�@�@�@�@���͂悤�������܂��I
���}�n�ƌ����Ǝ����̒��ł̓��}�nDSP
(�����ă��}�n�ł̓f�W�^���E�T�E���h�t�B�[���h�E�v���Z�b�T�[�ƌĂ�ł���)
����ԋ���Ȏv���ł݂Ă��܂��B
DSP-1���������ꂽ�����C�C�i�[�Ƃ͎v���Ȃ��牡�ڂŌ��Ă�����DSP-100�ƌ������Ɉ�����
(�m��\89800?)�ȃv���Z�b�T�[���o���̂ő����w���AQSD�[1000�Ƃ̕�����ׂ�A���s���Ă����̂����������v���o���Ă��܂��B
�ł������I�ɂ�QS�̕�����I�����v���Z�b�T�[�P�̂Ŏ�Ԍ������Ē����Ȃ�Ƃ������Ŕ��N���炢�Ŏ藣���܂����B���������̌�o�Ă����̂�����7�`�����l��CINEMA-DSP�d�l��AVX-2000DSP�ł����ˁB
����Ń��}�n�Ǝ��̃t�����g�G�t�F�N�g(���v���[���X)�@�������h���r�[�A�v�����W�b�N���̉f��Đ��A���y�Đ��̑��Ђł͑S�����킦�Ȃ����ꂪ�o�������̂̓��}�n�g�p�̕��X�Ȃ�A�����m�̎��ł����B
DSP-100�ł��t�����g�G�t�F�N�g�͎g���܂������f��̓h���r�[�T�����h�̂݁I
����AZ-1�̂܂܂ŁA�Ȃ�Ƃ��������ȂƂ͎v���Ă܂��B�@�l�I���W�����
��Z-11����������������A5300�͔���Ȃ������̂ł����B
���l��Z-11�͍�����(>_<)�����ꎞ5300�w���ɌX�����̂ł����E�E�E�B
Z�[7�o�^�Ԃ́H�p�����������̂ł͂Ȃ����I�H�ƌ�������̃X���ɏo�Ă��܂��̂ŁA
�����͂�������҂��Ƃɂ��悤���ȁH�Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F7890708
![]() 0�_
0�_
�|�� redfodera����
�@FOCAL_JMlab���t�h�[���ł������B���̑O���������̂ɁA�����܂ł͋C�t���܂���ł���(^^;)�B���̃��[�J�[�̃X�s�[�J�[�́A�t�����X��������Ƃ������Ƃł��Ȃ��̂ł��傤���ǁA�t�����X�����݂����ȉ����Ǝv���܂����i���j�B�g�����Ƃ��Ă���̂ɃL��������B���������D�݂̉��ŁA���ɃX�s�[�J�[���X������ۂ̌��ɂȂ肻���ł��B
���O���X�E�g�b�v��CD�g���C�̃C���[�W��^����
���~�j�R���|���e�Џo���Ă܂�
�@����炪�u�O���X�E�g�b�v�̐��i��P���I�ɏo���������v�ł���̂ɑ��AB&O�͐��V���b�v���\����ȂǁA�u�����h�ɂ�鍷�ʉ���C�t�X�^�C���̒�Ăɂ܂ŏ������悤�Ƃ��Ă���_�����S�ɈႤ�Ǝv���܂��B�s���A�E�I�[�f�B�I�����̂ЂƂ̃��f���Ƃ��āA�������[�J�[���������ׂ��|�C���g�ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂ւ�Ɋւ��ẮA����܂��������ނ���ł��B
�|�� 130theater����A�l�I���W����Asatoakichan����
�@YAMAHA�Ɋւ��Ẵ��X�A���肪�Ƃ��������܂��B
�@�]�k�ł����A���͎q���̍��Ƀ��}�n���y�����ɒʂ��Ă������Ƃ�����܂��B���w�Z�ɏオ��O�������Ă܂�������A�������o������y���̌������o��������悾�����悤�ȋC�����܂��i�j�B�Ƃ��낪���w�Z2�N���̎��ɉ��y�����Ȃe���`���Ȃ��h�c�ɂɓ]�Z���A���̍ۂɓd�q�I���K����������Ă��܂����悤�ŁA����ȗ��I�b�T���ɂȂ������Ɏ���܂Ŋy�퉉�t�ɂ͉��̂Ȃ����������[���Ƒ����Ă��Ă��܂��܂����B����ł��u���������̂܂܉��y�����ʂ��𑱂��Ă���E�E�E�E�v�Ǝv�����Ƃ�����܂��B��N��́i���܂��܂���̘b�ł����� ^^;�j�V�j�A�����̉��y�����ɑ����^��ł݂悤���ȁE�E�E�E�Ȃ�Ă��Ƃ����X�l���Ă��܂��B�X���b�h�ƊW�̂Ȃ����Ə����ăX�C�}�Z���B
�����ԍ��F7893279
![]() 0�_
0�_
���E�������A���ӂ́B
�@���E�������́u�L�[�{�[�h�v���܂߂�ƁAredfodera����̃x�[�X�A���̃M�^�[��
�@�ЂƂ܂��́u�s�q�h�n�v�̊����ł��ˁB
�@�����̂n�E�s�[�^�[�\�����m�E�L���O�R�[���Ɠ����ł��B
�@�ǂȂ������̕��ŁA�w������u���o���Ƃ�����o�g������O�����e����Ƃ��������
�@�u�����w���ەۑ���v�Ƃ��̃����o�[�̕��ł�����������A�u�I���W�o���h�v
�@���������ł͂Ȃ������ł��ˁB
�@������A������B�b���ǂ�ǂ�O��Ă��܂��܂��ˁB
�@�Ǘ��l����A�����ق��I
�����ԍ��F7894146
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
���̏ꍇ�AYAMAHA�͊y��ł���ւ���Ă��ăI�[�f�B�I�@�ނ����O�ōw���������Ƃ�����܂���B
NS-1000M��M���ɂ₯�ɍd���ȉ��ɒ������Ă��܂��ĐG�肪���������Ƃ�����܂���ł����B
�F����^����YAMAHA��DSP�ɂ��čl���Ă݂��̂ł����A���̃I�[�f�B�I�E���[�J�[�ƍł��قȂ�̂́A
��͂�y��i�V���Z�T�C�U�[�j�ƃX�^�W�I�p�G�t�F�N�^�[�̋Ɩ��@�œƓ��̃f�W�^���Z�p�������Ă���_���Ǝv���܂��B
YAMAHA�̓V���Z�T�C�U�[���t�������琻���ɒ��肵�Đ��E�I�ɂ��x�����W�߂Ă����̂ł����A
�g�s�b�N�X�͂�͂�CD�̓o��Ǝ��������ďo������DX7�V���[�Y��FM�ϒ��t���E�f�W�^���Ő��E��Ȋ����܂����B
�V���Z�T�C�U�[���x����̂̓V���Z�V�X�Z�p�ƃJ�X�^���E�`�b�v���ɂ��܂��B
1�䐔�S���ł͎����������Ȃ���Œቿ�i���������邽�߂ɂ͌o�ύ����I�ȃJ�X�^���E�`�b�v���삪�s���ł��B
����Ɍĉ�����l�Ɋy�퐢�E�ł͋}���Ƀf�W�^���E�G�t�F�N�^�[�����y���n�߃V���~���[�^�[�I�ȋ@�킪�������܂��B
�z�[���E�A���r�G���X�n�G�t�F�N�^�[��DSP�ƌĂюn�߂��̂����傤�ǂ��̎����ɂȂ�܂��B
�A���r�G���X�n�G�t�F�N�^�[�ł�YAMAHA��LEXICON�i�k�āj���o���ŁA���������ߒ��ŏn�����i�ݍ����Ɏ���킯�ł��B
�E�����܂����A����ALEXICON��DSP�A���S���Y�����g����YBA��2nd�u�����h��AV�v���A���v�����܂����B
���Ȃ݂�LEXICON��YAMAHA�ƈقȂ�A���S���Y�����I�[�f�B�I�E���[�J�[�e�ЂɍL�����Ă��܂��B
���ЂŐ��i���������ŁAKRELL�AMYRIYAD�AGOLDMUND���ނ�̃A���S���Y�����̗p���Ă���l�ł��B
http://www.electori.co.jp/lexiconmv-5page.html
YAMAHA���ςݏd�˂��V���~���[�g�Z�p�ƃJ�X�^���E�`�b�v�ւ̗��Ƃ����݂̃m�E�n�E�Ɋւ��ẮA
���̃I�[�f�B�I�E���[�J�[���ǂ��������ł����炭�e�Ղł͂Ȃ����낤�Ɛ������Ă܂��B
�J�[�I�[�f�B�I��DSP�����p�����Ǝ��H����L����Pioneer���炢�ł��傤���E�E�E
30�N�ɂ��y�ԗ��j���A�F����̕]���Ɍ��т��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���E�������AB&O�̊����y���݂ɂ��Ă��܂��B
��FOCAL_JMlab���t�h�[���ł������B���̑O���������̂ɁA�����܂ł͋C�t���܂���ł���(^^;)
SP���j�b�g�E���[�J�[�Ƃ��Ă��傫�Ȏ��т̂��郁�[�J�[�ł��������̃I�[�f�B�I�@��ł͋v�X�̏㗤�ł��ˁB
�ȊO��ȊO�A�J�[�I�[�f�B�I��SP���j�b�g�̔��ł͍����ł��ƂĂ����т�����A�����m�ł͂��Ȃ�傫�ȃV�F�A�������܂��B
�����Ŕ̔������l�ɂȂ���20�N�߂��Ȃ��ł����A��ނ������t�@���w�������Đl�C������܂��B
http://www.focal.tm.fr/
�f�ނ��Ǝ��̃m�E�n�E������A�E�[�t�@�[�ł̓|���O���X�i�O���[�̃X�g�[�����j�Ƃ����̂��L���ł����A
130theater�����NS-1000M�ł����b�̂������x�����E�����c�B�[�^�[�ő��p���Ă܂��B
�������ꂽ���z�̒ʂ�A�p���W�����ȃG�X�v�������������鉹���ł���ˁB
�����ԍ��F7894261
![]() 1�_
1�_
�@���͂悤�������܂��I
�l�I���W����̒E���Ɋ��ŎQ�������Ă�������(^^)
���ǂȂ������̕��ŁA�w������u���o���Ƃ��E�E�E�E�E�u�I���W�o���h�v
�@���������ł͂Ȃ������ł��ˁB
�́A�̂���Ƃ���ɁE�E�E�@�ł͂Ȃ������I
�O���[�v�T�E���h�S���̎����A��������Ă���܂�����[
�|�W�V�����@�h�����X�@�r�O�̓z�[���V�A�^�[�A����y�Z�b�g���x�I�H
���������b�ɁA�����u�I���W�o���h�v���b���o�Ďv�킸�����I�����܂���ł����B
�����ԍ��F7894847
![]() 0�_
0�_
satoakichan����A������������܂��B
�@�ނ��Ă��܂����悤�Ő\����܂���B
�@�b��U�������ɁA������Ԓ�x���̃~���[�W�V�������ۂ��āE�E�E�E�E�B
�@�����������o���h�͂ǂ��炩�Ƃ����Ɓu�R�~�b�N�o���h�v�ɂȂ�X���������悤��
�@�v���܂��B
�����ԍ��F7894879
![]() 0�_
0�_
�F����A�������������܂��B
�l�I���W����Asatoakichan����A���E�������A�o���h�^���ł��I
�n���h���E�l�[���̐Ԃ�FODERA�̂T���x�[�X�g���܂�����c
����̃t�B���K�����O�̃G�N�Z�T�C�Y���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
satoakichan����A
���O���[�v�T�E���h�S���̎����A��������Ă���܂�����[
�܂��͂ǂ�GS�̃R�s�[�������܂��傤���B
TESCO�̃��Y���C�g�^�̃x�[�X���̂Ƀt���[�E�}�[�P�b�g�łR��~�Ŕ����Ď����Ă܂�
��x���o���h�Ŏg�������ƂȂ��̂ŁA���̋@��ɐ���I
�}�b�V�����[���E�J�b�g�ɂ���̂ɗE�C������܂���(^^�U
�l�I���W����
�������������o���h�͂ǂ��炩�Ƃ����Ɓu�R�~�b�N�o���h�v�ɂȂ�X���������悤��
�@�v���܂��B
�N���C�W�[���h���t�������y�펝�������甼�[����Ȃ��ł�����A�ނ����ς����B
���R�z�b�g�u���U�[�X�̃m�R�M���E�l�^����s���܂��傤�I
�����ԍ��F7894934
![]() 1�_
1�_
�@�{���́u����v��KEF�ł��B���[�J�[����Kent Engineering & Foundry�̗��ŁA�{�Ђ̓C���O�����h�̃P���g�B�ɂ���܂��B�n����1961�N�ł����A��Ɏ҂̃��C�����h�E�N�b�N��BBC�̃G���W�j�A���������Ƃ��ŋߒm��܂����BLS3/5a�Ȃǂ̃X�^�W�I���j�^�[��BBC�Ƃ̃R���{���[�V�����ɂ���č��o���ꂽ�Ƃ����킯�ł��ˁB
�@���Ђ̐��i�͎����Ⴂ���ɃV���b�v��I�[�f�B�I�t�F�A�Ȃǂʼn��x���������Ă��܂��B�������A���̓����͂܂������ǂ��Ƃ͎v���܂���ł����B�g���Y��������DIATONE�A�C�O����JBL�I�h�Ƃ�������ɁA���������p�L�p�L���ƑO�֏o�鉹�����F�߂Ȃ��������́AKEF���܂߂����ׂẲ��B���X�s�[�J�[��ے肵�Ă��܂����i�{���͉��B���ł��X�N�G�A�[�ȃT�E���h���o���@��͂������̂ł����A�����͂���Ȃ��Ƃ͒m�炸�A�S��KEF��TANNOY�݂����ȉ����Ǝv���Ă܂����B�܂����������ăA�z�ł��� ^^;�j�B���ɓ��Ђ̑ȉ~�`�̒ቹ���j�b�g�����������i�i�^�Ԏ��O�j�́A�����o���u�Ԃɐ������P���Ă���n���ŁA���������ނ̉��Ƃ͈ꐶ�����Ȃ��ƌ��߂��Ă������̂ł��B
�@�Ƃ��낪�N���̗���Ƃ������̂͋��낵�����̂ŁA�g�V�����Ƌ��ɂ��̊Ԃɂ��DIATONE�̂悤�Ȍ���������JBL�݂����ȉA�e�̏��Ȃ����N����{���̃T�E���h�͔��ɍ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�������A��������o���Ă��Ȃ������̂ł��ˁB�����̌f���ł͉��x�������Ă��܂����A���̃T�u�E�V�X�e���̃X�s�[�J�[��iQ3�ł��B�ŏ��͌��O�ł������A���炭�]�����ǂ��̂Ōy���C�����Ŏ������Ă݂�Ɓi�ŏ��������̂�iQ9�ł��j�A���������D�݂̉��ł��������ƂɎ����g�����܂����i�j�BUniQ�h���C�o�[�ƌĂ�铯�����j�b�g�̂��������A�̂�KEF�Ɣ�ׂ�Ɩ��邭�L��������A�������𑜓x��˂��l�߂�悤�ȃX�s�[�J�[�ł͂Ȃ����Ƃ͊m���ł����ǁA�\�������₷�����ŁA�\�Z���ɓ���iQ3�̍w�����肵�܂����B
�@KEF�̏㋉�@��������Ă݂܂������A�ǍD�ȃp�t�H�[�}���X�Ő̊������悤�ȁg���������h�Ƃ�����ۂ͂܂������܂���B���ł�HARBETH��SPENDOR�Ƃ������Ⴂ���ɂ͖ь������Ă����悤�ȉp���u�����h���i���������������Ƃ���A���Ƃ������Ȃ̂��낤���Ɩڂ���������銴���ł����B�A�b�Ƃ����Ԃɉp���E���B�}�ֈƑւ��ł��i�܂��A���܂���TANNOY�����͍D�݂ł͂Ȃ��ł��� ^^;�j�B
�@���ɂƂ���KEF�́i�����Ӗ��ł́j�������̃I�[�f�B�I���i�ł������Ɠ����ɁA���݂̎��g�̃T�E���h�̍D�݂��Ċm�F�����Ă��ꂽ�M�d�ȃu�����h�ł�����܂��B��N�i2007�N�j�AMUON�Ƃ�������100�Z�b�g�̒��n�C�G���h���f����o���Ęb���U��܂��܂������A�w���͓�����̂́i������O���I ^^;�j��x�͒����Ă݂����Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F7894970
![]() 0�_
0�_
�F����A����ɂ��́B
���܂����AKEF!
�����ɓ��Ђ̑ȉ~�`�̒ቹ���j�b�g�����������i�i�^�Ԏ��O�j�́A
�������o���u�Ԃɐ������P���Ă���n���ŁA
�����������ނ̉��Ƃ͈ꐶ�����Ȃ��ƌ��߂��Ă������̂ł��B
���炭Reference��104�ł��ˁB
������U���u��邳�v�͕�����C�����܂��B
�{��HP�̃q�X�g���[�̓t�F�C�X���ʂ��Ă܂���̂ŁA��������c
http://speaker.kir.jp/kef/kef104ab.htm
����598�I�[�f�B�I����̒E�p��SUUSUI��907i��MOS�|LIMITED��Reference102�̑g�����ł��B
�A���_�[�ȉ��F�̑g�����ł����I�[�o�[�z�[�����o�Ăǂ�����܂������ł��B
���̒����͂��̃X�s�[�J�[�Ńt�H�[�}�b�g����Ă܂��B
http://www.kef.com/history/1970/model102.asp
���̎�����Reference�V���[�Y�ɂ͊e�@�했�Ƀ}�b�`���O������p�C�R���C�U�[���t�����܂����B
���[�U�Ԃł͎^�ۗ��_�́uKUBE�v�Ƃ����A�N�e�B�u�E���[�E�C�R���C�U�[�iDC�d���j�ł����B
����悪�����Ȃ锽�ʁA�n�C��������S/N�ቺ�������܂����A���́u�Z���v�������čD��Ŏg���Ă܂��B
���̌�AUNI-Q�̓o������ɉ��F�͂�����ƕ��j���傫���]�����܂����B
���j�b�g�������Ƃ��~�߁A�J�[�I�[�f�B�I�ɂ��i�o���܂�����������͒Z���ł����B
LS3/5A�Ŏg���u���i�v�̗_�ꍂ���~�b�h�o�X�E���j�b�gB120�͍ŏI���f�������낤���ē��肵�܂������A
����SP���肪���鎄�Ƃ��Ă̓��j�b�g������~�͎c�O�ł������������̗���ł��傤�B
�X�s�[�J�[�Ɛт����[���h���C�h�Ȑ��������߂Ă���̂͂����m�̒ʂ�B
�ߔN�̗����Ԃ�͂�����Ƃ����o�u������Ȃ��̂������ĐS�z�ɂȂ�܂�(^^�U
�����ԍ��F7895294
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́IKEF�ł��ˁB���̏ꍇKEF��m�����̂�������Â��Ȃ�
�����I�[�f�B�I���i�����ׁ̈A�ʂ��Ă����H�t���̃T�g�[�����œ�����
�S���҂��������Ă��ꂽ�̂��ŏ��Ŋm�� Model 105/4 �������Ǝv���܂��B
JBL�Ƃ͑S���Ⴄ���F�ň�u�I�H�ł������Ђ�������̂��������悤�ɋL�����Ă܂��B
���i���m���y�A��70���@�@�ł��̂ł�������r�[���̒�����A�y�������ɏ������莋������̋�I�ł����B
���E������T�u�V�X�e����iQ3���g���Ă�������Ƃ̎��B
�䂪�Ƃł�IQ9�����C���ł�(���̗����͑傫��(>_<))
JBL�ł̊��z�͌��E�������Ɠ����ɂȂ莟�Ƀn�[�x�XHL�R���p�N�g��
�������}���`�ɂ��Â��Ă����̂ʼn��F����̈�KEF�̃��[�Y�i�u���ȉ��i��IQ�V���[�Y�ɂ��܂����B
�������ŋ߂ɂȂ�2ch����͂�ǂ��Ȃ��Ă��܂����A�n�[�x�X���Ƃ��Ă����悩�����ȁ[
�Ǝ��X����̔O�����̒��ł��邮���(��)
�������E�����܂���redfodera�����
���܂��͂ǂ�GS�̃R�s�[�������܂��傤���B
�悵�I�܂��̓r�[�g���Y����ɂ��悤�I�I�����
���}�b�V�����[���E�J�b�g�ɂ���̂ɗE�C������܂���(^^�U
����Ȏ��͂Ȃ��A�����擪�ɗ����Ă�邼�I�����ŋ������ɐ��ʏ��ɍs���������f���܂�����B
�K�[�����e���h���h���f���@�Y��Ă܂����A�̐S�v�̎��B
�}�b�V���E���[���ɂ��ׂ����������Ɋ��オ���Ă���E�E�E
�l�I���W���X(�l�I���W����̗�������ł���)�@�R�~�b�N�o���h�̐���
�y�t�z�}�b�V���E���[���łȂ�Ƃ��E�E�E
���E���\����܂���ł����A�ł͎��炢�����܂��B
�����ԍ��F7895984
![]() 0�_
0�_
�F����A���ӂ́B
�@KEF���ŏ��ɕ������͎̂���104�������Ǝv���܂��B
�@�u�唻�Ă��v(�����ߕӂł͂���������)�̗l�ȃt�H�����̒�惆�j�b�g�ɐ悸�͋���
�@���̉��Ɋ���������ۂ́u���̃����h���u���b�W�v�ł����B
�@�C�M���X��SP��GODDMAN�ETANNOY�EQUAD�ELAWTHER�ERICHARD-ALLEN���̐��i�����o�����
�@���Ȃ����ɁA�uBBC-MONITOR�v����ł��ďo�Ă���SP�Q�̈�ł����ˁB
�@���̌��ROGERS-LS3/5a�AHERBETH�ASPENDOR���X�A�u�ٕ�Z��v���]���]���o�܂����B
�@�ɂɂ���JBL�Ƃ̔�r�͂��ꂩ��\�N�̒����ɂ킽���Ę_�c�̓I�ł��ˁB
�@���{�́u2S-305�v�A�����J�́uJBL�EALTEC�v����WESTREX�n�A�h�C�c��SIEMENS
�@�C�M���X�͏�L��SP�Q���Ċ�����̂́A�������A�����A�C��E���y�̈Ⴂ��
�@�ǂ��o�Ă���ƌ������Ƃł��B
�@�����̓��{�l�I�[�f�B�I�t�@����DIATONE�EJBL�̐�����āu����i���v�̉ʂĂ�
�@���B�n��SP�ɒH�蒅�����������ł��ˁB
�@JBL�ٌ̕�ł͂Ȃ��ł����A�������A�����܂ł�����A��n���꒼���ɑ��铹�H����
�@�C���[�W�́A��͂��X���{�l�ɂ́u����v�̂��Ǝv���܂��B
�@�l�G�܁X�A��������A�F�A������DNA�Ɏ�荞��ł����X�ɂ͒P���E����͊������Ȃ�
�@�Ȃ�̂��X�Ȃ邩�Ȃł��B
�@���{�l�̐��_�����A�����ɉe�����Ă���Ɗ����܂��ˁB
�@JAZZ���u�ґz�E�v�z�v�ƌ��т���͓̂��{�l�ƈꕔ�̃��[���b�p�l���������H
�@�uJAZZ�i���v�Ȃ�`�Ԃʼn��y�ɐڂ���Ƃ��������̂����A�ٗl�ȕ����ł���������
�@���̂悤�ȁu�e�L�g�[�l�ԁv�͍l�����肵�܂����B
�@�ŋ߂̉��B�nSP�ɑ���C���[�W��redfodera����̊����ł��傤���H�@��̂��鎖��
�@�ϋɓI�Ɏ�������悤�ɂȂ�܂����B
�@���E�������قǂɁu�ڂ���v�ƌ������Ƃ͖����ł����A����łȂ��Ƃ����Ȃ���
�@���l�|�ܖ{�����A�z���m���ɍL����l�ȋC���������܂��B
�@�D���ȃM�^�[�⌷�o�X�̉�����͂肵������Ɗ��������{�f�B�[����o�鉹�����҂���
�@�̂ŁAJBL�̉�����͓�����܂���B
�@�������ł��u�X�g���f�B�o���v�Ƃ��u�N�����i�v���Y��ȉ��ŕ��������Ǝv������
�@JBL�͑ʖڂł��傤�ˁB
�@�u���@�C�I�����v�̉��ƌ������́u�t�B�h���v�ɂȂ��Ă��܂��܂�����B
�@�����͌��y�l�d�t����悤�ȁu��l�v�ɂȂ肽���Ƃ��v���̂ł����A
�@�]�˂̉����ɐ��܂�u�i���v�ĂȂ��̂͐��܂ꂽ�Ƃ����玝�����킹�Ă��܂���B
�@�����l�d�t�ł��u�h���L�[�J���e�b�g�v�����ɂ͎������̂悤�ł��B
satoakichan����A
�@�����u�}�b�V�����[���v�͖����ł��B�J�c�����p�ł����H
�@���B�W���A�����猾���u�p���N�n�̃X�L���w�b�h�v�̕����藣��͂�낵���悤�ŁI
���E����l�A��E���I���W�Ɉ��̎���E�E�E�E�B
�@
�����ԍ��F7896940
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@�@������(^-^)/
�`���b�g���f���Ă���Ƙb���i��ŁA�^�C�w�����@�B
���`�ƁA�b�͑k����
�́A�����ɂ͋�J���܂����ˁB
���ɂ��鍠�͘V�܂̐�������ƃI�[�f�B�I�̃i�j���ɁA�悭�o�����Ă��܂������A
�����͂���Ȃ���E�E�E���������ň�i�ق֍s���I�Ƃ����܂����B
�ŋ߁A�L���ɂȂ����I�[�f�B�I�V���b�v�ł����A
�����A�������ЂƂ�œX�ԁA��i�قȂ̂ɊŔ͐����d�C�̂܂܁A�������킵�������̓X�ł����Bm(_ _)m
�������A�ނƂ̏o��ŃA�N�Z�T���[�ɍS��悤�ɂȂ����̂�������܂���B
�����A���Y�d���P�[�u���͊F���ŁAAPI,�I�[�����V���t�H�j�b�N�X�APAD�A
�g�����X�y�A�����g��������A�v��������Ƃ�܂����B
�Ō��1.2����12���H������I�[������ML�L���[�u�܂Ŕ����Ă��܂��܂������A�i�o�J�ł��ˁj
�d���Ď��̕s�ւȎ��ŋ�J�͂��܂������A���͗ǂ������A�ǂ����܂����B
���_�E�E�E���̃P�[�u�����g���Ƌ@��̉����Ă��邩�A
�P�[�u���̉����Ă���̂�����Ȃ��Ȃ�܂��B
����ȗ��A�P�[�u���͂��������ŗǂ��I�i�c�b�R�~�͖����Ƃ������ŁE�E�@m(_ _)m�j
�����āE�E�N���C�X���[�@�@�H�H�H�p�X�ł��B
�R�[������598�S������ɏ��������ȃC���[�W����L��܂����E�E�E�@�@�p�X�ł��B
�A�C���́E�E�E�@����ς�p�X�ł��B
���}�nAZ1��DSP�͗ǂ������ł��ˁB
�����p�C�I�j�A��AX10�ƕ��p�Ŏg���Ă��܂������AAZ1������ł����B
AZ1������������R�́A���ƂƒP�g���C��֍s�����藈����̌J��Ԃ��ŁA
SP�̐ړ_�s�ǂ������ł����A30kg�̃{�f�B���x����ɂ̓V���[�V����ア���ȁH
�����w������A�����o���h��g��ł��܂������A�p����������Ńi�C�V���ł��B
�Љ�l�ɂȂ������q���A�܂��A�}�`���A�o���h��2�|�������ł���Ă��܂��B
��N�A�n���̃��}�n�̔��\��i�H�j�Ŋ|�������o���h�̂ЂƂ����D���ł����B
�i�e�o�J�ŁA�Ƒ��Ō��ɍs���܂����B�n�b�n�b�n�E�E�E�@(^_^;)�j
�����B�B�B
�����ԍ��F7897450
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@�ӂ����сA������(^-^)/
�����ł��A�A�A
KEF���g���Ă��܂����A105/3S�Ə��^�̃R�[�_�[�V�̂Q�@��ł��B
���i�A���y���ɂ̓��[���b�p�n�̕����S�n�悭�����܂��ˁB
�ŋ߃n�[�x�XHL�R���p�N�g���܂������ǂ����ł��B
�́A�n�[�x�X��HL�T���ɂ������̂ł����E�E�E
�ׂɃ\�i�X�̃G���N�^�E�A�}�g�[�����F���ۂ����ʼn̂��Ă��܂����B
�v�킸�A���ꉺ�����I�ƃX�^���h�t���̃A�}�g�[���𒍕��B
����ȗ��n�[�x�X�ɉ��͖��������̂ł����AHL�R���p�N�g�ɂ͒�������܂����B
satoakichan����AHL�R���p�N�g�͂����ł���ˁB(^-^)/
�b��KEF�ɖ߂��āA
UNI-Q�h���C�o�[���c�C���h���C�u�i�E�[�n�[�j�̃��t�@�����XMODEL105/3S�ł��B
����̐L�т���������Ȃ��Ēn���ł����A���킢�̂��鉹�ł����B
�E�E�E�ł��g���Ă��邤���ɈÂ������A�`�I�Ǝv���܂����B(^_^;)
�R�[�_�[�V�͈���SP�ł������y����������ƒ������Ă���܂����B
redfodera����Ɏw�E�����܂Ń{�����̋t�h�[���͖Y��Ă��܂����B
���F�̓s�A�m���ō��ł��A���ꂾ���ł����l�̂��鉹�ł��B
�i����H�@�A�}�g�[�����E�[�n�[�͋t�h�[�����������ȁH�j
�X�^���h��SCM100�̎��ɍ�������u���b�N�𗧂ĂāA�g���Ă��܂��B
B��W��N805���炷�̂����SP�ł����A��肭��ƁA
11cm�E�[�n�[�Ƃ͎v���Ȃ����A�͋����A�����オ��̗ǂ��A���₩�ȉ��ł��B(^-^)/
�����ԍ��F7897629
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
�l�I���W����
���ŋ߂̉��B�nSP�ɑ���C���[�W��redfodera����̊����ł��傤���H
���@��̂��鎖�ɐϋɓI�Ɏ�������悤�ɂȂ�܂����B
�\����܂���m(_ _)m
�u��邢�E�Â��E�Z���v�̎O�d������荞��ł��܂�����������܂���B
�z�[�����烊�{���֏@�|�ւ�����l�Ȃ��Ƃɂł��Ȃ�����E�E�E�ӔC������������܂���B
���l�G�܁X�A��������A�F�A������DNA�Ɏ�荞��ł����X�ɂ�
���P���E����͊������Ȃ��Ȃ�̂��X�Ȃ邩�Ȃł��B
���ĉ�Ђ̎�������UREI��813BX�i��̓����z�[���E�c�B�[�^�[�������c�j�ƑΖʂ������A
���y���ł͂Ȃ��A����͉����𗁂т���̂Ȃ̂��ȂƁA�����̐��E�Ƀ��N���N�����̂����̊ԁE�E�E
��^�t���A�^�C�v�ɖƉu�̖����������ɂ̓��R�[�hA�ʂ����E�ŁA�ƂĂ��y�����Ƃ͊������܂���ł������A
����ƌ������u�Λ���������v�Ƃ�����q�]�|�ɑς����܂���ł����B
���uBBC-MONITOR�v����ł��ďo�Ă���SP�Q�̈�ł����ˁB
�����̌��ROGERS-LS3/5a�AHERBETH�ASPENDOR���X�A�u�ٕ�Z��v���]���]���o�܂����B
���̏ꍇ�́A�������̕Ћ��ɒu����Ă���LS3/5A��炵�����ɋՐ��ɐG��Ă��܂��܂����B
�����KEF�̃��C�b�V���[�Łi�o�C���C���[4�|�[���d�l�j�������̂ł����A
LS3/5A�}�j�A�̕��Ɍ��킹��Ɓu�ٕ�Z��v�����ꂼ��Ⴂ����������l�ł���B
����ɂ��Ă����̃X�s�[�J�[�����ł��傤�A�����̃��[�J�[���e�X�����d�l�Ő��삵�����̂́E�E�E�B
�u�s���o�̃X�s�[�J�[�v�Ƃ������ۂ��A�͂��܂�BBC���j�^�[�Ƃ����u�����h�͂̐�����Z���A
�����Ƀ����C�N�ł�C�b�V���[�ł����s�@�Ƃ��Ĕ̔�����A�n����搂��V�����𗧂����E�E�E�B
���Ɍ�������Reference102�Ɍ��z�𓊉e���Ă����ЂƂ�Ȃ̂ł���(^^�U
�����ԍ��F7897666
![]() 1�_
1�_
satoakichan����Aaudio-style����A�����́B
�A���X�A������������m(_ _)m
HERBETH��HL�R���p�N�g�����̒������i�ł��ˁB
Reference102��HL�R���p�N�g�łǂ���ɂ��邩�Y�ݔ��������Ƃ��v���o���܂����B
���s�@�͉�����ڂɂȂ�܂��ł��傤�H
��r�����̂͂�������ゾ�����l�ȁE�E�E
�E�[�t�@�[�̃Z���^�[�E�h�[���̑���ɉ~���`�̃q�[�g�p�C�v���L�тĂ��܂����B
B&W�ɑ�\�����C�e�^�̃t�F�C�Y�E�v���O�̓X�}�[�g�ł����A
���̃q�[�g�p�C�v�A��[�ɑ����̈Ⴄ���̂����Ă��āA���Ȃ���s�m�L�I�̐L�т��@�i�j
����������ۂɉQ�����O���O���I�R�~�J���߂��܂���(^_^;)
���F�ł͂Ȃ��Ă��̃s�m�L�I�̕@���D���ɂȂꂸKEF�ɂ�����܂���ł����B
���N�̔N����KEF�̌�p��T���������ĂэŏI�I�l��HL�R���p�N�g���c�����̂ł����A
���x�̓f�U�C��+���{���E�c�B�[�^�[�i��j��PIEGA��TP3�̑O�ɂ����Ȃ����I(^_^;)
�D�݂̐��i�ł���Ȃ��炢���u�����v�ꉟ��������Ȃ��Đ\����Ȃ����Ƃ��Ă��܂���m(_ _)m
������o���Ă��u�������U�镑���̗���ȋM�w�l�v�Ԃ�͌��݂ł��ˁB
���Ƃ���x�Ɏ��ɂ��Ă܂����A�]�T���ł������g�茳�ɒu���Ă��������Ǝv���܂��B
�}�C�i�[�E�`�F���W���J��Ԃ��ĐV�삪���ݏo���ꑱ����E�E�E
�ŋ߂̓��{�̐��i�ł͂߂����茸���Ă��܂��܂����ˁA���������T�C�N���̂��鐻�i�B
���ꂪ�ƂĂ��₵�������Ă܂��B
�����ԍ��F7897970
![]() 1�_
1�_
�|�� redfodera����
�@�����A����Reference104�������Ǝv���܂��B�ȉ~�`�̃��j�b�g�̓E�[�n�[�ł͂Ȃ��h�����R�[���i�p�b�V�u�E���W�G�[�^�[�j�ł������B���̃p�b�V�u�E���W�G�[�^�[�͈ꎞ���������[�J�[���������ĕ��y���i�сi�V�X�R���p�j�ɍ̗p�������Ƃ��������悤�ȋC�����܂����A���O�̒ʂ�u�ǂ�`��Ƃ������v�i���j�������Ƃ������Ƃō��ł͌������܂���ȁB����ƁA�J�[�I�[�f�B�I�ɂ��i�o���Ă��Ƃ������Ƃ͒m��܂���ł����B
���ߔN�̗����Ԃ�͂�����Ƃ����o�u������Ȃ���
�@�m���ɁB�Ⴂ�w���~�j�R���|����́u���Ɨp�v�Ƃ���iQ1����iQ3���̂����߂�P�[�X���ڗ��ƕ����܂������A��X�݂����ȔN�G�̓������I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��āAKEF���Ă̂͌��l�D�݂̃u�����h�������̂ɂ�������炸�A���̏͊u���̊�������܂��B����ɁAKEF�̎戵�X�͌����Ă���̂ɁA���̃T�C�g�ł���ʂɓ����Ă���̂́A�Ђ���Ƃ��āu�����������Ƃ͂Ȃ��A�܂������ł���X���߂��ɂȂ����ǁA�l�b�g�ł̕]�����ǂ��̂Ŕ������Ⴆ�i�������A���������ʂ͗ǍD�������j�v�Ƃ����荇���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��܂�(^^;)�B�����NHK�u�N���[�Y�A�b�v����v�ł����グ���Ă����悤�ɁA���{�l���Ă̂̓����L���O�Ɏア�����ł�����i�ԑg�ŕ`����Ă����̂͂������I�[�f�B�I�ł͂Ȃ��A���Ђł������ǁj�B
�|�� satoakichan����
�@iQ9�͂����ł��ˁBiQ�V���[�Y�̒���iQ3��iQ9���������炭�]�����ǂ��悤�ł��B���̋@��������Ĉ����Ȃ��̂ł����A���i�ݒ�ƃA�s�[���x�ł���2�@��͖ڗ����Ă���̂ł��傤�BHARBETH�̃X�s�[�J�[�͐���̖^�I�[�f�B�I�t�F�A�ł������܂������A���邭���₩�ŕi�̂��鉹�ŁA���ŎႢ���͂��̃X�s�[�J�[�̗ǂ���������Ȃ������̂��낤���ƁA�Y�ނ��Ƃ�����ł����i�j�B
���}�b�V���E���[���łȂ�Ƃ��E�E�E
�@�����}�b�V�����[���E�J�b�g�ɂ�����A�ĉf��u�m�[�J���g���[�v�ɏo�Ă������D�n�r�G���E�o���f���i���̉f��ŃA�J�f�~�[�����j�D�܂��l���j������L�����E�����݂����ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�䉓���\���グ�����Ǝv���܂��i�����j�B
http://www.nocountry.jp/
�|�� �l�I���W����
�@�{���ɁA�I�[�f�B�I���i�i���ɃX�s�[�J�[�j�͂��������ǂ��o�܂��ˁBJBL�͐��C�݂̃��[�J�[���������āA��C�����E�G�X�g�R�[�X�g���̂��̂ł��B���ʁA���C�݂�KLH�Ƃ�AR�Ȃ͊������x���������܂��B����������KEF�̌o�c�w�͓��{���̃X�s�[�J�[��]���āu�ƂĂ��A�O���b�V�����I�v�ƌ����������ł����A���̏ꍇ�̃A�O���b�V���Ƃ́u�U���I�v�Ƃ����A���܂�ǂ��Ӗ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@JAZZ�i���͍s�������Ƃ�����܂���B�n���s�s�Z�܂��Ȃ̂ŁAJAZZ�i�����̂����܂�Ȃ��A�d�����Ȃ��Ƃ������܂�(^^;)�B�W���Y�͖{���A�����J�ł́u�������y�v�ɐ���ʂĂĂ���悤�Ȃ��Ƃ����������܂������A���B�ł͐���Ȃ悤�ł��ˁB�����Ƀe�i�[�T�b�N�X�𐁂��Ă���z�����܂����ǁA�����̘b�ɂ��Ɓu���B�n�W���Y�̃~���[�W�V�����̓N���V�b�N�̑f�{�̂���z�����肾����A�e�N�j�J���Ȓ^���I�v���C�����ӂ��v�Ƃ̂��Ƃł��B�̂́u�W���Y�Ȃ��JBL�v�݂����Ȓ��������܂������A���B���X�s�[�J�[�ŃW���Y��炵�Ă��܂�������a�����Ȃ��̂́A���łɃW���Y�̖{�ꂪ�A�����J�ł͂Ȃ����B���̑��Ɉڂ��Ă��邱�Ƃ����W�ł͂Ȃ��̂�������܂���E�E�E�E�ȂǂƁA�����̂Ȃ����Ƃ������Ă݂��肵�܂��i�j�B
�|�� audio-style����
�@��i�قɂ͍s�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�������̎�Ɏ҂̐������͕��͂��B�҂ł��ˁB�uProCable�v�̎�@�Ƃ͕ʂ̈Ӗ��ŁA���̂���L�����N�^�[���Ǝv���܂��B����ɂ��Ă��A���̓X�̃z�[���y�[�W�͓ǂ݂ɂ����ł��i���j�B
�@�����w������A�o���h����낤�Ƃ��āE�E�E�E���܂��܂����i��j�B����܂ł�������Ƃ̂Ȃ��M�^�[�Ɏ���o�����̂��ԈႢ�̌��ł����ȁB�܂�Ń��m�ɂȂ�܂���ł����B�����u�L�[�{�[�h��S���������̂����ǁv�Ƃ�������A�����o�����̎��́E���[�_�[�i�̓z����u�n����Y�A���b�N�̓M�^�[�ƃx�[�X�ƃh�����X���낤���B�L�[�{�[�h�Ȃ�Ă����`�����`���������y��͂��Ăтł͂Ȃ���I�v�Ɛ�̂Ă��܂����B�܂��A�n�R�w���ɂƂ��Ă͈����M�^�[�����͂����Ă��A�V���Z��G���s�ȂB����]�T�͖���������ł����ǂˁB����ł���N�AYAMAHA��DX7���o�����Ƃ��́A�}�W�Ŕ��������Ǝv�������̂ł�(^^;)�B
�����ԍ��F7899820
![]() 0�_
0�_
�����ƌ��Ă�����ł����A������ꂽ�I
�厖�ȃ��[�J�[�Y��Ă��܂��H�i�Ђ���Ƃ��Č����Ȃ̂��ȁH�j
����Ԍ��C�̂���A�]�_�ƁA�I�[�f�B�I�t�@�C���ɐl�C�m���P�̃��[�J�[
���{�R�����r�A���c�d�m�n�m�ł��B
�ǂ�������Љ�ĉ������B
�����ԍ��F7901851
![]() 0�_
0�_
�@�u�����h�ʂɉ������̃I�[�f�B�I���i���܂Ƃ߂Ă��܂������A���̏������݂������ăg�s��ɂ��u��ڕҁv���I��点�Ă��������܂��B�E�E�E�E�Ȃ�ď����Ɓu�����APIONEER�͂ǂ������BDENON�́AMARANTZ�́I�v�Ƃ����˂����݂�����Ƃ͎v���܂����A�����̃��[�J�[�̐��i���g���Ă͂�����̂́A�ǂ����l�I�Ɏv�����ꂪ�Ȃ����̂ŁA����Ȃ���T�������Ă��������܂����i�j�����F��A�S�����E�E�E���j�B�܂�������L���ł��w���������Ƃ������������Ƃ��Ȃ��u�����h�ɂ��Ă͏����܂��A����10���N���炢�ɓ��{�ɓ����Ă���悤�ɂȂ����C�O���i�⍑���V�i�u�����h�Ɋւ��Ă��u�������̃I�[�f�B�I�v�Ƃ͌����܂���̂ŁA�����ďȂ��Ă��܂��B�������܂ŏ����Ă������̈ȊO�̃u�����h�ɑ��Ĉ�ƌ��������̕��́A���͂��A�b�v���Ă���������K���ł��B
�@���āA�Ō�̃l�^��B&O�ł��BBang&Olufsen��1925�N�̑n���B�䏳�m�̂悤�Ƀt�����`���C�Y���f���}�[�N�ɒu���Ă��܂����A�f���}�[�N�Ƃ������͂���B&O���͂���Ortofon�Ƃ�DALI�Ƃ�DYNAUDIO�Ƃ�VIFA�Ƃ������������ȃI�[�f�B�I���[�J�[�������������݂��܂��B�������������`���ł�����̂��낤���Ǝv���Ă��܂��܂��B
�@B&O�̐��i�ōŏ��ɖڂɂ����̂��A�i���O�p�J�[�g���b�W�ł��i70�N��㔼�̂��Ƃł��j�B�C�e�^�̃f�U�C�����������������̂́A���͂�������ٗl�ɒ����J���`���o�[���C�ɂȂ�܂����B����Ȃ��̂Ő���Ƀg���[�X�o����̂��낤���Ǝv���A���i���̂̍��ɋ^�����������ǎ����Ă݂邱�Ƃ͂���܂���ł����B
�@�Ƃ��낪���ꂩ�琔�N��A�^�I�[�f�B�I�G���ɍڂ��Ă���B&O�̃A�i���O�E�v���[���[�̃O���r�A�ɖڂ��B�t���ɂȂ�܂����B���j�A�g���b�L���O�^�͊m���ɖڐV���������̂ł����A�������̂͂��̃f�U�C���ł��B���̂ǂ̃��[�J�[�Ƃ����Ă��Ȃ��A�܂��ɖ����h�Ƃ��Ă̛������������l�����Ă��܂����B�C�e�^�̃J�[�g���b�W�͂��̃v���[���[�ƃh�b�L���O���ď��߂āg�����`�h�ɂȂ�̂��ƁA��������ł����B
�@���̑��A���̃��[�J�[�̃t�b�ꂽ�ӏ��̐��X�́A���������ŃN�h�N�h����������B&O�̃z�[���y�[�W���Q�Ƃ��Ă�����������ǂ��ł��傤�i�j�B
�@�ŁA���͎���B&O�̐��i���̂��̂����Ƃ��o�����̂́A7,8�N�O�ƁA���������V���߂̘b�ł��B�^�t�@�b�V�����r���ɂ���I�V�����ȃV���b�v�ŃT�E���h�V�X�e�������Ă��炢�܂����B���̊��z�͂Ƃ����ƁE�E�E�E���[��E�E�E�E���ƌ������炢���̂��B���҂��傫�������̂��A�����Ĉ����Ȃ����ǂ�����ƃC�}�C�`�ł����ˁB�n�C�t�@�C�n�ł͂Ȃ������₷�����S�ŁA���Ȃ��Ƃ��s���A�E�I�[�f�B�I��Nj����Ă���}�j�A�͒ʂ�߂��Ă��܂��ł��傤�B�G���Ō��������̂ł����AB&O�̃T�E���h�V�X�e�����w�������^�����l�̋L���ŁA�ނ͂�������R����C���e���A�Ƃ��ē������ĉ��͈�؏o�����ɋ��Ԃɏ����Ă��邾�����Ƃ̂��ƁB���������g�������A�����Ǝv�킹���ۂł����B
�@�Ђ���Ƃ���AV�V�X�e���̕��́i�������Ă��Ȃ����ǁj�������i�Ɍ��������o�����X�̎�ꂽ�X�O�����m�Ȃ̂�������܂��E�E�E�E�B�@
�@�Ƃ͌������AB&O�̃}�[�P�e�B���O�ɂ��Ă͍������[�J�[�����낢��Ɗw�ԂƂ��낪�傫���Ǝv���܂��B���V���b�v��z����Ƃ����헪�ł̓X�R�b�g�����h��LINN�������悤�ȂƂ��낪����܂����A������LINN�����O�ꂵ�Ă��āA�u�����h�C���[�W�����炵�Ă��镵�͋C������܂��ˁB
�@�E�E�E�E�Ȃ��A�g�s��ɂ��u���Õҁv�͂���ň�i���ł����A�����ŏ����A�[�e�B�N���X�V���x�܂��Ă��������A���̌㎟�Ȃ�X�e�[�W�u�W�]�ҁv�ɗՂ݂����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7901897
![]() 0�_
0�_
����ꂳ�܂Ō�����܂����B
�@�u�E���I���W�v�ɂ��t���������������L��������܂��B
�@����B&O�ł����Aredfodera����Ƃ̘b�ł����Љ���悤�ɈȑO�A����ɐ��_�̐��i��
�@����܂����B���B�������̂����z�̒ʂ�A�u���{�l�I�[�f�B�I�t�@�C���v������
�@���ł͑S���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�k���̉Ƌ�A�G�݁E�ԁE�H�Ɛ��i�ɘA�ȂƑ��Â��u���_���v�Ȋ��o�͈�N�̔�����
�@��ƕX�̒��Ő��������炵�̒m�b���l�܂��Ă��镨���Ǝv���Ă��܂��B
�@�a�V�ȐF�g���A�ӂ��܂Ə�̐����ł͍l�����Ȃ��f�U�C���A�@�\���Ƃǂ���Ƃ��Ă�
�@�u�y���ށv�ׂ̓���ł���Ɗ������܂��B
�@���݂̓��{�̉Ƌ�A�G�݂ɂ�����ȉe����^���Ă���̂ł́H
���̂���́u�W�]�ҁv�ƌ������Ƃł����A�u��ڕҁv���M���o�g���ɂȂ肻���ł��ˁB
�@
�����ԍ��F7902048
![]() 0�_
0�_
�� �@�܂������̂ł����H�@���ꂪ���̃X���b�h�ɂ����āA�A�i�^�ɑ���Ō�̏������݂ɂ������Ǝv���̂ŁA�悭�����Ȃ����B
���Ȃ�������ɏ���Ɂu�����v�Ƃ����̂đ䎌�������t���邩��I���Ȃ��̂ł��B
�� �@���́A���g�̌����������ƁE��`�咣���ؓ����Ăė��o���Ȃ��悤�Ȗ��n�Ȍ�m�Ƃ͂܂Ƃ��Șb�����������鉿�l�����o���܂���B�O��̃A�[�e�B�N���ŃA�i�^�ɂ̓n�b�L���\���グ���͂��ł��B�A�i�^�́u���������v�̂ł��B�̖̂���̎�l���̃Z���t�����Ȃ�u���O�͂�������ł���v�ł��B
���� [7839304] �ɂ����āA�u�����v�͕�����F�߂��������猾�����t�ł���A���肩��u���Ȃ��͓��������̂ł��v�ƌ����錾�t�ł͂Ȃ��|���w�E���܂����B�����āA���͓�������ӎu���Ȃ����Ƃ����Ȃ��ɂ��`�������͂��ł��B
����ɂ�������炸�A���Ȃ��́A����̌������t��َE���A����̈ӎv�����Ď����̏���ȍl����ɉ����t���Ă��܂��B
���Ȃ����I��肽���̂Ȃ�A���肪���_�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�悤�Ȏ̂đ䎌�͎c���Ȃ����Ƃł��B(���́A���Ȃ��Ɏ̂đ䎌�������ȂƋ����͂��Ă��܂���B���Ȃ�����������Ȏ̂đ䎌����������A���͂���ɑ��Đ����Ȕ��_������������܂���A�Ƃ��������̂��Ƃł��B)
�����ԍ��F7902054
![]() 4�_
4�_
�݂Ȃ���@�@������(^-^)/
���E�������@�@�����l�ł����Bm(_ _)m
�Y�ꂩ���Ă����A���������@�킪���グ���Ċy�����X���ł����ˁB
�W�]�҂��A�l�I���W���A��悤�ɔM���o�g�����y���݂ɂ��Ă��܂���B (^-^)/
�����ł��Bm(_ _)m
�O�X��
��UNI-Q�h���C�o�[���c�C���h���C�u�i�E�[�n�[�j�̃��t�@�����XMODEL105/3S�ł��B
����̐L�т���������Ȃ��Ēn���ł����A���킢�̂��鉹�ł����B
�E�E�E�ł��g���Ă��邤���ɈÂ������A�`�I�Ǝv���܂����B(^_^;)
����͕��i�l�b�g��t������Ԃ̉��ŁA
�l�b�g���O���ƍ��悪�L�тăo�����X�͐����Ă��܂����B
���̓����A���[���b�p�n��SP�́A�l�b�g�����߂̃^�C�v�������悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F7902275
![]() 0�_
0�_
�F����A�����́B
���E�������
���J�[�I�[�f�B�I�ɂ��i�o���Ă��Ƃ������Ƃ͒m��܂���ł����B
�����P�ނ��Ă��Ȃ�o���Ă���m��܂����BLUXMAN���ꏏ�ɑ㗝�X����Ă����݂����ł��B
������USA�ŃX�s�[�J�[�ȊO�Ƀp���[�A���v�������Ă��������ł��B
KEF�̃C���[�W�J���[�������X�J�C�u���[�̃R�[����ῂ����A�ԍڗpUni-Q�I�����C���i�b�v����Ă܂����B
����SP�̌����p�ɃI�[�N�V�����Ńn�C�G���h�@���2Way�N���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�N��500�~�œ��肵�܂������A
�D�ꂽ�v�ȏ�Ƀ��b�c���R�C���Ȃǃp�[�c��Ōy��2���~�͂��镨�ʓ����IKEF�̈ӋC���݂������܂����B
���ꂸ�ɓP�ނ������Ƃ��ɂ��܂�܂��B
�X���Ƃ͊W�Ȃ��b�Ő\����Ȃ��̂ł����A�F���珕�������������Ȃ��ł��傤��m(_ _)m
�ߏ��̏��w�Z�Ŗ{��������j���܂ŁA�����ƃ~�����}�[�̔�Ўҋ~�σ`�����[�e�B�[�E�o�U�[���J�����̂ŁA
�����͂����ɗ��������ƎG�݂�g�̉��̃��m�������W�߂Ċ�t���ɍs���܂����B
���̒��ɂ͎u�������Ƃ���������ȕ���������������̂Ő����X�s�[�J�[�������Ă���܂����B
HARBETH��LS5/12A�A�ŐV��BBC���j�^�[�ł��B���������J���̐V�i��5,000�~����E�E�E�B
�o�i���ꂽ���ꂳ��Ƃ��q����ɂ������|����ƁA��N���S���Ȃ�ɂȂ�������l���w�����ꂽ���̂��Ƃ̂��ƁB
�ǂ������������l�i���܂߂Ă����m�Ȃ���ɁA���܂�ɏ��z�Ȃ̂ł���������������Ă͂Ƃ��b�������Ƃ���A
�`�����e�B�ō��z�Ȋ�t����̂��E�тȂ��̂�5,000�~�{���̕��̂��C�����ł悢�Ƃ������Ⴂ�܂��B
�u5,000�~+���œ���ł���A���b�L�[�I�v�Ƃ́A�������ɑf���Ɏv�����A
�Y���������b�������̖��A�����~�ŏ����Ē����܂����B
��������Ă͂������̂́A�P�ӂ��@�����l�ŕ��G�ȐS���ł��B
���������ꍇ�A�ǂ��C�����ɐ܂荇��������Ηǂ��̂ł��傤�B
�����ԍ��F7902439
![]() 1�_
1�_
���A�������A����ꂳ�܂ł����B
�I���̏������݂��������̋C�Â������O�̃��X�����Ă��܂��܂����B
�\����܂���m(_ _)m
�l�X�ȃ��[�J�[�̂��Љ�A�{���Ɋy���܂��Ē����܂���
���肪�Ƃ��������܂�m(_ _)m
�u�W�]�ҁv��S�҂��ɂ��A
�ǂ��炩�̔ŊF�l�Ƃ���o���鎖���y���݂ɂ��Ă���܂��B
�����ԍ��F7902473
![]() 1�_
1�_
redfodera����ցA
�@SP���w������ĉ������\����܂��Ȃ��������ꂽ�I�[�i�[�ɂ��A�����E�~�����}�[��
�@��Ў҂̕��X�̂��߂ɂ�������SP��炷���Ƃɐs����Ǝv���܂��B���A
�@redfodera�������芪���́uUA�����ǁv�̗l����悵�Ă���H�E�E�B
�@�u��͐l�̂��߂Ȃ炸�E�E�E�E�E�v�]�X������܂����ЂƂ܂��͗l�q�����H
�����ԍ��F7902507
![]() 0�_
0�_
���E������� ���͂悤�������܂��I
��ω��������b�A�L�Ӌ`�Șb���X�@�{���Ɋy���������ł���B
��Q���E���I���W�ɂ����̎肪���������̂Ɗ��ӂ��Ă��܂�(^O^)
�����W�]�_�����҂������A�Ƃ����Ă��������܂��A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F7902904
![]() 0�_
0�_
�@���͂悤�������܂��A�F����B
�@�����������̃g�s�b�N�Łu�W�]�ҁv�������U�炩���Ă��悩�����̂ł����A���܂�u����X���b�h�v�ɂȂ�̂��u�d���v�Ȃ��ĉ��ł�����A�ȉ��̂Ƃ���Ɂu���E�������̃I�[�f�B�I�@��ƍ���̓W�]�v�Ƒ肵�ĕʂɗ��Ă����Ă��������܂����B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7920820/
�@��낵�����肢�v���܂�(^^)�B
�����ԍ��F7921004
![]() 0�_
0�_
http://www.youtube.com/watch?v=T4r0ntvyOL4&playnext=1&list=PLC23681D2C8C2ECF5
�[��̉f�挀��̃e�[�}�\���O�c
���������ŋ��������ς��ɂȂ�Ȃł��B
�y�c�M���̃V���Z�ŕ����u�h�r�b�V�[��A���x�X�N�v
�f�批�y����D���ł����c
�ǂ�قǖ���Ɋ������܂������c
�ŋ߂̉f��ł́u�Ō�̒��b���v�𐛑����Ɍ��Ă������������ł��B
�u�V�E��т��߂��݂����N���v�̐A�ؓ��̂悤�ł͉ł����킢�����B
�����ԍ��F13199754
![]() 0�_
0�_
-> �f�W�S������
�@�Â��X���b�h�Ƀ��X��t���Ă�����ċ��k�ł��B
�@�y�c�M�Ƃ����A70�N��̃V���Z�T�C�U�[�E�~���[�W�b�N�̑��l�҂ł����ˁB�m�����[�O�̋@����g�p���Ă����Ǝv���܂����A���R�̂��ƂȂ���P�������o�Ȃ��̂ŁA�c��ȉ̃g���b�N�_�E�������s�����ƕ����Ă��܂��B
�@�y�c�M�͉f�批�y���������肪���Ă��āA�ŋ߂ł͎R�c�m���ē̏���ł��Ȃ��݂ł����A������ԍD���Ȃ̂́u���̖��O�Y�@�K���X�̃}���g�v�̉��y�ł��i1989�N����j�B�f���炵������J�������[�N�̃o�b�N�Ŗ苿���y�c�T�E���h�͈����ł����B����͂������{���ł����A����ɂ͖����L�����N�^�[���o�ꂳ���Ă��ăX�g�[���[���d�w�I�ɂȂ��Ă��āA�������������[���������̂ł��B
�@70�N��̃V���Z�T�C�U�[�E�~���[�W�b�N�̒S����Ƃ��Ă�����l�v���o���̂��A�t�����X�̃W�������~�b�V�F���E�W���[���ł��B�f�批�y�̑�ƃ��[���X�E�W���[���̑��q�ŁA��\��uOxygene�v�͂悭�����܂����B���������B
�����ԍ��F13202656
![]() 0�_
0�_
���E�������ڂ����ł��ˁB
�f�悪�n�܂�O�ɂ����܂�̃e���b�v�̃o�b�N�ɗ��ꂽ�ȂŁA
�ŋ߂ɂȂ��ĕy�c���̉��t�ƒm��܂����B
���ӎ��̒��̋L�������ӂ�o�Ă��܂����B
�x�c���͂ǂ��炩�Ƃ����ƃ|�[�����[���A�I�ŁA
��Ҍ����ł͂Ȃ������悤�ȋC�����܂��B
�C�O�ŕ]������Ă�����ł��ˁB
���Ȃ݂ɉf��T�E���h�g���b�N�ł́u�����̕��vLP���܂����ˁB
�����剉���D���ǂ������Ƃ��������ł��B
����DVD����܂���c�B
�ς��ł̓o�C�N�̃J���T�LW1�̈ɓ��c�[�����O�̉���LP�B
SP�𗣂��Č������ɔ�����悤�ɂ��Č������ǂ����ėV��c
����Ȃ��Ƃ܂Ŏv���o���܂����B
���ɉf�批�y�ōD���������̂́u���̃����i�[�v�e�[�}�ȁB
�I�����s�b�N�ł悭��������ł��B
�u�j�L�[�^�v��L�E�x�b�\���m�̃t�@���ɂȂ邫�������̉f��ŁA
���C���h�ȃG���b�N�Z���̃j�L�[�^�e�[�}�Ȃ��D���ł����B
J�E���m�����̉f�悩��u���[�N���܂����B
�����ԍ��F13205185
![]() 0�_
0�_
-> �f�W�S������
�@�y�c�M�́u�W����̊G�v�́A�����[�X�����͓��l�̃l�^���������G�}�[�\���E���C�N���p�[�}�[�̓����A���o���Ɖ����Ɣ�ׂ�ꂽ�����ł��B�����Ƃ��A�N���V�b�N���ނɂ��Ă��Ȃ��璆�g�́u���b�N���̂��́v�ł�����EL&P�̃T�E���h���A���l�^�J�ɒǂ����i�Ƃ͂����Ă����F�̃A�����W�͂���������_�ł������j�y�c�M�̎d���Ԃ�̕������L���m����悤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł��B
�@���ʉ���LP�ł́A�����S�j���u���p�v���Ă����Ƃ����u���{�̎��q���v�i���������ȁH�j�Ƃ����f�B�X�N���m���Ă��܂����A���͒��������Ƃ�����܂���B�����Ƃ��A�剹�ʂōĐ�����ƃX�s�[�J�[��������ԋ��ꂪ����Ƃ��ŁA���̓_�ł������ÁX�ł��i�j�B
�@�u�����̕��v��TV�̗m�挀��Ō������Ƃ�����܂��B�W���[�W�EA�E�������́u�i�C�g�E�I�u�E�U�E���r���O�E�f�b�h�v�̃C�^���A�ł݂����ȕ]��������Ă����悤�ł����A�剉�̃��C�����h�E�������b�N�͈ȑO�̓A�C�h���I�l�C���ւ��Ă��������ł��ˁB�q���C�����̃N���X�e�B�[�i�E�K���{�͎��͂��܂�m��܂���i�����܂���� ^^;�j�B�u�ۉ�F�̃A�C�h���v���u�r��̕�W�v�������ł��i�����������ł��ˁj�B
�@�u���̃����i�[�v�̉��y�A�����ł��Ȃ��B���y�S���̃��@���Q���X�́u�u���[�h�����i�[�v�Ƃ��u�P�S�X�Q�@�R�����u�X�v�Ƃ��A���ɂ����낢��ǂ��X�R�A������܂��ˁB�G���b�N�E�Z���́u�O�����E�u���[�v�̉��y���ǂ������ł��ˁB�ł��A���̍�i�̃A�����J���J�łł͉��y���r���E�R���e�B�̂��̂ɕς���Ă��������ł��ȁB���X�g�����ς���Ă����ƕ����܂��B
�@���ƂȂ��A�����f�批�y�̘b���������Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�u�{�ECD�EDVD�v�̃R�[�i�[�ɂł��A������߂ĉf�批�y�̎G�k�X���b�h�ł����ĂĂ݂悤���ƍl���Ă��鍡�����̍��ł��i�j�B
�����ԍ��F13208464
![]() 0�_
0�_
���͂Ԃ���т܂����B3��ay�i28�Z���`WF�j�̃V�X�e���R���|��
�������͗ǂ��Ȃ������ł����A���͂т����艽�����Ǝv�����悤�ł��B
����X������x�Ǝv�����̂ł����A���킢�����Ȃ��Ƃ����܂����B
����16�ΑO��̂��Ƃł��B
�V���Z�ł̓L�[�X�E�G�}�[�\�����ʊi�������悤�ȋL��������܂��B
�W����̊GLP����܂�����܂��B
�������f��O�����u���[�̃��f���̓W���b�N�}�C���[�����ł��B
�������w���̍����������{�őf����̐��E�L�^�����܂����B
5�N�قǑO�ɑ��E����܂����B
�ڂ����Ɖf��͎��R�ɐh���ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�C�̐��E�ł̓N�X�g�[�ŗL���Ȃ悤�Ƀt�����X���L���ł��B
�������t�����X���X�[�p�[�W�F�b�g�t�B���i���Ђ�j�͓���ł����B
�����̂̉f��قł̓A���e�b�N���������Ă����L��������܂��B
�f��̔ǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F13209501
![]() 0�_
0�_
�X�s�[�J�[���Ƃ����A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B
�����A�ŋ߃}���V�����w�����A�\�t�@�AC-1VL�ATAOC�A����������
�����o��܂�������A�w���ł��܂���B
�����AP�̓V�̔����ŃA�R�M���G���L�ɕ�������Ɩ^�G����
�f�ڂ�����A����ł��@�Z�b�e�B���O�Ǝv�����̂ł����B�B�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�^���[�R�[���̃{�[�J���͗ǂ��̂ł��B
����[�@�A�R�[�X�e�B�b�N�T�E���h�����������I
![]() 0�_
0�_
�������̔ł��L�тĂ��܂������CCD�~�Ղɖ��@���|���ĉ���ς���B
���̃X���́CCD�~�ՂɃN���C�I���������āC�����ς�邩�ł����ˁB
�����C�����͔���܂��CCD�~�Ղɖ��@���|���܂��B
���@�̃O�b�c�́C�A�R���o�̏������NS�̃l�X�p�ŁC���g�Ŏ����郂�m�������܂��B
���g�p��CDP�́CHT01Ver1.0�i������Ver���オ���Ă��܂����j�Ȃ̂ŁC�O��VRDS�ƈ���āCCD�X�^�r���C�U���g���܂��B
�ŁC����CD���O�������Ė��@�̌��ʂ��m���߂�ƁC�����ς��̂�����܂��B
�w�b�h�z���Œ����ƁC���������ɉ��������ƌ����������ӂ��킵���ł��傤���BCD�X�^�r���C�U���R��ł��B
���̕ω��́C�C���V�����[�^�[�̃T�E���h�N�b�L�[�̂����肪�������ŁC���X�C�ʔ��������ω��O�b�c�ł��ˁB
���������B�A�R���o�̏�����́CMD���f�B�A�ɂ����ʂ��o�ďd�Ă܂���B
![]() 0�_
0�_
3���O�̓��o�V���̑��ʂ̃R�����u�t�H�v�Ɂu�����o�v�Ƃ����̂��ڂ��Ă��܂����B
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20070911AS1K1100211092007.html
�I�[�f�B�I������ɒʂ�����̂�����̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F6758389
![]() 0�_
0�_
�����N��́u�����o�v�́C�g�т��猩��܂��ł����B
�u�����v�Ɓu���o�v�̗Z�����w���ċ���̂ł��傤���H
�u�����v
�������̍m��h�Ɣے�h�ł́C���H�̃��[���Ɠ����Ɍ����܂���ˁB
�����܂ł����s���ł��傤���B�i��������̉S�j
�u���o�v
�����ăi���{�ȕ����ƁC�����Ɏ���ꂸ�̖L���Ȋ����ł��傤���B
���݂ɁC�����͋ɗ͂������h�ŁC�������͉��F�D��h����Ȃ��ł��B
�����ԍ��F6759423
![]() 0�_
0�_
> �����N��́u�����o�v�́C�g�т��猩��܂��ł����B
�O��̃����N��̋L�����̂́A���p�ŏ����ꂽ�L���ł��̂ŁA���̋L���͂ǂ��ł��ǂ��ł��B
"�����o" �Ƃ����p��̌����͂����� �� ����ł��ł��܂��B
http://www.google.co.jp/pda/search?q=%22%E5%85%B1%E6%84%9F%E8%A6%9A%22
> �u�����v�Ɓu���o�v�̗Z�����w���ċ���̂ł��傤���H
�ǂ��Ȃ�ł��傤�B�p�ꂾ�� "synesthesia" �Ƃ����炵���ł��B
5�͗A2�͐ԁA�Ɋ�����l�����݂���̂Ȃ�A�u�N���C�I�v�Ƃ���4����������Ɖ����ǂ�������A�Ƃ������Ƃ������Ă����قǕs�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����̎��̏����킪�����鉹��U���������邱�Ƃʼn����ǂ�������Ƃ����̂����邩������܂���B
CD�̃X�^�r���C�U�[���ƂȂ�ł��傤�B�~���d������Ɖ����ǂ�������H����Ɠ������Ƃ�10�~�ʂ����Ă�����X�s�[�J�[�̉��ɃC���V�����[�^�[�Ƃ��ĕ~���Ɖ����ǂ�������H
���R�[�h��CD���~�`�Ȃ��ƂɗR�����Ă���̂�������܂���ˁB
������ɂ��Ă��A�����o�̉\�������邩�ǂ����́A�u�ӌ��v������Ε����邱�Ƃł��B
���Ȃ킿�A������N���C�I�����Ȃ���͎̂����ł����ɐl�ɂ��Ă��������(or ���Ȃ��ł��������)�ACD������������Ȃ�A�������I�Ԃ̂ł͂Ȃ��l�ɑI��ł��������A�l���I��ł���������̂�����ɕʂ̐l�I��ŁA...�݂����Ȃ��Ƃł��B
�����ԍ��F6760823
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�zcanon�ڍs��
-
�yMy�R���N�V�����zwindows11�ɑΉ��ōw��
-
�y���̑��z���_�p�H
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC
-
�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N11���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
CD�v���[���[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j