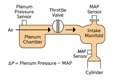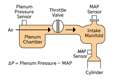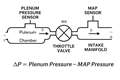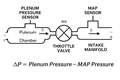���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S31979�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2025�N5��7�� 17:23 | |
| 14 | 4 | 2025�N5��8�� 07:53 | |
| 230 | 129 | 2025�N5��29�� 08:44 | |
| 0 | 2 | 2025�N5��5�� 21:08 | |
| 98 | 28 | 2025�N5��8�� 13:10 | |
| 19 | 5 | 2025�N6��15�� 14:19 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�Č��f�O���j�Y�g���̓d�r�h�ăX�^�[�g���Ӂ@��CCEO�u�������߂��v�V��Аݗ�
https://news.yahoo.co.jp/articles/6172fdd794fae42b6ea05b5781a811025b6f7040?page=1
�@���XAPB�Ђ𗧂��グ���̂́A���Y�����ԂŐ��E���̗ʎY�^EV�u���[�t�v�̎ԍڗp
�@�d�r���J�����A���Y�̃��W�F���h��1�l�ɂ���������x�]�p�����i68�j�ł��B
�S�[�������Y�̃��`�E���C�I���o�b�e���[�Z�p�𒆍��ɔ��蕥���Ă��܂����̂��n�܂�B
����őS�����d�r�̓������f�[�^���S�ė��o���Ă��܂��낤�ȁE�E�E
![]() 3�_
3�_
��͂�u���v�������̂ł���
�����ԍ��F26171543
![]() 2�_
2�_
���W���b�N�E�X�o���E����
������{����܂����I
�����ԍ��F26171875
![]() 0�_
0�_
������ > �X�Y�L > �t�����N�X 2024�N���f��
3�����Ɍ_���V���o�[4wd���f��
�����A�V���o�[�ɓh���s�ǂ�����N���͌���������?�Ɛ������Ă܂�����6�����ɔ[�ԗ\��ƂȂ�܂����B
�Ĉȍ~�ɏo��\���e�o���[�m���ő�ʂɃL�����Z���ł��o���̂ł��傤��?
�܂������͗ǂ��_�������_���������Č_���̂ŃL�����Z���͂��܂��A�A�A
������ƋC�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F26170901�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�o���[�m����Ȃ���e�r�^�[���ł���
�����ԍ��F26171070�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�[�Ԃ��߂łƂ��������܂��I
�����[�Ԃ��߂łƂ��������܂��I
����11�����ɃV���o�[���m�g�[���l����_�܂������A���܂��ɉ����A�������Ă��Ȃ���Ԃł��B
�{���ɃL�����Z���Ԃ��o�Ă���Ȃ玄�̏Z��ł���c�ɂɂ��ė~�����Ɗ肤����ł���〜
�����ԍ��F26171811�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����������ׂ�����
���肪�Ƃ��������܂��B
�_���Ǝv���Ă܂������n��ɂ���ĈႤ�̂ł��傤���B
������������㗝�X�A���K�f�B�[���[�ɂ���Ă���������̂�������܂���B
���݂Ɏ��͐��K�f�B�[���[�Œ������܂����i�l���͖w�ǂ���܂���ł������j
�Ƃ͂��������Ă݂��璍���͂܂������Ă��Ȃ��l�ł��̂Ŕ̔����̊g��ł��������̂�������܂���B
�����ԍ��F26171906�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���̓T�u�f�B�[���[�Œ��������̂Ō�ɂȂ��Ă����ł��ˁB
���ɂ���A�����[�Ԃ��ė~�������̂ł��B
�h���C�u�y����ł��������ˁI
�����ԍ��F26172390�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���̃^�[�{�Ԃ̎З��́A�J�y��2000cc�^�[�{�AFC3S�����^�A�x���c1800cc�^�[�{�A��1600cc�^�[�{�A���݂̓����H�[�O����E�^�A�����ă^�[�{���O�̂��߁A���s�����H�[�O��2.4L�ɏ��p���ł��܂����A�^�[�{���O�͉�������Ă���܂���B����10�N���炢�ŖƋ��Ԕ[�̎������������Ȃ̂łȂ�Ƃ��^�[�{���O�������^�[�{�Ԃɏ���Ă݂����Ɩϑz���Ă���܂��B
�@����AI���g�p���čl���Ă݂��̂ł����A���ЂƂʔ����A�C�f�A���W�܂�܂���ł����B
�G�k�̂悤�Ƀ^�[�{�Ԃ̖���������Ă݂܂��B
�@���X���Ȃ��Ƃ���AI�Ƃ̉�b���������A�b�v���������Ǝv���܂��B
![]() 2�_
2�_
�z���_�d���^�[�{�̂S�։��@�Ɋ��҂��܂��傤
�����ԍ��F26170386
![]() 7�_
7�_
�{���{�ɂ͂ǂ�����
�{���{���X�[�p�[�`���[�W���[�𓋍ڂ��Ă��郂�f���́A���T6�G���W�����ڂ́uS60�v�uV60�v�uXC60�v�Ȃǂ�����܂��B�X�[�p�[�`���[�W���[�́A�^�[�{�`���[�W���[�Ƒg�ݍ��킹���Ďg�p����A���]�悩��̃��X�|���X�����A�^�[�{���O�̌y���ɍv�����܂�
�����ԍ��F26170400
![]() 6�_
6�_
�X�[�p�[�`���[�W���[���V�[�P���V�����^�[�{���ڂ̒��ÎԔ������炢����Ȃ��H
�V�Ԃł��Ă�����2�X�e�[�W�σW�I���g���^�[�{�f�B�[�[���̎Ԏ킩�ȁB
�}�c�_��SKYACTIV-2.2D�Ƃ�BMW�Ƃ��B
�����ԍ��F26170406
![]() 8�_
8�_
���^�[�{���O�������^�[�{�Ԃɏ���Ă݂���
������ă^�[�{�Ԃɂ������Ӗ�����H
NA�����ă����b�Ɨ͂��o�Ă���p���[�o���h�͂��邵�ˁB
�^�[�{���O�A�����p���[�o���h�����炱���A
��������肭�g�����Ă����y���݂��L�郏�P�����A
��R��u���̒ሳ�^�[�{�ɏ����Ď�����邯�ǁA
�ǂ����Ă���胊�j�A�ȗ͊����~�����Ȃ�A
�d���쓮�Ԃ�I�Ԃ����Ȃ���ˁB
�����ԍ��F26170409
![]() 16�_
16�_
���r�C�ʉ��ň��k����グ�A���^�^�[�r���ʼnߋ�����������_�E���T�C�W���O�^�[�{�̓^�[�{���O���ɒ[�ɏ��Ȃ��ł��B
1.5L�_�E���T�C�W���O�^�[�{�Ԃɏ���Ă܂����A�^�[�{���O�͂قڊ����܂���B
���]�̔r�C���ʼn鏬�^�^�[�r���ƍ���]�p�̃^�[�r�����g��������V�[�P���V�����c�C���^�[�{�G���W�����^�[�{���O�����ړI�̗ނł��傤�B
���S�ɖ��������߂ɂ̓N�����N��]�ɂ��ߋ��o����X�[�p�[�`���[�W���[���炢�����Ȃ��̂��ȁB
�����ԍ��F26170417�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 10�_
10�_
���^�[�{���O�������^�[�{�Ԃɏ���Ă݂���
�y�ʋ��̑�r�C�ʎԂ��Ċ����ɂȂ邩�ȁB
�����ԍ��F26170428
![]() 6�_
6�_
��haghog����
���q�v�w���A�E�f�B A3 �X�|�[�c�o�b�N 30 TFSI S line�ɏ���Ă��܂����A�Ȃ��Ȃ��ǂ��Ԃł��B
���݂�1500�t�{�^�[�{�{�d���A�V�X�g�ł����A���q������Ă���̂͂���1000�t�ŁB
�o������HV�ŕ���Ă���悤�ŁA�^�[�{���O�͂��܂芴���Ȃ��Ƃ̂��ƁA���悵�Ă݂��́H
https://kakaku.com/item/K0001350667/catalog/GradeID=64733/
�X�o����CB18�{�^�[�{�{��HEV���l������悢�Ǝv���܂����H�@���͉��i�ł��傤���B
�����ԍ��F26170432
![]() 6�_
6�_
�^�[�{�̂Ȃ�����̓n�C�J����g��ŃJ���ɏ�銴�����y���������ł��B
�^�[�{���o�ė��ă^�[�{���O�Ƃ��悭��肾����Ă��܂������h�b�J���^�[�{�͑�D���ł��B
�����Â炢�ł��傤������Ӗ����т�܂��B
�J���ɏ��̂Ɠ����Ȃ�ł���ˁB
�^�[�{���O�̖����ԁc�H
��r�C�ʂ̑�^�g���b�N���ɂ̓��O���Ȃ������ł���B
�����ԍ��F26170457�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
���^�[�{���O�������^�[�{�Ԃɏ���Ă݂����Ɩϑz���Ă���܂��B
�^�[�{���ĉ�]���オ��قǁA��������ė͂��o��Ƃ����Ƃ̂ł��ˁB�^�[�{���O������̂̓^�[�{�ԂȂ�A������O�Ȃ̂ł́B
�����̒Njy�ł��ˁB
�^�[�{�̉�ꂽ�^�[�{�Ԃ��A�������������I�}�P�̂悤�ȃ^�[�{�������^�[�{�Ԃł��傤���B
�撣���ĉ������B
�����ԍ��F26170459�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���Ђ�N�Ђ�N����A����ɂ��́B���߂܂��āB
�ŏ��̃��X���肪�Ƃ��������܂����B�d���A�V�X�g�^�[�{�Ƃ����l�����͂����Ƒf���炵�����X�|���X�ݏo���Ă����̂ł��傤�ˁBHONDA���o���̂����烌�X�|���X�d���Ǝv���܂��B�����^�[�{�Ƃ����~�M���u�̂��Ƀ��[�^�[�Ƃ��������u����邱�Ƃ��S�z�ł��B���C���e�i���X�t�B�[����ς��Ǝv���܂��B
���Ȃ݂�AI�ɕ����Ă݂��Ƃ���
���z���_��F1�ł�**MGU-H�i�r�C�G�l���M�[���u�j**�͐M�����m�ۂɋ�J���Ă܂���
�Ƃ������ł����B���͂ŗ�����]��lj����i���Ȃ��Ă��o������@���Ȃ������l���Ă��܂��B
�����ԍ��F26170474
![]() 3�_
3�_
���́A���U�E�r�[�g���ɏ���Ă܂����B
�_�E���T�C�W���O�^�[�{�A
1200cc�A�P�O�T�n��
�͂Ȃ��̂ŁA�^�C�����O���܂芴���Ȃ����A
�^�[�{�Ǝv���Ă܂���B
�t�H���N�X���[�Q���A�J�^���O�ɂ��A
�^�[�{�̎咣���Ă܂���A
�ʂɂQ�O�O�Occ�̃^�[�{�Ԃ���܂����A
������͎Ԗ��Ƀ^�[�{�����Ă܂����ˁB
���̂��^�[�{�Ȃ̂ɁA�^�[�{����搂��ĂȂ��B
�^�[�{�Ƃ����̂��C�p���������̂��ȁB
���̒��x�̎ԂȂ�A�^�[�{���O�����Ȃ��ł����ˁB
�p���[�̖����^�[�{�Ԃɏ���Ă��������B
���炢�����܂����B
�����ԍ��F26170481�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�d���A�V�X�g�̃^�[�{��������̂ЂƂł����E�E�E
���ǂ��̎ԂŃ^�[�{���O��������قǂƂ́A�����A�N�Z�����[�N���X�C�b�`ON-OFF�I�ɂȂ��Ă��܂��H
���Ȃ݂Ƀ}�c�_��CX-60��PHEV�́A�f�r���[�����̓^�[�{�̑���Ƀ��[�^�[�ڂ����ƌ����Ă��悤�ȁE�E�E
2.5L��NA�Ƀ��[�^�[�t���ăV�X�e���o��323�n��
�R���d��͂���قǗǂ��킯�ł͂Ȃ��A����i�����j�ɐU���Ă��炵���ł���
�X�|�[�c���[�h�ł͏�ɃG���W���쓮�ŁA�A�N�Z�����ݍ���ő���Ȃ����̓��[�^�[�ʼn���
�܂������X�|�[�c�J�[�̃^�[�{�̍l�����ƈꏏ
�ɒ[�Ɍ����A���łɁAEV���s���ł���Ƃ����l�����������炵���ł���
���ƁA����̓��[�^�[�̌��ɕϑ��@������̂ŁAEV���s�ł�8�i�ϑ��炵���ł���
�������X�|�[�c�J�[�I�Ɍł߂āA��ʃC���[�W�Ƙ������Ă��܂����̂ŁA���Â͂������Ȃ��Ă܂���
����̕ϑJ�̓r���ɏo�������Ȃ̂ŁA��������ȎԂ͖����Ȃ��Ă�����������܂���
�E������
�����ԍ��F26170482
![]() 6�_
6�_
���P�Ƃ炼������A����ɂ��́B���߂܂��āB
�X�[�p�[�`���[�W���[�{�^�[�{�`���[�W���[�A�ǂ��ł��ˁB�܂��ɒ葬�̓X�[�p�[�`���[�W���[�ō���]�̓^�[�{�łƌ������ɂ��Ȃ������@�ł��ˁB
�̃S���tTSi���������̎���Ԃɏ�������ɁA���X�|���X�čl�R������Ȃ肢�����ł����B
���̎��v�������Ƃ̓X���b�g���O�̈���������Ԃ������X�|���X�͗ǂ��Ȃ�Ƃ������ł�������͂�A���C���e�i���X������Ƃ̖ʂ��炷��Ƒ�ςȂ̂ł͖����ł��傤���B
��肪�Ȃ���݂�ȃX�[�p�[�`���[�W���[�{�^�[�{�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���̓��C���e�i���X�t�B�[�ɂ���������Ă��܂��B�̐F�X����������p�����o��������̂�
AI�ɃX���b�g���O�̈����v���i�����ƌ������t���K���܂����B
��������肭��������̂����ǂ��̂��ȂǂƎv���Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F26170498
![]() 3�_
3�_
�ߋ��@���G���W���̔r�C�G�l���M�[�ʼnĂ�̂ŁA�^�[�{���O�Ȃ��͌����I�ɂ��蓾�Ȃ��̂ł́H
�A�N�Z�����ݍ��ށ��G���W���p���[�A�b�v���r�C�G�l���M�[�A�b�v���ߋ��@�ʼnߋ�������Ƀp���[�A�b�v�B
���ݍ��݂���A����Ƀp���[�A�b�v�܂ł̃^�C�����O�͓��R�ł��ˁB
�����ԍ��F26170504�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
��MIF����A����ɂ��́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂����B�]��ۂ̎Ԃ̐V�@�\�ɑa���̂�AI�Ɏ������W�߂ĖႢ�܂����B
AI�́�SKYACTIV-D��BMW�̉σW�I���g���^�[�{�iVGT�j�́A�ᑬ�g���N�ƃ��X�|���X�̗�����_�������ɗD�ꂽ�v�ł���ˁB
�Ƃ������ł����B�����lj����蒲�ׂĂ݂܂������A���̓V���O���^�[�{�̖����������̉��ǂŏo���Ȃ������ƍl���Ă��܂��B�c�C���^�[�{���ǂ����A�X�J�C�A�N�e�B�����ǂ��̂ł���������ǂ����@�͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
���B�Ԃ̒��Â͖��͂�����̂ł����A�C����p���l����ƍ��̎����ł͏�������Ƃ��낪����܂��B
�ł��A�A�h�o�C�X�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�܂������Ћ����Ă��������B
�����ԍ��F26170506
![]() 4�_
4�_
��JamesP.Sullivan����A����ɂ��́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂����B�����Ƃ��ȃ��X���Ǝv���܂��B�A�N�Z�����X�|���X��������NA�ɂ͂��Ȃ��܂����ˁB�ł����̓^�[�{�̃g���N�����Y����܂���B����2000〜4000��]�̕������g���N���͎̂Ă��܂���B
��R��v�l�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��K�v�Ȏ��ɂ̓p���[���p���[������Ȃ����ǁA���X�|���X���~�����ƌ����C�����ł��B
�܂�EV�Ԃɂ͏�������Ƃ�����܂��A�n�C�u���b�h�Ԃɏ�������ɓd�r�̏d�ʂɈ�a���������܂�����EV�͖������W�r��̋@�B�ł��B�q���̎��Ƀg�����[�o�X�ɏ�������Ƃ�����܂����A���̃p���[�͂Ȃ߂炩�Ő����Ǝv���܂����B�ł����͓d�r�̖�肪�������Ȃ��ƂƎv���Ă��܂��B
�����ԍ��F26170515
![]() 4�_
4�_
2025/05/06 11:06�i4�����ȏ�O�j
�^�[�{���O�����Ȃ����ς�d���A�V�X�g�^�[�{���ڎԂ���Ȃ��ł����ˁH
�����Z�f�X�Ƃ����̗p���Ă�̂ŐM�����͖��Ȃ��ł��傤���AF1��MGU-H�قǕ��G�ł�����܂��B
�Ƃ͂����^�[�{���O�̂ł�͈͂̓M�A�{�b�N�X���̃��[�^�[�ŃA�V�X�g���āA�^�[�r���̉�]���������G���W���ɔC���鐧�䂪�R�X�g�I�ɂ������I���Ǝv���܂��B
���B�Ԃɂ悭����_�E���T�C�W���O�^�[�{+�n�C�u���b�h�Ԃ͂��̕���������Ȃ��ł����ˁB
�l�I�ɂ͒ᑬ�g���N�ƃ��X�|���X�Ȃ�EV���x�X�g���Ǝv���܂��B
�G���W���ԂƂ͑S���Ⴄ������������ƂĂ��y�����̂ŁA����������Ȃ��Ȃ為�ЂƂ�����Ă݂鎖�������߂��܂��B
�����ԍ��F26170561
![]() 5�_
5�_
��kmfs8824����A����ɂ��́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂����B
�_�E���T�C�W���O�^�[�{�ǂ��ł��ˁB�x���c��1600cc�^�[�{�����H�[�O��1600cc�^�[�{�ǂ�����ƂĂ����X�|���X���ǂ��C�ɓ����Ă��܂����ǂ����3�N�Ԃ�7���L���ȏ�̂鎖�ɂȂ�܂����B
������������]����ɃX�o���̖��Ȃ̂ł������]�悪1100��]�O��ł���A�N�Z���ݍ��ނƃ��X�|���X���������߃X���b�g���J�x��50�����炢�ɂȂ��Ă��܂��܂����B����͒��]�ł̓^�[�r��������Ă��Ȃ����߂��ȂƎv���܂����B
����Ȃ�Ƃ��̐l���ŏ��߂�2.4L�^�[�{�ɏ������̂ł��B�ł��j�������Ƃ��������̃^�[�{���O���L��K���R�Ă��Ă��Ȃ��������܂����B
�A�b���r�C�ʂɂ͑傫�ȃ^�[�r�����t���ȂƂ��������ł����B�����Ȃ�Ƃ�͂�X�[�p�[�`���[�W���A�V�X�g�Ȃ̂��ȂƂ��v���Ă��܂��܂��B
�ł�2.4L�̃g���N�����Ȃ��̂��c�O�ł����B�X�[�p�[�`���[�W���[�t���ɂ���ɂ͑�������V�Ԃ̍w���ɂ��Ȃ�܂����A����Ń^�[�{���O�����H�v�Œ�R�ƂȂ��Ă���^�[�r����̃C���^�[�N�[���[�Ȃǂ̒�R���l������u��C�̓͂����v�������Ə�肭�]�����Ă�������@�͂Ȃ��̂��ȂƂ��l����悤�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F26170577
![]() 3�_
3�_
�������CJr.���X���肪�Ƃ��������܂����B���߂܂��āB
���ɂ���Ȃ̂�������܂���l�B�̂̔��X�J�݂����Ȋ����B
��r�C�ʂŃ��X�|���X�̌����G���W���B�y�ʃ{�f�B�A�ł����̎���ɂ͍���Ȃ��ł���ˁB���ꂪ�c�O�B
�P�[�^�[�n�C���݂����Ȍy�ʃ{�f�B�ł�1600cc��NA�ł��y�����^�]���o���܂����̂ˁB
�ł��ANA�ł��A�N�Z�����X�|���X�������Ȃ邱�Ƃ�����܂���ˁB�R�ԕ��̓���2000M���z����ƃ��X�������Ȃ��Ă��܂��B
����Ɠ��������^�[�{�ł��N�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��܂����BYouTube�̃g�~�^�N�`�����l���ʼn�A4G�G���W���ɃE�F�[�o�[��t���ĉ�1.5m���炢�͊��ꂽ�Ƃ���ł���C�̐U�����`����Ă���ƌ����V�[��������܂����B
�G���W�����Ƌ�C���ĐU�������ł��ˁB
����łӂƎv�����̂ł����A
�^�[�{���ċ�C���ɉ�������ł�Ԃ�A�u��Ɉ��͂��邯�ǁA�̐S�̋�C�́g�{�́h���܂��͂��ĂȂ��v���Ă��Ƃ������Ȃ����ƁB
�ȂǂƖϑz���Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F26170594
![]() 3�_
3�_
��haghog����
��NA�ł��A�N�Z�����X�|���X�������Ȃ邱�Ƃ�����܂���ˁB�R�ԕ��̓���2000M���z����ƃ��X�������Ȃ��Ă��܂�
����́A�p���[�������邩��B
���x�Om�Ɣ��80���قǂ̋�C���x�����Ȃ��̂ŁA�R�Ăł���K�\�����̗ʂ�����A�p���[�������܂��B
�A�N�Z���y�_���̓����ɑ��āA�G���W���o�͂����ΓI�ɏ������Ȃ邽�߁A���X�|���X���u�����v�悤�Ɋ����邾���ł��B
�����̏�ł́A�^�[�{�͉ߋ���������܂�����A�p���[�_�E���͏��Ȃ��͂��ł��B
���Ȃ݂ɁA660cc�̃^�[�{�i�R�y���j�ƃX�[�p�[�`���[�W���[�i�T���o�[�j�̗���������Ă܂��B
�����炩�ɃX�[�p�[�`���[�W���[�̕����A�A�N�Z�����X�|���X�͗ǂ��ł��i����Ă��Ċy�����B�x�����ǁj
��EV�Ԃɂ͏�������Ƃ�����܂���
�A�N�Z�����X�|���X�Ȃ�AEV�̕����͂�����Ə�ł��B�g���N���������������B
������12�N�O�A�͂��߂ă��[�t�Ɏ��悵�����A�Ƃ���R���̏���A���̃^�C�g�ȃR�[�i�[�ŁA
�������邽�߂ɃA�N�Z���ݍ����ɖڂ�����|���|�������܂����B
�����āA���[�t���Փ��������Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F26170713�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��haghog����
���X�[�p�[�`���[�W���[�{�^�[�{�`���[�W���[�A�ǂ��ł��ˁB
�}�[�`�@�X�[�p�[�^�[�{���v���o���Ă��܂��܂��B
���ׂ���A���ÎԂł܂������Ă����ł��ˁB
�낪�����Ԃ�������������ł����B
���̎Ԃ��^�[�{�Ԃł����A���O�͂��܂芴���܂���B
�ԏd���y���̂����邩������܂���B
�����ԍ��F26170725
![]() 3�_
3�_
���������r�C�ʂȂ�̃p���[���A�ߋ��Ńh�[�s���O����̂��^�[�{�B�h�[�s���O�̖r�C�Ȃ�A�r�C�������Ȃ��ƌ����Ȃ��͓̂�����O�B
�����^�[�{�i�_�E���T�C�W���O�܂ށj�͂��̗}���ɂ͑����撣���Ă���Ǝv���܂����ǂˁB
�����ԍ��F26170822�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��ZXR400L3����
�c�C���`���[�W���[���������߂���Ƃ��������̃��X�ł��B���{�ł̓}�[�`�����ł����ˁB
�}�j�A�b�N��AE92�ɏ���Ă܂������A�X�[�p�[�`���[�W���[���f���ւ̃^�[�{�L�b�g������A���������ł��ˁBFD3S����Ă�Ƃ�������܂������A�V�[�P���V�����^�[�{�����p��ł̃��O�͂��܂薳�������悤�Ɏv���܂��ˁB�h�b�J���V���O�����y�����ł����ǂˁB
�����ԍ��F26170826�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
������ς�Y������
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�w���̍��AAE91�̃X�[�`���[��݂��Ă���������Ƃ�����܂������A�^�[�{�Ԃ̂悤�ȊJ�����i�Ԋi��������̂����j������ƁA������ƕ|�������ł��i�肽�g�Ƃ��ẮA���Ă���A�J���̂ŁE�E�E�j
�b�x�~
���̂��Ayoutube�Ŗ������̓��悪�オ���Ă��܂��i�j
�X�C�t�g�ɔ��̃G���W���ڂ��܂��Ƃ��i����11000���������܂��j
�����ԍ��F26170889
![]() 3�_
3�_
��ZXR400L3����
AE101��SC�Ԃ̏���Ă��܂������A�Z�h�A�O���i2.5��3.0���͕s���j�̕����g���N��������
�r�C�ʂł���͏����˂�ƒɊ����܂�����
�����ԍ��F26170924
![]() 4�_
4�_
���烉�O������������Ԃ��~�����Ȃ�EV�����Ȃ��̂ł́B
EV�����Ȃ�ePower�Ƃ�eHEV�Ƃ��V���[�Y�n�C�u���b�h�ł����ˁB
�����ԍ��F26170941
![]() 4�_
4�_
2025/05/06 17:45�i4�����ȏ�O�j
�����Z�f�X�̂QL�N���X�̃^�[�{�G���W���i���͂���Ȋ����̂悤�ł��B
���Q�O�O�Q�|�Q�O�P�T�@���P�W�O�i�P�D�W�k�jM271����F�@
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M271_engine
�σo���u�^�C�~���O����n�܂�A1��X�[�p�[�`���[�W���ɂȂ�A
�����ƍĂу^�[�{�`���[�W���ɖ߂�A���̌㎟�����
���Q�O�P�P�|�Q�O�Q�O�@���Q�O�O�i�QL�j�@M274����F
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M270/M274_engine
�R�k�N���X�̒u�������̃_�E���T�C�W���O�G���W��
���Q�O�P�V�|�Q�O�Q�P C200�i�P�D�UL�j�@�l�Q�U�S����F
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M260/M264_engine
�c�C���X�N���[���^�[�{�ɕύX�B
�r������O�����肳��Ƀ_�E���T�C�W���O���P�D�T�k�ɂ��I���^�l�[�^��
�@���[�^�A�V�X�g����@�\���̗p�B
���Q�O�Q�Q�|�@���Q�O�O�@�l�Q�T�S����i�P�D�UL-2L�j�F
���̌�G���W����AT�ԂɃ��[�^��z�u�S�WV�A�V�X�g�n�C�u���b�h�V�X�e���ɕύX�B
�����ԍ��F26170966
![]() 3�_
3�_
�ӂƎv���܂������E�E�E
EV�Ȃ�A�Ȃ�����A�킴�ƃ��O�̂悤�Ȑݒ�����Ă��ł��傤��
�����ȗ̈�ŁA�ǂꂾ����a���Ȃ��l�̊��o�ɋ߂Â��A���S�Ɉ��肳���A�@�B�I���ׂ����点�邩�E�E�E
�܂��g���N�V�����R���g���[����VSC�������Ƃ��Ă��A�X�C�b�`ON�̃f�W�^���I�ɋ쓮�͂𗧂��グ�邱�Ƃ́A�ԗ��J����������������͔���������Ȃ�����
�����ԍ��F26170979
![]() 3�_
3�_
���A�h���XV125.���l����
���Z�h�A�O���i2.5��3.0���͕s���j�̕����g���N��������
���́A�M���̋t���������̂ł��傤�ˁB
�n�͂����A�������͌y���̕��Ɍ����Ă܂����B
�i64�n�͂����Ȃ��̂ŁE�E�E�j
����Ɋւ��ẮA����Ӗ������͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F26170982
![]() 3�_
3�_
��ZXR400L3����
�F�l�̏���Ă������B���B�I��v���I��SC�ł��s���͊����܂���ł������ǂ�
�X���Ɍ����Ăł����ǁE�E
������7�����[�h���ƑS�R�]�͂�����̂ɑ��x���~�b�^�[�ɓ�����̂��s���ł�����
�����ԍ��F26171007
![]() 4�_
4�_
��ZXR400L3����
���A�h���XV125.���l����
�g�C�`�̕�����������Ⴂ�܂��ˁB�����͂����ȕ������̃X�|�[�c�ł�����ˁB�r�[�g�A�J�v�`�[�m����GTO�݂����ȃw�r�[���n�C�p���[�܂ŁB���������ł��B
�������@�ނقǂނ�����������
�ʔ����ł��ˁB
���{�Ԃł�������ė��j��H���Ԃ��āA�����͂Ȃ��ł���ˁB
��haghog����
����Ȃ��牡������܂����B
�ߋ��̃^�[�{�ɑ�����҂ƁA���^�[�{�ɑ�����҂��߈Ⴄ�Ȃ��ĉ��߂Ďv���܂����B���������X�|�[�c�J�[�����Ȃ��Ȃ�܂�������ˁB
�����ԍ��F26171009�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��haghog����
�^�[�{���O�̂Ȃ��Ԃɏ�肽���̂ł����H
�n�C�G�[�X�̃f�B�[�[���ɏ��Ή������܂���H
�����ԍ��F26171086�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�����C������A����ɂ��́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
�͂��J����g��łƌ����o���͂���܂��A���̋����ɓ��ꂽ���オ����܂����B�r�K�X�K�����n�܂��Ă����̂ŏ�邱�Ƃ��o���Ȃ������̂��c�O�ł��B
�h�b�J���^�[�{�̘b�͓�����CarBoy�ɂ悭�o�Ă����`�{���[�V���O�̂��Ƃ��v���o���܂����B
NC���o���n�C�J���A��^�^�[�r���Ȃǎ�̓͂��Ȃ����Ǔǂ�ł��邾���ł킭�킭���鎞��ł����B
����^�g���b�N�ɂ̓^�[�{���O���Ȃ������ł��B
�o���������̂ʼn���܂��A��͂背�X�|���X�ƌ��������R�����������p���[�ƌ������ƂȂ�ł��傤�ˁB
�^�C�����O���ĎR�������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��ȂȂǂƍl���Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F26171087
![]() 2�_
2�_
���o�j��0525����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂����B
�m���Ɂ��^�[�{���ĉ�]���オ��قǁA��������ė͂��o��Ƃ����Ƃ̂ł��ˁB�^�[�{���O������̂̓^�[�{�ԂȂ�A������O�Ȃ̂ł́B
�����̒Njy�ł��ˁB
���͂��̖������l���Ă��܂��BNA����̓G�A�t�B���^�[����C��R�ł����B�^�[�{���G�A�t�B���^�[�Ɠ����悤�ɂ��̊Ԃɂ������̒�R������ƍl���Ă��܂��B�@NA�̔R�����G�A�t�B���^�[�L��Ɩ����ł͕ς���Ă��܂���ˁB
����Ɠ����悤�Ƀ^�[�{���l���Ă݂悤�Ǝv��������ł��B��C�͎��ʂ̂���S�̂ƍl����̂���������ł͑厖�Ȏ����Ǝv���܂��B�A�C�h�����O�̎��^�[�{�͗]�����Ă��܂���B�����Ė��̎���2000��]�����ƃ^�[�r�������n�߂܂����[���ɉ���Ă��܂���2500��]���炢����ߋ����̏���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���Ȃ킿�A�^�[�r���������Ȃ��ŋz�C��R���ς�錻�ۂ��N�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�^�[�r���͋�C�𑗂�d�������Ă���̂Ń^�[�r���̎d���ʂ�]�����Ȃ��ƔR���͐������Ȃ��Ƃ����ƍl���Ă��܂����B���̋L���ł̓^�[�r���̉�]���𑪒肷���B���o���悤�ȋC������̂ł������y���Ȃ������̂͂����ɖ�肪���������߂��Ǝv���܂��B
������AI�Ƙb������ăX���b�g���O�̓������^�[�r���ƃC���^�[�N�[���[�̎d���ʁA��R�ʂ𑪒�ł���̂ł͂Ȃ����ƌ������_�ɂȂ�܂����B
���ꂪ�v���i�����Ƃ������t�ɂȂ��ċA���Ă��܂����B
�����ԍ��F26171099
![]() 1�_
1�_
���o�j��0525����A�ēx�A���ӂ́B
���p���[�̖����^�[�{�Ԃɏ���Ă��������B
�X�~�}�Z���A���̒ʏ�̃h���C�u�X�^�C���͑�l3�l�Ƀ����R2�C�̏d�ʂɃJ�����Z�b�g���悹��̂���ł��B���k�����ԓ��ł͒ǂ��z����̃X�s�[�h���ُ�ɑ����̂Ńp���[�̖����^�[�{�̑I���}�͂Ȃ��̂ł��B
���߂�Ȃ����A��|�ɉ���Ȃ��āB
�p���[���o����G���W���i2.4L�j�Ȃ̂ɂ܂��p���[���o���邾���̋�C���}�j�z�[���h�ɓ͂��Ă��Ȃ���Ԃ��^�C�����O�Ȃ̂��Ȃƍl���Ă��܂��܂����B�p���[�ɂ͋�C���K�v�ł��B
�����ԍ��F26171107
![]() 2�_
2�_
���˂��݂���B����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��BNA�{EV�͍ŋ߂̂͂��ł����A����ł�������Ȃ��悤�ȃ}�c�_�̂���܂��I�Ɋ������Ă��܂��B���͈ȑO�J�y����FC3S�ɏ���Ă����̂ŎԂ̖��t���̗ǂ��͗ǂ������Ă��܂��B�p���[�S�U��Ȃ̂��}�c�_�̃G���W�j�A���������肩�˂܂���ˁB
���R���d��͂���قǗǂ��킯�ł͂Ȃ��A����i�����j�ɐU���Ă��炵���ł���
����D���ł���(^_^)�B
���āA�b��߂��܂����A����̓n�C�p���[�^�[�{�Ȃ̂Ƀ��O���ǂ����������̍H�v���l���Ă��܂��āB
�d�����[�^�[�̂悤�Ɂu��C��R���Ȃ��v�Ȃ甽�����s���ł����A
�^�[�{�͋�C�Ƃ����g���ʑ́h���������Ă���̂ŁA�����ɉ^���ʂ⊵���̒x�ꂪ�����ł���ˁB
�����ɋ߂Â��Ȃ��܂ł��A�u��C���܂��͂��ĂȂ��v�Ƃ������O������̂ł́H
��������ȉ�������A�������T���Ă݂Ă���Ƃ���ł��B
�����ԍ��F26171117
![]() 3�_
3�_
���i�C�g�G���W�F������A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���ɍŋߋC�ɂȂ��Ă���̂́A
�^�[�r���͉ߋ���ł���Ɠ����ɁA�z�C�n�́g������Ղ鑶�݁h�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł́H
���̉e���ŁA�R���}�b�v�ł̓}�j�z�[���h���ŔR������Ă���ꍇ�������Ǝv���܂����A�u�X���b�g���O�ɂ͍���/�ሳ�i�v���i�����j������̂ɁA�X���b�g����̃}�j�z�[���h�������ŔR�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��܂��B
�}�j�z�[���h���ł͂��́g��C���͂��ĂȂ��̂Ɉ������オ���Ă���h�Ɓh��C���͂��Ă���̂Ɉ������Ⴂ��ԁh�̏ɂ����āA
ECU�̓}�j�z�[���h���̈����������Ă���ƃ^�[�r���̒��]��͊댯�ȏ�ԂŁu��R�䂪�����Ȃ�댯��������邽�߂ɁA�R���𑽂߂ɏo������v�����Ă���\��������܂��B���ɃG���W���S�J��ˑR�̃A�N�Z���I�t���ɔ�������Ǝv���܂��B
�܂�A�����I�ɂ͂܂��z�C�������Ă��Ȃ��̂ɁA�R����������ɏo�Ă����Ԅ������ꂪ�g�Z��������R���̃^�C�����O�h��ł���̂ł͂Ȃ����ƁB
����**�u�R���͑��������邯�ǁA��C�ɂ͎��ʂ�����v**�Ƃ����M���b�v�B
�����Ɂg���̃^�[�{���O�h�̖{��������̂ł͂Ȃ��������ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F26171137
![]() 3�_
3�_
�����j�o�[�T���Z���`�����[����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���^�[�{���O�����Ȃ����ς�d���A�V�X�g�^�[�{���ڎԂ���Ȃ��ł����ˁH
�܂����͎����Ă��Ȃ��̂ŗǂ�����܂��A�d�C���[�^�[�ɂ��A�V�X�g�̓G���W�����ᑬ�g���N���L��f�G�ȑ�������邱�Ƃ͋^���̂Ȃ��������Ǝv���܂��B
���^�[�{���O�̂ł�͈͂̓M�A�{�b�N�X���̃��[�^�[�ŃA�V�X�g���āA�^�[�r���̉�]���������G���W���ɔC���鐧�䂪�R�X�g�I�ɂ������I���Ǝv���܂��B
�������̉������@�ł��ˁB�����Ƒf���炵�������������ł��傤�ˁB���B�̃G���W�j�A���킭�킭���č���Ă���̂��ڂɕ����т܂��B
�ł����ɂ͂܂����c�������Ƃ��L��̂ł͂Ȃ����Ǝv���čl���Ă��܂��B���{�l�I�ȍl�����Ȃ̂��ɂ߂�܂Ő�ɂ͐i�߂Ȃ��Ƃ����̂��A���͓����ł��̂ł�����(^_^)�B
�����ԍ��F26171147
![]() 2�_
2�_
��haghog����
���v���i����
���ɂ͕�����܂���ł����B
�i��Ƀ��P�b�g�Ȃ�Łj
�C���}�j���͋z�����́A�u�[�X�g���͋z�����܂��悤�Ƃ��鈳�͂Ƃ������߂ł��B
ODB2�Ō��Ă�̂ŁA�C���}�j�����u�������v�����ɂȂ�̂́A�A�N�Z���I�t�̎��i-6.6��-7.5×100Pa�j�݂̂ł��B
������A�A�N�Z���I���̎��̓^�[�{�ԂȂ爳�����悤�Ƃ͂��Ă��܂����A�|���邾���̈��������̂����ˁB
�i���������́A�Ԃɂ��̂ŁE�E�E�j
���̎Ԃ́A�u�[�X�g�͔�r�I�ȒP�Ɋ|����܂����A�������+1.1�͊ȒP�ɍs���܂��̂ŁA���~�b�^�[�̃S�j���S�j��km/h�܂ł��悤�Ǝv���ΊȒP�ɂ����܂��B
�C���}�j�ɋ�C�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂���B
2.4L�Ȃ�đ傫���̂��g���Ă邩��ł́H���āA���I�ɂ͎v���܂��B
�i�y���̂��D���Ȃ�ŁA����ȏd���̂���������Ƃ͂Ȃ����ǁE�E�E�j
�����p���[�̖����^�[�{�Ԃɏ���Ă�������
���́A64�n�͂̌y���^�[�{�Ԃɏ���Ă��������ł�����
�����ԍ��F26171148
![]() 2�_
2�_
��haghog����
�������Ă�����ʔ����L�����������̂œ\��܂�
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14208827064
�����ԍ��F26171161
![]() 3�_
3�_
��tarokond2001����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
������́A�p���[�������邩��B
�����A�p���[�������邩��B�ł��ˁB������{�����Ǝv���܂��B�^�[�{���O�����̎��Ƀp���[�������Ă��邩��Ƃ������ȂƎv���܂��B���Ńp���[�������Ă��邩�����ɂȂ��Ă��܂��B�R���Ȃ̂��A�\���Ȃ̂��A�l�����郂�m������Ă��Ȃ��̂Ȃǂ��l�����܂��B
���͍l�������������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�������̏�ł́A�^�[�{�͉ߋ���������܂�����A�p���[�_�E���͏��Ȃ��͂��ł�
�S�����̒ʂ�ł��B
80�N�O���{�̏�����ł����a-29�ɂ̓^�[�{�G���W�����ς�ł���A���{�̔�s�@�ɂ͂r�b�i�X�[�p�[�`���[�W���|�j���ς�ł���܂����B�p���[���o���ɕ����Ă��܂����̂ł��B
�������炩�ɃX�[�p�[�`���[�W���[�̕����A�A�N�Z�����X�|���X�͗ǂ��ł��i����Ă��Ċy�����B�x�����ǁj
�r�b�̕����A�A�N�Z�����X�|���X�͗ǂ��ł�
SC�̗ǂ��͂�͂胊�j�A�ȋ쓮�ɂ�鑦�����ł���ˁB
�����A����]��ł͂��̋쓮���̂��̂���]��R�ƂȂ��ăp���[��D���Ă��܂��B
���̈Ӗ��ł́ASC���^�[�{�ւ̗���͍����I�Ȑi���ƌ����邩������܂���B
���A�N�Z�����X�|���X�Ȃ�AEV�̕����͂�����Ə�ł��B�g���N���������������B
����͋^���悤�̂Ȃ������ł��B�d�u�ł͗L��܂���NOTE�@�d�p���[�ɂ͏�������Ƃ�����܂��B�ᑬ����������̃g���N�͎������Ă��܂��B�����d�u�ɂ͏���Ă��Ȃ������ł��B
���A�N�Z���ݍ����ɖڂ�����|���|�������܂����B
���̎����ɋ߂����̂������܂����B�����������ɂ����d�u�n�̂��̂��Ƃ�����NOTE���ȂƎv�������炢�ł�����B
�����ԍ��F26171163
![]() 2�_
2�_
��ZXR400L3����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
�}�[�`�X�[�p�[�^�[�{�̂��Ƃ��v���o���Ă��܂������ǂ̎Ԃ��������Ă��܂���ł����B
�m�����̍��`���[�{�Ƃ������Ă����C�����܂��B�ق�Ƃ��ȋL���̒��ō���Ă��܂������t��������܂���B�Ƃ��Ă��܂����˂m�h�r�r�`�m�́B
�����̎Ԃ��^�[�{�Ԃł����A���O�͂��܂芴���܂���B
���O���C�ɂȂ�Ƃ��̕ӂ�̉�]����g�p���Ă܂��܂��T��o�����Ƃ��Ă��܂��܂��B�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�Ȃ���Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26171178
![]() 1�_
1�_
���R�s�X�^�X�t�O����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
�����������r�C�ʂȂ�̃p���[���A�ߋ��Łg�h�[�s���O�h����̂��^�[�{�B
�h�[�s���O�̖g�r�C�h�Ȃ�A�r�C�������Ȃ��ƌ����Ȃ��͓̂�����O�B
�m���ɂ��̒ʂ�ł��ˁB
�����g������1.6L�ł͕�����Ȃ��������A**2.4L�ւ́g�r�C�ʃh�[�s���O�h**�����݂܂����B
�u�G���W���{�̂̃��X�|���X���ǂ���A�^�[�{���O��������̂ł́H�v�����������҂��āB
�Ƃ��낪���ۂ́A�r�C�ʂɌ��������傫�ȃ^�[�r�������ڂ���Ă������߁A
�ނ��냉�O�������ɂȂ��Ă��܂��܂����B
����ł��A�A�N�Z������ɋC��z���ĉ^�]���Ă���ƁA���܋����悤�ȃp���[�����o�Ă��邱�Ƃ�����܂��B
�t�Ɍ����A���ꂪ��ɏo�Ȃ��Ƃ������Ƃ́u�R�������܂������Ă��Ȃ��̂ł́H�v�Ƌ^������悤�ɂȂ�܂����B
���Ƃ��΄���
���q���ɃA�N�Z���J�x��20������p�b�ƃI�t�ɂ��Ă��A
���̌� ��3�b�Ԓ��x��17�����x�̊J�x�ł����x���ێ��ł��邱�ƂɋC�Â�����ł��B
����ɋC�Â��Ă���́A�����ŃX���b�g�����삵�������R��ǂ��Ȃ��ʂ�����A
�N���[�Y�R���g���[������ĉ^�]���邱�Ƃ������܂����i���܂����c�j�B
���̌��ۂ͂܂��ɁA**�u�l�Ԃɂ��X���b�g���̃h�[�s���O�v**�Ƃ������邩������܂���B
�A�N�Z���J�x�����ɕۂ��A�����ł킸���ɊJ��������R��ǂ�����
����͖{���A����̓d�q����ԗ��ł͋N���Ăق����Ȃ����ۂ̂͂��ł��B
���̑̌����A����̃X���b�h�𗧂��グ�����@�ɂȂ��Ă��܂��B
���͍��A�����l���n�߂Ă��܂��F
�}�j�z�[���h���iMAP�j�͐���ɂ͎g���Ă���B
�������A�^�[�{�̉�]����X���b�g���O�̃v���i�����͖{���ɎQ�Ƃ���Ă���̂��H
�����u�X���b�g���O�܂ŏ[���Ȉ������Ă��邩�ǂ����v�𐳂����]���ł��Ă��Ȃ��Ȃ�A
����͂��Ȃ킿�A�u�^�[�{���{���Ɏd�����Ă��邩�v�������Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�܂�A�^�[�r���́g�d���̗ʁh���������Ȃ�����A���m�ȔR���͐������Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
���A�����@�艺���悤�Ƃ��Ă���̂͂܂��ɂ��̎��_�ł��B
�����ԍ��F26171205
![]() 1�_
1�_
������Ɖ������X�����������̂Ń��X����܂��B
������ς�Y������A���ӂ́B���߂܂��āB
���ߋ��̃^�[�{�ɑ�����҂ƁA���^�[�{�ɑ�����҂��߈Ⴄ�Ȃ��ĉ��߂Ďv���܂����B
�m���ɂ����ł��ˁB�������H�����q���Ă��邾���Ȃ�Η]����ɂȂ�Ȃ��b�ł������͓����𑖂邱�Ƃ������B���쌧�̎R�x���H�ɂ悭�s���̂ŁB���̎��̃^�[�{���O�Ȃ̂��ǂ�����Ȃ����O���A�N�Z���J�x��傫�����āA�R���������������҂ɏ����s�����Ȋ�����^����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�@�T�[�L�b�g�𑖂�킯�ł͂���܂��}�J�[�u�}���z�̓^�[�{�łȂ���ꂵ���Ǝv���܂��B
�܂��X�|�[�c�J�[�̃J�e�S���[���ς���Ă��Ă��܂��܂����ˁB
�����ԍ��F26171217
![]() 1�_
1�_
��haghog����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
���r�b�̕����A�A�N�Z�����X�|���X�͗ǂ��ł�
�m�[�g�ł��������HSC�ʼn������āA���̌�G���W������藣���V�X�e���B
�����O���C�ɂȂ�Ƃ��̕ӂ�̉�]����g�p���Ă܂��܂��T��o�����Ƃ��Ă��܂��܂��B�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�Ȃ���Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B
�t�ɂ��������܂��B
MT�Ԃł����H
���̎Ԃ�MT�Ȃ̂ŁA���O�̗̈��ϑ��Ŕ�����i���j�܂��B
�C�ɂ��Ă��̂́A��ʂ�AT��CVT�Ń_���_�������������Ȃ̂��ȁH�ƁB
�i������܂��j�}�j���A���V�t�g������A��������̂��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F26171219
![]() 1�_
1�_
���A �鉹����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���^�[�{���O�̂Ȃ��Ԃɏ�肽���̂ł����H
�������̎Ԃ̃^�[�{���O�������������ł��B�ƌ�����萢�̒��ɂ���^�[�{�G���W���̃c�L���悭�����������ł��B
�����ԍ��F26171220
![]() 1�_
1�_
���A�h���XV125.���l����A�ēx�A���ӂ́B
������Ȃ͔̂@���H
�ނӂӁA�r�t�u�ɕ��ނ����̂��ȁB�܂��A�O�Ԃ��瓦���Ă����l�ԂɁA���z�������Ȃ��ł��������B
�����ԍ��F26171226
![]() 1�_
1�_
��haghog����
�NjL�Ő\����Ȃ��ł��B
�^�[�{���O��������̂ł���A������Ȃ��Ǝv���Ă͂��܂��B
�@�B�Ŗ����Ȃ�A�l�Ԃ��Ȃ�ׂ����Ȃ����邵���Ȃ��Ƃ��v���Ă܂��B
�i��]���̈ێ��Ȃǁj
���ꂪ����Ӗ��A�^�]�̊y���݂ł͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F26171242
![]() 1�_
1�_
��ZXR400L3����A�ēx���ӂ́B
�����v���i����
�悤�₭���̌��t���Ԃ��Ă����B
�v���i�����̓}�j�z�[���h�����K�������Ȃ�܂����A���������낦�v���i�������}�C�i�X�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
���ꂪ�̂̃h�b�J���^�[�{���Ǝv���Ă��܂��B�܂�^�[�r�����z�C�̒�R�ɂȂ��Ă��邽�߂ł��B
�i�v���i�����j�[�i�}�j�z�[���h���j���o���ꂪ���̎��̋z�C���̌W���ł��B�����m�邱�Ƃ��o����A�N�Z���I�t���ɔ�������M�N�V���N���͂Ȃ��Ȃ�Ǝv���Ă��܂��B
���̕��͂��`�h�̏����Ɋ�Â��lj����܂��ȉ��`�h
�����ۂɁA��P�i�v���i���|�}�j�z�[���h�j�̕ϓ������A���^�C���ɊĎ��ł���A
�g��C���܂��͂��Ă��Ȃ��̂ɔR������ɏo�Ă���h
�g���łɋ�C�����Ă�̂ɁA�R��������ĂȂ��h
�Ƃ������z�C�ƔR���̃Y����ECU���\����ł���\��������܂��B
����́A�l�Ԃł����Ƃ���́g�[�ċz���Ԃɍ����Ă��Ȃ��̂ɑ���o���Ă�h��ԂɎ��Ă��āA
���O���h�b�J�����M�N�V���N���̍��{�I�Ȍ����ł́H�ƍl���Ă��܂��B
�����\��������Ȃ��Ƃ�����[���Ă��炢�܂����B
�����ԍ��F26171243
![]() 1�_
1�_
��haghog����
�ȂA�s�v�c�Ȍ������łĂ����̂ŁE�E�E
���C���}�j�z�[���h���͋z�����́A�u�[�X�g���͋z�����܂��悤�Ƃ��鈳�͂Ƃ������߂ł��B
�O�q���܂������A���̉��߂͂����ł����H
wiki�̃v���i�������߂́E�E�E
�H�w�I�ɂ́A����ꂽ��Ԃ̋�C�����A�O���̑�C������������Ԃ��w���B���q�F�W�̗p��Ƃ��ẮA���q�F�̘F�S����̗�p�ނ̏[�����Ă����Ԃ������B
���i�v���i�����j�[�i�}�j�z�[���h���j���o���ꂪ���̎��̋z�C���̌W���ł��B�����m�邱�Ƃ��o����A�N�Z���I�t���ɔ�������M�N�V���N���͂Ȃ��Ȃ�Ǝv���Ă��܂��B
���̎��̃G���W���̏�Ԃ́AODB2�ŊĎ����Ă܂��B
�C���}�j�����u�[�X�g���Ɨ������Ă܂����A�i�v���i�����j�[�i�}�j�z�[���h���j���o�̃�P�́��Ȃ̂ł��傤���H
���̎Ԃ́A�O�q���܂������Ď��o���Ă܂��̂ŁA�A�C�h�����O��-6.6�`-6.7×100Pa�ł��B
���o�����������Ƃ���ŁA�����ς��̂ł��傤�H
�A�N�Z���I�t�̃M�N�V���N�����A�^�[�{���O���C�ɂ���Ȃ�A�N�Z���I�������ȁH�ƒP���Ɏv���܂��B
�����ԍ��F26171302
![]() 1�_
1�_
2025/05/07 08:05�i4�����ȏ�O�j
�^�[�{�Ƃ��������A�r�C�ʍ��̃g���N����ԉe������Ǝv���܂��B
�G���W�����C���i�b�v����������ԂŃ`���C�X�B�U�O�|�P�O�O�����^�����r����Έ�ڗđR�H
C200 �P�D�TL�@�}�C���h�n�C�u���b�h�@�O�|�P�O�O�F�W�D�Q�@�U�O�|�P�O�O�F�U�D�O�R
�@�@https://www.youtube.com/watch?v=BWOnOeodJyg
C200�@�P�D�WL �@�O�|�P�O�O�F�W�D�Q�W�@�U�O�|�P�O�O�F�T�D�Q�U
�@https://www.youtube.com/watch?v=PBRQxqmhIN8
�����R�V�@�����Z�f�X�Q�k�@�O�|�P�O�O�G�U�D�U�U�@�U�O�|�P�O�O�F�S�D�W�R
�@https://www.youtube.com/watch?v=jGa2sfvOmB4
���{�[�O�@�Q�D�SL�@�O�|�P�O�O�F�T�D�X�Q�@�U�O�|�P�O�O�F�R�D�X�U
�@https://www.youtube.com/watch?v=QqvKuTmDZoQ
V�R�V�@�RL�@turabo�@�O�|�P�O�O�F�S�D�W�Q�@�U�O�|�P�O�O�F�R�D�V�U
�@https://www.youtube.com/watch?v=ioixzTlBob8
V�R�V�@�m�`�R�D�T�{�n�C�u���b�h�@�O�|�P�O�O�F�S�D�U�R�@�U�O�|�P�O�O�F�Q�D�V�R
�@https://www.youtube.com/watch?v=ajUjLzwKjtI
V�R�V�@�RL turabo�@�S�O�OR�@�u�r�@�m�`�R�D�T�k�@�n�C�u���b�h�@�݊p
�@https://www.youtube.com/watch?v=OodDaTbYU44
�@
�ԊO��
���N�T�X�@RC�@�m�`�T�k�@�O�|�P�O�O�F�S�D�W�U�@�U�O�|�P�O�O�F�Q�D�T�Q
�@https://www.youtube.com/watch?v=LP9OlOWfchk
���N�T�X�@IS�R�O�O���e�@�m�`�Q�D�T�{�n�C�u���b�h�@�O�|�P�O�O�F�V�D�S�Q�@�U�O�|�P�O�O�F�T�D�Q�Q
�@https://www.youtube.com/watch?v=HChnL0MLPes
�����ԍ��F26171490
![]() 1�_
1�_
�~�X�t�@�C�������O�V�X�e����g�ݍ��ނƂ��B
�́A�G�{3�ɓ���Ă���z�������B
�����ԍ��F26171556
![]() 2�_
2�_
���������A�^�[�{���O�ɂ��āA���낢��E�E�E
https://motor-fan.jp/tech/article/13450/
https://motor-fan.jp/tech/article/13206/
https://motor-fan.jp/tech/article/13156/
https://motor-fan.jp/tech/article/9636/
https://motor-fan.jp/tech/article/9436/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%96
�Ȃ�ƂȂ��ł���haghog����́A�r�C�����͋z�C���̃��O���C�ɂ���Ă��銴��
NA�Ȃ�A�z�C�͎��ʂ������̂Ƃ��āA�����▬���Ȃǂ���g���āA�[�U�������グ�Ă�b�́A�悭�����܂����E�E�E
�^�[�{�Ȃǂ̉ߋ��@�ɂȂ�ƁA���̘͂b�ɂȂ��āA�p�X�J���̌����̐È��I�ȃC���[�W�ɂȂ�A���̂Ƃ��Ă̓����ɂ��ẮA���܂����Ȃ������Ȃ̂ł��傤
�ŁA��ʓI�ȃ^�[�{���O�́A�r�C���^�[�r�����܂ł̘b�������̂ł��傤
���ۂ͋z�C���̗�������RCFD�Ȃǂʼn�͂���Ă���Ǝv���܂���
�܂��̂���A���X�|���X�グ�邽�߂Ƃ����āA����^�C���^�[�N�[���[�Ȃǂŋz�C�o�H���ŒZ�ɂ���Ƃ��A����܂���
���Ȃ݂ɋC�ɂ���Ă���v���i�������āA���������ł̓v���i���`�����o�[�i���T�[�W�^���N�j���̈��͂ł���
�e�C���ɋϓ��ɉߋ����������߂̕����݂����Ȃ���
�ߋ������̃|�b�v�I�t�o���u���A�����ɕt�����Ă܂����
�Ȃ̂ŁA�v���i�������ߋ����ł���A���ʂȉ����ƌ����Ӗ��͂Ȃ������ł�
���R�A�z�C�o���u�̓����ɂ���āA�����������܂�����A�C���e�[�N�}�j�t�H�[���h���ň��͕ϓ��͏o�܂����A���̋C���Ɉ��e�����y�ڂ����A�Ȃ����ǂ��e����^������悤�Ƀv���i���`�����o�[�̗e�ςȂǂ����肳���̂ł��傤
�����ԍ��F26171611
![]() 2�_
2�_
��haghog����
�K�\�����Ԃł͂Ȃ��A�f�B�[�[���^�[�{���g���N�̑������������ėǂ��̂ł́H
�����ԍ��F26171673
![]() 2�_
2�_
���ɂǂȂ����R�����g���Ă邩������܂��A�x���c��M139�G���W�����G���N�g���b�N�G�L�]�[�X�g�K�X�^�[�{�`���[�W���[���Ă��āA���ʂɃf�B�[���[�Ŕ�����̂ł���ł����̂ł͂Ȃ��ł����B
�r�C�K�X�������̖@���ɂ͋t�炦�Ȃ��̂ŁA���̓��͂��g���ă^�[�r�������Ȃ��ł��B
�����ԍ��F26171871
![]() 2�_
2�_
�����̂Ƀ}�c�_�������Ǝv���̂ł����A�^�[�r�����H���Ԃł͂Ȃ������R�����ɂ��Ē��S�ɃV���t�g��ʂ����^�C�v���Ă���܂���ł����H���͋z�r�C�����ђʂ��Ă��悤�ȁB
�����ԍ��F26171880
![]() 2�_
2�_
��RBNSX����
�v���b�V���[�E�F�[�u�X�[�p�[�`���[�W���[�ł��ˁI
�Ȃ�����
�����ԍ��F26171883
![]() 2�_
2�_
�܂��A�}�c�_�̓��[�m�X800�̃~���[�T�C�N���ł́A���V���������R���v���b�T�[�Ƃ��A���낢��ς�������Ƃ���Ă��܂�����
�����ԍ��F26171888
![]() 2�_
2�_
��ZXR400L3����A���ӂ́B
���X���x���Ȃ��ăX�~�}�Z���ł����B���A��ĕ��͂��l���Ă��܂��B
��wiki�̃v���i�������߂́E�E�E
�H�w�I�ɂ́A����ꂽ��Ԃ̋�C�����A�O���̑�C������������Ԃ��w���B���q�F�W�̗p��Ƃ��ẮA���q�F�̘F�S����̗�p�ނ̏[�����Ă����Ԃ������B
����͐����������ł��B���̉�����Ԃ�����Ă���̂��^�[�{�ł����^�[�{���[���ɉ��Ȃ���Ԃ������Ԃ܂ł̎��Ԃ��^�C�����O�ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B
�����̎��̃G���W���̏�Ԃ́AODB2�ŊĎ����Ă܂��B
�C���}�j�����u�[�X�g���Ɨ������Ă܂����A�i�v���i�����j�[�i�}�j�z�[���h���j���o�̃�P�́��Ȃ̂ł��傤���H
����͐����ł��B�������̃X���𗧂Ă�O�ɂn�c�a�Q���g�p�����������̂ł����K�����L��܂���ł����B�A�܂�������ł��B
�����Ōy�����Ԃ̃^�[�{�Ԃ��w�����悤���Ƃ��v�����̂ł��������܂ł������o�܂���ł����B
���O�q���܂������Ď��o���Ă܂��̂ŁA�A�C�h�����O��-6.6�`-6.7×100Pa�ł��B
����̓}�j�z�[���h���ł�������Ƃ��v���i�����ł����H
�@���ꂪ����ƔR���}�b�v�̒lj����ڂ��o���܂��B���ۂɂ͂ǂ��Ȃ�̂�����܂��v���i�������}�j�z�[���h�������������������Ȃ��Ƃ��͑S�J�ƍl����Ǝv���܂����A�v���i�����������}�j�z�[���h�����Ⴂ�Ƃ��̓X���b�g������������Ă��܂��B���̎��Ƀ}�j�z�[���h�ɗ��ꍞ�ދ�C�̗ʂ̓}�j�z�[���h�Ŏ�����鈳���������Ȃ�܂��B���̗͊w�ł��ˁB�}�j�z�[���h�̃Z���T�[���z������Ă��܂��B�������C�������̂ɔ����R���ƂȂ�G���W�������ʂɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B
�@�����\�h���邽�߂Ƀ��[�J�[�̔R���͔Z���߂ɐݒ肳��Ă���A���[�U�[�ݒ�͕����ڂɂȂ�܂��B���߂ɂ��邱�Ƃ��\�Ȃ̂͒ʏ킻���������Ƃ�����l�̓G���W���S�J�X���b�g���S�J�̂��߁A�v���i�����ƃ}�j�z�[���h�����قƂ�Ǔ������Ȃ�܂��B��������v�Ȃ�ł����A���X���������`���[�j���O���������G���W���Ń��[�X�ɏo��ƃG���W���u���[�ɂȂ�Ǝv���܂��i�����܂ł����̐����Ɗ��z�A�����ł͂���܂���j
���^�[�{���O���C�ɂ���Ȃ�A�N�Z���I�������ȁH�ƒP���Ɏv���܂��B
����͐������̂ł����A�l���Ă��������ɂ��̃M�N�V���N���ɓ��B�����̂ł��B
�����ԍ��F26172010
![]() 1�_
1�_
�������@�ނقǂނ�����������A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂���
���U�O�|�P�O�O�����^�����r����Έ�ڗđR�H
�m���Ƀg���N�����邾���ł������͐����ł��B����͑S�J�̃G���W���̐��\�ł���S�J�̃^�[�{�̐��\�ł��B
�t�ɂ�����������������Ɨǂ��̂ł���
��60-100km/H�Ńu���[�L���O60km�܂ʼn���������܂��S�J����60-100km�����Ɠ��퐶���̃p�^�[�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�Ƃ����܂ŏ�����AI�ɑ��k������ȉ������M���Ă��������ƌ����܂���
������**�u�ĉ����e�X�g�v�����A���ۂɃ^�[�{���O��X�|���X��̊��ł����ʂ��Ǝv���Ă��܂��B
�g���N�̐�Βl�i�r�C�ʂ�^�[�{���\�j���ǂ��Ă��A�g��������������̉̒x���h�̓^�[�{�ԓ��L�̃N�Z�Ƃ��Č���₷���ł���ˁB
�����ԍ��F26172017
![]() 1�_
1�_
�������CJr.����A���ӂ́B
������**�u�ĉ����e�X�g�v�����A���ۂɃ^�[�{���O��X�|���X��̊��ł����ʂ��Ǝv���Ă��܂��B
�g���N�̐�Βl�i�r�C�ʂ�^�[�{���\�j���ǂ��Ă��A�g��������������̉̒x���h�̓^�[�{�ԓ��L�̃N�Z�Ƃ��Č���₷���ł���ˁB
����m���ɗL��ł����ς����R��������Ȃ�܂��B
��YouTube�Ńv���i�����������܂܈ێ�����ƃG���W���̃c�L���悭�Ȃ�Ƃ����̂𗬂��Ă���l�����܂��ˁB
���̐l���ǂ̂悤�ɒ������Ă���̂��͉���܂���B
�����ԍ��F26172020
![]() 1�_
1�_
���˂��݂���B����A���ӂ́B
�Q�Ƃ�ǂ܂����Ē����܂����B���̒m���̋͂��̒P���ȃ��[�U�[�̓��̒����i�����Ă��܂��ˁB�����ł��B
���Ȃ�ƂȂ��ł���haghog����́A�r�C�����͋z�C���̃��O���C�ɂ���Ă��銴��
�܂��ɂ��̒ʂ�ł��B�z�C���̃��O�����������Ă���Ƃ����l���Ɏ����Ă��܂��B
��NA�Ȃ�A�z�C�͎��ʂ������̂Ƃ��āA�����▬���Ȃǂ���g���āA�[�U�������グ�Ă�b�́A�悭�����܂����E�E�E
�����ł��B�܂��ɗ��̂ɂ��[�U�����̖��Œ����t�@���l������������Z���t�@���l������������A����a�ɂ����菬���a�ɂ����褃L���u���^�[�̐i���ƂƂ��ɕς���Ă����܂����ˁB
���^�[�{�Ȃǂ̉ߋ��@�ɂȂ�ƁA���̘͂b�ɂȂ��āA�p�X�J���̌����̐È��I�ȃC���[�W�ɂȂ�A���̂Ƃ��Ă̓����ɂ��ẮA���܂����Ȃ������Ȃ̂ł��傤
�܂��ɂ��̒ʂ肾�Ǝv���܂��B���̂�����ɕς�����悤�ȏ�Ԃł������̌��ɓ�������ԂɂȂ�܂ł̓����ɐ_�o���z���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
����ʓI�ȃ^�[�{���O�́A�r�C���^�[�r�����܂ł̘b�������̂ł��傤
�ł����ۂɂ̓v���i���ƃ}�j���Ƃ��������Ȃ�܂ł͂܂��ɗ��̂ł���ˁB
�����ۂ͋z�C���̗�������RCFD�Ȃǂʼn�͂���Ă���Ǝv���܂���
�Ȃ�قǃR���s���[�^��͂�����Ă����ł��ˁB�F�X�Ȃ��Ƃ��l�����Ă���B
���v���i�������ߋ����ł���A���ʂȉ����ƌ����Ӗ��͂Ȃ������ł�
�ߋ����͉�������Ă��Ȃ��Ƃ��̈����܂܂��Ǝv���܂��B���̕ϓ���m�邱�ƃC�R�[���^�[�r���̓�����m�邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�܂���t�ŃC���^�[�N�[���[��t���ւ����Ƃ��̕���y�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���z�C�o���u�̓����ɂ���āA�����������܂�����A�C���e�[�N�}�j�t�H�[���h���ň��͕ϓ��͏o�܂����A���̋C���Ɉ��e�����y�ڂ����A�Ȃ����ǂ��e����^������悤�Ƀv���i���`�����o�[�̗e�ςȂǂ����肳���̂ł��傤
����܂��Ɍv�Z�������Ƃ�����l���������Ȃ����e�̋C�����܂��B
�v���͐F�X�Ȃ��Ƃ��l���Ă���Ǝv���܂��B���̎���͋z�C�p�C�v��1�{�o��Ƃ��̐�̑傫�������������Ȃ��ƈ����ς�����x�̒m���ł����B
�����ԍ��F26172138
![]() 1�_
1�_
���A�h���XV125.���l����A���ӂ́B
���f�B�[�[���^�[�{���g���N�̑������������ėǂ��̂ł́H
�̃}�c�_�̃f�B�[�[���R���v���b�T�[�^�̃G���W���Ԃ����悵�����Ƃ�����܂������̎��̊��z�͂��̂܂܃^�R���[�^��6000��]�ƋU���Ă��N�ɂ�����Ȃ���ƌ������Ƃł����B
����ƃ����Z�f�X��220D�Ԃɂ����悵�܂����������č������̂��K�v�͖������ƌ������ƂŃ_�E���T�C�W���O�^�[�{�ɂ��܂����B
�����ԍ��F26172144
![]() 1�_
1�_
��Ho Chi Minh����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂����B
���r�C�K�X�������̖@���ɂ͋t�炦�Ȃ��̂ŁA���̓��͂��g���ă^�[�r�������Ȃ��ł��B
���������z�C�̈�ł������܂��ˁB�z�C�Ɍ��������R�������ΐ����͏o���Ȃ��Ǝv���܂��B
������d��SC�ƌ����l�����Ƃ������ł��ˁB
�����ԍ��F26172148
![]() 1�_
1�_
��RBNSX����A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂����B
�������̎Ԃ����悵�����Ƃ�����܂��B
�G���W���̉������C�����̂悢�G���W���ł���
�����ԍ��F26172150
![]() 1�_
1�_
���˂��݂���B����A���ӂ́B
�˂��݂���B����͎��Ɠ��N��̐l���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26172154
![]() 1�_
1�_
��haghog����
�^�[�{�Ԃ��ĂȂ����O���L��Ǝv���܂�
�A�N�Z�����J���z�C�𑝂₵�����̂�
����܂ł̒��]���˂̔r�C�K�X�ł̓^�[�r���̉�]��
�Ⴍ�����̋�C���������߂Ȃ�����ł����
�F�X�ȑ�͗L��܂���
��s�@�̏ꍇ�X���b�g���̒����ׂ͍����s��Ȃ��̂�
���O�̐S�z�͏��Ȃ��ł���
�Ԃ̏ꍇ�g�p���̉�]��(�r�K�X��)�̕ω������Ȃ�
(���Ȃ��Ȃ��A���͏�ɉ�)�������O�͏������ł��傤��
�n�C�G�[�X���グ������܂���
�^�[�{���O�[���͏�Ɉ��̉�]�ŃG���W������
CVT�ő��x���䂷��߂����o���邩��
��͂��łɃR�����g�L��悤��
�G���W������̔r�K�X�K�X�����Ȃ��Ă�
�^�[�r����������~�X�t�@�C�����O����
�������I�ɂ͍���]�܂Ŏg��Ȃ�
�f�B�[�[��
�X�|�[�c���̎ア�_�E���T�C�W���O�^�[�{
�����肩��I�Ԃ����Ȃ��ł��傤��
���
�^�[�{�ł�e-POWER�̃G�N�X�g���C����
���[�^�[�ő��邩��^�[�{���O�͖�������
�����ԍ��F26172498
![]() 2�_
2�_
��gda_hisashi����A���ӂ́B���߂܂��āB
���^�[�{�Ԃ��ĂȂ����O���L��Ǝv���܂�
�A�N�Z�����J���z�C�𑝂₵�����̂�
����܂ł̒��]���̔r�C�K�X�ł̓^�[�r���̉�]��
�Ⴍ�����̋�C���������߂Ȃ�����ł����
�܂��ɂ��̒ʂ�ł��B���̉��Ȃ��Ԃ����`�����o�[�̒��̋�C�̗ʂ��z����s�[����������A�z�肵����C�̗ʂ��������Ȃ��Ă��܂��Ɣr�C���������Ȃ��ăG���W���u���[�̌����ɂȂ�Ǝv���܂��B�z�肵����C���������߂Ȃ���ԂƑz�肵������������C���z�����܂��Ƃ��Ƀ^�[�{���O�ł���Ƃ������_�ɂȂ�܂��B
���F�X�ȑ�͗L��܂���
��s�@�̏ꍇ�X���b�g���̒����ׂ͍����s��Ȃ��̂�
���O�̐S�z�͏��Ȃ��ł���
��s�@�̏ꍇ�͈�葬�ŃG���W�����Ă���Ƃ�����ԔR��ǂ��ƕ��������Ƃ�����܂��B
��p�Ԃ̃G���W���͂�����͕p��ɋz�C���Ƃ��������A�v���i�������ω����Ă���Ǝv���܂��B
���̎��㑽����P���ق�0�̎���z�肵�ĔR���}�b�v�͍쐬����Ă���Ǝv���܂��B
�b�͕ς��܂����A�����ԂɎԂ��^�]����@��������̂�40km/h���炢�̑��x�ŃI�[�g�}����}�j���A���Ɉڍs�����400��]���炢��]���オ��̂�����܂����B�iCVT�̓����ł��ˁj
���b�����Ă���A�N�Z���ނƃX�g���X�����G���W���͉��܂��B�^�[�r�����d���������̂ł��傤�B
����Ń}�j���A���ɂ����u�ԂɃA�N�Z�����J���ƈ�u���t�������ăG���W�������܂��B�܂��Ƀ^�[�{���O��̌����܂����B
�����܂ł̂��Ƃ�����Ƃ͍l���Ă��܂���ł�����2.4L�G���W���ł��^�[�{���O�͖��m�ɑ��݂��܂��B
���Ԃ̏ꍇ�g�p���̉�]��(�r�K�X��)�̕ω������Ȃ�
(���Ȃ��Ȃ��A���͏�ɉ�)�������O�͏������ł��傤��
�܂��ɂ��̒ʂ�B�������X���ł̓G���W���̉�]���͏オ�����艺��������B
�^�[�{�G���W���ɂ͍ň��̊��Ǝv���܂��B�ł��̂Ń�P���K�v�ȂƎv���܂��B�����������烌�[�X�̏�ʂ̕����p�ɂɏo�����邩������܂���B
���^�[�{���O�[���͏�Ɉ��̉�]�ŃG���W������
CVT�ő��x���䂷��߂����o���邩��
����CVT�������҂Ȃ̂�������܂���B��肭�^�[�{���O����肭�B���Ă���Ă���̂�������܂��A���̂��߂Ɏ��ۂɂ���^�[�{���O���B����A����ɃA�N�Z����傫���J���Ă���̂�������܂���B
�������q���x40km/h�ő��s���Ƀ}�j���A�����[�h�ɂ����Ƃ���A�N�Z���J�x�����̂܂܂ł͉������Ă��܂����Ƃ�����A�N�Z���J�x��5�����x�����ċz�C���}�j�������Ă݂��0.12kPa�قNjz�C�����炷���Ƃ��o���܂����B
�Ƃ������͉����ǂ����ŔR������Ă���̂�������Ȃ��Ǝv���܂����B�ł�����͑��肵���킯�ł͂Ȃ��̂łȂ�Ƃ��B
���^�[�r����������~�X�t�@�C�����O����
����͊m���ɗǂ����@�Ȃ�ł������̐��̒��Ǝ��̔N�ł͑I���o���܂���B
���f�B�[�[��
�X�|�[�c���̎ア�_�E���T�C�W���O�^�[�{
�����肩��I�Ԃ����Ȃ��ł��傤��
�����I�����邩�V�������@��T�邩�Ƃ����̂�����̖��_�ł��B
�����[�^�[�ő��邩��^�[�{���O�͖�������
���[�^�[�p���[���S�Ăł��̂Ŕ��d�ɗ͂������ԂɂȂ�̂ɂ͂��Ȃ�̒�R�̂���Ƃ����Ǝv���܂��B
AI���lj����Ă���܂���
�������������������Ă���ƁA��͂�u��C�̓����v�������Ɛ[���������Ȃ��ƁA���O�̖{���I�ȉ����͓���̂��ȂƉ��߂Ďv���Ă��܂��B��
�Ƃ̂��Ƃł����B
�����ԍ��F26173144
![]() 1�_
1�_
�Ƃ��Ƃ����̐����̊G������AI�������n�߂܂����B���G�ȃ��m�͏o���Ȃ��̂ŊȒP�ȃ������グ�܂��B
�����ԍ��F26173172
![]() 1�_
1�_
2025/05/09 11:55�i4�����ȏ�O�j
���^�[�{���O�������^�[�{�Ԃɏ���Ă݂����Ɩϑz���Ă���܂��B
�ł���킯�Ȃ��ł��傤�B�r�C�K�X�̔r�o�G�l���M�[�Ń^�[�r�����̂�����B
������x�G���W���̉�]�����オ��Ȃ��ƃ^�[�r���ɏ\���ȗ͂�������Ȃ��ł��傤�B
�G���W���̉�]��d�����[�^�[�Ń^�[�r�����̂͒ʏ̃X�[�p�[�`���[�W���[�ł���B
�������Ă��܂��B�H
�����ԍ��F26173669
![]() 1�_
1�_
2025/05/09 12:13�i4�����ȏ�O�j
���܂�W�Ȃ�����1980�N��F1�@�P�T�O�O�����^�[�{�G���W���S������B�^�[�{���O������̂�
�X�^�[����Ƃ���C�ɃA�N�Z���y�_�����x�^���݃N���b�`�~�[�g����̂��Öق̗����B
���s����ΒǓ˂���Q�O�O���b�g���ȏ�ςR�������㔚���B
�����ԍ��F26173688
![]() 0�_
0�_
��������X�[�p�[�n�C�r�W��������A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���ł���킯�Ȃ��ł��傤�B�r�C�K�X�̔r�o�G�l���M�[�Ń^�[�r�����̂�����B
�܂��ɂ���͂ǐ^�̕ԓ��ł��B40�N�O���߂ă^�[�{�Ԃ��l�����̎�̓͂��Ƃ���ɂŏo�Ă����Ƃ��ɂ��̃n�C�p���[���������܂������A���̌����̓^�[�{���O�̂��錻���ł����B
�ꕔ�̎Ԏ��AT���g�����̓��������܂����A�ꕔ�̎Ԃ͂���ɔ�p�������ăc�C���^�[�{�ɂ�����A�^�[�r���̃T�C�Y��������������A�r�C�ǂ̑傫�����R���g���[��������l�X�̍H�v�����Ă��܂����B�قڃ^�[�{���O���Ȃ��Ƃ������Ȃ���A���̎��̓^�[�{���O����肭�B���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
CVT�͂��̓������甽�����x���̂�CVT�̂����ɏo���܂��������ۂɂ̓^�[�{���O���B������ɂȂ��Ă��܂��Ă���悤�Ɏv���܂��B�����AUTO�ƃ}�j���A���̐�ւ����o����̂Ŏ����Ă݂�ƒ��]���獂��]�ɕς�����Ƃ��͂܂��r�C�K�X�̓^�[�r�����[���Ă��܂���ł����B�����瑧�t�����ۂ��N���Ă����Ǝv���܂��B������}�j���A���ɂ��Ȃ���ATTO�̂܂܂ł���CVT����]���グ��܂Ŏ��Ԃ�������Ƃ�����ۑ���ɂȂ��Ă��܂����B2.4L��CVT�͑��̎Ԏ�Ƃ͈ႤCVT���g�p���Ă��܂����A�����ɐ[���H�����ނ���͂���܂���B
�@�Ƃ����������Ƀ^�[�{���O�����݂��Ă��܂��B
�̂̃G���W���Ɍ�t���^�[�{��t���ă^�[�{���O���o��B����͂�����������܂���B�ł����͂���21���I�ɂȂ�����ł��������̌�t���̃^�[�{����i���ł��Ȃ��̂ł��傤���Ƃ����̂��A���̍l���ł��B
���G���W���̉�]��d�����[�^�[�Ń^�[�r�����̂͒ʏ̃X�[�p�[�`���[�W���[�ł���
�������悭�������Ă��܂��BMad Max�ŃX�[�p�[�`���[�W���[�������V�[���͍ō��ł����B
EV�����[�^�[�Ƃ�������ŕʕ��Ɨ������Ă��܂��B
���������Ă��܂��B
�������Ă��܂���B���̓V���v���ɂ��ƈ�Z���T�[��t���ăR���s���[�^�[��̃}�b�v��ς��邱�Ƃ��o��������ƃ��X�|���X���ǂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��鎟��ł��B����������X�|���X�̗ǂ��Ԃ����Ɠ������x�̒l�i�ŏo�����Ȃ����Ɩϑz���Ă��܂��B
��F1�@�P�T�O�O�����^�[�{�G���W���S������B
���̎���ɗ\�I�ł�3bar���炢�̈���������1500�n�͏o���Ă��܂�������͂�F1�ł��^�[�{���O����������ł��傤�ˁB
���������v���܂��A�A�C���g���Z�i�A�}���Z���A�̖��O�����o�Ă��܂��B
AI���������������Ă��܂��B���u�����A�Z���T�[�lj��Ɛ����̔��z�ɋ������������������A�}���Ȃǂ�����Ă���̂ł��Љ�ł��܂��B�v
�ƒ������ł��ˁB
�@
�����ԍ��F26174146
![]() 0�_
0�_
2025/05/09 21:08�i4�����ȏ�O�j
�l�I�ɂ́u�h�b�J���^�[�{�v�c
�D���ł����ǂˁB
���̏ꍇ�A���̂��^�[�{�Ԃɉ��������A����܂Ŕ��������͖����ł����A�Ⴂ���ɃG���W�����[���Ɂu�ŃL�m�R�v�������A�ł������J�^�c����������F�l�̎Ԃ̃n���h��������@��L��܂������A���̎��̈�ۂ��A
�u����c�c�N���C�W�`�I�v
�����͖���̂悤�ȃ������Ƃ͂悭�������Z���t���Ǝv���܂��B
�l�I�ɂ̓^�[�{���O�͈��|�I�ȃp���[���y���ލۂ́u�^���v�̂悤�ȃ����ŁA�S�̒��ŁA
�u���邼�A���邼�A���邼�c�c�I�v
�Ǝv���Ȃ���A�N�Z���L�����L��܂��B
���̎Ԃ̃I�[�i�[�ł���F�l�͓����A�f�[�����t���̖��Ȃ̔@���A�u�`�J���������`�I�v�Ƃ܂Ō����Ă��܂�����(�f�[�����t���͂��̌�A�u�s�k�҂́Z��(�������֎~��)�v�Ƃ܂Ō����Ă܂������j�B
�܁A��k�͂������炢�܂łŁA�^�[�{���O�Ɋւ��Ă͌��_�ƌ������L�����ƌ�����ۂ��L��܂��ˁB
�����ԍ��F26174152
![]() 1�_
1�_
��v36�X�J�C���C���ǃm�[�}������A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���l�I�ɂ́u�h�b�J���^�[�{�v�c
�D���ł����ǂˁB
�����D���ł��B����Carboy �Ƃ�Option�Ƃ��Ă�ł����ɂ͗ǂ�����܂���ˁB������IHI��F1�^�[�r����t����̂��͂���Ă��܂����BIHI�ɂ���ƃ^�[�{���O���������Ȃ�Ƃ��F�X�����Ă��܂����B���͎��ۂɓ����̃`���[�j���O�J�[�ɏ�邱�Ƃ͏o���܂���ł�����FC3�ɂ͔r�C���v��t���Ă��č������H��SA�ɂ��ă{���l�b�g���J����Ɛԍ�������^�[�{�������Ă��܂����B
���̓�����m���Ă���ƍ��̃^�[�{�͐����ł���ˁB
���f�[�����t���̖��Ȃ̔@���A�u�`�J���������`�I�v
�܂��ɓ�����0�[400�̋L����ǂ�ł���Ƃ��ꂪ����܂��B�����ăG���W���u���[���b��ɂȂ��Ă��܂����B�G���W���u���[������N���b�`���[�ƌ������t���o���Ă��܂��B
���̃h�b�J���^�[�{�̃��O�����������X���[�Y�ɏo������ǂ��Ȃƌ����̂����̃X���̎�|�ł��B
�����ԍ��F26174169
![]() 0�_
0�_
��haghog����
���^�[�{���O�ɂ��čl�������Ƃ͂���܂����H
�^�[�{���O�ƌ����Ă��Ԏ�ɂ���ėl�X���Ǝv���̂ňꊇ��Ƀ��O�ilag�j�x�����f�����b�g�Ɲ�������̂͂ǂ����ȂƎv���܂��B
80�`90�N�㏉���̃X�|�[�c�J�[�̓^�[�{���O���G���W���̖��t���Ɏg���Ă��܂�����ˁB
�����^�[�{�Ԃł�32�Z�h���b�N��80�`�F�C�T�[�Ƃ͑S���ʕ��̃t�B�[�����O�ł����B
���ꂪ�C���y���̌y�ʉ��⎲���{�[���x�A�����O�ɂ���ȂNjZ�p�����W����x�ɒ��]�ł���������悤�ɂȂ�ʔ����������Ȃ��čs�����悤�Ɏv���܂��B
�v�̓X�|�[�c�J�[�ɂ����Ẵ^�[�{���O�̓G���W���̖��t���ł���h���C�r���O�v���W���[�̌��ł�����ƌ����܂��B
����Ƀ^�[�{���O�����Ƃ������̓A�C�h�����O��]���̂悤�Ȓ��]����^�[�r�����K�v���o�Ă��܂��B
�ł�������ă^�[�{�ł���K�v�������ł��傤���H
���̎Ԃ̃n�C�u���b�h�Z�p�����ɂ��������Ă���Ǝv���܂����LjႢ�܂����ˁB
�V�r�b�N��e:HEV��V�^�v�������[�h�Ȃ͂��̑�\��ł��B
�����A�^�[�{���O�����ĉ����������̂��C�}�C�`�`����ė��܂���B
�h���C�r���O�v���W���[�̊��������Ⴄ�̂�������܂��B
�ȒP�ȗႦ�Ȃ�����T�[�G�{�����[�V����V�ƃC���v���b�TWRX STI�̃G���W���t�B�[�����O�̍D�݂ł��B
�O�҂������オ��d���Ō�҂�������d���B
BNR32��S13�V���r�A�Ȃ��������Ƃ�������Ǝv���܂��B
�܂��{�N�̓h�b�J���^�[�{���D���Ȃ̂�86���ă^�[�{�L�b�g�����t���悤���ȂƎv���܂����ǂˁB
�����ԍ��F26174681
![]() 4�_
4�_
��AM3+����A����ɂ��́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���^�[�{���O�ƌ����Ă��Ԏ�ɂ���ėl�X���Ǝv���̂ňꊇ��Ƀ��O�ilag�j�x�����f�����b�g�Ɲ�������̂͂ǂ����ȂƎv���܂��B
�����������͖ѓ�����܂���B�܂��i���̗]�n�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�����ꂪ�C���y���̌y�ʉ��⎲���{�[���x�A�����O�ɂ���ȂNjZ�p�����W����x�ɒ��]�ł���������悤�ɂȂ�ʔ����������Ȃ��čs�����悤�Ɏv���܂��B
���ꂪ�����厖�Ȏ����Ǝv���܂��B���̒m�����^�[�{�Ԃ̐i���̓^�[�{��v����l�����̎�̏�ɏ���ĎԂ͐i�����Ă��܂����B�S�Ă��^�[�{����郌�X�|���X�𗁂���悤�ɂƐi�����Ă��܂����B�ʔ��݂��Ȃ��Ȃ����̂̓��X�|���X���ǂ��Ȃ������߂ɁA�}���Ƀg���N������Ă��銴�o���Ȃ��Ȃ������߂ł͖����ł��傤���HNA�ԂŐ\����܂����[�h�X�^�[�͏�����1600cc�ł��^�[�Ƃ��܂��������̌�1800cc��Ȃ荡��2000cc�Ȃ̂��ȁB�͂�����傤�����������Ȃ邽�ттɁA�y���ɉ��G���W�����������Ȃ����Ƃ��������o�܂����B����̓g���N���M���Ȃ�������ł��ˁB
�@����Ɠ����悤�ɁA�^�[�{�ɂ��N���オ��悤�ȃg���N���̓��O���Ȃ��Ȃ�Əo�ɂ����Ȃ邩������܂���B�ł����̎��͔R���}�b�v�̒�����z�C���~�b�g�̕ύX�ŏo����Ǝv���܂��B���̃^�[�{�Ԃ̓�����2000��]����5000��]�܂Ńt���b�g�ȃg���N�ɂȂ��Ă��܂�����B
���v�̓X�|�[�c�J�[�ɂ����Ẵ^�[�{���O�̓G���W���̖��t���ł���h���C�r���O�v���W���[�̌��ł�����ƌ����܂��B
����Ƀ^�[�{���O�����Ƃ������̓A�C�h�����O��]���̂悤�Ȓ��]����^�[�r�����K�v���o�Ă��܂��B
�ł�������ă^�[�{�ł���K�v�������ł��傤���H
�[���K�v������Ǝv���܂��B�������G���W���Ƀ^�[�{�Ńh�[�s���O���Ă܂��2�̃G���W��������悤�ɉ�]����G���W���ɂ͏���Ă݂����Ǝv���܂��B�����ăG���W����]�̃��~�b�g�Ƃ܂Ő����オ��G���W�����o����ō��ł��ˁB�����Ƃ��Ⴖ��n�̖��̂��^������Ǝv���Ă��܂��B
�������A�^�[�{���O�����ĉ����������̂��C�}�C�`�`����ė��܂���B
�h���C�r���O�v���W���[�̊��������Ⴄ�̂�������܂��B
�@�^�[�{���O���Ȃ��Ȃ�Ƃ����Ə����R��ǂ��Ȃ�A�����Ď��̐S�����肵�܂��B�����Ă��̃^�[�{���O�̌�����������x�����ł���ƁA���ǂ����܂Ŏ��̎Ԃ����Ƃ���Փ����}�����܂��B�����A�P�Ɏ��̐S�̖����̂��߂ɍl���Ă��܂��B
���C���v���b�TWRX STI�̃G���W���t�B�[�����O�̍D�݂ł��B
�����d���̐����Ό��G���W����CVT�̂��߂ɒ��]�ʼnĂ���B��������]�̃��X�|���X���悭�������̂ł��B�~�c�r�V�Ԃɂ͏���Ă��Ȃ��̂Ń���EVO�̃G���W���ɂ��Ă͉���܂���B�C�j�V����D�Ń���EVO�̂肪�~�X�t�@�C�������O�V�X�e�������đ����Ă���̂����ăG���W�����X�|���X�ɂ͋ꂵ��ł���낤�ȂƎv���܂����B
���{�N�̓h�b�J���^�[�{���D���Ȃ̂�86���ă^�[�{�L�b�g�����t���悤���ȂƎv���܂����ǂˁB
����͌l�̍D�݂ł��̂ōD���ȃ��m�͍D���ŗǂ��Ǝv���܂��B����FC3S��11�N����Ă��܂������A13�a�̃A�C�h�����O���̃g���N�͑f���炵�����m������܂����B�قڃA�C�h�����O�ł��Ȃ��ł��Ăऐᓹ��������葖���Ă���܂����B(^_^)�B
�����ԍ��F26174765
![]() 0�_
0�_
�ǂ����Q������l���ꏄ���ă��X���Ȃ��Ȃ����̂ł`�h�Ƃ̃����g�C�����A�b�v���܂��B
�����^�[�{�Ԃ̃^�[�{���O�ɂ��Ē������ƍl���Ă��܂��B
�`�h�Ԏ��������e�[�}�ł��ˁB�^�[�{���O�́A���R�@�ւɃ^�[�{�`���[�W���[�������ۂɕK���t���܂Ƃ��u�u���̗͕s���v�Ƃ��āA�ԍD����G���W�j�A�̊ԂŒ��N�c�_����Ă������ł��B
�^�[�{���O�Ƃ́H
�ȒP�Ɍ����u�A�N�Z����ł�����ۂɃp���[���o��܂ł̎��ԍ��v�ł��B����͈ȉ��̂悤�ȕ����I�v���ɂ���Đ����܂��F
1. �r�C�G�l���M�[�ˑ�
�^�[�{�`���[�W���[�͔r�C�K�X�Ń^�[�r�����ăR���v���b�T�[�����A�z�C���ߋ����܂��B�܂�A�G���W����]����R�Ăɂ��r�C�G�l���M�[���\���łȂ��Ɖߋ������オ�炸�A���ʂ��o�܂���B
2. �^�[�r���̊���
�������̃^�[�r���ƃR���v���b�T�[�͉�]�������傫���A�}�ɍ���]�ɂ͂Ȃ�܂���B���u�ԂɁu�u�[���v�Ɖߋ����Ȃ��̂͂��̂��߂ł��B
3. �z�C�o�H�̗e��
�C���^�[�N�[���[��p�C�s���O�̃{�����[�����傫���ƁA�ߋ������S�̂ɍs���n��܂łɎ��Ԃ�������܂��B
�Z�p�I�ȑ�
�ߋ����\�N�ŁA�^�[�{���O���������邳�܂��܂ȍH�v������Ă��܂����F
�� ���^�E�ኵ���^�[�r���̗̍p
�@�� �������̂Œ��]�ł����ʂ��o�₷���B
�� �c�C���X�N���[���^�[�{
�@�� �r�C���������邱�ƂŁA�������I�Ƀ^�[�r������B
�� �σW�I���g���^�[�{�iVGT�j
�@�� �r�C�̓��ĕ����ςɂ��āA���]����������グ��B
�� �d���^�[�{�ie-Turbo�j
�@�� �d�C���[�^�[�Ń^�[�r�����ɉă��O�������Z�p�BF1�ł��g�p�B
�� �n�C�u���b�h�A�V�X�g
�@�� �d�C���[�^�[�ōŏ��̉��������āA�^�[�{�������܂ł̎��Ԃ߂�i��F�g���^�̃^�[�{�{���[�^�[�j�B
���O���u���v���������������
���Ẵ����[�ԁiLancia Delta�A�����̃X�J�C���C��GT-R�Ȃǁj�ł́A�^�[�{���O�����C�Ƀg���N���y�銴�o���X�����Ƃ��čD�܂�܂����B���ł͖��Ƃ��Ă͂ނ���M�d��������܂���B
���Ȃ��̍l���Ă���u���O�v�̖{���͂ǂ��ɂ���Ǝv���܂����H
�E�x��邱�Ǝ��̂����H
�E����Ƃ��u�������̃Y���v���l�Ԃ̊��o�ƍ���Ȃ����ƁH
�E���邢�́A�g���N�������̂��̂��s���R�ł��邱�ƁH
���Ȃ��̍l�@�̈�[�����Ă���������A���[���@�艺���ċc�_�ł��܂��B
�ƌ����Ԏ��ł����B
�����ԍ��F26176172
![]() 0�_
0�_
����Ȋ����Ŏn�܂�܂����B
����ɑ��鎄�̕Ԏ�
���^�[�{���O�̖��͂��̎Ԃ̔r�C�ʂɑ��ď[���ȃp���[���o�Ă��Ȃ��Ƃ��Ɋ�������̂��Ǝv���Ă��܂��B
����ɑ���`�h�̕Ԏ����܂��ɖ{����˂��Ă����܂��B
���Ȃ��̍l����������ƁA**�u���O�́g�x��h�ł͂Ȃ��A�����ɑ���g�͕s���̊��o�h�Ƃ��Č����v**�Ƃ����������ł��ˁB����͔��ɉs�����_�ł��B
��1�^�[�{���O���u�������̋v���
1. �r�C�ʂƒ��]�g���N�̊W
�r�C�ʂ��傫����A�^�[�{�������O���炠����x�̃g���N�����R�z�C�œ����邽�߁A�u���O�̒J�v�͐Ȃ�܂��B
�� �Ⴆ�A3.0L�^�[�{�Ԃł́u�^�[�{�������܂Łv�ł����������̉��������邪�A
�� 1.2L�^�[�{�Ԃł͓���ł������N���Ȃ����o�ɂȂ�B
�܂�A���R�z�C���́g�n�́h���Ȃ��ƃ��O�̓��O�Ƃ��ċ�����������킯�ł��B
2. �̊������g���O�h�̐���
�u�����I�x���v�{�u�p���[�s���v���S���I�ȁg���O�h
���̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂��B
����0.5�b�̃��O�ł��A�n�͂̂���G���W���Ȃ炻��قNjC�ɂȂ�Ȃ��B
�t�ɁA���r�C�ʂŃA�C�h�����O�t�߂̃g���N�������G���W�����ƁA���ۂ̉������n�܂�܂Łu�������ĂȂ��v�悤�Ɋ����Ă��܂��B
3. ����͍��́g downsizing turbo �h�̖ӓ_
���r�C�ʁ{�^�[�{�i1.0�k〜1.5L�^�[�{�j�ɂ��肪���ȁu�������芴�v�́A���̓��O�Ƃ��������������̃g���N���R�ɋ߂��B
�����炱�����[�J�[�́F
���[�^�[�A�V�X�g�i�}�C���hHV�܂ށj
�ኵ���^�[�r��
CVT�ŏ�Ƀu�[�X�g���ۂ�
�ȂǂŖ��߂悤�Ƃ��Ă��܂��B
��2���_�F���O���g�����̒J�h�A�r�C�ʂ�����߂�
�u���O�Ƃ͉����̒J�ł���A�J���[���قǐl�͂�����g���O�h�Ɗ�����B
�r�C�ʂƎ��R�z�C�g���N��������ǂꂾ�����߂Ă��邩���̊��̍��ށB�v
����͂܂��ɂ��Ȃ��̌����ʂ�ł��B
������낵����A����̎Ԏ�Ŋ������u�T�^�I�ȃ��O�̌��v��A�u�ӊO�ƃ��O�������Ȃ������^�[�{�ԁv�̎��Ⴊ����A����ɐ[�@�肵�Ĕ�r�ł��܂��B�����v�������郂�f���͂���܂����H
�ƌ����Ԏ��ɂȂ�܂����B
���̂`�h�Ƃ̂��Ƃ�͍���̓��퐶���̒��Ŗ��ɂȂ�̂ŎQ�l�ɂ��Ă��������B
�����ԍ��F26176181
![]() 0�_
0�_
�Ȃ��₵����
��������AI�a�͂Ȃ����ڂ��܂��B
���������̃g���N�s���͂Ȃ��N����̂ł��傤���H
AI�������̃g���N�s�����N���闝�R�́A���r�C�ʃ^�[�{�G���W���̍\���I�E�����I�Ȍ��E�ɂ����̂ł��B�ȉ��A�������Đ������܂��F
🔧 �����g���N�s���̍��{����
1. �r�C�ʂ��������ƁA�R�ăG�l���M�[�i�r�C�G�l���M�[�j��������
�G���W���̉�]�����Ⴂ��Ԃł́A�R������C�����������R�₹�܂���B
�܂�A�^�[�{�����߂̔r�C�K�X�̗ʂ��͂�����Ȃ��B
���̂��߁A�^�[�r�������������A�ߋ������オ��Ȃ��B
�@�� ���ʂƂ��āA�u�������悤�Ƃ��Ă���C�������Ă����A�g���N���o�Ȃ��v�B
2. ���]��ł͋z�C���i�u�[�X�g�j���ق�0�ɋ߂�
�^�[�{���{�i�I�ɋ@�\����̂́A������x��]�����オ���Ă���B
����܂ł̋z�C��**���R�z�C��ԁiNA�j**�ɋ߂��B
���r�C��NA�G���W���͂��Ƃ��ƃg���N���ׂ��A�����Ɋ������ʂ�������ԑ̂����Ɓg��������h�ɂȂ�B
3. �G���W������́g�Ӑ}�I�ȗ}���h������
�^�[�{�Ԃł́A�m�b�L���O�i�ُ�R�āj�h�~�̂��߁A�_�Ύ�����R�������𐧌����Ă��邱�Ƃ������B
���ɒᑬ�����ח̈�ł̓G���W���ɕ��S��������₷���A����\�t�g���g���N���i���Ă��܂����Ƃ�����B
4. �����O�M�A�ݒ�i�G�R�`���[�j���O�j
���r�C�ʃ^�[�{�Ԃ͔R��d���̂��߁A���]�ō����M�A�ɓ���悤�ݒ肳��Ă���B
���]�E���M�A�ł͉�]�㏸���x���A�^�[�{�������O�ɑ��ꂵ�Ă��܂��B
📈 �܂Ƃߐ}�i���ʊW�j
���r�C�� �� �R�ėʂ����Ȃ� �� �r�C�G�l���M�[�����Ȃ�
��
�^�[�{�����Ȃ� �� �u�[�X�g��������Ȃ�
��
��C������Ȃ� �� �R�����R�₹�Ȃ� �� �g���N���o�Ȃ�
��
�u����ł�����Ȃ��v���o
✅ �⑫�F���R�z�C�Ȃ�H
NA�G���W���ł́A�A�N�Z���ɑ��ăX���b�g���������ɊJ���A��C�����R�ɓ���g���N�������オ��܂��i���ɒ��r�C�ʈȏ�j�B
����A�^�[�{�Ԃł͂��̋�C���g���k���đ��荞�ށh�ߒ��ɕ����I�ȃ^�C�����O�ƕK�v����������A���ꂪ�����g���N�s���̍����ł��B
�������]�݂ł�����A�u�ǂ�����Ώ����g���N�s���������ł��邩�v�ɂ��ċZ�p�E�������ʂ��炲��Ăł��܂��B����������܂����H
�Ɛi�݂܂����B
�����ԍ��F26176684
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�킽�����̃_���_�������e�L�g�[�ȏ������݂ɁA�^���ɂ��ԐM�����������k�ł�
���炪�x���Ȃ�܂��Ă��݂܂���
���Ȃ��₵����
�킽�����Ƃ��܂��ẮAAI�̉�ǂ�ł��܂��ƁA�����炳�܂ȊԈႢ���Ȃ�����A�������ɂ����ł���
�킽�������A���d���ŁA�v�����v�g���d�˂āA������i��ł����ƁA��������ł������E�E�E���ĂȂ��Ă��܂��܂�
�ŁA�������ɎГ��Řb���������AAI�̂ق����E�E�E���Ă���Ă��܂����Ƃ��A�ŋ߂����E�E�E
�₵���l�ԂɂȂ����܂�
�����ԍ��F26176693
![]() 1�_
1�_
���˂��݂���B����A����ɂ��́B
���X���肪�Ƃ��������܂����B
���̍l���ł�AI�̓f�[�^�[�̊W�߂Ŏ���҂̈ӌ��ɉ����ē������o���Ă��镨�ƍl���Ă��܂��B���̎���̐ݒ�prompt�ƌ����̂��ȁB������ӂ͊��S�ɑf�l�Ȃ̂ʼn���܂��A�ڕW�Ƃ��镨�Ƃ͔��Α��̎����������A��܂��ȖڕW�ɂ����蔽�Α��̎���������肵�ăf�[�^�����W�����Ă��܂��B�����ɑ��ċ^��𓊂�����B�Ȃǂ��Ă��܂��B����ɂ́AAI�Ɏ����̎��ɏo������𐄑������Ă��܂��B�܂�AI�ɋ�C��ǂ܂���������Ă��܂��BAI�͍���������W�߂�c�[���ł��邽�߁A�����͏o�Ă��܂��A�����̋��߂铚���̃o�b�N�{�[����T���o���Ă��Ă���܂��B
�@����̃v���i�����Ȃǂ͎��̒m��Ȃ����삩����������Ă��Ă���܂����B�Ȃ�ƂȂ����̃C���[�W�ɋ߂Â��o�b�N�{�[���Ƃ��Ďg�p�o����Ƃ���܂Ŏ��������ł���悤�ɂȂ�܂����B
�@�����X��ǂ݂Ȃ��玄�̗����ł��Ȃ����p���AI�Ɏ��₵�A���̎v���Ă��邱�Ƃ̎����グ�悤�Ƃ��Ă��܂��B
�@���̃X���ɎQ�����Ă���F�l�ɂ͖{���Ɋ��ӂ��Ă���܂��B�ǂ����v���i�����X���b�g���o���u�A�C���}�j���Ɋւ���l�@�͂قƂ�ǂ���Ă��炸�A�w��Ŕ��\������ǂ��ł����ƌ������U���iAI�|���ł��ˁj�܂ŏo�Ă��܂����B�������ԋZ�p��iJSAE�j
�@�܂������ɃG�l���M�[�𒍂��قǂ����Ⴍ�͂Ȃ��̂ŁA���i�h�b�g�R���Ɏ��̐���s�����A�b�v�����Ė���Ă��܂��B
���������킯�ł��t���������肪�Ƃ��������܂��B
���̌�v���i�����Ɏ���܂ł�AI�Ƃ̖ⓚ���A�b�v���Ă����܂��B
�Ō��AI�̃A�V�X�g�ł���
��AI�͕֗��ȑ��_�����ǁA�������Đl�Ƃ��Ƃ�ł���ꂪ�����Ă����A�T�����y�����������܂��ˁB
�S���[�����Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F26176764
![]() 0�_
0�_
�������R�z�C�̃G���W���ł��R�����[���o���Ă����烌�X�|���X�͗ǂ��͂��ł��B
AI�����������ʂ�ł��B�����Ă��̂��w�E�́A���R�@�ւ̖{����˂��Ă��܂��B
✅ ���R�z�C�iNA�j�G���W���̃��X�|���X���ǂ��Ȃ����
NA�G���W���͍\���I�Ɂu���炷����������v�����������Ă��܂����A���ۂɃL���̂��郌�X�|���X�ɂȂ邩�ǂ����͈ȉ��̏����ɂ������Ă��܂��F
1. �R���i��R��j���K���ł��邱��
�G���W���ɋ�C�����������u�ԁA�K�ȗʂ̔R����f�������˂ł���A�R�Ă������Ɏn�܂�A�g���N�������ɗ����オ��B
���ɃX���b�g���J�x�}�ώ��ɔR���̑��ʁi�������ʁj��K�ɂł��邩���|�C���g�B
�d�q�X���b�g���o��ȑO�̃��C���[�X���b�g���{���J���R������̎���̕����������s�������Ƃ������鏊�Ȃł��B
2. �z�r�C�n�̃`���[�j���O���K��
�������̃G�L�}�j�ⓙ���z�C�ǂȂǂ�g�ނ��ƂŁA�z�r�C�̗��ꂪ�X���[�Y�ɂȂ�A�R�Ă�����B
���ʂƂ��āA�A�N�Z������ɑ����]�㏸�̒Ǐ]���������Ȃ�B
3. �t���C�z�C�[���������Ⴂ�i�y�ʉ�����Ă���j
�t���C�z�C�[�����d���ƁA��]���u�d���v�Ȃ背�X�|���X���݂��Ȃ�B
�y�ʉ�����ƃA�N�Z������ɑ��ďu���ɉ�]���ω����邽�߁A���Ƀ_�C���N�g�Ȋ��G�ɁB
4. ECU���䂪�_�����Ȃ�
����Ԃ͔R���r�K�X�K���̂��߁A�Ӑ}�I�ɃX���b�g�����X�|���X���g�x�点�āh���鐧�䂪�����B
�X�|�[�c���[�h��ECU�`���[�j���O��**������g��点��h**�ƁA��C�Ƀ��X�|���X�����P���邱�Ƃ������B
🔧 ���_
�u���R�z�C�G���W���̓^�[�{��蔽�����ǂ��v�ƌ�����͍̂\���I�ȓ���������܂����A
���ۂɂ͔R������E�z�r�C�̐v�E�����̍ŏ���������I�ɏd�v�ł��B
✅ ��F���X�|���X�̗ǂ�NA��
�z���_ S2000�F����]�E�����z�r�C�E�����ȔR��
�g���^ AE86�i4A-GE�j�F�y�ʃt���C�z�C�[���Ɖs���R��
BMW E46 M3�FITB�i�Ɨ��X���b�g���j�ɂ��s�����X�|���X
�t�ɁA�����v���Â�NA�Ԃł́A���Ƃ��^�[�{�Ȃ��ł��g�������芴�h�͔������܂��B
�܂�A�uNA�����瑬���v�̂ł͂Ȃ��A�uNA�ŔR�Đ��䂪�L���Ă邩�瑬���v��ł��ˁB
�����S������A�uNA�Ń��X�|���X������ɗǂ������̍�v�����Љ�ł��܂��B����Ă݂�����������܂�
AI����]�v�Ȃ��Ƃ��l���A���܂��B
�����ԍ��F26177059
![]() 0�_
0�_
�F�l�A���͂悤�������܂��B
��https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26170383/ImageID=4039961/
��������Ă���ƃ�P�̈Ӗ����킩��܂���ˁB
�`�����o�[���̈��͂̓X���b�g���ƃV�����_�[�e�ʂƉ�]���Ɉˑ����܂��B
�v���i���`�����o�[���̈��̓X���b�g���ƃ^�[�{�̉�]���Ɉˑ����܂��B���X�����̊Ԃɍ����o����͖̂����ł���ˁB
���̍��𗝉����Ȃ��ƍœK�ȔR���̋������o���Ȃ��Ǝv���܂��B
�Z������ƃp���[���o�Ȃ��B��������ƃG���W���u���[�̌����ɂȂ�܂��B
��P�̑��肪�d�v���ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F26177488
![]() 0�_
0�_
>�����v���Â�NA�Ԃł́A���Ƃ��^�[�{�Ȃ��ł��g�������芴�h�͔������܂��B
����ł������Ȃׂă��b�T��������
�^�[�{���O�͖���
���ꂱ��
�t�Ƀ��b�T���G���W������Ƃ���^�[�{���O�͊����ɂ����Ȃ�̂ł�
�^�[�{���O�͋}�ɃA�N�Z���J�x��傫������Ƌz�C�ʂ�����Ȃ�����������
�A�N�Z���J�x���������傫��������O�͖ڗ����Ȃ��Ȃ�܂����
�����ԍ��F26177517
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����A����ɂ��́B
�����X���肪�Ƃ��������܂��B
���t�Ƀ��b�T���G���W������Ƃ���^�[�{���O�͊����ɂ����Ȃ�̂ł�
�܂��ɂ��̒ʂ�ł��B���̂�������G���W������������̂��̓G���W���z�C�ʂɓK���ȔR�����x��Ȃ��Ƃ͂��������܂��B
�̂̃L���u���^�[�̎���̓W�F�b�g�̌����ł��̔����Ȓ��������Ă��܂��������̎���͔R���}�b�v�Œ������Ă��܂��B
�R���s���[�^����ɂȂ�������G���W���̐����オ��̓L���u���^�[�����D��Ă��܂����B�ł��݂�ȔR���}�b�v�Ɏ�������ă��X�|���X�̌����}��܂����B
���̌�X�J�C���C��RS���o�����Ƀ^�[�{�`���[�j���O���n�܂�F�X�Ȏ�@�ŃR���s���[�^���䂪�n�܂�܂����B
�ł��c�������̓^�[�{���O�ł���A���̂��߃~�c�r�V��IHI���n�l�E�F�����C���^�[�r�����J�����܂����B����ł��c���Ă��܂����̂�
�݂�ȃA�N�Z�����[�N�ɒ��ӂ��Ă��܂��B��������ł��B
�Ȃ�ŃA�N�Z�����[�N�ɒ��ӂ��邩�ƌ����A�e���A�N�Z�����[�����ɑΉ�����}�b�v���������߂ł��B
���̑��݂��Ȃ��}�b�v�̕�Ƀ�P���K�v�ɂȂ��Ă��܂��B
���͊�{�I�ɃA�N�Z���J�x10〜20���ɗ}����悤�ɂ��Ă��܂��B�i���̃X�o���̓A�N�Z���J�x���ǂ߂܂��j
����ŗႦ�Γ��k�����ԓ��ŏ��q���Ă��鎞�ɁA�ǂ��z���Ԑ��ɓ���������ꡂ���]�Ɍ������Ԃ������Ƃ����Ԃɋߊ���Ă������ɗ\�����Ȃ��A�N�Z���S�J�����邱�Ƃ��ߋ����N�Ԃɐ���A�L��܂����B
���̎��͂�͂�^�[�r���͉���Ă��܂����z�C�v���ʂɃ^�[�r�����ǂ����Ă��炸�{���̃g���N�����������A������h�b�J���^�[�{�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂����B���̏�Ԃ̐S�����Č��\��Ȃ���������ł����(^_^)�B
�����ԍ��F26177589
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�r���̎��͂�͂�^�[�r���͉���Ă��܂����z�C�v���ʂɃ^�[�r�����ǂ����Ă��炸�{���̃g���N�����������A������h�b�J���^�[�{�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂����B
������ƈႤ����
���ǂ������������Ƀh�b�J���^�[�{�ɂȂ�̂�
�^�[�{�ɂ��G�N�X�g���p���[���傫���G���W��������ł���
��̎Ԃ��M�����������ł���
�����������͗L��܂���
�^�[�{���O���C�ɂȂ�Ȃ��l�����Ԃ�
���X�p���[���D���Ȃ����i����A�N�Z���J�x�Q�O%���ᑖ��Ȃ�
�đ���G���W���Ȃ烉�O�͏��Ȃ��Ǝv���܂���
�����ԍ��F26177598
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����A�ēx���X���肪�Ƃ��������܂��B
�����ǂ������������Ƀh�b�J���^�[�{�ɂȂ�̂�
�^�[�{�ɂ��G�N�X�g���p���[���傫���G���W��������ł���
�S�����̒ʂ�ł��B���̃��C���̎g�p�͓��������Ăꂷ�Ȃ��o���Ă����̂��y����ł��܂��B�R���ƎԂ̓�l�����̐��E�ł͒葬�̃g���N���獂��]�̑f���炵���g���N�܂Ŗ��i���Ă��܂��B�܂��ɑ�r�C�ʁA���X�|���X�̗ǂ��ݒ�B
�����S�J�̃��X�͑�R�҂��������߂ɃA�N�Z���S�J�ɂ��Ă��܂��B�\�z�O�̃^�[�{���O�Ɨ\�z�O�̋���ȃg���N�ɂт����肵�܂����B��C�Ƀg���N�������オ������ł��ˁB������h�b�J���^�[�{�Ƃ������͉���܂���BMT�Ԃ�FC�RS��������Ă��܂���ł����̂œ������o��ƌ������o�͗ǂ�����܂��B���[�^���[�^�[�{�̂ق����^�[�{���O�������������悤�ȋC�����܂��B�i���قǂ̖��������Ȃ������̂������͂���������������Ǝ���Ă����̂��͉���܂���j�B
����̎Ԃ��M�����������ł���
��̎Ԃ͋��낵���͑����Ăт����肵�܂����B���̎��͓���҂ɐ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂ̃g���N���ł����B
�����X�p���[���D���Ȃ����i����A�N�Z���J�x�Q�O%���ᑖ��Ȃ�
������ӂ͔R��C�ɂȂ�o���Ƃǂ����Ă��A�N�Z���J�x��Ⴍ�}���Ă��܂���ł���ˁB�ł����̃A�N�Z���J�x�Q�O���ł����X�|���X�̍����������Ă��܂��B�Q�D�SL�炵�����X�|���X�̎���2.4L�炵���Ȃ����������݂���̂ł��B
����ł��낢��l���Ă��������Ƀv���i���`�����o�[���ƃ}�j�z�[���h���̍���P���C�ɂȂ�o���܂����B
�����ʼn����N�����Ă���̂��B���m�肽���Ȃ��Ă����킯�ł��B
�ǂ�ȂƂ��Ƀ�P�͕ω�����̂��A�C�ɂȂ����疰��Ȃ��i���ꂪ�Ⴂ����������Q���ɑ������Ă�����������܂��A�����Ⴍ�Ȃ��j
���̒��őz�����Ă��邾���ł��B
�����ԍ��F26177627
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�^�[�{���O�ɂ��āA�[���l�����Ă��܂����A�l�ԂƎԂ��܂߂��V�X�e���Ƃ��Ẳ����x�ꂪ�����ɑ��݂��Ă��܂�
�t�Ƀp���[�Ȃǂ��f�W�^��ON-OFF�I�ɋ}�ɗ����グ��ƁA���̐����ɉߓx�ȕ��ׂ��������Ă��܂��܂�
�A�N�Z���̓X�C�b�`�ł͂Ȃ��A�A�i���O�I�ȃX���b�g���ł����A�]�̔F�m���f���瑫��̓����E�E�E�r���ȗ����āA���Ƃ��M���̎��ʂɗV�т͂قƂ�ǂ���܂��A�}�ȓ��͂͌��ł����A�T�X�y���V�����̃o�l��M���ɁA�G���W���}�E���g��f�t�}�E���g�Ȃǂ̃u�b�V���ނ�{�f�B�[�����ł����������x��̗v���ł����
AT�Ȃ�L�b�N�_�E���Ȃ����܂������
�v�̓q�g�̊��o�Ƌ@�B�̊��o����v�ł���A����ɉz�������Ƃ͂���܂��A�q�g�̊��o�����ꂱ���l���ꂼ��
������l�̐l�ł������A�ڂ̓����Ǝ葫�̓����A�g�̑S�̂̓����̉������x�̈Ⴂ�͑傫���ł����E�E�E
�@�B�Ƃ��Ă̏����̊��҂��A�������d�v�ł����A���܂̋@�B�Ƃǂ��������������A�l����Ɗy�������Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��������ł��傤
AI�̉ɁA�Ȃ�������悤�ɁA�^�[�{�̖�������܂����
�̂�NA���Ȃ�A�J���ɏ��Ƃ�����������Ȃ��ł���
�̂̃^�[�{�́A����ς�u�[�X�g�������āE�E�E�Ƃ����܂ł̃^�����A�ԂƂ̈��݂̌ċz�������̂�������܂���
���Ȃ݂ɂ킽�����A�f�B�[�[���^�[�{�������ł����A��r�I�������Ƃ����A�N�Z���ŁA����Ƀ��j�A�ɒǏ]���Ă����̂��C���������Ƃ����C���[�W�ł�
���ǂ��̎Ԃ́A�����Ɋւ��āA�����x�͂������A���̉����x�̎��ԓI�ω��ł�����x�Ȃǂ��C�ɂ���Ă�炵���ł���
�����ԍ��F26177638
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�͂��߂܂��āB
�傳��̓��O��R���ʼn��Ƃ����悤�ƍl�@����Ă���悤�ł����A
��{�I�ɂ̓A�N�Z���J�x���v�����邾���̋�C�������ɂ̓^�[�r���ʼnߋ��i�l�ߍ��݁j�ł��Ȃ������ŁA
�ŏ��̋�C�s���i�ƌ�����肩�͖{���̔r�C�ʁj����A�����e���|�x��Ĕr�C�ʁi�z����C�ʁj���傷�邩�炩�ƁB
������Ⴆ�Ζ{��1500cc�̎Ԃ�2000cc�����ɂ������̂��A4000cc�ɂ������̂��Ń^�[�r���̑傫�����ς��A
�d���ʂ��������čςޑO�҂̃^�[�r���͌y�������ɉ��o���܂��̂ʼnߋ��������ł��B
���a�̃h�b�J���^�[�{������Ă܂����������͂�����y���������ł����A
���͎����̎Ԃ�NA�ł����A�Ƒ��̌y�ł���NA�����ł��B
���O�����ړI�����ł͖����ł����A�ŋߑ������_�E���T�C�W���O�^�[�{���̉���ŁA���X�킩��₷��TDK����̃y�[�W������܂��B
TDK����̉Ȋw�Z�p�̉���ŁA�u�����Ԃ́g�_�E���T�C�W���O�h���x����g�ߋ��h�̃e�N�m���W�[�v�ł��B
https://www.tdk.com/ja/tech-mag/knowledge/116
�傳�R���Ń��O�i�J�j���������Ƃ���̂́A�o�C�N�Ȃǂŗǂ������u�h���t���v��ɋ߂��C�����܂��B
�̂̃C���W�F�N�V���������̍����ǂ������A��V�����܂����B
�r�C�ʂ��傫���ق��������ŁA�܂���r�C�ʃo�C�N�ł́i�̂́j�T�[�L�b�g���s�ł̓G���u������܂߂āA
�A�C�h�����O��3000�Ƃ�4000��]�Ŏg���P�[�X���������肵�܂����B
�^�[�{�̏ꍇ�����̎�@�Ń��O�͂��Ȃ��������邩�Ƃ��v���܂����A��������MT����ŔR����A
�����ő����V�����m�ł͂���܂��B
�����ԍ��F26177700
![]() 0�_
0�_
�r�Ⴆ�Γ��k�����ԓ��ŏ��q���Ă��鎞�ɁA�ǂ��z���Ԑ��ɓ���������ꡂ���]�Ɍ������Ԃ������Ƃ����Ԃɋߊ���Ă������ɗ\�����Ȃ��A�N�Z���S�J�����邱�Ƃ��ߋ����N�Ԃɐ���A�L��܂����B
�˂��|����C���ɃR�����g���܂�
�����������͉��邪
����Ȏ��ő��ɂƌ������悸����
(������̌������ƌ����̂������Ζ����Ƃ͌���Ȃ���)
�ǂ��z���Ԑ��Ɉڂ�̂͒x���Ԃ����邩��
�܂����ʂɍl���ǂ��z���Ԑ��Ɉڂ��Ēǂ��z�����͐������x���I�[�o�[
�����ɋ��낵�������Ԃ��Č��������Ă܂��P�T�Okm/h�I�[�o�[���炢
�Q�O�Okm/h�I�[�o�[�͐悸����
����ȎԂ��������Ĉ�u�Œǂ����Ȃ���
����Ȃɔ���Ă�����
�O�ɎԂ����鎖�͑z�肵�Ă��Č������͑z���
�ɂ��ǂ��z��(�A�N�Z���Q�O%)�ő債�����x�łȂ������Ȃ�
����s����
�^�[�{�ƌ������CVT�Ƒ��܂��ĉ����Ƀ��O���o����Ȃ��ł���
�l�������悤�Ȏ�(MT�ł���)����Ă܂�����
����ȕ|���̌��Ȃ�Ė����ł���
�^�[�{�̃��O���
�ǂ��z�����̒ǂ��z���Ԑ��̊m�F���ォ�����̂�
�A�H���ăA�N�Z���J���߂������炩
�P��
�_���[���ƒǂ��z���Ԑ������Ă���
�C��������݂����Ȋ�������Ȃ�����
���ʒǂ��z�����ɃA�N�Z��20%���ᖳ���ł������
��e�ʂ̃L�����o�[�Ȃ�č���������
�X�Ƀ��X�|���X�����Ȃ邾���ł���
is500f�Ƃ��ɂ���Ή��K����
(�^�[�{����Ȃ�CVT�ł�������)
�Ɛh���R�����g���Ă݂�
�����ԍ��F26177776
![]() 0�_
0�_
���˂��݂���B����ēx���X���肪�Ƃ��������܂��B
���l�ԂƎԂ��܂߂��V�X�e���Ƃ��Ẳ����x�ꂪ�����ɑ��݂��Ă��܂�
�V�X�e���̊Ԃ̖��̓��O���m���ɗL��Ǝv���܂��B���̃��O�͂��Ƃ��b�Ő\����܂��A100m���ŃX�^�[�^�[���Ȃ��Ă��甽������܂�0.24�b�ƌ����Ă��܂��B�����葁���Ƒ������M�N�V���N���Ă���̂ł��傤�B
���f�W�^��ON-OFF�I�ɋ}�ɗ����グ��ƁA���̐����ɉߓx�ȕ��ׂ��������Ă��܂��܂�
���������Ƃ���ł��B�l�Ԃ̑̂��ˑR�̗����オ��ł͂��������Ă��܂��܂��B��ʎ��̂̂悤�ɁB
���M���̎��ʂɗV�т͂قƂ�ǂ���܂��A�}�ȓ��͂͌��ł����A�T�X�y���V�����̃o�l��M���ɁA�G���W���}�E���g��f�t�}�E���g�Ȃǂ̃u�b�V���ނ�{�f�B�[�����ł����������x��̗v���ł�
�ǂ�����܂��B�l�Ԃ����������A�X�|�[�c�I��͗͂���������������̏�������Ȃ�܂��BEV�������ڂŌ���Ζ�肪�o�Ă���̂�������܂���B
���̂�NA���Ȃ�A�J���ɏ��Ƃ�����������Ȃ��ł���
�܂��ɃJ���ɏ��܂ł̎��Ԃ�NA�̂�ɂƂ��ẴA�N�Z�����[�N�Ȃ�ł��傤�ˁB
����r�I�������Ƃ����A�N�Z���ŁA����Ƀ��j�A�ɒǏ]���Ă����̂��C���������Ƃ����C���[�W�ł�
�������Ƃ����A�N�Z�����[�N�ɒ��ӂ��Ă��܂����A���R��2.4L�̃G���W���̃g���N����Ȃ��Ƃ������Ă��܂��܂��BNA�����200cc�Ⴄ�ƃg���N���͔��[�Ȃ��ς��܂�������B
�������Ɋւ��āA�����x�͂������A���̉����x�̎��ԓI�ω��ł�����x�Ȃǂ��C�ɂ���Ă�炵���ł���
�F�X�Ȃ��Ƃ��l���Ă����ł��ˁB�Ԃ̉����x�̂Ȃ߂炩�����l���Ă����ł��ˁB
����́A�v���i�������}���ɕς��̂Ɓi��������͂��߂邽�߂Ɂj�A��P�̕ω���m��A�R��MAP��ς�����[�[�^�[�{�̖��x�����P�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��͂肱���ɖ߂��Ă��Ă��܂��B���̎v�l�̏I���_�̂悤�ł��B�u���x�v�ƌ������t��m��܂���ł����B����t�������܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F26177847
![]() 0�_
0�_
���������`����A����ɂ��́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂����B
���傳��̓��O��R���ʼn��Ƃ����悤�ƍl�@����Ă���悤�ł����A
�܂��ɂ��̒ʂ�ł��B��t���^�[�{���n�܂���������R���S�Ă������C�����܂��BMotec�ƌ�����t��ECM����������FC3S�ɕt�����Ȃ����Ɩ͍��������Ƃ�����܂��B���ǂ͏o���܂���ł������ǁB
���ŏ��̋�C�s���i�ƌ�����肩�͖{���̔r�C�ʁj����A�����e���|�x��Ĕr�C�ʁi�z����C�ʁj���傷�邩�炩�ƁB
�܂��ɂ��̒ʂ�ł��B�����e���|�x���Ƃ���̔R���������ɂȂ�Ηǂ��Ȃƍl���Ă��܂��B
���d���ʂ��������čςޑO�҂̃^�[�r���͌y�������ɉ��o���܂��̂ʼnߋ��������ł��B
�܂��ɂ����ł��ˁB�������^�[�r�����đ�r�C�ʂƓ����g���N���o��.�Ƃ������ɂȂ�܂��B
�ł��ӂƎv�����̂ł���1600cc�̃G���W���̃_�E���T�C�W���O�^�[�{��180�n�͂��炢�o���Ă��܂���ˁB����������HONDA��2000S�����̂��炢�̔n�͂ł����g���N������Ƃ����Ƒ�^�̃G���W���A3L�N���X�ɂȂ��Ă��܂��B�����ł͂��Ǝv���̂ł����A�����܂Ńg���N����Ȃ��H����Ȃ��B�ȂǂƁB�x���c��180�b��1600cc176�n�͂��������L���͒肩�ł͂���܂���B���Ȃ��Ƃ�2000cc��NA�������n�͂ł����B
�����n�͂����߂Ă�������g���N�����߂Ă���Ǝv���܂��B
�������̎Ԃ�NA�ł����A�Ƒ��̌y�ł���NA�����ł��B
����NA�͍D���Ȃ̂ł�������͂��܂��܍Ō�ɑ�r�C�ʃ^�[�{�ɏ���Č����������Ƃ����̂�����ł��B
��TDK����̃y�[�W������܂��B
����ǂ݉���������܂����B���̃^�[�{������ǂ�����܂����B�]�肱�̕�������Ă��Ȃ��̂ŏ�����܂����B
���傳�R���Ń��O�i�J�j���������Ƃ���̂́A�o�C�N�Ȃǂŗǂ������u�h���t���v��ɋ߂��C�����܂��B
�o�C�N�̘b�͉��������ł��ˁB���̓o�C�N�̉����ɂ͎����߂Ȃ������̂Ńh���t����Ƃ������Ƃ�����܂���ł����̂�
AI�Ɏ��₵���Ƃ���o�C�N�̍���]�܂ł̓r���ŃX���b�g�����}�ɖ���������Ƒ�������ƌ������ۂƂ������Ƃ�m��܂����B
�����\�����߂�Ɖ����ɂł��L�錻�ۂȂ�ł��ˁB
���A�C�h�����O��3000�Ƃ�4000��]�Ŏg���P�[�X���������肵�܂����B
�Ȃ�قǂ���������i�������ł��ˁB�{���ɒ����ł͂����Ȃ���MT��p�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ł�����Ȃ�Ƃ��������Ǝv���Ȃ���܂��v������Ă��Ȃ��v���i�����𑪒肵�悤�ƌ������_�ɓ��B�����킯�ł��B
���̃C���W�F�N�V�����͓d�q����Ȃ̂Ń�P���L��A�R���̕�����K�ɂ��ł���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���܂��B
���������A�C�f�A������Ζ������Ă��������B�X�������肢�������܂��B
�����ԍ��F26177893
![]() 0�_
0�_
��haghog����
��AI�Ɏ��₵���Ƃ���o�C�N�̍���]�܂ł̓r���ŃX���b�g�����}�ɖ���������Ƒ�������ƌ������ۂƂ������Ƃ�m��܂����B
�{�����[���ƁA�C�����́H�ŁA���ꂼ��̍���]���ĕς���Ă��܂���B
250����4�C���@���b�h��2���ł����B
400����4�C����1.4���H�ł��B
���o�C�N�̍���]�܂ł̓r���ŃX���b�g�����}�ɖ���������Ƒ�������ƌ������ۂƂ������Ƃ�m��܂����B
���́ANa�̃o�C�N�Ȃ�ő��p���Ȃ��ł��B
�i�Ԃ̓^�[�{�j
�{���ɂ��������Ƃ����肢���܂��B
�����ԍ��F26178153
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����A���ӂ́B
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���˂��|����C���ɃR�����g���܂�
�����������͉��邪
����Ȏ��ő��ɂƌ������悸����
���������v���܂��B���̎��͊m�����k�����ԓ���120km�����n��ŁA����115km/h�ŏ��s���Ă��܂����B�i120km��ɂȂ�Ƌɒ[�ɔR�������̂Łj3�Ԑ����ł��B�ڂ̑O��110�L�����炢�̎Ԃ����Ēǂ��z���Ԑ��ɏo�悤�Ƃ��܂����B�����z��ǂ��z�����x��135km���炢�̑��x�ł����B�o�b�N�~���[�ɂ͂Ȃɂ��Ȃ�135km���炢�܂ŃX�s�[�h���グ���Ƃ��Ƀw�b�h���C�g���ڂɓ������̂ŃA�N�Z����S�J�ɂ��܂����B���̂��Ƒ��s�Ԑ��ɖ߂����Ƃ��ɂ͑��x���~�^�[��-20k�����炢�ł����B���̘e��2���BMW�A�F�͍��Ɣ��A���ł������Ă��܂��������Ɍ����Ȃ��Ȃ�܂����B���k�����ԓ��͔N�ɉ���������Ă���3�Ԑ��̑��x���o�������Ă��܂��������̂Ƃ������͗�⊾�������܂����B
�@���ꂪ���̓^���ł��B
�߂����ɂ��Ȃ����̂ɑ������������ł��B
������Ȃɔ���Ă�����
�O�ɎԂ����鎖�͑z�肵�Ă��Č������͑z���
�R���i�̎����ŎԂ͂قƂ�ǂ��܂���ł����B�Ƃ��������̑��x���ɂтт�܂����B�̃h�C�c�ɗ��s�����Ƃ��ɁA�ړ��Ō��n�̐l�Ɂi���{�l�̎ԂɐL�����Ă������160km���炢�ő����Ă����Ƃ��j�ǂ��z���Ԑ����h�J���Ƃ������Ƃ��ɒǂ������ꂽ���Ƃ�����܂����A������͂����ƒx�������͉̂���܂����B
���ɂ��ǂ��z��(�A�N�Z���Q�O%)�ő債�����x�łȂ������Ȃ�
�ǂ��z���͊댯�������̂łł��邾�������I��点�����Ǝv���Ă��܂��B�ɂ��ǂ��z��������Ȃ�ǂ��z���͂��܂���B
������ȕ|���̌��Ȃ�Ė����ł���
�Ȃ��Ǝv���܂��B���Ƃ�2��͓����������H�ł����A�����ƃY�[�b�Ɛ̂ł��B
��is500f�Ƃ��ɂ���Ή��K����(�^�[�{����Ȃ�CVT�ł�������)
����ɂ͋@��������瑖���Ă���̂ł����Ă݂����ł��B�قƂ�ǃt�F���[��������悤�Ȃ��̂ł��傤
�����ԍ��F26178222
![]() 0�_
0�_
��ZXR400L3����͂悤�������܂��B
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���{���ɂ��������Ƃ����肢���܂��B
����40�N�ȏ�O�̘b�ɂȂ�܂��̂ŋL�����B���ȂƂ��������܂����A���̍����̂Ƃ��낪�L��܂��̂ŁA�����ŋL���������Ă����Ƃ��������܂��B
�܂������b�Ƃ��̃X���ɊW����Ƃ��낾���������Ƃɂ��܂��B
��������HONDACB400Four�ɏ���Ă��܂����B�w���������������F�X����̂��Ƃł��F�X�ł��B
�܂��͂����良���Ă���͕̂x�m�R�Ƀc�[�����O����5���ړ�����ŋ}�ɃG���W���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�C���̂����ŃG���W���������Ȃ��Ȃ�̂�m�����̂͌�̂��Ƃł����B���n�ł͏\���ɐ����オ�邵�A�G���W���g���N������̂ŁA1500��]�H2000��]�H�Ńc�[�����O�͂��Ă��܂����B�������肩�ł͂Ȃ���ł��B�����ƃA�N�Z�c��t���������ƁA�����ƃA�N�Z�����ӂ��������ł͔����ɍ����������悤�ȋC�����܂��B�����{���ɒ肩�ł͂Ȃ��̂ōς݂܂���B�����̃G���W���̓��b�h�]�[����9000��]���炾�����C�����܂���������肩�ł͂���܂���B
�����́ANa�̃o�C�N�Ȃ�ő��p���Ȃ��ł��B
����ɂ��Ă͌���̃o�C�N�ɂ͈�ƐG��Ă��Ȃ��̂őS������܂���B
�o�C�N�̘b�̓o���o���`���̒��̗��R�T�[�L�b�g�̘b�����Ă���Ɠ����̃G���W���͐����ȂƂ�����ۂ����L��܂���B
��400����4�C����1.4���H�ł��B
�܂������ł͔��f���Ȃ��ł��������B������9000��]�����b�h�]�[�h�Ǝv���܂����A�������̃��x���ł̓G���W���͏d�������オ��܂��B
������AI�Ɏ��₵���Ƃ���o�C�N�̍���]�܂ł̓r���ŃX���b�g�����}�ɖ���������Ƒ�������ƌ������ۂƂ������Ƃ�m��܂����B
����̓��X�𗝉����邽�߂�AI�Ɏ��₵�����Ŗ{���ł͂���܂���B
�ȏ㓚���ɂȂ������͕s���ł������̋L���̒��̑q�ɂ̉�����o���������ł��B
�x�m�R�̂�����ŋC�����Ⴍ�Ȃ�ƃG���W���͉��Ȃ��Ƃ������Ƃ������ł��o�����Ă������Ƃ��v���o�����Ă����������肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F26178523
![]() 0�_
0�_
2025/05/14 10:38�i4�����ȏ�O�j
���h���t����Ƃ������Ƃ�����܂���ł����̂�AI�Ɏ��₵���Ƃ���o�C�N�̍���]�܂ł̓r���ŃX���b�g�����}�ɖ���������Ƒ�������ƌ������ۂƂ������Ƃ�m��܂����B
�����AI�̉��Ԉ���Ă��܂��B
�h���c�L�́u�A�N�Z���̃c�L���ǂ����錻�ہv�ł���A�L���u����FI�Ɉڂ�ς��������̘b�ł��ˁB
FI�̔����i�A�N�Z���̃c�L�j���������ăX���b�g���������J�����u�ԂɃG���W�����������āu�h���I�v�ƃp���[���o�Ă��܂����ۂŁA�����Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B
�ꎞ���̃h�D�J�e�B�Ȃ�ĊX���ŏ�ꂽ���̂ł͂Ȃ����炢�h���c�L������܂����ˁB
�ŋ߂͓d���X���b�g���������ĔR���}�b�v���f���炵���ǂ��Ȃ����̂ŁA�ڗ��h���c�L�̂���o�C�N�͂قڂ���܂���B
���̃X����AI�̉�������܂������ǁA�������͖̂ڐV�������͖̂����Ȃ��Ƃ����̂���ۂł��B
���X�|���X�̗ǂ�NA�Ԃ̗�ł�S2000��AE86��E46 M3�Ƃ��A����20�N�ȏ�O�̎Ԃ������o���Ă���̂��ŐV��AI�Ƃ��Ă͂ǂ��Ȃ́H�Ɗ����܂����B
�����Ƃ��Ă͌���ł�AI�ɕ�����胂�[�^�[�t�@���C���X�g���[�e�b�h�̂悤�Ȉ�ʌ����̋Z�p�n���Ђ�ǂ������ɂȂ�Ǝv���܂����B
�l�I�Ȉӌ��ł͐悲��o���V�^�|���V�F911GTS���^�[�{�G���W���̍ŏI�i���n�ɋ߂��Ɗ����܂��ˁB
�����ԍ��F26178605
![]() 1�_
1�_
�����j�o�[�T���Z���`�����[����A����ɂ��́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���̖��m���������������悤�ł��B�\����܂���B
�������AI�̉��Ԉ���Ă��܂��B
�h���c�L�́u�A�N�Z���̃c�L���ǂ����錻�ہv�ł���A�L���u����FI�Ɉڂ�ς��������̘b�ł��ˁB
�Ȃ�قǁAF1�^�[�{�ԑS�J�̎���͂����]��Ԃ̃��J�Ɏ��Ԃ��������d���ɔM�����Ă��܂����B
�Y�����Y�̂悤�ł��B����3�C��4�C���������ăp���[���i��o���Ă��鎞��A�A�N�Z�����X�|���X��ǂ����悤�Ƃ��Ċ댯�ȗ̈�ɂȂ��Ă��܂��Ă�����ł��傤�B
���ꎞ���̃h�D�J�e�B�Ȃ�ĊX���ŏ�ꂽ���̂ł͂Ȃ����炢�h���c�L������܂����ˁB
YouTube���ȂŃX���b�g���̂Ȃ��G���W���̃h�D�J�e�B�̉f�����������Ƃ�����܂��B�o�C�N���������Ă���l�������ǂ����悤���ƔY��ł���f���ł����B���ꂵ���L���ɂȂ��̂ł��ꂾ���ɂ��܂��B
��NA�Ԃ̗�ł�S2000��AE86��E46 M3�Ƃ��A����20�N�ȏ�O�̎�
����͂Ƃ݂����`���l���̉e���ł��B�G���W�������̃m�E�n�E�����J���Ă����̂Ō����Ă������߂ł��B
�������Ƃ��Ă͌���ł�AI�ɕ�����胂�[�^�[�t�@���C���X�g���[�e�b�h�̂悤�Ȉ�ʌ����̋Z�p�n����
�Q�l�ɂ����Ă��������܂��B�Ƃ�����amazon����
�����w���A���̊ԂɃ|���V�F911GTS���^�[�{�G���W���̍\���ɂ��Ă������B
���e�I�ɂ�AI�Ƃ̘b�������̌��_�Ɠ����Ń�P�Ɏ���_���͂���܂���ł����B911GTS�̍\����AI����͑��������Ă̗L�������̂ł����B
��͂�A���������f�������ł͏[���Ȑ������o���Ȃ���AI�ɒQ������JSAE�̓�������߂��܂����̂łǂ����悤���ȂƂ��v���܂�����
����邱�ƂɌ��߂܂����B
�����ԍ��F26178830
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�h�������܂�
���x�I�[�o�[�̌��͍r���ƍ���܂�������Ƃ��ẴX���[�Y�Ȓǂ��z���̓r���ƌ�������
�����ő���Ԃ��������Ď��͂��������Ă����ł���
�i���������Ă���{�o����O��Ŕ���Q��Ȃ珮�X�A���̂�Ώ���j
>�o�b�N�~���[�ɂ͂Ȃɂ��Ȃ�
�P�Q�O����/���̃G���A���Ď��͂R�Ԑ��Œ������J�[�u���߂���ɂ����̂͂�
�P�R�T����/���ő����Ă�����Ƃ��Q�O�O����/���ő����Ă��Ă����Ȃ�O���猩���邵�A�b�g�����Ԃɂ͒ǂ��t����Ȃ�
�X���傳��̎Ԃ͂��������p���[���g���N���L�邪
����ȃr�b�N������قǂł��Ȃ�
�P�R�T����/������̉����ł���Ȗ\�͓I�ȉ����͂��Ȃ��Ǝv��
�b�u�s�����疾�m�Ȍv�Z�͏o���Ȃ������������̕��ׂ��|�����Ă��Ă���������]�����オ���Ă����͂�
�i���o�͒��ۓI�Ȃ̂ł܂��l���ꂼ�ꂾ���ǁj
�����ʼn����������Ƃ���^�[�{���b�u�s���Ǝv����
�Ⴆ�P�R�T����/���t�߂܂ʼn������i���̂��炢�̑��x�ŏ\���Ɓj�A�N�Z�����ɂ�
���̒���̔w��ɔ���Ԃ����ăx�^���݂Ƃ���������
�b�u�s�̈�ԋ��ȕϑ�(�ϑ��͐������������v�[���[��̕ύX�j��
��U�n�C�M���[�h���ɂ����Ă������Ƃ�������Ƀ��[�M���[�h�w���ƂȂ�
�������b�u�s�̓�������Ȃ�����
���̎Ԃ͂����ԗǂ��͂�������
�b�u�s�̓A�N�Z���n�e�e����̂n�m�͂ق�Ɠ��ӂ���Ȃ�
�������ꂽ�Ƃ���傳��̎Ԃ���
�^�[�{���O�͖�����ł͂Ȃ����x�ꂪ�|���قǂł͂Ȃ�����
�Ɛl�̓^�[�{���O�łȂ��b�u�s����
��̂̒��������s�Ԃ͎Ԏ��̂̐��\���Ⴂ�܂o�͂������₵����Ȃ��i�댯�ȑ��s)�̎Ԃ�������������
�ŋ߂́i����j�Ԃ͎Ԃ̐��\�Ƃ��Ă͊i�i�����ᔽ���l���Ȃ���Β��������s���Ă�������
�K���Ȋ����ł͂Ȃ����Ȃ�]�T�������đ��Ă����肷��
�i�ܘ_�O�Ԃɑ��Ẵu���[�L���\���j
�����ԍ��F26178872
![]() 0�_
0�_
��haghog����
���x�m�R�Ƀc�[�����O����5���ړ�����ŋ}�ɃG���W���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�C���ł͂Ȃ��A�_�f�����Ȃ��Ȃ������琁���Ȃ��Ȃ����Ǝv���܂��B
����40�N�قǑO�ATZR125��5���ڂ܂ōs���܂������A�S�������܂���ł����B
�������ƃA�N�Z�c��t���������ƁA�����ƃA�N�Z�����ӂ��������ł͔����ɍ����������悤�ȋC�����܂��B
�_�f�����Ȃ��̂ŁA�J�u���C���������̂ł��傤�B
�����ԍ��F26178912
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����A���ӂ́B
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���̎Ԃ�������ł�K�v������܂���ł������A������1.6L�^�[�{�ł����B
��������80�̘V�l��60�̐l���悹�Ă���ȃ��`���͂��܂���B�Ƃ����������m�F�ł��B
���k�����ԓ��̓A�b�v�_�E��������̂ň�T�Ɍ��ʂ����ǂ��Ƃ������܂���B���̎ԂŃA�N�Z�������܂œ��ݍ���ʼn�����҂̂͂��������h�������ł���B
�������̎��Ԃ����b�������̂�10���b���������͉���܂���B������x�ƌ����Ă��o����҂ł͂���܂��A�������邩���Ȃ����͑��莟��ł��B�������Ă����Ȃ�����ƃX�s�[�h�͑��������Ǝv���܂��B��������͎������Ă��邱�Ƃł͂���܂���̂ŁB
���Ɛl�̓^�[�{���O�łȂ��b�u�s����
����͐������Ǝv���܂��BCVT�̃��X�|���X�̒x����DCT���͖��炩�ɒx���̂ŁB
�Ԃ�ς�������ł����܂Ŋ���Ă��Ȃ������̂ƑO�ɂ��q�ׂ��悤��115km�ȉ��ɗ}�����^�]�𑱂��Ă����̂Ńt�������̊��o�����������̂��Ǝv���܂��B
�։z�����ԓ��ŃX�s�[�h���~�^�[�����ł����Ƃ����Ԃɘb���ꂽ���Ƃ�����܂��B����30�N�ȏ�O�̘b�ł��ˁB
�����ԍ��F26179070
![]() 0�_
0�_
��ZXR400L3����A���ӂ́B
�ēx���X���肪�Ƃ��������܂��B
���C���ł͂Ȃ��A�_�f�����Ȃ��Ȃ������琁���Ȃ��Ȃ����Ǝv���܂��B
���l�b�g�Œ��ג����܂���������2300m����2400m�Ȃ�ł��ˁB�̂͒m��Ȃ���������Ǎ��͂������ׂ��܂��B�ǂ�����ɂȂ�܂����B
���̕W���ɂȂ�Ɛ��̕��_��95�x���炢�ɂȂ���������R�[�q�[�����߂�炵���̂ł����o���������āB
�Ɨ]�v�Ȃ��Ƃ������āB
���_�f�����Ȃ��̂ŁA�J�u���C���������̂ł��傤�B
�܂��ɂ���ł��B�����͂ɏ����N�������Ƃ��o���ă�O�i�_�f�����̕ω��j��m�邱�Ƃ��o����������Ɨǂ������̂�������܂���B
�����R����̌i�F�͗ǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F26179085
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�����I�Ƀ^�[�{���O�������͓���ł����
�X���傳���P�������^�[�{���O��
�R�O�N�O�̃^�[�{���O�ł����@
���̃^�[�{���O�ł���
���̎Ԃł����_�I�Ƀ^�[�{���O�͗L��܂���
�X���傳�H�ɑ̌������悤�Ȏ��͖����Ǝv���܂�
��̖l�̃R�����g�������H�[�O2.4�ɑ��Ă̎v���ł�
���̕��ʂ̎Ԃ�
���|��������قǂ̃��O��p���[(�g���N)�̎R�͖����Ǝv���܂����ǂ�
�@
�����ԍ��F26179307
![]() 2�_
2�_
��gda_hisashi����A����ɂ��́B
�ēx���X���肪�Ƃ��������܂��B
���X���傳���P�������^�[�{���O��
�R�O�N�O�̃^�[�{���O�ł����@
���̃^�[�{���O�ł���
���̎��₨�����͓���ł��B�^�[�r���̐i�������Ă����30�N�O�̃^�[�{���O�͔��ɑ傫�ȕ��ł���A���X�i������^�[�{�̎��͂�����ƁA���̃^�[�{�Ɍ������ނ��Ƃ͏o���Ȃ��悤�ɂ��v���܂��B�ł��������Ă����d���ł͉��ǂ������̉��P��50���O�ゾ�������ɍl���镨���Ԉ���Ă���ƌ������������܂��B�܂���30�N�O�̃^�[�{���O�Ɣ�r�����1/4�ȉ��ɂȂ��Ă��܂������̊Ԃ̐i���͉��i�K���o�Ă��܂��B�ł��̂ŁA�܂��{����˂��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƂƂ��v���Ă��܂��܂��B�v���i���`�����o�[����}�j�z�[���h�`�����o�[�܂ł̋�C�̗��ꃢP���������邱�Ƃ��o�������ɖ{���̃^�[�{���O�̉��P�̌��E��������ƐM���Ă��܂��B
AI�lj�������v�����܂�������P�Ƃ��������ʂ́A���܂Łu���ʁv��u�����x�v�Ŋ��o�I�ɏ�������Ă����������A
���l�Ƃ��đ����������������ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B
�u��C�̎d���ʍ��v��������悤�ɂȂ�A�R�����ߓn�������A������i�K�i���ł���̂ł͂ƁB��
���X���傳�H�ɑ̌������悤�Ȏ��͖����Ǝv���܂�
����͖{���Ɋ�Ȍ��ۂ��Ǝv���܂��B���̑̊��������Ă��܂��Ă���̂ŁA��@�����������Ɏ��Ԃ����������ƌ������ۂ����x������܂��B���ꂾ�����̂�������܂���B
�����|��������قǂ̃��O��p���[(�g���N)�̎R�͖����Ǝv���܂����ǂ�
����͂܂��ɐ������Ǝv���܂��B���|���������͓̂ˑR�o�������\�z�O�ɑ����Ԃ̂��߂ł����B�A�N�Z�����ݍ����肶��Ƃ����X�s�[�h�͏オ��Ȃ��Ɗ����Ă���B�ԑ������������s�Ԑ��ɖ߂�B���l����Ƃ����Ƃ����Ԃ̂��Ƃł���ˁB
���̒��̃C���[�W�ɋr�F�������Ă��܂��Ă��邩������܂���B
�����ԍ��F26179608
![]() 0�_
0�_
��haghog����
��CB400Four
4���Ȃ�A���v����Ȃ��H
�܂��āA4����
TZR125�i2�����j�͒P�C���Ȃ�ŁA�J�u���ΏI���ł��i�����x�ƂȂ������Ȃ��Ȃ������ǁj�B
�i���̂��߁A�M�����Ƃ���1�{�\���v���O�͎����Ă͂��܂��������j
�����ԍ��F26180008
![]() 1�_
1�_
��ZXR400L3����A���ӂ́B
���X���肪�Ƃ��������܂����B
CB400Four�ł��G���W���͉��Ȃ��Ȃ�܂����B���Ԃ邱�Ƃ͂Ȃ������ł����A�ǂ�ǂE�M�A�ő���悤�ɂȂ�܂����B
�ł��]��悭�o���Ă��܂���B�o���Ă���̂͒��ԏꂪ�����ς��ł��̂܂ܖ߂��Ă������Ƃ��炢�ł��B
�����ԍ��F26180034
![]() 0�_
0�_
�S�O�O����V4�i�m�b�R�O�j�ɏ���Ă������A180km/h�X�s�[�h���~�b�^�[���t���Ă��邩�����Ŏ����܂������A���~�b�^�[�͕t���Ă܂���ł����B
GSX400R���t���ĂȂ����f�������������ł��B
�T�����Ƌ�C�ɕ����܂��A���b�h�]�[���ɂ͓͂��Ă܂���ł����B
�����ԍ��F26181092
![]() 0�_
0�_
��RBNSX����A����ɂ��́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
�����ł��ˁB�ō����x�̃`�������W�ł����ǂ܂������̈�ʎԗ��̃^�C����180km/h�ȏ�Ή��ł͖���������������܂���B
�ō������`�������W���邱�Ƃ͂��Ă��܂���ł����B
�����ԍ��F26181433
![]() 0�_
0�_
��RBNSX����
�Ȃ��A���̘b�ɂȂ����̂��s���ł����E�E�E
���u���~�b�g�͗����Ǝv���܂��B
�R���J�b�g�̐��䂪����̂ŁA�K�^�S�g���܂���B
�ŁA�����炭���b�h�����肪180����/������������ɂȂ�悤�ȃM����ɐv����Ă���Ǝv���܂��B
�i�Z�p�Җڐ����ƁA�X�s�[�h���~�b�^�[��t����R�X�g�v��Ȃ����E�E�E�j
���[�^�[�́A1���������炢�̕\���ł��ˁB
NC30�AGSX�ł͂Ȃ��ł����AGPS���[�_�[�Ǝ��Ԃ̃X�s�[�h���[�^�[�͂��ꂮ�炢�̍�������܂��B
�����ԍ��F26181487
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�x�m�R5���ڂ̎_�f�́A�M���̍D����AI�ɕ����A�ȉ��̉ł��B
�L���u�ԂȂ�A�����܂��ˁB
�����n�̎_�f�Z�x�Ɣ�r���Ė�74����������܂���B����́A���n�ł̎_�f�Z�x����21���ɑ��A5���ڂł͖�15.5�����x�ɒቺ���邩��ł��B
�C���W�F�N�V�����Ȃ�A�R���ʼn��Ƃ����Ă����̂��ȁH
�����ԍ��F26181509
![]() 1�_
1�_
��ZXR400L3����A���ӂ́B
�A�����X���肪�Ƃ��������܂����B��RBNSX����̃��X�̕ԓ��͎��ɂ͏o���Ȃ��̂Ŏ��炳���Ē����܂��B
���C���W�F�N�V�����Ȃ�A�R���ʼn��Ƃ����Ă����̂��ȁH
���̃X���̖{��ƂȂ郌�X�ł��B
�������n�̎_�f�Z�x�Ɣ�r���Ė�74����������܂���B����́A���n�ł̎_�f�Z�x����21���ɑ��A5���ڂł͖�15.5�����x�ɒቺ���邩��ł��B
���̏ꍇ�̑�C���̓v���i�����ɑ������܂��B���x�������Ȃ�Ύ_�f�ʂ�����̂Ŕ����R���łȂ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ������ɂȂ�܂��B
�U��Ԃ��Ă݂�ƃ^�[�{�Ԃ͋z�C�n�������Ă��G�A�t�B���^�[�E�G�A�t���[���[�^�[�E�^�[�{�E�v���i���`�����o�[�E�X���b�g���E�}�j�z�[���h�ɂȂ�܂��B�v���i���`�����o�[�܂ł̒ʘH����C���ɑ������܂��B�܂���C����m��Ȃ���ΔR���͔Z���Ȃ�܂��B��C����m��ΔR���̒����͊ȒP�ł��B�Ƃ��낪�^�[�{�̏ꍇ�ł̓^�[�{������Ă���Ƃ��Ɖ���Ă��Ȃ��Ƃ��ł͈�u�ō��x5000m����n�ꐔ�烁�[�^�[�ɑ�������ω����o�Ă��܂��B�������u�ŁA������v���i����P�ƃ�P�ƃ`�����o�[�����K�v�ɂȂ��Ă���̂ł��B
�v���i��������C�����A-0.4�C���̎��A�{1�C���̎��ł́A�����}�j�z�[���h���ł��قȂ��Ă��܂��B
�ł��̂Ńv���i������m�胢P��m��ΔR�������܂ł�����������ƒ����ł���Ǝv���܂��B
���݂ɂȂ̂ł����A�����̂Ƃ��뎄�̎Ԃ�CVT���}�j���A���Ŏg�p���A�N�Z���ׂ����݂�����Ƃ������������Ă��܂����B
���1800��]���炢�ł��A�N�Z���ɑΉ�����G���W���̔������o��̂�2〜3�b�������Ă��܂����B
���̔����̒x���������̂���P�ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
AI���lj��̐�����t���܂������^�[�{�Ԃɂ�����z�C���́A��u�Łg���n�h����g�n��h�܂ŗ����ފ��ω��ł��B
�����炱���A�u���̃�P�i���͌��z�j�𑨂�����A**�]���̃}�b�v����ł͓����Ȃ������g�����̎肪����h**�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B��
�����ꕶ�lj�����܂�������ʓI�ɂ�MAP�Z���T�[�Ń}�j�z�[���h�����������ĔR������܂����A
�X���b�g���O��́g�����h���傫���ω����Ă���ł́AMAP�P�̂ł͉������x���ꍇ������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B��
�Ǝ��ɂ��z�������������o���Ă��܂���AI�����������̂͏��������̂Ƃ��Ďc���܂��B
�����ԍ��F26182020
![]() 0�_
0�_
��haghog����
���ǂ��z���͊댯�������̂łł��邾�������I��点�����Ǝv���Ă��܂��B�ɂ��ǂ��z��������Ȃ�ǂ��z���͂��܂���B
���̈ꕶ�ŁA�悤�₭�A�X���傳��̌����u�^�[�{���O�v�̈Ӗ����킩��܂����B
���́A�u��r�C�ʂm�`���X���傳��̋��߂鋆�ɂ̃G���W���v���Ǝv���܂��B
�^�[�{���O�ɂ́A�傫�������āA
�P�j�@�A�N�Z����ł���g���N�������オ��n�߂�܂ł̊�
�Q�j�@�g���N�������オ���Ă��玩���̎v���g���N�����オ��i�ɒ[�Ɍ����A
�ő�v���b�V���[�j�ɂȂ�܂ł̊�
�̂Q��ނ�����܂��B
�P�j�́A�l�X�ȋZ�p�ŏ������Ȃ��Ă��Ă�����̖̂����Ȃ邱�Ƃ͂���܂���B
���S�ɖ��������߂ɂ́A�A�N�Z���I����\�����đO�����ă^�[�r�����n�߂邩�A
�^�[�r������ɉĂ������������Ǝv���܂��B
�Q�j�́A�g���N�������オ��n�߂�ƂQ��ɔ�Ⴗ��悤�Ɂi���ۂɂQ��ɔ�Ⴗ��
�킯�ł͂���܂���B�����܂Ŕ�g�ł��B�j�g���N�������オ���Ă䂭�킯�ł����A
�i�������H��Łj���̍Œ��̋}���ȗ����オ��ɃX���傳��͋��|��������
�킯�ł��B
�ƂȂ�ƁA��Ƀ^�[�r�����Ă����ăg���N�̗����オ��������炩�ȕ����ǂ��E�E�E
�܂�͑�r�C�ʂm�`�G���W���������Ȃ̂��Ǝv���܂��B
���Ȃ݂Ɏ��́A�����Z�f�X AMG CLA45�i2,000cc��381hp�j�̃h�b�J�`���^�[�{��
��D���ł��B
�V�k�S�Ȃ���B
�����ԍ��F26182140
![]() 1�_
1�_
�������̂��̐悳��A���ӂ́B���߂܂��āB
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���̔Y�݂��R�҂��������Ē����������ł����Ӓv���܂��B
���u��r�C�ʂm�`���X���傳��̋��߂鋆�ɂ̃G���W���v
����͈�̓����ł��鎖�͊ԈႦ����܂���B�ł����̃^�[�{�̃g���N��NA�ŏo�����c����Ə��Ȃ��Ƃ��R�{�̔r�C�ʂ��K�v�ɂȂ�܂��B
�������̖��͂������ő�̖��_���Ǝv���܂��B��r�C�ʂ̗ǂ��͎v���G���W�������Ǒf���炵�����X�|���X�ƃg���N���A����^�[�{�G���W���͌y���G���W���ŋ���ȃg���N����̂̂���̃g���[�h�I�t�ŃG���W���̔��������]���ɂ��Ă��܂��܂����B
���ꂪ�^�[�{�Ԃ��n�߂��Ă��獡�܂ő����Ă���Y�݂ł��B�X�[�p�[�`���[�W���[�d�C���`���[�W���[�d���n�C�u���b�h���X�͂ɕ����킹�ĉ�������BNA��r�C�ʂ��͂ʼn������Ă��܂���ˁB
���^�[�{���O�ɂ́A�傫��������
���̕����͉ߋ��S�O�N�ԃ^�[�r��������Ђ����X�w�͂𑱂��Ă��܂��B
�����Ă��̎肱�̎�̉��ǂ𑱂��Ă��Ă��܂����A�����������ǂ����ŐV�������@���l���Ă���Ǝv���܂��B
���A�N�Z���I����\�����đO�����ă^�[�r�����n�߂邩�A
�^�[�r������ɉĂ������������Ǝv���܂��B
����͗\���R���}�b�v��~�X�t�@�C�������O�V�X�e���ɂȂ��Ă��܂��܂��B
����͂���Ŗ����䂫�N�����\��������܂��B
���X���傳��͋��|���������킯�ł��B
����͏�������āA�\�z�O�̋}���x�Œǂ��グ�Ă����Q��̎Ԃɋ����ċ��|�������A�ׂ����݂̂܂܂Ńt�����������������ŁA���̏����������������̂�������܂��^�[�{�̃t�������ɂтт����킯�ł͂���܂���BFC�RS�͒lj��R�������ăg���N�̃��~�b�g���O���Ă��܂����B
���g���N�������オ��n�߂�ƂQ��ɔ�Ⴗ��悤��
�^�[�{�̉����̓��j�A�ł͂Ȃ��̂͊m���ł��B�^�[�r�����t���ɉ���Ă��Ă��}�j�z�[���h���������ł��X���b�g���̗������x���オ���Ă��܂��̂ŏ[�U������C�̒��͔���I�ɏオ���Ă����܂��B�����}�j�z�[���h���ł��B
���ꂪ��P�̓����ł��B�Ō�ɂ̓G�A�t���[���[�^���K�v�ɂȂ邱�Ƃ��L��Ǝv���܂��B
����Ƀ^�[�r�����Ă����ăg���N�̗����オ��������炩�ȕ����ǂ�
��Ƀ^�[�r�����Ƃ����̂͊���̗��_�ł͂����Ȃ�܂����A����̒��̏Z��n����o�鎞�ɁA�^�[�r��������Ԃŗ������Ƃ��ʋ��邱�Ƃ��o���܂���B
��������Ƒ�r�C��NA�ɖ߂��Ă��܂��܂��B���̈����̃T�C�N����ؒf���邽�߂Ƀv���i���`�����o�[�̈����v��A��P���������ă^�[�r���̉ߓn�I��]�㏸�ɂ������R�������悤�Ƃ����̂����̈Ӑ}�ł��B
�킽����AI���ȉ����̒lj����ǂ��ƒ��܂���
���u�X���b�g���o���u�����O��̈��͍��i��P�j�����A���^�C���ő����A
ECU��������g��C�̉������h�Ƃ��Ċ�������A
����g���̔ł̃X���b�g���J�x�\���h���ł���̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B�v��
�������Z�f�X AMG CLA45�i2,000cc��381hp�j�̃h�b�J�`���^�[�{��
��D���ł��B
IHI�̃^�[�r���̂�ł����H
�����ԍ��F26182190
![]() 0�_
0�_
�r����̒��̏Z��n����o�鎞�ɁA�^�[�r��������Ԃŗ������Ƃ��ʋ��邱�Ƃ��o���܂���B
�����Ńt���u�[�X�g�ő���Ȃ��Ă�
�������H��135km/h���ɂ͏[���u�[�X�g��
�����胉�O���ӎ����������o����Ԃ͂��Ȃ�L��̂ł�
�ȒP�Ɍ����_�E���T�C�W���O�^�[�{
���������̂��̃^�C�v�̎Ԃ�
�������H�ł̉����ł��܂胉�O�������Ȃ������o����Ǝv���܂���
����Ƀu�[�X�g���܂�|�����Ă��Ȃ��Ă��]�T�ȃG���W���̎Ԃ�����
�}���������悤�Ƃ���Ƌ��\�ɂȂ��Ȃ��ł����@
�Ⴆ�X�e�b�v���S���Ń��O���s���ɂȂ�����
�댯�ȉ����͂��Ȃ���Ȃ��ł�����
�����ԍ��F26182413
![]() 2�_
2�_
��haghog����
�����������������B
�C���}�j�t�H�[���h�����u�[�X�g���ŁA����"�z�C��"�ł��B
ODB2�Ō��Ă�Έ�ڗđR�B
�}�C�i�X�̓C���}�j���i�A�C�h�����O��-6.6×100Pa���炢�j�ŃG���W�����z�C���鈳�́A�v���X�ɂȂ�u�[�X�g���A�^�[�r�����ߋ����鈳�͂ł��B
�i������ƃ�P�ɂȂ邩���ł����j
�^�[�{�̓A�N�Z��ON�̎������ߋ����܂���̂ŁA�قڂقڃ}�C�i�X�ł��B
���݂ɁA��C����1013HPa�ŁA�قڈ��ł��B
�����ԍ��F26182833
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����A����ɂ��́B
���X���肪�Ƃ��������܂����B
���ȒP�Ɍ����_�E���T�C�W���O�^�[�{
����͐������Ǝv���܂����A�x���c��1400cc�܂Ń_�E���T�C�W���O�����܂������A����X�o���ł�1800cc�ɃT�C�Y���グ�܂����B
�����ɖ{�����L��Ǝv���܂��B������ȃ_�E���T�C�W���O�͔R��̖����܂��A�ƌ������̂̓X�o���ł��B���r�C�ʂŃA�E�g�o�[����160km/h�ő��邱�Ƃ͑����R��̖�肪�o���̂ł��傤�B1600cc�̎���ł�120km/h�̑��s�͔R��}���ɗ����Ă��܂����B�����R��̖��͑��x���߂������Ȃ����߂̑䔃���Ă܂�����܂���B
���������H��135km/h���ɂ͏[���u�[�X�g��
�܂����{�ł�������Ƃ����͕߂܂�܂���ˁB����͈��̈��S�ۏ�̖��ł��B�I�͔R����ł͂���܂���B�����獂�����q�ɋ߂����Ƃ͂��邯�ljߌ��ȍ������q�͂��Ȃ��̂ł��B
������Ƀu�[�X�g���܂�|�����Ă��Ȃ��Ă��]�T�ȃG���W���̎Ԃ�����
�}���������悤�Ƃ���Ƌ��\�ɂȂ��Ȃ��ł����@
����͍Ō�ɃA�N�Z���̊J�x�Ɖ����x�Ƃ̘������L��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�A�C�T�C�g�̎����^�]�ő��x���グ��ƔR��͋ɒ[�Ɉ����Ȃ�܂��B���̂��߂�����Ƃ����َ��ȉ^�]�ɂ͂Ȃ�܂��������̑��ŃA�N�Z���J�x�����߂Ă��܂��B
2400cc�ł́{10km�̉����͏����r���ۂ��Ǝv���Ă��܂��B�܂�����͎���2400cc��I������Ƃ��ɂ��������l����v�f�������Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɂb500AMG�Ɏ��悵���Ƃ��ɂ͂����܂ōr���ۂ��Ȃ�����(^_^)�B
���X�e�b�v���S���Ń��O���s���ɂȂ�����
�댯�ȉ����͂��Ȃ���Ȃ��ł�����
�����Ȃ��Ǝv���܂����A�������̑��x�Œǂ��z������������A��납��Ƃ�ł��Ȃ����x�̎Ԃ����邩������܂���B
����͒P�Ȃ�m���̖��ł�����B
�����ԍ��F26183149
![]() 0�_
0�_
��ZXR400L3����A���ӂ́B
���X���肪�Ƃ��������܂����B
�������������������B
���ɑ厖�Ȏ��ł��̂ň�����������܂��B
���C���}�j�t�H�[���h�����u�[�X�g���ŁA����"�z�C��"�ł��B
ODB2�Ō��Ă�Έ�ڗđR�B
����͐����ł��B�����Ԃ̃u�[�X�g�����グ��Ƃ��ɂ͂�������R�����Ƃ�܂����B���Ȃ݂�2.4�k�^�[�{�ł̓}�j�z�[���h�������邱�Ƃ��o���܂��B
���}�C�i�X�̓C���}�j���i�A�C�h�����O��-6.6×100Pa���炢�j�ŃG���W�����z�C���鈳�́A
������������ł��B�ł������ɂ���̂́A�X���b�g���ł��B�X���b�g�������邩��z�C��R���オ��A�������܂��B
���v���X�ɂȂ�u�[�X�g���A�^�[�r�����ߋ����鈳�͂ł��B
�ł������ł��^�[�r������}�j�z�[���h�Ɏ��鏊�ɃX���b�g�����L��A�����ŗ��ʂ����Ă��܂��B
�����̉ߓn���ɂ̓v���i���`�����o�[�̒��ɂ͉������ꂽ������Ă��Ȃ����킩��Ȃ���C�����܂��Ă��܂��B
��������Ă���Η����͑����Ȃ����A�^�[�r�����O�̂��߂ɏ[���ȋ�C�����Ă��Ȃ���A�����������͒x���Ȃ�܂��B
�Ȃ��Ȃ�^�[�{���C���^�[�N�[���[���z�C��R�ɂȂ�܂��B1500��]���炢�ŋ�z���ɃX���b�g����S�J����ƁA�C���}�j���̈���0�C���łȂ��A���ɂȂ�܂��B�ق��1〜2�b�ł���-0.2�C���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�ق�̈�u�ł��B���̊Ԃ͉�]�����オ��܂���B
�����ăg���N������オ���Ă��܂��B���̌��ۂ͔R�����z�C���x�ɑΉ����Ă��Ȃ����炾�Ǝv���܂��B
�X���b�g���̗������x��m�邽�߂Ƀv���i��������}�j�z�[���h���̍����o���K�v�ƂȂ�܂��B
���Ŗڎ��ł���͈͂ł�-0.2�C�����x�̉A�������݂���鎖���l����z�C�ʂ͋ɒ[�ɒቺ���Ă���Ǝv���܂��B
���ꂪ�������o�ɂ��ďq�ׂĂ��邱�Ƃł��B
�����ԍ��F26183202
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�Ȃ��Ȃ����ݍ���Ȃ��ł��ˁB
�����}�C�i�X�̓C���}�j���i�A�C�h�����O��-6.6×100Pa���炢�j�ŃG���W�����z�C���鈳�́A
��������������ł��B�ł������ɂ���̂́A�X���b�g���ł��B�X���b�g�������邩��z�C��R���オ��A�������܂��B
�G���W���͑|���@�Ɠ����B
�X���b�g���̒�R�ʼnA���ɂȂ��Ă�킯�ł͂Ȃ��A�z���悤�ɂȂ��Ă�Ɖ��߂��Ă��܂��B
��C�z��Ȃ��ƁA�����ł��Ȃ��̂ŁANA�͊�{�A���ł��B
�^�[�{�͂�����@�������ŁA�z���������疳������C�𗬂�����ł�Ǝv���Ă��܂��B
�X���b�g���ŋz�C��R���オ��Ƌ��Ȃ�A�A���ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
��R�Ȃ̂ŁA�v���X�������ȁB
���C���^�[�N�[���[���z�C��R�ɂȂ�܂��B
������C�̖��x���グ�邽�߂̂��̂ŁA��R�Ƃ܂ł͂Ȃ��̂ł́H
���C���}�j���̈���0�C���łȂ��A���ɂȂ�܂��B
�C���}�j���͐�v���X�ɂ͂Ȃ�܂���B
�u�[�X�g���|�����āA����ƃv���X�ɂȂ�܂��B
������u�[�X�g���ƕ\�����邩�A�ǂ����ł��傤�ˁB
�C���͕ϓ����܂��̂ŁASI�P�ʎg���܂��傤�B
�ꉞ��͏o���܂������A�C���}�j���i�A�C�h�����O��-6.6×100Pa���炢�j�́A-0.2�C���ł��傤���H
�����ԍ��F26184142
![]() 0�_
0�_
��ZXR400L3����A����ɂ��́B
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���Ȃ��Ȃ����ݍ���Ȃ��ł��ˁB
���ݍ���Ȃ��̂ŊG���쐬���܂����B�Q�Ƃ̉�����Ȃ���������܂��B
���G���W���͑|���@�Ɠ����B
�X���b�g���̒�R�ʼnA���ɂȂ��Ă�킯�ł͂Ȃ��A�z���悤�ɂȂ��Ă�Ɖ��߂��Ă��܂��B
��C�z��Ȃ��ƁA�����ł��Ȃ��̂ŁANA�͊�{�A���ł��B
�G���W���̓p���[�����邽�߂ɋz�C�ʂ����Ă��܂��B���C�̐�ɃV�����_�[������܂��B�ł��̂ŇB���͉A���ɂȂ�܂��B
�X���b�g���o���u���J���ƃv���i���`�����o�[���̋�C�A���X���b�g����ʉ߂��܂��B���̎��J���Ă��邩���Ȃ����ŋ�C��R���ς��܂��B
�ʏ�A�C�h�����O���͎�|���Ă��܂��̂ŇB���̋�C���͉A���ɂȂ�܂��B
�ł����̉A����1�C���ł͂Ȃ�0.7�C�����x�ŃV�����_�[�����C���Ă��邩��ł��B
�X���b�g�����J���Ƃm�`���Ɠ��R��C���Ɠ����ɂȂ�܂��B
�����͗ǂ��ł���ˁH
���^�[�{�͂�����@�������ŁA�z���������疳������C�𗬂�����ł�Ǝv���Ă��܂��B
��@�Ƃ����\���͓������Ă��邩������܂���B�̊w���̎��ɑ|���@�̃��[�^�[��t���悤�Ƃ������Ƃ��L��܂��B
�v����ɁA�X�[�p�[�`���[�W���[�ł��ˁB
�ł��^�[�{�̎��͏펞�����Ă���킯�ł͂���܂���B������������̒ʂ�ł��B
���X���b�g���ŋz�C��R���オ��Ƌ��Ȃ�A�A���ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
��R�Ȃ̂ŁA�v���X�������ȁB
����͇A�̋�C�����オ��܂��B���Ȃ킿�v���i�����ɂȂ�܂��B
��������C�̖��x���グ�邽�߂̂��̂ŁA��R�Ƃ܂ł͂Ȃ��̂ł́H
���������Ɏ���o���Ă����̂͂��������ł�����C��R�ɂȂ邾�����C��R�̏��Ȃ��̂��ǂ��B�ƌ����ĉ������i��ł����܂����B
�ł��̂ł����ł͋z�C��R�A�������̓v���i���`�����o�[�O�̋�C��R�ƍl���ėǂ��Ǝv���܂��B
�������A�قƂ�Nj�C��R�͂Ȃ��Ǝv���܂����A�����ɂ͗]���ȋ�Ԃ��ł��A�ψ�łȂ���Ԃ��o������̂��Ǝv���܂��B
���C���}�j���͐�v���X�ɂ͂Ȃ�܂���B
�u�[�X�g���|�����āA����ƃv���X�ɂȂ�܂��B
����͈�x�����Ă݂Ă��������B�l�s�ł��I�[�g�}�ł������M���ŃX���b�g������ă^�[�r�������Ȃ���Ԃ����z�I�ɍ���Ă݂Ă��������B
�����Ă��̂��ƃX���b�g����S�J�ɂ���ƈ�u�A���ɂȂ��ĉ�������͂��߂܂��B
�����Ĕ����I�ȃg���N�ݏo���܂��B
��������u�[�X�g���ƕ\�����邩�A�ǂ����ł��傤�ˁB
����̓^�[�r���̎d���ʂɊւ�肻�ꂪ�����o�H�Ńv���i���`�����o�[�ɗ���킯�ŁA�����ɂ͎�̃^�C�����O�������܂��B
���C���͕ϓ����܂��̂ŁASI�P�ʎg���܂��傤
���ꂵ�܂��ˁB
���ꉞ��͏o���܂������A�C���}�j���i�A�C�h�����O��-6.6×100Pa���炢�j�́A-0.2�C���ł��傤���H
����������ׂĂ݂܂����B�A�C�h�����O��-6.6��100�o�����炢�ł����B
�G���W���u���[�L���������-8.0��100Pa���炢�ɂȂ��Ă��܂����B
���̐����͐̂���ς��܂���ˁB
�����ԍ��F26184850
![]() 0�_
0�_
���X�������Ȃ����̂܂Ƃ߂܂��B
�܂Ƃ߁G�G�����Ȃ���̐����ɂȂ�܂��B
��C�̗���͇@���A���B���C�Ɨ���܂��B
�@�̍����Ƀ^�[�r��������^�[�{�ԁA�G�A�t�B���^�[�����Ȃ�m�`�ԂƂȂ�܂��B
���R�C�̍����̓V�����_�[�ɂȂ�܂��B
�X���b�g���o���u�Ńv���i���`�����o�[�ƃ}�j�z�[���h�`�����o�[���d���Ă��܂��B
���Ă̒ʂ�X���b�g���`�����o�[�͋�C��R�ݏo���Ă��܂��B
�^�[�{����X���b�g���o���u�܂łɂ̓C���^�[�N�[���[�����܂�Ă���傫�ȋ�Ԃ�����Ă���܂��B
�^�[�{�͂ǂ̂��炢����Ă��邩�ǂ�����܂��A30�N���炢�O�ɂ̓^�[�r���̉�]�����v��頁��@����o�Ă����悤�ł������͎g���Ă��܂���B
�܂���ɗ����Ȃ������̂ł��B
��������ĊG�����Ă���ƃv���i�����̓^�[�{�̎d���ʂƃC���^�[�N�[���������̋�C��R�A����ċ�C�̎��ʂ̉^���ʂ����邱�Ƃ��o���܂��B
�v���i��������}�j�z�[���h�����Ђ����l�A���o�����邱�Ƃɂ��X���b�g����ʂ��C�̗����𐄒肷�邱�Ƃ��o���܂��B
�x����Η��ʂ͏��Ȃ��Ȃ�傫����Η��ʂ��傫���Ȃ�܂��B
���_�I�Ɍ����ƃ��o������ƁA���܂Ńu���b�N�{�b�N�X�������^�[�{�̉ߓn�̈�̉������\�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F26184862
![]() 0�_
0�_
>���_�I�Ɍ����ƃ��o������ƁA���܂Ńu���b�N�{�b�N�X�������^�[�{�̉ߓn�̈�̉������\�ɂȂ�܂��B
���O���L����Ċm�F���o���Ă�
����ς胉�O�͖������Ȃ��i�����Ȃ�Ȃ��j���ĂȂ�܂���
�����ԍ��F26184891
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����A���ӂ́B
���X���肪�Ƃ��������܂��B
�����O���L����Ċm�F���o���Ă�
����ς胉�O�͖������Ȃ��i�����Ȃ�Ȃ��j���ĂȂ�܂���
���ꂪ�����ł̈�Ԃ̃|�C���g�ł��B
�Ȃ����邩�Ȃ����Ȃ����͎��`�͂ɂ���Ă݂Ȃ��Ɖ���܂��A�����������A�^�[�r���̉����܂ł̎��Ԃ�3�b���炢�L��܂��B
����͐̂̃L���u���^�[���g�p���Ă�������ɁA�G���W���̏o�͒����ɂ͎蓮�ŃW�F�b�g�̌������悭���܂����B���ۂɂ͎G���ɍڂ��Ă��邾���ł����B�i����YouTube�̃g�~�^�N�`�����l���Ō��邱�Ƃ��o���܂��B�j
������R���s���[�^����ł��Ȃ����Ƃ����̂��h�v���i������}�j�z�[���h���h�F��P�̍l�����ł��B
�u3�b�����Ȃ����v�A�u3�b�����邩�v�͎���ɂ���ĕς���Ă��܂��B���̎���1�b�Ԃ�60����s���g������J�����iSONY��ILCE-1)���s�̂���Ă��܂��B
����ōs����180��͒����ł��܂��B
�������Ȃ��̂ł��傤���H
�����ԍ��F26185178
![]() 0�_
0�_
��haghog����
���X���b�g���̒�R�ʼnA���ɂȂ��Ă�킯�ł͂Ȃ��A�z���悤�ɂȂ��Ă�Ɖ��߂��Ă��܂��B
��C�z��Ȃ��ƁA�����ł��Ȃ��̂ŁANA�͊�{�A���ł��B
�Ȃ̂ŁA�|���@�ƕ\�����܂����B
���X���b�g�����J���Ƃm�`���Ɠ��R��C���Ɠ����ɂȂ�܂��B
NA�̎Ԃ�ODB2���ڂ��ĂȂ��̂ŁA�ǂ��܂ł����̂��͕�����܂���B
�t���X���b�g���Ȃ�Ȃ邩���A�Ƃ͐����ł��܂��B
���ł��^�[�{�̎��͏펞�����Ă���킯�ł͂���܂���B������������̒ʂ�ł��B
�͂��A�����܂���B
�K�o���ƃX���b�g�����J���Ȃ��ƁA�ߋ����Ă���܂���B
�\�����\��������NA�Ɠ��������ɂȂ�܂��B
������͈�x�����Ă݂Ă��������B�l�s�ł��I�[�g�}�ł������M���ŃX���b�g������ă^�[�r�������Ȃ���Ԃ����z�I�ɍ���Ă݂Ă��������B
�����Ă��̂��ƃX���b�g����S�J�ɂ���ƈ�u�A���ɂȂ��ĉ�������͂��߂܂��B
�i���̎Ԃ��ȁH�j�Ȃ�܂���B
�X���b�g����S����ƁA-7.6×100Pa�����炢�ł��B
�S�J�ɂ���ƁA�������ߋ����܂��B
�����őS�A���̌�o���Ȃ�Ă�����ł������ʁB
���̉����A���O�Ȃ��Ȃ炢�ł��B
�Ȃ�A���O������������ɂ́A�^�[�r��������������ƁA�ԏd���y������B
�ł���A�V���[�g�X�g���[�N�̃G���W����I��Ŕr�C�����グ��H�ł��傤���H
�����ԍ��F26185211
![]() 0�_
0�_
��ZXR400L3����A����ɂ��́B
���X���肪�Ƃ��������܂����B
���i���̎Ԃ��ȁH�j�Ȃ�܂���B
�X���b�g����S����ƁA-7.6×100Pa�����炢�ł��B
�S�J�ɂ���ƁA�������ߋ����܂��B
�����őS�A���̌�o���Ȃ�Ă�����ł������ʁB
���݂̌y�����Ԃ͑f���炵���Ƃ���܂Ō����Ă����ł��ˁB
�ł�������閾�m�ȓ��������͏o�����Ƃ��o���܂���ł����B
��Ӎl���ă����^�J�[�Ōy�̃^�[�{�Ԃ���邱�Ƃɂ��܂����B
�Ƃ肠�����h��Ƃ����Ă��������B
���̊��ł̓o�C�p�X�����邵�A�������H������܂��̂ŏ̐ݒ�͉\���Ǝv���Ă��܂��B
�����ɂ��Ă͂��炭���҂����������B
���ۂɑ��s����ƍl�������ς�邩������܂���B
�o����Όy�����Ԃ̉�Ж���������߂��������o����Ǝv���Ă���̂ł����B
�ŋ߂̉\�ł̓X�Y�L���ǂ��ƌ������ƂȂ̂ł����B
�����ԍ��F26185626
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
�V���v���Ɍ����ƁA��͂�u���O�͖����Ȃ�Ȃ��v�ł��ˁB
�C���W�F�N�V��������ɂȂ��āA�Z���T�[�͑����t���Ă��܂��̂ŕ�̓o���o���ł��B
��{�̓X���b�g���o���u��̈��𑪂釀�z�C���̓Z���T�[���Ŋ�{�̕��˗ʂ����߁A
���Ƃ͇��z�C���x�Z���T�[���⇀�����Z���T�[���Ȃǂōׂ�������s���A
�܂����n�Ή��̌��ł�����C���Z���T�[���ŕ�������܂��̂ŕW���̍����������Ȃ�����܂��B
���̂�����͓d�C�ł��̂ŏu���ɕ����܂��B
�^�[�{���O�͂�͂�A���]����A�N�Z�����J�������ɁA
�����ɂ͋z����C�ʁi�z�����ށA�ł͂Ȃ��^�[�r���ʼn������܂���C�ł����j�����Ă��Ȃ�����ŁA
����100�_���_��150�_�ł͖����ɂ���A���̏ł̇��R�����͕K�v�\���Ȑ���ł���Ǝv���܂��B
�O��\���܂������A�y�����Ԃ̏ꍇ�^�[�{���O�̓s���Ŏ���NA�D���ł��B
�������̇����O�����A�N�Z�����h���ƊJ�������ł͖����A�����_�E�܂Ƃ��̑債���J�x�ł͖������̃��O�ł��B
�A�N�Z���h���̎��͂܂�����Ȃ��́A�܂��͖��Ƃ��v���܂��B
�n�[�t�X���b�g���ȉ��̌����_�E�܂Ƃ��ŁA�O�Ԃɕt���ăX���X���s����ʂł��A
�������Ȃ��燀���O�����o�āA�Ȃ���I���鍠�ɏ����o�͂����債�܂��B
�����Ύ��R�ƉE�����A�W���X�g������x�̎��ł����A��葬�Ői�ނ̂Ɏ�A�N�Z����߂��̂����̓L���C�ł��B
�����A�����h�̇��ςȐl���ł��B
�����ԍ��F26185807
![]() 1�_
1�_
���������`����A����ɂ��́B
���X���肪�Ƃ��������܂��B
���V���v���Ɍ����ƁA��͂�u���O�͖����Ȃ�Ȃ��v�ł��ˁB
�V���v���ɂ͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�Ȃ��Ȃ�40�N�Ԃ����Ă��܂��������Ă��Ȃ�����ł��B
���C���W�F�N�V��������ɂȂ��āA�c�c�c
���̂�����͓d�C�ł��̂ŏu���ɕ����܂��B
����40�N�Ԃ̐i���̓^�[�{�̉��ǂƃZ���T�[�̉��ǂɂ��܂����B���낢��Ȃ��̂����P����Ă���f���炵������������o����悤�ɂȂ��Ă���܂��B
���^�[�{���O�͂�͂�A���]����A�N�Z�����J�������ɁA
�����ɂ͋z����C�ʁi�z�����ށA�ł͂Ȃ��^�[�r���ʼn������܂���C�ł����j�����Ă��Ȃ�����ŁA
�܂��ɂ��̒ʂ�ł��B�d���ʂ��ǂ����Ă��Ȃ���Ԃ������������B�Ƃ�����]�ł��B
�����̏ł̇��R�����͕K�v�\���Ȑ���ł���Ǝv���܂��B
��������͐������Ǝv���܂��B�ł��{���ɂ��ꂪ�������̂��ǂ����͉���܂���B
����ʼn����܂ł̎d���ʂ𑪒肷�镨�Ńv���i���`�����o�[���𑪒肵�A���ݔR���ɗǂ��g�p����Ă���}�j�z�[���h�����Ђ������܂胢P�������邱�Ƃɂ���āA�őP�̔R���������ł��Ȃ������l���Ă��܂��B
���������̇����O�����A�N�Z�����h���ƊJ�������ł͖����A�����_�E�܂Ƃ��̑債���J�x�ł͖������̃��O�ł��B
����͎��������Ă��܂��B�ƌ����������S�ɖY��Ă��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�����A�C�h�����O�X�g�b�v��̍Ďn�����̃X�^�[�g�̃A�N�Z���̃c�L�ƃA�C�h�����O����̃X�^�[�g�̃A�N�Z���̃c�L���قȂ邱�Ƃ͌o�����Ă���Ǝv���܂��B
���Ȃ���I���鍠�ɏ����o�͂����債�܂��B
�L��܂��L��܂��B���t�ɏo���Ă��Ȃ���������ǂ�����܂��B�܂��ɏ����ȃh���t���ł��ˁB
����葬�Ői�ނ̂Ɏ�A�N�Z����߂��̂����̓L���C�ł��B
��^���ł��B�A�N�Z���͐l�ƎԂ̐ړ_�ł����Ŋ�]���Ȃ����x�Ɏ��R�ɏオ���Ă����̂͌��ȕ��ł��B
�������A�����h�̇��ςȐl���ł��B
���������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26186012
![]() 0�_
0�_
��haghog����
�c�O�Ȃ���A�����^�J�[�����قǂ���Ȃ��ł���B
�i�����Ȃ��j
����Ԃł����̂ł́H�Ǝv�����ǁA���̎Ԃ͂�������܂���B
���̎Ԃ́A�A���g���[�N�X�ł��B
��ԋ߂��̂́A�z���_��NoneRS�i6MT�j�ł��傤���B
�����ԍ��F26186254
![]() 0�_
0�_
��ZXR400L3����͂悤�������܂��B���X�x���Ȃ��Đ\����܂���ł����B�ǂ����v�b�V�����Y�ꂽ�݂����ł��B
��
���n�̃����^�J�[�������T�����̂ł����y�̃^�[�{�Ԃ͂���܂���ł����B
����Ŏ��̎�Ŏ��̎Ԃ̃f�B�[���[�̌y�����ԃ^�[�{��T���Ă��܂��B
�����������҂����������B
���A���g���[�N�X�ł��B
�����ł����B���Ԃł��B�������Ă��Ȃ��������x�͏���Ă݂����Ԃł����B
����ԋ߂��̂́A�z���_��NoneRS�i6MT�j�ł��傤��
���肪�Ƃ��������܂��B�_�����œ������Ă݂�Ƃ������邩������܂���B
1�x�y�̃^�[�{�ɏ���Ă݂ă^�[�{���O�̍���̌��������Ǝv���Ă��܂��B
��͂�̌����Ȃ��ƃ�P�̊��o���킩��Ȃ��Ǝv���܂��B
����Ă݂Ă܂����b���o������ō��ł��B
�����ԍ��F26192704
![]() 0�_
0�_
���̃X�������Ă��韡�l����͂悤�������܂��B
���YouTube�����Ă����炱��Ȃ̂��o�Ă��܂����B
�C���^�[�N�[���[�̃A�b���ɂ��Ėʔ�����������Ă���܂���
��https://www.youtube.com/watch?v=nKXhMusUCyc
����҂ɂ͋������s���Ă��܂��B���16��40�b���炢�̏��ł��B
�Ȃ��Ȃ��Ԃ�����Ă��܂���B
�����ԍ��F26193704
![]() 0�_
0�_
�Ă͏����ƃi�t�^�������n���Ă��܂��ׁB�����j�q�g�C���p�̖F���{�[�������Ēu���Ă݂܂����B�ăo�[�W�����ɂȂ邩�ȁH
![]() 0�_
0�_
�����ܔ����H
�z�[���Z���^�[�Ƃ��ɔ����Ă��ŗǂ��Ȃ������H
�����ԍ��F26169953�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���O���p�̊����܃I�X�X���ł��@
���������ݕt���܂����c
�����ԍ��F26170109�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���^e-POWER�͉��ア�ƃu���[�L�����v�����炸�A���S��~��̃u���[�L�y�_���ł悤�₭�_�����܂��B
https://youtu.be/Ja3Ni76yKmg
���߂ɓ_��������ׂ̃u���[�L�߂A�����u���[�L���|�����ĕs���ɂȂ�܂��B�V�^e-POWER���Ɖ̐��䂪��肭�Ȃ��Ă��đA�܂����B
���߂̃u���[�L�����v�_���̕��@�Ƃ��āA�ӂƍ����u���[�L���v�����܂����B�������H�Ȃǂ̍\���u���[�L�������Ȃ�g���܂��B���S���������C���H
�����ԍ��F26169686�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���挩�����A�ɂ₩�Ȍ����Ńu���[�L�����v�_���������Ă��ʂɗǂ���Ȃ��H
�̂́A�p�J�p�J�u���[�L�����v��_����͉̂���ȉ^�]�ƌ����Ă��̂ŃG���u���𑽗p���Ă܂���
����HV����Ă��ăG���u���ŃR���g���[������ԂłȂ��̂ŁA�C�ɂ��Ė����ł���
�����ԍ��F26169701�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 10�_
10�_
��mokochin����
�����ȑO�͊ɂ₩�Ȍ����Ȃ�_���s�v�ƍl���Ă܂����B
������������ł́u��Ȃ��v�u���𑖂肽���Ȃ��v�ue-power�̌��ɂ�����ԊԂ���v�i���i����Ƃ��I�j�Ƃ������R�����g�������A�O�̎Ԃ̃u���[�L�����v�݂̂Ŕ��f���Ă�h���C�o�[�������ȂƉ��߂Ďv���n�߂܂����B
���ƌ����ċt�Ƀp�J�p�J���T�������ł��ˁB
�����ԍ��F26169710�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����u���[�L�͌��ւł��B
�����ԍ��F26169714�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
>���^e-POWER�͉��ア�ƃu���[�L�����v�����炸�A���S��~��̃u���[�L�y�_���ł悤�₭�_�����܂��B
�K�\�����Ԃ��A�N�Z�����������̎��R������苭�������ŃX�g�b�v�����v���_���Ȃ�������A�㑱�Ԃ͌˘f�������B
�����ԍ��F26169720�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�v���E�X�ł�B�����W�̃u���[�L�̓����v�_���Ȃ��Ǝv���Ă����ǁc
�����ԍ��F26169729�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�u���[�L�����v�͌㑱�ԂɎ~�܂邱�Ƃ�A�������邱�Ƃ�`���邽�߂ɂ���킯�ł���
AT���炯�ɂȂ��Ă���A���̖���������ӂ�ƂȂ��Ă��܂��Ă���܂��B
�����Ői��ł��Ă��_�����A�ԊԂ��J���ď��q���Ă��ău���[�L�͕K�v���Ȃ��͂��Ȏ��ɂ��_����
�S�R�A�㑱�Ԃ֎����̍s����`����C������܂���B
�̂���2��O�̓��������đ���Ƌ�����Ă܂����ǁA�Ԃ��f�J���Ȃ��Ă����
2��O�͌����܂���̂ŁA�㑱�Ԃ֓`����s�����ӎ�����
����Ȃ��ƁA�Ǔ˂���Ēɂ��ڂɑ����͎̂��g�ł�����ˁB
��^�Ԃ͎~�܂�Ȃ��̂ŁA���܂ŒǓ˂���Ă��Ȃ��̂͊�Ղł��B
�Ȃ̂ŁA�̂��͎Ԏ�Ɋւ�炸�x���͑ӂ�܂���̂�
���Ԃ̐����\�͂����A�Ԏ�Ɍ��炸���߂̎Ԋԋ����͎���Ă��܂��ˁB
e-POWER�Ńu���[�L�����v���_���Ȃ��Œ�~����悤�Ȏ����������܂�����
�قƂ�ǂ͏a�ł̐i��~�܂�����̒ᑬ�����������ȂƎv���܂��̂�
����AT�Ԃ�����������ł͂Ȃ��ł��ˁB
���ʂɗ���Ă��鎞�ɁA�ڗ����ău���[�L�����v�̋������ς��Ƃ͊����Ă͂��܂���ˁB
AT�ԑS�̂��ςȂ̂ŁB
�M����~���ɁA���Ȃ��O�ŃJ�b�N���u���[�L�Ŏ~�܂��āA���ꂩ��N���[�v�g����
�O�ɋl�߂�̂�߂ė~�������ȁB
���ƁA�u���[�L�����v������I�ɓ_���Ȃ���������Ă����s�v�c�Ƃ�
�S�R�A���������Ȃ������Ƃ�
�]�v�ɉ������đO�Ԃɒǂ���������ău���[�L���Ă̂��J��Ԃ��Ƃ�
��肢�l�͂����͂Ȃ��ĂȂ����
�o����͂��Ȃ̂œ��X�A���K���ė~�������ȁB
�����ԍ��F26169731
![]() 5�_
5�_
��>���^e-POWER�͉��ア�ƃu���[�L�����v�����炸�A���S��~��̃u���[�L�y�_���ł悤�₭�_�����܂��B
���K�\�����Ԃ��A�N�Z�����������̎��R������苭�������ŃX�g�b�v�����v���_���Ȃ�������A�㑱�Ԃ͌˘f�������B
�˘f���ƌ�����蕠�������ł��ˁB�i��납��Ǔ˂�����Ƃ��j
�^�]���J�b�R�����Ǝv���Ă��ł��傤���H
�i������^�]��U�����Ȃ��l�ɒ��X�Ɂj
�����ԍ��F26169734
![]() 5�_
5�_
���ƁA�E���ł��܂Ƃ��Ƀu���[�L�R���g���[�����o���ĂȂ��̂ɍ����͖����Ǝv���B
�����Ńu���[�L�ނ悤�ɐv����Ă���Εʂł�����
�v�����[�T�[���ᖳ����ł����犵���Ƃ����l���ň��ՂɎg����
���i�͂܂��ǂ����ǁA�댯�h�~�ׂ̈̋}�u���[�L�ɔ������Ă͂��Ȃ��̂�
��͂�댯�͑����Ă���͂��ł��B
�����ԍ��F26169737
![]() 11�_
11�_
�ł��A�ד��̍����u���[�L�̉B���p�҂́A����悤�ł��B
������S�[�J�[�g�����A�l�̌�y�ɂ����܂����B
�{�l���킭�A�E���ŃA�N�Z���A�����Ńu���[�L������ԈႤ���Ƃ��Ȃ����āB
���ʂ̓J�[�u�Ȃǂł́A���r���t�b�g���X�g�ɒu���ē��邯�ǁA�����u���[�L�̐l�͂��ꂪ�o���Ȃ����낤�ˁB
�����ԍ��F26169749�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
���́A�����u���[�L�g���܂��A�@�@
�C�[�p���[�ƊW�Ȃ��A���R�I�[�g�}�`�b�N�̎Ԃł����A
�����̃X���ł��A
���\�A�m��I�Ȉӌ����łĂ��悤�Ɋ����Ă���܂����B
�����́A�ے�I�ӌ������ł��ˁB
�����ԍ��F26169763�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���^e-POWER�̉u���[�L���獶���u���[�L�̘b��ɂȂ��Ă܂��̂ŁA
MT�Ԃɏ�芵�ꂽ�l�������u���[�L�͕|���ł��傤���AAT�Ƌ��K����AT�Ԃ�������Ė����A�����u���[�L�ŏ��n�߂��l�͍����u���[�L�͗L�肾�Ǝv���܂���B
�����u���[�L�Ɋ���Ă���̂ɉE�u���[�L�̕����|���Ǝv���܂��B�i���K���ł͉E���u���[�L��������Ǝv���܂����j
�l�l����Ԃ����ق������S���Ǝv���܂��B
�킽���́A���X�����u���[�L���܂���B
�����ԍ��F26169789
![]() 7�_
7�_
���R�z�@���Y����
�r���߂ɓ_��������ׂ̃u���[�L�߂A�����u���[�L���|�����ĕs���ɂȂ�܂��B
�u���[�L���E�������ł͂Ȃ�
�m���I�[�g�}�̃v���O�����ɉ��������Ȃ�
�m�[�}�����[�h�I�Ȃ̑I�ׂ邩�Ǝv���܂�
�G�R��X�|�[�c�͐ϋɓI�ɉ�����Ǝv���܂�
�����ԍ��F26169803
![]() 3�_
3�_
�����u���[�L���Ă܂�1�y�_����ɍS��Ȃ��Ă����ʂ�2�y�_������ł��������B
�����ԍ��F26169805�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
�b�����ɖ߂��܂����E�E�E
���������A�O�Ԃ̌�����O�Ԃ̃u���[�L�����v�̓_�������ɗ����Ă���^�]���n�҂��A
�u�u���[�L�����v��_�������Ȃ��ƒǓ˂����v�Ƌ����ϔO������Đ������ĉ���Ă��邾���ł��B
�X���傳��͋C�ɂ���K�v�̖������Ƃ��C�ɂ���Ă��邾���ł��B
�ԎЉ�ł́A�Q�A�R��O�◼���ƌ��̎Ԃ̓����⓹�H����s�҂Ȃǂ̏����Ȃ���^�]����̂�
�펯�Ǝv���܂��B
���ɂ́A�G���W���u���[�L�����Œ�Ԃ���Ԃ�����܂��iAT�Ԃł�MT�Ԃł����܂��j�B
���Y�̃����x�_���������悤�Ȃ��́B
�Ⴆ�A�O�Ԃ̃u���[�L�����v���̏Ⴕ�ē_�����Ă��Ȃ�������A���Ȃ��͒Ǔ˂����ł����H
�܂��́A�^�]�Z�p���Ă��������B
�����ԍ��F26169919�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 11�_
11�_
���i�C�g�G���W�F������
�����ʂ̓J�[�u�Ȃǂł́A���r���t�b�g���X�g�ɒu���ē��邯�ǁA�����u���[�L�̐l�͂��ꂪ�o���Ȃ����낤�ˁB
���t�g�t�b�g�u���[�L���낤���AMT���낤���t�b�g���X�g���g���܂��B
�i�C�g�G���W�F������̓J�[�u�r���Ńu���[�L�ނ̂ł��傤���H�H�H
�����ԍ��F26169932�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
������e-Power�ԁi�m�[�g�j�̓u���[�L�����v�]�X�����A���x����肵�Ȃ��Ԃ������B�K�\�����ԂŒǐ�����ƔR������Ȃ�̂ŁA�������ԊԂ����悤�ɂ��Ă��܂��B�K�\�����Ԓ��S�̐����ł͖��f�ȎԂł��ˁB
�u���[�L�����v�͒�~���鎞�i�M����A�a�ȂǂőO���Ԃ���~���Ă��鎞�j�͓_����ׂ��Ǝv���܂����A���ʂɉE���Ńu���[�L�߂Ηǂ��̂ł́H�������ǂ����͑��̎Ԃɂ͊W�Ȃ����A�ǂ���̑��œ���ł��Ԃ͔F�����Ȃ��̂ł́H�A�N�Z�����݂Ȃ���u���[�L���̐���i���ꂼ��Ɨ��ł͂Ȃ������j���ǂ��Ȃ��Ă���̂��m��܂��B
�����u���[�L�͏�肭�g����Ȃ����Ŏ��R�Ɏg���Ηǂ��Ǝv���܂��B������Ԓ��͍����i�����̂��Ƃ��j�Ńu���[�L�ނ��Ƃ�����܂��B���s���̓t�b�g���X�g�ɍڂ��āA�K�v�Ȏ��͓����Ă��܂����B
�����ԍ��F26170118�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
AT���肪�ł���O�ɖƋ���������̂ŁA�����u���[�L�͂��蓾�Ȃ��ł��B
�����Ԃ�MT�ł����E�E�E
���R�s�X�^�X�t�O����
��������e-Power�ԁi�m�[�g�j�̓u���[�L�����v�]�X�����A���x����肵�Ȃ��Ԃ�����
�����^�͒Ǔ˂����悤�Ƃ��Ă�̂��H�Ǝv����悤�ȃ����y�_���̐����͂ƁA�u���[�L�����v�̎d�l�ł����B
��Ԃŏ���ăr�b�N�����܂����B
�������̂��̐悳��
�����ɂ́A�G���W���u���[�L�����Œ�Ԃ���Ԃ�����܂��iAT�Ԃł�MT�Ԃł����܂��j�B
���������E�E�E
���̎Ԃ́A�T�C�h�u���[�L�������Ă�̂���Ȃ����ȁH
MT����Ă܂����A�G���u�������Ŏ~�܂��̂͏��₮�炢�B
��̓t�b�g�u���[�L���A�T�C�h�u���[�L�i���̏ꍇ�A�u���[�L�����v�͓_���Ȃ��j�Ŏ~�܂邩�B
���Ȃ�̏���ȍl���ł��B
����MT���́A�t�ɗ\���̃u���[�L�����v��_����v���Ă��܂��B
AT�Ԃ��������ŁAMT�Ԃ͓��������ƈقȂ�Ǝv���Ă���Ǝv���܂��̂ŁE�E�E
�����ԍ��F26170254
![]() 4�_
4�_
�N���w�E���Ă邩�Ǝv���܂����A�傳��̓���
�E���̓���̎n�܂�̎��_�Ŋ��S��~�O�A�������\���ɂ���Ă���B�Ȃ̂Ńu���[�L�����v���_���Ȃ��Ƃ���Ȃ珄�s���x����̌������̏؋����K�v�B
�E���S��~��Ƀ����v���_���ł͂Ȃ��A���S��~��Ƀt�b�g�u���[�L��ł���B(���[�J�[�������̍s��)
���f���`�F���W���E13�ł͉u���[�L�Ŋ��S��~�͂��Ȃ��̂ŁA��~�O�ɂ͕K���u���[�L�����v�͓_�����܂��ˁB����Ŗ����Ȃ̂��ȁH
�����ԍ��F26170361�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��ku-bo-����
e-power�u���[�L�����v�̓���́A������₷����~���O�ȊO�̓J�b�g����Ă鎖�������ł��ˁB
https://youtu.be/KuVGgCOg0uI?t=7
E13�Ȃ���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F26170487�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
c27����e-power�ԗ��̏���Ă����o���ł́A��u�A�N�Z�����Čy��������������v�͎b���_�����܂��B
���������c28e-power�ōs���ƃu���[�L�����v���_�����Ă��������ɂ͍ĉ������K�v�ł��Ȃ蒷���_�������܂܂ɂȂ�܂��B
e-power���i�����Ă����Ă܂����A�Z�ʂ������Ȃ��Ȃ��Ĉ�������ߎ��g�p�R���2�A3�������Ă܂��B
���ɉ^�]�����c27�̓G���W���I�t�̃^�C�~���O���A�N�Z���Œ����ł����ʂɃG���W���������炸�R��ǂ������B
�u���[�L�����v�����l��c27�̓A�N�Z���y�_���̒����ŎԊԂ����܂���Ȃ��㑱�Ԃɒ�~�O�̌x���Ń����v�𑁂߂Ɉ�x�_�����Čx���ł��܂������Ac28�͂��̌x��������s���Ɖ������삹���ɒ�~������Ȃ��炩�ȉ^�]�ł͒��������̊ԃ����v���_�������܂܂ŁA���Җڐ��ň�̂ǂꂾ�������u���[�L����ł��ƌ��������Ȃ邮�炢�_�����Ă܂��B
�l�I�ɂ͉E���̃A�N�Z������������肭�ł���Ȃ獶���u���[�L�͕s�v���Ɗ����܂��B
�����ԍ��F26171361
![]() 0�_
0�_
�^�]���͉��Ƌ����K�̂悤�ȍ����u���[�L���K���̊Ŕ��Ă��������B
���d�Ɩ����u���[�L�̋������䂪��������̂Ń����y�_���Ƃ������̂ɂ���ւ����̂��n�܂�B
�����ԍ��F26171706
![]() 1�_
1�_
�i�����܂߂āj�����������̐l�͍����u���[�L�Ɉ�a���͏��Ȃ��Ǝv���B
MT����̎��͋��K���Ă������Ƀu���[�L���Ȃ��Ȃ����܂�����ł��܂���ł����B
���ł͂�������E���u���[�L�ł��������ł���a���Ȃ����ʂɑ���E���䂪�\�ł��B
�i�s�ӂȃu���[�L���O�͖������ƂȂ��E���œ���ł��܂��j
�����肪���ł��������͉E���Đl������̂Ŋ����͏��Ȃ��Ƃ͎v�����A�����u���[�L���F�߂Ăق����Ȃ��B
�����ԍ��F26172072
![]() 0�_
0�_
������a����
��MT����̎��͋��K���Ă������Ƀu���[�L���Ȃ��Ȃ����܂�����ł��܂���ł����B
�悭�A��܂����ˁB
�������������̐l�͍����u���[�L�Ɉ�a���͏��Ȃ��Ǝv���B
���͗�����͉E�A�����E�ł����A�Ȃ����Ⴞ�����ł��B
�X�i�C�p�[�ɂ́A�Ȃꂻ�����Ȃ��ł��ˁB
�n���C�őS�e�O���܂����i�j
�����ԍ��F26172147
![]() 1�_
1�_
���K���ŋ����Ȃ������u���[�L�A�܂��Ԃ̍\������u���[�L�͉E�������O��ɍ���Ă���Ƃ��B
���čl��������u���[�L�͎ד��ł��傤�ˁB
�Ƃ͂����A�����u���[�L�̐l�͈�萔����悤�ł��B
�����A�����u���[�L�������Ŏ��̂��N�������Ęb���́A���ĕ��������Ƃ��Ȃ����ǂˁB
�܂��A�u���[�L������펞�����ł���Ă������Ƃ����o���Ȃ��������������m��Ȃ����ǁB
�����ԍ��F26172191�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��ZXR400L3����
���Ƃ̎������邱��ɂ́A�������芵��܂�������B���v�ł���B
�Ƃ͂����A���R�ɑ���E����ł���悤�ɂȂ�܂łƂȂ�ƁA�����^�]����悤�ɂȂ��Ă���1�������炢��
���������C�����܂��ˁB����܂ł͊��ꂽ�Ƃ͂����Ă��ӎ����ē���ł������ȁB
�����ԍ��F26172351
![]() 0�_
0�_
�r�����A�����u���[�L�������Ŏ��̂��N�������Ęb���́A���ĕ��������Ƃ��Ȃ����ǂˁB
�����u���[�L�̕������̂��N�������͗L��Ǝv���܂���
�E���u���[�L�Ŏ��̂��N������������̂Ƃǂ��悤��
�����u���[�L����������Ƃ��ꂪ�����ł̎��͕̂����Ȃ��ł���
���S�ɉ^�]�o����ΉE�ł����ł��ǂ��Ă���
���g�Ńu���[�L�܂Ȃ�����������
���ł������u���[�L�����Ȃ������Ƃ����������
����ۂ�
�����u���[�L�̕��͉E���u���[�L�̌o��������
�����u���[�L�̕������g�ɗL��(�y�Ƃ����S)�ƍl���I��ł������
�����u���[�L���g��Ȃ�����
�����u���[�L�͊댯���ƌ����Ă������͗L��܂���
�����s���Ȃ�킴�킴���Ńu���[�L���݂܂���
���̂S�����狳�K���ł̖Ƌ��̃X�^���_�[�h��AT�ɂȂ�܂�����
�������͂Ƃ������X�ł͂��ꂩ��ǂ��Ȃ��čs���܂�����
���Ńu���[�L��ł͂����Ȃ��@���͗L��܂���
����
���ɂ��낶��Ȃ�
�E�ł����ł��ł�
�l���܂ߍ����u���[�L�h��
�g���Ă݉��K������Č�����������
�E�h�͉E�ŗǂ����Ǎ��������Ă��Ȃ��Ńf�X���Ă�
�Ȃ�
�����ԍ��F26172512
![]() 0�_
0�_
���[�V���O�J�[�g�ō����u���[�L�̗��K����B
�N���b�`�̓��o�[����A�V�t�g�����o�[�A�G���W���̓��g�N���b�T�[�p�B
�����ԍ��F26172568
![]() 0�_
0�_
��RBNSX����
>���[�V���O�J�[�g�ō����u���[�L�̗��K����B
�Ӑ}���ǂ�����܂���
���[�X����[�̐��E�ł̍����u���[�L�͎�ɏd�S�ړ��⑬�x�̃R���g���[���Ɏg���Ǝv���܂���
�X�g���[�g�ł̍����u���[�L�͉E���œ��ރu���[�L�������ɕς��邾����
����������Ɣ�����背�[�V���O�J�[�g�ɋ߂��R���g���[����������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂�
�ܘ_
�R���Ƃ��ŃJ�[�u����O�ł`�s�Ԃł��`���b�g�i�����j�u���[�L����Ήd��O�ɗ^���Ȃ���₷���ł���
�����̍����u���[�L�̕��͂��������Ӑ}�ō����u���[�L�ł͂Ȃ����ʂɌ����_�Ŏ~�܂����肷��ׂ̃u���[�L���Ǝv���܂�
�����ԍ��F26172626
![]() 2�_
2�_
������ > ���N�T�X > LBX 2023�N���f��
�f�B�[���[�⒍�����������畷�����b�ł́A�A�A�A�A
�ELBX bespoke biuld <�I�[�_�[�ĊJ�I>
�@���������A���I100��̃I�[�_�[�g�Ŕ���o����A���̌�͋͂��Ȃ���̃I�[�_�[�g���������ŁA�唼�̐l�͒��炭�����ł��Ȃ��ł������A�N�����nj�̃I�[�_�[���n�܂���4��������u�S����200����v�̃I�[�_�[�g�����邻���ŁA�����Ȃ莟��I���B
�ELBX MORIZO RR <�I�[�_�[�ĊJ�͗��N�O���H>
�@��N�̉č�����I�[�_�[���J�n����A�X�܂ɂ���Ă͂����Ɏ�t�I��������A�L�����Z����Y�̘b�����X����A��t�I�������X�܂ł��������I�[�_�[���ł���X�܂��܂�����͗l�I
�����A�f�B�[���[�ł�2026�N�ɔN�����ǂ�����Ƃ����\������̂ŁA��t�ĊJ�͗��N�O�����Z���I�I
�@�܂��A����100��� MORIZO RR bespoke biuld �͑������ŁA��N�~���ɑS���撅1��I�[�_�[�g��������A���N�ɓ����Ă���͋͂��Ȃ�I�[�_�[�g�����邱�Ƃ�����Ƃ����B�����A���N�̔N�����nj�ɂ́A�I�[�_�[�ĊJ���H�H
�����ԍ��F26169075�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�ǂ��������Ƃł��傤�H�@26�N�g�܂Ŗ��܂��Ă܂���A���̂���26�N�O���̔N�����ǂ͗\�肳��Ă��܂���
�f�B�[���[�ɂ���Ă͊����Ďt���Ă��炸����������Ƃ����̂͂��蓾�܂���
LBX bespoke biuld�̓f�B�[���[�ł͂Ȃ����[�J�ł̒��I�ŁA�S���撅1��Ȃ�Ē����̎����͂ł��Ȃ��i���悤���Ȃ��j
�����ł͂Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�ǂ̃��N�T�X�X����̏��Ȃ̂��������ނׂ��ł��傤
�����ԍ��F26173032
![]() 10�_
10�_
���s�d�l�͑����K���t�F�[�Y2�Ή����Ǝv���̂ŁA2026�N9�����Y���܂łŏI���Ȃ�Ȃ��ł�����
��������ȍ~���̔�����̂ł���Ή��炩�̕ύX������̂ł́H
�����ԍ��F26179027�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���̓����]�E�̘b�ł�
���Ȃ݂�HEV���f���͍���̉��ǂŃt�F�[�Y3�Ή��ɕς�����悤�ł���
�����ԍ��F26180936�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����C�t�����̂ł����A�����]�E�̎����2025�N6�����Y�ȍ~�̂��̂��lj�����Ă܂���
���e�͖��m�F�ł����A�����d�l�ύX���������̂����m��܂����
�����ԍ��F26205509�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��
��ł����d�l�ύX����Ă�悤�ł�
�����ԍ��F26210799�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�zPC���B
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�X�V
-
�y���̑��z�摜����AI����
-
�yMy�R���N�V�����z�O���{�����̂��肪�𖠎��ɑ��Ƃ������ɂȂ��������
-
�y���̑��zBTO�p�\�R�������삷��Ƃǂ��Ȃ邩
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
�i�����ԁj
�����ԁi�{�́j
�i�ŋ߂P�N�ȓ��̓��[�j