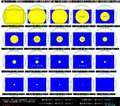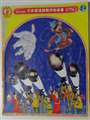���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S9709�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2025�N10��20�� 20:20 | |
| 69 | 12 | 2025�N10��17�� 22:05 | |
| 11 | 7 | 2025�N10��15�� 13:37 | |
| 10 | 3 | 2025�N10��10�� 07:21 | |
| 20 | 7 | 2025�N10��10�� 04:00 | |
| 37 | 34 | 2025�N10��10�� 03:42 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�����Y > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO
�v�����X�A�{�N�V���O�A�告�o�Ȃǂł͑̈�ق̂悤�ȏꏊ�ŊJ�Â���Ă��܂����ǁA�B�e�ł��鋗���̂��Ƃ��l������Ɩ��邳�Ƃ���Ȃ�̃Y�[���悪�~�����ł��ˁB
�B���f�q�̐i���������ł��܂��B
![]() 5�_
5�_
����͑̈�قȂǂƂ͈قȂ�A�Ɩ��ɂ�閾�邳�̃o���c�L���傫�������ׁA�V���b�^�[�X�s�[�h���グ�ɂ��������̂ł����A����͂������������x���ɐݒ肵�āA�V���b�^�[�X�s�[�h���グ�ăg���C���Ă݂����ł��B
�ȑO�͍H������Ō������鋐��Ȃڂ�ڂ�̂悤�ȏƖ��������̂ł����A�ŋ߂͗\�Z�k���̂悤�ł��B
�����ԍ��F26320935
![]() 0�_
0�_
�����Y > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO
�]�ˎ��㏉����1649�N�i�c��2�N�j�ɁA���݂̘a�̎R����o�s�̋I�m�쉈���Ɍ��Ă�ꂽ�I�B����Ƃ̕ʑ��u�ޏo��a�v�ƍl����ꂽ�����ł����A���s���ԋ�t���o�V�c�Ɉڂ���Č�A1906�N�i����39�N�j�Ɍ��O�₪����A11�N��������3�̓���r�ɖʂ��ĉ��ɂ��炵�Ȃ���A���������O�k���̗Տt�t(����)�ł����A���H�̖����ƂƂ��ɁA���y�║�x�ɂӂ��u�ό���v���J�Â����Ƃ������ƂŁA50-200mm/F2.8�ɍœK���Ǝv���B�e�ɍs���Ă��܂����B
�ϋq�Ȃ͉�ʉE���̎Ő��t�߂ƒr�̎���̒ʘH�t�߂Ƃ������ƂŁA���◓�����ǂ̂悤�ɎB�e�̎ז��ɂȂ邩�͂Ԃ����{�ԂƂ��������ł����B
�O�k�����͈�r�A�O�r�͎g�p�֎~�ł����A100-300mm/F2.8��200-400mm/F4�ł͌������͂��ł��B
![]() 10�_
10�_
�Ő��̕�����
�����ԍ��F26307886
![]() 7�_
7�_
2025/10/05 09:38�i1�����ȏ�O�j
��100-300mm/F2.8��200-400mm/F4�ł͌������͂��ł��B
����̓t���T�C�Y�ɕt���ĂƂ����b���ȁH
��G�c��MFT���t���T�C�Y��2�iISO���グ����̂�
200-400/4�ł�1�i���]�T������܂����
400��F5.6�Ńg���g��������F6.3��1/3�i��������Ƃ������Ƃ���
�~���[���X�͖]���[F5.6�́`400�o�]���Y�[���͏��Ȃ����ǂ��AMFT��50-200/2.8�Ɣ�r�ΏۂɂȂ�ł��傤
1/3�i�����ėǂ��Ȃ�]���[F6.3�̃Y�[���͂������o�Ă܂�
�����ԍ��F26308115
![]() 1�_
1�_
�����̎ʐ^�́AJPEG�B���ďo���̓��{�ł��傤���H
ISO5000�`6400�ł���m�C�Y�ł��ˁB
�����ԍ��F26308135
![]() 1�_
1�_
���|������ǃ_�n����
ISO6400���炢�Ȃ�@OM-1II�@�̍����x�͗ǂ��ł�����A
F2.8�̖��邳�͌����Ă��܂��ˁB
�Ƃ���ŁA���ԋ�t���o�V�c�@�́A���Ƃ̋߂��ɂȂ�܂��B
�킽���́@�V���ق̑I������ŁA���N�̑�͂c�̕���̋߂��ɋ��܂��B
�����ԍ��F26308146
![]() 1�_
1�_
�Ȃ�ł������������t���T�C�Y�Ɣ�r���Ȃ��ƋC���ς܂Ȃ��̂ł��傤���ˁB
MFT��MFT�̗ǂ������ăS�[�C���O�}�C�E�F�C�ł�������Ȃ��ł����B
���Ȃ��Ƃ����͂����ł����A�����Y�������t���T�C�Y/APS-C�͑S�����������̂ŁA�����Ă����Ȃ����̂��C�ɂ��Ă��d���Ȃ��ł����B
�����ԍ��F26308212
![]() 20�_
20�_
100-300mm/F2.8��200-400mm/F4�ł͌����� �Ƃ́H
�������͂Ȃ��Ǝv���܂����ǁB�B�B
������ ����͊m���Ɍ������ł����ǂˁB
���]���̎�U���̓t���T�C�Y�͎ア���A�d�����������̂�5�����\���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��i�O�O�G
�����ԍ��F26308228
![]() 4�_
4�_
2025/10/05 15:43�i1�����ȏ�O�j
���Ȃ�ł������������t���T�C�Y�Ɣ�r���Ȃ��ƋC���ς܂Ȃ��̂ł��傤���ˁB
������Ǝg���Ȃ瑼�t�H�[�}�b�g�Ƃ̔�r�͂��ׂ��ł���
�ǂ̒��x�̍�������̂��F�����Ă����ׂ��ł��傤
MFT�̗����ʒu�𐳊m�ɔF�����Ă��Ȃ���MFT�̊��������������Ă��Ȃ�
���Ȃ͉̂ߓx�ɍ����C�ɂ������鎖�ł��傤��
��MFT��MFT�̗ǂ������ăS�[�C���O�}�C�E�F�C�ł�������Ȃ��ł����B
����ŗǂ��̂����ǂ��AMFT�̖��͂������o���ĂȂ��̂��ă��[�J�[�Ȃ̂�������Ȃ�
�����50-200�͗ǂ�����150-600��MFT�͖]���ɂ͌����܂���ƃ��[�J�[���炪�錾�����悤�Ȃ��̂�����
�{���J�X�ɔᔻ����Ă�����ׂ��̔��헪
���Ƃ܂����������̃X���[���t�H�[�}�b�g�Ȃ̂�
OMDS��1�@�킭�炢�͏��^�y�ʋ@������ׂ�����Ȃ����ȁH
�ǂ�����������d���Ń��^�{�����Ⴀ��
�����ԍ��F26308435
![]() 2�_
2�_
��Tech One����
35mm����100-400mm��100-500mm�̃����Y����100-300mm/F2.8��200-400mm/F4�̂悤�ȉ𑜓x�E�{�P���������Ȃ��̂ŁA�X�|�[�c�B�e�Ƃ��Ή������������Ȃ��쐶�����̎B�e�Ȃ�Ƃ������A�����X�e�[�W�̎B�e�ɂ͂ǂ����ȂƂ����C�����Ă��܂��B
�ŁA����̉��ڂł����A
�E��������E�ɐ��C�i�Ђ傤���傤�̂˂Ƃ�@�E�@�����̂��݁j�@���Ôn�y�@��������ɗ��������Ñ�̗w
�@�I�[�P�X�g�����ŏ��ɃI�[�{�G�ɍ��킹�ă`���[�j���O����鎞�̂悤�ȉ��o���ɉ̗w���v���X������
�@������E�i�~�j�ɑ������܂������m�́u�z�����v�̖��邳�Ƃَ͈��ł��B
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc22/sakuhin/saibara/s3.html
�E�z�a�y�i���Ă�炭�j�@���nj�
�E���e�i����j�@���nj�
�E���L�i�炭����j�@�����y�́u�[�]���i�Ȃ���j�v�̕ʏ̂ň�l�ŕ����ꍇ�ɗp�����閼��
�@�@�@�`�x�e�`
�E����������E�z�a�y�i���������̂˂Ƃ�@�E�@���Ă�炭�j�@���nj�
�@�����͐��m���K�ł���A�i���j�ł��������440Hz�ł͂Ȃ�������ƒႢ�悤�ł��B
�@���Ȃ݂ɃI�[�P�X�g���ł̓o�C�I�����̉����ǂ������ɂȂ�悤��442Hz�ȏ�̂��Ƃ������ł��B
�E�����y�j�i���������炭�̂́j�@���nj�
�E����y�i���炭�j�@�����y
�E�ҏ�y�i���傤�炭�j�@�����y
�E���c�q�i���傤�������j�@�����y
�B�e�ł����ǁA18:00�̊J���O����B�e�|�C���g���`�F�b�N���A�����̗ǂ��Ȃ��l�p�̈֎q�ȈȊO�̊ϋq�͎Ő��̕���ȃG���A�Ƀr�j�[���܂��V�[�g����ɂ��č���Ƃ������ƂŁA�������p�̑���̈����Ő��̌X�Ε��ł̎B�e����X�^�[�g���A�O�����I���18:45�܂ŎŐ��̎Ζʂɗ������܂��Ƃ�����Ԃł����B
�����N���č����ɂ������̂͂��̂����̂悤�ł��B
�㔼�͉��ҁA�t�҂̈ʒu���m�F�ł����̂ŁA�U���H�����ɎB�e�|�C���g��ς��Ȃ���A�����ƎB�e�𑱂��Ă��܂������A�U���H������I�ɂ͈����ړ�����ς��������̂́A18:55����20:00���͔�r�I�y�ɎB�e�ł��܂����B
��r�E�O�r�̎g�p�֎~��100-300mm/F2.8��200-400mm/F4���g���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��B
����������掿���C�}�C�`��40���~���x��100-400mm/F4.5-5.6�N���X�͔����C�ɂ��Ȃ�܂���B
�����ԍ��F26308516
![]() 3�_
3�_
��taka0730����
�S��RAW�B��ŁAAI�m�C�Y���_�N�V�����ƌX����݂̂��Ă��܂��B
�g�[�^����6000���߂��B�e���܂������A�É��A�ʂŁ�taka0730����
�S��RAW�B��ŁAAI�m�C�Y���_�N�V�����ƌX����݂̂��Ă��܂��B
�g�[�^����6000���߂��B�e���܂������A�É��A�ʂł������烌���Y���\���Ă��鎞�Ԃ͂��Ȃ蒷���A�����I�ɂ͐����̓�����Ђ�����Ȃ��ɎB�e���Ă��銴���ł��B
���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
APS-C�@��70-200mm/F2.8��t���ĎB�e���Ă���l�͌������܂������ǁA�{�i�I�ȋ@�ނ̐l�͌������܂���ł����B�����Y���\���Ă��鎞�Ԃ͂��Ȃ蒷���ł�����A�����I�ɂ͐����̓�����Ђ�����Ȃ��ɎB�e���Ă��銴���ł��B
���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
APS-C�@��70-200mm/F2.8��t���ĎB�e���Ă���l�͌������܂������ǁA�{�i�I�ȋ@�ނ̐l�͌������܂���ł����B
�����ԍ��F26308576
![]() 4�_
4�_
����
��taka0730����
�S��RAW�B��ŁAAI�m�C�Y���_�N�V�����ƌX����݂̂��Ă��܂��B
�g�[�^����6000���߂��B�e���܂������A�É��A�ʂł������烌���Y���\���Ă��鎞�Ԃ͂��Ȃ蒷���ł�����A�����I�ɂ͐����̓�����Ђ�����Ȃ��ɎB�e���Ă��銴���ł��B
���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
APS-C�@��70-200mm/F2.8��t���ĎB�e���Ă���l�͌������܂������ǁA�{�i�I�ȋ@�ނ̐l�͌������܂���ł����B
���ςɂȂ����Ⴂ�܂����ˁB
�����ԍ��F26308580
![]() 0�_
0�_
�|������ǃ_�n����
�������������̂̓V���v���ŁA�}�C�N���t�H�[�T�[�Y���u�グ�āv�t���T�C�Y���u���Ƃ��v�K�v������̂ł����H�Ƃ����^��ł��B�@�O�҂����ł͑ʖڂȂ̂ł��傤���B
�t���T�C�Y�ɗǂ��Ȃ���������͎̂��R�Ȃ̂Ŕے���m������܂��A�s���葽�����ǂ�ł����Ō������Ȃ̂��ȂƁB
100%�����Ȃ�܂������A�u�͂��ł��v���x���ł����B�@�Ă̒�Ƃ��������R�Ƃ������A�قڔ��_�Ő�߂��Ă��܂��B�@�s�т��Ǝv���܂��H
�����ԍ��F26308710
![]() 15�_
15�_
200F2,8�͐����ȁB40-150F2.8���]���Ƃ����̂͂��Ȃ�B�e�̕����L����Bm4/3�̉\�����L�������B
300F4�͂����܂Ŗ]�����߂Ă��Ȃ��̂������Ȃ�ȁB
�����ԍ��F26318624�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����Y > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3
���s����200mm�]���[�ŎB�����莝���̌��̉摜�ł��B
�Q�{�f�W�^���e���R�����g�p�B��U�ꂵ�Ȃ��悤�ɒ�U�����[�h���𗧂��܂��B
�V�̖]�����Ŕ`�����悤�ȓ삪��̉�]���ł��B
�]���[�̎ʂ�͂��܂����Ƃ����l�����܂����A�킽���͍��{���Y�[���Ƃ��Ă͗Ǒ��Ǝv���܂��B
�킽���̗��p���Ă��郌���Y��OLYMPUS���ł��B�摜�Q�Ƃ̍ہAOM���i�ƕʕ��ނ���܂��̂ł����ӂ��������B
![]() 3�_
3�_
�m���ɂȂ��Ȃ��Ȏʂ肾�Ǝv���܂��I�I
�Ȃ��A�X����l�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�@�ł́A�g�����Ȃ��ł����܂ŎB����ł����H
�܂��]�k�Ȃ���A�����[���Ƀx�����_���璭�߂Ă��邢���̌��̂���������Ƃ́A���Ȃ�ʒu���Ⴄ�l�Ɍ�����̂ł����E�E�E�B
�����A�ƌ����Ă��V�̂ɂ͑S�R�ڂ����Ȃ��̂ŁA�G�߂Ƃ����Ԃł�͂葊���Ⴄ�̂ł��傤���ˁH�i��
�����ԍ��F26313422
![]() 2�_
2�_
�����̋u����͂��ƃR�����g���肪�Ƃ��������܂��B
200mm��2�{�f�W�^���e���R�����p�ł�����AMFT�̉�p��800mm�����ł��B
�莝���䂦�ɓ�k�̌��������낦�A��ʂ̒����Ɍ��������Ă���܂łɑ����g���~���O���Ă��܂��B
�F���ӏ܂��₷���悤�ɑ傫�߂ɂ��ăA�b�v���Ă��܂��B�ҏW����ő傫���ɓ��ꊴ���Ȃ��͉̂ۑ�ł��ˁB
�K���Ȑݒ�ŁA�u���Ȃ��悤�Ɍ�����ʒ����ɒu���A����ȑf�G�Ȍ����B��܂���B
�����ԍ��F26313437
![]() 2�_
2�_
���\���}�[�C����
�e���R���{�g���~���O�摜�ł��̉掿�ɂ͋����܂����B�f���炵���ł��B
�s���g�������肾���A�ƂĂ���C���Y�킾�����̂ł��傤�ˁB
���I�����p�X�B�����O�����W�̃Y�[�������Y�Ȃ̂ɂˁB�������B
�B�e���y�����Ȃ�܂��ˁB
�����ԍ��F26313583
![]() 1�_
1�_
�����c�̂�������ǂ��]���������������肪�Ƃ��������܂��B
����̃}���V�����ɂ���Ƃ���OM-1, M.ZD 100-400mm f5.0-6.3IS�ŊO�K�i�̎肷��Ȃǂ𗘗p���Ď莝���ŎB��܂��B
�莝���ɌŎ�����킯�ł͂���܂��A�O�r���Ă�]�T������܂���B
���H���s�̎��͎O�r���Q���܂��B
M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3�͖]���[�̎ʂ肪������Ȃ��Ƃ���l�������ł����A�킽���̎����Ă��郌���Y��200mm�ł��Ǒ��������܂��B
�����ԍ��F26313608
![]() 0�_
0�_
�@�@�u�X����l�v
�����J�Ȃ��ԐM���A���肪�Ƃ��������܂��B
���莝���䂦�ɓ�k�̌��������낦�A��ʂ̒����Ɍ��������Ă���܂łɑ����g���~���O���Ă��܂��B��
�@�����ł������B�@�g���~���O���Ȃ����Ă���̂ł��ˁB
�Ȃ��A�u��k�̌����v�ł����A��������������Ă��邨���l�Ƃ͈Ⴂ�܂��̂ŏ�Ő\���܂�����
�X����l�́A������������씼���ɂ��Z���Ȃ̂ł��ˁB�@
����Ȃ�A���{�Ō���̂Ƃ͈Ⴄ�킯�ŁA���������A�ȑO�I�[�X�g�����A�Œ��߂������l�Ǝ��Ă���l�ȁE�E�E�B
�ȏ�A�V�̂̎��͉��������܂����A�܂��Ԉ�������ƂȂ��ϐ\����Ȃ��ł��B
�����ԍ��F26315348
![]() 1�_
1�_
�����̋u����A
�����ɂ���͓̂V�̖]�����𗘗p����Ɠ|�����ɂȂ�̂���ȗ��R�ł��B���̕����̂̓V���t�@���ɂ͌�����Ă���܂��B
�ŋ߂͌��ʎʐ^�ł��k����ɂ�����Ƃ�V�����D�Ƃ������Ȃ�܂������A���ʐ}�ɓ����ɂ�����̂������A�B�e�����C��R���A�N���[�^�[���ƍ�����̂ɕ֗�������ł��B
���ƕ��i���B�e����ꍇ�͂������V����������A�n���𐅕��ɎB��̂���{�ł��B
�k����ł��삪��ł��\��Ȃ��̂ł����A���ʂ����ɂ���̂́A���Z����V�����̌ږ�Œn�w�̒S�C�ł������搶�ɋ����Ă��炢�܂����B�V�����D�ƂłȂ����ɂ͈�a��������܂������B�[�����������܂������B
�����ԍ��F26316051
![]() 1�_
1�_
�@�X����l
�����ł������B
�V�����D�Ƃ̊F�l�̉摜�\����@�̈�[���A���������������l�ł����ώQ�l�ɂȂ�܂����B
�ڂ��������������肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F26316824
![]() 1�_
1�_
�����Y > SONY > Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z
�L�p�����Y���~�����Ȃ�
���ɂ��������̂����̂R��
�@FE 16-35mm F2.8 GM II SEL1635GM2
�AFE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G
�BVario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z
�\�Z�I�[�o�[�ɂ�葦�������@
�A�ƇB�ŔY��Ŗ��A������ɓ��e���ꂽ�ʐ^���Q�l�ɂ��Ȃ�����F���̍D�݂���B�̃����Y�𒆌Âōw�����܂����B
���喳���ɍō��̐F���Ŗ{���ɔ����ėǂ������ł��B
�����ԍ��F26312259�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���킱�Ƃ���
�ʐ^�������Ă܂���ł����B�B�B
�B�e�f�[�^��������Ă��܂���B
�����ԍ��F26312276
![]() 2�_
2�_
�Õ����ׂ�Ă܂��ˁE�E�E�Ȃ��H
�����ԍ��F26312436
![]() 3�_
3�_
�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3
�㌷(���� 8.7) 2024.10.11 18:57(+8) OM-1, M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3 |
�\���� (���� 9.8 ) 2024.10.12 22:26(+8) OM-1, M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3 |
�\�O�� ����12.8 2024.10.15 20:39(+7) OM-1, M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3 |
���{���Y�[���̖]���[�͂ǂ��Ȃ̂��B���ʂ������Ƃ����]��������܂����A���s���Ɍ����B���Ă݂܂����B
���{���Ɩ������o�܂����A���{���Y�[���̖]���[200mm�̎ʂ�͂���Ȋ����ł��B
![]() 4�_
4�_
���\���}�[�C����
���s���Ɍ����B��ꂽ�Ƃ̂��ƁB
����͖쒹�ł��B���Ă݂ĉ������B
�����ԍ��F25949547�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���͎B��Ȃꂸ�A�Z��n�̌{��r�̐������B�邭�炢�ł��B
�`�F�R�𗷍s�������̖]���[�̉摜�ł��B
�����ԍ��F25950026
![]() 5�_
5�_
����������2024�N4��8���̊F�����H�̉摜������܂����B�B�e�n�̓A�����J�A�C���f�B�A�i�B�B
162mmF6.3 �莝���Ƃ�����ƒ��r���[�ȉ�p�ł����������������B
�����ԍ��F25950103
![]() 1�_
1�_
��T�A��������`�ɂĎB�e�B�Â��Ă�����Ȃ�Ɏg���܂����B
�v���L���v�`���Ō�������
�����ԍ��F25954091�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��������B����@�f���炵���摜�̓��e���肪�Ƃ��������܂��B
���]���������Ƃ悭�ʂ郌���Y�Ǝv���܂��B
�����ꖇ�A����̏㌷�O�̔������ł��B
�����ԍ��F25954554
![]() 2�_
2�_
�����ꖇ�A���I�X�̏\�l��ł��B���{���Y�[���ł��̂��炢�ʂ�Ǝ����ł������ł��B
�����ԍ��F25962007
![]() 1�_
1�_
�\�Z�閞��(����15.7) 2025.10. 7 20:02(+7) |
���Ҍ�(����16.9) 2025.10. 8 23:19(+7) |
���Ҍ�(����17.9) 2025.10.10 0:30(+7) |
����̗��s�̌��V���[�Y�ł��BOM-5�U, M.ZUIKO DIGITAL 12-200mm f3.5-6.3�B
�莝�� ��]��(�삪��)�B���{���Y�[���̖]���[�̎ʂ�͑��l�������قNJÂ�����܂���B
���ʂɊӏ܂���ɂ͔��������ł����A���{�Ɋg�傷��Αe���o�܂��B
�����ԍ��F26312373
![]() 1�_
1�_
�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [�u���b�N]
���̃����Y��E-M1�̑g�ݍ��킹�Ō����莝���ŎB���āA�u���b�W�J���� NIKON Coolpix P610 �Ɣ�r���Ă݂܂����B�y���e����߂āA�C�y�ɎB���Ă��܂��BP610�̉摜�ŏ[���Ɍ���`���Ă��܂����AE-M1�Ƃ��̃����Y�̕`�ʂɂ͑S���y�т܂���B
1���ځF35�~�����Z 600mm
2���ځF��L+�f�W�^�W�e���R�� 35�~�����Z1200mm
3���ځFCoolpix P610 35�~�����Z1200mm
![]() 4�_
4�_
2024/01/02 11:11�i1�N�ȏ�O�j
�f�W�^���e���R���̊G�Ƒ卷�͂Ȃ��Ǝv�����ǂ�
���������Ƃ������Ȃ�600�o�����Y�g��Ȃ��Ɩ����Ȃ̂ł��傤�c
�����ԍ��F25569283
![]() 2�_
2�_
2024/01/02 12:43�i1�N�ȏ�O�j
�����Ãe�c����
2���ڂ��x�X�g�̗l�q�ł��ˁB
�����OM�̋��͂Ȏ�U����f�W�^���e���R���̗D�G���ȑO�ɁA���̈����ȍ��{���Y�[�����������������Y���Ƃ����ؖ��ł��ˁB
�����ԍ��F25569370�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
>�j���[���ӂ�U�܂����偙�c ����
�����B��Ƃ��A�f�W�^���e���R���͌��\�L�����Ɗ����Ă��܂��B
�����ԍ��F25569592
![]() 2�_
2�_
>�i�^���A�E�|�N�����X�J�� ����
�J�����������Y��10�N�O�̃��f���Ȃ̂ɁA�����܂ŎB���ƃ`���b�g�������Ȃ�܂��B
���̃����Y�͉��i��y���ɒ��������\��L���Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25569599
![]() 6�_
6�_
2024/01/02 19:41�i1�N�ȏ�O�j
�L���ł��邱�ƂɈ٘_�͂Ȃ��̂����ǂ�
NIKON Coolpix P610�Ƒ卷�͂Ȃ��Ǝv������Ă͂Ȃ��ł���
MFT��×2�N���b�v������2/3�C���`�����菬�������炢�Ȃ̂�
NIKON Coolpix P610��1/2.3�^�Z���T�[�Ƃ�
�t���T�C�Y��APS-C�̍��������������̂�
�����I�ɓ�����O�Ȃ��Ƃ���
�����ԍ��F25569858
![]() 1�_
1�_
�����Ãe�c����A(���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����)�A����ɂ��́B
���������ړ��ĂŖ{�����Y���w�����āA�f�W�^���e���R���ŎB���Ă܂����A�l�I�ɂ͏\���������Ă��܂��B����ȏ�g�債�ĎB�肽���ꍇ�́A�����肾������ AF �̑������{�P�̔��������s�v�Ȃ̂ŁA�w���Ƀ����Y�ɓ���������A�Ƃ��ƂƓV�̖]�����ɍs���Ă��܂��������ǂ��C�����Ă܂��B
�܂��~�̖��͓����x�͍ō��ł����A�V�[�C���O�͋t�ɍň��Ȃ̂ŁA���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����̉摜���炢�̊g�嗦(��)���ƃ����Y���\�ɉ����āA���낻��C���̏�Ԃ̉e�������Ȃ��ł��傤����A���̋G�߂̎ʐ^�́A���܂��r�ɂ͌����Ȃ���������܂���B
�� �V�̖]�������� 150 �{���炢�H
�����ԍ��F25571317
![]() 3�_
3�_
1���ځF35�~�����Z 600mm
�@�ˑΊp������21.6mm
2���ځF��L+�f�W�^�W�e���R�� 35�~�����Z1200mm
�@�ˑΊp������10.8mm
�@��2/3�^�̑Ίp����=11mm�ɑ��āu1.97/3�^�v(^^;
��
1.39�{
0.72�{
��
3���ځFCoolpix P610 35�~�����Z1200mm
�@�ˑΊp������7.75mm
�@����f=258mm�A���Zf=1440mm
�t���T�C�Y
�@�ˑΊp������43.3mm
APS-C 1.5�{�n
�@�ˑΊp������28.8mm
APS-C 1.6�{�n
�@�ˑΊp������27.0mm
�����ԍ��F25571334�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���A�i�L�������Бҋ@������
���� �V�̖]�������� 150 �{���炢�H
�@��
���L����̎d�l�łȂ���A150�{�̏ꍇ�́u���v���n�~�o�������ȁH
���u���v�� ����p 0.5°�Ƃ���ƁA
���|�����E�́A66.4°�ȏ�̍L����d�l
(��JIS�̌��|�����E�ł́A75°�ȏ�)
�����ԍ��F25571702�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����A����ɂ��́B
�S�R�����Ȑ�������Ȃ���ł����A���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����̉摜 (���摜�́����Ãe�c����)���炢���̉����g�傷��ɂ́A�ᎋ���� 150 �{���炢�K�v����Ȃ��ł����ˁH
�����ԍ��F25571731�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���A�i�L�������Бҋ@������
���Zf=1200mm�̉摜���u�]�����̔{���Ƃ��āv150�{�ł́H
�Ƃ����Ӗ��Ȃ�A
�K�ł͖����Ǝv���܂��B
���Z=1200mm�́A�Ίp��p��2.07°�ł��̂ŁB
���|���E�@�@�� ���Zf=1200mm
��66.4°(��75°)�@�� 36.3�{ ���� ���L���E
��63.4°(��70.8°)�� 34.3�{ (���I�K��)
�@60°�@(��66.2°)�� 32.0�{ ���� �L���E
��47.1°(��50°)�@�� 24.2�{ ���u�W���v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�u�]�����̔{���Ƃ��āv�́A��L�̂悤�Ȋ�������(^^;
�Ȃ��A�u���v�̎���p��0.5 °�ł��̂ŁA
�]�����ɂ����ĕW����������Ă��鋌JIS�̌��|���E50°�ɑ��ẮA
(��JIS�̌v�Z��) 50°/0.5°=100(�{)�ɂȂ�܂��B
������(��JIS�̌v�Z��)�A150�{�Ƃ���ƁA
��JIS�̌��|���E�́A0.5°*150�{=75°�ɂȂ�܂��B
(��JIS�̌��|���E��66.4°)
�����ԍ��F25571763�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����g���Ă���V�̖]�����ł́A��75�{�Ŗ��������E��t�ɁA150�{�ł��ƌ��ʂ��ڂ̑O�ɂ���悤�Ɍ����܂��B���̔{���ɂȂ�ƃV�[�C���O�̉e����傫���܂��̂ŁA���Ȍ��ʂ̉摜���B��ɂ͑�C�̏�Ԃ����������Ă���t���œK�ł��B�̂͏d���ԓ��V�𗣂ꂩ�玝���o���āA�ԓ��V�����[�^�[�h���C�u�ŋ쓮�����ĎB���Ă��܂����̂ŁA�]�����ŎB�����摜�ɂ͗y���ɋy�т܂��A�莝���ł����܂ŎB���J����������Ȗ]�������Y�̓o��ɋ����Ă��܂��B
�����ԍ��F25571776
![]() 2�_
2�_
���A�i�L�������Бҋ@������
�ǂ���(^^)
�ڊዾ�̌��|���E�͋�̓I�ɉ��x�ł��傤���H
�ł���A�{�̂ƃA�C�s�[�X�̋@�햼���B
�܂����[�J�[HP�Ŏd�l���q�C����Ă���悤�ł���A���ׂĂ݂܂��B
���̃��X�́A������ʓI�Ȕ͈͂ɂȂ�܂����A
�u�� �]���� �{���v�Ȃǂʼn摜�������Ă��A�����x�͈̔͂��Ǝv���܂��B
�����Zf�Ɣ{���ɂ��ẮA��`�������̂Łu�O������v�ʂɗ��܂���
�����ԍ��F25571783�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�E50�{�Ō����� �E150�{�Ō����� https://www.mizar.co.jp/howto.html |
�u�{���ɂ�錩�����v https://my-best.com/products/496484 |
�ꉞ�A���Q�l
�E50�{�Ō�����
�E150�{�Ō�����
https://www.mizar.co.jp/howto.html
�@��
��150�{�ł͌��̑S�i�ł͂Ȃ��A���̈ꕔ
�����|���E��47°�ȉ��H
�u�{���ɂ�錩�����v
https://my-best.com/products/496484
(�T�C�g�����W���p��)
�E150�{�Ō��������R�����[�g�B�e
https://nyancotan.hatenadiary.com/entry/2016/09/24/064241
�@��
��������A150�{�ł͌��̑S�i�ł͂Ȃ��A���̈ꕔ
�����ԍ��F25571812�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
�����Zf=1200mm�̉摜���u�]�����̔{���Ƃ��āv150�{�ł́H �Ƃ����Ӗ��Ȃ�A�K�ł͖����Ǝv���܂��B
�͂��A����Zf=1200mm�̉摜� �́����Ãe�c����� 2 ���ڎʐ^�⎩���̌��ʐ^�ŁA����ł� ����̉��̊g��(��150�{���炢�H�Ƒz��) �ɂ͉����y�Ȃ��̂ŁA����Z1200mm��150�{� �ł͂Ȃ�����ł��B
���ڊዾ�̌��|���E�͋�̓I�ɉ��x�ł��傤���H �ł���A�{�̂ƃA�C�s�[�X�̋@�햼���B�܂����[�J�[HP�Ŏd�l���q�C����Ă���悤�ł���A���ׂĂ݂܂��B
���A�L���������܂��B�V�̖]������ ������I�Ɍ��ʐ^�͂�����̕����ǂ��̂ł́H� �Ǝv���Ă���i�K�Ȃ̂ŁA�܂�����O�ł��B���j
�����Ãe�c����
����75�{�Ŗ��������E��t�ɁA150�{�ł��ƌ��ʂ��ڂ̑O�ɂ���悤�Ɍ����܂��B(����)
���莝���ł����܂ŎB���J����������Ȗ]�������Y�̓o��ɋ����Ă��܂��B
�L���������܂��B�����͍���肿����ƈ��� \42k ��̍��ɓ��肵�܂������A�������莝���ł��ꂾ���B���̂��Ƌ����܂����`�B
�����ԍ��F25571883
![]() 1�_
1�_
(���ł�(^^;) ���{2048�h�b�g�p�g���~���O |
���摜 ��SX70HS ���Zf=1365mm |
���{1024�h�b�g�p�g���~���O |
���{1024�h�b�g�p�g���~���O 2 |
���݂܂���A�����ԈႢ�ł���(^^;
�����Ãe�c����
�ǂ���(^^)
�ڊዾ�̌��|���E�͋�̓I�ɉ��x�ł��傤���H
�ł���A�{�̂ƃA�C�s�[�X�̋@�햼���B
�܂����[�J�[HP�Ŏd�l���q�C����Ă���悤�ł���A���ׂĂ݂܂��B
�����ԍ��F25571887�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��
���[�J�[HP�Ŏd�l���q�C����Ă���悤�ł���A
��
���[�J�[HP�Ŏd�l�����J����Ă���悤�ł���A
�����ԍ��F25571888�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
�]������VIXEN NEW POLARIS 80M �ԓ��V�iD=80mm F=910mm�j
1981�N���������ꂽ���ł����A�������&�������̂悤�Ŗ����Ɍ����ł��B�������ǂ���Γy���̃J�b�V�j�̊Ԍ���������̂ŁA�����̍��Y���w���i�̐��\�̗ǂ���������܂��B
�A�C�s�[�X�͍�����
�EVIXEN Or. 6mm ���|���E�s���@�]�����t���i
�EVIXEN H.M 12.5mm ���|���E�s���@�]�����t���i
�EVIXEN 40mm 40°
�ESVBONY 23mm 62°
�EBORG 15mm 66°�@
�EBORG 6mm 66°
�ESVBONY 4mm 62°
�ł��BOr.6mm��H.M12.5mm�ɂ��Ă͍ŋߑS���g���Ă��܂��A�ȑOH.M12.5mm�Ō����������ɂ́A�C�b�p�C�C�b�p�C�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A���x�ǂ����E���܂����ƋL�����Ă��܂��BSNBONY 4mm�ɂ��ẮA��ɒ�ŋߏ��̎q���������W�߂ĊJ�Â���V�̊ϖ]��̎Q���҂��u200�{�Řf�����������v�ƌ����̂ŕ��̂��߂ɍw�����܂������A��������E�{�����Ă���A�Â��A�����Ɏ��E��������蓮�ǔ�����ƂȂ�̂ŁA�w�ǎg���Ă��܂���B
�����ԍ��F25572083
![]() 0�_
0�_
�����Ãe�c����
���ԐM���肪�Ƃ��������܂�(^^)
����75�{�Ŗ��������E��t�ɁA150�{�ł��ƌ��ʂ��ڂ̑O�ɂ���悤�Ɍ����܂��B
��
������ɊY������A�C�s�[�X�́A
���EVIXEN H.M 12.5mm ���|���E�s���@�]�����t���i
�ƁA
���EVIXEN Or. 6mm ���|���E�s���@�]�����t���i
���EBORG 6mm 66°
��
�s���̌��|���E�Aweb�����ňꉞ40°���炢�̂悤�ȋL�q������܂����B
�܂��A���|���E����JIS����JIS���s���m�ł��̂ŁA��؍��A�����̗����Ŏ����E���v�Z���Ă݂܂���(^^;
�y�����E�z�@���œ_���� 910mm
���߰��@�@�@�@�y�� ���|���E�z
mm �@ �{���@�@40° �@ 62° �@ 66°
�@ 4 �@ 227.5�@�@-�@�@0.27°�@�@-�@
�@ 6 �@ 151.7�@0.26°�@�@-�@�@0.44°
�@12.5�@72.8�@0.55°�@�@-�@�@�@-�@
�@15 �@ 60.7�@�@- �@�@ �@-�@�@1.09°
�@23 �@ 39.6�@�@-�@�@1.57° �@�@-�@
�@40 �@ 22.8�@1.76°�@ �@-�@�@�@-�@
�y�����E�z�@���œ_���� 910mm
���߰��@�@�@�@�y�� ���|���E�z
mm �@ �{���@�@40°�@ 62° �@ 66°
�@ 4 �@ 227.5�@�@- �@ 0.30°�@�@-
�@ 6 �@ 151.7�@0.27° �@ -�@�@0.49°
�@12.5�@72.8�@0.57° �@ -�@�@�@-�@�@
�@15 �@ 60.7�@�@-�@�@�@-�@�@1.23°
�@23 �@ 39.6�@�@-�@�@1.74°�@�@-�@
�@40 �@ 22.8�@1.83°�@�@-�@�@�@-�@
���̌��|�����E���0.5°�Ƃ���ƁA
����75�{�Ŗ��������E��t��
���߰� 12.5mm�˖�72.8�{�̎����E�� 0.55°�܂��� 0.57°�ł��̂ŁA������Ă���ʂ�ł��ˁB
���߰� 6mm�˖�152�{�ɂ��ẮA���|���E�s����40°�ő�ւ��ĂQ�����ɂ��Ă��܂����A�ǂ���̏ꍇ��
��150�{�ł��ƌ��ʂ��ڂ̑O�ɂ���悤�Ɍ����܂�
��
���̋L�q�ł͋�̓I�Ȏ����E���s���Ȃ���A
����0.5°���������E�̕������܂��̂ł́H�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25572386�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��
���̌��|�����E���0.5°�Ƃ����
��
���̎���p���0.5°�Ƃ����
�����ԍ��F25572396�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����A���肪�Ƃ��������܂��B
�u���ʂ��ڂ̑O�ɂ���v�͏��X��U���ȕ\����������܂��A���͂�����̂͊m���ł��B
�Ƃ���ŁA���|���E�ׂ����ĒT���Ă݂��Ƃ���A���������w�ϑ��w�����x�������邱�Ƃ��o���܂����B���\�N�U�肩�̍ĉ�ł��B����ɂ��ƁAOr.6mm�̌��|���E��42°�AH.M12.5mm�̌��|���E��39°�ƂȂ��Ă��܂��B
�v���o���Ă݂�ƁA���Ǝ����a���قړ������z���ϑ�����ۂɂ͗n��h�~�ׁ̈A�ڒ��ܕs�g�p��H.M12.5mm���g���đ��z�̑S�̑��𓊉e�łɉf���Ă��܂����B
�����ԍ��F25572462
![]() 1�_
1�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�ǂꂪ�������߁H�z�d�����Ȃ�ǂ�H���F����4��
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
-
�yMy�R���N�V�����z����\��
-
�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j