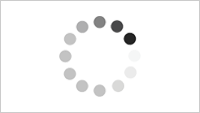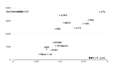���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S523�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 50 | 7 | 2015�N8��27�� 14:52 | |
| 627 | 185 | 2017�N1��29�� 10:28 | |
| 30 | 12 | 2015�N8��27�� 13:55 | |
| 53 | 12 | 2015�N8��14�� 13:43 | |
| 49 | 10 | 2015�N7��16�� 23:03 | |
| 9 | 6 | 2015�N7��22�� 21:43 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x �e���R���o�[�^�[�L�b�g
�e���R���L�b�g�i���Z420mm�����j�Ŗ쒹�B��A�r�O�͖��N�r�M�i�[�ł��B
�z�[���t�B�[���h�́A�����N���}��20�����̎R���ɗL������B
23����3���Ԃقǒ�����ɗV��ł��炢�A���y�Y�ɉ������B�点�Ē����܂����B
����C�Ԃɓ�����郂�f������Ȃ̂ŁA�������ʂ舫��ꓬ�B
����ł͒�����̎p�������Ė����A�B�ꂽ�ő喞���A�V�A���Z�C�����i�B
�A���PC�ʼn摜���m�F����ƁA���x�̎��Ȃ��猋�ʂ̓C�}�C�`�B
�Ȃ��Ȃ��v���ʂ�ɎB��Ȃ��A�ł��������B
���͉��Ƃ��c�ƈӗ~�����N���N�ƁB
�v���U��Ƀ��W���A�C�J���A���V�N�C�Ȃǂ��B��܂����B
![]() 20�_
20�_
����
�؉A�ł́A�����𗊂�ɒ������T���Ă��܂��B
�Ă͐�̖������܌�墂��āA�l�ꔪ��ł��B
�����Ȗ쒹�̎B�e�Ɋ��Z420mm�����ł́A�œ_�������Z���ł��B
���Z600mm�����ȏ�͗~�����ł��B
300mm F4�Ȃ犷�Z600mm�����B
�e���R���t����AF�l��5.6�ɏオ�邯�NJ��Z840mm�����B
�N���ɔ��������̂ł��傤���H
�p�i��100-400mm�̊J�����\�ŁA��������C�ɂȂ邵�B
�ǂ��炩�����āA�����Y�w���͏I���ɂ������ł��B
�����ԍ��F19083816
![]() 15�_
15�_
�����ł���o(^o^)o
���A����Ɓc�l�̓Y�[���͑�D���Ȃ�ł����c�p�i�\�j�b�N�̂̓X���[���āA�I�����p�X��300�~���_���Œ������Ă��܂��B
�����炭�̓e���R���Ή��ł��傤����c6004��856�Ȃ�P�œ_�ŏ\������o(^o^)o
�p�i�\�j�b�N�̏ꍇ�́A���C�J�̃l�[���o�����[�������̂Łc���߂̉��i�ݒ�Œl�����������낤�ƒl���݂��Ă��܂��B
�Y�[���ł��邱�Ƃ̖��͂͂���܂����A���p�I�ɂ̓R�X�p�̍��̕������Ȃ�傫�����ȁH�c�ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F19083990�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����Ȗ쒹���y���߂Ă����ł��ˁB�����Ɩ]�����~�����Ȃ����肵�āE�E�E
�����ԍ��F19084411
![]() 2�_
2�_
�����i�e������
�u�g������̓Y�[�������Y�A�掿�͒P�œ_�����Y�v���Y�݂ǂ���B
�@ 75-300mm�U�A40-150mm PRO�e���R���L�b�g�p����
300mm F4�e���R���L�b�g�ɓ���ւ��B
�A E-M1 �A75-300mm�U�A40-150mm PRO�e���R���L�b�g�p����
�p�iG-7��100-400mm�ɓ���ւ��B
��ԔF��AF �A�SK Photo�ɋ����ÁX�B
45-175mm PZ�̓L�[�v�i�ԎB��p�j�A�T�u�@E-PL6�ŃI����14-42mm EZ�Ƃ�
�R���r�Ń_�u���E�p���[�Y���L�b�g�B
���̑I����������ɓ���A�Y�݂�����݂Ȃ��甭�������̂�҂��ƂɁc
���������߂���
�������Ɩ]�����~�����Ȃ����肵�āc
�~�]�ɂ͍ی�������܂���A�ł����̒��g�����E�ł��B
����ȏ�́A�f�W�^���e���R���ƃg���~���O�ʼn䖝���邵���Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F19084688
![]() 7�_
7�_
enjyu-k����A�쒹�̐��X�̍�i�A�i�C�X�ł��ˁB
�����enjyu-k���A������I�����p�X��300mm��4.0���p�i���C�J��100-400mm��4-6.3����ɂ����A����ɔ[���̂������f���炵���ʐ^���B�����̂Ǝv���܂��B
��ɒ��̖����𗊂�ɒ��ɃA�v���[�`����Ă���Ƃ������Ƃł����A�쒹�̔�����M�d�ȃT�C����������\�́A���Ȃ킿���͂������A���͑傫�ȑ傫�ȃJ�M���Ǝv���Ă��܂��B
���ɃJ���Z�~�Ȃ��ƁA���̂�������E�����͂��Ȃ荂�߂̉��̂��߁A�����ł����t�B�[���h�ɂ����ăL���b�`���Â炭�A�����̗��ꂽ�Ƃ��납��ł�����̖���������\�͎���ŃV���b�^�[�`�����X�����̂ɏo���邩�傫�����E���邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁB
�������ɗ͌y�ʂȃV�X�e���ɂ���������r�Ńt�B�[���h�������邱�Ƃ������ł����A���������Ƃ��قNjM�d�ȃ`�����X�ɂ߂����Ă܂��B
���A���ꂩ��AG7��4K�t�H�g�A���Ƀv���A�ʂ͂����ł��ˁB
���Ƃ��ƘA�ʔh�̎����ł����A�B�e�X�^�C��������ɕς�肻���ł��B
�����ԍ��F19085483
![]() 1�_
1�_
F2.8PRO�͂�͂��Y��ł��ˁB
m4/3�̖]����Pro�����Y�̂̓e���R�����W���ŕt���悤�ɂȂ�A�p�i�\�j�b�N��100-400mm�A�I�����p�X��300mm�A�R�_�b�N��400mm�i����͊��Ҕ����ȁj�ƍ��܂ŕs���ӂȗ̈�ɖ{�̂������Y�����ݍ���ł��Ă܂���ˁB
���̓p�i�\�j�b�N�I�[�i�[�ׁ̈A�I�����p�X��Pro�����Y�ɂ͎肪�o���Ȃ��̂ŁA�uDual I.S.�v��Ή��̃p�i�\�j�b�N100-300mm���AG7�̉�ܕ�Ńe���[����������ƎB�e����B������100-400mm���ł�܂ł����Ɖ䖝�E�E�E�o���邩�Ȃ�(^^;)
�����ԍ��F19085848
![]() 0�_
0�_
��Ken Yidong����
2012�N6��29���AE-620�ŋ�X�B�ꂽ1���̎ʐ^�����_�ł��B
����1������A������ɛƂ��Ă��܂��܂����B
�����Ŏ��ʂł���̂́A���}�K���ƃL�r�^�L�ƃq���h�����炢�ł��B
�����𗊂�ɒT���Ă��܂����A�����Ă���Ȃ��ƌ������܂���B
������������������������āA�B�ꂽ���̍��g���͂��܂�܂���B
�J���Z�~�ƃT���R�E�`���E���B�ꂽ���́A�����킸�K�b�c�|�[�Y�B
�~�T�S�̎ʐ^���B�ꂽ�����A�v���o���Ă��܂��܂����B
������89����
���̃f�W�C�`�����@�A�p�i��G1�_�u���Y�[�������Y�L�b�g�ł��B
�����Y��2�{�Ƃ�������܂������A�J�����͍��������Ă��܂��B
G1���O�́AFZ50���g���Ă��܂����B
FZ50���茳�ɗL��܂��A���ł���������イ�M���Ă��܂��B
���̓I�����p�X�����C���Ɏg���Ă��܂����AG7 & 100-400mm�Ńp�i��
��A���邩���ł��B
�����ԍ��F19087571
![]() 4�_
4�_
�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [�u���b�N]
�{�����Y�́u�쒹�B�e�ɍœK�v��搂��Ă��܂��B
���̗l�X�ȕ\����ʂ��o����|�e���V�������L��̂��B
�{�����Y�ŎB�������̎ʐ^���A�b�v���Ă݂܂��B
�E�쒹�Ɍ��炸�y�b�g�⓮�����̒����������ǂ����B
�E�g���~���O���摜�����Ȃ�ł��L��ŁB
![]() 13�_
13�_
�쒹�B�e�ɍœK���͓�ł����A
���邢�ꏊ�œ����ĂȂ����
���ł��Ⴀ����łȂ�Ƃ��B��܂��B
�ǂ���g���~���O���Ă܂��B
�J���Z�~�͂��Ȃ�B�B�B
�����ԍ��F19071705
![]() 6�_
6�_
�������P������
���W������͒g�������͋C�A�J���Z�~�����A�I�T�M����͔w�i����ۓI�ł��ˁB
�������ł��܂����Ă܂��B�B
����͎��������̃A�W�g�ɋߕt���J���X��ǂ���������̃I�i�K�̃c�[�V���b�g�B
�ȑO�A��͂�W�c�ŃR�T�M��ǂ������̂��������Ƃ�����܂��B
�C�������Ƃ������A�`�[�����[�N�������ł��ˁB
�����ԍ��F19073556
![]() 2�_
2�_
�u�T�M�ł����B�l�b�g�ō��z�T���Ă���A�s�b�^���D�݂̂��̂����܂��ĂˁB��ōl����Ƃ��̃T�C�g�������ȏ�����������ł����A���̎��͕����オ���Ă���ł����U�荞�炻�������c�B�n�b�Ɩڂ��o�߂āA���₪�����Ȃƌx�@�E��s�ɘA�����āB���ǁA�����̈ꂩ�͔�Q���z���Ƃ��Ė߂��Ă��܂������ˁB�܂��A�J�����������ł����A�ʼn_�ɔ�ѕt������_�����Ă��Ƃł���B�v
����Ⴄ���̃T�M���낤�����I
�����ԍ��F19076661
![]() 6�_
6�_
�E�~�l�R�͖ڕt�������㊯�ۂ��ł����A���Ɉ��g�������܂��B
�����ԍ��F19079640
![]() 5�_
5�_
�͌��Œ����B���Ă���Ǝ��]�Ԃɏ�����W�C����ɐ����|����ꂽ�B
���������������Ė쒹�̎ʐ^���B�������ƃA���o���������Ă����B
�Â��ʐ^���肾���ʂ�͒��N���I���ȃW�C����I
�������̉͌��ł͒������Ȃ��Ȃ����ƒQ���Ă������B
����Ȑ�̖쒹���L����30�N���O�̌Ö{�������B
�ڂ��Ă����T���R�[�X������Ă݂Ă킩��͓̂����Ɣ�ׂĎ��ӂ������ɑ�n���������B
�͐�~�̂킸���Ȍ��Ԃɉ������߂�ꂽ�璹�����Ȃ��Ȃ�܂���ˁB
�����ԍ��F19082685
![]() 3�_
3�_
���������Ă��܂����c�o���̃q�i���~�ނ���ĂĂ݂��Ƃ����l�͌��\�����ł��ˁB
�l�b�g�ł����ȃP�[�X��ǂ݂܂����B
�r���Ŏ�������P�[�X�A�����܂ő����������P�[�X�B
�����ƃG�T�ɂȂ�g���{�Ƃ���߂܂���Ƃ������_�ł����_���ł����B
��ԓǂ݂ӂ������̂́A�������Ă��܂��߂��ė��Ă��܂��i�l�Ԃ̕��������̉Ƒ����Ǝv���Ă���j�̂��A���x�����x���g���C���Ė������������P�[�X�B�v�킸���邤�闈�܂����B
�����قƂ�nj������Ȃ��Ȃ����͓̂�֗���������ł��ˁB
���N�����C�ŋA���ė�����[
�����ԍ��F19085349
![]() 4�_
4�_
�J�����q���͎�q�H�������ł��B
�H���̃q�}�����������čU�h���J��L�����܂����B
���̃����Y�͊�]�������i68��~�ł����A�����^�͌��w�n�������Ŕ{�߂��l�i��������ł��ˁB�u�R�X�g�������Ďʂ�ɂ���������v�Ǝ��M����������ł��傤���B�������Ă݂�ƁuF6.7�ł��̒l�i����`�v�ƃu�[�C���O����A���j���[�A���ő啝�l���������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B�I�����p�X����́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ł͂��ꂾ���R���p�N�g�ɂȂ�܂��A�Ƃ����A�s�[����ǂ������AF�l�𗎂Ƃ��Ă��ʂ�ɂ������Ηǂ��Ƃ��āA�w���w�̔�������������̂�������܂���B
�ł����͍ŋ߂܂Ńz���g����ȃ����Y���g���Ă����̂ŁA���̎ʂ�͏Ռ��ł����B�������莝���������Ȃ��̂ŁA���̃R���Z�v�g�̓A���ł��B
�����ԍ��F19088161
![]() 8�_
8�_
�R�Ȓ��ތ������̃T�C�g�ɉ������j����̎ʐ^������܂��B
���̐l�͓��{�̖쒹���Ԏʐ^�̐��҂������ŁA�吳���ォ��B��n�߂Ă����ł��ˁB
������5kg������J�������g���A�����V���b�^�[�P�ɓ���ւ��������B
�ł�����ꂽ�c�c�h���̃q�i�ɔ�тȂ��狋�a����Z���_�C���V�N�C�̎ʐ^�Ƃ�����̂��B
����ώʐ^�͋@�ނ���ˁ[��
�����ԍ��F19090610
![]() 8�_
8�_
�ܓV�ł������B��ɏo�����܂��B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y��APS-C�ɔ�ׂ�ƍ����x�̉掿�����悤�ł����A�ȑO�g���Ă������{���R���f�W�ł͓ܓV�ŏo������̂͋C���d�������̂ɔ�ׂ�Ɖ_�D�̍��ŁA���\�y���߂܂��B�掿�͂�͂�t���T�C�Y�Ȃ�ł��傤���A�d�ʓI�Ɏ莝���ŋC�y�ɎB���Ƃ����C���[�W�����Ă܂���B�I�����p�X�̏ꍇ�A��U���@�\���{�f�B���ɂ���̂ŁA�]�������Y���g���ꍇ�̓{�f�B�ƃ����Y�̏d�ʔz���������Y���ɕ�Ȃ��ėǂ��Ƃ������_������̂ł͂Ȃ��ł����ˁB
�����ԍ��F19092956
![]() 7�_
7�_
�͌��Œ������~�T�S�ɏo��܂����B
�ȑO�A�͌��ŗy���ޕ��Ɍ����������Ƃ�����܂������A����͒�����ł��B
�ӊO�ɐ���s�����藈���肵�Ă���̂����m��܂���B
�������ҋחނ͍s���͈͂��L���ł��ˁB
�����Ƃ����Ԃɒʂ�߂��Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F19096064
![]() 4�_
4�_
�u�\�������̎w�ցv�i�R�����[�g�E���[�����c�j�Ƃ����{�ɁA�����̃n�g�͒��Ԃւ̍U���Ɂu�}�����Ȃ��v���Ƃ��ώ@����Ă��܂��B���R���ł���Α��肪�����ďI���ł����A���Ăɓ����ꂽ��Ԃł͋��낵�����Ԃ��N���Ă��܂��̂ł��B���̈�ۂ������āA�ǂ����n�g�ɑ��Ď��ȃC���[�W�������Ă���ł����A�ʐ^���B��悤�ɂȂ��ď����������ς��܂����B�n�g�̔��Ă͗͊��������ĂȂ��Ȃ��J�b�R�C�C�̂ł��B�A�I�o�g�͓��ɐF���L���C�ŎB��̂��y�����ł��ˁB
��L�̖{�́A���킢�������Љ�Ă��܂��܂������A���ҁi�m�[�x���܊w�ҁj����������ώ@�����肵���g�߂Ȓ��⓮���̎p���ʔ����������߂ł��B�n���J�����ɂɓ����Ă��܂��B
�����ԍ��F19125181
![]() 8�_
8�_
�Ñ�G�W�v�g�ł̓n���u�T���ۂ����_�i�z���X�_�j���M���ꂽ��������������ł��ˁB���̃n���u�T���I�ꂽ�̂��B����钹�Ƃ����E�҂ȃC���[�W����������ł��傤���A���̓Ɠ��ȕ��e��������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B���͎�ˎ�������́u�u���b�N�E�W���b�N�v��A�z���Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F19128069
![]() 3�_
3�_
�{�P��������̎ʐ^�Ƃ��āu�{�P�t�H�g�v�Ȃ���̂����Ă�O���[�v�������ł��ˁB�{�P�������܂�O�ʂɏo���͉̂������߂���銴���������Ă܂������A�t�Ɏv������{�P��\�������Ⴄ�Ƃ������z���u���ł��B�{�����Y�ł��g���C���Ă݂Ȃ��ƂȂ��B
�����ԍ��F19130957
![]() 3�_
3�_
�͌��ŋʃ{�P�Ƀg���C���Ă݂܂����B
�P�D�w�i�͖A�ł��B
�Q�D�w�i�͐��ʂł��B�i��H�����V���Ȃ̂Ŏ��p�`�ł��B�i�J���ɂ���Ɗۂ��Ȃ�H�j
�R�D�A�I�T�M����Ɛ��ʂƂ̋����������ƂȂ��ƃ_���ł��ˁB
�S�D�u�I���̒m������������˂��v�ƃA�I�T�M�������B
�L���m���̃M�������[�Ń{�P�t�H�g�W��������ł����A�w�i���ʃ{�P�ɂ��čۗ����������̍�������܂����B�ǂ��������ɎB�����̂��Ȃ��B
�����ԍ��F19133915
![]() 5�_
5�_
�����ƁA����ɂ��́B�����₵�����Ȃ̂ŁA�̂��̂��o�Ă��܂����B
75-300�̗͍��A�y�����q�����Ă��܂��B
���Ԃ�A���͂��̃����Y���Ȃ�������A����ȃV�[���͎B��Ȃ������Ƃ������̂���ŁA�y����������Ȃǂ��B��Ă��Ȃ������Ǝv���܂��B���̃����Y�́A�x�X�g���_�̂ЂƂł��B
������Ƃ܂��A�s���{�P�̉摜���o�����܂����A�I�����p�X���[�U�[�̕��ɂ́APro�����Y�ɂ��蒅�ڂ����ɁA�������Ďg���ė~���������Y�ł���(�������Ȃ��̂����́I)
�����ԍ��F19137513
![]() 9�_
9�_
������sunny����
���͈�l�œ˂��������Ⴄ�^�C�v�ł����A��͂葼�̕��̎ʐ^������̂͊y�����ł��B���̌����V�[���́u�ڂƖڂŒʂ������`��v�i�Â��j�Ƃ����������ǂ��ł��ˁB�ʐ^�͎B���Ă�l�̊y����ł銴�o���`���C�����܂��B
�n�N�Z�L���C�͂������������������ł����A�~�ɖk����n���Ă���O���[�v������悤�ł��B�͌����ނ�ő��������Ȃ�̂͂܂���̂悤�ł��B
�����ԍ��F19140097
![]() 3�_
3�_
���}�K���̓V�W���E�J���Ȃł����A���̉Ȃ̒��̖��O�ɊF�t���Ă���u�J���v���ĉ��Ȃ�ł��傤�ˁB���c���j����́u�쒹�G�L�v�̒��ŁA���̖��O�ɂ��ĕ�����F�X�����Ĕ�r�l���Ă��܂����A�e���̕��������O�̃x�[�X�ɂȂ��Ă���Ƃ����̂���{�I�ȍl�����ł��B�ނ͏�����ʂ��w���Ă����u�N���v�Ƃ������t�i�������̚e������u�N���N���v�ƌĂԒn��������j���ω��������̂��Ƒ����Ă��܂��B�����w���u�c�o�N���v�������悤�Ɂu�N���v���ω����Ă����t�������̂��ƁB���`��A�������������āA�ǂ������Ă������v���Ȃ����̂�������ł����B
�����ԍ��F19162912
![]() 4�_
4�_
�܂��R�V�A�J�c�o���������I
�ǂɕ����̉��𑛂�������ь����A���̒���`�����肵�܂��B�₪�ĎO�X�܁X�U���čs���A�p�������Ȃ��Ȃ�܂����B��֓n��O�ɖ��c��ɂ���ł����̂����m��܂���B
�W�Ȃ��ł����A����S���[�h�ŎB���Ă��āA�V���b�^�[�X�s�[�h���_�C�����ŃN���N���������Ă��܂��B�Ƃ��낪�ŋ߁A�N���N�����Ă����X��������Ă�C���B�B�����Ă܂��Q�������o���Ăˁ[�̂Ƀo�b�N���Ă�ˁ[��ƃI�����p�X�Ɏ������ނƁu�����c�����C�������Ē����܂��v���́u�����v�ĉ��Ȃ�
�����ԍ��F19166507
![]() 4�_
4�_
�C�\�q���h���̓꒣�葈���H�����܂����B
�����O��I�ɒǂ��Ēǂ������܂����B
���̗E�m�Ȗʍ\���ł��B
�����ԍ��F19169741
![]() 6�_
6�_
�E�~�l�R��c���܂�c�ǂ����Ă��c���́c�z�����āc���܂��c
�����ԍ��F19172668
![]() 3�_
3�_
�������ꂼ�ꐫ�i���Ⴂ�܂��ˁB
�L�A�V�V�M�͂Q�H���Ď����ߕt���Ɣ�ї�������ł����A1�H�͉��̂����]���Ė߂��ė��Ď��̑O������čs���܂����B��̂ǂ��v��ꂽ�̂��C�ɂȂ��ł����c
�����ԍ��F19182357
![]() 4�_
4�_
�z�V�S�C�i�S�C�T�M�̗c���j�����Ă���ƁA���ʂɕ�����ł�����̂��E���āA�܂�����𗎂Ƃ���ł��ˁB�����Ȃǂ�����Ɋ���ė���̂�҂��\���Ă���悤�ł��B����͂Ƃ������A���삪�ǁ[�ɂ����[�ɂ��ɖ��ŁA���������Ȏ��́u�����ƃV���L�V���L�������I�v�ƌ��������Ȃ�܂��B
�c�{�����Y�ɂ��l�K�͂���܂��B
�ʂ�͂�����F�l���Â���ł���ˁB
����S���[�h�ŎB���Ă܂����A���ʎ����ISO������ݒ�ɒ���t���܂��B
�Ȃ̂ŎB�肽���摜�ɂ���Č��ʂ̂���V�`���G�[�V������T���悤�ɂ��Ă܂��B
������Β��߂܂��B
���̏ꍇ�͏d�������Y�S����肻�����̕��������Ă܂��B
�����ԍ��F19185028
![]() 4�_
4�_
�Z�O���Z�L���C�͖ڂ��N���b�Ƃ��ĂčD���Ȓ��ł��B
�ł������̒��Ȃ�ŁA�Ȃ��Ȃ��L���C�ɎB��Ȃ��ł��B
����т��邩���ׂꂷ�邩�݂����Ȋ����ŁB
�Ǝv������AE-M1�ɂ̓n�C���C�g�E�V���h�E�R���g���[���Ƃ����@�\������悤�ł��B
�����@�\�Ă���ł͂ƂĂ��g�����Ȃ��Ȃ��B�B
�����ԍ��F19187805
![]() 5�_
5�_
�������������ĉ͌��֍~�藧�ƁA������L�W�o�g�̐����тɑ������܂����B
������͑̂��傫�����Ƃ������āA�����т������B
�H�����u���b�Ɩc��܂���Ɛ�����ۂ��ς��܂��ˁB
�I�����p�X���č��܂łقƂ�Nj��������ĂȂ������ł��B
�\����Ȃ����ǁA�{�f�B�������Y�������ÏL���Ēn���`�Ȋ����Ȃ�ł���ˁB
�ł��g���Ă݂�ƈ�ۂ��Ⴂ�܂��B
�����Y�͂��̃O���[�h�ɂ��ăE�\�b�Ƃ��������̉𑜓x�B
�肪�o�Ȃ�����SHG�����Y�ǂ�Ȋ����Ȃ̂��g���Ă݂����ł��˂��B
�o�Ă���G�ɖڂ��ӂ���̂�����ƎB��̂��y�����ł��B
�����ԍ��F19190489
![]() 4�_
4�_
���Y�̍����̃V�[�Y���ł��ˁB
������B���Ă݂���ł����A���̏ꍇ�ЂƂ�肪�B
�莝���Ȃ�ł����A�ǂ����Ă��B�e���ɗh�炵�Ă��܂��܂��B
���ƌ����ĎO�r�����������C�ɂ͂Ȃ�B
���̕ӂɗ����Ă�͂�}���x���ɂ��邾���Ō��\�Ⴄ�����B
�����ԍ��F19193231
![]() 5�_
5�_
APS-C����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ɉڍs����ɓ����ẮA�掿�����Ȃ藎����̂��o�債�Ă��܂����B�ł��S�R�y���߂܂��ˁB����RAW�ł͎B�炸JPEG�I�����[�ł��B������A�b�v���̎ʐ^�A�v�����g���āA�g���~���O�E�I�o�E�J���[�E�V���[�v�l�X�ȂNJȒP�Ȓ��������Ă��܂��B�I�o�����Ƒ傫����ۂ��ς��܂����A�P���Ƀp�^�b�ƑS�̂��]�Ԃ悤�ȕ������Ȃ��A�e���̊K���������ɑJ�ڂ���ӊO���������Ėʔ����ł��B
�����ԍ��F19193743
![]() 5�_
5�_
�q��ʐ^�Ƌ���Ȃ�Ă����ł��ˁB�l�b�g�ł��܂��܌����̂ł����A�Љ�͂ɋ�����������߂��������̂ł��B�u���m���B�邩�A�R�g���B�邩�v�ƌ����̂ł����A������ƕ�����C������̂ł��B���ł��傫���N���ɎB���������̎ʐ^���āA�ǂ����ʔ����Ȃ���ł���ˁB���������̂͒����u���m�v�Ƃ��ĎB���Ă���̂ł͂Ȃ��̂��B���̓����\��A�w�i�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ŋ������钹�̐����c�P�Ȃ镨�̂��ʂ��̂ł͂Ȃ��āA�h���}������������ʐ^��������������Ȃ��ł��傤���B������u�R�g���B��v�ƕ\�����Ă���̂��ȂƁB
�ł������͈Ղ��s���͓�B�B
�����ԍ��F19193844
![]() 6�_
6�_
���āA�ق�������A�b�v���Ă��܂��܂������A������ӂŏ��������Ǝv���܂��B
�����P������A����sunny����A�����e���肪�Ƃ��������܂����B
�{�����Y�͎��̒��ł͍��܂łň�Ԃ̃����Y�ł��B
���͉����B�邩�ȁB�B
�����ԍ��F19193867
![]() 7�_
7�_
�u�单���A�R�Q�����B���ĎQ�������B�v
�u�单�����ĒN����I�[����������ˁ[�̂���I�v
�u�v��ʂ��Ƃ��N����̂����̒��Ƃ������̂���B�v
�����ԍ��F19198978
![]() 4�_
4�_
��������̑f���炵����Ⴀ�肪�Ƃ��������܂��B����ŋ��k�ł������̃����Y��E-M1�ł�C-AF�ł̓��Ԓǔ��͂������ł��傤���H
�q���̉^����i���w�Z�A�c�t���j�Ŏg�������Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F19200844
![]() 1�_
1�_
���Ƃ��҂��V�V����
C-AF�A�ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁB
���ł钹�Ɋւ��ẮA�����ɃA�b�v�����悤�Ȏʐ^�͎B���Ƃ��������悤������܂���B�����܂�̓��m�ɂ�肯��ŁA��^�̒��͂��������s�������܂����A�c�o���̂悤�ȏ��^�ő������͔S���Ă��Ȃ��Ȃ������܂���B���������ł����ǁA�����Ă�q����]���ł��������̑傫���ő�������悤�ł���A�������炢�̓s���������Ȃ��ł��傤���B
��͂�͂�E-M1�̃X���Ŏ��₳���̂��ǂ��Ǝv���܂��B�I�����p�X�̃X���̓x�e���������\����悤�Ȃ̂ŁA�����Ȏ��_����̃��X���t���Ǝv���܂��B�{�����Y��AF�����ɒx���Ƃ����b�����܂���̂ŁA��͂�E-M1��AF���\�Ɉˑ�����Ǝv���܂��B
�V�W���E�J���͂悭���钹�Ȃ��ǁA�ߕt���Ȃ����A���傱�܂��������A�Ȃ��Ȃ��B�点�Ă���܂���B�G�i�K�A���W���ƍ��킹�āA���̋��O�Z��B
�����ԍ��F19202208
![]() 4�_
4�_
�����Ńc�~���B
�J���X�ƃo�g�����Ă܂����B
�c�~�̕����̂͏�������ł����A���Ă̓J���X�Ƃ͕ʊi�̑����ł��B
�ڂ��f�J���������u�����n���p�˂��B�B
�����ԍ��F19212327
![]() 4�_
4�_
���ɂ̓I�I�^�J���B
���킠�킵�Ă�Ԃɑf���炵�������Ŕ��ōs�����܂��܂����B
�ҋׂ̓����͑��̒��Ƃَ͈��ȕq�����������܂��B
�����ԍ��F19215323
![]() 3�_
3�_
�����ǂ��̂�����Ƃł� |
�ǂ�����ł����̂��\�z�����܂��� |
�Ƃ肠�����u���̊ۍ\�}�v������Ƃł� |
�����Y�Ⴂ�܂����A����ʏꏊ�ōă`�������W���܂��� |
Captain Caribe����A�����́B
�����f�G�Ȏʐ^�����肪�Ƃ��������܂��B
������s�ō`�ɗ�����������ɒ��B��Ƀ`�������W���Ă݂܂����B
���N�ɂȂ��ė��q�@���悭�B��悤�ɂȂ�����ł����A���ł钹�͐�����������ł��E�E�E��
�i�������~�܂��Ă��钹������̂ł����E�E�E�A������̂��E�E�E�j
���Ƃ��҂��V�V����
�����̃����Y��E-M1�ł�C-AF�ł̓��Ԓǔ��͂������ł��傤���H
�O��̓����i�����Ă��铮���j�Ɋւ��Ă͂��Ȃ薞�����Ă��܂��B
�^���S�̓��}�i�����炭�����U�O����/�����炢�j��A�ʁu�g�v�{C-AF�ŎB��܂������P�P�����s���g���O�ꂽ�J�b�g�͂���܂���ł����B
�b-�`�e�{�s�q�̓C�}�C�`�ł����E�E�E
��Captain Caribe����
�W�Ȃ��b�ł��݂܂���B
�𑜓x�ɂ��ł����A�\�蓦�������Ă��������܂��B�A
�����ԍ��F19216479
![]() 4�_
4�_
���ށ[��������
�ߋ����ŃL���C�ɎB���Ă܂��ˁ[
���ł钹�̓z���g����ł��ˁB���͐l�������ԑΉ����݂��i�ȑO���{���R���f�W�X���ŏ�肢�l�ƎB���ׂĒɊ��j�u���ł��ᓖ����v���Ɓu�g���~���O�v���p���Ă��܂��B���\����1���ʂ́u�܂����Ƃ��v�[�̕��Ɏʂ������̉摜�������������ʂɃg���~���O�c
���͔�ʑ̂̈�ɉ߂��Ȃ��Ǝv���Ă܂����A���Ăɂ͂�͂薣�����܂��B
�����̎ʐ^�W�i�����L������B�e�j�����܂����B
�^�����ȓ~�H�Ő�̗я���Ԏp�͂ǂ��������i�`�b�N�ł��B
�����ԍ��F19218095
![]() 3�_
3�_
�⍇��������̃C���^�r���[�œǂ݂܂����B
�����������B��̂ł͂Ȃ��T���V���O�G���X���ʂ����܂˂�i�ɂȂ�Ȃ��ƁB
�T���V���O�G���X���ĉ��Ȃ̂��悭�킩���̂ł����B
�ł������ƒ����B���Ă�ƃt�c�[����Ȃ��������ʂ������������鎞���Ă���܂���ˁB
�u�C�̂�������ˁ[�́H�v���[���[�ł���
�����ԍ��F19221160
![]() 6�_
6�_
�œ_�����Ă܂��ł����͋C���悩�����̂ŃS�~���s����܂��� |
���f�[�^�͒��~���O���Ȃ��Ɠ��� |
��͉����ł� |
��Ɗx�E�����ő������܂����� |
Captain Caribe����A�����́B
�����قƂ�ǁu���ł��ᓖ����v���ł��B
�u�g���~���O�v���͂��܂ɁE�E�E
���ߋ����ŎB���Η��z�ł����A�Ȃ��Ȃ��A�l�l�̎v���ʂ�ɍs���Ȃ��Ƃ��낪���R�̐ۗ����ƁE�E�E
�����͔�ʑ̂̈�ɉ߂��Ȃ��Ǝv���Ă܂����A
�����ł��ˁA��ʑ̂̈�ł��ˁB
�����Ăɂ͂�͂薣�����܂��B
�������ł�����̂ɓ���܂��B
�܂����E���ŏC�s���Ă��܂����̂ŁA�\�蓦�������Ă��������܂��B
�����ԍ��F19222107
![]() 2�_
2�_
�u���������H�v�u���������H�v |
�u�Ⴄ�݂��������v�u�ǂ����Ȃ�v |
�u���������ȁv�u��������������v |
�u���킯�҂ǂ����`�v |
���ށ[��������
�P���ږʔ����ł��B���Ăɂ��F��ȑ�����������܂���ˁB���i�R���ɂ́u�s���g�����ĂȂ��v�Ƃ��u�s���g���Â��v�Ƃ������������������Ă���l�B�����܂����A�ނ�ɂ͑N���������Ɉ��Z���������̌��@�������܂��B
�g�r�̓꒣�葈���H�͎����ŋ߉͌��Ō��܂����B�i�B�����ʐ^�͉����̂Ƌt���Ń��^���^�ł������c�j���������������ɂ��Ă���G���A�ɕʂ̌̂��N�����ė����悤�ł��B�Ăɑ��������ᒹ�������̏Z�������߂ė����鎞��������Ȃ̂��Ǝv�����肵�Ă܂��B
�������B��ꂽ�����L������̓T�����[�}������A���T���j���ɗ������B��ɎR�ɓo���Ă���̂ŁA�R�����̐l�Ɂu�T���f�|�v�ƌĂ�Ă��������ł��B�T�����[�}�������߂ĎR�����œ����܂ŗ����ɂ̂߂荞�ސl������Ƃ́B���̃��X�̉ĉH�̎Ȗ͗l�D���Ȃ�ł����A��������̎ʐ^�ŗ����̂�����ƌ����ڂ��}�b�`���Ă��邱�Ƃ��킩��i���z�h�ł����B
�J���E�̌Q������Ă�Ɖ��������g������܂��B
�����ԍ��F19223992
![]() 3�_
3�_
�����܂���A�ǂ��������������̍D���Łc
�����ԍ��F19227147
![]() 3�_
3�_
���m�N���ʐ^�W�������B
�u�E�B���E�o���b�N�w�X�̒��̎q���x���B
���ŐX�̒��ɗ��̎q�����]�����Ƃ�˂�B
�l�D�͂Ɓc���A�����イ�܂�`�v
���ꂪ�ɐ^��A�L�ɏ������ă��c�ł���
�����ԍ��F19235430
![]() 2�_
2�_
���}�K���͐l��ꂵ�Ă�Ǝ��������悤�ł��ˁB
�q�}�����̎�ł������Ă��邩�ȁB
�����ԍ��F19255811
![]() 4�_
4�_
�u����܉��ăL���C�Ț����v�Ɩ݂�����������ƃK�r�`���E������o�����Ă��Ƃ����x������܂����B
�����ԍ��F19257377
![]() 5�_
5�_
ED12-40mm�����̂ł����A�h�o�h�H�\�����ăY�[���Ɏ�艞���������ł��ˁB
�{�����Y�͂��̓_�X�R�X�R�ƃY�[���ł���̂��@���I�Ƃ����������ۂ��Ƃ������c
�����ԍ��F19258711
![]() 4�_
4�_
��N�Ɠ������i�ɂ܂��o����ł͂Ȃ��B
�͌��̊����ς��A���������̊������ڂ���Ă����B
��N�̎ʐ^������ƒN���ʂ̐l���B�����ʐ^�Ɋ����܂��B
�����ԍ��F19258715
![]() 3�_
3�_
�ŋ߁A�~�܂���̂�RAW�ŎB��悤�ɂȂ�܂����B
JPEG��F�X�������Ă���ƁA�掿���K�T�K�T���Ă���C������̂ł��ˁB
RAW�����H�����������炩�Ȋ��������܂��B
������т��̂�RAW���ƘA�ʂ̏������݂Ɏ��Ԃ�������̂ňˑRJPEG�ŎB���Ă܂��B
���̕ӂ͋@�킪UHS-�U�Ή����Ƙb������Ă���̂�������܂���B
�����ԍ��F19273091
![]() 3�_
3�_
�����̃m�[�gPC��AdobeRGB�ɑΉ����Ă��邱�Ƃ����������B
����PC�̕\����JPEG�o�͂��AsRGB����AdobeRGB�ɐ�ւ�����ł����B
���`��A�Ⴂ����[�킩���c
�����ԍ��F19273329
![]() 5�_
5�_
�����w�ł́A�����ɋߕt���Ē���������̂ɁA�a�t���ɂ��Ȃ��l�t���@�i�鉻�@�j�Ƃ����̂����邻���ł��B�ΏۂƂ��铮���Ɍ����҂̑��݂��C�t��������ŁA�댯�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ����X�ɂ킩�点�Ă�����@�ȂƂ��B
���������AA Shadow Falls (Nick Brandt)�Ƃ����A�t���J�̖쐶������]�����g�킸�ɎB�����ʐ^�W�������ł����A�܂��ɓ鉻�@���g�����悤�ŁA�����ɂ͎��̋L�ڂ�����܂��B
�gNinety-nine percent of the time, I�fm just waiting.�h
���������Ȏ��ɂ�ƂĂ������I
�����ԍ��F19275501
![]() 3�_
3�_
�ŋ߁A�P���g������i�A�b�v��PC�̃o�b�N�O���E���h�Ɏʐ^���̗p���ꂽ�L���ȕ��j�̃u���O��ǂ�ł܂��B�����Œm�����Ռ��̎����I
RAW�ŎB�����ʐ^�́AJPEG�ɕϊ�����i�K�ŁAAdobeRGB�ɂ�sRGB�ɂ��w��ł���A�܂�RAW�ɂ͐F��ԂƂ����T�O�͂Ȃ��Ɨ������Ă���܂������A���͂����ł͂Ȃ��IRAW�ɂ��F��Ԃ͓K�p����AsRGB�ŎB����RAW��sRGB�ȏ�̐F����JPEG�ɏo�͂ł��Ȃ��I
���̎����Ă�u�}���f�W�^�����̂����݁v�Ƃ����{�ɂ́uRAW�ɂ͐F��Ԃ��w�肳��܂���v�Ə����Ă������̂ŁA�����v������ł����̂ł����A���������usRGB�ŎB����RAW�v�Ƃ�����������������x�e�����̕��͌��\���āA�C�ɂ͂Ȃ��Ă���ł���ˁB
��{�́u���v�̘b�炵���ł��B�V�����c
�����ԍ��F19276091
![]() 4�_
4�_
����A�P���g���Ύ�������Ă���B
�����ԍ��F19277111
![]() 3�_
3�_
�P���g������ɂ��u��Ȃ킯�ˁ[�v�Ƃ��u���[�J�[�ɂ���ĈႤ���v�Ƃ����_���E�������悤�ŁA�����ӔC��������ꂽ�̂��A�Q�僁�[�J�[�ɑf���𖾂����āi����l���j�����ȉ��˗����������ȁB������Ƒ҂��āA�������[�J�[�ɂ���ĈႤ�Ƃ�����A�j�R���A�L���m���͕�����Ƃ��āA�I�����p�X�͂ǂ��Ȃ�̂�H�ƌ����Ă����̊ᒆ�ɂ͖��������Ȃ̂ŁA�I�����p�X�̃T�|�Z���Ƀ��[���Ɖ���Ƃ��܂����B
�ł�����S�R��{�́u���v����Ȃ������BRAW��JPEG�ƈ���āu�ƊE�W���d�l�v���Ȃ��݂����Łi������\�t�g���ʂɑΉ�����̂��ˁj���[�J�[���u�������Ă܂��v�ƌ�������O���ɂ�킩���Ƃ������Ƃ݂����ł��ˁB
�����ԍ��F19278369
![]() 3�_
3�_
�I�����p�X����������B
sRGB�ŋL�^����RAW�́AJPEG���l��sRGB�͈͓̔��ŋL�^����邻�����B
OLYMPUS Viewer3��RAW�t�@�C���̃v���p�e�B������ƑI�������F��Ԃ��m�F�ł���B
���Ȃ��Ƃ��I�����p�X�ɂ��ẮA�P���g������̌����Ă����ʂ�Ƃ������ƂɂȂ�B
�킩�邱�Ƃ͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B
�낭�Ɋm�F�����Ȃ��ʼn��i�R���ɏ������ޘA���̑��݁B
����킩���Ă������A�ނ�ɂ͂Ƃ��Ă̓z���g�͓��e�Ȃǂ������Ă����̂��B
���������̒��r���[�Ȓm�����Ђ��炩�������A�N���{�N�ɍ\���Ă�`�A���Ēm�邩�I
�����ԍ��F19279040
![]() 5�_
5�_
�E�`�̐E��ɂ̓f�W�J��������������̂����A�I�����p�X�̂������ɈÂ߂Ɏʂ�B
�ʐ^���̒��������́u�I���ɂ͂��������������R�v�ƌ����Ă����A�t�B�������C�N���Ă��ƂȂ̂��B
E-M1���A��6000�ŎB���Ă����Ɣ�ׂĈÂ߂Œn���Ȏʂ�Ɋ�����B
�����Ƃ��A���ʎ��I�Ƃ����̂��s���R�ɂ͎v���܂��B
�����ԍ��F19284555
![]() 5�_
5�_
�͌��ŃJ���Z�~�ɏo������B
�ނ�̑��̋߂��������낤���B
�ł��邾���߂��ŎB�肽���Ƃ͎v���Ă��邪�A���܂�T���肽���Ƃ����C���Ȃ��B
�S�D�����I���͔ނ�̐����ɉe����^�������Ȃ��̂��B
��э��݂��B�邽�߂̉a�����̂���|�C���g�Ȃ�Ď���ł��s���낤�B
�i�ł��z���g�ɐS�D�������c�͎����ł͌���낤�ȁc�j
�����ԍ��F19285615
![]() 4�_
4�_
��������ӁA�I�����p�X�Ɏ��̂Ƃ���₢���킹�A��قlj��������B
------------ ��������A���q�l��肢�����������[�� ------------
�M�ЃJ�����ɂ�����RAW�ɂ��āA���f�����܂��B
RAW�ɂ́A�J�����̃C���[�W�Z���T����o�͂��ꂽ�A�ʐ^�̍ޗ��ƂȂ�f�[�^�ƁA�B�e���ɃJ�����{�̂̐ݒ肪�ǂ̂悤�Ȑݒ�ł������̂��Ƃ����f�[�^�����ꂼ����߂��Ă���Ǝv���܂��B
���āA�B�e���ɃJ�����{�̂̐F��Ԑݒ肪�Ⴆ��sRGB�ł������ꍇ�A�C���[�W�Z���T�o�̓f�[�^�����ɑ��āAsRGB�ݒ�Ɋ�Â������炩�̉��H���J�������ōs���A���̌��RAW�L�^�����̂ł��傤���B
���̏ꍇ�A�ǂ̂悤�Ȏd�g�݂ŁA���̂悤�ȃf�[�^�ɉ��H���Ă���̂ł��傤���B
RAW�́A�������Ȃ���A�F���m�肵�Ȃ��͂��ł��B
����āA�����O�̒i�K�ŁA������sRGB�̐F����Ɏ��܂�悤�ɃC���[�W�Z���T�o�̓f�[�^���������H���邱�Ƃ͖����Ȃ悤�Ɏv����̂ł����B
����Ƃ��A�C���[�W�Z���T�o�̓f�[�^�����ɑ��ẮA�J�������ł͐F��Ԑݒ�f������悤�ȉ��H�͍s��ꂸ�A�M�Џ���RAW�����\�t�g�Ō�������������ۂɁA�J�����{�̂̐F��Ԑݒ肪���f���ꂽ�����ƂȂ�̂ł��傤���B
�M�Џ���RAW�����\�t�g�ł́A�������A�J�����{�̂̐F��Ԑݒ�ɍS�����ꂸ�A�J���[�ݒ�Ƃ������ڂŁmsRGB�n�^�mAdobe RGB�n�^�mProPhoto RGB�n����I���ł���悤�ɂȂ��Ă���͂��ł��B
����1�y��2�ɂ��āA�����̏�œ���̌��ʂƂȂ�͂����ƍl���Ă��܂����A�������ł��傤��?
1�@�J�����̐F��Ԑݒ��sRGB�Ƃ���RAW���ARAW��������AdobeRGB�Ƃ����ꍇ
2�@�J�����̐F��Ԑݒ��AdobeRGB�Ƃ���RAW���ARAW��������AdobeRGB�Ƃ����ꍇ
------------ �����܂ŁA���q�l��肢�����������[�� ------------
�I�����p�X����̉v�|
RAW�́A�������邱�Ƃɂ���ĐF��m�肳���B
��������܂ł́A�J�����̐ݒ�Ɋ�Â������H�͂���Ȃ��B
����āA�����1�y��2�̃P�[�X�ɂ��ẮA��������AdobeRGB�ݒ肪���f����A�ǂ��������̌��ʂƂȂ�B
�����ԍ��F19287561
![]() 5�_
5�_
�����݂����ƂɃI�����p�X�ɍēx���������A�����݂Ɠ��l�̉��������B
�T�|�Z�����ׂ����l�߂���������Ȃ��ƓK���ɉ���Ƃ������Ƃ𗝉������B
���̌��t���߂����_�͎ӂ�B
�����ԍ��F19290498
![]() 2�_
2�_
RAW�摜�Ɋւ���l�b�g����ǂ�ł݂����ARAW�f�[�^��R�AG�AB���ꂼ��̃t�H�g�_�C�I�[�h�ɂ�����K���l�̏W���ł���A�e��f�̐F�ƊK�������Z�œ����o���O�̏�Ԃł��邱�Ƃ��l����ƁA�F��Ԃ��K�肷�邱�Ƃ�����Ƃ������A���̒i�K�ł킴�킴�l����Ӗ����Ȃ��悤�Ɏv����B
�����A��������Ɖ��̂��߂�RAW�̐F��Ԃ̎w����s�����j���[������̂��Ƃ����̂��^��ɂȂ�B���̓_���T�|�Z���ɖ₢���킹��ƁA�\�ߎw�肵�Ă������ƂŌ������ɉ��߂ĕҏW���邱�ƂȂ�JPEG�ɔ��f�����Ƃ̉������B�f�t�H���g�l�̂悤�Ȃ��̂ł��ˁB�l���Ă݂�f�t�H���g�l���Ȃ��ƁA�����ȑO�Ɍ����\�t�g�ŕ\�������悤���Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��ȁB
�����ԍ��F19293518
![]() 1�_
1�_
��Captain Caribe����
>RAW�摜�Ɋւ���l�b�g����ǂ�ł݂����ARAW�f�[�^��R�AG�AB���ꂼ��̃t�H�g�_�C�I�[�h�ɂ�����K���l�̏W���ł���A�e��f�̐F�ƊK�������Z�œ����o���O�̏�Ԃł��邱�Ƃ��l����ƁA�F��Ԃ��K�肷�邱�Ƃ�����Ƃ������A���̒i�K�ł킴�킴�l����Ӗ����Ȃ��悤�Ɏv����B
���̂Ƃ��肾�Ǝv���B
�Ȃ��A���̃X���b�h����A�j�R���A�\�j�[�A�L���m���̉��m�F�ł���B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000789764/SortID=19167596/#19275522
������̉��A���R�����A�I�����p�X�Ɩ{���I�ɓ����B
http://blog.goo.ne.jp/chimaki-1014/e/ff02bc9a4f9e96ae4d636016c912477e
�P���g���Ύ��́u�������͓��R�̎��v�Əq�ׂĂ��邪�A���߂��瓖�R�̂��Ƃ��Ǝv���Ă����̂Ȃ�A�p���������Ƃ͂Ȃ��������낤�B
���́A�폜���ĂȂ��������ƂƂ���C�Ȃ̂��낤���A����Ƃ��e�Ђ̉���ɁA���߂Đ������m�����u���O�ɏ����L�߂悤�Ƃ���̂��낤���B
�Ȃ��A���̃J���[�}�l�[�W�����g�֘A�̋L����ǂނƁA��{�l�͌䎩���̒m���Ɏ��M���X�ȗl�q�����A�Ƃ���ǂ�������ɉ������B
�Ƃ���ŁACaptain Caribe�����AdobeRGB�ɑΉ������m�[�g�p�\�R�����䗘�p�Ƃ̂��Ƃ����A�����悯��A���̃m�[�g�p�\�R���̃��[�J�[�y�ь^�ԁAWindows�R���g���[���p�l���́u�F�̊Ǘ��v�Ńf�B�X�v���C�Ɋ���Ƃ��Ċ֘A�t����ꂽ�v���t�@�C�����������Ă��������Ȃ����낤���B
�����ԍ��F19294706
![]() 1�_
1�_
��DHMO����
�P���g���Ύ������Ɠ��l�Ɏ��ӏ��ɗ���A���[�J�[�̑����S���̒m�����x���𗝉����Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�ނ��匩���������������J�b�R�����v�����Ă���B
�p�\�R����MacBook�i12-inch�AEarly 2015�j
�f�B�X�v���C�v���t�@�C���̃f�t�H���g�́u�J���[LCD�v
�v���t�@�C����ς��Ă����Ɣw�i�̐F�����ς��̂ŁA����ׂĂ݂����A�J���[LCD��sRGB�Ɠ����ݒ�Ɏv����B
�����D�ɗ����Ȃ��_������BRAW�t�@�C������MacBook�̎ʐ^�\�t�g���g�p���āAAdobeRGB��sRGB���ꂼ��Ō�������JPEG���쐬���A�v���r���[�Ō���ׂ�Ɠ���̐F���Ɏv����B�f�B�X�v���C�̃v���t�@�C����ς���Ɨ����Ƃ������悤�ɕω�����B��蒲�ג��B
�����ԍ��F19296276
![]() 3�_
3�_
RAW�̍����A�ʂ������Ă݂܂������A30���͌y�������܂��B���̌�̏������݂Ɏ��Ԃ�������̂͂��傤���Ȃ��Ƃ��āA�S��RAW�ŎB�邱�Ƃɂ��܂����B�����B�鎞�͑��A��l�̑Ή��Ȃ̂ŁA�掿��������ōs�����߂ɂ́ARAW�ŎB���Ă������������������L���肻���ł��B
�J���Z�~���ĒT���Ă鎞�͂ǂ��ɂ����Ȃ��̂ɁA����������Ăăt�g�C�t���Ɩڂ̑O�ɂ����肷���ł���ˁc
�����ԍ��F19296723
![]() 3�_
3�_
�O�͊��Z315mm�Œ����B���Ă����̂ŁA���Z600mm�̈З͂��g�ɟ��݂܂��B
���i�A����ʼn����ɂ���A���邢�͔��ł��钹�������������āA���܂��ۂɂ͎c��Ȃ��B
�]���E�����ŎB���Ă݂ď��߂āA����Ȋ炵�ĂA����Ȕ�ѕ�����Ƃ킩��B
�����ł��f��ł��A���̈�ԍD���ȃp�^�[���́A����̒��̔���퐫�ł��B
���i�Ɖ����ς��Ȃ����킪������T����A�v�������Ȃ�����킪���������c
�����B�邱�Ƃ́A����ɒʂ�����̂������܂��B
�����ԍ��F19298374
![]() 3�_
3�_
JPEG�B���ďo���̍ו����g�債�Ă����ƁA����܂���Ɍ����Ă��܂��B����ł��@��ɂ���āA����قǂł��Ȃ��@��ƋC�ɂȂ�@�킪����܂��B�O�Ɏg���Ă�����6000�͂����ł��Ȃ�������ł����AE-M1�͂�����Ƃ܂��炪�L�c�C�����ł��B���R�ƃZ���T�[���\�̍����Ȃ��ƍl���Ă��܂����B�Ƃ��낪�ARAW�ŎB��n�߂Ă킩������ł����APC�Ō�������Ƃ��܂�C�ɂȂ�Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A����͌����\�t�g�̍��ƍl�����܂��B���ɂƂ��Ă͖ڂ���ł����B
�����ԍ��F19298465
![]() 4�_
4�_
�a�c���ꂳ��̎ʐ^�W����
�������������c
�u�I�}�G������������ƃ}�V�Ȏʐ^�B���Ă��瓊�e����v
�z���g�����ł���
�����ԍ��F19298477
![]() 3�_
3�_
��Captain Caribe����
���g����MacBook�i12-inch�AEarly 2015�j�́AAdobeRGB�Ή��ł͂Ȃ��A�ق�sRGB�ɋ߂��F��܂ł����\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��͂��B
http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/apple-macbook-12-inch-retina-display-2015
>�J���[LCD��sRGB�Ɠ����ݒ�Ɏv����B
���S�ɓ����ł͂Ȃ��A�قړ����Ǝv����B
>RAW�t�@�C������MacBook�̎ʐ^�\�t�g���g�p���āAAdobeRGB��sRGB���ꂼ��Ō�������JPEG���쐬���A�v���r���[�Ō���ׂ�Ɠ���̐F���Ɏv����B
http://pc.usy.jp/wiki/250.html#yf98046d
�uWindows���ɂ�����U2410�̂悤�ȍL�F�惂�j�^���g���ꍇ�̗��ӓ_�v��ǂ�łق����B
AdobeRGB��JPEG�摜���ŁA�f�B�X�v���C�̐F����̐F�̕����ɂ��ẮAMac��ColorSync�ɂ��A�قړ����F�ɕϊ�����āA�\�������B
AdobeRGB��JPEG�摜���ŁA�f�B�X�v���C�̐F��O�̐F�̕����ɂ��ẮA�قړ����F�͕\���s�\�B
Mac��ColorSync�ɂ��A�f�B�X�v���C�̐F����́A�ł��邾���߂��F�ɕϊ�����āA�\�������B
�f�B�X�v���C�̐F�悪sRGB�ɋ߂��̂ŁAAdobeRGB��JPEG�摜��sRGB��JPEG�摜�Ƃ��A�قړ���̕\���ƂȂ�B
�f�B�X�v���C�̐F�悪AdobeRGB�ɋ߂���AAdobeRGB��JPEG�摜��sRGB��JPEG�摜�ƂŁA������F�̕������o�Ă���B
�Ⴆ�A���̃X���b�h�̎ʐ^��50%�O���[�œh��Ԃ��ꂽ�����̕\��������Ă���B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18083031/#18131678
�����ԍ��F19304148
![]() 1�_
1�_
���炭�C�s�̗��ɏo�悤�Ǝv���Ă����̂����B�B
��DHMO����
�����g����MacBook�i12-inch�AEarly 2015�j�́AAdobeRGB�Ή��ł͂Ȃ��A�ق�sRGB�ɋ߂��F��܂ł����\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��͂��B
sRGB�F���101.8%��\���ł���Ƃ���܂��ˁi�Ƃ���������Ȑ������ł���j 13-inch��MacBook Air�ł͂�������63%���ƁB�Ƃ������Ƃ́A���������v���t�@�C����p�ӂ��Ă��Ă��A���̃f�B�X�v���C�ŕ\���ł���Ƃ͌����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �A�b�v���߁`�A�i���Ă��i�Ƃ����b�ł͂Ȃ��̃l�j
�����S�ɓ����ł͂Ȃ��A�قړ����Ǝv����B
�J���[LCD�Ƃ����̂́APC�f�B�X�v���C�̓����f���Ď����������ꂽ�v���t�@�C���Ȃ�ł��ˁBLab�v���b�g������ƁA�J���[LCD�̐F���sRGB����L�����AAdobeRGB���͂�͂肩�Ȃ菬�����Ȃ��Ă��܂��B
���Ⴆ�A���̃X���b�h�̎ʐ^��50%�O���[�œh��Ԃ��ꂽ�����̕\��������Ă���B
���̕������Ƃ������AAdobeRGB�ɂ���ƑS�̂̕\���������ފ����ł��B�����炪�t�@�C���{���̐F�Ȃ��ǁA�\��������Ȃ��̂ł�������������̂ł����ˁB�����摜���v���t�@�C����ς��Č���ΈႢ�������Ă��ARGB�̈قȂ�摜���v���t�@�C���Ō������͈Ⴂ�������Ȃ��Ƃ����̂́AColorSync���������Ă��邩��Ƃ������Ƃł��ˁB��̂Q�摜�͎���PC�ł͓����Ɍ����܂��B
����PC�ł�AdobeRGB��\���ł��Ȃ����Ƃ��킩�����킯�ł����A�l�b�g��������ƁA�E�B���h�E�Y���e�������߂�����}�b�N���f�U�C����������Ŏg��ꑱ�����̂́A����ColorSync�Ƃ������͂ȃJ���[�}�l�W�����g�V�X�e�������������炾�ȂǁA�Ȃ��Ȃ��ʔ����T�������܂����B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F19305763
![]() 2�_
2�_
�摜���A�b�v���Ă݂�ƁA�ԈႢ�ɋC�t���܂����B
�i��j��̂Q�摜�͎���PC�ł͓����Ɍ����܂��B
�i���j��̂Q�摜�̌��摜�͎���PC�ł͓����Ɍ����܂����B�A�b�v��Ɍ����AdobeRGB�̕��͂�����Ō����܂��B
�����ԍ��F19305821
![]() 1�_
1�_
�u�Ⴆ�A���̃X���b�h�̎ʐ^��50%�O���[�œh��Ԃ��ꂽ�����̕\��������Ă���B�v�Ƃ����̂́A���̂悤�Șb�B
ColorSync���K�ɓ����Ă���Ƃ��āAAdobeRGB�̎ʐ^�f�[�^��AdobeRGB�̐F��ɋ߂��F��̃f�B�X�v���C�ɕ\�������ꍇ�ƁAAdobeRGB�̎ʐ^�f�[�^��sRGB�̐F��ɋ߂��F��̃f�B�X�v���C�ɕ\�������ꍇ�Ƃ�����ׂ�B
50%�O���[�œh��Ԃ���Ȃ������́A�قړ����F���\�������B
50%�O���[�œh��Ԃ��ꂽ�����ɂ��ẮAAdobeRGB�̐F��ɋ߂��F��̃f�B�X�v���C�̕��́A�f�[�^�{���̑N�₩�ȐF���\�������B
�������AsRGB�̐F��ɋ߂��F��̃f�B�X�v���C�̕��́A�f�[�^�{���̑N�₩�ȐF��\�����鐫�\���Ȃ��̂ŁA�f�B�X�v���C�̐F��̒��łȂ�ׂ��߂��F(�f�[�^�{���̐F��肭���F)���\�������B
sRGB�̐F��ɋ߂�MacBook�i12-inch�AEarly 2015�j�̃f�B�X�v���C��AdobeRGB�̃f�B�X�v���C���Ƃ��Đݒ肷��ƁAColorSync������ɓ����Ȃ��B
��ʑS�̂��s���ɂ����F�ƂȂ�B
�ʐ^�f�[�^�̃v���t�@�C�����s�����ƁAColorSync������ɓ����Ȃ��B
���̂��߁A���i.com�f���ɃA�b�v�����摜�́A��ʑS�̂��s���ɂ����F�ƂȂ�B
�����ԍ��F19308212
![]() 1�_
1�_
�����F�ł��v���t�@�C�����Ⴆ��RGB�l���قȂ� |
AdobeRGB�i���j��sRGB�̐F��i�n���`�͐l�̉���ԂŊO���ɍs���قǍʓx�������j |
AdobeRGB�摜��sRGB���Ō���Ɖ��́u������Ō�����v�̂����ׂĂ݂��B
�J���[�}�l�W�����g�̓J���[�v���t�@�C�������ɍs����B�摜�̃v���t�@�C���i�Ⴆ��AdobeRGB�j��RGB�l���o�͐�̃v���t�@�C���i�Ⴆ��sRGB�j��RGB�l�ɕϊ����ĕ\������B�ϊ���F��Ԃ̐F��Ɏ��܂�Ȃ��F������C�F����̋ߎ��F�Œu����������B ���摜�Ƀv���t�@�C�������ߍ��܂�Ă��Ȃ��ꍇ�́A�J���[�}�l�W�����g�͍s��ꂸ�A�摜��RGB�l���o�͐�v���t�@�C����RGB�l�ƌ��ĕ\������B
���̎��ɖ��ƂȂ�̂́ARGB�l�͐F��Ԃ̒��ł̑��Έʒu�ɉ߂����A����RGB�l�ł����Ă��v���t�@�C�����Ⴆ�ΐF���قȂ邱�Ƃ��BAdobeRGB�͐F�悪�L���A��荂�ʓx�̐F���܂ށBAdobeRGB�ɂ�����ʓx85%�n�_�̐F�Ɣ�ׂāA��ʓx��Ԃł���sRGB��85%�n�_�̐F�͍ʓx���Ⴂ�B�]���āA�v���t�@�C���̖��ߍ��܂�Ă��Ȃ�AdobeRGB�摜��sRGB���Ō���ƁA�摜��RGB�l����ʓx��sRGB�v���t�@�C���ŕ\������邱�Ƃɂ��A������Ō����Ă��܂��B
�܂�sRGB���i����PC�j�ɂ����ĉ摜��AdobeRGB�ŕ\��������ƁAAdobeRGB�v���t�@�C���ɕϊ����ꂽRGB�l��sRGB�v���t�@�C���Ō��邱�ƂɂȂ�A�����悤�ɂ�����Ō����Ă��܂��B
���������AAdobeRGB�f�B�X�v���C�����āc
�����ԍ��F19315272
![]() 2�_
2�_
�f�W�^���@����g���Ă��Ă��m��Ƃ��炯�ł��B
E-M1�̎d�l�������RAW��12bit���X���X���k�ƂȂ��Ă܂��B
�r�b�g���ĉ���˂�c�@0��1����2�ʂ��\���f�[�^�̍ŏ��P�ʂł����B12bit����2��12���4,096�ʂ�̏���\���邻���ȁBRAW�f�[�^�̓t�H�g�_�C�I�[�h�ŋL�^���ꂽ�K���l������A4,096�i�K�̉��ԖڂƂ����`�ŋL�^����Ă��邱�ƂɂȂ�B�t�H�g�_�C�I�[�h�͒P�F�Ȃ̂ŁA����ɂ��鑼�̐F�̃t�H�g�_�C�I�[�h�̊K���l���Q�Ƃ��ĐF�����Z����BRGB3�F�S�̂̃o���G�[�V�����Ƃ��ẮA4,096�̂R���687���F�ƂȂ�B����AJPEG�͋K�i��8bit�Ƃ���Ă���A�P�F��256�K���ARGB�S�̂ł͂���3���1,677���F�ƂȂ�B����ς��Œ�������Ȃ�f�[�^�ʂ��傫��RAW����̃X�^�[�g�̕����_��ł��ˁB
���X���X���k�̓f�[�^�������������Ɋ��S�Ɍ��ɖ߂��鈳�k���@�������ł����A�t�@�C���������₷�����邽�߂ɂ́A��͂舳�k�͕K�v�Ƃ������ƂȂ�ł��傤�B
�t���T�C�Y�J������RAW��14bit���嗬�̂悤�ł��B�I�����p�X��14bit���l���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��悤�ł����A�C���^�r���[�ł̓R�X�g�������銄�ɑ傫�ȍ����Ȃ��ȂǂƓ����Ă��܂��B�ł��o�͑��������ׂɂȂ��Ă���Ǝ���ς���Ă����ł��傤���ˁB
�����ԍ��F19320599
![]() 1�_
1�_
687���F�Ƃ�1,677���F�Ƃ��������F���ł����A�l���Ă݂�Ƃ��ꂾ���F���L���Ƃ������A���݂��ׂ����Ƃ��������ł��B�ǂ�ǂ�ׂ��������Ƃ���ŁA�l�Ԃ̎��o���������������̂��Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��ˁB
����͂Ƃ������ARAW�ŎB���Ă����Ό����i�K�Ŕ@���l�ɂ������ł���c���Ǝv������A����Ȃ��Ƃ��Ȃ��ł��ˁB�s���g�͓��R�����ĂȂ��Ƃ����A�I�o���������������Ă��Ȃ��ƁA�����E�Õ��̊K�����c��Ȃ��B�����Y��ʂ��ē����������Z���T�[�ŋL�^�����l�Ȃ̂�����A�l���Ă݂�Γ�����O�̘b�ł����B�ł��f�W�^���̓t�B����������y�Ȃ悤�ł��B�v���̃u���O��ǂ�ł�ƁA�t�B��������͎B�e����ł͏�ɘI�o�v�ŘI�o�𑪂�V�r�A�ɊǗ����Ă������A�f�W�^���ł͌�ŘI�o�����ł���̂ŃA�o�E�g�ɂȂ����A�Ȃ�ď����Ă�l�����܂����B
�����ԍ��F19323994
![]() 1�_
1�_
AdobeRGB��sRGB�Ƃ̐F���r�ɂ��Ă����A�n���`�̕��ʐ}�Ŕ�r�����AMac�̏ꍇ�AColorSync���[�e�B���e�B���g���āA3�����Ŕ�r���邱�Ƃ����E�߂���B
�����ԍ��F19324301
![]() 0�_
0�_
DHMO����͎ʐ^�͎B���Ȃ���ł����H
���͍ŋ߂܂Ŏʐ^�����������Ȃ��߂����Ă�����ł����c�ǂ����Ă����Ȃ�����������B
�u�w�I�����p�X�E�y���x�̒���v�i�ĒJ���v�j��ʔ����ǂ݂܂����B��q�b�g�ƂȂ����y���̂悤�Ɉꎞ����悷��悤�Ȃ��̂́A�ĒJ���̂悤�Ȑl�ƈႤ���Ƃ���肽����A�������Ë����Ȃ��l�����Ȃ��Əo�Ă��Ȃ��ł��ˁB�A�b�v���̃X�e�B�[�u�E�W���u�Y�݂����ł��B
�����ԍ��F19326362
![]() 3�_
3�_
�{�����Y���ǂ��ȂƎv�����Ƃ̈�́A�p�[�v���t�����W���C�ɂȂ�P�[�X���قƂ�ǂȂ����Ƃł��B�O�Ɏg���Ă������{���R���f�W��\�j�[��SEL55210�ł́A��w�i�Œ����B��ƃt�����W����������P�[�X�������A����Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A�{�����Y�͐v�̊���Ⴄ�ƍl������܂���B
�p�[�v���t�����W�̓f�W�^�����L�̌��ۂŁA�����Y�̐F�����������������ł��B�i�t�B�����͂�����x���݂����邽�߁A�≖���q���O�����I�ɕ��z���ĐF�������z�����Ă����炵���B�jED�����Y�Ƃ����A�F�ɂ����ܗ��̕ω������Ȃ��f�ށi����ᕪ�U�K���X�j���g�p���ĐF������}����v�͍L���s���Ă���悤�ŁA���̎g���Ă������{���R���f�W��SEL55210�ɂ��̗p����Ă��܂����B�{�����Y��ED�����Y�ɉ����ăX�[�p�[ED�����Y����������Ă��܂����AM.ZUIKO DIGITAL�ł��ꂪ�̗p����Ă���̂́A�{�����Y�ȊO�ł�M.ZUIKO PRO�����Y�݂̂ł��B
�X�[�p�[ED�����Y�͂��u�ɋ߂����w�������������Y�Ƃ̂��ƁB�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃T�C�g�Ɏ���F�����̔����ʂ̃O���t������܂����A�F���ł̒ጸ���ʂ��傫���A�ʏ탌���Y�ɔ�ׂ�ED�����Y�͔����A�X�[�p�[ED�����Y�͍X�ɂ��̔����A�ƂȂ��Ă��܂��B�{�����Y�����y�����Y�̊��ɃR�X�g��������������_�̈�Ȃ̂ł́B
�����ԍ��F19335462
![]() 5�_
5�_
�����Y�̊�b����̖{��ǂ�łāA�����Ă݂�Γ�����O�Ȃ̂����A���ɈӊO�Ɋ����Ă��܂������Ƃ��������B����́A�����Y�Ƃ����̂͂ǂ��v���悤���A�������[���ɂ͂ł��Ȃ��Ƃ������ƁB�p�[�v���t�����W�ɂ��Ă��A�����Ȃ��̂̓t�����W�Ƃ͊�����ꂸ�A�𑜊��̒��܂�̖����Ƃ��Ċ���������x�ȂƂ��B�����Y���g���Ďʐ^���B��ȏ�A�����Y�����Ƃ͕t�������Ă����˂Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
���������̎ʐ^���C�}�C�`�Ȃ̂͂��������������������̂��[
�u���≺��Ȃ�������v
�����ԍ��F19338625
![]() 4�_
4�_
���N�ɂ͔������ꂻ���ȃI�����p�X�̃T�������B�N�����Ƀv���[���g���Ă����Ύg���Ă݂����̂ł����B�C�ɂȂ�̂́A���������]���P�œ_���Ďg������͂ǂ��Ȃ�ł��傤�B�Y�[�������Y�ł����ۂɒ����B��̂͂قƂ�ǖ]���[�Ȃ�ł����A�������ƍL�p���ɖ߂��ĒT���Ƃ����̂��悭���܂��B���{���R���f�W�Ȃd���Y�[���ɃY�[���A�E�g�{�^�����t���ĂāA�ꎞ�I�ɍL�p���ɖ߂��̂ɕ֗��ł����B�i�{�^�������𗣂��Ƃ܂��]�����ɖ߂��Ă����̂ł��B�j����̖��Ȃ�ł��傤���B
��������������Əd����1.5kg���x�̂悤�ł��B�j�R���̃T�������̔{�̏d���ł����A�ʑ��t���l���Ȃ��g��Ȃ��I�[�\�h�b�N�X�ȑ���Ƃ݂��܂��B�{�����Y�̉����Ő��Z���Ă݂�ƁA��͂�T�������͂��������̏d���ɂ͂Ȃ肻���ł��ˁB
�{�����Y�̖]���[�œ_����300mm÷F6.7=�����Y�L���a44.8mm
�T�������ɂ����300mm÷F4=75mm�i44.8��1.7�{�j
�d�ʂ��L���a�̎���ɔ�Ⴗ��Ɖ��肷���1.7×1.7=2.9�{
�{�����Y�d��423g×2.9=1,227g
�����ԍ��F19341528
![]() 4�_
4�_
�ȑO�������쒹�B�e�̎w��{�Ƃ��̊Ԕ������a�c���ꂳ��̎ʐ^�W���A�����悤�ɒ����B���Ă��Ă����܂�Ɉ�ۂ��Ⴄ�̂Ŗʔ��������B�w��{�͍����@�ނ��g���A�ǂ̂悤�ȍ\�}�ŎB������ǂ����J�ɉ�����Ă����B�f�ڂ��ꂽ�ʐ^�͑f���炵���ʂ�̂��̂���B�Ƃ��낪�ł��ˁc���ꂪ�S�R�ʔ����Ȃ��̂ł��B�u�����牽�H�v�Ǝv���Ă��܂��܂��B�a�c����̎ʐ^�́A�����������璹�ƗV��ł����A�Ƃ���������Ă�悤�ɁA���Ƃ̌�������������ʐ^�ł��B����ς蒹���u���m�v�Ƃ��ĎB�邩�A����Ƃ��u�R�g�v�Ƃ��ĎB�邩�̍�����Ȃ��̂��ȁB
�����ԍ��F19344548
![]() 4�_
4�_
����ƊE�l�̃u���O��ǂ�ł���ƁA�t�B�����ƃf�W�^���̑傫�ȈႢ�́A�ǂ��܂ň����L���邩�̊���A�t�B�����ł̓t�H�[�}�b�g�̑傫���������̂ɔ�ׁA�f�W�^���ł͉�f���ɕς�������Ƃ��ƌ����B�t�B��������͑傫�������L�����L���ʐ^�͒����ŎB��̂����ʂŁA�t�H�[�}�b�g�����������C�J���ŎB��Ɩ��炩�Ɍ���肵�������ȁB�f�W�^���ł�������f���ł���t�H�[�}�b�g�̑傫�������掿�͗ǂ��̂����A�t�B����������̍��͂Ȃ��A�����Y�̐��\���⒚�J�ȎB�e�E�����Ƃ������\�t�g�ʂ̉e���̕����傫���̂ł͂Ȃ����Ƃ̂��Ƃ������B
��������APS-C�܂ł��r�����b�̂悤�ł����A�C���[�W�Z���T�[�̐��\���傫�����サ�A�t�H�[�}�b�g�̏��������̂ł��t�B�����𗽉킵���Ƃ����������炫�Ă���Ǝv���܂��B�����A�l�Ԃ̖Ԗ��̕���\��300ppi�O��ƌ��x�����邻���Ȃ̂ŁA�����ꂻ���炩��u���[�L��������̂����m��܂���B
�����ԍ��F19353827
![]() 4�_
4�_
�t�H�[�}�b�g�̑傫���ɂ��掿�����Ă��������ǂ����痈���ł��傤���B
�t�B�����̏ꍇ�A�������\����l���Ɖ��肷��ƁA�t�H�[�}�b�g�̑傫���ɂ��掿���͊g�嗦�̍��ɂ�錩�����̖�肾�ƍl�����܂��B����A�C���[�W�Z���T�[�̏ꍇ�́A��f���������ł���A�g�嗦�̍��͐����Ȃ��̂ŁA�X�̉�f�i�t�H�g�_�C�I�[�h�j�̊��x�����e�����邱�ƂɂȂ�܂��B�t�H�g�_�C�I�[�h�̊��x�͏Ɠx�ɔ�Ⴗ��̂ŁA�����x�̐��\�ł��t�H�[�}�b�g�̏��������̂͌X�̃_�C�I�[�h�̊J���ʐς��������Ȃ�A���ʂ����Ȃ��Ȃ镪�������x���Ⴍ�Ȃ�ƍl�����܂��B���ɒ�Ɠx���ł̓m�C�Y�̉e���Ŋ��x���������ቺ���邽�߁A���x�����傫���g�傷��悤�ł��B�i�o���I�ɂ��Ⴆ�R���f�W�̍����x�掿�̓K�b�N���Ɨ������ފ����ł��B�j����ł��t�B�����̖ʐύ��قǂłȂ��̂́A�l�Ԃ̖ڂ��ăf�W�^���̍���f���ɔ��������ɐS�D���邩��Ȃ�ł͂Ȃ����Ǝv�����肵�Ă܂��B
�����ԍ��F19356346
![]() 3�_
3�_
���������Ύ���MacBook��Retina�f�B�X�v���C�������BRetina�͉p��ŖԖ��Ƃ̂��ƁB�Ƃ������Ƃ́A���̃f�B�X�v���C�͖Ԗ��̕���\300ppi��B�����Ă���Ƃ������Ƃ��B���ȃA�b�v���B����H�v�Z�l��226ppi�ɂȂ��Ƃ邼�I�A�b�v���߁`�A���x�����i���Ă��A�Ǝv�������A�p�������O��300ppi�������������ׂĂ݂��B
�����iPhone4��326ppi�Ɣ��\�����ۂɁA�X�e�B�[�u�E�W���u�X���u30cm��̃f�B�X�v���C������Ƃ��v�̕���\�Ƃ��Č��������ƂȂ̂ˁB�m�[�gPC���ƃX�}�z��藣��Č��邩��A226ppi�ł��\���Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B����12�C���`�f�B�X�v���C�̉𑜓x��3�S����f�B�l�Ԃ̌��E���Ă���Ȃ���Ȃc�@40�C���`��4K�e���r�i110ppi�j��8�S����f�A��8K�e���r�i220ppi�j��32�S����f�ɂȂ邪�A��ʂ��傫���Ȃ�Η���Č��邾�낤���A������������f���ăz���g�ɗv���ł����ˁc
�����ԍ��F19358830
![]() 3�_
3�_
����f�ɂȂ�Ή�f�s�b�`���������Ȃ��ăt�H�g�_�C�I�[�h�̊��x��������A�����x�Ɏキ�Ȃ锤�B�e�Ђ̋@��ɂ��āA��f�s�b�`�ƍ����x���\�i�����ł�DxOMark��Low-Light ISO���g�p�j�̑��֊W���v���b�g���Ă݂܂����B
�꒼����ɕ��Ԃ̂��Ǝv������A��7R�U�̂悤�ȍŋ߂̍���f�@�͍����x���\�����ɍ����B��7R�U�ō̗p���ꂽ���ʏƎˌ^�Z���T�[�͑��������\�̂悤�ł��BGX8�������ł����A�����x���m�ۂł���ƂȂ�ƁA����f���̗���͑��������ł��ˁB
�����ԍ��F19360440
![]() 3�_
3�_
�t���T�C�Y�̍����@�ɔ�ׂ���y���ɒႢ�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Z���T�[�̍����x���\�ɁA�{�����Y�̈Â�F�l�̑g�ݍ��킹�B�u�ǂ������B��Ɍ����Ƃ�˂�I�v�Ƃ��������M���A�O�r�h�Ȃ炢���m�炸�A�Z���T�[�傫����͂���Ȏ�y�Ɏ��������܂����B����ō����x�����Ă��������B��܂����B���͍��{���R���f�W���g���Ă܂������A����ɔ�ׂ��V���̂悤�Ȃ���ł��B����ɃR���f�W�ł������x�͕K���h��G���ƌ�������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A��u����}���ăL�b�`���B���ΈӊO�ɃL���C�Ȃ�ł��B�܂����̃A�b�v�����ʐ^�ŕ������Ē����邩�ƁB�u�ʐ^�������猾���Ƃ��{�P�I�v�X�C�}�Z���A�X�C�}�Z���c
�����ԍ��F19364788
![]() 4�_
4�_
�����̎ʐ^���Ȃ��Ȃ��s���b�Ƃ��Ȃ��̂́A��͂��u���Ȃ낤�Ǝv���Ă���܂��B���܁`�Ƀs�V���Ɨ���̂�����Ƃ������Ƃ́A�t�Ɍ����قƂ�ǂ͔����Ƀu���Ă�낤�ȂƁB���H�T����u��������邾�낤�A�ł����H��k����˂��U�߁A�������̎�u���Ɨ������ɂ�T����u����Ȃ��s������邵�����˂��B�����A�ʂ��Ă݂˂��e�R�}�ʂ��Ă钹�̈ʒu���o���o���ł����B��Z�u��������ł��v�Ɩ��t���܂������ˁc
�����ԍ��F19367792
![]() 6�_
6�_
�p�i�\�j�b�N���J�����\���Ă���400mm�Y�[�����ǂ������ł��ˁB
�]���[���Â������̕��R���p�N�g�ȑ���ʼn��Ƃ��莝���ł������B
�������Ƃ��Ă͖{�����Y�Ǝ��Ă���ƌ����܂��B
�{�����Y����ɏd����P�����Z���Ă݂��
�{�����Y�]���[�œ_����300mm÷F�l6.7=�����Y�L���a44.8mm
�p�i�Y�[������400mm÷F�l6.3=63.5mm�i44.8mm��1.4�{�j
�d�ʂ��L���a�̎���ɔ�Ⴗ��Ɖ��肷���1.4×1.4=2.0�{
�{�����Y�d��423g×2.0=846g
�����A����Ȃ�I�����p�X�̃T��������肮���ƌy�ʂɂȂ肻���ł��B
�����掿�͒P�œ_��藎�����ł��傤�ˁB
�ϔY�͐s���܂���c
�����ԍ��F19370681
![]() 4�_
4�_
�ĒJ���v���́u���t�푈��OM�̒���v�Ƃ����{���ʔ��������B���ɂ��鐻�i�Ɠ����悤�Ȃ��̂����͈̂Ӗ����Ȃ��ƁA�����̑傫���d�����t�̔����̗e�ρE�d�ʂ�ڎw���Đv����̂ł��B�ǂ�������炻��Ȃ��Ƃ��\�Ȃ̂��B�Ⴆ�A�y���^�v���Y���̉��ɂ����ďꏊ������Ă����R���f���T�[�����Y��p���A����Ƀy���^�v���Y���̉����������Y��ɉ��H���đS����������ȂǁB
�ȑO�ǂ{�Ȃ̂����A�u�R�X�g��������Εi�����オ��v�i�O�ؔ��K�j�������悤�Ȗʔ����������B������͔_�@�̐v�Ȃ̂����A���i�_�������邱�Ƃ��ڕW�Ȃ̂��B�����B������ƁA�R�X�g��������Ɠ����ɐ��\���オ��Ƃ����ɉ�����ł����B
���͂��́u�]���̔����ɂ���v�Ƃ��������ȖڕW�ɈӖ�������̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B�u�]���̔����v�ƂȂ�ƊW�ҒN�����A�����Ȏ�i�ł̓_�����A�l������ς��Ȃ��ƃu���C�N�X���[�ł��Ȃ��A�Ƃ����F�������܂�A�p���_�C���V�t�g���N�����Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F19380070
![]() 4�_
4�_
�\�j�[�X���ł́A�t���T�C�Y�~���[���X���o�ꂵ���ȏ�A�掿�Œǂ��t���Ȃ����r���[�ȃZ���T�[�T�C�Y��I��ł��܂����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͏�������^���A�Ɛ邤�l�����܂����B���̓J�����̗p�r���D�݂��l���ꂼ�ꂾ�Ǝv���܂����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃Z���T�[�T�C�Y�͊m���ɒ��r���[�ȋC�����܂��B��̂ǂ�����Č��܂�����ł��傤���B
��`�T�C�g������ƁA�u�l�������ĕ����鍂�掿�v����Ƀ����Y�̃T�C�Y������o�����A�Ɣ��R�Ƃ����\���ɂȂ��Ă��܂��B�ł������Y�v�̑O��ƂȂ�Z���T�[�Ίp�����t���T�C�Y��1/2�B�u�t���T�C�Y�̔����v�Ƃ����̂����͌��ߎ肾������Ȃ��ł��傤���B�I�����p�X�̋������ł���y���̓n�[�t�T�C�Y���������AOM�͏]���̈��t�̔����̃T�C�Y��ڕW�ɊJ�����ꂽ�@�킾�����B�����ڂ̂Ȃ���ǂ���������A�����ď]���̃t�B�����T�C�Y�Ɏ����Ȃ��V�����l������I�B�܂��ߋ��̐����̌��������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19385037
![]() 5�_
5�_
�P�@�W���E�r�^�L���B�������̐ݒ��RAW��������Ƃ���Ȋ����ł����B
�@�B�������ɘI�o����Ă���ǒ�����̊炪�Â��B
�Q�@����Ō������ɘI�o���X�ɖ��邭���Ă݂��B
�@�S�̂����邭�Ȃ����Ⴄ�̂ō��x�͔w�i��ῂ����B
�R�@�Ƃ��낪�V���h�E�̒������ƈÕ������𖾂邭�ł���̂��I
�@�i������o�������I�j
�����A�V���h�E�̎����グ���ƐF�������������Ȃ̂ŁA�F���������グ�Ă܂��B
E-M1�iJPEG�o�́j���ƎB�e���ɃV���h�E�R���g���[�����ł����ł����A������͑҂��ĂĂ���Ȃ��̂�RAW�ŎB���Ď��㒲��������Ǝv���܂����B�܂��m����炯�ł����������ʔ����I
�����ԍ��F19387314
![]() 4�_
4�_
���N�T��c�̊F��Ȃ͕����������ȁ`
�����̓��Y����̓��̏�̏��}���L�閳���ł����`
�o�������^�b�`���ʔ����Ă��c���炵�܂����`
�����ԍ��F19397721
![]() 3�_
3�_
�쒹���B��̂ɏœ_�����̈Ⴂ�͑傫���ł��ˁB
���̌o���͋͂��ł����v���o���Ă݂܂����B
�P�@���{���R���f�W FinePix S1�F���Z1200mm
�@�����������]���͏��߂Ă������̂ŁA�Ⴄ���E��`�����C�����܂����B�쒹�����߂ĎB����ɂ́A���i���荠�Ŏ�y�Ɏ��������Ĉَ����̐��E��̌��o���鍂�{���R���f�W�͂��E�߂ł��B�掿���R���f�W�Ȃ�Ȃ̂ƁAAF���R���g���X�g�Œx���i�ő�0.14�b�j���ߔ��Ă��B��ɂ�����_������܂����B�ӓ_�Ƃ��ẮA�����܂Ŗ]���������ƁA�����ɒ�������ǃA�b�v�ŎB�邩�Ɍ������グ�A�����悤�Ȏʐ^����B��悤�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������Ȃ�����܂��B
�Q�@��6000+SEL55210�F���Z315mm
�@�����́u������]�I�ɉ����Ȃ��Ă��܂����v�ƃK�b�N�����܂������A����͂���ŃA�����Ǝv���悤�ɂȂ�܂����BAF�������i�ő�0.06�b�j�����A�ʂ������āA���Ăł����ߋ������`���R�}�J���������ł��r�V�o�V�B��܂���I�����̒��͒��߂ċ߂���������_���悤�ɂ��āA�ǂ�����Ē�����ɋߕt�������l����悤�ɂȂ�܂����B�܂��AAPS-C�͉掿���ǂ��̂ŁA�����������Ă��\�}�ň�ۓI�ɂ��邱�Ƃ��l���n�߂܂����B����SEL55210�͂��������V���[�v�ɂ��ė~���������B
�R�@E-M1+�{�����Y�F���Z600mm
�@AF�E�A�ʂƂ��Q�Ƒ卷�Ȃ��A����ŎB���͈͂��L���萢�E���L�������Ɗ����܂��B�莝���ŕ������o����������B��X�^�C���̎��ɂ͒��x�ǂ������ł����A���đ��x�������s���͈͂̍L���ҋׂ̏ꍇ�́A���������œ_�������~�����Ȃ�܂��B
�����ԍ��F19400561
![]() 5�_
5�_
�������N���I��肩���c�Ƃ������ƂŁH�{�X���ɓ��e�����ʐ^��20�������I��ŁA�t�H�g�u�b�N������Ă݂܂����B�Q��~���̃\�t�g�J�o�[�ň���i���͌��\�e�������ł������A����ɂ���Ɖ�������炵�������邩��s�v�c�ł��ˁB
���H�u�u�b�N�ɂ���قǂ̎ʐ^���ǂ��ɂ������v�ł����H
�t���I�������ǂ���Ⴛ��ŃG�G��ł��I
�����ԍ��F19404347
![]() 6�_
6�_
����A�摜�t�o�y���݂ɂ��Ă܂��B
�njR���������l�ł��@�@�@�@(�O���O)
�����i����H�j�����������Y���g�p���Ă��܂���
�C�y�Ɏg����ǂ������Y�ł��B(^_-)-��
�t�o�����摜�͂��ׂĎ莝���i�����Ɏ�Ԃꂵ�Ă��܂��j
�p�������Ȃ���O�r�ƌ����������Ă��܂���B
���݁A�l�P�ɃX�e�b�v�A�b�v���l���Ă��邪�Ȃ��Ȃ�
���������������܂�܂���D($�E�E)/~~~
�����ԍ��F19408138
![]() 6�_
6�_
�����������Z�[����������
�J���Z�~��������W��������\��L���ł��ˁB�F���������R�Ŕ������B��͂��ʂ��������ł��ˁ[�B���̃g���~���O���ł͌��E������܂��B
���̓�6000�̃X���ł��Ƒ����Ă܂����B���͂��l����̂��D���Ȃ̂ŗǂ���Ȃ�ł��R�R�B
�O�r���g���Ǝ�U���}���邱�Ƃ��ł��ĉ摜���V���[�v�ɂȂ邻���ł����A���������̂��ז��������ł��B�O�r�͂Q���ւ��܂��������ǂP����g���Ă܂���B�{�f�B�͔��Ă��B�邽�ߑ��ʈʑ���AF�̂���E-M1�ɂ��܂������A���͂ǂ����̂ŁBAF�̒x�����{���R���f�W�ł͎��ɂ͔��Ă͎B��܂���ł������A��肢�l�̓W���X�s���̔��Ă��B���Ă܂����B���̏Ռ��͖Y����܂���B
�Ƃ���Łc�I�����p�X�̃����Y�͂ǂ����{�P���L���C�Ɋ������܂���B�����������Ƃ��ăX�b�L�����Ȃ����������܂��B�{�����Y�����ł͂Ȃ��āA���̃����Y�̍��ł������悤�Ɋ����邱�Ƃ�����܂��B����̓I�����p�X�̃����Y�v���j�̖��ł͂Ȃ��̂��A���𑜂ł��邱�ƂƊW�������Ȃ����ƁA�O����^��Ɏv���Ă��܂����B
����Ȑ܁ACAPA�l�b�g�Ń��[�J�[�e�Ђւ́u�{�P�`�ʁv�Ɋւ���A���P�[�g�L�����B���𑜂ɂ��邽�߂ɂ͋��ʎ�����}���Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�}���߂���ƃ{�P�������Ȃ�Ƃ����W�����}�����邻���ŁA�ǂ��o�����X�����邩�Ɋe�Еv�X�̍�����������悤�ł��B�����ł͊e�Ђ̌X���͂킩��܂��A�I�����p�X�Ɋւ��ẮA�v�w�j���u�J�����獂�𑜁v�ƌ������Ă��邱�Ƃƍ��̈�ۂ��l����ƁA���Ȃ�𑜗D��ɐU��Ă��Ȃ����Ƒz�����Ă��܂��B�i�{�����Y�̑���ۂ��u���������I�v�ł����B�j
�{�P�͎��R�ȕ����D�܂����ł����A���肫����ȕ`�ʂɊ��������Ȃ��̂́A���̓˂��l�߂��𑜂�����������Ƃ��v����ł���ˁB
�����ԍ��F19410623
![]() 4�_
4�_
�����B���Ă���ƁA�U�����Ă���l����u���ꉽ�Ē��H�v�Ɛ����|�����܂��B�u�C�\�V�M�ł��v�u�C�\�V�M�c�Ȃ̖��O���Ǝv���Ƃ�����v�i�I���������I�j�A�u���Ԃ�c�`���E�T�M���ȁv�u�T�M���Ă���Ȃɍ�����Ԃ́H�v�A�u�`���E�Q���{�E�ł��v�u������v�@���������ł������A�t�c�[�̐l�͒��̖��O�Ȃm���ł�����ˁB�Ƃ��������ɊS�̂���l�������������Ȃ��ł��ˁB�E�`�̃J�~����Ɂu���������B������`�v�Ƃ������Ă��u�́H�v�ŋ����I���B�B
�ł��悭�U�����Ă���l�͋M�d�Ȋώ@�҂ŁA�v��ʏ�����炳��鎖������܂��B�u�����̃e�g���|�b�g�悭�J���Z�~���Ƃ܂��Ă��v�u�I�V�h��������̂͂��������̒r����ȁv���ɂ͂���Ȃ̂��B�u���̌����ȁA��p���X���R�C����Łv�u�́H�v�u�N��������������v���̌�A�{���Ƀ��X��ڌ����܂����B�U������ׂ��B�B
�����ԍ��F19418274
![]() 4�_
4�_
�������������ԉ͌��Œ����B���Ă��邤���ɑ啗�ׂ������_�E�����邱�ƂQ��B�������łP���ނ莅�𐂂�Ă���l���_�Ɏv���Ă��܂��B
�c�o���̂悤�ȏ������đ������͎��ɂ͓���ł��BSEL55210�͊��Z315mm�������̂ŁA������x�͒ǂ����̂ł����A���Z600mm�ƂȂ�ƁA���]�����x�Ɍ������Ă��܂��܂��B�]����߂��ƒǂ���̂����A���x�͒��������߂��ĉ𑜂��Ȃ��B�c�o���͊��ɓ�����ċv�����A���̋ꂳ��Y��Ă����̂ł����A�q���A�}�c�o���ɑ������A�Ăтǂ����S�J�I
�I�����p�X�������̏Ə�����o���Ă��邱�Ƃ�m�����̂ŁA�]���[�̂܂܂Œǂ���̂��A��ɓ���Ď����Ă݂����ł��B��������̂�t����͍̂D�݂��Ⴀ��܂��A����͐܂��ݎ��ŃR���p�N�g�B�I�����p�X�炵���ł��B
�����ԍ��F19428343
![]() 3�_
3�_
��Captain Caribe����A����ɂ��́B
�v���U���75-300mm�U��t���ĎB���Ă݂܂����B
�c�O�~�ƃA�J�Q���Ƃ́A���ΖʂŃ`���b�g�������Ă��܂��܂����B
�A�J�Q���̓s���ÂŃC�}�C�`�A�c�O�~�̓}�Y�}�Y�B
�~�\�T�U�C�Ƃ�3��21���ȗ��A2�x�ڂ̂��ΖʁB
�����B�ꂽ�̂ŁA���`���������B
���Ζʂ̃W���E�r�^�L���́AAF�������ăs���Âǂ��납�{�P�{�P�ŗܖڂɁc�B
��A����̃V�W���E�J�����A�����[�Y�x��Ď��s���܂����B
�Z�O���Z�L���C�ƃJ�����q���́A���Ƃ��B��܂����B
2���ԂقǁA75-300mm�U�Œ�����ɖ�����ł��܂����B
�����ԍ��F19430848
![]() 6�_
6�_
��enjyu-k����
�����O�ʂ�H�~�n�Ȋ����̂��ʐ^����B
�~�\�T�U�C�͂��`�u���[�B
���߂ĎB�钹��V�[���͊����������Ď~�߂��܂���ˁB
�����B��ɍs�������̂������ׂ�����ʁB��X�Ƃ��Ă���Ɨ]�v�Ȏ�����l���Ă��܂��܂��c�U�������˂鎄�̎B�e�X�^�C�����ƁA�I�����p�X�̃T���������A�p�i��400mm�Y�[���̕����R���p�N�g�ō����������ȁB��������ƃ{�f�B���p�i�̕����������ǂ��낤���B�ł�GH4�ł�AF�Ǐ]�A�ʂ͕b7�R�}�Ȃ�ˁB�p�i�͂ǂ����đ��ʈʑ��������Ȃ��̂��Ȃ��BE-M1�ŕb9�R�}�A��6000�ŕb11�R�}�AV3�ŕb20�R�}�ŁA���ʈʑ����ɂ͂܂��L�ё゠�肻���B�܂��X�y�b�N�����ׂĂ��Ė�Ȃ��A��6000�ł����ȋ�w�i����AF���A�ʂ��K�b�N���x���Ȃ��Ă����ǁB����͂Ƃ������A�����͂ǂ�����B���z�̕R�����邨�㊯�l����ւ����A�����Ǝ���ϋɓI�Ɏ�`���ȂǁA�单���Ƃ��Ă̐M�p��n���ɐςݏグ�ė�������A���Ƃ��Ȃ邩���m��Ȃ��B�ł����̃����Y�̎�y�Ȋ��ɃL����ʂ���̂Ă�������ˁB�������������c���ĉ��̘b��˂�I
�����ԍ��F19433910
![]() 3�_
3�_
�l�̂��Ȃ��͌��Ŗ쒹�̖������ƁA���X�������^�����Đ����o���Ă݂܂��B
�u�s�s�s�s�c�v���Ă��O�v������J�^�J�i�̐���Ǝ����ɓ˂�����ł܂����B
�ł����������u���Ԃ������v�Ɗ��Ⴂ���Ă���邩���m��܂���B
�����ł́u���������̂������v�Ǝv����̂ł��܂���
�����ԍ��F19436207
![]() 4�_
4�_
�w�]�͔@���ɂ��ĘA�ʐM�k�ƂȂ肵���x
�E��ōu����Ȃ��J�Â������ɁA�u���҂̎ʐ^���B���Ă�����ł����A�\��𑨂���̂�����̂ł��B���e�ɖڂ𗎂Ƃ��Ă��鎞�Ԃ������A���̃X�N���[����U��Ԃ��Ă��鎞�Ԃ������ŁA���X�ڂ��グ�Ē��O������Ƃ����悤�ȃp�^�[���������B�Ō�̕������B�肽����ł����A���̏u�ԂƂ����̂�����B�Ƃ��낪�A����X�^�b�t���A�ʂ��L���Ȃ��Ƃ��B�u���낻�납�ȁv�Ƃ����ӂ�ō����A�ʂ���ƂP���ʂ͖ڂ��グ���V�[���������Ă��܂��B����͎g������Ă�ŘA�ʋ��M�҂ɂȂ�܂����B�������ł��悤���~�܂��Ă��悤���S�ĘA�ʂł��B
�����ԍ��F19443742
![]() 3�_
3�_
AF�̋����͋@��ɂ���ĈႢ�܂��B��6000����E-M1�ɕς������ɂ́A�ǂ�����������Ȃ������ł����B���܂œ�Ȃ��B��Ă�����ʂłȂ��Ȃ����ł��Ȃ��B���Ǝv�����܂ŋ��Ɏv���Ă�����ʂŃX�p�X�p���ł����肷��BAF�Ǐ]�A�ʒ��͍������荇��Ȃ������肷��g������̂����A���̐U�����Ⴄ�B�ł�����V���N�����ė����̂��u����̓C�P���v�Ǝv���V�[���͂�͂�B��Ă�B�v�킸�j���b�Ƃ��܂��B
�����ԍ��F19446558
![]() 4�_
4�_
�A�b�v���Ă݂�ƃJ�������J�C�c�u���������ڂ��肵�Ă܂��ˁB���摜�̓N���A�Ȃ��肾�������A�g�債�Ă݂�Ɗm���ɉ𑜂��ǂ��Ȃ��B�O����C�ɂ͂Ȃ��Ă���ł����A���i�R������ɃA�b�v�����摜�̓f�[�^�����Ȃ�Ԉ�����Ă��銴���ł��B������JPEG�̉掿��F�X�ς��Ĕ�r���Ă݂܂������A100KB���x�̉摜�Ɋ������߂��ł��B�𑜂��Ă���摜�͉掿�𗎂Ƃ��Ă�����ȂɈ�a���Ȃ��̂ŁA��͂茳�摜����������B���Ƃ�����ł��ˁB
�����ԍ��F19447215
![]() 3�_
3�_
�ʐ^���B��̂͊G��`���̂Ɠ������Ƃ����l�����܂��B
�����ʐ^�͎����̊�����\�������i���Ǝv���܂��ˁB
���鉹�y�ƂƏ����Ƃ̑Βk��ǂ�ł��Ă킩������ł����A�ނ�ɂ͎v���悤�ɂȂ�Ȃ��\���̋ꂵ�݂�˂����������ɐ����G�N�X�^�V�[�����邻���ł��B���܂��Ȃ����Ȃ��A�����̈�߂�������ł��Ȃ��A�Ƌꂵ��ł��鎞�ɁA�s�ӂɕǂ������Ėڂ̑O�ɒn�����o�b�ƍL����悤�Ȋ��o���Ƃ��B�I�����Ċi�D�����Ɗ�����炵���B������x�͎����Ńn�b�Ƃ���ʐ^���B���Ă݂������̂ł����B
�ǂ����ǂ����N���B
�����ԍ��F19448229
![]() 4�_
4�_
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�{�����Y�����̓��e�ǂ������C�y�ɁB
�A�C�T�c�s�v�A�\�蓦�����R�ł��肢���܂��B
�l�I�ɂ͍��N���F�X�y���݂Ȏ����B�I�����p�X�̃T��������p�i�\�j�b�N��400mm�Y�[�����ǂ�ȑ���Ǝʂ�Ȃ̂��BE-M1�̌�p�@���o�ꂷ��̂��B���������Ə���i���Y�ʂ����Ȃ��̂����ב҂��̂܂܁c�j�����̃V���{�����ĎB�e�Ɋv�����N������̂����҂��Ă܂��B
�����ԍ��F19451425
![]() 5�_
5�_
�P���g���Ύ��̃u���O�Œm�����̂����A�t�H�g�}�X�^�[����Ƃ����̂��ʔ������B�ߋ��̏o��������ƃn�e���̂��Ƃ��ł͂���̂����B�m������������ǂ��ʐ^���B���Ƃ͎v���̂ł����ARAW���������̍������āu�����I�v�Ǝn�߂����ڂ��J���ꂽ�C�����邵�A���̏ꍇ�u�m���ł���v�����������Ȃ����Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F19452882
![]() 5�_
5�_
����ƊE�l�̃u���O��ǂ�łĎv���������������B�u���O��I�o�ɖ��ڒ��߂��邾��I�v�ƌ����̂ł��B�ŏ��Ӗ����킩��Ȃ��������A�����RAW��������悤�ɂȂ��ĕ������ė����BRAW�������ɘI�o���������Ė��邭������Â������肷��̂����A�Ⴆ�Ό��X�Â߂ɎB���Ă��܂������̂𖾂邭���悤�Ƃ��Ă��A�����U���U�����ăL���C�ɂȂ�Ȃ��B�\���ȊK�����c���Ă��Ȃ���ł��ˁB���̐l�u�傫���t�H�[�}�b�g�̃J�������l����O�ɁA�܂����̃J�����ŊK�����\���g����K����t����v�Ƃ��B�I�o��K���ɂ���Ƃ������́A�����ȃO���f�[�V�������\�Ȍ���f�[�^�Ƃ��Ď�荞�ނƂ����Ӗ�������̂��ƁB
�����ԍ��F19455380
![]() 5�_
5�_
���ƂԂ��������Ƃ��Ă���܂��H
�́A�o�C�N�ŎR���𑖂��Ă������ɁA�g���l�������u�Ԃɓ��������Ĕ��ł��������w�����b�g�ɂԂ����������Ƃ����̂�����܂����B�ˑR���ꂽ�̂ŁA����������������Ȃ�������ł��傤�ˁB�w�����b�g�ɉ��������c���Ă܂������A������̃_���[�W�͂���قǂł��Ȃ������̂��A���̂܂ܔ��ōs���܂����B�����͉��̒���������܂���ł������A���v������̓q���h���������̂����c
�����ԍ��F19474973
![]() 3�_
3�_
��X�����Ă���̂����A���͂�����x�傫���B��Ȃ��Ɖ𑜂��Ȃ��B�a�c���ꂳ��̃u���O�ɂ��ƁA�����̃A�J�V���E�r�����B�����o���Ƃ���1DX��V3�ł͔@���ɉ𑜂̍������邻���ȁB�����̂��́A�����������ʂ�Ȃ��������̂́A�Z���T�[�̑傫���t���T�C�Y�̕����y���ɉ𑜂���炵���B�Ӂ`�ށB
1DX��1810����f�AV3��1839����f�ŁA��f���͂قڍ��������̂ɉ��̂Ȃ̂��B���ׂĂ݂�ƃ����Y�̉𑜌��E�Ƃ����̂������ł��ˁB�Ⴆ�A�����̖��������Y���g��546nm�̌��𑨂������A�𑜌��E��F5.6��268�{/mm�ƂȂ�B���������F5.6�̃����Y�ʼn����̂��̂��ʂ������A�t���T�C�Y�Z���T�[�ł͑���1mm�̑Ώۂɑ���𑜂�268�{���������A1�C���`�Z���T�[�̏ꍇ�͓����Ώۂ�����0.37mm�ƂȂ�𑜂�99�{�����ɗ����Ă��܂��B���������A�j�R���ł�MTF�Ȑ���ʏ��10�{/mm��30�{/mm�ŕ\�����Ă���̂ɁA�j�R�����ł�20�{/mm��60�{/mm�ɕς��Ă���̂́A�Z���T�[���������Ȃ�ƃ����Y�̉𑜓x���グ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƌ����Ă��ł����B
�������𑜌��E��F�l���������قǍ����A�i��Ɖ𑜌��E�������Ă����Ƃ��A�ł��������Y�͖��邢��������Ȃ��ĉ𑜌��E�������Ƃ��A�m������B���������\�ȍ�������̂��B��L�̗��F4�Ȃ�375�{/mm�AF2.8��536�{/mm�AF2��750�{/mm�ł��B���ۂ̃����Y�ł͉𑜂������l���Đv�����ł͖����̂Ō��E�܂ł͂����Ȃ����������ASHG�����Y��F2�ō�����肷���ł��B
�����ԍ��F19476839
![]() 4�_
4�_
�I�����p�X�v���U�ŃT�����������ė��܂����B
MF�Ńs���g�g�傷��ƁA�{�����Y��茩�������V���[�v�B��Ԃ��̌����������̂��A�摜�����肵�Ă��ăs���g�������y�ł��ˁB�莝���B�e�͏\���\�ȏd�������A�{�����Y���d�����Ƃɂ͕ς��Ȃ��B�{�����Y�̏ꍇ�A�X�g���b�v����ɂ����āA�̂̑O�Ń����Y��������Ɏ����Ȃ�������Ă��邽�߁A��l�̔��Ăɂ��Ή��ł��邵�A�c�o�����Ԓǂ������邱�Ƃ��\�����A�T���������ƌ��ɂ����āA�B�鎞�ɏ��߂Ď�Ŏ��`�ɂȂ肻���ŁA���ꂾ�ƈꔏ�x��邵�A�����Ԃ̎莝���͖������ۂ��B�Y�[���������̂ŁA�W���i�ɂ��t���Ă������A�Ə���ɗ���Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���܂ŎB��Ă������̂��B��Ȃ��Ȃ�\��������܂��BAF���x���Ƃ�����ł͂Ȃ��̂����@�q�Ɋ����Ȃ������C�ɂȂ�_�ł��B�{�����Y�Ɣ�ׂĖ��͓I���ƌ�����Ɛ��������ȏ�������܂��ˁB�{�����Y�̎�y���ƃR�X�g�p�t�H�[�}���X�͉��߂Đ����Ǝv���܂��B
�c���̊��ɃJ�~����̃_�C�G�b�g��������_���x���q���ċg���n�߂Ă邵�A�����C�}���}������ˁ[���I
�����ԍ��F19478352
![]() 6�_
6�_
�{�����Y�ƃT�������̓��������ꂱ��l���Ă���Ɓu����ς薜�\�ȃ����Ȃ�Ė�����ȁv�Ǝv���܂��B
�a�c���ꂳ��̖{��V3���Љ��Ă��āA�����ʔ����ǂ�ł����A�a�c����̃u���O�ɂ��Ɓu�L���v�Ƃ����ᔻ���������炵���B�a�c����̋L����V3�̃_���ȏ��m�Ɏw�E���Ă��āA�Ӗ��킩���b�����A�u�t���T�C�Y�̕����̂��v�Ƃ�����ʏ펯�H���}�ɐl��ᔻ�������̂�����̂����m��Ȃ��B�a�c����̍l�����͖����ŁA�����̂��̂��B��Ȃ�f�R�t���T�C�Y�����A�����T�Ō��܂��n�߂����W���̎ʐ^���B��Ȃ�V3�ŁA���ꂼ��̓�������ĎB������ƁB�a�c����͏����Ă��Ȃ����ǁA�{���͂�������������Ȃ��ł��傤���B�u�J�����������Y�����F������H�B�肽����̕����厖����H������B��铹��Ȃ牽�ł���������Ȃ����v
�����ԍ��F19480213
![]() 4�_
4�_
�����Y�̐��\�\���Ɏg����MTF�Ȑ��ɋ^�₪�����Ē��ׂĂ݂܂����BMTF�Ȑ��̉����͉�ʒ��S����̋����B�t�H�[�}�b�g�ōł����������ł���Ίp����21.6mm�Ȃ̂Ŕ�����10.8mm��\������B�c����1����ʑ̂��̂��̂̃R���g���X�g��\���A����ɋ߂��قǍČ������ǂ����ƂɂȂ�B
�^��1�́A����g20�{/mm�ƍ����g60�{/mm��2�n�\������Ă��邪�A���̍����g�̕������x�����Ⴂ�̂��B
�����Y�͎c�������Ɖ�܌��ہi�����Y�̂悤�ȁu���v��g�ł�������ʉ߂���ƌ��ɔg�䂪�o���邻���ȁj�̂��߁A�ǂ�����Ă���ʑ̂�100%�Č����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ڂ��Ďʂ��Ă��܂��B�ڂ̑e������g�̐��͎��ʂł��Ă��A�����g�Ŗڂ��ׂ����Ȃ�����ʂ��ɂ����Ȃ�悤�ł��B�i�Ō�̓R���g���X�g�[���ɂȂ�Ƃ��B��������悤�ɂ͌������ԂȂ�ł��傤�ˁB�j
�^��2�́A�����i���˕����j�Ɠ_���i���S�~�����j�͉��̈Ⴄ�̂��B
������m��������A���������ł����Ă��o�c��ƃ}������B��Ǝʂ肪�Ⴄ�����ȁBMTF�Ȑ��ł͎������o�c��A�_�����}����̎ʂ�ɓ�����B�Z���T�[�͕��ʂ����A�����Y�̌����ʂ͘p�Ȃ��Ă��āA�p�Ȃ��傫�������͎ʂ肪�ڂ���B���˕����Ɠ��S�~�����ł͂��̌����ʂ̘p�ȓx�����Ⴄ���߁A�������ł����Ă����̎ʂ�����قȂ邱�ƂɂȂ�B���������悤�ȕ������悤�Șb�����A�����Y�Ƃ͂����������d�s�v�c�ȃ����炵���B
���āA�p�i��300mm�Y�[���Ƃ�MTF�Ȑ����r���Ă݂�ƁA���ڔ�r�ł���̂͒���g20�{/mm�̕����݂̂����A�p�i�Y�[���̕������炩�ɃR���g���X�g�������B����Ŗ{�����Y�ɓ����I�Ȃ͎̂������قڃt���b�g�Ȏ��ŁA�摜�̋ψꐫ�������Ɗ�������̂ł͂Ȃ����낤���B
�����ԍ��F19481870
![]() 3�_
3�_
�F��ȃ����Y��MTF�Ȑ������Ă݂�ƁA�t���b�g�ȓ����̂��̂��ď��Ȃ��ł��ˁB�{�����Y�̏ꍇ�̓t���b�g�Ȃ͕̂��˕��������ł����A���y�����Y�̊��ɂ����܂ł������̂ɂ͐v�҂̎��O�������܂��B�f�l�l���ł����A�t���b�g�łȂ��ꍇ�́A�摜�ɃR���g���X�g�̔g�����邱�ƂɂȂ�A�ǂ������������Ȃ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�{�����Y�̑���ۂ��������Ȋ����������̂́A�𑜂��ǂ��Ƃ��������A���̓��������������������̂����m��܂���B
�Ƃ���ŁA�T�������̐�`������悭�ǂ�ł݂�ƁuE-M1�Ƃ̑g�ݍ��킹��400ms�ȉ��̍���AF���\�v�Ə����Ă���B����H400ms����0.4�b�ł���ˁH�t�H�[�J�X���~�b�^�[���g���Ă�0.2�b�Ƃ��Ȃ�ł����ˁH
�ȑO���{���R���f�W���g���Ă�������AF���x�����Ă��B��ɂ����������A����ł����̍ő���0.14�b�ł����B�{�����Y��E-M1�̑g�ݍ��킹���ƁA�����܂�̖��͂�����̂́A���{���R���f�W�Ȃ���ɂȂ�Ȃ������ł��B�T�������͂�����Ƃ̂�т艮����Ȃ̂�������܂���B�������Ƃ���Ǝ��̎B�����̂������Ă��Ă��܂��Ȃ��B���{���R���f�W�ł��N���A�Ȕ��Ă��B��l�͂��܂������A�u�B�l�Ȃ�B���v�Ɓu���̂悤�Ȃǂ������c�ł��B���v�̊Ԃɂ́A�Â��Đ[�`���삪����Ă���̂ł��c
�����ԍ��F19496770
![]() 3�_
3�_
�͌�������Ă���ƁA�`���E�Q���{�E�����ł����̂��������̂ŁA���˓I�ɃJ�������������B���������̂łڂ���Ƃ����B��Ȃ��������A���ɏ����炵�����̂�͂�ł���̂����������B�ҋׂɂƂ��ẮA���ꂪ�����ł��B�ł��a�c���ꂳ��̂悤�Ɂu���������ҋׂ͍D���ɂȂ�Ȃ��B������B��Ȃ��v�Ƃ����̂�������C�����܂��B
�����ԍ��F19499427
![]() 4�_
4�_
�����̏Ə��킪�͂����̂ŁA���������o�����̂����c
���������g���O�ɏƏ��}�[�N���ڂ���ɂ��������Ȃ���ł����ǁB���̏ꍇ�A�����ڂ̉E���ߎ��i���͉����j�Ńt�@�C���_�[�����x�����̈�Ԓ[�����̕��܂ʼnĂ��ł���ˁB�i�ŋ߂̓t�@�C���_�[�t���̃f�W�J���������āA�����ŐF�X�����Ă݂���ǁA���x�����̕��������Ē�������Ȃ��̂������̂��B�j���̎��_�ňӋC�j�r���Ă��܂��āA�܂����x�m�F���邱�ƂɁB
���̎��A�������炩�����������Ă����̂ł��B�u���[�N��A����ɗ����Ă͂�����B�S�Ƀt�H�[�X��������̂��B�ڂ���ăt�H�[�X�̓����ɐg���ς˂Ȃ����B�t�H�[�X�ƂƂ��ɍ݂�Ƃ��B�v�������A�ڂ���Ē��̓�����������˃I�r�����c���ăW�F�_�C�̋R�m���Ⴀ��܂����A�ڂ����Ē��B��邩�{�P�I
�����ԍ��F19500027
![]() 4�_
4�_
�Ə�����Ď���ł�����Ă����m�ł����H
�ȑO�A�c�o���̖{��ǂ��ɁA�q�������ɁA�R���f�W�Ŕ��Ă��B����@�Ƃ��čڂ��Ă����̂ł��B�R���f�W�i�������t�@�C���_�[�̖�����j�̑O�ʂƔw�ʂɂ��ꂼ��j���ō�����ւ������Z���n���e�[�v�œ\��t����B���ꂾ���I�ł���̗ւ�����ʂ��đΏۂ𑨂������ɉ摜�����ɂȂ�悤�Ɉʒu�����Ă����A�\�����p�ɂȂ�̂��B�������̕���������₷����ˁH��������Ă݂邩�ȁB
���A�������s��p�Ȃ̖Y��Ă��B�X�^�b�t�`�I
�����ԍ��F19514373
![]() 4�_
4�_
���̖����������ƕ�����Ɩʔ����낤�ȂƎv���܂��B
�ŏ��ɕ�����悤�ɂȂ����̂̓R�Q���́u�M�B�[�v�Ƃ������ł����B
����܂Œ����ǂ��ɂ���̂��S���킩��Ȃ������̂ɁA���̂���ӂ��T���Ƃ����Ƃ���B
����Ɣ����J�����C�����܂����B
�����ԍ��F19517128
![]() 4�_
4�_
�\�j�[�̃�7�ƃ�7R�����\���ꂽ���̃v�����[�V�����r�f�I�͍͗�ʼn��x�����܂����BE-M1�̃R���Z�v�g�r�f�I���a�ڂ����ǍD�݂ł��B�����̂Ɖ~�����J�����ƃ����Y�ɏ��X�Ɍ`��ς��Ă�����������u���x�����x����蒼���ĒH�蒅���܂����v�Ƃ������b�Z�[�W���B���������̂Łu�킠�v�Ǝv�킹����̂�n����ăX�Q�[�ȂƎv���܂��B
�d�����{���̔ɖZ���ɓ˓����t�܂ł͂��������������ł��B
�ł��ʐ^���e�͂��C�y�ɁB
�����ԍ��F19520725
![]() 3�_
3�_
���Ȃ��Ȃ��Ă����X�N�[�^�[�p������A�c�Ƒ�̈ꕔ��ϗ��Ă����Ă�������肵�āA�T�������w�������ɖڏ������Ă����B�i�u�債���ʐ^�B���ł��Ȃ��̂Ƀo�b�J����Ȃ��́v�����K�}���K�}���c�j�p�i�Y�[���͑��ʈʑ���AF�{�f�B���������A���Ȃ��������Ƃɂ��悤�Ǝv�����̂��������A�����Ŏv��ʕ������I
�x�m�t�B���������Z600mm�̃Y�[�����o������ł��ˁB�d�����I�����p�X�̃T�������ƂقƂ�Ǖς���B�����ʐ^�Ƃ̏����悳��̍������܂������掿�ǂ��ł��BAPS-C�̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y���掿�ɗ]�T������܂��B�{�f�B�͍ŐV��X-Pro2���ǂ������ł����A�O���b�v���o�������Ă��Ȃ��̂���_�ł͂���܂��B
�v��ʃJ�E���^�[�p���`�𗁂т��C���ł��B
��6000�ɂ������������Y����������ȂƎv���Ă���ł���ˁB
�~���[���X�ł����]���̑I�����������邱�Ƃ͊��}�ł����A�܂������Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F19543386
![]() 4�_
4�_
�����悳��̃g�[�N�C�x���g�ɍs���Ă��܂����B
�i�d�����Z����������Ƃ��Ⴄ���I�j
X-Pro2��400mm�Y�[���̔̑��ł��B�d�����t�ƈ���āA�莝���ŃX�g���[�g�t�H�g�̂悤�ɎB��铮���ʐ^�A�Ƃ����������u�܂��Ɏ�����������Ă邱�Ƃ��ȁv�Ǝv���Ȃ��畷���Ă܂����B���̐l�͒�����͖p�c�Ȋ����ł����A�u���O�ǂ�ł�Ɛc�̂���l�ł��B�ȑO�A���t�h�H����@����Ă��S�������܂���ł����B�i���̓��t�@�ɋ����Ȃ��̂ŁA���̐l���������Ⴉ�肫�ɂȂ�Ӗ���������܂���ł������B�jX-Pro2�ɂ��G���Ă݂܂������A�����ȊO���ɔ����āA�y�����AAF��V���b�^�[���T�N�T�N�����ċC�����C�C�I����͍������nj��\�l�C�o���Ȃ����Ǝv���܂����B
�ł��A���̏ꍇ�͖������Ă��������ނȂ�A����ς�I�����p�X���ȁB�x�m�t�B�����̃{�f�B���ĊF�O���b�v�̏o�����肪���r���[�Ȃ�ł���ˁBGF5�̃O���b�v�Ɍ��C��������NEX-6�ɏ��ւ��Ĉȗ��A����͏���Ȃ����ł��B�i�I�����p�X�ł�������̂�E-M1�����ł��B�j
������̗��R�́A�{�����Y�ŃI�����p�X�̃t�c�[����Ȃ��˂��l�ߕ���m�������Ƃł��B�T��������MTF�Ȑ������Ă��������Ă��A�{�����Y�̐����ȁH�Z�M�����ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F19562275
![]() 3�_
3�_
�f�W�J��info�ŏЉ��Ă����I�����p�X�E�T�������̃e�X�g�L�������Ă���ƁA�V���b�^�[�V���b�N�̍��ڂɔ�r�p�Ƃ��Ė{�����Y�̌��ʂ����ׂ��Ă����B�ڂׂ̍������C���͖{�����Y���T�������̕����������ɉ𑜂��Ă܂��ˁB�ł��A�����Ǝv�����̂́A�ǂ���̃����Y���É����[�h�ɂ��������i�i�ɉ𑜂���_�ł��B�É����[�h�Ȃ�ĉ��t��̂��߂ɂ����Ȃ��́H���x�̔F���������������̂ŁA����͈ӊO�ł����B
����Ŏ~�܂蕨�ŐÉ����[�h�������Ă��ł����A���ꂪ�V�����̉掿�ŕ����܂�������Ɨǂ��I
�掿�ւ̉e���͎�u�������ł͂Ȃ���ł��ˁB�~�܂蕨��P���[�h�ŎB���ĂăV���b�^�[�X�s�[�h���x���Ȃ肪���Ȃ̂������o��v���Ȃ낤�Ǝv���܂��B
�b���͑S���É����[�h�ŎB���Ă݂����ł����A�A�ʋ��k�Ƃ��Ă͂��o�i�J�V���J�V�����j�������Ƃǂ�������オ���ȂƂ͊����܂��c
�����ԍ��F19565959
![]() 4�_
4�_
�u�K�i���~��闇��No.2�v�i�}���Z���E�f���V�����j�Ƃ����G������܂��B�A���ʐ^���G�ɂ����悤�ȃt�H�����ŁA����Ȃ̗L��H�ƈ�ۂɎc��܂����B���̃R�T�M�̎ʐ^�͋��R�̎Y���ł����A�H�v������ʔ����̂��B���H�i�����Ɗ���������ˁc�j
�����ԍ��F19582427
![]() 4�_
4�_
������x�����r�^�L���������I�Ƃ������ƂŁA�O�B����������E�т̎ҕ��ɏ���B�i�ǁ[���Ă��s�R�ҁj�p�����ʂ܂ܐ����Ԃ��߂��A���߂ċA�肩�������ɑ����Ō����܂����B�����̓ܓV�Ŗؗ��Ɉ͂܂ꂽ�����ɂ��̈Â������Y�ł́u�}�g���Ɏʂ�낤�ȁv�Ɣ������߃��[�h�ł������A�v�������L���C�ł��B
����҂Ă�A�~�܂蕨��P���[�h�ŎB���Ă���̂����A�����������ʂ̖R�������ƁAISO������l�ɒ���t���Ă��܂����BISO������200�Ȃc����A�ǂ����É����[�h�ɂ����P���[�h�̃v���O��������ւ��悤�ł��ˁB�É����[�h�ł́AISO�𐘂��u���ăV���b�^�[�X�s�[�h��������d�l�̂悤�ł��B�d�q�V���b�^�[���ƃu���ɂ�������A���ꂾ���ᑬ���g����Ƃ������f�Ȃ̂ł��傤�B�掿���ǂ��Ȃ�Ɗ��������R�́A�u�������邱�ƂȂ��炱�̐ݒ肪�����Ă܂��ˁB
�����ԍ��F19585806
![]() 3�_
3�_
�͌��ŃJ���E����Ԃ̂����������B�u�����Ԃh�ȃJ���E���ȁv�ƌ��グ�Ă���ƁA�ˑR�����~���Ă����B��[�I���̕�����Y�ɂ܂ŁB����������ȍ��������炤�܂����Ɩ�������������ȁc���Ċ��S���Ƃ�ꍇ���I�t���Ƃɂ����c
����͂��Ă����A�a�c���ꂳ��̖{�ǂ�ł�Ɓu�X�|�b�g�������g���v�Ƃ���܂��B���������Ȃ����������Ɩ������A�W���E�r�^�L����Ŏ����Ă݂܂����B�̐F�ŃX�|�b�g��������ƁA��薾�邢���͂͂������蔒���ۂ��Ȃ�B���ꂪ�ʏ�̕����������ƁA�S�̂ς����]���ƂȂ�A���������ƈÂ��ʂ锤�B��������B�鎞�͋t����������w�i�Ƃ̖��Í����傫���ꍇ�����\����̂ŁA�����������ꍇ�ł��������D�悵�����邳�Ɏʂ���Ƃ������Ƃł��ˁB
�I�o��ł������ł��邯�ǁA��Ȃ��Ƃ���Ă�Ԃɔ��ł����Ⴄ���ARAW�������ɂ������ł��邯�ǁA�K�����c���Ă��Ȃ��ƃU�����Ă��܂��B����͎g���܂��B
�����ԍ��F19589633
![]() 3�_
3�_
�a�c����̖{���悭�ǂނƁA�X�|�b�g����������ɘI�o�����Ə����Ă������B�X�|�b�g��������ςނƂ����P���Șb�ł͂Ȃ���ł��ˁB
�J�����̑����͔��ˌ����������ł��B���̏�ɍ����Ă���ˌ��͈��Ȃ��A���ˌ��̓��m�ɂ���ċ������܂��܂��B�J�����ɂ͔��ˌ��̓K�ȋ����Ȃ�ĕ������������A���˗����Ƃɂ���18%�ɂȂ�悤�ɒ�������Ƃ��B�i18%�����R�E�̕��ς炵���B�j�Ȃ̂ŏ����̐�i�F���B���Ă�18%�̃O���[�ɂ��Ă��܂��B�X�|�b�g�������ƁA��ʑS�̂̕��ς��Ƃ�����Ώۂ��i���đ����Ƃ͂������̂́A���̔��˗���18%�ȊO�ł������ς�18%�ɒ������Ă��܂��B�Z�ʂ�������̂��˃`�~�́c
�l�Ԃ̊Ⴊ�����̐�i�F�����邱�Ƃ��ł���͉̂��̂Ȃ낤�B
����̍L������������������̂ł��傤���B
�����ԍ��F19607755
![]() 3�_
3�_
�T�������ɂ��ẴI�����p�X�ւ̃C���^�r���[��ǂ�ł���ƁA�{�����Y�����������ɏo����Ă����B����300mm�ł��{�����Y�Ƃ́u�܂����������̈Ⴄ���\��ڎw�����v�ł����B����͂܂��A�{�����Y�ł����璹����̃A�b�v���B���Ă��A�g�傷��ڂ��肵�Ă܂���B�����ȁA���ꂾ���͌����Ă����B�g�ѐ��͖{�����Y�̈������B�o���Ă����I�i���ă��[�J�[�Ɍ����Ăǂ�����c�j
����͂Ƃ������c
�~�܂蕨�͐É����[�h�ŎB�邱�Ƃɂ��܂����B
�ʂ�̎������Ⴄ�̂ŁA�����߂�܂���B
���̂͂܂������Ă܂��B
���̂ł����Ă��d�q�V���b�^�[�̕����V���b�N�����Ȃ����A�~�܂蕨���̍��͖����ɂ���A�𑜂����ǂ��A�����܂���オ��悤�Ɋ����܂��B�����A�d�q�V���b�^�[�͒[�̉�f���珇�ɏ������Ă��������ŁA�������̂͌`���i�i�����Ďʂ��Ă��܂��B���ꂽ��f�Ԃł̓V���b�^�[�̎��Ԃ�����Ă��ł��ˁB�p�b�ƌ��ŕ����郄�c�͍폜���邾���Ȃ��A�����Ȃ̂������āA�i�X�ǂꂪ����Ȃ̂�������Ȃ��Ȃ��Ă���B�s�v�c�̍��̃W�W�C���I���́c
�����ԍ��F19610050
![]() 3�_
3�_
�\�j�[�̃�6300�����\����܂����B��6000��AF�ő�0.06�b�́A�x�m�t�B������X-Pro2�ɒǂ��t����܂������A��6300�ł�0.05�b�ɏk�߂āA�T���X��NX1��0.055�b�����悤�ł��B0.01�b�̍��Ȃ�đ債�����ƂȂ��悤�Ɍ����܂����A�䗦�ōl�����17%�̒Z�k�ł��B�����B�鎞�̎����Ƃ��ẮA�J������AF���\�̃M���M�����E���g���āu�B�ꂽ�A�B��Ȃ��c�v�ƉԐ肢������Ă�悤�Ȋ����Ȃ̂ŁA�̊��I�ɂ͌��\���������Ȃ����Ǝv���܂��B
�ł��ǂ����]�������Y�͏o���Ȃ���ł���c�Ǝv���Ă���A����200mmF2.8�Y�[���Ƀe���R�����o����ł��ˁB��6300��2�{�e���R����t����Ί��Z600mmF5.6�ƂȂ�܂����A�����Y�����̓e���R�����݂�31���ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�i�x�m�t�B������400mm�Y�[����21���A�I�����p�X�̃T��������17���ł��B�j���������������Ƃ����牽�ł��`�ʓI�ɔ@���Ȃ���ł��傤�H�Ǝv���܂��ˁB�x�m�t�B�����̃J�E���^�[�p���`�Ɏ����ŌJ��o���ꂽ�\�j�[�̃A�b�p�[�J�b�g�A���Ƃ��]�������ȁc
�����ԍ��F19614318
![]() 3�_
3�_
CP+�̋Z�p�A�J�f�~�[�Ƃ����̂ɍs���Ă݂܂����B�I�����p�X��PRO�����Y�J���̘b�����A����Ȃɍׂ����b�͖��������ł��ˁB�܂��A�Z���Ԃ̈�ʌ����Z�~�i�[�����A����Ȃ��ȁB�ł��܊p�Ȃ�ŁA�j�R���̃T�������̂悤��PF�����Y���g�������^���͍l���Ȃ������̂����₵�Ă݂܂����B���������A�ƌ����Ă܂������A��H�����������Ă����c�i�V���N���Y�����I�}�G�́j
�u��y�A�j�R�������PF�g�����T���������o���܂������A�E�`���l���Ă��ǂ�������Ȃ��ł��傤���B���^�E�y�ʂ̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̍l�����Ƃ������Ǝv����ł����B�v�u����A�����͂�����B����PF�����Y�́A��������������ƃ����O��̃t���A���o�Ă��܂��B�j�R������̏ꍇ�́APF�t���A���y��������Z�p���J�����āA���^����D�悳�����悤�����ǁA�E�`��PRO�����Y�̓v���ł����S���Ďg����掿��ڎw���Ă邾��B���̌��_�͖����ł��Ȃ������c�v
�����ԍ��F19636032
![]() 3�_
3�_
�J��������Y�̌��J���������Љ�Ă���u���O������̂ł����A�����ŁA�I�����p�X�̃T�������̉��i�����̍������i�t���T�C�Y�p�̃T��������20���~�ȉ��ɑ��ăI�����p�X�̃T��������30���~�j�ɂ��čl�@����Ă���̂�ǂ݂܂����B
��ʓI�ɏ����ȃC���[�W�T�[�N���p�̃����Y�͑��ʂ̕���\�����߂Ă���̂ŁA���̕��R�X�g��������Ƃ����̂ł��B����100�{/mm�̉𑜗͂��������Y�ł���A�t���T�C�Y�Z���T�[�̑Ίp��43.26mm�ɂ�����4,326�{���̉𑜂�����̂ɑ��A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y��21.63mm�̂���2,163�{���̉𑜂ƂȂ�B������t���T�C�Y���l��4,326�{���ɍ��߂悤�Ƃ�����A4,326÷21.63=200�{/mm�ƂȂ�A�K�v�ȃ����Y�𑜗͂�2�{�ɂȂ�܂��B
��������A�t���T�C�Y�ł��������A�ƂȂ�܂����A���x�͓�����p�ł݂��Ƃ��̏d�ʂ�T�C�Y�̖�肪�o�Ă���B�����Ȃ̂͌y�ʁE�R���p�N�g�̑㏞�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���������A�E���PC�̓��ւ��������Ă���ǁA������������\���Ə��^�ɂȂ�������Ȃ��ł���ˁB���^��D����
�����ԍ��F19640082
![]() 3�_
3�_
�R�Q���ł����ˁH�C�É����[�h�ł��i���Ԃ�j�B |
MF�̂܂��ꓖ����B |
��ѕ��_���������ł����w�i�ɂ�� C-AF�����܂���ō���܂��i�g���~���O�j�B |
�������l�Y�~���^�ԃ`���E�Q���{�E�i��o�b�N���� C-AF�̕����܂�������Ȃ��ł��j�B |
Captain Caribe����C
�����́C���߂܂��āB
�@�I���� 300mm f4���y���݂ɑ҂��Ă����̂ł����C���̏d�ʂƉ��i�Ɍ˘f���Ă����Ƃ���ɂ��̃X���ɔw����������Ă�����̃����Y���w�����܂����B�@���ʁC�ƂĂ��������Ă��܂��B
�@�X����l�ւ̌������˂đʍ��\�点�Ă��������܂��C�X���������e�͂��������B
�����ԍ��F19641478
![]() 4�_
4�_
��divecat1954����
����ɂ��́B���̃X�����㉟���Ƃ͊������ł��B
�R�Q���͂������܂ł�������O�Ȋ�Ȃ̂����킢���ł��ˁB��ѕ���MF�ŎB��Ȃ�āA�ǂ������ɂ͑z�������E�ł��B�R���ڂ̓R�~�~�Y�N�H���������͂��ڂɂ����肽���ł��B�`���E�Q���{�E�̓n�b�Ƃ���V�[���ł��ˁBC-AF�͔w�i�ɖ�������w�i�ł͗ǍD�Ȃ̂͑S�������ł��B���G�Ȕw�i�ł������܂���グ��R�c�����������Ȃ����ƒT���Ă܂��B
�T�������̓A�}�]���Œ������Ă���ł����A�L�����Z�����Ă��܂��܂����B
���[�U�[��������Ɩ{�����Y�Ƃ̍��͗�R�I�����Ȃ��Ǝv�����ʁA����ς莩���ɂ͕�̎������ꂩ�ȂƁB�����̉摜�̓f�[�^�����k����Ă���݂����ŁA��r����Ɩ{�����Y�̂ڂ���x�������ڗ����܂����A�l�����炢���ӏ܂��Ă���͎̂����̂�������PC��ʂŁA�\���ȉ掿�ł��B
�����̏ꍇ�A�ʐ^���B�邾������Ȃ��āA�Ԃ�Ԃ������鎩�R����T�������y������ł���ˁB�{�����Y�̋C�y���͎̂Ă������ł��B
�����ԍ��F19644028
![]() 5�_
5�_
Captain Caribe����C
�@���X���肪�Ƃ��������܂��B
�� �ʐ^���B�邾������Ȃ��āA�Ԃ�Ԃ������鎩�R����T�������y������ł���ˁB�{�����Y�̋C�y���͎̂Ă������ł��B
�@�܂����������ł��B�@�҂��������ɂ͑҂��C�����������ɂ͕����C��������ΎB��C����������Ƃ�����������Ƃ��B�@�����E��Ɏ����Ă�����y����ނ���������̎��R�x�ł�����B
�@�R�~�~�͌�ʃA�N�Z�X�̗ǂ��͐�~�ɏo�Ă���܂��̂ő��ɂ��ʂ��Ă��܂��B�@���v�O2���Ԃقǂ̃V���[�^�C���ł��B
�����ԍ��F19647555
![]() 4�_
4�_
��divecat1954����
�R�~�~���̊���Ĉ�ۓI�ł��ˁB�A�܂����I�}�C�t�B�[���h�̉͌��ł��ڌ��Ⴊ����̂ŏ����T���Ă݂͂��̂ł����A�d�����Z�����Ȃ��Ă����̂ŗ��~�ɍĒ���ƂȂ肻���ł��B
�����ŃE�O�C�X�����������B���i�݂̒�����Ȃ��Ȃ��o�ė��Ȃ��̂ɁA�~�̖��щ���Ƃ邶��Ȃ����I�J�����ꂳ��l�A�B������Ȃ��ʼn����S�\�S�\����Ă����A����ǂ��낶��Ȃ��B�����ŎB���Ă�ƁA�u����܂�ǂ��Ȃ�v���ɂ݂�����B�����牽����ĂƎ茳�����Ă��č��_���������B�����p�̂���a������āA�~�̎}�ɓ\��t���Ă����̂��B�Ȃ�قǁA�J�������ɏo������Ȃ��E�O�C�X���~�̉Ԃɗ��ʐ^���悭����̂ŕs�v�c���������A��������ĎB���Ă��̂��B�A�b�^�}�����ȁc���ĒN�����S���邩�I�o��̃g�L���L�������悤�ȉa�t���ʐ^�B���ĉx�ɂ���悤�ȃ`���P�ȍ��������Ƃ���I
�����ԍ��F19659743
![]() 4�_
4�_
�E�O�C�X�̈ꌏ���Ƒ��ɘb���Ǝv��ʋc�_�ɂȂ��Ă��܂����B
�u�l���ꂼ��l�������Ⴄ�͓̂��R�Ȃ�Ȃ��́B��点�ʐ^���B����������Đl�ɖ��f���������Ȃ����B�̂����ɂǂ����������b����Ȃ���v
�u�����̏�Łw�E�\�x���B���Ă��B����̐l��r�����āv
�u����Ȏז��Ȗ�Ȃ����A���̐l���ǂ��������B�]�v�Ȃ����b�v
���������m��u������R�~�ɃE�O�C�X���c�v�Ȃ�Ă����M���Ȃ�����ȁI
�����ԍ��F19664129
![]() 3�_
3�_
���ԏ�ɏo�Ă��Ȃ��E�E�E |
�w�i�̍�����Ȃ��i�g���~���O�j |
�����i�g���~���O�j�C���̖͎��R�̕��ł��B |
��n�Y�����鎖�͖������C�o�`�s���ɂ��Ȃ�Ȃ����ԗ\���HMF�i�g���~���O�j |
Captain Caribe����C
����ɂ��́C���ז����܂��B
�@�E�O�C�X�C�؉A�ɋ��Đl�O�ɂ͂Ȃ��Ȃ��o�Ă��Ă���Ȃ��̂ɁC�ԋ߂ł��ꂢ�ɎB���Ă��܂��ˁB
�@�a�t��������͎��X�����|�����܂��C�B�e����Ԃ͌`�̗ǂ��Y��ݒu���āC�A��ۂɓP�����ċA�������������Ⴂ�܂����B�@�w�i���l���č\�}�����߂ăt���[�~���O���C�d����ނɎO�r�𗧂Ăāu�����C�����ɗ��Ă���v�ƂȂ�̂ł��傤�ˁB
�@�����ŏ��͉����m��܂���ł������C�֏悳���Ă������������܂��̂ŁE�E�E�E�E�B
�����ԍ��F19670685
![]() 4�_
4�_
��divecat1954����
��͂蒿�����b����Ȃ���ł��ˁB�l������J���Z�~�̉a�t���͂悭�����b�����A�k�C���̃^���`���E�̂悤�ɕی슈���Ƃ��ċ��a����Ă���������܂����B���̕������ŕs���Ɏv��ꂽ���ɂ͂��l�т������܂��B
�~�܂蕨�̉掿���É����[�h�Ō��I�Ȍ�����ʂ����ƁA���x�͋C�ɂȂ��ė���̂���ѕ��̉掿�ł��Bdivecat1954�����MF�Ƀg���C����Ă���悤�ł����A�������s���낵�Ă݂Ȃ��Ƃł��B���܂ł����ƒ���9�_�ŎB���Ă��̂ŁA����1�_�ɕύX���Ă݂�ƁAAF���x���オ��̂��̊��ł��܂����B�����A�Ώۂ��������Ƒ�������̕����܂肪�����Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F19682316
![]() 3�_
3�_
�a�c���ꂳ��̃u���O�ŁA���@���T���E�~���j�G����Ƃ����t�����X�̃l�C�`���[�ʐ^�Ƃ�m��܂����B�u�َ��َ̈��͗F�B�����Ă킯�ł��Ȃ����ǁv�Ȃ�ċC�ɂȂ�܂��B�ނ̓j�R���́u���E�̎ʐ^�Ƃ����v�̃T�C�g�ł����グ���Ă��܂��B�i�������ʐ^�Ƃ��Č��������ĐF��ȋ����E���i�̐l�����Ėʔ����ȂƎv���T�C�g�ł��B�j
���āA�~���j�G����̌����T�C�g��`���ƁA�炪�����t���[���A�E�g���Ă�����A�t���ɉH���g���Ă�����B�����ł��˂��B�������Ǝu�������Ă���悤�ȁB�����ƐF�X����Ă݂悤�ƗE�C���N���Ă��܂��B�I���������܂̂��Ⴍ����i����ɒ��Ԃɂ���˂���j
�����ԍ��F19684994
![]() 4�_
4�_
��Captain Caribe����
���͂悤�������܂�
�ʔ����đS���ǂႢ�܂���
���{�����Y��ED�����Y�ɉ����ăX�[�p�[ED�����Y����������Ă��܂����AM.ZUIKO DIGITAL�ł��ꂪ�̗p����Ă���̂́A�{�����Y�ȊO�ł�M.ZUIKO PRO�����Y�݂̂ł��B
�̂�����
�I�����p�X�̂P�O�O�|�R�O�O�Ɣ�ׂāA�F�̕t���Ă��郌���Y�������ȁ[�Ǝv���Ă�����ł�
61�Ő���m��Ă邵�A�R�O�O�e�S�A�������Ⴆ�[�[�Ǝv���Ă�����ł�����
�e�w�`�e�Ȃ���̂��ŋߒm�������x�ł��āA�ɂ��Ȃ��Ă������邩�̂R�O�O�e�S���
�܂��͂V�T�|�R�O�O���ȁ[�[�Ǝv���Ă��܂�
�����ԍ��F19687224
![]() 2�_
2�_
����
�I�����p�X�̂P�O�O�|�R�O�O����Ȃ���
�p�i�\�j�b�N�̂P�O�O�|�R�O�O�ł���
�����ԍ��F19687456
![]() 1�_
1�_
���������܂ꂽ����
���肪�Ƃ��������܂��BPRO�����Y�͂������̐ꖡ�I�𑜗͂Ȃ�PRO�����Y�ł��ˁB�I���͂��̐l�̎B�e�X�^�C���ɂ��̂����B���̏ꍇ�́A�͌��̉��[���������B���͈͂��L���闘�_�������܂��B
�T�����������������Ă��܂����̂Ŗϑz�x�ߒ��B�t���T�C�Y�Ȃ����Y�̃T�C�Y���炵�ėL�蓾�ˁ[�ƍl���Ă܂������A�y�ʂȃj�R���̃T��������������A�������ƍl�����肵�āB�ł����t�@���j�R�����C�}�C�`����߂Ȃ���������̂ł����i���w�t�@�C���_�[�Ƃ��j�R���̃��j���[�W�J�Ƃ��j���Ƃ����ă\�j�[�ɂ̓����Y���������Ȃ��B���̃����Y�̍����F�X���Ă݂��ł����A��C�����Y�͕ʊi�Ƃ��āA�ǂ������r���[�Ȉ�ۂ��܂��B�ϑz��痂���������ɖ{�����Y�̍�������Ƌ}�ɃV���t�ɖ߂�݂����ȁB�L���s�L���s�M�����i����H�j�ƃf�[�g������Ƀo���o���̃L�����A�E�[�}���ł���Ȃ̌��ɋA���ăV�����ƂȂ�݂����ȁB���̘b��˂�
�����ԍ��F19688745
![]() 3�_
3�_
���̂��炢�߂��� AF�ł��ǂ������C�ł��t���[�~���O���E�E |
�����ď������C�s���ÁH�C��ʑ̂��J�����u���H�C�� ISO�̉摜�r��H |
AF���Ɛ�s���������܂��B�@�����͑S���m�[�g�� |
Captain Caribe����C
�����́C
�@�T���������b��ł����C���̃����Y�C�X���傳��́w�o���o���̃L�����A�E�[�}���ł���ȁx�̈ꌾ�C�Ȃ��Ȃ��ǂ�����˂��Ă�Ǝv���܂����B�@�y�ʂŃR�X�p���Q�C�h���l�����Nj���������h��Ȃ��āC�h�悤�����ĉ҂����ǂ��ȁh�̗Ⴆ���҂�����ł��B
�@�����̏��R�~�~�^�������ăg�r�ƃm�X���̃z�o�����O�ȂǁC�ǂ���s�[�L���O����� MF�ł��B�@�T�������� E-M1�� AF�ɂ��Ęb����Ă��܂����C�~���[���X�ł͗ǂ�����b��̂悤�ŁC���� Nikon�P�Ōo�����܂������CSony�ł������悤�ɘb��ɂȂ��Ă�����������܂����B�@���ɃR�~�~�Ɋւ��ẮC���t�@�����g���̕����u���s����e�w AF���Ƌ��Ă����܂��B
�@E-M1�ō���Ƃ���́C75-300�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł� C-AF�ɐݒ肷��ƃt�H�[�J�X�����O������������C���o�[�Ő�ւ��Ȃ��� MF���ł��Ȃ��Ƃ���ł��B�@��ʂɌ�����e�w AF�ł� C-AF�ł� AF���X�^�[�g���Ȃ���t�H�[�J�X�����O�� MF�������͂��ł��B
�@���āC�A�b�v���Ă����摜���g���~���O����Ȃ̂Ŋ��Z 600mm�ł͑���Ȃ��̂��Ǝv���C��l�ɕ���ăI���� X1.7�e���R���ƃX�e�b�v�_�E�������O���|�`���Ă��܂��܂����B�@�@���f�̍Ȃɂ����`���b�g�������Ċ撣���Ă��炨���Ƃ̎Z�i�ł��C���Ăǂ��Ȃ�܂����E�E�E�B
�����ԍ��F19690517
![]() 2�_
2�_
��divecat1954����
�~���[���X��AF�̓��t�@�ɔ�ׂ�Ƃ܂��܂��Ȃ�ł����ˁB�����A���͉��i�R���Ō���鎖���L�ۂ݂ɂ͂��Ă��܂���B���{���R���f�W���g���Ă������ɁA����Ń}�g���Ȕ��Ă͎B��Ȃ��ƌ����l�����\���āA�����g���l�ꔪ�ꂵ�Ă����̂ŁA����ς肻������ȁ`�Ǝv���Ă����̂ł����A��肢�l���A���H�ʂɎB��邯�ǁc�Ɛ��r�摜������I�B�Ԃ���т܂����B
�i���������������j��������Ȃ�������ˁ[���I
�����ԍ��F19702392
![]() 2�_
2�_
�����悳��̃u���O��ǂ�ł�ƁAX-Pro2��XF400mm�Y�[���̑g�������7D2��EF400mm�Y�[���̑g�����̕���AF���\�͑����Ƃ̂��ƁB��������ŎB���Ă��A�O�҂̕��������܂肪�ǂ��ꍇ�������������ȁB�r�̍��ł��ȁB���������AF�ݒ�̎g�����Ȃ��ō����o��ƌ����܂��B�Ӂ`�ށA�����u����ς�t���T�C�Y���ȁv�Ȃ�Č����O�ɁA���s���낵�Ă݂˂I
�ł��d�����}�W�Z�����Ȃ��ė��āA������ǂ��낶��Ȃ��̂��B
���B��O�ɃI�}���}����ƁI
�Ƃ������ƂŎb�����������ł����A���e�͂����R�Ɂ`
�����ԍ��F19702405
![]() 2�_
2�_
�Z�����Ɨ]�v�Ƀu���u���������Ȃ�܂��c
�����B��ɕ������͎̂��R�ƐG�ꍇ�����Ƃł�����܂���ˁB�C���C�����Ă��S������������Ă����悤�ȋC���B���@���T���E�~���j�G����̌��t���S�ɟ��݂܂��B�u���R�́A���ɂƂ��ĕa�݂��ɂȂ�悤�Ȗ��͂������Ă���A�����G��Ă��Ȃ���C�����܂Ȃ��̂ł��B�v�ܗǂ��a�c���ꂳ���E�̃~���j�G����ʐ^�W���͂����c�t�����X��ǂ߂c
�����ԍ��F19712371
![]() 2�_
2�_
�~���j�G����͎q���̍����玩�R�̎ʐ^���B���Ă��������ł��B�ʐ^�W������ƁA��ۉ敗�ł������蒊�ۉ敗�ł������肷��ʐ^�����\����܂��B�ǂ����Ă����Ȃ����̂��{�l�ɕ����Ă݂Ȃ��ƕ������ł����B���ۉ�ł�����݂̃s�J�\�����������ɕ`�����f�b�T�����������Ƃ�����܂����A���ɐ��k�Ȃ��̂ŁA�����ȂǍ��ɂ������o�������ł����B�������O�`���Ȃ��邱�ƂɖO������Ȃ��Ȃ���̂Ȃ̂����m��܂���B
�����ԍ��F19715698
![]() 2�_
2�_
���C�J�EX�o���I�Ƃ����f�W�J���̍��ɖڂ�������܂����B�������̓I�Ɏʂ��Ƃ�I���̃����Y�̕`�ʂ����ʓI�Ɋ������܂��B�ǂ������J���N���ȂƁA���C�J�F�̃����Y���o���Ă���p�i�\�j�b�N�̃C���^�r���[��ǂނƁA���C�J���̃����Y�͔�ʑ̂𗧑̓I�ɕ\���ł���悤�A������������ʘp�ȓ������������Ă��邻���ȁB���S�̓s�V�b�Ƃ��Ă��Ȃ�����ӂ͏��������������Ă��āA���ꂪ���̊��ɂȂ���Ƃ����悤�Ȍ����������Ă��܂��B�Ӂ`�ޗ��̊����Ӑ}�I�ɉ��o���Ă���̂����B
�|���Ė{�����Y�̏ꍇ�͂ǂ��ł��傤�B���̊����o�����߂ɂ����Ď��ӂɎ������c���H����Ȃ���N�\���炦���I����MTF�͉������ł��꒼���ɂ���I�c�Ƃ����}�b�h�T�C�G���e�B�X�g�Ȋ��������Ȃ��ł��Ȃ��c�܂����������O�ꂵ���Ƃ����ǂ��̂ł���
�����ԍ��F19730573
![]() 3�_
3�_
��ѕ��Ɍ����ẮA�É����[�h���~�߂ă��J�V���b�^�[�ɖ߂��܂����B�掿�������ǂ��Ȃ낤�Ɓu�c��ł��c�v�Ƃ����^�S�ËS�Ɏ��̃K���X�̃n�[�g���ς����Ȃ��c
��ѕ��̉掿����ŁA���ƍl�����鎖�cAF�̐ݒ�ƌ����Ă��F�X�����ł���ˁB�����g���Ă�uAF-C�{�����A�ʁv�̐ݒ��AF�^�[�Q�b�g�̎g���������掿�ւ̉e�������肻���ł��B�҂Ă�A���������AAF���b�N�I�����Ă̂�����܂����ˁB���̐ݒ�����Ă݂�Ɓu��v�ɂȂ��Ƃ�B�����E-M1�̃I�[�i�[�Y�u�b�N�œ������̐ݒ�Ƃ��Đ�������Ă�������Ȃ�ł����A���Ⴀ�u�W���v�ł͂Ɓc�債�ĕς���Ȃ��B�u���v���ƃs���g�̐�ւ�肪�g��ł悤�ɂ������ƂȂ��āA���������Ȏ��ɂ͂ǂ����C�����ǂ��Ȃ��B�uOFF�v�ɂ���ƃs���g�̐�ւ�肪�����Ȃ��Ă��킵�Ȃ����A�ǂ������̏ꍇ�́A�ǂ�������ł����ƘA�ʂ��Ă��̒�����E������A����܂�W�Ȃ����B
����H�uOFF�v���ƃs���{�P�̃J�b�g�͑����邪�A�s���g�������Ɖ掿�����ǂ��C�����܂��B������掿���Ԉ������ă��b�N�I������̏����e�ʂɉĂ����Ƃ��I�H�����Ǝ����Ă݂Ȃ��Ƃł����A���\�V���b�N�����c�I���̐t��Ԃ��`�I
�����ԍ��F19733941
![]() 2�_
2�_
�n�C�L�[�ŏt�炵���C |
���C |
���̖��͊�点�Ă���܂��B�@�{�P�̉ԂƁi�g���~���O�{�I�o��j�C |
�ŋߔ��ł���Ȃ��B�@�R�~�~�i�H�p�j�𗧂Ă��Ƃ�����f�W�^���e���R���ŁC |
Captain Caribe����C
�@���v���Ԃ�ł��B
�@���C�Q�l�ɂ����Ă��������Ă܂��B�@AF�ݒ�����܂���ˁC�V�`���G�[�V�����ɂ���ēK���Ȑݒ�͈قȂ�悤�Ɏv���܂��B�@�u�G��m��Ȃ�m��E�E�E�v�ŁC����̋����C����Ƃ̋����i�Ώۂ̃t���[�����̑傫���j�ƁC�����̃t���[�~���O�̘r�O�łǂ̐ݒ肪�����܂肪�ǂ��̂��C���X���s���낵�Ă��܂��B�@�͂�쌴�w�i�ł̃R�~�~�ł� AF��� MF�C���ډ��̌��_�ł��B�@���邢�����Y���ƈ���Ă��邩���H�C�ł������z���ǂ����܂���B
�@�Ƃ���ŃX���傳��͓������̎��i�Ⴆ�ΐ������������o���̍��j��U���͂ǂ�����Ă��܂����H�iOFF�H�CAUTO�H)
�@�t�����g�e���R���ł����C���\�d���ĐL�т������ɂ��Ȃ薳�����|�����Ă���悤�ŁC�Y�[�������O�̒�R�������܂��B�@�܂��莝���ł̓u���������܂���B�@�Ȃ̂Ńf�W�^���e���R���ɕ����Ă܂��B
�����ԍ��F19734749
![]() 3�_
3�_
��divecat1954����
�n�C�L�[�̕��͋C�ǂ��ł��ˁB���ʐ^���摜���ʂň�ۂ��ς��̂��y�����ł���ˁB��U���̓I�[�g�̂܂܂ň�x���������Ă܂���B������掿�ɉe���������ł��傤���B���肻���ł��ˁc
�����̎B�����ʐ^�����x�����Ԃ����肵�܂����H���͂܂������ł��B�B�������́u�ǂ��ȁv�Ǝv���̂ł��������ɐF�Ă��銴���ł��B�ł��D���ȏ����≹�y�͌J��Ԃ�������Ǒ̌��ł��܂���ˁB���͎Ⴂ���ɗ��s�����t���[�W�����������ɖO�����ɒ����Ă��܂��B�t���[�W�����̓{�[�J�����Ȃ��C���X�g�D�������^���ł����A���x�����Ă�����悤�ȏ��Ǒ̌��ł���Ȃ�����܂��B�ʐ^�ł������������o��\���ł��Ȃ��Ƃ悭�v���܂��B�i���̃n���h���l�[�����t���[�W�����̃q�b�g�i���o�[�j
�����ԍ��F19755046
![]() 3�_
3�_
�����q�o����ɖ��C |
�z�I�W���͚���C |
�`���E�Q���{�E�͌���Ă��C�R�~�~�͎p�������܂���ł����B�i�S�Ă��Ȃ�g���~���O�j |
Captain Caribe����C
�����́C���v���Ԃ�ł��B
�������̎B�����ʐ^�����x�����Ԃ����肵�܂����H
�@���[�J���̃R���N�[���ɉ��債���肵�܂��̂� B5�� A4�Ƀv�����g����̂ł����C�̂Ă�͔̂E�тȂ��̂ŕ����ɏ����Ă܂��ˁB�@�������C�ǂ��Ȃ�������ڂɂ��܂��B
�@�J���Z�~�A�܂����ł��C���̃t�B�[���h�ł͂߂����ɂ��ڂɂ�����܂���̂ŁB�@�J���Z�~�̃_�C�u����x�������Ƃ�����܂����C���̑f�����������Ȃ�Ƃ������Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B
�@��U���̗L���łǂ��ς��̂��m�F���Ă݂����Ǝv���̂ł����C���̂Ƃ���̐S�̃R�~�~������Ă���܂���B�@���N�Ɏ����z���ɂȂ肻���ł��B
�����ԍ��F19770736
![]() 2�_
2�_
��divecat1954����
�����b�A�����q�o���Ƀz�I�W������ł����B���ꂪ�Ȃ��Ȃ��B��Ȃ��ł��B�q�o���̓}�S�}�S���Ă��邤���ɏ��֔����čs���Ă��܂����A�z�I�W���͕q���ŋߕt���Ȃ����B�g�����Ȃ��ăc�o�����߂��ė��n�߂܂����ˁB�܂���Z�u�~���B�@�v�̏o�Ԃł��i���肫�蕑���Ƃ������j
�G���F���X�g�i���c�y��A�������j�Ƃ����f������܂����B�l�b�g�ō��]����Ă����̂ŁA���鋰�錩���̂����A�ӊO�Ɋ��������B���n�Ń��P�������������āA�ߍ��Ȏ��R�`�ʂ̔��͂��n���p�Ȃ��B�A���s�j�X�g�̖��������̃u���O�ŁA�z���g�̍��n�̎ʐ^���������A����������āA���Ɨׂ荇�킹�̔������ł��B���ʐ^�ł��������Ǝv���̂����A����퐫�͐l�̐S��ł��̂�����܂��ˁB
�����ԍ��F19772938
![]() 2�_
2�_
�I�����p�X�̒����o�c�v������Ă�ƃJ�����ƊE�̊��ω��̑傫������������܂��B�I�����p�X�̔����8�牭�~������Î��Ƃ����C���ŁA�J�������Ƃ̔���͂���1����800���~�قǁB3�N�O�͂��ꂪ1�牭�ȏ゠�����̂ŁA����2���ȏ�k�����Ă���B�X�}�z�̕��y�ɔ����f�W�J���s��̏k���͐��܂����B3�N�O�̉c�Ƒ����������2���Ƃ����S��A���Ƃ����ƍ\�������ăg���g���ߕӂ܂Ŏ����Ă����悤�����A���C���̈�Î��Ƃ��D���łȂ�������A��̂Ă��ĂĂ����������Ȃ��B
�ł��p�C�͍X�ɏk�����Ă�����ł��傤�ˁB�o�C�N�ɏ���Ă����A�o�C�N�G���ȂǓǂ�ł܂������A�������A���`�����ɏ���Ă��I�o�����B���y�����Ԃɏ��ւ��A�\���������Ȃ��Ȃ�A�e���[�J�[�̃��C���i�b�v���啝�ɐ�������A�o�C�N�G�����ǂ�ǂ�p���ƂȂ�A�u�����������Ƃ��N����̂����v�Ɗ��S������܂������A�J�����ł��������Ƃ��c�H
�����ԍ��F19776075
![]() 3�_
3�_
�����Ə���͏������Ă��܂����B�ŏ��̓z�b�g�V���[�ɕt���Ă����̂����A���ł��Ă邩�ǂ������������B����Ȃ�ƍ��ł̓d�q�������}�ɂ���ƁA�w�i�ɍ��ł��Ă��s�b�Ɩ�̂Ńs���{�P�A���B�Ə��}�[�N����������AF�G���A�ɍ��킹�悤�ɂ��A�Ə���ɑ���ڂ̈ʒu���Œ肳��Ă��Ȃ��̂ŁA���悤���Ȃ��B�Ə�����t�@�C���_�[�̉��ɔz�u�ł���u���P�b�g�������Ă݂����A����͂���ňʒu���߂ƃ}�[�N�������ʓ|���B���������Ȏ��͂��̎��_�Ŕ������F���̐o�ƂȂ��Ďl�U�����c
�����ԍ��F19790946
![]() 0�_
0�_
�F�{����ςȂ��ƂɁc��Ђ��ꂽ���ɂ͂��������\���グ�܂��B���͊֓����Z�ł����A�n�k�������ɓ������Ƃ����b�������Ċo�債�Ă܂��B
�}�C�t�B�[���h�ł́A�O�r�Ƒ�C�����Y�œy�肩��B��l�ƁA���݂����Ɍy�ʃV�X�e���������ĉ͌�������l�����܂��B�ƌ����Ă��A�����̂����ő���������ꂽ�肵���炩�Ȃ��̂ŁA����܂�Y�J�Y�J���荞�܂�悤�ɂ��Ă܂��B�����L�тė��āA����ɂ����Ȃ����̂����邪�B�쒹�̕ߊl�◑�̍̎�͒��b�ی�@�ŋ֎~����Ƃ��ł��ˁB�ᔽ������P�N�ȉ��̒���100���~�ȉ��̔����Ƃ��B
�����ԍ��F19792894
![]() 1�_
1�_
�L�W����͒n�k�̑O�����@�m���Ė��Ƃ����b���̂���`����Ă���R�B���ۂ̏��͐l�Ԃ̐��b�O���x�����������B���Ƃ��n�k�\�m���ďo�������ł����ˁB
�����ԍ��F19796492
![]() 2�_
2�_
�i�X�Ɩ��炩�ɂȂ�F�{�̎S��Ɍ��t���o�Ȃ����A�����đ��l���ł͂Ȃ��B���{�͕����̃v���[�g���Ԃ��荇���n�k�̑������A�ȑO�ǂn�k�w�҂̖{�ɂ��ƁA���ꂼ�ꂪ�Ɨ����Ă����ł͂Ȃ��B�n�k�G�l���M�[�̌��́A�v���[�g���݂��ɂԂ��荇���ď��X�ɒ~�ς����c�݂����A����͓��{���c�f����e�v���[�g���E�ʂŋN�����Ă���B���̂����̂P�J���Œn�k���N����A�c�݂��������Ă��܂��ƁA���̕����̉ӏ��Ŏ����������镉�S�������B�܂荡�܂őS�̂Ŏ����������Ă����c�݃G�l���M�[�̕��S���W�����A�A���I�Ɏ��X�ƌ��E�����Ēn�k���N����\��������B�����n�k�w�I�Ȏ��ԒP�ʂ͐��\�N�ȏ�̘b�ł����āA�Y�ꂽ���ɂ���ė���A�Ƃ����������o�傹�˂Ȃ�ʕ|��������B
�����ԍ��F19797012
![]() 1�_
1�_
�u���������́H�I�v�C�u�ׂ������Ƃ������Ǝ����Ă��I�v |
���̘A�ʂ͑Ώۂ����������� AF-C�ō��ł��܂����B�@���̔��F�������Ă�̂��ȁH |
�s�̂̋���ƃ{���g�i�b�g�ŎO�r���ɕt���Ă܂��B |
Captain Caribe����G
�����́C
�@�c�o��������肵�Ă��܂��ˁC������ƃL���L�������ė��܂����B
�@���͏Ə���� 3���ڂ̂悤�ɕt���Ă��܂��B�@�E�ڂ� EVF���C���ڂŏƏ�������āC���ᎋ�͂ł��Ȃ��̂ŏƏ���Ń^�[�Q�b�g��ǂ������ăt�H�[�J�X�͒u���s���C�܂��� AF-C�i���� 9�����j�ŃJ�����C���ł��B�@�Ώۂ��������������ɂ� AF-C���ǂ��撣�����Ɗ����܂����B
�����ԍ��F19802028
![]() 2�_
2�_
��divecat1954����
�����A�C���c�o���ł��ˁB�c�o�����C���c�o���̕��������čD���ł����A�E�`�̃t�B�[���h�ł́A��������ʉ߂��邾���ŎB�ꂽ���߂����Ȃ��ł��B�Ə�����Ďs�̂̋���ŕt������Ȃ�ł����B�H��̓[���A���������ł��������o�����i�̎��ł͂ƂĂ��g�����Ȃ���A�C�e���ł����B
���̊Ԃɂ��A�\�j�[����E�}�E���g��300mm�Y�[�����o���Ă܂����B��6000���g���Ă����́A����Ȃ̂�����ȁ[�Ǝv���Ă܂������A���ƂȂ��Ă͊��Z450mm�Ƃ����̂����r���[�Ɋ����Ă��܂��܂��B�����ED�����Y��2���ł����BSEL55210��2���ł������A�p�[�v���t�����W�����\�o�Ă܂����B�{�����Y��3���i�X�[�p�[ED������̂Ŏ���4�������j�A�T��������3���i�S���X�[�p�[ED�Ŏ���6�������j�A�t�W��XF400mm�Y�[����6���i����7�������j�ł��B���x���������܂����B
�����ԍ��F19804342
![]() 2�_
2�_
Captain Caribe����G
�����́C
�@���������X���傳��́h���h�����g���������̂ł���ˁB�@�ŋ߂̃�6300�� AF�ɂ�����Ɩ�����܂����C���̓j�R�P�̊��Z 810mm���� m4/3�Ɉڂ��ė����̂ł��̃����Y�̊��Z 600mm�ł� �������Ȃ� �Ǝv���Ă��܂��܂��B�@�Ƃ͌����C�e�Ђ� 300mm�����Y�̒��ł͍ۗ����Čy���i�Â��ł����E�E�E�j���C�������ɗǂ��ʂ�܂���ˁB
�@�C���c�o�����Ă�����Ƃ��肵�Ă��āC��Ԏp���W�F�b�g�퓬�@�iF86�Z�C�o�[�C�Â��I�I�j�̂悤�Ɋ����܂��B�@���ʂ̃c�o���̓O���C�_�[���ȁB
�����ԍ��F19807679
![]() 2�_
2�_
��divecat1954����
�j�R�����͎����������܂����B�R���p�N�g����AF�����͂������̂ł����A�F�X�C�ɂȂ鏊�������āA�I�����p�X�ɗ���Ă��܂��܂����B�{�����Y�̓T��������EF�Y�[���ȂƔ�r�����Ⴄ�ƁA�𑜗͂ɂ͌��E������Ȃ��Ǝv���܂��B���Ƃ����ďd�������Y���S�O����̂ł��B���͓��ꂾ���ő�^�o�C�N�������̂́A������O�Ɏ����ɂ͏�肱�Ȃ��Ȃ��������A���l�ŏ��������Ƃ����Â��ߋ������j�Ȃ̂Łc
���͉��̒������̓n�������悤�ɂȂ�����ł��傤�B�R�A�W�T�V�̓j���[�W�[�����h�ӂ肩��ԓ����z���Ă���Ă���݂��������A�c�o�������̂��������g�̂œ���A�W�A������ł���悤�ł��B�v���[�g�e�N�j�N�X�Ƃ��W�Ȃ��̂ł����ˁB
�c�S���h���i�嗤�ɐ��܂ꂽ�������ނ̑c��͂₪�ĈٕςɋC�t���n�߂��B
�u�����A�ŋ߉��������ˁH�v
�u���ȁB�����Ŏq��Ă���̖��������ȁB�k�ֈړ����Ă݂�H�v
�u�����v
�������Ē������͓n��̏K����g�ɕt�������A�嗤������ƈړ��𑱂���ɘA��A���̈ړ������͂ǂ�ǂ��Ȃ�̂������c
�����ԍ��F19810596
![]() 2�_
2�_
�~�܂蕨��C-AF�ƍ����A�ʂŎB���Ă܂��B�ŏ���S-AF�ŎB���Ă���ł����A���͘A�ʂ��Ă��̒�����}�V�Ȃ��̂��E���K���Ȃ̂ŁAS-AF���Ɠ����悤�ȃR�}���茩��悤�ɂȂ��Ėʔ����Ȃ���ł��ˁBC-AF���ƁA������ƃ{�P�Ă݂���N���A�ɂȂ�����ƁA�g������̂��ʔ����B�A�b�v�ŎB�ꂽ�����͋�X�߂��Ɏ~�܂������b�̂����ɎB�������̂������̂ł����A�A�ʂ̍ŏ��̓N���A�ɂȂ�ɂ����āA�P�b���炢�o�����ӂ肩��N���A�ɂȂ�n�߂��ۂ�����܂��B��U�ꂪ�܂����������Ă��Ȃ��e�����傫���̂��ȁB
�N���I�u���Ƃ��̈�o������ˁ[���v�Ȃ�ăz���g�̂��Ƃ������Ƃ�̂́I
�����ԍ��F19815810
![]() 2�_
2�_
�ŋ߁A��ѕ��͎�U����OFF�ɂ��ĎB���Ă܂��B�u���̂Ђǂ��J�b�g�͏o�Ă���̂����A�����ƎB���Ɖ掿���V���[�v�ɂȂ�C�����܂��B
E-M1�ɂ͘A�ʒ��̎�U���I���E�I�t�Ƃ������j���[�������āu�H�v�ł������A����͎�U����A�ʒ�����������ƘA�ʑ��x�������x���Ȃ邽�߁A�����đI���@�\��݂��Ă���悤�ł��B��U���ɂ͂ǂ����Ă�������x�̍쓮���Ԃ������邩��ȂƎv���܂����A�����ňړ����̔�ʑ̂ł͂��̍쓮���ԕ������u���Ďʂ��Ȃ��낤���A�Ƒf�l�l�����Ă݂���B
�����ԍ��F19819104
![]() 2�_
2�_
Captain Caribe����G
�����́C
�@�X���傳��͑��ς�炸���͓I�ł��ˁB
�@�x�ꂽ�R�����g�ł����C�c�o���͔w���ɑ��z�����������āu�ʂ߁v���ƌ����Ă���̂��ǂ��ł���ˁB
�@����ɂ��Ă��J���Z�~�͑A�܂����C�S������̃t�B�[���h�ɒT���ɏo������̂ł��������邱�Ƃ��ł��܂���B�@����ɃV�W���E�J���ɗV��ł��炢�܂����B�@���ނ��^��ł��ē����R�[�X���s��������̂Ő��ʂ���̔�юp���B�����̂ł����C���܂�H�����Ȃ���ł��ˁB�@�����ŏK�������������v���o���܂����iPaint�Ő�\��j�B
�����ԍ��F19819476
![]() 2�_
2�_
��divecat1954����
���͂��A1���ږʔ����ł��ˁB�Ȃ�قǁA1�H�̃V�W���E�J���̋O�Ղ�ǂ������̂Ȃ�ł��ˁB�e�ۂ����ł��݂����ł��B�L�r�^�L�͔w�������F�Ȃ�ł����B���݊����o�܂��ˁB
�ӂƎv���o�����̂����A��6000����E-M1�Ɉڂ��Ĉ�a�������������Ƃ̈�ɁA�u�B�ꂽ��������Ȃ������̂ɎB��Ă��v�Ƃ����̂��������B���́A�s���g���������悤�ɂ͌����Ȃ������̂ɁA�����ƎB��Ă��Ƃ����Ӗ��ł��B���̒��ł͓�̂܂܈ӎ��̒�ɖ�����A�i�炭�s���s���ƂȂ��Ă����̂����A�u����̓t�@�C���_�[�̒Ǐ]���̍��������̂ł́v�Ǝv�����������B�t�@�C���_�[�����ۂɎB����̕\���ɒǂ��t���Ă��Ȃ�������Ȃ����ƁB
�r���Ńt���[�����[�g�ݒ���u�W���v����u�����v�ɕς����������A���͓��Ɉӎ����܂���B�i���ꂽ���������jE-M1�̕\���^�C�����O��0.016�b�i�u�����v�ݒ莞�j�ł����AE-M5 Mark2�ł�0.010�b�Ȃ̂ŁAE-M1�����@��ł͒Z�k���ꂻ���ł��B
�����ԍ��F19821817
![]() 3�_
3�_
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y��APS-C�ɔ�ׂ�Ƃ�͂���_�������Ă��āA����͉�f���ł��B��6000�i24�S����f�j����E-M1�i16�S����f�j�Ɉڂ��Ĉ�ԍ����������̂͐��ʂ̕`�ʂŁA��6000���Ɠ����������邪�AE-M1�ł̓U�����BGX8��PEN-F��20�S����f�ł����ЂƂȊ����ł��B�t�B��������̃l�C�`���[�ʐ^�Ɣ�r����ƁAE-M1�ł����Ȃ荂�掿�Ȋ����Ȃ̂����A�f�W�^������̍���f�ʐ^�͂����ʎ����̂��̂��ƌ��킴��Ȃ��B
�\�j�[�̓����Y�������ɂ��Ă��A400mm�Y�[�����o�����t�W��24�S����f�Ɉڍs�����̂ŁA�g���Ă݂邩�Ɩ����Ă܂��B�Ƃ͌����{�����Y�V�X�e���̌y���E�n���h�����O���Ղ��͈��|�I�ł��c
�����ԍ��F19824604
![]() 1�_
1�_
��Captain Caribe����G
�@��O�̃R���Chttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463666/SortID=19070879/ImageID=2482858/�C�f�G�ȉ�ł��ˁC�A�W�T�V�ł����B�@�n��̘b�肪����܂������C�L���N�A�W�T�V�͈�N�ɖk�ɂƓ�ɂ𔒖�����߂ĉ�������炵���ł��ˁC���� 32,000km���Ƃ��B
�@���̓n����H�C�������邩�炳�I�C�Ȃ�ĂˁB
�@�ӂނӂށC�u�t���[�����[�g�������Ɂv�ˁB�@�ȂB�������������悪�B��Ă�����C�B��������̉悪�B��Ă��Ȃ������肷��̂ŃJ�X�^�����j���[���m�F����ƁC�W���̂܂܃O���[�A�E�g���č����ɐݒ�ł��܂���ł����B�@�{���C�ߋ��X��������܂������C�s�[�L���O���g���ƍ����ɐݒ�ł��Ȃ������ł��B�@�C�}�C�`���ĂɂȂ�Ȃ��s�[�L���O�C�����~�߂悤���ȁB
�@�ŋ߁C��p�������ł��C�O����߂Â��Ɠ������Ă��ł��傤���H�@�@
�����ԍ��F19825075
![]() 2�_
2�_
��divecat1954����
�W���E�r�^�L�̌��Ԃ���l�A���܂��Ă܂��˂��B�R�A�W�T�V�́A���̗��݂������藧���Ă��āA�������炾�Ɩڂ̑O�Ńz�o�����O���Ă����Ƃ����|�C���g������̂ł��B���̎����̋x���́A�����J�������\�����l�����܂��B
���t�ɒ��������Y��t�����l�������ł����A�F����B������ɔw�ʉt���Ŋm�F���Ă܂��B���͉t���͉��O�ł͌���̂ŁA�m�F�͂����t�@�C���_�[�ł��B���̓_�̓~���[���X���L��ł��B
�����ԍ��F19827359
![]() 2�_
2�_
�{�����Y��MTF�Ȑ��ł́A���ӕ����ɍs���ɏ]���āA���˕����Ɠ��S�~�����̐����傫������Ă����B���̃p�^�[���́A��ʂɔ�_�����̉e�����傫�������ȁB��_����������Ɠ_�����_�Ƃ��Ďʂ�Ȃ��A�c�_�Ƃ����_�Ƃ��Ďʂ��Ă��܂��悤�ł��B
�Ȃ�قǁA���������Ӗ��ł͖{�����Y�̂悤�ɕ��˕����̂݃t���b�g�Ƃ����̂łȂ��A�T�������⑼�Ђ̑�C�����Y�̂悤�ɁA���˕����E���S�~�������݂��ɋߐڂ��Ă�������𑜊����ǂ����ƂɂȂ�B���������Y�ɂᏟ�Ă�̂��c
�����ԍ��F19830215
![]() 2�_
2�_
��Captain Caribe����G
�����́C
�@�R�A�W�T�V�Ȃ�ł��ˁB�@�ǂ���ʑ̂��ǂ��B�e�ꏊ�ɋ��Ă����͖̂���̍K���ł��ˁC�J�����̐��\���ɂ߂��邵�C�B�e�҂̘r�����邱�Ƃ��ł��܂��B�@���͍�N�R�~�~�Y�N�ɏo����Ă��炷�����蒹�B��ɛƂ��Ă��܂��܂����B�@�����C���ǂ������Y�C���ǂ��{�f�B���~�����Ȃ��Ă��܂��Ė��ӕ��~�Ɗi������H�ڂɁE�E�E�E�B
�@�iI was thinking to myself,"This could be Heaven or this could be Hell"
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E
�@�@"You can check-out any time you like, But you can never leave! "�j ---- Hotel California �ł��ˁB
�@���̃����Y�C�{�P���C�ɓ���Ȃ��i����{�P���Č����̂ł��傤���j�ꍇ������܂��B�@�܂��C����Ȕw�i�ŎB��Ȃ���Ηǂ��ƌ�������܂łł����E�E�E�B
�@
�����ԍ��F19831051
![]() 1�_
1�_
��divecat1954����
�����{�P���͍D�����Ⴀ��܂���˂��B���������40-150mmPRO��T�����������������������āA�I�����p�X�̓{�P�����]���ɂ��ĉ𑜂�Nj����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
���~�͉E�ɓ����ł��B�ǂ��@�ނ�������đf���炵���ʐ^���B����Ȃ��Ƃ͎v���A�K���̐�����T���Ă��܂��܂��B�ł��܂��A���ꂱ��l����̂��y�����ł���ˁB�@�ނɂ����AF��掿���Ⴄ�͎̂����ł����B
�P���g���Ύ��̃u���O�ŏЉ��Ă����t�F�C�X�u�b�N�̓����J�������Ƃ����̂�`���Ă݂��B����[�A�A�[�e�B�X�e�B�b�N�Ȏʐ^����Ő����I�@�ނ����邱�ƂȂ���A�I�m���̊����������ɂ�Ȃ�܂���ˁB
�����ԍ��F19833261
![]() 1�_
1�_
�}�C�t�B�[���h�̉͌��͓d�Ԃōs���܂��B���ł������}�C�t�B�[���h�ɂȂ������Ƃ����ƁA�ŏ��̓c�o�����B�肽���āA�l�b�g�Ńc�o���������������w��T���čs�����̂ł��B�ł��w�ɓ��̓��C���[���āA�����������Ȃ��悤�ɂ��Ă������B�������肵�����A�܊p�����̂�����ƁA�͌��֕����čs������A���������͋C���ǂ��āB���̉͌��ւ��F�X�s�������ǁA���������������Ƃ������B���߂͕�������������\�F��Ȓ�������܂��B
�����ԍ��F19835978
![]() 0�_
0�_
�X�Ȃ�掿�����ڎw���čl�������ʁA�����Y�̕ی�t�B���^�[���O�����ɂ����B�t�B���^�[���[�J�[�̃T�C�g�Ŋm�F����ƁA���ߗ���98.5%�ƂȂ��Ă���B�Ƃ������́A���̃t�B���^�[�͌���1.5%���Ղ��Ƃ�̂��B����łȂ��Ă��Â������Y�������イ�̂ɉ����Ă���Ƃ�˂�I
�ł͂Ɓc���������I���A����́I�c�Ƃ����������Ⴀ��܂���ˁc�ł������Ⴄ�悤�ȁc
�����ԍ��F19839237
![]() 2�_
2�_
�ʋΘH�̓r���ɂ���I�t�B�X�r���̎Ԍɂ͋x���̓V���b�^�[���܂�B
���̑O�̒n�ʂɎ~�܂�c�o�������������B���N�������̓V���b�^�[���J���Ă��邽�߁A�Z������щ���đ���肵�Ă������A�x���ɂȂ�ƒ��ߏo����ēr���ɕ��Ă�����Ȃ����B�l�ԂȂ�Ă��Ăɂ�����C�J���̂ɁA�Ɣ߂����݂Ă���ƁA����H�V���b�^�[�̌��Ԃ��璆�ɂ����肱�I
����ƁA���N�̓V���b�^�[�̉��ɔ����܂��ċ͂��Ɏ����グ�Ă������B
�j���Q�����ėD�����l��
�����ԍ��F19842404
![]() 0�_
0�_
���āA�ق�������A�b�v���Ă��܂��܂������A������ӂŏ��������Ǝv���܂��B�i��H�ǂ����ŕ������䎌�c�j�F�X�l�������A�x�m�t�B������400mm�Y�[���������Ă݂邱�ƂɌ��S�����܂����Bdivecat1954����A���݂܂���A���~�ɔs��܂����c
�{�����Y�́A���T���̂悤�Ɏ����o�������łȂ��A�𑜌��E�ׂ���A�{�f�B�̐ݒ�ʼn掿�������ɕς�邱�Ƃ�̊�������ƁA�������y���߂܂����B���肪�Ƃ��B
�����ԍ��F19842409
![]() 3�_
3�_
��Captain Caribe����G
�@�������`�C�}�E���g�`�F���W�ł������`�I�@�@�p�i�� LEICA�ł͂Ȃ��� X�}�E���g�ɍs���̂ł��ˁB�@APS-C�ɕ��A�����̂͌���� m4/3�ł͉�f���s���Ɗ�����ꂽ�̂ł��傤���ˁH
�@�Â��s�k�ł��ˁC�x�m�̃{�f�B�͂������Ȃ̂ł��������H�@�@����V���n���y����ł��������B
�@�X���傲��J�l�ł����C�֏悵�Ċy���܂��Ă��������܂����B�@�c�o�����B��ɏo�����Ă͂���̂ł����C�܂��q��Ă��n�܂��Ă��Ȃ��̂��C�}�C�`�����ȍ̉a�������ǂ��V�[���ɏ��荇���܂���B�@�ɂł����ق��������B
�ł́C�܂��ǂ����ł�����܂��傤�B
�����ԍ��F19843112
![]() 3�_
3�_
�F����̍��A�f�G�ł��ˁB
�����Y�̐��\�����O�ɘr���Ȃ��̂Ŕ��Ďʐ^�͎B��܂���B
���̃����Y�̖��͂͂�͂�@�����AE-M5 MarkII�̃o���A���O�����������āA
�ϋɓI�Ƀ��[�A���O���ł̒��]�����y����ł���܂��B
����Ȃ��Ƃ����肵�Ă��邩��A45�x������グ�ăN�}�Q��������B�e����ہA
������S���C�ɂ�����Ō�����Ă��܂��̂ł��i���j
�����ԍ��F19994124
![]() 3�_
3�_
�������̎q��G
�����́C���߂܂��āB
�@�����̃X���傳��� X�|�}�E���g�̕��ɂ����z������āC���������ɂȂ��Ă����Ȃ������m��܂���̂ŁC�G�z�Ȃ��玄���烌�X�����Ē����܂��B�@�@Captain Caribe����C��ڂɌ��ĉ������ˁB
�@1���ځF�w�i�̃L���L�����f�G�ł��C�܂��e���̖ڐ������[�A���O���̌��ʂ��o�Ă���Ɗ����܂��B
�@2���ځF���͂��̂��炢�̏œ_���������Ȃ̂ł����C����������[�A���O���̌��ʂł��傤���C���K���ɒ��ԓ��肵�������ł��B
�@3���ځF�����������̕s���芴���ǂ��̂ł́E�E�E�H
�@������ѕ����B��̂́C�G�S���s�����Ă��鏊���ʑ̂ɃJ�o�[���Ă��炨���Ƃ̍��_�ŁC�w�^�ȓS�C���茂���Ă܂��B
�@���̃����Y�Â����ǁC�y���ăR�X�p���ǂ��āC���[�A���O�����n�ߎ莝���ł���y�ɐF�X�����Ċy���߂�X�O�����̂ł���ˁB
�����ԍ��F19997329
![]() 4�_
4�_
��divecat1954����
���߂܂��āB���肪�Ƃ��������܂����B
�X���傳��͂��߁A�F�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ��������������v�炢��������ڂ��܂����c
�悭�l�����2���ڂ̎q�K���͕ʂ̃����Y�i14-150II�j�ł����ˁB���炵�܂����B
1���ڂ̃I�V�h���e�q�̃L���L���̐��̂́A���̎������L�̃|�v���̖Ȗтł��B
�e�q�̓����삵���Ȗт���ѕY���Ă���̂ł����A���̂ӂ�`���ƕ��V����_������EVF����`���Ă݂�ƁA
���ߑ����o�邭�炢�������ł��B�����������ɂƂ����ɓ���ɐ�ւ����Ȃ����̌ł����Ȃ�Ƃ����������̂ł��B
�N�}�Q��������ڂ���摜���Ԉ���Ă܂����B
JPEG�B���ďo���B�����������A�R���g���X�g�������Y�{���̃|�e���V�����������o���Ă���܂���B
���ډ����ɂȂ�Ȃ���Ηǂ��̂ł����c�B
�����ԍ��F19999701
![]() 2�_
2�_
�����̎q��Adivecat1954����A����ɂ��́B
�y����ł�����Ⴂ�܂��ˁB�N�}�Q���������Ă݂����ł��B
��������o�����i�͂Ȃ��̂ł����c
����X-Pro2��XF100-400�ŎB���Ă܂��B�Ⴂ�����X�B
�ǂ��̂́A����f���𑜂Ńg���~���O���Ă����ׁBAF���x���ǂ��B�����Y�`�ʂ��@�ׁB
���`��ȓ_�Ƃ��ẮAE-M1�̂悤�Ɋe��ݒ��o�^���ă����^�b�`�Ő�ւ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�i�r�b�N���ł��B�j�т̒��Ȃǒ�Ɠx�ł�AF���x���B��6000�Ɠ����ŋ�w�i�����B
���߂Ďv���܂����AED75-300�̕`�ʂ͂�͂�Ɠ��ŁA���Ƃ����̂��A�V���t�Ń}�W�Ńn�[�h�{�C���h�H�x�m�t�B�����̓e���r�J�����p�̃����Y�������ƍ���Ă܂����A�I�����p�X�̃��[�c�͌������ŁA�o�b�N�O���E���h�̍����e�����Ă���̂ł͂Ǝv�����肵�܂��B
�ł͎��炵�܂����B
�����ԍ��F20032376
![]() 1�_
1�_
��Captain Caribe����G
�����́C���v���Ԃ�ł��B
�@�����ƍĂя������݂�����Ǝv���Ă܂����I�I�@�@�Ƃ͌������̂� m4/3�͈ꎮ�h�i�h�i�����������ł����H
�@�t�W�̃V�X�e���͉������w�_�炩���x�ƌ������C�w�n�b�L���N�b�L�����ᖳ���x�ƌ������C�X���傳�ߋ��ɓ��e����Ă���J���Z�~�̉�Ɣ�ׂĂ��@�u�`���b�g�Ⴄ�Ȃ��C�v�@�Ǝv���܂����B�@�@�t�W�̊G���Ȃ̂��C�����Y�̐��i�Ȃ̂��H�C����Ƃ���f������������ł����ˁH�@�@�@�l�I�ɂ̓j�R���P�{1Nikkor 70-300�ŎB������Ɏ��Ă�Ɗ����܂������E�E�E�E�B
�@���āC�t�W�̃V�X�e���ł͔�ѕ��͂ǂ��ł����H�@�@���̍��N�̂��肫�蕑���̐��ʂ�\���Ă����܂��ˁB
�����ԍ��F20035605
![]() 3�_
3�_
��divecat1954����
���������I���A����́I
���͂���J�b�R�ǂ��ʐ^�ł��˂��B���������̖쒹���B���햡�̈�ł���ˁB
���̎ʐ^�A���ɊS�̖����Ɛl�Ȃnj����������܂��A��ɂ��܂��B���ƃW���[�b�Ɗ������āA��l�Ńj�^�j�^���߂Ă��܂��B
ED75-300��XF100-400�A�𑜓x�͕ʂɂ��ĉ掿����͂�Ⴂ�܂��ˁBED75-300�̓��A���e�B�������܂��BE-M1��ED75-300�͏������Ă��܂����̂ŁA�����̓t�W�̋@�ނ�˂��l�߂Ă݂����ł��B
�����ԍ��F20040468
![]() 2�_
2�_
��Captain Caribe����C
�@�i�炭�����������Ă��܂������C���V�[�Y�����̃R�~�~���ăV�[�������܂����̂œ\�点�Ă��������܂��B
�@C-AF�� MF�̕����܂�͓����x�ŁC�g�|�^���� 1000���B�������� 10�������ǂ��ɂ�����銴���ł��B
�@E-M1 markII ���Ƃǂ��Ȃ�̂��ȁ`�C�Ȃ�ĕ��~���E�E�E�B
�����ԍ��F20578534
![]() 2�_
2�_
��divecat1954����
�����������Ă���܂��B
�R�~�~�Y�N�̔��ėǂ��ł��ˁ[
�����}�C�t�B�[���h�ŒT���Ă��܂�����U�����B
�R�~�~�Y�N���Ď��ԑѓI��AF�͌��������ł��ˁB
E-M1markII�̃v���L���v�`���g���Ă݂����ł��B
�u�}�ʐ^�v�͂����O���O�����܂����c
�ł͂܂�
�����ԍ��F20602403
![]() 1�_
1�_
��Captain Caribe����G
���X���肪�Ƃ��������܂��B�@�n���u�T�̔�яo���C�����ł��ˁI
���n�ł����N�n���u�T�����鎖�ŗL���ȏꏊ������C���N�͈�x�s���Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂��B
E-M1 mk2�̃v���L���v�`���C�J�V�I�ł̓p�X�g�A�ˁCnikon1�ł̓x�X�g���[�����g�L���v�`���C�Ɠ��l�̋@�\�Ǝv���Ă��܂����C��������d�q�V���b�^�[�ł��̂ŁC�����ɃZ���T�[����̓ǂݏo�����x�������Ȃ��Ă���Ƃ����ǂ������̑�������C������ǂ��Ė]�������Y��U��ƃ��[�����O�V���b�^�[�c���������Ȃ��̂ł́C�Ǝv���C�}�C�`�ϋɓI�ɂȂ�܂���B�i�Y�t����� nikon1�ʼnߋ��ɎB�����R�~�~�̔�яo���V�[�����R�}���蓮��ɂ������̂ł��C�c��ł���̂�����܂��B�j
�R�~�~�̃o�g���V�[���͓ˑR�n�܂�C�������ǂ��Ŗu�����邩����܂���̂ő��͓Y�t�̂悤�Ƀs�������܂���B�@mK2�ł͂ǂ��Ȃ�̂������Č������͎v���܂����C���̂��߂����ɂ��̋��z���₷�̂��S�O���܂��B�@�@���������Ă��ɂ������Ԃ͂悩�����̂ł����C�|�`�|�`�Əo��������悤�ŁC���~��}����̂Ɏl�ꔪ�ꂵ�Ă���܂��B
�����ԍ��F20608457
![]() 1�_
1�_
��divecat1954����
�R�}���蓮����Ăł����ł����B���������ɉ��H������ł����ˁB�i�܂������������Ă܂���B�j�R�~�~�Y�N�̔�яo���̗l�q���ǂ�������ʔ����ł��B�j�R���P�̉掿���ǂ��ł��ˁB
�v���L���v�`���͓d�q�V���b�^�[�c�����ł���ˁBX-Pro2�ł��d�q�V���b�^�[�Ŕ�ѕ����B���Ă݂܂������A��͂�w�i���i�i����̂����������̂ŁA�g���Ă��܂���B�O���[�o���V���b�^�[�@���o��܂ł́A�C�ɂ����g����A�Ƃ��������ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł����ˁB
�p�i�\�j�b�N��300mm�Y�[���̓��j���[�A������āADual IS�A240fps�A�h�o�h�H�d�l�Ή��ŁA�����Ɩ��͓I�ɂȂ�܂����ˁBED75-300����U�������X�g�ݍ��ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤���A���̕��y�ʂ����AAF����̍�������h�o�h�H�d�l�͉\���Ǝv���̂ŁA���j���[�A�����l���ė~�����ł��B�o����ΐ�p�t�[�h���B
�����ԍ��F20612425
![]() 0�_
0�_
�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II
�}�C�R�`�_(��o��)�^�I
�����ԍ��F19068009
![]() 2�_
2�_
���W����̂��Ȃ����C�ɂȂ�܂��E�E�E
���s�ɂ܂�����Ō��悤���ȁi��
�����ԍ��F19068020
![]() 6�_
6�_
������o(^o^)o
�v���Ԃ�ɍs��������o(^o^)o
�����ԍ��F19068097�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����܂����Ƃ����܂��ˁB
�ʐ^���ǂ��ł��ˁB�����^�C���ɉf���钅���Ɨn�����ޕ��W�͂�B
�����ԍ��F19068101
![]() 1�_
1�_
���̃����Y�ɂ͒��ڂ��Ă܂��B
9�`18�ƍ��킹����A�ō��̗��J�����ɂȂ肻����o(^o^)o
�����ԍ��F19068135�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�c�[�V���b�g����V���b�g���B�������_���ł���Ă܂��̂Ő���B
�����ԍ��F19068146�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���̎ʐ^���t�H�[�N�V���K�[�Ɍ������
�݂�Ȃ��Ȃ������Ă��邩��`
��l�Ɉ������Ȃ��Ȃ���
�E�E�E���炵�܂���
�����ԍ��F19068234
![]() 1�_
1�_
�t���̃����Y�ɂ͒��ڂ��Ă܂��B
�t9�`18�ƍ��킹����A�ō��̗��J�����ɂȂ肻����o(^o^)o
�t���i�e������
�����������悤�ɗ��J����
�w�}�C�N��4/3�����Y�u�b�N�xP126:�R�������q��
�J������E-P5
�����Y��17mmF2.8&9-18mm&14-150mm
�������ɕM��I�����A�Ƃ͎v�������
�܂��ɂ����{�I�Ȃ���R�{
�P�œ_&�L�p�Y�[��&���{���Y�[��
���̃V���v���ȑg���킹��,��i���c����Ă���
�����ԍ��F19068289
![]() 2�_
2�_
�ǁ[������Ȃ�����
�������I
�����ԍ��F19069410�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���s�����ł��˂��`(*^^*)
������ݽޗ~�����`(>_<)
�����ԍ��F19071415�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����l�U������
�����s���������炢�ł�( ´_�T`)�J�̓��ł��C�ɂ��Ȃ��ł����̂ł��肪�����ł��B�B
�����ԍ��F19071699�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
m.zuiko14-150mm�U�͑��ɕ֗��Y�[���ȂǂƁA��i���Ɍ���ꂪ���ł����A���Ȃ�������ő�o�͗p�����`�S�̉ƒ�p�v�����^�[���������g���Ă���܂���̂ŁA���̒��x�Ȃ�t���T�C�Y���낤���A�`�o�r-�b���낤���A�͂��܂��}�C�N���t�H�[�T�[�Y���낤���A����ɒP�œ_���낤���L�b�g�����Y���낤���A����i�����ǂ��̂ȂǑS����ʂ���������̂ł͂Ȃ��ƌo����m���Ă���܂��̂ŁA����P�{�ōς܂�����̂͌g�ѐ����炢���Ă����ɏd��A�֗��ȃ����Y�Ǝv���܂��B
�@
�@�o�b�̓��{�摜�ł́A�t�H�[�}�b�g���f���A�����̗L���ʼn掿�̍��͗�R�ł����A�ʐ^�ł��̈Ⴂ�����o���͕̂s�\�ł��B
�@����䂦�AOM-D E-M1+m.zuiko14-150mm�U�͓���������Ȃ��Ǝv���܂��B�@
�����ԍ��F19087455
![]() 2�_
2�_
�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
������̃����Y�A�w�������ӂ������̂́A�I�����p�X�I�����C���ŗ\��ł������̂܂܂ɂȂ��Ă��܂��B
�w���ł��Ȃ��Ԃɗ�ÂɂȂ��čl���Ă���̂ł����A������̃����Y�����p�i��F4�����Y�����������ǂ��C�����Ă��܂����B
���R�Ƃ��ẮA
�E�Ȃ�Ƃ����Ă��������B�y���B�{1�{����Ƃ��Ɏ����o���₷���B
����ɂ��܂��B���i���͂��܂�C�ɂ��Ă��܂���B�iF4���\�������̂Łj
�Ƃ����킯�ŁA���҂Ŗ����Ă�����̂��ӌ��Ȃǂ������������ł��B
�E���ɗ����������ȕ�
�E�����悤��2�҂Ŗ����Ă����
�E�p�i�������Ă��ăI�������������Ă����
�E�I�����ăp�i�ɂ���Ηǂ������Ǝv������
�E�I�����ăI���ŗǂ������Ǝv������
�Ȃ��A���̎g�p�{�f�B��E-M1�ł��B�����Y�̓Y�[�������𑵂���ׂ��A�Ȃ�ׂ��I�����p�X���ɂ��Ă��܂��B
���낢��Ȃ��ӌ����������������ł��B
���āA���̋L�������Ă���r���ɃI�����p�X�I�����C�������璍���\�ɂȂ��Ă����̂Œ������Ă��܂��܂����B�B�B
���[�[�[�B�����������₵���̂ɈӖ��Ȃ��ł��B
���݂܂���B�I���ŗǂ������Ƃ����ӌ�������������������܂���B
![]() 6�_
6�_
���Ȃ�\��t���Ă��܂���B
���̓p�i������������R�Ƃ��ăp�i�����Y�̓����Y�Ƃ��Ă̎����ƌ��������L�~�ƌ������̂����܂芴�����Ȃ���������ł��B����Ȃ�ɍ����ȃ����Y�Ȃ̂ɃS�������O�ɚ����t���ĉ���Ă����̂�����Ƒ厖�ɂ��悤�Ƃ�������������Ă��܂��܂����B����͐l���ꂼ�ꂾ�Ǝv���܂��B(���͋����̕��������h�ł��B)
�I���̃����b�g�͖h�o�h�H�Ɖ����t�H�[�J�X�N���b�`���傫���Ǝv���܂��B
�����i���B�鎞�ɓd������꒼���Ă��������ɌŒ�ł���Ƃ��̂͋��݂��Ǝv���܂��B
�ƌ����Ă��܂��茳�ɂ͂���܂��c
�����ԍ��F19004146�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
�l�̓I�����p�X�̒lj�������Ă܂��B
��{�I�ɂ͏o�ڋ������Y�͎g��Ȃ��c�͂��Ȃ�ł����c����ς�~�����Ȃ��Ă��܂�o(^o^)o
���X�A�R���p�N�g�Ńt�B���^�[���g����9�`18�����p���Ă���̂�o(^o^)o
�lj������郁���b�g�͑傫���ł���H
�����ԍ��F19004323�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���@����Panasonic��OLYMPUS���J��������ɂ����̂�
���̍L�p�Y�[�������Y�̂����ł�
�J�����@�ނ��Pg�ł��y����������
Panasonic�Ȃ�f�l�P�{�V-�P�Sf4�̑I����204g�{300g=504g
�J������OLYMPUS��I�������
Panasonic�V-�P�Sf4�ł͐F���������
(�A�����̑g���킹�ł��f���炵�����͂���܂�)
OLYMPUS&OLYMPUS����400g���z����J������534g�������܂�
���̏d���͎R�����ł͂��Ȃ�̃n���f�B�ł�
������EOS-�l�Q�{11-22mm�ł���
���ǁ@
�R�����͌y�ʗD��Panasonic�{Panasonic
���i�g���ŏd�ʓx�O��OLYMPUS�{OLYMPUS
��
�����ԍ��F19004343
![]() 3�_
3�_
�J�������I�����p�X�̏ꍇ�́A�p�i7-14mm�̓I�X�X�����ɂ����ł��B
E-M1���ƃp�[�v���t�����W�͕�����(�H)��������܂��A���S�[�X�g�͂�͂�o��悤�ł��B
�܂��A�p�i�@�ł̎g�p���Ɣ�ׁAAF���ŗ����ቺ����悤�ł��B
�p�i7-14mm�̐��ݔ\�͂������o����̂́A�p�i�@�������Ă��ƂȂ̂����B
My�����Ő\����Ȃ��̂ł����A������Ƀe�X�g���ʂ�����܂��B
http://engawa.kakaku.com/userbbs/1411/ThreadID=1411-826/#1411-894
�����ԍ��F19004481�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���ɂ��͂��ɂ��
�����Ȃ�ł���ˁB�p�i�̓f�U�C�����C�}�C�`�Ȃ�ł��B�����ȑO�p�i��12-35mm�������Ă����̂ł����A�I����12-40�o�ɔ����ւ����̂̓f�U�C���̍����傫���ł��B12-40mm�͂������悷���āA�n�[�g���h�L���[�����Ċ����ł��B���L�~�����Ƃ����_�ł͂����I���ƃp�i�ł͔�r�ɂȂ�Ȃ����炢�ł��B��������L�~������������̂͒f�R�I���������킯�ŁA�����炱���I�����|�`���Ă��܂��܂����B
�����i�e������
�I����9-18�o�̏������͏Ռ��I�ł���ˁB�����ɗ]�T���o������9-18�o��lj�����Ƃ����̂��L�肩���B���������̍L�p�Ȃ̂ŁA�Ȃ�ׂ������o�������B���͑傫���ł��ˁB
��Vinsonmassif����
EOS M��11-22mm�͎����������Ƃ���܂��BAPS-C�Ȃ̂ɂ��̏������A�����т����肵�܂����B�p�i��7-14mm���������ł����A�������ł�11-22mm�ɂ͏��ĂȂ��ł��B�ł��A�L���m������×1.6�Ȃ̂ŁA���Z��p��9-18mm�Ǝ����悤�Ȃ��̂ŁA�����܂łт����肷�邱�Ƃ��Ȃ��̂����B�F�����͎��O�ɕ����Ă����̂ŁA�I����I��ŗ��R�̈�ł��B���ꂪ����������A�����Ɩ����Ă����Ǝv���܂��B
���ɂ�`�� mark2����
��Ⴀ�肪�Ƃ��������܂��B���\�Ⴂ�܂��ˁB���������Ƃ���ς�I���@�ɂ̓I�������Y���Ȃ��Ďv���܂��ˁB
�����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͂�����Ƃ��������Ȃ���ł���ˁB�p�i�ƃI���Ŏ�U���̏ꏊ���Ⴄ�Ƃ��A�Y�[���̕������Ⴄ�Ƃ��A�F�����Ȃǂ̕�̌�������Ⴄ�Ƃ��A�`�e�̑����Ƃ��B�����Ɠ��ꂵ�Ă��ꂽ�炢���̂ɁB
���̏ꍇ����ɂ��܂肱����肪�Ȃ��̂ƁAE-M1������������Ă���̂ō��̂Ƃ���{�f�B�̓I���Ōp���ł��B�p�i�����p����Ȃ�����ƔY�̂ł����B
�����ԍ��F19004728
![]() 4�_
4�_
�r�����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͂�����Ƃ��������Ȃ���ł���ˁB
������,�ʂ̉�Ђ����炱���Ȃ邱�Ƃ͒N�����\���ł���
�Ƃ͉]���@�g���č���̂̓��[�U�[
���̃}�C�N��4/3�@�f�g3�r�f�l1�r�f�l1�r�d-�l�T
�����Y�ƃJ�����莝���̋@�ނ̑g���킹��
�o×�o,�n×�o,�o×�n,�n×�n�m���߂�������
���ɍL�p�Y�[�������Y�͂ǂ����Ă����̃����Y���C�ɂȂ邵
�������荢��Ƃ݂đ��̋@�ނɐ�������J�����X���ɂ͏����Ă邵
�ł����������d-�l�T�������̂͂���
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO�̂���
�ł�,�ł����̃����Y�ɂ͂d-�o�T���������Ă邩��
�����ԍ��F19004995
![]() 3�_
3�_
����p�i7mm�A�����I��7mm�A�E��p�i14mm�A�E���I��14mm |
��p�i7-14mmF4.0�A���I��7-14mmF2.8 |
��E-M1+�p�i7-14mmF4.0�A�EE-M1+�I��7-14mmF2.8 |
��E-M1+�p�i7-14mmF4.0�A�EE-M1+�I��7-14mmF2.8 |
���������Ă��܂��̂�
�������͐l���ꂼ��Ȃ̂ŃR�����g�͍T�������Ă��������܂���
�����ŊȈՃe�X�g�������ʂ��A�b�v�����Ă��������܂��A�w������������Ă�����̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B
�E�ʐ^1����(�ߐڎB�e�̔�r)
�`�e�Ńs�B�s�B(����)�ƂȂ������_�ŃV���b�^�[����Ă��܂��B
�E�ʐ^�Q����(�S�[�X�g�A�t���A�[�̔�r)
���ߏォ��p���b�N�{�[���X�p�C�����̋������č�����E�����֓K���ɃV���b�^�[����Ă��܂��B
���i�l�̓p�i�ɍ��킹��F4.0�ɂĎB�e
�����ԍ��F19005731
![]() 12�_
12�_
��Vinsonmassif����
�ʂ̉�ЂȂ͕̂������ł����ǁA�����������[�U�[�����āA���݊���Ăق��������Ƃ���ł��B
�Ƃ͂����A�{�f�B�������Y���I�������������Ƃ͊�������Ƃł��B
�P�œ_�����Y�̓p�i�̃����Y���C�ɓ����Ďg���Ă܂��B
�����S�}��������
���肪�Ƃ��������܂��B��ώQ�l�ɂȂ�܂��BE-M1��2��ł��ˁB���Ɠ����ł��B�V���o�[�̓L�����y�[���̎��ɔ��������܂����B
�p�i�Ƃ̔�r�ł́A����Ƃ����_�ł̓I���̈����ł��ˁB����Ƃ����̂͑傫�ȃA�h�o���e�[�W�ł��̂ŁA�I���ɂ��ėǂ������Ǝv���鍷�ł��B
�S�[�X�g�A�t���A�ɂ��Ă͂ǂ������ǂ����Ƃ��������ł��ˁB�����Ƃ��o�Ă��܂����A���̍�Ⴞ���ł͂ǂ��炪�����A���Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ����ƁB
������͂��̂��y���݂ł��B���܂ŎB��Ȃ������ʐ^���B���Ǝv���ƃ��N���N���܂��B
�����ԍ��F19007472
![]() 1�_
1�_
gngn����
��������͂��̂��y���݂ł��B���܂ŎB��Ȃ������ʐ^���B���Ǝv���ƃ��N���N���܂��B
�����͂��Ɨǂ��ł��ˁA�����Ď��́u300mm F4 PRO�v�f�����ł���
�\�ł́u300mm F4 PRO�v��������11�����ƂX���̍q��ՂɁA�Ԃɍ���Ȃ��̂��c�O�ł��B
��́A�p�i�\�j�b�N�̖]���Y�[���uLEICA DG 100-400mm F4-6.3�v�A�J�����Ƃ̃A�i�E���X������C�ɂȂ鑶�݂�
�����ԍ��F19013595
![]() 3�_
3�_
���������Ă܂����ǂ��Ǝv���܂�(^o^�U
�����ԍ��F19046985�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���S�}��������A���l�U������
�lj����X���肪�Ƃ��������܂��B�����Y�͂��܂����B
�^�C�~���O�悭�A�A�Ȃ̑O���ɓ͂����̂ŁA�A�Ȑ�Ɏ����Ă����܂����B
�A�Ȑ�̃��W���[�Ɋ��Ă���܂����B�L�p�ʔ����ł��B�����Ƒ����������Ă����悩�����B
����ɂ��Ă��A�g���ǂ��낪����B���܂ł�12�o�܂ł����Ȃ������̂ŋC�Â��Ȃ������̂ł����A11�����ȉ��ɂ���Ƃ��Ȃ�c�݁H�܂��ˁB
�l�̊炪��ʒ[�ɂ���ƁA�т�[��Ƃ����s���R�Ȋ�ɂȂ�܂��B
�\�}�̎B����Ƃ��A�C��t���Ȃ��Ƃ����Ȃ������ł��B
�傫���́B���[��B����ς�傫�������B12-40mm�Ƒ卷�Ȃ��Ƃ��͂����A�{1�{�lj��Ŏ��������ɂ͂�����Ƒ傫���B
���x��9�|18�o���w�����悤���Ɖ�����ł��B
�p�i��7-14mm���ǂ��ł����A���L�~�����̂̓I���ł��ˁB���^�y�ʂ�9�|18�o�ŕ₤���Ƃɂ��܂��B
���������A300�oF4��LEICA DG 100-400mm F4-6.3�͍��̂Ƃ���l���Ă܂���B���C�����q���B��Ȃ̂ŁAPRO�Y�[��3�{����Ώ\�����ȂƁB
�����ԍ��F19050515
![]() 4�_
4�_
��gngn����
���߂łƂ��������܂��B
�p�i�������Ȃ��̂ł����A�~�]�ɂ�����̂͂�͂�I�����i�ŁA���~�������Ă���܂��ˁB
�����ԍ��F19051082
![]() 3�_
3�_
�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [�u���b�N]
�]�������Y�̋��͂ȃ��C�o�������\�ɂȂ�܂����ˁB
http://digicame-info.com/2015/07/leica-dg-100-400mm-f4-63lumix.html
�œ_������T�C�Y�A���i�ȂǂЂƉ���̃N���X�ƂȂ�܂����A�I�����������Ă����̂͊������ł��B
���߂̓I�����p�X75-300II�֑f���ɍs������ł������A���i��T�C�Y�E���������Ȃǂ̏ڍׂ��o�Ă���l���悤�Ǝv���܂��B�����A���C�J�u�����h�Ȃ̂ł�������ł��傤�˂�(´�_�`)�B
�����ԍ��F18971451�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�P�œ_�����Y�Ȃ炢���m�炸
���̎�̖]���Y�[�������Y��LEICA�u�����h�͗v��Ȃ�
�J��e5.6�ɂ�������Ă��炢��������
�Ƃ͉]��800mm����������,Nikon�P��300mm���l���邩
���̃����Y�Ŗڎw����
�����ԍ��F18971554
![]() 5�_
5�_
�y���݂ł��B
�����ԍ��F18971564
![]() 5�_
5�_
���C�J�ł͂Ȃ���X�����Y�ŗǂ������Ǝv���܂��B
���ƁA100-300�̒u���������x���̗����ł��p�ӂ��ė~�����ł��B
����10���͒����Ă���ł��傤���A�G���g���[���[�U�[�ɂ͎肪�͂��ɂ����ł��B
�����ԍ��F18971573�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
���C�J�����Y�Ȃ̂ŁA�ǂ�ȂɈ������ς����Ă�20���~�R�[�X���Ǝv���܂��B
���Z800�o�����Ȃ�AEF400mmF5.6L��AF�Ή��̃A�_�v�^�[�����܂���肪����Ǝv���܂��B
�O�r�ڂ���MF��̂Ȃ�A���̕����掿���ǂ������m��܂���B
�����ԍ��F18971635�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�l��20���~�R�[�X�ƌ��Ă��܂��B
�����A�����܂ł��C���I�Ȃ��ǁc5.6����Ȃ��̂��s���ł��B
�����ԍ��F18971716�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�ł��ˁB
���C�J���������u�ԋ��������炬�܂����i�j
�l�i�����A�d���Ȃ肻���ł��B
�����ԍ��F18971801
![]() 5�_
5�_
������B
�l�I�ɂ�LUMIX G 25mm/F1.7�̕����C�ɂȂ��Ă��āA���ꂪ�R���~�ȉ���42.5mm/F1.7�Ɠ����悤�ɍő�B�e�{��0.2�{
�Ƃ���������A�I����25mm/F1.8�Ɠ���ւ������Ǝv���Ă܂��B
���łɓ�����LEICA�ł͂Ȃ�G�V���[�Y�H��17.5mm/F1.7�Ƃ������l�Ȋ����ŏo���炢���Ȃ��Ďv���Ă܂��i�j
�����ԍ��F18972053
![]() 5�_
5�_
���������Z400mm&800mm�����ł����Ȃ�A�ōl����Ɓi�j
EF200mmF2.8L USM
��9���~
EXTENDER EF2X-3
��4���~
AF�A���}�E���g�A�_�v�^�[
��4���~
�̕��������C������ (^^;;
�L���m���̃J�����������Ă����
�����Ƃ��A����Ȃ�
EF100-400mmL�̐V�^�̕��������Y���g���邩��(ry
�����ԍ��F18972080�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
����Ɨ����c���Ċ����ł�(���ށ�)
�����ԍ��F18972239�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���C�J�u�����h�ɂ����̂́A�掿�ɕ��X�Ȃ�ʈӗ~�����邩��Ȃ�ł��傤�ˁB
���l�i�͂�͂�20���~�������Ⴄ�̂ł��傤���H
�����Ȃ�Ǝ肪�o�܂���˂��B
F4-F6.3�ł͂Ȃ��AF5.6�ʂ���������T�C�Y�Ȃǂ͂ǂ���������ł����ˁH
�����ԍ��F18972850�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�����Y > �I�����p�X > M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
�c�O�I�I�I�@
����A�V���b�v�̒S���҂Ƀ��[���ŃN�G���[�ł����A���̃����Y�̔����ĊJ�͖���ł��B
�l�̃v���~�A�������9�����܂ŁA���A�I���I�������������ł����B
![]() 1�_
1�_
���̉��iCOM�̉E���ɓ\���Ă���Amazon�̓���
�P�P�_�ɂ���,�V���P�S�����͂��������@�����H
�K��?���s�������K�v�����甃���Ȃ�����
���̃����Y���B�e�ɕK�v�Ȑl������������Ă��܂�����
�����ԍ��F18964973
![]() 2�_
2�_
yzi2007����
����ɂ��́B
�������̃����Y���L�^�����X���Ŗ��O�ɒ������A��T�ؗj���ׂōw�����܂����B
���̃����Y�́A���Y�Ƃ������Ƃł����A�܂�������������Ȃ̂ő����̍ɐ��Y���Ă��������̂�����ė����̂�������܂���B
yzi2007�����������ɓ�����Ƃ����ł����B
�ŁA��������ƊȒP�Ȏ��^�]���⎎�B���ł��܂����̂ŁA�A�b�v���Ă݂܂����B
�g���Ă݂����z�Ƃ��ẮA�{�f�B�[EM-5�U�ɑ��ē����x�̏d�ʂ�����܂��̂ŏd�S���O���ɂȂ邽�߁A����ł�������ƃL�[�v���Ă��Ȃ��Ƃ����܂���ˁB
����ƁAMF�������Ă݂܂������A�t�H�[�J�X�����O�����O���߂���悤�Ȋ��o���܂������A����Ă��邤���Ɋ���Ă��܂����B�ł��A�P�Q�|�S�OPRO�̕������Ղ������܂��B�i�Ƃ͌������̂̎��Ƃ��ẮA����܂Ŏg�p���Ă����X�|�P�W�̂����Ȋ��G�����ׂ���g���N����������Ղ��ł��j
�t���ϐ��́A�X�|�P�W�̕��ɌR�z������悤�Ɏv���܂����B�V�|�P�S�́A���\�ȒP�ɁA�e�͂Ȃ��S�[�X�g���o�����܂��B�V�������ɍ��킹��ƑO�ʂ��J��o���Ă��邽�߁A�t�[�h����s���ɂȂ�悤�Ȋ����ł��B���ƌ����āA����ȏ㒷��������P�����̖�肪�o�ė��邽�߁A���ꂪ�M���M���ȃT�C�Y�Ȃ�ł��傤�ˁB�����́A�B�e���ɂ�����Ǝ����̎蓙�œ��������Ă������̂����m��܂���B
���͂���Ő��i�ʐ^���B�肽���Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�W���A�x���g���ď����������V�̐����Ƃ��ăJ�����Ɏ��߂�ꂽ�炢���Ȃ��Ɩ��݂Ă��܂��B
�ł́A�ꑫ����Ɏ��炵�܂����B
�����ԍ��F18965226
![]() 5�_
5�_
�X���傳��A
�͂��߂܂��āB�{���ɂ��ɂȂ�����\��ł����ł��傤�ˁB
����܂�12-40 PRO��40-150 PRO�͔��\�A�I���I���ł̗\���t�J�n�Ɠ�����
�\�܂������A�|�C���g��������Ƒ���Ȃ������̂ŏ����҂��������
���������ł��B
6�����{�����Ƃ������ƂŁA�\���ċx�݂ɊԂɍ����Ȃ��Ɗ��҂��Ă��܂������A
�������������ł��ˁB
�����|�C���g�����������g���ƃI���I�����ň��Ȃ̂œ�̑���ł��܂��B
�ق��Ŕ������炢�Ȃ炻����������ł���Ӗ����Ȃ��ł��B
�����ԍ��F18965414
![]() 1�_
1�_
�����ł��ˁB
��������A���N�̃v���~�A������X�V����߂�B
�����ԍ��F18965431
![]() 0�_
0�_
�����킹�̐Ԃ�������
�I���I�������̏ꍇ�A�����ł����F
�ʏ퉿�i
146,880�~
�v���~�A��������i
139,536�~
�����|�C���g�l�����㉿�i�iMAX15%)
118,605�~
�v���~�A������N�[�|�����i
110,302�~
���ƁAT�T�C�g���[�����o�R��1654�@�s�|�C���g���Q�b�g�ł��B
�����ԍ��F18965461
![]() 0�_
0�_
�I���̃I�����C���V���b�v�̍���̑Ή��͂܂����ł��ˁB
���[�U�[���ꂪ�S�z�ł��B
�����ԍ��F18990079
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����zA20?
-
�yMy�R���N�V�����z30���\��
-
�y�~�������̃��X�g�z�T�[�o�[�p����PC �\����
-
�y�~�������̃��X�g�z10��7��
-
�y�~�������̃��X�g�z�����Y
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h
- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��
�i�J�����j