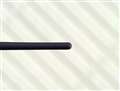���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S15512�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 2024�N9��25�� 20:20 | |
| 9 | 2 | 2024�N9��25�� 13:15 | |
| 33 | 9 | 2024�N9��24�� 22:28 | |
| 100 | 20 | 2024�N9��24�� 12:28 | |
| 121 | 26 | 2024�N9��23�� 16:08 | |
| 86 | 52 | 2024�N9��22�� 20:40 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > �x�m�t�C���� > FUJIFILM X-M1 �{�f�B
���T���ɔ��\�����݂����ł��B
�����ɐV�����Y�̔��\������ƕ����Ă��܂��B
�C�ɂȂ�l�i�́AX-M1�Ɠ����͖��������m��܂���B
�����ԍ��F25901531�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
�����`�`�`
�����ԍ��F25903208
![]() 1�_
1�_
����ĔL������
XC15-45mm �����Y�L�b�g99800�~�ʂȂ玩���������܂��B
�����ԍ��F25903785�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����䂤����A�͂��߂܂���
AF���\�͑啝�Ɍ��サ�Ă���Ɨ\�z���܂��B
X-T50����t�@�C���_�[�ƃ{�f�B����U�����ȗ��������f���Ȃ̂ł��傤���H
XC15-45mm �����Y�L�b�g�ŏ\���~���Ȃ��ƁA���̃��[�J�[�Ə����ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F25904223
![]() 2�_
2�_
�f�W�^�����J���� > �j�R�� > Z6III �{�f�B
�u�t�@�[���E�F�A Ver1.02�v�����J����܂�����
https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/541.html
![]() 5�_
5�_
�ύX���e�͈ȉ��̒ʂ�B
- �ꕔ�� CFexpress �J�[�h�ɂ����āA���悪����ɋL�^�ł��Ȃ��ꍇ������B
- �L�� LAN ���g�p���ĉ摜�]�����s�����Ƃ��A�G���[�ƂȂ�ꍇ������B
��ʑ̌��o�m���n���[�h�́AZ6�V�ɓ��ڏo���Ȃ��悤�ł��ˁB
�����ԍ��F25903399
![]() 0�_
0�_
���W���[�A�b�v�f�[�g����Ȃ�����ˁB
�����ԍ��F25903762�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�f�W�^�����J���� > �p�i�\�j�b�N > LUMIX DC-G9M2 �{�f�B
�c��߂̊p�x�ŃA���e�i���]�[���ɓ����Ζ�薳�� |
�A���e�i����p�������ɍ��킹��ƃs���g�����Ȃ� |
�[�����g�債�ă]�[���ɓ����ƁA�[���Ńs���g������ |
�[�����]�[������O���ƁA��͂�s���g�����Ȃ� |
G9M2����肵�Ă���1�N�߂����o���A���N�B���ʑ̂��قڈ�ʂ莎�������ŁA�ǂ����g���{�̃z�o�����O�B�e�ŏ����̕ߑ��������Ⴍ�A�����܂肪�オ��Ȃ��Ɗ����Ă��܂������A�F�X�����Ă�����ɁA
�u���ʈʑ���AF�����C���Z���T�Ȃ̂ŁA���ɍג�����ʑ̂̓t�H�[�J�X�ł��Ȃ��̂����H�v
�Ƃ����C�����Ă����̂ŁA�����������l���Ȃ��璲�ׂĂ݂܂����B
�e�X�g�p�̔�ʑ͎̂����Ԃ̃��W�I�A���e�i�ŁAAF���[�h�̓]�[���ł��B
1���ځF�A���e�i���������ʂɃ]�[�����ɓ���ĎB�镪�ɂ́AAFC�Ŗ�薳���s���g�����܂��B
2���ځF�J��������]�����ĉ������ɃA���e�i�����킹��ƁA�s���g�������w�ʂɂ���ǂ̖͗l�ɍ���
3���ځF�A���e�i�[�����]�[���ɓ����ԂŃY�[���A�b�v����ƁA�[���Ńs���g������
4���ځF�Y�[���A�b�v�����܂ܒ[�����]�[���O�ɓ������ƁA�s���g������Ȃ��Ȃ�ǂɍ����Ă��܂�
G9M2�̑��ʈʑ���AF�̓��C���Z���T���Ǝv���܂��̂ŁA�c���ɂ̓s���g�����Ă��A�����ɍ���Ȃ��͓̂��R��������܂��A����^�ʖڂɎ������Ƃ���A4���ڂ̏�Ԃł�AFS�̃R���g���X�gAF�ł��s���g�������܂���ł����B
�ǂ������ʈʑ���AF�A�R���g���X�gAF���킸�A�قڐ^���̃G�b�W�ɂ̓t�H�[�J�X�����Ȃ������ł��B
�܂�AFC�̏ꍇ�A�A���e�i�ƕǂ̊ԂɃs���g�������Ă����Ԃ���AAF-ON�F�ߑ��Ŏ�O�ɃT�[�`�����Ă������ɒ��߂Ă��܂��A���̕ǂɍ��킹�ɍs���Ă��܂��܂����B
�A���e�i���c�₠����x�߂̏ꍇ�́A�����s���g�ʒu����ł��L�b�`���A���e�i�܂Ŏ�O�ɃT�[�`���āA�s���g�������܂��̂ŁA���ʈʑ����̏ꍇ�A�����̃{�P�̓t�H�[�J�X�����Ă��ω��������A��ʑ̂������Ɣ��f���āA���Α��ɓ����Ă��܂��悤�ł����B
������{�P���ɒ[�ɑ傫����Ύd���Ȃ��̂ł����A���ۂɂ͖ڎ��Œ��X�s���g�����Ă����Ԃł��A�����悤�ɔ��f���Ă��܂��悤�ł��B
���̂悤�ȌX�����琄������ƁA�̂������čג����g���{���������Ńz�o�����O���Ă���Ƃ����AFC�ŎB�e����ƁA���炩�ɍ��������ȃg���{�Ƀs���g�����Ȃ�������AAF-ON�F�ߑ��ʼn���T�[�`���Ă��t�H�[�J�X����O�ɗ��Ȃ������肵�Ă��d���Ȃ��̂�������܂���B
�������̐�������������A�s���g���S�R���Ȃ����ɁA�J������������x��]�����������������Ȃ��̂ŁA���̋@��ɗ]�T���L�����玎���Ă݂܂��B
![]() 9�_
9�_
��GG@TBnk2����
2���ځA4���ڂł����AAF�̉��Ƌ߂��t�@���N�V�����ɐݒ肳����AF�߂ɂ���Ɖ�܂���
�p�i�\�j�b�N�̃s���g���킹�͈ʑ����݂̂łȂ��A���̎��̍œK�ȏ�Ԃňʑ������R���g���X�g�����߂Ă��܂��B�i�l�p�̘g���ς��Ǝv���܂��jS5M2�̎��͂��̂��߂̖��������������̂ł���G9M2�͑������P�͂���Ă��Ă�̂ł����A�グ��ꂽ���e�ł͉������ɍ��킹�ɍs���Ė������ł邩�ƁA���̂��߂�AF�������ʼn��Ƌ߂ɍ��킹��@�\ ���������Ă܂�
���ƃg���{�͔F���@�\�g���Ă܂����A�Ⴆ�O���[�v�œ����F������āA�g���Ɏ��߂�Ȃ�
�����ԍ��F25898899�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�p�i�\�j�b�N���ĉ��Ȃ̂ł��傤�H
�掿�̒ቺ�Ɍq���邩��ƈʑ���AF��ے肵�Ă����̂Ɏ�̂Ђ��Ԃ��Ĉʑ���AF�𐄏��B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����S�҂ɔ���܂����Ă����̂ɁA�Ή����f����̔����~�����珉�S�҂ɂ̓t���T�C�Y�������Ă���Ɛ�`�B
����ȏꓖ����I�Ȕ��������郊�[�_�[�����J���҂͕s�K�ł��ˁI
�����ԍ��F25899300
![]() 8�_
8�_
������89����
AF-ON�F�ߑ��ɂ��Ă͍ŏ��̃R�����g�ɂ������Ă���ʂ�A�A���e�i���������̏ꍇ�͍���Ȃ��ł��B
�܂��A4���ڂɂ��Ă͂���������������Ă���܂����A���ʈʑ�����AFC���낤���A�R���g���X�gAF��AFS���낤�������܂���ł����B
���̉������ɍ���Ȃ����ɂ��ẮA�̓d���Ƀt�H�[�J�X���Ă݂�Ύ����葁���m�F�ł��܂��B
����ɁA�g���{�͔�ʑ̔F���ł͂قƂ�nj��o����܂���B
�H�ɑS�̂�F��������A����̔��˂F�������肵�܂����A�����I�ɂ͂قڊ��҂ł��܂���B
�����ԍ��F25899476
![]() 1�_
1�_
����ɂ���
��GG@TBnk2����
> �ǂ������ʈʑ���AF�A�R���g���X�gAF���킸�A�قڐ^���̃G�b�W�ɂ̓t�H�[�J�X�����Ȃ������ł��B
����͂��̒ʂ�ł��āA����DC-G9(������͑��ʈʑ����͂��Ă��Ȃ��ł���)�̂��납�炻���ł����B
�ƁA�����܂ŏ����Ċ��������������̂ʼnߋ��̃X���b�h�����Ă݂��̂ł����A�����ԍ��F25639065 ��
> �Ȃ��A���������o���Ȃ����ł����A����͐���DC-G9��DFD+�R���g���X�gAF�ł������ɂ͍��ł����ADC-G9M2��AFS(DFD+�R���g���X�gAF)����������ł��B
�ƑS���������Ƃ������Ă��܂�����(^^;
�����ԍ��F25899901
![]() 1�_
1�_
��GG@TBnk2����
S5M2�ł������z�ԑ��Ƀs���ƍs���Ă܂����ˁB
AF�̉��߂͈�xAF�����킹�Ă���̈ړ��ł��B�A���S���Y���̕Ȃ������Ƀs���g�����镨��G9���ォ��l�I�Ɏv���Ă��āAAF�����Ƃ��Ĉʒu������Ȃ��Ȃ�A�R���g���[���_�C�����̃t�@���N�V�����L�[�ɐݒ肵�Ă���uAF�߁v�uAF���v�ňʒu���킹���Ă��邩�炠�܂�C�ɂ��Ė����̂�����ȁB
AF�̃]�[���i���߂�Ȃ����O���[�v�Ə����Ă܂����j��AF�G���A�ő�ł��_���ł����A�F���@�\�̎���AF�͈͂�傫�����Ȃ���AF�������X��������܂��B�B�Ⴆ�ŔF���@�\�Ńg���b�L���O�����悤�Ƃ���ƒǔ��A�]�[���łȂ��t���G���A�ŔF���������ق����ǔ��A�F���������܂��B
OM-1�ł����l�ł����F���@�\�g���ꍇ�̓J�����ɂ��C����AF�͈͍͂L�߂������ł�
�����ԍ��F25900835
![]() 1�_
1�_
��YoungWay����
�m���ɈȑO�̌��R�~�ł��A�����悤�ȉ��p�^�[���ɂ��ď����b��ɂȂ�܂����ˁB
����͋�̓I�ȃe�X�g��ʑ̂Ŏ������̂ƁA���̌��ʂ�AFS��AFC�ł̃T�[�`����̈Ⴂ�����������Ă����̂ŁA�V������������ł݂܂����B
��������AF-ON�F�ߑ��Ńt�H�[�J�X�����ꍇ�A�قڐ^���̍ג�����ʑ̂�AF������Ȃ��̂͂Ƃ������Ƃ��āAAFS�ł͈ꉞ���ňʒu�܂ł̓T�[�`���������̂ł����AAFC�ł͍��ňʒu�܂őS�R�͂��Ȃ����ɁA���X�ɒ��߂Č�둤���T�[�`���n�߂�̂ŁA�u���ꂶ�ፇ�������v���Ċ����Ȃ͍̂������Ƃ���ł��B
����ɂ��Ă��A���������^���̃G�b�W�^�p�^�[������������ʑ̂́AAFS/AFC��킸�A�s���g�������Ă����Ԃ���t�H�[�J�X���Ă�����Ȃ��̂ɂ́A������Ȃ��眱�R�Ƃ��܂����B
�����ԍ��F25901920
![]() 2�_
2�_
��GG@TBnk2����
����DC-G9M2����ɒZ�߂̓���(4K60p)�B�e�ƁA�Î~��ł͓��̂łȂ����̂��ʂ��悤�ȗp�r�Ɏg�p���Ă���A�Ƃ��ɐÎ~��B�e�ł�MF����{��AF-ON��AFS���N������悤�Ȏg���������Ă���̂ŁA����Ȃɍ�������͂��Ă��Ȃ��̂ł����A����ł��Ƃ��ǂ��u��H�v�Ǝv���悤�ȋ����������܂��ˁB
���ʈʑ����ʼn��������o�ł��Ȃ��̂͑����p�̑f�q�Ɏd�|���Ă���Ռ��}�X�N�����E�����݂̂��Ƃ����̂����R�ŁA���Ћ@�����l���Ǝv���܂����A�R���g���X�gAF�ł����������o�ł��Ȃ��̂́A�Z���T�[�̓ǂݏo�����������ӕ����ł��邱�ƂɊW�����肻���ł��B
OLYMPUS�@�͂����ԑO���瑜�ʈʑ������o�̓I�[���N���X�ɂȂ��Ă��āA���̎�_�͂Ȃ��̂ł����A���Ђ����l�̕������̗p���Ă��Ȃ��̂́A�����g���[�h�I�t(AF���Z�ʂ������铙)������̂��Ǝv���Ă��܂��B
EOS R1��DPCMOS�̈ꕔ�̉�f���c�����ɂ��ăN���X�����ɑΉ����Ă��܂������A���̃A�C�f�B�A���̂͂����v���������Ȃ̂ŁA�����炭�����ɂ͂��Ȃ�̎�Ԃ����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�܂��A�����Ɋւ��Ă͑��Ћ@���܂߃J�����������X����Ȃǂł����Ă��͑Ή��ł���̂ŁA����قǖ��ɂ͂Ȃ��ĂȂ��悤�ɂ��v���܂��B
�����ԍ��F25902844
![]() 5�_
5�_
�����݂̂̔�ʑ̂ɍ��킹�邱�Ƃ�
�ǂꂾ�������ł��傤�ˁH
����ƁA�g���{�B�肽���Ȃ�p�i��
�I�Ȃ��Ǝv���܂����ǁB
�~���[���X�̈ʑ����Z���T�[��
�����ꕔ�iEOSR1�j�������A�������̂�
�̃��C���Z���T�[�B
�傰���ł��B
�����ԍ��F25902858
![]() 2�_
2�_
������
��ق�
> ���ʈʑ����ʼn��������o�ł��Ȃ��̂͑����p�̑f�q�Ɏd�|���Ă���Ռ��}�X�N�����E�����݂̂��Ƃ����̂����R��
�Ə������̂ł����A���ʈʑ����ʼn������̃��C���Z���T�[�����\�����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���̂́A���������Z���T�[�̓ǂݏo�����������ӕ����ł��邩�炾�Ǝv���̂ŁA���{�����͓����Ƃ������ƂɂȂ�܂���(^^;
���̂����ŁADC-G9/DC-G9M2��AF�G���A��1�_�̂Ƃ���AF�̈�̃T�C�Y��ς�����̂ŁA�����ɂ����̒����`�̗̈�S�̂ŃR���g���X�gAF�����Ă���悤�ȋC�ɂȂ�܂����A���ۂ̂Ƃ���͗̈���g�債�Ă����C���Z���T�[�̖{���ƕ��������邾���ŁA�ʂƂ��ăR���g���X�g�����Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
DC-G9�ŏ��߂Ă��̋����ɋC�Â����Ƃ��͐��������������̂ł����A0.04�b�ō��ł����邽�߂ɂ�AF�̈�S���̓ǂݏo����҂��Ă����Ȃ��̂ŁA1���C���ǂݏo���Ȃ菇���R���g���X�g���o�����Ă���̂��B�ȂǂƖϑz���ĂЂƂ�[�����Ă���܂���(��)�B
�����ԍ��F25903246
![]() 3�_
3�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B
�ʏ�B�e12bitRAW �ߓx�Ȓ��� |
�n�C���]�B�e14bitRAW �ߓx�Ȓ��� |
�ʏ�B�e12bitRAW �������� |
�n�C���]�B�e14bitRAW �����Ȃ� |
OM-1MK2���n�C���]�B�e��14bit RAW���I���ł���悤�ɂȂ�܂����B
����̓n�C���]�B�e14bit RAW�ƒʏ�B�e12bit RAW �ɉߓx�Ȓ������s���j�]�x���̔�r�����܂����B
�B�e���̘I�o�͑S�������P�R�b�I���EISO5000�ł��B�i�����Y�̓p�i���C�J12mm F1.4 �i��J���j
���ӓ_�Ƃ��Ĉȉ�������܂��B
�E�킴�Ɖߓx�Ȓ������s���j�]�̓x�����m�F���Ă���
�E�{���n�C���]�B�e12bit RAW�Ƃ̔�r�����ׂ������B�e���ɂ����܂ŋC�����Ȃ�����
�E��������bit�[�x�ȊO�ɉ�f�����{�ȏ�Ⴄ�̂ł��̉e�������邩��
�摜�����ɂ��Ă�
�E�o���Ƃ�OMworkspace��TIFF�����o���̂ݍs���m�C�Y�����͍s���Ă��Ȃ�
�E��L��ƌ��Lightroom�Ńp�����[�^�����i�������ڂƒ����l�͑o�������ł��j
�E�n�C���]14bit�摜��Ai�m�C�Y���_�N�V�������s���ƃt�@�C�����j�������i���ꂿ����ƋC�ɂȂ��Ă܂��j
��L�ɂ�����悤�Ɍ����Ȕ�r�ł͂���܂���B�i��f���ƃX�^�b�N�������Ⴄ���߁j
�������Ȃ��炻��Ȃ�ɋ����[���Ⴂ�͏o�����Ǝv���܂��B
�n�C���]14bit RAW���~���ƐF�̔j�]���N���ɂ����Ɣ��f�ł��܂��B
���x�@�����܂�����n�C���]12bit 14bit�̍��ق��m�F�ł�����Ǝv���܂��B
�������n�C���]�͐��̎ʂ��Ă��鐔���i�Ⴂ�ɈႢ�܂��ˁB
�n�オ�u���Ȃ���ō��Ȃ�ł����ǁE�E�E
![]() 11�_
11�_
�t���T�C�Y�@��Lumix S5�̉摜���Q�l�ɓ\�t���܂��B
��p��20mm�ł��������������߂Â���悤�����g���~���O���Ă��܂��B
�X���肪����ɉ�p���ɂ������̂ł����AOM-1MK2�ɔ��S5�̕����e�����y���ł��B
OM-1MK2�́u�����݂̏����v���ߓx�Ɏ{�����ƂŗΐF�ɕϐF���Ă��܂��B
�摜�����ɂ��āAS5�̉摜���m�C�Y���_�N�V�����͍s�킸��RAW2�����̂܂�Lightroom�Ō������Ă��܂��B
�F���x�͌����ȍ��킹���ł��Ă��܂���̂ŎQ�l���x�ɂ������������B
�����ԍ��F25861938
![]() 10�_
10�_
��Seagulls����
����ɂ��́B
����͎O�r�Œ�̎莝���n�C���]�B�e�ł��ˁB
13�b�ł�����Ƃ��������L�т�����Ă��܂����A���܂����̒ǔ����ʂ��o�Ă��܂��ˁI
>�n�C���]14bit �� �ʏ�B�e12bit �j�]�x���̔�r
>����Ȃ�ɋ����[���Ⴂ�͏o�����Ǝv���܂��B
>�n�C���]14bit RAW���~���ƐF�̔j�]���N���ɂ����Ɣ��f�ł��܂��B
14bit��12bit�̈Ⴂ���A�}���`�V���b�g�ƃV���O���V���b�g�̈Ⴂ���f�R�傫���Ǝv���܂��B
��͂�A�����n�C���]�ǂ����Ŕ�ׂȂ��ƈႢ�͕�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƁB
�ł��A�V�̂̂悤�ɋ��͂ȉ摜���������߂���Ƃ���14bitRAW�͂��肪�����ł���ˁB
�����ԍ��F25862118
![]() 19�_
19�_
�����[���ł�
�q�������
�P���ɊG�Ƃ��Ă�
Lumix S5 14bit RAW�̕����D��
�����ԍ��F25862551
![]() 7�_
7�_
��Tranquility����
��14bit��12bit�̈Ⴂ���A�}���`�V���b�g�ƃV���O���V���b�g�̈Ⴂ���f�R�傫���Ǝv���܂��B
����͂�A�����n�C���]�ǂ����Ŕ�ׂȂ��ƈႢ�͕�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƁB
�m���ɂ����ł��ˁB
�ʓ��i�P�N�O�j�ʏꏊ�ł̃n�C���]12bit RAW�摜���v���Z�X�E�����p�����[�^�[�ŏ������Ă݂܂����B
�i������ʑ̂Ƃ������Ƃł��e�͂��������j
�����܂ŎQ�l�ł����A�n�C���]���m�͓����x�Ɍ����܂��ˁB�}���`�V���b�g�̃X�^�b�N���掿�ɋy�ڂ��e���͌v��m��Ȃ��ł��ˁB
��DAWGBEAR����
���P���ɊG�Ƃ��Ă�
��Lumix S5 14bit RAW�̕����D��
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�B��ꏊ��O�i�̏�ԁi�������߂����X������̗L���j�E��̏�Ԃɂ���Ă��Ⴂ�܂���
�{���ɉ����������Â��ꏊ�ł͈��|�I�Ƀt���T�C�Y�@�̕�����Ԃ��ǂ��悪�B��܂��B
�R���đ���������RAW�������낤����肪�o�ɂ����ł��ˁB
�����ԍ��F25863310
![]() 5�_
5�_
�n�C���]�̖���Y��ł���
�n�C���]��14bit�̏��������Ă�낤��
�n�C���]Raw���m��12bit��14bit���r����Ȃ�
���������ŎB���������̈Õ�(�^���ÂȂƂ�)��+5EV�Ƃ��������������グ�Ă݂�Ƃ���ƍ����킩��Ǝv���܂�
�����ԍ��F25863470�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����o������
���n�C���]Raw���m��12bit��14bit���r����Ȃ�
�����������ŎB���������̈Õ�(�^���ÂȂƂ�)��+5EV�Ƃ��������������グ�Ă݂�Ƃ���ƍ����킩��Ǝv���܂�
�����͂悭�킩��܂��ALightroom�̘I���ʂ��{�T�ɂ�����S�Đ^�����ɂȂ����̂ł����݂̏������{�P�O�O�ɂ��Ă݂܂����B
�������������i�����E�ꏊ�j�ł͂Ȃ��̂ňꉞ�Ƃ������ƂŁB
�����ԍ��F25864587
![]() 2�_
2�_
��Seagulls����
���肪�Ƃ��������܂��[�̐S�Ȃ��Ƃ��`�����Ă܂���ł���
����̎ʐ^���Ƃ����ƌ��ł��Ȃ��ł���
���S�Đ^�����ɂȂ����̂�
DN����ԍL���Ƃ���(ISO200)�̐ݒ�ŁA�����Ă��Ȃ�^���ÂȃV�[������Ȃ��ƁA���̔�r�o���Ȃ��ł���
��������ȂɃV�[���ɏo���킵����14bit�ŎB���Ĕ�r���Ă݂Ă�������
�����ԍ��F25864952�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��Seagulls����
>�n�C���]���m�͓����x�Ɍ����܂��ˁB
>�}���`�V���b�g�̃X�^�b�N���掿�ɋy�ڂ��e���͌v��m��Ȃ��ł��ˁB
�͂��A�����摜�̃X�^�b�N�͌��ʂ��ƂĂ�����܂��ˁB
>�{���ɉ����������Â��ꏊ�ł͈��|�I�Ƀt���T�C�Y�@�̕�����Ԃ��ǂ��悪�B��܂��B
>�R���đ���������RAW�������낤����肪�o�ɂ����ł��ˁB
�������ɘI�o�s���摜��Õ��̃��x���������グ��悤�ȑ���̓_�C�i�~�b�N�����W�̍L���ق��i��Z���T�[�Ƃ��X�^�b�N�摜�Ƃ��j���L���ł����ǁA�K���ȘI�o��^����ꂽ�摜����������ꍇ�ɂ��ẮA������قLj��Ȃ��Ǝv���܂��B
����o������
�����F�X�Ɗ��Ⴂ����Ă���Ǝv���܂��B
>�n�C���]��14bit�̏��������Ă�낤��
14bit�ŋL�^����Ă��邩��14bit�̏��ɂȂ�ł��傤�B
>�n�C���]Raw���m��12bit��14bit���r����Ȃ�
>���������ŎB���������̈Õ�(�^���ÂȂƂ�)��+5EV�Ƃ��������������グ�Ă݂�Ƃ���ƍ����킩��Ǝv���܂�
>DN����ԍL���Ƃ���(ISO200)�̐ݒ�ŁA�����Ă��Ȃ�^���ÂȃV�[������Ȃ��ƁA���̔�r�o���Ȃ��ł���
12bit��14bit�̈Ⴂ�͈Õ��Ɍ������b�ł͂Ȃ��ł���B
�����ԍ��F25865772
![]() 3�_
3�_
��Tranquility����
����o������
������Ƃ����t�������������肪�Ƃ��������܂��B
�����Ɍ����ɔ�r����͓̂���ł���ˁBMK2�ɂȂ��Ă��܂蓊�e���Ȃ��̂œ��₩���Ǝv���Ă��e�͂��������B
�������@�\�]������ׂɎB�e���Ă���Ƃ������Ƃł��Ȃ��̂ł܂������̋@��ɂł������Ȃ��Ƃ��������Ă݂܂��B
���ǂ��̃X���b�h�ɂ����Ắu����ς�n�C���]�������v�݂����ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�������Ȃ��玩���I�ɂ͂��Ƃ�12bit��14bit�ɂ��܂荷�����������Ȃ������Ƃ��Ă�
OMDS��OM-1MK2����悷��ۂɁu14bit�ł��c����悤�ɂ����v�̂͗ǂ����݂������Ǝv���܂��B
�p�i�\�j�b�N��GH5S�ł�������14bitRAW��I���ł���悤�ɂ����̂Ɂi�������f���A���l�C�e�B�uISO�̐�삯�j
���̌�͑S���X�`�����[�U�[�̊��ǂ���܂��Ă���Ȃ��͎̂c�O�Ɏv���Ă��܂��B
���������Ȃ̂œ������ɓ������p�������ĎB����Lumix S5��OM-1MK2�̕��ʂɏ��������摜���ڂ��Ă݂����Ǝv���܂��B
�o���Ƃ���p���Ⴂ�܂����A��̂ݑ傫���g���~���O���Ă��܂��B�i�����ɑS�̂��o���Ƒ��Ŏg���Ȃ��Ȃ�̂Łj
����̋�͔��������݂����ŁA����ԐF�A���̏�͎�������Ă���̂ł����AOM-1MK2�����S�ɗΐF�ɓ]�т̂ɑ�S5�͂��܂苭�����ꂸ�ɗǂ������ł��B
�����ԍ��F25866022
![]() 6�_
6�_
��Seagulls����
����o������
����Z���T�[�̏o�͂ł�����A12bit���낤��14bit���낤���A�L�^�ł��閾�Â͈͓̔͂����ł��B������bit�����傫���������ʂ������i���K���̃L�����ׂ����j�̂ŁA���͂ȉ摜���������Ă��~�����j�]���ɂ������ƂɂȂ�܂��B��bit���ŕ`�ʉ\�͈͂��Â����ɍL����킯�ł͂���܂���B
12bit�ɑ���14bit�̌��ʂ����҂ł����ʑ̂̂ЂƂɁA����ʐ^������܂��B�R���g���X�g�̒Ⴂ�t���b�g�ȉ摜�i���Ô͈͂������j����A�K���𐮂��邽�߂ɊK����啝�ɍL���āi�������Í���傫�������L���ā��R���g���X�g���������āj�d�グ�邱�Ƃ����ʂł��BSeagulls����̓V�̐�������ł���ˁB
�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��킩��₷������ЂƂA�b�v���܂��̂ł������������B�͂����傤���̖k�A�����J���_�̎ʐ^�ł��B
�B�����܂܂ł͔��ɒ�R���g���X�g�Ńt���b�g�ȉ摜�̕��̋����q�X�g�O�����̎R���A������L���āi���Í��������L���āj�L���ȊK���Ɏd�グ��킯�ł��B�摜�̖��Ï��̃L�����ׂ����قǁibit�����傫���قǁj���炩�ȊK���Ɏd�グ���邱�ƂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25866042
![]() 6�_
6�_
��Seagulls����
>�������ɓ������p�������ĎB����Lumix S5��OM-1MK2�̕��ʂɏ��������摜
�yOM-1MK2�ʏ�B�e�E�ʏ팻��(12bitRAW�j�z
�@ISO6400 F1.4 15�b
�y�������Lumix S5(14bitRAW�j�z
�@ISO10000 F1.4 20�b
�I�o�f�[�^������ׂ�ƁAOM-1mk2�̕���1�i�Ԃ�I�o���A���_�[�ł��ˁB
>����ԐF�A���̏�͎�������Ă���
�ԐF��ΐF�̃J�u���͑�C�����낤�Ǝv���܂����A���F�̈Ⴂ�̓Z���T�[�̊��F���ɈႢ�ɂ����̂ł��傤�B
�ǂ���̕����ǂ����Ƃ����ƁA��ʑ̂ɂ�肯��E�D�݂ɂ�肯��E�Ӑ}�ɂ�肯��ȕ����Ȃ̂ŁA�Ȃ�Ƃ������܂���B��}��������Η̍ʓx��������Ƃ����čD�݂Ɏd�グ�邱�Ƃ��ł��܂����B
�����ԍ��F25866065
![]() 3�_
3�_
��Tranquility����
�F�X�����Ē������肪�Ƃ��������܂��B
�ꉞ�A�j�]�x�����̍������悤�Ƃ��Ă����̂ŕ������Ƃ��Ă͍����Ă����̂��ȂƎv���܂��B
���I�o�f�[�^������ׂ�ƁAOM-1mk2�̕���1�i�Ԃ�I�o���A���_�[�ł��ˁB
����2�_�̉摜�ɂ��Ă͌����Ȕ�r�ł͂Ȃ��̂ŎB�e�����𑵂������̂ł͂���܂���B
�ʏ�A�F�X�ȏ����ŎB�e���Ă��Ƃ���ǂ��������̂�I�ԂƂ����v���Z�X�̒��̂��܂��܂�2�_�ł��B
���Ȃ݂ɂł����AS5�̕��͂��Ȃ薾��߂ɎB��Ȃ���(����̂悤�ɂP�i�����x)�����悤�Ɏʂ�Ȃ��̂ł��B
�Ȃ̂ł��܂��ܑI��2�摜��OM-1MK2�̕����P�i�A���_�[�Ȑݒ�Ƃ����͓̂����Ƃ��Ă͗��ɂ��Ȃ��Ă���̂ł��B
���ԐF��ΐF�̃J�u���͑�C�����낤�Ǝv���܂����A���F�̈Ⴂ�̓Z���T�[�̊��F���ɈႢ�ɂ����̂ł��傤�B
�����Ƃ�����ł͖����̂ł����A����Ɍ����Č�����S5�̕����]�v�ȐF���t�����D�܂������ʂɂȂ��������ł��B
OM-1MK2�̕��͓V�̐�ߕӂɃ}�[���^���ۂ������������B�ꂵ�Ă��܂��������F���x�������Ă��c�����܂܂ɑ���
S5�͂ǂ̐F���x�ɐݒ肵�Ă����������ψ�ȐF�̎ʂ�ł��B��������Əꍇ�ɂ��̂ł����܂Łu���̎B�e���́v�Ƃ��������ł��B
�����ԍ��F25866485
![]() 4�_
4�_
��Seagulls����
>S5�̕��͂��Ȃ薾��߂ɎB��Ȃ���(����̂悤�ɂP�i�����x)�����悤�Ɏʂ�Ȃ��̂ł��B
�����Ȃ�ł��ˁBS5�̕����������x���Ⴂ�̂ł��傤���ˁB
>OM-1MK2�̕��͓V�̐�ߕӂɃ}�[���^���ۂ������������B�ꂵ�Ă��܂��������F���x�������Ă��c�����܂�
�J���[�m�C�Y�݂����Ɍ����܂����A�y���Z�E�X��������̐Ԃ��U�����_�Ɉ�v���Ă���Ƃ��������܂��ˁB
https://unitec.cocolog-nifty.com/blog/2022/10/post-2d2903.html
������ɂ���A�Z���T�[�̕������x�����ɋN������Ƃ��낪����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25866568
![]() 1�_
1�_
��S5�̕��͂��Ȃ薾��߂ɎB��Ȃ���(����̂悤�ɂP�i�����x)�����悤�Ɏʂ�Ȃ��̂ł��B
�����ŏ��������̕����A������Ɛ��m�Ŗ����̂ŕߑ����܂��B
���i�B�e����ISO���x�ƘI���b���͂��������ɂ����ĎB�e���Ă���̂ł���
��������w�W�Ƃ��ăp�i�\�j�b�N�@�Ō����Ƃ���́u�}�j���A���I�o�A�V�X�g�v(���݂̘I�o�ƃJ���������������W���I�o�Ƃ̍�)�����p����̂ł����A���̋@�\��OM-1MK2�ɂ����ڂ���Ă��܂��B
OM-1��OM-1MK2(G99��G9��)��+0.7����+1.0�ŎB�e���Ă���Ƃ����S5��+1.7����+2.0�ߕӂŎB�e����Ƃ������Ƃ����Ă���
������OM-1����Ƃ��ĂP�i�I�o�I�[�o�[�ɂ��Ă����ł͖����Ƃ������Ƃł��B(�J�������̘I�o���肪�ǂ��Ȃ��Ă邩�܂ł͕�����Ȃ�)
���i�B�e���ɏ�XMFT�@�̕����Ȃ������邭�ʂ�Ƃ͎v���Ă��āA�悭�l���Ă݂��MFT�@���O�a���₷�������Ȃ̂��Ƃ��v��Ȃ��������ł���
�����G9pro2�Ȃ͕��i�g���ł�(�J�������Z�o����W���I�o��)�₯�ɈÂ��ʂ�̂ňꏏ�Ɏg�����͊��������܂��B(�P�Ƀx�[�X���x�̍��Ƃ��H)
�ȏ�A�`����N�����ł����B
�����ԍ��F25866574
![]() 4�_
4�_
��Seagulls����
>OM-1��OM-1MK2(G99��G9��)��+0.7����+1.0�ŎB�e���Ă���Ƃ����S5��+1.7����+2.0�ߕӂŎB�e����Ƃ������Ƃ����Ă��Č�����OM-1����Ƃ��ĂP�i�I�o�I�[�o�[�ɂ��Ă����ł͖����Ƃ������Ƃł��B
���ʂƂ���S5�̕���1�i���I���ʂ������ł���ˁB����ʼn摜���������邳�ɂȂ�Ƃ�����AISO���x�̊���Ⴄ�̂�������܂���ˁBG9pro2���B����͘I�o�i���x�E�i��E�I�o���ԁj�ɑ���摜�̖��邳�̐ݒ�Ⴂ�ł����āA�O�a�Ƃ͖��W�ł��傤�B
�����ʑ̓���I�o�ł���A�ǂ̃J�����������x�̉摜�̖��邳�ɂȂ��Ă����Ȃ��ƍ���܂��ˁB�B�B
�����ԍ��F25866582
![]() 3�_
3�_
���߂܂��Ď莝���n�C���]�i�O�r�g�p�j12bitRAW�E14bitRAW�̔�r�B�e���s���܂����B
�I�o�����͓����AF1.4 SS2.5�b ISO8000
�����͑O�l�AOMworkspace��TIFF�����o���i�m�C�Y���������j��Lightroom�ŕҏW���Ă��܂��B
�����������ĉ_������Ă���ׁA�S�������摜�ɂ͂Ȃ��Ă��܂��T�˓������Ǝv���܂��B
�i�O�i�̖X��14bitRAW�̕������ŗh��ĉ𑜊����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�j
�����͔�r���Ă����ق͂킩��܂���ł����B
12bitRAW�Ńt�@�C���T�C�Y38.5MB�A14bitRAW�Ńt�@�C���T�C�Y46.3MB�iTIFF�����o����͗��t�@�C���Ƃ��ɓ���143MB�j
�ƃt�@�C���T�C�Y��14bit���ɂ߂đ傫���Ƃ������Ƃ��Ȃ��̂Ŋ�����12bitRAW��I�����邱�Ƃ��Ȃ����ȂƂ��������ł��B
�t�@�C���T�C�Y�̍������܂薳���̂Ŗ{����14bit�ɂȂ��Ă���̂��Ƃ����^��͂���܂����E�E�E
�Ƃ������Ƃō���̌��͏I���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25902060
![]() 4�_
4�_
��Seagulls����
�����́B
���؎B�e����ꂳ�܂ł��B
����̂悤�ȉ_�̂��鐯�i�ʐ^�ł��ƁA���X�̖��Í�������Ȃ�ɂ����āA���ʂ̕��i�B�e�Ƃ���قǕς�肪�Ȃ��ł���ˁB
�u�ߓx�Ȓ����v�Ƃ���܂����A12bit��14bit�ʼn摜�����ϐ��̍��ق��킩��Ƃ�����A�����Ƃ����Ɖߌ��Ȓ��������Ȃ��ƌ����Ȃ���������܂���ˁB���S�ɔj�]���Č�����悤�ȁB�u�����ԍ��F25866042�v�Ɏ��������_�ʐ^���x�̏����ł��A����قnj����Ă��Ȃ���������܂���B
�Ƃ����Ƃ���ŁA���`�ʐ^���܂߂Ĉ�ʓI�ȗp�r�ł�12bit�ł��\��������Ƃ������Ƃ����B
�����ԍ��F25902123
![]() 3�_
3�_
�����ƁI
��j���`�ʐ^
���j���i�ʐ^
�����ԍ��F25902128
![]() 0�_
0�_
�n�C���]12bitRAW����ɒ��� |
�n�C���]14bitRAW����ɒ��� |
�n�C���]12bitRAW�p�����[�^�[�����O |
�n�C���]14bitRAW�p�����[�^�����O |
��Tranquility����
�X�ɔ���ѕ����֕ҏW���Ă݂܂����B
�V���h�E�����グ�̑O�i�����{�m�F���Ă݂Ă������掿�ƌ����Ă������Ǝv���܂��B
�悭WEB��̋L����u���O�Ȃ����Ă���Ɓu14bitRAW�Ȃ̂ŃV���h�E���̎����グ���S���Ă����v
�݂����ȋL�q������܂�����ǁA����OM-1MK2��12bit/14bit�ؑւ��ł͍��ق͖������Ƃ��킩��܂����B
14bitRAW�ɂ͊��҂��Ă����̂ł����A��������12bit�ł������Ȃ��Ƃ������ʂƔF�����Ă��܂��B
�i���А��J����14bitRAW�S�ʂ̘b�Ɋg�債�Ă��܂��Ɩʓ|�ȃ��X���o�Ă������Ȃ̂�OM-1����Łj
���Ȃ݂ɍ���̎B�e�ł͕��������A�_�������̂�ISO8000 SS2.5�b�ł���ƍ�������
SS6�b���x�ł͑S�č������s�ƂȂ�܂����B
�{���͓V�̐���B��ɍs�����̂ɁA���C����S�T����Z�b�g�����ɎB�e�����̂͂��̂Q�������ł����B
�����ԍ��F25902434
![]() 1�_
1�_
��Seagulls����
>�悭WEB��̋L����u���O�Ȃ����Ă���Ɓu14bitRAW�Ȃ̂ŃV���h�E���̎����グ���S���Ă����v
>�݂����ȋL�q������܂�����ǁA����OM-1MK2��12bit/14bit�ؑւ��ł͍��ق͖������Ƃ��킩��܂����B
�ubit�����傫�����_�C�i�~�b�N�����W���L���v�Ɗ��Ⴂ���Ă���l���悭���܂��B
�����ԍ��F25902493
![]() 4�_
4�_
�f�W�^�����J���� > SONY > ��6700 ILCE-6700 �{�f�B [�u���b�N]
�����Z���T�[FUJIFILM GFX100�������Ă�F�l����A�u�ŋ߂̃X�}�z������v�ƌ����ĂĎʐ^�������Ă��������A��i���Ɠ��{�g�債�Ȃ��Ƃ����X�}�z�̂ق����p�b�ƌ��ăL���C�Ɍ����܂����B�{������ƁA�F�l�ɂ��̎B�e��p�Ɏg���Ă���X�}�z����Ă��āA�����̃\�j�[APS-C�@�ƊȒP�ɎB�e��r���Ă݂܂����B�Q�l�Ƃ��Ăǂ����B
���_�ł����Ǝ������v���Ă��X�}�z�Ƃ͊��S�ɂ����ʕ��̉掿�ɂȂ��Ă܂����B��i�⎺���͎B�e���Ă܂��A���ɂ��Ȃ肢���Ӗ��Ŕ����Ă��Ă���Ǝv���܂��B���ς�炸�f�W�^���L���܂���̃X�}�z�̎ʐ^�ł����A���܂܂ł̂悤�ȓh��G�ł͂Ȃ��A���{�Ō��Ă����������𑜂��Ă���B�������̊Ԃɂ�1�C���`���̃T�C�Y�𓋍ڂ��ĂāA�J�[���c�@�C�X��APO�F�����Y�����Ă邾�Ƃ��̂悤�ł��B
�{�P�͂܂��܂�APS-C�ɂ͂��Ȃ��܂��A�]�������Y���������ɂ͂��Ȃ��܂��AHDR�͕������ʐ^��AI�ō������Ă���̂��A�f�[�^�Ō������APS-C��RAW�����_�C�i�~�b�N�����W������܂����B������HDR���������ĕςȋC����������������悤�ɂ��v���܂��B���ꂪ�X�}�z�ŃT�b�Ǝ��o���ĉ����l�����Ƀ^�b�`���邾���Ŏ���Ǝv����APS-C���[�U�[�Ƃ��Ă͂Ȃ��₵���Ƃ���ł��B��������肪APS-C����t���T�C�Y�Ɉڍs���Ă���̂��ȂƂ��v���܂����B
���낻�돬�����t���T�C�Y�ɃX�e�b�v�A�b�v���Ȃ��ƁA�Ǝv�������̍����ł��ˁB
![]() 5�_
5�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
������������Ⴄ�ƁA�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͂���Ƀ}�Y�C���ƂɂȂ�܂����B����4800����f��iPhone 16 Pro Max��3300����f�̃�7c II�����Y�L�b�g��荂�掿�Ȗ�ł�����A������t���T�C�Y���X�}�z�Ɏ���đ���̂͊ԈႢ�����[����B
�����ԍ��F25892799�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
�u�`���I�J�����v�́A���������̃_�C�i�~�b�N�����W�̈������A���ԈˑR�Ƃ��Ă��āA
�܂��A�u�`���I�J�����v��HDR���s���R�u���v�ɂ܂�Ȃ��̂ŁA
�u�`���I�J�����v�� Jpeg�ݒ荀�ڂɁy�i�`������HDR�z���X�}�z�I��HDR �Ƃ����ݒ�@�\��V�݂���A
4/3�^�ł��\���ɃX�}�z�ɏ��Ă�̂ł́H
�Ǝv�����肵�܂�(^^;
���P�V���b�g�B�e�݂̂ŁA�������B�e��HDR�Ƃ͈Ⴂ�܂�
�����ԍ��F25892860�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 10�_
10�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
����������肪APS-C����t���T�C�Y�Ɉڍs���Ă���̂��ȂƂ��v���܂����B
�����낻�돬�����t���T�C�Y�ɃX�e�b�v�A�b�v���Ȃ��ƁA�Ǝv�������̍����ł��ˁB
�������lj摜�G���W���̃V���{�C�Ȃ���ăt���T�C�Y�ł̓X�e�b�v�A�b�v�ɂȂ�Ȃ�����C�����ā@��
�����ԍ��F25892882�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
2024/09/16 13:07�i1�N�ȏ�O�j
�Ƃ肠����
�t���T�C�Y��APS-C�������}�E���g�ɂ���ꍇ
APS-C�̓t���T�C�Y�ɑ��Ė]���X�y�V�����Ƃ����Ӗ�������̂�
���̎��v�Ɋւ��Ă̓X�}�z�ɐH���邱�Ƃ͐�ɖ����ł���
�����ԍ��F25892894
![]() 12�_
12�_
2024/09/16 13:13�i1�N�ȏ�O�j
���Ƃ��̍�Ⴍ�炢�̍��Ȃ�APS-C�@�̐ݒ�Ŏ����悤�ɂł���Ǝv����
�X�}�z�̂�DSLR���㏉���̃G���g���[�@�I�Ȗ��t������
�h��ʼnf����G
���̏ꍇ�f�t�H���g�ł́A���Ƃł�����Ղ�
�f���ȊG�Ɏd�グ��̂���ʓI�ł�
�����ԍ��F25892901
![]() 10�_
10�_
�����̎ʐ^/����\�t�g�iPhotoShop���j�̉摜�����Z�p�̖��i�Ԃ�������
���X�摜���x�������������v���܂�
�����h��G�̎���͏I������̂ł��傤
�`�h�����ŁA��f�����F�������~�����ʐ^�ɕϊ����Ă���鎞��Ȃ̂�
�����������G���W���𓋍ڂ����J�������o�Ă���̂���
���[�J�[�Ƃ��Ă͍��ʉ��̐}��ɂ����d�l�͍���̂ł��傤����
���y�d����ڎw�����[�J�[�ɂ̓`�����X�����m��Ȃ�
�����ԍ��F25892933
![]() 5�_
5�_
�\�j�[����̃Z���T�[�J���̗͂̓���������ƁA1�C���`��LYTIA�Z���T�[��������A���ꂩ�������X�}�z�ɒ�߂Ă���̂��ȂƎv���܂����B�uSharp��AQUOS R6��1�C���`���ځv�Ƃ��o�������Ƃ��Ɏ��ʐ^���������ɂ܂��܂����APS-C�̑����ɂ��y�Ȃ��ƈ��S�����̂ɁA���̂܂ɂ��X�}�z�Z���T�[�̐����オ���N�ő������i��ŁA�Ȃ��������i���������C�����܂����B���̂����X�}�z�ł��������ă}�C�N���t�H�[�T�[�Y���ڂ��Ă������Ȑ���������܂��ˁB
�����ԍ��F25892960
![]() 4�_
4�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
�X���傳��́@�����낻�돬�����t���T�C�Y�ɃX�e�b�v�A�b�v���Ȃ���
���ꐳ������������܂���A�f�l�l���ł����A�X�}�z�����̃`�b�v�i�Ⴆ��A18pro����)���J�����ɐςނƒ��ˏオ�鉿�i��Aps-�ȉ��@�͖����A�N�ɂ������Ă��炦�Ȃ������H
�t���T�C�Y�@�ȏ�̃Z���T�[�T�C�Y������A���z�ł����b�g��d���鐔�������߂�Ǝv���܂��A�c���炭�̊Ԃ́c�B
�����ԍ��F25892985
![]() 2�_
2�_
�����̂����X�}�z�ł��������ă}�C�N���t�H�[�T�[�Y���ڂ��Ă������Ȑ���������܂��ˁB
�u���ۂ̏œ_�����ƃ����Y���݂̓s���v�ŁA���Ȃ薳���ł�(^^;
�P�^���ڂ̃X�}�z�ł���A
�E���Zf=19mm�Ȃǂ̒��L�p�ɂ��Ă���B
�E�P�^�̗L���ʂ�S�ʎg�킸�ɃN���b�v(�J�������g���~���O)���Ă���
�E��L�Q�����̗���������Ă���
�̂́A�u���ۂ̏œ_�����ƃ����Y���݂̓s���v�ł��B
�����Zf=24mm�ŁA���ۂ̏œ_�����́A
�@�E�P�^�Ŏ�f=8.8mm
�@�E4/3�^�Ŏ�f=12mm�E�E�E4/3�^�̃����Y���݂��l������ƁA�u�X�}�z�v�ǂ��납�A�P�œ_�R���f�W�̌��݂ɂȂ�܂���(^^;
��̂��X�}�z�ł��̂ŁA�X�}�z�̌��݂� 20~30mm�Ƃ��ɂȂ�ƁA�w���҂̐l�������S���̈�Ƃ��������̈�܂Ō������܂�����A
�u��ʐ��Y�ɂ��R�X�g�ጸ�v�̌������������A
�P�Ƌ@��ŃR�X�g������悤�Ƃ���A20���~�ǂ��납 �����������50���~���Ă��܂��A
�����Ȃ�ƍw���҂͍X�Ɍ�������̂ŁA���i���i�K�ŏ����Ă��܂��܂�(^^;
�����ԍ��F25892996�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 11�_
11�_
��masterm����
���`�h�����ŁA��f�����F�������~�����ʐ^�ɕϊ����Ă���鎞��Ȃ̂�
�������������G���W���𓋍ڂ����J�������o�Ă���̂���
����Ȃ�̂������ˁB
����ȃJ�������o���Ƃ��Ă��A��ʐl�ɂ͔����Ȃ��l�i�Ɨ\�z�B
���ʂ����߂�Ȃ�A����Ȃ�̑Ή����x�����K�v������B
�����ԍ��F25893014�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�����肪�Ƃ��A���E����
���݂̋Z�p�Ȃ�ˁB
�������^�����Y���o��ǂ��Ȃ邩��������B
�����ԍ��F25893114
![]() 3�_
3�_
�����^�����Y
�y�掿�����z�Ȃ�A�F�����Ȃǂ̌��_���X���[�ł��邯��ǂ��A
�y�掿����̎�i�z�Ƃ��� 4/3�^�𓋍ڂ��悤�Ƃ���Ȃ�A�{���]�|(^^;
�������A�y���ۂ̏œ_�����ɂ����݁z���͎c�����܂�(^^;
�����ԍ��F25893150�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�����肪�Ƃ��A���E����
�m���ɁB����B
�����ԍ��F25893159
![]() 2�_
2�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
���X���Ǝv���܂��B
�J�����s��͂���10���N�̊ԂɃs�[�N����1/20�܂ŋK�͂��k�����܂����B
�����̓X�}�z�̃J�������\�̑䓪�ł���A����͂ǂ̃J�������[�J�[���F�߂Ă���Ƃ���ł��B
���掿�Ƃ������[�h�Ɂy�_�C�i�~�b�N�����W�E�����E�t�s���\�E�𑜓x�z���܂܂Ȃ��̂ł���A�p�b�ƌ����Y�킳�ł̓X�}�z�̉掿�����iJPEG�j�͑f���炵���Ǝv���܂��B
�����Ă��̉��₩�ȕ`�ʂ͐��̑命���������錋�ʂ������炵�A�J�����s��͐��ނ��Č��݂̎s��K�͂ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B
���̐���X�}�z�̃J�����i���͎~�܂邱�Ƃ��Ȃ��ł��傤���A���Z�����Ɏg����`�b�v�̂���Ȃ�i���ɂ��AAF���\��AI�F�����\�̕���ɂ����Ă��J������u������ɂ��Ă��܂������������͂Ȃ���������܂���B
�i���i�J����������������Ⴄ�ł��傤���j
�����ԍ��F25893728�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
���q��89523����
���ꂩ��͒�R�X�g�ቿ�i�J�������o�����[�J�[�����ڂ���邩���ˁB
�Ⴆ�P���R�[�B
�����������[�J�[��5���~�O��̃f�W�^�����t�_�u���Y�[���L�b�g�o���Ă��ꂽ��A��萔�͔����Ǝv���B
�����ԍ��F25893738�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
���Ȃ��Ƃ����̕��X�̓X�}�z�ɕς���l�Ȏ��͖����Ǝv���܂��B
���N��͉���܂��B
�����ԍ��F25893770�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
���@�\�ɂ���t���T�C�Y�ƂقƂ�Ǖς��Ȃ����i�ɂȂ���APS-C�̈����Ƃ��������b�g�͎����Ă��܂��܂�����A���[�J�[���t���O�V�b�v��APS-C����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�ƂȂ�A�@�\�őI�ׂt���T�C�Y�����I����������܂���B
�i�x�m�t�B�����AOM�V�X�e���������j
��r�P�̋����Ȃ�̂́APL�t�B���^�[���g�����Ȃǂƌ����Ă܂��ˁB
�y���^�b�N�X��OM�V�X�e���͐�̐F���Y��ɏo�₷���Ǝv���̂ŁA���F���Y��Ƃ��A���Z���Ƃ��Ɠ����A�u���[�J�[�̐F�����v���Ǝv���܂��B
��i�ƃn�C���C�g���V���h�E�R���g���[���̗��K�����Ă���̂ŁA���������Ȃ̂�iPhone13Pro�ł��B���Ă݂܂����B
���@��ł��݂܂��AOM-5�̎B���ďo���ł��B�iRAW�ҏW�ł��������Ƃ͉\�ł��B�j
�������ł̓t���A�Ŕ����ۂ��Ȃ�܂����A�n�C���C�g���V���h�E������ƃp�L�b�Ƃ��������ɂȂ�܂��B
����ɍʓx���グ�ăI�����W�F�������i�z���C�g�o�����X�H�j����Ƃ��X�}�z���ۂ��Ȃ�Ǝv���܂��B
�����ꂪ�X�}�z�ŃT�b�Ǝ��o���ĉ����l�����Ƀ^�b�`���邾���Ŏ���Ǝv����APS-C���[�U�[�Ƃ��Ă͂Ȃ��₵���Ƃ���ł��B
�X�}�z�̓t���I�[�g�ł���ł�����ˁB
4k�T�C�Y�ⓙ�{�ŕ��ׂ�Ή𑜊��ɍ�������̂��킩��܂����A�X�}�z�T�C�Y�AFHD�T�C�Y�̒P�i�Ō���A�܂��Ⴂ�͂킩��Ȃ��ł��ˁB
�~���[���X�����������@�\���I�[�g�łł���悤�ɂȂ�̂��Ƃ����Ƃ�����Ɠ���i�Z�p�I�ɂ͉\�����^�p���j�Ƃ��č��Ȃ��j�C�͂��܂����ALUMIX��LUT�K�p�̂悤�ɁA�������Ⴄ�����œ����͂���Ǝv���܂��B
�摜�����̖��Ȃ̂ŁA�X�}�z�������悤�ɂȂ�A�������̓J�����A�v����RAW�ҏW�A�v������������̂����Ԃ̖�肩������܂��ǁB
�]�k�ł����A���I�ɂ́i���̓��H�A�����Ԃ̃X�s�[�h�ɂ�����j�����Ԃ̃u���̑傫����1/8�b��1/15�b���D�݂ł��B
�Q�l
�J������TV�F�y�J�����Z�p����z�X�}�z�̎ʐ^�̓L���C�I�H�u�X�}�z�J�������l����v�`�𑜌��E����摜�����܂Ł`
https://youtu.be/7oD3__nhOrw?si=YjqmMf7658hw0cGJ&t=728
�iURL�����N�̓X�}�z���摜�����̃`���v�^�[�ɔ�т܂����A�ŏ����猩�邱�Ƃ������߂��܂��B�j
�����ԍ��F25893829
![]() 2�_
2�_
F2.5 1/14�b ISO2635 233mm(35mm���Z) |
F2.5 1/100�b ISO55 233mm(35mm���Z) |
F1.8 1/33�b ISO672 23mm(35mm���Z) |
F1.8 1/50�b ISO-486 23mm(35mm���Z) |
�F����A�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�lj��ŃX�}�z�ō����B�e���܂����B��i�́u�G���v����͂苰�낵�����ƂɂȂ��Ă��āA�ŋߏo��iPhone16pro�͂��Ԃ�����Ƃ��ꂢ�Ȃ�ł��傤�ˁE�E�������̂��A�]���͈��̐ꔄ�������Ǝv���Ă��̂��A10�{���炢�܂ł̖]���Ȃ�X�}�z�ł��u�g����v�掿�ɂȂ��Ă������Ƃł����ˁB�m���ɂ��������ʂ�A�X�}�z�͂ǂ�ǂ�i������̂ł��傤���ǁA�ʐ^���B�e���Ă���V�������Ȃ��āA�B�e�����C�g�߂��Ă�����ւ�̒��w���Ɠ������Ў�ŃT�b�Ǝ��o���ă^�b�`�ŒN�ł��L���C�Ƃ����̂��Ȃ�Ƃ��������܂����B�܂��A�������Ƃł��傤���ǂˁB
�X�}�z���[�J�[�ɂ����ƎB�e���ʓ|�ȋV�������o��X�}�z���o���Ăق������̂ł��ˁB
�����ԍ��F25893951
![]() 4�_
4�_
���}���`���f�B�A�}�X�^�[����
�@�X�}�[�g�t�H����(�C�y��)�|�P�b�g�ɓ���āA�v���������ɎB�e�ł���֗����͍ō��ł��B
�������A���x����蒼���̏o����B�e�ł͎g�����������ł����A�����̑����͈̂��t����B
�X�ɁA����̓����͉�ʂ��Â��Ċ��ŎB�e���鎖�ɂȂ莞�ɂ͖ҏ��ʼn��x�x���ł̎B�e�҂��͕s�ցB
UP�ʐ^��Canon��APS-C�J�����ŁA�Q���ڂ̓X�}�[�g�t�H���ł��B���!?�A3���ڂ̂悤�ȍL�p�ʐ^�Ȃ�X�}�[�g�t�H���ł��]�T!?�A�Ȃ�ɂ��Ă��K�ޓK���ŃX�}�[�g�t�H���ƈ��t�J�������g��������Ηǂ������Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɂR���ڂ͌��ɍs���Ȃ������l�ւ̐����p�Ƃ��ċ@�̂����B���Ă��|���Ȃ��v���}篎B�e�����̂ł����A�ԋ߂̃u���[�C���p���X�̑��x�͐q��łȂ���ʓ��Ɏ��߂�̂͑�ςł����B
�����ԍ��F25894879
![]() 5�_
5�_
����f�W�C�`��~���[���X�͐������̂��߂̓���B
�����A�������͎��Ԃɂ�Ƃ肪����l����B
�X�}�z�������@��
�����ԍ��F25894898�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > CANON > EOS R5 Mark II �{�f�B
R5�����^�Ɣ�r���āA�Ï����ア�Ƃ̂��b������܂����l�I�ɂ͖��Ȃ��ł��ˁB
���ƁA���ꂾ���㏈���̋Z�p�����B�������ŁARAW�{�ӏ܂��邱�Ƃɂǂ�قLjӖ�������̂��낤���Ǝv���������̍��A�A�A
R5m2�͌㏈�������Ȃ�ӎ����ꂽ�@�킾�Ǝv���܂��̂ŁB
�������r���i�K�Ƃ��ĎQ�l�ɂ͂��܂����A�܂��͏����\�t�g�E�G�A�Ō������ʂ����Ĕ[���������ǂ����ł���ˁB
���܂��A����R5�������ĂȂ��̂Ŕ�r����ł��Ȃ��̂�AI�m�C�Y�����̔�r�����ł��܂��B�B�B
���Ȃ݂ɁAdpreview�̔�r�摜�����\�������قȂ�̂ŋ^��������܂��B
�����\�t�g��r�łȂ��_�����łȂ��ARAW��JPEG�Ńt�@�C�������قȂ�����A���邳���قȂ�����ƌ����Ȕ�r���ł��Ă��Ȃ��ł��B
�����Y���قȂ�͎̂���w�i������̂ŋ��e�ł��܂����E�E�E����ȊO�͂��Ȃ�^��������܂��ˁB
![]() 20�_
20�_
������75����
dpreview�̔�r�摜�����\�������قȂ�̂ŋ^��������܂��B
dpreview�͒�ʕ��͂��o���Ȃ��f�l�ł�����A�S�����ĂɂȂ�܂���B
�܂��A�]�����]���������s���m�Ȃ��߁A����������r����ł��Ȃ��B
quantitative analysis
���ʂ𐔒l�����A�q�ϓI�ɑ��ΓI�ɕ]������
�����ԍ��F25892928
![]() 3�_
3�_
2024/09/16 14:48�i1�N�ȏ�O�j
�����ꂾ���㏈���̋Z�p�����B�������ŁARAW�{�ӏ܂��邱�Ƃɂǂ�قLjӖ�������̂��낤���Ǝv���������̍��A�A�A
���������l����l������ˁB
RAW�̓Z���T�[��������������̂܂܃f�W�^���f�[�^�[�ŋL�^���������B�㏈���ƍl����̂́B�H
�����ԍ��F25892993
![]() 0�_
0�_
���݂��ǂ��Ȃ��Ă邩�͗ǂ��������Ă܂��A�����̃f�W�J���ɑ��闝���͈ȉ��ł��B
�E�C���[�W�Z���T�[����̖��t�������̃X�b�s���f�[�^���q�`�v�t�@�C���ɓ����B
�E���̍ۂɁA�f�W�J���̃��j���[�Őݒ肵���ʓx���F�̕��疾�邳���̏��X�́w���t���x�����q�`�v�t�@�C���ɓ����B
�i���t�@�C���ŏ������Ȃ�Ėʓ|�Ȃ������l����������܂���ł��j
�E�w���t���x���ɏ]���ăX�b�s���摜�f�[�^�����H������̉摜�f�[�^��Jpeg���k�`���ň��k�ۑ������̂�Jpeg�t�@�C���B
�ERAW�t�@�C�����̃X�b�s���摜�f�[�^������i���������u���E�W���O�\�t�g�Ȃ��p�r���[��������j�A���Ƃ��Ⴆ�Ȃ��摜�����邱�Ƃ��o���锤�ł��B�v�͖��t������ĂȂ�������RAW���������́G�����H�́C�������́A�ƌ����Ӗ��ł��ȁB
�Ȃ̂ŃX���^�C�ɂ���wRAW�Ŕ�r���鎞��Ȃ̂��x�ƌ����^��ɂ��ẮA���������C���[�W�Z���T�[�̃X�b�s���摜�������Ƃ���ŁA�C���[�W�Z���T�[�̐����\��������Ȃ��B�f�W�^���J�����Ƃ��Ă̑������\���C���[�W�Z���T�[�̒������{�f�W�J���̖��t�����\�A�����Ȃ����ɂ͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B
���݂ɂ��̖��t����Ɂw�߂��x�̂�Jpeg�摜�f�[�^�A�ƌ��������ŁA����܂�Jpeg�ŗL�̔�t�Ȉ��k�ɂ��A���l�^�f�[�^�����S�ɕ����o���Ȃ����́A�������c�ł����ˁH
�E�E�E�ȏ�̐^�U�̒��́A�����g�Ńl�b�g���������Ȃ�}���قŒ��ׂ�Ȃ�A���D���ɋX�����ł��B
�����ԍ��F25893049
![]() 4�_
4�_
����̓j���[�����l�b�g���[�N�̃m�C�Y���_�N�V�����ł��傤���H
�������ł��ˁB
�摜�E���ɂ��锒���������ƕ�����܂����A�𑜓x���A�b�v���Ă܂��ˁB
���������������x�������Ȃ�����A���ʂ̒P�ʃ��[�h�ɕW���ŕt�������ł��ˁB
�����ԍ��F25893070
![]() 4�_
4�_
��taka0730����
�͂��A�j���[�����l�b�g���[�N�m�C�Y���_�N�V�����ł��B
�f���ɂ������ł���˂��B�B�B
�����������������x�������Ȃ�����A���ʂ̒P�ʃ��[�h�ɕW���ŕt�������ł��ˁB
�m���ɂ����ł��B
�t�@�[���A�b�v�ł���Ă��ꂽ���������ł����ǁB�B�B
Canon�����낵�����肢���܂��I�i�ҋ@���Ԃ������Ă��҂��܂��j
�����ԍ��F25893152
![]() 1�_
1�_
�X���傳��̃R�����g�̓��e�ɑS�ʓI�ɓ��ӂ���킯����Ȃ��̂ł�����
�A�b�v���ꂽ�j���[�����l�b�g���[�N�m�C�Y�ጸ�̌��ʂ͂ƂĂ��ǂ��ł���
�ςȕ���p�C�ɂȂ�Ƃ��떳���A���ʏo�Ă܂��ˁ[�I
�����ԍ��F25893170�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����Ɍ�����RAW�f�[�^�Ƃ����ǂ��A�m�C�Y�W�Ƃ���������Ă�����̂ł͂Ȃ����������H
����͒u���Ƃ��ăJ�������ł̃j���[����RAW�m�C�Y������DXO��C�g���[���ATopaz�ALuminar neo���̑����X�Ƃ̔�r���C�ɂȂ�܂��B���[�J�[�̗D�ʐ����Ă���̂��ȂƁB
�����ԍ��F25893202�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
dpreview�̔�r�摜��RAW�̃|�e���V���������邽�߂ɎQ�l�ɂ��Ă���l���Ă��Ȃ��Ǝv���܂���B�����Ƃ��Ă��A���S�҂�RAW�ɑ��ċ����͈͂ł����F�����ĂȂ��l�����ł��傤�ˁB
https://youtu.be/CkIznWgGpj8?si=RMjTSHwKIvJa-R1g
���������uR5�����^�Ɣ�r���āA�Ï����ア�Ƃ̂��b�v���ǂ������邩�̖��ł����A���i�̊ϗ��Ԃ���ISO�ŎB���ĂƂ���������RAW�̏��ʂ��͂��e�X�g���邱�Ƃ́i���̏ꍇ�j�Ȃ��ł��B
�܂����̂悤�Ȕ�ʑ̂�Ȃ̋����V�l�}���v���Z�b�g����d�グ�鎖�͕��ʂȂ��ł��傤���A�P�x��������i���͏Ɩ�����肭�����炸�j�A�ɂȂ��Ă��镔���������グ����ł����炩�ȊK���E�F�̑N�x���ێ��������݂����ȃn�[�h�����Ȃ��̂ł���A�����RAW�̔�r�Ƃ��Ă͐������܂���B�m�C�Y����肭��������A�Ƃ�������Ӗ��X�}�z�I�ȉ掿�̔��e�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�Ƃ͂����uRAW�̎��́v�𑽕��ʂ��画�f����̂ł͂Ȃ��A�P���ɈÏ��ł̃m�C�Y���\���݂����̂ł����dpreview�̔�r�摜������Ȃ�ɗL�p���Ǝv���܂��B�j���[�����l�b�g���[�N�m�C�Y���_�N�V�����₻��ɋ߂������́AR�T�U�����łȂ�R�T�̃f�[�^�ɂ��K�p�\�ł��傤����AR�T�U���uISO12800�ő��v�v�Ȃ�R�T�́u����ɂ��������グ�Ă����v�i���ǂ����H�j�v�I�Ȑ����͏o���锤�ł��ˁB
�����ԍ��F25893253
![]() 5�_
5�_
2024/09/16 18:22�i1�N�ȏ�O�j
�㏈���ł��̂Ȃ�
���ǁARAW�i�K�ł̍������̂܂܌��ʂł̍��ɔ�Ⴗ�邾������Ȃ����ȁH
RAW�Ƃ������ݔ\�͂ڔ�r���鉿�l�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ǝv����
�����ԍ��F25893261
![]() 6�_
6�_
���J����SP����
��dpreview�̔�r�摜��RAW�̃|�e���V���������邽�߂ɎQ�l�ɂ��Ă���l���Ă��Ȃ��Ǝv���܂���B�����Ƃ��Ă��A���S�҂�RAW�ɑ��ċ����͈͂ł����F�����ĂȂ��l�����ł��傤�ˁB
�����������L�����o�āA���������ɎQ�l�ɂ����T�C�g���o�܂��āA�Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B
https://asobinet.com/info-sample-eos-r5-mark-ii-dp-studio/
���Ƃ͂����uRAW�̎��́v�𑽕��ʂ��画�f����̂ł͂Ȃ��A�P���ɈÏ��ł̃m�C�Y���\���݂����̂ł����dpreview�̔�r�摜������Ȃ�ɗL�p���Ǝv���܂��B
���j���[�����l�b�g���[�N�m�C�Y���_�N�V�����₻��ɋ߂������́AR�T�U�����łȂ�R�T�̃f�[�^�ɂ��K�p�\�ł��傤����AR�T�U���uISO12800�ő��v�v�Ȃ�R�T�́u����ɂ��������グ�Ă����v�i���ǂ����H�j�v�I�Ȑ����͏o���锤�ł��ˁB
���݂܂���B���ꂪ�ł��Ȃ��̂ł��̃X���b�h�𗧂��グ�܂����A�����Ԃ������dpreview��R5��R5m2��RAW��JPEG���_�E�����[�h���Ď�����������AExif�����m�F�肢�܂��B�����ɂ킩��Ǝv���܂����A�O������������Ⴎ����ŁA�A�A
�{���ɁA�����ڂ̖��邳�܂ňႤ�̂͏ł�܂����B
�܂��A�����ɂ�����d�v�ȗv�f�����J����Ă��Ȃ����ߑS���L�p�ł͂Ȃ��Ƃ̌��_�Ɏ���B�B�B
photonstophotos.net����̃f�[�^�����邩��ɂ͂��Ȃ�͍��Ȃ̂ł����Adpreview�͂��܂�ɂ�R5���ǂ����܂��B
���́A���̃J�����Ɣ�r���Ă�R5�͗D������Ă���悤�ȋC����v���܂��E�E�E
���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
RAW�Ƃ������ݔ\�͂ڔ�r���鉿�l�͎����Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v���̂ł����A����̕ω��ƂƂ��ɕۑ��`����O��������ς�����Ǝv���Ă��܂��B
�ŋ߂ł�CR2�ACR3�ł������������܂����̂ŁB�iCR3�̂ق������掿�ɂȂ������ʁA�R���s���[�g���\�[�X��v������悤�ɂȂ�܂������B�B�B�j
RAW���Z���T�[�������̂܂o���Ă���Ƃ͌����Ȃ����ォ�ȂƁB
DPRAW�̓f���A���s�N�Z��CMOS�̐��f�[�^�Ɍ���Ȃ��߂��Ǝv���܂����A�A�A
�����ԍ��F25893319
![]() 0�_
0�_
2024/09/16 19:26�i1�N�ȏ�O�j
������75����
�l�I�ɂ�RAW�������ǂ����͂��܂�d�v�����Ă��Ȃ�����
�l��RAW���g���͍̂��r�b�g������Ƃ��������ł���
���ł��邩�ǂ����͂ǂ����ł��ǂ��Ǝv��
�j�R����10�N�ȏ�O��RAW��NR�����Ă��Ă̂����邵�i�j
�����܂�RAW����ɂ��̂��Ƃ̉摜����������Ƃ͎v���̂�
��Ƃ��ĈӖ�������Ƃ�����������
���Ȃ݂��t������DSLR�ɂ�TIFF��RAW�Ƃ��Ă����J����������܂���
������8�r�b�gTIFF�i�j
�����ԍ��F25893332
![]() 1�_
1�_
��������X�[�p�[�n�C�r�W��������
������͂�����
���݂܂���B
���e�����͂��̃R�����g���������Ă���܂��āA�A
��RAW�̓Z���T�[��������������̂܂܃f�W�^���f�[�^�[�ŋL�^��������
�ł�������̂ł����A�uDAWGBEAR����v������������Ă���ʂ�A�ŋ߂͏�����������Ă���̂ł͂Ƌ^���������Ă��܂��āB�B�B
���Ȃ݂ɁACanon����̓f���A���s�N�Z��CMOS�Ȃ̂ŁA�{���̐��f�[�^��DPRAW�ł��B�iDP����Ȃ����_�ʼn��H�ς݂Ȃ�ł���ˁj
�������������̂́A�����̋Z�p�̔��W��
�@�@RAW����̌㏈���̔�d���傫���Ȃ��Ă���B�i�㏈���́uDIGIC X�v�ɂ�鏈����AI�m�C�Y�������w���Ă��܂��j
�@�Adpreview�͑O���������B
�Ȃ̂ŁA���ɕߑ������dpreview��RAW��r�����Ƃɂ����L���ɑ��Ă�����Ƌ^�������������ł��B
�e���[�J�̏����\�t�g�Ō�������JPEG�Ŕ�r���Ȃ��ƁA�uDIGIC X�v�Ȃǂ̐^�̃J���[�T�C�G���X�̍����o�Ȃ��̂ł́H�Ƃ��A�A
�����\�t�g�Ō�������JPEG���A�J�����{�̂���o�͂��ꂽJPEG�Ŕ�r���Ȃ��ƃX�^�[�g�n�_������Ă�悤�Ɏv���܂����̂ŁA�^��𓊂����������Ă��������܂����B
�������v���̕���Adobe�Ȃǂ̐��i���x�[�X�ɂȂ�̂ŁA���̂����Ŕ�r��������������ł����AAdobe�Ȃ̂�Capture One�Ȃ̂��ɂ���Ă��P�[�X�o�C�P�[�X�ŁA�t�]���ۂ�����̂ł͂ƁB�B�B
�����ԍ��F25893359
![]() 1�_
1�_
����ł����̂Ȃ�A�����Y����o���o������Ă����̂ł����ˁB
�����ԍ��F25893429
![]() 2�_
2�_
���̍l���ł���
�v���ɍŏ����炻���܂ōl���Ă������ǂ������Ǝv��
���������Y�̐v�ł́A�J�������Řc�ȕ���邱�Ƃ�O��Ɍ��w�v���܂����
����Ȃ烉�{�T�C�g���]�����ׂ��Ȃ̂͂��̕���ꂽ���Ƃŗǂ����Ȃ�
���āA�Z���T�[�̓����͂܂��A�㏈����AI-NR�����邱�Ƃ�z�肵�Ă���ɍœK�Ȑv��I��ł�킯����Ȃ��̂ŁA�㏈���͌㏈���A�ȂƎv���A�f�̃Z���T�[�̓�������͂�m�肽���Ȃ�܂���
�����ԍ��F25893474�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
2024/09/16 21:27�i1�N�ȏ�O�j
�܂��~���[���X�ł̓����Y��͂ǂ�������Ă邩��Ȃ�
�ے肵���班�Ȃ��Ƃ����������Y�g���Ȃ��i�j
�l��DSLR����̓����Y��匙�����������ǂ�
�~���[���X�͂ǂ����ł���������
EVF�̓����Y���̌��ʂ������Ă����̂�
�B������\�}���ς�����Ď��ɂ͂Ȃ��c
�����ԍ��F25893503
![]() 1�_
1�_
������75����
���X���m���܂����B
���N�O�܂œ�����Adobe��1078�~�^���̂��z�{�Ńt�H�g�V���̃v���ł��g���Ă���܂����B
���A�M�S���Ȃ�A�t�H�g�V���G�������g�ɏ@�|�ւ����Ă��z�{�͐���Ă��܂��܂����B
�v���̏ꍇ�A���炭�J�����}���͎B�邾���A�㏈���̃f�U�C�i�[����i�N���G�C�^�[���ȁj�͉摜�f�[�^���t�H�g�V���ł������ƃN���C�A���g����w���ʂ�Ɏd�オ�邾���A�̕��Ƃ��Ƃ͍����v���Ă܂��i�Ԉ���Ă��炷���܂���j�B
10�N�߂��O��Adobe�̃Z�~�i�Q���̋@�����A���̃v���̎菇�ƌ����̂�q�����܂����B�����������牽���ƌ������C���[���d�˂��A�h�b�g�P�ʂŔ��ɓ���ׂɓ���C�������ŁA�A�}�ƃv���̑傫�ȍ��ƌ����̂����������܂����B
�����A����Ȏ��ォ��RAW�̓X�b�s���摜�{�A���t�@�́w�����x������낤�Ȃ��A�Ƃ͎v���Ă���܂����B
�����A�����Nj�����ɂ͂��܂�ɂ��d�l�����G���낤�Ɨe�Ղɑz���ł����̂ŁA�����Ƃ��Ă�
�@�@�@�@��t��Jpeg���́A��������F�̈����Ղ����Ȃq�`�v�ʼn���Ȏd�オ���M�邱��
��I�т܂����B
�c�l���Ă݂��A�C���[�W�Z���T�[�ɓ���O�Ƀv���e�N�^�i�t���Ă�j�A�����Y�R�[�e�B���O�A�Z���T�[�̃��[�p�X�t�B���^�A�Z���T���̂��́A�`�^�c�ϊ�����t�B���^�����O�̃A�v�����n�[�h�����o�Ă�̂ŁA���̎��_�ŃX�b�s�����ł͖����Ȃ�Ǝ����͗������Ă܂��B
���łɃt�@�C�����r���[�C���O����ɂ��A�f�B�X�v���C�̐F���Č�����炪����Łw�^�Ɂx�X�b�s���ȏ��͊|������Ă�Ɨ������Ă܂��B
�Ȃ̂ŁwRAW�������܂ŃX�b�s���Ȃ̂��x�́A������x�ȏ�l���Ă����ʂ����Ȃ̂ŁA�l���Ȃ����Ƃɂ��Ă܂��B
�����ԍ��F25893514
![]() 0�_
0�_
2024/09/16 21:49�i1�N�ȏ�O�j
���v���̏ꍇ�A���炭�J�����}���͎B�邾���A�㏈���̃f�U�C�i�[����i�N���G�C�^�[���ȁj�͉摜�f�[�^���t�H�g�V���ł������ƃN���C�A���g����w���ʂ�Ɏd�オ�邾���A�̕��Ƃ��Ƃ͍����v���Ă܂��i�Ԉ���Ă��炷���܂���j�B
���Ƃɂ��Ă���͈̂ꕔ�ł��傤��
�f�W�^���ɂȂ茻�����^�b�`�̓J�����}���̃T�[�r�X�c�Ƃ݂����Ȃ��̂ɂȂ����ꍇ�������ł�
�i�t�B��������̓t�B�����n���܂ł��d������������Łj
���̏ꍇ�A�J�����}���͘J�����Ԃ������ł����炵��������
JPEG�B���ďo����˂��l�߂��肵�܂�
�v���ɂȂ�ł��̎ʐ^RAW�ŎB��́H�ƌ���ꂽ���Ƃ���܂��i�j
�����ԍ��F25893530
![]() 2�_
2�_
���v���ɂȂ�ł��̎ʐ^RAW�ŎB��́H�ƌ���ꂽ���Ƃ���܂��i�j
�����A�\���Ŏv���o�����B
�̂͂s�h�e�e�[�i�Ȃ�Ă̂��������ȁ`
�����ԍ��F25893554
![]() 1�_
1�_
�hDPreview�́h �Ƃ����\���Ɉ�a���������܂��B���m�ɂ́A�hDPreview�ŏЉ��Ă���ʐ^�́h�A�ł���ˁBDPreview�͈�x�ׂꂩ���āA���͏����̕ҏW�����ʼn^�c���Ă���݂����ł��B�����A�ʐ^��e�L�X�g�ɕҏW���͊֗^���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�v����ɏЉ�Ă��邾���BDPreview�Ƃ�����Ђ��ꑮ�̃J�����}�����ق��A���邢�͗L���ň˗����ĎB�e���Ă���Ƃ���Θb�͕ʂł����E�E�E
�܂��ARAW�̔�r�Ƃ����\�����ςł��BRAW�́A�\���p��JPEG�摜���܂�ł��܂����A�����RAW�Ƃ��ĕ\�����Ă��邾���ŁA�����ڂł̔�r�͂ł��Ȃ��͂��ł��B
���́AYoutube�̔�r�L����M�p���Ă��܂��B�������l�����Ăł��邱�Ƃ��d�v�ł��B�P�Ƃ̃J�����A�����Y�̋L���͒L���̉\��������A�M�p�ł��܂��A��r�L���͎����̖ڂŔ��f�ł���̂ŐM�p���Ă��܂��B���ꂾ���āA���炩�̍�ׂ�����̂�������܂��A����������o������A�����M�p�ł�����̂��Ȃ��ł��傤�B���i.com�̋L�����A�������Ă���l�̖��O�����āA�M�p�x�����߂Ă��܂��B
�ŋ߂̃m�C�Y�ጸ�@�\�͑f���炵���Ɗ����Ă��܂����A���ۂɎg���Ă݂�ƁA���̂��������Ԃ�������A�ŏI�i�K�̒�o�̊ԍۂłȂ��ƁA�g���C�����܂���B�������������āA�����Ƀm�C�Y�ጸ�������Ă����r���āA��o�摜�����߂�Ƃ������p�r�ɂ͕s�K���낤�Ɗ����Ă��܂��B
�R���e�X�g�́A���낢�����������܂����A�m�C�Y�ጸ���g��Ȃ����ƂƂ������������������Ƃ�����܂���B���̂��������������邩������܂���B�����RAW�摜�̓Y�t��v������R���e�X�g���ƁA�m�C�Y�ጸ�����摜�͂͂˂���Ǝv���܂��B
�ʐ^�B�e�̍ŏI�ڕW�́A���l�ɔ����Ă��炦��ʐ^���B�邱�Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B���̂��߂Ȃ�AAI�����A�����ȂǂȂ�ł����肩�ȂƎv���Ă��܂��B�C�O�̃R���e�X�g�T�C�g�i1X�Ȃǁj�́A����AI�摜�͕s�A�Ƃ��炢���������ĂȂ��ł��B�����ł��Ȃ�撣��Ȃ��Ƃ܂��F�߂�ꂻ�����Ȃ��ł��B�摜�ɂ͔̔������ǂ����L�ڂł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25893640�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�u���[�j���O����
���̂͂s�h�e�e�[�i�Ȃ�Ă̂��������ȁ`
���b�A���͂Ȃ��́H
�����ԍ��F25894432
![]() 1�_
1�_
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z�O���{�Ȃ�
-
�y�~�������̃��X�g�z���ʼn���VR�Q�[�������K��
-
�y����E�A�h�o�C�X�z�\��
-
�y�~�������̃��X�g�z�� E�}�E���g�n
-
�y�~�������̃��X�g�z�w�����X�g
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
�i�J�����j