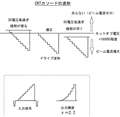-
EOS 5D
- �f�W�^�����J���� > EOS > EOS 5D
- ���t�J���� > EOS > EOS 5D
EOS 5D Mark II EF24-105L IS U �����Y�L�b�g
�uEOS 5D Mark II�v�ƕW���Y�[�������YEF24-105mm F4L IS USM�̃L�b�g���f���B���i�̓I�[�v��

-
- �f�W�^�����J���� -��
- ���t�J���� -��
�y�t�������Y���e�zEF24-105mm F4L IS USM �����Y
EOS 5D Mark II EF24-105L IS U �����Y�L�b�gCANON
�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �������F2008�N11��29��
EOS 5D Mark II EF24-105L IS U �����Y�L�b�g �̃N�`�R�~�f����
�i101282���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S1085�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2009�N12��25�� 22:39 | |
| 16 | 45 | 2009�N12��24�� 15:21 | |
| 113 | 41 | 2009�N12��21�� 20:31 | |
| 69 | 8 | 2009�N12��17�� 13:03 | |
| 1 | 0 | 2009�N12��16�� 13:16 | |
| 78 | 131 | 2009�N12��12�� 22:30 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 5D Mark II EF24-105L IS U �����Y�L�b�g
�N���[�^�[�̂������͂����蔻�錎�̎ʐ^���B�肽���āC���C�u�r���[�B�e�����݂܂����B�Ƃ��낪�I�o�I�[�o�[�n������Ȃ��Ȃ������o�����C�ʓ|�ɂȂ��Ď~�߂Ă��܂��܂����B�i������j
�����ǂނƁC�������[�h�̓��C�u�r���[�p�̕]�������ɌŒ肳���Ƃ̂��ƁB
�ʏ��AF�B�e�ł̓X�|�b�g+�I�o��ł��܂������܂����C���C�u�r���[�B�e���ƕ�͈̔͂��܂��B�}�j���A���ł��܂������܂ŎB�e���邵���Ȃ��̂��ȥ��
�F���������Ƃ���܂���H
![]() 0�_
0�_
�{�f�B�[�Ⴂ�ł����A���傤�ǁA����50D�ł���Ȃ��Ƃ�����Ă��܂����B
Av���[�h�ł��傤�ǂ����ȂƎv���ăV���b�^�[���ƘI�o�I�[�o�[�ɂȂ�A
�I�o��ł͕������܂���B
Av���[�h�̃V���b�^�[���x���Q�l�ɂ��Ă��傤�ǂ悳�����ȃV���b�^�[���x
��M���[�h�ɂ���ƃ��C�u�r���[�ł͌����w�nj����܂���B
�d���������̂�Av���[�h�Ńs���g�����킹��M���[�h�ɐ�ւ��ĎB�e���Ă܂����B
�����ԍ��F10680904
![]() 0�_
0�_
�@�s���g�����C�u�r���[�ō��킹���烌���Y��MF�ɂ��ăt�H�[�J�X�ʒu���Œ肵�Ă��܂��āA���Ƃ͒ʏ�B�e���[�h�ŃX�|�b�g��������Ȃ�A�}�j���A���ŘI�o���߂�Ȃ�ł��܂������Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F10680937
![]() 0�_
0�_
��C�̂�炬�Ȃlje�������Ȃ��V���ő_���̂��~�\�Ƃ̎��A���̋��������m�f�A�V�̎ʐ^�ł͐�p�\�t�g�ŏC�����āA�N���[�^�[��������̎ʐ^�ɂ��܂����ǁB
�����ԍ��F10682946
![]() 0�_
0�_
>KISH1968����
���g���̃����Y�͉��ł����H�Y��ɎB��Ă��܂��ˁ[�B
>���쐅������
�Ȃ�قǁB�B�B
���ɓ������Ȃ��悤�f�������K�v�����肻���ł��ˁB
���x����Ă݂܂��B
>�R�����e����
�V�̂Ƀn�}��\��͂���܂��C�R�ɂ͓o��܂��B
�R���ł̐��͑f���炵���������ł����C�ŋ߂͎O�r�S���ł������������
�����ԍ��F10684079
![]() 0�_
0�_
>���쐅������
���C��������������v������i�j
���C�������Ă�����c�O�Ȃ���O���ł��B
�����ԍ��F10684159
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��������܂��B
�����Y�̓J���������Y�ł͂Ȃ��A8cm�̋��ܖ]�����ł��B
��T�]���������̂ł����Ȃ��Ȃ��V��Ɍb�܂ꂸ�A
����ƍ���e�X�g�B�e���ł��܂����B
�����ԍ��F10684585
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 5D Mark II �{�f�B
������
EOS 5D Mark II �{�f�B��Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE�����Ă�����݂Ȃ���ɂ��̔Ŕw����������Ď������ԓ��肳���Ă��������܂������A�ǂ����Macro-Planar ZE���f�����C�O�ł̔����������ɔ��\���ꂽ�悤�ł��Bhttp://www.zeiss.com/C1256A770030BCE0/WebViewTopNewsAllE/F33FD84215ECA852C1257681001E93E7
�C�O�ł̔�����Macro-Planar T*50mm F2 ZE��12�����ŁAMacro-Planar T*100mm F2 ZE�����N�����������ł����A���{�ł����̂����ɔ���������ł��傤�ˁB�n�[�t�}�N���Ȃ���A������̃}�N�������Y�����ɂȂ��Ă����ĂȂ��ƕ]���̂��̕`�ʗ͂ł��̂ŁA5D Mark II�ɂ�����ǂ�ȉ悪����܂����c�悾�ꂪ�B�����A�l�i���C�ɂȂ�c�B�{�f�B�����Ď����J�肵�Ȃ���B(��)
������ƔႢ�̘b��ŃS�����i�T�C�Bm(_ _)m�@���܂�ɂ��ꂵ���������̂ł��c�B
![]() 5�_
5�_
��Sketch shot����
�킽����Macro-PlanarT* 100mmF2.8��50D�Ŏg���Ă���܂����O�O
�������������Y�ƂȂ��Ă��܂��܂������A5D MkII�Ŏg���̂ɂ�
���H���K�v���Ƃ������ƂŁA����Ȃ瑼�̕��ɂ��̂܂g���Ē�����
�����ǂ����Ȃ��Ǝv�����������ł���ˁO�O�G
50D�̃t�@�C���_�[�ł���ԃs���g�̎R�݂̒͂₷���L���̂��郌���Y
�������L��������܂��B
���݂ł́ACarl Zeiss Distagon T* 2.8/21 ZE���R�V�i���ł���
���L�����Y�ł́A�B���Carl Zeiss�����Y�ƂȂ��Ă܂��B
������A�Ȃ��Ȃ��f�G�ȃ����Y�Ƃ��ċC�ɓ����Ă���܂��O�O
Macro-Planar ZE�����l�Ɋ��҂���̂��A���̃����Y�̂������ł����ˁ�
�����ԍ��F10591920
![]() 0�_
0�_
ANALOG.MAN����
Macro-Planar������Ă��܂����̂ł����I
�c�O�ł����A1�x�ł����̕`�ʂ�̌����Ă���̂ŁA���̂��Ǝ��̂����Y���Ǝv���܂��B
Zeiss�ɂ͖{���Ɍ��I�ȕ`�ʂ̃����Y�������̂ł����A�ނ�݂ɔʂȂǂ��g�킸�ɂ��ꂾ���̕`�ʂ�����̂͋��قł��B
����ȏ�ɗL�肪�����̂��A���L���Ă��郌���Y�S�ẴJ���[�o�����X�������ɑ����Ă��鎖�ł��B
�����Y���������Ă��F�������Ă���̂ŁA�{���ɎB�e���₷�������Y�Q�ł��B
�R�V�i��Zeiss�͎g���������Ȃ��̂ł����AZeiss�́g���h�͌p������A���f�W�^���ɓ�����������I�ȃX�p�C�X����������Ă�����̂Ǝv���܂��B
�����@�����ΐ���g���Ă݂����ł��B
�����ԍ��F10592041
![]() 0�_
0�_
�����N����A���͂悤�������܂��B
�����X�����Ă��悤�Ǝv�������炢���̃����Y�̔��\���������v���Ă���҂ł��B
���{�}�N���̓Z���T�[�ʂɓ��{�ŎB�e�o����̂ɑ��A�n�[�t�}�N����1/2��
�傫���܂ł����������Ȃ��Ƃ������ł��ˁB�g�嗦�����{�ɔ�ה����Ȃ̂ŋɏ���
��ʑ̂ɂ͌����Ȃ��ł����Ԃ̎B�e�ł�EF50mm�R���p�N�g�}�N���i�n�[�t�}�N���j
�ō��������Ƃ͖w�ǂ���܂���B
EF50mm�R���p�N�g�}�N�����d��͂��Ă܂��������{�P�����ꂵ���̂�
Macro-Planar T*50mm F2 ZE�̓��{�������{���Ɋy���݂ł��B
�����ԍ��F10592224
![]() 0�_
0�_
��17�{��Y/C�}�E���g��Zeiss�����Y�����g���Ă��Ȃ��̂ŁA5D��5D2�̃~���[�����܂����E�E
�@�ق�ƁA���̂����[���ł��l�b�I
�@�@����Y/C�}�E���g��Zeiss�����Y�ɊS������A�g�o�Ȃ��߂Ă܂����A���ݐ�Ȃ��ł��܂����B
�@�@�@�@�������ɁA�~���[����邱�Ƃ͂ł��܂��A���̂܂g������̂�����悤�ł��ˁB
�@�@�@�@�@�@17�{�̓��ɂ́A�L����55��1.2�Ƃ�85��1.2�Ȃ�Ă̂�����̂ł��傤�ˁB
���킽����Macro-PlanarT* 100mmF2.8��50D�Ŏg���Ă���܂����O�O�������������Y�ƂȂ��Ă��܂��܂������A5D MkII�Ŏg���̂ɂ͉��H���K�v���Ƃ������ƂŁE�E
�@�����ł����B�@���H���K�v�ł����B�@
�@�@�����Ȃ�Ƃ܂��܂��y�d�̑��݉��l�����܂�܂��ˁB
�@�E�E�ŁA���낢�뒲�ׂĂ݂���A�Ɋy�����܂g�o�ɂČ������Ⴂ�܂����_��/
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����Ȃ��ق����ǂ���������~~�j
http://zeiss0.hp.infoseek.co.jp/zaiko0906-elefoto.htm
�@�@�@�@Macro-PlanarT* 100mmF2.8�̏ꍇ�A�����Y��ʂ̂ł��ρi�i��K�[�h�H�j�������ɐڐG���邩������܂���B
�@�@�@�@�@���̂��߁A�����i�`0.5mm�j���K�v������Ƃ̂��ƁB�@MP60mmf2.8�����l�ł��ˁB
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@���̈ʂȂ�Ȃ�Ƃ������邩���E�E�I�H
�����ԍ��F10592235
![]() 1�_
1�_
��C�`�S�̐X����@
85mmF1.2��50���N�L�O(1982�N��)��60���N�L�O(1992�N��)��2�{�Ƃ������܂����B
85mmF1.4�Ƃ͊J������S���Ⴄ�`�ʂ����܂��B�ʔ������炢����85mmF1.4�̕����y���������Y�Ɏd�オ���Ă��܂��B
�J�^���O��́A85mmF1.2��50���N��60���N�ł܂����������X�y�b�N�������Ǝv���܂����A�d����50���N�̕�������܂��B�����A���̊ܗL�ʂ̈Ⴂ���Ǝv���܂��B
55mmF1.2�͎c�O�Ȃ��玝���Ă��܂���B�Y������200mmF2.0���Ă��܂��܂����̂ŁE�E�E�B
���������ɁA�~���[����邱�Ƃ͂ł��܂���
����5D�A5D2�Ƃ����Âōw�������̂Ŏv�����č�邱�Ƃ��o���܂����B
���ɂƂ��ẮA�����V�i�ł͎�ɓ���Â炢�����Y�����������ƂĂ��E�C������̂�(��)
�����ԍ��F10592522
![]() 1�_
1�_
Sketch shot����
��85mmF1.2��50���N�L�O(1982�N��)��60���N�L�O(1992�N��)��2�{�Ƃ������܂����B
�@�z���g�ł����[���I�@�����Ȃ��ق����ǂ�������������܂���~~�G
�@�@200mmf2�͗��ApoSonnar�ł��ˁH
�@�@�@�������V���u�������܂����A����ȏ㕷���ƃK�}�������E�ɁE�E(�j
�@�}�N���v���i�[��60mm���A100mm(y/c)�ɐ����Ă��܂������E�E
�@�@�y�d�̂��l�i�Ȃ�A�Q�{�ł���ނ��E�E
�����ԍ��F10592641
![]() 0�_
0�_
��Sketch shot����
�����ł��ˁ`
���̃����Y���g���Ă������炱���̍���� Distagon T* 2.8/21 ZE�w����
�����o�܂�����܂��̂ŗǂ������Ǝv���܂��B
�ނ��낻��ŃR�V�i�Ƃ������[�J�[��M�����錋�ʂƂȂ�E�E�E
ULTRON 40mm F2 SLII Aspherical���w�����Ă��܂����Ƃ����O�O�G
���̃����Y���p���P�[�L�̂悤�Ȍ`������Ă��郌���Y�ł����A�ǂ��ʂ�
�����Y�ł����B
Tessar 2.8/45 T*��50D�̎��Ɏg���Ă���܂����̂ŁA�X�i�b�v�p�̑���ɂ�
�v���w���������܂����B
�`�ʂ́ATessar�Ƃ͈Ⴄ�����Y�ł����i���Ă̕`�ʂ́A��̖ڂɂ������Ȃ��قǂ�
�s���̂��郌���Y�Ŋy�����ł��B
����C�`�S�̐X����
�����Y�̉��H�ł�����{�{���쏊����ŗL���ʼn��H���Ă��炦�܂���O�O
�R�V�i����Zeiss ZE�Ɣ�ׂ�ƘI�o�������\����ۂ�����܂�����
�Ȃ�͂߂A���Ȃ��Ǝv���܂����@���ꂱ���f�W�^���̗��_������
���x�����̏�Ńg���C�ł��܂����ˁB
�����AY/C�p�̃}�E���g�A�_�v�^�[�ł��ƃ����Y�����̍ۂɃ����Y���O����
����A�_�v�^�[��t���ւ���K�v������܂��̂Ń����Y�̖{��������
�A�_�v�^�[�����낦�������g�����肪�ǂ���������܂���B
Leitz-R�p�̃A�_�v�^�[���ƃ}�E���g�ɃA�_�v�^�[��t�����܂܃����Y����
���o���܂��̂ŁA�֗��Ȃ�ł����ǂˁO�O�G
�����ԍ��F10593279
![]() 0�_
0�_
ANALOG.MAN����
�f���炵�������Y�̕`�ʂ𐔑����̊�����Ă��܂��ˁI
�����Y�Ɋւ��ẮA���ۂɂ����ȏŎg���Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ������������ł�����ˁB
Tessar 2.8/45 T*���A�i�������̃s���g�ړ��Ɍ˘f���������������ł����B
��C�`�S�̐X����
Y/C�}�E���gZeiss�̕`�ʂ͖{���ɂ��E�߂ł����AANALOG.MAN����̋�悤�Ɏg���Â炳�͏�ɕt���܂Ƃ��܂��B
���ƁA�d���B�������䖝�o����Β����t�������ɂȂ�Ǝv���܂���B
���E�߂�80�N��㔼�܂ł� WEST GERMANY���ł����E�E�E�B
�����ԍ��F10593838
![]() 0�_
0�_
�F�����́A
�{���́AEF300f4L��5D2�̒��������܂����B
�@�����������łȂ��ĔY��ł܂��B
�@�@�V�O�}�̃Y�[��(70-300APO)��舫���̂ŁE�E�@�@�B��̂k�P�Ȃ̂�(���j�@�@�}�C�N���A�W���X�g�����g�Œ������B
�@�@�@�@�@�ŁA�{��ł����AMP60mmf2.8(Y/C)���w�����邱�ƂɌ��߂܂����_�n/
�@�@�@�@�@�@�@100mm�͂y�d�̗l�q�����Ă��灖�����ł��i�H�j
ANALOG.MAN����
�������Y�̉��H�ł�����{�{���쏊����ŗL���ʼn��H���Ă��炦�܂���O�O
�@�����ł����B�@����Ă��炦�܂����B�₷�肪���ʂȂ玩���ł�����ł������E�E
�@�@�I�o�̖��A���̃X���ł݂܂����B�@�J���ŃA���_�[�A�i��ƃI�[�o�[�X���݂����ł��ˁB
�@�@�@�͂����肵���X���̂悤�ł��̂łȂ�Ƃ��Ȃ肻���ł��B�@�����i��D��ŁA�T�u�_�C�����Ă܂��̂ŁB
��Sketch shot����
�@�d�ˁX�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B�i�傳��AANALOG.MAN������j
�@�@�����ZEISS�̐[�����Ɉ��S���Đ����܂�(�j
�@�@�@60mm�b(1/2�{�j�ł����A������y���݂ł��B�@�ǂ����ł��ł�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10594165
![]() 0�_
0�_
��Sketch shot����
�܂��܂��m��Ȃ������Y�̑����킽���ł����A����Ȃ�Ɋy����ł���܂��O�O
Zeiss�̃����Y�̈�ۂƂ��ẮA�J���O���t�B�y���ŃV�b�J���Ɨ֊s���Ƃ���
�͋����G�Ƃ����C���[�W������܂��B
Leitz�̃����Y�́A�ΏƓI�ɍd�����M�Ő�����d�˂��悤�ȗ͋����������Ă��܂��B
���̂킽���̍D�݂ł���Leitz�̃C���[�W���]���C���[�W�ɋ߂��̂ŕW���悩�璆�]��
�܂ł́ALeitz�̃����Y���g���Ă���Ƃ���ł��B
����Zeiss�̃����n���̌������G���~�����Ȃ鎖��������ł���ˁO�O�G
website�������Ă��������܂����I
�������Ă��������܂��[�B
����C�`�S�̐X����@
�����Y���H�́A�}�X�L���O�����Ƃ��Ă��ׂ������������o��ł��傤������Ǝ҂�
���C������̂�1�̎肾�Ǝv���܂��B
����قǍ��z�ł́A���������悤�Ɏv���܂��̂ŁB
����Ƃ�����̃T�C�g���Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������B
Y/C�����Y�̎���ɂ���Ă����H���ς�����肵�܂��̂ŁA�����Y�I�тɖ𗧂�
�v���܂��B
http://www.pebbleplace.com/Personal/Contax_db.html
�����ԍ��F10594871
![]() 1�_
1�_
��C�`�S�̐X����
Sketch shot����
ANALOG.MAN����
���A�d������A���Ă��Č��ɗ��܂�����A����������オ���Ă܂��ˁ`�B(��)
3�l�̉�b����[�`��Zeiss���̈�[�������B��c�B
Macro-Planar T*100mm F2 ZE�����N�����ɔ����ɂȂ�Ƃ��̏��ɗ���������l�����l�ł܂����c�B
���H���H���͂�����݂Ǝ��܂��Ƃ����I�B�~���[�������Y�����܂�����I(^^;)
CANYON����
���̓n�[�t�}�N��������������Ƃ�����܂���̂ŁA���{�}�N���Ƃ̈Ⴂ�������Ƃ��Ă킩��Ȃ��̂ł����A�����ł����Ԃ̎B�e�Ȃ炻�����邱�Ƃ͖����̂ł��ˁB(^^)
���̃}�N���Ƃ͈�����悷ZF��ZK�ŎB��ꂽ���̂��̓Ɠ��Ȑ��E���`����Ǝv���Ƒ������N�ɂȂ�Ȃ����ȁ`�ƁB����A���{�ł̔����͂܂��ł����B(��)
�����ԍ��F10594955
![]() 0�_
0�_
���͂܂����ɂ��������Ă܂����B
�@�Б����������ƁE�E�@�@�T�d�ɁE�E(�j
�y�d�܂��ǂ������ł��ˁA�z���g�B
�@�@�@�ł��̈����i���������j300f4LIS�@�������Ĉ�C�ɔ�э��ނȂ�āA������̂ł���(��G�j
�����ԍ��F10595348
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ���A�}�N���v���i�[50&100�����{�ł������ɔ��\����܂�����[�B
Macro-Planar T*50mm F2 ZE��119,500�~�I
Macro-Planar T*100mm F2 ZE��185,500�~�I
�o������������ƂȂ��Ă��܂��B
���₠�A����ɂ��Ă������Ȃ��ł����c�H
�����ԍ��F10637142
![]() 0�_
0�_
�����N����@������
ZF,ZK�}�E���g��7500�~���ł���
�v���₷��50�����������̂Ŕ�ׂ�ƍ���������Ǝv���܂���
�����ƂȂ��9����㔼�ŏo�Ă���̂ł��傤��
100�����͈ꐡ�肪�o�܂���50�����̕��͂Ƃ肠���������ƂȂ�Α��\������\��ł��O�O
�����ԍ��F10637228
![]() 0�_
0�_
rifurein����@������
�����N�����Ă��Ȃ����낤�Ǝv���Ȃ��珑�����݂܂������A������rifurein����B(^^)
��ZF,ZK�}�E���g��7500�~���ł���
�Ƃ������Ƃ́A�l�i�����Ȃ�Ă�����ZF,ZK�}�E���g�Ɠ����������������炢�Ŏ�ɓ��肻���ł��ˁB
50������9����㔼�ŏo�Ă���Ȃ�100�����͂����炭�炢�ŗ���������ł��傤�ˁH
50�����̕��A�Q�b�g����܂�����g���������Ă��������ˁ`�B�O�O
�����ԍ��F10637862
![]() 0�_
0�_
�����N����
���ɍ������\����܂����ˁB
��Macro-Planar T*50mm F2 ZE��119,500�~�I
��Macro-Planar T*100mm F2 ZE��185,500�~�I
CONTAX�pZeiss�̓����̒艿��
Macro-Planar T*60mmF2.8��128,000�~
Macro-Planar T*60mmF2.8C��108,000�~
Macro-Planar T*100mmF2.8��198,000�~�A�������ƋL�����Ă��܂��B
���邳�̈Ⴂ�A���{��1/2�{�̈Ⴂ�͂���܂����A��͂葊�ς�炸�̒l�i�ł��ˁi�j
�����ԍ��F10639132
![]() 0�_
0�_
Sketch shot����
�Ȃ�ق�CONTAX�pZeiss�̓����̒艿�������悤�ȉ��i�ݒ肾�����̂ł��ˁB�i��j
�����Ȃ�ƒl�i�����Ȃ�Ă���܂ő҂��A�ߏ��̃L�^�����Ƀ}�E���g�Ⴂ�i�j�R���}�E���g��Macro-Planar T*100mm F2���������A�R���^�b�N�X�}�E���gMacro-Planar T*100mmF2.8���������c�j��10���~�قǂŕ���ł܂��̂ł�������c���A�R���^�b�N�X�}�E���gMacro-Planar T*100mmF2.8���ƃ~���[�Ɗ��������ł��ˁB(^^;)
Planar T* 1.4/50 ZE×�p�iG1(�t�H�[�T�[�Y��2�{)×�N���[�Y�A�b�v�t�B���^�[�Łu�Ȃ����Macro-Planar T*100mm F2�v�i�j�̉摜��\���Ă����܂��B
�����ԍ��F10643359
![]() 0�_
0�_
�\�z�����������\�����܂�����^^
����A������100�}�N�����Ă��܂��܂����B
IS�t���̃}�N�������Y�Ƃ����̂́A���߂Ăł������莝���B�e�ł���Ƃ����̂�
����y�ŗǂ��Ǝv���܂���^^
�ʂ�́A�����ɂ��L���m���Ƃ����ʂ�ōD�݂̕������Ƃ��납������܂���ˁB
Macro-Planar ZE�������l�q���Ă���l���܂��傤���˂�w
�����ԍ��F10650490
![]() 0�_
0�_
ANALOG.MAN����
�\�z�������Ȃ葁�����\�ł����ˁ`�B
������A������100�}�N�����Ă��܂��܂����B
��IS�t���̃}�N�������Y�Ƃ����̂́A���߂Ăł������莝���B�e�ł���Ƃ����̂�
������y�ŗǂ��Ǝv���܂���^^
���ʂ�́A�����ɂ��L���m���Ƃ����ʂ�ōD�݂̕������Ƃ��납������܂���ˁB
�������AEF100mm F2.8L �}�N�� IS USM�ɍs���ꂽ��ł��ˁ`�B�������̃����Y��IS�ɂ͔��Ɏ䂩�����̂��c�B�������A�����ɂ��L���m���炵���ʂ���Ă����̂͊m���ɍD�݂̕������Ƃ���ł��ˁBPlanar�̌��I�ȕ`�ʂ�m���Ă��܂��Ɠ��Ɂc�B�i�j
Macro-Planar ZE�����Ђ���������Ă��������B(^^)
�����ԍ��F10652640
![]() 0�_
0�_
Macro Planar ZE �������ł��`�I�H
�@�@�Ȃ�Ł[�[�H�H�H
�@�@�@�@����ł��ƃ{�f�B�ƌ��������Ȃ��ł����A�����Y�����ł͎B��܂���
�@�@�@�@�@�@�@�߂����������E�E�E�E�E�E(���G)�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j701�����Ă��܂������`
�����ԍ��F10678246
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 5D Mark II �{�f�B
�債�����ł͂Ȃ��̂ł����A�L���m���̊���ƂTD�Q�̎��엦�͂X�V±�P���ɂȂ�̂ł��傤���H
�VD�Řb��ɂȂ��Ă邯�ǁA����������Ȃ̂��Ȃ��E�E�E
![]() 4�_
4�_
�X���O�D�T�x���āA�債�����Ɩ����Ǝv�����Ă����ǁAPS�œ������Ă݂��猋�\�C�ɂȂ邱�Ƃ��킩�����E�E�E
�Q�������Ă��C�ɂȂ�Ȃ���������
�����ԍ��F10583035
![]() 0�_
0�_
�A�T�q�J�����ɏ�����Ă�t�@�C���_�[�̌X���͖�莋����Ȃ�������ł���
�����ԍ��F10583255
![]() 0�_
0�_
>�{���A�e�X�g�B�e���āA��̌X�����킩���Ă��܂����B�i���j
���\����܂���I�I
CMOS�̌X���A����A�����E�E�E�E�E
�J������ł̓R���}���~���ł����ۂ̎B�e�摜�ōl����Ƒ傫���ł��B
�����ԍ��F10583287
![]() 0�_
0�_
�f�W�^���J�����}�K�W���̔�r�ɂ��o�Ă܂�����`�`�`
�c�R�O�O�r�@���엦��X�W�D�T���@�X���@�O�D�R�x
�������ł��B
���̋@��@�d�n�r�V�c�A�j�|�V�A�d�n�r�T�O�c�͂O�x�ł��B
(^_^)/~
�����ԍ��F10583359
![]() 2�_
2�_
>�f�W�^���J�����}�K�W���̔�r�ɂ��o�Ă܂�����`�`�`
>�c�R�O�O�r�@���엦��X�W�D�T���@�X���@�O�D�R�x
>���̋@��@�d�n�r�V�c�A�j�|�V�A�d�n�r�T�O�c�͂O�x�ł��B
�f�W�^���J�����}�K�W���Œ��ׂ��̂́A�g���܂��܁h���X���@�O�D�R�x�A�O�x�������ƌ������ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�H
�d�n�r�V�c�A�j�|�V�A�d�n�r�T�O�c�����āA�X���Ă���̂�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
����ȂɐM���ł���L���ł����e�Ɏv���܂��B
�Ⴆ�A100�䒲�ׂ����ʂȂ�ΐM�ߐ��������܂����ǂ��I
�����ԍ��F10583443
![]() 1�_
1�_
���d�n�r�V�c�A�j�|�V�A�d�n�r�T�O�c�����āA�X���Ă���̂�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
������Ⴛ������
���ʂ͌X���Ă��Ȃ��̂ɁA
kawase302����݂����ɌX���Ă���̂�����̂Ɠ�����@(*_*)���_(^^;)
�����ԍ��F10583485
![]() 3�_
3�_
nikon�̃J�������H�Ɛ��i�ł�����ˁA�����x�����������ł��傤�ˁB
�J�^���O�Ɂu�t�@�C���_�[�X����0°�v����
�����ԍ��F10584894
![]() 1�_
1�_
>>kenzo5326
�������ˁ[�B
�����ԍ��F10586482
![]() 1�_
1�_
--> anjfjo����
> ���̃X�N���[���ڌ���ꍇ�A�ڂ̈ʒu�Ō�����͈͂��ς��Ȃ����Ƃ͂킩��܂��B
> ���������ۂ̓X�N���[���̑����y���^�v���Y����ʂ��Č��܂��B
> �v���Y���͋��ł�����ڂ����X�N���[���̌�����͈͕͂ς��܂��B
���H
�Ȃ����Ɏʂ����ꍇ�A�ڂ����ƌ�����͈͂��ς��̂ł��傤���H
�v�����g�����ʐ^�ڌ���Ό�����͈͂��ς��Ȃ����A��������Ɏʂ��ƌ�����͈͂��ς��̂ł��傤���H�H�H
���������āA���̘g�ŁA���E�����������邱�Ƃ������Ă���̂ł����H
����Ȃ�A���ڌ���ꍇ�ł��Ⴆ�Γ��̂悤�Ȃ��̂�ʂ��Č���Ȃ�A
�ڂ����Γ��ɂ��������đS�������Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂Ɠ����Ӗ��ł����ˁB
�������A�ڂ����X�������Ă��S��������悤�ɏ\���傫�ȃy���^�v���Y�����g�����Ƃ͓��R�ł��B
����������āA���엦100%�̃t���O�V�b�v�̓y���^�������傫���̂ł��B
�Ƃ������A����ȏ����I�ȗ��R�Ō�����͈͂���������x�́A���傤���Ȃ��@��͂������ɍ��Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E
�����ԍ��F10586629
![]() 0�_
0�_
2009/12/06 10:07�i1�N�ȏ�O�j
�X���́ACMOS�̎��t�����߂��ƌ��w�t�@�C���_�[�Ƃ̊Ԃɍ����o�܂��B
�����ӂƕ��s�����킹�₷����^�B���f�q�ɔ�ׁAAPS-C�Ȃǂ͒������ɒu����܂��̂ŕ��s���o���ɂ����̂�������܂���B
�ȑO�A�����[�J�[��CCD��0.5�x�X���Ď��t�����Ă����Ƃ��ŁA�������߂܂����B
�����ԍ��F10586682
![]() 1�_
1�_
Happy_Orange����
�������ł��傤���ˁA���엦�_���̂ق�����������H
�����唼�̂ЂƂ͂ǂ����f���邩�͕ʂƂ��Ď��m�̎����ł���B
�v����ɂ��������b��͑����͕��ɂȂ邪���܂ł������̂�
���Ƃ��Ă͂������Ǝv���܂���B
�\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����@
>�ȑO�A�����[�J�[��CCD��0.5�x�X���Ď��t�����Ă����Ƃ��ŁA�������߂܂���
�@�����Ȃ�ł����H�@�H�Ɛ��i�����ɓ�����O�ꂠ���ł��ˁA�����̍s����������
���Ă���ΊO��ɓ����邱�Ƃ͂Ȃ��̂��Ȃ��H�H�H�H�H
�����ԍ��F10586723
![]() 1�_
1�_
���������ł��傤����
�������Ȃ��I
�{���ɂ������̂������Ƃ����Ƒ�R���܂���B
�N�Ƃ͌����܂��B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B(^^;)
�����ԍ��F10586752
![]() 3�_
3�_
�����ɉ��𗧂����Ă���悤�Ɏv���܂��B
���엦�̘b���瑼�̐l���������Ă��Ȃ��X���̘b�ɗU�����Ă܂���ˁB
�c�_���ǂ���Ɏ����Ă����������m��܂��A�킴�킴���J����
�Ǝv��������B
�����ԍ��F10587108
![]() 0�_
0�_
���������������ł����A�A�A�A
�Ȃ�EOS X2���Z���T�[���X���Ă܂��āA���������ƂȂ�������
����܂��B
�H�Ɛ��i�ł����炿���ƑΉ����Ă����Ȃ�Ή��̖�������܂���B
���엦���J�^���O��100����搂����ƁA�Z���T�[�̌X�����J�^���O��
搂�Ȃ����Ƃ͑S���Ⴄ���ł��B
���X�������ꏏ�̋c�_���d�|���Ă��Ӗ��͂���܂���B
�����ԍ��F10587161
![]() 0�_
0�_
����t���ŌĂ�Ȃ��Ǝv���A���x�͕��ł����i�j
>���엦���J�^���O��100����搂����ƁA�Z���T�[�̌X�����J�^���O��搂�Ȃ���
���͂����ł͎��엦100���̘b�͉��������Ă܂����A���엦�Ƃ�����
�����@�ǂȂ����̃X���ŃA�T�q�J�������p�ɌX���̘b����������������������ł��B
������܂��ǂ��ł��������Ƃł����A���L�҂��C�t�����Ƃ͂�قǂłȂ�����
�Ȃ��Ȃ�����̂��Ȃ��āB
�ł��AX2�̃Z���T�[�̌X���ɋC�t���ꂽ�Ȃ�Ă������Ȃ����Ďv�����������ł��AHappy_Orange����B
�����ԍ��F10587329
![]() 3�_
3�_
�M���̎��ƌĂ킯�ł͂Ȃ��̂ɁA�Ȃ�ł���Ȍ����������ł����ˁH
�Z���T�[�̌X�����Ď��ۂɂ���������悭�킩��܂���B
1�x����Ε��ʂ͋C�����܂��B
���������A�}�������炵���l�ł��ȁB
�������Ŏ��엦�̘b�����Ă������ǂ����ȂNJW������
�X����l�̎�|�y�т��̌�̏������݂͎��엦�ɂ��Đi��ł��܂�����ˁB
����ȗ���ł̔����ł���M�����G��Ă��悤�����܂����A
����A�G��Ă��Ȃ����炱���A�b�����炷���ʂ��o�Ă���̂ł��B
�����ԍ��F10587392
![]() 0�_
0�_
2009/12/06 13:28�i1�N�ȏ�O�j
����@��A0.5�x�X���Ă��Đ����C�ɂȂ�܂����B
�i�Ƃ������A�g�����ɂȂ�Ȃ��j
�t�B�����J�����ł͖����������ڂƂ������Ƃ𗘗p���āA���܂��ɃX�y�b�N�ɂ͍ڂ�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10587508
![]() 3�_
3�_
>�X����l�̎�|�y�т��̌�̏������݂͎��엦�ɂ��Đi��ł��܂�����ˁB
�����@�����ł����A����canon�ۛ��Ȃ��̂ŁA����̓X���傳��Ɏ���Ȃ��Ƃ��B
�X���傳��\����܂���ł����B
�����ԍ��F10587565
![]() 0�_
0�_
���f�W�^���J�����}�K�W���Œ��ׂ��̂́A�g���܂��܁h���X���@�O�D�R�x�A�O�x�������ƌ������ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�H
�@�A�T�q�J�����̎��엦�̌��ʂ��g���܂��܁h�����������A�̂��Ǝv���܂��B
�@�S���Y�ʂ͕�����܂��A��悤�ɏ��Ȃ��Ƃ����S��͒��ׂȂ��Ɛ��m�Ȍ덷���z�͂킩��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@���������Z�̊m�����v�̎��ƂŊ댯���̌v�Z���K�����C������̂ł����A�ڂ������Ƃ͎v���o���܂���B
�����ԍ��F10588144
![]() 3�_
3�_
���͋������������̂̓L���m���̋K�i�̐ݒ�̂������Ȃ�ł���ˁE�E�E
�����̎��͂��炵�āA�T�����Ȃ���n�j�Ȃ�ł���B�����A�X�W���͂X�V±�P���Ȃ̂��ǂ��������������������B
�TD�Q�̎��엦�K�i�����\���Ăق����ł����
�����ԍ��F10664947
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 5D Mark II �{�f�B
���o�ł����炷�݂܂���B
���o�ɑi���镨����������܂���ł����̂ŁA�P�ƂŃX���b�h�����ĂĂ��܂��܂�����
���T�C�Y���Ĕ�r����ۂɗǂ�������鍂��f�̈Ӗ��������]�X�ŁA���Ⴂ���Ă���l�������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����o�ɑi���Č��܂����B
���Q�l�ɂ��Ă��������A�Ȍ�͌���̏����Ȃ���r�����肢�������B
�i�Ԕ����ȃR�����g�����邱�Ƃ�ɖ]�ށj
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=10397629/
�i�Q�l�j
![]() 11�_
11�_
5D2�͍����x�ł��A���𑜂ł��A5D���y���ɗǂ��ł��ˁB
���m�ɂǂ̈ʉ��P�������͂�����Ɠ���ł����B
�����ԍ��F10642911
![]() 2�_
2�_
���ꖾ�āA�Ӗ��s��......
���Ďv���̂́A���o�J�ȉ��������H
�����ԍ��F10642924
![]() 7�_
7�_
�����DPP�͂ǂ���Ȃ�ł����H
�o�C�L���[�r�b�N�@�ł����H
��ʓI�ɂ́A�o�C�L���[�r�b�N�@��p���邱�Ƃ�������Ȃ��łł����H
�j�A���X�g�l�C�o�[�@���Ɩ�������݂�������
�j�A���X�g�l�C�o�[�@
�G�b�W�ɂ̓W���M�[�i�M�U�M�U�j����������B
�ł��������Ă���摜�̎��͏�̗�����Ă̂Ƃ���Œ�ł��B
��قǓ��ʂȏꍇ�ȊO�A�g�����͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�o�T
http://www.geocities.jp/numada777/ip05.html
http://tt.sakura.ne.jp/~hiropon/lecture/trans.html
���ǂǂ̕⊮���g���̂���Ԃ�����ł��傤���ˁH
�o�C���j�A�@�H����Ƃ��o�C�L���[�r�b�N�@�H
�I�Ԃɂ̓t�H�g�V����Ȃ��Ƃ��߂��Ă��Ƃł��傤����
�����ԍ��F10643076
![]() 5�_
5�_
�����ƎQ�l�ɂȂ�y�[�W������܂���
��͂�A�o�C�L���[�r�b�N�@��p����⊮���ǂ������ł��ˁB
���T�C�Y�ő����̑������������Ă��܂��͎̂d���Ȃ��ł��B
�������A�I�[�o�[�T���v�����O���ʂ����҂���Ȃ�A���̑�����
�l�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
��ʓI�ɂ́A���T�C�Y���Ă������ڗ����܂����B
���Ȃ��Ƃ����{�s�N�Z���Ō�����͂܂��ɂȂ�܂��B
�t�Ɉ����L���Ɨ������ɂȂ�܂��ˁB
���o�C�L���[�r�b�N�@
�@�����Ƃ����x�̍����摜�⊮�����ł��B�܂��̃s�N�Z���̐F���▾�邳�ȂǑS�Ă̗v�f���v�Z���āA�s�N�Z����⊮���܂��B�摜�S�̂ɖ����Ȃ����ԐF�^�K�������A�⊮���Ă���܂��B���̕��@�ɔ�ׂ�ƌv�Z�Ɉ�Ԏ��Ԃ�������܂��B���i�͂����I�����Ă����n�j�ł��B
������ȂǁA���m�N����l�̉摜�����̕��@�Ŋg��E�k������ƁA���̂܂��ɃA���`�G�C���A�X������������ԂɂȂ�܂��B��Ńo�P�c�ŐF�𗬂����݂������Ȃǂɂ͋�J���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
���o�C���j�A�@
�u�o�C�L���[�r�b�N�v�Ɓu�j�A���X�g�l�C�o�[�v�̒��ԓI�Ȑ��x�A�X�s�[�h�̕⊮���@�ł��B
�@
���j�A���X�g�l�C�o�[�@
�@�����Ƃ��e���摜�⊮�ł��B�g�j�A���X�g�l�C�o�[�h���g��ԋ߂��ׂ̃s�N�Z���h�ŁA����Ȃ������߂܂��B��L�̓�ƈ���āA���f�[�^�ɑ��݂��Ȃ��F�E���邳�̃s�N�Z���͐������܂���B���A���`�G�C���A�X�͂�����܂���B
�����m�N����l�̉摜�����̂܂܃��m�N����l�Ŋg�k�������ꍇ�͂����I�т܂��B
�o�T
http://www.g-studio.com/guent/Resize.html
�����ԍ��F10643091
![]() 6�_
6�_
�����ǂǂ̕⊮���g���̂���Ԃ�����ł��傤���ˁH
�o�C���j�A�@�H����Ƃ��o�C�L���[�r�b�N�@�H
�I�Ԃɂ̓t�H�g�V����Ȃ��Ƃ��߂��Ă��Ƃł��傤����
������B�B�B�B��������Ȏ����ׂĂ�̂ł����H�������l�b�g�ŁB�B�B�H�H�H�@���R��R�Ƃ����̂ł����B�B�B
���j�A���X�g�l�C�o�[�@
���G�b�W�ɂ̓W���M�[�i�M�U�M�U�j����������B
���ł��������Ă���摜�̎��͏�̗�����Ă̂Ƃ���Œ�ł��B
����قǓ��ʂȏꍇ�ȊO�A�g�����͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�u�摜�̎��v�Ƃ��B�B�B�B�̖��ł͂Ȃ��B�B�B�B�u�A���`�G�C���A�X�v�Ƃ����Ēm���Ă܂����H�H�H
�h�b�g�G�Ƃ����̂܂��𗎂Ƃ����ɔ{�{�Ń��T�C�Y����ۂɂ̓j�A���X�g�l�C�o�[�@���u�ō��掿�v�ɂȂ�܂��B
�{���Ɂu�l�b�g�R�s�y�v���I���邾���Ȃ�ł��ˁB�B�B�Ɋ����܂���orz
�����ԍ��F10643166
![]() 17�_
17�_
���͂悤�������܂��p�g�X����O�O
�����DPP�̃��T�C�Y�͂��̍ō��掿�̃j�A���X�g�l�C�o�[�@��
�g�������̂Ȃ̂ł����H
�o�C�L���[�r�b�N�@�ł����H
�������������̂͂������ł͂Ȃ����̓����ł���B
�ł��掿��D�悷��ۂ́A�j�A���X�g�l�C�o�[�@���g���Ă�l��
���Ȃ��݂����ł����B
�ǂ���ɂ��Ă��ʓ|�������Ȃ�܂�����ˁB
����5D�Ȃ�AJPEG�ŃV���b�^�[�{�^�������������ŒN�ł�
�ȒP�ɍ��掿��ꂽ�Ƃ����̂ɁE�E�E
���T�C�Y�Ȃ�ĂTD���g���Ă鎞�́A���ꂱ���l�������Ƃ��Ȃ������ł���H
�g�z�b�z�iToT)
�����ԍ��F10643241
![]() 6�_
6�_
���������������̂͂������ł͂Ȃ����̓����ł���B
���ł��掿��D�悷��ۂ́A�j�A���X�g�l�C�o�[�@���g���Ă�l�͏��Ȃ��݂����ł����B
������B�B�B����Ȏ��₵�Ă鎞�_�ł��̃X�����������ĂȂ���摜�⊮�̊�{���������ĂȂ����Ď��Ȃ�ł���B
�u�𑜁v�Ɓu�𑜊��v�̈Ⴂ���킩��₷���}�ɂ��Ă���Ă邾���Ȃ�ł�����B
�ʐ^�̌����Ńj�A���X�g�l�C�o�[�@���g���킫��Ȃ���ł���B�����Ƃ����Ȃ��Ƃ����ᖳ���ł��B
������5D�Ȃ�AJPEG�ŃV���b�^�[�{�^�������������ŒN�ł��ȒP�ɍ��掿��ꂽ�Ƃ����̂ɁE�E�E
����͓��ӂ��镔�������邯�ǁA���B�e�҂̃X�L�����オ�����Ƃ��ɐ�Ɍ��E������̂�5D���Ƃ����b�ł���B
���b�L���O����̌������掿�i���𑜊��ł��傤�ˁj�Ɍ�����̂�
���ۂɍ��掿�Ȃ̂��ƌ����͕̂ʖ��ł��B���̐蕪�������܂��傤�ƌ������ł��傤�B
���������́u�ӖړI�ɏ�ɃA���`���b�L���O����v�Ƃ����킯����Ȃ��ł���B�z�b�z
�����ԍ��F10643270
![]() 14�_
14�_
�ϔ{�́A�P�Ɋg��E�k���E�ϔ{�����i�o�C�L���[�r�b�N�A�E�E�E�E�E�Ȃǁj��
�V���[�v�l�X�ʁA��ʑ̂̓��e�i�l���A���J���́A�ԁE�E�E�E�E�E�j��
�Z�b�g�ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂���܂��H
PC�i�\�t�g�j��ł̕ϔ{�́A���w�I�ȕϔ{�ł͂Ȃ��f�W�^���I�ɂ����̂ł�����A
����̔{����������g���Ă����܂��B
�̎d���͕ϔ{�����ɂ���ĕς��܂����B
�V���[�v�l�X�́A
�Ⴆ�A�g�嗦�������Ȃ�A����ɂ��킹�ăV���[�v�l�X�ʂ��傫������̂����ʂł��B
���{�i100���j��200%�Ɋg�債�����̂ł̓V���[�v�l�X�ʂ��Ⴂ�܂��B
�X���傳��̔�r�́A������Ɨ��\������悤�Ɏv���܂��E�E�E�E�E�E�A���I
�����ԍ��F10644310
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 5D Mark II �{�f�B
����g�s�b�N�Љ�ł��A�A
�L���m����DSLR�ŎB�e�����t�B�����t�F�X�e�B�o��������܂��I
Canon USA�卸�Ȃ�ŁA�������{��͂��߂�������Ȃ����ǁB
http://can-dofilmfest.com/
�悩������ǂ��ł����H
������
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > CANON > EOS 5D Mark II �{�f�B
�_�C�i�~�b�N�����W�͍L�������ǂ��Ǝv���܂����H�����Ă��~�������炩�ȕ����ǂ��Ǝv���܂����H
�Ȃ�ƂȂ��A�_�C�i�~�b�N�����W���ǂ��������̂����������ɋc�_���Ă�l�������悤�ȁE�E�E
http://www.pit-japan.com/ws30/d_range01.html
![]() 4�_
4�_
2009/12/10 20:34�i1�N�ȏ�O�j
����2
�J�����K���}�ƃ��j�^�K���}�̐���
http://qtake.hp.infoseek.co.jp/1-8.html
�ƊE�l�炵���������e���ł����A���e�͑�ō����Ă��܂��B
�r�f�I�J�����ŁA�O�����N�̋ƊE�W���O���[�X�P�[���`���[�g���B�������g�`�ʐ^���o�Ă��܂��B�i�Ƃ���������ȊO�͎s�̂���Ă��Ȃ��j
�����p�J�����͂����ƌ����ɒ�������܂��B
�����ԍ��F10609890
![]() 0�_
0�_
2009/12/10 21:18�i1�N�ȏ�O�j
����3
�v���p�f���@���75���h���C�o�[�̗�i�@���̂��ߒ萔�ƕi��\�L�͏����Ă���܂��j
�����ǂł͑����̉f���@�킪�V���[�Y�Ɍq���邽�߁A���̏����̗������Z�ɂȂ��čŏI�I�ȐM���i���Ƃ��Ă͖����ł��Ȃ����̂ɂȂ�܂��B
���̂��߁A�v���p�ł͂��̂悤��DC�\���A���v����{�ł��B
���̌����x���傫���ꍇ�A�T�O�i��`�g�����̗j���ڗ��悤�ɂȂ�܂��B
�i��̑O�̘b�B���͋Ǔ����ׂăf�W�^���`���ł��B����ƁA���̉�H�ɂ��Ă�����IC����������ƃV���v���ɂȂ��Ă��܂��j
���w�I�Ȃ��Ƃ͂Ƃ������A�f���Z�p�҂̊Ԃł͏�L�̂��Ƃ��u�����Đ��v�Ƃ������t�́A�T�O�h�~��P�x�̐������Đ����ێ����邽�߂ɓ���I�Ɏg���Ă��܂��B
�����ԍ��F10610130
![]() 0�_
0�_
�@
�����p�J�����Ƃ́A��L�̎ʐ^�̂悤�Ȃ��̂ł��ˁB
���Ȃ݂�2�J����Ikegami����ł��B�����Y��FUJINON�B
�ō��x�̒������Ȃ��ꂽ
���̃J������ʂ��đS���݂̂Ȃ����
�ԑg�������ɂȂ��Ă���̂ł��l�B
�����ԍ��F10610601
![]() 0�_
0�_
�@
�Ƃ���ŁAWindows�̃��j�^�ݒ�̓K���}2.2�B
����AMac�̃��j�^�ݒ�̓K���}1.8�������̂ł���
�O���t�B�b�N�ɋ���Apple�Ђ݂̂����Ȃ����������Ƃ�
�ǂ�ȑ_���ŃK���}2.2�ł͂Ȃ������̂�
�ǂȂ��������m�̕��͂�������Ⴂ�܂����H
���̕����A�Ȃ�ƂȂ����o�ɋ߂������̂ł��傤���E�E�E
�����ԍ��F10610717
![]() 0�_
0�_
2009/12/10 22:55�i1�N�ȏ�O�j
�� �� �� �� ��
�����́B
>�ǂ�ȑ_���ŃK���}2.2�ł͂Ȃ������̂�
����͎����[���̍s���������~�����Ƃ���B
�u����ƌ����ڂ��߂���������v�ƌ����Ă��˂��B
Windows�̏ꍇ�́A�{���̂Ƃ���͉����l�����P�Ɂu�e���r�Ƃ���Ȃ��ɂ����v�Ǝv���܂��i�j
�����ԍ��F10610848
![]() 1�_
1�_
�@
�\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����
������
Apple�Ђł́A�Ƃ������V���R���o���[�ł�
�l�̓���ւ�肪�������āA�ŏ��Ɍ��߂��n�Ɗ��̐l��
�R�����g���c��Ȃ�������ł��傤�ˁB
�|�Y�������Ȏ��������������B
�O���t�B�b�N�E�f�U�C���̐��E�̓G�C���b�̐��E�Ȃ̂��ȁH
�i�L���[�A�Q���R�c�����ł������j
�����ԍ��F10610950
![]() 0�_
0�_
[10608657] �\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����H��:
>> �l�Ԃ̎��o�ɕK�v�Ȏw���I�ȑ傫���A�܂�K���}���|�����d�q���A�܂�d�q�̗���A
>> �܂�##�d��##�����o���������������V�X�e���Ȃ̂ł��B
>
> ���̍����͂ǂ��B
�J��Ԃ��l�ł����ACRT�Ɏg����u�������͓d�q�e�ɑł��o�����d�q�ɂ���ė�N����A���̌u�������ŗL�̃G�l���M�[�o���h�M���b�v�ɏ������g���̌��q���܂��B���R�A����������q�̐��͓��˂����N�d�q�̐��ɔ�Ⴕ�܂��B
������������́u�u���v�A�u�o���h�M���b�v�v���L�[���[�h�Ƃ��Č�������̂��X�������ƁB
> �����ƂȂ�f�[�^�̒����܂ň�Ȃ�
> �ǂ�ȃJ�[�u�����Ƃ����̂��ȁB���肷��Έ�ԑ����̂ł����ǁB
> �܂��A���Ȃ��̖ϑz�ł������ł�����ǂ�ȃJ�[�u���m�肽��
�f�[�^�����ꂽ���ǂ����F���o����\�͎͂葤�ɂ���Ă܂��܂��ł��傤�B
[10587869]�ŏЉ�� IT8 �Ƃ����A�m�o�I�ɓ����ȃO���[�X�P�[�������`���[�g������܂��B
�`���[�g�ɒ���Ă���Kodak�Ђ�ftp�����N�悩��_�E�����[�h�ł���e�O���[�p�b�`��CIE XYZ�\�F�n�ł̕W���l�����A�O���t�����܂��B
���x�̕W���l��CIE XYZ�\�F�n������ "XYZ_Y" �ŕ\����Ă��܂�:
SAMPLE_ID�@XYZ_X�@XYZ_Y�@XYZ_Z
GS1�@68.58�@71.14�@58.39
GS2�@61.14�@63.54�@52.45
GS3�@53.96�@56.21�@46.80
GS4�@46.93�@48.80�@40.32
GS5�@40.54�@42.21�@34.49
GS6�@35.06�@36.60�@29.91
GS7�@30.82�@32.25�@26.34
GS8�@26.71�@27.98�@22.88
GS9�@22.55�@23.60�@19.02
GS10�@18.77�@19.52�@15.67
GS11�@15.36�@16.15�@13.01
GS12�@12.92�@13.58�@10.91
GS13�@10.52�@11.08�@8.87
GS14�@8.26�@8.69�@6.95
GS15�@5.94�@6.25�@5.17
GS16�@4.97�@5.21�@4.16
GS17�@3.58�@3.74�@2.84
GS18�@2.61�@2.74�@2.07
GS19�@1.98�@2.03�@1.48
GS20�@1.25�@1.31�@1.07
GS21�@0.97�@1.03�@0.84
GS22�@0.76�@0.80�@0.64
> �e���r�W�����̎B�����`�����\���̃J�[�u�n����S���킩���Ă��Ȃ��B
> �i�܂�́A�n���������f�W�J�����킩���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ���j
�q�g����������ׂɍ����f�B�X�v���[�̓q�g�̒m�o�����ɑ������\����������������l�A�v����Ă���Ƃ킩���Ă��Ȃ��B
����`�ȊK���Œm�o���ꂤ������}������A���_�I�ɂ͌����悢�\�����@�̓A�i���O�E�f�W�^�����킸�A���j�A�ł͂Ȃ�����`�ȃG���R�[�f�B���O���Ƃ킩���Ă��Ȃ��B
���[�U�[�Ɏ��o�I�ɍD�܂����Ƃ����_�C�i�~�b�N�����W�̐L�k�J�[�u��sRGB�J�[�u���̊W���킩���Ă��Ȃ��B
�f���M���̏��_�I�ɂ͏d�v�Ȏ��g���\�����킩���Ă��Ȃ��B
�ܘ_�A�M���̐�����͂�f�����O��@�ȂǁA�킩���Ă��Ȃ��B
�^��Ǔ��̃A�i���O�f�q��DC�o�C�A�X��p�����쓮�_�ݒ�̕K�v�������킩���Ă��Ȃ��B
�g�����X�E�ϐ��퓙�̃C���s�[�_���X�ϊ��v�Z���킩���Ă��Ȃ��B
�d�C��H�ł̃t���[�e�B���O�d�ʂ�A����o�����̃Q�C���E�`���o�H���̉e���ŕψʂ�������͓d�ʂ̃N�����s���O��T���v�����O���킩���Ă��Ȃ��B
�r�f�I�A���v���͑��̉f���M���̓����p���X��̃u�����L���O��d����1���������T���v��&�z�[���h����L���p�V�^�̎��萔�̃~�X�}�b�`�ɂ��T�O���ۂ��A���������r�f�I�A���v�o�͑���AC�J�b�v�����O���o�āA�u���E���njŗL��DC�o�C�A�X�d���������ϓ���������Ǝv���Ă���B
AC�A���v���̃A�i���O��H�̃J�b�g�I�t���g�����ӂ̈�ʓI�ɑz�肵���鉞���Ȑ��̌`�ƁA���ꂪ��`�g�̍Č��ɂǂ̗l�ȉe�����y�ڂ����邩�킩���Ă��Ȃ��B
�����A���w�̑f�{���Ǝ�Ȃ̂ŁA���w�A����A�d�C�A�M�������̗��ފT�O�̐ȉ��߂̂��ƁA���_�E���Ⴂ�E�I���C�R�~���Ȃ��펞�܂��U�炵�Ă���̂��킩���Ă��Ȃ��B
�܂�A�����Ă��Ȃ����Ƃ����A�����Ă��Ȃ��B
�����ԍ��F10611671
![]() 2�_
2�_
[10608194] �s�����w����H��:
> ���̓̓ɂ���̔����̏��ŁA���������Ǝv���镔��������܂��B
> �@�u�d���v �� �u�d���v �̕����̑O�オ �� �u##�d��##�v �E �u##�d��##�v �̂悤�Ɍ����܂��B
> �@## �� ������������Ă���������Ƃ��肪�����ł��B
##�L���͕��������ł͂���܂���B
��ꖼ�A����J��Ԃ��Ă��ǂ����|�C���g�𗝉��o���Ȃ��l�q�Ȃ̂ŁA�u�������d�v�v�ƍX�ɒ��ӂ������ׂɁA���Y�P������E����͂��̂ł��B
�u�d���v���̃L�[���[�h��
����������
�@��������
�@�@���_�Ł�
�@�@�@���M���M���F��
�@�@�@�@�d��
�@�@�@��/�M���M���F��
�@�@��/�_�Ł�
�@��/������
��/��������
�ƋL�q�����ɂ������܂��@(^^;
��ꖼ�A�^��ǁE�u���E���ǂ̎d�g�݂𗝉��o�����A�J�\�[�h����^��̒��ɔ�������d�q�̗���́u�d���v�ł���ƔF���ł��Ȃ��̂ł��傤:
===
�@�@[10608187]
�@�@������A���j�^�ւ̓��͂͂����܂Łu�d���v�œ`������ł���B
�@�@�i�����̃|�C���g�������Ȃ�d���ł��ǂ��B��R�ŏI�[���邩�烂�j�^���͂܂ł͓d���Ɠd������Ⴗ��j
===
���ƁA�u�d�q���̓d���v�͗Ⴆ�r�f�I�f�b�L�ƃ��j�^�Ƃ̊Ԃ�75���̒�R�ŏI�[�����ڑ��P�[�u���ɗ���Ă�����̂̂��ƂƁA���킯���F���̗l�ł����B
�����ԍ��F10611688
![]() 1�_
1�_
[10610717] �������H��:
> �Ƃ���ŁAWindows�̃��j�^�ݒ�̓K���}2.2�B
> ����AMac�̃��j�^�ݒ�̓K���}1.8�������̂ł���
> �O���t�B�b�N�ɋ���Apple�Ђ݂̂����Ȃ����������Ƃ�
> �ǂ�ȑ_���ŃK���}2.2�ł͂Ȃ������̂�
> �ǂȂ��������m�̕��͂�������Ⴂ�܂����H
���̃T�C�g�ɋ���ƁA�J���[�}�l�[�W�����g�Z�p�������B���Ă��Ȃ�������\�N���O�A�f�B�X�v���[�̕\�������[�U�[�v�����^�[������̃R���g���X�g�����ɋ߂Â���ׂɕW���K���}��1.8�Ƃ����炵���ł�:
http://www.earthboundlight.com/phototips/gamma-18-or-22.html
���݂̓L�����u���[�^�[�ƃJ���[�}�l�[�W�����g�c�[�����g���A���j�^�[�ƃv�����g�̃}�b�`���O�͔�r�I�e�Ղɍs���܂��̂ŁA�}�b�N���[�U�[�̓K���}1.8�ɂ������K�v�͂Ȃ��ł��傤�B
�K���}2.2��sRGB�AAdobeRGB�̕W���K���}�ł���A���A��ʓI�ȃ��j�^�[�̕��������ɂ��߂����̂ł��B
�g�p�@�ނ̃R���g���X�g��̗L�����p��Windows���[�U�[�Ƃ̉摜�����̉~�������l����ƁA���Ƀf�W�J�����[�U�[�̓K���}2.2���g�������X�������Ɓ@(^^)
�����ԍ��F10611735
![]() 2�_
2�_
�@
���̓̓ɂ���@������
���萔��������ɂ��ւ�炸�A�����̂킩��T�C�g���Љ������
���肪�Ƃ��������܂����B
Mac�̃K���}1.8�̓�A2.2�ւƍ��킹��ׂ��w�j�Ȃǂ�������܂����I�I
�����Ő�[�̍l�����������gWYSWYG�h�̂���
����ς�A�������悭���o�I�ɍ��킹�Ă����B
����͐i�݁A�ŐVMac OS X�ł̓f�t�H���g�ݒ�l��
�K���}2.2�ɂȂ������Ƃɔ[���ł��܂����B
�����ԍ��F10611995
![]() 0�_
0�_
2009/12/11 12:51�i1�N�ȏ�O�j
>IT8�`���[�g�œ����ƒm�o����閾�x�́A���͎w���I�ł���
����Ȃ��Ƃ͒N�������m�ł��B
IT8�`���[�g���A�ǂ����ău���E���ǂ̃K���}�����ɉe������̂��H�H
�i�u���E���ǂ̓����̘b�Ƃ͊W�����j
�e���r�W�����̓J�����K���}0.45�ƃ��j�^�K���}2.2�ɂĊ������Ă��܂��B
�u�J�����̑O�ɂ�����i�ƃu���E���ǂ���Č��������i�����W�ɂȂ�v
���ɊȒP�Ŗ����ł����A�����J�n�ȗ��A���Ȃ��Ƃ��S���E�̃e���r�W�����V�X�e���͂��̃J�[�u�ʼn^�c����Ă��܂��B
�i�J�����̃O���[�X�P�[���g�`�Ƌ��ɉ��x���A�����N�ς݁B�j
�i�j�[��H�ȂǁA�n�C���C�g�̃J�[�u�����k�����肷��b�͂����ł͔����j
�f�W�J�����[�J�[��sRGB�ŊG����Ə̂��Ă���̂́A���[�J�[������Ȕ��f�ōs���Ă��邱�ƂŁA��ʂɂ��̃J�[�u�����̓��[�U�[�ɖ����J�B
�u���b�N�{�b�N�X�Ȃ��̂Ȃ̂Ŋ�{�I�ȃV�X�e���̘b��Ƃ��Ă͓K���܂���B
�i�܂�����sRGB�J�[�u��5D�U�̓���́A������̐l�ɂ͈ꕔ�s�]���Ă��܂��j
>�q�g����������ׂɍ����f�B�X�v���[�̓q�g�̒m�o�����ɑ������\����������������l�A�v����Ă���Ƃ킩���Ă��Ȃ��B
�f�B�X�v���C�����Ő��藧���Ȃ�����A�g�[�^���V�X�e���Ƃ��ăJ�������ɕ�����Ă��邱�Ƃ́A���̗��R�Ƌ��ɁA���m�Ȋ��������̃����N�i�����j���o���Ă��܂��B
���Ȃ��l�̌Ŏ������l���ŁA���̒��̊������������Ƃ��Ă����ʂł��B
�l�b�g�ɃE�\���𗬂��Ȃ��ł��������B
>���������r�f�I�A���v�o�͑���AC�J�b�v�����O���o�āA�u���E���njŗL��DC�o�C�A�X�d���������ϓ���������Ǝv���Ă���B
������A�����Ɠǂ�ł��Ȃ��B
NHK�Z�p���ȏ��A�̂̉�H���ȗ������������e���r�̘b�B
�u�����Đ��v�̈������̂�DC�o�C�A�X�i�����܂Ńy�f�X�^���i�u���b�N���x���j�̐��DC�d���̂��Ɓj���ϓ����Ă��܂��܂��B�i���Ɣ��A�D�F�̔��W�������j
���̂͑�̃I�[�P�[�B
�܂��A�ł������p�Ŋ����Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��̂ŁA�掿�]�����ڂɁu�������Đ��v���ڂ�����܂��ˁB
�v���p�̃��j�^�́A�ŏI�i�ł�����ƃo�b�N�|�[�`�N�����v��H�𓋍ڂ��u�u���b�N���x���v���Œ肵�Ă��܂��B
�i�f���M���̖��E�Â̊W�A�܂�G�Ƃ��Ă̒������Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���j
���I�ȉ�H�̓���������̂ŁA���������I�[�f�B�I�A���v�ōs���悤�ȁuDC�o�C�A�X�d���v�Ƃ����p��A�����ł͂��Ȃ��a��������܂��B�i�u���E���Ǒ����猩���d�C�I�Ȏ��_�Ƃ��Ă͊ԈႢ�ł͂Ȃ����j
�����ԍ��F10613116
![]() 0�_
0�_
2009/12/11 22:16�i1�N�ȏ�O�j
���t�ł͓`���ɂ����̂ŁA���������Ă�����e��}�ɂ܂Ƃ߂Ă����܂����B
�i���ۂ�CRT�̃J�\�[�h�ɃI�V���ĂČ��Ă��܂��j
���͐M����10�X�e�b�v�Ƃ����d�C�I�ɓ��Ԋu�ȕω������M������͂����ꍇ�Ő������܂��B
���͐M���̓V���N�`�b�v�������ƁA���{��NTSC�K�i�ł�0.714Vp-p�Ƃ����r�f�I���x���ŁA���̂܂܂ł̓u���E���ǂ��쓮����ɂ͏��������邽�߁A�K�v�ȃ��x���A40Vp-p�ȏ�܂łɑ������܂��B
���̊ԁA���j�^�����ł͏o���邾�������ȑ����ɓw�߂܂��̂ŁA�d�C�I�Ȑ��`�c�݂͔��������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�i���̒i�K�ł͑f�q�̈�Ԓ������̗ǂ��Ƃ�����g���ł��傤�B��ʂł�AC�A���v���嗬�ł��B�j
CRT�ւ̉f���M���̓��͂̓J���[���ł͈�ʂɃJ�\�[�h�ł��B
�r�[�����o�n�߂�i������J�b�g�I�t�d���Ƃ����j�J�\�[�h�̓d���́A�i���o���c�L�ɂ���ĈقȂ�܂����A���������{100V���x�ł��B
�J�\�[�h����A+25�`30KV���x�̍������������i�d�q�́|����{�Ɉړ�����j�ɂ܂ŏ��������v���[�g�ʁi�V���h�[�}�X�N���j�Ɍ����ēd�q�˂��܂��B�i���̊ԁA�O���b�h�ʼn��������j
�r�[���d���́A�J�\�[�h�d�����Ⴂ�����قǑ�������܂��B
���̂��߁A���͂Ƃ͏㉺���t�̔g�`�����r�f�I�M���Ńh���C�u���܂��B
�r�[���d���������Ɣ������܂��B
�ł�����u���v�͌��点�Ȃ��A�܂�r�f�I�M���̃y�f�X�^���������J�b�g�I�t�d���Ɠ���DC�d���l�ɂȂ�̂��]�܂����ł��B
�O�q�̂悤�ɁAAC�`���̂܂܂ŃJ�\�[�h���h���C�u����Ɖf���̓��e�ɂ��A���̃y�f�X�^����DC�l���ϓ����Ă��܂��܂��B
���̂��߁A�ǂ�ȉf�����e�̎��ł�����Ƀy�f�X�^��DC�l���ێ�������H�\�����K�v�Ƃ������Ƃł��B
�@��ɂ��l�X�ł����A��ʓI�ȃJ���[�e���r�ł͍ŏI�i��O�Ńy�f�X�^���N�����v���Ă������M�����ADC�A���v�\���̃J�\�[�h�h���C�u��H�ɓ������̂������A�����Ǘp�ȂNJ����ȓ�����������̂̓J�\�[�h�i�Ńo�b�N�|�[�`�i�ʑ��I�ɃV���N�`�b�v�̒��㕔���j���T���v�����O���ăz�[���h����悤�ɂȂ��Ă��܂��B
���̂悤�ɁA�u���E���ǁi�^��ǁj��I-V�J�[�u�����̈�ԓd����0�ɋ߂��Ƃ��납��u�g�킴��Ȃ��\���v�Ȃ̂ł��B
����2.2�Ƃ����̂́A�����čD��ʼn��o���Ă���킯�ł͂���܂���B
�m�o�I�ɓ����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������R���Ӗ��s���ł����A�Ⴆ�D�݂̃J�[�u�ɂ������Ă��e���r�n���L�����̃A�i���O��H�Z�p�ł͉ƒ�ɕ��y�����邽�߂̃R�X�g�����̒��ł͂ƂĂ�����s�\�ł����B
�����ԍ��F10615421
![]() 0�_
0�_
2009/12/12 00:11�i1�N�ȏ�O�j
>���������r�f�I�A���v�o�͑���AC�J�b�v�����O���o�āA�u���E���njŗL��DC�o�C�A�X�d���������ϓ���������Ǝv���Ă���B
���͐��N�ԁA�Ɩ��Ńu���E���ǂ̓�������Ă��܂������A���̌����������ɕs�v�c�Ɏv���Ėʔ������̂����牽�������Ƃ��Ă��邩�z�����Ă���̂ł����c
���C�t���܂����B
�܂����J�\�[�h�ɂ͏�ɌŒ肵��DC�o�C�A�X�d�����|�����Ă���ƁH�H
���̂悤�ɋ����I�ɌŒ肵���d�����|����̂̓u���E���ǂ̏ꍇ�A�v���[�g�̍����ƃO���b�h�i�S�̓I�ȋP�x�����肳��邽�߃X�N���[���ƌĂ�ł���j�����ł��B
�X�N���[���d���͒ʏ�Z�b�g�����̃{�����[���Œ����o����悤�ɂȂ��Ă��܂����i�v���[�g�̍��������R�ŕ������Ă���j�A�܂����������o���ɍH��Œ���������Ȍ�Ē������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F10616198
![]() 0�_
0�_
�ʏ�̔���`�̉��������̃u���E���ǂł͂Ȃ��A�I�[�f�B�I�̐^��Ǔ��l�A���j�A�ƊŘ��A�܂� I-V�J�[�u�̔���`�ȗ����オ�蕔�����\���N���A������Ŏg�p����u���E���ǂ��l�@���悤�B
����́A�܂�A��́u���v���x�������j�A��̉����Ɉʒu�����Ďg�p����u���E���ǂ̂��Ƃł���B
�ʏ�̔���`�u���E���ǂł́A�u�����L���O�i�܂�J�b�g�I�t�j�d���Ɖf���́u������x���v�̓d���͋߂����̂ł��낤�B
����ɑ��A���j�A�u���E���ǂ̓u�����L���O�d���ƍ���d���Ƃ̊Ԃɂ́A����`�̗����オ�蕔���͎g�p���Ȃ����A�����̓d�������K�v���낤�B
����āA���j�A�u���E���ǂł͍���d���ł́A�u�����L���O���ɔ�ׁA����Ȃ�̋��x�̓d�q�����������邾�낤�B
���̍���̓d�q�����f���Ƃ��Ė]�܂����u���v�ł͂Ȃ��u�D�F�v�ƌ����̂�h���ɂ́A���͕\���ʂ̔���������������ςޘb�ł���B
�\���ʂɓh�z�����u�������̗ʋy�і��x�����邱�ƂŁA�������̓d�q�����x�ɑ��A�u���E���ǂ͊��ł��Â��o����B
�i�u�����������炵�A���ʓI�ɂ͔����ʂ̓d�q�F���q�o�͌����������A�Â����邱�Ƃ́A�������グ�Ė��邭����̂ɔ�ׂĂ����Ɨe�ՂȂ��ƂȂ̂ł���j
�܂�A���j�A�ƊŘ鉞�������u���E���ǁA���Ƃ��A�^��ǂ�����̂́A�Z�p�I�ɏ\���\�Ȃ��ƂȂ̂ł���B
�W���I�Ȕ���`�u���E���ǂ̃K���}2.2�ɍ��킹��ׂɁA�e���r�J�����̓K���}0.45�̉f���M���𑗏o����B
���ʓI�ɂ͔�ʑ̖̂��邳�ƁA����`�u���E���ǂɉf���o�����f���̖��邳�͐��`�E���j�A�ȊW�ƂȂ�B
����ɑ��A���j�A�u���E���ǂŔ�ʑ̖̂��邳�ɔ�Ⴗ��f�����f���o�������ꍇ�A�e���r�J���������j�A�ȉf���M���𑗏o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�������A����͎��͉f�����o���ŃK���}0.45�̔���`�ȉ��������������H���Ȃ���A�Ƃ������\�s���̂������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B
�ł͉��́A
�� ��M���ł̓��j�A�u���E���ǂɔ�ׁA�������������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ�����`�u���E����
�� ���M���ł͎�M�@�̔���`�������\������t����`���������̉�H��g�ݍ��B���V�X�e��
���Ƃ����A���j�A�V�X�e���ɔ�ׁA�R�X�g�╡�G���̖ʂŕs���ȑg�ݍ��킹���g�p����Ă���̂��H
����̓g�[�^���V�X�e���̕]�����q�g�̖ڂł���邩��ł���B
�M���̑���M�ɂ́A���ɃA�i���O�̏ꍇ�A�K���m�C�Y����������B
IT8 �����O���[�`���[�g�������ʂ�A�q�g�̖ڂ͈Õ��ł̋͂��Ȗ��邳�i�܂�M�����x���j�̍���q���ɒm�o����B
���j�A�V�X�e���̏ꍇ�A�f���M���ɍ�������m�C�Y�͓��ɈÕ��ł̊K����傫�������m�C�Y�ƒm�o�����B
�ΐ��I�ȃG���R�[�f�B���O�i�܂�K���}�j���s������`�V�X�e���̏ꍇ�A�����m�C�Y�̃G�l���M�[�͈Õ�����n�C���C�g���ψ�ɕ��U����A�m�o���ɂ����Ȃ�B
�܂�A�����ɓd�C�I�ȃ��x���ł�S/N��͓����ł��A����`�V�X�e���̓��j�A�V�X�e�����掿�͗D��Ă���ƒm�o�����̂ł���B
����́A����`�ȊK���Ńq�g�ɒm�o���ꂤ��A�m�C�Y���Ɉ�����ʑ��E������}��������_�I�ɂ͌����悢�\�����@�́A�A�i���O�E�f�W�^�����킸�A���j�A�ł͂Ȃ�����`�ȃG���R�[�f�B���O������ł���B
�� �g�[�^���V�X�e���̖ړI�y�ѕ]����@�̖�
�� �����I�A���w�I�A�d�C�I�A���_�I���̍\���v�f�̖�
���̗����̖ʂ��l�@�A��������\�͂��������s�\���ȃ\�^�R�~���̏ꍇ�A�����t�[���G��́A�T���v�����O�ANHK���ȏ��ȂǁA���e���낭�ɗ��������Ă��Ȃ����̂���ח��āA�u�u���E���ǂ̓K���}2.2�A�e���r�J�����̓K���}0.45�Ő����͊������A�l�Ԃ̒m�o���͂��̔���`�̍\�����e���r�V�X�e���ōŏI�I�ɑI�����ꂽ���Ƃ͊W�Ȃ��v�ƁA����������ɂȂ��Ă���̂��낤�B
�����ԍ��F10616752
![]() 0�_
0�_
�@
�����A����ɂ��Ă������t����v���Y�}�̎���Ȃ�ł���˂��B
�����FDP�͂ǂ�ȍĐ��J�[�u�������Ă����ł��傤�E�E�E�B
�J�����̃��K�V�[�ȃK���}�͕��Q�͂Ȃ��̂��ȁH
�Ƃ���ŁA�u���E���ǂ̃K���}2.2�{�e���r�J�����̃K���}0.45��
�m�C�Y��m�o���ɂ�������Ƃ������\������Ƃ������Ƃ�
�̂̃I�[�f�B�I�̃m�C�Y�ጸ��@�Ɠ����ł��ˁB
���R�[�h��RIAA�����ɂ���h���r�[�E�m�C�Y���_�N�V�����ɂ��Ă�
���ɕt����������߂ċL�^���A�Đ����Ɏ�߂āA�g�[�^����
�t���b�g�ȉ��ɂ���ƁA�m�C�Y�͏����ȉ��ɂȂ��Ėڗ����Ȃ��Ƃ������́B
�������邱�Ƃɂ��A���̃J�b�e�B���O�U�����������Ȃ�
���R�[�h�ׂ̗̍a�Ƃ̋������������Ƃꂽ��
�e�[�v��MOL�ɂ��]�T�����܂��Ƃ��������b�g������܂��B
�����̃A�����J�̐l�͈̂��B���₢��A���ł��X�S�C���Ƃ̓A�����J���B
�ǂ����Ėl��̓V�X�e���I�Ȃ��Ƃ̓T�b�p����
�R�`���R�`���ׂ������Ƃ���邾���̃{���N���Ȃ�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F10616868
![]() 0�_
0�_
2009/12/12 11:43�i1�N�ȏ�O�j
>���j�A�u���E����
�����̂ł��B
�������I�I
�����ԍ��F10617953
![]() 0�_
0�_
2009/12/12 12:06�i1�N�ȏ�O�j
�� �� �� �� ��
>����ɂ��Ă������t����v���Y�}�̎���Ȃ�ł���˂��B
>�����FDP�͂ǂ�ȍĐ��J�[�u�������Ă����ł��傤�E�E�E�B
�u���E���̃K���}2.2�Ƃ����O��ŕ������J�n���A�n�C�r�W�����A�f�W�^���ɂȂ��Ă����炭��CRT�̎��オ�����܂����ˁB
�܂��c��ȃA�[�J�C�u������]���e���r�ԑg�Ƃ̌݊���A��悤�Ƀm�C�Y�ጸ���ʂ̃����b�g�����邽�߂ɁA���̃J�[�u�n�������ĕς��闝�R�͂Ȃ��A�����قڐ̂Ɠ����J�[�u�ɃJ�����̒����𐮂���������Ă��܂��B
�t����v���Y�}�̗������́ACRT�Ƃ܂������قȂ�J�[�u��`���܂��B
CRT�̂悤�Ƀ���XX�ƌ�����悤�ȒP���ȃJ�[�u�ł͂Ȃ��A���G�ȋȐ���`�����߂ɁA������Ƀf�W�^�������ɂ���e�[�u�����p�ӂ���Ă��܂��B
���������̉t���e���r�͂��̕���Â��A���ł����̕�J�[�u�̔@���Ő��\�������Ă���킯�ł��B
�i�����p�e���r�Ɋւ��Ắu�����ɕ����v�Ƃ����K���͒Ⴂ�ł��傤�j
�����p�t�����j�^�̃J�^���O�����Ă��������B
���̗l�q���������Ă��܂��B
�u10�r�b�g�摜�����G���W���ɂ�銊�炩�ȊK���v
http://www.sony.jp/products/Professional/monitor/products/LMD1751W.html
�p�\�R���̃��j�^�ɘb���ڂ��ƁA��͂肱�̕���l�X�ł��B
�i�i�I�Ȃǂ́A�����x�ȃ�2.2��e�[�u���Ƃ����̂蕨�ɂ��Ă��܂��ˁB
CRT�ł́A���[�U�[���������蒲��������������̐S�z�͂���܂���ł����B
�iCRT�͌o�N�ω����傫���̂ŁA�Z���ԂŒ����������Ȃ���Ȃ�܂���j
�����ԍ��F10618061
![]() 1�_
1�_
�@
�\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����@����ɂ���
�뎚������ɂ��ւ�炸�iFDP��FPD�A�|���|���j
���������Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B
�����̌��ꂪ�ςݏグ�Ă�����2.2�̋Z�p�j�B
EOS 5DII�̎ʐ^�ҏW�Ƃ̊Ԃɂ����ڂȊW�����邱�Ƃ�������܂����B
���ꂩ��̎���A�ʐ^�̎�Ƃ������̂�
�g���j�^�E�f�B�X�v���C�h��ʂ��Č����������肵�Ă������ƂɂȂ�܂��B
���������Y���ǂ��Ȃ��背���Y���𗐔��˂��A�B�e�M�����ǂ̂悤�ȉߒ����o��
�䂪���_�o�ɂ܂œ��B���邩�𐳊m�ɗ������Ă�������
���L���y���߂�Ǝv���܂��B
�@�ރg�[�^���̐��\�������ł��邵�A����_�������₷���Ȃ�܂��B
�܂��A�d�C�Ƃ��v�Z���Ƃ��́A�Ȃ��Ȃ�����ł���
�����́q�J���������j�^���v�����^�r�̌��E�_�u�_�C�i�~�b�N�����W�v��
��������Ɣc�����Ă������Ƃɂ��A�����̎v���ʐ^��
�m���[���̏�Ԃ����A���Ȃ�悭�B���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F10618914
![]() 1�_
1�_
[10617953] �\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����H��:
>> ���j�A�u���E����
>
> �����̂ł��B
�܂��A�f���d���̑b��z������l�B���f���M���̐U���ɑ��A�P�x�����j�A�ɉ��������M�@���������Ă������Ƃ������̂͊ȒP�ł��傤��...
�����ԍ��F10620214
![]() 1�_
1�_
2009/12/12 22:30�i1�N�ȏ�O�j
���̓̓ɂ���
���̗���͂ł͂��̂悤�ȑ��u�ɗގ�����̂��ƁB
http://ci.nii.ac.jp/naid/110003687518
�Љ�肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10620907
![]() 0�_
0�_
���̐��i�̍ň����i������

EOS 5D Mark II EF24-105L IS U �����Y�L�b�g
�ň����i�i�ō��j�F ���i���̓o�^������܂��� �������F2008�N11��29��
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����zwindows11�ɑΉ��ōw��
-
�y���̑��z���_�p�H
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC
-
�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j