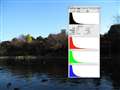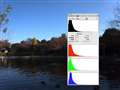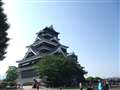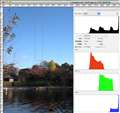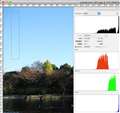PowerShot G10
1470����fCCD/���w5�{�Y�[�������Y/3.0�^�u�N���A���C�u�t�� II�v�𓋍ڂ����R���p�N�g�f�W�^���J�����B���i�̓I�[�v��
���i���̓o�^������܂��� ���i���ڃO���t
����
�ň����i(�ō�)�F
¥39,000 (1���i)
PowerShot G10CANON
�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �������F2008�N10�����{
���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S388�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2008�N12��23�� 23:16 | |
| 15 | 14 | 2008�N12��23�� 23:12 | |
| 214 | 170 | 2008�N12��23�� 09:57 | |
| 4 | 9 | 2008�N12��21�� 23:32 | |
| 4 | 10 | 2008�N12��21�� 21:57 | |
| 2 | 3 | 2008�N12��21�� 00:55 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^���J���� > CANON > PowerShot G10
�����́B
�ŋ߁APower Shot G10���w�������҂ł��B
������ƋC�ɂȂ������Ƃ��������̂ŁA���₵�܂��B
�w������̉t����ʂɏ��h�~�t�B�����݂����Ȃ��̂��\���Ă��Ȃ������̂ł����A
�݂Ȃ���̓t�B�����͓\���Ă���܂������H
�i�g�ѓd�b��V�K�w�������Ƃ��Ƀt�B�������\���Ă���̂悤�ɁE�E�E�j
�\���Ă����Ă����������͂Ȃ��̂ł����E�E�E�B
![]() 0�_
0�_
�g�т͕��ʓ\���Ă��܂��ˁB
�f�W�J���œ\���Ă�����̂��Ă����ł����H
�l�͒m��Ȃ��̂ł����ǁB
G10�͓\���ĂȂ��ł���B
�f�W�J���̏ꍇ�A�t���ی�t�B�����Ƃ����̂��w�����ē\��̂����ʂł��B
�g�тɓ\���Ă���悤�Ȃ̂������\���Ă������Ƃ��Ă��A
��������Ȃ̂Ŕ������āA�������̂�\��Ȃ����܂��ˁA�����ƁB
�����ԍ��F8820410
![]() 0�_
0�_
�ی�t�B�����݂����̒����Ă܂���ł���
���N�ɂȂ��ăy���^�b�N�X�A���R�[�ƂR��ڂł���
�ǂ�������ĂȂ������Ǝv���܂���
�g�тƃf�W�J���͈Ⴄ�̂�������܂����
�\�j�[��p�i�\�j�b�N�͌g�т��o���Ă��邩�璣���Ă���̂��ȁH
�����ԍ��F8820432
![]() 0�_
0�_
���܂ōw�������R���f�W��f�W�C�`�œ\���Ă������̂͂Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F8820438
![]() 0�_
0�_
���ɓ\���Ă����Ă��A�o���̊ȈՃt�B�����ł��ˁB
�قƂ�ǎg���Ȃ��̂ŁA�����ɔ������ĉt���ی�t�B������\��܂��B
�ԂŌ����A�V�Ԏ��Ƀr�j�[�������Ԃ��Ă���悤�Ȃ��̂ł��B
���ʂ͔[�Ԃ��ꂽ�璼���ɔ������܂���ˁH
�����ԍ��F8820532
![]() 0�_
0�_
���̑O�������f�w�Q�O�O�͓\���Ă���܂����B
�������A�ʏ�̕ی�t�B�����ƌ�����悤�ȃ��m�ł͂Ȃ��A�������Ȃ��Ɖt�����g�����ɂȂ�܂���B
�P�Ȃ鍫��ނ̂悤�ȃ��m�ł��B
���ɂ����l�̂��̂��\���Ă������@�킪����܂����A�ǂ̋@�킾�������o���Ă��܂���B
�����ԍ��F8820571
![]() 0�_
0�_
�f�W�J���ł́A�\���Ă��Ȃ��̂����ʂȂ�ł��ˁB
�ǂ������`�B
�݂Ȃ���A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F8820672
![]() 0�_
0�_
�p���[�V���b�gA1000IS�ɂ͓\���Ă���܂�����BEOS50D���������C���E�E�E
G10�͂���܂���ł����ˁB
�����ԍ��F8825814
![]() 0�_
0�_
��
�T�OD�Ƀt�B�����Ȃ�ē\���Ă���܂���B
�Ă������f�W�J���Ƀt�B�������\���Ă���ق������������Ǝv�����ǁE�E�E�E
�����ԍ��F8826095
![]() 0�_
0�_
���������A�g�ѓd�b�̂悤�ɕی�t�B�������͂��Ă���J���������X�������܂��B
�u�ی�t�B�����v�Ƃ����Ă��@�\�����܂g���p�ł͂Ȃ��A�����܂ŏo���ɃL�Y���t���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̂��̂�
���̂܂܂͎g���܂���̂ł����ӂ��B
�ł��A���������ی�t�B������V�[�g���͂����y���݂Ƃ����̂�����܂����(��
�����ԍ��F8830434
![]() 1�_
1�_
�f�W�^���J���� > CANON > PowerShot G10
���߂ē��e���܂�
�f�W�J���w�����l���Ă܂��B
���\�����ĂĂ��AG10��GX200���Ŗ����Ă�����������݂����ł����A
�l���ł��B
���܂܂�PowerShotS60���g���Ă܂����B
G10�Ȃ烁�f�B�A�����̂܂g���邵�A�g������Ă���Ǝv���̂ł����c
�p�r�͕��i��A�F�l�ƗV���̖�O�A�����̎ʐ^�Ƃ��܂��܂ł����A�l�����͕��i�B��ق����D���ł��B
���X�V��ł�F�l�Ƃ��̓�����B�����肷�����ł��B
�܂��܂��J�����g�����Ȃ��ĂȂ��ł����A�}�j���A���ŎB�����肷��̂��D���ŁA
�������GX200�Řr�������Ƃ����C�����܂����A�o�����X�̂悳������G10���c
���ƁA�V���b�^�[��180s�J����GX200�ƌ��w5�{��G10�Ɓc
�܂��D�݁A�ƌ��������܂łȂ̂�������܂��A
�A�h�o�C�X������������K���ł��B
�܂Ƃ܂�̂Ȃ����͂ő�ϐ\����܂���
��낵�����肢�������܂��B
![]() 0�_
0�_
����番�͂̒ʂ���ۂ��C�͂��܂��ˁ`�B
����d���Ȃ�G10�A180�b�I���d���Ȃ�GX200�����H
�����ԍ��F8821141
![]() 1�_
1�_
>���܂܂�PowerShotS60���g���Ă܂����BG10�Ȃ烁�f�B�A�����̂܂g���邵
PowerShotS60�̓R���p�N�g�t���b�V���AG10��GX200��SD�J�[�h�Ȃ̂Ń��f�B�A�͎g���܂���ˁ`
�����ԍ��F8821468
![]() 1�_
1�_
�@�����Ƃ��A�������̂���A���̐[���ǂ��J�����ł��B�ǂ��炩��I�Ԃ͓̂���ł��B�l�͂f�w�Q�O�O���g���Ă��܂����A�l�Ȃ�ɔ�ׂ�ƈȉ��̒ʂ�ł��B
�@�f�w�Q�O�O�ŋC�ɂȂ�̂́A�f�P�O�Ɍ��炸�L���m�����i�������ł��x���Ƃ������Ƃł��B�{���ɍ��ׂȎ��ԍ��Ȃ̂ł����A���i�Ɍ��炸�l�����B��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���ŃX�s�[�h�͑厖�ɂȂ�Ǝv���܂��B���X�Ŏ��@�Ŏ������Ƃ��������߂��܂��B
�@���Ɏ����B�e�ɂ��ẮA���@�Ƃ��O�t���X�g���{���g����̂��悢�ł��ˁA�ł��A�f�P�O�͂d�n�r�̃X�g���{�������Ăd�|�s�s�k���g����̂ɑ��āA�f�w�Q�O�O�̓J�������ŃX�g���{�̘I�o���䂪�ł��܂���B���@�ŃX�g���{�̐ړ_�̌��Ă��������B�ł�����A�����B�e��������x�����ꍇ�A�f�P�O�ɂ͂�����Ƃ����A�h�o���e�[�W������悤�ȋC�����܂��B
�@���Ƃ̓T�C�Y�̖��Ƃ������Y�̉�p�Ǝ����̗p�r�Ƃ̃o�����X�Ƃ��\�Z�Ƃ����݂Ȃ�����@��������Č��߂邵������܂���B
�����ԍ��F8821652
![]() 1�_
1�_
�p���V���b�gG�V���[�Y�́AG7����SD�J�[�h�ɕς���Ă��܂��B
G10�́AND�t�B���^�[�������֗����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8821847
![]() 2�_
2�_
G10�ɂ͌��w�t�@�C���_�[����������Ă��܂��B
���ꂾ���ŏ\����GX200���֗����Ǝv���܂��B
���ꂩ��AF���F���Ȃǂ̋@�\�Ɋւ��Ă�Canon�̕����ꐢ�㕪���x�i�����Ă��܂��B
���@���ׂ�Ǝ����o����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8822136
![]() 1�_
1�_
>��������
�����ł���ˁB���Ƃ�����肽���Ƃ��v���Ƃ��A�I���������̂̓_���g�cGX200�Ȃ�ł���ˁc
�����܂��B
>m-yano����A�������߂���
�����Ȃ�ł����B�Ȃ���ɃR���p�N�g�t���b�V�����Ǝv������ł܂����B
���肪�Ƃ��������܂��I
>�����t�E�q���N���[����
GX200�����ۂɂ��g���ɂȂ��Ă�����������̂��ӌ��A���ɎQ�l�ɂȂ�܂��B
�m����G10�͎�傫���ł����A�܂����e�͈͂��ȂƂ����v���Ă�̂�
G10���Ȃ��c
�X���ŃT���v���摜�Ȃǂ������̂ł����A���̃V���[�v���͍D���Ȋ����͂���̂ł����A
�ǂ�����O�A���i����Ŏ����̎ʐ^���Ȃ��̂������c�O�ł����B
�����ł̐l����͂�͂����ł����H
>�������߂���
GX200�ɂ͓�������Ă��Ȃ���ł��ˁB
�Q�l�ɂȂ�܂��B���肪�Ƃ��������܂��B
>�Y�}����3.5����@
�������ɁA�F�X���ׂĂ���Ƌ@�\�I��GX����G10���ȂƎv���Ă��Ă��܂��B
�f�W�J�����̈����Ȃ�܂������A�����Ĉ����������ł͂Ȃ��̂łP���㕪�i��ł鍷���傫���ł��ˁI
�����ԍ��F8822224
![]() 0�_
0�_
�݂邫�`�䂳��ɂ���
����G10��GX200���g���Ă܂����A�����Ƃ��ǂ��J�����ł���B
�������A���i�͑S���ΏƓI�ł��ˁI�I�@
G10��GX200���D��Ă���Ƃ���́A
�P�D�����x�B�e�����掿�Ȃ���
�Q�DAF�̔\�͂���������
�R�D���悪�Y��
�S�D�]������������
GX200��G10���D��Ă���Ƃ����
�P�D�i��������ϓI�ł����j�F���ǂ��i�D���H�j�Ȃ���
�Q�D���쐫���ǂ�����
�R�D�������Čg�ѐ����ǂ�����
�S�D�L�p����������
�ł��I�I
���I�ɁA�ǂ��炩���I�ׁI�I�Ƃ���ꂽ��A���킸GX200��I�т܂��B
���̗��R��
�P�DG10��GX200�ł�G10�̕����掿�͗ǂ��ł��I�I�@�������A�掿�]�X�����߂��ꍇ�AG10�̉掿�͈��f�W�^���̑����ɂ��y�т܂���B�@�����B�e�⓮�������B�e�ɂ����Ă��AG10�̓R���f�W�Ƃ��Ă͗D�G���Ǝv���܂����A����N���X�̈��f�W�̕������Ⴂ�ɗD�G�ł��B
�Q�DG10�̃X�C�b�`��_�C�����ނɂ��āA���슴�o�I�ɐ����`�O�n�O�ȕ����������܂��B
�R�͕��̃_�C�����͍d���A�w�ʃ_�C�����͌y���ăN���b�N�����Ȃ��A�{�^���ނ͂Ȃ�ƂȂ��ߓx������܂���B�@���쐫���C���������Ȃ��`�@���Ɗ����Ă��܂��B�@���̓_GX200�͑S�Ă̑���n���y���g���Ă��ċC�����������ł��B
�R�DG10�́i���I�ɂ́j�d���ł��B�@�傫���ł��B�@���߂�P6000���x�̑傫���Ȃ炢����ł����������
��������������݂邫�`�䂳�A�f�W�J�����w�����Ƃ����祥��������f�W���ᒆ�ɖ����ꍇ�́AG10���ǂ��I�����Ǝv���܂��B�@GX200�͉�����f�W�J����J�����������Ă���l���A�u���̃J�����y�����Ȃ��`�v���Ǝv���J�����ł���A���\����G10�����i��ł��B
�����ԍ��F8822821
![]() 3�_
3�_
����ɂ���ł��B
����GX200����G10�ɔ��������܂����B
�ƌ������ŁA���R�Ȃ���GX200���G10�̕������C�ɓ���ł�(���I
GRDII���ȑO�g���Ă܂������AGX200�ƌ��������R�[�͂�����ƐF���Ԃ�o�鎖������̂ŁA���S�҂̕��ɂ�G10�̕��������߂��ȁE�E�E���[�����Ɠ����ŕȂ���������D�܂����������ł�����
���Ȃ݂Ɏ��������Ŏq�����B��Ȃ�A����ۂǘr�Ɏ��g��������ȊO�́A����@�ł��f�W�C�`�̕������|�I�ɎB��₷���ƍl���܂��ˁB�掿���Ƃ邩�֗������B�邩�œ���ł����A�g��������̂���Ԃ̗l�Ɏv���Ă��܂��B�ł͂ł�(^^//
�����ԍ��F8823204
![]() 3�_
3�_
�����́B
������GX200��G10�Ɨ��������Ă��܂����A�I�ԂȂ�G10�̕��ł��ˁB
�L�p�d����I�o�d��(180�b�j�Ȃ��GX200�ł����ǁB
28mm-140mm�ł��̂Ŏg������͗ǂ��ł���B
�����ԍ��F8823921
![]() 1�_
1�_
GX200�������Ă��܂����A24mm����̍L�p�͕��i���B��Ƃ��ɂ͑�Ϗd�܂��B
����Ɛ���������A����͎g���܂��B
�����Â��Ƃ���͂��߂ł��B�m�C�Y�����R�[�͐̂��瑽���B
�����قŎB�����ʐ^�͎U�X�ł����B
�ł��A�y���ď������̂Ńf�W��̃T�u�J�����Ƃ��Ď�Ԃ牺���Ďg���Ă܂��B
G10�̑傫���d������ɂȂ�Ȃ���A�f�W��̃����Y�L�b�g�����ɓ��ꂽ�炢�����ł����H
�������́A����B����K�v�Ȃ�ŋߏo�����Ȃ�PowerShot��SX1 IS���������ƁB
����͓��悪�t���n�C�r�W�����ŎB��܂��B
�L�p��28mm����ł���CMOS�Ȃ̂ʼn掿�������҂ł������ł��B
����Ȃ痷�s�p�Ƃ��Ĉ��ōς܂���ꂻ���Ȃ̂ō���������Ă݂܂����B
�����ԍ��F8825048
![]() 1�_
1�_
�݂邫�`�䂳��AG10�̔Ȃ̂�G10���������߁B
> ���Ƃ�����肽���Ƃ��v���Ƃ��A�I���������̂̓_���g�cGX200�Ȃ�ł����
G10�ł��\���B��܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500211327/SortID=8782444/ImageID=177072/
15�b�ł�ISO���グ��A�钆�Ȃ̂ɁH���H
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501911289/SortID=8636968/ImageID=154922/
GX200�̔�Up���ꂽ�AGX100��180�b�B
�I�������߂��ė��ꂵ�܂��E�[���H�ȃf�L�A�R�����B�肽���Ǝv���Ȃ甃���ł����B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00502011284/SortID=8450555/ImageID=127848/
�ŋ߂̓V�̎ʐ^�̗��s�͍����A�Ȃ��5006�����I
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501911289/SortID=8806154/ImageID=180102/
���̂́A�킸��1600���A
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501911289/SortID=8820589/ImageID=182501/
�����ԍ��F8827400
![]() 1�_
1�_
>BVB����
��r���肪�Ƃ��������܂��I
���͔ޏ������t�������Ă��܂��B�Ȃ�ŁA���t�͂Ƃ肠�����������Ȃ��Ǝv�����肵�Ă܂��B
�����A�����܂Ŏ����̃��C���@�Ƃ��Ă̍w�����l���Ă܂��B
�f�W�J���͍��܂łQ��ڂ����Ă��܂����i�����ւ��j
����łR��ڂł��B���\����G10����A�Q�l�ɂȂ�܂��B
>Coshi����
�f�G�Ȏʐ^���肪�Ƃ��������܂��I
�ޏ��̃��t�ŎB�����肵�܂����A�܂��܂��r�Ɏ��M�͂Ȃ������Ȃ�Łc
G10���Ȃ��c
>�܂悢������
���ۂɗ����g���Ă���̂��ӌ��͋M�d�ł��I���肪�Ƃ��������܂��I
>jyaganta����
����������͂�����ƋC�ɂȂ��Ă�����ł����A����ς�g�����肢����ł��ˁI
�Â��������Ƃ����̂͋M�d�Ȃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂��I
SX1 IS�͑S�R�l���ĂȂ������̂Ō��Ă݂܂��I
>��Ă��Ⴓ��
�f�G�Ȏʐ^�ł��ˁI
�m����180�b�ł���Ȃɗ��ꂿ�Ⴄ��ł��ˁc
����ɂ��Ă��A��Ȃ̂ɒ��H�݂����Ȃ̂��Ƃꂿ�Ⴄ��ł��ˁB������
���Ƃ�Ă��Ⴓ�Ƃ��Ă鍇���ʐ^��G10�ŎB��ꂽ���̂Ȃ�ł���?
�S�R����Ȏʐ^���B���Ȃ�Ă���Ȃ�������ŁAG10�ł��Ƃ��ł��B���Ȃ�
�ǂ�����ĎB��̂��Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F8828553
![]() 0�_
0�_
�݂邫�`�䂳��@
> ���Ƃ�Ă��Ⴓ�Ƃ��Ă鍇���ʐ^��G10�ŎB��ꂽ���̂Ȃ�ł���?
LX3�ŎB��܂�����G10�ł��B���͂��ł��B
�������Ă��邽��EXIF�������Ă��܂����AF2.0�A�V���b�^�[���x2�b�AISO80�B
G10�́AF2.8�Ȃ̂ŃV���b�^�[���x or ISO��2�{���K�v�ł����A���ՎB�e�͕ʁB
�����������Ă��邽�ߔ{�͕s�v�Ɨ\������܂��B
��̓I�ɂ́AF2.8�A�V���b�^�[���x2�b�AISO100�ŏ\���Ǝv���܂����A
�_���Ȃ�ISO200��OK�AG10��GX200��荂���x�������̂Ŗ��Ȃ��B
�l�I�ȕ]���A
- �L�p��28mm����Ώ\��
- ������LX3�������AGX200�͘_�O
- DIGIC�̐i���́A���Ђ��2����ȏ��
- �������t���݂̍��@�\�͎g��������Ő���
G10�̔��\�O�������̂�LX3�ɂ��܂������A���Ȃ�G10�B
�V�̌����ʐ^�����̓X�e���C���[�W���L��
http://www.astroarts.co.jp/products/stlimg6/index-j.shtml
���ɂ��AStarMax�ȂǁA���낢�날��悤�ł���B
http://ggrillot.free.fr/astro/starmax.html
����Mac�Ȃ̂ŁA����\�t�g�ō������Ă܂����ǁB
�����ԍ��F8829591
![]() 0�_
0�_
�݂邫�`��@����
�ǂ�����ǂ��J�����ł��鎖��O�u���Ƃ��āB
����GX200���w����������N�قǂŎ�����Ă��܂��܂����BG10��G11���o��܂Ŋm���Ɏg��������ł��傤(�@
�l�I��ς���ł����B
�܂��AGX200�Ƃ��������R�[�Ɠ��̂�������掿�����ɂ͍����܂���ł����B�X�i�b�v�ɂ͗ǂ����Ƃ��Ďʂ�悤�ł����E�E�E�B
�����Ŏ����A�{�f�B�ו��̑��肱�݂�f�U�C���ʂ�G10�͂ƂĂ��D��Ă��܂��B
�掿�B�R���͎G�����ʓ��ł͂킩��Â炢�Ǝv���܂����A���ۂɎg�����Ȃ��Ă݂��G10�̉掿��GX200�͂��Ƃ�葼�̃R���p�N�g�f�W�^���J���������|���Ă��܂��B(�������A�R����RAW���܂߂Ă̑��])
���f�W�^���g���̕����A�v���O�����I�[�g�ł͂Ȃ��}�j���A����ϋɓI�Ɏg���Ă���l�Ȃ�G10�������Ɏg�����ō��掿���������邩�ƁB
�t�������A�v���O�����I�[�g�ł͂��̐��\���[���Ɋ��\�ł��Ȃ��Ƃ������ɂ��Ȃ�܂����B
(�������A�����I�ɂ͈��f�W�^������ł��B������܂��ł���)
�_�C�����̑��쐫���A�▭�ȃg���N�łƂĂ��g���₷���ł��B
�w�ʂ̃{�^���ɕt�����X�́E�E�E�E���ꂾ���G7/9�̂܂܂ł��Ăق��������ł����B
�����AGX200�ɂ�����G10�ɖ����@�\��ɂ����v�����Ƃ�����܂��B
1�͓d�q������B1�͍L�p24�~���B1�͖��邢�����Y�B�����Ėʔ��������̃N�`�o�V�J�L���b�v�̑��݂ł��B
�{�f�B�̑傫����d���B�����ď�L�����������猩��ɁA
�|�P�b�g�ɓ���ĕЎ�Ŏ�y�ɃX�i�b�v���y���݂����Ȃ�AGX200�B
������ƃJ�����𑀍삵�A�{�i�I�Ɏʐ^���y���݂����Ȃ�AG10�@
�ł��傤���B
�����ԍ��F8830399
![]() 0�_
0�_
�f�W�^���J���� > CANON > PowerShot G10
���Ȃ�̍��]���ł��B�����ƍw���ɌX���܂����B
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/12/04/9765.html
�����A��̔��F��������Ǝ₵���ȁ[�Ɗ�����̂ł����A���ۂ̂Ƃ���
�ǂ��Ȃ�ł��傤���H
���̐���݂�I�Ƃ������A�������Љ�������Ȃ��ł��傤���H
�����͎B�e���̐ݒ�i�s�N�`���[�X�^�C���H�j�ł����܂ŕς��Ƃ��B
�iG7�����L���Ă���̂ł����Araw�͈��������Ƃ�����܂���B�j
�h���I�Ɣw���������Ă��������B
![]() 0�_
0�_
����ɂ���ł��B
����RAW�B�肵�����Ȃ��̂ł����A���V���ɘI�o�������ƍ��킹�i���i�Ȃ�-1/3�`-2/3�}�C�i�X��������߁j��RAW�B�肵�ADPP�̃s�N�`���[�X�^�C���i���i�jWB�i���z���j�Ō�������A�\�t�ʐ^���炢�ɂ͕��ʂɎʂ�܂���`(^^��
���̗F�l�́A�������i�g���Ă���1DsMK3�ŎB�����ʐ^�Ǝv������ł��܂���(^^;;;�@���w���̍ۂ́ARAW�B�肵��DPP�ł��D�݂̐�Ɍ������Ă݂Ă��������B
���ق��ł������̃u���O�ɂ���APowerShotG10�ʐ^�ł��A�����Ȃ�Ƃ����Q�l�ɂȂ�K���ł��B�ł͂ł�m(_ _)m
http://coshi.exblog.jp/tags/PowerShotG10/
�����ԍ��F8732430
![]() 4�_
4�_
������ƌ��t���炸�Ō��������ƍ���̂ŁA�⑫���Ă����܂�m(_ _)m
>�������i�g���Ă���1DsMK3�ŎB�����ʐ^�ƁE�E�E
���u���O�T�C�Y�̎ʐ^�Ō����ꍇ�ƌ������ł�(^^;; �ł͂ł�m(_ _)m
�����ԍ��F8732465
![]() 1�_
1�_
Coshi����
���肪�Ƃ��������܂��B
>���V���ɘI�o�������ƍ��킹�i���i�Ȃ�-1/3�`-2/3�}�C�i�X��������߁j
>��RAW�B�肵�ADPP�̃s�N�`���[�X�^�C���i���i�jWB�i���z���j�Ō�������A
>�\�t�ʐ^���炢�ɂ͕��ʂɎʂ�܂���`(^^��
�����ł����A�Ȃ�قǁB�Q�l�ɂ����Ă��������܂��B
����ɂ��Ă��q�������u���O�̂��ʐ^�A�𑜊��Ƃ������F�Ƃ����A����
���炵���ł��ˁBG10���D�����Ƃ����鏊�Ȃ��悭�킩��܂����B
���āAG7�͂��낻�돈�����邩�B�B�B
�����ԍ��F8732816
![]() 0�_
0�_
Coshi����̎ʐ^���f���炵���̂ł���]�Ƃ͈Ⴂ�܂����L�����̎ʐ^��
�����ł��Q�l�ɂȂ�K���ł�
�l�I�Ȋ��z�ł���G10�͉��O�̌��ʂ����������ł��Ɩ{���ɗǂ��G�������Ă���܂��B
�t�������Ǝ����Ȃ���̃R���f�W�Ƃ������鍷�ł������悤�ȁE�E
��͂肻�̕ӂ̓f�W�C�`�̏o�Ԃƌ������Ƃ���ł��傤��
�ł��y���̂�(���̃N���X�ł͏d���ł���)���U���J�����Ƃ��Ă͍ō��̔������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8732941
![]() 1�_
1�_
2008/12/04 16:41�i1�N�ȏ�O�j
�X����a���F�l����ɂ���I
�boshi�a��{�ȃp�p�a�̍��̌�ł͂������܂����Ƃ͎v���܂����^��������Əo�����Ă��������܂��B
�f10��RAW�B��ɂ�DPP�ɂČ����{������Ɖ��H���܂����B
���̋@�킪�͂��߂Ă�RAW�B��ł���J�����������̂ł͂��߂͂�����ƌ˘f���܂��������ł͎��Ԃ������DPP�𑀍삵�Ă��܂��B���\�y�����ł��B������Ƃ܂ł͖^�̃X�L���ł͕\���ł��܂����\�a�ݕt���ł��B�@�@�@�@�@�ʕ�����
�����ԍ��F8733198
![]() 2�_
2�_
>���̐���݂�I�Ƃ������A�������Љ�������Ȃ��ł��傤���H
���Љ��Ă�L���̂Q�g�ڂ̎ʐ^�͂������ł��傤���H
���Ȃ�ǂ��F���o�Ă�Ǝv���̂ł����B
���ƁA���̋L������̐F�̔�r�Ȃǂ������ĎQ�l�ɂȂ邩������܂���BG10��������Ƃ����o�ꂵ�Ă܂��B
�y�ɒB�~��̃f�W�^���ł�����!�z�f�W�^�����6�@��掿�Ό�
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/11/06/9544.html
CANON�̉�ɂ��āA
���L���m���͓`���I�ɐ�̐�����߂Ɏʂ�
�Ƃ���܂����A���̋L���̌㔼�ɏ����\�t�g�ȊO�ɂ��RAW�����摜�̔�r������A
������ł͐F���̍��͏������Ȃ��Ă܂��B
RAW������O��Ƃ���Ȃ炠�܂�S�z���Ȃ��Ă悳�����ł��B
�����ԍ��F8733513
![]() 0�_
0�_
���������悤�Ő\����܂��A��͐���Ηǂ��Ƃ������̂ł͂���܂���B
���ۂɂ͐��������璆�V�Ɍ������āA����g�F����ɕω�����̖����̃O���f�[�V���������݂��܂����A���z���ӂ͔����ۂ��͂��ł��B����������̂̓J���������ł���ARAW�\�t�g�ł���A�㏈���ŊȒP�ɐF����ς��邱�Ƃ͂ł��܂����A���R���ۂ��i�`�������ɕ\������͓̂���ł��B���������Ӗ���G10�̃X�^���_�[�h�ɂ͍D�������Ă�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8733514
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
�ʐ^�f�l�ł����A���܂��ܐ���B�����ʐ^������܂����̂Ō�Q�l�܂łɃA�b�v���܂��B
RAW�B��ŁA�z���C�g�o�����X�����͎B�e���ݒ�A�s�N�`���[�X�^�C���̓^�C�g���̒ʂ�ł��B
���̑��A���T�C�Y�ȊO�͉��̏��������Ă��܂���B
Coshi�����t���X�P������������Ă���悤�ɁA�F���͌㏈���ŊȒP�ɕς����܂��B
���낢��B���āA���D�݂̐F��������̂��y�����Ǝv���܂��B
�B���Ă��Ċy�����Ȃ�J�����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�����ԍ��F8733852
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́B
���������̊Ԉɓ��哇�ŎB�����ʐ^������̂ŎQ�l�܂�
�ɓ\���Ă����܂�m(_ _)m
�l�I�ɂ͋�̐F���A�J�����̃t�B�[�����O���l���ꂼ��̊���������̂�
�ӌ����F�X�o�Ă��Ă��܂��Ǝv���܂��B
���������Ӗ��ł�DPP�Ȃǂ�RAW���������Ď����D�݂̐��
�d�グ��Ƃ����Ӗ��ł͂��̐����傫���E�F�[�g���߂��
�v���̂Ŏ����ꉟ�����܂���B
�ꖇ�ڂ̎ʐ^
�z���C�g�o�����X�@�@������
�s�N�`���[�X�^�C���@�G�������h
���邳���@�@�@�@�@�@�|1.0
�Q���ڂ̎ʐ^
�z���C�g�o�����X�@�@���z��
�s�N�`���[�X�^�C���@���i
�R���ڂ̎ʐ^�@
�z���C�g�o�����X�@�@���z��
�s�N�`���[�X�^�C���@�X�^���_�[�h
ps�@Coshi����̎ʐ^�����Ă����ߑ��o���Ⴄ�ق�
�@�@�f���炵���ʐ^����ł�(^_^)
�����ԍ��F8734602
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���A��������̃R�����g����Ⴀ�肪�Ƃ��������܂��B
������������Q�l�ɂ����Ă��������܂��B
�����Ɓ[�A�t���X�P����@�̂�������Ɠ���B�B�B
>���ۂɂ͐��������璆�V�Ɍ������āA����g�F����ɕω�����̖����̃O���f�[�V������
>���݂��܂����A���z���ӂ͔����ۂ��͂��ł��B����������̂̓J���������ł���A
>RAW�\�t�g�ł���A�㏈���ŊȒP�ɐF����ς��邱�Ƃ͂ł��܂����A���R���ۂ��i�`��������
>�\������͓̂���ł��B���������Ӗ���G10�̃X�^���_�[�h�ɂ͍D�������Ă�Ǝv���܂��B
�����ʂɐ���Ⴂ���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂ł����AG10�ɂ͂��̂悤�ɍD�������Ă�
�i�`�������ȕ\�����\�Ƃ����A�h�o���e�[�W�������ł����B�B�B�t���t���B�B�B
�B�B�B�����ǎ��̖ڂɂ͗�̃��r���[�ł�LX3��GX200������̂ق����O���f�[�V�����̖L�x����������i��g�ڂ̍��j�̂ł����A���̂悤�ȍD�������ɂ�����i���R���ۂ̃i�`�������ȕ\�������Ћ@��ł��܂��ł��Ă��邱�Ƃ�������悤�ȁj���Ƃ����r���[�Ȃǂ��Љ�������܂���ł��傤���H
�����ԍ��F8736126
![]() 1�_
1�_
���̍���2����ɎB�e���Ă��܂��̂ŁA���ۂɂ͔Z�x�̔Z�����͋C�ł͂Ȃ������̂ł��傤�B
���ۂ̏�Ԃ�m���Ă��郌�r���[�҂�
�����̐F���ł��h��ɏo�Ă���̂�DMC-LX3�B���ۂ����Z���F�ʂŕ\������Ă��邪�A���h���͂����B
�������ڂɋ߂����R�ȐF��PowerShot G10�B
�Ə����Ă���u���r���[�̒��g�v���u�i�`�������v�Ƃ����u����v���ʂ�\�����Ă���悤�Ɏv���܂��B
��Ꭹ�̂��A���ꂼ��̋@��A���ꂼ��̃��[�J�[�̃����Y�̓�����ǂ��o���Ă�Ǝv���܂���B
�����A�摜�����ċq�ϓI�ȕ]�����ł��Ȃ�������Ȃ��킯�ł��Ȃ��̂�
�D���ȕ`�ʂ̃J������I��ł͂������ł����H
���̒��ɂ̓x���r�A�ł����B�e���Ȃ��l�����邱�Ƃł����B
���V�C���ǂ���A���ł��ǂ��ł��썑�̂悤�Ȑ�ɓ��閂�@�̃t�C�����u�x���r�A�v���s��܂����ˁO�O�G
�����ԍ��F8736165
![]() 0�_
0�_
G9��G10�͑����G���͕ς���Ă���Ǝv���܂����AG9��JPEG�Ŏg���Ă���ƁA���ނ����p�p����Ɠ����悤�Ɏ₵���F�Ɋ����邱�Ƃ�����܂��B
���̓t�W��I�����p�X�A�j�R���Ȃǂ��g���Ă��܂��̂ŁAG�V���[�Y���������Ă���悤�Ɋ������܂��B�R���g���X�g����߁A���F����߂Ɋ����Ă���܂��B
�������A����͊F���s���Ă���悤�Ȓ����ɂ���āA�D�݂̐F�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�����AG9�ł͂���܂����A��_�ɐ�Ԃ��o���āA�I�����p�X�u���[��x���r�A�̔��F��^���č�邱�Ƃ�����܂��B
���S�z�ɋy���ADPP�Ŏ��R�ȐF��������Ă͂������ł��傤���B
�����ԍ��F8737778
![]() 0�_
0�_
�����̐���݂�I�Ƃ������A�������Љ�������Ȃ��ł��傤���H
����B�������g�t���������������B
P���[�h�A-1/3EV�AJPEG�B���ďo���ł��B
G10�̂������ŁA�f�W��͖����Ă��܂��B
http://www.imagegateway.net/ph/AEG/RequestViewAlbum.do?i=JDLCZYR2r4
�����ԍ��F8737877
![]() 0�_
0�_
���B�B�B�����ǎ��̖ڂɂ͗�̃��r���[�ł�LX3��GX200������̂ق����O���f�[�V�����̖L�x����������i��g�ڂ̍��j�̂ł����A
�u�h���I�Ɣw���������Ă��������B�v�Ƃ̂��Ƃł����̂ŐG��܂���ł������A
���w�E�̉摜�Ɋւ��Ă����ΑS�����̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B
�P�g�ڂ̉摜��G10�̋�͎v������O�a���Ă܂��B
�����Ƃ��O�a�����Ȃ��̂�LX3�ł��傤�B
��r�L���̕M�҂�
�������ڂɋ߂����R�ȐF��PowerShot G10
�Ə����Ă܂����A���Ȃ��Ƃ�G10���Ӑ}���Ă����Ȃ����킯�ł͂Ȃ��A
���O�a���Ă��܂������ʁi�����������F�ɂȂ�܂��j���A���܂����ۂ̐F�ɋ߂��������A
�M�҂̖ڂ̃_�C�i�~�b�N�����W�������Ă������������̂ǂ��炩�ł��傤�B
�S�@��̉摜������ׂ�ƁA����f�Ȃ��̂قǖO�a���Ђǂ��X��������̂ŁA
����f���̕��Q�����邩������܂���B
G10��1500����f�ALX3��1000����f�ł�����A���ׂĂ̏�ʂ�G10������Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��Ǝv���܂��B
http://www.dpreview.com/reviews/canong10/
G10�̃��r���[�ł��BP6000��LX3�Ƃ̔�r��T���v���摜������܂��B
�����ԍ��F8740435
![]() 0�_
0�_
�A�L���Z����
���W���[�i���ꂳ��
���@�̃t�B�����E�x���r�A���s��܂����ˁB�����悭�g���܂����B�ł��B�e�Ώۂɂ���ăv���r�A��������A�X�e�B�A��������A�F�X�g�������Ă܂����B�f�W�J���͂��ꂪ�V�[�����ɕς�����̂������b�g�Ȃ킯�ŁA���̑���x���r�A���̂��̂ł͂Ȃ������܂Ńx���r�A���ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B���̃x���r�A���������̍D�݂ɍ������ۂ��ł��ˁB
��c��������
���[���I�I���炵���B
���`�����`���𑜂��āA���������F���C�C�I�I
���炵����Ⴀ�肪�Ƃ��������܂��B�F���悹�Ă��F�������O�a���������Ȃ��A��i�Ȋ��������܂����B135�T�C�Y�̃x���r�A�Ƃ͈Ⴂ�܂����ʎ����̕\���������܂��B�������x�������I�H�x�^�b�ƂȂ炸���̊�������܂��ˁB
�݂Ȃ���A���肪�Ƃ��������܂����B
�������߂܂����B
�Ƃ肠�����������h�o�V�����Ă݂���ƁB
�i����Ȃ��ƂȂ�A��̔����X�g���b�v�����ł������Ƃ���悩�����B�B�B�j
�����ԍ��F8740483
![]() 0�_
0�_
���@�Ǝv������A�����A���ԍ���gintaro���C�ɂȂ邱�Ƃ��B�B�B
�������킹�Ȃ��ŁB�B�B���Ă���ς�C�ɂȂ邩���B
���̐��F�͖O�a���Ă��ł����I�I�I�@�z���g�ł����B�B�B
G7�ł͂��̐F��������O�������̂ł����B
����܂����A�ǂ����悤�B
�����ԍ��F8740547
![]() 0�_
0�_
��̐F��G10�̐F�����ʂƂ������A���R�ł��ˁB
�ł������A�ʐ^�Ƃ����͎̂��R�̐F��\������Ƃ������A1�̌��Ő��镨�Ȃ̂�
LX3�̔��F���D���Ȃ�A����ł����̂ł͂Ȃ��ł����H
��̂ɉ����Ď��R�E�̊K�����A��������PC���j�^�[���8bit�K���ŕ\���ł��܂����H
LX3�̓��A�����͌����ɐF���x���オ�������F�����܂����A���������ł͂����ł����ۂɂ��������܂����H
�F����m�ۂ���AdobeRGB�̐F��Ԃ̕������R���ƌ����āA�ς��ƌ��ɖ��������̐F�����u���R�v�Ǝv���܂����H
���o����Ă��Ȃ��ʐ^�ȂǑ��݂��Ȃ��̂ɁA�u���R�v�Ƃ������x�����\��Ȃ��ƋC�ɓ���Ȃ��ł����H
�l�̖ڂɂ͒r�ɕ����Ԙ@�̉Ԃ��A�Ԃ̃}�N���D���̐l���B��ʐ^�̂悤�Ɂu�ڂɌ������v���Ƃ͂���܂���B
������u���R�v����Ȃ��i�����������F���j�̂ő��ʂɋ����܂����H
�̔��F���u�ǂ�����v�s���̂����R����Ȃ��u��ׁv�Ȃ̂ɁA��̉��������Ă�̂��A�ƁB
�����ԍ��F8740972
![]() 1�_
1�_
�����C�ɂȂ�܂��̂ŃR�����g�����Ă��������܂��B
> ���O�a���Ă��܂������ʁi�����������F�ɂȂ�܂��j
�F�f�q�̂֓��͂��O�a�i�ő�j���Ă���ł͐������Ȃ�܂��B�ԁA���ő�l�ɋ߂��Ȃ��Ă���Γ��R�A�����Ȃ��Ă��܂��B�������߂��������i���F�j�Ȃ��Ă���̂͐F�X�y�N�g����������C�w��`�d����Ƃ��ɎU�����Ղ��Ă��܂����R���ہi���[���[�U���j�ł����āA�B���f�q�����ł��ӂ�o���d�ׂ��F���͂����������Ă���Ƃ������Ƃł͂���܂���BG10���O�a���Ă��邩�甒���Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�ނ��낻��͐������Č��`�ʂ��Ǝv���܂��B
�l�Ԃ̖ڂ̃J���[���Ƃ̃_�C�i�~�b�N�����W���قɂ��Ă͑����܂���B
�֑��ł����A�����̎ʐ^������ׂ�ƕK���ʓx�̍������̂��I������܂��B����͒��łƂ����Ă��ǂ����炢�ł��B���̌���a�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F8741333
![]() 0�_
0�_
G7�̃��[�U�[��G10���������܂����B
�ǂ��Ȃ����_��
�@RAW�ŎB���B�i�݂Ȃ��q�ׂĂ��܂����A�F�͌�ōD���Ȃ悤�ɕύX�\�j
�A����̃^�C�����O�����Ȃ��Ȃ����B
�BG7��肳��ɑ@�ׂȕ`�ʗ́B
�CSDHC�J�[�h�Ή��i16G�̃J�[�h�ŎB��܂����Ă��܂��B�j
�D�œ_�������₷��
�E�d�r�̗e��UP
�����Ȃ����_
�@�P�O���d���Ȃ����B
�A����̉掿������Ă���B�i�e�ʂ����Ȃ��čς݂܂����j
�����B�肵���̂�URL���猩�Ă��������B
�����ԍ��F8741390
![]() 1�_
1�_
���ꂩ��A���̃X�������Ă��Ďv�����̂ł����A
��̕��ł��낢��Ȉӌ����q�ׂ��Ă��܂���
���̘_���I�ȍ����������܂��Ȃ��̂��������ł��B
�_�����q�ׂ�Ȃ炻�̈��p���URL��Y�t����Ȃ�
���ׂ��ŁA�����̂Ȃ������ɐU���Ă͂����܂���B
�����̖ڂ�M���邵���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8741457
![]() 1�_
1�_
>���̐��F�͖O�a���Ă��ł����I�I�I�@�z���g�ł����B�B�B
���������ۂ̋��F�̏ꍇ������܂��̂ŁA���F����ɖO�a���Ӗ�����킯�ł�
����܂��A�����������F�͖O�a���Ă�ꍇ�������Ǝv���܂��B
���̉摜�ɂ��ẮA�_�E�����[�h���Đ̃q�X�g�O������������Ŕ��f���Ă��܂����A
�������Ԉ���Ă��܂�����A�ڂ������������Ă��������B
LX3������̃q�X�g�O�����ƌ���ׂĂ�
�����̖ڂɂ͗�̃��r���[�ł�LX3��GX200������̂ق����O���f�[�V�����̖L�x����������
�Ƃ������z�ƃ}�b�`���Ă�Ǝv���܂��B
��ʂ�G10�͋�̕`�ʂ���肾�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A����݂͂Ȃ���̍������Ă��킩��Ǝv���܂��B
�����A15M�̍���f�@�ł�����A�P�x���̑傫����ʂł́A10M�@�Ƃ���ׂč��̂��ꍇ�����邾�낤�Ƃ������Ƃł��B
���ۂɂ́A���̂���ʂ��݂���̂���ςȂ��炢��������܂��A�P�g�ڂ̉摜�͂���������ɂȂ��Ă�\��������Ƃ͎v���܂��B
���킹�Ă��܂����悤�Ȃ̂ł����A�I�o��ɋC�����āA�܂�RAW�ŎB��̂ł���A�قږ��Ȃ����낤�Ƃ�����{�I�ȍl���́A�ŏ��ɏ������Ƃ���ł��B
�p�[�t�F�N�g�ȋ@��͑��݂��Ȃ��Ƃ����O��Ńx�X�g�ȑI�����B�B
�����ԍ��F8742396
![]() 0�_
0�_
�u���F�v�Ƃ����\���ŐF�̂��Ƃ�������ƁA�����^�O�����܂��̂ł����E�E�E
���V�A���̂��Ƃł���ˁH
�ŁA�u�O�a�v�Ƃ����\���ŕ\����錻�ۂŁA���V�A���ɂȂ鎖�͂Ȃ��ł��B
�̖��x���オ���Đ��F�ɂȂ�̂͒P���Ɂu���邢�v�ł����āA�I�o�̖��ł��B
�������Y�̃R���g���X�g�����������ł��A���邢�����͔����ۂ��Ȃ�܂��ˁB
�F�̐��E�Łu�O�a�v�Ƃ����A�O�����E�O���F100%�����ɊK�����V�t�g���邱�Ƃł�����
���Ԃ�A�p������Ⴂ���Ďg���Ă�̂ł��傤�B
���ǁA�I���W�i���ƂȂ镗�i�ڌ��Ă��Ȃ��̂ɁA�K����疾�邳�́u���R���v���ǂ����������͕̂ςł��B
�������i�E�V��E�G�߂ł��A���R���Ԃɂ���ĊK���̏o���͈قȂ�܂����B
�l��G10���R�Ƃ����̂́u��ʘ_�v�Ƃ��āA���̎����̌ߌ�Q���̒i�K��
G10�ȊO�̉摜�̐F�̔Z���́u���R�ł͂Ȃ��v�Ƃ������ƂŁA�u�ʐ^�v�Ƃ��Ĉ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł��B
���I�o��ς��đS�̂̕��͋C�����邱�Ƃ�NG���ƁA�ʐ^�\�����̂��u���������v�ł���ˁH
����遁�K�����L�����O���f�[�V�������L�x�A�Ƃ����̂͊Ԉ���Ă��܂���
���ڂ̐�͔��ڂł���������R�ŁA�F������Ă�����ׂĊK���L���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F8742519
![]() 2�_
2�_
���R�ȐF�Ƃ��G���̃J�����]�_�ɂ悭�g���܂����A�t�B�����ł��f�W�^���ł����R�ȐF���o�邱�Ƃ͂Ȃ��A�_�]�҂̊��o����o�����t�ł��傤�B
���Ȃ��Ƃ��AG10���������R�̐F�ɋ߂��Ƃ����L�q�ł������Ƃ������a�����o���܂��B
�ł́A�ǂ̂悤�ȐF���D�܂����v�����Ƃ����ƁA���ꂼ��̐l�̊������͈Ⴄ�ł��傤���A�l�I�ɂ�LX3��P6000����ېF�ɋ߂��悤�Ɍ����܂��B
IXY�f�W�^����S30�`�V���[�Y�́A��ېF����肭�o���A�N������D�܂����F�����o���Ă����Ǝv���܂����AG9�@G10�����肩��G���̕�����������Ă��Ă�̂��ȁH�Ƃ������܂��B
RAW�B��Ŗ{�̂�����J�����Ȃ̂ŁA�G���̓��[�U�[�̘r�ɂ������Ă���̂ł��傤�B
�����ԍ��F8743500
![]() 0�_
0�_
�����������Ă��邩������܂���B
�L���F�Ƃ��A��ېF�̘b���ł͂Ȃ��A���R�Ȋw�I�Ȑl�ԂɔF�m�ł���F�ʂ̒����Č������b��ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂��BG10�͑��@��Ƃ̔�r�œo�ꂵ���̂ł����āAG10���x���`�}�[�N���A�ƌ����Ă����ł͂���܂���B
���͍ŋ߂̃J�����A����������܂߁A�u�ʓx�̍������̂��ǂ��v�Ƃ���Ă��邱�Ƃɖ�肪����悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F8743898
![]() 0�_
0�_
�Ȃ�Ƃ������B
�Ⴆ�A��勐���̃��C�J�ƃc�@�C�X�A�ǂ���̕`�ʁE�F������ېF�ɋ߂��̂ł��傤�H
������勐���A�j�b�R�[���ƃL���m�������Y�ł������ł��B
�����͊ȒP�Łu��ېF�ɋ߂����Ȃɂ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B��ۂȂ�Đl���ꂼ��ł�����B
�L���F�Ƃ������Ƃł����A���̋L���F�͌֒�����Ă��܂��B
�L���F�̕����R���g���X�g���Ⴉ�����Ƃ��A������ł����A�Ƃ������Ƃ͖ő��ɂ���܂���B
�֒����ꂽ�L���F���u��ېF�v�ɋ߂��̂ł���A����͎��R�i�����ł͒����I�Ȃ̈Ӂj�Ȕ��F�ł͂���܂���B
���R�u���R���C�L�C�L�Ǝʂ������Y�i�J�����A�t�C�����j�v�́A���R�ȕ`�ʂ����郌���Y�ł͂Ȃ��̂ł��B
�Ⴆ��EF50mm/F1.8�͑�ώ��R�ȕ`�ʂ����郌���Y�ł��B�t��EF50mm/F1.4�̓����Y�`�ʂɉ��o�����݂��܂��B
�����đ��̐l��2�҂��r���āuEF50mm/F1.8�͑f���C�Ȃ��v�Ƃ����悤�ȕ]�������܂��B
���R�ȕ`�ʂ́A���̏ꍇ�f���C�Ȃ��̂ł���i�j
���X�߂����ڂɂ��Ă镔���̓�����A�X��玩�R���u���b�N����炪�A�N�₩�ȐF�Ŗڂɔ�э���ł��܂����H
LX3�̂悤�ȐF���ŁA���͑S�Ĕ���ꂽ��ǂ��ł��傤�H
�ǂ������̒��S�ʓI�Ɂu���R�v�Ƃ������t�ɊÂ��Ƃ������A�ア�Ƃ������A����ɑf�G�ȃC���[�W����������Ƃ�����
���R�����f�����X���Ă��Ƃł��B�f���C�Ȃ����Ď��ł��B�N�������Ă���Ȃ����Ď��ł��B
�L���m�������Y�̂��̓������������낪��Ȃ��ƁAG10�͏ꍇ�ɂ���Ă͐����܂�Ȃ��J�����ł��B
�����ԍ��F8744850
![]() 2�_
2�_
�t���X�P����
���Ȃ��̃��X�ɑ��ăR�����g�����ӎ��͑S������܂���ł����B
�F�ʂ̒����Č����Ƃ������Ƃł�����A�S�ẴR���f�W�͌����Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
�R���f�W�̉掿�́A�L���F�̏����ł�����A�u���R�ȐF�v�Ƃ����]�����������o���͈̂�a���������܂��B�����܂ł��A�`�������N��̂ɑ��銴�z�ł��B
�A�L���Z����
��G10�͏ꍇ�ɂ���Ă͐����܂�Ȃ��J�����ł�
����ɂ��܂��ẮA�S���������܂��B
�����A���R���������f�Œ��قǂ��Ƃ͎v���܂���B�J�����ŕ\���ł��Ȃ��قnj������p��\�����Ƃ�����܂��B���̎p��\�����������AG10�̒��f�ȊG���ɔC�������͂���܂���ˁB
�����ԍ��F8749207
![]() 0�_
0�_
>���̉摜�ɂ��ẮA�_�E�����[�h���Đ̃q�X�g�O������������Ŕ��f���Ă��܂����A
>�������Ԉ���Ă��܂�����A�ڂ������������Ă��������B
gintaro����̃R�����g�ɕ⑫���܂����A��̐��O�a���Ă���Ƃ����̂́A��L�̃q�X�g�O����������Έ�ڗđR���Ǝv���܂��B
>�Ə����Ă܂����A���Ȃ��Ƃ�G10���Ӑ}���Ă����Ȃ����킯�ł͂Ȃ��A
>���O�a���Ă��܂������ʁi�����������F�ɂȂ�܂��j���A���܂����ۂ̐F�ɋ߂��������A
>�M�҂̖ڂ̃_�C�i�~�b�N�����W�������Ă������������̂ǂ��炩�ł��傤�B
�����Ӑ}���� G10 �������Ȃ������ǂ����͕���܂��A�I�o�����߂Ȃ��߁A���O�a�����̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B�����ł���A�P���ɘI�o������ΐ̍Č����͗ǂ��Ȃ�܂��B
�܂��A�_�C�i�~�b�N�����W���L����A���F�ł͂Ȃ����邢�Ƃ��čČ�����܂��B
>�F�f�q�̂֓��͂��O�a�i�ő�j���Ă���ł͐������Ȃ�܂��B
�F�f�q�ւ̓��͂��O�a����ƁA���ΓI�ɐԁA�������Ȃ�A���̗l�Ȑ��F�ɋ߂��F�ɂȂ�܂��B
���ꂪ�����ōł��C�ɂȂ�̂́A������̃O���f�[�V�������A�������F���A�ƐF�����ω����Ȃ���O���f�[�V��������P�[�X�ł��B
�����ԍ��F8749689
![]() 0�_
0�_
�u���R�v=�����I�ȁA�Ƃ����Ӗ��Ɩ��L�����̂ł����E�E�E
���R�u�厩�R�v���ǂ����������Ȃǂƌ������o���͂���܂���B
���R�Ȕ��F=�厩�R�̔��F�ł͂Ȃ��ł���ˁH���{��̈Ӗ��Ƃ��āB
�����ԍ��F8749732
![]() 0�_
0�_
on the willow����
�ŁA���̃q�X�g�O��������A���ۂɐ��F�������̂��A���O�a���������Ȃ̂��A�̈Ⴂ���킩��̂ł����H
��̐F�����x�ɂ���āA�����Q���������X�J�C�u���[�����F�����ƕω�����̂́A���R���ۂł��B
���R���ۂŋN��������̖��x�ω��ƁA�B�e�f�q�̓��͖O�a�ƁA���̃q�X�g�O��������ǂ߂܂����H
�ł�����u�O�a�������炾�v�u����f���f�������炾�v�Ƃ����ӌ��ɔ��_���Ă��܂��B
�P���ɁA���̎��̋��F�������̂��Ǝv���܂��B
����ׂ�Δ���܂����A�X�̐F������G10�̕�������߂ł���ˁH
���̉摜�Ɣ�ׂ�u�I�o������߁v�ł����A�ߌ�2���ɎB�e�����摜�ł���A���邭�ē��R�ł��B
�ʂɁA�S�̂̃_�C�i�~�b�N�����W�������߂ɗ��Ƃ��C���̘I�o��I���@�킪�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł��B
���ۂɎB�e�҂����������Ɣ�ׂāA���邳���F��G10�̖��x�����R���A�ƌ����Ă�̂ł��傤�B
������u�B�e�҂̖ڂ������v�Ƃ����悤�Ȏw�E������قǂ̏؋������̃q�X�g�O�����ɂ���܂����H
�P���ɐ̎B�e��f���O�a����قǂ̓��͌����������̂ł���A���Ӊ�f�ɂ��e�����܂���
���RRAW�Ō������Ă��~���悤�̂Ȃ��摜�f�[�^�ƂȂ��Ă��܂��B
���Ȃ��Ƃ�
�����O�a���Ă��܂������ʁi�����������F�ɂȂ�܂��j���A���܂����ۂ̐F�ɋ߂��������A
���M�҂̖ڂ̃_�C�i�~�b�N�����W�������Ă������������̂ǂ��炩�ł��傤�B
�͏ؖ����ė~�������ȂƎv���܂��B
���l�Ԃ̊�̃_�C�i�~�b�N�����W���ǂ̒��x���邩�������Ă��Ă̔����ł��傤����B
���ۂ̐F�ւ̋߂����O�a�̂������Ƃ����Ă�킯�ł�����A�ʂ̋@��̐F�͎��ۂƂ͋߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����ˁH
�����Ă邱�Ƃ��������Ă�悤�Ɏv���܂����A����ɂ͓˂����܂Ȃ��E�E�E�ʔ����ł��ˁB
�����ԍ��F8749906
![]() 1�_
1�_
�A�L���Z����
>���ۂɐ��F�������̂��A���O�a���������Ȃ̂��A�̈Ⴂ���킩��̂ł����H
���͎��ۂ̋�̐F���ǂ��ł��������ɂ��Ă͑S�����y���Ă��܂��A���O�a���Ă���̂̓q�X�g�O���������Ă̒ʂ�A��������������ł��B
>�ł�����u�O�a�������炾�v�u����f���f�������炾�v�Ƃ����ӌ��ɔ��_���Ă��܂��B
�O�a�͋N�����Ă��܂��̂ŁA�����ے肷��Ӗ��͂���܂���B
����������f�i�ɏ���f���j�ɂ����̂��ǂ����́A���͒f�����܂��A�\���̂P�Ƃ��Ĕr�������܂���B
>����ׂ�Δ���܂����A�X�̐F������G10�̕�������߂ł���ˁH
�q�X�g�O�������r���܂������A�����g�͋�̖O�a�قLjႢ������l�ɂ͊����܂���ł����B
>���̉摜�Ɣ�ׂ�u�I�o������߁v�ł����A�ߌ�2���ɎB�e�����摜�ł���A���邭�ē��R�ł��B
���邭�ē��R���ǂ����͕ʂƂ��āA�O�a���������Ƃ��ĘI�o�������Ă��܂��B�I�o��������ΖO�a���Ȃ��̂��قڎ����ƌ����č����x���Ȃ��ł��傤����B�����A�I�o��������ƒ��Ԓ��i�X�̐F�����j���������Ă��܂��ł��傤�B
�S���̐����ł����A���̃T���v���ł͈Õ���������Ă��Ȃ��̂�������܂���B
>�P���ɐ̎B�e��f���O�a����قǂ̓��͌����������̂ł���A���Ӊ�f�ɂ��e�����܂���
>���RRAW�Ō������Ă��~���悤�̂Ȃ��摜�f�[�^�ƂȂ��Ă��܂��B
�̖O�a���x�ł͎��Ӊ�f�ɉe�����Ȃ��ł��傤�B
>���ۂ̐F�ւ̋߂����O�a�̂������Ƃ����Ă�킯�ł�����A�ʂ̋@��̐F�͎��ۂƂ͋߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����ˁH
>�����Ă邱�Ƃ��������Ă�悤�Ɏv���܂����A����ɂ͓˂����܂Ȃ��E�E�E�ʔ����ł��ˁB
����A�ł�������ۂ̐F�ɂ͌��y���Ă��܂���B�B�e�҈ȊO�͎B�e���̋�̐��͂킩��܂���B
�ł����A���O�a�������ʁA���܂��B�e�҂̋L���Ɏc�����F�����i���邳�j�ɂȂ����\�����ے肵�܂���B
�����ԍ��F8750548
![]() 0�_
0�_
on the willow����
���ǂł��ˁA�킩��Ȃ��̂ł��B�ł�����A�`���[�g�`�F�b�N�ł��Ȃ������r���悤���Ȃ��̂ł��B
�ƂȂ�ƎB�e�҂̎�ς����ɔ��f����ق�������
�ʏ�L���F�Ŕh��ڂɂȂ�̂��A���F�C���̕������ۂɋ߂��Ƃ����A���悻�����������Ƃ��낤�Ƃ������Ƃł��B
����ƋC�t�����̂ł����A�F�ɂ����āu�O�a�v�Ƃ������t���g���Ƃǂ��������ۂ��w���̂�����������܂���ˁH
�ł���u�F�E�O�a�v�Ō������āA�J���[�ʐ^�E�摜�̐��E�ł́u�F�O�a�v�̈Ӗ��ׂĂ��������B
���w�E�̏�Ԃ́u�F���O�a���Ă���v�ł͖����āu���x���オ���ĔZ�x�������Ă�v�Ƃ����܂��B
�I�o�I�[�o�[��I�o�O�a�Ƃ����Ȃ����Ȃ��ł����A�u�F�̖O�a�v�ɂ͕ʂ̈Ӗ�������܂��̂ŕs�K���E�s�K�ł��B
�����ԍ��F8750762
![]() 2�_
2�_
>>���ꂪ�����ōł��C�ɂȂ�̂́A������̃O���f�[�V�������A�������F���A�ƐF�����ω����Ȃ���O���f�[�V��������P�[�X�ł��B
>��̐F�����x�ɂ���āA�����Q���������X�J�C�u���[�����F�����ƕω�����̂́A���R���ۂł��B
>���R���ۂŋN��������̖��x�ω��ƁA�B�e�f�q�̓��͖O�a�ƁA���̃q�X�g�O��������ǂ߂܂����H
�R���F�̂����P�F�������͂Q�F���O�a����ƁA�F�����ω����Ȃ���O���f�[�V�������Ă��܂��܂��B
������ɂ�����������܂���̂ŁA���X�ɒ[�ȗ�Ő������܂��B
���͂ƍ��͓����@��A�����I�o�ŎB�e�������̂ł��B
�_�C�i�~�b�N�����W100%�ł͍����炪���A���F�A�A�ƃO���f�[�V�������Ă��܂��Ă��܂��B����́A���͂R���F�̂R�F�Ƃ����قږO�a���A���F�͐Ɨ��O�a���A�Ɛ��F�̒��Ԃ́A�������O�a���Ă��܂��B
�ł�����A�ԁA�A�̂��ꂼ��̐F�̊���������Ȃ���O���f�[�V�������Ă��܂��̂ŁA�F���̕ω��ƂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�E�̃_�C�i�~�b�N�����W400%�̕��́A�F�o�����X�̕��ꂪ���Ȃ��̂��킩�邩�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8750781
![]() 1�_
1�_
�������O�a���Ă��܂������ʁi�����������F�ɂȂ�܂��j���A���܂����ۂ̐F�ɋ߂��������A
�����M�҂̖ڂ̃_�C�i�~�b�N�����W�������Ă������������̂ǂ��炩�ł��傤�B
���͏ؖ����ė~�������ȂƎv���܂��B
���łɏ������Ƃ���A���͂����̉摜�̃q�X�g�O�����i�j�����Ă����l���܂����B
�i�A�L���Z����͌��Ă����������ł��傤���H�j
LX3�̉摜�̃O���t������ƁA�E�[�t�߂Ƀs�[�N���������R���m�F�ł��܂��B
G10�̕��ł́A���̎R���O���t�E�[�ɂׂ�����Ɖ����Ԃ��ꂽ�`�ɂȂ��Ă��܂��B
�ł�����E�E�E�i�ȉ��ȗ��j
�������A�Z���Ԃ̂����ɋ�̋P�x���}���ɕω������\����A
G10�̉摜�̃q�X�g�O�������{���̋�̎p�f���Ă��āALX3����̃O���f�[�V������
����ɝs�����Ă���\��������܂����ǁB
�����l�Ԃ̊�̃_�C�i�~�b�N�����W���ǂ̒��x���邩�������Ă��Ă̔����ł��傤����B
�����A�l�Ԃ̊�̃_�C�i�~�b�N�����W���ǂ̒��x���邩���������i�H�j��ł̏�k�ł��B
�i�Ƃ������A�ڂ̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƌǂ������邩�́A���܂�W�Ȃ��悤�ȁE�E�j
�����ԍ��F8750887
![]() 0�_
0�_
on the willow����
�ŁAG10�̂��̌X������f�ł����Ƃ���́u�O�a�v�Ȃ�ł���
�`���[�g��r�̉摜�̐��u�O�a�v���ĂȂ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B
���̗����͔���܂���ˁH
�c�O�Ȃ��瓯�����r���[�L���ł�ISO800���̔�r�摜��������܂��AG10�̐n�͗������C���ł��B
���̋@��́A�ʂ̐F�n���Ɣ�r���Ă��N�₩�ł��B
����́A�Z�x�E�ʓx�Ɋւ��āu�@��ɂ�鉉�o������v���̕\�ꂾ�Ǝv���܂����������ł����H
�n��̓��͂ɑ��āA������`���[�j���O�i�G���j������Ă���悤�Ɍ����܂����E�E�E
�����ԍ��F8750890
![]() 1�_
1�_
�A�L���Z����
>���w�E�̏�Ԃ́u�F���O�a���Ă���v�ł͖����āu���x���オ���ĔZ�x�������Ă�v�Ƃ����܂��B
>�I�o�I�[�o�[��I�o�O�a�Ƃ����Ȃ����Ȃ��ł����A�u�F�̖O�a�v�ɂ͕ʂ̈Ӗ�������܂��̂ŕs�K���E�s�K�ł��B
�F�O�a�Ƃ́H
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=8524557/
>�F�O�a�Ƃ͂q�f�a�̈�܂��͓�̃`�����l���̃q�X�g�O�������E�̕ǂ�
>�ւ�t������ԂƔF�����Ă��܂����A
�N���٘_�������Ă��܂���ˁB
�O�a�̈Ӗ������͉��L�̂Ƃ���ł��B
�ق��]��y�O�a�z[��] -�X��
�P�@�܂݂����Ƃ̂ł���ő���x�ɒB���āA����ȏ�]�n�̂Ȃ����ƁB�u�\��Ԃ̌�ʎ���v
�@�u���Ɂ\�����l�̊�ɂ͂����͐^�ÂɌ������v
�Q�@��������̂��ƂŁA����ʂ��������Ă����A����ȏ㑝�����Ȃ��Ȃ�ő���ɒB������ԁB
�R�@����Ă��邱�ƂɖO�������邱�ƁB��J�Ƃ͋�ʂ����B�S�I�O�a�B
gintaro����⎄���w�E���Ă���̂́A�P���ȘI�o�I�[�o�[�ł͂Ȃ��A���ɂR���F�̂����P�F���u�O�a�v���Ă�����w���Ă��܂��B
�R���F�̂����P�F�ȏオ�O�a���Ă��܂��ƁA���̎O���F�̃o�����X�i�F���j���ێ��ł��Ȃ��Ȃ�܂�����A���x��Z�x�ł͂Ȃ��K����F���̂��̂ɂ܂ʼne����^���܂��B�i��F�Ԃ��K�N���F�O�a����Ȃǁj
�ł�����A�O�q�̃T���v���ɂ���ʂ�u���x���オ���ĔZ�x�������Ă�v�̂Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B
�����ԍ��F8750934
![]() 0�_
0�_
�Z�x�E�ʓx�Ɋւ��āu�@��ɂ�鉉�o������v�̂͑S���ے肵�܂���B
�܂��A�Z�x��ʓx���������ǂ��A�Ƃ��v���܂���B
�����A
>�ŁAG10�̂��̌X������f�ł����Ƃ���́u�O�a�v�Ȃ�ł���
>�`���[�g��r�̉摜�̐��u�O�a�v���ĂȂ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B
>���̗����͔���܂���ˁH
��̐��O�a����̂ƁA�`���[�g�̐��������ނ̂Ƃ͊֘A�͖����Ǝv���܂����B
�B�e�������S���قȂ�܂��̂ŁB
�A�L���Z����́u���̗����͔���܂���ˁH�v�̈Ӗ���݂͂��˂Ă��܂��B
�����ԍ��F8750962
![]() 0�_
0�_
�{�C�Ŏʐ^�p�ꎫ�T�Œ��ׂ����������ł���B
http://www.optronics.co.jp/lex/detail.php?id=8243
�����ԍ��F8750975
![]() 1�_
1�_
���Ȃ݂ɎO���F�iCMY�j�ł͂Ȃ��O�����iRGB�j�ł��B
�p��͂����������������琳�m�ɂ��Ă����������A��������܂ꂸ�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8751096
![]() 1�_
1�_
>���Ȃ݂ɎO���F�iCMY�j�ł͂Ȃ��O�����iRGB�j�ł��B
>�p��͂����������������琳�m�ɂ��Ă����������A��������܂ꂸ�����Ǝv���܂��B
�O�����Ƃ����\���͖w�Lj�ʓI�ł͂Ȃ��A�i���́j�O���F�Ƃ����\���̕����ǂ����Ǝv���܂����B
�i���ꂪ Additive light (three) primary color �ŁA three primary color �͎O���F�ł����A���̂ȂǂŌ������Ă��A���̎O���F��ĎO���F�Ƃ��ċL�q���Ă���T�C�g���������Ǝv���܂��j
Google �Łu�O�����v���������Ă��o�Ă��Ȃ��ł����ˁB
�܂��A�i���̎O���F�̂����j�����S�ɔ��ł����Ԃ��u���O�a���Ă���v�ƕ\�����Ă��S�����������Ƃ��R�����g���Ă����܂��B
�O�a�F�isaturated color�j�ł����A�����̐F�Ɗ�����l�Ԃ̎��m�o�̑����ł�����A�ނ���S���m�o�I�Ȃ��̂ł����āARGB �ł̕\����O��Ƃ����f�W�J���ł̋c�_�Ƃ͂�����ƃY�����w�E���Ǝv���̂ł����B
���̖O�a�F�͔��ɋ������g���̈�i�P��F�Ƃ������j�̃G�l���M�[�v���t�@�C�����������w���A RGB �ł̕\���͂ނ���s���ӂŁAXYZ �\�F�n�Ń}�C�i�X�̐Ԃ����݂���̂��A���̕ӂ肪�����ł��B
�i����� gintaro����̎w�E������ɂ��Ăł͂Ȃ��ł����j
�����ԍ��F8751174
![]() 0�_
0�_
���႟�����܂��ˁO�O
on the willow����ɋ������u�Ԃ��o�����F�O�a����v����
Red���F�O�a�������ʁAR�̒l���ő�ɂȂ�܂��̂�R�l�ɂ��K���\�����s�\�ɂȂ�܂��B
���̌��ʐ��܂��̂́ARed100%�̐F�\���ŁA�Ԃ��O�a����Ɛ�100���ɂȂ�A�Ƃ����܂��B
�����悤��
Blue���F�O�a�������ʁAB�̒l���ő�ɂȂ�܂��̂�B�l�ɂ��K���\�����s�\�ɂȂ�܂��B
���̌��ʐ��܂��̂́ABlue100%�̐F�\���ŁA���O�a����Ɛ�100���ɂȂ�A�Ƃ����܂��B
on the willow�����Ⴂ���Ă���̂�
���O�a���Đ��F�ƂȂ�A����ɖO�a����Ɣ��ɂȂ��Ă��܂��_��
�܂�͑S�̖��x���オ���Ă��邱�Ƃ������Ă��邾���Ȃ̂ł��B
�F���O�a������Δ��ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ͂���܂���B
�Ԃ��O�a�������Ĕ��ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��̂ł��B�������ł��B
����Ƃ��A�O�����iRGB�j��Blue�����A����Red�AGreen�ƈقȂ�F�̕ω�������Ƃ��v���ł����H
�����ԍ��F8751240
![]() 2�_
2�_
�܁A���̎O���F�ł������ł����ǂˁB
�����A�����f�菑�������u�O���F�v�Ə�����
�V�A���i���F�j�A�}�[���^�i�ԃs���N�j�A�C�G���[�i���邢���F�j�̎��ł����炲���ӂ��O�O
�����ԍ��F8751262
![]() 2�_
2�_
>���O�a���Đ��F�ƂȂ�A����ɖO�a����Ɣ��ɂȂ��Ă��܂��_��
>�܂�͑S�̖��x���オ���Ă��邱�Ƃ������Ă��邾���Ȃ̂ł��B
����́A�O�a�̌������I�o�i�ߑ��j�ɂ���Ƃ����_�����ẴR�����g�ł���ˁB
�����i���� gintaro������j�w�E���Ă���̂́A
�i���炩�̌����Łj�_�C�i�~�b�N�����W������ �܂��� AE ���I�o�ߑ��C�����̂ݖO�a����i���A�A�Ԃ͘I�o�ɍ��킹�Ė��邭�Ȃ�j�����F�ɂȂ�A
�Ƃ����_�ł���B
�����A�O���F�̂����P�F�ȏオ�O�a������Ԃ́A�K���͂������F�����Y���Ă���\����r���ł��܂���A�P���Ɂu���x���オ���ĔZ�x�������Ă�v�ł͂Ȃ��ł���ˁH
>�F���O�a������Δ��ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ͂���܂���B
�O���F�̑S�Ă��O�a������A�Ƃ����Ӗ��ł��B
>�����A�����f�菑�������u�O���F�v�Ə����ƃV�A���i���F�j�A�}�[���^�i�ԃs���N�j�A�C�G���[�i���邢���F�j�̎��ł����炲���ӂ��O�O
����A������ςł���B
���@���F�̎O���F�ł�����A�Е����u���̎O���F�v�Ə����Ȃ�A���߂āw�F�́x�O���F�Ə����Ȃ��ƁO�O
�Ƃ������ƂŁA���̃X���b�h�Ŏ������y���Ă���̂͌��̎O���F�ł��A�Ə����Ƃ��܂��B
�����ԍ��F8751315
![]() 0�_
0�_
�����͊ȒP�ŁA���F�i�V�A���j�����o���ɂ͐i�u���[�j�Ɨi�O���[���j�̌����K�v�Ȃ̂ł��B
�Ƃ������Ƃ́u�Ɨ��O�a�i100���j���č�����Ɛ��F�ɂȂ�v�͐������ł���
�u���O�a�i100���j����Ɛ��F�ɂȂ�v�͌��Ȃ̂ł��B
�̃��x�������グ�āi�O�a�����āj���F�ɂȂ�킯���Ȃ��̂ł��B
����͐F�����̊�{�ł�����A�ʐ^�W�̌f���ł͖�肪����Ƃ������Ƃł����������Ă��܂��B
�����ԍ��F8751368
![]() 2�_
2�_
���� RAW �ŎB�e���ꂽ�悤�ł��̂ŁA�ɒB�~�ꎁ�̂悤�� RAW �t�@�C������邩 SILKYPIX �őS���������邩�A���R���ɗ���ł݂���ǂ��ł����H
�n�[�h�E�F�A�ҁA�掿�ҁA�ɑ����āuRAW ���ؕҁv������Ă��ꂽ�肵�āB
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/11/06/9544.html
�����ԍ��F8751413
![]() 2�_
2�_
>�Ƃ������Ƃ́u�Ɨ��O�a�i100���j���č�����Ɛ��F�ɂȂ�v�͐������ł���
>�u���O�a�i100���j����Ɛ��F�ɂȂ�v�͌��Ȃ̂ł��B
>�̃��x�������グ�āi�O�a�����āj���F�ɂȂ�킯���Ȃ��̂ł��B
���́A�N���u�������x�����グ�āv�Ȃ�ăR�����g���Ă��܂����B
�ނ���A�O�a���邱�ƂŁA���ΓI�ɂ͎O���F�̂����������x�����������ł��B
>�i���炩�̌����Łj�_�C�i�~�b�N�����W������ �܂��� AE ���I�o�ߑ��C�����̂ݖO�a����i���A�A�Ԃ͘I�o�ɍ��킹�Ė��邭�Ȃ�j�����F�ɂȂ�A
�ƃR�����g���Ă��܂���ˁB
�����ԍ��F8751414
![]() 1�_
1�_
�ł�����A�匳�̘b���u���O�a����Ɛ��F�ɂȂ�v�Ƃ���gintaro����̘b�̐^�U�ɂ��Ăł���ˁH
������on the willow����
>�F�f�q�ւ̓��͂��O�a����ƁA���ΓI�ɐԁA�������Ȃ�A���̗l�Ȑ��F�ɋ߂��F�ɂȂ�܂��B
�Ə����Ă���킯�ł��B
�܂���������ŁA���O�a������ԂŁA�ԂƗ������Ȃ��Ă����ƁA���F�ɋ߂Â��Ă����܂��B
���F�ɂȂ�ɂ́A�Ɨ��O�a���Ȃ��Ă͂����܂���B�������Ԃ��O�a����O�ɁB
���Ԃ�t���J���[�̉摜��Photoshop�ȂǂŘA���I�ɘM�钆�Őg�ɂ����m�����Ƃ͎v���̂ł���
�F�ɂ��āu�O�a�v����ǂ��Ƃ��A���Ղɍl���E���������ł��B
�������Ƃ��Ⴄ��ʑ̂ł����u���O�a����ƃ}�[���^�ɂȂ�v�����������ƂɂȂ�܂��B
�����O�a������ɁA�Ԃ��O�a��������킯�ł���ˁH
�����Ȃ�Ƃ����A�Ȃ�ł��A���ł���ˁO�O
�Ƃ����킯�ŁA�t���X�P����8741333�ŋ��Ă邱�Ƃ��������̂ł��B
�F�͑S�ăo�����X�ł�����A���I�ɘb������̂Ȃ琳�m�ɕ\�����ׂ��ł��B
�u�F�f�q�ւ̓��͂��O�a����ƁA���ΓI�ɐԁA�������Ȃ�A�S�̖̂��x���オ��܂��B�v�Ƃ��B
�����ԍ��F8751449
![]() 1�_
1�_
����l�̋c�_�A���S���Ĕq�����Ă��܂����B
JPEG�o���̊G��@����ɂ��Ă���̂ŁAG10�̐��\�]�X�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤���A�T��on the willow���w�E����Ă���悤�ȃ_�C�i�~�b�N�����W��I�o�����̖��ɍs������������܂���B
�̘I�o�I�[�o�[�����łȂ��A��̊��炩�����C�ɂȂ�܂��B�U���U�����Ă��܂��B�ܘ_�A�m�C�Y��������Ί��炩�ɂȂ�̂ł����A��ȊO�̕����̉𑜓x�������܂��B�������m���āA������ۂ�����Ńm�C�Y�������Ċ��炩�ɂ���Ȃǂ̍H�v�͂ł��Ȃ����̂��Ǝv���܂��B
�����Y�͐V�����Ȃ�܂������A�F�������C�ɂȂ�܂��B������\�t�g�ŕ�\�ł��傤���A�J�������ŕ�ł���Ǝv���܂��B
�ꉞ�Adpreview�̃T���v���������N�����Ă��������܂��B
http://www.dpreview.com/reviews/canong10/page9.asp
G9��Highly�@Recommended�iOnly Just�j�ł������̂ɑ��AG10���ꃉ���N��������Recommended�ɂȂ����͎̂c�O�ł��B
JPEG�o���ł̘I�o��_�C�i�~�b�N�����W�����̉��P�A�F�����̕�A�����I�ȃm�C�Y�����Z�p�̊J���ȂǁA�X�Ȃ�i����]�݂܂��B
�����ԍ��F8751797
![]() 0�_
0�_
����
JPEG�o���̊G�[�[��JPEG�摜
�����ԍ��F8751803
![]() 0�_
0�_
�A�L���Z����
>���Ԃ�t���J���[�̉摜��Photoshop�ȂǂŘA���I�ɘM�钆�Őg�ɂ����m�����Ƃ͎v���̂ł���
>�F�ɂ��āu�O�a�v����ǂ��Ƃ��A���Ղɍl���E���������ł��B
���́[�A��̐F�́A����ԋ����A���ɗA�Ō�ɐԂƂ����F�̃o�����X�Ő��藧���Ă���̂́u��̐��v����鎞�ɂ͑O������ɂȂ�܂��B�܂��A���̓_�ɂ��Ă͓��Ɍ��y�͂��Ă��Ȃ����̂́A�ŏ��ɃA�b�v�����@[8749689] �ł̃q�X�g�O����������Ε���Ǝv���܂��B
�ł�����A
>�܂���������ŁA���O�a������ԂŁA�ԂƗ������Ȃ��Ă����ƁA���F�ɋ߂Â��Ă����܂��B
>���F�ɂȂ�ɂ́A�Ɨ��O�a���Ȃ��Ă͂����܂���B�������Ԃ��O�a����O�ɁB
���ł͂���܂���B�u��F�v�ł͐��O�a����Ǝ��ɋ������e�����AG10 �̍��̗l�ɐ��F�ɋ߂��Ȃ�܂��B
���X�ł����A�����ł́u��F�̈Ⴂ�v�ɂ��ĉ�b����Ă�����ł���ˁH
��ʑ̂��Ⴆ�Ή]�X���Ԉ���Ă͂��܂��A�����ł� G10 �Ƒ��@��̋�F�̈Ⴂ�ɂ��Ă���肳��Ă�����ł�����A�ނ��덬���������̂ł́H
�A�L���Z���ˑR�J���[�`���[�g�������o������A�����������O�a�����Đ��Ȃ�]�X�̘b�����n�߂����R���킩��܂���ł������A�ǂ����u��F�ɂ��Ęb�����Ă���v�O���������̂��ƒm���ď��X�r�b�N�����Ă��܂��B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�i���́j�O���F�̂����A�F���O�a����ƍ��̂悤�Ȑ��F�ɂȂ�܂��B�i�X�ɌJ��Ԃ��܂����A�L�����̃T���v���ʐ^�̐�̐F�ɂ��Č��y���Ă��܂��j�����āAG10 �̍��͈Ӑ}�I���ǂ����͕ʂƂ��āA���O�a���Ă��܂��B
����āA�X���傳�w�E���ꂽ�b��ɖ߂�܂����A
>��̔��F��������Ǝ₵���ȁ[�Ɗ�����̂ł����A���ۂ̂Ƃ���ǂ��Ȃ�ł��傤���H
>�����ǎ��̖ڂɂ͗�̃��r���[�ł�LX3��GX200������̂ق����O���f�[�V�����̖L�x����������
�̂́A���̕ӂ�Ɍ���������̂�������܂���ˁB
�����A���W���[�i���ꂳ������Ă���悤�ɁA
>JPEG�o���̊G��@����ɂ��Ă���̂ŁAG10�̐��\�]�X�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤���A
���ɂ����l���̕����ARAW ������ JPEG �o���ł͋�̕\�����Ⴄ�_�͎w�E����Ă��܂��B
�����������ƁARAW �ł͐� JPEG �قǖO�a���Ă��炸�AJPEG �ł̊G���̓R���g���X�g�����߂邽�߁A���������J�b�g����O�a���Ă���l�ɂ������܂��B
�����ԍ��F8752912
![]() 0�_
0�_
�O�a�ƌ����Ă��A���͎��A�o�͎��̓�ʂ肠��܂��B
������̏ꍇ�ɂ���A���ꂾ���̍ޗ�����O�a�肷�邱�Ƃ͂ł��܂��E�E�E�B
�Ƃ͌������̂́A�f�W�J���D���Ȑl�X�̊ԂŁu�������͖O�a���Ă���v�Ƃ�������b�͓��풃�тł�������� G10 �̋�̐F�Ȃ��̓T�^��ł��̂ŁA�u���̋O�a���Ă��邩�ǂ����͂킩��Ȃ��v�Ɨ͐����邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���܂��B
���ہA�V�A���ɂȂ�Ƃ����u���ہv�������āu�O�a���Ă���v�Ƃ����������͂悭����܂����Agintaro���� �ɂ��Ă�����̂��肫����̉�b�Ƃ��Ĕ��������������Ǝv���܂��B
����Ȍ��I�����ċc�_����قǂ̂��Ƃł��Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F8753120
![]() 0�_
0�_
�ł�����A���x�������悤��
�u�iBlue�j���F�O�a����Ɛ��F�ɂȂ�v�ƌ����Ă͂����Ȃ��̂ł����āO�O�G
��̐F�͏�����Blue�����ŏo���Ă͂��炸�AGreen���������Ă���̂�
�u���ꂼ��̐F�v���O�a�������ʐ��F�ɂȂ�܂��B
�܂�u��̐F���iBlue�j�v�Ƃ��Đ��I�Șb�����Ă͂����Ȃ��̂ł��B
�Ⴆ�A�X�J�C�u���[�ƃR�o���g�u���[�ł͍\��������̃o�����X���傫���قȂ�܂�
�R�o���g�u���[���ƖO�a���Ă����ΐ��F�ł͂Ȃ��}�[���^�ɂȂ�܂��B
��Green���Red�̍\�������������̂ŁB
�^�Ă̋�̓R�o���g�n�ɂȂ�₷���̂ŁA���R�O�a���Ă��E�E�E�ł��B
����͐F������Έ�ڗđR�ȐF�̊�{�ł��B
�����ԍ��F8754207
![]() 1�_
1�_
�܂��A��̐F�͐F�X����܂��B�[�Ă��⒩�Ă��͐Ԃ���ԋ����ł����A�Ԃ���ɃO���f�[�V��������ꍇ������܂��B
�������A���x�������܂����A����̋�F�̈Ⴂ�ɂ��ẮA
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/12/04/9765.html
�ł̃T���v���ɂ���AG10 �Ƃ��̑��̋@��̋�F�̈Ⴂ�ɂ��Ęb�����Ă����ł���ˁB
�����ė[�Ă���̘b�����Ă����ł͂Ȃ��̂́A�F�����Ă���ł��傤�B
�܂��A
>��̐F�͏�����Blue�����ŏo���Ă͂��炸�AGreen���������Ă���̂�
>�u���ꂼ��̐F�v���O�a�������ʐ��F�ɂȂ�܂��B
�Ƃ̂��Ƃł����AG10 �̉摜������Δ���ʂ�A�u�����v���O�a������Ԃł��A���ΓI�ɗ��\�������Ȃ�A���ɂ���l�Ȑ��F�ɂȂ�܂��B�z���␄���ł͂Ȃ��A��Ⴊ����A�q�X�g�O�������A�b�v����A�u���F�v�ƕ\�����Ă���̂��ǂ̕��������}�����Ă��܂�����A��ڗđR�ł���ˁB
>�Ⴆ�A�X�J�C�u���[�ƃR�o���g�u���[�ł͍\��������̃o�����X���傫���قȂ�܂�
>�R�o���g�u���[���ƖO�a���Ă����ΐ��F�ł͂Ȃ��}�[���^�ɂȂ�܂��B
>��Green���Red�̍\�������������̂ŁB
�R�o���g�u���[�Ƃ͂ǂ�ȐF���A�����Ƃ��܂��B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC
��̓I�ɂ͂����Ɍf�ڂ���Ă��܂��B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E5%90%8D%E4%B8%80%E8%A6%A7_(%E3%81%93)
�X�ɂ����P��
http://lucky-colors.com/jis-foreign/cobalt-blue/
���Ă̒ʂ�AJIS �ŋK�肳��Ă���R�o���g�u���[�͐ɗ����������F�ł���A�Ԑ������u����܂���v
�����ԍ��F8763983
![]() 1�_
1�_
�͂͂́A�z���g�ł��ˁO�O
�ł������g�œ����������Ă��܂���ˁB
���R�o���g�u���[�͐ɗ����������F�ł���A�Ԑ������u����܂���
�܂�Ɨ�����������ނ̐n���A�A�̏��ɖO�a���āA���F�ɂȂ�A�Ɓi�j
���ʂɗ[�Ă��Ƃ������Ă܂���O�O
����͐Ɨ̌���������Ɛ��F�i�V�A���j�ɂȂ邩��Ƃ����P���ȗ����ł��B
�ƐԂ̌���������ΐԓ��i�}�[���^�j�A�ԂƗ̌���������Δ����F�i�C�G���[�j�ɂȂ�܂��B
�܂�́A�O�a���Ă��������Ԃ����̖��ł��B
�̉�f���O�a������ɁA�̉�f���O�a��������A���킹�Z�Ő��F�ɂȂ��������ł���ˁH
����������A�������O�a���Ă����F�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
����́A�Ԃ������O�a���Ă��ԓ��ɂȂ�Ȃ�������A�������O�a���Ă������F�ɂȂ�Ȃ��̂Ɠ������Ƃł��B
�O���̂悤�Ƀq�X�g�O�����q�X�g�O�������܂���
�J���[�o�����X�����Ă���摜�u�S�́v��O�a�����āA�P�F�̖O�a���ǂ��������������ςł��B
���F�̉摜���ƖO�a�����Ă��Ȃ̂ɁA���O�a����Ɛ��F�ɂȂ�Ƃ����̂͂��������ł��傤�H
�����F�́u����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
��发�ǂ߂Έꔭ�ŏo�Ă���b�Ȃ�ł����ǂˁE�E�E
�����ԍ��F8765220
![]() 1�_
1�_
���������Ȃ��Ă��܂����i�܁j
>�܂�Ɨ�����������ނ̐n���A�A�̏��ɖO�a���āA���F�ɂȂ�A�Ɓi�j
������čŏ�������̘b�ł���B
�ŏ�������T���v���̋�F�̘b�����Ă��܂���ˁH�I
�T���v���̋�F�́u�A�A�ԁv�����������F�ŁA���̏��̖��邳�ō\������Ă���u�����v���AG10 �̋�F���A�O���F�̂������O�a���Đ��F�ɂȂ��Ă���Ƃ����u�����v���A�S�čŏ���[8749689]�ɋ������Ă��܂��B
���x�����x�������܂����A���`�`�`�`����u�������O�a����Ɛ��F�ɂȂ�v�Ȃ�Ęb�����Ă��܂�����āB
>�܂�́A�O�a���Ă��������Ԃ����̖��ł��B
>�̉�f���O�a������ɁA�̉�f���O�a��������A���킹�Z�Ő��F�ɂȂ��������ł���ˁH
�ł�����A�u��F�v���O�a����Ȃ�A���R���̏��ԂŖO�a�����ł����ĂB
�������A�q�X�g�O����������킩��悤�ɁA�͖O�a�u���Ă��Ȃ��v��ł����ĂI�I�I
>�J���[�o�����X�����Ă���摜�u�S�́v��O�a�����āA�P�F�̖O�a���ǂ��������������ςł��B
���́[�A�u��F�v�̎O���F�̍\��������ɂ̓q�X�g�O�������������ł����c
�������A�J���[�o�����X�����Ă���āH�I�c���
���̎O���F�̓o�����X����ꂽ�疳�ʐF�i�F�����j�ɂ����Ȃ�܂���c
���ǁAgintaro��������Ă���
>�P�g�ڂ̉摜��G10�̋�͎v������O�a���Ă܂��B
�̈Ӗ����S���ʂ��Ă��Ȃ������A�Ƃ������Ƃł��ˁB
�\����Ȃ��ł����A���ǁA�O�a�Ƃ��A�q�X�g�O�����Ƃ��A��������������̎O���F���̂��̂̈Ӗ����킩���Ă�������Ȃ���Ȃ��ł����H
�Ƃ������A
>�Ⴆ�A�X�J�C�u���[�ƃR�o���g�u���[�ł͍\��������̃o�����X���傫���قȂ�܂�
>�R�o���g�u���[���ƖO�a���Ă����ΐ��F�ł͂Ȃ��}�[���^�ɂȂ�܂��B
>��Green���Red�̍\�������������̂ŁB
�͂ǂ��Ȃ����̂ł��傤���B���Ԃ������R�o���g�u���[�H
�i����A�ԈႢ��������ԈႢ�ł����ł��B�ǂ��܂ł��`����Ă��Ȃ��������Ƃɂ�����ƍ��܊����j
��������A�O�������āA���̎O���F�̒�����Ȃ�ł����Ăˁc
�����ԍ��F8765470
![]() 1�_
1�_
����₷���悤�ɒ������Ă����܂�
>���x�����x�������܂����A���`�`�`�`����u�Ԃ�����āA������������O�a����Ɛ��F�ɂȂ�v�Ȃ�Ęb�����Ă��܂�����āB
�����ԍ��F8765502
![]() 1�_
1�_
���������čŏ����玩���̃��X��ǂނƗǂ��ł���O�O
�����ԍ��F8765541
![]() 1�_
1�_
�ł͐������ăR�����g���܂��傤�B
���[�́A���ǁAgintaro��������Ă���
>�P�g�ڂ̉摜��G10�̋�͎v������O�a���Ă܂��B[8740435]
����n�܂��Ă��܂��B�����⑫����`�� [8749689] �ɂ�2�摜�̃q�X�g�O�������f�ڂ��Ă��܂��B��������A
�E��F�́A�A�A�ԁA�̏��̋����̎O���F�ō\������Ă��邱��
�EGX200 �͎O���F�̂ǂ���O�a���Ă��Ȃ��̂ɑ��AG10 �̂���͐��O�a���Ă��邱��
�EGX200 �ɔ�� G10 �ł͐��O�a���邱�ƂŐF�����Y���A���F�ɂȂ��Ă��邱��
���w�E���Ă��܂��B
���̌�A�O�a�F���ǂ��̂Ƃ��A�F�̎O���F���O�����ƌĂԂׂ����A�Ƃ����R�����g�������܂����A����͒u���Ƃ��āA�����ŋ߂̃A�L���Z����̎w�E������ƁA
>�u�iBlue�j���F�O�a����Ɛ��F�ɂȂ�v�ƌ����Ă͂����Ȃ��̂ł����āO�O�G
>��̐F�͏�����Blue�����ŏo���Ă͂��炸�AGreen���������Ă���̂�
>�u���ꂼ��̐F�v���O�a�������ʐ��F�ɂȂ�܂��B
��̐F�͏�����Blue�����ŏo���Ă��Ȃ��A�Ƃ����w�E�̓Y���Ă��܂��Bgintaro����⎄�͂������A���̕����T���v���́u��F�v�͏����Ȑ����ł͂Ȃ��A�Ƃ����͔̂F�����Ă��܂����A�����O��ɘb�����Ă��܂��B
���̍ŏ��̃��X[8749689]�̃q�X�g�O�����ł����m�ł����A������[8752912]�ł�
>��̐F�́A����ԋ����A���ɗA�Ō�ɐԂƂ����F�̃o�����X�Ő��藧���Ă���̂́u��̐��v����鎞�ɂ͑O������ɂȂ�܂��B
�ƃR�����g���Ă��܂��B
�X�ɁA�uGreen���������Ă���̂Łu���ꂼ��̐F�v���O�a�������ʐ��F�ɂȂ�܂��B�v�Ƃ̎w�E�ł����A[8749689]�̃q�X�g�O����������Ε�����Ƃ���A�O�a���Ă���̂͐����ŁA�͖O�a���Ă��܂���B�������AG10 �̋�F�͐��F�ɂȂ��Ă��܂��B
����́A�͖O�a���Ă��Ȃ����A���O�a����܂Ŗ��邢�ƁA���ΓI�ɗ�Ԃ������Ȃ邽�߂ł��B
>�܂�u��̐F���iBlue�j�v�Ƃ��Đ��I�Șb�����Ă͂����Ȃ��̂ł��B
>�Ⴆ�A�X�J�C�u���[�ƃR�o���g�u���[�ł͍\��������̃o�����X���傫���قȂ�܂�
>�R�o���g�u���[���ƖO�a���Ă����ΐ��F�ł͂Ȃ��}�[���^�ɂȂ�܂��B
>��Green���Red�̍\�������������̂ŁB
���ɏ������悤�ɁA�u��̐F���iBlue�j�v�Ƃ����O��Řb�����Ă���̂́A�A�L���Z�����ł��B�i[8751368]�̎w�E�������悤�ɃY���Ă��܂��B�j
�܂��A���x�[�X�ŗ��Ԃ������F�ł́A���O�a����Ɛ��F�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����w�E�͊m���ł����A�R�o���g�u���[�͗��Ԃ������F�ł͂���܂���B
>����������A�������O�a���Ă����F�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B
G10 �̉摜�ŖO�a���Ă���̂͐����ł��B
>����́A�Ԃ������O�a���Ă��ԓ��ɂȂ�Ȃ�������A�������O�a���Ă������F�ɂȂ�Ȃ��̂Ɠ������Ƃł��B
�O���F�̘b�����Ă���̂ł�����A�u�Ԃ�����āA����������̋��x��ω�������v�悤�Șb�͒N�����Ă��܂���B�����Řb�����Ă���̂́A
>�F���O�a����ƁA���ΓI�ɐԁA�������Ȃ�A���̗l�Ȑ��F�ɋ߂��F�ɂȂ�܂��B
�Ƃ������Ƃł��B
>�O���̂悤�Ƀq�X�g�O�����q�X�g�O�������܂���
>�J���[�o�����X�����Ă���摜�u�S�́v��O�a�����āA�P�F�̖O�a���ǂ��������������ςł��B
�Ӗ��s���ł��B�J���[�o�����X�����Ă���摜�Ƃ͉����w���Ă���̂ł��傤���B�܂��A�P�F�̖O�a�Ƃ͐F�̖O�a���w���Ă���̂��Ǝv���܂����A���x�������Ă���悤�ɁA��F�͐����ł͂��A�ԁA�����������F�ł��B���̎O���F�̂����A�F���O�a������ԁA�Ƃ������Ƃł��B
>���F�̉摜���ƖO�a�����Ă��Ȃ̂ɁA���O�a����Ɛ��F�ɂȂ�Ƃ����̂͂��������ł��傤�H
>�����F�́u����Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
>��发�ǂ߂Έꔭ�ŏo�Ă���b�Ȃ�ł����ǂˁE�E�E
���F�̘b�����Ă���̂́A�A�L���Z�������ƁB
�܂��A�����͐�发��ǂނ悤�Șb�ł͂Ȃ��A���发�ł��c
�ȏォ��A�A�L���Z����́A
�Egintaro����̐��O�a���Ă���A�Ƃ����w�E���u��F���������邷���A�O���F�̂����A���O�a������ԁv�Ƃ����̂𗝉����Ă��Ȃ�
�E�ǂ����q�X�g�O�����𗝉����Ă��Ȃ�
�E�R�o���g�u���[��Ԃ���苭���Ƃ��A�O�a�F�i�P��F�j����Ă���
�E�O���F�̖̐O�a���u�P�F�̖O�a���ǂ��������������ςł��B�v�ȂǂƎw�E���Ă���
�Ȃǂ���A
>�\����Ȃ��ł����A���ǁA�O�a�Ƃ��A�q�X�g�O�����Ƃ��A��������������̎O���F���̂��̂̈Ӗ����킩���Ă�������Ȃ���Ȃ��ł����H
�Ƃ����^�O�Ɏ���܂����B
�����ԍ��F8766381
![]() 2�_
2�_
���O�a���Ă����ԂŁA�Ԃ�����ΓI�Ƀ��x�����オ�����̂ł���A�q�X�g�O������ł����ꂪ����܂��ˁH
�����ʂ͂��������̂�I�o���オ�����Ƃ����܂����B
������f�ւ̓��͒i�K�Ő��ɒ[�ɖO�a�����̂ł����
��f���x����RGB���ꂼ��̊��x�ɂ�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�q�X�g�O������Ő̃��x���������A�Ԃ�̃��x�����ʏ�ł���ꍇ��
��ʓI�Ɍ��������̐F���ł������Ƃ������Ƃł��B
�������̐F�������Ȃ�̂������X������A���@��ł�
�̘I�o���x���������A�ʓx���m�ہi��j����X��������A�Ƃ����b�ł���ˁH
G10�͔�r�I�̕�������Ȃ��̂Ō����܂܂ɂȂ��Ă���A�ƁB
���R�A���̕��̉摜�̃q�X�g�O�������݂��
�������ԁi�������Z�x���m�ۂ���Ă���j�ɂȂ��Ă���Ƃ͎v���܂��H
�r���ňӌ����ꂽ������������Ⴂ�܂����A���̊m�F��
RAW�f�[�^�ꌻ���\�t�g�œ���p�����[�^�ŏ������Ȃ��Ɗm�F�ł��Ȃ��͂��Ȃ̂ł��B
���ꂪ�A����JPEG�摜��r�Œf���ł��鍪�����m�肽���ȁA�ƁO�O
>�\����Ȃ��ł����A���ǁA�O�a�Ƃ��A�q�X�g�O�����Ƃ��A��������������̎O���F���̂��̂̈Ӗ����킩���Ă�������Ȃ���Ȃ��ł����H
�Ƃ������Ƃł��\���܂���̂ŁA����O�O
���l�̎��ۂ̐E�̕]�����Aon the willow����̕]���ɉe��������ł�����܂��B
�����ԍ��F8769135
![]() 1�_
1�_
�A�L���Z����
>���O�a���Ă����ԂŁA�Ԃ�����ΓI�Ƀ��x�����オ�����̂ł���A�q�X�g�O������ł����ꂪ����܂��ˁH
����Ă��܂���B
>�����ʂ͂��������̂�I�o���オ�����Ƃ����܂����B
�F���O�a������Ԃ͐F�����ς�鋰�ꂪ���邽�߁A�P���Ɂu�I�o���オ�����v�̂Ɠ����ł͂���܂���B
�������I�o�ߑ����O�a�̌����̂P�Ƃ��čl�����邱�Ƃ́A���͊��Ɂu���x���v�R�����g���Ă��܂��B
�@���i���炩�̌����Łj�_�C�i�~�b�N�����W������
�@���܂��� AE ���I�o�ߑ��C�����̂ݖO�a����
�@���i���A�A�Ԃ͘I�o�ɍ��킹�Ė��邭�Ȃ�j�����F�ɂȂ�A
>������f�ւ̓��͒i�K�Ő��ɒ[�ɖO�a�����̂ł����
>��f���x����RGB���ꂼ��̊��x�ɂ�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�����ł͂���܂���B
�O�a�Ɏ���𗝉����Ă��������Ă��Ȃ��悤�ł��B
�����͒i�K�ŖO�a�����Ɖ��肵�Ă��A���̌����͒P���ɘI�o�ߑ��A�������͋ɏ���f���ɂ���f������̃_�C�i�~�b�N�����W���Ⴂ�ꍇ�ł��������܂��B
���ꂪ�������ƒf�肵�Ă��܂��A�\���Ƃ��Ĕے�����Ă��܂���B[8750548]
��f���x����RGB���ꂼ��̊��x�ɂ�������邱�Ƃɂ͌��т��܂���B
>�q�X�g�O������Ő̃��x���������A�Ԃ�̃��x�����ʏ�ł���ꍇ��
>��ʓI�Ɍ��������̐F���ł������Ƃ������Ƃł��B
���R�ł��B���ꂪ�u��F�v�ł�����B
�������A���O�a���Ă���ꍇ�́A���̂��ꂼ��̃��x������͂̒ʂ�\���ł��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�F���̕ω��Ƃ��Č���܂��B
>�������̐F�������Ȃ�̂������X������A���@��ł�
>�̘I�o���x���������A�ʓx���m�ہi��j����X��������A�Ƃ����b�ł���ˁH
�S���Ⴂ�܂��B
��͂��f�̖O�a�Ƃ����Ӗ��A�����Ă��̉ߒ��𗝉����Ă��������Ă��Ȃ��悤�ł��B
�J�����͐����̘I�o��������@�\�������Ă��܂���B
�܂��A�摜�����ŐF�����ɂ��Ă��A�O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ė{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
>G10�͔�r�I�̕�������Ȃ��̂Ō����܂܂ɂȂ��Ă���A�ƁB
�S���Ⴂ�܂��B
�̖��x���グ���������Ȃ�A[8750781]�Ő��������Ƃ����O�a������K�v�͂���܂��A�O���f�[�V�������s���R�ɂȂ�A�K���������A�ȂǖO�a���Ă��܂��f�����b�g�͑�������܂��B
���͒i�K�ŖO�a���Ă��Ȃ��Ƃ�����A�ނ���R���g���X�g���グ���𑽂����������߂Ƀn�C���C�g���J�b�g����Ă��܂����ƌ���ׂ��ł��傤�B
>���R�A���̕��̉摜�̃q�X�g�O�������݂��
>�������ԁi�������Z�x���m�ۂ���Ă���j�ɂȂ��Ă���Ƃ͎v���܂��H
���ɐ��������Ƃ���A���̎咣�ɂ͖���������܂��B
>�r���ňӌ����ꂽ������������Ⴂ�܂����A���̊m�F��
>RAW�f�[�^�ꌻ���\�t�g�œ���p�����[�^�ŏ������Ȃ��Ɗm�F�ł��Ȃ��͂��Ȃ̂ł��B
>���ꂪ�A����JPEG�摜��r�Œf���ł��鍪�����m�肽���ȁA�ƁO�O
���x�������Ă��܂����A���̋L���̃T���v���摜�ɂ��ĊF����b�����Ă����ł���B
���̃T���v���摜�ɂ��Đ��O�a���Ă���Ƃ��������͕ς��悤������܂��A���F�ɂȂ��Ă���Ƃ����������ς����܂���B
���̌����ɂ��Ă͊F���ꂼ��\���������Ă��邾���ŁA�N�������f�����Ă��܂����BRAW �Ƃ̕\���i�G���j�Ƃ̈Ⴂ�ɂ��ẮA����[8752912]�Ō��y���Ă��܂��B
>�\����Ȃ��ł����A���ǁA�O�a�Ƃ��A�q�X�g�O�����Ƃ��A��������������̎O���F���̂��̂̈Ӗ����킩���Ă�������Ȃ���Ȃ��ł����H
>�Ƃ������Ƃł��\���܂���̂ŁA����O�O
�������R�����g�ŁA���̎v���͈�w�����Ȃ�܂����B
>���l�̎��ۂ̐E�̕]�����Aon the willow����̕]���ɉe��������ł�����܂��B
���̓A�L���Z����̐E�̕]���͂��Ă��܂��A�ł��闧��ł�����܂���B
�O�a�Ƃ��A�q�X�g�O�����Ƃ��A���̎O���F�Ȃm��Ȃ��Ă��S�����̂Ȃ��E��͑�R����܂�����B
�����ԍ��F8770112
![]() 1�_
1�_
�c�O�Ȃ���A�J�����͐t�߂̃��x��������@�\�����Ă���̂ł��B
�����āA�̐F�������摜�ɂ́A��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�X��������܂��B
�Ɨō\�����ꂽ��̐F�ɐԂ݂������Ă��܂��Ă���T���v���摜�̋@��͂ǂ�Ƃǂ�ł��傤�H
�ŏ����画���Ă����ƂȂ�ł����ǂˁA�ǂ����邩�ق��Ă܂����i�j�O�O
G10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă邾���ł��B
JPEG��8bit�摜��Ŕ������ł��邩��Ƃ����āA��f����ǂݎ��Hi-bit�摜�ł����ł�킯�ł͂Ȃ��ł����ˁO�O
���Ȃ݂Ƀ_�C�i�~�b�N�����W400���Ƃ����̂��A���ۂɂ͂���܂���O�O
Hi-bit�摜����C�ӂ̕����̊K����⊮���āA�n�C���C�g���ƃV���h�E�������Ă邾���ł�����B
�����甒�܂ł�100���Ƃ��Đ�o�����ꍇ��
4�{�̊K���͂��肦�Ă��A4�{�̃_�C�i�~�b�N�����W�͑��݂��Ȃ��̂ł��B
�����ԍ��F8770197
![]() 1�_
1�_
�A�L���Z����
>�c�O�Ȃ���A�J�����͐t�߂̃��x��������@�\�����Ă���̂ł��B
�p��͐��m�ɁA�ƃR�����g����Ă����̂̓A�L���Z����ł���ˁB
�A�L���Z����̍ŏ��̃R�����g�́A
>�̘I�o���x���������A�ʓx���m�ہi��j����X��������A�Ƃ����b�ł���ˁH
�ł����B
�I�o�̈Ӗ��́A
http://www.smalldisney.com/words/photo/rosyutsu.html
>�t�B������B���f�q�iCCD�ACMOS���j�Ɍ��Ă邱�Ƃ������B
�Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�d�q�V���b�^�[�ł����Ă��A�����Ɨ����ĘI�o���R���g���[������@�\�� G10 �͂������ALX3 �ɂ� GX200 �ɂ�����܂���B
���́u�t�߂̃��x�����v�ƌ��t��ς��Ă��܂��ˁB
���x���̕�͉摜�����łł��܂��̂ŁA
>�܂��A�摜�����ŐF�����ɂ��Ă��A�O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ė{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
�Ɗ��ɃR�����g���Ă��܂��B
>�����āA�̐F�������摜�ɂ́A��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�X��������܂��B
>�Ɨō\�����ꂽ��̐F�ɐԂ݂������Ă��܂��Ă���T���v���摜�̋@��͂ǂ�Ƃǂ�ł��傤�H
������ꍇ�ɋ�F�ɐԂ������o��X�����o�錴���̑����̓z���C�g�o�����X�̖��ł��B
����� G10 �̋�F�̐O�a�Ƃ͊W������܂���B
>�ŏ����画���Ă����ƂȂ�ł����ǂˁA�ǂ����邩�ق��Ă܂����i�j�O�O
�Ƃ������ƂŁA�c�O�Ȃ��獡�������ĂȂ��ł���O�O
>G10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă�>�����ł��B
���̋@�킪�F��������Ă��Ȃ��Ƃ͌����܂���B
�������AG10 �̖̐O�a�Ƃ͕ʂ̖��ł��B
G10 �̕���キ���@��̕�������Ƃ����̂́A���ɏ������ʂ薳��������܂��B
>JPEG��8bit�摜��Ŕ������ł��邩��Ƃ����āA��f����ǂݎ��Hi-bit�摜�ł����ł�킯�ł͂Ȃ��ł����ˁO�O
���̉�f�f�[�^���O�a���Ă��邩�ǂ����܂ł͒N���f�����Ă��܂���B
�t�ɁA���̉�f�f�[�^���O�a���Ă��Ȃ��A�ƒf���ł���f�[�^������܂���B
>���Ȃ݂Ƀ_�C�i�~�b�N�����W400���Ƃ����̂��A���ۂɂ͂���܂���O�O
>Hi-bit�摜����C�ӂ̕����̊K����⊮���āA�n�C���C�g���ƃV���h�E�������Ă邾���ł�����B
>�����甒�܂ł�100���Ƃ��Đ�o�����ꍇ��
>4�{�̊K���͂��肦�Ă��A4�{�̃_�C�i�~�b�N�����W�͑��݂��Ȃ��̂ł��B
�������ŏ�����Ă���Ӗ��͗�������Ă���̂ł��傤���c
�uHi-bit�摜����C�ӂ̕����̊K����⊮���āA�n�C���C�g���ƃV���h�E�������Ă邾���ł�����B�v�Ƃ̂��Ƃł����A�C�ӂ̕����Ƃ��A�⊮�Ƃ��Ӗ��͂킩���Ďg���Ă�������Ⴂ�܂����H
�_�C�i�~�b�N�����W���g�傷���@�̐������s���m�ł����A4�{�̃_�C�i�~�b�N�����W�����݂��Ȃ��Ƃ����咣�̍����Ɏ����Ă͑S���̈Ӗ��s���ł��B�����ɂȂ��Ă��܂���B
�܂��́A�O�a����A�Ƃ����Ӗ��𗝉�����Ȃ��ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��Ă����Ȃ��Ǝv���܂���B
�����ԍ��F8770306
![]() 0�_
0�_
���[��B
RAW�����\�t�g�Łu�I�o�v�Ƃ����p�����[�^�[�����邱�Ƃ��������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ł���ˁH
����ƃJ�������ŐF����������ʂł���������JPEG�摜��Photoshop�ȂǂŊJ���ăq�X�g�O�����������ꍇ��
�q�X�g�O����������ꂽ��ԂŌ����邱�Ƃ̃h�R�ɖ���������̂������ł��܂���B
���q�X�g�O�����Ƃ́A���̉摜�̌�����������̂ł�����B
�����āA�F�O�a���Ă�悤�Ɍ����Ă���̂�8bit�ɏ����o���ꂽ�摜��
RAW�i�K�ł̓n�C���C�g�������m�ۂ���Ă�A�Ƃ����̂�����������Ƃ����̂ł��ˁH
���R��f���x���ŖO�a���Ă����
�J��������JPEG�ݒ�ŃR���g���X�g�������Ă��u�O�a�����F���v�ɂȂ�͂��ł���
���ۂɂ͂����Ȃ�Ȃ��̂ł��B
����Ꮡ���o���ꂽ8bit�摜������ɘM���ĕ���悤�Ƃ���Ζ������o�܂����B
�����AWB�ŐԂ݂��������ꍇ�A��̑��̑S�Ă̐F���Ԃ݂�����܂���B
���z���C�g�o�����X�Ƃ����̂͂����������̂ł�����B
���ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ����̂̓��`���[�h�͈̔͂ł͂Ȃ��ł���B
������摜�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ɖ�f���x���ł̓d���̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃł͈Ӗ����ς��܂��B
�����ԍ��F8770657
![]() 1�_
1�_
�ŏ�����u�o�͂܂ł̒i�K�Ő����ł���v�Ƃ����b�ł���B
�����ԍ��F8770730
![]() 0�_
0�_
���ŏ�����u�o�͂܂ł̒i�K�Ő����ł���v�Ƃ����b�ł���B
�ŁA�ŏ�����A���ꂪ���ۂ̖��x�������낤�Ƃ����Ă��ł���B
����̐F���^���ɂłĂ��Ȃ��������Ă��Ƃł��B�H�̉��₩�Ȍߌ�2���ł�����B
�����ԍ��F8770915
![]() 1�_
1�_
�����玸�炵�܂��A���߂܂��āB
���͍���G10���w������\��̌�G9���[�U�[�ł��B
�v����Ɂc
�{���́u�B�e�ΏۂƂȂ�����v�̐F������Ȃ��ȏ�́A�e�@�̃T���v���̂ǂꂪ�������Č������Ă���̂����f�s�\��
�G�߂��l�������G10�̋�̐F�����m�ŁA���@��͕�Łu�����ɂ���炵����v�̐F�ɂ��Ă���\��������B
�������A�ႦG10�̋�̐F�����m�ł��u�����ڂ��l��������v�̐F�Ƃ��Ă͑�������肷�銴������B
���Ď��ł��傤���H�X���I�ɂ́B
�����ԍ��F8771328
![]() 0�_
0�_
�܂�܂����������Ƃł��B
8bit�����o���̐F�����S�ĂȂ�ARAW�摜���猻�����邱�Ƃ̃����b�g�Ȃǔ������܂��B
�ʏ�̓J�������̊ȈՌ����ݒ�i�I�o���܂ށj��JPEG���L�^���Ă���킯�ł�����B
�����ԍ��F8771619
![]() 1�_
1�_
>�G�߂��l�������G10�̋�̐F�����m�ŁA���@��͕�Łu�����ɂ���炵����v�̐F�ɂ��Ă���\��������B
>�������A�ႦG10�̋�̐F�����m�ł��u�����ڂ��l��������v�̐F�Ƃ��Ă͑�������肷�銴������B
����Ă��Ȃ��ق��͖O�a���ĊK���������A��������͖O�a�����K�����c��A�Ƃ����̂͏펯�I�ɂ���܂���B���ɖ����̂���������Ǝv���܂��B
�����A�f�W�J���͂��������l�Ԃ̖ڂ��������ƃ_�C�i�~�b�N�����W�������ł�����A�����ځ�CCD �̓��́A�ł�����܂���B�ł�����A���̏������ł͂��܂��ܖO�a���Ă��܂��� G10 �̐�̂ق��������ڂɂ��߂������A�Ƃ������Ƃ��l�����܂��B[8740435]
���� RAW �ł͖͐O�a�����A�K�����c���Ă���̂ł���AJPEG �ɂ����Ƃ��Ƀn�C���C�g���̂ĂĂ��܂��Ă���Ƃ������Ƃł��ˁB����͂���Ŏc�O�ł��B��F�̖��x���グ��ɂ��Ă��A�O�a�����Ƃ��i���K�������킸�Ɂj���x���グ�邱�Ƃ͏\���ł��܂�����B[8750781]
�����ԍ��F8772938
![]() 0�_
0�_
>RAW�����\�t�g�Łu�I�o�v�Ƃ����p�����[�^�[�����邱�Ƃ��������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ł���ˁH
�m���Ă��܂���B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%B2%E5%87%BA_(%E5%86%99%E7%9C%9F)
>�ʐ^�Z�p�ɂ����ĘI�o�Ȃ����͘I���Ƃ́A�t�B�����⊣�Ȃǂ̊����ޗ���ACCD�C���[�W�Z���T�Ȃǂ̌ő̎B���f�q�����ɂ��炷���Ƃł���B
RAW�����\�t�g�ł͐��Ɂu�I�o�v���V�~�����[�g���Ă��܂��ˁB
���ꂪ�����H
>����ƃJ�������ŐF����������ʂł���������JPEG�摜��Photoshop�ȂǂŊJ���ăq�X�g�O�����������ꍇ��
>�q�X�g�O����������ꂽ��ԂŌ����邱�Ƃ̃h�R�ɖ���������̂������ł��܂���B
�O�a�Ƃ������t�̈Ӗ��ƃf�����b�g�������邱�Ƃ��������߂��܂��B
>�����āA�F�O�a���Ă�悤�Ɍ����Ă���̂�8bit�ɏ����o���ꂽ�摜��
>RAW�i�K�ł̓n�C���C�g�������m�ۂ���Ă�A�Ƃ����̂�����������Ƃ����̂ł��ˁH
�����ł͌��̃T�C�g�̃T���v���摜�ɂ��Č���Ă��܂��B�i�����������낤�H���̌��t�j
���̃T�C�g�̃T���v���摜�ɂ��āARAW �ł̓n�C���C�g�������m�ۂ���Ă���ƒf���ł��鍪����������Љ�肢�܂��B
>���R��f���x���ŖO�a���Ă����
>�J��������JPEG�ݒ�ŃR���g���X�g�������Ă��u�O�a�����F���v�ɂȂ�͂��ł���
>���ۂɂ͂����Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�T���v���摜�ɂ��āA���ۂ͂����Ȃ�Ȃ��Ƃ��������́H
>����Ꮡ���o���ꂽ8bit�摜������ɘM���ĕ���悤�Ƃ���Ζ������o�܂����B
�N�� JPEG �摜�����^�b�`���邱�ƂɌ��y���Ă��܂���B
>�����AWB�ŐԂ݂��������ꍇ�A��̑��̑S�Ă̐F���Ԃ݂�����܂���B
>���z���C�g�o�����X�Ƃ����̂͂����������̂ł�����B
���̃R�����g�̌��̔����́A
>�����āA�̐F�������摜�ɂ́A��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�X��������܂��B
>�Ɨō\�����ꂽ��̐F�ɐԂ݂������Ă��܂��Ă���T���v���摜�̋@��͂ǂ�Ƃǂ�ł��傤�H
�Ƃ̂��Ƃł����B
���āA�A�L���Z����Ɏ���ł��B
[8749689] �ɃA�b�v���� G10 �� GX200 �̎ʐ^���r���āA��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�ԁv�������̂͂ǂ���ł��傤���H
>���ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ����̂̓��`���[�h�͈̔͂ł͂Ȃ��ł���B
>������摜�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ɖ�f���x���ł̓d���̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃł͈Ӗ����ς��܂��B
������O�ł��B�ł́A[8770197]�Ŏ咣����Ă���A
>���Ȃ݂Ƀ_�C�i�~�b�N�����W400���Ƃ����̂��A���ۂɂ͂���܂���O�O
>4�{�̊K���͂��肦�Ă��A4�{�̃_�C�i�~�b�N�����W�͑��݂��Ȃ��̂ł��B
�̍��������肢�������܂��B�ǂ̂悤�ɔC�ӂ̕����̊K����⊮���āA�ǂ̂悤�Ƀn�C���C�g���ƃV���h�E�������Ă�̂��A���m�Ȑ��������肢���܂��B
�܂��A���܂ł͗����Ƃ��܂������A���L�̐��������肢���܂��B
�E�O�������������p�ꂾ�Ƃ��鍪���A��发�̒�
�E���Ԃ������R�o���g�u���[�̐���
�����ԍ��F8774068
![]() 0�_
0�_
�������ɍw�����܂����I
��芸�����[�d�����������̂ŁA�����s�ǃ`�F�b�N�������ƍs�����Ƃ���ł�
��on the willow����
�������t������Ȃ������݂����ŃX�~�}�Z��
�gG10��������Ă��Ȃ��h�ƌ����Ӗ��ŏ������̂ł͂���܂���
�S�Ă̋@��ŁA�����ꏭ�Ȃ������Ă���Ǝv���Ă��܂�
�G�߂��l������ƁA�(����Ă�ł��낤�ω���)���������Ă�G10�̋�̐F�����m��
���@��͕(����Ă�ł��낤�ω���)�Łu�����ɂ���炵����v�̐F�ɂ��Ă���\��������B
�c�Ə����̂����m���������Ǝv���܂��āA���������Ē����܂�
�����ԍ��F8774333
![]() 0�_
0�_
>�G�߂��l�������G10�̋�̐F�����m��
���̉摜�� G10 �̋�͔��ł��܂��̂ŁA�u��̐F�v�Ɋւ��Ă��������Ȃ� G10 �̈Ӑ}�����F�ł͂Ȃ��ł��B
�����ԍ��F8774337
![]() 0�_
0�_
�����s�̂�������
�����Ȃ̂ł����H
�܂��q�X�g�O��������Ɗm���ɂ��������܂��ˁA�ł��ςɒf������̂͊댯���Ǝv���܂�
�ĂуA�L���Z������̔��_���Ă�Řb�����[�v�����Ⴂ�܂���H(���)
�l���g�Ƃ��Ă͌����I�ȕ����͗]�苻�������āA(���ʓI�ɂł�)�����܂B��違�Ӑ}�������t�����o����Ȃ�n�j�Ȃ��C�y�X�^���X�ł��̂ŁA���̕ӂ苂��œǂ�Œ�����K���ł�
�����ԍ��F8774504
![]() 0�_
0�_
���C�ł��ˁO�O�ł͂Â��܂��傤��
��RAW�����\�t�g�ł͐��Ɂu�I�o�v���V�~�����[�g���Ă��܂��ˁB
�����ꂪ�����H
RAW�����\�t�g�́A�ʐ^�@�I�ȈӖ��ł̘I�o�̓V���~���[�g���Ă܂����H
�u�I�o�v�Ƃ������t��������������������ł����E�E�E
��>����ƃJ�������ŐF����������ʂł���������JPEG�摜��Photoshop�ȂǂŊJ���ăq�X�g�O�����������ꍇ��
��>�q�X�g�O����������ꂽ��ԂŌ����邱�Ƃ̃h�R�ɖ���������̂������ł��܂���B
���O�a�Ƃ������t�̈Ӗ��ƃf�����b�g�������邱�Ƃ��������߂��܂��B
RAW�摜��Hibit�摜�i��f���x���j�ł͍�������8bit�����L���͈͂ŋL�^���Ă���̂ł��B
�܂�A�O�a���Ă��Ȃ���Ԃł��B
�Ⴆ��10bit�O���[�X�P�[���ł����1024�K���̏����܂��B
���̒�����u�C�ӂ͈̔͂��v256�K�����ɕϊ������̂�8bit�摜�i�O���[�j�ł��B
�ǂ��̃|�C���g�𔒂Ƃ��A�ǂ��̃|�C���g�����Ƃ��邩�́A���[�J�[���̍ٗʂƂȂ�܂��B
�K������1024�K������1023��256�K���̔��Ƃ��A0�����ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
�������Ɍ����A����́u�ł��Ȃ��v�킯�ł����B
���̂悤��RGB�e�`�����l���ɉ����āu�����܂�v�������Ȃ����
AWB�ŃL�����u���[�V��������ăV�t�g�����F���256�K�����ێ��ł��܂����ˁH
�u�����͉��Όn�̌��ł�����AAWB�Ŕ��ɒ��������
20�����̃}�[���^�𑫂�20�����̃C�G���[�������K�v������܂��B
���������܂蕔�������݂��Ȃ���A�}�[���^�����͕W����80���ŖO�a���A�C�G���[��120���ŖO�a���܂��B
�����̕��j���[�g�����|�C���g������Ă���킯�ł�����B
�����8bit�摜��Photoshop�ŘM���Ă��������Ƃł��B
�Ƃ��낪���ۂ́AHi-bit�摜�̗]�T�悩��f�[�^�������Ă��āAAWB��̐F����ێ����܂��B
�u������AWB��ł��A�}�[���^�A�C�G���[�Ƃ��j���[�g��������n�܂�Ƃ������Ƃł��B
�܂�hi-bit�摜�Ƃ����傫�����{�n�}����A8bit�摜�Ƃ����������n�}��
�k�ڂ͓����Łi�ꍇ�ɂ���Ă͏k�����āj�C�ӂ̓s�s�𒆐S�Ƃ���悤�������ĕ\�����Ă�悤�Ȃ��̂ł��B
�ł�����u��f���x���ŖO�a����قNjɒ[�Ȗ��Í�������̂łȂ�����v
8bit�摜��ŖO�a���ĂĂ�RAW�摜�ł͖O�a���ĂȂ��̂ł��B
RAW�摜�ł͖O�a���Ă��Ȃ��F���A8bit�ɐ�o���Ƃ��Ɂu�����I�ɐ��F������v���F�ŏo����
�q�X�g�O������͖O�a���Ă�̂Ɓu�����Ɍ����܂��v�B
8bit�Ő�o���Ƃ��Ɂu��̐F��Blue�n�ɕ����v�������v���Z�b�g����Ă����
�q�X�g�O�����Ō��Ă����c������ԂŌ���܂��B
8bit��ŖO�a����f��ł��O�a�A�Ɗ��Ⴂ����Ă��܂��H
���R��f��ł��O�a���Ă���A�����������Ă�����܂���B
�ł��A���̒��x�̖��邳�̋�ŖO�a���Ă��܂��قǃf�W�^���J�����̓�������Ȃ��̂ł��B
���≖�̕���ꡂ��ɐF�O�a���₷���ł�����B
��������Ȃ̂Ń_�C�i�~�b�N�����W�̘b�����܂��傤�B
�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̓V�O�i���ő�l�ƃm�C�Y�̕��ł���ˁH
��f�ɂ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W�ł����ƁA�����������ĂȂ��Ƃ��̓d�ׁ��m�C�Y���x���ł��B
�����������Ă���Ƃ��̍ő���~�d�ׂ��V�O�i���ő�l�ł��B
��ƂȂ��Ԃɑ��āA�ő���~�d���[�m�C�Y���x����4�{�ɂȂ��Ă���A�_�C�i�~�b�N�����W��4�{�Ƃ����܂��B
��ԊȒP�ȕ��@�́A1��f�ʐς�4�{�ɂ�������킯�ł��B
�����d�r��4�{�ɂ���C���[�W�ł�
�Ƃ��낪�A���Ƀ_�C�i�~�b�N�����W4�{��搂��f�W�J���ł��A��f�ʐς�4�{�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���
1��f������̍ő���~�d�ׂ�4�{�ɂ��Ȃ��Ă��܂���B
���ǁARAW�摜12bit�i4096�K���j�ȏ�̋@���10bit�i1024�K���j�O��ʼn摜���쐬��
���̊K�����ő���ɐ�����悤��8bit�i256�K���j�ɕϊ����Đ�o���Ă邾���̂��Ƃł��B
�܂�A8bit�ł�1�K���̊Ԃ�10bit�ł�4�K���f�[�^������܂��B
8bit�ł̃n�C���C�g��10���͖�25�K���ł����A���̕�����10bit�f�[�^��ɂ���K���f�������
���ʓI�Ɏ����₷���n�C���C�g���̊K�����⊮����܂��B
�������Ƃ��V���h�E���ɂ��s���ƌ��ʓI�ɊK�����̂悢�u�_�C�i�~�b�N�����W��4�{���邩�̂悤�ȁv�摜�ɂȂ�܂��B
����ł�10bit�摜��8bit�摜��4�{�̊K���ł�����A4�{�̊K���f�[�^�����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�����āA�A�L���Z����Ɏ���ł��B
��[8749689] �ɃA�b�v���� G10 �� GX200 �̎ʐ^���r���āA��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�ԁv�������̂͂ǂ���ł��傤���H
�J���[�s�b�J�[�Ń_�C���N�g�ɓ����ꏊ�̐F��ǂނƂł���
�EG10��C25M0Y0
�EGX200��C40M10Y0
�ԈႢ�Ȃ�GX200�̕����}�[���^�������Ă܂��ˁB�ڂŌ��Ă�����܂��B
�������̂��Ƃ𗝉����ĂȂ��Ǝv���̂ł���
R100��G90%B90����R50%G10��B10%�̐F�Ƃł́A��҂̕����Ԃ̃��x�����Ⴂ�̂Ɂu�Ԃ��v�ł��B
�O�҂�G90%B90%�̕����x�Ƃ���R100������90������������܂��̂ŁA����10���̓ˏo��������܂���B
��҂�G10��B10%�̕�������āA����40���̓ˏo������܂�����u�Ԃ��v�����܂��B
�܂�q�X�g�O�����̌������ԈႦ�Ă�̂ł���B
�_�C���N�g�ɑ����āA�v�Z�������Δ��邱�Ƃł��B
���E�O�������������p�ꂾ�Ƃ��鍪���A��发�̒�
����ł͎g���Ă܂��ˁB����ē`���Ǝ��̂ł�����B
���E���Ԃ������R�o���g�u���[�̐���
�X�O��̃��X�ŊԈႢ��F�߂Ă��܂����A���ۂɂ͔������������U���ł��B
�Ԃ̂Ȃ��n�̋�ŐԂ������̂͂��������Ƃ����b���o�����߂ɁB
����2�_�ɗ͂����Ȃ��Ƙ_�j�ł��Ȃ��悤�ł͋l�݂͋߂��ł���O�O
�����ԍ��F8774885
![]() 1�_
1�_
KND-711����
���̏�ʂ͖��Â̍����傫���̂ŁA��ʉ������ɘI�o�����킹�邩�A��ɘI�o�����킹�邩�A���邢�͂ǂ��������ɂ��邩�A�Ƃ����I���ɂȂ�͎̂~�ނȂ��ł��B
���̉摜�Ɋւ��Ắu�ǂ��������v���̗p�����������܂����B
����d����������ΘI�o��������A�n�ʂ��d����������ΘI�o���グ��A�ƁA�B�e�ҁi�܂��� RAW �����ҁj���C��������������̘b�Ȃ�ł��B
����ƁALX3 �� SILKYPIX �ł̌����AG10 �� DPP �ł̌����A�Ƃ����Ⴂ���d�v�ł��B
SILKPIX �́i��ʓI�ȃf�W�J���ŎB�����摜�Ɣ�ׂ�Ɓj�Õ�����╂�����悤�ȊG�������܂��B����ɑ��ADPP �̃f�t�H���g�́iSILKYPIX �Ɣ�r����Ɓj���Ȃ�n�C�R���g���X�g�ł��B�Õ��͎v�������蒾�߁A�n�C���C�g�́E�E�E�܂��A����������͂������������ɔ���܂��ˁB
�����ăf�t�H���g�̊G���X���� SILKYPIX �͓�ADPP �͍d���A�ƌ����܂��B����Ă��̍��͂��傤���Ȃ��A�Ǝ��͎v���܂��B
�ʂɓ���ǂ��킯�ł��A�d���������G���Ƃ����킯�ł�����܂���BSILKYPIX ���Ɖ��������ADPP ���Ƃ������Ƃ�����ۂɂȂ��ʂ������ł��B�������ӏ҂̍D�݂���ԑ傫���ł��B
����̏ꍇ�͊��l�����u���̐�́E�E�E�v�ȂǂƂ�������������Ă���܂��B���������l�X�ɂƂ��ẮA����Ɍ����Ă� DPP �̊G��肪���������ɍ�p�����A�ƌ����č\��Ȃ��Ǝv���܂��B
���Ƃ� RAW�f�[�^�́u�v���O�a���Ă��邩�ǂ����ł����A�����ł͖O�a�������Ƃ���܂ł͍s���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ARAW�f�[�^�� SILKYPIX �Ō������� LX3 �̐�Ɠ����悤�ɂȂ邩�ǂ����B������Ɛ̐F�������Ȃ�悤�ȋC�����܂��i�����O�a�ƌ����̂ł��傤���j�B
�����ԍ��F8775026
![]() 0�_
0�_
�A�L���Z����
�ȑOCCD�T�C�Y�Ɖ�f�s�b�`�v�Z�ŁA��萳�m�ɋ߂��f�[�^������|�߂���X��
�U�X�R���Ă�肵�Ĕn���ɂ����i�u�Ԉ�������l�������āA�����Ƃ��炵�����l��
���č����ˁv�݂����ȁj������A���ǂ͎����̎咣���鐔�l����R�������ƕ�������
��p�������̂����Y��ł����H�i���l�͒p�����������肪�Ȃ���������܂��c�j
�����g�𐳂����ƉߐM����̂͌��\�ł����A���ɏ����I�ȊԈႢ�̎��т�����̂ł�����A
���܂�ォ��ڐ��Œf��I�Ɍ��̂͊��S���܂���ˁB
�����ԍ��F8775870
![]() 9�_
9�_
���̒��A���r���[�Ȓm���ł����ނ��炵�����l������̂ɂ͋����܂��B
�ԈႦ�Β������Ă��炦��A�^���ɋc�_���邱�Ƃ��ł���̂ł����B
>RAW�����\�t�g�́A�ʐ^�@�I�ȈӖ��ł̘I�o�̓V���~���[�g���Ă܂����H
>�u�I�o�v�Ƃ������t��������������������ł����E�E�E
�͂��H
����ł�RAW�����\�t�g�́u�I�o�v�Ƃ͂ǂ�������`�Ȃ̂ł��傤���B
�Ǝ���`�͂�߂Ă��������ˁB�I�J���g�Ȋw�̐��E�ɓ����Ă��܂��܂��B
������ƂŘI�o������i����掆�ւ̘I���ʂ����߂�j�͕̂��ʂɍs�����Ƃł����B
>���O�a�Ƃ������t�̈Ӗ��ƃf�����b�g�������邱�Ƃ��������߂��܂��B
>RAW�摜��Hibit�摜�i��f���x���j�ł͍�������8bit�����L���͈͂ŋL�^���Ă���̂ł��B
>�܂�A�O�a���Ă��Ȃ���Ԃł��B
���x�����x�����x�����x���R�����g���Ă��܂����A�����ŋc�_����Ă���̂͌��̃T���v���ʐ^�ɂ��Č���Ă��܂��B����RAW �ɂ��Ă̌����͊���[8752912]�ɂČ��y�ς݂ł��B
>�Ⴆ��10bit�O���[�X�P�[���ł����1024�K���̏����܂��B
>���̒�����u�C�ӂ͈̔͂��v256�K�����ɕϊ������̂�8bit�摜�i�O���[�j�ł��B
>�ǂ��̃|�C���g�𔒂Ƃ��A�ǂ��̃|�C���g�����Ƃ��邩�́A���[�J�[���̍ٗʂƂȂ�܂��B
����Ȃ��Ƃ͓�����O�ł��B
���������Ă���̂́A���̃T���v���ʐ^�� RAW ���O�a���Ă��Ȃ��Ƃ���u�����v�������Ă��������ƌ����Ă��܂��B
>�K������1024�K������1023��256�K���̔��Ƃ��A0�����ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
>�������Ɍ����A����́u�ł��Ȃ��v�킯�ł����B
�ł��܂���B
�q�X�g�O�����Ƃ����A�O�a�Ƃ����A�f�W�^���f�[�^�ւ̒m���͂قڂO�Ȃ�ł��ˁB
>���̂悤��RGB�e�`�����l���ɉ����āu�����܂�v�������Ȃ����
>AWB�ŃL�����u���[�V��������ăV�t�g�����F���256�K�����ێ��ł��܂����ˁH
���ɏ����Ă��܂����A���̃T���v���ʐ^�� RAW ���O�a���Ă��Ȃ��Ƃ��鍪���������Ă��������ƌ����Ă��܂��B
�����������܂ܒf�肷��̂��u�������ł͉��Ƃł�������v�ƌ����܂��B
>�u�����͉��Όn�̌��ł�����AAWB�Ŕ��ɒ��������
>20�����̃}�[���^�𑫂�20�����̃C�G���[�������K�v������܂��B
�u�����ɂ���Ă��̐��l�͑啝�ɈقȂ�܂����B
>���������܂蕔�������݂��Ȃ���A�}�[���^�����͕W����80���ŖO�a���A�C�G���[��120���ŖO�a���܂��B
>�����̕��j���[�g�����|�C���g������Ă���킯�ł�����B
>�����8bit�摜��Photoshop�ŘM���Ă��������Ƃł��B
�Ђ���i�����܂�H�j����邽�߂ɂ��J�����͘I�o���R���g���[�����܂��B
�t�ɁA�I�o�����ɃR���g���[��������Ȃ��ꍇ�A�������͉�f�̃_�C�i�~�b�N�����W���Ⴂ�ꍇ���� RAW �ł����C�ŖO�a���܂��B�Ԃ≩�F���O�a���₷���ƌ����鏊�Ȃ͂��̂�����ł��BRAW �ł͖O�a���Ȃ��A�Ƃ�����ł͂���܂���B�ł�����f�����邩��ɂ́A����̃T���v���ʐ^�ł� RAW �͖O�a���Ă��Ȃ��A�Ƃ���������������Ă��������Ɖ��x���i�j
>�ł�����u��f���x���ŖO�a����قNjɒ[�Ȗ��Í�������̂łȂ�����v
>8bit�摜��ŖO�a���ĂĂ�RAW�摜�ł͖O�a���ĂȂ��̂ł��B
����A�ł������f���x���ŖO�a���Ă��Ȃ������Ƃ��鍪�����B
>RAW�摜�ł͖O�a���Ă��Ȃ��F���A8bit�ɐ�o���Ƃ��Ɂu�����I�ɐ��F������v���F�ŏo����
>�q�X�g�O������͖O�a���Ă�̂Ɓu�����Ɍ����܂��v�B
>8bit�Ő�o���Ƃ��Ɂu��̐F��Blue�n�ɕ����v�������v���Z�b�g����Ă����
>�q�X�g�O�����Ō��Ă����c������ԂŌ���܂��B
���x�������Ă��܂����A��̖��x���グ��A�ɒ[�Șb���F�ɂ���ɂ��Ă��A��O�a������K�v�͂���܂���B
[8750781]�̃_�C�i�~�b�N�����W400% �̋�F�ł��A���x�̍�����F�̕����͖̐O�a���Ă��܂���ˁB
>8bit��ŖO�a����f��ł��O�a�A�Ɗ��Ⴂ����Ă��܂��H
�����A�S���B
����A�����O����قlj��x�������Ă��܂����A����̘b�͌��̃T���v���ʐ^�ɂ��Ăł��B
�����āA�q�X�g�O����������Δ���ʂ�A���m�ɖO�a���Ă��܂��B
����CCD���x���ŖO�a���Ă���Ƃ��A���Ă��Ȃ��Ƃ��f�����Ă��܂���B���͂��̗����̉\���ɂ��ďq�ׂĂ��܂��B
���āARAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ��ƒf�����鍪����������Ă��������B
�����ԍ��F8776262
![]() 2�_
2�_
>��f�ɂ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W�ł����ƁA�����������ĂȂ��Ƃ��̓d�ׁ��m�C�Y���x���ł��B
�ԈႢ�ł��B
�V���b�g�m�C�Y�Ȃǂ͌��������邱�Ƃɂ���Đ�����m�C�Y�ł��B
�M���̎w�E���Ă���Ód���m�C�Y�͐ÓI�ȃm�C�Y�ł������菜����@������܂��B
�������A�O�a�d�חʂ����Ȃ�����f�����ꂽ CCD �ɂ����āA�����Ƃ����Ȃ̂̓V���b�g�m�C�Y�̕��ł��B
>�����������Ă���Ƃ��̍ő���~�d�ׂ��V�O�i���ő�l�ł��B
>��ƂȂ��Ԃɑ��āA�ő���~�d���[�m�C�Y���x����4�{�ɂȂ��Ă���A�_�C�i�~�b�N�����W��4�{�Ƃ����܂��B
���̐������ƘI���ʂŃ_�C�i�~�b�N�����W���ω����Ă��܂��܂��i�j
���m�ɂ͖O�a����܂Ō������Ă����̓d�חʁi�O�a�d�חʂƂ����܂��j���ő���~�d�ׁi�M���̑���ł����j�ł��B
�ŁA����͉�f�M���ɂ�����_�C�i�~�b�N�����W�ł��B�ʐ^�̂���͈Ⴄ�ƌ���Ă����̂͋M�����Ǝv���܂����B
>��ԊȒP�ȕ��@�́A1��f�ʐς�4�{�ɂ�������킯�ł��B
>�����d�r��4�{�ɂ���C���[�W�ł�
1��f������̖ʐς�4�{�ɂ���Ǝ���ʐς�4�{�i�ȏ�j�ɂȂ�܂����A�O�a�d�חʂ�4�{�ɂ͂Ȃ�܂���c
���R�͕����Ă��������B
>�Ƃ��낪�A���Ƀ_�C�i�~�b�N�����W4�{��搂��f�W�J���ł��A��f�ʐς�4�{�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���
>1��f������̍ő���~�d�ׂ�4�{�ɂ��Ȃ��Ă��܂���B
>���ǁARAW�摜12bit�i4096�K���j�ȏ�̋@���10bit�i1024�K���j�O��ʼn摜���쐬��
>���̊K�����ő���ɐ�����悤��8bit�i256�K���j�ɕϊ����Đ�o���Ă邾���̂��Ƃł��B
�M�����Ȃɂ����Ⴂ���Ă���̂������Ă��܂����B
�_�C�i�~�b�N�����W400% ������Ă���@��͐̂��牽�@�킩����܂����A�K�������M���̏����Ă�����@�Ŏ������Ă����ł͂Ȃ��ł����A��f���x���̃_�C�i�~�b�N�����W��4�{�ɂȂ������Ƃ��_�C�i�~�b�N�����W 400% �ƌ����Ă����ł�����܂���B
>�����āA�A�L���Z����Ɏ���ł��B
>��[8749689] �ɃA�b�v���� G10 �� GX200 �̎ʐ^���r���āA��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�ԁv�������̂͂ǂ���ł��傤���H
>>�J���[�s�b�J�[�Ń_�C���N�g�ɓ����ꏊ�̐F��ǂނƂł���
�܂��A�O���f�[�V�����̂����F���A�J���[�s�b�J�[�ŐF�����̂͂����߂��܂���B�Ȃ��Ȃ�A1��f�`����f�݂̂������ڂł��Ȃ�����ł��B�q�X�g�O�����Ō���ׂ��ł��傤�B
���ɁACMYK �ɂ�����}�[���^�iM�j�́ARGB �ł����iB�j�𑽕��Ɋ܂�ł���F�ł��B
���������A���̃X���b�h�̘b��́A�u���̎O���F�ɂ�����̖O�a�v�Ȃ�ŁA�}�[���^�����グ��Əœ_���{�P�܂��B
����āA����́u�ԁv�������̂͂ǂ���ł��傤���A�Ƃ������ƂȂ�ł����B
�Ȃɂ��A�ŏ��̋M���̎咣�́A
>�����āA�̐F�������摜�ɂ́A��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�X��������܂��B
>�Ɨō\�����ꂽ��̐F�ɐԂ݂������Ă��܂��Ă���T���v���摜�̋@��͂ǂ�Ƃǂ�ł��傤�H
�ł�����B
>�ԈႢ�Ȃ�GX200�̕����}�[���^�������Ă܂��ˁB�ڂŌ��Ă�����܂��B
�Ƃ������ƂŁA�q�X�g�O�������A�b�v���܂��B
��F�ɂ��Ă� G10 �̃q�X�g�O����������ƃ}�[���^���O�a���Ă��܂��ˁB
���������Ԃ͖O�a���Ă��Ȃ��̂ɁA�}�[���^���O�a����͎̂O���F�́u�v�̉e���ł��B
�i�œ_���ڂ���ƌ����Ӗ��������邩�Ǝv���܂��j
�܂��A�r���̖��ʐF���������Ă��AGX200 �̐Ԃ������������߂Ȃ̂��킩��܂��B
>������ꍇ�ɋ�F�ɐԂ������o��X�����o�錴���̑����̓z���C�g�o�����X�̖��ł��B[8770306]
�̎��̎咣�����t�����Ă��܂��B
>�������̂��Ƃ𗝉����ĂȂ��Ǝv���̂ł���
>R100��G90%B90����R50%G10��B10%�̐F�Ƃł́A��҂̕����Ԃ̃��x�����Ⴂ�̂Ɂu�Ԃ��v�ł��B
���́[�A����A�O���F�̔䗦���Ⴄ�̂œ�����O�ł��B
>�܂�q�X�g�O�����̌������ԈႦ�Ă�̂ł���B
>�_�C���N�g�ɑ����āA�v�Z�������Δ��邱�Ƃł��B
���́A���ɏ������ʂ�}�[���^�͐̉e���������̂ł��B
�i�}�[���^��Ԃ��ƌ��Ƃ������Ƃ́A����W�̐l�Ȃ�ł��傤���j
�܂��A�����ł́u���̎O���F�ł̖̐O�a�v�ɂ��Č���Ă��܂��B
>���E�O�������������p�ꂾ�Ƃ��鍪���A��发�̒�
>����ł͎g���Ă܂��ˁB����ē`���Ǝ��̂ł�����B
��͂́i��j
�����ł͎g���Ă���݂����ł���B
���E���Ԃ������R�o���g�u���[�̐���
>�X�O��̃��X�ŊԈႢ��F�߂Ă��܂����A���ۂɂ͔������������U���ł��B
>�Ԃ̂Ȃ��n�̋�ŐԂ������̂͂��������Ƃ����b���o�����߂ɁB
�M���̎咣�S�Ă������������Ǝv���A�[���ł��镔���������ł��B
>���w�E�̏�Ԃ́u�F���O�a���Ă���v�ł͖����āu���x���オ���ĔZ�x�������Ă�v�Ƃ����܂��B[8750762]
�Ƃ��ˁB
����ł͂��낻��{���̎咣�𖾂炩�ɂ��Ă���������Ɓi�j
>����2�_�ɗ͂����Ȃ��Ƙ_�j�ł��Ȃ��悤�ł͋l�݂͋߂��ł���O�O
�������͂��łɋl�܂�Ă���Ƃ������ƂɋC�t���ꂽ���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8776373
![]() 2�_
2�_
�ւ��݂Ղ�����
>������A���ǂ͎����̎咣���鐔�l����R�������ƕ�������
>��p�������̂����Y��ł����H
>�i���l�͒p�����������肪�Ȃ���������܂��c�j
�Ȃ�قǁA���т�����̂ł��ˁB
�ԈႢ���w�E��������̂͑�ςł��B
�ԈႢ���w�E�������X�Ȃ�ԈႢ���w�E�����̌J��Ԃ��ŃG���h���X�ł�����B
�Ⴆ��
>�V���~���[�g
����� Simulate �ł�����A����[�g�i�j�ɂ͂Ȃ�܂���B
�V���~���[�g���Č�p�͏��Ȃ��Ȃ��ł����ǁA��p�͌�p�ł��B
>>�X�O��̃��X�ŊԈႢ��F�߂Ă��܂����A
�Ƃ����A�ǂ��ŊԈႢ��F�߂Ă���̂��������������Ƃ���ł��B
RAW �ł̓n�C���C�g�������m�ۂ���Ă���ƒf���ł��鍪���͂����ς�ł����ˁB
�����ԍ��F8776638
![]() 3�_
3�_
�쎟�n����ꌾ
�@�^���ȋc�_�ɂ́u����Ă͂����Ȃ��v���Ƃ�����������܂��ˁB
�P�j���_���o��O�Ɂu�������������v���Ƃ�O��Ƃ������������肩����
�@�@�i�u�����Ȃ����v�u����₵�Ď����̏���������ǂݒ����v���X�j
�Q�j����ɔ��_���ꂽ�_�ɂ��āA��̓I�ɔ��_�����Ɏ��������肩����
�@�@�i�u�O�ɂ������܂������v�ƌ����Ă���_�ɕԓ����Ȃ��A���j
�R�j����̎咣������Ɋg����߂��Ĕᔻ����c�c�@���X
�u�c�_�ɏ��v�ł͂Ȃ��A�c�_��[�߂�̂��ړI�Ȃ玩�R�ɔ�������
�͂��̂��Ƃ���ł����A����l�̑Θb�͂��łɂւ��݂Ղ����w�E
���ꂽ�u�ォ��ڐ��v�̉��V�ɂȂ��Ă��܂��Ă���悤�ȁB�ǂ��炪���
���[����j�������͉��ɂ����Ƃ��āA�������������Ȃ�܂���
���̂ւ�����炷�邱�Ƃ���͂��߂Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤�B
�����ԍ��F8778512
![]() 3�_
3�_
���P�j���_���o��O�Ɂu�������������v���Ƃ�O��Ƃ������������肩����
�O�a���Ă��Ȃ��Ƃ����炠�̐�͎��͖��o���ł��B
�E�E�E�Ƃ������x�ŁA�������������Ƃ͎v���Ă܂���B
�B�e���I�o�������Ă����̃O���f�[�V�������o������������Ă��������������̂ł��B
�R�̒[�ɍs���ɏ]���čʓx��������F�����O���[�������ɉ�]���Ă����ɂ�������炸�A�̃��x�������Ƃ�������B
�����ԍ��F8778793
![]() 0�_
0�_
���A
�A�L���Z����͂������ł���
on the willow����ȉ��̌��t����������o���Ȃ��(^_^;)���ꂾ���Ŋ��S���܂����B
>>��f���x���̃_�C�i�~�b�N�����W��4�{�ɂȂ������Ƃ��_�C�i�~�b�N�����W 400% �ƌ����Ă����ł�����܂���B
�����ԍ��F8779868
![]() 2�_
2�_
���s�̂�������A�����́B
>�O�a���Ă��Ȃ��Ƃ����炠�̐�͎��͖��o���ł��B
>�E�E�E�Ƃ������x�ŁA�������������Ƃ͎v���Ă܂���B
>�B�e���I�o�������Ă����̃O���f�[�V�������o������������Ă��������������̂ł��B
>�R�̒[�ɍs���ɏ]���čʓx��������F�����O���[�������ɉ�]���Ă����ɂ�������炸�A�̃��x�������Ƃ�������B
�i���[���Ɓj��̃��X�ŏ����܂������ALX3�̃q�X�g�O����������ƁA�̃��x�������ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��A������ƃO���f�[�V�������m�F�ł��܂��B
G10�̃q�X�g�O�����ƌ���ׂ�ƁA���O�a���Ă�ƒf�肵�Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�������RAW���x���ł͂킩��܂���B
�S�@��̔�r�ł́A����f�̂��̂قǖO�a���������X���ł��̂ŁA�f�q�̐��\���W���Ă�\��������Ƃ͎v���܂����A
��������̗v�������傫�����낤�Ǝv���Ă܂��B
�����G10��LX3�Ɋւ��ẮA�d����Ƃ������A��̐F�ɑ���A�v���[�`�̈Ⴂ�����邩�ȁA�Ǝv���܂��B
��Ŏ������p�����L���i�y�ɒB�~��̃f�W�^���ł�����!�z�f�W�^�����6�@��掿�Ό��j
�ɂ�����܂����A�u�L���m���͓`���I�ɐ�̐�����߂Ɏʂ�v�X��������Ǝv���܂��̂ŁB
���Ȃ݂ɁA����EOS���[�U�[�ł����A���̋L�҂Ɠ����悤�Ɂu�L���m���̗͂Ȃ���̔��F�v���c�O�Ɋ����邱�Ƃ�����܂��B
�������A����͂��Ԃ�ɍD�݂̖��ł����A�����ɂƂ��Ă�CANON�̑��̖ʂł̃A�h�o���e�[�W���Ђ����肩�����悤�ȃt�@�N�^�[�ł͂���܂���B
�����A����̉摜�Ɋւ��ẮA���̕ӂ����ڂɏo���\��������ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F8779983
![]() 1�_
1�_
�\��t����摜�ł����A�Ȃ���̕�����GX200�̐Ԃ݂��o�Ă�Ƃ��������Ĕ͈͎w�肵�Ă���̂ł��傤���H
���Ɖ���P6000�̉摜�ł͓������Ƃ����Ȃ��̂ł����H
���������A�O�a�d�חʂ����Ȃ�����f�����ꂽ CCD �ɂ����āA�����Ƃ����Ȃ̂̓V���b�g�m�C�Y�̕��ł��B
�V���b�g�m�C�Y�̓_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͊W���܂���B�V���b�g�m�C�Y�ʼne�������̂́A�K���̍Č����ł��B
�V���b�g�m�C�Y�̖��́A1�̓����ɑ��ĉ�f��1�̏o�͂����Ȃ��ꍇ������Ƃ������Ƃł��B
����͗ǂ��m���̖��Ƃ��Đ�������܂����A��f���̂��u��̂ɉ�����1�̓����ɑ���1�̏o�͂�����v���x�̐��x�ł�����
���̃o���c�L���z�����邽�߂ɁA1��f������̖ʐς�傫�����āA�T���v���̕ꐔ�𑝂₵�A�������K���o�͂ɂ��Ă��܂��B
����̓O���f�[�V���������̎��R���Ɋւ��܂��̂ŁA��f�ʐς̑傫�ȋ@��̕����`�ʂ��ǂ��Ȃ�܂��B
��f�ʐς����������Ƃ̃f�����b�g�́A�K�����������Ƃł͂Ȃ��āA�K���̍Č��������Ƃ������Ƃł��B
���܂��A�O���f�[�V�����̂����F���A�J���[�s�b�J�[�ŐF�����̂͂����߂��܂���B�Ȃ��Ȃ�A1��f�`����f�݂̂������ڂł��Ȃ�����ł��B�q�X�g�O�����Ō���ׂ��ł��傤�B
�ł́A�����ƐԂ݂̏o�Ă�Ƃ�����u�͈͎w�肵�āv�q�X�g�O�����\������Ă͂������ł��傤�H
P6000�̕����ƁA��蔻��₷���ł��ˁB
���႟�A�}�[���^���ł��A��+���i�}�[���^�͐ԂƐƂ̓��䗦�g�ݍ��킹�ł�����j�ł��\���܂���B
�}�[���^�������ɂ͐Ԃ̌����K�{�ł�����A�Ԃ̉e�����Ă�킯�ł��B
���V�A���{�}�[���^���Ԃł�����
��>�K������1024�K������1023��256�K���̔��Ƃ��A0�����ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
��>�������Ɍ����A����́u�ł��Ȃ��v�킯�ł����B
���ł��܂���B
���q�X�g�O�����Ƃ����A�O�a�Ƃ����A�f�W�^���f�[�^�ւ̒m���͂قڂO�Ȃ�ł��ˁB
RAW�摜�ł͂ł��Ȃ��̂ł���B
���ꂪ�ł����Ԃɂ����i�K��AWB�Ȃǂł̃z���C�g�o�����X���s���K���̗]�n�����̂ł��B
1024�K�������Ȃ��f�[�^�iWB�����j�ɑ����炩�̕��@��WB�����A��̂ĂȂ��Ă͂����Ȃ��f�[�^���o�܂��B
�ł�����A��̂Ă�f�[�^��̔��i���x�ő�̈Ӗ��j���_�C���N�g��8bit�o�͂̔��ɂ͂ł��܂���B
RAW����8bit���N�����̂́A������10bit�f�[�^��8bit�f�[�^�ɕϊ�����̂Ƃ͈Ӗ����قȂ�܂��B
�B�e�f�q�͍ŏ���������ɍ��킹�ĐF��f���o���Ă͂���܂���
RAW�摜���RGB�ő�l�i�ʏ�Ȃ甒�j�����̂܂ܔ��Ƃ��Ă͎g���Ȃ��̂ł���B
��>���E�O�������������p�ꂾ�Ƃ��鍪���A��发�̒�
��>����ł͎g���Ă܂��ˁB����ē`���Ǝ��̂ł�����B
����͂́i��j
�������ł͎g���Ă���݂����ł���
���ۂɎʐ^�����H���錻��ł���
���ۂ̌������E��RGB�A���j�^���RGB�A�摜�f�[�^��RGB��CMYK�A�t�C������CMY�A��掆��CMY�A�����CMYK��
�u�O���F�v�ł̓g���u�����N����̂ł��B
�������F�����́A�ǂ̒i�K�ł��܂����ɂ����RGB�ł�������ACMY�ł�������}�`�}�`�ł��B
�܂�Photoshop�����ōς�ł�l�ɂ́A�D���ɑ�����Ă�����č\���܂��ˁB�����������Ƃł��B
�����ԍ��F8780124
![]() 1�_
1�_
�����āARAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ��ƒf�����鍪��
�܂����Ⴂ����Ă܂����ARAW�摜����f���x���ł�8bit�摜�����L���͈͂Ō����Ă���A�Ƃ͌����܂����B
�ł����A���̃T���v���摜�łǂ����́uRAW�摜�����Ă݂Ȃ��Ɣ���Ȃ��̂�JPEG�Ō�����̂��H�v�ƌ����܂����B
����ŁAJPEG�̉摜�������͈͂Ō����Ă���̂��A�Ƌ���̂�
RAW�i��f���x���j����8bit�摜���N�����i�K�ŁA�J�������ɐF������R���g���X�g�������Ă���̂�
�ǂ��炩���������Ƃ������b�ł��Ȃ��ł��傤�H�ƌ����Ă��܂��B
�l�Ԃ̊�����R���x���オ��ΖO�a����̂�
���ۂɌ����ڐ��F�̋�ł���A�摜��ł����F�ŗǂ��̂ł́H�ƌ����Ă��܂��B
�l�Ԃ̖ڂŌ��Ă��O�a�C���Ȃ̂ɁA���F�̗ǂ��u���[�ɕ\������Ă���A����͒�������Ă���ƌ������Ƃł��B
���T���v����EXIF���������A��{�I�o�ɂ��قǃo���c�L�͂Ȃ��ł���ˁH�S��-2/3�i�����Ă��܂����B
�����ARAW�摜�i�K�ł͕K��8bit�摜�������܂������Ă��܂��̂�
�O�a���Ă��邩�ǂ����͂��Ă����A8bit��ŖO�a���Ă����Ԃ��͊m���ɊK���]�T��������̂ł��B
�܂�RAW�摜��JPEG�摜�̊W�́A�����摜��Hi-Bit�摜��8bit�摜�̊W�Ƃ͈قȂ�̂ł��B
�O�҂̓_�C�i�~�b�N�����W�ƊK�����قȂ�܂����A��҂͊K���̍������ł��B
RAW�摜��JPEG�摜�̊W���[���I�ɕ\����
8bit256�K���̉摜����A�C�ӂ̔��_�ƍ��_���߂āA6bit64�K���̉摜���o���̂Ɠ������Ƃł��B
8bit�摜�̔��_��6bit�摜�̔��_�Ɠ���ɂ���K�v�͂���܂���B
�C���[�W�Ƃ��Ă̓t�C������̉摜����掆�ɏĂ��t����̂Ɠ�����
��掆�ł̓t�C������̃t���K�����g�����Ƃ͂܂�����܂���B
������̓t�C�����̕����_�炩���ꍇ����������ŁA�d���t�C�����ɏ_�炩����掆�Ƃ����g�ݍ��킹���Ȃ��͂���܂���B
�����A������T���v���ʐ^��RAW�摜�ڌ��Ȃ���Δ���Ȃ����Ƃł��B
�������A�J�������Œ����ł���F����Z�x�A�R���g���X�g���x�̕�ʂ�8bit�摜���t���Ă��Ȃ����Ƃ͂���܂���B
�����̒��x�̕����܂�͑��݂��Ă���Ƃ������Ƃł��B
���������Ӗ���
�u8bit��ŖO�a���Ă���ȏ�i�J���[�o�����X�������Ă���̂Łj�F����͂ł��Ȃ��v
�Ƃ����̂͌�肾�Ƃ����Ă��܂��B
�������A���̗ʂ�r�������O���Εʂł���H
������̃T���v���摜�ł�+2�i�����A���͖O�a���܂��B
������ł�RAW�����\�t�g�́u�I�o�v�Ƃ͂ǂ�������`�Ȃ̂ł��傤���B
����͌��X�u�̘I�o���x���������v�Ƃ���������̕\���ɑ��Ă̘b�ł���ˁH
���ʂ̃J�����ł̓J���[���̘I�o�Ƃ��������������܂��A�t�C���������Ă��̎��ɂ͂��܂��B
����̓v�����{�i�N�����C�g�j�ɋ߂Ă����l�������̂ŊԈႢ�͂Ȃ��ł��B
�I�����Ԓ��ɐF�t�B���^�[�����ɂ��������ԂŐF���������s���̂Łu�I�o�v�Ȃ킯�ł��B
�@�ނɂ���ẮA�F�̕t�������ŕʁX��3��I�o�����Ă��t�����肵�܂��B
�����R�e�F���Ƃ̘I�����Ԃ��f�[�^�Ƃ��čT�����܂��B�������Ȃ��Ǝ����F�����Č��ł��Ȃ��̂ŁB
���ʐ^�̂���͈Ⴄ�ƌ���Ă����̂͋M�����Ǝv���܂����B
�ł�����ARAW�摜�������܂�������Ă�i�K�ŁA8bit�摜���ʐ^�Ƃ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W���L���킯�ł���ˁH
�K���̍��́A���������̃r���ʼn��K���Ăɂ��邩�̍��ł��B
�_�C�i�~�b�N�����W�̍��́A�r���̍������̂̍��ł��B
�܂�_�C�i�~�b�N�����W��4�{�������ꍇ�́AISO200����Ƃ����
������ISO100�Ŕ�Ȃ����x���܂ŁA�Õ���ISO400�Ńt�H���[�ł���͈͂܂ł̖��Í��ɑΉ�����Ƃ������Ƃł��B
�����e�x4�{�Ƃ����Ӗ��ł�����B
��>>�X�O��̃��X�ŊԈႢ��F�߂Ă��܂����A
���Ƃ����A�ǂ��ŊԈႢ��F�߂Ă���̂��������������Ƃ���ł��B
[8765220]�̖`���ł��B�X�O��̃��X���āA���̃��X�������݂��܂���B
�����ԍ��F8780132
![]() 1�_
1�_
�S���ɂ�����Ɖ����Ă����Ƃ����Ȃ�킯�ŁB
�܂��A��������Ȃ��Ƌ�̓I�ɔ��_���ĂȂ��ƌ�����Ȃ�v�����Ȃ��̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F8780142
![]() 1�_
1�_
gintaro���� �������p���炵�܂����B
>>�B�e���I�o�������Ă����̃O���f�[�V�������o������������Ă��������������̂ł��B
>>�R�̒[�ɍs���ɏ]���čʓx��������F�����O���[�������ɉ�]���Ă����ɂ�������炸�A�̃��x�������Ƃ�������B
>
>�i���[���Ɓj��̃��X�ŏ����܂������ALX3�̃q�X�g�O����������ƁA�̃��x�������ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��A������ƃO���f�[�V�������m�F�ł��܂��B
>G10�̃q�X�g�O�����ƌ���ׂ�ƁA���O�a���Ă�ƒf�肵�Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�u�̃��x�������v�� G10 �̉摜�ɂ��Ă̂��̂ł��B
�u�O�a�v�Ƃ����̂́u�����W���z���邱�Ɓv�ł��i�������t�̒�`�ŝ��߂Ă܂����A�����������Ƃɂ��Ă����܂��傤�j�B
�uG10 �̐O�a���Ă��Ȃ��̂Ȃ�i���̏�ʂł́j�B�e�I�o�������Ă��̃��x�������̐�ɂȂ�B�����������g�͂�����������B�e�������Ƃ������B����Čo����A���� G10 �̐�͖O�a���Ă���ƒf���ł���v
���������Ӗ��ł��B
�u�o����v�Ȃ�Č��t������������������o���قǂ̑�ςȎ��Ԃ��Ƃ͎v���܂��ǂˁB�����Đ�������Ȃ���Ă��Ƃł��B
>�y�ɒB�~��̃f�W�^���ł�����!�z�f�W�^�����6�@��掿�Ό�
���̋L������� RAW�f�[�^����ɓ���܂��B
�b�̗��ꂩ��͊O��܂����AG10 �̎��͍͂����Ɗ����܂����B
���� G10 �����Ƃ͂����炭�����̂ł����ARAW�B�e�ł���f�W�J���Ƃ������Ƃŋ��������莸�炳���Ă��������܂����B
�����ԍ��F8780352
![]() 0�_
0�_
>�\��t����摜�ł����A�Ȃ���̕�����GX200�̐Ԃ݂��o�Ă�Ƃ��������Ĕ͈͎w�肵�Ă���̂ł��傤���H
�͂��A�Ԗ����o�Ă�Ƒ����ł�̂͋�̈ꕔ�������Ȃ̂ł����H
>���Ɖ���P6000�̉摜�ł͓������Ƃ����Ȃ��̂ł����H
�q�X�g�O�����ł͍ŏ����� GX200 �Ƃ̔�r�������Ă��܂����B
GX200 �Ƃ̔�r�ł͕s�\���Ȃ�A�ǂ����������ŁB
>���������A�O�a�d�חʂ����Ȃ�����f�����ꂽ CCD �ɂ����āA�����Ƃ����Ȃ̂̓V���b�g�m�C�Y�̕��ł��B
>�V���b�g�m�C�Y�̓_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͊W���܂���B�V���b�g�m�C�Y�ʼne�������̂́A�K���̍Č����ł��B
���[��A�R�������Ă͂����܂���B
�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̓m�C�Y�ƐM���̍ő�l�̔�ł��B�����ăV���b�g�m�C�Y���l�̃o���c�L�Ƃ��ďo�Ă���m�C�Y�ł�����A���R�_�C�i�~�b�N�����W�ɉe����^���܂��B1��f������̖ʐς��ɒ[�ɋ����R���p�N�g�f�W�J���ł͓��ɁA�ł��B
>��f�ʐς����������Ƃ̃f�����b�g�́A�K�����������Ƃł͂Ȃ��āA�K���̍Č��������Ƃ������Ƃł��B
�u�K���������v�Ƃ́H
>���܂��A�O���f�[�V�����̂����F���A�J���[�s�b�J�[�ŐF�����̂͂����߂��܂���B�Ȃ��Ȃ�A1��f�`����f�݂̂������ڂł��Ȃ�����ł��B�q�X�g�O�����Ō���ׂ��ł��傤�B
>�ł́A�����ƐԂ݂̏o�Ă�Ƃ�����u�͈͎w�肵�āv�q�X�g�O�����\������Ă͂������ł��傤�H
>P6000�̕����ƁA��蔻��₷���ł��ˁB
����ł͂������Łi�j
�����ƁA�z���C�g�o�����X�̖��łȂ����͗����Ă��������ˁB
>RAW�摜�ł͂ł��Ȃ��̂ł���B
�f�W�^���f�[�^�Ƃ��Ă͉��̖��������ł��܂����A���ꂪ�ʐ^�Ɛ��藧���ǂ����͕ʂ̘b�ł��B
RAW �ł��Ӗ�������̂Ƃ��ǂ����ƁA�ł��Ȃ��Ƃł͈Ⴂ�܂����A����� RAW �ł��O�a���邱�Ƃ�����܂�����A���̏ꍇ�� JPEG �ł��O�a���A����т�F���̃Y���Ƃ��Č��ʂɂłĂ��܂��B
�K���ƃ_�C�i�~�b�N�����W���������Ă���悤�ł��B�ڂ����͌�q���܂��B
>���ۂ̌������E��RGB�A���j�^���RGB�A�摜�f�[�^��RGB��CMYK�A�t�C������CMY�A��掆��CMY�A�����CMYK�Ɓu�O���F�v�ł̓g���u�����N����̂ł��B
�M���̐E��Łu�O���F�v�Ƃ����p��Ńg���u�����N���邩�ǂ����ł͂Ȃ��A�O�������������p��ł���Ƃ̍������I���Ă��������ˁB
>����ŁAJPEG�̉摜�������͈͂Ō����Ă���̂��A�Ƌ���̂�
>RAW�i��f���x���j����8bit�摜���N�����i�K�ŁA�J�������ɐF������R���g���X�g�������Ă���̂�
>�ǂ��炩���������Ƃ������b�ł��Ȃ��ł��傤�H�ƌ����Ă��܂��B
�M�����f�����Ă��邩�畷���Ă���̂ł��B�ēx�f������Ă���ӏ����o���܂��B
#>RAW�摜��Hibit�摜�i��f���x���j�ł͍�������8bit�����L���͈͂ŋL�^���Ă���̂ł��B
#>�܂�A�O�a���Ă��Ȃ���Ԃł��B
#>�ł�����u��f���x���ŖO�a����قNjɒ[�Ȗ��Í�������̂łȂ�����v
#>8bit�摜��ŖO�a���ĂĂ�RAW�摜�ł͖O�a���ĂȂ��̂ł��B
#>�����ARAW�摜�i�K�ł͕K��8bit�摜�������܂������Ă��܂��̂�
#>�O�a���Ă��邩�ǂ����͂��Ă����A8bit��ŖO�a���Ă����Ԃ��͊m���ɊK���]�T��������̂ł��B
�ł�����ARAW�摜���O�a���Ă��Ȃ��Ƃ����������Ă��������B
�������Ȃ��Ȃ�ARAW�Ȃ�O�a���Ă��Ȃ��ƒf������ׂ��ł͂���܂���B
�M�����uRAW �Ȃ� 1024bit �Ȃ̂� JPEG ���]�T������v�Ƃ����咣�́A�O�a���Ă��Ȃ��Ƃ��������ɂ��Ȃ�܂��A�_�C�i�~�b�N�����W�ƊK�������������Ă��܂��B
>�l�Ԃ̊�����R���x���オ��ΖO�a����̂�
>���ۂɌ����ڐ��F�̋�ł���A�摜��ł����F�ŗǂ��̂ł́H�ƌ����Ă��܂��B
�����ڂƓ������ǂ����ɂ��Ă͂����ł͌��_�͏o�܂��A�ǂ����ǂ����Ƃ͕ʖ��ł��B
�i�D�݂̖��ɕt���Č��_���o������͂���܂���j
�܂��A���܂��܂ł���\���ɂ��Ă��ے�ł��܂���B
�u���O�a���Ă���v�Ƃ��������ɑ��A
>�ł�����u�O�a�������炾�v�u����f���f�������炾�v�Ƃ����ӌ��ɔ��_���Ă��܂��B[8749906]
>���w�E�̏�Ԃ́u�F���O�a���Ă���v�ł͖����āu���x���オ���ĔZ�x�������Ă�v�Ƃ����܂��B[8750762]
�ƖO�a��F�߂Ȃ��̂͋M���ł����B
>���������Ӗ���
>�u8bit��ŖO�a���Ă���ȏ�i�J���[�o�����X�������Ă���̂Łj�F����͂ł��Ȃ��v
>�Ƃ����̂͌�肾�Ƃ����Ă��܂��B
�O�a����ƐF����͂ł��܂���B����ɂ��Ă͂���ƍ��ӂ���ꂽ�Ƃ������Ƃł����ł��ˁB
����� JPEG ���낤���ARAW ���낤�������ł���B
�ŁARAW ���O�a���Ă��Ȃ��Ƃ����������o���Ă��������A�ƌ����Ă���̂ł��B
���̌�����[8752912]�ŃR�����g�ς݂ł��B
�����ԍ��F8780500
![]() 3�_
3�_
>������ł�RAW�����\�t�g�́u�I�o�v�Ƃ͂ǂ�������`�Ȃ̂ł��傤���B
>�I�����Ԓ��ɐF�t�B���^�[�����ɂ��������ԂŐF���������s���̂Łu�I�o�v�Ȃ킯�ł��B
�����ł���B���ɂ��������Ԃ��u�I�o�v�ƌ����܂��B�Ώۂ��t�B�������낤����掆���낤���B
�����āA�M���̓J���������ɐ����̘I�o��ς���@�\������A�Ə������̂ŁA����Ȃ̂͂���܂���A�Ǝ��������Ă��܂��B
>���ʐ^�̂���͈Ⴄ�ƌ���Ă����̂͋M�����Ǝv���܂����B
>�ł�����ARAW�摜�������܂�������Ă�i�K�ŁA8bit�摜���ʐ^�Ƃ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W���L���킯�ł���ˁH
>�K���̍��́A���������̃r���ʼn��K���Ăɂ��邩�̍��ł��B
>�_�C�i�~�b�N�����W�̍��́A�r���̍������̂̍��ł��B
�����̏����Ă��邱�Ƃ�ǂ��ǂ�ł��������B
RAW �͊K�������邩������܂肪����i�]�T������Ƃ����Ӗ����Ɖ��߂��Ă��܂��j�A�ƋM���͌J�肩�����Ă��܂��������ł͂���܂���B
�K���̓r���̊K���B�����ă_�C�i�~�b�N�����W�̓r���̍������Ƃ���ƁA�K���ƃr���̍����͒��ڊW���Ȃ��̂ł��B
�Ⴆ CCD �̏o�͂� 8bit�i8bit RAW�j�������Ƃ��Ă��AWB �����킹����� 8bit JPEG �ɂ��邱�Ƃ͂ł��܂��BRAW �� 8bit �����Ȃ��ꍇ�A�K�����������Ƃ����蓾�邾���ł��B
�t�� CCD �̓����Ƃ��ă_�C�i�~�b�N�����W�������ꍇ�A������K���𑝂₵�Ă��A�O�a�i�┒��сj��h����킯�ł͂���܂���B
>�܂�_�C�i�~�b�N�����W��4�{�������ꍇ�́AISO200����Ƃ����
>������ISO100�Ŕ�Ȃ����x���܂ŁA�Õ���ISO400�Ńt�H���[�ł���͈͂܂ł̖��Í��ɑΉ�����Ƃ������Ƃł��B
>�����e�x4�{�Ƃ����Ӗ��ł�����B
#>���Ȃ݂Ƀ_�C�i�~�b�N�����W400���Ƃ����̂��A���ۂɂ͂���܂���O�O
�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA���ꂪ���蓾�Ȃ��Ƃ������R���q�ׂĂ��������B
>���Ƃ����A�ǂ��ŊԈႢ��F�߂Ă���̂��������������Ƃ���ł��B
>[8765220]�̖`���ł��B�X�O��̃��X���āA���̃��X�������݂��܂���B
>�͂͂́A�z���g�ł��ˁO�O
����ł����H���ꂪ�R�o���g�u���[�̌����w���Ƃ͂킩��܂���ł����B
�����ԍ��F8780503
![]() 2�_
2�_
�K��takebeat����A
>>��f���x���̃_�C�i�~�b�N�����W��4�{�ɂȂ������Ƃ��_�C�i�~�b�N�����W 400% �ƌ����Ă����ł�����܂���B
�������Ⴂ���Ă��܂��H
��f���x���i�����ł� CCD �̏o�̓��x���Ƃ����Ӗ��j�̃_�C�i�~�b�N�����W�� 400% �ɂȂ�����ł͂Ȃ��Ƃ����͈̂ȑO���猾���Ă��܂��B
�Ⴆ�AF30 �� F31fd �Ɣ�r���āAF100fd �� CCD �̃_�C�i�~�b�N�����W���L���Ȃ����̂ł���AF30 �� F31fd ���������x�����͗ǂ��Ȃ��Ă��锤�ł����A�܂��n�j�J�� SR �Ȃǂł�2��f�ɕ�����K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F8780507
![]() 0�_
0�_
���͂��A�Ԗ����o�Ă�Ƒ����ł�̂͋�̈ꕔ�������Ȃ̂ł����H
����Δ���܂��ˁB
��GX200 �Ƃ̔�r�ł͕s�\���Ȃ�A�ǂ����������ŁB
�����ڂɍł�����₷���摜����͓�����̂ł��ˁB
�����[��A�R�������Ă͂����܂���B
�R�������Ă���̂͂�����ł��B
���_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̓m�C�Y�ƐM���̍ő�l�̔�ł��B
�������ăV���b�g�m�C�Y���l�̃o���c�L�Ƃ��ďo�Ă���m�C�Y�ł�����A���R�_�C�i�~�b�N�����W�ɉe����^���܂��B
�m�C�Y�̎�ނ��������Ă��܂���B
��1��f������̖ʐς��ɒ[�ɋ����R���p�N�g�f�W�J���ł͓��ɁA�ł��B
�V���b�g�m�C�Y��1��f�̖ʐς��������f���ɉe����^���邱�Ƃ͏����܂����B
�ł����A����̓_�C�i�~�b�N�����W�ɂ����Ăł͂���܂���B
����₷�������O���[�̃x�^������f�ɋψ�ɓ��͂����ꍇ�V���b�g�m�C�Y���Ȃ���ψ�̃O���[�ƂȂ�܂��B
�V���b�g�m�C�Y�����݂���ƁA�O���[�ɔ����ȐF�ނ炪�o�܂��B
�ꍇ�ɂ����10�̓��͂ɑ���9�Ƃ��̐��l���o�͂����f�����邩��ŁA���ꂪRGGB4�ŋN����܂��B
���̐F�ނ�i�m�C�Y�j���摜�̊K����s���m�ɂ���i�r�ꂽ�摜�ɂȂ�j�A�Ƃ������Ƃł��B
������ł͂������Łi�j
�����ł����ǂˁB�����Ă��B
���f�W�^���f�[�^�Ƃ��Ă͉��̖��������ł��܂���
�ʐ^�ɂȂ�Ȃ�����RAW�摜���f�W�J���̓��͂ł͂��̂悤�ȏ����͂��Ȃ����J�����Ƃ��Ăł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�ʐ^�ɂȂ��Ă��Ȃ��f�W�^���f�[�^�Ƃ��Ăł�������ǂ����ƌ����̂ł��H
���M���̐E��Łu�O���F�v�Ƃ����p��Ńg���u�����N���邩�ǂ����ł͂Ȃ��A�O�������������p��ł���Ƃ̍������I���Ă��������ˁB
���ꂪ�ŏd�v���̂悤�ł��ˁB
�ł͌��̎O���F���k�߂��p��ƌ������ƂŁB
�����X�Ƃ��Ɠ����ł��ˁB
�O�������������p�ꂶ��Ȃ����玩���̌������Ƃ͐������A�Ƃ������Ƃł����炲����ɁB
��#>RAW�摜��Hibit�摜�i��f���x���j�ł͍�������8bit�����L���͈͂ŋL�^���Ă���̂ł��B
��#>�܂�A�O�a���Ă��Ȃ���Ԃł��B
�ʏ�͈̔͂ŁA�ł��ˁB
��#>�ł�����u��f���x���ŖO�a����قNjɒ[�Ȗ��Í�������̂łȂ�����v
��#>8bit�摜��ŖO�a���ĂĂ�RAW�摜�ł͖O�a���ĂȂ��̂ł��B
��f���x���ŖO�a����قNjɒ[�Ȗ��Í�������̂łȂ�����A�Ɩ��m�Ɍ��肪����܂��ˁB
��#>�����ARAW�摜�i�K�ł͕K��8bit�摜�������܂������Ă��܂��̂�
��#>�O�a���Ă��邩�ǂ����͂��Ă����A8bit��ŖO�a���Ă����Ԃ��͊m���ɊK���]�T��������̂ł��B
���������d�l�ł���B�ŏ�����RAW�摜�́B������Hi-bit�摜���Ⴀ��܂���B
���uRAW �Ȃ� 1024bit �Ȃ̂� JPEG ���]�T������v�Ƃ����咣
����Ȏ������Ă��܂���B
��1024bit�͓��̓~�X�ł���ˁH���Ԃ�10bit1024�K���̂��Ƃł��傤�B
�����܂�RAW�摜��JPEG�摜�̊W�́A�����摜��Hi-Bit�摜��8bit�摜�̊W�Ƃ͈قȂ�̂ł��B
�����O�҂̓_�C�i�~�b�N�����W�ƊK�����قȂ�܂����A��҂͊K���̍������ł�
�Ɩ��L���܂���
�������ڂƓ������ǂ����ɂ��Ă͂����ł͌��_�͏o�܂���
���ꂪ�匳�̘b�������͂��ł��B
���M���̓J���������ɐ����̘I�o��ς���@�\������A�Ə������̂�
�f�W�^���J�����ɂ͐E�ԁE���ׂĂ̘I�o������@�\��������Ă��܂��B
�t�C�����J�����ɂ͑��݂��Ă��Ȃ��ƌ������Ƃł��B
��RAW �͊K�������邩������܂肪����i�]�T������Ƃ����Ӗ����Ɖ��߂��Ă��܂��j�A�ƋM���͌J�肩�����Ă��܂���
����Ȃ��Ƃ͌����Ă��܂���B
�_�C�i�~�b�N�����W�ɗ]�T������Hi-bit�摜���ƌ����Ă��܂��B
��CCD �̏o�͂� 8bit�i8bit RAW�j�������Ƃ��Ă��AWB �����킹����� 8bit JPEG �ɂ��邱�Ƃ͂ł��܂��B
������܂��ł��B
�������ꂾ�Ƃ܂Ƃ��ȉ摜�ɂȂ�Ȃ�����A�f�W�J���͊K���ɃA�h�o���e�[�W�̂���Hi-bit���������܂��B
���Ɍ���Web�J�����̏o�͂�8bit�ł��ˁBWB���킹��Ƃǂ��Ȃ邩����₷���Ǝv���܂��B
��#>���Ȃ݂Ƀ_�C�i�~�b�N�����W400���Ƃ����̂��A���ۂɂ͂���܂���O�O
���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA���ꂪ���蓾�Ȃ��Ƃ������R���q�ׂĂ��������B
����܂���A�ƁA���蓾�܂���A�͕ʂ̈Ӗ��ł���H
�B�e�f�q���x����400���Ɋg�債�Ă���@��͂Ȃ�����ł��B
�܂�́A����т��������ƃJ�����������f�����i�K�ŘI�o�𗎂Ƃ�
�Õ��̃f�B�e�[���͈Õ���������ĊK����L�������āA�������̃_�C�i�~�b�N�����W���g���Ă܂���ˁH
���ꂪ�ł���̂́A�������̃f�W�^���G���W���̏o����
�L�������邾���̗]�v�ȊK����Hi-bit�i12bit�ȏ�j�摜�������Ă��邩��ł��B
������ł����H���ꂪ�R�o���g�u���[�̌����w���Ƃ͂킩��܂���ł����B
����͎c�O�ł��B
�����ԍ��F8780607
![]() 1�_
1�_
>����Δ���܂��ˁB
>�����ڂɍł�����₷���摜����͓�����̂ł��ˁB
�M���̍�������������ƁH�I
�������̍����͎����Œ���͓̂�����O�ł��B
�����łł��Ȃ��̂Ȃ瓦���Ă���̂͋M���ł���B
>���_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̓m�C�Y�ƐM���̍ő�l�̔�ł��B
>�������ăV���b�g�m�C�Y���l�̃o���c�L�Ƃ��ďo�Ă���m�C�Y�ł�����A���R�_�C�i�~�b�N�����W�ɉe����^���܂��B
>�m�C�Y�̎�ނ��������Ă��܂���B
�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8
�V���b�g�m�C�Y�͓��R���ʉ\�ȐM���l�ł͂���܂���m�C�Y�ł��B���ʉ\�ȐM���l�Ȃ�m�C�Y�Ƃ͌����܂���B
���āA�m�C�Y�̎�ނɂ���ă_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��Ƃ��������������Ă��������B
��发�A�������͐��T�C�g�ł��肢���܂��B
>�ł����A����̓_�C�i�~�b�N�����W�ɂ����Ăł͂���܂���B
���̃_�C�i�~�b�N�����W�̒�`���I���Ă��������B
���͏�L�̑O�q�̒ʂ�ł��B
>����₷�������O���[�̃x�^������f�ɋψ�ɓ��͂����ꍇ�V���b�g�m�C�Y���Ȃ���ψ�̃O���[�ƂȂ�܂��B
>�V���b�g�m�C�Y�����݂���ƁA�O���[�ɔ����ȐF�ނ炪�o�܂��B
>�ꍇ�ɂ����10�̓��͂ɑ���9�Ƃ��̐��l���o�͂����f�����邩��ŁA���ꂪRGGB4�ŋN����܂��B
>���̐F�ނ�i�m�C�Y�j���摜�̊K����s���m�ɂ���i�r�ꂽ�摜�ɂȂ�j�A�Ƃ������Ƃł��B
�ԈႢ����R����܂��B
�m�C�Y�̌����̓V���b�g�m�C�Y�����ł͂Ȃ��ł�����A�V���b�g�m�C�Y����������ψ�̃O���[�ɂȂ��ł͂���܂���B�i�ނ��둽���̐F�����̌����̓V���b�g�m�C�Y�ł͂���܂���j
�������A�V���b�g�m�C�Y�Ɍ��炸�S�Ẵm�C�Y�͊K����s���m�ɂ��܂��B
����ł��B�����f�̏o�͂� 11 �������ꍇ�A�M���͂��̌����̃m�C�Y�����ʕt���̂ł����H
�����������łR��B�e������f�̏o�͂��A9, 11, 10 �ł����B���̂����V���b�g�m�C�Y�̗ʂ́H
�܂��A���̏ꍇ�̃_�C�i�~�b�N�����W�̎Z�o���́H
>�ʐ^�ɂȂ�Ȃ�����RAW�摜���f�W�J���̓��͂ł͂��̂悤�ȏ����͂��Ȃ����J�����Ƃ��Ăł��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
#>�K������1024�K������1023��256�K���̔��Ƃ��A0�����ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
#>�������Ɍ����A����́u�ł��Ȃ��v�킯�ł����B
WB ������ߒ��ŕK�v�ł���A�J�����͍s���܂���B8bit RAW ���� 8bit JPEG �����l�ɁB
�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł��B
�M���̘_�_�͂����ł��B
>���̂悤��RGB�e�`�����l���ɉ����āu�����܂�v�������Ȃ����
>AWB�ŃL�����u���[�V��������ăV�t�g�����F���256�K�����ێ��ł��܂����ˁH
�����܂蕔���i�]�T�Ƃ������Ƃł��傤�j�������Ă��A256 �K���������I�Ɉێ��ł��Ȃ��Ă� JPEG �摜�͐������܂��B
�ǂ�ȃJ�������A�Ⴆ�Δ���т��� RAW ����ł� JPEG �摜�͋N�����܂�����B
�t�Ɍ����A10bit RAW �ɕ����܂蕔�������낤�������낤���A JPEG �摜�͐������܂��B
�܂�A 10bit RAW ������O�a���Ă��Ȃ��Ƃ��������ɂ͂Ȃ�܂���B
>�ł͌��̎O���F���k�߂��p��ƌ������ƂŁB
>�O�������������p�ꂶ��Ȃ����玩���̌������Ƃ͐������A�Ƃ������Ƃł����炲����ɁB
���́A�������p��͎O�������ƃR�����g�����̂͋M���ł���H
���x�͊J������ł����H
>�ʏ�͈̔͂ŁA�ł��ˁB
>��f���x���ŖO�a����قNjɒ[�Ȗ��Í�������̂łȂ�����A�Ɩ��m�Ɍ��肪����܂��ˁB
>���������d�l�ł���B�ŏ�����RAW�摜�́B������Hi-bit�摜���Ⴀ��܂���B
�ł�����T���v���摜���ʏ�͈̔͂ł������̂� RAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ������Ƃ��������������Ă���������B
�����܂�RAW�摜��JPEG�摜�̊W�́A�����摜��Hi-Bit�摜��8bit�摜�̊W�Ƃ͈قȂ�̂ł��B
�����O�҂̓_�C�i�~�b�N�����W�ƊK�����قȂ�܂����A��҂͊K���̍������ł�
����ł́A�M���̌���Hi-Bit�摜��8bit�摜�̒�`�𖾂炩�ɂ��Ă��������B
�O�����������ł����A��ʓI�łȂ��p����g��Ȃ��l�ɂ��邩�A�Ǝ��̗p��ɂ͐������B
�������ڂƓ������ǂ����ɂ��Ă͂����ł͌��_�͏o�܂���
>���ꂪ�匳�̘b�������͂��ł��B
�������A �����ڂ̘b�ɂ��ẮA�B�e�҈ȊO�͂킩��Ȃ��A��[8750548]�ŃR�����g�����ʂ�ł���B
�����ډ]�X�ɂ�������Ă���̂͋M�������ł��B
>���M���̓J���������ɐ����̘I�o��ς���@�\������A�Ə������̂�
>�f�W�^���J�����ɂ͐E�ԁE���ׂĂ̘I�o������@�\��������Ă��܂��B
�I�o�Ƃ́A�t�C�������掆�Ɍ��Ă邱�Ƃ������܂��B
����Ȃ�A�O���F���ƂɘI���ʂ����߂�@�\�i�J�����Ō����V���b�^�[�j���K�v�ł��B
�ǂ̃J����������ȋ@�\������ƁH
���_�C�i�~�b�N�����W�ɗ]�T������Hi-bit�摜���ƌ����Ă��܂��B
�ł�����A�T���v���摜�� RAW �ł̓_�C�i�~�b�N�����W�ɗ]�T���������Ƃ����������B
�����ԍ��F8780687
![]() 2�_
2�_
��#>���Ȃ݂Ƀ_�C�i�~�b�N�����W400���Ƃ����̂��A���ۂɂ͂���܂���O�O
>�B�e�f�q���x����400���Ɋg�債�Ă���@��͂Ȃ�����ł��B
�B�e�f�q���x���� 400% �Ɋg�債�Ă���@�킪����Ƃ͒N���R�����g���Ă��܂���B
�N�������Ă��Ȃ����Ƃ��u���ۂɂ͂���܂���v�Ǝw�E���Ă���̂ł����H
>�܂�́A����т��������ƃJ�����������f�����i�K�ŘI�o�𗎂Ƃ�
>�Õ��̃f�B�e�[���͈Õ���������ĊK����L�������āA�������̃_�C�i�~�b�N�����W���g���Ă܂���ˁH
����͂P�̕����ł�������܂����ˁB
�������u�������̃_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ̂��Ƃł����A���摜�ɂ���Ȃ�̃_�C�i�~�b�N�����W���K�v�ł��B
>���ꂪ�ł���̂́A�������̃f�W�^���G���W���̏o����
>�L�������邾���̗]�v�ȊK����Hi-bit�i12bit�ȏ�j�摜�������Ă��邩��ł��B
��͂�ǂ����Ă��������Ă��܂��悤�ł��ˁB�]�v�ȊK���ł͂Ȃ��A�]�v�ȃ_�C�i�~�b�N�����W���K�v�Ȃ�ł��B
�K���͂����炠���Ă��A���������\���ȃ_�C�i�~�b�N�����W��������ΈӖ�������܂���B
�K���ƃ_�C�i�~�b�N�����W�͊֘A������̂ł͂���܂���B
�M���������Ă��Ȃ����e����ׂ܂��B
�E��F��������ƐԂ������Ȃ�Ƃ��������iP6000�̉摜�H�j
�E�u�K���������v�Ƃ́H�̉�
�E�m�C�Y�̎�ނɂ���ă_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��Ƃ�������
�E�m�C�Y����������m�C�Y�̎�ނ����ʂ�����@
�E�����������ŎB�e������f�̏o�͂��A9, 11, 10 �ł����B���̂����V���b�g�m�C�Y�̗ʂ́H
�E�܂��A���̏ꍇ�̃_�C�i�~�b�N�����W�̎Z�o���́H
�E�T���v���摜���ʏ�͈̔͂ł������̂� RAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ������Ƃ�������
�EHi-Bit�摜��8bit�摜�̒�`
�E�E�ԁE���ׂĂ̘I�o������@�\��������Ă���J����
�E1��f�ʐς�4�{�ɂ���ƖO�a�d�חʂ�4�{�ɂȂ鍪��
���m�ɂȂ�����
�EJPEG �ł� RAW �ł��O�a���Ă�����F�����Č��ł��Ȃ��Ȃ�[8780500]
�E�R�o���g�u���[�ɂ͐Ԑ����͂قƂ�ǂȂ�[8780503]
�EGX200 �͖��ʐF�������Ԑ����������i�Ԃ��Ă��z���C�g�o�����X�̖��j[8780503]
�E�V���b�g�m�C�Y��1��f�̖ʐς��������f���ɂ�苭���e����^����[8780607]
�E�O�����͐����ȗp��ł͂Ȃ�[8780607]
�����ԍ��F8780703
![]() 2�_
2�_
���M���̍�������������ƁH�I
�T���v���摜������Ζ������ƌ����o�����̂͂�����ł�����B
���s���̗ǂ��T���v���摜�����Řb��W�J����͕̂ςł��B�T���v���摜��4������܂��B
�����̃_�C�i�~�b�N�����W�̒�`���I���Ă��������B
�ʐ^�ɂ����Ẵ_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́u���e�x�v�u���`���[�h�v�ƕ\������Ă��܂��B
�܂茻���̐��E�ł̖��Í����A�ǂꂾ�����������A����ׂꂳ�����Ɏʐ^�摜�ɍČ������邩�ł��B
�|�W�e�B�u�摜�ł����A������_�Ƃ��āA�ǂ��܂ł̖��x���K���\���ł��邩�ƂȂ�܂��B
�ł�����_�C�i�~�b�N�����W400���i�����j��搂��t�W�̐��i�ł́u����т��Ȃ��v�ƌ��ʂ�\�����܂��B
���m�C�Y�̌����̓V���b�g�m�C�Y�����ł͂Ȃ��ł�����
�u����₷�������v�Ɩ��L���Ă��܂���ˁH
�����ăV���b�g�m�C�Y���ǂ������m�C�Y���H�Ƃ��������ɁA�m�C�Y�͑��ɂ�����ƌ����o���Ăǂ��������ł����H
���X�_�C�i�~�b�N�����W�̐����ŁA��{�I�ȃm�C�Y�ɂ��Ęb��������
�u�V���b�g�m�C�Y�̕����d�v���v�ƌ����o���ꂽ�̂ł͂Ȃ��̂ł����H
�������������łR��B�e������f�̏o�͂��A9, 11, 10 �ł����B���̂����V���b�g�m�C�Y�̗ʂ́H
�������Ⴂ���Ă��܂��H
�V���b�g�m�C�Y�Ƃ́A���Z�����m�C�Y�ł͂���܂���B���Z�����m�C�Y�ł��B
���܂��A���̏ꍇ�̃_�C�i�~�b�N�����W�̎Z�o���́H
�V���b�g�m�C�Y�͊K���̐��m���Ɋւ����肾�Ɩ��L���Ă���̂�
�Ȃ��_�C�i�~�b�N�����W�����ɂȂ�̂ł����H
�������u�����������łR��B�e������f�̏o�͂��A9, 11, 10 �ł����B�v��
�ǂ�����ă_�C�i�~�b�N�����W�𑪂�̂ł����H
�������������������̓��͌��̋����ƁA���̉�f�ł̏o�́A���̎��̍����x���̒l���炢�͎����Ă��������ˁB
��256 �K���������I�Ɉێ��ł��Ȃ��Ă� JPEG �摜�͐������܂��B
������A���������Ɛ��i�̎����������ƂɂȂ�̂ŁA�������Ȃ��ōςނ悤�ɐv����Ă���̂ł��B
��10bit RAW ������O�a���Ă��Ȃ�
�Ƃ������Ă��܂����ˁH
�ǂ�ȃJ�����������i��J����1�����V���b�^�[�J���Ă�Δ�т܂��B
�ɒ[�ȗ���苓���Ď����̐�������͐�����̂͂����g�̃X�^�C���ł����H
���ł�����T���v���摜���ʏ�͈̔͂ł������̂� RAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ������Ƃ��������������Ă���������B
�ŏ�����uRAW�摜�����Ȃ���Δ��f�t���Ȃ��b���v�ƌ��������Ă��܂���ˁH
������ł́A�M���̌���Hi-Bit�摜��8bit�摜�̒�`�𖾂炩�ɂ��Ă��������B
8bit�摜�͍ŏ��l�ƍő�l�̊Ԃ�2��8�敪=256�K���̂���摜�ł��BRGB�摜�ł����3�`�����l������܂��B
Hi-bit�摜�Ƃ́A��ʂ�8bit�摜���K�����̑����摜�ŁA�����ɂ�9bit�i2��9��=512�j�ȏ�̉摜�ł��B
���ۂ̃f�W�^���J�����摜�ł́A10�A12�A14bit�ł̐������s���܂���
Photoshop�ł�16bit�y��32bit�K���܂ŃT�|�[�g����Ă��܂��B
Photoshop�����ۂ�Hi-bit�摜��肳���Hi-bit���T�|�[�g����̂�
�F�������Ȃǂ̎��ɋN����K����т�h�~���邽�߂�
8bit�摜�̒������A��x16bit�ɕϊ��㒲�����A�����ēx8bit�ɖ߂��������������̊K���m�ۗ������܂�܂��B
�����ԍ��F8782350
![]() 1�_
1�_
�������ډ]�X�ɂ�������Ă���̂͋M������
���̃X�������߂���ǂ�ł͂ǂ��ł��傤�H
�̌����ڂ̘b��ȊO�̉����ł��Ȃ��Ǝv���̂ł����B
���I�o�Ƃ́A�t�C�������掆�Ɍ��Ă邱�Ƃ������܂��B
�O�ɂ������܂������ARAW�������́u�I�o�v���ɘI���ʂ����߂Ă��܂���ˁH
�f�W�^���J�����ł́ARGB���ꂼ���ʁX�ɐM�������܂�����ARAW�������ɂ��ꂼ��̘I�o�����܂��B
���̘I�o�������u�J���[�o�����X�����v�Ƃ������Ƃł��B
���̋@�\���f�W�J���ɖ�����A�f�W�J�����ŐF�������s���Ȃ��ł���ˁH
��G10�ł̓}�C�J���[�Ƃ��āAJPEG�쐬���ɔ��f�����F������ݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
���ł�����A�T���v���摜�� RAW �ł̓_�C�i�~�b�N�����W�ɗ]�T���������Ƃ���������
���S�Ɋ��Ⴂ���Ă���Ǝv���̂ł����E�E�E
RAW�摜�̃_�C�i�~�b�N�����W���L���̂́u�d�l�v�ł��B
�����Ă݂�A10L����o�P�c�Ƃ������ƂŁA��������K�v�ȗʂ����o���čŏI�o�͂��s���܂��B
���̌������i��15L���������ꍇ�ARAW�ł�����i�O�a�j���܂���
�ŏI�o�͂�4�`5�k�̃o�P�c�Ŏ���́A�����̏����ێ����Ă��܂��A�Ƃ����Ă܂��B
�ł�����T���v���摜���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł�RAW�摜�Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�̗]�T�����邱�Ƃɕς�肠��܂���B
���N�������Ă��Ȃ����Ƃ��u���ۂɂ͂���܂���v�Ǝw�E���Ă���̂ł����H
�u���Ȃ݂Ɂv�Ƃ������{��̈Ӗ����������ł����H
���ڂ͊W�Ȃ����A1�̘b��ɂ��Ȃb��Ƃ��Đ�������Ƃ��Ɏg�����t�ł��B
������͂P�̕����ł�������܂����ˁB
��̓I�ȕ��@���������Ƌ�ꂽ�̂Ő��������܂łł��B
�����摜�ɂ���Ȃ�̃_�C�i�~�b�N�����W���K�v�ł��B
����ł����A���́u���摜�v�Ƃ͂ǂ̉摜�̂��Ƃł����H
�����̕��i�Ȃǂł͂Ȃ��Ƃ���ARAW�摜�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�O�q�̂悤��RAW�摜�́u����Ȃ�̃_�C�i�~�b�N�����W�v���m�ۂ��Ă܂�������͂Ȃ����ƁB
����͂�ǂ����Ă��������Ă��܂��悤�ł��ˁB
���Ȃ����������Ă��邾���ł��B
Hi-bit�ƍ��_�C�i�~�b�N�����W�͕͂ʕ��ł��B
RAW�摜�́A���̗���������Ă���Ɖ��x�����L���Ă��܂��B
�M���������Ă��Ȃ����e����ׂ܂��B
�E��F��������ƐԂ������Ȃ�Ƃ��������iP6000�̉摜�H�j
�E�u�K���������v�Ƃ́H�̉�
�E�m�C�Y�̎�ނɂ���ă_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��Ƃ�������
�E�m�C�Y����������m�C�Y�̎�ނ����ʂ�����@
�E�����������ŎB�e������f�̏o�͂��A9, 11, 10 �ł����B���̂����V���b�g�m�C�Y�̗ʂ́H
�E�܂��A���̏ꍇ�̃_�C�i�~�b�N�����W�̎Z�o���́H
�E�T���v���摜���ʏ�͈̔͂ł������̂� RAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ������Ƃ�������
�EHi-Bit�摜��8bit�摜�̒�`
�E�E�ԁE���ׂĂ̘I�o������@�\��������Ă���J����
�E1��f�ʐς�4�{�ɂ���ƖO�a�d�חʂ�4�{�ɂȂ鍪��
����̐����Ŕ����������O���čČf���Ă��������B
���́A�����牽�܂Ŏ����̗������x���ɍ��킹�Ĕ[��������Ƃ����p���ɑ�ςȈ�a��������܂��B
����Ɏ����Ŗ��Ӗ��Ȏ���𑝂₵�āu�����Ă��Ȃ����ڂ���R����v�Ƃ����p�������̂��s�v�c�ł��B
�����ԍ��F8782353
![]() 1�_
1�_
>���̃X�������߂���ǂ�ł͂ǂ��ł��傤�H
on the willow���� �ł͂���܂��E�E�E�B
���͂��̃X���ŏ�����ǂ�ł��܂�����B�X����ł��� ���ނ����p�p���� �̍Ō�̃R�����g [8740547] ������܂ł́B
����ȍ~�͉��Ń_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ��m�C�Y�Ƃ��̘b�ɂȂ�̂��킩��܂��B
�����̐l���ӂ��Ɋ�����ł��낤�Ǝv����u��̖O�a�v���A�n�i����ے肷�� �A�L���Z����B
�Ǝ��v�z����������̂͂��������Ȃ̂ł����A����������Ɏ咣��������{���̗��R�͉��Ȃ̂ł��傤�H
�f�W�J���D���D��������A�����Ȃ錇�_�����F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��H
���_���L�܂������ʂ̃f�W�J���E�̐��ނ��뜜�H
�S�ꂩ��f�W�J���Ɍ��_�͖����ƐM���Ă���H
�P�ɋC���������Ȃ邩��H
�u���Ȃ݂Ɂv��̖O�a���ċ@��̌��_�ł͂Ȃ��ł���H
�����ԍ��F8782994
![]() 1�_
1�_
>�T���v���摜������Ζ������ƌ����o�����̂͂�����ł�����B
>���s���̗ǂ��T���v���摜�����Řb��W�J����͕̂ςł��B�T���v���摜��4������܂��B
�͂��A�ł����玄�̍����Ƃ��ăT���v���摜���A�b�v���܂����B�Ԍn�������Ƃ��ă}�[���^���������グ��̂͏œ_���ڂ��܂���A�ƒ��ӂ��Ă��܂��B�iG10 �̓}�[���^���̂��̂��O�a���Ă��܂��j
�M���͎��̎咣�⍪���ɔ��_������悤�ł�����A�M���̔��_�̍����ƂȂ�摜���A�b�v���Ă��������B
�M���̔��_�̍������M�����p�ӂ���͓̂�����O�ł��B
�_�_�͂����ł��B
>�����āA�̐F�������摜�ɂ́A��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�X��������܂��B
>�Ɨō\�����ꂽ��̐F�ɐԂ݂������Ă��܂��Ă���T���v���摜�̋@��͂ǂ�Ƃǂ�ł��傤�H
�ł�����A�̐F���������ɂ���āu�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�Ƃ��������m�ɂ��Ă��������B
�������A���ʐF���������グ�āA�z���C�g�o�����X�̉e���łȂ��������m�ɂ��Ă��������B
�̐F�������A�ƌ����鍪�������Y��Ȃ��B
-------------
>�����̃_�C�i�~�b�N�����W�̒�`���I���Ă��������B
>�ʐ^�ɂ����Ẵ_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́u���e�x�v�u���`���[�h�v�ƕ\������Ă��܂��B
����ł͋M���̌����_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A�ʐ^�p��ł̃��`�`���[�h�ilatitude�j�Ɠ����Ƃ������Ƃŗǂ��̂ł����H
[8770657] �ŋM���́A
>���ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ����̂̓��`���[�h�͈̔͂ł͂Ȃ��ł���B
>������摜�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ɖ�f���x���ł̓d���̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃł͈Ӗ����ς��܂��B
�ƃR�����g���Ă��܂����H�I
-------------
>�V���b�g�m�C�Y�Ƃ́A���Z�����m�C�Y�ł͂���܂���B���Z�����m�C�Y�ł��B
�Ԉ���Ă��܂��B
�V���b�g�m�C�Y�̈Ӗ����������Ă���̂��Ǝv���Ă����̂ł����A�����ł͂Ȃ��悤�ł��ˁB
�V���b�g�m�C�Y�̓t�H�g�����d�ׂގ��̌덷�ł��B�܂�A�{����������d�ׂ������Ȃ���������A������������܂�����A�i�]���Ɂj���Z����鎖������A�i���肸�Ɂj���Z����鎖������܂��B
�����炱���A�t�H�g���������i�����ʂ������j�̂ł���A�V���b�g�m�C�Y�͕��ω����ꏭ�Ȃ��Ȃ�܂��B
-------------
>�V���b�g�m�C�Y�͊K���̐��m���Ɋւ����肾�Ɩ��L���Ă���̂�
>�Ȃ��_�C�i�~�b�N�����W�����ɂȂ�̂ł����H
�ł�����A�V���b�g�m�C�Y���m�C�Y�̈��ł�����A�_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����܂��B
�덷�i�o���c�L�j�P�̐M��������A���̌덷�̌����͉��ł���P�ȉ��̍������M���͈Ӗ��𐬂��܂���B
�Ⴆ�� �P�O �Ƃ����o�͂��������ꍇ�A���ꂪ�{���X�ł��邩�A�P�P�ł��邩�͎��ʂł��Ȃ��̂ł��B
�M���͂�����u�K���݂̂ɉe�����A�_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��v�Ǝ咣���Ă��܂����A�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͗L���ȐM�����ƃo���c�L�i���m�C�Y�j�Ƃ̔�ł�����A���R�̂��ƂȂ���_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����܂��B
�V���b�g�m�C�Y�̓_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��Ƃ����̂́A�I�J���g�Ȋw�ƌ����Ă��ǂ��咣�ł��B
���ɍ���������̂Ȃ�A��发����T�C�g����Ă��������ƌ����Ă��܂��B
-------------------
>�ŏ�����uRAW�摜�����Ȃ���Δ��f�t���Ȃ��b���v�ƌ��������Ă��܂���ˁH
�������A�M���͂����� RAW �͖O�a���Ă��Ȃ��ƒf�����Ă��܂��B
�܂��A�P�����V���b�^�[���J���Ȃ��Ă��A�����̖��Í��ŋ�̐F����ԂƂ������Ƃ͗ǂ����邱�Ƃł��B
�ł�����ARAW �͖O�a���Ă��Ȃ��Ƃ��鍪�������߂Ă��܂����B
����ł́A�M���̎咣�Ƃ��Ă� RAW �͖O�a���Ă��邩�ǂ����͔���Ȃ��A
JPEG �̏o�͒i�K�ł͖͐O�a���Ă���A�Ƃ������ŋX�����ł��傤���B
--------------------
>8bit�摜�͍ŏ��l�ƍő�l�̊Ԃ�2��8�敪=256�K���̂���摜�ł��BRGB�摜�ł����3�`�����l������܂��B
>Hi-bit�摜�Ƃ́A��ʂ�8bit�摜���K�����̑����摜�ŁA�����ɂ�9bit�i2��9��=512�j�ȏ�̉摜�ł��B
�ł́AJPEG�摜��8bit�摜�A10bit RAW �摜�� Hi-bit �摜�Ƃ��Ă��ǂ��A�Ƃ������Ƃł����H
[8780132]�ŋM���́A
���܂�RAW�摜��JPEG�摜�̊W�́A�����摜��Hi-Bit�摜��8bit�摜�̊W�Ƃ͈قȂ�̂ł��B
���O�҂̓_�C�i�~�b�N�����W�ƊK�����قȂ�܂����A��҂͊K���̍������ł�
�Ƃ����咣���Ă��܂����A���̐����ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B
�����ԍ��F8783130
![]() 1�_
1�_
>�̌����ڂ̘b��ȊO�̉����ł��Ȃ��Ǝv���̂ł����B
�����ł���B�e�J�����ł̋�F�i�F�j�̍Č������X���b�h�̘b��ł��B
�����āAG10 �̋�F�́A�O���F�̐��O�a���Ă���Ƃ��������ƁA�X���傳�u��̔��F��������Ǝ₵���ȁ[�Ɗ�����v�Ƃ��uLX3��GX200������̂ق����O���f�[�V�����̖L�x����������v���Ƃɉe�����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����b�ł����B
���ۂɔ������Ă���̖O�a�����Ƃ���ے肵�Ă���̂͋M���ł���B
--------------
>�O�ɂ������܂������ARAW�������́u�I�o�v���ɘI���ʂ����߂Ă��܂���ˁH
>�f�W�^���J�����ł́ARGB���ꂼ���ʁX�ɐM�������܂�����ARAW�������ɂ��ꂼ��̘I�o�����܂��B
>���̘I�o�������u�J���[�o�����X�����v�Ƃ������Ƃł��B
�f�W�^���J�����ŘI�o�Ƃ̓V���b�^�[���J���ăZ���T�[���Ă邱�Ƃ������܂��B
RAW�����\�t�g�ł̘I�o�Ƃ́A�����܂Ŏ��ۂ̌�����Ƃ̌��������i�V�~�����[�V�����j�ł���A���ۂɘI�����Ă����ł͂���܂���B
���̂Q�͑S���Ⴄ���Ƃł���A�������Ƀf�W�^���J������ RGB ���ꂼ��ɘI�o��ς�����Ȃ獡���������ƐF���̕ω��ɋ����Ȃ�܂��B�i�ʂɘI�����邱�ƂŔ���т�h����j
�������A�ʏ�̃f�W�^���J�����ł� RGB �ꊇ���ĘI�o�����邱�Ƃ����ł����A���̂��߁u�����O�a����v�Ƃ������Ƃ��N���܂��B
�M����[8780607]�ŁA
>�f�W�^���J�����ɂ͐E�ԁE���ׂĂ̘I�o������@�\��������Ă��܂��B
�Ə����Ă��܂����A����� CCD �ŎB�����A�擾�����摜�f�[�^���摜�����Ń��x�������邱�Ƃ��w���Ă���Ƃ������Ƃŗǂ��̂ł��傤���B
�����ł���A���͊���[8770112]�ɂāA
>�܂��A�摜�����ŐF�����ɂ��Ă��A�O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ė{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
�ƃR�����g�ς݂ł��B
--------------
>RAW�摜�̃_�C�i�~�b�N�����W���L���̂́u�d�l�v�ł��B
>���̌������i��15L���������ꍇ�ARAW�ł�����i�O�a�j���܂���
>�ŏI�o�͂�4�`5�k�̃o�P�c�Ŏ���́A�����̏����ێ����Ă��܂��A�Ƃ����Ă܂��B
����ARAW�摜���_�C�i�~�b�N�����W���L�����ǂ����ł͂Ȃ��A
>�ł�����A�T���v���摜�� RAW �ł̓_�C�i�~�b�N�����W�ɗ]�T���������Ƃ���������
�Ɩ₤�Ă��܂��B
����Ɋւ��Ắu�킩��Ȃ��v�Ɖ��Ɖ��߂��Ă����܂��B
�u�킩��Ȃ��v�ł�����A���܂ł̗l�� RAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ��������̂悤�ɒf�����A�����_���ɂ���̂͂�߂Ă��������B
����ɂ��������摜�Ƃ́ACCD �o�̓f�[�^�Ƒ����Ă���������Ǝv���܂��B
--------------
�M���������Ă��Ȃ����e����ׂ܂��B�i���Ȃ����܂����j
�E��F��������ƐԂ������Ȃ�Ƃ��������iP6000�̉摜�H�j
�@���uG10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă�v�̍����ƂȂ�
�E�u�K���������v�Ƃ́H�̉�
�E�m�C�Y�̎�ނɂ���ă_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��Ƃ�������
�E1��f�ʐς�4�{�ɂ���ƖO�a�d�חʂ�4�{�ɂȂ鍪��
���m�ɂȂ�����
�EJPEG �ł� RAW �ł��O�a���Ă�����F�����Č��ł��Ȃ��Ȃ�[8780500]
�E�R�o���g�u���[�ɂ͐Ԑ����͂قƂ�ǂȂ�[8780503]
�EGX200 �͖��ʐF�������Ԑ����������i�Ԃ��Ă��z���C�g�o�����X�̖��j[8780503]
�E�V���b�g�m�C�Y��1��f�̖ʐς��������f���ɂ�苭���e����^����[8780607]
�E�O�����͐����ȗp��ł͂Ȃ�[8780607]
�E�T���v���摜�� RAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ��������ǂ����͕s��[8782350]
�����ԍ��F8783388
![]() 1�_
1�_
�T���v��4�_�̋�̕������A�Z���������甖�������܂ŒZ����ɑI�������q�X�g�O�����ł��B
���I���ʒu�ɃY��������̂́A�̎}��_����������ʂő��ӂ͂���܂���̂ł��������B
�͂����肵�Ă���̂�P6000���u���O�a���Ă���v�Ƃ��������Ȃ�u�O�a���Ă���v���Ƃł��B
��������Ӑ}�I�ɗႩ��O�����̂��Ǝv���Ă��܂����B
������d�v�Ȃ̂́A�ԁE�E�̎R�̈ʒu�ł��B
4�̃T���v���̒��Ő̃��x�����ő�l�ɂ������Ă��Ȃ��̂�LX3�����Ȃ̂�
LX3�̎R�̈ʒu����Ƃ���ƁA�Ԃ̃s�[�N�ʒu�͖��x�Z���^�[�̒��Ԃ���Ă��܂�
�����ďd�v�Ȃ̂́A�ԂƗ̎R�ƁA�̎R�Ƃ̊ԂɊu���肪���邱�Ƃł��iRGB�`�����l����j
�����悤�ɁA���x��GX200�̃q�X�g�O����������ƁA�ԂƗ̃s�[�N��LX3�Ɠ����ʒu�ł��B
����ɑ��āA�̃��x���͖��x���Â����ɃV�t�g����ALX3�ɑ��݂����u���肪����܂���B
G10��P6000�ł����̊u���蕔���͊m�ۂ���Ă��܂�����A���炩��GX200�ł͐̃��x�����������Ă��܂��B
GX200�ɐ̃��x���������s���Ă���Ƃ��������͂���ŗǂ��ł��ˁH
�ŁAG10��P6000�Ƃ�����ׂ�Ɠ��������Łu���O�a���Ă���v�ƌ����o���Ȃ�P6000�����O�a���Ă��܂��B
��������T���v���Ɏ����o���Ȃ������̂ł��傤���B
�܂��AG10��P6000�ł́A�ԂƗ̎R�̈ʒu���悭���Ă���
�Ԃ̃��x���̓Z���^�[�����E���ɃV�t�g���Ă��܂����A�Ƃ̊u������c���Ă��܂��B
LX3�AG10�AP6000�̃q�X�g�O���������Ĕ��邱�Ƃ́A�قړ����\���̋�̌����Ă������Ɓi������O�ł����j
�����o�����X�̂܂܁A��Max�Ɏ����Ă��邱�Ƃ���AG10��P6000�Ő�Max�Ȃ̂͑S�̘I�o�̖��ł��邱��
GX200�̐F�\���o�����X�́A��������B�e�������ʂ̃q�X�g�O�����Ƃ��Ắi����3�Ɣ�ׂ�Ɓj�s���R�ł��B
��������8bit�o�͂ł̔�r�ł�����A���ۂǂ��������̂���RAW�摜�����Ȃ��Ɣ���܂���B
GX200�������������āA����3�@�푤�����������̂����m��Ȃ�����ł��B
�����ԍ��F8784647
![]() 1�_
1�_
��>������摜�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ɖ�f���x���ł̓d���̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃł͈Ӗ����ς��܂��B
���ƃR�����g���Ă��܂����H�I
�f�q���x���̐M���Ƃ����Ӗ��ł̃_�C�i�~�b�N�����W�ƁA
�摜�̃��`���[�h�Ƃ����Ӗ��ł̃_�C�i�~�b�N�����W��2��ނ���܂��B
�ʐ^�̃��`���[�h�Ƃ����Ӗ��Ŏg����̂�
�t�W�̃T�C�g�Ȃǂł̃_�C�i�~�b�N�����W�̎�舵�����ŗ������ꂽ�Ƃ������Ƃł�낵���ł��ˁH
��>���ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ����̂̓��`���[�h�͈̔͂ł͂Ȃ��ł���B
����̈Ӗ��Ȃ̂ł����A���`���[�h�Ƃ����̂́A�P���ȃ_�C�i�~�b�N�����W�����A�i���O�I�Ȋ��e�x������̂ł��B
������������āu���e�x�v�Ƃ����a�t����ꂽ�̂��Ǝv���܂����E�E�E
�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ����ƁA���m�ɂ��̕��i���j�̂��ƂɂȂ�܂��B
���`���[�h�̓t�C�����Ȃǂ̓������痈��_�C�i�~�b�N�����W�Ȃ̂ŁA�s�[�N�����Ƀf�[�^�̒��i���͂���܂���B
����тȂ�����n�C���C�g�̃f�B�e�[�����c��A�ׂ�Ȃ�����f�B�e�[������������A�Ƃ��������ł��B
�ł�����A�P���Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�����`���[�h�Ƃ͌����Â炢������������
�_�C�i�~�b�N�����W�{�f�W�^���G���W���̕�����`���[�h�A�Ƃ����̂��Ӗ��I�ɂ͐��m���ȂƁB
���V���b�g�m�C�Y�̓t�H�g�����d�ׂގ��̌덷�ł�
������C�R�[���K���덷�ł���ˁH
�K���덷�ł͂Ȃ��ƒf�����ꂽ���R�̕����ɒm�肽���̂ł����H
���덷�i�o���c�L�j�P�̐M��������A���̌덷�̌����͉��ł���P�ȉ��̍������M���͈Ӗ��𐬂��܂���
�ł�����A1�ȉ��̐M���Ŕ��f���Ȃ��悤�ɉ�͂��܂���ˁH
���̂��߂ɂ�Hi-bit�ŃT���v�����O���ăf�W�^���G���W���ɏ���������̂ł��B
���_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͗L���ȐM�����ƃo���c�L�i���m�C�Y�j�Ƃ̔�
�M���Ƃ����Ӗ��ł̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A�L���ȐM���̃s�[�N�ƃm�C�Y�Ƃ̔�ł���ˁH
�I�[�f�B�I�Ȃǂ̃_�C�i�~�b�N�����W�́A��{�m�C�Y���x���ƐM���̃s�[�N���x���̍��ł��B
�Ȃ̓r���Ƀm�C�Y�������Ă��A����Ń_�C�i�~�b�N�����W�ɉe���ȂǗ^���܂���B
���Ⴆ�� �P�O �Ƃ����o�͂��������ꍇ�A���ꂪ�{���X�ł��邩�A�P�P�ł��邩�͎��ʂł��Ȃ��̂ł��B
���̎��ʂł��Ȃ��m�C�Y���A�ǂ̂悤�ɑ����āA�ǂ̂悤�Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�i�䗦�j�Ƃ��ďo���̂�
����m�肽���̂ŋ����Ă��������B�I�J���g�Ȋw�ł͂Ȃ����m�ȕ��@������̂ł��傤����B
���M���͂����� RAW �͖O�a���Ă��Ȃ��ƒf�����Ă��܂��B
���Ă܂���B
�_�C�i�~�b�N�����W�ɗ]�T������̂ŖO�a���ɂ����Ɖ��x���������Ă��܂��B
�����āA������ƒ��ׂ�̂Ȃ�ARAW�摜�̉�͂��K�v���Ƃ����Ă��܂��B
������ł́A�M���̎咣�Ƃ��Ă� RAW �͖O�a���Ă��邩�ǂ����͔���Ȃ��A
��JPEG �̏o�͒i�K�ł͖͐O�a���Ă���A�Ƃ������ŋX�����ł��傤���B
���_�C�i�~�b�N�����W�̉摜�����o���Ӗ����킩���Ă��Ă��������Ă���̂Ȃ�A�����������Ƃł��B
RAW�摜�i�f�q�j�̒i�K�ł́A�l�Ԃ����Ɗ����閾�x�ȏ�̏����L�^�\�ł�����B
���ł́AJPEG�摜��8bit�摜�A10bit RAW �摜�� Hi-bit �摜�Ƃ��Ă��ǂ��A�Ƃ������Ƃł����H
�������B
JPEG�摜��8bit�摜�A�͖��Ȃ��ł����ARAW�摜�͂�����Hi-bit�摜�ł͂Ȃ��Ɖ��x�������Ă��܂���ˁH
RAW�摜�̈Ӗ��𗝉����Ă���̂ł����H
RAW�摜�Ƃ́u�摜�ɂȂ��Ă��Ȃ��M���f�[�^�v�ŁA�f�[�^�K����Hi-bit���g���Ă�̂ł��B
�Ⴆ�APSD��TIFF��8bit�摜��16bit�摜�Ƃ̈Ⴂ�Ƃ͕ʕ��Ȃ̂ł���B
Hi-Bit�摜��RAW�摜���������Ă��܂��H
�����ԍ��F8785304
![]() 1�_
1�_
�������ł���B�e�J�����ł̋�F�i�F�j�̍Č������X���b�h�̘b��ł��B
��������A�����ڂɍS���Ă���͖̂l�����ł͂Ȃ��̂ł́H
���������A�ʏ�̃f�W�^���J�����ł� RGB �ꊇ���ĘI�o�����邱�Ƃ����ł����A���̂��߁u�����O�a����v�Ƃ������Ƃ��N���܂��B
���Ⴂ���Ă��܂��B
�x�C���[�z��ɂ����ẮAR�f�q�̏��AG�f�q�̏��AB�f�q�̏����ʂɋL�^���Ă���̂�RAW�f�[�^�ł��B
JPEG�ł����ARGB�͓Ɨ������`�����l���Ƃ��ċL�^����Ă��܂��B
�����āA�F���̕ω��ɑΉ��ł��邩�炱��AWB�Ȃǂ̋@�\���\�ƂȂ��Ă���̂ł��B
�t�C��������̓����Y�̑O�ɐF���ϊ��p�t�B���^�[��t���ĎB�e���Ă܂�����ˁH
���u�����p�͌����Ȏ��F�̃t�B���^�[�ł����B
������� CCD �ŎB�����A�擾�����摜�f�[�^���摜�����Ń��x�������邱�Ƃ��w���Ă���Ƃ������Ƃŗǂ��̂ł��傤���B
AWB�AWB�@�\�������ɂ�����s���Ă��܂��B
���O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ė{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
�ł�����A�ʏ�͈̔͂ł͖O�a���Ȃ��_�C�i�~�b�N�����W�̍L���Ō�����͂��Ă��܂��B
�O�a���ĐF�����ς���Ă�����AWB�Ȃǎ��܂���B
������ARAW�摜���_�C�i�~�b�N�����W���L�����ǂ����ł͂Ȃ��A
���ꂪ���Ȃ��̑S�Ă̎���ɑ��铚���Ȃ̂ł����A�Ȃ�RAW�摜�̓����ɂ��Ĕ�����̂ł����H
������ɂ��������摜�Ƃ́ACCD �o�̓f�[�^�Ƒ����Ă���������Ǝv���܂��B
CCD�o�̓f�[�^��RAW�摜�ł���ˁH���Ⴂ����Ă��܂��H
���E��F��������ƐԂ������Ȃ�Ƃ��������iP6000�̉摜�H�j
�@���uG10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă�v�̍����ƂȂ�
�V�A���Ƀ}�[���^�𑫂��Ɛ��Ȃ邽�߁A�}�[���^���ɒ������܂���肭�����ł��Ȃ��ƃ}�[���^�������A
�̃C�G���[�����ƍ��킳���ĐԂ������܂��B
�F���̂��Ƃ������Ă���ΊȒP�ȗ����ł��BPhotoshop��ł��Č��\�ł��B
���J���[�o�����X�������ɏo��X���C�_�[������Έ�ڗđR�ł���ˁB
�E�u�K���������v�Ƃ́H�̉�
��f�ʐς����������Ƃ̃f�����b�g�ɁA�悭�K�����������Ƃ����w�E�����邩��ł��B
�E�m�C�Y�̎�ނɂ���ă_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��Ƃ�������
��q�ς�
�E1��f�ʐς�4�{�ɂ���ƖO�a�d�חʂ�4�{�ɂȂ鍪��
�����e�ʂ̃R���f���T��4�{����Ɍq���Ă��������B����Ȃ�e�ʂ͕ς��܂��A����4�{�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F8785311
![]() 1�_
1�_
[8784647] �A�L���Z����
>�͂����肵�Ă���̂�P6000���u���O�a���Ă���v�Ƃ��������Ȃ�u�O�a���Ă���v���Ƃł��B
����A�u�O�a���Ă��Ȃ��v��Ȃ������́H
���ȂA���̐l�́B
�����ԍ��F8785388
![]() 1�_
1�_
�����玸�炵�܂��B����オ���Ă���c�_��q�ǂ����Ē��������Ő������ɂȂ����C�����܂��B
�f�l�ɂ͂ǂ���̕��̂��������������̂��S��������܂��A����͂���Ƃ��āA�c�_�̎d���Ƃ��ċC�ɂȂ邱�Ƃ�����܂����̂ŃR�����g�����Ē����܂��B
�ǂȂ������A����Ă͂����Ȃ����ƁA�Ƃ��ĉ��_��������Ă��܂������A����ɉ����Čl�I�ɂ́A���l�̈ӌ��ɑ��āA��͂��H��Ƃ��Ԃ����̂́A���܂�ǂ������͂��܂���B�܂��A���Ȃ��̓����Ă��Ȃ����ƁA�Ƃ��ĉӏ�������(���X��)������悤�Ȃ������X�}�[�g�Ȋ����́A��͂�v���܂���B
�X���Ƃ͑S���W�Ȃ��b�ŋ��k�ł����B
�����ԍ��F8785578
![]() 1�_
1�_
�����s�̂�������
�l�́u�F�̖O�a�v�Ƃ����T�O�ɉ����Č��F�́u�v���O�a�������ʁu�V�A���v�ɓ]�Ԃ��Ƃ͂Ȃ��ƌ����Ă��܂��B
���̕\���Ő�������Ƃ܂����߂܂�����u�O�a�v�Ƃ����Ă��܂���
P6000���݂����u���O�a����Ɛ��F�ɂȂ�v�ƒf���͂ł��Ȃ��悤�ł���ˁO�O
8bit�K���ŃO���f�[�V���������ǂ��Ȃ邩�A�Ƃ����Ӗ��ł͖����Ȃ̂ł����E�E�E
��8bit�O���[�X�P�[���ō����ʐ^���v�����g���āA�₵���v���������l�Ȃ画��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F8786001
![]() 1�_
1�_
>����A�u�O�a���Ă��Ȃ��v��Ȃ������́H
>���ȂA���̐l�́B
�������z�ł��B
�����ԍ��F8786111
![]() 2�_
2�_
���႟�A���̒i�K����c�_�������܂����H�O�O
�����̋C���Ȃ��Ă����Ă���Ȃ�A�܂�Ȃ��g���������Ă����܂���H
�����ԍ��F8786268
![]() 1�_
1�_
[8784647] �ɂ��Ă͌�ŃR�����g���܂��B
�i�Ȃ�������t�H�[�J�X���{�P�Ă���̂Łj
�ȒP�ɏ����A
>�����āA�̐F�������摜�ɂ́A��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�X��������܂��B
>�Ɨō\�����ꂽ��̐F�ɐԂ݂������Ă��܂��Ă���T���v���摜�̋@��͂ǂ�Ƃǂ�ł��傤�H
�̍����ɂȂ��Ă��܂����B
�M���̌����u�̐F�������摜�v���ǂ�ŁA�u�u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂłĂ���v�̂͂ǂ�ł��傤�H
>�V�A���Ƀ}�[���^�𑫂��Ɛ��Ȃ邽�߁A�}�[���^���ɒ������܂���肭�����ł��Ȃ��ƃ}�[���^�������A
>�̃C�G���[�����ƍ��킳���ĐԂ������܂��B
>�F���̂��Ƃ������Ă���ΊȒP�ȗ����ł��BPhotoshop��ł��Č��\�ł��B
�Ƃ̂��Ƃł����A�J������ RGB �œ��삵�Ă���Ƃ������Ƃ͂����m�ł����H
>�_�C�i�~�b�N�����W�{�f�W�^���G���W���̕�����`���[�h�A�Ƃ����̂��Ӗ��I�ɂ͐��m���ȂƁB
���������A�����ł����_�C�i�~�b�N�����W�̒�`�͉��ł����H
�������̒��Ɂu�_�C�i�~�b�N�����W�炵�����́v�������āA
�_�C�i�~�b�N�����W�Ȃ�Ă��������A�i���O�I�T�O�ł���B
�����������A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8
�ȊO�̒�`������̂Ȃ�A����ɂ��Ă̐����ƍ����������Ă��������A�ƌ����Ă���̂ł��B
>���V���b�g�m�C�Y�̓t�H�g�����d�ׂގ��̌덷�ł�
>������C�R�[���K���덷�ł���ˁH
>�K���덷�ł͂Ȃ��ƒf�����ꂽ���R�̕����ɒm�肽���̂ł����H
�K���덷�Ƃ������t�����߂ďo�Ă��܂������A�i�P�K�����m�C�Y�����ȉ��Ȃ�j�m�C�Y�̌��������ł���K���ɉe����^����A�Ǝ��͊��ɃR�����g���Ă��܂��B�K���i���ʎq���A�T���v�����O�j�ɉe����^����Ȃ炻��̓m�C�Y�ł����A�m�C�Y�̓_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����܂��B
>�ł�����A1�ȉ��̐M���Ŕ��f���Ȃ��悤�ɉ�͂��܂���ˁH
>���̂��߂ɂ�Hi-bit�ŃT���v�����O���ăf�W�^���G���W���ɏ���������̂ł��B
Hi-bit �Ƃ͉����w���Ă��邩�s���m�ł����A��葽���� bit ���Ƃ����Ӗ����Ɖ��߂��܂��B
�P�ȉ��̐M���̍��������ł��Ȃ��ł�����A�����������Hi-bit�ŃT���v�����O���Ă��Ӗ��͂���܂���B
>�Ȃ̓r���Ƀm�C�Y�������Ă��A����Ń_�C�i�~�b�N�����W�ɉe���ȂǗ^���܂���B
�V���b�g�m�C�Y�Ƃ́A�Ȃ̓r���ɓ˔��I�ȃm�C�Y�����邱�ƂƓ����ł͂���܂���B
>���̎��ʂł��Ȃ��m�C�Y���A�ǂ̂悤�ɑ����āA�ǂ̂悤�Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�i�䗦�j�Ƃ��ďo���̂�
>����m�肽���̂ŋ����Ă��������B
�ł�����A���ꂪ���̎���ł��B�M���̓V���b�g�m�C�Y���ʂ̃m�C�Y����ʂ��t���ƌ����Ă���̂ł�����B
�i���V���b�g�m�C�Y�̓_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��j
>RAW�摜�i�f�q�j�̒i�K�ł́A�l�Ԃ����Ɗ����閾�x�ȏ�̏����L�^�\�ł�����B
�l�Ԃ̖ڂ��f�q�̕����_�C�i�~�b�N�����W���L���Ƃł������̂ł����H
�ނ���A�l�Ԃ̖ڂ��O�a���₷���i���l�Ԃ�薾�x���������₷���j�̂ł���B
>RAW�摜�̈Ӗ��𗝉����Ă���̂ł����H
>RAW�摜�Ƃ́u�摜�ɂȂ��Ă��Ȃ��M���f�[�^�v�ŁA�f�[�^�K����Hi-bit���g���Ă�̂ł��B
RAW �̐����͌��\�ł��B���������Ă���̂́AHi-bit �摜�Ƃ����M���Ɠ��̗p��̒�`�ł��B
9bit �ȏオ�g���Ă��鑽�K���摜�f�[�^�A�Ƃ�����`�ł���� 10bit RAW �� Hi-bit �摜�Ɋ܂܂��͂��ł����B
���ł́AJPEG�摜��8bit�摜�A10bit RAW �摜�� Hi-bit �摜�Ƃ��Ă��ǂ��A�Ƃ������Ƃł����H
>JPEG�摜��8bit�摜�A�͖��Ȃ��ł����ARAW�摜�͂�����Hi-bit�摜�ł͂Ȃ��Ɖ��x�������Ă��܂���ˁH
>Hi-Bit�摜��RAW�摜���������Ă��܂��H
�������Ȃɂ��A�M��������ɒ�`�����p��ɂ��t���������������ł��B
Hi-bit �摜�Ƃ����Ǝ��p�ꂪ���m�ɒ�`�ł��Ă��Ȃ��̂ŁA���m�ɒ�`���邩�A�g��Ȃ��悤�ɂ��肢���܂��B
>�x�C���[�z��ɂ����ẮAR�f�q�̏��AG�f�q�̏��AB�f�q�̏����ʂɋL�^���Ă���̂�RAW�f�[�^�ł��B
>JPEG�ł����ARGB�͓Ɨ������`�����l���Ƃ��ċL�^����Ă��܂��B
�ł�����ARGB ���ʂɋL�^���邱�ƂƁA�ʂɘI������i���I�o�j����̂Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B
�܂� RGB ���ʂɘI�o�R���g���[���ł���ƌ����Ă���̂ł��ˁB
--------------
>�O�ɂ������܂������ARAW�������́u�I�o�v���ɘI���ʂ����߂Ă��܂���ˁH
>�f�W�^���J�����ł́ARGB���ꂼ���ʁX�ɐM�������܂�����ARAW�������ɂ��ꂼ��̘I�o�����܂��B
>���̘I�o�������u�J���[�o�����X�����v�Ƃ������Ƃł��B
�f�W�^���J�����ŘI�o�Ƃ̓V���b�^�[���J���ăZ���T�[���Ă邱�Ƃ������܂��B
RAW�����\�t�g�ł̘I�o�Ƃ́A�����܂Ŏ��ۂ̌�����Ƃ̌��������i�V�~�����[�V�����j�ł���A���ۂɘI�����Ă����ł͂���܂���B
���̂Q�͑S���Ⴄ���Ƃł���A�������Ƀf�W�^���J������ RGB ���ꂼ��ɘI�o��ς�����Ȃ獡���������ƐF���̕ω��ɋ����Ȃ�܂��B�i�ʂɘI�����邱�ƂŔ���т�h����j
�������A�ʏ�̃f�W�^���J�����ł� RGB �ꊇ���ĘI�o�����邱�Ƃ����ł����A���̂��߁u�����O�a����v�Ƃ������Ƃ��N���܂��B
�M����[8780607]�ŁA
>�f�W�^���J�����ɂ͐E�ԁE���ׂĂ̘I�o������@�\��������Ă��܂��B
�Ə����Ă��܂����A����� CCD �ŎB�����A�擾�����摜�f�[�^���摜�����Ń��x�������邱�Ƃ��w���Ă���Ƃ������Ƃŗǂ��̂ł��傤���B
�����ł���A���͊���[8770112]�ɂāA
>�܂��A�摜�����ŐF�����ɂ��Ă��A�O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ė{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
�ƃR�����g�ς݂ł��B
--------------
�����ԍ��F8786294
![]() 1�_
1�_
>������� CCD �ŎB�����A�擾�����摜�f�[�^���摜�����Ń��x�������邱�Ƃ��w���Ă���Ƃ������Ƃŗǂ��̂ł��傤���B
>AWB�AWB�@�\�������ɂ�����s���Ă��܂��B
����́u�I�o�v���R���g���[�����čs���Ă����ł͂���܂����B
���x�������Ă��܂����A�u�I�o�v�Ƃ̓t�B�������掆�Ɍ��Ă邱�Ƃ������܂��B
>������ɂ��������摜�Ƃ́ACCD �o�̓f�[�^�Ƒ����Ă���������Ǝv���܂��B
>CCD�o�̓f�[�^��RAW�摜�ł���ˁH
�����ł� RAW �摜�Ƒ����Ă�����Ă������A�Ƃ������Ƃł���B
>���O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ė{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
>�ł�����A�ʏ�͈̔͂ł͖O�a���Ȃ��_�C�i�~�b�N�����W�̍L���Ō�����͂��Ă��܂��B
>�O�a���ĐF�����ς���Ă�����AWB�Ȃǎ��܂���B
CCD ���x���ŖO�a���Ă��AWB �͎��܂���B�����Ȃ����ʐ^�Ȃ�āA�����������ɂ��邶��Ȃ��ł����B
���������A�O�a���Ȃ��_�C�i�~�b�N�����W�̍L���A�Ƃ͉����w���Ă���̂ł��傤���B
�O�a�A�ƃ_�C�i�~�b�N�����W�̈Ӗ��𐳊m�ɐ������Ă��������B
��͂�A���̂Q�𗝉����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ�����ۂ������ł��ˁB
�A�L���Z����́A�A�i���O�J�����ƁA����i�����j�̒m���͂��邩������܂��A�f�W�^���f�[�^����̎O���F�Ɋւ���m���Ɍ����Ă���Ƃ�����ۂ������Ȃ����ł��B
�Ǝ��p����I���Č��������̂ł͂Ȃ��A�L�`���ƒ�`�Ƃ��̍����𖾂炩�ɂ��Ă��������B
>�E�u�K���������v�Ƃ́H�̉�
>��f�ʐς����������Ƃ̃f�����b�g�ɁA�悭�K�����������Ƃ����w�E�����邩��ł��B
�ɂȂ��Ă��܂���B�K�����������Ƃ́A�����w���Ă���̂ł��傤���B
>�E�m�C�Y�̎�ނɂ���ă_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��Ƃ�������
>��q�ς�
�����͂ǂ��ɂ��Ȃ��ł���B
���͍����������܂�����ˁB
>�E1��f�ʐς�4�{�ɂ���ƖO�a�d�חʂ�4�{�ɂȂ鍪��
>�����e�ʂ̃R���f���T��4�{����Ɍq���Ă��������B����Ȃ�e�ʂ͕ς��܂��A����4�{�ɂȂ�܂��B
�O�a�d�חʂɂ������f�̓R���f���T�Ɠ����ł͂���܂���B
�����Ƃ��āA��f�T�C�Y���Ⴄ CCD ���ׂĂ݂Ă��������B�O�a�d�חʂ͉�f�T�C�Y�ɔ�Ⴕ�Ă��܂����H
-----------------
�M���������Ă��Ȃ����e����ׂ܂��B
�E�u�K���������v�Ƃ́H�̉�
�E�m�C�Y�̎�ނɂ���ă_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����Ȃ��Ƃ�������
�E1��f�ʐς�4�{�ɂ���ƖO�a�d�חʂ�4�{�ɂȂ鍪��
�EHi-Bit�摜�̒�`
�E�E�ԁE���ׂĂ̘I�o������@�\��������Ă���J����
�E�M�����g���Ă���u�O�a�v�Ɓu�_�C�i�~�b�N�����W�v�̒�`
���m�ɂȂ�����
�EJPEG �ł� RAW �ł��O�a���Ă�����F�����Č��ł��Ȃ��Ȃ�[8780500]
�E�R�o���g�u���[�ɂ͐Ԑ����͂قƂ�ǂȂ�[8780503]
�EGX200 �͖��ʐF�������Ԑ����������i�Ԃ��Ă��z���C�g�o�����X�̖��j[8780503]
�E�V���b�g�m�C�Y��1��f�̖ʐς��������f���ɂ�苭���e����^����[8780607]
�E�O�����͐����ȗp��ł͂Ȃ�[8780607]
�E�T���v���摜�� RAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ��������ǂ����͕s��[8782350]
�����ԍ��F8786346
![]() 1�_
1�_
[8784647]�ɂ���
>�͂����肵�Ă���̂�P6000���u���O�a���Ă���v�Ƃ��������Ȃ�u�O�a���Ă���v���Ƃł��B
P6000���A�Ƃ������Ƃ� G10�����O�a���Ă���͔̂F�߂��Ƃ������ƂŋX�����ł��傤���B
>G10��P6000�ł����̊u���蕔���͊m�ۂ���Ă��܂�����A���炩��GX200�ł͐̃��x�����������Ă��܂��B
�EG10 �� P6000 ���グ���Ă���̂ł͂Ȃ��AGX200 ���������Ă���Ƃ��������́H
�E�̃��x����������ƐԌn�������Ȃ�Ƃ��������́H
>GX200�ɐ̃��x���������s���Ă���Ƃ��������͂���ŗǂ��ł��ˁH
GX200 �Ɍ��炸�A�Z�x�E�ʓx�Ɋւ��āu�@��ɂ�鉉�o������v�̂͑S���ے肵�Ă��܂��A�_�|������Ă��܂��B
==============
���߂ď����܂����A���������Ă���̂�
>G10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă�>�����ł��B
�̍����ł��BP6000 ������Ă��Ȃ��Ƃ͎��͑S�������Ă��܂��A�X���傳���y���Ă����
>��̔��F��������Ǝ₵���ȁ[�Ɗ�����̂ł����A���ۂ̂Ƃ���ǂ��Ȃ�ł��傤���H
>�����ǎ��̖ڂɂ͗�̃��r���[�ł�LX3��GX200������̂ق����O���f�[�V�����̖L�x����������
�Ƃ����_�ł��B
�M���́AG10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă鍪���Ƃ���
>�����āA�̐F�������摜�ɂ́A��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�X��������܂��B
>�Ɨō\�����ꂽ��̐F�ɐԂ݂������Ă��܂��Ă���T���v���摜�̋@��͂ǂ�Ƃǂ�ł��傤�H
�Ƃ��R�����g���Ă��܂����̂ŁA����ɂ��Ă̍������L�`���Ɖ��Ă��������B
===============
�����ԍ��F8786374
![]() 2�_
2�_
�m���� �A�L���Z���� �����g�́u�O�a�v�Ƃ������t���g���Ă��Ȃ��悤�ł����B
[8736165]
[8740972]
���̂�����ǂ�ł��A���������������������̂��S�R�킩��Ȃ��ł��ˁi�������萻�i�i�삷�邩�炻���Ȃ�̂ł��傤�j�B
���������̋�̐F�́u���R�v�ł͂���܂����B�����������Ƃ��������炨�������Ȃ�B
�u���̋�̐F�͎��R�ł͂Ȃ��v �� ���̂��Ƃ̏ؖ��͂���������ł��B
�����������������Ƃ͌����܂��B
�i��O�͂��邪�����Ƃ��āj�u�O�a�v�́u���̋�̐F�v�ɂȂ�\�������B
���Ȃ݂ɓr������i�ӎv�a�ʂł��Ă��Ȃ����ƂɁj�C�t���Ă܂������ǁA�i���[�U�[�Ԃ́j�f�W�J���E�ł́u�O�a�v�Ƃ́u�����W���z���邱�Ɓv�Ȃ�ł��B
�{���̌��t�̒�`�Ȃ��͒m��܂����B�ł����[�U�[�̊Ԃł͂��������g���������Ă����ł��i�Ƃ������Ƃ͂����炭 �A�L���Z���� �����g�m���Ă���͂��j�B
gintaro���� �� [8740435] �̔����́u�O�a�v�Ƃ������t�����Ȃ�Ȃ��B�X���傳��ɂƂ��Ă��d�v�Ȃ̂́u���ہv�Ȃ�ł��B
������i�m���Ă��Ȃ���H�j�O�a�Ƃ����P��Ɋ��ݕt���B �� �������� �A�L���Z���� �̍s�ׁi�����j���u���i�i��̂��߂ɂ���Ƃ����雛������P��o���v�Ƃ��Ď��͌����Ă���̂ł��B
�ǂ��܂Ŋm�M�ƂȂ̂����ɂ͂킩�肩�˂܂����A�u���̋�̐F�����R�v�Ə��������_�Łu�A�E�g�v�ł��B
�E�m���Ă��āu���R�v�Ə����� �� ���i�i��̂��߂ɉR��t�����i�m�M�Ɓj������u�A�E�g�v
�E�u���ہv��m��Ȃ����� �� �m��Ȃ��ś���������ח��Ă鎞�_�Łu�A�E�g�v
�E�{���Ɏ��R�Ɗ������u�̂݁v������u���R�v�Ə����� �� ���o�I�Ȏ��ۂɑ��A�������_�I�ȗ��Â������邩�̂悤�ɏq�ׂĂ��鎞�_�Łu�A�E�g�v
�����ԍ��F8786471
![]() 3�_
3�_
���M���̌����u�̐F�������摜�v���ǂ�ŁA�u�u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂłĂ���v�̂͂ǂ�ł��傤�H
�q�X�g�O�����Ŗ����Ȃ̂�GX200�ł��ˁB
�Ɛ̑����x�����������Ă܂�����A�u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂłĂ���v��Ԃł��B
�܂��摜�S�̂̃q�X�g�O����������Ɣ���܂����A���̋@��ɔ�בS�̓I�ɖ��x���Ⴂ�\���ƂȂ��Ă��܂��B
���Ƃ̂��Ƃł����A�J������ RGB �œ��삵�Ă���Ƃ������Ƃ͂����m�ł����H
RGB�摜�̃f�[�^��Photoshop�i�Ƃ������S�Ẵ��^�b�`�\�t�g�j���CMY��ł���̂͂���������܂��H
��CMYK�摜�́A����Ȃ�̃\�t�g����Ȃ���ΘM��܂��B
R+G=Y
R+B=M
G+B=C
����͉t�\�ȐF�̑��ւł��B
�����������A�����ł����_�C�i�~�b�N�����W�̒�`�͉��ł����H
���_�C�i�~�b�N�����W�Ȃ�Ă��������A�i���O�I�T�O�ł���B
�E�C�L�y�f�B�A�ŗ͐�����Ă�����̂ł��B
�ʐ^�ɂ����Ẵ_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ����T�O�����݂���̂�
�x�m�t�C�����̃T�C�g�����Ă�����Ƃ���̎����ł��B
�f�W�x���̈Ӗ��͂��킩��ł���ˁH
�Ⴆ�A�ŏ��M���ɑ��ĉ��{�܂ł̐M���������邩���_�C�i�~�b�N�����W�ŁAdB�ŕ\����܂��B
�ł�����A�A�i���O���瑱���T�O�ł����A�f�W�^���ɑΉ����Ă��Ȃ��T�O�ł͂���܂���B
����̐�����Wiki�̐����ƑS�������ł���H
���ۂ̐��E�̖��Í���200dB�i200�{�j�̃_�C�i�~�b�N�����W���������Ɖ��肵���ꍇ��
�f�W�J���̑f�q���x����100dB�i100�{�j�����Ȃ���A100dB���Ő�o���ق�����܂���B
���i�P�K�����m�C�Y�����ȉ��Ȃ�j
�����Ȃ�Ȃ��g�ݍ��킹�ɂ��Ă�Ƃ����Ă��܂���ˁH
�ꉞ�A��f�ɂ͓d�q��60000���̊K�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
10bit��1024�K���A14bit�ł�4096�K���ł�����1�K�����S���V���b�g�m�C�Y�����Ŗ��܂邱�Ƃ͍l���ɂ����̂ł��B
�V���b�g�m�C�Y����������m���́A���̉�f���̑Ή��d�q�Ɍ���������Ȃ��Ɣ������܂���
�S���̉�f���O�a���������i�K�i��ʂ͐^�����j��0.41��=��60000÷60000
1/100���x�̓d�q�ɂ������̗��q��������Ȃ��ꍇ�́A600�̓d�q�ɉ�����4.1���̏o�����ɂȂ�܂��B
���̓�����킹�čl�����
���P�ȉ��̐M���̍��������ł��Ȃ��ł�����A�����������Hi-bit�ŃT���v�����O���Ă��Ӗ��͂���܂���B
���i���Z���X�ȉ��肾�Ɨ����ł��܂���ˁH�V���b�g�m�C�Y���덷�͈̔͂Ɏ��߂�H�v�����R����܂��B
�P�ʁu1�v�Ȃǂł͉�͂��Ă��Ȃ��̂ł��B14bit�ł���10�ȏ�̒P�ʂŃT���v�����O���Ă��܂��B
�����āA8bit�ɋ[�����Z�����160�ȏ�̒P�ʂʼn�͂��Ă���v�Z�ɂȂ�܂��B
���K���i���ʎq���A�T���v�����O�j�ɉe����^����Ȃ炻��̓m�C�Y�ł���
���V���b�g�m�C�Y�Ƃ́A�Ȃ̓r���ɓ˔��I�ȃm�C�Y�����邱�ƂƓ����ł͂���܂���B
�V���b�g�m�C�Y���ǂ̒��x��������Ă��邩�͏�̃f�[�^�ŗ����ł���Ǝv���܂��B�ł��掿�ɂ͉e�����镔���ł��B
�Ȃ̓r���ɋȂɊ֘A�����m�C�Y���A�����������Ƃ��Ă��_�C�i�~�b�N�����W�ɂ͊��Z���܂���B
���̔����p�^�[�����Ȃ�����A�Ȃƃm�C�Y�M���̕������ł��Ȃ�����ł��B
���m�C�Y�̓_�C�i�~�b�N�����W�ɉe�����܂��B
�_�C�i�~�b�N�����W�̓A�i���O�I���Ƃ����Ă݂���A�����o���Ă������ϖZ�����ł��ˁB
���l�Ԃ̖ڂ��f�q�̕����_�C�i�~�b�N�����W���L���Ƃł������̂ł����H
�܂��_�C�i�~�b�N�����W�ł��ˁB�f�W�^���ł����ɕ\�����Ȃ��̂͗����������������Ǝv���̂ł����B
�l�Ԃ̖ڂ̃_�C�i�~�b�N�����W���u�L���v�ƌ�����̂́A���x���ɍ��킹�ăo���A�u���ɍi����ς�������
�]�Ƃ����摜�����G���W���ňÕ��Ɩ����̕�������A�L���̒��ō�������1�̉摜�Ƃ��ĔF�����邩��ł��B
�܂�A�[���I�ȃ_�C�i�~�b�N�����W�ł��B
�����āA�l�Ԃ̊�́A���邢�����ւ̓K���͈͂ɁA�����E������܂��B���������Ï����̕����D��Ă܂���ˁH
�f�q�ɉ����ẮA���̗��q��������Ȃ��Â��A�O�a����܂ł̓f�[�^�o�͂��閾�̂ق��������̂ł��B
�܂�A�i���V���b�^�[�X�s�[�h�̑g�ݍ��킹�ŘI����������x�R���g���[�������������̖��x�ł����
�ԈႢ�Ȃ��l�Ԃ̊�i�Ԗ��j�����f�q�̕����D��Ă��܂��B
�����A�P���ɕ����I�ȓ��͒l�ƁA�l�Ԃ̊Ⴊ�]���g���ĉ�͂�����̓��͒l�Ƃ��ƁA�J�[�u�������قȂ�܂��B
�ł�����A���ۂɃf�[�^�Ƃ��ċL�^����Ă��邩�ǂ����ƁA�ڂɌ������Ƃ��ɂǂ����͈قȂ�܂��B
��Hi-bit �摜�Ƃ����M���Ɠ��̗p��̒�`�ł��B
8bit�摜�A16bit�摜�Ƃ����\���͂��邪�A��bit�摜�Ƃ����������͂Ȃ��Ƃ����̂ł��ˁH
�uHi-bit�f�[�^�v�Ō������Ă݂Ă͂������ł����H
��9bit �ȏオ�g���Ă��鑽�K���摜�f�[�^�A�Ƃ�����`�ł���� 10bit RAW �� Hi-bit �摜�Ɋ܂܂��͂�
RAW�摜�f�[�^�́u�摜�v�Ɩ��O���t���܂����A���̂܂܂ł͉摜�ɂȂ��Ă��Ȃ��f�[�^�p�b�P�[�W�ł�����B
���������Ȃ��Ɖ摜�ɂȂ�Ȃ��f�[�^�Ȃ̂�RAW�摜�ƌĂсA���t�B�����Ɠ����悤�Ɂu�����v���K�v�ɂȂ�܂��B
���M��������ɒ�`�����p��ɂ��t���������������ł��B
���Ⴂ���Ă�Ǝv���܂���H
�����ԍ��F8786511
![]() 1�_
1�_
���I�o�Ƃ̓V���b�^�[���J���ăZ���T�[���Ă邱��
��RAW�����\�t�g�ł̘I�o�Ƃ́A�����܂Ŏ��ۂ̌�����Ƃ̌��������i�V�~�����[�V�����j�ł���A���ۂɘI�����Ă����ł͂���܂���B
�Ȃ����̕��������A�i���O����̊T�O�ɍS��̂��s�v�c�ł��ˁB
�Ƃ������A�A�i���O����ł��A�����Y�ƈ�掆�̊ԂɃJ���[�t�B���^�[��u����
���̂��������Ԃɂ���ĐF���Ƃ̘I�����R���g���[�����Ă����킯�ł��B
�V���b�^�[�ŃR���g���[�����Ă��镨�������u�I�o�v�Ƃ����l�������Ԉ���Ă��܂��B
�������������ƐF���̕ω��ɋ����Ȃ�܂��B�i�ʂɘI�����邱�ƂŔ���т�h����j
WB�����邱�Ǝ��̂��F���̕ω��ɋ����Ȃ��Ă邱�Ƃ̏ؖ��Ȃ̂ł����E�E�E
���i�ʂɘI�����邱�ƂŔ���т�h����j
�ʂɘI�o�����ł͂Ȃ��A�ʂɘI����������̂�3CCD�����̃J���������ɑ��݂��܂��ˁB
���Ǝc�O�Ȃ���A����т�RGB�S�Ă̌��̌��ʂȂ̂ŁA�ʂɘI�o�����Ă��h���܂����B
���ꊇ���ĘI�o�����邱�Ƃ����ł����A���̂��߁u�����O�a����v
�������Ⴂ���Ă܂���H�J���[�o�����X����܂���B
������� CCD �ŎB�����A�擾�����摜�f�[�^���摜�����Ń��x�������邱�Ƃ��w���Ă���Ƃ������Ƃŗǂ��̂ł��傤���B
��܂��ɂ͂����ł��ˁB
���O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ė{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
�b���߂�܂����A���̂��߂�RAW�摜�ł͍L���_�C�i�~�b�N�����W�Ńf�[�^�L�^���Ă���ƌ����Ă܂��B
�t�C�����ł͖O�a�����Ɏ��Ă���摜���A�f�B�e�[���D�悳�������C�ӂ̓_�ɍ��킹�ĘI�������
���R�ł������Ă��ł́A����сi�O�a�j���镔�����o�܂���ˁH
RAW�摜��Jpeg�����o���摜�̊W���A����Ɠ������Ƃ������Ƃ����̗������ĖႦ�Ȃ��̂ł��傤�H
�������ł� RAW �摜�Ƒ����Ă�����Ă������A�Ƃ������Ƃł���B
������Ă������Ƃ������A���̒ʂ�Ȃ̂ł����E�E�E
��CCD ���x���ŖO�a���Ă��AWB �͎��܂���B
�F�����킹��WB�Ȃ̂ɁA�F�����ς���Ă��Ă�WB�����̂ł��ˁi�j
�����āA�܂��}�ɖO�a���Ă���̂͋��̑O��ɂȂ��Ă��܂��B
���A�L���Z����́A�A�i���O�J�����ƁA����i�����j�̒m���͂��邩������܂��A�f�W�^���f�[�^����̎O�����F�Ɋւ���m���Ɍ����Ă���Ƃ�����ۂ������Ȃ����ł��B
�ς݂܂���f�W�^���M���Ă���Ԃ̕������͒����ł��i����ŔѐH���Ă܂�����j
�_�C�i�~�b�N�����W�͐�����������ǂ��ł��ˁH
�O�a�����Ɍ��肵�Ȃ�����x���I�[�o�[�Ȃ����ł���ˁB
�I�o�������ĈÕ��f�B�e�[����⊮������@����Ԍ����I�ł��B
���ɂȂ��Ă��܂���B�K�����������Ƃ́A�����w���Ă���̂ł��傤��
�K���������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�f�q��60000�̓d�q�ɑΉ�����Ȃ�A�f�q�ʐς�������ꂾ����������d�q������ł��傤�H
���ʂƂ��āu�d�q�ʁv�̕�������܂����A�O�q�̂悤�Ɍ덷�͋z�������̂ŁA�K�����������Ȃ邱�Ƃ͂���܂���B
���הO�ł���60000�̓d�q�ʂƂ����̂́A�Ƃ��鐻�i�̃f�[�^�őS�Ă��S�Ă��̐��ł͂Ȃ��ł���H
�������Ƃ��āA��f�T�C�Y���Ⴄ CCD ���ׂĂ݂Ă��������B�O�a�d�חʂ͉�f�T�C�Y�ɔ�Ⴕ�Ă��܂����H
�����v���Z�X�ō���Ă܂���ˁB���i���ƂɃ}�`�}�`�ł��B
��f�ɑ��Ĕz��������Ă��镔���̖ʐς�����܂����B
�����v���Z�X�̎B�e�f�q��ɉ����ĖO�a�d�חʂ͖ʐςɔ�Ⴗ��A�ł�낵�����ƁB
��GX200 ���������Ă���Ƃ��������́H
�����܂�����H
�q�X�g�O�����̍\���ɉ�����GX200�����̑ш悪�قȂ�܂��B
�����̐F���̍��Ȃ�A�q�X�g�O������̋N���̈Ⴂ�Ō���܂����A�ш悪�قȂ�͕̂s���R�ł��B
�E�̃��x����������ƐԌn�������Ȃ�Ƃ��������́H
��q
�u�������L�`���Ɖv���Ă��镔���ɂ����݂��̂͂������Ȃ��̂��ƁB
�����ԍ��F8786535
![]() 1�_
1�_
���ƁA�f�W�^���̂��Ƃ����������Ă��Ȃ��A�Ƃ�
�f�W�^���f�[�^����̎O���F�Ɋւ���m���Ɍ����Ă���Ƃ�����ۂ������Ȃ����A�Ƃ������
Hi-Bit��RAW�摜�ɂ��ė������Ȃ��̂͐����s�v�c�Ȃ̂ł����E�E�E
�V���b�g�m�C�Y�������o�����̂͂�����ł����A���̌덷�ɑ���Ώ��@�𗝉�����Ă��Ȃ�������B
�����g�̃z�[���y�[�W�ł��u�_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ������t�����p����Ă��܂���
���̏ꍇ�́u�_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ͉��ɑ���_�C�i�~�b�N�����W�Ȃ̂ł��傤�H
�����ԍ��F8786548
![]() 1�_
1�_
>�͂����肵�Ă���̂�P6000���u���O�a���Ă���v�Ƃ��������Ȃ�u�O�a���Ă���v���Ƃł��B
�����ł��ˁB�ڗ����Ȃ����x���ł���GX200��LX3���O�a���Ă镔��������ł��傤�B
���x�̖��ł��邱�Ƃ́A�����ŏ��ɖO�a�ɂ��Ăӂꂽ���X�ɂ������Ă���܂��B
�����ԂԂ�������܂������A���Ȃ��Ƃ����̓_�Ɋւ��Ă͌�������v�����悤��
�Ȃɂ��ł��B
�����ԍ��F8788247
![]() 3�_
3�_
�܂����ƂȂ��A�L���Z����̌����Ă鎖���������ȁA�Ƃ������͕��������B
�����ԍ��F8788547
![]() 4�_
4�_
���������ƂȂ��A�L���Z���c�_�����ݍ��킹����肪�Ȃ��ȁA�Ƃ����������͕�����܂����B
�i���e�����������ǂ����A����ȑO�̖��ł��j
�ŏI�I�Ɍ�������v�����Ƃ������Ƃ́A���lj��̂��߂�gintaro����Ɋ��݂�����ł��傤���H
���̂�����͋��s�̂�������Ɠ��ӌ��ł��ˁB
�����ԍ��F8792041
![]() 5�_
5�_
�u�_�c���͔̂��l���ۂ��v���߂����Ă��߂Ă���Œ���
�u�u���b�R�v�Ƃ�������̌�p���������Ƃ��Ă��A
�u���Ȃ��́w�u���b�R�x���S�R�킩���Ă܂���ˁv�Ȃ��
����Ȃ���Ζ{��ɖ߂邱�Ƃ͂ł���͂��Ȃ�ł����A
�ӂ���u�₳�����搶�v�Ƃ��ď��S�҂̎���ɓ����Ă���
���قǑΓ��ȋc�_������͓̂���̂�������܂���B
�㔼�͊���I�Ȃ��Ƃ�ɂȂ��Ă��܂��܂������A
on the willow���_�_���ӏ������ɂ����̂͊g�U����
�c�_�����A�u�c�_�����ݍ��킹��v��Ŗ𗧂���
�悤�ȋC�����܂��B
�@�P�F�̃f�[�^�ʂ����ł��ɂȂ邱�ƂŐ��m�Ȕ䗦��
����ĐF�����ς��H�Ƃ������ۂ����邱�Ƃ͏��߂�
�m�������A�l�I�ɂ͕��ɂȂ�X���ł����B
�u��͐��Ƃ͌���Ȃ��v�Ƃ����̂̓A�L���Z�����
����ꂽ�Ƃ��肾�Ǝv���܂����A�u����v���B�鎞��
���ꂩ�玄���I�o�ɋC�����悤�Ǝv���܂��B
P.S.
�O���̔��X�ƃu���b�R���ۂ��͖��W�Ȃ��Ƃ͏��m
���Ă���܂��̂ŁA���̂ւ�̃c�b�R�~�͂����ق�(^^;)
�����ԍ��F8792605
![]() 2�_
2�_
�Ƃ������A�Ȃ�ǂ������̂ł���
�u���O�a���������ł̓V�A���ɂȂ�Ȃ��v
���甽�_���������ł��B
���O�a������ɁA�S�̘̂I�����オ���ĐԂ������x�����オ���
���R�F���ȂǕς��̂ł��B
���J���[�䗦���ς��킯�ł�����B
���̓_�ɋ^�₪����Ȃ炢����ł�����͏o���܂��B
�����ԍ��F8792698
![]() 1�_
1�_
�A�L���Z����
�@�m���̖R�����l�ԂȂ��̂ʼn����Y�������Ƃ������Ă�����
�\����Ȃ��̂ł����A���b�̘I�����Ԃ̑O���ɐ��O�a���A
�c��̎��Ԃ��I���������ꍇ��
�����O�a������ɁA�S�̘̂I�����オ���ĐԂ���
�����x�����オ��Γ��R�F���ȂǕς��
�@�ƌ���ꂽ�P�[�X�ɂ�����̂ł��傤���B���������Ȃ�
���ꂪ���̃C���[�W���Ă����ł��B������̃X����
�c�_�͘I���I����̉摜�ɂ��Ă̘b���Ǝv�������̂ŁB
�����ԍ��F8792814
![]() 0�_
0�_
�e�k�L���O����
��悤��CCD�̘I�����ɖO�a���Ă��܂��ꍇ������܂��B
�����A�f�W�J����CCD�̃f�[�^�����͂������ĉ摜�Ƃ���V�X�e���̂���
CCD�f�[�^�i�K����o�̓f�[�^�ɐ�o���܂ł̊Ԃɕ����܂肪����
���̕����܂��C�ӂɗL�����p�����i��RAW�����ƍl���Ă����Ǝv���܂��B
���̃X���̒��ł��������܂������A���ۂ̕��i���傫�ȃo�P�c�Ȃ�
CCD���x���iRAW�摜�j�͒����炢�̃o�P�c
JPEG�摜�͂����菬���߂̃o�P�c�Ƃ��������ł��B
���̂ǂ��̒i�K�ł��ӂ�Ă��O�a�͂��܂����A�����F���́��O�a�ł�����
�ǂ����ɔ��F�����߂��i�K�Łu���̉摜�͖O�a���Ă�v�Ƃ����܂��B
�����Ȃ�Ɓu�O�a�v�Ƃ������t���̂̈Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂�
�u�O�a�v�Ƃ������t�̎g�������C�ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F8793010
![]() 0�_
0�_
�A�L���Z����
�@���������肪�Ƃ��������܂����B
�@���F�̋�͐��F�ɂȂ�ׂ��ł���悤�ɁA���F�̕�����
�O�a����͖̂��Ȃ��悤�ȋC�����܂����A���̖R�����m��
�ł͗����ł��Ȃ����Ȃ̂�������܂���B�ڂ�����������
���������Ă����ʂɂȂ邩������܂��A�����Ȃ���
���Ƃɂ��Ď��͂��̂ւ�łЂ��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8793070
![]() 0�_
0�_
��F�ɂ��ā@
----------------
>�q�X�g�O�����Ŗ����Ȃ̂�GX200�ł��ˁB
>�Ɛ̑����x�����������Ă܂�����A�u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂłĂ���v��Ԃł��B
>�܂��摜�S�̂̃q�X�g�O����������Ɣ���܂����A���̋@��ɔ�בS�̓I�ɖ��x���Ⴂ�\���ƂȂ�>�Ă��܂��B
������Ǝ���ɑ��ē����Ăق������̂ł��B
�M���̎咣�͉��L�̒ʂ�ł����B
>G10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă�
>�����ł��B
�����āA���̍����Ƃ��āA
>�����āA�̐F�������摜�ɂ́A��̐F�ɗ]��܂܂�Ȃ��u�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�X��������܂��B
>�Ɨō\�����ꂽ��̐F�ɐԂ݂������Ă��܂��Ă���T���v���摜�̋@��͂ǂ�Ƃǂ�ł��傤�H
�Ƃ̂��Ƃł������A���̋@��Ƃ́AGX200 �������w���Ă����̂ł��傤���B
�܂��AGX200 �͖��ʐF�������Ԃ��͎̂��������ʂ�ł��B����āA�̐F���������Ƃɂ���āu�Ԍn�v�̐F�����ΓI�ɂł�Ƃ��������A�z���C�g�o�����X�̉e�����ƌ���ׂ��ł��傤�B
�t�� P6000 �͐��O�a���Ă���ɂ��ւ�炸�A���炩�� G10 �����Ԃ݂���������F�ɂȂ��Ă��܂��B
���Ƃ̂��Ƃł����A�J������ RGB �œ��삵�Ă���Ƃ������Ƃ͂����m�ł����H
CMYK �̐����͂���Ȃ��ł��傤�B�����w�E���Ă���̂́ARGB �f�[�^������I�Ɏ����Ă���J�����ŁA������̂ɁA�̃��x��������̂ł͂Ȃ��A�}�[���^����������Ƃ��������������Ȃ��A�Ӗ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�M���́A���������邽�߂ɁA�Ȃ��u�}�[���^�𑫂��v�̂���_���I�ɐ�������K�v������܂��B
�����ԍ��F8800843
![]() 3�_
3�_
�_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��āi���̂P�j
----------------
>�Ⴆ�A�ŏ��M���ɑ��ĉ��{�܂ł̐M���������邩���_�C�i�~�b�N�����W�ŁAdB�ŕ\����܂��B
>�ł�����A�A�i���O���瑱���T�O�ł����A�f�W�^���ɑΉ����Ă��Ȃ��T�O�ł͂���܂���B
�������A�f�W�^���ɑΉ����Ă��Ȃ��T�O�ł͂���܂���B
�_�C�i�~�b�N�����W�̒�`��₤���ɑ��āA
��>���ƁA�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ����̂̓��`���[�h�͈̔͂ł͂Ȃ��ł���B
�ƃR�����g������A
>�摜�̃��`���[�h�Ƃ����Ӗ��ł̃_�C�i�~�b�N�����W��2��ނ���܂��B
�ƃR�����g������A
>�_�C�i�~�b�N�����W�{�f�W�^���G���W���̕�����`���[�h�A�Ƃ����̂��Ӗ��I�ɂ͐��m���ȂƁB
�ƃR�����g�����Ƀu����̂ŁA�₢�����Ă���̂ł��B
���ǁA�M���ɂƂ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͉��������m�ɂł��Ȃ��܂܁A���̎��X�Ń��`�`���[�h�Ɠ�����������A�����łȂ�������ł͘b�ɂȂ�܂���B
�i�I����AHi-bit �摜�Ƃ����p��ɂ��Ă����l�j
�Ƃ������ƂŁA�_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��Ă͍Ō�ɂ܂Ƃ߂܂��B
>�Ⴆ�A�ŏ��M���ɑ��ĉ��{�܂ł̐M���������邩���_�C�i�~�b�N�����W�ŁAdB�ŕ\����܂��B
>���ۂ̐��E�̖��Í���200dB�i200�{�j�̃_�C�i�~�b�N�����W���������Ɖ��肵���ꍇ��
>�f�W�J���̑f�q���x����100dB�i100�{�j�����Ȃ���A100dB���Ő�o���ق�����܂���B
200db �� 200�{�Ƃ����̂́A�ŏ��M���ɑ債��200�{�̐M����������Ӗ��̂悤�ɏ�����Ă��܂����A����͑傫�ȊԈႢ�ł��B����ł� 8bit �� 255db �Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�i�ŏ��M�� 1 �ɑ��� 255 �܂ň�����A�ŏ��M���ɑ��� 255�{�j
���ۂɂ̓_�C�i�~�b�N�����W = S/N�� = 20×log10(Signal/Noise) �ł����� 48db �ƂȂ�܂��B
�����������Ƃ��납��A�f�W�^���f�[�^�ɑ���m�����Ȃ��Ɣ��f���Ă��܂��B
>�ꉞ�A��f�ɂ͓d�q��60000���̊K�������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
���낢��˂����݂ǂ��떞�ڂł����A�܂��͂��̍����m�ɂ��Ă��������B
�M���̎咣�ɂ��ƁA�O�a�d�חʂ͉�f�T�C�Y�ɔ�Ⴕ�܂�����A�ǂ�� CCD �ł��d�q60000�����O�a�d�חʂł͂Ȃ��͂��ł���ˁB
����L���T�C�g�ł́AKodak 35mm �t���T�C�Y 1100����f CCD �̃X�y�b�N�̖O�a�d�חʂ�6���G���N�g�����i���d�q�U�����j�ƏЉ��Ă��܂��B
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/ccd/ccd.html
���̃T�C�g�Ŏw�E����Ă��� kodak �t���T�C�Y CCD �͂��ꂾ�Ǝv���܂��B
http://www.ccd.com/pdf/ccd_105.pdf
�M���̎咣�ł́A�O�a�d�חʂ͉�f�T�C�Y�ɔ�Ⴗ��Ƃ��B
�ł̓t���T�C�Y 1100 ����f�̉�f�T�C�Y�ƁA����̘b��ƂȂ��Ă���R���p�N�g�f�W�J�� 1/1.7inch 1200�`1500����f�N���X�ŁA�O�a�d�חʂ������d�q�U�����Ȃ�ł��傤���B
�咣���߂��Ⴍ����ł��ˁB
G10 �� 1/1.7inch CCD �͏œ_��������t�Z����ƁA�t���T�C�Y�Ƃ͖ʐϔ�ł������� 5% �ȉ��A��f�s�b�`�� 6.8��m �� 1.7��m�A�O�a�d�חʂ��d�q�U�����Ə����Ă��鎞�_�Ō���̃f�W�^���J�����ɏڂ����Ȃ����Ƃ��悭�킩��܂��B
>10bit��1024�K���A14bit�ł�4096�K���ł�����1�K�����S���V���b�g�m�C�Y�����Ŗ��܂邱�Ƃ͍l���ɂ����̂ł��B
��q���܂����A�_�C�i�~�b�N�����W�𗝉����Ă���A�ǂ̒��x�̊K���ŏ������ׂ������킩��̂ł��B
�{���Ƀf�W�^���ɏڂ�����A���̕ӂ�̈Ӗ���������͂��ł��B
>�V���b�g�m�C�Y����������m���́A���̉�f���̑Ή��d�q�Ɍ���������Ȃ��Ɣ������܂���
>�S���̉�f���O�a���������i�K�i��ʂ͐^�����j��0.41��=��60000÷60000
>1/100���x�̓d�q�ɂ������̗��q��������Ȃ��ꍇ�́A600�̓d�q�ɉ�����4.1���̏o�����ɂȂ�܂��B
���{��ɂȂ��Ă��܂����BCCD �͌��q���t�H�g�_�C�I�[�h�ɓ����邱�Ƃœd�q�i�Ɛ��E�j����o���܂��B�u1/100���x�̓d�q�ɂ������̗��q��������Ȃ��ꍇ�v�A�Ƃ͌��̃T�C�g��ǂ̂��낤�Ƃ͎v���܂����A���������Ă��Ȃ��̂̓����o���ł��B
�ނ̂����ʂ�A�O�a�d�חʂ���f�ʐςɔ�Ⴗ��̂ł���A1/1.7inch CCD �̖O�a�d�חʂ͓d�q�ɂ��� 3750 ���ł��i�j
�ނ��咣����v�Z�̍����������ɂł���߂�������ł��傤�B���ꂾ���̖ʐϔ䂪����ƁA�������Ƀv���Z�X���[���̈Ⴂ�������Ă�����������܂���B
�������A�ނ͓����A���̎咣�ł���
>�O�a�d�חʂ����Ȃ�����f�����ꂽ CCD �ɂ����āA�����Ƃ����Ȃ̂̓V���b�g�m�C�Y�̕��ł��B
�ɑ��A
>�V���b�g�m�C�Y��1��f�̖ʐς��������f���ɉe����^���邱�Ƃ͏����܂����B
�ƈ�U�͓��ӂ��Ă���͂��Ȃ�ł���ˁB
���̌�A�ނ� CCD �f�q�͐l�Ԃ̖Ԗ����_�C�i�~�b�N�����W���L���Ƃ���������ł����ĂĂ܂����A���Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă����܂��B
�����ԍ��F8800882
![]() 3�_
3�_
�_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��āi���̂Q�j
----------------
�_�C�i�~�b�N�����W�̒�`�i�����Ѝ��ꎫ�T���j
�_�C�i�~�b�N�]�����W[dynamic range]
�������u�̑�����ȂǂŎ�舵���ł������ƍł��㉹�Ƃ̔�B�ʏ�͉�����ŕ\���A�P�ʂɃf�V�x����p����B�A���v�ł͍ő�o�͂ƎG�����x���̔�Ȃǂ������B
�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A����������`�ł��B����ȊO�̒�`�͋M���̃��[�J�����[���ł��B
�摜�̈Õ����疾���܂ł̖��Í��Ƃ����Ӗ��ł̓��`�`���[�h�Ɠ����Ƃ������܂����A
http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/imagingdevice/guide/dic/dynamic.html
�������A�_�C�i�~�b�N�����W����掆�ɏĂ��ۂ̘I���͈̔́i���e�x�j�Ƃ����Ӗ��͂���܂���B
���̕ӂ̐蕪�����Ȃ��A�p��𐳊m�Ɏg��Ȃ��̂ŁA���x���u�M���ɂƂ��Ẵ_�C�i�~�b�N�����W�v��₢���������̂ł��B�i�I���̎g�������߂��Ⴍ����AHi-bit �摜�Ƃ�����`���B���j
CCD �̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��ẮA�����̐�����������₷���Ǝv���܂��B
http://www7.ocn.ne.jp/~terl/TechWin/TechWin.htm
>���x�ƃm�C�Y
>�m�C�Y�v�f�Ƃ��ẮF���V���b�g�m�C�Y�A�Ód���A���Z�b�g�m�C�Y�A1�^���m�C�Y�̂S����̂ł���B
>�_�C�i�~�b�N�����W�͖O�a�M���ʂɂ�����A�m�C�Y�̗ʂ�\�����̂ł���A���L�̎��Œ�`�����B
>�@�@�@�c�q��20 log�o�O�a�M���ʁ^�m�C�Y�ʁirms�j�p
�_�C�i�~�b�N�����W��������ƁA�ǂ̒��x�ŗʎq�����邩�i���ǂ̒��x�̊K���Ńf�W�^���f�[�^�����邩�j�����m�ɂȂ�܂��B
�ȒP�ɂ����A8bit �f�[�^�� 48dB �Ƃ����̂͏������ʂ�ł����A48dB �ȉ��̃A�i���O�M���ł���A8bit �K���ɂ���Ώ\���ŁA�t�� 10bit �� 12bit �ŗʎq�����Ă��A�m�C�Y���ׂ����K���������邾���ŁA�Ӗ����Ȃ��Ȃ�܂��B
�����������Ӗ�������A�ނ̎咣����悤�ɁA�V���b�g�m�C�Y���K���ɂ����e����^���A�_�C�i�~�b�N�����W�ɉe����^���Ȃ��Ƃ����咣�������ɂ��������̂����悭�킩��܂��B
>���P�ȉ��̐M���̍��������ł��Ȃ��ł�����A�����������Hi-bit�ŃT���v�����O���Ă��Ӗ��͂���܂���B
>���i���Z���X�ȉ��肾�Ɨ����ł��܂���ˁH�V���b�g�m�C�Y���덷�͈̔͂Ɏ��߂�H�v�����R����܂��B
>�Ȃ̓r���ɋȂɊ֘A�����m�C�Y���A�����������Ƃ��Ă��_�C�i�~�b�N�����W�ɂ͊��Z���܂���B
>���̔����p�^�[�����Ȃ�����A�Ȃƃm�C�Y�M���̕������ł��Ȃ�����ł��B
���������A�ȁi�M���j�ƃm�C�Y�����S�ɕ����ł���Ǝv���Ă���̂ł��傤���B
�ނ̓_�C�i�~�b�N�����W�����Í��A�Ƃ����T�O�����Ȃ��A�f�W�^���f�[�^�i�ƃA�i���O�f�[�^�̗ʎq���j�ɂ��Ĕ��ɑa���̂��悭�킩��܂��B
���N�A�f�W�^���f�[�^����舵���Ă�����������܂��A�������Ď�舵���̂͂܂��ʂł��B
�i���̕K�v���Ȃ������̂��Ǝv���܂����j
�����ԍ��F8800912
![]() 3�_
3�_
G10�������Ƃɓ͂��ėL���V�Ȃ̂ŁA�C����������ԐM���܂��O�O
�ł��A�_�C�i�~�b�N�����W�Ɋւ���Wiki�ł̐������S�ĂƂ����Ă����l���A�}�ɐ��������o���̂��ςȘb�ł��ˁi�j
�����ԍ��F8801065
![]() 1�_
1�_
���̑�
---------------
>��Hi-bit �摜�Ƃ����M���Ɠ��̗p��̒�`�ł��B
>8bit�摜�A16bit�摜�Ƃ����\���͂��邪�A��bit�摜�Ƃ����������͂Ȃ��Ƃ����̂ł��ˁH
>�uHi-bit�f�[�^�v�Ō������Ă݂Ă͂������ł����H
�ł�����A�M���̓Ǝ��̃_�C�i�~�b�N�����W�̒�`�Ɠ��l�A�����̓��̒������ł̗����ŁuHi-bit �摜�v�ƘA�Ă�����̂ł�����A���� Hi-bit �摜�̒�`�����߂Ă���̂ł��B
�M�����uHi-bit�摜�Ƃ́A��ʂ�8bit�摜���K�����̑����摜�ŁA�����ɂ�9bit�i2��9��=512�j�ȏ�̉摜�ł��B�v�ƒ�`���Ă����Ȃ���A�ォ�炠���ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��ƌ������畷���Ă���̂ł��B
��������������������ɂȂ��Ă���p��𑼐l�Ɏg���ׂ��ł͂���܂���B
>���l�Ԃ̖ڂ��f�q�̕����_�C�i�~�b�N�����W���L���Ƃł������̂ł����H
>�܂��_�C�i�~�b�N�����W�ł��ˁB�f�W�^���ł����ɕ\�����Ȃ��̂͗����������������Ǝv���̂ł����B
�ȂO�_�O�_�����Ă���悤�ł����A�l�Ԃ̖Ԗ��̃_�C�i�~�b�N�����W�͖�80dB�������ł����A
���N�̂P�Q���ɔ��\���ꂽ���C�h�_�C�i�~�b�N�J���[�J������ 65dB �ł��B
http://www.sanyo.co.jp/koho/hypertext4/0812news-j/1208-2.html
����ȃJ�����Ȃ� 80dB �ȏ������܂����AG10 �̃Z���T�[�� 80dB ����Ƃ͎v���܂���B
���Ȃ݂� 12bit �f�[�^�� 72dB �ł��B
���I�o�Ƃ̓V���b�^�[���J���ăZ���T�[���Ă邱��
��RAW�����\�t�g�ł̘I�o�Ƃ́A�����܂Ŏ��ۂ̌�����Ƃ̌��������i�V�~�����[�V�����j�ł���A�����ۂɘI�����Ă����ł͂���܂���B
���Ȃ����̕��������A�i���O����̊T�O�ɍS��̂��s�v�c�ł��ˁB
�I�o�Ƃ́i�����Ѝ��ꎫ�T���j
��]����y�I�o�z�X��
�P������ł邱�ƁB�܂��A����킵�������ƁB�u�₪�\�����R���v�u�����\����v
�Q�J�����ŁA�����Y�̃V���b�^�[���J���āA����t�B�����̊������Ɍ��Ă邱�ƁB�I���B
http://www.smalldisney.com/words/photo/rosyutsu.html
>�t�B������B���f�q�iCCD�ACMOS���j�Ɍ��Ă邱�Ƃ������B
�Ƃ������Ƃł��B�A�i���O����̊T�O�]�X�ł͂Ȃ��A�O�����Ɠ��l�A�M�������m�ȗp��𗝉����Ă��Ȃ������ł��B
>�ʂɘI�o�����ł͂Ȃ��A�ʂɘI����������̂�3CCD�����̃J���������ɑ��݂��܂��ˁB
>���Ǝc�O�Ȃ���A����т�RGB�S�Ă̌��̌��ʂȂ̂ŁA�ʂɘI�o�����Ă��h���܂����B
�S�������ł��Ȃ��悤�ł��ˁB3CCD �� RGB �ʂɘI�����Ă��܂����A�ʂɘI�o���R���g���[�����Ă����ł͂���܂���B
RGB ���ʂɘI�o���R���g���[���ł���ARGB ���ꂼ��ɑ��ĖO�a���Ȃ��I���ʂŎB�e�ł��܂��B�I���ʂ��킩��A�摜������ RGB �̃��x�������āAWB����邱�Ƃ��ł��܂��B���S�ɔ���т�h�����Ƃ͂ł��܂��A�����O�a����Ƃ������ꍇ�ɗL���ł��B
���ꊇ���ĘI�o�����邱�Ƃ����ł����A���̂��߁u�����O�a����v
���������Ⴂ���Ă܂���H�J���[�o�����X����܂���B
�I�o�Ɖ摜�����̃��x�������Ƃ�������ɂȂ��Ă��邩��A�����������R�����g�ɂȂ�̂ł��B
���ꂼ��̘I���ʂ�������A�摜������ RGB ���ꂼ��̃��x�������킹��̂͊ȒP�ł��B
>������� CCD �ŎB�����A�擾�����摜�f�[�^���摜�����Ń��x�������邱�Ƃ��w���Ă���Ƃ������Ƃŗǂ��̂ł��傤���B
>��܂��ɂ͂����ł��ˁB
�Ȃ�ΘI�o�Ƃ������t���g���ׂ��ł͂���܂���B
�I�o�Ɖ摜������̃��x����͑S���Ⴂ�܂��B
>���O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ė{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
>�b���߂�܂����A���̂��߂�RAW�摜�ł͍L���_�C�i�~�b�N�����W�Ńf�[�^�L�^���Ă���ƌ����Ă܂��B
>RAW�摜��Jpeg�����o���摜�̊W���A����Ɠ������Ƃ������Ƃ����̗������ĖႦ�Ȃ��̂ł��傤�H
RAW �ł����Ă��A�O�a���Ă��Ȃ��Ƃ͒f���ł��Ȃ��ƃR�����g��������ł͂Ȃ������̂ł����H
����Ƃ��ARAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ��Ƃ��A��ɂ��Ȃ��ƒf���ł���̂ł����H
�O�a���ĐF�����ς���Ă��܂�����A�I�o�������Ă��{���̐F���o�����Ƃ͂ł��܂���B
>��CCD ���x���ŖO�a���Ă��AWB �͎��܂���B
>���F�����킹��WB�Ȃ̂ɁA�F�����ς���Ă��Ă�WB�����̂ł��ˁi�j
>�����āA�܂��}�ɖO�a���Ă���̂͋��̑O��ɂȂ��Ă��܂��B
�M���̃J�����́ACCD ���O�a������AWB �����Ȃ��Ȃ�̂ł����H
���̃J�����͖O�a���������̐F��������邾���ł����B
>�������Ƃ��āA��f�T�C�Y���Ⴄ CCD ���ׂĂ݂Ă��������B�O�a�d�חʂ͉�f�T�C�Y�ɔ�Ⴕ�Ă��܂����H
>�����v���Z�X�ō���Ă܂���ˁB���i���ƂɃ}�`�}�`�ł��B
>��f�ɑ��Ĕz��������Ă��镔���̖ʐς�����܂����B
>�����v���Z�X�̎B�e�f�q��ɉ����ĖO�a�d�חʂ͖ʐςɔ�Ⴗ��A�ł�낵�����ƁB
��f�T�C�Y���S�{�ɂȂ�����O�a�d�חʂ��S�{�ɂȂ�Ə������̂͋M���ł�����A���̍������B
�����Ȃ��������ŃO�_�O�_�����͎̂��Ԃ̘Q��ł��B
��������� CCD ����ׂĂ������ł���B
�����ԍ��F8801093
![]() 2�_
2�_
��̑�l������I�ɂȂ��ĂȂ��ł����������C�ǂ߂�
�����ԍ��F8801127
![]() 2�_
2�_
>CCD�f�[�^�i�K����o�̓f�[�^�ɐ�o���܂ł̊Ԃɕ����܂肪����
>���̕����܂��C�ӂɗL�����p�����i��RAW�����ƍl���Ă����Ǝv���܂��B
CCD �ł͖O�a���Ă��ARAW �ł͖O�a���Ă��Ȃ��Ƃł��H
���́u�����܂�v���ĉ��ł����H
�܂��悭�킩��Ȃ��p���A�����܂���ˁB
�ԁ]�ǂ܂�y�����i�܁j��z
�P���H����ꍇ�́A�g�p�����ɑ��鐻�i�̏o�����̔䗦�B
�Q�H�i�̌��`���ɑ���H�p�\�ȕ����̔䗦�B
�����ACCD �ŖO�a���Ă��A�ǂ������m�̂Ƃ���ɗL���f�[�^���c���Ă���ƐM���Ă�����ۂ��B
>�ł��A�_�C�i�~�b�N�����W�Ɋւ���Wiki�ł̐������S�ĂƂ����Ă����l���A�}�ɐ��������o���̂��ςȘb�ł��ˁi�j
Wikipedia �� Wiki �Ɠ����ł͂���܂����B�p��͐��m�Ɂi�j
�����A�킩��₷���̂ň��������ɏo�����Ƃ͑����ł����ǂˁB
�M�����߂��Ⴍ����Ȑ��l�뗝�_�������o���Ă����̂ŁA������Ɛ������������ł��B
�_�C�i�~�b�N�����W�̎��Ȃ́A���������Ԃ�O�ɂ����i.com �ŃR�����g���Ă��܂���B
�M�����Q�l�ɂ��ė����ł��Ȃ������T�C�g���܂߂ďЉ�ς݂ł��B
���Ȃ猟�����Ă݂Ă��������B
>�ǂ����ɔ��F�����߂��i�K�Łu���̉摜�͖O�a���Ă�v�Ƃ����܂��B
�M���̃f�W�J���ł́A�����Ԃ��B��ƖO�a���Ă���̂ł��傤���B
���Ƃ͂����A���ʂ͊K���͂�����̂ł���B
�����ԍ��F8801137
![]() 1�_
1�_
�n�C�}�`�b�NC����
�M���Ȃ��ɂ����ł��ˁB
�Ԉ�������ƂX�ƁA�������ォ��ڐ��ʼn��X�Ə����l�ɑ��āA�w�E�ƒ��������X�Ƃ���Ă��邾���ł��B
������ƕ���Ȃ���ˁB
���s�̂�������
>[8736165]
>[8740972]
>���̂�����ǂ�ł��A���������������������̂��S�R�킩��Ȃ��ł��ˁi�������萻�i�i�삷�邩�炻���Ȃ�̂ł��傤�j�B
>�ǂ��܂Ŋm�M�ƂȂ̂����ɂ͂킩�肩�˂܂����A�u���̋�̐F�����R�v�Ə��������_�Łu�A�E�g�v�ł��B
>�E�m���Ă��āu���R�v�Ə����� �� ���i�i��̂��߂ɉR��t�����i�m�M�Ɓj������u�A�E�g�v
>�E�u���ہv��m��Ȃ����� �� �m��Ȃ��ś���������ח��Ă鎞�_�Łu�A�E�g�v
>�E�{���Ɏ��R�Ɗ������u�̂݁v������u���R�v�Ə����� �� ���o�I�Ȏ��ۂɑ��A�������_�I�ȗ��Â������邩�̂悤�ɏq�ׂĂ��鎞�_�Łu�A�E�g�v
�قړ��ӂ��܂��B
�����ԍ��F8801158
![]() 1�_
1�_
�������Ă���������1�l�Œ������X6���t����̂͐q�킶��Ȃ��Ǝv��
�X�����オ���Ă���Ǝז��������A�h�ł�������������2�l�����ł������H
�����ԍ��F8801174
![]() 5�_
5�_
�ȑO�ɂ������̕���������Ă܂����E�E�E
�w���������Ɂx���낻�낱�̏�ŋc�_����̎~�߂܂��H
on the willow����͂����g��HP���������̂悤�Ȃ̂ł�����ɂł��U������
�v�������A�D���Ȃ����R�~���j�P�[�V�������ςގ��ł���H
�����ԍ��F8801187
![]() 5�_
5�_
�����܂ŏ��������Ƃ��Ȃ��悤�Ȑl���ˑR����āA�Ӗ��̂Ȃ��ꌾ�R�����g�𑱂����������ۂǐq�킶��Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F8801197
![]() 2�_
2�_
�Ȃ����̃z�[���y�[�W�]�X�Ǝw�}����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����킩��܂��A��������Ȃ為�Ђ��҂����Ă��܂����A�����̐l�ɗL�p���Ǝv���܂���B200dB�i200�{�j�A�Ȃ�Ă̂͊��قł����A
>>G10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă�
>�����ł��B
��������ƍ�������b�Ȃ�A�����[���b�ł��B�������A���ȃ_�C�i�~�b�N�����W�̒�`�Ȃ�Ă̂��o�Ă��邩��A���̎w�E�ƒ����������Ȃ��ł���B
���̃X���b�h�̘b��́A���̃X���b�h�ő����܂���B
�����ԍ��F8801236
![]() 1�_
1�_
���A����ς茻�ꂽ �n�C�}�`�b�NC����
�����ԍ��F8801267
![]() 1�_
1�_
�Ăщ����玸�炵�܂��ˁB
�ꉞ�ȑO�������݂��Ă��Łg�|���Əo�h���ᖳ�����珑���Ă��ǂ��ł���ˁH
��芸�����A���������ė~�����Ƃ͎v���܂��B�i�N�E�ǂ��� �Ƃ��͖��L���܂���Afor ALL�I�ȈӐ}�ł��j
on the willow����A�u�ށv���ĒN���Ȃ��ď��ߔY�݂܂�����H�i��j
�����ԍ��F8802666
![]() 0�_
0�_
�܂��A�����X���̓N�`�R�~�y�[�W���d���Ȃ��ĕs�ցA�Ƃ�����������Ǝv���܂����A�����I�ɂ́A�������݂�c�_�̎��R�̂ق����D�悳���ׂ����낤�Ǝv���܂��B
�����Aon the willow����̎w�E�ɑ��āA����������V���ɓ˂����݂ǂ���𑝂₵�Ă䂭�\�}�̌J��Ԃ��ŁA���l�ɂƂ��Ă��ǎ҂ɂƂ��Ă��A�L�v�ȋc�_�ɂȂ��ĂȂ��_�͎c�O�Ɏv���܂��B
�ȉ��́A�c�_�̔��[�ɂȂ������̂Ƃ��āA�����̒��ł̂�����Ƃ��Ă̂܂Ƃ߂ł��B
���Ƃ��ƁA���́A
>�P�g�ڂ̉摜��G10�̋�͎v������O�a���Ă܂��B
>���ۂ̋��F�̏ꍇ������܂��̂ŁA���F����ɖO�a���Ӗ�����킯�ł�
>����܂��A�����������F�͖O�a���Ă�ꍇ�������Ǝv���܂��B
�Ƃ�������蔭���H�ɑ���A�A�L���Z�����
>�ŁA�u�O�a�v�Ƃ����\���ŕ\����錻�ۂŁA���V�A���ɂȂ鎖�͂Ȃ��ł��B
>�F�̐��E�Łu�O�a�v�Ƃ����A�O�����E�O���F100%�����ɊK�����V�t�g���邱�Ƃł�����
>���Ԃ�A�p������Ⴂ���Ďg���Ă�̂ł��傤�B
�Ƃ��������_�H�ƁA����ɑ���on the willow����̓˂����݂��A�c�_�̎n�܂肾�����Ǝv���܂��B
���̓_�Ɋւ��āA���ǁA�A�L���Z����́A
>�͂����肵�Ă���̂�P6000���u���O�a���Ă���v�Ƃ��������Ȃ�u�O�a���Ă���v���Ƃł��B
�ƁA����on the willow����̂��Ƃ��Ƃ̎咣����������F�߂�ꂽ�����ŁA
>�u�F�̖O�a�v�Ƃ����T�O�ɉ����Č��F�́u�v���O�a�������ʁu�V�A���v�ɓ]��
�Ƃ����A�u�N�������ĂȂ��咣�v�ɔ��_���Ă����̂��Ɨ͐�����Ă���悤�ł��B
���̕ӂ��͂����肵���̂́Aon the willow����̔S�苭�������̂������Ƃ������܂����A����ŁA���Ⴀ�A��̔����₻�̌�̋c�_�͂Ȃ����A�Ƃ����E�͊����A�����ւ����܂���B
����Ȓ��q�ł�����A���̐�̋c�_���A�L�Ӌ`�Ȏ������݂邱�Ƃ͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
������⑫���Ă���������on the willow����ɂ͊��ӂ��Ă���܂����A����ŁA���ꂪ���������Ŏ��Ԃ��Ƃ点�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��A�S�ꂵ���C�����Ă��܂��B�B
�����ԍ��F8804069
![]() 4�_
4�_
gintaro���� �� [8742396] �ʼn�����������Ă܂�����ˁi���ɏd�v�Ȉꕶ�ł��j�B
���ǂ�ł� gintaro���� �̔����ɉ������������Ȃ����A�w�������ҁA���@���[�U�[�A����ǂ��납���̋L���̒��҂ɑ��Ă��z���̍s���͂������͂Ɏv���܂��B
�����ԍ��F8805384
![]() 1�_
1�_
�����́B
���X���b�h�ŏЉ��"DC Watch"�̎ʐ^�A�ʂ̎�i�ł̕��́A���ɂł����炨�������������B�u�����҂̏����̂Ȃ��]�ځv�͂܂������Ȃ̂ŁA��������H�����摜�̓��e���܂���B�菇�����Љ�A�e���łǂ����B�ړI�͋�̕����̐F��f�̃O���f�[�V�����̂킸���ȕω��̊ώ@�ł��B
����Ȃ�̋@�\�̂���O���t�B�b�G�f�B�^�[��p����
�_�E�����[�h�������ꂼ��̎ʐ^�ARGB��3�F�ɕ������܂��B���ꂼ��O���[256�K���ɂȂ�܂��B
�`�����l���̃n�C���C�g���̂킸���Ȗ��Í������������悤�ɁA���邳�ƃR���g���X�g�����Ċώ@�B
(�����̓O���[256�K����"���E�`�`�ԁE��"�̃J���[�O���f�[�V�����ɕϊ����Ċώ@���܂���)
�莝���̃\�t�g��G10�̉摜�����������A�ȉ��̐ݒ�Ŗ��m�ɂȂ�܂����B
Win95����� PaintShopPro4.2J �ł́A�`�����l��������A���邳:-50�A�R���g���X�g:+95
PowerShot A620�t���� PhotoStudio ver.5 �ł́A�F������A���邳:-128�A�R���g���X�g+120
EPSON�̃X�L���i�[�t���� PhotoShop 5.0 LE �ł͓�����B
G10�ȊO�̋@������邳�ƃR���g���X�g�̐ݒ���������Ď����ƁALX3 �Ƒ���3�@��ł͗l�q���Ⴄ�̂��ώ@�ł��邩�ƁB
�����ԍ��F8806022
![]() 0�_
0�_
�m���ɃR���g���X�g��������킩��₷���Ȃ邩������܂���ˁB
G10 �̐�́u�iBlue�j�v�ɂ��~���Ȃ���܂���i���ӕ��������j�B�킸���Ɍ�����o���c�L�̓m�C�Y�ł��B
���������i.com �O�㖢�����̒p���������X���b�h�ł��ˁi�����܂ł��l�I�ɂˁj�B
�ǂ��� G10 �̋��i�삷��Ȃ�����ƕʂ̐���ɂ�������̂ɁB
���́u���̋�͂������������Ȃ낤�ȁv���đ�̂킩������ł����ǁA���ꂾ�� G10 ��i��ł��܂��ˁB�i��ǂ��납 G10 �̗D�G�|�C���g�������Ă��܂��ˁB
����͑��ΓI�� LX3 ���������낷���ƂɂȂ��Ă��܂��܂����A��r�Ƃ��������セ��͂��傤���Ȃ��ł��ˁB��r�A�Ό��B�ǂ����̃|�C���g�ɂ��ėD������킹�邱�ƂɂȂ����Ⴂ�܂�����B
�������������ň���J����Ȃ�Ĕn���炵���ł��B��ÂɌ���Ό����Ă��܂��B
gintaro���� �������Ă܂��B�u�p�[�t�F�N�g�ȋ@��͑��݂��Ȃ��Ƃ����O��Ńx�X�g�ȑI�����B�B�v���āB
�����ԍ��F8806122
![]() 1�_
1�_
�Ȃ�Č��������B�B
�����ԍ��F8809555
![]() 6�_
6�_
�����ł��ˁI�I�@
�ʔ����o�g���Ȃ̂őS���ǂ܂��Ă��������܂����B�@
on the willow���U�߂āA�A�L���Z���|�g�|�g�ςȕ��i����ւ������j�𗎂Ƃ��Ȃ���A��������Ă���l�q�͔��ɖʔ����ł��B
�˂����܂ꂽ�Ƃ��ɁA���p��Ƃ����t�̒�`�ɓ�����A�L���Z����̋Z�́A��ɏ��ĂȂ��i�͂��́j�_��ɏ��Ă��p�Ƃ��āA�ƂĂ����ɂȂ�܂��B�@
����͔�J���ނ��܂��ˁI�I
�A�L���Z����͂ƂĂ��l�C��������̂悤�ł����A���̗��R�����ƂȂ��킩��܂����B�@
on the willow����̂������̕����������Ǝv���܂����A���ĂȂ����������܂��B
�ł��A�C���I�ɂ�on the willow������������܂��I�I
�����ԍ��F8809844
![]() 7�_
7�_
�ꂢ����
�����������̂ł��傤���H
�E���̎O���F���O�����ƌĂԂׂ����Ƃ����咣�ł����H
�E�������ɎO���F�Ƃ����ƌ��̎O���F�ł͂Ȃ��āA�F�̎O���F���w���Ƃ����咣�ł����H
�E�f�W�J���ł͌��̎O���F�ŐF��\�����Ă���̂ɁA������̂Ƀ}�[���^��������Ƃ����咣�ł����H
�����͂ǂ���Ԉ���Ă��܂����A����ȊO�Ȃ疾�m�Ɏw�E���Ă��������B
�����ԍ��F8810345
![]() 2�_
2�_
on the willow���͂悤�������܂�
�V�A���Ƀ}�[���^�𑫂��ƐF�ɂȂ��Ă邱�Ƃł��B
���F�̋��F�ɂ���ɂ̓}�[���^�𑫂��̂������ł���
�����ԍ��F8810765
![]() 0�_
0�_
>�}�[���^�𑫂�
���������Ȃ��̂ˁB���q����܂͖ق��Ă邩�A����������Ύ���`���ɂ��悤�ˁB
���̎���̃T���v�����O�Ƃ����_�ł͂��̃X���b�h�ɂ��Ӗ������������ȁB���\���������݂��������C��t���āB
�����ԍ��F8811256
![]() 2�_
2�_
���ꂢ����
�F�̎O���F�����ꍇ�͐������ł����A���̏ꍇ�͌��̎O���F�̘b�ɂȂ锤�ł��̂œ��ěƂ�Ȃ��Ǝv���܂���
�����ԍ��F8811393
![]() 2�_
2�_
��̕\���ɂ��ẴX�����Ǝv���A�ŏ�����������ǂ�ł��܂��������������͖Y��܂������w�O�a�̒�`(?)�x�ɂ��Ă�
�_�c�ɂȂ荡���A�O���F�ɂ��ẴX���������Ă��܂��B����ɂ��Ă͂���Ӗ��A�������L�Ӌ`�ȃX�����Ǝv���܂���
�F�̕\���͂ɂ��Ă͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H���X�̃X���傳��̎���������ɂ���AG10�ł̕\���͂�
�ւ�����e�������Ǝv���܂��B
�����B�������̕\���́i�����ڂɋ߂��j�̂���@��ɋ���������܂��B
RAW���g���A�g��Ȃ��͂��܂�d�v�����Ă͖����A�B�������̕\���͂��d�v�����Ă��܂��B
�l�̍D�݂�����܂����wʲ�����߸��ҁx�ł͂ǂꂪ�����̂ł��傤���H
���X�ł�������ǂ��Ȃ�ł��傤�H
�����ԍ��F8811656
![]() 0�_
0�_
PC�i�������čs��������@
���炩�̃f�W�J�����������ł����H
�f�W�J�����O�Ɏ����o���āA�\�}��ς��ĉt����ʂ��ώ@���Ă��������B��������킩��Ǝv���܂���B
���Ȃ�g�ѓd�b�̃f�W�J���ł������ł��B
�A�L���Z���� �͂��������f�W�J���̊ώ@���l�@������Ă��Ȃ�����������u�O�㖢�����̒p���������v���ď����܂����B
������x�����N��̎l�@��̉摜�����������ׂČ��Ă��������B
�l�@��Ƃ����ʂ̃f�W�J���Ɖ���ς��Ȃ����A����������ʂł͎l�@��Ƃ��قƂ�Ǔ������������ł��낤���Ƃ������ł��܂��B
�܂�ǂ��I��ł��ꏏ�B
��̐F�̈Ⴂ��m�肽������̉��̎l���B�ł��ǂ�� RAW�����Ȃ̂ŁA�B���ďo���̋�̐F��m�肽���l�ɂ͂��̋L���͎Q�l�ɂȂ�܂���B
�܂肱�̋L���Ő�̐F�ɔM���Ȃ邱�Ǝ��Ԕn���炵���̂ł��B
�����ԍ��F8811734
![]() 1�_
1�_
>�V�A���Ƀ}�[���^�𑫂��ƐF�ɂȂ��Ă邱�Ƃł��B
>���F�̋��F�ɂ���ɂ̓}�[���^�𑫂��̂������ł���
�����܂ŃA�J���T�}�ȃ|�b�Əo�̃j�b�N�l�[���́A����ɑO�㖢���ł��ˁ�
�u�F�̎O���F�v�ł̓V�A���Ƀ}�[���^�𑫂��ƐF�ɂȂ�͓̂��R�ł��B
�����A�c�O�Ȃ���f�W�J���摜�̒��g�́u���̎O���F�v�̃f�[�^�ł��B
�킴�킴�u�F�̎O���F�v�ɕϊ�����K�v���Ȃ����A�u�}�[���^�𑫂��v�_���I�K�R�����S���Ȃ���ł���B
�����ԍ��F8811811
![]() 1�_
1�_
����ɂ��́B���ז��̂��ŁE�E�E
���X���b�h�Љ�̎ʐ^�̋�̕`�ʂɊւ��āE�E�E
���L�p�̃����Y�A�����ӌ����̒����������Y�ŎB��ƁA�����I�o�A�摜�����ł��A��̕��A�V���ɋ߂���͐��Z�������Ȃ����Ȃ��Ďv���܂��B����Ȏʐ^�̕����A���Ԃ�A�����C�C���ƁB
�K�����L�p�����Y�̃\���ł����ӌ����͂��قNj����͂Ȃ������ŁA�ł��A����ɖ؉A�̈Â������̕`�ʂ�����ׂ�I�o���x�����R�R�ɂ��Ⴂ�������āA�����RAW�����\�t�g�̕Ȃ����肻���ŁA�悭�킩��Ȃ����Ă̂����z�ł��B
����4�@��ǂ���AAuto�̂܂�JPEG�B���ďo���Ȃ�Ⴂ�͂����Ă��A�B��肪�������炵�Ă��Ƃǂ��ɂł��B��A������y���ރf�W�J���Ǝv���܂��B�L�p�̉�p�����͂ǂ��ɂ��Ȃ�܂��B
�ŋ߂������w�����ꂽ��A�w����������Ă�����ɂ́A�Ⴂ�͔Y�܂�����肩������܂��B
�����ԍ��F8811941
![]() 0�_
0�_
���̎O���F�ł́A�}�[���^�𑫂������ɕ�F�̗��������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�F�i���j�����́u�F�𑫂�����F�������v�Ɠ����Ȃ̂ŁA�A�L���Z�����
���̐��������ĂȂ��̂��Ɗ������̂ł����B�B�B
���ƁA�����Ԃ�ȕԐM������������܂��ˁB�B�B
�����ԍ��F8812136
![]() 2�_
2�_
�����炨�q����܂͖ق��Ă���āB
�O�a�̘b����H �Έ���������Ђ��Ⴀ���������B����̓��^�b�`�ˁB���ɃV�A�����ۂ��ʂ��Ă���̂����Ȃ́B
����Ȃ璚�J�ɓ����Ă����Ǝv����B
�X�b�]�R����������
>���L�p�̃����Y�A�����ӌ����̒����������Y�ŎB��ƁA�����I�o�A�摜�����ł��A��̕��A�V���ɋ߂���͐��Z�������Ȃ����Ȃ��Ďv���܂��B
�I�o�Ⴂ�܂���B
�����ԍ��F8812226
![]() 1�_
1�_
>�F�i���j�����́u�F�𑫂�����F�������v�Ɠ����Ȃ̂ŁA�A�L���Z�����
>���̐��������ĂȂ��̂��Ɗ������̂ł����B�B�B
�ނ̎咣�̍����Ƃ��Ă��镔�����ēx�����o���܂��B
>�V�A���Ƀ}�[���^�𑫂��Ɛ��Ȃ邽�߁A�}�[���^���ɒ������܂���肭�����ł��Ȃ��ƃ}�[���^�������A
>�̃C�G���[�����ƍ��킳���ĐԂ������܂��B
�ł�����A���x���������l�ɁA���̎O���F�̘b�����Ă���Ȃ��ŁA�F�̎O���F�������o���āu�}�[���^�𑫂��v�Ƃ������_�ŏœ_���ڂ��܂���A�ƁB
�������ނ̘_�|�͂��̌�́u�}�[���^���ɒ������܂���肭�����ł��Ȃ��ƃ}�[���^�������v���|�C���g�ɂȂ�܂��B
�u��肭�����ł��Ȃ��v�ꍇ���O��ł́A�ނ��咣����uG10���̖��x���グ���������̂ł͂Ȃ��A���̋@�킪�̔Z�x�m�ۂ̂��߂ɐF������Ă�v�̍����ɂ͂Ȃ�܂���B
��F�]�X�̘b������Ȃ�A�V�A�����猸�F���ĐԌn�̐F�������Ȃ��v���̓}�[���^���ǂ��̂����̂ł͂Ȃ��A�V�A�����̂̔Z�x�ł��B�V�A���͐Ԃ̕�F�ł�����B�i������Ԃ̐������ǂ̒��x�������A�Ƃ����Ӗ��������V�A���ł��j
�����ԍ��F8812253
![]() 3�_
3�_
���s��������B����ɂ��́B
�����̉��肪�Ƃ��������܂��B
���͂��̌�A�Y�N��ɍs���Ă��܂��A���X�̃��X�t���Ő\�������܂���B
�Ҏ����Ă��܂���BFUJI-F100fd�������Ă��܂��B
�����ƗV��Ă���g�Ȃ̂őf�G�ȃ��X�͂����܂����ۂ̕��i�ƎB������̉��
�������A���Ȃ�������ƔY�݂ɔY��ł��܂��B
�I�o���������ǂ��̂��A�s���g�ʒu��ς�����ǂ��̂��悭����܂���B
�ǂ���I��ł��ς��Ȃ��͈̂ӌ��Ƃ��Ă��ꂩ��d�܂��B
�����ԍ��F8816473
![]() 0�_
0�_
on the willow����
��w��Mac���g���ďK�����F�ƌ��̑��ւ̘b�ƈقȂ�悤�Ō˘f���Ă��܂��B
on the willow����̃��X��ǂނƁA���̂܂ܑ�����Ƙb���A�L���Z����S�̂̂��Ƃɋy�т����Ȃ̂ŁA������ӂŎ��炵�܂��B
���̃X���b�h��ǂ�Ŏ����Ř_���I���Ǝv���Ă���l�قNJ���I�ȕ��͏����Ă��Ă����C�ȂƑ�ϕ��ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F8817820
![]() 3�_
3�_
�ꂢ����@
�����̓��ōl���ĂȂ����炨�q����܂Ȃ�ł���B
�������܂Ƃ��Ȃ��q����܂͔��Ȃł���B���Ől�̊�����t�Ȃł������l���Ȃ��̂ˁB
�{���̂��q����܂ɓ{�����肵�Ȃ��B
���Ƙ_���Ɨ��_�͈Ⴂ�܂��B
�����ԍ��F8817880
![]() 1�_
1�_
�ꂢ����
��w�ŏK�������Ƃ𐳂����������Ă̔������ǂ����͗ǂ��킩��܂��A
>�i�F�̎O���F�ł́j���F�i���V�A���j��F�ɂ���ɂ̓}�[���^�𑫂��̂������ł���
�ƌ������������Ȃ�A���̕ԓ��́u����Ȃ̓�����O���A���ꂪ�ǂ������v�Ƃ������Ƃł��B
�X���b�h���L�`���Ɠǂ�ŁA�����ōl���ď�������ł��܂����H
�����ԍ��F8818680
![]() 4�_
4�_
�ꂢ����
�ꂢ����͈�ԍŏ��̃J�L�R��
���F�ɂ��Ă̓A�L���Z����̕��������������B
�@�Ə����ꂽ����ǁA�O���F�̌����Ɩ�������咣�͒N������
���܂����ˁB�ӌ����Η����Ă���킯�ł��Ȃ����Ƃɂ���
������������ƌ����͕̂ς����A�����蓹�����c�_��
�悤�₭�{��ɖ߂������ɁA�킴�킴����Ȃ��Ƃ�����l��
����Ƃ��v���Ȃ��B������on the willow����͂ꂢ�����
�J�L�R���A�L���Z����̎咣�S�̂��x��������̂Ɖ��߂���
�ēx����ɐG�ꂽ�̂��Ǝv���܂��B
�������Ř_���I���Ǝv���Ă���l�قNJ���I�ȕ��͏����Ă��Ă����C
�@�Ƃ����̂͂ǂȂ����w���Ă̂��Ƃ��킩��܂��A�_���I��
���̂��Ƃ��l����l�́A���_�����炵���葊��̎咣��c�Ȃ�����
���Ă܂Ƃ��ȋc�_�������l�Ɍ���������������̂ł��B������
���肪���������l���Ƃ킩�������_�ŋc�_���̂��̂���߂Ă��܂�
���Ƃ���������ǁAon the willow����͊���I�ȉ��V�ɂȂ���
���܂������̃X���ŁA�������ĂȂ�����Ō�܂ŋc�_�𑱂����B
���̔S�苭���ɂ͂قƂقƊ������܂��B����Łu����݁v�̕���
����X���ɍŏ�����P���J���̃J�L�R�������肷��̂��T�����
��A�M�������[�Ɍ������邱�Ƃ������ł����ǂˁc�c�B(^^;)
�����ԍ��F8818717
![]() 3�_
3�_
�������� �e�k�L���O���� ��
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500211327/SortID=8732257/ImageID=180776/
����Ȃ킩��₷���̍���Ă����������̂ɁE�E�E�B
�u�}�[���^�𑫂��Ȃ��v�́u�O�a�v�ƃC�R�[���ł��B�Ȃ��Ȃ�B
���O�a���Ă���Ȃ�}�[���^�͑����Ȃ��B
�t�ɁA
�}�[���^�������Ȃ��̂Ȃ�Ԃ܂��͐��O�a���Ă���B����͐�O������O�a���Ă���B
�O�a���Ă��邩���Ă��Ȃ��������Ȃ̂ɁA�u�A�L���Z���������ł��B�}�[���^�͑����܂���B�܂�O�a���Ă��܂��B���ꂪ�����ł��v���āA���H�I
�����ԍ��F8820270
![]() 3�_
3�_
�\����Ȃ��ł����A�q�ϓI�ɂ݂Ăꂢ����̔����͂��Ȃ�I�J�V�C�ł���B
�e�k�L���O����̕�����₷���G�ɂ�����ł���ڗđR�ł����A
on the willow��������߂Ƃ���F����͓��R�������Ă��邱�Ƃ��A
�����琳�����Ƃ������Ă��c�B�N������Șb�����ĂȂ��̂ɁH
���������u���̎O���F�v�̘b�Ɂu�F�̎O���F�v�������o�����Ƃ��̂��̂��ԈႢ�ł��B
on the willow����͉��x���S�苭�����������Ă�����̂ɁA
�܂�������Ȃ���������������Ƃ́c�B
�m�M�ƓI�ɂӂ��������X�����Ă���Ȃ�ʂł����A�^�ʖڂɋc�_����C������Ȃ�A
�������������Ɠǂ�ł��烌�X���ĉ�������B
�����ԍ��F8821109
![]() 5�_
5�_
�����قǂɂ��n�����炷�����B
�ʖڂȐl�̓����B���Ёi�H�j�ɗ���B
��w���AMac���A�A�h�r���B
�����ԍ��F8823045
![]() 0�_
0�_
���ꂢ����
�摜���u�o�b��Ń��^�b�`���鎞�ɁA�F�̎O���F����ɍs�����@�v���͉̂���Ԉ���Ă��Ȃ����ł�
���������́u�J���������ł̉摜�������ɂ͌��̎O���F��p���Ă���v���Ęb�ł��̂Łi�Ԉ���ĂȂ��ł���ˁH�j
�I�O��Ȏ����咣���Ă鎖�ԂɂȂ��Ă��܂��Ă܂�
�����ԍ��F8823495
![]() 0�_
0�_
��̉摜�����Ă��炦�킩��Ƃ���RGB�̌��̎O���F����舵������CMY������܂��B
�t�H�g�V���b�v�ʼn摜��CMYK�i�F��ԁj�ɕϊ�����Ɓu�J���[�o�����X�v�̒����͍s���Ȃ��Ȃ�܂��B
����ł�RGB�̌��̋�Ԃ�CMY�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ�����Ȃ���������ł��B
�����ԍ��F8823648
![]() 0�_
0�_
������G10�̘b��ł���ˁB�ǂ����ăt�H�g�V���b�v����H
���̑O��ԈႢ�ł��邱�ƂɂȂ��C�t���Ȃ��̂ł��傤���˂��c�B
�i���Ȃ݂ɃG�������c�̃��x�����RGB����{�Ȃ�ł����ǁc�j
���Ԙb�I�ɉ摜�����̘b�����Ă邾���Ȃ�CMY������ł��傤�B
�������A���̓J�������Ő��������RGB�x�[�X�̉摜�����ɂ��Ă̘b�ł��B
G10������RGB���킴�킴CMY�ɒu�������Ă�Ƃł��H
���ǂ̂Ƃ���A���l�������o�����b������Ɏ����̒�ł����ʂ��Ȃ��펯�Ƃ���
�b�����Ƃ��邩���₱�����Ȃ��Ă��ł���B
�i�u����ł͍������邩��O�������������v���Ƃ��A�u�A�h�r�ł�CMY�v���Ƃ��c�j
������A�u�^�ʖڂɋc�_����C�͂���̂��H�v�Ɩ₤�Ă���̂ł��B
> RGB�̌��̋�Ԃ�CMY�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ�����Ȃ���������ł��B
���������������A�N������Șb���ĂȂ����ĂB�B
�����ԍ��F8824570
![]() 1�_
1�_
�S�R�ǂ�łȂ��Ȃ����B
>����ł�RGB�̌��̋�Ԃ�CMY�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ�����Ȃ���������ł��B
�����m����I���ɗ��Ȃ��łˁB
�F�ʌ���o�����ĂȂ炵�傤���Ȃ����ȂƎv�������Ǒ�w���Ȃ�āE�E�E�B�w�m�����Ǝv�����ȁB
�����ԍ��F8825184
![]() 0�_
0�_
�ւ��݂Ղ�����
KND-711����
���s�̂�������
�e�k�L���O����
���߂ł���A����ɋ����قǒN���̎v���c�{�ł���B
���炩�ɈӐ}�I�ɘ_�_�����炵�ɂ������Ă�B�I���ł��B
���̃X���������܂œǂ�ŁA�V�R�ł��̂悤�ȏ������݂�����킯�Ȃ�����Ȃ��ł����B
�v����ɁA�f�R�C�B�@�I�g���ł��B�@���F�������Ȃ������炻�����֍s���Ă���ƁB
���̕��̓o��ň�ԃg�N���Ă�̂͒N�ł����H
�܂�܂ƈႤ�����֗U������Ă܂���B�O�a�͂ǂ��Ȃ�����ł����H
on the willow���������Ă��ꂽ�_�_�́H
��߂Ȃ��߂Ɛ��X���X�Ɛ錾��������̂ɁB
�����ԍ��F8825331
![]() 1�_
1�_
�A�L���Z���� �ɂ��Ă͑O����킩���Ă���̂łǂ��ł���������������̂ł����A����ȊO�̓��J�c�N�Ƃ���������ł��܂��āB�����܂���B
�ł��������Ə����Ă�Ǝv���܂����ǂˁA���� (^^;
�u�O�a�͂��̋�ɂȂ�\�������v�Ƃ��A�uG10 �̋�т₷���킯�ł͂Ȃ��B�ǂ̋@����ꏏ�v�Ƃ��B
����ŃI�g������Ȃ��Ǝv���܂���B�ꂢ���� �͑�w�Ŋw��ŕ@���X�Ȃ�ł���B����Ȃ���u�����v�Ȃ�ĕ��ʌ����܂���B
���������ꂪ�O�a����Ȃ��Ȃ�āASILKYPIX ��R�[�̌����\�t�g�ɑ����_�Ȓ���ł��ˁB�Ƃ������A����猻���\�t�g���g���Ă��鉽�����\���̃��[�U�[�̖ڂ̓t�V�A�i�ł����B
�����ԍ��F8825624
![]() 0�_
0�_
�����́B
�܂������X���b�h�̗���ƊW�Ȃ��^��Ȃ�ł����A���̃X���b�h�Łu���F�v�ƌ������t�����т��яo�Ă��܂����ǁA�u���F�v���Ă���ȐF�Ȃ�ł����H
��Ȃ̂Ɂu���F�v�A���Ɂu��F�v���Č��t�����邯�ǁB
�u���̐F�v�Ȃ�C����̗��������A�u���F�v�́u���̐F�v�̖��邢(�����ۂ��A���邢�͑N�₩���̗�����)�F�Ȃ̂��ȁB�ΐ����̑��݂ɂɂ������V�A�����̐F���Ă��ƂȂ̂��ȁB�����́A�C���N�W�F�b�g�v�����^�̈�������u�V�A���v�̃C���N�̐F������ƁA�u�V�A���v�̌��t���u���F�v�̌��t�̕����Ɋ����܂��B�u�V�A���v�́u���̐F�v�Ƃ͈Ⴄ�F�Ɍ����܂��B
�F�̖��O�Ǝ��ۂ̐F�́A�n���ɂ��Ⴄ�̂ł��傤���H�@����Ƃ��F�̊��������Ⴄ�̂��ȁH�@����Ƃ����X���b�h�Љ�̎ʐ^�A���������Ă���g�R���Ƒ��̐l�����ڂ��Ă���g�R�����Ⴄ�̂��ȁH
�����ԍ��F8825883
![]() 1�_
1�_
�F�̖��O�Ƃ����ƁA�G�̋�Ƃ��F���M�̉e�����đ傫���Ǝv���܂��c�B
�i��ނ̕�����Ȃ��āA�Ⴆ�Ε�ݎ��̐F��������A���M�̓h����������j
�������A�����S�Ă���Ȃ��āA�l�l�Ŏv�����͂���Ǝv���܂����ǂˁB
�����u�V�A���v�Ƃ������u���F�v���Ċ����ł��B
�}�[���_�́c���F�H�����H����ȂƂ���ł��B
�P�F�Ō���ƁA�J�^�J�i����Ɋ����ōl�����Ⴂ�܂��ˁB
�����ԍ��F8826671
![]() 0�_
0�_
�f�W�^���J���� > CANON > PowerShot G10
�͂��߂܂��āB
����LUMIX��FX35���g���Ă��܂��B
�ŋ߃J�����ɋ����������āA�����̗̈�܂ōL���Ă����Ȃƍl���Ă��܂��B
�w���䂦�Ȃ��Ȃ����K�I�ɗ]�T���Ȃ��̂ŁA
�R���f�W�̂Ȃ��ł��A�i���I�o��
�ׂ����ݒ肪�ł����ʃ��f���Ƃ��āi����Ă��炷���܂���j
G10��GR DIGITAL II�̍w�����������Ă��܂��B
���i�A�F�l�����̃C�x���g����݉�Ȃǂł̎B�e�ɉ����āA
���i�Ȃǂ��Ƃ��čs������Ǝv���Ă��܂��B
GR�̕��̓Y�[�����Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����A
GR�ŎB�e�����ʐ^�����Ă�Ɩ��������Ă����Ȃ��Ƃ��v���܂��B
�l�̂悤�Ȏg�����ł�����A�ǂ���̋@�킪�������߂ł��傤���H
�܂��A����ȊO�ł������̕���������A�Ȃ�Ă����@�킪����܂�����
�Q�l�܂łɋ����Ă���������Ǝv���܂��B
�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
![]() 0�_
0�_
�P�œ_�ŕs�ւ������Ȃ����ǂ����AFX35���Y�[�������Ɉ����Ԏg���Ă݂�
���f��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8799180
![]() 1�_
1�_
GR DIGITAL II �́A�J�����T�C�N���̑������猾���A�ꐢ��O�̂��̂Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��f���́A1000����f�Ŏ�U��������܂���B�A���A�s�v�c�Ȃ��ƂɎ�U�ꂵ�����Ƃ͂���܂��A1000����f�ō��������Ƃ�����܂���B
�������A�ォ��o��GX200��3����}�C�Z�b�e�B���O��2�B
GX200�ŏo���邱�Ƃ�GRD II�ł͏o���Ȃ������������܂��B
���A�������������܂Ȃ��Ȃ�X���̌��_�́A���P����Ă��܂���B
(�C���Œ��邩������܂���B)
�����āA����I�Ȃ̂̓X�g���{�̎コ�A�ݒ�̓���ł��B
�Ԉ���Ă��R���p�ŏW���ʐ^���B��Ȃ��悤�ɁB
�X�g���{���������Ȃ����Ƃ�����܂��B(�����x�Ȃ̂�)
�l�C�������Ȃ����̂́A���i�ɔ��f����Ă��܂��B
���S�O�O�O�O�~���܂����B
GRD II���̂Ȃ獡��GX200�ł��傤�B
�Y��Ȏʐ^���B��Ȃ�G10��������܂���B
���R�[�́A�r�Ɍ��������ʐ^�����B��܂���B
�����ԍ��F8800091
![]() 2�_
2�_
���X���肪�Ƃ��������܂��B
�����������߂���
�P�œ_���Ă������t����s���Ƃ��Ȃ��l�ɂ�
����ς��ʃR���f�W���w������̂͑����ł�����^^;(��)
�����������e������
�m����GR�͑O���f���������ł������A�����������O�Z���[�ł���ˁB
���̕����\�Ƃ��Ă͍ŐV�̂��̂�茩����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ȁA��
�f�l�̖l���Ȃ�ƂȂ��v���Ă����Ƃ���ł����B
�R���p�ł̏W���ʐ^�B��ƌ�X�֗��ł���ˁi����Ȃ��Ƃ͂��Ă����j
�ǂ�ȃV�[���ł��I���B���@�킪�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
���̒��Ŏʐ^�̎B�e�ɂ��ď��������āA�}�j���A�����삷�邱�Ƃ�
�����̎v���`�����ʐ^���B���悤�ɂȂ��Ă�����������Ȃƍl���Ă��܂��B
���̂Q���r������ł͂�͂�G10�̂ق����ǂ������ł����ˁO�O
P6000�͓d�r�̖�肪����Ƃ������ƂȂ̂Ō��ɂ͓���܂���ł������B
�����ԍ��F8801153
![]() 0�_
0�_
�X���傳�܁@������
�������̗̈�܂ōL���Ă����Ȃƍl���Ă��܂��B
�Ƃ̂��ƂȂ�A�Ⴂ�ɂȂ�܂����A�ׂ����ݒ���ł�����僂�f����
�f�W�^��������x�����������Ƃ�����������܂���ˁB��
�^�����Ȃ�G10�Ƃ��قǕς��Ȃ����z��W�Y�[���Z�b�g�����܂����c�B
�ł��C�����āc�B�f�W��ɂ͂��낢��ȏ��i�U�f�j���c�B
�u����ς���ނ̃R���p�N�g������ԂŁA������Ƃ��낢���肽���āc
�f�W��͑傫���Ă����邵�����ڂ�������ƋC�ɂȂ�B�v
�Ƃ��������Ȃ�t���I�[�g�ŊȒP�ɎB�e���ł��A������Ƃ��������
�ʐ^���B��₷��G10����������������܂���B��
�悭�悭���������������܂��B
�����ԍ��F8801311
![]() 0�_
0�_
�A�����炢�����܂�
�P�œ_�F�Y�[���ł��Ȃ������Y�̂���
��ʂ̺��ނ�28�~������5�{�Y�[���Ƃ����Ă܂���ˁB
�܂�P�œ_�Ƃ����̂�28�~���Ƃ�35�~���Ƃ��ɌŒ肳���
���āA�����ς����Ȃ��i���{�Ƃ���ύX�ł��Ȃ��j�����Y
�̂��Ƃ������܂��B
�Ȃ̂ŃY�[���������Ƃ��͋ߊ��A�t�Ƀ��C�h�ɂ������Ƃ���
���ɉ�����Ȃǂ��Ē��߂��Ȃ���Ȃ�܂���B
�������A���̕����邳���o�����Ƃɂ͗D��Ă���܂��B
���̂ǂ���i�Y�[��or�P�œ_�j�Ƀ����b�g�������邩�ɂ����
�I�����܂��B
�����ԍ��F8801335
![]() 0�_
0�_
������Ƃ͑��̏���y���ɂ��C������Ƃ���
���R���Ɏ����Ă������Ƃ����肵���Ƃ����
���͏���������邩������Ȃ��ł���ˁi���ɏ��q�Ɂj
�����J�����̋���������A��ɂȂ�Ȃ������Ƃ��Ă�
G10���炢���M���M�����e�͈͂̃T�C�Y���ȂƁc���⏭���傫�����ȁB
�G�r������^��������I�_�M���W���[�̃J������肱������Ă銴������
���قǃI�^�N���ۂ��Ȃ��i���R���ł̏��q����̖ڂƂ��āj�Ƃ����Ӗ���
G10�͂��Ȃ�o�����X�̗ǂ��J�����ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F8801525
![]() 1�_
1�_
������
GR DIGITAL II�Ɠ����P�œ_���f����I�Ԃ�Ȃ�DP1�̕��������Ǝv���܂��B
�Y�[�����g���Ȃ�PowerShot G10���ǂ��Ǝv���܂����A�L�p�ɖ��͂������Ă���̂Ȃ�
LX3�����肩�ƁB
�����ԍ��F8805099
![]() 0�_
0�_
���R���f�W�̂Ȃ��ł��A�i���I�o��
���ׂ����ݒ肪�ł����ʃ��f���Ƃ���
�i���������ƁA�����ǂ��ς��̂��@�����Ɨ\�K���Ă܂����H�H
�t�B�����J�����ƈ���ăf�W�J���̏ꍇ�A�V���b�^�[�X�s�[�h��ς���v�f�Ƃ���ISO�l�������܂����B
�܂��A�P�Ɍ��ʂ��������������Ȃ�AND�t�B���^�[���g���Ƃ����������܂��B
�i���Ĕ�ʊE�[�x��ύX���悤�Ǝv������A���t�Ɏ���o�������L��܂���B
������/�t�B������͂�����܂����A�t�B�������t�Ɏ���o���Ă݂�Ɗy���������m��܂���B
50/1.4�t���ł����Ȃ肨�������Â��L��͂��ł��B
�{�i�I�Ƀf�W�^�����t�Ɏ���o���̂́A���ꂩ���ł��ǂ��ł��傤�B
�����ԍ��F8810617
![]() 0�_
0�_
GR�U���g���Ă��܂��BEOS�����C���@�ŁA�T�u�Ƃ��Ďg���Ă܂��BGR�U�Ƃ͐F�̏o�������Ȃ�Ⴄ�̂Ō˘f���܂��ˁBGR�U�̕����N�Z������܂��B���ꂪ���Ɗ�������A�y�����J�����ł��B�Z�œ_�Ƃ����̂��A�B��y�����̈���Ǝv���܂��B����ꂽ��p�ł��낢��H�v����͎̂ʐ^�̌��_��������܂���B
���āA�������������Ȃ�G10��I�т܂��B��͂�F����EOS�Ɠ��n�Ƃ����̂��ő�̗��R�ł��B�@�������A�ʐ^���B��y������GR�U�̕����ゾ�Ǝv���܂��B���̕ӂ͎g��������ł��傤���B
�����ԍ��F8820277
![]() 0�_
0�_
�f�W�^���J���� > CANON > PowerShot G10
���߂Ă܂��āB
�ߓ��AG10���w������l���ł��܂��B
�ʔ̓X�i���h�o�V��r�b�O�J�����j�Ŕ������Ǝv���Ă���̂ł����A
�Ⴆ�A���邨�q����G10���w�������Ƃ���A��f������{�^���̉����������Ȃǂ̍��ׂȕs�ǂŁA
�w�������ʔ̓X�ŏ��i�������Ă�������ꍇ�A
�s�Ǖi�i�H�j�́A���[�J�[�ɕԕi����̂ł��傤���H
�܂����A���̂��q����ɔ̔�����Ȃ�Ă���܂����ˁH
G10�Ɋւ��鎿��ł͂Ȃ��A�\����܂��A
�m���������������������������B
��낵�����肢���܂��B
![]() 0�_
0�_
�����s�ǂŃ��[�U�[����ԕi���ꂽ�������[�J�[��
�Ԃ����ɂ��X���������鎖�͑S�������n�Y�B
��ꂻ��Ȗʓ|�Ȏ����킴�킴���Ă��A���o������X��
�M�p���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂���i�j
�܂��C�H�ނȂǂň����������Ă�y����R���鐢�̒���
�����c
�����ԍ��F8812870
![]() 0�_
0�_
�l��������ƒm�肽���ł��B
���X�͂ǂ����ĕԕi��������̂ł��傤�H
�����Ƃ���̑����ɂȂ邩��H
���[�J�[���猙�Ȋ������邩��H
�X������ɂ���Ă��A���Ȋ������l�Ƃ��Ȃ��l�����܂��ˁB
�L�^�����Ȃ����傫���ł���B�l�̌o���ł́B
���h�o�V�Ȃ��͂ނ���d���Ƃ��ĒW�X�Ǝ������Ă���A�Ƃ����C�����܂��ˁB
�܂��A�Ȃ�ɂ���A�ԕi����X�����̋q�ɏo���Ƃ����P�[�X�͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����m���Ă���l����������Ȃ�u���Ă݂����Ƃ���ł��ˁB
�����ԍ��F8813151
![]() 0�_
0�_
�X�ɂ��鏤�i��S�ĊJ�����Ĕ����y�����i�R���̏�A�ɂ��邶���B
�����ԍ��F8813614
![]() 4�_
4�_
�V���b�v�]��������ƁA�J�������Ղ�����Ƃ��A���X�̃S�������Ă������Ƃ��A�ݒ肪������Ԃł͂Ȃ������A�Ȃǂ̐������Ă��܂��B
���ꂪ�q���g�ł��B
�����ԍ��F8814048
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂Ɏ����̒m�荇���͖^�ʔ̓X�ɋ߂Ă��܂����A�����䂤���R�ŕԕi���ꂽ���͂������������[�J�[�ɕԕi����邻���ł��B
���Ƃ́A���ɖ�肪�Ȃ��Ƃ��A���[�J�[������ԕi��t���o���Ȃ����͂ǂ��ɂ������ɂ����čĔ̂����Ⴄ�݂����ł�����(-.-;)�܂��J�����S������Ȃ��̂ŁA�������͂ǂ����͒m��܂��ǂˁB
�����ԍ��F8815072
![]() 0�_
0�_
����ɂ��́I
�J�����ł͂Ȃ��ł����A�ȑO�m�l���Ɠd�ʔ̓X�ɋ߂Ă���TV�Q�[���S���ł����B
�P�ɓ`�[�������̂���ς�������Ȃ��l�������Ȃ�Ď���͌����Ă܂������A���̒m�l�͂�����Ɖ����ĕԕi�ɉ����Ă������ł��B
�E�E�E�ł����A�X�������낢��Ȃ炨�q�����낢��ŁA�펯�͂���̂��q�������A
����A�����炩�ɂ�������I�݂����Ȃ��̂������Ă���l�̕��������݂����ł��B���݂��ɁA�펯�͂��ꂪ������O�ɂȂ�A���ʂȂ��Ȃ������Ă���Ȃ��݂����ȕ��ɂȂ��Ă����炵���ł���B
�����A�m�F�͂��Ă��܂��A���l�蕨�ɂ���A
�ʏ탋�[�g�ł͓���ł��Ȃ��d���l�ł���Ă邨�X��
�����������̂�����Ă�����Ęb�ł��B�̂͐V�h�ɂ���Ɠd�ʔ̓X�̑�����
�����������̗��ꂪ���������炵���ł����A���͑傫�ȊŔ��\���Ă���̂�
�����������Ƃ͂��Ȃ��Ȃ��������ł��B���̑���A�����͂Ȃ��Ȃ�܂������E�E�E�B
�����ԍ��F8816933
![]() 0�_
0�_
���[�J�[�ɋ߂Ă������c�����������Ē����܂��B
�����s�Ǖi�́A���[�J�[�ɑ���Ԃ���čɂƌ����`�ɂȂ�܂��B
���̌�A�c�ƏC���ƌ����`�Ō̏�ӏ����āA���̑��̉ӏ��͓_������
�̏�ӏ�������ΏC�����܂��B�X�ɂ́A�t�C�������ȂǂɃL�Y���������
�O����V�i�Ɍ������āA������ʂ��ĕۏ؏���t���āA������V�i��������
�Ăяo�ׂ��܂��B���̎��_�ŁA�H��o�׃��x���̐V�i�ɂȂ��Ă�̂ŁB�B
�t�C�������Ȃǂ̃t���[�������ɏ����t���Ă镨�͌����ƁA�������̕���
���Ō������̃A�E�g���b�g���i�Ƃ��āA�Г��̔�����܂��B���ꂪ�A���Ȃ����
��ɓ���̂ŁA���\�ǂ��������ȁB�B���̃A�E�g���b�g���i�ł��A�傫�ȃL�Y��
�O�ς̎C��Ȃǂ͂�����ƌ������܂��B�܊W���������܂��B
�����ƁA�O�ς̑傫�ȃL�Y�͌������āA�̏�ӏ��͂�����ƒ�����
���[�J�[���c�̃A�E�g���b�g�V���b�v�Ŋi���̔����Ă�Ǝv���܂��B
����ł��A���[�J�[�̕ۏ؏��͂�����ƕt���Ă��܂��B�A���A���[�J�[��
����ẮA�ۏ���Ԃ����V�i�����Z�������肷��ꍇ������܂��B
���i.com���������A�E�g���b�g�i���݂�����A����Ӗ��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F8817664
![]() 0�_
0�_
�ʔ̓X�̏ꍇ�A�̔����̒��ɏ��i�m���̏��Ȃ���������
��������R�̐��������A�q�Ƃ��߂ĕԕi�܂��͑��@��ƌ����𔗂��邱�Ƃ�����܂�
���̏ꍇ���[�J�[�ɕԕi�����邱�Ƃ��o�����A��X�W���i�Ƃ��Ĕ̔������肷��݂����ł���
���܂ɒʏ�i�ƍ�����ꍇ������݂����ł��i�X�̌������j
�C�ɂȂ�悤�ł�����w����A�J���m�F�����ق��������ł�
�i�f�W�J���͔��ɕ������Ă��Ȃ��ꍇ�������̂ŁA���ł͔��f�o���Ȃ��̂Łj
�����ԍ��F8817881
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���A���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�������S���܂����B
���ɁA�����ۂ肳��₨����Ȃ�������̂��b�ɋ����[�����̂�����܂����B
�������Ƃ��Ă��A�^�S�ËS�ɂȂ��Ĕ����̂��A�₵�����Ƃ��Ǝv���܂����B
���͍����A�^�ʔ̓X��G10���w�����܂����I
�܂����������G���Ă��܂��A�v�����ȏ�ɖ������Ă��܂��B
����G10�ŁA����̕��i�⍡�N���܂ꂽ����̎q�����B���Ă��������Ǝv���܂��I
�����ԍ��F8819491
![]() 0�_
0�_
������Ȃ�������
���`�I���߂ĕ����b�ł����I
�Ȃ�قǁA�����Ȃ�ł��ˁB�Ȃ�ɂ���A�C�����Ă����Ȃ炢���ł���B
���ʂɎg���Ă��Ă��̏Ⴊ�o�邱�Ƃ͂����ł�����A
��x�C�����Ă���Ă����ق�������Ӗ����S�����B
�A�E�g���b�g�̓X������Ȃ�A�����ɔ����ɍs�������Ǝv���܂����B
�����ԍ��F8819663
![]() 0�_
0�_
�f�W�^���J���� > CANON > PowerShot G10
�{���AG10���w�����܂����B���ɂ���^�C�v�̃J�����o�b�O���g���A�g�т������ƍl���Ă��܂����A���g�p����Ă���o�b�O�A���E�ł���o�b�O��������Ћ����Ă��������B�i���[�J�[���≿�i�������Ă���������Ə�����܂��j
![]() 0�_
0�_
���w�����߂łƂ��������܂�
PORTER�̏_�炩�߂̃��U�[�̃o�b�N�̂̓T�C�Y�I�Ƀo�b�`���ł�
�N�b�V������������܂��c
�ڂ������i���͖Y��܂������A
9750�~�ł���
�������A�Ԃ牺����� ���Ȃ�d���ł�
�����ԍ��F8814537
![]() 0�_
0�_
���o�ł����E�E�B
G10�̃T�C�Y�Ƀs�b�^���ł��B�����ɂ̓x���g�ʂ��ƃ����O
���t���Ă��܂��B���ƃV�b�J���������n�ŁA���n�̒��i�ԁj
�ɂ̓N�b�V�����ނ������Ă��܂��B�Q�[���@�f�W�J������Ƃ���
�_�C�\�[�Ŕ����Ă܂��B105�~�Ȃ�B
�����ԍ��F8815157
![]() 2�_
2�_
�X���傳�܁@������
�悸�͂��w�����߂łƂ��������܂��B
�ړ����́A����̃P�[�X�ɓ��ꂽ�܂܃����x���Ƃ����A�E�g�h�A���[�J�[��
�o�b�O�i�N�b�V�������i�V�j���g���Ă܂��B�|�P�b�g������������
���z�E�g�сE���E�蒠�Ȃǂ��낢�됮�����Ď��[�ł��ĕ֗��ł��B�x���g
���������߁A���߂���V�����_�[�Ƃ��Ă����p�\�ł��B
�l�i�͖Y��܂����B
�����ԍ��F8815292
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^���J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
-
�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^���J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j