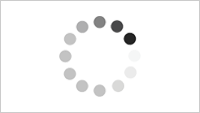OM SYSTEM OM-1 Mark II 100-400mm II ���]�������Y�L�b�g
- �摜�����G���W���uTruePic X�v�ƗL����f����2037����f ���ʏƎːϑw�^�uLive MOS �Z���T�[�v���ځA�t���b�O�V�b�v���f���̃~���[���X���J�����B
- ���^�y�ʁE�h����h�H���\�E���͂Ȏ�Ԃ��@�\������A���]������}�N���̈�܂Ŏ莝���B�e���\�B4K 60p�̍����ׂȉf�������炩�ɕ\���B
- ���^�y�ʂ̒��]���Y�[�������Y�uM.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II�v���B�{��8�{�A�h���E�h�ܐv�̑o�ዾ���t���B
- �t�������Y
-
- �{�f�B
- 12-45mm F4.0 PRO�L�b�g
- 12-40mm F2.8 PRO II �L�b�g
- 100-400mm II ���]�������Y�L�b�g


-
- �f�W�^�����J���� 136��
- �~���[���X��� 124��
�y�t�������Y���e�zOM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II
OM SYSTEM OM-1 Mark II 100-400mm II ���]�������Y�L�b�gOM�f�W�^���\�����[�V�����Y
�ň����i(�ō�)�F¥375,990
(�O�T��F�}0 ![]() )
�������F2025�N11��14��
)
�������F2025�N11��14��
OM SYSTEM OM-1 Mark II 100-400mm II ���]�������Y�L�b�g �̃N�`�R�~�f����
�i2456���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S32�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 2024�N10��6�� 18:21 | |
| 4 | 0 | 2024�N10��6�� 02:55 | |
| 98 | 9 | 2024�N9��18�� 13:31 | |
| 117 | 11 | 2024�N8��10�� 19:05 | |
| 117 | 23 | 2024�N6��9�� 20:54 | |
| 56 | 16 | 2024�N6��9�� 07:42 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B
�� �莝���n�C���]�V���b�g�̍����A���S���Y�������P���܂����B
�� ����̈��萫�����サ�܂����B
![]() 11�_
11�_
��You Know My Name.����
�����A�b�v�f�[�g���܂������ǁA�����ɂ��̑䕗�̂����Ŗ싅�̎B�e���ł��܂���B
�莝���n�C���]�V���b�g�͌��\���p���Ă���̂ŁA�ǂ��i�����Ă���̂��y���݂ł��B
�����ԍ��F25870006
![]() 4�_
4�_
�ꉞ�t�@�[���A�b�v���ς܂��܂����B
�����ԍ��F25870170
![]() 2�_
2�_
�� �|������ǃ_�n����
�莝���n�C���]�V���b�g�́A�����͂��܂�g���ĂȂ��ł��ˁB�B�B
�o�[�W�����A�b�v�O�ɏ��������Ă݂܂������A��r���Đ����X�s�[�h�͕ς��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�iE-M1�n����OM-1�ɑ��������́A�[�x�������܂߂ď����X�s�[�h�͌��ςł������ǁj
�� �O���[���r�[���Y5.0����
�����A���悤�₭���܂����B
�����ԍ��F25871483
![]() 3�_
3�_
�莝���n�C���]�V���b�g��E-M1 mark III�̂��납�炿�傭���傭�g�p���Ă����̂ł����A�����̂Ƃ����DC-G9M2�̕���OM-1 mark II��荇��(�����Ă���Ƃ���̂��܂���)�����܂��C�����Ă��āA���C�����Ă��܂����̂ŁA���������o�[�W�����A�b�v�����Ĕ�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B
�ł����A���T���͓V�C����낵���Ȃ��悤�ł��c
�����OM-1 mark II�̕��́AAF����̉��ǂ͓��ɓ����Ă��Ȃ��悤�ł��ˁB
�����ԍ��F25871570
![]() 3�_
3�_
��You Know My Name.����
���̏ꍇ�́A�Ⴄ�悤�ł��B
OM-1�ł͏����Ɏ��s���邱�Ƃ����܂ɂ������̂��AOM-1mk2�ł͂قƂ�ǎ��s���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�N���b�N���g�����t�o���������ł͂Ɗ����Ă��܂��B
��YoungWay����
OM-1�̃o�[�W�����A�b�v�ɂ�
�ES-AF��C-AF��(�I�[���^�[�Q�b�g) ���́A��v�Ȕ�ʑ̂ɑ���AF���\�����サ�܂����B
������܂������ǁA�����OM-1mk2�ŃI�[���^�[�Q�b�g��AF���X�^�[�g������ۂɉ��P���ꂽ�_�ŁAOM-1�ł�AI��ʑ̔F��AF�Ɂm�l���n�������Ă��Ȃ��̂ŁA�������Ⴄ�悤�ł��B
���Ȃ݂�DC-G9M2�̎B���f�q��SONY���ł͂Ȃ��Ɣ��\����Ă��܂����A�����C�X���G������������N���C�A���g�̉�Ђ̃R���v���C�A���X�ɒ�G���Ă��܂��̂ŁA��������������Ȃ�������A�g���Ȃ��ł��B
OM SYSTEM�̂T���V���N����Ԃ������x�`�Ȃ̂��e�����Ă܂����c
�����ԍ��F25871707
![]() 0�_
0�_
���X�Ȃ���...
Ver.1.2�ł̃e�X�g�ł��B
�g�r�̑O���ւ̔�яo���ł��B
SH�Q�@�T�O�R�}/�b�@�A�ʁB�@���F���L�ł��B�@AF�g�͑S�ʁiALL�j�ł��B
�ߋ����������̂ŁA���ʂ͂܂��܂����ȂƊ����܂����B�@
�T�O�R�}�ڂ�����ƁA�͂ݏo�����炢����ȏ�ߋ������ƌ������i�ǂ����Ȃ��j���ȂƎv���܂����B
�B�e���̃C���[�W�Ƃ��ă^�C�����v�X�œ��扻���܂����B�@�i�P�b�ȂɂT�O�R�}�\���i�P�b�j�ƁA�P�b�ԂɂT�R�}�\���i�P�O�b�j�ł��j
�X�`�[���摜�́AJPEG�B���ďo���A�g���~���O�����ł��B�@�i�J�����͌Œ�łȂ��U���Ă܂��̂ŁA�w�i�̕ω��͂���܂��B�j�@
�����x�g�p�Ŗ��Í��̕ω��������Č������ł������A
�s���g�͂����ނ˗ǍD�ł����̂ŁA�g���~���O���܂߂Ē�������Ώ����ǂ��Ȃ�Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F25916841
![]() 4�_
4�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B
OM�}�C���̌����y�[�W�ɃL�[�}�h���C�J���[�ɑ���OM SYSTEM×OUTDOOR MONSTER�}���`���[�X�{�g�����lj�����܂����ˁB
�Q���ɂ�OM SYSTEM×OUTDOOR MONSTER�I���W�i���p�[�J�[���Q�b�g���A�e�ʂ̎q�Ƀv���[���g���܂������ǁA����̃{�g���͎����p�ł��B
1.5L��1L�̐^��f�M�X�|�[�c�{�g���������Ă��܂���0.5L�N���X���Ɠ��e�ʂɑ��đ傰���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�|�C���g��]�点�Ă��������Ƃ����̂�����A�|�`�b�Ƃ��܂����B
�z��ȏ�ɗǂ������ł��B
OM�}�C�����V���b�s���O�̎��Ɏg��������ǂ��̂ł����c
����ɂ��Ă��O�����傫���ł��B
![]() 4�_
4�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B
�����͖����̂悤�ł����ǁA�Ƃ肠�������H�Ƃ������ƂŎB�e���Ă݂܂����B
�t�@�[���E�F�A��Ver.1.2�Ƀo�[�W�����A�b�v����
�E�莝���n�C���]�V���b�g�̍����A���S���Y�������P���܂����B
�E����̈��萫�����サ�܂����B
�Ƃ������ł����ǁA�n�C���]�͐i�����Ă���悤�ł��B
�܂����̍��x���Ⴍ�A�r���̊Ԃŏ����I�ɂ͗ǂ��Ȃ��ł����ǁA�܂��܂��Ƃ����Ƃ���ł��傤���B
![]() 12�_
12�_
�������Ƃ������ƂŁA���h�ߏ��Č�����80ml�قǂ��������āA�Ē���B
���x�������Ȃ����̂ŁA����Ɍ��������Ȃ������ŎB�e���܂������ǁA���������Ă����u�Ԃ����A�������s�B
�����ԍ��F25894575
![]() 7�_
7�_
���|������ǃ_�n����
�������B��̂͌|���Ȃ��ł��ˁB
����ƃR���{����̂��I�X�X���B
�����ԍ��F25894580�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�|������ǃ_�n����
���n�D�y������悭�����Ƃ�܂���B�B�B
�܂��A�D�y�ɂ���͂���܂��ˁB
�����ԍ��F25894605
![]() 3�_
3�_
���u���[�j���O����
�邪�Ȃ��Ă����̎g���悤�ł��B
��2���ԑO�ɃA�b�v�������4000�C�C�l�˔j��
https://x.com/Kfish1882/status/1835979653405913168?t=-ih07IHnObOkWBOTyu_e9g&s=19
���ʐ^�ʼn҂��l�́A�@�ނ���ʂ�ȑO�ɘr���ǂ���
�����ԍ��F25894625�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�����ł̓J��������Y�̐��\�Ȃǂ����������猎�����̎ʐ^�łn�j�B
�����ԍ��F25894643
![]() 24�_
24�_
���͂悤�������܂��B
�֏悵�āE�E�E�_�ސ쌧���s�ŎB���� �� �ł��B
�n�C���]�ŎB��Ηǂ������̂����E�E�E
����M���Ă��Ȃ��ASD�J�[�h ���� �p�\�R���ֈڂ��������� �B���ďo���ł��B
�����ԍ��F25894968
![]() 7�_
7�_
�킽���͓V�̂��͖̂ő��ɎB��܂��A���낢��ȍ�i��\�}�̃A�C�f�A������悤�ŁA���ɂȂ�܂��B�����́A�y�������̂����߂��ɂ������悤�ł��B
�ߌ�7���A������t�߂ŎB�e���܂����B
�����ԍ��F25894979
![]() 6�_
6�_
�|���Ȃ��Ǝv���͎̂��R�ł����A�킴�킴����Ȃ��Ă��D�D�D
���������̂�]�v�Ȃ����b�ƌ�����Ȃ��ł��傤���ˁB
�����ԍ��F25894982
![]() 25�_
25�_
��Orchis�B����
������͉��l�w����2.5km���炢�̈ʒu�ł����猎�����グ��p�x�͑�̓����ł��ˁB
��C����Q�̏�Ԃ͂�����̕���������Ǝv���܂����ǁA28°���x�̍��x�i�p�j���ƌ����ʉ߂����C�̋������Z���Ȃ�܂�����A�ߌ�7���O����C�̉e�������Ȃ��A�F�Â������Ȃ��ł���ˁB
�t�@�[���E�F�A���o�[�W�����A�b�v����Ă���A�莝���n�C���]�̍����̎��s�����Ȃ��Ȃ��Ă��銴���ł�����A�������l�͂���Ǝv���܂��B
��R232����
18:50�ł��ƁA���x�i�p�j�͖�17°���x�ł�����A��C�̉e�����ĉ��F���ۂ��Ȃ��Ă��܂��܂���ˁB
��C�̏����͂�����̕����ǂ������ł��ˁB
���Z2000mm�Ƃ��Ȃ�ƌ����t�@�C���_�[���ɑ���������̂���ςł���ˁB
���u���[�j���O����
�D�y�̕����ܓx���������A���x���Ⴍ�Ȃ�Ǝv���܂����A��C�͊֓����N���A�[�����ł��ˁB
���W���b�N�E�X�o���E����
��Tech One����
��z���̌����āA���͂���ł����ˁB�@��������Y
���̒����W�F�b�g�@���ʉ߂Ƃ����̂��̌������Ƃ�����܂��B�@�����[�~���`�\�[�_���̒����`
https://x.com/Kfish1882/status/1835979653405913168?t=-ih07IHnObOkWBOTyu_e9g&s=19
�o�c�Ŋ��ׂ����ł����ˁH
�A�C�f�A�����ł����ǁA�r�͂ǂ��ł����ˁH
���Ȃ݂ɁA������2048×1365�s�N�Z���̉摜�ł����ǁA���̒��a����400�s�N�Z���A�����̐g������500�s�N�Z���ł�����A35mm�����Z�Ŗ�680mm�̃����Y�ŏ�������10m������Ɨ��ꂽ�ʒu����B�e�����Ƃ��������ł��傤���B
OM-1mk2�ŎB��Ȃ�A12-100mm/F4��100m�[��F8�܂ōi��A�d�g����̃R�}���_�[ FC-WR�ŁA���f������̋߂��Ɏd���G���N�g���j�b�N�t���b�V�� FL-900R�������A�x�[�X�̘I���͌��ɍ��킹�A2048×1365�s�N�Z�������g���~���O����n�j�ł��ˁB
���̓s���g�ʒu�ŁA�ʐ^�̏œ_�������Ă���悤�Ɍ������ʊE�[�x�Ƀ��f�����������ɂ͍Œ��ł�26m�Ƀs���g��ݒ肵�A���ɍ��킹��Ȃ�ŒZ��42m�Ƀs���g��ݒ肷��K�v������܂����ǁA���̂悤�Ɍ��̕\�ʂ̕`�ʉ]�X�͖��O�̏ꍇ�́A���f������Ƀs��������悤�ɂ��������ǂ��ł��傤�ˁB
https://keisan.casio.jp/exec/system/1209002710
��
https://keisan.casio.jp/exec/system/1239785915
�Ōv�Z����A�����������Ă��錚���Ȃǂ̃o�b�N�Ɍ����B�����ނ��Ƃ͂���قǓ���͂Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F25895286
![]() 6�_
6�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�@�͂P��������N�C�����ĂȂ��B
https://digicame-info.com/2024/07/20246333.html
����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�́A�ꕔ�̃t�@���̂��߂����ɁA�t���T�C�Y��荂�������Y����郁�[�J�[�ɂȂ��Ă��܂����B
���N�O�Ȃ�A�����@�̔���グ��ʂ̓}�C�N���t�H�[�T�[�Y�������̂ɁA�ŋ߂͂��������V�@����o���Ȃ��Ȃ����s�l�C�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�B
�����ԍ��F25838348�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 13�_
13�_
2024/08/05 09:15�i1�N�ȏ�O�j
���ꕔ�̃t�@���̂��߂����ɁA�t���T�C�Y��荂�������Y����郁�[�J�[
�}�W�ŁB
�����ԍ��F25838366
![]() 3�_
3�_
9�ʂ�G100D���Ǝv���B
�����ԍ��F25838368�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
�Ȃ�X���傪�����ă����L���O�グ��������Ⴂ�܂����H
�����ԍ��F25838517�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 30�_
30�_
��A��E-P7��E-M10�����ꂷ���ĔN�x�������������̂������Ă邩�ƁB
�����ԍ��F25838675
![]() 19�_
19�_
OLYMPUS PEN E-P7
�{��8/5����@�̔��ĊJ���܂����B
�����ԍ��F25838827
![]() 10�_
10�_
PEN�͂܂�OLYMPUS�̖��O�ŏo����ł��ˁI�H
�����ԍ��F25838837�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
G100D���Č��\����Ă��ł���
�����ԍ��F25839101
![]() 4�_
4�_
������89����
�������炢�́w�l�x����
2024 �N 4 �� 17 �� ��PEN E-P7��OM-D E-M10 Mark IV���ꎞ��~��
https://jp.omsystem.com/information/detail/in20240417.pdf?attach=true&fld=pdf&browserview=true
2024 �N 8 �� 2 ���@��PEN E-P7�̂ݎĊJ����
https://jp.omsystem.com/information/detail/in20240802.pdf?attach=true&fld=pdf&browserview=true
���x�ŁA
OM-D E-M10 Mark IV�̎ĊJ�͂܂��ł�����A�ꎞ�I�Ȃ��̂ł��傤�ˁB
������ɂ��Ă��A�����J��������������Ă����ł��傤���ǁA���[�J�[�I�ɂׂ͖��͔�����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25839363
![]() 5�_
5�_
���C��������Fujifilm�ɑ��ĕs�M���傫���Ȃ����̂�
GH5�𒆌ÂŎ����c
GH5M2���܂����i2��ڗ\��ρj
45-200ii�̍Ĕ̂Ƃ��~�����ł��i���������Y������������Ȃ���j
�����ԍ��F25839547�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�݂�Ȃ��݂�ȓ����J�����ƃ����Y��������A�c�}���i�C���႟�i�C�ł����I�I������ǂ��̂ł��I�I
�����ԍ��F25842588
![]() 13�_
13�_
OM System�ŕ��y�@�̍ɂ��͊����Ă��邹���ł��傤���AOM-1mkII�̓X���������i���������Ă��܂��ˁB���܂قǁA�^�ʔ̓X��1��{�f�B���Ă��܂����B
BLX1���P�I�}�P�A�|�C���g10%�t����268000�~�ł����̂ŁA����23���~���B����OM-1��OM-1mkII�̎������i���̑傫���ɔ[�����������ݐꂸ�ɂ��܂������A����Ȃ�[���B���I�ɂ̓��b�L�[�ł����B
�����ԍ��F25845202
![]() 9�_
9�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B
�m�[�g���@�i���������C���摜�@ |
���i�������摜���V���L�[�s�N�X�Ō��� |
�i�������摜�@�h�r�n�P�Q�T�O |
�i�������摜�@�h�r�n�Q�T�O�O |
���������炿����ƒx��̂Q/�Q�V�ɂ����Q����肵�A�e�X�g�B�e���J�n�������̂�
�u�c���n�@PureRAW�S�v�̃o�O�����Ō����o���Ȃ��ɂȂ�܂����B
�F����̋��͂�������1������̂R/�Q�V�ɖ������Ɏ���A��������{�ԎB�e�J�n���܂����B
��Q��������23,875�V���b�g�i���J�V���b�^�[�̂ݎg�p�j�A���B��𒆐S�ɕ��i�E�Ԃ���R�B��܂����B
���̔��ăV�[���͖��_�̂��ƁA���B���Ă����̂��H�y���������Ă��܂��B
�X�V���ꂽ�uPureRAW�S�v�̓G�b�W�������玩�R�Ȋ����̉摜�ւƑ�ω����A�F����Ɋ��Ă���悤�ł��B
�T/�Q�V�@�f�W�J�����������ɂ́A
�y�n�l�@�r�x�r�s�d�l�u�n�l�|�P�@�l�������U�v�̃_�C�i�~�b�N�����W�̓t���T�C�Y�@�ɏ����Ă���z
�Ɓu�c�������������@�b�����������@�v���������v�ɂ����Q�̃��r���[���f�ڂ���A�悤�₭�����Q�̐i����
���m�Ɏ����ꂽ�悤�ł��B
���̎��́A�ŏI�o�Z��24.5.18�́u�Y�܂����n�l�|�P�U�@��������Ȃ��H�v�Ə̂��鎄��
�����݂ɁA�T/�V�u�|������ǃ_�n�v������������ƂŒm��܂����B
�����āA
OM-1�U��OM�[�P�Ɠ������ʏƎːϑw�^�k�������l�n�r�Z���T�[�A�摜�����G���W��TrurePicX�̗p�B
�Ƃ������ƂŁA��{�I�ɂ͓����掿�ɂȂ�͂��Ȃ̂ŁA�ȑO����ǂ��摜���o���Ă��ꂽOM-1��
�i�������摜���\���Ēu���܂����B
�������AOM-1�ŎB�����i�������摜��Low�摜��\���Ēu���܂��̂ŁAOM-1�U�̉掿�Ǝv����
�������������B
![]() 12�_
12�_
�������������痣�ꂽ�摜�ɂȂ�܂����A�r�b�N�����̂ł����B
�J���V�J�ɂ͉ߋ��R�x�o����Ă��܂����A��ʓI�ȑ̖т͔��`�O���[�ȕ�����������̂�
�v���Ă��܂����̂ŁA�{���Ƀr�b�N�����܂����B
�V�R�⋛�ނ�ŎR�̒��ɓ��荞��ł��������ɂ́A��x�{���̃N�}�ɏo������o����
����̂ŁA�P�V�`�P�W�N�O����R�ɓ��鎞�̓A�����J�����h�q�K�X�E�X�v���[�i�X���̕��˗͂���
��^�N�}�E�O���Y���[�Ή��j�ƌ����������Ԃ牺���Ă��܂��B
�P�`�Q���ڃs���g���킹�͓�̎��ŁA�V���b�^�[����������ł������A�J���V�J�̊�t�������Ă����
�ѕ��݂��o�b�`�����킹�ĎB��܂����B
�����ԍ��F25756712
![]() 11�_
11�_
���͂悤�������܂��B
���[�āA�掿�ɂ��Ă͏\���ɍĊm�F�o�������Ǝv���܂��̂ŁA��ԋC�ɂȂ�
���̂ւ�AF���\�i�ǐ����E�s���g���x�j�ɂ��ēZ�߂Ă݂܂����B
�ߋ��̏������݂ł��n�V�r���K���̘A�����ăV�[�����ڂ��Ă��܂������A�����
�����i�J���Z�~�E�c�o���j���S�ɂ������������B
�W�J�b�g�������Čf�ڂ��܂��B
�����ԍ��F25757260
![]() 6�_
6�_
�����ł��B
�s���g���x���ǂ��悤�ł��B
�����Q�����̎��ʂň�ԋ������̂́A���̘A�ʒ��̒ǐ��������邱�ƂȂ���
���̃s���g���x�ł��B
��͂�Q��̂q�`�l���݂ō����������\�ƂȂ������ʂł��傤�ˁB
�����ԍ��F25757269
![]() 5�_
5�_
���x�̗����V�[���́A
�������J���Z�~�A�����Ȑ����Ԃ��A���̋P���A�w�i�̌��i�Z�W���j����苭�����邽��
�I�o��́[�O.�V�ɁA����Ƀ_�[�N���Ɍ������܂����B
���̎B�e�X�^�C���͎莝���A�u�J�V���J�V���I�v�ƃ��J�V���b�^�[�B
�����Q�ɂȂ��āA�o�b�t�@���������݂ŋC�����ǂ��A�ʏo����悤�ɂȂ�A
���ɂƂ��čō��̊�т������Ă��܂��B
���J�V���b�^�[�ɍS���ȗ��R��
�@�E���ăV�[���B�e�������A�d�q�V���b�^�[�ł͔w�i�̖X�E���Ȃǂ��ΌX���Ă��܂�
�@�E�����̓d�q�V���b�^�[�ł͎B�������G�������Ȃ�
����ł��B
�����ԍ��F25757321
![]() 4�_
4�_
���x�͐����痣�ꂽ�V�[���̃P�[�X�ł��B
�z�o�����O�̎B�e�ł́A���Ћ@�ɂ͖���OMDS�@�̓��Z�����p���܂��B
���̓��Z�����p����A�z�o�����O���S���S�����\�ł��B
����͌��p�ɂȂ�܂����A�������悪�B�ꂽ�Ǝv���܂��B
���̃t�B�[���h�͑Ί݂̑�܂łX�O���A���ӂ̈��܂ł͂V�O�`�W�O���B
���̃P�[�X�ł͂`�e���~�b�^�[���P�O�`�U�T���Őݒ肵�Ă����ƁA�`�e�Ώە��̓J���Z�~����
���Ȃ��̂ŁA�傫�ڂ�AF�g�ł��Ƃ��ȒP�ɃJ���Z�~�𑨂������܂��B
�s���g���x���ǂ��ł���[�B
�����ԍ��F25757361
![]() 7�_
7�_
�g���b�L�[�Ȕ�ѕ������钱�A���̔��ăV�[���ɂ�AF���~�b�^�[�����p���Ă��܂��B
����������q�̃J���Z�~�B�e�A�����č���̂P���ڂƂQ���ڂƂł͋����ݒ��
�l�����E�^�p���@�͈Ⴂ�܂��B
�J���Z�~�ł͎B�e�҂͈���������܂��A����̂P�E�Q���ڂł̓V�r�A�ȋ��������߂�
�B�e�Ҏ��瓮������ċ������킹������̂ł��B
�P���ځE�E�E�䂪�Ƃ̋��[������Ȃ̂ŁA�����Y�͂S�O�|�P�T�O���Q.�W���g�p�B
�@�@�@�@�@�@�@���~�b�^�[�͂S�`�T���̋����͈͂Őݒ肵�A���͈̔͊O�ɒ����ړ�������O�㍶�E��
�@�@�@�@�@�@�@����ړ����A�ʂ���̂ł��B
�Q���ځE�E�E�t�B�[���h�͖쒹�B�e�ŖK�ꂽ�Ǘ����ꂽ�X�B
�@�@�@�@�@�@�@���ݍr�炵�h�~�ŎU�����ȊO�͐N���֎~�ŁA���܂ł͖�P�T���Ƃ������B
�@�@�@�@�@�@�@���͂��̉Ԃ̖��z�����ړI�Ȃ̂ŁA�Ԃ�艜�Ƀs���g�����������Ȃ�������
�@�@�@�@�@�@�@�ݒ�B�A�o�E�g�P�O�`�P�T���Őݒ肵�A�ԂɃs���g�����������Ɏ���O��ړ�����
�@�@�@�@�@�@�@�A�ʂ��邾���ł��B
���̓J���������@�\���\���ɗ������A���p���邱�Ƃɂ��y�����������Ă��܂��B
���[�J�[����^����ꂽ�J�����@�\�Ɂu���[�����[���v�ƕ���������Ă��y�����Ȃ����A
�B�e�Z�p���オ��Ȃ��̂ŁA�B�邽�߂ɂ͂ǂ���������̂��H���ɎB����@��
�Ȃ��̂��H�l���邱�Ƃɏd����u���Ă��܂��B
AF���~�b�^�[�����ݒ�̈�Ƀ����O�p��o�^���Ă��܂��B
�����Y�ɂU���`���̐�ւ��X�C�b�`������܂����A�ҋחp�ɂQ�O�`�X�O�O����ݒ肵�Ă��܂��B
���R�̓t�H�[�J�X�̏r�q�������߂Ă̂��Ƃł��B
�ҋׂƌ����Ă��A�Q�O�O�`�R�O�O����ɔ�ԃN�}�^�J�Ȃǂ̑�^�ҋׂ�����A���`���^�̃n���u�T�E
�n�C�^�J�E�`���E�q�ȂǓˑR����Ėڐ���s���[�Ɖ߂������Ă������𑨂���ɂ́A�u���̃t�H�[�J�X��
�K�{�B
�s���g�ʂ������p�̂`�e��P�O�����炢�ɂ�������A�����ɐ���ł����`���E�q���ˑR�t���b�ƕ����オ����
�P�[�X�ł͂P�`�Q�e���|�`�e���x��Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F25758872
![]() 4�_
4�_
���b�L�[�I
�N�}�^�J�o���҂����Ă�����A�ڂ̑O�̖ɂP�O�H�ȏ�̃G�i�K�W�c�������Ă��܂����B
���炭�e���Q�H�Ɨc���P�O�H���炢��������܂���B
���Ɍ����u�G�i�K�c�q�v�̎������߂�������Ȃ̂ł��傤�B
�G�i�K�c�q���B�낤�Ɖ䂪�X�̌����ɂ͑吨�̃J�����}�������N�K��܂����A
���͐Â��ɎB�肽���h�Ȃ̂ň�x���s�������Ƃ�����܂���B
����A�G�i�K�̗c�������߂Č����̂ł����A�قƌ����̂ł��傤���H������Y��ȐԂ���
�������̂ł��ˁB
�����ԍ��F25759093
![]() 3�_
3�_
���⋛����
���ς�炸�f���炵���ʐ^�����肪�Ƃ��������܂��B
��D���ȃG�i�K�ƕ����āA�ȑO�B���Ă����G�i�K�𓊍e�����Ă��������܂��B
�G�i�K���ق͗c���̍��͐Ԃł����A��������ɏ]���ĉ��F�ɂȂ邻���ł��B
�ʋ@��ł����A�B�e�ɍs���ċ��R�G�i�K�c�q���ۂ��V�[�����B�鎖���ł��܂����B
�����Ō�̒c�q�Ȃ̂ł��傤���A��̓o���o���ɔ��ł����Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F25759393
![]() 3�_
3�_
�����ł͂Ȃ������̊ԈႢ�ł�
�����ԍ��F25759402
![]() 0�_
0�_
��HDV������������
���͂悤�������܂��B
�N�}�^�J�B��Ŗڐ��͐��S����̉����ɂ������̂ŁA�ŏ��͉������ŗ����̂�
������Ȃ�������ł��B
�@
�����Ĕ��ŗ����́A���̑傫�ȗt�ŕ����Ă���A���ŗ��������̑唼��
���̒��ɓ��荞�̂ŁA�����Ȗ��������̃J�����}���Ɓu�����H�����H�v�Ƃ����ł����B
�e�q�ꏏ�̃V�[���ɋC�Â��A�Q���u�G�i�K���I�v�ƕ�����A�ʂ��܂���܂������A�����Ƃ����Ԃ�
��ы����čs���܂����B
�c���̐Ԃ��ق������̏��B�萬���I�ł��B
�����Q���肵��2�������ł����A�ǂ�ȏ��ł����ʂ��o���₷���@��ɐi�������̂�
�y�����ł��B
���������Q�l�ɂȂ����ڂ��Ă����܂��̂ł������������B
�����ԍ��F25759871
![]() 4�_
4�_
�m�[�g���@�B�e�����Q�V�O�� |
�m�[�g���@�B�e�����R�Q�O�� |
�g���~���O�@�B�e�����Q�V�O�� |
�g���~���O�@�B�e�����Q�W�O�� |
�����̖ړI�ł���N�}�^�J�o����҂��ƂR���Ԕ��A�P�P�F�O�O�ɃG�i�K��ƂƂ̏o���
���������̂̈Ӓn�E��ɂ̎��ԑтɓ˓��ł��B
����ɑ҂��ƂQ���Ԕ��A�悤�₭���̃N�}�^�J������܂������A���邱�Ƃ��Ȃ��t�������꒼����
��ы����čs���܂����B
�O���������܂ʼnJ�������̂ŁA�������鎼�C�ɋt���Ƃ����������������A�t���A������
�N�}�^�J����������܂Ń���������ԁB�i�R���ڃg���~���O�摜�Q�Ɓj
�y�P�T�O�|�S�O�Of4.5��1.�Q�T�z�̓t���A����{���ꂽ�����Y�APureRAW�S�ɂ�錻���ł��t���A�����ʂ�
����Ɣ����Ă���̂ŁA����ȏ�̉掿�͖]�߂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�S���ډ摜�́A�t���A�̉e�������Ȃ������̂ŏ����傫�ڂɃg���~���O���Ă݂܂����B
����͑�C�̏�Ԃ��ǂ��Ȃ�H������̎B�e�����ł����B
�����ԍ��F25760014
![]() 1�_
1�_
�����Q�ł̒������B�e�̃e�X�g�����悤�Ǝv���A���̃X���b�h�`���ɍڂ����N�}�^�J��
�B�����ꏊ��K��܂����B
�N�}�^�J�����ꂽ�͕̂W���P�O�O�O�����̔����Ńe�X�g��ނɂȂ炸�A�v��������
�g�r�̔��ăV�[���B��ɐ�ւ��܂����B
�����Q�B�e�`PureRAW�S�����̈�A�掿�e�X�g���ʂ͂����̒ʂ�A�f���炵������
�ł����B
�@
�R�E�S���ڂ̓N�}�^�J�o���҂��Ɍ��ꂽ�V�W���E�J���ł����A����ł͎�t�E�V�W���E�J���̔����E����
�䂩��ăV���b�^�[����Ă��܂��B
�����ԍ��F25760100
![]() 3�_
3�_
�ǂ��V�C�ł��ˁ[�B
���x���Ⴂ�u�₩�ȋC��ŁA�쒹�B�e�ł͎ʂ���ǂ��ō��̓���
�Ȃ肻���ł��B
�P�E�Q���ڂ͕��ʂ̃c�o���B
���̒��͂R�E�S���ڂ̃C���c�o���ƈ���āA�H�̐F�����ǂ��̂ő�R�B�肽���̂ł����A
���̃t�B�[���h�ł͎��X��������Ȃ��M�d��Ȃ�ł��B
�����ԍ��F25761302
![]() 4�_
4�_
�C���c�o���́u����ނ�����v�^�C�v�B
�ł��A�u�O�B�[��v�Ɛ����s����p�ɂ͔������������܂��B
����̎B�e�����͂R�W���@�r�r�͂R�Q�O�O
�S/���@�B�e�����Q�T���`�R�O���@�r�r�͂Q�T�O�O�Ƃ��������ŎB�e�������ʁA���u���������B
���̌��ʂ܂��āA����͂r�r���R�Q�O�O�ɃA�b�v���܂����B
�S���ڂ̎B�e�����͂S�O���Ȃ̂ŏ]���ʂ�̂r�r�Q�T�O�O�A�M���M�����i�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B
����A�B�e�����R�O���ȉ��ł̂r�r�͍Œ�R�Q�O�O�C�m���ȂƂ���ł͂r�r�S�O�O�O�܂ŏグ������
�����悤�ł��B
������莝���B�e�Ȃ̂ŁA�O�r�g�p���̂r�r�͂R�Q�O�O�ł��n�j���ȁH
�莝���B�e�ł́y�����Y���x�����̒u���ꏊ�z�A�y���E�̐U����z�Ńu���ɑ傫�ȍ���
�o�܂��̂ŁA�r�r�l�͍��ڂ̂ق������S�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25761358
![]() 5�_
5�_
�������ł��ˁB
���͔��ł钹�́A�g���r�Ƃ��J�����Ƃ����������ł钹���炢�����B�������ƂȂ���ł����ǁA�����ɔ��ł�c�o���Ȃ�Ď��ɂ͑��������B
�������A���ꂾ�����x���グ�Ă������ȃm�C�Y���X�̏�A�𑜊��̍�����������Ƀr�b�N���BPureRAW�̌��ʂ������ł��ˁB
�����ԍ��F25763129
![]() 2�_
2�_
�������ɂ����炩�Ȃ���2012����
�������ɔ��ł�c�o���Ȃ�Ď��ɂ͑��������B
�����V�[�����̃X�s�[�h�͊����Α債�����Ƃł͖����Ȃ�܂���B
����ɏ�q����AF���~�b�^�[�Ƒ傫�ڂ�AF�g�̐ݒ�����p���邱�Ƃł��B
OM-1�ł͐��ӂ̒��F��AF�g�p�͐��ʂ̋P���E�g�̋P���Ńs���g���O��Ă��܂������A
�����Q�ł͑S�����Ȃ��悤�ł��B
�����A�}����Ƃ��g���b�L�[�C���Ȕ�ѕ��ł́A�莝���̎��Ƃ��Ă͏�q�����ʂ�
�����Y���������y���r�̘e����߂��`�ԁz���K�b�`���ێ����A���̉�]�E�O�㍘��܂��Ĕ�ʑ̂�ǐ�
�o����悤�ɂ��邾���ł��B
�����A�����Y���x���鍶��̈ʒu�͔��ɑ厖�ŁA�y�����Y�t�[�h�̍Ő�[�z������Ŏx����̂ł��B
��ʓI�ɃJ�����{�̂ɋ߂������Y�A���邢�͎O�r���ӂ���������P�[�X�Ɣ�ׂ�Ə㉺���E�̗h���
�����Ĉ��芴�͔��Q�ɂȂ�͂��ł��B
�傫���d�������Y�قǏ㉺���E�ւ̃u���Ђ��傫���Ȃ邱�Ƃ������邩�Ǝv���܂��B
���ăV�[�������łȂ��A�}�~�܂�̒��̏ꍇ�������ł��B
�`���R�`���R�Ɠ������A����ї���������Ȃ��������u���I�m��AF���鎞��
�����ŁA����ɂQ�O�����炢���ꂽ�ʒu�̏����Ƃ��Ȃ�Ɠ�Փx������ɏオ��܂��B
�����ԍ��F25763940
![]() 4�_
4�_
����ȃJ���Z�~�̎ʐ^���������ł��傤���H
�ǂ��ʂ������̂ŁA�B���т������܂��B
�����āAPureRAW���R���S�Ƀo�[�W�����A�b�v�A�_�炩����ۂ����i�`�������ȉ𑜂ւ�
�ω����Ă��܂��B
�w�i���U���c�L���Ȃ����ߍׂ₩�Ȕ������ɂȂ��Ă���A���ꂪ���S/�R�摜�ƕ�����Ȃ�
���̂ɂȂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25764008
![]() 5�_
5�_
�쒹�t�B�[���h�E�V�K�J��
�N���c�O�~�͒��X�B�炵�Ă���Ȃ����B
�x���S�������A�S�O�`�T�O�����炢����Ă��Ȃ��ƒ����X�̒��ɉB��Ă��܂��܂��B
����Ȗ�ő��̃J�����}�������Ȃ����E�ꏊ�ŁA�Ε��̔@�������Ƒ҂�������
���Ȃ��ƐX�̉��ɃR�\�R�\�Ɖ��������Ă��܂��܂��B
����͒N�����Ȃ��悤�ȃt�B�[���h���J�����Ő�����������
�悤�₭�B�����ʐ^�ł��B
�~�~�Y��T���Ȃ��痎���t�̒����������Ă��遉���B
��̉e�ɉB��������l�߂čs���܂������A���Ɍ���Ă���悤�ŋ������l�߂��Ȃ��܂�
���p����V���b�^�[����Ă��܂����B
�ꏏ�ɂ������������̑̐��Ō��p�A���Ƃ��S�J�b�g�A�ʂ����Ƃ���ŏI���܂����B
�����ԍ��F25765079
![]() 2�_
2�_
�����͕ς�����ڂ��Ă݂܂��ˁB
�k�J�����̏ォ�璭�߂Ă��āA�ӂƂP�T�O�|�S�O�Of4.5��1.25�����Y�ł͂ǂ̒��x��
�ʂ肪����̂��ȁH�Ǝv���A�`���Ă݂������i���͂P.�Q�j�ł͌����Ȃ������J���Z�~��
�����̂ŁA�����e���R����1.25�����Ńe�X�g�B�e�������̂ł��B
�P���ځE�E�E�P�T�O�����i���Z�R�O�O�����j
�Q���ځE�E�E�S�O�O�����i���Z�W�O�O�����ɂ�������ł����A������ƃ����O�ɐG���Ă��܂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʓI�ɂ͂V�T�U�����ɂȂ��Ă��܂��܂����j
���J���Z�~�܂ł̋����̓f�[�^��P�P�U��
�R�E�S���ځE�E�E�B�e�����͖�V�T���A��O�̑�i�}�t�j���ĎB�e���܂����B
�n�l�|�P�̉𑜗͂ƌ����\�t�g�iPureRAW�S�j�������A�������̎B�e���z��ȏ��
�ʂ�ɂȂ������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25766420
![]() 2�_
2�_
���̕���
���P���ځE�E�E�P�T�O�����i���Z�R�O�O�����j
�@�@�Q���ځE�E�E�S�O�O�����i���Z�W�O�O�����ɂ�������ł����A������ƃ����O�ɐG���Ă��܂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʓI�ɂ͂V�T�U�����ɂȂ��Ă��܂��܂����j
2�{�e���R�������̂��߁A��q�̋��������͑S�ĂQ�{�ɒ��������Ă��������B
�����ԍ��F25766584
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 Mark II �{�f�B
AI��ʑ̔F��AF�ɂ��ĖԂ̋߂��ɂ���R���h�����v���Ԃ�ɎB�e���Ă݂܂����B
�t���C���ł������ASingle�^�[�Q�b�g(1�_)�ASmall�^�[�Q�b�g�i9�_�j�Ńg���b�L���O���X�^�[�g�����Ă̎B�e�ł������AOM-1��肩�Ȃ�i�����Ă���悤�ł��B
![]() 9�_
9�_
�ق��Amk2�͂����܂ō����܂����I
OM-1�͟B�z�����ƌ��ɂȂ�قǃs���g������Ȃ��ł�����ˁB
��T�y�j���A�������ŋv�X�Ɏ������Ă��܂����B
�ƂȂ�ƁA����\�肳��Ă���A�t�@�[���E�F�A�̑�K�̓A�b�v�f�[�g���Ȃ�����y���݂ɂȂ��Ă��܂��B
�����͉��ǂ���Ă�Ηǂ��Ȃ��c�c
�����ԍ��F25758568
![]() 6�_
6�_
���|������ǃ_�n����
12-100mm�ŎB���Ă�݂��������ǁA�Q�[�W���ʂ�����ʖڂȂ�B���Č������A���꒹�F���ł����ł��Ȃ��BOM-1 Mark II �łȂ��Ă��I�����p�XE-PL5�ł��B��Ă܂�����B
�E�I�����p�XE-PL5�Ŗ쒹�B�e���r���[�i2015�N�j
https://review.kakaku.com/review/K0000418142/ReviewCD=862731/
�����ԍ��F25758654�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
��ʑ̂��h��l�b�g�ɂ������Ă����v�Ȃ̂����ʂł���� |
���������̂���x�ł�����ƍl�����Ⴂ�܂��ˁB |
OM-1�ł͂P���O�i�Ƃ��������ł��� |
�S���@�g���b�L���O�͗ǂ��Ȃ��Ă܂����ǁA�܂��s���� |
�����N���F���N�J�b�c�F����
���ق��Amk2�͂����܂ō����܂����I
��OM-1�͟B�z�����ƌ��ɂȂ�قǃs���g������Ȃ��ł�����ˁB
�{����OM-1��OM-1mk2�Ɣ�r����ƃZ�b�e�B���O��ς��Ȃ��玎���B������Ă��Ă������������ł��B
OM-1�����\���ꂽ����搂������OM-1mk2�p�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���邭�炢�ł��B
OM-1�̃t�@�[���A�b�v�Ɋւ��Ăł����ǁA�摜�����G���W���̔������x���琄������ƁA����قNJ��҂ł��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
ISO12800�ȏ�̍����x�ł̎B�e���l������ƁA�܂�OM-1����������邤���ɔ��������������ǂ��̂ł͂Ƃ��������ł��B
�����ԍ��F25759717
![]() 2�_
2�_
�R���g���X�gAF���ƌ��������� |
���ʈʑ���AF�ɂȂ��Ă��Ȃ���P |
�C���e���W�F���g��ʑ̔F��AF�ł��������i�� |
�g���b�L���O�����Ȃ������ǂ����������āA�ǂ����ȁ`�Ƃ������� |
���A�}�]���J�t�F����
�I�����p�X���ォ��ԁE��Ȃǂ̏�Q���z����AF���C�}�C�`�ƌ����Ă���̂ŁA�ɋߏ�ŎB�e�ł��铮�����̃R���h���Ō����������ł���B
���Q�[�W���ʂ�����ʖڂȂ�
�Q�[�W�igage�܂���gauge�j���āH�H�H
PENTAX67��300mm/F4�Ƃ�105mm/F2.4�����ĎB�e���Ă��A���������������ƃP�[�W�icage�j�͎ʂ����Ⴂ�܂��ˁB
�B�ɕ����߂�ꂽ�R���h�����B�e�����킯�ł�����A�R���h�������낵�������Ɏʂ�����B��������摜�̕������A���ł́H
�쐶�̃R���h�����B�e���邽�߂ɃA���f�X�R���Ƃ��`�x�b�g�Ȃǂ֏o������d�����Ȃ��ł����A�������Ƃ��Ă����f�肵�܂����c
���E�I�����p�XE-PL5�Ŗ쒹�B�e���r���[�i2015�N�j
https://review.kakaku.com/review/K0000418142/ReviewCD=862731/
�������̃��r���[�ł͂Ȃ��悤�ł��ˁB
�������A�ԉz���Ƃ���z���Ƃ����ݓ������}�t�z���Ƃ��Ƃ������摜�͊F���ł����ABORG�ł�����MF�����ł��Ȃ���AE-PL5�͊�D��AF/�����oAF�����Ȃ��ł�����A���F���Ƃ��S�����W�ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA����̎B�e���ɂ͒��F�������Ă���g��EVF�ɕ\������Ă��܂������ǁA�R���h���̎p���E�A���O�����ɒ[�ɕω�����ƁA�g���b�L���O���O��܂��B
�����ԍ��F25759727
![]() 10�_
10�_
���A�ǂ��ł��ˁB
�����͏���OM-�P��E-M1III�œ�������싅�̃l�b�g�z���̎B�e�́A�I�����p�X�{�̑���AF���~�b�^�[���g���ĎB�e���Ă܂����B
�B�i�������͖ԁj�܂ł̂����悻�̋�����ڎ��Ŕ��f���A�B�����O�ɂ̓s���g������Ȃ��悤�J�����{�f�B��AF���~�b�^�[�@�\���g���ĎB�e�B
�{�f�B���ɓ��ڂ���Ă�AF���~�b�^�[�A����͂���Ő����������Ă܂����ǁA�������̟B�̏ꍇ���ƁA�������B�̖T�ɂ���ꍇ�ɋ����̐ݒ肪����A�ǂ����Ă��B��AF�������Ă��ꂿ�Ⴄ�B���W���[�şB�܂ł̋������v��킯�ɂ������܂��ˁB
AI��ʑ̔F�������şB�̒��̓����Ƀs���g�������Ȃ炱��قNJy�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł����B
����OM-1�ł����A�H�ɗ\�肳��Ă���ƌ����Ă�OM-1���̃��W���[�A�b�v�f�[�g�ŁAAF���P�ɂ��Њ��҂��Ă܂��B�i���߂Ă��ꂭ�炢�͂���Ă���܂���ˁHOMDS����j
�����ԍ��F25763097
![]() 2�_
2�_
�F�X�������N���Ă��܂����B
���ȊO�̓������Ƃǂ����傤���HOM-1��AI��ʑ̔F���̃��r���[�ł́A�u���L�v���[�h�ł�����L�ȊO�̓����ŗL�����������ă��r���[���ǂ����Ō����̂ł����B
�������̟B�̒��̑��̐F�X�ȓ����ł��L�������ł��傤���H
�����ԍ��F25763115
![]() 3�_
3�_
�B�e�������Ⴂ�߂��܂��B
�J��������B�܂ł̋����A�B���璹�܂ł̋����̔䗦���S���قȂ�悤�ł��B
����ɎB�e���̏œ_�������傫���قȂ�(����75mm�A�E��25mm)�B
�S�Ă̏�����OM1�ɕs���ɂȂ��Ă���B
�����B�e�����Ŕ�r���Ȃ��ƕs�����ł��B
�����ԍ��F25763254
![]() 11�_
11�_
�������ɂ����炩�Ȃ���2012����
�������͏���OM-�P��E-M1III�œ�������싅�̃l�b�g�z���̎B�e�́A�I�����p�X�{�̑���AF���~�b�^�[���g���ĎB�e���Ă܂����B
����AF���~�b�^�[�𑽗p���Ă��܂������ǁA���ʂ̃l�b�g�Ɍ�������30�x���E�ɐU���������Ł�R���̂Q�͎B�e�����������Ȃ�܂�����A�t���ʂɂȂ����Ⴄ���Ƃ������A��͂��ʑ̔F���Ɋ撣���Ă����Ȃ��ƃ_���ł���ˁB
��AI��ʑ̔F�������şB�̒��̓����Ƀs���g�������Ȃ炱��قNJy�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł����B
���Ђ̐��i�œ����悤�ȏ����Ŏ����B������Ă��Ȃ��̂Ŗ{�����ǂ����͔���܂��ǁA�z���t���悤�Ƀg���b�L���O���S���Ă���邻���ł�����AOMDS�ɂ��撣���ė~�����ł��ˁB
���������̟B�̒��̑��̐F�X�ȓ����ł��L�������ł��傤���H
�����悤�Ȍ��ʂł����̂ŁA���\�������Ȃ��ł��傤���B
Single�^�[�Q�b�g(1�_)�Ńg���b�L���O�J�n���B�e�R�R�}�ڂ����Ƀs��������Ƃ������ۂ��N�����̂ŁA�ǂ��Ȃ��Ă�Ƃ����������N���܂����B
�����ԍ��F25764181
![]() 1�_
1�_
���ו�s����
���B�e�������Ⴂ�߂��܂��B
���J��������B�܂ł̋����A�B���璹�܂ł̋����̔䗦���S���قȂ�悤�ł��B
������ɎB�e���̏œ_�������傫���قȂ�(����75mm�A�E��25mm)�B
�����悤�ȎB�e�����ŎB�e����OM-1�̉摜�Ŕ�ʑ́i���Ɋ�Ɂj�Ƀs���������摜���Ȃ������̂ŕۑ����Ă��Ȃ������̂ł����A75mm�ŃP�[�W�����ꂾ�������ڂ��Ȃ��Ŋ�ɍ��ł�����ԂŃg���b�L���O�ł������Ƃ�A25mm�ŃP�[�W�ł͂Ȃ����̉H���ɍ��łł������Ƃ͂قƂ�njo���������Ƃ͂���܂���B
�����ԍ��F25764278
![]() 0�_
0�_
�쒹�B�e��OM-1�g���Ă܂����ǎ}���Ԃ�ŃK���K��AF�����Ȃ甃���ւ��������ł��B
���̒��x�Ȃ�]��ς��f�����Ȃ��Ƃ��������܂�Q�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��B
�܂��A198+�L���b�V���o�b�N�͎��Ԃ̖��Ǝv���̂ł����̎����ȁB
�����ԍ��F25764793�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��G�V�������vP����
�I�����p�X���ォ��ԁE��Ȃǂ̏�Q���z����AF���C�}�C�`�ƌ����Ă���̂ŁA��30���ōs���铮�����Łm�P�[�W�z���̒��F���n�������������ł���B
�l�������҂��Ă�ƁA�B�ꂽ�͂��̉摜�����Ƃ����蓾�܂��ˁB
�����ԍ��F25765069
![]() 0�_
0�_
���l�������҂��Ă�ƁA�B�ꂽ�͂��̉摜�����Ƃ����蓾�܂��ˁB
�����ł��ˁA���肪�Ƃ��������܂��B
���N�̃h�[���ł����ǁA�����͂��̒��x�B�������̂Ŏ�芸�����H�̃A�b�v�f�[�g���Ă݂čl���܂���B
�����ԍ��F25765183�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�|������ǃ_�n����
���X���肪�Ƃ��������܂��BAI��ʑ̔F���̌��L���[�h�ŁA���ƐF��ȓ����şB�z���ł��C�P�����Ȃ�ł��ˁB
���҂����Ⴂ�܂��B
�����ԍ��F25765380
![]() 1�_
1�_
���c�̌��\�f�[�^���Ɣw�ԍ���2�̑I�肪177cm�A35�̑I���178cm |
�W���C�A���g�ł��ˁB |
���ł��̑Ŏ҂��ƃ��t�g���̊O��Ȃ��炪�B��₷���ł��B |
�V���b�^�[���x�������Əグ�������ǂ����������B |
��G�V�������vP����
���n����̉摜�ł��傤���B
�g���~���O�����T�C�Y����Ă���悤�ł����A����Ɏʂ��Ă���̂��O�ێ肾�Ƃ���ƁA���\�������Ȃ݂����ł��ˁB
���̏ꍇ�A�h��l�b�g�Ȃǂ̕⋭�p�̃��C���[���f�荞�݂ɂ����A�ʘH���ŁA����q��O�̊ϋq�Ȃǂ��ז��ɂȂ�Ȃ��Ȃ����悤�ɂ��Ă��܂����ǁA�J�����}���Ɠ����悤�ȏ����ŎB�e���悤�Ƃ���ƊO��Ȃ��璴�]���ő_�������Ȃ��ł��B
�t�ɑO�̊ϋq�̎ז��ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���ɂ�150-400mm/F4.5�����E�ł����ˁB
150-600mm/F5-6.3�͖]���[����150-400mm/F4.5���5cm�قǒ����Ȃ�̂ŁA�Ȃ̑O��̊Ԋu�ɂ���Ă͑O�̐l�̓��ɂԂ���\�����o�Ă������ł��B
F4�Ƃ�F4.5���炢�Ȃ�ISO�͗}����ꂻ���ł����ǁA��蒷�œ_�ňÂ������Y�̏ꍇ��A��葬���V���b�^�[���x�ɂ������ꍇ�́AOM-1mk2�̕����ǂ��Ƃ����C�����܂��B
�����ԍ��F25765693
![]() 0�_
0�_
�������ɂ����炩�Ȃ���2012����
�����i���E�L�j���[�h�ŁA�قƂ�Ǒ��v�ȃ��x���ɋ߂Â��Ă���Ǝv���܂��B
��ʑ̃u�����܂߁A�u�����e������Ǝv���܂����c
�����ԍ��F25765700
![]() 1�_
1�_
���̐��i�̍ň����i������
![OM SYSTEM OM-1 Mark II 100-400mm II ���]�������Y�L�b�g](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001717553.jpg)
OM SYSTEM OM-1 Mark II 100-400mm II ���]�������Y�L�b�g
�ň����i�i�ō��j�F¥375,990�������F2025�N11��14�� ���i.com�̈����̗��R�́H
- ���i��r
- �X�y�b�N
- ���r���[
- �N�`�R�~
- �����L���O136��
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����z����p�\�R��
-
�yMy�R���N�V�����zSUBPC 2025 WHITE
-
�y�~�������̃��X�g�za
-
�y�������߃��X�g�z���N�̂����ɂ���őg�ߓI�Ȏ���Q�[�~���OPC��
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�J����
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2025�N12���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2025�N12���z

�^�u���b�gPC
- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2025�N12���z

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j