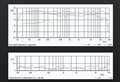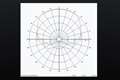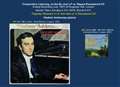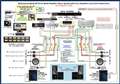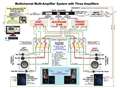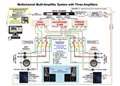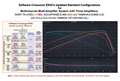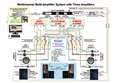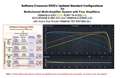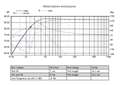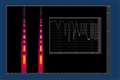���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S425�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 2023�N12��26�� 12:25 | |
| 115 | 189 | 2023�N11��18�� 09:31 | |
| 2 | 25 | 2023�N10��29�� 00:55 | |
| 17 | 6 | 2023�N7��22�� 22:39 | |
| 3 | 5 | 2023�N7��1�� 18:31 | |
| 128 | 200 | 2023�N5��8�� 23:57 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�O�X����200���ɒB�����̂ŁA�V�X���ł��B
�O�X��
�T�u�E�[�t�@�[�A
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25482284/
�����ԍ��F25550041�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�{���́A���j�^�[�I�[�f�B�I���������Ă��܂����B
�g�[���{�[�C�͖��������̂Ńu�b�N�V�F���t���������܂������Asilver�V���[�Y���v���̂ق��ǂ������̂ŁA�܂��܂��������Ă��܂���(��
�T�C�Y���ł́A20���a��BRONZE500/6G�����x�悢���s����D364mm�A�����T�C�Y���ƁA15���a��SILVER/300/7G��D389mm�B
�Ƃ̃��r���O�ɍœK�ȃT�C�Y���ł��B
�A���v��MODEL30��ROKSAN/bkak�Ɣ�r���܂������AMODEL30����ROKSAN/bkak�Œ��������ABRONZE500/6G�̃|�e���V�����������o���������ǂ��Ȃ������������܂����B
SILVER/300/7G�͂ǂ���Œ����Ă��𑜊��������N���A�ȃT�E���h�ł����B
ROKSAN/blak�́A�`�����l�����ƂɃg�����X����������E�Ώ̃��C�A�E�g�ŁA�f�W�^�����Ƃ��d�����Z�p���[�g����Ă���̂ŁA���̉e�����������悤�ł��B
ARCAM/SA30������p���[�ƍ������ŁA�V���ȃ��C�o���o���ł��B
�����[�J�[�́ACaspian��Attessa���C�ɂȂ�Ƃ���ł��B
�C�M���X���͂��߂Ƃ��郈�[���b�p�n���[�J�[�́A�v���A���v�ƃp���[�A���v��Ɨ�����̂ł͂Ȃ��A�v�����C���A���v�̃A�b�v�O���[�h�Ƃ��ăp���[�A���v��p�ӂ���P�[�X�������悤�ł��B
�����ԍ��F25550074�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ɒቹ�Ɋւ��ẮA����܂Œ��������X�s�[�J�[�Ɣ�r����ƁB
KEF/Q�V���[�Y/�p�b�V�u���W�G�[�^�[�̉����^�C�v
KLIPSH/RP�V���[�Y/�L���r�l�b�g���傫��30hz���炢�܂ŐL�т�d���Ȓቹ
MONITOR AUDIO/SILVER�V���[�Y/���̒��ԂŁA��������Ƃ����ቹ�Œ��܂������������܂����B
����ł��āA�L���r�l�b�g��KLIPSH�����R���p�N�g�Ȃ̂ŁA���r���O�z�[���V�A�^�[�ɂ��œK�Ȉ�ہB
�o�����X�I�ɂ͂��Ȃ肢�������ŁA�`�u�ɂ��s���A�ɂ��ǂ����ɂ������Ă����ۂł��ˁB
�����炭�g�[���{�[�C��SILVER300/7G�ł��A���������ɂȂ肻���ł��B
�����ԍ��F25550480�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���j�I�͓���p�Ő́X�A��l�C�ł���
���̌�DALI�ɂƂ��ĕς���
���̐l�C��Polk�ł��ˁB
���j�^�[�Ƃ̓X�^�W�I�̃��j�^�[�ł͂Ȃ�
���y�����j�^�[����Ӗ��������ł��B
�����ԍ��F25550675�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
�����ł��ˁB
polk������p�Ŕ���Ă܂����A���j�I�̕�����������N���A�ŃN�Z�������قڌ�����ۂ��ł��ˁB
KLIPSH/RP�͉��s���T�C�Y�������킸�AKEF/Q�V���[�Y�͒ቹ��邢�̂ŁB
�����ԍ��F25550729�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɁAARCAM�ɂ��ăn�[�}���ɖ₢���킹�܂������A��T�Ԃ����Ă��ԓ������Ȃ��ł��ˁB
�n�[�}���n���甃���̂�߂悤���ȁB
�����ԍ��F25550793�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���N�Z�������قڌ���
�ꉞ�A�čl�������߂Ă����܂���
��o���ƌ����Ȃ��悤�B
���[�J�[�̌����Ă���ʂ�Ȃ̂�
�����ԍ��F25550864�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
SILVER/300/7G�́A���h�o�V�ɍɂ���݂����Ȃ̂ŁA�������Ă��画�f���悤�Ǝv���܂��B
POLK/R�V���[�Y�AKEF/Q�V���[�Y�ɔ�ׂ�ƃR�X�p�͈����ł���(��
�����ȑO�Ƀi�X�y�b�N�̉c�Ɨ͂͗����Ă�悤�Ȃ̂ŁAPOLK�f�m�}���A���ɂ͏��ĂȂ��ł��傤�ˁB
���Âł�����Ȋ����Ȃ̂ŁA
Q750/\110000
SILVER300/7G/\210000
�����ԍ��F25550955�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���c�Ɨ�
�����ł͂Ȃ��A���j�^�����O�Ɍ����ĂȂ�����
�A���v�V�^�A���^�̒�����ׂ�
�V���̍����킩��܂���ł����B
��������B&W�ł������A
�������͂�����킩��܂����B
�g���Ă���l�̃R�����g�ł�
�C���ȉ��͏o���Ȃ��A
�����Ă��S�n�悢SP�������ł��B
(����Ӗ��n�C�e�N)
�����ԍ��F25551051�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�������ł͂Ȃ��A���j�^�����O�Ɍ����ĂȂ�����
�A���v�V�^�A���^�̒�����ׂ�
�V���̍����킩��܂���ł����B
��������B&W�ł������A
�������͂�����킩��܂����B
�V�����Ăǂ̐���̘b�ł���?
������Z�p���Ⴂ�Ƃ������ł��ˁB
�܂��AB&W�����������Ȃ��ł�����(��
���̕��l�i�������ł����AB��W�̓T�u�Ŏg���Ă�̂ŁA�ႤSP���ق����̂Ǝ��܂�̂����T�C�Y���D��ł��ˁB
�Ă��A���X�ALINTON�������Ƃ��Ă��̂ŁA����ȂɃn�C�X�y�b�N�Ȃ̂͋��߂ĂȂ��ł����B
�����ɂ悵����́A�������Ȃ莨���삦�Ă��ł��傤�ˁB
���͂Ȃ������Ă܂��܂����S�҂Ȃ̂ŁB
�A�o�b�N�ɂ��AQ750��SILVER/300/7G���邻���Ȃ̂ł܂��܂���r���ɍs���Ă��܂�(��
�X���H�����j�I�͒l�i�オ�肷�����̂ŁA����Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ă܂����B
b��w�Ȃ͂����ɒl�����Ă��܂������A�i�X�y�b�N�o�R���Ⴛ�������̂��ł��Ȃ����ł����A���j�I�̐�s���͌��������ł����B
�܂��s��͐������ł�����ˁA�l�i�����t�B�[�����O�ł���(��
�����ԍ��F25551083�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���V�����Ăǂ̐���̘b?
����Șb���ł�
�����ԍ��F22147210
�����ԍ��F22149928
���̐l�C�͉c�Ɨ͂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25551197�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�����̐l�C�͉c�Ɨ͂ł͂Ȃ�
S8���Đ̂̋@��ł���ˁB
����ƁAB��W/803��r���āAS300/7G�ƂȂ�̊W������̂��悭������܂��B
�����ɂ悵����̒��ł̓��j�I�̕]�����Ⴂ�Ƃ������ł��ˁB
�����ԍ��F25551253�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�G���[�S������
�I�ԂȂ�ASP���j�b�g�̃{�C�X�R�C����
�U���̕\�ʂړ������^�C�v���悢�ł��傤
�ׂ��ȐU������C�ɓ`���܂�
�~�����U���̕\�ʂɏo�āA
�_�X�g�L���b�v���t���Ă܂��B
�n�j�J�����ʂ̏ꍇ�̓\�j�[�̂悤��
�\�ʂɓ˂��o���~���������Ă����
�J�����ɁA���j�b�g�������畷������
�����S�R�悩�����̂ŋC���t���������ł�
�_�C���g�[�����n�j�J���U�����g���Ă܂���
�{�C�X�R�C���͕\�ʂɏo�Ă��܂��B
����ĂȂ��̂́A�ׂ��ȉ����K�v�Ȃ�
�T�u�E�[�t�@�[���炢�A���Ƃ͓�������Ȃ�����
���̂̋@��ł����
��{�͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25551858�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
���Ƃ́AFYNE AUDIO/F502/F501�������\��ł����A��������40���ȉ��ʼn��i���̉��l���{���ɂ���Ȃ甃���܂���������Δ����܂���(��
https://s.kakaku.com/review/K0001139507/
KEF�������i�����u���Ȃ̂ŃR�X�p�͍����ł����B
���ہA�i�X�y�b�N�̉c�ƃ}���͌��\���߂Ă����āA���̉e�������邻���ł��B
����{�͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B
7G�̓c�C�[�^�[���i�����Ă܂��ˁB
�����ԍ��F25551975�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���m���ǂ���Δ���鎞��ł͖����ł�����ˁB
��肭�}�[�P�e�B���O�Z�������Ȃ��Ɣ���܂���B
���̓_�A�f�m�}���n�͉��i�ݒ�܂ߔ���D���̂悤�ł��B
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1187876.html
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=18888
�����ԍ��F25551994�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̃X�s�[�J�[�Ȃ����������ł����A�ꕔ�̃}�j�A�ɂ�������Ȃ��ł��傤(��
https://www.phileweb.com/sp/review/article/202312/19/5420.html
�����ԍ��F25552113�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
�����̃X�s�[�J�[�Ȃ����������ł���
�����C���^�[�i�V���i���V���E�Ō������܂���
�݂Ȃ����Ă邯�ǁA�����悩�����Ƃ̘b����ڂɂ��܂����
https://www.phileweb.com/sp/interview/article/202303/01/919.html
�����ԍ��F25552709�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
��FYNE�������\��A���i���̉��l���{���ɂ���Ȃ�
��KEF�R�X�p�͍����ł���
���̒��ŁAAV���g���Ȃ�KEF�ł�
�������ʂ̉���������ł��傤
���t������̂̓A���v��
�����ԍ��F25552742�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�������悩�����Ƃ̘b����ڂɂ��܂����
���������ʂ̉���������ł��傤
�����t������̂̓A���v��
�����悩�{���悩�݂�����(��
�V�����r�W�l�X���f�����o�Ă��Ȃ��ƁA�X�s�[�J�[���i�����Ȃ������ł��ˁB
https://youtu.be/ZxcjeiLECRw?si=_ENJKc0vNFbiqI5q
�����ԍ��F25552787�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���������A�n�C�G���h�X�s�[�J�[�����Ă�l�B���āA�z���g�ɉ����ǂ��Ǝv���Ĕ����Ă�̂�?
�ڂ����͕�����܂��A�C���e���A�Ŕ����Ă�w�������ł��傤�ˁB
https://youtu.be/nEtv116Y77U?si=w4t4EvwRDZVkGLFI
�܂���Ȃ�ŁA���ł�����Ȃ�ł��傤��(��
�����ԍ��F25552848�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���C���e���A�Ŕ����Ă�w��
�I�����p�XS8R�ł���
�v�E�[�t�@�[�Ɍ����܂���
�Е��̓{�C�X�R�C���̂Ȃ��h�����R�[��
�������܂�Ȃ��h�����R�[���ƌ����Ă܂���
���l�ς��낢��A�����̊�����
��e���ɂ�����
(��b�̗l�q�ŃP�����b�N�͊֗^���Ă��Ȃ�)
�C���e���A���d�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25552921�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�N�����͂ǂ������邩�A�ӏ܂��Ă��܂����B
���f���/�C�I���V�l�}
�X�N���[��/9.8m × 5.5m
���苗��/12m
����/MAX84db
���V�X�e��
�X�e�[�W�X�s�[�J�[/JBL C222
�T���E���h�X�s�[�J?/JBL 9310
�T�u�E�[�n�[/JBL 4642A
�p���[�A���v/QSC DPA4.3
�v���Z�b�T�[/QSC DCP300
�����z
�d�ቹ�͂��������o�Ă܂������A�S�W���ɔ�ׂ�Ƃ������艹���ł����B
�t�����g�̎��̓S�W���̎������N�b�L���������Ă�����ہA�T���E���h��7.1ch�������̂ł������ɃT���E���h���ʂ�����B
�����A���̉����ɓ��ʍS���Ă͂��Ȃ������ō�i�̉��o�Ƀv���X�A���t�@���x�Ŏ��R�Ȋ����B
�f��Ƃ��ẮA�W�u���e�C�X�g�̉����A�j���[�V�����B
�����ēւ̃I�}�[�W���I��i�ŁA�{��ē̐Â��ȓ��ȓI�X�g�[���[�Ƃ����������B
�G���^���������A�[�g������������オ��ɂ͌����邪�A���������y���߂܂����B
�����ԍ��F25560498�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�A�o�b�N�ɂăX�s�[�J�[������r
���X�s�[�J�[
MONITOR AUDIO/SILVER300/7G
KEF/R5 META
KEF/Q750
���A���v
MODEL40N
SILVER300��͂蒆���悪�N�b�L���X�b�L���A�𑜊�����������������B
������r����ƁAKEF/Q750�̒�悪�����Œ������Ă��܂����B
KEF/R5 META�́A������̉𑜊��͂����܂ō����Ȃ����A�S�̂̃o�����X�͍����t���b�g�X���B
�S�̓I�ɔ�r����ƁASILVER300�͂��h���V�����X���ʼn��i���̉��l���������A����3�@�풆�ł�KEF/R5 META���㎿�Ȉ�ہB
�ł������A��͂�AKLIPSH/RP�V���[�Y�̃z�[���^�̒�����̐L�т₩���ƃN�b�L�����A�����Ė��x�̍������ƃX�s�[�h���A�d���ȃG���N���[�W���[�A�S�̓I�Ȋ����x��������o�Ă���A��͂�l�I�ɍD���ȉ������Ƃ������_�Ɏ���܂����̂ŁAKLIPSH/RP6000F2���w�����鎖�ɂȂ�܂����B
��i�ق̓���ł�POLK/R700�����]������
https://youtu.be/ju1ZvCwS_IY?si=3DozKy3oLxUHmiL_
����ɉ����A�f�U�C���I�ɂ����̃f�U�C���������_���r���e�[�W��������AAV�C���e���A/�T���E���h�Ƃ̃o�����X�������Ƃ����̂��v���ł����B
����70/�f�U�C��30�̊����B
�ЂƂ܂�����ɂāA�t�����g�X�s�[�J�[�����̗��͏I���܂���(��
���̂��Ƃ́A�A���v�����ւƑ���...
�����ԍ��F25560505�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���z�[���^�̒�����̐L�т₩���ƃN�b�L����
�����o���Ȃ���Ȃ����E�ɂ悤�����ł���
�����ԍ��F25560819�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�������o���Ȃ���Ȃ����E�ɂ悤�����ł���
�W�u���̐��E�ł���(��
�_�C�������h�c�C�[�^�[�Ƃ��A�x�����E���Ƃ���ɂ͏オ����悤�ł����A���̂Ƃ��낱�̕ӂŊy����ł����܂��B
�A�o���M�����h�Ƃ��ł����̂̓����|
�����ԍ��F25560875�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��s�X���b�h�F
�y��6�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24559812/#tab
������i���ݕԐM��180�j�ɂȂ�A�ԐM���Q�O�O���ɒB����Ə������݂��ł��Ȃ��Ȃ邻���ł��̂ŁA���̐V�X���b�h�Ɉڍs���܂��B
�u���U�v�ɑ������̃X���b�h���u���V�v�ł͂Ȃ��u���P�P�v�Ɩ��ł��Ă��闝�R�́A��قǐ������܂��B
����܂ł̌o�܂ȂǁA���̏������݈ȍ~�̂������̎��ȃ��X�ŏЉ�܂��̂ŁA�F�l�̓��e�́A�ǂ��Ă��m�点����܂ł������������B
![]() 1�_
1�_
���̃X���b�h�́A�Q�O�P�X�N�P�Q���R�P���i��A���I�j�ɊJ�n�������L�̂P�O���̃X���b�h�̌p�������ł��B
�O�P�D�y�����̃v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד����H�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284
�O�Q�D�y���@�����v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד��H�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776
�O�R�D�y�`�����l���f�o�C�_�[�ŕ�����Ƀo�����X�����x�������H�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab
�O�S�D�y�\�t�g�E�F�A�`�����l���f�o�C�_�[ EKIO�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
�O�T�D�y���@�\�t�g�`�����f�oEKIO �� DAC8PRO �Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/
�O�U�D�y���X�@�\�t�g�`�����f�oEKIO �� DAC8PRO �Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23398907/#tab
�O�V�D�y���X�X�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab
�O�W�D�y���S�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab
�O�X�D�y���T�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24004016/#tab
�P�O�D�y��6�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24559812/#tab
���̂悤�ɁA��s�X���b�h���P�O���i�P�O�{�j����܂��̂ŁA���̃X���b�h�͐�s�X���b�h���Ƃ̐��������d�����āA�y���P�P �\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z�ƕ\�肷�邱�Ƃɂ������܂����B�]���āA�u���V�v����u���P�O�v�́A�X���b�h���Ă͑��݂������Ԃł���Ƃ������������B
�����ԍ��F24859398
![]() 1�_
1�_
�����̐�s�X���b�h�ł́ABOWS����A�����ɂ悵����A��M���Ƃ��đ����̊F�l�̒g�������x���Ƃ����͂Ɏx�����A���̃}���`�A���v�I�[�f�B�I�V�X�e���̍\�z��i�߂邱�Ƃ��ł��܂����B
�܂��A���i.com�ɂ����邱���̐�s�X���b�h����ՂƂ��āA�Q�O�Q�O�N�S���ɕč��� Audio Science Research Forum�i�ȉ��ł� ASR�Ɨ��̂��܂��j�ɂ����āA���̃u���O�I�X���b�h�G
�yMulti-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC�z
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
���J�n���A�{�����݂ŁA�����g���܂߂����e�����T�W�S���ɓ��B���Ă���A���E������̉{���K����P�R���V���ɔ����Ă���܂��B
����ASR�X���b�h�͑S�ĉp��ł����A�ŋ߂� Microsoft Edge �� Goggle Chrome �� AI���{���@�\�ł��A���Ȃ�܂Ƃ��ȓ��{��\������܂��̂ŁA�F�l�������葁�������ɂȂ肽���ۂɂ́A�u���E�U�̓��{�����������������B�i���܂́A�Ӗ��s���A�����s���ȁA�������ȓ��{��\������܂��̂ŁA���̍ۂ́A�p�ꌴ���������������I�j
�܂�����ASR�X���b�h�ɂ��ẮA�ȉ��̂Q�ӏ��Ƀn�C�p�[�����N�ڎ����쐬���Ă���܂��̂ŁA�K�v�ɉ����Ă������������A�L�����p���ĉ������B
�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-23#post-961964
�ƁA�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hyperlink-index-for-the-specific-thread-on-multichannel-multi-driver-multi-way-multi-amplifier-stereo-project-using-multichannel-dac.27831/post-962823
�ł��B
�����ԍ��F24859403
![]() 2�_
2�_
���́G
�u�}���`�`�����l���Q�}���`SP�i�X�s�[�J�[�j�h���C�[�o�[�Q�}���`�E�F�C�Q�}���`�A���v�Q�X�e���I�I�[�f�B�I�V�X�e���v
�ɂ��āA����܂ł̌o�܂͂ŏڂ��������o���Ɣ��ɒ���ȋL�q�ƂȂ�܂��̂ŁA�ڍׂɂ��Ă��m��ɂȂ肽�����X�́A��ŏЉ����s�X���b�h�Ǝ���ASR�X���b�h�����Ԃ������Ă�������Ƃ��ǂ݂���������悤�A���肢�\���グ�܂��B
���̈���ł́A���Ɂu�قڊ����̈�v�ɓ��B���Ă��錻�݂̃}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�������������������Ƃ͔��ɑ�ł��B �������Ȃ���A��������t�ŋL�q����ƒ���ɂȂ邱�Ƃ��������܂���̂ŁA�u�S���͈ꌩ�ɂ������I�v�A�u�D�ꂽ�}����ʐ^�́A�����̕��͂ɗD��I�v�ƌ����ϓ_����A�ȉ��̂������̓��e�ł́A�ŐV��ԗ�����u�}���v�Ɓu�ʐ^�v���A�S�����A�����Ȍ��ɋ��������Ă��������܂��B
�����́u�}���v�Ɓu�ʐ^�v�̑唼�́A�Q�O�Q�Q�N�T���R�O�����݂̍ŐV�V�X�e���\�������L���Ă���ASR�X���b�h���e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-27#post-1206700
�ŏڍׂɐ������Ă�����̂ł��B
�����ԍ��F24859407
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
�V�X�e���̍\���} |
12��̑�^VU���[�^�[�̍\���} |
�\�t�g�E�F�ADSP(XO/EQ)�ł���EKIO�̍\������ |
EKIO�N���X�I�[�o�[����уf�B���C�ݒ�̏ڍ� |
�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂P�|�z
�V�X�e���̍\���}
12��̑�^VU���[�^�[�̍\���}
�\�t�g�E�F�ADSP(XO/EQ)�ł���EKIO�̍\������
EKIO�N���X�I�[�o�[����уf�B���C�ݒ�̏ڍ�
�����ԍ��F24859415
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
�V�X�e���S�̍\���̃u���b�N�} |
�P�Q�A��VU���[�^�[���܂ރA���v��DAC�̔z�u�} |
���ۂ̔z�u�ʐ^ |
�A���v�ADAC�Ȃǂ̔w�ʔz���̗l�q |
�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂Q�|�z
�V�X�e���S�̍\���̃u���b�N�}
�P�Q�A��VU���[�^�[���܂ރA���v��DAC�̔z�u�}
���ۂ̔z�u�ʐ^
�A���v�ADAC�Ȃǂ̔w�ʔz���̗l�q
�����ԍ��F24859420
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
�œK����́u�����v���g��������VU���[�^�[�\���͈� |
���X�j���O�|�W�V�������猩��SP�i�X�s�[�J�[�j�Q |
���E��SP�Q�̋ߐڎʐ^ |
SP�Q�w�ʂ̔z����SP�P�[�u�����O�{�[�h |
�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂R�|�z
�œK����́u�����v���g��������VU���[�^�[�\���͈�
���X�j���O�|�W�V�������猩��SP�i�X�s�[�J�[�j�Q
���E��SP�Q�̋ߐڎʐ^
SP�Q�w�ʂ̔z����SP�P�[�u�����O�{�[�h
�����ԍ��F24859422
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
�S��ASIO�h���C�o�[�ɂ��PC���ł̓��o�͍\���T�O�} |
ASIO���o�͂̏ڍׁiJRiver MC���p�̏ꍇ�j |
ASIO���o�͂̏ڍׁiRoon���p�̏ꍇ�j |
ASIO4ALL�\���ݒ�̏ڍ� |
�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂S�|�z
�S��ASIO�h���C�o�[�ɂ��PC���ł̓��o�͍\���T�O�}
ASIO���o�͂̏ڍׁiJRiver MC���p�̏ꍇ�j
ASIO���o�͂̏ڍׁiRoon���p�̏ꍇ�j
ASIO4ALL�\���ݒ�̏ڍ�
�����ԍ��F24859429
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
�I�[�f�B�I�V�X�e����p���S����PC�Q��̏ڍ� |
�P�Q�A��VU���[�^�[�̋ߐڎʐ^ |
�P�Q�A��VU���[�^�[�̕ʔz�u�ʐ^�|�P�| |
�P�Q�A��VU���[�^�[�̕ʔz�u�ʐ^�|�Q�| |
�y�}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̍ŐV�i2022�N�T��ƂR�O�����݁j�̐}������юʐ^�Љ�|���̂T�|�z
�I�[�f�B�I�V�X�e����p���S����PC�Q��̏ڍ�
�P�Q�A��VU���[�^�[�̋ߐڎʐ^
�P�Q�A��VU���[�^�[�̕ʔz�u�ʐ^�|�P�|
�P�Q�A��VU���[�^�[�̕ʔz�u�ʐ^�|�Q�|
����H��ɂ��P�Q�A��VU���[�^�[�iIEC 60268-17���K�̃v���d�lVU���[�^�[�j�̎����ɂ��ẮA���̂Q���e�ŏڍׂɋ��L���Ă���܂��B
- My nostalgia and preference for large glass-face VU meters: DIY of 12-VU-Meter Array in multichannel multi-driver multi-way multi-amplifier stereo audio system: #535
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1202570
- NISHIZAWA R-65 VU meter plus ATV205EXT VU amp board is compatible with IEC 60268-17 VU meter specification/standard: #545
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-28#post-1221214
�����ԍ��F24859436
![]() 1�_
1�_
�A���v�Q�ɁA�D�ꂽHiFi�v�����C���A���v�i�C���e�O���[�e�b�h�A���v�j���̗p���Ă��邱�Ƃ́A���̃}���`�V�X�e���̑傫�ȓ����ł��B
�A���v�Q�̑I���ɂ́A�����̎��Ԃ��₵�āu������ł̐T�d�Ȏ����v���s���Ă܂���܂����B
�ߋ��̉��i.com�X���b�h�����ASR�X���b�h�ŁA�����ڍׂ����L���Ă���܂����A�A���v�Q����ɂ��Ă̗v���w�i�A�܂�����̉������Ȃǂ́AASR�̂��̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419
�ŏڂ������L���Ă���܂��B
HiFi�v�����C���A���v�i�C���e�O���[�e�b�h�A���v�j���p�̗��_�ɂ��ẮA����2�̓��e���傢�ɎQ�l�ɂȂ�Ɗm�M���Ă���܂��B
- A serious jazz fanatic friend came to my home for audio sessions using my multichannel multi-driver multi-way multi-amplifier stereo system: #438
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-933173
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audio-listening-with-age-diminished-hearing.12846/post-1175606
�����ԍ��F24859441
![]() 1�_
1�_
���̃}���`�`�����l���Q�}���`�A���v�V�X�e���̃f�W�^���M������уA�i���O�M���̊e�i�K�ɂ�������g�������A����Ƀ��X�j���O�|�W�V�����ɂ��������C���̎��g�������́A�ڍׂɑ��肵�Ă���܂��B������ASR���e�������������B
- Where in my multichannel multi-driver (multi-way) multi-amplifier stereo system should I measure/check frequency (Fq) Responses? #393
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-20#post-826262
- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-1_Fq Responses in EKIO�fs digital output level: #394
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-827624
- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-2_Fq Responses in DAC8PRO�fs analog output level: #396
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-828796
- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-3_Fq Responses in amplifiers�f SP output level before protection capacitors: #401
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-831487
- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-4_Fq Responses in amplifiers�f SP output level after protection capacitors: #402
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-833427
- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-5_Fq Responses in actual SP room sound at listening position using one measurement microphone: #403
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-837485
- Frequency (Fq) responses in the completed system measured by using �gcumulative white noise averaging method�h under the present standard crossover configurations and relative gains_Part-6_Summary, discussions, and a little step forward: #404
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-843454
�����ԍ��F24859444
![]() 1�_
1�_
�܂��A�eSP���j�b�g�i�h���C�o�[�j�Ԃɂ�����A 0.1 msec���x�̃^�C���A���C�������g�������ɑ��肵�āA�������Ă���܂��B
���̂��߂ɁA�������j�[�N�ȁu���Ǝ��́v������@�Ƒ���p�V�O�i�����l�ā��쐬���ė��p���Ă���A���E�I�ɂ��]���ƒ��ڂՂ��Ă���܂��B
����p�ɍ쐬���������M���Q�̗��p�ɂ�������������́A�������Ȃ��A���m�点�������B
- Precision measurement and adjustment of time alignment for speaker (SP) units: Part-1_ Precision pulse wave matching method: #493
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1048913
- Precision measurement and adjustment of time alignment for speaker (SP) units: Part-2_ Energy peak matching method: #494
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1049923
- Precision measurement and adjustment of time alignment for speaker (SP) units: Part-3_ Precision single sine wave matching method in 0.1 msec accuracy: #504, #507
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-26#post-1061868
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1062729
- Perfect (0.1 msec precision) time alignment of all the SP drivers greatly contributes to amazing disappearance of SPs, tightness and cleanliness of the sound, and superior 3D sound stage: #520
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1098097
�����ԍ��F24859450
![]() 1�_
1�_
�u�����o�N��J���Ă��邩���H�v�Ƃ́u���p�Ŏ���ȋ^���v��������Yamaha NS-1000 �̃E�[�t�@�[JA-3058�ƃT�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000 �ɂ��ẮA�ŋ߁ABOWS����A�����ɂ悵����A�̂��w�������A�����Ɂu�ߓn�����v�𑪒肵�A��������40�N�ȏ���o�����ł��A�����ׂ��D�ꂽ�ߓn�����������Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B
- Measurement of transient characteristics of Yamaha 30 cm woofer JA-3058 in sealed cabinet and Yamaha active sub-woofer YST-SW1000: #495, #497, #503, #507
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1051202
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1055089
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1060433
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1062729
�����ԍ��F24859452
![]() 1�_
1�_
�ȏ�������܂��āA�{�X���b�h�`���ɂ�����G
������܂ł̌o�Љ�
�����́u�}���`�`�����l���Q�}���`SP�i�X�s�[�J�[�j�h���C�[�o�[�Q�}���`�E�F�C�Q�}���`�A���v�Q�X�e���I�I�[�f�B�I�V�X�e���v�ɂ�����ŐV�\���̏Љ�i�Q�O�Q�Q�N�T���R�O�����݂̍ŐV�\���j
���A�ЂƂ܂������Ƃ����Ă��������܂��B
�ł́A�F�l�A����܂łƓ��l�ɁA��낵�����t�������̂قǁA���肢�\���グ�܂��B
����ȍ~�̂��Q���A�����e�A���w�����A�S��芽�}�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24859463
![]() 3�_
3�_
BOWS����A�����ɂ悵����
���m�点����̂�Y��Ă���܂������A���́u�^�C���A���C�������g�������聕�����������@�v�������]�����Ă������Ƃ肪�A�����ł�����܂����B
ASR�̃X���b�h�G�hTime aligned speakers - do they make sense?�h
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/
�̓��e�ԍ�#86
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1190338
�Ŏ��̕��@���Љ���Ƃ���A�����Ă� Dougey_Jones���瑬�U�Ń��X������A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1190350
�u�����������K�v�͂���܂���B���͂��ꂪ�ǂ�قǏd�v�������łɒm���Ă��܂��B�ł��L���ȃ^�C���A���C�������g�X�s�[�J�[���ŏ��ɓ������ꂽ�Ƃ��A����i�����Љ������ƒ������@�j�͂܂������I�v�V�����ł͂���܂���ł����B����ɂ��A��������Ă��Ȃ��X�s�[�J�[�ɂ��̗��_�� *�lj�* �ł���悤�ɂȂ�܂��B����͑f���炵�����Ƃł��B�l�I�ɂ́A���Ȃ��̃A�L���t�F�[�Y E-460 ���A�܂����ł��B�v�@�Ƃ̔����ł����B
�܂��A���X���b�h�� #126;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1193736
�ŁA�ēx�A���̕��@�ɐG�ꂽ�Ƃ���Agnayrly���瑬�U����������A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1194416
�u����ɂ��́Adualazmak ����B
�ŏ��ɁA���̃X���b�h�� #86 �ɓ��e���ꂽ���Ȃ��̃v���W�F�N�g�����N���y�����ǂ�ł��܂��B���Ȃ��̕��@�́A����܂łɎ��������������ł��A�ł��L�͈͂ɏW���I�Ɂi�����Ɂj�^�C�~���O���v�邽�߂̃E�F�[�u���b�g�o�[�X�g�̎g�p���@�ł��B��������L���邽�߂ɂ��Ȃ�����₵���f���炵���w�͂��^���܂��B�v�@�ƕ]�����Ă���܂����B
���̏�ŁA�ނ������悤�ȕ��@���������悤�ŁA���̗l�q���Љ�Ă���܂����B
�܂��A�����G
�u�������A�I�[�f�B�I�V�X�e���̋q�ϓI/��ϓI�ȃ`���[�j���O�́A���X�j���O���̃��X�j���O�|�W�V�����ŐT�d�Ɏ�ϓI�ȃ��X�j���O�Z�b�V�����ɂ���čŏI�I�ɕ]������K�v������܂��B�v�@
�Ə��������Ƃɑ��ẮA
�u���ӂ��܂��B���ǂ́A�����y���܂��邱�Ƃł���ˁH�@��葽���̐l�X�����m�Ȏ��Ԓ����ŃX�s�[�J�[�����Ƃ��ł���i��������ɂƂ��Ă̓t���b�g�����ƃt�F�[�Y�ł��j�A���̉����ɂ��čl����ς��邩������܂���B�v
�Ǝ^�����Ă���܂����B
�C�O�ł��A�����ȃ^�C���A���C�������g�����̏d�v���𐳂����F�����Ă���l�͈ӊO�ɏ��Ȃ��悤�Ȃ̂ł����A���̃X���b�h�ɎQ�����Ă���l�B�A���� Dougey_Jones���� �� gnayrly����A�͂悭�������Ă���悤�Ɍ��܂����B
�܂��A���̃X���b�h�̂����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/time-aligned-speakers-do-they-make-sense.33961/post-1187458
�ŁA���̃����N���G
https://www.audiofrog.com/time-alignment-part-three-delays-and-crossovers-for-tweeters-and-mids/
�邱�Ƃ��ł������Ƃ́A������̎��n�ł����B
�����ԍ��F24862223
![]() 3�_
3�_
�F����A
�ȑO�ɂ����x�����b�������悤�ɁA�����g�A���Č��\�s�A�m��e���Ă�������������A�D�ꂽ�s�A�m���t�Ƃ��̗D�ꂽ�^���̍Đ��́A��Ɏ��̃}���`�`�����l���|�}���`�A���v�Đ��V�X�e���ɂ������v�ȉۑ�Ɗy���݂ɂȂ��Ă���܂��B
���āAASR�̂��̃X���b�h�G
The Truth about many "Audiophile" Piano Recordings
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-truth-about-many-audiophile-piano-recordings.30668/
�ł́A�s�A�m�^���ɂ��ċ����[���������Ƌc�_���s���Ă���A�����A���܁A�y�����Q�����Ă��܂��B
���̃X���b�h�̂����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-truth-about-many-audiophile-piano-recordings.30668/post-1272914
�ŁA�����[���h������s�A�j�X�g Andras Schiff �i�A���h���[�V���E�V�t�j�� 2010�N���C�v�c�B�b�q Bachfest �ɂ�����u���E���y��Y�I�v�i���Ǝ����m�M���Ă���j�o�b�n�u�t�����X�g�ȑS�ȁ{�C�^���A�R���`�F���g�v�Ƒt���t��i�S�Q���ԂP�T���j�̑f���炵�� YouTubev�r�f�I�X�{�G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhIP1CNbYhVObXv7ByHmE5oETjj6RXyAN
����P�Ȃ��Љ�A���̑f���炵�����t�Ƌ��ɁA���ٓI�ɗD�ꂽ�^���ɂ��āA�}�C�N�Ƃ��̐ݒ�i�r�f�I�ɂ́A�Ȃ����قƂ�ǎʂ��Ă��Ȃ��I�j����ј^���Z�p�A�^���G���W�j�A�A�Ȃǂɂ��Ċy���������Ă���܂��B
�������Ȃ���A�}�C�N�̎�ށ^�@���ݒ���@�A�^���Z�p�ɂ��ẮA���܂���ɕ�܂�Ă��܂��B�ǂ����APZM (Pressure Zone)�}�C�N�iBoudary�}�C�N�Ɠ��`�j���g���Ă���悤���A�Ƃ����Ƃ���܂ł͒����Ƒz�����i��ł���̂ł����A������A�܂����m�F�ł��B
����ł́A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-truth-about-many-audiophile-piano-recordings.30668/post-1278163
�Œ����悤�ɁA�����A�����������ȁi�W�́H�j���ቹ�m�C�Y���T�u�E�t�@�[�Œ����킯�āA���̃��C�u�����ł́A����������i�������Ȃ��悤�ɕҏW�j�����A�Ȃǂ̕��Y��������܂��B
������ɂ��Ă��A���ɁA���ٓI�ɁA�D�ꂽ���C�u�^���ł��̂ŁA������������A����Ȃ�ɗD�ꂽ�Đ����u�ŁA��������ƒ����Ă݂ĉ������B
�s�A�m�̘^���Ƃ��ẮA���݂̍ō������ł���Ɗ����Ă���܂��B�������A���C�u�^���Ƃ́I�H
�܂��A�����ׂ����ƂɁA�Q���ԂP�O�����郉�C�u�R���T�[�g�ŁA�V�t�́A�s�A�m�̃y�_������x���g�킸�A�S�ĈÕ��ŁA�܂��~�X�^�b�`�́A�قځi����A���S�ɁH�j�F���A�Ƃ����_������I�Ȗ����ł��B
���̃v���N�����ł́A���́A����܂ł̓O�����E�O�[���h�̉��t�ɐS���������Ă����̂ł����A����A���������A�������ō��^���i�ʂ̃V�t�̉��t�����ł������Ƃ́A�傫�Ȋ�тł��B
�A���v�����Ŗ����ɗD�ꂽ�ߓn�������m�F�ς݂̒��i�E�[�t�@�[�j���܂߂āA�S�Ă�SP�Q�i�T�u�E�[�t�@�[�A�E�[�t�@�[�ABe-�~�b�h�����W�ABe-�c�B�[�^�[�A�z�[�� �X�p�[�c�B�^�[�j�Ԃ� 0.1�~���b���x�̃^�C���A���C�������g������B�����Ă��鎄�̍Đ����ŁA���ɑf���炵�������Đ����m�F���A���\���Ă���܂��B
�����ԍ��F24876535
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����A
���낻��@���n������悤�ɂ��v���܂��̂ŁA���炽�߂āA�V���v���ō����\�ŁAXLR�o�����X�A�E�g�ŁA�ǂ��炩�Ƃ����ƃv���d�l�ŁA��킭�� OKTO DAC8PRO �̔��W�^�̂悤�ȂP�U�`�����l��DAC���j�b�g�o��ւ̊�]���A
�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/minidsp-flex-eight.36451/post-1279976
�ƁA�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-1279987
�ɓ��e���܂����B
���������܂����B
�uUSB 16 �`�����l�� ASIO ���� (PC ����� 1 �{�܂��� 2 �{�� USB 2.0 �P�[�u���ɂ��) �� 16 �`�����l���̃o�����X �A�i���O�o�͂ŁA���ɂ͏\���ł��B���������āAES9028PRO �܂��� ES9038PRO (�܂��͐V���� AKM DAC �`�b�v?) �� 2 �� (�܂��� 3 ��?) ���ڂ��� 16-Ch Sync Pro DAC (OKTO?) DAC16PRO(?) �ɑ��鎄�̒P���Ȋ肢�ł��B�v
�u8 �`�����l���� AES/EBU �X�e���I���͂́A�����I�Ɏg�p����\��������A�v���̃t�B�[���h�ɂ���l�ɂƂ��Ċ��}����܂�...�������APC �̐�p ASIO �h���C�o�[�́A���̃M�A�� 16 �`�����l�����ׂĂ�F������K�v������܂��B�B������̂͂ƂĂ��ȒP���Ǝv���܂��B�@OKTO �� Pavel �����������Ă���邱�Ƃ�����Ă��܂��B�v
�����ԍ��F24877110
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����A�F����A
���̊����ς݂̃}���`�A���v�V�X�e���ɂ����āANS-1000���L���r�l�b�g����30 cm�E�[�t�@�[ JA-3058 �i���� A-S3000 �Œ����쓮�j�ƕ��p����A�܂��͂����u��������E�[�t�@�[�̕��F�́A�y���������Ă���܂��B
���E�̃T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000 �͌p���g�p���܂��̂ŁA�����Ă݂�V�E�[�t�@�[�́A��������b�����Ă���悤�ɖ� 45 Hz�` 500 Hz ���Y��ɃJ�o�[���Ă������̂ŁA�����\�ȃo�X���t�L���r�l�b�g�ł��邱�Ƃ��]�܂����A�ƍl���Ă���܂��B
���āA����AASR�̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/midrange-dome-drivers-banned.15060/post-1275075
�ŁA�t�����X�̐V���X�s�[�J�[���[�J�[ Revival Audio �� ATALANTE 5 ��m��܂����B
���̎ʐ^�������̒ʂ�A�܂��Ж����i�I�j�AATALANTE 5 �́AYamaha NS-1000 �iNS-1000M�j �� 2020�N���݂Ŗ͕킵���f�U�C���Ƃ����v���܂���I
�����I�ɂ́G
Yamaha NS-1000:
395(W)x710(H)x349(D) mm, 39.0 kg, 40 Hz - 20 kHz, 90 dB/W/m
Revival Audio ATALANTE 5:
420(W)x710(H)x355(D) mm, 33.0 kg, 28 Hz - 22 kHz, 89 dB/W(2.83V)/m
�ƁA�i���ɁH�j���Ă���܂��B
Revival Audio �Ђ� HP�́G
https://revivalaudio.fr/
�ŁAATALANTE 5 �̃y�[�W�́G
https://revivalaudio.fr/product/atalante-5/
����ȃ��r���[�������܂����B
https://www.hifipig.com/revival-audio-atalante-loudspeakers/
�܂��A�����̎ʐ^�G
https://www.chameleonracks.gr/Speakers/Revival-Audio-ATALANTE-5--en?filter=&sort=pd.name&order=DESC
�ŕ�����悤�ɁA�w�ʂQ�|�[�g�̃o�X���t�i�܂��͋�C�����j�^�C�v�ŁA
������ǂ����߂̍d���X�|���W�L���b�v�Q���������邻���ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/midrange-dome-drivers-banned.15060/post-1284017
���āA���� 30 cm�E�[�t�@�[�@BSC (Basalt Sandwich Construction) woofer �ɋ����ÁX�Ȃ̂ł����A�Z�p���A�X�y�b�N��A�ǂ��ɂ��A�S����������܂���B�����ŁA Revival Audio �ЂƂ̒��ڃ��[���A�����J�n���āA�₢���킹�Ă���܂��B
1. I could download and take a look at your Owner's Manual for ATALANTE 3, and found the cabinet is rear ported (bass reflex) design with the port cap for making it into quasi(?) sealed cabinet if needed. I assume ATALANTE 5 would be also ported (bass reflex) cabinet, right? If this would be the case, is the port cap (lid) also available for ATLANTE 5?�@�i��L�̒ʂ�����ς݁j
2. As far as you would be OK for public disclosures, I would like to know the technical and specification details of your three SP drivers, especially the new 30 cm woofer, including;
Magnet Weight,
Total Weight,
Sensitivity (dB/W/m),
Nominal Impedance (ohms),
Air Gap Height (mm),
Voice Coil Diameter (mm),
Voice Coil Height (mm),
Linear Coil Travel (p-p) mm,
Maximum Coil Travel (p-p) mm,
Magnetic Gap Flux Density (in T, Tesla),
Moving Mass (in gram)
Anechoic sealed and ported Fq responses
�iBOWS����A�����ɂ悵����̂��w���̎����ŁA����Ȏ�����ł���悤�ɂȂ��Ă���܂��B�j
3. Any of the total on-axis and off-axis Fq response data for ATALANTE 5, preferably by KLIPPEL in anechoic or quasi-anechoic environments.
4. As far as possible, the details of cabinet material and inner (heavily reinforced?) structure, and the sound absorbance (glass wool?) materials and quantities. Is the woofer chamber completely separated from the upper chamber of midrange and tweeter in ATALANTE 5?
5. The details of your crossover LC-network; detailed photo will be fine, block diagram, and also the details of the parts list (capacitors, inductors, etc.), as well as the crossover slope configurations (which can be found in the detailed photo, though).
�u�Z�p�ӔC�� CTO�� R&D����֎�����e�𑗂�A������܂��I�v�A�Ƃ̂��Ƃʼn҂��ł��B
���Ȃ݂ɁARevival Audio �Ђ̂ӂ���̑n�Ǝ҂ɂ��ẮA����ȋL�q������܂��B
Revival Audio Atalante Loudspeakers are handmade in France, the brand has been created by Daniel Emonts, an engineer in the HiFi industry for more than 30 years, and Jacky Lee, a Swiss-based Taiwanese Strategist Executive, who has worked with Dynaudio, IBM and L�fOréal. The speakers are designed in collaboration with the A+A Cooren Design Studio.
Daniel has worked previously on many speaker models and technologies at Dynaudio of Denmark and French brand Focal. Daniel built his first speaker at the age of 14 and has dedicated himself to acoustics for almost four decades. He designs all Revival Audio products and technologies in their lab in France.
�ǂ����A �g�b�v�� Daniel Emonts���́A�f���}�[�N��Dynaudio�Ђƃt�����X�� Focal�Ђœ�������A�X�s���A�E�g���č�N���Q�O�Q�P�N�� Revival Audio ���A���U�X�őn�Ƃ����悤�ł��B
���āA�ǂ̂悤�ȉ����邩�A�y���݂ł��B
�����ԍ��F24885555
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�E�\�t�@�\������a�A�Ⴂ���g���Ő邽�߂�
�傫�ȃh�\�уX�R�\�J�\���g���āA
�K�x�Ȕ���ŖL�������o���Ă���
�ǂ��炩�Ƃ����ƃr�N�^�[SX�\900�̍l��������
����a�\�t�g�h�\����ATC(�}���`�[�q�t��)��
�m���Ă܂����A���}�nNS�\2000A�Ƃ��A
�ŋ߂����s���Ă����̂����B
NS�\1000�̓n�\�h�h�\���Ȃ̂�
dualazmak����̍D�݂ɍ��������|�C���g����
����܂���B
�����w���̎���
���������Adualazmak����͒ǂ��z���Ă܂���
�����X�y�b�N�ŋC�ɂȂ�̂́A���x�AQo�Amo�A
�w���Ɏセ�������炢(�̂Ȃ���̍l����)
�n�Ǝ҂���14�˂Ŏ���SP�Ƃ́A���{���ƒ��j�a��
�����ō�������������A���ƂȂ��������Ă܂��B
�����ԍ��F24886183�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
��NS�\1000�̓n�\�h�h�\���Ȃ̂�dualazmak����̍D�݂ɍ��������|�C���g��������܂���B
�����͓����ł��āA�~�b�h�����W�ƃc�C�[�^�[�́A NS-1000 �̂��̂��p�����p���AATALANTE 5 �� LC�l�b�g���[�N����������ăA�N�e�B�u�����A����➑̂ƃE�[�t�@�[�������A���v�����Ŏg���A�Ȃ�Ă��Ƃ����z���Ă���܂��B��������ƁA������[�J�[�ۏ͏������܂��ˁI
������A���ł� NS-1000 �̃x�����E���h�[���~�b�h�����W�́A���E�I�Ɍ��Ă��w�i����O�w�H�j�ɓ���D����̂��Ɗm�M���Ă���܂��B
�܂��AATALANTE 5 �̏ڍׂ�m���Ă���̔��f�ɂȂ�܂����B�B�B
�����ԍ��F24886342
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�@BSC (Basalt Sandwich Construction) woofer ���ăn�j�J���\���̐U���Ȃ�ł����ˁH
�@�Z�p�������Ă݂����ł��B
�@�ŋ߁A���߂ɐ������ꂽ�n�j�J���R�[���̃��j�b�g���ėǂ��Ȃ��Ǝv���܂����B
�@���x�ȃR�[���̂��߁@�U����ʂ��Ĕw�ʂ���̉����������Ȃ��A���e�ʖ��ł��������Ȓቹ���o���Ă��܂����B
�@
�����ԍ��F24886401
![]() 1�_
1�_
BOWS����
�n�j�J���\���ł͂Ȃ��A���܂ŒN���g�������Ƃ��Ȃ��u�����₩�璊�o��������@�ہv���g�����T���h�C�b�`�\���̂悤�ł��B
https://revivalaudio.fr/technology/bsc-woofer/
�̋L�ڂɂ��A
�u������̓����F�@
�n�����ō��̃h���C�o�[�܂�
������́A��ɗ�p���ꂽ�n��܂��̓}�O�}���Ŕ�������܂��B����́A�ÊD�F�̂�����ΐ��ł���A���E���ő�ʂɔ�������Ă��܂��B
�ϊ����ꂽ������@�ۂɂ͋����[������������A�X�s�[�J�[�̐U���ł̎g�p�ɓK���Ă��܂��B
���̃����O�����K���X�@�ۂ����͂邩�ɋ����A�P�u���[�����͂邩�ɋ��͂ł��B
��K�\�����x�[�X�̑f�ނł��邽�߁A�����\���̂��߂ɂ��g�p���Ă��܂��B
Revival Audio �R�[���͊ܐZ���ꂽ������@�ې��n�ŁA�w�ʂɐڒ��܂̂��Ȃ�����w������A����ȑ@�ۂ���̃t�F���g�̑w�ŕ����Ă��܂��B����́A�����ō������������A�������\���Ɍ������ꂽ�R�[�����\�����܂��B�v
�������ł��B
�����ÁX�ł����A���@���Ă݂Ȃ����Ƃɂ͉��������܂���ˁB���{�ŁA�������s���ŁA���X�Ɏ����ł���悤�ɂ��Ă���!�@�Ɨv�]���Ă����܂��B
�����ԍ��F24886817
![]() 1�_
1�_
Revival Audio ��������܂������A�_���_���ł��ˁB���� HP�ɏ悹�Ă�����ȏ�́A�����o���Ȃ������ł��B����ł͔����킯������܂���ˁB���{�ł̓W�J���S�����肾�����ł��B�Ƃɂ����A�C�O�̑���]�����҂��Ȃ���l�q�����܂��B
���āA�u�������v����u���y�ӏ܁v�ցA�������d�S���ړ����Ă���܂��B
ASR�ł́A��̃j�b�`�ȁu�����[�g���y�Ƃ��̑��̌Êy�v�̕ʃX���b�h���Ċ����������Ă��܂��B
�܂��A�}���`���̃��C���X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�ł́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1310404
����n�߂��u�A�����e�V���[�Y�v�ŁA�I�[�f�B�I�@��ƕ��������̃`�F�b�N�A�`���[�j���O�ɓK�����u�D�ꂽ�^���i�ʂ̉��y�����v���n���I�ɏЉ���L���邱�Ƃ��J�n���܂����B
��{�I�ɂ́A���� CD��_�E�����[�h�w�������I���W�i�������ŁAAdobe Audition 3.0.1 �ŗ�̃J���[�X�y�N�g�����͂��s�������ʂ�Y�t���@�u���̃I�[�f�B�T���v���[�����v�@���Љ�L���܂��BYouTube�N���b�v��������ꍇ�ɂ́A����ւ̃����N���\��܂����A���̉�����ۏ��邱�Ƃ͕s�\�ł��̂ŁA�����܂œǎ҂̎Q�l�܂łɁB�B�B
�J�e�S���[��W���������ɁA�ЂƂ��̓��e�Ƃ���\��ŁA�����́u�͂��߂�=introduction�v�̓��e�Ɏ����ŁA�A�ڑ�P��Ƃ��āA����A�u�t���I�[�P�X�g�������v�ɂ��ď����܂����B
����A�T��i���イ�����j���e���x�̃y�[�X�ŁA�C���ɐi�߂�\��ł��B
���肷���̍ۂɁA���܁A���Η����������A���ӌ��ȂǁA ASR�ł��A�����ł��A������ł����\�ł��̂ŁA������������������K���ł��B
�����ԍ��F24920226
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
��ŏЉ���G
���u�A�����e�V���[�Y�v�ŁA�I�[�f�B�I�@��ƕ��������̃`�F�b�N�A�`���[�j���O�ɓK�����u�D�ꂽ�^���i�ʂ̉��y�����v���n���I�ɏЉ���L���邱�Ƃ��J�n���܂����B
�ł����A�{���X���R�O���܂łɁA�ȉ��̒ʂ�A�A�ڂ��܂����B
[Part-00] Introduction: #587
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1310404
[Part-01] Full Orchestral Music: #588
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1311722
[Part-02] Solo Piano Music: #590
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1314703
[Part-03] Typical(?) Smooth Jazz Music with Guitar: #591
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1315676
[Part-04] Bimmel Bolle Antique Orgel; Extremely High-Energy High-Frequency Sharp Transient sound: #592
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1316155
[Part-05] Color Spectrum of Tracks in CBS/Sony's "Super Audio Check CD": #593
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1316865
[Part-06] Female Vocal in Jazz and Popular Music, and One Male Vocal Track for Comparison: #596
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1319250
[Part-07] Female Vocal and Counter Tenor in Early Classical Music: #639
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1320575
[Part-08] (Smooth?) Jazz Trio: #640
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1322787
[Part-09] Organ Music: #641
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1325412
[Part-10] Lute Music: #642
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1329188
[Part-11] Violin Music: #643
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1332948
��������������\��ł��B
�����ԍ��F24945305
![]() 0�_
0�_
�܂��܂����L�����������͑��X����̂ł����A�L�����Ȃ��Ȃ肻���ł��̂ŁA��U�i�b��I�Ɂj�I�����邱�Ƃɂ��܂����B
[Part-12] Cello Music: #644
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1336989
[Part-13] Harpsichord (Cembalo, Clavecin) Music: #645
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1339729
[Part-14] Piano Concertos: #650
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1340684
[Part-15] Again, CBS/Sony's "Super Audio Check CD": Analyzed by Adobe Audition 3.0.1 and MusicScope 2.1.0: #651
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1341056
[Part-16] A Cappella Chorus and A Cappella Vocal Ensemble: #652
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1343542
[Part-17] Excellent Quality Music Tracks, But Containing Unacceptably High Gain Low-Frequency Air Conditioning Noises; What Counter Measures Can We Have? #658
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1345536
[Part-18] An Interlude or Provisional Finale of the Post Series: #669
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1348148
�����ԍ��F24965560
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
���͌��ʂ��K��҂ɂƂ��āA
�ǂ��ɂȂ���̂�
�킩��Â炢��������܂���
�Ⴆ�A
�����ł悭�g����y�ȂŁA
�������ƁA���̕��̓|�C���g
�Ȃ��������Ȃ̂����
���l�̊y�Ȃ������Ƃ�
�e�ш�ł̊y��̕�����������
�����Ղ̎g����������Ƃ�
�l�ɓ`����̂��������
�c���A�����̐�������
���͌��ʂ̈Ӗ�����Ƃ���
�������������A�ʔ����Ɉ�������
�����O���t�́A
�S�ĈӖ����������Ȃ���
���������Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24967674�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����A
�M�d�Ȃ��ӌ��A���Ӑ\���グ�܂��B
���ۂ̂Ƃ���AASR Forum �ɂ����Ă� Adobe Audiotion �́u����X�y�N�g���v�� MucisScope �̕��͌��ʂ��A�����������ł���l�́A�c�O�Ȃ��瑽���͂Ȃ����Ƃɏ��������Ă��܂��B
�i�^�C���A���C�������g�̑���ƒ����ɂ��Ă��A���l�ł��B�����̕�����l�͐�^���Ă���܂����A������Ȃ��l�͕�����Ȃ��܂܂ŁA���X�Ɨ��_�I�ȋc�_��_���𑱂��āA������ɂ͓��ݍ��܂Ȃ��I�j
����A�����o�[�ł��� Doodski��������̈�l�ŁA�u���̃X�y�N�g���͉����Ӗ�����́H�@���V�т��H�v�ƒ����Ă����ۂɂ́A�����A�����܂����B�ނɂ��ẮA���e�ԍ�#597�`#638 �ŁA���̐l�X�̎Q�l�ɂ��Ȃ�悤�Ɂu���J�ȁi����I�j����Ǝ���v���s���A�悤�₭#638�ŃX�y�N�g�����͂̈Ӌ`�𗝉����Ă���܂����B
����A���́i�I�j��Î҂��܂ސ�����ASR�d���̕��X����́APM�l�ԒʐM�ŘA��������G
�u���̘A�����e�̈Ӌ`�Əd�v���������̎Q���҂ɗ��������ɂ͏��X���Ԃ������邩������Ȃ����A����ASR Forum ��A���炭����OD�t�H�[�����ł��A���t�@�����X�����Ɋւ���c�_����������s����ۂɂ́A�ЂƂ̋������I�Ȍn���I��L�i�Ƃ��̕��@�j�Ƃ��ĎQ�Ƃ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B�v
�Ƃ̂��ӌ��Ɨ�܂��Ղ��Ă���܂��B
�܂��APM�A���ŁA�����̕����特�����L�i���� Sony Super Audio Check CD����� YouTube �ɃA�b�v����Ă��Ȃ��������̉����j�ɂ��āA���L��]�����Ă���A�Ή����Ă���܂��B�܂��A�������Ȃ��J���ĎQ�Ƃ��Ă��� YouTube �������A�����č��i�ʂł��邱�Ƃ��^���ĉ�������������܂��B
���Ⴆ�A�����ł悭�g����y�ȂŁA�������ƁA���̕��̓|�C���g�Ȃ��������Ȃ̂����
�����l�̊y�Ȃ������Ƃ��A�e�ш�ł̊y��̕����������������Ղ̎g����������Ƃ�
�m���ɁA���̕ӂ�܂œ��ݍ���ŘA�ڂ��邱�Ƃ��l���܂������A������܂߂�Ɗe���e���X�ɒ���ɂȂ�A���ł��������������ł����A���̓��e�������ߑ�ȕ��S�ƂȂ�܂��̂ŁA����́A�Ƃɂ����W��������y��ɓ�������`�ŁA���ꂼ��́u���Ȃ�̃T���v���[�����v���n���I�A�ԗ��I�ɏЉ���L���邱�Ƃɗ��߂܂����B
�����̓ǎ҂���́APM�ŁA�����ɂ悵����̂��w�E�ɑ�������˂������₪���Ă���A�ʂɏ��������Ă��܂��B
�A�ڂ́A�ЂƂ܂��u�b��I�ɏI���v��錾���Ă���܂��̂ŁA�ǎ҂̊F����̔����iPM�ʐM�A���e�������݁j�����炭�������A���̌�A�K�v�ɉ����āA�����ɂ悵����̋M�d�Ȃ��������Q�l�ɂ����Ă��������Ȃ���A�X�̃T���v���[�����ɂ��Ă̏ڍׂȏ��������p���������ƍl���Ă���܂��B
�i���́jASR�̏d������́G
�u�X�y�N�g�����͂��܂߂āAASR�ł��A���̃t�H�[�����ł��A�O�Ⴊ�Ȃ����Ɍn���I�ȉ����Љ�Ȃ̂ŁA�X�y�N�g���̈Ӌ`���\���ɗ������Ă���I�[�f�B�I�t���[�N�ł��A�y�X�����ӌ����q�ׂɂ������ʂ����邩������܂���ˁB�v
�u�܂��A�M�a�قǂ̃��x���ɒB���Ă���}���`�`�����l���V�X�e�����\�z���Ă���l�́A�c�O�Ȃ�����ɏ����Ȃ̂ŁA�݂Ȃ���A�ߊ�肪������ۂ�������Ă��邩������Ȃ����A�M�a�̃X���b�h�ւ̃A�N�Z�X���̋}�㏸�i�ŋߋ}�����ĂP�T���Q�������j�́A�����̓ǎ҂�����̘A�ڂɔ��ɒ��ڂ��Ă��邱�Ƃ�@���Ɍ���Ă��܂��B�v���ɐ[�����ӂ��܂��B�v
�Ƃ�PM�A���Ղ��܂����B
�A�����e�̏����Ǝ��M�ŏ��X��ꂽ������܂��̂ŁA���炭�x�e���Ȃ���A���̃X�e�b�v��T�d�ɒT��܂��B
����ƁA�A�A
��́G
�u�A���v�����E�[�t�@�[�������A�ł���Ζ��L���r�l�b�g�ŐV�����Č��݂� 30 cm JA-3058 in NS-1000���L���r�l�b�g�Ɣ�r�������I�v
�̍\�z�́A���ł��������Ă��炸�A�s�ӁA�������p�����ł��B
���� KLH �� Model Five �ŐV�^�@�i�Ƃ���25cm�E�[�t�@�[�A���L���r�l�b�g�j�ɂ��ď����W���ł��B���Ȃ�A��������������LCR�l�b�g���[�N�̓o�C�p�X���āA�A���v���������݂܂��B
�����ԍ��F24967846
![]() 1�_
1�_
�����ł��B
�u����OD�t�H�[�����ł��A�v�@���@�u���̃I�[�f�B�I�t�H�[�����ł��A�v
�����ԍ��F24967853
![]() 0�_
0�_
���߂܂��āA��Topping DM7��EKIO�i�������Łj�Ń}���`�`�����l���̎������ł����A����Ƃ��܂������܂����B
Web�p��WindowsPC�Ɠ����{AMAZON MUSIC HD�̂��߁A����≹���ϓ������肷�錻�ۂɔY�܂���܂����B
�ŏI�I�Ƀo�b�N�O�����h�ł̗D�揇��UP�ƁA�A�v�������A���^�C�������ɕύX���邱�Ƃɂ��������܂����B
FB�̃I�[�f�B�I�}�}�j�A�ł��グ�Ă��܂��B
����HP�ł̖{���̓��e���ȉ��ɂȂ�܂��B�F�l�̓��e�������ɔ��ɖ��ɗ��������Ƃ����ӂ������܂��B
https://office-mos.com/soft-channel-device-ekio-windows-settings-air-recording/
�����ԍ��F24973219
![]() 2�_
2�_
moto888����
���Q���A���Ӑ\���グ�܂��B�@�uEKIO�Ń}���`�`�����l���v�̒��Ԃ���������悤�ŁA�����������܂��B
���̃V�X�e���̍ŐV�́A������ł������������܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1206700
�����ł��A���ŋ߁A�T�v���Љ�Ă��܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1348148
EKIO�ł́A�O���[�v�x���i�^�C���A���C�������g�����j�� 0.1�~���b�ȉ��̐��x�Őݒ�ł��܂��̂ŁA����A��C���̔g�`����Ń^�C���A���C�������g�ɂ����킵�ĉ������B���̃^�C���A���C�������g�����ɂ��ẮA�����ŗv�Ă��܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1098097
�����ԍ��F24973400
![]() 2�_
2�_
moto888����
���}���`�`�����l���A����Ƃ��܂������܂����B
���߂łƂ��������܂��A���ꂩ�炪�{�Ԃł��ˁB
�����ԍ��F24973748�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
moto888����
������x�̖ڏ���������܂�����A���S�ʂ�����APC�̓I�[�f�B�I�Đ��i�Đ��\�t�g�{EKIO�j��p�Ƃ����悤�A�����߂��܂��B
���̏ꍇ�A�u�I�[�f�B�I�Đ��v��p�ɁA���Ȃ�Â�����PC�Q��i���S�t�@�����X�Ŗ����j���g���Ă��܂��BPC�Ƃ��Ă̐��\�͒��Ȃ��̂ł����AJRiver MC �� EKIO ���ғ��������ŁA���\��̖������������Ƃ͈�x������܂���B�ʏ�� Windows 11 Pro 64 bit �ŁA�L��Home LAN �ŃC���^�[�l�b�g�ɂ͏펞�ڑ����Ă���܂��B
PC�̃X�y�b�N�Ȃǂ́A�����̃X���b�h�������������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-12#post-458361
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1206700
EKIO��JRiver MC �̉ғ��ɂ́A���ɗD��x�Ȃǎw�肵�Ă���܂��A���̖�������܂���B
�����ԍ��F24974062
![]() 1�_
1�_
PC���p�̃}���`�`�����l���I�[�f�B�I�ł́A���S�ʂ��l�������V�X�e���́u�N���v�Ɓu�I���i�V���b�g�_�E���j�v�̃v���Z�X�ɂ����ӂ��K�v�ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-880351
�ꌩ���G�Ɍ����邩������܂��A���͒ʏ�A�V���b�g�_�E�� �V�[�P���X�� 1 ���ȓ��Ŋ������A�N�� (�_��) �V�[�P���X�� 2 ���ȓ��Ŋ������܂��B
�����ԍ��F24974088
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
���Ⴆ�A�����ł悭�g����y�ȂŁA�������ƁA���̕��̓|�C���g�Ȃ��������Ȃ̂����
�Ƃ̂��w�E�Ղ��Ă���܂����B
�{���A�t���I�[�P�X�g�������Ɋւ��鎄�̏Љ�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1311722
�������ɂȂ�ꂽ�C�M���X�̕�����PM�A��������A�Q�Ԗڂ̉����G
Schubert: "Rosamunde", Kurt Masur and Leipzig Gewandhaus Orchestra (412 432-2 Philips)
�ɂ��āA�u�������Ƃ��̒��ړ_�v�ɂ��Ă̎��̋L�ځE������M�d�ŁA���ɎQ�l�ɂȂ�܂��A�Ƃ̎ӎ������������܂����B
���̓��e�V���[�Y�S�P�W��ŏЉ���S�����ɂ��āu�������v���ڍׂɏ������Ƃ͂ł��܂���ł������A��L�̂悤�Ɂu�������v�Ɓu���ڗv�f�v���w�E�����������������܂��B
���ꂩ��A�u���܂���H�v�̊��͐@���܂��A�uSony Super Audio CD�v�̑S�g���b�N�����L���ė~�����A�Ƃ̗v�]�������͂��Ă���܂��B
����́A�S�g���b�N�̐��䕪�͂� MsuicScope���͌��ʂ��A�����ŏЉ�܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1341056
��̋��ٓI�ȍ�����e�X�g�E�`�F�b�N�p�g���b�N�i�g���b�N�Q�O�j�ɂ��ẮA���̓��e�œ��ʂɎ��グ�܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1316155
���̗D����́i�I�j�uSony Super Audio CD�v�́A���{�݂̂Ń����[�X����A�C�O�ł͒��Âł�����͂قڕs�\�ł��̂ŁA���v�]�̕��ɂ͌l���p����őΉ����Ă���܂��B���C�i�[�m�[�c�����q�͓��{��I�����[�ł��̂ŁA�����S�ĉp�������qPDF���쐬���Ă��m�点���Ă���܂��B���̎��̖|��ɂ��p�����q�́A��̓��e�ɂ��Y�t���Ă���܂��̂ŁA��������������ł����炲���������B
�����ԍ��F24974770
![]() 0�_
0�_
�F����A
�uSony Super Audio CD�v���u�\�j�[�@�X�[�p�[�I�[�f�B�I�`�F�b�NCD�v�́A���������{�ꃉ�C�i�[�m�[�c�����q��PDF���܂߂āA��������������ł�����A���m�点�������B
�����ԍ��F24974796
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@���������͂ƃJ�e�S�������ł��ˁB
�@���������ā@�����������Ă܂���B
�@��r�����̓�����A�b�v���Ă���̂Ł@���̎�̌��l�^�ȂɊւ��Ă�
�E���ɒ��ڂ��ĕ����̂��ϓ_�����m�ł��邱��
�E���u�A���ɂ���Ċϓ_�̍����o�₷������
��30�b�ȓ��Ō�����������
�@���@�����Ɣ]���L���������Ȃ�����
��Youtube�ō폜����Ȃ�����
���^�������������ǂ�����
�@���@�^���������̂��ϓ_�Ƃ��Ă͗L��
�E���y���͂���܂���Ȃ�
����x���߂���A�ȒP�ɓ���ς��Ȃ�����
�@���Ă��ƂɋC���g���Ă��܂��B
�@���ɁA�Z�������͕K�{���ڂ��Ǝv���Ă��܂��B
�@�����Ƃ��Ắ@���J���Ă��r����̐��\�`���S�{�́A�^�����ā@���C�u�����I�ɕۑ����Ă��ā@�Â����̂Ɣ�r���Ă���̂Ł@�ǂꂾ���ǂ������������Ă��ȒP�ɕς����Ȃ��̂Ł@���J���Ă���悤�ȕ��������ɂȂ��Ă��܂��B
�@���������A�lj����N�G�X�g���@���y�����R�����Ƃ������܂����A�����̌����̂��߂ɂ���Ă����Ł@���܂�ς������͂Ȃ��ł��B�i�Ƃ������A���ƂȂ��Ă͕ς����Ȃ��j
�����ԍ��F24974859
![]() 2�_
2�_
BOWS����
���v���Ԃ�ł������܂��B���̌����A�S�����������ӂł��B
�����A���ʁA
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1310404
�ȍ~�̘A�ړ��e�ŏЉ���L�����u�I�[�f�B�I �T���v���[�����v�̂قƂ�ǑS�ẮA����2019�N�̂V�����Ƀ}���`�`�����l���I�[�f�B�I�\�z������ NS-1000 �����ɒ��肷��ȑO��������������C�u�����ɕێ����A�u�T���v���[ �v���C���X�g�v�Ƃ��ď�p�������Ă��鉹���ł��B
���[Part-00 Introduction] ���e�ɂ��������悤�ɁA�V�X�e���J���̊e�X�e�b�v�̎�ϓI (�ꍇ�ɂ���Ă͋q�ϓI) �]���ƌ��̂��߂ɁA�D�ꂽ�^���i���̂��܂��܂ȉ��y�g���b�N�ō\�������u�I�[�f�B�I �T���v���[ �v���C���X�g�v����Ɉێ������p���邱�Ƃ͔��ɏd�v�ł���ƍl���Ă���܂��B
step-by-step �ŃV�X�e���\�z��i�߂�ɂ������āA���Ձ^�s�ς́u�I�[�f�B�I �T���v���[ �v���C���X�g�v���g���āA�X�e�b�v���Ɏ�ϓI�ȕ]������ɍs�������Ƃ͑吳���ł������Əq�����Ă���܂��B
�����ԍ��F24975207
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
����̘A�ړ��e�ŏЉ���u�I�[�f�B�I �T���v���[���y�����W�v�́A�Љ���J�e�S���[�i�W�������j�����ɕ��ׂ�ƓY�t�̒ʂ�̃v���C���X�g�ɂȂ�܂��B
�S�U�O�ȂŁA���T�C�Y�͖� 7.5 GB �ł��B�@�������v�]������A�S�Ă̔k���������A�܂Ƃ߂ċ��L�����Ă����������Ƃ��\�ł��B
�����ԍ��F24975227
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
����Ă��肪�Ƃ��������܂��A������ƕʌ�
�V�X�e���ł�������������
�EST ��T925��NS1000�̉��ɒu���Ă���̂͂Ȃ�
�ETW��6-8.8kHz�̋����Đ��Ȃ̂͂Ȃ�
ST�͌�����NS1000�̏�ɒu�������Ȃ������A��r�������㉺�����������Ƃ��A
TW�ш�ɂ��Ă�T925�̕����ш�I�ɔ��������ATW�͋����Ȃ��Ă��܂���
�̂ł��傤���H
�����ԍ��F24975445
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
�����ŁA���ɏڂ������L���Ă��܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-370571
�������A���Q�l�܂ŁB
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1033673
�����ԍ��F24975512
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
���ETW��6-8.8kHz�̋����Đ��Ȃ̂͂Ȃ�
Be-TW�̍Đ�����́AEKIO�ł͎w�肵�Ă���܂���B�i��q�� 25 kHz �ɂ�����n�C�J�b�g -48 dB/Oct �͎w�肵�Ă��܂��B�j
Yamaha Be-TW JA-0513 �i3 cm�j�́ABe-SQ JA-0801 �i8 cm�j�Ɠ��l�ɔ��ɗD�ꂽ Be-�h�[���ł����A 14 kHz �����ł� 20 kHz �ɂ����ă��X�|���X���ቺ���܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-837485
����́A���� mikessi ������ϑ����w�E����Ă���Ƃ���ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-696677
�hCareful study of my NS1000 samples showed the tweeter response drops like a stone beyond ~15kHz,�h
����A�D����̂� Fostex T925A �́A40 kHz �܂Ńt���b�g�ł��B�i�l�Ԃ́A25 kHz �ȏ�͂قƂ�ǒ����܂��B�j
���� ST �Q�C���̏_��Ȓ����@�\�ɂ��ẮA�ŋ߂̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1332948
����������ǂ�ł݂ĉ������B�u���E�U�̓��{���ł��A�������������������Ƃ����������������邱�ƂƎv���܂��B
�����ł́A�N��ˑ��� 7 kHz�` 20 kHz �ɂ����钮�͂̒ቺ�X���Ƃ��̕�ɂ��Ă�����Ă��܂��B
�ȑO�ɂ������܂������A 25 kHz �� -48 dB/Oct �̃n�C�J�b�g�t�B���^�[��ݒ肵�Ă��鍪���Ɨ��R�́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1189326
�������������B
�����ԍ��F24975547
![]() 0�_
0�_
�����ł��B
�������ł́A�N��ˑ��� 7 kHz�` 20 kHz �ɂ����钮�͂̒ቺ�X���Ƃ��̕�ɂ��Ă�����Ă��܂��B
�������́A
�u�����ł́A�N��ˑ��� 7 kHz�` 20 kHz �ɂ����钮�͂̒ቺ�X���Ƃ��̕�ɂ��Ă��G��Ă��܂��B�v
���炵�܂����B
�����ԍ��F24975551
![]() 0�_
0�_
�F����A
���� ASR Forum �ɂ�����u�}���`�`�����l���I�[�f�B�I �v���W�F�N�g�v�X���b�h�S�̂ɂ��Ẵn�C�p�[�����N�ڎ����A���L�̂Q�ӏ��ɂ���܂��̂ŁA�����p�������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-961964
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hyperlink-index-for-the-specific-thread-on-multichannel-multi-driver-multi-way-multi-amplifier-stereo-project-using-multichannel-dac.27831/post-962823
�����ԍ��F24975554
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
���݂� Fq���X�|���X�́A�Y�t�}�̒ʂ�ł����A �uTW �� 6 kHz - 8.8 kHz�v�Ƃ����̂́A�ǂ��ł����ɂȂ��܂������H
�����������̂悤�ɋ��L���Ă���ӏ�������A��������K�v������܂��̂ŁB�B�B
�����ԍ��F24975605
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�ڍׂȂ��������肪�Ƃ��������܂�
�� �uTW �� 6 kHz - 8.8 kHz�v�Ƃ����̂́A�ǂ��ł����ɂȂ��܂������H
TW��ST�̑ш悪����Ă���F�����Ȃ��������߂ł�
�E�`��6.3k-9.5kHz�̋��ш�Ŏg���Ă���Tw������̂œ��l����
�����ԍ��F24977550
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
�����ł��B
�����Ȃ�ł��B�@Be-TW �́A6000 Hz �ȏ�ʼn̂��Ă���A ST �́A3��F�ƕی�� 10��F����ł��̂ŁA�P�^�i1/3 + 1/10) �� 2.3��F�@�̃n�C�p�X�i���[�J�b�g�j�ŁA�� 8800 Hz �ȏ�ʼn̂��Ă܂��B�܂�A8800 Hz �ȏ�ł́ABe-TW�� ST ���ꏏ�ɉ̂��Ă��܂��B
�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1033673
�ŁATW�����AST�����ATW+ST�A �̐M���Ƌ�C���������ɑ��肵�Ă���ʂ�ł��i�Y�t�̑���}�j�B
���́iTW��ST���ꏏ�ɉ̂��Ă���I�j�_���AST�̕����I�z�u�Ɩ��ڂɊւ���Ă��܂��B
����Ȕz�u���̗p����l�͈�ʓI�ɂ͌����܂��AASR Forum �̏�A�ŁA���Ɠ��l�� TW��ST�����Ȃ����Ė炵�Ă���l�����l�̔z�u�iST��TW�ŁAWO��SQ���㉺���狲�ށI�j��������āA�u�ځi���H�j����̑f���炵���I�v�ƒm�点�Ă���܂����B�����ɂ悵������A�@�����A��x�����Ă݂ĉ������B
���Ȃ݂ɁA���ɒu���Ă���ST�͏��������グ�āA���X�j���O�|�W�V�����̃\�t�@�[�ɍ����Ă��鎄�̊�i���j�̕��������Ă��܂��B
�����ԍ��F24977836
![]() 1�_
1�_
�F����A
��� Audio Sampler Tracks �A�ړ��e�ɏ]���āA���́u�I�[�f�B�`�F�b�N�����v�v���C���X�g���X�V���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1356792
�ɏ������Ƃ���A�S�U�O�ȁi�k�I���W�i�������j�����[���� ZIP�t�@�C���i6.5 GB�j���쐬�ς݂ł��B���������������܂�����A���m�点�������B
�����ԍ��F24980106
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�� TW��ST�����Ȃ����Ė炵�Ă���l�����l�̔z�u�iST��TW�ŁAWO��SQ���㉺���狲�ށI�j���������
�Ȃ�ق�
�^�������Ȃ̂ł��傤��
���͍��E�Ȃ̂ŏc�����̈ʒu���x�Ⴂ�ł���
�n�C���x���ɂȂ��Ă���ƌ����Ă���̂���
TW�ł͋ɂ߂ă��j�[�N�ł���
���\�J�\�ł��v�������Ȃ��̂ł�
�����ԍ��F24980322�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
ST���g���Ă���l�́A�ш�I�ɂ́A�����ꏭ�Ȃ���TW�Ɣ���āi�d�Ȃ��āj���܂��̂ŁA�^�������I�Ȍ��ʂ͂��Ȃ茰�������A�ƍl���Ă���܂��B���̂悤�ɁA�㉺�����ł��̂ŁA���Ɣ]�͊ȒP�ɓ����I�Ɋ�����̂�������܂���B
���܂��ꂽ�Ǝv���āA��x�AST�����ɒu���z�u�������Ă݂ĉ������I�i���̐ݒu�̂悤�ɁA���C��SP��������R�Ocm�ȏ㕂���Ă���K�v����ł����B�B�B�j
�����ԍ��F24980540
![]() 1�_
1�_
�F����A
����I�i�N�ԂQ��I�j�Ɏ��{���Ă���S�ẴR�l�N�^�[��IPA�i�C�\�v���s���A���R�[���j�ɂ�銮�S���|���P�O���R�O���̐��V���������ɍs���܂����B
�Ȃɂ���A�ړ_�������̂ŁA���J�ɐ��|����ɂ͂S���Ԃقǂ�����܂����A�N�Q��̎��{���������Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B
������AASR�ŋ��L�����Ƃ���A��������t�H���[�����Ă���܂��B����������������������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1364698
�Ƃ���ɑ������Ƃ�ł��B
�����ԍ��F24990850
![]() 0�_
0�_
2022/11/02 22:27�i1�N�ȏ�O�j
�댯���w��� IPA �ł����B
���̐��̒��A���ɕ��a�ł��Ȃ��B
IPA �Ƃ����� India Pale Ale �ł��傤���B
�܂��A�^�u���C�h���� ASR �ł������������Ă��������B
�����ԍ��F24991806
![]() 0�_
0�_
�Q�`�R���~���x�ŕ��i�쐬�ɕ֗��Ȍ����`�RD�v�����^
���`������� IPA �ł̐�������ꍇ������炵���ł���
���N���l���������G�^�m�[���ɂ���l�����邻���ł�
�Ȃ��A���̊댯���͒��ׂĂ���܂���
�����ԍ��F24992004
![]() 0�_
0�_
���͉��w�^��w�^�������w�@����̐��ƁiPh.D.�j�ł��āA�e��̐���N���[���u�[�X�i�N���[���x���`�j�̏��ۏ����Ȃǂɂ�����IPA�̗��p�ɂ͈��S���@�K���ʂ��܂߂Đ��ʁ��K�n���Ă���܂��B
�����ԍ��F24992077
![]() 1�_
1�_
�Ƒ����킸���ł��z���\�������邩�ł���
�C���t���G���U��R���i�N�]��
�E�B���X������
�j�R�`����g���G���i�l�C���A�[�g�A�t���O�����X�ށj���z���Ƃ����܂�ɁA�E�B���X���]�֖�����蔲���邱�Ƃ�����炵��
�Ғŕ��ʂɍs�����Ƃ��A���������M�܂ł�
�u�����܂�v�ł�����^����ɂ��Ă������ł�����
�����ԍ��F24992106
![]() 0�_
0�_
���Q�l�܂łɁB�B�B�����m��������܂��B�B�B
Audio-Technica �́u�ړ_�N���j�J�v AT-6025 �́A�ɂ߂č����ł����A�����͒P�Ȃ�W�O�`�X�O�� IPA�i�C�\�v���s���A���R�[���j�ł��B�c��̂P�O�`�X�O���́A���ł��B�@�e�ʓI�ɁA���܂�ɂ������ł��̂ŁA���͈����ɍw���ł��� 480 ml �� �P�O�O�� IPA �ŕ�[���܂��B
��ʂɁA���ێ��ɂ�����N���[���x���`�̏��ۏ��łɂ́A�V�O�`�W�O���� IPA�X�v���[���g�p���܂��B�R�O�`�Q�O���̐��͏��ې������ł��B�������AHEPA�t�B���^�[�o�R�ŋz�C�������r�C���Ȃ��畬�����܂��B
���́A���N�ɘj���āA���̂悤��IPA���g�������ɏ]�����Ă܂���܂����B
���̌��́A�����܂őł��~�߂Ƃ������܂��傤�I
�����ԍ��F24992220
![]() 1�_
1�_
�͂��A���肪�Ƃ�
�O�P�D�y�����̃v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד����H�z
��YouT����Ń}���`�A���v�Ƃ͉����ׂĂ݂܂��B
�����ԍ��F24992254
![]() 0�_
0�_
�F����A
���x���x�I�̊��͔ۂ߂܂��� ASR Forum �ɂāA�X�s�[�J�[�̏����������ɂ��ď����ʔ����c�_�Ǝ������s���Ă���A�����T�ώҁ��o���҂Ƃ��ĕ����I�ɎQ�����Ă���܂��B
��������������ł�����A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-1361122
�ȍ~�������������B
�����ԍ��F24992319
![]() 0�_
0�_
�����ƁA�����ł��B
��Audio-Technica �́u�ړ_�N���j�J�v AT-6025 �́A�ɂ߂č����ł����A�����͒P�Ȃ�W�O�`�X�O�� IPA�i�C�\�v���s���A���R�[���j�ł��B�c��̂P�O�`�X�O���́A���ł��B�@�e�ʓI�ɁA���܂�ɂ������ł��̂ŁA���͈����ɍw���ł��� 480 ml �� �P�O�O�� IPA �ŕ�[���܂��B
�������́G
�u�c��̂P�O�`�Q�O���́A���ł��B�v
���炵�܂����B
�����ԍ��F24992325
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����
����l�l�̂��w���^���x���̎����ł����鎄�́u�^�C���A���C�������g��SP�ߓn�����̑���ƒ����v�ɂ��āA�܂��܂��A�����쐬�����e�X�g�M���Q���g���ē�������ƒ�������]�������iYems����A�h�C�c�ݏZ�j���R���^�N�g���Ă����܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1366363
��
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1367026
�ł��B
ASR Forum �ł́A��֗̕��Ȍl�ԘA��PM�V�X�e�����g����̂ŁA���� Yems����Ƃ̑��k�^�x�����J�n���Ă���܂��B
��� PM�V�X�e���ő��k���Ă���̂ŁAASR�ł��A�����ł��A�S�Ă͏Љ�Ă���܂��A���̕��łP�O�l�ڂ̐M�����L�̂���]�ł��B
�܂��A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1364737
�ł́AMarcosCh����A
��Hi Dualazmak, thanks for sharing, someday someone will have to print this valuable thread into a reference book...
�Ƃ̒g��������Ղ��܂����B
������ABOWS����A�����ɂ悵����̂��w���Ƃ��x���������Ă����I�@�ł������܂��B
���炽�߂Ċ��Ӑ\���グ�܂��B
����ɁA������́G
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24859394/?cid=mail_bbs#24980106
�ł��m�点�������́u�I�[�f�B�`�F�b�N�����v�v���C���X�g�ŐV�łɂ��Ă������̕��X����PM�R���^�N�g������A�Ή����ł��B
ZIP�t�@�C�����p�ӂ��܂����̂ŁA�����ɂ悵����ւ� ASR ��PM�ł��A���\���グ�܂��B
�����ԍ��F24994728
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����A�F����
Tim Link ����ɂ��uSP�����������v�Ɋւ���l�X�Ȏ����i���s����j�ł����A���ǂ̂Ƃ���A�����w�E���Ă�������֎��ʂ�����悤�ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-1368460
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-1368493
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-1368734
�R�߂̃����N�ŁA�����A�ēx�A���������悤�ɁA
�P�D�S�Ă�SP���j�b�g�Ԃɂ����� 0.1 msec�@���x�̃^�C���A���C�������g
�Q�DSP���j�b�g�E�L���r�l�b�g�̕����I�z�u�A���ɂ���炪��������
�R�DSP�Q�̔w��ƃ��X�j���O�ʒu�̔w��ɂ�����u�����I�Ƀf�b�h�ȋ�ԁv�̕K�v��
�����肪�A��͂�L���ł��ˁB
�����ԍ��F24995278
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
���j�b�g�z�u�ŏ����ȉ��z�����A
0.1ms���x�̕�ʼn��̟��݂��Ȃ�
�X�e���I�̌����ʂ�ł���
�����ǂ̂Ƃ���A�����w�E���Ă��������
�����Ɏ��ʂ���̂́A���������̂�
�����ƍl�@���������̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24995552�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�@�X�s�[�J�[���݂̏����ł����A�^�C�����C�����g���k�����邱�Ƃɂ�鉼�z�_�����͌����I�ȉ����@���Ǝv���܂��B
�@�ŋ߁A�����^�̃t�������W���g���n�߂ā@���z�ł͂Ȃ��{���̓_�����̉����Ă��܂����A����ω��z�͖{���ɏ��ĂȂ��ȂƎv���͂��߂Ă��܂��B
https://theaterbeat.shop-pro.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=Gr2R-TLCz1U&t=10s
�@�}���`�E�F�C���������Ă���ƕs���͖����ł����A�_�����t�������W���������ƂŁ@�}���`�E�F�C�����Ɓ@�ǂ����Ă�����ɂ�蕽�ʕ����Ɉړ����Ă��銴�����킩���Ă��܂��B
�@�t�������W�ł����Ă��G���N���[�W���̑傫�Ȃ��̂́A����̕��˖ʐς��傫��������A�o�X���t�|�[�g����̘R����ˉ����ō������Ă��銴�������܂��B
�@Youtube�ł́@���j�b�g����30cm�̋ߐڈʒu�Ƀ}�C�N���Z�b�e�B���O�����I���}�C�N�^���Ł@��ԕ\���͕������܂��A��������Ɓ@���Ƃ̍����傫���ł��B
�@7cm�̖��^�̕��ʃt�������W�X�s�[�J�[�Ńo�X���t�|�[�g����̉��R��������A�G���N���[�W���̔�����@�قړ_����
�@���j�b�g�̐K�Ƀf�b�h�}�X�Ԃ�����ŐU�����̂�}��������A����ɐ��x���オ��܂����B
�@�������A7cm���j�b�g�Ȃ�Ł@����a�E�[�t�@�[�̂悤�ȕ��̂悤�Ȓቹ�͂���܂��A1L�̒����^�Ƃ��Ă͋K�i�O�̒ቹ���o�Ă��ā@�T�u�E�[�t�@�[�����ł����Ƃ��g���܂��B
�@�X�s�[�J�[�͖��\�ł͖����̂Ł@�������āA����Ë�����̂��@�g����̑z������ł����A���낢��ʔ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F24997407
![]() 2�_
2�_
BOWS����
�����Ȃ���̂��쌩�A���肪�Ƃ��������܂��B
���́A����̓����C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[�ŁA�����̊J�n���ォ��َ��܂ŁA�_�����i�I�jSP�𒆐S�Ɏ������s���܂����B���ɂ��A�����̒�������SP�������������܂����B
���ʓI�ɁA�������Ɋ����i�Ռ��H�I�j����SP�́A Fyne Audio �� F1-12S �݂̂ł����B������A���ɍ����ł����B�B�B
https://www.fyneaudio.com/product/f1-12s/
��̍ŐV Audio Sampler Playlist�����W�i�U�O�ȁj�� Audio CD�ƃf�[�^DVD �Ŏ��Q���AF1-12S�ɂ��ẮA�Ȃ�Ǝ������̂��߂Ɂi���̗���҂�������ɂ�������炸�j�P���Ԃقǂ��[�ĂĂ���āA�f�[�^DVD���R�s�[����PC�o�R�ŁA���̂̒m��Ȃ�������DAC�ƒ������p���[�A���v�ŁA�������莎�������Ă��炢�܂����B�f�B�|���[�́AAXISS�Ђł��B
http://www.axiss.co.jp/
���̌��݂̃Z�b�g�A�b�v�𗽉킷��i�Ɗ������j������^���Ă��ꂽ�̂́A���� F1-12S �����ł����B
F1-12S �́A���̎�̍����@�Ƃ��Ă͊��x�i�\���j�����ɍ�����96 dB (2.83 Volt @ 1m, nominal impedance 8 Ohm)����܂��̂ŁA�ƒ�ŁA�莝���̃A���v�Q�ŁA�炷�̂ɂ��K���Ă���Ɗ����Ă��܂��B��ʓI�ȃv�����C���A���v��p���[�A���v�ł��y�X�Ƌ쓮�ł��܂���A�Ƌ��i���蕶��H�j�ł����B
�ȑO���b�����������A�ł����AAccuphase�Ђ͐V�����Љ��̎������� F1-12 �����܂������A�߁X�A F12-12S �֍X�V���邻���ł��BF1-12S�ł́A���ቹ�i 20 Hz - 50 Hz�j�̉ߓn�������傢�ɉ��P����Ă���A�Ƃ̂��Ƃł����B
�����d�l�Ƃ��ē����l�b�g���[�N���o�C�p�X����SP�o�C���f�B���O�|�X�g�̑��݉\�����p���{�Ђ֖₢���킹�Ă���܂��B��ɂ���āA�Q��̃X�e���I�A���v�A�܂��͂S��̃��m�����A���v�ŁA�}���`�`�����l�������쓮�������A�Ƃ����킯�ł��B
�ł��A���܂�ɂ������Ȃ̂ŁA���̂Ƃ���A�u���v���W�F�N�g�v�̈���o�܂���B
���̂悤�ȐV�����u���v��^���Ă����_�ł́ATokyo International Audio Show ���L�Ӌ`�ł����B
F1-12S �́A���ቹ�i40 Hz�ȉ��j�́A��ʂ̂R�U�O�x���˃|�[�g����̔��������C���ɂȂ�悤�ł����A���炭�T�OHz�ȏ�́A�����g�̈�܂œ_�����ƍl���Ă��悳�����Ȏd�l�ŁA���I�ɂ́A���݂̎��̃V�X�e���𗽉킈�������Ȋ�����^���Ă���܂����B�������A���̃��X�j���O���łǂ���A�ǂ��������邩�A�͉ۑ�ł����B
���t�������W�ł����Ă��G���N���[�W���̑傫�Ȃ��̂́A����̕��˖ʐς��傫��������A�o�X���t�|�[�g����̘R����ˉ����ō������Ă��銴�������܂��B
������f���ƁAF1-12S �̂��̓��قȊO�`�O�ςɂ��[���ł��܂��B�ǂ�ȉ����ł��A�����ʂł��A�剹�ʂł��ASP �����S�ɏ����Ă��܂����A�����ʒu�����E�A�O��A�㉺��1m���x�ړ����Ă��A�X�e���I�C���[�W�������܂���B�i�����ʒu�́A�قڂP�ӂTm�̐��O�p�`�̒��_�ł����B�j�@���ቹ�`�ቹ�@�̉ߓn�������A���̎��ɂ͑f���炵���������܂����B
F1-12S ��͕�ł���悤�ȑ���a�œ_������ DIY SP�쐬�͂��蓾�邾�낤���H�@�Ƃ̖����c��܂��Ă���܂��B
����قǑf���炵���̌��ł����B�i���Ȃ��Ƃ��A���ɂƂ��ẮB�B�B�j
�����ԍ��F24997873
![]() 0�_
0�_
dualazmak����ABOWS����
������̓����C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[��
�q�}�������̂łՂ���ƍs������A
���Ԃ��ԈႦ���悤�Œ��璆
�������āA�X�}�z�Ō��J���Ԃ�T�����̂ł���
���O�o�^�y�[�W�ɔ����A�悭�킩��Ȃ�
������������Ă�ƁA�x���`�̐l����Ăɑ���o��
�����Ƃ����Ԃɒ��ւ̗�ɁA
2�Ԗڂ�3�Ԗڂ̓z�e�������3���ԊF�Ώ܂̉�b��������
������ł̓Y�����݂����Ƃ��A���߂Ă���
�}�j�A����Ȃ�1�Ԃ̐l�́A������̒����ɋ����A
������ƊԈ�����Ⴝ�����A�����܂�������s�ސT�̂悤��
���X�A�o��ɏo��ꂸ�ł����B
�}�j�A�̃K�b�c�ɋC��t����ł��ˁB
��F1-12S ��
���^F1-12�́A�z�[���ƃR�[���̂Ȃ��ڂ�
�z�[���̌������Â��̂��A750Hz�ł͈������肷���̂悤�ȋC��
���܂����A���悪������Ǝキ�āA
�p���ۂ܂����悤�ȁA�����n��������Ȃ������Ă��܂����B
��r��B&W��TAD�������̂ŁA���܂��܁A�����������̂���
�V�^�́A�ǂ�Ȃ̂������Ă݂����ł��B
�����܂�ɂ������Ȃ̂�
�~���Ȃ̂��A�ǂ������������ŁA���K���o���������Ȃ�܂���
�y�A600���~���炢��SP�Ȃ�����Ɋ����Ă��邩������܂���B
���o�X���t�|�[�g����̘R����ˉ����ō������Ă��銴����
�_�N�g�̘R��́A���������Ȃ��ł���
�t�������W�́A�_�N�g��w�ʂɂ���
�K�X�����Ɗ����ASW�g����������������
�}���`�Ȃ�E�[�t�@�[��150Hz�ȉ������g�p�ɂ���ƒ��ቹ�R��͌��邵
�_�N�g��10Hz���炢�̃`���[�j���O�ɂ���
�����ꂷ��ŁA�z���ޕt�߂�������o��
�_�N�g�̓K�X�����A���܂�~���炸20Hz�܂Ńt���b�g�ɏo�Ă������
������Ă��܂��ƁA�R��͋C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂���B
�����ԍ��F24999575
![]() 1�_
1�_
������̓����C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���[
���́Aweb���O�o�^�i�\��j�J�n�̓��i�X��12���j�ɁA���U�œ���o�^���Ă��肵�܂����B
�w����i�X��12���j�̂O�O�F�O�O����o�^���悤�Ƃ�����A�T�C�g���I�[�v�����Ă��Ȃ�!�@���܂ʼn��x���g���C�������_���I
�O�X�F�O�O�ɂȂ��Ď����ǁ�LUXMAN �֓d�b������A�u�����A�����10������I�[�v�����܂���B�v�@�Ƃ́A�̂ȕԓ��ŁA�v�킸�A�u����Ȃ�A�Ȃ�10�������t�J�n�Ə����Ȃ��̂ł����H�v�A�Ƃ��Ȃ苭���R�c���܂����B
����ŁA�\��J�n�̂X��10���̂P�O�F�O�O�ɁA�\��o�^���܂����I���݂����Ȃ̂ŁA�����P�O���Q�W�����j���ɗ\��A�قڏI�����낤�낵�Ă܂����B
�����ԍ��F24999704
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����
����ȓ����f�U�C���̂R-way �A�N�e�B�u�i���̓A���v�R��g���jSP�A�ǂ��v���܂����H�@
https://www.me-geithain.de/en/rl-901k2.html
�i���炭�j���ŁA�E�[�t�@�[�T�C�Y�� 400 mm cone�A�~�b�h�����W�� 125 mm cone�A�c�C�[�^�[�� 25 mm dome �ł��B
550 x 500 x 430 mm �ŏd�ʂ� 48 kg ������܂��B
�f�U�C���R���Z�v�g�I�ɂ́A����Ȃ��́i�A���v�͑g�ݍ��܂��R�y�ASP�[�q�ŊO���A���v�Ń}���`�쓮�j������ł��Ȃ����낤���A�Ǝv�Ă��Ă���܂����B
�����ԍ��F25005684
![]() 0�_
0�_
�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/speaker-stands-for-geithain-rl-901k.34206/post-1364575
�ƁA�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/speaker-stands-for-geithain-rl-901k.34206/post-1364808
�Ɏ��ۂɓ��������l�̊��z������܂��B
�����ԍ��F25005772
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@F1-12S �́@�������������Ƃ������̂łȂ�Ƃ��ł��B
���^���m�C�̓������j�b�g���u���b�V���A�b�v�������̂Ȃ̂Ŋ��҂͎��Ă܂����A���������@�U���O��ʒu���E�[�t�@�[�̃R�[���Ƃ���ăN���X�I�[�o�[������ňڑ���肪�o��_�Ɓ@�R�[�����z�[���̉����ƃE�F�[�u�K�C�h�����˂�̂Ł@�����������Đv��������Ȃ̂ŕȂ��o�������Ȃ��Ǝv���܂����B�������A�ȉ~�`�̃R�[���ɂ���Ηǂ����Ȃ����@�ł��������B
����Ɓ@�J�b�g�I�t 30cm���a��750Hz�͂�����ƒႷ�����Ȃ��@
>����ȓ����f�U�C���̂R-way �A�N�e�B�u�i���̓A���v�R��g���jSP�A�ǂ��v���܂����H�@
geithain�̃X�s�[�J�[�́@�G�����ʼn����܂������A�X�^�W�I������nj����ŃR���V���}�[�p�̐��i�͒m��܂���ł����B
�w�ʂɁ@XLR�̒[�q�Ɠd���C�����b�g�A�d���{�^���������ĂȂ��Ē�������ӏ��������Ƃ������ƂƁ@�X�N�G�A�Ȍ`��@�X�^�W�I������ǂ̕ǂɖ��ߍ��ނ��Ƃ��l�����Ă���낤�ȂƎv���܂����B
�@���j�b�g���̂�3way�œ����ɂ���̂Ȃ�@�����Ȃ邾�낤�ȂƂ����`��ł��ˁB��̂ɃW�F���Z����3way�����͂������悤��
�@�����\����X�s�[�J�[�̍\���̏ڍׂȏ�����̂őz��������܂����@�C���t�����_�Ƃ��Ă�
�E�E�[�t�@�[�̌��a�ɑ��ăG���N���[�W���̓��e�ʂ��������B�����ɃA���v�ނ������Ă��邽�߁A����ɏ������B
�@�� �w���ɕ����Ȃ��悤�ȋ��x�ŏd�����E�[�t�@�[�U�����낤��
�@�@�@�d�����U�����m���ɓ��������߂Ɂ@MFB�������ĐU���̓�������m���ăt�B�[�h�o�b�N���Ă�\������
�E�N���X�I�[�o�[ 550Hz
�@�� �E�[�t�@�[�̐U�����d���ꍇ�A�����ȏオ�������̂Ł@���̂��炢�Ő��������ǂ��Ƃ������f���H
�E125mm�R�[���^�~�b�h�����W
�� �N���X�I�[�o�[ 550Hz�Ŏg�����߂ɂ́A�w����������K�v������̂Ńo�b�N�`�����o�[��������x�̗e�ʂ��K�v�����A�~�b�h�����W�̗��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂������Ȃ��B
���������ʐς̂���~�b�h�����W�o�b�t���Ȃ̂Ł@�E�[�t�@�[�̑O�ʕ��˂��j�Q����Ă��Ęc����������
�E�A���v�@�w�ʂɑ傫�ȕ��M�킪�L��A�d�����Ƃ���@���j�A�d���H�@���@���j�A�A���v�H
�@�@���j�A�A���v�̏ꍇ�A���^�ł�����̂ŕ��M���v�H
�@�Ƃ��v���܂��B
�@�R�[���^�����Ƃ��Ắ@JBL LE14C�@��5cm�R�[���ł������A�N���X�I�[�o�[��2KHz�Ŋy��p�̂悤�ɃE�[�t�@�[���������܂ŕ����U�����Ȃ�����v�ł����̂Ł@���オ�Ⴄ�����ł��ˁB
�@���������ł���\���ł����A�����͌������ł��傤�ˁB
�@30�`40cm�E�[�t�@�[�̓�������
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=141674746
�@����̂悤�Ɍy�ʃR�[����PA�p�������Ǝv���܂��B
�@�G���N���[�W����e�ʂ���ʊJ���Ł@LF���ʓr�K�v�̂悤��
�@�E�[�t�@�[�̃Z���^�[�L���b�v���폜���ā@�R�[���^�~�b�h�����W���p�������̂��@�o�b�N�`�����o���ǂ����邩�Ƃ��������Ɓ@���������R�[���^�~�b�h�����W���ă��m����Ő��O�Ł@MarkAudio�̂悤�ȃt�������W�ɂȂ�Ǝv���܂����A�E�[�t�@�[�Ƃ̃}�b�`���O������B
�@���Ԃ�@geithain�������������Ĉ����������Ɏv���܂��B
�@�l�́A�}���`�E�F�C�̓��j�b�g�Ԉʑ���N���X�I�[�o�[���X���l������K�v������A�����b�g�ƃf�����b�g�̗��Ƃ��������ɂ߂���������̂ƁA����a�E�[�t�@�[�̏d�����U���̏������x��Ĕ������������������čD������Ȃ��̂Ł@����������x�ڂ��Ԃ��ā@�������t�������W�ł�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�O�q�� Theater Beat�����낢�낢�����Ă��ā@�����ɂ���Ȃ�t�������W�P�{�@�܂��́@�t�������W�{TW�����肪�œK������Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F25006592
![]() 2�_
2�_
BOWS����
�����̂悤�ɂ��쌩�Ղ��A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
F1-12S�ɂ��ẮA��͂�\�ł���Ή䂪�Ƃ̊��Ō��݂̃V�X�e���Ɣ�r�����ł��铹��T��܂��B���̏ꍇ�́A�܂��͓����̃l�b�g���[�N��M�����āA�V���O��DAC�i�K��OPPO SONICA DAC ���������ł����A�������DAC8PRO���g����j�ƃo�C�A���v�ŋ쓮���A�㗬PC����EKIO��DSP(XO/EQ)�R���g���[�������s���邱�Ƃ����݂܂��B
Geithain RL-901 K2 �ւ̂����@�A�����������܂��B
���́i�����j�G
�����������ʐς̂���~�b�h�����W�o�b�t���Ȃ̂Ł@�E�[�t�@�[�̑O�ʕ��˂��j�Q����Ă��Ęc����������
�����
�����j�A�A���v�̏ꍇ�A���^�ł�����̂ŕ��M���v�H
������ɂ͋C�t���Ă���܂������A���̑��̂��w�E�A�����@�܂ł͎����Ă���܂���ł����̂ŁA���ӂł��B���炭 ASR Forum �ł̃��[�U�[�⑪�苤�L�߂����ł��B
���āA����̌ߌ�A�V��ɂ��b�܂ꊣ�������S�n�悢���J����Ԃ���эō��̃V�X�e����ԂŁu���y�v�����\���F�X�l���Ă���܂����B�����͂����ɏЉ�Ă���Ƃ���ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1206700
����A�����C���^�[�i�V���i���I�[�f�B�I�V���E�Ŏ����������X�̒�������SP�������v���o���Ȃ���A�u�䂪�Ƃ̊��ł��̃��x���܂ŒB���ł��Ă���Ȃ�A���̊��ŁA����ȏ�̉��P��]�ނ͎̂ד��œD�����ȁH�v�Ƃ������G���������Ă���܂��B
��͂�A�����Ȃ�ADIY�I�ɃE�[�t�@�[������V�����Ĕ�r���邠���肵���Ȃ������A����ł����݂̃A���v�����̗\�z�O�ɗD�ꂽ�ߓn�����ƃ~�b�h�����W�ւ̃X���[�Y�Ȍq����𗽉킷��ɂ́A���Ȃ�T�d��DIY�ƒ������s�����ȁA�Ǝv�������点�Ă���܂��B
�����ԍ��F25007244
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����
Andrew Jones ���̐v�ďC�ɂ�铯���r�o�Ƃ��� MOFi SoucePoint 10 ����������܂����B
https://www.mofielectronics.com/sourcepoint10
�y�A�� US$3,699.00 �������ł��B
�P�O�C���`�i25.4 cm�j�R�[���E�[�t�@�[�ƂP�D�Q�T�C���`�i3.2 cm�j�h�[���c�C�[�^�[�̃f���A�������̐V�v�������j�b�g�ŁABOWS���w�E�̂悤�Ɂi�I�j�A���͗~���炸�� 42 Hz�܂ŁA�N���X�I�[�o�[�� 1.6 kHz �� 30 kHz �܂ŃJ�o�[���Ă��܂��B
����Ƀz�[���ł͂Ȃ��A�h�[�����̗p���Ă���_�ŁA���I�ɂ͍D��ۂł��B�@8���i6.2�� minimum)�ŁA�\���� 91 dB/2.83V/1m ����܂��B
�����ɂ悵����̂��w�E�̂悤�ɁA�����I�ɃE�[�t�@�[�R�[���������߂̋�C�����Ƃ��Ĕw�ʂɂQ�{�̒ʋC���i�o�X���t�Ƃ͌��킸��vented����C�����ƌ����Ă���j��݂��Ă��܂��B
�����ɁA�}�j���A��������܂��B
https://static1.squarespace.com/static/593ed9b6d2b857c8eaf78246/t/636a8dc2e5db343df39fea78/1667927490966/Mofi_SourcePoint10+%283%29.pdf
�����ɁAAndrew Johns �ɂ��z���C�g�y�[�p�[�i�v�T�O���j������܂��B
https://static1.squarespace.com/static/593ed9b6d2b857c8eaf78246/t/636ce839a3768c026fad290a/1668081722745/SourcePoint+10+White+Paper+11-10-22.pdf
�Ȃ��A������A�a�n�v�r����Ƃ����ɂ悵������SP�ɑ��Ďw�E���ꂽ�u�����Ƃ����v����������d�l�ł���悤�Ȉ�ۂ��Ă���܂��B 42 Hz �ȉ��́A�K�ȃT�u�E�[�t�@�[�ɔC����Ƃ����������B�B�B
�r�o�\�ʃo�b�t���̌`��͌��ʓI�ɉ�܂�ጸ����A�ƃz���C�g�y�[�p�[�ł�搂��Ă��܂��B
�������ڂ��Ă���܂��B
�����ԍ��F25012665
![]() 0�_
0�_
ASR Forum �ł́A���̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/andrew-jones-mofi-speakers.39018/
�Řb��ɂȂ��Ă���܂��B
�����ԍ��F25012672
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
>MOFi SoucePoint 10
�@�������茩�܂����B
�@FYNEAUDIO�������ł����A�����̃E�[�t�@�[���E�F�[�u�K�C�h�Ƃ��Ďg���̂����s��݂����ł��ˁB
�@FYNEAUDIO�̃z�[���^�̃c�B�[�^�[�Ɣ�ׂ�WF��TW�̐U���O��ʒu���߂��Ƃ����Ӗ��ł́A�����₷���ł��ˁB
�@�h�[���^TW�Ƃ̓����Ƃ����̂́@��̂���悭����\����40�N�قǑO��FOSTEX���X�s���A�E�g�����G���W�j�A���ݗ��������C�[�l��DX200,DX160���Ă̂��@�قƂ�Ǔ����\���ł��B
https://shinchanaudiomusic.blog.fc2.com/blog-entry-1264.html
�@�Ȃ̂Ō͂�Ă���\���Ȃ�ň��S���͂���܂����A�C�}�C�`����I�ȃA�v���[�`������̂��Z�p������Ă��悭�킩��܂���ł����B
�@�_�����̓����Ƃ����_�ł́@GENELEC�� The Ones�V���[�Y�̓����X�^�W�I���j�^�[����Ԑi��ł���悤�Ɏv���܂��B
�@https://www.genelec.jp/studio-monitors/sam-coaxial-studio-monitors/
�@�t�����g�o�b�t���̒[�܂Ōp���ڂȂ��Ȗʍ\�����ꂽ���`�Ƃ����A�E�[�t�@�[��2�㉺�ɔz�u�������z�����\���ƌ����A�^�C�����C�����g���܂߂Đ���\�ȃ`�����f�o�ƃV�[�����X�Ń��j�b�g�Ƀ}�b�`���O�����p���[�A���v��������Ă��āA�`���[�j���O��ۏ�����Ԃŏo�����ł���_�A�}�C�N�𗧂Ăă��[���`���[�j���O��GLM�Ƃ����\�t�g�E�F�A���������Ă���_���܂߂ā@�ł��i�����V�X�e�����Ǝv���܂��B
�@�l�i�͒���܂����A�A���v�܂߂����i�Ȃ��CP�͗ǂ��Ǝv���܂��B
�@�����Ƃ��A�������ꂽ�V�X�e���Ȃ̂Ŏ����ł�����Ƃ���͖��������Ł@�I�[�f�B�I���y�ɂ͌����Ȃ��ł���
�����ԍ��F25012943
![]() 0�_
0�_
2022/11/17 04:43�i1�N�ȏ�O�j
Incredible Demo of Andrew Jones New Mofi Speaker - SourcePoint 10:
https://www.youtube.com/watch?v=CU67rJ33eZw
Andrew Jones Proves Anything is Possible! New Speakers - The Sourcepoint 10:
https://www.youtube.com/watch?v=C87j8YN_zGc
Why Andrew Jones left Elac and his New Speakers!:
https://www.youtube.com/watch?v=gRaijWgy59w
mofi loudspeakers:
https://www.youtube.com/results?search_query=mofi+loudspeakers
���ꂮ�炢�͒m���Ă����Ȃ��ƂˁB�܂��A���̐��i�ɂ͓��ʂȂ��͉̂����Ȃ������ł����B
�����Ƃ��ATAS, Stereophile ���Ȃǂ̕Ď��łׂ͂��J�߂����ł��傤����ǂ��B
�����ԍ��F25013101
![]() 0�_
0�_
SoucePoit 10 ��YouTube�r�f�I�́A�������S�Č��Ă���܂����A���������Ƃ��낪���X�����ĐM�p���Ă���܂���B
BOWS����A
���h�[���^TW�Ƃ̓����Ƃ����̂́@��̂���悭����\����40�N�قǑO��FOSTEX���X�s���A�E�g�����G���W�j�A���ݗ��������C�[�l��DX200,DX160���Ă̂��@�قƂ�Ǔ����\���ł��B
����͏����ł����B�������Ƃ��l�����l�������ł��ˁB�������ׂČ��܂��B�Ƃ����Ă��A����͖��������ł��ˁB
GENELEC ���i�ɂ��ẮAASR Forum �ł� GENEELC �V���p�� GENELEC��ӓ|�̕��X�����������܂��̂ŁA��X GENELEC���i�͒��߂Ă���܂����Aairm ���܂߂đ�R�҂ɂ��q�ϓI�ȑ���f�[�^���L�x�ɓ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�����ŁA���\�Ɛ��m�������߂�A��͂�GENELEC����ɂȂ�悤�Ɏv���܂����ADIY�I�ɐG��v�f���Ȃ����ƁA�A���v�����͎��̍D�݂ł͂Ȃ����ƁA�����Ă��̃��b�N�X�̊ϓ_�ʼn䂪�Ƃɂ͍���i���r���O�ɒu���̂ɓ��ӂ�����ꂻ���ɂȂ��I�j�A�Ȃǂ̓�_������܂��B
MOFi �� SoucePoit10 �́A���܂���ʂȍŐV�Z�p���g���Ă��Ȃ��_�ɒ��ڂ��Ă��܂��B�����炭�AELAC����ڐЂ��� Andrew Jones ���A���i����i�y�A��$3,700�j��ݒ肵����ŁA�܂� 42 Hz �ȉ��̓T�u�E�[�t�@�[�ŃJ�o�[����Ɗ�����āA�ނ̒����o����������� SourcePoit10 �ɂȂ����̂ł��傤�B
���i�́i����ȁH�j�V�R���Z�v�g�̓�����A�G�邱�Ƃ��i�قځj�s�\�ȓ����A���v��DSP���܂܂�Ă��Ȃ����Ƃɂ��A�D�������Ă܂��B
������ɂ��Ă��A�e��̑���f�[�^�̕�҂������ƍl���Ă���܂��B
�����ԍ��F25013178
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
>����͏����ł����B�������Ƃ��l�����l�������ł��ˁB�������ׂČ��܂��B�Ƃ����Ă��A����͖��������ł��ˁB
�@���傢�ƒ��ׂ܂�����A�߂��R���Z�v�g�ł���Ȃ̂�����܂����B
Tangband W8-2314
�y20cm�|�@�ۍ����y�[�p�[�R�[���R�A�L�V�������j�b�g�z
����
�E25mm tweeter with 8�h woofer coaxial speaker design.
�EUnderhung motor design with neodymium magnet to reach low thd (2nd, 3rd harmonic distortion).
�EBamboo fiber paper cone with durable rubber surround.
�EAluminum / magnesium alloy membrane with back chambers design to perform 800 up to 40khz.
�C���s�[�_���X�F4��
�Đ����g���ш�F38Hz�`40kHz
���́F50/100W
�o�͉������x���F90dB
�Œዤ�U���g���F38Hz
Mms�F23.14g
Vas�F51.27L
�����N���X�I�[�o�[���g���F2.5�`4kHz
�o�b�t���J���a�F��182.6mm
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=169236806
https://mx-spk.shop-pro.jp/?pid=137527402
http://www.tb-speaker.com/products/w8-2314#tab-382
�@�������ɕ��͂�����܂�
https://audioxpress.com/article/test-bench-tang-band-speaker-w8-2314-high-end-coaxial-driver
�@�G�b�W�̌`����o�����炸�������܂��E�F�[�u�K�C�h�̋@�\���l�������v�ɂȂ��Ă���B
�@�U���n���y��Q���Ⴗ�����@VAs 51L�Ə������G���N���[�W���ɉ������߂�v�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�@�����N���X�I�[�o�[��2.5KHz�ƒ��f
�@���������ǂ��������Ƃ�����ۂ����܂����B
�@�c�B�[�^�[�̃O�����K�C�h�ɍD�݂������ꂻ���ł���
>�����ŁA���\�Ɛ��m�������߂�A��͂�GENELEC����ɂȂ�悤�Ɏv���܂����ADIY�I�ɐG��v�f���Ȃ����ƁA�A���v�����͎��̍D�݂ł͂Ȃ����ƁA�����Ă��̃��b�N�X�̊ϓ_�ʼn䂪�Ƃɂ͍���i���r���O�ɒu���̂ɓ��ӂ�����ꂻ���ɂȂ��I�j�A�Ȃǂ̓�_������܂��B
�@�����ł����Adualazmak����ƌ����Ă��������������ƈႤ�l�̓X�s�[�J�[�v�҂��A�ǂ�ȃA���v(�^��ǁ`A���`D��)���ڑ����ڑ�����Ă��@�Ƃ肠���������悤�Ȓ��f�ɑË�����������Ȃ��v�ɗ��Ƃ��������߂���s�̎Ԃ̂悤�ȒP�̃X�s�[�J�[���ADSP�`�A���v�`�P�[�u���`�X�s�[�J�[���j�b�g�̑g�������`���[�j���O���ċɌ��܂Ő��\���グ����p���[�h�X�s�[�J�[�̕������[�V���O�J�[�݂����ōD���ł��ˁB
�@�ȑO�A���̂悤�ȍ\����IK MULTIMEDIA�Ђ́@iLoud MTM �������ʒu�Ƀ}�C�N���Z�b�e�B���O���ĉ����������Ă������蕷�����Ă��炢�A�\���������܂����B
�@�c�O�Ȃ���A�j�A�t�B�[���h���j�^�̂��ߍL���������Əo�͌��E�Ɏ������̂ƁADAC�ƃA���v�̕i�ʂ��l�i�Ȃ�Ł@�f�B�e�[���\�����l�̗v���ɍ���Ȃ������̂ł����A���g���o�����ĕ��i�������X�̃`���[�j���O�{�����牻���邩���Ǝv���܂����B
>MOFi �� SoucePoit10 �́A���܂���ʂȍŐV�Z�p���g���Ă��Ȃ��_�ɒ��ڂ��Ă��܂��B�����炭�AELAC����ڐЂ��� Andrew Jones ���A���i����i�y�A��$3,700�j��ݒ肵����ŁA�܂� 42 Hz �ȉ��̓T�u�E�[�t�@�[�ŃJ�o�[����Ɗ�����āA�ނ̒����o����������� SourcePoit10 �ɂȂ����̂ł��傤�B
�@���̎�̐V�K�Z�p��Ȃ����̗ǂ��ői��������Ă̂͐�`���ɂ����ł��ˁB
�@��≽�̕ϓN���Ȃ����Ǝ��̋����̗ǂ�������n�[�x�X�̃X�s�[�J�[�Ɠ������炢�@�Œ�t�@�����t���Ăق����ł��ˁB
�����ԍ��F25013379
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
��GENELEC�A���b�N�X�̊ϓ_
�������ɓƓ��ł��ˁB
���^�̂��̂́A�ቹ�����Đ����Ă銴��������̂�
���g���̎���@�ɂ͋y�Ȃ���������܂���B
�j�A�t�B�[���h�Ŏg���Ǝ��g�������A
�ʑ��������Ă��āA�����݈͂Ղ��ł��B
�܂�����������AV�ɂ������Ă��āA
13ch�{�T�u�E�\�t�@�[×2�ł́A
��������ቹ�܂ŏo�Ă���_�����̈З͂������܂����B
�����ԍ��F25013380�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
������ȓ����f�U�C���̂R-way �A�N�e�B�u�i���̓A���v�R��g���jSP�A�ǂ��v���܂����H�@
�K�C�U�C���˂��A�C���t���܂���ł����B
RL-901���������܂����A
�����ȓS�ŋ��n���Ƃ��A50�N�O�ł�
�����ƃf�U�C������Ă��ȂƎv��������ǁA
���͂Ȃ��Ȃ��A�s�A�m�Ȃł������A
�O�����h�s�A�m�����̂܂܁A�ǂ�ƒu���Ă���悤��
���A���Ȋ����ł����B
���E���h���ĂȂ����Ȃ̂ɉ������V���[�v
�����Ȃ̂Ō����ڂ͎���������
������l�������Ǝv���܂����B
�����ԍ��F25013442�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
���K�C�U�C���˂��A�C���t���܂���ł����B
��RL-901���������܂����A
�����A�������ꂽ��ł��ˁB����ہA���Ƀs�A�m�̈�ہA�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��B
�����x���Ȃ���A�ǂ��ŕ����ꂽ�̂��A�����ĉ������B�����A��̉����W���g���Ď������Ă݂����I
�h�C�c�̖{�ЂƃR���^�N�g���āA���{�̃f�B�[���[�ɂ��Ă͏�����肵�܂����B
http://esfactory.co.jp/
EASTERN SOUND FACTORY CO., LTD.
205 Shinyoshida-cho, Kohoku-ku Yokohama-shi,
Kanagawa 223-0056
phone.045-548-6592
facsimile.045-548-6593
�֑��ł����AASR �̗�̌l��PM�̑����ŁA�t�@�C�����L�������m�点���Ă���܂��̂ŁA������������� 6 GB �قǂ�ZIP���_�E�����[�h���Ē����Ă݂ĉ������B
�����ԍ��F25013736
![]() 0�_
0�_
BOWS����
���A���肪�Ƃ��������܂��I
��Tangband W8-2314
���y20cm�|�@�ۍ����y�[�p�[�R�[���R�A�L�V�������j�b�g�z
���Đ����g���ш�F38Hz�`40kHz
����ӗ~���������鋻���[�����j�b�g�ł��ˁB20 cm�R�[���ŁA���������܂��i��C������w�ʂɂQ�|�[�g�H�j���� 38 Hz �܂ŋ��U����Ƃ́A������Ƌ����ł��B����XO 2.5 kHz ���A�܂��܂��B�B�B
���� Yamaha Be-Mid �́A500 Hz �` 6000 Hz �i�����{�[�J���̂قƂ�ǑS����j��f���炵�������ŃJ�o�[���Ă���̂ŁA����Ƃ̔�r���ǂ��Ȃ�̂��B�B�B�����Ă݂����U�f�ɋ���܂��B
�^�́u�����R-way�v�ŁA�S�ăR�[���ƃh�[���AXO�� 500 Hz, 6000 Hz �Ȃ�ă��j�b�g�́A�A�A�Ȃ������ł��ˁB
�^�́u�����Q-way�v�ŁAXO�� 500 - 600 Hz ������̃��j�b�g�́A�A�A������Ȃ��������H�H�H
�i�����{�[�J���́A�Ȃ�ׂ��~�b�h�����W�����ŃJ�o�[�������̂ł��B�j
�������� 500 - 600 Hz �܂ʼn����Ă������ȃh�[���ƂȂ�A�x�����E��������ɂȂ肻���ŁA���S�����v�́i�o�b�N�`�����o�[�̊m�ۂ��܂߂āj�n�[�h�����������ł��ˁB
�F�X�����͐s���܂��ABOWS�����˂Ă��炲�w�E�̂悤�ɁA�ǂ��܂łőË����邩�A������SP�I���̊�{�ɂł��邱�Ƃ������ł���悤�ɂȂ����܂��B
�����ԍ��F25013769
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����
Tangband W8-2314
�y20cm�|�@�ۍ����y�[�p�[�R�[���R�A�L�V�������j�b�g�z
�ł����A�����ŏ����ڂ������Ă���܂��B
http://www.tb-speaker.com/products/w8-2314#tab-406
����ȁA���Ȃ�ڍׂȑ��莑��������܂��B
http://www.tb-speaker.com/zh-tw/uploads/editor/files/W8-2134-07%20voice-coil-july-2019_S.pdf
�Ȃ��Ȃ��A�悳�����ł��B
�Y�t�ʐ^�̐Ԙg�������݂�ƁA�c�C�[�^�[�̔w��ɂ́u����Ȃ�H�v�̃o�b�N�`�����o�[������悤�ŁA�N���X�� 800 Hz �t�߂܂ʼn�����ꂻ���ȕ��͋C���B�B�B�B�������A�c�݂Ƃ̌��ˍ����ŁA�ǂ��܂ʼn������邩�́A����Ă݂Ȃ��ƕ�����܂��B
����ŁA�E�[�t�@�[���c�C�[�^�[�i10��F�ی�R���f���T�͊��܂���I�j���A���v�����ŁA�㗬��EKIO��DSP(XO/EQ)���Ď��s���낷��ɂ́A�ʔ��������Ȃƍl���Ă���܂��B�������肵��������āA�Q�y�A�̃o�C���f�B���O�|�X�g�A�����ɂ悵�����̒Z���u��C�����_�N�g�v�w�ʂɂQ�{�i�W���\�j��݂���A���Ȃ�V�ׂ����B�B�B
���� 38 Hz �܂ŋ��U�i�{�����ȁH�j�Ƃ���܂����A�A���v������ 30 Hz ������܂ň�������邩���A�Ƃ��v���܂����A���ꂪ�܂�����Ύ莝���̃T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000 �� 45 Hz ������ŃN���X������Η]�T�\�����낤�ȁA�Ǝv���܂��B
���S�����Q-way�Łi�܂��͍��z�����Ȃ��Łj���s���낵�ėV�ԁi������݂̎��̃V�X�e���͂��̂܂܉����j���߂ɂ́A�œK��������Ȃ��B�B�B
�����ԍ��F25013824
![]() 0�_
0�_
�����ƁA���̏ꍇ�A�~�b�h�����W�����˂�c�C�[�^�[�̕ی�R���f���T�[�́A10��F�ł͂Ȃ��A68��F�ł��ˁI
�����ԍ��F25013831
![]() 0�_
0�_
�Y�t�摜�� Tangband W8-2314 �̐��������ł��B
�i�Q��̓��e�̉摜�ɂ́AW8-2313 �̏���݂��Ă��܂����̂ŁA�������ĉ������B�j
�����ԍ��F25013837
![]() 0�_
0�_
http://www.tb-speaker.com/products/w8-2314#tab-429
�ɂ��A���������܂����A�p�b�V�uLCR�l�b�g���[�N�ł��A�Y�t�̃��X�|���X������ꂻ���ł��̂ŁA�A���v�����ɂ��ď㗬�� DSP(XO/EQ)����A30 Hz �����肩���肭�炷���Ƃ��ł��邩���A�ƍl���Ă���܂��B
�i����ł��A���̏ꍇ�A�T�u�E�[�t�@�[�����p����ł��傤���B�B�B�j
�T�u�E�t�@�[�����鉹���͌�����̂ŁAW8-2314 �ɂ��^�̓����_�����̃����b�g���ABOWS�����̂悤�Ɂi�I�j����ł��邩������܂���B
�������A��т����ɏn�l���A�X�ɏ����W���܂��B
�����ԍ��F25013849
![]() 0�_
0�_
����ȃ��|�[�g������܂����B
https://audioxpress.com/article/test-bench-tang-band-speaker-w8-2314-high-end-coaxial-driver
�E�[�t�@�[�ƃc�C�[�^�[�̌Q�x���f�[�^������̂ŁAEKIO�Ń^�C���A���C�������g�𐮂���ۂɂ��Q�l�ɂȂ肻���ł��B
�����Ƃ��A���Ȃ�A��̕��@�Ō����ɔg�`�����đ����܂����B�B�B
�ƒ�ł͂��蓾�Ȃ��قǂ̑剹�ʂł͏����c�ނ悤�Ɍ����܂����A�ʏ�̉��ʁi����ł��ƒ�ł͑剹�ʁH�j�Ŏg���͈͂ł́A���Ȃ��悤�ɓǂ߂܂��B
�Ȃ��Ȃ������[�������Q-way �ł��ˁB
�����ԍ��F25014155
![]() 0�_
0�_
BOWS����
���炵�܂����B
https://audioxpress.com/article/test-bench-tang-band-speaker-w8-2314-high-end-coaxial-driver
�́ABOWS����̂��Љ�ɁA�����Ɗ܂܂�Ă���܂����B�i�������I�ł��B�j�@��������ǂ�ł���܂��B
�����ԍ��F25014162
![]() 0�_
0�_
W8-2314 �Ő��삵�Ă���SP�r���_�[��������̂ł��ˁB
http://tobinekospeaker.livedoor.blog/archives/6642698.html
http://tobinekospeaker.livedoor.blog/archives/7618385.html
���́A����ȕ��ɂ��肢����̂��ߓ������B�B�B
�l�b�g���[�N�Ȃ��̂Q�y�A�[�q�d�l�Ȃ�A�����ō�Ƃ�����y�ŁA�m���ŁA������������܂���ˁB
�t�����g�o�b�t���́A
https://www.mofielectronics.com/sourcepoint10
��^����̂��ʔ��������A�Ɩ��z���n�߂Ă���܂��B
�����́A����܂ŁI�@�Ƃ������܂��B
�����ԍ��F25014213
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@W8-2314�ɂ��Ȃ���C�ł��ˁB
�@Tang Band�͍���|�s�����[�ȃ��j�b�g���[�J�[�Ł@����~�̈����ȃ��j�b�g���炱�̃N���X�܂ł��J�o�[���Ă���CP�̍������[�J�[�ł��ˁB
�@�������F�l�̑�����10cm�N���X�̎���X�s�[�J�[���Ă��܂����A���Ƃ͂����肵�������̂��̂����������悤�Ɏv���܂��B
>�N���X�� 800 Hz �t�߂܂ʼn�����ꂻ���ȕ��͋C���B�B�B�B�������A�c�݂Ƃ̌��ˍ����ŁA�ǂ��܂ʼn������邩�́A����Ă݂Ȃ��ƕ�����܂��B
�@�������ł������r���[�L������Ɓ@TW��f0�� 700Hz�Ȃ�Ł@�������Ă��@1.5KHz�ȏ�ŃN���X�̕�������ł��傤�ˁB���܂艺����ƁA�U�����傫���Ȃ��Ęc�������ĕԂ��ĉ������邩������܂���B
�@f0 38Hz�ł����A�傫�Ȗ����ɓ��ꂽ�ꍇ�̎d�l�l�Ł@Vas 51L�ƂȂ��Ă��ā@�����Ȕ��ɉ������߂Ďg�������A�傫�߂̔��ɓ���Ĕw�����������Ƀo�X���t�̃`���[�j���O����@���������ɉ����̂����Ƃ��ł������ł��ˁB
�@��т˂�����́A�p�C����A�J�V�A�W���ނŔ�r�I�����ȃG���N���[�W�����Ă����r���_�[����ł����@W8-2314�i�����悤�Ƃ��Ă�����ł��ˁB2020�N�̋L���Ȃ�Ł@���܂����i���ł����Ƃ������Ƃ��납��
�@�����W�߂Ċy����ł݂Ă��������B
�����ԍ��F25014299
![]() 2�_
2�_
dualazmak����
���K�C�U�C��
�������x���Ȃ���A�ǂ��ŕ����ꂽ�̂�
�n�C�G���h�V���E�E�g�E�L���E�ł��A�R���i�O�������̂ł��Ȃ�ȑO����
�ʐ^���������̂ł���������ƌ����炸�ł��A���݂܂���B
�����͂����������s�������āA�u����ɂ��܂肻���Ȋ����ł����B
��Tangband
����������Ŏg�������Ƃ�����܂���A�l�i�͎荠
���͈��芴�����āA���������B�p�\�R�����Ŏg���Ă܂����B
���������̂�1��/�Q���A�}�O�l�b�g�J�o�[��������ƋȂ����Ă���
�ʐ^�����Č������Ă��炢�܂������A�����������̂ŏ������킢��������������
30cm��NS-1000�ƃK�`�Ŕ�ׂ��A�H��̂��y���݂Ȃ�A�悳�����ł��B
�����ԍ��F25014332
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����
�t�H���[�A�b�v�A���肪�Ƃ��������܂��B
�����ɂ悵����
Geithain RL-901 K2 �� Tangband W8-2314 ���A���̌�����Ă���ꂽ�̂ł��ˁI�������ł��B
�iTangband W8-2314�j�@
��30cm��NS-1000�ƃK�`�Ŕ�ׂ��A�H��̂��y���݂Ȃ�A�悳�����ł��B
��͂�A�A�A�u���L�V�X�e���ƃK�`�R�I�v�́A�ƂĂ��ƂĂ������ł��傤�ˁB
���Ȃ�A���݂̂Q�K�I�t�B�X�̏��փf�X�N�ɂ��� Klipsch ProMedia 2.1 THX Certified ���ւ��邠���肪�ւ̎R���H�I
���������A��N�A�H�t�̃n�C�G���h�V���b�v�̃X�^�W�I�� Fyne Audio F701WN ��PC,�@DAC,�@���������œO�ꎎ�����������ۂɂ��A���̂悤�Ɋ������̂ł����B
���L�V�X�e���ƃK�`�ŏ��������铯��SP�܂��͏�����SP�ƂȂ�A��͂� Fyne Audio F1-12S �� Geithain RL-901 K2 ������ɂȂ炴��Ȃ��A�A�A�Ƃ̊����[�߂Ă��܂��B
��ÂɂȂ��ďn�l���܂��B�@���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25014673
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
Tangband �Ŏg���Ă����͓̂���W8-2314�ł͂Ȃ��A
�������ʂ̃t�������W�ł����A
��������Ă��܂����悤�ł��݂܂���
�����������Ƃ�Ă�A�K�������������D��Ƃ�
��������Ȃ��Ǝv���܂��B
�����̓E�\�t�@�\�A�c�B�[�^�[�Ƃ�
���炩�̊���肪����ꂽ��Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F25014859�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
�����ł��I
�������������Ƃ�Ă�A�K�������������D��Ƃ͂�������Ȃ��Ǝv���܂��B
���̒ʂ�A�ƂĂ������ł��B�@��������G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1369079
�ɂ������܂������A�^�C���A���C�������g�̊������ɉ����āASP�̔z�u�i�����j�A���E�ԋ����A���X�j���O�ʒu�܂ł̋����A�O��̋�ԁA�����̓K�x�ȃf�b�h�j���O�A�O�~�A�V��ޗ���Ƌ�z�u�A�ȂǂȂǁA���ׂĂ������I�Ɋ�^���܂��ˁB
���̌��݂̐ݒ�́A����炪�A�قƂ�NJ�ՓI�ɍœK������Ă���悤�Ɋ����Ă���܂��B
�����Ɏ���܂ł́A�����ɂ悵����ABWOS����̂��w���A�������́A�킽���ɂƂ��Đ��ɗ��j�Ղł���A����ł���܂����B
���炭�A����ȏ�́u���C�S�v�͗}�����āA�Ƃɂ������y���y���݂����Ǝv���܂��B
�������A�e��̏����W�Ƌ��L�͌p�������Ă��������܂��B
�����ԍ��F25015234
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����A
������Ƃ��������{�D��S�ƁA�Ƃ���K�v���ɔw����������āA����DSP�}���`�`�����l��-�}���`�A���v�V�X�e���Ń��A���^�C���� LP�Đ����ł���悤�ɐݒ肵�܂����B
���݂ł����ɗD�ꂽ���\��LP�g���[�X�@�\���ւ� DENON DP-57L �� MC�J�[�g���b�W DL-301II �ł��B
�ڍׂɂ��ẮAASR�̎��̃X���b�h���e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1410137
�������������B
���ɗD�ꂽ�^���i�ʂ�LP����������o���āA���Ȃ��Y��ɐ�|���āA�e�X�g���ł��B����LP�́A�^���i�K�ł͂W�g���b�N���L�v���p�����e�[�v�ւ̃f�W�^���^���ł���A�f�W�^�����}�X�^�[�����CD�ł��Ĕ�������Ă���܂��̂ŁALP���A���^�C�����t�ƃ��b�s���O����CD���t�Ƃ̔�r�����{���ł��B
DENON DP-57L �� DL-301�U�J�[�g���b�W�ł��B�t�H�m�v���A���v Audio-Technica AT-PEQ30 �ƃI�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X Tascam US-1x2HR �̗D�ꂽ���\�i�����x�A��c�݁j�����܂��āA���X�Ȃ���D�ꂽ�g���[�X���\�ɍĊ������Ă���܂��B
LP�ł��A�p�C�v�I���K���� 32Hz ���ቹ�n�C�Q�C���ɍ���̑����p�C�v�����d�Ȃ��Ă��A������������Y��ɁA���i�ʂŁA�Đ�����܂��B
ASR���e�ɏڂ����������悤�ɁA�ŋߔ�������Ă���45��] 30 cm �� HiFi LP�Ղ����A���^�C���Đ��������A�Ƃ̎v��������܂��B
���̍\�����g���ƁA�����Â��������\�ȁA������A�i���ORCA���C�����x���o�̓I�[�f�B�I�@����A����DSP�}���`�`�����l��-�}���`�A���v�V�X�e���ŁA���A���^�C���Œ������Ƃ��ł��A�K�v�Ȃ�Ջ@���ςɃf�W�^���^�����\�ł��B
�����ԍ��F25052131
![]() 2�_
2�_
�t�H�m�v���A���v Audio-Technica AT-PEQ30 �ɂ�����Ƃ��������������āA�z�u���ύX���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1415647
LP���A���^�C���Đ����̍\�z�ƒ����́A����łЂƂ܂������ł��B�߂����ɗ��p���܂��B�B�B�B
�����ԍ��F25059679
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����A
ASR �̎��̃X���b�h�ŁADrCWO ����ނ��J������ rooExtend-box �̏Љ�i�Ɛ�`�H�j���܂߂āA�ނȂ�̃V���v���Ŕ������i�H�j�}���`�`�����l���V�X�e���A�������t�������W�z�[���{�T�u�E�t�@�[�̋��L�����܂����B�ނ��A�A�i���O LP�v���[���̃f�W�^���V�X�e���ւ̎�����B������Ă��܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1416830
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1416888
�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���_�ɍS����̂悤�Ȃ̂ŁA�ߓn�����A�^�C���A���C�������g�A���g�������Ȃǂ̎����l�̋��L�����肢���܂������A�����̉����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1416998
�̂悤�ɁA�W���X�g�t�B�b�g�̃f�[�^�i���g���������܂߂āj�́A�܂����L����܂���i�����܂ő��肳��Ă��Ȃ��̂����B�B�B�j
���L���ꂽ�f�[�^�́A�V�X�e���S�̂Ƃ��Ă̒P����g���p���X�ɑ���u�ߓn�����v�����ŁA���Ƃ��Ă͏��X�s���ł��B
�����ŁA�����A���̊�{�|���V�[�₻�̎�����A�����ŏЉ�Ĕ����≞���i�Ȃ������H�j��҂��Ă���܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1417691
�����ԍ��F25061588
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
������LP�́A�X�N���b�`�m�C�Y�ƁA
�n�E�����O�}�\�W���Ƃꂸ���܁A
40�N���炢�O��CD�ɂ��܂����B
����̗L�y���ł̓��R�[�h������
�v�`�v�`���킸�A��������Ă����ł����ˁB
���R�[�h�ې@���Ȃ���
�j�̂Ȃ����\�U�\�ǂݎ��ł��Ȃ��̂�
�Ód�C�̋z���S�~�͂ǂ����Ă���̂���
�s�v�c�Ɏv���܂����B
�����ԍ��F25064324�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�@�����́@�C���� 15Kg �^�[���e�[�u�� ���h���C�u�� Micro RX-5000 �A Audio Carft�̃����|�C���g�A�[�� �A DENON DL-305 �A���c����CR-NF�^ �d�r�d�� �C�R���C�U�@�� �e�N�j�N�X SL-10 (�W���P�b�g�T�C�Y�v���[��)��2��\���ł������ARX-5000�́A�N���܂ł́@������A��]����܂ł̎��ԁA�A�[���̃o�����X�A�j�������A�d�r�`�F�b�N�@���X�N���̂��߂̋V�������Ȃ�ʓ|�Ł@���܂�����ł��܂��B
�@SL-10�����X�g���Ă܂��B
�@�F�l���@Micro SZ-1 (30Kg�X�e�����X�@�G�A�t���[�g �^�[���e�[�u�� �{ �G�A�T�X���U��)���g���Ă��ā@RX-5000 �Ɣ�ׂĂ��@��l�Ǝq�ǂ����炢�����Ⴄ�̂Ł@�A�i���O�v���[���͕��ʏ������Ǝv���Ă��܂��B
�@����������Ɓ@��y�ȍ�������LP-12�݂����Ȃ̂��~�����Ƃ���ł͂���܂����A���̂Ƃ���i�߂�����͖����ł��B
�@�w�b�h�V�F���Ƀw�b�h�A���v�Ԃ����ނ̂��`���z���������܂����A���̂����@�w�b�h�V�F����ADC�Ԃ�����Ł@COAX�o�͂��Ă̂��L��ȋC�����܂��ˁB
�����ԍ��F25064455
![]() 1�_
1�_
BOWS����
���������b�N�X�̋z���^�\���e�\�u����
���������Ǝv���Ă������̘b���ۂ��ł���
���̂����A�A�\���̐�ɏd��t����
����C���i�[�V�A�Ƃ��n�܂�A
����Ⴤ�o�C���E����
�������͖C���� 15Kg �^�[���e�[�u�� ���h���C�u�� Micro RX-5000 �A Audio Carft�̃����|�C���g�A�[�� �A DENON DL-305 �A���c����CR-NF�^ �d�r�d�� �C�R���C�U�@��
BOWS����A���C�ɂ�����������s�ł���
�����ԍ��F25064623�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����
�Ȃ�Ƃ����Ă�BOWS����̂��Ƃł��̂ŁA�u����Ȃ�Ɂv���ʓ�����LP�Đ������������i�������H�j���Ƃ́A�z���͂��Ă���܂����B
TechDAS Air Force One �Ƃ܂ł͍s���Ȃ��Ƃ��Ă��B�B�B
���C���� 15Kg �^�[���e�[�u�� ���h���C�u�� Micro RX-5000 �A Audio Carft�̃����|�C���g�A�[�� �A DENON DL-305 �A���c����CR-NF�^ �d�r�d�� �C�R���C�U�@�� �e�N�j�N�X SL-10 (�W���P�b�g�T�C�Y�v���[��)��2��\��
�ł��A���܂�����܂����I
��SL-10�����X�g���Ă܂��B
�����A�́A�m�l��ʼn��x���A���������Ƃ�����܂��B���̒m�l���A���P�O�N���O�Ƀ��j�A�g���b�L���O�ɃS�����o�����āA������߂Ď�����������ł��̂ŁABOWS����̂��ƂȂ�A�������������e������Ċ����Ɉێ�����Ă���̂ł��傤�ˁB
���A�i���O�v���[���͕��ʏ���
�����A�e���Œ��n�C�G���h�ȁu���ʓ���LP�v���[���[���������Ă���܂��̂ŁA�����ł��B
����ŁA����� DP-57L+DL301II�̕����ł��AASR�ł��������悤�Ɂu���z���������͐�Ɍ�@�x�I�v�ƐS�Ɍ��߂āA AT-PEQ30�̍w���i�Ƃ���EMF�V�[���h���H�j�����ɗ��߂Ă���܂��B
����ł��A���N�̗D�ꂽ�^���� LP�Ղ𐔏\�N�Ԃ�ɐ�A�Ód�h�~���{���āA���̃}���`�A���v�V�X�e���Œ����Ă݂�A����Ƀ��}�X�^�[CD�ƒ�����ׂĂ݂�ƁA�A�i���O�̗ǂ��Ɩʔ������u�m�X�^���W�b�N�Ɂv�h��A�ɂԂ��ɂ͊y���߂܂��B
���̂Ƃ���A�f�W�^���^���ōŏ���LP�����[�X���ꂽ���i�� LP�iASR�ŏЉ���p�C�v�I���K�����t�j�̂Q���g�A1964�N���̌Â����D����A�i���O�^���ŗD�ꂽ�s�A�m���tLP�i���t�҂��A�����A�Ⴉ�肵���I�̊���LP�j1���A�̂R���������������ĉx�ɂ����Ă���܂����A����ȏ�̎莝��LP�̕����^�����͍l���Ă���܂���B�قƂ�ǍĔ�CD�����b�s���O�ς݂ł��̂ŁB
���̂R���́A����������}�X�^�[������CD�ł���������Ă���̂ŁA���A���^�C��LP�Đ��ƃ��b�s���OCD�̔�r�������A����Ȃ�ɖʔ����ł��B
�}���`���ł́ALP���t���Ȃ���Fq���X�|���X���ׂ��������ł���̂ŁA���}�X�^�[CD�Ɣ�r�������Ȃ���A�ǂ�ȕ���Fq�������ă��}�X�^�[CD�������̂���z�����V�~�����[�g�ł��܂��B���V�тł����B�B�B
���ꂩ��A�W���Y�ƃN���b�V�b�N�̗����ŁA�ŋ߃����[�X���ꂽ�S�T��]�R�Ocm�Ղ̍��i��LP���Q�C�R�����A���������Ǝv���܂��B
�����A���߂̔Ղ�����܂����炲�����������B
���₢��A���y�t���[�N�A�I�[�f�B�I�t���[�N�Ȓm�l�̗��K���ɁA���̃}���`�`�����l�� �}���`�A���v���ł��A�uLP�̃��A���^�C���Đ����A���������A�܂Ƃ��ɂł����I�v�A�ƌ��������A���������A�����Ȃ�ł��B
�����ԍ��F25065783
![]() 1�_
1�_
��1964�N���̌Â����D����A�i���O�^���ŗD�ꂽ�s�A�m���tLP�i���t�҂��A�����A�Ⴉ�肵���I�̊���LP�j1��
�ł����A�����ŏ����ڂ������L���Ă���܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1421330
�����ԍ��F25066688
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�@�A�i���O�I�[�f�B�I�Ń^�[���e�[�u���ɑ��镨�ʓ������Ă̂͏��̌��Ł@�^�̋��낵���́A���R�[�h�Ղɂ��邱�Ƃ�Ɋ����Ă��܂��B
�@�C�O�̃��b�N�o���h�̃A���o���ł����@�F�l���R���N�V���������@�����A���o����
�E�e�X�g�v���X(�v���f���[�T�[�ւ̃v�����[�V�����Ɏ������ޔi)
�E(�C�O)�I���W�i���t�@�[�X�g�v���X
�E(�C�O)�Z�J���h�v���X
�E������
�@���������ȁH��A�����ĕ������Ă��炢�܂����B
�@�e�X�g�v���X���@���ŗႦ��Ɓ@�u�x��H���v���x���̑N�x�ɑ��ā@�����Ղ́@�u�����v�ɂ����������Ȃ������ł��B
�@�}�j�A���@�e�X�g�v���X�A�t�@�[�X�g�v���X���v���~�A���i�Ŏ�����闝�R���悭�킩��܂����B
�@���������ՂɎ���o���n�߂�Ɓ@�^�[���e�[�u�������y���ɍ��z�ɂȂ邻���ł��B
�@���̎�����m���Ă���@�f�W�^���́A�����ɑ���R�X�g�Ɨ����͌��Ⴂ�Ɉ����Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F25067678
![]() 2�_
2�_
����A���̘b�A�����W���Y���̗F�l���畷������܂����B�@�{���ɁA�|�����E�ł��ˁB
�ނ́A�u�E(�C�O)�I���W�i���t�@�[�X�g�v���X�v�@������������Ă���悤�ł��B
�����ԍ��F25068645
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
�ȑO�A���x���A���̒����Ș^�����T�E���h�G���W�j�A�� Igor Kirkwood ����i���ł����Ɠ��l�� Yamaha NS-1000x ���t���A�N�e�B�u�A�A���v�����ŗ��p����Ă���j�Ƃ̗L�Ӌ`�ȏ������ɂ��Ă��b�����Ă���܂������A�ŋ߁A�ނ����̃X���b�h���ĖK����A�ނ̌��݂̃Z�b�g�A�b�v�iNS-1000x �Q�y�A�����p�j���Љ�Ă���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1454798
�����ŁA����A�ނ̃Z�b�g�A�b�v�ɂ��ĐV�����X���b�h�𗧂��グ�ď����������Ă���A�Ƃ��肢���Ă���܂����Ƃ���A�捠�A���̊�]������Ă���āA�ގ�Â̐V�X���b�h���J�n����܂����B
Sound engineer's monitoring and HiFi + HT system with active Yamaha NS-1000x, multi-subs and FIR QSys processor in a particular and treated room
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/sound-engineers-monitoring-and-hifi-ht-system-with-active-yamaha-ns-1000x-multi-subs-and-fir-qsys-processor-in-a-particular-and-treated-room.41250/
�ނ́A NS-1000x �� Be-Tweeter ��FOCAL�̋t�h�[���^ Beryllium tweeter �Ɋ������� Yamaha Be-mid-range �� 1800 Hz (80 dB/Oct QSC FIR flilter) �Ō��������Ă��܂��B�]���āA��X������Ȃ�������i�I�j Yamaha Be-mid �́A��500 Hz �` 1800 Hz ���J�o�[���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/sound-engineers-monitoring-and-hifi-ht-system-with-active-yamaha-ns-1000x-multi-subs-and-fir-qsys-processor-in-a-particular-and-treated-room.41250/post-1458103
����A���̏ꍇ�́AYamaha Be-tweeter �̎�_��₤���߂ɁA FOSTEX T925A ��lj����Ă���܂��i�ꏏ�ɉ̂킹�Ă��܂��j�̂ŁA�����قȂ�A�v���[�`�ł��ˁB
��n�߂ɁA���̓��e����A�����ނ̃X���b�h�ւ̎Q�����J�n�����Ă��������Ă���܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/sound-engineers-monitoring-and-hifi-ht-system-with-active-yamaha-ns-1000x-multi-subs-and-fir-qsys-processor-in-a-particular-and-treated-room.41250/post-1472228
����A�ނ̃T���E���h�V�X�e���ɂ��������� NS-1000x �y�A�i�t�������W�p�b�V�u�쓮�A�ƌ�����j�̗��p���@��Q�C���ݒ�Ȃǂɂ��Ă��A���q�˂������ł��B
�����ԍ��F25125321
![]() 0�_
0�_
dualazmak����@
Igor Kirkwood ����̂�����A�y�������ł���
AV�A���v�Ƃ̓A�i���O�ڑ�
QSC QSys Core 110f ��AD����������
�p�\�R�����͂���ΐ藣���A
�P�ƂŃ`�����f�o�ɂȂ�̂ł��傤��
�����ԍ��F25137684�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��AV�A���v�Ƃ̓A�i���O�ڑ�
��QSC QSys Core 110f ��AD����������
���p�\�R�����͂���ΐ藣���A
���P�ƂŃ`�����f�o�ɂȂ�̂ł��傤��
���̂悤�ł��B�]���āAAV�A���v�� �yADC��DSP(XO/EQ/delay)��DAC�z ���A���v�Q�@�̍\���ł��̂ŁA���Ƃ��Ă͉����ʂł͏����^��������Ă��܂����A�����͓˂����܂Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
QSC QSys Core 110f �̔w�ʃ}���`�[�q����XLR�I�X�ϊ��P�[�u���i�����I�j���g���ăA���v�Q�փo�����X�ڑ����Ă���̂ł��傤�ˁB�s�ςȔw�ʎʐ^�����������̂ł��B�i�Y�t�̂悤�ɁA�o�����X�ł��A�A���o�����X�ł��A�ǂƂ�ł��o����悤�ł��B�j
������AIgo����́A5.1Ch�T���E���h�̔��W�^�ő�����SP��SW��炷 AV�V�A�^�[�^�̐ݒ�ł���A�s���A�QCh�X�e���I�Đ������ɂ̃}���`�h���C�o�[�^�}���`�A���v�i5-way, 10-Ch�j�Ŗڎw���Ă��鎄�̕������Ƃ͑傫���قȂ��Ă��܂��̂ŁA�����ʂœ˂����ނ͖̂��ȋC�����܂��B
�ނƁA���̃V�X�e���̃`���[�j���O����`���Ă��� jlo����i�����Œ����ȃT�E���h�G���W�j�A�ł���Jean-Luc Ohl���I�j�́A�A���v�Q�� CROWN CT8150 (8x125W)�AROTEL RMB1077 (7x130W)�AHYPEX (2x100W) �Ŗ������Ă���i�H�I�j�悤�ł����i���� HiFi�A���v�Ƃ͔�r�������Ƃ��Ȃ��A�Ə�����Ă��܂��j�ASW�́A�A���v������ SVS PC2000 �i12�C���`�A500W�j���S�{�i���I�j�g���Ă��܂��B
���ɕ�܂��A�Ƃ����Ӗ��ł́u����Ȃ�ɗD�ꂽ������ԁv���l�H�I�ɍ��Ă���̂ł��傤���A���̃A���v�\���ł́A�����I�ɂ͍œK�ł͂Ȃ����Ƃ����̌o������͐��@�ł��܂��B
������A�����m�̒ʂ�A���̏ꍇ�́A�A�L���� E-460 �� YAMAHA MX-A5200 �̔�r�����Ŗ��m�ɉ����������ɂ߂��Ƃ��납��A���v�I���̒������H���n�܂�܂����B�܂��A���H�̓r���ł́AE-490�AROTEL RB-1582 MkII�ABENCHMARK AHB2 ��O��I�Ɏ��̊��Ŕ�r�������āA���m�ɉ��������m�F�����o�����������܂��B
�^�C���A���C�������g�����ł́A���������ƂɁA���́u�G�l���M�[�s�[�N�}�b�`���O�@�v�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1049923
�ƁA�قړ��l�̕��@�Œ������Ă���悤�ł��B
����ŁA���́A��́uST=Super Tweeter �̍����p���X�������[�������}�[�J�[�Ƃ���^�C���V�t�g�@�v�̕������x�ƍČ������������A�Ɛ\���グ���Ƃ���A���ɋ�����������A���A���PM�l�ʐM�ŁA�����쐬�����g�[���o�[�X�g�p���X�V�[�P���X�i�W�g�A�R�g�j�Ȃǂ����L���Ă���A�ޓ������̕��@�������Ă݂邻���ł��B������A���b�Ԃ́u�`�b�A�s�b�A�v�b�A�|�b�A�{�b�A�A�A�A�u�[�v���PC�ŋ�C�^�����邾���Ő��m�ɑ���ł���̂ŁA�u�ڂ���̑�����@���I�v�ƕ]�����Ă���Ă��܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1048913
��
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1061868
�ł��ˁB
�܂��A�����ɂ悵�����BOWS����ɁA�U�X���w������������XO���g���ߕӂɂ�����V���O���p���X��C���g�`�� 0.1 msec ���x�̑���Ɣg�`�}�b�`���O�A���� SW-WO, WO-SQ �̃N���X�A�ɂ��ẮA�����s��������ƒ������u�m���Ƀx�X�g���I�p�Ƌ��ł��B������A���̐M������Ă���܂��B�����̌㔼�ŏڍׂ��V�F�A�������@�ł��ˁB
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1061868
SW��WO�̉ߓn�����]���ɂ��A�傢�ɋ���������l�q�ŁA���̕��@�Ǝ��̐M���ł���Ă݂邻���ł��B����ł��ˁB
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1051202
������ɂ��Ă��A���ł� NS-1000x �������]�����āA�}���`�A���v�Œ����쓮���Ă���T�E���h�G���W�j�A�B�ƋM�d�ȏ��������ł��邱�Ƃ́A�ƂĂ����������Ƃł��B
�����ԍ��F25138675
![]() 0�_
0�_
��قǁA�����l�b�g�Œ��ׂ���AROTEL RMB1077�@��RCA�A���o�����X���݂͂̂̑Ή��ł��ˁB
CROWN CT8150�@�́A���[���[�q���͂ł����A�o�����X���͑Ή��ł��ˁB
�����ԍ��F25138794
![]() 0�_
0�_
QSC QSys Core 110f ��ADC-DSP-DAC �����́A48 kHz 24 bit ������̂悤�ł��B
https://www.qsc.com/resource-files/productresources/dn/dsp_cores/core_110f/q_dn_core_110f_specs.pdf
A/D - D/A �ɁA�ǂ̃��[�J�[�́A�ǂ��AD-DA �`�b�v�i�v���Z�b�T�j���g���Ă���̂��H�ɂ������ÁX�ł����A�܂��ڍׂ������Ă���܂���B
������ɂ���A�ޓ��̐M�������ƃA���v�\���́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�s���AHiFi�I�[�f�B�I�ł͂Ȃ��A�v��PA�I�Ȏw���^�n�D�ł���悤�Ɋ������܂��B
�����ԍ��F25138831
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
Core 110f�̂����A��ς��肪�Ƃ��������܂�
����ɋƖ��p�A�A���v�̒��g�̔z���������o��������
�V�[���h�Ƃ��z�����v�肻���ł����A
�����I�ł悳�����A48k�͎c�O�A�v���p�ł�������ƕ�����Ȃ������A
96k/24bit�͂ق����Ƃ���ł��B
�������Œ����ȃT�E���h�G���W�j�A
dualazmak����̂���Ă��鎖�́A���̃��x���̐l
�����ł��}���`�A���v�̃G�l���M�[�s�[�N�}�b�`���O�@�͊v�V�I�A
�[�������}�[�J�[�̃^�C���V�t�g�@�Ő��x�����؍�
�C�O�ōL�����āA���{�͋t�A���ł��傤��
��Igo����́A5.1ch�T���E���h�̔��W�^�ő�����SP��SW��炷 AV�V�A�^�[�^�A
���s���A2ch�X�e���I�Đ������ɂ̃}���`�Ŗڎw���Ă��鎄�̕������Ƃ͈قȂ���
2ch�͉��y�A�������Ă������͂���A���ɂ͋Ȃ̐S�n�悳���y���ނ���
���ɂɎ���ɂ͈ʑ��͔����Ēʂꂸ�B
AV�́A�Ԃ��N���b�V���A�e���A�n��A�����͉̂��y�ł͂Ȃ���
��Ԃɉ����������сA3�����ňړ�
���̍Č��ŁA�ʑ��̐��m�����y���������E���܂��B
�������̂̍��ŁA2ch��AV�ŋ@��̈Ⴂ�͏o��ł��傤
AV�ł����y�͒������A2ch�ł��f���������
�E�G�C�g�ɂ���āA�@���I�ׂ悢�ł��傤�B
���y�ɓ�������SP�́A���F���Â�ł܂���AV�ɂ͎g���܂���
NS-1000�̓��j�^�[�Ȃ̂ŁA�\�������L���ł�
dualazmak����AIgo����̑I������SP�������V���[�Y�Ȃ̂�
�ƂĂ������[���ł��B
��SW��WO�̉ߓn�����]���ɂ��A�傢�ɋ���������l�q��
���܂ŁA�ǂ�����Ă����̂ł��傤�H
�����ԍ��F25139339
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
�t�H���[�Ƃ��ԐM�A���肪�Ƃ��������܂��B�@���ׂē����ł������܂��I
ASR �ɂ����鎄�̃v���W�F�N�g�X���b�h�A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
Igor Kerkwood����̃V�X�e���Љ�X���b�h�i���������I�ɎQ�����j�A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/sound-engineers-monitoring-and-hifi-ht-system-with-active-yamaha-ns-1000x-multi-subs-and-fir-qsys-processor-in-a-particular-and-treated-room.41250/
��������A���X�A�`���Ă݂ĉ������B
ASR�ŁA����ɉ����ʔ������Șb���X���b�h������A�����ł��ȒP�ɂ��Љ�����܂��B
���������A���Ƃ���낵���A���t�������̂قǁA���肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F25139582
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�A�����J�̕��ł����ANS-1000 �iNS-1000M �ł͂Ȃ� NS-1000�I�j�̎������ NS-5000 ���w������āA��r�I�����ȃA���v�Ŕ�r�������J�n���ꂽ�l�����܂��B
�������A�n�߂Ă��܂��B�@�����A�K�₵�Ē����Ă݂������̂ł��B���X�ߍx�̍����Z��X�A�������ł��B
���̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/yamaha-ns-5000.1118/post-1472297
�ނ̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/yamaha-ns-5000.1118/post-1493392
�����ԍ��F25152203
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
BOWS���炲�w�E�����������������uLP�����v���X���T�̓D���v�ɓ��ݍ��ނ���͖ѓ��Ȃ��̂ł����A���t�@�����X�łƂ��Ă̗D�ꂽ�S�T��]LP���P�C�Q���T���Ă���܂����B
���̃W���Y���̃I�[�f�B�I���Ԃ��犩�߂�ꂽ�r���E�G���@���X�̃s�A�m�g���I�A�P�X�V�V�N�A�i���O�^���̂Q�O�Q�P�N�ă}�X�^�����O�ă~�L�V���O�A���o���i�Ǔ��A���o���̃��}�X�^�����O�Ĕ́j���Q�O�Q�P�N�ɂS�T��]�̏d�ʋ�LP�i180�O�����I�j�Q���g�Ŕ�������Ă���A���������t���A�傢�ɋC�ɓ����Ă���܂��B�����ɓ��肵��CD�łƂ̔�r�������A�Ȃ��Ȃ��ʔ����āA�y����ł���܂��B
�䋻����������ł�����A�`���Ă݂Ă��������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1539152
�����ԍ��F25203404
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����
����DIY�H��Ŋ��������� IEC 60268-17 ���S�K���̃K���X���� 12-VU-Meter Array ���A���y�ɍ��킹�ėx���Ă���r�f�I�������Ă���I�@�Ƃ̗v�]�����E�e�n������Ă���܂��̂ŁA�A�A������ YouTube �ւ̃A�b�v������Ă݂܂����B
- Dancing video of my IEC 60268-17 compatible large glass-face DIY 12-VU-Meter Array
_____Part-1: with "High Frequency Linearity Check Track" of Sony SUper audio Check CD: #750
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1562861
_____Part-2: with typical "Full Orchestra Music"-1: #751
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1562866
_____Part-3: with typical "Full Orchestra Music"-2: #752
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1562867
_____Part-4: with typical "Jazz Piano Trio Music": #753
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1562874
�����ԍ��F25228523
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
VU���[�^�[���悠�肪�Ƃ��������܂��B
�g�F�n�̏Ɩ����C���[�W�ɂ҂�����
�����������ăX�^�W�I�݂����ł��B
�j�������W�ASQ�̓��͂������ł���
��͂艹�̍����B
ST��T�Ɠ����ʂ̓��͂Ɍ����܂��ˁB
�����ԍ��F25228909�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
�䏳�m�̒ʂ�A���̃V�X�e���ł͑��`�����l���Ԃ̑��Q�C���i�S�̂�F�����j�́ADSP EKIO�ɂăf�W�^�����x���ł��A����ъe�A���v�ŃA�i���O���x���ł��A�����悤�ɂ������ł��܂��̂ʼn��Ƃł��Ȃ�̂ł����A����̂S�{�̃r�f�I�N���b�v�ł́ASony Super Audio CD �̌����ɍ쐬���ꂽ�s���N�m�C�Y�̍Đ��łقڃt���b�g�ɂȂ�ݒ�ʼn��y���Đ����Ă���܂��B
�A���v��SP�n�C���x���o�͂����C�����x���ɉ�����VU�\�������Ă��܂��̂ŁA�eSP���j�b�g�ւ̓��̓��x���𒉎��ɔ��f���Ă��܂��B
�ȑO���b�������悤�ɁATW �� ST �͑傫���d�Ȃ��Ĉꏏ�ɉ̂��Ă��܂����ABe-TW�� 14 kHz �����Ń_��������ł���̂ɑ��āA�����z�[�� ST = FOSTEX T924A �͍������� 40 kHz �ȏ�܂Ńt���b�g�ɉ������܂��B
�����Ƃ��A�N��ˑ��̍����g���͒ቺ�͔ۂ߂��A�T�C���P���̃e�X�g�M���ŁA�w�b�h�z���ł܂Ƃ��ɕ�������̂� 10 kHz �����E�ł����A�ʔ������Ƃɉ��y�M���Ƃ��Ă� 10�`20 kHz ��������ƍĐ�����Ă�������A�܂Ƃ��ŁA�����ŁA3D��ʊ��ɂ��D��Ă��܂��B
�ۖ������ł͂Ȃ����`����畆�`���ɂ��]�ւ̓��͂��W���Ă���̂ł��傤���A�I�[�f�B�I�̖ʔ����ł���A��햡�ł��ˁB
���̂�����́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1332948
�ƁA�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1316155
�ŏڂ������L���Ă���܂����B
YouTube �N���b�v�́AAdobe Premiere Rush �ɂ�铮��ҏW�̗��K�����˂č쐬���܂����B
����ɂ��Ă��AWindows 11 Pro �� Snipping Tool �ɂ��PC��ʔC�Ӕ͈͂̃r�f�I�^��@�\�͑�ϕ֗��ł��ˁB
��ʃL���v�`���[�^��� Canon EOS-5D Mark IV �ɂ��B�e�r�f�I�̗����� Adobe Premiere Rush ��Ō����Ɏ��Ԏ������킹����K�ɂ��Ȃ�܂����B
�����Ń}�E�X�|�C���^�[�̓������r�f�I�L���v�`���[���Ă����A���̓�������v������悤�� Premiere Rush ��Ŏ��Ԏ������킹����� EOS-5D �ɂ��r�f�I�摜���㉺���E�g���~���O���ĂP�Q�A��VU���[�^�[�����݂̂��̗p����A�Ƃ����菇�ł��B
���̌�ɃL���v�V�����ȂǑ}�����ăt���n�C�r�W����mp4����Ƃ��ďo�͂����闬��ł��B
�������Ɨ��K�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F25228998
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����A�F����
�Ƃ���n�C�u���b�hSACD�ɂ����� DSD�w��CD�w�̋q�ϕ��͓I���Ⴈ��ђ�����̑���ɂ��āA������Ƌ�������X���b�h�������オ���Ă��܂��B���܂���H�I�̊��͐@���܂��B�B�B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/does-dsd-recording-benefit-japanese-traditional-instruments.43632/
���Ȃ�̌�����A�q�ϓI���͂Ǝ������ʕ�v������Ă���܂����̂ŁA�{���A�����ڂ������e���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/does-dsd-recording-benefit-japanese-traditional-instruments.43632/post-1570775
����������������ł�����A�`���Ă݂ĉ������B
�����ԍ��F25236922
![]() 0�_
0�_
���X���b�h�ɏ����Ă����̂ŁA�����ł��Ę^���܂��B
�����ɂ悵����
�ȑO�� Adobe Audition 3 �� 3.01�p�b�`�̃C���X�g�[���ɂ��āAASR�̌l�ԘA���V�X�e���ł��b�������Ă��������܂������A���̍ۂɂ́A�������A�����ɂ悵�����Windows 11 (?)�@���ɂ́A���܂��C���X�g�[���ł��Ȃ������̂ł���ˁB
���́A������A�Ƃ���I�[�f�B�I�F�l�Ɠ������Ƃ�b���Ă��āA�ނ� Windows 11 �ւ̃C���X�g�[���ɓ�a���Ă���A������Ɩ{�i�I�ɑŊJ��A�������T�����Ƃ���A���X�̗��Z�i����H�v�j�ŁA�m���ɃC���X�g�[���ł��邱�Ƃ��������܂����B
�v�́A�C���X�g�[���[.exe �t�@�C���i�i�K�I�ɂQ����j�ɑ��āAWindows 11 �ł͂Ȃ� Windows XP ���Ǝv�����܂��Ă��ƁAWi��dows 11 �ւ����Ȃ��d���߂āA���̌�� Windows 11 ��Ŋ����ɋ@�\����A�Ƃ����킯�ł��B
�ڍׂ��K�v�ł�����A��� ASR PM �̑����ł��m�点���܂��̂ŁA�����炩�������������ł����Ă��������B
�܂��́A�����ŏڍׂ����`�����邱�Ƃł��A�S�����Ȃ��ł��B�i���̎��̋��L�C���X�g�[���t�@�C���ނ����茳�ɂ��邱�Ƃ��O��ł��B�j
�ēx�A�C���X�g�[���t�@�C���ނ��K�v�ł�����AASR�@�� PM �ł��A���������B
�����ԍ��F25253071
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
���X���b�h�ł̋M�a�̏������݁A���܂����B
��dualazmak����
��
�����A�����肪�Ƃ��������܂�
��
��ASR PM�ɋL�����܂�����
���X�p�т��s�K�ő��M�ł��Ȃ��悤�ł�
��dualazmak����̃��\���͓ǂ߂܂��̂�
�������\�t�g�̃C���X�g�[���@��
�������������܂��ł��傤��
�ł́A�{������ ASR PM �̑����ŏ������m�点���܂��̂ŁA�����ɂȂꂽ���ǂ������A�����ł��A���������B
�����ԍ��F25253075
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
ASR�ł́A�ŋ߁A�Z�L�����e�B�̋������s���܂����B
�A�J�E���g�ݒ�ŁA�u�p�X���[�h�̋����ύX�v�@�Ɓ@�u���A�h�o�R��2�i�K�F�ؐݒ�v�@�������߂��܂��B
90�����ƂɃ��A�h�o�R��2�i�K�ݒ肪�v������܂��B
��� Adobe Audition 3 �C���X�g�[���̌��AASR PM �̑����ɏ����Ă����܂��B
�����ԍ��F25253174
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
ASR PM �ŁA�V���� PM�X���b�h�u���炽�߂� Adobe Audition 3 �̃C���X�g�[���I�v�i���Ƃ����ɂ悵�����̎Q���j�����܂����̂ŁA������ɏ������݂܂��I
�����ԍ��F25253181
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
�ȑO���b������ Revival Audio �̌�����g�D�E�[�t�@�[���� Atalante 5 �ɂ��āA�n�߂Ẵ��r���[�����J����Ă��܂��B
���z�I�ȑ�����ł͂Ȃ��悤�ł����A���茋�ʂ��܂܂�Ă��܂��B
https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-regalove/4180-revival-audio-atalante-5#
�`�F�R��̂悤�ł����AGoogle Chrome �ł́A�قڂ܂Ƃ��ȓ��{��ɖ|��܂��B
��ϓI�ȋL�ڂ���z������ƁA�t�����X���ł����A�ǂ��炩�Ƃ����� Spendor, Harbeth �Ȃǂɋ߂��p���I�Ȉ�ۂ����H�@�O�ϓI�ɂ��A�A�A�@�Ɗ����Ă��܂��B���ۂɒ����Ă݂������̂ł��B
�����ԍ��F25253692
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
ASR ��PM�X���b�h�ɂ������Ă����܂������AAdobe Audition 3 �ł́AFLAC�����͓ǂ߂܂���A�����܂���B
FLAC�����́E�ҏW�������Ƃ��ɂ́AJRiver �� Roon �� dBpoweramp Music Converter�iCD Ripper ���܂߂āA���������߁j�Ȃǂ�FLAC�� WAV�� AIFF �̔kPCM�ɕϊ����Ă��番�́A�ҏW���Ă��������B
�ҏW��́A�t�@�C������ւ��� WAV�� AIFF �ŕۑ����āA�K�v�Ȃ� FLAC �֍ĕϊ��A�ł��ˁB
���ꂩ��A�u���܂��v�Ƃ��� MusicScope 2.1.0 �̃C���X�g�[���[���܂߂Ă����܂����B����́ADSD-DSF ���܂߂āA�ǂ�Ȍ`���̉����t�@�C���ł����͂��Ă����D����̂ł��B�������AMusicScope �ʼn������Đ����Ē������Ƃ��ł��܂��B�o�͐�́AWindows �̃f�t�H���g�ݒ�Ƃ��Ďw�肵���X�s�[�J�[��ASIO�h���C�o�[�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F25254144
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�\�\�X��ς��肪�Ƃ��������܂��B
�����\�t�g��OS��XP��PC�����ĂȂ���
����Ȃ��̂�������܂���A�n�\�h�܂ߌ������Ă݂܂��B
�����ԍ��F25255549�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
�R�C�S���O�ɁA������̗v���ɉ����āA��� ASR PM ���m�点�������@��p������A Windows 11 Pro 64 �̌��sPC�ւ�����ƃC���X�g�[���ł��܂�����B
�����ԍ��F25255574
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����A�F����
�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1594396
�ŏڍ׃V�F�A���Ă��܂����AEKIO���J���E���Ă���t�����XLUPISOFT�Ђ�Giullaume BADAUT ����ƁA�ŋ߁A�ēx�A�ӌ��������Ă���i�v�]���܂ށj�A�Q�̋M�d�ȏ������炢�܂����B
�P�DVoicemeeter Banana �Ƃ��� ASIO�h���C�o�[���g���� ASIO4ALL�����VB Audio Cable/Bridge ���g�킸�� EKIO�ւ�I/O���m���ł���B�V�����`���[�g���A���́A�����G
http://www.lupisoft.com/ekio/articles/using-voicemeeter.htm
�Q�D�i���Ƀ}���`�`���l���I�[�f�B�I�\�z�Ȃǂɂ����āj�@�\�����Ȃ��i�`�����l�����A�t�B���^�[���������j��EKIO�������ԕ]���������ۂɂ́A�]���p�̃��C�Z���X�R�[�h�i�]�����Ԃ̎��Ԑ����̂݁j�s���Ă��炦��B�������]����ۂɂ́A���[���� Guillaume ����֊�]��`����B�imail to: contact@lupisoft.com�j
EKIO I/O��pASIO�h���C�o�[�̊J�����A���������v�]���Ă���܂��B
�����ԍ��F25263810
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
��EKIO���J���E������Giullaume BADAUT �����
��F�͈͂��ƂĂ��L��
�Z�p�I�ȉ�b���ł���̂����݂ł��ˁB
��Voicemeeter Banana
�ȑO�g���Ă݂�����24bit48kHz�܂�
�������悤��
���͉��P���ꂽ�̂�������܂���ˁB
�����ԍ��F25264260�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��Voicemeeter Banana
�ŐV�Łi�C�ӊ�t�\�t�g�j�ł� 192 lHz 24 bit �܂őΉ����Ă���悤�ł��B
�����ԍ��F25265921
![]() 0�_
0�_
�����ƁA 192 kHz 24 bit �ł��B
�����ԍ��F25265924
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����A�F����A
8-Ch DAC�Ƃ��āAOKTO DAC8PRO �̐��\�Ɖ����ɂ͔��ɖ������Ă���̂ł����A�ŋ߂̃t�@�[���E�F�A�X�V�i���͍X�V�̕K�v�Ȃ��I�j�ɂ����邿����ƕ|����APavel����Ɣނ̂قڌl��Ƃ̗l�����Z��OKTO Reserarch�Ђ́u�p����=sustainability�v�ɂ͏��X�^��������n�߂Ă���̂ŁA���� DAC8PRO�������ɋ@�\���Ă���ԁi����������ł���ƐM���Ă��܂����B�B�B�j�ɁA��ւ̃}���`�`�����l��DAC�A������ 12-Ch �܂��� 16-Ch ���������� USB 2.0 ASIO 192 kHz 24 bit �ŏ����ł�����́A�����낻��T�����ƍl���Ă���܂��B
�����̃����e�i���X�T�[�r�X�A�\�t�g���n�[�h�E�F�A�̃A�b�v�f�[�g�A��Ђ̌p�����A�ȂǂȂǂ��l������ƁA�v���I�[�f�B�I�E�̃}���`�`�����l��DAC�܂��̓}���`�`�����l��ADC-DAC�i���Ȃ킿�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�j�֏�芷����ׂ����ȁA�Ǝv�Ē��ł��B
�����ŁA�ŋ߁A�hHow many people want a 12-channel or 16-channel DAC? And a 7-channel or 12/16-channel power amplifier?�h �Ƃ̃^�C�g���̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-many-people-want-a-12-channel-or-16-channel-dac-and-a-7-channel-or-12-16-channel-power-amplifier.41498/
�ŁA�������������A�ӌ��������Ă��܂��B���������������܂����炲���������B
������������W���܂����A�������݂ł́A
Antelope Orion Studio Synergy Core (OSSC); �Ȃ�� Cirrus Logics��2-ch���͍ō�DAC Chip CS43198 ���P�Q�������쓮�I
https://jp.antelopeaudio.com/products/orion-studio-synergy-core/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/267431/?gclid=CjwKCAjwyeujBhA5EiwA5WD7_ffekjh92RxAx5ojAtnJ8Ulw1L46w36mNaxcfqIoGY-6o3S_pQPKlhoChUAQAvD_BwE
�ƁA
MOTU 1248; ESS Sabre32 Ultra �i�����H�j���ځ@
https://motu.com/products/avb/1248
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/196991/
�̂Q�ɒ��ڂ��Ă��܂��B
Antelope �́A�ȑO����N���b�N�W�F�l���[�^�E�N���b�N���z��Ŗ���y���Ă�����Ɓi�u���K���A�j�ł��̂ŁA2-Ch����DAC�P�Q�̓����쓮�ɂ́A��قǂ̎��M������̂ł��傤�B���ɋ����[�����i�R���Z�v�g�ł��B
�A���A���܂��܂ȃT�[�r�X�Ȃǂɉ����Ċ�ƂƂ��Ắu�p�����v�ɂ����҂���ƂȂ�ƁAMOTU 1248 �ɌR�z���オ�肻���ȁB�B�B
����A��������ƌ����A�������܂��B
�����ԍ��F25287022
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɁA�A�A
Antelope Orion Studio Synergy Core (OSSC)�@�́AADC�ɂ� AKM�̍���ADC�`�b�v�R�i�R���Ǝv���܂��B�j�����p���Ă��܂��B
ASR �� PM�i�l�ԘA���X���b�h�j�ŁA��������� Antelope OSSC �̓�����ʐ^�����������Ă���܂��B�����䋻��������AASR ��PM�V�X�e���ŃV�F�A�����Ă��������܂��B
�����ԍ��F25287035
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
���Q�ɒ���
��MOTU 1248 �ɌR�z
�L�͂��Ǝv���܂��ADAC�̗��z�͐M���ł���q��
���y���Ȃ特�����܂ރC�R���C�W���O�Œ���
���ȒP�B
�����ԍ��F25287114�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����A�F����
�ŋ߂́G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-many-people-want-a-12-channel-or-16-channel-dac-and-a-7-channel-or-12-16-channel-power-amplifier.41498/page-4#post-1614618
�ɂ�����������܂��āALAN/WAN�o�R�� Audio�M���`���v���b�g�t�H�[���Ƃ��āADANTE�i���C�Z���X����A�L���j�Ƌ����܂��͂�����ւ��� Ravenna�v���b�g�t�H�[���i�����A�I�[�v���\�[�X�AOpen/Free Audio Over IP�j�ɂ��ď����W���w�K���ł��B
https://www.ravenna-network.com/what-is-ravenna/
DAC, DAC-DAC�i�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�j �Ȃǂ̋@�킪�n�[�h�I�Ɂi�Ƃ����Ă�LAN�|�[�g�j����у\�t�g�I�� Ravenna�ɏ������Ă���A Cat.5e �ȏ��LAN�P�[�u���� PC�ȂǂƐڑ����āAASIO, WASAPI �Ȃǂ��A�قڃ[�����C�e���V�[�i�[���x���j�ŁA��ʂɁi192 kHz 24 bit 36-Ch ���x�Ȃ�y���A�y���I�j���̂܂ܗ����邱�Ƃɉ����āAAES/EBU���܂ޑS�Ẵv���s��̓]���v���g�R�[���ɑΉ����Ă���悤�ł��B
USB 2.0 �ł�ASIO�i�ш搧�����l�b�N�j�Ƃ́A���S�Ɂu������v�ł���킯�ł��ˁBThunderbolt �Ή��ւ̈ڍs���l���Ă��܂������A����ɂ��u������v�A�ł��ˁB
�������A�l�b�g���[�N�� IP�A�h���X�n�́Ahome LAN ��DHCP�n�Ƃ͓Ɨ�������ׂ��ł����APC���ŕ�����GB-LAN�|�[�g������A���̂ЂƂ� Revenna ��p�ɂ��邱�Ƃ͋ɂ߂ėe�Ղł��B�܂�PC��LAN�|�[�g���ЂƂ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A������ PCI-GB-LAN�J�[�h�ő��݂��邱�Ƃ��A�������ȒP�ł��B
LAN�݂̂Ȃ炸�A�ʐM���x�ƈ��萫�����m�ۂł���AWAN���A���Ȃ킿�C���^�[�l�b�g�o�R�ł̓`���ł��V�[�����X�ɋ@�\����悤�ł��B
���łɁA��Ƀv���ƊE�ł�DANTE�i�L���j���ւ���v���b�g�t�H�[���Ƃ��čL���g����悤�ɂȂ��Ă��Ă���̂����m��܂��A���ɂ͏����ł����̂ŕ����ł��B
�����ɂ悵����ABAWS����A��낵������o���i����j�A���ӌ��ȂǁA���������������B
�����ԍ��F25288298
![]() 0�_
0�_
Revenna �Ή��̑��`�����l��DAC�̑����́A
Merging Technology�i�X�C�X�j �� HAPI MkII �ł��B
http://dspj.co.jp/products/merging/Hapi_overview.htm#spec
https://dspjapan.shop-pro.jp/?pid=166740118
16-Ch �ɂ���ɂ́ADA8�^HAPI 8ch DA�g�����W���[���iup to PCM 192kHz�j���Q���I�G
https://dspjapan.shop-pro.jp/?pid=166740542
���K�v�ł��̂ŁA���z�� \469,700 + \440,000 = \909,700 �ƂȂ���ɍ����ł����A�����_�ł͋��ɂ� 16-Ch DAC �ł���Ǝv���܂��B
DSD256 �܂őΉ����� DA8P ���W���[��������܂��B
DA8P�^HAPI 8ch DA�g�����W���[���iPCM 192kHz/DXD/DSD256�j
https://dspjapan.shop-pro.jp/?pid=166740557
����́A�Ȃ�ƂP���� \320,100 �ł��B
����A���̂Ƃ���A���A���ł����A�����[�����i�ł͂���܂��I
�����ԍ��F25288354
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@MOTU M4��^���Ɏg���Ă��܂����A�v���@��̗L�̓��[�J�[���������ā@�l�i�̊��ɂ����ƍ���Ă���Ȃ��Ƃ�����ۂł��B
�@���͂��낢��o�Ă�̂ʼn��������₷�����_(^o^)�^
�@DANTE�́@�W�����������ċ@�킪�[�����Ă�����ۂł��B
�@�������ALAN�o�R�̃p�P�b�g�ʐM�Ȃ�Ł@�r�b�g�N���b�N���x�̓������ł���́H���^��ł����B
��Merging Technology�i�X�C�X�j �� HAPI MkII
�@�������茩�������ł����@Word Clock��IN/OUT���o�Ă��ā@���̂ւ�͔�����Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂����B
�@�g������Ă��@�d���n�͂���������Ɠd���R���z�u���Ĉ��艻�����ق����ǂ��Ƃ͎v���܂����A�z������烌�C�A�E�g�͎茘����ۂł��ˁB
�@�{�[�h���i�Ƃ��Ă͍����ł����A�R���g���[���[�̃t�@�[���E�F�A��PC���̃A�v���J����Ȃ̂Ɓ@�n�C�G���h�̃v���@����Ŕ���鐔�����Ȃ���Ł@����Ȃ���Ȃ����Ǝv���܂��B
�@����Ɓ@PC����DANTE�{�[�h��������������������ۂ�����̂ƁA�ł����獂���x���[�h�N���b�N�ʼn^�p��������˂��@�Ǝv���ƂR�����~�����̂ł����A���l�i�ȊO�͗ǂ������ł��ˁB
�����ԍ��F25288476
![]() 1�_
1�_
Merging Twechnology �� HAPI MkII �p DAC �{�[�h�ADA8 (IOM-H-DA8) / DA8P (IOM-H-DA8P)�@�ɂ́ADAC�`�b�v�Ƃ��� ESS �� ES9028PRO �����ڂ���Ă��邱�Ƃ�m��܂����B
http://dspj.co.jp/products/merging/download/New version of DA8_DA8P module.pdf
�W�`�����l����ESS DAC�`�b�v�ł��̂ŁA���̌X���Ƃ��Ă� OKTO DAC8PRO �iES9028PRO�j��AMOTU 1248, MOTU 16A �i������� ESS ES9016S Sabre32 Ultra ���Q��) �Ǝ��Ă��邱�Ƃ��z������܂��B�����Ƃ��A�����͌�i��preamp �`�b�v�ɂ��e������邱�Ƃł��傤���B�B�B
�����ԍ��F25289248
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����
��قǁA�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-many-people-want-a-12-channel-or-16-channel-dac-and-a-7-channel-or-12-16-channel-power-amplifier.41498/post-1623795
�ɂ������܂������AAntelope�Ёi�A���e���[�v�Ёj�� Orion Studio Synergy Core (OSSC) ����� Orion 32+ Gen3 �ɁA�������ڂ��Ă���܂��B
����OSSC �ł́ACirrus Logics �̃t���b�O�V�b�v�i���́j�Q�`�����l��DAC�`�b�v CS43918 ���P�Q�g�p���A�A���e���[�v���`���ƋZ�p���ւ�i���E�g�b�v�N���X�H�j�N���b�L���O�Z�p����g���āA���v�Q�S�`�����l��h�o�͂��������Ă��܂��BCS43918 �́ADSD256 �ɂ��Ή����Ă��܂����AOSSC�ł� 192 kHz 24 bit �܂ł��u�]�T�������āv��g���Ă���悤�ł��B
Antelope �̐v�R���Z�v�g�́A���̎�v�ȃ}���`�`�����l�� DAC-ADC ���[�J�[ (MOTU�AREM�AFocusrite�ATASCAM�ȂǁA����ɂ� Merging Technology)�Ƃ͑傫���قȂ�܂��B����瑼�Ђł́A�}���`�`���l�� DAC-ADC ���j�b�g�� ESS �܂��� AKM �}���`�`���l�� DAC �`�b�v (�ʏ�A�`�b�v������W�`���l��) ���g�p���Ă��܂��B
�����āA�悭�m���Ă���悤�ɁAAntelope �̓I�[�f�B�I �N���b�L���O����� �ō���̃e�N�m���W�[��~�ς��A���E�̃��[�_�[�̂ЂƂɂȂ�܂����B���Ђ̃N���b�L���O�Z�p�ƂQ�`�����l�����Ƃ� �P�̎��DAC �`�b�v�𓋍ڂ����v�̑g�ݍ��킹���A���ׂĂ� DAC �o�̓`�����l���̗D�ꂽHiFi�����Ɍ��ʓI�ɍv������Ǝv���܂��B
���̓z�[��HiFi �I�[�f�B�I�ݒ�Ń}���`�`�����l�� (12 �`�����l���ȏ�) DAC(-ADC) ���j�b�g���g�p�������ƍl���Ă��邽�߁A���̓_�͏��Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͔��ɏd�v�ł��B
����ɁAOSSC �� O32G3 �́AAntelope�Ђ����ӂƂ��Ă���I�[�u�����x���䐅�����U�탂�W���[���𓋍ڂ��A�����64 �r�b�g���x�����N���b�L���O�̃}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^�[/�f�B�X�g���r���[�^�[�Ƃ��Ă��@�\���邱�Ƃi�Љ�T�C�g�Œm��܂����B
����ARME�AFocusrite�AMOTU�AMerging Technology �̐��i�����r���[ (����є�r) �������ʁA�ނ�͍ŋ߁AAVB�ADante�ARavenna�Ȃǂ̃C�[�T�l�b�g��̃f�W�^��I/O������G���N�g���b�N/�G���N�g���j�b�N �~���[�W�b�N�̃��C�u �R���T�[�g��z�[����������Ȃǂ̃v���t�F�b�V���i���ȃ}���` I/O��x���A�v���P�[�V�����ɏd�_��u���Ă���悤�Ɋ����܂��BDAC �`�b�v�̑I���́AES9016 (�܂��� 9018) C370 Sabre 32�AES9028S�AES90318S �Ȃǂ̃}���`�`�����l�� DAC �`�b�v�̗��p�ɗ��܂��Ă���悤�ł��B
�������A������ ESS DAC �`�b�v�̏o�͉��������łɂقڍō�������HiFi ���x���ɒB���Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă��܂��B���ہA���͌��݁A�W�`�����l���o�͗p�� 1 �� ES9028PRO ������� OKTO DAC8PRO ���g�p���Ă���A���ɖ������Ă��܂��B
����ł́ABOWS���w�E�̒ʂ�ADAC���j�b�g�̉����́APCB�v�����łȂ�PS�i�R���f���T�j���W���[����v���A���v���W���[���ɂ��ˑ����܂��ˁB
���ɍK�^�Ȃ��ƂɁAANTELOPE �͓��{�ɂ��Ȃ�D�ꂽ�T�|�[�g�ƃT�[�r�X �l�b�g���[�N/�g�D���ێ����Ă���悤�ł��B�i�����̓u���K���A����̃����[�g�T�|�[�g�ł��傤���B�j MOTU�ARME�AFocusrite�AMerging Technology �����l�ł��傤�B
�\�ł���AAntelope OSSC (�܂��� O32G3) �� MOTU 16A �̊Ԃ̃z�[�� �I�[�f�B�I �Z�b�g�A�b�v/���ł̃e�X�g/��r�Z�b�V��������z�������ƍl���Ă��܂��B
�Ƃ���ŁA���Ȃ�x����Ȃ���AOSSC (����т��̑��̋Ɩ��p DAC-ADC) �� D-Sub 25 (DB25) �A�i���O�o�͂��A������ TASCAM �݊���/DB25-to-8 �̃s�������ŕW��������Ă��邱�Ƃ��m��܂����BDB25-�I�XXLR �P�[�u��/�A�_�v�^�[�͓��{�ł��L���荠�ȉ��i�œ���ł��܂��̂ŁA���̓_�̕s���͉�������܂����B
�A���e���[�v�Ђ̐v�R���Z�v�g�A�ǂ̂悤�Ɏv���܂����H�@���肷���̍ۂɂ�����������������K���ł��B
�����ԍ��F25300911
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�@�����ɂ悵����
Antelope �Ђ�OSSC�Ŏg���Ă��� Cirrus logic ��DAC�`�b�v CS43198 �ɂ��āA�ЂƂ��O�i�����I�H�j�Ȃ̂́A�o�͓d����4V�ł͂Ȃ��A�����̂QV�ł��邱�Ƃł��B
https://www.cirrus.com/products/cs43198/
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS43198_DS1156F2.pdf
����́A���o�C���@�ނȂǂւ̓��ڂɂ�����ȓd�͂��l�������v�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������AOSSC �̃v���A���v�\����DAC�@��W���̂SV�̏o�͂��������Ă��܂����A�����ʂł̓v���A���v���W���[���i�Ɠd���H�j�̑I���Ɛv���d�v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����@�ł��܂��B
�e���ŁAOSSC �́ARME �� MOTU �Ɣ�r����ƖF���ŁA��������A�F�C�i�H�j������A�����Ə�����Ă���A���ɒቹ���L���ł�������Ƃ��Ă���A�i�N���V�b�N���y�ɂ͍œK���H�j�A�Ƃ���Ă��邱�Ƃ́A���́u2V�A�E�g��4V�֏����v�ɂ��A�����Ă�̂����A�Ƒz�����Ă���܂��B
�܂��A���̂�����܂Ō@�艺����ƁA�P�ɉ����ɑ���D�݁^�n�D�̑I����ɂȂ肻���ł����B�B�B
�����ԍ��F25301095
![]() 0�_
0�_
�ŋ߂̂������̓��e�ɂ����āG
�i��j CS49138�@�i��j CS43918
(��) CS43198
�ł������܂��B
�����ԍ��F25307550
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
��Ravenna�v���b�g�t�H�[���i�����A�I�[�v���\�[�X�AOpen/Free Audio Over IP�j�ɂ��ď����W���w�K��
�q�����܂������A������dualazmak������2���x��ł���
��Antelope ���O�A�o�͓d�����QV
�����g�M���`���ł͒�d�����L���ł�
ex.�jLVDS
�U�������t�ˏ��Ȃ��A��������
���A���e���[�v�Ђ̐v�R���Z�v�g�A�ǂ̂悤�Ɏv���܂����H
firewire�AIEEE�AUSB�ƍ����I�ɗ�������
TASCAM �݊��ɂ��������͍D�������Ă܂�
��Ravenna�����A LAN�P�[�u���ŁAASIO, WASAPI �Ȃǂ��A�قڃ[�����C�e���V�[�i�[���x���j
�f���炵��
�ł�PC�Őݒ��́ASPDIF��
PC�Ɛ藣���Ďg����̂��ق����ł�
�iPC�I�[�f�B�I�̘g�O�g�p�j
�����ԍ��F25309140�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����A
����ہA���肪�Ƃ��������܂��B
Antelope Orion Studio Synergy Core (OSSC) �́A���ɋ����[���A�������������W���ł��B
�����ɂ悵����ABOWS����A
�v�����������̗l�X�� DAC-ADC �i�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�j�߂Ă���ƁAWindows 11 Pro PC����Thunderbolt 4 (TB4) �ŁA�]�T�]�T�Ńf�W�^���M���𑗂肽���Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B�i���́A���������Windows�h�ŁAApple Mac�͎g�������Ƃ��Ȃ����A��������ϐl�ł��I�j�B
�����ŁAM/B�� TB4 ���g�ݍ��܂�Ă��āA�t�@�����XCPU�N�[���[�ŁAZ790 �`�b�v�Z�b�gM/B �ŁA�É��i���������j�́u���^�vPC��g�މ\�����T���Ă��܂��B
����������������ł́A
M/B: Asrock Z790 PG-ITX/TB4
CPU cooler: Noctura NH-P1
CPU: Intel Core i7-13700T [1.4GHz/16�R�A(P�R�A8+E�R�A8)24�X���b�h/UHD770/TDP35W] Raptor Lake-S(�����d�͔�)
PC Case: Fractal Design Define 7 Mini�@�i���É��@Noctura�t�@����w�ʂ�1�����ʼn^�p�������B�j
PS: Fractal Design ION+2 Platinum 660W (FD-P-IA2P-660)�i�Z�~�t�@�����X Zero RPM�Ή��j
�Ȃ�ȒP�ɑg�߂����Ǝv���Ă��܂��B�i�����\GPU�͕s�v�ł��̂�CPU����GPU��M/B�� HDMI, DP Ports �ŏ\���ł��B�j
�������A
DDR4-3200 128GB
OS SSD: M.2 PCI-E Gen4x4 500GB
Data SSD: M.2 PCI-E Gen4 4x4 2TB
�������z�肵�Ă��܂��B
�����ԍ��F25309395
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
���ڂ��Ă��铯���|�C���g�\�[�X��^�u�b�N�V�F���t�^�C�v�� MoFi SourcePoint 10 �ɂ��āA�悤�₭���Ȃ�ڍׂȑ���f�[�^���܂ޕ]�����|�[�g�����\����܂����B
https://www.erinsaudiocorner.com/loudspeakers/mofi_10/
MoFi�Ђ�����ꂽ SourcePoint 10 �̕]���ł��̂ŁA������������ēǂޕK�v�����邩���A�ł����A�����čD��ۂ������Ă��܂��B10°�` 30°�� off-axis �ł̎w�������x�X�g�������ł��̂Ŏ��̊��i���ESP�Ԋu���Q���A���X�j���O�|�W�V�����܂łR�D�R���ASP�Q�͓��U��Ȃ��ŕǂƕ��s�z�u�j �ɂ��}�b�`�������Ɏv���܂��B
�������ɁA40 Hz �ȉ��̍Đ��͍���ȗl�q�ŁA�u�D�ꂽ���^�T�u�E�[�t�@�[�i���E�I�j�Ƒg�ݍ��킹����A���Ȃ肢���ł��傤�B�v�A�Ƃ�������Ă��܂��B���̈Ӗ��ł́AFOSTEX CW250D 2��i���E�j�Ƒg�ݍ��킹��Ɩʔ������ȁA�Ɩ��z���Ă���܂��B
�쓮�A���v�́A�莝���� Accuphase E-460 �܂��́@Yamaha A-S3000 �P�ƂŁA�������㗬�� PC���� EKIO�� XO/EQ/delay �̓R���g���[���A�A�A�ȂǂȂǁA�����Ă݂����ł��ˁB
DAC�́ADAC8PRO��2-CH���p�A�܂��� OPPO Sonica DAC, �܂��͍��ł��f���炵�� ONKYO DAC-1000 �������ł��B
���{�ŁA�����ݏo�̉\���́H�H�H
�����ԍ��F25312946
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
��M/B�� TB4 ���g�ݍ��܂�A�t�@�����XCPU�N�[���[�ŁA�u���^�vPC��g��
PC�͏ڂ����Ȃ��Adualazmak����ɃC���X�g�[���������Ē������x���Ȃ̂�
���Ƃ������ł����ł��B
M/B��3�A4���~�̃~�h���ȏオ�悢�ł��A
�R�X�g�팸�ł悢M/B�̎������Ȃ������̂�2���~�ȉ��ɂ�����2�����o�������������܂���
SATA�̖{��6�ŃX�g���[�W�s���ɂȂ�lj��p��PCI�{�[�h�t������A�N�������x��
�d����肪�キ�A���M�ƌ����Ńx���`�ɉe��
�莝���̌Â��p�\�R���ʼn��y�Đ����Ă݂܂������A
CPU�͒�X�y�b�N�ł��悳�����ł���
�M�K�w���c��PC�ʼn��y�͎d���̔��e�ɂȂ��̂����A
�����f�����H�Ƃ��Q�[�������Ȃ��̂ł����
TB4�ړI�Ƃ��A�t�@�����X�Ȃ����GPU��TPD�̒Ⴂ�^�C�v���悳�����ł���
�����ԍ��F25316088
![]() 1�_
1�_
�F����
�֑��ł����AASR Forum �ɂ����鎄�̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�ւ̉{���K����Q�O������܂����B
�ihttps://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc�j
ASR�́A�L����`���F���Ō��₷���A���Ƃ��Ă͉^�c���j���C�ɓ����Ă���܂��B
�`���́G"Come here to have fun, be ready to be teased and not take online life too seriously. " ���A�����ł��ˁB
Forum �̎d�g�݂���Ă���u���O�`���\�t�g�E�F�A�@Community platform by XenForo�@�����ɗD����̂ŁA�\����n�C�p�[�����N�@�\�A�ҏW�@�\�A�l�ԘA��PM�@�\�A���v�@�\�A�ȂǂȂǏG��ł��B���������e��Q���҂��ʐ����ł��邱�Ƃ́A���i.com ���܂ޑ��̃I�[�f�B�I�t�H�[�����T�C�g�Ɠ��l�ŁA"not take online life too seriously�I" ����{�ł��ˁB
���̎�ÃX���b�h�����Ȃ蒷��ɂȂ��Ă���̂ŁA����ɑ���@�u�n�C�p�[�����N�ڎ��v�@���쐬���āA�K�X�A�X�V���ێ����Ă��܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-23#post-961964
��
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/hyperlink-index-for-the-specific-thread-on-multichannel-multi-driver-multi-way-multi-amplifier-stereo-project-using-multichannel-dac.27831/
�ł��̂ŁA���ɂȐ܂�ɁA���Η��A�����p�������B
�����ԍ��F25317657
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@����X�s�[�J�[�E�G�ŗL���l�̐Γc����̃��X�j���O���[����K�₵�ā@�@�ވꎮ��������ŋ�C�^�����Ă��܂����B
�@���̍쐬�������C���X�s�[�J�[�V�X�e���̍Đ�������������ł����̂Ł@�����Ɣ�r����`�Ŕ�r������쐬���܂����B
https://www.youtube.com/watch?v=ENg5NGMgReU
�@�g�p���Ă��郆�j�b�g�͈ȉ��̂��̂ł��B
D3404/552000
https://www.scan-speak.dk/product/d3404-552000/
18WE/4542T00
https://www.scan-speak.dk/product/18we-4542t00/
18WU/4747T00
https://www.scan-speak.dk/product/18wu-4747t00/
26W/8867T00
https://www.scan-speak.dk/product/26w-8867t00/
26W/8861T00
https://www.scan-speak.dk/product/26w-8861t00/
�@�c�B�[�^�͏_�����z�f�ނɎ������ܐZ�����e�L�X�^�C���h�[���ł����A�{�C�X�R�C�����ȉ~�`�Ł@���c�~�Ŗ��ƂȂ������g���̋��U�Ɓ@���E�̎w�����̍L�����J�o�[����ǂ����j�b�g�ł����i�l�i���ǂ����ǁj
�@�����A���ܐZ�̋��U���g�������悩���ɒǂ�������n�[�h�h�[���̃��j�b�g���悭�����̂ł����A����ɂ���ׂď_�炩�����ljs��������Ȃ��A�ǂ��o�����X�ł����B
�@�~�b�h�o�X���@�ȉ~�{�C�X�R�C���̃l�I�W�E���}�O�l�b�g�̒��⎥�C��H�̐������j�b�g�ł��B
�@����A�����ɒl����X�s�[�J�[���j�b�g���Ǝv���܂��B�i�w�����邩�͒u���Ƃ���....�j
�����ԍ��F25342289
![]() 3�_
3�_
BOWS����
���ɋ����[���q���A�q�������Ă��������܂����B
�^���̂���J�A���@���\���グ�܂��B
�����A�����悤�ȁA�l�X�ȉ����ɂ���r�����i�D�ꂽ�}�C�N�͎����ĂȂ��̂ŁB�B�j��p�ɂɍs���Ă���̂ŁA���x�����킹���܂߂�����J�𗝉��ł��܂��B
�ȑO�A���m�点���܂������A���� Audio Sampler/Reference Playlist �́A�����ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1348148
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1356792
D3404/552000 �͂ƂĂ��悳�����ł��ˁB�������܂����A���ケ��𓋍ڂ�������SP�̓o��ƃ��r���[�����҂��܂��B
�Γc����̃��C���V�X�e���̎p�́A�t�H�[�J���̃��[�g�s�A Grande Utopia Evo�AGrande Utopia EM Evo ��A�z�����܂��ˁB
�����ԍ��F25342802
![]() 0�_
0�_
�����ƁA�ȉ~�Z���^�[�̃~�b�h�o�X�́A������ł��ˁB
18WE/4542T00
https://www.scan-speak.dk/product/18we-4542t00/
�X�y�b�N�V�[�g�����܂������A���͓I�ł��ˁB
�����ԍ��F25342914
![]() 0�_
0�_
�T�u�E�t�@�[�Ƃ��āA�Q���A���͗����ł���̂ł����A�������j�b�g�ł͂Ȃ��A�����ĈႤ���j�b�g��A�z����Ă��闝�R�́H
26W/8867T00
https://www.scan-speak.dk/product/26w-8867t00/
26W/8861T00
https://www.scan-speak.dk/product/26w-8861t00/
������x�̑z���͂ł���̂ł����i�����U���ɗ͔����邽�߂Ɋ������ʂ��قȂ郆�j�b�g��A�������H�j�A���{�l�� BOWS����̂��l����������������������K���ł��B
�Q�̃T�u�E�t�@�[�ɂ��āA�����قȂ� XO/EQ ��ݒ肳��Ă���̂ł��傤���H�@����Ƃ��A�S�������M���ŋ쓮�H�H
�����ԍ��F25342926
![]() 0�_
0�_
������A���������������B
�������A�SSP�Q�ɂ��Ċ����ȃ^�C���A���C�������g���m������Ă�����̂ł��傤�ˁB
���̏ꍇ�A������@�Ɛݒ���@�́H�@�\�Ȃ炲�����������B
�����ԍ��F25342935
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@�T�u�E�[�t�@�[��2��ވႤ���R�͕������т�܂������A�~�b�h�E�[�t�@��2��ނȂ̂́A�ŏ�1�{�����Ďg���Ă�����A�����Ɨǂ��ȉ~���C��H�̗ǂ����̂��o����Ŕ��������ā@2�{�g������ǂ���������Ƃ���������Ă܂����B
�@�ŏ�����p���Ŏg�����߂ɂS�{�������킯�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝא����܂��B
�@�ł��A�قȂ��ނ̃T�u�E�[�t�@�������Ďg���Ă����ʃI�[���C�Ƃ�
�@�^�C���A���C�����g������ĂȂ��ā@�{�l�H���u�e�L�g�[�ɒ����v�����炵���ł����A�����܂�������Ōo���L�x�ȕ��Ȃ�Ł@�u�e�L�g�[�Ȓ����v�̃��x������l���킵�Ă��ā@���ƌo���ł��̂������N�I���e�B�̃X�s�[�J�[������Ă܂��B
�����ԍ��F25343064
![]() 4�_
4�_
2023/07/14 17:03�i1�N�ȏ�O�j
������ǂ�����
�u����ǂ�����̘^���@���C���@vs�@���ȁ@�����@�v���C���[�o�́i���Y�p�C�I�[�f�B�I�j�@�����@W8-1808��C�^���v
http://bhbs480.blog.fc2.com/blog-entry-1872.html#comment4437
�u���O�E�n�C�G���h����X�s�[�J�[�y�����Ǝ���̕����z
http://bhbs480.blog.fc2.com/blog-category-10.html�@
���Ȃ݂ɁA�ّ�̎������ł́A
�P�D�����@(wav �t�@�C��)
�͉��y�I�Ɋy���߂�Ƃ��Ă��A
�Q�D���������Y�p�C�I�[�f�B�I�̏o�͂����R�[�_�Ř^����������
�͑S���ʖڂł������B�P�ɔ�r���ĕώ������肷���āA���͂⒮���Ɋ����Ȃ��܂�Ȃ����y�Ɖ����Ă��܂����B
�Ƃ������A����J�l�ł����A����ǂ�����B
�����ԍ��F25343913
![]() 1�_
1�_
ListenFirstMeasureAfterwards����
�@�Q�l�ɂȂ邲�ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�@���y�̍Đ��Ɓ@���ɘ^���Ɋւ��Ắ@�܂������Ŏ��s���낵�Ȃ���O�ɐi�����Ƃ��Ă���̂Ŏ���ʂƂ���͑��X���邩�Ǝv���܂��B
�@��������ӌ���������������肪�����ł��B
�@�����́Adualazmak�����Ă��X���ł��̂Ł@�ł��܂�����Youtube�̕����A�l�����Ă��X���ɓ��e�������������ł��B
�@ListenFirstMeasureAfterwards����ɂ́A�ߋ��Ɋy�Ȃ̑I�����܂�Ȃ��Ƃ������ӌ������������܂������A����̓v���C�o�b�N���܂�Ȃ��Ƃ������ӌ������������܂����B
�@�����Ł@2�_���肢������܂��B
�@1�_�ڂł���
�@�w�E�����������悤�ɁA���J����Ɋւ��Ă͂܂��܂�����Ȃ��Ƃ��낪����̂Ł@��������P��i�߂Ă��������Ǝv���܂��B
�@�����Ł@�ǂ��������Ɗ�������������ListenFirstMeasureAfterwards����������悤�ȉ��y���̂���I�Ȃ�������ŁA���y�I�ɖ����ł���悤�ȍĐ����̘^�������Ă��������A���ȂƍĐ����̔�r��Ƃ��Č��J�������������ł��B
�@�l�́AListenFirstMeasureAfterwards���y�I�ɖ����ł��Ă��铮����r�����̃��t�@�����X�Ƃ��ĉ��P�ɋ��݂����Ǝv���܂��B
�@2�_�ڂł���
�@ListenFirstMeasureAfterwards����̎��g�̃X���ł��낢���r�������ĕ]������Ă��܂����A�\�������w�I��������A���̐���������Ł@�l�̂悤�Ȋ����̒Ⴂ�l��ɂ́@�����Ⴄ�̂������ς�킩��܂���B
�@���܂��ẮA1�_�ڂ̂��肢�ō쐬���ꂽ������e���v���[�g���āA��r�@��̍Đ�����Ƃ��ĕ��ׂČ��J���Ă�����������Ő������Ă��������Ɓ@���ƕ]���̕R�Â����o���Ĕ[���������Ǝv���܂��̂Ł@��r�����f�[�^�Ɖ�����Z�b�g�Ō��J���Ă����������ł��B
�@�l�݂̂Ȃ炸�A��������̐l�̖��ɗ��Ǝv����̂Ō�肢���܂��B
�@�l�̂悤�ȉ��y���̒Ⴂ�l�Ԃƈ���ā@�o���L���Ŋ����̍���ListenFirstMeasureAfterwards����Ȃ�A�T�N�T�N��������J�����������Ǝv���܂��̂Ŋy���݂ɂ��đ҂��Ă���܂��B
�����ԍ��F25343979
![]() 4�_
4�_
2023/07/14 18:35�i1�N�ȏ�O�j
��BOWS����
Linn Specialist ����� YouTubes �͉��y�Ƃ��ĖO�������Ȃ��ł��ˁB
https://www.youtube.com/watch?v=jxFtreEI1o0
https://www.youtube.com/watch?v=CytQnz7fDTI
https://www.youtube.com/watch?v=3y_X5RbdP4Q
Benz Micro LP-S ������ł��邱�Ƃ������� YouTubes ����͂�����Ɣ���܂��ˁB
���}�� YouTubes �̂��Q�l�܂ŁB
�����ԍ��F25343998
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@�Ȃ@�{�Ƃ͈قȂ闬��ɂȂ��Ă������߁A����ȏ�@dualazmak����̃X���������̂��ǂ��Ȃ��Ǝv���܂����̂Ł@�X�������L�ɕ����܂����B
���P�P�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO...�@����̕���X��2023/07/16 13:11
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25346496/#tab
�@�����������Đ\����܂���ł����B
ListenFirstMeasureAfterwards����
�@�{���Ɋւ��́@�ȍ~�@����X���ɏ������ނ悤�ɂ��肢���܂��B
�@
�����ԍ��F25346514
![]() 1�_
1�_
BOWS����
����Ȃ邲�z���A���S�����A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�������A�d�X���@���\���グ�܂��B
dualazmak
�����ԍ��F25347241
![]() 0�_
0�_
BOWS����
�S���t�قȂ̂ł����A���́i�����j�����ŋ߂ɂȂ��� ASR���Ԃ���̑����̗v���ɉ�����`�ŁA�R�����g�s�� YouTube �r�f�I�̃A�b�v���[�h���J�n���܂����B
���쌠�Ȃǂɂ��ẮA��{�I��YouTube �̎��O�R����M�����Ă���A���̂Ƃ��돜�O�i�f�ڕs�j��x���͎���Ă��܂���B���f�ڂ���Ă�����̂����܂Ōp������邩�A�����폜����邩�AYouTube �́u�h�f�l�v�ł��̂ŁA�F�ڕs���ł͂���܂����B�B�B
���ɂȐ܂�ɁA���Η��������B
- Dancing video of my IEC 60268-17 compatible large glass-face DIY 12-VU-Meter Array
_____Part-1: with "High Frequency Linearity Check Track" of Sony Super Audio Check CD: #750
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1562861
_____Part-2: with typical "Full Orchestra Music"-1: #751
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1562866
_____Part-3: with typical "Full Orchestra Music"-2: #752
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1562867
_____Part-4: with typical "Jazz Piano Trio Music": #753
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1562874
- Five "real air-recorded transient-sound tracks" of Sony Super Audio Check CD played and analyzed by MusicScope 2.1.0: #760
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1600038
�����ԍ��F25347378
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����
�܂��܂��I�̊��͐@���Ȃ��̂ł����AASR Forum �ɂ� DSP�\�t�g�E�F�A�x�[�X�̃I�[�f�B�I�V�X�e���ŁA�T�u�E�t�@�[�ƃE�[�t�@�[�̊Ԃɂ�����^�C���A���C�������g�����Ɋւ��鏭�X�f�p�ȃX���b�h�����Ă��ď��������s���Ă���܂��B
"Compensating for mains and sub delay"
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/compensating-for-mains-and-sub-delay.46331/
���̘b��ɂȂ�ƁA�����Ȃ���AREW�� RePhase ���u�����ŕ��G�œ���ȁH�v���@�ŗp���āA�x����ʑ���]���ώ@������邱�Ƃɖ�N�ɂȂ��Ă�������X���o�ꂵ�āA���Ȃ�u�u���b�N�{�b�N�X�v�ǂ��Ղ�ȗ��_��V�~�����[�V�����̏Љ�A���X�Ƒ����X��������܂��B
�����ŁA�u�^�C���A���C�������g�v�����ɓ������āA���́iBOWS����A�����ɂ悵���w���́j�A�W�g�A�R�g�A�P�g�̃g�[���o�[�X�g�i�����g�\���̋�`�g�[���o�[�X�g�g�j��p�����G
�P�D�g�[���o�[�X�g�g�^�C���V�t�g�@�ɂ�鑪��ƒ���
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1048913
�Q�D300 msec���̒��S�ɑ��d���g���g�[���o�[�X�g��ݒ肵���G�l���M�[�s�[�N�}�b�`���O�@�ɂ�鑪��ƒ���
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1049923
�R�D�P�ꐳ���g�̌����Ȕg�`�}�b�`���O�ɂ�� 0.1 msec ���x�̑���ƒ���
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1061868
�������悤�ɁA�����̌��ʂ�REW-RepHase�ƑΔ䂷��ׂ��A�ƒ�Ă����Ƃ���A�����̕��X���狭���S�����A���������̂��߂ɍ쐬�����e��̃g�[���o�[�X�g�M���̌l�Ԃł̋��L���i�߂Ă��܂��B
�Ⴆ�AREW-RePhase �̓`���t�̂悤��OCA���́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/compensating-for-mains-and-sub-delay.46331/post-1655530
�ŁA�u�g�[���o�[�X�g�ɂ�钲���́A����܂ł�������Ƃ��Ȃ��̂łƂĂ���������i�M�������L���Ă���I�j�v
�������ŁA�܂��A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/compensating-for-mains-and-sub-delay.46331/post-1655560
�ł́A�u���Ȃ��̂R�̕��@�́A�ƂĂ����܂��@�\���Ă���悤�ł��ˁB�v�Ǝw�E����Ă���A�ނ֑��������̐M���ŁA���ۂɌ�����i�߂Ă��܂��B
����AOCA�����܂߂āA���̂R�̕��@�� REW-RePhase �Ō����Ă����悤�ȓ��e�����҂ł������ł��̂ŁA����s���𒍖ڂ��Ă���܂��B
���I�ɂ́A���Ɓu�^�C���A���C�������g�v�Ɋւ��ẮAREW-RePhase �̂悤�ȁu�u���b�N�{�b�N�X�v���ڂ̏����⒲���ł͂Ȃ��A�������\���ɗ����ł��āA���x��Č������m�F�ۏł��Ă���A���́u�f�p�ŊȌ��ȁv�R���@�Ŏ�����Ă���̂ł����A��O�҂� REW�₻�̑��́u�����ȁv�\�t�g�ł������Ă����Ȃ�A���̂R���@�̔F�m�x�ƕ��y�̌���Ɍq���肻���Ȃ̂ŁA�Ȃ�ׂ��^���ɑΉ����Ă���Ƃ���ł������܂��B
�u���̓����v�ɂ�����ABOWS����A�����ɂ悵����̋��͂Ȃ��w���ɁA���炽�߂Ċ��Ӑ\���グ�܂��B
�����ԍ��F25348562
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
>�����ŋ߂ɂȂ��� ASR���Ԃ���̑����̗v���ɉ�����`�ŁA�R�����g�s�� YouTube �r�f�I�̃A�b�v���[�h���J�n���܂����B
�@���挩�܂����B
�@�l���A�b�v���Ă���悤�ȍא�̔�r�ƈ���Ĉ�Ȃ܂�܂�ł��ˁB
�@VU���[�^�[���U��Ă���̂��y�����ł��B
�@����݂�ƐU���́@Sub Woofer �� Woofer���x�z�I�Ȃ��Ƃ�������܂��ˁB
�@����̂����炬���A�g�̉��Ȃǁ@���R���͉��y�ƈ�������z�i���搬���������j�ɂȂ��Ă����Ȃ����Ǝv���̂Ł@����VU���[�^�[�Ō��Ă݂�Ɩʔ������Ǝv���܂����B
�@
>���쌠�Ȃǂɂ��ẮA��{�I��YouTube �̎��O�R����M�����Ă���A���̂Ƃ��돜�O�i�f�ڕs�j��x���͎���Ă��܂���B���f�ڂ���Ă�����̂����܂Ōp������邩�A�����폜����邩�AYouTube �́u�h�f�l�v�ł��̂ŁA�F�ڕs���ł͂���܂����B�B�B
�@���������폜������Ă܂�(��)
�@�C�[�O���X�̃z�e���J���t�H���j�A���@�r�[�g���Y���AJazz��Verve���[�x�����A�R���̑ΏۂƂȂ��Ă�����̂̊�͂悭�킩��܂���B
�@����̍��ł͌��J���Ȃ��Ƃ�������܂��B
�@���ۂɃA�b�v���[�h���ċʍӂ��邩�ǂ����Ŕ��f���邵���Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F25350305
![]() 1�_
1�_
BOWS����
�������������A���肪�Ƃ��������܂��B
��VU���[�^�[���U��Ă���̂��y�����ł��B
�I�[�f�B�I�E�ɂ����鋽�D�n�D��1�Ƃ��āAVU���[�^�[���D���ōS����X���A���E���ɑ��X�����܂��B
����ŁA����ȃX���b�h���A���܂ł������ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/douk-vu3-review-vu-meters.26827/
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/vu-meters-lets-see-em.487/
�Ƃ��낪�A�����ŏЉ�����̂́A�قƂ�ǑS�Ē������Ȃǂ̋UVU���[�^�[��M�~�b�N��VU���[�^�[�u���ǂ��v�ŁA���܂ł� IEC 60268-17 �̊�ɓK������ VU���[�^�[�͓���ȓ����v���p�r�������Đ����̔����I�����Ă���ADIY����I�[�f�B�I�E�G�ł͓���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
���́A���p�I�ϓ_������S�`�����l�����v�� 5-way 10-�`�����l���̃I�[�f�B�I�M���A�����SP���j�b�g�֓��͂����SP�n�C���x���M����VU���j�^�[�A���������邽�߂ɁA�M�d��IEC 60268-17�K���̐��V R-65 ��^�K���X��VU���[�^�[12���g���ĂP�Q�A��VU���[�^�[�A���C�����삵�ďЉ�܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1202570
�݂Ȃ���A������ď^���ĉ�����̂ł����A�Ȃ��ɂ́A�u�j�̋������܂߂āA�{���ɂ����� IEC 60287-17 �����œ����Ă���̂��H�r�f�I�œ����Ă���l�q�Ə؋��������Ă���I�v�@�Ƌ��̕��X�������܂��̂ŁA�u�T�u�E�[�t�@�[�`�����l������X�[�p�[�c�C�[�^�[�`�����l���܂ŁA������Ɠ����Ă���A�ƂĂ����ɗ����Ă܂���I�v�@�Ƃ����l�q�����������邽�߂Ɂ@YouTube �r�f�I�쐬�Ƀ`�������W�����킯�ł��B
������́u�ߓn�����v�̕]���ɍœK�ȉ����� MusicScope �Đ������r�f�I�T�{�ł����A�A�A
ASR �̂Ƃ���X���b�h�ŁA�ߓn�����̑���ƃ`���[�j���O�Ő���オ�肪����A���̉ߓn�����]���Ƃ��̌��ʂɊ�Â� XO/EQ/Delay �ݒ�̗l�q���Љ�Ă���܂����B���̓��e�́G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1065579
���́u�Ƃ���X���b�h�v�ł́A�ߓn�����́u��ϓI�{�q�ϓI�]���œK�ȉ����W�v�ɂ��Ă̏����������X����A������� Sony Super Audio CHeck CD ����K���������� MusicScope �ōĐ�����l�q�� YouTube �r�f�I�ł��Љ���A�Ƃ����o�܂ł��B
�ŋ߂́A���݂ł��S���������Ă��Ȃ� Sony Super Audio Check CD �g���b�N�̏Ɖ�i�l�I���L�v���j�����������Ă���܂��B�i�C�O�ł́A�قƂ�Ǔ���s�\�ł��B�j
�����ł��ڍׂɏƉ�܂����̂ŏƉ�������Ă��܂��B�B�B�B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1316155
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1341056
�����ԍ��F25350704
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
�ߋ�2�N�قǏ�����ȕ��@�AAUDIO-TECHNICA �� High-to-Low�R���o�[�^�[ AT-HLC150 ���g�����@�A�Ńc�C�[�^�[�iTW�j�ƃX�[�p�[�c�C�[�^�[(ST)���_��ȃQ�C���ݒ�Ŏg���Ă܂���܂����B
�_��ȑ��Q�C���ݒ肪�\�ł������AST���쓮����A���v�iA-S301)�̃{�����[���Q�C���́ATW���쓮����A���v�iTA-A1ES�j�̃{�����[���Q�C���̎x�z���ɂ���܂����B
����A��{�i�����j�ɖ߂��āATW��ST�����S�ɓƗ����ăQ�C�����䂵����������AHiFi�O���[�h�Ńv�����[�X�� [2-IN 4-OUT]x2 (L&R)���[�h XLR���C�����x���E�A�N�e�B�u���z��@BEHRINGER DS2800 �����܂����B
�ڍׂ́A��ɂ���� ASR Forum �̎��̃X���b�h�̂����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1674329
�ŋ��L���Ă���܂��̂ŁA���������������܂����炲�Η��������B
�����ł́A�����}��4�������A�\��t���Ă����܂��B
�����ԍ��F25368675
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@���傢�Ɓ@���������t���Ă���悤�ŏ������ǂ��������܂������A�����t�������Ȃ�ŏ����܂��B
�@Be-TW��Super-TW���X�v���b�^�ŕ����ēƗ��ɂ�����Ă̂͐������������ł��B
�@�������A�����Ɨǂ��������@�������Ȃ����Ǝv���܂����B
�@dualazmak����̎������@�̖��_�͂Q�_
�P�D�X�v���b�^�[ BEHRINGER�͑f�̂܂܂ł͉����ǂ��Ȃ��B
�Q�D�X�v���b�^�[�Ł@through ����Super-TW�Ł@Spritted����Be-TW�̕����ǂ�
�@�P�ł����ABEHRINGER�̐��i�͕��������Ă��Ď茳�ʼn^�p���Ă��܂��B
�@�������A�S�����c�S�ʑł��������R���f���T�����A�lj����ă`���[�����Ă܂��B
�@BEHRINGER�̐��i�ł����A��H�������̏o�����͈̂����Ȃ���ۂł��B
�@�R�X�g�̐���ŕ��i�̃O���[�h���Ⴂ���ƂƎ������C�}�C�`�Ȃ�Ł@�����̓{���[���Ƃ��đ������n�̉��Łu���[���A������܂������[�v�ƂȂ��ł����A�����ɔ��c�S�ʑł���������Ă݂�Ƃ��Ȃ艹�̗��������ǂ��Ȃ�A��O���[�h�̕��i����������Ɓu���̂��炢�o���@�������ˁH�v�Ƃ������ɃO���[�h�A�b�v���܂��B
�@�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�����������̉��̕ω���Youtube�ɃA�b�v���Ă��܂��B
https://www.youtube.com/watch?v=wswoyUNXT2k
��Type4-0��Type4-1�̔�r
�@�`���[�����Ďg���Ƃ����̂������Șb�Ȃ̂Ł@�����Ɨǎ��̃X�v���b�^�̕����ǂ��Ǝv���܂��B
�@�Q�D�ł����ATrough��IN-OUT�����Ł@Spritted���o�b�t�@�A���v���܂�����̐M���Ƃ���ƁA���R Through�̕����������A��m�C�Y�ł��B
�@dualazmak����̃V�X�e���ł́@Super-TW�����̂��������\���Ȃ�Ńm�C�Y�ɉߕq�ɂȂ�܂��B
�@�Ȃ̂Ł@Super-TW���Ɂ@��m�C�Y��Through���g���A��r����ƒ�\����Be-TW���ɁA�o�b�t�@�ʂ��ăm�C�Y�̑�����Sprited���g���������ǂ��ł��B
�@�S��I�Ɂ@Be-TW����Through���g���������Ƃ͗������܂����A�m�C�Y�I�ɂ͗ǂ��Ȃ��ł��B
�@�Ȃ��A�l�́@Through���Ƀo�b�t�@�A���v�������Ă��Ȃ��ƍl���Ă��܂����A�Ђ���Ƃ�����@Through���ɂ��o�b�t�@���v�������Ă��ā@�Q�C������������������������܂���B
�@��������ƑO����܂��B
�@�ł́A�ǂ���������悢���ł����A
�@�P�ɓ��͂��҂ɕ����邾���̃p�b�V�u�X�v���b�^�����Ηǂ��̂ł́H
�@Be-TW,Super-TW�̎��̓v�����C���A���v�œ��̓C���s�[�_���X 10K���ȏ�̂͂��Ȃ�Ł@��҂ɕ����ăp���łȂ��ł�5K���ƂȂ�A�\��DAC���ŏo�͂ł��܂��B
�@��������Ɓ@Be-TW/Super-TW�̗����̐M�����̏��Ȃ��C�[�u���ȐM���ɂȂ�܂��B�i�d�����v��Ȃ������オ��ŃP�[�X�l���Ȃ���T��~�ŏo����j
�����ԍ��F25368914
![]() 1�_
1�_
BOWS����
����̂��쌩�A�������A�������A���w���A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�܂���BOWS����Ȃ�ł͂́A�傢�Ɋ��҂��Ă������w�E�Ղ��܂����B
���āA�܂��A�Q.����...
�������A���� TW �� ST �̂ǂ���� through ���ɂ���ׂ����A���Ȃ�O��I�ɔ�r�����������܂����B������A���̎g�����ł́ADS2800 �́A6 kHz �` 25 kHz �̍�����ł������p���܂���̂ŁABOWS���� YouTube�œO�ꌟ�����ꂽ�悤�ȑS�ш�i15 Hz �` 25 kHz�j�ő����I�ȉ�����]�������Ƃ́A���Ȃ�قȂ��Ă��܂��B
���̂��߁A6 kHz �I�[�o�[�̍�����ɓ������āASW, WO, SQ�͒��ق�������ԂŁA�ɂ߂č��G�l���M�[�ŋɂ߂ĉߓn�I�ȁi�s���j�T�E���h������� SONY Super Audio CD �̃g���b�N�Q�O���uBimmel Bolle Antique Orgel�v���g���āATW�̂݁AST�̂݁ATW+ST�������A�����ꂩ�� DS2800 �� through���ɂ��Ȃ���A�O��I�������܂����B
���̉����́A�ȑO�ɂ��m�点�����悤�ɁA
https://www.youtube.com/watch?v=k1kD5NEdnwI&t=14s
��
https://www.youtube.com/watch?v=bVja-mHFnAw
�ŋ��L���Ă���܂��B
���āA���̌l�I�Țn�D�̖��ł����A���� 8 kHz �` 14 kHz ������̊y���̉����Ɖ��F�Ƃ��ẮA���}�n Be-SQ (�~�b�h�����WSP���j�b�g�j����̘A�������܂߂āA �t�H�X�e�b�N�X T925A �����z�[���i�ɂ߂č��\���ȁA�i���̖��@�j�����A���}�n�� �Rcm Be-TW �i�x�����E�� �h�[��TW�j�̕����D�݂Ȃ̂ł��B����́A���N NS-1000 �����p�������Ă������̎��Ɣ]�ɐ[�����݂����l�I�Țn�D�ł��B
���̂��߁A 6 kHz�ɂ�����N���X�I�[�o�[�ȍ~�́A6 kHz �` 20 kHz �Đ����́A�u�����܂ł� Be-TW ������v�ł���K�v������܂��B�������Ȃ��牽�x�����聕���L���Ă���悤�ɁA���� Be-TW �́A14 kHz �ȍ~�Ō����ɉ��~���n�߂܂��B�����Ƃ��A���ꂪ�ǂꂭ�炢���ł��邩�́A�N��ˑ��̍�������\�͂̒ቺ�ɂ��ˑ����܂��̂ŁA����̈�ł͂���܂��B
����AT925A �́A���w�E�̒ʂ���ɍ������ŁA�����������ꡂ��ɒ����� 40 kHz ������܂Ńt���b�g�ɍĐ����܂��B���̂��߁A���̋@��Q�ɂ����� T925A �̖����́A�����܂Œ�Q�C���쓮�� Be-TW���킸���Ɂi�I�j�⊮���邱�ƁA�܂��i�قƂ�Ǖ������܂��I�j 14 kHz �ȍ~�� Be-TW�̉��~�����āABe-TW + ST �Ƃ��� 21 kHz �܂Ńt���b�g�������邱�Ƃ����ɂȂ�܂��B
�����܂��āABe-TW �� ST �̂ǂ���� DS2800 �� through ���ŋ쓮���邩�ɂ��āA�T�d�ɔ�r�����������ʁA��͂� Be-TW �� through ���ɂ��������A�u���̎��Ɣ]�v�ɂƂ��čD�܂������ʂƂȂ�܂����B ST �� through���ŋ쓮����ƁA���ɔ����Ȃ̂ł����A�S�����������Ŕ�r���Ă��A���h�肷����A�L���L������������̈�ۂ��@�����A Be-SQ �Ƃ̘A�����̓_�ŁA�ƂĂ��킸���Ȉ�a���������܂����B
Be-TW�� ST �́A8 kHz �` 21 Hz �ňꏏ�ɉ̂��Ă��܂����A���̃f�t�H���g�����[�`���̑��Q�C���ݒ�ł́A���X�j���O�ʒu�ɂ����鉹�����x���Ƃ��āAST�� Be-TW������ 6 �` 10 dB �Â��ɉ̂킹�Ă���܂��B����́A��� NS-1000�L���r�l�b�g�Œ�� Be-TW �̕����I�Ȉʒu�z�u�A�����Ď��̋ɂ߂ē���Ń��j�[�N�� ST �̈ʒu�iWO�̉�)�Ƃ����ڂɊW���Ă���܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-2#post-370571
���̔z�u�ɂ��ẮA��N���������A�����ɂ悵����Ƃ��A���Ȃ�˂�����ŋc�_�������Ƃ�����܂����B���B�̎��Ɣ]�́A�����̍��E�z�u�ɂ��Ă͕q���ł��邪�A�㉺�z�u�ɂ͔�r�I�݊������e�ŁABe-TW �� ST�i10 dB �ȏ�ቹ���j�� WO��SQ���㉺���狲�ݍ��ނ��ƂŁA6 kHz�`20 kHz �ɂ�����[���I�ȁu�ʔ����v���\�z�ł��āA 0.1 msec�^�C���A���C�������g�Ƒ��܂��āA���ɗD�ꂽSP�������������Ղ̗Տꊴ����������Ă���i�炵���j�A�Ɠ�l�Ŕ[���������Ă���܂����B����́A���ɔ����Ȃ̂ł����A���̃V�X�e���̑傫�ȓ����Ɨ��_�ɂȂ��Ă��܂��BST�̉������グ������ƁA�������̂��Ƃł����A����������������˂���銴�o�������Ȃ�܂��̂ŁAST�����̍œK���iBe-TW��� 10 dB �Â��I�j���A���ɏd�v�ȃt�@�N�^�[�ɂȂ�܂��B
�Ƃ����킯�ŁA���X�j���O�ʒu�ł̓O�ꎎ���̌��ʂƂ��āA�uBe-TW �����D��AST�́A�����ȕ⏕���v�̎��_�Ǝ�������A Be-TW�� DS2800 ��through �ŋ쓮���邱�Ƃ�I�����܂����B
�����ԍ��F25369517
![]() 0�_
0�_
���āA
�P. �� Behringer �̈�ʓI�ȁu�����A�����i�ʁv�ł����ADS2800 ���Q�K�̏��K�̓I�[�f�B�I�V�X�e���őS�ш�i15 Hz �` 20 kHz
�j�������ۂɂ́A��͂�BOWS���w�E�̌��O����邱�Ƃ��ł��܂����B�������A 6 kHz �` 20 kHz �݂̂Ŏ�����������ɂ����ẮA���i�̉����I�Ȗ��͊������܂���ł����B����́A���̍����撮�͂̋͂��Ȓቺ�Ƃ����ڂɊW���Ă���܂����B�B�B
�X�y�b�N�I�ɂ́AART MX225 �Ɣ�r���Ă��\���ɗD��Ă��܂��̂ŁA����� DS2800 ���i�����I�ɁH�j6 kHz �` 20 kHz �ł̗��p����ō̗p���܂����B���炭�A��������Ɨ��p�������ĉ����̕ω��̗L����ǐՂ��܂��B�����Ƃ��A���̉���ł��̂ŁA�ω�����ϓI�ɑ����邱�Ƃ͍��������܂���B
���Ȃ��A�l�́@Through���Ƀo�b�t�@�A���v�������Ă��Ȃ��ƍl���Ă��܂����A�Ђ���Ƃ�����@Through���ɂ��o�b�t�@���v�������Ă��ā@�Q�C������������������������܂���B
����A�����C�ɂȂ��Ă���܂����̂ŁA�[�i����ɓV���J���Ē��߂Ă݂܂������A�ǂ����t�����g PCB���̉�H�\����炵���A�����܂ŕ������邱�Ƃ��S�O�������߁A���m�F�ł��BBehringer�@�̂���������ł́A�uthrough �� input �̐��m�ȃR�s�[�ł��I�v�Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�����Ńo�b�t�@�A���v�͊���ł��Ȃ��ƔF�����Ă���܂��B
���Ă��āADS2800 �̓����́A�{���ł��� 12-Ch�ȏ�̃}���`�`�����l��DAC�����܂ł́u���n���v�Ƃ��čl���Ă���AAntelope Sutudio Synergy Core (OSSC) �� MOTU 16A �̒����E�]���́A�p�����Ă���܂��B
BOWS����̂��F���Ƃ��ẮA������́u�����ԍ��F25300911�v�G
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24859394/?cid=mail_bbs#25300911
�ł��b������ Antelope OSSC �́A�ǂ̂悤�Ɏv���܂����H�@���肷���̍ۂɁA�ȒP�ɂ�����������������K���ł��B
�i���Ƃ��ẮA Antelope�Ђ̃N���b�L���O�Z�p�ɋ����ÁX�Ȃ̂ł����B�B�B�j
�����ԍ��F25369518
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
�V�X�e���S�̍\���̏Љ�^���L���ŐV��ԂɍX�V���܂����B
The latest system setup of my DSP-based multichannel multi-SP-driver multi-amplifier fully active audio rig as of August 3, 2023
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1678290
����ɔ����āA�u�N���^�_�V�[�P���X�v�Ɓu�V���b�g�_�E�� �V�[�P���X�v���ŐV�ɍX�V���܂����B
The latest "startup/ignition sequences" and "shutdown sequences" in my DSP-based multichannel multi-SP-driver multi-amplifier fully active audio rig as of August 3, 2023
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1679301
�����ԍ��F25374773
![]() 0�_
0�_
>Antelope OSSC �́A�ǂ̂悤�Ɏv���܂����H
�@Antelope�Ђ̃��C���i�b�v���悭�킩��̂ł����@����̂��Ƃł����H
https://jp.antelopeaudio.com/products/orion-studio-synergy-core/
�@Antelope���Ę^���C���^�[�t�F�[�X�̃C���[�W�������āAWord Clock�̓�������Ƃ��ɋ����Ǝv���܂��B
�@➑̎ʐ^���ā@����H���͂����ˁ[�����@�Ǝv������
��16 DC-coupled analog output channels over a D-Sub 25 connector allowing control of modular synthesizers;
�@D-Sub 25�s���R�l�N�^�ŏo�͂��ā@�ɍא��ň�������o���ă^�R���z����XLR�o�͏o�Ă�́H�Ǝv���܂����B
�@12ch�̃f�B�X�N���[�g�v���A���v���ڂ��ā@�}�C�N�v���Ȃ�ł��Ȃ�_�o�g���ăm�C�Y��Ɛ��X�������̃`���[�j���O����Ƃ��낪�d������Ă��ā@��̖ʐς̑唼���^���n�Ɏ���Ă�Ȃ��́H�Ǝv���܂����BDAC�Ɋւ��Ă��ł���Ȃ�IV�ϊ��̉�H�Ƀ��\�[�X�߂��ׂ��ł����AEIA���b�N�Ɂ@�����̓��͂��Ԃ�����ł�Ƃ�����l������Ɓ@���Ȃ�DAC�܂��̔�d�͏��Ȃ����ł��B
�@�ڂ����͊�̎ʐ^���Ȃ��ƂȂ�Ƃ������܂��A
�@����Ɠd���R�l�N�^�@18V 1�n�����Ă��Ƃ́A�����Ŏg�p����DSP��}�C�N�v���A���v�ADAC�A�A�i���O��H���@���ׂăX�C�b�`���ODC/DC�R���o�[�^�Ő��������˂��@�ނ����ł��Ă��邾�낤���ǃm�C�Y�Ⴍ�Ȃ����낤�Ȃ�
�@�X�^�W�I����l����Ɓ@���b�N�ɉ������߂�K�v�������ĊO���d���P�n���͍����I�����ǁA����ρ@➑̂ł������ĕ����̃g�����X�����������AC 115/230V���͂̃��j�A�d���ŋ����̂ق����悭�˂��H
�@�Ǝv���܂��B
�@�l�I�Ȑ����ł́@�R�X�g���z�Ƃ��ā@�C���^�[�t�F�[�X �R�� �^���@�S���@�d��2���@DAC �P���@���x����Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�Ȃ̂ő��`�����l��DAC�Ƃ��Ďg���ɂ́@���Ȃ�R�X�p�������ł��B
�@�����������`�����l��DAC���ā@�Y���@�킪���Ȃ��̂Ř^�����ƈ�̉������I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X���Y�����܂����A�v�����[�X�̐��������DAC�Ƃ��Ă͂ǂ����Ȃ��Ǝv�����܂��܂��ˁB
�@�ȏ�́AAntelope�g�������Ƃ̂Ȃ��@�l�̐����Ȃ�ŋY���Ǝ���Ă��������B
�����ԍ��F25376099
![]() 1�_
1�_
BOWS����A
�����Z���ɂ�������炸�����z����������������A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
��12ch�̃f�B�X�N���[�g�v���A���v���ڂ��ā@�}�C�N�v���Ȃ�ł��Ȃ�_�o�g���ăm�C�Y��Ɛ��X�������̃`���[�j���O����Ƃ��낪�d������Ă��ā@��̖ʐς̑唼���^���n�Ɏ���Ă�Ȃ��́H�Ǝv���܂����B
���l�I�Ȑ����ł́@�R�X�g���z�Ƃ��ā@�C���^�[�t�F�[�X �R�� �^���@�S���@�d��2���@DAC �P���@���x����Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�Ȃ̂ő��`�����l��DAC�Ƃ��Ďg���ɂ́@���Ȃ�R�X�p�������ł��B
��͂�A���̂悤�Ɋ������܂����B�B�B
�����AAntelope OSSC�� MOTU 16A�ׂ�Β��ׂ�قǁA�^���A�ҏW�AWAV�@�\�̖L�x���ɂ͈��|�������̂́A���A������DAC�Ƃ��Ă����̗��p�ł́u�R�X�p�������H�v�Ɗ����閈���ł��B
���ݗ��p���Ă��� OKTO DAC8PRO���A�@���Ɏ��̖ړI�Ɋ����Ƀt�B�b�g���Ă���̂����A�܂��܂������������Ă���܂��B
12-Ch �ȏ��HiFi DAC���j�b�g���w������Ȃ�A�����_�ł́A�ȑO���b������Merging Technology�i�X�C�X�j �� HAPI MkII �Ȃǂ̒������ō����ȕ��������Ȃ������ł��ˁB
http://dspj.co.jp/products/merging/Hapi_overview.htm#spec
ttps://dspjapan.shop-pro.jp/?pid=166740118
16-Ch �ɂ���ɂ́ADA8�^HAPI 8ch DA�g�����W���[���iup to PCM 192kHz�j���Q���I�G
https://dspjapan.shop-pro.jp/?pid=166740542
���K�v�ł��̂ŁA���z�� \469,700 + \440,000 = \909,700 �ƂȂ���ɍ����ł����A�����_�ł͋��ɂ� 16-Ch DAC�ł���Ǝv���܂��B
OKTO DAC8PRO ���Q�䗘�p�Ŋ��S�������삪�����ł���ō��Ȃ̂ł���... OKTO�� Pavel ����́A���̕����́A���܂��Ɋᒆ�ɂȂ������ł��B
�ŋ߁ADAC8PRO �̐V�t�@�[���E�F�A�ƐVUSB�h���C�o�[�������[�X����܂����̂Łi���̗��p�ł́A�͊댯���A�b�v�f�[�g�̕K�v���͊F���ł����j�A�ēx�A�l�I�ɂ� Pavel ����֘A�����āA�Q���DAC8PRO�̓�������i�������P��PC����F���j�̎����ȂǁA�v�]���Ă�₢���킹�Ă݂܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25376509
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
>��͂�A���̂悤�Ɋ������܂����B�B�B
MOTU M4��^���Ɏg���Ă��܂����A�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X��DAC�����ā@�^���i���̊m�F�̃v���C�o�b�N�Ɏg�������Ȃ̂Ł@���y�ӏ܂��邽�߂̕i�i�͕K�v�Ȃ��āA�e����������𑜓x������Ηǂ��̂Ł@���̂悤�ȗp�r�����̐��\����DAC�������ڂ����͓̂�����O�ł��ˁB
>�ȑO���b������Merging Technology�i�X�C�X�j �� HAPI MkII �Ȃǂ̒������ō����ȕ��������Ȃ������ł��ˁB
https://tascam.com/jp/product/klotz_d-sub_analog-multi/top
�@����ɁA���������̂��v��݂����Ł@����ɂW�`9���~���ɂȂ�܂��ˁB
>OKTO DAC8PRO ���Q�䗘�p�Ŋ��S�������삪�����ł���ō��Ȃ̂ł���... OKTO�� Pavel ����́A���̕����́A���܂��Ɋᒆ�ɂȂ������ł��B
�@�n�[�h�I�ɂ́A8CH��DAC�`�b�v�g���Ă���̂őΉ����Ă���ł��傤���A�Q������������Ƀ��[�h�N���b�N�i�\�ł���}�V���N���b�N�j�̓������K�v�Ȃ�ł����A�O���N���b�N�[�q�������̂œ�������ł��ˁB
�@�������� ESS DAC�n�� 50�`100MHz�Ń`�b�v���ŃT���v�����[�g�R���o�[�^�iSRC�j�������Ă���̂Ł@SRC�N���b�N�̓����͍l�����Ă��Ȃ��ł��B(�������Ƃ��Ă��A���̎��g���т̍����x�N���b�N�̎��v�������̂Ő��i�������B)
�@��������߂�A�t�@�[���ƃh���C�o�̃A�b�v�f�[�g�őΉ��ł���Ǝv���܂����A�J�������Ȃ�ɂ�����Ǝv���܂��B
�@�ŏ�����ADAC 2CHIP���ڂ����}���`�`�����l��DAC�̕���������������܂��ˁB
�����ԍ��F25376626
![]() 1�_
1�_
BOWS����
�����̂��ԐM�A���肪�Ƃ��������܂��B
��>�ȑO���b������Merging Technology�i�X�C�X�j �� HAPI MkII �Ȃǂ̒������ō����ȕ��������Ȃ������ł��ˁB
��https://tascam.com/jp/product/klotz_d-sub_analog-multi/top
���@����ɁA���������̂��v��݂����Ł@����ɂW�`9���~���ɂȂ�܂��ˁB
�����Ȃ�ł����A�v�����[�X�ł� DSsub-�WXLR �A�_�v�^�́A���Ȃ�����ȑI����������悤�ł��B�M�����́H�H�H�ł����B�B�B
���@�ŏ�����ADAC 2CHIP���ڂ����}���`�`�����l��DAC�̕���������������܂��ˁB
���ɂ��̒ʂ�ł��I��قǁA���� OKTO �Ђ� Pavel����֔��M�����̂ł����A�Ō�ɂ���������Ă����܂����B
�hOn the other hand, in case if you would develop a new product DAC16 PRO, that should be the most welcome solution for me and other multichannel-league people, of course.�h
�܂��A���v�Ƌ��L�̃o�����X���l����� OKTO�Ђ����v�x�O���� DAC16 PRO ���J������\���́A�A�A����Ȃ��[���ɋ߂����ł����B�B�B
�����ԍ��F25376638
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�F����
�����A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/post-1700265
�ɂ��������̂ł����B�B�B
TEAC UD-701N
https://teac.jp/jp/product/ud-701n/feature
https://www.fujiya-avic.co.jp/blog/detail/478
�́A���������ѓd�������̎ʐ^�����Ă��A�܂�TEAC�Ǝ��̍ŐV�f�B�X�N���[�g DAC�`�b�v�̓��ڂ����Ă��A���Ȃ茘�S�����i�ʂɍ��ꂽ USB-DAC ���l�b�g���[�N�X�g���[�}�[�v���[���[�ł���Ǝv���A�܂��A 10 MHz BNC �ɂ��O���}�X�^�[�N���b�N�����@�\��������Ă��܂��B
�����ŁA�ӂƍl�����̂ł����A�i���z�Ƃ��ẮA�܂��܂��ΏۊO�ƂȂ�܂����j�A���� UD-701N ���U�䒲�B���āA�U�|�[�g�� 10 MHz �}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^���� BNC�œ��������A���̂U���USB�ڑ���PC�Ɍq������A���� 12-�`�����l��DAC�Ƃ��� USB-ASIO �ŔF�������邱�Ƃ͂ł��܂��ł��傤���ˁH
�����AUSB-ASIO�ł�12-�`�����l�������F�����s�̏ꍇ�A�W�|�[�g�ȏ��GB�X�C�b�`���O�n�u�o�R�ŁA�P��� Widnows 11 PC����12-�`�����l���̓����X�g���[�}�[ LAN-DAC �Ƃ��ĔF�������邱�Ƃ́H�H
��������Ȃ��Ƃ��\�Ȃ�A 10 MHz �O���N���b�N�Ή��́A���̂������ȁA�Q�`�����l���i�X�e���I�jUSB-DAC���l�b�g���[�N�v���[���[���A�������A��DAC�Ƃ��Ďg���邩������Ȃ��A�ȂǂƖ��z���Ă���܂��B
�O�̂��߁ATEAC�Ђւ��A����ȃj�b�`�Ȏg�����̉\���ɂ��Ė₢���킹�Ă���܂��B
�����ԍ��F25401103
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�F����
���l�̃A�v���[�`�́AANTELOPE�Ђ̍����\�X�e���IDAC-ADC �ł���AMARI�i10 MHz Clock BNC IN ����� WordCluck BNC IN �̗������A�����������j�ƁA���Ђ̃N���b�N�W�F�l���[�^�[ OCX HD, Pure 2, TRINITY, 10MX �Ȃǂ̂P��g�ݍ��킹��Ή\��������܂���B
�����\����T���Ă݂܂��B
�����ԍ��F25401392
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
PC������o����1�I�����邾����
�����̓����͖����ł�
�����ԍ��F25401889�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
>���� UD-701N ���U�䒲�B���āA�U�|�[�g�� 10 MHz �}�X�^�[�N���b�N�W�F�l���[�^���� BNC�œ��������A���̂U���USB�ڑ���PC�Ɍq������A���� 12-�`�����l��DAC�Ƃ��� USB-ASIO �ŔF�������邱�Ƃ͂ł��܂��ł��傤����
�@�ʔ����A�C�f�A�f�X�K�A�c�O�Ȃ��猴���I�ɉ����M���̐��m�ȓ����͕s�\���Ǝv���܂��B
�@USB�ڑ��ŗ���鉹���M���́@�p�P�b�g�M���Ȃ̂Ŗ{���I�ɓ����Ƃ����T�O�������ł��B
�@PC��USB�[�q����@�U���DAC�ɑ��ā@�U�̉����p�P�b�g�𑗐M����^�C�~���O����������ɂȂ��ā@6���DAC����M����^�C�~���O���Y���܂��B
�@����ɁA�p�P�b�g���������������ꍇ�A�p�P�b�g�̍đ�������̂ł���ɃY���܂��B
�@USB DAC���ł́@���ꂼ���DAC���ŏ��̃p�P�b�g��������^�C�~���O���N�_�ƂȂ�A������x�o�b�t�@�����O������Ł@�Đ����n�߂܂��B
�@�U���DAC�ԂŁ@�Đ��̋N�_�𑵂���d�g�݂������̂Ŋ��S�ȓ����͕s�\�ł��B
�@���ۖ��A����6��̉����Đ��̃Y�����ǂ̂��炢�ɂȂ邩�ɂ���ā@���e�͈͂��ǂ����̔��f�ɂȂ�܂����AUSB�͋����a�̂��߁A�O�t��HDD,�}�E�X��L�[�{�[�h�̃p�P�b�g���ꏏ�ɗ���邽�߁A6�䕪�̉����M���𗬂��Ă��鎞�Ɂ@�����̃p�P�b�g�������݂œ�������AWinodws�̓s���ɂ�著�o���҂����ꂽ�肷��̂Ł@�Đ��J�n�����^�C�~���O�̉^�ɂ���ā@����o���c�L���ς��܂��B
�@���̃Y���́@�}�X�^�[�N���b�N�̃Y���ǂ���ł͂Ȃ����߁A�}�X�^�[�N���b�N������Ӗ��������ł��B
�@����ȑO�ɁA������USB�@��ɓ����ɉ����o�͂����蓖�Ă��邩�Ƃ����@Windows�̎d�g�݂��N���A�[����K�v������܂����A������͂悭�킩��܂���B
�����ԍ��F25401922
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�����̌䉞���Əڍׂ������J�Ȃ�����A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B
���U���DAC�ԂŁ@�Đ��̋N�_�𑵂���d�g�݂������̂Ŋ��S�ȓ����͕s�\�ł��B
��
�����ۖ��A����6��̉����Đ��̃Y�����ǂ̂��炢�ɂȂ邩�ɂ���ā@���e�͈͂��ǂ����̔��f�ɂȂ�܂����AUSB�͋����a�̂��߁A�O�t��HDD,�}�E�X��L�[�{�[�h�̃p�P�b�g���ꏏ�ɗ���邽�߁A6�䕪�̉����M���𗬂��Ă��鎞�Ɂ@�����̃p�P�b�g�������݂œ�������AWinodws�̓s���ɂ�著�o���҂����ꂽ�肷��̂Ł@�Đ��J�n�����^�C�~���O�̉^�ɂ���ā@����o���c�L���ς��܂��B
��
�����̃Y���́@�}�X�^�[�N���b�N�̃Y���ǂ���ł͂Ȃ����߁A�}�X�^�[�N���b�N������Ӗ��������ł��B
���ɖ����Ő����͍ő�̂�����A���ɔ[���������܂����B��͂�A���̍\�z�ŕ����̓Ɨ�DAC���j�b�g�����S�����쓮���邱�Ƃ͕s�\�ł��邱�Ƃ��̂ɖ����܂����B
����A
������ȑO�ɁA������USB�@��ɓ����ɉ����o�͂����蓖�Ă��邩�Ƃ����@Windows�̎d�g�݂��N���A�[����K�v������܂����A������͂悭�킩��܂���B
�Ɋւ��܂��ẮA�\�ł��邱�Ƃ����x���m�F���A�ꎞ�I�ɂł͂���܂����Z���Ԃ̃e�X�g�]���Ŏ��H�ς݂ŁA���̌���ł͒��o�I�ɂ��S����a�����Ȃ����Ƃ������ς݂ł��B
�Ⴆ�A�A���v�̔�r�]���̈�Ƃ���DAC8PRO �� SONICA-DAC �p���Ă���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-493606
�Y�t�}�|�P�ō\���������������B
�܂��A���݂ł��f�W�^�����͐M���S�̂� VU���[�^�[�Ń��j�^����ړI�����̂��߂ł͂���܂����AKORG DS-DAC-10 �� DAC8PRO�ƕ��p���Ă���܂��B���ꂼ��̐�p USB-ASIO�h���C�o�[�o�R�Ŗ��Ȃ��Ɨ����ĔF������܂��B
VU���[�^�[���j�^�����O�ł́A10 msec ���x�̓�����������Ώ\���ł��̂ŁA�P�O���Ԉȏ�ɂ��y�ԘA������ł��A������̖��͑S������܂���B�ȁi�g���b�N�j�̃W�����v�̍ۂɂ́A���ʓI�Ƀ^�C�~���O�����Z�b�g����邱�Ƃ��v�����Ă���悤�ł��B
�Y�t�}�|�Q�A�Y�t�}�|�R�@�������������B
�ȑO�ɂ����m�点�����Ǝv���܂����AVU���[�^�[�̓���́AYouTube�r�f�I�ł��Љ�Ă���܂��B
https://www.youtube.com/watch?v=k1kD5NEdnwI
https://www.youtube.com/watch?v=5thJQvBfiO8
https://www.youtube.com/watch?v=jTdjKA6_lgU
https://www.youtube.com/watch?v=f3H80GQWvcM
�����ԍ��F25402071
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
DSP�}���`�`�����l�����ŁA������DAC���j�b�g�𗘗p�����ꍇ�̓����́u����v�ƁA������u�⏞�v���đS���́u�o�́v��������\���ɂ��āA�����ڂ����������Ă݂܂����̂ŁA���肷���̍ۂɂ��Η��������B
�hCan I (we) temporarily synchronize outputs of multiple DAC units (each of them has own independent ASIO driver) in 10 micro second (0.01 msec) precision in DSP-based multichannel audio setup?�h
�uDSP �x�[�X�̃}���`�`�����l�� �I�[�f�B�I �Z�b�g�A�b�v�ɂ����āA������ DAC ���j�b�g (���ꂼ��ɓƎ��̓Ɨ����� ASIO �h���C�o�[������) �̏o�͂� 10�ʕb (0.01 �~���b) �̐��x�ňꎞ�I�ɓ��������邱�Ƃ͂ł��܂���?�v
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1711757
���Ɍ��肳�ꂽ�������ł͂���܂����A����DAC��DA����J�n���_�̑��ΓI�����i����j���A����̎����������Ɂi�I�[�f�B�I�����Z�b�V�������Ɂj�ω������ۂ���Ă���ꍇ�ɂ́A���̘������㗬��DSP�̃O���[�v�x���ŕ⏞�i��j���Ă�邱�ƂŁA����DAC���j�b�g����̏o�͂�10�ʕb (0.01 �~���b) �̐��x�Łi�ꎞ�I�Ɂj���������邱�Ƃ��\�ł����B
���̊��ł́A���������ŁA�W���Ԉȏ�ɘj���āA���x���������肵�āA��ɓ�������Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B�������A���̊ԁA���PC�ݒ�ɕύX�������Ȃ����Ƃ��K�{�ł����B�B�B
�������A����Ȑ�������� before and after �ŕK�v�Ƃ���Z�b�g�A�b�v�����I�ɏ�p���邱�Ƃ͂��蓾�܂��A�K�v�ɉ����Ď����I�ɗ��p����@��͂��邩���A�A�A�A�ł��B
�����ɂ悵����
���̎������ɋC�t���Ďv���o�����̂ł����A�������A�����ɂ悵����̏ꍇ�AASIO4ALL ���o�R���������Đ����s���ł������Ǝf�����L�����h��܂����B
�����ŁA���������Ԃ�����A�u�_�����Ɓv�����o��̏�ŁAUSB-DAC �i��ʂ� USB 2.0 �d�l�j���A������PC�u�}�U�{�v�� USB 3.0 �|�[�g�Ɍq���ł݂ĉ������I�@���̊��ł́A USB 3.0 �|�[�g�ւ̐ڑ��ŁAEKIO�����24�`�����l�����o�ł��A���Ɉ��肵���A�����ȍĐ����\�ł��B���`�����l���ɂȂ�Ȃ�قǁAUSB 3.0 �|�[�g�ڑ��̕������肵�Ă����ۂ�����܂��B
������Ƃ����u�ڂ���v�̊��G�ł��B�ǂ����č��܂Ńg���C���Ȃ������̂��H�H�H
���Ȃ݂ɁAUSB 3.0 �n���ɂ́A���� USB�f�o�C�X����،q���Ȃ����Ƃ������߂��܂��B�}�E�X��L�[�{�[�h�́A�i�����̂悤�Ɂj USB 2.0 �q���ʼn������B
����A�䏳�m���Ǝv���܂����AUSB�c���[��USB�|�[�g��USB�f�o�C�X�́u�ō����x�v�̊m�F�Ȃǂ̂��߂ɁA�ƂĂ��֗��Ɏg���Ă��܂��B
"USB Device Tree Viewer, UsbTreeView (x64)" (now v.3.8.8.0)
https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview_e.html
�����ԍ��F25417840
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����
ASRF �̌p���������̒��ŁA�I�[�f�B�I�~�L�T�[���g�킸�ɁA2�̃X�e���IDAC���j�b�g�̕Б��`�����l���������g���āuDAC����J�n�́u����v�𑪒肷��Ƃ������������ݒ�̒�Ă�����܂����̂ŁA�lj��������s���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1718741
���ʂ́A�I�[�f�B�I�~�L�T�[���g���āA�eDAC���j�b�g�����L&R�������������Ċϑ���������̕��@�Ɠ��l�ł������A�Ȃ�ׂ��V���v���Ȑݒ�ŕK�v�ȃf�[�^�𒊏o����A�Ƃ����ϓ_����́A�Ó��ŁA�ʔ��������ł͂���܂����B
�����ԍ��F25426927
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
�����AWindows PC ��ASIO�h���C�o�[�o�R�ŕ�����DAC ���u���u�{�i�I�Ɂv���S�����ŗ��p�������Ȃ�A���̋@�\���������ăT�|�[�g���Ă���I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�i�܂��͂��̂悤��DAC���u�j���g���K�v�����邱�Ƃ͗������Ă���܂��B
�Ⴆ�A����FAQ�Ŗ��m�ɏq�ׂ��Ă���悤�ɁB�B�B�B
https://synthax.jp/faq-fireface-ufx-reader/items/ufx-multiple-use.html
�������A�����ɂ悵����́A����FAQ�Ŏw�E����Ă���悤�ɁAFireface ����A�������p����Ă�����̂ł��傤���H
�i���̂悤�ɂ������������������o�܂��������悤�ɁA���ڂ낰�ɋL�����Ă���܂��B�j
�����ԍ��F25427563
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
��Fireface ����A�������p����Ă�����̂ł��傤���H
�������APC����SP�Ƃ���Fireface 1���
3way�̃X�e���I�ʼn^�p���ł�
Fireface�̓��[�h�N���b�N�[�q������
������̓������\
PC������Fireface(1)�AFireface(2)�A�ƔF������܂��B
OCT�͕�����̉^�p�͍l������Ă��炸
���[�h�N���b�N���炸(�n�[�h)
PC�������������ʂł��Ȃ��悤�ł��B(�\�t�g)
���C��SP��OCT�ōl���Ă��܂�����
�n�[�h�ƃ\�t�g�̗��ʂ���
�����g�p�����[�J�[�ɔے肳��
���Ȃ�Fireface���Ȃ�
�������A����̓n�[�h�̃`�����f�o��
�g���Ă���̂ŁA�����͋x�~���ł��B
�����ԍ��F25430368�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
���肪�Ƃ��������܂��I
����FAQ�G
https://synthax.jp/faq-fireface-ufx-reader/items/ufx-multiple-use.html
��ǂ�ŁA���̓��e�𗝉����Ă���܂����B
��Fireface�̓��[�h�N���b�N�[�q������A������̓������\�APC������Fireface(1)�AFireface(2)�A�ƔF������܂��B
���������Ă���܂����A���̏ꍇ�APC�ƂQ���Fireface�Ƃ̐ڑ��́AUSB�P�[�u��1�{��1��ڂ� Fireface �Ɍq�������ŁA2��̑S�`�����l���������F�������̂ł��傤���H
����Ƃ��APC����͂Q�{��USB�P�[�u���ŁA���ꂼ��� Fireface �q���K�v������̂ł��傤���H
�����Ƃ��A�P�S-CH �܂œ����ł���قڏ\���ł��̂ŁAMOTU 16A �i16-CH) �� MOTU Ultralite mk5 �i�w�b�h�h�t�H���o�͂����P-PDIF/AES-EBU ���g����14-CH�j�Ȃ�A�����䓯���^�p�̕K�v�͂Ȃ����Ƃ��A���m���Ă͂���܂��B
�����Ȃ���AOKTO DAC8PRO �� MOTU, RME, Antelope �̒��ԂɈʒu���� HiFi DAC ��p �@��ŁA 12-CH�` 16-CH �̒P�̃��j�b�g�́A�j�b�`�Ŏs����ɂ߂ď������̂ŁA�肪�͂����i�т̐��i���o������\���͐�]�I�ł��ˁB
�����ԍ��F25430387
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
���Q���Fireface�Ƃ̐ڑ���
PC����͂Q�{��USB�P�[�u���ŁA
���ꂼ��� Fireface �q���K�v������܂��B
�N���b�N�̓f�C�W�[�`�F�[��
��12-CH�` 16-CH �̒P�̃��j�b�g�̓j�b�`�ŁA
�肪�͂����i�т̐��i���o������\���͐�]�I
Fireface�AMOTU�ȂNjƖ��p��
�����A�������Ȃ̂ł��傤
�J����A�M�������܂߂��
�Ɩ��p�͈����ƌ����邩������܂���
AD/DAC/DSP/���G�ȉ���\�t�g�܂œ���
AV�A���v�͔j�i��������܂���
�����ԍ��F25430471�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
�����̌�A���A���肪�Ƃ��������܂����B�S�Ĕ[���A�����ł��I
�݂Ȃ���
�ʌ��ł����A���� ECM8000 �i�Q�O�O�W�N�w���� Made in Germany!) �̌���m�F�Ɓu�K�v�Ȃ�Z���v�ɂ��āA�����[�����������s���Ă���܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1720912
��
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1721446
��
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1721731
�O�Ԗڂ̓��e�ɏ������Ƃ���A���̋��F�̈�l�������ɍŋߍZ�����ꂽ Earthwork M50 �� mached pair �������Ă��邱�Ƃ�������܂����̂ŁA�߂��@��Ɏ��� ECM8000 ��ނ̎���I�[�f�B�I�V�X�e���Ɏ��Q���āAEarkork M50s �ƌ�����r���āA���݂̎���ECM8000 ��Fq�����i�܂�A�Z���Ȑ� 15 Hz�` 22 kHz�j��\��ł��B
���łɁA������ʌ��ł����A�A�A
ASR�̎��̃X���b�h�A�ނ̃X���b�h�A�����Čl��PM�V�X�e���ŁA�p�ɂɏ��������Ă��� pma���A ���Ɏ���A���v�G
https://pmacura.cz/DIY_250W_4ohm_amplifier.html
���g���āA���Ɠ��l�� DSP-EKIO�x�[�X�̃V���v���Ȏ���2-way SP�ɂ�銮�SSP�����}���`�`�����l���E�A�N�e�B�u�V�X�e���̍\�z�ɒ��肳��܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/building-a-2-way-small-active-speaker-with-software-crossover.48035/
�������A����������悤�Ɋ����ȃ^�C���A���C�������g���A�܂����E�T�u�E�[�t�@�[�̒lj�������ɓ����Ă���悤�ŁA�����������Ǝv���Ă���܂��B
�Ƃ������A�����A�T�u�V�X�e���i�Q�K�̏��K�̓I�t�B�X�p�H�j�Ƃ��āA���̂悤�ȃV���v���Ȏ���2-waySP�̍\�z�A�v���X���E�T�u�E�t�@�[�A�́A�傢�ɂ���Ă݂����Ǝv���Ă���܂����̂ŁA��s���Ă���������悤�A�ނ̔w�����������ł�����܂��B
�����ԍ��F25430963
![]() 2�_
2�_
��ŏЉ�� pma ����̃X���b�h�ŁAppakaki����́A����ȃV�X�e���G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/diy-audio-nirvana-12-dayton-reference-fast-project.26350/
��m��܂����B�t�������W�P���{�T�u�E�[�t�@�[�@��OKTO DAC8PRO �ɂ��}���`�`�����l���\���ł��B�ǂ����t�������W�P���ɑ��Ă�DSP�� XO/EQ�Ƒ��Q�C��������K�p����Ă���l�q�ł��B
�u���܂łōō��́A��O���̉��y�ӏܑ̌��v�Ə�����Ă���A���̃V�X�e���ƑΔ䂵�āA�z���ł��܂��B
����A��͂�t�������W�P���ł́A���X�j���O�|�W�V�����̐��������Ȃ肫���悤�ł��B�œK�|�W�V�������班���ړ�����ƁA�����ȉ�����ʂ��O���A�����A�悤�ł��B
���̓_�ł́A���̃V�X�e���̌���ݒ�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1678290
�ł́A�œK���X�j���O�|�W�V�����ɍ��E�A�㉺�A�O��@�ł��Ȃ�̗]�T�i���Ȃ��Ƃ��ȂƓ�l�Ń\�t�@�[�ɍ����ĉ��y���y���ނɂ͏\���ȗ]�T�I�j������܂��̂ŁA���̈Ӗ��ł́A�t�������W�P���̓����ppakaki����̃X���b�h�Ŋw���Ă��������܂����B
�����ԍ��F25432953
![]() 0�_
0�_
�����F�@ppakaki ����@�ł͂Ȃ��Appataki ����@�ł��B
�����ԍ��F25432973
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�������Ƀp�iTV55�C���`����ꂽ�̂ł��傤���H
�s�A�m���������h���Ǝv���܂���
���͉��Ɍ��ւɍs����o����������̂ł��傤��
���t�������W�P���̓��
���œK�|�W�V�������班���ړ�����ƁA�����ȉ�����ʂ��O���A�����
����̎w�����������������̂ł��傤�A�c�B�[�^�[����ꂽ��������邩������܂���B
�t�������W�P���̓���͂ǂ��炩�ƌ����ƁA�p���[�̖���
�߂Â��ăJ�o�[����j�A�t�B�[���h�Ɍ����Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25434984
![]() 1�_
1�_
�p�i�T�T�C���`�S��OLED TV �́A���i��SP�Q�̌������̃_�C�j���O���[���ɂ���܂��B
TV��̉��ɁA�傫�ȃX�g�b�p�[�t���̃S���L���X�^�[�S�����t�����d���Č����ؐ��v���[�g��ݒu���Ă���A�e�Ղɉ�]�ړ����ăI�[�f�B�I���[�����Ɍ����邱�Ƃ��o���܂��B
�I�[�f�B�I�V�X�e���Ɍq���ŁA�{�i�I�Ƀr�f�I��DVD�f�����������Ƃ������ɁA���̂悤�ɔz�u���܂����A���i�̓_�C�j���O���[���ł̂���y�e���r�����p�ł��B
���́A�Ӑ}�I�ɁA����TV���I�[�f�B�IPC�̃Z�J���h���j�^�[�Ƃ��Ďg���܂��B�܂�摜�����X������ HDMI�P�[�u���P�{��TV�֑����āA���͑S�Ė{�i�}���`�`�����l���I�[�f�B�I�V�X�e���ōĐ����܂��B
���́A�u�t�]�ɔ��z�v�ɂ��ẮA�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-dm7-8-channel-dac-review.35661/post-1249336
�ŏڂ��������܂����B
������TV���ł��̂ŁAPC�ƃs�N�Z���� Xit�ŁA4K �ԑg���o�b�`���ł��ˁB
PC��DVD�Đ����e�Ղł��̂ŁA�摜�������Z�J���h���j�^�[�Ƃ��Ẵp�i�SK OLED�@�T�T�C���` TV�ŕ\�������܂��B
�����ԍ��F25435217
![]() 0�_
0�_
���ꂩ��A���̔z�u�̏ꍇ�ł� TV�̉���ʂ��ă_�C�j���O�ƍs�������o���܂��B�i������Ƌ����ł����A�T�u�E�[�t�@�[��TV��̊Ԃɂ́A�ʂ���Ԃ���I�j�B
�܂��A�������A�_�C�j���O���[���Ƃ��̍����̃L�b�`������́A�L���ƌ��ւ֒ʂ���ʃ��[�g������܂���B
�����ԍ��F25435224
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
�����g���Ă��鑪��p�}�C�N BEHRINGER ECM8000 �i2008�N�ɓ��ʑI�����ꂽ���j�b�g�j�̌��݂ɂ�������g���������A�����ڂ������聕�m�F���܂����B
�䋻����������ł�����A���肷���̍ۂɂ��Η��������B
- Frequency response of my BEHRINGER ECM8000 measurement microphone (specially selected unit in 2008)
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1737299
�����ԍ��F25452427
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
�uASIO4ALL + VB Audio Virtual/HiFi Cables�v �����S�ɑ�ւ��邱�Ƃ��ł�����ɗD�ꂽ��t�\�t�g�E�G�A �uVB-Audio MATRIX�v�G
https://vb-audio.com/Matrix/
�̎��p�ƕ]�����J�n���Ă���܂��B
���̎g�p�J�n�̊T�v�́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/vb-matrix.48989/post-1760796
���̃V�X�e���ɂ�����A����܂ł̌o�܂��܂ޏڍׂ́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1760732
�������������B
�����ԍ��F25488496
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�� �uVB-Audio MATRIX�v
I/O���킩��Ղ��Ȃ�܂�����
RME�̃\�t�g�Ɏ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25491613�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���������A�œK�����܂����B
44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.2 kHz, 192 kHz �̂�����̉^�p���s�ł��AVB-Audio Matrix �͔��Ɉ���Ō��S�ł��B
VB-Audio MATRIX (VASIO64A setup) as system-wide ASIO and other audio I/O routing center: Replacement for ASIO4ALL and VB-Audio Virtual/HiFi Cables: Part-2_Further optimization in conformity with present configuration of DSP "EKIO"
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1766633
�����ԍ��F25495883
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�����S
���͓I�ł��ˁA�\�t�g������Ȃ�A
���g�ސ��_�I�n�[�h����������܂��̂�
�����ԍ��F25498247�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���������g�����Ă��܂��B
VB-Audio MATRIX (VASIO64A setup) as system-wide ASIO and other audio I/O routing center: Replacement for ASIO4ALL and VB-Audio Virtual/HiFi Cables: Part-3_VB Matrix VAIO4 as Windows default audio playback device feeding into system-wide DSP Center "EKIO"
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1774506
�����āA
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/vb-matrix.48989/page-3#post-1775331
�����炭�A�}�U�[�{�[�h�� Realtek High Definition Audio �i�����I�� VB Matrix ���ꡂ��ɁAꡂ��ɁA���I�j�́A����A�g�����Ƃ͊F���ł��傤�B
�����ԍ��F25506609
![]() 0�_
0�_
�F����A
���̃X���b�h�ł̃��X�i�ԐM�j�������ȃ��X���܂߂ĂP�W�W�����܂����B
�ԐM�����Q�O�O���ɒB����ƁA����ȏ�̕ԐM���ł��Ȃ��Ȃ�悤�ł��̂ŁA�V�X���b�h�ֈڍs�������܂��B
�y���P�Q�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25510026/#tab
�ɂāA���������A��낵�����肢�\���グ�܂��B
�Ȃ��A�����ł��A�p��ł����A���������s���Ă���܂��̂ŁA�������������A���Q���������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�����ԍ��F25510030
![]() 1�_
1�_
���̃��[���A�R�[�X�e�B�b�N�f�U�C���ɂ���
�����C���[�W�Ɍ����A�����ÂA�b�v�f�[�g���ł��B
����܂ł̗���
�E2way�X�s�[�J�[�ƃf�W�^���A���v���w��
�E�G�[�W���O
�E�X�s�[�J�[�Z�b�e�B���O(�X�s�[�J�[�X�^���h����)
�E���g����������
�E��������(�R�[�i�[���^���L����A���V���A�C�\���[�^�[����AUSB���z�A�[�X����A�d���R���Z���g�H���AEQ)
����̗\��
�E��������(�o�C���C�������O�ALC�l�b�g���[�N���X�A�z���A�g�U)
�E�d������
�EAB���A���v�V�X�e��
�E�t�������W�A�}���`�A���v�V�X�e��
�����ԍ��F25423651�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�}���`�A���v�ɂ���Ȃ�A�o�C���C���͖��ʁB
�Ɨ��d���i�I�[�f�B�I�p��p�d���A�U600V����̐�p�~���g�����X�j�A�A�[�X�H���A�[�X�_�����\�{�ł����ށj
�܂��͐�p�R���d�r�i���f�J�[�g���b�W�̌������A���f�z�������g�p�j
���܂ƂȂ��ẮA�z���_�̃I�[�f�B�I��p�|�[�^�u���o�b�e���[�������ł����A�̔��I����Ă܂��A�ʏ�͂W���~�A�I�[�f�B�I�p�͂Q�V���~�B
�����ԍ��F25423687
![]() 1�_
1�_
���G���[�S������
����ɂ��́@���v���Ԃ�ł�
��������̃t�������W�@�R�C�Y�~�����Ŕ����܂����BSPK�@10�p�ł��A�}�[�N�@8�p�i���F�̕t�^�j������܂��A�����Ȃ��̐g�ŁA�}���`�͂ł��܂��A���̓��t�I�N���B�i�ł��B
�i���ȉ��z�A�[�X�����Ȃ�̐������܂����B
�d���͓d���̃g�����X��m�C�Y�t�B���^�[�t���d���^�b�v�ł��B
�m�C�Y�ʂ�DAC�ނȂǂ̓o�b�e���[�d������Ԃ炵���ł����A�ŋ߂�GaN�̃A�_�v�^�[���ǂ��炵���ł��B
�o�b�e���[�d���������ŃX�C�b�`���O�d�����Ă�̂�����悤�ł���ᖡ���K�v�Ȃ悤�ł��B
PC�����USB�A�C�\���[�^�[�g���Ă��܂����A�A�}�]���ȂǂŊi���ŃA�C�\���[�^�[������܂��B
�iTI�Ђł̓`�b�v������悤�Șb�������܂������A���ǂ��Ȃ������ł��j
�ŋ߂͊i���I�[�f�B�I��Ԃ̕����ɍs���Ă��܂��B��͂�t�������W�͒P�������ȉ��ŗǂ��ł��B
�}�j�A�̂悤�ɃI�[�f�B�I���I�ɂ́A�����W��~����ƃ}���`�ɂȂ�̂ł��傤�ˁB
���炵�܂����B
�����ԍ��F25423808
![]() 0�_
0�_
��cantake����
���v���Ԃ�ł��B
�t�������W�������ł��ˁB
���́A�ŏI�I�ɂ�GENELEC�̃t�������W�Ƀ`�������W�������ȂƎv���Ă��܂����������ł��B
�܂��́A�����I�ɒቹ�}���`�`�����f�o�Ƃ��ŗV�тA�J�[�X�e�pAB���}���`�A���v/10ch�Ƀ`�������W���悤���ȂƎv���Ă��܂��BFLR2��2�ARLR2x2�A�T�u�E�[�n�[2
https://www.escorp.jp/catalog/products/4532817508265
�ŏI�I�ɂ͕������R�b�N�s�b�g���������ł��ˁB
https://ascii.jp/elem/000/004/155/4155365/
���z�A�[�X�́A�O�����h�P�[�u�����d�v�݂����ł��ˁB
�m�[�}����USB�P�[�u�����ƌ��ʂ͔��������̂ŁA�����\��ł��B
�d���͐��f�n��Anker�̃����_�S���`�E���C�I���d�r���������Ǝv���Ă��܂��B
Anker�̃��o�C���o�b�e���[�͒������\�Ȃ̂ŋC�ɓ����Ă��܂��B
https://www.ankerjapan.com/pages/powerhouse-longlife
�A�C�\���[�^�[�́A���[�^����n�u�܂ł�SFP�ɂ���Ɨǂ������ł��B
�X�g���[�}�[����NEO Stream�͑Ή����Ă��܂��ˁB
�܂��A��肽�����Ƃ͎R�ς݂ł����A�����Âi�������Ă����\��ł��B
TBC
�����ԍ��F25423852�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G���[�S������
��cantake����
����ɂ���
�t�������W�Ɂ@�������ė��܂����B
�ȑO��2way���g�p���Ă����̂ł����A���̂Ȃ���ɁA����[���ł����A
�����̕������̂��͓Y��������AGENELEC�܂ł́@�Ă��͂��܂���ł������A
NC7v2_WN�L���r�l�b�g��Tangband 8cm�t�������W���j�b�g W3-1878���o�b�t�����g�p����
���݁@���V���W�F�l���[�^�[���@�쐬���ł��B
�G���[�S��������@�ŏI�ړI�܂ŒB���ł���Ƃ����ł��ˁB
���͂����I���ɓ����Ă��Ă܂��̂ŁA���̒i�K���ŏI���ȂƎv���Ă���܂��B
�ł͈��������@�e�ɂĉ��������Ă��������܂��̂Ł@��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F25423897
![]() 1�_
1�_
���Ȃ艓�����̂�ɂȂ肻���ł���
�撣���Ă�������
���˕�������C���[�W�ɂ͂Ȃ�Ƃ������܂����ǂ˂�
�C���[�W�̓C���[�W�ł����炠��ł�����
�����ԍ��F25423947�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���I���t�F�[�u���^�[�{����
���x���肪�Ƃ��������܂��B
����t�������W�����ł��ˁB
���������̂����`�������W�������ł��ˁB
���V���A�C�\���[�^�[�撣���Ă�������(��
�����ԍ��F25424136�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���[���A�R�[�X�e�B�b�N�̊�b
https://youtube.com/watch?v=vduWcRBOWFI&si=U1V8l5aMPgHL2cQU
�����ԍ��F25424276�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G���[�S������
����ɂ���
�C���[�W�ʐ^�����Ĉ��|����܂����B
�����͋����̂Ŏ�̓���悤���Ȃ��̂ł����A���R�~�����Q�l�ɂ��ēV��R�[�i�[�ɂ́A�z�[���Z���^�[�ŕ��F���ۂ��{�[����u���Ă��܂��B�y���Ď�y�ɐݒu�ł��܂��������Ă����S�ł��B
�ǂ͋z���ނ��Ă��܂��B�z�[���Z���^�[�ɂ͖��������̂ŃA�}�]����30�p�̎l�p�Ȋi���i�w���A�z���������o�Ă��܂��B���ʃe�[�v�Ŏ��s���ł��܂��̂ŊȒP�ł��B���������ɂ͌��ʓI�Ǝv���Ă��܂��B�ǃR�[�i�[�͋C�x�߂ŃN�b�V������u���Ă��܂��B
�g�U�͂��Ă��܂��A�{���̓ʉ�����ނȂǂ͎��s����̂͂��X�ɗ��߂Ζ����Ŏ�ɓ��肻���ł��B����X�s�[�J�[�{�b�N�X���ɓ���Ă���������܂��B
�C���[�W�ʐ^�Ƃ͑S���Ⴂ�܂����A�v�A�I�[�f�B�I�ł��V�ׂ܂��B���炵�܂����B
�����ԍ��F25424545
![]() 0�_
0�_
���G���[�S������
���I���t�F�[�u���^�[�{����
�t�������W�ł����A�{�b�N�X�̉e�����傫���悤�ł��ˁB�l�p�����łȂ��X�s�[�J�[�ɂ����͂������܂��B�ؑ\�̍H�[�̃J�l�L������̑��ی^�A�}�j�A�̕���G���̎���ł������悤�Ȃ̂�����܂����B�O�����i�ł͒B���^�̒��S�i�Ȃǂ�����܂����B
��ʐ��Y���ł��Ȃ��̂ʼn��i�����߂ł����A���ϓI�ɂ����y��Ԃ��y���߂����ȋC�����܂��B
����͂��܂��܋����p�[�c��BOX���o�i����Ă����̂ŗ��D�����̂ł����A�h���ɂ��ă`�������W���悤�Ǝv���Ă��܂��B
�J�����L���郄�X����������ςł����B�^��ǃV���O���A���v�����Ǝv���Ă��Ĕ\���̍������j�b�g�ɂ��܂����B
�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ��b�Ŏ��炵�܂����B
�����ԍ��F25424610
![]() 0�_
0�_
��cantake����
���v�A�I�[�f�B�I�ł��V�ׂ܂��B
�I�[�f�B�I�͉Ȋw�Ɗ����̑����|�p�ł��ˁB
�������������ɂ����Ɋy���ނ��B
�����܂��܂��������ł�(��
�����ԍ��F25424623�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G���[�S������
����ɂ��́B
Star Wars Theater�ł��B
https://www.youtube.com/watch?v=Z7cHZBuzSYU
�X�N���[������ɋ@��ނ��S�������A�������肵�Ă���̂��ǂ��ł��ˁB
14000Watt�̓d�r�쓮�œd���m�C�Y�����������ł��B
�����ڏd���Ȃ̂ʼn�����O�b�Y����������܂���B
Kaleidescape�͏��߂Ēm��܂����B
�����ԍ��F25424743
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�v�������������ł���(��
�����A�c�ɂ̓y�n�����āADIY�z�[���V�A�^�[�n�E�X����肽���ł��ˁB
�d���̓\�[���[���d���A�쉈���������琅�͔��d�ł��傤���B
�����ԍ��F25424782�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��Kaleidescape
�f���pNAS�݂����ł��ˁB
DTS PLAY-FI�ɑΉ�����A���C�����X��AV�A���v������Ȃ����ł��ˁB
https://dts.com/ja/dts-play-fi/
�����ԍ��F25424798�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G���[�S������
�\�[���[�␅�͔��d�͓d�r�������ł����A�m�C�Y���o�Ȃ��D�G�ȃC���o�[�^���g���K�v������܂��ˁB
�ߏ��Ƀ\�[���[���d���Ă��鏊������ƒ��ԁA���������Ȃ邻���ł��ˁB�K���䂪�Ƃ̎��ӂɂ̓\�[���[���d�͂���܂��B
Kaleidescape���g���āA��������BD���v���[���[�ɃZ�b�g�����A�W�������R���őS�����삷��悤�ł��ˁB
�����ԍ��F25424830
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
��Kaleidescape���g���āA��������BD���v���[���[�ɃZ�b�g�����A�W�������R���őS�����삷��悤�ł��ˁB
�����ł��ˁB
�f��f�������X���X�X�g���[�~���O�̎���ł��ˁB
���ߏ��Ƀ\�[���[���d���Ă��鏊������ƒ��ԁA���������Ȃ邻���ł��ˁB�K���䂪�Ƃ̎��ӂɂ̓\�[���[���d�͂���܂��B
�\�[���[���d����Ȃ��ł����A�ߏ��ɃX�[�p�[�������āA24���ԃG�A�R���ғ����Ă�̂Ŏ���邳���ł��ˁB
���́ANTT�̌��d�U���f�o�C�X�Ɋ��҂��Ă��܂��B
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1529382.html
�����ԍ��F25424872�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���r���OAV�V�X�e��
�Ƌ�/�T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h�������܂����B
�������/4��
�_�{�̐ڍ������X��������ł��B
���x����蒼���Đ��x���߂܂����B
���̌�A�C���V�����[�^�[�ݒu���Ċ����ł��B
�����ԍ��F25449467�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G���[�S������
���x�͊p�̓g����ɒ��킵�܂��H
�ӏ���������ƃA�b�v���܂���
���I�͖ʗ���������ƂȂ��ǂ��ł���
�����ԍ��F25449521
![]() 0�_
0�_
��ktasks����
�v�����ۂ��ł��ˁB
�_�{�͈ʒu���킹�����Y�C�̂ŁA���x�I�ɂ̓C�}�C�`�ł����ˁB
���́A������܂�(��
https://www.noe.co.jp/business/architectural-acoustics/own-products/ags/lineup/
�����ԍ��F25449543�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Q���V�X�e���Ƀf���t���[�U�[��ݒu���܂����B
�I�[�f�B�I�̔z�u���c�^���牡�^�ɕύX���܂����B
�O�������ꂪ�L����A���E�̉��̊g�U�̃o�����X���A�b�v���������ł��B
�R�[�i�[���^���L�͎l�ӏ��ݒu���ċz�����ʂ����҂������Ƃ���ł��B
���Ƃ́A�^���ރf���t���[�U�[�Ŏl���̃o�����X������A�قڊ����ł��B
�f�B�t�F�[�U�[�͍���A������̃��m��g�ݍ��킹�Ďg�p���܂����B
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B085M34J93?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
�����ԍ��F25468777�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ƁA�{�[�J���n�̒�ʊ��A�ቹ�̌��݂������đS�̓I�Ƀp���t���ɂȂ�����ۂł��B
bluOS��4.0�ɃA�b�v�f�[�g���ꂽ�̂őS�̓I�ɍœK������Ă��������ł��ˁB
�����ԍ��F25468814�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���r���OAV�V�X�e���ɂ��f�B�t�F�[�U�[��ݒu���܂����B
�ݒu�O
2.1ch/Amazon music�Ŋӏ܂������̒ቹ���ATV���ɗ��܂��Ă�����C���������B
�ݒu��
2.1ch/Amazon music�Ŋӏ܂������̒ቹ���A�i�`�������ɕ��U����ăX�b�L���������܂����ቹ�ɂȂ�����ۂł��B
���̌��ʁA�{�[�J����ʊ��ƕ��������オ���������ł��ˁB
���Ȃ݂ɁADynamic EQ/ON�̕����ቹ�i�`�������ɑ�������đ̊��A�b�v���܂��B
�����ԍ��F25469200�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Q���V�X�e���Ƀf�B�t�F�[�U�[�Ɗϗt�A����lj����A�i�`�������T�E���h�ɒ����B
���[���A�R�[�X�e�B�b�N�f�U�C���ŏI�`�Ԃ܂ł��Ə����ł��B
�����ԍ��F25474023�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
AV�V�X�e���̃T���E���h�X�s�[�J�[����Ȋ����B
�C���V�����[�^�[��lj������ʃe�[�v�Œ�B
�L���̂���T�E���h�Ȃ�܂����B
�����ԍ��F25474025�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɍ���̊ϗt�A���͂�����̃V���b�v�ōw�����܂����B
https://hitohachi18.com/
�f�U�C���̃Z���N�g���ǂ��X�����e�ł����B
�����ԍ��F25474036�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���r���OAV�V�X�e�������C���[�W
AV�V�X�e��/4.1.2
�A���v/X1700H
�t�����g�X�s�[�J�[/Wharfedale/LINTON Heritage
�T���E���h/KLIPSH
�T�u�E�[�t�@�[/KEF/KC62x2
�f��ӏ�/Audyssey OFF
�T���E���h���[�h/DOLBY ATMOS/�T�u�E�[�t�@�[ON
���y�ӏ�
�s���A�_�C���N�g���[�h/�T�u�E�[�t�@�[OFF
AV�A���v�͂䂭�䂭�O���[�h�A�b�v
�t�����g�v���A�E�g�\��
�����ԍ��F25482636�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���P�P�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e��
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24859394/#tab
�̖{�ł͂Ȃ��X���ɕς���Ă������߁@�X�����܂��B
�@���̃X���́@���L�̑����ł��B
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24859394/#25343913
�@����Ƃ��ẮABOWS���@����X�s�[�J�[�E�̗L���l�@�Γc�����Ń��C���V�X�e������C�^�����Č��J��������
https://www.youtube.com/watch?v=ENg5NGMgReU&t=710s
�@�ɑ�����e�ƂȂ�܂��B
�@���Ɉ��p���̃X�����R�s�y�������������܂��B
![]() 1�_
1�_
[ListenFirstMeasureAfterwards����]
������ǂ�����
�u����ǂ�����̘^���@���C���@vs�@���ȁ@�����@�v���C���[�o�́i���Y�p�C�I�[�f�B�I�j�@�����@W8-1808��C�^���v
http://bhbs480.blog.fc2.com/blog-entry-1872.html#comment4437
�u���O�E�n�C�G���h����X�s�[�J�[�y�����Ǝ���̕����z
http://bhbs480.blog.fc2.com/blog-category-10.html�@
���Ȃ݂ɁA�ّ�̎������ł́A
�P�D�����@(wav �t�@�C��)
�͉��y�I�Ɋy���߂�Ƃ��Ă��A
�Q�D���������Y�p�C�I�[�f�B�I�̏o�͂����R�[�_�Ř^����������
�͑S���ʖڂł������B�P�ɔ�r���ĕώ������肷���āA���͂⒮���Ɋ����Ȃ��܂�Ȃ����y�Ɖ����Ă��܂����B
�Ƃ������A����J�l�ł����A����ǂ�����B
[BOWS����]
ListenFirstMeasureAfterwards����
�@�Q�l�ɂȂ邲�ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
�@���y�̍Đ��Ɓ@���ɘ^���Ɋւ��Ắ@�܂������Ŏ��s���낵�Ȃ���O�ɐi�����Ƃ��Ă���̂Ŏ���ʂƂ���͑��X���邩�Ǝv���܂��B
�@��������ӌ���������������肪�����ł��B
�@�����́Adualazmak�����Ă��X���ł��̂Ł@�ł��܂�����Youtube�̕����A�l�����Ă��X���ɓ��e�������������ł��B
�@ListenFirstMeasureAfterwards����ɂ́A�ߋ��Ɋy�Ȃ̑I�����܂�Ȃ��Ƃ������ӌ������������܂������A����̓v���C�o�b�N���܂�Ȃ��Ƃ������ӌ������������܂����B
�@�����Ł@2�_���肢������܂��B
�@1�_�ڂł���
�@�w�E�����������悤�ɁA���J����Ɋւ��Ă͂܂��܂�����Ȃ��Ƃ��낪����̂Ł@��������P��i�߂Ă��������Ǝv���܂��B
�@�����Ł@�ǂ��������Ɗ�������������ListenFirstMeasureAfterwards����������悤�ȉ��y���̂���I�Ȃ�������ŁA���y�I�ɖ����ł���悤�ȍĐ����̘^�������Ă��������A���ȂƍĐ����̔�r��Ƃ��Č��J�������������ł��B
�@�l�́AListenFirstMeasureAfterwards���y�I�ɖ����ł��Ă��铮����r�����̃��t�@�����X�Ƃ��ĉ��P�ɋ��݂����Ǝv���܂��B
�@2�_�ڂł���
�@ListenFirstMeasureAfterwards����̎��g�̃X���ł��낢���r�������ĕ]������Ă��܂����A�\�������w�I��������A���̐���������Ł@�l�̂悤�Ȋ����̒Ⴂ�l��ɂ́@�����Ⴄ�̂������ς�킩��܂���B
�@���܂��ẮA1�_�ڂ̂��肢�ō쐬���ꂽ������e���v���[�g���āA��r�@��̍Đ�����Ƃ��ĕ��ׂČ��J���Ă�����������Ő������Ă��������Ɓ@���ƕ]���̕R�Â����o���Ĕ[���������Ǝv���܂��̂Ł@��r�����f�[�^�Ɖ�����Z�b�g�Ō��J���Ă����������ł��B
�@�l�݂̂Ȃ炸�A��������̐l�̖��ɗ��Ǝv����̂Ō�肢���܂��B
�@�l�̂悤�ȉ��y���̒Ⴂ�l�Ԃƈ���ā@�o���L���Ŋ����̍���ListenFirstMeasureAfterwards����Ȃ�A�T�N�T�N��������J�����������Ǝv���܂��̂Ŋy���݂ɂ��đ҂��Ă���܂��B
[ListenFirstMeasureAfterwards����]
��BOWS����
Linn Specialist ����� YouTubes �͉��y�Ƃ��ĖO�������Ȃ��ł��ˁB
https://www.youtube.com/watch?v=jxFtreEI1o0
https://www.youtube.com/watch?v=CytQnz7fDTI
https://www.youtube.com/watch?v=3y_X5RbdP4Q
Benz Micro LP-S ������ł��邱�Ƃ������� YouTubes ����͂�����Ɣ���܂��ˁB
���}�� YouTubes �̂��Q�l�܂ŁB
�����ԍ��F25346501
![]() 0�_
0�_
ListenFirstMeasureAfterwards����
�@�Q�l������肪�Ƃ��������܂��B
�@�������O�o���Ă���A�悤�₭�S���������Ƃ��o���܂����B
�@���̗����������|������������܂��ł��傤���H
�@�ǂ̂悤�ȈӐ}�ł��̗���������̂��H
�@���̗Ⴉ�牽�����A�K�����ׂ��Ȃ̂��킩��܂���B
�@�Öق̗����ł͂Ȃ��A�ł��܂�����ڍׂɐ�������������Ə�����܂��B
�@�l��Youtube�Ɂ@��r�����̌���(WAV�t�@�C��)�ƍĐ����u(���Y�p�C�I�[�f�B�I)�����C���^�������t�@�C���Ȃǂ������܂����B
�@����ɑ���ListenFirstMeasureAfterwards����@�́A�u�ώ������肷���āA���͂⒮���Ɋ����Ȃ��܂�Ȃ����y�Ɖ����Ă��܂����B�v�ƈӌ�����Ă����̂Ł@�����ƍĐ����̔�r�ƍl���Ă��܂����B
�@�Ⴆ�@sakuraro ����́@�u�Z�Z�X�s�[�J�[��r �Ō�Ɍ��Ȃ���....�v�݂����ȓ��悪��Ƃ��Ď������Ǝv���܂������A�������Ȃ���@��͍�҂̃I�[�f�B�I�V�X�e���łP�ȍĐ����ꂽ����ł����B
�@�Ȃ�̂��߂ɁA���̓�������p�����̂ł��傤���H�Ӑ}�����������������B
�@�܂��A���y���͂���̂͂��������y�Ȃ��Ƃ�����ł���A�I�Ȃ̎Q�l�ɂ������v���܂���
�@The way we were�@�� 5��28�b
�@I never had a chance�� 2��40�b
�@The very best "Carmen Fantasy" percussion�@��20��20�b
�@�ƒ������܂��B
�@����Ŕ�r������쐬������Q���Ԓ����܂����A��r���邽�߂ɐ_�o�ْ̋��������܂��A���̋L���Ƃ̔�r������Ȃ�܂�
�@�e�Ȃ̂����@���y�����D���t���[�Y���܂ށ@30�b���x�̋�ԁ@(�� 2��05�b�`2��36�b�j�Ƃ�������Ő��������肢�܂��B
�@�܂��A����ɂ́A���Ȃ̏o�T������܂���B
�@���p���悤�ɂ����p�����s���ł��̂Ł@�����m�ł�������Ă��������B
�@�܂��A�@�uBenz Micro LP-S ������ł��邱�Ƃ������� YouTubes ����͂�����Ɣ���܂��ˁB�v�ƃR�����g����Ă��܂��B
�@����̃V�X�e���́ALP12�̓X�^���_�[�g���ā@�^��ǃA���v�v���A����^��ǃA���v�A���[�T�[PM2�𓋍ڂ�������ȍ\���̃o�b�N���[�h�z�[���X�s�[�J�[�Ɓ@���Ȃ�Ȃ������ē���ȍ\���Ł@�قƂ�ǂ̐l���Đ����̑z����������̂��Ǝv���܂��B
�@���̂悤�ȍ\���ł́@�@Benz Micro LP-S �����̓���̉��ɂǂꂾ����^������̂������炸�A����ł��邱�Ƃ����͓̂���Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ��l�͂����ς蕪����܂���ł����B
�@ListenFirstMeasureAfterwards���@Benz Micro LP-S�@���������ł���A��ʓI�ŏ������Ă���l�̑����@DENON DL103���ł̍Đ�����^�����Ă��炢�A���J���Ă͂��炦�܂��H
�@����ҏW���߂�ǂ��Ȃ�AWAV��FLAC�ł���������@�l�̕��œ���ҏW���Č��J���܂��B�@�@�@
�@�ȏ�@��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F25346506
![]() 4�_
4�_
2023/07/18 06:28�i1�N�ȏ�O�j
��BOWS����
���n�C�G���h�ɐ��ʂ��Ă��Čo���L�x��ListenFirstMeasureAfterwards����@���炷��Ɠ��R�̂��Ƃ�������܂��A���͂��Z�����ā@�l�ɂ͂ǂ������Ӑ}�ł���Youtube��I�����āA�E�߂Ă����������̂��A�܂����y���̂��長���ǂ���͂ǂ����H
Linn Specialist ����� YouTubes �ɂ͊S������܂����̂ŁA�ȑO����ǐՂ��Ă��܂����B
Phono Cartridge �ł����A�J�[���b�W�Ƃ��Ă͎��d�������āA���̌��ʂ�����x����g�[���A�[���ɂ��Ȃ�̕��S��������̂ł̂ŁA����܂ő��̃J�[�g���b�W���[�J�[�������Ă������@�� Benz Micro �Ђ͂��̉ۑ�ɉʊ��ɒ��킵�� �����I�E���y�I�ɔ��Ƀo�����X�̎�ꂽ Benz Micro LP-S �ݏo���܂����B����́A Benz Micro �J�[�g���b�W�ɐ��ʂ��Ă�����Ȃ�e�Ղɗ����o���邱�Ƃł��傤�B
�����ŁAYouTubes �ɂ����� �u���̎��ł́v Micro LP-S �̍Đ�����ɂ��܂����Ȃ��Ă��� Linn Speciallst ����ɂ���� YouTubes 3�_�Ɍ��y��������ł��B
�ǂ������y�I���ƌ����܂��Ă�����ɑ�������͓���ł��B���͂�A�����̗̈�ł��B���̃R���T�[�g���ĉ��t���ǂ����f���炵�����������������̂Ǝ��Ă��܂��B���ʂ̉��y�]�_�ƂȂǂ͔�������p���Đ�������̂ł��傤���A�̋g�c�G�a�̂悤�Ȑl�͒[�I�ɖ{����\�����܂��B���{�ł̗�̃z���r�b�c�̉��t��[�I�Ɂu�Ђъ��ꂽ�����i�v�Ə̂����̂��ނł��B
���́u�Ђъ��ꂽ�����i�v�ƌ���ꂽ�����ł������̂悤�ȉ��t�ł���ȂƗ����o���܂��B
�I�[�f�C�I�ɂ����ẮA�Ր��ɐG���Đ����y�����ɂƂ��Ă͖O���Ȃ��D�܂������y�ł��B
���̈Ӗ��ŁALinn Specialist ����̗�� YouTubes �̍Đ����y�͎��̋Ր��ɐG��܂����B
���ꂪ�A���l�ɂƂ��Ă͂ǂ������邩�͒肩�ł͂���܂���A�l���ꂼ��ł��B
���ꂪ�Ր��ɐG��Ȃ���A����ŗǂ��ł��B
���̉��i�R���f���̓��e���e������A���̐l�̃I�[�f�C�I�Ɋւ��郌�x���͎��ɂ͑�̂킩��܂��B
���̐l�̃��x���ɍ��킹�Ď��͘b������̂����ł��BDENON D103 �Ȃǂ͎��̊ᒆ�ɂ͂���܂���B
��� Linn Specialist ����� YouTubes ���Ċ��������Ƃ���A���͂��̂悤�ȕ��Ƃ͂��ꂩ����i��ł��b�o���邱�Ƃł��傤�B
�Ō�ɁA���͕]�_�L������ؐM�p���Ă���܂���A�M���Ă���͎̂����̎��ƒ��������ł��B
�܂��A����ȂƂ���ł��B
�����ԍ��F25349090
![]() 0�_
0�_
ListenFirstMeasureAfterwards����
�@���肪�Ƃ��������܂��B
�@�l�̊��҂��Ă����Ƃ́A���Ȃ��|���قȂ�܂����@�������Ă��炢�A�l��ListenFirstMeasureAfterwards�����߂Ă�����̂��Ⴄ���Ƃ�������܂����B
�@ListenFirstMeasureAfterwards����̋Ր��ɐG�ꂽ���̂��@���y�I�Ȃ��̂Ƃ������Ƃł��ˁB
�@�Ր��ɐG��邩�ǂ����́A���l�ɂ͔��ʂł��Ȃ��B
�@�l�́A�I�[�f�B�I�@��̐v�A�J��������Ă���̂Ł@���S���́A���ʁA�����x�ASN�A�������Ƃ������h���h�Ɋւ�����̂Ł@�����������߂邽�߂ɁA�ْ����Ȃ��炠��T�������A������ꂷ�悤��r�������s���Ă���A���J���Ă�����̂��@���̂悤�Ȏ�|�̂��̂ł����āu�O���Ȃ��D�܂������y�v�Ƃ͋t�ł��ˁB
�@�����̉��y�Ɋւ��鉿�l�ς��@�ėp�I�łȂ��Ǝ��̂��̂ł���Ƃ������Ƃ����o���Ă���@ListenFirstMeasureAfterwards���@���g�����Ă��X���Ō䎩�g�̉��l�ς������̂͂��܂�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@��O�҂��@�����Ƃ͊������قȂ�Ǝv�����ꍇ�́@���Y�X����ǂ܂Ȃ���Ηǂ������ł��̂�
�@���̂悤�Ɏ��o���Ă���ListenFirstMeasureAfterwards���@�킴�킴���l�ς̈قȂ�l�̏������݂�T���ā@�@�u�ώ������肷���āA���͂⒮���Ɋ����Ȃ��܂�Ȃ����y�Ɖ����Ă��܂����B�v�ƁA�������ލs�����悭�킩��܂���B
�@�Ⴆ�Č����Ȃ�A�l�̑O�ɏo�Ă��Ėʂƌ�������
�@�u���O�̊�͕s�H�Ō���ɑς���I�v
�@�ƌ�������̂悤�Ȃ��̂ł��B
�@�ق��Ă��ǂ��̂ɁA�Ȃ�ł킴�킴����Ȃ��Ƃ���H�@�l�͗����ł��܂���B
�@�u����ł͕s�H�Ƃ͂ǂ��������Ƃł����H�v�Ɩ₤�ƁH
�@�u����͉��̍D�݂Ȃ�Ő����ł���A�Ƃɂ������O�̊�͌�������v
�@�ƁA�c�_�ɂ��Ȃ�Ȃ��ł��B
�@���̂悤�ȍs���͂��T���ɂȂ���������낵�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25350298
![]() 5�_
5�_
�����Ŏ��炵�܂��A�{���Ȃ�S�Ăɖڂ�ʂ��Ă��珑�����ނׂ��Ȃ̂�������܂���
�����Ɩڂ�ʂ��������̂���Ɏ���ȏ������݂ɂȂ�܂��A���݂܂���A��Ɏӂ��Ă����܂�
������������������Ă��������܂�������̑o���̌����������͂킩�����C�����܂�
�ǂ�������ɊԈ���Ă͂��Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�ǂ����Ă����̎�̘b�͑傫�Ȃ����b�̃A�h�o�C�X���݂��������݂��������Ȃ�͎̂���������
�������^�`���������ƂɊF��������ԂƎv���Ă��܂�w
�Ȃ�Γ���ł̘b�Ȃ̂ő��l�̓���̈��p�Ȃǂł͂Ȃ��A�����̓�����o���āA�K�v�Ȃ炻��ɑ������A������
�����ŏ����Ęb��i�߂�̂��ł��傤�A���̊̐S�̖����𑼐l�̈��p�Ȃǂōς܂����Ƃ��邩��b�͂���ɂ�₱�����Ȃ�̂��Ǝv���܂�
�����o���セ�ꂪ�ł���l�Ȑl�͂���ȏ������݂͂��Ȃ����������ł�
�����ԍ��F25351767
![]() 1�_
1�_
������[�����������
�@�x���Ȃ��Ă��݂܂���B
�@�������肪�Ƃ��������܂��B
>�ǂ�������ɊԈ���Ă͂��Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�ǂ����Ă����̎�̘b�͑傫�Ȃ����b�̃A�h�o�C�X���݂��������݂��������Ȃ�͎̂���������
>�������^�`���������ƂɊF��������ԂƎv���Ă��܂�w
�@���̎�̘b�肪�@���ɗႦ���邱�Ƃ������ł��ˁB
�@�����̐_�l����Ԃł���B
�@�M����_�l�̕z�����s���A�Η����鑼�̏@���Ɛ킢�����肤��B
�@�����̃I�[�f�B�I�}�j�A�̕��Ɛe��������A�W��₨��K��Ȃǂ����Ă��܂����A�I�[�f�B�I��͑��l���ł̋�����Ƃ����Ȃ��A�����ʼn������Ȃ��Ƃ킩����ł���A��l�Ő[�݂Ƀn�}��̂ŏ@���Ɋׂ�₷������������Ǝv���Ă��܂��B
�@������ł��A�B�e�����Î~��������ʐ^/�J�����Ƃ�����́A�摜�Ƃ����l�b�g���ł��A�A�E�g�v�b�g��]�����₷�����߁A�l�b�g��̎ʐ^���e�T�C�g���ł��݂��Ɍ𗬂��邱�Ƃ��ł��₷���A���ݗ������₷���Ќ�I�Ȏ���Ǝv���܂��B
�@�I�[�f�B�I��́A�ʐ^�̂悤�Ƀl�b�g���e�ł̕]����A�R���y�e�B�V�����A�R���e�X�g�ɂ��q�ϓI�ȕ]��������킯�ł��Ȃ��A��R�҂̕]����ӌ������ɂ����������L��A�����̗����ʒu���킩��ɂ����B
�@�܂��A�������\�z�����V�X�e����l�ɕ]�����Ă��炤�Ƃ������Ƃ��@�����I�ɓ�����߁A���ݗ����ɂ����A��C�T�I�Ȑl��������ۂł��ˁB
�@�����ł��A���ݗ��������L�����i�Ƃ��ē���́A�L���Ȏ�i�Ǝv���쐬/���e���Ă��܂��B
�@�����Ȑl���A�����Ȉӌ���Ԃ��Ă��ā@�����ł��C�t���Ȃ��_���w�E���ꂽ�肵�Č������L����܂��B
�@�����̓��e�Ɍ���Ȃ���ł����A�l�Ɉӌ�����Ƃ��́@�C�ɓ���Ȃ������ꍇ�A�ǂ��̕��������ŋC�ɓ���Ȃ����H�@�ł́@�ǂ����P����C�ɓ���̂����A����ɋC�t����A���P�̎����������炷���e�����߂��ق��������ł��B
�@�����łȂ��@�P�ɋC�ɓ���Ȃ��ƌ����Ɓ@����ɉ��̉v��^���Ȃ��̂Ł@"�]��"�ł͂Ȃ�"����"�ɐ��艺����܂��ˁB
�@�������C�ɓ���Ȃ��̂����̂��H�������ƕ��͂ł��Ȃ��悤�Ȃ�@����Ȃ������ǂ��ł��ˁB
�����ԍ��F25355340
![]() 6�_
6�_
�X�s�[�J�[�P�[�u���ACD�v���[���[��Ȃǂ̑ѓd�������s���ƁA��R�������ăX�s�[�J�[���ѓd�����܂�܂��ˁB
�@�A���~����➑̂ƃh���C�o�[�̊Ԃɋ���ł݂܂����B
�@�v���V�[�{���ʂʼn����y���Ȃ��������H�H�H
�@�L�b�`���p�A���~��������A�J�b�g�̃M�U�M�U�𗘗p���ĕ��d�ł��I�I
�@�ɂԂ��Ȃ̂Œ����ڂŌ��ĂˁB(^-^)
![]() 2�_
2�_
�͂��߂܂���
�����̓��u�n�[���j�[������ŃA���v����P�[�u���܂߃X�s�[�J�[�ѓd�������Ă܂��B�I�}�P�ɃT�u�E�[�n�[�������B
������������͕������Ȃ������������ĂɂȂ�܂��B�A�A�������������ꉹ�����ꂽ�C���[�W�B
���Ƀo�b�N�O�����h�̉��t�����ĂɁB
���[�J�[�H���ς��߂��ĉ����������Ƃ��Iwww
���ƂȂ��A�R���o��CD������Ɏ��Ă�B
�����ԍ��F24974868�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�ѓd���Â����Ă��܂����I�I
�@�X�s�[�J�[�O���̔������x���A���~�������܂Ȃ��ƐÓd�C�������Ȃ��āA���܂��Ă����݂����ł��B
�����܂ŊO���̔����܂ŋ��ނƁA16cm�t�������W�ł��������X�g���X�Ȃ���܂��B
�@�������f�U�C��������Ȃ̂ł�蒼�������I�I�@
�@�A���~���̃M�U�M�U�͋���ł��鑤�ɂ͂���܂���B
�����ԍ��F25311944
![]() 0�_
0�_
https://www.terrabyte.co.jp/JMAG/exe-jmag/jmag-sample5.htm�@����q��
�@�X�s�[�J�[�̑ѓd�����d�̓{�[�C�X�R�C������ł��B�@
�n�߂�������̑ѓd���l���Ă��܂����܂��{�[�C�X�R�C�����̂̑ѓd�͏��Ȃ��l���Ă��܂����B
�@���������͐U���ŁI�I�@�{�[�C�X�R�C���ƐU���ł͂Ȃ����Ă��܂�����A�{�[�C�X�R�C�����d���ꂽ�ѓd�͐U���łɒ��܂���A�����I�ɃA���~���ŕ��d����Ƒѓd�̔Z�W���ł��āA�����@�U���ł̕����U�����j�Q�����H�H
�@�ŁA�X�s�[�J�[���j�b�g�̂قڑS�����A���~���ŋ��ށI�I
�����ԍ��F25316620
![]() 0�_
0�_
�����A
�@�X�s�[�J�[�̑ѓd�̔��d�̓{�[�C�X�R�C������ł��B�@
�n�߂͋������̑ѓd���l���Ă��܂����A�܂��{�[�C�X�R�C�����̂̑ѓd�͏��Ȃ��l���Ă��܂����B
�����ԍ��F25316653
![]() 0�_
0�_
�����ԍ��F25322964
��L���Q�l�ɁA�A���~�����X�s�[�J�[�̓�����h���ɏ���t���Ēn���������āA�V���R���X�v���[�ȂǓ��ʕ���h�z���܂����B
�V�i����܂��I�I
�@�ѓd�ĂȂ��X�s�[�J�[�ւ̃t�@�C�i���A���T�[�I�I
�����ԍ��F25325974
![]() 0�_
0�_
��s�X���b�h�F�@
�y���S�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab
������i���ݕԐM��180�j�ɂȂ�A�ԐM���Q�O�O���ɒB����Ə������݂��ł��Ȃ��Ȃ邻���ł��̂ŁA���̐V�X���b�h�Ɉڍs���܂��B
����܂ł̌o�܂ȂǁA���̏����ȍ~�ł��Љ�����܂��B
![]() 0�_
0�_
�Q�O�P�X�N�̔N���i��A���j����A���L���ꂼ��̃X���b�h�G
�y�����̃v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד����H�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284
�y���@�����v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד��H�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23151776/#23151776
�y�`�����l���f�o�C�_�[�ŕ�����Ƀo�����X�����x�������H�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23181110/#tab
�y�\�t�g�E�F�A�`�����l���f�o�C�_�[ EKIO�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
�y���@�\�t�g�`�����f�oEKIO �� DAC8PRO �Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/
�y���X�@�\�t�g�`�����f�oEKIO �� DAC8PRO �Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23398907/#tab
�y���X�X�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23523450/#tab
�y���S�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab
�ɂċM�d�ȏ������������Ă��������A���̌��ʂƂ��āA
PC�\�t�g�E�F�A�ł���LUPISOFT�Ђ̃`�����l���f�o�C�_�[�i�N���X�I�[�o�[�jEKIO�G
http://www.lupisoft.com/ekio/
http://downloads.lupisoft.com/ekio/EKIO_user_manual.pdf
��
�X�e���I4-way 8-�`�����l�� DAC�@�ł��� OKTO RESEARCH�Ђ� DAC8PRO;
https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf
��p���āA
�P�D�@Windows 10 Pro 64bit PC�����ŁARoon �� JRiver MC26 ���� 192 kHz 24bit �̃X�e���I�f�W�^���M����AD�ϊ��Ȃ��� EKIO �ɓ��͂��� 192kHz 24bit �̂܂܂ŃX�e���I4-way �W-�`�����l���̃f�W�^���`�����l���f�o�C�_�[�������ш敪���i�N���X�I�[�o�[�����j���s���A
�Q�D�@�f�W�^���W-�`�����l����USB�P�[�u���P�{�œ����� DAC8PRO�� �o�͂��� DAC�ϊ������A���ꂼ��̃A�i���O�����M�����A���v�Q�i�X�e���I�A���v�S��A�܂��̓��m�����A���v�W��j�ɓ����āA�X�e���I4-way 8-�`�����l���̃}���`�A���v�I�[�f�B�I�����\�z����A
���Ƃ�i�߂Ă���܂��B
����ɁA���E�P�䂸�̓Ǝ��A���v�����T�u�E�[�n�[�iYAMAHA YST-SW1000�@�Q��j�������܂��̂ŁA�����I�ɂ́A�X�e���I5-way
10-channel �̃}���`�A���v���ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F24004023
![]() 0�_
0�_
�Ę^�ɂȂ�܂����A����̃}���`�A���v���̑Ώۂł���X�s�[�J�[�Q�ɂ��ďЉ�܂��B
�\���́A3-way�̃��C���X�s�[�J�[ �i�E�[�t�@�[WO�A�X�R�[�J�[SQ�A�c�C�[�^�[TW�j�ɉ����āA���E�ɃX�[�p�[�c�C�[�^�[ST�A����т�������E�ɃA���v�����̋��͂ȃT�u�E�[�t�@�[SW���g���A�����I�ɂ�5-way�̍\���ł��B
���N���p���Ă��郁�C���X�s�[�J�[�́A�����e�i���X�Ɖ������d�˂č��ł���D���� YAMAHA NS-1000 �ł��B NS-1000M�ł͂���܂���B�iNS-1000 �̔w�ʁA���A�V�A��Ԃ� NS-1000M ��� 5mm �����A�O�ʃo�b�t���́A���� 15 mm �������A���d�ʂ� 39 kg ��NS-1000M ��� 8 kg ���d���Ȃ��Ă��܂��B�j
�]���āG
WO 30 cm �R�[��
SQ 8.8 cm �x�����E�� �h�[��
TW 3.0 cm �x�����E�� �h�[��
�ł��B
https://sawyer.exblog.jp/12639976/
�ŕ���Ă�����ɑS�������ŁASQ�����TW�̃A�b�e�l�[�^�[�́A-4 �` -5 dB �̐ݒ�� WO �Ƃ̂Ȃ���A�o�����X���ō��ŁA�����\�͂��t���ɔ������Ă���Ă���A�o���o���̌����ł��B
http://audio-summit.co.jp/2019/04/04/ns-1000m%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%B4%97%E6%B5%84%EF%BC%89/
http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/
��������Q�l�ɂ��āA�Q�O�Q�O�N�ĂɃA�b�e�l�[�^�[�����S��������ăI�[�o�[�z�[�����A����ɁG
http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/
���Q�l�ɂ��āANS-1000�͂R�[�q�����Ċe���j�b�g�ɒ������A�����̃N���X�I�[�o�l�b�g���[�N�ƃA�b�e�l�[�^�[�͓P�����A�N���X�I�[�o�[�l�b�g���[�N�̑S�ẴR�C���ƃR���f���T�[��V�i�Ɍ������A���S�ɃI�[�o�[�z�[�������A�b�e�l�[�^�[�Ƌ��ɊO�t���{�b�N�X�����Ă���܂��B
�N���X�I�[�o�[�́ANS-1000 �I���W�i���Ƃقړ��l�́G
500Hz�C���� -12 dB/Oct
6000Hz, ���� -12 dB/Oct
�ł��B
ST�́A���ɍ��\���ȃz�[���^ FOSTEX T925A �ŁA�A�b�e�l�[�^�[�� -15 dB ������Ŗ炵�Ă���܂��B���J�b�g�́A 1.5 ��F �R���f���T�[�ꔭ�݂̂ł��̂ŁA ��@8 kHz, -6 dB/Oct �X�ŁANS-1000 ��TW �Ƃ��Ȃ�d�Ȃ��Ă��܂����A -15 dB �A�b�e�l�[�^�[�ݒ�ōœK�����Ă���A10 kHz �ȏ�Ŗ{�̂������Ă��܂��B���� ST �́ANS-1000 �̃X�s�[�J�[�ˑ�̒��ɔz�u���Ă���A�v�n �� �r�p ���ATW �� ST �ŏ㉺���狲�ނƂ����A������Ɠ���Ȕz�u�ɂ��Ă���܂��B
���E�� SW �́AYAMAHA YST-SW1000 �Q��ŁA120W 5���̋��̓A���v�����A�c0.01���A�J�b�g�I�t���g�� 30 Hz�`130 Hz �A���ρi-24dB/oct�j�A���x�������\�A�ʑ����]�\�A�S�ă����R������\�A����d��100W�A�O�`���@ ��580×����440×���s440mm�A�d��48kg�@�ł��B������A�ߋ��Q��̃��}�n�ł̃����e�i���X���o�āA���܂ł������A�����ł��B
�\�t�g�E�F�A�`�����l���f�o�C�_�[ EKIO�́A���Ƀ`�����l�����������̗L���ł���肵�Ď��p���J�n���Ă���A���̐ݒ�Ǝ��p�ɂ��ẮA�X���b�h�G
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23212699/
�̍Ō�̂����肩��n�܂�A���̌�́G
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23251861/
�ŁA���Ȃ�ڍׂɏ����������Ă��������܂����ŁA������������������B
���̉���������A���������A�قڊ��������}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e���ɂ��ď����������Ă��������܂��B
�Ȃ��A���Q�l�܂łɁB�B�B�B
ASR (Audio Science Review) Forum �ɂāA���ׂĉp��ł����G
�yMulti-Channel, Multi-Amplifier Audio System Using Software Crossover and Multichannel-DAC�z
�Ƒ肵���X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
����Â��Ă���܂��̂ŁA��������������ł�����K�₢�������A�܂����Q���������B
�����ԍ��F24004029
![]() 1�_
1�_
�}���`�A���v�ֈڍs�O�́A����̃V���O���A���v���̋@��\���́A�Y�t�摜�̒ʂ�ŁA�}���`�A���v���\�z����A���̊����ێ����邽�߂ɁA�����̂r�o�P�[�u���ڑ��ؑփ{�[�h�𐧍�ς݂ł��B
�����ԍ��F24004051
![]() 1�_
1�_
���āA�{�N�i�Q�O�Q�P�N�j�P���Ɂi�b��I�Ɂj���������}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e���̊T�v�}�ł��B
�����ԍ��F24004062
![]() 0�_
0�_
���̃}���`�A���v���\�z�̒��j�ƂȂ�̂��A�`�F�R���a���̎�s�v���n�ɂ���@OKTO RESEARCH�ЁG
https://www.oktoresearch.com/index.htm
�̂W�A���}���`�`�����l��DAC�@�uDAC8PRO�v�@�ł��G
https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
https://www.oktoresearch.com/assets/dac8pro/DAC8PRO_owners_manual.pdf
DAC8PRO �́A�Q�O�P�W�N�ɓo��ȗ��A���̋��ٓI�ȍ����\�ƃR�X�g�p�[�t�H�[�}���X���A���E�I�ɑ傫�Șb��ƂȂ��Ă���܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
DAC�`�b�v�� ES9028PRO ��ł����A�D�ꂽ XMOS�R���g���[���[�i�Ɠ����\�t�g�̐v�Ǝ����j�ɂ���āAES9028PRO�̐��\���Ɍ��܂ň����o���Ă��邱�Ƃ�������A�������A���̂W�`�����l���S�Ăɂ����ċ��ٓI�ȉ������\����������Ă���A�������݂ł����E�ō��N���X�̂P�O�w�i�����炭�T�w�j�ɓ��� DAC�ƌ��Ȃ���Ă���A���ۂɗ��p���J�n���Ă��� Hi-Fi�I�[�f�B�t�@������������̐�^���e���Ɍf�ڂ���Ă��܂��B
���́A�Q�O�Q�O�N�Q���P�T���� DAC8PRO�{�����R���iApple Remote�ł��ADAC8PRO�ƃy�A�����O���ďo�ׁj�����A�l�A���łQ�O�Q�O�N�T���X���ɓ��肢�����܂����B���炭�A�i�m���ɁH�I�j�A���{�ł͍ŏ��̗��p�ƂȂ�܂��B�@�i���̌�A���{�ł������̕��X�����肳��Ă����܂��B�j
�u�l�A���v�Ƃ����Ă��AOKTO�Ђ̃z�[���y�[�W�ŁA�N���W�b�g�J�[�h���ςŔ������������ŁA������ FedEx �̍��ۍq��ݕ��ւŁA�v���n���o�����Ă���T���ڂɎ��̎���i��t���j�ɔz�B����܂����B
�Ȃ��AOKTO�Ђ́A�㗝�X����؎g��Ȃ���`�������ŁA�z�[���y�[�W����̔������B��̍w����i�ł��B
�����ԍ��F24004080
![]() 0�_
0�_
�O�X���b�h�A
�y���S�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO��NS-1000�}���`�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23659380/#tab
�ŏЉ���悤�ɁA�{�N�P���ɁA���̃}���`�`�����l���V�X�e���ɂ�����A���v�\�����i�b��I�Ɂj���肵�A���������Ă���܂��B
���̍\���Ǝ�v�ݒ���摜�S���œY�t���܂��B
�����ԍ��F24004106
![]() 0�_
0�_
�\�t�g�E�G�A�`�����f�o�i�N���X�I�[�o�[�jEKIO �̓��ʂ̐ݒ�́A�V���O���A���v�i�A�L�� E460�j�{LC�l�b�g���[�N�ɂ�������Ƃ̔�r�̂��߂ɂ��AYAMAHA NS-1000 �̃I���W�i��LC�l�b�g���[�N�ƃA�b�e�l�[�^�[�̃p�����[�^�[��͕킵�Ă��܂��B
�N���X�I�[�o�[�t�B���^�[�́A�S��LR�^ -12 dB/Oct �ł���A���̐ݒ�őS�ш�ɓn���Ĉʑ����K�ł��邱�Ƃ��m�F�ς݂ł��B
�Ȃ��AEKIO�̓��������� IIR�t�B���^�[�ŁA 64 bit���������_�ɂ�鍂���v�Z�ł��B
"EKIO uses IIR filters. The processing is done using a cascade of second order transposed direct form II biquad sections. Every calculation is done using 64 bit floating point numbers."
�ڍׂ́A�����������������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-411328
�����ԍ��F24004117
![]() 0�_
0�_
�V���O���A���v���A�}���`���Z���A�̂�����ɂ����Ă��A���łɃX�R�[�J�[�A�c�C�[�^�[�A�X�[�p�[�c�C�[�^�[�p�̂R�̃A�b�e�l�[�^�[�����S�ɔr�����A���ꂼ��̉�H��22���̌Œ��R��}�����Ă���܂��B
���̌o�܂ɂ��܂��ẮA
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-475216
�ŏڍׂɕ��Ă���܂��̂ŁA��������������̕��́A�����������B
���݂ł́A�\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[EKIO �̑ш斈�Q�C�������ŁA�A�b�e�l�[�^�[�̋@�\���ւ��Ă���܂��B
�����ԍ��F24004122
![]() 0�_
0�_
�ЂƂ�̓��e�ŁA�����ł����A�����ł��B
�}���`���Z���@���@�}���`�A���v��
�����ԍ��F24004124
![]() 0�_
0�_
���̂悤�ȃf�W�^���\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�i�\�t�g�`�����f�o�j���ŏ㗬�ŗ��p����}���`�`�����l���|�}���`�A���v�\���V�X�e���ɂ����ẮA��Ƃ��Ĉȉ��̂悤�ȍ��ڂ��d�v�ƂȂ�܂��B
���ŏ㗬��Windows 10 PC���ɂ�����S�� ASIO �\���ɂ�� I/O �̊m��
���f�W�^�� I/O �ɂ��\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�i�\�t�g�`�����f�o�j�̓K�Ȑݒ�
���x���A���C�e���V�[�A�`�����l���ԓ����A�̊m���Ȑݒ�ƍ\��
���ʑ����̓K�ȉ�������ѐݒ�
���}�X�^�[�{�����[������ƃ`�����l���ԑ��Q�C���ݒ�^������A�ǂ��łǂ̂悤�ɍs����
�����́A���݂ɂ��W�^�e���������d�v�ȉۑ�ł���A������T�d�Ɍ����A�����A�����@���Ȃ���}���`���̍\�z��i�߂Ă܂���܂����B
�o�܂̏ڍׂɂ��ẮA���肷���̍ۂɁA���ɐ��E������S���V���ȏ�̖K��^�{�������� ASR (Audio Scieince Review Forum)�̎��̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�����������Ƃ����������B
�p�ꂪ�l�b�N�̊F�l�́A�ŋ߂̃E�F�u�u���E�U��AI�|��@�\�ł��A���������܂Ƃ��ȓ��{��ɖ|���悤�ł��̂ŁA�����Ă݂Ă��������B
�܂��A�`���ł��Љ�����i.com �ɂ������s�X���b�h�Q���A�ŏ����炲��ǂ���������A�o�܂�����������������Ƌ��ɁA�����̕��X���璸�Ղ����A���̕��ʂ̗D�ꂽ�u���ȏ��I�ȏ��ƋM�d�Ȏ����v�����肵�Ă��������܂��B
�����̗v�f���܂߂āA���̃X���b�h�ł��A�f�W�^���\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�ƃ}���`�`�����l��DAC�𗘗p���� �}���`�`�����l���|�}���`�A���v �I�[�f�B�I�V�X�e���ɂ��āA���������p�������Ă��������܂��B
�����ԍ��F24004166
![]() 0�_
0�_
��������o�ł͂������܂����A���������V�X�e���̃��X�j���O�|�W�V�����ɂ�������g�������Ȑ��A����уf�W�^�����x���ADAC8PRO�̃A�i���O�o�̓��x���A����ъe�A���v�̏o�̓��x���i�v���A�E�g�A�܂��̓w�b�h�t�H���o�́j�ɂ�������g�������Ȑ������L�����Ă��������܂��B
�ڍׂ́G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-672384
�����
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-684244
�������������B
�����ԍ��F24004193
![]() 0�_
0�_
�i�b��I�Ɂj���������V�X�e���̑S�̍\������у��X�j���O���i���X�j���O���[���j�̏ڍׂ���ʐ^�ɂ��ẮAASR�ɂ����� ���̓��e�������������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419
�����ԍ��F24004205
![]() 0�_
0�_
���Q�l�܂łɁA�@��\���ƃ��X�j���O���̗l�q���A�����ł��A�S�������\���Ă����܂��B
�ł́A���������A�������ȂǁA��낵�����肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24004235
![]() 0�_
0�_
�F����A
����ASR�X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�̑S�̂ǂ��Ă��ꂽ���ŁA������ NS-1000 �� Be-SQ �̋��ق̐��\���悭��������A������g�����}���`���̍\�z���\�z����Ă��������A���̃v���W�F�N�g�ł��A�uNS-1000�ȊO�̃X�s�[�J�[������̗D�ꂽ�X�s�[�J�[���j�b�g���g���āA�����悤�ȃ}���`�V�X�e�����\�z����\�z�͂Ȃ��̂ł��傤���H�v�@�Ƃ̐^���ȓ��e������܂����̂ŁA�������J�ɉ������Ă���܂��B
���������������܂�����A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-696677
�Ǝ��̉����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-697543
�������������B
�����ԍ��F24006151
![]() 0�_
0�_
�lj����ł����A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-701695
�̒ʂ�A��N���A�l�Ԃł��p�ɂɏ����������Ă��������Ă��� gene_stl��������Q��������A���ɋ�������L�v�ȃR���j�P�[�V�����������Ă���܂��B
�����ԍ��F24012576
![]() 1�_
1�_
����ɒlj��ŋ��k�ł����A�傢�ɋ����[���������������Ă��܂��B
�����܂ł��Q�l�܂łɁB�B�B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-701939
�ȍ~�A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-702891
������܂ŁB�B�B
���ʂ�������@�ł���悤�ɁA���� mikessi����́A�قƂ�ǃv������DIY�X�s�[�J�[�r���_�[���I�[�f�B�I�M���Ƃł��B
ASR ��PM�V�X�e���ŁA�ނ́u�H�[�v�̎ʐ^�A���o�������N�𑗂��Ă��ꂽ�̂ł����A��̃����N�̃|�X�g�Ŕނ������Ă���悤�ɁA����DIY�X�s�[�J�[�H�[�́A�قƂ�ǐ��ށ��؍H�H��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��؍މ��H�̑�^�A���^�A���^�̃v�����u�ނ��������A���̉��ɕʎ��̓��ʎ��������u�������̎��������v�Ƃ��Đ݂��Ă��܂��B
�����A�X�y�[�X�I�ɂ͂Ȃ�Ƃ��\�ȏ���̒�ɁA����� DIY�H�[�����Ă���A�Ɩ��z���Ă���܂����A����Ɏ����߂���A���x�����{�C�Ŏ��̉Ɠ����B�B�B�i�j�@�@���|�ł��̂ŁA�w�����킦�� mikessi�X�s�[�J�[DIY�H�[�߂邾���ɗ��߂Ă����܂��B
NS-1000X ���}���`�A���v���ň��p����Ă���A���̉��B�̕��i�����ȃ��R�[�f�B���O�G���W�j�A�A�炵���j������M�d�Ȍ���ƁA�K���]�i�R���i������������B�B�B�j�̘A����������Ă��܂��B
���Ƃ��ẮA����قǂ̃V�X�e���ł͂Ȃ��悤�Ɏv���Ă͂���̂ł����B�B�B���ڂ��ĊS�������Ă��������Ă���̂́A�����������v���܂��B
�����ԍ��F24015775
![]() 0�_
0�_
�F����A
�����܂ł��Q�l�܂łɁB�B�B
ASR�ɂāA�V�����X���b�h���J�n���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/
�ƂĂ��j�b�`�ȕ���ł����A�����[�g���y�ɂ�������������́A����A�����ɂȂ育�Q���������B
�����ԍ��F24017581
![]() 1�_
1�_
�F����A
ASR�̎�Î� amirm ���A���̒������� Trinnov Altitude ��]�����邱�ƂɂȂ����̂ŁA���O�ɁA���̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-questions-for-flagship-processors-trinnov-storm-jbl-lyngdorf-datasat.21093/
�ŁA����Ȃ��Ƃ������]�����Ă���I�I�A�Ə�������オ���Ă��܂��B
���Ƃ��ẮA�Q�O�Q�O�N�̏����ɁATrinnov Altitude ���^���Ɍ������A����̓G���g���[�N���X��Linux OS PC �i�t�@���m�C�Y���d���g�m�C�Y�����ځH�j�Ƀ}���`�`�����l��DAC���l�ߍ��������A�ƌ��Ȃ��ĉ�������o�܂�����܂��̂ŁAamirm �̕]�����ǂ��o�邩�A�����ÁX�ł͂���܂��B
�����A���݂̊��x�⊴�G���A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-questions-for-flagship-processors-trinnov-storm-jbl-lyngdorf-datasat.21093/post-721161
�ɏ����Ă����܂����̂ŁA������������A�����������B
�����ԍ��F24040775
![]() 0�_
0�_
�F����A
�����A��Ƃ��Ēቹ�̍Đ��ƑS�̃o�����X�̃`�F�b�N�ɕp�ɂɎg�p���Ă��邱�̃p�C�v�I���K�������G
https://youtu.be/i8-nCDXjYr4
�̒ቹ���̐���X�y�N�g����������肢������A�����ɑ��茋�ʂ����炢�܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/bass.18999/post-719623
��
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/bass.18999/post-721150
�������������B
���ቹ�p�C�v�ƃz�[���g�[�������킳���āA 15 Hz - 50 Hz �̖L�x�Ȓቹ���o�����X�ǂ��܂܂�Ă��܂��B
�����ԍ��F24040802
![]() 1�_
1�_
�F����A
���Q�l�܂łɁA,,,
ASR Forum�ł́A���l�̓��e�ŁA����܂łɂ����x����_���i��c�_�H�j���s���Ă����̂ł����A�܂��܂� "Things that cannot be measured" �Ɩ��ł������̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/
��,�G���h���X�ŁA�Y�I�ȁi�H�j�c�_�����X�Ƒ������Ă��܂��B
���́A����Ə�k�����߂āA����ȃR�����g�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-724007
�𓊂�����A
�������É����������āA����ȓƂ茾�i�l�I�ȓƔ��j�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-723262
�𓊂��Ă��܂����A
�^�����Ă�����Âȕ��X�����������ŁA�����̂悤�ɕK�v�ȏ�ɔM���Ȃ��Ă���ʁX�ɂ́A�Ă��ɐ��A�̊�������܂��B
����A���̒��ł��A�u�A���v�̍����g�n�[���j�b�N�c�݁v�ɂ��āA���������[�����Ƃ肪����܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-727530
�ƁA���̎��́G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-727535
�ł��B
�����ɑ��āA���̃V�X�e���̂悤�ȑш�ʃN���X�I�[�o�[�̃}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e���̊ϓ_����A���̊��G���G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/things-that-cannot-be-measured.20808/post-727574
�̂悤�ɏ�������ł��܂��B
�F�l�̂��ӌ��₲���z�́H�H
�����ԍ��F24051709
![]() 0�_
0�_
�F����A
������A�����܂ł��Q�l�܂łɁA�A�A���̃X���̓��e�Ƃ͒��ڊW���܂��A�A�A
ASR �̎��̐V�X���b�h�A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/
�Őe�����Ȃ����t�����X�� Harmonie���A�����I�ȑ����� LP, CD, DVD ��f�W�^���������̐����A�Ǘ��Ɋւ��ĐV�X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-do-you-sort-organise-your-cds-lps-k7s-tapes-physical-medias.21849/
�����Ă��܂����̂ŁA
���X�S�肪���鎄���A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-do-you-sort-organise-your-cds-lps-k7s-tapes-physical-medias.21849/post-726137
�Ŏ��̃|���V�[�Ǝ��ۂ̉^�p���Љ�Ȃ���Q�����Ă��܂��B
��͂�A�F����A���ꂼ��A����Ȃ�ɋ�J����Ă���悤�ŁA�����[���������������Ă���܂��B
�����ԍ��F24051729
![]() 1�_
1�_
�F����A���v���Ԃ�ł������܂��B
���āAASR �̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/dbx-driverack-venu360-review-audio-processor.22497/
�ɂ����āAamirm����ɂ�� DBX DriveRack VENU360 �̑���]�����|�[�g������Ă��܂��B
�{���icom �X���b�h�̖`���ł����Љ���悤�ɁA��N�A�Q�O�Q�O�N�̂P���`�Q���ɂ����āA���́i�����j�A�}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e���̍\�z�ɂ����� DBX DriveRack VENU360 �Q��𗘗p���邱�Ƃ��A���Ȃ�^���Ɍ������������Ă���܂������A��N�Q�����{�Ƀ\�t�g�E�F�A�`�����f�o�i�N���X�I�[�o�[�j EKIO �� OKTO DAC8PRO �̑g�ݍ��킹���p���u�����v���A����ɂ���čŏ㗬�� Windows PC���� 192 kHz 24 bnit �����ɂ��f�W�^���N���X�I�[�o�[�i�`�����l�����������j�� DAC8PRO �ւ̊��S ASIO �o�͂��\�ł��邱�Ƃ��m�M�ł����̂ŁADBX DriveRack VENU360 �̗��p�͌����邱�Ƃɂ������܂����B
���\���ꂽ��L�� amirm�����DBX DriveRack VENU360 �̑���]�����|�[�g�̓��e�Ƒ��]�́ASINAD���ȃW�b�^�[�m�C�Y���܂߂āA���Ȃ�c�O�Ȍ��ʂƕ]���ƂȂ��Ă���A���p��́i���o�I�ɂ́j�傫�Ȗ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v������̂́A���Ȃ��Ƃ����̉����i�ʓI�ɕq���ȃ}���`�`�����l���v���W�F�N�g�ɂ����� DBX DriveRack VENU360 �̗��p������������Ƃ́A���ʂƂ��ēK�ł������Ɣ[���A���g���Ă���܂��B
��������A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/dbx-driverack-venu360-review-audio-processor.22497/post-750480
�̓��e�ŁA���̕ӂ�̌o�܂��A�ȒP�ɋ��L���Ă���܂��B
�ȏ�A���Q�l�܂łɂ��m�点���܂����B
�����ԍ��F24088510
![]() 0�_
0�_
�F����A
ASR ��
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/dbx-driverack-venu360-review-audio-processor.22497/post-765313
�ȉ��ŏ��������J�n���Ă��܂����AAKM �� AK4493 �܂��� AK4499 DAC�`�b�v�𓋍ڂ���dspNexus 2/8 ���܂��Ȃ��o�ꂵ�܂��B
https://danvillesignal.com/dspnexus-dsp-audio-processor
����́A�\�t�g�E�F�A�`�����f�oEKIO��OKTO DAC8PRO �������{�b�N�X�ɓ��ڂ����悤��DSP���u�ŁA��]���� AK4493�܂��� AK4499�x�[�X�ł��̂ŁA�����ÁX�Ŋ��҂ł������ł��B
�܂��A
https://www.stereo.net.au/forums/to...that-threatens-your-bank-account-dspnexus-28/
�̏��ɂ��A
"The dspNexus is very close to release. The first units will go to an early adopter program while we still add additional software features. Most of this will be Raspberry Pi support.
The retail price of the dspNexus is $3000 with the standard DACs (AKM AK4493 or TI PCM1792A based). We also have an AKM AK4499 version but these will be very limited. You may have heard that AKM had a foundry fire that has essentially stopped supply for 2021.
At some point in 2021, we will have a dspNexus 2/16. It will be 2U height since the XLRs will be double row. We designed the motherboard to support an additional DAC motherboard for this purpose."
�������ŁA�{�N���ɂ͂Q�C���P�U�A�E�g�� dspNexus 2/16 ���o�ꂷ��\��ŁA�����ɂ悵����̂悤�ȁA�W�`�����l������}���`���̍\�z�ɂ͍œK�������B�B�B�@
�Q�C���P�U�A�E�g�ŁA�S�P�U�`�����l���̃V���N�������������ł���A�ō���DSP�v���Z�b�T�ɂȂ邩���m��܂���B�������A�S�`�����l���� 192 kHz 24 bit �ȏ�œ�����������邱�Ƃ������ł����B�B�B���҂ł������ł��B
�����ԍ��F24110668
![]() 1�_
1�_
dualazmak����A����ɂ���
2-8��DAC�ŐVUSD3000-�A2-16�ł�����ɂȂ邩�ł��ˁB�A�L����DF-65��2-8�C�R���C�U�[�Ȃ���\88���~�Ɣ�ׂ�ƁA���͓I�Ȓl�i�ɂȂ肻���ł����B
�����ԍ��F24111511�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
���v���Ԃ�ł��B
���̃}���`�V�X�e���́A���A�l�Ŕ��ɉ����ŁA�f���炵�����������\���Ă���܂��B
dspNexus 2/16�A�����ł��B
�l�t���ƕ]�����ǂ��o�邩�A���ɋ���������܂��B�P�U�`�����l���̊��S�����i�H�j�ɂ����҂������ł��ˁB
�����ԍ��F24111547
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�����ɉ����ŁA�f���炵�����������\���Ă���܂��B
�z���ł��邾���ɁA���ꂽ�ƌ��������ł��B
�����ԍ��F24111870�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����A�F����A
Dunville Signal �Ђ̃R���^�N�g�t�H�[���G
https://danvillesignal.com/talk-to-us
�ɂāA�ȉ��̖₢���킹�𓊂��Ă݂܂����B
***************************************************************
As I have my ongoing multichannel multi-driver multi-amplifier project;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
And as I recently provisionally completed the audio system with software crossover EKIO on Windows 10 PC, OTKO DAC8PRO and three amplifiers;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419
(My handle name in APSR Forum is dualazmak.)
I am very much interested in Danville Signal's dspNexus 2/8 and dspNexus 2/16.
Let me have some inquiries, therefore, as follows (sorry in random order):
1. The home electricity in Japan, my country, is 100V 60Hz or 100V 60Hz. Are your dspNexus 2/8 and dspNexus 2/16 compatible with these electricity?
2. Up to how high sampling rate may you process audio signals in all channel operation (i.e. 8-channel on dspNexus 2/8, 16-channel on dspNexus 2/16)? I currently process everything in 192 kHz 24 bit using JRiver MC and software crossover EKIO for full 8-channel operation of OKTO DAC8PRO at 192 kHz 24bit. I need, therefore, at least up to 192 kHz24 bit, can you go higher with dspNexus? I well understand that even the extraordinary expensive TRINNOV ALTITUDE 32 processes signals up to 192 kHz 24bit.
3. Incase if I would like to use two of dspNexus 2/8 for simultaneous output of 16-channel of one digital stereo L&R signal, how can you fully synchronize the two dspNexus 2/8? Does dspNexus 2/8 has synchronization clock input? Or, the can first dspNexus 2/8 provide sync clock signal into the second dspNexus 2/8 through AES/EBU digital connection or other routes?
4. Can your USB ASIO driver in Windows PC can recognize two dspNexus 2/8 properly (separately), and can we send one digital stereo L&R signal simultaneously in full synchronization from JRiver MC (or Roon) into the two unit of dspNexus 2/8?
5. As for your dspNexus 2/16, I understand that you will use two of the DAC chip (AK4493 or AK4499), and the all of the 16 channels are of course fully synchronized, right?
6. Let me also ask about your plan for marketing in Japan with enough warranty. Do you plan to assign, or already assigned, suitable distributor(s) or dealer(s) in Japan?
7. In case of the use in Japan, how long would be your warranty, and how it will be handling possible repair, maintenance and/or hardware/software updates?
8. If possible, please let me know the planned price of dspNexus 2/16.
Thank you in advance for your kind attention of the above inquiries.
with my best regards,
***************************************************************
�����ԍ��F24119617
![]() 0�_
0�_
�����ł��B
��The home electricity in Japan, my country, is 100V 60Hz or 100V 60Hz.
�������́A�������G
The home electricity in Japan, my country, is 100V 60Hz or 100V 50Hz.
�ł��BDaville Signal�ւ��������Ă����܂����B
�����ԍ��F24119628
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����A�݂Ȃ���A
Dunville Signal �� CEO �ł��� Al Clark ����A�����A���J�ȉՂ��܂����B
�P�DdspNexus �́A�d�����̍\���Ǝd�l�Ƃ��āA���{��100V 60/50 Hz ���ł����Ȃ����삷��B
�Q�DdspNexus �̃}�U�[�{�[�h�iADC �� DACs�j�́A384 kHz �܂őΉ����Ă��邪�A���������� 192 kHz 24 bit �őΉ��^�\�����Ă���B
�R�D�c�O�Ȃ���AdspNexus 2/8 �ɂ́A�O���N���b�N���͑Ή��͂Ȃ��A�Q��� dspNexus 2/8 �����S�ɓ������삳����d�g�݂͔����Ă��Ȃ��B���̈Ӗ��ɂ����āAdspNexus 2/16 �̊J���Ɣ�����҂��ė~�����B�@�{�N�H�ɔ����\��� dspNexus 2/16 �ł́A�Q���DAC�`�b�v���Q�i�̃{�[�h�\���Ŏg�����A���ʂ̃}�X�^�[�N���b�N���瓯���M����^����̂ŁA�P�U�`�����l���S�Ă����S�ɓ�������B
�S�DUSB ASIO driver �́A�Q��� dspNexus 2/8 ��ʁX�ɔF������͂��ł��邪�A��L�̂悤�ɂQ������S��������d�g�݂��Ȃ��̂ŁA����͔��I�ȗ��p���@�ƂȂ�B
�T�D���H�����\���dspNexus 2/16 �ł́AAK4499 ���Q�g�������������AAKM�H��̉Ќ�AAKM�� AK4499 �̐��Y�ĊJ�̒f�O�����肵���̂ŁA�܂��ƂɎc�O�Ȃ��� AK4499 �̗̍p�͕s�\�ɂȂ����BAK4499 �́A���ݓ����鐢�E�ō���DAC�ł���ƕ]�����Ă��������ɔ��Ɏc�O�ł���B����AAKM�́A�߂������ɁA����ɔ��ɍ����\��DAC�`�b�v�̊J���Ƌ������������Ă���A�傢�Ɋ��҂��Ă���B
�i����� dspNexus 2/16 �̊J���ɂǂ�DAC�`�b�v���g�����ɂ��Ă͌��y�Ȃ��BES9028PRO �܂��� ES9038PRO ���Q�̗̍p�ɂȂ炴��Ȃ��̂��H�@���������Ȃ�A����͂���ŁAES�t�@���̎��Ƃ��Ă͊��}�I�j
�U�D�u���̂Ƃ���́A�v���{�ł̔̔��ɂ��ėA���㗝�X��̔��㗝�X��݂���\��͂Ȃ��A Dunville Signal in USA����̒��̂�z�肵�Ă��邾���ł���B�������e��̃t�@�[���E�F�A�� USB�|�[�g���g���ďC���A�A�b�v�O���[�h���\�ł���B
�V�D�C�O�����̔̔��ł��A��{�I�ɕۏ͂P�N�ԂƂ���\��B�ۏ؊��Ԓ��̕s��ɂ́A��胂�W���[���i��j�̑��t��u�S�̂̃Z���h�o�b�N�őΉ�����B
�W�DdspNexus 2/8 �̉��i�� AK4438 �̗p�� US$3000 �ƌ��肵�����AdspNexus 2/16 �̉��i�́A���݁A�܂�����ł���B
�Ƃ̂��Ƃł��B
������́A������뗝�������|�ɉ����āA�u���ʂ� EKIO + DAC8PRO�� 8-channle 192 kHz 24 bit �̊����ȓ���i���Ă���̂ŁA�����Ƃ��Ă� dspNexus 2/16 �̓o������҂��A�����҂����Ă��������B�v�@���Ƃ�m�点�܂����B
�܂��A���� dspNexus 2/16 �̃x�[�^�e�X�g�ɂP�U�`�����l���� 192 kHz 24 bit �t�������o�͂ŋ��͂ł��������A�lj���SP�h���C�o�[�iSP���j�b�g�j��lj��A���v��p�ӂ��đΉ��\�Ȃ̂ŁA�����Ȃ��A�����ĉ������A�Ƃ��`���܂����B
�����ԍ��F24121452
![]() 2�_
2�_
�X�y���~�X�̒����ł��B
"Dunville Signal" �ł͂Ȃ��āA"Danville Signal" �ł��B
���炵�܂����B
�����ԍ��F24121508
![]() 2�_
2�_
�F����A
CD�t�H�[�}�b�g�� 44.1 kHz 16 bit (Fq�� 22.05 kHz) ���� HiRes �����ł́A������� 22 kHz�ȏ�̋ߒ����g�`�����g�̑ш�A���Ƃ��A192 kHz�����ł� 22 - 96 kHz�ADSD256(4x) 5.6 MHz�����ł́A22 - 176.4 kHz, �ɔ���ȃm�C�Y���܂މ\���A�댯�������邱�Ƃ́A����܂łɂ��L���F������Ă���܂����B
�܂��A�\���Ȍ��������Ƀ_�E�����[�h�̔�����Ă��� HiRes �����ł́A�s�K�ȃ}�X�^�����O������A�b�v�T���v�����O�����ɂ���āA���̂悤�Ȓ����g�̈�ł̃m�C�Y�����Ȃ荂���x���Ŋ܂܂��\�����������Ƃ��A�e���Ŏw�E����Ă���܂��B
�ŋ߂ł́AMusicScope �� Adobi Audiotion �Ȃǂ̗D�ꂽPC�\�t�g�E�F�A���g���āA�e�퉹���̑S�ш�i�����g�ш���܂ށj�ɂ킽����g���X�y�N�g���A�g���b�N��A���o���̗ݐώ��g���s�[�N�X�y�N�g���A���ȒP�ɕ��͂��邱�Ƃ��ł��܂��B
����ɂ��āAASR �� amirm ���A���ŋ߁A"Comparison: PCM DXD DSD (Sound Liaison High Res Format Comparison)" �Ƒ肵�āA���ɋ�������X���b�h�����ĂĂ����܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/comparison-pcm-dxd-dsd-sound-liaison-high-res-format-comparison.23232/
���̂悤�Ȓ����g�̈�ɂ�����m�C�Y�́A�������Ȃ����̂́A�����I�Ȓ��o�ւ̈��e���̉\���ɉ����āA���ݕϒ��A�G�C���A�V���O�_�E���A�w�b�h���[���̉ߑ�Ȑ�L�A�ꍇ�ɂ���Ă̓c�C�[�^�[�̃{�C�X�R�C���̏Ă��t���Ȃǂ̔��U��܂��͑�����i�A���v�j��X�s�[�J�[�ɖ��������N�����\��������܂��B
�����A���̈�ȏ�̑ш�ɁA�ƂĂ���Ȕ�r�I�����x���̔���m�C�Y�i�H�j���܂ރ_�E�����[�h�w�� DSD������ۗL�A�o�����Ă���܂��̂ŁAMusicScope ���C���X�g�[�����āA���͂ƑΉ��̌������J�n���܂����B
�ڍׂɂ��ẮAASR�̎��̃X���b�h�̖{���̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-777900
�Ƃ���ȍ~�������������B
���̌��ʂƂ��āA���݁A�Y�t�摜�̂悤�ɁA -48 dB/Oct (LR) high-cut at 22.049 Hz �̒����g�m�C�Y�J�b�g�t�B���^�[��������@EKIO �� EQ�\����W���I�ɗ��p�����������^���Ɍ������Ă���܂��B
�����ԍ��F24132336
![]() 1�_
1�_
Adbi Audition �ł͂Ȃ��AAdobe Audition �ł��ˁB���炵�܂����B
�����ԍ��F24132398
![]() 2�_
2�_
�F����A
��̌��A����ł��B
���́AEKIO����� 192 kHz 24 bit �œ��삳���Ă��܂��̂ŁA�����O���� LUPISOFT�Ђ� Guillaume ����Ƃ��b�����āA
�u�n�C�J�b�g�i���[�p�X�j�t�B���^�[�̃J�b�g�I�t���g�� Fc ���A96 kHz �܂ł̔C�ӂ̎��g���ɐݒ肵�����A���Ƃ��Ă� 23 kHz �` 40 kHz �̂ǂ����ɐݒ肵���\����ۑ����A�ă��[�h���ď�p�������B�v
�Ƃ̎|��`���āAEKIO �̃}�C�i�[�A�b�v�f�[�g�����肢���Ă���܂����B
���������AGuillaume����A�����A�b�v�f�[�g�����|�̘A��������AEKIO�� �ŐV��Version 1.0.7.3 �ɂȂ�܂����B
�����ŁAASR�̃X���b�h�ōŋ߂ƂĂ��^���ɋc�_���Ă���悤�ɁA�{���AHighCut (LowPass) LR �t�B���^�[�� 25.000 kHz �ɐݒ肵�A�����X�� -12dB/Oct, -24 dB/Oct, -48 dB/Oct �ɐݒ肵���R�̍\�����쐬���i�������͓Y�t�}�̒ʂ�j�A�^���u���C���h�e�X�g�ɂ���r�������J�n���܂����B
�ڍׂ́AASR �̃|�X�g #384�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-788873
��,
����ȑO�̃|�X�g #361�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-777846
����
�|�X�g #383;
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-787695
�܂ł������������B
�����ԍ��F24148363
![]() 1�_
1�_
�F����A
���Q�l�܂łɁB�B�B�B
MusicScope ����� Adobe Audition 3.01 �́A���݁A������������Ńt���o�[�W����������A�C���X�g�[���A���������p�@�\�ƂȂ��Ă��܂��B�T�|�[�g�͏I�����Ă���̂ŁA���ȐӔC�ł̗��p�ƂȂ�܂��B
�����_�E�����[�h�����N�A�C���X�g�[���[�t�@�C�����܂ޏڍׂ��K�v�ȍۂɂ́AASR Forum ��PM�V�X�e��(�l�ԘA���V�X�e��)�ł��m�点�������BPM���ł́A���{��ɂ�鑊�ݘA�����\�ł��B
�����ԍ��F24150273
![]() 0�_
0�_
�F����A
���Ȗh�q��Ƃ��āA�f�W�^�� High-Cut (Low-Pass) LR�t�B���^�[ -48 dB/Oct �� 25.000 kHz �ɐݒ肵�ď�p���邱�Ƃɂ������܂����B
�ڍׂ́G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-795103
�Ƃ���ȑO�̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-777900
�ȍ~�������������B
�����ԍ��F24157203
![]() 0�_
0�_
�F����A
����͎��̏����ԍ��F24040775 (2021/03/25 00:29) �̃t�H���[�A�b�v�ł���A�Ԃ��Ȃ����p�\�ɂȂ�\��������Ə�����Trinnov Altitude �Ɋւ���amirm����̃��r���[�Ɋւ���b��ł��B
���傤�Ǎ����Aamirm����́A����Trinnov Altitude 16�̃��r���[�𓊍e���܂����B���i��17,000�ăh���ł��I
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/trinnov-altitude-16-review-av-processor.23763/
����Aamirm����Trinnov Altitude 16��DAC�@�\���q�ϓI�ɑ��肵�������ŁA�����EQ-DSP�@��Ƃ��Ă�Trinnov Altitude 16�̂���Ȃ�]�����Ӑ}�I�Ɂi�܂��͂����ł͂Ȃ����H�j�����������Ƃ́A���ɂƂ��Ĕ��ɋ����[�����Ƃł��B
Trinnov Altitude 16�̕��ꂽDAC�p�t�H�[�}���X�́Aamirm����̃��r���[�ɂ���悤�ɁA�{���Ɏc�O�Ȃ��̂ł����B OKTO DAC8PRO�i�����g�p���Ă���j��DAC8STEREO�����͂邩�ɗ���Ă��܂��B����ɁATrinnov Altitude16��96kHz����f�W�^���M����S���Đ��ł��܂���B
�\�z�ʂ�A�����̐l��Trinnov Altitude 16�̎�ȉ��l�i17,000�ăh���ɑ���??�j�́A����������̕EQ-DSP�\�t�g�E�F�A�Ƌ@�\�ł���Ǝw�E���A�������܂����B
�������A�����ł̓��e��39
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/trinnov-altitude-16-review-av-processor.23763/post-797412
�ŁAAmirm����́A�Ȍ��ɁA�������m�M�I�ɁA�uxover�̂悤�Ȃ��̂̓e�X�g�ł��܂������A�����ɂ̓G�L�T�C�e�B���O�Ȃ��͉̂����Ȃ��Ǝv���܂��B���[��EQ���Ӗ�����ꍇ�A����͂���قǗL�p�ł͂���܂���B���X�j���O�e�X�g���ł��d�v�ł��B�v�A�Ɖ������܂����B�@
���́A����amirm����̃X�^���X�Ɗm�M�Ɋ��S�Ɏ^�����܂��B
Trrinov Altitude 16�Ɋւ����L�̂��Ȃ�c�O�Ȍ��ʂƃR�����g�́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-questions-for-flagship-processors-trinnov-storm-jbl-lyngdorf-datasat.21093/post-721161
�ŋ��L�������̌��O�A����т���ɑ��� Scott Borduin����̔����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-questions-for-flagship-processors-trinnov-storm-jbl-lyngdorf-datasat.21093/post-721866
�ɔ��ɂ悭��v���Ă��܂��B�ނ́A�����Łu���Ȃ������y�����悤�ȃX�e���I �}���`�h���C�o�[ �A�v���P�[�V�����̏ꍇ�ATrinnov�ɂ͂����炭�قƂ�Ǘ��_���Ȃ��B�v�Ə����Ă��܂��B
������ɂ���A���Ȃ��Ƃ����̏ꍇ�́A�u���̃}���`�`�����l���{�}���`SP�h���C�o�[�{�}���`�A���v�̃v���W�F�N�g�ɂ����ẮA���Ɂi�ُ�ɁH�j������Trinnov���p�̓��ɂ͓���Ȃ��I�v�A�Ƃ���2�N�O�ɉ���������͐����ł������Ƒ傢�Ɉ��g���Ă���܂��B
�����ԍ��F24160229
![]() 1�_
1�_
�F����A
�u����v�i�I�j�A�_�E�����[�h�w������ HiRes �����ɂ��ẮA�O�̂��߁AMusicScope �� Adobe Autition 3.01 ���g���āA�^���i�����m�F���邱�Ƃ�S���������ł��B
���Q�l�܂łɁA�A�A���̂ЂƂ̍D����A�����ŋ��L���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/post-797621
�����ԍ��F24162747
![]() 1�_
1�_
�^�C�v�~�X�A�C���ł��B
��j Adobe Autition 3.01
���j Adobe Audition 3.01
�����ԍ��F24164662
![]() 0�_
0�_
�F����A
�S�ẴI�[�f�B�I�V�X�e���ł́A�x���A�ʑ��A�ߓn�����AS/N��A�c�ݗ��A�ȂǂȂǁA�ƕ���Łu���g�������v���A�����I�ȉ����i�ʂ�����Â�����ɏd�v�ȗv�f�ł��邱�Ƃ́A�F������䏳�m�̒ʂ�ł��B
�u���g�������v���u�T�C���M���X�C�[�v�v�ő��肷�邩�A�u�s���N�m�C�Y�v�ő��肷�邩�A���c�_��������܂����A���́A���ۂ̃I�[�f�B�I�ӏ܂̏ɑ����Ă���Ƃ����ϓ_����A�u�s���N�m�C�Y�v�ɂ�鑪����D�݂܂��B
�܂��A�u���g����������v�́AFFT (Fast Fourier Transform �����t�[���G�ϊ�)��p�����u���v��́v�ł��̂ŁA���͑Ώۂ̃f�[�^�ʁi���G�l���M�[�ʁj�������قǐ��x�ƍČ��������܂�܂����A�܂����́i�����j�̑ΏۂƂ�����g���̈�ɉ����āA�n�j���O���i�I�[�f�B�I��͂ł͈�ʓI�ɗ��p�j�̃T���v�����O���iFFT Size�j ��K�ɐݒ肷��K�v������܂��B
���� FFT Size�̐ݒ�́A���̗L���ȃ\�t�g�E�F�AREW�ł��w�E����Ă���悤�ɁA���g���������u�����S���w�I�Ȓ����o�v�ɓK�������āu���g�������Ȑ��v��\���������ł��A���ɏd�v�ł��B
�����̊ϓ_���l�����A���Ȃ�̏n�l�Ǝ��s������d�ˁA�������n�I�ł����A���ɐM�����A�Č����A���x�A���萫���D��A�������_��ɁiFFT Size��l�X�ɕς��āj���g�������𑪒�ł���u���̕��@�v�i�I�j���m���ł��܂����B
�ڍׂ� ASR Forum �̎��̃X���b�h�ŋ��L���Ă���܂��̂ŁA��������������ł�����A�����������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-805911
�V�X�e���S�́i�S�Ă�SP�h���C�o�[���ɖ炵����ԁj�ɉ����āA����ƑS�������{�����[���ƃQ�C���ݒ�ɂ����� SW, WO, Be-SQ, Be-TW, ST �X�̎��g���������ڍׂɕ��͂��Ă���܂��B
������A���ׂāA���X�j���O�|�C���g�ɂ�����X�e���I���E�����Đ��A�s���N�m�C�Y�AECM8000�}�C�N�P�{�ɂ�鑪��ł����A���̑�����@�́A�Ѓ`�����l���̋ߐڑ����A�f�W�^�����x���A���C�����x���A�A���v�o�̓��x���A�̉����M���̎��g����������ł��A�ėp�I�ɗ��p�ł��܂��B
�����ԍ��F24172910
![]() 1�_
1�_
�F����A
�����p�����s���N�m�C�Y�ɂ����g�������̑���iCumulative Pink Noise Averaging �Ə̂��Ă���܂��j�ɂ��āA�����������ݍ������ƌ����s���Ă���܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-812651
�g���\�t�g�⑪����@�ɉ����āA�g��������K�v������܂����A�������������ɕ����I�Ȏ��g�����������Ă���̂��A�u�����S���w�I�Ɂv���H�^�������ꂽ���g�����������Ă���̂��A�\���ɒ��ӂ���K�v������܂��B
EKIO ���܂� DSP-EQ �\�t�g�������^�[�Q�b�g���g�������Ȑ����A�u�����I�^�[�Q�b�g�v�Ȃ̂��A�u�����S���w�I�^�[�Q�b�g�v�Ȃ̂����A�K���������m�ɂ���Ă��Ȃ����Ƃ������A���̓_�ɂ����ӂ��K�v�ł��B
�������A�ŏI�I�Ȏ����ɂ�����u���g�������v�́A���X�j���O�|�C���g�ŁA�M���ł��鑪��p�}�C�N���g���āA�u�����S���w�I�X���[�W���O�ƃA�b�e�l�[�V�����v���������āiRew������Ă���悤�Ɂj����]������K�v������܂����A���F�A���g�����������FFT��p����u���v��́v�ł��̂ŁA�������肵���������s���ł��傤�B
��̃����N�|�X�g�̍Ō�ɂ������܂������G
�����ʂƈႢ�͂��Ȃ�悭�\�z/�\������Ă����Ƃ��Ă��A3�̕��@�̊Ԃ�Fq�����Ȑ��̈Ⴂ�����ė������邱�Ƃ͋����[���d�v�ł��B
��������ɂ���A���g���������͂� FFT�ɂ�铝�v�f�[�^����Ɋ�Â��Ă��邱�Ƃɏ�ɏ\�����ӂ���K�v������܂��B���������āA���ʂ͍��v�f�[�^�T�C�Y�i�T���v���̍��v�G�l���M�[�j�A�T�C���X�C�[�v�܂��̓s���N�m�C�Y�AFFT�T�C�Y (�����/�܂��͑��̕������A���S���Y��)�A����ыȐ��\���̂��߂� XY �ΐ� (�܂��͐��`) �X�P�[���A�Ȃǂɑ傫���ˑ����܂��B
�����ԍ��F24182665
![]() 0�_
0�_
�F����A
SINAD�A�W�b�^�[����� linearity�i�_�C�i�~�b�N���x���̒������j�̑���l�ɂ����āAOKTO DAC8 Stereo ���� Stereo XLR DAC ���o�ꂷ�邱�Ƃ́A���͂�Ȃ��̂ł́A�Ǝv���Ă���܂������A�A�A�A
�ǂ����AESS ES9038PRO DAC ���ڂ̐V���i Topping D90SE �́A��������悤�ł��B
�Ȃ�ƁASINAD �� 123 ��B�����A�W�b�^�[�͑�����x�ȉ��A-120 dB�` 0 dB �łقڊ����Ȓ������ł��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d90se-review-balanced-dac.24235/watch
�M������@�\���͕ʖ��Ƃ��āASINAD�A�W�b�^�[����� liniarity�i�_�C�i�~�b�N���x���̒������j�ɂ����ẮA����܂ł̍ō����\��B�����Ă���悤�ł��B���ꂪ�AUS$�W�X�X�قǂŎ�ɓ���Ƃ́B�B�B
���́A�W�`�����l���ȏ�̃}���`�`�����l��DAC���K�v�Ȃ̂ŁA���̂Ƃ���g�p���� OKTO DAC8PRO �����I����������܂��A�X�e���I�Q�`�����l�� XRL�o��DAC�ōō����\�����߂�Ȃ�ATopping D90SE �̓R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�̓_��������͂���I�����ƂȂ�ł��傤�B
D90SE �̉��i�� US$899 �i����ł�ł���ё������܂߂Ă�12���~���x�H�j�ŁA���\����������Ɛō��P�T�O���~�� Mola Mola Tambaqui DAC ��傫�����킵�Ă��܂��B
��������ɂȂ������̂ł��BOKTO�Ђ� Topping�Ђ̑䓪�́A�n�C�G���hHiFi�I�[�f�B�I�̐��E�ɁA�V���������J������悤�Ɋ����Ă���܂��B
�����ԍ��F24190309
![]() 1�_
1�_
D90SE �́A���ł� Amazon Japan �ɂā�90,000 �ŏo�i����Ă��܂��B
�����ԍ��F24192486
![]() 1�_
1�_
D90SE �ɂ́A�i�����܂ށj�����̃n�C�G���hHiFi�w���̐l�X�ɂ͖��p�ȁAMQA�Đ��@�\�� Bluetooth 5.0 LDAC�`���@�\�����ڂ���Ă���A����炪���i�����������グ�Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̋c�_��ASR�t�H�[�����ł�����ł����AOPPO SONICA DAC �̏ꍇ�������ł������悤�ɁA���I�ɂ́A���p�ȋ@�\�́u�g��Ȃ��v�����ł��̂ŁA�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�I�Ɍ��Ă����Ȃ��ł��ˁB
�J���҂̃R�����g�ł́AMQA�F�Ǝ����ɔ������i�]�ł́A�u1�䂠����ꌅ�h���v�Ƃ̂��Ƃł��B
���Ђɑ��ẮAD90SE �����̃X�y�b�N�ŁAOKTO DAC8PRO �����ȏ�i�ł����10�`�����l���ȏ�j�̃}���`�`�����l��DAC�̊J����v�]���܂����B�������AMQA��Bluetooth �͖��p�ł��A�Ɛ\���グ�Ȃ���B�B�B
�����ԍ��F24192502
![]() 1�_
1�_
�F����A
���g������������@�Ƃ��āA����́u�ݐσs���N�m�C�Y���ω��@�v�ɑ����āA����A�u�ݐσz���C�g�m�C�Y���ω��@�v�������A�����Ă���܂��B
�܂��́ADAC�֓��͂���O�̃f�W�^�����x���̐M���� EKIO �ݒ�̔��f�ƍČ����������܂����B
�ڍׂ́G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-823166
�������������B
�����ԍ��F24199764
![]() 1�_
1�_
���Q�l�܂łɁA�A�A
D90SE �̓����ʐ^�����e����Ă��܂��B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d90se-review-balanced-dac.24235/post-826068
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d90se-review-balanced-dac.24235/post-826073
�����g�p���Ă��� OKTO DAC8PRO �ł������ł����A�V���v���Ȃ������������Ɛv����A�e���̃n���_����������Ȃ���Y��Ȃ悤�ł��BTOPPING �́A�����̃I�[�f�B�I���[�J�[�Ƃ��ẮA���ɗǐS�I�ŁA�����ꂽ�Z�p��~�ς��Ă��Ă���Ƃ�����ۂ������܂����B
�i���� D90SE ���g���\��͂���܂��B�B�B�j
�c�O�Ȃ���f�C�X�R���ɂȂ��Ă��܂��� OPPO SONICA DAC �i�ۗL�AD90SE�Ɠ��l�� ES9028PRO�𓋍ځj�ł��A���l�̈�ۂ������Ă��܂��B
�����ԍ��F24205168
![]() 0�_
0�_
�F����A
�u�ݐσz���C�g�m�C�Y���ω��@�v�ɂ�鎄�Ȃ�̎��g������������@���m���E���ł����̂ŁA���������}���`�`�����l�� �}���`SP�h���C�o�[ �i�}���`�E�F�C�j �}���`�A���v �V�X�e���́A�ǂ̉ӏ��Ŏ��g���������m�F�E�L�^���Ă����ׂ����A�T�d�ɍl���Ă���܂��B
���̂��߂ɁA�M���ɑ���I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X�P��ƁA�M���ɑ��� SP-level to RCA line-level �ϊ���iHigh-to-Low�ϊ���j����z�i�����j���܂����B
�ڍׂ́A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-826262
�������������B
�����ԍ��F24205172
![]() 0�_
0�_
�F����A
�m���E���ł������Ȃ�̎��g������������@���u�ݐσz���C�g�m�C�Y���ω��@�v�ɂ���A�̑���ƍl�@���������܂����B
������������AASR�ɂ����鎄�̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-823166
����
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-837485
�܂ł��A��������Ƃ����������B
�����ԍ��F24226534
![]() 0�_
0�_
�F����A
����́A������������g�������X���A�C�ӂ̌X���ɒ����ł���悤�ɁA�����V�X�e���Ɏ�������Ă���܂��B
�ڍׂ́G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-843454
�ȉ��������������B
�����ԍ��F24236961
![]() 0�_
0�_
�F����A
�u�ݐσz���C�g�m�C�Y���ω��@�v�ɂ����g����������ƍl�@���o�āAYamaha A-S301�ŃX�p�[�c�C�[�^��P�Ƌ쓮�����邱�Ƃ����肵�܂����B ����ŁA�v�����C���A���v4��ƃA�N�e�e�B�u�T�u�E�[�n�[�ɂ��\���ƂȂ�܂����B
�ڍׂ́A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-843454
�����
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-845616
�������������B
�����ԍ��F24240346
![]() 0�_
0�_
�F����A
�A���v�S��ƃA�N�e�B�u�T�u�E�[�t�@�[�ɂ�� 5-way 10-channel �ŐV�\���ŁA��p���Ă���`���[�j���O�p�����W���Ȃ���A���̔]�Ǝ��ɍł����K�ȑ��Q�C���ݒ�Ɣ��������s���A���̏�Ԃł̎��g���������A�m���ƌ������������u�ݐσz���C�g�m�C�Y���ω��@�v�ő��肵�܂����B
�ʏ�̃��X�j���O���ƕ����ŁA���X�j���O�|�W�V�����iSP�\�ʂ���� 3.6 m�̈ʒu�j�ɂ����鑪��p�}�C�N�P�{���g�������g����������ł��B
�����ł̃x�X�g�`���[�j���O��Ԃɂ�������g�������ƂȂ�܂��B
�ڍׂɂ��ẮA
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-860978
�ŏڂ��������L���Ă���܂��̂ŁA�����������B
�����ԍ��F24265564
![]() 1�_
1�_
�F����A
�g���e���I�[�f�B�I�ɂ����āu�X�s�[�J�[�������銴�o�v�́A���B����ɖڎw���Ă�����̂��Ǝv���܂����A���̃V�X�e���ł́A���Ȃ荂�x�Ȏ����ł��ꂪ�����ł��Ă���悤�Ɋ����Ă���܂��B
�ł́A�u�X�s�[�J�[�������銴�o�v����������v�f������́A�ǂ�Ȃ��̂��A�ǂ̂悤�ɁA�����ɁA��������K�v������̂ł��傤���H
���������I�ɎQ�����Ă��� ASR �� �uWhat makes speakers "disappear " and can it be measured?�v �Ƒ肳�ꂽ���̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/
�ŁA���́A���܂�ɂ������� Floyd Toole ������Q������āA���ɋ���������������s���Ă��܂��B�@
����A�����������B �u���E�U�̓��{���ł��A�T�v�͏\���ɔc���ł���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24270424
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�@�����������Ă��܂��B
>�g���e���I�[�f�B�I�ɂ����āu�X�s�[�J�[�������銴�o�v�́A���B����ɖڎw���Ă�����̂��Ǝv���܂����A���̃V�X�e���ł́A���Ȃ荂�x�Ȏ����ł��ꂪ�����ł��Ă���悤�Ɋ����Ă���܂��B
>�ł́A�u�X�s�[�J�[�������銴�o�v����������v�f������́A�ǂ�Ȃ��̂��A�ǂ̂悤�ɁA�����ɁA��������K�v������̂ł��傤���H
�@�i���̘b��ł��ˁB
�@ASR�̃X���b�h���Ă݂܂���
Thursday at 3:23 PM�@#46
napilopez
-----------
....
I'm a little surprised no one has mentioned a lack of resonances. That is one of the most important qualities for a speaker to avoid revealing itself as a wooden/metal/plastic box. It modifies timbre, can make a note stand out in the time domain, and just sticks out like a sore thumb.
Directivity is important for sure when it comes to the spatial presentation aspect, and I find wider directivity speakers are usually a bit more likely to have this disappearing effect, but having minimally audible resonances is paramount.
...
-----------
�@���Ă̂������ā@�����@���̂Ђƕ������Ă�Ȃ��Ǝv���܂����B
�@�X�s�[�J�[�̑��݂��킩����Ă̂́A�悯���ȉ����X�s�[�J�[������o����邱�Ƃ���̗v�����Ǝv���܂��B
�@�ŋ߁A�X�s�[�J�[�������銴�o�@��̌����܂����B
https://www.youtube.com/watch?v=xYjjy7Y2CwY&t=733s
�@���̓���̖`���Ƀf�b�h�}�X�̗L���Ɋւ��Đ������Ă��܂����A�f�b�h�}�X�Ƃ����^�J�ō�����d����X�s�[�J�[���j�b�g�̌��Ɏ��t�������̂Ɩ�������(�ʏ�)���r���܂����B
�@���̓���ł͍��͂͂�����킩��܂��A��������Ɓ@�f�b�h�}�X�����ł́@�܂��ӂ��̃X�s�[�J�[�̖���ł����A�f�b�h�}�X�����t����Ɓ@�������^�X�s�[�J�[���ۂ��Ȃ�A�X�s�[�J�[�̑��݂�����������ɕω����܂����B
�@���ۂɖ��Ă���X�s�[�J�[�̃t�����g�o�b�t����G��ƁA�f�b�h�}�X�����ł̓o�b�t���̐U�����������܂����A�f�b�h�}�X�L��ł́@�o�b�t�����U�����Ă��܂���B
�@�܂�A�X�s�[�J�[�̑��݊��́@���y�M���ƒ��ڊW���Ȃ��X�s�[�J�[�{�b�N�X�̋��U���܂ސU�����X�s�[�J�[�{�b�N�X������o����Ă��Ă���̂��Ă��邱�Ƃ���̗v�����Ǝv���܂��B
�@�d�����f�b�h�}�X��t���邱�Ƃɂ��@�U���̐U����啝�Ɍ��炵�Ă悯���ȉ����o�Ȃ��Ȃ���ʂ�����܂��B
�����ԍ��F24270639
![]() 4�_
4�_
BOWS����
2019�N�̑�A�������BOWS����ɂ�邲�w���₲�������Ȃ���A���̃}���`�A���v�V�X�e���\�z�̗��H�́A���蓾�܂���ł����B�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�ŋ߂́A���� kakaku.com ���� ASR �Ɏ������ڂ��A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�i�X���b�h�ւ̉{���K����A�U���X�����A�߁X�V����ɓ��B���܂��B�j
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?forums/member-area.36/&order=view_count&direction=desc
�����
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/
����Â���Ƌ��ɁA�e���ŗL�Ӌ`�Ŋy�����������𑱂��Ă���܂��B
���āA�f�b�h�}�X�� YouTube�N���b�v�A��ϋ����[���q�����܂����B
���� ASR���e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-863844
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-864116
�����
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/post-864562
�ɂ��������悤�ɁA��ՓI�i�H�j�ȗl���ŃX�s�[�J�[���������������������ɂ́ABOWS���w�E�̃L���r�l�b�g���U�̏������܂߂āA���ɑ����̍v���t�@�N�^�[���u�����Ɂv��������K�v������Ɗ����Ă��܂����AASR�ɂ����� Floyd Toole���m�̃R�����g�₲�w�E���A������x�����Ă��܂��B
�K���ɂ��ABOWS����̂��x���������āA�܂����X�j���O���[�����̍œK���̑��܂��āA���̌��݂̃}���`�A���v�[�}���`�E�F�C�V�X�e���ł́A���Ȃ�̍������ŁA�����̗v�f���u�����Ɂv�B������Ă��āA����܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��f���炵���u�X�s�[�J�[�������v�����\�ł��Ă���܂��B
���̈���ŁABOWS����̂��w�E�Ƃ��o����q�����A�X�Ȃ�u�X�s�[�J�[�������̌���v�����āANS-1000 ��➑̋��U�̗}���ɂ��ẮA���������H�v�̗]�n�����肻���Ɏv���Ă���܂��B
���� NS-1000 �� Be-midrange SQ �ɁA�傫�ȃf�b�h�}�X�����t����Ƃ����U�f�ɂ�����܂����A�����n�[�h���������悤�ɂ������܂��̂ŁA�܂��́ASP�O�ʁi�o�b�t���ʁj�Ɍ��߂̉��ł𗼖ʃe�[�v�ŋ��łɓ\��t����悤�Ȃ��Ƃ������Ă݂悤���ȁA�Ǝv�Ē��ł��B�@
BOWS����́A����Be-SQ�Ƀf�b�h�}�X�������I�Ɏ��t���Ă݂邱�Ƃ𐄏�����܂����H�@�S kg �̐^�J�_���P�[�u���^�C�g�ƌ���̗��ʃe�[�v�ŌŒ肷�邱�Ƃ͉\��������܂��A����Be-SQ�́A�r�X�S�{�i�U�{�ł͂Ȃ��I�j�ŌŒ�ł��̂ŁA���x�I�ɏ����s��������܂��B�^�J�_�́A�P�`�Q kg ���x�ł������Ȍ��ʂ�����ł��傤���H
�܂��A���� 30 cm �E�[�t�@�[�ɂ��f�b�h�}�X��t�i�Œ���܂߂āA����Ƀn�[�h�������I�j�����߂��܂����H
NS-1000 �́A NS-1000M �Ɋr�ׂ�➑̂�����ɏd�����łł����A�K���ɂ��������݂ȃT�����l�b�g������̂ŁA�o�b�t���ʂɉ������ꂵ������t���Ă��T�����l�b�g�ŖډB���ł��܂��B
��́u�r�o�����v�Ɋւ���ASR�X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-makes-speakers-disappear-and-can-it-be-measured.25313/
�́A������AFloyd Toole ���m�̐ϋɓI�Ȃ��Q���A�������������Ă���A���炭�A���ɋ����[�����߂Ċw�Ԃ��ƂɂȂ肻���ł��B
���́A�ȑO���b�������A���� Mitch Barnett ����� Igor Kirkwood ����ɉ����āAFloyd Toole����Ƃ��������������Ă��������Ă���AToole����͌��݂ł� NS-1000����� NS-1000M �i���� Be-�~�b�h�����W�j����ɍ����]������Ă����邱�Ƃ����܂��āA�����̋M�d�Ȃ������Ɗ���������Ղ��Ă���܂��B
���������A���w���Ƃ��x���̂قǁA���肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24271013
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@�����������Ă��炢���肪�Ƃ��������܂��B
�@�l���f�b�h�}�X�ɋ������������̂́@������20�N�ȏ�O�Ƀ��W�I�Z�p�ŕʕ{����ƍ������J����i�߂Ă������j�E�F�[�u�X�s�[�J�[�ł��B
�@�ꕔ�̋L�������J����Ă��܂��B
https://aedio.co.jp/beppu/RG/UniwaveSpeakerPP202-207.pdf
�@���̃X�s�[�J�[�́u�悯���ȉ����o���Ȃ��v�ɓO���Ă��܂��B�Ȃ̂Ńf�b�h�}�X�͓��R�E�[�t�@�[�ɂ��c�B�[�^�ɂ����t���A���łȃG���N���[�W���A�O���S���ʂɌ���̃t�F���g��\��t���@�G���N���[�W������̐U�����˂�}�����݃^�C���A���C�����g�������ŋ��U�������\���ɂȂ��Ă��܂��B
�@�F�l�������Ă���̂ʼn���������Ă��܂����@�X�g�C�b�N�ȉ��̃��j�^�[���Ł@�X�s�[�J�[������������ł��B
�@���͐��m����ŗ]�v�ȉ����o���Â��Ȃ�ł����A�G���������Ď|���������Ȃ��Ă��܂����悤�ŕ����Ă��Ċy�����Ȃ��ł��B
�@�Ƃ܂��A�X�s�[�J�[�ɂ����ā@�ǂ̂�����Ńo�����X���Ƃ邩�H�Ɋւ��ā@���낢�닳����ꂽ�X�s�[�J�[�ł���܂����B
�@�����������o���̏��dualazmak����̈Ă��l���܂���
>���� NS-1000 �� Be-midrange SQ �ɁA�傫�ȃf�b�h�}�X�����t����Ƃ����U�f�ɂ�����܂����A�����n�[�h���������悤�ɂ������܂��̂ŁA�܂��́ASP�O�ʁi�o�b�t���ʁj�Ɍ��߂̉��ł𗼖ʃe�[�v�ŋ��łɓ\��t����悤�Ȃ��Ƃ������Ă݂悤���ȁA�Ǝv�Ē��ł��B�@
�@�܂����̓\��t���ł������߂̗������l�����܂��B
�@�o�b�t���ɋϓ��Ɍ����J�������ɋS�ڃi�b�g�����t���@���łɉ����o�b�t���ɌŒ肵�Ĉ�̉�����Ȃ���ʂ͂���Ǝv���܂����A�ڒ��܂œ\��t�����x�ł́@��̉��܂ł͂������A�ڒ��܂��ɏՍނƂ��ē����A�p���ĉ������R�U�����ė]�v�ȋ��U������\��������܂��B
�@�܂��A����\��t����ʒu�ɂ��@�o�b�t���̐U�����[�h�i�ސU���̕��Ɛ߂̈ʒu�j���ς���ā@�p���Ĉ����Ȃ�\��������܂��B
�@�����A�ڒ��܂ł���A���A�ł���̂Ŏ����Ă݂�̂͌�w�̂��߂ɂ��L�Ӌ`���Ǝv���܂��B
�@�t�ɉ��̓\��t���ł悭�Ȃ�\���Ƃ��ā@NS-1000�̐v�̌Â����y������邩������܂���B
https://www.audio-masterfiles.com/masterfiles/file056/file56-4.html
�@��NS-1000��NS-5000�̃G���N���[�W���̓����\���̔�r������܂����ANS-1000�J�������́@���ƌo���Ƒ���ŃG���N���[�W����v����̂����ʂł����B�ŋ߂́A�X�s�[�J�[�̐U�����[�h���V�~�����[�V�������ā@���S�ɗ}�����ނ̂ł͂Ȃ��A�j�]�̖����悤�ɓK�x�ȐU���ɗ}�����ރG���N���[�W���̍\���v�i���j�b�g�̎x���A�x���̓�����A���A�x�����x���j������̂Ł@���Ȃ�G���N���[�W���̍\�����Ⴂ�܂��B
�@�Ȃ̂Ł@NS-1000�̃G���N���[�W���́@���܂��ܓ����肾�����\��������A�ϐk�⋭�H���̂悤�ɒlj��⋭������ƐU�����[�h�����ǂ����\��������܂��B���lj��́@�x���lj��ɔ�ׂČ��A�\�Ȃ���y�Ȏ������@�Ƃ������܂��B
�@���z�I�ɂ́ANS-5000�̃G���N���[�W���\�������ɁA�V�K�ɃG���N���[�W�����쐬���ā@���j�b�g���ڐA����Ƃ������@�͌��ʂ�����Ǝv���܂����A�p���[�A���v�������邭�炢�̃R�X�g�͂����肻���ł��B
�@����ƁA���j�E�F�[�u�X�s�[�J�[�Ŏ��{���Ă���悤�Ɂ@�G���N���[�W����S�ʌ���̑e�уt�F���g�ŕ����͕̂���p�Ȃ����ʂ�����Ǝv���܂���....���h�����A���Ȃ̂Ń��r���O����ǂ��o�����\���������ł�(�j
>BOWS����́A����Be-SQ�Ƀf�b�h�}�X�������I�Ɏ��t���Ă݂邱�Ƃ𐄏�����܂����H�@�S kg �̐^�J�_���P�[�u���^�C�g�ƌ���̗��ʃe�[�v�ŌŒ肷�邱�Ƃ͉\��������܂��A����Be-SQ�́A�r�X�S�{�i�U�{�ł͂Ȃ��I�j�ŌŒ�ł��̂ŁA���x�I�ɏ����s��������܂��B�^�J�_�́A�P�`�Q kg ���x�ł������Ȍ��ʂ�����ł��傤���H
�@�܂��A�f�b�h�}�X�lj��ɂ����ʂ͂���Ǝv���܂��B�㉹�̔������̌���ɂ��q����܂��B
�@�f�b�h�}�X�̒lj��ł�����̋L�����Q�l�ɂ����Ɨǂ��ł����A���炩�̌`�Ń��j�b�g�Ɏ�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@����ƁA���j�b�g�̃t���[�����f�b�h�}�X�̎��ʑ����ɑς�����悤�ɍ���ĂȂ��̂Ł@���U�ɂ��t���[���ό`���l������Ɓ@�f�b�h�}�X�̎x���lj��͕K�{���Ǝv���܂��B
�@NS-1000�̃G���N���[�W�����ā@�w�ʂ����܂��������H�@����Ύx���̒lj���Ƃ����Ɗy�ɍs�Ȃ��܂����A���j�b�g�̃C���X�g�[�����y�ł��B���j�b�g�̌�둤����肪�͂��Ȃ��Ɓ@���낢�댵�����Ǝv���܂��B
�@�{���́@�E�[�t�@�[���j�b�gJA-3058A�Ƀf�b�h�}�X��t����̂��ǂ��ł����A��L�̋L���ɂ��� �U���n���ʂ�1000�{�͂ق����ƂȂ��Ă��܂��BJA-3058A�̏����͕s���Ȃ̂Ł@�������Y30cm�E�[�t�@�[��FOSTEX FW305�̏������Q�l�ɂ���Ɓ@�U���n���� 55g�Ȃ̂Ł@55Kg�̃f�b�h�}�X�ƂȂ�܂��B
�@����\�Ȃ��̂Ƃ���
https://www.monotaro.com/p/2014/1967/?t.q=%90%5E%E8J%20%8A%DB%96_
�@150mm�� 300mm���@�Ł@��45Kg
�@�܂��A45Kg�̉���C���X�g�[�����邱�Ƃ������I�ł͖����ł����A���ʂ͔��Q�ɂ���Ǝv���܂��B
�@�]�k�ł����A�l�̓��m�^���E�̑S�i10%������������_���ā@�^�J�ۖ_�����܂����B
�����ԍ��F24273563
![]() 2�_
2�_
2021/08/05 15:05�i1�N�ȏ�O�j
BOWS����
�����J�Ȃ��A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�z�����\�z���Ă����Ƃ���A�f�b�h�}�X�̒lj��́A���Ƀn�[�h�����������ρ^�����ł��ˁB�����ŁA�f���炵�������ƁuSP�������v���������Ă���Ă��鎄�́u�R�h���C�o�[�����A���v�쓮 NS-1000���v�ɂ��āA����ȏ�̕����I���ς������邱�Ƃ́A�f�O�������܂��B
���Ȃ݂ɁANS-1000 �́A�o�b�N�o�b�t�������O�����Ƃ͂ł��Ȃ��i�܂��͎��̂��Ƃ��f�l�ɂ͕s�\�ȁj�\���ł��B
����ł́A���Îs��� NS-1000, NS-1000M �܂��� NS-1000X ����肵�āA�f�b�h�}�X�lj����܂߁A�O��I�ɁA�{�c�ɂ��邱�Ƃ��o��ŁADIY�I�ɗV��ł݂����Փ��ɂ�����Ă���܂����A�̗́A�C�͂̈ێ����\�����܂߁A�������ďn���������܂��B
���āA�����������������G
https://www.audio-masterfiles.com/masterfiles/file056/file56-4.html
�́A�����ɂ������ł����B���ɋ����[���A�[���A�[���̓��e�ł����B
NS-5000 �ɂ��Ă��A���ɓ����ŁA�����ԍ��F23141926�@�ł��������悤�ɁA�����ۗ��������͂������܂���ł����B
��������ANSX-10000 �́A���ۂɕ��������Ƃ��Ȃ��̂ł����A���ɖ��͓I�ł��ˁB����̒��×Ǖi������ł���A���� NS-1000���Ɠ��l�ɁA�}���`�A���v���Ŗ炵�Ă݂����Ǝv���܂����A���Îs��ł��A�قƂ�Ǐo�Ă��܂���ˁB
����AIgor Kirkwood �����ł����p����Ă��� NS-1000X �́A���܁A���×Ǖi���o�Ă���悤�ł��̂ŁA����������ɖ��͓I�ł��B
�܂��́A�ŋ߁A���S�ɃA���v�S��{�A�N�e�B�u�T�u�E�[�t�@�[�̍\���ɗ������������݂̃V�X�e�������\���A����ASR�X���b�h�����Ă��� Floyd Toole���m�̂��������܂߂āAroom acoustics �̉��P�����s������A�����������������Ǝv���܂��B
�ȑO���b�������ASonas Faber IL Cremonese + Benchmark AHB2�i���m���[�h�łS��Ńo�C�A���v�쓮�j�A�Ƃ����S���ʂ̍\�z���������Ă���܂��A������ɍs���ۂɂ́A�S���ʂ̃X���b�h���A���icom�ł͂Ȃ��A�����炭 ASR�ŗ����グ�邱�ƂɂȂ肻���ł��B
���������A��낵�����肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24274205
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@�����@10cm�ȉ��̃��j�b�g�Ȃ�f�b�h�}�X��������̂͊y�ł����A�������ƃG���N���[�W�����猟�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂Ŏs�̂̃X�s�[�J�[�ւ̓K���͓���Ǝv���܂��B
>����ł́A���Îs��� NS-1000, NS-1000M �܂��� NS-1000X ����肵�āA�f�b�h�}�X�lj����܂߁A�O��I�ɁA�{�c�ɂ��邱�Ƃ��o��ŁADIY�I�ɗV��ł݂����Փ��ɂ�����Ă���܂����A�̗́A�C�͂̈ێ����\�����܂߁A�������ďn���������܂��B
�@�f�b�h�}�X�̌��ʂ͂ǂ�Ȃ��̂��̌�������������A�l������Ă���悤�� 8cm���j�b�g MarkAudio Alpair5V3�@�ƂUL���炢�̃��A�o�b�t�����O���锠���w�����ăX�s�[�J�[�g��ł݂ā@��ǂ��Ńf�b�h�}�X�lj������Ă݂Ă͂ǂ��ł��傤�H
�@Alpair 5V3�́A�_���p�[���X�ŐU���̓������q���ł������f�B�e�[���\���ɗD��܂��B
�@8xm �V���O�����^���R�[���t�������W�Ȃ̂őш���ɒ��̃����W�͋����A����͂��ʖڂł����A�}���`�E�F�C�ƈ���ā@�V���O���R�[���t�������W�Ȃ�ł͂̉����ʒu�������ŋɂ߂Ă܂Ƃ܂�ƃo�����X�̗ǂ��������܂��B
>���āA�����������������G
>https://www.audio-masterfiles.com/masterfiles/file056/file56-4.html
>
>�́A�����ɂ������ł����B���ɋ����[���A�[���A�[���̓��e�ł����B
>
>NS-5000 �ɂ��Ă��A���ɓ����ŁA�����ԍ��F23141926�@�ł��������悤�ɁA�����ۗ��������͂������܂���ł����B
�@�I�[�f�B�I�u�[���������Ď��Ək�����A�X�s�[�J�[���j�b�g���J�����Ȃ��Ȃ���YAMAHA���A���݁@�����X�s�[�J�[�J������Ƃ�����NS-5000�̕����ɍs������Ȃ���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�V�f�ނŊ�b�J������X�s�[�J�[���j�b�g��郁�[�J�[�͍�����FOSTEX���炢����Ȃ�����
�@�x�����E���͌y���č����͂��邯�ǖғłȂ�Ń��j�b�g����郁�[�J�[�͌�����Ǝv���܂��B�J�i�_�̃p���_�C�������͓I�ɍ���Ă��邯�ǁA�������U�������ă��j�b�g���͓̂�����B
�@���Ⴖ��n�x�����E�����A�\�t�g�h�[���̕����A�U���̎����������ē����̗ǂ��X�s�[�J�[�Ƃ��Ă܂Ƃ߂₷�����NS-5000�̓\�t�g�h�[���ɕς����Ǝv���܂��B
>��������ANSX-10000 �́A���ۂɕ��������Ƃ��Ȃ��̂ł����A���ɖ��͓I�ł��ˁB����̒��×Ǖi������ł���A���� NS-1000���Ɠ��l�ɁA�}���`�A���v���Ŗ炵�Ă݂����Ǝv���܂����A���Îs��ł��A�قƂ�Ǐo�Ă��܂���ˁB
NSX-10000�͍������Ĕ���܂���ł����ˁB�ł����ۂɂ��̂��炢�̉��i����Ȃ��ƒނ荇��Ȃ������Ǝv�����ANS-1000M���������ā@����Ɣ�ׂ�ꂽ�̂��s������Ȃ��ł����ˁB
>�܂��́A�ŋ߁A���S�ɃA���v�S��{�A�N�e�B�u�T�u�E�[�t�@�[�̍\���ɗ������������݂̃V�X�e�������\���A����ASR�X���b�h�����Ă��� Floyd Toole���m�̂��������܂߂āAroom acoustics �̉��P�����s������A�����������������Ǝv���܂��B
>�ȑO���b�������ASonas Faber IL Cremonese + Benchmark AHB2�i���m���[�h�łS��Ńo�C�A���v�쓮�j�A�Ƃ����S���ʂ̍\�z���������Ă���܂��A������ɍs���ۂɂ́A�S���ʂ̃X���b�h���A���icom�ł͂Ȃ��A�����炭 ASR�ŗ����グ�邱�ƂɂȂ肻���ł��B
�@IL Cremonese�́A�\�i�X�Ƃ��đ傫�ȃV�X�e���ł��ˁB
�@������}���`�ŋ쓮����͖̂ʔ������ł��B
�@YAMAH�̃A�L�����[�g�ȉ��y�\���ɔ�ׂ�ƃ\�i�X�̂�Ȋy�퉹�͑ǂ̂悤�ȋC�����܂����A���̕����ŋɂ߂�Ȃ�t�����R�Z���u������ktema���Ǝ��̉��������Ċy�������ł���
�����ԍ��F24274625
![]() 1�_
1�_
BOWS����
���ԐM�A���肪�Ƃ��������܂��B
��YAMAH�̃A�L�����[�g�ȉ��y�\���ɔ�ׂ�ƃ\�i�X�̂�Ȋy�퉹�͑ǂ̂悤�ȋC�����܂����A���̕����ŋɂ߂�Ȃ�t�����R�Z���u������ktema���Ǝ��̉��������Ċy�������ł���
�̃t�����R�E�Z�u�������́A������ Sonus Faber �̑n�n�҂ł����ˁB Ktema �͒��������Ƃ�����܂��A�L����ǂL���͂���܂��B�m���ɁAIL Cremonese �i����A�D�ꂽ���z�[���Œ������j�Ɠ�����������SP�ł��ˁB���������͒[�q�̓o�C�A���v�Ή��ł͂Ȃ��A�V���O�����C�A�����O�ł��̂ŁA�����܂ŁA�l�b�g���[�N�ݒ���܂߂ăt�����R�E�Z�u�������̎v�z�Ɛv��M�����āA�������肵���A���v�Ŗ炷�ׂ����i�ł���ƌ��܂����B���E�Ɨ��� AHB2 ���m���[�h�ŋ쓮�A�Ƃ��B�B�B�B�ǂ����ŁA�������肵���������ŁA�����Ă݂����Ǝv���܂��B
���āA���̃��r���O���I�[�f�B�I���[���ł����A���܂��͑��q�̂Ƃ���ֈڐݗ\�肾�����A�b�v���C�g�s�A�m���A���ʂ̎���ŁA�܂��������Ă���܂��B������ڐ݂܂��͓P�����āASP�Q���Ĕz�u�A�Đݒ肷�邱�Ƃ����ʂ̉ۑ�i�S�̂ɏ������ֈړ������AL&R�Ԋu�������L����v��j�ƂȂ��Ă���܂����A�����̃R���i�����Ċg��►��Ƃ̓]���Ȃǂ����܂��āA�ۗ���Ԃł��B
�R���i��������i������Β��肵�����̂ł����A���ɂȂ邱�Ƃ��B�B�B�@�ǂ����A���E�͑傫���ϗe���Ă��܂��A�Q�O�P�X�N�̏H������́u���a�ȁv�ɂ́A�����߂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�ƈ��W����C���ɂȂ邱�Ƃ��������̍��ł��B�@����ɂ��Ă��A�Q�O�P�W�N�̏H�ɕč��ł̎d�����グ�ċA���������Ƃ́A���ʘ_�ł����A�����ł����B�@���܂�A�d���ł��A�F�l�K��ł��A�n�Ă��邱�Ƃ͔��Ƀn�[�h���������Ȃ��Ă��܂��܂����B
�K���A���ǂ��v�w�́A�t�@�C�U�[���N�`���Q��̐ڎ���I���܂������A����ł����f�͑�G�ł��B
BOWS����ɂ�����܂��Ă��A�����h�~���O�ꂵ�āA�����S�ɂ��߂����������B
����Ƃ��A��낵�����肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24275059
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@���C�������肪�Ƃ��������܂��B
�@���̂Ƃ���Ƒ��Ƃ��ǂ����C�ł��B
�@���^�b�ɂȂ�܂���....
>�̃t�����R�E�Z�u�������́A������ Sonus Faber �̑n�n�҂ł����ˁB Ktema �͒��������Ƃ�����܂��A�L����ǂL���͂���܂��B
�@�t�����R�Z���u��������Sonus Faber�𗧂��グ�������� ELECTA AMATOR �Ƃ��C�^���A�炵�����y���Ɉ�ꂽ���f��������Ă��܂������A�������ċ@�킪�����A�������̐��i���C���i�b�v���o���ċK�͂��傫���Ȃ�����Ȃ��̂���A�������i�܂ŕi��������ƂƂȂ��Ă������_�Ł@�t�����R�Z���u�������͍�肽���X�s�[�J�[����ꂸ�A�����̖��O���������K���[�W���[�J�[�����グ�ā@�v������̂���X�s�[�J�[��������̂����� ktema���Ƃ����F���ł��B
�@IL Cremonese�́A���� Sonus �̒��_���f���炵���AB&W��800�V���[�Y�Ɠ������A�ǂ�ȃ\�[�X�������x���ő��Ȃ����Ȃ����\�X�s�[�J�[���Ǝv���܂��B����AKtema�́@�Z���u�������̚n�D�����f����Č����s���������Ƃ͂����肵�ā@�̂��グ��X�s�[�J�[�ł��邪�A�\���b�h�ȋȂɂ��܂�����Ȃ��̂��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�Ȃ��Ȃ������Ȃ���ł����A�@��L����������������B
�@�������L���g����悤�ɂȂ�����A�����a�t�������W��R���f���T�X�s�[�J�[���̓���s����̂͂����肵����|�ɏG�ł��X�s�[�J�[�����p����Ă͂ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F24275890
![]() 1�_
1�_
BOWS����A
�ēx�̂��ԐM�A���肪�Ƃ��������܂��B
�������A�t�����R�E�Z�u�������̏��߂āA�������̓��e���m�F���Ă���܂����B�t�����R�E�Z�u�������́A�ɂ��܂�Q�O�P�R�N�ɐ�������܂����̂ŁA
http://www.arkgioia.com/news/franco_serblin.pdf
����LABORATORIUM�iStudio Franco Serblin�j�Ђ̑����⏫���ɂ́A�ꖕ�̕s���������܂����AKtema �́A����ǂ����Œ����Ă݂����Ǝv���܂��B
���āA�ȉ��́A���߂̔������I�Ȍ����Ȃ̂ł����A�A�A�A
����A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-857793
�ŕ����悤�ɁA�قڍŏI�I�� OKTO DAC8PRO �́G
CH1+CH2 XLR�A�E�g��SONY TA-A1ES �� Be-TW ���쓮�A
CH1+CH2 �̃w�b�h�z���A�E�g RCA��YAMAHA A-S301 �� ST (Fostex T925A) ���쓮�A
�Ƃ����\���ŁA Be-TW �� ST �����S�Ɨ��Q�C������ł���悤�ɂ����̂ł����i�Y�t�} Option-4�j�A�������蕷���Ă���ƁA����ȑO�̍\���Ɋr�ׂāA���ɋ͂��ł����A����̑N���x�i�������A�������j���ቺ������ۂ�����܂��āA������A�ЂƂO�̍\���i�Y�t�} Option-3�j�Ƃ̓O��I�Ȕ�r�������s���Ă���܂����B
������̍\���ł��A���X�j���O�ʒu�ɂ�������g�������́A�Y�t�̓������g�������Ȑ��ɂȂ�悤�A�����Ɋe���x���E�Q�C����ݒ肵�Ă���܂��B
����Option-3 �ł́A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-831487
�ŏڂ������� Audio-Technica �� High-to-Low �R���o�[�^�[ AT-HLC150 ���g���Ă��܂��B
���́A��ɃJ�[�I�[�f�B�I������ AT-HLC150 ���g�����Ƃ́A�����A�S���ד����Ǝv���Ă����̂ł����A�����ɍw�����ēO��I�ɕ]�������Ƃ���A�d�l���Łu20 Hz - 40 kHz �S���±1.0 dB �v��搂��Ă���悤�ɁA�������p���� 5 kHz - 22 KHz �ł͉����iS/N��c�݁j���قڊF���ŁA���ɗD����̂ł��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B
����ŁA�Y�t�} Option-3 �̍\���� Option-4 �̍\�����A�ēx�A�O��I�ɔ�r���������Ƃ���A��͂� Option-3 �\���̕����A����i�����đS�̉����j�̑N���x�i�������A�������j�ɂ����āA�͂��ɗD��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B�����ꏏ�ɕ����Ă���Ɠ����A������̕������������o�C�I�����̉��Ȃ������Y��őf���ɏo�Ă�ˁA�ȂǂƐ\���܂��B
�ǂ����A OKTO DAC8PRO CH1+CH2 �̃w�b�h�z���o�͂́A�M���d�l�Ƃ��Ă͔��ɍ��i�ʂȂ̂ł����ACH1+CH2 ��XLR�o�͂Ɓi���Ɂj����쓮�ŕ��p����ۂɂ́A���ɔ����Ȓx����ʑ��̍�������悤�ŁA���ꂪ����iBe-TW �� ST�j�ɂ�����͂��ȁu���̓܂�v�������Ă���悤�ł��B
����AOption-3 �� AT-HLC150 ���p�\���ł́AA-S301 �̃Q�C���^�{�����[���v����́ATA-A1ES �̔z���ɂ͂Ȃ�܂����A����ƑS�̉����̑N���x�i�������A�������j����сu�X�s�[�J�[�������v�͋��ٓI�ɑf���炵���A Option-4 �ɗD��܂��B
����ŁAOption-3 �̍\���ɖ߂����Ƃɂ��܂����B
Be-TW �� ST �́u�d�Ȃ�v�Ɓu�q���v�̔������́A���ɏd�v�ł��邱�Ƃ��A�Ċm�F���܂����B
���ɁA���̍\���ł́AST�̓���Ȕz�u�ʒu�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-370571
���A�S�̂Ƃ��Ẳ����\���Ɓu�X�s�[�J�[�̏������̎����v�ɑ傫����^���Ă���̂ŁA Be-TW �� ST �̓Ɨ��쓮�ɂ����郌�x���^�Q�C���A�ʑ��A�x���́i���s����ɂ��j�����������ɏd�v�ł��邱�Ƃ��ĔF���������܂����B
BOWS����A�����ɂ悵����A�������ɂ�������������]�́A���ł����������Ă���܂��B
�V�^�R���i�E�C���X�������I������A�A�A�A�����k�\���グ�܂��B
���̍ۂɂ́AASR �̌l�ԘA���V�X�e���i���{��ł����Ȃ��I�j�𗘗p���܂��傤�B
�����ԍ��F24276530
![]() 0�_
0�_
�F����A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-871745
�ŃV�X�e���\���}���ŐV�̏ɍX�V���܂����̂ŁA�����ł��A���̓��e�Ǝ��̓��e�ŏЉ�Ă����܂��B
�����ԍ��F24277409
![]() 0�_
0�_
�F����A
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/midrange-dome-drivers-banned.15060/
�ŁABe-�h�[���h���C�o�[���܂ށu�~�b�h�����W�i�h�[���j�h���C�o�[�v�ɂ��āA�ƂĂ������ɕx�ޏ��������s���Ă���A���������I�ɎQ�����Ă���܂��BBe-�h���C�o�[�̍����\�z�A�肤��ł��A�Q�l�ɂȂ�܂��B
��������������ł�����A�����������B
�����ԍ��F24281025
![]() 0�_
0�_
�F����A
��قǁA�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-922816
�ɏ����Ă����܂������A�����O�Ɏ��̐e���Ȃ�ASR�t�H�[�����̗F�l��1�l���AJBL�̌��f�U�C�i�[/�G���W�j�A�ł���GregTimbers����JBL EverestDD67000���g���āA���Ɠ��l�́u���S�ɃA�N�e�B�u�ȃ}���`�`�����l�� 4-way �X�e���I�V�X�e���v��DIY�\�z���Ă���A�ƒm�点�Ă���܂����B
https://positive-feedback.com/interviews/greg-timbers-jbl/
�Y�t�摜�́A Greg Timber ���̃X�e���I�ݒ�ɂ�����}���`�A���v�\���ł��B
�ނ�UHF���k�h���C�o�[�i�X�[�p�[�c�C�[�^�[�j�̋쓮�ɁA�������i�����Ď荠�ȉ��i�́jPioneer ELITE A-20���g�p���Ă��邱�Ƃ�m�邱�Ƃ͎��ɂƂ��Ė{���ɋ����[�����Ƃł��B
�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-871745
�ƁA���̃X���b�h�̒��߂̏����ԍ��F24277409�@����с@�����ԍ��F24277414�@�ł��m�点���Ă���悤�ɁAGreg Timber���Ɠ��l�ɁA�����A�������i�����Ď荠�ȉ��i�́jYamaha A-S301���g�p���āA���^���z�[���̃X�[�p�[�c�C�[�^�[�ł���FostexT925A���쓮���Ă��܂��B
�����ԍ��F24365294
![]() 1�_
1�_
�F����A
�i�b��I�ɁH�I�j�V�X�e���\�����Œ肵�Ă���قڂR�������o�߂��A�f���炵�����������\���Ă���܂��B
���āA�A�A
ASR Forum �ɂ����鉢�Ă̗F�l�B�̊��߂ɉ����āA���݂̃}���`�`�����l���E�}���`�A���v�V�X�e���̍\���ƃ��X�j���O���A����ю��̃V�X�e���̓����I�ȑ��ʂ����X�A�ЂƂ̓��e�Ɏ��Z�߂ďЉ�Ă���܂��̂ŁA���������������܂����炲���������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-kit-we-bought-our-current-setups.564/post-938205
�܂��A�F�l�̊��z�₲�ӌ����A������ ASR Forum �ł�������������������K���ł��B
�Ȃ��AASR Forum �ł́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?search/27001167/
�Ō�����悤�ɁA�ŋ߂ł͏����Q���X���b�h�⊈���̈���g�債�āA���������s���Ă���܂��B
���̃V�X�e���\�z�Ɋւ����ÃX���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�ւ̖K��{���́A�S���E�łW���P�����܂����B
������̃j�b�`�Ȏ�ÃX���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lute-music-stunning-recordings-we-love.21247/
�́A�b�肪�o�s�����������Ȃ��ɂ������炸�ŁA���̑��Z�������āA�X�V�����Ă���܂����B�B�B
�����ԍ��F24397214
![]() 0�_
0�_
�ЂƂ�̓��e�ŁA���݂̍\�������Z�߂� ASR Forum �ɂ����鎄�̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-kit-we-bought-our-current-setups.564/post-938205
�ɂ��Ă��m�点���܂������A���l�̕�����uDAC��A���v�̔w�ʔz���̗l�q�ƁASP�Q�w�ʂ̔z���̗l�q���A�ʐ^�Ō����Ă���I�v�@�Ƃ̗v��������܂����̂ŁA����ASR Forum ���e�ɁA�Y�t��4���̎ʐ^��lj����܂����B
�����ԍ��F24411733
![]() 0�_
0�_
ASR Forum �ɂ����鎄�̃v���W�F�N�g�X���b�h�ւ̉{���K����W���S�����܂����̂ŁA�ȒP�ȃn�C�p�[�����N�ڎ����쐬���܂����B
���������������܂�����A���Η��������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-961964
�����ԍ��F24428940
![]() 0�_
0�_
���Q�l�܂łɁA�A�A
ASR Forum �́A���̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/why-arent-we-pushing-for-more-4-8-channel-dacs-for-a-quality-stereo-setup.26753/
�́A���̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/why-arent-we-pushing-for-more-4-8-channel-dacs-for-a-quality-stereo-setup.26753/page-10#post-958149
�ȍ~�ŁAFOCUSRITE Scarlett 18i20 2nd gen (�� 3rd gen) ����� MOTU UltraLite Mk5 �ɂ��ċ����[�����������i�߂��Ă��܂��B��������A�����ɓ���10�`�����l��DAC�v���Z�X���T�|�[�g���Ă���悤�Ɍ����܂��B����������OKTODAC8PRO��菭�����悤�ł����B�B�B
���� ASR�X���b�h�́A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-964323
�ł��Љ�Ă����܂����B
�����ԍ��F24433157
![]() 0�_
0�_
�F����A
�M�����Ȃ��悤�Ȑ��\�^���i�̐V�����A���v���o�ꂵ���悤�ł��B
Topping PA5
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-pa5-review-amplifier.28512/
����́A�{���ɃI�[�f�B�I�A���v�̐V�����A�V���E�ƂȂ�̂ł��傤���H
���́A�܂������m�M�����Ă��A�ςɂ܂܂ꂽ�悤�ȋC�����ł��B
�����ԍ��F24468650
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@�����������Ă��܂��B
�@��肪�Ƃ��������܂��B
�@Topping PA5�̏�肪�Ƃ����������܂��B
�@�[�q���t�H���W���b�N���Ă����̂��@���̃A���v�̏o������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@�n�C�G���h�ƌ������@�o�����X�ڑ�����{�̃v���p�iPA�n�j�̂悤�ȋC�����܂��B
�@D���A���v�̃p���[IC���ā@��������������BTL�\���i�t���o�����X�j�������ł��B
�@���ۂ̏��i�̉��i�тł̓A���o�����X���͂������ā@�Б��O�����h�ɗ��Ƃ��ē����I�Ƀo�����X�ɕϊ����Ă���A���v�������̂Ł@�t���o�����X�̕����A���v�Ƃ��Ă͖{���̓���ƂȂ�܂��B
�@�������ǂ��̂́A�X�C�b�`���O���g����ʏ� 300�`400KHz��600KHz�ɏグ�Ă��ā@�I�i�̃|�X�g���[�p�X�t�B���^�̎��萔���グ�ĕ��ׂ��y�����Ă���̂������Ă���Ɛ������܂��B
�@���g����P���ɏグ��� �X�C�b�`���OON��OFF��ON �̑J�ڎ��ԂɊђʓd��������ă��X���ēd�͌�������������A���M�����肷��̂ł����A�グ�邱�Ƃ��o�����̂́@�I�i�̃X�C�b�`���O�f�q��ς��Ă����\���������ł��ˁB
�@������@�o�����ē���������Ă���Ǝv���܂����A�ǂ̃p���[IC���g���Ă���̂��A����Ƃ��I�i���f�B�X�N���[�g�őg��ł���SiC���̍����X�C�b�`���O�f�q���g���Ă��邩������Ǝv���܂��B�V�^�p���[IC�Ȃ�A�J���⡂̂悤�ɁA������`����̃A���v���o�Ă��邩���ł��B
�@D���A���v�̗ǂ������́@�����ł͂Ȃ��Ċ�Ɠd���̍�荞�݂̗ǂ������Ȃ�Ł@�����������o�Ă����猩�Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�܂��A�ߏ�Ȋ��҂͂��Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B
�@�Ƃ肠�����@Amazon�ł��������Ă݂�Ƃ�
�@�f�����ǂ���A�������ā@���j�A�d����lj�����Ɖ����邩������܂���B
�����ԍ��F24468986
![]() 1�_
1�_
BOWS����A
���ԐM�A���Ӑ\���グ�܂��B
�����A���M���^�ŁA�����ʐ^��g�p�f�q�ނ��܂߂āA���炭�l�q���̂���ł��BASR�ł͐���オ���Ă܂����B�B�B�B
���āA���̃V�X�e���́A�قڊ������đf���炵�����������\���Ă���܂����A�W���Y���ۂɁA�������� vivid �ȃE�[�t�@�[�i60 Hz�`600 Hz�� 5dB �ȓ��̃t���b�g���\�j�����������āG
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-970374
�ȍ~�ŋ��L���Ȃ��猟�����ł��B
�s�̂̊������ꂽSP�̗��p�����A20 cm �E�[�t�@�[���j�b�g���P������ځi�I�j�A�D�ꂽ�O�ʃo�X���t�|�[�g�i���\�j�A�������l�b�g���[�N�Ȃ��A���v�����i�I�j�A�傫���͍ő�ł��O��W380, H490, D380 mm�A�d����25kg�ȏ� 30 kg�ȉ��A����MDF �A�����⋭�ށA�K�ȋz���ށA��Ȃ����h���iYST-SW1000 �̏�ɒu���v��j�Ȃǂ̏����ŁA�E�[�t�@�[��pSP������܂��͐���ϑ����邱�Ƃ��������ł��B
�E�[�t�@�[���j�b�g�́A���܂�����������A��������]������T�[�r�X������Ή����p���I�ɗ��p�\�ȍ�����Ђ̐��i���A�ƍl���Ă���A�d���}�O�l�b�g��FOSTEX FW208N �����ɂ��Ă���܂��B
�������A�T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000�AYamaha ��Be-�~�b�h�h�[���A Be-�c�C�[�^�[�A FOSTEX T925A�X�[�p�[�c�C�[�^�[�́A���̂܂܃}���`���Ōp�����p���A�\�[�X�ɉ����� NS-1000 �� 30 cm �E�[�t�@�[�ƁA��L�̐Vvivid 20 cm�E�[�t�@�[���A�A���v A-S3000 �́@SP-A, SP-B �Ő�ւ��Ē����Ă݂悤�Ƃ����A�V�ѐS�ł��B�@���܂������Ȃ���A�Q�K�̃I�t�B�X�ŁA�ʂ̏��K�̓}���`�V�X�e���̈ꕔ�Ƃ��ė��p�ł��܂����B�B�B
�����A�����߂̃E�[�t�@�[���j�b�g�i�ł�������i�j�Ȃǂ������܂�����A���������������܂�����K���ł��B
�����ԍ��F24469402
![]() 0�_
0�_
Topping PA5 �̓�������Z�p���A�ǂ����ł����ɂȂ��܂�����A�ȒP�Ō��\�ł��̂ŁA�����ł����L���Ă���������K���ł��B
�����A�������Ă��������܂��I
�����ԍ��F24469409
![]() 0�_
0�_
BOWS����A
SiC�f�q�A�\������ł��ˁB
�����Ζ����Ă����^������w�̍H�w�n��w�@����ѓ������Ζ����Ă����č��J���t�H���j�A�̖^��w�̍H�w�n�������A����ɂ����ƘA�g���Ă邢�����̑��d�@�����ʐM��Ƃł́A�ߔN�A����� SiC��GaN���A��ɋ��d����ɂ������d���^���d���ł̍����X�C�b�`���O�ɉ��p���錤���Ǝ������i��ł��邱�Ƃ��������Ă���܂����B
SiC��GaN �f�q�������p�I�[�f�B�I����Ŏ��p�������̂́A����������̏������ȁA�Ǝv���Ă���܂������A���Ȃ�}���ɃI�[�f�B�I����ł̎������i�݂���̂�������܂���ˁB
���Ȃ݂ɁA�J���t�H���j�A�ɑ勓���Đi�o�����w���Ă����D�G�Ȓ����̌����ҒB�E�Z�p�ҒB���A�R���i�Ђň�Ăɒ����{�y�A�����܂����̂ŁASiC��GaN�̎����Z�p��m�E�n�E�𒆍��{�y�Ɏ����A�������Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂��B���̂������ Topping �Ђ̐��i�J���ɑ傢�ɉe�����Ă���̂ł́A�Ƒz�����Ă���܂��B
�߂������� Topping PA5 �̓����ʐ^�Ƒf�q�ނ����炩�ɂȂ�̂��y���݂ɑ҂��܂��B
BOWS��������w�E�̒ʂ�APA5 ��PA�Ƃ����l�[�~���O���炵�āA�܂�TRS�t�H���W���b�N���猩�Ă��A�v��PA�n�̗���̐��i�ł��ˁB
����܂ł́APA�n�̐��i�͑剹�ʍĐ��͓��ӂł�����̂́AHiFi�n�C�G���h�̊ϓ_�ł� SINAD�l���ӂ��߂������i�ʂ̓_�ŁA�ƒ�n�C�G���h�I�[�f�B�I�ɂ͎g���Ȃ����̂��قƂ�ǂł������A�����ɂ��� PA5 �̓o��ŁA���̋��E����C�ɂȂ��Ȃ�APA�n�̐��i�ŁA�剹�ʍĐ����\�ŁASINAD�����ɗD��A�R�X�p�����Q�ȃI�[�f�B�I�A���v�������ł��ēo�ꂵ�Ă���悤�ȗ\��������܂��B
���́u�ߏ�Ȋ��҂͋֕��I�v�ɑS�������ł����A�I�[�f�B�I�A���v�ɂ����Ă��V���������̑����������Ă���̂����B�B�B
���ꂪ�A�{���Ɍ����̂��̂ɂȂ�Ȃ�A��������ъC�O�̍��z�n�C�G���h�A���v���[�J�[�̏����́A�@���ɁH�@�F����A��X���X�Ƃ���Ă��邩������܂���ˁBHypex�� Purifi ���ABenchmark ���A�A�A���߂Ă��邩���H
PA5�ɂ��ẮA�d�����j�b�g�i�d���A�_�v�^�[�j���O�t���ł��邱�Ƃ��A���ɂ��Ȃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B
�������������Ă�����������̔��ɍ����� DENTEC DP-NC400-4-EXP �iHYPEX NC400 �S��ځj���d�����j�b�g���O�t���ɂ��邱�Ƃʼn���������������Ă��܂����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-461114
�̂�Topping PA5 �ł��A���̊O�t�� 38 V �d���A�_�v�^�[���g�����X�{��e�ʃR���f���T�^�� 38 V �d�����j�b�g�Ɍ������邾���ŁA����ɋ��ɂ̉����i�ʉ��P���ȒP�Ɏ����ł���̂�������܂���B�����ŁA�ʔ������E���߂Â��Ă���悤�ȋC�����Ă��܂����B
���̃V�X�e���ł́ADAC8PRO�����p���Ă��܂��̂ŁA�o�����X���͂͑劽�}�ł����A�A���o�����X�ɖ߂����͖ѓ��������܂���BXLR-to-TRS �́A�ϊ��A�_�v�^��ϊ��P�[�u���őS�����Ȃ��ł����B�B�B
BOWS����A�����ɂ悵����ATopping PA5 ��O��I�ɕ��͂��Ă��������܂��H�i�j
�i���͑S���̃G���h���[�U�[�́u�Ǒf�l�v�ł��̂ŁA�ƂĂ��ƂĂ��A�A�A�j
�����ԍ��F24470047
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����A�F����
�����A�����G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-24#post-995305
�Ō��y���v�悵�Ă���v�V�I�ȁi�H�j�E�[�t�@�[���T�u�E�[�t�@�|���j�b�g�A SEAS EXTREME "L26ROY" (XM001-04) woofer (sub-woofer)�@�Ɋւ��āA���o����lj������A�������������������A���肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24474462
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@���낢�뎋��������H�삵������������肵�Ă��܂����A��������I�ȃf�o�C�X�̓o��ʼn������オ����Ă̂́@���܂薳�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�@�������Ă���l���A�n���Ɋ������i���g���č�荞�݂�����A�V�����f�o�C�X�g���ɂ��Ă������Ȃ���ǂ����ނƂ����Ȃ��ƃn�C�G���h�ɓ��B���Ȃ��ł��B
�@�Ȃ�Ł@�n�C�G���h�قǎ��Ƃ�������̂Ł@�ƂĂ����z�ɂȂ�̂��ȂƎv���܂��B
�@Topping�ł����A�Z�p�͂͂�����x�����Ĉ����͂Ȃ���ۂł��B
�@DAC(D70)�g���Ă��܂����A���̂܂܂��Ɓ@�܂��܂����Œl�i���@���傢�ƃR�X�p�ǂ����ȂƎv�����x�ł��B
�@PA5�ł����@�d�����ア�ł��ˁB
�@�d���́@�����ł��O�t���ł��ǂ��ł����A�������ƃA���v���̂��傫���Ȃ�f�����b�g������A�O�t������
�d���������C���������Ȃ�����ɃR�l�N�^�����ނ̂œd���̎���������̂Ł@�꒷��Z�ł��B
�@PA5�́@140W@8���@�Ȃ�Ł@�P���v�Z����� �ő�p���[���� 8.75A�@���`������ 17.5A����܂��B
�@�u�ԓI�ȋ����Ȃ�œd���R���f���T���狟������ɂ��Ă��@�SA�̃X�C�b�`���O�d���͕n��ł́H
�@PA5�����m�����Ŏg�p���ā@�e�X7A���炢�̃��j�A�d����t����Ɓ@���Ȃ�ǂ��Ȃ肻���ȋC�����܂��B
�@����� SEAS EXTREME "L26ROY" �ł����A����I�ȗD�������ۂ��X�s�[�J�[���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�C�ɂȂ�̂��U���n����118g���Ă̂�25cm�N���X�Ƃ��Ắ@���Ȃ�d�����ł��B(38cm �E�[�t�@�[��90�`150g���炢)�@���C�M���b�v 10mm�ɑ��� �{�C�X�R�C������38mm�Ȃ̂Ł@���Ȃ�̃����O�{�C�X�R�C���ŁA�U�����傫���Ă��쓮�͂����������A���L�̃G�b�W�ŃX�g���[�N���傫���@�悭�����U���ł��ˁB
�@�A���~�U���ƃ����O�{�C�X�R�C���Ȃ�ŐU���v���d�����̂ŋ��͂Ȏ��C��H�ŋ쓮�͏グ�Ă���v�ł��ˁB������ f0��25Hz�Ȃ̂Ł@�_���p�[�ƃG�b�W�͂����Ł@���^���ŋ�C�𐧓���R���o�l�Ƃ���v�ł��ˁB
�@�Ȃ̂Ł@dualazmak����̈Ă͗��ɂ��Ȃ��Ă���̂ŗʊ��Ǝ����͌��シ�邪...�����̐����n�Əd�����U���̂��߁A�U���̎������x���Ȃ����C�ɂȂ�܂��B
�@�Y�t�̔g�`�́@1KHz 10�g�̃o�[�X�g�T�C���g�̌����Ɓ@10cm�t�������W��38cm�E�[�t�@�[2���̃o�[�`�J���c�C���X�s�[�J�[����C�^�������Ƃ��̔g�`���r���Ă��܂��B
�@�y�ʐU����10cm�t�������W�́@�o�[�X�g�M�����I����Ė����ɂȂ������ɂR�g�Ŏ������Ă��܂����A�o�[�`�J���c�C����10�g�ȏ�ł��������Ă��܂���B38cm���j�b�g�ŐU���n���d���ă_���p�[����邭�ĉߓn�������t�������W�ɗ��܂��B
�@�N���V�b�N�̂悤�Ɂ@�ቹ�����y���I���K���̂悤�Ȏ������������ƋC�ɂȂ�Ȃ��t�@�N�^�[�ł����A�W���Y�̂悤�Ƀh�����X�̗����オ��A����������̃L���̗ǂ�����������\�[�X�ł͂ǂ����ȁH�Ǝv���܂��B
�@
�@
�@
�@
�����ԍ��F24476008
![]() 3�_
3�_
BOWS����
�����́A�����Ă����̂悤�ɁI�A���ɓI�m�Ŏ����ɕx�ނ��ԐM�A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
��PA5�́@140W@8���@�Ȃ�Ł@�P���v�Z����� �ő�p���[���� 8.75A�@���`������ 17.5A����܂��B
���u�ԓI�ȋ����Ȃ�œd���R���f���T���狟������ɂ��Ă��@�SA�̃X�C�b�`���O�d���͕n��ł́H
�S�������ł��B���̂Q�N�Ԃ� BOWS����A�����ɂ悵����B�̋���ɂ��A�������̒��x�̐������ł���悤�ɂȂ��Ă���܂��āA�d���̕n�コ�ɋC�Â��Ă���܂����B4A�̃X�C�b�`���O�d���A�_�v�^�[�ŁA�n�C�G���h�ȃ}���`�h���[�o�[�X�s�[�J�[��剹�ʂł܂Ƃ��ɋ쓮�ł���Ƃ͐M����B�B�B
������ɂ��Ă��ATopping PA5 �́A���ڂ��l�q���A�����̌����A�ł��B
���āASEAS EXTREME "L26ROY"�@�Ɋւ���A��������Ɏ����ɕx�ރR�����g�A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B
���̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/what-measurements-parameters-tell-you-to-not-use-a-subwoofer-for-mid-range-frequencies.25138/
�ł��A���낢��c�_����Ă���̂ł����ABOWS����̂悤�Ȕ��ɓI�m�Łu�I���˂��v�w�E�́A�قƂ�nj�������܂���ł����B
���� Yamaha 30cm JA-3058 �E�[�t�@�[�́A�拭�� NS-1000 ���L���r�l�b�g�ɒ������āA���܂��Ɍ����o���o���Ō��݂Ȃ̂ł����A�@������͍i�I�j�ł��̂ŁA���������Ă��Ă��邩�ȁ`�A�Ƃ������鍡�����̍��ł��B
�����AL26ROY���r�I�R���p�N�g�Ȗ��L���r�l�b�g�i���w�E�̂悤�ɂ��ꂪ�D�܂����I�j�Ɏ��߂āAYamaha 30cm�E�[�t�@�[�Ɛ�����ւ��Ďg����悤�ɂ����ꍇ�A���܃W���Y�Ȃǂ��ۂɁA���Ȃ��Ƃ��A�u�����́i�H�j�vYamaha 30cm �E�[�t�@�[�������C�悭���Ă���邱�Ƃ����҂��Ă���A�ƌ��������x�̑��v��ł��B
�����d���U���n�d�����̓}�O�l�b�g�ŋ쓮���邱�ƂŁA���́u�����オ��v�͂���Ȃ�Ɏ����ł��邪�A�u���������聁�����v�̐��䂪�ǂ̒��x���܂��ł��Ă���̂��H�@���u�L���v�|�C���g�ł��ˁB�@�ƂĂ��[���A�[���ł��B
���������������� 38 cm �o�[�e�B�J���c�C��SP�̌����f�[�^�[�ł����A����SP�́A�o�X���t�^�ł����A����Ƃ����^�ł����H
L26ROY�̏ꍇ�ASEAS�����̔�r�I�R���p�N�g�Ŋ拭�Ȗ��L���r�l�b�g�Ɏ��߂邱�Ɓi����H�j�́A�u���������聁�����v�̐���ɂ����ʓI�ɓ����̂ł��傤���H
���̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/desk-tower-3way-wip-bliesma-t25b-eton-3-212-seas-l26roy-hypex-pe-boxes.21039/
�Ŗ{�i�I�Ɏ��쁕�]�����Ă��� headshake����Ƃ͏W���I��ASR�̂o�l�l�ԘA���V�X�e���ňӌ��������Ă���Œ��Ȃ̂ł����A�ނ� L26ROY �� 35 Hz - 500 Hz���\�ɍ��ꍞ��ł���A�傢�Ɋ��߂Ă���܂��B�܂��A����͋��R�ōK�^�Ȉ�v�Ȃ̂ł����A�ނ́i���j�~�b�h�����W�ɂ́A�Ȃ�Ǝ��Ɠ��������́i���ł����E�ō����x���́jYamaha�x�����E���h�[���� 500 Hz �N���X�Ŏg���Ă��܂��B
���{�ł� L26ROY ���g���Ă�����́A�����炭�قƂ�ǁi�S���H�j�����Ȃ������ł����ASEAS���i�͂Q�C�R�̓X�Ŏ戵�����邱�Ƃ͊m�F�ł��܂����̂ŁA���̉\���͖₢���킹���ł��B�L���r�l�b�g�̎���́A�傢�ɂ�������̂ł����A���ԓI�ɂ��A���ɂ̊댯���ɂ��z�����āA�v�}�������č��ӂɂ��Ă���SP����H�[�ɂ��肢�����������A�Ɣ��f���Ă��܂��B�����ł̏��������ł̑�����\�ł��B
����Ȃ킯�ŁA�u�_�����g�v�ł��A�l���I�� �uL26ROY in ���L���r�l�b�g�v �������Ă݂悤���A�Ǝv�Ē��ł��B�����Ă݂āA�����_���Ȃ�A�Q�K�̃I�t�B�X�ŕʂ́i���K�́H�j�}���`�V�X�e���̍\�z�Ŏg���Ă݂邱�Ƃ��ł������ł����B�B�B�B
�������Yamaha 30cm�����̂܂܈ێ�����̂ŁA�A���v�� SP-A �� SP-B �ŏu���ɐ�ւ��Ĕ�r�����ł��邵�A�W���Y�ƃN���b�V�b�N�i�����ς炱����ł��j�Ő�ւ��Ďg���̂��ꋻ���Ɩ��z���Ă���܂��B
�����ԍ��F24476421
![]() 2�_
2�_
BOWS����
headshake����ɁA�ނ� �uL26ROY in ���L���r�l�b�g�v�ŁABOWS����Ɠ��l�́u1 kHz 10 waves�v�ɂ�錸�������̑��������Ă��炦�Ȃ����낤���A�Ƃ��肢���܂����B�ނ́A���\�A���̎�̑��肪�D���ŁA���ӂȗl�q�ł��̂ŁB
�������茋�ʂ����܂�����A�����ł����m�点���܂��B
�����ԍ��F24476920
![]() 1�_
1�_
����A�l���Ă݂�ƁAL26ROY �̏ꍇ�́A 30 Hz�`500 Hz �]�[���Ŗ炷�̂ŁA���������𑪒肵�Ă��炤�Ȃ�A 300 Hz 10 waves ���K�����A�ł��ˁB���̎|�Ahaeshake����֒����̘A�������܂����B
�����ԍ��F24477036
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
>�����AL26ROY���r�I�R���p�N�g�Ȗ��L���r�l�b�g�i���w�E�̂悤�ɂ��ꂪ�D�܂����I�j�Ɏ��߂āAYamaha 30cm�E�[�t�@�[�Ɛ�����ւ��Ďg����悤�ɂ����ꍇ�A���܃W���Y�Ȃǂ��ۂɁA���Ȃ��Ƃ��A�u�����́i�H�j�vYamaha 30cm �E�[�t�@�[�������C�悭���Ă���邱�Ƃ����҂��Ă���A�ƌ��������x�̑��v��ł��B
�@�����䂤�p�r�����̃��j�b�g�Ɍ����܂��ˁB
>���������������� 38 cm �o�[�e�B�J���c�C��SP�̌����f�[�^�[�ł����A����SP�́A�o�X���t�^�ł����A����Ƃ����^�ł����H
�@�悭���ĂȂ������̂ł����t�����g�Ƀo�X���t�|�[�g�͂���܂���ł����B
�@�y��p��38cm���j�b�g2�{�� 300�`400L���x�̑傫�Ȕ��ɓ��ꂽ���̂ł��B
�@�\�[�X��1KHz�̃T�C���g�Ȃ�Ł@����/�o�X���t�ǂ���ł����܂�e���Ȃ��ł��ˁB
>���ӂɂ��Ă���SP����H�[�ɂ��肢�����������A�Ɣ��f���Ă��܂�
�@���̕����ǂ������ł��ˁB
�@�������肵���������͍̂����܂�܂��B
�@�������A�o����@�����Ȕ��ɓ����Ɣw�ʂ̉������オ���Ĕw�ʂɕ��˂��������R�[�����đO�ɏo�Ă���̂Ł@������x�͗e�ς��������ق����ǂ��ł��B
�@�ቹ�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��w�ʈ���������Ӗ��Ńo�X���t�\���ɂ��ā@�W���Ė��ɂ��o�������������b�オ�����Ă悢���Ǝv���܂��B
>headshake����ɁA�ނ� �uL26ROY in ���L���r�l�b�g�v�ŁABOWS����Ɠ��l�́u1 kHz 10 waves�v�ɂ�錸�������̑��������Ă��炦�Ȃ����낤���A�Ƃ��肢���܂����B
>30 Hz�`500 Hz �]�[���Ŗ炷�̂ŁA���������𑪒肵�Ă��炤�Ȃ�A 300 Hz 10 waves ���K�����A�ł��ˁB
�@�ǂ�������Ă݂����ł��ˁB
�@��Ԃ͂���قǕς��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@���̎�̃e�X�g���ƁA���A�M����1KHz���낤���A200Hz���낤���A���M���ɂȂ������ƂŁ@���������Ă����U���ƐU���n���̂̌ŗL�̐U���̍����ɂȂ�̂ŕȂ��������Ėʔ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24477759
![]() 2�_
2�_
BOWS����
�ēx�A�ēx�̂��ԐM�A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�S�ė����ł��Bheadshake���猸�������f�[�^�[�����܂�����A���m�点���܂��B
omicron�́A�܂��܂��f�����m��܂���B
���ꂮ������f���ꂸ�A���S���m�ۂ��A�N���X�}�X�ƐV�N�����}���������B
����Ƃ��A��낵�����肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24477795
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����
��̂������̏������݂̉����ł����A�Y�t�悤�ȑO�ʃp�X���t�Q�|�[�g�̐v���A�^���Ɍ������ł��B
������̃|�[�g���^�C�g�ȃl�W�~�߃L���b�v�ŕ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��܂��B
���̃��X�j���O���̊ϓ_����A�w�ʃo�X���t�|�[�g�́A�������Ă��܂��B�|�[�g����̕��ˁi���ɕ��艹�H�j�͉\�Ȍ�����������̂ŁA�����w�ʂւ̌���t�F���g��E�[���z���ނ́A�K�ɐݒu��������ł��B
�Q���ڂ̑z��ʐ^�̂悤�ɁA�X�O�x���Ƃ̉�]�z�u���������Ƃ��ł��܂����A���A�Q�|�[�g�S�J�A�P�|�[�g�̂݊J���A�P�|�[�g�J���Ȃ�����܂��͊O���H�㑤�܂��͉����H�A�ȂǂȂǁA���낢���r�������\�ɂȂ�܂��B
�������A�㗬��EKIO�� 30 Hz�`500Hz �̃N���X��EQ�́i���j�A�_��ɒ����\�ł��B
���L�̋��勭�̓T�u�E�[�t�@�[���A���Ȃ��Ƃ� 15�`40 Hz �̈�ŁA�p�����p���܂��B
����ŁAL26ROY �� Yamaha 30 cm ���A���낢���r���āA�����V��ł݂悤���Ǝv�Ē��ł����A�\�ł�����ӌ��Ղł���K���ł��B
�����ƁA�O���� W330��H400xD420 mm ��z�肵�Ă���A�d�ʂ͕Е������� 25�`30 �����@���l���Ă��܂��B�������A���i28 mm���H�j�œ����̋����t���[�����ݒu���܂��B
�����ԍ��F24483836
![]() 0�_
0�_
���̗\�z�i�q���H�j�ł́A���̑z��}���x�X�g�ł͂Ȃ����ƁB�B�B�H�H�H�@�������́A�����Ŏ����̎��Ŋm���߂�ق����@�͂Ȃ������ł��ˁB
�����ԍ��F24483859
![]() 0�_
0�_
���̃f�U�C���i�v�j���������Ă���܂��B���s�� 415 mm ��z�肵�Ă���܂��̂ŁA�قڗ����̂ł��B���́A 35 mm�ȏ���l���Ă���܂��B �����p�̉\�����l�����āA45 mm ���Ă����SP�H�[�������܂��B
�����ԍ��F24496410
![]() 1�_
1�_
�����G
http://www.troelsgravesen.dk/TJL3W-John.htm
�ŁAL26ROY ���i�����Ƃ���j���̂S�O���b�g���L���r�l�b�g��DIY���삵�Ă�����L���������܂����B
> So how does it sound? All told very well, the bass is very tight with no boom and I can now play Hot Chip�fs �gComing On Strong�h CD without having to worry that the W18E001�fs cones popping out of their cores...
�Ə�����Ă��܂��̂ŁABOWS��������w�E�̂悤�ɁA���ɂ��_���s���O���A�s���ቹ�̌����ɂ����ʓI�ɓ����Ă���̂����m��܂���B
�����ԍ��F24498582
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�X�s�[�J�[�Ɏ��������悤�ł���
�������V�X�e���S���ւ�������������Ă͂������ł��傤
NS1000�ƃT�u�E�[�t�@�[�ATW�AST�Ƃ��łɂ��Ȃ�̐�L�e��
�����J�X�^���ƂȂ�Ɣ������Ńy�A20���~���炢�s������
15�C���`�ʂ̑�^SP�ɂ��āA�l�b�g���[�N��DAC8PRO�ʼn����ł����
���F�����������j�b�g�Ƀ}���`�A���v�̃m�E�n�E�Ő����̉\�������܂�܂��B
��������ł���A15�C���`�Ƒ�^���Ƀz�[��SP�̃}���`���悢��������܂���
�����
L26ROY�͐U���d����\���ŁA�p���[���Ԃ�����Ŏg���J�[�X�e�����̂悤�ȋC�����܂��B
NS1000��90dB/W�ł��Ɣ\��������500�g���N���X�Œ��ቹ������܂�
�d�����U���͑喡�ɂȂ肪���A�p���[����Ȃ��ƌ��C���Ȃ��A
�����ƃf�B�X�R�̂�̂悤�Ȃ̂�����܂��̂�
�����ԍ��F24511853
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
���v���Ԃ�ł��B�R�����g�A���肪�Ƃ��������܂��B
BOWS������AL26ROY �̐U���n�̏d���ƒ�\���ւ̌��O���f���Ă���܂��B
���́A�����A�ēx�A NS-1000/NS-1000M �̌X��SP���j�b�g�AJA-3058(A), JA-0801, JA-0513 �̓�������ɐT�d�ɒ��ߒ����āA���炽�߂Ċ��S�ɒ^���Ă���܂��B
https://jp.yamaha.com/files/ocp/ja_jp/products/audio-visual/special/hifi-history/speaker/ns_1000m_catalog.pdf
���E�̃T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000�i���}�n�łQ��̃I�[�o�[�z�[���ς݁j�ABe-�~�b�h�����W(JA-0801)�ABe-�c�C�[�^�[(JA-0513)�A����уX�[�p�[�c�C�^�[(FOSTEX T925A) �́A���݂ł����ɉ����ŁA���� JA-0801 �� 500 Hz - 6000 Hz �̍����]�T�ŃJ�o�[����ɂ߂Ē�c�݂ȃ~�b�h�����W�Ƃ��āA���ł��j��ō��̃��j�b�g�i�̂ЂƂj�ł���Ǝv���܂����AASR Forum �ł���ɂ��̂悤�ɕ]������Ă��܂��B
����A30 cm�E�[�t�@�[ JA-3058 �́A���ł��\���Ɍ������Ă���̂ł����A�N���b�V�b�N�n�ł͉��̕s�����Ȃ��̂ł����A���ܒ����W���Y�i��� Karel Boehlee Trio�j�ł͏��X�́u����ꂳ�܁v���͔ۂ߂��A���������^�C�g�Ńr�r�b�h�ȉߓn�������~�����Ȃ����܂��B
����ŁA���̂悤�ȑS����ւ�������ɓ����Ă͂���̂ł����A���̑O�ɁA�E�[�t�@�[�������������āA�V��ł݂����A�Ƃ����킯�ł��B
�]�k�ł����A����A�_�����g�� FOSTEX�Ђ֓d�b���A�P�X�X�S�N�����łP�X�X�U�N�i���Ǝv�����L�����B���j�ɍw�����Ĉ��p���Ă��� T925A �̃I�[�o�[�z�[�����\���ǂ����f�����Ƃ���A�Ȃ�Ɓu�������\�ł���I�v�Ƃ̂��ƂŁAT925A �Q�{����@�����A�P�T�ԂŊ��S�I�[�o�[�z�[������Ė߂��Ă܂���܂����B���炭�G�[�W���O���K�v�ł����A���̐���x�A�N�x�����܂�i�h��j�܂����B
�Ƃ������Ƃ������āA�ł�����Y�ŁA�������肵�����ŁA���[�J�[�i��o���L�x�ȍH�[�j�ɂ�钷���I�ȏC����I�[�o�[�z�[�����Ή��\�ȃE�[�t�@�[���j�b�g��I�Ԃׂ����A�Ƃ��l���n�߂Ă��܂��B
���L���r�l�b�g�\�ŁA 90 dB/W �ȏ�̔\���ŁA45 Hz - 600 Hz ���قڃt���b�g�ŁA�U���n���y���āA�O�� 415 x 415 x 415 mm�@���x�i���e�� 37 - 41 ���b�g�����x�j�̓����L���r�l�b�g�Ɏ��߂āimax.���a 28 cm�H�j�A���s����Ō������Ă݂�i�V��ł݂�j�A�A�A�A�����߂̃E�[�t�@�[���j�b�g���������܂�����A�������������B
�����ԍ��F24511922
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
���E�[�t�@�[�������������āA�V��ł݂����A
�����s����Ō����A�A�A�A�����߂̃E�[�t�@�[���j�b�g
�����A 90 dB/W �ȏ�A45 Hz - 600 Hz ���t���b�g�A�U���n���y���A���e�� 37 - 41 ���b�g�����xmax.���a 28 cm�H
���݂܂���A12'�Ȃ�ߋ��ɂ��낢�뎎�����̂ł����B
���������ʂ悩�����͈̂ӊO�ɂ��t�������W��JBL E120-8�ł����AD130��15'�Ŏ����H���̂܂܂�12'�A�t�F���C�g�ɂȂ���D��E�ɂȂ������f���ł����B�I�N�Ō������܂���3�N���炢�O�̓y�A3���~�ʂ������̂ɁA����1�ł��̂��炢�A���x�̂悢�͖̂�����������܂���B����100���b�g���Ȃ̂ł�����ƍ����܂���ˁB
dualazmak����̏ꍇ��SW��100Hz�܂Ŏg���̂ł���AEKIO�ŕ����̂�45 Hz -600 Hz�t���b�g�łȂ��Ă��悢�̂ł́H
�d�����R�[����fo�������ĒႢ���g���̋��U�Ńu�[�X�g�����ቹ���o�����߁A�o�[�^�[�͉��݂̓��A�𑜊��̒ቺ�B
EKIO�͎����グ������̂ŁA�y�����\���ȃE�[�t�@�[���g���܂��B
�V��ł݂�Ȃ�APA�p���L�x�ł��i�������ł��A���݂܂���j
https://www.soundhouse.co.jp/material/eminence/
�_�C�J�X�g�t���[����50���b�g�������ƁA���̕ӂł��傤
�i�����l�܂�\������A��C�������͕K�v��������܂���j
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/167484/
�����ԍ��F24513683
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
���肪�Ƃ��������܂��B
��قǂ܂ŁAEminince ���W�Ȃǂŕ����Ă���܂����B
https://www.soundhouse.co.jp/material/eminence/
���̂悤�ɁA���̊�]�����Ƀ}�b�`����ׂ��A���ł��g���āA���Ȃ��Ƃ� 100 - 600 Hz �����������t���b�g�ŁA8���ŁA 92 dB/W�ȏ�ŁA�ƍi�荞�ނƁA�قڗB��A�����������������@KAPPA PRO-10A ���Y������悤�ł��B
�W���Y�i���ɃL�b�N�h�����Ȃǂ̍Đ��j���ӎ�����ƁA�Ȃ�ׂ� 60 Hz ������܂ł͉ߓn�����ɗD�ꂽ�E�[�t�@�[�ōĐ����A �T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000�iYST�Ƃ����Ă��o�X���t�\���ł��̂ŁA�ߓn�����͕K�����������ł͂Ȃ��j �ɂ́A15Hz �` 45 Hz��S������������ł��i -24 dB/Oct �̓����}�X�n�C�J�b�g�� -12 dB/Oct ��EKIO��XO�n�C�J�b�g�j�B
�܂��A�ꕔ�̃W���Y�Đ��ł́AYST-SW1000 ���g��Ȃ����Ƃ��z�肵�Ă���܂��B���̍ۂɂ́A�E�[�t�@�[�� 50 Hz - 110 Hz ������́AEKIO ��EQ �ŁA���������グ�邱�Ƃ����e���Ǝv���Ă���܂��B
���܁A���炽�߂� SEAS XM001-04 L26ROY �̎d�l�G
http://www.seas.no/images/stories/extreme/pdf_datasheet/L26ROY-XM001-04_Datasheet_v2.pdf
���ڍׂɒ��߂Ă���܂��B
�m���ɐU���n��118 g �Ə����d���A���x�� 87.0 dB (2.8V,1m) �� NS-1000 �� JA-8053 30cm �� ��92 dB/W �ɏ������܂����A�}�O�l�b�g�� 1.2 T �Ŕ��ɋ��͂Ȃ̂ŁA�A���v�����iYamaha A-S3000�j�ŒP�Ƌ쓮����Ȃ�A5dB�̊��x���́A���e���H�i�\���ɕ₦�邩�H�j�ƍl���܂����A���̂�����̊��x���́A�ǂ��Ȃ̂ł��傤���H�@�������A4���Ȃ̂ŁA8���� JA-8053�@�Ɠ��̒������Ŕ�r����̂́A���Ȃ荢��ł��B�@����ŁA55 Hz �` 450 Hz �̑S��łقڃt���b�g�ł��邱�Ƃ́A��͂�A�u��������v�v�f�ł��B
PA�I�ɑ剹�ʂŎg���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��p�p���[����l 250 W �́A�ƒ�HiFi�p�r�ł͏\�������邭�炢�̗]�T�d�l���Ǝv���܂��B
���ŁA��C���_���s���O�i�Ɠ����z���ށA�t�F���g��E�[���j�����܂��@�\��������A�������� DIY���p��ŕ���Ă���悤�ɁA���������܂Ƃ��ȉߓn����������ꂻ���ɂ��v���܂����A���̕ӂ�́u�l���o��I�v�ŁA���ۂɂ���Ă݂Ȃ��ƕ�����܂���A�A�A�Ǝ��o�͂��Ă���܂��B
�܂��܂��A�Y�܂����������Ă���܂��B
�����ԍ��F24514389
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
��5dB�̊��x���́A���e���H�i�\���ɕ₦�邩�H�j
�d�C�I�ɂ͎����オ�邯��ǁA�����̂悳�A�͋����݂����Ȃ��͕̂₦�Ȃ��P�[�X�����邩������܂���B
���̃��j�b�g�Ƃ̂Ȃ���Ŕ��f����Ƃ悢�ł��傤�B�����͏グ���艺����������Ղ������܂������B
���u�l���o��I�v�ŁA���ۂɂ���Ă݂Ȃ���
EKIO�͏_�������̂ŁA����Ȃ�ɂ��������ł�
���܂��܂��A�Y�܂�����
�y�����Y�݂ł��ˁAdualazmak����Ȃ�A�ǂ̃��j�b�g�ł��A�͂������o�������ł��B
�������A�n�}��Əꏊ�����܂��A�����̓E�[�t�@�[�����ł����Ȃ�̖{�������܂����B
�茳�Ɏc���Ă���̂����ł�4�Z�b�g16�{��15�C���`�����u�ɁA���ɂ��z�[����~�b�h�o�X�Ƃ�
���ꂼ������Ⴄ�̂Ŏ��ւ��Ċy���ނ̂�����ł��B
JBL��TAD�̑�^�X�s�[�J�[����������̂͑�ςł����A���j�b�g�Ȃ�z�C�z�C����ւ����܂��B
�ƂĂ������ŋ����Z���ɂ҂�����
����̏ꍇ�A�ŏI�I��1�{��5way�Ƃ��S�[�������߂ă��j�b�g��I��ł������������_���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24515048
![]() 2�_
2�_
�����ɂ悵����
��r�V�~�����[�V�����}�܂ō쐬���������A���ӂł��B
�����A�l�X�� SLP�}����ʃL���v�`������jpg�摜�����A�c���X�P�[�������킹�Ĕ�r���邱�Ƃ��悭����܂����A���̂悤�ɂ��܂��d�˂Ă݂�ƒ������@�ւ̓W�]���J���܂��ˁB
���d�C�I�ɂ͎����オ�邯��ǁA�����̂悳�A�͋����݂����Ȃ��͕̂₦�Ȃ��P�[�X�����邩������܂���B
�m���ɁA kick-up �� fade-out �Ƃ����ߓn�����̌��ケ��������̍\�z�̎�ړI�ł��̂ŁA���̓_���u�L���v�ł��ˁB
Yamaha 30 cm JA-8053 ��SPL�}�� L26ROY ��SPL�}�̏d�ˍ��킹�ȂǁA����Ɍ������Ă݂܂��B
EKIO �̔��ɏ_��ȃf�W�^�����x���ł�XO/EQ����ъe�`�����l���̃f�W�^���Q�C���ݒ�͂��������ɋ��͂ł����A�����āA���̏ꍇ�́A�eSP���j�b�g���쓮����A���v�� HiFi�O���[�h�̂��Ȃ苭�͂Œ�c�݂ȁu�C���e�O���[�e�b�h�i�v�����C���j�A���v�v���g���Ă���̂ŁA�����̃{�����[���i�Q�C���j�ł��������\�ł��B�@�����i�K�ł́A�A���v�iA-S3000�j�̒��g�[���R���g���[���[�Ŕ��������Ă݂āA�悳�����Ȑݒ肪������A�����������EKIO�ŁA�f�W�^�����x���ōČ����邱�Ƃ��e�Ղł��B
�������ADAC8PRO �̃v���A���v�@�\�ɂ��`�����l���Ԃ̉ϑ��Q�C���ݒ�i�L�������I�j���K�v�ɉ����ď_��Ɏg���܂����A�����������EKIO�ݒ�ōČ��\�ł��B
�ł��A���̒ʂ�A�E�[�t�@�[���������ł��A�D���ɓ��ݍ��ޗ\��������܂��i�j�B
��x�ɕ����̗v�f��ύX����ƍ������������Ƃ́A�ߋ��̌o��������Ɋ����Ă���܂��̂ŁA����܂ł� step-by-step ��`�͌������܂��B
�������ݍ��ނƂ��Ă��ASP�Q���܂ތ���̃Z�b�g�A�b�v���������A�u�V�E�[�t�@�[�{�L���r�l�b�g�v �� Yamaha A-S3000 �� SP-B �Ɍq���ŁASP-A��Yahama JA-8053 �Ɣ�r���������������邱�ƁiEKIO�ݒ���܂߂āj����n�߂�ׂ��A�Ɩ��z���ł��B
����ŁA�u�E�[�t�@�[�{EKIO�ݒ�t�@�C���v���A�N���V�b�N�n���y�ƃW���Y�y���y�Ő�ւ��Ė����ł���Ȃ�A�u����ł悵�I�����܂ŁI�v�Ǝ�������o����A�K�{�ł��ˁB
���ɂȂ邩���܂߂āA�܂��܂��\�z�i�K�ł����A�������ݍ���A�����ł��AASR�X���b�h�ł��A���m�点�����L�����Ă��������܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B����Ƃ��A��낵�����肢�\���グ�܂��B
�I�~�N�����́A�܂��܂����̂��m��܂���B�@���f���ꂸ�Ɉ��S���m�ۂ���āA�ǂ��V�N�����}���������B
�����ԍ��F24515164
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�@L26ROY�͗ǂ��X�s�[�J�[���Ǝv���܂����A�W���Y�����߂��Ă̂������������Ă܂��B
�@�����ɂ悵���w�E����悤�Ɂ@�W���Y�̃h������E�b�h�x�[�X�̃p���V�u�n�̒ቹ�͂ǂ������ƌ����� �{����100�`200Hz�����肪�[�����Ă��邱�Ƃ��d�v�Ł@���ۂɕ����Ă݂�ƐU���n���d����fo�̒Ⴍ�Ĕ\�����Ⴂ�X�^�W�I���j�^�[�p�̃E�[�n�[�����@�U���n���y���Ĕ\�����ǂ��y��n�̃E�[�n�[�̕����������ł��銴�������Č����Ă���Ǝv���܂��B
�@�l�͎��g�������̃t���b�g�Ȃ��̂ɋ����������Ƃ������A�ςɗ��l�߂Ńt���b�g�ɂ������͕̂����Ă��Ċy�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�@�N���V�b�N�̂悤�Ɏ������������ăI�P�S�̂̃o�����X�����Ă��邱�Ƃ���̉��y�Ȃ�ǂ���ł����A�y�킪���Ȃ��ā@�����Ԃ������W���Y�̂悤�ȃW�������́@�����̗ǂ��ቹ���~������˂��Ǝv���܂��B�N���V�b�N�̂悤�ɕ����̃R���g���o�X��I���K���Œቹ�̊���������Ă���Ȃ�Ƃ������A���������{���̒ቹ�͂قږ����W�������Ȃ�Ł@����ό����Ă�X�s�[�J�[���Ⴄ�ȂƎv���܂��B�@
�@�]�k�ł����A���܂ň�ԁ@�����̗ǂ��ቹ�����̂��}�[�`�����[�K���̃R���f���T�^�̃E�[�n�[�ł����B���̃o�b�t���^�Ȃ�Ł@100Hz�ȉ��ȂS���o�Ȃ��̂ł����A�U���n�����̂������y���ā@�����������āA�������悭�A�ቹ�̃f�B�e�B�[�����o�Ă��邱�Ƃ��悭�������āA���̌�@JBL4343�݂����ȁ@�d�����U���n�̃E�[�n�[�̃X�s�[�J�[��������A�ቹ�������e���|�x��ā@�f�B�e�B�[�����ׂ�ā@�����Ȃ�h�J���ƈ������ł��郊�j�A���e�B���c���������܂����B
�@�y��n�̃E�[�n�[���ā@�R���f���T�^�ɋ߂��Čy�������o�Ă����Ńp���V�u�Ȓቹ�Ɍ����Ă��܂��B
�@�y��n�̃E�[�n�[���������ɂ́A�w���������Ȃ����ƂƁA�����炢�U����ʂ��Ĕw�ʂ̉��������Ă��Ȃ��悤�Ɂ@��e�ʂ̃G���N���[�W�����K�v�Ȃ̂Ł@dualazmak����̗v�]�ƍ���Ȃ��Ǝv���܂����A���e�ʖ��Ōy���e�ޒቹ���o��Ƃ�������l�͎������킹�Ă��܂���B
�@�M�^�[�A���v�̂悤�Ɍ�ʊJ���^�Ńf�J���y��p�E�[�n�[��炷�ƈĊO�s���邩���Ǝv���܂��B
�@�ȑO�A�F�l��45cm�E�[�n�[x2���@�ŏ����ʃo�b�t���Ŗ炵�ā@���Ȃ蔗�͂�����ł���y��������������Ł@���Ȃ����Ă̂��s���邩������܂���B
�@�ǂ����l�����܂Ƃ܂��ĂȂ��ā@���킷�悤�Ȃ��Ƃ������Ă��݂܂���B
�����ԍ��F24516539
![]() 2�_
2�_
dualazmak����A�����́B
�Ȃ��ASEAS L26ROY�ɂ�������Ă���̂��킩��Ȃ��ł��B
Madisound �ł́A�E�[�t�@�[�ł͂Ȃ��A�T�u�E�[�t�@�[�ɕ��ނ���Ă��郆�j�b�g�Ȃ̂ŁA
500Hz�܂Ŏ�������A���ʂ̃E�[�t�@�[�Ƃ��Ďg���͉̂����I�ɖ���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���l�ɁAPA�p�̃��j�b�g���A�����Ƃ��Ă͂܂����������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-10-subwoofers/seas-l26roy-10-subwoofer-d1001-04-4-ohm/
SEAS��Web�ł��AExtreme Woofers�̂Ƃ���ɂ́A
>Welcome to our SEAS Extreme (sub-) woofer product page.
�Ɗ��ʕt���ł͂���܂����u�T�u�E�[�t�@�[�v�Ə�����Ă��܂��B
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=category&id=97&Itemid=603
SEAS�őI�ԂȂ�A��͂�26cm������ł����AExcel�V���[�Y�̕����������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
SEAS Excel W26FX-001
https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-10-woofers/seas-excel-w26fx-001-e0026-10-aluminum-alloy-cone-woofer/
Excel�̃��j�b�g���g���ƁA�s��2way�Ńy�A100���O��Ƃ��ɂȂ�̂ł����A
W18��W16�͎����Ă܂����A�������ɉ��͎���������ėǂ��ł��B
W26��W18�Ȃǂƈ���āA����a�̂��߃A���~�}�O�l�V�E�������̂悤�ł��̂ŁA
�����ǂ�����Ă���̂��͂킩��Ȃ��ł����A�V���[�Y�Ƃ��ďo���Ă���̂ł�����A
�����ɂ͈��ȏ�̂��̂͂���̂ł͂Ȃ����Ƃ͎v���܂��B
W26FX001
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=362:e0026-08s-w26fx001&catid=49:excel-woofers&Itemid=359
W18EX001
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=357:e0017-08s-w18ex001&catid=49:excel-woofers&Itemid=359
�����ԍ��F24516692
![]() 2�_
2�_
blackbird1212����ABOWS����A�����ɂ悵����
���X�̋M�d�Ȃ������A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B
�{���̌ߌ�܂��͖����A����̕��j�i�āj�Ȃǂɂ��ĉ��������Ă��������܂��̂ŁA����������낵�����w���̂قǁA���肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24517113
![]() 0�_
0�_
blackbird1212����ABOWS����A�����ɂ悵����
SEAS XM001-04 L26ROY �ɏ��X��������Ă����̂́G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/desk-tower-3way-wip-bliesma-t25b-eton-3-212-seas-l26roy-hypex-pe-boxes.21039/
�� headshake���狭�����߂�ꂽ�o�܂����������߂ł��B
�������Ȃ���A���̃X���b�h�ŊF����O���җl����̋M�d�Ȃ������i���ӂł��I�j�āAL26ROY�ւ̂���������U�̂ĂāA���j���Ċm�F�A�č\�z���邱�Ƃɂ������܂����B
�ȉ��ɗv�_���܂Ƃ߂Ă݂܂��B
�P�DSP�Q�̑�����ւ��ɂ́A�܂��˓����Ȃ��B
�Q�D�i����Ȃ��DIY�\�Z����������̂ŁI�j�N���V�b�N�A�W���Y���킸�A�S�Ẳ����Đ��ŁA�����鉹���v�f�Łi���̎�ϓI��r�����Łj���݂� JA-8053�𗽉킷�� 50 �` 500 Hz�̍Đ���ڕW�Ƃ���B�������A��p�A���v�ŁALC�l�b�g���[�N�Ȃ��ŁA�����쓮����B
�R�D���݂̃Z�b�g�A�b�v���������AYamaha 30cm JA-8058 �Ɣ�r�������Ȃ���V�E�[�t�@�[��]������B�ЂƂ̗v�f������ύX������j���������A�E�[�t�@�[�ȊO�ɂ͈�̕ύX�������Ȃ��B�i�T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000�ABe-�X�R�[�J�[ JA-0801�ABe-�c�C�[�^�[ JA-0513�A�X�[�p�[�c�C�[�^�[ T925A �́A���ꂼ��ꑮ�A���v�쓮�ňێ�����B�j
�S�D�C���e���A���Ϗ�̗v������сi�f�O�����ꍇ�Ɂj�ʕ����i�Q�K�I�t�B�X�̕ʃV�X�e���j�ł̗��p�\�����l�����A�I�[�v���o�b�t���^�ł͂Ȃ��A�L���r�l�b�g�^�̍\���Ƃ���B
�T�D���݂̃V�X�e���Ƃ̊O�ϓI����ѕ����I�i���@�I�j�}�b�`���O���l�����A�L���r�l�b�g�O���̏���́AW415 x H470��D415 mm�Ƃ���B30 mm���{�[�h��p����ꍇ�A���e�ς͍ő�Ŗ�50�k�ƂȂ�B�i25 mm �{�[�h�Ȃ�� 55�k�m�ۉ\�B�j
�U�D�����邱�Ƃ��\�ȃo�X���t�|�[�g�i���a50�`80 mm�A����250�`350 mm�H�j��O�ʂɂQ�|�[�g�݂���BSP�w�ʂ���ǂ܂Ŗ� 40 cm �̋�Ԃ��m�ۂł��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�O�Z�i�O���ҁj�̂��ӌ�����������ŁA�w�ʃo�X���t�Q�|�[�g�̃f�U�C���i���\�j�����e����B
�V�D�V�E�[�t�@�[�̗v���F���x 87 dB�ȏ�A�U���n�d�� 70 g �ȉ��A���E 1.2 T�ȏ�A��p�p���[��� 150 W���x
�ȏ�̏����^�v�����l�����Ȃ���Ablackbird1212���炨�m�点����������SEAS Excel E0026 W26FX001 �i���X�����H�j�̏����߂Ă���܂����B
http://www.seas.no/images/stories/excel/pdfdataheet/e0026_w26fx001_datasheet.pdf
�܂��A�����G
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=362:e0026-08s-w26fx001&catid=49:excel-woofers&Itemid=359
�Ɍf�ڂ���Ă���60 L�L���r�l�b�g�i�|�[�g���a70 mm ����263 mm �܂��͓��a 80 mm ����352 mm�j�ɂ����鉞���f�[�^�i�Y�t�L���v�`���[�}�j�́A�Q�l�ɂȂ肻���ł��B
����50�k�e�ς̂Q�|�[�g�v�Œ��x�̉����������ł���A45�`500 Hz �Ŗ��Ȃ��g�������Ɍ����܂����A�����̉������ʕ��A�K�v�Ƃ���ΈӐ}�I�ȉ��ʂ̐ݒ�́AEKIO ��EQ�ŏ_��ɒ������邱�Ƃ��\�ł��B�i�ʑ������ɂ��e������̂ŁA�����I��EQ�ݒ�́A�Ȃ�ׂ��g�������͂Ȃ��̂ł����B�B�B�j
�܂��A�����ɂ悵��������w�E�̂悤�ɁA���x�������ƂȂ�ꍇ�ɂ́A�E�[�t�@�[�ȊO�̃Q�C���� EKIO�̑ш斈�̃Q�C���ݒ�i�܂��� DAC8PRO�v���A���v�@�\�A�܂��͊e�A���v�̃{�����[���^�Q�C���j�ʼn����āA�E�[�t�@�[�ɍ��킹�邱�Ƃ��e�Ղł��B
���݁A�ʏ�́i���剹�ʁj�Đ��ł́A���� JRiver �� ��-12 dB�AEKIO�̓��̓p�l���Q�C���͍��E�Ƃ� -4 dB �ł��̂ŁA�f�W�^�����x���ł��w�b�h���[���ɂ͏\���ȗ]�T�i�}�[�W���j������܂��B�܂��e�쓮�A���v�̃{�����[���i�Q�C���j�ʒu�́A��� -17 dB �t�߁i���ɍ��\���� T925A ���쓮���� A-S301 �� -30 dB�t�߁j�ł��B
�E�[�t�@�[���j�b�g�̑I�����܂߁A�F�l�̊��݂̂Ȃ����ӌ��������Ղł���K���ł��B
�����ԍ��F24517652
![]() 0�_
0�_
�����݁A�ʏ�́i���剹�ʁj�Đ��ł́A���� JRiver �� ��-12 dB�AEKIO�̓��̓p�l���Q�C���͍��E�Ƃ� -4 dB �ł��̂ŁA�f�W�^�����x���ł��w�b�h���[���ɂ͏\���ȗ]�T�i�}�[�W���j������܂��B
�̕����ł����A���A�Ċm�F���܂����B
�|�s�����[��W���Y�n�̃n�C�Q�C���Ș^�������ł́A���̊��ɂ�����剹�ʍĐ��ł��A����JRiver �̍Đ��Q�C���͖� -24 dB �ł��B
�����ԍ��F24517852
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�悢SP�Ƃ͉����������A�����Ă��Ċy�������̂��Ǝv���܂��A
���j�b�g�^�ԂŌ�������ƌ��\���悪�q�b�g����̂ʼn��̌X�����炢�͂��߂邩������܂���B
E120-8�Ƃ�KAPPA 10pro�Ƃ�
(BOWS����̉Ƃ��Ȃ肩�Ԃ��Ă��܂��܂����j
���Ȃ�O�Ɏ��������Ă��āA���낢�����Ă݂����ʁA���ቹ�Đ��͉��y�̊j�ŁA���j�b�g�Ƃ��Ă�
12�C���`�A��100dB/W�A��100���b�g���A���肵�Ȃ����x�i�t�����g����50mm�j�����͕��s�ʂ��Ȃ����A�z���ނɗ���Ȃ�(���Ȃ�)
�A�x���g�ő������i�ቹ��L���ړI�Ƃ͈Ⴂ�A�w�������̌��j���悩�����A
���̂܂܂ł͌ÏL�����܂ǂ肾���ǁA�f�W�^���I��f���̓ʉ���������ƁA�N�Z���ۂ��������Ĕ��Q�ɔ����̌y���d�C�����ϊ��@�ɂȂ�����ł��B
JA-3058 ��12�C���`�A70���b�g�����x�i���[�J�[�͂悭�܂Ƃ߂Ă�Ǝv���܂��j
���v�]��50���b�g���i���j�b�g�e�ςƕ⋭�A�_�N�g�Ŏ����͍X�Ɍ���j��10�C���`���炢�܂ŁA�����̒ቹ���ƂȂ�ƐU���d�߂ł��ƂȂ������j�b�g���l�����A�W���Y�Ƃ����߂��Ă���悤�Ȍy���Ȕ����Ƃ͋t�����ɂȂ肻���ł��B
���N���V�b�N�A�W���Y���킸�A�S�Ẳ����Đ��ŁA
�������鉹���v�f�Łi���̎�ϓI��r�����Łj���݂� JA-�𗽉킷��
�S�Ẳ����A�����鉹���v�f(����AV�ł��ˁj
���Ȃ�n�[�h���������C�����܂��B
���N���b�V�b�N�n�ł͉��̕s�����Ȃ�
�����ܒ����W���Y�ŁA�^�C�g�Ńr�r�b�h�ȉߓn�������~����
�[���ȃ��C���@�͂���̂ŁA
����������U�̂ĂāA���F�Ⴂ�̗V�т��y���ނ̂��悢�̂ł́H
�K�v�ɂ���Ă�YST-SW1000��70Hz���炢�܂Ŏg���Ă��悢�̂�������܂���B
������Ȃ��DIY�\�Z����������̂ŁI
���������萻����������X�^�[�g���悢�����A���J������ǂ�����A���͂����\�z����܂��B
�`���o���Ă��炨���������Ȃ��ƃ��X�N��
�����ԍ��F24518416
![]() 2�_
2�_
�����ɂ悵����A�F����
���肪�Ƃ��������܂��B
��A���ł��ˁI�@������ƃo�^�o�^���Ă���܂��̂ŁA���ӁA���������Ă��������܂��B
�����ԍ��F24520333
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����A�F����A
���[���ȃ��C���@�͂���̂ŁA
������������U�̂ĂāA���F�Ⴂ�̗V�т��y���ނ̂��悢�̂ł́H
�͂��A��ӁAKarel Boehlee Trio �̔�r�I�g�F�n��CD�^���ƁAThomas EnhcoTrio �� flac 192 kHz �_�E�����[�h��������ׂȂ���AYamaha 30 cm JA-8053 �̒ቹ���A����͂���ł��Ȃ�̗D����̂���... �Ƃ̊���[�߂Ă���܂����B
�ЂƂ��ƂɃW���Y�ƌ����Ă��A�^���G���W�j�A�̍D�݂�e�C�X�g�ɉ����ĉ����̉ߓn�����͑傫���قȂ�A�Ƃ������R�̗v�f���ĔF�����Ă���܂��B
�߂������ɁASony Super Audio Check CD ��SP�ߓn��������g���b�N�P�S�i63Hz�`1 kHz�̃T�C���g�W�g����Ȃ�g�[���E�p�[�X�m�g[���N�^���M����]�ŁA�e���g�����ɂR�b�Ԃ̋x�~��Ԃ��͂��݁A������g���̐M�����P�b�Ԋu��3�Đ������j���g���āABOWS�����肳�ꂽ�悤�ɁA����p�}�C�NECM8000�ɂ��ߐژ^����JA-8053 �� YST-SW1000 �̉ߓn�����i�L�b�N�A�b�v�ƃt�F�[�h�A�E�g�̔g�`�p�^�[���j��������Ƒ��肵�Ă݂悤�Ǝv���܂��B
���̏�ŁA
���K�v�ɂ���Ă�YST-SW1000��70Hz���炢�܂Ŏg���Ă��悢�̂�������܂���B
���T�d�Ɍ������Ă݂܂��B
���āA�]�k�ł����A
�y�����̃v�����C���A���v�Ń}���`�A���v�V�X�e���\�z�͎ד����H�z
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924414/#23140284
�ɂď��������J�n���A�F�l�̂������Ƃ����������������n�߂��̂́A�Q�O�P�X�N�̑�A���ł����B
���ꂩ��Q�N�ԂŁA���݂̔��ɖ������ׂ��}���`�V�X�e���\�z�ɓ��B�ł������Ƃ͊����ʂŁA���ӂɊ����܂���B
�܂��Q�O�Q�O�N�S���Q���ɊJ�n���� ASR Forum �ɂ����鎄�̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�ւ̖K��{���́A�����ȓ��ɂP�O����ɓ��B�������܂��B
����Ƃ��A��낵�����t�������A���w���������̂قǁA���肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F24521304
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����Ablackbird1212����
�މ�V�N�A�{�N����낵�����肢�\���グ�܂��B
Yamaha 30 cm JA-3058 �E�[�t�@�[ in NS-1000 ���L���r�l�b�g�i�A���v�����쓮�j����� Yamaha�T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000 �̉ߓn�����𑪒肵�Ă݂܂����B���ׂčČ����͊����ł��B
������ƖZ�������Ă���̂ŁA�ڍׂ͏ȗ����܂����A�F�l�̖ڂɂ́A��ڗđR���Ǝv���܂��B
�A���v������ JA-3058 �́A�\�z�����ǂ�����....
�����ԍ��F24523988
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�Ȃ��Ȃ���������Ȃ��ł���
���o�͂̉����x�������ꂽ�炢�����ł��傤�H
�����ԍ��F24524825
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����A�F����A
�������߂�lj����Ă��܂��̂ŁA�Y�t�摜�������������B
�����o�͂̉����x�������ꂽ�炢�����ł��傤�H
������A��������͂��Ă���̂ł����A���̏ꍇ�AJRiver��ASIO4ALL��EKIO��ASIO4ALL��DIHIHNK ASIO��DAC8RPO �ōĐ����Ă��܂��̂ŁA�e���Ƀo�b�t�@�i���C�e���V�[�j������܂��B
�܂��A�^���͍Đ�PC�Ƃ͕ʂ�2��ڂ�PC�� Adobe Audition 3.01 �ōs���Ă���A������ł� TASCAM US1x2HR �̓��o�̓o�b�t�@��Widnows �� Audition 3.01 �̃o�b�t�@�i���C�e���V�[�j������܂��B
�e�o�b�t�@�T�C�Y�́A�\���ȗ]�T������Ă���̂ŁA�S�́i20Hz�`25 kHz�j�Ƃ��Ă�PC�Đ���������x���ł���ΑS�����͂Ȃ��A������\�Ƃ���悤�ɗ]�T�̃o�b�t�@�T�C�Y���w�肵�Ă��܂��B
���̏������ŁA����ɃA���v��SP�̒x���̋͂��ȍ����A������ƌ��o�ł��鑪��n�������ł��邩�A���s���낵�Ă���i�K�ł��B
�������A�ǂ����̎��g���̍��������A���v�A��������SP�ŁA���ΓI�Ȋ�_��݂��āA��������̑��ΓI�ȉ������ԍ����v������悢���Ƃ͕������Ă���̂ł����A���̌��ʂ͂����܂Ŏ��̃V�X�e���ƃZ�b�g�A�b�v�ŗL�̑���ɂȂ�܂��̂ŁA���܂艞���x���̑���ɍS�邱�Ƃ͈Ӗ����Ȃ��̂ł́A�Ǝ��⎩�����Ă���܂��B
�ȑO���b�������悤�ɁASP���j�b�g���݊Ԃ̒x���i�������������j�́AREW Wavelt ��͂Ō��Ă���܂��G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/#post-370515
����
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/page-2#post-370519
���������āA�����ȉ����x������Ɏ��Ԃ������邱�Ƃ��S�O���Ă���܂��B
�����ԍ��F24524884
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�Đ��Ƙ^�����Q���PC�ɂ܂�����̂ŁA�~���������Ȃ��Ă܂��ˁB
TASCAM���Đ�PC�ɂȂ��AAudycity�ōĐ��Ƙ^�����ɂ��邾���AJRiver�̒x���͑S�ш拤�ʂ��Ǝv���̂�PC(Audycity�Đ���ASIO4ALL��EKIO��ASIO4ALL��DIHIHNK ASIO)��DAC8RPO��AMP��SP��MIC��TASCAM��PC(Audycity�^��)
���Ǝv���܂��B
�����̌��ʂ͂����܂Ŏ��̃V�X�e���ƃZ�b�g�A�b�v�ŗL�̑���ɂȂ�܂��̂ŁA���܂艞���x���̑���ɍS�邱�Ƃ͈Ӗ����Ȃ��AREW Wavelt ��͂Ō��Ă���
���Ȃ����Ƃ𐔒l�Ŋm�F�A�������j�b�g�Ԃɉ����̎��ԍ��������EKIO�ŕ�A�g�p�ݔ�����Œᒆ�����̉����x��̌ŗL�l���ς��̂ŁA�ŗL�l��������Ώۂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24525115�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
���ɒP���ŁA�������M�����̍�������n���l���Ă���Ƃ���ł��B
�Ⴆ�A
40 Hz (for SW),
200 Hz (for WO),
2000 Hz (for SQ),
9000 Hz (for YW),
13000 Hz (for ST)
�Ɂu�����Ɂv �V���[�v�ȃp���X�g�����������쐬���Ę^�����A���Ԏ����L���Ċώ@���m�F����Ƃ��B�B�B�B
Sony Super Audio Check CD �� track-8 �X�|�b�g�T�C���M���i20Hz - 20 kHz�j���g���āAAdobe Audition 3.01 ��ŃR�s�y�i�R�s�[�A�~�b�N�X�y�[�X�g�j����A����ȐM����ms �P�ʂŐ��m�ɍ��킹�Đ��m�ɍ쐬�ł��܂��B�������ԕ����L���~�b�N�X�y�[�X�o���h���쐬���Ă���A������Əd�Ȃ��Ă��镔��������肾���A���m�ɑS�ẴX�|�b�g���g�����Ɋ܂މ��������܂��B
������ꔭ�Đ��Ř^�����āA�x�ꂪ��ԏ��Ȃ��i�͂��j��13000 Hz ����̑��Βx���⎞�Ԏ���̍L����̒��x������A������x���m�ȑ��Βx���������邩���A�ƍl���Ă���܂��B�ǂ̎��g���ш�i�ǂ�SP���j�b�g�j���x��Ă��邩�́A�g�債�����Ԏ���ōׂ����ԕ�����I�����āA���̕����̎��g�����͂�����Έ�ڗđR���ƁB�B�B�B
Audition 3.01�́A���Ԏ�����ю��g�����̗����Ő��x�Ɗ��x���\���ɂ���̂ŁA�g�������Ɏv���܂��B
�����ԍ��F24525170
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
���u�����Ɂv �V���[�v�ȃp���X�g�����������쐬���Ę^�����A���Ԏ����L���Ċώ@���m�F
���Ȃ荂�x�ŁA���f����̂�����悤�Ɋ����܂��B
�ړI�͊e���j�b�g�Ԃ̉����𑵂��鎖�Ȃ̂�
�Ⴆ�E�[�t�@�[�ƃX�R�[�J�[
�܂��E�[�t�@�[�ȊO���J�b�g�A�E�[�t�@�[����500Hz�̂P�p���X�����đ��Βx�ꑪ��
���ɃX�R�[�J�[�ȊO���J�b�g�A�X�R�[�J�[����500Hz�̂P�p���X�����đ��Βx�ꑪ��
�����S�ẴN���X�I�[�o�[���g���Œ��ׁA��Ԓx��郆�j�b�g�ɍ��킹�āA�e���j�b�g�Ƀf�B���B�l�����A�E�[�t�@�[�A�X�R�[�J�[�A�E�[�t�@�[�{�X�R�[�J�[�����̔g�`�Ɉُ킪�Ȃ����m�F���ȒP�ł́H
�����ԍ��F24525362�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
�����قǁA�Y�t�̂悤�Ȏ��ԁ|�X�y�N�g���̃o���h�����Q�����쐬���Ă���܂����B
����������F�̏c���o���h�������ɑ�����g�����z�́A�����̂悤�ɓ����ł����A�ቹ�����ł͑��肵�₷���悤�ɃG�l���M�[���グ�Ă��܂��B
���̔g�`���Đ��^�����āA�^���g�`�̎��g�����̍ő�G�l���M�[���������Ԑ����A�ቹ�������Ēx�����邩�ǂ��������Ԏ��g��œ��̓p���X�i�c�ɐ����j�Ɣ�r����A�u���ΓI�Ȓx���v�����邱�Ƃ��ł������Ɏv���Ă��܂��B
���g���i�ƍĐ��A���v��SP���j�b�g�j�ɉ������u���ΓI�Ȓx���v����������ɂ́A���̕��@�Ō����I�ɂ͐��������Ɏv���܂����A�������ł��傤���H
�����ԍ��F24525399
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
���������킩��܂���
�E���Q�{�̃I�����W���A�c�����ʼn������ቹ�A�㑤�������A�Đ�����ƁA�I��������A�֍s������A���Y���ʂ��A���ԃY���œǂݎ��̂ł��傤���H
�����ԍ��F24525453�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
�^�������g�`�̉摜��ŁA�Y�t�}�̂悤�ɏk�ڂ����킹�ĂX�O°��]���������͎��g���X�y�N�g���Əd�ˍ��킹��ƁA���F�̃h�b�g�Ŏ������e���g���s�[�N�̎��Ԏ��̈ʒu����������̂ł́A�Ƃ̎Z�i�ł��B
�����ԍ��F24525455
![]() 0�_
0�_
���܂�����ł��邩�ǂ����H�H�H�ł����A�ꔭ�^�������̊ȒP����ł��̂ŁA�ߓ����Ƀg���C���Ă݂܂��B
���ꂪ�g����A���ɕ�����₷���A�u���o�I�Ɂv���Βx�����c���ł��܂��̂ŁB�B�B
�����ԍ��F24525478
![]() 1�_
1�_
2ms�ʂ̕���\������Ύg�������ł���
�����ԍ��F24525600�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����́A���r���O�����X�j���O���[�����A�ȎҒB�ɐ�̂���Ă���̂ŁA�Q�K�I�t�B�X�̃f�X�N�g�b�v�Ŏg���Ă��� Klipsch ProMedia 2.1 THX �� EKIO �őш敪�������M�������āA�����V��ł݂܂����B
�E�[�t�@�[�́A�����̂悤�Ƀo�X���t�|�[�g�t���̕ʔ��ŁA���̉��ɂ���܂��B�����������̐M����JRiver �ōĐ����AAdobe Audition 3.01 �Ř^������ƁA�E�[�t�@�[�������ΓI�ɖ� 30 ms �x�����Ă��邱�Ƃ�������܂����B
����ŁAEKIO �̃O���[�v�f�B���C�@�\�ŁA�E�[�t�@�[�ш����̎��g���̈�� 30 ms �x����������A�����̒ʂ�A���Ԏ��̐�������ɂ҂����葵���܂��B
���t�ɂ�����̂ŁA���ԕ���\�͂���قǍ�������܂��A�V���v���ŁA��ڗđR�ŁA�Č������ǂ��āA���Βx��������ړI�ɂ͎g������@���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24526223
![]() 1�_
1�_
���̃I�t�B�X�����́A�����I�ɂ̓��C�u�ŁA���s�Ζʕǂ������A�]���Ďc����������ł��̂ŁA�^���g�`���ׂꂽ�c�q�i�����ȉ~�j�ɂȂ��Ă��܂����A���X�j���O���[���́A����Ȃ�̉����������Ă܂��̂ŁA����قǂ̉��ȉ~�ɂ͂Ȃ炸�A���Ԏ����g�債�Ă� 2�`3 ms ���x�̎��ԕ���\���m�ۂł���̂ł́H�@�Ɗ��҂��Ă���܂��B
�����ԍ��F24526248
![]() 0�_
0�_
�ቹ��̐M���ł́A����ɓK�����G�l���M�[���������悤�Ƃ���Ǝ��Ԏ������ɂ��L���邱�Ƃ͓��R�ł��̂ŁA���̍L����̒��S�ʒu�������邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�܂��B�Ȃɂ���A 100 Hz�M���́A�g�̃s�[�N�Ԋu���̂� 10 ms �ł����A�A�A
�C���p���X�̎��Ԓ��S�́A8 kHz �ȏ�̏������܂Ƃ܂����X�|�b�g������ɐ��m�Ɂi1 ms���x���Łj����ł��邱�Ƃ��A���̕��@�̃����b�g�ł��B
���̃X�|�b�g�̒��S���玞�Ԏ��̐������������A�ቹ��̒x������ڗđR�ɕ�����܂����AAdobe Audiotion 3.01 �́A���Ԏ����g�傷��A������� ms �� ��s �P�ʂŃJ�[�\���ʒu�̎��Ԃ𐔒l�\�����Ă����̂ŁA���ԕ���\�͏\���ɉ҂��邱�ƂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F24526283
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�@���肵�Ă��炢���肪�Ƃ��������܂����B
�@63Hz�̔g�`�ł����A�ꕔ���Ă݂܂����B
�@30cm���̃E�[�t�@�[�Ƃ��ẮA�����オ�藧��������������ǍD�Ǝv���܂����B
�@�d���U���n�Ȃ�@����肪�x��܂��B
�@������������ǂ���ł����A�C�ɂȂ����͖̂����ɂȂ��Ă���̔g�`�ł��B
�@63Hz�Ȃ̂Ł@1�g 16msec�@������5.4m�@�������������ꍇ�Ђ��Â�Ȃ��猸�����܂��B
�@�c���g�`����63Hz�ɂȂ�͂��ł����A�c�������������ɏd�ˍ��킹�Ă݂�Ɓ@�c��������63Hz�Ƃ���Ă��܂��B
�@�l������v����
�P�D�����̎c�����d�Ȃ��ĚX������Ď��g��������Č�����B
�Q�D�쓮�͂��������E�[�t�@�[�̐U�����������̐U���G�l���M�[�ɂ��ŗL�U�����g���Ŏ��R�U�����Ă���B
�@�̕����ƍl������܂��B
10�g���ƁA�P�̐��������Ԃ̕��������Č����̂Ł@�P�`�R�g���x�Ɍ��炵���ق����ǂ������ł��B
�@�P�g���ƁA�����s�\���ɂȂ邩������܂���B
�@�T�u�E�[�t�@�[�́AYST�����ŋ��U���g���Ă���̂Ł@��������������������܂��ˁB
�@�����āA�U�����������Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B
�@�U���̃��J�j�Y���́A�����ƍl���Ȃ���f�[�^����Ă����ƌ����Ă���Ǝv���܂��B
�@
�����ԍ��F24526333
![]() 2�_
2�_
BOWS����
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�{�N����낵���I
�Ȃ�قǁA���̂悤�ɏڍו��͂ł���킯�ł��ˁB���ɎQ�l�ɂȂ�܂��B
�m���ɁA������̔g�`�́A���̂P�D�Q�D�̕������Ǝv���܂����A�ɂ������āA�������̂悤�ɃC���p���X���R�g�Ɍ��炵�āA�Čv�����Ă݂܂��B
��͂�AASR Forum �ŋ��L����O�ɁA������BOWS����͂��ߏ����̂��ӌ��₲�����Ղ��邱�Ƃ́A�吳���ł��I
���炭�i�I�j�A�U���n���d��SEAS L26ROY �ł́A�����オ����݊��ŁA�Q�D�̎c�����������邱�Ƃ��z������܂��B
��� headshake ����i�݃Z���g���C�X�j�́A���̍ň��̗����ʼn�����Q���������炵���A���̌�A���M�s�ʂɂȂ��Ă���AL26ROY�̉ߓn�����f�[�^�͖�����ł��B�������F���Ă���̂ł����B�B�B�@���̑���f�[�^�́A�Q�l�܂ł� haedshake ����֑����Ă����܂������ԐM�͂���܂���B
�֑��ł����B�B�B
ASR Forum �ŁA�ʂ̃Z���g���C�X�ߕӂ̃I�[�f�B�I���ԂƘb���Ă�����A������d�̌�A���d�����ۂɓd�͉�Ђ̃~�X�ō��d���T�[�W���������� DAC8PRO���܂ނ������̃I�[�f�B�I�@�킪�đ����������ł��B
��d�O�Ƀu���[�J�[�ؒf�A�R���Z���g����d���P�[�u�����A���d�̍ۂ������ɂ͋@��ނ𗧂��グ���ɓd�͂����肷��̂��\���Ɋm�F���Ă���ĊJ�A���ēx�̂ɖ����܂����B�C��ϓ��œ��{�ł������○�J�������Ă���A�l���ƂƂ͎v���܂���B�d�v�ȋ��P�܂����B
�����ԍ��F24526668
![]() 1�_
1�_
BOWS����
���T�u�E�[�t�@�[�́AYST�����ŋ��U���g���Ă���̂Ł@��������������������܂��ˁB
���@�����āA�U�����������Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B
����́A���Ƃ��Ă��\�z�ʂ�ł����B
���̃f�[�^�[�����Ă��܂��ƁA�T�u�E�[�t�@�[���i�T�u�E�t�@�[�����I�H�j�A����a�Ōy�ʋ쓮�n�̃T�u��p�E�[�t�@�[���j�b�g���g���āA���͂Ȑ����͂̃A���v�����쓮�ŁA���삵�����Ȃ�܂����B�B�B�B�L�����Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F24526681
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
>�m���ɁA������̔g�`�́A���̂P�D�Q�D�̕������Ǝv���܂����A�ɂ������āA�������̂悤�ɃC���p���X���R�g�Ɍ��炵�āA�Čv�����Ă݂܂��B
�@�ɂȂƂ��ŗǂ��̂ł��肢���܂��B
�@���ډ��Ɣ��ˉ�����������Ƃ�₱�����̂�
�@����Ɓ@�ǖʔ��˂̎��ԍ��́A�����ƕ����̃f�B�����W�����Ō��܂��Ă���̂Ł@���g��������Ă������͈��ɂ��������ǂ��ł��B
�@�����̖ڐ���������悤�ɍ���ł��炦�킩��₷���ł��B
�@�c�������̓X�s�[�J�[�̐U���n�ƃo�X���t�̋��U�̉e�����邽�߁A���͎��g�����ς���Ă��A�c���͓����悤�Ȏ��g���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�@�c�������̓X�s�[�J�[�̐U���n�ƃo�X���t�̋��U�̉e�����邽�߁A���͎��g�����ς���Ă��A�c���͓����悤�Ȏ��g���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�@��ʓI�Ȏ��g�������ł́@�A���T�C���g���g���̂Ł@�����������ߓn�����͕]���ł��Ȃ���Ŏ��g���������ώ��ɂ���̂ɖ�N�ɂȂ�̂͂ǂ����ȂƎv���܂��B
>����́A���Ƃ��Ă��\�z�ʂ�ł����B
�@��ʓI�ȃX�[�p�[�E�[�t�@�[�́A�f���̒ቹ��N���V�b�N�̌��y���I���K���̎��������Đ��ł���Ηǂ��Ȃ̂Ł@����ł�����ł����A�h������a���ۂ̈ꔭ�ڂ̔j�������Ɏ������鉹���ɂ͒Ǐ]�ł��Ȃ��ł��ˁB
>���̃f�[�^�[�����Ă��܂��ƁA�T�u�E�[�t�@�[���i�T�u�E�t�@�[�����I�H�j�A����a�Ōy�ʋ쓮�n�̃T�u��p�E�[�t�@�[���j�b�g���g���āA���͂Ȑ����͂̃A���v�����쓮�ŁA���삵�����Ȃ�܂����B�B�B�B�L�����Ȃ��ł��ˁB
�@
�@�ȑO�r�N�^�[�́A�^���ʂ���R��������Ă��܂����B
https://audio-heritage.jp/VICTOR/Speaker/ik-380.html
https://aucfree.com/items/f342267522
�@�����͂�38cm�E�[�t�@�[�ɑ�e�ʂ̃G���N���[�W���Ƃ����@���U�ɗ��炸���ʂ��畨�ʂ����ďo��X�[�p�[�E�[�t�@�[�ł��B
�@�E�F�X�^���̋���z�[���g���̒r�c�\���r�N�^�[�ƍ��グ�����̂Ȃ̂Ł@�h���h�������d�����ł͂Ȃ��@�����̑���������Ȃ��ƍ����܂���B
�@���݁A����ȗ①�ɂ̂悤�ȃX�[�p�[�E�[�t�@�[�̎��v�͖����ł��傤�ˁB
>��� headshake ����i�݃Z���g���C�X�j�́A���̍ň��̗����ʼn�����Q���������炵���A���̌�A���M�s�ʂɂȂ��Ă���AL26ROY�̉ߓn�����f�[�^�͖�����ł��B�������F���Ă���̂ł����B�B�B�@���̑���f�[�^�́A�Q�l�܂ł� haedshake ����֑����Ă����܂������ԐM�͂���܂���B
�@�����
�@�������̘b���Ǝv���Ă�����A��Q�������Ă�����ł��ˁB
>ASR Forum �ŁA�ʂ̃Z���g���C�X�ߕӂ̃I�[�f�B�I���ԂƘb���Ă�����A������d�̌�A���d�����ۂɓd�͉�Ђ̃~�X�ō��d���T�[�W���������� >DAC8PRO���܂ނ������̃I�[�f�B�I�@�킪�đ����������ł��B
�@�����A�|���ł��ˁB�o���Ȃ���Ηǂ���ł����A�艖�ɂ����ďW�߂Ă����@�킾�����ł��傤�Ɂ@�c�O�ł��ˁB
�����ԍ��F24526873
![]() 2�_
2�_
dualazmak����ABOWS����
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
���������Ă���g�`�ɂ��Ă�
��������5m�Ԋu�̕ǂł̒�ݔg�Ɍ����܂��ˁA
���̎��g���ł���N���Ă��銴��
�v���������Ԃ͂���܂����H
���g�����Ⴂ�̂ő�͓��
�X�s�[�J�[�̌����U���Ĕ��˂����炷
�R�[�i�[�Ɍ��߂̋z����
�����ʒu�����A���g����
�������݂�����ꏊ�Ƀ��X�|�W�ł��傤��
�Z���g���C�X�̌�
��d�Ƃ͋��낵���ł��ˋC��t���Ȃ��ƁB
���T�u�E�[�t�@�[���A
������a�Ōy�ʋ쓮�n�̃T�u��p�E�[�t�@�[�g���āA
�����͂Ȑ����͂̃A���v�����쓮�ŁA���삵�����Ȃ�
mo���y���A������Qoc�̋쓮�͂̑傫���A
���j�b�g�ɑ傫�ȗe�ς�^�����
�h�X���u���u���ł͂Ȃ��A
�����y�����R�Ȓቹ���t���b�g�Ђ˂�o����銴���B
�ቹ�͔��ŏo���̃Z�I���[�ʂ�
�A���E�[�t�@�[�ł��̂܂�20Hz�t���b�g�Ƃ����z�I������
������Ƒ傫�Ȕ��ɂȂ肻���Ȃ̂�SW�����ʓI��
�g���������悢�Ǝv���܂��B
�d�����x������SW�ɑ��Ă�
dualazmak����̌����ŃG�l���M�[�̃s�[�N������
SW�ȊO��x�������đ�����������悳�����ł��B
���̌����ŁA�f�ʂ̔g�`���X���C�X���Č�����
�����ł��ˁB
�����ԍ��F24526915
![]() 1�_
1�_
�����݂�����BOWS����ɏ����݂��Ă܂�����
���e�����Ԃ��Ă܂��ˁA���ǂ낢���B
�����ԍ��F24526923
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�����������Ă���g�`�ɂ��Ă�
����������5m�Ԋu�̕ǂł̒�ݔg�Ɍ����܂��ˁA
�����̎��g���ł���N���Ă��銴��
���v���������Ԃ͂���܂����H
�������̂����@�B�B�B�@���S�ȁu�����[�g�{���v�ŁA�����ȁu�^�Ɛl�ߕ߁I�v�A�����m��܂���B
���̃��X�j���O�\�t�@��SP�������č����āA����̌���ɔ����ǂƘL���֑����K���X���������̃h�A������܂��BSP�\�ʂ��炱�̔����ǂ܂ł̋������A�Ȃ�� 4.9 m �ł��B
���̔����ǂ̂��̃K���X�����h�A�́A�p�C�v�I���K���� 32 Hz �ቹ��剹�ʂŒ����Ƌ����ăr�r��܂��̂ŁA���̕ӂ肪�����U�ƒ�ݔg�́u���v�ɂȂ��Ă���悤�ł��B
�^���ɉ��y���ۂɂ́A���̓��e�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-636419
�̒��ŁA
"Of course, the sliding doors between the rooms are kept open during the listening sessions as shown in this photo. I often place sound absorption sponge mattress in front of the white wall and the glass door leading to the corridor."
�Ə������悤�ɁA���ǂƃh�A�O�Ɍ����X�|���W�}�b�g���X�i��150 cm ���� 240 cm�j���q�_��ɂ��Ēu���̂ł����A����̉ߓn��������̍ۂɂ́A���������Ă���܂���ł����B
�Ƃ����킯�ŁA���w�E�́u5m�Ԋu�̕ǂł̒�ݔg�v�A�Ƃ������w�E�͐����̂悤�ł��B
ASR Forum �ւ̓��e�����čđ��肷��ۂɂ́A���̒�ݔg�^���g�́u���v���\���ɎՉ����f�b�h�����A�܂��P�O�g��N�ɉ����ĂR�g��N�ł̘^�����͂�����Ă݂܂��B
���Ȃ݂ɁA�֑��ł����AASR Forum �̎��̃v���W�F�N�g�X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�ւ̖K��{�����A���̐����ɂP�O����ɓ��B���܂����B
�����ԍ��F24527567
![]() 1�_
1�_
�F����A
�X�[�p�[�c�C�[�^�[ FOSTEX T925A �̃I�[�o�[�z�[�������e�i���X�ɂ��āA������̓��e�ŐG��܂������A���C�Łu�Y��v�Ȑ��Ƀ��t���b�V�����ꂽ T925A �̋A�҂ɔ����āAT925A �ւ̓��͏������������������܂����B���̌o�܂������G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1033673
�ŋ��L���Ă���܂��̂ŁA��������������Η��������B
�����ԍ��F24527579
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�����肪�Ƃ��������܂��A�t���b�^�[�G�R�[�̓X�s�[�J�[�̐��ʂƔw�ʂ̕NJԂł������A
���˖ʂ̕ǂ͊J�������L���A�ʐς͏��Ȗڂł����A�����������Ȃ��߂�������o���̂ł��傤
������Ƃ��������p�l���ł����������Ƃ����l�i�A�������ቹ�ւ͌��݂��Ȃ��ƌ��ʂȂ�
�a���Ƃ̕ǂ��ꕔ�A����������\���ɂ��邲����������Ă�������������܂���B
���X�j���O���[���̑O��ɍL����Ԃ�����̂́A���I�ɂƂĂ��L�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24527678
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
��̑��Βx������p�̐M���ł����A��̍��}�̕����쐬�Ӑ}��������₷����������܂���ˁB
�܂��A���C�����x���M����^�����邱�ƂŁAEKIO �̃O���[�v�x���ݒ肪���m�ɁA���o�I�ɁA���f����邩�ǂ����������܂����B
�E�}�����̌��ʂł��āA�������A������ƒx�����Ă���A���o�I�ɂ��ȒP�ɉ�͂��ł��܂��B
�܂��A�F�\���K���}�ݒ�������G��ƁA�e���g���s�[�N�̉�̒��S���Ԃ̈ʒu�����߂邱�Ƃ��e�ՂɂȂ�܂��B
Adobe Audition 3.01 �Ř^�����āA�������Ă��܂��B
�߂������ɁA�ɂ�������A���C���V�X�e���ő��Βx���̗L���ƒ��x�𑪒肵�Ă݂܂��B
�����ԍ��F24527880
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
���a���Ƃ̕ǂ��ꕔ�A����������\���ɂ��邲����������Ă�������������܂���B
�����֓��ݍ��ނƁA���x�����A�Ɠ����B�B�B�B�@���낵��I
�^���ɒ����ۂɁA�Q�K�̉�������傫���ďd���}�b�g���X���R���قǎ������ނ��炢�Ȃ�A�u�܂��܂��I������Ă�́H�I�v���x�̔����ŖٔF���Ă���܂��B
�����A�ʐ^�̂悤�ɏ��Y��ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�N�b�V������A�ѕz��A�G���S���[�^�[�o�C�N�i�������y���Ȃ���R�O���� 230 Hz �ł͂Ȃ��A230 kcal���x�̊��𗬂��܂��j��A�_�E���R�[�g�Ȃ��U�����Ă�������A���˖ʂ����Ȃ��āA�z������āA�����I�ɂ͍D�܂����̂ŁB
�s�A�m�́A�A�A���������čs���͂��Ȃ̂ł����A���낢�날���āA�܂��������Ă���܂��B�^���ɒ����ۂɂ́A�傫�ȃN�b�V�����W���Ō��ՊW�̏�ƁA���̉��̒ꕔ���J�o�[���܂����A�u�܂��܂��I������Ă�́H�I�v�B�B�B�B
�����ԍ��F24527907
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�ʑ�������r�W���A���Ō���̂��������낢
������낵����A�����J�����������������B
����̐l����т����ł��B
���̗\�z�ʂ�ł����ˁB
�����ԍ��F24525453
�����ԍ��F24527926�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����X�j���O���[���̑O��ɍL����Ԃ�����̂́A���I�ɂƂĂ��L�����Ǝv���܂��B
�͂��A���̓_�́A���̉Ƃ����Ă�ۂɒf�łƂ��ď��炸�Ɂi�u�I�[�f�B�I�̂��߂��I�v�Ƃ͂��܂苩�т܂���ł������j�A�I�[�f�B�I���l���Đv���܂����B
�V��́A����قǍ����͂���܂��A�z�����ɂ����ꂽ���������ʊw�͗l������]���y�n�p�l���ŕ����Ă��܂��B����́A�Ɠ����A�C���e���A�f�U�C���I�ɑ傢�ɂ��C�ɓ���ł��B�������_���āA�̗p���܂����B
�����ԍ��F24527927
![]() 0�_
0�_
���ʑ�������r�W���A���Ō���̂��������낢
��������낵����A�����J�����������������B
���₢��A���ɊȒP�ł���B�@���z���̒ʂ�̕��@�ł��I
Adobe Audition 3.01 �Ř^�����āA�^���g�`���u����v�\�������āA���Ԏ��g�債�āA�J�[�\���ňʒu��ǂށi�J�[�\���ʒu��XY���͉�ʉ����ɐ��l�ŕ\���j�A���ꂾ���ł��B
���L���邽�߂ɂ́A�K�v�ȕ������X�P�[�����݂ʼn��jpeg�L���v�`���[���āA�p�[���[�|�C���g�Ɏ�荞��ŁA�⏕�����g���ăf�B���C��ǂݎ��l�q������������A�ł��B
���̃f�B���C����p�M���A������������A���ł������Ă��������܂��̂ŁA ASR Forum ��PM�i�l�ԘA���j�V�X�e���ł��m�点�������BPM�V�X�e���ł͓��{��ł��S����肠��܂��A�t�@�C�����L���e�Ղł��B
�����ԍ��F24527944
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�������֓��ݍ��ނƁA���x�����A�Ɠ���
�����p�l��4〜5���ł���20���~�R�[�X�ł��B
���ޑ�H����ɓ����n���A�ǔ����āA
���̂���ɂ��Ęa���ɔ�����悤�ɂ��A�z���ނ����݁A
�N���X�̕ǎ��\��Ȃ�ȒP�ł́H
���s�A�m�͖��������čs���͂�
�V���Ŏז��A���Ƃɒu���Ƃ��Ẵp�^�[������
�Ƃ�ł��Ȃ��{���{���s�A�m�ł����É�����
��������čs���܂�����B
�������ŕK�v�Ȃ�d�q�s�A�m��15���~���炢
�����t���ĂȂ��čς݁A�R���p�N�g
���Ճ^�b�`�ƌ������̂́A�����܂ł̋Z�ʂɂȂ�����
�����ւ�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24527951�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���ʑ�����
�ł͂Ȃ��A���Ԃ���ł��ˁB
�ʑ������ʑ���]�́AASR Forum �ł����X�c�_���Ă��܂����A���ɕ��G�œD���ɂ͂܂�܂��B����������āA�����ʑ��ɉe�����y��EKIO�ł̒x���ݒ��P��XO�ȊO�� EQ �ݒ�́A�ɗ͎g��Ȃ���`�ł��B
����YST-SW1000 �������x��Ă���Ȃ�A�ȑO�ɂ����b�������悤�ɁA�u�����I�ɁI�v���������O���֓������āA�x�������킹�����ł��B�d���ł����A���U�r���ɂ̓e�t�������̉Ƌ�X�x�[����ݒu���Ă���̂ŁA�O�� 50 cm �͈̔͂Ȃ�ȒP�ɓ������܂��B
�����ԍ��F24527954
![]() 1�_
1�_
�悭�悭�l����A�u�ʑ�����v�Ɓu���Ԃ���v�́A����Ӗ��œ������Ƃł��ˁB�@
XO�t�B���^�[�ŁA�^�C�v�ƌX�ɍ��킹�āA�ʑ����]�����邩�ۂ��͕ʖ��ł����A���E�̃T�u�E�[�t�@�[�̈ʑ����]�X�C�b�`���ǂ���ɂ��邩�̓��X�j���O�|�W�V�����Ƃ̗��݂ŁA���s���낪�K�v�ł�������B�B�B
ASR�ł��A�ʑ���]�A�]�X�A�ʼn��X�Ƌc�_���������Ƃ�����܂��B����latgency �� phase issue �́A������肾�I�ƍ��ꂷ��l�����܂��B
�p��͕ꍑ��ł͂Ȃ��̂ŁA���X�A�������܂��B�܂��Ă⎄�͉����H�w�̐��Ƃł͂���܂��B�B�B�B
�����ԍ��F24527969
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
���u�ʑ�����v�Ɓu���Ԃ���v�́A����Ӗ��œ���
BOWS����H���A�^�C���A���C�����g�ƌĂԂ炵���ł��B
�i50�N�O�͂���ȃn�C�J���Ȗ��O�͂Ȃ������ł��B)
��YST-SW1000 ���x��Ă���Ȃ�A���U�r���ɂ̓e�t�������̉Ƌ�X�x�[����ݒu�A�O�� 50 cm �͈̔͂Ȃ�ȒP�ɓ�����
30ms���炢�Ȃ�A�����܂��ˁB�ʑ����]SW���g����̂�
�e�t�������̉Ƌ�X�x�[���͉����v���ł���
��������Ƃ���B
�����ԍ��F24528537�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
��BOWS����H���A�^�C���A���C�����g�ƌĂԂ炵���ł��B
���i50�N�O�͂���ȃn�C�J���Ȗ��O�͂Ȃ������ł��B)
time alignment �ł��ˁBASR �ł��������܂��B�i�D�����\���ł��ˁB�����g�����Ƃɂ��܂��B
���e�t�������̉Ƌ�X�x�[���͉����v���ł���
�����ł��B�^�C���A���C�����g�i�I�j����ŗ��z�̈ʒu�����܂�����A�Ƌ�X�x�[���͓P�����܂��I
�����ɏd�ʋ��̂������Ă�����i�O��ɐU�����Ă�����j�A�m���ɉ����v���ł��ˁB
����ł́AREW�̃f�[�^���Q�l�ɁAYST-SW1000 �̃|�[�g�ʂ́ANS-1000 �L���r�l�b�g�\�ʂ�� 13 cm �O���i���X�i�[���j�ɂ���܂��B
�����قǁAAdobe Audition 3.01 �� Sony Super Audio Check CD�� track-14 �����Ԏ��g��ŕҏW���āA1 kHz �܂ł́u�R�g�\���v���Y��ȋ�`�C���p���X�������쐬�ł��܂����B
�T���Ɂihopefully so...�j�A�d���}�b�g���X�R������������Łi�I�j�A�������U�炩�����܂܂ŁA�i�ߐژ^���ł��̂Łj��r�I�����ʂŁAYST-SW1000 �� JA-8053 �̉ߓn�������Čv�����Ă݂܂��B�@
�ł���A��������v���p�������쐬�ς݂̃^�C���A���C�������g����i�^����u�I�j�������ɂ�肽���ł��ˁB
�����ԍ��F24528682
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�ߓn��������f�[�^���ڍׂɒ��ߒ����Ă���܂����B
�܂��A�C���v�b�g�p���X�ł����A�}-�P�̂悤�ɁA���ۂɃA���v��SP���j�b�g�����i������j���͐M���́A���S�ȋ�`�ł͂Ȃ��A���Ԏ���Ńp���X�̑O��ɂ��́u�Q�C���v���K�E�X���z�I�ɍL���������̂ł��邱�Ƃɒ��ӂ���K�v������܂��B���z�́A���ׂ� 500 Hz �̉��ł���A���̃Q�C���i���ʁj����`�p���X�ŋ}���ɗ����オ���āA����������A�������o���������A�����ł͂Ȃ����Ƃ�F�����Ă������Ƃ���ł��B
���̏�ŁA�}�|�Q�ɂ�����c�������̉�͂́A�����������C���v�b�g�p���X�̐��암���ɏd�Ȃ��ď��Ȃ��炸���ݕϒ����Ă��邱�Ƃ��F�����邱�Ƃ���ł��B
�c�������́A��͂���́u���̉�v�Ƃ��Ė߂��Ă���̂ŁA�}�|�Q�Ŏ������悤�ɁA��P�������ƁA��Q���������A��܂��ɓ��肷�邱�Ƃ��\�ł��B��Q�������́ASP�̔w��̃X���C�h�h�A���[�ǂƔ����ʂ̊Ԃʼn������Ă���̂ŁA�P���������������i�� 5 ms�j�����������Ă���A�Ɖ��߂ł��܂��B
���̉�͂���ASP�ʂƔ����ʂƂ̉��̉������Ԃ��� 25 ms �ł��邱�Ƃ�������܂��B
�����Q�Q���̉����� 345 m/s �ł��̂ŁA���������� 345 x 0.025 = 8.63 m �ł���A�]���� SP���甽���ʂ܂ł̋����́A�� 4.32 m �ƌv�Z����܂��B
��قǁA���݂́i���肵���ۂ́jSP�ʒu�����̔��ǂ܂ł̋������ʐ^�}�ʏ�ł͂Ȃ��A���W���[�Ő��m�ɑ������� 4.35 m �ł����B
�}�C�N��[�́ASP�\�ʂ���10 cm �قǗ���Ă����̂ŁA�L�^���ꂽ�ꎟ�������̉��������́A���̕ǂ��^�Ɛl�Ȃ�A4.35 + 4.25 = 8.60 m �ł���͂��A�ƂȂ�܂��B�����āA���� 8.60 m �́A��L�̑���Ŋϑ����v�Z���ꂽ 8.63 m �Ƃقڊ����Ɉ�v���܂��I
�܂��Ƀh���s�V���̔Ɛl�ߕ߁A�ƌ��������ł��B
�Ƃ������߂ŁA��낵���ł��傤���H
�����ԍ��F24529103
![]() 1�_
1�_
�����A��̉��߂���������A�R�g�p���X�ɂ��āA���������ቹ�ʂŁA��̕ǂƂ̊Ԃ̔������\�Ȍ���E���A JA-3058 �́u�ߓn�����v�Ɍ���ƁA���Ɂi�قڊ����Ȃ܂łɁH�j�D��Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ肻���ł����A�A�A�A�T���Ɏ����Ă݂܂��B
�����܂ŏڍׂɉ�͂��Ă݂�ƁA��������SP�Q���������݂����Ȃ�܂����ASP���j�b�g�P�̂̐��\���������ȏ�O��I�ɒNj����Ă����܂�Ӗ��͂Ȃ��A��͂�A����́AJA-3058 �̂��܂��ɗD�ꂽ�f����m������ŁA���X�j���O���S�̂Ƃ��Ẳ����i�ʂ����߂�w�͂����߂��邱�Ƃ��������Ă���܂��B
�����ԍ��F24529136
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�N���}�̃\�i�[�݂����ł��ˁB
�ǂ͓���ł����̂ŁA�ǂ̂悤�ɂ���Ɣ��˃��x���������邩�A�Ⴆ�Γ����̕ǂɃ}�b�g��V��܂ŗ��ĂāA�X�s�[�J�[����U��ɂ��Č��ʂ����邩�A����C���e���A�I�ɋ��e�ł�����@�ɒu�������ł��傤��
�����ԍ��F24529306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�T�u�E�[�t�@�[ YST-SW1000 �ɂ��Ă��A�p���X�O����܂߂ĕ\�����A����X�y�N�g�����܂߁A�c���X�P�[�����܂߁A�c�����Ԏ��𐳊m�ɑ����āA���₷���\���ɂ��܂����B
���낢�댩���Ă��Ėʔ����ł��B
Kick-out �����オ��́A��͂� YST�̃w�����z���c�����p�ł��̂ŁA31.5 Hz �ł͂��Ȃ�݊��ł����A63 Hz �ł͂P�g�ڂ��炫����Ɠ����Ă���A�v���̂ق��ǍD�ł��ˁB
Fade-out �������́A31.5 Hz �ł́A���S�ɂQ�D�T�g���i65 ms�j�قǗ]��U�����Ă��܂����A63 Hz �ł́A���������v���� 40 ms �قǂŏ������Ă���悤�ł��B����͎��̗\�z�����x�^�[�Ȋ����ł��B
�ЂƂʔ����ώ@�́A�����̐���\��������ƁA���C���� 31.5 Hz�A63 Hz�o���h�͑債���x�����Ȃ��̂ł����A������ቹ�̔��ɒ�Q�C���̋�C�U�����o���h�� 10�`20 ms �قǒx�����Ă��邱�Ƃ��r�W���A���I�Ɋm�F�ł��邱�Ƃł��i�������Ȃ������ɔ����ȑ���ɂ͂Ȃ蓾��j�B������ł��m�F�ł��܂����A 63 Hz �̐���\���̕����͂�����ƕ�����܂��B
YST-SW1000 �̓��쌴���ƍ\���i��^�L���r�l�b�g�Ńw�����z���c���̃o�X���t�|�[�g�j���l����ƁA�ƂĂ��Ó��Ȑ���X�y�N�g���ł���ƍl�����AAdobe Audiotion 3.01 �ɂ�镪�͂̃����b�g���ĔF�����Ă���܂��B
YST-SW1000 �̉ߓn�����]���́A����Ŋ������Ǝv���܂��B
�@�①�ɑ�p�b�V�u�T�u�E�[�t�@�[�̎���ɂ͓˓����Ȃ��i�I�j�̂ŁA���̑��茋�ʂ����܂��Ȃ���A�^�C���A���C�������g����ɂ��O��ړ���N���X�I�[�o�[�A�ʑ����]���܂߂āA����ɍœK�����܂��B
�����ԍ��F24529800
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����
�����̗l�q�ł����A����Ȃ悤�ɕ��́A���߂���ƁA������1�g�̔g�`�������ԉ��т��Ă��邱�Ƃ������ł������ł��B
����ŁA�Q�C���͋ɏ������ł����A������Q�g���A���l�ɕϒ��ŏ����ԉ��т��邱�Ƃ������ł��܂��B
�����ԍ��F24530909
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����
���b�����Ă��鎄�Ȃ�́u�^�C���A���C�������g�v������@�ł����A�e�X�g�M���̍쐬�Ƒ�����@�̌��ɂ��āA�Y�t�}�̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂����B�@����ŗ����ł���ł��傤���H
���P�ւ̂��w�E�ȂǁA���������������B
�����ԍ��F24531240
![]() 0�_
0�_
�}�̃A�b�v���[�h���ł��Ă��Ȃ������̂ŁA�ē��e�ł��B
�����ɂ悵����ABOWS����
���b�����Ă��鎄�Ȃ�́u�^�C���A���C�������g�v������@�ł����A�e�X�g�M���̍쐬�Ƒ�����@�̌��ɂ��āA�Y�t�}�̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂����B�@����ŗ����ł���ł��傤���H
���P�ւ̂��w�E�ȂǁA���������������B
�����ԍ��F24531248
![]() 1�_
1�_
�_�u��܂����B
�P��ڂł��A�b�v���[�h�ł��Ă��܂����B���炵�܂����B
�����ԍ��F24531249
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�{���ߌ�A�����ɏ������čđ��肵�܂����B
�P�D��̋������s�ǂɂ�锽���i��ݔg�j�́A�K�ɎՉ��^�������邱�Ƃɂ��A�قڊ��S�ɏ������Ƃ��ł��܂����B
�Q�D���Ȃ�́u�^�C���A���C�������g�v�i���Βx���j���肨��є��������@��K�p���A�T�u�E�t�@�[�̒x��𑪒�ł��A�S�Ă�SP�Q���قڊ����ɑ��ݒx���[���ɒ����ł��܂����B
�R�C��̔����i��ݔg�j���قڃ[���̂ŁA�W�g��N�ƂR�g��N�ɂ��T�u�E�[�t�@�[�ƃE�[�t�@�[�̉ߓn������T�d�ɑ��肵�܂����B
�@�@�i�R�D�̌��ʂ́A�Y��ɂ܂Ƃ߂�̂ɏ������Ԃ�������܂��̂ŁA���炭�����҂��������B�j�@�@
�܂��A�����́A�Q�D�̃^�C���A���C�������g�i���Βx���j����ƒ����ɂ��āA���̓��e�ŋ��L���܂��B
�����ԍ��F24533801
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�^�C���A���C�����g�̐}�ŁA����g���͎��g�����ω����ĕ��������Ă���悤�Ɍ����܂��ˁA���͉����Ӗ����Ă���܂����H
�����ԍ��F24533919�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
 |
 |
|---|---|
�^�C���A���C�������g�i���Βx���j�̃r�W���A�����Ƒ���̌��� |
���݂̃}���`�V�X�e���ɂ�����^�C���A���C�������g�i���Βx���j����ƒx���̃[���� |
�^�C���A���C�������g�i���Βx���j�̃r�W���A������@�̌����Ƃ��̌��،��ʁi��p�A�b�v�����}�Ɠ����j�����}�Ɏ����܂����B
���ɉE�}�̂悤�ɁA���̃^�C���A���C�������g����p�M�������݂̃}���`�`�����l���E�}���`�A���v�V�X�e���iEKIO�ň�̒x���ݒ�Ȃ��j�ōĐ����A����� Adobe Audition 3.0.1 �Ř^�����܂����B
����̖ړI�i�eSP���j�b�g�ɂ����g���s�[�N�̎��Ԓ��S���e�Ղɓ���ł���j�ɓK����悤�ɐ���\���̃J���[�X�P�[�������Đ������Ԏ���`�����Ƃ���A�����̂悤�ɃE�[�t�@�[�iWO�j�A�~�b�h�����W Be�X�R�[�J�[�iSQ�j�ABe�c�C�[�^�[�iTW�j�A�z�[���X�p�[�c�C�[�^�[�iST�j�̎��g���s�[�N�́A�S�ē���̐������Ԑ���ɑ����Ă���A���Βx�����Ȃ����Ƃ��Ċm�F�ł��܂����B
����A�T�u�E�[�t�@�[�ɂ��Đ����̎��Ԓ��S�́A����SP�Q�ɑ��Ė� 15 ms�x��Ă��邱�Ƃ��}���͂ł��A�܂� Adobe Audition 3.01 �ŃJ�[�\���ʒu�̎��Ԏ� ms �f�W�^�����l�\��������m�F�ł��܂����B
�����ŁA�f�W�^�� XO/EQ �ł��� EKIO �̃O���[�v�x���@�\�ŁA����SP�Q�iWO, SQ, TW, ST�j��SW�ɑ��� 15 ms �x�������܂����B���̐ݒ�ő�����s���A�E�}�̂悤�ɁA�m���ɑS�Ă�ST�Q�����͐M���Ɠ����悤�Ɂu���Βx���[���v�Ő�������ɏ���Ă��邱�Ƃ��m�F���܂����B
���̂悤�ɁA���̃V���v���ȁu�^�C���A���C�������g�̃r�W���A����͖@�v�́A���Βx���̉�������Ɣ������ɗL���Ɏg���܂��B
���āA15 ms �̒x���� SW �̕����I�ȑO���ړ��ʼn������悤�Ƃ���ƁA�����̎����P�V���ɂ����鉹���� 342 m �ł��̂ŁA342 x 0.015 = 5.13 m �ƂȂ�A�� 5m �̑O���ړ����K�v�ƂȂ�܂��̂ŁA��������ł��B�@�����ŁA���ʁA���� EKIO�ɂ��f�W�^���x�� 15 ms ���̗p���邱�Ƃɂ��܂����B
������s���ƁAEKIO �́u���_�v���v�Q�C���J�[�u��ł́ASW��WO�̃N���X�ߕӂŁu���ݕϒ��ɂ��H�v�����́u�g�ł��v�������܂����A�N���X�|�C���g�ߖT�ŏ��ʂ�bell�^EQ�� SW �� WO �ɉ����邱�ƂŁA�قڍ��v�Q�C���́u�g�ł��v�������邱�Ƃ��ł��܂����B
����ŁA���ۂ̉��y������̒������ʂ́H�H�@
���ꂩ��A�P�T�Ԉȏォ���ĐT�d�Ƀ[���x���� 15 ms �x���̍����A�u��ϓI�v�ɂ������r�ׂ܂��B
�{���̒�����̈�ۂƂ��ẮG
�ʏ�̃N���V�b�N���y�̍Đ������ł́A�����ȓ�d�ӌ������ł����Ȃ���A�L�Ӎ��m�ɒ���������͍̂�����A�A�A�Ƃ������x�ł����A���t�}�j�m�t�̃s�A�m���t�ȑ�Q�ԁ|��R�y�̖͂`���ƓW�J���ɂ�����呾�ۂ̉��́A���X�X�s�[�h���ƃ^�C�g�������サ����ۂ�����܂��B�i�v���Z�{���ʂ�������܂���B�j����ɁA�T�d�ɒ�����ׂ����ł��B
����A��薾�m�ȑ���ۂƂ��ẮASW��WO�̗�����Ɍׂ���W���Y�L�b�N�h������A�w��܂̌��ւ̐ڐG�Œ�����`������ɂ��u�C�߉��v�I�ȉ������E�b�h�x�[�X�̒ቹ���Ȃǂ̍Đ��ɂ����āA���́u�����オ��̃V���[�v���v�A�u���܂聁�^�C�g���v�A�u�N�s�x��N�x�v�A�����āu�X�s�[�h���v�A���L�ӂɌ��サ���悤�Ɋ������܂��i�Ɠ��������j�B
������ 15 ms�A����� 15 ms�A�A�A�Ƃ������o�ł��B
�W�g��N�ƁA�R�g��N�ɂ��ߓn��������̏ڍׂɂ��ẮA�����ȍ~�ɋ��L�ł���A�Ǝv���܂��B
�i�f�[�^�͊����ɘ^���ς݂ł��B�j
�����ԍ��F24533939
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
������g���͎��g�����ω����ĕ��������Ă���悤�Ɍ����܂��ˁA���͉����Ӗ����Ă���܂����H
�������ԕ��̒��ŁA�\���ȃG�l���M�[�i�Q�C���j���������悤�Ƃ���ƁA���g����������Ή�����قǎ��ԕ���傫�����Ă��K�v������܂���ˁB���̂������T�d�ɍl�����A�Œቹ������ 300 ms �̎��ԕ��̐M�����쐬���A���������̃V���[�v�ȃs�[�N�́A���ԕ��̒��S�Ɉʒu����悤�ɐM�����쐬���܂����B
�Ƃ������ƂŁA�ɂȂ��Ă��܂����H
�����ԍ��F24533954
![]() 0�_
0�_
���́A��̓��e�� 15 ms �Ə����Ă���Ƃ���́A�u16 ms�v �Ɠǂ�ʼn������B
���ۂ�EKIO�@�ɂ�点�Ă���̂́A16 ms �̒x���ݒ�ł��I
�����ԍ��F24533966
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�����肪�Ƃ��������܂��B
�Ȃ��Ȃ����j�[�N�Ȏ�@�ł��ˁB
���̏�ԂŁA�]���̋N�_����e���j�b�g�̔g�`�𑊑ł݂�Ƃǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤�H�������낻���ł��B
dualazmak����̂����́A���͔g�`�ł͂Ȃ��G�l���M�[�̃s�[�N�ō��킹��l�����ɂȂ��Ă���̂����B
�����ԍ��F24534175�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
BOWS����
���Ȃ��Ȃ����j�[�N�Ȏ�@�ł��ˁB
�͂��A���Ȃ藝�l�߂ōl���āA�ƂĂ��V���v���ȕ��@���l�Ă��܂������A����قǂ��܂��g����Ƃ́A�����\�z�O�ł����B
���]���̋N�_����e���j�b�g�̔g�`�𑊑ł݂�Ƃǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤�H
�ǂ̂悤�ȑ���n�Ɣg�`�ϑ���z�肳��܂����H�@�u�]���̋N�_�v�Ƃ́A�ǂ����A�����A�z�肳��Ă��܂����H
�����͔g�`�ł͂Ȃ��G�l���M�[�̃s�[�N�ō��킹��l����
�m���ɃG�l���M�[�s�[�N�̎��Ԓ��S�����킹�邱�ƂŁA���ʓI��SP���j�b�g�Ԃ̃^�C���A���C�������g�� ms �P�ʂň�v�����Ă��܂��B
���̕��@�̂ЂƂ̃~�\�A�L���́A�u�c�C�[�^�[�{�X�p�[�c�C�[�^�v����������̔��ɃV���[�v�ō��G�l���M�[�ȃs�[�N���A�M���o���h�̎��Ԓ����ɐ��m�ɔz�u�ł��邱�Ƃł��B
����ɂ���āA����}�ł�������������悤�ɁA�^���������ۂ̋�C�����̐���g�`�ŁA���Βx���̊�ƂȂ�s�[�N�ʒu�� ms �P�ʂŔ��Ɍ����Ɍ��߂邱�Ƃ��ł��A���̈ʒu���玞�Ԑ�������`�����Ƃ��ł���̂ŁA��������̒ቹ��̑��Βx����ms�P�ʂŐ��m�ɔc�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
�������f�W�^�������̃}���`�`�����l���|�}���`�A���v�\���ł́A�e���Ƀo�b�t�@�[�i���C�e���V�[�j�����݂���̂ŁA�eSP�����ɂ��Č����M���iJRiver�̔��M�j����́u��Βx���v�𐳊m�ɑ��肷�邱�Ƃɂ͑傫�ȍ�������܂����A�d�v�Ȃ̂́u��Βx���v�ł͂Ȃ��ASP���j�b�g�Ԃ́u���Βx���v�ł��̂ŁA���̂��̕��@�́A���x�ƍČ����ɗD��A�傢�ɔėp��������u���Βx�����^�C���A���C�������g�v�̑��肨��ђ������@�ł���ƍl���Ă���܂��B
���̕��@�́A���E�I�Ɍ���ƁA�N�������ɂ���Ă������ȕ��@�ł����Aweb�ł��A���ȏ��ł��A�I�[�f�B�I���Ђł��A���������L��������܂���B
�ł́A���ɁA�����i��ݔg�j���ɏ����������X�j���O���ɂ�����W�g��N�A����тR�g��N�ɂ��ߓn��������̌��ʂ̎��Z�߂ɂ�����܂��B
���āA�]�k�ł����A�A�A
�����i��ݔg��c���j���قڊ��S�Ɂu�E���v���Ƃ́A�ߓn�����̑���ɂ͕K�{�ł����A���ۂ̉��y�ӏ܂ɂ��D�܂������ǂ����́A�傢�ɋc�_�̗]�n������܂��ˁB�@
���������i��ݔg�j��u�c���v�����S�Ɂu�E���v���Ƃ����z�Ȃ�A�������ɃV�X�e�����\�z���邱�Ƃ����z�I�ɂȂ�܂����A����͊y�������X�j���O���ł͂Ȃ����Ƃ͖����ł��B
���Ď������u�t�Ƃ��ċ���̂���`�������Ă������m���̓��c�ی��q����w�ɂ́A�f���炵�����y�z�[��������A��w�̑n�n�҂��A���X�e���_���̃R���Z���g�w�{�[���y�z�[�����قڊ��S�ɖ͕킵�Č��z���ꂽ�f���炵���z�[���ł��B���̌��z�̉ߒ��ŁA���̕����u�c���ρv�Ƒ肵���{��������A�R���Z���g�w�{�[��͂��Ȃ���u�c�����ԁv���ςƂ���z�[����v���ꂽ�o�܂��Љ��Ă��āA���ɋ����[���q�ǂ������Ƃ��v���o���܂����B
�I�[�P�X�g�����܂ޑS�Ă̘^�����y�́A���ꂪ���t���ꂽ�z�[����X�^�W�I�̉������i������c���j���܂����M���ł��̂ŁA����𐳊m�ɍĐ�����ɂ́A�������I�ȃ��X�j���O�����D�܂����Ƃ̋c�_���悭����܂����A���́A���̋c�_�ɂ͑S���^�������˂܂��B
���̗��R�́A��X�̉ƒ냊�X�j���O���[���ɂ�����X�e���I�Đ��́A����ʒu�ɑ�����SP�Q����̑O�ʂւ̉������˂ł���A�܂���ۂ̉��y�z�[���ő̌��������A�����A�V��A���@�Ȃǂ���̔�����c�����A�ڂ̑O��SP�Q����u������v�������ĕ��˂��Ă��܂��B�܂�A�����ɖ������I�Ȋ�������Ă��A���ۂ̃z�[���g�[�����Č����邱�Ƃ͕s�\�ł��B
�����A�^�ɗ��z�I�ȍĐ���ڎw���Ȃ�A���ɑ����̃}�C�N������������ɔz�u���ă}���`�g���b�N�^�����A����Ȗ������̂R������Ԃɔ��ɑ�����SP�Q��z�u���A���`�����l���Đ��n���\�z���āA���ꂼ���SP�Q���i���Βx�����܂߂āI�j�����ɐ��䂵�Ȃ��瑽���̐ꑮ�A���v�ŋ쓮����A�ƂȂ�̂ł��傤�B�@�����炭�A���\���~���̔�p���K�v�ɂȂ�܂��ˁB
���������āA��X�̃��X�j���O���[���ɂ�����u������c���v�́A���X�i�[�X�l���D�ރe�C�X�g�ɍ��킹�āA���y�z�[����^���X�^�W�I�̑S��������́u������c���v���u�[���I�ɍČ��v���悤�Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̈Ӗ��ɂ����Ă��A�����������I�Ɍ���Ȃ��f�b�h�����邱�Ƃ́A�D�܂������Ƃł͂Ȃ��ƁA����A�������ĔF�����܂����B
���X�j���O���[���́A�K�x�ȁu������c���v�́A�D�݂ɍ��킹�ĕK�v�ł���A�Ɗ����Ă���܂��B
�����ԍ��F24534535
![]() 0�_
0�_
��̉������ˁi��ݔg�j���镽�s�ʁi�����ǁj�́i�قځj���S�f�b�h���̗l�q�ł��i�j�B�\�t�@���̖ѕz�������A���g�̓q�_�܂�̌���̃}�b�g���X�ł��B�@�������A�Ӑ}�I�Ɂi�I�j�U�炩���Ă��܂��B�W�g��N�A����тR�g��N�ɂ��SP�ߓn��������̂��߂����ɁA�i�قځj���S�Ƀf�b�h�����Ă���܂��B
�u�܂��܂��A��������������Ă�́I�H�v�A�����E�i�Ђキ�j���̂ł����A�������A��p�������͂������܂���B
���̃R�[�i�[�����̎Չ��́A�ʓr�l���ď��u�������܂����A��̃X���b�h�ł��������悤�ɁA���S�Ƀf�b�h�����邱�Ƃ́A�������Ă�낵���Ȃ��ƒ����āA�����āA����܂��B
�����ԍ��F24534834
![]() 0�_
0�_
�Q��̍����̉��e�́ABOWS����ł͂Ȃ��A�����ɂ悵���� �ւ̉ł����B�@���炵�܂����B
�����ԍ��F24534847
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�����]���̋N�_����e���j�b�g�̔g�`�𑊑ł݂��
���ǂ̂悤�ȑ���n�Ɣg�`�ϑ���z�肳��܂����H�@�u�]���̋N�_�v�Ƃ́A�ǂ����A�����A�z�肳��Ă��܂����H
�E�[�t�@�[�ƃX�R�[�J�[�̏ꍇ
Ekio�̓����ɃN���X500Hz�̂�����1�g������́A������N�_�Ƀ}�C�N�ŏE����1�g��
������E�[�t�@�[�����A�X�R�[�J�[�����A�E�t�@�[+�X�R�[�J�[�̍����Ŏ��{�A�N�_�����킹�Ĕ�r�ł��B
�}���`�E�F�C�̓��j�b�g�Ԃ̂Ȃ����ۑ�̍���ɂ���
�V���������ł����̔g�`���ǂ��Ȃ����̂��́A�ǂȂ����m�肽���ł��傤�B
���݂�dualazmak����̋Z�ʂ��炵���瑢����Ȃ�����
�����āA�]���̂�����1�g���̔g�`�̃s�[�N�ō��킹���ꍇ�Ƃ̍����Ŕ�r��
�V���������ł̓G�l���M�[�Ō���̂ŁA�Ⴆ�A���U�����傫���i���x�������j�Ȃ�Ȃ�
�A�h�o���e�[�W���������Ƃɂ��Ȃ�܂��ˁB
�����̕��@�́A���E�I�Ɍ���ƁA�N�������ɂ���Ă������ȕ��@�ł����A
��web�ł��A���ȏ��ł��A�I�[�f�B�I���Ђł��A���������L��������܂���B
�Ő�[����Ȃ��ł��傤���H
���ɂ������Ƃ��Ă��A��ƃm�E�n�E�̗̈悩������܂���B
�����ԍ��F24534901
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�������˖ʁi�����ǁj�́i�قځj���S�f�b�h���̂��ʐ^�A�Ȃ��Ȃ��V�ѓ|���Ă܂���
���u�܂��܂��A��������������Ă�́I�H�v�A�����E�i�Ђキ�j����
�����ł͒�ݔg��ŁA�g���v�Z�ł������t������A�֎q�ɗ����Ėѕz���f���Ȃ���A
�q���Ƀp�\�R���̘^���X�^�[�g�{�^�����������Ĕ��˂̑傫���Ƃ�������A
�Ƒ�����͉�����Ă�̂Ɣ����ڂŌ����Ă܂����B
�ǂ����A�ǂ̂��炢�Ō����̂��͂���Ă݂Ȃ��Ɗm��ł��Ȃ����A
�����ɓ����Ă��Ȃ��ƑË��Ă��o�Ă��܂���B
�厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
���͑�Ƃ��̐����ł��ˁB
����ύX�͎v���̂ق���R�����肵�܂��B
�����ԍ��F24535559
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
��Ekio�̓����ɃN���X500Hz�̂�����1�g������́A������N�_�Ƀ}�C�N�ŏE����1�g��
��������E�[�t�@�[�����A�X�R�[�J�[�����A�E�t�@�[+�X�R�[�J�[�̍����Ŏ��{�A�N�_�����킹�Ĕ�r�ł��B
���̎�|�͗����ł��܂����AEKIO�ւ̓��͂�JRiver����ASIO4ALL���o�R�����f�W�^���M���ł��̂ŁA���̓��̓^�C�~���O�� ms���x�Ō��肷��ɂ́A����PC���ŏ�������Ƃ��Ă��A�f�W�^���M���̃f�W�^���t�B�[�h�o�b�N�ɂ��^���ƁA�}�C�N�ɂ���C�^���������Ȃ���Ȃ炸�A�n�[�h���������ł��B�Ȃɂ���JRiver�AASIO4ALL�AEKIO�ADIYIHNK ASIO �̂��ꂼ��Ƀo�b�t�@�[�i���C�e���V�[�j������܂��̂ŁA���̕����̑S�̒x���͂��������Ƃ͌���܂���B�i���������łȂ��Ă��A�S����ɓn���ē���̒x���Ȃ�A�S����肪�Ȃ��I�j
�܂��A16 ms �̒x����ݒ肵���̂́ASW��WO�̊Ԃł��̂ŁAWO��SQ�̊ԁi�x���[���j�ɂ͉��̕ω����Ȃ��A�S�́iWO+SQ�j�Ƃ��� 16 ms �ꏏ�ɒx�����Ă��邾���ł��B���̑��������Ȃ�ASW��WO�̋��ڂ̌q����ł��傤�B
��ĂƂ��āA�Ⴆ�R�b�i3,000 ms�j ���̖����M����p�ӂ��A���̊J�n����1,000 ms �̈ʒu�� 1 kHz �̃V���[�v�ȁi4 ms �����x�H�j�P��g�� -10 dB���x�̃Q�C���ō쐬���iSQ�ōĐ��������C�^���ł���_�Ƃ��Ďg����j�A�������琳�m��200 ms�o�߂����ʒu��SW�ł�WO�ł��Đ������ 100 Hz �̃p���X�i50 ms���ōő�Q�C�� -15 dB���x�H�j�����M�����쐬���āA��C�^�����邱�Ƃ��ł��܂��B
���̐M�����ASQ�����������Ȃ���Đ����ASQ+SW�@�̉��ASQ+WO �̉��ASQ+(SW+WO) �̉����A�x���ݒ�Ȃ��A����� WO 16ms�x���ݒ肠��Ř^�����āASQ�� 8 kHz ������������ SW��WO ��100 Hz �����i�G�l���M�[�s�[�N�����j�܂ł̎��Ԃ� ms���x�ő��肷��A16 ms �x���Ƃ��̒x������Ċm�F�ł��܂����A�܂��e�Đ��ɂ����� 100 Hz �P��p���X�̔g�`�����o�I�Ɋm�F���邱�Ƃ��ł��܂��B
�x���ݒ�Ȃ��ł́A100 Hz�p���X�̈ʒu�� 16 ms �x��Ă���SW�ƁA�x��Ȃ���WO�Ŕ��������̂ŁASW+WO�̔g�`�Ɛ���͉����ԕ����֍L����ł��傤���AWO16 ms �x���ݒ�Œx���[���ɂ���A�^�����ꂽ�p���X�̉��i���ԁj�����̕��͋����Ȃ�͂��ł��B
������ 100 Hz �����̘^�����A�Q�C���g�`�X�y�N�g���Ɛ���X�y�N�g���̏㉺�����\���Ŕ�r���邱�Ƃ��ł��܂��B
�悤����ɁA���Ƃ��ẮA�����܂ŁA����ԓ_��݂�����C�^�������̍Đ���͂ŁA���ΓI�ȃ^�C���A���C�������g���A�Q�C���g�`���͂Ɛ��䕪�͂Ŋm�F�������킯�ł��B
50 ms �̕����ɑ���ɏ\���ȃG�l���M�[������ 100 Hz �s�[�N�p���X���쐬�ł��邩�A�܂������Ă���܂���̂ŁA�������l�b�N��������܂���B������100 Hz �Ȃ�P�b�ԂɂP�O�s�[�N�������܂�Ȃ��킯�ł��̂ŁB�B�B
�Y�t�}�̂悤�ɁASony Super Audio Check CD �� track-14 ���� 125 Hz �W�g��N�M���́A 64 ms ���ɂW�g�����e���Ă��܂��̂ŁA������R�g�Ɍ��炵�� 32 ms���̐M�����ASW ��WO �ł̋��ʍĐ��Ɏg�����Ƃ��œK��������܂���B���̏ꍇ�́A�ꎞ�I��SW�̃n�C�J�b�g�� 90 Hz �t�߂܂ŏグ�Ă����iEKIO�ł��AYST-SW1000 �� -24dB/Oct �n�C�J�b�g�ł��j�ASW��WO���ʂ̔����Ɏg�������ł��B
�����āA���̐M���� 200 ms�@�܂���150 ms ��O�ɁA�����g���b�N���� �u1kHz �W�g �� 2ms �Ɏ��߂�-10 dB�̋�`�g�v����_�Ƃ��ăR�s�y���Ă����Ă����ASQ�����ɂ�������Ƃ��Ďg�������ł��B
�������ł��傤���H
�����ԍ��F24535701
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
��̃R�����g���������Ƃ���ŁA������̖��Ă��v�����܂����B
�܂��A�T�b�قǂ̖����M����p�ӂ��A���̂P�b���_����A���m�� 200 ms �Ԋu�̊J�n���ԂŁASuper Audio Check CD track-14����A�����g�����Ɂi�I�j�A1 kHz, 5.513 kHz, 2.756kHz, 2 kHz, 1 kHz, 500 Hz, 250 Hz, 125 Hz, 63 Hz, 31.5 Hz �̂��ꂼ��W�g��N -10 dB �p���X�̂P�O����z�u���܂��B
���̐M�����A�X��SP���j�b�g�P�ƂōĐ����Ę^���A�܂��S����SP���̂킹�Ę^���A���ꂼ��x���ݒ�Ȃ��̏ꍇ�ƁA�x���ݒ肠��̏ꍇ�Ř^�����܂��B�i�A���ATW�����͏�ɉ̂킹�� 1 kHz�̊���ԓ_��m��I�j�@���̘^���f�[�^����A�eSP�̔����J�n�����ʒu�𐳊m�ɓǂݎ���āA�P kHz ���������̎��ԊԊu�𑪒肷��A�e���j�b�g���ǂ̂悤�ɑ��ΓI�ɒx�����Ă��邩�A���Ă��Ȃ�����ǂݎ��܂��ˁB
�x�����[���Ȃ�A�����J�n�Ԋu�͏�� 200 ms �̂͂��ł��B�@ST�̊�_����̔����J�n�����́A200 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms, 1000 ms, 1200 ms, 1400 ms, 1600 ms �ɂȂ�͂��ł��B
WO�@�� SW�@�̔����Ԋu�����́A�x���ݒ�Ȃ��ł� 16 ms �ԉ��т���̂ŁA 216 ms �ɂȂ�͂��B�B�B�B�܂�ASW�̔����́A��_���� 1616 ms�ɂȂ�B�B�B�B�����̓J�[�\���ʒu�����̃f�W�^���\���ims�P�ʁj�Ő��m�ɓǂނ��Ƃ��ł��܂��B
����AEKIO�@�ɂ��u�N���X�I�[�o�[���g���ߖT�ł̌q����v���u���m�Ɂv����ɂ́A��̓��e�ŏ������悤�ɁA�N���X�I�[�o�[���g���̋ߖT�Ƀe�X�g�M����݂��āA�o���̒P�Ɣ����ƍ��������ɂ�����u�g�`�v���r�K�v������܂��ˁB
�����ԍ��F24535784
![]() 0�_
0�_
�����ł��B�ō���N���g���́A10 kHz�@�ł��̂ŁA�A�A
�܂��A�T�b�قǂ̖����M����p�ӂ��A���̂P�b���_����A���m�� 200 ms �Ԋu�̊J�n���ԂŁASuper Audio Check CD track-14����A�����g�����Ɂi�I�j�A10 kHz, 5.513 kHz, 2.756kHz, 2 kHz, 1 kHz, 500 Hz, 250 Hz, 125 Hz, 63 Hz, 31.5 Hz �̂��ꂼ��W�g��N -10 dB �p���X�̂P�O����z�u���܂��B
���̐M�����A�X��SP���j�b�g�P�ƂōĐ����Ę^���A�܂��S����SP���̂킹�Ę^���A���ꂼ��x���ݒ�Ȃ��̏ꍇ�ƁA�x���ݒ肠��̏ꍇ�Ř^�����܂��B�i�A���AST�����͏�ɉ̂킹�� 10 kHz�̊���ԓ_��m��I�j�@���̘^���f�[�^����A�eSP�̔����J�n�����ʒu�𐳊m�ɓǂݎ���āA�P0 kHz ���������̎��ԊԊu�𑪒肷��A�e���j�b�g���ǂ̂悤�ɑ��ΓI�ɒx�����Ă��邩�A���Ă��Ȃ�����ǂݎ��܂��ˁB
�����ԍ��F24535816
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
���P0 kHz ���������̎��ԊԊu�𑪒肷��A
��10��
��C�ɂ������Ȃ�10kHz�N�_�ŁA�Ԕ��킸����
�ϑ��g�`��1�����悢�ł��A�A���͓������͂�����̂ŁB
�ŏ��̂P�g���厖�ŁA����͂��邾��
�Ⴆ��[���h���ōŏ��̃S�[�����L�^�ł����āA
�Q�ʈȉ��͂��܂�o�Ԃ��Ȃ��悤�Ȋ����B
�N�_����2�b�Ƃ��J����ƁA��������2�b�̖����g�`�����鎖�ɂȂ�܂��B
Audacity�ł͔����Ƙ^�����ł��܂����A���C�e���V�������Ă��ϓ��͂قƂ�ǂȂ��A15kHz�ł�5�ςł��Ƒ���銴���ł����B
��JRiver�AASIO4ALL�AEKIO�ADIYIHNK ASIO �̂��ꂼ��Ƀ��C�e���V�[������S�̒x���͂��������Ƃ͌���܂���
dualazmak����̃V�X�e���ŌJ��Ԃ����x��m���Ă����Ă��悢�����B�v�������Ƃ����ۂ͂ǂ��Ȃ̂������͂������܂��H
�����ԍ��F24536023�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
�قڂقڗ����ł��B
��_�́AST�ɒS�����������̂ŁA�قƂ�Ǖ������Ȃ��ł��� 15 kHz �� -10 dB �P�g�ɂ��Ă݂܂��B
ECM8000 �}�C�N�́A������ƕ����Ă����̂ŁA�K���Ǝv���܂��B
Adobe Audition �����ɋ��͂Ȃ̂ŁA�����悤�ɂ��쐬�ł��܂����Ams�P�ʂł̎��Ԑ��x����эČ����ɂ��D��Ă��܂��B
����ŁA�c���͎E������ԁi�K���A�܂����̎Չ���Ԃ��L�[�v���Ă��܂��I�j�ŁA100 ms �Ԋu�łP�O���A���ׂĂ݂܂��B
���ꂼ��̗�N���A�\�Ȃ�P�g�A�G�l���M�[�I�ɕs���Ȃ�Q�g�A�ł����ˁB
���g�\���ł��A���Ԏ����g�傷��Δ����J�n�i�g�`�̗����オ��j�����𐳊m�ɓǂ߂܂��̂ŁA���ԊԊu�� ms���x�Ŋm���ɑ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�����ԍ��F24536421
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�����^��ݔg���i�قځj�����ɎE������Ԃł́A�W�g��N�A�R�g��N�ɂ�� WO �� SW �̉ߓn�����f�[�^���Z�߁i�f�[�^�[���W�͊����ς݁I�j�Ɏ�肩����O�ɁA�A�A�A
�^�C���A���C�������g�̒���������Ɛ����������̕��@�m���Ǝ��H���A��ɕЕt���悤�Ƃ��Ă���܂��B
���� Sony Super Audio Check CD track-14 �̂W�g��N�M���Q�ł����A�ڍׂɒ��߂�Β��߂�قǁA���܂��I���ɍ���Ă��邱�Ƃ������ł��܂��B�@
�܂��A���ɍ����g�̈�ɂ����邻�̐M���� Adobe Audition 3.01 �ŒZ�k�J�b�g�i�P�g���A�R�g���A�Ȃǁj���悤�Ƃ���ƁA���Ԏ��͎w���ʂ�ɃJ�b�g�ł��܂����A����ɑ�����N�g�̐U���igain/amplitude�j�ɂ��Q�C���_�E���̉e�����y�Ԃ��Ƃ��m�F�ł��܂��B����́AAdobe Audiotion 3.01 �̃J�b�g����ɂ����鎞�Ԏ����x�i�U���ւ̐��K���z�I�����H�j�Ƃ��̐U���ւ̉e�����֗^���Ă���\��������܂��B
�����ŁA�����ɂ悵����̂��ӌ��Ƃ͏������Ⴕ�܂����A�\�j�[�́u�Y��ȂW�g��N�v�Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�L�߂ɃR�s�[���y�[�X�g���āA�e��N�p���X�̔��������オ�莞���������ɔz�u���邱�Ƃɂ��A���}�̂U�b�ԐM�����쐬���܂����B
�[�������̊�ƂȂ�u15 kHz 2ms���M���v�́A���������オ�莞���������� 3.0000 �b�̈ʒu�ɐݒ�i�����j���A��������A�P�O�̂W�g��N�p���X���A�����ɔ��������オ�莞�ԊԊu 200 ms �ŕ��ׂ܂����B�������A�^�����ɖ��Ăɋ�ʂ��邽�߂ɁA63 Hz �� 31.5 Hz �̃p���X�Ԋu������ 400 ms �ɂ��Ă���܂��B
�E�}�ɁA15 kHz �[���}�[�J�[�Ɗe��N�p���X�̎��Ԋg��̗l�q�������܂������A���̂悤�Ɏ��Ԏ����g�傷�邱�ƂŁA�e�p���X�̔��������オ�莞���� ms �ȉ��̐��x�i����Ɋg�傷��� 0.1 ms���x�j�Ŋm�F�A�ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B
�ł���A���ӂ����ӂɁA���̐M�����g���ċ�C�^�����A�u�������^�C���A���C�������g����v�@�Ɓ@�u�������^�C���A���C�������g�����v�@�����݂܂��B�@���ׂāAST�����ɂ�� 15 Hz �[���}�[�J�[����̑��Ύ����Ōv�����܂��B
���ӂ��ׂ��́A����20���ɂ����鉹���� 344 m/s �ł��̂ŁA50 cm �̃T�E���h�s�����ł��A 0.5m�^ 344m/s = 0.00145 s =1.45 ms �ł��̂ŁAST�����Ƒ��h���C�o�[�iSP���j�b�g�j�Ƃ̓��������^���ŁA�T�E���h�̍s���i�����j����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ł��ˁB
���̂��߁ASP�Q�\�ʂ��� 2m �̈ʒu�ɑ���p�}�C�N���Œ肵�āA�e�h���C�o�[�iSP���j�b�g�j�ƃ}�C�N��[�́u�����̍��v�� 5 cm �ȉ��i0.145ms �ȉ��j�ɂȂ�悤�Ȑݒ�Ř^������\��ł��B
����ŁA�T�E���h�s�����ɂ��덷�́A0.2 ms �ȓ��ɒ����邱�Ƃ��ł��A���ʂƂ��ă^�C���A���C�������g����� 1 ms �̐��x�͏\���Ɋm�ۂł��܂��B
���Βx����ݒ肷�� SW �� WO ���݊Ԃ́u�g�`�̘A�����v�ɂ��ẮAST+SW�AST+WO�AST+(SW+WO) �̔g�`���r����A�u�q����v�����ĂɁA�g�`�ώ@�ő�������͂��ł��B
���ɁA�^�C���A���C�������g�������Ȃ��iEKIO�Œx���ݒ�Ȃ��j�@�Ɓ@�����Ȕ�������iEKIO�Ō����� ms���x�̒x���ݒ��j�@�ɂ����āASW+WO �ɂ��u 63.5 Hz �W�g�v�́u�g�`�v���ǂ̂悤�ɂȂ邩�A���ɋ���������܂��B
�����ԍ��F24538607
![]() 0�_
0�_
�Q�ӏ��A�����ł��B
�y������R��̒i���z
����ŁA�T�E���h�s�����ɂ��덷�́A0.2 ms �ȓ��Ɂ@�w���߂�x�@���Ƃ��ł��A���ʂƂ��ă^�C���A���C�������g����� 1 ms �̐��x�͏\���Ɋm�ۂł��܂��B
�y��ԉ��̒i���z
���ɁA�^�C���A���C�������g�������Ȃ��iEKIO�Œx���ݒ�Ȃ��j�@�Ɓ@�����Ȕ�������iEKIO�Ō����� ms���x�̒x���ݒ��j�@�ɂ����āASW+WO �ɂ��w63 Hz �W�g�x�́u�g�`�v���ǂ̂悤�ɂȂ邩�A���ɋ���������܂��B
�����ԍ��F24538706
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
|---|---|---|
�}3�@�����Ȏ��Ԍv���ł� SW �� 16 ms �x�����m�F |
�}�S�@16 ms �x���� ST,TW,SQ,WO �ɐݒ肷��ƁA�قڊ����ɑ��Βx���͂Ȃ��Ȃ�I |
�}�T�@16 ms�x�������̗L���ŁAWO��SW���d�Ȃ� 63 Hz������WO+SW�T�E���h�g�`���r |
�����ɂ悵����ABOWS����
�쐬�����@�u�^�C���A���C�������g����������p�M���v�@���g���āA������͂��܂����B
�S�Ă̋�C�^���ɂ́AST�ɂ�� 15 kHz �[���}�[�J�[��炵�ē����ɘ^�����Ă���̂ŁA�}�R�̂悤�ɁA���̃[���}�[�J�[�ʒu�� 3.000 �b�̈ʒu�ɐ��m�ɍ��킹�邱�ƂŌ����Ɏ��Ԏ�����͐M���ƈ�v�����āAms���x�ȉ��̐��x�ŁA���Ԍv�����\�ł��B
�}�R�Ɏ������悤�ɁA����̃r�W���A�����䕪�͂ł����肵���Ƃ���i�I�j�ASW�̔����́A��}�[�J�[�ɑ��� 15�`16 ms �x�����Ă��邱�Ƃ������Ɋm�F�ł��܂����B
�����ŁA�uST + TW + SQ + WO�v�ɑ��āAEKIO �̃O���[�v�f�B���C�ݒ�� 16 ms �̒x�����s�킹���Ƃ���A�}�S�̂悤�ɁA���Βx���������ɕ�ł��܂����B�قڊ����ȁ@�u�^�C���A���C�������g�������v�@�ł��B
����ŁA�ł����ڂ��Ă����A WO �� SW ���d�Ȃ镔���ɂ����� WO+SW �̋�C�^���T�E���h�g�`���A�x����������A�x�������Ȃ��A�Ŕ�r�����̂��}�T�ł��B�@
50 Hz �� -12 dB/Oct �̃n�C�J�b�g��ݒ肵�Ă���SW�̃Q�C���i�{�����[���j�������グ��WO�T�E���h�ƈꏏ�ɘ^�������̂ŁA�x���ݒ�Ŋ��S�Ƀ^�C���A���C�������g����v�������g�`�́ASW�P�Ƃ̔g�`�ɋ߂��Ȃ��Ă���_�́A���e�͉������B
�ȏ�A�قڗ\�z�Ƒz��ʂ�̐�������Ɣ������i���ʂƂ��Đ���Ɠ��l�� 16 ms�x���j���ł��܂����B
���ʓI�ɂ́A����́@�u�c���у}���`�g�[���̈ꔭ�^���Ńr�W���A�����䕪�́v�@�ɂ��^�C���A���C�������g����Ɣ������̑Ó������m�F�ł������ƂɂȂ�܂��B
�ł́A���̏h��A�u�����^��ݔg���i�قځj�����ɎE������Ԃł́A�W�g��N�A�R�g��N�ɂ�� WO �� SW �̉ߓn�����f�[�^���Z�߁i�f�[�^�[���W�͊����ς݁I�j�v�@�Ɏ�肩����܂��B�@
��������A����́u���}���P�O�g����A��ݔg�ƔƐl���m�F�I�v�Ɠ��l�ɁA�Y��ȃf�[�^�������Ă���܂��B
�����ԍ��F24540644
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
SW�����܂����ˁA���炵���ł��B
15kHz�g���K�[��500Hz�̃E�[�t�@�[�A�X�R�[�J�[���ꂼ��̒P�i�g��g�`�ŁA�R�̂��ꂪ����̂��C�ɂȂ�܂��ˁB
�����ԍ��F24540783�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
15 kHz �̃g���K�[�́A���Ƌ�ʂ��邽�߂ɂ��Ӑ}�I�ɒc�q�^�ŁA 2 ms �� 15 kHz �𑽐��g�œ���܂������A���̊J�n���Ԉʒu�����m�ɔc���ł�������̂ŁA���̃Q�C���i���ʁj�́A�ڂ������������g���Ƃ̌��ˍ����ŁA�獷���ʂɐݒ肵�Ă��܂��B
������ 2 ms �̋������ԕ��ł��̂ŁA������g�̃o�b�N�O���E���h�m�C�Y�⍂���g�G���ɏ�������Čv������邽�߁A�c�q�^�̌`�́A�߂ɌX������A�����g�m�C�Y�Ə������ݕϒ����Ă����肵�܂��B
�Ƃ����킯�ŁA�g���K�[�c�q�́A�����܂Ŏ��Ԉʒu�[���̃}�[�J�[�Ƃ��Ă����̋@�\�ł��̂ŁA�����`���c��ł����ɂ��Ă��܂���B
����̏c�꒼���p���X�̈ꔭ�^���ƃr�W���A����}���@�́A�����ɂ悵������w�E���ꂽ�悤�ɁA
�P�D�u�G�l���M�[�s�[�N�}�b�`���O�ɂ��^�C���A���C�������g����Ɣ������v
�ł����A����`�����́A���̕��@�́A
�Q�D�u�g�`�}�b�`���O�ɂ��^�C���A���C�������g����Ɣ������v�@
�ł��ˁB
�����Z���ԕ��i0.5�b�ȉ��j�̂R�`�P�O�g��`���͂ɑ���SP�������A��ɐ��K���z�^�̃G�l���M�[���������̂Ȃ�A�P�D�Ɓ@�Q�D�Ŋϑ������x������v���Ă����������Ȃ��ł��傤�B
�G�l���M�[�̎R�̋}�s�x���قȂ��Ă��A�R�S�̂����s�ړ�����ΎR�������������ړ�����킯�ł��̂ŁB�B
���̃V�X�e���ł́A�K���ɂ��ASW�� 31.5 kHz �����́A��r�I�Y��Ȑ��K���z�ɋ߂��̂ŁA�Q�D�̕��@�ł��P�D�Ɠ����x�����m�F�ł����A�ƍl���Ă��܂��B
����ƁA�Q�D�̃r�W���A���@�ŃG�l���M�[�s�[�N�i���ɒቹ�����j�̒����ʒu��������ۂɂ́A���o�I�ɔ��f���₷���悤�ɐ���\���̃J���[�X�P�[���i�K���}�l��O�a�A����j�����܂����A����́A���삪���E�ǂ��炩�ɕ����R�ł����Ă��A�R���t�߂̐��K���z�ɋ߂������݂̂��o���ĎR���ʒu����肷�邱�Ƃɑ������܂��̂ŁA�����̐��암���̕�iSW�ł́A�]�k��o�X���t��C�U���Ŏ��Ԏ��i�s�����֍L����X���j�����܂���菜���āA�R���t�߂̍��G�l���M�[���������Œ��S�i����j�ʒu�����߂Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�]���āA���Ȃ��Ƃ��A���X�x���ʂ��傫���Ȃ��A������SW�������x�����Ă���A���̃V�X�e���ł́A�P�D�A�Q�D�̂�����ł��A�قړ������ʁi16 ms�@�̂���)�����肳�ꂽ�Ƃ��������ł��B
�P�D�A�Q�D������̕��@�ł��A����p�M��������Đ��A�^�����邾���Łu�eSP�Ԃ̑��Βx���v������ł��܂��̂ŁA�ȕւōČ����ǂ����p�ł��܂��B
�����́A�P�D�̕��@�ł́A�\�ߌ����Ɋ��m�̎��ԗʂ������炵�Ď��g�����قȂ�p���X���쐬���Ă������Ƃ��L���A�~�\�@�ł��B�x�����Ȃ���A�M���Ɠ������ԊԊu�̍Đ��ɂȂ�܂����A�x��������ꍇ�ɂ́A ms���x�Ő��m�ɒx���ʂ�����ł��܂��B�܂��A15 kHz �̃g���K�[��_�i�[�������_�j��݂��邱�ƂŁA�����f�W�^�����M����̐�Βx���Ƃ͖��W�ɁuSP���j�b�g�Ԃ̑��Βx���v�𐳊m�ɔc���ł��邱�Ƃ��A�P�D�̕��@�̗��_�ł��B
�����ԍ��F24541139
![]() 0�_
0�_
��L������܂��̂ŁA�ē��e���܂��B
��̓��e�́A�������ĉ������B
�����ɂ悵����
15 kHz �̃g���K�[�́A���Ƌ�ʂ��邽�߂ɂ��Ӑ}�I�ɒc�q�^�ŁA 2 ms �� 15 kHz �𑽐��g�œ���܂������A���̊J�n���Ԉʒu�����m�ɔc���ł�������̂ŁA���̃Q�C���i���ʁj�́A�ڂ������������g���Ƃ̌��ˍ����ŁA�獷���ʂɐݒ肵�Ă��܂��B
������ 2 ms �̋������ԕ��ł��̂ŁA������g�̃o�b�N�O���E���h�m�C�Y�⍂���g�G���ɏ�������Čv������邽�߁A�c�q�^�̌`�́A�߂ɌX������A�����g�m�C�Y�Ə������ݕϒ����Ă����肵�܂��B
�Ƃ����킯�ŁA�g���K�[�c�q�́A�����܂Ŏ��Ԉʒu�[���̃}�[�J�[�Ƃ��Ă����̋@�\�ł��̂ŁA�����`���c��ł����ɂ��Ă��܂���B
����̏c�꒼���p���X�̈ꔭ�^���ƃr�W���A����}���@�́A�����ɂ悵������w�E���ꂽ�悤�ɁA
�P�D�u�G�l���M�[�s�[�N�}�b�`���O�ɂ��^�C���A���C�������g����Ɣ������v
�ł����A����`�����́A���̕��@�́A
�Q�D�u�g�`�}�b�`���O�ɂ��^�C���A���C�������g����Ɣ������v�@
�ł��ˁB
�����Z���ԕ��i0.5�b�ȉ��j�̂R�`�P�O�g��`���͂ɑ���SP�������A��ɐ��K���z�^�̃G�l���M�[���������̂Ȃ�A�P�D�Ɓ@�Q�D�Ŋϑ������x������v���Ă����������Ȃ��ł��傤�B
�G�l���M�[�̎R�̋}�s�x���قȂ��Ă��A�R�S�̂����s�ړ�����ΎR�������������ړ�����킯�ł��̂ŁB�B
���̃V�X�e���ł́A�K���ɂ��ASW�� 31.5 kHz �����́A��r�I�Y��Ȑ��K���z�ɋ߂��̂ŁA�P�D�̕��@�ł��Q�D�Ɠ����x�����m�F�ł����A�ƍl���Ă��܂��B
����ƁA�P�D�̃r�W���A���@�ŃG�l���M�[�s�[�N�i���ɒቹ�����j�̒����ʒu��������ۂɂ́A���o�I�ɔ��f���₷���悤�ɐ���\���̃J���[�X�P�[���i�K���}�l��O�a�A����j�����܂����A����́A���삪���E�ǂ��炩�ɕ����R�ł����Ă��A�R���t�߂̐��K���z�ɋ߂������݂̂��o���ĎR���ʒu����肷�邱�Ƃɑ������܂��̂ŁA�����̐��암���̕�iSW�ł́A�]�k��o�X���t��C�U���Ŏ��Ԏ��i�s�����֍L����X���j�����܂���菜���āA�R���t�߂̍��G�l���M�[���������Œ��S�i����j�ʒu�����߂Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�]���āA���Ȃ��Ƃ��A���X�x���ʂ��傫���Ȃ��A������SW�������x�����Ă���A���̃V�X�e���ł́A�P�D�A�Q�D�̂�����ł��A�قړ������ʁi16 ms�@�̂���)�����肳�ꂽ�Ƃ��������ł��B
�P�D�A�Q�D������̕��@�ł��A����p�M��������Đ��A�^�����邾���Łu�eSP�Ԃ̑��Βx���v������ł��܂��̂ŁA�ȕւōČ����ǂ����p�ł��܂��B
�����́A�Q�D�̕��@�ł́A�\�ߌ����Ɋ��m�̎��ԗʂ������炵�Ď��g�����قȂ�p���X���쐬���Ă������Ƃ��L���A�~�\�@�ł��B�x�����Ȃ���A�M���Ɠ������ԊԊu�̍Đ��ɂȂ�܂����A�x��������ꍇ�ɂ́A ms���x�Ő��m�ɒx���ʂ�����ł��܂��B�܂��A15 kHz �̃g���K�[��_�i�[�������_�j��݂��邱�ƂŁA�����f�W�^�����M����̐�Βx���Ƃ͖��W�ɁuSP���j�b�g�Ԃ̑��Βx�����^�C���A���C�������g�v�𐳊m�ɔc���ł��邱�Ƃ��A�Q�D�̕��@�̗��_�ł��B
�����ԍ��F24541150
![]() 1�_
1�_
BOWS����A�����ɂ悵����
�������ݔg���A�قڊ����ɎE������ԂŁAWO �� SW �̉ߓn�������@�W�g��N�A�R�g��N�@�ő��肵�����ʂ��܂Ƃ߂܂����B
���Ԏ�����уQ�C�������܂߂ăL���v�`�����A�W�g��N�@�Ɓ@�R�g��N�@�̔g�`��r���e�ՂɂȂ�悤�ɔz�u���Ă���܂��B
���낢�댩���āA�ʔ����ł��ˁB
�@
Yamaha 30 cm JA-3058 �́A���ł��A�Ȃ��Ȃ��D�G�ŁA�u������Ƃ���ꂩ�ȁH�v�Ɗ�����������p���Ă���܂��B
���߂�Ȃ��� JA-3058�I
�܂��܂��撣���Ă܂��ˁB�@���ꂩ�����Ɉ��p���܂��B
���ɁA��̓��e�ŋ��L�����悤�� SW �Ƃ̃^�C���A���C�������g�������ɍ��킹���̂ŁASW��WO���ꏏ�ɉ̂킹�Ă��A������̉ߓn�������L�ӂɉ��P���ꂽ��ۂ�����܂��B
SW�́A�t�F�[�h�A�E�g���� 31.5 Hz�ł̓R�[���̂Q��]�k������A63 Hz �ł̓R�[���]�k�͂قڂP��Ŏ��܂�܂����A���̌�Ƀw�����z���c���̋�U���c��܂��B
��͂�SW�́A���݂�EKIO�ݒ�ł���u50 Hz�F-12 dB/Oct�v �Ő�AYST-SW1000 �g���� -24 dB/Oct �n�C�J�b�g�@�\���A58 Hz ������ɐݒ肷�邱�Ƃ��D�܂����悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F24542224
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�����̃g���K�[���́A15k�g���̃}�[�J�[�ō��킹�Ă���̂ł��ˁH
WO�̒Ǐ]���͂ƂĂ��悭�āA1kHz�ł�1�g�ڂ��痧�オ���Ă��܂��ˁB
SQ��WO��500Hz�ASQ��TW��6kHz�̊W�͂ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F24543210
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
SW �� WO �̏d�Ȃ蕔���ŁA�u�x����������v�A�u�x�������Ȃ��v�@�̔�r�ł����ASW��WO�T�E���h�̃Q�C�����قڍ��킹�āA�đ��肵�܂����B
�܂��A�uWO-only �̘^���g�`�v�A�@�uSW-only �̘^���g�`�v�A�@�uWO+SW �̘^���g�`�v�@��������ƕ\�����āA������₷���v���[���V�[�g��Y�t�̂悤�ɍ���Ă݂܂����B
�����ԍ��F24543267
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
�������̃g���K�[���́A15k�g���̃}�[�J�[�ō��킹�Ă���̂ł��ˁH
�ߓn��������̘b�ł����H�@
�ߓn��������ł́A�g���K�[�͉��̊W���Ȃ��i���̐ݒ���Ȃ��j�A��N�M���Ɣ�r���Ă��邾���ł���I
�����ԍ��F24543269
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
��SQ��WO��500Hz�ASQ��TW��6kHz�̊W�͂ǂ��ł��傤���H
��������@�u�}�S�@16 ms �x���� ST,TW,SQ,WO �ɐݒ肷��ƁA�قڊ����ɑ��Βx���͂Ȃ��Ȃ�I�v�@�i�����ł��Ę^�j�́A�^���M���p���X�̊e�J�n�����́A�e�p���X�����Ԋg�債�Ĉʒu�𐳊m�ɓǂ����ł��I
�]���āAST, TW, SQ, WO �̑��݊Ԃł́Ams ���x�Œx���̓[���ł��B
�ł��̂ŁA���ڂ������ 500 Hz ����� 6 kHz �ɂ�����q���蕪�͂́A�^�C���A���C�������g�@�̊ϓ_����́A���Ȃ����Ƃɂ��܂����B
�����A�ƂĂ��ƂĂ����܂������A�u�`�b�A�s�b�A�v�b�A�A�|�b�A�{�b�A�u�[�v�@�̉������炵�Ă���ƁA�{���ɕϐl��������Ă��܂��̂ŁA�x������Ɣ������A�ߓn��������A��������A������őł��~�߂ɂ��܂��I
��̔�������ݔg�̖��E�����U�P�����Ȃ��ƁA�A�A���������ɂ��ĉ������I�@�ƌ����Ă���܂��B
��U�P�����āA���r���O�����X�j���O���[����Еt���āA���y�ӏ܂ɖ߂�܂��B�@���̃R�[�i�[�̎Չ���́A�����p�����܂����B�B�B
�����ԍ��F24543277
![]() 2�_
2�_
dualazmak����
�������A�ƂĂ��ƂĂ����܂������A�u�`�b�A�s�b�A�v�b�A�A�|�b�A�{�b�A�u�[�v�@�̉������炵�Ă����
�����l�ł����B�����Ƒ����ł���悤�ɂȂ�܂���A
�����ł̓J�[�y�b�g���O�~�ɂ�����A�X�s�[�J�[�ʒu�����A���j�b�g�����Ŋm�F���ĉ������Ă܂��B
dualazmak����̕��@��1��������PC�œǂ݃f�B���B�m�F�Ȃ̂ŁA�o���h���m�F�܂߁A�����ƌ����Ԃŏo�������ł��ˁB
����I�����B
��ST, TW, SQ, WO �̑��݊Ԃł́Ams ���x�Œx���̓[���ł��B
�����ڂ������ 500 Hz ����� 6 kHz �ɂ�����q���蕪�͂́A
�N���X�̓^�C���A���C�������g�łP�ԑ厖�ȂƂ���ł�
�t�������W�ɑ���}���`�̌��_�͑ш�Ƀ��j�b�g�Ԃ̂Ȃ��ڂ��o���Ă��܂����ł����AEkio�Ńl�b�g���[�N���Ȃ��Ȃ�A�d�C�I�Ȉʑ��Y�����Ȃ��Ȃ����̂ł��傤�ˁB
Wo��Sq�̓{�C�X�R�C���ʒu���O��ɂTcm���炢�Y���Ă������A0.1ms�͕�l�����肻���ł��A����q���蕪�͂�����Ă��悢�����A��̖{���͋��ɁA�ɂԂ����Ǝv���܂��B
����U�P���A���̃R�[�i�[�̎Չ���́A�����p��
�����h�A�J���Ȃ��̂ł́H
�����ԍ��F24545347�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
ASR Forum �ł��A�܂��Q�́u�^�C���A���C�������g����ƒ������@�v�𓊍e���܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1048913
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1049923
�����ɂ悵����̂����͂Ƃ������ɁA�[�����Ӑ\���グ�܂��B
��dualazmak����̕��@��1��������PC�œǂ݃f�B���B�m�F�Ȃ̂ŁA�o���h���m�F�܂߁A�����ƌ����Ԃŏo�������ł��ˁB
������I�����B
�������ɁA�}�C�N�����ݒ肵�Ă���A�u�����Ƃ����ԁv�@�Ŋ����ł��I
ASR Forum �ł��A�ǂ�ȃ��X��ӌ������邩�A�y���݂ł͂���܂��B
���t�������W�ɑ���}���`�̌��_�͑ш�Ƀ��j�b�g�Ԃ̂Ȃ��ڂ��o���Ă��܂����ł����AEkio�Ńl�b�g���[�N���Ȃ��Ȃ�A�d�C�I�Ȉʑ��Y�����Ȃ��Ȃ����̂ł��傤�ˁB
�S�������ł��BLC�l�b�g���[�N�̔r���́AWO�̉ߓn�����̉��P�ɂ��傫����^���Ă��܂��B
��Wo��Sq�̓{�C�X�R�C���ʒu���O��ɂTcm���炢�Y���Ă������A0.1ms�͕�l�����肻���ł��A����q���蕪�͂�����Ă��悢�����A
������A����ɓ����Ă���܂��B�����A 500 Hz �t�߂ł� 0.1 ms �P�ʂ̒x���ݒ�́A�g�`�I�ɂ��A���o�I�ɂ��A���ʂł��Ȃ����x�����낤�ȁA�ƍl���Ă���܂��B�@�ɂ��ł�����i�I�~�N�����ő��Z�����Ă���I�j�A�g���C���܂��B
����U�P���A���̃R�[�i�[�̎Չ���́A�����p��
�������h�A�J���Ȃ��̂ł́H
�ړ����邱�Ƃŋ�������ꂻ���ȁA�u�X�|���W�~���v��u�v�`�v�`�ɏՍނ̒��ڊ����v��u�����Ƃ��l�����ł��B
�C���e���A�I�ɂ����e�ȑD�܂����̂ŁA�u�v�`�v�`���ڊ����v�����i���V��܂Őςݏグ�邱�Ƃ́A���ۂ��ꂻ���ł����B�B�B
�����ԍ��F24545865
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
�@�o�x��Ă��݂܂���ł����B
�@�܂��܂��ǂ����Ă��܂���...�k���ăX�������܂����B
�����ԍ��F24529800�@�� YST-SW1000�̂P�O�g�g�`����Ă��炢�@���肪�Ƃ��������܂����B
�@�X�y�N�g�������L����Ă��ā@�悭�킩��܂����B
�@10�g���͒��͒Ǐ]���Ă��܂����A�U��������������@31.5Hz ����� 63Hz�ƈقȂ���g���ŋ쓮������ɁA������YST���U���g���Ǝv���铯��ш�ł��炭�U�����p�����Ă��܂��ˁB
�@
�^�C���A���C�����g�̉����͂킩��₷���ėǂ��ł��ˁB
15msec�̒x���́@EKIO�Ȃ�ł͂̕�ł��ˁB
�����ԍ��F24534535
>���̕��@�́A���E�I�Ɍ���ƁA�N�������ɂ���Ă������ȕ��@�ł����Aweb�ł��A���ȏ��ł��A�I�[�f�B�I���Ђł��A���������L��������܂���B
�@B&W�@�I���W�i���m�[�`���X�̂悤�ɁA�`�����f�o�܂Ŋ܂߂ă}���`�A���vx�}���`�E�F�C�X�s�[�J�[���V�X�e��������Ă�����̂��ALINN�̍ŏ�ʃV�X�e���̂悤�ɁA�}���`�A���v���������ꂽ�X�s�[�J�[�Ȃ炠�肻���ł����@�悭�m��܂���B
�@�ɂ߂Đ����h�̂܂��Ƃ��ȕ��@���Ǝv���܂��B
�@�X���ɏ]���ā@�^�C���A���C�����g�������Ă����l���悭�킩��܂��B
�ڂ����ǂ�Ł@�܂��R�����g���܂��B
�@�Ƃ���Ł@�}�C�N��ECM8000���g�p���Ă���悤�ł����AADC(�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X)�́A�������g���ł��傤���H
�@�V�X�e���ɒx���v�����܂܂��̂ň�Ԋm���Ȍ����́A�X�s�[�J�[�o�͂��R�������̂Ł@�@��ch�^�C�v��ADC�Ȃ�A�}�C�N�ƃX�s�[�J�[�[�q�o�͂��ɘ^���ł���ȂƎv���܂����B
�@
�@�Ȃ��A�^�C���A���C�����g�Ɋւ��ā@�����ɂ悵���P���T�C���g�ł̕]�����Ă͈̂Ӗ�������܂��B
�@�����a���A�ʕ{�r�K���u���j�E�F�[�u�X�s�[�J�v�Œ����ȃX�s�[�J�[�̒P���T�C���g���v�������f�[�^���f�ڂ���Ă��܂����B
�@
https://jbl43.net/JBL4344l.html
�@JBL4344 4way�Ńc�B�[�^���X�p�[�c�B�[�^�̓z�[���ł��B�N���X�I�[�o�[�́@320Hz,1.3KHz,10KHz
�@
�@�P���T�C���g���ƁA�^�C���A���C�����g�ȊO�̃��j�b�g�̋��U���A�d�Ȃ肪�킩��܂��B
�@�����T�C���g�̕����U��������ނ̂Ŕg�`�͂��ꂢ�ɂȂ�܂����A�ߓn�������݂����̂ŒP���̕����킩��₷���ł��B�X�y�N�g���͑J�ڂ���̂ŗ���܂���
�@���̊G���ł́@�S�Ă̎��g���łP�g���Ɏ��Ԃ����K������Ă����Ł@�^�C���A���C�����g�ƌ������ʑ��A���C�����g�Ȃ�ł����A�e���j�b�g�̓����Əd�Ȃ肪�킩���Ėʔ����ł��B
�@���Ƀz�[���h���C�o�{�V���[�g�z�[���̃c�B�[�^�ƃX�[�p�[�c�B�[�^�̐U���̕����ʒu���Ⴄ�̂ŋ��ʂꂵ�Ă���l���悭�킩��܂��ˁB
�@�^�C���A���C�����g������ɂ���Ă���̂łQ�̃��j�b�g�̃Y�����킩��₷���ł����A�^�C�����C�����g���߂��ƕ����g�`���P���̕����������₷���ł��ˁB
�����ԍ��F24546090
![]() 2�_
2�_
BOWS����
���Ƃ���Ł@�}�C�N��ECM8000���g�p���Ă���悤�ł����AADC(�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X)�́A�������g���ł��傤���H
��ŏЉ�� ASR Forum �̂Q�̓��e�ɂ������܂������ATASCAM US-1x2HR ��ʂ�PC�� USB�Ōq���ŁA�^�����Ă��܂��B
���́A�����܂�SP���j�b�g�Ԃ́u���Βx���v�ɍS���Ă��܂��̂ŁA�^���n�őS���ɑ��Ēx���i���C�e���V�[�j�������Ă��A���ꂪ���ƂȂ�Ȃ��悤�ɁA��Ɋ�^�C���}�[�J�[�����ꏏ�ɘ^�������`�ɓO���Ă��܂��B
����Ԋm���Ȍ����́A�X�s�[�J�[�o�͂��R�����i�����j���̂Ł@�@��ch�^�C�v��ADC�Ȃ�A�}�C�N�ƃX�s�[�J�[�[�q�o�͂��ɘ^���ł���
�S���������Ƃ��l���Ă���܂����BAudio-Technica �� high-to-low �R���o�[�^�[ AT-HLC150, AT-HLC-130 �́A15Hz - 40 kHz �S���±1dB �̗D����̂ŁA���̂悤�ȑ���ɂ��g���邱�Ƃ͊m�F���Ă���܂��B
ADC �ɂ����郉�C�����͂ƃ}�C�N���͂̊Ԃ̒x���́A�A�A�Ȃ��ł��傤�ˁB
��JBL4344 4way�Ńc�B�[�^���X�p�[�c�B�[�^�̓z�[���ł��B�N���X�I�[�o�[�́@320Hz,1.3KHz,10KHz
�P�P���ɉ䂪�Ƃɂ���Ă��āA�U�X�V�W���Y�t���[�N�̗F�l�́A�ŋ߁A JBL4344 �̃t�����X�g�A�i���w�����A�Z�b�g�A�b�v���ł��B�I�~�N������������������A����PC�⑪��n������āA�K�₷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�Y�t���������� JBL4344 �̒P���T�C���g�����f�[�^�́A���̗F�l����������ɎQ�l�ɂȂ��Ċ�ԂƎv���܂��B
���́A�ނɁA�u���S�Ƀ}���`�A���v�����āA�����̃f�W�^���h���C���� EKIO ���g���āA�ш敪���ƃ^�C���A���C�������g�������������ǂ����H�v�A�Ƙb���Ă���Ƃ���ł��B���̃X���b�h���A�ŋ߁A�`���Ă���悤�ł��B�@LC�l�b�g���[�N�����S�r��������AJBL4344 ��SP�h���C�o�[�B���A�ǂ̂悤�ɉ������邩�ɂ��A�傢�ɋ�������ł��B
�����̊G���ł́@�S�Ă̎��g���łP�g���Ɏ��Ԃ����K������Ă����Ł@�^�C���A���C�����g�ƌ������ʑ��A���C�����g�Ȃ�ł����A�e���j�b�g�̓����Əd�Ȃ肪�킩���Ėʔ����ł��B
�[���ł��B����n���A�Â�o���ƃL�����Ȃ��ł��ˁB�@
�Z�g�T�C���g�`�ŁA���̃V�X�e���̊eSP���j�b�g�ɓK�������g���ŁA�K�ȃG�l���M�[�𓊓�����A�Ƃ����A���e�X�g�M�����A�ǂ̂悤�ɍ쐬���ׂ����A�l���Ă��܂��B�@��{�I�ɂ́ASony Super Audio CD �̃g���b�N�P�S�̂W�g��N�M�����Q�l�ɂ��āAAdobe Aoudition 3.01 �ō�ꂻ���ɂ��v���܂��B
���̎��g�����N���X�I�[�o�[�����ɍ��킹�āA�Ⴆ�AWO��SQ�̌q����ϑ��Ȃ�AWO�P�ƁASW�P�ƁAWO+SQ�����A�����ꂼ��^�����āA�g�`���r�ώ@�ł��ˁB�@�ɂ��ł���A����Ă݂܂��B
�����ԍ��F24546342
![]() 0�_
0�_
BOWS����
�����ԍ��F24542224
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24004016/?cid=mail_bbs#24542224
�ŁA�����ƒ�ݔg���قڊ��S�ɎE������ԂŁA�W�g��N�ƁA�����]�̂R�g��N�̃f�[�^�����Z�߂Ă��܂��BWO��SW�̗����𑪒肵�Ă���܂��B
�����ԍ��F24546371
![]() 1�_
1�_
BOWS����
�x���ɂ�鐸�x�͂���܂���
�X�s�[�J�[�����̕������o���g���K�[��
OSC�̐��E�Ȃ̂Ő��Z����͓��ӂł����A
��ʐl�͕~��������
�}�C�N�ƃp�\�R���Ŋ���������������
dualazmak����̕��@��
�c�B�[�^�[�͏�ɃI���A15kHz�̊�g���瑪��Ȃ̂�
�����ɉ����u�̔�r�ɂȂ��Ă��܂��B
��g�͐́A�����l�����̂ł����A�c�B�[�^�[�͏�ɃI���̔��z�͂Ȃ������̂ŁA���Ƃ��̗����Ǝv���܂����B
4343�g�`�Ama�̉����ז��ł��ˁA�����́{�ɓ]�����Ƃ���ō��킹�Ă܂����A�ŏ��́{�s�[�N�ō��킹�������悳�����Ɍ����܂��ˁB���������Ȃ��U�����|�����ɍ~��o���Ƃ���Ȃ̂őĐ������Ȃ����ABOWS����͂ǂ����͂���܂����H
dualazmak����
1�g�̏d�v�������F���̂悤�ł��̂ŁA
�����̂��ƁA�������ꂽ��
�N���X�̃��j�b�g���A�����g����0.1ms���݂ŕ�l��������̂ł͂Ǝv���܂��B
Wo��Sq�̈ʒu�Y���ŕ���ق�̂킸������
NS-1000���d�グ�ł�
���F�l�́A�ŋ߁A JBL4344 ���w��
Foo���ڂ�����
�z�[���͂��Ȃ薳���ꒃ�Ȃ̂�
�m�[�}���ƃ}���`�A���v�̍��ɋ������̂ł́B
�z�[�������͉�����
�^�C���A���C�����g�̃m�E�n�E���}�X�g�A
dualazmak���x���̕��͂߂����ɂ��Ȃ��̂ŁA
���F�l�͂��Ȃ�K�^���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24546999�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
��قǁA���}���AWO��SW�̉ߓn�����ɂ��Ă��AASR Forum �ŏ����ڂ����A���e�����L�������܂����B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1051202
�����쐬�����A�Y�t�}�������Ă���܂��B
�����ԍ��F24548367
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
>��ŏЉ�� ASR Forum �̂Q�̓��e�ɂ������܂������ATASCAM US-1x2HR ��ʂ�PC�� USB�Ōq���ŁA�^�����Ă��܂��B
�@�Ȃ��Ȃ��ǂ����ł��ˁB
�@��ʋ@���4CH�̂��~�����Ȃ�܂��ˁB�o����X�s�[�J�[�M���ƃ}�C�N�� 8CH
�@�l�͋�C�^�������Ă����ŔY�݂ǂ���ł��B
>���́A�����܂�SP���j�b�g�Ԃ́u���Βx���v�ɍS���Ă��܂��̂ŁA�^���n�őS���ɑ��Ēx���i���C�e���V�[�j�������Ă��A���ꂪ���ƂȂ�Ȃ��悤�ɁA��Ɋ�^�C���}�[�J�[�����ꏏ�ɘ^�������`�ɓO���Ă��܂��B
�@���u�����x�����ĕ֗��ɂȂ����Ԃ�A�l���邱�Ƃ������܂��ˁB
>�S���������Ƃ��l���Ă���܂����BAudio-Technica �� high-to-low �R���o�[�^�[ AT-HLC150, AT-HLC-130 �́A15Hz - 40 kHz �S���±1dB �̗D����̂ŁA���̂悤�ȑ���ɂ��g���邱�Ƃ͊m�F���Ă���܂��B
�@�l�Ȃ玩�삵���܂��܂����A����͗ǂ������ł��ˁB
>ADC �ɂ����郉�C�����͂ƃ}�C�N���͂̊Ԃ̒x���́A�A�A�Ȃ��ł��傤�ˁB
�@���j�A�A���v�̒x���Ȃ�� usec�I�[�_�[�ł��傤�B
>�P�P���ɉ䂪�Ƃɂ���Ă��āA�U�X�V�W���Y�t���[�N�̗F�l�́A�ŋ߁A JBL4344 �̃t�����X�g�A�i���w�����A�Z�b�g�A�b�v���ł��B�I�~�N������������������A����PC�⑪��n������āA�K�₷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
>�Y�t���������� JBL4344 �̒P���T�C���g�����f�[�^�́A���̗F�l����������ɎQ�l�ɂȂ��Ċ�ԂƎv���܂��B
�@���ɁA�o�b�t���Ƀ}�E���g���ꂽ�~�b�h���j�b�g�Ɓ@�c�B�[�^�̃z�[���h���C�o�Ɓ@�X�p�[�c�B�[�^�̐U���ʒu���傫���قȂ�̂Ł@�g�`�ώ@����Ɩʔ����Ǝv���܂��B
>���́A�ނɁA�u���S�Ƀ}���`�A���v�����āA�����̃f�W�^���h���C���� EKIO ���g���āA�ш敪���ƃ^�C���A���C�������g�������������ǂ����H�v�A�Ƙb���Ă���Ƃ���ł��B���̃X���b�h���A�ŋ߁A�`���Ă���悤�ł��B�@LC�l�b�g���[�N�����S�r��������AJBL4344 ��SP�h���C�o�[�B���A�ǂ̂悤�ɉ������邩�ɂ��A�傢�ɋ�������ł��B
�@��������Ƃ˂�.....JBL�̃X�^�W�I���j�^�[����Ȃ��ā@B&W�ɂȂ��Ă��܂������ł���(��)
>�Z�g�T�C���g�`�ŁA���̃V�X�e���̊eSP���j�b�g�ɓK�������g���ŁA�K�ȃG�l���M�[�𓊓�����A�Ƃ����A���e�X�g�M�����A�ǂ̂悤�ɍ쐬���ׂ����A�l���Ă��܂��B�@��{�I�ɂ́ASony Super Audio CD �̃g���b�N�P�S�̂W�g��N�M�����Q�l�ɂ��āAAdobe Aoudition 3.01 �ō�ꂻ���ɂ��v���܂��B
�@�����m��������܂��Awave gene �g���ƊȒP�Ɂ@�C�ӎ��g���A�o�̓��x����wav�t�@�C�������܂��B
https://efu.jp.net/soft/wg/wg.html
�����ԍ��F24549178
![]() 2�_
2�_
BOWS����
�������m��������܂��Awave gene �g���ƊȒP�Ɂ@�C�ӎ��g���A�o�̓��x����wav�t�@�C�������܂��B
�����ł����Bwavegene �ȑO�����g���Ă܂����B�������A�ǂꂩ��PC�ɂ͎d����ł���͂��B�B�B�@�ɂ��ł�����g���C���܂��B
�Ƃ���ŁA�����]�̂R�g��N�������ɂȂ��āA�A���v������Yamaha 30 cm JA-3058 �̉ߓn�����́A�ǂ��v���܂����H
�����ԍ��F24542224
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24004016/?cid=mail_bbs#24542224
�����ԍ��F24549415
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����
����́@�u�������˂̔Ɛl�{���v�@�̌��ł����A�u����̒�ݔg����Ɛl�{���Ɏg���܂��B�v�Ƃ̎�|�ɂ��āAASR Forum �ł����e�����L���Ă���܂��B���ɂȐ܂�ɁA���Η��������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/post-1055285
�����ԍ��F24552984
![]() 1�_
1�_
�����A���A�C�����܂������A���̃X���b�h�̕ԐM�����A���낻��P�W�O���ɂȂ�܂��ˁB
BOWS���� and/or �����ɂ悵���� ���琔���̃��X�������Œ��Ղł��܂�����A�y���U....�z �̐V�X���𗧂��グ�āA���z���p�����邱�Ƃ��l���܂��B
�����ԍ��F24553002
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
���A�l�ŁA�����ɂ悵���A�u�v���p�̈ړ��d�ʂ��y���ĉߓn�������悳������30 cm �ȏ�̃E�[�t�@�[�͌����̗]�n���肩���H�v�Ƌ��̈Ӗ����A�����������Ă��܂����B
�Ⴆ�AEMINENCE "NEODYMIUM SERIES" �́@KAPALITE 3012HO �́A�W���ŐU���n�d�� 47 g�A���x 100.5 dB (1W/m) �ŁA��r�I���������L���r�l�b�g�i28 - 76 L�j�ł��g�������Ɍ����܂����A�������씠�ŊȒP�ɗV��ł݂�Ȃ�A���̂�����ł����ˁH
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/175667/?gclid=Cj0KCQiAraSPBhDuARIsAM3Js4qpJ4kH8EVQdojX6MMNSrPBnHucxOaJnmF5oa6EF8yydVYscB48yQsaAs8OEALw_wcB
����ł́A���̎�� PA�p�E�[�t�@�[�́A�u�o�^�o�^�U���n�ŁA�ƒ�� HiFi �I�[�f�B�I�ɂ́A����݂܂����I�v�Ƃ̐��������܂��̂ŁA���Ղɔ�т����Ƃ͂������܂��B�B�B�B
�����ԍ��F24555009
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
���������씠�ŊȒP�ɗV��ł݂�Ȃ�A���̂�����ł����ˁH
�Ȃ��Ȃ��悳�����ł���
���o�^�o�^�U���n�ŁA�ƒ�� HiFi �I�[�f�B�I�ɂ́A����݂܂����I
���Ŏ���ł��傤�BEkio�̔\�͂Ȃ炢����Ǝv���܂��BSW1000�����ė���邩�ł���
�����ԍ��F24555924
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����ABOWS����
�T�C���P�Ɣg�ɂ��V���[�Y�̗�N�M������肵�܂����B
���̃N���X�I�[�o�[�|�C���g���g���i50 Hz �t�߂� 500 Hz �t�߁j��O���ɒu���āG
3.000 �b�� 10 kHz �̃}�[�J�[
3.200 �b�� 1 kHz �T�C���P�Ɣg
3.400 �b�� 500 Hz �̃T�C���P�Ɣg
3.600 �b�� 100 Hz �̃T�C���P�Ɣg
4.000 �b�� 50 Hz �̃T�C���P�Ɣg
4.400 �b�� 40 Hz �̃T�C���P�Ɣg
4.800 �b�� 31.5 Hz �̃T�C���P�Ɣg
�̍\���ł��B
�������̒ʂ�AWO �� SW�@�ɑ��� 0.5 ms �X�e�b�v�Ń[���x������ 7 ms ���Βx���܂ł̂P�T�X�e�b�v�� EKIO �̃O���[�v�x���i�Q�x���j�Őݒ肵�āAWO��SQ�̌q���蕔���� 500 Hz�����ڍׂɋ�C�^�����܂����B
�����̂悤�ɁA����̂W�g��N�ł��m�F���Ă����悤�ɁAWO �� SQ �ɒx���͂Ȃ��A �ق� 0.2 ms�P�ʈȉ��̐��x�� SQ��WO�̊Ԃł́A�x���[�����œK�ł��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B
�]���āASQ�A WO �̂�������A SW�ɑ��Ă� 16 ms �x���ݒ�Ŋ����ł��B
���}�n�� NS-1000 ��v����ۂɁA�ǂ�قnj����ȃ^�C���A���C�������g����⒲��������Ă����̂��m��܂��A�A���v������ SQ �� WO �̊ԂŁAms�I�[�_�[�Œx�����Ȃ��Ƃ��������ƃ��}�n�̐v�ɂ́A��������ł��B
�ώG�ɂȂ�̂ŏ����܂���A�Љ�܂��A ST-TW�@�ԁATW-SQ �Ԃɂ��x�����Ȃ����Ƃ��A���R�̂��ƂƂ��đ��聕�m�F���Ă���܂��B
�������A�S���ڂ̐}�̂悤�ɁA(ST+TW+SQ+WO) �� SW�ɑ��� 16 ms �x�������邱�ƂŁASW�������Ɉ�v�������邱�Ƃ��A����̂W�g��N�Ɠ��l�ɁA���̒P�Ɣg��N�ł��m�F���܂����B
�P�Ɣg��N�ł��A50 Hz ������ł� SW �� WO ���A�Q�C�R�g�̗]�k������܂��ˁB�@����́ASQ ����� WO �� 500 Hz �ߕӂł��A���l�ł��B
��ӁA������������Ă����̂ŁA�����͐Q�s���C���ł��B
�����ԍ��F24556916
![]() 1�_
1�_
�����ł��B
��j�@�������̒ʂ�AWO �� SW�@�ɑ��� 0.5 ms �X�e�b�v�Ń[���x������ 7 ms ���Βx���܂ł̂P�T�X�e�b�v���A�A�A
���j�@�������̒ʂ�AWO �� �wSQ�x�@�ɑ��� 0.5 ms �X�e�b�v�Ń[���x������ 7 ms ���Βx���܂ł̂P�T�X�e�b�v���A�A�A
�����ԍ��F24556991
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
���肨���l�ł��A���₷���ł��˃A�v���͉������g���ł��傤�H
Sq��Wo�̎��Ԃ��ꂪ����悤�Ɍ����܂��A�ǂ̒��x�ł��傤�H
�����ԍ��F24557833
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
��Sq��Wo�̎��Ԃ��ꂪ����悤�Ɍ����܂��A�ǂ̒��x�ł��傤�H
�������I�̂��ώ@�ł��B�@�\�z���ꂽ�i�j������ł��B
���̊g��}�ł����̂悤�ɁA�����́u����v�́A�����̑O��W�ɂ�铞�B���ԍ��ł͂Ȃ��A�uSP�U���n�̊������[�����g�̍��v�ɂ�铮���́u����v�ł��I
�܂�AWO�̐U���n�� SQ�i���y��Be�h�[���j�Ɋr�ׂ�ꡂ��Ɋ������[�����g����i���ʂ���j�ł��邽�߁A�����ɓ����M������M���Ă��AWO�R�[���̐U���i�����ł̓T�C���g�ɂ�闧��������ɂ��ŏ��̒�̎��Ԉʒu�j�́A���Ɍy�ʂ�Be�h�[���� SQ �ɑ��� 0.3 ms�قǒx��܂��I
WO�́A���̂悤�ɏ�������������ɂ͏����x��܂����A���̌�͕K���ɐM���ɒǏ]���悤�Ƃ��Ċ撣��܂��B
�]���āASQ�̐U���p�^�[���͗��z�I�ȃT�C���g�`�ɔ��ɋ߂��̂ɑ��āAWO�̐U���p�^�[���́A�N�����������肩��ŏ��̃v���X���R���s�[�N�܂ł̊Ԃ́A���Ԏ��̐i�s�����������āA�ق�̏����������������ꂽ��Ώ̌n�i���S�ȃT�C���g�`�ł͂Ȃ��j�ɂȂ�܂��B
�����x�ꂪ 0.3 ms �ł��̂ŁA���̌�́u�������[�����g���v�ɂ����ɋ͂��ȁu�s�ψ�Ȃ���v�́A0.1 ms �` 0.3 ms ���x�ł���Ɗώ@�ł��܂��B
���̂��߂ɁA�g�`�́u����v�́A�������ԍ��������Ă͂���܂���i�I�j�̂ŁA����ɒx����������ƁA�������ȑ��ݕϒ����܂��B
������ϑ������̂��A�E�}�ł��B
WO�ɑ��āA 0 ms, 0.1 ms, 0.15 ms �̒x�������ꂼ��^����ƁASQ+WO�̋�C�^���g�`�ɂ́A�قƂ�Ǖω�������܂��A 0.2 ms�x���ɂȂ�ƁA�ˑR�A���ݕϒ��ɂ��傫�� �u����A����v ���n�܂�l�q�������������B
������ WO�ւ� 0.5 ms �x���ݒ�ŁA���́u����A����v���ϑ����Ă���܂����̂ŁA�N���X���g���ł��� 500 Hz �݂̂Ȃ炸�A���̑O��ł̃^�C���A���C�������g�������ɂ��z�����āA�����͈��S�����l���A SQ��WO�̊Ԃɂ́A�����Ēx���ݒ��݂��Ȃ����Ƃɂ������܂����B
���̈ȏ�̊ώ@�Ɣ��f�́A���炭�������̂��낤�A�ƍl���Ă���܂����A�������ł��傤���H
�l�X��web���⏑�Ђł��A�^�C���A���C�������g������Ă���ƁA�N���X�I�[�o�[���g���ߕӂŋ�C�^����F����������ł���l�q�𑽁X�݂����܂����A��L�� �u0.5 ms ���炵�ɂ�鑊�ݕϒ�����v�̂悤���́A���������āA������ώ@�����悤�ȋC�����Ă���܂��B
�^�C���A���C�������g�̐������������ɁA���̉��݂��I��EQ�ݒ�Ŏ����グ�ĉx�ɓ��邱�Ƃ́A�u�g�`����������Ɗώ@�v���Ȃ�����A�傢�Ɏד��ł���ƌ��������ł��B
�Ƃɂ����ASW��WO�ł́A�u�U���n�������[�����g�v���傫����������Ă��܂��̂ŁA���Ӑ[������A�ώ@�A���͂Ɣ������i����H�A���Ȃ��H�A�ǂ̒��x�H�j���ƂĂ��d�v�ł��邱�Ƃ��w�т܂����B
�����ԍ��F24558336
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
���A�v���͉������g���ł��傤�H
���ɍ��@�\�Ŏg���₷�� Adobe Audition 3.01 �ł��B
�V�O�i���쐬���A�^�����A�g�`���͂��A�K�v�Ȃ�w�i�m�C�Y�̍팸�������A�Ȃ�ł��ł��܂��B
Adobe Audition �̍ŐV�Ղ́A�������L���ł����A Audition 3.01 �́A�P�O�N�قǑO�ɁA�i���������������H�jAdobe �Ђ��u�����Ȃ��]���Łv�����C���X�g�[���[�����J���܂����B
���ł́A���̃C���X�g�[���[�́AAdobe�Ђ̃T�C�g�ɂ͂������܂��AASR Forum �̗F�l��������A���� web�������ē����̖����Ŗ������ȃC���X�g�[���[����肵�܂����B
ASR Forum �ł́i�ł��j�A�W���I�Ɏg���Ă���̂ŁA���E���̐l�B�Ə�L����ɂ́A�œK�ł��B���ɁA���܂��������Ă���A���̏_��Ȑ���X�y�N�g���\���͏G��ł��B
�����ԍ��F24558370
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
�ŋ߂� 2-way, 3-way SP�V�X�e���̐v�ł́A���炭�����ʒu�̑���ɂ�铞�B���Ԃ������l�����āAWO�������O���֔z�u���āA�����ʒu���������킹�����𑽂̂��������܂����A�u�U���n�������[�����g�̍��v�A���l�������ߓn�����A�����������l������K�v������܂��ˁB
���̓_�ŁA����A�����̗p�����^�C���A���C�������g����n�� EKIO �ɂ�鐳�m�Ȓx�����������g�����ƂŁANS-1000 �L���r�l�b�g + ST + SW �Ȃǂ̋����nSP�Q�i�قړ��ꕽ�ʂ� SP���j�b�g�͈ʒu�j�ɂ����Ă��A�܂����̃}���`�`�����l���A�}���`�A���v�����쓮�ł��A���ɐ��m�ȃ^�C���A���C�������g�������ł��邱�Ƃ�������܂����B
�����ԍ��F24558404
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
Audition 3.01�̂���肪�Ƃ��������܂��A�T���Ă݂܂��B
��Wo�ɑ��āA 0 ms, 0.1 ms, 0.15 ms �̒x�������ꂼ��^���A
��0.2 ms�x���ɂȂ�ƁA�傫�� �u����A����v ���n�܂�l�q������
�����͌��݁A�����ʒu���킹�Ȃ̂ŁA�s�[�N�����ɂ��悤���Ǝv���Ă܂�����
�i���̒��s�[�N�炵���j
�Ȃ�قǁAdualazmak����̌��ʂł��ƁA�����ʒu���킹���悳�����ł���
Wo��Sq�̐U���ʒu�Â��Wo��O�ɏo�����ʂ͂���̂�
NS-1000�̏ꍇ�́A���炩�l�����ꂽ�v�ɂȂ��Ă���̂�������܂���B
�����ԍ��F24558515
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
��Audition 3.01�̂���肪�Ƃ��������܂��A�T���Ă݂܂��B
�����������ƃC���X�g�[���A������a�����\����ł��B
3.0 ���C���X�g�[����A3.01 �ւ̃p�b�`�Ă܂��B
ASR Forum �̌l�ԘA���V�X�e���́A�t�@�C���̂��Ƃ���ł��܂��̂ŁA�����̉���o�^��������āA�l�ԘA���ł��A������������A�i���{��Ŗ��Ȃ��ł��j�A�C���X�g�[���[�A�p�b�`���܂߂āA����`���ł��܂��B
�l�ԘA���ł��A�{���s�v�Ńn���h���������ŏ������A�t�@�C�������\�ł��B�t�@�C���́AZIP������A���ł����Ƃ�ł��܂��B
�����ԍ��F24558533
![]() 1�_
1�_
�����ɂ悵����
��NS-1000�̏ꍇ�́A���炩�l�����ꂽ�v�ɂȂ��Ă���̂�������܂���B
�����A���̂悤�ɑz�����Ă��܂����A�ڍׂ͕s���ł��B
���̂悤�ȁA0.1 ms�P�ʂ̊ώ@�ɂȂ�܂��ƁANS-1000 �I���W�i���� LC-�l�b�g���[�N�iWO��H�ɂ�SQ��H�ɂ��A�傫�ȃR���f���T�ƃR�C������j�ł��A���}�n�͂��܂��������Ă����̂�������܂��B�B�B�B�@LC-�l�b�g���[�N�ƃA�b�e�l�[�^�[�́A���S�ɍ폜�ς݂ł��B
���SP�P�[�u�����O�{�[�h���g���āA�O�t��LC-�l�b�g���[�N�{�b�N�X�o�R�̋쓮�ɊȒP�ɖ߂���Z�b�g�A�b�v�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����A�����܂Ŗ߂��đ��聕��r���鎞�ԂƋC�͂́A�A�A����܂���B
�����ԍ��F24558557
![]() 1�_
1�_
�X���b�h�ւ̕ԐM�����P�X�O���ɒB���܂����̂ŁA���ӂɂł��A�w���T�F�B�B�B�B�x�@�̐V�X�������ĂāA���z���p������悤�ɂ������܂��B
�����ԍ��F24558569
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
Adobe Audition 3.0 ���C���X�g�[���A���s����ɂ́A�t���[�̓K���V���A���i���o�[���K�v�ɂȂ�܂��B
�����������ɂ���a���܂����B
���̂�������AASR Forum �̌l�ԘA���V�X�e���ʼn����ł��܂��B�B�B�B
�����ԍ��F24558583
![]() 1�_
1�_
dualazmak����
���U�����肪�Ƃ��������܂�
ASR Forum �A����o�^���Ă݂܂����AHN��AINIYOSHI
�A���V�X�e�����悭�킩���Ă܂���A��낵�����肢�v���܂��B
�����ԍ��F24559509
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
�@�o�x��܂����B
�@�Q�O�O�ɂȂ�O�ɊԂɍ����܂����B
>KAPALITE 3012HO
�@�p�����[�^����Ɓ@����Ȃ�ɑ傫�ȃG���N���[�W�����K�v�Ȃ��ł��ˁB
�@30L�͂������ɃL�c�C�ƌ������A�w���̑傫����Ԃ��ƃX�s�[�J�[�̖{���̗ǂ����o�Ȃ������ł�
�@�����Ɂ@�����A�_���{�[���̗����J���Č�ʊJ�����Ŏ����Ă݂�Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�@���������y��n�X�s�[�J�[�́@���l�߂Œǂ���������A���o�ŋl�߂��ق������������肵�܂��A
�@SW�ƍ��킹��̂���������ł��ˁB
�@�P���T�C���g�@���肪�Ƃ��������܂��B
�@�A���g���Ƃڂ₯��_�������Ă��܂����ˁB
>�]���āASQ�̐U���p�^�[���͗��z�I�ȃT�C���g�`�ɔ��ɋ߂��̂ɑ��āAWO�̐U���p�^�[���́A�N�����������肩��ŏ��̃v���X���R���s�[�N�܂ł̊Ԃ́A���Ԏ��̐i�s�����������āA�ق�̏����������������ꂽ��Ώ̌n�i���S�ȃT�C���g�`�ł͂Ȃ��j�ɂȂ�܂��B
�@�}���`�E�F�C���邠��ł��ˁB
�@�����̈قȂ�ш�̃X�s�[�J�[�̐܂荇�����������ł��ˁB
>�^�C���A���C�������g�̐������������ɁA���̉��݂��I��EQ�ݒ�Ŏ����グ�ĉx�ɓ��邱�Ƃ́A�u�g�`����������Ɗώ@�v���Ȃ�����A�傢�Ɏד��ł���ƌ��������ł��B
�@������ǂ������邠�܂�A�{���̖ړI�ł���u���y���y���������v�ł͂Ȃ��u���g���������t���b�g�ɂ���v�Ƃ�����i���ړI�ɂȂ����T�^�ł��ˁB
�@���g�����������łȂ��A�^�C�����C�����g�A�c�A���˓��X�̑j�Q�v�����g���[�h�I�t�W�ɂ���̂��I�[�f�B�I�Ȃ�Ł@�ǂ̂ւ�Ő܂荇�������邩���d�v�ł��B
>�Ȃ�قǁAdualazmak����̌��ʂł��ƁA�����ʒu���킹���悳�����ł���
>Wo��Sq�̐U���ʒu�Â��Wo��O�ɏo�����ʂ͂���̂�
>NS-1000�̏ꍇ�́A���炩�l�����ꂽ�v�ɂȂ��Ă���̂�������܂���B
�@���������͑���Z�@���Ȃ��������@�^�C���A���C�����g�Ƃ����l�������Z�����Ă��Ȃ��ăf�B���C�����������ł�����A�������d�˂�NS1000��ǂ�����@�����Ȃ��Ă��Ƃ������Ƃ���Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24559575
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����ABOWS����
���́ASQ��WO�̏d�Ȃ蕔����ǂ����މߒ��ŁA��ςȊԈႢ��Ƃ��Ă���܂����B
�����x��Ă���WO��SQ�ƃ}�b�`���O������ɂ́A�uWO��x�点��v�̂ł͂Ȃ��A�uSQ��x�点��v�̂ł����ˁI
���́A�t�ɓ������Ă����̂ŁA��ԈႢ��Ƃ��Ă��܂����B
���ӁA�����������i���Ԏ��O���j��SQ���������������āA�^���f�[�^�[����蒼���܂��̂ŁA�Q���قǁA���炭�������݂����ɂ��҂����������B�\�������܂���B
�Q�O�O���ɒB����܂łɁI�@�����f�[�^�[���Љ�܂��B
�����ԍ��F24559652
![]() 0�_
0�_
BOWS����A�����ɂ悵����
������������ SQ�������x�������ċ�C�^�����I���܂����̂ŁA���}���C���f�[�^��Y�t���܂��B
�iASR �ł̋��L�O�ɋC�Â��čK���ł����B���p������������ł��B�j
��͂�A�����ɂ悵�����̂悤�ɁA�w�ŏ��̃s�[�N�ō��킹�����ʁx�ƂȂ��Ă��� SQ �� 0.3 ms �x���������g�`���A�ł��D�܂������Ƃ��m�F�ł��܂����B
��⊾���̂ł������A�Q�O�O�����B�O�ɁA���������Ă��������܂��B
�����ɂ悵����
�����A���⍡���AASR ��PM���܂��BAdobe Audition 3.01 �̌��ł��B
�����ԍ��F24559795
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
ASR �ŁAmember�������܂������A�܂� AINIYOSHI ��������܂���B
���̃X���b�h�G
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�ŁA
Hello, it is very nice finding this thread!
�����ł����̂ŁA��������ł݂Ă��������B
�����ԍ��F24559802
![]() 0�_
0�_
�F����A
���̃X���b�h�ł̃��X�i�ԐM�j�������ȃ��X���܂߂ĂP�X0�����܂����B
�ԐM�����Q�O�O���ɒB����ƁA����ȏ�̕ԐM���ł��Ȃ��Ȃ�悤�ł��̂ŁA�V�X���b�h�ֈڍs�������܂��B
�y���U�@�\�t�g�`�����f�oEKIO��DAC8PRO�Ń}���`�A���v�V�X�e���z
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24559812/#tab
�ɂāA���������A��낵�����肢�\���グ�܂��B
�Ȃ��A�����ł��A�p��ł����A���������s���Ă���܂��̂ŁA�������������A���Q���������B
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/multi-channel-multi-amplifier-audio-system-using-software-crossover-and-multichannel-dac.12489/
�����ԍ��F24559813
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
�ȑO�� Adobe Audition 3 �� 3.01�p�b�`�̃C���X�g�[���ɂ��āAASR�̌l�ԘA���V�X�e���ł��b�������Ă��������܂������A���̍ۂɂ́A�������A�����ɂ悵�����Windows 11 (?)�@���ɂ́A���܂��C���X�g�[���ł��Ȃ������̂ł���ˁB
���́A������A�Ƃ���I�[�f�B�I�F�l�Ɠ������Ƃ�b���Ă��āA�ނ� Windows 11 �ւ̃C���X�g�[���ɓ�a���Ă���A������Ɩ{�i�I�ɑŊJ��A�������T�����Ƃ���A���X�̗��Z�i����H�v�j�ŁA�m���ɃC���X�g�[���ł��邱�Ƃ��������܂����B
�v�́A�C���X�g�[���[.exe �t�@�C���i�i�K�I�ɂQ����j�ɑ��āAWindows 11 �ł͂Ȃ� Windows XP ���Ǝv�����܂��Ă��ƁAWi��dows 11 �ւ����Ȃ��d���߂āA���̌�� Windows 11 ��Ŋ����ɋ@�\����A�Ƃ����킯�ł��B
�ڍׂ��K�v�ł�����A��� ASR PM �̑����ł��m�点���܂��̂ŁA�����炩�������������ł����Ă��������B
�܂��́A�����ŏڍׂ����`�����邱�Ƃł��A�S�����Ȃ��ł��B�i���̎��̋��L�C���X�g�[���t�@�C���ނ����茳�ɂ��邱�Ƃ��O��ł��B�j
�ēx�A�C���X�g�[���t�@�C���ނ��K�v�ł�����AASR�@�� PM �ł��A���������B
�����ԍ��F25252777
![]() 0�_
0�_
dualazmak����
���A�����肪�Ƃ��������܂�
ASR PM�ɋL�����܂�����
�X�p�т��s�K�ő��M�ł��Ȃ��悤�ł�
dualazmak����̃��\���͓ǂ߂܂��̂�
�����\�t�g�̃C���X�g�[���@��
�����������܂��ł��傤��
�����ԍ��F25252881�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�X�s�[�J�[]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�ǂꂪ�������߁H�z�d�����Ȃ�ǂ�H���F����3��
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
-
�yMy�R���N�V�����z����\��
-
�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�X�s�[�J�[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j