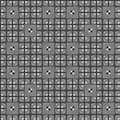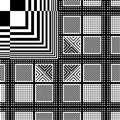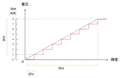OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II �L�b�g
- �L����f����2037����f���ʏƎːϑw�^�uLive MOS�Z���T�[�v�ƁA�]�����3�{�����������摜�����G���W���uTruePic X�v���ڂ̃~���[���X���J�����B
- �m�C�Y�����Z�p�ɂ���p�ōō�ISO 25600�A�g���ōō�ISO 102400�̍����x��B���B�h����E�h�H�ی쓙��IP53�A-10�x�̑ϒቷ���\������Ă���B
- �u5���V���N����Ԃ��v�ōő�8.0�i�A�{�f�B�P�̂ōő�7�i�̕���ʂ������B�W���Y�[�������Y�uM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II�v���t���B
�N���J�x����
�ň����i(�ō�)�F
¥327,800
���͂���̑I��
�������݂̉��i��\�����܂�
- ���͂���n��
����
�ň����i(�ō�)�F
¥209,000 (1���i)
- �t�������Y
-
- �{�f�B
- 12-100mm F4.0 PRO�L�b�g
- 12-40mm F2.8 PRO II �L�b�g


-
- �f�W�^�����J���� -��
- �~���[���X��� -��
�y�t�������Y���e�zM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II
OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II �L�b�gOM�f�W�^���\�����[�V�����Y
�ň����i(�ō�)�F¥310,000
(�O�T��F�}0 ![]() )
�������F2023�N 2��24��
)
�������F2023�N 2��24��
OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II �L�b�g �̃N�`�R�~�f����
�i10855���j���̃y�[�W�̃X���b�h�ꗗ�i�S163�X���b�h�j![]()
| ���e�E�^�C�g�� | �i�C�X�N�`�R�~�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 2023�N6��12�� 21:16 | |
| 23 | 6 | 2023�N6��9�� 13:59 | |
| 26 | 6 | 2023�N6��6�� 13:42 | |
| 440 | 49 | 2023�N4��23�� 03:50 | |
| 71 | 16 | 2023�N4��24�� 23:23 | |
| 1009 | 198 | 2023�N4��25�� 21:26 |
- �u����̍i���݁v�̖��ԐM�A�������͍ŐV1�N�A�����ς݂͑S���Ԃ̃N�`�R�~��\�����Ă��܂�
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 �{�f�B
�����́B
�J���[�N���G�C�^�[�̎g�������킩��Ȃ��Ƃ������APEN-F�ł̐ݒ�̓����ƈႤ�̂Ŏf�������ł��B
�Y�t�̃t�@�C���́APEN-F�ł̃J���[�N���G�C�^�[�̐ݒ��ʂł��B
���̂悤�ɁA�P�Q�̃J���[���Ƃɍʓx�̐ݒ肪�ł��āA������L���ł��܂��B
�C�G���[��+2�A�}�[���_��-1�Ƃ��B
OM-1�̃J���[�N���G�C�^�[�̐ݒ�́A���̂悤�ɃJ���[���Ƃ̐ݒ肪�ł���̂ł��傤���H
�}�j���A���ʂ�Ƀt�����g�_�C�����ŐF�I���A���A�_�C�����ōʓx�̕ύX���s���Ă��A���[�_�[�`���[�g�̌`
�Ɏc��Ȃ��̂ŁA�Ӑ}�ʂ�ɐݒ�ł��Ă���̂��A�悭�킩��Ȃ��̂ł��B
�i�y���^�b�N�X�Ō����Ƃ���́A�J�X�^���C���[�W�̂悤�Ȑݒ�����āAC1�`C4�ɓo�^�������j
�ڂ������A����������������ƍK���ł��B
��낵�����肢���܂��B
![]() 3�_
3�_
�����g����
�܂��I�����p�X�p��ł̓J���[�N���G�C�^�[�ł͂Ȃ��J���[�N���G�[�^�[�ł��B
����́u�摜�S�̂̐F��F��30�i�K�ƍʓx8�i�K�̑g�ݍ��킹�Őݒ�v������̂ŁAPEN-F��OM-1�ňႢ�͂���܂���B
�u12�F�����ꂼ��̍ʓx��±5�͈̔͂Œ����v����̂̓J���[�N���G�[�^�[�ł͂Ȃ��J���[�v���t�@�C���R���g���[���ł��B
�����PEN-F�Ǝ�����p�@E-P7�����̌ŗL�@�\��E-M1�n(OM-1�܂�)�ɂ͑��݂��܂���B
�Ȃ��Â��@���RAW�t�@�C���̓_���ł���(����E-M1��NG��E-M1mk2�ȍ~��OK)�AOLYMPUS/OM Workspace�́u�F�����v�Ƃ���
�J���[�v���t�@�C���R���g���[�������@�\���g���A�u12�F�����ꂼ��̍ʓx��±5�͈̔͂Œ����v���邱�Ƃ͉\�ł��B
�����ԍ��F25298465
![]()
![]() 8�_
8�_
�����A���t�@����
�����̕ԐM�A���肪�Ƃ��������܂����B
���̂Ƃ���AOM Workspace�́u�F�����v�ŁAPowder Blue ���ۂ��v���t�@�C�����쐬���܂����B
�����OM Workspace�ŌĂяo������A�v�����Ƃ͂ł���̂ł����i��{RAW+JPG�ŎB���Ă���̂Łj
�ǂ����Ȃ�J������JPG�̒i�K�œK�p�ł���Ǝv��������ł��B
PEN-F�̕����ȑO����g���Ă����̂ŁAOM-1�ł��Ă�����ł�����̂��Ǝv���Ă��܂����B
�ʕ��Ȃ̂ł��ˁE�E�E�J���[�N���G�[�^�[���������Ă݂Ă��A��ʑS�̂œ���̐F������������̂ŁA
�����Ӑ}�������̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��܂����B
�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25299265
![]() 0�_
0�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 �{�f�B
���N�ɂȂ���OM-1�A�p�i���C�J100-400�Ŗ쒹�B�e���n�߂��҂ł��B
�R�Ŗ쒹�B�e������ꍇ�A�������̓����������A�������}��肪����̂Ńs���g�����킹��̂Ɏl�ꔪ�ꂵ�Ă��܂��B
������P84�ɁAC-AF�Ǐ]���x������܂����A�ʐ^�Ŗ쒹�B�e�̏ꍇ�A�v���X�ɂ���̂��}�C�i�X�̕��������̂��悭�킩��܂���B
�F�l�ǂ��ݒ肳��Ă��邩�A�����Ă��������܂��ł��傤���B
�C��̖쒹�͎B��₷���̂ł����A�т�R�̖쒹�B�e�ɋ�킵�Ă���܂��B
![]() 5�_
5�_
��HDV������������
�쒹�́A����g�}��t���ϓ��ɂ���̂ŁA�s���g���킹���ق�Ƃɑ�ςȂ�ł���ˁB�}�̌��Ԃɂ��邽�߁A������AF�G���A�̃|�C���g���ŏ��ɂ��ĎB�e���Ă��܂��B
�����ԍ��F25294147
![]() 2�_
2�_
�}��肷��Ǝ}�Ɏ����čs����܂��̂ŁA��{�I�ɂ͔F���̓I�t�ŎB���������������Ǝv���܂��B
�������ƑO�s���ɂȂ肪���������̂Ńs���g�ʒu�����ł����炩���ɂ��炵�Ă��܂��B
�����ԍ��F25294176
![]() 3�_
3�_
��HDV������������
����ɂ��́B
C-AF�Ǐ]���x�́A�f�t�H���g�ݒ�̂܂B�e���Ă��܂��B
�V�r�A�ȎB�e�⌺�l�̕��ł���A���x����������Đݒ��ǂ����ނ̂ł��傤���ǁA���͂����܂ł��Ă��Ȃ��̂�����ł��B
>�R�Ŗ쒹�B�e������ꍇ�A�������̓����������A�������}��肪����̂Ńs���g�����킹��̂Ɏl�ꔪ��
���̂悤�ȏł́A�T�ˈȉ��̐ݒ�ŎB���Ă��܂��B
�@�EAF�^�[�Q�b�g�FSingle
�@�EAI��ʑ̔F���FOff
�@�EAF�Ńs���g���킹�����Â炢�Ɗ�������AMF�ɐ�ւ��Ď����Ńs���g�����킹��
�~�܂蕨�Ɠ������́A�J�X�^�����[�h�iC1�`C4�j�Ɏ��O�ݒ�����Ă�������A
Fn���o�[�@�\��mode2�i�H�j��AF�ݒ���ւ��₷�����ĉ^�p���Ă��܂��B
���Ƃ́A�b�����C���ł����ǁA
�}��肵�Ȃ��Ƃ���ɏo�Ă����̂�҂A���ł�����ł��͎B��Ȃ��A�Ƃ��������ł��傤���B
�����ԍ��F25294202
![]() 5�_
5�_
��HDV������������
�U���̂Ƃ��ɒ����B�e���Ă��܂��A�q�X�g���b�J�[�B�e�����C���ł��B
��C-AF�Ǐ]���x������܂����A�ʐ^�Ŗ쒹�B�e�̏ꍇ�A�v���X�ɂ���̂��}�C�i�X�̕��������̂��悭�킩��܂���B
�⋛����ɋ����Ē����āAC-AF�Ǐ]���x�́u+�Q�v�̏r�q�ݒ�ɂ��Ă��܂��B
�����Ē��������e�ł��B�Q�l�ɂ��Ă��������B
�����@�̐ݒ�ɂ��ċ����Ē����܂����B
C-AF�Ǐ]���x�ł����A�ݒ�͕ς����Ă��܂����B
MX-1�͐ݒ��ς��Ă��܂���ł������A���@�ł�-2�u�S��v�ɂ��Ă��܂��B
������ƎԂł͈Ⴄ�Ǝv���܂����C�ɂȂ��Ă��܂����B
�EC-AF�Ǐ]���x��M1X����ς�炸�u+�Q�v�̏r�q�ݒ�ɂ��Ă��܂��B
�EAF�����D��E�E�E�n�e�@�K�������Ŕ�ʑ̂𑨂����邩�H�Ƃ����Ɩ����B�ݒ肪�`�e�����D��ɂ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�e�̓������]�v�ɂȂ��Ă��܂��A���ʂ`�e���x���Ȃ�Ƃ̔��f�ł��B
�E�`�e�X�L�����E�E�E�n�e�@�@���߂��疳���܂ł̊ԂŃs���g�ʂ�T���܂����A����͗]�v�Ȃ��Ƃł`�e���x��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ�Ƃ̔��f�ł��B
�E�`�e�g�E�E�E�E�E�E�E�E�l�P�w�ł͂P�_�i���j������܂������A�n�l�|�P�ł͂`�e�|�C���g���P�O�T�R�_�Ƒ����Ȃ����̂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�P�w���̂P�_�i���j�����������V�r�A�߂��āA�O�r�g�p�E�Õ��B��ȊO�̓��̎B�e�ł�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p���ăs���{�P�������Ƃ̔��f�����Ă��܂��̂Ŏ��͎g�p���܂���B
���Ē��B��ł́A�~�h���`�e�g�`���[�W�g�A�����[�h�ݒ莞�͂���ɉ������[�W�g���g���܂��B
�J�[���[�X�̎B�e�͐��łȂ��̂ŕ�����Ȃ��̂ł����A�t�H�[�~�����[�ł���w�����b�g�Ƀt�H�[�J�X
�����ʑ̌��o��ݒ肷��ł��傤���A�Y�t�ʐ^�̂悤�ɔ��E�X�J�C���C���ł����炠����x�̓J�����C����
�~�h���g�Ńt�����g��_���ł��傤�ˁB
���B��ł͒P����C-AF�����ŎB�����ق����ǂ����ʂ��o�܂��BM1X��OM-1�Ƃ̔�r�ł͒f�ROM-1��
�D�G�ŁA�r���Ńs�����O���Ă�����������̂ŃW���X�s���������ł��B
�܂����x�Ȕ�ʑ̌��o�͐��n����Ă��Ȃ��A�s�����O������̕����ɃX���[�Y�����Ȃ����������܂��B
�����A���𑨂��ĒǏ]���锒�g�̓���������̂�����̐i���ʂŎQ�l�ɂȂ�̂ŁA�����������Č��\
�g���Ă��܂��B
AF�g�P�_�ł́A������Ƃł��O���ƃJ������AF�@�\�ɖ������o�āA���傢�{�P�`��{�P�ƐF�X�ȃP�[�X��
�o��悤�ȋC�����܂��B
���B�肪���ŁA���̉����ォ��J�[���[�X�ɂ��ėސ����Ă��܂����炠���܂ł��Q�l�Ƃ������Ƃ�
���肢���܂��B
�����AC�[AF��TR�p�ݒ肳����OM�̋Z�p�w�̍l�����ɂ́A�ǂ����Ă��[���o���܂���B
�i����TR�����o�ꂵ����������A�e�X�g������2�x�Ǝg���Ă��Ȃ��̂ʼne���͂���܂��ǁj
�����ԍ��F25073084
���N�̓R�A�W�T�V�����Ȃ������ł��B
���ډ����ł����P��UP���܂��B
�����ԍ��F25294249
![]()
![]() 4�_
4�_
��komcom����
��SMBT����
���ł��ł�����
���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�|�C���g���������A�F����OFF�ɂ���Ƃ������ł��ˁB
���ɂ�MF�ŁA�Ȃ�قǁB
�����ԍ��F25294323
![]() 1�_
1�_
��Lola T70 MkIIIB����
�ڍׂȐ������肪�Ƃ��������܂��B
���ꂾ���ׂ̍����ݒ������Ă���̂ł��ˁB
�����Ȑݒ�������Ă݂āA�����̔[���̂����ݒ�ɂ��悤�Ǝv���܂��B
��ʑ̔F���́A�܂��܂��i���̓r���Ɗ����Ă��܂��B
�m���ɒP����C-AF���ǂ���������܂���B
��ώQ�l�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F25294340
![]() 3�_
3�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 �{�f�B
�܂������ƌ����܂��A�����ė~�������Ƃ�����܂��B
EOS����OM-1�ɔ����ւ��āA�F�X�Ǝ����B������Ă��܂��B
�t�H�[�J�X�u���P�b�g�ŎB�e������10���ɂ��Ă�50���ɂ��Ă��A�Đ������5�������ʂ��Ă��܂���B
�Đ��摜�����͎B�e�����Ɠ������Ɨ������Ă���̂ł����A�ǂ��Ȃ�ł��傤���H
�Ⴆ�ΎB�e������10���ɐݒ肷��ƁA�ʂ��Ă���Đ��摜��10�����Ǝv���̂ł����A
���ݒ肪�ǂ����Ԉ���Ă���̂ł��傤���H
���������肢���܂��B
�����ԍ��F25288758�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���܂���������
�t�H�[�J�X�X�e�b�v�̐ݒ萔�l�����������Ă������ł��傤���H
�g�p�����Y�ɂ��Ǝv���܂����A�X�e�b�v�̐ݒ肪�e���A5�R�}�ŎB�e�\�R�}���������ς��Ȃ̂�������܂���B
�����ԍ��F25288823
![]()
![]() 5�_
5�_
Tranquility����A�܂������Ɛ\���܂��A
�����̕ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�B�e����50���A�B�e�X�e�b�v�̐ݒ�l1�ɂ���ƁA30�����B�e�o���܂����B�@
�Đ��摜������ƁA�����Âs���g�̍����Ă�ʒu������Ă���悤�ł���ł����̂��ȁ[�Ǝv���܂��B
�B�e����50���ɑ��čĐ��摜��30��������̂ŁA����ȏ㖇���𑽂��B�e���Ă��Ӗ����Ȃ��ƃJ���������f�����̂����m��܂���B
���肪�Ƃ��������܂����B
����ňꌏ�����ł��B
���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
�����A���̕ӂ̂��Ƃ͎���ɂ͉���������ĂȂ��ł��ˁ[�B
���������B�e�X�e�b�v���ǂ��������̂����A����̐����ł͗��������Â炢�ł��B
�����ԍ��F25288935�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�܂���������
������ȏ㖇���𑽂��B�e���Ă��Ӗ����Ȃ��ƃJ���������f�����̂����m��܂���B
�B�e�����̐ݒ�ɂ�����炸�A�s���g���������ɒB������A�B�e�����~����܂��B
�Ȃ��A�t�H�[�J�X�X�e�b�v�P�łR�O���A�t�H�[�J�X�X�e�b�v�T�i�H�j�łT���Ƃ������Ƃ���l����ƁA���Ȃ�̍L�p�ŁA���邢�́A���Ȃ艓���Ƀs���g�����킹�āA�B��ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����������B�e�X�e�b�v���ǂ��������̂����A����̐����ł͗��������Â炢�ł��B
�u�t�H�[�J�X�u���P�b�g�v���[�h�̏ꍇ�́A�s���g�����킹���ʒu���������ɂ����s���g���ړ�����̂ŁA�v�����ʒu�ɔ�ʊE�[�x�̒��S������悤�ɂ���ɂ͉����Ƀs���g�����킹��Ηǂ��̂��Ƃ��A�B�e�����������ɂ��邩�Ȃǂ́A�o����ςނ����Ȃ������ł��B
�������A�u�[�x�����v���[�h�Ȃ�A�_�����s���g�ʒu�̎�O���Ɖ����̑o���Ƀs���g���ړ����ĎB�e���Č����̂ŁA��ʊE�[�x�̐[���ƒ��S�ʒu���v���ʂ�ɂ���ɂ́A������x�̌o�����K�v�ɂȂ�܂����A�t�H�[�J�X�u���P�b�g�̂悤�ɁA�v�����ʒu�Ƀs���g�����Ȃ��āA�Ƃ�ł��Ȃ��ʒu�Ƀs���g������Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ����A��ō��������Ԃ��Ȃ���̂ŁA��芸�����A�u�[�x�����v���[�h�Ŋ����E�E�E�Ƃ����̂͂������ł��傤���H
�����������́A�u�[�x�����v���[�h�Ő�����͎B�e���Ă���u�[�x�������v�ł����A�p���t�H�[�J�X���D�܂Ȃ����Ƃ������āA�u�[�x�����v���[�h�ŕs�����o���邱�Ƃ͖w�ǂȂ��A�u�t�H�[�J�X�u���P�b�g�v���[�h�́AE-M1�i����j�ɏ����ڂ��ꂽ���Ɏ����Č��������ŁA�ȍ~�́u�[�x�����v���[�h�����g�p���Ă܂��B
�����ԍ��F25289132
![]()
![]() 11�_
11�_
���܂���������
�ݒ肵���t�H�[�J�X�X�e�b�v���ƂɃs���g�ʒu���ړ����Ȃ���B�e���܂��B�r���Ŗ������ɒB������B�e�͏I�����܂��B
�Ƃ���܂��̂ŁA�t�H�[�J�X�X�e�b�v��1�`10�ł��̂ŃX�e�b�v�������Ȃ��ƎB�e��������ɖ������ɒB���Ď~�܂��Ă��܂��̂ł�
�����ԍ��F25289341
![]()
![]() 2�_
2�_
���J���N����A�܂������Ɛ\���܂��B
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
���Ȃ�g������ł�����l�Ƃ������܂����B
�o���Ɋ�Â������ɂ͐����͂�����܂��B
���������Ƃ����Ǝg������Ŏ����Ȃ�Ɍo���l�����������Ǝv���Ă��܂��B
�[�x�����������ł��ˁI��O���牜�܂Ńs���g�������Ă镗�i�ʐ^���B�肽���ł��B
���͉Ԃ̃}�N�����悭�B��̂Ńt�H�[�J�X�u���P�b�g�ɋ������������̂ł����A���܂Œʂ�̎B����Ƃ������A���͎B�肽���Ԃ�������ƒP�œ_�̖��邢�����Y�ŁA�t�H�[�J�X�|�C���g�����炵��5-6������7-8���B��A���̒�����C�ɓ���������I�т܂��B
���̕����������肭��悤�Ɏv���܂��B
�����낢��Ƌ����Ă��������B
��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F25290091�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����89����A�܂������Ɛ\���܂��B
�����̕ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
���������悤�ɃJ���������f���Ď~�܂�悤�ł��ˁ[�B
�g���Ă��鎞�͂Ȃ��Ȃ������܂ł킩��܂���ł����B
��͂艽���������V���b�^�[����Ďg�����܂Ȃ��ƃ_���ł��ˁB
���ꂩ������낢��Ƌ����Ă��������B
��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F25290099�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 �{�f�B
���₳���Ă��������B�n�C���]�V���b�g���Ɏ莝���n�C���]�@�\�𗘗p�������Ǝv���Ă��܂��B�������Ă���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�́ALEICA DG SUMMILUX 15mm�E�E�ALEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm�E�E�A�V�O�}30mm F1.4 DC DN�E�E�E,
LEICA D VARIO-ELMAR 14-150(�t�H�[�T�[�Y�����Y�ɃA�_�v�^�[�� EM 1 MK2�ɑ������Ă��܂�)�ł����A������OM-1�̃n�C���]�V���b�g�@�\�ɋ����邱�Ƃ��\�ł��傤���H���}�w�������������Ă��܂��BMK2�ł͎g�p�������Ƃ��Ȃ��A�ǂȂ��������m�ł����狳���Ă��������B��낵�����肢�������܂��B
![]() 4�_
4�_
��mochmatch����
�n�C���]�͂ǂ̃����Y�ł��B�e�\�ł���B
���ۂ�OM-1�ƃp�i���C�J�����Y����Ńn�C���]�B�e���Ă���܂��B
�����ԍ��F25228506
![]() 12�_
12�_
��Seagulls����
�@�����̕ԐM�A���肪�Ƃ��������܂��@������܂�
�@���������Y�ɔ�r�͂���Ă͂��Ȃ���������܂��A���Ȃ����𑜓x�ŎB�e�ł��Ă��܂��ł��傤���H
�@�����I�ɂ͖��Ȃ��悤�ɂ͎v����̂ł����A�������u���@�\���̊ϓ_�Ń}�b�`���ĂȂ��̂��ƐS�z�ł���
�@
�����ԍ��F25228518
![]() 3�_
3�_
��mochmatch����
�����͎莝���n�C���]���O�r�g�p�Ő���B�e���Ă���܂��̂�
�c�O�Ȃ����Ԃ��Ƃ̑����͎����Ă��܂���B
�ł��Ï���SS���x���Ȃ�悤�ȏŖ�����A�J�����{�̂̎�Ԃ����D�G�Ȃ̂ő��v�ȋC�����܂��B
�ȉ��̃X���b�h�Ŏ����ȊO�̕����摜���A�b�v���Ă���Ă��܂��̂ł��Q�l�܂ŁB
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=24818705/#tab
�����ԍ��F25228541
![]() 6�_
6�_
�����Y�́u�@�\�v�ɂ͈ˑ����܂��A�u���w���\�v�͉e����^����悤�Ɏv���܂��B
�B���f�q�̑f�̔\�͂�4000����f�A6000����f�A�ƍ���f������ƁA�����Y��
�u�A���v��������悤�ɂȂ�̂Ɠ����ŁA�����̃n�C���]�ł����Ă��A�����Y�̐��\��
�J�o�[������̂ł͂���܂���B
�p�i�\�j�b�N�ƃI�����p�X�^�n�l�c�̃����Y�̓t�H�[�T�[�Y�E�l�C�e�B�u�̌��w�n�ł���
�V�O�}��V�O�}��OEM�Ǝv����100-400mm�Ȃǂ́A���傫�ȃt�H�[�}�b�g�p��
�]�p�ł�����A�����ȃt�H�[�}�b�g�ł���t�H�[�T�[�Y�Ŏg���ƁA����l�ɂ���Ă�
���\���s������悤�Ɋ�����Ǝv���܂��B
����̓n�C���]�ɂ��邩�琫�\���s������̂ł͂Ȃ��A���ʂɎg���Ă��Ă��s������
���܂��B100-400mm�͕֗������ǁA�Ȃꂪ�Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă���l�������̂��A
����ȗ��R�ɂ��̂ł��B�����ƃt�H�[�T�[�Y�l�C�e�B�u�̗����Ȗ]���Y�[�����o����
�ق������̂ł��B����̏�͂R�O���~���z��300�o�P�œ_��100���~�N���X��150�|400mm
�Ȃ̂ł�����B�B�B
�����Ƃ��A�s���Ƃ����Ă��t���T�C�Y�p��APS-C�Ŏg�����Ƃ��Ɠ��l�́u�s���v�ł��B
�C�ɂ��Ȃ��l�͋C�ɂ��Ă��Ȃ��悤�ł��B
�i��荂���ȃ����Y�̒��S�������g�����獂���\�Ƃ������������܂����A
���[�W�t�H�[�}�b�g�̃����Y�������ȃt�B�����^�B���f�q�Ŏg���Ɛ��\���s�����܂��B
�t�B��������A������唻�̃����Y��35�o�t�B�����ŎB��̂Ɠ������Ƃł��B
���C�J��135���i���Ō����t���T�C�Y�j�Ƃ����u�����ȃt�H�[�}�b�g�v�p�ɁA�����p�Ƃ�
�i�Ⴂ�ɍ����ׂȃ����Y��p�ӂ����̂ő听�����܂����j�B
����ł��A�n�C���]�V���b�g�Ƃ����������������s�Ȃ����Ƃɔ����A�m�C�Y�ጸ�Ƃ�
�_�C�i�~�b�N�����W���L���Ȃ����悤�Ɋ������邱�ƂȂǂ̌��ʂ́A�����Y���ǂ��ł���
������͂��ł��B
���Q�l�ɂȂ�K���ł��B
�����ԍ��F25228563
![]() 10�_
10�_
��quagetora����
�e������̂̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ł͂Ȃ��A
��f�s�b�`�ł��ˁB
�ł����炱���Ɍ��炸�A
�n�C���]�ł̃V���L�b�Ƃ������𑜂Œ�m�C�Y�ȎB�e���ʂ͂��ڂɂ����������Ƃ͂���܂���B
�����ԍ��F25228618�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
��mochmatch����
OM-1�̃��r���[�ɂ������͏�����Ė����A���̕���������Ă܂����A���Ԃ�[�x�����Ƃ��v���L���v�`���[�݂����Ƀ����Y���ƍ��킹�ĎB�e����@�\�ł͖��������ł��̂Ŏg����Ǝv���܂��B
���܂��܌��������r���[���ƃ����Y���J�����̐��\���Ǝv���܂���
https://www.toshiboo.com/entry/g9highres01
�����ԍ��F25228634
![]() 7�_
7�_
��mochmatch����
�uFAX�v�̗p�����X�L�����������Ƃ͂���܂��ł��傤���H
�����Y�𑜓x�̐��� �R�s�[����FAX�̈�����݂����Ȋ����ɂȂ�܂��̂ŁA
�P�Ƀn�C���]�ɂ���Ζ��X�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�w���O�Ɏ��p�����Ă��炤�������^�����Ċm�F����ق����ǂ����ƁB
�����ԍ��F25228676�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
#quagetora����
WIND2���������ɂȂ��Ă���悤�Ƀt�H�[�}�b�g�T�C�Y�̖��ł͂Ȃ��ł���B
�Z���T�[�̉�f�s�b�`�ɑ��ă����Y�̉𑜗͂��\�����ǂ����ł��B
����荂���ȃ����Y�̒��S�������g�����獂���\�Ƃ������������܂���
����ł͂Ȃ��^���ł��B
�Z���T�[�T�C�Y�ɑ��ăC���[�W�T�[�N�����傫�����������Y�̎��ӕ������g��Ȃ��čςނ̂ʼn摜���ӂ܂ł̉𑜗͂��オ��܂��B
���Ƀ����Y�̏œ_�����Ɖ𑜗͂������Ƃ��ēd�q������őf�̂܂ܔ�r�����ꍇ�A�����̒P�œ_���C���[�W�T�[�N�����傫���V�t�g�����Y�̕������ӂ܂ł̉𑜗͂͏�ł��B
�����A���̕��ł����d���Ȃ�܂����ǁB
�t���T�C�Y�p�̃����Y��APS�ɂ��Ă������I�ɂ͓����ł��B
�����C�J��135���i���Ō����t���T�C�Y�j�Ƃ����u�����ȃt�H�[�}�b�g�v�p�ɁA�����p�Ƃ͒i�Ⴂ�ɍ����ׂȃ����Y��p�ӂ����̂ő听�����܂���
����̓����Y���̂̉𑜗͂��グ������ł����ăt�H�[�}�b�g�T�C�Y�͊W�Ȃ��ł��B
�����ԍ��F25228933
![]() 4�_
4�_
��mochmatch����
�n�C���]�V���b�g��PENTAX�̃��A�����]�����[�V�����́A�Z���T�[�V�t�g��Ԃ������p�����Z�p�Ȃ̂ŁA�����Y�͊�{�I�ɉ��ł�OK�ł��B�����������Y�{�f�B�̋�����Ԃ���[�x�����Z�p�͓d�C�M���̂���肪�K�v�ŁA�������[�J�[���m�łȂ��Ɠ����Ȃ��ꍇ������܂��B
�����ԍ��F25229153�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
���X�e�A�P�C�X����
�i�t���T�C�Y�p�����Y��APS-C�Ŏg���Ƃ��j
>�Z���T�[�T�C�Y�ɑ��ăC���[�W�T�[�N�����傫�����������Y�̎��ӕ������g��Ȃ��čςނ̂ʼn摜���ӂ܂ł̉𑜗͂��オ��܂��B
���̐����͐���������܂���B�u�t���T�C�Y�p�����Y��APS-C�Ŏg���Ƃ��A�C���[�W�T�[�N���̎��ӕ������g��Ȃ��čςށv�ł��B
�i��ʒ������̑��ł��A�����Y���ӕ����g���Ă��܂��j
���̂Ƃ��ɉ摜�̉𑜂��オ�邩�ǂ����̓����Y�Ɖ摜�̉�f���������ł����A35mm���p�����Y��APS-C�Ŏg���Ă������Y���̂̉𑜗͕͂ς��܂���B
�i���C�J�͒����p�Ƃ͒i�Ⴂ�ɍ����ׂȃ����Y��p�ӂ����j
>����̓����Y���̂̉𑜗͂��グ������ł����ăt�H�[�}�b�g�T�C�Y�͊W�Ȃ��ł��B
�����Y�ƃt�H�[�}�b�g�̃T�C�Y�͑傭�W���܂���B
���C�J���𑜗͂��グ�������Y��p�ӂ����̂́A�]�ʐ^�̐��ׂ��ɑ��āA����ȑO�̑傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̃����Y�ł͉𑜗͂��s�����邩��ł��B
�I�����p�X�̓t�B����35mm���n�[�t�T�C�Y��pen�����Ƃ��ɁA�ʏ��35mm���p�����Y�������𑜗͂̃����Y��p�ӂ��܂����B
�t�H�[�T�[�Y�E�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�p�����Y���A35mm���p�����Y���������𑜗͂ō���Ă��܂��B
�ŏI�I�ɑz�肳���ʐ^�̃T�C�Y�Ɩ]�ސ��ׂ��ɍ��킹�āA�t�H�[�}�b�g�ɉ����ă����Y�̉𑜗͂�Ή�������K�v������̂ł��B
�f�W�^���J�����̏ꍇ�A��f�s�b�`�ɍ��킹�ă����Y��p�ӂ���K�v�����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F25229176
![]() 19�_
19�_
���ς�炸�Y���Ă�B
�����ԍ��F25229244�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 11�_
11�_
#Tranquility����
����ς肠�Ȃ��Ƃ͘b�����ݍ���Ȃ��ł��ˁB
�t���T�C�Y�p�����Y���t���T�C�Y�@�ɕt���Ă��āAAPS�N���b�v������𑜓x���オ��Ȃ�Ă��Ƃ͖����ł���B
�܂��Aquagetora���A�u�V�O�}��V�O�}��OEM�Ǝv����100-400mm�Ȃǂ́A���傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̓]�p�ł�����A�����ȃt�H�[�}�b�g�ł���t�H�[�T�[�Y�Ŏg���ƁA����l�ɂ���Ă͐��\���s������v�A�Ə����Ă����̂ŁA����͈Ⴄ�Ə������܂ŁB
���������Y���g�p���Ă��ăt�H�[�}�b�g�T�C�Y������������Ɛ��\��������Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��ł��B
���������Y�Ȃ�t�H�[�}�b�g�T�C�Y��ς��Ă��𑜂��ς��Ȃ��̂͂�����܂��ł��B
����A�C���[�W�T�[�N���̑傫���̈Ⴄ�����Y�i�����Y�̉𑜗͂������Ɖ��肵�āj���r�����ꍇ�A�C���[�W�T�[�N���̑傫���������ӂɂ����ɂ��������Ẳ𑜂ŗL���ł��B
APS�Ƀt���T�C�Y�p�����Y������̂ƁAAPS�p�����Y������̂Ƃł͉�ʑS�̂ł̉𑜓x�ɍ����o�܂��B
�V�t�g�����Y�Ƃ����̒P�œ_�ł��������ƁB
�����Ȕ�r�ɂ͂Ȃ�Ȃ���
�L���m�� TS-E24mm F3.5L II��MTF
https://cweb.canon.jp/ef/lineup/ts-e/ts-e24-f35lii/spec.html
�L���m�� EF24mm F1.4L II USM��MTF
https://cweb.canon.jp/ef/lineup/wide/ef24-f14lii/spec.html
TS-E24mm F3.5L II�̏ꍇ�A24mm�̐�܂ŗ]�T�����邩��S�R�Ⴄ�ł���B
�����C�J���𑜗͂��グ�������Y��p�ӂ����̂́A�]�ʐ^�̐��ׂ��ɑ��āA����ȑO�̑傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̃����Y�ł͉𑜗͂��s�����邩��ł��B�I�����p�X�̓t�B����35mm���n�[�t�T�C�Y��pen�����Ƃ��ɁA�ʏ��35mm���p�����Y�������𑜗͂̃����Y��p�ӂ��܂����B�t�H�[�T�[�Y�E�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�p�����Y���A35mm���p�����Y���������𑜗͂ō���Ă��܂��B
���̂˂��A����̓����Y���̂̐��\���ł����ăt�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ƃ͊W�Ȃ��B
���`�A����B
�����ԍ��F25229775
![]() 11�_
11�_
�����ƂˁA
���S�������S�_����30%�܂ł͈̔�
���ӕ����[�����璆�S�_�܂ł̊Ԃ̒[������80%�܂ł͈̔�
�̂ɁA���S���̑��͎��ӕ���ʂ�
�Ȃ�Ĉ�ʓI�ł͂Ȃ����ȍ쐬�̑O�������z�肵�Ă����ł���B
�����Y�̉𑜗͂ɂ��Ă��A��f�s�b�`�͖������Ă��邵�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃����Y�̉𑜗͕͂K�R���������Ẳ𑜗͂Ȗ�ŁA
���s�t���T�C�Y�̉�f�s�b�`�ł���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�قǂ̉𑜗͂������Ă��A
�B�e���ʂƂ��Ẳ𑜋�̓n�C���]�����y���ɏ��Ȃ���f���Ńn�C���]�����𑜂��Ă܂�����ˁB
����͈ȑO�Ɏ��ʌ��ʂŎ����܂����������ɒP�ɔF�߂����Ȃ������悤�ł��B
�܂��A�B�e���ʂ̎ʐ^�����Ă��邩�A�P�ɃX�y�b�N�����Ă��邩�̈Ⴂ�ł��傤�B
����̎B�e���ʂ����Ă�����������Ȃ��ƍ��ꂵ�Ă������炢�ł����炲�{�l�̎B�e�͂���ȂɎ��팋�ʂ����ݑ����Ă��鎖������e�Ղɔ��f�o������Ă��̂ł��B
�����ԍ��F25229837�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
���X�e�A�P�C�X����
>quagetora���A�u�V�O�}��V�O�}��OEM�Ǝv����100-400mm�Ȃǂ́A���傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̓]�p�ł�����A�����ȃt�H�[�}�b�g�ł���t�H�[�T�[�Y�Ŏg���ƁA����l�ɂ���Ă͐��\���s������v�A�Ə����Ă����̂ŁA����͈Ⴄ�Ə������܂ŁB
�t�H�[�}�b�g�̈Ⴄ�傫���̎ʐ^���傫���ɂ��Č���Ƃ��A�����ȃt�H�[�}�b�g�̕������𑜗͂̃����Y���K�v�ɂȂ�܂��B�����Y�͎g�p����t�H�[�}�b�g�̃T�C�Y�ɍ��킹�Đv����̂ŁA�傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̃����Y�������ȃt�H�[�}�b�g�ɓ]�p����ƁA�𑜗͂��s������ꍇ������܂��Bquagetora���� �̃R�����g�͊Ԉ���Ă��܂����B
>���̂˂��A����̓����Y���̂̐��\���ł����ăt�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ƃ͊W�Ȃ��B
�t�B�����̎ʐ^�œ����T�C�Y�Ŏʐ^������Ƃ��A�����ȃt�H�[�}�b�g�̕����g�嗦���傫���Ȃ�܂��B�������荂�𑜂̃����Y���K�v�ł��B
�f�W�^���̎ʐ^�œ����𑜓x�Ŏʐ^������Ƃ��A�����ȃt�H�[�}�b�g�̕�����f�s�b�`���������ł��B�������荂�𑜂̃����Y���K�v�ł��B
�����ȃt�H�[�}�b�g�ɂ͍��𑜗͂ȃ����Y���K�v�ɂȂ邩��A�t�H�[�}�b�g�ɍ��킹�����\�ō��̂ł��B
�Ⴆ�A35mm���̃����Y��MTF�`���[�g�́u10�{/mm�E30�{/mm�v�ɂȂ��Ă��܂��B
����A�Ίp����1/2�̃t�H�[�T�[�Y�E�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃����Y�́u20�{/mm�E60�{/mm�v�ł��B
�����ȃt�H�[�}�b�g�ɂ͍��𑜗͂ȃ����Y���K�v�Ƃ������Ƃł��B
�@���������A�I�X�J�[�E�o���i�b�N����̃��C�J�J�����J���X�g�[���[�A�ĒJ���v����̃I�����p�Xpen�̊J���X�g�[���[��ǂ�ł݂Ă��������B
�����ԍ��F25229950
![]() 16�_
16�_
��WIND2����
���X�e�A�P�C�X����
>���S�������S�_����30%�܂ł͈̔�
>���ӕ����[�����璆�S�_�܂ł̊Ԃ̒[������80%�܂ł͈̔�
>�̂ɁA���S���̑��͎��ӕ���ʂ�
>�Ȃ�Ĉ�ʓI�ł͂Ȃ����ȍ쐬�̑O�������z�肵�Ă����ł���B
������V���v���ȓʃ����Y�ōl���Ă݂Ă��������B
�Ⴆ�A�œ_����100mm F2.0�Ƃ��������Y�B
���̃����Y�̗L�����a��50mm�ł��B��ʒ������Ɍ������郌���Y�́A�����Y�̑S�ʂ�ʉ߂������ł��B���̂Ƃ��u�����Y�̒������������g���v�Ƃ������Ƃ́A���a���i�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Z���T�[�T�C�Y�ɊW����܂���B
�L�p�����Y�ɂ悭���郌�g���t�H�[�J�X�̃����Y�̏ꍇ�A�C���[�W�T�[�N���̓����Ɍ���������́A�O�ʁi�ˏo����O���ɒu�����߂̃����Y�ł��j�̓�����ʂ������ɂȂ�܂��B�ł����A���ۂ̌����Ɏg���钆�ʂ����ʂɂ����Ă̓����Y�̂قڑS����ʂ������ł��B�^�������g���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�܂���B
�_�����̋ʃ{�P�i���a�H�̂��郌�����^�̃{�P���j�̗֊s�ɂȂ���̓����Y�̉���ʂ������ł�����A��ʒ������ł������Y�̑S�̂��g���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�����ԍ��F25229953
![]() 13�_
13�_
���X�e�A�P�C�X����
�ǐL�B
>�L���m�� TS-E24mm F3.5L II��MTF
>.https://cweb.canon.jp/ef/lineup/ts-e/ts-e24-f35lii/spec.html
>�L���m�� EF24mm F1.4L II USM��MTF
>https://cweb.canon.jp/ef/lineup/wide/ef24-f14lii/spec.html
>TS-E24mm F3.5L II�̏ꍇ�A24mm�̐�܂ŗ]�T�����邩��S�R�Ⴄ�ł���B
�����̃����Y��MTF�̒l���Ⴄ�̂́AF3.5��F1.4�Ƃ������邳�̈Ⴂ���ő�̗v���ł��ˁB
���邢�����Y�قǑ傫�������Ȃ���̂ŁA���𑜗͂̃����Y�����͓̂���̂ł��B
�����ԍ��F25229954
![]() 11�_
11�_
�����ƁA���ȕs���B
���L�A�������܂��B
�i��j
�Ⴆ�A�œ_����100mm F2.0�Ƃ��������Y�B
���̃����Y�̗L�����a��50mm�ł��B��ʒ������Ɍ������郌���Y�́A�����Y�̑S�ʂ�ʉ߂������ł��B
�@�@��
�i���j
�Ⴆ�A�œ_����100mm F2.0�Ƃ��������Y�B
���̃����Y�̗L�����a��50mm�ł��B��ʒ������Ɍ�������̂́A�����Y�̑S�ʂ�ʉ߂������ł��B
�����ԍ��F25229957
![]() 9�_
9�_
APS-C�@�Ƀt���T�C�Y�����Y���g�����ꍇ�A
�����Y�̃C���[�W�T�[�N�������A
APS-C�Z���T�[�̊O�̑��A���͂ǂ��s�����Ⴄ��H
���H����������APS-C�@�ɒ������r�[�ɃC���[�W�T�[�N���̑傫�����������Ȃ�H
����Ȏ��A����͂����Ȃ��B
�����ԍ��F25230171�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
�F�l
�M�d�ȃR�����g��R���肪�Ƃ��������܂�
�����A�c�_�����������ɍs���Ă��܂�����������܂��̂ŁA�܂���x�����Y��OM SYSTEM PLAZA�Ɏ�������Ŏ����Ă݂����Ǝv���܂�
���̌��ʂŔ[��������ňӎv���肵�܂�
�i�Ⴂ���̓T�N�b�ƏՓ��������܂������A�ސE��Ȃ̂ō����T�d�ɂȂ�܂����j
�܂��A���ʂ͋��L�����Ă�������
�R�����g���������F�l�S��芴�ӂ��܂�
���肪�Ƃ��������܂���
�����ԍ��F25230184�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
��Tranquility����
�������ȃt�H�[�}�b�g�ɂ͍��𑜗͂ȃ����Y���K�v�ɂȂ邩��A�t�H�[�}�b�g�ɍ��킹�����\�ō��̂ł��B
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɍ��킹�ă����Y���̂̐��\��ς���̂Ȃ�A����̓����Y�̐��\���ł����ăt�H�[�}�b�g�T�C�Y�͖��W�B
���𑜗͂ŃC���[�W�T�[�N���̑傫�ȃ����Y�����Ή�ʑS�̂̉𑜗͂͏オ��܂���B
�܂��킩��Ȃ��̂��ȁB
�{���Ȃ�A�������\�ŃC���[�W�T�[�N���̑傫���̈Ⴄ�����Y�Ŕ�r���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����̂�
�L���m�� TS-E24mm F3.5L II�ƃL���m�� EF24mm F1.4L II USM�̔�r��F�l���Ⴄ�̂͂킩���Ă��ď����Ă���B
������A�����Ȕ�r�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A�ƒA���������Ă���B
���Ȃ��Ƃ��������[�J�[�A�����œ_�����A���N���X�iL�����Y�j�B
EF24mm F1.4L II USM��F3.5�ɍi���Ă�TS-E24mm��MTF�ɂ͓͂��Ȃ��ł��傤�ˁB
���X���ł��������������ǁA��킩����ŗ��܂Ȃ��ł���Ȃ����ȁB
���`����B
�����ԍ��F25230219
![]() 9�_
9�_
��mochmatch����
LEICA D VARIO-ELMAR 14-150�̃t�H�[�T�[�Y�����Y���ƃ����Y�쓮���x�̊W�ŃG���[���ł�\�����L�肻���ł���
�������ޑO��mk2�Ŏ�����Ă͂Ǝv���܂�
�����ԍ��F25230256
![]() 1�_
1�_
��WIND2����
>APS-C�@�Ƀt���T�C�Y�����Y���g�����ꍇ�A�����Y�̃C���[�W�T�[�N�������AAPS-C�Z���T�[�̊O�̑��A���͂ǂ��s�����Ⴄ��H
�J���������̕ǂȂǂɓ������ĔM�ɂȂ�A������ӂɉ_�U�������邾���B
�����ԍ��F25230830
![]() 15�_
15�_
���X�e�A�P�C�X����
>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɍ��킹�ă����Y���̂̐��\��ς���̂Ȃ�A����̓����Y�̐��\���ł����ăt�H�[�}�b�g�T�C�Y�͖��W�B
quagetora����́u�V�O�}��V�O�}��OEM�Ǝv����100-400mm�Ȃǂ́A���傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̓]�p�ł�����A�����ȃt�H�[�}�b�g�ł���t�H�[�T�[�Y�Ŏg���ƁA����l�ɂ���Ă͐��\���s������v�Ƃ����̂́A�����Y���̂̐��\�i�𑜗́j�̂��Ƃ��q�ׂĂ��܂���B
�傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̃����Y�������ȃt�H�[�}�b�g�Ŏg�p����Ɓu�����Y���̂̐��\�v���s������\��������̂ł��B35mm���p�̃����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃n�C���]�Ŏg�p����ƁA�Ȃ�����ɁB
quagetora���� �͂�������O���ꂽ�̂ł����āA�Ԉ���Ă��܂���B���͂��̗��R��������܂����B
��{�I�ɃJ���������Y�͎g�p�t�H�[�}�b�g�ɍ��킹�āA�v�������𑜗͂�z�肵�Đv�����̂ł��B
���ꂪ�u��킩����v�ł���Ȃ�A�킩��悤�ɂȂꂽ�炢���Ǝv���܂��B
�܂��A2�{�̃����Y��MTF�`���[�g��Ꭶ����Ă��܂������A����́u���𑜗͂ŃC���[�W�T�[�N���̑傫�ȃ����Y�����Ή�ʑS�̂̉𑜗͂͏オ��܂��v�̍����ɂ͈���Ȃ��Ă��Ȃ��ł��B�B�B
�����ԍ��F25230835
![]() 20�_
20�_
���ꂥ�H
APS-C�@�Ƀt���T�C�Y�����Y�g���Ă������Y�̒[�܂Ŏg���Ă�Ƃ����̂Ɩ������Ă���Ȃ��B
���b�p�����̐l�͊Ԉ���Ă悤���Ȃ낤�����ł��L��ȂȁB
�����ԍ��F25230908�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
�����A����Ƃ��Ƃ��猾�����˂Ȃ�����
�B�h���Ă������ǁA
�N���u�����Y��ʂ��������̌��v
�̎��Ȃb���ĂȂ�����ˁB
���m�ɗ����o����l�Ȃ瓖�R�������Ă��鎖�����ǁA
�X�|�b�g�ĂĂ���̂́A
�u�Z���T�[�Ŏ~�߂���v
�̎��݂̂ł�����B
���Ȃ��̏������͉{���҂ɑ���
���炩�Ɍ��U���I�ȏ���������������ˁB
�����ԍ��F25230971�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 9�_
9�_
����ƁA
���x���������ǁA��ԏd�v�Ȏ���
����ɂ�����B�e���ʂ̏o���ł����āA
���Ȃ��̍D���ȗ����ł������ł������ł�����܂���B
�����Y�̉𑜗͂�������B
�����炠�Ȃ��̂��b�͂������r���[�Ȃ�ł���B
�ŁA���ǂ̂Ƃ���ǂ�Ȏʐ^���B���̂��H
�Ƃ����ŏI���ʂɒH����ĂȂ��ł�����ˁB
�����ԍ��F25231008�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 11�_
11�_
�����悤�Șb��͉��x���������A����ɖڂ�ʂ��Ă���Ή����������������肻���Ȃ��̂ł���...
�Ⴆ�A�ȉ��̃R�����g�͂��ׂĐ������ł��B
���u�t���T�C�Y�p�����Y��APS-C�Ŏg���Ƃ��A�C���[�W�T�[�N���̎��ӕ������g��Ȃ��čςށv�ł��B
�i��ʒ������̑��ł��A�����Y���ӕ����g���Ă��܂��j
���̂Ƃ��ɉ摜�̉𑜂��オ�邩�ǂ����̓����Y�Ɖ摜�̉�f���������ł����A35mm���p�����Y��APS-C�Ŏg���Ă������Y���̂̉𑜗͕͂ς��܂���B
���t�H�[�}�b�g�̈Ⴄ�傫���̎ʐ^���傫���ɂ��Č���Ƃ��A�����ȃt�H�[�}�b�g(������f�s�b�`)�̕������𑜗͂̃����Y���K�v�ɂȂ�܂��B�����Y�͎g�p����t�H�[�}�b�g�̃T�C�Y�ɍ��킹�Đv����̂ŁA�傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̃����Y�������ȃt�H�[�}�b�g�ɓ]�p����ƁA�𑜗͂��s������ꍇ������܂��Bquagetora���� �̃R�����g�͊Ԉ���Ă��܂����B
���t�B�����̎ʐ^�œ����T�C�Y�Ŏʐ^������Ƃ��A�����ȃt�H�[�}�b�g�̕����g�嗦���傫���Ȃ�܂��B�������荂�𑜂̃����Y���K�v�ł��B�f�W�^���̎ʐ^�œ����𑜓x�Ŏʐ^������Ƃ��A�����ȃt�H�[�}�b�g�̕�����f�s�b�`���������ł��B�������荂�𑜂̃����Y���K�v�ł��B
��L���Ԉ���Ă���Ǝv������́A�e�N�j�J���Ȃ��Ƃ��������Ă��Ȃ����A���̗͂���s���ł��B
��������A��WIND2����@�͑O�ҁA���X�e�A�P�C�X����@�͌�҂ł����ˁB
�n�C���]�͏����ȃV�X�e���ŏ����ł��ǂ����ʂ��c�����߂̕��@�Ƃ��ėǂ��A�C�f�A���Ǝv���܂����A���ۃt���T�C�Y�ł��g����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�ǂ����Ă��̘b��ł��̂悤�ȋc�_(��������)�ɂȂ�̂��A�ƂĂ��s�v�c�ł��B
����Ǝv���Ȃ痈�Ȃ���悢�̂ɁA�Ǝv���͎̂��������Ȃ̂���...
�����ԍ��F25231048
![]() 33�_
33�_
��WIND2����
>APS-C�@�Ƀt���T�C�Y�����Y�g���Ă������Y�̒[�܂Ŏg���Ă�Ƃ����̂Ɩ������Ă���Ȃ��B
�������ĂȂ��ł���B
�����ƌ������Ȃ��́A�ʃ����Y�����̃C���[�W�T�[�N���������̓����Y�̐^�������ʂ������ŁA�C���[�W�T�[�N���O���̓����Y�̒[�̕���ʂ�����������Ă���Ƃ��v���Ă܂��H
������������������A���w�Z���Ȃ�������x�����炢���Ă��������B
>�X�|�b�g�ĂĂ���̂́A�u�Z���T�[�Ŏ~�߂���v�̎��݂̂ł�����B
�C���[�W�Z���T�[���~�߂���ƁA�C���[�W�Z���T�[����O�ꂿ�Ⴄ���ɈႢ�͂Ȃ��ł���B
�����ԍ��F25231116
![]() 20�_
20�_
���D�_�s�f�ł�������
�����́B
�t�H���[���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F25231117
![]() 5�_
5�_
SIGMA 56mm/F1.4 ������Ƒ����ł����ǁc |
COSINA�@42.5mm/F0.95�@������ƊÂ��H |
Schneider�@75mm/F5.6 |
CANON 85mm/F1.2 �����Y�̎��ӂ��g��Ȃ���F2.4 |
��mochmatch����
���n�C���]�V���b�g�͑��Ѓ����Y�ł��Ή����܂��ł��傤���H
Seagulls����Aquagetora����A����89����A�|�|�[�m�L����ATranquility ������������܂�Ă��܂����A�B�e�͉\�ł��B
�����A�掿�Ɋւ��ẮAquagetora����ATranquility����A�D�_�s�f�ł������w�E����Ă���Ƃ���A�����Y����Ƃ������͔ۂ߂܂���B
�`���[�g���B�e���s�N�Z�����{���X�ɂS�{�g�債�ă`�F�b�N����Ɖ𑜓x�A�e�����A�R���g���X�g�̓����Y�ɂ���đ�Ⴂ�ł��B
�K���Ȏ��ɁAAPS-C�̃C���[�W�T�[�N�����J�o�[�o����V�O�}30mm F1.4 DC DN��m4/3�ɗv�������掿���ӎ����Ă��AAPS-C���̉�ʎ��ӂ̉掿�ቺ�ɂ͖ڂ��Ԃ���m4/3�̃C���[�W�T�[�N���܂ł�MTF�J�[�u���\�Ȍ��荂���ێ����Ă���悤�ł�����A����قǍ����͊����Ȃ��Ǝv���܂��B
�C�ɂȂ��Ă���̂�LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6�ŁA1000����f���x����ɂȂ��Ă���悤�ȊÂ�������悤�Ɋ����Ă��܂��B
��Tranquility����
���D�_�s�f�ł�������
�����Y�̎��ӂƃC���[�W�T�[�N���̎��ӂ̋�ʂ����Ȃ��l������͕̂s�v�c�ł��ˁB
�ނ�ɂ͑�̂̃V�[�g�t�B�������g���唻�J�����p�̍L�p�����Y����ɂȂ��Ă����ł��傤���ˁB
�S���T�̃C���[�W�T�[�N���ł���152�~���ɑ���75mm/F5.6�Ƃ����L�p�����Y��������A�O�ʁE��ʂ̋���ȉ������Y�̎��ӂ͎g��Ȃ��Ƃ������͗L�肾�Ǝv���܂����ǁA85mm/F1.2�N���X�Ń����Y�̎��ӂ͎g��Ȃ��ƂȂ�ƁA�P�Ȃ�Â������Y�ɂȂ����Ⴂ�܂��ˁB
���C�J���T�C�Y�p�̃����Y�̓����Y�̌��a�i���Ɍ�ʁj���P�`�����̂��������a�H�������̂��w�ǂł����ǁA���������������Y��m4/3��APS-C�Ŏg���Ύ��ӌ����̈��e�����瓦��邱�Ƃ͏o���܂����ǁA�B���f�q�̃s�b�`�Ɍ��������𑜓x���Ȃ���Α�̂̒��������Y���ɂȂ����Ⴂ�����ł��ˁB
�����ԍ��F25231220
![]() 5�_
5�_
�܂�������A�@�����������߂Ċm�F���Ă����܂���B
�ł��ˁA�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�p�ɍ���Ă��邩��𑜗͂����郌���Y������Ƃ����āA
���ۂ̕`�ʂʼn𑜂������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł́H
���ۂɉ𑜂��ĂȂ����B
�܂��A���팋�ʂ����Ă�������Ȃ��l������݂��������ǁB
�O�ɂ����������ǁA�𑜗͕͂K�R�B
�Ă��A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Z���T�[�̉�f�s�b�`���𑜂�����܂ł͉𑜂��Ă��Ȃ��ȂƂ����̂����ہB
�t���T�C�Y�����Y��APS-C�Ɏg���ɂ������ẮA����f���t���T�C�Y�ƈ�ʓI��APS-C�̉�f�s�b�`�͂قړ��ꂾ����S���x��͂Ȃ��ǂ��납�L�Ӌ`�Ɏg�p���Ă܂���B
���Ȃ݂Ƀt���T�C�Y�����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ɏg�p�]�X�͔ے�͑S�����ĂȂ����ǂˁB
�����ԍ��F25231327�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���b�p���I�J�V�C
APS-C�Z���T�[�O���C���[�W�T�[�N�����̌���APS-C�Z���T�[���̌��Ɠ���H
�Ƃ������̓t���T�C�Y�Z���T�[�̒[�̑���APS-C�ł��[�Ɏʂ荞�ނƂ������ɂȂ�B
�������ۂ�APS-C�ł̓J�b�g�����B
����A����ǂ��납�A
���̌����Ă��鎖�̓����Y�̂���P�ʖʐψ�_��ʉ߂������A���̓Z���T�[�ʑS�ʂɎʂ荞�ނƂ������ɂȂ�B
�����A���ۂ͂����ł͂Ȃ��B
�Ȃ����Ƀ��`���N�`���Ȏ��������Ă���Ƃ������Ȃ��B
�����ԍ��F25231372�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�����Q�l�݂̂�1000�h�b�g�p ���u100���h�b�g�v�摜 |
�u�����Q�l�̂݁v�̎Q�l�p�i�W�{�g��摜�j |
�t�H�[�}�b�g�ʂ̃����Y�𑜓x�Ƃ̑��ւȂ�(�ܘ_�P���v�Z(^^;) |
(��r���؉\�ȕ���)
�܂��́A
�Y�t�摜�P���������̂܂g�����u100���h�b�g�v�����摜���B�e���A�𑜂����Ă݂Ă��������B
���́u������100���h�b�g�v�̒i�K�ł��A(�������̃J�����ƃ����Y�ɂ��)�B�e�摜��(���Ɂu�[���ȊO�v�ƒ[��)�̉𑜋�̍��ق��A�ӊO�ɑ傫���Ǝv���邩������܂���B
(�J�����ƃ����Y�A�i��ݒ�ɂ��)
kakaku�̉摜�A�b�v�̐����1024�h�b�g�p�ȉ��ɂȂ邽�߁A
�Y�t�摜�́u�����Q�l�̂݁v�� 1000�h�b�g�p ���u100���h�b�g�v��JPEG�摜�Ƃ��Ă��܂��B
���摜�A�b�v�ɂ��Ĉ��k�Ȃǂɂ����C�ɂȂ�ꍇ�́A�u�����Q�l�̂݁v�ɕ������邽�߂ɁA
�摜�����\�t�g�ȂǂŁu�Q�l���v�������s���Ă�������(^^;
�����āA�Y�t�摜�S�������g�����u400���h�b�g�v�����摜���B�e���A�𑜂����Ă݂Ă�������(^^;
���̓Y�t�摜�S�������g���u400���h�b�g�v�����摜�́ARGGB�̒P�J���[�B���f�q�Ȃ� 1600����f�����Ɖ��肷��ƁA�����̃J�����ƃ����Y�Ȃ�A�]�T�Ɏv���邩������܂��A
�u400���h�b�g�v�����摜���𑜂����邱�Ƃ́A���\����Ǝv����ł��傤(^^;
��
�𑜋�̕]���p�Ƃ��āA
�E�����H�̎B�e�摜
�E�y���{�z�ŁA�摜�������Ɖ摜�[�����A�e�X1024�h�b�g�p�ŕۑ������摜���K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
���łɁA�t�H�[�}�b�g�ʂ̃����Y�𑜓x�Ƃ̑��ւɂ��āB
(�v�Z��͔��I�Ȓl������̂Œ���(^^;
�O���[�������Z���Ȃ�قǁA���I�ɂȂ�u�ڈ��v�Ƃ��Ă��܂�)
�����ԍ��F25231386�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
(��)
���E�y���{�z�ŁA�摜�������Ɖ摜�[�����A�e�X1024�h�b�g�p�ŕۑ������摜
��
kakaku�ɉ摜�A�b�v����ꍇ�́A�e�X1024�h�b�g�p�ȉ��ŁB
�����ԍ��F25231398�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��WIND2����
>�X�|�b�g�ĂĂ���̂́A�u�Z���T�[�Ŏ~�߂���v�̎��݂̂ł�����B
�@�@��
���������Ă��܂����B
�w�Z���T�[�Ŏ~�߂���x�̂݁A�Ɍ��肷�闝�R�́H�@����͓��ʂȌ��Ȃ�ł����H
�C���[�W�T�[�N���͉~�`�ł��B�C���[�W�Z���T�[�͒����`�ł��B
���ʒu�ŃZ���T�[���~�߂���ł��A�c�ʒu�ɂ�����Z���T�[����O��Ă��܂���������܂��B
�����Y�͂��̂܂܂ŁA�Z���T�[�T�C�Y�̈Ⴄ�J�����ɕt���ւ���ƁA�������ł��Z���T�[�ɓ���������O�ꂽ��B
���̃Z���T�[����O�ꂽ���́A�����Ⴄ�̂ł����H
�����ԍ��F25231483
![]() 13�_
13�_
����̖͂R�������ɋ����Ă��������B
>�t�H�[�}�b�g�̈Ⴄ�傫���̎ʐ^���傫���ɂ��Č���Ƃ��A�����ȃt�H�[�}�b�g�̕������𑜗͂̃����Y���K�v�ɂȂ�܂��B�����Y�͎g�p����t�H�[�}�b�g�̃T�C�Y�ɍ��킹�Đv����̂ŁA�傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̃����Y�������ȃt�H�[�}�b�g�ɓ]�p����ƁA�𑜗͂��s������ꍇ������܂�.
�������ȃt�H�[�}�b�g�ɂ͍��𑜗͂ȃ����Y���K�v�ɂȂ邩��A�t�H�[�}�b�g�ɍ��킹�����\�ō��̂ł��B
���́u�t�H�[�}�b�g�v�̈Ӗ����悭�킩��܂��A�u�C���[�W�Z���T�[�̃T�C�Y�v�Ɨ������ď������Ă��������܂��B
�܂��A�����Q�O�O�O����f�̃t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�Ȃ�A�t���T�C�Y���t�H�[�T�[�Y�̂ق������𑜗͂̃����Y���K�v�ɂȂ�A�Ƃ����̂͗����ł��܂��B
�������A�����ɂ́A�t���T�C�Y���ƃ\�j�[���U�P�O�O����f�AAPS-C���ƕx�m�t�C�����łS�O�Q�O����f�̃J�������̔�����Ă��܂��B
�����̓t�H�[�T�[�Y�Ŏ嗬�̂Q�O�O�O����f�Ɣ�ׂĂ���f�s�b�`�ł����A����قǕς��Ȃ��Ǝv���A�����ł���A�����̃Z���T�[�ɑΉ����郌���Y�̓t�H�[�T�[�Y�Q�O�O�O����f�Ɠ����x�̉𑜗͂��K�v���ƍl���܂����Ⴄ�̂ł��傤���H
�܂�A�u�t�H�[�}�b�g�̑召�v�ł͂Ȃ��A�Z���T�[�́u��f�s�b�`�̑召�v�ɍ��킹�����\�Ń����Y�����A���Ă��Ƃł͂Ȃ��̂��H���Ă̂����̋^��_�ł��B
�t�H�[�}�b�g�̑召�Ɋւ�炸�����Q�O�O�O����f�Z���T�[�������݂��Ȃ��̂ł���A�u���t�H�[�}�b�g�̂ق������𑜂��K�v�v���Ă̂͗����ł��܂����A�����͂����ł͂Ȃ��̂ł�����A�P���Ɂu���t�H�[�}�b�g�̂ق������𑜂��K�v�v�̂͂�����ƈႤ�̂ł́H�Ǝv���܂����A���̗���������Ȃ��̂ł��傤���H
�����ԍ��F25231596
![]() 5�_
5�_
�����Ȃ������i����
������ƈ��p���O�サ�܂����A���e�͂��B
>�u�t�H�[�}�b�g�̑召�v�ł͂Ȃ��A�Z���T�[�́u��f�s�b�`�̑召�v�ɍ��킹�����\�Ń����Y�����A���Ă��Ƃł͂Ȃ��̂��H���Ă̂����̋^��_�ł��B
���͂��������Ă��܂����B
�w�ŏI�I�ɑz�肳���ʐ^�̃T�C�Y�Ɩ]�ސ��ׂ��ɍ��킹�āA�t�H�[�}�b�g�ɉ����ă����Y�̉𑜗͂�Ή�������K�v������̂ł��B�f�W�^���J�����̏ꍇ�A��f�s�b�`�ɍ��킹�ă����Y��p�ӂ���K�v�����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��ł��傤�B�x
�i�����ԍ��F25229176�j
�w�f�W�^���̎ʐ^�œ����𑜓x�Ŏʐ^������Ƃ��A�����ȃt�H�[�}�b�g�̕�����f�s�b�`���������ł��B�������荂�𑜂̃����Y���K�v�ł��B�x
�i�����ԍ��F25229950�j
�w�傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̃����Y�������ȃt�H�[�}�b�g�Ŏg�p����Ɓu�����Y���̂̐��\�v���s������\��������̂ł��B35mm���p�̃����Y���}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃n�C���]�Ŏg�p����ƁA�Ȃ�����ɁB�x
�i�����ԍ��F25230835�j
>�����ɂ́A�t���T�C�Y���ƃ\�j�[���U�P�O�O����f�AAPS-C���ƕx�m�t�C�����łS�O�Q�O����f�̃J�������̔�����Ă��܂��B
�����̓t�H�[�T�[�Y�Ŏ嗬�̂Q�O�O�O����f�Ɣ�ׂĂ���f�s�b�`�ł����A����قǕς��Ȃ��Ǝv���A�����ł���A�����̃Z���T�[�ɑΉ����郌���Y�̓t�H�[�T�[�Y�Q�O�O�O����f�Ɠ����x�̉𑜗͂��K�v���ƍl���܂����Ⴄ�̂ł��傤���H
35mm���J�����ł��Z���T�[�V�t�g�̍��𑜉摜��d�g�݂��̗p�����悤�ɂȂ��Ă��܂�����ˁB
����ɑΉ����郌���Y�́A���R���̉�f�s�b�`�ɉ����č��𑜗͂ɍ����ł��傤���A�]������̃����Y�ł����̉𑜓x�������\������ΗL�Ӌ`�Ɏg����Ǝv���܂��B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃n�C���]�V���b�g�́A�ő�Ŗ�8000����f�̉摜�������܂��B���̉�f�s�b�`��35mm���ɂ���ƁA���悻3��2000����f�ɂȂ�܂��B�V���������Y���Ƒ��v��������܂��A�]�����炠�郌���Y�A���ɗ����ȃ����Y�ł́A���̉𑜓x�������\�͂Ȃ���������܂���B
quagetora����́u�V�O�}��V�O�}��OEM�Ǝv����100-400mm�Ȃǂ́A���傫�ȃt�H�[�}�b�g�p�̓]�p�ł�����A�����ȃt�H�[�}�b�g�ł���t�H�[�T�[�Y�Ŏg���ƁA����l�ɂ���Ă͐��\���s������v�Ƃ����R�����g�́A�X���傳��́w�n�C���]�V���b�g�͑��Ѓ����Y�ł��Ή����܂��ł��傤���H�x�Ƃ����₢�ɑ��āA���������\�����뜜�������̂ł��ˁB
�����ԍ��F25231678
![]() 12�_
12�_
�����Ȃ������i����
���L�̌��A�{��?�͂��̒ʂ肩��(^^)
���Z���T�[�́u��f�s�b�`�̑召�v�ɍ��킹�����\�Ń����Y�����A���Ă��Ƃł͂Ȃ��̂��H
�������Ȃ���A�����̐��i�ł͂����Ȃ��Ă��炸�A
�߂���Ƃ��Ă̓t�W�� X-H2�p���������Y������B
���x�m�t�C�������uX-H2�v��4020����f�Z���T�[�Ƀt���Ή����郌���Y�̃��X�g�����J ���e��:2022�N9�� 9��
https://digicame-info.com/2022/09/x-h24020.html
��
���́uX-H2�v�̗L��4020����f���܂߂āA
������f�T�C�Y�ʼn����тɂ����̂��Y�t�摜�̕\�ł��B
�uX-H2�v�̗L��4020����f�Ɠ�����f�T�C�Y�ł���A
�}�C�N�t�H�[�T�[�Y�� 2500����A
�t���T�C�Y�� 9500����(^^;
�Ȃ��A���w���[�p�X�t�B���^�[���X�̋@�킪����܂����A
���̉�f���Ȃ�u�[�F�̖�肪�o�ɂ����قlj𑜂���Ă��Ȃ��v��ԂɂȂ�܂��̂ŁA
���w���[�p�X�t�B���^�[���X�̋@��̉�f������A
���ۂ̃����Y�𑜓x�́u�v���Ă���قǂǁA���𑜂ł͂Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂�(^^;
�����ԍ��F25231724�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��Tranquility����
����͎����ׂ̈ɓ��ʂɗ���ł����܂��B
�����̃Z���T�[����O�ꂽ���́A�����Ⴄ�̂ł����H
�����Ȃ�ł����H
���炭�A���Ƃ������t�����߂��g�����Ă��邩�Ǝv���܂��̂ŁA���t���u���v�œ��ꂵ�܂��B
�������Ƃ���ƁA�`PS�|C�Z���T�[�O���t���T�C�Y�Z���T�[�̒[�Ŏ~�߂鑜�ł�APS-C�Ŏ~�߁A
�ʂ荞�ނ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂����H
APS-C�O�̑��̓����Y�̂ǂ���ʂ��Ă��鑜���H�ł��B
����ƁA
���v�������𑜗͂�z�肵�Đv�����̂ł��B
���ƁA���ۂɃ����[�X����Ă��鐻�i����������Ɖ𑜗͂̂��郌���Y���ǂ����͕ʂł���B
�����ԍ��F25231884
![]() 3�_
3�_
��WIND2����
>����͎����ׂ̈ɓ��ʂɗ���ł����܂��B
����͂ǂ����B
���܂ł̂͒ʏ�̗��݂Ƃ������Ƃł����B����͒N�̂��߂������̂ł����H
>>���̃Z���T�[����O�ꂽ���́A�����Ⴄ�̂ł����H
>�����Ȃ�ł����H
�������₵�Ă��܂��B���������������܂���B
>���炭�A���Ƃ������t�����߂��g�����Ă��邩�Ǝv���܂��̂ŁA���t���u���v�œ��ꂵ�܂��B
�u���v�Ɓu���v�͈Ӗ�����Ƃ��낪�܂�ňႢ�܂��B
�u���v�Ə����Ă����̂͂��Ȃ��ł�����A���́u���v�ɂ��ď����܂����B
>�������Ƃ���ƁA�`PS�|C�Z���T�[�O���t���T�C�Y�Z���T�[�̒[�Ŏ~�߂鑜�ł�APS-C�Ŏ~�߁A�ʂ荞�ނ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂����H
���͂���Ȃ��ƑS�������Ă��܂��B�u���v���u���v�Ɗg����߂������Ȃ��������l���������ł́B
>APS-C�O�̑��̓����Y�̂ǂ���ʂ��Ă��鑜���H�ł��B
���͂��łɏ����Ă��܂��B���Ȃ��̍l���́H
>>�v�������𑜗͂�z�肵�Đv�����̂ł��B
>���ƁA���ۂɃ����[�X����Ă��鐻�i����������Ɖ𑜗͂̂��郌���Y���ǂ����͕ʂł���B
���ۂ̐��i��v����Ƃ��ɁA���ꂼ��ɑz��i���\�̖ڕW�j������ł��傤�B
���̒ʂ�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ�����s�Ǖi�B
�����ԍ��F25232200
![]() 16�_
16�_
��mochmatch����
���[�ALEICA D VARIO-ELMAR 14-150�������Ă���ʐ^�F�B�̉ƂɊ������s�J�s�J��OM-1���������̂Ŏ����Ă��炢�܂����B�iMMF-1�g�p��MMF-3�g�p���������͎��O�j
�莝���n�C���]�ŎB�e���邱�Ƃ��o���܂����B
���̃����Y�̖��E��I�ɒʏ�B�e�ŏ\�����Ǝv���̂ŎB�e���ʂɋ����������𑜓x�̌��オ���邩�ǂ����܂ł͊m�F���Ă��܂���B
�`�e���x�́A���Ȃ�̂�т�X�`�`�`�`�`�`�`�Ƃ��������ł����B�i�����j�iC-AF�̓O���[�A�E�g���đI���ł��܂���j
�����̎Ԃ��玩�OOM-1�������o���͖̂ʓ|�������̂ł����i�����܂���O�O�G�j�A����������������̂Ŏ����Ă��炢�܂����B
OM-1���������Ƃ��i�w�������̂�m��Ȃ������j�p�i��8mm�i�w�������̂�m��Ȃ������j�������Ă���15�o�������Ă����Ǝv���̂ł����A�����̓n�C���]�V���b�g�B�e�ł���͂��Ȃ̂Ŏ����Ă��܂���B
�����ԍ��F25232214
![]()
![]() 3�_
3�_
��Tranquility����
�Ă̒�A����̈Ӑ}�𐳊m�ɋ��ݎ��Ȃ����Ȃ��炵���ł��ˁB
�ڂ̑O�̕������̂��̂��������ĂȂ��B
�Ȃ�قǁA
����̎B�e���ʂŔ��f�o���Ȃ���ł��B
�����ԍ��F25232288�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
SIGMA�@���C�J���o�[�W���� |
OM SYSTEM �o�[�W���� |
SIGMA�@30mm/F1.4�@�d�}�E���g |
SIGMA�@30mm/F1.4�@m4/3�}�E���g |
��Tranquility����
��>APS-C�@�Ƀt���T�C�Y�����Y���g�����ꍇ�A�����Y�̃C���[�W�T�[�N�������AAPS-C�Z���T�[�̊O�̑��A���͂ǂ��s�����Ⴄ��H
���J���������̕ǂȂǂɓ������ĔM�ɂȂ�A������ӂɉ_�U�������邾���B
����A����APS-C�̃n�C�G���h�@���o�Ă������A100-300mm/F4�Ƃ�400mm/F2.8�Ȃǂ��g������t���A�Ȃǂ͂ǂ��Ȃ�܂����ˁB
�����ÁX�ł��B
SIGMA��100-400mm/F5-6.3��OM SYSTEM��100-400mm/F5-6.3�Ƃ̍��ł����ǁA��Q�̉�/���E�ʂ̃����Y�͂��ꂼ��̃C���[�W�T�[�N���ɍ��킹�Č��a���ς��Ă���悤�ł��ˁB
���R�A�������ɂ��t���A�J�b�^�[���p�ӂ���Ă����ł��傤���ǁA�t�[�h�̒����Ƃ����œK�����K�v�ł��ˁB
�ŁA30mm/F1.4���`�F�b�N���Ă݂܂������ǁA�d�}�E���g��m4/3�}�E���g�ł͌�ʂ���Ō㕔�܂ł̃t���A�J�b�g�őΉ����Ă���悤�ł����ǁA���˗��O���̕������������茵�����݂����ł��ˁB
�����ԍ��F25232393
![]() 2�_
2�_
��WIND2����
>����̈Ӑ}�𐳊m�ɋ��ݎ��Ȃ�
�wAPS-C�@�Ƀt���T�C�Y�����Y���g�����ꍇ�A�����Y�̃C���[�W�T�[�N�������AAPS-C�Z���T�[�̊O�̑��A���͂ǂ��s�����Ⴄ��H�x
�w�X�|�b�g�ĂĂ���̂́A�u�Z���T�[�Ŏ~�߂���v�̎��݂̂ł�����B�x
���̕��͂́u���v���u���v�̂��Ƃ��Ɠǂސl�͂��Ȃ��ł���B
�����̍앶�~�X�ňӐ}���`���Ȃ��������Ƃ�ǂސl�̂����ɂ��Ȃ��ʼn������B
����ɁA35mm���p�����Y���g�����ۂ�APS-C�Z���T�[��O�̑��ɂ��ẮA���͂����ƑO�ɏ����Ă��܂��i���j�B
�u�t���T�C�Y�p�����Y��APS-C�Ŏg���Ƃ��A�C���[�W�T�[�N���̎��ӕ������g��Ȃ��čςށi�����ԍ��F25229176�j�v
�u�C���[�W�T�[�N���v�Ƃ́u���������~�`�͈̔́v�������́u�œ_�ʂɌ��ꂽ�~�`�̑��v�̂��Ƃł��B
���̌�ɁA���Ȃ��́u���v�������Y�̂ǂ���ʂ邩��b��ɂ��Ă��܂����ˁB
����ɑ������Ȃ��̃R�����g�ł�����A�N�����u���v�̂��Ƃł͂Ȃ��āu���v�̂��ƂƓǂނɌ��܂��Ă܂��B
�����ԍ��F25232407
![]() 18�_
18�_
��Tranquility����
���Ȃ����g�̖{���̗���̖͂�����������̂����ɂ��Ȃ��ł������������ł��ˁB
�������ł����炻�������������ł����A
���Ȃ��̏ꍇ�A���Ƃ����������Ɗg����߂�������ɏ��O�����܂Ŋ܂߂Ă��鎖���~�G�~�G�ł����̂ŁA���Ɍ��肵���̂ł���B
�����Y�̉𑜗͂ɂ��Ă��A
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�����Y�͉𑜗͂������v��������Ă���B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɑΉ����Đv��������Ă���B
�܂��A�m���ɊԈႢ�ł͂���܂���B
�ł��������܂ł̕\���ł́A���Ȃ��̎���B�e���ʂ���Ȃɋ��ގ��Ɠ��l�A�{���҂Ɏ�����F��U�������邪�̔@�����r���[�ł��B
�ŁA���ǁA����ł̎B�e���ʂł͂ǂ��܂ʼn𑜂���̂��H(���R�Ȃ�������B�e�̎��ł͂���܂���B)
�Ƃ����ŏI���ʂ�����܂���B
������̔F���ł́A����̃����Y�ł͂܂��܂��𑜗͕͂s�����Ă��܂��B
�����ԍ��F25232444�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�i�`�X�E�h�C�c�̐�`��b�ł��������[�[�t�E�Q�b�x���X�̗L���ȃZ���t�H�u�R���S���ΐ^���ƂȂ�v�Ƃ������f�}�S�[�O���o���̂����Ȃ̂ŁA�t�o���Ă����܂��B
CANON�̃f�[�^�ł͔���ɂ����悤�ł����A���C�J�ƃc�A�C�X�ƃy���^�b�N�X�̃����Y�ŁA�C���[�W�T�[�N�������C�J���̔����̈ʒu�im4/3�����j�Ɏ����������������Έ�ڗđR�ł���ˁB
�C���[�W�T�[�N���̔����������Y���a�̔����ƌ����̂͊ԈႢ�ł��B
�����ԍ��F25232454
![]() 12�_
12�_
�A���Ɣ�r���ꂽ��A
�ނ���Q�b�y���X���s���ɂ����v��(^^;
�����ԍ��F25232463�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���|������ǃ_�n����
�𑜕s���̃T���v������A�b�v���Ă��邠�Ȃ��������o�����Ƃ���Ő����͂��[�����܂�ł���܂����B
�Ƃ����킯�ŁA���҂��܂��������lj���������̂͂���܂���ł����ˁB
�܁A�����̎��ł����B
�����ԍ��F25232481�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
��������������ǁA�Ȃ�Ńn�C���]���g���郌���Y�͉��̘b�ɉ𑜓x�̘b���Ƃ������̘b���o��̂��낤�B�����Ă�{�l�͂����̂悤�ɓ��e�ς��ă����Y�̎g�p�ɕς��Ă邵�B�܂����Ӗ������b��
�����ԍ��F25232543
![]() 19�_
19�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 �{�f�B
SONY SF-M64T 64GB
https://kakaku.com/item/K0001219403/
�ō����\�łȂ��J�[�h�ł��邱�Ƃ͏��m���Ă��܂����A���̋@��ō����A�ʂ���Ȃ��͂�͕s���ł��傤���H
![]() 3�_
3�_
�����ł��ˁAV90��SD�͂������ق��������ł��B
V90��SD�J�[�h�Ȃ�SLCNAND�̂��̂ŁA�ϋv���ɗD�����̂��̗p����Ă��邱�Ƃ������ł��B
����ǂ���ł����PROGRADE�ASUNEAST�AKingston������B
�R�X�p�����߂�Ȃ�SABRENT�Ƃ��ǂ��ł��傤���B
�������Amazon�̃Z�[���ő啝�l����������̂ŁA�Z�[���܂ł͑҂����ق��������ł��B
�����ԍ��F25224402�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 3�_
3�_
���s�E�a�E����
���܂߂�PC�փo�b�N�A�b�v�����Ȃ������
���Օi�ł���SD�͂���Ȃ�ł��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł����H
�i���i�ł��u�����h�i�ł��f�[�^�����͂��蓾�܂�����
�������́A�i�v�ۏؕi�̕����w������悢�̂ł͂Ȃ��ł����B
�����ԍ��F25224423
![]() 2�_
2�_
���s�E�a�E����
����ɂ��́B
�ō��X�y�b�N��V90�d�l�͂�������
����V60�̃J�[�h���1.5�{�����ł���
�l�i��2�{�ȏ�ɂȂ�܂��̂ŁA
�o�b�t�@�J�����Ԃɂ��炢�炵�Ȃ��A
�o�b�t�@�t���ɂȂ�Ȃ��悤�B��A
�ȂǍH�v�����Ύg����̂ł�
�Ȃ��ł��傤���B
���Օi�ł����A�ЂƂ܂��g���Ă݂�
�B�e�ł���ς�V90�I�ƂȂ�����A
V90���w������A�X���b�g�Q�ɗ\����
�}���Ă����A�Ȃǎg�������ł��B
�����ԍ��F25224439
![]() 4�_
4�_
���s�E�a�E����
SLC�͂قږ����̂ŁAuhs-ii V90�ł��ƌ��� pSLC���Ǝv���܂��B
V90�ł��ő发���E�Ǎ����x�͈Ⴂ�܂��̂Ń��[�J�[���Ƃɍ����L��܂��i�{���͍ő�ł͂Ȃ��Œ���������x���厖�Ȃ�ł��傤���j
���r���[���������グ�Ă�������A�Ƃ�Ȃ�l���������茟����Ă�������̂ŁA���Љ�v���܂��B
�i�ŏ���h�O���Ă܂��j
ttps://asobinet.com/review-best-for-the-om-system-om-1/
����OM-1�͏��L���Ă��炸E-M1X�ł����AV60��SD�J�[�h�����܂Ɏg���Ă܂��B
V90�����z�ł͗L��܂����A�傳�\�Z�̊W��V60��I�������̂ł���A�o�b�t�@�l�܂�A���A�^�C�~���O�𗝉����Ȃ���g�p����Ηǂ��̂��ȁH�Ǝv���܂����B
���R�������̘A�ʂ���ł�����V90���ŏ�����I���I�X�X���ł��B
�����ԍ��F25224441�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 11�_
11�_
����ȎQ�l�y�[�W������܂��B�������[�J�[�h�搶�B
https://www.memorikado.jp/-Kamera/OM-System-OM-1
E-M1�U�EX�EOM-1�ʼn��L�̃J�[�h���g���Ă��܂����̊��I�ȈႢ�͊��������Ƃ�����܂���B
Sony Tough G�@128GB
ProGrade Digital Cobalt�@128GB
Thoshiba�@N501�i?)�@32GB�@��E-M1�U�̃L�����y�[���ł������
E-M1�U�EX�E�V�Œ��Ⓓ�̎B�e�Ńv���L���v�`���[H��F�l�B�i3�l�j���ASony Tough G�����C���Ŏg���Ă��܂��B
60FPS��120FPS�̘A�˂�����ƃo�b�t�@�t���܂ň�u�Ȃ̂ŁA���������B�e������Ȃ�ō����N���X�̃��f�B�A���g�����Ƃ������߂��܂��B
�������A�ʂ�A�����čs��Ȃ��Ƃ��ARAW�L�^10FPS�ł��܂ł��A���B�e�������Ƃ��łȂ���ATough M�N���X�ł��\�����Ƃ͎v���܂��B
Sony Tough G�́i�������[�J�[�h���啪�Љ��ŕi���̂��߁H�j���i���������Ă��܂��Ă��܂����A�wNextorage�i �l�N�X�g���[�W�F���Љ��Őݗ����ꂽ��Ёj 128GB UHS-II V90 SDXC�������[�J�[�h F2PRO�V���[�Y pSLC 4K 8K �ő�ǂݏo�����x300MB/s �ő发�����ݑ��x299MB/s �x�Ƃ����̂��A�܂��Sony Tough G���Ǝv����̂ŁA�����͔����������ɂ�����l���Ă��܂��B
��Tough M�̃N���X�͎d�l���Ⴄ�݂����Ȃ̂Œ��ӂ��K�v��128GB���f���̏������ݑ��x���x��
���w���̋@��ō����A�ʂ���Ȃ��͂�͕s���ł��傤���H�x
�����ԍ��F25224574
![]() 5�_
5�_
���s�E�a�E����
�����S���B�e���Ȃ��O��Ȃ犄���ł����g���܂�
�����ԍ��F25224589
![]() 2�_
2�_
���s�E�a�E����
���ۂɃv���L���v�`���[H�ESH�𑽗p���Ă��ăo�b�t�@�N���A���Ԃ̒�����������̂́A
�~�܂��Ă����ʑ́i�����j�����x��߂̉掿�D��ݒ�ŎB����肪��т��̐ݒ�̃v���L���v�`���[H�ESH�ŎB���Ă��܂��ăo�b�t�@�N���A�܂Őݒ�ύX��҂��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ȃ������ł��B
���o�b�t�@���ł�����̕����̂܂܂̐ݒ�ŎB�e�͂ł��܂����A�ݒ�̐�ւ��̓o�b�t�@���N���A����Ȃ��Ƃł��܂���B
�g�p�҂̃~�X�ł����A�F�l����ł��A���A���Ȏ��s�ł��B
TOUGH SF-M64T [64GB]�i���i�R���ň�6731�j���w���������Ă���Ȃ�A
�EEXCERIA PRO KSDXU-A064G [64GB]�i���i�R���ň�8329�j�@�E�E�EOM-1�����F��I�ȃJ�[�h
�E�L���O�X�g�� 64GB Canvas React Plus�iAmazon6980�j�@�E�E�E���E�I�ȃ������[�����
�EProGrade Digital COBALT 64GB�iAmazon11900�F���X�l�����̔�����j
������̒��V90�N���X�����ɓ���邱�Ƃ������߂��܂��B
OM-1�Ŏg���Ă�����薾�炩�ɉ��K�ȃJ�[�h�͍�����o�ꂵ�Ȃ��Ǝv���̂ŁA�����Ƒ����J�[�h��������?!�Ƃ����Y�݂������Ȃ����_������܂��B
�����ԍ��F25225000
![]()
![]() 5�_
5�_
���s�E�a�E����
����ɂ��́B
OM-1�ŁA���O���������Ă���u�L���O�X�g�� Canvas React Plus�v���g���Ă��܂����A
�R�X�g�p�t�H�[�}���X���ǂ��̂ŋC�ɓ����Ă��܂��B
�i128GB�����C�����p�ŁA64GB�͗\���Ŏ����Ă��܂��j
���͖쒹����Ȕ�ʑ̂ł����A���܂ɍ����A�ʂ�������������̂ŁA
�����Ƃ������̔����Ƃ��č����x�̃J�[�h�͈ꖇ�͎����Ă����đ��ł͂Ȃ��C�����܂��B
���āA�u�L���O�X�g�� Canvas React Plus�v�ł����A
�����O����Amazon.co.jp�̔̔��i���ɐ�ƂȂ��Ă���̂ŁA�^�Ԃ����������j���[�A���i�ɕς�邩�������ˁB
�iAmazon�Ō���̔�����Ă���̂́A�}�[�P�b�g�v���C�X�̎�舵���ł��j
���̑����X�Amosyupa����̂��ӌ��Ɏ^�����܂��B
�����ԍ��F25225288
![]()
![]() 3�_
3�_
�����̔@���A�傳��s�݂Ŏ傳��̎���ƊW�Ȃ������ɍs���̂����i�R�����ۂ��ėǂ��ł��ˁB
�ő��������͏������A���ۂɑ̊��o����̂��ǂ����m��܂���SONY�P���ŗ����オ�����l�N�X�g���[�W�i���ɑ�p�̌Q���d�q�ɔ�������q��Ёj���ő��ł����ˁHcfexpress typeb�̓l�N�X�g���[�W�����Pro���g���Ă܂����A���ɖ�肠��܂���B
https://www.nextorage.net/articles/230221/
�傳��̗\�Z����ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F25225341�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
����OM-1��X-H2�ŁASUN EAST��V90 128GB���g�����o��������܂��B
OM-1�Ŗ쒹�B�e�����Ă��āA�ō����̘A�ʂ��g�����Ƃ��ɂ̓o�b�t�@�S�J�܂ő҂�������ۂł����B
Write 150MB/s��V60��Write 290MB/s��V90�ł͌��\�Ⴄ�Ǝv���܂���B
X-H2���g���n�߂�SLC��CF Express�����̂ł����A���̂��������x���o�܂��B
�Ȃ�OM-1��CF Express�ɑΉ������Ȃ������̂����r���^��ł��B
�����͂�����܂����A�ϋv���̍���SLC�̕����Ă�����������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂���B
�����ԍ��F25225392
![]() 2�_
2�_
��SMBT����
���i�R�������łȂ��A�O�O���ĒH�蒅�����l���Ԉ���������g�U����Ƃ����Ȃ��̂ōēx�����Ă����܂��ˁB
�R�o���g���l�N�X�g���[�W�̐V���i�������ł���pSLC�ł��B
SLC�ł͗L��܂���B
�����ԍ��F25225412�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
���^�L�X�e���N���J������
pSLC��p�̈Ӗ��Ƃ��������Ȃ���
�������ĖႦ�Ȃ������B(^_^;)
https://www.udinfojp.com/
pseudo���^��
�����ԍ��F25225441�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
���悱chin����
���肪�Ƃ��������܂��I
�����ԍ��F25225452�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�݂Ȃ��܁A���X���肪�Ƃ��������܂����B���u���v�B��Ȃ�Ƃ��������u���v�B��Ȃ�V90�ɂ���ׂ����Ɣ��f�������܂����B
Good�A���T�[�͎��ۂɒ���_���Ă���������ł��낤�Ǝv���������̂��ӌ��d�������܂������A���̂����̃A���T�[���\���ɎQ�l�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
M-1�ł͎B��Ȃ��ʐ^��OM-1�ł͎B���悤�ɋF��܂��B�Ă��A�܂��͂��Ă���OM-1�ɓd�r�����Ȃ��Ƃ����܂���B
�����ԍ��F25225679
![]() 3�_
3�_
ProGrade -15%�������̂ōw�����܂����B�ł��AOM-1�ɂ͂܂��d�r�������Ă��܂���B
�����ԍ��F25235121
![]() 1�_
1�_
�f�W�^�����J���� > OM�f�W�^���\�����[�V�����Y > OM SYSTEM OM-1 �{�f�B
APS-C��RAW�T�C�Y��14bit�Ȃ̂ɁAOM-1��12bit�Ȃ̂ł����H
�Z���T�[���\���オ���Ă��Ă���Ȃ�14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B
![]() 5�_
5�_
��Kazkun33����
RAW�������鎞��14bit�̕����ǂ��̂����m��Ȃ����ǁA�ŏI�I��JPEG�ɂ���Ȃ�12bit�ł��ǂ��悤�Ɏv���܂��B
�ŏI�I��JPEG�Ȃ猩��ׂȂ��Ƃ킩��Ȃ��悤�Ɏv���܂����A�t�@�C���e�ʂ������܂�����12bit�ł��ǂ��悤�Ɏv���܂��ˁB
�����ԍ��F25223831�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
����f���ň��k����RAW�ł�����A
�P���v�Z�Ȃ�t�@�C���T�C�Y�S�{�ł�����E�E�E�I���ł���Όl�����(^^;
�����ԍ��F25223877�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���ʂ�12bit�ŏ[���Ȃ̂��������x��D�悵�Ă���̂��C�ɂȂ��ĕ����Ă݂܂����B
�����ԍ��F25223942
![]() 1�_
1�_
��Kazkun33����
��������ēǂ�������
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=24721901/
�����ԍ��F25223965
![]() 7�_
7�_
��Kazkun33����
����14bit RAW�ƂȂ��Ă��A�m�C�Y���������
�掿������܂�L�p�ł͂Ȃ���������܂���B
���Ƃ��A�����}�C�N���A���f��GH5S�ł�
RAW��14bit�ł����A�e�ʂ������Ȃ邹�����A
�A�ʂɐ������o��悤�ł����ASD�J�[�h�d�l
�ł��̂ŁA�o�b�t�@�N���A�҂����C�ɂȂ�ł��傤�B
�iGH6��Cfexpress type B�Ή��j
�uAF�Ǐ]�ł̘A�ʍō�����12bit RAW�����JPEG�ł̓��J�V���b�^�[�A
�d�q�V���b�^�[�Ƃ���8�R�}/�b�i14bit RAW����7�R�}/�b�ƂȂ�j�v
�E�p�i�\�j�b�N�y�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�@�z�i2022�N�~�j
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/special/lineup/1467722.html
�����x�ɂ��s���ȁu�ϑw�^�vCMOS�A
SD�J�[�h�d�l�ŁA50�R�}/�b�Ȃǒ������A�ʂ�
�����OM-1�ł��̂ŁARAW�A�ʔ\�͂�
�o�b�t�@�N���A�҂����ԂƂ��A�l�X�Ƀo�����X��
�l���̏��RAW12bit�̑I���ɂȂ���
�̂ł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B
�ŏI�I�ɂ悭������`��Jpeg�i8bit),
HEIF�ł�10bit�ł��̂ŁARaw������
�B�l�̕��͐��\����������̂����ł����A
12bit�ł���Ȃɍ���̂��ȁ[�A�Ƃ��v���܂��B
�����ԍ��F25224000
![]() 9�_
9�_
��Kazkun33����
���ʂ�12bit�ŏ[���Ȃ̂��������x��D�悵�Ă���̂��C�ɂȂ��ĕ����Ă݂܂����B
�����ł��ˁB
�������x�̖��͑傫���Ǝv���܂��B
�������x���l�����12bit�ɂȂ�Ǝv���܂����A�e�ʂ������ď������x���グ��ɂ̓o�b�t�@��f�B�A�̏������݂Ȃǂ̖�������܂����A�f���G���W���̏������x���d�v�ł��B
�I�����p�X�Ƃ��Ă̓R�X�g���܂߂�12bit���ǂ��Ɣ��f���Ă̌��ʂ��Ǝv���܂��B
�~���[���X�ɂȂ������ƁA�d�q�V���b�^�[���ŘA�ʖ����͈�C�ɑ����܂����B
�����ɏ������邽�߂̃X�s�[�h�邽�߂ɂ̓R�X�g���₹�Ηǂ��̂ł��傤���ǁA���\�ƃR�X�g�̃o�����X���d���������ʂł�12bit�ł͂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25224028�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
����������ēǂ�������
��https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=24721901/
��P�N���O�ł����ȁA���p��������瓖�����������݂��Ă܂����A�������莸�O���Ă܂�����B
���������ΐ��������Ɂw�ƒ�p�v�����^�̈���掿�x�ɂ��ĐF�X���_��W�J����Ă�����m����������Ⴂ�܂����B�ŋ߂͂����Z�Ȃ̂��S�R���̌f���Ɏ��_��W�J����Ă܂��A�B�����������ꂽ�̂ł��傤�ȁB
���ƂȂ����������������̂́A���̃X���������悤�ȓW�J������ł��B
�E�E�E�Ԃ����Ⴏ�Č����A�ӔC�s���Ăȓ����f���ŃZ���T�[���\�A�q�`�v�ɓZ���v�d�l�̏��X��u�����Ƃ���Ŗ{���ɒH�蒅�����Ȃ��A���������[�J�[����ɒ��k�����Ďe�ׂ�u��������������Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�ސ��䃌�x���ŏ��L���Ă��ʖڂł��B���\��o����Ή��S������L���āA���[�J�[����ƐS������ʂ̈ӋC���݂���������Łw�d�l�����āx�Ɨ��߂Γ��͊J����A�����m��܂���B
�܂����݂��ɂԂ��ł̏������݂ł��傤����A�w�ߓx���Ȃ��āx�ƌ����A�������͕t���͂��܂����E�E�E
�����ԍ��F25224036
![]() 7�_
7�_
>APS-C��RAW�T�C�Y��14bit�Ȃ̂ɁAOM-1��12bit�Ȃ̂ł����H
bit���̓Z���T�[�Ō��܂�̂ŁA���傪����̂Ȃ�\�j�[�Z�~�R���_�N�^�ɂǂ����ƂȂ�܂��B
�J��������14bit���ł��Ȃ����Ȃ��ł����A�Ӗ�������܂���B�@44.1kHZ�̉������A�b�v�T���v�����O���������̃n�C���]�����Ɠ���������ł��B
�Ȃ��Abit����ADC�̃t���X�P�[��(D�����W)�l�͒��ڊW����܂���B�@14bit��12bit���D�����W��4�{�傫����ł͂���܂���B
�����ԍ��F25224043
![]() 7�_
7�_
������������Ă������Ƃ�Y��Ă��܂����B
����v���܂����B
�����ԍ��F25224053
![]() 1�_
1�_
14bit��12bit�̈Ⴂ�B����͊K���ׂ̍����̈Ⴂ�ł�����14bit�͊K�����ׂ������f�[�^���傫���Ȃ邵�������d�����Ȃ��ł��B
�Ȃ̂ŃZ���T�[�̐��\�]�X�Ƃ͒��ڂ͊W����܂���B14bit�̕����������̒����Ŗ����������₷���B
��̓I�ɂ�14bit�̕�����̕`�ʂ̂悤�ɂȂ��炩�ɃO���f�[�V�������Ă����G���������̊��炩����������̂ł��B
�O�u���͂��̈ʂɂ��āc
�J�����̐v�ł̃R�X�g�z���ŃZ���T�[�A�V���b�^�[�AAF���\�A�A�ʐ��\�̑��ɉ摜�����G���W���̃`�b�v�Ȃǂ�
�ǂꂾ���R�X�g�������邩�ƌ�����肪����܂��B
�\�Z�������Ȃ�ǂ���ō��̐v������Ηǂ��̂ł����A����ł͕������l�i�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�ǂ����Ńo�����X�����K�v���o�ė��܂��B
���̃J�����͘A�ʐ��\������̈�ł���̂ŁA�����A�ʋ@�Ƃ��Đv���Ă��܂��B��������ƎB�e�f�[�^�������ŋL�^���Ȃ��ƒǂ����܂���B
�B�e�R�}���ɋL�^���x��ǂ������悤�Ƃ�������14bit����12bit�̕����v���Ղ��̂ł��B
�ܘ_�̔����i�������Əグ�Ă��ǂ��Ȃ��14bit�ɂ��ĉ摜�����G���W������荂���������o����`�b�v���g���A
�L�^���f�B�A�����z�ō�����CFexpress���̗p����Ηǂ����̂��o���܂����A
���Еi�Ɩ{�i�Ƃ̔�r�ŋ����͂��l�����Ƃ��ɂ��̎d�l�ł��̉��i�łȂ��Ƌ����o���Ȃ��ƍl�����̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25224056
![]() 4�_
4�_
�Z���T�[�̃A�E�g�v�b�g��12bit�Ȃ̂ł�����A�J������12bit�Ƃ��������̘b�ł��B
�����ɘA�ʃR�}����f�[�^�T�C�Y�̎���͈�؊֗^���܂���B
�����Z���T�[��14bi���o�͂Ȃ�A�K�R�I�ɃJ�����̎d�l��14bit�ɂȂ�܂��B
���ׂĂ̓Z���T�[����Ȃ̂ł��B
�����ԍ��F25224073
![]() 8�_
8�_
�������Z���T�[��14bi���o�͂Ȃ�A�K�R�I�ɃJ�����̎d�l��14bit�ɂȂ�܂��B
���ꂪ�����ł��BM4/3�̃\�j�[���̃Z���T�[��12bit�ł��B
GH6�͕ʃ��[�J�[�Ȃ̂�14bit�o�͂ɂȂ�܂��B
GH5s���m��14bit�o�͂������Ǝv���܂�
�����ԍ��F25224118�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�����̃\�j�[�@�͒P�ʂ�14bit�A�A�ʂ�12bit�ƌ����d�l������܂����B
�Z���T�[�̏o�͂�14bit������K������14bit�ɌŒ肳���ƌ�����ł͂���܂���B
�����ԍ��F25224338
![]() 6�_
6�_
��Kazkun33����
���Z���T�[���\���オ���Ă��Ă���Ȃ�14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B
�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W���L���Ȃ�A���̒ʂ�ł��B
DXOMARK�̃Z���T�[�X�R�A��Landscape(�_�C�i�~�b�N�����W)�͎��̂��̂ł��B
��7C�iRAW 14�r�b�g�j�@14.7EV
��6400�iRAW 14�r�b�g�j 13.6EV
E-M1 Mark�U�iRAW 12�r�b�g�j 12.8EV
OM-1 �̃X�R�A�͂܂������̂ł����A
��������܂��ƁAOM-1 �̃_�C�i�~�b�N�����W��E-M1 Mark�U���班���ǂ��Ȃ��Ă���ARAW 14�r�b�g�ɕς��Ă����A�̂�������܂���B
�܂��AE-M1 Mark�U�Ɠ������Ƃ��Ă��ARAW 14�r�b�g�ɕς��Ă��ǂ������A�̂�������܂���B
�Ȃ����̂悤�ɁA�_�C�i�~�b�N�����W�����܂�L���Ȃ��Ă��ARAW 14�r�b�g�̃J����������܂��B
EOS RP�iRAW 14�r�b�g�j 11.9EV
����������܂�����A���̃X�����䗗���������B
�w�Z���T�[��RAW�̃_�C�i�~�b�N�����W�x
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001129952/SortID=24245149/
�����ԍ��F25224565
![]() 3�_
3�_
����������Ƃ���
�\�j�[��12bit�o�͐����̓Z���T�[���G���W���̏����\�͂��Ǝv���܂��B
��Kazkun33����
�Z���T�[��RAW�o�͐��\�̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ō��܂��Ă��܂��܂��BM4/3�Z���T�[�͏]����12bit�܂ł�����ƌ����Ă��܂������A�G���W���̐��\���グ��14bit�����܂ŏグ�Ă���̂�GH6�ł��BOM-1�͂����܂ŏ����\�͂��オ���Ė�����14bit�܂ŕK�v�Ƃ��ĂȂ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25224653
![]() 4�_
4�_
������89����
�\�j�[�̃Z���T�[��12bit������Ƃ����ӌ��Ƃ͏������_����������܂��H
������14bit���K�v�ł���Α��̃Z���T�[��g�ݍ��ނ��Ƃ��I�����ɂȂ�̂ł��B
�ł����ۂɂ͂������Ȃ������B
�R�X�g�A�d�l�A�����Ƃ̋����𑍍͂��I�ɔ��f���č��̐��i�ɂȂ����ƌ����̂����̌����������ƂȂ�ł��B
�����ԍ��F25224773
![]() 5�_
5�_
��������Ƃ���
OM-1�̃Z���T�[��IMX472�ƌ����Ă��܂����A4/3�Z���T�[�ŗ��ʏƎˁ��ϑw�^�͂��ꂾ���ł��B
���݃p�i����̃Z���T�[�����͂���Ă��Ȃ��l�Ȃ̂ŁA����ȊO�̑I�����͖�����ŁB
�u���̃Z���T�[�v�Ƃ͋�̓I�ɉ��ł��傤���B�@�����������APS-C�Z���T�[�ł��傤���B�@���������Ȃ�4/3�̔ے�ɂȂ�̂ł��蓾�Ȃ��ł��傤�B
***
�l���Ⴂ�����Ă���������܂����Abit�����_�C�i�~�b�N�����W�ł͂���܂���B
�K�i�ŏ�̊K�܂ŏオ��Ƃ��A�i����bit���ɑ������܂��B�@���̂Ƃ��A��̊K�܂ł̍����͊֗^���܂���B
��̊K�܂ł̍����ɑ�������̂́u�t���X�P�[�������W�v�ƌĂ��X�y�b�N�ł��B
�����̌��z���ł���̊K�܂ł̍����͂܂��܂��ȗl�ɁA�t���X�P�[�������W���قȂ�A/D�R���o�[�^�[�����݂��܂��B
�t�Ƀt���X�P�[�������W��������bit�����قȂ�A/D�R���o�[�^�[�����݂��܂��B
�_�C�i�~�b�N�����W�̗D������̂Ȃ�A�t���X�P�[�������W�Řb�����Ȃ���Ȃ�܂���B�@bit���Řb�����Ă����Ӗ����Ƃ������ł��B
�ł�bit���Ƃ͉����Ƃ����Ɓu�K���v�ł��B�@�i���������Ȃ�ƁA�₪�ĊK�i�͊K�i�łȂ��Ȃ�A�M�U�M�U�������Ȃ��āA���炩�Ȉꖇ�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25225036
![]() 8�_
8�_
��Tech One����
�t���X�P�[�������W���L���Ȃ�_�C�i�~�b�N�����W�������Ȃ�A������f�[�^�ʂ͑�����̂ł͂Ȃ��ł����H
OM-1�͍����x�����ƃ_�C�i�~�b�N�����W���オ�����Ƃ������Ă܂���12bit�ŏ[���Ȃ̂ł��傤���H
�n�C���]�AHDR���̕������摜���������鎞��14bit�Ƃ���Ƃ��掿���ǂ��Ȃ�̂Ǝv���̂ł����B
�f�[�^�ʂ�4�{�ɂȂ��Ă��������x�͖�薳���Ǝv���܂������f�l�̐�m�b�ł����H
�����ԍ��F25225212
![]() 1�_
1�_
��Kazkun33����
��OM-1�͍����x�����ƃ_�C�i�~�b�N�����W���オ�����Ƃ������Ă܂���12bit�ŏ[���Ȃ̂ł��傤���H
ISO�ɂ���ă_�C�i�~�b�N�����W�͕ς��܂��B�ʏ�A�_�C�i�~�b�N�����W�ƌ����ꍇ�A�_�C�i�~�b�N�����W�̍ő�l�̂��Ƃ�b���Ă��邱�Ƃ������ł��B
�����x�ł͊���x(OM-1 ��ISO 200)�ɔ�ׂāA�_�C�i�~�b�N�����W�͊i�i�ɋ����Ȃ�܂��B
�ł��̂ŁA�����x�m�C�Y��������x�����āA����ɂ�荂���x�̃_�C�i�~�b�N�����W��������x�L���Ȃ��Ă��ARAW 12�r�b�g����Ώ\���ł��傤�B
�܂�A�����ő厖�Ȃ̂̓_�C�i�~�b�N�����W�̍ő�l�ł��B
���̋L���ɂ��܂��ƁAE-M1 Mark2�AMark3�AOM-1�̃_�C�i�~�b�N�����W(PDR(Photographic Dynamic Range))�̍ő�l�͎��̂��̂ł��B
Photons to Photos
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm
E-M1 Mark2�F�@9.82(ISO 200)�A9.84(ISO 251)
E-M1 Mark3�F�@9.74(ISO 200)�A9.45(ISO 251)
OM-1�F�@9.54(ISO 200)�A9.27(ISO 251)
��������܂��ƁAOM-1�̃_�C�i�~�b�N�����W�́AE-M1 Mark2�AMark3 �Ƃ��܂�ς��Ȃ��ł��B�ނ���A���������Ȃ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25225275
![]() 1�_
1�_
��pmp2008����
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y��Live MOS�Z���T�[�̐��\����͓���A�掿�����シ��ɂ͉摜�G���W���̌��サ���Ȃ��̂ł��ˁB
�����ԍ��F25225336
![]() 2�_
2�_
��Kazkun33����
���}�C�N���t�H�[�T�[�Y��Live MOS�Z���T�[�̐��\����͓��
����͕�����Ȃ��ł��B
���掿�����シ��ɂ͉摜�G���W���̌��サ���Ȃ��̂ł��ˁB
�掿�̍��ڂɂ����̂ł��傤�B
�����x�̕`�ʂł�����A�ŋ߂̃m�C�Y�����̃\�t�g�͐����݂����ł��̂ŁA�摜�G���W���łȂ��āA�㏈���ł��悢�A�̂�������܂���B
����AISO 200 ���炢�̍������܂��ƁAM43 �ł��\���Y��ȋC�����܂��B
�����ŁA����ɃO���f�[�V�����Ƃ���Nj�����Ȃ�A�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W���L���āARAW14�r�b�g�Ƃ��i�ނ��ƂɂȂ�̂ł��傤�B
�����܂ł��������ŁA�ǂ����Ă�M43�ŎB�e���������́A�����Җ]��ł���̂ł��傤����ǁA
�����łȂ���AM43�̐��\�����҂����ɁA���̃t���T�C�Y�ŎB�e����A�悤�ȋC�����܂��B
�����l����ƁAM43 �ł����܂ł���Ă��A�����炭�����i�ɂȂ��āA����قǔ���Ȃ����낤
�ƃ��[�J�[�͍l���Ă���A�̂�������܂���B
�����ԍ��F25225404
![]() 4�_
4�_
�f�G�Ȏʐ^�Ɍ����B�ꂷ��̂́A
�J�����̃Z���T�ł͂Ȃ��A
�B�e�҂̃Z���X�B
�����ԍ��F25225547
![]() 9�_
9�_
�Z���X��1�Ԃł��傤�B
�����A�b�̎�|�𗝉��ł��Ȃ��̂��A���̗��R�Ȃ̂�������܂��|�C���g���O�����R�����g����Ă��ˁI
�����ԍ��F25225730
![]() 6�_
6�_
���\�j�[�̃Z���T�[��12bit
�Ƃ�����M4/3�̃_�C�i�~�b�N�����W��R�`�v�t�H�[�}�b�g��12bit�ɂȂ��Ă��邩��\�j�[�̃Z���T�[��12bit�ɂȂ��Ă���A�Z���T�[��̃_�C�i�~�b�N�����W����RAWbit��12bit����オ��Ȃ��Ƃ݂Ă܂��B
�f�W�^���ł�bit���͊m���ɐF�̊K���x�ł����ARAW��bit���̓_�C�i�~�b�N�����W���W���Ă��܂��B
�t���T�C�Y��14bit��16bit�ɂł��邩�Ɠ�����bit���グ�ă_�C�i�~�b�N�����W���₷�̂ɔM�S�Ȃ͓̂���ɗ͓���Ă�\�j�[�ƃp�i�\�j�b�N�������Ǝv���܂��BGH6��OM-1�̃Z���T�[�g��Ȃ��̂��A���ʈʑ����ɂł��Ȃ������̂���������ւ���ł邩�ȂƁB
�I�����p�X�ɕt���Ăł����A�_�C�i�~�b�N�����W�̊g���@�\�������Ȃ����̃��[�J�[�ł��̂ŁA���܂�RAW��bit���ɂ�������Ė����̂�������܂���B���̕ς��Ƃ��ċ��͂Ȏ�Ԃ��ƍ������̃m�C�Y���_�N�V�����Ń_�C�i�~�b�N�����W�������̂�Ώ�������Ƃ��Ă���̂ł͂Ǝv���܂���
�����ԍ��F25225965
![]() 0�_
0�_
�Ȃ��̋c�_�A10�N���炢�O�Ƀt���T�C�Y�@�iSONY?)�̔ł悭�����C������B
�Ă��Ƃ�10�N��ɂ͂P�Sbit�ɂȂ��Ă��Ȃ��ł����B
�����ԍ��F25226190
![]() 1�_
1�_
>Kazkun33����
>�t���X�P�[�������W���L���Ȃ�_�C�i�~�b�N�����W�������Ȃ�A������f�[�^�ʂ͑�����̂ł͂Ȃ��ł����H
���݂܂���B�@�t���X�P�[�������W��D�����W�͎������܂��B
�������� http://www.ned-sensor.co.jp/support/about2.html �́u���x�E�O�a�I���ʁE�O�a�o�͓d���v�u�_�C�i�~�b�N�����W�v���������������B
���������̐������킩��Ȃ��Ă��AA/D�R���o�[�^�[��bit�����ǂ��ɂ��o�Ă��Ȃ�������AD�����W�ƊW�Ȃ��͉̂��ƂȂ��킩��Ǝv���܂��B�@���������Z���T�[�͌��|�d���ϊ��̃A�i���O�f�q�ł��̂ŁAbit���Ƃ����T�O���̂���܂���B
�f�[�^�ʂɊւ��ẮA12bit��14bit�͂ǂ����16bit�f�[�^�ȉ��Ȃ̂ŁA���̐����͈̔͂��قȂ邾���ŃJ�����̃������[����ʂ͕ς��Ȃ��͂��ł��B
�������A�Z���T�[����̃f�[�^�o�X����2bit�ȉ����ƁA�ʐM�f�[�^�̗ʂ͈���Ă��܂��B�@4bit�ȏ�ł���ΐ�グ�ł���̂ŒʐM�f�[�^�̗ʂ͓����ɂȂ�܂����A��ʐl�ɂ̓f�[�^�V�[�g������ł��Ȃ��l�Ȃ̂ł킩��܂���B
>OM-1�͍����x�����ƃ_�C�i�~�b�N�����W���オ�����Ƃ������Ă܂���12bit�ŏ[���Ȃ̂ł��傤���H
��ɂ��������l�ɁAbit���͊K�i�́u�i���v�ł��B�@�ʂ̊K�Ƃ́u�����v�ł͂���܂���B
���������ARAW���x���ł�E-M1 mkIII�Ɠ��������Ȃ̂ŁAmkIII�ŏ\���������̂Ȃ�OM-1���\���Ƃ������ɂȂ�܂��B
12bit��14bit�ɂ���ƊK����4�{���炩�ɂȂ��ł����AJPG�ɗ��Ƃ��ۂ�8bit�Ɉ��k�����̂ŁA�ŏI�I�ɍ����o��̂��ǂ����͂킩��܂���B
>�n�C���]�AHDR���̕������摜���������鎞��14bit�Ƃ���Ƃ��掿���ǂ��Ȃ�̂Ǝv���̂ł����B
�Z���T�[�o�͂�12bit�Ȃ̂ł�����A14bit�ɂ��Ă��ς��Ȃ��Ǝv���܂��B�@����12bit�̏���Ȃ��̂ŁA4�{���邩�ŏ�ʌ��Ƀ[����2�t���邾���̘b�ł��B
�O�҂͉���2�r�b�g���\�t�g�E�F�A�ŕ�ԉ��Z���ĂȂ߂炩�Ɍq���鎖�͂ł��܂����A����ɈӖ������邩�ǂ����͂킩��܂���B
���Ƀ[����t���邾���̌�҂͍ŏ�����Ӗ�������܂���B
>�f�[�^�ʂ�4�{�ɂȂ��Ă��������x�͖�薳���Ǝv���܂������f�l�̐�m�b�ł����H
�f�[�^�ʂ�������Ώ������ׂ͊m���ɑ����܂��B�@�������A4�{�ɂȂ��Ă����Ȃ����ǂ����̓��m���悩�Ǝv���܂��B
���Ƃ��C���^�[�l�b�g�łǂ����̃T�C�g������Ƃ��AURL����͂��ĕ\�������܂ł̎��Ԃ�1ms����4ms�ɂȂ��Ă������ς��܂��A1�b��4�b�ɂȂ�u�x���v�ɂȂ�܂��B
>ALL
�ēx�����܂����AA/D�R���o�[�^�[(�ȉ�ADC)��bit�� �� �_�C�i�~�b�N�����W�ł͂���܂���B�@��̒ʂ�K�i�̒i���ł��B
�ʂ̗Ⴆ������ƁA�s�U��12(���ۂ�4096)�������邩�A14(���ۂ�16384)�������邩�̈Ⴂ�ŁA�����Ƀs�U�̒��a�͊֗^���܂���B
�����̕����w���������s�U�̒��a�x�ƍl���Ⴂ�����Ă��܂��B
D�����W���L���Ȃ�ƊK�������炩�ɂ���ړI��bit���𑝂₷���͂���Ǝv���܂����A����͌��ʂł��B
�P�̂�ADC���ƃt���X�P�[�������W�͓�����bit�����قȂ�`�b�v�͕�������܂��B�@bit�������Ȃ�ADC�͕���\���r���������A����ADC�͍������������Ƃ������ł��B
�����ԍ��F25226780
![]() 7�_
7�_
��Tech One����
���t���X�P�[�������W��D�����W�͎������܂��B
�@D�����W���L���Ȃ�ƊK�������炩�ɂ���ړI��bit���𑝂₷���͂���Ǝv���܂����A����͌��ʂł��B
�L���m���̃J�����p��W�ɂ��Ɓu�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A�f�W�^���J�������Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���A���邢��������Â������ւ̍Č��\�ȕ��̂��Ƃ������܂��B��ʓI�ɁA�≖�J�����i�t�B�����J�����j�̏ꍇ�́u���`�`���[�h�v�ƕ\������܂��B�v�Ƃ���Ă���A�ł����邢���ƍł��Â����̏o�͂̔��2�i�@�Ŏ������l�ł��B�A���A�_�C�i�~�b�N�����W�͑���@�ɂ��l�͈قȂ邪�X���͕ς��Ȃ��l�ł��B
�_�C�i�~�b�N�����W���Z���T�[�o�͂̕���\�ARAW�̌��ʂ̍ő���ʂ��Ă���ꍇ�́A�Z���T�[���\���ő�Ɉ����o���Ă��Ȃ����ƂɂȂ�̂ł��ˁB⇦pmp2008����̐����ł���A���̌��O�B
�����ԍ��F25227100
![]() 0�_
0�_
���L���m���̃J�����p��W�ɂ��Ɓu�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A�f�W�^���J�������Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���A���邢��������Â������ւ̍Č��\�ȕ��̂��Ƃ������܂��B��ʓI�ɁA�≖�J�����i�t�B�����J�����j�̏ꍇ�́u���`�`���[�h�v�ƕ\������܂��B�v�Ƃ���Ă���A�ł����邢���ƍł��Â����̏o�͂̔��2�i�@�Ŏ������l�ł��B
�z���}�ł����H
���́A�Q�i�@�Ŏ����K�v�������ł��傤���H
�P�O�i�@�̕\���ŗǂ�����Ȃ��ł��傤���H
�L���m���l�̎ʐ^�p��W�����ǂ��Ă��A�����ɂ��w�Q�i�@�x�łƂ͏����Ă܂��B
�E�B�L�y�f�B�A�ɂ͎��̂悤�ɏ����Ă܂����B
�w�_�C�i�~�b�N�����W�i�p: dynamic range�j�Ƃ́A���ʉ\�ȐM���̍ŏ��l�ƍő�l�̔䗦�������B�M���̏��ʂ�\���A�i���O�w�W�̂ЂƂB�x
�c�P�ɔ䗦�����Ɍ��y���Ă���A���i�@�ŕ\�����ׂ��A�Ƃ͏����Ă܂���B
�f�V�x���ŕ\�������A�Ƃ���̂ŗႦ��50db���i�@��110010dB�����A�Ȃ�Ėʓ|�L���\���Ȃ�Ă���Ă��܂���āB
���݂ɃX���`���̎��̂P����ǂނƁc
��APS-C��RAW�T�C�Y��14bit�Ȃ̂ɁAOM-1��12bit�Ȃ̂ł����H
�wRAW�T�C�Y�x���t�@�C���T�C�Y�Ɖ��肷��Ȃ�A14�r�b�g�ŕ\���ł���ő�l���Q�̂P�S��|�P�ł�����P�U�R�W�R�o�C�g�c����͉����ł��ȁB
�wRAW�f�[�^�����̂��߂ɃC���[�W�Z���T�[�i�{���X�̉�H�j�����̋���(�F�̔Z���ł��ǂ����j�ƌ����A�i���O�l������r�b�g���x�A�ƍl����Ȃ�A���̃Z���T�[���f���o���f�[�^���O�`�P�U�R�W�R�܂ł̂P�S�r�b�g�ɏ������A����Ȃ�܂������ł��܂��B
���ǂ̂Ƃ���A�v�҂ɒ����������m�����Ǝv���܂��B�c����Ȃ苳���Ă����Ƃ͎v���܂��ˁB
D�����W�������҂���14�r�b�g�ʼn�H���삵����m�C�Y�ɖ����������12�r�b�g�łƑ卷�Ȃ��R�X�g���ɂȂ����Ƃ��A��H�v����ω߂����Ƃ��A�f�o�C�X����ɓ���Ȃ������������Ƃ��A�����͐F�X�ł���ł��傤���A�O�삪�Ƃ₩���������Ƃ���Ő^���ɂ͒H�蒅���Ȃ��B
�����ԍ��F25227341
![]() 6�_
6�_
��Kazkun33����
��{�I�ȂƂ�����m�F�������Ǝv���A���₵�܂��ˁB
>�Z���T�[���\���オ���Ă��Ă���Ȃ�14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B
>OM-1�͍����x�����ƃ_�C�i�~�b�N�����W���オ�����Ƃ������Ă܂���12bit�ŏ[���Ȃ̂ł��傤���H
12bit����14bit�ɂ��邱�Ƃʼn����ς��̂ł��傤�H�@
Kazkun33����́A�������҂��Ă���������̂ł��傤�H
>�}�C�N���t�H�[�T�[�Y��Live MOS�Z���T�[�̐��\����͓���A�掿�����シ��ɂ͉摜�G���W���̌��サ���Ȃ��̂ł��ˁB
�����Ȃ̂ł����H
>�i�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A�j�ł����邢���ƍł��Â����̏o�͂̔��2�i�@�Ŏ������l�ł��B
���̂悤�Ȑ����͏����ł����B
>�_�C�i�~�b�N�����W���Z���T�[�o�͂̕���\�ARAW�̌��ʂ̍ő���ʂ��Ă���ꍇ�́A�Z���T�[���\���ő�Ɉ����o���Ă��Ȃ����ƂɂȂ�̂ł���
�u�_�C�i�~�b�N�����W���Z���T�[�o�͂̕���\���Ă���v�Ƃ́H
�u�_�C�i�~�b�N�����W��RAW�̌��ʂ̍ő���ʂ��Ă���v�Ƃ́H
�����āA������bit���Ƃ̊W�́H
���낢��Ƙ_�|��������܂���̂ŁA�����������肢�������ł��B
�����͕ʃX���b�h�ł���������Ă��܂����A�����������������������Ǝv���܂��B
�@
�����ԍ��F25227351
![]() 9�_
9�_
������͂�����
��Tranquility����
���L���m���l�̎ʐ^�p��W�����ǂ��Ă��A�����ɂ��w�Q�i�@�x�łƂ͏����Ă܂��B
2�i�@�͈Ⴂ�܂��ˁB�_�C�i�~�b�N�����W�͏o�͔��2�̗ݏ�Ŏ������l�Ȃ̂ł����\�����Ă��܂��܂����B
�ԈႢ���_���o���A����Ԃ����Ȃ��ŁA���_�����Ȃ����̌�����������@�ŕԂ��ĉ������B
Tech One����̃R�����g��ǂ�Œ�����A���₳��Ă��邱�Ƃ̓������킩��Ǝv���܂��B
�܂��A�c�_�ɂȂ�Ȃ�����Ԃ��ɑΉ����Ă��X�����r��邾���Ɣ��f�����R�����g�ɂ͑Ή����Ȃ��l�ɂ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25227478
![]() 5�_
5�_
��Kazkun33����
>�ԈႢ���_���o���A����Ԃ����Ȃ��ŁA���_�����Ȃ����̌�����������@�ŕԂ��ĉ������B
����Ɣ��_�͈Ⴂ�܂��̂ŁB
���l�����킩��Ȃ����玿�₵�Ă��܂��B
�R�����g�ŁA�ǂ̂悤�Ȃ��l���Ȃ̂������ł��܂���ł����̂ŁB
���̗����Ȃ��ɓ��ӂ��[�������_�����蓾�܂����ˁB
>Tech One����̃R�����g��ǂ�Œ�����A���₳��Ă��邱�Ƃ̓������킩��Ǝv���܂��B
Tech One����@�̃R�����g�͓ǂ�ł��܂����A�����ł��܂��B
�������A����� Kazkun33���� �̂��l���̐����ł͂Ȃ��ł���ˁB����l�͕ʐl�ł��傤���B
Tech One���� �̃R�����g�ɑ��āu�����ԍ��F25227100�v�Ɂw���̌��O�x�Ƃ��ԐM�����Ă��܂��B
���̎���̈�́A���̌��O�̓��e�Ȃ̂ł����B
>�܂��A�c�_�ɂȂ�Ȃ�����Ԃ��ɑΉ����Ă��X�����r��邾���Ɣ��f�����R�����g�ɂ͑Ή����Ȃ��l�ɂ��Ă��܂��B
����Ɣ��_�͈Ⴂ�܂���B
�X���b�h���r���̂́A�����̏ꍇ�A�����^��ɂ܂������������A���₷��҂̐l�i�ے�ɑ��邱�Ƃ������Ƃ��đ����ł��B�܂��A�����̘_���������ƍl����Ȃ�A���_�ɍĔ��_������������Ȃ�ł����A����������ɑ���̐l�i�ے������Ƃ������Ƃ�����܂��B
�܂��A��O�҂�������ˑR����āA�c�_�ɓ��e�ɊW�Ȃ��r�炷���߂̃R�����g������Ƃ����̂������ł��ˁB
�����^��ɂ܂�����������A���ʂ͍r��邱�Ƃ͖����ł���B
�����ԍ��F25227693
![]() 13�_
13�_
��Kazkun33����
>�X�����r��邾��
������傫�Ȍ����́A����������Ă����������A��F���Łi���邢�͌̈ӂɁj���萻�i�̃l�K�e�B�u�R�����g���J��Ԃ��l�����邱�Ƃł��ˁB
����ƁA�X���傳�Q���҂̋c�_�����܂��R���g���[���ł��Ȃ����Ƃ����R�ɂ��邩������܂���B�܂��A����́u���Ȃ��Ă������v�Ƃ����l��������Ƃ͎v���܂����B
�����ԍ��F25227748
![]() 9�_
9�_
Kazkun33����
>�_�C�i�~�b�N�����W���Z���T�[�o�͂̕���\�ARAW�̌��ʂ̍ő���ʂ��Ă���
�_�C�i�~�b�N�����W�ƃZ���T�[�o�͂̕���\(bit���̎��ł��傤��)�ɑ召�W�͂���܂���B
�܂��A�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͖��Í��ł��̂ŁA�_�C�i�~�b�N�����W < RAW�̌��ʂ̍ő���� �͂��蓾�Ȃ��Ǝv���܂����B
>�Z���T�[���\���ő�Ɉ����o���Ă��Ȃ����ƂɂȂ�̂ł��ˁB
�O�v�̂Ȃ��̂ʼn��Ƃ��B
>⇦pmp2008����̐����ł���A���̌��O�B
�����������Ă���̂ʼn������O�Ȃ̂��킩��܂���B
�Ƃɂ����A���̎咣�́uA/D��bit����D�����W�ƊW�͂��邪�AD�����W���̂��̂ł͂Ȃ��v�ł��B
����OMDS�ł�SONY�Z�~�R���̒��̐l�ł��Ȃ��̂ŁA�Z���T�[�̒��ʼn����N���Ă��邩����Ă��킩��܂���B
�����ԍ��F25227803
![]() 6�_
6�_
�����ł��B
×�_�C�i�~�b�N�����W < RAW�̌��ʂ̍ő����
���_�C�i�~�b�N�����W > RAW�̌��ʂ̍ő����
�����ԍ��F25227812
![]() 1�_
1�_
��Tech One����
�R�����g�͕��ɂȂ�܂��B�ł����A������Ƃ������肢���B
���p�����Ƃ����g�̃R�����g����ʂł���悤�ɏ����Ă���������Ə�����܂��B
�����ď�����Ă���Ƃǂ��܂ł����p��������ɂ����āA���̗͂����Ɏ�Ԏ��܂��Ă��܂��܂��̂ŁB
���݂܂���B��낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F25227824
![]() 5�_
5�_
��Tech One����
��Tranquility����
�X���傳��̎�����A���̂悤�ɉ��߂��Ă��܂��B
�uOM-1��RAW��12�r�b�g���邪�A���ꂪ14�r�b�g�ł���Ȃ�i14�r�b�gAD�ϊ��Ƃ��܂��j�ARAW�f�[�^�i������JPEG�摜�j�͂���ɗǂ��Ȃ�̂��H�v
����͓���ł����A��ʘ_�Ƃ��Ă͎��̂悤�ɍl���܂��B
�Z���T�[��̌��f�[�^�i�A�i���O�j���f�W�^���f�[�^�ɕϊ����āARAW�f�[�^�����ۂɁA
�E�r�b�g�������Ȃ��ƁARAW�̃O���f�[�V�����͊��炩�Ŗ����B���������̌��f�[�^���̂ĂĂ���B
�E�r�b�g�����K�ł���ƁARAW�̃O���f�[�V�����͊��炩�ł���B
�E�r�b�g������������ƁARAW�̃O���f�[�V�����͂����ǂ��Ȃ炸�A���ʂł���B
�����ԍ��F25227922
![]() 3�_
3�_
���f�̑傫���ɂ���ĕK�v��ADC�̕���\���ĕς��Ǝv���̂ł��������t�H�[�}�b�g�Œ��f�@�ƍ���f�@�ňقȂ�r�b�g�����Ă��Ɩ����ł���� ���̂���
���Ȃ݂�
�����J�����Ńr�b�g���ς�����(�ς�����Ⴄ)�J������������DR�̕ω��͂���Ȋ����ł�
16bit��14bit��DR���ς��Ȃ���
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#FujiFilm%20GFX%20100_14,FujiFilm%20GFX%20100
14bit��12bit��DR����
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Canon%20EOS%20R6%20Mark%20II,Canon%20EOS%20R6%20Mark%20II(ES)
�����ԍ��F25228089�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
pmp2008����
>�uOM-1��RAW��12�r�b�g���邪�A���ꂪ14�r�b�g�ł���Ȃ�i14�r�b�gAD�ϊ��Ƃ��܂��j�ARAW�f�[�^�i������JPEG�摜�j�͂���ɗǂ��Ȃ�̂��H�v
�K����2bit�����炩�ɂȂ�̂͊m���ł��傤�B
�������AJPEG�A���j�^�[����8bit�ł��̂ŁA�l�����鎖���ł���摜�ɂȂ������_�ō����o�邩�ǂ����͂킩��܂���B
A/D�̃r�b�g����ς�����A�܂��̓r�b�g���ȊO�͓���X�y�b�N�̃J���������݂���̂ł���Ό��ł���Ǝv���܂����A�����Ȃ��ł���ˁB
��o������
�O���Ă����炷�݂܂��AEOS R6 MarkII �̃O���t�̓��J�V���b�^�[�Ɠd�q�V���b�^�[�̔�r�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F25228175
![]() 5�_
5�_
��pmp2008����
��ʘ_�͏d�X���m���Ă��܂��B
�����ł͎���̌`�Ԃ�����Ă͂��܂����A�X���傳��̊e���R�����g��q�ǂ���ɁAOM-1��12bit������APS-C��14bit�ɔ�ׂė��Ǝ咣�������悤�ł��B
����ŁA12bit���Ƌ�̓I�ɂǂ̂悤�ɉ掿�Ɏx�Ⴊ������̂��A12bit�ɔ�ׂ�14bit��RAW�ɃX���傳��͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����҂��Ă���̂����������������̂ł��BTech One���� �̂��������ʂ�A�ŏI�I�Ȋӏ܊���8bit�Ƃ����Ȃ��ŁB
�Ȃ��u����f�قǃG���C�v�Ƃ������o�Ǝ��Ă���悤�Ɏv����̂ł��B
�����^��ւ̐��������ۂ���Ƃ�����A�悭���鍪���Ȃ��l�K�R�����g�݂����Ɏv���܂��B
�����ԍ��F25228197
![]() 11�_
11�_
��Kazkun33����
���Z���T�[���\���オ���Ă��Ă���Ȃ�14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B
���[�U�[�̍���ɂ���̘V�����l����ƁA12bit�ł��\���߂���Ƃ����v�����B
�����ԍ��F25228206
![]() 0�_
0�_
��Tech One����
���p���Ɩ{���̕������z�����肪�Ƃ��������܂��B
����Ȃ�ǂ߂܂��B
�����ԍ��F25228231
![]() 6�_
6�_
��Tech One����
���K����2bit�����炩�ɂȂ�̂͊m���ł��傤�B
�����ł����A
���f�[�^�i�A�i���O�j�̃_�C�i�~�b�N�����W������������A�����12�r�b�g�ϊ�����RAW��14�r�b�g�ϊ�����RAW�A�������炻�ꂼ��摜�ɂ��āA�����ڂŌ��Ă��Ⴂ�͎��ʂł��Ȃ��A�悤�Ɏv���܂��B
���ǂ̂Ƃ���A�ǂ̂��炢�ǂ��Ȃ�̂��́A������Ȃ��ł��ˁB
���������AJPEG�A���j�^�[����8bit�ł��̂ŁA�l�����鎖���ł���摜�ɂȂ������_�ō����o�邩�ǂ����͂킩��܂���B
�����́ARAW�����ŘI�o�i�g�[���J�[�u�j��ς�����m�F�ł���A�悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F25228236
![]() 2�_
2�_
��Tranquility����
�����������Ƃł������B
�����ԍ��F25228243
![]() 0�_
0�_
��pmp2008����
�X���傳���12bit�ł͂Ȃ�14bit���ǂ��Ƃ��������̂ŁA14bit�ɉ��������҂��Ă���̂ł��傤�B
���̈Ⴂ�ɂ��掿�ւ̉e���̒��x�������m�����炩�A���邢�͉�����]��ł���̂��Ǝv���̂ł��B
�m���A�����g�͌����E�Ńf�[�^��͂��Ȃ����Ă����Ƃ������Ƃł����̂ŁA���������₵�Ă��܂��B
�������A��̓I�Ȑ������Ȃ��炸�����ۂ��Ă���̂ŁA�悭����l�K�L�����݂������Ȃ��A�Ɓi�l�I�Ȋ��z�ł��j�B
���̈Ⴂ���m���ɂ�����12bit���Ǝx�Ⴊ����Ƃ����̂��n�b�L���킩��A����14bit�A���邢�͂���ȏ�̃J������~�����Ȃ邩������܂���̂ŁA�������Ă������������Ǝv���Ă��܂��B
���Ƃ����āA����OM-1�ŕs�s���͂��܂芴���Ă͂��Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F25228260
![]() 9�_
9�_
pmp2008����
>���f�[�^�i�A�i���O�j�̃_�C�i�~�b�N�����W������������A�����12�r�b�g�ϊ�����RAW��14�r�b�g�ϊ�����RAW�A�������炻�ꂼ��摜�ɂ��āA�����ڂŌ��Ă��Ⴂ�͎��ʂł��Ȃ��A�悤�Ɏv���܂��B
���������v���܂��B�@�����A�l���F�m�ł��Ȃ�������2bit���̉��P�͊m���ɑ��݂���Ǝv���܂��B
>RAW�����ŘI�o�i�g�[���J�[�u�j��ς�����m�F�ł���A�悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��B
bit�����ς�����A�܂���bit���ȊO�͓����X�y�b�N�̃J����������Ό��ł���Ǝv���܂��B
�����łȂ��J�������m��bit���ȊO�̗v�f���ז����ĉ��������Ă���̂��킩��Ȃ��Ǝv���܂��B
�X���傳���
�����I�ɉ��ƂȂ��r�b�g���������������掿���낤�ƍl����C�����͗����ł��܂����A����������������Ȃ��Ǝv���܂��B
�������A������m���߂��i���Ȃ��ȏ�A�\���ɉ߂����A�N�����������Ȃ��Ǝv���܂��B
����ł͑ʖڂł����H
�����ԍ��F25228262
![]() 5�_
5�_
��Tech One����
��EOS R6 MarkII �̃O���t�̓��J�V���b�^�[�Ɠd�q�V���b�^�[�̔�r
���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ł������ł��BR6 mk2�͓d�q�V���b�^�[�ɂ����12bit�ɂȂ��Ă��܂��d�l�̂��߂���ȕω�������܂�
�\�j�[�̂������̋@����A�ʎ���12bit�ɂȂ����肷��̂ł��� ���{�T�C�g�ł͘A�ʎ��̊G���g�����ƂȂ��̂œ������s���Ȃ�ł���� ���������Ӗ���R6mk2�͋M�d�ł�
��f�̑f�q���̂�DR�͍L�����ǂݏo��bit���������邱�Ƃ�DR���ቺ���Ă��܂���ł���
�����ԍ��F25228267�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��Tranquility����
����ʘ_�͏d�X���m���Ă��܂��B�����ł͎���̌`�Ԃ�����Ă͂��܂����A�X���傳��̊e���R�����g��q�ǂ���ɁAOM-1��12bit������APS-C��14bit�ɔ�ׂė��Ǝ咣�������悤�ł��B
�Ȃ��u����f�قǃG���C�v�Ƃ������o�Ǝ��Ă���悤�Ɏv����̂ł��B
�����^��ւ̐��������ۂ���Ƃ�����A�悭���鍪���Ȃ��l�K�R�����g�݂����Ɏv���܂��B
���̋^��𗝉����Đ^�ʖڂɑΉ����Ē����Ă�����ɑ��āA���̗l�Ȍ��������ł��Ȃ��̂ł��ˁB
�����ԍ��F25228271
![]() 5�_
5�_
����o������
���_�I�ɂ́A�m�C�Y�̉e����������ARAW��2�r�b�g�̈Ⴂ�́A���̂܂܃_�C�i�~�b�N�����W�� 2EV �Ƃ��Č����A�Ǝv���܂��B
R6 mk2 �̃O���t��ISO 100 �́A������ 2EV ���ɂȂ��Ă��܂��B�@�����āAISO ���オ��ARAW��2�r�b�g�̈Ⴂ�́A�����āA�Ō�͍��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����́A��Ɠx�������m�C�Y�ɖ�����邩��ł��傤�B
�����ԍ��F25228326
![]() 5�_
5�_
�t��������� �Ƃ������厖�Ȃ��ƌ����ĂȂ�����
�����Z���T�[�f�q���̂̐��\������(DR���L��)�� �ǂݏo������ۑ����Ńr�b�g������������邱�ƂŐ��\������(DR���ቺ)����Ă���̂��Ƃ�����
���R6mk2�̃O���t�̂悤�ɍ����x���\�͈ێ������܂� �ኴ�x�̃s�[�N���\�t�߂������������̂ł͂Ȃ���
�܂� om-1�̃O���t�̂悤�ɑf���Ƀ��j�A�ȓ�����`���Ă���̂� �r�b�g��������Ă��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ���
�Ǝv���܂���
�����ԍ��F25228341�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��Kazkun33����
���͕��ʂɎ��₵�������ł����B
����ɂ��Ă̂��Ȃ��̕Ԃ�������B
�@�@��
>�ԈႢ���_���o���A����Ԃ����Ȃ��ŁA���_�����Ȃ����̌�����������@�ŕԂ��ĉ������B
>Tech One����̃R�����g��ǂ�Œ�����A���₳��Ă��邱�Ƃ̓������킩��Ǝv���܂��B
>�܂��A�c�_�ɂȂ�Ȃ�����Ԃ��ɑΉ����Ă��X�����r��邾���Ɣ��f�����R�����g�ɂ͑Ή����Ȃ��l�ɂ��Ă��܂��B
�����Ȃ��l�K�R�����g���J��Ԃ��l�̔����Ǝ��Ă���̂ł��B
������x�����܂����A����Ɣ��_�͈Ⴂ�܂��B
Tech One����̃R�����g�́A���Ȃ��̂��l���̐����ł͂Ȃ��ł���ˁB
�����^��ɂ܂�����������A���ʂ͍r��邱�Ƃ͖����ł���B
���́A�����g�̂������ɂȂ������Ƃ̓��e���m�F�����������ł��B
�c�_�i�ł���̂Ȃ�j���ɐi�߂邽�߂ɁB
�Ȃ�14bit��]�ނ̂ł����H
�����ԍ��F25228393
![]() 10�_
10�_
��Tranquility����
���Ȃ�14bit��]�ނ̂ł����H
���[�U�[�Ȃ�ł�����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̉掿�������ł��ǂ��Ȃ邱�Ƃ��F���Ă��邩��ł��傤�B
�₵�������������ł��Ȃ��̂ł��ˁB
�����ԍ��F25228403
![]() 4�_
4�_
��Kazkun33����
>���[�U�[�Ȃ�ł�����A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̉掿�������ł��ǂ��Ȃ邱�Ƃ��F���Ă��邩��ł��傤�B
�u14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B�v
�u���ʂ�12bit�ŏ[���Ȃ̂��������x��D�悵�Ă���̂��C�ɂȂ��āv
�uOM-1�͍����x�����ƃ_�C�i�~�b�N�����W���オ�����Ƃ������Ă܂���12bit�ŏ[���Ȃ̂ł��傤���H�v
�u14bit�Ƃ���Ƃ��掿���ǂ��Ȃ�̂Ǝv���̂ł����B�v
���������������14bit��]��ł���̂� Kazkun33���� �����g�ł����ǁAOM-1�̃��[�U�[�������̂ł����H
>�₵�������������ł��Ȃ��̂ł��ˁB
����ɂ��������������Ȃ��̂ŁA���������₵������������܂��B
12bit���Ɖ����x�Ⴊ�������̂ł����H�@����͂ǂ̂悤�ȏꍇ�ł����H
14bit���ƁA�掿�����シ��̂ł����H�@�ǂ̂悤�ɕς��̂ł����H
�����ԍ��F25228426
![]() 12�_
12�_
����o������
>R6 mk2�͓d�q�V���b�^�[�ɂ����12bit�ɂȂ��Ă��܂��d�l�̂��߂���ȕω�������܂�
>��f�̑f�q���̂�DR�͍L�����ǂݏo��bit���������邱�Ƃ�DR���ቺ���Ă��܂���ł���
�d�q�V���b�^�[�Ń_�C�i�~�b�N�����W�����܂�̂́A�d�q�V���b�^�[�̉e���ł́B
RAW��12bit�ɂȂ邩��ł͂Ȃ��B
��pmp2008����
>���_�I�ɂ́A�m�C�Y�̉e����������ARAW��2�r�b�g�̈Ⴂ�́A���̂܂܃_�C�i�~�b�N�����W�� 2EV �Ƃ��Č����A�Ǝv���܂��B
�m�C�Y�̉e�����Ȃ��Ȃ邾���ŃZ���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W�͊g�債�܂��B
bit���ƃ_�C�i�~�b�N�����W�͕ʂ��̂��ƁB
�����ԍ��F25228552
![]() 8�_
8�_
��Tranquility����
���m�C�Y�̉e�����Ȃ��Ȃ邾���ŃZ���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W�͊g�債�܂��B
�����ł��B
��bit���ƃ_�C�i�~�b�N�����W�͕ʂ��̂��ƁB
�m�C�Y��������ARAW�f�[�^�����ŏ��l�� 1 �ł��B
�ő�l��RAW�̃r�b�g���Ō��܂�܂��B2�r�b�g�������4�{�A���Ȃ킿�_�C�i�~�b�N�����W�� 2EV �����܂��B
�����ԍ��F25228619
![]() 3�_
3�_
���͂悤�������܂�
��Tranquility����
���d�q�V���b�^�[�Ń_�C�i�~�b�N�����W�����܂�̂́A�d�q�V���b�^�[�̉e���ł́B
��RAW��12bit�ɂȂ邩��ł͂Ȃ��B
�L���m���̍ŋ߂̃J�����͓d�q�V���b�^�[�ɂ����DR�������邱�Ƃ͒m���Ă܂��������̗��R�͐�������Ă܂���ł��� R5�̂Ƃ��ɊC�O�̌����ł�AD�ϊ���bit���Ɋւ��錾�y�������� R6mk2�ł͓��{�T�C�g�ł�12bit�ɂȂ邱�Ƃ��������ꂽ �Ƃ����o�܂�������(���܂�L���m���̏��͒ǂ��ĂȂ��̂Ōo�܊Ԉ���Ă邩��)����ς肻���������Ƃ��Ə���ɔ[�����Ă܂���
�m���ɓd�q�V���b�^�[���̑��̗v����DR���������Ă��܂��Ă���Ƃ����\��������܂�����
���������Z���T�[�ɉ����Ă̓��J�V���b�^�[����Ȃ��Ɋւ�炸����͓����Ń��Z�b�g������(�d�q�斋�������)�^�C�~���O���Ⴄ���炢�ł�
�m�C�Y�ɂ����DR���ቺ���Ă�Ɛ������Ă���T�C�g������܂��� ��ISO�݂̂Ŕ�����2stop����������m�C�Y�Ƃ����̂͑z��������ł�
�d�q�V���b�^�[���̓��[�����O�c�݂�}�������Ӑ}��A�ʑ��x�����߂����Ӑ}��bit�����������������ǂݏo�����[�h�ɂ��邱�ƂŌ���DR�������Ă��܂��Ă���ƍl���Ė����͂Ȃ��͂��� �v���Ă܂�
�����ԍ��F25228766�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
����o������
���܂� om-1�̃O���t�̂悤�ɑf���Ƀ��j�A�ȓ�����`���Ă���̂� �r�b�g��������Ă��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ���
�Ȃ�قǁA�����Ȃ̂ł��傤�B
��Kazkun33����
�ǂ����A���_���o���悤�ł��B
�����ԍ��F25228840
![]() 3�_
3�_
���ЂƂ�
��Tranquility����
��bit���ƃ_�C�i�~�b�N�����W�͕ʂ��̂��ƁB
�ʕ��ł��� �ł�
��pmp2008����
���m�C�Y��������A
�m�C�Y�������Ɖ��肷���DR���`���ɂ��Ȃ����Ⴄ�̂Ńm�C�Y���P�x�ɂ�炸��l�Ɋ܂܂�Ă���Ɖ��肵��
���̐M�����ߕs���Ȃ��œK��AD�ϊ�����v���ł����Ƃ���Ƃ��̃r�b�g����DR��"��v���܂�"
�m�C�Y�ɖ�����Ȃ��M���M���̐M�������傤�Ǎʼn��ʃr�b�g��1�ƂȂ�A�O�a���ő�l�ł���킷���ƂɂȂ�̂ł����DR�̒�`���̂��̂ł�
�܂��r�b�g���Ƃ�2�i���ŕ\�����ꍇ�̌����ł���DR��2���ɂ���log�\�L���邩��l���킩��₷����v���܂���
�O����v�����郉�{�e�X�g�̌��ʂ�DR������ƈ�v���邩�͂�����ƕ��G�ł�����
�r�b�g��������Ȃ��Ə��̂Ă���DR��������܂����A�ʎq���m�C�Y�����傷�邽��DR����������Ƃ������������܂���
�����ԍ��F25228858�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
RAWbit�ɂ��Ă��낢��ƌ����Ă܂����A��������bit���グ��͊K���͖L���ɂȂ�܂����A�C���[�W�Z���T�[�Ɍ��Đ��l�ɕϊ��������ʂł�����A�Z���T�[����������Ύ����ƌ��E�͏o�Ă���킯��bit���ƃ_�C�i�~�b�N�����W�͊W�����Ƃ͌����ꖳ���Ǝv���܂�
�����ԍ��F25229041�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�u���d�ϊ��v�ł�����A
�B���f�q�T�C�Y�Ƃ��������A�X�̎���f�q�T�C�Y�ɂȂ�܂���(^^;
�����ԍ��F25229063�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��pmp2008����
>�ő�l��RAW�̃r�b�g���Ō��܂�܂��B2�r�b�g�������4�{�A���Ȃ킿�_�C�i�~�b�N�����W�� 2EV �����܂��B
����͈Ⴄ�̂ł́B�_�C�i�~�b�N�����W�̉����̓m�C�Y�A����͖O�a�ł���ˁB�l�������t���Ǝv���܂��B
��o���������ꂽ�uPhotons to Photos�v�̃f�[�^�ł́A�Ⴆ�� FUJIFILM GFX100 �̃_�C�i�~�b�N�����W��12EV���炢�ŁA16bit�ł�14bit�ł��_�C�i�~�b�N�����W�ɕς��͂���܂���B
�܂��A�����g�́u�����ԍ��F25224565�v�ł́A���L�̂悤�ɋL���Ă����܂����B�_�C�i�~�b�N�����W�́u�ő�l��RAW�̃r�b�g���Ō��܂�܂��v�Ƃ��������ƍ����܂��H
>DXOMARK�̃Z���T�[�X�R�A��Landscape(�_�C�i�~�b�N�����W)�͎��̂��̂ł��B
>��7C�iRAW 14�r�b�g�j�@14.7EV
>��6400�iRAW 14�r�b�g�j 13.6EV
>E-M1 Mark�U�iRAW 12�r�b�g�j 12.8EV
>�_�C�i�~�b�N�����W�����܂�L���Ȃ��Ă��ARAW 14�r�b�g�̃J����������܂��B
>EOS RP�iRAW 14�r�b�g�j 11.9EV
�܂�Abit����AD�ϊ��ŔC�ӂɌ��߂���Ƃ������Ƃł���ˁB�_�C�i�~�b�N�����W���L������͂ȉ摜�����ɂ��ꂾ���ς����邱�ƂɂȂ�A������bit����傫�����邱�Ƃ̈Ӗ������邩������܂��A��قǓ���ȏ����łȂ��ƌ��ʂ͂킩��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���Ȃ݂ɁuPhotons to Photos�v�̃f�[�^�ɂ��A��L�@��Ȃǂ̃_�C�i�~�b�N�����W�̍ő�l�͉��L�̒l�ł��B
��7C�iRAW 14�r�b�g�j�@11.59EV
��6400�iRAW 14�r�b�g�j 10.51EV
EOS RP�iRAW 14�r�b�g�j 9.11EV
E-M1 Mk2�iRAW 12�r�b�g�j 9.84EV
E-M1 Mk3�iRAW 12�r�b�g�j 9.74EV
OM-1�iRAW 12�r�b�g�j 9.54EV
�_�C�i�~�b�N�����W�̐��l�͑�����@�ő傫���ς��悤�ł��B
����ƁA�uPhotons to Photos�v�ł� OM-1�̃_�C�i�~�b�N�����W��E-M1 Mk2/Mk3�ɔ�ׂė��悤�ȃf�[�^�ɂȂ��Ă��܂��i����덷�����H�j���A���@�̉摜�Ŕ�ׂĂ݂�ƁAOM-1�̕����A�Õ��������グ�����̑ϐ����𑜂��F�Č����m�C�Y�������Ɨǂ��Ȃ��Ă��܂��B
����� OM-1�̕����_�C�i�~�b�N�����W���L���Ƃ������ƂŁA���[�J�[�̐����u�Â�����1/2�i�A���邢����1/2�i�A���킹��1�i���_�C�i�~�b�N�����W�����サ���v�Ƃ��������ɖ����͂���܂���B
�����ԍ��F25229077
![]() 11�_
11�_
����o������
EOS R6 Mk2�̓d�q�V���b�^�[�ŁA�ኴ�x���̃_�C�i�~�b�N�����W���ቺ����͕̂s�v�c�Ȋ��������܂��ˁB
�d�q�V���b�^�[�̉e�������łȂ��A�ǂݏo�����x�Ȃlj�H���ɂ��W�����肻���ł��B���[�U�[�����R��m�����Ƃ���ňӖ��Ȃ����Ƃ�������܂��A�m��悤���Ȃ������ł����B
�d�q�V���b�^�[��12bit�ɂ��Ă���̂́A�掿�����łȂ��J�����̃p�t�H�[�}���X���܂߂Ă��ꂪ�œK�Ƃ̃��[�J�[�̍l���Ȃ̂ł��傤�B
>�M�����ߕs���Ȃ��œK��AD�ϊ�����v���ł����Ƃ���Ƃ��̃r�b�g����DR��"��v���܂�"
Tech One���� �R�����g�́u�K�i�v��u�s�U�v�̗Ⴆ�͕�����₷���ėǂ��Ǝv���܂����A���́w�ߕs���Ȃ��œK��AD�ϊ��x���u�K�i��1�i�̒��悢�����v�u�s�U�̈��ɂ��傤�Ǘǂ��傫���v���Ƃ��āA������J�����E�Z���T�[�ɂ�炸���Ƃ���Ƃ����������ƂɂȂ�܂��ˁB
�������A����͌ォ��C�ӂɎ��R�Ɍ��߂邱�Ƃ��ł����Ⴄ�킯�ł��B
�����ԍ��F25229085
![]() 9�_
9�_
��Tranquility����
���_�C�i�~�b�N�����W�̉����̓m�C�Y
���ꂪ��������ꍇ�͂���܂����A�����łȂ��ꍇ������܂��B
�_�C�i�~�b�N�����W��
Kazkun33���A�����ԍ��F25227100�ň��p�����A�L���m���̃J�����p��W�̎��̐����ł��B
�u�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A�f�W�^���J�������Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���A���邢��������Â������ւ̍Č��\�ȕ��̂��Ƃ������܂��B�v
�����炭�ATranquility����̍l���������Ă���̂́A�m�C�Y�������ŁARAW�f�[�^�ɂ���ƃm�C�Y��0�i�[���j�ɂȂ鎞�ł��B
���̃m�C�Y��0�̎��̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��āA���l���ɂȂ�܂�����A
���̓��e������������������A�̂�������܂���B
�����ԍ��F25229295
![]() 2�_
2�_
��pmp2008����
>���̃m�C�Y��0�̎��̃_�C�i�~�b�N�����W�ɂ���
�m�C�Y���u0�v�Ƃ����̂͂��肦�Ȃ��Ǝv���܂����A���ɂ������Ƃ�����_�C�i�~�b�N�����W�͖�����ɂȂ����Ⴂ�܂��B
�C���[�W�Z���T�̃_�C�i�~�b�N�����W�́E�E�E
�u�O�a���M���ƈÎ��G���M���̔�v
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/60/3/60_3_299/_pdf
�u�����\�ȐM���̍ő�l�ƍŏ��l�̔䗦��\�������l�v
https://www.klv.co.jp/corner/what-is-dynamic-range.html
�u�M���O�a����ʁi��f�̖O�a�j�ƃm�C�Y�̗ʁi�ÈŎB�e���j�̔䗦�v
https://imagesensor-info.com/83/
�܂�A�_�C�i�~�b�N�����W�̉����́u�V�O�i�����m�C�Y�ɖ�����Ĕ��ʂł��Ȃ��Ȃ郌�x���v�A����́u�Z���T�[���O�a���ăV�O�i�������ʂł��Ȃ��Ȃ郌�x���v�Ƃ������ƁB
�����ԍ��F25229338
![]() 11�_
11�_
��Tranquility����
���m�C�Y���u0�v�Ƃ����̂͂��肦�Ȃ��Ǝv���܂����A���ɂ������Ƃ�����_�C�i�~�b�N�����W�͖�����ɂȂ����Ⴂ�܂��B
���̒ʂ�ł��B�ł��A����̓A�i���O�Ɍ��������Ƃł��B
���܂�A�_�C�i�~�b�N�����W�̉����́u�V�O�i�����m�C�Y�ɖ�����Ĕ��ʂł��Ȃ��Ȃ郌�x���v
�m�C�Y������A���̒ʂ�ł��B
�A�i���O�f�[�^���f�W�^���f�[�^�ɕϊ����鎞�A�����Ȓl��0�i�[���j�ɂȂ�܂��B�����āA�ǂ��܂ł̒l��0�ɂȂ邩�́AAD�ϊ��̕���\�i�r�b�g�j�Ō��܂�܂��B
����ŁA�������肢�������܂��ł��傤���H
�����ԍ��F25229371
![]() 3�_
3�_
��pmp2008����
>�ǂ��܂ł̒l��0�ɂȂ邩�́AAD�ϊ��̕���\�i�r�b�g�j�Ō��܂�܂��B
����͈Ⴄ���ƁB
�V�O�i�����m�C�Y�ɖ�����鉺�����u0�v�ɐݒ肷�邾���ŁA�O�a�������Ƃ̊Ԃ��ǂꂾ���ׂ����������邩�i��bit��AD�ϊ����邩�j�Ƃ͊W�Ȃ��̂ł́B
�����ԍ��F25229380
![]() 12�_
12�_
���m�C�Y�������ŁARAW�f�[�^�ɂ���ƃm�C�Y��0�i�[���j�ɂȂ鎞�ł��B
pmp2008����A�uRAW�f�[�^�ɂ���Ɓv�Ƃ����d�v�������X�b�����(�N���ꂪ)�ȉ����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�⑫���Ă����ẮH
�����ԍ��F25229449�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
��pmp2008����
DR��������̃A�i���O�M����15stop�̃A�i���O�M����
12bit��AD�ϊ���ʂ���12stop�̃f�W�^���f�[�^�ɂ����Ȃ�Ȃ�
�Ƃ������Ƃł���� ����͐������Ǝv���܂�
���̂Ƃ��̃m�C�Y���āAAD�ϊ��ɂ���Đ�����ʎq���m�C�Y���A�i���O�M���̃m�C�Y����������ԂŁA���̃m�C�Y�ɖ�����Ȃ��ŏ��̒l�͍ʼn��ʃr�b�g��1 �Ƃ������Ƃł���
�����ԍ��F25229463�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
��Tranquility����
���V�O�i�����m�C�Y�ɖ�����鉺�����u0�v�ɐݒ肷�邾���ŁA
����͈Ⴂ�܂��B
�����Ȃ�܂��ƁA��������̂���ςȂ̂ŁA���₢�����܂��B
�E�A�i���O�f�[�^��12�r�b�g��AD�ϊ��������́A�f�W�^��0�ƃf�W�^��1�̋��ڂ̃A�i���O�f�[�^�̒l��A�Ƃ��܂�
�E���l��14�r�b�g��AD�ϊ��������́A�f�W�^��0�ƃf�W�^��1�̋��ڂ̃A�i���O�f�[�^�̒l��B�Ƃ��܂�
A �� B �̊W�͂ǂ��Ȃ�܂��ł��傤���H
��������l���ɂȂ�Ɨ������i�ށA�̂�������܂���B
�����ԍ��F25229486
![]() 5�_
5�_
����o������
���̒ʂ�ł��B
�����ԍ��F25229530
![]() 2�_
2�_
�����肪�Ƃ��A���E����
�����A�Ȃ�قǁB�������Ȃ��ƁA�������Ȃ��ƂɂȂ�܂��ˁB
�����ԍ��F25229537
![]() 3�_
3�_
����o������
�m���ɁA�uAD�ϊ��ɂ���Đ�����ʎq���m�C�Y�v���m�C�Y�ł��ˁB�Ȃ̂ŁA���́u�m�C�Y0�i�[���j�v�̘b�͕���킵�������ł��ˁB
�����ԍ��F25229548
![]() 3�_
3�_
��Tranquility����
����YouTube�����ĉ������B
https://m.youtube.com/watch?v=ckHaCYf3lZE&pp=ygUb44OA44Kk44OK44Of44OD44Kv44Os44Oz44K4
https://m.youtube.com/watch?v=-Apht3BXugQ
�����ԍ��F25229552
![]() 1�_
1�_
��Kazkun33����
������YouTube�����ĉ������B
�ӂ��̓��e�ł����B
�����ԍ��F25229581
![]() 2�_
2�_
���Ɖt���e���r�Ō��Ă��̂ŁA�V���{���O���f�[�V�����Ⴕ���Ȃ��Ėʔ����Ȃ������ł��B
�����ԍ��F25229599
![]() 2�_
2�_
�����������ł��Ȃ��l�͑��肵�Ȃ���B
�����ԍ��F25229616
![]() 6�_
6�_
��Kazkun33����
�@�ނ��茩�āA����̎ʐ^������Ȃ����[�U�[�������ėv������������ł́H
�܂��A�ǂ�ȂɌ������ׂ悤���A�����\���낤���A�B�e���ʂɔ��f�������Ȃ���ΑS���Ӗ�����܂����ˁH
���A���������A����̎ʐ^�����Ă�����������Ȃ��ƃh�����Ă��̂����܂����ˁB
���������l���āA�������g�ŎB�����ʐ^�ʼn��̎��т������낤�Ȃ��B
�����ԍ��F25229780�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
������f���ň��k����RAW�ł�����A
���P���v�Z�Ȃ�t�@�C���T�C�Y�S�{�ł�����
�����ƁA�A�A�݂Ȃ���A���Ⴂ����Ă��܂���B
���ʁi����\/�\���̕��@�ƌ����������������j��4�{�ł����A�f�[�^�e�ʁi�t�@�C���T�C�Y�j��14/12�{�ł���B
���肪�Ƃ��A���E����@�Ƃ����낤�����B�B�B
���f�[�^�ʂɊւ��ẮA12bit��14bit�͂ǂ����16bit�f�[�^�ȉ��Ȃ̂ŁA���̐����͈̔͂��قȂ邾���ŃJ�����̃������[����ʂ͕ς��Ȃ��͂��ł��B
�ς��܂���BCPU���Z��DSP���Z��16bit�A���C���̏ꍇ�������̂�12/14bit�ŕς��Ȃ��ꍇ�������ł����A����������ʂ͂��̂܂܌����Ă��܂��B���ʂ̓������i�[����16bit����l�߂≺�l�߂Œu�����肵�܂���i�uun-pack�v�Ƃ����j�B�upack�v�ƌ����āA�l�߂Ċi�[���܂��B
�Ƃ������A�������o�X�ш�̐��������邽�߁A�������A�N�Z�X���͈��k�E�𓀂���̂����ʂł��B
���k�i0.5�`0.6�{���炢�j���ă�������write���A���Z���Ƀ���������read�����摜�f�[�^���𓀂��ď������Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA���摜�f�[�^��bit���͂���Ƀ���������ʂɉe�����܂��B
��12bit��14bit�ɂ���ƊK����4�{���炩�ɂȂ��ł����AJPG�ɗ��Ƃ��ۂ�8bit�Ɉ��k�����̂ŁA�ŏI�I�ɍ����o��̂��ǂ����͂킩��܂���B
�掿�ɑ���e���Ƃ����_�ł́A�݂Ȃ��������悤�ɁA�ʏ��RAW�����ł͍ŏIJPEG�̍��͕�����Ȃ��ł��B���X�����グ�Ă��B
�ł����A�V�̎B�e���������́A60���Ƃ��d�˂ď�������̂ŁA12bit���Ƒ���Ȃ��ƌ����܂��ˁB�m���ɍŏI8bitJPEG�ɔ[�߂�Ƃ��Ă��A60���i��6bit�j���Z����̂Ȃ�14bit�ł���ƍŏI�o�͂�1bit�̍������o��i���Ƃ��ĕ\���ł���j���ƂɂȂ�܂��B���͂�������ƂȂ��̂Ŏ����͖����ł����B
�ŁA�X����́A
��APS-C��RAW�T�C�Y��14bit�Ȃ̂ɁAOM-1��12bit�Ȃ̂ł����H
�ɂ��ẮA
�EOM�̓\�j�[�Z���T�[�K�{
�E�����i�����H�j�̃\�j�[��m4/3�Z���T�[��12bit�̂��̂�����������
�����ł��傤�B
�����ԍ��F25229871
![]() 5�_
5�_
�����[���낤�S����
�������A�u�C���[�W�v�ł���(^^;
�{���́u�P���v�l�v�Ə����Ă����̂ł����A������ƃL�c�C�Ǝv���āu�P���v�Z�v�ɏ��������܂���(^^;
��̗�� ���[���낤�S��������Ă��܂����A
�����܂ŏ����K�R�������������Ƃ����������Ă����ʂ��ۂ��Ǝv���܂����̂ŁA�蔲�����܂������A
����� ���܂�ׂ����Ꭶ��������������܂���(^^;
����́A���̃X���̍����ڂ̓�����ɂ���ƁA���[���낤�S��������Ă��邱�Ƃ��ȉ�����q�g���o��ł��傤���A
RAW�ȑO�̗ʎq���̒i�K�ł��g���f�����X�ŒE�͊������ς��ł��̂�(^^;
�����ԍ��F25229892�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��pmp2008����
�����肪�Ƃ��A���E����
>�m�C�Y�������ŁARAW�f�[�^�ɂ���ƃm�C�Y��0�i�[���j�ɂȂ鎞
>���̃m�C�Y��0�̎��̃_�C�i�~�b�N�����W
>�A�i���O�f�[�^���f�W�^���f�[�^�ɕϊ����鎞�A�����Ȓl��0�i�[���j�ɂȂ�܂�
>�ǂ��܂ł̒l��0�ɂȂ邩�́AAD�ϊ��̕���\�i�r�b�g�j�Ō��܂�܂��B
>�uRAW�f�[�^�ɂ���Ɓv�Ƃ����d�v�������X�b�����(�N���ꂪ)�ȉ����Ă���
�u�m�C�Y��0�̎��̃_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ͉��H
�u�ǂ��܂ł̒l��0�ɂȂ邩�v�Ƃ́H
�Ӗ����킩��܂���B
�����Ō����u�_�C�i�~�b�N�����W�v�̉����Ə���͉��ł����H
�uRAW�f�[�^�ɂ���Ɓv�����ǂ��ς��̂ł����H
�@
>�E�A�i���O�f�[�^��12�r�b�g��AD�ϊ��������́A�f�W�^��0�ƃf�W�^��1�̋��ڂ̃A�i���O�f�[�^�̒l��A�Ƃ��܂�
>�E���l��14�r�b�g��AD�ϊ��������́A�f�W�^��0�ƃf�W�^��1�̋��ڂ̃A�i���O�f�[�^�̒l��B�Ƃ��܂�
>A �� B �̊W�͂ǂ��Ȃ�܂��ł��傤���H
�u�f�W�^��0�ƃf�W�^��1�̋��ځv�Ƃ͉��ł����H
�_�C�i�~�b�N�������W�̈Õ��̉����ƌ����Ӗ��ł��傤���H
����ʼn������������̂��킩��܂���B���������������܂��B
�����ԍ��F25229932
![]() 12�_
12�_
��Kazkun33����
>����YouTube�����ĉ������B
�͂��A���܂�����B
�ӂ��̓��e�ł����B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�r�b�g���ƃ_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ͉��̊W������܂���B
�r�b�g�͂ł��ˁA�ǂꂾ���̕���\�Ńf�[�^���������邩�����̘b�Ȃ̂ŁA�Ⴆ�ł��ˁA�_�C�i�~�b�N�����W��10EV�ł��낤��12EV�ł��낤���A���̃f�[�^�S���8bit�Ȃ�256��������A12bit�Ȃ�4096��������Ƃ��������Ȃ�ł��ˁB
�ł�����A�r�b�g���������ƃ_�C�i�~�b�N�����W���L���Ƃ��������Ɋ��Ⴂ����Ă���������܂����ǂ��A����͑S������܂���B
�P�Ƀf�[�^�����f�[�^���������Ńf�[�^���������邩�ƌ��������̘b�ł��̂ŁA�����͊ԈႢ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
����ŁH
�����ԍ��F25229934
![]() 12�_
12�_
�����肪�Ƃ��A���E����
��pmp2008����
�����g�̂����̐������ł��Ȃ��̂ł��傤���H
���̏��������Ƃ͂ǂ����Ԉ���Ă��܂����H
���O�͊Ԉ���Ă���A�������Ă��Ȃ��A�����ł́A���_�ɂȂ�܂���B
�I�����������A���O�������ł��Ȃ��������A�ł́A���ɂȂ�܂���B
���̂Ƃ��뉽�������Ȃ����Ă��܂���̂ŁA��������낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F25229955
![]() 14�_
14�_
��Tranquility����
�����₢�������܂������ATranquility����ɂ��������������ɂ́A�����炭�A�F�X�Ɛ������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�A����͑�ςȍ�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�����������ł��B
�\����܂���A���̏����ԍ��F25229486 �̎��₩��n�܂������Ƃ�́A�ł���Ƃ����Ă��������B
�����ԍ��F25229960
![]() 6�_
6�_
��pmp2008����
�����肪�Ƃ��A���E����
>�E�A�i���O�f�[�^��12�r�b�g��AD�ϊ��������́A�f�W�^��0�ƃf�W�^��1�̋��ڂ̃A�i���O�f�[�^�̒l��A�Ƃ��܂�
>�E���l��14�r�b�g��AD�ϊ��������́A�f�W�^��0�ƃf�W�^��1�̋��ڂ̃A�i���O�f�[�^�̒l��B�Ƃ��܂�
>A �� B �̊W�͂ǂ��Ȃ�܂��ł��傤���H
�₢�̈Ӗ��𗝉����ɂ������͂ł����A���炩�ɘA������A�i���O�f�[�^���f�W�^���������Ƃ��ɁAAD�ϊ��̃r�b�g���̑傫������0��1�̕��͏������A�Ƃ����Ӗ��ł����ˁBbit���̑傫�ȕ����u�K�i�v�̈�i�̍����͒Ⴂ�ł�����ˁB
���Ƃ��āA���ꂪ�ǂ����āE�E�E
�w�m�C�Y�̉e����������ARAW��2�r�b�g�̈Ⴂ�́A���̂܂܃_�C�i�~�b�N�����W�� 2EV �Ƃ��Č����x
�w�ő�l��RAW�̃r�b�g���Ō��܂�܂��B2�r�b�g�������4�{�A���Ȃ킿�_�C�i�~�b�N�����W�� 2EV �����܂��x
�E�E�E�ƂȂ�܂����H
�����ԍ��F25229963
![]() 15�_
15�_
(�J������TV�����YouTube���悩��)
�� ���̃f�[�^�S���8bit�Ȃ�256��������12bit�Ȃ�4096��������Ƃ��������Ȃ�ł���
�Ԉ���Ă܂��˂��� ��
�r�b�g���͊K����\�����̂�DR�Ƃ͊W�Ȃ��A�Ƃ����̂͂�������"���ʂ�"�����Ă܂�
�Ȃ����ƌ����� �A�i���O�M����DR�ɑ��� ����S�Ă��܂ޏ[���ȃr�b�g���� AD�ϊ�����ǂݏo���� ������RAW�t�@�C���Ƃ��ď����o�����Ƃ����v��"���ʂ�"����邩��ł���
10EV��12EV�ɑ肵��8bit�̗���o������(�킩��₷������݂̂��鐔�����������̂ł��傤����)�A����ĂȂ��r�b�g���ł�DR�ɉe���^�����Ⴂ�܂�
����̋c�_(�̂Ȃ��̈�̃g�s�b�N)�̂悤�� ���ʂ���Ȃ��P�[�X�̘b �Z���T�[�̃A�i���O���\�ɑ��ăr�b�g��������Ă��邩�ǂ����l����ꍇ�� �������f�W�^���ŕ\����DR���l����K�v������܂�
�����ԍ��F25230025�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�A�i���O���f�W�^���ɕϊ�����ƁA�_�i������s�v�c�ȃX���B
�����ԍ��F25230107
![]() 3�_
3�_
���f�[�^�ʂɊւ��ẮA12bit��14bit�͂ǂ����16bit�f�[�^�ȉ��Ȃ̂ŁA���̐����͈̔͂��قȂ邾���ŃJ�����̃������[����ʂ͕ς��Ȃ��͂��ł��B
���ς��܂���BCPU���Z��DSP���Z��16bit�A���C���̏ꍇ�������̂�12/14bit�ŕς��Ȃ��ꍇ�������ł����A����������ʂ͂��̂܂܌����Ă��܂��B���ʂ̓������i�[����16bit����l�߂≺�l�߂Œu�����肵�܂���i�uun-pack�v�Ƃ����j�B�upack�v�ƌ����āA�l�߂Ċi�[���܂��B
���̃f�[�^���V���A���^�p�������]������̂��A�ۑ������^�ҏW���H�����A�o�b�n�V�X�e�����r�b�g�v���Z�X�V�X�e��(����Ȃ̂��������邩�͂��Ă����j�Ȃ̂��A�ŏ��X�ς���Ă���̂ł͂Ȃ��ł����H
�r�b�g�x�^�l�f�[�^�͊m���ɍō����ŕۊǂł��܂��B���k�v���Z�X�����܂������Ƃ���ł����c���������̂܂�܂ł͂o�b�n�V�X�e���ł̕ҏW���H�͂Ԃ���Ԕ��ł��B
�t�Ƀr�b�g�X�J�X�J��Ԃŕۑ����ꂽ�łɂ�A��������������炠����������Ȃ��B
���߂ĂP�������k�ʊ|���Ƃ���A�݂����ȁB
�o�b�n�摜�ҏW�ł͊�킭�o�C�g�P�ʂɑf���ɕ��ׂĒu�����������X�̉��Z�͂��Ղ����B
���ꂪ14�r�b�g�Â���ď�������A�Ȃ�ĉ��������̈�����k���ƁB
�c40�N�߂��O�ɁA�W�O�W�U��Ńr�b�g�ϒ��e�`�w�f�[�^�̈��k�L��������������ۂɂ͂Ԃ���т܂������B
�����A�f�[�^���X�g���[�W�ɕۑ�����ۂɂ͈��k�O��Ńr�b�g�x�^�l�ۑ��A�o�b�n�V�X�e���ʼn��Z�����O��̏ꍇ�͈�U�x�^�r�b�g�p�^�[���ɓW�J���āA���X�̍�Ƃ��I���ēx���k�O��Ńr�b�g�x�^�l���A�܂����ʂȏ��ł��傤���B
�c�Ə��X�X���{���痣�ꂽ��b�ɂȂ��Ă܂����A��Ԃ̖��̓X���傳����������b��S�ė����ł��Ă邩�A�ł��傤���B
�����ԍ��F25230150
![]() 3�_
3�_
�����ł��ˁA�X���傳��̎���X���ł�����A
�X���傳�����������Ă���N����̉����͖������āA
�X���傳��Ή��ɐ��퉻���܂��傤(^^;
�����ԍ��F25230165�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����肪�Ƃ��A���E����
������͂�����
���Ă����Ȃ��Ȃ��Ă܂��B
�����ԍ��F25230215
![]() 2�_
2�_
��Tranquility����
���Ӗ����킩��܂���B
�����Ō����u�_�C�i�~�b�N�����W�v�̉����Ə���͉��ł����H
�uRAW�f�[�^�ɂ���Ɓv�����ǂ��ς��̂ł����H
�u�f�W�^��0�ƃf�W�^��1�̋��ځv�Ƃ͉��ł����H
�_�C�i�~�b�N�������W�̈Õ��̉����ƌ����Ӗ��ł��傤���H
�����̋^��͉����܂������H
�����̓�����YouTube���̒��ɂ������Ǝv���܂����I
�����ԍ��F25230220
![]() 0�_
0�_
��Tranquility����
���X���b�h���r���̂́A�����̏ꍇ�A�����^��ɂ܂������������A���₷��҂̐l�i�ے�ɑ��邱�Ƃ������Ƃ��đ����ł��B
���܂��A�����̘_���������ƍl����Ȃ�A���_�ɍĔ��_������������Ȃ�ł����A����������ɑ���̐l�i�ے������Ƃ������Ƃ�����܂��B
�����������̓W�J�ł��ˁB
�܂������������Ȃ��̂́A�咣������ӂ₾����ł��傤�B
�����ԍ��F25230365
![]() 10�_
10�_
����x�������߂Ŏ��̍l�����܂Ƃ߂܂���
�m�C�Y���܂ރA�i���O�M����AD�ϊ��������Ƃ�DR�ɂ���
������
�A�i���O�̃m�C�Y�ɖ�����Ȃ��ŏ��̐M���ƁA�ʼn��ʃr�b�g1�ɑΉ�����l�̂����傫�ȕ�
�����
�A�i���O�M���̖O�a�l�ƁA�f�W�^���l�̍ő�l�ŕ\�����l�̂��������ȕ�
�ƂȂ�܂�
���� ����̂��ꂼ��̑召�W��AD�ϊ��ɂ����DR���ێ�����邩�ቺ���Ă��܂��������܂�Ƃ����̂��킩��Ǝv���܂�
����𑵂���12bit��AD�ϊ�������ƁA���̐M����15stop�ł�14stop�ł��f�W�^���f�[�^��DR��12stop�ƂȂ�܂��A11stop�̐M����11stop�̂܂܂ł���
����
����14stop���������f�q���������Ƃ���14bit�ŕϊ������ꍇ�A iso���x���Ƃ�DR�͗��z�I�ɂ͎��̂悤�ɂȂ�܂����
iso, DR
100, 14
200, 13
400, 12
800, 11
�F
�����Ⴆ�Α��x�⏈���ʂ��ӂ݂�12bit�ŗ��p���悤�ƍl�����
iso, DR
100, 12
200, 12
400, 12
800, 11
�F
�ƂȂ�܂�
12bit�Ɏ��܂�Ȃ�����12stop�ɐ�������āA�����������܂鍂iso��DR�͈ێ�����܂�
�Ƃ������Ƃ�
�r�b�g��������Ă��Ȃ��ꍇ�͏�̃����N�Ŏ�����R6mk2��12bit�̂悤�Ȓ�iso���}����ꂽ����������
����Ă���ꍇ�͓����������N�Ŏ�����GFX�̂悤�Ƀ��j�A�ł���
�܂� om-1�̃O���t�̂悤�ɑf���Ƀ��j�A�ȓ�����`���Ă���̂� �r�b�g��������Ă��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ�����
�����ԍ��F25230377�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�Ƃ������A�Z���T�[�̎d�l���OM-1��14bit���I���o����A�̂��Ǝv���܂���B
E-M1mk2�Ɠ����Z���T�[��GH5��14bit�ł����A12bit���I���o���܂�����B
14bit�L�^�́A���_�I��12bit���4�{�̏��ʂ������Ă���̂ŁA�L�x�ȊK����F�ʂ��L�^�������B�e�ɓK���Ă���A12bit�͘A�ʑ��x��D�悵�����ꍇ�ȂǂɗL���ł��B
�����ԍ��F25230383�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���ʂɃf�B�X�v���C���g���Ăĕ\���ł���̂͂�������10bit�A12bit�f�[�^�̐F�����n�߂�̂̓R���g���X�g��4 �{�ɂ��鎞�H
8bit��jpeg�ʼn��ARAW�ʼn��Ȃ������o�����瑽����Α����ق����ǂ��Ǝ����ӐM���Ă��邯�ǁA���ۂɂ�12bit�ł��[���Ȃ̂����B���Õ��̔j�]��DR���E���낤����A12bit������Ώ����ȐF�[�x�̐N���̉摜�j�]�ɂ͂Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ��C�����܂��B
�t��Kazkun33����12�r�b�g��RAW�����������炱��Ȃӂ��ɔj�]�����Ƃ����G���o���Ă݂Ă͂������ł��傤���B
�����ԍ��F25230432�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
���ʂ��Ⴓ��
���̓f�B�X�v���C��z�肵�Ă܂����B
�����ԍ��F25230504
![]() 0�_
0�_
�����ł������B�ł͈���ł����ˁB
�͂��܂��S�̖ڂ�
�����ԍ��F25230540�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
��hunayan����
M4/3��14bit��GH5s�����ł���BGH6��14bit�����A���̑���12bit�܂łł��B
�����ԍ��F25230622
![]() 2�_
2�_
�u�ʏ�̈���v���̂̃_�C�i�~�b�N�����W�u�����v�́A���Ȃ苷���ł�(^^;
�����ԍ��F25230630�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�����܂ł��܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B
�E�r�b�g���͊K����\�����̂ł���B
�E�r�b�g����傫�����Ă��_�C�i�~�b�N�����W�͍L���Ȃ�Ȃ��B
�E�_�C�i�~�b�N�����W�̍L���ɍ��킹�����炩�ȊK����ׂɃr�b�g����傫������B
��APS-C��RAW�T�C�Y��14bit�Ȃ̂ɁAOM-1��12bit�Ȃ̂ł����H
���Z���T�[���\���オ���Ă��Ă���Ȃ�14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B
�v�҂́A12bit�d�l�Ƃ����B���̗��R�́A�v�҂��m���Ă��܂��B
�����ԍ��F25230704
![]() 2�_
2�_
(�X���́u�N�v�E�u���v?)
�X����Kazkun33���e:403��
2023�N4��16�� 12:43 �ŏ��̓��e
��APS-C��RAW�T�C�Y��14bit�Ȃ̂ɁAOM-1��12bit�Ȃ̂ł����H
���Z���T�[���\���オ���Ă��Ă���Ȃ�14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B
�y�ȗ��z
hirappa���e:5708��Good�l��196��
2023�N4��21�� 18:48 �ԐM98����
(��)
���v�҂́A12bit�d�l�Ƃ����B���̗��R�́A�v�҂��m���Ă��܂��B
�E�E�E�����ƌ����Ύ����Ȃ���E�E�E(^^;
�����ԍ��F25230729�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����o������
���Ԉ���Ă܂��˂��� ��
�����ł��ˁB�����A��ʂ̎����Ҍ������ƁA���̂悤�ɕ�����₷������̂��A����Ȃ̂ł��傤�B
�����łȂ��ꍇ������A�Ȃǂƌ����o������A�F���f���� youtube �̃`�����l���o�^�Ȃǂ��Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F25230755
![]() 3�_
3�_
����o������
������x�������߂Ŏ��̍l�����܂Ƃ߂܂���
����͕�����₷���ł��B
�Ƃ���ŁA�C�ɂȂ�̂́ADXOMARK�̃Z���T�[�X�R�A��Landscape(�_�C�i�~�b�N�����W)�́A���̂悤�ɁA���_�l���Ă�����̂����邱�Ƃł��B
��7C�iRAW 14�r�b�g�j�@14.7EV
E-M1 Mark�U�iRAW 12�r�b�g�j 12.8EV
����ɁATranquility���w�E�̂悤�ɁA�uPhotons to Photos�v�ł̃_�C�i�~�b�N�����W�͎��̂悤�ŁADXOMARK���A���Ȃ苷���̂�
����7C�iRAW 14�r�b�g�j�@11.59EV
��E-M1 Mk2�iRAW 12�r�b�g�j 9.84EV
���ǂ̂Ƃ���A�e�탌�r���[�ł̑���l�͂悭������Ȃ��āA�@��Ԃ̔�r�ɂ����g���Ȃ��A�̂�������܂���B
�����ԍ��F25230773
![]() 2�_
2�_
��Tranquility����
�����炩�ɘA������A�i���O�f�[�^���f�W�^���������Ƃ��ɁAAD�ϊ��̃r�b�g���̑傫������0��1�̕��͏������A�Ƃ����Ӗ��ł����ˁB
�����ł��B
�����Ƃ��āA���ꂪ�ǂ����āE�E�E
�����܂ŗ���A���Ƃ��������ł��B
����������������悤�ɐ����ł��Ȃ��āA�\����Ȃ��ł��B
�����ԍ��F25230792
![]() 2�_
2�_
����o������
>10EV��12EV�ɑ肵��8bit�̗���o������(��)�A����ĂȂ��r�b�g���ł�DR�ɉe���^�����Ⴂ�܂�
>�Z���T�[�̃A�i���O���\�ɑ��ăr�b�g��������Ă��邩�ǂ����l����ꍇ�� �������f�W�^���ŕ\����DR���l����K�v������܂�
>�A�i���O�M����AD�ϊ��������Ƃ�DR�ɂ��āE�E�E
>���� ����̂��ꂼ��̑召�W��AD�ϊ��ɂ����DR���ێ�����邩�ቺ���Ă��܂��������܂�
>����𑵂���12bit��AD�ϊ�������ƁA���̐M����15stop�ł�14stop�ł��f�W�^���f�[�^��DR��12stop�ƂȂ�܂��A11stop�̐M����11stop�̂܂܂ł���
���낢��Ɗ�{�I�ȗ������Ԉ���Ă���悤�ł��B
�Ⴆ�A�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W��15stop(15EV�E15�i)�ł�14stop(14EV�E14�i)�ł�11stop(11EV�E11�i)�ł��A���ꂼ��̃A�i���O�f�[�^��12bit��AD�ϊ�����̂́A���ꂼ��̃_�C�i�~�b�N�����W�S�̂�12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɂ���Ƃ������Ƃł��B
AD�ϊ���bit����EV�͖��W�ł��B
�u��������낦��v�Ƃ��u�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ��A�Ӗ��s���ł��B
���������_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̓A�i���O���ʂ̎w�W�ł�����B
��pmp2008����
>����������������悤�ɐ����ł��Ȃ��āA�\����Ȃ��ł��B
�Ԉ�����������Ă��d������܂���̂ŁA�����ł���B
�����ԍ��F25230812
![]() 11�_
11�_
��Kazkun33����
>�����̋^��͉����܂������H
�����Ȃ���Ȃ��̂ŁA�����ǂ��l���Ă���̂��킩��܂���B
�����ł��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
>�����̓�����YouTube���̒��ɂ������Ǝv���܂����I
�������A����܂���ł����B
�ŁAKazkun33���� �̌��ł����E�E�E
RAW��12bit�ʼn����x�Ⴊ�������̂ł����H�@����͂ǂ̂悤�ȏꍇ�ł����H
14bit��RAW�ɉ������҂���̂ł����H�@�ǂ̂悤�ɕς��̂ł����H
�����ԍ��F25230817
![]() 10�_
10�_
��pmp2008����
����o������
�����Ԉ���Ă���̂ł����H��ʂ̎����҂ɂ킩��l�ɋ����Ē����܂��H
�����ԍ��F25230828
![]() 1�_
1�_
��Tranquility����
���Ⴆ�A�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W��15stop(15EV�E15�i)�ł�14stop(14EV�E14�i)�ł�11stop(11EV�E11�i)�ł��A
�����ꂼ��̃A�i���O�f�[�^��12bit��AD�ϊ�����̂́A���ꂼ��̃_�C�i�~�b�N�����W�S�̂�12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɂ���Ƃ������Ƃł��B
12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɁA15EV�͓���Ȃ��ł��B
Tranquility����́A�����Ƃ�����T���Ă��܂��B�t�ɁA������������A�ڂ�������̓��e�Ǝ��̓��e�A�S�ė����ł��܂��B
�����ԍ��F25230904
![]() 3�_
3�_
������89����
��{�I��MFT�� 12bit�ł��� �B��Ȃ���ł��ˁB
����ł�14bit�Ɣ�r���ĘR��Ȃ��g�[���W�����v����̂ŁA
��������ȑO�̖�肪�o�Ă��܂��ˁB
����͎x�Ⴊ����܂��ˁB
�����ԍ��F25230922�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��Kazkun33����
��ʓI�ȋ�̗�̂ق����ǂ��ł��傤�� �����ł������e�͂�
0.5V(�{���g)�̃m�C�Y���܂�4V�ŖO�a����A�i���O�M����DR�͂킩��܂����H
���8�� �i��(2���Ƃ���log)�ŕ\����3stop�ł�
�����2bit��AD�ϊ��� ����𑵂���(�܂�ő�l��4V�Ƃ���)�f�W�^���M���ɕϊ����܂������
3����4V ---> 3
2����3V ---> 2
1����2V ---> 1
0����1V ---> 0
�ƂȂ�܂� 0����3�܂ł̒l������f�W�^���M���ɂȂ�܂�
���̃f�W�^���M���ŕ\�����Ƃ̂ł���ŏ��l�̓f�W�^���l1�̎���1V�ł��ˍő�l�̓f�W�^���l3�̎���4V�ł�
���4�� �i��(2���Ƃ���log)�ŕ\����2stop�ł�
DR��1stop�ቺ���Ă��܂��܂��� �����͖��炩�ł��� AD�ϊ��̃r�b�g��������Ă��Ȃ�1V�����́A�M�����̂ĂĂ��܂�������ł�
����3bit�ɂ��܂�
3.5����4.0V ---> 7
3.0����3.5V ---> 6
2.5����3.0V ---> 5
2.0����2.5V ---> 4
1.5����2.0V ---> 3
1.0����1.5V ---> 2
0.5����1.0V ---> 1
0.0����0.5V ---> 0
�ŏ��l�̓f�W�^���l1�̎���0.5V�ł��ˍő�l�̓f�W�^���l7�̎���4V�ł�
���8�� �i��(2���Ƃ���log)�ŕ\����3stop�ł�
�҂����葫��Ă��܂�
�Ō��4bit�ɂ��܂�
3.75����4.00V ---> 15
3.50����3.75V ---> 14
�F
0.75����1.00V ---> 3
0.50����0.75V ---> 2
0.25����0.50V ---> 1
0.00����0.25V ---> 0
�f�W�^���l1�̎�0.25V�ł����ǂ���̓m�C�Y�ɖ�����Ă܂��A�m�C�Y�ɖ�����Ȃ��ŏ��l�͌��̃A�i���O����0.5V�ł��ˍő�l�̓f�W�^���l15�̎���4V�ł�
���8�� �i��(2���Ƃ���log)�ŕ\����3stop�ł�
�r�b�g��������Ă���̂Ȃ炻��ȏ㑝�₵�Ă�DR�͏オ��܂���
�������Ԉ���Ă���̂ł����H��ʂ̎����҂ɂ킩��l�ɋ����Ē����܂��H
�r�b�g���͊K����\��DR�Ƃ͊W�Ȃ��A�Ƃ悭������̂͂��������������ł�����O��Ƃ��ăr�b�g����"����Ă���"�K�v������܂�
����ł�10��12stop�̐M���̗�ɑ�����8bit�̊K���̐������������߁A����Ă��Ȃ������Əd���̋������ԈႢ���w�E���܂���
�����ԍ��F25231024�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
��pmp2008����
�� �Ƃ���ŁA�C�ɂȂ�̂́ADXOMARK�̃Z���T�[�X�R�A��
�����ł̐����͂����܂ŗ��_�l�ł���
���f�ɒ��ڂ��āA�F���l�������A����`�̕ω��������͈͂ŁA�m�C�Y�͑S�Ă̋P�x�Ɉ�l�Ɋ܂܂�Ă���Ƃ��Ă� �����ɂȂ�܂�
���{�e�X�g�ł�
��ʑS�̂́A�����炭�O���[��ŁA���������Ĕ���`�̕ϊ����܂܂ꂽ���Ƃ̉摜�ŁA��l�łȂ��m�C�Y�̉���������Ƃ��āA�v���⊷�Z������Ă����Ȃ����ȂƎv���܂�
���ɁA��f���DR�Ȃ̂��A�������̉𑜓x�Ɋ��Z������ʑS�̂�DR�Ȃ̂��́A��ʂ��čl�����ق����ǂ������ł�
�����ԍ��F25231097�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��Kazkun33����
�B���f�q�����ł͖����A�I�[�f�B�I�ł�192kHz/24bit�T���v�����O�̃n�C���]�����̕���CD��艹���ǂ��ƐM�����܂���Ă���l�������悤�ł����A�����ɂ̓m�C�Y�����ł͂Ȃ��c�ݗ��������ɉe����^���Ă���̂ŁA�����r�b�g���𑝂₵�T���v�����O���g�����グ��Ηǂ��Ƃ������ł͂Ȃ��悤�ł��B
���Ȃ݂ɗ��_�I�ɂ�16bit�̃_�C�i�~�b�N�����W��96dB�Řc�ݗ���0.0015%�ł����ǁA���ۂ�CD�ł��ꂾ���̃X�y�b�N���N���A���Ă��镨�͖�������ł͂Ȃ��A�n�C���]������CD��������̂����邩���A�A�i���O��H�̓������l������Ƃ��Ȃ�^�₪�c��܂��B
�_�C�i�~�b�N�����W�̒�`��Tranquility��������Ă���悤�Ƀm�C�Y���x���ƖO�a���x���̔�Ƃ������ɂȂ�܂����ǁA�m�C�Y���x�����ł��Â��P�x�ƁA�O�a���x�����ł����邢�P�x�Ƃ��āA���̔䗦�ő��肷��ƁuPhotons to Photos�v�̃f�[�^�ɋ߂����l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�m�C�Y�̗v���ɂȂ��Ă���̂̓t�H�g�_�C�I�[�h�̌ŗL�̃m�C�Y�A�A���v�̃m�C�Y�AAD�ϊ��̍ۂ̗ʎq���m�C�Y�ł����ǁAAD�ϊ�����O�̃m�C�Y�͒�R�̗��[�Ŕ�������M�G�����e�����Ă��܂��B
�d�ׂ�d���ɕϊ����邽�߂ɕK�v�Ȓ�R�͔����̂ō\������Ă��܂����A���̕����Ŕ�������m�C�Y�͔M�G�����x�z�I�ł�����A���̕t�߂ł̃m�C�Y�L�����Z�����O�̓��j�A���e�B�ɂ��e�����Ă��܂��B
���Ȃ݂ɒ���G���̒�R�ł��m�C�Y��-150dBm�ȉ��ɗ}����Ƃ����̂͌������悤�ł��B
https://www.cined.com/labels/lab-test/
��Lab Test�ł����̕ӂ̃f�[�^�����\����Ă��܂����ǁA���j�A���e�B���������A14bit�̃����b�g�͂��܂芴�����Ȃ��ł��ˁB
��́A�傫�ȉ�f�Ə����ȉ�f��g�ݍ��킹�ă_�C�i�~�b�N�����W���L���悤�Ƃ���CCD�B���f�q�����݂��܂������A���j�A���e�B�������A�V�̎B�e�ɂ͕s���������������ł��B
�I�[�f�B�I�p�ɂ��Q�C���̈قȂ�Q��16bit��AD�R���o�[�^���g��18bit�̃f�[�^��t���[�e�B���O�����Ƃ����̂�����܂������ǁA�_�C�i�~�b�N�����W�͑��₹�Ă��c�ݗ��͗ǂ��Ȃ������ł��B
�����ԍ��F25231153
![]() 7�_
7�_
����o������
�ȂA�������s�v�c�Ȃ��Ƃ����Ă��܂��ˁc
�����ԍ��F25231188
![]() 9�_
9�_
��o������
>�r�b�g���͊K����\��DR�Ƃ͊W�Ȃ��A�Ƃ悭������̂͂��������������ł�����O��Ƃ��ăr�b�g����"����Ă���"�K�v������܂�
���̒ʂ�ł����A���̓���́u���i�����ꂽ�J�����v���Ώۂł��̂ŁA���̑O��͖������Ă���Ɖ��߂���ׂ��ł��傤�B
pmp2008����
>12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɁA15EV�͓���Ȃ��ł��B
�����̓Z���T�[�̐v����ŁA�u15EV�̌��𗁂т��Ƃ��ɔ�������d�� �� ADC�̃t���X�P�[���d���v�ɂȂ�l�ɐv����Ηǂ���ł��B
�܂��A������bit���͊֗^���Ȃ������킩��܂��B
�����ԍ��F25231222
![]() 5�_
5�_
��Tech One����
�����r�b�g���͊K����\��DR�Ƃ͊W�Ȃ��A�Ƃ悭������̂͂��������������ł�����O��Ƃ��ăr�b�g����"����Ă���"�K�v������܂�
�����̒ʂ�ł����A���̓���́u���i�����ꂽ�J�����v���Ώۂł��̂ŁA���̑O��͖������Ă���Ɖ��߂���ׂ��ł��傤�B
��o������̏����ԍ��F25228089 �ɂ��� EOS R6 Mark2 �̃O���t�́A���ۂɔ̔�����Ă��鐻�i�ł��A���̑O������Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ������Ă��܂��B
���̃�7C�̃w���v�K�C�h�ɂ́A�Î~�悪12�r�b�g�̕���\�ɐ��������ꍇ��������Ă��܂��B���̏ꍇ�A�����炭�A���̑O��͖�������Ȃ��ł��B
��7C �w���v�K�C�h
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000154190.html
-------------------------------------------------------------------------------
�t�@�C���`���i�Î~��j
RAW�ɂ���
�E�{�@�ŎB�e����RAW�摜�́A1�s�N�Z���ɑ���14�r�b�g�̕���\�������Ă��܂��B
�������A�ȉ��̎B�e���́A12�r�b�g�̕���\�ɐ�������܂��B
-�m���b��NR�n
-�mBULB�n
-�mRAW�L�^�����n���m���k�n�ɐݒ肵�ām�A���B�e�n���s���ꍇ
-------------------------------------------------------------------------------
�����ԍ��F25231307
![]() 2�_
2�_
��Tech One����
>>12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɁA15EV�͓���Ȃ��ł��B
>�����̓Z���T�[�̐v����ŁA�u15EV�̌��𗁂т��Ƃ��ɔ�������d�� �� ADC�̃t���X�P�[���d���v�ɂȂ�l�ɐv����Ηǂ���ł��B
�t���X�P�[���d�������̂悤�ɐv������͓̂��R�̂��Ƃł��B���̏�ŁA���́AADC�̍ŏ��o�͒l�u1�v�ɑ�����͒l�ł��B
Tech One������A�����炭�ATranquility����Ɠ������Ⴂ������Ă��܂��B
��o������̏����ԍ��F25231024 �̐������G��ł��̂ŁA����ǂ��������B
�����ԍ��F25231349
![]() 1�_
1�_
���|������ǃ_�n����
�u���V���b�g�m�C�Y�v���Y��Ȃ��ł����Ă�������(^^;
�����x�����ɂȂ�قǁA�u���V���b�g�m�C�Y�v�̑��݂��ł��Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B
(�Y�t�摜�̉��\�E�����́A���V���b�g�m�C�Y�Ɋւ��ȈՌv�Z��� S/N��)
�����ԍ��F25231416�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����o������
�킩��₷�����������Ē����A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25231453
![]() 2�_
2�_
���|������ǃ_�n����
�����N����Q�Ƃ���ƁAAPS-C��X-H2S�̃_�C�i�~�b�N�����W���t���T�C�Y���݂Ȃ̂�X-Trans�Z���T�[�ł��邩��ł��傤���H
�����ԍ��F25231477
![]() 4�_
4�_
��pmp2008����
>12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɁA15EV�͓���Ȃ��ł��B
15EV��12bit�̕���\�Ńf�W�^���f�[�^������Ƃ��������ł���B
���������Ȃ����Ȃ��ł��傤�ɁB
����o������
>2bit��AD�ϊ��ŁE�E�E
>3����4V ---> 3
>2����3V ---> 2
>1����2V ---> 1
>0����1V ---> 0
���̏ꍇ�A�A�i���O�̃_�C�i�~�b�N�����W��0~4�̕��ł���u4�v�Ƃ������Ƃł���ˁB
AD�ϊ��Ȃ�u2bit��4�̃f�[�^�v�ɕϊ�����܂���ˁB
>�����͖��炩�ł��� AD�ϊ��̃r�b�g��������Ă��Ȃ�1V�����́A�M�����̂ĂĂ��܂�������ł�
�Ȃ��u0�v���̂Ă�̂ł����ˁH
>����3bit�ɂ��܂�
>3.5����4.0V ---> 7
>3.0����3.5V ---> 6
>2.5����3.0V ---> 5
>2.0����2.5V ---> 4
>1.5����2.0V ---> 3
>1.0����1.5V ---> 2
>0.5����1.0V ---> 1
>0.0����0.5V ---> 0
���̏ꍇ���A�i���O�̃_�C�i�~�b�N�����W��0~4�̕��ł���u4�v�Ƃ������Ƃł���ˁB
AD�ϊ��Ȃ�u3bit��8�̃f�[�^�v�ɁB
>�Ō��4bit�ɂ��܂�
>3.75����4.00V ---> 15
>3.50����3.75V ---> 14
>�F
>0.75����1.00V ---> 3
>0.50����0.75V ---> 2
>0.25����0.50V ---> 1
>0.00����0.25V ---> 0
������A�i���O�̃_�C�i�~�b�N�����W��0~4�̕��ł���u4�v�Ƃ������Ƃł���ˁB
AD�ϊ��Ȃ�u4bit��16�̃f�[�^�v�ɁB
>�m�C�Y�ɖ�����Ȃ��ŏ��l�͌��̃A�i���O����0.5V�ł��ˍő�l�̓f�W�^���l15�̎���4V�ł�
�ł���Ȃ�A0.50V����4.00V�̊Ԃ��A�i���O�̃_�C�i�~�b�N�����W������A���̕���8bit��AD�ϊ����ׂ��ł́B
����ł�16�̃f�[�^�ɂȂ邱�Ƃɕς�肠��܂��B
>�r�b�g��������Ă���̂Ȃ炻��ȏ㑝�₵�Ă�DR�͏オ��܂���
�Ӗ����킩��܂���B
�����Ō����Ă���_�C�i�~�b�N�����W�͉��̕��ł����H
�_�C�i�~�b�N�����W�́A����ꂽ�A�i���O�f�[�^�̗L���ȕ��̍L�����Ӗ����܂���ˁB
�C���[�W�Z���T�[�Ȃ�A��f���Ƃɓ�����d�ׂ̒l�ʼn摜�����ɗL���ȍŏ��ƍő�̒l�̔�B
AD�ϊ��ɊW�Ȃ��A�ŏ����猈�܂��Ă���l�ł���B
��o������ �̐����͐�����AD�ϊ��̍l�����ł����H
�u���炩�ȃA�i���O�f�[�^�v���u�K�i��̃A�i���O�f�[�^�v�Ɍ��������Ă��邾���̂悤�Ɍ����܂����ǁB
�u�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�ȂǂƏ����Ă��܂������ǁA�������{����Ԉ���Ă���̂ł́B
�����ԍ��F25231522
![]() 9�_
9�_
��Tranquility����
��15EV��12bit�̕���\�Ńf�W�^���f�[�^������Ƃ��������ł���B
�����������Ȃ����Ȃ��ł��傤�ɁB
12bit�̕���\�̏o�͂ŕ\����̂́A0EV����12EV�܂łł��B
���̕��͂Ȃ�A�������肢�������܂��ł��傤���H
�����ԍ��F25231544
![]() 1�_
1�_
��om-1�̃O���t�̂悤�ɑf���Ƀ��j�A�ȓ�����`���Ă���̂� �r�b�g��������Ă���E�E�E
���낢��ƒ[�܂�܂����ARAWbit�ƃ_�C�i�~�b�N�����W�̓f�W�^���ƃA�i���̊W�ł����璼�ڂ͊W�������ǁA���ʂƂ��Ă͊W���Ă�ł́B
Kazkun33���Ȃ�14bit�ɂ������������܂茩���Ė����̂ł��� ����������M4/3��12bit�Z���T�[��14bit�ɂł��邩�ł́A���ς�炸�����̂��Ƃ��Ă����Ė��������Ă܂���
12bit��14bit�ɂ��Ċm���ɊK���͗ǂ��Ȃ�܂����ARAWbit�ɂ�����12bit��14bit�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂Q�i���QEV�_�C�i�~�b�N�����W�������邱�Ƃɂ͂Ȃ邯�ǃZ���T�[�̌��E������Ǝv���܂��B
M4/3��14bit��GH5s�͎B���f�q�̃Z���T�C�Y��傫�����B���f�q1������̎���\�͂����߂Ă��܂��B���݂�M4/3��20M�Z���T�[�̃Z���T�C�Y�̓t���T�C�Y��80M�����̃Z���T�C�Y�ʼn�f�����グ�Ă��Z���T�C�Y���������Ȃ邩��M4/3��20M�����E�ARAWbit���Z���T�C�Y���グ���Ȃ�����12bit�����E�ƌ����Ă����Ǝv���܂�
OMDS��GH6�̂悤�Ƀ\�t�g�A�N�Z���[�^�[�܂Ŏg����14bit�ɏグ�邩�͍���Z���T�[�T�C�Y��������20M�ɉ������Ă��Ă��邪�ȋC�����܂����ǂˁB
�����ԍ��F25231557�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
������89����
��RAWbit�ƃ_�C�i�~�b�N�����W�̓f�W�^���ƃA�i���̊W�ł����璼�ڂ͊W�������ǁA���ʂƂ��Ă͊W���Ă�ł́B
�T�˂����ł��B
�������ARAWbit�̓f�W�^���ł����A�_�C�i�~�b�N�����W�̓A�i���O�Ɍ�����̂ł͂Ȃ��ł��B
������Ǝv���āAWikipedia��������A���̋L�ڂł��B
Wikipedia
-------------------------------------------------------------------------------------------
�_�C�i�~�b�N�����W�i�p: dynamic range�j�Ƃ́A���ʉ\�ȐM���̍ŏ��l�ƍő�l�̔䗦�������B
�M���̏��ʂ�\���A�i���O�w�W�̂ЂƂB
-------------------------------------------------------------------------------------------
���ꓙ�ŁA�_�C�i�~�b�N�����W�̓A�i���O�f�[�^�Ɍ���A�ƍl����������܂�����A����͊ԈႢ�ł��B
�����ԍ��F25231602
![]() 2�_
2�_
�u�ʎq���Ώۂ̍Œ�l�ƍō��l�v�ɑ��āA
�P�Ȃ�z��ɂ����Ă͎��R�� bit����ݒ�\�ł����Ă��A
�����I�ɂ� �ǂ��Ȃ�ł��傤�H
�Ⴆ�A�P�i�����W���I�ł������Ƃ��āA
����ȊO�͂ǂ��Ȃ�ł��傤�H
���������A�J�����ƊE�̏펯�I�Ȕ͈͂ŁB
�����ԍ��F25231619�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
pmp2008����
����http://www.ned-sensor.co.jp/support/about2.html�Ő�������Ă���D�����W�������ɂȂ������̂ł����AADC�̗ʎq���G���Ɛ����g�̍ő�U���Ƃ̔�(S/N��)���l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������ł��ˁB
�C���[�W�Z���T�[�S�̂Ƃ��Ă�D�����W���グ���{�H���́A
(1) ��f�̖O�a�I���ʂƖO�a�o�͓d�����グ��
(2) ADC�̃t���X�P�[���d����O�a�o�͓d���ɍ��킹��
(3) ADC�̕ϊ��r�b�g���𑽂����
���ȂƎv���܂��B
�ǂ��������ɑ��ẮA(1)(2)�̑��݂���������ŁA(3)��������Ă�D�����W�͌��サ�܂���A�������ł��傤���B
���̓���������������������Ă���̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25231635
![]() 3�_
3�_
��pmp2008����
>�_�C�i�~�b�N�����W�̓A�i���O�f�[�^�Ɍ���A�ƍl����������܂�����A����͊ԈႢ�ł��B
����ł́A���q�˂��܂��B
�u�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ͉��ł����H�@�ǂ̂悤�ɒ�`����܂����H
>Tech One����
>ADC�̗ʎq���G���Ɛ����g�̍ő�U���Ƃ̔�(S/N��)
����̓f�W�^���f�[�^�̐��x�Ɋւ��悤�Ɏv���܂����A�_�C�i�~�b�N�����W����Ȃ��ł���ˁB
�����ԍ��F25231651
![]() 7�_
7�_
��pmp2008����
�����ƁA�����ẴR�����g���������肷������Ă��܂��܂����B���݂܂���B
>12bit�̕���\�̏o�͂ŕ\����̂́A0EV����12EV�܂łł��B
>���̕��͂Ȃ�A�������肢�������܂��ł��傤���H
���݂܂���B���͂ɂ���̂͌��_�����ŁA���̗��R���킩��܂���B
12bit�Ƃ������Ƃ́A��L�R�����g�̗Ⴞ�ƁA0EV����12EV�̕��ɂ���A�������d����4096�i�K�ɂ��ďo�͂���Ƃ������Ƃł���ˁB���ꂪ�A0EV����15EV�̕�����4096�i�K�ɂł��Ȃ��Ƃ������Ƃł����H�@���Ƃ�����A����͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F25231765
![]() 7�_
7�_
������89����
>RAWbit�ɂ�����12bit��14bit�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂Q�i���QEV�_�C�i�~�b�N�����W�������邱�Ƃɂ͂Ȃ�
�E�E�E�̂ł����H
���̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ́A���̃_�C�i�~�b�N�����W�ł����H
�����ԍ��F25231773
![]() 6�_
6�_
��pmp2008����
�u0EV����15EV�̕�����4096�i�K�ɂł��Ȃ��Ƃ������Ƃł����H�v
����A���������āA�t�ł����H
0EV����8EV�̕�����4096�i�K�ɂł��Ȃ��Ƃ������Ƃł����H
�����ԍ��F25231786
![]() 7�_
7�_
��Tech One����
����ŗǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25231805
![]() 0�_
0�_
��Tranquility����
��12bit�Ƃ������Ƃ́A��L�R�����g�̗Ⴞ�ƁA0EV����12EV�̕��ɂ���A�������d����4096�i�K�ɂ��ďo�͂���Ƃ������Ƃł���ˁB
�����ꂪ�A0EV����15EV�̕�����4096�i�K�ɂł��Ȃ��Ƃ������Ƃł����H�@���Ƃ�����A����͂Ȃ��ł����H
���̕��͂Ȃ�A���������������܂��ł��傤���H
12bit�̕���\�̏o�͂ŕ\����̂́A12EV�͈̔͂ł��B��̓I�ȗ�́A0EV����12EV�Ƃ��A3EV����15EV�ł��B
�����ԍ��F25231816
![]() 2�_
2�_
��Tranquility����
���u�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ͉��ł����H�@�ǂ̂悤�ɒ�`����܂����H
�_�C�i�~�b�N�����W�̒�`�́A�Ώۂ��A�i���O�f�[�^�ł��f�W�^���f�[�^�ł��A��`���͕̂ς��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F25231830
![]() 3�_
3�_
>pmp2008����
>12bit�̕���\�̏o�͂ŕ\����̂́A12EV�͈̔͂ł��B��̓I�ȗ�́A0EV����12EV�Ƃ��A3EV����15EV�ł��B
���̗��R�����������������B
0EV����15EV�̃����W�i�͈́j����12bit�i4096�K���j�ɂł��Ȃ����R�������Ă��������B
����܂ł̃R�����g�́u���_�v����ŁA�����Ȃ�u���R�v������܂���̂ŁB
>�_�C�i�~�b�N�����W�̒�`�́A�Ώۂ��A�i���O�f�[�^�ł��f�W�^���f�[�^�ł��A��`���͕̂ς��Ȃ��ł��B
�u�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ͉��́u�����W�i�͈́j�v�������܂����H�@����͂ǂ̂悤�ɒ�`����܂����H
�����ԍ��F25231868
![]() 5�_
5�_
�l�̎�ςɂ���`��
�Ȋw�I�E�Z�p�I�Ɍ��܂��͊w�p�c�̓��ɂ���`��
�����Ⴒ����(^^;
�����ԍ��F25231871�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
2023/04/22 16:08�i1�N�ȏ�O�j
��pmp2008����
���k���ċL�^����H
�Ǝ��₳��Ă���̂���
�v���܂��B
���j�A�Ɉ��k�Ȃ�
�摜�ҏW�ɂ͖�薳���ł��ˁB
���k�����Ȃ�A
�Õ�����ċL�^�Ƃ������@��
�j�R�������Ă����悤�ȁB
������ɂ���A
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y��
���݂̃Z���T�[�Ȃ�A
12�r�b�g�Œ��x���܂�܂��̂�
����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��A
����s�s���͂Ȃ��ł��B
���ƃx�C���[�Z���T�[��
�����ɋL�^�o���Ȃ��_������
�摜�����̊ϓ_������
�c�_�ɂȂ��Ă܂��ˁB
�����Y�����ӂ̓{�P�܂����A
��������MTF�͐��1�i���S�j�ɂ�
�Ȃ�܂���B
�����A�Z���T�[�����S�Ȑ��E��
�L�^�o���Ă��邩�̂悤�ȋc�_��
��a���������܂��B
�P�V���b�g�Ŋ������悤�Ƃ���
�v�l�̂܂~�܂��Ă���悤�ł����A
�`�h�̎���̉摜�����Ƃ��Ⴄ�A
10�N�O���炢�O�̍l���̂悤�ł��B
���������A�����̃����Y���g����
�K���͊����ɂ͌������܂���̂ŁA
����̋�_�ɂȂ��Ă܂���B
�I�[�f�B�I�}�j�A���āA
�������������Ȃ̂ł��傤�ˁB
���ۂɂ̓����Y�̕����d�v�B
�������������I�Ȓl�i�Əd�ʂ��d�v�B
�f�W�J���͂�͂�c���E�ł��ˁB
�����ԍ��F25231876�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 8�_
8�_
��Tranquility����
�����̗��R�����������������B
��o������̏����ԍ��F25231024 �̓��e���ڂ����ł��B������������Ȃ�A�����12bit�Ɋg�����邾���ł��B
���u�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ͉��́u�����W�i�͈́j�v�������܂����H�@����͂ǂ̂悤�ɒ�`����܂����H
�u�����W�v�Ƃ������t�͈Ӗ����L���ł��B
�u�_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ����p��̈ꕔ�ł���u�����W�v���o���āA�u�_�C�i�~�b�N�����W�v�ɉ����悤�ɁA���̈Ӗ����l����i��`����́j�̂́A�悭������Ȃ��ł��B
�����ԍ��F25231990
![]() 4�_
4�_
����o������
�����2bit��AD�ϊ��� ����𑵂���(�܂�ő�l��4V�Ƃ���)�f�W�^���M���ɕϊ������
3����4V ---> 3�E�E�E�E�E4.0V
2����3V ---> 2�E�E�E�E�E2.6V
1����2V ---> 1 �E�E�E�E�E1.3V
0����1V ---> 0�E�E�E�E�E0.0V
�ʼn������Ȃ��B
�����ԍ��F25232143
![]() 1�_
1�_
��pmp2008����
>��o������̏����ԍ��F25231024 �̓��e���ڂ����ł��B
���x���ǂ�ł��܂����A��������͂���܂����B
12EV�̕���12bit�i4096�K���j�ɂł���̂ɁA�����蕝�̍L��15EV���Ȃ�12bit�i4096�K���j�ɂł��Ȃ��̂ł����H
�u�r�b�g��������Ă��Ȃ��v�Ƃ��u����Ă���v�Ƃ������Ă���܂����A����͂ǂ������Ӗ��ł����H
>�u�_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ����p��̈ꕔ�ł���u�����W�v���o���āA�u�_�C�i�~�b�N�����W�v�ɉ����悤�ɁA���̈Ӗ����l����i��`����́j�̂́A�悭������Ȃ��ł��B
�p��́udynamic range�v�ł��ˁB���L�A�p�a�����ɂ���Ӗ��ł��B
�ydynamic�z
���͂́A���I�ȁA���͓I�ȁA�_�C�i�~�b�N�ȁA(��)�͊w(��)�́A���Ԃ́A�G�l���M�[����A�@�\�I��
�yrange�z
�͈́A���A�L����A�r���E�E�E
������udynamic range�v�̈Ӗ��́u�@�\�I�ȁi�g����j�͈́v�ł����ˁB
���L�A�J�����̃_�C�i�~�b�N�����W�idynamic range�j�ɂ��Ċe��WEB�T�C�g�ɂ�������̏E���W�߁B
�E�f�W�^���J�������Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���A���邢��������Â������ւ̍Č��\�ȕ��̂���
�E�B���f�q�i�Z���T�[�j��������邱�Ƃ̂ł���ł��Â������Ɩ��邢�����͈̔�
�E�����\�ȐM���̍ő�l�ƍŏ��l�̔䗦��\�������l
�E���ʉ\�ȐM���̍ŏ��l�ƍő�l�̔䗦������
�E��x�̎B�e�ŃJ���������ʂł��閾�邳�͈̔�
�E�J�����̃Z���T�[���Č��ł��閾�邳�i�P�x�j�̗̈�̎�
�E�Z���T�[��L�^�}�̂Ȃǂ̓d�q�@�킪�������Č��ł���M���̍ő�l�ƍŏ��l�̔䗦�₻�͈̔�
�E�M���̍ŏ��l�ƍő�l�̔䗦�������A���ʂ�\���w�W�A���������̂ЂƂ�
�E�M���̍Č��\�͂�\���l�B���ʂ܂��͍Č��\�ȍł������M���ƁA�ł��ア�M���Ƃ̔�
�E�@�킪���ʉ\�Ȗ��Ô䗦�̕��L����\�����l�̂���
�E���̃J�����ň�x�Ɏʂ��i�L�^����j���Ƃ��ł��閾�邳�͈̔͂��������t
�E������f���A�摜�Ȃǂɂ�����M���̑傫���͈̔͂�\���w�W�ŁA�ő�l�ƍŏ��l�̔䗦�̂���
�E�d�q�@�킪�Č��ł���M���̍ő�l�ƁA�ŏ��l�Ƃ̔䗦�̂���
�E���≹�Ȃǂ�F���i�܂��͍Č��j�ł���ő�l�ƍŏ��l�̕��̂��ƁB�܂��͂��̕��i���j��䗦�ŕ\��������
�ŁA�_�C�i�~�b�N�����W�́u�ŏ��l�E�ő�l�v�Œ�܂�܂���ˁB���ꂪ�urange�v�̗��[�ɂȂ�܂��B
�C���[�W�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W�̗��[�́A��f�Łu�V�O�i�����m�C�Y�ɖ������Ƃ���̓d�ׂ̒l�v�Ɓu�O�a����Ƃ���̓d�ׂ̒l�v�ł���ˁB
�w�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�x�Ƃ������̂����邻���ł��ˁB����̓A�i���O�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ɓw��`���͕̂ς��Ȃ��x�Ƃ������Ⴂ�܂����B
���Ƃ���ƁA�u�m�C�Y�ɖ������Ƃ���̃f�W�^���f�[�^�v�Ɓu�O�a����Ƃ���̃f�W�^���f�[�^�v�����[�H�@����Ȃ̂����ł����H
����Ƃ��Ⴄ�����ł����H�@���Ƃ����炻��͉��ł����H
�����ԍ��F25232181
![]() 9�_
9�_
�����낢��Ɗ�{�I�ȗ������Ԉ���Ă���悤�ł��B
�ʎq���m�C�Y�̊T�O�𗝉��ł��Ȃ��l���A�����������ł��Ă����o�������pmp2008����Ɍ����錾�t�c�B
�I�[�f�B�I�ł��f���ł��A�_�C�i�~�b�N�����W�̊T�O�́u�\�����Ƃ��ł���ő�l�ƍŏ��l�̔�v�ł��B
�������ő�l�͑��肪�e�Ղł����A�ŏ��l�̕��̓m�C�Y�̒��ł̊ϑ��ƂȂ�̂ʼn��������āu�\���Ă���v�Ƃ��邩���f������Ȃ�܂��B�����ʼnf����ISO�K�i�ł́uSNR=1�ƂȂ�P�x�v���_�C�i�~�b�N�����W�̉����Ƃ��Ē�`���Ă��܂��B
SNR=1�Ƃ́A�M���ƃm�C�Y�̑傫���������Ƃ������Ƃł��B�f�W�^���f�[�^��1step�オ��Ȃ����Ƃɂ́u�M���v�͊ϑ��ł��Ȃ��̂ŁA�f�W�^���f�[�^�̍ŏ��X�e�b�v���e�����܂��B��o������̂��������ʂ�A�����I�Ȑv���ł��Ă�����̂́A�ŏ��X�e�b�v���ߕs���Ȃ����蓖�Ă��邱�Ƃ�������ł����B
�����āA���x�̈�������킪�₽�瑽�������o���Ă��Ӗ����Ȃ��A������������Z���T�[�̐��x���ǂ��Ă��\���ł��錅�������Ȃ���ΐ��x�������̂Ɠ����ł��B�X���傳��̍ŏ��̋^��ł���14bit�̕���������Ȃ��́H�Ɋւ��Ắu12bit���ł���p�Ό��ʂ�������������ł́H�v�Ǝv���܂��B
�B�e�����⌻���̎d����14bit�ɂ���Ɣ����ɗǂ��Ȃ�P�[�X�������āA���������[�U�[������ɑ�������m�������ɒႢ�Ƃ�����Abit�������Ȃ����Ƃ̃����b�g(���x/����d��/�A�˖����Ȃ�)������Ȃ��ł����ˁB
�]�k�ł����u����ɂ܂������ɓ�����r��Ȃ��v�Ƃ����̂͑S���^���ł��Ȃ��ł��ˁB���̕��́u����(���ǂ����Ƃ����Ă���)�ɓ����Ȃ��������瑊�肪�����v�Ƃ������l�ςœ����Ă��܂����A�Z�p�̊�b�����肸�ɂ������������Ă������Ĕ[�����Ȃ��l�����X�ƌJ��o���u�^��v�ɂЂ����瓚���Ă�����l�͔敾���Ă��܂��̂ł��B
�u�����[���ł���܂ʼn������Ȃ����肪�����v�Ƃ����͔̂��Ɏ��Ȓ��S�I�Ř����Ȃ̂ł��B
�����ԍ��F25232201
![]() 32�_
32�_
���u�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�ȂǂƏ����Ă��܂������ǁA�������{����Ԉ���Ă���̂ł́B
�� ����܂ł̃R�����g�́u���_�v����ŁA�����Ȃ�u���R�v������܂���̂ŁB
�� ���x���ǂ�ł��܂����A��������͂���܂����B
�����Ă�������Ȃ̂́A����̐l�������獧�ؒ��J�ɐ������Ă��A�����������ł��Ȃ��ꍇ�Ɂu��������Ă��Ȃ��v�ƂȂ邱�ƂȂ�ł���ˁB
�������ہA�������_�ł������̓��͐l���ꂼ��ł��B���J�̐l�d�C�̐l�A�n�[�h�̐l�\�t�g�̐l�A���ꂼ��ɉߋ��̗�����o���Ɋ֘A���āA�����̕����L���Ă������̂ł��傤�B
���������̕��́A�������l���Ă��铹�Ɋ��S�ɉ��������̈ȊO�́u����ɑ���v�Ƃ͔F�߂܂���B
���̐l�����낢��Ȋp�x����ꐶ�����������Ă��A�����̓��Ƀs�^���ƈ�v���Ă��Ȃ���u��������ĂȂ��v�ƔF�������ł��B
�����ł��Ȃ����^����Ԃ��遨��������遨�����ł��Ȃ������肪�Ԉ���Ă���ƍl���遨�^����Ԃ��遨���肪���Ă��܂�������f�O���u���̐l�͎��̋^��ɓ������Ȃ��B�����玄���������v�@�c���ꂪ�����̓W�J�ł��B
���j�AA/D�ϊ��̊�{���S���������ĂȂ��̂ɁA�l�̐����ɕ��݊�낤�Ƃ����ӎ����[���̐l�ɉ��������Ă����ʂ��Ǝv���܂����A�ꉞ�����Ă݂܂��B�܂��b�̑O��Ƃ��āARAW�f�[�^�͋P�x�ɑ��ă��j�A(���`)�ȏd�݂������Ă��܂��B
10�i���ňꌅ�̐����́A0����9��10�i�K��\�����Ƃ��ł��܂��B
�E"0" �͉����Ȃ��A�M�����m�C�Y���[���B����͕K�v�����_�C�i�~�b�N�����W�ɕK�v�ȋP�x�l��\�������ƂɂȂ�Ȃ�
�E"1" �͐M���Ƃ��ĕ\�����Ƃ��ł���A�ł������Ȑ����B���j�AA/D�ϊ��ł���A�ő�l���猩���1/9�̒l
���̕��̗����́u�P�x����10EV���낤��15EV���낤���A�����10�i�K�ɕ������邾��������\����v�Ƃ������́B
�ł́u�\����v���u��ʂł���v�ɕς��Ă݂�Ƃǂ��ł��傤�B
���j�A�Ȑ��E��0.1��0.2�̋�ʂ�\���ɂ́A"0." �Ƃ��������ꌅ���K�v�Ȗ�ł��B
1�X�e�b�v�̏d�݂�0.1�Ƃ��āA�̐���������A0.0�ȊO��0.1�`9.9 �܂�99�i�K�ɐM����\�����Ƃ��ł��܂��B
�������ꌅ�����Ȃ��āA9�Ƃ���������\�������B�ł�0.1��0.2�̍������\���������B
�c����̓��j�AA/D�ϊ����ƕ����I�ɂł��Ȃ���ł��B
����Z�p�I�ɂ͔���`A/D�Ƃ������̂������āA�Ⴆ�ŏ���1�X�e�b�v��0.1V�Ȃ̂�����ǂ��A�Ō��1�X�e�b�v��1V�ɂ���A�Ƃ�������������܂��B����Ȃ�u�ق�A������10�i�K��100�{�߂�����\���ł������낤�v�Ǝv���邩������܂���B����������`��12bit�̕ϊ����s���ɂ́A�����������bit���̑���A/D�R���o�[�^�Ɠ����Ȑ��\���K�v�ł���A�킴�킴���������āA�ォ�烊�j�A�l�ɕϊ����������ςȂ̂ŁAA/D�ϊ���RAW�f�[�^�̊�{�̓��j�A�Ȃ̂ł��B
���Ȃ݂�JPEG�Ȃǂ̋P�x������Log�ɋ߂�����`�l�ɕϊ�����ċL�^����Ă���̂ŁAJPEG���8bit�ł��A�����ɋL�^����Ă���P�x�̃_�C�i�~�b�N�����W��10bit��������14bit�������肷���ł��B
�c�����A���ʂȒ����������Ă��܂����c�B
�����ԍ��F25232406
![]() 21�_
21�_
�v���F15EV��12bit�i4096�K���j�ɕ�������B
A�N�F�r�b�g������Ȃ��̂ŏo���܂���B
B�N�F���x���C�}�C�`�ł����Ǐo���܂����B
���A�����ƁAA�̓_�����ȁB
�����ԍ��F25232445
![]() 3�_
3�_
2023/04/23 00:51�i1�N�ȏ�O�j
�@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̌��݂̃Z���T�[���\�́A���x12EV���x�ł��B
�@�]���܂��āA14bitRAW�͕K�v����܂��A
�@14bitRAW�ɂ����RAW�摜�f�[�^�̗e�ʂ����ʂɑ����܂����A�A�ʑ��x�������܂��B
�@�܂�A�Ӗ�������܂���B�i�����R��������12bitRAW�ɂ��Ă���A�Ɛ��@�ł��܂��j
�A�@�@�ɂ��ւ�炸14bitRAW�K�[�Ƃ������́A
�@���������ăK�[�K�[�����Ă���̂ł��傤���B
�@�Ӗ���������܂���B
�@���Ȃ��Ƃ����݂̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ōs���c�_�ł͂���܂���ˁB
�B�t���T�C�Y�i�Ⴆ�Γ��Ƀ\�j�[�j�ɂ�12bit�o�͏o����f�W�J��������܂����A
�@����͈ꗥ�@12EV�@�Ȃ̂ł��傤���H
�@�����炨�������������B��pmp2008����
�C�@�B�ɂ����ā@12EV�@�łȂ��̂ł���A
�@
�@�\�j�[�͔@���Ȃ鏈��������14EV��12bit�o�͂��Ă���̂ł��傤���B
�@�����炨�������������B��pmp2008����
�@�����N�ォ�Ƀ\�j�[��16bitRAW�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��̂ŁA
�@�@�@���̍ۂɁ@�\�j�[�͂�������Ă���ƌ����Ă��܂�����@�ƋL�ڂ����Ă��������i��������܂���j�B
�Ȃ����̘b�肪�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ōs����̂��A�����ɋꂵ�݂܂��B
���������X�ƁE�E�E�B�������Ăт�����ł�����B
���̎�̘b�肪�D���Ȑl�͈�萔���������邩�Ƃ͎v���܂����A
����ł܂�ƁA�u���������ʐ^�v����グ��l�ɂȂ�̂ŁA���ӂ��K�v���Ƒ����܂��B
�܂�@�܂�Ȃ��ʐ^�@�ł��ˁB
RAW���A�͎̂g���l�͈ꈬ��ł������A���̍��͊��C����������ł����ǂˁB
RAW�K�[����ɂȂ��Ă��āA�X�}�z���[�U�[�Ɍ�����������Ȃ��Ȃ������E�E�E�B
����@�K�[�̈��ɁA�Ⴂ�l�ȂǒN���D���D��œ�����̂ł����ˁ`�B
�ł�B
�����ԍ��F25232495
![]() 9�_
9�_
���S�҂Ȃ̂œڒ����Ȏ���������������܂���B���������������B
�悸�A�J�����ɂ�����_�C�i�~�b�N�����W�i�ȉ�DR�j�Ƃ̓J�������������閾�邳�̕��̂��ƂŁA���̍ŏ��l�ƍő�l�̔�ŕ\�����AEV�łȂ玮(1)�ŕ\�����Ɨ������Ă��܂��B
�@�@DR = log2 (�ő�̖��邳 / �ŏ��̖��邳) �E�E�E ��(1)
���ɁA<DR�̓Z���T��ADC�ɓ���O�̓d���l�ł���(2)�ŕ\�����āA������AD�ϊ����s���Ɨʎq���̊W��1bit�ڂɑ�������d���ȉ��̕ω��������Ȃ��Ȃ�̂�RAW�Ƃ��ĕۑ������f�[�^��DR�͐��������>�A�Ƃ����̂��f�W�^���h�i�ł����̂��ȁj�̎咣�ł���ƔF�����Ă��܂��B
�@�@DR = log2 (�ő�̖��邳�̎��̓d�� / �ŏ��̖��邳�̎��̓d��) �E�E�E ��(2)
AD�ϊ���̐��l�́A�L�ӂȍŏ��l��[1]�ōő�l�� [2^AD�ϊ���bit��] �Ȃ̂ŁADR�͍ő�ł���(3)�̂悤�ɂȂ�A�Ƃ����咣�ł��ˁB
�@�@AD�ϊ����DR�̍ő�l = log2 (2^AD�ϊ���bit�� / 1) �E�E�E ��(3)
ex)12bit ADC�̎�
�@�@DRmax = log2(2^12 / 1) = 12�@�@�iEV��12�i���j
�O���t�ɂ���ƁA�}1�̐Ԗ��̊Ԃ��J�������F���ł���DR���Ƃ����킯�ł��B
����łȂ�ł����A�ȏ�̎咣�̓Z���T�̓��������`�ł���A�܂�Z���T�̏o�͓d�������͂��閾�邳�ɒP����Ⴗ��Ƃ����O����Ƃ��̂ݐ������܂��B
�}2�ɁA�Z���T�̏o�͂����`�i�P�����j�̎��Ɣ���`�̎��̗�������܂��B
����`�̗�͉��ł��悩������ł����A����͈ꎟ���ɂ��Ă܂��B
������ƃI�t�Z�b�g�̂���o�݂͂����Ȋ����Ǝv���Ă���������Ǝv���܂��B
�}2���Ɏ������ʂ�A���`�̎��͉����̍ő�l�ƍŏ��l�̔�Ƃ���ɑΉ�����c���̒l�̔�͈�v���܂��B
����ēd���l�̍ő�l�ŏ��l�̔��DR�ɑΉ����܂��B
����ŁA����`�̎��͈�v���܂���B����Ă��̏ꍇ�A�o�͓d������DR�����߂悤�Ƃ���ƌ�����l�����߂邱�ƂɂȂ�܂��B
�܂��AAD�ϊ��l���d���Ɉˑ�����ʂȂ̂ŁAADC�̃r�b�g������DR�����߂鎎�݂����܂������܂���B
�܂��A�Z���T�̏o�͂�����`�ɂȂ����l���܂��ƁA���̂悤�Ȃ��Ƃ��������܂��B
�@�E�Z���T�̓��������`�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ��i�I�t�Z�b�g������Ƃ��j
�@�E�Z���T�̓��������`�ɂȂ��Ă��Ȃ��̈���g���Ă��鎞�iDR�̏�[���[�ŏo�͂��݂�Ƃ��Ƃ��B����̂��H�j
�@�E�Z���T�̏o�͂����`�����Ă���AD�ϊ�����Ƃ��ilog�A���v���g����HDR�Z�p��������炵���j
���ɂ����邩������܂���B
�Ƃ肠�����A�ȏォ��Z���T������`�ȓ��������Ƃ��AADC�̃r�b�g����DR�̒i���ƈ�v���Ȃ��Ȃ�܂��B
���āA�ł�RAW�B�e��DR���ǂ��Ȃ��Ă��邩���l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B
�܂��ARAW�B�e�Ȃ̂Ńf�[�^��ADC���ǂݎ�����l�����̂܂ܕۑ�����܂��B
���l���̕����q�ׂ��Ă���悤�ɁAADC�ɂ͕���\��S/N�䓙�������āA����炪ADC�̃_�C�i�~�b�N�����W�ƌ����邱�Ƃ�����悤�ł��B�������AADC��DR�ƃJ������DR�͕K��������v���Ȃ����Ƃ�����̂͐�ɏq�ׂ܂����B�����ŏd�v�Ȃ̂́AADC�ɂ��ǂ߂�͈́i�_�C�i�~�b�N�����W�j������A���ꂪ���ۂ̕����ʁi���̋����j�ɑΉ����Ă���Ƃ������Ƃł��B
���ɁAADC��DR�̏�������͌��̋����ɒ����Ƃǂ��ɂȂ邩�l���܂��B�}3�̂悤�ɁA�c���̒l���牡���̒l�����߂�i�D�ł��B����ƁA�J�������F���ł�����̋����̏��������������܂��B����2�l�̔䂩��ARAW�f�[�^�̕\��DR��������܂��B
��������ۂ̍�Ƃɒ����ƁA�����Ȗ��邳�̔�ʑ̂�p�ӂ��āA�B�e�����f�[�^�����ƂсE���ׂꂵ�Ă��Ȃ����m�F���āA���ʂł����������̖��邳�ׂāB�B�B�B�B�B�ǂ����Ō������Ƃ���܂��ˁB
�ȏ�A�����ł����B
�����܂Œ��������Ƃ��ĊԈ���Ă���ǂ����悤�B
���ƁA����҂���̎���̓����ɂ͈�Ȃ��Ă��܂���B�����܂���B
�����ԍ��F25232519
![]() 5�_
5�_
���[�A���͗����Ă���Ԃɔ���`�ɂ��ď����Ă���Ă���������܂����ˁB
������Ⴂ�܂����B
��cbr_600f����
������C�ɂȂ�_���B
raw�͋P�x�ɑ��ă��j�A���Ƃ̂��Ƃł������A�����Ƃ͌���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���j�A�ȓ����̎���f�q����̏o�͂����`�ϊ������Ă���ADC�ɓ��͂����
https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu/81/2/81_97/_pdf
RAW�����ɂ��āi6.1 RAW�f�[�^���`�����@�ɁARAW������`�̏ꍇ�Ƀ\�t�g�Ő��`�����s���Ƃ���j
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/65/3/65_293/_pdf
ADC���̂����j�A�Ȃ��̂��g���Ă���Ƃ����̂͗������Ă������ł��B
�����AADC�̑O�Ŕ���`�ϊ����s�����ADC�̐��o�͂ł���raw�f�[�^������`����������Ǝv���܂��B
�������Araw���P�x�ɑ��ă��j�A�ȃJ����������Ǝv���܂��B
�O�̓��e���܂߂܂��Ď����w�E�������̂́A���`�E����`��������V�X�e������`�݂̂�O��ɂ��Č���Ă������̂��Ƃ����_�ł��B
�����ԍ��F25232520
![]() 4�_
4�_
��Tranquility����
��12EV�̕���12bit�i4096�K���j�ɂł���̂ɁA�����蕝�̍L��15EV���Ȃ�12bit�i4096�K���j�ɂł��Ȃ��̂ł����H
�ł��܂�����ǁA���̌��ʁA
�P�x��15EV���������f�[�^�A���̒�P�x����0EV����2EV�͑S�Ď����A�o�͂����̂́A3EV����15EV�̋P�x��12EV�̃f�[�^�ł��B
���u�r�b�g��������Ă��Ȃ��v�Ƃ��u����Ă���v�Ƃ������Ă���܂����A����͂ǂ������Ӗ��ł����H
�P�x��15EV���錳�f�[�^���A����Ȃ��悤�ɁA�f�W�^���ɕϊ�����ɂ́A15�r�b�g�ȏ��AD�ϊ�����K�v������܂��B
�O�q�̂悤�ɁA12�r�b�gAD�ϊ��ł́A�f�[�^�������܂��B
���̂��Ƃł��B
�����ԍ��F25232693
![]() 5�_
5�_
��cbr_600f����
���Ђ��ł��B
cbr_600f����̐����ō��܂ł̋^�₪�X�b�L�����܂����B
12bit��14�r�b�g�����JPEG�łȂ�ł���ȂɈႤ�낤�H��
�܂��A�߂�ǂ������ē˂��l�߂Ē��ׂȂ������Ƃ����̂�����܂����B
����ɔ�ׁA���X���ł͒P�ɗg�������g����߂ł̓˂����݂����o���Ȃ��A�������ׂ邾���ŁA�������܂����A�����܂����Ƃ��������ɂȂ��ĂȂ��A���̈Ӗ����m��Ȃ��l�����܂�����B
�������A���ʂȒ����������Ă��܂����c�B
�����A����Ȏ��͂���܂���B
�������Ă���l�͕������Ă܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25233112�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��Tranquility����
���_�C�i�~�b�N�����W�́u�ŏ��l�E�ő�l�v�Œ�܂�܂����
�����ł��B
���C���[�W�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W�̗��[�́A��f�Łu�V�O�i�����m�C�Y�ɖ������Ƃ���̓d�ׂ̒l�v�Ɓu�O�a����Ƃ���̓d�ׂ̒l�v�ł���ˁB
�����ł��B
���u�m�C�Y�ɖ������Ƃ���̃f�W�^���f�[�^�v�Ɓu�O�a����Ƃ���̃f�W�^���f�[�^�v�����[�H�@����Ȃ̂����ł����H
�܂��A�A�i���O����f�W�^���̕ϊ��́A�f�[�^������L�����Ŋۂ߂�A�悤�Ȃ��́A�Ƃ����C���[�W�łǂ��ł��傤���H
�܂�A�f�[�^�̈Ӗ��͉����ς��Ȃ��ł��B
�����āA��́u�V�O�i�����m�C�Y�ɖ������Ƃ���̓d�ׂ̒l�v�Ɓu�O�a����Ƃ���̓d�ׂ̒l�v���ꂼ�������L�����Ŋۂ߂āA
�������ŏ��l�A�ő�l�Ƃ��āA�_�C�i�~�b�N�����W���ēx�v�Z����
�w�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�x������ȃC���[�W�ő�����ꂽ�炢�����ł��傤���H
�����ԍ��F25233494
![]() 7�_
7�_
�����܂���B
��̐��`����`�Ɋւ��铊�e�Ɍ��������܂����B
�ΐ����k�ɂ�鍂DR���Z�p��ΐ��ϊ��^CMOS�C���[�W�Z���T�[�Ƃ������̂��������̂ŁA�Z���T�̏o�͂����`����`�����̐��i����ʓI�ł���Ǝv������ł��܂����B
����������`�̕��͌����i�K�̕���Y�Ɨp�������A���t�Ɏg��ꂽ�Ⴊ������܂���ł����B
�܂��uRAW������`�̏ꍇ�Ƀ\�t�g�Ő��`�����s���v�Ə�����Ă��������ɂ́uRAW�f�[�^�͐��`���������v�Ƃ�������Ă��܂��č������Ă����̂ł����A���̎�����ƂقƂ�ǂ̕���RAW�f�[�^����`�Ƃ��Ĉ����Ă��܂��B
�ǂ���RAW�f�[�^�͋P�x�ɑ��Đ��`�������ƍl���ėǂ��悤�ł��B
�����������Ă����܂���ł����B
���āA���`�݈̂����Ă����Ȃ����f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W��ADC�̃_�C�i�~�b�N�����W�̘b���ȒP�ɂȂ�܂��B
��Tranquility����
5EV�̃_�C�i�~�b�N�����W��������f�q�̏o�͂ƁA�����3bitADC�œǂ��̒l�̃O���t���Ƃ��ēY�t���Ƃ��܂��B
�����f�q�̏o�́A�Ԑ���ADC�̏o�͂ɂȂ�܂��B
�����ɂ͑f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W�̍ŏ��l��1�P�ʂƂ���ڐ���ł��Ă����܂����B
5EV�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ��āA32�ڐ�����܂��B
�܂��A1EV���Ƃɑ傫���ڐ���ł��Ă��܂��B
����Ȃ̂ł����A���e�̓_�C�i�~�b�N�����W�̕���bit�����Ⴄ������pmp2008����̏����ԍ��F25232693�Ɠ����ɂȂ�܂��B
�O���t������Ε�����ʂ�A����f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W�̓��AADC�̃_�C�i�~�b�N�����W���Ⴂ2EV���̏�����A�����ق�3EV�̏��3bit�ŊK��������Ă��܂��B
�����ԍ��F25233709
![]() 2�_
2�_
WIND2����
�����J�ɂǂ����ł��B
400kcal(80g������)����
�r���܂Ő��������������Ă܂������A���낢��C�Â��ꂽ�悤�ŗǂ������ł��B
�u����`�̕�v���Ď��ۂɂ̓I�t�Z�b�g�����ɂ�錴�_�Y���̕���炢�����ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
Tranquility����̏������݂��܂��Ȃ̂́A���������̍l���̕����������Ƃ��������ɂȂ�����ꐶ�����T���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����c�B
Tranquility�����hirappa����̊��Ⴂ�́A
�E15EV���ꂽ�Â����낤���A������ "0"���������Ă���悢
�E���Ƃ͍ő�l��0��2�_�Ԃ�bit���ɉ��������ŕ������邾��
�Ǝv��ꂽ���Ƃł��傤�B
�_�C�i�~�b�N�����W�̈Ӗ��́A�u���閾�邳������т��Ȃ��悤�Ɏʂ����Ƃ��A�ǂꂾ���Â��Ƃ���̊G���������邩�H�v�Ȃ�ł���ˁB
�Ȃ̂�-15EV�̈Â��Ń[�����o�������ł̓_���ŁA��������͂��ɖ��邭�Ȃ����Ƃ��ɁA����ɉ������ׂ����������o�Ă��Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ����ϓ_�������Ă��܂��B�Â��Ƃ���̏��ʂ�����Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A�Ⴆ�ő�l�𐳋K������1�Ƃ����Ƃ��A�����_�ȉ������ڂ܂Ő������ǂ߂邩�c�Ƃ�������Ƃ��Ă̌������K�v���Ƃ������Ƃ��c�B
���ۂɂ͊e��̃m�C�Y������̂�bit�������ł͌��܂�Ȃ��Ƃ��A�t�Ƀm�C�Y�̂������ŕ��ω������1LSB��菬������o�Ă���Ƃ��ׂ����b�͂��낢�날��܂����A�Ƃ�����Z�p�̘b�͐ςݏグ�Ȃ̂ŁA�ǂ����ŋȉ����Đςݏグ�Ă��܂����F�������߂�̂͗e�Ղł͂���܂���B�Ԉ�����F���Ɏ��_�͌Œ肳��A�^���͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F25233961
![]() 14�_
14�_
����Ȃ�����Ȃ������������Ă�ɂ�����Ȃ�A�ʐ^�B��ɍs���������y���ɗL�Ӌ`����Ȃ��ł����ˁB
�����ԍ��F25234180�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 13�_
13�_
�F�X�������������Ƃ���ŁA
12bit�ۑ������ł��Ȃ�����ꏏ�B
�ǂ����������14bit��12bit��I�ׂ�@���
��ׂ�@�\�I�ɗ�����Ƃ��������͉���
�ς��Ȃ��B
�����ԍ��F25234350�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
��cbr_600f����
�������������������܂������A���̋^��ł���u�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W15EV��12bit��AD�ϊ�����ꍇ�Abit������Ȃ���12EV���̃f�[�^�ɂȂ��Ă��܂��v�Ƃ��������̐����ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
>-15EV�̈Â��Ń[�����o�������ł̓_���ŁA��������͂��ɖ��邭�Ȃ����Ƃ��ɁA����ɉ������ׂ����������o�Ă��Ȃ�������Ȃ��A
>�Â��Ƃ���̏��ʂ�����Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A�Ⴆ�ő�l�𐳋K������1�Ƃ����Ƃ��A�����_�ȉ������ڂ܂Ő������ǂ߂邩�c�Ƃ�������Ƃ��Ă̌������K�v���Ƃ������Ƃ��c�B
�Â��Ƃ���̏��̎��̓Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W����Ȃ̂ŁA���̂��������Ƃ���u�i�킸���Ȗ��邳�Ɂj�������ׂ��������v�u�����_�ȉ������ڂ܂Ő������ǂ߂邩�v�́A�P�ɉ�bit�ŏo�͂���Ă��邩�i��AD�ϊ��̕���\�j�ɂ�邱�Ƃ��Ǝv���܂����ǁB
���̕����̓Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W�̉����t�߂̂��ƂŁA���̈ʒu��AD�ϊ���12bit���낤��14bit���낤���A���j�A���낤������`���낤���A�����ł���ˁB
�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W���L�������傫�Ȗ��Í����Abit�����傫�ȕ������炩�ȊK���ŕ\���ł���i���ꂪ�u��Ƃ��Ă̌������K�v�v�ł���ˁj�Ƃ��������̂��ƂŁB
���Ȃ݂ɁA���͔N����N���f�����̂����Ă���킯���Ⴀ��܂����B�R�����g����̂̓R�����g���鎞�Ԃ����鎞�����ł��B
�����ԍ��F25234624
![]() 9�_
9�_
��400kcal(80g������)����
���J�ȃO���t�ł��������肪�Ƃ��������܂��B
�����A�������D�ɗ����Ȃ��Ƃ��낪�B
>5EV�̃_�C�i�~�b�N�����W��������f�q�̏o�͂ƁA�����3bitADC�œǂ��̒l�̃O���t���Ƃ��ēY�t���Ƃ��܂��B�����f�q�̏o�́A�Ԑ���ADC�̏o�͂ɂȂ�܂��B
>����Ȃ̂ł����A���e�̓_�C�i�~�b�N�����W�̕���bit�����Ⴄ������pmp2008����̏����ԍ��F25232693�Ɠ����ɂȂ�܂��B
>�O���t������Ε�����ʂ�A����f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W�̓��AADC�̃_�C�i�~�b�N�����W���Ⴂ2EV���̏�����A�����ق�3EV�̏��3bit�ŊK��������Ă��܂��B
�܂��A�O���t�̊�_�u0�v�ɐڂ��������Ȏl�p�̓m�C�Y�����Ƃ������Ƃł���ˁB��P�x���Ń_�C�i�~�b�N�����W5EV�͈̔͊O�ł�����B
�����āA�O���t�̉E���̐��������ɂȂ镔���ƐԐ��̉E�[����v���Ă���̂ŁA�J�����Ō����A�_�C�i�~�b�N�����W�̏���Ŕ��g�r���Ȃ��M���M���I�o�ɂȂ��Ă���킯�ł��ˁB
�ŁA�O���t�ɂ́A�u�_�C�i�~�b�N�����W5EV�v�̍��̕��Ɂu������v�Ƃ����u�_�C�i�~�b�N�����W���Ⴂ2EV�v�Ƃ��������Z���ΐ��ŏ����Ă���܂��B����́u�_�C�i�~�b�N�����W5EV�v�̒��͈̔͂ł�����A�u�_�C�i�~�b�N�����W���Ⴂ2EV�v�Ƃ��������͂��������ł��B
����ɁA�O���t�����Ɂu3bitADC�v�̐����������āu0�v�������u������2EV�v�Ƃ̂��ƁB�������A�f�W�^���̊K���u0�v�́u������v�ł͂Ȃ��āA����2EV�͈̔͂��u0�v�̃��x���Ƃ������ł���ˁB�u0�v�́u������Ȃ��v�Ƃ������Ƃł͖����ł��B����ŁA0����7��8�i�K��3bit�̃f�[�^���o���オ��킯�ł��傤�B
���ǁA�O���t�̐Ԃ����́A�_�C�i�~�b�N�����W5EV�͈̔͂�3bit��AD�ϊ������8�i�K�̃f�[�^�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����ǁB���x���u0�v�����͈Â��̂Ńm�C�Y���܂܂�Ă��܂�����ǁA�܂��A���ۂ̃J�����������Ȃ��Ă��܂��B
�y�R�����g�̒����z
���͑O�̃R�����g�Łu���ꂼ��̃A�i���O�f�[�^��12bit��AD�ϊ�����̂́A���ꂼ��̃_�C�i�~�b�N�����W�S�̂�12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɂ���Ƃ������Ɓv�Ə����܂������A����́u�_�C�i�~�b�N�����W�S�́v�ł͂Ȃ��āu�Z���T�[�̏o�͑S�́v�ł����B�������܂��B
���ۂ̉摜�́A�f�W�^���摜�̈Õ��̓m�C�Y�ɖ�����Ă���Ƃ�������g�r�����̂܂܃f�W�^���摜�ɂȂ��Ă��܂�����ˁB�I�o�I�[�o�[���I�o�s�����W�Ȃ��A�Z���T�[�̃A�i���O�o�͑S�̂��f�W�^�������Ă���킯�ŁB
�ł��܂��A���̂��Ƃ́u15EV����12bit��AD�ϊ������12EV�������o�͂���Ȃ��v�Ƃ����b�ɊW�͖����Ƃ���ł͂���܂��B
�����ԍ��F25234630
![]() 9�_
9�_
��pmp2008����
>��ʑ̖̂��Í��iEV�l�j���Z���T�[���ێ��ł��閾�Í��i�_�C�i�~�b�N�����W�AEV�l�j���傫���ꍇ�A�ʐ^�ɂ���Ɣ�ʑ̖̂��Í��̈ꕔ�͎����܂��B
�i�����ԍ��F24245765�w�Z���T�[��RAW�̃_�C�i�~�b�N�����W�x�X���b�h�@pmp2008����j
>�Z���T�[���ێ��ł��閾�Í��i�_�C�i�~�b�N�����W�AEV�l�j�����ARAW�f�[�^��bit���i�K���j���傫���ꍇ�ARAW�f�[�^�ɂ���ƃZ���T�[���ێ��ł��閾�Í��̈ꕔ�͎����܂��B
�i�����ԍ��F24245770�E�����ԍ��F24245838�w�Z���T�[��RAW�̃_�C�i�~�b�N�����W�x�X���b�h�@pmp2008����j
>R6 mk2�͓d�q�V���b�^�[�ɂ����12bit�ɂȂ��Ă��܂�
>��f�̑f�q���̂�DR�͍L�����ǂݏo��bit���������邱�Ƃ�DR���ቺ���Ă��܂�
�i�����ԍ��F25228267 ��o������j
>�r�b�g��������Ȃ��Ə��̂Ă���DR��������܂�
�i�����ԍ��F25228858 ��o������j
>�A�i���O�M����DR�ɑ��� ����S�Ă��܂ޏ[���ȃr�b�g���� AD�ϊ�����ǂݏo���� ������RAW�t�@�C���Ƃ��ď����o�����Ƃ����v��"���ʂ�"�����
>10EV��12EV�ɑ肵��8bit�̗���o������i�����j����ĂȂ��r�b�g���ł�DR�ɉe���^�����Ⴂ�܂�
�i�����ԍ��F25230025 ��o������j
>12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɁA15EV�͓���Ȃ��ł��B
�i�����ԍ��F25230904�@pmp2008����j
>DR��1stop�ቺ���Ă��܂��܂��� �����͖��炩�ł��� AD�ϊ��̃r�b�g��������Ă��Ȃ�1V�����́A�M�����̂ĂĂ��܂�������ł�
�i�����ԍ��F25231024�@��o������j
>12bit�̕���\�̏o�͂ŕ\����̂́A0EV����12EV�܂łł��B
�i�����ԍ��F25231544�@pmp2008����j
�E�E�E�Ƃ����悤�Ȃ��ӌ�������܂����B
��L�R�����g��ǂ݁A�D�ɗ����Ȃ��Ƃ��낪�������̂ŁA���L�̂悤�Ɏ��₵�܂����B
�w12EV�̕���12bit�i4096�K���j�ɂł���̂ɁA�����蕝�̍L��15EV���Ȃ�12bit�i4096�K���j�ɂł��Ȃ��̂ł����H�x
���ԐM���肪�Ƃ��������܂����B
>�ł��܂�����ǁA
15EV�͈̔͂�12bit��AD�ϊ��ł���̂ł��ˁH
>���̌��ʁA�P�x��15EV���������f�[�^�A���̒�P�x����0EV����2EV�͑S�Ď����A�o�͂����̂́A3EV����15EV�̋P�x��12EV�̃f�[�^�ł��B
�o�͂����̂�12EV���Ƃ���Ǝ�����̂͒�P�x��3EV���ɂȂ�Ǝv���܂����A����ς��̂Ă��Ă��܂��̂ł����H�@�Ƃ������Ƃ́A����ς�ł��Ȃ��H�@��o������ ���u�r�b�g������Ȃ�����ł��Ȃ��v�u�r�b�g�ɓ���Ȃ��f�[�^�͐�̂Ă���v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂������B�B�B
>�P�x��15EV���錳�f�[�^���A����Ȃ��悤�ɁA�f�W�^���ɕϊ�����ɂ́A15�r�b�g�ȏ��AD�ϊ�����K�v������܂��B
�O�q�̂悤�ɁA12�r�b�gAD�ϊ��ł́A�f�[�^�������܂��B
12bit��15bit�ŁA���A�i���O�f�[�^�̃f�W�^���������͈͂��ς��Ƃ����̂̓w������Ȃ��ł����H
�ǂ�������f�[�^�S�̂��f�W�^����������̂��Ǝv���܂����B���ہA�ǂ�ȃJ�������A�Õ��m�C�Y�┒�g�r�����̂܂܋L�^����Ă��܂���ˁB
�����āA�w�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�x�Ƃ������̂ɂ��āB
>�A�i���O����f�W�^���̕ϊ��́A�f�[�^������L�����Ŋۂ߂�A�悤�Ȃ��́A�Ƃ����C���[�W
>�u�V�O�i�����m�C�Y�ɖ������Ƃ���̓d�ׂ̒l�v�Ɓu�O�a����Ƃ���̓d�ׂ̒l�v���ꂼ�������L�����Ŋۂ߂āA�������ŏ��l�A�ő�l�Ƃ��āA�_�C�i�~�b�N�����W���ēx�v�Z����
�_�C�i�~�b�N�����W�́A�A�������f�[�^�̒��ŗL���Ɏg���镔���ł���ˁB���̊O���ɂ͎g���Ȃ��Ƃ��낪�Ȃ����Ă���킯�ł��B�ʐ^���ƈÕ��m�C�Y�Ƃ��A�O�a�̔��g�r�ł��ˁB
�܂�A�_�C�i�~�b�N�����W�́A�A�������A�i���O�o�͂̒��́u�@�\�I�ȁi�g����j�͈́i��range�j�v�Ƃ��������ł��B
�f�W�^���������摜�f�[�^���Ƃ���ƁA�Ⴆ�A8bit��256�K���i0~255�j�A12bit��4096�K���i0~4095�j�ō��Ɣ��̊Ԃ̖��邳��\������킯�ł���ˁB�����ŁA�f�W�^���f�[�^�́u0����ő�l�܂Łv�̑S�Ă��摜���Ɏg���܂��B�ł�����A�f�W�^���ł͑S�̂̒�����g����͈͂������u�_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ����T�O�͂�����Ȃ��Ǝv���̂ł��B
�����āA�f�W�^������bit���������ł��A0�͉摜�̈�ԍ����Ƃ���A�ő�l�͈�Ԕ����Ƃ�����Ӗ����邾���ł��B����ŁA�摜�̎��ۂ̍����E�����͕\���}�̂Ɉˑ��ł��B
������bit���̈Ⴂ�́A0�̍��ƍő�l�̔��̊Ԃ̑e�����炩���̈Ⴂ�Ƃ��Č�����킯�ŁAbit�����傫�ȕ�����荕���A���邢�͂�蔒���\���ł���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł���ˁB
�܂�A�f�W�^���f�[�^�͑S�̂��g���Abit���Ɋւ�炸�Œ�l�ƍō��l�̎����Ƃ���͓����A�Ƃ����Ƃ��납��A�u�f�W�^���f�[�^�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�Ƃ������t�͂��������Ǝv���̂ł���B
�����ԍ��F25234646
![]() 10�_
10�_
��400kcal(80g������)����
���݂܂���A�����ł��B
��j���ǁA�O���t�̐Ԃ����́A�_�C�i�~�b�N�����W5EV�͈̔͂�3bit��AD�ϊ������8�i�K�̃f�[�^�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����ǁB
���j���ǁA�O���t�̐Ԃ����́A�A�i���O�f�[�^�S�̂�3bit��AD�ϊ������8�i�K�̃f�[�^�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂����ǁB
�����ԍ��F25234716
![]() 7�_
7�_
���o�͂����̂�12EV���Ƃ���Ǝ�����̂͒�P�x��3EV���ɂȂ�Ǝv���܂����A����ς��̂Ă��Ă��܂��̂ł����H�@
��̂Ă��܂��B
��12bit��15bit�ŁA���A�i���O�f�[�^�̃f�W�^���������͈͂��ς��Ƃ����̂̓w������Ȃ��ł����H
�u���A�i���O�f�[�^�̃f�W�^���������͈́v�́AAD�ϊ��̓��͂ł��̂ŁA12bit��15bit�ŕς��Ȃ��ł��B
���ǂ�������f�[�^�S�̂��f�W�^����������̂��Ǝv���܂����B
�����ł��A�S�̂��f�W�^�������܂��B���̍ۂɃf�[�^�������邱�Ƃ�����܂��B
�����ہA�ǂ�ȃJ�������A�Õ��m�C�Y�┒�g�r�����̂܂܋L�^����Ă��܂���ˁB
��7C�ŎB�e�������ł����A
�P�x���̑傫����ʑ̂�ISO 100�œK���I�o�ŎB�e���āARAW�����ŃV���h�E�̘I�o��+3���炢�グ�āA���{�Ō���ƃm�C�Y�������܂��B
�ł��A�m�C�Y�ɖ�����Ă͂��܂���̂ŁA�����͌��̃A�i���O�̃_�C�i�~�b�N�����W�̉����ł͂Ȃ��ł��B
�܂�A����ɋP�x�̒Ⴂ�����͐�̂Ă��Ă��āA�摜�f�[�^�ɂ͓����Ă��Ȃ��A�Ƃ����\��������܂��B
�����ԍ��F25234757
![]() 9�_
9�_
��pmp2008����
>��̂Ă��܂��B
�@�@��
�����R�����g�Ɩ������Ă��܂��H
�@�@��
>�u���A�i���O�f�[�^�̃f�W�^���������͈́v�́AAD�ϊ��̓��͂ł��̂ŁA12bit��15bit�ŕς��Ȃ��ł��B
>�����ł��A�S�̂��f�W�^�������܂��B
���L�̂悤�Ȃ������ł����B
�w�Z���T�[���ێ��ł��閾�Í��i�_�C�i�~�b�N�����W�AEV�l�j�����ARAW�f�[�^��bit���i�K���j���傫���ꍇ�ARAW�f�[�^�ɂ���ƃZ���T�[���ێ��ł��閾�Í��̈ꕔ�͎����܂��B�x
�w�r�b�g��������Ȃ��Ə��̂Ă���DR��������܂��x
�w12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɁA15EV�͓���Ȃ��ł��B�x
�w12bit�̕���\�̏o�͂ŕ\����̂́A0EV����12EV�܂łł��B�x
�w�P�x��15EV���������f�[�^�A���̒�P�x����0EV����2EV�͑S�Ď����A�o�͂����̂́A3EV����15EV�̋P�x��12EV�̃f�[�^�ł��B�x
�u������v�u��̂Ă���v�u����Ȃ��v�u�o�͂���Ȃ��v
����́u�S�̂��f�W�^�������܂��v�Ɠ��e�������܂��ǁB�B�B
>�P�x���̑傫����ʑ̂�ISO 100�œK���I�o�ŎB�e���āARAW�����ŃV���h�E�̘I�o��+3���炢�グ�āA���{�Ō���ƃm�C�Y�������܂��B
�ł��A�m�C�Y�ɖ�����Ă͂��܂���̂ŁA�����͌��̃A�i���O�̃_�C�i�~�b�N�����W�̉����ł͂Ȃ��ł��B
�ǂ̃J�����������悤�ɂȂ�܂���ˁB
�A�i���O�M���̑S�̂��f�W�^�������Ă���Ǝv���̂ŁB
>�܂�A����ɋP�x�̒Ⴂ�����͐�̂Ă��Ă��āA�摜�f�[�^�ɂ͓����Ă��Ȃ��A�Ƃ����\��������܂��B
�u�A�i���O�M���̑S�̂��f�W�^�������܂��v�ƒ��O�R�����g�ɏ����Ă�������Ⴂ�܂��B
�u�S�́v�ł�����u��̂Ă͖����v�Ƃ����ӂ��ɓǂ߂܂����B�B�B
�����ԍ��F25235201
![]() 10�_
10�_
��pmp2008����
������
�ЂƂ���ǂ��ł����H
������ɋP�x�̒Ⴂ�����͐�̂Ă��Ă��āA�摜�f�[�^�ɂ͓����Ă��Ȃ��A�Ƃ����\��������܂��B
����́A�P�x�̍������������l�ł����H
���l�ł����12bit�̕\���ɍ��_��������ł����ǁB
�����ԍ��F25235210�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
������Ȃ�����Ȃ������������Ă�ɂ�����Ȃ�A�ʐ^�B��ɍs���������y���ɗL�Ӌ`����Ȃ��ł����ˁB
�͂��A����͑S�������ă~�^���V����(�H)�̂��������ʂ�ł��B
�����܂���A�ʐ^�̊����Ȃǂ̘b�Ƃ͂��悻�W�Ȃ��b�ł����A��������������Ă�����X���u���{����Ԉ���Ă���v�Ă�肳�ꂽ�̂�������ƃJ�`���Ɨ��Ă��܂��܂��āc�B
pmp2008����
Big�Ȃ����b�Ƃ͎v���܂����A���߂������ǂ��̂ł͂Ȃ����Ɓc�B�O�q�̒ʂ�Ԉ����������ςݏグ�Ă��܂����l�́A�ӎ��������ɌŒ����Ă��܂��āA�ǂ�Ȑ��������ɓ����Ă����Ȃ��̂ł��B�ǂ�قnj@�艺���Ē��J�ɏ������Ƃ���ŁA�����ƔF������邱�Ƃ͂Ȃ����߁A
�u���̋^��ɓ������Ȃ��v���u���������(���̔F���ʂ��)��������͂��v���u�������Ȃ��̂͐������Ȃ�����v
�Ƃ����_�@�Łu�^��ɓ������Ȃ��l�v�̃��b�e����\���ăX�g���X�����܂邾���ł��B���t�K�����J�Ȃ����ŁA�ԓx�̖\�͂�U����Ă��邱�ƂɋC�Â��Ȃ��̂ł��B
���Ă��āA���{�l�͂�����������Ƃ��āA�������Ⴂ������Ă��鑼�̕��̂��߂ɂ���������ƕ⑫���B
����O���[�`���[�g�������Ɖ��O�̗����ɒu���āA1�J�b�g�ł��̗������ǂꂾ���B��Ă��邩�H�Ƃ����P�[�X�B
�m�C�Y�͔��ɏ��Ȃ��āAA/D��10bit��12bit�̏ꍇ�̍����o�₷�������ł̊ȈՓI�ȃC���[�W�ł��B
bit���������Ƃ����̂͒P�ɊK�������炩�Ȃ����ł͂Ȃ��u�����グ�Č��������Ƃ��ɈÕ��̃G�b�W(�G��)�������邩�H�v�Ƃ������ɂȂ��Č���܂��B�m�C�Y�͒Ⴂ�̂�bit��������Ȃ��Ƃ����ꍇ�A�R���g���X�g�̒Ⴂ�G���������Ȃ��Ȃ��ł��B
����ɂ��Ă����Ⴂ�̓��e���������Ȃ�āATranquility�����hirappa����̓z���g�ɒ���������ł��ˁB
�����ԍ��F25235231
![]() 12�_
12�_
��cbr_600f����
3�r�b�g���Y��ɊK���\���o���Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F25235277
![]() 2�_
2�_
��cbr_600f����
���͂悤�������܂��B
�v����ɑ�G�c�Ɍ����ƁA
�f�[�^�͑S�ċL�^����邯�ǁA
0EV����2EV��3EV�ɕϊ�����Ă��܂�����
(�ϊ������0EV����2EV�͕\�����ꂸ��̂Ă��Ă��鎖�Ɠ���)
�K���������Ȃ��Ă��܂��Ƃ������߂ł�낵���ł����ˁH
����̓n�C���C�g�������l�ł���ƁB
���̉��߂������Ă���Ƃ���ƁA��i�B��ł̃n�C���C�g�̊K�����o�Ȃ��Ȃ��ɍ��v�����ł���ˁB
JPEG��8Bit�K��������`�ł��邪�̂ɁA
255�̊Ԋu�͓��Ԋu�ł͂Ȃ��Ƃ������ł����ˁH
�����ԍ��F25235380�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�͂́A�X����a�������̂��ŁA�`�^�c�ϊ��A���̗ʎq���r�b�g���̏��X���w�e�L�X�g�x�[�X�x�ōu�ߐ����ꂽ�Ƃ���ŁA����Ȃ��F�f�l�̐��������瑼�l�l������d�q��H��W�b�N�̑f�l���e�Ղɗ����ł���Ȃ��B
�c�Ǝv���܂����A���������������낤���_���_��������ẮB�܂������܂ߊF����ɂԂ��Q���ł��傤������͂Ȃ����B
���X�̍u�߂͂b�p�o�ł��Z�p�]�_�Ђ�琽���������炩��o�ł���Ă���d�q�H�w�̊�b�e�L�X�g���A�A�i���O�f�o�C�Z�Y�ЁA�}�C�N���`�b�v�Ђ��̃f�o�C�X�����疳���ŏo����Ă���h�L�������g�ނ�ǂ���A����Ȃ�ɂ͗����ł��锤�ł��B�c�d�q��H�ɋ���������A�ł����B
���������f�W�J����EV�l��_�C�i�~�b�N�����W�ɒ[�����w�r�b�g�x�̂��b�����A�����܂ŕ��G����ɂȂ�̂́A�Ⴆ��Ȃ�A
�w�I�[�g�}�Ԃɏ��ɂ�����A�G���W������̂��߂̂b�o�t���_���w�ɂ�Ȃ�܂��x
�������ɑs��ȐS�z���Ă���悤�Ȃ��̂ŁA����Ȃ���
�w���S�^�]��S�����Ƃ��܂��傤�A�g���u�b����i�`�e�̂����b�ɂȂ�܂��傤�x
�ł������B
�����ԍ��F25235382
![]() 3�_
3�_
��cbr_600f����
>A/D��10bit��12bit�̏ꍇ�̍�
���������b�͂��Ă��Ȃ��ł��B
�w12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɁA15EV�͓���Ȃ��ł��B�x
����͂��������Ȃ��ł����H�Ƃ����b�ł��B
�����ԍ��F25235483
![]() 6�_
6�_
��Tranquility����
�������R�����g�Ɩ������Ă��܂��H
���̕��͂ɖ����͂Ȃ��ł����A�B�����͂���܂��B���̞B�����䂦�ɁA�ǂݎ肪�A���̕��͂̈Ӗ������Ⴆ�邱�Ƃ͂��肦�܂��B
Tranquility����̍l���Ⴂ�̍��{�����́A���l0�i�[���j�ߕӂł̌���ɂ���A�Ɛ������Ă��܂��B
�����ŁA�m�F�ł����A
EV0 ���Ӗ�����̂́u0�v�ł͂Ȃ��āu1�v�ł��B����͔F������Ă���ł��傤���H
���ǂ̃J�����������悤�ɂȂ�܂���ˁB
�Ȃ�Ȃ��ł��B
���A�i���O�M���̑S�̂��f�W�^�������Ă���Ǝv���̂ŁB
�A�i���O�M���̑S�̂��f�W�^�������Ă��A�f�W�^�����̎d���ŁA���ʂ��قȂ�܂��B
�����ԍ��F25235496
![]() 5�_
5�_
������͂�����
�����Ƃ�����q�����Ă��܂������@�����������������ɊS�̖���
�l�ɑ��Ă����珑���Ă������Ƃ������̂ł��傤�B
CQ�o�ŎЂ͓����A�}�`���A�����̎G���Ђł�����
���͂����Ɛ��삪�L�����e�������Ă���悤�Ɏv���܂��B
���Ȃ莋�_�Ƃ��Č����Ń��[�J�[���ɑ���u�x�̏��Ȃ�
���̂������@AV�ƊE�̜u�x�̍����̒��Ő����܂̂悤�ł��B
���[�U�[�̎��_�Ō����J���Ɓ@�U�������̂ƈႢ�܂��B
�����ŗʎq���ɂ��덷����ɂ��Ă���l�����܂���
���܂�1��f�ʐς̑傫���Ȃ����i�ł͂���Ȃ��Ƃ��
���̖ʐς��炭��_�C�i�~�b�N�����W�⊴�x�̖��͂ǂ�����
�̂��Ƃ��������C�ɂȂ�܂��B
�������r�f�I�J�����͂��̖��͂ƂĂ��傫���AA/D�ϊ���
bit�������ɂȂ鎖�͂قڂ���܂���@8bit�őΐ��L�^��
����Ɗ����܂����@
������q�����Ă��Ă�����v���o���܂���
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17074484/
�����ԍ��F25235498
![]() 3�_
3�_
���A�}�`���A�J�����}������
�����₢�������܂������A������ƕ�����Ȃ��ł��B
��WIND2����
�����₢�������܂������A������ƕ�����Ȃ��ł��B
��cbr_600f����
��Big�Ȃ����b�Ƃ͎v���܂����A�E�E�E�C�Â��Ȃ��̂ł��B
�Ȃ�قǁA�s�����͂ł��ˁB
�����ԍ��F25235502
![]() 3�_
3�_
�A�b�v�摜�́A�摜�����E�f���@��̉�Ёu�t�H�g�����v�̉�����B
�w�f�W�^���J�����̊K���ƃ_�C�i�~�b�N�����W�x
https://www.photron.co.jp/support/imaging/knowledge/n02.html
�_�C�i�~�b�N�����W���L��12bit�Z���T�[�́A�Â������Ɩ��邢�������ɎB���ł��܂����A�L���͈͂�4,096�K���ŕ\������̂�1�K�����J�o�[����͈͂��L���Ȃ�܂��B
�_�C�i�~�b�N�����W������12bit�Z���T�[�́A�Â������Ɩ��邢�������ɎB���ł��܂��A�����͈͂�4,096�K���ŕ\������̂�1�K�����J�o�[����͈͂������i�ׂ����j�Ȃ邽�߁A�������ȕω��𑨂��邱�Ƃ��ł���Ƃ����܂��B
�����ԍ��F25235562
![]() 6�_
6�_
��pmp2008����
�u12bit�Z���T�[���Č��ł��閾�Í���12EV�܂Łv
�u15EV�̖��Í����Č�����ɂ�15bit�ȏオ�K�v�v
���ꂪ�����Ȃ�A�f�W�^���J�����ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ȏ��Ȃ͂��B
�������A���̂悤�ȋL�q�������M���ł���L���i��Ƃ⌤���@�ւȂǂ̉���j�͌�����܂���B
�ǂ��ł��̂悤�ȏ���m�����̂ł��傤���H
�����ԍ��F25235574
![]() 6�_
6�_
�����̂悤�ȋL�q�������M���ł���L���i��Ƃ⌤���@�ւȂǂ̉���j�͌�����܂���B
��
�u�l�̒����\�͂̌��E���x�ŁA
�y�������Ƃ̏ؖ��z�͏o���Ȃ��B�v
�����ԍ��F25235584�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��WIND2����
���邢���͗L�������������̂ŁARAW�f�[�^��10bit�ł����Ă��Â����̂悤�Ȑ��x�s���͋N���Ȃ��ł��B
���������I�o�ŎB���Ă���̂ɒ������ɊK�����R�����Ɗ�������A����͔���т����߂ɋN�����Ă��邩�A�W���g�[���J�[�u�̈Ⴂ��������܂���B
CIPA����߂銴�x�̋K�肪����̂ŁA�����I�o�ŎB��ǂ��̐��i�ł����ԋP�x�͓������炢�Ɏʂ�̂ł����A�s�[�N���ǂ��܂Ŕ���Ɏʂ邩�́A���i���ƂɈႢ�܂��B
�������Z���T�[�̃J�����͖���߂ɘI��������SN��D�悵�A�傫�ȃZ���T�[�̃J������RAW�f�[�^��ł͈Â߂Ɏʂ��A�����Œ��ԋP�x�����邭�Ȃ�悤�ȃg�[���J�[�u���g�����Ƃ������ł��B���̂��߃n�C���C�g���S��Ƃ��A�n�C���C�g�D��Ńg�[���J�[�u��ݒ肷��ΏƖ�����̊G�����悭������A�Ƃ������Ƃ͂���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25235596�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
�����肪�Ƃ��A���E����
>�u�l�̒����\�͂̌��E���x�ŁA�y�������Ƃ̏ؖ��z�͏o���Ȃ��B�v
��������ł���B����ŁH
pmp2008���� �������u�ԈႢ���v�Ƃ��������u�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ɖ摜��bit���͊W�Ȃ��v�Ƃ����L�q�͂�����������̂ł����B
�����ԍ��F25235608
![]() 7�_
7�_
�����܂ł��܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B
�E�r�b�g���͊K����\�����̂ł���B
�E�r�b�g����傫�����Ă��_�C�i�~�b�N�����W�͍L���Ȃ�Ȃ��B
�E�_�C�i�~�b�N�����W�̍L���ɍ��킹�����炩�ȊK����ׂɃr�b�g����傫������B
��APS-C��RAW�T�C�Y��14bit�Ȃ̂ɁAOM-1��12bit�Ȃ̂ł����H
���Z���T�[���\���オ���Ă��Ă���Ȃ�14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B
RAW��12bit������AADC��12bit�Ƃ͌���܂���B
�Z�p�͐ςݏd�˂���Ȃ̂ł͂Ȃ��A��������p�ł��邱�Ƃ���ł��B
�����ԍ��F25235616
![]() 2�_
2�_
��cbr_600f����
�����ł��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25235619�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�V��ɂȂ�ȁA�悭�����錾�t�ł��B
�V��͖ڐ�̋Z�p�Ɏ�����A���������ɂ���Z�p�ɍl�����y�Ȃ��Ȃ�B
�������A����������̂́A
�V��ɂȂ�A�����ēV�����B
�V��ɂ������Ă��Ȃ��V�炳���cbr_600f����ł��傤���B
�����Ɖ��p�͂�g�ɂ��܂��傤�B
�����ԍ��F25235632
![]() 2�_
2�_
2023/04/25 13:01�i1�N�ȏ�O�j
�b���Q�ɕ�����Ă��܂��ˁB
��14EV��12bit�ŕۑ��������̂Q�̎d�l
�@�Õ��QEV��̂ĕ���
�@�E�Õ���2EV���āA12EV���A12bit�ŕۑ����Ă���B
�@�E����������̓��[�J�[�i�\�j�[�j�Ɋm�F�����킯�ł͂Ȃ��B�i�������j
�@������ł�낵���ł����B���������������@��pmp2008����
�A14EV�̑S�̂�12bit�ŕۑ��������
�@�E�~����r
�@�@�u14EV��ۑ�����ہv�́A
�@�@14bit���~���̕����Č��x�������@�́@12bit���~���̕����Č��x���Ⴂ
�@�E�������N���ǂ��炪�ǂ��Ƃ������Ƃ��͏����Ă��Ȃ��i��Tranquility����͏o���邩�ǂ������Ă���j
�@�E���̕����͂ǂ̃��[�J�[���̗p���Ă��邩�͕s���B
�@�E�������}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɂ͌���W�������B
�@������ł�낵���ł����B���������������@��cbr_600f����
-----------------------------------------
�@�̐�̂ĕ����́A�t���T�C�Y�Ƃ`�o�r�|�b�ōs���Ă�������ł��B
�A�̑S�̕ۑ������ł́A14EV��12bit�ŕۑ�������~���͍r���Ȃ�͓̂�����O�ł����A
���������u12EV��12bit�ŕۑ��v����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ƃ͊W����܂���B
�@���A���A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ƃ͌���W����܂���B
���Ⴂ����A���̎�̘b�������o���Ȃ��A���`���O���Ă����̂ŁA
�ʃX���b�h�ł���Ă��炦�܂����B
-----------------------------------------
���ƁA
�����o�Ȃ��Ƃ͌����܂��A
�@��̂ā@�ł���A���`���Ԓ����~���͕ς��܂���B
�Õ����ǂ������グ���ł����A�Ƃ����b�ł��B
�@��̂ā@�A�S�̂����k�@�ǂ���ɂ��Ă��A
���������o�͔}�̂��ō�10bit�ł����Ȃ��ł����A
��������JPEG���̂Wbit�ł��B
�J��Ԃ��܂����A
�����o�Ȃ��Ƃ͌����܂��A
�u���[�U�[���������܂ŋC�ɂ���b�ł͂���܂���v
�i���̎�̘b���D���Ȑl����萔����Ƃ͗������Ă��܂����ǂˁj
�b�͑��̂Ƃ��Č����Ȃ��ƁB
����������f�����オ��߂��āA�ǂ������Y���t���T�C�Y�ō�낤�Ƃ����
�����I�ȃV�����m�ɂȂ�Ȃ���������āA
������̕�����肾�Ǝv��Ȃ��̂��낤��
�����ԍ��F25235640
![]() 3�_
3�_
��Tranquility����
�����ԍ��F25235562 �͐������ł��B�ł��A������A���̘b��ƍ����čl����ƁA�����炭Tranquility����́A�܂��܂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�����͍l���Ⴂ���₷���Ƃ���Ȃ̂ł��B
�����ꂪ�����Ȃ�A�f�W�^���J�����ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ȏ��Ȃ͂��B
�����ł͂Ȃ��āA���ƂɂƂ��Ă͎��ɑ���Ȃ����A�Ǝv���܂��B
���ǂ��ł��̂悤�ȏ���m�����̂ł��傤���H
���̍l���ł����āA���肵�����ł͂Ȃ��ł��B
�����{�X�����������݂ł��Ȃ��Ȃ�܂����A���̘b��ɂ�������������������̂ł�����A
��������m�Ő\���グ�܂��ƁA
����́A���̂悤�ɁA�f���ł��Ƃ肷��O�ɁA
�܂��́AAD�ϊ��̓��发����������ǂ܂�邱�Ƃ������߂��܂��B
�����ԍ��F25235670
![]() 9�_
9�_
Tranquility����
>�u15EV�̖��Í����Č�����ɂ�15bit�ȏオ�K�v�v
�̓�����
https://article.photo-cafeteria.com/EVDB.html �́u5. EV�l����f�V�x���v
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl1962/45/4/45_4_335/_pdf �́u3�D�ʎq���v
�ɂ���܂��B�@������ǂ߂A���X�̋^�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
>�u�Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ɖ摜��bit���͊W�Ȃ��v
�ϊ����x(�i��)���ǂ����邩�œ����͕ς��Ǝv���܂��B
�����A�uEV15��15bit�ϊ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������[���͖����ȏ�AEV15��12bit�ϊ��́u�ł��邪�A�x�X�g�ł͂Ȃ��v�������ł��傤�B
�����ԍ��F25235672
![]() 4�_
4�_
�ǂ����݂Ȃ���
��Tranquility����
25235562
�킩��܂����I
������̐}�A�Ԉ���Ă�ƌ����܂���
���Ⴂ�|�C���g�͂����ł���
���̃X���ł�AD�ϊ��̘b�����Ă��邽�ߐ��`�̕ϊ��ɂȂ�܂� ���_�͑����Ȃ���
���̐}�́Alog�O���t�Ɛ^���O���t���������Ă��邽�߂��������Ȑ}�ɂȂ��Ă܂���
�_�C�i�~�b�N�����W�̓��`�`���[�h�Ɠ����ƍl���� ���`�`���[�h���C���[�W����Ƃ��ɂ�����悤�ɃR���g���X�g�̕ω�������`�̕ϊ����C���[�W���Ă��܂��Ă���̂ł�
�Ȃ̂Ō��_�Y���ĂĂ����������v��Ȃ��̂ł�
������O���ɂ��������ǂ��̃X����̕�����ǂݕԂ��Ă݂Ă͂������ł��傤��
�����ԍ��F25235707�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�܁A���͂Ƃ�����A
14Bit���K�v�Ȑl�A12Bit�ŕs���Ȑl��14Bit�@���g���������A
12Bit�Ŗ����o����l��12Bit�@���g��������Ȃ��ł����ˁH
�����ԍ��F25235709�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���A�}�`���A�J�����}������
>�@�Õ��QEV��̂ĕ���
>�E�Õ���2EV���āA12EV���A12bit�ŕۑ����Ă���B
>�@�̐�̂ĕ����́A�t���T�C�Y�Ƃ`�o�r�|�b�ōs���Ă�������ł��B
���ۂɍs���Ă��邩�͕ʂɂ��āA�������u�m�C�Y�������Õ��������h��Ԃ��v�Ƃ�������������Ă���̂ł���A���̂悤�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�������A�u15bit���Ɛ�̂Ă�K�v���Ȃ��A12bit���Ɛ�̂Ă���v�Ƃ��� pmp2008���� �̂��l���̐����ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�I���W�i���̌��f�[�^�Ɋ܂܂��m�C�Y��AD�ϊ��̑O���炠����̂ŁAAD�ϊ���bit���ŕς�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤����B
��Tech One����
�u15EV�̖��Í����Č�����ɂ�15bit�ȏオ�K�v�v
���ꂾ�����ƕ��͂��B���ł������B
�u�Z���T�[�̎��_�C�i�~�b�N�����W15EV�̖��Í���]�����ƂȂ��Č�����ɂ�15bit�ȏ��AD�ϊ����K�v�ŁA12bit�̕ϊ����ƃ_�C�i�~�b�N�����W����3EV������̂Ă���̂�12EV�̖��Í������Č��ł��Ȃ��v�Ƃ��� pmp2008���� ��̂��咣�̂��Ƃł��B
���́A���̂��咣�ɋ^�₪����܂��B
>������ǂ߂A���X�̋^�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��肪�Ƃ��������܂��B
�ǂ݂܂������A��L���咣�𗠕t������e�͂���܂���ł����B
>�uEV15��15bit�ϊ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������[���͖����ȏ�AEV15��12bit�ϊ��́u�ł��邪�A�x�X�g�ł͂Ȃ��v�������ł��傤�B
�u12bit���15bit�̕������Í��̍Č������ߍׂ����A�K�������炩�ɂł���̂ŁA15bit�̕����x�^�[�ł���v�Ƃ������Ƃł���Γ��ӂł��B
�����ԍ��F25235725
![]() 8�_
8�_
��pmp2008����
>���̍l���ł����āA���肵�����ł͂Ȃ��ł��B
�����ł����B
���咣�̗��t���ƂȂ���͂���̂ł����H
>�܂��́AAD�ϊ��̓��发����������ǂ܂�邱�Ƃ������߂��܂��B
�����g�ł͂ǂ�Ȗ{�����ǂ݂ɂȂ��āA���咣�̂悤�ȍl���Ɏ������̂ł��傤���H
����o������
>������O���ɂ��������ǂ��̃X����̕�����ǂݕԂ��Ă݂Ă͂������ł��傤��
���x���ǂݕԂ��Ă��܂����A���咣���D�ɗ����܂���B
�R�����g�ŋ^��Ɏv���Ƃ���͂����������܂������A���ꂼ��ɕԓ��͖����A�u�ォ��ǂݕԂ��v�����ł́B�B�B
>���̐}�́Alog�O���t�Ɛ^���O���t���������Ă��邽�߂��������Ȑ}�ɂȂ��Ă܂���
>���_�Y���ĂĂ����������v��Ȃ��̂ł�
�A�b�v�����̂͊T�O�}�ł��ˁB
�����_�C�i�~�b�N�����W�̃J������12bit�A�L���_�C�i�~�b�N�����W�̃J������8bit���Ꭶ����Ă��܂��B
��o������ �� pmp2008���� �̂��咣�ł́A���̂悤�Ȃ��Ƃ͕s�\�ɂȂ�͂��ł���ˁB
�u���_�𑵂����������}�v���Ƃǂ��Ȃ�܂����H�@�������}�����������������܂��B
�����ԍ��F25235753
![]() 7�_
7�_
��Tranquility����
����o������ �� pmp2008���� �̂��咣�ł́A
�����̂悤�Ȃ��Ƃ͕s�\�ɂȂ�͂��ł���ˁB
�����ł� AD �ϊ��ł���͕s�\�ł�
�o����͂��ƍl�����Ă�����͂��̑z��̉������ɔ���`�̕ϊ��������Ă��܂��Ă܂� ������
���A��0 ������1�ƕ\���� ������1bit�̓�l�摜��15EV�̃_�C�i�~�b�N�����W��\������A�Ƃ����咣�Ɠ����ł���
���u���_�𑵂����������}�v���Ƃǂ��Ȃ�܂����H�@
���������}�����������������܂��B
�����ł��ː}�Ŏ������������̂��Ɠ`�����邩��
�����ӂ�ɂ�
�����ԍ��F25235775�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�߂���ďp���ɂ����Ă��܂��Ă���悤�ȁE�E�E(^^;
�����ԍ��F25235776�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����o������
>�����ł� AD �ϊ��ł���͕s�\�ł�
�u�����_�C�i�~�b�N�����W�̃J������12bit�A�L���_�C�i�~�b�N�����W�̃J������8bit��AD�ϊ��͕s�\�v�Ƃ������ӌ��ł��ˁB
���̉�Ёi������Ѓt�H�g�����j�͕s�\�Ȃ��Ƃi�̐����Ɏg���Ă���ƁB
>���A��0 ������1�ƕ\���� ������1bit�̓�l�摜��15EV�̃_�C�i�~�b�N�����W��\������
�_�C�i�~�b�N�����W�Ȃ�̊K����\�����邩�ǂ����Ƃ����b�͂��Ă��܂���B
��o������ �̂��ӌ��ɉ����āuAD�ϊ����ł���i�\�j���A�ł��Ȃ��i�s�\�j���v�Ƃ����b�ł��B
15EV���̃O���f�[�V������1bit�ŕϊ������2�K���ɂȂ�܂���ˁB2bit�Ȃ�4�K���A3bit�Ȃ�8�K���ɁB��������O���f�[�V�����̏�[�≺�[���̂Ă邱�Ɩ����B����A�Ȃ��ł��Ȃ��̂ł����H
�����ԍ��F25235802
![]() 7�_
7�_
2023/04/25 17:31�i1�N�ȏ�O�j
��Tranquility����
�܂��A�N��
�@���ۂ̂Ƃ���͒m��Ȃ�
���瓚�����Ȃ��̂ł���B
�Z���T�[���[�J�[���炵����A
14EV��12bit�Ɉ��k�I�Ȃ��Ƃ܂ł��ďo�͂���̂�
�@�P�ɗv�]�Ƃ��Ė���
������Ȃ����������m��܂���B
�܂�A
�A�ʑ��x���グ�邽�߂�12bit�o�͂������J�������[�J�[�ɂƂ��āA
�@���k�I�ȓ�������܂��v�]�͖���
������Z���T�[���[�J�[���@�\�Ƃ��ĕt���Ȃ�
�Ƃ����̂�������܂���ˁB
���[�J�[�W�҂ł��Ȃ����[�U�[��
���ۂ̂��Ƃ���͂�������܂���B
���[�U�[��A/D�ϊ��̖{��ǂޕK�v�Ȃ�Ă���܂���ˁB
�����������������l�́A�܂�
�ʐ^�̖{��ǂ�ŕ����ׂ��ł��B
A/D�ϊ��̖{�H
�킹�Ă����B
�����ԍ��F25235854
![]() 3�_
3�_
���A�}�`���A�J�����}������
>�܂��A�N�����ۂ̂Ƃ���͒m��Ȃ����瓚�����Ȃ��̂ł���B
�J�����̃_�C�i�~�b�N�����W��AD�ϊ�bit���Ƃ̊W�́A����L��������������܂��B�ǂ���������e�ł��B
��ɏЉ�����[�J�[�̉�������̈�ł����ATech One���� �́u�K�i�v��u�s�U�v�̗Ⴆ���킩��₷���Ǝv���܂��B
���ꂪ�u�Ԉ���Ă���v�Ƃ����l�������܂����A���̕��X�̌����悤�ȉ���͖ڂɂ������Ƃ�����܂���B
����Ƃ͕ʂɁA���[�J�[���Õ��m�C�Y�̏������ǂ����Ă��邩�͉摜�G���W���̘b�ŁAAD�ϊ���bit���Ƃ͕ʂ̂��Ƃł��傤�B������́A�O���̈�ʃ��[�U�[�ɂ́A���[�J�[�̐����ȊO�͕�����Ȃ����Ƃł��ˁB
>14EV��12bit�Ɉ��k�I�Ȃ��Ƃ܂ł��ďo�͂���
14EV�̃_�C�i�~�b�N�����W��12bit��AD�ϊ�����̂́u���k�v����Ȃ��ł��傤�B�P�Ȃ�f�[�^�`���́u�ϊ��v�Ƃ��������ŁB
�����ԍ��F25235903
![]() 10�_
10�_
��Tranquility����
�����咣�̗��t���ƂȂ���͂���̂ł����H
�Ȃ��ł��B
�ł��A�l����Ε�����܂��B
�������g�ł͂ǂ�Ȗ{�����ǂ݂ɂȂ��āA���咣�̂悤�ȍl���Ɏ������̂ł��傤���H
���̂�����́A���̈ӌ��̊m���炵���f�������A�Ƃ������Ƃł��傤���H
����ł�����ATranquility����̃A�v���[�`�́A���̂悤�ȓ����f���ő��l�̈ӌ������߂�̂ɂ͌����Ă��Ȃ��ł��B
�������܂菑�����݂ł��܂���̂ŁA��������`�����܂��B
�E���̘b��Ŋ��Ⴂ�₷���Ƃ���́A����2�_�ł��B
1. ���l0�i�[���j�t�߂̍l�@
����͈�ʓI�Ȃ��ƂŁAAD�ϊ��̒m��������Η����ł��܂��B
�܂��A�����ԍ��F25235496 �Ŏ��̎�������Ă��܂��B�������������������K�v������܂��B
�������ŁA�m�F�ł����A
��EV0 ���Ӗ�����̂́u0�v�ł͂Ȃ��āu1�v�ł��B����͔F������Ă���ł��傤���H
2. �_�C�i�~�b�N�����W�ƊK���̂����
����́A���Ȃ����ȍl�@�ł��̂ŁA��������̂͂�������ł��B
�Ō�ɂȂ�܂����A�Z���Ԃł������A�F�X�ӌ������ł��A���肪�Ƃ��������܂����B
Tranquility����̗������i�ނ��Ƃ��F�O���Ă���܂��B
�����ԍ��F25235961
![]() 6�_
6�_
��Kazkun33����
���͎���f�q�Ȃǁu�A�i���O���̃_�C�i�~�b�N�����W�v�ƃA�i���O�l���f�W�^���l�ɕϊ����镔���uADC�̃_�C�i�~�b�N�����W�v��2�������āARAW�̕\���_�C�i�~�b�N�����W��2�̓��ǂ��炩���������ɂȂ�A�ƍl���Ă��܂��B
ADC�̕���\��12bit����14bit�ɂ���ƁAADC�̃_�C�i�~�b�N�����W��2EV�����L����܂��B
�������A�����ɃA�i���O���̃_�C�i�~�b�N�����W��2EV�����L���Ȃ���RAW�̕\���_�C�i�~�b�N�����W�͍L����܂���B
OM-1�ŗ��ʏƎˌ^CMOS�Z���T�ɂȂ������Ƃ̓A�i���O���̉��ǂł��̂ŏ]�����A�i���O���̃_�C�i�~�b�N�����W�͍L�����Ă�͂��ł��B�ł����A�ǂꂾ���_�C�i�~�b�N�����W���L�������̂����d�v�ł��B�Ⴆ�A�̃\�j�[�����ʏƎˌ^�̃Z���T���o�������͕\�ʏƎˌ^���2�{�_�C�i�~�b�N�����W���ǂ��Ȃ��������ł��B�����A�_�C�i�~�b�N�����W��1EV�グ��ɂ̓_�C�i�~�b�N�����W��2�{�ɁA2EV�グ��Ȃ�4�{�ɂ���K�v������܂��B���ʏƎˌ^�ɕς��������ł͓͂��Ȃ��\��������܂��B
�Ȃ̂ŁAOM-1�̓_�C�i�~�b�N�����W�����サ�����A12bit����14bit�ɕς���قǂ̓_�C�i�~�b�N�����W�����サ�Ȃ������Ƃ����\���������ł��܂��B
�܂��AAPS-C�ł͊���14bit�ɂȂ��Ă���̂ŋZ�p�I�ɂ�14bit�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y������͂��Ƃ����w�E�ɂ��Ăł����A���t�̃V�F�A�̓L���m���A�j�R���A�\�j�[���傫�������̃��[�J�[�̃Z���T�T�C�Y�̓t���T�C�Y��APS-C����͂��Ǝv���܂��B
�Ȃ̂ŁA�ŐV�Z�p�͐�Ɏ��v�̌����߂�t���T�C�Y��APS-C�Ŏg���āA�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͈���x��Ďg����Ƃ����悤�ȉ\�����l�����邩�Ǝv���܂��B�����A����Ɋւ��Ă͎��M�������ł��B
��Tranquility����
>�ŁA�O���t�ɂ́A�u�_�C�i�~�b�N�����W5EV�v�̍��̕��Ɂu������v�Ƃ����`
�����͎��̏�������������h��������������܂���B
�uADC�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�ɑ�������P�x3EV�͈̔͂̊O���́A�u����f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W�v2EV���̏������ƌ����Γ`���ł��傤���B
�}�Ɏ����Ă���P�x2EV�̕����́A�u����f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�ɂ͊܂܂�Ă��܂����A�uADC�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�i�ɑ�������P�x�͈̔́j�ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ��̂ŁAADC�����0�Ɍ�����Ƃ����Ӗ��ɂȂ�܂��B�u����f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W�v��2EV�������킯�ł͂���܂���B
�u����f�q�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�ƁuADC�̃_�C�i�~�b�N�����W�v�̓�̃_�C�i�~�b�N�����W������Ƃ������Ƃ𗝉�����K�v������Ǝv���܂��B
>����ɁA�O���t�����Ɂu3bitADC�v�̐����������āu0�v�������`
�ʎq���ƌ����āA�ȒP�Ɍ����Ƌߎ��l���g���Ă����ł��B�m�����̕�����������Ă��Ǝv���܂��B
����ʂ��v�邽�߂ɓ��Ԋu�̖ڐ��̒�K��p�ӂ��āA0�`1�ڐ��ڂ܂ł́u0�v�Ƌߎ�����A�܂����̖ڐ��܂ł��u1�v�Ƌߎ�����A�܂����̎����u2�v�Ƌߎ����Ă����āA�ȍ~�͋ߎ����������݂̂ŗʂ������Ƃ����l�ȊT�O�ł��B�u0�v�ƂȂ��Ă镔���͕��������Ă��āA�ق�Ƃ�0�łȂ���������Ȃ�����0���Ƃ������Ƃɂ��Ĉ����A�ƌ��������܂莖�ł��B
�Ⴆ�b�����܂��B
���Ȃ��̓{�g���ɐ����l�߂āA������Ђɔ[�i���Ă܂��B1�{�{�g����[�i���邲�Ƃɋ��������炦�܂��B
�����ł́A���Ȃ��͗ʂ��A�i���O�I�ɕω����鐅�������A����ň�����Ђ͔[�i���ꂽ�{�g���̖{���Ƃ����f�W�^���I�Ȑ����������Ă��܂��B
�ŁA������A�Ȃ��̏o�������ă{�g���������������W�߂邱�Ƃ��o���܂���ł����B���R�[�i����0�ł��B���̎��A���Ȃ���������ЂɁu�[�i����0�{�����A�����0�`0.9�{���͐����������̂��B�������o���v�ƌ����Ă݂Ă����������Ă���Ȃ��ł��傤�B
���̂悤�Ɉ�����Ђł̓{�g��1�{�ɖ����Ȃ�����0�Ƃ��Ĉ����Ē[�����l�����Ă���܂���B����Ɠ��l�̍l�������f�W�^���Ő��������ۂ̊�{�ŁA�A�i���O�l���ǂꂾ���ł��낤�Ƃ��A�f�W�^���l��0�Ȃ炻���0�ł���ƈ����܂��B
��������A�Ȃ������Ƃ����������Ō����A�u0�v�͗ʂ�0�ł������Ƃ�����������A�u1�v�͗ʂ�1�ł���Ƃ�����������A�u2�v�� �c�c �ȉ����l�A�Ȋ����ɂȂ�܂��B
���ꂪ����������܂ł̋c�_�𗝉����鏕���ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
���ƁA���l���̕����f�W�^���M�������̖{��ǂނ悤�����Ă���Ă܂����A����̓f�W�^���ł̐����̈�����ʎq���Ȃǂ̍��܂ł̋^��Ɋւ��铚�������ȏ���1�`2�͂��炢�ɍڂ��Ă邩��Ȃ�ł��B
����1���Љ�܂����A���W������o�Ă���u�f�B�W�^���M�������v�Ƃ������߂ł��B
�����ԍ��F25235981
![]() 6�_
6�_
�݂Ȃ���
�������ׂ݂܂����B
�����H�w�̉���ŁA�u�ʎq���r�b�g��1���₷�Ɨʎq���G����1/2�ƂȂ�̂ŁA�M���Ηʎq���G�����2�{�ɂȂ�v�Ƃ�������������܂��BTech One���� ���Љ�̘_���ł́A�ʎq���G���̍��Ɂu�r�b�g����1bit�������S/N�䂪2�{�ɂȂ�v�Ƃ���܂��B
�܂�A���̔g�`�ƃf�W�^���f�[�^�̃Y�����m�C�Y�ŁAbit�����傫���قǃf�W�^���f�[�^�̔g�`�̍Č������ǂ��Ȃ�ƁB����͂킩��܂��B
�C���[�W�Z���T�[�̈Õ��m�C�Y�́A���̃A�i���O�o�͂ɂ��܂܂�Ă��鑪��l�́u�h�炬�v�̂悤�Ȃ��̂ł���ˁB���̃m�C�Y�͌��f�[�^��ʎq������bit���Ɋւ�炸�����傫���ő��݂���킯�ŁA�ʎq���m�C�Y�̘b�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�C���[�W�Z���T�[�̃A�i���O�o�͂�AD�ϊ�����Ƃ���1bit���₵�Ă��A�Õ��m�C�Y�����邱�Ƃ͖����ł�����B
�J�����̏ꍇ��AD�ϊ�bit���́u�K���̊��炩���v�ɉe�����܂���ˁB����͉𑜂̂��ߍׂ��������߂��f���Ɏ��Ă���Ǝv���܂��B��f�����������摜�ł͂�����u�W���M�W���M�ȁv�摜�ɂȂ�킯�ł����A���́u�W���M�W���M�v���ʎq���m�C�Y�ɑ�������Ǝv���܂��B�܂���bit���̉摜�ł́u�g�[���W�����v�v������܂��B������ʎq���m�C�Y�̈�Ⴉ�ƁB
�u�r�b�g����1bit�������S/N�䂪2�{�ɂȂ�v�Ƃ����������ƁA1bit������Ɖ摜�̃_�C�i�~�b�N�����W��1EV������悤�Ȋ��������܂����A�b���Ⴄ�Ǝv���܂���B�J�����̃_�C�i�~�b�N�����W�����߂�Õ��m�C�Y�͗ʎq���m�C�Y���Ⴀ��܂���B
�����ԍ��F25236020
![]() 13�_
13�_
��400kcal(80g������)����
ADC�ŕϊ�����14bit�̃f�[�^���A���̃_�C�i�~�b�N�����W���������ɁA12bit�ɕϊ��ł��܂��ł��傤���H
�����ԍ��F25236039
![]() 1�_
1�_
�������s�U�ŗႦ��ƕ������Ă���������̂� ����Ă݂邩
�s�U�A�l�Y�~�ɉ���ꖂ��܂���
���Ȃ��̓l�Y�~��ꖂ�ꂽ�Ƃ���͐H�ׂ�������܂��� ꖂ�ꂽ�Ƃ���̓|�`�ɂ����܂��傤
���Ȃ݂ɂ��Ȃ��̓s�U���J�b�g���܂�
���Ȃ��̓s�U����D���Ȃ̂Ń|�`��肽������H�ׂ����̂ł� ���{���H�ׂ����̂ł�
���āA
�l�Y�~��1/16�̉���ꖂ�ꂽ�s�U��8�����J�b�g�����Ƃ��ɂ��Ȃ��̓|�`��16�{�A�H�ׂ邱�Ƃ͉\���낤��
��
�����ԍ��F25236045�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
���X�A�X����Ɏ���𓊂������āA��������g�������Ƃ邢���̂��N�`��
�X����Ɍ�������Ă��炷��������������A
�N���G��������������Ȃ��Ȃ肨���炭���ӎ҂ł���R�e�n���ɂ��H���|�邠�肳�܁B
������Ԃł��ȁB
���l�̃X���b�h�ōD�����肵������A�N������łȂ��܂Ƃ߂��������ŏ�������ŃV�����邵���Ȃ��B
�Ȃ��P�Qbit�Ȃ̂������悤�Ƃ������A���l�̗̒n������C�܂܂ɐ�̂��Ă邾���̔y�ł���B
MFT�̓f�[�^���y���̂���������AI�m�C�Y���_�N�V������n�C���]�B�e�A�Q�C�������ō��掿����ڎw���Ă�A
������]�����Ă�����Ηǂ������̘b�B
�����ԍ��F25236049
![]() 7�_
7�_
���܂��ܔ`�����҂ł���
���w12bit�̃f�W�^���f�[�^�ɁA15EV�͓���Ȃ��ł��B�x
��������āA�P�Q���P�T������A12�̒���15�͓���Ȃ��B
�Ď����Ⴀ�Ȃ��ł���ˁB
�Ȃ�����_�������ł����ˁH
�����ԍ��F25236085
![]() 1�_
1�_
��hirappa����
���[�ǂ�����B
���j�A�ł͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�ꉞ�߂����Ƃ������͒m���Ă��܂����A�����Ɉ�_�C�i�~�b�N�����W�����Ȃ����͕�����܂���B
���������������Ȃ����ȁ`�B�i���M������܂���j
����̕��ɂȂ��ł����ALOG�`���Ƃ����ׂ̂Ă݂ĉ������B
���Ƃ��āARAW�`���Ƃ͕ʂ̌`���ɂȂ�܂��B
�m��OM-1�ł�log�B�e���ł����Ǝv���܂��B
��������Ă��邱�Ƃ́AADC�ŕϊ������f�[�^���v���Z�b�T�̒���log���ɒʂ��Ă���ʎq���������Ă�Ǝv���܂��B�v�����������`�ϊ��ł��B
���̎��A���Ⴂ�r�b�g���ŗʎq�����Ă��_�C�i�~�b�N�����W�����Ȃ��Â炢�ł��B
�����AADC�ŗʎq�����Ă��炳��ɉ��Z��ɗʎq��������̂ŗʎq���덷��2�x�����Ă��܂��B
�܂�2�x�ڂ̕ϊ��̎��ɖ��炩��RAW�摜�����܂��B�܂��A�ϊ���̃f�[�^���덷�Ȃ�����RAW�摜�ɂ��߂��Ȃ��Ȃ�܂��B
�܂��A�_�C�i�~�b�N�����W�����قǕς��Ȃ��Ă��P�x�ɑ���K���ɑe�����������܂��B
�Ȃ̂ŁA�_�C�i�~�b�N�����W��14EV�ɋ߂����̂��m�ۂł��Ă��A�K���\���ɖ�肪�o�邩������܂���B
�X���b�h�̘b�肩��傫�������̂Ǝ�������قǗ������ĂȂ��̂łł����܂łɂ��܂����Alog�B�e�ALOG�`���ȂǂŒ��ׂ�A�������[�܂�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25236093
![]() 3�_
3�_
��400kcal(80g������)����
���X���b�h�̘b�肩��傫�������̂�
�b���ADC�ł͂Ȃ��ł��B
���̘b��́A14EV�̃_�C�i�~�b�N�����W��12bit�ɕϊ��o���邩�ł���ˁB
���_�Ƃ��ẮA�o����ł��ˁB
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25236123
![]() 4�_
4�_
���_
�E�r�b�g���͊K����\�����̂ł���B
�E�r�b�g����傫�����Ă��_�C�i�~�b�N�����W�͍L���Ȃ�Ȃ��B
�E�_�C�i�~�b�N�����W�̍L���ɍ��킹�����炩�ȊK����ׂɃr�b�g����傫������B
��APS-C��RAW�T�C�Y��14bit�Ȃ̂ɁAOM-1��12bit�Ȃ̂ł����H
���Z���T�[���\���オ���Ă��Ă���Ȃ�14bit�ɕύX���Ă��ǂ��Ǝv���̂ł����B
RAW��12bit������AADC��12bit�Ƃ͌���܂���B
���ƁAADC�ŕϊ�����14bit�̃f�[�^���A���̃_�C�i�~�b�N�����W�Ȃ킸�ɁA12bit�ɕϊ��ł��܂��B
�ȏ�
�����ԍ��F25236133
![]() 8�_
8�_
�������d�����ɂ��܂��傤
�����ԍ��F25236137
![]() 4�_
4�_
�ǃX���ł����ˁB
�����ԍ��F25236139
![]() 4�_
4�_
�܂���
�����ԍ��F25236140
![]() 3�_
3�_
���̐��i�̍ň����i������

OM SYSTEM OM-1 12-40mm F2.8 PRO II �L�b�g
�ň����i�i�ō��j�F¥310,000�������F2023�N 2��24�� ���i.com�̈����̗��R�́H
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z�������̂ς�����
-
�y�~�������̃��X�g�zPC�\��20251031
-
�y�~�������̃��X�g�z���C��PC�č\��
-
�yMy�R���N�V�����z����\��
-
�y�~�������̃��X�g�zpc�P�[�X
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j