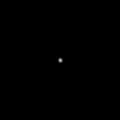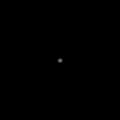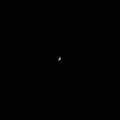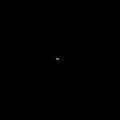デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10
【第1回 望遠端での絞り値】
こんばんは。
望遠端720mmでの絞り値による写りの違い、主に解像感のわかりそうなオリジナルサイズ写真を「フォト蔵」に登録しました。興味とお時間のある方はどうぞ。
フォト蔵のアルバム「HS10 疑問解消試し撮り」
http://photozou.jp/photo/list/197457/1292551
001〜003の3枚、F5.6/8.0/11、三脚使用の手ブレ補正OFF、マニュアル露出、毎回10秒セルフタイマーで、毎回AF。
HS10にはF11まで絞りがありますが、解像感だけならF5.6がいいようです。
<この書き込みには、F5.6の1枚だけをリサイズして投稿しています>
<補足>
EXIFの日時を隠蔽しているためか、他に原因があるのか、"Exif Quick Viewer"ではEXIFは見れないようです。
書込番号:11247209
![]() 8点
8点
【第2回 Canonテレコン TC-DC58N 装着】
続いて
フォト蔵のアルバム「HS10 疑問解消試し撮り」
http://photozou.jp/photo/list/197457/1292551
の004〜007の4枚
Canon PowerShot A620 (換算35〜140mm4倍ズーム・1/1.8型CCD・710万画素)で使っていたCanon製テレコンバージョンレンズ TC-DC58N を取りつけてみましたが、望遠鏡の代わりにはなるものの、画質的には使い物にはならないようです。
絞りを絞り込む事で、幾分かは色のにじみ(青色)が改善されますが。
<この書き込みには、テレコン取付外観の1枚だけをリサイズして投稿しています>
<参考>
TC-DC58N
1.75倍、ネジ径58mm、直径75mm、長さ50mm、重量185g
購入価格は中古で3,000円はしなかった。
Kenko TELE BRACKET は中古で500円だったかな。
<余談>
Nikon製0.75倍ワイドコンバージョンレンズ NH-WN75 を 58-52ステップダウンリングを介して取りつけてみましたが、換算35mm以下ではけられるのでまったく使い物になりませんでした。
書込番号:11247216
![]() 8点
8点
カラスが巣作っていますね〜。
鳥トリにも良さそう・・・。
書込番号:11247909
![]() 5点
5点
フロントテレコンの序列は、
1位・・・Nikon TC-E17ED
2位・・・オリンパ TCON−17
・・・で、パープルフリンジは簡単には出ません。
HS10は注文してあるが10日待ちと言われているよ・・・
地元量販店ですが、10日後に入荷して価格が下がったらどうしてくれると
言っているが、ウダウダの返事でした・・・
入手したら、自称超望遠マニアですから3倍から4倍のテレコンを自作するよ。
書込番号:11249285
![]() 5点
5点
【第3回 手ブレ補正+電子手ブレ補正】
換算720mmでシャッタースピードいくつまで手持ちで頑張れるか、手ブレ補正のご利益は。
被写体は、また携帯中継アンテナのカラスの巣、そこそこスローシャッターがかなう暗い曇りを待って。
ブレ防止モードの[撮影時]と[撮影時+D](センサーシフトと電子式の併用)を撮りました。
3枚ずつ撮って、
[撮影時]
1/100秒で3枚のうち1枚はほぼ満足の手ブレ補正。2枚はブレが残ってます。
[撮影時+D]
1/100秒で3枚とも同じ程度のブレ補正結果。コントラストのある部分、箱の輪郭やネジのようなくっきりしたモノは、十分に効果があるようです。一方、カラスの巣の部分は、3枚とも同じようなボケになっています。
得手不得手のシーンがあるのかも。明るくコントラストのある部分は良いけど、暗くてコントラストの低い部分はボケた感じとか。
ふたつの使い分け、説明書には記述が見当たりませんが、手ブレ補正不足も数多いけどギリギリの解像感を期待するなら[センサーシフトのみ]、最高品質ではないかもしれないけど歩留まりが良いのが[電子式の併用]ってトコでしょうか。更にアドバンスモードの[連写重ね撮り]も手ブレを押さえるらしいからややこしい。
それぞれ1枚ずつ、価格コムにはピクセル等倍トリミングした写真を投稿。元画像サイズのモノは以下
フォト蔵のアルバム「HS10 疑問解消試し撮り」
http://photozou.jp/photo/list/197457/1292551
008)センサーシフト手ブレ補正のみ
009)電子手ブレ補正併用
いちおう作例
010)手持ち720mm 1/125秒 ISO400の例
<価格コム写真はリサイズのみ。手ブレ補正の作例で鳥が目的ではありません>
書込番号:11254827
![]() 5点
5点
【第3回 焦点距離とマクロ撮影距離・範囲】
[11245870]雑用係3さんの「中間焦点距離での最短撮影距離」のスレッド、マクロ時の中間焦点距離での最短撮影距離が興味深くて、確かめてみました。
換算焦点距離(実焦点距離) 距離 横の長さ
720(126) 188cm 96mm
500(77.7) 117cm 97mm
300(43.1) 36cm 67mm
200(30.3) 13cm 47mm
135(22.1) 8.3cm 45mm
105(17.5) 9.0cm 52mm
80(13.3) 7.5cm 57mm
50(8.0) 5.8cm 67mm
35(6.0) 4.2cm 70mm
24(4.2) 3.6mm 80mm
換算焦点距離はレンズ鏡筒の目盛り
実焦点距離は付属パソコンソフト"FINPIX STUDIO"で見たEXIFより
距離はレンズ鏡筒先端から
横の長さは長辺方向に写った定規の目盛り
換算24mm広角端限定のスーパーマクロでは、レンズ鏡筒から目測1mm(cmではない!)離した物差しの目盛りにもピントがあいます。この時、横の長さは約34mm。照明を考えると実用性は疑問だけど。目ざわりにポツポツ白いのはレンズ表面のゴミ、たぶん。
カタログスペックではマクロには期待してなかったけど、換算焦点距離105〜300mmあたりは虫撮り・花撮りマクロにはとてもおいしそう。望遠端換算720mmで188cm/96mmもおもしろそう。特にマクロにはバリアングル液晶モニターはうれしいし。
011)
換算24mmスーパーマクロ、距離目測1mm、AUTOモード、手持ち
012)
換算720mm超望遠マクロ、距離約2m、マニュアル露出、カスタムホワイトバランス、三脚使用(うっかり手ブレ補正ONのまま)
共にリサイズのみ。照明は60W青色ガラスの白熱電球卓上スタンド1灯のみ。
オリジナルサイズ画像はフォト蔵のアルバム【HS10 疑問解消試し撮り】
書込番号:11259568
![]() 6点
6点
【第5回 センター固定AFモード】
購入直後にAFモードを[センター固定]にして、特に望遠端換算720mmで撮ってみて、しっかり中心で目的被写体を狙ったにもかかわらず、ピントが抜けることがままありました。<例写真013:ピンぼけカワセミ>
一応モニターにはAFエリアを示す枠とおぼしき横長長方形が表示されてはいるのですが・・・
[センター固定]でのAFエリアの範囲を確認してみました。毎度のケータイ中継鉄塔、背景はこれ以上ない単純さの曇り空。意外な事に大きくAF枠から離れた中央以外でも合焦します。<例写真014>
一方、[エリア選択]でAFエリアを中央にした時は、正方形のAF枠から少しでも外れると合焦しません。もちろん枠内ではバッチリ。<例写真015/016>
さらに[オートエリア]だと、<例写真014>の目的被写体位置では、AFフレームは中央から動かないのにしっかり合焦します。目的被写体がさらに中央寄りになるとAFフレームはソコに移動して合焦します。
勘ぐる所、[センター固定]や[オートエリア]は中央付近で合焦すべきモノが見つからないと、さらに周辺部を捜すような親切(お節介)仕様になっているのかも。この時[オートエリア]でもAFフレームは移動しません。説明書の仕様を越えても、どこかにピントを合わせようと努力しているのかも。
目的被写体に限定してAFさせるには、予想外にAF範囲の広がる可能性のある[センター固定]よりも、厳密に把握できる[エリア選択]の方が確実なようです。
<補足>
望遠端で背景が曇り空の単純な状況で確かめただけで、他の状況でどうなのかはわかりません。
本当に[エリア選択]でカワセミに合焦するのかは確かめていません。
今回はフォト蔵アルバムの写真はありません。
<余談>
説明書にあるように[マクロ]では[エリア選択]は選べず、[センター固定](あるいはこれに似た挙動のAF)しか使えません。虫/花マクロで目的被写体が中央にない時は撮りづらく感じます。(Canon A620 のアクティブAF枠に慣れていると)
A620では露出の明るさに応じてモニターに反映されていたのだけど、HS10では勝手に明るさを調整するので、不適正露出に気付くにくくなりました・・・と、<013>の言い訳を。
液晶保護シートの貼り方が下手糞なのは見なかった事にしてください。
<裏技>
マニュアルフォーカス時に[マクロボタン]をちょんと押すとマニュアルフォーカスが解除されます。[AF C/S/M]ボタンを押して[コマンドダイヤル]を回す説明書通りの操作より早いです。
<[11259568]の訂正>
「第3回」ではなく「第4回」でした。
マクロ撮影換算24mmでは「3.6mm」ではなく「3.6cm」です。
書込番号:11264269
![]() 4点
4点
【第6回 連写重ね撮りのノイズ】
[11264419][11265791]で、"連写重ね撮り"した写真をフォトレタッチで明るくすると暗かった所に緑色の線状ノイズが見えるとの報告がありました。
"連写重ね撮り"と同時保存された"処理前画像記録"(説明書119ページ)の2枚のオリジナルサイズJPEGをフォト蔵アルバム【HS10 疑問解消試し撮り】にアップロードしました。<017と018> 自分で検証したい方はどうぞ。
"017)連写重ね撮り"を不自然なほど明るくすると暗かった空に表れます。"018)処理前画像記録"には表れません。
代わりに白い縦筋が見えますが、降っている雨の筋だと思います。
空に見える白い円形のボケは、レンズに付いたゴミが左上からのライトで白くボケて写ったモノのように思います。
価格コムには緑線が見えるようにフォトレタッチ・リサイズしたモノだけを。<019>
個人的には問題にならない微小な程度と思います。
書込番号:11271242
![]() 3点
3点
【第7回 マニュアルフォーカス】
[11279645]で月をマニュアルフォーカス(MF)で撮るとオートフォーカス(AF)より良くなるのか作例を見たいとの事でしたので試してみました。
020)三脚+MF
021)三脚+AF
022)手持ち+AF
023)020と同時に撮ったRAW
マニュアル露出、ホワイトバランスは[晴れ]、コントラスト(トーン)はHARD、三脚は10秒セルフタイマー、MFは液晶モニターを虫眼鏡で拡大してピント確認、AFは[センター固定]、5枚ずつ撮ってパソコン画面でチェック、最も良いものをセレクト。
RAWは"グレーツール"だったか、それで灰色ポイントを指定、明るさ(コントラスト)調整、輪郭強調あり。
共に価格コムサイズ1024×1024をトリミング、ピクセル等倍。
020〜022のどれも区別がつかない、と思う。RAWの023も、色合い・コントラスト・輪郭強調が違うだけで、JPEGよりもとりわけ解像感が高いとも言いづらい、と思う。
<補足>
もっとも良いソレは区別がつきませんが、歩留まりは違います。"三脚+MF"は明らかなピンぼけが1枚。"三脚+AF"は5枚とも同じレベルのピントぴったし。"手持ち+AF"は見るに耐えるのは2枚。
結論としてはAFまかせで十分のようです。ただ、個々の機器のばらつき、当たり外れがあるかもしれません。中にはMFだとさらによく写るヤツとか。
<余談>
RAW現像ソフトのSILKYPIX、ずっと以前体験版を一度だけ使って以来ほとんど初めて。トリミングや無劣化保存するためのTIFF保存ができないようです。HS10付属版の制約なのかな、どうなんだろう。
小生のパソコンモニターはノングレア処理の艶消しで、その画面でRAWいじりしてます。昨今の光沢液晶モニターとは輪郭や細部の見え方が違う可能性があります。とは言うものの、ちょっとザラザラし過ぎ、擬色も多い気はしました。
ピクセル等倍で投稿できたので、フォト蔵アルバムのオリジナルサイズ画像はありません。
書込番号:11281401
![]() 8点
8点
【第8回 ズームアップ3枚撮りとねらい撮りズーム】
(説明書54・51ページ)
[ズームアップ3枚撮り]、撮像センサーの狭い領域を切り出してそのまま小さな画素数の写真を撮る"トリミングズーム"とでも呼ぶような機能で、
1枚目が1倍で[3648×2736]、
2枚目が1.4倍[2592×1944]、
3枚目が2倍[2048×1536]になります。(画像サイズL/3:2設定の時)
一方、[ねらい撮りズーム]は、撮像センサーの狭い領域の画像を大きなサイズに拡大する従来からある"デジタルズーム"みたいで、画像サイズL/3:2設定の時、上記の"2枚目1.4倍"に相当する範囲を[3648×2736]に拡大した写真が撮れるようです。
フジ固有とも思われる他社機種使用者にはわかりにくい名前で、ふたつが異なる設定手順を踏むのは不思議です。
どちらも30倍ズーム換算720mmもあれば使う事もないような機能にも思えますが・・・
広角端の換算24mmで使うと、[ズームアップ3枚撮り]なら24mm、34mm、48mm相当の3枚になります。レンズの開放F値は換算24mm/F2.8、34mm/F3.2、48mm/F3.6ほどになる雰囲気ですが[ズームアップ3枚撮り]ならF2.8の明るいままで撮れます。
この1/3EVや2/3EVのレンズ明るさの違いで得られるシャッタースピードが欲しくて、画像サイズの違いによる画質の差を気にしないなら、たとえば暗めの室内での動く子供やペット撮りなら、役に立つ事があるかもしれません、と漠然と思います。
一眼レフでは、ファインダーで見えてるのに写真には写らないみたいなことがないように、視野率100%に限りなく近く、でも100%は絶対越えないことを求めているらしいのに、コレは写らない周囲をも敢えて見せています、視野率100%を越えています。フジは一眼レフとは違うコンデジの道を追求するのでしょう。
半ば机上の論、作例写真はありません。気になる方は実機で確かめてください。
書込番号:11284117
![]() 3点
3点
【第9回 EVFと手ブレ補正と流し撮り】
「手ブレ補正」と「流し撮り」、理屈では相容れないモノのようにも思えて試してみました。スローシャッターを試せる夕暮れ時まで待って。と思っていたら予想以上に暗くなり過ぎてISO800になったけど。
40〜50キロのスピードでしょう、このレベルならEVFを覗きながらの流し撮りに何の問題もないようです。300キロのレーシングカーで誰か試してくれるのを待ちましょう。
今回もフォト蔵アルバムはなし。
書込番号:11284635
![]() 3点
3点
【第10回 前後撮り連写】
散歩がてらに撮ってみて、どうもしっくりきません。ホントに過去にさかのぼって撮れてるのか。
デジタル表示のストップウォッチを撮って試しました。直射日光の当たる日なた、マクロで1/500秒。シャッターボタン半押しで待機、10秒の桁が9から0に変わる瞬間に全押し。
(1)ストップウォッチを直接見て
(2)背面液晶モニターを見て
(3)背面液晶モニタに写る1秒の桁を紙で隠して
(2)は背面液晶モニターの表示遅れ(タイムラグ)を意識したモノ。
(1)(2)は全押しタイミングは1秒桁の数字を見ていると予想できます。つまり人間の反応タイムラグはなし。(ばらつきはあり)
(3)は1秒桁が見えないので、10秒桁が変わったと認識してから全押し、人間の反応タイムラグも含んだ現実的なシーンのシミュレーション、たとえば枝に停まったカワセミが飛び立つ瞬間みたいな。
[前後撮り連写]の設定は、全押し前6コマ/後0コマ(全押し瞬間の1コマを含めて合計7コマ)。全押し前の時刻、10秒桁が"9"が何コマ(枚)写っているかをチェック。
10fpsでは
(1)5枚
(2)3〜4
(3)0
3fps
(1)6
(2)4
(3)3
<結論>
10fpsでは背面液晶モニターやたぶんEVFファインダーを見ていてはカワセミの飛び立つ瞬間、足が枝から離れる直前は撮り逃します。(カメラは三脚に固定して)モニターでなく直接カワセミを見ていたとしても人間タイムラグがありますからきびしいかもしれません。
3fps連写速度を落としても、コマ数がさほど改善しないのは・・・
背面モニターに写る映像はシャッター半押し後は10fpsや3fpsで更新されている雰囲気です。モニターの表示タイムラグが大きくなっている分、それを見て反応(全押し)してもタイミングはさらに遅れてしまいます。
[前後撮り連写]、スペック性能を発揮した写真を撮るには何かしら知恵か努力が必要なのかも。
<補足>
何度か撮った写真から判別しましたが、数値は絶対的な信頼性のあるものではありません。この"試し"は、数値を得る事を目的にしたモノでなく、傾向をつかむためのモノです。人間タイムラグは人によって違うでしょうし、シャッタースピードや他の設定で連写速度が変わる事も考えられます。ストップウォッチの表示タイムラグもありえます。
写真投稿はありません。興味のある方は実機で確かめで把握する事が肝要かと思います。
書込番号:11313373
![]() 6点
6点
【第11回 クローズアップレンズ】
<<< 投稿写真には虫が写ったものがあります。嫌いな方は拡大表示を避けてください。 >>>
Kenko ACクローズアップレンズNo.4(色消しレンズの焦点距離250mm)径49mmをステップダウンリングを介して取り付けてみました。
換算720mmの無限遠相当ピント位置で撮影距離250mmになり、机上の試し撮りではマクロ最短距離で220mmほど。どちらの場合も撮影範囲は長辺(横)12mm弱。
望遠端から広角側へズームダウンすると、最短撮影距離は短くなりますが、広角で画角が広くなるので写る範囲は広く、被写体は小さく写ります。たとえば換算50mmでは距離250mmで横172mm、最短距離42mmで横60mm。作例写真はなし。
投稿写真は4枚とも換算720mm。
長辺(横)12mm弱ですから被写体の大きさもわかるかと思います。
ピントの合う範囲は極めて狭く、ハエトリグモの手前の眼に合うと、奥の隣の眼はピンぼけになります。
AFの働く距離範囲も著しく狭く、クイックフォーカスOFF・マクロOFFでは換算720mmでは23cm〜25cmの2cmほどしかありません。
250mmの撮影距離が稼げるとレンズ鏡筒による内蔵フラッシュの"けられ"はないようです。(レンズフードはなし)
フラッシュの自動調光も働くようですが、発光量調整が必要かもしれません。
フラッシュ時、ピンぼけ部分の輝点には色収差みたいなのが派手華やかに現われます。好みが割れそうです。
予想した以上に大きく写ったと思いますが、情報量とでも言うのか"見ての満足感"はイマイチの気もします。
027)換算720mm最短付近
マクロON
028)赤ちゃんかまきり
マクロOFF、フラッシュ発光
窓ブラインドの羽にぶら下がっています。
手持ち。
029)ハエトリグモ
マクロOFF、フラッシュ発光(発光量-0.7EV)
窓ガラスにいるので本来は頭が下向きの縦構図です。
カメラの底面は窓ガラスに押し付けてレンズを持って向きを定めてます。
030)おしべめしべ
マクロOFF、ストロボフラッシュ(発光量-0.7EV)
テーブルのコップに差してあった名前を知らない花のおしべめしべ。
三脚使用、花のコップを前後させておおよそのピントを合わせた後AF操作。
<補足>
Canon PoweShot A620 用に購入していたクローズアップレンズです。A620本来のフィルター径はHS10と同じ58mm径ですが、クローズアップレンズは主に望遠側でしか使わないこと、ACの49mmと58mmは価格が倍ほど違うことから廉価な49mmをステップダウンリングを介して使っていました。
机上試写では換算50mmではわずかに"けられ"が見られます。実際の撮影では、手ブレ補正で撮像センサーがセンターからずれることが考えられるので、更に望遠側での使用に限定されそうです。
マクロONで最短距離を探る時、遠方から近距離へ撮影距離を詰めてピンぼけになり始める距離と、近距離から遠方へピンぼけからピントが合い始める距離は違うようです。前者の方が短くなります。
ココに記述の距離は、どちらかを意識していません。あくまで目安と言う事で。
手持ちの時、被写体を背面モニターの中心に配したつもりでも、撮れた写真では上部にずれていることがたびたびあります。手ブレ補正で撮像センサーが背面モニターで見た時の中央の位置から動いているのだと思いますが、正常な範囲なのか異常なのかわかりません。028)がそうです。
027)を除いて、オリジナルサイズ画像はフォト蔵アルバム【HS10 疑問解消試し撮り】。
書込番号:11353414
![]() 3点
3点
スッ転コロリンさん こんばんわ アリを見ていたら別な場所で赤いのが動いてるように思えた。0.1〜0.2ミリ位だ。レンズを通して見たらこんなやつだった。動く距離は少ないがレンズを通して見ると早い早い、ピンが合わず、苦労した。No.5 2毎使用
書込番号:11353612
![]() 6点
6点
教訓
4ミリのアリもそうだった、拡大した4ミリのアリを8ミリの枠の中で追うというのはなかなか難しい、すぐ枠からからはずれ、ピンもずれる。8ミリの画面に合わせようとすると早い早い、見た目に遅いからと思っても被写体として狙うのは鳥よりも難しい。
赤いダニ?は目の良い私でも普段は気が付かないだろう、0.1ミリ〜0.2ミリ、一寸目を離すともう分からない、見つけて、見逃す、カメラで探すとまるで宇宙をさまよっている感覚だ。宇宙酔い、やっと見つけても3ミリ位の枠の中だから早い早い、すぐに消えてしまう。被写体を探す、追うだけで疲れてしまう。
設定
ピンの事はお任せする、今回普通に思っていたシャッター速度の考えを変えないといけない。それを強く感じた、小さいものを大きく撮る場合には、動いてる被写体は相当の早さのシャッター速度が必要、見た目に遅くても奴らの足を止めるのは1/1000位のシャッター速度が必要と感じた。それだけ拡大率が多いのだから、そうなのかも知れない。
ほとんどの写真がピンが有ってもぼけぼけ、足がないのだ。むろん体に合わせても足はぼけるのだが、無くては、消えていては話にならない。小さいものはシャッター速度を上げる。それは忘れてはならない。手持ち撮影。
書込番号:11354721
![]() 4点
4点
【第12回 円盤フレアー】
[11382706]で脱線横レスした「曇り空を背景に枝にとまったカラス」(031)で中央に紫色の円盤が写る件、再現検証しました。勝手に「円盤フレアー」と呼びます。
"曇り空を背景"の代わりに模様ガラス、"枝にとまったカラス"は黒いフェルト布です。プログラムAE、オートホワイトバランス、黒フェルトをスポット測光。テスト撮影の様子は(034)。
換算720mm、300mm、105mm、50mm、24mmで黒フェルトが適当な大きさに写る距離に変えて撮影。それぞれ「保護フィルターもレンズフードも無し」と「同有り」。保護フィルターは Kenko PRO1D PROTECTION(W) 58mm (透明、反射防止コーティングあり)。
032)換算720mm、保護フィルターもレンズフードも無し
033)換算300mm、保護フィルターもレンズフードも無し
保護フィルターの有無は円盤フレアーの写りには関係ありません。たぶんレンズフードも。720mm・300mmでははっきり写ります。撮影前のEVFファインダーでも注意すればわかります。(背面モニターではわかりにくい)
105mmではよく見れば写っているなの程度。50mm・24mmでは黒フェルト全部が紫っぽく写ってよくわかりません。投稿写真はなし。
黒フェルトを少し横にずらして撮っても円盤フレアーは画面の中央に写ります。
素人考え、撮像センサーやその周辺で反射した光がレンズに戻って再び反射、それがまた撮像センサーに戻って円盤フレアーとして写るような。
これは「不具合」なのか「逆光だからと許容する」のか、人によって判断がかわりそうなレベルにも思いますが・・・。
フォト蔵アルバムの写真はなし。
書込番号:11403201
![]() 4点
4点
テスト撮り、ありがとうございます。
でも、ちと、これは問題ですね。気を付けないといけないねぇ。
書込番号:11404399
![]() 4点
4点
【第13回 レンズの歪曲収差】
やっと付属以外のRAW現像ソフトを使えるようになったので試しました。投稿写真はJPEGはGIMPでリサイズのみで再JPEG保存、RAWはDCRawでTiff出力、GIMPに読み込みリサイズ後JPEG保存。輪郭強調などは行なっていません。
歪曲収差補正のないソレは、「ぷっ」と噴きたくなるほど。よく見るとカメラJPEGは色収差補正も効いているようです。カメラJPEGは 3648×2736、DCRawの出力するTiffは 3664×2742 とちょっとだけ広くなります。
無料ダウンロードのRAW現像ソフトDCRawについては[11440397]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11440397/
オプション設定は "-w -q 0 -m 1 -T"、暗黙の明るさ自動補整、カメラのホワイトバランス設定を継承、bilinear補間、カラースムーシング、暗黙の8ビット、Tiff出力ってトコ。bilinear補間は選択できる4種類の補間の中で「素直なノイズ」が得られる気がします。
オリジナルサイズJPEGはフォト蔵のアルバム【HS10 疑問解消試し撮り】
http://photozou.jp/photo/list/197457/1292551
<補足>
HS10付属のSILKYPIXでは歪曲収差補正されています。色収差補正の有無は確かめてませんが、できるのならされているでしょう、たぶん。
広角端で絞り値F5.6は小絞りボケの懸念があり、解像感の評価にはふさわしくないかもしれません。
DCRawについての[11440397]の書き込み中、思い違いがありました。「使っているとわかるでしょう」ってことで。
書込番号:11452145
![]() 4点
4点
【第14回 シーンポジションの花火】
これからシーズン、知っておいて損のないコト、かも。他のシーンポジションはもちろん、Canonコンデジの[打ち上げ花火]モードとは違うので戸惑いもあります。
[花火]では、ISO100、2秒、F8.0 になります。
コマンドダイヤルで1/2秒〜4秒に変更できます。露出補正やホワイトバランスは変更できません。(余談:Canonコンデジでは露出補正操作でシャッタースピードを変更できます) 花火に不要なフラッシュやマクロも使えません。
フォーカスモードは普通は[AF-S]になります。[MF(マニュアルフォーカス)]にも変更できます。説明書149ページでは[AF-C]もできるかのようになってますが、小生のHS10ではできません。
[AF-S]となっていますが、実際はオートフォーカスせずに無限遠付近にピント位置を決め打ちしている雰囲気です。夕方の景色で確かめた限りでは、遠方ドンピシャ(無限遠)ではなくて微妙にずれている気がします。
絞り値がF8.0、広角なら十分に被写界深度に入るかもしれません。(これは確かめていません)
厳密なピントを要求するなら、[MF]に切り替えて、微調整が必要かも。ただし、真っ暗な花火会場では適当な距離の所に明るい代用被写体があればラッキーですが。
三脚使用が前提になるので、ブレ防止モードを[OFF]にすることをお忘れなく、自動では切り替えてくれません。(説明書25ページ)
実際の花火撮影には至ってませんが、事前の予備知識としてまとめてみました。
<余談>
[花火]でピント位置が遠方に決め打ちされ、そこで[MF]に切り替えると微調整できるのは、[MF]ピント位置は他の撮影モードにも継承されるようなので、応用できるかもしれません、ないかも・・・。
花火の写真はありません、失礼。
書込番号:11698290
![]() 5点
5点
【第14回 シーンポジションの花火】の補足(1)
[花火]で[マニュアルフォーカス]できなくなることがあります。この時は[AF-S]に戻しても遠方にはピントが合いません。
電源OFF/ONで、とりあえずは復帰するようです。
不具合の再現手順はもっか調査中。
あ〜ぁ・・・。
書込番号:11704262
![]() 4点
4点
【第14回 シーンポジションの花火】の補足(2)
ファームウェアのバージョンは1.02
シーンポジションの[花火]で、[AF-S]から[MF]にして、[AE/AF LOCK]ボタンを押したり、フォーカスリングを回したり、また[AF-S]に戻したりを繰り返したりしているうちに、[AF-S]でも[MF]でも遠方にピントが合わなくなりました。最初にこの不具合に遭遇した時は、[AE/AF LOCK設定]は[R/A:押下切替]だったと思います。(説明書118ページ)
その後、試すと、ある時は容易に不具合状態になり、別のある時はなりません。よって厳密な再現手順は不明のままです。
<余談>
再現手順の確認はやめます、たぶん。
使用上は問題なさそうなモニター表示の明らかなバグもあります。
[AE/AF LOCK設定]は[R/A:押下切替]
[花火]で、[AF-S]から[MF]にして[AE/AF LOCK]ボタンを押す。(説明書63ページ)
シャッターボタン半押しで[EL]アイコンが2個表示されます。写真(1)
[P]モード(プログラムAE)で同様の操作をした時の正常な画面は写真(2)、[EL]アイコンは1個です。
書込番号:11707235
![]() 3点
3点
【第15回 擬色?】
工事現場の足場を見上げた写真、床の穴は素通し、白く写って欲しい所が、電飾の電球のようにカラフルに写っています。
41)全体リサイズ
42)200%拡大
GIMPにてトリミング後、拡大(補完無し)
今まで撮った写真ではこんな現象は気付かなかったけど。頻繁に起こるのでなければ、無視しちゃうか。原因を考えるのも面倒だし。
フォト蔵のアルバム【HS10 疑問解消試し撮り】のオリジナルサイズ画像は無し。
書込番号:11803197
![]() 4点
4点
敬愛するスッ転コロリン様。
何故、撮影 年月日を・・・。あなたのお陰なのですよ! 恥ずかしいからUPしないけど。
全てを自分の支配下に置かなきゃ、気が済まないのですか?
書込番号:11803578
![]() 2点
2点
スッ転コロリン様。
今日、念願の 悪あがき 自分ながらに撮影できました。
最初は蝶に狙いを定め、ゆっくり近づいて・・さあピントを確かめようとした途端に逃げら
れてしまい、他の選択肢を考えあわせましても「え〜いやーめた・・」・・その時一匹の虫
が私の周りをクルクル回り、うるさい気持ちでおりますと・・目の前の枝に停まり私を観察
しておりました。
昨日の書き込みを ’所詮子供の戯れ事と’歯牙にもかけないあなたが眩しいです。
流石!ミスターデジタル。ミスターHS10ですね!
体長 約5〜6cm(目算)
羽を広げた距離 約7cm(目算)
目の端から端までの距離 約7ミリ(6.76ミリ・・サンプルの撮影13ミリから割出し)
鬼ヤンマの子供ではないかと思います。
これの撮影で 私の夏 も終わったかなーと、しんみりしてしまいました。が、次がありますね・・^^
書込番号:11806810
![]() 4点
4点
【第16回 RAWはカメラJPEGを凌ぐか】
「所詮コンデジのRAW」とか「裏面照射C-MOSだから」などと言う声も聞くコレ。付属のRAW FILE CONVERTER(HS10限定SILKYPIX)がTifファイル出力できるようになったので、改めて試しました。
SILKYPIXでRAW現像、Tif出力。これを別の写真修正ソフトに読み込んで輪郭補正処理など。
43)左:JPEG/右:RAW(ピクセル等倍)
44)カメラJPEG(リサイズ)
結果は・・・「いいじゃん、コレ」
赤パラソルの下、ボートの船外機を見ると解像感の違いは一目瞭然。青パラソルの下の転がっているブロックや木の箱(?)は質感の差も。雲の"くっきりもこもこ感"や木々の葉っぱも。
オリジナルサイズのカメラJPEGとRAW現像JPEGをフォト蔵のアルバム【HS10 疑問解消試し撮り】に
http://photozou.jp/photo/list/197457/1292551
拡大写真にはおさまっていないオリジナル画面の中央あたり、ボートの赤色の"へさき"も、確かに違います。
<補足>
例写真は別の写真修正ソフトで仕上げていますが、付属SILKYPIXだけでも似た効果は期待できます。暇つぶしにお悩みの方は、ご自身で体験を。
色合いについては評価しないでください。
小生はノングレア(艶消し)表面の液晶モニターで見ています。ツルツル艶有りのモニターでは印象が違うかもしれません。
書込番号:11924448
![]() 2点
2点
こんばんはスッ転コロリン様。
解像力と言っていいのでしょうか ビックリしてます。向こう岸の岸際に植わっている植物
に如実に現れていますネ。
プラスチックバケツの質感もベンチのそれも色(評価するなとの事ですが)も、勿論ボート
の船外機のラインもくっきりしてますが、私が一番に ここが違うなぁ〜と思いますのは
’透明感 'ですね。女性の背中から膝下辺りに当たっている日の光がそう思わせます。
私は今日もクローズアップ撮影しましたが修行不足もありまして、ピントが有るのか無いの
か判然としません。虫の写真がそうでして、No4+No3で撮影したモノです。
虫のサイズは、No2.No4.No4+No2.No4+No3.での撮影で 4.6ミリの
近似値を得ております。
書込番号:11924884
![]() 3点
3点
【第17回 換算720mmは木星に届くか】
思い付きで気楽に木星を撮ったら、木星のガリレオ衛星が写っていてびっくりしたのは、すでに[11926819]で報告済み。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11256034/#11926819
それなら、気合いを入れれば、木星の表面の模様は・・・
Webで調べると今時の木星の視半径は角度の24.9秒。換算720mm、HS10の撮像素子上には直径は18.3ドットほどに写る計算。表面の模様を描けるかどうか微妙なトコ。
今の自分にしては最高の技術、RAW撮りした画像16枚を合成しました。50×50ドットの領域をトリミング、200×200ドット400%に拡大してあります。
おおおっと驚く明らかな模様が。普通に見る木星の写真では(47)のように横縞に写ってるけど、西の空に傾きかけたので縦になったと勝手に解釈。
合成しなくてもカメラJPEG1枚でも模様らしきものはうっすら見えます、写っています。少し暗めの露出の方が見えやすいかもしれません。
45)木星16枚合成400%拡大
46)カメラJPEG200%拡大
換算720mm、ISO100、1/60秒、F5.6、WB:太陽光、マニュアル露出、マニュアルフォーカス。
トリミング(512×512ピクセル)後、200%拡大(1024×1024)。色や明るさ・輪郭補正はなし。
(45)の16枚合成の1枚目のカメラJPEGです。
47)露出不足気味200%拡大
1/125秒、他は(46)と同じ。撮影日・時刻は(46)と違います。
<余談>
ISO100で1/60秒や1/125秒って、木星って明るいですね。この露出値を探る試行錯誤に手間取りました。ここまでやる人はいないと思うので、具体的な手順は省略します、面倒だし。
拡大画像を用意したので、フォト蔵のアルバム【HS10気楽にショット】のオリジナルサイズ画像はなし。
書込番号:11935702
![]() 7点
7点
Mr,HS10.からDr,HS10.へ・・果ては、HS10という骨を使ってデジタルという可能性で重ね拡大し・・・凄い!素晴らしい!お見事!
撮影錬金術師スッ転コロリンのデジタルマイスターへの道はどこまで続く・・・!?^^
書込番号:11936244
![]() 2点
2点
うーん うーん うーむ
すごい すごい 確かにすごい
スッ転コロリンさんはすごい
素晴らしい…! ! ! ! 本当に素晴らしい…! ! ! !
書込番号:11938099
![]() 4点
4点
【第17回のオマケ 換算720mmは金星にも届いた!?】
今時の金星の視半径が角度の19.0秒ってことは、換算720mmでは撮像素子上では直径14ドットほどの計算。
手持ち、換算720mm。512×512ドットのトリミング後、1024×1024ドットに拡大(200%)。
こうなると土星までやっちゃうかな、機会がくれば。
書込番号:11947102
![]() 2点
2点
【第18回 月とRAW撮り】
既に[11281401]【第7回 マニュアルフォーカス】で月とRAW現像をやってますけど、その時よりはRAW現像にも少しは慣れたかも。あらためて試みました。
48)カメラJPEG
カメラJPEG(3648×2736)から1024×1024をトリミング。画質劣化なくトリミングできると言うBuffを使いました。
49)レタッチA
(48)のトリミング後JPEGを、Yimgで弱いノイズ除去と輪郭補正。再JPEG変換にはGIMP。
50)レタッチB
(48)のトリミング後JPEGを、GIMPでレベル(明るさとコントラスト相当)補正と輪郭補正、再JPEG出力。
51)RAW現像
HS10付属の RAW FILE CONVERTER の SILKYPIX で現像、JPEG出力。カメラJPEGではわかりづらい模様もくっきりしたかも。
手持ち、換算720mm、WB:晴天、WB微調整:赤+1/青+1、トーン:HARD、シャープネス:SOFT
投稿済み[11978973]と同じ日に撮ったモノです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11977271/#11978973
Buff、Yimg、GIMPは無料ダウンロードソフトです。面倒なので処理手順詳細は省略。
書込番号:11984694
![]() 4点
4点
【第19回 エネループの寿命末期の挙動】
試し撮りではないけど、SANYOのNiH充電池のエネループを使っている人は多いと思うし、その寿命末期の時の症状をあらかじめ知っていても悪くないかも、と思って紹介。
2006年10月からCanonのコンデジに使い始めて、途中からHS10に流用してほぼ4年、怪しい挙動が頻発しだしました。電源ON状態で待機していると、突然液晶モニター真っ暗、すぐに「ピコッ」っと音がして復帰、しばらくするとまた再発。短い時間に電源OFF/ONしたような、電池の接触不良で瞬間停電したような、そんな感じです。
最初は接触不良を疑って、電極を綿棒で拭いたりしたけど、良くなったような変わらないような。この状態のエネループをHS10から取り出してテスターで電圧を測っても十分のようだし、1.5Vの豆電球をつないでも眩しく光ります。充電器にセットしてリフレッシュするとやたら時間がかかるのがとても変。
聞きかじり(見かじり?)の知識だと、「電池の内部抵抗が高くなった状態」ってことのよう。負荷をかけない状態だと十分な電圧だけど、カメラに装填して電力を使い出すと(大きな電流が流れると)一気に電圧が下がるみたいな。電気の容量はかなりの量残っているから、豆電球みたいな小電力のものだと十分に光るし、完全放電させようとリフレッシュさせると、放電にやたら時間がかかります。
今まで使っていた複数本の充電池を使う機器だと、たとえば4本だと、そのうちの1本だけが著しく劣化してこれが他の3本の電池の足を引っ張って4本としては性能を発揮できないってパターンがほとんどだったんだけど、エネループはバラツキが少なく4本とも同程度に劣化するみたいです。4本の中の1本だけが悪いのなら、その1本を特定しようと何度か充電前/後に電圧を測ってみたりしたのだけど、その1本を特定できません。
Canonのコンデジでは、電池寿命の末期には、10枚くらいしか撮れなくなって、それから電源が入らなくなってってわかりやすい劣化の症状だったけど、HS10のOF/ONを繰り返す瞬間停電風の挙動は初体験。
勘ぐる所、HS10は下限(終了)電圧がCanonより高めに設定してあるのかも。下限電圧が高いと充電池のメモリー効果が起こりやすいらしいから、そのためにバッテリーリフレッシュ機能がHS10本体にあるのかも。
HS10では使えなくなっても、実際には電気容量はあります。あまり電力を必要としない機器なら問題なく使えるハズです。これからはコードレスマウスの電池として第二の人生(?)を送る事になりそうです。
書込番号:12026756
![]() 3点
3点
【第20回 動画で置きピン、おまけにHD動画キャプチャー】
説明書76ページには
「ピント・露出・ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。」
とありますが、
[動画撮影]ボタンを押す前に[マニュアルフォーカス]にしておくと、意図通り動画撮影中にオートフォーカスしなくなります。たとえば、
☆手前を人や自動車が通っていて背後の被写体にピントを合わせたままにしたい時。
☆飛んでる飛行機を狙って、もたもたオートフォーカスしている間に飛び去ってしまう、なんて事態を避けたい時。
・・・などなど、あらかじめ背後の被写体や遠方のソレにマニュアルフォーカスしておく"置きピン"の技が使えます。
しかし、動画撮影中にピントリングを回してもピントは変わりません。ズームするとピントがずれます。ズームした後、元のズーム焦点距離に戻しても、元のピント位置とはズレてしまうようです。
[AE/AF LOCK]ボタンによるAFロックあるいはAEロック操作をしても、この場合はピントも露出もロックできません。
<余談>
説明書の記述や[AE/AF LOCK]ボタンが期待したように働かない事から、[マニュアルフォーカス/置きピン]の技はフジが意図した事ではなく、たまたまそう働くだけのように思います。(動作の確認が不十分ってことです。)
<おまけ>
投稿写真"52)カイツブリの親子"は、[マニュアルフォーカス/置きピン]とまったく関係ありません。ただ動画つながりってだけです。
HD動画(1920×1080)からキャプチャーした静止画JPEGから価格コムサイズ(1024×1024)をトリミング、JPEG保存。ピクセル等倍になります。動画からのキャプチャーにはCanonデジカメ付属のZoomBrowserEXを、トリミング・再JPEG化には画質劣化がないらしい無料ダウンロードソフトのBuffを使いました。
キャプチャーしたトリミング前のJPEG画像は、フォト蔵のアルバム【HS10 疑問解消試し撮り】
http://photozou.jp/photo/list/197457/1292551
いつもは親鳥の羽根に隠れていてなかなか姿を現さない幼鳥。この時はHS10を三脚に載せて動画を撮っていたので、鑑賞に耐える静止画を撮ることはできませんでした。それで動画から静止画抽出を試しました。
書込番号:12099449
![]() 2点
2点
【第21回 太陽系を越えてオリオンへ】
既に弟子゛タル素人さんが[11937917]にて写真投稿してくださっているオリオン大星雲(M42星雲)、試みました。
53)ISO6400(リサイズのみ)
換算720mm、ISO6400、F5.6、1/2秒、WB:晴天、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT、手ブレ補正OFF、三脚使用。リサイズのみ。
54)ISO6400〜1600(等倍トリミング)
ISO感度を変えて、それぞれの最長露光時間に設定しました。ピントはこの時の撮影の1枚目で明るい星でマニュアルフォーカス、以降はピントはそのままで撮影。
512×512ピクセルをトリミング、4枚張り合わせで1024×1024ピクセル、価格コムサイズのピクセル等倍になります。(A)は"54"と同じ元画像です。
ぱっと見た目、(C)ISO3200がベストかな。
が、(A)(B)2枚のISO6400の細部を見比べると微妙に様子が違います。暗めの星の明るさも違います。星のままたきの原因、大気層のゆらぎ(かげろうと同じ)のためでしょうか。そうなら、偶然の幸運を期待して数多く撮った中から選び出すことが、より良い写真を得るには必要でしょう。今回は2〜3枚ずつしか撮ってませんでした。
換算720mm、背面液晶モニターで(明るい大三つ星でなく)オリオン大星雲のある小三つ星がかろうじて視認できるのでなんとかフレーミングできました。
きっかけを与えてくださった弟子゛タル素人さん、ありがとうございました。
<余談>
なんだかたいそうなサブタイトルになっちゃいました。【第XX回 銀河系を越えてアンドロメダへ】が実現できるかどうかは定かでありません。
ピクセル等倍画像を載せたので、フォト蔵のアルバム【HS10気楽にショット】のオリジナルサイズ画像はなし。
し、か、し、凄いですよね、HS10。
書込番号:12123696
![]() 3点
3点
Hey! デジタル錬金術師。
あなたがまた突拍子もない事やらかすもんだから、周り皆黙っちゃったじゃないですか。
私もISO3200が一番表現できてるとおもいますが、周りの星に目を向けますと、自転
の影響で幅広くなってますね。
電気を消してモニターを観るとA.Bとも霞の様なあわあわがあるのですが、コレ、ノイズ?
できればss1/10くらいで写して貰って、RAW現像重ね合わせて・・無理?
書込番号:12131890
![]() 2点
2点
こんばんは。
「霞の様なあわあわ」、温度警告表示(説明書13ページの[静止画撮影時]の[14])が出るまで、オートパワーオフ(説明書123ページ)をOFFにして30分ほどでも撮影時状態で放置した後、レンズキャップをしたままISO6400・1/2秒で撮ってみてください。
肉眼で見るよりHS10の方が暗い所で写るので、ノイズなのか空にあるもやもや(あわあわ)なのかはわかりません。
書込番号:12135288
![]() 3点
3点
【第22回 スポーツファインダー】
針金細工で作ってみました。スポーツファインダーなんて呼ぶのは気恥ずかしい、ただの素通しファインダーです。白いビニール被覆針金に赤・黒マジックで塗装。針金は100円ショップで購入。
レンズも何もない素通しなので視野も広く、EVFの表示遅れもないので、動きモノを狙うのにはイイかもしれない、と思って。望遠端の換算720mm、手持ちでは微妙なフレーミングは難しいので、それなら枠を厳密な大きさの長方形に作る必要もなかろうと、安易に円形で済ませました。
レンズフード側の支柱をわざと曲げて、曲がり具合で方向を微調整します。
とりあえず、おもしろそうに撮れたのを2枚。
55)56)自作スポーツファインダー
57)鴨離陸
換算720mm、WB:晴天、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT、AFモード:センター固定、クイックショット:ON。トリミング(1283mm相当)、リサイズ、輪郭補正、明るさ補正。
臆病な鴨、カメラから逃げることはあっても、カメラの方に近付いてくるのはあまりないようです。必死の形相です。
58)鴨飛翔
換算720mm、WB:晴天、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT、AFモード:センター固定、クイックショット:ON。トリミング(1283mm相当)、リサイズ、輪郭補正、明るさ補正。
目の前を飛び去ったシーンでなくて、こちらに向かってくるトコを撮りたいのはヤマヤマだけど、それが難しい。百発百中とは行かないけど、飛んでいる鴨にピントを合わせようとAFは頑張っているようです。
"57・58"のフォトレタッチ前のオリジナルサイズ画像は、フォト蔵のアルバム【HS10 疑問解消試し撮り】
http://photozou.jp/photo/list/197457/1292551
書込番号:12201198
![]() 6点
6点
【第23回 青赤イルミネーションのにじみ】
イルミネーションを撮った写真、ピンボケと見間違うばかりの写真が撮れました、ピントは合わせてたつもりなのに。ピントとブレに細心の注意を払って、撮り直しました。
59)リサイズ
60)ピクセル等倍トリミング
換算154mm、WB:晴天、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT
よく見ると、青色と赤色のイルミ光源のまわりにはにじみが見られますが、白色や緑色ではさほどではありません。目に鮮やかな青色・赤色のまわりのにじみに惑わされてピンボケに見えるようです。
この青色・赤色のにじみは何? ベイヤー配列の撮像素子とRAW現像や輪郭補正(シャープネス)などの画像処理を疑って検証しました。
ベイヤー配列では赤色・青色の画素数は緑色のソレの半分しかありませんから、赤色・青色は緑色に比べて原理的に解像感が悪い、ボケて見えても当然かも。
61)HS10 JPEGとRAW
カメラJPEGとHS10付属の RAW FILE COVERTER (SILKYPIX) で現像した画像、フリーソフトのRAW現像ソフトの UFRaw で現像した画像を、価格コムサイズでは200%拡大になるようにトリミングしたソレを3枚並べました。
初期設定のままの SILKYPIX が一番青色がにじんでいます。バイリニア補完の UFRaw は解像感は劣るものの青色のにじみは少ないようです。例写真は載せてませんが、SILKYPIX でシャープネスを強調すると青色のにじみは少なくなります。
62)A620 JPEGとRAW
比較のために5年ほど前の1/8型710万画素CCDの Canon PowerShot A620 でのRAW撮り・現像も試しました。これも200%拡大。
CCDのA620でも程度は違うものの赤色・青色にじみが見られますから、HS10の裏面照射C-MOS撮像素子の特性とは言いがたいようです。
HS10でもA620でも、JPEGやRAW現像補完の方法で赤色・青色のにじみは違うようです。またシャープネス処理でも変わるようです。純粋な赤色や青色は肉眼では緑色より暗く見えますし、赤画素・青画素の倍の数ある緑画素がシャープネス処理に大きく影響するのかもしれません。白色や緑色はシャープネスが効きやすいけど、緑色成分のない赤色や青色はシャープネスが効きにくくボケて見えやすいとか。
ココに載せた写真はHS10のシャープネス設定:SOFTで撮っていますが、STDやHARDだとまた違うかも、にじみが少なくなるかもしれません。
ベイヤー配列とRAW現像などの画像処理に原因があるとの前提で検証しましたが、別の前提では別の検証結果がでるかもしれません。たとえばレンズの色収差や、HS10独特の紫色の円盤フレアーも関係あるかもしれません。紫色は"赤色+青色"ですから。
また、青色や赤色イルミ光源にだけ光のにじみのように見せる反射板や散乱板があったり、風や人為的なソレでコードでぶら下がっているイルミが揺れて、1/20秒ではブレている可能性なども否定はできません。
<補足>
画素数1000万画素の一般的なベイヤー配列撮像素子のデジカメは、赤画素・青画素はそれぞれ250万画素、緑画素は500万画素です。この少ない画素データーからひとつのピクセルに赤色・青色・緑色の3色のデータを含む1000万ピクセルの画像を作ります。この変換作業がRAW現像時の画素補完です。
61)
換算137mm、WB:晴天、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT
SILKYPIX は初期設定のまま、UFRawはバイリニア補完・カラースムーシングOFFで明るさがJPEGと同じように見えるように調整しました。カメラJPEGや SILKYPIX と UFRaw では拡大が違って見えるのは、カメラJPEGや SILKYPIX では行われる歪曲収差の補正を UFRaw は行なわないためではないかと推測します。
62)
換算140mm、WB:晴れ、色効果:ソフト
A620は"色効果:ソフト"の輪郭の強調を抑えた設定、裏技CHDKでRAW撮りしています。UFRawではいくつかの補完が選べる中の、AHD補完はもっとも解像感が高いものの癖のあるノイズが出る補完、バイリニアは解像感は劣るものの癖の少ないノイズのソレです。AHD補完では擬色を抑制するカラースムーシングONです。
狙ったピント位置は機関車の前部の白いイルミネーションのトコロです。マニュアルフォーカス+[AE/AF LOCK]ボタンのカメラ検出のAF、あるいは、背面液晶モニターを虫眼鏡で確認しつつのマニュアルフォーカスで撮った複数枚の写真の中から最も良さそうなのを選びました。マニュアルフォーカスで、フォーカスリングを極わずか回して、微妙にピント位置をずらしたモノも撮りましたが、上記の[AE/AF LOCK]ボタンあるいは虫眼鏡のそれより良くなることはありませんでした。
もちろん三脚、10秒セルフタイマーです。
この書き込みのきっかけの写真は[12270838]
UFRawなどについては[11843102][11664439][11440397]
円盤フレアーは[11403201]
<余談>
写真は載せてませんが、シーンポジションの"夜景(三脚)"では、換算720mmでISO200・1/17秒・F5.6と、ココに載せた写真より1EV弱ほど明るい露出設定値になっていました。この方がココに載せた写真より華やかに見えるかもしれません。
まず"夜景(三脚)"で撮ってみて、その露出値を参考にマニュアル露出を加減するみたいな撮り方が失敗がすくなくイイかもしれません。いきなりマニュアル露出を試すよりは。
まぁ、検証と呼ぶには我ながら不満足なソレですが、それ以上に不満な人はご自身で確かめてください。
ピクセル等倍、あるいは200%拡大でココに載せたのでフォト蔵の方にはナシ。
書込番号:12311802
![]() 2点
2点
スッ転コロリンさん
あなたの熱心なのは解りますが、勉強途中の若い人たちにキチンと解るようにお話ししてあげてください。
あなたは自分だけ理解し、自分の満足の為に、自己満足の為に口コミしているのですか。
若い人が違うと指摘したらキチンと話して理解出来るまで、納得出来るまでお話ししてください。
じしいが意固地になってキチンと語らず、検証も結果も出さずに、新たに別な形で、いかにも検証したと偽りの口コミは恥ずかしいものです。
現場を知らない人たちに適当な嘘で固めるのはやめてください。
とりあえず、電灯にピンが来ている、の話ですから、電灯にピンを合わせたものと、そうでないものとの比較を撮影してください。
それと、
「この機会、自分のスタンスを表明しておくかな。意見は拝聴しますが、ためにならない議論をする気はありません。"捨てぜりふ"と感じさせるモノは、続ける意味がないと判断したことを臭わすメッセージです。
・・・だけでは失礼かとも思ったので、今回だけといろいろ書いてはみましたが、説得したりされたりする気も無いのが信条、でソレラは削除。あらためて・・・」
もキチンと撤回なさってください。この価格コムの全員を馬鹿にしていることになりますよ。
このようなことは、思っても表示しないことですね。
書込番号:12317663
![]() 3点
3点
【第24回 銀河系を越えてアンドロメダへ】
[12190406]でastro.bozuさんが紹介してくださった高感度長時間露光の裏技、あらためてありがとうございます。写っちゃいましたよ、アンドロメダ星雲。ISO6400・30秒で撮影直後、この緑色が背面液晶モニターに現われた時には、感激モノでした。HS10の裏技でない高感度長時間露光のISO6400・1/2秒では、そこに写っているハズの信念で、パソコン画面で明るくフォトレタッチ(レベル補正)してやっと現われるだけですから。
もちろん撮影時にはEVFでも背面液晶モニターでもソレの存在を確かめることはできません。換算720mmの画角で捉えられる近くには目印になりそうな明るい星もありません。
[12201198]の針金スポーツファインダーは、鳥撮りだけでなくこのためにも作ったモノ。暗い夜空のあの辺にあるハズで、覗き穴から見当をつけます。役に立ちました。
63)アンドロメダ星雲
換算720mm、ISO6400、8秒、F5.6、WB:太陽光、WV微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT、三脚使用、手ブレ補正OFF。リサイズのみ。
64)30秒〜1/2秒の4枚合成
写真はISO6400、露光時間30秒・8秒・2秒・1/2秒の4枚を、ピクセル等倍を100%表示とした時の50%表示となるようにトリミング・リサイズ・合成。
<補足>
一見星のように見える無数の白い点々はノイズで、線状のモノがホントの星です。日周運動で動いているので線状に写ります。アンドロメダ星雲も日周運動で動いているので、楕円形に写っているソレは星雲のホントの形ではありません。
8秒・2秒で見える"右端の星雲"と"左端の星"の中ほどにあるふたつの星が30秒に写っていない理由はわかりません、不思議です。
星雲の色が緑色なのはホントの色ではなくて、高感度長時間露光ではわずかな光が緑に写る(緑色に比べて赤色青色の感度が低い)特性があるのではと推測します。それゆえ、高感度長時間露光を封印してあるのかもしれません。
[12190406]astro.bozuさんの高感度長時間露光の裏技は
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11680503/#12190406
<余談>
65)オリオン座 30秒
換算26mm、ISO6400、30秒、F2.8、WB:太陽光、WV微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT、三脚使用、手ブレ補正OFF。リサイズのみ。
ISO6400・30秒の実写を見たい人もいるかと思うので。東の空、オリオン座を含んでいます。山の向こうが熊本市、街の灯りに照らされた星空は、眩しいほどの緑色に写ります。上端左右端や山肌のように十分暗い所では緑被りはありませんが、点々ノイズが目立ちます。
66)オリオン座 4秒
換算26mm、ISO6400、4秒、F2.8、WB:太陽光、WV微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT、三脚使用、手ブレ補正OFF。リサイズのみ。
"65"とは少し構図の違うソレ。こちらは露光時間4秒。換算24mmで撮っていたつもりですが、どちらも少しだけズームがズレていたようです。広角だからブレも目立ちにくいだろうと気を抜いてセルフタイマーは2秒だったかもしれません。オリジナル画像をチェックするとピントも微妙にずれている気も。
書込番号:12325835
![]() 2点
2点
ISO6400は私のテスト撮りでは無理という結論が出ています。
このようなドット表現が必要なものは特にダメです。
(いい加減で良いような被写体の画像には使えます)
おそらく私を信用しないスッ転コロリンさんでしょう。今回と同じようにISO3200で計算して自分で実験してください。
また、三脚はどっしりしたもの、押しても動かないぐらいのものを使ってください。
ピントも必ずずれますから必ずしっかりとガムテープでレンズに貼り押さえて撮影してください。
(ロングタイム撮影の常識です)
書込番号:12326106
![]() 2点
2点
ノンフィルターさん、こんばんは。
[12326106]、ありがたいご意見、いたみいります。
書込番号:12326529
![]() 1点
1点
今、夜空に写る緑色の星といったらハートレー彗星でしょう。
今はおおいぬ座のあたりにいる(オリオン座の左下の方角)と思います。
お写真はアンドロメダ大星雲ではないでしょうね。ちなみにアンドロメダ大星雲は実はとっても大きく、換算400mmで画面いっぱいになってしまいます。
書込番号:12326728
![]() 2点
2点
こんばんは、明神さん。
熊本の12月初めの夜10時頃、ほとんど真上、ちょっと西北よりのところ。前もって星図ソフトで確認、当夜は肉眼では星とはどことなく違うような光、双眼鏡では淡くボケた芯のない光のにじみ。点や線でなく面積を持って広がって写るのはコレしかないと思ったのですが。他にあるのかな?
「換算400mmで画面いっぱい」は意外でした。大きさを意識していたことはないのですが、肉眼でも双眼鏡でも月より大きいようには思えませんでした。
Wikipediaの"アンドロメダ銀河"によると
視等級 +4.3
視直径 190' × 60' (単位は角度の分)
月の直径は約0.5度(角度の約30分)ですから長い方は月の6倍、短い方でも2倍、それほど大きいとは思いもよりませんでした。もちろんこの数字は天文台の望遠鏡で観測したソレでしょうから、HS10で撮れた写真との比較には使えないでしょう。
ついでにWikipediaの"オリオン大星雲"
視等級 2.9等
視直径 66' x 60'
これとて月の2倍ほどの大きさです。[12123696]のHS10で撮ったオリオン大星雲は、とてもそれほどの大きさはありません。(HS10で撮ったピクセル等倍の月は[11984694])
ISO6400とは言え、換算720mm・F5.6(実焦点距離126mm・計算上の口径22.5mm)の三脚固定撮影では、星雲のもっとも明るい部分、肉眼で見えるほどの極めて限られた狭い部分しか写らないのかも、思います。
ネットで見かけたアンドロメダ銀河の写真は、ほとんどが赤道儀追尾で数十分露光の写真か、アンドロメダ座やカシオペア座からソレを見つけ出すための案内図みたいな写真で、比較できそうな超望遠三脚固定撮影ってのは見つけられませんでした。
アンドロメダ星雲であることを示すには、アンドロメダ座やカシオペア座が写った広い範囲の写真から段階的にズームアップして換算720mmまで撮って、写っている星々を比較・同定すればイイかと思いますが、かなり面倒そうです。
次の機会とやる気があれば試してみましょう。
<余談>
換算720mmの対角線画角を計算すると3.44度、アンドロメダ星雲なら長い方とほぼ同じ、月なら7個弱ならびます
星の三脚固定撮影、星が日周運動で線状になり、一方ノイズは点状であることを活かせば、フォトレタッチソフトのメディアンフィルター処理で、点状ノイズだけを消せそうです。
[12325835]"63)アンドロメダ星雲"のオリジナル画像を、無料ダウンロードソフトのIrfanViewにこれまたダウンロードしたPhotoShop用プラグインMedian.8bf(http://reddog.s35.xrea.com/)で処理してみました。つまらなくなるくらいにノイズが消えちゃいます。
換算720mm、ISO6400、8秒、F5.6。メディアンフィルター処理、リサイズ、(トリミングはなし)。
<余談の補足>
"点状ノイズ"と書いてますが、1ピクセルの点ではなく、数ピクセルの大きさがあります。ノイズは1ピクセルの点であることを前提にしたノイズ低減処理(メディアンフィルター)では消せません。Median.8bfは適用領域の大きさを広めに設定することで、消すことができるようです。
星が日周運動で線状に写らないほど露光時間を短くして星が点状に写れば、メディアンフィルターは星とノイズの区別がつかなくなって、ノイズも肝心の星々も全部消してしまうでしょう。(広がって写っている星雲は消えないかもしれません。)
星の写真のノイズ除去には、RAW現像時のダークフレーム処理や複数枚の合成(コンポジット)が有効と聞いてますが(ネットで見てますが)、パソコンの制約とやる気の問題で試してはいません。
書込番号:12330582
![]() 1点
1点
スッ転コロリンさん こんばんは。
この星雲の正体わかりました!
M33(三角座銀河)です!
この星雲、アンドロメダ大星雲から比較的近いところにあり、双眼鏡でも目視可能なんです。
以前、180mm(288mm相当)で撮った写真があったのでちょっと貼らせて下さい。左の2つの写真は180mmのMFレンズなのでレンズ情報が入っていませんがご容赦。
周りの星の関係なども似ているでしょ。
ちなみに同じレンズで撮ったアンドロメダ大星雲も貼っておきます。もっと露出時間を延ばしたり、画像処理をかければこの2倍くらいになるのですが、とりあえず撮って出しJPEGで。
アンドロメダ大星雲は広角でも写ります。
書込番号:12330906
![]() 3点
3点
こんばんは。明神さん、ありがとうございます。
M33とM31(アンドロメダ星雲)、アンドロメダ座を挟んだちょうど反対側のようですね。
ご掲示の写真も参考になると思います。対応する星の同定はこれから試みます。
次の機会、やる気になってきました。こんどは星図(星座図?)もプリントして持っていこうと思います、各ズーム焦点距離の画角、写る範囲を描いて。昔からの思い込みで位置を勘違いしていたかもしれません。
書込番号:12331250
![]() 1点
1点
さてさて、HS10でまともな写真が撮れるスッ転コロリンさんなのでしょうか。
嘘付く気は無いのでしょうが、間違いだらけが続きます。
これからのスッ転コロリンさんに期待して良いのでしょうか。
是非、良い方向に向かってほしいものです。 ガンバレー!!
書込番号:12332342
![]() 3点
3点
[12311802]【第23回 青赤イルミネーションのにじみ】のつづき
にじみは色収差、青色のソレは紫外線の色収差ではないかとの仮定から、後日試しました。
軸上色収差であれば絞りを絞る(絞り値を大きくする)ことで減ることが期待できますが、絞っても違いは感じられませんでした。
紫外線なら紫外線カットフィルターが効果あるかもと、手元にあったNikon製L37cフィルターを使って見ましたが、違いは感じられませんでした。
にじみは軸上色収差ではないようです。紫外線カット効果の強いフィルターならどうかは、わかりません。L37cフィルターは肉眼で見た目、ほとんど着色を感じられません。
書込番号:12390655
![]() 1点
1点
にじみは、強い光に起こる現象、又、明暗の激しい場所、暗い場所での明るい光線によって起こる現象です。大きいカメラなどではあおりや、F64とか絞って回避することも可能です。
他にはPLフィルターをよく使います。この場合はPLフィルターの効果は有りませんでしたか…?
書込番号:12412288
![]() 2点
2点
【第25回 ウルトラスーパーマクロ!?】
フィルム一眼レフ用の撮影レンズを逆向きにしてクローズアップレンズとして取付けました。レリーズケーブルをねじ込んでいる白いのはフィルムケースの蓋です。
「コンデジでもココまで撮れる」と見るか「コンデジじゃ〜」と見るか、悩ましい。
68)味の素
クローズアップレンズ(Canon FD50mm/F1.4)、換算720mm、ISO100、1/2秒、F11、WB:AUTO、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT。光源は天井蛍光灯とLED懐中電灯。リサイズ、輪郭補正。
69)食塩
クローズアップレンズ(Canon FD50mm/F1.4)、換算720mm、ISO100、1/2秒、F11、WB:AUTO、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT。光源は天井蛍光灯とLED懐中電灯。リサイズ、輪郭補正。
70)グラニュー糖
クローズアップレンズ(Canon FD50mm/F1.4)、換算720mm、ISO100、1/4秒、F11、WB:AUTO、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT。光源は窓外光とLED懐中電灯。リサイズ、輪郭補正。
71)外観
Canon PowerShot A620、換算52mm、ISO50、1秒、F8.0、WB:カスタム、色効果:ソフト。リサイズ、輪郭補正。
68〜69のオリジナルサイズ画像はフォト蔵のアルバム「HS10 疑問解消試し撮り」
http://photozou.jp/photo/list/197457/1292551
書込番号:12471684
![]() 5点
5点
フレーム幅は1mm位ですかね?もっと狭いですか?
ウルトラスーパー凄いです^^!
3枚目のグラニュー糖の粒などは、ピントのコサイン誤差が床面の被写体の手前にあり
その被写体へのピントの鋭さを如実に物語っているようです。
光学への理解、カメラレンズの造詣が深くなければ成しえないクローズアップの業ですネ^^
ヘリコイドしちゃったんですね^^!
新年明けましておめでとうございます。スッ転コロリン様^^
書込番号:12474444
![]() 2点
2点
こんばんは。興味をもっていただきありがとうございます。
写る範囲の目安、2.4mm×1.8mmです。
<補足>
歪みや1mm刻みの物差しを撮って読み取り推測する数値の信頼性は疑わしそうなので、計算値を目安にあげておきます。
画像の縦横比は"3:4"ですから三平方の定理より対角線は"5"になります。これらの数値で対角線から短辺・長辺を求めます。
35mmフィルムの大きさ24mm×36mm、「実焦点距離126mmが換算720mm」からHS10の撮像センサーの大きさを計算すると、
対角線長 : (√(24×24+36×36))×(126÷720)=7.57mm
長辺 : 7.57×4÷5=6.06mm
短辺 : 7.57×3÷5=4.54mm
クローズアップレンズとしての一眼レフ用レンズの焦点距離は50mm、HS10の実焦点距離は126mm。よって拡大率は
126÷50=2.52倍
これらから被写体の撮影範囲は
長辺 : 6.06÷2.52=2.40mm
短辺 : 4.54÷2.52=1.80mm
この計算はHS10のフォーカスが無限遠相当の時のソレです。実際の撮影では、無限遠相当とは限りませんから、微妙に違うかもしれません。検算・検証はしてませんが、実感、こんなものでしょう。
書込番号:12476132
![]() 2点
2点
ナイスを入れた人は納得、理解の上に入れたんだろうね。すごいなー。
私にはでたらめの計算式しか思えない。
なぜこんな計算式が正解とするのか??。。。
正解なの????????
書込番号:12477602
![]() 5点
5点
【第26回 太陽系に戻って土星】
72)土星 ピクセル等倍
換算720mm、WB:太陽光、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:ソフト、セルフタイマー:10秒。価格コム表示で等倍表示になるように512×512ピクセルの範囲をトリミング。
73)土星 RAW8枚合成200%拡大
RAW撮影、8枚分から合成。撮影条件は、1/20秒、高速連写の他は"72"と同じ。RAW現像。明るさ/コントラストのなどの調整、200%表示になるようにトリミング・拡大。
フォト蔵のオリジナルサイズ画像はなし。
土星については国立天文台の[今日のほしぞら]などを
http://www.nao.ac.jp/koyomi/
書込番号:12545881
![]() 3点
3点
だめだこりゃーー!! 左右14ドットでボケボケで何だか解らないよー!!
拡大したらよけいだめだーーー!!
なぜ望遠を使わないのだろー??
(自己満足レベルが低いのかなー)
書込番号:12547840
![]() 2点
2点
http://www.astroarts.jp/photo-gallery/gallery.pl/photo/4170.html
1000mmでここまで来るんだから、せめて理解出来る物を作ってください。
書込番号:12549301
![]() 4点
4点
【第27回 ぐるっとパノラマ】
説明書36ページ、およびフジのWebのFinePix HS10:特長
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/finepixhs10/feature003.html
写真は三脚の水準器で水平を出して、雲台(カメラ)を上または下に向けて雲台を水平回転させています。
74)空パノラマ
横構図、元サイズ:720×5760、撮影情報は上段のモノ
説明書に明記してある通り、空は苦手なようです。仰角(上向き角度)が増えて空の割合が増えると、水平時に較べて一見撮影画角が広くなったように写ります。が、つなぎ目をうまく認識できなくてデーターが欠落しているのでしょう、目立ちませんが。
もっと問題は、背面液晶モニターやファインダーでは見えているのに、実際は写らない範囲が上下にかなりあります。下段のような出来上がりを期待して地上ギリギリがファインダー下端に収まるように構図を決めたつもりでも、中段のように地上はカットされて写りません。カットされる分を見越して再度構図を調整したのが下段です。
75)俯瞰パノラマ
縦構図、元サイズ:1280×3240
何も考えずにパノラマを撮る時は、"74)空パノラマの上段"のように水平線(地平線)が構図の真ん中を横切るように構えて撮るかと思いますが、意図して仰角を付けても、この場合はマイナスの仰角、下向きにしても、うまく処理してくれるようです。思った以上に賢いのかも、HS10。
"76)狭角パノラマ"と"77)パノラマでない素の換算24mm"
縦構図、元サイズ:1280×1080
水平回転の度合を加減すると、"素の換算24mm"(対角線画角84度)よりも狭い範囲しか写らない写真も撮れちゃいます、パノラマなのに。
上記フジWebには左右方向・上下方向ともに3段階が示してあります。これらの撮り分け方はフジのサポートに聞いても教えてくれませんでしたが、実機でパノラマ撮影中に下端に表示されている"矢印"、これがカメラをパノラマ回転させると動くのですが、目安、半分ほどまで動いた所で回転をやめて、撮影完了するまで待つと最小画角のパノラマ。3/4ほどで回転中止で中間画角、最後まで回転すると最大画角パノラマに撮れるようです。
書込番号:12793651
![]() 2点
2点
【第28回 換算24mmの実測値】
HS20EXRの換算焦点距離疑惑が持ち上がって気になっていたのが、HS10の広角端の換算焦点距離はホントに24mmなのかな? 簡単に知る方法はないかと知恵を絞って・・・
手前と奥、2本の定規(巻き尺)を平行に並べて、広角端で写真を撮る。写ったそれぞれ長さと2本の定規の間隔から、"三角形の相似ナンタラ"でレンズ主点(レンズ中心)と被写体(定規)との距離が求められそう。この値と35mmフィルムカメラの諸数値とまた"三角形の相似ナンタラ"から換算焦点距離を。
<< 結論 >>
2本の定規の間隔 : 926mm
手前の定規 : 855mm
奥の定規 : 2205mm
以上の値から、広角端の実測値は換算焦点距離で【 23.7mm 】となりました。
<補足>
焦点距離は無限遠被写体の時のソレらしいので、無限遠相当被写体でマニュアルフォーカス・ワンプッシュAF。当然、近距離ではピントがあわないのでマニュアル露出で絞り値F11まで絞り込んで、ピンぼけながらもなんとか巻き尺の目盛りが読めるように。
目安のために巻き尺で合わせた"レンズ先端"までの距離は1500mmほど、奥の巻き尺からレンズ主点までの距離は計算では【 1512.5mm 】。まぁ、そんなものでしょう。光軸中央の目印にカマボコ板を立てています。
長さの読み取り誤差を±5mmとして、誤差を見越した換算焦点距離の最小値〜最大値は【 23.4mm〜24.1mm 】となりました。
上等な部屋ではないので、写真はぼかしてあります。
<余談>
実際の撮影ではどぉ〜でもイイコト。これがわかったからといって何も変わらないから。
書込番号:12815338
![]() 2点
2点
ヘイ、教授^^
実は、HS20のピントがあまり思わしく無いのですよ。
そこで頼みがあるんですけど・・色々撮り較べしてくれないですか?
まだ、この機種をお持ちでないと思うので送りたいのですが、妙案ないですかね?
例えば・・?? 強引で失礼かもしれないですけどお願いします^^
書込番号:12844346
![]() 2点
2点
こんばんは、[12844346]yellowfairyさん
撮り較べ、お力にはなれません。HS10の1年間の不具合と我慢をまとめて、近いうちにフジに点検修理に出すつもりですので。
また、機種の比較にはあまり興味ありません。今ある機種でどうしたらうまく撮れるかなら興味ありますが。
ご掲示の写真はクローズアップレンズを付けたモノではありませんか。クローズアップレンズにも普及価格・高価格の違いもあるようです。まずクローズアップレンズなしの素のレンズで、超望遠の"かげろうボケ"や手ブレ・被写体ブレのない状況、最低感度で、ご自身のHS10/HS20EXRで撮り較べしてみては。
ピントの甘さをごまかすためにはシャープネス設定を"強め"にするのは効果がありそうですが、比較するには逆に"弱め"にする方がイイかもしれません。比較するには2機種の画素数の違いも考慮する必要があるでしょう。
そして、明らかにHS20EXRが劣るようでしたら、フジにご相談を。
書込番号:12845171
![]() 2点
2点
1ヶ月以上前の記事ですが、
一気に読ませていただきました。
大変興味深い内容でした。
ノンフィルターさんがいい味出してます。
書込番号:13003541
![]() 4点
4点
こんばんは、ぺぺぺぺぺぺぺぺぺぺろんちーのさん。
お立ち寄りいただきありがとうございます。
このスレッドの更新、HS10の復活までには今しばらくかかりそうです。
書込番号:13005460
![]() 0点
0点
【第29回 広角端でF2.2で撮る裏技、他人の褌】
世の中には素晴らしい(?)コトを発見する人がいるものです。
カタログスペック広角端換算24mmでF2.8のHS10、なんとF2.2で撮れる裏技
2chの掲示板[富士フイルム FinePix HS10 Part5【光学30倍】]の#391以降
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dcamera/1300592338/391-
F2.8ではわずかに絞り込まれていて、裏技F2.2だと本当に絞りが開くようです。撮り比べしましたが、絞り優先AEでのシャッタースピード値を見る限り、効果はあるみたい。画質は、中央部ではほとんど違いなく、周辺部の色収差だかパープルフリンジだかが、微妙に違うかも、気のせいかもってぐらい。
この"0.6"の差、2/3段ほどになるかな。その分シャッタースピードを早くできるのは、暗いシーン、手持ちの夜景や室内ではブレを抑えるのに役に立つかも。
広角端だったかは定かでないけど、夜景で輝くライトみたいなの、"絞り開放"で撮ったつもりなのに、絞りの形を反映したような光芒が現れていたのが不思議でした。少し絞り込まれていたとすると納得いきます。
マニュアル露出の望遠端換算720mmでF29にする方の裏技、これは小絞りボケだか、ピントが甘くなるばかりで、実用性は疑問です。作例写真は略。
<余談>
しばしば目ざわりなほど見かける「明るいレンズ」の語句、Google検索してみました。検索結果の1番目が
http://aska-sg.net/shikumi/018-20060111.html
なるほどね、作例写真に「暗いレンズだと暗く写る」って示してあるな。これを読んだらああなるわけか・・・。
書込番号:13178635
![]() 1点
1点
【第30回 太陽の黒点】
別機種のスレッドの太陽黒点の写真に触発されて試みました。太陽撮影専用のフィルターではなくて汎用フィルターの3枚重ね。3枚も重ねたら"手軽"とは言いがたいって気も。
3枚のフィルターはレンズ側から
ND16(16倍の減光フィルター)
C-PL(円偏光フィルター)
C-PL でないAFのないフィルムカメラ時代の普通のPLフィルター(30年以上昔のモノ)
換算720mm、ISO100、F8、1/4000秒、WB:太陽光、シャープネス:ソフト。
AFモード:センター固定、試行錯誤のマニュアル露出、高速連写の1枚目。
C-PLと普通PLを重ねると減光度可変の減光フィルターになりますが、最大減光時は著しく青色になりました。写真は色の修正などはなく、リサイズあるいはトリミングのみ。
撮ってみるもんだね、黒点も太陽面の周辺の減光もそれっぽく写っちゃいました。輪郭のユラユラと言うかガクガクと言うか、大気の揺らぎ、陽炎でしょう。このユラユラ分、黒点の部分も甘く写っていることになります。そうすると、条件が良ければもっといけるのかも。
これでも明るすぎるなら絞り値F22の裏技も必要かと思っていたけど、そこまでは必要なかったようです。
西を向いて撮っているので左が南になります、大雑把。
触発された別スレッド
サイバーショット DSC-HX100V [ブラック]のクチコミ、デジカメ買い過ぎさんの[13268665]太陽
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13268665/
黒点情報 SWC宇宙天気情報センター
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
<余談>
以前から気になっていたのだけど、天体写真みたいな限界的写真を連写で撮ると、一枚めと以降残りは、微妙に画質と言うか粒状感が違うみたい。一枚目だけが粒状感は荒いけど解像感はいいみたい、ホント微妙だけど。
書込番号:13279936
![]() 1点
1点
スッ転コロリンさん こんばんは。
綺麗に撮れていますね。言われる通り陽炎で周囲がゆらいでいますが、黒点もはっきり写っていますね。
シーイングの良い時は、かなり使える事、間違いないですよ。
私の望遠鏡用フィルターを使うやり方は、口径が10mmに絞られるので分解能は不利ですね。(安さで勝負のやり方ですから仕方ないですね。)
それに較べて、スッ転コロリンさんのものはF値から計算すると15mmくらいなので、黒点の見え方が有利になっているように見えます。
いや〜スッ転コロリンさんのチャレンジ精神には頭が下がります。
以前の木星や土星の写真なんかも、あまりにも素晴らしくHS10の限界を極めていると思いましたし、ここまで分析を的確にされるなんて、非常に優れた技術屋さんだといつも感心しています。
これからもご指導よろしくお願いします。
書込番号:13280520
![]() 2点
2点
こんばんは、デジカメ買い過ぎさん。
おもしろいことのきっかけ、ありがとうございました。
これからもおもしろい事見つけたらやってみます。
書込番号:13280787
![]() 1点
1点
【第31回 レリーズタイムラグ】
HS10を使っていて、何がイライラするかと言うと、「ココゾ!」って狙った瞬間にシャッターが切れないこと。シャッターボタンを押して気持ちの悪い"間"をおいてから切れること、しばしば。
さらにイラツクのが、これを確かめようと室内や窓から外の景色に向かって安易な気持ちで試し撮りしても、現象が現れないこと。
"安易"でなく気合いを入れて確かめてみました。
シャッターボタン半押し後、オートフォーカス(AF)完了するとピピッ音やファインダー/モニター画面表示に現れます。普通のデジカメだと、ここで全押しすると間髪を入れずシャッターが切れるハズ、たぶん。
HS10の挙動をじっくり観察すると
、
(1)シャッターボタン半押し開始
(2)AF完了の合図(音や画面表示)
(3)一瞬、画面左下の[シャッタースピード/絞り値表示](以下[露出値表示]と記)が消えます。
(4)コンマ何秒か後、[露出値表示]が復活。
(5)シャッターボタン全押し、シャッターが切れて撮影。
で、(3)〜(4)の"コンマ何秒"かの間に全押ししてもすぐには応答しません。(4)で[露出値表示]が復活してから切れます。
この"コンマ何秒"、以前は手ブレ補正機能の準備時間じゃないかと勘繰っていたのですが、明るさに関係しているようです、露出値ではなくて被写体の明るさ。レンズキャップをしたまま(真っ暗)マニュアル露出で1/4000秒でも1秒でも1秒弱(コンマ8〜9秒)、昼の明るい屋外では体感的には瞬時(コンマ1秒?)。ただし望遠側だと開放F値が大きくなるからか、ちょい長くなります。
(たぶん)普通のデジカメだとAF後は瞬時に撮れていた、というより、AF完了までの時間を体感会得・予測してシャッターボタン全押ししていたのが、HS10だと被写体の明るさやズーム度合で変わる予測できない得体の知れない"間"にイライラさせられていたってコト。
で、発想の転換・・・
AF完了後画面左下をにらんでちょい待機、(4)の"[露出値表示]の復活"を目視確認してからシャッター全押し。これだとシャッターボタン全押し後すぐ切れるからイラダチも少なくなるかも、シャッター半押し開始から撮影までの総時間が短くなるわけではないけど。
<補足>
説明書26ページには「AFが合うとインジケーターランプが緑色に点灯」みたいに書いてありますが、シャッターボタン半押し開始から"緑点滅"、これが点きっぱなしの"点灯"に変わったかどうかは、"点滅でない"ことはしばらく見ていないとわかりません。さらに、AUTOで露出不足になるほど暗いと、AF合焦しても"点滅"のままです。それで、このインジケーターランプは役に立ちません。
シャッターが切れる時の「カシャッ」の電子音、1秒未満のシャッタースピードではシャッターが"閉じる"時に鳴っている雰囲気です。ここで扱っているのはシャッターが"開く"ですので、スローシャッターで試す時は注意を。
<余談>
先日の花火撮影であまりにもタイミングが合わないので、今回気合いを入れて探ってみました。購入から1年以上経った数日前、気付いたことです。まぁ「そんなコト、先刻承知ヨ!!」って人がいるとは思うけど。
今回は作例写真はありません。
別の不具合らしきものに気付いたのだけど、それは新規スレッドを立ててでも。
書込番号:13410288
![]() 1点
1点
【第32回 画像拡大チェックで[DISP/BACK]ボタン】
ひょっとして「知らなかったのは自分だけかも」って気がしなくもないが・・・
説明書121ページの[画像拡大チェック]、[DISP/BACK]ボタンも有効です。[再生]ボタンも。
1年以上これに気付かずに、[画像拡大チェック]から[撮影済み画像確認]するのに、一度[シャッターボタン]半押ししてから[再生]ボタンを押してました。説明書には[シャッターボタン]は書いてなくて[MENU/OK]ボタンしか書いてないけど。
[DISP/BACK]と[再生]、一見同じような挙動だけど、
【第29回 広角端でF2.2で撮る裏技、他人の褌】
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11247209/#13178635
の[拡張開放絞りF2.2設定]は[再生]では無効になりますが[DISP/BACK]では継承されます。
ただし、[再生]では続く[info]ボタンでのヒストグラム表示などの[撮影時情報確認]が使えますが、[DISP/BACK]では使えません。
状況や目的に応じて使い分ける意味があるかも、どぉ〜でもいいかも・・・。
書込番号:13411496
![]() 1点
1点
【第33回 AF前後のプチフリーズ】
"プチフリーズ"の用語、一般的なのか小生の解釈が正しいのかは別として・・・
一瞬、画面が固まったように、それまで滑らかに表示更新されていたのが瞬間静止画に見えること。
AF(オートフォーカス)ではAF開始(シャッターボタン半押し開始)とAF完了の2回起こるようです。
静止している被写体では気になることはありませんが、動いているモノを追う"流し撮り"では、滑らかに追っていたつもりが、突然「カクッ」と止まって表示されて慌ててしまいます。
マニュアルフォーカスでも[シャッターボタン半押し開始]のプチフリーズは起こります。さすがにAF完了はないけど。
この回、あらためてココに書こうとしたきっかけは"打ち上げ花火"、「ヒュルルル〜」と上がってシャッター半押しの瞬間プチフリーズ。「しまった全押しか!!」と思い違い、で、再度半押しすると
[13410311]AF完了後に素早く再度シャッターボタン半押しで不具合
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=13410311/
が起こってシャッターが切れず絶妙のシャッターチャンスは幻・・・、することたびたび、困ったものです。
頭では起こることが理解できていても、撮影のその場では・・・、精神衛生上よくないです。
書込番号:13426149
![]() 1点
1点
【第34回 コンティニアスAF(C-AF)】
初心者向けの便利機能と思いこんでいて、当初はほとんど使った記憶がないコレ、最近、思い直しました。
「動きのある被写体の撮影に適しています」と説明書にも書いてあるように、あらためて表通りを30〜40キロで走るクルマを斜め前、50mほどのトコから狙ってみても、まぁ使えそうな雰囲気。
思い直した使いこなしの最大のポイントは、シャッターボタンの[一気全押し]を心掛けること。説明書にも書いてあるけど「C-AFでない普通のAFの時はシャッターボタン[半押し]を意識すること」が大事。一方、C-AFでは[半押し]は無視して[一気全押し]。
より確実にするには、まずAFフレームに的確に捉え続けるために[手ブレ補正:常時]。それでも換算720mmでは捉えるのが難しいから換算500mm以下で抑える方が。そして動くモノを追うってことでISO感度はちょい高めISO400ぐらい、昼間でも。高くなったISO感度を早くできるシャッタースピードに回すか、被写界深度を稼げる絞りに回すかは、これからの要検討。とりあえずはシャッタースピードの方がイイ気がするけど。
HS10のC-AF、【シャッターボタンを押していなくてもAFを続け、半押しで再度AFをやり直し】。前回【第33回 AF前後のプチフリーズ】で触れたように、[半押し]を意識するとプチフリーズした瞬間に、それまでAFフレームで滑らかに追っていた被写体が逃げてしまいがちです。ここで素早く[半押し]をやり直すと・・・
[13410311]AF完了後に素早く再度シャッターボタン半押しで不具合
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=13410311/
・・・この不具合のドツボに落ち込んでしまいます。
[半押し]を無視して[一気全押し]すると昼間の明るさならコンマ何秒かのタイムラグでシャッターが切れます。もちろんAFフレームから外れていた場合にはピンボケ写真になるコトもあるわけですが、上の不具合で撮影タイミングを逃してしまうよりはマシです。
<余談>
サーキットを疾走するレーシングカーも中央のAFフレームに捉えられている限りはなんとか写ります。が、それがジャスピンだったかは今は確認することができません。撮れた写真のEXIF情報を解析しても、普通のAF(S-AF)とC-AFとを区別することができないからです。たくさんの写真の中のどれがC-AFだったのかがわからないからです。
【シャッターボタンを押していなくてもAFを続け〜】、これってどうなんだろう、被写体を狙っていない時も電池消耗するわけだし。シャッターボタン[半押し]でC-AFする方が理にかなっているような。フジの考えていることはわからん・・・。
まぁ、[撮影画像表示:画像拡大チェック]にしておいて、撮影後も[画像拡大チェック]のままにしておけば、撮影状態ではないから[C-AF]も[手ブレ補正:常時]も働いてない、電池消耗しないと期待したいけど。
・・・と言うわけで、サンプル写真はなし。興味のある方はご自身でお試しください。って、確かめてもいなかったのは小生だけかもって気も。
書込番号:13621518
![]() 1点
1点
【第35回 広角での中心部と周辺部のピント】
"86"は"87"の中心部をピクセル等倍トリミングしたもの。
"86"を少し離れて見ると、真ん中付近に円形のピンボケが見える気がします。ズームは広角端の換算24mmではなくて換算27mmほど、今となっては断定はできないけど、この構図なら右のカラフルタオルにピントを合わせていたと思います。
どう理解していいものやら・・・。中央部と周辺部とで像面ピント位置が違っていて、手前のタオルに合わせたピントでは、周辺部では被写界深度内に収まっているものの、中心部はソレに収まらなくなったとか。
HS10を使ってもう1年半ほどかな、広角でのピントはよくわかりません。中心はまあまあだけど周辺部は流れがひどいとか、中心部で無限遠被写体を狙う時は無限遠でなく5〜10mほどの中距離(?)でAFロックして撮った方がイイと感じることも。かと言って、断言できるほど顕著ではないし。
写真の中心ピンボケとそれらが関係あるのかもわからないけど、気持ちはモヤモヤしたままです。まぁ、ここに書いてもすっきり解決する気もしないけど。
<余談>
とは言うものの、弱望遠とでもいうのか換算50〜135mmあたりで撮った遠景は、オヤッと感心するほどのピントが来ている写真も(時に)撮れます。1年半で、評価する眼が慣れたと言うか甘くなっただけかもしれない、そんな心配も。
書込番号:13683529
![]() 1点
1点
【第36回 彩度最大RAW現像較べ・夕方の日暈編】
日暈のスレッド[12912889]に貼った写真、見返すと恥ずかしくなるくらい酷いのであらためてRAW現像チャレンジ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12912889/#13744983
88)
付属の Raw File Converter (HS10専用機能限定Silkypix)で現像。
ホワイトバランスはデフォルトのカメラ設定を引き継いだモノ(ひょっとすると"太陽光"固定かも)。彩度を最大、ノイズ除去も最大、他にもいくつかの設定をいじって。Tif出力をNeatImageでノイズ除去して、GIMP2で傾き修正、トリミング、リサイズ、再JPEG保存。
89)
無料ダウンロードのRAW現像ソフト Rawtherapee で現像。
現像の方針は"88"と似たようなモノ、歪曲収差補正・色収差補正あり。NeatImageのノイズ除去はなし。GIMP2で傾き修正、トリミング、リサイズ、再JPEG保存。RawTherapeeで傾き修正やトリミング・リサイズができたかもしれないけど、使いなれたGIMP2で。
90)
換算24mm、WB:晴天、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT。リサイズ、再JPEG保存。
カメラJPEGだけを見た時、日暈が写っているのはわかったけどそれだけ、特に感慨もなし。あらためてRAW現像してみて、ダイナミックな色合いは凄い、と感激。カメラJPEGが白黒写真に見えちゃう。
どれが本当の色だったかは、今となってはわからないけど。
RAW現像で彩度は調整できるけど、ホワイトバランスの調整だけでは気に入った色合いを作り出すのは難しいのかな。ちゃんとした市販のRAW現像ソフトだとできるのかな、使ったことがないからわからないけど。
書込番号:13749723
![]() 1点
1点
D3 の掲示板にHS10で殴り込みですね!(こう言っちゃ失礼ですか?)
その日暈が右の途中で途切れるところで・・これは雲のレンズ効果なのでしょうか?
書込番号:13750134
![]() 2点
2点
こんばんは、yellowfairyさん。興味を持っていただきありがとうございます。
[13750134]「雲のレンズ効果」、わかりません。日暈を映し出す雲がそこで途切れたからかな。
書込番号:13753247
![]() 1点
1点
【第37回 高速連写・前後撮り連写の画像のゆがみ】
シャッタースピード1/4000秒で10fps連写、疾走するレーシングカーを撮ると伸びたり縮んだり歪んだり。
91)普通に横構図
92)普通に横構図
93)シャッターボタンが上の縦構図
94)シャッターボタンが下の縦構図
手持ち、流し撮りでなくカメラの向きは固定してココゾの瞬間に連写、たぶん"前後撮り"ではなく普通の"高速連写"。
ISO1600、1/4000秒、F5.6、WB:くもり、マニュアル露出、マニュアルフォーカスの置きピン。
トリミングなし、リサイズのみの連写の2〜3コマを並べて1枚に合成。
ズームを適度に抑えて車体全部が1枚に収まるようにした方が作例として現象は見やすいのだろうけど、撮影直後の画像の確認で、コマが連続しているのが面白かったのでついつい。
上下逆さまの横構図も試せばよかっと、後の祭。
<補足>
動画用のC-MOSセンサーでは「ローリングシャッター現象」とか呼ぶらしく、静止画ではくだけて「こんにゃく現象」とかも呼ばれている雰囲気。
「ローリングシャッター」でweb検索してヒット
Fujifilm ローリング歪みを読出方向の工夫で軽減する特許〜sonetのえがみさんのブログより
http://egami.blog.so-net.ne.jp/2011-10-19
出願日が 2010.3.19 だとHS10には間に合わなかったかな、その後のどれかの機種に採用されたかもわからないけど、フジも気にはなってたわけだ。
他社では機械式レンズシャッター(グローバルシャッター)を連写時にも働かせて「こんにゃく現象」をなくしているみたい。
<余談>
個人的には「ローリング〜」よりは「ライン順次露光・読み出し」としてくれた方がイイとも思うのだけど。対する用語の「グローバルシャッター」は「全画素同時露光〜」とか。
一眼レフのフォーカルプレーンシャッターでも似たような現象はあって、これも「ローリングシャッター現象」と呼んでることもあるみたい。
この例は流し撮りではありません、念のため。流し撮りをすればクルマの歪みはないハズです、流れた背景の方は歪んでいても気にはならないかと。
書込番号:15078054
![]() 0点
0点
【第38回 広角端でF2.2で撮る裏技<続編>】
[13807611]やこのスレッドの[13178635]でも触れた、広角端換算24mm/F2.8をF2.2まで開いてしまう裏技。違いのわかりやすい写真が撮れたので手順を改めて紹介。
<手順>
(1)[A:絞り優先AE]または[M:マニュアル露出]モードで
(2)ズームを広角端換算24mm、絞りをF2.8に。
(3)望遠端換算720mmにズーム。
(4)シャッターボタンを半押し、半押ししたままズームを広角端換算24mmに戻してシャッターボタン全押し。ピンボケの写真が1枚撮れます。
(5)[コマンドダイアル]を左右どちらでもいいので1クリック分回します。これは絞り値を変更する操作です。[M:マニュアル露出]モードでは[露出補正ボタン]を押したまま[コマンドダイアル]を。
(6)これで拡張開放絞りF2.2になります。
<F2.8とF2.2の比較写真>
換算24mm、WB:電球、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:ソフト、マニュアル露出。リサイズのみで色合いや明るさの調整はなし。
手持ちですので微妙に構図がずれてます。
同じISO感度・シャッタースピードでの絞り値違いの分、明るさも違います。街灯のハレーション(にじみ)に違いが見えます。F2.8ではわずかに絞られた絞りの形が反映されています。
<補足>
ズーム操作したり[モードダイアル]を回すと、F2.2は解除されます。
(4)でズーム戻しを、たとえば換算50mmで止めると、F2.8になります(本来はF3.6)。
[M:マニュアル露出]・広角端でF11、シャッターボタンを半押ししたまま換算720mmへズーム、全押しピンボケ写真を1枚、[露出補正ボタン]+[コマンドダイアル]で絞り値変更操作すると拡張最小絞りF29になります。[A:絞り優先AE]ではF20。
換算720mm/F29の写真も撮ってみたのですが、小絞りボケなのかどうにもピンボケ、使い物にはならないようなので写真はナシ。
今回、ファームウェアバージョン1.04で確認しました。
[13178635]で紹介した2チャンネル掲示板はリンク切れのようです。
【重要】
カメラが不調になっても小生は関知しません。説明書にはない使い方のようですので、いわゆる自己責任ということで。
書込番号:15081296
![]() 0点
0点
【第39回 ISO6400で30秒露出 高感度長秒露出の裏技】
HS10をマニュアル露出でいじって、たぶん誰もが「だまされた!」と思う仕様、高感度ではカタログスペック(仕様)通りの長秒露出ができない制約。
仕様ではシャッタースピード[M:30秒〜1/4000秒]とありますが、30秒露出ができるのはISO100の時のみ、感度が上がるにしたがってシャッタースピード値は短く(速く)なって、ISO6400では1/2秒までしか使えません。
にもかかわらず、ISO6400で30秒露出を可能にする裏技。
(1)[モードダイアル]を[M:マニュアル露出]モード
(2)ISO100・シャッタースピード値を30秒「30"」に。「"」の付かない「30」は1/30秒です。絞り値は適当ナンデモ。
(3)[撮影メニュー]の[カスタム保存]の手続き。説明書97ページ・42ページ
(4)[モードダイアル]を[C:カスタム]モード
(5)ISO感度を[ISO6400]に変更。説明書58ページ。
これでISO6400、シャッタースピード30秒に設定完了、とりあえずは。
(6)もう一度(3)の[カスタム保存]の手続き。
(6)の手続きで、次回からはモードダイヤルを他のモードから[C]に回すことで、あるいは[C]にしたまま電源ONで簡単にISO6400・30秒が実現できます。
[コマンドダイアル]を回す(シャッタースピードを変える操作)でシャッタースピードが短くなる方へは変更できます。30秒に戻したい時は[C]のまま電源OFF/ON。ISO感度も変更できます。
前回書込[15081296]の[広角端でF2.2で撮る裏技]もこのあと続けてできます。ただし30秒露出時は、シャッターの開いている時間(露光時間)に30秒、長秒撮影ノイズ除去にも30秒、計60秒の間カメラは黙々と働き続け、一見操作不能のようになります。カメラが壊れたと勘違いして電源OFFや電池を抜いたりしないように。
逆の手順、F2.2に設定した後でISO6400・30秒に設定することはできない雰囲気です、試した限りでは。
ここでの手順は[12190406]でastro.bozuさんが紹介された手順を元にして少し変えています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11680503/#12190406
(要点は、あらかじめ[M]を[C]に登録しておくと、[C]で働く[M]の挙動が本来の[M]とは違って高感度時のシャッタースピードの制約がなくなるようです)
<余談>
ISO6400・30秒を活かすシーンってのはそうそうはないようで、適当な参考写真は用意できませんでした。
このスレッドを遡った[12325835]に夜空(オリオン座)の写真がありますが、夜空の僅かな街明かり(光害)でもカラーバランスの崩れた緑色に写ってしまいます。光害のない真っ暗な星空に憧れているのですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11247209/#12325835
シャッタースピードの制約、他機種では[高速シャッターと絞り値]に制約があるモノもあるようです。その点、絞り値に関係なく1/4000秒が使えるのは、ちょっとだけうれしい、かも。
【重要】
カメラが不調になっても小生は関知しません。説明書にはない使い方のようですので、いわゆる自己責任ということで。
書込番号:15085081
![]() 0点
0点
【第40回 明るいシーンの連写重ね撮り】
知らなかったのは自分だけかも。「暗いシーンの高感度でもノイズの少ない写真が撮れます」の効能書きから、「暗いシーン専用」と勝手に思い込んでいたのだけど、明るいシーンでも撮れちゃうのね、ちゃんとISO100で。
(97)まずは4枚比較、ピクセル等倍になるように元写真から512×512ピクセルの範囲をトリミング、4枚並べて1024×1024ピクセルに合成。
・オートモード(JPEG+RAWの高速連写5枚の1枚目)
・連写重ね撮りの処理前画像
・連写重ね撮り(4枚合成)
・上のオートモード、JPEG+RAWの高速連写5枚からRAW4枚を合成
4枚合成するとザラザラ粒々ノイズが少なくなってます。理屈から考えると、複数枚合成するとノイズが少なくなって、一枚だけ写真(単写)ではノイズに埋もれて見えなかった微妙な濃淡(ディテール)が見えてくるハズ。確かに4枚合成するとザラザラ粒々ノイズが少なくなってます。
「コレは凄い! 大発見!!」と喜んではみたモノ、コレを活かす被写体には巡り合えずにしばし悶々。とうとう9月に撮っていたソレっぽいかな?ってのを引っ張り出しました。
(98)連写重ね撮り〜もこもこ雲
換算324mm。フォトレタッチ(明るさ、かなりの輪郭補正、リサイズなど)あり。
ノイズが少なくなった分強力な輪郭補正(ディテール強調)ができるハズともくろんで、「なんだか凄く仕上がったぞ」と喜んだのもつかの間、連写合成でないオートモードで撮ったソレを同じように処理して価格コムサイズ(長辺1024ピクセル)にリサイズしたら、どっちもあまり変わらなかったりして。
(99)連写重ね撮り〜ねっとり湖面
換算31mm。フォトレタッチ(わずかな輪郭補正、リサイズ)あり。
三脚でなく、公園の遊歩道の橋の手摺りにカメラを押し付けて撮影。微妙なブレを微妙な輪郭補正でごまかし。
水面のわずかなさざ波が4枚合成で消えて、油を流したようなねっとり感に見えなくもないかな。
<補足>
三脚・"手ブレ補正:切"・セルフタイマーでカメラブレを極力なくすことが肝要です。手持ちでは手ブレ補正が効いていても極端に解像感が悪くなります。
[普通の単写]に較べて[連写重ね撮りの処理前画像]は著しくノイズがあります。連写重ね撮りはノイズ除去する前のデーターを合成していて、この前画像が出力されているのかも。これが裏面C-MOSセンサーの素に近い写真だとすると怖い・・・。
[RAW4枚合成]は試しに試みたモノ。本題の連写重ね撮りとは違うので評価は割愛。
<余談>
コンパクトデジタルカメラで昼間撮るのに三脚は邪魔。いや、無骨でサイズだけはでかいHS10ならデジイチぽくて恥ずかしくはないかな、真摯に写真を撮ってるようで。
今後、"昼間の連写重ね撮り"が活きるシーンに巡り合っても、そんな時に限って三脚は携行してないような気もします。
なお、[連写重ね撮り]はノイズ減とそれに伴う微妙なディテール(濃淡差)の回復描画が効能で、強引な輪郭補正で解像感が一見良くなったように見えても、本当の解像感は向上してないハズです、たぶん。
書込番号:15221876
![]() 3点
3点
【第41回】偏光フィルターのフレアー
「ちょっとこだわってみるか」で雨上り直後の曇、三脚に偏光フィルターと気張って紅葉撮りに出かけた時のこと、撮影直後の写真を背面液晶モニターで見ても、あまりりにも抜けの悪いシーンが。
偏光フィルターに直接空からの明かりが当たる逆光のシーン、特に顕著。一面白けていてこれがフレアーか。
帰って、フィルターにハンディLEDライトを当てて確かめてみました。透明無色のプロテクトフィルターに較べても、かなり光を散乱するようです。
まぁ、偏光フィルターの効果とフレアーの害、状況に応じてまめに付け外しましょうってこと。
偏光フィルター: marumi Degital Circular P.L.D 58mm、コーティングの反射は緑色、中古品購入。
プロテクトフィルター:Kenko PRO1D PROTECTOR(W) 58mm、コーティングの反射は薄青色、新品購入。
"紅葉と瓦屋根"の写真は、比較を意図して撮った写真ではありません。露出の違いなども見た目に影響します、たぶん。偏光フィルターの効果は"瓦の照かり具合"でわかるかと。
書込番号:15422485
![]() 1点
1点
【第42回】ベイヤー画素配列の画素補間処理シミュレーション
HS10ユーザーにとっても、そうでない人にも、ほとんどどぉでもいいハナシ。
RAWファイルから色情報のない画像を抜き出して、それに色フィルターを重ねてとりあえず着色、足りない色はまわりの画素から補ってフルカラー天然色画像のできあがり。RAW現像ソフトがやってくれてることを、わざわざグラフィックソフトでシミュレーション、使ったのは PaintShop Pro 4.2J (for Win95)。
"103)"は元画像から512×512ピクセルをトリミング、4枚合わせて1024×1024ピクセル。各ピクセルが見やすいように、これを400%拡大してアップロード。
103)A
一応はRAW現像ソフトだけど、無料ダウンロードソフトのDCRawに"-v -w -d -W -T"オプションを付けて得た色なし画像。純粋無垢のRAWデータそのものでなく、あとのカラー化のためにホワイトバランスに相当する係数が各画素データに施されています。
103)B
ベイヤー配列画素センサーのカラーフィルターに相当するモノ。2×2のベイヤー単位配列は、HS10ではBGGRの並びのようです。
103)C
上記"A"の色なし画像に"B"のカラーフィルターを重ねると、とりあえずは色付き画像になります。実際には"A"と"B"の乗算、具体的には"104)設定"の"演算"。ベイヤー配列の2×2単位配列には青・赤画素は1個ずつ、緑画素は2個あるので、緑の強い画像になるのでしょう。青画素のピクセルには赤と緑のデータはなし(値=0)、赤・緑の画素も同様ですから、かなり暗い画像になります。
103)D
補間処理、それぞれの画素で、値=0でデータのない色を隣接画素から補います。赤画素と青画素では隣接する上下左右4画素から緑色を("104)設定"のファイル名:G)、赤色と青色のない緑画素は上下あるいは左右の2画素から(同ファイル名:R&B)、みたいに。これらはもっとも簡便な処理だと思います。実用に耐えるRAW現像ソフトは、もっとムズカシイ処理をしているものと察します。
104)
PaintShop Pro の設定画面のWindowsスクリーンキャプチャー。わかる人はわかるだろうし、わからない人は勉強してくださいまし、説明も面倒だから。無料ダウンロードソフトのGIMP2でも同様のことはできたかと思います。
105)
補間後の天然色写真。明るさやコントラストの適正化、輪郭強調・ノイズ除去などは施されていません。拡大で左端に見られる橙色の縦線はソフトのバグかメモリーの異常でしょう。なにしろWin95時代の化石のようなソフト、当時は今のデジカメの1000万ピクセルを越えるような画像をパソコンで扱うなんて考えてなかった時代かもしれませんから。
106)
カメラJPEG。毎度のコト、EXIF編集あり。
書込番号:16073476
![]() 1点
1点
【修正】
EXIFがないと拡大鑑賞はできないみたい。
[16073476]の1枚目、"103)補間処理経過"に"106"のEXIFをコピーして再アップロード。
拡大鑑賞できるといいのだけど・・・。
書込番号:16073523
![]() 1点
1点
【第43回】拡張マクロ
仕様を越えて近付いて大きく撮る裏技。換算135mm・撮影距離13mm(13cmでない!)で長辺29mmの範囲が撮れるようになります。
<手順>
(1)マニュアルフォーカス、[A:絞り優先AE]または[M:マニュアル露出]モードで
(2)ズームを広角端換算24mm、絞りをF2.8に。
(3)望遠端換算720mmにズーム。
(4)フォーカスリングを"近距離側"に十分に気の済むまで回す。
(5)シャッターボタンを半押し、半押ししたままズームを換算135mmに戻してシャッターボタン全押し。ちょっと見、ピンボケの写真が撮れます。
一見ピンボケのこの時、ピント位置は仕様の範囲を越えて極めて近距離になってます。換算135mmで撮影距離13mm。
フォーカスリングを回したり[AE/AF LOCK]ボタンを押すと、"拡張マクロ"は解除されて仕様の範囲に戻ってしまいます。ズームリングを回しても。
(1)〜(5)は、(4)を抜くと、ズーム戻しの換算焦点距離が異なるだけで[15081296]の【第38回 広角端でF2.2で撮る裏技<続編>】と同じです。換算135mmの通常開放F値はF4.5ですが、(5)に続けて絞り値変更の操作をするとF3.6の"拡張開放絞り"になります。
換算135mm・F3.6でなくF8で撮りたい時は(2)でF8に設定して同様の手順、そして絞り値変更の操作でF8に設定できるようです。
ズーム戻しの換算焦点距離を変えると
換算200mmで、撮影距離90mm、長辺37mm
換算300mmで、撮影距離220mm、長辺47mm
ほどになるようです、厳密には測っていませんが。
撮影距離はレンズ鏡筒先端、フィルターねじのあるソコからの距離です。カタログ等にある"レンズ先端からの距離"が"レンズのガラスの先端"ならば、少し基準が異なるかもしれません。
<補足>
仕様では
(普通の)マクロ: 広角端約10cm〜/望遠端約2m〜
スーパーマクロ: 広角端限定で約1cm〜
実撮影ではこのスレッドを遡った[11259568]
(普通の)マクロの倍率最大: 換算約135mmで撮影距離8.3cm・長辺45mm
スーパーマクロ: 撮影距離1mm・長辺34mm
これらのどれより狭い範囲を大きく撮れます。
オートフォーカスしたりフォーカスリングを回すと"拡張マクロ"は解除されるので、現実にはカメラを前後させて距離を合わせることになります。被写界深度が極めて浅いので手持ちではかなりムズカシイかも。なにより画素数の貧しいHS10のEVFや背面モニターではピントがどこにあるのかさえ判りづらいです。
三脚固定(手ブレ補正は当然OFF)で撮る時、"拡張マクロ"状態でシャッターボタン半押しした瞬間、それまでとピント位置や構図が微妙に変わって見えます。原因も対処法も不明です、今のところ。
写真はRAW撮り、RawThrapee Ver3 でRAW現像、JPEG化。色収差補正あり、歪曲収差補正ナシ、通常写真と同じ程度の輪郭・ディテール補正あり。ホワイトバランスはカメラ設定を継承、明るさ・コントラストは意図して操作しない、いわゆる"眠い"ままです。写真のEXIFの実焦点距離から計算すると換算131mmほどになります。F値はF3.6でなくF4.5になってます。
ズーム戻しの換算焦点距離を短くすると、撮影距離も更に短くなりますが、レンズのガラスに近過ぎて危険でもあります、ほどほどに。ひょっとするとピント位置がレンズのガラスの内部にあるようになるかも。
なお、これらの操作で不具合が起こっても関知しません、いわゆる自己責任ってヤツで。
<余談>
2010年4月の発売以来、4年と3ヵ月。今さらの感がしなくもないかも。
書込番号:17746035
![]() 1点
1点
2010年4月の発売から5年を超えて、イマサラだけどマダマダなのだ。
【第44回 ポートレートモード】
奇麗なお姉さんを撮る機会もなくて、未体験のほったらかしだったポートレートモード。「いっちょ試してみるか」で試みたのは去年の7月。
「顔キレイナビ」(顔認識)でAF枠に気を遣わなくて済むのは楽チン。一方、綺麗に撮るには最低感度のISO100で撮りたいところだけど、曇りの天気、望遠にズームすると勝手にISO200になって、たぶんカメラ内画像処理でソフトな効果を与えているのだろうと思うそれも、自分の基準では「ピントの甘い失敗写真」にしか見えなかったので、撮れた写真はほったらかし。
しばらく経って"JPEG+RAW"で撮っておいたRAWを現像、「あれ、ピントそこそこ来てるじゃん」。でも、綺麗なお姉さん、こんな無粋な所の例写真でさらし者にするのは気が引けて、公開は見合わせ。
が、最近思い直して、改めて気合を入れてRAW現像。コンデジでも結構いけるかも、自画自賛。
RAW現像は無料ダウンロードソフトの RawTherapee ver4.2.147。気を配ったのは、肌色と髪の毛の柔らかさ、触りたくなるようなソレ。どこぞで見かける油ベトベト整髪料でゴワゴワにしたように見える"解像感命"のソレとは違って。
今思うところの RawTherapee 現像での設定の"肝"は、
(い)シャープ化のRLデコンボリューション
(ろ)ノイズ低減
(は)ディテールレベルのコントラスト
(に)HSVイコライザーの肌色域の微妙な色相シフト
ってトコかな。
(い)(ろ)(は)は設定ダイアログボックスのスクリーンキャブチュー画像を添付。
(い)RLデコンボリューションは、初期型裏面照射CMOSイメージセンサーの欠点、明部輪郭のにじみを抑えるのに効果あります。耳ピアスの鎖のクッキリ感に注目。
(ろ)ノイズ低減は、色ノイズと輝度ノイズの低減処理、クッキリ感とのバランスを試行錯誤。
(は)ディテールレベルのコントラスト、値1.00は変化なし、1.00より大きいとシャープに、1.00より小さいとソフトになります。髪の毛の柔らかさには、レベル3とレベル4を小さくソフトにしているのが肝。レベル1とレベル2は値を大きくシャープ(輪郭強調)に。
(に)HSVイコライザーは、黄味がかった肌色域だけを微妙に赤色方向へ色相シフト。
109)カメラJPEG、ポートレートモード、換算300mm。
110)RAW現像、柔らか髪
111)RAW現像、(い)(ろ)(は)未処理、ノイズ低減や柔らか髪の処理はなし。
112)設定画面
ピクセル等倍拡大表示だと「やっばりコンデジ」だけど、長辺1024ピクセルの価格コムサイズや50%拡大(縮小)表示程度だと、結構イケてるのではないかな。
<お詫びと言い訳>
パソコンモニターは三菱 Diamondcrysta RDT231WLM-S、ノングレアでない光沢画面、組込済のsRGB設定でDVI-D接続。写真用のソレではないしキャリブレーションとやらもしてないので、意図通りに他のパソコンで表示されるかは知りません。
書込番号:18945207
![]() 0点
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「富士フイルム > FinePix HS10」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 9 | 2025/05/07 1:38:09 | |
| 15 | 2018/04/29 10:36:18 | |
| 6 | 2017/10/26 22:27:24 | |
| 3 | 2016/10/25 8:50:08 | |
| 3 | 2016/03/20 19:21:31 | |
| 7 | 2015/10/10 14:31:18 | |
| 5 | 2014/07/14 20:50:05 | |
| 5 | 2014/07/16 0:02:33 | |
| 7 | 2014/07/12 20:57:29 | |
| 2 | 2014/06/30 0:07:31 |
クチコミ掲示板検索
最適な製品選びをサポート!
[デジタルカメラ]
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】PCカレン
-
【欲しいものリスト】タフなやつ
-
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】252
価格.comマガジン
注目トピックス
(カメラ)
デジタルカメラ
(最近3年以内の発売・登録)