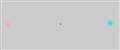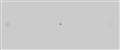�ʔ����L�����������̂ŁA�V�F�A���Ă����܂��B
�L���ɂ��ƁA�u�Ԗ��ł͒��S���i���Ȃ킿�����̃����Y�̌����j�t�߂ł����F�𑨂��Ă��܂���B�v�Ƃ̎��B
��ʂɃK���X�̒P�����Y�ł͐F�����⋅�ʎ����Ȃǂ����������܂����A�l�Ԃ̖ڂ̃����Y�ł��鐅���̂ł́A�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ������Ȃ��̂ł��傤���H�]�̕��ŕ���Ă���̂ł��傤���H - Quora
https://jp.quora.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E3%81%AB%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%8D%98%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%81%A7%E3%81%AF%E8%89%B2%E5%8F%8E%E5%B7%AE%E3%82%84%E7%90%83%E9%9D%A2%E5%8F%8E%E5%B7%AE%E3%81%AA%E3%81%A9
���Ń����N����Ă��������������ʔ����B
���������
http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/kieru.html
�����ԍ��F24068199
![]() 5�_
5�_
�l�Ԃ̖ڂ̃����Y�ł��鐅���̂ł́A�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ������Ȃ��̂ł��傤���H�]�̕��ŕ���Ă���̂ł��傤���H
�ːl�Ԃ̊Ⴊ1�ԍ����\�ȃJ����
�J�����̐i����
�l�Ԃ̊������{�ɂ��č��ꂽ
�ؓ��ň��������Đ����̂̌��݂�ς���
�s���g���킹����
�i�R���̃s�[�N��10���炢�j
�l�Ԃ̊�ɂ͏��������L��
�F���x�̈Ⴂ���]�������
�l�Ԃ̊�̖Ԗ��͋��ʂ�
���ʂɉf���Ă�
�^�������Ȃ��̂͐^�������Ȃ�
�]������Ă��܂�
�����h��Ă��]���݂�Ȃ݂�ȕ���Ă��܂�
�n����̐����ōł��Ⴊ�ǂ��̂́w��x
���F���I�C�����o����
���O�����J�b�g��
���i���X�b�L���N�b�L��
�����ԍ��F24068262�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
2021/04/08 11:54�i1�N�ȏ�O�j
�l�̖ڂ͐F�X�������낢����˂���
����ʂ��Ȗʂ�����P���ȃ����Y�Ŗ�肪�o�ɂ���
����͎ʃ����ł����t�B������p�Ȃ����č��掿�ɂ����̂Ɠ�������
�����Ĕ]����͂����Ȗʂœ�����O
���Ȃ݂ɐҒœ����̖ڂ͊�{�\���I�Ɍ��_������
��{�\���I�ɍł��D��Ă���̂̓C�J�^�R�Ƃ��̓�̓����̖�
�Z���T�[�ŗႦ��Ȃ�Ғœ������\�ʏƎ˃Z���T�[
��̓����͗��ʏƎ˃Z���T�[
�䂦�ɐҒœ����̖ڂɂ͖ӓ_������
�����ԍ��F24068346
![]() 3�_
3�_
�u���̍זE�v�Ɓu���̍זE�v�̊��x����
�V�̖]������`���l��
���������������Ă���Ǝv���܂���
���퐶���ŋC�Â����Ƃ͏��Ȃ��ł��ˁB
�u���̍זE�v�̎g�����Ɋ���Ă��Ȃ�����
���_�E���c�E�a���Ȃǂ̖ڎ����Ȃ��Ȃ��ł��܂���B
�P�X�W�U�N�@�n���[�a���ڋߎ���
�����炵�̗ǂ��Ƃ���ɂU�p�N���X�̏��^�]�������o�����߂Ă����
��R�l������Ă��āu�����āv�ƌ����܂���
�a��������̐^�ɓ���Č����Ă���Ă�
���Ȃ�̕����u�����Ȃ��v�ƌ����Ă܂����B
�]�����ʼn��������Ă�����ۂ�
�F�̈Ⴂ���������A���r���I�Ƃ�
���邭�đ�^�̎U�J���c�Ȃ�
�u���̍זE�v����Ȃ��Ă������郂�m�H�����܂��i�j
�����ԍ��F24068378
![]() 7�_
7�_
�ł��A�F�������Ȃ���
(�Ό��̔F���͂ł���炵��)
�����ԍ��F24068398�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��
�C�J�E�^�R�̎��o�ɂ��āB
�����ԍ��F24068400�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�F��������u���̍זE�v��
�쒷�ނƒ��ނɂ�������
��
����ȊO�̓����́A�F���������邱�Ƃ͏o���Ȃ��c
���Ă��Ƃ炵���B
���ʕ��͐F�f�ʼnh�{������Ă��肷�����
���H�����Ȃǂ͊F
�F�̈Ⴂ�ɕq���ɐi�����������L���������悤�ȋC�����邪
���ۂ̐��E�͂����ł��ĂȂ��B
��ł��˂�
�����ԍ��F24068507
![]() 2�_
2�_
2021/04/08 13:51�i1�N�ȏ�O�j
�M���ނ͒�����͖�s���ł������������Ă����̂�
�F��������K�v���Ȃ�����
�����Ĉ�x�F�o���މ����Ă��܂��������
���̂��ƂɍĂѐF�o�Ƃ����\�͂��Ď擾����
���Ō��Ă�����ꂽ��ɂ����F�o����
�����ԍ��F24068536�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���F��������u���̍זE�v��
���쒷�ނƒ��ނɂ�������
�q�g���F���ł���O���F�̐F�o�ł́H
�ꕔ�F�o�Ȃ��ł̐F�o���̂͑����̓����ł���悤�ł��B
�����ԍ��F24068568�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����肪�Ƃ��A���E����
���F��������u���̍זE�v��
���쒷�ނƒ��ނɂ�������
������ƁA�ɂ킩���Ł@�Ԉ���Ă����悤�ł��ˁB
�E���ށA�����ށA��ށA���ނɂ�4�^�C�v�̐��̍זE�������̂�����
�E�����̚M���ނł͐��̍זE��2�^�C�v���������Ȃ��̂łQ�F�^�̐F�o�����L���Ȃ�
�E�������M���ނł��쒷�ނł�3�F�^�F�o��L����悤�ɂȂ������̂�����l�������ł���
�Ƃ����ق����A���Ԃ����ł��傤�B
���݂܂���ł����B
�����ԍ��F24068583
![]() 3�_
3�_
�u��̍\���v��Web����
�p���E�[���E�����́E�Ɏq��
�P��̋��ʃK���X�����Y�Ɣ�r����̂��i���Z���X�B
�����̂������K���X�����Y�ɗႦ�邱�Ƃ��������A���ʃ����Y�ł͂Ȃ������B
�ʂȂ狅�ʎ����͂Ȃ��A�����B
���ɋP���V���E�X���Ȃ��āA�u��������_�v�Ɍ�����l������̂��ȁB
�����ɂ͂��тɘc�u���݂����v�Ɍ����܂��B
�u��������_�v�łȂ��Ȃ�F�����Ȃ�ĔF���ł��Ȃ��A�����B
���邢�͖ڂ̕���\�E�𑜗́A�����鎋�͂��F������F���ł�����قǂɂ͍����Ȃ��Ƃ��B
�l�Ԃ̊�͎O�r�ɌŒ肵���J�����ł͂���܂���B
�����ƋÎ����Ă������ł��킸���Ɋዅ�͓����Ă���A�����B
�ƁA���肷��ƁA
�ǂ����̃��[�p�X�t�B���^�[���X�f�W�J���݂̂����A
�Ⴀ�邢�͔]�́A�킸���ɉ�f�V�t�g����������(���ԍ��̂���)�������������āA
�F�Y��(�F����)��������A�����B
<�]�k>
�G��Ă���̂́u�F�����v�Ɓu���ʎ����v�ł����B
�u�c�Ȏ����v�ɂ��G��ė~���������ł��B
�ڂ͒��M�^�c�Ȃ݂����ł��A�����̎����ł́B
�u���тȁ��v�Ɍ�����ł��A���͌��������藧�̂́A
�ዅ�������Ă��āA���������������ɔ��f���Ă���̂����B
�����ɏ������̂͂��ׂĎv�����̉����ł��B
�M���ł��镶���⒲���Ɋ�Â������̂ł͂���܂���B
���낢�뉼���͕����т܂����A
���l�v�Z�V�~�����[�V�������D���Ȑl��A
���낢��ڂ������̃G���W�j�A������݂����Ȃ̂ŁA
�����Ă���邩������܂���B
�����ԍ��F24068590
![]() 1�_
1�_
�l�Ԃ̖ڂŎ����Ȃǂ̌��ۂ��������Ȃ��̂́A��ɔ]���ŕ����Ă邩�炾�Ǝv���܂��B
�������������Y��ʂ��ċL�^�����G�Ɛl��������G�̍��������Ƃ��ĔF������Ă���̂ł��傤����B
�����l���F���������̂܂܋L���ł���Ȃ�A���̒��̗֊s�͓��F���ƔF������A���ꂪ�^���̐��E�ƂȂ�ł��傤�B
�q�g�����m������d�g�݂́A����ڂ����\�̕���J�����̓���f�[�^���������Ĕ������L�����Ă���킯�ł�����A�X�}�z�̕���J�����̂��ꂪ��ԋ߂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F24068650
![]() 4�_
4�_
�ʔ����ł���
�d�q��Ԃ��A�J�����������Y��AHDR�A�s�N�Z���V�t�g�AAI���𑜂ȂǁA�ǂ�ǂ����Ă�������J�댴�n�I�ȃq�g�̊�̎d�g�݂ɋ߂Â��̂�������܂����
���̊�͎��XDeepFake��������Ă����Ȃ��炢���܂�
�����ԍ��F24068664�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���l�Ԃ̖ڂŎ����Ȃǂ̌��ۂ��������Ȃ��̂́A��ɔ]���ŕ����Ă邩�炾�Ǝv���܂��B
���ӂł��B
�܂��A�����╶���̂���܂ł�����悤�ł��B
�\���N�ȏ�O�̋L���ł����E�E�B�A�t���J���ǂ����̕����ł́u�����v�̊T�O�������炵���A
�������ʏ�̃x�b�h(���X�����ō\��)�ŐQ��ƋC�����������Ƃ��B
(������͕��R�ȂƂ���ŐQ�Ă��Ȃ��炵��)
�����ԍ��F24068714�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���{�l�͓���7�F�Ŋ����邯�Ǒ����̐l�͏��Ȃ��Ƃ���������摜�G���W���̂���݂�̂��ȁc
�����ԍ��F24068770�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�݂Ȃ���A�����[���b��F�X�Ƃ��肪�Ƃ��������܂��B
�u�Ԗ��ł͒��S���i���Ȃ킿�����̃����Y�̌����j�t�߂ł����F�𑨂��Ă��܂���B�v�Ȃ�A�[�����ŐF���ω����Ă��C�Â��Ȃ��̂��Ǝv���A�e�X�g�p�̊ȒP�ȃy�[�W������Ă݂܂����B
https://ok2nd.sakura.ne.jp/x-test/c-check.html
���������N���b�N����ƁA���E�̐F���ς��܂��B�F�̕ω���3��ނ����ł��B�p�\�R���Ȃǂ̑傫�ȉ�ʂŌ��邱�Ƃ�z�肵�Ă��܂��B
��ʂɖڂ��߂Â��ĉ�ʒ������Î�������ԂŁA�[�����ŐF���ς���Ă��C�Â��Ȃ����̂Ȃ̂��Ǝv���č��܂������A�C�Â��Ă��܂��܂��ˁB
�������������Ă������ł��A�Ⴊ�����ɓ����Ď��ӂ����Ă��܂��Ă���̂��H����Ƃ��A�킸���Ȃ���u���̍זE�v�����ӂɂ����݂��Ă��邩��Ȃ̂��H
�����ԍ��F24068771
![]() 1�_
1�_
�Ƃ���ŁA�{�肩��͊O��܂����A�F���āA�悤����Ɏ��g���̈Ⴂ�ł���ˁB�l�Ԃ̊Ⴊ3���F�ŔF������d�g�݂��Ƃ��āA�e���r��J������������RGB��3���F�Ŗ����Ă��ǂ������悤�ȁH
�����̎��g���̈Ⴂ�����̂܂܋L�^�ł���f�q�Ƃ�������̂܂܍Č��ł���f�B�X�v���C�̎d�g�݂�����ΐF�̍Č����Ƃ��Ă̓x�X�g���Ǝv���̂ł����A3���F�x�[�X�̕����R�X�g�Ȃǂ̖ʂō��₷����������ł��傤���H
�����ԍ��F24068790
![]() 1�_
1�_
���l�Ԃ̊Ⴊ3���F�ŔF������d�g�݂��Ƃ��āA�e���r��J������������RGB��3���F�Ŗ����Ă��ǂ������悤�ȁH
�́A�����悤�ȋ^��������܂������A
�q�g�̎��o�Ɉ˂邩�炱���́u�O���F�v���ƁB
�����A�f��̃v���f�^�[�݂����ɐԊO�����������Ȃ�������A�O���F�̊T�O�������A�u����̎O���F�v���o�ꂵ�Ȃ��������Ǝv���܂��B
�Ȃ��A�Y����Ă��邯��ǂ��A��F�t�B���^�[�^�̎B���f�q������܂������A
�P�B���f�q�����ŃJ���[�M����������悤�ɂȂ�O�́u�_�C�N���C�b�N�v���Y���v�Ȃǂ��g���O��(�������I�ɂ͎O�u�ǁv��)�ł������B
�����ԍ��F24068824�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�X�b�]�R���������� �̍l�@�͓I���˂Ă���悤�Ɏv���܂��B
�l�Ԃ̊�̐����͔̂ʂ������B�p���ȂǑ��̌��w�G�������g�Ƌ������Ď����ጸ���Ă���悤�ł��B
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cataract/30/1/30_10-016/_pdf/-char/ja
��ꌟ���Ȃǂŋ����I�ɓ��E���J���i��̍i����J���ɂ���j�ƁA�l�̊������Ɏ��������邱�Ƃ��킩��܂��B�������F�������B
�Ԗ��̐��̂́A���ӕ��ɂ��i�����͂Ȃ��ł����j���邻���ł��B
�����ԍ��F24068842
![]() 1�_
1�_
�����w�ɂ��ڂ������j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
�����ĉ������B
�E�j�Ƃ������ς��Ⴊ����܂����A�]���X�͂���܂���B�����ŁA�ǂ�����ĐM���������Ă���̂ł��傤�B
�����s�v�c�Ɏv���Ă��܂��B
�����ԍ��F24068965
![]() 1�_
1�_
2021/04/08 19:28�i1�N�ȏ�O�j
��6084����
���˂��Ȃ��H
�킩��ǁi�j
��w�ł͐����w�Ȃ����������O�i�j
�����ԍ��F24069002
![]() 1�_
1�_
���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
�L��������܂��B
���A���F�l�͑̒����́[�݂����ď�k�Ō����Ă܂����B
���ӓ_
�q�g�̊�͔]���X�����яo�������m���Ď��ŁA�b�b�t���Ȃ��āA���ڂb�o�t�Ɍq�����Ă�����Ď��ł���ˁB
�b�b�c�݂�����U�V���A���M���ɂ��Ȃ��ŁA���ڃZ���T�[����z����]���X�ɂ��Ď��ŁA�n�[�l�X�̕������ӓ_���ė����Ő������ł����B
���̗F�l�Ɍ��킹��ƃE�j�̊�͐l�ɋ߂��\���������ł��B�ł��z���̂Ȃ������Ⴄ�݂����B�E�j�͂ǂ�Ȃӂ��ɊO�E�������Ă���̂�����B
�����ԍ��F24069026
![]() 2�_
2�_
2021/04/08 19:45�i1�N�ȏ�O�j
��6084����
�l�̖ڂ͔z���̎�����������ӓ_�ł���ƌ�����Ǝv���c
�Ȃ�Ő^�ɔz���W�߂�H�i�j
�m�\���l���č�����\���ł͂Ȃ�
���������Őg�ɒ������\���䂦�ɂ������Ȃ���
���ꂪ�i���̖ʔ��������ǂˁ�
(*´�ցM*)
�����ԍ��F24069038
![]() 2�_
2�_
���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
���Ȃ�Ő^�ɔz���W�߂�H�i�j
�]���X����Ƃт��������炾���琬��s���ł����Ȃ����̂��Ƃ������܂����B
���˃����Y�Ȃ�Đ^�ɁE�E�E�E
�m�\��������̂ł͂Ȃ��E�E�E���������܂��s���S�ˁA�_�l������s���ō�����H�H
���̒m�\���Ă̂��܂��܂��Ȃ�ł���B
�����ԍ��F24069077
![]() 1�_
1�_
2021/04/08 20:03�i1�N�ȏ�O�j
��6084����
���������}���������
(*´�ցM*)
�����ԍ��F24069082
![]() 0�_
0�_
���j���[���ӂ�U�܂����偙�c����
���}���͔ے肵�Ȃ��ł��ˁA�ނ��뗝�n�̂ЂƂ̕������}���������Ă��ˁB
�����ԍ��F24069100
![]() 0�_
0�_
�p���������̂��قڋ��ʂł��B�a�C�Ƃ��Ẳ~���p���ƌ����̂͂���܂����B
���ʂ�_�����킯�ł͂Ȃ��āA���ʂ̂ق������肵�Ă���̂ŁA���R�Ƃ����Ȃ����Ƃ������Ƃł��傤�B
���ʂƂ��Čv�Z���Ă��A���ʘp�Ȃ����ʂł���A��قNJp�x���Ȃ���قږԖ��ɏœ_�����Ԍ��ʂɂȂ�܂����B
�����ԍ��F24069535
![]() 2�_
2�_
���X�b�]�R����������
> �ڂ͒��M�^�c�Ȃ݂����ł��A�����̎����ł́B
����̒[�̕��́A�����M�^�̎���������A�Ƃ������Ƃł���ˁH
�����ł��B���������A3�����̋�Ԃ�2�����̖Ԗ��ɗ��Ƃ�����ł���̂�����A�M�^�̎����������������������H
�ŋ߁A�L�p�����Y�̒M�^�������f�W�^����ł���J�����������ł����A����ꂽ�摜���āA�ȂA�����ł��B
�L�p�����Y�̊G�́A�����A�M�^��������������l�̖ڂ̌������ɋ߂��Ȃ�A���R�Ɍ�����C�����܂��B
�����ԍ��F24071051
![]() 1�_
1�_
��N�����O�ɓˑR�̉E�ږԖ������ňꎞ�͊��S�Ɍ����������B
��p�̌��ʁA�������߂��������݂����̉E�ڂł͒����������ł͂Ȃ�
���X�c��Ō�����B
�K���F�o�Ɉُ�͖����A���̘c�݂����ڂ�����Ă���Ă���̂ŕ��i��
�����Ɏx��͖����B
���͐F�������d�������Ă���̂ŐF�o�����ł����������͍̂K�����Ǝv����
����B
�ڂ��Đ�������ˁB
�����ԍ��F24071089
![]() 4�_
4�_
�����̖ڂŔ�������ʃ{�P��F�����Ă݂��ƁA
���������Ђǂ����w�n���Ƃ����̂͌����܂����
���̂͂���Ȋ����� �����ɃA�b�v�ł���悢�̂ł���
�����ԍ��F24071123�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
2ndart����
���e�X�g�p�̊ȒP�ȃy�[�W������Ă݂܂����B
����Ă݂܂����B�����ȑO�����ŊȈՎ������Ă݂Ďv������茩����ȂƎv���Ă܂������A
����w�i�Ƃ̋P�x�������Ȃ��s���N�́A���O�コ����Ɖ��x�������Ȃ��Ȃ�܂����B
�����ɐF���������Ă����ł͂Ȃ��Ƃ��A��ʓx�ɂ͎ア�̂����c�B
�c�Ɋւ��Ă͐V�������K�l�ɂ��c�Ȃ����炭����ƕ���Ă��܂��܂����A���ꂾ�����ăp�[�X�̊W�������Ⴎ����ɂȂ��Ă���Ǝv����ł����A���s�Ƃ������Ƃ��܂�Ō����Ă���悤�ɔF�����Ă��܂��]�͂������ł���ˁB
�����ԍ��F24071283
![]() 2�_
2�_
2021/04/10 08:00�i1�N�ȏ�O�j
��̘b���Ƌ��̓t�B�b�V���A�C�����Y�Řc�G�����Ă�Ǝv���l�����邯�ǂ�
���������ȃf�[�^�����ɔ]���ϊ�����
���ۂ͋�ԔF��������i�K�ł͐l�̎��E�������삪�L���͈͂�c�݂Ȃ����ʂɔF�����Ă邾�낤��
�����̕�����������Ǝv��
���������t���ዾ�Ŏ���̍��E����ւ�����A�㉺����ւ��Ă�
10��������Ε��ʂɐ����ł���悤�ɂȂ���Ă̂������\�͂̍����������Ă��
�����ԍ��F24071543
![]() 2�_
2�_
cbr_600f����
> �e�X�g�p�̊ȒP�ȃy�[�W
�ŏ��́A�w�i���ɓK���ȐԂ�̐F��t���Ă��܂������A�F�����̖��x�����ʂł͂Ȃ��������߁A���Í��ɊႪ�������Ă��܂��Ǝv���A����������u�g���N�X���[���ʁE�O�F���v�̉摜���g���āA���4��9���̒��ɍ�蒼���܂����B�ł��A��͂�A�F�̕ω��ɂ͋C�Â��Ă��܂��܂��B
�u�g���N�X���[���ʁE�O�F���v�̉摜�̊e�F�����S�ɖ��x�������ł͂Ȃ����߁A��̉摜�����m�N���ɂ������̂ƐF�摜��u��������^�C�v������Ă݂܂����B
https://ok2nd.sakura.ne.jp/x-test/c2-check.html
�ŏ��̓O���[�ŕ\������܂��B�}�E�X�N���b�N�ŐF���\������܂��B����ł��A��͂�A�F�̕ω��ɂ͋C�Â��Ă��܂��܂��B
�������A���̃o�[�W�����ōēx�}�E�X�N���b�N����Ƃ܂����̃O���[�̉摜�ɖ߂�̂ł����A���̏ꍇ�A���E�̐F����F�Ɍ����܂��B�����A�E�����F�Ɍ����܂��B
����Ŏg���Ă���摜��Y�t���Ă����܂��B
�����ԍ��F24071582
![]() 1�_
1�_
��2ndart����
�����J�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�F�����ɂ���F�A�������茩���܂���ˁB
�P�x�ƐF���͂�͂芮�S�ɕ����ł��Ȃ����̂ŁA�v�Z�㓯���P�x�▾�x�ɂȂ��Ă���͂�i���������邱�Ƃ�����܂��B
Web�̐F�㌟�������Ă݂�Ɣ����Ɉ��������邱�Ƃ�����̂ł����A���̉e�������邩������܂���B
�Ƃ�����A�l�̔]���g�������ɂ��h���̈Ⴂ��F�Ƃ��ĔF�����Ă��邾���ŁA��ΓI�ɐ^���ȐF�������ł͂Ȃ���ł���ˁB
�����ƒ����g���������F���l���n���ɗ��āu���̐[���������F���N�����ɂ͌����Ȃ��̂��H�H�v
�Ȃ�Č�����������܂���B
�����ԍ��F24073263
![]() 2�_
2�_
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/mark/melens.html
https://annex.jsap.or.jp/photonics/kogaku/public/31-01-sougou.pdf
�l�Ԃ̊�̊p���͑S�ʂƌ�ʂƂŋ��ܗ����Ⴂ�A�����̂͒��S���͋��ܗ����������ӕ��͋��ܗ����Ⴂ���ܗ����z�^�̃����Y�ŁA�X�Ɋp���͑o�ȖʁA�����̂������ʁA�Ԗ����قڋ��ʂł���A���ʎ����A�R�}�����A���ʘc�ȁA��_�������C������Ă���Ƃ̂��ƁB
�Ȃ������̂͐ԂƗ�2�F�ɑ��Ă����F���������ꂽ�A�N���}�[�g���w�n�ŁA�ɂɑ��Ă͐F�����̕�@�\���Ȃ��������ڂ₯�Č�����͂������A�����]���ŏC�����Ă���炵���Ƃ̂��ƁB
�X�ɂ͊p���Ɛ����̎��̂��ዅ�̒��S������ΐS������Ɋp���E�����́E�Ԗ��̌����Ɗዅ���̂̎����S������Ă��Ęb�����ɂ�₱�����Ȃ��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B
�����ԍ��F24073383
![]() 2�_
2�_
������܂̂���
���K�l�͐F�������N�����͂������ǁA
���ʂɊ|���Ă��鎞�A�C�ɂȂ�܂����B
�|������O��������J��Ԃ��Ă��A
�C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ���A
���͂ł͔��ʂł��Ȃ����炢
�����Ȍ��ۂ��Ă��Ƃ����A
�]��������́B
<�⑫>
�ӎ����Ē[�̕���������A
�����Y���X�����肷��A
�F�������킩�邩������܂���A
�C�����܂��B
�����ԍ��F24073388
![]() 1�_
1�_
�F���͐�����l�ԂɂƂ��āA�l�X�ȖʂŁA���R�Ƃ������s���悭�o���Ă��邪�A�n���̋�C�������̔g���тɂƂ��ē������������Ƃ������̒a�����̔����Ɍq�������̂�������Ȃ��B
��C�̐����������Ɉ���āi���炩�̔��ʐ������܂܂��Ȃǁj�A�����̎��O������ԊO�����̔g�����J�b�g����Ă�����A�܂肻�̔g���тɂƂ��ē����łȂ�������A�l�Ԃ̐F�ɑ���d�g�݂�����Ă����Ǝv���܂��B
�����A���炩�̔��ʐ������܂܂��ȂNj�C�̐����������Ɉ���Ă�����A�������̂��a�����Ȃ�������������Ȃ����A�a�����Ă����̂悤�Ȑi���͂Ȃ����������B
�����ԍ��F24073611
![]() 1�_
1�_
���Ȃ݂Ɏ��͎d�����A���F�������J�[�h��D50���������������Ă��܂���B
�����ԍ��F24074240
![]() 0�_
0�_
�l�̖ڂ́A��]���قƂ�ǂ̋@�\��S���Ă���B
�ڂɏ�Q���������Ă��Ă�����Ă��܂��̂ŁA�Γ��ǂ����o�ł��Ȃ��B
���������̂ŁA�������N����A�O�̓_������Ɛl�Ԃ̊炾�ƌ�F�����Ă��܂��B
�����ԍ��F24075588
![]() 1�_
1�_
�u���[�j���O����
���F�������J�[�h�̎g�������ǂ�������Ȃ���ł����B
�����ԍ��F24083471
![]() 0�_
0�_
2ndart����
����͐F�������d�������Ă���l�����̌����`�F�b�N�p�X�P�[���ł��B
���E�̐F����������������F�]���ɒl��������ŁA���ق�����ꍇ�͗ǂ��Ȃ�
�Ɣ��f���鎖���ł��܂��B
�����������ł��u����������̋߂��ł͂��̌��ʂ��ς��܂��B
�ł��̂œ����e�[�u���ɍ����Ă��Ă��ꏊ�ɂ���Ĕ����Ɍ��ʂ��ς��܂��B
���_�A�ȈՓI�Ȃ��̂ł͂͂���܂������ǂ����i�����j��T���R����������
���������E���E�����鎖����������܂���B
�����ԍ��F24084522
![]() 0�_
0�_
���u���[�j���O����
�X�}�z�Ŋg��\���������Ɍ��Ă����E�̐F���Ⴂ�܂����A
���̏ꏊ�ł̎B�e���Ɍ�����A�����ƃn�b�L���ƈႤ�悤�Ɍ�����̂ł��傤���H
�����ԍ��F24084598�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���肪�Ƃ��A���E����
�����ł��ˁA�E���̕���M���ۂ������܂��ˁB
����͎���̒��̊Ԃ̃e�[�u���̏�ŎB�����̂œ�����O�Ƃ����Γ�����O
�ł����E�E�E�E
���̈ʂȂ�܂��������ł��A�ꏊ�ɂ���Ă͂����ƌ����ɐF�̈Ⴂ���o�܂��B
���Ƀ~�b�N�X���ɊO�����������ޗl�ȏ�ł͌����ɕς��܂���B
���ƁA�ʐ^�Ƃ���̎������ł��M�������[�݂��Ă�l�ȏ����Ɛ��m�ȐF
�]���͌������ł��B
�����ԍ��F24084668
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɁA�R���͎B�e���Ɏg�p������̂ł͂���܂���B
���Ɏd�����A���x���v���̎B�e�ɂ͗�����܂����������g���Ă���l
�͌������������ł��B
�B�e��̃v�����g��F�Z�������̐��ʕ����������F���ǂ����f����
�V�[���Ŏg���̂��������g�����ł��B
�C���e���A�R�[�f�B�l�[�^����Ƃ����g���Ă���ƕ����܂����B
�����ԍ��F24084701
![]() 0�_
0�_
���u���[�j���O����
�ǂ���(^^)
���ꂮ�炢�̍��قł���A
�E����
�E�B�e�@��
�E�z���C�g�o�����X
�E�\��(���܂̎��̏ꍇ�̓X�}�z)
�̑g�ݍ��킹�ŁA�����������\�ς��̂ŁA���ۂɌ��������͂ǂ����ȁH�Ǝv���܂������A
��͂�E���̕���M(�}�[���^)���ۂ��������̂ł��ˁB
�R���i�БO�ɋ�X���������Ă����m�[�gPC�́u�ςȐF�v������[�Ȃ��������̂ŁA
���̃X�}�z(Xperia)�ł͂ǂ����ȁH�ƋC�ɂȂ����Ƃ���ł���(^^;
���u�ςȐF�v������[�Ȃ�����
�F�����o���o���ɃY���������ŁA���R��������ƈӊO�Ɉ�a�������Ȃ�����ǂ��A
Excel�Ȃǂ̐F�I���p���b�g?������ƁA���F����F���e�X�o���o���ɃY���ĕ\������A���R�Ƃ��܂���(^^;
�����ԍ��F24084716�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
> ���F�������J�[�h
> ���E�̐F����������������F�]���ɒl��������ŁA���ق�����ꍇ�͗ǂ��Ȃ�
�́A�X�܂ŐF���C�ɓ����Ĕ����������A���Č��Ă݂���S�R�Ⴄ�F�ł������肵�����Ƃ�����܂��B�m���Ɍ����őS��������F�Ɍ����܂��ˁB
�ł��A���̉��F�������J�[�h�̎d�g�݂��ǂ�������܂���B���z���ɋ߂����F���Ȃ痼�������Ɍ�����Ƃ������Ƃ͖{���̐F�Ƃ��Ă͍��E�����Ȃ̂��A�����ɂ���č��E�Ⴄ�F�ɂȂ�d�g�݂��ǂ�������܂���B�h���̈Ⴂ�Ƃ�����Ȃ����������ǁB�����˂̈Ⴂ�H
�h���Ƃ��ł́A�j��ł������h���A�ł����������Ƃ�������܂����B
https://news.livedoor.com/article/detail/20038357/
https://www.gizmodo.jp/2019/02/blk3-kickstarter.html
�F�ɂ��ăl�b�g�Ō�������ƁA�����ς��o�Ă��܂��B���[�����̂������Č��\����B
�A�����ΐF�Ɍ�����̂́A�ΐF�˂��Ă��邩��B�܂�A�ΐF�̔g���͎̂ĂĂ���B
�Ԃ��RGB�l��F00�A00F�����ǁA��080�B0F0���Ƃ��Ȃ薾�邢�ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ������Ⴄ�H
���̍זE�̂����A�Ԑ��́A�ΐ��̂̊��x���ł������̂́A�ł��ԐF��ΐF�̔g���Ƃ͂��Ȃ肸��Ă���炵���B
�A�v�����F�X����܂��ˁBAndroid�A�v���u�F����� �v�u�F����v�Ȃǂ������Ă݂��B�J�����Ō����F��RGB�l��ߎ��F�̖��O�������Ă��ꂽ�肷��B�ł��A�������ς��ΈႤRGB�ɂȂ�B
�����ԍ��F24085296
![]() 0�_
0�_
�������ɂ���č��E�Ⴄ�F�ɂȂ�d�g�݂��ǂ�������܂���B
�g���ʂ́u���ˁv��u�z���v�Ȃǂ̓����Ⴄ���Ƃ��A���ɗ��p���Ă���̂ł��傤�B
���Ƃ��Ή��w�n�Ȃǂ̏o�g�ł����āA���w���͂̉�����́u�z�����x���́v�Ȃǂ𗚏C���Ă���܁A�����I�ȕ����ɂ͋^��������Ȃ��ł��傤�B
(��̓I�ɁA�ǂ̂悤�ɑg�ݍ��킹�Ă���̂��H
���炢���C�ɂȂ�Ƃ���)
�����ԍ��F24085444�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>���m���Ɍ����őS��������F�Ɍ����܂��ˁB
���������ʂ�B
���ꂪ�d�����Ɣ��ɖʓ|�Ȏ��ɂȂ�܂��B
�q��ŔF�������F�ƌ���ł̐F�̍��ق͂�������ł��B
��������͋ƊE���邠��̂��b�B
�F�Z�������Ɏ����čs���A���̎������ŐF���m�F�������Ƃ��댩�{���
M���ア�Ƃ̎w�E�L��B
�m���Ƀ\�R�Ō����M������Ȃ������B
���̌�Ђɖ߂茻��Ŋm�F�����Ƃ���M�͑���Ă��肻�̏�̔��f��M��
����ێ������̎w�E�ӏ����C���B
����A���̋q��ɍĐF�Z����͂��Ċm�F�����Ƃ������S���҂́uM��
�オ���Ă����ԗǂ��Ȃ����ˁv�Ƃ̊��z�B
�����Łu����M�ł͈�ؕς��Ă��܂���v�Ɠ`����Ɛ��������r�b�N���B
�ȁ`��Ď��͓��풃�ю��ł��B
������������x�Ǘ����Ă��Ȃ��Ɛl�Ԃ̖ڂȂ�Ă���Ȃ��̂ł��B
�����ꏊ�Ō��Ă��ߑO�ƌߌ�A�V�C�̗ǂ������ŐF���Ȃ�ĊȒP�ɓ]��
�܂��B
�����ԍ��F24086821
![]() 0�_
0�_
��
���ɁA�J���[���[�^�[�ŏƖ��̌v�������Ă��āA���Ȃ��Ƃ��J���[���[�^�[�̕\���l�ȂǂɑO���ƕω��������Ă��A
�u�q�̊��o�v���D�悳�ꂻ���ŁA�Ȃ��Ȃ���ςł���(^^;
���������d���Ŕ��Ă���Ƃ��ƁA���C�ȂƂ��́u�������v�݂���(^^;
�����ԍ��F24086913�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���͂����Ɩ��Ȃ̂́h�L���F�h�ł��B
���̂��b�͂܂��ʂ̋@��ɁB
�����ԍ��F24086951
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�f�W�^�����J�����v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 8 | 2025/10/22 7:35:29 | |
| 4 | 2025/10/21 22:49:28 | |
| 1 | 2025/10/21 19:37:22 | |
| 11 | 2025/10/21 21:21:58 | |
| 15 | 2025/10/22 6:42:52 | |
| 0 | 2025/10/21 7:34:21 | |
| 7 | 2025/10/21 11:44:29 | |
| 4 | 2025/10/20 18:40:51 | |
| 5 | 2025/10/20 16:32:20 | |
| 2 | 2025/10/21 15:29:57 |
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z���z�m�F�p
-
�y���̑��z����ҏW�p��������PC
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC�i���\��
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC�@2026
-
�yMy�R���N�V�����zAirStation
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j