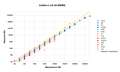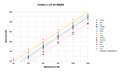ISO感度に関して、「標準出力感度」 と「推奨露光指数」とがあるので、どちらを採用しているのかで、メーカー間のISO感度が変わるとのコメントを見掛けました。
・フジのISO感度はチートなのか? (個人ブログ(「ゆきのり」さん)、2017/05/04)
http://xtrans.blog.fc2.com/blog-entry-5.html
・なぜ異なるメーカーのカメラの露出が合わないのか? (個人ブログ(「フローデベ」さん)、2018/05/06)
http://flow-developers.hatenablog.com/entry/2018/05/06/140437
この2つのブログ記事には、共通点があります。
(1) ISO感度がメーカー毎に異なる理由を、「標準出力感度」 と「推奨露光指数」との違いとしている。
(2) 検証に用いているのは、DPReviewのサンプル画像の露出条件の差異。
(3) 検証対象に、富士フイルム機が含まれる。
私には、この主張が正しいのか間違っているのかは判断出来ませんが、やや強引な論理立てとの印象は受けます。
ISO感度を、メーカーの設定値ではなく、、ISO12232準拠の測定値に置き換えている評価サイトがあります。良くご存じのDxOMarkです。DPReviewの露出条件で検証する事自体は特に問題ないと思いますが、ISO感度そのものの測定を行っているDxOMarkの結果と合わせて検証した方が、検証の信頼性が上がると思います。
何故、DxOMarkの測定値による検証が行われていないのか?理由は、X-Transを採用以降(初採用はX-Pro1(2012/02発売))、X-Transだろうがベイヤーだろうが、DxOMarkでは富士フイルム機の評価を一切行わなくなったからです。ブログ記事の内、1つ目は富士フイルム機がテーマなので、当然と言えば当然ですが、2つ目も富士フイルム機を含める為に、全く同じ論理展開となっています。
「標準出力感度」 と「推奨露光指数」に関しては、「CIPA-デジタルカメラの感度規定」が制定されていますが、「概要書」も合わせて発行されています。「概要書」には、以下の記載があります。
「CIPA規格 「デジタルカメラの感度規定」 はデジタルカメラの感度の特性値を規定するものである。
感度に関連する特性値の規格としては1998年制定のISO12232がデジタルカメラのISO スピード(ISO Speed)を規定しているが、その主たる測定量「ISO noise Speed」は非可逆圧縮のカメラには適用できないため、 一般の民生用カメラへの適用には制限があった。
そこで広く一般の民生用カメラに適用可能で、 カタログ等に感度の値として記載できる特性値として「標準出力感度」 と「推奨露光指数」の2つを新たに定義した。
「標準出力感度」はカメラ(撮像系)の光感応性に基づいて規定される物理的な測定量であり、 「推奨露光指数」 はカメラの提供者による画質官能評価に基づく露出の推奨設定指標であるから、 概念的には異なるものであるが、 カメラを使用する上ではその露出制御に関して大略類似の機能を果たし、いずれもそのカメラ(撮像系)に必要な光量を示す「実用感度」 を表わす指標として相応しいものである。
本規格ではデジタルカメラの感度としてこの両者をそれぞれ規定するとともに、 そのカタログ等に対する表記事項を併せて規定した。」
> いずれもそのカメラ(撮像系)に必要な光量を示す「実用感度」 を表わす指標として相応しいものである。
とありますから、「標準出力感度」 と「推奨露光指数」との2種類が存在するものの、それぞれのISO感度が異なって当然と言う訳ではなさそうです。
DxOMarkのISO感度測定結果の一部を、ご紹介しておきます。グラフでは、以下の関係が分かり易いよう、色分けしてあります。
・標準出力感度: 富士フイルム、オリンパス、パナソニック、ペンタックス ← 赤系
・推奨露光指数: キヤノン、ニコン、ソニー ← 青系
今回用いた測定結果に限れば、大きく、3グループに分かれます。「標準出力感度」 と「推奨露光指数」との区分では、別れていません。
・ほぼ規格値: ペンタックス(K-1、K-3ii)
・規格値より約0.5EV低い(約0.5EVの幅で分布): キヤノン(1DX2、M5)、ニコン(D5、D7500)、ソニー(α7Rii、α7Sii)、パナソニック(GH5、G8)、富士フイルム(X100)
・規格値より1.0EV以上低い: オリンパス(E-M1ii、E-M10ii)
(注) ここでは、DxOMarkのMeasured ISOを規格値と(便宜的に)表現しました。
【ご参考】
・CIPA-デジタルカメラの感度規定 - 概要書
http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-X004-KEY_J.pdf
・CIPA-デジタルカメラの感度規定 (2004/07/27制定)
http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-004_JP.pdf
書込番号:22037162
![]() 5点
5点
1.0EVもずれてたら誤差で許される範囲を大幅に超えてますね(´・ω・`)
そういえばD3とD3sは設定した感度と実際の感度が違うだけで
高感度画質に差が無いって言ってる人もいたなああ
書込番号:22037184
![]() 3点
3点
こんなのややこいから一般ユーザーの99%はとことん検証なんてしないでしょう。
逆に言えば、メーカーは高感度耐性が良いように見せかけようという意図があればある程度ごまかせるということかな。「ISO12800で撮りましたけどノイズは許容範囲内です^o^」みたいな書き込みは割とあるから。
書込番号:22037263 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 2点
2点
弊社の基準です。
こういうの、計量法に引っ掛からないのですかね。
書込番号:22037356
![]() 2点
2点
やっぱりPENTAXがイイですね。真摯なとこ。
書込番号:22037397
![]() 9点
9点
70年代のASA100のフィルムの箱には
EEカメラで無い場合は
この数値を目安にしして下さい。
とお天気アイコンと印字されてました。
シャッター速度 1/250秒の場合
快晴スキー場のアイコン F16
快晴 F11
明るい曇り F8
曇り F5.6
実際にデジタルカメラで撮ってみたら
自分の使うデジタルカメラが
ドンピシャだったので安心しました。
昔 この数値より
3絞りくらいズレてたので
写真屋さんに行ったら
そりゃ露出計の故障だよ。
と修理に出しました。
書込番号:22037421 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 3点
3点
一般的には,想定した写真の明るさと異なる場合,PC上で明るさを変えれば多くは問題解決.
なのでこうして重箱の隅を突っつくことは必要ないかも.
個人的には,各メーカで感度が違っていたらISO(International Organization for Standardization)とは呼べなくなるので,驚いています.こうした差は誤差,個体差のレベルなのか検証が必要でしょうが,個人で検証するのは無理かな.
書込番号:22037610
![]() 3点
3点
まあ、癖が安定していればそれにあわせて補正して使えば
困ることはないし
フィルム時代だとプロはフィルムを大量にロット買いして
まず試し撮りして実際の感度を調べて、同じロットならその感度で撮影
ロットが変わるとまた感度をしらべるてのをくりかえすのも分野によっては普通だったので
(スタジオのポジでの撮影とかね)
それに比べれば同じカメラを使う限り常に同じだけの誤差を考えればいいだけなら楽とも言える
しかし露出関連の許される誤差って±0.3EVまでじゃなかったっけか???
書込番号:22037644
![]() 4点
4点
>あふろべなと〜るさん
多分私のこの書き込みの事だと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000063183/SortID=10584180/
まあ実際、実行感度は機種によって違います。
とりあえずD3の時は実際の感度が表記のiso200はiso320でしたのでNDフィルターをよく使いました。
ちなみに当時のキャノン5Dはiso200に対して実行感度はiso160でした。
書込番号:22038451
![]() 2点
2点
CIPAの規定するISO感度は、指摘されているように2つ定義されています。
・標準出力感度(SOS)
適正な露光量におけるJPEGの出力値(118)で定義される。
・推奨露光指数(REI)
適正な露光量におけるJPEGの出力値は規定されていない。メーカーの裁量による。
SOSはメーカーを越えても明るさがそろうはずです。
一方REIはメーカー間で明るさが異なっていても構いません。
DxOMarkのMeasured ISOは、センサー単体の特性を表す値です。
センサーの特性に対して、カメラメーカーにはカメラのISO感度を決定する設計上の自由度があります。
カメラのISO感度とMeasured ISOが異なっていても問題はありません。
書込番号:22038616
![]() 6点
6点
懐かしの「USO800」、
CIPAの規定前だったと思いますが
どのメーカーでしたっけ?(^^;
書込番号:22039117 スマートフォンサイトからの書き込み
![]() 1点
1点
昔はこんなに高感度になるなんて想定していませんでしたからね。
そもそも適正露出なんて誰が決めるのかっていうと、人間の脳の中でいい加減に判断しているわけなので、
被写界深度同様、CIPAが基準値を決められないのでしょう。
ある意味、人間の感性を理解して絵作りするノウハウがないと几帳面に設定するしかないよね〜、みたいな?
書込番号:22039206
![]() 1点
1点
 |
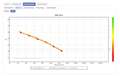 |
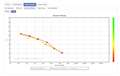 |
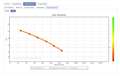 |
|---|---|---|---|
DxOMarkによるISO感度測定(E-3、G1、E-P1) |
DxOMarkによるSNR18%測定(E-3、G1、E-P1) |
DxOMarkによるDynamic Range測定(E-3、G1、E-P1) |
DxOMarkによるColor Sensitivity測定(E-3、G1、E-P1) |
皆さん
コメント、ありがとうございます。
皆さんが仰るように、複数の機材を使用し、さらに露出管理が厳しいシネマ撮影のような状況(シネマレンズはF値ではなく、F値を透過率の平方根で除したT値が使われている位ですから‥)でない限り、お使いになられている機種のISO感度が、他機種と異なっていたとしても、大きな問題とはならないと思います。私は、JPEG撮って出し専門ですが、被写体の殆どが静体なので、構図を変えずに露出補正のみ変えて、数枚、必ず撮るようにしています。数少ない動体撮影の場合でも、露出をノーチェックと言う事はあり得ませんから、個人的にも問題はありません
F値やシャッター速度には撮影の意図を反映なさると思いますが、ISO感度はノイズとの関連でのみ、捉えられている方が殆どだと思います。
さらに、最初の書き込み[22037162]のグラフをご覧になれば分かるように、メーカーや機種毎に、ISO感度の絶対値がズレている場合でも、傾きは殆ど一致しています。これは、F値、シャッター速度、ISO感度の間で、EV値(の差)を全く同様に扱える事を意味します。
と言う訳で、メーカーや機種毎に、ISO感度がズレていても、シネマ撮影のような状況でない限り、実使用では問題にならないと思います。ただ、ISO感度をパラメーターとした作例をご覧になる場合には、(ペンタックス以外の)APS-C機とm4/3機との許容出来るISO感度の差が、仮に約1.0EVと見做せた場合、実際の差は約1.5EVとの疑いは出て来ますね。
次の書き込みで、最初の書き込み同様、DxOMarkでの測定事例を取り上げます。そこで、まず、DxOMarkの測定に関して触れておきます。
DxOMarkの測定結果のみから、メーカーや機種の優劣を判断する事は、私の場合、絶対にありません。ただし、DxOMarkは非常に再現性の高い測定を確立しているので、機種間の比較では、重宝しています。
この書き込みでは、以下の4/3、m4/3の計3機種を取り上げます。
・E-3: 2007/11発売、4/3、3648×2736(998万画素)、画素ピッチ4.75μm
・G1: 2008/10発売、m4/3、4000×3000(1200万画素)、画素ピッチ4.33μm
・E-P1: 2009/07発売、m4/3、4032×3024(1219万画素)、画素ピッチ4.29μm
(注) G1とE-P1のセンサーは同一かもしれません。
1枚目は、Manufacturer ISOとMeasured ISOとの相関性です。かなりズレています。
2〜4枚目は、SNR18%、Dynamic Range、Color Sensitivity のPrint表示での比較です。1枚目ではあれだけズレていたのに、横軸をMeasured ISOにするだけで、非常に一致した結果となっています。画素ピッチが異なっていても、センサーサイズが同じで、かつ、「イメージセンサーの設計技術/製造技術がほぼ同等と見做せる」場合には、DxOMarkのPrint表示では、SNR18%、Dynamic Range、Tonal Range、Color Sensitivity は、(今回程でないにせよ)ほぼ一致します(*)。
これらの結果から、直ちに、DxOMarkのMeasured ISOは、ISO12232に完全に準拠しているとまでは、断言出来ませんが、Measured ISO等の再現性が高い事は、実感頂けたと思います。
(*)
【ご参考】
縁側で簡単に説明しましたので、ご興味のある方は、ご参考になさって下さい。
・2つの連続する書き込み
https://engawa.kakaku.com/userbbs/2182/ThreadID=2182-48/
書込番号:22041202
![]() 1点
1点
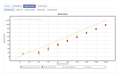 |
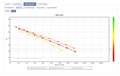 |
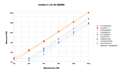 |
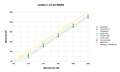 |
|---|---|---|---|
DxOMarkによるISO感度測定(E-P1、E-M5、E-M1ii) |
DxOMarkによるSNR18%測定(E-P1、E-M5、E-M1ii) |
DxOMarkによるISO感度測定(オリンパス) |
DxOMarkによるISO感度測定(キヤノン) |
次に、以下のm4/3の3機種を取り上げます。
・E-P1: 2009/07発売、m4/3、4032×3024(1219万画素)、画素ピッチ4.29μm
・E-M5: 2012/03発売、m4/3、4608×3456(1593万画素)、画素ピッチ3.76μm
・E-M1ii: 2016/12発売、m4/3、5184×3888(2016万画素)、画素ピッチ3.35 μm
1枚目は、Manufacturer ISOとMeasured ISOとの相関性です。1つ前の書き込みでの例に較べると、まぁまぁ一致している方だと思います。
2枚目は、SNR18%のPrint表示での比較です。1枚目がまぁまぁ一致していたのに、1つ前の書き込みとは逆で、3機種間でのズレが目立ちます。これは、「イメージセンサーの設計技術/製造技術がほぼ同等と見做せない」場合だからです。実際、新しい機種程、SNR18%は向上しています。
以上から分かるように、DxOMarkは、測定の再現性は高い(性能差の有無が結果に反映されている)と個人的には感じています。1つ前の書き込みを含め、計6枚のグラフから、最初の書き込み[22037162]のグラフや、これから触れる3〜4枚目のグラフが、どの程度信用出来るのかを、ご判断頂ければ、と思います。
3枚目のグラフでは、オリンパスの以下の機種を取り上げました。このグラフから、E-520(2008/05発売)までと、E-30(2008/12発売)以降とで、オリンパスのISO感度の基準が変わったと判断出来ると思います(ISO感度の基準が変わっていないと見做す事の方が余程不自然です)。 E-M5(2012/03発売)以降でも、オリンパスのISO感度の基準が、再び変わったようにさえ見えます。
パナソニックのISO感度の変化は、ザックリとしか確認していないのですが、パナソニックもオリンパスに同調していると思われます。となると、m4/3陣営に「大人の事情」が存在するのかもしれませんね。
【オリンパス】
〇(グラフでは赤系):4/3、●(グラフでは青系):m4/3
〇E-410: 2007/04発売、4/3、3648×2736(998万画素)、画素ピッチ4.75μm
〇E-3: 2007/11発売、4/3、3648×2736(998万画素)、画素ピッチ4.75μm
〇E-520: 2008/05発売、4/3、3648×2736(998万画素)、画素ピッチ4.75μm
〇E-30: 2008/12発売、4/3、4032×3024(1219万画素)、画素ピッチ4.29μm
●E-P1: 2009/07発売、m4/3、4032×3024(1219万画素)、画素ピッチ4.29μm
〇E-5: 2010/10発売、4/3、4032×3024(1219万画素)、画素ピッチ4.29μm
●E-M5: 2012/03発売、m4/3、4608×3456(1593万画素)、画素ピッチ3.76μm
●E-M10ii: 2015/09発売、m4/3、4608×3456(1593万画素)、画素ピッチ3.76μm
●E-M1ii: 2016/12発売、m4/3、5184×3888(2016万画素)、画素ピッチ3.35 μm
4枚目のグラフでは、キヤノンの以下の機種を取り上げました。多少の上下はあるものの、オリンパスのような明らかな変化はないと判断出来ると思います。
【キヤノン】
〇(グラフでは青系):フルサイズ/一眼レフ、●(グラフでは緑系):APS-C/一眼レフ、■(グラフでは赤系):APS-C/ミラーレス
●初代X: 2006/09発売、APS-C、3888×2592(1008万画素)、画素ピッチ5.71μm
〇1Ds3: 2007/11発売、フルサイズ、5616×3744(2103万画素)、画素ピッチ6.41μm
●X3: 2009/04 発売、APS-C、4752×3168(1505万画素)、画素ピッチ4.70μm
●X5: 2011/03発売、APS-C、5184×3456(1792万画素)、画素ピッチ4.31μm
〇1DX: 2012/06発売、フルサイズ、5184×3456(1792万画素)、画素ピッチ6.94μm
●X7i: 2013/04発売、APS-C、5184×3456(1792万画素)、画素ピッチ4.31μm
〇1DX: 2016/04発売、フルサイズ、5472×3648(1996万画素)、画素ピッチ6.56 μm
■M5: 2016/11発売、APS-C/ミラーレス、6000×4000(2400万画素)、画素ピッチ3.72 μm
書込番号:22041236
![]() 2点
2点
>ミスター・スコップさん
DxOが測定しているのは厳密にはISO感度ではないですよ。
今のカメラが採用しているISO感度はSOSまたはREIで、規定を見ればわかりますが、これらはRGB画像(≒JPEG)で保証されるものです。DxOはRAWを測定しており、RAWを単純に画像化したものを測定して算出した数値はカメラのISO感度の適正さの評価に使用できるものではありません。
DxOはセンサーが飽和する時点の設定感度を測定しており、これはDxOがセンサースコアを算出するための3つの数値、Landscape、Portrait、Sportsを出す際の補正に使用しています。
このMeasured ISOとManufacture ISOに差があるのは主にハイライト側の階調を確保するためのもので、DxOのサイトでも英語ではありますが説明されています。オリンパスは確かに1evほど低い値になっていますが、実はFuji Xシリーズも2/3evほど統一的に低くなっています(ご丁寧に、富士のカメラのEXIFにその差の数値が明記されているのでわかります)。最近ではライカのカメラも1evほど低く設定しているものが出ています。センサーが飽和してしまうとデータ的には無いものと同じになってしまうので(吹き飛ぶ、と表現されてます)、そうならないようにRAWの段階でアナログの増幅を低くとどめています。これはセンサー固有の感度と同じ設定感度では使えない方法です。なので、オリンパスも富士も最低常用感度をISO200としているのですが、これらのカメラの本来の最低感度(センサーの固有感度)はISO100前後です。固有感度以上の設定感度においてはデータは増幅されたものですが、この増幅をRAW前のアナログ手法でどれだけやるか、の差が数値として表れているのです。富士のダイナミックレンジ拡張200%・400%の設定すると最低感度がISO400・ISO800と制限を受けることからもわかることと思います。
言い換えると、センサーの固有の感度が100、設定感度100の時にセンサーが飽和ぎりぎりになる条件がある場合、設定感度を200にすると、センサーの感度は固定で変えらず、得られる光の量は半分なのでそのままではアンダーになるため増幅をしますが、これをアナログでやるか、デジタルでやるか、そのデジタルでやる割合が、このManufacture ISOとMeasured ISOの差として表れているのです。そしてその理由は上で書いた通りハイライト側が吹き飛んでしまわないため、です。
m43陣営の大人の事情、とはちょっと含んだ言い方ですが、パナは調べたらわかりますが、パナの場合Manufacture ISOとMeasured ISOの差はバラバラです。ほぼ0からほぼ1evまであったと思います。上にも書きましたが、最近はライカでも1ev差のものがありますし、富士は全機種2/3evです(中判は1/2ev)。何もそんな怪しい事情はなく、単にメーカーの画作りの方針の差、というだけです。あるとすれば、小型のセンサーほど白とびしやすい傾向があるということでしょうか。
書込番号:22251879
![]() 6点
6点
ぱおとうさん
貴重なコメント、どうもありがとうございます。
ド素人故の、疑問等々が浮かんだのですが、諸般の事情により、コメントさせて頂くとしても、半月以上先になりそうです。申し訳ありません。
書込番号:22253799
![]() 0点
0点
>ぱおとうさん
> DxOが測定しているのは厳密にはISO感度ではないですよ。
DxOMarkはISO Standard 12232で規定されている測定方法の一つであるsaturation-based methodで測定を行っています。
よってDxOMarkの測定値もISO感度です。
ISO sensitivity - DxOMark
https://www.dxomark.com/About/In-depth-measurements/Measurements/ISO-sensitivity
ISO 12232:2006 - Photography -- Digital still cameras -- Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index
https://www.iso.org/standard/37777.html
書込番号:22253965
![]() 1点
1点
じよんすみすさん
いつもいつも、ありがとうございます。
> DxOMarkはISO Standard 12232で規定されている測定方法の一つであるsaturation-based methodで測定を行っています。
以前、じよんすみすさんから、DxOMarkに関する有益な情報を多数教えて頂いたので、このご指摘に関しては、了解していました。
5つ上の書き込み[22041202]で、
> これらの結果から、直ちに、DxOMarkのMeasured ISOは、ISO12232に完全に準拠しているとまでは、断言出来ませんが、Measured ISO等の再現性が高い事は、実感頂けたと思います。
と、やや曖昧な記述になっているのは、DxOMarkのMeasured ISOが、絶対値として完全に正しいのかどうかは、断言出来なかったからです。さらに付け加えると、個人的には、絶対値はあまり信用していません。寧ろ、再現性の方が、断然、重要だと思っています。ですので、先の書き込み通り、
> DxOMarkは非常に再現性の高い測定を確立しているので、機種間の比較では、重宝しています。
と考えています。ただし、
> DxOMarkの測定結果のみから、メーカーや機種の優劣を判断する事は、私の場合、絶対にありません。
との注釈付きです。
【ご参考】
個人的に絶対値を重視していないのは、縁側でコメントしましたが、実体験に基づいています。
ただし、この点に限らず、PAMdiracさんからは、散々、ご指導を頂きましたので、私の個人的な見解を、他の方に押し付ける積りは、毛頭ありません。
「実測値が絶対値として正しいかどうかは重要ではなく(注3)、世の中のトレンド(ここで取り上げた例では、B社の測定値)に合っていれば、OKと言う考え方に傾いてしまいます。
(注3)
製品ZのISO規格策定に多少関わっていましたが、策定段階で既に、各社が同一サンプル品(複数)で行った測定値はバラバラで、ISO規格値は妥協の産物でした。」
・縁側での書き込み (2018/8/26、この1つ上の書き込みに、このスレでの書き込みを、ほぼそのまま引用しました)
https://engawa.kakaku.com/userbbs/2182/#2182-63
書込番号:22254398
![]() 1点
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「デジタル一眼カメラ」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 1 | 2025/09/30 2:00:56 | |
| 9 | 2025/09/30 1:08:17 | |
| 1 | 2025/09/29 20:44:54 | |
| 0 | 2025/09/29 20:01:08 | |
| 8 | 2025/09/29 18:28:21 | |
| 35 | 2025/09/30 1:59:03 | |
| 13 | 2025/09/29 12:58:36 | |
| 8 | 2025/09/28 17:07:01 | |
| 7 | 2025/09/28 18:12:01 | |
| 29 | 2025/09/29 6:37:38 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】メイン機メモ
-
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
-
【欲しいものリスト】次のMini-ITX このPCケースに惚れそう
-
【欲しいものリスト】Core Ultra 3 205出たらこのくらいで組みたい
-
【欲しいものリスト】グラボなし
価格.comマガジン
注目トピックス
(カメラ)
デジタル一眼カメラ
(最近3年以内の発売・登録)