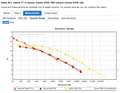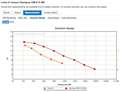-
ƒ؟77
- ƒfƒWƒ^ƒ‹ˆêٹلƒJƒپƒ‰ > ƒ؟ > ƒ؟77
- ˆêٹلƒŒƒtƒJƒپƒ‰ > ƒ؟ > ƒ؟77
ƒ؟77 II ILCA-77M2 ƒ{ƒfƒB
79“_ˆت‘ٹچ·AFƒZƒ“ƒTپ[‚ً“‹چع‚µ‚½ƒfƒWƒ^ƒ‹ˆêٹلƒJƒپƒ‰
ƒVƒ‡ƒbƒv‚ھ”ج”„‰؟ٹi‚ًŒfچع‚·‚é‚ـ‚إ‚¨‘ز‚؟‚‚¾‚³‚¢ ‰؟ٹiگ„ˆعƒOƒ‰ƒt
’†Œأ
چإˆہ‰؟ٹi(گإچ)پF
¥57,500 (2گ»•i)
- •t‘®ƒŒƒ“ƒY
-
- ƒ{ƒfƒB
- ƒYپ[ƒ€ƒŒƒ“ƒYƒLƒbƒg


-
- ƒfƒWƒ^ƒ‹ˆêٹلƒJƒپƒ‰ -ˆت
- ˆêٹلƒŒƒtƒJƒپƒ‰ -ˆت
چإˆہ‰؟ٹi(گإچ)پFƒVƒ‡ƒbƒv‚ھ”ج”„‰؟ٹi‚ًŒfچع‚·‚é‚ـ‚إ‚¨‘ز‚؟‚‚¾‚³‚¢ ””„“ْپF2014”N 6Œژ 6“ْ
ƒfƒWƒ^ƒ‹ˆêٹلƒJƒپƒ‰ > SONY > ƒ؟77 II ILCA-77M2 ƒ{ƒfƒB
ƒپپ[ƒJپ[‚جƒTƒ|پ[ƒg‚©‚瓾‚½ڈî•ٌ‚إ‚·پB
ƒXƒyƒbƒN•\‚ة‚ح‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إŒë‰ً‚·‚éگl‚à‚¢‚é‚©‚ئژv‚¢پA
‰\‚â–د‘z‚إ‚ح‚ب‚ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹‚بڈî•ٌ‚ئ‚µ‚ؤچع‚¹‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB
‚ب‚¨پA12bit‚ج—ا‚µˆ«‚µ“™‚ً‹cک_‚·‚é‚آ‚à‚è‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@
ڈ‘چ”شچ†پF18012600
![]() 8“_
8“_
ƒ\ƒjپ[‹@‚حپA14bitڈo—ح‚حژd—l‚ة‚»‚¤ڈ‘‚¢‚ؤ‚ ‚é‚©‚ç‚ث
ڈ‘‚¢‚ؤ‚ب‚¢‚ج‚حپA12bit‚¾‚ث
‹t‚ةپA14bit‚ب‚ج‚حƒ\ƒjپ[‹@‚إ‚ح””„’†‚جƒtƒ‹ƒTƒCƒY‚¾‚¯‚¾‚و
‚µ‚©‚àپAچ،‚ج‚ئ‚±‚ë’PژتŒہ’肾‚ث
ڈ‘چ”شچ†پF18012762پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 6“_
6“_
JPEG‚ح8ƒrƒbƒg‚¾‚µپAPCƒ‚ƒjƒ^پ[‚à8ƒrƒbƒg‚¾‚µپB•ت‚ة—ا‚¢‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢پH
ڈ‘چ”شچ†پF18013760پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 7“_
7“_
ƒ\ƒjپ[‚³‚ٌ‚حپARAWƒfپ[ƒ^پ[‚جƒrƒbƒgگ”‚ً‹C‚ة‚·‚é‚و‚¤‚بپA‘½ڈƒŒƒxƒ‹‚جچ‚‚¢ƒ†پ[ƒUپ[‚ًƒ^پ[ƒQƒbƒg‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢—l‚ب‚ج‚إپA‚»‚ê‚ح‚»‚ê‚إ‚ ‚è‚©‚ب‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18013858
![]() 14“_
14“_
ژ©•ھ‚ح‚»‚ê‚إگ¦‚چ¢‚ء‚ؤ‚ـ‚·(—ـ)
ڈ‘چ”شچ†پF18013862
![]() 9“_
9“_
12‚ب‚ج‚©14‚ب‚ج‚©‚حEXIF‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·‚وپB
ƒ؟99‚ج—ل
http://soar.keizof.com/~keizof/SLT-A99V/Friday-20140815/EXF09945.html
BitsPerSample: 14
ƒ؟77‚ج—ل
http://soar.keizof.com/~keizof/SLT-A77V/Eno-20140727/EXF07620.html
BitsPerSample: 12
”Y‚ق‚±‚ئ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
‚à‚ء‚ئ‚àپAˆس–،‚ج‚ ‚éƒfپ[ƒ^‚ب‚ج‚©پH‚»‚ê‚ح‰œ‚جگ[‚¢ژ؟–â‚إ‚·‚ھپBپBپB
ڈ‘چ”شچ†پF18016282
![]() 3“_
3“_
[18012600] ‚ ‚‚غ‚³‚ٌH‚:
> ƒپپ[ƒJپ[‚جƒTƒ|پ[ƒg‚©‚瓾‚½ڈî•ٌ‚إ‚·پB
>
> ƒXƒyƒbƒN•\‚ة‚ح‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إŒë‰ً‚·‚éگl‚à‚¢‚é‚©‚ئژv‚¢پA
> ‰\‚â–د‘z‚إ‚ح‚ب‚ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹‚بڈî•ٌ‚ئ‚µ‚ؤچع‚¹‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB
ƒ\ƒjپ[‚جRAW‚حپiŒآگl“I‚ة‚ح‰؛‚ç‚ب‚¢پAژ‘م’x‚ê‚إپAƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY‚ھ‚»‚à‚»‚àڈ¬‚³‚¢12MP’ِ“x‚جA7s“™‚إ‚ح‚¢‚¢‰ءŒ¸‚â‚ك‚é‚ׂ«پjˆ³ڈk‚ھگ¬‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA•K‘R“I‚ةڈî•ٌ‚ًژج‚ؤ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‰]‚¤•¾ٹQ‚ھ‚ ‚邯‚ê‚اپAˆ½‚é“ء’è‚جƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒYگ§–ٌ‚ج’†‚إ‚حƒZƒ“ƒTپ[‚©‚瓾‚ç‚ê‚éƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚à‚»‚ê‚ب‚è‚ة‹Lک^ڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚حپA‚ـ‚ پA•]‰؟ڈo—ˆ‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ˆِ‚ةپA12bit‚ئ‚©14bit“™‚ئ‰]‚¤“ءگ«‚ًپAژہچغ‚ة‚»‚ê‚ھ•¨—“I‚ة‚ح‚ا‚¤‰]‚¤ˆس–،‚©‚à‰ً‚è‚à‚¹‚¸پA‘ü‰L“غ‚ف‚ة‚µپAŒfژ¦”آ‚إ’m‚ء‚½‚و‚¤‚ب”Œ¾‚ًŒJ‚è•ش‚·ƒEƒ}ƒVƒJ‚ھژUŒ©‚³‚ê‚ـ‚·پB
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281267/SortID=17491978/#17494203
14bit‚جADC‚ً“‹چع‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئوگ‚ء‚ؤ‚¢‚é–^ƒپپ[ƒJپ[‚جƒfƒWƒCƒ`‚إ‚àپAƒZƒ“ƒTپ[‚جƒmƒCƒYپAژل‚µ‚‚حADC‚جگ«”\ŒہٹE‚©‚çپAژہچغ‚ة‚ح‹Lک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éƒfپ[ƒ^‚ج‰؛ˆتƒrƒbƒg‚حƒmƒCƒYپA‚آ‚ـ‚è—گگ”‚ئ‹و•تڈo—ˆ‚ب‚¢‚ج‚إپA—Lˆ×‚بƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚حچإچ‚11bit’ِ“x‚ج‹@ژي‚à‚ ‚é‚ئDxoMark‚جƒeƒXƒg‚إ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18035854
![]() 10“_
10“_
ƒ³ƒحƒحƒة‚³‚ٌپA‚à‚µ‰ً‚é‚ب‚çپAˆب‰؛‚جژO“_‚¾‚¯‚إ‚à‹³‚¦‚ؤ‚‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚©
‰½ŒجپA12bitRAW‚©‚çپA12EV‚ً‘ه‚«‚‰z‚¦‚éƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ھ’ٹڈo‚إ‚«‚é‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH
11EV’ِ“x‚جڈî•ٌ—ت‚ب‚çپA12bit‚إ‚à14bit‚إ‚à“¯‚¶‚إپA14bit‚ة‚·‚邱‚ئ‚ح–³ˆس–،‚إ‚ ‚é‚ئ‚نپ[‚±‚ئ‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH
ˆب‘OپAƒRپ[ƒW‚³‚ٌ‚ھ99‚إƒeƒXƒg‚µ‚½پAژB‰eڈًŒڈ‚ھ12bit‚جڈêچ‡‚ئ14bit‚جڈêچ‡‚إ‚حپAJPEG‚ة‘ه‚«‚بˆل‚¢‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚ ‚ê‚ح‚»‚à‚»‚à‚±‚جbitگ”‚حٹضŒW‚ب‚پARAWˆ³ڈk‚جƒAƒ‹ƒSƒٹƒYƒ€“™‚ج•ت—vˆِ‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH
ژ؟–â‚خ‚©‚è‚إگ\‚µ–َ‚ب‚¢
ڈ‘چ”شچ†پF18037330پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
> ‰½ŒجپA12bitRAW‚©‚çپA12EV‚ً‘ه‚«‚‰z‚¦‚éƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ھ’ٹڈo‚إ‚«‚é‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH
ƒ\ƒjپ[‚جڈêچ‡پA—ل‚¦‚خ14bit‚جcolumn ADC‚ً“‹چع‚µ‚ؤ‚¢‚éژB‘œ‘fژq‚جƒfپ[ƒ^‚ًپA”ٌگüŒ`‚ةƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚إ‚µ‚ه‚¤پB
گlٹش‚ج–ع‚حپAٹî–{“I‚ة‚ح‹P“xچ·‚ً”ٌگüŒ`‚ة’mٹo‚·‚é‚ج‚إپAڈî•ٌƒGƒ“ƒgƒچƒsپ[“IپA‚آ‚ـ‚èƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚ةژg—p‚·‚éƒrƒbƒgگ”‚ج—LŒّ—ک—p‚جٹد“_‚©‚ç‚ح”ٌگüŒ`ˆ³ڈk‚ج•û‚ھچ‡—“I‚إ‚·پB
ƒ\ƒjپ[‚جRAWƒtƒ@ƒCƒ‹‚جˆ³ڈk•ûژ®‚ج“ءگ«‚حگ³ژ®‚ة‚حŒِٹJ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إپAژ—‚½—l‚بŒ´—‚جsRGB‚âAdobeRGB‹Kٹi‚ً—ل‚ةژو‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_RGB_color_space
—ل‚¦‚خAdobeRGB‚إ‚حپAƒfپ[ƒ^‚حƒKƒ“ƒ}ژwگ”’l563/256 ~= 2.199‚جƒKƒ“ƒ}ƒJپ[ƒu‚إƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚·‚é‚ئ’è‚ك‚ؤ‚¢‚éپB
[0..1]‚جٹش‚جگüŒ`‚ج“ü—ح‚جڈêچ‡پAƒKƒ“ƒ}•دٹ·‚³‚ꂽڈo—ح‚ح‚ا‚¤‚ب‚é‚©پF
“ü—ح’lپi0.00پj-> ڈo—ح’l= 0.00^(256/563) = 0
“ü—ح’lپi0.01پj-> ڈo—ح’l= 0.01^(256/563) ~= 0.123193
“ü—ح’lپi0.03پj-> ڈo—ح’l= 0.03^(256/563) ~= 0.203189
“ü—ح’lپi0.09پj-> ڈo—ح’l= 0.09^(256/563) ~= 0.334570
“ü—ح’lپi0.18پj-> ڈo—ح’l= 0.18^(256/563) ~= 0.458529
“ü—ح’lپi0.31پj-> ڈo—ح’l= 0.31^(256/563) ~= 0.587109
...
“ü—ح’lپi0.80پj-> ڈo—ح’l= 0.90^(256/563) ~= 0.903513
“ü—ح’lپi0.90پj-> ڈo—ح’l= 0.90^(256/563) ~= 0.953221
“ü—ح’lپi1.00پj-> ڈo—ح’l= 1.00^(256/563) ~= 1
‹P“xچ·‚ھ0.01‚µ‚©‚ب‚¢[0.00-0.01]‚جٹش‚ةپA–ٌ0.123193‚جڈo—ح‹و•ھ‚ً”z•ھ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
‚»‚µ‚ؤپA‹P“xچ·‚ھ0.20‚ ‚é[0.80-1.00]‚ةپA–ٌ0.096487‚جڈo—ح‹و•ھ‚ً”z•ھ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
‚±‚ج—l‚ةپAƒqƒg‚ھ’mٹo‚µˆص‚¢پAˆأ‚¢’l‚إ‚جڈ¬‚³‚ب‹P“x‚جچ·ˆظ‚ةڈo—ح‹و•ھ‚ً—Dگو“I‚ة”z•ھ‚µپA‚»‚µ‚ؤ‹P“xچ·‚ً’mٹo‚µ‚ة‚‚¢–¾‚é‚¢•”•ھ‚إ‚ح‘ٹ‘خ“I‚ةڈo—ح‹و•ھ‚ً‹·‚ك‚éپB
’تڈي‚جJPEG“™‚ج8bit‚جƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚إ‚حAdobeRGB‚جڈêچ‡پA‚ا‚¤‚ب‚é‚©پB
8bit‚إ‚ح0,1,...,255‚جگ®گ”’l‚ً•\Œ»ڈo—ˆ‚éپB
‚و‚ء‚ؤپA—ل‚¦‚خ“ü—ح’lپi0.18پjپA‚آ‚ـ‚è18%ƒOƒŒپ[‘ٹ“–‚ج–¾‚邳‚إ‚حپAڈo—ح’l‚ح0.458529*255 ~= 116.925پAژlژجŒـ“ü‚µ‚ؤ117‚ئ‚ب‚éپB
‚آ‚ـ‚èپAAdobeRGBڈ€‹’‚ج8bit JPEG‚ج‰و‘œƒtƒ@ƒCƒ‹‚إ‚حپA18%ƒOƒŒپ[‘ٹ“–‚جRGB’l‚حپA‘fگl‚ھچl‚¦‚»‚¤‚ب255*0.18=(46,46,46)‚إ‚ح‚ب‚پA(117,117,117)‚ئ‚ب‚éپB
—v‚·‚é‚ةپAگ^‚ءˆأ‚ئ18%ƒOƒŒپ[‚جٹش‚ةپA118Œآ‚ج’l‚ً”z•ھ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
‚»‚µ‚ؤپA18%ƒOƒŒپ[‚ئ100%‚ج–¾‚邳‚جٹش‚ة(256-118)=138Œآ‚ج’l‚ً”z•ھ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
ڈ®پA[0,1,2,...,255]‚ئ8bit‚إƒGƒ“ƒRپ[ƒh‚³‚ꂽsRGB‚جڈêچ‡پA‚ا‚ج—l‚بƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ھ‹Lک^ڈo—ˆ‚邾‚낤‚©پB
http://en.wikipedia.org/wiki/SRGB
8bitƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚إ‚جsRGB’lپu255پv‚جپA”ٌگüŒ`ƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‘O‚ج‹P“x‚ح“–‘Rچإچ‚‚ج‹P“xپA‚آ‚ـ‚è1.0
‚»‚µ‚ؤپA8bitƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚إ‚جsRGB’lپu1پv‚حپAWikipedia‚جsRGB‹Lژ–‚ً“ا‚ك‚خ‰ً‚é’ت‚èپA1/255/12.92 ~= 0.00030352 ‘ٹ“–‚ئ‚ب‚éپB
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW(DR)‚ئ‚ح‹Lک^ڈo—ˆ‚éچإچ‚‚ج‹P“x‚ئپiƒ[ƒچ‚إ‚ح‚ب‚¢پjچإڈ¬‚ج‹P“x‚ج”ن—¦پB
‚و‚ء‚ؤپA8bit‚جsRGB‚ةƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ح255*12.92 = 3294.6 ~= 2^11.6859
ڈî•ٌƒGƒ“ƒgƒچƒsپ[‚ج8bitپA‚آ‚ـ‚èپuˆظ‚ب‚é256Œآ‚ج’l‚ًژو‚肤‚é•دگ”پv‚ئپAADC‚ج8bit‘ٹ“–پA‚آ‚ـ‚è8EV‚جDR‚ئ‚ًچ¬“¯‚µ‚ؤ‚¢‚éژز‚ھپA[18013760]‚àژ¦‚·’ت‚èپAƒfƒWƒJƒپ‚جŒfژ¦”آ‚إ‚ح‘½‚¢پB
‚µ‚©‚µپAڈم‹L‚إگà–¾‚µ‚½’ت‚èپA—ل‚¦‚خ8bit‚جsRGBƒfپ[ƒ^‚إ‚ح8EV‚إ‚ح‚ب‚پA–ٌ11.6859EV‚جDR‚ھƒGƒ“ƒRپ[ƒh‰آ”\‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
“¯—l‚ةپADxOMark‚ة‚و‚éA77II‚جDR‘ھ’è’l‚حچإچ‚12.64EV‚ئ‰]‚¤‚ھ‚±‚ئ‚ھژ¦‚·’ت‚èپAƒ\ƒjپ[‚جˆ³ڈk•ûژ®‚àƒGƒ“ƒgƒچƒsپ[ƒrƒbƒgگ”‚ئƒGƒ“ƒRپ[ƒh‰آ”\‚بDR‚ھ“¯‚¶‚بپA’Pڈƒ‚ةگüŒ`پEƒٹƒjƒA‚ب‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚ح–¾‚ç‚©پB
‚»‚µ‚ؤپAچإچ‚DR‚ح12EV‚ً’´‚¦‚é’لISO‚إ‚حپAƒZƒ“ƒTپ[‚جژ‚آٹK’²گ«‚ً—]‚·‚ئ‚±‚ë‚ب‚‹Lک^‚·‚é‚ة‚حپAADC‚ً14bitƒ‚پ[ƒh‚إ‰^—p‚·‚é•û‚ھ–]‚ـ‚µ‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB
ڈ‘چ”شچ†پF18037499
![]() 3“_
3“_
AdobeRGBڈ€‹’‚ج8bit JPEG‚ج‰و‘œƒtƒ@ƒCƒ‹‚إ‚ح–ٌ11.6859EV‚جDR‚ھƒGƒ“ƒRپ[ƒh‰آ”\
‚ئ‚¤‚¢‚±‚ئ‚إ‚·‚ھپA‚±‚جƒ؟77II‚جƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚جچإچ‚‚ھچإچ‚12.64EV‚ئ‚ح‚¢‚ء‚ؤ‚àiso100‚إ‚ح‚·‚إ‚ة12EV‚®‚ç‚¢پB
”نٹr‚إ‚إ‚ؤ‚¢‚éCANON‚ج‚P‚c‚w‚â‚V‚O‚c‚إ‚ح‚»‚à‚»‚àƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ھ11.6‚d‚u‚ة‚¢‚©‚ب‚¢‚©‚ç8bit‚إژB‚ء‚ؤ‚¨‚¯‚خ‚¢‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·‚©پHپ@‚±‚±‚ھ‚و‚‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚إ‚·پB‚±‚ê‚ء‚ؤژہچغ‚جٹ´ٹo‚ئˆل‚¢‚ـ‚¹‚ٌپHپ@
AdobeRGBڈ€‹’‚ج8bitپ¨–ٌ11.6EV‚جDR
12bit‚جRAWپ¨پ@پHپH‚ج‚c‚q
14bit‚جRAWپ¨پ@پHپH‚ج‚c‚q
‚±‚جٹضŒW‚ً‚ف‚é‚ئ12bit‚جRAW‚إ‚·‚إ‚ة12.64EV‚ب‚ٌ‚ؤ’´‚¦‚ؤ‚»‚¤‚إ‚·‚و‚ثپB14bit‚إژB‰e‚·‚é‚ب‚ٌ‚ؤ‚»‚à‚»‚à–³‘ت‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚إ‚·‚©پHپ@‚¾‚ئ‚µ‚½‚ç‚ب‚؛14bit‚ة‚±‚¾‚ي‚é‚ٌ‚إ‚·‚©پH
چ•ƒVƒƒƒc‚³‚ٌپA‚t‚f‚x‚g‚³‚ٌپAƒRپ[ƒW‚³‚ٌپA‚ا‚ب‚½‚إ‚à‚¢‚¢‚ٌ‚إ‚·‚ھپA12bit RAW‚¾‚ئچ¢‚ء‚ؤ14bit RAW‚¾‚©‚çڈ•‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بژہ‘جŒ±‚ً‹³‚¦‚ؤ‚à‚炦‚ب‚¢‚إ‚·‚©پH
ژ„‚حSONYƒ†پ[ƒUپ[‚إ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا12bit RAW‚إژB‰e‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ھ14bit RAW‚إژB‰e‚إ‚«‚é‚ئ‚«‚ح‚µ‚ئ‚±‚¤‚©‚ئچl‚¦‚ؤژB‰e‚·‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚جچsˆ×‚ھ–³‘ت‚ب‚ج‚©ˆس–،‚ھ‚ ‚é‚ج‚©’m‚肽‚¢‚ج‚إ‚·پB
ƒ³ƒحƒحƒة‚³‚ٌ
پ„پ„8bit‚جsRGB‚ةƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ح255*12.92 = 3294.6 ~= 2^11.6859
‚±‚جŒvژZ‚ً12bit RAW‚ئ14bit RAW‚إŒvژZ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚ب‚¢‚إ‚·‚©پH
ˆب‘O‚ة‚à‚±‚جکb‘è‚جژپA“oڈꂳ‚ê‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚¢‚ـ‚¾‚ةژك‘R‚ئ‚µ‚ـ‚¹‚ٌپB
14bit‚ح–³‘ت‚ب‚ج‚إ‚·‚©پH‚±‚جŒvژZ‚¾‚ئŒ»چف‚جƒZƒ“ƒTپ[‚¾‚ئ12bit‚إ‚àڈ\•ھ‚ب‚و‚¤‚ةگ„‘ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB‚إ‚ح‚ب‚؛ƒJƒپƒ‰ƒپپ[ƒJپ[‚ح14bit‚ة‚±‚¾‚ي‚é‚ج‚إ‚·‚©پHپ@
ڈ‘چ”شچ†پF18037561
![]() 1“_
1“_
ƒJپ[ƒ‹ƒ‰ƒCƒX‚³‚ٌ
D800E‚إ‚جƒeƒXƒg
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=15274446/
ƒ؟99‚إ‚جƒeƒXƒg
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416459/Page=70/SortRule=2/ResView=all/#15148780
14bit‚ج•û‚ھ12bit‚و‚è‰وژ؟‚⌻‘œ‚ة—L—ک‚ة‚ب‚é‚ئ‚¢‚¤ڈî•ٌ‚ح’m‚ç‚ب‚¢‚إ‚·پB
ƒ\ƒjپ[‚³‚ٌ‚ة‚à‚¤‚؟‚ه‚ء‚ئچl‚¦‚ؤ—~‚µ‚¢‚ج‚حپAڈںژè‚ةƒ‚پ[ƒh‚ً•د‚¦‚é‚ب¥¥¥‚ئ‚¢‚¤ژ–‚إ‚·‚ثپB
ƒjƒRƒ“‚ح 12/14 ژB‰eژز‚ج”»’f‚إ‘I‚ׂـ‚·پB14bit‚و‚èƒtƒ@ƒCƒ‹—e—ت‚ًڈ¬‚³‚‚·‚邽‚ك‚ةپA
ژB‰eژز‚جˆسژu‚إ 12bit‚إژg‚¤پBپ@‹@ژي‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حکAژت‚جƒRƒ}‘¬پAƒoƒbƒtƒ@ٹm•غ‚ج‚½‚ك‚ة
12bit‚ةگف’è‚·‚éپB
ƒtƒ@ƒCƒ‹‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚ء‚ؤ‚àƒoƒbƒtƒ@‚ھŒ¸‚ء‚ؤ‚à‚و‚è”ü‚µ‚¢‚¾‚낤پAŒ»‘œ‘دگ«‚à‘‚·‚إ‚ ‚낤
14bit‚ةگف’è‚·‚éپBپ@
‚±‚ê‚ھژB‰eژز‚جˆسژu‚إŒˆ’è‚إ‚«‚ـ‚·پB
ƒ\ƒjپ[‚³‚ٌ‚ح BIONZ‚جڈˆ—“sچ‡‚إڈںژè‚ة 12/14bitƒ‚پ[ƒh‚ً•د‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚·پB
ƒ؟7sچw“ü‚àچ‚ٹ´“xڈdژ‹‚µ‚ؤ‚جژ–‚إ‚·‚ھپAƒTƒCƒŒƒ“ƒg‚ةگف’è‚·‚é‚ئڈںژè‚ة12bit‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB
ƒAƒ“ƒPپ[ƒg‚ة‚à‚و‚ڈ‘‚«‚ـ‚·‚ھپA‚±‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح‚»‚ë‚»‚ë‚â‚ك‚ؤ—~‚µ‚¢پB
ڈ‘چ”شچ†پF18038027
![]() 3“_
3“_
‚ ‚ءپIڈم‹L‚جƒٹƒ“ƒN‹t‚إ‚µ‚½¥¥¥پB
ƒ؟99‚إ‚جƒeƒXƒg
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416458/SortID=15274446/
D800E‚إ‚جƒeƒXƒg
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416459/Page=70/SortRule=2/ResView=all/#15148780
ڈ‘چ”شچ†پF18038030
![]() 1“_
1“_
> BIONZ‚جڈˆ—“sچ‡‚إڈںژè
‚ب‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚µپA
ˆس–،‚ج‚ ‚é14ƒrƒbƒgƒfپ[ƒ^‚ج“¾‚ç‚ê‚éڈêچ‡‚ئ‚»‚¤‚إ‚ب‚¢ڈêچ‡‚إ
‹و•ت‚µ‚ؤچإ“K‰»‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
ڈ‘چ”شچ†پF18038236
![]() 3“_
3“_
ƒ³ƒحƒحƒة‚³‚ٌپA‚ا‚¤‚à‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤
Œم‚إ‚³‚ç‚ةŒم‚إڈع‚µ‚“ا‚ٌ‚إ‚ف‚ـ‚·
14bit14EV‚إƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚µ‚½‚à‚ج‚ًپA”ٌگüŒ`‚ة12bit‚جٹي‚ة“ü‚ê‚é
گ³’¼پA‚±‚±‚ةٹmگM‚ھژ‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½‚ٌ‚·‚وپA‚»پ[‚ب‚ج‚©‚ب‚ء‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚¯‚اپA‚»‚ꂶ‚ل‚à‚¤پuRAWپv‚¶‚ل‚ب‚¢‚¶‚ل‚ٌپA‚»‚ٌ‚بƒnƒY‚ھ‚ب‚¢‚ء‚ؤ
‚ـپARAW‚ج’è‹`‚ًژ©•ھ‚إچى‚ء‚½‰´ژ©گg‚ھƒEƒ}ƒVƒJ‚ب‚ٌ‚¾‚¯‚ا‚ث
‚إپA‰¼‚ة‚»پ[‚¾‚ئ‚µ‚ؤ‚àپAƒfپ[ƒ^—ت“I‚ة‚ح1/4‚ة‚ب‚é‚ھپA‚»‚ê‚حگlٹش‚جŒ©‚¦•û‚ًژQچl‚ة‚µ‚½ٹشˆّ‚«•û‚إ‚ ‚é‚©‚çپA’Pڈƒ‚ة—LŒّ‚ةژg‚¦‚é‚ئژv‚¦‚éڈî•ٌ‚ھ1/4‚ة‚ب‚é‚ي‚¯‚¶‚ل‚ب‚¢‚µپA‚ق‚µ‚ë‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‰e‹؟‚µ‚ب‚¢‚¾‚낤
‚»‚ê‚و‚è‚àپA14bit‚ئ‚¢‚¢‚ب‚ھ‚çپA2EVˆبڈم‚àƒmƒCƒY‚ھ–„‚ـ‚ء‚½ƒfپ[ƒ^‚±‚»–³‘ت‚إ‚ح‚ب‚¢‚©
‚ء‚ؤژv‚ء‚ؤ‚½
‚¯‚اپc
ƒJپ[ƒ‹ƒ‰ƒCƒX‚³‚ٌپA
river38‚³‚ٌ‚ج‚ ‚جƒXƒŒƒbƒhپA“ء‚ةƒRپ[ƒW‚³‚ٌ‚ج”نٹrژتگ^‚ًŒ©‚ؤپu‚ ‚êپHپv‚ء‚ؤ‚ب‚ء‚½‚ي‚¯‚و
‰´ژ©گgپA‚»‚ج‚؟‚ه‚ء‚ئ‘O‚جƒXƒŒƒbƒh‚إپA’تڈيŒ»‘œ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA12bit‚à14bit‚àٹضŒW‚ب‚¢‚¾‚ë‚ف‚½‚¢‚بڈ‘‚«چ‚ف‚à‚µ‚ؤ‚é‚و
‚إپA‚±‚ê‚ح‰´‚جٹ¨ˆل‚¢‚ب‰آ”\گ«‚à‘ه‚ب‚ٌ‚¾‚¯‚اپA‚»‚¤Œ¾‚¦‚خپuگآ‹َپv‚ھƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒv‚âگF‚ھ‚¨‚©‚µ‚‚ب‚ء‚ؤ‚éژتگ^‚ج‚ظ‚ئ‚ٌ‚اƒ\ƒjپ[‚جAPS-C‹@پc‚ء‚ؤژv‚ء‚ؤ‚ث
‚إپA‚â‚ء‚دپA‚±‚ج12bit‚ح14bit‚ئ”ن‚ׂé‚ئپA‚©‚ب‚茩—ٍ‚è‚·‚é‚©‚à‚ء‚ؤژv‚¢‚ة•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚‚ج‚و
‚¾‚ء‚½‚çپAچ‚‹‰ژuŒü‚ج‰وژ؟‚ةچS‚é‘w‚ھچw“ü‚·‚é‚إ‚ ‚낤Aƒ}ƒEƒ“ƒg‚جƒtƒ‹ƒTƒCƒY‹@‚حپA–³ڈًŒڈ‚إ14bit‚إ‚ ‚é‚ׂ«‚إ‚حپH‚ء‚ؤ‚ث
ڈ‘چ”شچ†پF18038532پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 2“_
2“_
river38‚³‚ٌ
‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پB‚±‚¤‚¢‚¤ƒXƒŒ‚حٹy‚µ‚¢‚إ‚·‚ثپB
پ„پ„ƒ\ƒjپ[‚³‚ٌ‚ة‚à‚¤‚؟‚ه‚ء‚ئچl‚¦‚ؤ—~‚µ‚¢‚ج‚حپAڈںژè‚ةƒ‚پ[ƒh‚ً•د‚¦‚é‚ب¥¥¥‚ئ‚¢‚¤ژ–‚إ‚·‚ثپB
‚¨‹Cژ‚؟‚ي‚©‚è‚ـ‚·پBکAژت–‡گ”‚ھ‚ا‚ꂾ‚¯ڈ‚ب‚‚ب‚낤‚ئ14bit‚إ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚à‚µ‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·‚و‚ثپB
‚ئ‚±‚ë‚إƒ؟‚V‚جڈ¤•iگà–¾‚ج‚ئ‚±‚ë‚إ
–L‚©‚بٹK’²•\Œ»‚ً‰آ”\‚ة‚·‚é16bit‰و‘œڈˆ— / 14bit RAWڈo—ح‘خ‰
ƒCƒپپ[ƒWƒZƒ“ƒTپ[“à‚إAD•دٹ·‚³‚ꂽ14bit‚جƒfƒWƒ^ƒ‹گMچ†‚ًپAگVٹJ”‚جƒtƒچƒ“ƒgƒGƒ“ƒhLSI‚ئپuBIONZ Xپv‚جƒVƒXƒeƒ€“à‚إˆê“x16bitڈˆ—‚µ‚ؤ‚©‚çپARAW‰و‘œ‚ة14bitڈo—ح‚·‚邱‚ئ‚إپA‚و‚è–L‚©‚بٹK’²•\Œ»‚ئچ‚‰وژ؟‚ًژہŒ»‚µ‚ـ‚·پB
پ¦ ’·•bژƒmƒCƒYƒٹƒ_ƒNƒVƒ‡ƒ“پAƒoƒ‹ƒuژB‰eپAکA‘±ژB‰eژ‚جڈًŒڈ‚إ‚ح12bit‚إ‹Lک^‚³‚ê‚ـ‚·
http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7/feature_1.html
‚±‚ê“ا‚ق‚ئچإڈ‰‚ح14bit‚إAD•دٹ·‚µ‚½‚à‚ج‚ً16bit‚إ‰و‘œڈˆ—‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚ثپB
16ƒrƒbƒg‚©‚ç14ƒrƒbƒg‚©16ƒrƒbƒg‚©‚ç12ƒrƒbƒg‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB
‚»‚µ‚ؤ‚»‚ج‚±‚ئ‚إ–L‚©‚بٹK’²•\Œ»‚ً‰آ”\‚ة‚·‚é‚ئ‚ ‚è‚ـ‚·پB
‚±‚ج‚ ‚½‚葼ژذ‚ح14bit‚ح14bit‚ج‚ـ‚ـ‚ب‚ٌ‚إ‚·‚©‚ثپH
گl‚ة‚و‚ء‚½‚ç16bit•دٹ·‚ب‚ٌ‚ؤ‚ئƒAƒŒƒ‹ƒMپ[‚ً‚¨‚±‚·گl‚à‚¢‚»‚¤‚إ‚·پB
‚½‚¾ƒ؟77II‚ب‚ٌ‚ؤ’Pژث‚إ‚à12bit‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚‚ç‚¢‚ب‚ج‚إپAڈo—حƒtƒ@ƒCƒ‹‚ھ12ƒrƒbƒg‚إ‚ ‚낤‚ھ1‚Sƒrƒbƒg‚إ‚ ‚낤‚ھ•د‚ي‚è‚ھ‚ب‚¢‚ئ”»’f‚µ‚ؤƒ؟‚V‚VII‚ةچع‚¹‚ؤ‚±‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚©پA14ƒrƒbƒg‚جٹK’²‚ً‚إ‚«‚é‚ج‚حƒtƒ‹ƒTƒCƒY‚¾‚¯‚¾‚ئ‹@”\گ§Œہ‚µ‚½‚ج‚©‚±‚ê‚ھ‚ا‚؟‚ç‚©‚إ‹Cژ‚؟‚جژ‚؟•û‚à‚©‚ي‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·‚ثپBƒ³ƒحƒحƒة‚³‚ٌ‚ج‚¨کb‚ً‚¨•·‚«‚·‚é‚ئ‚ا‚¤‚à‘Oژز‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ھپB
‚à‚µ‚ي‚©‚é‚©‚½‚¨‚ç‚ꂽ‚狳‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
ڈ‘چ”شچ†پF18038585
![]() 1“_
1“_
[18037561] ƒJپ[ƒ‹ƒ‰ƒCƒX‚³‚ٌH‚:
> AdobeRGBڈ€‹’‚ج8bit JPEG‚ج‰و‘œƒtƒ@ƒCƒ‹‚إ‚ح–ٌ11.6859EV‚جDR‚ھƒGƒ“ƒRپ[ƒh‰آ”\
‚ٌ‚ب‚±‚ئپAڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپBAdobeRGB‚ئsRGB‚ًچ¬“¯‚µ‚ب‚¢‚إ‚‚¾‚³‚¢پB
CRT‚â‰tڈ»“™‚جƒ‚ƒjƒ^پ[پA‚»‚µ‚ؤAdobeRGB‚جƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO“™‚إŒ»‚ê‚é”ٌگüŒ`‚بپuƒKƒ“ƒ}پv‚ئ‰]‚¤ٹT”O‚³‚¦—‰ً‚µ‚ؤ‚¢‚ê‚خپAAdobeRGB‚جڈêچ‡‚حƒKƒ“ƒ}‚ح563/256‚ب‚ج‚إپA8bitƒfپ[ƒ^‚ج‚؛ƒچ‚إ‚ح‚ب‚¢چإڈ¬‹P“x1/255‚ح
x^(256/563) = 1/255
‚ئ‰]‚¤•û’ِژ®‚ج‰ً x ‚ً‹پ‚ك‚邱‚ئ‚إپAƒٹƒjƒA‚ج‘ٹ“–’l x ‚ح exp( log(1/255) * 563/255 )پA‚آ‚ـ‚è–ٌ 0.00000509907867 ‚ئ‰ً‚锤‚إ‚·‚ثپB
“–‘RپAƒGƒ“ƒRپ[ƒh‚³‚ꂤ‚éچإچ‚‚جƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ح 1/0.00000509907867 ~= 196113.86 ~= 2^17.581
‚آ‚ـ‚èپA8bit‚جAdobeRGB‚جƒfپ[ƒ^‚جڈêچ‡پA–ٌ17.581EV‚جDR‚ھƒGƒ“ƒRپ[ƒh‰آ”\پB
> AdobeRGBڈ€‹’‚ج8bitپ¨–ٌ11.6EV‚جDR
> 12bit‚جRAWپ¨پ@پHپH‚ج‚c‚q
> 14bit‚جRAWپ¨پ@پHپH‚ج‚c‚q
>
> ‚±‚جٹضŒW‚ً‚ف‚é‚ئ12bit‚جRAW‚إ‚·‚إ‚ة12.64EV‚ب‚ٌ‚ؤ’´‚¦‚ؤ‚»‚¤‚إ‚·‚و‚ثپB
RAWƒtƒ@ƒCƒ‹‚جƒfپ[ƒ^‚ھƒKƒ“ƒ}ƒJپ[ƒu“™‚ً—p‚¢پA”ٌگüŒ`ƒGƒ“ƒRپ[ƒh‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پAƒLƒ„ƒmƒ“‚âƒjƒRƒ“‚ف‚½‚¢‚ب’Pڈƒ‚ةƒٹƒjƒA‚بڈêچ‡پAƒGƒ“ƒRپ[ƒhڈo—ˆ‚éچإچ‚DR‚حڈî•ٌƒGƒ“ƒgƒچƒsپ[‚ئ“¯‚¶‚ة‚ب‚éپB
‚آ‚ـ‚è14bit‚جƒٹƒjƒARAW‚ة‚ح—ک_ڈمپAچإچ‚14EV‚جDR‚µ‚©ƒGƒ“ƒRپ[ƒhڈo—ˆ‚ب‚¢پB
‚»‚µ‚ؤپAƒLƒ„ƒmƒ“‚جڈêچ‡پAژB‘œ‘fژq“™‚جƒAƒiƒچƒO•”•ھ‚جS/N”نپAژل‚µ‚‚حA/D•دٹ·‰ٌکH‚جگ«”\‚جŒہٹE‚©‚ç‚©پAŒِڈجپu14bitپv‚جADC‚©‚çڈo—ح‚³‚ê‚é‰؛ˆت–ٌ3ƒrƒbƒg‘ٹ“–‚حپAژہ‚حژB‘œ‘fژq‚ة“üژث‚µ‚½Œُ‚ج‹P“x‚ئ‘ٹٹضگ«‚ج‚ب‚¢پA‘ü‚جƒmƒCƒYپE—گگ”‚ب‚ج‚إپA—LŒّDR‚ح–ٌ11bit‘ٹ“–‚¾‚ئDxOMark‚ج‘ھ’茋‰ت‚إ”»–¾‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
ڈ®پADxOMark‚ج—LŒّDR‚ج’è‹`‚حپAپu‹Lک^ڈo—ˆ‚éچإچ‚‚ج‹P“x‚ئپAƒmƒCƒY‚ئ—Lˆ×‚ةژ¯•تڈo—ˆ‚éچإڈ¬‚ج‹P“x‚ئ‚ج”ن—¦پv‚ئ’è‹`‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
•¨—Œ»ڈغپA”ٌگüŒ`ƒGƒ“ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒOپAڈî•ٌƒGƒ“ƒgƒچƒsپ[پAƒmƒCƒY‚ھٹـ‚ـ‚ê‚éژہچغ‚جƒfپ[ƒ^‚ً‚ا‚¤‘ھ’è‚·‚é‚©“™‚ً—‰ً‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پA’Pچ×–E‚بƒXƒyƒbƒNƒIƒ^ƒN‚حƒLƒ„ƒmƒ“‚جپu14bit ADCپv‚ئ•·‚¢‚½‚¾‚¯‚إ—L‚è“ï‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپ@(^^;
ڈ‘چ”شچ†پF18038613
![]() 3“_
3“_
[18038027] river38‚³‚ٌH‚:
> ƒjƒRƒ“‚ح 12/14 ژB‰eژز‚ج”»’f‚إ‘I‚ׂـ‚·پB
> [..]
> ƒ\ƒjپ[‚³‚ٌ‚ح BIONZ‚جڈˆ—“sچ‡‚إڈںژè‚ة 12/14bitƒ‚پ[ƒh‚ً•د‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚·پB
> ƒ؟7sچw“ü‚àچ‚ٹ´“xڈdژ‹‚µ‚ؤ‚جژ–‚إ‚·‚ھپAƒTƒCƒŒƒ“ƒg‚ةگف’è‚·‚é‚ئڈںژè‚ة12bit‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB
>
> ƒAƒ“ƒPپ[ƒg‚ة‚à‚و‚ڈ‘‚«‚ـ‚·‚ھپA‚±‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح‚»‚ë‚»‚ë‚â‚ك‚ؤ—~‚µ‚¢پB
ژB‘œ‘fژq‚ج‰و‘f“à‚إ‚حپA“üژث‚·‚éŒُژq‚ح“dژq‚ً—م‹N‚·‚éپB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E9%9B%BB%E5%8A%B9%E6%9E%9C#.E5.86.85.E9.83.A8.E5.85.89.E9.9B.BB.E5.8A.B9.E6.9E.9C
‚»‚µ‚ؤپA—م‹N‚³‚ꂽ“dژq‚حپA‰و‘f“à‚ج”÷چׂبƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ة’~گد‚³‚ê‚éپB
ƒVƒƒƒbƒ^پ[‚ھ•آ‚¶پAکIŒُ‚ھڈI—¹‚µ‚½ŒمپA’~گد‚³‚ꂽ“d‰×‚ة”ن—ل‚µٹe‰و‘f“à‚جƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ةŒ»‚ê‚é“dˆ³‚ً‘ھ’è‚·‚邱‚ئ‚إپAٹe‰و‘f‚ة“üژث‚µ‚½‹P“xƒfپ[ƒ^‚ً“¾‚ç‚ê‚éپB
“–‘RپAگV‚µ‚¢کIŒُ‚ًژn‚ك‚é‘O‚ةپAˆب‘O‰و‘f“à‚جƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ةˆب‘O’~گد‚³‚ꂽ“d‰×‚حژج‚ؤ‚ؤپAƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ً‚ـ‚ء‚³‚ç‚جڈَ‘ش‚ة‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB
‚±‚جپAکIŒُ‘O‚ةƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ج“d‰×‚ًƒNƒٹƒA‚·‚éچى‹ئ‚ً‰و‘f‚جپuƒٹƒZƒbƒgپv‚ئ‰]‚¤پB
–â‘è‚حپAٹe‰و‘f‚جƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ة‹ح‚©‚ب‚ھ‚ç‚àپAƒٹƒZƒbƒg‚µ‚ؤ‚àٹô‚ç‚©‚ج“d‰×‚ھ•K‚¸ژc‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
‚ـ‚½پA‚±‚جژc—¯“d‰×‚ح‰و‘fٹش‚إ”÷–‚ة‚خ‚ç‚آ‚پB‚»‚µ‚ؤپA‚±‚جژc—¯“d‰×‚حƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ج“dˆ³‚ة‰e‹؟‚ً—^‚¦پA‰و‘fٹش‚جڈo—حگMچ†‚ً‚خ‚ç‚آ‚©‚¹‚éپB
‚±‚ج•¨—“ءگ«‚ج”÷ڈ¬‚بچ·ˆظ‚ة‚و‚é‰و‘f‚جƒٹƒZƒbƒgŒم‚جƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ج“dˆ³‚ج‚خ‚ç‚آ‚«پA‚آ‚ـ‚èƒmƒCƒY‚ج‰e‹؟‚ً‚ا‚¤’لŒ¸‚·‚é‚©پB
CCDپACMOS‚ً–â‚ي‚¸پA“dژqژB‘œ‘fژq‚ً“‹چع‚µ‚ؤ‚¢‚éƒXƒ`ƒ‹—p‚جƒfƒWƒJƒپ–w‚ا‘S‚ؤ‚ج‹@ژي‚حپu‘ٹٹض“ٌڈdƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒOپvپi‰p:Correlated Double Sampling, CDSپj‚ئ‰]‚¤ƒmƒCƒY’لŒ¸ژè–@‚ًچج—p‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
CDS‚إ‚حپAƒٹƒZƒbƒgŒم‚ج‰و‘f‚جƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ج“dˆ³‚ً‘ھ’肵پAƒfپ[ƒ^‚ئ‚µ‚ؤRAM‚ة‹Lک^‚µ‚ؤ’u‚پB
‚»‚µ‚ؤپAکIŒُŒم‚ج‰و‘f‚جƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ج“dˆ³‚ً‘ھ’肵پA‚»‚ج‘ھ’è’l‚©‚çپAˆب‘O‹Lک^‚µ‚ؤ‚¢‚½ƒٹƒZƒbƒgŒم‚ج“dˆ³’l‚ًˆّ‚«ژZ‚µپAŒ‹‰ت‚ئ‚µ‚ؤƒٹƒZƒbƒgŒم‚ج“dˆ³‚ج‚خ‚ç‚آ‚«‚ج‰e‹؟‚ًƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹‚µ‚½پA“üژثŒُ‚ة‚و‚éڈƒ“d‰×‘‰ء—ت‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚éپB
‚آ‚ـ‚èپA‰و‘œƒfپ[ƒ^‚ً“¾‚éˆ×‚ة‚حپAƒٹƒZƒbƒg’¼Œم‚ئپAکIŒُŒم‚ئپAŒv“ٌ‰ٌپA‰و‘f‚جƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ج“dˆ³‚ً‘ھ’è‚·‚éپB
Double Sampling ‚ئ‰]‚¤–¼ڈج‚ح‚±‚±‚©‚ç—R—ˆ‚·‚éپB
“dژqگو–‹ƒVƒƒƒbƒ^پ[‚جپu‘O–‹پv‚حپA‰و‘f‚ًƒٹƒZƒbƒg‚µ‚ؤ‚¢‚ƒٹƒZƒbƒg–½—ك‚جپu‘Oگüپv‚ھژB‘œ‘fژq‚ج•\–ت‚ًˆع“®‚µ‚ؤ‚¢‚‚à‚ج‚ئƒCƒپپ[ƒW‚إ‚«‚éپB
‚±‚±‚إ–Y‚ê‚ؤ‚ب‚ç‚ب‚¢‚ج‚حپACDS‚ًژہژ{‚·‚éˆ×پAƒJƒپƒ‰‚حƒٹƒZƒbƒg‚µ‚½‰و‘f‚جژc—¯“d‰×‚ً‘ھ’èپA‚»‚µ‚ؤ‹Lک^‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‰]‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
‚آ‚ـ‚èپA“dژqگو–‹ƒVƒƒƒbƒ^پ[‚ًژB‘œ‘fژqڈم‚ًˆع“®‚³‚¹‚é‚ئ“¯ژ‚ةپAƒJƒپƒ‰‚حA/D•دٹ·‰ٌکH‚ًچى“®‚³‚¹پAƒ_پ[ƒNƒtƒŒپ[ƒ€‚ًˆê–‡ژB‰e‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‰]‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB
‚»‚µ‚ؤپAکIŒُڈI—¹ŒمپAƒJƒپƒ‰‚ح‚à‚¤ˆê‰ٌپAA/D•دٹ·‰ٌکH‚ًچى“®‚³‚¹پAٹe‰و‘f‚ج“dˆ³‚ً‘ھ’è‚·‚éپB
ƒXƒgƒچƒ{‚ج“¯’²ƒXƒsپ[ƒh1/250•b‚ً‚à’Bگ¬‚µ‚ؤ‚¢‚éچ‚‘¬‹@ٹBژ®ƒtƒHپ[ƒJƒ‹ƒvƒŒپ[ƒ“ƒVƒƒƒbƒ^پ[–‹‚جˆع“®‘¬“x‚ة‚ح”نŒ¨‚إ‚«‚ب‚¢‚ة‚µ‚ؤ‚àپA“dژqگو–‹پA‚à‚ئ‚¢پAƒٹƒZƒbƒg‘Oگü‚جˆع“®‘¬“x‚حپAƒچپ[ƒٹƒ“ƒOƒVƒƒƒbƒ^پ[Œ»ڈغ‚ً’لŒ¸‚·‚éˆ×‚ة‚àڈo—ˆ‚邾‚¯‘پ‚¢پAٹè‚ي‚‚خ1/60•b‚و‚è‘پ‚¢•û‚ھ–]‚ـ‚µ‚¢پB
‚µ‚©‚µپA‚»‚ê‚ة‚حCDS—p‚جƒ_پ[ƒNƒtƒŒپ[ƒ€‚ً“dژqگو–‹‚ئ“¯ٹْ‚µ‚½1/60•bˆب“à‚إژو“¾‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB
‚آ‚ـ‚èپAژB‘œ‘fژq‚ج‘S‰و‘f‚ً1/60•bˆب“à‚ةA/D•دٹ·‚µپA“ا‚فڈo‚µپAƒoƒbƒtƒ@پ[ƒپƒ‚ƒٹپ[‚ة’~گد‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB
[16617369]‚إگà–¾‚µ‚½’ت‚èپArampژ®‚جcolumn ADC‚إ‚حپAADC‚ج‰ً‘œ“x‚ً14bit‚©‚ç12bit‚ة‰؛‚°‚邱‚ئ‚إپA•دٹ·‚ة•K—v‚بژٹش‚ً’Zڈkڈo—ˆ‚éپB
ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒ‚پ[ƒh‚â“dژqگو–‹ƒVƒƒƒbƒ^پ[‹@”\‚ج‚ب‚¢ƒjƒRƒ“‹@‚إ‚حپACDS—p‚جƒ_پ[ƒNƒtƒŒپ[ƒ€‚ً‰½‚ھ‰½‚إ‚à1/60•bˆب“à‚ةژو“¾‚·‚éپA“™‚ئ‰]‚¤ژٹش“Iگ§–ٌ‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إپAƒVƒƒƒbƒ^پ[ƒ{ƒ^ƒ“‰ں‰؛ŒمپAƒ~ƒ‰پ[“™‚ھ’µ‚ثڈم‚ھ‚é‚ج‚ة•K—v‚بژٹش“™‚ًٹ¨ˆؤ‚·‚é‚ئپAƒ~ƒ‰پ[‚جژn“®“™‚ئ•½چs‚ةcolumn ADC‚ً”نٹr“I’x‚¢پA14bit‚ج•ھ‰ً”\‚إچى“®‚³‚¹‚ؤ‚àƒtƒHپ[ƒJƒ‹ƒvƒŒپ[ƒ“ƒVƒƒƒbƒ^پ[–‹‚ھˆع“®ٹJژn‚·‚é–{کIŒُ‘O‚ةCDS—pƒ_پ[ƒNƒtƒŒپ[ƒ€‚جژو“¾‚حڈ\•ھٹش‚ةچ‡‚¤‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
–ق‚àپAژB‘œ‘fژq‚جcolumn ADCپAژB‘œ‘fژq‚ًگ§Œن‚·‚éNikon ‚جExpeed“™‚جASICپAƒoƒbƒtƒ@پ[ƒپƒ‚ƒٹپ[—p‚جDDR RAM‚ج‘رˆو“™‚جگ«”\‚حڈي‚ةگi•à‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپANikon D810‚ةچ،‰ٌژہ‘•‚³‚ꂽ36MP‚جژB‘œ‘fژq‚ئ“dژqگو–‹ƒVƒƒƒbƒ^پ[ƒ‚پ[ƒh‚حپAگ”ڈ\•ھ‚جˆê•b“à‚ة36MP‘S‰و‘f‚ً14bit A/D•دٹ·‚µپAƒfپ[ƒ^‚ًژB‘œ‘fژq‚©‚çڈo—ح‚µپACDS—pƒ_پ[ƒNƒtƒŒپ[ƒ€‚ًRAM ƒoƒbƒtƒ@پ[‚ة‹Lک^‚·‚éگ«”\‚ً—L‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھ...
‚µ‚©‚µپAŒ»ژہ“I‚ة‚حپANikon D810‚à“dژqگو–‹ƒVƒƒƒbƒ^پ[ژg—pژ‚جCDS—pƒ_پ[ƒNƒtƒŒپ[ƒ€‚حA/D•ھ‰ً”\12bit‚إژو“¾‚µ‚ؤ‚¢‚é‰آ”\گ«‚à‚ب‚¢–َ‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
ڈ‘چ”شچ†پF18038646
![]() 2“_
2“_
[18038585] ƒJپ[ƒ‹ƒ‰ƒCƒX‚³‚ٌH‚:
> ‚½‚¾ƒ؟77II‚ب‚ٌ‚ؤ’Pژث‚إ‚à12bit‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚‚ç‚¢‚ب‚ج‚إ
ƒ؟77II‚ج—LŒّDR‚ح12.64bit‚ئ‰]‚¤DxOMark‚ج‘ھ’茋‰ت‚ًŒ©‚éŒہ‚èپA‚±‚ê‚حƒJپ[ƒ‹ƒ‰ƒCƒX‚³‚ٌ‚جٹ¨ˆل‚¢پB
ADC‚ج•ھ‰ً”\‚âBIONZ‚جƒfپ[ƒ^ڈˆ—‚ھ12bit‚ةگ§Œہ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ê‚خپA12.64bit‚ئ‰]‚¤DR‚ح—ک_“I‚ة‚ح•s‰آ”\‚ة‚ب‚éپB
•K‘R“I‚ةپAƒ؟77II‚حپAƒ\ƒjپ[‚جŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚é’ت‚èپA14bitˆت‚ج—LŒّƒfپ[ƒ^‚ًADC‚©‚çژو“¾‚µپABIONZ‚إƒfپ[ƒ^‚ج•ھ‰ً”\‚ًڑت‘¹‚µ‚ب‚¢—l‚بڈˆ—پEƒGƒ“ƒRپ[ƒh‚µپAچإڈI“I‚ة‚حپiŒآگl“I‚ة‚ح‚¢‚¢‰ءŒ¸‚â‚ك‚ë‚وپA‚ئŒ¾‚¢‚½‚¢پj”ٌ‰آ‹t‚بˆ³ڈk‚ًژ{‚µپARAWƒtƒ@ƒCƒ‹‚ة‹Lک^‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB
ڈ‘چ”شچ†پF18038705
![]() 3“_
3“_
ƒtƒBƒ‹ƒ€ƒXƒLƒƒƒiپ[‚حRGB(IRپH)‚à‚»‚ꂼ‚ê16ƒrƒbƒg‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚ب‹C‚ھ‚µ‚ـ‚·پB
‚»‚ٌ‚ب‚ةچ‚‹‰‚ب‹@ژي‚إ‚ب‚‚ؤ‚àپBپBپB
‚»‚ê‚ھˆس–،‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚©پA‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚©پH
چ،‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚ح‚à‚¤‰“‚¢گج‚جکb‚إ‚·پB
‚±‚ê‚©‚ç‚حƒfƒBƒXƒvƒŒƒC‚àRGBٹe8ƒrƒbƒg‚جژô”›‚©‚ç‰ً‚©‚ê‚é‚ج‚إ
ڈ«—ˆ‚حژ‹”F‚إ‚«‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚إ‚·‚ثپB
ƒ؟99‚ة‚¨‚¢‚ؤپA
12ƒrƒbƒgRaw‚ئ14ƒrƒbƒgRaw‚ء‚ؤƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY‚ةˆل‚¢‚ھ‚ ‚ء‚½‚©‚بپH
‰آ‹tˆ³ڈk‚µ‚ؤ‚à—ً‘R‚ئ‚µ‚½چ·‚ح‚ ‚é‚©‚àپB
ڈ‘چ”شچ†پF18038739
![]() 1“_
1“_
14ƒrƒbƒg‚ً16ƒrƒbƒg‚ةƒAƒbƒvƒRƒ“ƒoپ[ƒg‚·‚é‚ج‚حپABIONZ X‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚©‚çپARAWƒfپ[ƒ^‚ًƒfƒBƒeپ[ƒ‹ƒٹƒvƒچƒ_ƒNƒVƒ‡ƒ“‚âڈ¬چi‚èƒ{ƒPٹةکa‚إ‚¢‚¶‚é‚©‚炾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤڈˆ—Œم‚ة14ƒrƒbƒg‚ة–ك‚µ‚ؤ‹Lک^‚·‚éپBکAژت‚إ12ƒrƒbƒg‚ة—ژ‚ئ‚·‚ج‚حپA14ƒrƒbƒg‚¾‚ئƒfپ[ƒ^‚ھ‘ه‚«‰ك‚¬‚ؤکAژت‚ة‹Lک^‚ھ‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚¯‚ب‚¢‚©‚炾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18038790پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 2“_
2“_
ڈع‚µ‚‚حپAƒ³ƒحƒحƒة‚³‚ٌ‚ھڈ‘‚¢‚ؤ‚ـ‚·‚ھپA‘هژG”c‚ةSONY‚حڈˆ—‚ًŒy‚‚·‚邽‚ك‚ةCMOS‚©‚ç‚جڈo—ح‚©‚ç12bit‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚é‚炵‚¢‚ج‚إپA14bit‚جƒfپ[ƒ^‚©‚ç12bitRAW‚ًگ¶گ¬‚µ‚ؤ‚¢‚é–َ‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚إپAˆ«ڈًŒڈ‰؛‚âRAWŒ»‘œ‘دگ«‚ھ—ژ‚؟‚ؤ‚ـ‚·پB
‚±‚ê‚حٹmڈط‚ب‚¢‚ٌ‚إپA‚»‚ج’ِ“x‚ة•·‚¢‚ؤ—~‚µ‚¢‚إ‚·‚ھپAڈم‰؛‚إ‚ح‚ب‚‰؛ˆت2bitچي‚ء‚ؤ‚é‹C‚ھ‚µ‚ـ‚·پB
ˆ«ڈًŒڈ‰؛‚جRAWŒ»‘œ‚ً—ا‚‚·‚é‚ج‚إپA‚±‚جچ·‚ً’ةٹ´‚µ‚ؤ‚ـ‚·پB
‚»‚ꂾ‚¯Œمڈˆ—‚ھ•K—v‚بکr‚¾‚ئŒ¾‚¤‚±‚ئ‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚¯‚ا(ٹ¾)
‚µ‚©‚µپASONY‚جCMOSگ«”\—ا‚¢‚ف‚½‚¢‚إ‚·‚ثپB
‚ب‚ج‚إپAAPS-C‚حƒ؟77‚©‚çƒ؟77II‚ة‚µ‚½‚©‚ء‚½‚ٌ‚إ‚·‚ھپAˆہ‚‚ب‚ء‚ؤ‚©‚ç‚إ—ا‚¢‚©‚ب‚ئ(ڈخ)
Nikon‚حCMOS‚©‚ç‚جڈo—ح‚ح14bi‚إپA‚»‚±‚©‚ç12bitRAW‚ًگ¶گ¬‚µ‚ؤ‚é‚炵‚¢‚ج‚إپAچ،“xD4‚ئD810‚إژژ‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18038862پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚ ‚ءپACMOS‚جڈo—ح‚جŒڈ‚حSONY‚جƒTƒ|پ[ƒg‚ج•û‚ةٹm”F‚µ‚½‚çپAکb‚µ‚ؤ‚‚ê‚ـ‚µ‚½پB
‚µ‚©‚µپAƒ؟77II‚ج‘O‚إƒ؟7R‚جچ ‚إ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18038922پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
> کAژت‚إ12ƒrƒbƒg‚ة—ژ‚ئ‚·‚ج‚حپA14ƒrƒbƒg‚¾‚ئƒfپ[ƒ^‚ھ‘ه‚«‰ك‚¬‚ؤ
> کAژت‚ة‹Lک^‚ھ‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚¯‚ب‚¢‚©‚炾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
’x‚¢SDƒJپ[ƒh‚إ‚حکAژت–‡گ”‚ھ—ژ‚؟‚é‚©پH
’x‚¢SDƒJپ[ƒh‚إ‚ح14ƒrƒbƒg‚©‚ç12ƒrƒbƒg‚ةژ©“®گط‚è‘ض‚¦‚·‚é‚©پH
‚»‚¤‚إ‚ح‚ب‚¢‚و‚¤‚بپBپBپB
ڈ‘چ”شچ†پF18039085
![]() 0“_
0“_
—^‚¦‚ç‚ꂽƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ة‚ا‚ꂾ‚¯ٹK’²‚ھچڈ‚ٌ‚إ‚ ‚é‚©‚إ‚µ‚ه...
—ل‚¦‚خ‰و‘œکM‚ء‚ؤ14bit(16384ٹK’²)‚ة”ن‚ׂؤ12bit(4096ٹK’²)‚ح‚µ‚©چڈ‚ٌ‚إ‚ب‚¢‚ج‚إƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒv‚µ‚â‚·‚پA‚ـ‚½‚ح12bit‚ة”ن‚ׂؤ8bit‚¾‚ئ‚à‚ء‚ئƒgپ[ƒWƒƒƒ“ƒv‚µ‚â‚·‚‚ب‚é‚ئ‚©...
Œ»‘œ‚إŒ‹چ\”hژè‚ةکM‚éگl‚ب‚ç16bit(65536ٹK’²)‚ج’†”»‚ب‚ٌ‚©‹X‚µ‚¢‚ج‚إ‚ح?
ƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒv‚µ‚½‚çƒmƒCƒY‰ء‚¦‚ê‚خ•ھ‚©‚ç‚ب‚‚ب‚é‚©‚ç—ا‚¢‚¶‚ل‚ٌ(^^)
ڈ‘چ”شچ†پF18039269
![]() 1“_
1“_
‚ ‚ئپA‚ ‚â‚س‚â‚ب‚ج‚حƒLƒ„ƒmƒ“‚جRAW‚ھ12EV‚µ‚©‚ب‚¢‚ج‚ة14bit‚ح–³‘ت‚ب‚ج‚©پH‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚ء‚·‚ث
AD•دٹ·‚جچغ‚ة‚إ‚éƒmƒCƒY‚ھ‰؛ˆت2bit’ِ‚ً–„‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚©‚çپA—ل‚¦‚خ12bitƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚ب‚çژہژ؟10EV’ِ“x‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ء‚ؤ‚±‚ئپH
‚»پ[‚نپ[ˆس–،‚إ12‚©‚ç14bit‚ج‰¶Œb‚ء‚ؤ‚¢‚¤‚ب‚çپAƒLƒ„ƒmƒ“‚ج14bit‚و‚è‚àƒ\ƒjپ[‚ج12bit‚ج•û‚ھپA‚و‚ء‚غ‚ا—L—p‚بƒfپ[ƒ^‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚é‚ء‚ؤŒ¾‚¦‚é‚و‚ثپA’لٹ´“x‚إ‚ح“ء‚ة
‚ظ‚ٌ‚ئ‚ج‚ئ‚±‚ë‚ح‚اپ[‚ب‚ٌ‚¾‚ëپH
‚ٌپ[پA‚»‚à‚»‚àپA2bit•ھ‚ھٹ®‘S‚ة–„‚ـ‚é’ِ‚جƒmƒCƒY‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚ب
‚»‚¤‚إ‚ح‚ب‚پA‚»‚±‚ة’™‚ـ‚é‚ ‚é’ِ“x‚جƒmƒCƒY‚ھ‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ڈمˆتbit‚جڈî•ٌ‚ًگ³ٹm‚ة“¾‚邽‚ك‚ةپA‚ ‚¦‚ؤ‰؛ˆت2EV‚ًژج‚ؤ‚ؤ‚¢‚é‚ب‚ٌ‚ؤ‚±‚ئ‚ح‚ب‚¢‚جپH
‚»پ[‚·‚邱‚ئ‚إپAISO‚ًڈم‚°‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ئ‚«‚àپA‚P‰و‘f‚جگ³ٹmگ«‚ئ‚©ƒmƒCƒY“ءگ«‚ھ—ا‚‚ب‚é‚ئ‚©پc
ڈ‘چ”شچ†پF18039335پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
’†”»ƒfƒWƒoƒbƒN“™‚ج‰و‘fƒsƒbƒ`6ƒ~ƒNƒچƒ“‚جKodak‚جCCD‚ج—LŒّDR‚ح–ٌ11.66EV |
Leica M8پAM9‚ج‰و‘fƒsƒbƒ`6.8ƒ~ƒNƒچƒ“‚جKodak‚جCCD‚ج—LŒّDR‚ح–ٌ11.97V |
6ƒ~ƒNƒچƒ“‚جCCD‰و‘f‚ج—LŒّDR‚حٹi’i‚ةڈ¬‚³‚¢CMOS‰و‘f‚جDR‚ة‚³‚¦—ٍ‚é |
> Œ»‘œ‚إŒ‹چ\”hژè‚ةکM‚éگl‚ب‚ç16bit(65536ٹK’²)‚ج’†”»‚ب‚ٌ‚©‹X‚µ‚¢‚ج‚إ‚ح?
ٹm‚©‚ة’†”»‚جƒfپ[ƒ^‚حپu16bitپv‚ئ‰]‚¤گ_کb‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚و‚ثپ@(^^)
‚µ‚©‚µپA’†”»‚جƒfƒWƒoƒbƒN‚âLeica‚جM8پAM9‚إچج—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½Kodakژذ‚جCCD‚حS/N”ن‚ھ‚ ‚ـ‚è—ا‚‚ب‚¢‚ج‚إپA16bit‚جADC“™پAژہ‚ح•K—v‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
Phase OneپAƒnƒbƒZƒ‹—p‚جƒfƒWƒoƒbƒN‚âLeica S‚ة“‹چع‚³‚ꂽ6ƒ~ƒNƒچƒ“ x 6ƒ~ƒNƒچƒ“‚ج‰و‘fچ\‘¢‚جKodak‚جCCD‚جڈêچ‡پAƒfپ[ƒ^ƒVپ[ƒg‚ة‚؟‚ل‚ٌ‚ئچں‚ج—l‚ة‹Lڈq‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پF
پ@Saturation signal: 42ke-
پ@Read Noise (f=18MHz): 13e-
‚آ‚ـ‚èپF
پ@ˆê‰و‘f‚جƒLƒƒƒpƒVƒ^‚ج–Oکa—e—تپFپ@4–œ2گç“dژq
پ@“ا‚فڈo‚µƒŒپ[ƒg1800–œ‰و‘f/•b‚جڈêچ‡پA‰و‘f‚ج“ا‚فڈo‚µژ‚ةچ¬“ü‚·‚éƒmƒCƒY‚ج•Wڈ€•خچ·پFپ@13“dژq
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW(DR)‚حپuچإچ‚‚جگMچ†ƒŒƒxƒ‹‚ئپAƒmƒCƒY‚ئ—Lˆ×‚ةژ¯•ت‚إ‚«‚éچإڈ¬‚جگMچ†ƒŒƒxƒ‹‚ئ‚ج”ن—¦پv‚ئ’è‹`ڈo—ˆ‚ـ‚·پB
Kodak‚جƒsƒbƒ`6ƒ~ƒNƒچƒ“‚جCCD‰و‘f‚جڈêچ‡پAƒmƒCƒY‚ج•Wڈ€•خچ·‚حپu13“dژqپv‚ب‚ج‚إپADR‚ح“–‘RپA42000/13 ~= 3230.77 ~= 2^11.6577 ‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB
dB•\‹L‚إ‚ح 42000/13 ‚ح
پ@10^x = 42000/13; dB = 20 * x
‚ئ‰]‚¤•û’ِژ®‚ً‰ً‚¯‚خپA
پ@x = log( 42000/13 ) / log(10) ~= 3.5093
پ@db = 20 * 3.5093 = 70.186
‚ئ‚ب‚èپA‚±‚جCCD‰و‘f‚جS/N”ن‚ح–ٌ70.186dB‚¾‚ئ‰ً‚è‚ـ‚·پB
‚»‚µ‚ؤپAƒfپ[ƒ^ƒVپ[ƒg‚ة‚حپAٹm‚©‚ة "Dynamic Range (f=18MHz): 70.2dB" ‚ئ‹Lڈq‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
—v‚·‚é‚ةپAƒپپ[ƒJپ[ژ©گg‚ھ‰و‘f‚جDR‚ح–ٌ70.2dBپA11.66EV‚ئ–¾‹L‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB
‚»‚ج—l‚ب‰و‘f‚جگMچ†‚ً16bit‚ج•ھ‰ً”\‚ًژ‚آADC‚إ•دٹ·‚µ‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA“¾‚ç‚ê‚éƒfپ[ƒ^‚ج‰؛ˆت–ٌ4bit‚ح“–‘RپA“üژثŒُ‚ج‹P“x‚ئ‚ح‘ٹٹضگ«‚ج‚ب‚¢ƒmƒCƒYپE—گگ”‚µ‚©ٹْ‘زڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌپB
‚»‚µ‚ؤپAژB‘œ‘fژq‚©‚çˆّ‚«ڈo‚µ‚½‚±‚جDR 11.66EV‚جƒAƒiƒچƒOگMچ†‚حپAƒJƒپƒ‰‚ج“dژqٹî”آ‚جƒmƒCƒYچ¬“ü‚âADC‰ٌکHژ©‘ج‚جƒmƒCƒY‚ة‚و‚èپAژلٹ±’ل‰؛‚·‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB
ژہچغ‚ةپALeica S‚ًDxOMark‚ھ‘ھ’肵‚½‚ئ‚±‚ëپAچإچ‚DR‚ح–ٌ11.09EV‚ئ‰]‚¤پAƒZƒ“ƒTپ[Œإ—L‚ج—ک_’l‚و‚è‹ح‚©‚ة’ل‚¢Œ‹‰ت‚ھڈo‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚ـ‚½پALeica M8‚âM9‚ةچج—p‚³‚ꂽ6.8ƒ~ƒNƒچƒ“ x 6.8ƒ~ƒNƒچƒ“‚ج‰و‘fچ\‘¢‚جKodak‚جCCD‚جڈêچ‡پAƒfپ[ƒ^ƒVپ[ƒg‚ة‚و‚é‚ئپA–Oکa—e—ت‚ح6–œ“dژqپA“ا‚فڈo‚µƒmƒCƒY‚ح15“dژq‚ئ‚ب‚é‚ج‚إپADR‚ح60000/15 = 4000 ~= 72.04dB ~= 11.966EV ‚ئپA13bit’ِ“x‚ج•ھ‰ً”\‚جADC‚إڈ\•ھ‚¾‚ئ‰ً‚è‚ـ‚·پB
‰؛ˆتƒrƒbƒg‚ً—گگ”‚ة‚·‚邱‚ئ‚حپAˆêژي‚جƒfƒBƒUپ[(dither)ڈˆ—‚ئ‚ب‚èپAٹeƒŒƒxƒ‹ٹش‚ج‹«ٹEگüپiڈٹˆàƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒvپj‚ح‚ع‚₯پAٹK’²گ«‚حŒ©‚©‚¯ڈم‚حŒüڈم‚µ‚ـ‚·پB
‚µ‚©‚µپA—گگ”dither‚ً‚·‚éˆ×‚ة‚حپA‚ب‚ة‚à16bit‚جADC“™•K—v‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB—ل‚¦‚خ12bit•ھ‰ً”\‚جADC‚جƒfپ[ƒ^‚ة4bit‚ج—گگ”‚ًƒpƒ\ƒRƒ“ڈم‚جŒمڈˆ—‚إ‚‚ء‚آ‚¯‚ê‚خپA‘S‚“¯—l‚جپu16bitپvdither‚ھچs‚¦‚ـ‚·پB
ٹô‚çADC‚ج•ھ‰ً”\‚ًچ‚‚ك‚ؤ‚àپA‰؛ˆتƒrƒbƒg‚ھ—گگ”‚إ‚ ‚ê‚خپAگMچ†‚ً‹Lک^‚·‚éڈم‚إ‚ح‰½‚çˆس–،‚ھ‚ب‚¢‚±‚ئ‚³‚¦‰ً‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢پA16bitگ_کb‚âƒJƒ^ƒچƒOƒXƒyƒbƒN‚ً‘ü‰L“غ‚ف‚ة‚·‚éƒIƒ^ƒN‚جٹٹŒm‚ب—ل‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پF
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501310147/SortID=15162374
‚µ‚©‚µپA–ع‚ھگكŒٹ‚جƒIƒ^ƒN‚ئˆل‚¢پA’†”»ƒfƒWƒoƒbƒNƒپپ[ƒJپ[‚⃉ƒCƒJژذ‚حCCD‚ھCMOS‚ة‘خ‚µپAƒmƒCƒYپAƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒWپAٹK’²گ«“™‚إ—ٍ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚؟‚ل‚ٌ‚ئ”Fژ¯‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA’†”»ƒTƒCƒY‚جCMOSژB‘œƒZƒ“ƒTپ[‚ً’ٌ‹ں‚إ‚«‚éƒپپ[ƒJپ[‚ھ“oڈꂵ‚½“r’[پA‚±‚¼‚ء‚ؤCCD‚ًژج‚ؤپACMOS“‹چع‚ة‘–‚ء‚½‚ج‚à“–‘R‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پB
ڈ‘چ”شچ†پF18039988
![]() 2“_
2“_
> AD•دٹ·‚جچغ‚ة‚إ‚éƒmƒCƒY‚ھ‰؛ˆت2bit’ِ‚ً–„‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚©‚çپA—ل‚¦‚خ12bitƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚ب‚ç
> ژہژ؟10EV’ِ“x‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ء‚ؤ‚±‚ئپH
DxOMark‚ج‘ھ’肾‚¯‚إ‚حپAƒLƒ„ƒmƒ“‚جƒfƒWƒJƒپ‚جDR‚ً’ل‰؛‚³‚¹‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حژB‘œ‘fژqٹضکA‚جƒmƒCƒY‚ب‚ج‚©پA‚»‚ê‚ئ‚àADC‰ٌکHٹضکA‚جƒmƒCƒY‚ب‚ج‚©‚ح”»•ت‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB
‚µ‚©‚µپAˆê”ت“I‚ةŒ¾‚¦‚邱‚ئ‚حپAA/D•دٹ·‘O‚جƒAƒiƒچƒO‚جڈَ‘ش‚جگMچ†‚ة‚»‚à‚»‚àچ‚ƒŒƒxƒ‹‚جƒmƒCƒY‚ھٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡پA•ھ‰ً”\‚جچ‚‚¢ADC‚ًژg‚ء‚ؤ‚à‚ ‚ـ‚èˆس–،‚ح‚ب‚¢پA‚ئ‰]‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
‚à‚µƒLƒ„ƒmƒ“‚جژB‘œ‘fژq‚جڈo—ح‚·‚éƒAƒiƒچƒO‚جگMچ†‚ھپAٹù‚ة—lپX‚بچ¬“üƒmƒCƒY‚ج‚¹‚¢‚إ—LŒّDR‚ھ’ل‚¢ڈêچ‡پAٹô‚çADC‚ج•ھ‰ً”\‚ً‚ ‚°‚ؤ‚à—LŒّDR‚حŒüڈم‚µ‚ـ‚¹‚ٌپB
—ل‚¦‚خƒmƒCƒWپ[‚بAMƒ‰ƒWƒI‚ج•ْ‘—‚ًپA‘–چs’†‚جژش‚جƒJپ[ƒ‰ƒWƒI‚جƒXƒsپ[ƒJپ[‚ج‘¤‚ةƒ}ƒCƒN‚ً’u‚«پAƒŒƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒOƒXƒ^ƒWƒI‚إژg‚¤—l‚بچ‚‹‰ک^‰¹‹@چق‚إک^‰¹‚µ‚ؤ‚àپA“¾‚ç‚ê‚郌ƒRپ[ƒfƒBƒ“ƒO‚ج‰¹ژ؟‚حڈٹ‘Fژش‚ج‘–چs‰¹‚ة‚ـ‚ف‚ꂽƒmƒCƒWپ[‚بAMƒ‰ƒWƒI‚جƒŒƒxƒ‹‚ً’´‚¦‚ب‚¢‚ج‚ئ“¯‚¶‚إ‚·‚ثپB
> ‚ٌپ[پA‚»‚à‚»‚àپA2bit•ھ‚ھٹ®‘S‚ة–„‚ـ‚é’ِ‚جƒmƒCƒY‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚ب
> ‚»‚¤‚إ‚ح‚ب‚پA‚»‚±‚ة’™‚ـ‚é‚ ‚é’ِ“x‚جƒmƒCƒY‚ھ‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ڈمˆتbit‚جڈî•ٌ‚ً
> گ³ٹm‚ة“¾‚邽‚ك‚ةپA‚ ‚¦‚ؤ‰؛ˆت2EV‚ًژج‚ؤ‚ؤ‚¢‚é‚ب‚ٌ‚ؤ‚±‚ئ‚ح‚ب‚¢‚جپH
چ‚ˆتƒrƒbƒg‚جƒٹƒjƒAƒٹƒeƒBپEŒ´گMچ†‚ة‘خ‚·‚é’‰ژہگ«‚ً‰ü‘P‚·‚éˆ×‚ةپAŒ´گMچ†‚جDR‚©‚ç—ک_“I‚ة’è‚ـ‚é•ھ‰ً”\‚¬‚肬‚è‚جADC‚إ‚ح‚ب‚پADR‚ة—]—T‚ج—L‚éپA”ٌڈي‚ةچ‚‚¢•ھ‰ً”\‚جADC‚ًژg‚¢پA‰؛ˆتƒrƒbƒg‚ًژج‚ؤ‚é‚ئ‰]‚¤‰ٌکHگفŒv‚âƒAƒvƒچپ[ƒ`‚à—ل‚¦‚خƒIپ[ƒfƒBƒI‚جگ¢ٹE‚إ‚ح“–‘R‚ ‚è‚ـ‚·پB
‚µ‚©‚µپA‰ٌکHگفŒv‚جƒAƒvƒچپ[ƒ`پEƒtƒBƒچƒ]ƒtƒBپ[‚©‚çچl‚¦‚ؤ‚àپAƒLƒ„ƒmƒ“‚جƒJƒپƒ‰‚حپu14bitپv‚جADC‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚éٹ„‚ة‚حپAŒ‹‹اچؤŒ»‚إ‚«‚é—LŒّDR‚ح‹£چ‡ƒپپ[ƒJپ[‚ة”ن‚×—ٍ‚ء‚ؤ‚¢‚éٹ´‚ح”غ‚ك‚ـ‚¹‚ٌپB
ڈ‘چ”شچ†پF18039995
![]() 3“_
3“_
ˆس–،‚ج—L–³‚ة‚©‚©‚ي‚炸پAƒrƒbƒgگ”‚ھ‘½‚¢‚±‚ئ‚ً‘P‚µ‚ئ‚·‚é
ƒ†پ[ƒUپ[‚àڈ‚ب‚©‚炸‚¢‚邱‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پB
ڈ‘چ”شچ†پF18040413پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 2“_
2“_
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ئbitٹK’²‚ح•ت‚¶‚ل‚ب‚¢‚إ‚·‚©?
—ل‚¦‚خ12bit‚جƒ‚ƒUƒCƒN‚ھ‘ه‚«‚¢‚ج‚ئ16bit‚جƒ‚ƒUƒCƒN‚ھƒXƒS~‚چׂ©‚‚ب‚ء‚ؤ‚é‚ف‚½‚¢‚ب...
ڈ‘چ”شچ†پF18040431
![]() 3“_
3“_
‚¤پ[ƒEƒ}ƒVƒJ‚ب‚à‚ٌ‚إ‚و‚‚ي‚©‚ç‚ب‚¢پB‚إ‚à–ت”’‚¢پB
پ„پ„ƒ؟77II‚ج—LŒّDR‚ح12.64bit‚ئ‰]‚¤DxOMark‚ج‘ھ’茋‰ت‚ًŒ©‚éŒہ‚èپA‚±‚ê‚حƒJپ[ƒ‹ƒ‰ƒCƒX‚³‚ٌ‚جٹ¨ˆل‚¢پB
ADC‚ج•ھ‰ً”\‚âBIONZ‚جƒfپ[ƒ^ڈˆ—‚ھ12bit‚ةگ§Œہ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ê‚خپA12.64bit‚ئ‰]‚¤DR‚ح—ک_“I‚ة‚ح•s‰آ”\‚ة‚ب‚éپB
‚c‚q‚حbit‚ج’Pˆت‚إژ¦‚·ڈêچ‡‚ئ‚d‚u‚إژ¦‚·ڈêچ‡‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚·‚ثپB‚±‚±‚ً‚ـ‚¸چ¬“¯‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚¤پ[‚ق‚¸‚©‚µ‚¢پB
چ¬—گ‚آ‚¢‚إ‚ةپA‚à‚ء‚ئƒEƒ}ƒVƒJ‚بژ؟–â‚ً‚³‚¹‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
‚ب‚ٌ‚إƒjƒRƒ“‚âƒLƒ„ƒmƒ“‚ح‚¢‚آ‚ـ‚إ‚àƒٹƒjƒA‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚ثپH
—ل‚¦‚خ‰ٹ“V‰؛‚إ–Xژq‚ً‚©‚ش‚ء‚½گl‚ًژB‰e‚·‚é‚ئ”wŒi‚ةکIڈo‚ًچ‡‚ي‚¹‚é‚ئپAٹç‚ھگ^‚ءˆأ‚ة‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپAƒmƒ“ƒٹƒjƒA‚ج‚ظ‚¤‚ھپA‚±‚جژ‚جٹç‚جڈî•ٌ‚ًڈE‚ء‚ؤ‚‚ê‚é‚ٌ‚إ‚·‚و‚ثپB‚¾‚ء‚½‚炱‚¤‚¢‚¤ڈَ‹µ‰؛‚إ‚حƒmƒ“ƒٹƒjƒA‚ًچج—p‚µ‚ؤ‚¢‚é‚r‚n‚m‚x‚ج‚ظ‚¤‚ھƒjƒRƒ“‚âƒLƒƒƒmƒ“‚و‚èٹç‚جچؤŒ»گ«‚ة—L—ک‚ب‚ٌ‚إ‚·‚©پH
‚»‚à‚»‚à‚P‚c‚w‚â‚V‚O‚c‚ح14bit‚إ‚µ‚©ژB‰e‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚ثپB3bit‚àƒmƒCƒY‚¾‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ةپB
12bit‚إژB‰e‚إ‚«‚½‚çپA‚V‚c‚چ‚پ‚’‚‹‡U‚ب‚ٌ‚©‚àƒXƒyƒbƒNƒIƒ^ƒN‚¶‚ل‚ب‚¢گl‚حŒ«‚چX‚ةکAژث‰آ”\–‡گ”‚ھ‘‚¦‚é12ƒrƒbƒg‚ً‘I‘ً‚إ‚«‚½‚ç‚و‚©‚ء‚½‚إ‚·‚ثپB
‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤƒ؟77II‚ح12.64bit‚à‚ ‚é‚ج‚ة14bit‚إژB‰e‚إ‚«‚ب‚¢پB
‚±‚¤‚¢‚¤‚جŒ©‚é‚ئNIKON‚ح12bit‚ئ14bit‚ھ‘I‚ׂؤ‚¢‚¢‚إ‚·‚ثپB
ڈ‘چ”شچ†پF18040582
![]() 0“_
0“_
‚»‚¤‚¢‚¦‚خA7s‚ج4k“®‰و‚ح8bit‚إ‚µ‚½‚ء‚¯? ‚à‚ء‚ئ‚¨چ‚‚¢4KƒJƒپƒ‰‚ح10bit‚إ‚µ‚½‚و‚ث...پ@(‚¤‚邨‚ع‚¦)
ڈ‘چ”شچ†پF18040680
![]() 1“_
1“_
ƒ³ƒحƒحƒة‚³‚ٌپA‚ا‚¤‚à‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤
‚±‚ê‚إپAژ©•ھ‚ج‚ب‚©‚إ‚¾‚¢‚½‚¢‚ج’زهë‚ھچ‡‚¤Œ‹ک_‚ھڈo‚¹‚½‚وپ[‚ب‹C‚ھ‚·‚éپcپA‚©‚à ڈخ
‚ـپA”ٌگüŒ`‚ة–„‚ك‚½12bitRAW‚ھپA”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚ئچ‡‚ي‚¹‚ؤ‚ا‚ج’ِ“x‚ج—LŒّ‚بڈî•ٌ‚ج‘¹ژ¸‚ھ‚ ‚é‚©‚ء‚ؤ‚ج‚حپAٹ´ٹo‚إٹm”F‚·‚邵‚©‚ب‚¢‚ج‚©‚ب
‚إ‚à‘ز‚ؤ‚و
77‡U“™‚جAPS-C‚ج14EVƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚ج12bit‚ح”ٌگüŒ`‚ة–„‚كچ‚ٌ‚¾RAW‚¾‚ئ‚µ‚½‚çپA“dژqگو–‹‚ة‹Nˆِ‚·‚éگ§Œہ‚إ12bitƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚·‚éRAW‚ئ‚حپA“¯‚¶12bitRAW‚إ‚à”ٌƒٹƒjƒA‚ئƒٹƒjƒA‚ئ‚إپA‘S‚ˆل‚¤‚à‚ج‚ء‚ؤ‚±‚ئپH
“¯‚¶ƒپپ[ƒJپ[‚¾‚©‚ç‚ء‚ؤ‚¢‚¤گو“üٹد‚ھ”»’f‚ً‹¶‚ي‚¹‚é‚ج‚©‚بپH
‚¢‚âپ[پA‰œ‚ھگ[‚¢‚جپ[ ڈخ
ƒJپ[ƒ‹ƒ‰ƒCƒX‚³‚ٌپA‚»پ[‚نپ[‚±‚ئ‚¾‚و
‹t‚ةŒ¾‚¦‚خپAƒLƒ„ƒmƒ“ƒZƒ“ƒTپ[‚إ‚حپA11EV‚ً‚؟‚ل‚ٌ‚ئژو‚èڈo‚·‚ة‚ح14bit‚ھ•K—v‚ء‚ؤ‚±‚ئ
‚±‚ê‚ھپA12bit‚¾‚ئ10EV‚ئ‚©9EV‚µ‚©ژو‚èڈo‚¹‚ب‚‚ء‚؟‚مپ[‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه
‚ئ‚حŒ¾‚¦پA99‚ئ5D3‚إ‚حپAISO800•س‚è‚©‚çژو‚èڈo‚¹‚éDR‚ھ‹t“]‚·‚é‚©‚çپAˆêٹT‚ةƒ\ƒjپ[ƒZƒ“ƒTپ[‚ھ—D‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚àŒ¾‚¦‚ب‚¢ˆê–ت‚à‚ ‚é‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢پH
‚إپA”ٌگüŒ`‚ة–„‚ك‚éƒ\ƒjپ[12bitRAW‚جڈêچ‡پA14EV‚ًژو‚èڈo‚¹‚é14bit‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ب“à—e‚ج‹l‚ـ‚ء‚½12bit‚ب‚ج‚¾‚©‚çپA14bit‚إژB‰e‚إ‚«‚ب‚¢‚ب‚ٌ‚ؤ”كٹد‚·‚é‚à‚ج‚¶‚ل‚ب‚¢‚ٌ‚¶‚ل‚ثپH
ƒjƒRƒ“‚جƒٹƒjƒA‚ب12bitRAW‚حپA12EV‚µ‚©ژو‚èڈo‚¹‚ب‚¢‚ٌ‚¾‚©‚çپc
ڈ‘چ”شچ†پF18040731پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚ پA‚»پ[‚©
‚»‚à‚»‚àƒAƒiƒچƒOگMچ†‚ةƒmƒCƒY‚ ‚é‚©‚ç‚ء‚ؤ—vˆِ‚ب‚çپA‚؟‚ه‚ء‚ئچl‚¦•û‚ھˆل‚¤‚ج‚©
‚ـپA‚إ‚à‚»‚ê‚ب‚çپA12bit‚©‚ç14bit‚µ‚½ˆس–،‚ھ‘S‚‚ب‚¢‚ا‚±‚ë‚©پAگé“`‚جˆ×‚ة‘S‚–³ˆس–،‚ة‚إ‚©‚‚ب‚ء‚½ƒfپ[ƒ^‚ً‚¨‹q‚ة’ح‚ـ‚¹‚éپc‚ء‚ؤپA‚»‚ê‚ح‚³‚·‚ھ‚ة‚ ‚蓾‚ب‚¢‚ء‚·‚و‚ث ٹ¾
‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚حپA‚â‚ء‚دپAAD•دٹ·‚ج‰ك’ِ‚إ‚جƒmƒCƒY‚ھ‘ه‚«‚ب—vˆِ‚ب‚çپAƒLƒ„ƒmƒ“ƒZƒ“ƒTپ[‚à16bitƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚إ‚«‚ê‚خ13EV’ِ“x‚حژو‚èڈo‚¹‚é‰آ”\گ«‚à‚ ‚é‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚©‚بپH
‚ٌ‚إپA‚»‚ٌ‚ئ‚«‚ة‚â‚ء‚ئƒ\ƒjپ[14bit‚ئ‹£‘ˆ‚إ‚«‚é–َ‚¾‚ثپADxOƒ}پ[ƒN‚ج“_گ”“I‚ة‚à ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18040930پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
’†”»‚ج11.09EV‚جƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ة65536’i•ھچڈ‚ٌ‚إ‚ ‚ء‚½‚ç‰و‘œ—ٍ‰»‚µ‚¸‚ç‚¢‚ثپB
ڈ‘چ”شچ†پF18041047
![]() 3“_
3“_
‚»‚ء‚©پA‚½‚¾‚جƒmƒCƒY‚حٹب’P‚ةڈœ‹ژ‚إ‚«‚ؤ‚à—گگ”‚بƒmƒCƒY‚حٹب’P‚إ‚ح‚ب‚¢¥¥¥
‚±‚±‚ھƒLƒ„ƒmƒ“‚ئƒ\ƒjپ[‚جچ·‚ة•\‚ê‚ؤٹeپX‚ج“ء‹–‚ة‚àٹض‚ي‚邱‚ئ‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ثپB
‚ـ‚½پAƒ\ƒjپ[‚³‚ٌ‚ح‰¹‹؟‚à“¾ˆس‚¾‚©‚çƒhƒ‹ƒrپ[Œ¤‹†ڈٹ‚ئˆêڈڈ‚ة‚ب‚ء‚ؤƒhƒ‹ƒrپ[‚©‚¯‚ؤ‚é‚ٌ‚¾پIپH
‚¯پ[‚¼پ[پ—ژ©‘‚ٌ‚ج‚ب‚¼‚©‚¯‚à•ھ‚©‚è‚ـ‚·‚¯‚اپA‚ئ‚ب‚é‚ئƒ\ƒjپ[‚³‚ٌ‚ة 12/14‚ج‘I‘ًژˆ‚ًگف‚¯‚ؤ
‚à‚炤‚±‚ئ‚حŒ»چs‚¶‚لڈo—ˆ‚ب‚¢‚ء‚ؤژ–‚ة‚ب‚é‚ج‚©‚ب¥¥¥پB
‚إ‚àپA“dژqگو–‹‚ةٹضŒW‚µ‚ؤ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚çپARX1‚à ƒ؟7R‚à“dژqگو–‹–³‚¢‚ج‚ة 12bit‚ة‚ب‚é‚ج‚ح‚ب‚؛پH
ژ„‚ح‚¾‚¾‚±‚ث‚ؤپA‚½‚ئ‚¦Œ‹‰ت‚ح“¯‚¶(ˆأ•”‚ج‚ف‚جƒeƒXƒg‚¶‚ل“¯‚¶‚¶‚ل‚ب‚¢)‚إ‚à‰½‚ًژB‚ء‚ؤ‚é‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚¢
ژB‰eژز‚ة‘I‘ً‚ج—]’n‚ًژc‚µ‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ثپB
ڈ‘چ”شچ†پF18041279
![]() 0“_
0“_
>> ƒLƒ„ƒmƒ“‚جڈêچ‡پAژB‘œ‘fژq“™‚جƒAƒiƒچƒO•”•ھ‚جS/N”نپAژل‚µ‚‚حA/D•دٹ·‰ٌکH‚جگ«”\‚جŒہٹE‚©‚ç‚©پAŒِڈجپu14bitپv‚جADC‚©‚çڈo—ح‚³‚ê‚é‰؛ˆت–ٌ3ƒrƒbƒg‘ٹ“–‚حپAژہ‚حژB‘œ‘fژq‚ة“üژث‚µ‚½Œُ‚ج‹P“x‚ئ‘ٹٹضگ«‚ج‚ب‚¢پA‘ü‚جƒmƒCƒYپE—گگ”
>> ‰؛ˆتƒrƒbƒg‚ً—گگ”‚ة‚·‚邱‚ئ‚حپAˆêژي‚جƒfƒBƒUپ[(dither)ڈˆ—‚ئ‚ب‚èپAٹeƒŒƒxƒ‹ٹش‚ج‹«ٹEگüپiڈٹˆàƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒvپj‚ح‚ع‚₯پAٹK’²گ«‚حŒ©‚©‚¯ڈم‚حŒüڈم‚µ‚ـ‚·پB
‚µ‚©‚µپA—گگ”dither‚ً‚·‚éˆ×‚ة‚حپA‚ب‚ة‚à16bit‚جADC“™•K—v‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB—ل‚¦‚خ12bit•ھ‰ً”\‚جADC‚جƒfپ[ƒ^‚ة4bit‚ج—گگ”‚ًƒpƒ\ƒRƒ“ڈم‚جŒمڈˆ—‚إ‚‚ء‚آ‚¯‚ê‚خپA‘S‚“¯—l‚جپu16bitپvdither‚ھچs‚¦‚ـ‚·پB
’†”»‚ھ12ƒrƒbƒg‚إ‚¢‚¢‚ئ‚±‚ë‚ً16ƒrƒbƒg‚ة‚·‚é‚ج‚ح‚³‚·‚ھ‚ةپAپhگ_کbپh‚ً‚آ‚‚邽‚ك‚ةپA‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚ـ‚·‚ثپB
NKON‚âSONY‚جژg‚ء‚ؤ‚¢‚é‰f‘œ‘fژq‚إ‚ح“–‘R14bit‚ھ•K—v‚ب‚ج‚إ14bit‚ة‚¹‚´‚é‚ً“¾‚ب‚¢‚¯‚ê‚ا‚àپA‚¶‚ل‚ CANON‚ح‚ا‚¤‚©‚ئ‚¢‚¤‚ئپA14bit‚ج‚à‚ج‚ج3bit‚ح’P‚ب‚éƒmƒCƒY‚¾‚¯‚ê‚ا‚àپu14bitپvdither‚ة‚ب‚é‚©‚çƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒv‚ح‚ع‚₯‚ؤپAٹK’²گ«‚حŒüڈم‚³‚¹‚ؤ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·‚ثپB‚إ‚àƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒv‚ح‹t‚ة‚¢‚¤‚ئƒmƒCƒY‚جڈ‚ب‚³پAƒZƒ“ƒTپ[‚ب‚è‚`‚c‚b‚جگ«”\‚ج—ا‚³‚ً•\‚µ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ئ‚à‚¢‚¦‚é‚ج‚إ‚·‚ثپB‚¾‚©‚çƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒv‚ھ‚إ‚ؤ‚à‚ھ‚ء‚©‚肹‚¸‚ة‰و‘œڈˆ—‚إƒmƒCƒY‚ً‘«‚¹‚خ‚¢‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·‚ثپB
>>AD•دٹ·‚ج‰ك’ِ‚إ‚جƒmƒCƒY‚ھ‘ه‚«‚ب—vˆِ‚ب‚çپAƒLƒ„ƒmƒ“ƒZƒ“ƒTپ[‚à16bitƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚إ‚«‚ê‚خ13EV’ِ“x‚حژو‚èڈo‚¹‚é‰آ”\گ«‚à‚ ‚é‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚©‚بپH
‚±‚ê‚حCANON‚ھGX7‚جڈêچ‡‚ج‚و‚¤‚ةSONY‚جƒZƒ“ƒTپ[‚ًژg‚ء‚½ڈêچ‡‚ةپA‰f‘œ‘fژq‚ج–â‘艻‚`‚c•دٹ·‚ج–â‘è‚©‚ـ‚½‚ح‚»‚ج—¼•û‚©‚ ‚é’ِ“xگ„‘ھ‚إ‚«‚»‚¤‚إ‚·‚ثپB
>>ژ„‚ح‚¾‚¾‚±‚ث‚ؤپA‚½‚ئ‚¦Œ‹‰ت‚ح“¯‚¶(ˆأ•”‚ج‚ف‚جƒeƒXƒg‚¶‚ل“¯‚¶‚¶‚ل‚ب‚¢)‚إ‚à‰½‚ًژB‚ء‚ؤ‚é‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚¢
ژB‰eژز‚ة‘I‘ً‚ج—]’n‚ًژc‚µ‚ؤ—~‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ثپB
‚±‚ê‚ح‚â‚ء‚د‚è‚»‚ج’ت‚è‚إ‚·‚ثپBڈ‚ب‚‚ئ‚à‚±‚جƒ؟77II‚جڈêچ‡پAکAژت‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ14bit‚إ‚«‚½‚ح‚¸‚إپA14bit‚ب‚çپAiso50‚ئ‚©100‚جژ‚ح‚c‚q‚ھ12bit‚ً’´‚¦‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·‚à‚ج‚ثپBژ„‚à‚±‚ê‚©‚ç‚حژB‰e‚إ‚«‚é‚ئ‚«‚ح14bit‚إژB‰e‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚ـ‚·پB
‚إ‚à—ل‚¦‚خƒ؟77II‚جڈêچ‡‚¾‚ئiso400‚®‚ç‚¢‚ة‚µ‚؟‚ل‚¤‚ئ‚à‚¤‚»‚±‚ح‚³‚·‚ھ‚ةƒmƒCƒY‚إ‚¢‚ç‚ب‚¢‚©‚ç12bit‚إ‚و‚‚ب‚é‚ج‚©
‚â‚ء‚د‚è‚ب‚ٌ‚ç‚©‚جگl‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح—L‰v‚بڈî•ٌ‚ًڈˆ—‰ك’ِ‚إژ¸‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پA‚±‚ج•س‚ح‚à‚â‚à‚₵‚ـ‚·پB
>> ‚µ‚©‚µپA–ع‚ھگكŒٹ‚جƒIƒ^ƒN‚ئˆل‚¢پA’†”»ƒfƒWƒoƒbƒNƒپپ[ƒJپ[‚⃉ƒCƒJژذ‚حCCD‚ھCMOS‚ة‘خ‚µپAƒmƒCƒYپAƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒWپAٹK’²گ«“™‚إ—ٍ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚؟‚ل‚ٌ‚ئ”Fژ¯‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA’†”»ƒTƒCƒY‚جCMOSژB‘œƒZƒ“ƒTپ[‚ً’ٌ‹ں‚إ‚«‚éƒپپ[ƒJپ[‚ھ“oڈꂵ‚½“r’[پA‚±‚¼‚ء‚ؤCCD‚ًژج‚ؤپACMOS“‹چع‚ة‘–‚ء‚½‚ج‚à“–‘R‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پB
‚ح‚ء‚«‚茾‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½‚ثپBپiڈخپjپ@‚¢‚آ‚àCCD‚ًگâژ^‚·‚éگl‚ھ“\‚ء‚ؤ‚¢‚é‰و‘œ‚ً‚ف‚é‚ئپA“¯‚¶ƒZƒ“ƒTپ[‚إ”ن‚ׂ½‚ئ‚«پACCD‚ب‚ٌ‚ؤCMOS‚ة”ن‚ׂؤ‘S‘RمY—ي‚¶‚ل‚ب‚¢‚µپA‚½‚¾‚ب‚ٌ‚©‚ع‚₯‚½ٹ´‚¶‚ھƒtƒBƒ‹ƒ€‚ء‚غ‚¢‚ئ‚¢‚¤‚©پA‚ب‚ٌ‚©‰ù‚©‚µ‚‚³‚¹‚ؤ‚邾‚¯‚¶‚ل‚ب‚¢‚إپAژ©•ھ‚ھŒ©ٹµ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚çƒmƒXƒ^ƒ‹ƒWپ[‚ةگZ‚ء‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚إŒ©‚ؤ‚邱‚ء‚؟‚ح—ا‚³‚ھ‚ي‚©‚ç‚ٌ‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚»‚¤‚¢‚¤چl‚¦‚إ‚à‚¢‚¢‚إ‚·‚ثپB‚·‚ء‚«‚肵‚ـ‚µ‚½پB
ڈ‘چ”شچ†پF18041511
![]() 2“_
2“_
‚¾‚©‚ça77II‚ح‚±‚ٌ‚ب‚ةˆہ‚¢‚ج‚©‚ب‚ پB
7D2‚ج”¼’l‚إ‚·‚و‚ثپB
گ«”\“I‚ة‚»‚ٌ‚بƒVƒrƒA‚ب‚à‚جژB‚é‚ي‚¯‚¶‚ل‚ب‚¢‚µپA
‘¬‚¢‚ظ‚¤‚ھ‚¢‚¢‚©‚à‚إ‚·‚ثپB
a99II‚جڈêچ‡‚ح‚±‚ꂶ‚ل‚¢‚¯‚ب‚¢‚و‚¤‚ب‹C‚à‚µ‚ـ‚·پB
12bit‚ئ14bit‚ًگط‚è‘ض‚¦‚ؤکAژت‘¬“x‚ً•د‚¦‚é‚ج‚حŒ‹چ\“‚¢‚ج‚©‚ب‚ پH
ƒNƒچƒbƒvکAژت‚حa77II‚ئ“¯‚¶‚إ‚ئ‚©
ˆê”ت“I‚ة‚ح‚±‚جژè‚جƒJƒپƒ‰‚ً‘I‚شگl‚حکAژت‘¬“x‚ئAF’اڈ]گ«‚ًڈdژ‹‚µ‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18041572
![]() 1“_
1“_
ƒfƒBƒUپ[‚ء‚ؤپAƒŒƒ^ƒbƒ`‚جژ‚ئ‚©‚ةژg‚¤‚ ‚ê‚ء‚·‚و‚ث
‚ب‚ٌ‚إپA‰؛ˆتƒrƒbƒg‚ً—گگ”‚إ–„‚ك‚é‚ئ‚»‚ê‚ئ“¯‚¶‚ة‚ب‚é‚جپ[پH
•ھ‚©‚éگlپA‚¨ٹè‚¢‚ء‚·
ڈ‘چ”شچ†پF18041688پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
>> ‚µ‚©‚µپA–ع‚ھگكŒٹ‚جƒIƒ^ƒN‚ئˆل‚¢پA’†”»ƒfƒWƒoƒbƒNƒپپ[ƒJپ[‚⃉ƒCƒJژذ‚حCCD‚ھCMOS‚ة‘خ‚µپAƒmƒCƒYپAƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒWپAٹK’²گ«“™‚إ—ٍ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚؟‚ل‚ٌ‚ئ”Fژ¯‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA’†”»ƒTƒCƒY‚جCMOSژB‘œƒZƒ“ƒTپ[‚ً’ٌ‹ں‚إ‚«‚éƒپپ[ƒJپ[‚ھ“oڈꂵ‚½“r’[پA‚±‚¼‚ء‚ؤCCD‚ًژج‚ؤپACMOS“‹چع‚ة‘–‚ء‚½‚ج‚à“–‘R‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پB
•د‚ي‚ء‚½‚ج‚ح‚P”شڈ¬‚³‚¢ƒTƒCƒY‚ج’†”»ƒZƒ“ƒTپ[‚إپA‚±‚ê‚و‚è‚à‘ه‚«‚¢’†”»ƒZƒ“ƒTپ[60MP 80MP‚جƒZƒ“ƒTپ[‚حCCD‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚وپBڈ¬‚³‚¢ƒZƒ“ƒTپ[‚حkodak‚ھچى‚ç‚ب‚‚ب‚ء‚½‚ج‚©‚ب?
ڈ‘چ”شچ†پF18041696
![]() 0“_
0“_
‚ ‚ئ16bit‹@‚جƒJƒپƒ‰‚ح19MP/30.7x15.8mmƒZƒ“ƒTپ[‚جRed epic dragon‚à‚¾‚ثپB‚½‚ش‚ٌ...
ڈ‘چ”شچ†پF18041719
![]() 0“_
0“_
‚¢‚âپAˆل‚¤‚ي‚±‚ê
ƒLƒ„ƒmƒ“‚à12bitژ‘م‚©‚ç11EV‚حڈE‚¦‚ؤ‚é‚ء‚غ‚¢
‚اپ[‚ب‚ء‚ؤ‚ٌ‚¾پA‚±‚è‚ل
’†”»‚ج16bit‚àƒLƒ„ƒmƒ“‚ج14bit‚àپA‘S‚‚à‚ء‚ؤ–³ˆس–،‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚ء‚·‚©‚ث
‚ب‚ٌ‚©پAڈ‚µ‚®‚ç‚¢ƒپƒٹƒbƒg‚ف‚½‚¢‚ب‚à‚ٌ‚ح–³‚¢‚جپIپH
‚ب‚ٌ‚à‚ب‚¢‚ب‚çچ¼‹\‚¾‚و‚ثپA‚±‚êپAƒLƒ„ƒmƒ“‚³‚ٌپA‚اپ[‚ب‚جپH
ڈ‘چ”شچ†پF18043464پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
چإ‹كٹ´‚¶‚é‚ج‚إ‚·‚ھپAƒ؟7S‚جٹG‚ھپAچ،‚ـ‚إ‚جƒ؟‹@‚ئ‚حƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN‚³‚ھ‚®‚ٌ‚ئڈم‚ھ‚ء‚½‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚é‚ج‚إ‚·پB
-0.3EV‚©‚çپ[0.7EV‚إژB‚é‚ئپAƒrƒbƒNƒٹ‚·‚é‚‚ç‚¢چت“x‚âƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN‚³‚ھ—ا‚¢‚ئٹ´‚¶‚ـ‚·پBƒ؟99‚âƒ؟7‚إ‚حڈo‚ؤ‚±‚ب‚¢ٹG‚إ‚·پB
‚±‚ê‚ء‚ؤپA”ٌگüŒ`RAW‚ج‚¹‚¢‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH
‰½‚µ‚ëپAƒ؟7S‚حپA“®‰و‚إ14EV‚ة”—‚é”ٌگüŒ`ژB‰e‚·‚é‚ج‚إپAچ‚‹‰‚ب”ٌگüŒ`‰ٌکH‚ھ‘g‚فچ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB
‚»‚ê‚ھپAژتگ^‚ة‚àچD‰e‹؟‚ً‚·‚é‚ج‚©‚بپH
‚±‚ج‰ٌکH‚ًپAژںٹْƒtƒ‹ƒTƒCƒY‚ة‚à‘g‚فچ‚ٌ‚إ—~‚µ‚¢پB
ٹْ‘ز‚µ‚ؤ‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18043863پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
orange‚³‚ٌپA‚ب‚ٌ‚©پAٹ¨ˆل‚¢‚µ‚ؤ‚é‚ء‚غ‚¢‚و
’Pڈƒ‚ة7s‚جƒZƒ“ƒTپ[‚حƒoƒPƒ‚ƒm‚ب‚¾‚¯‚¾‚و
’لٹ´“x‚ً‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‹]گµ‚ة‚µ‚ب‚¢‚إ‚جچ،‚ـ‚إ‚ة‚ب‚¢چ‚ٹ´“xگ«”\‚¾‚©‚ç‚ثپ[
ISO12800‚ئ‚©‚إ‚à9EVڈo‚¹‚é‚ٌ‚إپA‚±‚ج•س‚إ‚à‚»‚ج’ِ“x‚ج•âگ³‚إ’تڈيŒ»‘œ‚ب‚ç‚خپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا–â‘è‚ب‚¢ƒŒƒxƒ‹‚إ‚µ‚ه
ƒ}ƒW‚إپA‚±‚جƒZƒ“ƒTپ[‚ح‘A‚ـ‚µ‚يپA—~‚µ‚¢‚يپ[ ڈخ
‚إپA‚ ‚‚ـ‚إ‚àڈî•ٌ—ت‚حپA14bitRAWپ„”ٌگüŒ`‚ة–„‚ك‚½12bitRAW
–â‘è‚حپAƒtƒ‹ƒTƒCƒY‚ج12bitRAW‚ھ14bitƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚ًƒGƒ“ƒRپ[ƒh‚µ‚ؤ‚ج12bit(”ٌگüŒ`RAW)‚ب‚ج‚©پA12bitƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚جƒٹƒjƒA12bitRAW‚ب‚ج‚©‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚¶‚ل‚ثپH
“®‰و‚حپA‚ي‚©‚ç‚ٌ ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18043927پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 3“_
3“_
ڈî•ٌ—ت‚حƒrƒbƒg’·‚»‚ج‚à‚ج‚إ‚حپH
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚حپu”ٌگüŒ`‚ة—تژq‰»‚·‚ê‚خپvƒrƒbƒg’·‚ئ‚حٹضŒW‚ب‚‚ب‚é
‚¾‚¯‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚إ‚حپH
ڈ‘چ”شچ†پF18044014
![]() 0“_
0“_
‚ٌپ[پA
‚ٌ‚¶‚لپAƒٹƒjƒA‚بRAW‚ب‚çپA‰؛ˆت2ƒrƒbƒg‚ھƒmƒCƒY‚ة–„‚à‚ê‚ؤ‚و‚¤‚ھپA’†ٹش‚جٹK’²‚ً‹ة’[‚ةکM‚é‚وپ[‚بŒ»‘œ(ƒŒƒ^ƒbƒ`‘دگ«)‚حپA‚ا‚ج’ِ“x‚إˆل‚¢‚ھڈo‚é‚©‚ح•ت‚ة‚µ‚ؤ‚àپA’Pڈƒ‚ة14bit‚ج•û‚ھپA12EV‚ج—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚ھ‹l‚ـ‚ء‚½12bit‚و‚è‚àچ‚‚¢‚ء‚ؤ”Fژ¯‚إ‚¢پ[‚جپH
ڈ‘چ”شچ†پF18045011پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
‰؛ˆت2bit‚ئ‚©‰½‚©ˆس–،‚ھ•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚¯‚اپA12EV‚جƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚إ14bit‚ب‚ç16384x16384x16384ٹK’²(RGBٹeگF)پ@12bit‚ب‚ç4096x4096x4096(RGBٹeگF)‚جگF‚إژتگ^‚ھ•\Œ»‚³‚ê‚ؤ‚é‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·‚©?
ڈ‘چ”شچ†پF18045105
![]() 1“_
1“_
ƒrƒbƒgگ”‚ةٹض‚µ‚ؤ‚ي‚©‚èˆص‚گà–¾‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئƒTƒCƒg‚ھ—L‚è‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپAڈذ‰î‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/spv/0909/24/news001.html
‚±‚±‚إ‚حپAƒ‚ƒjƒ^پ[‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جژ–—ل‚إ‚·‚ھپAƒZƒ“ƒTپ[‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à“¯—l‚ج‚±‚ئ‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
Œ»‘œ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ؤƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒv‚ھ”گ¶‚µ‚½‚è‚·‚é‚ج‚حپAƒ‚ƒjƒ^پ[‘¤‚جپuŒ©‚¦پv‚ج–â‘è‚à‚ ‚è‚»‚¤‚إ‚·پB
ƒ‚ƒjƒ^پ[‚إ‚حپA8ƒrƒbƒgپ¨10ƒrƒbƒg‚ةٹg’£‚·‚é‚ة‚à‘ه•د‚بŒ»ڈَ‚إ‚·پB
12ƒrƒbƒgپA14ƒrƒbƒg‚ج‰و‘œ‚ًگ¶‚إŒ©‚éژè’i‚à–³‚¢‚ج‚إ‚·پB
ژB‚ء‚ؤڈo‚µ”h‚âپAڈ‚µƒgپ[ƒ“‚ً‚¢‚¶‚é’ِ“x‚ج•û‚ة‚حپA14ƒrƒbƒg‚حƒtƒ@ƒCƒ‹‚ھڈd‚½‚¢‚¾‚¯‚ج‘م•¨‚ئŒ¾‚¤‹C‚ھ‚µ‚ؤ—ˆ‚ـ‚µ‚½پB
ڈ‘چ”شچ†پF18045712پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
‚ٌپ[پA
‚ ‚â‚س‚â‚ب‚ب‚ٌ‚¾‚¯‚ا‚³پ[پAƒ\ƒjپ[RAW‚ج”ٌگüŒ`‚ةƒGƒ“ƒRپ[ƒh‚³‚ꂽRAW‚¾‚ئپA14EV‚جٹK’²‚ً14bit‚إ16384ٹK’²‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA12bit‚ة‚·‚é‚خپA14EV‚ً4096ٹK’²‚ةٹشˆّ‚‚ي‚¯‚إپAƒTƒCƒYƒ_ƒEƒ“‚âƒAƒbƒv‚ة‚»‚êˆس–،‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚¢‚¢‚ئژv‚¤‚¯‚اپ[پA
ƒLƒ„ƒmƒ““™‚جƒٹƒjƒA‚بRAW‚إ‚حپA14ƒrƒbƒg‚إ‚à—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚ھڈمˆت12bitپA‚آ‚ـ‚è12EV‚µ‚©‚ب‚¢ڈêچ‡پAڈمˆت12bit‚ة‚ح—LŒّ‚ب4096ٹK’²‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA13bit–ع‚ج4096ٹK’²‚ئ14bit–ع‚ج8192ٹK’²‚ھƒmƒCƒY‚ب‚çپAŒ‹‹ا‚ح12bitRAW‚ئ“¯‚¶—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚µ‚©‚ب‚¢‚ج‚©‚ب‚ء‚ئپH
‚ب‚ٌ‚©پA‚±‚جچl‚¦ژ©‘ج‚ھٹشˆل‚ء‚ؤ‚é‹C‚à‚·‚邯‚ا ڈخ
AD•دٹ·Œم‚ةپAڈ‚ب‚‚ئ‚à13EVˆبڈم‚ج—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚ھ‚ب‚¯‚ê‚خپA’P‚ة–³‘ت‚ةƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY‚ھ‚إ‚©‚¢‚¾‚¯‚¾‚µپA
ˆ³ڈk‚جچغ‚ةƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY‚ً12bitRAW‘ٹ“–‚ج‘ه‚«‚³‚جƒTƒCƒY‚ة‚إ‚«‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA14bit‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ج‰¶Œb‚ھƒ[ƒچ‚ا‚±‚ë‚©—]Œv‚بڈˆ—‚ً‚³‚¹‚镾ٹQ‚ًٹoŒه‚إ‹q‚ًéx‚µ‚ؤ‚é‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚جپH‚ء‚ؤپc
ڈ‘چ”شچ†پF18046031پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
ƒ‚ƒjƒ^پ[‚ئژتگ^‚إ‚؟‚ه‚ء‚ئˆل‚¤‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
ˆ³ڈk‚·‚é‚ئƒfپ[ƒ^‚ھŒ‡—ژ‚·‚é‚©‚ç‰وژ؟‚ھ—ژ‚؟‚éپA‚ئ‚©
ƒŒƒ^ƒbƒ`‚ة—LŒّ‚ب‚ا‚ئ
‚¢‚¢‚ـ‚·‚ثپBRaw‚إ•غ‘¶‚©Jpeg‚و‚è‚إ•غ‘¶‚©‚ة‹ك‚¢ٹ´ٹo‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
کAژت‚·‚é‚ئ‚«‚ح‘هژG”c‚بژتگ^‚µ‚©ژB‚ç‚ب‚¢‚©‚çپAŒy‚¢ƒtƒ@ƒCƒ‹‚إ‚à–â‘è‚ب‚‚ؤژB‚ê‚ؤ‚ب‚¯‚ê‚خکb‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢ƒPپ[ƒX‚à‘½پX‚ ‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ƒ‚ƒjƒ^پ[ٹسڈـ‚ھ’†گS‚ب‚ç‚ ‚ـ‚è‹C‚ة‚µ‚ب‚‚ؤ‚à‚¢‚¢‚و‚¤‚بپB
ƒXپ[ƒpپ[ƒnƒCƒrƒWƒ‡ƒ“‚إŒ»چف‚جژتگ^‚ًŒ©‚é‚ئ‚©ŒمپX‚ة‚à”ُ‚¦‚é‚ئ‚©چl‚¦•û‚ح‚¢‚ë‚¢‚ë‚ ‚è‚ـ‚·‚ثپB
D300‚à12bit‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚ب‹C‚ھ‚µ‚ـ‚·پBD750‚âD810‚ح12/14bit‚ةگط‚è‘ض‚¦‚ç‚ê‚é‚ج‚©‚بپB
ڈ‘چ”شچ†پF18046095
![]() 2“_
2“_
ƒXƒJƒXƒJ‚ب•¨‚ئ‚¬‚ء‚µ‚è‹l‚ـ‚ء‚½•¨‚ًکM‚é‚ئ‚ا‚؟‚ç‚ھ•ِ‚êˆص‚¢‚©‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚إ‚·‚©‚ث? ƒŒƒ^ƒbƒ`پ^Œ»‘œ‚ةٹض‚µ‚ؤ‚ح...
ڈ‘چ”شچ†پF18046207
![]() 1“_
1“_
پ„14EV‚جٹK’²‚ً14bit‚إ16384ٹK’²‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA12bit‚ة‚·‚é‚خپA14EV‚ً4096ٹK’²‚ةٹشˆّ‚‚ي‚¯‚إپAƒTƒCƒYƒ_ƒEƒ“‚âƒAƒbƒv‚ة‚»‚êˆس–،‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚¢‚¢‚ئژv‚¤‚¯‚اپ[پA
---“÷ٹل‚إŒ©•ھ‚¯‚ç‚ê‚é‚©”÷–‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ثپB
ڈ‘چ”شچ†پF18046279
![]() 1“_
1“_
ƒrƒbƒg‚ةڈمˆت‚ئ‚©‰؛ˆت‚ئ‚©‚جٹT”O‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB
—ل‚¦‚خپA‚ ‚éڈئ–¾‚ھ‚ ‚ء‚ؤپAڈء“”‚ئ‘S“_“”‚ئ‚جٹش‚ً256’iٹK‚إ’²Œُ‚·‚é‚ج‚ھ8ƒrƒbƒg‚إپA1024’iٹK‚إ’²Œُ‚·‚é‚ج‚ھ10ƒrƒbƒgپA4096’iٹK‚ھ12ƒrƒbƒgپA‚»‚ج‚³‚ç‚ة4”{‚ھ14ƒrƒbƒgپB
‚¾‚©‚çپA—ل‚¦‚خپA8ƒrƒbƒg‚إ10/256‚ئŒ¾‚¤–¾‚邳‚ھ‚ ‚ء‚½ڈêچ‡پA12ƒrƒbƒg‚إ‚ح160/4096‚ئŒ¾‚¤–¾‚邳‚ة“™‚µ‚¢پB
‚±‚±‚إپA160/4096‚ئŒ¾‚¤–¾‚邳‚ج—ׂة158/4096‚ئŒ¾‚¤–¾‚邳‚ھ•ہ‚ٌ‚إ‚¢‚½ژ‚ةپA8ƒrƒbƒg‚إŒ©‚é‚ئٹغ‚ك‚ç‚ê‚ؤپA“¯‚¶–¾‚邳‚ھ“ٌ‚آ•ہ‚ٌ‚إŒ©‚¦‚éپB
‚à‚µپAƒZƒ“ƒTپ[‚جƒmƒCƒY‚ھ12ƒrƒbƒg‚إ5پ`6’ِ“x‚ج—h‚炬‚إ‚ ‚ء‚½‚çپA12ƒrƒbƒg‚إ‚ح‹P“xچ·‚ئ‚µ‚ؤ‹Lک^‚³‚ê‚é‚ھپA8ƒrƒbƒg‚إ‚حƒmƒCƒY‚ئ‚µ‚ؤŒں’m‚³‚ê‚ب‚¢پB14ƒrƒbƒg‚إ‚حپAچX‚ة4”{•qٹ´‚ة‚ب‚éپB
‘هژG”c‚ة‚±‚ٌ‚بƒCƒپپ[ƒW‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
”ٌگüŒ`‚جڈˆ—‚جƒCƒپپ[ƒW‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAٹ´“x‚ج‰؛Œہ‚âڈمŒہ‚ب‚ا’[‚ء‚±‚ج•û‚إ‚حپA“ü—ح‚ئڈo—ح‚ھ”ن—لٹضŒW‚ة–³‚¢‚©‚ç•âگ³‚µ‚ؤ‹Lک^‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئŒ¾‚¤‚±‚ئ‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
‚±‚ê‚à—ل‚¦‚é‚ئپA100‚ئ‚¢‚¤Œُ‚ھ“–‚½‚ء‚½‚çپA100‚ئ‚¢‚¤“d‹CگMچ†‚ھ”گ¶‚·‚éپB‚±‚جڈًŒڈ‚إپAŒُ‚ً50‚ة‰؛‚°‚½‚çپAƒZƒ“ƒTپ[ڈo—ح‚ح40‚µ‚©ڈo‚ب‚¢پBٹ´“x‚ج‰؛Œہ‚إ‚ح‚±‚ٌ‚بژ–‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚و‚ثپB‚±‚جپA“ü—حڈo—ح‚جٹضŒW‚حپA‚ ‚ç‚©‚¶‚ك‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚éƒZƒ“ƒTپ[Œإ—L‚ج“ءگ«‚¾‚©‚çپAƒٹƒjƒA‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚ة•âگ³‚·‚é‚ج‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18046451پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
گlٹش‚جژ‹ٹo“ءگ«‚ً‘O’ٌ‚ئ‚·‚ׂ«‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
‚q‚f‚a‚جٹe‹P“x‚ھ(0,0,0)‚ج‚ئ‚«‚حچ•گF‚ةŒ©‚¦‚éپB
‚µ‚©‚µپA
(0,1,0)(1,0,0)(0,0,1)‚إ‚à“¯‚¶چ•گF‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·‚و‚ثپH
ڈ‘چ”شچ†پF18047199پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
(FF,FF,FF)‚ھ”’‚ئ‚µ‚ؤ‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚¾‚و‚ث
Œ©‚¦‚邯‚اپc
ƒqƒ“ƒg‚ھ‚ق‚¸‚©‚µ‚‚ؤپA‚³‚ء‚د‚è‚ي‚©‚çپ[‚ٌ
’m‚ء‚ؤ‚é‚ٌ‚ب‚çپAˆس’nˆ«‚µ‚ب‚¢‚إ‹³‚¦‚ؤ‚وپ[
ڈ‘چ”شچ†پF18047255پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
‚ پ[پA‚â‚ء‚ئŒq‚ھ‚ء‚½‚ء‚·پA—ک_“I‚ب‚à‚ٌ‚ئژہچغ‚ةٹ´‚¶‚ؤ‚é‚à‚ٌ‚ھ
ƒ³ƒحƒحƒة‚³‚ٌ‚جگà–¾‚ھ‘S‚ؤ—‰ً‚إ‚«‚½پA‘½•ھ ڈخ
ƒfƒBƒUپ[Œّ‰ت‚جژd‘g‚ف‚à‰ً‚ء‚½پ[
ˆس–،‚ً‚ف‚¢‚¾‚¹‚خ‚±‚ꂾ‚¯‚ب‚ٌ‚¾‚بپA‚إ‚à‚à‚µ‚©‚µ‚½‚猻‘œƒ\ƒtƒg‚جŒ“‚ثچ‡‚¢‚à‚ ‚ء‚ؤپARAWƒtƒ@ƒCƒ‹Œ`ژ®‚ًٹب’P‚ة’ا‰ء‚إ‚«‚ب‚¢‚µ‚ھ‚ç‚ف‚à‚ ‚ٌ‚ج‚©‚à
‚µ‚©‚µ‚±‚êپAٹˆژڑ‚¾‚¯‚جگà–¾‚ح“‚¢‚ء‚·‚ث ڈخ
Œ‹ک_‚حپAƒ\ƒjپ[ƒZƒ“ƒTپ[‚±‚»پA14bit‚ئ‰آ‹tˆ³ڈkپAƒfƒ‚ƒUƒCƒN‚ح‚¶‚ك‰f‘œƒGƒ“ƒWƒ“‚ةچS‚ê‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚©‚ب
TLM‚à‰ï‚ي‚¹‚ؤپA–ـ‘ج–³‚¢‚±‚ئ‚µ‚·‚¬‚¾‚ë
7‚جƒLƒƒƒpƒVƒeƒB‚إ6‚ً”ٹِ‚·‚éƒLƒ„ƒmƒ“‚ة‘خ‚µ‚ؤپAƒ\ƒjپ[‚ح10‚جƒLƒƒƒpƒVƒeƒB‚ج‚¤‚؟4‚®‚ç‚¢‚µ‚©”ٹِ‚µ‚ؤ‚ب‚¢‚ٌ‚¶‚ل‚ثپH
ڈ‘چ”شچ†پF18050707پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
پ@ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒJƒپƒ‰‚حپA‰و‘fژq‚جڈo—ح‚ًƒrƒbƒg‚إ—تژq‰»‚µ‚ـ‚·پB‰و‘fژq‚جڈo—ح‚حƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ئ‚µ‚ؤگ”’l‰»‚³‚ê‚ـ‚·‚ثپBƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ئ‚حپA‰و‘fژq‚ج–Oکa“dˆ³‚ًƒmƒCƒY‚إٹ„‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚·پB
پ@‚آ‚ـ‚èپA‰و‘fژq‚جڈo—ح‚ھƒmƒCƒY‚ج‰½”{‚إ‚ ‚é‚©‚ً—تژq‰»‚µ‚ؤƒrƒbƒg‚ة‹Lک^‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBچإ‹ك‚ج‰و‘fژq‚حƒmƒCƒY‚ھڈ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ھ‘½‚‚ب‚邽‚ك—تژq‰»‚ة‘½‚‚جƒrƒbƒg‚ھ•K—v‚ة‚ب‚é‚ئŒ¾‚¤‚ي‚¯‚إ‚·پB
پ@—ل‚¦‚خپAŒ‹‰ت‚ھ‚Q‚T‚T”{‚إ‚ ‚ê‚خ8ƒrƒbƒg‚إٹش‚ةچ‡‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚SپC‚O‚X‚U”{‚ة‚ب‚é‚ئ‚P‚Qƒrƒbƒg‚ھ•K—v‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBچX‚ة‚P‚UپC‚R‚W‚S”{‚ة‚ب‚é‚ئ‚P‚Sƒrƒbƒg‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚é‚ي‚¯‚إ‚·پB
پ@ˆê”ت“I‚ب‰و‘fژq‚جƒfپ[ƒ^پ^ƒmƒCƒY”ن—¦‚ح‚R‚O‚O”{‚©‚ç‚RپC‚O‚O‚O”{‚‚ç‚¢‚¾‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA‚P‚Sƒrƒbƒg‚ج“oڈê‚حپAچإ‹ك‚جƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ھŒ…ˆل‚¢‚ة—ا‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئŒ¾‚¤‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
پ@ˆبڈم‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚©‚çپA‚q‚`‚vƒfپ[ƒ^‚جƒrƒbƒgگ”‚ًکIڈo‚ج’Pˆت‚إ‚ ‚é‚d‚u‚ئٹضکA‚أ‚¯‚ؤچl‚¦‚é‚ج‚ح‘أ“–‚إ‚ب‚¢‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB‚d‚u‚ئٹضکA‚أ‚¯‚½14ƒrƒbƒg‚ج12ƒrƒbƒg‰»‚حچؤچl‚³‚ꂽ•û‚ھ—ا‚³‚»‚¤‚إ‚·‚وپB
پ@—ل‚¦‚خƒmƒCƒY‚ً‰¼‚ة4”{‚ة‚·‚é‚ئ‚©ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ً4•ھ‚ج1‚ة‚·‚é‚ب‚ا‚ھچl‚¦‚ç‚ê‚é‚ئ‚±‚ë‚إ‚·‚ھپA‚·‚¢‚ـ‚¹‚ٌپA“–‰غ‘è‚ھƒLƒƒƒmƒ“‚ة‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إپA‚±‚±‚ـ‚إ‚ةپB
ڈ‘چ”شچ†پF18052065
![]() 0“_
0“_
”¼•ھ‚ھˆê’i‚ب–َ‚¾‚©‚çپAƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO’iٹK‚¶‚لEV’lƒCƒRپ[ƒ‹bitگ”پA‚±‚±‚ح•د‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢‚ء‚µ‚ه
‚ ‚ئ‚حپA‚±‚ê‚ً‚ا‚ٌ‚بRAW‚ة‚·‚é‚©‚ج–â‘肾‚¯
‰آ‹tˆ³ڈk‚©”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚©پA‚ح‚½‚ـ‚½bitگ”‚ً—ژ‚ئ‚µ‚ؤڈم‚©‚ç‰؛‚ـ‚إ‚جڈî•ٌ‚ھ“ü‚é‚و‚¤‚ةپuگl‚ج–ع‚ج“ءگ«پv‚ًژQچl‚ة‚ب‚é‚ׂ—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚ًژc‚µ‚ب‚ھ‚çٹشˆّ‚‚©
‘½•ھپAگوگ¶‚جڈ‘‚«چ‚ف‚ً‚ف‚ؤ‚é‚ئƒ\ƒjپ[‚ح”ٌ‰آ‹t‚إƒLƒ„ƒmƒ“‚ح‰آ‹tˆ³ڈk‚¾‚ب
‚ب‚à‚ٌ‚إپAƒLƒ„ƒmƒ“‚ج‚وپ[‚ب12EV‚à—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚ًچج‚ê‚ب‚¢ƒZƒ“ƒTپ[‚إ‚حپA‚و‚¤‚·‚é‚ة‰؛ˆتƒrƒbƒg‚حƒmƒCƒY‚â—گگ”‚ب‚ي‚¯‚إپA14bitRAW‚ة‚µ‚ؤ‚àŒ‹‹ا—~‚µ‚¢ڈî•ٌ‚ح12bit‚ئ•د‚ي‚ç‚ب‚¢‚ء‚ؤ‚±‚ئ
Œ‹‹ا‚ح‰؛ˆتƒrƒbƒg‚جƒmƒCƒY‚â—گگ”‚ً‚»‚ج•ھ‚جŒëچ·‚إ‚ع‚©‚µ‚½‚à‚ج‚ھƒfپ[ƒ^‚ئ‚µ‚ؤژc‚é‚ج‚إپA‚ ‚½‚©‚à14bit•ھ‚جچׂ©‚بƒfپ[ƒ^‚ھ‘¶چف‚µ‚ؤ‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ؤ‚邾‚¯
‚¾‚©‚çپA12bitRAW‚إ‚ ‚ئ‚©‚ç2bit‚ج—گگ”‚ً‘«‚µ‚ؤ‚â‚ê‚خ‚±‚ê‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ة‚ب‚é‚ء‚ؤ‚±‚ئ
‚إپA‚ـپ[پAژہچغ‚حADC‚ج‰ك’ِ‚إ‚ج‚éƒmƒCƒY‚ھ‚ا‚ٌ‚بگ«ژ؟‚إ‚ا‚ê’ِ‚ج‚à‚ٌ‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚©‚çپA14bit‚ة‚·‚éˆس–،‚àڈ‚ب‚©‚炸‚ ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ء‚ؤ‚ئ‚±‚©‚بپH
‚ ‚ء‚ؤ‚éپH ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18052292پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
‚إ‚à‚ء‚ؤپAƒ\ƒjپ[ƒZƒ“ƒTپ[‚ًژg‚ء‚½D800‚ج‚وپ[‚بƒjƒRƒ“‹@‚حپA‘½•ھ14EV‚ً”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚إ14bitRAW‚ھ‚إ‚«‚é‚ٌ‚إ‚µ‚ه
‚½‚¾پAŒ»چف‚جˆê”ت“I‚بچإڈI“I‚بڈo—ح‚ھJPEG8bit‚ب‚ج‚ةپA‚±‚±‚ـ‚إ•K—v‚ب‚ج‚©پH‚ء‚ؤ‹^–â‚حڈي‚ة‚آ‚«‚ـ‚ئ‚¤‚©‚à ڈخ
‚¾‚©‚çپAگFپX‚بŒ`ژ®‚ً‘I‚ׂé‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚©‚ب
‚±‚ج‚ض‚ٌ‚حپAƒjƒRƒ“‚ھˆê•àگi‚ٌ‚إ‚éٹ´‚¶‚ھ‚·‚é
‚؟‚ه‚ء‚ئ‘O‚ـ‚إ‚حپAƒLƒ„ƒmƒ“ƒZƒ“ƒTپ[‚حچ‚ٹ´“x‚إƒ\ƒjپ[ƒZƒ“ƒTپ[‚ًڈم‰ٌ‚ء‚ؤ‚½‚©‚çپAISO‚ھڈم‚ھ‚è‚ھ‚؟‚بƒXƒ|پ[ƒcژB‰e‚ب‚ٌ‚©‚إ‚ح—ا‚©‚ء‚½‚ٌ‚¾‚¯‚ا‚ثپ[پAچ،‚حچ‚ٹ´“x‚à•د‚ي‚ç‚ب‚¢‚µپc
چ،‚ج—¬‚ê‚إ‚حپA‘½•ھ‚»‚ج‚¤‚؟پATLM‚جŒ¸Œُ•ھ‚ً‚ن‚¤‚ن‚¤ƒ`ƒƒƒ‰‚ة‚µ‚؟‚ل‚¤‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚جپH
ٹو’£‚ê‚وپAƒLƒ„ƒmƒ“
‚إپAƒ\ƒjپ[‚حRAWŒ`ژ®‚ً•د‚¦‚é‚©‰آ‹tˆ³ڈk‚ً’ا‰ء‚إ‚«‚é‚©پAچ‚‘¬ڈˆ—پAڈ‘‚«چ‚ف‚ً‰آ”\‚ة‚إ‚«‚é‚©پA‚ئپAٹGچى‚è‚©
ٹو’£‚ê‚وپAƒ\ƒjپ[
‚±‚ٌ‚ب‚ئ‚±پH
ڈ‘چ”شچ†پF18052376پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 2“_
2“_
‚ پAڈ‰‚ء‚د‚ب‚©‚çٹشˆل‚ء‚ؤ‚é
D800‚ج‚وپ[‚بƒjƒRƒ“‹@‚حپA‘½•ھ14bit‚ًپu‰آ‹tˆ³ڈkپv‚إپcپA‚ث
ڈ‘چ”شچ†پF18052396پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
ٹù‚ةA‚q‚vŒ`ژ®‚ج‚q‚پ‚—‚ح‰آ‹tˆ³ڈk‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ح‚¸‚إ‚حپH
JPEG‚جƒTƒ€ƒlƒCƒ‹(‘ه‚«‚¢‚و)‚à–„‚كچ‚ٌ‚إ‚ ‚邵پB
ڈ‘چ”شچ†پF18057089پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
‚¤‚ٌپA
‚»پ[ڈ‘‚¢‚½‚آ‚à‚è
‚إ‚à‚ء‚ؤپA‚»‚±‚ھƒ\ƒjپ[RAW‚جˆê”ش‚ج–â‘è“_‚¾‚ئ‚àڈ‘‚¢‚½‚آ‚à‚è
‰´‚ج‘z‘œ‚إ‚حپAƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚حڈي‚ة14bit‚إپA12bit‚ة‚·‚é‚ج‚حŒمڈˆ—‚ًŒy‚‚·‚邽‚ك‚¶‚ل‚ب‚¢‚©‚بپ[‚ء‚ئ
“dژqگو–‹‚حٹضŒW‚ب‚¢‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚©‚ب‚ء‚ئ‚ث
‚آ‚¢‚إ‚ةپAƒLƒ„ƒmƒ“ƒZƒ“ƒTپ[‚ھ12EV‚µ‚©‚ئ‚ê‚ب‚¢‚ج‚إ—ٍ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚وپ[‚ب‚±‚ئ‚àڈ‘‚¢‚½‚ھپA‚ ‚‚ـ‚إ‚جDxOƒ}پ[ƒN‚ھڈںژè‚ةچى‚ء‚½ƒ‹پ[ƒ‹‚ًŒ³‚ة•ھ‚©‚è‚â‚·‚¢‚وپ[‚ةچl‚¦‚½‚¾‚¯‚إ‚ ‚ء‚ؤپAƒvƒٹƒ“ƒg‚إDR‘‚¦‚邱‚ئ‚©‚çچl‚¦‚ؤ‚àپA—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚ئ‚نپ[ٹد“_‚إŒ»ژہ‚ح‚»پ[’Pڈƒ‚ب‚±‚ئ‚إ‚à‚ب‚¢‚ء‚·‚ثپA‚«‚ء‚ئ
ڈ‘چ”شچ†پF18057286پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 0“_
0“_
‚ پA‚ي‚©‚è‚أ‚êپ[‚ب
ƒ\ƒjپ[RAW‚حپA12bit‚à14bit‚à”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚ب‚ج‚ھپc‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚ء‚·
ƒ\ƒjپ[14bit‚حپA14EVچج‚ê‚ؤ‚àRAWƒtƒ@ƒCƒ‹‚ة‚·‚é’iٹK‚إڈî•ٌ‚ًٹشˆّ‚‚±‚ئ‚ة‚ب‚é
‚½‚¾پA‚±‚ج’iٹK‚ج‘O‚ة‚·‚إ‚ةƒfپ[ƒ^‚ًکM‚ء‚ؤ‚é‚©‚çپA‚±‚ê‚à‚ب‚ٌ‚©‰e‹؟‚ ‚邶‚ل‚ب‚¢‚©‚بپH
‚إپA‚ـپAƒtƒ@ƒCƒ‹‚حڈ¬‚³‚‚ب‚é‚ئ
ƒ\ƒjپ[12bit‚حپA14EV‚ً12bit‚ة”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk
گl‚ج–ع‚ج“ء’¥‚ًژQچl‚ة‚ب‚é‚ׂ—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚ًژc‚µ‚ب‚ھ‚çٹشˆّ‚‚ء‚ؤکb‚ب‚ي‚¯‚¾‚¯‚اپc
ژہ‚ح‚±‚ê‚ھپAگآ‹َ‚ًƒgپ[ƒ“ƒWƒƒƒ“ƒv‚³‚¹‚錴ˆِ‚¶‚ل‚ب‚¢‚ء‚ؤپA‰´‚ح‹^‚ء‚ؤ‚é
‚إ‚à‚ء‚ؤپAƒLƒ„ƒmƒ“ƒZƒ“ƒTپ[‚حپA‚»‚à‚»‚à12EV‚µ‚©‚ب‚¢ƒٹƒjƒARAW‚ب‚ٌ‚¾‚©‚çپA12bit‚ئ‚©14bit‚ئ‚©Œ¾‚ء‚ؤ‚àپAƒ\ƒjپ[ƒZƒ“ƒTپ[‚ئ‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئˆس–،چ‡‚¢‚ھˆل‚¤‚ٌ‚¾‚¼‚ء‚ئ
’Pڈƒ‚ةƒ\ƒjپ[12bitRAW‚ھƒLƒ„ƒmƒ“12bitRAW‚و‚è‚à—LŒّ‚بƒfپ[ƒ^‚ء‚ؤˆس–،‚إ•K‚¸‚µ‚à‘S‚ؤ‚ة‚¨‚¢‚ؤ—ٍ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ء‚ؤ‚ج‚حپAگ³‰ً‚¶‚ل‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚و‚ء‚ئ
گوگ¶پA‚±‚ٌ‚ب‚ئ‚±‚إچ‡‚ء‚ؤ‚éپH ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18057342پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 2“_
2“_
‚ ‚çپA‚»پ[‚©‚¢‚½‚آ‚à‚肶‚ل‚ثپ[‚و
‚ب‚ةŒ¾‚ء‚ؤ‚ٌ‚¾‚ë
ƒ\ƒjپ[RAW‚ح‰آ‹tˆ³ڈk‚¶‚ل‚ب‚پA”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚¶‚ل‚ب‚¢پH
12‚à14‚à
’²‚ׂé•û–@‚حپcپAƒپپ[ƒJپ[’®‚‚µ‚©‚ب‚¢‚ب‚©‚à ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18057353پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚ـ‚½پAٹشˆل‚ء‚ؤ‚é
‚²‚ك‚ٌ
‘O‚ج‘OپAƒLƒ„ƒmƒ“12bitRAWپ¨ƒLƒ„ƒmƒ“14bitRAW
ƒ\ƒjپ[12bit‚ئƒLƒ„ƒmƒ“14bit‚ً”نٹr‚µ‚ؤ‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚ء‚·
ڈ‘چ”شچ†پF18057366پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚¦پ[پH
ƒfƒWƒ^ƒ‹‚جˆ³ڈk‚حپA‚·‚ׂؤ‰آ‹tˆ³ڈk‚إ‚·پBƒJƒپƒ‰‚¾‚ء‚ؤ‰آ‹tˆ³ڈk‚إ‚·پB
ƒjƒRƒ“‚إ‚ح‚ي‚´‚ي‚´ƒچƒXƒŒƒXˆ³ڈk‚ئڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‘¼ژذ‚à“¯‚¶‚إ‚·پBRAW‚حˆ³ڈk‚ئ‚·‚çڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ھپARAW‚حˆ³ڈk‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18057369
![]() 0“_
0“_
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ئbitٹK’²‚ح“¯‚¶‚ب‚ٌ‚إ‚·‚©?
bitگ”‚حژOŒ´گF‚ًŒ³‚ةگF‰”•M‚ج12گF‚©36گFƒZƒbƒg"‚ف‚½‚¢‚ب‚à‚ج"‚©‚ئژv‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚½پB
ڈ‘چ”شچ†پF18057378
![]() 0“_
0“_
‚¦پH
JPEG‰و‘œ‚ً‚ب‚ة‚àکM‚炸‚ةڈمڈ‘‚«•غ‘¶‚·‚é‚ئپA‚ا‚ٌ‚ا‚ٌ—ٍ‰»‚µ‚ؤ‚¢‚‚ج‚ح—L–¼‚بکb‚إ‚حپH
‚»پ[‚نپ[ˆس–،‚¶‚ل‚ب‚¢‚ء‚ؤپH ڈخ
‚¢‚â‚إ‚àپAƒfƒWƒ^ƒ‹‚جˆ³ڈk‚ء‚ؤ‚±‚êˆبٹO‚جˆس–،‚ ‚é‚©‚ب
ƒچƒXƒŒƒXˆ³ڈk‚ح‰آ‹tˆ³ڈk‚إ‚حپH
ڈ‘چ”شچ†پF18057399پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 2“_
2“_
ژتگ^چD‚«‚ٌپA“¯‚¶‚ئ‚نپ[‚و‚èپADR‚ً‘‚â‚·‚ة‚حچ،ˆê”شˆأ‚¢‚ئ‚±‚ë‚ج‚³‚ç‚ة”¼•ھ‚جˆأ‚³‚ً”Fژ¯‚إ‚«‚ê‚خ‚¢پ[‚ٌ‚إپAچ،‚و‚è‚à‚Q”{چׂ©‚چڈ‚ٌ‚إ‚â‚ê‚خ‚¢‚¢‚ي‚¯‚ء‚·‚و
1bit‘‚₹‚خپA‚Q”{چׂ©‚‚ب‚é‚إ‚µ‚ه
ڈ‘چ”شچ†پF18057437پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚¦پ[‚ئ‚إ‚·‚ثپ[پAژ„‚حRAW‚جژ–‚ًڈq‚ׂؤ‚¢‚ـ‚·پBŒ¾—t‘«‚炸‚إچد‚ف‚ـ‚¹‚ٌپB
RAW‚ح‰آ‹tˆ³ڈk‚إ‚·پB
JPEG‚حپAگج‚©‚ç”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚إ—L–¼‚إ‚·‚و‚ثپB‰½“x‚àJPEG‚ًŒ»‘œ‚·‚é‚ئ‰وژ؟‚ھˆ«‚‚ب‚éپB
‚±‚ê‚حٹF“–‘R’m‚ء‚ؤ‚¢‚镨‚ئپAڈب‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBژ¸—炵‚ـ‚µ‚½پAJPEG‚ج”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚ً’m‚ç‚ب‚¢گl‚à‚¢‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚©‚çپAڈ‘‚«’¼‚µ‚ـ‚·پB
پ@پ@JPEG‚حگج‚©‚ç‹Kٹi‚إŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚¨‚èپA”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚إ‚·پB
پ@پ@RAW‚ح‰آ‹tˆ³ڈk‚إ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18057508
![]() 0“_
0“_
JPEG‚ئ‚©‚ج”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚حگlٹش‚ج–ع‚ة‘e‚ھ–ع—§‚½‚ب‚¢‚و‚¤‚ةڈî•ٌ‚ًگط‚èژج‚ؤ‚ؤ—e—ت‚ًڈ¬‚³‚‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
RAW‚ح‚ـ‚¾‰و‘œ‚ئ‚µ‚ؤگ¶گ¬‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إ”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚ً‚©‚¯‚邱‚ئ‚حڈo—ˆ‚ب‚¢‚ئپAژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ٌ‚إ‚·‚ھپB‚ا‚¤‚ب‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤
پ@‚و‚낵‚¯‚ê‚خپAڈع‚µ‚¢گl‹³‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒXƒŒƒ“ƒW‚ئbitگ”‚ح’è‹K‚ج’·‚³‚ئ–عگ·‚è‚جچׂ©‚³‚ف‚½‚¢‚بٹضŒW‚¾‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ھپB
‚»‚µ‚ؤپAJPEG‚ة‚·‚é‚ئ‚«‚حƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒXƒŒƒ“ƒW‚جˆê•”‚ًگط‚èڈo‚µ‚ؤ‰و‘œ‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚éپBƒlƒKƒtƒBƒ‹ƒ€‚جƒ‰ƒeƒBƒ`ƒ…پ[ƒh‚ً‚·‚ׂؤژg‚ء‚ؤƒvƒٹƒ“ƒg‚µ‚ب‚¢‚ج‚ئ“¯‚¶—l‚ةپB‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ھپB
ڈ‘چ”شچ†پF18057540
![]() 0“_
0“_
RAW‚ء‚ؤ‹Kٹi‚ھƒپپ[ƒJپ[‚ة‚و‚ء‚ؤƒoƒ‰ƒoƒ‰‚ب‚ٌ‚·‚و
12bit‚إ12EV‚ً‘ه‚«‚ڈم‰ٌ‚éDR‚ھ‹Lک^‚³‚ê‚ؤ‚邱‚ئ‚©‚ç‚àپAƒZƒ“ƒTپ[‚©‚ç‚جڈî•ٌ‚ً”ٌ‰آ‹t‚ةˆ³ڈk‚µ‚ؤ‚é‚ج‚ح–¾‚ç‚©‚ء‚·‚و
ڈ‘چ”شچ†پF18057635پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚ٌپA‘ز‚ؤ‚و
‚ـ‚³‚©‚ئ‚حژv‚¤‚ھپARAWŒ»‘œ‚ج‚ ‚ئ‚جRAWƒtƒ@ƒCƒ‹•غ‘¶‚ج‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ء‚ؤ‚éپH
‚±‚ê‚حپAƒgپ[ƒ“ƒJپ[ƒu‚âWB“™‚جƒpƒ‰ƒپپ[ƒ^‚ً•د‚¦‚邾‚¯‚إپA‚»‚ê‚ً•غ‘¶‚·‚邾‚¯‚إپA‚»‚à‚»‚à‚جƒZƒ“ƒTپ[‚©‚çچج‚èڈo‚µ‚½Œُ‚ج‘ه‚«‚³‚جƒfپ[ƒ^‚ً•د‚¦‚ؤ•غ‘¶‚µ‚ؤ‚é‚ي‚¯‚¶‚ل‚ب‚¢‚ء‚·‚و
TIFF‚ئ‚©‚ئ‚حˆل‚¤‚©‚ç‚ث
‚ء‚ؤپA‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚é‚ي‚¯‚¶‚ل‚ب‚¢‚و‚ثپH
ٹˆژڑ‚¾‚¯‚ء‚ؤ‚ق‚¸‚©‚µ‚ثپ[ ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18057707پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚¨‚¶‚ل‚ـ‚µ‚ـ‚·پB
چ•ƒVƒƒƒcƒہ‚³‚ٌ‚ج—‰ً‚إگ³‚µ‚¢‚ج‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپA
ˆ³ڈk‚ج—L–³‚â‚»‚ج‰آ‹tگ«‚ئپA”ٌگüŒ`پi”ٌ‰آ‹tپj‚بڈˆ—‚ھ‚ب‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚ا‚¤‚©‚حپA•ھ‚¯‚ؤچl‚¦‚ئ‚¢‚½•û‚ھ—ا‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ(ژہچغ‚حˆêڈڈ‚ةڈˆ—‚³‚ê‚ؤ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚¯‚ا)پB
A: ‘fژq‚ج“¾‚½ƒfپ[ƒ^‚ًƒXƒgƒŒپ[ƒgپiگüŒ`پj‚ةگ”’l‰»‚µ‚½ƒfپ[ƒ^
B: A‚جƒfپ[ƒ^‚ة”ٌ‰آ‹tپi”ٌگüŒ`پj‚ب•دٹ·ڈˆ—‚ًژ{‚µ‚½ƒfپ[ƒ^
C: B‚جƒfپ[ƒ^‚ًˆ³ڈk‚µ‚½ƒfپ[ƒ^پپƒJƒپƒ‰‚©‚çڈo—ح‚³‚ê‚ؤƒ†پ[ƒUپ[‚ھƒAƒNƒZƒX‚إ‚«‚éپuRAWپv
B‚جڈˆ—‚ة‚حڈم‚إگà–¾‚³‚ê‚ؤ‚é‚و‚¤‚ةƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW‚ً‰ز‚®‚½‚ك‚جڈˆ—‚âپA
‹@ژي‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حRAWƒŒƒxƒ‹‚جƒmƒCƒYƒٹƒ_ƒNƒVƒ‡ƒ“ڈˆ—‚ھٹـ‚ـ‚ê‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB
A‚©‚çB‚ح”ٌ‰آ‹t•دٹ·‚إ‚·‚ھپAB‚©‚çC‚ح‰آ‹t‚جڈêچ‡‚ئ”ٌ‰آ‹t‚جڈêچ‡‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚و‚ثپB
A‚جƒfپ[ƒ^‚ًƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚جRAW‚ئچl‚¦‚é‚ب‚çپAA77II‚جپuRAWپv‚حپu”ٌ‰آ‹tˆ³ڈkRAWپv‚إ‚·‚ھپA
B‚جƒfپ[ƒ^‚ًƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚جRAW‚ئچl‚¦‚é‚ب‚çپAA77II‚جپuRAWپv‚حپu‰آ‹tˆ³ڈkRAWپv‚ئŒؤ‚ش‚ׂ«‚à‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB
‚؟‚ب‚ف‚ةپANIKON‚جRAW‚حگüŒ`‚ئ‚¢‚¤کb‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ھپAD90‚ب‚ا‚ح12bitRAW‚إDR12EV’´‚¦‚ؤ‚ـ‚·پB
‚½‚µ‚©پANIKON‚جRAW‚ج”ٌگüŒ`گ«‚جکb‚حD70‚جچ ‚©‚çپA‚µ‚©‚àƒچƒXƒŒƒXˆ³ڈkRAWپiپپ‰آ‹tˆ³ڈkRAWپj‚ة‘خ‚µ‚ؤ•ٌچگ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18058558
![]() 0“_
0“_
ƒjƒRƒ“D810‚جگà–¾ڈ‘‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚ ‚ء‚½‚وپ[
”ٌˆ³ڈkRAW‚حپA•¶ژڑ’ت‚è‚»‚ج‚ـ‚ٌ‚ـ‚إƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY‚ھ‚₽‚ç‚إ‚©‚¢
ƒچƒXƒŒƒXˆ³ڈk‚حپA‰آ‹t‚إˆ³ڈkپA‰آ‹t‚¾‚©‚çƒfپ[ƒ^‚ج“à—e‚ح”ٌˆ³ڈk‚ئ“¯‚¶‚إƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY‚ھڈ‚µڈ¬‚³‚‚ب‚é
ˆ³ڈkRAW‚حپA”ٌ‰آ‹t‚ةˆ³ڈkپA‚à‚؟‚ë‚ٌƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚ة‚ح•œŒ³•s‰آ”\‚¾‚¯‚اپAƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY‚ھ”¼•ھ‚®‚ç‚¢‚ة‚ب‚éٹ„‚ة‚حپA‰وژ؟‚حپu‚ظ‚عپv“¯“™‚¾‚ء‚ؤ
‚ب‚ج‚إپAorange‚³‚ٌ‚جڈ‘‚¢‚½پuRAW‚ح‚·‚ׂؤ‰آ‹tˆ³ڈkپv‚ء‚ؤ‚ج‚حٹ¨ˆل‚¢‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚¾‚ث
‚إپA‚ ‚炽‚ب‹^–â‚ھ ڈخ
D810پA‚¢‚‚çprint‚¾‚©‚ç‚ء‚ؤپA14EV‚ً‘ه‚«‚ڈم‰ٌ‚é‚ء‚ؤپA‚ب‚ٌ‚©‚¨‚©‚µ‚‚ب‚¢‚ء‚·‚©پH
‚ب‚ٌ‚©پA’N‚à‚ھٹشˆل‚ء‚ؤ‚é‹C‚ھ‚µ‚ؤ‚«‚½‚¼پ[
ڈ‘چ”شچ†پF18058566پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 3“_
3“_
”ٌ‰آ‹tˆ³ڈkƒCƒRپ[ƒ‹”ٌگüŒ`‚ئŒ©‚½•û‚ھگ³‰ً‚إ‚حپH
‚ٌ‚¾‚©‚çپAƒjƒRƒ“‚جڈمˆت‹@ژي‚ة‚حƒٹƒjƒA‚à”ٌƒٹƒjƒA(”ٌگüŒ`)‚à—¼•û‚³‚ê‚ؤ‚é‚ء‚ؤˆس–،‚إپAˆê•àگi‚ٌ‚إ‚é‚ء‚ؤژv‚ء‚½‚و
‚إپAƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚ئ‚ح‚ ‚‚ـ‚إ‚àAپA‚·‚ب‚ي‚؟پAƒZƒ“ƒTپ[‚©‚ç‚ج‘f‚جڈî•ٌ‚ئ’è‹`‚µ‚ب‚¢‚ئپA‚àپ[پA‚ف‚ٌ‚ب‚ك‚؟‚ل‚‚؟‚ل‚ة ڈخ
D90‚حپA77‡U‚ج‚وپ[‚ةپA14bitƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚ج12bit(”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk)RAW‚ب‚ج‚©‚بپH
‚½‚¾پAƒjƒRƒ“‚جŒ»چs‹@‚إ12‚©14‚ً‘I‚ׂ郄ƒc‚ج12bit‚حپAƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚©‚ç‚·‚إ‚ة12bit‚ب‚ٌ‚¾‚ئژv‚¤
ڈ‘چ”شچ†پF18058622پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚i‚o‚d‚f‚ھ‘S‚ؤ”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚ئ‚¢‚¤‚ج‚àٹشˆل‚¢پB
‚إ‚àپAچ•‚³‚ٌ‚جˆ³ڈk‚ج’è‹`‚ھٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¤پB
—تژq‰»‚·‚é‘O‚©Œم‚©پB
ڈ‘چ”شچ†پF18058757پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 2“_
2“_
‚ٌپH
’N‚©JPEG‚ھ‘S‚ؤ”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚ب‚ٌ‚ؤڈ‘‚¢‚½‚ء‚¯‚©
‚ـپA‚¢‚¢‚© ڈخ
—تژq‰»‚·‚é‘O‚جˆ³ڈk‚ء‚ؤ‚اپ[‚نپ[‚±‚ئپH
ˆ³ڈk‚ء‚ؤƒfƒWƒ^ƒ‹ƒfپ[ƒ^‚¾‚©‚ç‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚µ‚هپH ˆل‚¤‚جپH
ƒAƒiƒچƒO’iٹK‚جˆ³ڈk‚ء‚ؤپHپHپH
“ن‚©‚¯‚خ‚©‚è‚إگà–¾‚µ‚ب‚¢‚ب‚çپA‚؟‚ه‚ء‚©‚¢ڈo‚³‚ب‚¢‚إ‚و ‹êڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18058844پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 6“_
6“_
‚ پA‚»‚ء‚©
ژہچغ‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ج‚©پ[
14bit”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚àپA–¾‚é‚¢•û‚ًگد‹ة“I‚ةٹشˆّ‚¢‚ؤپAˆأ‚¢•û‚ح‹ة—حژc‚·‚وپ[‚ة”ٌگüŒ`(”ٌ‰آ‹t)‚ةˆ³ڈk‚·‚é•û‚ھŒّ—¦“I‚¾‚©‚çپA‚±‚ٌ‚بˆ³ڈkƒAƒ‹ƒSƒٹƒYƒ€‚ھ“–‚½‚è‘O‚¾‚ئژv‚ء‚ؤ‚½‚¯‚اپA
‚»پ[‚¶‚ل‚ب‚پA’Pڈƒ‚ةڈˆ—‚âƒtƒ@ƒCƒ‹‚ًŒy‚‚·‚邽‚ك‚¾‚¯‚ة•½‹د“I‚ةٹشˆّ‚¢‚ؤٹب’Pˆ³ڈk‚ء‚ؤ‰آ”\گ«‚à‚ ‚é‚ج‚©
‚إ‚àپA‚±‚ꂶ‚لپA14bit‚ً‚©‚½‚éژ‘ٹi‚·‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ب ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18059389پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚؟‚ه‚ء‚ئ’²‚ׂؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB
http://cygx.mydns.jp/blog/?arti=431
ˆê‰‚±‚±‚ةپAˆ³ڈk•û–@‚ھچع‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB
ƒzƒ“ƒg‚©‚ا‚¤‚©•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپB
ڈ‘چ”شچ†پF18060930
![]() 0“_
0“_
ƒtƒ@ƒCپEƒEƒFپ[ƒoپ[‚³‚ٌپA‚ا‚¤‚à‚ ‚è‚ھ‚ئ
‚¢‚³‚³‚©Œأ‚¢‚و‚¤‚ب‹C‚à‚·‚邯‚اپA‚»‚ê‚إ‚àپA‚½‚‚³‚ٌ‚جƒqƒ“ƒg‚ھ“]‚ھ‚ء‚ؤ‚é‚ثپ[
‚½‚¾پA–â‘è‚ب‚ج‚ح‰´‚ةƒvƒچƒOƒ‰ƒ€‚ً“ا‚ف‚ئ‚”\—ح‚ھ”ُ‚ي‚ء‚ؤ‚ب‚¢‚ء‚ؤ‚±‚ئ
ٹجگS‚ج“à—e‚ھ‚³‚ء‚د‚è‚ي‚©‚ç‚ٌ ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18061277پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
“dŒ¹“dˆ³‚ھ‚T‚u“®چى‚·‚é‚ئ‰¼’肵‚ـ‚·پD
ˆب‰؛‚à‰¼’è
‚`پ^‚cƒRƒ“ƒoپ[ƒ^‚ج“ü—ح”حˆحپ@‚Oپ`‚T‚u
ژB‘œ‘fژq‚جڈo—حپ@پ@‚P‚uپ`‚S‚uپDپDپDپDپD‚`پ^‚c‚ج“ü—ح‚ج‘S‚ؤ‚ھژg—p‚³‚ê‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پD
--------------------------------------
‚`پ^‚cƒRƒ“ƒoپ[ƒ^‚جƒQƒCƒ“پA‚O“_‚ج‚خ‚ç‚آ‚«‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپA‘fژqگ»‘¢ژ‚ة‘ھ’肵‚½•âگ³ƒfپ[ƒ^‚ة‚و‚è•âگ³‚·‚é‚ح‚¸پD
ژB‰eژپA–³Œّ‘fژqپiŒُ‚ھ“–‚½‚ç‚ب‚¢‘fژqپj‚جƒfپ[ƒ^‚©‚çˆإ“d—¬‚ً‹پ‚ك•âگ³‚·‚éپD
پi’·ژٹشکIŒُژ‚حپAژ–‘O‚ة‘S‘fژq‚ً“ا‚فڈo‚·پj
‚¨‚»‚ç‚پA‘S‘fژq‚جٹîڈ€‚ة‚ب‚éˆإ“d—¬‚ئپAچإ‘هکIڈo‚ج’l‚ًپAگ»‘¢ژ‚ة‘ھ’肵پA•âگ³ƒfپ[ƒ^‚ئ‚µ‚ؤژ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ي‚ê‚éپD
گو‚ة‰¼’肵‚½پAˆأˆإ‚ج’l‚ً‚P‚u‹ك•س‚جگ”’l‚ئ‚µ‚ؤپA–¾‚é‚¢ˆê’è‚جŒُ‚ً“–‚ؤ‚ؤ‘ھ’肵‚½’l‚ً‚S‚u‹ك•س‚جگ”’l‚ئ‚µ‚ؤژ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ح‚¸پD
پi‚±‚جڈêچ‡‚`پ^‚c‚ج•âگ³’l‚ح‚±‚جƒfپ[ƒ^‚ةٹـ‚ـ‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپj
‚`پ^‚cƒRƒ“ƒoپ[ƒ^‚ح’تڈيپA‚P‚k‚r‚aˆبڈم‚جŒëچ·‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚éپD
‚P‚k‚r‚a‚جŒëچ·‚ئ‚µ‚ؤپA‘fژqڈo—ح‚P‚Qپپ‚‚‚‰‚”پA‚`پ^‚cپپ‚P‚Q‚‚‚‰‚”‚ب‚ç‚خپA•ھ‰ً”\‚ح‚P‚Pƒrƒbƒg‚ة‚ب‚éپD
--------------------------------------
ˆبڈم‚ًچl‚¦چ‡‚ي‚¹‚ê‚خپA‘fژq‚جڈo—ح‚ئ“¯‚¶•ھ‰ً”\‚ج‚`پ^‚c‚µ‚©•K—v‚ب‚¢‚ئچl‚¦‚é‚ج‚ح‘ه‚«‚بٹشˆل‚¢‚إپA•ھ‰ً”\‚جچ‚‚¢‚`پ^‚c‚ً—p‚¢‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پD
‰و‘œ‚جڈo—حƒfپ[ƒ^‚حپA‘fژq‚ج•ھ‰ً”\پ{‚Pƒrƒbƒg‚ ‚ê‚خ—ا‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پD
ڈ‘چ”شچ†پF18121389
![]() 1“_
1“_
‚ـ‚³‚µ‚پA•W–{‰»‚ج’è—‚©‚ئپB
ڈ‘چ”شچ†پF18121871پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
http://kakaku.com/camera/digital-camera/
ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒJƒپƒ‰‘Sگ»•i(280گ»•i)
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/
ƒfƒWƒ^ƒ‹‚PٹلƒJƒپƒ‰‘Sگ»•i(337گ»•i)
‚ئ‚½‚‚³‚ٌ‚جگ»•i‚ھkakaku.com‚ة“oک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚³‚ؤپA‚»‚ج’†‚إپ@"”ٌ"‰آ‹tˆ³ڈkRawپ@‚ًƒTƒ|پ[ƒg‚µ‚ؤ‚¢‚é‹@ژي‚ح‚ا‚ج‚‚ç‚¢‚ ‚é‚ٌ‚¾‚낤پB
‚à‚µپA‚»‚ê‚ھ1%ˆب‰؛‚إ‚ ‚é‚ب‚ç‚خپA—لٹO‚ئ‚µ‚ؤ‚à‚¢‚¢‚©‚à‚ثپB
‚آ‚ـ‚èپA‚»‚ê‚حˆê”ت“I‚ةŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é Raw ‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ئپB
ڈ‘چ”شچ†پF18122731
![]() 1“_
1“_
RawŒ`ژ®‚©‚ا‚¤‚©‚ً”»’f‚·‚é‚ج‚حƒپپ[ƒJپ[‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پH
‚»‚ê‚ئ‚àCIPA‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پH
‚»‚ê‚ئ‚à‰؟ٹi.com‚جڈيکA‚³‚ٌ‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پH
‚»‚ê‚ئ‚àƒvƒچƒJƒپƒ‰ƒ}ƒ“‚ب‚¾‚낤‚©پH
‚»‚ê‚ئ‚àژGژڈƒ‰ƒCƒ^پ[‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پH
‚»‚ê‚ئ‚àژ¯ژز‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پH
”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚ب‚à‚ج‚ة Raw ‚ئ‚¢‚¤–¼‘O‚ً•t‚¯‚½ƒپپ[ƒJپ[‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
ڈ«—ˆپAYCrCb 4:2:2 ڈo—ح‚ة Raw ‚ئ‚¢‚¤–¼‘O‚ً•t‚¯‚éƒپپ[ƒJپ[‚ھڈo‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
‚إ‚àپA‚»‚ê‚ç‚ح Raw ‚إ‚ح‚ب‚¢پB
‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚à‚ئ‚¢‚¤‚ب‚çپu‚ب‚ٌ‚؟‚ل‚ء‚ؤ Rawپv‚ئŒؤ‚ش‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
‚±‚ê‚ھ‚¨‚¶‚³‚ٌ‚جژه’£‚إ‚·پB
‚²ژ^“¯‚¢‚½‚¾‚¯‚é•û‚حƒiƒCƒX‚ً‚¨ٹè‚¢‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB
ڈ‘چ”شچ†پF18122909
![]() 1“_
1“_
‚ب‚é‚ظ‚اپ[پA
‰؛ˆت1bit‚حپAADC‚إ‚آ‚ش‚ê‚é‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚ء‚·‚ث
‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚حپA—LŒّ‚بDR12EV‚ً—]‚邱‚ئ‚ب‚ژg‚¤‚½‚ك‚ة‚حپA‚ـپ[پAƒLƒ„ƒmƒ“‚ج14bitRAWپA14bitADC‚ح‚»‚ê‚ب‚è‚ة—LŒّ‚ئ‚نپ[‚©پA•K—v‚إ‚ ‚é‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚ء‚·‚ث
‚إپA‹t‚ةŒ¾‚¦‚خپA14bitADC‚إ‚حپAچإ‘ه13EV’ِ“x‚جDR‚µ‚©“¾‚ç‚ê‚ب‚¢‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚ء‚·‚ث
‚»‚±‚إپA‚ـ‚½‹^–â‚ھ ٹ¾
D750‚حپADR‚إ13.7EV‚ئ‚©گM‚¶‚ç‚ê‚ب‚¢ƒeƒXƒgŒ‹‰ت‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚é‚ٌ‚¾‚¯‚اپA‚±‚ê‚ء‚ؤپcپH
16bitADC‚ء‚ؤ‚±‚ئ‚ء‚·‚©‚ث
‰؛ˆت2bit‚ًƒoƒbƒTƒٹگط‚ء‚½14bitRAW‚ب‚ج‚©‚بپ[
‚ ‚جƒTƒ“ƒvƒ‹پA‚؟‚ه‚ء‚ئچ،‚ـ‚إ‚جƒtƒ‹ƒTƒCƒY‹@‚ئ‚حˆل‚¤‚ب‚ء‚ؤٹ´‚¶‚½‚ٌ‚¾‚¯‚اپA‹C‚ج‚¹‚¢‚©‚ب ڈخ
‚ پ[پA‚»‚ê‚©‚ç
ƒjƒRƒ“‚ح”ٌ‰آ‹tˆ³ڈkRAW‚â‚ء‚ؤ‚é‚ٌ‚إپA1%‚ب‚ٌ‚ؤ‚ج‚ح‚ن‚¤‚ة‰z‚¦‚ئ‚é‚و ڈخ
ڈ‘چ”شچ†پF18123471پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
> 1%‚ب‚ٌ‚ؤ‚ج‚ح‚ن‚¤‚ة‰z‚¦‚ئ‚é‚و ڈخ
‚ي‚ھ“¹‚ًچs‚‚ء‚ؤٹ´‚¶‚إ‚·‚ثپB
‚ا‚ء‚©‚ج’N‚©‚³‚ٌ‚ف‚½‚¢پB(ڈخ)
# گ¢ٹE‚إ‰½‹@ژي‚جƒfƒWƒJƒپ‚ھ‘¶چف‚·‚é‚ج‚©‚بپH
ڈ‘چ”شچ†پF18123659
![]() 0“_
0“_
ƒyƒ“ƒ^ƒbƒNƒX‚ج—L–¼‚بƒfپ[ƒ^پ[ڈo—ح‚ح12bit‚¾‚¯‚اA/D•دٹ·‚ح22bitڈˆ—‚إ‚·‚ثپB
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/digital/k10d/feature.html
ڈ‘چ”شچ†پF18124515
![]() 0“_
0“_
‚ا‚ٌ‚ب•”•i‚ًگد‚ٌ‚إ‚¢‚é‚©‚àڈd—v‚¾‚¯‚اپB
ˆس–،‚ج‚ ‚éƒfپ[ƒ^‚ئ‚µ‚ؤ‰½ƒrƒbƒg’·‚ب‚ج‚©‚ھ‹C‚ة‚ب‚é‚ب‚ پB
ڈ‘چ”شچ†پF18124525
![]() 0“_
0“_
‚»‚ê‚ھپA‚ ‚ê‚©‚بپ[
چ‚‚¢•ھ‰ً”\‚جADC‚ً—p‚¢‚ؤپA•K—v‚ب‚ئ‚±‚جگ³ٹmگ«‚ًڈo‚·‚ء‚ؤƒ„ƒc‚ب‚ج‚©‚ب
A/D•دٹ·‚إ‚جƒmƒCƒY‚ج‰e‹؟‚ًڈ¬‚³‚—}‚¦‚邽‚ك‚ة‚حپA‚¢‚¢•û–@‚ب‚ٌ‚¾‚ëپ[‚ث
‚ـپA‚إ‚àپAژہچغ‚جƒRƒXƒg“I‚ب‚à‚ٌ‚ئ‚©‚ح‰´‚ة‚ح‚³‚ء‚د‚肾‚µپA‚ا‚ٌ‚‚ç‚¢Œّ‰ت‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚à‚ي‚©‚ٌ‚ب‚©‚ء‚½‚è‚·‚邯‚ا ٹ¾
14bitADC‚©‚ç‚ج‹گ§”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk12bitRAW‚و‚è‚©‚حپAƒyƒ“ƒ^ƒbƒNƒX‚ج14bitRAW‚حپA“¯‚¶”ٌ‰آ‹tˆ³ڈk‚إ‚àگڈ•ھ‚ئچS‚ء‚ؤٹو’£‚ء‚ؤ‚éٹ´‚¶‚ھ‚·‚é‚ثپ[
ڈ‘چ”شچ†پF18129169پ@ƒXƒ}پ[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚جڈ‘‚«چ‚ف
![]() 1“_
1“_
‚±‚جƒXƒŒƒbƒh‚ةڈ‘‚«چ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚éƒLپ[ƒڈپ[ƒh
- bit
- RAW
- 14bit
- ƒrƒbƒg
- ˆ³ڈk
- ƒfپ[ƒ^
- ƒmƒCƒY
- ڈo—ح
- ƒZƒ“ƒTپ[
- ‰و‘f
- ٹK’²
- ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒŒƒ“ƒW
- ڈˆ—
- ڈî•ٌ
- •دٹ·
- ژB‰e
- ‹Lک^
- “dژq
- •ھ‰ً
- ƒپپ[ƒJپ[
- jpeg
- ژB‘œ‘fژq
- ‹P“x
- ‘ھ’è
- •K—v
- ˆل‚¢
- “ü—ح
- CMOS
- ƒtƒ@ƒCƒ‹
- CCD
- ’†”»
- ƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO
- چإچ‚
- ‰و‘œ
- ƒGƒ“ƒRپ[ƒh
- گMچ†
- ƒٹƒZƒbƒg
- ƒWƒƒƒ“ƒv
- ‘fژq
- “dˆ³
- ƒGƒ“ƒR
- Œ»‘œ
- sRGB
- کAژت
- –â‘è
- گ«”\
- ƒVƒƒƒbƒ^پ[
- ƒŒƒxƒ‹
- ƒeƒXƒg
- ƒtƒ@ƒCƒ‹ƒTƒCƒY
پuSONY > ƒ؟77 II ILCA-77M2 ƒ{ƒfƒBپv‚جگV’…ƒNƒ`ƒRƒ~
| “à—eپEƒ^ƒCƒgƒ‹ | •شگMگ” | چإڈI“ٹچe“ْژ |
|---|---|---|
| 37 | 2025/05/31 7:44:11 | |
| 2 | 2024/08/16 22:12:42 | |
| 36 | 2024/08/10 7:35:37 | |
| 4 | 2024/02/01 10:01:14 | |
| 15 | 2024/04/14 13:35:28 | |
| 6 | 2023/11/30 19:53:02 | |
| 4 | 2023/08/01 20:21:38 | |
| 9 | 2023/07/08 17:00:36 | |
| 0 | 2023/06/04 11:29:03 | |
| 4 | 2023/05/18 14:47:31 |
پuSONY > ƒ؟77 II ILCA-77M2 ƒ{ƒfƒBپv‚جƒNƒ`ƒRƒ~‚ًŒ©‚é(‘S 15222Œڈ)
ƒNƒ`ƒRƒ~Œfژ¦”آŒںچُ
چإ“K‚بگ»•i‘I‚ر‚ًƒTƒ|پ[ƒgپI
[ƒfƒWƒ^ƒ‹ˆêٹلƒJƒپƒ‰]
گV’…ƒsƒbƒNƒAƒbƒvƒٹƒXƒg
-
پy—~‚µ‚¢‚à‚جƒٹƒXƒgپzٹO•t‚¯HDD
-
پy—~‚µ‚¢‚à‚جƒٹƒXƒgپza
-
پyMyƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“پzWindows11‘خ‰‚إCPUٹ·‘•‚ئƒfƒBƒXƒN‘‹
-
پyMyƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“پzpc
-
پyMyƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“پzƒپƒCƒ“ƒAƒbƒvƒOƒŒپ[ƒhچإڈIچe
‰؟ٹi.comƒ}ƒKƒWƒ“
’چ–عƒgƒsƒbƒNƒX
- ‰tڈ»ƒeƒŒƒr‚ج‚¨‚·‚·‚ك11‘IپI گl‹Cƒپپ[ƒJپ[‚جچ‚‰وژ؟ƒ‚ƒfƒ‹‚âچ‚ƒRƒXƒpƒ‚ƒfƒ‹‚ًŒµ‘Iپy2026”N1Œژپz

‰tڈ»ƒeƒŒƒrپE—L‹@ELƒeƒŒƒr
- iPad‚ج‚¨‚·‚·‚كƒ‚ƒfƒ‹پI ProپAAirپA–³ˆَپAmini‚جˆل‚¢‚ئ‘I‚ر•û‚ً“O’ê‰ًگàپy2025”N12Œژپz

ƒ^ƒuƒŒƒbƒgPC
- Œg‘رƒLƒƒƒٹƒA‚جƒNƒŒƒWƒbƒgƒJپ[ƒh‚ً”نٹrپI ‚¨‚·‚·‚ك‚جچ‚ٹزŒ³ƒJپ[ƒh‚àڈذ‰îپy2026”N1Œژپz

ƒNƒŒƒWƒbƒgƒJپ[ƒh
پiƒJƒپƒ‰پj
ƒfƒWƒ^ƒ‹ˆêٹلƒJƒپƒ‰
پiچإ‹ك3”Nˆب“à‚ج””„پE“oک^پj