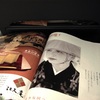デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-N2
http://nekoant.at.webry.info/200611/article_4.html
結構気になっていました「ダイナミックレンジ拡大機能」ですが、FinePix F10と撮り比べてみました。購入のご参考にして下さい。
結果は割と良好でした。ただ、F10がわざと弱い撮り方でくらべていますので、F10が悪いわけではなくデジタルカメラでは一般的だと思います。N2の効果ありということでお願い致します…
書込番号:5600964
![]() 0点
0点
う〜ん、分かりません。
F10も露出補正で、似たようになりそうな気もしますし・・・。
書込番号:5601034
![]() 0点
0点
そうですね。よく考えたらプログラムの露出も違うでしょうから違わないのかもしれません。マルチ測光も違う訳ですし。
ただのオート撮りでの違いだけでお願いします…
書込番号:5601128
![]() 0点
0点
F10に-1/3EVの露出補正を加えたら、
どういった結果になったでしょうかね?(^^;)
F10の方が明るいので、Autoでの露出傾向の差という事が読み
取れますが、F10がハイライト側で急激に飛んでいるかどうかの
点も見極めてみた方が良いように思えます。
N2も、アンダーに撮ってトーンカーブを持ち上げているようなら、
黒側階調が失われている可能性もあります。N2の詳細は存じ
ませんが、ダイナミックレンジというよりは、白ピーク対策という
解釈の方が正確なのかも知れません(^^;)
書込番号:5601152
![]() 0点
0点
まったく持って推論でしかないのですが・・・
両画像をフォトショでヒストグラム表示させてみると、
・F10のハイライトはもちろん白トビしているが、N2のは243くらいでおさまっていて、白トビは起きていない。
・双方の最アンダー部は、F10が7くらい、N2が4くらいで大差はない。ここから想像するに、F10に露出マイナス補正かけると「黒ツブレ」が起きそう。
・中間調〜アンダーにかけての山を見ても、N2の方が山の幅がせまい(=レンジが広い)ように見える。
・当然コントラスト処理といった「画像処理」の影響もあるだろうが、コントラストはむしろN2の方が強い。
といったところを見て、
N2のCCDレベルのダイナミックレンジは実際広くなっているのではないかと思いましたが、どうでしょうか?
少なくとも、受光量多いはずの1/1.7型ハニカム600万画素同等くらいにはいっているという推論が、
このシーンにおいては成り立つかも・・・なんて思うのです。
同じような検証方法でボクの手持ちのF30とA20とを比べると、
F30の方が広くはなるんですよね。(ただこの2つだと、コントラスト処理はA20の方が強い。)
もちろんF10批判しているわけではなく、素朴な疑問?でございますので、
ムーンライダーズ先生、くろこげパンダ先生にも検証していただければなんて思いました。
書込番号:5601258
![]() 0点
0点
もともとハニカムCCDに普通のCCDがかなうはずもないので、対決ではなく個性の違いが分かればと思います。近づいてきただけでも十分ですし。
正直、いつ働いているかわかりません(^^;
書込番号:5602064
![]() 0点
0点
ken311さん、こんにちは。
私もちょっと明るさを変えたり
レタッチしてみましたが
レタッチと露出補正した物と
同じになるかどうか分からないので、やめました。
レタッチした感じでは、N2の方が良さそうに思いましたけど。
あと、先生じゃないので
先生は、やめてくださいね。
書込番号:5602104
![]() 0点
0点
補足
>> F10がハイライト側で急激に飛んでいるか
>> どうかの点も見極めてみた方が良い
↑↑↑
ねねここさんの作例の事ではなく、F10がそういった
絵作りになっていないかどうかという意味です。
(表現がマズくてすいません(^^;)
------------------
ken311さん(私も先生の呼称は、辞退いたします(^^;)
ヒストグラムは分布データですから、実際の階調確認は
特定の部位や輝度範囲を目視でしてみた方がイイです(^^;)
黒側の差は、弱冠F10が有利のようですが、確かに、思ったほどの
差は無いみたいですネ。(有っても、必要・有用な階調かどうかは
疑問ですし・・・。)それに対して、白の表現差は、かなりの差が付
いていますから、全体としてはN2が有利と考えて良いでしょうネ。
F10は明るめに仕上げる露出傾向ですから、-1/3程度の補正で
どこまで追いつけるかどうかが見所になると思います。
ねねここさんが仰るように、何も考えずに撮るなら、N2の方が
白飛びに関して良い結果が得られると考えて良いと思います。
手間いらずという特徴は、F10のノイズ性能も同じ意味あいですし。
------------------
暗部ばかりのシーンだと、また違った印象になる可能性もありますが、
ダイナミックレンジ拡大機能が、白側の量を検知して動的に効果量を
調整していたら、そういったシーンでもN2が破綻する事はないだろ
うと思います。(=N2が、露出値とトーンカーブで調整していた場合)
まあ、気が向いたら、またその辺の検証をなさってみてください。
> ねねここ さん (^^;)
書込番号:5602248
![]() 0点
0点
追記
>> N2が、露出値とトーンカーブで調整していた場合
ダイナミックレンジ拡大機能が、↑こういった手法であるという
こと前提で、話をさせて頂いております。実際がどうなのかは、
私には判りません。そう外れてはないと思いますが・・・(^^;)
書込番号:5602255
![]() 0点
0点
http://nekoant.at.webry.info/200611/article_6.html
一回目は分かりにくい被写体だったので別のものも載せました。オート比較のご参考に。
露出1/3はそのうち試してみます。ダイナミックレンジというより一眼にありがちな白飽和を抑える機能があるのかもしれません。以前試したSANYO MZ1の「ダイナミックレンジ拡大モード」の画質に似ています。
デジカメメーカーみたいに記事を小出しにしようと思ったのに。ネタが…(^^;
書込番号:5602453
![]() 0点
0点
> ネタが…(^^;
ありゃ! 無理やり引き出しちゃいましたかネ?(^^;;)
--------------------
N2、白ピークの扱いを上手にまとめているようですね。
感心しました(^^;)
書込番号:5603109
![]() 0点
0点
ムーンライダーズさん くろこげパンダさん
お呼び名の件、スミマセンでした。
以後は心の中だけにとどめます(笑)。
ねねここさん
色々ネタ提供?スミマセン。
いずれにせよ、実写画像でいい感じかどうか、という点について、
N2は結構良さそうだ、というのがボクの正直な感想でございます。
細かなところの追究はそれ自体楽しいからしているだけで、
決してアラ探ししようというのではありませんので、ご了承いただけるとうれしいです。
書込番号:5604425
![]() 0点
0点
ネタは新鮮なうちが美味しいのでいいんですが。
ちなみに、BLOGにマニュアル夜景の見本も追加しました…
書込番号:5608463
![]() 0点
0点
ねねここ さん
その夜景は、ダイナミックレンジ拡大機能を使った撮影ですか?
-----------
mmode1.JPGの水面(左下)に、得体の知れないものが
写ってますね(^^;恐)
書込番号:5608478
![]() 0点
0点
ねねここさん、はじめまして。
N2はサンプルが激しく少ないのでありがたく拝見させていただいてます。
ちょっと不思議に思ってるのですが、N2のダイナミックレンジ拡大は「機能」(設定等で切替可能?)なんでしょうか?
メーカーHPを見る限り機能というよりは新型CCDの特性と理解していましたが・・・
あとISOオートではどこまで増感されるのでしょうか?
書込番号:5608615
![]() 0点
0点
ダイナミックレンジ拡大機能というと切り替えかと思っていましたが、どこにも設定が見あたらないので、おそらく自動でやっているかもしれません。
みひゃえるさんがおっしゃるように、CCDの受光量が上がったので、新しいCCDの機能の名称だと思います。いつ、どの程度かは実際分かりませんが急な白飛びは少ない印象です。すごく効いている。というよりよく粘っている感じです。
ただ、大きく効いた場合は、白い自動車(ダイハツ ラパン)の様にコントラストが低く見えますから階調がある分、一眼のRAWデータ的に見栄えは落ちるのかもしれません。
>くろこげパンダさん
東京湾に怨念がおんねん…と思いましたが他にも写っているのでビニールのゴミみたいです(^^;
>みひゃえるさん
オートでは他機種と同じようにISO320のようです。ただ、何となくですが、W30と比べるとISOの上がりがスムーズな気もします。なんとなくです。
高感度モードでは自動でISO1600まで上がります。富士のF10と同じで1/100秒に保とうとします。蛍光灯1灯の部屋で試すとISO800やISO1000が多いようですので、無理にISO1600にしない感じです。まだ、検証中ですが…
書込番号:5608961
![]() 0点
0点
F10でもF30でも白ピークは粘らないので(F30はF10よりは多少改善されている気もしますが)、露出は常に多少抑えめを心がけざるを得ず、そうするとシャドーは沈みすぎ、写真全体として暗っぽくなる、というのが悩みの種なので、レンジが広いのはうらやましいです。
それにしてもN2、個人的にはまったくノーマークだったのですが、相当良さそうですね。
他の1000万画素機は、600万画素と比較してもそう変わらないじゃないか、という印象でしたが、このカメラの精細度はちょっとビックリしました。
その上レンジが広くて、高感度も良いとなると、ちょっと隙がない感じです。
ソニーは外に売っているのと自社で使っているので、CCDを差別化している? のでしょうか(^^;?
書込番号:5609016
![]() 0点
0点
SONYはDSC-S85の時にも14bit A/Dコンバーターで白飛びしにくいことをうたってましたけど
結局トーンカーブ、とくにハイライト側を寝かせて眠い画像になっただけだと記憶しています、
最近で言えばZ1000もかなり眠い感じになりますね。
各社1000万画素になってピクセル等倍でのぱっと見の画質より本質的な画質に向かっているようですね。
※眠い画像はほめ言葉です。
書込番号:5609030
![]() 0点
0点
F10で、露出ずらしした画像をチェックしてみましたが、
-1/3EVで間に合うときもあれば、-2/3EVでも足りない
時もありました。N2のダイナミックレンジ機能は、露出
とトーンカーブ処理だけの話ではないのでしょうかネ?
どういう原理なんだろう? > N2
ユーザーインターフェースといい、独自性の多いカメラですネ(^^;)
書込番号:5609296
![]() 0点
0点
パソコンで写真を見る限りRGB各色256階調で、それはすなわち黒潰れ(シャドー側)から白とび(ハイライト側)までの間を各色は256分割しているわけで、
そうすると黒潰れから白飛びの間をガンマカーブもなしで当分割していればCCDのダイナミックレンジの差がそのまま画像のダイナミックレンジの差となりますが、
現実は絶対的にトーンカーブをいじってくるわけで、そうすると256分割する際も均等に分割するのではなく分割点によっては粗に分割されたり、密に分割される部分が出るわけで、
結果、パソコンで見る画像で「CCD」のダイナミックレンジを語ることは出来ないというのが事あるごとにいわれています。
逆に言えば、出てくる画像を見てどこが疎になっていてどこが密になっているのか?という議論は出来るわけです。
FUJIFILMのZ1/2/3やF10/11/30シリーズはハイライト側とシャドー側はこの分割点が疎になっていて、中間調の中でも人肌のあたりが密になっているといえるでしょう、
逆にN2やZ1000等の画像を見ているとハイライト側は結構密になっている印象を受けます。
前述の「14bit A/D変換」とか、今回の「ダイナミックレンジ拡大機能」等の言葉は技術的な側面よりも、いかにもすごい技術ですよと宣伝に使うための言葉で昔からSONYが良く使う手ですし、
そこには「白飛びを抑えてハイライト側の階調表現を改善したロジック」にどんな名前をつけようか?とSONYが相当悩んだのでは?と見ることも出来ます。
最終的には各色256階調の中でダイナミックレンジをどう拡大するの?という話になるのでメーカーの言葉に惑わされないのが肝心ですね。
書込番号:5609376
![]() 0点
0点
@ぶるーとさん
>>ソニーは外に売っているのと自社で使っているので、CCDを差別化している? のでしょうか(^^;?
多分ですが、ソニー製1/1.8型1000万画素は、実搭載はN2が初だと思ってます。
N1も1/1.8型800万初搭載機で、同じCCDが他社機にのったのは数ヶ月後でしたし。
正直言ってCCDの素性も結構良さそうですよね。
迷わずこれを購入されるねねここさんはさすがですね。
書込番号:5609384
![]() 0点
0点
[5609376] 適当takebeatさん
お説、よく判るのですが、フジのSR素子だと、ハードウェアを利用
して階調データの確保をしていますが、あれと同じ事は 『露出+トーン
カーブ』では出来ないですよネ。何故なら、SR素子はハードレベル
(=アナログレベル)では黒潰れの弊害を出さないからです。
要するに、N2は 『純粋にソフト処理だけなのか?』 と
いうところが興味の対象です(^^;)
階調をどう畳み込むか?(どこを蜜にするか?)という点では、
お説の通り、方式に関わらず共通した問題だとは思います(^^;)
書込番号:5609436
![]() 0点
0点
補足
>> SR素子はハードレベル(=アナログレベル)では
>> 黒潰れの弊害を出さないからです。
↑原理上の話です。実状(優位性)となると、もう少し話がややこ
しくなります。HRで作れば、素子1個あたりの受光面積が大きく
できるでしょうから、低ノイズになった分、アンダーに撮っても、
黒潰れには強くなるかも知れません。
どっちが有利かは、想像の域を出ませんですが・・・(^^;)
輝度レンジが広い被写体では、SRの方が有利そうにも思え
ますが、輝度レンジが狭い被写体の時は、ただの低感度カメラ?
になってしまう事になるのでしょうかね?(^^;) > SR素子
------------
話が脱線気味にでスイマセン m(_ _)m(^^ゞ)
書込番号:5609493
![]() 0点
0点
富士のSR素子は面白いですね、一回の撮影でアンダーとオーバー二回撮って合成しているようなものですから、
それでもカメラ内部でSR画素の合成に飽き足らずご自分でSR素子の合成バランスを調整できるRAW現像ソフトを作られた方をどっかで見かけたような記憶があります。
SONYの1/1.7型1000万画素CCDはSONYに先駆けてCASIOのZ1000が搭載していますね、
サイズ表記は「なぜか1/1.8型」と発表当初から言われていましたが、
CCD自体のダイアミックレンジがあがっていればそれはZ1000にも同じことが言われるわけで、
そう思えばZ1000が意外にハイライト側の階調表現がうまくていい感じに眠い画質だったのもなるほどと思えます。
ところで、
http://www.sony.jp/products/Consumer/DSC/DSC-N2/feat1.html
このページの「ダイナミックレンジ領域の比較、ヒストグラムイメージ」は完全に説明不足ですよね、
これを素直に解釈するとあきらかにRGB各色256階調と言う枠をはみ出てRGB各色300階調くらいになっています(^_^;)
書込番号:5609585
![]() 0点
0点
あ、すいません、
Z1000のCCDはシャープの可能性が高いですね、
どっかで頭がこんがらがってました(^_^;)
書込番号:5609896
![]() 0点
0点
>ken311さん
いや、ken311さんがFUJI板の方にN2がいいって書き込みをされていたので、こっち覗いてみたんですよ。
思った以上でした。
コンパクトのSRはもう一回復活してほしいですね。間違いなく買いますから。今だと500万+500万で1000万画素か、600万+600万で1200万画素とかになるのでしょうか?
ただ、くろこげパンダさんが指摘されていますが、SRの潜在能力は過剰性能とも言えると思うので、トーンカーブ処理だけでも何とか出来るのであれば(ノイズが浮いたりしなければですが)パラメーターをある程度可変にして、設定できるようにしてくれればそれでもいいです。
というか、今ならN2を買え、ということなのかもしれませんが。
書込番号:5610023
![]() 0点
0点
素人考えですが,CCD自体のダイナミックレンジというのは,デジタル段階での階調化に関係なく,アナログ出力の段階で評価できるのではないでしょうか.つまりダイナミックレンジの上下限界とは,ある値以上(以下)の輝度では輝度差が分別不能になるということであり,両限界の差が広ければダイナミックレンジが広いということではないでしょうか.
書込番号:5610188
![]() 0点
0点
CCDのダイナミックレンジのについては私も昭和1桁さんと同じ考えでそれが定説でしょう、
しかしJPEG出力しかないカメラでは画像処理した画像しか見ることが出来ないのでCCDのダイナミックレンジが広いか否かはユーザーに判断できるすべがありません、
「CCDのダイナミックレンジ」と「出力された画像のダイナミックレンジ」の関連性は通常の撮影ではわからないでしょうね、
それがわかる画像があるのかなぁ?と、もし知っている方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください、
その辺非常の興味がありますので。
書込番号:5610261
![]() 0点
0点
>http://nekoant.at.webry.info/200608/article_27.html
これはハイとローの2枚を撮って合成するSANYO MZ1の写真ですが、N2も何となく似ています。MZ1のダイナミックレンジ拡大モードはCCDのダイナミックレンジをフルに使うわけではなく80%だけとかをハイ側とロー側に移動させ、1回のシャッターで撮った2枚の画像を合成するようです。
N2のCCDはあまり移動させずに必要なときにハイ側が広げられるのかもしれません。実際は画素数が増えた分CCDへの光量が減るわけですから、それをおぎなえるCCDの感度にでき、その上で画像エンジンが今まで切り捨てざるを得なかった数パーセントを使えるのかもしれません。
富士のS3Proでも通常撮影のDレンジ/スタンダードは、400%の中の100%しか使わないようですので、絵になる写真は必ずしもCCDのダイナミックレンジをすべて使わなくてもいいからのような気がします。個人的にですが…
>ぶるーとさん
N2は買うと昼間のF30の露出補正の手間が少なくなるので、はまったらまずいです。F30はノーマル補正で一番透明感がある画像なのでそこは残念ですが、使用用途にはダントツなのは間違いないです(^^;
>Ken311さん
株と同じで、ハイリスクorハイリターンでしょうか(^^;
書込番号:5610349
![]() 0点
0点
適当takebeatさん
それを伺って安心しました.前のコメントに
>最終的には各色256階調の中でダイナミックレンジをどう拡大するの?という話になるのでメーカーの言葉に惑わされないのが肝心ですね。
とありましたが,トーンカーブをいじることは既に各社とも最善を尽くしているはずですので改善には限度があると思います.よって本製品のダイナミックレンジが有意差をもって良くなっているのであれば,メーカのいうようにCCDが改善されている可能性は大きいと推測します.
書込番号:5610385
![]() 0点
0点
MZ1はプログレCCDなのでほぼ一瞬で二コマ撮影することが出来ますが、N2の場合そのような手段ではなく、CCDの基本性能をアップしていると読めますね、
http://www.sony.jp/products/Consumer/DSC/DSC-N2/feat1.html
ただ、これも言葉のマジックがあり「従来機比59%アップ」とはどのような比較をしたのかが非常に興味があります、なにせ同じサイズと画素数のCCDのデジカメは無かったわけですから、
たとえば、Z1000に搭載されているであろうシャープのCCDは
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/051101-a.html
「1000万画素でも800万画素と同じ感度」といっていますが、
もしこれを宣伝文句に使うならば逆説的に使って「800万画素の技術のままで1000万画素を作れば感度は落ちる、これをベースと考えれば感度が従来比**%アップと宣伝しても嘘じゃないだろう」となるわけです。
書込番号:5610406
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
どんなにダイナミックレンジの広いCCDがあっても、
最終的には各色256段階に押し込めるしかないのでハイライト側に階調を持っていったらその分他の部分にしわ寄せが来ます。
そしてもし今回256階調をきちんと使い切ったのであれば、以前は256階調使い切ってなかったわけで、
そして従来普及タイプのデジカメの画像はわざとハイライトを希薄にしてシャドーを均一にする傾向があったのでそうなのかもしれませんが。
N2がダイナミックレンジを意識した結果眠い画調になったのであれば、それはCCDのダイナミックレンジがきっかけなのかもしれません。
書込番号:5610595
![]() 0点
0点
適当takebeatさん
>そしてもし今回256階調をきちんと使い切ったのであれば、以前は256階調使い切ってなかったわけで
今回も以前も,それなりに256階調をきちんと使い切っているが,今回はCCD自体のアナログダイナミックレンジが改善されている,とは考えられませんか.
書込番号:5610633
![]() 0点
0点
CCDのダイナミックレンジの拡大が実画像にも良い結果を与えたと考えてもいいのですが確認する手段が無いのです。
そこで
>>しかしJPEG出力しかないカメラでは画像処理した画像しか
>>見ることが出来ないのでCCDのダイナミックレンジが広いか
>>否かはユーザーに判断できるすべがありません、
>>「CCDのダイナミックレンジ」と
>>「出力された画像のダイナミックレンジ」の関連性は
>>通常の撮影ではわからないでしょうね、
>>それがわかる画像があるのかなぁ?と、
>>もし知っている方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください、
>>その辺非常の興味がありますので。
この発言になるわけです。
書込番号:5610676
![]() 0点
0点
CCD自体が良くなっていることを確認する方法は私には分かりません.ただ改善の方法がCCDであろうとデジタル手段であろうとユーザにとっては結果さえ良ければよい訳ですから,メーカが嘘をついてまでCCDと説明しなければならない理由はないと思います.従って反証がない限り,素直にメーカの説明を受け止める方が妥当ではないでしょうか.
書込番号:5610840
![]() 0点
0点
メーカーは稀に嘘をつきます、そしてそれ以上にわざと誤解を招くあいまいな表現を多々使います。
つまり今回の件に限って言えば、
たとえば八割がたは画像処理でハイライト側の表現を改善したとします、
しかし画像処理でよくなったというよりCCDのおかげでよくなったといった方がより高い宣伝効果があれば画像処理の方は伏せておいてCCDの改良とハイライト側の表現の改善を結びつけたPRをします。
もちろんこれは嘘ではありませんが、真実でもありません。
つまりこれが
>>メーカーの言葉に惑わされないのが肝心ですね。
となります。
さて、肝心のN2の画質の話ではなくなったのが心苦しいので私の発言の解説のための発言(^_^;)はこの辺にさせていただきたいと思います。堂々巡りになりますので。
書込番号:5611046
![]() 0点
0点
そのソニーの説明は、単に CCD の飽和出力電圧が 59% アップしたということではないのでしょうか。
同じ画素ピッチでも、世代で飽和出力電圧が向上することはあるようです。感度はなかなか上がらないみたいですけど。
書込番号:5611371
![]() 0点
0点
カシオの Z1000 とペンタックスの A20 は、動画が 25f/s です。やっぱりシャープ製かな、と思うのですが、
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/051101-a-2.html
1037万画素、とは書いてませんね。
書込番号:5611415
![]() 0点
0点
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/link/ccd.htm
ペンタックスはSONYかもしれませんが、CASIOは可能性が低いんですよね。
飽和出力電圧が 59% アップだとしても比較対象はなんでしょう?
書込番号:5611456
![]() 0点
0点
確かに比較対象が無いですね。他社との比較をするわけないし。
N1 の CCD としても説得力無いですしね。
59% と数値化できる要素は飽和出力くらいしかないように思ったので。
A/D 後の出力を RAW のビットにどのようにマップするかは各社それぞれらしいですが、Gセンサーの飽和出力をフルビットにすれば飽和出力アップ分はデータとして生きますよね。
従来機と同じ露出で撮るなら、従来は白飛びしていた部分がデータ的に白飛びしなくなる。
従来機で白飛びしないシーンでは露出を(従来機比)オーバー目にすればノイズが減る。
もちろんそのデータをどう生かすか(どう料理するか)は腕の見せ所でしょうが、α100 のダイナミックレンジオプティマイザーのような処理(明暗にわけたマスク処理と推測)でなければ、出てくる画像はやはり眠くなる部分はあるのでしょうね。
上の方でサンヨーのダイナミックレンジショットが例に上げられていましたが、あれは二回露光しているので、フォトショップの HDR 機能に類似すると思います。
ダイナミックレンジショットは眠くなるのもさることながら、青空の色がマゼンタになるので私には使えない機能でした。
書込番号:5611715
![]() 0点
0点
59%のダイナミックレンジ改善というのは結構大きな改善で,それを256段階にどう配分しようと可成りの改善が期待できます.私はSonnyの説明を素直に受け止めたいと思います.
書込番号:5611902
![]() 0点
0点
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200609/06-0911B/
3.ダイナミックレンジ拡大※2
直射日光下での撮影時などに有効な「ダイナミックレンジ拡大」機能を搭載。CCDが受け取る光量を調整し、CCDの持つダイナミックレンジを最大限まで使うことができるようになりました。従来機種「DSC-N1」と比較して約159%のより幅広い色再現性を実現しました。
※2) 「ダイナミックレンジ拡大」は、ISO160以上で作動します。
のようです…
書込番号:5612408
![]() 0点
0点
ねねここさん参考になります、
プレスリリースのときと商品のカタログ的なサイトで表現が違うのがわかりました。
プレスリリースの書き方ではCCDのダイナミックレンジがあがっているのではなく、
それまでは感度が上がったときには十分に生かせていなかったCCDのダイナミックレンジを、
今回露光の仕組みを改善して生かせるようになったと読めます。
その結果、感度が上がったときの画像のダイナミックレンジがN1に比較して159%になったと。
確かに感度が上がると階調が減るデジカメも多いので、多少感度が上がってもそれまで以上に階調が残るようになるのは正しい進歩の方向ですね。
一般的に感度を上げるとハイライト側の階調が不足気味になるので感度が上がったら相対的に露光量を減らすした上で画像処理をしているのかな?
でもそうするとこんどはシャドー側が厳しくなりますね。
今回の件を頭に入れて改めてN2の画像拝見させていただきます。
書込番号:5612530
![]() 0点
0点
> ※2) 「ダイナミックレンジ拡大」は、ISO160以上で作動します。
ということは、
高感度 = 露光時間が短くなる。
= 飽和していない領域が増える。
= 白ピーク位置を見直す。
= サンプリングビット数を上げて、捨てていた部分を利用する。
= 眠くならないようにトーンカーブや階調の畳み込み方を見直す。
という方法なんでしょうかネ?(^^;)
書込番号:5612560
![]() 0点
0点
補足
>> = 眠くならないように・・・見直す。
感度指標(感度値)も満たさせないとイケナイですよネ。
中間調からハイライト側にかけて、今まで以上に階調が
密になっているのかも知れませんネ?
書込番号:5612578
![]() 0点
0点
>みひゃえるさん
前回の答えは間違ってました。すいません。
暗めの場所でオートでは最高ISO400に増感するようです。ちょっと嬉しい誤算でした(^^;
書込番号:5613673
![]() 0点
0点
toねねここさん
すみません、気を使わせてしましましてm(_ _)m
とりあえずN2購入しました。
書込番号:5613991
![]() 0点
0点
高感度時に露光量を減らせば高感度でなくなるので無意味だし,ダイナミックレンジの拡大にもなりませんね.以下は私の憶測です.
HPではCCDの受光量「ダイナミックレンジ」と表現しているので(ちょっと変だが),露光量を減らすのでなく,CCDのダイナミックレンジを目一杯広げるか,狭くするかを切り替えているのではないかと思います.つまり
>直射日光下での撮影時などに有効な「ダイナミックレンジ拡大」機能を搭載。CCDが受け取る光量を調整し、CCDの持つダイナミックレンジを最大限まで使うことができるようになりました。従来機種「DSC-N1」と比較して約159%のより幅広い色再現性を実現しました。
※2) 「ダイナミックレンジ拡大」は、ISO160以上で作動します。
において,「CCDが受け取る光量を調整」というのは,ダイナミックレンジの調整ではないかと思います.ISO160以上ではダイナミックレンジを最大限に利用するが,ISO160未満では白飛びが起きないので狭くする.敢えて狭くする理由は,被写体のダイナミックレンジが小さい場合はCCD出力のダイナミックレンジも狭い方が256段階に情報を有効に割り当てられるのではないでしょうか.
書込番号:5615189
![]() 0点
0点
「CCDが受け取る光量を調整」
これが正しい日本語であれば、CCDに入る光の量を調整することになります、
CCDに入る光の量を調整できるのはシャッタースピードと絞り、もしくはNDフィルターなど物理的な手段しかありません。
書込番号:5615233
![]() 0点
0点
仰るとおり変な日本語ですが,
http://www.sony.jp/products/Consumer/DSC/DSC-N2/index.htmlでは,
>CCDの受光量「ダイナミックレンジ」が、約59%もアップ(従来機比)。
と表現していますので.
書込番号:5615459
![]() 0点
0点
補足しますと,Sonyの日本語によれば,
CCDの受光量=ダイナミックレンジですから,
「CCDが受け取る光量を調整」=「CCDの受光量を調整」=ダイナミックレンジの調整
となります.
書込番号:5615520
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
> 高感度時に露光量を減らせば高感度でなくなるので無意味だし,
> ダイナミックレンジの拡大にもなりませんね.
> 「CCDが受け取る光量を調整」=「CCDの受光量を調整」
> =ダイナミックレンジの調整
後の引用部は、露光量を減らす事を仰っておられます。
話が矛盾されていらっしゃいますよ(^^;;)
----------------------------
高感度の仕組みについて誤解があるようです。
基礎感度より上の高感度は、もともと、露光不足で撮影したもの
を増幅(ストレッチ)してツジツマを合わせているので、高感度の
正体は、露光量を減らす事と後処理での増幅(=レベルの見直し)
の両方による擬似的なものと考えれば良いと思います(^^;)
基礎感度として扱うか、高感度として扱うかは、その後の信号処理
のあり方の問題であって、受光素子自体は常に受動的(パッシブ)
状態のまま、いつも同じ使い方であるとお考え下さい。
絞りやSSで露光量を変え、得られた信号(撮像信号)を、どの感度
として処理するかを、予め決めてあった通りに(=撮影した露光量
に合わせて)処理しているだけなんですネ。
書込番号:5615703
![]() 0点
0点
被写体の輝度域が広い場合は、露光量を減らしても白飽和は起こり
えます。露光量を減らしても、被写体に高輝度領域がある限り、F値
やSSによる抑制でも間に合わなくなる部分が残るからです。
高感度では、基礎感度に対しての比較なら、その(CCDで)飽和する
領域は少なくなります。露光量を減らしているのですから当然です。
そうすると、基礎感度では飽和していた領域が、高感度では階調と
して現れてきます。従来なら、この部分を捨てていた(?)ところを、
高(多?)ビットのサンプリングを活かして、データとして確保でき、
出力データ上(ビットマップ上)に再配置しなおせば、白ピーク付近
の階調を再現することが出来ます。
但し、グレーレベルの基準点は、感度指標上、同じ明るさにしておく
必要があるでしょうから、グレーの中間点から白側に階調を詰め込む
事になると思われます。
N2のダイナミックレンジ拡大機能を、このように推察してみた訳です(^^;)
書込番号:5615717
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
誤解があるようですね.私は露光量を減らすことは一切言っていません.むしろ
>「CCDが受け取る光量を調整」=「CCDの受光量を調整」 =ダイナミックレンジの調整
と書いたのは,Sonyの説明にある光量を調整というのは,露光量を減らすことでなく,CCDのダイナミックレンジを調整することではないかと言っているのです.
あと「高(多?)ビットのサンプリング」云々がよく分かりません.CCDの話に限ればアナログ素子ですから・・・.
書込番号:5616219
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
>基礎感度として扱うか、高感度として扱うかは、その後の信号処理のあり方の問題であって、受光素子自体は常に受動的(パッシブ)状態のまま、いつも同じ使い方であるとお考え下さい。
CCDはアナログ増幅機能も含んでいると考えてよいですか.またN2のCCDはダイナミックレンジ拡大のON/OFF機能(ISO160以上か否か)があるようですが,それも含むと考えて良いですか.
書込番号:5616402
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
適当takebeatさんが仰るように、CCDが受光する光量の調整方法は
限られていますし、何れも露光量の調整に該当するものです(^^;)
昭和1桁さんが取れる、残されたお説は、素子そのものの改善
ぐらいしか考え難いです。
それと、
> 高感度時に露光量を減らせば高感度でなくなるので無意味だし,
> ダイナミックレンジの拡大にもなりませんね.
↑コレが、何を言わんとするのか意味不明です。高感度撮影の
原理が理解できていらっしゃるのか、疑問を感じました(^^;;)
------------------
> CCDの話に限ればアナログ素子ですから・・・.
> CCDはアナログ増幅機能も含んでいると考えてよいですか.
> またN2のCCDはダイナミックレンジ拡大のON/OFF機能(ISO160
> 以上か否か)があるようですが,それも含むと考えて良いですか
どのような方法が取られているかは判りかねますが、信号は
アナログあっても、増幅やダイナミックレンジのコントロールは
デジタルでも可能です。
高感度化の方法は、(原理的に)アナログで増幅する方法もあれば、
広範囲で高密度なデジタルデータを作成しておき、データの再配置
と切り捨てをする方法でも可能です。どちらでしているのかは存じま
せんが、後者の方法が、コストや画像処理の点で効率が良いと思い
ます。
-------------------
高ビットのサンプリング(=広範囲で高密度なデータが作成できる)を
すれば、今まで捨てていた領域を利用できる可能性が出てきます。
ですから、高感度撮影時のように、露光量を抑えた事で出現した白階
調部分を捨てることなく、活かす事ができ、その使えるようになった領
域を59%としてアピールする事もできるだろうと思います。
書込番号:5616502
![]() 0点
0点
「露光量」という言葉の使い方に、くろこげパンダさんと昭和一桁さんで違いがあるのだと思います。
くろこげパンダさんのおっしゃっている「露光量」は絶対値で、例えば1/250秒 F2.8は1/125秒 F2.8の1/2の露光量、ということを言っています。ISOは関係ありません。
昭和一桁さんのおっしゃっている「露光量」は相対値で、ISO100 1/125秒 F2.8と、ISO200 1/250秒 F2.8はイコールだという認識なのではありませんか?
実際問題、CCDというのは単なる光の受け皿、まあ、バケツのようなものなので、絶対的な露光量が1/2なら、溜まる光の量(現実には光電変換された電子ですが)も1/2となります。
それがアナログアンプによって(くろこげパンダさんによるとデジタルでもいいようですが)、ISO100よりISO200は2倍に増幅され、同じ明るさになる、という流れですね。
バケツの側から見ると、ISO200の時には絶対的露光量は1/2になるので2倍の余裕が出来、ISO100の時にはバケツから溢れてしまっていた(飽和してしまっていた)光も受け止めることが出来るわけで、この部分をもったいないから活用しよう、というのがN2の考え方なのではないですかね?
書込番号:5616565
![]() 0点
0点
@ぶるーとさん
> ISO100の時にはバケツから溢れてしまっていた(飽和してしまって
> いた)光も受け止めることが出来るわけで、この部分をもったいない
> から活用しよう、というのがN2の考え方なのではないですかね?
そのように、推察してみたわけです。
いつもながら、判り易くて簡潔ですね〜(^^;恥)
結局、ISO160は、『基礎感度(ISO100)+ダイナミックレンジ拡張』
の処理により出来上がった感度値という事ではないでしょうか?
だから、ISO160以上で常時ONなのでしょうネ?
----------------
ちなみに、露光量にISO値を持ち込んだら、
露出値になっちゃいますよね?(^^;)
書込番号:5616750
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
>コレが、何を言わんとするのか意味不明です。
私の意見と直接関係ありませんので無視してください.
>どのような方法が取られているかは判りかねますが、信号はアナログあっても、増幅やダイナミックレンジのコントロールはデジタルでも可能です.
>高感度化の方法は、(原理的に)アナログで増幅する方法もあれば、広範囲で高密度なデジタルデータを作成しておき、データの再配置と切り捨てをする方法でも可能です。どちらでしているのかは存じませんが、後者の方法が、コストや画像処理の点で効率が良いと思います。
広範囲で高密度のデジタルデータを作成するには,ADCの入力電圧がある程度大きいことが不可欠です.よってSonyだけでなく一般にアナログで増幅しています.その前提でないとCCDの機能の話は現実的でありません.
>高ビットのサンプリング(=広範囲で高密度なデータが作成できる)をすれば・・・
現にN2のCCDで行っている方法を推測したいと思います.
@ぶるーとさん
露光量については無視してください.
>バケツの側から見ると、ISO200の時には絶対的露光量は1/2になるので2倍の余裕が出来、ISO100の時にはバケツから溢れてしまっていた(飽和してしまっていた)光も受け止めることが出来るわけで、この部分をもったいないから活用しよう、というのがN2の考え方なのではないですかね?
そうかも知れませんが,実際には白飛びは高感度の時に起きやすいのではないでしょうか.だから高感度時にダイナミックレンジの拡張が必要と理解していたのですが.
書込番号:5616959
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
> 広範囲で高密度のデジタルデータを作成するには,
> ADCの入力電圧がある程度大きいことが不可欠です.
> よってSonyだけでなく一般にアナログで増幅しています.
> その前提でないとCCDの機能の話は現実的でありません
アナログ増幅していないとは、言ってないですよ。
『CCDがアナログなんだから・・・』という事を仰ったから、そのこと
自体は、今回のテーマの原理を考える(推察する)上で、懸案事項
にはならないという事を説明するために、デジタルでの増幅やダイ
ナミックレンジをコントロールする方法を示しただけです。
ADコンバーターの動作点(スイートスポット)を確保するために
アナログ的に増幅することは有り得ると思います。
※ 要は、増感のための増幅をどこでしているかが問題のハズです。
アナログ+デジタルなのか、アナログオンリーなのか、デジタル
オンリーなのかは、判らないハズですが・・・。
-----------------
『CCDがアナログなんだから・・・』 と主張なされても、ダイナミック
レンジ拡大機能がアナログ部分のみでの改善で果たされていると
する、『唯一無二の推論』 とはなり得ないです。その事を理解して
頂く為の説明をしたに過ぎません。> デジタルでの増感方法
そもそも
> 高感度時に露光量を減らせば高感度でなくなるので無意味だし,
> ダイナミックレンジの拡大にもなりませんね.
↑この文言は誤りですよ。この発言を無視したままでは、
話が噛み合わないですよ。
増感の実態は、露光量を減らすことで高感度としているのです。
書込番号:5617220
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
今の議論はSonyのCCD改善の説明を正確に理解することですから,アナログだけで話を閉じることが出来るはずです.デジタルの例を持ち出された趣旨は分かりましたが,現実にはないシステムの話が突然出てきて,私にはチンプンカンプンでした.
>↑この文言は誤りですよ。この発言を無視したままでは、
話が噛み合わないですよ
これは適当takebeatさんの
>一般的に感度を上げるとハイライト側の階調が不足気味になるので感度が上がったら相対的に露光量を減らすした上で画像処理をしているのかな?
でもそうするとこんどはシャドー側が厳しくなりますね。
に対するコメントの積もりで書きました.適当takebeatさんに失礼なのでこれ以上追求しないで下さい.
@ぶるーとさん
私の誤解に気が付きました.高感度時に白飛びが多いのは,バケツが溢れるからでなくバケツに余裕があるのにアナログ出力が制限されるからですね.
ところで,CCDのダイナミックレンジが切り替えられるということは,飽和出力電圧が例えば1vと1.59vというように2通り(低感度時と高感度時)になるということでしょうか.これが正しければ私にとって疑問はほぼなくなります.
書込番号:5617950
![]() 0点
0点
>くろこげパンダさん
私の場合、例えばくろこげパンダさんの説を下敷きに、ロムってる方に分かりやすいであろう例え話を作っているだけなんですよ。
一応文系なので、それが出来ないと存在価値が(^^;・・・
アナログとデジタルの話ですが、とりあえず話を単純化するため、
CCD→アナログアンプ→A/Dコンバーター
という風に信号が流れていくとするなら、今までの話の流れからして、CCDは完全に受動的であるので、それ自体のダイナミックレンジは一定で変わらず、アナログアンプも単純な増幅器であるため、それ自体でダイナミックレンジ拡大に寄与するものではない、と考えた方がいいのではないでしょうか?
そうすると問題はA/Dコンバーターの部分で、ここでサンプリングが行われ、アナログ信号がデジタルに変換される訳ですが、その際に今までは、高感度での撮影の際、実際には有意信号であるのに切り捨てられていた部分(バケツの余裕の部分ですね)があったのを、N2ではその部分まである程度サンプリングして白ピークに粘りを持たせるために活用している、ということなのではないでしょうか?
書込番号:5618192
![]() 0点
0点
昭和1桁さんが私に失礼かどうかを考える必要はありません、
自身の発現にぜひ責任を持ってください。
私はプレスリリースと製品サイトの文言の違いがわかった時点でメーカーに問い合わせ中ですのでくろこげパンダさんの考察を読みながらメーカーからの返答があるまで色々考え中です、
書込番号:5618201
![]() 0点
0点
と書いた矢先に
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5615986
こちらのスレッドで紹介された写真を元に京都のおっさんさんが見事な考察をされています。
露出を抑えて中間から下を持ち上げているとすれば私の稚拙な考えも的を射ていたのではないか?とも思えます(^_^;)
書込番号:5618261
![]() 0点
0点
@ぶるーとさん
アナログアンプはCCDに内蔵されていても外にあっても本質には関係ありませんが,アンプ後の出力電圧を1vと1.59v(例えば)の2通りの上限でカットする機能も必要かと思います(しないと後の処理に差し障ると思います).ADCは許容入力電圧に注意すれば単に接続するだけでOKだと思います.厳密には所用ビット数を増やす必要がありますが,Sonyお得意の14ビットADCなら充分でしょう.
書込番号:5618537
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
> 現実にはないシステムの話が突然出てきて,
N2のダイナミックレンジ機能の仕組みを推察しているのですから、
現実にあるかどうかの問題ではなく、現実に可能かどうかの話として
聞いてください。私が示した推察は、方法として可能だと思いますよ(^^;)
--------------
> 高感度時に白飛びが多いのは,( ・・・中略・・・ )
> バケツに余裕があるのにアナログ出力が制限されるからですね
アナログ出力が制限されるというより、適切な階調を得るための
振幅が失われて、同一のデータ値(RGB値)に化けてしまうん
だと思います。
高感度になるほど、ノイズの振幅が無視できなくなりますから、
階調データ化する段階で、ノイズの揺らぎのために、データ化に
必要な信号振幅が確保できなくなり、本来なら異なるRGB値に
なる画素群が、(ノイズの影響で)同一のデータ値に変換されて
しまって、白飛びと等価の状況を招くのだと思います。
高感度が飽和しやすいのではなく、誤変換を招きやすいから
そうなると考えれば、すべてツジツマが合うと思いますが・・・(^^;)
--------------------
アナログ段でノイズの振幅を抑え、高ビットで高密度なデータが
確保できれば、高感度撮影だからこそ、ダイナミックレンジを
確保する事ができ、N2の仕様にもマッチした推察になると思います。
実際がどうなのかは、やはり、判りかねますが・・・(^^;)
書込番号:5618610
![]() 0点
0点
補足
>> ノイズの揺らぎのために、データ化に
>> 必要な信号振幅が確保できなくなり、
電気に詳しくない人は意味が判らないでしょうから、補足します(^^;)
仮に信号電圧1.5Vに、+-0.1V幅の揺らぎを持つノイズが乗ると、
ADコンバーターが受け取る信号は1.4〜1.6Vの揺らぎを持つ
電気信号になってしまいます。
1.4Vの信号が1.5Vになった時にAD変換されたり、1.6Vが1.5Vに
なった時にAD変換されてしまう事があるわけです。本来1.4Vと1.6V
の信号値なのに、両方とも同一の1.5Vとして変換されてしまうので、
同じデータ値を取ることになり、階調差が失われるわけです。
書込番号:5618656
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
白飛びが起きるのは信号が大きいときで,しかもISO200といったノイズに余りシビアでない感度でも起きますから,雑音の影響は無視できないにしても一義的ではないと思います.
それよりバケツが溢れていない状態でアンプの利得を上げて行けば,バケツが溢れる以前に出力が飽和電圧の閾値を超える可能性は大と考えられます.その時は閾値を上げてあげよう(ダイナミックレンジを拡大)という発想が,Sonyの説明からは読み取れます.
書込番号:5618718
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
> しかもISO200といったノイズに余りシビアでない感度でも
> 起きますから,雑音の影響は無視できないにしても一義的
> ではないと思います.
一義的でないのはその通りですが、ISO200がノイズにシビアで
ないと考えるのは早計です。原理的には、1段増感は2倍に信号
レベルを増幅することになるのではないですか? なら、ノイズ
レベルも倍になりますよ。
(↑被写体上の白ピークを同じ所に設定した場合)
一義的な話をしているのは、その部分での原理を理解してもらう
ためです。要点を絞って話しているに過ぎません(^^;)
-----------------------
私が申し上げた、デジタル増幅によるダイナミックレンジ拡張機能は、
アナログ段階で2倍に増幅(←感度1段増感時)しないのです。
要するに、露光量低下で出現した新たな白ピークを上限値として
再設定してしまうので、増幅率を増感段数分必要としないのです。
ですから、電気信号増幅のクリップ限界や、ADコンバーターの
入力電圧の限界値においても、アナログ的手法でのみ増感しよう
とする方式よりも限界値に触れ難く、さらに、露光量が少ないため、
原理的には低感度より白ピーク確保に有利になるのです。
信号増幅をアナログ増幅のみに頼らないので、それらのクリップに
対しても、ボトルネックになり難いのです。
ただ、そのしわ寄せが、適当takebeatさんにご説明頂いたように、
『どこを蜜にするか?』 の問題となって現れてくるわけです。
デジタル部分で、増幅と等価のことが出来る事を理解して
頂けないと、話が錯綜するばかりですよ(^^;;)
書込番号:5618877
![]() 0点
0点
デジタル処理で増幅ができることは理解していますが,ご提案の原理が難しくてよく理解できません.一方Sonyが
>CCDの受光量「ダイナミックレンジ」が、約59%もアップ(従来機比)。
と説明している以上,アナログでダイナミックレンジを拡張していると考えた方が正解だと思います.こちらの原理はコロンブスの卵みたいに明快に理解できたと思っています.
書込番号:5619057
![]() 0点
0点
> ご提案の原理が難しくてよく理解できません.
orz (^^;;;)
@ぶるーとさんにバトンタッチ!(^^ゞ)
私には、昭和1桁さんの仰るダイナミックレンジ拡張法と
いうのが、どのようなものを想定なされていらっしゃるのか
よく判らないのですが・・・(^^;;)
----------------
話を、少し遡りますが・・・(^^;)
クリップレベルのお話も少しおかしいですよ。
感度を上げて行くという事は、露光量が減って行くことですから、
CCDが出力する電圧も下がるわけです。それを2倍しようが4倍
しようが、もとの信号が1/2や1/4になっているのですから、必要な
部分の信号レベルは、原則、クリップしない事になります。よって、
高感度にするほど階調が失われる事の原理説明にはならないです
よネ(^^;)
アナログアンプで増幅してもSN比は原理上変わりません。ですから、
アナログアンプで増感しようが、先にAD変換しておこうが、結局
信号のクリーン度は同じことなんです。要は、微小信号を正確に
デジタルデータにコンバートできるADコンバーターを用意して
おけば良いわけです。
書込番号:5619441
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
今ISO100でバケツが丁度一杯の時に出力電圧が飽和電圧の閾値に達するものとします.ISO200に設定するとバケツは半分になりますが,2倍に増幅するので同じく閾値に達します.
次にそれから入力光が強まった場合,ISO100ではバケツが一杯ですから出力電圧は上がりません.ところがISO200ではバケツに余裕がありますから,出力電圧は閾値で制限しなければ更に上昇します.故にISO200の時に閾値を高く設定すればダイナミックレンジが拡大できる訳です.
次に高感度時に白飛びが起きやすい理由はよく分かりませんが,一つの可能性として,低感度でバケツが一杯になる際,突然スパッと一杯になるのでなく,多くの自然現象に見られるようにだらだらと一杯になるのではないか.そうすると閾値への到達も若干ソフトランディングになっている可能性がある.ところが高感度でバケツの半分に達するのは当然ながらスパッと達する.よって高感度時の閾値到達は唐突である.
ダイナミックレンジの改善度が1.59倍といった曖昧な値になっているという事実は,上記のメカニズムが可成り曖昧性を含んでいることを物語る.よって高感度時の閾値到達と低感度時の閾値到達の実態がかなり曖昧なものであることが推察される.
>アナログアンプで増幅してもSN比は原理上変わりません。ですから、
アナログアンプで増感しようが、先にAD変換しておこうが、結局
信号のクリーン度は同じことなんです。要は、微小信号を正確に
デジタルデータにコンバートできるADコンバーターを用意して
おけば良いわけです
前にも書きましたが,アナログアンプをなくすと微小なアナログ電圧をAD変換することになり,これは殆ど禁止的だと思います.それにSonyの従来製品はアナログでやっていると思うので,敢えて改変はしないでしょう.
書込番号:5619844
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
私が申し上げた原理と同じ事を仰ってますよ(^^;)
しかも、増感に合わせて露光量を落としていないと
出来ない方式です。自説が完結なされていらっしゃいません。
------------
お説との相違点は、アナログ的に処理するかデジタル的に
処理するかの違いであって、真相は、互いに判らないですネ。
アナログ増幅がどの程度必要かどうかも、定かではないと
思います。それに、どちらの方式であるかは、ダイナミック
レンジ拡張機能を考えるにあたって、懸念する必要のない項目です。
-------------
白トビの仮説はあまりに荒唐無稽ですから、コメント
できませんです(^^;)私が申し上げた、高感度時の
白飛び現象は、原理上、起こり得ることです。
--------------
> アナログアンプをなくすと微小なアナログ電圧を
> AD変換することになり,これは殆ど禁止的だと思います.
↑ これ推測でしょ?
サンプリングビット数が増えたら、微小な電圧ステップを
扱う事になるので、それに必要な電圧レベルがあるかどうか
の問題ですよ。先にアナログ的に引き伸ばしてしまったら、
高ビットサンプリングのADコンバーターは必要なくなるのでは
ないですか?(=14ビットも必要ないでしょ?)
もちろん、全く電圧増幅していないとは限りませんが、先にも
申し上げてきたように、原理には関係してこない懸念材料です。
書込番号:5620861
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
>私が申し上げた原理と同じ事を仰ってますよ
それなら結構ではありませんか.歩み寄れて嬉しいです.ただ私は何も変えていない積もりですが.
>お説との相違点は、アナログ的に処理するかデジタル的に処理するかの違いであって、真相は、互いに判らないですネ。アナログ増幅がどの程度必要かどうかも、定かではないと思います。
私はあくまでN2がどうなっているかを論じています.そしてN2が14ビットADCを使っている以上間違いなくアナログです.
>白トビの仮説はあまりに荒唐無稽ですから、コメントできませんです
正直私もよく分かっていません.しかし高感度のダイナミックレンジが拡大されれば大幅に改善されますから,最早過去の話ですね.
>サンプリングビット数が増えたら、微小な電圧ステップを扱う事になるので、それに必要な電圧レベルがあるかどうかの問題ですよ。
実際には非常に困難ですから,N2でやっている筈ありません.
>先にアナログ的に引き伸ばしてしまったら、高ビットサンプリングのADコンバーターは必要なくなるのではないですか?(=14ビットも必要ないでしょ?)
Sonyは在来機種で14ビット使って自慢の処理をしていますが,N2も14ビットといっています.従って余裕はせいぜい1ビットでしょう.
>原理には関係してこない懸念材料です
貴方が原理的にデジタルをお好みになる気持ちは分からないではありませんが,原理よりもN2がどうなっているかです.
書込番号:5620959
![]() 0点
0点
昭和1桁さんは結局CCD自体のダイナミックレンジが広がっていないことを納得したのでしょうか?
CCD自体のダイナミックレンジが広がったのではなく、
それ以降のロジックによりCCDのダイナミックレンジを有効活用できるようになったと。
書込番号:5621405
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
> N2が14ビットADCを使っている以上間違いなくアナログです.
> 実際には非常に困難ですから,N2でやっている筈ありません.
根拠をお持ちなのでしょうか? 示してください。
それに、既に申し上げた通り、アナログでの可能性を否定して
おりませんし、原理を考える上においては、どうでも良いファク
ターです。
ハイブリットでやる事だって出来ますよ。(アナ+デジ)
↑アナかデジか、考える必要が無い事の証拠です。
---------------
> N2も14ビットといっています.従って余裕はせいぜい1ビットでしょう.
出力画像は8ビット階調ですから、6ビットも余分に
持っている事になります。アナログで前処理されているなら、
6ビットも余剰分はいらないでしょ? この余剰分は一体、
何に使われているのでしょうか?
---------------
> 原理よりもN2がどうなっているかです.
お互い、推察でしかないのですから、N2がどうなってるかは
判らないハズです。原理を推察するしか、やり様がないです。
書込番号:5621710
![]() 0点
0点
補足
>> アナログでの可能性を否定しておりませんし、
『アナログ増幅が全くされていない』 とは
言っていないという意味(意図)です。
書込番号:5621721
![]() 0点
0点
適当takebeatさん
CCDの用語に何々を含めるか決めるかによりますが,要するにADCの入り口すなわちアナログ出力のダイナミックレンジが広がっていると思います.なお本機のリアル・イメージング・プロセッサの説明図ではCCDの直後にADCが接続されています.
書込番号:5624629
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
>根拠をお持ちなのでしょうか? 示してください
N2が14ビットであることは本機のリアル・イメージング・プロセッサの説明図に出ています.微小電圧の変換が困難であることは常識だと思います(データは手元にありませんので勘弁してください).仮に困難でなくとも,14ビットADCではアンプをデジタルで内蔵する余裕はありませんね.
>出力画像は8ビット階調ですから、6ビットも余分に持っている事になります。アナログで前処理されているなら、6ビットも余剰分はいらないでしょ? この余剰分は一体、何に使われているのでしょうか?
驚きました.議論以前ですな.14ビットリニアの用途はSonyではリアルイメジングプロセッサという部分で,ノイズキャンセル,トーンカーブの処理,JPEG圧縮,その他もろもろです.
基本原理については同意できたと考えます.あとN2で実際にどうやっているかに貴方があまり関心をお持ちでないなら,この辺で議論は終わりにしたいと思います.
書込番号:5624656
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
推測の話であったハズなのに、断定的に
仰ってる事に問題を感じました(^^;)
> 驚きました.議論以前ですな.・・・ノイズキャンセル,
> トーンカーブの処理,JPEG圧縮,その他もろもろです.
サンプリングビット数に余裕があってトーンカーブが
イジレルということは、データ値としてレベルをシフト
出来ているという事です。それなら、各レベル間をスト
レッチすれば、増幅にも使える事になるハズです。
仰るような処理方法があるからといって、デジタル増幅を
していない事の証拠には当たりません。
真相は、私にも貴方にも判らないハズです。
----------------
> あとN2で実際にどうやっているかに貴方があまり関心を
> お持ちでないなら,この辺で議論は終わりにしたいと思います.
了解しました。実状の推測よりも、原理の推測が肝心であると
考えております。実状は、真実を知ってこそ役に立つ情報だと
考えます。
書込番号:5625387
![]() 0点
0点
デジタル処理にはリニア(非圧縮)データであることが必須で,Sony ではこれに14ビットをフルに使っています(他社では12ビットもあるが).8ビットデータというのはJPEG圧縮後のデータ長です.これって基本です.
なお前に
>>ADCは許容入力電圧に注意すれば単に接続するだけでOKだと思います.厳密には所用ビット数を増やす必要がありますが,Sonyお得意の14ビットADCなら充分でしょう
と書きましたが訂正します.高感度時と低感度時のアナログ出力電圧(ADC入力電圧)を同じに設定(情報のダイナミックレンジは異なるが)すれば,所要ビット数が増えることはありません(14ビットに余裕がなくてもOK).
書込番号:5625556
![]() 0点
0点
あんまり読んでませんけど、ダイナミックレンジだ何だ言う前に、デジカメの基本的な動作原理に興味を持った方がよいと思いますけど。ISO感度がどうしたとか、思いっきり誤解されているようなので。
ある露光量で CCD からの最大飽和電圧 X(mV) にちょうど達したとする。
露光量を半分にすると CCD出力は (1/2) * X(mV)
つまり CCD の入力・出力曲線は「線形」ということらしいです。
RAWデータ においては最大飽和電圧 X(mV) をフルビットにマップする
全機種こうではありませんが、考え方としてはこれでよいと思います。
この機種は 14bit ですが、12bit の場合は 4095 ですね。
ISO感度なんてどうでもいい話です。
ISO感度を倍にする、とは、アナログ(別にデジタルでもよい)のゲインアップを倍にする、ただそれだけの話。RAWデータ へのマッピングが変わるわけではありません。
デジタルで ISO感度を倍にするもっとも簡便な方法は、RAWデータ の値を 1bit分「左シフト」する(MSB がオンの場合にはフルビットにする)、です。1bit左シフトすれば、値としては「倍」になります(LSB は 0 で埋められるので、精度は失われる)。
昭和1桁さん が今も A1 をお持ちなら、RAW現像でいろいろ試してみればわかりやすいと思います。
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/beta/sakura/bbs/?mode=all&namber=108&space=0&type=0&no=0
このログはためになると思いますけど。
私もよくわからなかったのですけど、
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/beta/sakura/bbs/?mode=all&namber=108&space=0&type=0&no=0#335
ここから下のツリーで理解できました。
今のままでは不毛どころか、疲ればかりが溜まっていきそうです。
書込番号:5625576
![]() 0点
0点
補足。
RAWデータ:A/D変換直後のデータ。アナログをデジタル化しただけで、何もいじっていないデータ。
書込番号:5625614
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
>ISO感度なんてどうでもいい話です。ISO感度を倍にする、とは、アナログ(別にデジタルでもよい)のゲインアップを倍にする、ただそれだけの話。RAWデータ へのマッピングが変わるわけではありません
SonyのN2ではISO感度を160以上に変えるとダイナミックレンジが変わる(RAWデータ へのマッピングが変わる)ような改良をしたのです.ご苦労様ですがこのスレをよくお読み下さい.コロンブスの卵です.
書込番号:5625825
![]() 0点
0点
昭和1桁さんに理解と納得していただくのは大変に難しいです。
なんせ、SONY(に限らずメーカー)の言い分を「信じる」方のようですので。
コロンブスの卵もなにもRAW段階では何も変えずに現像時のトーン設定を変えただけですよね?
他のカメラメーカーで同様のことはすでに行われています。
SONYの14bitADCの説明に使用している図は誤解を与えるものだということは以前に書き込んだのですけど御納得をいただけていませんから。
書込番号:5626147
![]() 0点
0点
もう少し補足。
アナログ → デジタルへのマッピングは通常白のクリッピングレベルを基準として行われます(ここに余裕を持たせる機種と持たせない機種はある)。
クリッピングレベルとは
「最大飽和電圧」レベルであり、同時に
「適正露出(絞りとSSの組)の 2.5 段オーバーに振ったポイント」でもあります。
ここのマッピングを可変とするやり方も考えられなくはありませんが、そうすると「露出(露光値)」の意味が無くなるので、考えにくいです。
例えば
「ISO100 で 最大飽和電圧 X をフルビットにマップする」場合、通常は
「ISO200 でも X をフルビットにマップする」です(X の2倍までアナログ段で増幅されても、2*X でなく X)。
なぜこうするか?
「RAWデータに輝度の基準を持たせるため」です。
デジタルデータというのは単なる値にすぎません。12ビットの場合それは 0 - 4095 の範囲を持った値です。しかしアナルグフロントエンドからデジタルへのマッピング(A/D変換)の基準を固定すれば(この場合では最大飽和電圧をフルビットに固定する)、そのデータには
「値の大きさと受光量の大きさが比例する」
という「意味」が出てきます(CCD の入出力は線形、A/D も線形だから)。
比例どころか「比例定数(受光量)」もわかってしまうのです。
これはとりもなおさず「最大飽和電圧をフルビットに固定」したからにほかなりません。
こうしておけば、その RAWデータはいかようにも料理できます。
ビットシフトしなければ撮影者の意図どおりの露出(露出基準が 8bit jpeg の中間輝度となる)で画像となります。
ビットシフトすれば撮影時の二倍の明るさの画像、二分の一の明るさの画像、なども思いのままに得ることができます。
「A/D変換の基準を固定しない」方法では、処理が複雑になる以上にメリットが見出せません。
この方法だと「ビット精度」は上がるでしょう。例えば最大飽和電圧にはるかに達していないデータはフルビット基準を大幅に下げることでビット精度は上がります(その効果は不明です)。
まあでも、こんなことをするくらいなら初めからビット数を上げればよいだけの話。ペンタックスの K10D のように 22bit A/D にすればよいのです。
> スレをよくお読み下さい
私は収集がついていないスレを他人に対して「よく読んで理解しろ」とはよく言えません。
書込番号:5626167
![]() 0点
0点
kuma_san_A1さん
>他のカメラメーカーで同様のことはすでに行われています
ということは私が知らなかっただけでSonyの方法は嘘でないと考えてよいですか.
書込番号:5626298
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
議論が振り出しに戻りますな.ROMの皆さん,ご迷惑だったら無視してください.
貴方の議論は全て線形のシステムを前提にされています.しかし実際にはバケツが飽和する時点で線形でなくなるのです.
例えばISO100である被写体を撮影するとして,輝度ある大きさの部分でバケツが飽和するとします.それ以上の輝度を持つ部分はすべて白レベルになりますね.
次にISO200で同じ被写体を撮影するが,バケツは飽和せず,かつ出力電圧の閾値が高く設定されていれば,ISO100で白だった部分に階調が現れます.以上はアナログで起きる現象ですから,RAWへのマッピングが変わるのです.
書込番号:5626314
![]() 0点
0点
CCD(というか受光素子一般)に ISO感度という概念はありません。
「光」は「波動」であると同時に「粒子(光子)」でもあります。1個2個と数えられます。光子一個あたりのエネルギーはその波長に反比例しますが、可視光線の場合高々二倍の差ですので一定としてよいでしょう。
光子が素子に入射した時、同じく粒子である「電子」と衝突した際にエネルギーの交換をし、エネルギーをもらった電子が電圧を発生させます(光電効果)。
この時に発生させることの出来る電圧には「素子ごと」に最大値が存在します。最大飽和電圧です(このスレの中ではバケツの大きさと表現されています)。
バケツの大きさは「素子ごとに一定」で変動しません。
素子からの出力は、アナログのまま(必要に応じて)アンプで増幅されるのが一般的なようです。理由は ISO感度を後で自由に変えるため、と同時に A/D に扱いやすい電圧を得るためでもあると思います。
最大飽和電圧にアンプの基準増幅率を掛けた値 X をフルビットにマッピングします。これを ISO100 とします。
ISO200 の時は単純にアンプの増幅率が基準増幅率の二倍となるだけです。出力電圧の最大値は 2 * X になるかもしれませんし、リミッターをかけて X のままかもしれません(それは私にはわかりません)。ともかく ISO200 の時も X をフルビットにマップするのです。理由は先にも書いたとおり、「RAWデータに輝度の基準を持たせるため」です。そうでなければデータに輝度情報を入れるか、システムが覚えていなければならず、複雑化するからです。
ISO200 の時にはバケツ一杯でなくてもフルビット表現されてしまいます。すなわち「ISO感度を上げるとダイナミックレンジは低下する」です。
じゃあ ISO200 の時に値 X をフルビットとするのではなく、「2 * X をフルビットにマップ」すればどうなるか?
答えは「これをそのまま画像処理したら ISO200 ではなくなる(ISO100 相当になる)」です(理由は少しご自分で考えてみてください)。
つまり意味が無いのです。
この時は RAWデータを左に1ビットシフトして RAW現像すれば ISO200相当の画像が得られます。でも X より上の部分は白飛びします(左シフトによるオーバーフロー)。
結局のところ
「フルビット基準をどこにとろうと同じこと(素子のダイナミックレンジは変わらない)」
なのです。
だったら基準の変更は複雑化するだけで意味が無いことになります。
表面上(出来上がった jpeg画像上)ダイナミックレンジを拡大する方法はいろいろあります。なぜなら RAWデータのダイナミックレンジよりも jpeg画像のダイナミックレンジが狭いからです(狭い範囲に広い範囲を押し込める方法を考えればよい)。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5615986
この機種は↑これの [5617664] で書いた方法を用いているのでしょう。
RAWデータを左シフトする方法は「なんちゃって高感度」と呼ばれることがあります。この方法で出来た画像の Exif を ISO160 と表示はしないかもしれませんので、もしかしたら同様のトーンカーブ処理を「アナログアンプ」で行っているのかもしれません。
いずれにせよ「画像が明るいにもかかわらずハイライトが残っている(見かけ上のダイナミックレンジは上がっている)」のは確かですから、それを実現する方法は別に何でもよいのではないですか?
素子のダイナミックレンジが従来より上がっているかはわからない。画像を見てユーザーが納得できればそれでよい。私はそう考えます。
書込番号:5626650
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
>ISO200 の時にはバケツ一杯でなくてもフルビット表現されてしまいます。すなわち「ISO感度を上げるとダイナミックレンジは低下する」です
アナログの世界では,誤解を避けるためフルビットでなく飽和電圧と表現します.
(値 X を飽和電圧とした場合)ISO200の時はバケツ一杯でなくともXに達しますが,その時の輝度はISO100でバケツ一杯の時の輝度と同じですから,ダイナミックレンジは変わりません.低下するというのは常識的にも変じゃありませんか.ISO200の場合は露出を半減にしていることをお忘れなく.
(値2 * X を飽和電圧とした場合)ISO200の場合ISO100の2倍の輝度まで飽和が起きません.つまりダイナミックレンジは2倍になります.
飽和電圧は何れにせよフルビットに変換されますが,ISO100ではバケツ飽和が起き,ISO200では起きていない場合には,マップされた内容は明らかに違うはずです.バケツ飽和が起きていなければマップされた内容は同じですが.
よって
>フルビット基準をどこにとろうと同じこと素子(アナログ出力)のダイナミックレンジは変わらない
は誤り.
>素子のダイナミックレンジが従来より上がっているかはわからない。画像を見てユーザーが納得できればそれでよい。私はそう考えます
それは思考停止です.
書込番号:5627011
![]() 0点
0点
昭和1桁 さん
ご説明がよく判らないので質問します(^^;)
>(値 X を飽和電圧とした場合)・・・
↑この説明は、ISO200に増感した場合、ADコンバーターに
入力する前にアナログ増幅(増感)をした場合の説明では
ないのですか?
アナログ増感をしたら、折角確保した(露光量を抑えて出現した)
新たな白ピークを、コンバート前に切り捨ててしまう事になると
仰っている訳ですよね?(^^;)
書込番号:5627129
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
>↑この説明は、ISO200に増感した場合、ADコンバーターに入力する前にアナログ増幅(増感)をした場合の説明ではないのですか?
そうです.
>アナログ増感をしたら、折角確保した(露光量を抑えて出現した)新たな白ピークを、コンバート前に切り捨ててしまう事になると仰っている訳ですよね?
一寸意味不明ですが,ISO200で(値 X を飽和電圧とした場合)にはバケツが半分以上の輝度に対して入力情報を切り捨てることを指摘されているなら,その通りです.それを切り捨てないように2Xを飽和電圧とすればダイナミックレンジは2倍になるということです.
書込番号:5627332
![]() 0点
0点
まあ、メーカーの開発者でもない限り、実際の動作の詳細などわからないものですが、折角なので推測で「楽しみ」ましょうよ。
>ダイナミックレンジは変わりません.低下するというのは常識的にも変じゃありませんか.
光 → CCD素子 → アンプ → A/D変換(12bit)→画像エンジン→ JPEG 出力
CCD の撮像を単純化すると上記の通りということにします。(細かい違いは無視してください)
まず、CCD 素子自体が、ISO 値というものは持っていないというのは共通認識としていいですよね?
CCD 素子が飽和出力分の光を受けると、100% の電荷が出力され、アンプでは増刊されずに、 A/D 変換に出力されるということになります。この時の値は 4095 (12bit フルビット)ですよね?
この状態を ISO100 とします。
さて、絞りを1段絞ると、50% の光しか受けられないため、CCD は 50% の電荷しか出力されません。しかしながら、アンプで2倍に増感し、A/D 変換時には、やはり 4095 として出力される。これが ISO 値としては 200 ということになると思います。
昭和一桁さんは、ここでより強い光を受けた場合、CCD の余っているダイナミックレンジ分が使えるのではないか、という話だと思いますが、実際にはアンプ部でクリッピングされてしまい、A/D 変換時には、やはり 4095 として出力されてしまうことは変わりないかと思います。
>それを切り捨てないように2Xを飽和電圧とすればダイナミックレンジは2倍になるということです.
逆にクリッピングしないのであれば、ISO 値が異なることになってしまいます。(=単なる露出の話ですよね?)
また、昭和一桁さんは、ISO200 だとダイナミックレンジが2倍、と考えているようですが、ダイナミックレンジとは S/N 比ともいい、信号の出力とノイズの比を指しますから、ISO200 時は CCD からの信号、つまり正味の輝度情報もノイズも2倍になりますから、ダイナミックレンジは広がることはありません。むしろ、CCD からの輝度情報は半分(半分を超えた部分はアンプでクリッピングされてしまう)、ノイズは一定ですから ISO 値が上がるとダイナミックレンジが下がるというのが一般的な常識かと思います。
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/aboutus/pdf/tech/ff_rd050_001.pdf
上記に、CCD の同一画像処理に置ける S/N 比較があります。縦軸が S/N、横軸が明るさです。ISO 値が上がるほど、S/N 比(ダイナミックレンジ)が低くなるのが読み取れるかと思います。
書込番号:5627404
![]() 0点
0点
さて、それではなぜ ISO 値が 160 以上でないとこの機能は効かないのか、が謎なのですが、それがある意味答えなのかもしれません。ダイナミックレンジ増加分が 59% とのことなので、単純に暗めに撮像し、ISO160 に増感時に暗い部分だけ持ち上げて見かけ上ダイナミックレンジを広げているという 5617664 の京都のおっさんさんの推測がビンゴかと思っています。
これが出来るようになったのが、高感度化によるノイズの低減の結果かと。CCDの出力段でノイズが減らないと、いくら画像処理で頑張ってもノイズを減らすことはできません。F10/F11 から F30 になって基本感度が ISO80 から ISO100 になったのも、CCD のノイズレベルの低下があってことのようです。同様に、今回の SONY 製 1030万画素 CCD も、ノイズ低減分を生かすために 12bit ではなく 14bit A/D 変換した上で、京都のおっさんさんの言うダイナミックレンジ拡大処理をしているのではないでしょうかねぇ。
もちろん推測ですが。
書込番号:5627417
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
> それを切り捨てないように2Xを飽和電圧と
> すればダイナミックレンジは2倍になるということです.
↑ こちらは、アナログ増幅をせずに、そのままADコンバート
した場合のお話ではありませんか?
そうなると、アナログ増幅説に執着なされていたお説が・・・(^^;;)
------------------
デジタルで増幅(後処理)した場合は、新たに出現したピーク範囲
のどこをトップレベルにして、8ビット階調に組み直すかを、被写
体の輝度分布を考慮しながら決める事も可能になりますよね?
例えば、夜景の中の点光源なんかだと、白階調の確保は(概ね)必要
が無いと思います。しかし、それが点光源であることは、画面全体の
輝度データ(=分布状況)を分析した時に判るわけですから、アナログ
増幅でツジツマをあわせてからADコンバートしてしまうと、その
分布状況を十分に把握する事ができなくなります。
増感(露光量低下)で出現した新たな白階調を全てデジタルデータ
に変換するには、前処理でのアナログ増幅は都合が悪くなると
思います。
( ※ アナログ増幅の有無の話ではありません。デジタルでの
後処理増幅に優位性がある事の説明をしております。)
書込番号:5627472
![]() 0点
0点
もう1つ、
1/2.5 CCD を採用した一部の安い機種などは暗部の階調など残っていない物も多い中、F30 を触っていて思うのは、暗部の階調がちゃんとあることに驚きます。明部が比較的階調が残らない(明るめの露出なら当然)写真でも、ディスプレイでは表現しきれないような暗部までしっかり階調が残ります。
実際、RAW ではないので限界はありますが、レタッチして暗部を持ち上げても比較的耐える画像になります。これが低ノイズ化のメリットだとすれば、生データで自動的に行ってくれるのが N2 のダイナミックレンジ拡大機能なのではないでしょうか。
書込番号:5627479
![]() 0点
0点
n the willowさん
>実際にはアンプ部でクリッピングされてしまい
そのクリップする電圧を飽和電圧としてXとか2Xとかに設定しようという話です.
>ISO200 だとダイナミックレンジが2倍、と考えているようですが
飽和電圧を2Xにする条件をお忘れなく.
>それではなぜ ISO 値が 160 以上でないとこの機能は効かないのか、が謎なのですが、
謎ではなく簡単な話なんですが,まだおわかり頂けませんか.
書込番号:5627535
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
>↑ こちらは、アナログ増幅をせずに、そのままADコンバートした場合のお話ではありませんか?
??アナログ増幅はやりますよ.
本日はこの辺で
書込番号:5627568
![]() 0点
0点
> 昭和1桁さんに理解と納得していただくのは大変に難しいです。
ギブアップします(^^;;;)
書込番号:5627620
![]() 0点
0点
[5627620] くろこげパンダさん
>ギブアップします(^^;;;)
でしょ?
論理的につながらないことを、本人に気づいていただけない様子が見て取れます。
書込番号:5627652
![]() 0点
0点
こちらのスレッドとか
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5096859
そこで紹介されている
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4508195&Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=14bit&LQ=14bit&ProductID=00501110729
のスレッドで…ご理解いただけなかった経験があります。
書込番号:5627695
![]() 0点
0点
なるほど・・・(^^;)
信念が強いというか、信仰に厚いというか・・・
ご性分が真面目な点だけは、救われました(^^;;;失敬)
書込番号:5627779
![]() 0点
0点
[5627620] くろこげパンダさん
> ギブアップします(^^;;;)
ありゃ、くろこげパンダさん も思考停止?
ざっと読んだ限り、昭和1桁さん以外の方々には共通認識があるようです。
CCD → アナログアンプ入力・アナログアンプ増幅・アナログアンプ出力
ダイナミックレンジはこの系で上限が決定している、という認識です。
ダイナミックレンジとは信号の高低の幅のことであり、きちんとした定義は知りませんが、上は最大飽和電圧、下はノイズで決まるとするのが一般的でしょう。
A/D は 12ビットあればダイナミックレンジのボトルネックにはならないと思います(下の方はノイズが支配的だから)。
あとはソフトウェアノイズリダクションをする、8ビットjpeg という狭い受け皿に押し込める方法を工夫する、といった処理であり、これらの処理をダイナミックレンジ向上とは普通呼ばないと思います(これらの処理が重要でないという意味ではありません)。
つまり A/D 以降にダイナミックレンジを向上させるマジックは存在しません。アナログの系で地味な努力をするのみです。
蛇足ですが、フジフィルムのハニカムSR はアナログの系での努力ですが、発想の転換という意味でコロンブスの卵的アプローチと思います。
[5627011] 昭和1桁さん
> アナログの世界では,誤解を避けるためフルビットでなく飽和電圧と表現します.
これはよいのですが、
> (値2 * X を飽和電圧とした場合)ISO200の場合ISO100の2倍の輝度まで飽和が起きません.
(露光値を ISO100 の時に比べて ISO200 の時には半分とする条件の下)これもよいのですが、ISO200 というのは「アナログアンプのゲインを(ISO100 の時の)二倍に引き上げる」ことによって達成しています。
つまり飽和電圧も二倍になりますが、
「ノイズ量も二倍に増加」
していることをお忘れなく。
> つまりダイナミックレンジは2倍になります.
よって昭和1桁さんのこの結論は間違っています。
単にアナログアンプからの信号出力が二倍になっただけ。ノイズも二倍に増幅されており、画像の暗部はノイズに埋もれたままです。
書込番号:5628049
![]() 0点
0点
上で書いたことを式で表現しておきます。
ISO100時の最大飽和電圧を X、ノイズレベル(ノイズの電圧)を x とします。
ISO100 の時のダイナミックレンジ: X - x
昭和1桁さん の提案通り、ISO200時の最大飽和電圧を 2X としてみます(この時のノイズレベルは前述のとおり 2x です)。
ISO200 の時のダイナミックレンジ: (2X - 2x) / 2
結局 ISO200 の時もダイナミックレンジは X - x のままです。
最後の「割る2」が不明かもしれませんが、ここを私は「ご自分で考えてみてください」と書いたのです。その他の方々も「白ピークレベル」など、言葉を変えて表現されています。
単純に「アナログアンプからの出力をそのまま表示するディスプレイ」を考えれば明白です。ISO100 の時と ISO200 の時のディスプレイ輝度は同じにしなければなりません(そのように露出を決定した、と昭和1桁さん は書いておられます)。「割る2」をしなければディスプレイの明るさが両者(ISO100 と ISO200 の両者)同じになりません。
書込番号:5628083
![]() 0点
0点
ありゃ? ディスプレイ輝度の説明はおかしいですね。
逝ってきます orz
書込番号:5628094
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
大分ご理解が進んできましたね.もう一息です.
>昭和1桁さん以外の方々には共通認識があるようです。CCD → アナログアンプ入力・アナログアンプ増幅・アナログアンプ出力ダイナミックレンジはこの系で上限が決定している、という認識です
冗談ではありません.私こそ一所懸命そのことを主張していたのです.同意見の方が現れて嬉しいです.
>つまり飽和電圧も二倍になりますが、「ノイズ量も二倍に増加」していることをお忘れなく
ノイズの問題もそれなりに関係あるとは思いますが,バケツの飽和がノイズ以前にダイナミックレンジを決定的に支配します.
ISO100の時のダイナミックレンジはバケツの容量で決まってしまい,S/Nより遙かに小さい値です.
ISO200で増幅率が増えるとS/Nは確かに劣化しますが,飽和電圧を上げない限りダイナミックレンジはISO100よりほんの僅か低下するだけでしょう.
次にISO200のまま飽和電圧を2倍に上げても雑音は増えませんから,ダイナミックレンジが拡大されます.
書込番号:5628443
![]() 0点
0点
以前の説明で、
#絞りを1段絞ると、50% の光しか受けられないため、CCD は 50% の電荷しか
#出力されません。しかしながら、アンプで2倍に増感し、A/D 変換時には、
#やはり 4095 として出力される。これが ISO 値としては 200 ということに
#なると思います。
#昭和一桁さんは、ここでより強い光を受けた場合、CCD の余っている
#ダイナミックレンジ分が使えるのではないか、という話だと思います
これを昭和一桁さんの考え方として理解してよろしいでしょうか?
>そのクリップする電圧を飽和電圧としてXとか2Xとかに設定しようという話です.
これが話を奇妙にしている原因だと思いますが?
まず、クリップする電圧を2倍に、ということですが(生CCDから出てくるのは電圧じゃないという話はさておき)、言葉の意味をそのまま受け取ると、
光 → CCD素子 → アンプ → A/D変換(12bit)→画像エンジン→ JPEG 出力
のアンプ部の上限を2倍に引き上げようという話でしょうか?
アンプ部だけを2倍にしても、A/D変換以降の後段の話がおかしくなります。
というのも、アンプの最大出力→A/D変換の最大出力(4095)となるように回路的に組まれますから、アンプ部を2倍にしても全体のダイナミックレンジが広がるわけではないんです。
>次にそれから入力光が強まった場合,ISO100ではバケツが一杯ですから
>出力電圧は上がりません.ところがISO200ではバケツに余裕がありますから,
>出力電圧は閾値で制限しなければ更に上昇します.故にISO200の時に閾値を
>高く設定すればダイナミックレンジが拡大できる訳です.
このバケツが一杯というのは、CCDの飽和出力のことですよね?
CCD素子の飽和出力(CCD素子のバケツ一杯分)は、受光面積と伝送部免責および効率でほぼ決まり、各社ともその時点での持てる技術を最大限使って向上させようとしている部分です。簡単に2倍とかに設定できるものではありません。ISO 値は後段のアンプ部の増感率で決まり、CCD としては ISO200 だろうが ISO10000 だろうが、CCD の飽和出力は一定です。
>ISO200ではバケツに余裕がありますから
問題はここです。ISO200 ではバケツに余裕がある、というのはちょっとおかしくて、ISO200 というのは CCD の出力を、アンプ部で2倍に増感する状態を指しますよね。CCD 素子の飽和出力の半分でも、アンプ部で強制的に2倍にされ、出力としては白(4095)になってしまいますから、回路全体としてみたときには決してダイナミックレンジが高い状態ではなく、むしろノイズも2倍以上になりますからダイナミックレンジとしては低くなります。
入射光を制限すれば(つまり絞れば)、CCD素子として白飛びに余裕ができますが、それでは単純に低露出で撮影しただけになってしまいます。
京都のおっさんさんの指摘通り、昭和一桁さんはCCDについてちょっと違う理解をされているのではないでしょうか?
書込番号:5628506
![]() 0点
0点
>ノイズの問題もそれなりに関係あるとは思いますが,バケツの飽和がノイズ以前に
>ダイナミックレンジを決定的に支配します.
ダイナミックレンジ=S/N 比です。簡単に言えば、信号の最大値-ノイズ成分 を対数的に表しただけですから、ノイズ成分の問題を避けることはできません。
>バケツの飽和がノイズ以前にダイナミックレンジを決定的に支配します.
全く逆です。サンプル画像等で、白い空が青くなるのを見て、白飛びにばかり目がいってしまうようですが、CCDのダイナミックレンジが狭いとされる最大の問題は、白飛びではなくて黒潰れなんです。白飛びは入射光を減らせばいくらでもコントロールできます。白い空も青くなります。ただ、このときに中間調〜暗部の階調が十分に得られないから、CCDはダイナミックレンジが狭いとされているのです。
>ISO100の時のダイナミックレンジはバケツの容量で決まってしまい,
>S/Nより遙かに小さい値です.
バケツの容量とは、CCD の飽和出力ですよね?
ISO100 とは、アンプ部での増感をしないということですよね?
S/N (=ダイナミックレンジ)より遥かに小さな値というのが????です。
>ISO200で増幅率が増えるとS/Nは確かに劣化しますが,
理解していただき良かったです。
>飽和電圧を上げない限りダイナミックレンジはISO100よりほんの僅か低下するだけでしょう.
飽和電圧とは何を指していますか????
書込番号:5628533
![]() 0点
0点
昭和1桁さんは、ISO100 の時に比べて、ISO200 の時はバケツの容量が増える、と思い込んでるんじゃないのかなぁ。ちがうかな?
書込番号:5628550
![]() 0点
0点
昭和一桁さんの下記の書き込みが誤解のもとじゃないですかね。
#次にそれから入力光が強まった場合,ISO100ではバケツが一杯ですから出力電圧は
#上がりません.ところがISO200ではバケツに余裕がありますから,出力電圧は
#閾値で制限しなければ更に上昇します.故にISO200の時に閾値を高く設定すれば
#ダイナミックレンジが拡大できる訳です.
ISO200 というのは増感率を2倍にするということですが、ノイズ量は一定ですから
ダイナミックレンジ(S/N比)は低下します。(これはご理解いただいていると思います)
さて、このときに閾値を高く設定するというのが理不尽なんですよ。
アンプの最大出力は、CCDの飽和出力に合わせているのではなくて、A/D 変換の 4095 が画像の白になるように、アンプ部で調整しているだけの話です。ですから、アンプ部で2倍にして、その上限を無限大にしても、結局 A/D 変換後は全部 4095 になって白飛びするだけです。もし A/D 変換のビットを増やして、4095 以上の数値に変換しても、白の基準点が 4095 ですから、それ以上は意味が無いですからね。
白の基準点を変えるということになると、今度は増幅率が変わるということですから、ISO200 じゃなくなってしまいますから、話が変わってしまいます。簡単に言えば、低露出で撮影しているだけです。
昭和一桁さんは、白飛びばかり気にしているように見受けられますが、白飛びなんて入射光を減らせば良いだけの話です。問題は、そのときにどうやって中間調〜暗部の階調を確保するか、ということなんですよ。
書込番号:5628617
![]() 0点
0点
on the willowさん
>これを昭和一桁さんの考え方として理解してよろしいでしょうか?
はい結構です.
>アンプの最大出力→A/D変換の最大出力(4095)となるように回路的に組まれますから、アンプ部を2倍にしても全体のダイナミックレンジが広がるわけではないんです
言葉が足りなかったかも知れません.前に書いたのですが,飽和電圧を変えたときも,ADCの入力では飽和電圧がフルビットにマッピングされるように,電圧を再調整していると思います.実際には増幅したり減衰させたりでなくもっとスマートなやり方だと思いますが.これをしないと1ビット増やしてデジタル内で調整しなければならなくなりますね.
>このバケツが一杯というのは、CCDの飽和出力のことですよね?
バケツとはCCDの一部の受光ダイオードの部分です.私はCCDというとAD変換直前までを言いたいのですが(Sonyの説明図にそって),誤解を招くので注意しています.
>ISO200 ではバケツに余裕がある、というのはちょっとおかしくて
ISO100ではバケツ一杯のときにアナログ出力が飽和電圧に達します.ISO200ではバケツ半分で同じ電圧に達します.よってバケツには余裕があります.
>むしろノイズも2倍以上になりますからダイナミックレンジとしては低くなります。
飽和電圧を上げなければノイズ分だけ僅かに低くなるのは仰るとおりです.
>入射光を制限すれば(つまり絞れば)、CCD素子として白飛びに余裕ができますが、それでは単純に低露出で撮影しただけになってしまいます
??増幅していればよいのでは.
>ダイナミックレンジ=S/N 比です
信号がS/N比が低い段階で飽和したらどうなりますか.飽和すればいわゆるS/N比よりダイナミックレンジの方が小さくなります.Sonyのダイナミックレンジの説明も飽和を意識しています.
>アンプの最大出力は、CCDの飽和出力に合わせているのではなくて、A/D 変換の 4095 が画像の白になるように、アンプ部で調整しているだけの話です
上記のように飽和電圧はADCのフルビットにマップするように再調整します.
>白飛びばかり気にしているように見受けられますが、白飛びなんて入射光を減らせば良いだけの話です
それでも白飛びを減らす必要性はいささかも減らないと思いますが.
書込番号:5628829
![]() 0点
0点
[5628083] での私のダイナミックレンジの定義がおかしいんですね。
ISO100時の最大飽和電圧を X、ノイズレベル(ノイズの電圧)を x とします。
誤)
ISO100 の時のダイナミックレンジ: X - x
正)
ISO100 の時のダイナミックレンジ: (X - x) / X
「全体の中で有効なレンジの割合(比率)」あるいは「単位ボルトあたりの有効出力のレンジ」でしょう。
再生系のディスプレイの輝度の規格が決まっているわけではないでしょう。
もし「誤」をダイナミックレンジとすれば、ディスプレイの輝度を上げることでいくらでもダイナミックレンジを拡大できることになってしまいます。
オーディオで言えばアンプのボリュームを上げれば音量(音圧レベル)は上がりますが、それはダイナミックレンジとは言わないでしょう。
on the willowさん も言われてますが、2X の最大飽和電圧をフルビットにマッピングするとは、結局 ISO100 で撮影していることになります。[5626650] でも既に書いてますが。
書込番号:5629093
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
貴方のダイナミックレンジの話にバケツ飽和の問題が出てこないのが理解できません.
>2X の最大飽和電圧をフルビットにマッピングするとは、結局 ISO100 で撮影していることになります
それでいいんですよ.バケツ飽和が起きていなければ,ISO100で撮った写真とISO200で撮った写真は同じでも不思議でありません.飽和が起きた場合のみ違ってきます.露出が少なくできたメリットは色々あるでしょうが.
書込番号:5629146
![]() 0点
0点
いくつかのやりとりを通じて、お互いの「ダイナミックレンジの定義」を確認しあうことができました。
増幅率により信号とノイズが共に比例上昇する理想的なアンプを用います。
基準増幅率における信号電圧を X、ノイズ電圧を x とします。
***************** 昭和1桁さん の定義 *****************
ダイナミックレンジ:信号電圧 - ノイズ電圧
で表現できる。
故に基準増幅率を n倍にするとダイナミックレンジは
(n * (X - x)) / (X - x)
と、元のダイナミックレンジの n倍となる。
よって
「アンプの増幅率を上げればダイナミックレンジはいくらでも増やせる」
********************************************************
************************ 私の定義 ************************
ダイナミックレンジ:(信号電圧 - ノイズ電圧) / 信号電圧
で表現できる。
故に 1 - x/X で表現され、x/X は増幅率に左右されない定数である。
よって
「アンプの増幅率にかかわらずダイナミックレンジは一定」
**********************************************************
詳しい方が簡単なダイナミックレンジの規定をしてくだされば、問題は解決すると思います。
書込番号:5629347
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
勝手に私の定義を書かれては迷惑します.私は(Sonyも)単純な増幅器のダイナミックレンジを論じていません.あくまでCCD(ADC入り口まで)のダイナミックレンジです.それにはバケツ飽和の問題を離れて議論できません.信号が途中で頭打ちになるデバイスにおいて,扱いうる信号の幅は如何という問題です.
書込番号:5629463
![]() 0点
0点
昭和1桁さん、話の発端を覚えていますか?
「CCDのダイナミックレンジが広がれば白飛びはなくなるのか?」
ということです。
CCDのダイナミックレンジが広がったのが白飛び減少に役に立ったのは結果論であって、
白飛びを抑える仕組みはあくまで「白飛びしない露出で撮影している」ではありませんか?
書込番号:5629578
![]() 0点
0点
適当takebeatさん
>白飛びを抑える仕組みはあくまで「白飛びしない露出で撮影している」ではありませんか?
ちょっと意味不明ですが,同じ露出で撮影し,従来機種では白飛びするがN2では白飛びしないという結果になれば,カメラが改良されたと考えて良いと思います.それを詳しく見ると,ISO160以上でCCDのダイナミックレンジが広がったからということでしょう.ISO160以上でないと効果がないというのは制限付きの改良ということでしょう.
何を仰りたいのでしょうか.
書込番号:5629615
![]() 0点
0点
>信号が途中で頭打ちになるデバイスにおいて,扱いうる信号の幅は如何
アナログ段においては単純に、飽和信号量からCCDの固定ノイズまでの間ではないでしょうか?
バケツの例えを最初に持ち出したのは私ですが、誤解してはいけないのは、露光量が1/2になってバケツの余裕が増えたからといって、それはS/N(ダイナミックレンジ)が良くなることを意味しているわけではないということです。というか、逆に明らかに悪くなります(白飛びうんぬんではなく、ノイズが浮いてくる、という方向ですが)。
N2のやり方は確かに白ピークに粘りを持たせるのに効果的ですが、厳密な意味でのダイナミックレンジを拡大しているわけではありません。
どうも、ここでもやはり昭和1桁さんと他の皆さんで、言葉の使い方に違いがあるように思います。
昭和1桁さんの言う「ダイナミックレンジ」は、画像処理も終わって出力された写真のラチチュード=ダイナミックレンジだと思います。
対する他の皆さんは、S/N=ダイナミックレンジでしょう。
ただ、個人的にはそれが見せかけであれどうであれ、結果にちゃんと反映されるのであれば、写真というのは要するに見せかけのものだと思うので、まったく問題ありませんが。
書込番号:5629744
![]() 0点
0点
今回のN2のケースは
たとえばISO160で撮影したときはISO160で適正露出になるシャッタースピードと絞りが使われます
しかし実際にはISO100で撮っているのです、
したがってハイライト側に余裕が出来て結果的に白飛びが抑えられます、
もちろんこのままでは単なるアンダーな写真になるのでハイライト以外をISO160の状態に持ち上げます。
非常に単純な話です。
書込番号:5629764
![]() 0点
0点
p,s
上の方で私は
>>メーカーは稀に嘘をつきます、そしてそれ以上にわざと誤解を招くあいまいな表現を多々使います。
と書きましたが、
今回の場合もSONYが「ダイナミックレンジ拡大機能」と書いたのは嘘に近い誤解を招くあいまいな表現の代表的なものだと思います、
ここは「ダイナミックレンジ圧縮機能」とでも書いた方が現実に即してい他の二・・・と思っています。
書込番号:5629789
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
昭和1桁さんの方法が破綻しない条件を考えてみたら、イメージ
なされていらっしゃる原理がようやく推察できました。ご説明上、
肝心なポイントを抜いてしまっていたから、理解が進まないのだと
思います。
-------------------
この説明を加えておかないと、想定(考え)のズレが埋まら
ないと思います。
※ 理解し易いように、仮の数値で話をします。ダイナミック
レンジの増分も仮の値で書いてます。
1.CCDの出力飽和電圧 1Vとする。
2.ADコンバーターの最大入力電圧(フルビットデータを
得る電圧=白飽和データを得る電圧) を3Vとする。
--------------------
上記の条件では、基礎感度でもCCDの出力電圧を3倍にまで増幅
する必要が生じます。これを、『基本増幅率』 と呼ぶ事にします。
基礎感度では、
【CCD出力上の白ピーク電圧】×【基本増幅率】= 1V × 3倍 = 3V
(=ADコンバーターへの入力電圧)
とすることで、適正にデータ変換が完了します。ここで、カメラの感度を
2倍にすると、露光量が半分に減らされます。よって、基礎感度の時と
同じ白ピーク点をフルビットデータに変換するには、CCD出力の0.5V
のところを白ピーク電圧と定める必要があります。
増幅率 = 【基本増幅率】×【増感分(露光量減少分)】= 3 × 2 = 6倍
故に 【CCD出力上の白ピーク電圧】× 6倍 = 0.5V × 6倍 = 3V
これで、基礎感度で撮影した時と同じ(被写体上の)白ピークになりました。
つまり、従来どおりの増感が完了した事になります。しかしこれでは、ダイ
ナミックレンジは拡大しないので細工を施します。CCD出力における白ピー
ク点(電圧)を変更し(=引き上げ)、その分、増感分の増幅率を抑えてしま
います。仮に、CCD出力上での新たな白ピーク電圧は 0.555・・Vとします。
増感用の増幅率は2倍から1.8倍に変更します。これで、被写体上の白ピ
ーク点が変更された事になります。
【基本増幅率】×【Dレンジ拡大を含む増感】= 3 × 1.8倍 = 5.4倍
【CCD出力上の新たな白ピーク電圧】× 5.4倍 = 0.555・・V × 5.4倍 = 3V
となり、CCD出力の白ピーク(新たな設定点)を0.05V引き上げできた分が
ダイナミックレンジを拡大できた分にあたります。
↑ 基本原理としては、この説明でヨロシイですか? > 昭和1桁さん
-------------
ここで説明している 『ダイナミックレンジ』 は、N2の 『ダイナミック
レンジ拡張機能』 を指してます。
-------------
しばらくオフラインします。
書込番号:5629860
![]() 0点
0点
@ぶるーとさん
>昭和1桁さんの言う「ダイナミックレンジ」は、画像処理も終わって出力された写真のラチチュード=ダイナミックレンジだと思います
最終的にはそこに直結しますが,一応Sonyの説明に忠実にCCD出力(ADC前)のダイナミックレンジを考えています.Sonyはダイナミックレンジが1.59倍増えたといっていますから,相対的な値であり,ISO100における飽和出力電圧に対して何倍の出力電圧が得られるかという値(扱える輝度が何倍になるか)と考えて良いのではないかと思います.
これは増幅器で通用しているS/N=ダイナミックレンジとは全く違う概念です.
書込番号:5629909
![]() 0点
0点
適当takebeatさん
>たとえばISO160で撮影したときはISO160で適正露出になるシャッタースピードと絞りが使われます.しかし実際にはISO100で撮っているのです
いいえ,ISO160で撮影するときは実際にもISO160で撮ります.
書込番号:5629920
![]() 0点
0点
じゃあこう言い換えましょうISO160で撮っているときもハイライト付近だけはISO100で撮っています。
書込番号:5629943
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
>↑ 基本原理としては、この説明でヨロシイですか?
よろしうございます.ご理解いただき誠に有り難うございます.
書込番号:5630177
![]() 0点
0点
>ちょっと意味不明ですが,同じ露出で撮影し,従来機種では白飛びするがN2では
>白飛びしないという結果になれば,カメラが改良されたと考えて良いと思います.
>それを詳しく見ると,ISO160以上でCCDのダイナミックレンジが広がったから
>ということでしょう.ISO160以上でないと効果がないというのは制限付きの改良
>ということでしょう.
大事な指摘ですよ。意味不明と言わずよく考えていただければと思います。
白飛びしないように撮るのは簡単です。絞ればいいんですから。
ダイナミックレンジが広がったから、と簡単に考えるのではなく、どうやってダイナミックレンジが広がったのか、なぜ ISO160 以上の制限付きなのか、まで考察しないと面白くないですよ。
書込番号:5630221
![]() 0点
0点
適当takebeatさん
貴方の言わんとすることは分かります.要するに露出を少なくして飽和を抑制し,あとは増幅度を調整して辻褄を合わせているだけだということですね.仰るとおりです.
まあ,それでもマニュアルで露出を減らし尚且つ適正露出の撮影データを得ることは困難ですから,ユーザにとっては有難いコロンブスの卵ではないかと思います.
書込番号:5630258
![]() 0点
0点
on the willowさん
>白飛びしないように撮るのは簡単です。絞ればいいんですから。
バ〇チョン式に露出を減らして尚かつ最適露出のデータを得られるのはユーザに受けると思います.
>ダイナミックレンジが広がったから、と簡単に考える
Sony がそう説明していますので.
>どうやってダイナミックレンジが広がったのか、
私の理解を縷々説明しています.
>なぜ ISO160 以上の制限付きなのか、
その辺はメーカーに聞くしかないと思います.
書込番号:5630312
![]() 0点
0点
昭和1桁さんは色々と誤解されていますね。
1)ノイズを十分小さいものとして無視している
実際は、ダイナミックレンジは信号とそれに含まれるノイズの比を対数で表した物ですから、ノイズは十分に小さいとは言えません。逆に、ノイズによってダイナミックレンジが制限されていると思った方が良いと思います。
ノイズを無視したら、そもそもダイナミックレンジの話なんかできませんよ?
ダイナミックレンジ(db)=20・Log(飽和電荷量/最小電荷量)
CCD のダイナミックレンジは大まかに上記で表します。
京都のおっさんさん風に対数表記ではなく、簡単にすると
ダイナミックレンジ:(正味の信号 + ノイズ) / ノイズ
この(正味の信号+ノイズ)というのが信号であり、この最大値が飽和出力です。
2)白飛びを抑えることがダイナミックレンジの拡大につながると思っている
昭和1桁さんの言われる複雑な方法をとらなくても、白飛びを防ぐのは簡単です。
絞ればいいんですから。それではなぜ絞らないかと言えば、もちろん中間調〜暗部の階調が得られないからです。中間調を適正値に合わせると、ダイナミックレンジが狭いCCDでは、白飛び、黒潰れが起きるのです。
昭和1桁さんの言われる方式では、ダイナミックレンジが小さくなるのは昭和1桁さんのも認める所だと思いますが、それでも白飛びが防げるとお考えなのは間違いです。
それを踏まえていただいた上で、昭和1桁さんの方式の問題点を指摘します。
光 → CCD素子 → アンプ → A/D変換(12bit)→画像エンジン→ JPEG 出力
上記の図において、白い光が 50% の時、CCD では飽和出力の 1/2 の出力となり、アンプで2倍に増感して、A/D 変換時に 4095 の「白」を得る、という流れは共通理解で良いと思います。昭和1桁さんは、それ以上の光が入ってきたときにアンプの上限を増やすことでダイナミックレンジが広がると信じておられるようですが、
光(70%) → CCD素子(70%) → アンプ(2倍→140%) → A/D変換(12bit をオーバー)
アンプのクリッピングレベルを増やしても、A/D できなくなります。
そこで、A/D のビット数を1ビット(2倍)増やします。
光(70%) → CCD素子(70%) → アンプ(2倍→140%) → A/D変換(13bit)→8191
白レベルが 4095 のままだと、8191 も 4095 も同じ「白」にしかならないので、当然ですが 8191 を「白」にします。すると、4095 はグレーになる訳ですよね?
ここで、「増感」の意味を考えてみましょう。増感とは、ある明るさを「白」に持って行くように感度を上げることです。言い方を変えれば、CCD 素子では飽和出力に満たない値を白にすることです。A/D 変換の白レベルを変えてしまったら、いくらアンプで2倍にしているからといっても、ISO200 ではなくなってしまいます。
さらに、ノイズ成分を見てみましょう。ノイズ成分が CCD 飽和出力の 1% だとしましょう。これは、アンプで2倍されますから、 A/D 変換時には 82 程度がノイズ成分になり、使えない領域になります。基本感度ではノイズ成分は 41 程度ですから、ダイナミックレンジは広がっていません。(その他の要因を考えると、ISO 値が上がるとダイナミックレンジは小さくなります)
これをもっと簡単に行う方法があります。絞るだけです。
光(70%) → 絞り(50%) → CCD素子(50%) → アンプ(2倍→100%) → A/D変換(12bit)→ 4095
白レベルを変える必要も無く複雑なアナログ処理無しで、同じことになります。
昭和1桁さんの言われる方法では、単に暗い画像を得るだけになります。
私が、
#逆にクリッピングしないのであれば、ISO 値が異なることになってしまいます。
#(=単なる露出の話ですよね?)
と書いた意味がわかりますでしょうか?
書込番号:5630491
![]() 0点
0点
昭和1桁さん
お詫び
>> 信念が強いというか、信仰に厚いというか・・・
↑ 茶化してしまった事をお詫び申し上げます m(_ _)m
昭和1桁さんのお説は、原理としては成立しております。
-----------------
で、ズレが生じた点に話を戻しますが・・・。
昭和1桁さんのお説を以って、デジタルでの増感処理を
否定する事はできないです。ですから、断定的に仰って
いた点は望ましくないですネ(^^;)
『基本増幅率』 の部分がシステム上必要なら、そこはアナログで行
なうにしても、増感のための増幅はアナログでもデジタルでも同じ事
です。原理上、どちらの方式でも元信号は同一のSN比と仮定して話
を進められますから、変換精度の問題を持ち込むなら、ADコンバーター
の変換性能(=デジタル増感時の不都合)を明確に提示してこそ、話が
そこへ移せるという事になります。
どちらの推測も、ダイナミックレンジの確保の要は、『露光量を下げ
て、新たな白ピーク点を設定する』 というところで果たしています。
増感方法は、ダイナミックレンジ拡張機能の原理を推測するに
おいては、特に必要とするファクターではなかった訳です(^^;)
-----------------
原理の話以上に踏み込むことになる、『実状(実態)』の話は、
デバイスに詳しい御方に講釈してもらうしかないですネ(^^;)
書込番号:5630492
![]() 0点
0点
>バ〇チョン式に露出を減らして尚かつ最適露出のデータを得られるのは
>ユーザに受けると思います.
なぜこれが今までできなかったかと言えば、暗部だけ増感すれば暗部ノイズが非常に目立つからです。ノイズが減った CCD だからこそできることでしょう。
>Sony がそう説明していますので.
それでは思考停止ですよね?
カタログやホームページの説明は判りやすくアピールするために、必ずしも技術的に正しい説明ではありません。スマートズームの比較も元絵のサイズが異なったりしていて正しい説明になっていません。
そもそも、CCDの受光量を「ダイナミックレンジ」とは呼びませんしね。
>どうやってダイナミックレンジが広がったのか、
昭和1桁さんの言われる方法も含め、ISO を上げるとダイナミックレンジは狭まるというのは理解していただいていたと思っていたのですが。
>その辺はメーカーに聞くしかないと思います.
京都のおっさんさんの推測は、その辺りも非常に良く説明していると思いませんか?
書込番号:5630536
![]() 0点
0点
on the willowさん
>1)
ノイズの話は私のダイナミックレンジの定義では一義的には関係ないと思います.ダイナミックレンジには色々な定義があり得ると思います.私は今回は@ぶるーとさんへのレスに書いたように許容輝度の幅の相対比で考えています.それが写真における寛容度との関係が最も近いからです.
>昭和1桁さんの言われる方式では、ダイナミックレンジが小さくなるのは昭和1桁さんのも認める所だと思いますが、それでも白飛びが防げるとお考えなのは間違いです。
理解できません.それ以前に私は自分の推薦する方式を云々しているのではありません.あくまでSony のN2がどうなっているかだけを議論していますので,他の方式の話で混乱させないでください.
>光(70%) → CCD素子(70%) → アンプ(2倍→140%) → A/D変換(12bit をオーバー)
飽和電圧をADCの最大入力に合わせると言っています.
>昭和1桁さんの言われる方法も含め、ISO を上げるとダイナミックレンジは狭まるというのは理解していただいていたと思っていたのですが
理解できません.なおダイナミックレンジの定義は1)に従って考えています.
書込番号:5630851
![]() 0点
0点
くろこげパンダさん
お詫びなんてとんでもありません.
>昭和1桁さんのお説を以って、デジタルでの増感処理を否定する事はできないです
仰るとおりです.
その他異論ありませんが,私はあくまでN2がどうやっているのかの議論に徹していますので.デジタルを排除しているような印象を与えたかも知れません.実は私は現役の頃,大学でデジタル信号処理の講義をした経験もあるので,デジタルは好きな方なのです.オーディオなんてデジタルアンプが最高と考えています.
書込番号:5630958
![]() 0点
0点
>ノイズの話は私のダイナミックレンジの定義では一義的には関係ないと思います.
これは私にとっての「ダイナミックレンジ」だ、と独自のダイナミックレンジを定義されても、誰も付いて行けないと思いますよ。すれ違い以前の問題ですね。
画像にしても同じことです。最低感度があって、飽和出力がある。そこに黒から白の幅があります。ノイズを無視したら、アンプでの増感で ISO160000 でも実現できますからね、絵に描いたの餅です。Sony N2 がどんな方式を採用している推測する上で、そんな方式を採用しているとお思いですか?
>理解できません.それ以前に私は自分の推薦する方式を云々しているのでは
>ありません.あくまでSony のN2がどうなっているかだけを議論しています
>ので,他の方式の話で混乱させないでください.
他の方式ではないですよ。昭和1桁さんだけではなく、私も含め、皆がSony のN2がどうなっているかを話しています。
私は、昭和1桁さんの言われている方式が、Sony の N2 で採用しているとは思えない、つまり、実質的に低露出で撮影しているのと何ら変わらないと指摘しているのです。技術的に理解できないのであれば、読み返していただくしかありませんが…
>>光(70%) → CCD素子(70%) → アンプ(2倍→140%) → A/D変換(12bit をオーバー)
>飽和電圧をADCの最大入力に合わせると言っています.
飽和電圧というのはCCD素子の飽和出力のことですか?アンプの飽和電圧ですか?
ISO200 では、バケツ半分以上は A/D しきれない部分です。ここをどう処理するかについては、くろこげパンダさんの言われる
>【基本増幅率】×【Dレンジ拡大を含む増感】= 3 × 1.8倍 = 5.4倍
>【CCD出力上の新たな白ピーク電圧】× 5.4倍 = 0.555・・V × 5.4倍 = 3V
で正しいならば、従来と同じ「白」の光量(CCD 飽和出力の50%)が入射しても「白」にはなりませんから、低露出で撮影しているのと変わらず、ダイナミックレンジの拡大にはなりません。
1.8 倍しかしていないという時点で ISO200 ではありませんし、単に ISO200 で適正露出のものを ISO180 で撮っただけということです。
基本感度(ISO100)に対して、ISO 値を上げると、CCD素子の暗電流等、ノイズ成分の比率が大きくなり、結果的に黒〜白の幅が小さくなります。信号的に見ても、画像的に見ても、ダイナミックレンジが小さくなります。
一番理屈が合うのは京都のおっさんさんが言われたように、ISO100 で暗めに撮像した上で、中間調〜暗部を持ち上げて(ISO160 程度に増感して)調整しているのではないか、というのが一番理屈に合っているし、ISO160 以上の制限付きであるのも納得できますよね。
書込番号:5631390
![]() 0点
0点
書こうかどうか迷ったのですが。
結局のところ線形じゃない増幅に対してソニーが「ISO160」と明記してしまったところに混乱の原因があると思うのです。
我々が認識している増感は、暗部、中間、ハイライト問わず一様に(リニアに)増幅させる処理のことです。
リニアじゃない増幅は「トーン処理」の範疇に入りますから。
これはハードウェア処理・ソフトウェア処理にかかわらず、従来はそう呼んできたと思います。
書込番号:5631781
![]() 0点
0点
なんか、言葉の定義をめぐっての論戦になってしまってますよ(^^;)
↓これを書いておいたのも、論点が錯綜しないようにする為でした。
>> ここで説明している 『ダイナミックレンジ』 は、
>> N2の『ダイナミックレンジ拡張機能』 を指してます。
----------------
ここでの論点は、Sonyが言うところの 『ダイナミックレンジ拡張機能』
が如何なるものか? という点に的を絞っておいた方が良いと思います。
----------------
京都のおっさんさんの別スレでのお説は、当初よく判らなかった
のですが、on the willowさんのご説明でよく判りました。
原理に立ち返れば、主張してる事は、皆さん同じです(^^;;)
昭和1桁さんと私の説は、アナ・デジの違いはあれど、考え方は
同じです。そして、施すべき非線形処理の部分の説明を割愛して
いるのです(←デジで後処理すれば良いだけ)。露光量を抑えて
新たな白ピークが出現することさえ説明しておけば、ダイナミック
レンジ拡張機能の根幹部分の説明を満足させられるからです。
京都のおっさんさんのご説明は、その非線形処理の部分に視点を
置いて、ご説明なされておられます。が、それでは、白ピークが
出現する様を描写できていない(?)ように思えます。
実際、白ピークを出現させる説明を目論む者から見ると、何を
仰ってるのか理解できませんでした(^^;←馬ッ鹿で〜す!)
原理のさわりの部分に焦点を合わせた説明と、より正確な実態像に
焦点を合わせた説明とが、入り乱れていただけだと思います。
書込番号:5631933
![]() 0点
0点
訂正
× 言葉の定義をめぐっての論戦になってしまってますよ
〇 名称の定義をめぐっての論戦になってしまってますよ
こういった、言い回し方一つとっても、随分違うのですよね(^^;)
書込番号:5631948
![]() 0点
0点
説もなにも、ふつうに「トーン処理」なのです。[5626147] で既に kuma_san_A1さん が書かれておられます。
アナログで行おうがデジタルで行おうが(それぞれメリットデメリットはありましょうが)トーン処理には変わりありません。
さらに「リニアなトーン処理」という概念を適用するなら、(アナログ・デジタル問わず)増感処理も「トーン処理」の範疇と言うことができると思います(ふつうはそう呼びませんが)。
もっとも、それと N2 の評価とは全然別の話です。ねねここさん のアップされた画像を見て、私はいいなと思いました。
ただ、ここは「思考するスレ」になっているようなので、この機種の「ダイナミックレンジ拡大機能」の本質を推測しようという姿勢でいるだけです。
書込番号:5632008
![]() 0点
0点
ちょっと言葉不足かもしれませんので。
ダイナミックレンジ拡大機能の本質はトーン処理でしょう。
ただしその裏には地道なアナログ系の改良があったと思います(アナログ系で従来機種よりダイナミックレンジが実際に拡大したかもしれない)。
また、ソフトウェア処理(ノイズリダクション処理)も進化している可能性はあります。
けっきょくはデジカメは「出た目勝負」なので、その出力された画像を見てユーザーが判断すればよいと思います。
書込番号:5632027
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
> 説もなにも、ふつうに「トーン処理」なのです。
> この機種の「ダイナミックレンジ拡大機能」の本質を
> 推測しようという姿勢でいるだけです。
理解しております(^^;)
両者、読み手に対してのアプローチの仕方が違っていただけです。
目視上で飛んでいたハズの白ピークが出現する様を語る方が
読み手には理解しやすいだろうと察します。シャドー側を
持ち上げるというご説明は正確ではありますが、白ピークの
出現の説明というより、中間調を救済する事に重きをおいた
説明になってしまいます。
話を単純化させるなら、新たに出現した白ピークを再設定すると
いう点に的を絞れば良く、非線形処理の話まで満足させようとす
ると、原理を展開して理解する必要が生じ、話が複雑になってし
まいますよネ(^^;)
※ だから、非線形処理に関する部分は、ワザと省いてあったのです。
([5612578] くろこげパンダ で説明済みでもあります。)
昭和1桁さんも同じ意図であったと思います。
白ピークの確保に、何故、『シャドーを持ち上げて・・・』の説明から
アプローチをするのか(=必要とするのか)、困惑してしまいました。
私の理解が進まなかったのもそれが原因です(^^;;;)←やっぱりバカ
トーン処理という言葉を前面に押し出せば、8ビットJPEGを
トーン処理して白階調を出現させていると捉えてしまう方も
出てくると思いますよ。露光量を減らして出現した白ピークを
利用する話にしておけば、その誤解も避けられます。
書込番号:5632124
![]() 0点
0点
昭和1桁さんも(?) 私も 『目視上でのダイナミックレンジ向上』
を 『ダイナミックレンジの向上』と単純に表現していたに過ぎな
いわけです。
※ 各々、主張されている原理が全て同じである以上、名称の
使い方や、原理説明の範囲に対する許容度の違いが、論点
ズレの原因だったと思われます。
------------------
デジ増感・アナ増感の違いは、また別の機会にでも・・・(^^;;;)
書込番号:5632126
![]() 0点
0点
> 目視上で飛んでいたハズの白ピークが出現する様を語る方が
読み手には理解しやすいだろうと察します。
これに対する誤解が延々と続いていたのがスレが長引いた原因です。ハードウェアのダイナミックレンジ拡大により白飛びしなくなった、との誤解です。
8ビットjpeg での出力で本当にダイナミックレンジが上がっているかをこの機種で調べるには、ISO100 と ISO160 とで「同じ露光値」で撮影してみればよいのです。
ねねここさん の別スレの画像で言うなら、A*ISO160wide を
F8.0、SS1/250sec
で撮ればわかるでしょう。
おそらく白飛びする部分は変わらないでしょう。
このときに黒つぶれしていた部分に諧調が出てくるならダイナミックレンジは向上した、黒つぶれがそのままならダイナミックレンジは変わらずと言えるでしょう。ある範囲内のトーン処理をしているのか、8ビットより広い範囲を 8ビットに押し込める(適当takebeatさん おっしゃるところの)ダイナミックレンジ圧縮処理をしているのか、がわかると思います。
そのためにはむしろ真っ暗に近い場面を撮る方がわかりやすいのですが、それが可能な撮影機能をこのカメラが持っているかどうかが問題ですが(暗いところでも ISO100 と ISO160 で撮影できなければ比較できない)。
書込番号:5632197
![]() 0点
0点
on the willowさん
>独自のダイナミックレンジを定義されても、誰も付いて行けないと思いますよ
非直線部分を含んだCCDのダイナミックレンジに直線系の増幅器のダイナミックレンジ=S/N比の定義を当てはめる方が無理だと思いませんか.私はSony が意味しているダイナミックレンジに忠実なのです.S/N比が1.59倍になるわけではないでしょう.
>ノイズを無視したら、・・・・
ISO100からISO200に切り替えた時点で既にノイズは増えています(ノイズが増えるのを許せない場合はISO100で撮るしかありません).その状態で輝度の受け入れ幅が増えれば,(ISO200としては)ノイズに無関係に扱える輝度幅がふえるわけです.
>実質的に低露出で撮影しているのと何ら変わらないと指摘しているのです
ISO200で撮影すればISO100で撮影するより低露出ですが,カメラが勝手に200にするのでなく,ユーザが200に設定するのだから,名目的にも低露出であり,わざわざ「実質的に」をつけると意味不明になります.
>飽和電圧というのはCCD素子の飽和出力のことですか?アンプの飽和電圧ですか?
ISO200 では、バケツ半分以上は A/D しきれない部分です
飽和電圧というのはアンプの出力です.ISO200でバケツの半分以上を有効に取り出すために,飽和電圧(出力の閾値)を上げるのです.その後フルビットにマッピングするように調整します.実際にはくろこげパンダさんの計算のように増幅度をそのように調整していると思います.
>1.8 倍しかしていないという時点で ISO200 ではありませんし、単に ISO200 で適正露出のものを ISO180 で撮っただけということです。
露出は実質的にも名目的にもあくまでISO200として撮っています.但しバケツ以降の増幅率を従来より下げるとバケツ上の白ピーク電圧が上がります.つまり被写体の輝度の上限を上げることができます.これが輝度受け入れのダイナミックレンジの拡大なのです.
書込番号:5632438
![]() 0点
0点
わたしのリンク先を見ると
・RAW現像時の露出調整
・トーンカーブによる中間調を持ち上げた例
・ガンマとコントラストとコントラスト中心で持ち上げた例
・露出調整で持ち上げ(結果的に生成画像白ピーク以上にデータがあるので)て、DR拡張を使ってハイエストを押し込んだ例
があります。
カメラ内で2/3段なり1段なりアンダー露出を行い、2つ目以降の方法を用いれば、ハイエストを圧縮して見かけ上白飛びを押さえることが可能です。
RAW記録可能なカメラでSILKYPIX Developer Studio 3.0をお持ちなら、ご自分のカメラで1段アンダーで露出して以下のテイストバンクより
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/community/stf/?mode=al2&namber=8&rev=&no=0
Zone Hi用のテイストを適用してみてください。
もちろんノイズは増えますので、アナログ段でのノイズ対策や、画像生成時のノイズに対する処理を同時に行うと思います。
14bitADCは、イメージャーの飽和出力と12bitRAW(画像生成はこのデータで行うと思われる)のフルビットを合わせるためのデジタルアンプ処理に使われていると考えるのが妥当です。
少なくともアナログアンプのノイズ混入を減らせます。
難しいアナログアンプの調整よりコストダウンも出来ますし…。
ノイズを減らせた分は「ダイナミックレンジ向上」と言っても良いのですが、『14bit「で」(または「の」)トーン調整して豊かな階調』みたいに説明をされると…それは間違いなわけです。
書込番号:5632439
![]() 0点
0点
昭和1桁さんの説明上の破綻というか矛盾しているところを一緒に考えた方がよいのでしょうか?>みなさん
書込番号:5632444
![]() 0点
0点
Sony が言っているダイナミックレンジという用語の従来の写真用語で最も近いのは寛容度(ラチチュード)だと思います.
書込番号:5632452
![]() 0点
0点
イメージャーの非直線部分(飽和出力付近)までRAWに記録されていたとして、それをそのまま使うとハイエストでカメラの個体毎に期待外の色づきが起こります。
そのため、通常はマージンを取って非直線部分の下に「白クリップレベル」を設定するのが常道だと思います。
もちろん記録されているので、それをあるロジックに従ってカメラ個体に合わせた利用方法は考えられます。
この件は異存がないと思います。
書込番号:5632456
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
>ハードウェアのダイナミックレンジ拡大により白飛びしなくなった、との誤解です。
誤解ではありません.
>このときに黒つぶれしていた部分に諧調が出てくるならダイナミックレンジは向上した、黒つぶれがそのままならダイナミックレンジは変わらずと言えるでしょう
N2がやっているのは白飛び対策だけで,黒潰れ対策はやってないと思います.宣伝もしてません.N2を持っておられる方に是非試していただきたいと思います.
書込番号:5632523
![]() 0点
0点
「159%の改善」についてですが…
2^(-3/3)=1.58740…
つまり、約159%です。
ISO160はISO100の2/3段アップですので、イメージャーからの出力のADはISO100と同一で露光量のみ2/3段減らすことによってデジタル信号のフルビットまでの余裕を2/3段稼いでいるだけですね。
で、あとはトーンの調整で暗部から中間調をきっちり2/3段持ち上げて、ハイライトからハイエストにかけて階調を圧縮すれば「159%の改善」の出来上がりです。
同じ言い方をすれば、α-7 DigitalなどのZone Hiは「約200%(約1段だから)の改善」だし、FUJIのSR機だと「400%(2段だから)の改善」です。
何も難しいことはしていませんね。
書込番号:5633136
![]() 0点
0点
kuma_san_A1さん
2^(-3/3)は 2の(2/3)乗 の誤りですね.電卓では4の0.3333乗で出ます.
1.59の由来がよく分かりました.他社でも同様のことをやっているとはこのことですか.
どうも有り難うございます.
書込番号:5633245
![]() 0点
0点
あ!表計算ソフトのセルからコピーするときに間違えました。
そうです。
2^(2/3)のことです。
書込番号:5633279
![]() 0点
0点
他社でも…
FUJIのSRはハードウェアも使ってますがトーンの配置というかハイライトからハイエストを圧縮という意味では同様です。
一番近いのはα-7 Digitalやα Sweet DIGITALのZone Hiですね。
また、NIKONのデジタル一眼レフなどで同様にハイエストが粘るトーンを設定しているカメラもあります。
書込番号:5633290
![]() 0点
0点
>あとはトーンの調整で暗部から中間調をきっちり2/3段持ち上げて、ハイライトからハイエストにかけて階調を圧縮すれば「159%の改善」の出来上がりです
アナログで輝度受け容れ幅を拡大した後,デジタルでこの処理を行うことによって中間の全域にわたって階調を再調整するわけですね.そうすれば白飛びだけでなく黒潰れも改善されるということですか.
もっと早く教えて欲しかったですね.
書込番号:5633591
![]() 0点
0点
>アナログで輝度受け容れ幅を拡大した後,デジタルでこの処理を行うことによって中間の全域にわたって階調を再調整するわけですね.
違います。
露光量を減らした(つまりアンダーに露出)だけです。
暗部は12bitRAWというか処理のカメラでもたっぷりと情報があるのに落とし込んでつぶしているカメラがほとんどです。
それをちゃんと出しただけです。
ただし、ノイズは目立つようになるけど、そもそもISO160にした場合のノイズとレベル的にはあまり変わらないので問題ないのです。
「もっと早く」とおっしゃいますが、最初からそう書いていますし、みなさんもそのように説明されていたので遠慮してました。
過去に御納得いただけなかった経緯もございますし。
「あなたが明確に実証をされていないのであれば、メーカーがわざわざそのようなことをうたうはずがありませんから、メーカーの言い分を信じる」というような御主張だったと記憶しています。
書込番号:5633718
![]() 0点
0点
>私はSony が意味しているダイナミックレンジに忠実なのです.
>S/N比が1.59倍になるわけではないでしょう.
Sony が意味している、ではなくて、昭和一桁さんがカタログかホームページを読んで Sony が意味していると思っている、が正解ではないですか?だから、独自の定義と申し上げている訳で。
> 露出は実質的にも名目的にもあくまでISO200として撮っています.但し
>バケツ以降の増幅率を従来より下げるとバケツ上の白ピーク電圧が上がります.
>つまり被写体の輝度の上限を上げることができます.これが輝度受け入れの
>ダイナミックレンジの拡大なのです.
よく考えてください。アンプ部で 1.8 倍しかしていないということは、ISO180 で撮っているのと何ら変わらないということです。ですから、昭和1桁さんの推測は、ダイナミックレンジを拡大しているのではなく、単に ISO180 で低露出で撮って白飛びを抑えているのと全く変わりないロジックなのです。
繰り返しになりますが、昭和1桁さんの推測は、カメラに ISO200 と設定したら、内部的に ISO180 で撮る、というだけです。低露出で撮っただけなので、白飛びは確かに抑えられますが、ダイナミックレンジ拡大にはなりません。
>N2がやっているのは白飛び対策だけで,黒潰れ対策はやってないと思います.
>宣伝もしてません.N2を持っておられる方に是非試していただきたいと思います.
くろこげパンダさんが言われるように、重要なのは非線形のトーン処理なのですが、上記の発言からも昭和1桁さんは、それには全く言及していないというより、上記の御説で白飛びが抑えられる=ダイナミックレンジが拡大すると思っているようでしたので。
何度も書いているように、中間調〜暗部のトーンが上げられるのはどうしてかと考えれば、黒潰れ対策こそがメインで、それがCCDのノイズ低減(=高感度化)だと認識すべきだと思いますが。
> もっと早く教えて欲しかったですね.
いや、ですから京都のおっさんさんが以前からこのように推測していて、このスレでも皆さんから何度も指摘されているのですが…
書込番号:5633719
![]() 0点
0点
>違います....それをちゃんと出しただけです
ちゃんと出して貰えば充分です.
書込番号:5633768
![]() 0点
0点
>みなさんもそのように説明されていたので遠慮してました。
>過去に御納得いただけなかった経緯もございますし。
私を含めてですが、聞く耳を持つのは重要ですね。
>ちゃんと出して貰えば充分です.
でも、kuma_san_A1さん以外の方も、皆さんちゃんと説明されてたと思いますよ?
書込番号:5633848
![]() 0点
0点
on the willowさん
>昭和一桁さんがカタログかホームページを読んで Sony が意味していると思っている、が正解ではないですか?
その通りです.だから、私独自の定義ではないのです.ところで貴方はS/Nが1.59倍になるとお考えなのですか?
>カメラに ISO200 と設定したら、内部的に ISO180 で撮る、というだけです。低露出で撮っただけなので、白飛びは確かに抑えられますが、ダイナミックレンジ拡大にはなりません。
内部的に180で撮ると考えるかどうかは,考え方だけで実質に関係ない話です.要するにISO200で白ピークの時点でバケツが半分を超えていれば実質的に目的を達成しています.従来ははバケツの半分にしかならなかったので,明らかに受け入れ輝度の幅は拡大されます.それをダイナミックレンジの拡大と見るか否かは定義の問題が絡みます.
>白飛びが抑えられる=ダイナミックレンジが拡大すると思っているようでしたので。
ダイナミックレンジという言葉は誤解の元なので敢えて避けます.輝度受け入れ幅の拡大効果の一つは白飛び抑制ですが,更に中間階調の最適な再配備が可能になります.
>中間調〜暗部のトーンが上げられるのはどうしてかと考えれば、黒潰れ対策こそがメインで、それがCCDのノイズ低減(=高感度化)だと認識すべきだと思いますが。
ノイズ低減は勿論望ましいですが,ノイズの改善がなくても輝度幅の拡大によって中間調の改善が期待できます.
書込番号:5634073
![]() 0点
0点
昭和1桁さん、「これまで書いたことは全部忘れてください」で良いのではないですか?
で、結論は[5633136] (計算式だけ訂正してね)ということで。
問題点としてはハイライトからハイエストが輝度情報にしろ色情報にしろ圧縮されるので
・色合いが若干不自然になる
・細かなディテールが圧縮されるためつぶれる
現象とトレードオフしていることになります。
つまり良いことだけではないということです。
ダイナミックレンジ拡大機能の考察の結論
・露出計に対し感度をISO160と2/3段上にずらしてアンダー露出で撮影(イメージャーとADCはISO100となんら変わらない)し、そのリニアデータを元にトーン調節により、白ピーク(フルビット近く)の3段と1/6段下のレベル(2.5段と2/3段を加算…[2^(-11/3)=0.078745]…約7.87%)を18%グレー基準値の118/255となるようにし、暗部からミッドハイライトまでは基準カーブに近似する。
ハイライトとハイエストは圧縮する。
みなさん異存がなければ、これでしめられると思うのですが…。
書込番号:5634194
![]() 0点
0点
kuma_san_A1さんの説明で、やっと昭和1桁さんも理解されたようですので、私もそろそろ終わりにしたいと思いますが…
>その通りです.だから、私独自の定義ではないのです.
ですから、「Sony の言うダイナミックレンジ」というのがそもそも昭和1桁さんの解釈に過ぎず、独自の定義だと申し上げている訳です。
>内部的に180で撮ると考えるかどうかは,考え方だけで実質に関係ない話です.
ですから、Sony N2 の実質的な動作を推測しているのですよね?
昭和1桁さんの推測は、低感度で撮影するのと何ら変わりないというのはご理解いただいたということでよろしいのでしょうか?
>ノイズ低減は勿論望ましいですが,ノイズの改善がなくても輝度幅の拡大によって
>中間調の改善が期待できます.
ノイズを無視して、ダイナミックレンジという一般的な言葉に、昭和1桁さんの独自の定義を加えると、こういう誤解の元になるということを指摘させていただいています。
ノイズの改善が無ければ、CCD素子が本質的に持つショットノイズや暗電流等のノイズも増幅され、中間調〜暗部を持ち上げようとしてもノイズが目立ってしまいます。(=中間調の改善につながらない)
書込番号:5634252
![]() 0点
0点
すいません、書き込んだ後に、[5634194] kuma_san_A1さんの書き込みを拝見しました…
>みなさん異存がなければ、これでしめられると思うのですが…。
kuma_san_A1さんのご説明に異存ありません。
書込番号:5634262
![]() 0点
0点
また計算間違えちゃいました。
誤:・露出計に対し感度をISO160と2/3段上にずらしてアンダー露出で撮影(イメージャーとADCは ISO100となんら変わらない)し、そのリニアデータを元にトーン調節により、白ピーク(フルビット近く)の3段と1/6段下のレベル(2.5段と 2/3段を加算…[2^(-11/3)=0.078745]…約7.87%)を18%グレー基準値の118/255となるようにし、暗部からミッドハイライトまでは基準カーブに近似する。
正:・露出計に対し感度をISO160と2/3段上にずらしてアンダー露出で撮影(イメージャーとADCは ISO100となんら変わらない)し、そのリニアデータを元にトーン調節により、白ピーク(フルビット近く)の3段と1/6段下のレベル(2.5段と 2/3段を加算…[2^(-19/6)=0.11136]…約11.14%)を18%グレー基準値の118/255となるようにし、暗部からミッドハイライトまでは基準カーブに近似する。
ミスが多くてごめんなさい。
書込番号:5634297
![]() 0点
0点
> ダイナミックレンジ
↑ この言葉は、いつも長引く原因になり易いですネ(^^;)
被写体の輝度域を押し込めた(CCDに感光させた)所までで話を
完結させてるのか、素子の裸特性や実態まで含めて話を完結させ
てるのか・・・ってところでズレてるんでしょうネ?
ズレが認識できたようなので、閉めても良いと思います。
ズレの説明責任を果たしたい方はご自由に・・・ということで・・・(^^;)
書込番号:5634387
![]() 0点
0点
私もこの辺で終わりにしたいと思います.最後の方で黒潰れにも効果を期待した発言をしましたが,それは間違いのようですので取り消します.その他は回りくどい理解でお騒がせしましたが,大筋は間違ってはいなかったと思います.どうも有り難うございました.
書込番号:5634498
![]() 0点
0点
ダイナミックレンジについて理解してもらうのが目的で「AJISAI(テスト版)でのトーン調整」というのをリンクしているのですが、目的が達成できない?
昭和1桁さん、「大筋は間違ってます」ですよ。
最初の書き込み内容は妥当ですけど…その後が。
メーカーのセールストークは「ちゃんと説明しても理解してくれる人は少ないだろうから『イメージ』でアピールしよう」という方向みたいです。
わたしの年代でもすごい抵抗があるので、昭和一桁の大先輩なら言語道断だと思いませんか?
この掲示板で読み書きしていても感じますけどね(理解してもらえると嬉しい)。
・しめましょうと言った本人が「蛇足」しちゃいましたが、「どこが議論上ずれているのかを指摘し合う」のを終わりにしたかっただけです
書込番号:5634578
![]() 0点
0点
私も on the willowさん からダイナミックレンジの式を学ぶことができました。
最小出力に対し最大出力が何倍か。コントラストと同じようなものなのかな?
あと 2/3段は 0.67 とかやっちゃって…。ちゃんとべき乗計算しなきゃ駄目ですね。
お恥ずかしい限りです。
書込番号:5635029
![]() 0点
0点
S/Nでいうダイナミックレンジ(6dbが2倍…単位の書き方間違ったらゴメン)も段数(EV…これはリニアデータのbit数に一致)も光学濃度(計算式はwebで検索)もルクス秒(でしたっけ?他のスレッドでフィルムの特性のグラフで紹介してもらった)も比を対数表示ですよね?
書込番号:5635098
![]() 0点
0点
この場合に対数を用いる理由は、変数(この場合は 最大出力/最小出力)の変動が大きい場合にも、結果として出る値(関数値)の変動が少なくて済むように、と理解しています(この場合は変数の変動は大きくはないでしょうが)。対数にプロットすれば「ダイナミックレンジ 0(db)」という意味が出てくるとは思いますけど。
掲示板は情報交換の場であり正しい理解に到ればそれでいいので、これまでのやりとりは全然どうでもいいです。私自身もたくさんおかしな書き込みがあると思います。
ただ「バケツの量が半分」云々の記述から思うに、やはり「ハードウェアの ISO値の操作で白飛びを回避している」との考えでいらっしゃるのだなと思います。そこが残念です。
自分の体験上、物事の理解って他人から説明を受けてすぐにがてんがいくほど簡単には行かないものです。
理解の仕方は人それぞれ、でも真実は一つ。
自分は「自分が無知だった頃、こういう説明を受ければ理解しやすかったろうな」ということを念頭に置いて書き込みをしています。
書込番号:5635335
![]() 0点
0点
kuma_san_A1さん
>「大筋は間違ってます」ですよ
間違っていたのは取り消した部分だけと思っています.私が
>>もっと早く教えて欲しかったですね
といったのは
>>アナログで輝度受け容れ幅を拡大した後,デジタルでこの処理を行うことによって中間の全域にわたって階調を再調整するわけですね.そうすれば白飛びだけでなく黒潰れも改善されるということですか
についてでした.この部分は貴方が否定されたので私の早とちりであった訳ですが.過去の発言に対して全面的に非を認めたように誤解されていますね.
京都のおっさんさん
>「バケツの量が半分」云々の記述から思うに、やはり「ハードウェアの ISO値の操作で白飛びを回避している」との考えでいらっしゃるのだなと思います。そこが残念です
ADC以前で光量の受け入れ幅(Sonyでいうダイナミックレンジ)が広げられていると思います.ただしデジタルで階調の再調整はあると思います.
最後にN2ユーザのみなさんに,
私はSonyのHPにおけるダイナミックレンジ拡大の説明は正しいと思います.是非実機で確かめていただきたいと思います.
書込番号:5635832
![]() 0点
0点
とりあえずひとつSONYから返答が来ました、
それは、
サイトの説明は光量の調整をCCDが行っているのではなく、
あくまでCCDに当たる以前に光量調整を行っているということを説明したものとの回答でした。
書込番号:5635894
![]() 0点
0点
皆様の熱い?ご議論は、自分にはもうわからないことだらけのレベルになってきたので恐縮ですが、
購入して少し使ってみた印象としては、
ボクのへっぽこ目で見る限りは、他の所持コンデジと比べてハイライト部もシャドー部も両方しっかり描写できているように感じました。
結果として出来上がる画像でこれならいいなあと思っております。
書込番号:5636169
![]() 0点
0点
ところでken311さん
あのカウンターの光の加減は
・レフ球などのスポットライト風に写る
のと、
・アクリルカバー越しの照明もしくは間接照明風に写る
のとどっちが現実に即した描写なのでしょうか?
書込番号:5636227
![]() 0点
0点
>>あのカウンターの光の加減は
自分の目にどう写るかという極めて主観的な判断でいうと、
スポットライト的でもあり、間接照明風でもあるって感じなんですよね。
状況としては、いつも右端の扉の最上部に撮影時だけわざわざライト(100V-100W)を取り付けて、影ができるようにして撮ってます。
ノイズを見たいという観点なので、影をあえて作りたいという思惑ですね。
takebeatさんに購入してもらって検証したりしてもらうと楽しいんですけどいかがでしょう?
書込番号:5636268
![]() 0点
0点
直接光が当たっているのであればF30の描写の方が現実に近いかもしれませんね。
Z1000は1000万画素一番乗りだったので非常に興味があり買いましたが、
今出ている1000万画素は面白みにかけるので購入意欲がわきません
N2と同じCCDを搭載した28mmレンズ搭載のデジカメが出たらわかりませんが。
書込番号:5636543
![]() 0点
0点
>ADC以前で光量の受け入れ幅(Sonyでいうダイナミックレンジ)が広げられている
>と思います.ただしデジタルで階調の再調整はあると思います.
独自の解釈から抜けきれない方がまだいらっしゃいますが、
【CCDの受光量「ダイナミックレンジ」が〜】というホームページの表記についてソニーに問い合わせたところ、ダイナミックレンジとは、画像が黒から白まで表現する幅のことで、CCDの受光量そのもののことをダイナミックレンジと言っている訳ではないとのこと。
まあ、当然とは思いますが。
書込番号:5644300
![]() 0点
0点
世間一般のダイナミックレンジに関する根深い誤解は、フィルムの撮影経験に起因するのかな、と勝手に思っています。
私はフィルム経験が無いのであてずっぽうですが、ラティテュードと白飛びは同義なのではないかと。
「A というフィルムでは白飛びするが、同じ露出で B というフィルムでは白飛びしない。よって B がラティテュードが広い」
といったような。
明暗に対する入出力が CCD は線形という違いはありますが、同じようなことをシミュレートするには CCD換装システムがあればよいのでしょうね。
A という CCD、それと感度(ISO感度ではない)が同じで飽和電圧のみ大きい B という CCD。
B を使う時にクリッピングポイントを B の飽和電圧に合わせるのなら、同じ露出で白飛び部分は減るのでしょう。でも画像生成のトーン処理が A と同じであれば、結局はアンダー露出で写したのと同じ(感度が低いのと同じ)になるでしょう。
と予想します。
書込番号:5645330
![]() 0点
0点
こんな記事もありました。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/compact/2006/05/29/3860.html
ゾーンHi みたいな処理は、他のメーカーもおおっぴらには言っていませんが、実はこっそりやってるような気もします。
無責任な発言ですけど、キヤノンはやっていない、サンヨーはやっていそう、みたいな。
書込番号:5648945
![]() 0点
0点
on the willowさん
>ダイナミックレンジとは、画像が黒から白まで表現する幅のことで、CCDの受光量そのもののことをダイナミックレンジと言っている訳ではないとのこと。
私が輝度の受け入れ幅と解釈していた通りではないですか.
書込番号:5649356
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
>結局はアンダー露出で写したのと同じ(感度が低いのと同じ)になるでしょう。
元々白飛びしていなかった部分に限ればアンダー露出になると思います.しかし全画面については適正露出になっています.そこで階調の再調整が必要になるのではないでしょうか.
ご紹介のHPの中でSonyの技術者は
「S/N比とダイナミックレンジの向上が技術課題だと捕らえています」
といってますね.すなわちS/Nとダイナミックレンジを別物と考えています.
書込番号:5649469
![]() 0点
0点
>>私が輝度の受け入れ幅と解釈していた通りではないですか.
まるっきり逆でしょう、
>>輝度の受け入れ幅
というからにはSONYが否定したCCDの受光量の事を指してしまいます。
書込番号:5649535
![]() 0点
0点
[5649469] 昭和1桁さん
>ご紹介のHPの中でSonyの技術者は
「S/N比とダイナミックレンジの向上が技術課題だと捕らえています」
といってますね.すなわちS/Nとダイナミックレンジを別物と考えています.
良く読めば「と」が誤りであることに気づくはずです。
採録した記者が理解していなくて、編集デスクも理解していないとこういうことになります。
「S/N比、つまりダイナミックレンジの向上が…」と置き換えると、意味の通じる記事になります。
書込番号:5649613
![]() 0点
0点
適当takebeatさん
原文は
「CCDの受光量「ダイナミックレンジ」が、約59%もアップ(従来機比)。」です.
「画像が黒から白まで表現する幅のことで、CCDの受光量そのもののことをダイナミックレンジと言っている訳ではないとのこと」
の意味は,受光量「ダイナミックレンジ」とあるので,受光量=ダイナミックレンジと読めなくもないが,CCDの「受光量受け入れ幅」=ダイナミックレンジであると釈明したものと思います.
なお,私自身は受光量そのものをダイナミックレンジとはいっていません.
書込番号:5650400
![]() 0点
0点
kuma_san_A1さん
>良く読めば「と」が誤りであることに気づくはずです
誤りではないと思います.S/Nの向上とダイナミックレンジの改善は関連はありますが,信号の飽和を含んだ領域にまたがる場合には別個の改善手段が有効です.
書込番号:5650510
![]() 0点
0点
S/Nは最大記録レベルとノイズレベルの比だからデバイスのダイナミックレンジそのものです。
対数で表示すると引き算で求められます。
月曜に編集部に訂正促すメール出しておきますね。
59%改善についても根拠となるものは2/3段マイナス露光であると示しましたからデバイスの改善とは何の関係もないことを理解していただいたはずです。
露出制御とトーン設定なのです。
何度も同じことを書かせないで欲しいですね。
>素人考えですが,CCD自体のダイナミックレンジというのは,デジタル段階での階調化に関係なく,アナログ出力の段階で評価できるのではないでしょうか.
この部分だけですよ。筋が通ってそうな書き込みは。
すぐその後からおかしな独自理論になっているので「忘れてください」というのをお勧めしたのですが…。
昭和1桁さんあてのコメントでした。
書込番号:5650813
![]() 0点
0点
kuma_san_A1さん
アンプを除くCCDに改善を行っていないことは承知しています.にもかかわらず「CCDの受光量「ダイナミックレンジ」が、約59%もアップ(従来機比)。」というのはカメラとしてCCDに入ってくる受光量の幅が広がった.Sonyはそれをダイナミックレンジの拡大といっているのです.この記事でも後処理云々といっていますので,Sony はデバイスのS/Nとは別の概念で語っています.
訂正を促すメールを送っても私と同じ返答が返ってくるでしょう.
書込番号:5650917
![]() 0点
0点
>私が輝度の受け入れ幅と解釈していた通りではないですか.
全く違います。そもそも輝度の受け入れ幅とは何ですか?
光の受け入れ幅ということですか?受け入れ幅とは何ですか?
皆さんに正確に伝わるよう、正しい用語を使っていただければと思います。
昭和一桁さんはご自分の発言をお忘れでしょうか?
>「CCDが受け取る光量を調整」=「CCDの受光量を調整」=ダイナミックレンジの調整
その後、どうやって「増えた受光量を処理するか」という話になったんですよね?
つまり、トーンカーブによる調整を否定した上で、受光量の拡大=ダイナミックレンジの拡大だという推測を展開されたのは忘れないでください。
>カメラとしてCCDに入ってくる受光量の幅が広がった.Sonyはそれをダイナミック
>レンジの拡大といっているのです.
昭和1桁さん独自の「ソニーのダイナミックレンジ」理論はいい加減に止めましょうよ。ソニーはそれを否定しています。受光量=ダイナミックレンジではないと言っているのですから、受光量(の幅が広がった)=ダイナミックレンジの拡大ではないということです。
ソニーが主張しているのは画像のダイナミックレンジ(黒から白の幅)が広がった、つまり黒潰れや白飛びをしにくくなったという1点のみです。
ソニーの説明は、すでにご自分の推測の正しさを支える内容ではないんですよ。
書込番号:5651037
![]() 0点
0点
>アンプを除くCCDに改善を行っていないことは承知しています.
昭和1桁さんは、CCDでは改善が無いことをやっと理解されたようですが、アンプ部で改善されていると主張されています。
しかし、昭和1桁さんの技術的説明では、単に低露出で撮影したのと全く変わらない結果にしかならないことは私が何度も説明しました。
59% アップの理由も説明できておらず、画像のダイナミックレンジが広がる理由にもならない、それでもご自分の説にしがみつく理由はなんでしょう?
書込番号:5651062
![]() 0点
0点
長い長い文章を用意したのですが、消しました (^_-;)
結論としては、昭和1桁さんは、白飛びが発生するロジックが理解できていない。だから、逆に白飛びさえ抑えればいいと思っている。だから、露光量と CCD とアンプ部のダイナミックレンジの説明がめちゃくちゃなんだと気付きました。
昭和1桁さんのロジックについて、くろこげパンダさんがまとめられたコメントがあります。
[5629860] くろこげパンダさん2006年11月12日 17:17
[5630177] 昭和1桁さん2006年11月12日 18:45
このロジックは、単に ISO180 で撮影しているに過ぎないというのは理解されたのでしょうか?
昭和1桁さん、なぜ白飛びが起きるのでしょう。よく考えてください。
書込番号:5651164
![]() 0点
0点
on the willowさん
>受け入れ幅とは何ですか?
Sonyのいっている「ダイナミックレンジとは、画像が黒から白まで表現する幅」と同じと考えて頂いて結構です.画像が黒から白まで変わるのは入ってくる輝度が変化するからでしょう.
>ソニーが主張しているのは画像のダイナミックレンジ(黒から白の幅)が広がった、つまり黒潰れや白飛びをしにくくなったという1点のみです
SonyはCCDの受光量「ダイナミックレンジ」が、約59%もアップ(従来機比)といっていますから,(黒から白の幅)が広がったのはCCDの受光量「ダイナミックレンジ」が拡大されたからと言っていることになります.
>昭和1桁さんは、CCDでは改善が無いことをやっと理解されたようですが、アンプ部で改善されていると主張されています
私はCCDの受光ダイオード(バケツ)の部分は改善されてないと当初からいっています.その後の増幅度を変える訳ですが,これをアナログでやるかデジタルでやるかは原理的には同じだが,現実にはN2ではアナログだろうといっているのです.
>昭和1桁さんの技術的説明では、単に低露出で撮影したのと全く変わらない結果にしかならないことは私が何度も説明しました
全く変わらないのではありません.ダイナミックレンジ拡大後の画像は,画面全体としては適正露出でありながら,拡大前に飽和点以下だった部分のみ拡大前に比べて低露出になるのです.ここが貴方の最大の誤解点だと思います.
>59% アップの理由も説明できておらず、画像のダイナミックレンジが広がる理由にもならない、それでもご自分の説にしがみつく理由はなんでしょう?
説明できています.くろこげパンダさんは完全に理解されておられますよ.貴方がまだお分かりになっていないだけです.
>このロジックは、単に ISO180 で撮影しているに過ぎないというのは理解されたのでしょうか?
上記のように単にISO180 で撮影しているのとは違います.
>昭和1桁さん、なぜ白飛びが起きるのでしょう。よく考えてください。
バケツの飽和かアンプの出力の飽和かの何れかが起きることによって発生します.
書込番号:5652158
![]() 0点
0点
>SonyはCCDの受光量「ダイナミックレンジ」が、約59%もアップ(従来機比)と
>いっていますから,(黒から白の幅)が広がったのはCCDの受光量
>「ダイナミックレンジ」が拡大されたからと言っていることになります.
その解釈が間違っていると何度も…
ソニーに確認しましたが、広がったのはダイナミックレンジであって、受光量を指し示している訳ではないということです。
断定して書かれているから、その根拠を皆さん求めているのですが、結局、昭和一桁さんの「解釈」にすぎないんですよね。
>ダイナミックレンジ拡大後の画像は,画面全体としては適正露出でありながら,
>拡大前に飽和点以下だった部分のみ拡大前に比べて低露出になるのです.
>ここが貴方の最大の誤解点だと思います.
ご自分の説を理解できないとは…(苦笑)
いいですか、
[5629860] くろこげパンダさん 2006年11月12日 17:17
のくろこげパンダさんの説明は、ISO180 で撮影した場合と全く同じロジックです。
良く読みかえして、ISO180(と設定したら)、アンプが何倍して、白ピーク電圧を何ボルトに設定するかよく考えてみてください。
その上で適正露出になりえないのは何度も指摘しましたが、これが理解できないと、適正露出になり得ないのも当然理解できませんね。
ちなみに飽和点とは何ですか? ADC 前の電圧ですか?
ADC 前の最大入力電圧は一定で、ADC のビット数も同じと言っていましたよね?
何が拡大するんですか?
>くろこげパンダさんは完全に理解されておられますよ.
くろこげパンダさん、ご説明をお願いします。
>バケツの飽和かアンプの出力の飽和かの何れかが起きることによって発生します.
なぜバケツの飽和やアンプの出力の飽和が起こるのか、という問いです(苦笑)
書込番号:5652294
![]() 0点
0点
「Sonyの言っている」にこだわっているから抜け出せないんですよ。
これ以上ないほど明快に説明したはずなのに…。
書込番号:5652326
![]() 0点
0点
> 対数で表示すると引き算で求められます。
なるほど対数にする意味はありますね。勉強になります。
で…再燃させるつもりは無かったのですが。
昭和1桁さん は「159%」という数値が導出されたことに満足されただけで、本質的な誤解は解けていないことはわかっておりましたので、考える材料として CCD換装システムを提示しただけなのですが。あと T50 の記事の紹介は「N2 以前にも同様のことは行われていたようだ」程度の理由です。
CCD換装で言いたかったのは、
「ダイナミックレンジの上がった CCD に交換しただけでは、出力画像のダイナミックレンジは上がらない」
ってことだったんですけど、どうもそこにも誤解があるようで。
出力画像のダイナミックレンジの上がらない理由は、8bit jpeg → 表示(出力系)のダイナミックレンジが、CCD → RAWデータ(入力系)のダイナミックレンジより狭いから、です。
別の言い方をすれば
「画像処理に細工をしなければ、見た目のダイナミックレンジは上がらない(見た目のダイナミックレンジを上げるには、画像処理に細工をする必要がある)」
です。
この場合の細工とは(ゾーンHi のような)トーン処理であったり、(覆い焼きのような概念の)マスク処理であったりしますが、目的は「ダイナミックレンジの範囲が狭い出力系に、ダイナミックレンジの広い入力系を押し込める」ことです。
これらのことは「体験して」「感じて」「考えて」みてくださいとしか言いようがありません。材料はこのスレにいっぱいあると思います(例えば RAW撮りもその一つ)。
別に恩着せがましく言うわけではありませんが、自分がダイナミックレンジを知りたいと思った時(撮影していて必要性を感じた時)、すぐにはこれだけの材料は揃いませんでしたので(よって自分はすぐには目的を達成できなかった)。
正直言って 昭和1桁さん がダイナミックレンジにこだわる理由が私にはよくわかりません。
・ダイナミックレンジを何故必要とするのか(出力画像のダイナミックレンジを上げるため? あるいはラティテュードを上げるため?)。
・ダイナミックレンジをどのように拡大するのか(独自理論がおありのようです)。
・ADCまでで拡大されたダイナミックレンジをどうやって結果の出力画像に適用するのか。
これらのことが平行に語られ、(これらはどれも重要なので)そのこと自体はよいのですが、それらのどれもが何か違和感のある言葉で語られているように私には感じられます。
書込番号:5652400
![]() 0点
0点
> 「Sonyの言っている」にこだわっている
「ミノルタのGTレンズ」に似た響きを感じますね(わからない人ごめんなさい)。
書込番号:5652441
![]() 0点
0点
on the willowさん
>ソニーに確認しましたが、広がったのはダイナミックレンジであって、受光量を指し示している訳ではないということです
私もダイナミックレンジが広がったと解釈していますし,受光量自体を意味していないと明言もしています.食い違いはありませんね.
>ちなみに飽和点とは何ですか? ADC 前の電圧ですか?
そうです.
>ADC 前の最大入力電圧は一定で、ADC のビット数も同じと言っていましたよね?
何が拡大するんですか?
ダイナミックレンジ拡大前はISO100でバケツが一杯になる受光量の時に飽和電圧(例えば1v)に達するように設計されています.このままISO200(先に160でなく200で議論してますから200で行きます)にすると,増幅度が2倍に設定され,バケツが半分の時に同じ飽和出力電圧に達します.出てくる画像は感度が違っても全く同じものが出力されます(ノイズは増えるが).
ダイナミックレンジを2倍に拡大する時は一旦飽和電圧を2倍(2v)にすると考えて下さい.するとバケツが一杯になるまでダイナミックレンジが拡大されますから画像の内容は白飛びが減るなど変わりますが,適正露出です.このまま2vをADCのフルビットに対応させればダイナミックレンジが拡大されたデジタルデータが得られます.ここでADCの電圧を一定に揃えたいので,2vを1vに減衰させると考えてください.それでもデジタルデータはDRが拡大されたまま適正露出です.
以上の説明では理解の容易のために一旦飽和電圧を2vに上げた後1vに減衰させるように説明しました.これを一度にやるためにはアンプの増幅度をISO200の時の半分にすれば同じことですね.それでもDRは拡大され適正露出のままです.
別の説明をすれば,ISO200に設定することにより露出が半減するのでバケツは2倍の光量まで飽和しません.また増幅度が半減していますから,バケツが半分に達しない光量に対しては貴方が仰る通り拡大前より暗くなりますが,バケツが一杯になる光量ではフルビットに対応しますから全画面では最適露出が確保される訳です.
外でも述べましたが,デジタル系のビットに余裕があれば上記のアナログ操作をデジタルで行うことも原理的に可能です.しかしSonyは既に14ビットをフルに利用しているようですので,・・・・
>なぜバケツの飽和やアンプの出力の飽和が起こるのか、という問いです(苦笑)
上記の説明で尽くされていると思います.
書込番号:5653204
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
>正直言って 昭和1桁さん がダイナミックレンジにこだわる理由が私にはよくわかりません。ダイナミックレンジを何故必要とするのか(出力画像のダイナミックレンジを上げるため? あるいはラティテュードを上げるため?)
同じことと考えています.デジカメの銀塩に及ばない項目の一つとしてダイナミックレンジが挙げられ,各社とも改善に努力していますよね.
書込番号:5653243
![]() 0点
0点
ISO100とISO200の説明をしているので合わせます。
説明上「一旦飽和電圧を2Vにして後で1Vに減衰させる」として、一度にやるには…と書かれてますがm」結局「アナログではなにもしない」ということです。
単に1段露光量がアンダーになるだけです。
基本感度と同じ画作りのためにはAD前のアナログ段で2倍に増幅しますが、それをしないで「1段」の飽和までのマージンを稼ぐということです。
で、中間調までを持ち上げハイライトからハイエストライトまでを圧縮します。
これらはAD後のデジタル信号に対して処理されます。
弊害は通常中間グレーの上2.5段までリニアに再現されるのですが、リニア領域を2段程度に狭めることになります。
バケツの話はもう結構です。
イメージャーの飽和電圧は固定して考えてください。
アナログアンプで増幅したから飽和電圧が変化するって考えたらダメです。
変化するのはアンプ出力です。
ADのフルビットに対応する電圧も固定して考えてください。
この辺の用語を定義しない、混用するところがわかりにくくしている原因です。
書込番号:5653326
![]() 0点
0点
> 単に1段露光量がアンダーになるだけです
ここが理解できないみたいだからコロンブスの卵的発明だと思っているみたいです。
ずーっと「適正露出になる」って言っておられますから。
反証はできますけど、本人がまず「自分は間違っているのではないか?」という立脚点に立たないことにはどうしようもありません。
こちらが重要なことを書いても読んでいませんから。
書込番号:5653641
![]() 0点
0点
kuma_san_A1さん
>結局「アナログではなにもしない」ということです。単に1段露光量がアンダーになるだけです。
増幅度を減らすだけで,受光量がDR拡大前の2倍の時に飽和電圧に達する(フルビットにマッピング)という重要な変更が行わるのです.
>バケツの話はもう結構です
バケツの有効利用がDR拡大のポイントです.
>イメージャーの飽和電圧は固定して考えてください。
説明目的で2vに上げるといいましたが,最終的に1vに固定しています.
>アナログアンプで増幅したから飽和電圧が変化するって考えたらダメです。
>ADのフルビットに対応する電圧も固定して考えてください
その通りです.
書込番号:5653747
![]() 0点
0点
京都のおっさんさん
>単に1段露光量がアンダーになるだけです
同じ飽和電圧に対して,受け入れ光量のレベルが2倍にアップすることがお解りになりませんか.
書込番号:5653785
![]() 0点
0点
デジカメの宣伝には随所にダイナミックレンジの拡大をうたっていますが、
これは詐欺商法に近いと感じています、
たとえば規格のがっちりしているオーディオCDではさすがにダイナミックレンジの拡大をいうと詐欺になるので、
広いダイナミックレンジを狭いところに押し込める技術としてコンプレッサーという言葉が使われ
「ダイナミックなコンプレッション」など、狭い範囲に広いものを押し込める表現をしています。
デジカメの画像もRGB各色8bitであるかぎりそれ自体が広くなる要素はありません。
昭和1桁さんはメーカーの宣伝文句を鵜呑みにしメーカーに踊らされているだけのように思えます。
書込番号:5653791
![]() 0点
0点
kuma_san_A1さん、
難しい(が正確な)指摘をしても昭和1桁さんは「理解できません」で終わってしまうし、それ以上理解しようとしません。逆に簡単に説明しても、指摘している問題点に気付いていないのか、気付かないふりをしているのか。アナログ、デジタルに限らず、一定の正確な知識があれば、ご自分の説の怪しさに気付くと思うのですが。
昭和1桁さん、御説の怪しい部分はあとで説明しますが、1点だけ。
>>なぜバケツの飽和やアンプの出力の飽和が起こるのか、という問いです(苦笑)
>上記の説明で尽くされていると思います.
全く説明になっていません。なぜバケツの飽和やアンプの出力の飽和が起こるのか、きちんと説明できないということは、理解できていないということですよね?
書込番号:5653799
![]() 0点
0点
on the willowさん
>なぜバケツの飽和やアンプの出力の飽和が起こるのか、きちんと説明できないということは、理解できていないということですよね?
余りにも失礼ですね.簡単な話です.バケツの飽和は受光ダイオードが受け付けないからだし,アンプの飽和は閾値(あるいはADCの最大入力電圧)で打ち切られるからです.
>御説の怪しい部分はあとで説明しますが
期待しています.
書込番号:5653871
![]() 0点
0点
>デジカメの画像もRGB各色8bitであるかぎりそれ自体が広くなる要素はありません。
適当takebeatさんの言われる通り、8bit JPEG sRGB で規定されている以上、最終的に出力される画像信号としてはダイナミックレンジは変えようがないんですよね。
私としては、「内部で扱える映像の幅が広くなった」ぐらいに捉えていますが、昭和1桁さんにそれが理解できるかどうか?
昭和1桁さんの御説は技術的に色々とおかしい部分が一杯ありますし、大学で講義されたことがあるぐらいのレベルであれば、当然考慮しなければならない部分が抜けています。それらを今までずっと指摘してきたのですが、「自分は間違っていない」という点から抜け出そうとしない人に、技術的問題点を指摘してもラチがあきません。
同じ話の繰り返しです。
それに付き合っても構わないのですが、もっと簡単に、 Sony N2 では昭和1桁さんが主張されるような方法をとっていないことを証明できます。それを理解していただくためには、まずは白飛びがなぜ起きるのかを理解していただかないと、先には進めないという状況ですね。
昭和1桁さんの理屈はある意味非常に簡単で、白飛びを防ぐには白方向に信号レンジを広げれば良い、という考えに基づくものだと思います。しかし、それ以前に、なぜ白飛びが発生するのか、また、撮像システムの基本的な構造や動作の知識が不正確なので非常におかしなものになってしまっていると感じます。
書込番号:5653872
![]() 0点
0点
昭和1桁さん の提唱する「ISO200」が、結局は「ISO100」でしかないことの証明。
-------------------------------------------------------------
ISO100 の時の18%グレーの被写体の出力電圧 = 1(V) * (1/2)^(2.5) = 0.177(V)
ISO200 の時の18%グレーの被写体の出力電圧 = 1(V) * (1/2)^(2.5) = 0.177(V)
ISO100 の時も ISO200 の時も適正露出下での主要被写体(18%グレー)の出力電圧は同じ。なぜなら ISO200 の時は
露出を 1/2倍
アンプ増幅率を 2倍
にしているから。
「ISO200 の時は 2V まで活用する。ADC へ出力するときは(ADC の最大入力が 1V なので)出力を 1/2倍に減衰させる」
だそうなので、
ISO200 の時の18%グレーの被写体の出力電圧 = 0.177(V) * 1/2 = 0.0884(V)
この 0.0884(V) という値は
「ISO100 の時、18%グレーの被写体を、適正露出の一段アンダーに撮った時の出力電圧に等しい」
なぜなら
ISO100 の時の18%グレーの被写体の一段アンダーの出力電圧 = 1(V) * (1/2)^(3.5) = 0.0884(V)
だから。
以上題意は示された。
-------------------------------------------------------------
わざわざ計算せずとも
「アナログアンプで増幅率を(ISO200のために)わざわざ二倍に引き上げた直後に、1/2倍に減衰させる」
って、
「なら初めから何もしなきゃいいじゃん」
ってだけで、特に証明する必要性を感じませんが。
書込番号:5653878
![]() 0点
0点
>バケツの飽和は受光ダイオードが受け付けないからだし,アンプの飽和は閾値(あるいはADCの最大入力電圧)で打ち切られるからです.
いや、ですから「なぜ受光ダイオードが受け付けない状態になったり,アンプの閾値(あるいはADCの最大入力電圧)で打ち切られるようなことになるのか」という質問なんですよ。
ラチがあかないので答えを書いちゃいますが、「バケツの容量やアンプ容量に対して光量が多すぎるから」ですよね?
白飛びに関して一番問題なのは、光量だということに気付いていただきたいです。
どうでしょうか?
書込番号:5653885
![]() 0点
0点
皆さんもういいかげんこの話題飽きませんか?
それより
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/dcamera/1152086297/774-776
これ面白いですね。
ADC は 16bit もあれば充分見たいですよ。
前に価格のどっかのスレで参考にしたんですけど(リンク示せなくてすいません)、コンデジの極小画素化によって「電子の数が 4096個以下になる」日はもうすぐって感じです(もしかしたらもうそうなってるのかも)。
もう「12bit RAW」すら必要無くなってくる可能性すらあります。
こと諧調・ダイナミックレンジに関する限り、かなり絶望的な状況ですね。
書込番号:5653906
![]() 0点
0点
>わざわざ計算せずとも
まさにその通りですが、昭和1桁さんは、白飛びの原因がバケツ容量だと思っているので、バケツ容量を使い切れば白飛びが改善すると思い込んでいるようです。
バケツを使い切る+ISO200 のためアンプ2倍にする+ADCの辻褄を合わせる為に半分に減衰する、という一連のロジックが、単純に情報を2倍にして半分にするだけ、つまり ISO100 で撮影しているのと何ら変わりないとは気付きません。(厳密にはアンプで2倍して減衰させている分だけ、ノイズは増える)
書込番号:5653911
![]() 0点
0点
on the willowさん
私が期待しているのは[5653204]に対する反論です.貴方風の言い方をするなら,それができないために話をそらそうとしておられませんか.でなければまともに反論してください.
>ラチがあかないので答えを書いちゃいますが、「バケツの容量やアンプ容量に対して光量が多すぎるから」ですよね?
バケツの方は仰るとおりですが,アンプの方が必ずしも同意できません.というのは例えばDR拡大をしていないISO200ではバケツが半分の時に出力は飽和します.それはバケツに対して光量が多すぎるのではなく,飽和(フルビットに対応する)の閾値に達したため,打ち切られたのです.
書込番号:5653919
![]() 0点
0点
ごめんなさい、ちょっと補足させてください
昭和1桁さんは、ISO200 の時はバケツの半分しか使えない、という観点から立脚しています。
ISO100 = バケツ1杯分の情報が使える
ISO200 = バケツ半分の情報しか使えない
アンプの容量を2倍にすると、アンプ部最終段までは、
ISO100 = バケツ1杯分の情報が使える
ISO200 = バケツ1杯分の情報が使える
ということになり、ISO200 でも2倍の情報が使えるから、
2倍の情報を 1/2 に減衰させているので、ダイナミックレンジが広がるという認識なのだと思います。ですが、皆さんお気づきのように、大きな勘違いをされていて、次の点に気付いていないようです。
・アンプ部で2倍していない(2倍して半分にしている)
=ISO100 と同じ増幅率=ISO200 ではない
・ISO100 で長時間露光したのと変わらない
ISO200 で撮るより、2倍のシャッタースピードで ISO100 で撮った方が綺麗だというだけの話です。
昭和1桁さんの立脚点の話に戻ります。
なぜ ISO200 で撮影するのか、それは光量がバケツ半分までしか使えない、ではなく、バケツ半分までの光量しかないから、アンプで2倍にしているに過ぎません。
もっと光量が稼げるなら、ISO100 で撮ればいいだけです。
書込番号:5654013
![]() 0点
0点
>でなければまともに反論してください.
いや、ですから昭和1桁さんに伝わるように、丁寧に説明(反論)しているつもりです。皆さん飽きているのは、昭和1桁さん以外には伝わっているからですよ。
>アンプの方が必ずしも同意できません.
いや、ですからバケツに対して光量が多すぎるのではなく、バケツ容量や、アンプ容量に対して「光量が多すぎる」からですよね。
もっと詳しく説明すると、ISO100 だと増感しないので、アンプ容量は関係ありませんから、バケツ容量より「光量が多すぎると」白飛びします。ISO200 だと増感するので、バケツ半分以上、つまりアンプ容量を超えるぐらい「光量が多すぎると」白飛びします。
白飛びの原因が、CCDやアンプが処理できる容量より「光量が多すぎる」ことだということを理解してください。
書込番号:5654035
![]() 0点
0点
議論も大きく飽和しているようで、N2の板の表示やリロードが遅くなっていて他のN2を検討している方に迷惑が掛かる可能性がありますので、終了するか「すべての口コミ」のほうに移られて続けていただければ助かりますm(_ _)m
書込番号:5654139
![]() 0点
0点
on the willowさん
>・アンプ部で2倍していない(2倍して半分にしている)
=ISO100 と同じ増幅率=ISO200 ではない
増幅率に関しては仰るとおりに認識しています.よって出てくる映像はバケツ半分以下については当然暗くなります.しかし露出はあくまでISO200に設定されていますから,バケツが受ける光量が拡大前の2倍まで大きくできる点がDR拡大なのです.
今,輝度1から輝度11までの11段階のグレイゾーンがあったとします.狭DRで撮影すると5までは飽和せず,6以上は白飛びします.同じ対象を2倍のDRで撮影すると10まで白飛びせず,11以上は白飛びします.
2枚の写真の5以下の明るさを比較すると異なって当然ですね.前者は明るく,後者では暗く写って良いのです.すなわちDRが2倍になるためには下の半分は暗くてよいのです.
>・ISO100 で長時間露光したのと変わらない
長時間でなく,ISO100で200並みの露出をしたのと変わず,拡大前に白飛びしてなかった部分は暗くなります.
>白飛びの原因が、CCDやアンプが処理できる容量より「光量が多すぎる」ことだということを理解してください
元々の原因はその通りに理解しています.
以上をご理解いただければ議論を止められるのですが.
書込番号:5654422
![]() 0点
0点
だから、視点がズレてるだけだと言っているのに・・・(^^;;)
------------------------
昭和1桁さん の御主張
『59%増』は、レンジ拡張前の白ピークを基点とし、新たに再設定
した白ピークのシフト量に着目して、『ソニーが言うところの、ダイナ
ミック拡張』 と御主張。
起算定点がDR拡張前の白ピーク点なのですから、間違いなく59%
の増分が発生します。
---------
※ 但し、現象としてはレンジが上に伸びた(と言うよりシフトした)ので
あって、『ダイナミックレンジ』 の本来の定義に当てはまらないと思います。
------------------------
on the willowさん の御主張
『ダイナミックレンジ』 の本来の定義である、最小レベルと最大レベルの
比率とする事で、機能を評価する事を御主張。(= 信号系が持つSN比)
御主旨を推察、要約すると、↓↓
露光量の減少で黒階調の一部がノイズフロアレベル以下になるため、
そこをトーン処理して、望むべき明度に復元しても、一旦、ノイズフロア
レベル以下になった部分は無効になる。すなわち、黒レベル端が浮いてくる
ことになるので、単純にダイナミックレンジが拡張したとする事はできない。
************************
『レンジ』と『ダイナミックレンジ』の名称を切り分けると、和平
交渉が成立するかも・・・?? 適当takebeatさんの 『コンプレッション』
という表現もイイですね(^^;)
************************
ご異存なければ、終了して下さい(^^;)
書込番号:5655097
![]() 0点
0点
>しかし露出はあくまでISO200に設定されていますから,
>バケツが受ける光量が拡大前の2倍まで大きくできる点がDR拡大なのです.
あの、露出とか ISO 値(増感)というもの自体を理解されていないんですね。
アンプの最終段(=ADCの入力時)で増感されていないのですから、ISO200 ではありませんし、ISO は増感値であり、露出ではありませんから、「露出はあくまで ISO200」という言葉自体が成り立ちませんよ。
>今,輝度1から輝度11までの11段階のグレイゾーンがあったとします.
>狭DRで撮影すると5までは飽和せず,6以上は白飛びします.同じ対象を2倍の
>DRで撮影すると10まで白飛びせず,11以上は白飛びします.
何度も申し上げますが、昭和1桁さんの説明では、狭DRも2倍のDRにもなりませんから引用した例えは成り立ちません。しかも、輝度とは何を指し示しているのか(入射光?CCDの出力?)明確ではありません。
用語は正確に使われるか、きちんと定義されることをお願いいたします。
飽和出力10のCCDがあったとします。ISO100 では10までの入射光には白飛びせず、11以上の入射光は白飛びします。
ISO200 にすると、5までの入射光は白飛びせず、6以上の入射光には白飛びします。
そこで、アンプ容量を2倍にします、というのが昭和1桁さんの独自理論ですよね。
ISO200 の場合、6の入射光があった場合、アンプで2倍され、12になります。
しかし、ADC 入力前に半分に減衰させるので、また6になります。
表にすると、次のようになります。
光量 → CCD → アンプ → 減衰 → ADC(出力)
1 → 1 → 2 → 1 → 1
2 → 2 → 4 → 2 → 2
5 → 5 → 10 → 5 → 5
6 → 6 → 12 → 6 → 6
10 → 10 → 20 → 10 → 10(白)
11 → 11 → 22 → 11 → 10(白飛び)
一目瞭然ですが、増感していませんから ISO200 ではないのです。
つまり、6以上の入射光があるなら、ISO100 で撮ればいいだけです。11以上の入射光があるなら、もっと光量を減衰させれば(絞れば)いいだけです。全てのデジカメはすでにそれを実現する手法を持っています。昭和1桁さんの独自理論は、何も解決しません。
>>白飛びの原因が、CCDやアンプが処理できる容量より「光量が多すぎる」
>>ことだということを理解してください
>元々の原因はその通りに理解しています.
何度も言いますが、それを本当に理解されているのであれば、白飛びさせない方法も簡単ですよね。絞るかシャッタースピードを早めればいいのです。
それでも、なぜ白飛びが防げないか、がキーファクターなのに、昭和1桁さんは懸命に「白飛びを防ぐことだけ」を考えてる。
昭和1桁さんが、今の知識からですと、ご自分の間違いに気付くのは難しいかもしれませんね。昭和1桁さんの為だけにこのスレを使うとご迷惑をおかけすることになるようですので、もし他の掲示板に移行されるようでしたら、ご案内ください。
書込番号:5655622
![]() 0点
0点
on the willowさんの滅茶苦茶な論理にお付き合いするのに疲れました.このスレの議論ではくろこげパンダさんに私の見解を完全に御理解いただいたことで満足し,スレ主さんの勧告に従って引っ込みます.
書込番号:5655794
![]() 0点
0点
昭和1桁さん の主張なんて元々ありませんよ。だってご自身で「撮影モデル」を提示されてませんから。
だから自分の考えすら整理できていない。整理できていないから言っていることがその場その場でころころ変わっています。
まず ISO100 でどういう条件で撮るのか。
ISO200 にしたときは、ISO100 での撮影と比べて何を一定として何をどれくらい変化させるのか。定数は何か、変数は何か。
CCD への入射光(一定?)、絞りとシャッタースピード(変化?)、CCD の飽和電圧は(当然一定でしょう)? それをアンプでどのように増幅させるのか(ISO100 の時の二倍?)?
何やら最後のほうは「ADC の手前まででダイナミックレンジが二倍になる工夫を SONY はした」らしいので、ここの段階までのモデルをちゃんと提示されないことには話になりません。ADC 以降は関係無いようですから(「諧調の再調整はしているでしょうが、それ以前で云々」のくだりから)。
素子の飽和電圧は一定値、素子のノイズも一定値(以下になることは無い)。これは素子ごとに固有、よってその後のアンプ操作でダイナミックレンジが減ることはあっても増えることは無い(アンプで飽和電圧を二倍にしてもノイズも二倍になるから)。
というのがその他(ほぼ)全員の見解なのです。
書込番号:5656166
![]() 0点
0点
ちなみにこの機種の「ISO160 という(Exif上の)表記はおかしい」ってことは、すでに [5631781] で書いてます。
線形じゃない増感を「ISO感度のアップ」とは呼ばないでしょう?
書込番号:5656209
![]() 0点
0点
> 線形じゃない増感を「ISO感度のアップ」とは呼ばないでしょう?
確か、ISO感度の指標条件として、リニアリティまでは規定されて
いないような事を、ブルーミングとスミアさんか誰かに教わったよ
うな記憶があるのですが・・・??(^^;)
------------------
信号機の左端は、青色でしょうか?緑色でしょうか?
青信号とは呼んでも、緑信号とは言いませんよネ?
でも、実態は緑色とするのが適当でしょう。だから
と言って、ワザワザ、青信号の呼称を否定する事も
しないでしょう。
こういったズレを 認識・許容 できないようなら、
議論は延々と続きます。
それと、
相手の主張の何たるかを理解なされたなら、後は、
自己完結あるのみです。問答をするから、延びて
しまうのです。
私からは以上です(^^;)
書込番号:5656865
![]() 0点
0点
最後に1つだけレスさせてください。
私がダイナミックレンジに受光量が影響していないと断言しているもう1つの理由です。
ken311 さんのブログから
N2 ISO100
http://dejicameamagoiwana.up.seesaa.net/image/DSC00023.JPG
N2 ISO200
http://dejicameamagoiwana.up.seesaa.net/image/DSC00024.JPG
見比べてみると、N2 の ISO200 では、カレンダーの反射等を見るとダイナミックレンジ拡大が効いているのがわかります。
しかしながら、
ISO100 F2.8 SS 1/5
ISO200 F2.8 SS 1/10
ISO100 と比較して ISO200 ではキチンと受光量が半分になっています。
よって、ダイナミックレンジ拡大機能に受光量(の拡大)が関連していないのがわかります。
書込番号:5657644
![]() 0点
0点
サンプルをちゃんと見れば一目瞭然なのに、それすらしてないってことです。
書込番号:5659932
![]() 0点
0点
間違って来ちゃったけど、話の展開読んでいません。
楽しそうですね、お決まりのメンバーで(笑)
気が向いたら来ます。bye!
書込番号:5660285
![]() 0点
0点
さらっと読んでみたけど、5D板やα100板より余程レベルが高いですね。
(あちらでは素人ばかりで苦労します)
殆ど適当takebeatさんの言うことが正しいです。
書込番号:5660301
![]() 0点
0点
こっちにもプロはいないと思いますけど。
楽しむのなら新スレでお願いしますよ。
私的にはフルサイズ1000万画素で電子の数が6万個に衝撃受けました。
書込番号:5660550
![]() 0点
0点
>電子の数が6万個
何の根拠も無いと思いますが。
ビット数と電子の数を関連づけることにも無理があります。
というか、関係ない。
書込番号:5660599
![]() 0点
0点
ソニータムロンコニカミノルタさん
>さらっと読んでみたけど、5D板やα100板より余程レベルが高いですね。
>(あちらでは素人ばかりで苦労します)
どういうつもりかな?
ここって「賢者の買い物」サイト、って知ってる〜?
書込番号:5662627
![]() 0点
0点
>どういうつもりかな?
>ここって「賢者の買い物」サイト、って知ってる〜?
知ってるよ。
ヲタ同士が好きに議論して悪いという決まりもないけど。
見たくないなら飛ばしてね。
書込番号:5662859
![]() 0点
0点
>賢者の買い物
賢くなるためには商品の本質を知ることも必要ですね。
デジカメだから理詰めの商品なのです。
それを知りたがる人が多いのは、ごく自然なことです。
カメラだから写真が撮りやすければ中身は知らなくて良いと言うのも、知りたいヲタにとっては迷惑な価値観の押しつけになります。
書込番号:5662918
![]() 0点
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「SONY > サイバーショット DSC-N2」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2014/05/15 18:57:53 | |
| 3 | 2008/10/29 11:09:12 | |
| 1 | 2007/10/12 18:39:16 | |
| 1 | 2007/09/11 19:09:57 | |
| 1 | 2007/08/23 17:51:10 | |
| 1 | 2007/05/29 0:50:29 | |
| 1 | 2007/02/18 22:22:38 | |
| 4 | 2007/02/28 9:02:28 | |
| 6 | 2007/01/28 15:54:03 | |
| 2 | 2007/01/25 16:03:56 |
クチコミ掲示板検索
最適な製品選びをサポート!
[デジタルカメラ]
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】PC構成20251031
-
【欲しいものリスト】メインPC再構成
-
【Myコレクション】自作構成
-
【欲しいものリスト】pcケース
-
【欲しいものリスト】2025PC構成2
価格.comマガジン
注目トピックス
(カメラ)
デジタルカメラ
(最近3年以内の発売・登録)