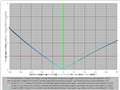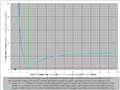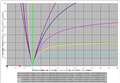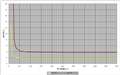�T���̉ɂԂ��X���b�h�Ƃ��Č��Ă��炦��Ǝv���܂��B
�����̏������݂ł��G���ł��A
�u�]���͍L�p�ɔ�ׂĔ�ʊE�[�x���A�{�P���傫���v
�u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���̂Łc�i���j�v
�Ƃ����L�ڂ����������܂��B
������Ď����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F13872028
![]() 5�_
5�_
�ꌾ�ōς܂���g���Ă͂܂�܂��h
���œ_�����̒�����A�i��̐ݒ�l�A�Z���T�[�̃T�C�Y�ɂ���āA���ʂ̈Ⴂ�͂���܂���
�����ԍ��F13872078
![]() 4�_
4�_
���̎�̘b�͓����Z���T�[�T�C�Y�A���l�Ŕ�ׂ�Ǝ��O��̘b�Ȃ̂�
�ԈႢ�Ȃ��������ł�����
(*´��`)�m
�{�P�͂قڏœ_�����Ƃ��l�Ō��܂���̂ł�
�����ԍ��F13872104
![]() 4�_
4�_
�Z���T�[�T�C�Y������Ă��A�����œ_�����Ɠ����i��l�Ȃ�A�{�P��͊�{�I�ɓ����ł���B
�����ԍ��F13872123
![]() 6�_
6�_
���t������Ȃ������̂ŒNjL�B
�L�p���]�����{�P�₷���͎̂����B
�����ԍ��F13872128
![]() 2�_
2�_
�ڂ����m�肽���ꍇ�́A���L���Q�Ƃ��ĉ������B
����ʊE�[�x�Ɋւ���v�Z��
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
�����ԍ��F13872138
![]() 2�_
2�_
�������ߎq����
��H
�l�ɑ��Č����Ă܂��H
�l�Ƒ����ߎq����̌����Ă邱�Ƃ͑S�������ł���
(*´��`)�m
��p�̎�������ނ���Z���T�[�T�C�Y�����킹�Ę_���Ȃ��Ƒʖڂ��Ă����ł�
�����ԍ��F13872195
![]() 0�_
0�_
���ӂ���Ȃ��āA������O�̕��ł��B
�����ԍ��F13872211
![]() 1�_
1�_
�炶��(������)�U
�����ԍ��F13872227
![]() 0�_
0�_
�Z���T�[�T�C�Y���قȂ�A��p���ς���Ă��܂��̂Łc
�w�i�ւ̎ʂ荞�݂≓�ߊ����܂߂��Ӗ��ŁA�Ⴂ�͂���Ƃ�������̏������݂ł�
�g��O�̕��h�Ƃ����Еt�����́A���܂�D�܂����Ȃ��ł��ˁc
�����ԍ��F13872234
![]() 10�_
10�_
�I���̏ꍇ�̓{�P���u�����傫����B
�������ق��ė~������B
���{�P�⋐�u����苐����������B
�T���̉ɂԂ��X���b�h�Ƃ��Č��Ă��炦��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13872259
![]() 12�_
12�_
���u�]���͍L�p�ɔ�ׂĔ�ʊE�[�x���A�{�P���傫���v
���u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���̂Łc�i���j�v
�قړ�����ł��B
�Ƃ��낪�A�����̎B�e�́A���ۂɍi��u�i��l�v�Ɓu��ʊE�[�x�v�Ɓu��ʑ̂Ƃ̎B�e�����v�̎O�p�W�̋삯�����ł��B�����������ɔY��A�ǂ��ł������Ă邱�Ƃł����L�����a�Ŕ�r���Ă܂��B
�]���̔Y�ݕ��́A��ɊJ���Ŏg�p����Ƃ��ɁA�����ނ˓�̍��ڂŔY�݂܂��B�J���l���e�P�D�W�ŏœ_�������Z���A�Ⴆ�W�T�����e�P�D�W�Ȃǂ̖]�����A����Ƃ��J���l�́A�P�i�Ɣ����Â����ǁA��ʊE�[�x���I�ׂ�P�R�T�����e�Q�D�W���������Ƃ����悤�ȔY�ݕ��ł��B
���������Ƃ��́A�L�����a�Ŕ�r���ē������o���܂��B�W�T�����^�e�P�D�W���S�V�D�Q�A��������̂P�R�T�����^�e�Q�D�W���S�W�D�Q�Ƃ������ɂȂ�܂��B�����Ȃ�A���̃����Y�́A�������̂ǂ����ŁA�{�P���i�ڂ���͈́j�́A����Ȃɕς��Ȃ��Ƃ������ɂȂ�܂��B
�t�ɂQ�O�O�����e�Q�D�W���ƂQ�O�O�����^�e�Q�D�W���V�P�D�S����܂��B����ƂP�R�T����������ʊE�[�x���Ƃ������ɂȂ�܂��B�Ȃ��Q�O�O�����e�S�́A�L�����a�T�O�Ȃ̂ŁA�{�P���͂W�T�����e�P�D�W�ƂP�R�T�����e�Q�D�W�Ǝ������̓��m�ɂȂ�܂��B�g���₷���Ǝv���܂�����ʊE�[�x�̐[���ƎB�e�����̊W�Ō����Δw�i�����̌��ʂ́A�W�T�e�P�D�W�ƂP�R�T�e�Q�D�W�ƕς�炸�A�Փ����������Ƃ��ɂ́A��⊾��������������Ȃ��Ƃ������ɂȂ�܂��B
���Ƃ��ƃj�R���n�ł����A�L���m���̂d�e�����Y�̃��C���i�b�v���A���͗L�����a���A���̂������ӎ������\���ɂȂ��Ă��ĂU�O�c�ƂT�c�Q�Ŋy����ł��܂��B�L���m���̂d�e�P�O�O�����e�Q��Q�O�O�����e�Q�D�W�Ȃǂ��A���̑�\�i�ł��B�L���m���̓t�B�������ォ�烂�f���B�e�i�|�[�g���[�g�j�Ɍ����Ă���Ƃ���A���̃����Y�̃��C���i�b�v���݂�ƁA�J���[�̔�ʊE�[�x���ӎ����Ă���̂ŁA�Ȃ�قǂƊ��S�������܂��B�k�����Y�̑��݉��l�́A�J���g�p�O�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13872287
![]() 3�_
3�_
����A���̎�̘b�ɂȂ�Ƃǂ����Ă��[�x�ƃ{�P�̑傫�������ꎋ����Ă��܂��悤�ł����A���̓�͕������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B
���́A��ʊE�[�x�͍i��ƎB�e�{���ɂ���Ă̂��܂�Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H
�i�ɒ[�Ɋӏ܃T�C�Y���قȂ�ꍇ�͕ʂł����j
�܂�A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ƍi�肪�����ł���A
�P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�
�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��B
���̎��A�]���̕������ΓI�ɔw�i���傫���A�O�i���������Ȃ�B�w�i���{�P�Ă���ꍇ�͌��ʓI�ɔw�i�{�P���傫���A�O�i���{�P�Ă���ꍇ�͑O�i�{�P���������Ȃ�B
�Ǝv���̂ł��B
�P�͋c�_�̗]�n�͂���܂��A�Q�͂ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F13872309
![]() 2�_
2�_
�NjL�ł��B
�Q�̎��i��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�j�A�ǂ̏œ_�����ł��{�P�����͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�B
�i�Ⴆ�Δw�i�ɊŔ��������Ƃ�����A��f�����s�����Ȃ�����ǂ��܂ŕ��������ʂł��邩�͕ς��Ȃ��j
�����ԍ��F13872370
![]() 0�_
0�_
���������A�]���̃{�P���Ɍ��܂Ő��������߂ɓ������[�^�[�V���[�ŃM�������B���Ă��
�����ԍ��F13872481
![]() 0�_
0�_
�����������ŏ������̂ŁA���炢�����܂����AMWU3���܁B
�����ԍ��F13872526
![]() 0�_
0�_
�{�P�̗ʁE�E�E���������Ɣ���₷���ł��ˁB
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html
�����́A�{�P���O�_�}�̑傫���@���Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F13872573
![]() 0�_
0�_
�����傫���Ŏʂ�ꍇ�A��ʊE�[�x�������ł����A
�p�[�X���Ⴂ�܂��̂ŁA���̔w�i�͈̔͂��Ⴂ�܂��B
�������ł͔w�i���V���v���Ȗ]���̕������{�P��Ɗ����܂��B�����B
�����ԍ��F13872690
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́�
�������i�̂����Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ���E�E�E
�����p�[�X�̖��{�ɂ͂܂��Ă܂��̂�^_^;�B�B�B
���̕ӂ̘b���A�\���������Ă���Ƃ͌������ł����ǂ�orz
���鐯�J���������1�[��
�B�e�{���������ł��i��ʂɔ�ʑ̂��傫���ő����Ă��j�E�E�E��p���Ⴄ�̂ŁB�B�B
�w�i���g�傳���H���{�P���g�傷��H�H�������~���傫���H�H�H^_^;�i������ȗ����ŗǂ��̂��H�H�i�j�j
������E�E�E�������̃{�P�ʂ��傫��
���R�������k�ŗǂ��̂��ȁH�H^_^;�E�E�E�p�[�X�͋�肾(>_<)
�B�e���������S�Ɉ�v���Ă��Ȃ��̂ŁA�Q�l�ɂȂ�Ȃ���������܂��E�E�E
�قڎB�e�{����F�l�̋߂������ڂ��Ă����܂��B
�����ԍ��F13872896
![]() 1�_
1�_
��قǂ����������܂������A���̎�̘b�ł����s���Ɋ�����̂����̂S�ł��B
�@��ʊE�[�x�ƃ{�P�ꎋ���Ă���
�A�w�i�{�P�ƑO�i�{�P���čl���Ă��Ȃ�
�B�B�e�����ƎB�e�{���i�Z���T�[�T�C�Y�������ł���A��ʓ��̔�ʑ̂̑傫���j�̂ǂ���𑵂����̂��A�O�Ȃ���r����Ă���
�C��ʊE�[�x�ƃ{�P�Ɋւ��鏔�������ʂɔ�r����Ă��āA�S�̂̐������Ȃ�
����Ȃ���A���������߂����ĉ������������N���܂��ɏ�L�̗�ł��B
�A�͈�ʓI�Ƀ{�P���w�i�{�P�Ȃ̂Ŏd���Ȃ���������܂��A�B�Ɋւ��Ă�MWU3����A���ӂ�ׂȂƁ`�邳��A�����ߎq������O����܂����ˁB
�Y�t�摜�̂悤�ȏŁA35mm�A50mm�A85mm�̒P�œ_���g���A�{�f�B��F�l�Ɣ�ʑ́i�L�����j�̑傫���𑵂��Ĕ�ʊE�[�x�Ɣw�i�{�P�ƑO�i�{�P���r���Ă݂����Ƃ�����܂��B
�ȉ��A���ʂ�\���Ă����܂��B
�����ԍ��F13873151
![]() 3�_
3�_
���̎�̘b�́@�B�e�����ȂLj��̏������߂����ł��Ȃ��Ɓ@�����̖����b�ɂȂ�悤�ȁd�C�����܂��B
�����ԍ��F13873157
![]() 1�_
1�_
���ƃ��{�}�� �Q����
���������Ⴂ�܂����ˁB
���������ʂ�ł��B
F5.6�ł̔�r�ł��B
�����ԍ��F13873180
![]() 4�_
4�_
F2�̉摜���g���~���O���Ă킩��₷�����܂��B
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ɣ�ʑ̂̑傫���i�܂�B�e�{���j�y�эi��Ƒ������ꍇ�A�L�p�ł��]���ł���ʊE�[�x�͈��ŁA�]���ł͔w�i�{�P�i�Ƃ������w�i���̂��́j���傫���Ȃ�A�O�i�i�Ƃ������O�i���̂��́j���������Ȃ邱�Ƃ��킩��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13873197
![]() 4�_
4�_
�X�ɁA��قǒNjL�ŏ��������ł��B
��ʊE�[�x�������ꍇ�A���̓{�P�̃f�B�e�[��������ɂȂ�܂��B
�w�i�̑傫�����ɂȂ�悤�Ƀg���~���O�Œ������Ă݂܂��B
������{�I�Ȃ��Ƃ��Ǝv���̂ł����A���̓_���͂�����L�ڂ��Ă���G�����������Ƃ�����܂���B
�����ԍ��F13873214
![]() 5�_
5�_
�c�Ƃ������ƂȂ�ł����A������x�ŏ��ɖ߂���
�u�]���͍L�p�ɔ�ׂĔ�ʊE�[�x���A�{�P���傫���v
�u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���̂Łc�i���j�v
�Ƃ����L�ڂ����������܂��B
������Ď����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H
�����S�O�O�P����@����ɂ��́B
�p�[�X�̂��b�͂������A�œ_�������Z�������Y�͉�p�Ɋւ�炸�p�[�X�������Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������ł�����ˁH
���̓p�[�X�͉�p�i�܂�œ_�����ƃt�H�[�}�b�g�T�C�Y�j�ɂ���Ă̂��܂�Ǝv���܂��B�����łȂ���R���f�W�͑S�ĕ������p�[�X�ɂȂ��Ă��܂��܂�����c�B
�����B�e�����̏ꍇ�A�L�p�ŎB�����摜���g���~���O����Ɩ]���ł̉摜�Ɠ����p�[�X�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F13873257
![]() 2�_
2�_
����ɂ��́B���܂藝�����Ă���킯�ł͂���܂��B
�Ƃ肠���� �M�q���Ē����� �� [13873197] �̂����́u�B�e�{���𑵂����v�Ƃ͒ʏ�͌���Ȃ��Ǝv���܂��B
��ʊE�[�x�̃p�����[�^�[�́i���Ƃ��āj�A
�EF�l F
�E���e�����~�a ��
�E�œ_���� f
�E��ʑ̋����i�B�e�����ɋߎ��j s
�̎l�ł��B
�Q�l URL http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
�ʏ�́u�B�e�{�����v�Ƃ����ƁA�u�J�����̃t�H�[�}�b�g�T�C�Y�i��L�ł� �j���v�̏����̉��A�B���ʏ�ł̔�ʑ̂̑傫�����������Ȃ�悤�ɎB�邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
�܂� �� �� ���Af/s �� ��� �����̏����ł��B
�M�q���Ē����� �̗�ł́A�g���~���O�ɂ���Č��ʓI�� �� ��ω������Ă��܂��Ă��܂��ˁB
�܁A�P�Ȃ�p��̎g�p�@�̖��ł��̂ŁA���̏����̉��ł̔�ʊE�[�x��]�����邱�Ƃ͗L�Ӌ`���Ƃ͎v���܂��B
�����ԍ��F13873308
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
�����A�ǂ�����Ƃ������蒸����Ǝv���܂����A
[13873197]��[13873167]���瓯���T�C�Y�Ő肾���Ă��܂��B
�܂�A�����Y�͓����ŏ������B���f�q�̃J�����ɕς����̂Ɠ����ł��B
�����ԍ��F13873337
![]() 0�_
0�_
�܂莄�̐����Ō����Ƃ���� �� ���ω����Ă��܂��Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F13873345
![]() 0�_
0�_
[13873167]�Ƃ��̃g���~���O�ł���[13873197]�̔�r�����Ă���̂ł͂Ȃ��āA
[13873197]�̒��̂R��̏œ_�����̉摜���r���Ă���̂ł����A[13873197]�̒��ł����e�����~�a ���ω����Ă��܂��Ă��܂����H
�����ԍ��F13873370
![]() 0�_
0�_
�������݂܂���B���̊��Ⴂ�ł����B
�\����܂���ł����B
�����ԍ��F13873397
![]() 0�_
0�_
�����B�e�{���ŎB���Ă��A�w�i�̑傫�����Ă����Ԃ�ς����̂Ȃ�ł��˂��B
�����ԍ��F13873411
![]() 1�_
1�_
�v��������ߎ����Ă��܂���
�O����ʊE�[�x Dn �� �����ʊE�[�x Df �� ��Fs^2 / f^2
�Ȃ̂ŁA
�B�e�{�� s/f �� ���Ȃ�����ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��A�Ƃ����̂����̗\�z�ł��B
�ق�Ƃ͂���������Ƃ����Ƃ��Ȃ�������Ȃ���ł��傤���B
�����ԍ��F13873439
![]() 0�_
0�_
�����A�����炱�����t�����������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B
�]���ɂ���Ɣw�i���傫���Ȃ�̂������Ȃ�ł����A�O�i��傫��������������L�p�ɂ���ׂ��Ȃ�ł��ˁB
�Ⴆ�C���~�l�[�V�����̑O�{�P��傫����肽��������L�p�Ŋ���ĎB��̂��K���Ă���Ǝv���܂��B
�v�Z���肪�Ƃ��������܂��B
�����A���w�͂܂��������ł��āc�i���ƁA����ƎЉ�Ɖp��Ɨ��Ȃ��j
�����B��A���S�҂ɂ�����������悤�ɒ��J�ȉ��������Ȃ��Ǝv���Ă����̂��f�W�^���t�H�g�Ƃ����G���ł����B
�c�O�Ȃ��Ƃɔp���ƂȂ��Ă��܂��܂������A�Q�O�O�W�N�U�����P�O�Q�y�[�W�ɃV�O�}����̒����Ƃ��ă}�N�������Y�̓��{�B�e�A0.5�{�B�e���̏œ_�����ʔ�ʊE�[�x���f�ڂ���Ă��܂����B
����ɂ��A�B�e�{���ƍi�肪����ł���Ώœ_����������Ă��s���g�ʂ���O�������[�x�͓���ɂȂ邱�Ƃ�������Ă��܂��B
�i���̃f�W�^���t�H�g�ł����A���_�Ƃ��ď����𑵂�����r�͘_���Ă��܂���ł������j
0.5�{�AF2.8�̗�Ō����ƁA
�œ_����50mm�c�B�e����220mm�A����̐[�x221mm�A�O���̐[�x219mm
�œ_����105mm�c�B�e����400mm�A����̐[�x401mm�A�O���̐[�x399mm
�œ_����180mm�c�B�e����613mm�A����̐[�x614mm�A�O���̐[�x612mm
�Ƃ��������ŁA���������ʊE�[�x��2mm�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�l�̌ܓ��̊W���A���ׂĂ��ꏏ�ɂ͂Ȃ��Ă��܂��A�T�ˏ�L�̂悤�ȓ��e�ł����B
�}�N�����������̕�����������������A���{�Ŕ�r���Ă݂Ă��炦��Ɨǂ��̂ł����B
�����ԍ��F13873546
![]() 3�_
3�_
 |
 |
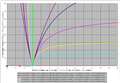 |
|---|---|---|
�P�D�B�e�����i���k�j�������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ� |
�Q�D��ʑ̂��傫���i�����j�Ɏʂ��ꍇ�i�����j��ʊE�[�x�͕ς��Ȃ� |
�]���̕����i�����j�w�i�{�P���傫���i�����j�O�i�{�P���������Ȃ� |
�����ԑO�̃��X�ɑ��Ăł����E�E�E
�w�P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�
�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��B
���̎��A�]���̕������ΓI�ɔw�i���傫���A�O�i���������Ȃ�B�w�i���{�P�Ă���ꍇ�͌��ʓI�ɔw�i�{�P���傫���A�O�i���{�P�Ă���ꍇ�͑O�i�{�P���������Ȃ�B�x
�����������O���t���~�����ł����H
�����ԍ��F13873966
![]() 5�_
5�_
��͂�펯�I�ɍl���ĉ�p���Ⴄ���̂�����ƍl����̂�
����������Ǝv���܂�
�قȂ鋗���ɂ���Q�̔�ʑ̂��悤�Ɏʂ����Ƃ�
�ł��Ȃ�����ł�
����͂܂蓯�����̂��B��Ȃ��Ƃ������Ƃł��̂�
��p�����R����ƍl����Ȃ�u��r�v�ł�����
�B�e�������K�R�I�ɓ���ƍl����ׂ��ł��傤
���Ƃ���Εϐ��͗L�����a�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F13874708
![]() 1�_
1�_
����͑����}�N�������Y�֘A�̃N�`�R�~���ꕔ�c�_���ꂽ�Ǝv���܂��B
��ʊE�[�x�������ł�����A�g���₷���]���i������Ƌ����j��I�ԂƂ������_�ł��B
�܂�j�R��60/2.8�i�債�����Ƃ���܂��̖̂������Y�j�͕K�v�Ȃ��̂ł��B
�������]���̉掿�ƒl�i�����ł���A60/2.8�}�C�N����I��ł��X�����ł��傤�B
�ώ@�p�x�����ĉ�����������ӎ����邱�ƁA���ꂾ���ł��B
�����ԍ��F13874864
![]() 2�_
2�_
�����A�����܂œ˂����b�������̂ł��ˁi�j
�p�[�X�y�N�e�B�u���W���Ă���̂ł��傤��
�]���ł͈��k���ʂł��̂��̂̔�ʑ̂̋����̍������ۂ��Ȃ��悤�Ɍ����邩��
������Ƃ̋����̍������Ȃ��悤�Ɍ����Ă��{�P�Č�����
�t�ɍL�p�ł̓f�t�H�������ʂł��̂��̂̔�ʑ̂̋����̍������ۂ�肠��悤�Ɍ����邩��
�����̍�������悤�Ɍ����Ă��{�P�Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����
�ʔ����ł��ˁ�
(*´��`)�m
�����ԍ��F13875082
![]() 1�_
1�_
��܂����낤����ɂ͂��������b�ɂȂ��Ă���܂��B
�����ł��ˁB���̃O���t�̃C���[�W�ł��B2���ڂ̃O���t�̏����ɂ������ʊE�[�x�́u�܂����������v�Ǝv���Ă����̂ł����A�u�قƂ�Ǔ����v���������̂ł��傤���H
BABY BLUE SKY����ɂ����������₳���ĉ������B
���قȂ鋗���ɂ���Q�̔�ʑ̂��悤�Ɏʂ����Ƃ��ł��Ȃ�����ł�
�Ƃ���܂����A�B�e�{���������ł���s���g�ʂ����͂܂����������悤�Ɏʂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����Ƃ���Εϐ��͗L�����a�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
����́A�{�P�ʂ����łȂ���ʊE�[�x�ɂ������邱�Ƃł��傤���H
�܂��A��قǎ��������悤�Ȕ�r�@�ŎG���ɍڂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B
���̏ꍇ�ł���܂����낤����̃O���t�Ƃ͈قȂ�u�]���͔�ʊE�[�x���v�Ə�����Ă��܂��B
���鐯���߂炳��
�}�N���ł͂����ł��傤�ˁB�����A�}�N���B�e�ł͂��܂�]��������Ƃ킸���ȃu����������Ȃ��Ȃ肻���ł��ˁB
���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
�������ł����ł��傤���H
�J�������n�߂čŏ��̂���A�u�]���͔�ʊE�[�x���v�̃E�\�i�H�j�ɔY�܂���܂����B
�����̏�����q�ǂ����A�b�v�ŎB��ƕЕ����{�P�Ă��܂��A�u���Ⴀ�L�p�ŋ߂Â��ĎB��Ɨǂ��̂��H�v�ƍl���܂��������ʂ͗ǂ��Ȃ�܂���ł����B
���ۂ̎B�e�V�[���ɂ����ẮA���┭�\��ȂǎB�e������ς����Ȃ����Ƃ�����܂����A�ԁA�q�ǂ��A�l���ȂǁA�܂��͎B�肽���傫���������āA���̂��߂ɏœ_������ς�����B�e������ς����肷��͂��ł��B
�Ȃ̂ɂ�܂����낤����̃O���t�Ō����ƂP���ڂ̑O���������łQ���ڂ̑O������Ō���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�������Ƃ��Ă����������ɑ����Ɗ����Ă��܂��B
�����ԍ��F13875258
![]() 4�_
4�_
�J�L�R�u13873214�v�̓{�P�̔�r�ł�����܂��ˁi�L��������̓����Q�Ɓj�B
���̏ꍇ�A��p�̒P���t���ƌ����܂��i���a�̔��ł�����܂��j�B
�����ԍ��F13876218
![]() 0�_
0�_
�����炱�������b�ɂȂ��Ă���܂��B�i�O�O�j�m
�w2���ڂ̃O���t�̏����ɂ������ʊE�[�x�́u�܂����������v�Ǝv���Ă����̂ł����A�u�قƂ�Ǔ����v���������̂ł��傤���H�x
�u�قƂ�Ǔ����v���������̂ł��傤�ˁB
��ʑ̂̈ʒu�ł͑S�Ă̋Ȑ��̌X����v����̂ł����A��������Ƃ��ăJ����������w�i���ɂ����Ă̌X�̕ω����A�L�p�ł͋}���Ɍ����Ă����܂����]���ł͊ɂ₩�Ɍ����Ă����̂ŁA���e�����~���l�����ĕ�����������ƌ덷���x�̈Ⴂ���o�Ă��܂��B
�����Ƃ��A�L�p�ł͂��͈̔͂��w�i���ɁA�]���ł̓J�������ɏ����ړ����邾���̘b�ł����āA�����̂��̂͂��܂�ω����Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�w�J�������n�߂čŏ��̂���A�u�]���͔�ʊE�[�x���v�̃E�\�i�H�j�ɔY�܂���܂����B�x
�����ŏ��̂���́u�]���́i�����j�v�Ƃ�������M���Ă��܂����B�����Ƃ��������Ɩ]�������Y��}�N�������Y�������Ă��܂���ł����̂ŁA����ō��邱�Ƃ͂���܂���ł������B
�����A�v���̕��ł������́u�]���͔�ʊE�[�x���v�̂ق��Ɂu��ʊE�[�x�����{�P�������v�̌�������Ă�����̂Ǝv���܂��B
��̃O���t�̂悤�ȋȐ��Ń{�P�������Ă����̂ł͂Ȃ��A���I�ɑ����Ă������̂��Ɗ��Ⴂ����ƁA��̂悤�Ȍ���ɂȂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F13876564
![]() 2�_
2�_
�X����l
�L�p�̃p���t�H�[�J�X�Ɩ]����̍i��J���ł̃{�P��C�Q�l�܂ł�UP�u���Ă����܂��B
�����ԍ��F13876914
![]() 0�_
0�_
��܂����낤����
�Ȃ�قǁA�u�قƂ�Ǔ����v��ʊE�[�x�̒��ł��A�L�p�Ɩ]���őO��̔�d����Ⴄ��ł��ˁB�����̂��̂͂��܂�ω����Ȃ��悤�ł����A���ۂ̎B�e�ł͖����ł���덷�̂悤�ł��ˁB
�������肪�Ƃ��������܂��B
����̌��A��͂�v���̕��ł�����������ł��傤���B
���i.com�̏������݂ł��v���𖼏������u���{�B�e�ł͖]���}�N�������L�p�}�N���̕�����ʊE�[�x���[���̂Ŋy�v�Ƃ����b������Ă���A�т����肵�����Ƃ�����܂��B
�T���ăJ�����̐��E�ł́A���͈̔͂܂ł͗������ۂ��̂ł����A���������������ƂƂ���Ɏv�l��~���Ă��܂��Ⴊ����悤�Ɏv���܂��ˁB
��THE BEATLES�t�@������
�������݂��肪�Ƃ��������܂��B
�ł��A4���ڂ�1���ڂɔ�ׂĎB�e�{���������A�p���t�H�[�J�X�ł͂Ȃ��ł��ˁc�B
��Ԏ�O�Ɖ��̗t�A����̌������͔�ʊE�[�x����O��Ă��܂��B
�i�������ʐ^�̗ǂ������Ƃ͖��W�ł����A���̂悤�ȃX���Ȃ̂ŏ������Ē����܂����j
�����ԍ��F13877517
![]() 2�_
2�_
�M�q���Ē�����
��4���ڂ�1���ڂɔ�ׂĎB�e�{���������A�p���t�H�[�J�X�ł͂Ȃ��ł��ˁc�B
���C���݂܂���I
�Ԉ���ĉ摜UP���Ă܂���i�|�|�G�j�B
�u���y�Y���Ă����܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F13879108
![]() 0�_
0�_
���� �M�q���Ē����� �Ɠ��l�A�B�e�{���̊ϓ_�����ʊE�[�x���l����̂͂��肾�Ǝv���܂���B
��������̔�ʑ́E�E�E�Ⴆ�Ύq���̊�ȂǁE�E�E���B�e����Ƃ������ꍇ�A�B�e�҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂͂�͂��ʑ̂̎B�e�{���ɂȂ�܂�����B
�ŁA�p��̎g�p�@�̓˂����݂ɂȂ�܂����B
�u�B�e�{���v�ƌ������ꍇ�ɂ́A�����܂ł��B���ʏ�̑傫���������̉��{���H�Ƃ������b�ɂȂ�܂��B
�ł��F���t���T�C�Y���g���Ă�킯�ł��Ȃ��A���̏ꍇ�B�e�҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́u�B���ʏ�̂ǂ̂��炢�̊����Ŏʂ��Ă��邩�v�̂͂��ł��̂ŁA�u�t���T�C�Y���Z�B�e�{���v�Ƃ����p��ɂ��Ȃ�������Ȃ��ł��i���Ԃ̗p��͂ǂ����ɂ���Ǝv���܂��j�B
��������čl���Ă����ƁE�E�E
�u���Z�B�e�{�������ɂ���B�e���@�̏ꍇ�A��ʊE�[�x�́w���ZF�l�x�Ō��܂�v
�Ƃ����������ɂȂ��čs���܂��B
�u���ZF�l�v�Ƃ����p��͌��I�ɂ͑��݂��Ȃ��悤�ŁA�܂����i�R���̉ߋ��X���ł����݂�e�F���Ȃ��l������������悤�ł����A���ZF�l�Ƃ́A���� F�l�Ɂu�t���T�C�Y���Z�W���iAPS-C�Ȃ�W���� 1.5�j�v���悶�����̂ł��B
���ZF�l�������������ɒ�`����ƁA���� [13873439] �ł̎���
Dn �� Df �� (��*(���ZF�l)*(s^2))/(���Z�œ_����^2)
�ƕ\���邽�߁A���Z�B�e�{����肾�Ɣ�ʊE�[�x�͊��ZF�l�Ō��܂邱�Ƃ��킩��܂��i������ �� �̓t���T�C�Y�̋��e�����~�a�ŁA�����悻 0.03mm ���x�̒萔�j�B
��������čl���Ă����ƁE�E�E
BABY BLUE SKY���� �� [13874708] �ŏ����ꂽ�A
>��p�����R����ƍl����Ȃ�u��r�v�ł�����
>�B�e�������K�R�I�ɓ���ƍl����ׂ��ł��傤
>
>���Ƃ���Εϐ��͗L�����a�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�́A���́u���Z�B�e�{�����v�̓�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��i�W���I�Ɋ܂܂��j�B
�ǂ̎B�e������F�߂� or �F�߂Ȃ��Ƃ������v�z�͕ʂƂ������܂��āA�����܂ł�������A�_����ł̘b�ł��B
�����ԍ��F13881431
![]() 2�_
2�_
�Ȃ�ق�D�D�D
���P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�
���Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ�
���ۂ̎B�e�Ō����A�����̏ꍇ�́u�P�v���]���ň����ꍇ�i�g�債�����ꍇ�j�ɊY�����Ă��āA�u�Q�v���Y�[�����g���ē��̎B�e���Ă���ꍇ�ɊY�����Ă��銴���ł��B
���̎B�e���ƁA�q��@�̋Ȍ|��s�̏ꍇ�A�t�@�C���_�[�Œǂ��Ȃ���A��ʑ̂̑傫���������傫���ɂȂ�悤�Ɏʂ��܂��B�S�����Y�[�����g���A�u�Q�v�̂悤�ȎB�e�̈�ɂȂ�Ǝv���܂��B�܂��A�����Y��ς��Ȃ��琻�i���B�e�����肷�鎞���A��ʑ̂̑傫�������낦�܂�����u�Q�v�̂悤�Ȋ����ɂȂ�Ǝv���܂��B
�w������ɃY�[�����g���Ă��āA�ӂƁA��ʊE�[�x���C�ɂȂ�A��ʓ��̔�ʑ̂̑傫�������ɂ����ꍇ�̔�ʊE�[�x���e�œ_�������ƂɎ�v�Z���Ă݂���������܂��B���̎��̌��ʂ��u�Q�v�̂悤�Ȋ����ł����B�����A���܂蕷���Ȃ��b�������̂ŁA�m�E�n�E�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B�@�ނ̌��������̂ɗL�����a���A�悭�g���Ă��܂����A�����܂ł��B�e�������̏ꍇ��O��ɂ��Ă��āA���̎B�e��i�̎B�e�̏ꍇ�́u�Q�v�̂悤�Ȋ����ł�����B�i��ɂ��掿�̕ω���O���ɎB�e���Ă��܂����B�i�n����������Ȃǁj
�݂Ȃ��܂̉����āA��v�Z�̌��ʂƓ��������ɂȂ��Ă��ď������S���܂����B
�����ԍ��F13881536
![]() 1�_
1�_
�x���X�ł���
>���قȂ鋗���ɂ���Q�̔�ʑ̂��悤�Ɏʂ����Ƃ��ł��Ȃ�����ł�
>�Ƃ���܂����A�B�e�{���������ł���s���g�ʂ����͂܂����������悤�Ɏʂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�������ɂ����ł������ꂪ�\�Ȃ̂�
�B���ʂɐ���������
���邢�͏\���ɉ�������
�����Ă��̂悤�ȕ��ʂł�
��ʊE�[�x��{�P�ʂɂ��čl����K�v������܂���
�����ԍ��F13883185�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�w���Z�B�e�{�������ɂ���B�e���@�̏ꍇ�A��ʊE�[�x�́w���ZF�l�x�Ō��܂�x
�u���Z�B�e�{���Ƃ�����́v�����ŁA�u���ZF�l�Ƃ�����́v����肩�A�u���Z�œ_�����Ƃ�����́v�i����p�j�����ł���A��ʊE�[�x�͈��ɂȂ�܂��B�i���̃O���t�j
�܂����̏ꍇ�́A�O�i�E�w�i�̃{�P���قړ���ɂȂ�܂��B�i�E�̃O���t�j
�u���ZF�l�Ƃ�����́v���p�����[�^�[�ɂȂ肤�邩�ǂ����͂킩��܂���B
�����ԍ��F13883649
![]() 4�_
4�_
�t�H�[�}�b�g�͌Œ肵�čl���邱�Ƃɂ��܂��B
�u���{�������Ȃ�A��ʊE�[�x��F�l�����Ō��܂邩�H�v
�Ƃ������ł���ˁB
�����́A�����l���č����x���Ȃ��P�[�X���������ǁA��ʓI�ɂ͊ԈႢ�A���ȁH
��ʊE�[�x�v�Z�T�C�g���ł́A�����Ă��ߎ�����p���Ă܂��̂ŁA��̌X�������������܂��B�������A���p�I�Ȕ͈͂ŁA�ߎ��̑Ó���������AF�l�������ł���ʊE�[�x���傫������Ă���ꍇ������Ǝv���܂��B
�܂��A�ȉ��̃T�C�g�ɂ����ʊE�[�x�̌������o���_�Ƃ��܂��B
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
�Ⴆ�Ό����ʊE�[�x��
(e�E(s�|f)^2) ÷ (f^2�|e�E(s-f))
�����ŁAs�F��ʑ̋����Af�F�œ_�����Ae�FF�l×���e�����~�a�B
�����ŕ����e�E(s-f)�̍�������ƁA��ʊE�[�x��e�����ŁA�]����F�l�����Ō��܂邱�Ƃ����_����܂��B�������A���̑���͂������ł��B�܂�Af^2��e(s-f)�̃I�[�_�[���߂��ꍇ�͂��ꂪ�傫���Ȃ�͂��ł��B
�킴�Ƃ�������������Ă݂܂��B�i�v�Z�~�X���A������w�E���������B�j
�Ⴆ�A35mm�t���T�C�Y�̃J�����ŏc�ʒu�B�e�A���f���̂��o����̑S�g�Ƃ���
1800mm�̕���(36mm)�����ς��ɎB��Ƃ���ƁA
f/s���œ_����/��ʑ̋�����36/1800=0.02
���e�����~�a��0.025mm�Ƃ�F8�܂ōi��ƁA
e��0.2
���̏����ŁA�œ_����20mm�A30mm�A200mm�A300mm�̃����Y�ŎB�e�����ꍇ�̌����ʊE�[�x�͂��ꂼ��
942mm�A713mm�A505mm�A496mm
�ƂȂ�A�L�p�Ɩ]���Ō��\�ȍ����o�܂����B���ꂪF4�Ȃ�
318mm�A287mm�A246mm�A244mm
�ƂȂ�܂��B30mm��300mm�̍������ꂭ�炢�Ȃ���p��F�l�����Ō��܂�ƍl���Ă����Ȃ���������܂���B
��������u�]���قǔ�ʊE�[�x�͐v���Ƃ�������܂��B�������A���ۂɂ͂��̈Ⴂ���������AF�l�����Ō��܂�ƍl���č����x���Ȃ��P�[�X�������A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
����A�ڂ��Ɋւ��ẮA�M�q���Ē�����̋�Ƃ���A���k���ʂ̂��߁A��ʊE�[�x�������ł��]���̕����ڂ��̓x�����͑傫��������A�ŗǂ��Ǝv���܂��B
�X���`���̖��u�]���͔�ʊE�[�x���A�{�P���傫�����ăz���g�ł����H�v�ɑ��铚���́A�u�z���g�v�ł��B
�����ԍ��F13883868
![]() 3�_
3�_
>��ʊE�[�x�v�Z�T�C�g���ł́A�����Ă��ߎ�����p���Ă܂��̂ŁA��̌X�������������܂��B
�ߎ����ł������e�l�Ŕ�ʊE�[�x�̃Y���͏o�܂��ˁB���̕����͓P��B
���ƁA�����̋c�_�A�����Y�̌J��o���ʂ͖������Ă܂����A���̕ӂ��ǂ��Ȃ̂��ȁH
�����ԍ��F13884059
![]() 0�_
0�_
�c�_�������ɂȂ��Ă��āA�X����Ƃ��Ă͂��ꂵ������ł��O�O
�F�l�A���肪�Ƃ��������܂��B
���s�̂�������
�u�B�e�{���v�̒�`�ł����A�Z���T�[�T�C�Y�Ɠ����傫���́A�����������`���҂�����B�e�����̂����{�ł���ˁB�ł��̂ŁA�B�e�{���������Ńt�H�[�}�b�g�T�C�Y���Ⴄ�����̏ꍇ�A��ʊE�[�x���{�P�ʂ�����Ŏʂ�͈͂������Ⴄ���ƂɂȂ�܂��B
�܂�A
���ł��F���t���T�C�Y���g���Ă�킯�ł��Ȃ��A���̏ꍇ�B�e�҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́u�B���ʏ�̂ǂ̂��炢�̊����Ŏʂ��Ă��邩�v�̂͂��ł��̂ŁA
�̌�ɂ́A
�u�����ȃt�H�[�}�b�g�T�C�Y�̏ꍇ�͎B�e�����𗣂��A�������͏œ_����������������K�v������A�ǂ���̏ꍇ���B�e�{�����������Ȃ�̂ŁA��ʊE�[�x���[���Ȃ�܂��B�v
�Ƒ����܂��B
���̒i�K�Łu��ʊE�[�x�͍i��ƎB�e�{���ɂ���Ă̂��܂�v�ɖ����͖����ƍl���܂��B
���āA�t���T�C�Y���Z�B�e�{���Ƃ����T�O�͖ʔ������ł��ˁB
�������ZF�l�̍l�����͓���Ŏg���Ă��܂��B�������A��ʊE�[�x��F�l���W����v�f�̈ꕔ�ł�������܂���A���Z��ʊE�[�xF�l�Ƃł����������ǂ���������܂���B
���̌v�Z���̏œ_�����AF�l�A�B�e�{����S�ăt���T�C�Y���Z����Ƃ������Ƃł��ˁB�S�����Z���Ă���̂ŁA���Ƃ܂������������ʂɂȂ肻���ȋC�����܂��ˁB
�������͂�������
�A�C�R���Ɓu�w������v�Ƃ����\������A��v�Z�����̂̓t�B���������g�p�̍��ł��傤���H��ϋM�d�Ȏ��̌��̃J�L�R�~�A���肪�Ƃ��������܂��B
�������A���܂蕷���Ȃ��b�������̂ŁA
���[��A��͂�̂��炠�܂�b��ɂȂ�Ȃ����e�Ȃ̂ł��傤���B
�����ԍ��F13884792
![]() 1�_
1�_
BABY BLUE SKY����
�������Ă��̂悤�ȕ��ʂł�
��ʊE�[�x��{�P�ʂɂ��čl����K�v������܂���
���������A�u�B���ʂɐ��������ʁv�݂̂��r���邨�b�ł͂Ȃ��A���̏����𑵂��ĉ����r���邩�A�̂��b�ł��B
�P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�
�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ�
�P�̓Z���T�[�T�C�Y�ƎB�e�����i�܂�B�e�ʒu�j�A�y�эi��𑵂��Ă��܂��ˁB
�Q�̓Z���T�[�T�C�Y�Ɣ�ʑ̂̑傫���i�܂�B�e�{���j�A�y�эi��𑵂��Ă��܂��B
BABY BLUE SKY�������ꂽ�A
����͂�펯�I�ɍl���ĉ�p���Ⴄ���̂�����ƍl����̂�
����������Ǝv���܂�
����������A������
����͂�펯�I�ɍl���ĎB�e�{�����Ⴄ���̂�����ƍl����̂�
����������Ǝv���܂�
�ƂȂ��Ă��܂��܂��H
���������P�̏����ł���p�͈Ⴂ�܂����B
���̗������y��ł��Ȃ��̂�������܂���B���̌��A���̕���������������K���ł��B
�����ԍ��F13884803
![]() 0�_
0�_
�c�Ƃ����܂ŏ����āA
gintaro����قȂ�v�Z���ʂ�����܂����B
���p�I�Ȕ͈͂ŁA�u�t�H�[�}�b�g�͌Œ�Ƃ��āA���{�������Ȃ�A��ʊE�[�x��F�l�����Ō��܂�v�ƌ����Ȃ����������A�Ƃ������Ƃł��ˁB
�P���Ȏ���Ȃ̂ł����A
��1800mm�̕���(36mm)�����ς��ɎB��Ƃ���ƁA
f/s���œ_����/��ʑ̋�����36/1800=0.02
�Ƃ����Ƃ���ł����Af�̓����Y�̏œ_�����i�܂�A��Ō�����20mm�A30mm�A200mm�A300mm�ȂǕ�������Ă��܂��ˁj�As�͔�ʑ̋���[mm]�i�܂�B�e�����A�����Y�Ɣ�ʑ̂̊Ԋu�j�̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł��傤���H
�����ԍ��F13884816
![]() 0�_
0�_
�M�q���Ē����� ������
�����̖����b�ɂȂ��ė��܂�����
����ł͎B�e�������ł̘b���@��������ł͔�ʑ̂��傫���ɂĎB�e������ς���@����ł́d
��͂�����ꂵ�Ȃ��Ɠ����͏o�Ȃ��Ǝv���̂ł����d
�����ԍ��F13884916
![]() 0�_
0�_
���ƃ��{�}�� �Q����
���͍ŏ�����A������������̏������P�D�Q�D�Ƃ��Ė��m�ɋ�ʂ��Ă��܂���B
�Ⴆ��܂����낤������P�̏ꍇ�́A�Q�̏ꍇ�́A�ƕ����ăO���t�����Ă���Ă��܂��B
�����A�P�͂��܂�ɂ�������O�߂��āA�c�_�̕K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�t�ɂQ�͂������͂����������ꂽ�悤�ɁA���܂�c�_���ꂽ���Ƃ������悤�Ɏv���܂��B
�����X����Ƃ��āA�����ꂵ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����A�Q�ł��肢�������Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɂQ�̏ꍇ�A���ƃ��{�}�� �Q����͂ǂ̂悤�Ȍ��_�ł��傤���H
�����ԍ��F13884991
![]() 1�_
1�_
���[�ƁA���������������������m��܂���B
���X�X�����Ă̎�|�́A
�u�]���͔�ʊE�[�x���A�{�P���傫�����Ă����̂́A�����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H�v�i�^�C�g���ƍŏ��̏������ݎQ�Ƃ��������j
�ł���A���̐^�ӂ́A
�u�P�D�B�e�����������ꍇ�v�@�͂����ł��傤���ǁi�����̈ꕔ�j�A
�u�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�v�@�͈��Ȃ��ł��傤���H
�Ƃ������̂ł��B
�����ԍ��F13885062
![]() 1�_
1�_
�M�q���Ē�����@�ԐM�L��������܂�
�����̍l���ł����@�s���g�̍������͈�_��������܂��@��ʊE�[�x���͗L��������Ńs���g���L���Č����Ă����Ԃ��Ǝv���Ă��܂��B
���e�����~�̍l�����ł́@�����ʐ^�ł��g�嗦���ς�{�P�ʕς��܂��̂Ł@�M�q���Ē�����̃e�X�g�ŎO��ނ̃����Y�ŎB�����ʐ^�̔w�i�����傫���ɂ������_�Ł@�{�P�ʕς��Ă��܂��Ă���l�ȋC�����܂��B
������������܂��@�ȒP�Ɍ����Ɓ@�������ʐ^�Ńp���t�H�[�J�X�Ɍ����Ă��傫������ƃ{�P�Ă��鎖���L��܂��̂Ł@�g�債�Ă̌��͐��m�ł͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�@
�����ԍ��F13885227
![]() 0�_
0�_
��f�̓����Y�̏œ_�����i�܂�A��Ō�����20mm�A30mm�A200mm�A300mm�ȂǕ�������Ă��܂��ˁj�As�͔�ʑ̋���[mm]�i�܂�B�e�����A�����Y�Ɣ�ʑ̂̊Ԋu�j�̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł��傤���H
�����ł��B
�œ_����(�����Y�Əœ_�̋���)�F��ʑ̋���(�����Y�Ɣ�ʑ̂̋���)�����̒����F��ʑ̂̒���
�ƍl���Ă܂��i�����Y�J��o���������ߎ������ǁA���̏ꍇ�͖��Ȃ��͂��j�B
��ʑ̂��傫���Ɏʂ��Ƃ������Ƃ́A�E�ӂ����B
���̏����̂��ƁAf��30mm�Ƃ������Ƃ�s��30÷0.02=1500mm�Ƃ������ƂŁA
30mm�̃����Y��1.8m�̐l���c�����ς��ɎB��ɂ�1.5m�̋����ŎB��B
���ꂪ300mm�̃����Y�Ȃ�15m�̋����ŎB�e���邱�ƂɂȂ�܂���ˁB
���ꂼ��̏ŁA�ǂ����F8�ŎB�e���āA��ʊE�[�x���قȂ�Ƃ������Ƃł��B
�Ⴆ�A���̐������ȉ��̌v�Z�y�[�W
http://shinddns.dip.jp/
�ɓ���Čv�Z���Ă��AF�l��5.6�ȏ�̂Ƃ���ł�30mm��300mm�̏ꍇ�Ŕ�ʊE�[�x�͂���Ă܂���ˁB
�����ԍ��F13885367
![]() 1�_
1�_
��gintaro����
�wF�l��5.6�ȏ�̂Ƃ���ł�30mm��300mm�̏ꍇ�Ŕ�ʊE�[�x�͂���Ă܂���ˁB�x
����͎���2011/12/10 15:17�@[13873966]�̏������݂Ōf�����Ă��钆���̃O���t�̈Ӗ�����Ƃ���Ɠ����ł͂���܂��H�@
�M�q���Ē�����͏œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω��ɂ��āA�܂���������ł͂Ȃ����Ƃ���ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��A������x�̕ω��͂��邱�Ƃ�F��������ŁA���̂���Ƃ����̂���������[13873966]�̍��̃O���t�̂悤�Ɍ���Ă��邱�Ƃɂ��ċ^���悵�Ă���ƁA���͗������Ă��܂��B
��ɁA[13873966]�̒����̃O���t��F16�ɂ����Ƃ��̂��̂��f�ڂ��܂��B�{�P�̗ʂ��J�[�u��`���Ă��邹���ŁA�œ_�����ɂ���Ĕ�ʊE�ƂȂ�͈͈͂ړ����܂����A���̗ʂɂ͑傫���͕ω����Ă��Ȃ��Ƃ����_�ɂ��āA�M�q���Ē������2011/12/11 10:17�@[13877517]�̏������݂Łu�܂����������ł͂Ȃ������ۂ̎B�e�ł͖����ł���덷�v�Ɣ[������Ă��܂��B
�������ł́u�傫���͕ω����Ă��Ȃ��v�̒��x�̖��ɂ͐G��܂���B
�����ԍ��F13885567
![]() 1�_
1�_
��܂����낤����
�{���I�ɓ������Ƃ������Ă�Ǝv���̂ł����A���͒�ʓI�ł��ˁB�����̌v�Z�ł�
���u�܂����������ł͂Ȃ������ۂ̎B�e�ł͖����ł���덷�v
�ł͂Ȃ��A���ۂɂ��肻���ȎB�e�ŁA�����炩�ɖ����ł��Ȃ����������Ă���A�Ƃ������Ƃł��B
�����Ă����������^�̃O���t�ł����Am=0.036�AF=2.8(APS-C)�ƂȂ��Ă��܂��B����m��F�Ƃ������p�����[�^��ς���O���t�͕ς��܂����A�l�ɂ���Ă͂�͂薳���ł��Ȃ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F13885661
![]() 0�_
0�_
���ƃ��{�}�� �Q����
���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B
���M�q���Ē�����̃e�X�g�ŎO��ނ̃����Y�ŎB�����ʐ^�̔w�i�����傫���ɂ������_��
�����[13873214]�̎��ł͂Ȃ��ł��傤���H����͔�ʊE�[�x�ł͂Ȃ��A�I�}�P�Ƃ��ă{�P�̃f�B�e�[�����r�����摜�ł��B
��ʊE�[�x�̔�r�Ƃ��ėᎦ�����̂�[13873167][13873180][13873197]�̂R�ŁA���ꂼ��̒���3��ނ̃����Y���B�e�{���Ŕ�r���Ă���A�w�i���傫���ɂ͂��Ă���܂���B
��L���e�ł�����x���ӌ�������Ɗ������ł��B
gintaro����
���т��т��肪�Ƃ��������܂��B
���œ_����(�����Y�Əœ_�̋���)�F��ʑ̋���(�����Y�Ɣ�ʑ̂̋���)�����̒����F��ʑ̂̒���
�ƍl���Ă܂��i�����Y�J��o���������ߎ������ǁA���̏ꍇ�͖��Ȃ��͂��j�B
���̕����܂������o���Ă��܂���̂ŁA�����l���Ă��܂��ˁB
�B�e�������ǂ��v�Z����̂��A�����킩��Ȃ��āA
��̕��ł�����man�������Ă����������u�{�P�v�Z�@�v
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html
��Agintaro�������Ă����������u��ʊE�[�x�̌v�Z�v���g�����Ȃ��Ă��܂���ł����B
�œ_�����ƎB�e�������P���ɔ�Ⴗ��̂��ǂ����A���邢�͌덷�͖������ėǂ��͈͂Ȃ̂��������o���Ă��Ȃ��̂ł��B
[13873546]�ŋL�����V�O�}�̎����ł��A�P���Ȕ��ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B����͎B�e�{�����ɒ[�ɍ����ꍇ������ł��傤���H
�܂��A�u�{�P�v�Z�@�v�Ɓu��ʊE�[�x�̌v�Z�v�ŃV�~�����[�V�������ʂ��قȂ邱�Ƃ��C�ɂȂ�܂��B
�t���T�C�Y�ōi���F8�Ƃ��A�œ_����30mm�A�B�e����1.5m�ƁA�œ_����300mm�A�B�e����15m����͂����ۂ̔�ʊE�[�x�́A�u�{�P�v�Z�@�v��800����f�����i���ꂪ��f���̏���j�ł�0.928m��0.848m��8cm�̍��A�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�ł�1.658m��1.334m�Ƃ�30cm�ȏ�̍��ƂȂ�܂��B
�܂��A�i���F1.4�Ƃ���ƁA�O�҂�0.07m��0.147m�Ŗ�8cm�̍��A��҂�0.234m��0.233m�łقڈꏏ�ƂȂ�܂��B
�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�͈ȑO����悭���p����Ă��Ă���A�u�{�P�v�Z�@�v�̓o��͂����P�A�Q�N�������Ǝv���܂����A�ǂ��炪�M���o���܂��ł��傤���H
�܂��Agintaro����͌����ʊE�[�x���o���Ē����܂������A������u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�Ƃ͈قȂ�悤�ł��B
�O����ʊE�[�x�����킹�Ĕ�ʊE�[�x���o���ƁA�ǂ̂悤�ɂȂ�܂��ł��傤���B
�ēx�A���肢�o����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13885731
![]() 0�_
0�_
�M�q���Ē����� ����ɂ�
������������������
[13873197]
���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ɣ�ʑ̂̑傫���i�܂�B�e�{���j�y�эi��Ƒ������ꍇ�A�L�p�ł��]���ł���ʊE�[�x�͈���
���̎ʐ^���_��35�o�����Y�̕����̔w�i�̃{�P���������Ȃ��@35�o�����Y�̕�����ʊE�[�x���[�������܂�
��[13873214]�̎��ł͂Ȃ��ł��傤���H����͔�ʊE�[�x�ł͂Ȃ��A�I�}�P�Ƃ��ă{�P�̃f�B�e�[�����r�����摜�ł��B
�Ə�����Ă��܂����@���ۂ͓����Ɍ����邽�߁@����Ŕ�ʊE�[�x�����ƌ����Ă���l�ȋC�����܂��d
���������@�����~�ɂ���ʊE�[�x�͎B�e������肪�����Ł@��ʊE�[�x�v�Z�ň�ԏd�v�ȁ@���e�����~�萔�ł����@�B�e������Ϗ܋����Ȃǂ��ς�Ɓ@�萔1300���@1000�`1500�̒��ł����邮�炢�ł�����d
��͂�@�����̖����b�ɂȂ肻���ł��̂Ł@����ŏI��ɂ��܂��B
�F�X�t�������Ă��������L��������܂����B
�����ԍ��F13886192
![]() 1�_
1�_
�M�q���Ē����� �������Ƃ����L��܂����B
����̃e�X�g��ʊE�[�x�ł͂Ȃ��@�p�[�X�̃e�X�g�Ƃ��Ă͂ƂĂ����ɐ���@�F�X�ȋ^�₪�������܂����B
�{���Ƀp�[�X�������Ă���ƔY�݂܂��ˁ@����Ŗ{���ɍŌ�ɂ��܂��B�F�X�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F13886452
![]() 1�_
1�_
��ʑ̂̑傫���i�{���j�������A��ʊE�[�x�������̏ꍇ�A
�{�P�͖]���̕����傫���Ƃ͂����茋�_�ł����Ǝv���܂��B
�� �]���͔�ʊE�[�x���A�{�P���傫�����ăz���g�ł����H
��ʊE�[�x���킯�ł͂���܂��A�œ_�������Ŗ]���̃{�P�i�{���j���傫���ł��B
�����ԍ��F13886766
![]() 0�_
0�_
�����̕����܂������o���Ă��܂���̂ŁA�����l���Ă��܂��ˁB
�B�e�������ǂ��v�Z����̂��A�����킩��Ȃ��āA
�}�N���I�ȎB�e�ȊO�ł́A�œ_�����͔�ʑ̋������P���ȏ㏬�����Ȃ�A���̂悤�ȏł́u�œ_�����F��ʑ̋����v�𑜔{���ƍl���đ��v�ł��傤�B
�u�{�P�v�Z�@�v�ł��A���̔䂪���Ȃ�A���˂�����̑傫�����ς��Ȃ����Ƃ��m���߂��܂��B
���u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�͈ȑO����悭���p����Ă��Ă���A�u�{�P�v�Z�@�v�̓o��͂����P�A�Q�N�������Ǝv���܂����A�ǂ��炪�M���o���܂��ł��傤���H
�����A�ǂ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�l�̈Ⴂ�͍̗p���Ă��鋖�e�����~�a�̈Ⴂ�ł��傤�B
�Ⴆ�A�ڂ��v�Z�@��F12.5�Ƃ�����A��ʊE�[�x�̌v�Z��F8�̒l���o�Ă����ł��B
�t�H�[�}�b�g���Œ肵�čl���Ă���킯�ł����A��萳�m�ɂ͋��e�����~�a���Œ肵�čl�������킯�ł���ˁB�ǂ̒l���̗p���Ă����܂��܂��A��U���߂��炻���ς��Ȃ����Ƃ��d�v�ł��B
���܂��Agintaro����͌����ʊE�[�x���o���Ē����܂������A������u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�Ƃ͈قȂ�悤�ł��B
�O����ʊE�[�x�����킹�Ĕ�ʊE�[�x���o���ƁA�ǂ̂悤�ɂȂ�܂��ł��傤���B
���{����F�l���Œ肵����ŏœ_������傫�����Ă䂭�ƁA�����ʊE�[�x�͏������Ȃ�O����ʊE�[�x�͑傫���Ȃ�܂��B���̍��v����ʊE�[�x�ł�����A���҂͑��E����X���ɂ���܂��B�����A����ł��Ȃ��A���R�덷�͎c��܂��B
�ڂ��v�Z�@�̕����g���Ă݂܂����A�t���T�C�Y��
f=30mm�As=1.5m��F28���Ɣ�ʊE�[�x�͖�����Ńp���t�H�[�J�X�������܂����A
f=300mm�As=15m��F28�ł͔�ʊE�[�x��3m�ɂ����Ȃ�܂���A���o����͐[�x�ɓ����Ă��A�Ԃ͐[�x����͂ݏo�Ă��܂��ł��傤�B
�����ԍ��F13887587
![]() 1�_
1�_
���̃O���t�́u�K�E�X�̌��������v���g�����v�Z�ł���A���̌������̂��ߎ����Ȃ̂Ō덷�͂���܂��B
http://shinddns.dip.jp/ �ŏЉ��Ă���v�Z���@����{�I�ɂ́u�K�E�X�̌��������v���瓱���Ă�����̂Ǝv���܂��i�����Ɗm�F�����킯�ł͂���܂���j���A����ɋߎ����d�˂Ă���̂Ō덷���]�v�ɑ傫���Ȃ��Ă���_�ɂ����Ӊ������B���ɍL�p�����Y�ŋߐڎB�e������ꍇ��F�l�̑傫�������ł͂Ђǂ��Ȃ�܂��B
�Ƃ͂����Ă��A���������̌����Ɍ덷������ȏ�͌\���S���ł��傤���ǂˁB
����ŁA���[�J�[�̌v�Z�l�͂����ƕ��G�ȁA���ۂ̃����Y�̐v�Ɋ�Â��������Ȍv�Z�����Ă�����̂Ǝv���܂��B
�K�E�X�̌��������̋ߎ����鏊�Ȃ́u�����Y�������āA�����������ł�����̂Ƃ��Ă���v���Ƃɂ��܂����A���[�J�[�̌����v�Z�ł͂����ƃ����Y�̒����܂Ő��m�Ɍv�Z�ɂ���Ă�����̂Ǝv���܂��B
�����덷�����낤�ƂȂ��낤�ƁA�����ő��_�ƂȂ��Ă���u�]���͔�ʊE�[�x���̂��v�Ƃ����h�œ_�����Ɣ�ʊE�[�x�̌X���h�ɂ��Ă����A�K�E�X�̌����������������ߎ��v�Z�ł��\���c�����邱�Ƃ͂ł���͂��ł���A�Ǝv���Ă܂��B
�����ԍ��F13887687
![]() 3�_
3�_
�������덷�����낤�ƂȂ��낤�ƁA�����ő��_�ƂȂ��Ă���u�]���͔�ʊE�[�x���̂��v�Ƃ����h�œ_�����Ɣ�ʊE�[�x�̌X���h�ɂ��Ă����A�K�E�X�̌����������������ߎ��v�Z�ł��\���c�����邱�Ƃ͂ł���͂��ł���A�Ǝv���Ă܂��B
�����������l���܂��B
�����āA�J��Ԃ��܂����A��܂����낤����̌v�Z���ʂ͎��̎咣�Ɩ������Ă�킯�ł͂���܂���B
��܂����낤����̃O���t��APS-C�ő��{��0.036�AF�l2.8�Ƃ������A���ʂȏꍇ�̂��̂ł����A���̂悤�ɔ�ʊE�[�x�̔����ł́A�[�x�̏œ_�����ɂ�邸��͏������Ȃ�܂��B
�܂�A���܂��܁A��ʊE�[�x�̍����o�ɂ����p�����[�^��I��ł����킯�ł��B
�Ⴆ�A���{����(0.018)�ɂ��āAF�l��16�Ƃ��ɂ���A��ʊE�[�x�͑傫���炯�܂���ˁB���ꂪ���̎咣���Ă��邱�Ƃł��B
�����ԍ��F13889320
![]() 1�_
1�_
gintaro����͎����ŗǂ��������������ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13889640
![]() 1�_
1�_
�������M�̍l��������Ӗ������߂āA�܂Ƃ߂Ă����܂��B
�t�H�[�}�b�g�A���e�����~�a���Œ肵�čl����B
���̂Ƃ��A��ʊE�[�xD�́A
���{��(m)�AF�l(F)�A�œ_����(f)
�̊��ƍl������i��ʑ̋������œ_����÷���{���@�Ƃ���j�B
���̊�D=D(m,F,f)��f�ˑ����A�܂�A�œ_�������ω������Ƃ���ʊE�[�xD���ǂꂾ���ω����邩�A���A���ɂ���B
D�̎��̋�̌`�̓K���X�̖ڂ���̏Љ�ꂽ�y�[�W�Q�ƁB
�������番����X��
�E��ʊE�[�x�͊m���ɏœ_�����Ɉˑ�����
�E���{���������������œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω����傫��
�EF�l���傫�������œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω����傫��
�����ۂ̎B�e�ւ̉e��
�E���{�����傫���ꍇ�AF�l���������ꍇ�́A��ʊE�[�x�͐��A�œ_�����ɂ��[�x�̕ω��͂킸���Ȃ̂Ŏ��p����ɂȂ�Ȃ��B
�E���{�����������ꍇ�AF�l���傫���ꍇ�́A��ʊE�[�x���̂��[�����߂ɁA��������p����Ȃ��B
�E���̊Ԃ̒��r���[�ȂƂ���ŁA�œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̍������ɂȂ�̈悪���݂���B
�Ƃ����킯�ŁA�����Ƃ���ʊE�[�x���C�ɂȂ�J���t�߂ł̎B�e�A�ߐڎB�e�ł͖��͌����܂���B�i�O���t�Ŏ�����Ă�̂͂��̃P�[�X�B�j
�������A�p���t�H�[�J�X�ɂȂ�܂ōi���Ă��܂��ƁA��͂���͌����Ȃ��Ȃ�܂��B
���̔������A�����܂������A���̌��ۂ���ɂ������Ă���Ǝv���܂��B
�����鐯���߂炳��@
��ʎ��A�u�ڂ��v�Z�@�v�A�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�A�S�Ăɂ��ċ�̓I���l�������āA
���� �]���͔�ʊE�[�x���A�{�P���傫�����ăz���g�ł����H
����ʊE�[�x���킯�ł͂���܂���
�́A�ԈႢ�A���Ƃ������Ƃ�Ꭶ�����Ă����Ȃ̂ł����A�ǂ������������̂ł��傤���B
���܂肿���ƍl�������ƂȂ��̂ŁA���������Ă邩������܂��AF�l���Œ肵�Ă��œ_�����ɂ���Ĕ�ʊE�[�x���ω����邱�Ƃ́A���݂̂Ȃ�����F�߂Ă��܂��B
�����ԍ��F13889724
![]() 4�_
4�_
gintaro����A�����炭�N���M���ɐ����ł��Ȃ��Ǝv���܂��B���₷�݂Ȃ����B
�����ԍ��F13889737
![]() 0�_
0�_
�œ_�����\�{���Ⴄ�����Y��f/8�܂ōi���ē̌덷���o�܂����A���x�������ł���B
�ڂ��ɂ��قǎʐ^�����Ă��Ȃ��Ȃ�������ɂ����ł��B���p�\���A�V���v���Ŏg���₷���ł��B
���Ȃ݂ɑ��Θ_�����H�ώ@�ŏؖ����ꂽ���ɂǂ̈ʂ̌덷���������������m�ł����H
�_���v�Z�Ǝ����l�́u�������قڈ�v�v�ł����B����Ő��E���F�߂��̂ł��B
�F���A�ő��Θ_��萸�x���������h�Ȍ��_���ł����Ǝv���܂��B
���Θ_������ȏ�A��ΐ��m�Ȃ��̂��Ȃ��ł�����A���߂Ă����ʂł��B
�����ԍ��F13889816
![]() 1�_
1�_
�u�����Y�̌����͋ߎ��v�Ƃ���܂����A����͔F�߂Ă�������Ȃ����Ȃ��ƁB��̂ɂ��������o���ł����B
�ŁA��G�c�ɂ�炸�˂�����ōl����ƂȂ�ƁA�u��ʑ̋������œ_����÷���{���v�ł͂Ȃ���ł���ˁi�����g���ꂪ���{���ł��邩�̂悤�ɏ����܂������j�B
>�K���X�̖ڂ���̏Љ�ꂽ�y�[�W�Q��
���ꎄ�̃��X�̃����N��Ɠ����ł��ˁB
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
�����̋L�����g����
���{������ʑ̋���÷t
�ł��ˁB
�ŁA�����N��̃y�[�W�͖����ł����A���o���ꂽ��(25)��(26)�͂ǂ��ł����������Ă���悤�ł����E�E�E�B
��(2)�͂����Ԃ���������ł���ˁB
�����̂Ƃ���������Ƃ�낤�Ƃ���ƁA��������Y��Ȏ��ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ȁi�̂�����L���j�B
���������͂����炭�R���s���[�^�[�Ɍv�Z�����ăO���t�����Ă������ƂɂȂ�ł��傤���A�������牽�������邩�Ƃ����ƁE�E�E�ǂ��Ȃ�ł��傤�H
�����ԍ��F13889862
![]() 0�_
0�_
���ƃ��{�}�� �Q����
�����̎ʐ^���_��35�o�����Y�̕����̔w�i�̃{�P���������Ȃ��@35�o�����Y�̕�����ʊE�[�x���[�������܂�
�Ȃ�قǁA�������܂����I
���ɂƂ��Ĕ�ʊE�[�x�������Ɍ�������r�摜���A���ƃ��{�}�� �Q����ɂƂ��Ă͈Ⴄ��ۂ������Ƃ����̂����{�ɂ������̂ł��ˁB
�{�P�̃f�B�e�[����r�摜�́A����ɂ���Đ[�x���Ɍ����悤�Ƃ�����ł͂Ȃ��A�[�x�������ꍇ�A���̂悤�ɂȂ�̂ł́H�Ƃ������Ƃ����������Čf�ڂ��܂����B
������ɂ��Ă��A���t�����������������肪�Ƃ��������܂����B
���鐯���߂炳��̏������݂͂����Q�l�ɂ����Ē����Ă���܂����A���̕��̋C�����Q���Ȃ��悤���t��I��ł���������K���ł��B
�����͖鏑���܂��B
�����ԍ��F13890203
![]() 2�_
2�_
���œ_�����\�{���Ⴄ�����Y��f/8�܂ōi���ē̌덷���o�܂����A���x�������ł���B
�܂�A�]���̂ق�����ʊE�[�x���Ȃ�킯�ł��ˁB
2���Ƃ����Ă������ʊE�[�x��2�{�ȏ�Ⴂ�܂����A�����܂ł�����̘̏b�ŁA���łɏ������悤�ɍi����͑傫���Ȃ�܂��B�t���T�C�Y��F8���i��Ȃ��ł����H
���_���v�Z�Ǝ����l�́u�������قڈ�v�v�ł����B����Ő��E���F�߂��̂ł��B
���v�덷�͈̔͂ŗ��_�l�Ɗϑ��l�͈�v���Ă�����ł���B�܂��A���Θ_�̘b�͂����Ƃ��āA���̏ꍇ�A���{����i���ς���Ό덷�͖�����ɂ��Ȃ�܂��B
�������݂͂悭�Q�l�ɂ����Ă��������Ă܂����A���鐯���߂炳��炵����ʃ|�J�ł����ˁB
�����ԍ��F13891969
![]() 0�_
0�_
�����s�̂�������
�w�u��ʑ̋������œ_����÷���{���v�ł͂Ȃ���ł���ˁi�����j��������Y��Ȏ��ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ȁx
�K�E�X�̌�������W�J����ƁA
�@�@�k����×�i���O�Q�{�Q���{�P�j÷��
�@�@�@�k�F�B�e����
�@�@�@���F�����Y�̏œ_����
�@�@�@���F�B�e�{��
�Ƃ����܂�肭�ǂ����ɂȂ�܂��ˁB
����̖ʔ����Ƃ���́A�B�e�{�����P���đ����Ă����ƁA�B�e�����������Ȃ��Ă������Ƃł��B
�E�����X�ł���(��)�B
�����ԍ��F13892196
![]() 0�_
0�_
�O��̔�ʊE�[�x�͈ꉞ�v�Z��ɂ͂���܂����A���p��ł͊W������ł��傤���B
AF��MF���ǂ̂悤�ɂ���Ă��܂����A�s���g�̎R�͉����ɂ���̂ł��傤���A
�����ŋc�_������g�U���܂����A�ɂ���������ʔ����b���Ǝv���܂��B
���H���痣�ꂽ�_����v�Z���咣�������Ƌ�Ȃ�A��������邩���m��܂��B
�ǂ��������Ă���o�����������ǂ������m��܂���B
�����ԍ��F13893195
![]() 1�_
1�_
�� �������M�̍l��������Ӗ������߂āA�܂Ƃ߂Ă����܂��B
���݂܂���A����������Ƃ��܂����B��肭�����ł��Ȃ���A
�b�����u���ĉ������ˑR�������Ă��邩���m��܂���B���������߂��܂��B
�����ԍ��F13893308
![]() 1�_
1�_
���K�E�X�̌�������W�J����ƁA
�@�@�k����×�i���O�Q�{�Q���{�P�j÷��
�B�e�{��0.01�Ȃ�0.0098
0.02�Ȃ�0.0192
0.036�Ȃ�0.0335
�Ƃ��������ŁA���ꂭ�炢�Ȃ�덷�͏������ł��ˁB
������ɂ���A���z�I�ɔ������w�n�ł́A�B�e�{��m�����߂�ƁAf/L�͌��܂��Ă��܂��킯�ŁA�œ_������10�{������B�e������10�{����悢�킯�ł��ˁB
���ۂ̃����Y�ōŒZ�B�e����(m=0.1�`)������ɂȂ�ƁA����������̌������̂��g���Ȃ��Ȃ�̂ł��傤�B
�����ԍ��F13895768
![]() 0�_
0�_
gintaro����
�܂��A�œ_����(�����Y�Əœ_�̋���)�F��ʑ̋���(�����Y�Ɣ�ʑ̂̋���)�����̒����F��ʑ̂̒����̌��A�����o���܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
���ɁA�u�{�P�v�Z�@�v�Ɓu��ʊE�[�x�̌v�Z�v�ł̃V�~�����[�V�������ʂ̈Ⴂ�ł����A�����Ԉ�������l���L�����Ă��܂��܂����B�v�Z�@�g���Ă��v�Z�ł��Ȃ��Ƃ́c�i�܁j
�������́A�u�{�P�v�Z�@�v�ł�F1.4��30mm��300mm���قړ���l�ł����B
�F�l�A�ꕔ�٘_�������Ă���܂����A����܂ł̂Ƃ���gintaro����[13889724]�ł܂Ƃ߂ĉ����������e�����ꌩ���ɂȂ��Ă��邩�Ǝv���܂��B
�E��ʊE�[�x�͊m���ɏœ_�����Ɉˑ�����i�����̓_���Ԉ���Ă���A���̃X���ŗ����ł��܂����B�ǂ̍i���B�e�{���ł��A�����Ə����Ȍ덷�Ǝv���Ă��܂����j
�E���{���������������œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω����傫��
�EF�l���傫�������œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̕ω����傫��
�����ۂ̎B�e�ւ̉e��
�E���{�����傫���ꍇ�AF�l���������ꍇ�́A��ʊE�[�x�͐��A�œ_�����ɂ��[�x�̕ω��͂킸���Ȃ̂Ŏ��p����ɂȂ�Ȃ��B
�E���{�����������ꍇ�AF�l���傫���ꍇ�́A��ʊE�[�x���̂��[�����߂ɁA��������p����Ȃ��B
�E���̊Ԃ̒��r���[�ȂƂ���ŁA�œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̍������ɂȂ�̈悪���݂���B�i�����̓_�����̃X���ł킩�������ƂŁA���ɋ����[���ł��j
�����ňӌ����������̂��ǂ̂�����܂ł��u��ʊE�[�x���T�˓����v�Ɗ����邩�A�ł��B����͊������Ȃ̂Ő����͂���܂���ˁB
�����g�A���l�̈�ۂ����Ō����A5%���x�Ȃ�u�T�˓����v�ƌ����Ă悢�Ɗ����܂��B
�������A���ۂ̎B�e�ł͂킩��܂���B
���ɏ������A�b�v�ŎB�e�����ꍇ��5%�̍����������獷�ق�������ł��傤�B
�i�������A���̃V�`���G�[�V�����ł͍i���Ă��[�x�ɍ����o�܂��j
�܂��A300mm��15m����āA����30mm��1.5m����Đl�����c�B�e�����ꍇ�ɁA�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�ɂ��1.66m��1.33m�̐[�x�����������邩�Ƃ����ƁA�l�����̂͂ǂ�����[�x���Ɏ��܂��Ă��܂��܂��̂Ŋ����ɂ����ł��傤�B���鐯���߂炳��̊��o�ɋ߂���������܂���B
�l���Ȃǂł͂Ȃ��A�O��ɘA�������u�����v���L�^����ꍇ�ɂ́A���l�ʂ�ɐ[�x�����d�v�ɂȂ邩������܂���ˁB
�����Ȃ���������A���ۂɎB�e���Ă݂邵���Ȃ��ł��傤�B
���̏T���A���Ԃ���ꂽ���ȂLj��Ԋu�̕��Ŏ���������ŁA�[�x�̍���������V�`���G�[�V�����������Ă݂����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13903559
![]() 1�_
1�_
[13889862] ��
>���{������ʑ̋���÷t
����͊ԈႢ�ŁA�u���{����t÷��ʑ̋����v���������ł��B�����܂���B
��ʑ̋���:s
�œ_�����@:f
�̋L����p���āA�����Y�̌�����
1/s + 1/t = 1/f
�ł��̂ŁAt �����������
���{���� f / (s - f)
���o�܂��B
�ŁA�����ŏЉ�Ă����ĂȂ�ł���
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
�̎�(2)�͂��������ł��ˁB��萳�m�Ȏ���
�� = F * �� * (t/f)
�ł��傤�B���{�}�N���߂��ŃÂɓ�{�̍������܂��B
����Ō����ʊE�[�x�iDf�j�̂��߂܂��ƁA
Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)
�ƂȂ�܂��B���ʂ̔�ʊE�[�x����͂蓙�{�}�N���߂��Łi�����N��̎��Ɣ�ׂāj��{�̍����t���܂��B
���q�� ��Fs �͏������B�e�����ł͖����ł��܂��̂ŁA
�B�e�{��:m
�̋L����p���āA
Df = ��F * {s / (s - f)} * (1 / m^2)
��Ԗڂ̍� {s / (s - f)} �����邱�Ƃ�
�u�œ_�����������ق�����ʊE�[�x���w�[���x�v
�ƌ����܂��B
�����ԍ��F13904859
![]() 0�_
0�_
>��Ԗڂ̍� {s / (s - f)} �����邱�Ƃ�
>�u�œ_�����������ق�����ʊE�[�x���w�[���x�v
>�ƌ����܂��B
��̍��������ʂ����ɒ����B
m = f / (s - f) �ł����A�u�B�e�{�����Ȃ�A�B�e�����͏œ_�����ɔ��v�Ƃ��Ă��T�ˍ����Ă���ł��傤�B
�ł��̂ŁA�B�e�{�����Ȃ�A��Ԗڂ̍� {s / (s - f)} �͈��Ƃ��ėǂ��ł��傤�i�œ_����y�{�Ȃ�A�B�e������y�{����A�䂦�ɓ�Ԗڂ̍��͈��j�B
����āA
�u�t�H�[�}�b�g�� F�l�A����юB�e�{�����������̎B�e�ł́A��ʊE�[�x�͏œ_�����Ɉˑ����Ȃ��v
�ƌ����܂��B
�����ԍ��F13904891
![]() 0�_
0�_
����H���ꂾ�Ɣ�ʊE�[�x���e�ɔ�Ⴕ���Ⴂ�܂���ˁB
�p���t�H�[�J�X�iDf=������j��^����p�����[�^�͂���͂��ł�����A�ǂ������������͂��B
�����ԍ��F13905258
![]() 0�_
0�_
������x�v�Z���Ă݂܂������A
�� = F * �� * (t/f)�@�E�E�E(2`)
�Ƃ���
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
�̎�(8) �ɑ������ƁA��(9) ���炿����
Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)�@�E�E�E(9`)
�ƂȂ�܂��B
�Ȃ��A�����N��̎�(9)��
Df = sf - s
�̌�A�ł��i���̏ꍇ�́usf�v�͈�̕ϐ��ł��i�us-far�v�̈Ӗ��Ǝv����j�j�B
�p���t�H�[�J�X�̏����͎�(9`)���
��Fs > f^2
�ŁA�e�Ղ�
s > (f^2) / (��F)
���Ƃ킩��܂��B
�܂��A��ʊE�[�x�� F�l�ɔ�Ⴗ��̂́A�����I�ɂ��펯�I�i�o���I�j�ɂ��[�������b���Ǝv���܂����B
�����ԍ��F13906592
![]() 0�_
0�_
�������� [13904891] ���������傢�����Ə����Ă����܂��B
>�u�t�H�[�}�b�g�� F�l�A����юB�e�{�����������̎B�e�ł́A��ʊE�[�x�͏œ_�����Ɉˑ����Ȃ��v
�����
�u�t�H�[�}�b�g�� F�l�A����юB�e�{�����A���� f^2 >> ��Fs �Ƃ������Ƒ傫�ڂ̎B�e�{���A���������ׂĖ��������������̎B�e�ł́A��ʊE�[�x�͏œ_�����Ɉˑ����Ȃ��v
�Ə��������܂��B
��Fs �� f^2 �ɑ��Ė����ł��Ȃ��قǑ傫���ꍇ�́A[13906592] ����u�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â����B�e�v�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ƃǂ��ł������b���ȁA�ƁB
�����ԍ��F13906643
![]() 0�_
0�_
�����́B
�v�Z���Ɋւ��Ă͊F���܂ɂ��C�����āc�B
������͎��ʂ̕��ł����A�[�����炵���O�ɏo��ꂸ�����Ƃ�����r�ʐ^���B��܂���ł����B
����ł��ꉞ�A�b�v�v���܂��B
�T��180cm���x�̍������c�ʒu�AF8�ŏœ_����28mm�A75mm�A200mm��3��B��܂����B
�O���[���̒��Ƀs���g�����킹�Ă��܂��B�������߂̍�̊Ԋu��180cm���炢�A��{��{�̍�̊Ԋu��5cm���炢�ł��B
�ǂ��ł��傤�A��ʊE�[�x���Ⴄ�̂������Ȃ̂��A���ʏo���銴���ł��Ȃ��ł��ˁc�B
�����ԍ��F13906783
![]() 0�_
0�_
>��Fs �� f^2 �ɑ��Ė����ł��Ȃ��قǑ傫���ꍇ�́A[13906592] ����u�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â����B�e�v�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ƃǂ��ł������b���ȁA�ƁB
��Fs �����Ȃ��ōl���Ă݂܂����B
>Df = ��F * {s / (s - f)} * (1 / m^2)
���̎�����������
Df = ��F * C * (1 / A)
������
C = s / (s - f)
A = m^2 - {��FC / (s - f)}
������ C �͂قڒ萔�i[13904891]�j�B
�܂��A�� A = m^2 - {��FC / (s - f)} �ɂ����āAf �� s �͔��W�i[13904891] �Ɠ������R�j�B
�䂦�ɏœ_���� f ���傫���Ȃ�A��� {��FC / (s - f)} ���������Ȃ�A���� A �� m^2 �ɋ߂Â��悤�ɑ傫���Ȃ�i������ A < m^2�j�B
A ���傫���Ȃ�̂����� Df �͏������Ȃ�i�����ʊE�[�x���Ȃ�j�B
�ƌ������ƂŁE�E�E�B
���������u�œ_�����������Ȃ�Ό����ʊE�[�x�͐Ȃ�v���Ƃ�������܂������E�E�E�B
��FC �̓t���T�C�Y�ł� 0.1 �ȉ����炢�iF=2.8 �Ƃ��āj�B
s - f ���Ăǂ̂��炢�ł��傤�H �œ_���� 50mm �̃����Y�� s = 250mm ���炢�H ��������� s - f = 200 �ƂȂ�A{��FC / (s - f)} �� 0.0005 �Ƃ���߂ď������B
�B�e�{�������܂�傫���Ȃ��Ƃ��͊m���ɖ]���̂ق�����ʊE�[�x�͐ƌ����Ă����̂�������܂��E�E�E�A�����܂� {��FC / (s - f)} �������e�����邩�ƌ����ƁE�E�E�͂āH�Ȋ����ł��B
���Ƃ͎�v�ȏœ_�����̃����Y���s�b�N�A�b�v���āA�u�B�e�{���̊��Ƃ��Ă̌����ʊE�[�x�v�̓��O���t��`���B�œ_�����̐��������O���t��p�ӂ���B
�E�E�E�Ƃ��������ł����ˁB
�����킽���͂��C���N���܂��i�u�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â����B�e�v�ɂȂ�̂ŁA�債�ďd�v�łȂ��C������j�B
�����ԍ��F13906917
![]() 1�_
1�_
�A�����݂܂���B
>�B�e�{�������܂�傫���Ȃ��Ƃ��͊m���ɖ]���̂ق�����ʊE�[�x�͐ƌ����Ă����̂�������܂��E�E�E�A�����܂� {��FC / (s - f)} �������e�����邩�ƌ����ƁE�E�E�͂āH�Ȋ����ł��B
�u�B�e�{�������܂�傫���Ȃ��Ƃ��͊m���ɖ]���̂ق�����ʊE�[�x�͐ƌ����Ă����̂ł����E�E�E�A�B�e�{�����傫���Ȃ��Ƃ� (s - f) ���傫���Ȃ� �� {��FC / (s - f)} �����ɏ������Ȃ�A�Ƃ������ƂŁE�E�E����ς�e���͏��Ȃ��Ǝv���܂��v
�Ƃ��������ł��B
�N���O���t���v���b�g���Ă���Ȃ��ł����ˁB���͏œ_�����͂���Ȃɉe�����Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F13906952
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������@
�⑫���肪�Ƃ��������܂����B
�p���t�H�[-�J�X��^����e�l�̑O��ł́A�e�l�Ɣ�ʊE�[�x����Ⴕ���Ⴈ�������ȁA�Ƃ����^��ł����āA
�u f^2 >> ��Fs �Ƃ������Ƒ傫�ڂ̎B�e�{���v�̘b�ł���A��肠��܂���B
���s�̂�������̎����������āA�T�C�g�̎��͏o���_�Ƃ��Ă͂ӂ��킵���Ȃ������悤�ł��B
�����ŁA�i�O���t�̑���Ɂj
Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)�@�E�E�E(9`)
�Ɋ�Â��Čv�Z���Ă݂܂��傤�B
���e�����~�a�F��=0.033(�u��ʊE�[�x�̌v�Z�v�̃y�[�W�ɂ���t���T�C�Y�̒l)
�i��F�e=9
�œ_����(f)�F�`30mm�A�a300mm
��ʑ̋���(s)�F�`3m�A�a30m
�`�̏ꍇ�A�����ʊE�[�x�͖�����ł��B
�a�̏ꍇ�A�����ʊE�[�x��3293mm����3.3m�ł��B
���̃��f���̌��A
�u�t�H�[�}�b�g�AF�l�����ł��A�œ_�����ɂ���Đ[�x�Ɏ��p�㖳���ł��Ȃ��Ⴂ���o��ꍇ������v
���ꂪ�����̎咣���Ă��邱�Ƃł��ˁB�]���B�e�ł͍i���Ă��i���Ă��Ȃ��Ȃ��p���t�H�[�J�X�������Ȃ��A�Ƃ��������ۂƂ��đ̊��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���s�̂�������̎咣�ɂ͂قƂ�Ǔ��ӂł��܂����A
����Fs �� f^2 �ɑ��Ė����ł��Ȃ��قǑ傫���ꍇ�́A[13906592] ����u�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â����B�e�v�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ƃǂ��ł������b����
����͂���Ȃ̂��Ǝv���܂��B�قȂ�f�i��s�j���m���r���Ă�̂ŁA����̃p�����[�^�Ńp���t�H�[�J�X�ɂȂ��Ă��Ă���������ł͂����Ȃ��Ă��Ȃ������肷��킯�Ȃ̂ŁA�����́A��ł��������Ƃ�������ȂƂ���ł��B
�����ԍ��F13907034
![]() 0�_
0�_
�����A�⑫�ł͂Ȃ��āA���܂ōl���Ă�������Ȃ������̂��A���̃X���ŎB�e�{���Ȃǃq���g�Ĉ�C�ɓ����J�����Ƃ������Ƃł��B
���݂̖��� [13906917] �̂��̎��ł��ˁB
A = m^2 - {��FC / (s - f)}
y = A
x = s - f
B = ��FC
�Ƃ��܂��B
�B�e�{�� m �����̎��Af ��傫������Ƃǂ����H ���b��ƂȂ��Ă��܂��B
���̂Ƃ��́A�ux �́A�œ_���� f �ɐ����i���W���� 1 �j�v�ł��ˁBf ��10�{�ɂȂ�� s ��10�{�A����� x ��10�{�B
���̎��͈ȉ��̂悤�ɏ���������܂��B
y = m^2 - (B / x)
����� y = 1/x �Ƃ�������������{�ɂȂ��Ă܂��ˁB��L��ϐ� x �ɂ��Ĕ������܂��B
y' = B / x^2
����͂������ y' > 0 �Ȃ̂ŁA�E���オ��́i�œ_���� f ���傫���Ȃ�Ay ���傫���Ȃ�j�O���t�Ȃ̂ł����A���́u�オ���v�͂����قǂ̂��̂ł��傤�H
���AB �� 0.1 ���x�ł��i[13906917] �Q�Ɓj�B
����ɑ��� x �͂����ނˁA
200 < x < 30,000
���x�ƁA�ƂĂ��Ȃ��傫���ł��i�P�ʂ̓~�����[�g���j�B�E�̍��� 20,000 ��
s > (f^2) / (��F)
�� f=50, ��= 0.03, F=2.8 ���狁�߂܂����B
�܂��L�̕������́u���ۂɎg�������̃O���t�̌X���ix �̕ω��ɑ��� y �̕ω��̊����j�v�́A�ق� 0 �ɋ߂��Ȃ�܂��B
���B�e�{�����̏ꍇ�̌����ʊE�[�x�́A�œ_���� f �̉e�����قƂ�ǎȂ�
����ő�ӂ͎����ꂽ�ƌ����Ă悢�̂ł́H
�����ԍ��F13907418
![]() 0�_
0�_
>�E�̍��� 20,000 ��
>s > (f^2) / (��F)
>�� f=50, ��= 0.03, F=2.8 ���狁�߂܂����B
�u�E�̍��� 30,000 �́v�̊ԈႢ�ł��B
���ۂɂ����ƌv�Z����� 29,711 �ł����B
�����ԍ��F13907425
![]() 0�_
0�_
������ő�ӂ͎����ꂽ�ƌ����Ă悢�̂ł́H
���łɔ���[13907034]������̂ŁA�ؖ��͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
��ʂɊ�f(t)�̕ω������ǂ�Ȃɏ������Ă��A1/f(t)�̕ω������������Ƃ͌����܂����ˁB
f(t)=0�ƂȂ�_t�̋߂��ł͖�����ɂȂ蓾�܂�����B
�����ԍ��F13907474
![]() 0�_
0�_
�����A������������ʖڂ݂����ł��B
50mm �����Y�̃p���t�H�[�J�X�߂��ɂȂ��
m^2 �� (B / x) ���ɂ߂ċ߂��l�ɂȂ�B
�Ƃ��낪 500mm �����Y�̏ꍇ�A�ꌅ�I�[�_�[���Ⴄ�̂ŁA50mm �����Y�̂Ƃ��� x ���g����
m^2 �� 10 * (B / x) ���炢�ɂȂ�B
Df ��������������Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F13907527
![]() 1�_
1�_
��������ʖڂȗ��R��
>��ʂɊ�f(t)�̕ω������ǂ�Ȃɏ������Ă��A1/f(t)�̕ω������������Ƃ͌����܂����ˁB
����ł��ˁB
�uf(t)�̕ω������������邽�߁A1/f(t)�̕ω����傫���v���Ċ����ł����B
�����ԍ��F13907538
![]() 0�_
0�_
�� �œ_�����ɂ���Đ[�x�Ɏ��p�㖳���ł��Ȃ��Ⴂ���o��ꍇ������
������Ȃ炻��͍ō��ٔ��f�ł��B�����������l�����K�p�ł��܂��B
�����I�ɔ�ʊE�[�x�s�ς̌��_�̓V���v���ŕ�����₷�������ŋ����Ă����h���Ǝv���܂��B
�덷�͏o�܂�������͉��p�Ɩw�NJW�Ȃ��ꍇ�ł��B
28�~����300�~���ŔY�ޏꍇ�A���ʂ��ɂ�����ʊE�[�x���厖�Ȃ��ƈ�t����ł��傤�B
�����ԍ��F13907540
![]() 1�_
1�_
���덷�͏o�܂�������͉��p�Ɩw�NJW�Ȃ��ꍇ�ł��B
�l�t�H�[�T�[�Y�̍��{���Y�[��M.ZD14-150/F4.0-5.6�ő�^�o�X���B��܂��傤�B���Z���{��0.01�Ƃ��āA�����ł��ڂ����~�������͂ǂ�����悢���H
�V���v���ŕ�����₷����ʊE�[�x�s�ϐ_�b��M����Ȃ�u�J��F�l�̏������L�p�[�ŎB��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�łƂ��낪���ۂ́A�L�p�[�ł͊J���ł�40m�`50m��܂Ńs���g�������Ă��܂��A����A�J���e�l�̑傫���]���[�̕��́A����ɍi��Ȃ��ƃo�X1���ʊE�[�x�ɓ���܂���B���ꂪ��������̋A���ł��B
���ꂭ�炢�̔{���ł́A14mm��150mm�̏œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̍��́A14mm@�t�H�[�T�[�Y��28mm@�t���T�C�Y�̃t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ�ɕC�G���܂��ˁB
���������Ⴂ���ǂ��ł��ǂ��l�͋C�ɂ��Ȃ���Ηǂ��ł��ˁB
�ʂɁA�œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ�ɋC��t����ƁA���v���Ă�킯�ł͂Ȃ��̂ł�����B
�����ԍ��F13910491
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
�܂��͐������l���o���̂���ŁA�ǂ̒��x�����p�͈͂Ƃ���̂��͐l���ꂼ��ł��傤���牟���t������c�_�����肵�Ă��d���Ȃ��ł��傤�B
�����A����o���ꍇ�͏������K�v�ł��ˁB����ɂ���Ċe�������f�o���܂�����B
gintaro����
�o�X�̗�́A�u�����ł��ڂ����~�����v���w�i�ڂ��̂��ƂȂ���킸�]���ł��ˁB
�u�����ł��[�x��������v�Ƃ����Ӗ����Ǝv���܂����A���̗�ł̎B�e�����͂ǂ̂��炢�Ō��ς����Ă��܂��ł��傤���B
�����ԍ��F13910779
![]() 0�_
0�_
�� ��ʊE�[�x�s�ϐ_�b��M����Ȃ�
�s�ςȐ_�b�Ƃ͋M���̑z�������ŁA�M���̔]���Ŋ�������b�ł��傤�B
�d���@���Ă��Z�����̐��m�ł͂Ȃ��ƌ����l�����܂��i�����ł��傤���ǁj���A
���p�ł͕�����₷���K�C�h�ɂȂ�܂��B�����덷���o��̂��o���Ă��ǂ��ł��傤�B
�ڂ��ɂ��Ȃ��Ă�������Ȃ��덷�ɋC�ɂȂ��Ă��A�v�Z�����Ηǂ��b�Łi�C���ςނȂ�j�A
�ʓ|�Ȏ��������ꂽ���ɂ����l�ƌ��������̂ł��B�s���g�̈ʒu�𐳊m�ɐݒ肷�邽��
����a�����Y���~�����̂ł�����A4/3�̈Â������Y�ł͓���Ǝv���܂��B
�ɂ�����܂�����`�������W���Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F13912239
![]() 0�_
0�_
���ɉ��x�������܂������A�p���t�H�[�J�X�ɋ߂��قǏœ_�����ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ���傫���Ȃ�܂��B
�p���t�H�[�J�X �E�E�E �B�e�{���̏������i�����Ƀs���g�����킹��j�B�e�B�������� F�l��傫�������B�e�B
�t���T�C�Y�� F2.8 �Ƃ����Ɓi�B�e�{�������ɏ������Ƃ��ȊO�́j���܂�Ⴂ���o�Ă��܂���B
F10 ���炢�ɍi��ƈႢ���o�Ă��܂��B�ƌ����Ă��A50mm �����Y�� 5m ��̔�ʑ̂��B�����ꍇ�i�B�e�{�� 1/100�j�ƁA500mm �����Y�� 50m ��̔�ʑ̂��B�����ꍇ�i�B�e�{���͂�͂� 1/100�j�ŁA�悤�₭�����ʊE�[�x 1/2�{�ł��i�O�҂� 7.5m�A��҂� 3.2m�j�B
�ŁA�t���T�C�Y��菬�����t�H�[�}�b�g���� �� �����������߁AF10 ���x�ɍi���Ă����܂�Ⴂ���o�Ă��܂���B
�t���T�C�Y�ŁA�Ȃ����œ_����10�{�Ő�ɏ��������x�̈Ⴂ�ł��̂ŁB
�v�f�Ƃ��Ă͂܂������ʂ̂��̂ł����A���k���ʂ̈Ⴂ�ɂ��w�i�̑傫���̈Ⴂ�A�{�P�̑傫���̈Ⴂ�A�Ȃǂ̂ق����C�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȋC�����܂����B
�t���T�C�Y���炢�ɂȂ�ƁA�œ_�����ɉ������u��ʊE�[�x�̈Ⴂ�v�u���k���ʂ̈Ⴂ�v�u�{�P�̑傫���̈Ⴂ�v�̑g�ݍ��킹���l���n�߂Ă݂�Ƃ������낢��������܂���ˁB
�Ƃ͌����E�E�E�A�����ɂ͉�p����ԂɋC�ɂ���悤�ȋC�����܂����B
�����ԍ��F13912572
![]() 0�_
0�_
����͂ǂ������ƌ����ƁA
�u�]���͔�ʊE�[�x���v
�ł͂Ȃ��āA
�u�t���T�C�Y�ȏ�̃��[�W�t�H�[�}�b�g�̏ꍇ�A�L�p�����Y�̂ق����e�ՂɃp���t�H�[�J�X��������v
�Ƃ������ۂ��Ɖ��߂����ق������R�Ȃ悤�Ɏv���܂����E�E�E�B
�����ԍ��F13912652
![]() 0�_
0�_
�O�͘b������܂������A�t�H�[�}�b�g�Ƃ���قNJW�Ȃ��ł��傤�B
�≖����𑜂����܂�ǂ��Ȃ������̂Ńp���t�H�[�J�X���e�Ղɓ�����Ǝv���܂��B
�p���t�H�[�J�X�ɂȂ�Ȃ��悤�A��菬�������e���a�Ōv�Z�������ł��B
�����ԍ��F13913775
![]() 0�_
0�_
�� �p���t�H�[�J�X�ɋ߂��قǏœ_�����ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ���傫���Ȃ�܂��B
���̎��̌v�Z�덷���傫���Ȃ邾���ł��傤���A
�p���t�H�[�J�X�ɋ߂��ł�����A���덷���o�Ă��A���p����Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F13913928
![]() 0�_
0�_
�����܂���A�����ԈႦ�Ă܂����B
�u�œ_�����������Ȃ�Ɣ�ʊE�[�x���Ȃ�v�̐����Łu�t���T�C�Y�̂悤�ȃ��[�W�t�H�[�}�b�g�ɊW���A�������t�H�[�}�b�g�ł͉e�������Ȃ��v�̂悤�ɏ����܂������ԈႢ�ł��B
������������ �M�q���Ē����� �� [13884792] �̏������݂ɐG������A��p�𑵂��Ȃ��ōl���Ă��܂��܂����i[13884792] �̏������ݎ��̂͐������ł��j�B
�������́A
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɑS�����W��
�E���Z�B�e�{���������������B�e
�E���ZF�l��傫�������B�e
�ɂ����āu���Z�œ_�����������Ɣ�ʊE�[�x���Ȃ�v
�ł��B
���ׂĂɁg���Z�`�h�ƕt���邱�ƂŃt�H�[�}�b�g�̊_���������Ȃ�܂��i��͂��p�𑵂��邱�Ƃ͖��l���ʂ̏d�v�����ł�����j�B
�ؖ��� [13906917] ��
Df = ��F * C * (1 / A)
C = s / (s - f)
A = m^2 - {��FC / (s - f)}
����A�t�H�[�}�b�g�W���i�Ⴆ�t�H�[�T�[�Y�Ȃ�l 2�j�� k �Ƃ����āA����t�H�[�}�b�g�ɂ����� A�ADf �����߂�ƁA
A = (m/k)^2 - [{(��F / k^2) * C} / (s - f)] = A / k^2
�� Df = (��F / k^2) * C * (A / k^2) = ��F * C * (1 / A)
����̓t���T�C�Y�ɂ����� Df �ƑS�������i�덷�� C �̕��������Ȃ̂ŁA��̐����͊����j�B
�ŁA�u���ZF�l���傫���B�e�ő�ӂ͗L���v�ł��̂ŁA�����I�ɂ̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̏������ق����u�]���قǔ�ʊE�[�x���Ȃ�v�̌��ʂ��Ă��߂�Ɍ����ƌ����܂��i���邢�̓t���T�C�Y�ł��Œ��ꒃ�i�邩�j�B
����� gintaro���� �� [13910491] �͗ǂ���ł��ˁB������
>�L�p�[�ł͊J���ł�40m�`50m��܂Ńs���g�������Ă��܂�
����͌v�Z�ԈႢ�ŁA���̏ꍇ�̌����ʊE�[�x�́u17�`18m�v�ł��B
���Ȃ݂ɖ]���[�� 140mm�i���Z280mm�j�Ƃ���ƁA�]���[ F4 �� 2.6m�AF5.6 �� 3.8m�B
�t���T�C�Y 28mm �� F4�A280mm �� F4 �� F5.6 �̌����ʊE�[�x���قڈꏏ�ł��Bs / (s - f) �̍��̌덷���킸���ɏo�邾���ł��i���ׂĊ��Z����t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�͖����ɓ������j�B
��ʓI�ɂ� F�l��i���ȏ�ɔ�ʊE�[�x���Ȃ�u�]���ɂ�����ʂ���v�Ɣ��f���Ă悢�ł��傤�B��i���Ƃ́A�����ʊE�[�x�� 1/��2 �{��菬�����Ȃ邱�Ƃł��B
[13910491] �̗�ł́i�]���[�� F�l���L�p�[�� F4 �Ɠ���ɂ����Ƃ��āj5�i���ȏ�ɔ�ʊE�[�x���Ȃ��Ă���̂ŁA�[���ɖ]���ɂ�����ʂ���A�Ɣ��f�ł��܂��B
�����A���ێB���Ă݂���ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁi�p�[�X�Ƃ��j�B�����͖]�������Y�����ĂȂ����A�R���f�W�̍��{���Y�[���͉��Ă��܂��Ă邵�Ŏ��ʂł��܂��� (T_T)
�����ԍ��F13914404
![]() 0�_
0�_
>�i�덷�� C �̕��������Ȃ̂ŁA��̐����͊����j
�i�덷�� C �̕��������Ȃ̂ŁA�����̐����͊����j
�̕ϊ��~�X�B
���������������o�Ă���̂Łu��v���ƌ����^�����˂Ȃ��B
�����ԍ��F13914412
![]() 0�_
0�_
>�� Df = (��F / k^2) * C * (A / k^2) = ��F * C * (1 / A)
������
�� Df = (��F / k^2) * C * {1 / (A / k^2)} = ��F * C * (1 / A)
�̊ԈႢ�B
�����ԍ��F13914424
![]() 0�_
0�_
�ŁA�u��ʊE�[�x��������v�Ƃ́A�悤�́u�w�i���ڂ��������v�킯�ŁB
�傫���t�H�[�}�b�g���Ȃ��A���邢�͊��ZF�l�̏����������Y�������Ȃ��A�R���f�W�̍��{���Y�[�����������Ă��Ȃ��A���Ă����l���u���Ƃ��w�i���ڂ��������v�Ƃ����Ƃ��̋���̍�Ƃ��Ă��̕��@�͗L���Ƃ������Ƃł��ˁB
�t�Ƀt���T�C�Y �{ ���邢�����Y�������Ă���l�ɂ͑債�ďd�v�Șb�ł͂Ȃ��āA
�u�p���t�H�[�J�X�ŎB�肽����A�L�p�����Y�̂ق������܂�i��Ȃ��ł��B��܂���v
�Ƃ��������x�̘b�ł��B
�����ԍ��F13914446
![]() 0�_
0�_
�t���T�C�Y�̘b�ŁA�B�e�{�� 0.01�{�̎��A
28mm F2.8 �̌����ʊE�[�x�F1217mm
600mm F4.0 �̌����ʊE�[�x�F1237mm
�ł��B
�t���T�C�Y���Ă̂́u�]���ɂ����Ƃ��̔�ʊE�[�x�������ʂ��ア�v�Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����ł��ˁB
������x�����͂��̂������l�i�������Ȃ銄�ɂ͏����̌��ʂ��������Ȃ��Ƃ����B�܂����ꂪ��Ƃ������̂Ȃ̂ł��傤�B
�����ԍ��F13914469
![]() 0�_
0�_
�M�q���Ē�����@
���o�X�̗�́A�u�����ł��ڂ����~�����v���w�i�ڂ��̂��ƂȂ���킸�]���ł��ˁB
���u�����ł��[�x��������v�Ƃ����Ӗ����Ǝv���܂����A
���������Ƃ���ł��ˁA�������܂��B���w�E���肪�Ƃ��������܂����B
�O���[�v�ʐ^���B��̂ɁA���̔�ʊE�[�x��ۂ����܂����ł��i��Ȃ��i�V���b�^�[���x�������Ȃ��AISO���グ�Ȃ��j���߂ɂ́H(�����F�L�p�Ŋ��)
�Ƃ������p���A���ӂ��킵��������������܂���B
�����̗�ł̎B�e�����͂ǂ̂��炢�Ō��ς����Ă��܂��ł��傤���B
���Z�B�e�{�������Z�œ_����÷�B�e����
�ƍl������̂ŁA���Z�B�e�{��0.01�Ȃ�t���T�C�Y(28mm/300mm)�ł��t�H�[�T�[�Y(14mm/150mm)�ł��A�L�p��2.8m�]����30m�ł��ˁB
���̂��炢�̎B�e�{���Əœ_�����Ȃ�
�t���T�C�YF5.6�`F16
�t�H�[�T�[�YF2.8�`F8
�v�Z��͂��ꂭ�炢��F�l�Ŕ�ʊE�[�x�̍����傫���Ȃ�͂��ł��B
[13906783]�̎B���ׂł����A�����B�e�{��0.02���x�ŁA28mm/200mm��F8�ł�����A����ł����͏o�Ă�͂��ł��B
����ʊE�[�x���Ⴄ�̂������Ȃ̂��A���ʏo���銴���ł��Ȃ��ł��ˁc�B
�Ƃ̂��Ƃł����A200mm�̉摜���ƁA��ʌ���́A���炩�ɔ�ʊE�[�x����O��Ăڂ��Č����܂��B
����A28mm�ł����A���̃T�C�Y�Ō���Ȃ�A���̕ǂ܂Ŕ�ʊE�[�x�ɓ����Ă�ƌ�����Ǝv���܂����A�������ł��傤�H
���̕ǂ̃s���g�������Â��A�Ɗ�����Ȃ���������k�����Ă݂�A���s���g�̍������摜�ɂȂ�܂��B���̎��ł��A200mm�̉摜����͂ڂ����܂܂ł��B��ʊE�[�x�͊Ϗ܃T�C�Y�ɂ��܂�����B�������A����ɏk�������200mm�̉摜���p���t�H�[�J�X�Ɍ����܂��B
�ڂ��v�Z�@�Ōv�Z���Ă݂܂��B
A:�œ_����28mm�AF8�A��ʑ̂܂ł̋���1.4m
����ꂽ���A200����f�����ł͌��2.2m���x�܂ŁA50����f�����ł͖������܂ł��[�x�ɓ���܂��B
B:200mm�AF8�A10m
������ƁA200����f�����ł͌��0.9m���x�܂ŁA50����f�����ł�2m�܂ł��[�x�ɓ���܂��B
�u50 ����f�����v�Ƃ����̂́A�����炭50����f�Ƀ��T�C�Y���ĊϏ܂����Ƃ��̔�ʊE�[�x�Ƃ����Ӗ��ŁA���̂Ƃ��AA�̓p���t�H�[�J�X�AB�͔�ʊE�[�x2m�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�A�b�v���ꂽ�摜�͒���1024�s�N�Z���Ƃ����70����f���x�ł��傤���B50����f�����̐��l�̓A�b�v���ꂽ�摜�̈�ۂɋ߂��悤�ł��B
���ۂ̌��ɂ����ẮA�B�e�̐ݒ�i�{���AF�l�A�œ_�����j�̖��ȊO�ɁA�摜�����ʊE�[�x�̍����ǂ��ǂݎ�邩�Ƃ�����肪����܂��ˁB��p���Ⴂ�܂����A���ɁA�s���g�̂���Ɩ]���ɂ��g����ʂ��ǂ��蕪���邩�B����̏ꍇ�ł���A����̓K�Ȉʒu�ɁA�ڂ��i�f�B�e�C���j�̔��ʂ��₷���ڕW����������킩��₷��������������܂���B
�����ԍ��F13914492
![]() 1�_
1�_
>>�L�p�[�ł͊J���ł�40m�`50m��܂Ńs���g�������Ă��܂�
>����͌v�Z�ԈႢ�ŁA���̏ꍇ�̌����ʊE�[�x�́u17�`18m�v�ł��B
�v�Z�ԈႢ�ł͂Ȃ��A���e�����~�̈Ⴂ�ł��ˁB
���s�̂�������͋��e�����~0.03�A���͂��̏������݂ł�0.033���̗p�Ə����Ă܂��B
�ߏœ_��������
f^2 - ��Fs��0
�����藧�悤�ȃp�����[�^�̑O��ňႢ���傫���Ȃ�̂ŁA�Ɋւ��Ă��A�����̍����傫�ȈႢ�ɂȂ��ł��ˁB
�����ԍ��F13914611
![]() 1�_
1�_
�� ��ʊE�[�x�������ʂ��ア�Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����ł��ˁB
�]���ɗ~�����̂́A��ʊE�[�x���{�P���Ǝv���܂��̂ŁA
28��600�~���͔�ʊE�[�x�������ł��A�{�P��21�{����������܂��B
�����ԍ��F13915208
![]() 0�_
0�_
�� �R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����ł��ˁB
�R�X�g�̓{�P�̖ʐςƒP����Ⴗ��Ǝv���܂��i�]���̒l�i�͏œ_�����̕������Ɖ���j�B
�L�p�̔�ʊE�[�x�̓p�[�X���痝�����Ă�������₷���Ǝv���܂��B��p���L�����A
�����Y���猩�������̎��p���������Ȃ�A���s���ɋ߂Â��܂��B�v�Z���A�v��������Ȃ�܂��B
������Ƃ����撣��A�������͊���ɂ߂A��ʊE�[�x���傫���ς��܂��B
�����ԍ��F13915387
![]() 0�_
0�_
>�v�Z�ԈႢ�ł͂Ȃ��A���e�����~�̈Ⴂ�ł��ˁB
�����A�ق�Ƃ��B�����I
�����ԍ��F13916588
![]() 0�_
0�_
���`��A���e�����~�a�� 10% �̈Ⴂ���A��ʊE�[�x�ɂȂ�ƎO�{�̈Ⴂ�ƂȂ��Č����B
�t�Ɍ����Ɣ�ʊE�[�x���Ē�����������Ȃ��̂Ƃ������ƂŁB
�����Ȃ�Ƃ�͂�]���̈��k���ʁi�p�[�X�̈Ⴂ�j�Ƃ��A�{�P�̑傫���Ƃ��̘b�����Ȃ��ƕЎ藎���ɂȂ�C�����܂��B
�����ԍ��F13916662
![]() 2�_
2�_
�� �t�Ɍ����Ɣ�ʊE�[�x���Ē�����������Ȃ��̂Ƃ������ƂŁB
�i��Ƃ����������������Ƒ����܂��B
gintaro����̖��i���������̑O��Ő��x�����߂�j��gintaro���g���������Ă���܂����B
�����ԍ��F13916964
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��@
>�p���t�H�[�J�X�ɂȂ�Ȃ��悤�A��菬�������e���a�Ōv�Z�������ł��B
�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�i3:2�̃A�X�y�N�g��Łj1200����f��̋��e�����~�a��ݒ肷��ƁA�t���T�C�Y�ł�
�� = 0.0086mm
�ł��B
�V�O�}�� SD1 �Ƃ����J����������̂ŁA1200����f�s�N�Z�����{�Ƃ����̂͌����Ĕ��I�Ȑݒ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B
����Ŋ��o�̗�Ƃ��ăt�H�[�T�[�Y�́u���Z 28mm - 280mm�AF�l�� 4.0 - 5.6�v�Ƃ��� 10�{�Y�[���ł̎B�e���l���܂��B�B�e�{���� 0.01�{�ł��i���Z�B�e�{������ 0.005�{�j�B
�L�p�[�ł̌����ʊE�[�x �� 918mm
�]���[�ł̌����ʊE�[�x �� 1002mm
���x�͐[�x���t�]���Ă��܂��܂����B
���Ȃ݂ɂ��̃����Y���uF4.0 �ʂ��� 10�{�Y�[�������Y�v�ɂ���ƁA
�]���[�ł̌����ʊE�[�x �� 709mm
�ƂȂ�A�m���ɖ]�������[�x�͐ł����A�̓x�����͂܂���́u2/3�i�v�ł��B
���ǂ̂Ƃ���u�]��������ʊE�[�x���H�v�Ƃ������莩�̂������������ł��傤�ˁB
�B�e�{�������킹���l�@���̂��̂́A�����g�͊y���������ł����B
���ۂ̎B�e�ɂ����ėL�p�Ȃ̂́u�{�P�̑傫���v�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F13917098
![]() 0�_
0�_
�܂����Ă������ԈႢ (T_T)
>�B�e�{���� 0.01�{�ł��i���Z�B�e�{������ 0.005�{�j�B
�t�ŁA�B�e�{�� 0.005�{�A���Z���� 0.001�{�A�ł��B
�����ԍ��F13917103
![]() 0�_
0�_
��j�@�t�ŁA�B�e�{�� 0.005�{�A���Z���� 0.001�{�A�ł��B
���j�@�t�ŁA�B�e�{�� 0.005�{�A���Z���� 0.01�{�A�ł��B
�����ԍ��F13917105
![]() 0�_
0�_
��ʊE�[�x�̌v�Z�͂��̂��炢�ɂ��āA��ʊE�[�x�̐���l���Ă݂����Ǝv���܂��B
�Ⴆ�Ώܖ��������z�������̂��A�Ȃ�Ƃ��H�ׂ���̂��ƁA���������Ă��܂����̂�����܂��B
�L�`�ܖ������ƓK���ɍl���܂��ƁA�]���̕������葁���ƌ����܂��B�L�`��ʊE�[�x���ł��B
�����ԍ��F13917129
![]() 0�_
0�_
�� �L�`��ʊE�[�x
���ꂪ�ǂ��������̂������ǂ�������܂���B����Ƃ����狳���ė~�����ł��B
�������M�q���Ē�����̎����i�J�L�R�ԍ�[13873214]�j���������悤�ɁA
��ʊE�[�x�O�̎����ǂ߂�Ƃ��́A�����ł��Ȃ������ł��B�����ǂ߂�E�ǂ߂Ȃ��̂ł��B
�Ȃ̂ɂȂɂ��u�𑜂��������v������܂��B
�����ԍ��F13917162
![]() 0�_
0�_
�� �B�e�{�������킹���l�@���̂��̂́A�����g�͊y���������ł����B
�� ���ۂ̎B�e�ɂ����ėL�p�Ȃ̂́u�{�P�̑傫���v�Ȃ̂ł��傤�ˁB
�B�e�{���������̍l�@�͑厖���Ǝv���܂��B
�ʐ^�͍\�}�ł����A�œ_�������Ⴄ�ꍇ�A�����\�}�Ŕ�r�ł��܂���B
�\�}�v�f�̂ǂ�����Ȃ���Ȃ�܂��A��v��ʑ̂̑傫���A�B�e�{���͏���Ȃ����̂ł��ˁB
�{�P������v��ʑ̂Ƌ�Ȃ�E�E�E
�����ԍ��F13918711
![]() 3�_
3�_
�������Ȃ�Ƃ�͂�]���̈��k���ʁi�p�[�X�̈Ⴂ�j�Ƃ��A�{�P�̑傫���Ƃ��̘b�����Ȃ��ƕЎ藎���ɂȂ�C�����܂��B
����������ʊE�[�x�́A�ڂ��̑傫�������e���x���Ɏ��܂�͈͂̂��Ƃł����A�ŏ�����A���҂����S�ɐ藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�ǂ�����A[13873966]�ł�܂����낤����̏Љ�Ă��ꂽ��̃O���t�i���肵�܂����j���l���Ă�킯�ł��B
�O���t�𐅕������Ő�A��_��x���W���i�O��/����j��ʊE�[�x�B
�O���t�𐂒����Ő�A��_��y���W���ڂ��̑傫���B
�c�Ɍ��邩���Ɍ��邩�B��ʊE�[�x�Ƃڂ��̑傫���݂͌��ɋt���̊W�ɂ���܂��B
�蕪���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A������ς��邱�Ƃ͂ł��܂��B
�������̂����Ă��Ă��A���ӎ��ɉ����āA�K�Ȍ���������悢�ł��傤�B
�ڂ����~�����Ȃ�ڂ��̑傫��������悢�ł��傤�B
�s���g���~�����Ȃ��ʊE�[�x�͂悢�w�W�ɂȂ�܂��B
�l�H�I�Ȏw�W�ɂ����܂��A����ł��A�����Y�Ƀ����������Ă邭�炢�d�p����l������킯�ł��B
���鐯���߂炳��̂悤�ɁA��̌����ɌŎ�����K�v�͂���܂���B
�d�v�Ȃ͎̂w�����őΐ����͂����A�ƁA�킴�킴�s���R��I�ԕK�v�͖����ł��傤�B
�����ǂ̂Ƃ���u�]��������ʊE�[�x���H�v�Ƃ������莩�̂������������ł��傤�ˁB
�u�w�i�܂ł�����x��������ʂ������ꍇ�ɁA�L�p�ł͂��ꂭ�炢�i��Ηǂ�������ˁA�Ƃ���
�o����]���Ɏ�������Ŏ��s���邱�Ƃ͂Ȃ����H�v
�Ƃ������ɂ͈��̈Ӗ�������܂��ˁB
�����āA�u���v�ȏꍇ���������ǁA���ۂɎ��s���邱�Ƃ�����v�Ƃ����̂��A���̃X���̌��_�ł��B
�����A�X���傳��̎�|�Ƃ��āA��ʂɑ����̋c�_�ɂ����Ĕ�ʊE�[�x�ƃ{�P����������Ă���_���s���ŁA������ċc�_�������A�Ƃ����̂�����Ǝv����ł����A��ʊE�[�x�Ƃڂ���S���ʂ̂��̂Ƃ��ċc�_���悤�Ƃ���͖̂��������肻�����A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13919968
![]() 0�_
0�_
�Ƃ���Łu�{�P�̑傫���v���ĉ��x���o�Ă��Ă܂����ǂ��A�{�P�̑傫�����ĉ��̂��Ƃł��傤���H
�u�������A�_�����̑��̒��a�v�ł��傤���H
���Ƃ���Ƃ����ƍl���āA
b�F�{�P�̑傫��
m�F�B�e�{��
F�FF�l
f�F�œ_����
�Ƃ�����
b = mf / F
�ƂȂ�܂������B
���鐯���߂炳�� [13915208]
>28��600�~���͔�ʊE�[�x�������ł��A�{�P��21�{����������܂��B
�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA���Ԃ��Ă���̂ł��傤�B
����ɕό`�����
b = mD
�ł��ˁi������ D�F�����Y�L���a�j�B
���Ɓu���Z�{�P���a�v�� k * b �ł��ˁi������ k �̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y���Z�W���j�B
�Ȃ�ł���Șb���n�߂����ƌ����ƁA�u��ʊE�[�x����b�ɂȂ�Ȃ��v����ł��B
�ӂ��u�]���̂ق�����ʊE�[�x���v�ƌ�������u���{�̖]�����������ʊE�[�x�͂��ꂭ�炢�Ȃ��v�ƒ�ʓI�Ɏ�����˂Ȃ�܂��A���e�����~�a�����ɂ��т��Ȃ̂Łu�b�ɂȂ�Ȃ��v�킯�ł��B
��������A�i�������ł͂Ȃ��āj�C�Ӊ��������̓_�����̑傫���Ŕ�ׂ��ق���������Ȃ��́H�ƁB
�ŁA�����܂ł͎����Ă����Ă܂��� m(_ _)m
�����ԍ��F13921252
![]() 0�_
0�_
>�C�Ӊ��������̓_�����̑傫��
�u���̑傫���v�ł����A���������o�܂����B
s �F�B�e����
s'�F�_�����Ƃ̋���
������ s' > s �Ƃ���B
s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}
������ b �� [13921252] �Œ�`�������́B
�u�C�Ӊ��������̓_�������A�]���͉��{�̑傫���Ń{�P��v�Ƃ������`�����҂����̂ł����A�c�O�Ȃ����Y��Ȍ`�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B
�ł���� 1 - s/s' �Ȃ̂ŁA�������ł��B��ʊE�[�x�̎������Y��B
���������t�H�[�T�[�Y�̗�ł̌��ʂ́A
s' - s = 17.4m �̏ꍇ�́A�e���[�̃{�P�͍L�p���� 4.5�{�B
s' - s = 50.6m �̏ꍇ�́A�e���[�̃{�P�͍L�p���� 6.8�{�B
�ƂȂ�܂����B
�����ԍ��F13921353
![]() 0�_
0�_
�ȑO�����ʊE�[�x���[���Ė��邢�����Y���~���������̂ł����A������p�ł͖����ł��ˁB
��������ʊE�[�x���[���ă{�P���傫�������Y�Ȃ�A����ɋ߂����̂�����܂��B
���]���ł��B
�傫�ȃ{�P���~�����ꍇ�A�p�[�X�̈Ӗ������������܂��B�{�P �� �w�i���ɂȂ�܂��B
�����̏ꍇ50�`135�~����ǂ��g���܂����A�傫�ȃ{�P���o�����߂ɂ́A
��ʊE�[�x�������Ɗ����܂��B�l�̊炪�������ʂɐ�ꂽ�͗l�͋C�����ǂ�����܂���B
���]�����~�����̂ł����A���o����Ƃ̃e���p�V�[���\�͂��~�����ł��B
�����ԍ��F13921356
![]() 2�_
2�_
>�c�O�Ȃ����Y��Ȍ`�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B
�Ƃ͌����A�u�{�P�̑傫���̔�r�v���Ɓu��ʊE�[�x�̔�r�v�Ƃ͈قȂ�A�u���e�����~�a�͖��W�v�Ƃ��������b�g������܂��B
�s���g�ʂ������ s' ���w�肵�Ă�����������悢�i�����I�ɂ� s' - s > 0 �̏����j�B
s' �������܂�A�]���̃{�P�̑傫�����L�p���̂���̉��{���́u��ӂɁv��܂�܂��i���ꂪ�����b�g�j�B
�����ԍ��F13921359
![]() 0�_
0�_
>���������t�H�[�T�[�Y�̗�ł̌��ʂ́A
>s' - s = 17.4m �̏ꍇ�́A�e���[�̃{�P�͍L�p���� 4.5�{�B
>s' - s = 50.6m �̏ꍇ�́A�e���[�̃{�P�͍L�p���� 6.8�{�B
�ŏI�I�� s' �� ������ �Ƃ���Ɓi10�{�Y�[���Ȃ̂Łj�{�P�̑傫���� 10�{�ɋ߂Â��܂��B
���̋߂Â����́E�E�E�܂��������ɋ߂��ƌ����Ă�������Ȃ��ł��傤���i�ڂ������ׂĂ܂��j�B
�����ԍ��F13921378
![]() 0�_
0�_
���ƈꉞ�q���g�ƌ��������ƌ������B
>s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}
���̎�����A�C�Ӌ��e�����~�a�ɂ������ʊE�[�x�͏o�܂���B
���̎� �� ���e�����~�a
�Ƃ����āA
���̋��e�����~�a�ɂ������ʊE�[�x �� (s' - s)
�ł��B
b �� s �͊��m�̕ϐ��Ȃ̂ŁAs' �����܂邵��ʊE�[�x�����܂�B
�{�P�̑傫�����ȒP�ɏo���鎮�ŁA�Ȃ�����ʊE�[�x���܂�ł���̂ŁA������̂ق����T�O�̏W�����傫���ł��B
���ꂩ��́u��ʊE�[�x�v�ł͂Ȃ��u�{�P�̑傫���v�Ō��ׂ��ł��傤�B
�����ԍ��F13921389
![]() 0�_
0�_
�X���̃X�s�[�h�ɂȂ��Ȃ����Ă����Ȃ��X����ł��B
���̃X���̈Ӌ`�Ƃ��čl���Ă����̂́A���鐯���߂炳���
���B�e�{���������̍l�@�͑厖���Ǝv���܂��B
�ʐ^�͍\�}�ł����A�œ_�������Ⴄ�ꍇ�A�����\�}�Ŕ�r�ł��܂���B
�\�}�v�f�̂ǂ�����Ȃ���Ȃ�܂��A��v��ʑ̂̑傫���A�B�e�{���͏���Ȃ����̂ł��ˁB
���ȑO�����ʊE�[�x���[���Ė��邢�����Y���~���������̂ł����A������p�ł͖����ł��ˁB
��������ʊE�[�x���[���ă{�P���傫�������Y�Ȃ�A����ɋ߂����̂�����܂��B
���]���ł��B
�傫�ȃ{�P���~�����ꍇ�A�p�[�X�̈Ӗ������������܂��B�{�P �� �w�i���ɂȂ�܂��B
�����̏ꍇ50�`135�~����ǂ��g���܂����A�傫�ȃ{�P���o�����߂ɂ́A
��ʊE�[�x�������Ɗ����܂��B�l�̊炪�������ʂɐ�ꂽ�͗l�͋C�����ǂ�����܂���B
���߂��ł��B
���邢�́A�w�i�{�P�͗~��������l�̐l���𗼕��[�x���Ɏ��߂����A�Ƃ��������B��Ƃ��͏œ_�����Ɛ[�x�͂قږ��W�A�Ƃ��ł��ˁB
�l�̐[�x�ɑ��鋖�e�͈͂͂Ƃ������A��݂����ɖ]�����[�x���i���ۂɐ��Ƃ��킩��܂������j�A�Ƃ����m���̌�肪���炩�ɂȂ����ŗǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13921613
![]() 1�_
1�_
>��݂����ɖ]�����[�x���i���ۂɐ��Ƃ��킩��܂������j�A�Ƃ����m���̌��
��ʊE�[�x���_�͌��E������̂ɁA��ʊE�[�x�Ƃ������t�𗔗p�������ʂ����Ȃ����̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13922167
![]() 1�_
1�_
���M�q���Ē�����
�����ɂ͂قړ��ӂł��܂����A��_�����A
>�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��B
>�Q�̎��i��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�j�A�ǂ̏œ_�����ł��{�P�����͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�B
�i�Ⴆ�Δw�i�ɊŔ��������Ƃ�����A��f�����s�����Ȃ�����ǂ��܂ŕ��������ʂł��邩�͕ς��Ȃ��j
�����A����ł��ˁB
��ʊE�[�x�́A�ڂ��́u�傫���v�����e���x���ɂ���悤�Ȕ͈͂ł��B���ꂪ��`�ł��B
�f�B�e�[���̎c����͖��W�ŁA�Ƃɂ����ڂ��̑傫���i�̋������z�j�Ŕ�ʊE�[�x�͌��܂�܂����A�ڂ����傫���Ȃ����������o�[�X���낤���s���ڂ����낤���A�Ƃɂ����A���̑傫�����傫���Ȃ�����A�E�g�Ȃ�ł��ˁB
��̎B���ׂ�
����ʊE�[�x���Ⴄ�̂������Ȃ̂��A���ʏo���銴���ł��Ȃ��ł��ˁc�B
�Ə�����Ă闝�R���A�u��ʊE�[�x�`�f�B�[�e�[���̎c����v�Ƃ����i������j�C���[�W��������Ă邽�߂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�u���{����F�l���������A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v
���ꂾ�Ɛ������̂�������܂���i���z�����Y�ł́j�H
�����ԍ��F13922732
![]() 0�_
0�_
���{�P�̑傫�����ȒP�ɏo���鎮�ŁA�Ȃ�����ʊE�[�x���܂�ł���̂ŁA������̂ق����T�O�̏W�����傫���ł��B
���ꂩ��́u��ʊE�[�x�v�ł͂Ȃ��u�{�P�̑傫���v�Ō��ׂ��ł��傤�B
�����A�S���������Ƃł���B�����ʊE�[�x�̎�
��Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)�@�E�E�E(9`)
���ɂ��ĉ����A�ڂ��̑傫�����i��萸���Ɂj���܂�܂����A
������ߎ�����A���s�̂�������̋��߂��A�ڂ��̑傫���̌���
��s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}
�ɂȂ�܂��B�O���t����܂����낤�������Ă���Ă܂��B
�������t�ɉ����ē������ʊE�[�x�̎��́A(9`)���̋ߎ����Ƃ��Ă悭�g������̂ł��B
���ӂ��u�]���̂ق�����ʊE�[�x���v�ƌ�������u���{�̖]�����������ʊE�[�x�͂��ꂭ�炢�Ȃ��v�ƒ�ʓI�Ɏ�����˂Ȃ�܂��A���e�����~�a�����ɂ��т��Ȃ̂Łu�b�ɂȂ�Ȃ��v�킯�ł��B
�L�p�Ɩ]���ł́A�p���t�H�[�J�X��������F�l�����i���Ⴄ�A�Ƃ��A
��ʑ̂���20m�̋����܂ł���ʊE�[�x�ɓ��邽�߂̍i�肪���i���Ⴄ�A
�Ƃ����������Ȃ�A���e�����~��10%�̌덷��F�l10%���x�̍��ɑΉ����܂����ǂˁB
����Ŕ�ʊE�[�x�̌��������������Ă��������v�Z����̂͌����������i�j�A�Ƃ����̂͂��̒ʂ�ŁA��ʊE�[�x�Ɋւ��Ă�
�E�L�p�ł̓p���t�H�[�J�X�����₷��
�E�]���ł͍i���Ă��i���Ă��Ȃ��Ȃ���ʊE�[�x�������Ȃ�
���炢���ӎ����Ă���������Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F13922811
![]() 0�_
0�_
>�����A�S���������Ƃł���B�����ʊE�[�x�̎�
�����ł��̂œ����ɂȂ�͓̂��R�ł����A�u���e�����~�a�v�Ƃ�����́A�����I�Ɂu�C�Ӊ��������̃{�P�̑傫���v�Ƃ����ق����T�O�I�ɂ킩��₷���ł��B
�����
Df = ��Fs(s - f) / (f^2 - ��Fs)�@�E�E�E(9`)
�͕ό`���Ă�
Df = (��F * C) / [m^2 - {��FC / (s - f)}]
C = s / (s - f)
�Ŕ��ɕ��G�ł��B
����u�C�Ӌ����̃{�P�̑傫���v��
s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}
b = mf / F
�ƃV���v���ł킩��₷�����A���̋C�ɂȂ�Ίo���₷���B�ȒP�ȓd��ł̌v�Z�̂��₷���͂����炪��i���͌g�ѓd�b�̓d��Ōv�Z���Čv�Z���₷����̊��ς݂ł��j�B
�����Ƃ��Ăǂ��炪���͂��͖��炩�ł���B
�ŁA�u����̃{�P�̑傫���̌����v�Ɓu�����ʊE�[�x�̌���(9`)�v�́A�v�Z���Ă݂�Ɣ����ɒl�ɈႢ���o�܂��B
���͂���� (9`) �̂ق����ߎ����Ǝv���܂���.
�Âƃ̊W�� (2`) ���u�����̎��_�ł̊p�x�v�� t �̕ω��ɑΉ����Ă��܂���B
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
�� (5) �� (8) �̎����ߎ��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
��萳�m�Ȃ̂́u����̃{�P�̑傫���̌����v���Ǝv���܂����B
�����ԍ��F13923018
![]() 0�_
0�_
��s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}
��s �F�B�e����
��s'�F�_�����Ƃ̋���
���m�ɂ́As,s'�̓����Y��_����̋����ł����āA�B���ʂ���̋����ł͂Ȃ��ł���ˁB�����ŋߎ����g���Ă܂��B
����A(9`)�͋��s�̂������g�������Ă��ꂽ���ŁA�O�p�`�̑����ȊO�A�ߎ��͎g���ĂȂ��ł��傤�H
�ߎ����̂ق����o���₷���Čv�Z���e�ՂȂ͓̂��R�ł���ˁB
�����ԍ��F13923411
![]() 0�_
0�_
�Y������ߎ�������
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
��(28)���ł����ˁB(m=f/s�Ƃ���)
���A�ߎ�����ʂ�͕ʂɂ��āA��ʊE�[�x�������ڂ������̕����d��ȂǂŌv�Z���₷���A�Ƃ����̂͂���̂�������Ȃ��ł��ˁB
�s���g�̍����͈͂����߂����Ȃ�ŏ������ʊE�[�x�̌����g���ł��傤���A���ǖړI����Ǝv���܂����B
�����ԍ��F13923739
![]() 0�_
0�_
�œ_�������\�{�Ⴄ�A20�~���� 200�~���̃����Y�A�œ_������100�{�ŎB�e�A
���e�����~�a0.002mm�i���ŏ���f�s�b�`�̔{�j�A�ߎ������Ŕ�ʊE�[�x���v�Z�������ʁA
�@f/2.8 �̎��ɁA�덷 1/1000 �����A
�@f/8�@�̎��ɁA�덷 1/200 ���A�ƔF�߂܂����A
�v�Z�����K���ŁA�������ɒ[�ł����A�ڂ��ɂ��Ȃ�܂Ŋώ@���Ă��Ⴂ��������܂���A
�덷���傫���Ďg���Ȃ��Ƌ�l�́A�g��Ȃ��ėǂ��Ƃ��������Ȃ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F13924712
![]() 0�_
0�_
�ؖ��͂���܂��A���X�҂������v�������̂́A
�œ_�[�x���[���Ȃ����ꍇ�A�v�Z�덷���傫���o�������̉\��������Ǝv���܂��B
���̎��_���M���̋��ȏ����^���������^���ւ̋ߓ������m��܂���i���ȏ���ǂ��������܂��傤�j
���͐^���܂ł܂��H�蒅���Ă��܂��A���p�\���Ŋ��Ғʂ�̌��ʂ��o��A�ƔF�����Ă��܂��B
�����ԍ��F13924845
![]() 0�_
0�_
gintaro����̂��ӌ�
����͂����肸�\����܂��A�m�F�����ĉ������B
���u���{����F�l���������A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v
���ꂾ�Ɛ������̂�������܂���i���z�����Y�ł́j�H
�́A�⑫����ƁA
�u���{����F�l���������A��ʊE�[�x�͖]���̕����Ȃ邪�A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v
�ƌ������Ƃł��傤���H
������A[13873167]��[13873197]���A�]���̕�����ʊE�[�x���Ɗ����܂��ł��傤���H
�����ԍ��F13925042
![]() 0�_
0�_
>���m�ɂ́As,s'�̓����Y��_����̋����ł����āA�B���ʂ���̋����ł͂Ȃ��ł���ˁB�����ŋߎ����g���Ă܂��B
���H �ŏ����烌���Y��_����̋����ł���Ă��܂��B
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
���̃y�[�W�ƈꏏ�ł��B���� s' �́A���̃y�[�W�� sf �݂����Ȃ��̂ł��B
�ŁAgintaro���� ����������Ă���̂��悭�킩��Ȃ��̂ł����A����u�]���͔�ʊE�[�x���v�́u�^�v�Ō������t���Ă��āA���̌X�����u���ZF�l���傫���A�B�e�{�����������A���e�����~�a���傫���A�قǖ]���̔�ʊE�[�x�̐������ɂȂ�v�Ɩ��炩�ɂȂ��Ă��܂��B
�ŁA��ʔ�r�ɐ����������Ƃ������Ƃł��i���e�����~�a�̈Ⴂ�Ō��ʂ��傫���قȂ�j�B
��������́u��ʊE�[�x���_�̌��E�v�Ƃ��܂������A���_���E�̗��R�͂�����B�u���[�U�[���g����ʊE�[�x�����߂Ă��Ȃ��v�Ȃ�ł��ˁB
0.03mm �ł� 0.033mm �ł������ł����A�u���e�����~�a��������Ƃł���������}���Ƀs���g�������Ă��Ȃ��ƃ��[�U�[�͊����邩�H�v�ƌ�������A�����́u�K�����������ł͂Ȃ��v�ł��B
���Ⴀ���H �Ƃ����������u�{�P�̑傫���̎��v�ɂ͂���Ǝv���܂��B
>s' �̓_�����̑��̑傫���i���a�j= b * {(s' - s) / s'}
������� y(x) �Ƃ��܂��i������ x = s' �ƒu���������j�B
y(x) = b * {1 - s/x} �ł��B
����� x �ɂ��Ĕ����B
y'(x) = s * b * (1 / x^2)
�L�p���� s �� s1�Ab �� b1�A�]������ s �� s2�Ab �� b2�AF�l�͈��i�ʂ��Y�[���j�A�Y�[���{���� z �{�Ƃ��܂��B
���炩�� s2 = z * s1�Ab2 = z * b1 �����藧���A�s���g�ʂł̈ꎞ�����W���́A
y'(s1) = b1 / s1
y'(s2) = y'(s1)
���������܂��i�I�j
�܂�s���g�ʂł́u�����ɑ���{�P���a����̌��z�i��ŋ��߂������W���j�v�͂Ȃ�ƈ��Ȃ̂ł��I
�u���Ⴀ�Ȃ�ŁA�s���g�ʂ�����̃{�P�͖]���[�̂ق����傫���́H�v�̋^��ɂ́A�������������ăs���g�ʂł̓����W�������߂܂��B
y''(x) = (-2) * s * b * (1 / x^3)
y''(s1) = (-2) * b1 * (1 / s1^2)
y''(s2) = (-2) * b2 * (1 / s2^2) = (1 / z) * y''(s1) > y''(s1)
�]�����̃{�P���傫���̂́u�����W�����傫������v�Ƃ킩��܂����B
y(x) �͏�ɓʂ̊��ł����A�L�p���͂�葁���X�����[���ɋ߂Â��i�{�P�̑傫�����������̓_�����{�P�̑傫���ɋ}���ɋ߂Â��j�Ƃ������Ƃł��B
�ꎞ�����W��������̏ꍇ�A�����W�����傫���ق��������炭���[�U�[�́u�s���g�̍����Ă���͈͂������v�Ɗ����邱�Ƃł��傤�B
�ŁA���鐯���߂炳�� �� [13921356] �̗�͂����炭�]�����̂ݍi���āA�u�ꎞ�����W�����]�������������v�ꍇ�Ȃ�ł��傤�ˁB����͂���œ��l�ɍl�@�ł���ł��傤�B
�ŁA���ꂾ������[���[�̋��߂Ă�����ł͂Ȃ��ł��傤�ˁB
�M�q���Ē����� �� [13873214] ������ƁA�u�摜�̊g��k�������Ńp�[�X�̈Ⴂ�i�w�i�̑傫���̈Ⴂ�j���z���v������ԂŃ{�P�����悤�Ƃ��Ă��܂��B
�܂������͂����܂ł͍l���Ă��܂��B
���������̂́A��ʊE�[�x�͒�̐��_���A�Ƃ������Ƃł��B�������킩��h���B
�����ԍ��F13925321
![]() 0�_
0�_
>�u���e�����~�a��������Ƃł���������}���Ƀs���g�������Ă��Ȃ��ƃ��[�U�[�͊����邩�H�v�ƌ�������A�����́u�K�����������ł͂Ȃ��v
�s���g�������Ă���Ɗ����邩�����Ă��Ȃ��Ɗ����邩�A���m�ɂ͐S���������邵������܂���B
�����ǂ�����p���t�H�[�J�X�t�߂ł͋��e�����~�a 10% �̈Ⴂ�Ŕ�ʊE�[�x���S�R����Ă��܂���ł��傤�H
�������ʂ̂�������ɑ傫���āA�ʂ����ĐS�������ɂȂ邩�ǂ����B
�u��ʊE�[�x 17m �` 50m �͈̔͂ɑS������ 95% �̊����Ő��K���z����v�ł����E�E�E�B
�����ԍ��F13925367
![]() 0�_
0�_
>y(x) �͏�ɓʂ̊��ł����A�L�p���͂�葁���X�����[���ɋ߂Â��i�{�P�̑傫�����������̓_�����{�P�̑傫���ɋ}���ɋ߂Â��j�Ƃ������Ƃł��B
�����̐����͂��������ł��ˁB
���ǂ́u�L�p���͖������ł̃{�P�T�C�Y�� 1/z ������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����ˁB
�ŁA�u�������ł̃{�P�T�C�Y���s���g�������Ă���Ƌ��e�ł���p���t�H�[�J�X�v���Ă��Ƃł��B�킩��₷���ł��ˁB
�����ԍ��F13925404
![]() 0�_
0�_
�F���ꐶ�����v�Z���Ă��鎞�A�����̓T�{���Ă��܂������A
���ƂŔ�ʊE�[�x�v�Z����������x����āA�m���߂Ă݂܂����B
��܃{�P�������ē��������~�a 0.002mm�A100�{�œ_�����Ōv�Z���܂��ƁA��ʊE�[�x�A
�L�p 12mm f/16 �� 322.5mm�A�]�� 1200mm f/16 �� 316.8mm�i98.2%�j�ɂȂ�܂��B
���s�̂�������A�����ł́A����܂����A�J�L�R[13872690]�Ɠ������_�ł��ˁB���i�I�j��
�����ԍ��F13925423
![]() 1�_
1�_
���݂܂���A��̌v�Z�͍����~�a������ 0.001mm �̏ꍇ�ł��B
���� 0.002mm �̏ꍇ�́A682.1mm �ƁA633.6mm (92.9%) �ł��B
�i��ƁA�����~���g�債�Čv�Z����̂Ɠ������ʂ��o�܂����A����͌덷�g����ʂ����m��܂���B
�����ԍ��F13925446
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
�ǂ̒��x�̑傫���Ŋӏ܂��邩�ȂǁA���e�����~���ǂ��ݒ肷�邩�ɂ���Ĕ�ʊE�[�x���傫���ς��悤�ȏł́A��ʊE�[�x���̈Ӗ��������̂�������܂���ˁB
[13906783]�̍�̗�ł́A�T���l�C���ł͂ǂ���p���t�H�[�J�X�Ɍ����A�N���b�N����Ɓi����ƕ��ʂ̊ӏ܃T�C�Y��������܂���ˁj�]�����Ő[�x���悤�Ɍ����A����͎������o���Ȃ��̂ł����s�N�Z�����{�ӏ܂���Ƃ܂��ǂ���������炢�Ɍ����܂��B
�������A���̂悤�ȏł͎ʐ^�̒��̗v�f�Ƃ��Ă͏d�v�ł͖������Ƃ������̂����B
����B�e�{�����傫���ꍇ�ȂǁA�u���e�����~�a��������Ƃł���������}���Ƀs���g�������Ă��Ȃ��Ɓv���[�U�[��������ł́A�傫�ȈӖ��������Ă������ł��B
�����Ă��̏ꍇ�͎B�e�{����F�l�����Ȃ�œ_�����Ɋւ�炸�[�x�����A�ƁB
�i���������������̗�ȂǁB����������[�x�����Ɍ����Ă���̂����������Ƃ�����A���{���玄��������Ă������ƂɂȂ�܂����j
���鐯���߂炳��
�v�Z���肪�Ƃ��������܂��B
����͂܂��������Ȃ����ʂł��ˁB���ɂ͐�����m���߂�p������܂��A�Q�l�ɂ����Ă��������܂��B
�����ԍ��F13925615
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
���e�����~�a �� ��f�s�b�`�ł���B
����ɂ��Ă���f�s�b�` 0.002mm �Ƃ́A2����f�����܂��B���̂�������f���� [13917098] �ł�����A12M �����̉�f�s�b�` 0.0086mm �ł��B��f���v�Z���́A��f�s�b�`�Fp [mm] �Ƃ����āA
��f�� �� (36/p)^2 * (2/3)
�ł��i�������A�X�y�N�g�� �Q�F�R�j�B
���鐯���߂炳�� �͂�͂�o���Ɋ�Â��Ă���̂ł��傤���A���̓{�P�ɂ��Čo�����m�����i����ɋ������j�����������߂ɁA�����Ԃ������Ă��܂��܂����B���ꂩ��w�ԕ��ɂ͖����ė~�����Ȃ��ł��B
��������������u��ʊE�[�x�v�Ȃ�đO���I�̌ÏL�����p�̖͂����l���͎̂ĂĂ��܂��܂��傤�i�œ_�[�x��p�����ԐړI��@�B�������ߎ���p���Ă��邭���ɕ��G�Ȏ��j�B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̗Ⴞ���Ĉꐶ�����v�Z���Ă���ʊE�[�x 50m ���A������ 17m ���A���āB�������̃{�P�v�Z������ 28/800 �� 0.035mm �ł���i�������t���T�C�Y���Z�{�P�T�C�Y�j�B�����n���炵���B
>�����Ă��̏ꍇ�͎B�e�{����F�l�����Ȃ�œ_�����Ɋւ�炸�[�x�����A�ƁB
�������ɐ[�x���ꍇ�ɂ́u���̌`������v�Ƃ����Ӗ��ɂ����Ĕ�ʊE�[�x�̎��͗L�Ӌ`��������܂���ˁB�Čf���܂�
Df = ��F * {s / (s - f)} * (1 / m^2)
{s / (s - f)} �͂قڒl 1 �̒萔�Ƃ��Ă悢�ł��i���Ƃ��Əœ_�[�x���g���Ă鎞�_�ŋߎ��ł��̂Łj�B
����Ɓi�[�x�̐ꍇ�ɂ́j�����ʊE�[�x�̐[���́u���ZF�l�ɔ��v���A�u���Z�{���̓��ɔ����v����Ƃ����������킩��܂��i���Z�`�Ɋւ���ؖ��� [13914404]�j�B
�����ԍ��F13925656
![]() 0�_
0�_
�K���Ȍv�Z���ŗǂ��̂ł����A�Ђ���������~���������ɂ���A
�œ_���� 100�{���Ⴄ�����Y�� f/16 �܂ōi���Ă��A��ʊE�[�x�̍����͂��Ƃ̌��ʂɂȂ�܂��B
����͑O��_�A�o�����S�ďd�Ȃ��z��̃����Y�̌v�Z�ł�����A
����ȏ㐸�m�ł��Ă������p��̈Ӗ����Ȃ��Ǝv���܂��B
��������p�x��ς��āA�{�P�Əœ_�[�x�̔��͔@���ł��傤�B
�����~�a�����̔g���̔����i0.0002mm�j�ɌŒ肵�āu��l�v�ƌĂ�Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɏ�� 12/16�A1200/16�A100�{�œ_�����̌v�Z�́A�����~�a�� 0.0002mm �ɐݒ肷��ꍇ�A
��ʊE�[�x�́A�o���Ƃ� 63.4mm �Ƃ҂�����ł��i�v�Z��� 99.93% ��v�j�B
�����ԍ��F13925658
![]() 0�_
0�_
�� ���e�����~�a �� ��f�s�b�`�ł���B
0.0002mm �ɂ��Ă��܂��܂����i���j�B
��f�T�C�Y�͂��̎������ō��ȃ����Y�̒��������̍����~�E�{�P�̔����ȉ��K�v�ł����A
�����~�͉��p�ɂ���ĈႢ�܂��B�����ł͌v�Z�덷�̍l���Ő蕪�������Ă��������Ă��܂��B
�����ԍ��F13925675
![]() 0�_
0�_
99.93% �͈ꉞ����Ȍ��ʂ�����܂����A�s�C���Ȃ��炢�o��������C�����܂��B
�덷�Ő����ł��Ȃ������m��܂���B�����ꉟ���K�v�ł����A��U�����グ�܂��B
�����ԍ��F13925792
![]() 0�_
0�_
�ꉞ�ł����A�ۓۂݗp���ȏ��I�Ȑ����͂����ł��B
��ʊE�[�x�Əœ_���������W�ƌ�����̂́A��ʑ̂��ߏœ_�������߂��ꍇ�ł��B
�i������ߏœ_�����������Ă��܂����A�����~�a���������ɂ��邱�Ƃł����ǂ��Ԃ����Ƃ��o���܂��B
��ʑ̂��ߏœ_�������������ꍇ�́E�E�E�ł����A��O�ł��߂Â��ƌ덷���傫���Ȃ�܂��B
�����ԍ��F13925912
![]() 0�_
0�_
���M�q���Ē�����
�����u���{����F�l���������A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v
���ꂾ�Ɛ������̂�������܂���i���z�����Y�ł́j�H
���́A�⑫����ƁA
�u���{����F�l���������A��ʊE�[�x�͖]���̕����Ȃ邪�A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�v
���ƌ������Ƃł��傤���H
�͂��A���������Ӗ��ŏ����܂����A���A���������ǂ����͂킩��܂���B
������ƌv�Z���Ă݂������ł́A����ς�Ⴄ�悤�ȋC�����܂��B
��������A[13873167]��[13873197]���A�]���̕�����ʊE�[�x���Ɗ����܂��ł��傤���H
�����A���ꂾ�Ǝ����ɂ͔�ʊE�[�x�̈Ⴂ�͌����܂���B
�{��0.1���x�H�ƁA��r�I�{�����傫���̂�F5.6�ł��Ⴂ�������Ȃ��悤�ł��B
�����ԍ��F13926659
![]() 0�_
0�_
�����s�̂�����
�܂��́A�����Ƃ��l�сB
�����H �ŏ����烌���Y��_����̋����ł���Ă��܂��B
�����ł��ˁB���݂܂���A���S�Ɏ����̊��Ⴂ�ł����B
�i�X�M�j���̓��o�ɂ͋ߎ��͎g���ĂȂ��Ǝv������ł����߁A�ڂ��̌������ߎ����Ǝv���Ă��܂��܂������A
���������Ƃ���A�ڂ��̑傫���̎��͌����ɐ����݂����ł��B�i�X�M�j���ߎ��Ȃ�ł��ˁB
��ώ���v���܂����B
���̑��̓_�͂��������������Ă������ł��B
�����Ⴀ���H �Ƃ����������u�{�P�̑傫���̎��v�ɂ͂���Ǝv���܂��B
�Ɋւ��ẮA�������
����܂����낤����̏Љ�Ă��ꂽ��̃O���t�i���肵�܂����j���l���Ă�킯�ł��B
�Ə����Ă܂����A�ʐ^������ہA�P�_�݂̂̂ڂ��̑傫���͑傫�ȈӖ����������A�����̊��Ƃ��Ẵ{�P�̑傫������ۂ����߂܂��B
�{���I�Ȃ̂͒l�ł͂Ȃ����ł���O���t�ł��B�]���̂ق����ڂ����傫��������Ƃ����̂́A��܂����낤����̃O���t�����Ă��A�]���قnjX�����l���傫���Ȃ邱�Ƃ����炩�ł��B
�����⑫����ƁA���ۂ̊ӏ܂ɂ����ďd�v�Ȃ̂̓s���g�ʂł̌X���ł͂Ȃ��A�O���t�̂����I�Ȍ`��A�������́u��ʊE�[�x�ʕt�߂ł́v�X���ł͂Ȃ��ł��傤���B
��f����l�̊�̉𑜗͂̊W�ŁA�s���g�ʕt�߂̕ω��͌����Ȃ������肷��Ǝv���܂��B
�����A�u�s���g�ʂł̌X������v�v�Ƃ����w�E�͏d�v�ł��ˁB����́A���e�����~�����ΓI�ɏ������i����ʊE�[�x�����ΓI�ɏ������j�ł́A�œ_������ς��Ă��{�P�̑傫���̕ω��͔��ɋ߂����Ƃ��Ӗ����܂��B�����A���̃X���ŁA��ʊE�[�x���œ_�����ɂ��Ȃ��A�Ƃ������������������̂����̂��߂ł��B
���l�ɁA���e�����~�̑O��ʼn������I�Ȃ��Ƃ��N����킯�ł��Ȃ��A���l�Ƃ��Ă̔�ʊE�[�x�ɐ�ΓI�ȈӖ��͂���܂���i�u�֗��v�ł͂���܂��j�B�l�̖ڂ͗h�ꓮ����̒��Ŕ�ʊE�[�x�f���܂����A����T�C�Y��Ϗܕ��@�ɂ���Ĕ�ʊE�[�x�͕ς��܂��B
�����͔�ʊE�[�x�͂ЂƂ̊�ɂ�����l�ł͂Ȃ��A��i�ڂ��a�j�̊��Ƃ��čl���Ă��܂����A���̌����ł͂ڂ��̑傫�����l���邱�Ƃ���ʊE�[�x���l���邱�Ƃ͑S�������ł��i�݂��ɋt���j�B
�u�]�����L�̔�ʊE�[�x�̐ʐ^�v�Ƃ����̂́i����ɂ��ƂÂ��\���ł���ꍇ���������ǁj�A���Ƃ��Ă̔�ʊE�[�x�ɂ��āA���ɌX�����݂ł̃O���t�̌`��ɂ��Č����Ă���Ƃ����߂�����Ȃ����ԈႢ�Ƃ�������Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F13928376
![]() 1�_
1�_
�M�q���Ē�����@
���u���{����F�l���������A�ڂ������͑傫�����قȂ邾���ŁA�f�B�e�[���̎c����͓���ɂȂ�
����ς萳���������B���_���ɏ�����
���{����F�l���Œ肵�āA�œ_������ς���ꍇ�A�]���̕���
�E��ʊE�[�x�͋����i�����o����ꍇ�������j
�E�w�i�̂ڂ��͑傫��
�E�ł��A�f�B�e�C���̎c����͓���
�ł��B������A�M�q���Ē���������悤�ɁA�L�p�摜�̔w�i���g�債�Ė]���摜�Ɣ�ׂ��肩���ł́A��ʊE�[�x��s���g�̈Ⴂ�͐�ɂ킩��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�ȒP�ɗ��R��������܂��B
�f�B�e�C���̎c���������̂ɁA�����Y���炓'�̋����ɂ���w�i���ʂɂ����ĊԊu���̕��s�ȂQ�����������ł��邩�ǂ��������܂��B�ڂ����a���A���ʂɂ����镽�s���̊Ԋur������ƕ����ł��Ȃ��Ȃ�A�ƍl����ƁA���s�̂�������̃{�P�������g���āA
����m��/�QF
�������ł�����E�B
������
���F���{���A���F�s���g�ʂ���w�i�i���s���j�܂ł̋����A���F�����Y����s���g�ʂ܂ł̋���
�i�������A�v�Z�̉ߒ���m=f/s�Ƃ����ߎ��͎g���Ă܂��B�j
����F���Œ肷��ƁA����͏œ_�����ɂ��܂���B
���������āA���̈Ӗ��Ńf�B�e�C���͓����ŁA�œ_�����ɂ��܂���B
�����ԍ��F13928418
![]() 0�_
0�_
�������~�a 0.002mm�A100�{�œ_�����Ōv�Z���܂��ƁA��ʊE�[�x�A
�L�p 12mm f/16 �� 322.5mm�A�]�� 1200mm f/16 �� 316.8mm�i98.2%�j�ɂȂ�܂��B
������f������܂��A���ꂱ���ڂ��ɂ��Ȃ肻���ł��ˁB�B
���̏ꍇ�ł��A���{����0.002���x�i�d�Ԃ����ɂP���A�ł��ˁj�Ɏ��ǂ��Ȃ�܂����H
12mmF16 : �p���t�H�[�J�X
1200mmF16 : 8.1m
>��ʊE�[�x�Əœ_���������W�ƌ�����̂́A��ʑ̂��ߏœ_�������߂��ꍇ�ł��B
�i������ߏœ_�����������Ă��܂����A�����~�a���������ɂ��邱�Ƃł����ǂ��Ԃ����Ƃ��o���܂��B
�ނ���t�ł��B
�Z�p�̐i���ʼn�f���������A��Â̐i���Ől�̊�̉𑜗͂����サ�A���e�����~�a���������Ȃ��Ă��A�B�e�{���͎B�e�҂̔C�ӂł��B���e�����~���ǂ�Ȃɏ��������Ă��A��q�̒ʂ�A�B�e�{���ł����ǂ��z�����Ƃ��ł��܂��̂ŁA������܂���B
�����ԍ��F13928484
![]() 0�_
0�_
�A������B�ȒP�Ȗ@�����ЂƂB
���e�����~�ƎB�e�{�����Œ肵�āA�œ_�������Ƃ��f�ŎB�e����Ƃ�
�u�p���t�H�[�J�X��������F�l�̔䁁�œ_�����̔�v�ł��B
F:F'=f:f�f
����͖ڈ��Ƃ��Ă܂��܂����p�I�ł��傤�B
�����ԍ��F13928531
![]() 0�_
0�_
���Q�l�ɂȂ邩������܂��A����Ȃ��̂�����܂��B
�S�͉̂������������Ă��炢�����̂ł����A�����I�ɂ͎����������������Ƃ�������Ă��܂��B
http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field#DOF_vs._focal_length
�ʌ��ł����A�Ⴄ�t�H�[�}�b�g�̔�r���B
http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field#DOF_vs._format_size_2
gintaro����A
���Ӗ��ȏ������݂͂�߂܂��傤�B
�����ԍ��F13928549
![]() 0�_
0�_
�_���A�v�Z���͏�̃����N���Q�Ƃ��ėǂ��Ǝv���܂����A���p����̍l���������܂��B
��ʊE�[�x�����ł͂���܂��A�C�ɂȂ鎞�́A����Ȃ����ł��i������A���N�������j�B
�ߏœ_�����̐����̈�Ƃ��̏ꍇ�͂����ł��i1/3�Ƃ��ǂ�����܂��B3�̓��b�L�[�i���o�[�j�B
���܂�ł͂���܂��A�ʐ^�͐��\�{�œ_�����ŗǂ��B���܂��i�|�[�g���[�g�́`30�{�j�B
10�{�O��ł��Y��ɎB�肽�������̂ŁA�ߋ��������������܂����i�h�C�c���̓L�c�C�ł��j�B
�}�N���ł͔�ʊE�[�x�Əœ_���������W�̂��펯�ŁA�܂����i�̏ꍇ�A�ߏœ_���߂��܂�
���ė~�����ꍇ������܂����A��ʊE�[�x�͖����ł��̂Řb��������ƈႢ�܂��B
��ʑ̂��ߏœ_�����̋߂��܂ōs������덷���傫���Ȃ�܂����A���̎��A��ʊE�[�x�������Ղ�
�g���܂��̂ŁA���̑��ݎ��̉������ɍs���Ă��܂������m��܂���B�덷�͂Ȃ�����ł��B
�����ԍ��F13928999
![]() 0�_
0�_
�� ���邢�́A�w�i�{�P�͗~��������l�̐l���𗼕��[�x���Ɏ��߂����A
����́A�ł��Ȃ�������ł����A�ꖇ�ɔ[�܂�ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�������g���ׂ��ł��B�v���͊�{�I�ɓ�l�B��Ȃ��Ǝv���܂��B��l���͎B��܂����A
�K���ɘA�˂��āA���ꂼ��\��̗ǂ����̂�I��ō������܂��B
�������Ȃ����͎̂ʐ^�ƌĂȂ��l��������܂��i�ɒ[�œ���łȂ���ΐÎ~�悪�B��Ȃ��Ƃ��j
����͂܂��`�����X������܂����炨�t�������Ă��������B
�����ԍ��F13929011
![]() 0�_
0�_
gintaro���� �������Ă����������悤�ł��ꂵ���ł��B
>�{���I�Ȃ̂͒l�ł͂Ȃ����ł���O���t�ł��B
��܂����낤����̃O���t���ĉ��x���o����Ă܂����A������������Ȃ��̂Ŋ����������Ă��������B
>�d�v�Ȃ̂̓s���g�ʂł̌X���ł͂Ȃ��A�O���t�̂����I�Ȍ`��A�������́u��ʊE�[�x�ʕt�߂ł́v�X��
��������ł��B
�Łu��ʊE�[�x�v���o���o���Ȃ̂Łigintaro���� �����g���Ă�����ʂ�j�������{���I�ł��ˁB
>���̌����ł͂ڂ��̑傫�����l���邱�Ƃ���ʊE�[�x���l���邱�Ƃ͑S�������ł��i�݂��ɋt���j�B
�{�P�͐�ΓI�A��ʊE�[�x�́i���e�����~�a�ɂ��j���ΓI�Ȃ̂ŁA��ʊE�[�x�͎��̌`�������������ł���B
Df = (��F * C) / [m^2 - {��FC / (s - f)}]
C = s / (s - f)
���̎��Łu���ΓI�Ȕ�ʊE�[�x�v�͋��܂�܂����A���̒l�Ŏʐ^�͂킩��܂���B�Ăш��p���āA
>�{���I�Ȃ̂͒l�ł͂Ȃ����ł���O���t�ł��B
�ʐ^��m��ɖ{���I�Ȃ̂́u�{�P�́i�����ɑ���)�v���ł���O���t�ł��ˁB
�M�q���Ē����� �ׂ̈��ꂽ����N�i����j�ɂ́u���e�����~�a�v�͂���܂���B
����u����{���̌��A����F�l�̌��A�œ_�����ɂ���ʊE�[�x�ɈႢ�͋N���邩�H�v�ł��B
���̈�ԍŌ�́u��ʊE�[�x�v���B������ł���̂ł�����A�{�P�ɔ��z�]�����邱�ƂŃu���[�N�X���[�o������ł��B
>�u�p���t�H�[�J�X��������F�l�̔䁁�œ_�����̔�v�ł��B
>
>F:F'=f:f�f
�u��ʊE�[�x�v�ɂ������Ƃ��������������ɂȂ��ł����A�v�́u�{�P�̑傫�����ɂ���B�e�v���Ă��Ƃł��B
b = mf / F
�����ԍ��F13930388
![]() 0�_
0�_
>�����͔�ʊE�[�x�͂ЂƂ̊�ɂ�����l�ł͂Ȃ�
���Ԃ͂����ł͂Ȃ��ł��ˁB���e�����~�a�Ƃ������t�����ׂĂ���Ă��܂��B
��ʊE�[�x�̓s���g�����e�ł����̊�ɑ���l�Ȃ�ł���B
>��i�ڂ��a�j�̊��Ƃ��čl���Ă��܂���
[13910491] �̏������݂Ɩ������܂����B
����Ɓu�{�P�̊��v�Ƃ����̂Ȃ�ŏ����炻�̊��������ė~���������ł����B
�����ԍ��F13930424
![]() 0�_
0�_
�u�{�P�̃f�B�e�B�[���v�̍l�@�ł��܂����i�������w�i�j�B
�Ƃ肠�������_�̂ݏ����܂����A�u�{�P�̃f�B�e�B�[���͓���v�ł��B
����́A�B�e�摜�i������f�ł��ǂ��j���B�e��Ɋg��E�k�����Ă��u�f�B�e�B�[���͓���v�ł��B�ו��ɂ�����܂őS������B
�����Ă݂�Ζ]���Ƃ����̂́u�w�i���g�債�Ďʂ��v���̂��Ƃ������Ƃł��i�g�債�Ďʂ�����A�w�i�̃s���g���Y���Ăڂ₯�Ă��܂����̂��ӏ҂Ƀo���Ă��܂��j�B
�����ԍ��F13931060
![]() 0�_
0�_
������������Ȃ��� �M�q���Ē����� �� [13873214] �̒���_�̑f���炵���ɂ͌h���������܂��B
�����̎B�e�o���̂��܂��̂Ȃ̂ł��傤���A���Ȃǂ́u�R���f�W�̍��{���Y�[���e���[�{�P�v���o�����Ă��Ȃ��獡�����܂���ł����B
�u�{�P�̃f�B�e�B�[������v�̏ؖ��B
�s���g�ʂ���w�i�܂ł̋������A�ϐ� Df �Ƃ��܂��B[13925321] �̋L�����g���� Df = x - s �ł��B
�w�i�̑��ʂɂ����鑜�{���� m'�A�w�i�̑��ʂɂ�����{�P�� b'�A�L�p���ɓY���� 1�A�]�����ɓY���� 2 ��t����B���ƌ��X�̎B�e�{���� m �ȂǁA���o�������g�p����B�B�e�{���Ɋւ��Ă͓O�ꂵ�Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ōČf�����
m = f / (s - f)
�ł��B
m1' = {1 / (s1 + Df)} * {(s1 * f1) / (s1 - f1)} = (m * s1) / (s1 + Df)
m2' = {1 / (s2 + Df)} * {(s2 * f2) / (s2 - f2)} = (m * s2) / (s2 + Df)
b1' = b1 * {Df / (s1 + Df)}
b2' = b2 * {Df / (s2 + Df)}
������ s2 = z * s1, b2 = z * b1 ��p���āi������ z �̓Y�[���{���j�A
m2' / m1' = z * {(s1 + Df) / (s2 + Df)}
b2' / b1' = z * {(s1 + Df) / (s2 + Df)}
M = z * {(s1 + Df) / (s2 + Df)} �Ƃł��u���ƁA
�u�]�����͍L�p���ɔ�ׁA�w�i�̑傫���� M�{����邪�A�{�P�� M�{����邽�߁A�{�P�̃f�B�e�B�[���͓����v
���邢��
�u�]�����̔w�i�́A�L�p���̔w�i�� M�{�Ɋg�債�����̂̂��߁A�{�P�̃f�B�e�B�[���͓����v
�ŏI���ł��B
�����ԍ��F13932920
![]() 1�_
1�_
>m = f / (s - f)
���������B
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
���̃y�[�W�̋L�����g����
m = t / s
�ł��B��(4) ��葜�{���̎������܂�܂��Bm' �͂��̉��p�B
�����ԍ��F13932944
![]() 0�_
0�_
>�i�g�債�Ďʂ�����A�w�i�̃s���g���Y���Ăڂ₯�Ă��܂����̂��ӏ҂Ƀo���Ă��܂��j
>�u�]�����̔w�i�́A�L�p���̔w�i�� M�{�Ɋg�債�����̂̂��߁A�{�P�̃f�B�e�B�[���͓����v
�����܂���B���̓�̌������͊ԈႢ�ł��B
�w�i�� M�{�Ɋg�債�Ă���B�������{�P�� M�{�Ɋg�債�Ă���B����ă{�P�̃f�B�e�B�[���͓���B
>�u�]�����͍L�p���ɔ�ׁA�w�i�̑傫���� M�{����邪�A�{�P�� M�{����邽�߁A�{�P�̃f�B�e�B�[���͓����v
���̌��������������ł��B
�����ԍ��F13933059
![]() 0�_
0�_
gintaro����A���s�̂�������A���鐯���߂炳��A�����āA��܂����낤����
�F����̂������ŁA��͑S�ĉ����܂����B
�c�悤�ȋC�����܂��B
��ʊE�[�x�ɂ��ւ��u�ӏ܃T�C�Y�v���A�ꖇ�̉摜�̒��ł��ꏊ�ɂ���ĈႢ�A�B�e�{���𑵂��������̉摜�ł��s���g�ʈȊO�͈Ⴄ���Ƃɒ������ׂ��ł����B
�uF�l���������ƃ{�P�͑傫���Ȃ�v
�u�B�e�{�����傫���ƃ{�P�͑傫���Ȃ�v
�uF�l�ƎB�e�{�����ꏏ�ł���A�t�H�[�}�b�g��œ_�����Ɋւ�炸�O��̃{�P�̑傫���͓������v
�u�ӏ܃T�C�Y���傫����{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���₷���Ȃ�v
���S�Ă͂��ꂪ���ɂȂ��Ă��āA��܂����낤����̃O���t�ƈꏏ�Ɍ��Ă������������̂ł����A
�u�摜���k�����Ă����ƁA���X�ɑO�オ�{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���ɂ����Ȃ�A�ŏI�I�ɂ̓p���t�H�[�J�X�ɂȂ�v
�u�摜���g�債�Ă����ƁA���X�ɑO�オ�{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���₷���Ȃ�A�ŏI�I�ɂ̓s���g�ʈȊO�̓{�P�����ɂȂ�B�������A��f���ɂ���Ċg��ɂ͐��������邽�߁A�����܂ł͓��B���Ȃ��v
�u�w�i�͊ӏ܃T�C�Y���ی��Ȃ��������Ȃ��Ă����B���̓x�����̓p�[�X���傫���L�p�قnj����B�ӏ܃T�C�Y������菬�����Ȃ�ƃ{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���Ȃ��Ȃ邽�߁A�{�P���̂��������iF�l�������傫���B�e�{��������菬�����j�ł́A�L�p�ɂȂ�قǃs���g�ʂ���߂��i�K�Ŕw�i���{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���Ȃ��Ȃ�i��������ɍL�p�w�i�{�P���E�Ƃ��܂��j�v
�X�ɁA
�uF�l���������������ꍇ�́A�{�P���傫���L�p�w�i�{�P���E�ɒB���Ȃ��B�܂��A�œ_�����Ɋւ�炸�s���g�ʕt�߈ȊO�̓{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���̂Ŕ�ʊE�[�x�͓����v
�u�B�e�{�����������傫���ꍇ�́A�{�P���傫���L�p�w�i�{�P���E�ɒB���Ȃ��B�܂��A�œ_�����Ɋւ�炸�s���g�ʕt�߈ȊO�̓{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���̂Ŕ�ʊE�[�x�͓����v
�u�B�e�{�����������������ꍇ�́A�œ_�����Ɋւ�炸�s���g�ʕt�߈ȊO�̓{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���Ȃ��i�������ɒ[�ȑO�i�̓{�P��j�B����Ĕ�ʊE�[�x�͓����v
�u��ʑS�̂̊ӏ܃T�C�Y���������傫���ꍇ�́A�œ_�����Ɋւ�炸�s���g�ʕt�߈ȊO�̓{�P�Ă��邱�ƂɋC�t�����ߔ�ʊE�[�x�͓����v
�u��ʑS�̂̊ӏ܃T�C�Y���������������ꍇ�́A�œ_�����Ɋւ�炸�s���g�ʕt�߈ȊO�̓{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���Ȃ����ߔ�ʊE�[�x�͓����v
�u�������t�H�[�}�b�g�ő傫���t�H�[�}�b�g�Ɖ�ʏ㓯���傫���Ɏʂ��ƁA�B�e�{���͏������Ȃ�v
�����āA���ʂƂ��āA
�uF�l�������傫���A�B�e�{�������͈͓̔��Ŕ�r�I�������A��ʑS�̂̊ӏ܃T�C�Y�����͈͓̔��̏ꍇ�̂ݍL�p�w�i�{�P���E�������A�œ_�����ɂ���ă{�P�̑傫�����Ⴄ�悤�Ɍ�����B�܂��ʊE�[�x���قȂ�v
�ƂȂ�܂��B
�܂��A��̔�r�ʐ^���A��Ԍ��̒��̊ӏ܃T�C�Y���ꏏ�ɂȂ�悤�Ƀg���~���O���Ă݂܂��B
�N�̌����Ƃ������������悤�Ɏv���܂����A�_���ł��傤���H
�����ԍ��F13933706
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������
�����Ԃ͂����ł͂Ȃ��ł��ˁB���e�����~�a�Ƃ������t�����ׂĂ���Ă��܂��B
��ʊE�[�x�̓s���g�����e�ł����̊�ɑ���l�Ȃ�ł���B
�����ł��ˁB�ЂƂ̊����ʓI�ȋ��e�����~�Ɋւ���A�l�Ƃ��Ă̔�ʊE�[�x����ʓI�ł��B�����A�ڂ��̑傫�����A�w�i�̂���_�ɂ�����ڂ��̔��a�ł�����l�ł����A���ƌ��Ȃ��Ă�킯�ł��B
�����ʂ͏�Ɂu�l�v�Ƃ��u���v�Ƃ��l�����܂��̂ŁA�K�X�A�l�Ƃ��Ă̔�ʊE�[�x�Ɗ��Ƃ��Ă̔�ʊE�[�x���g�������Ă܂����A�����͂��̂ւڒ��ɂ���Ă��܂��̂ŁA�ǂސl�ɂƂ��č����̌����ɂȂ�����������܂���B
�T�O�Ƃ��Ă킩��₷���̂́u�ڂ��̑傫���v�̕��Ȃ̂ł��傤�ˁB
����܂����낤����̃O���t���ĉ��x���o����Ă܂����A������������Ȃ��̂Ŋ����������Ă��������B
�������s���g�ʂ���w�i�܂ł̋���(x)
�c�����ڂ��̗�(y)�ł����A
�ڂ��̗ʁi�ڂ��w���ƌĂ�Ă܂��j���ڂ��̔��a/���e�����~�a
�Ɛ��K������Ă܂��B
�����ł����Ax>0�͈̔͂ł͋��s�̂�������̌�ڂ��̌������g����
y=(�ڂ����a) * (1/��) �� (mf/F) * (1-(s/(s+x))) * (1/��)
�ƂȂ�܂��B�e�p�����[�^�͂���܂Œʂ�A��APS-C��ʑΊp����0.07%�Ƃ���܂��B
�O���t�̉��ɏ����Ă܂����A
F=2.8, m=0.036
�Ƃ����ꍇ�ɕ�����f(=400, 200, 100, 50, 25mm)�ɑ��Ă��ꂼ��O���t�������Ă���Ă܂��B
����ɁAy=1�Ƃ��������ȓ_����������Ă܂����A���̒����ƃO���t�̌�_��x���W����ʊE�[�x�B
��̎���x�ɂ��ĉ������Ƃ�
x=��Fs/(mf-��F)
����ʊE�[�x�Ƃ킩��܂��B
y=2�̐������Ő�A���e�����~�a2�ɂ������ʊE�[�x�ł��B
���F(f=25mm)�̃O���t�Ɖ��F(f=50mm)�̃O���t���r�����
y=1�̓_���Ő��Ă��A���O���t�Ƃ̌�_�͂قڈ�v���Ă��Ĕ�ʊE�[�x�͂قړ����B
�����ȓ_�����グ�Ă䂭�ƌ�_������Ă䂫��ʊE�[�x�ɍ��������Ă��܂����A�ŏI�I��y=30�ȏ�ɒB�������_�łǂ�����p���t�H�[�J�X�ƂȂ�Ăэ����Ȃ��Ȃ�܂��B
���ꂪ�A�摜���k�����Ȃ��猩��ׂ��Ƃ��Ɋώ@����錻�ۂƂ��āA�X���傳��̐�������Ă邱�Ƃł��ˁB
�����ԍ��F13933984
![]() 0�_
0�_
�M�q���Ē�����
�����ꂽ���Ƃ͑S�Đ������Ǝv���܂��B
�����Ƃ��Ă��M�q���Ē�����̖���N�̂������ōl���������ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�����̖��
���P�D�B�e�����������ꍇ�A�]���̕�����ʊE�[�x�͐Ȃ�
���Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă���ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��B
���̎��A�]���̕������ΓI�ɔw�i���傫���A�O�i���������Ȃ�B�w�i���{�P�Ă���ꍇ�͌��ʓI�ɔw�i�{�P���傫���A�O�i���{�P�Ă���ꍇ�͑O�i�{�P���������Ȃ�B
�Ɋւ��ẮA�Q�̂݁A�ȉ��̂悤�ɕς���ΐ����ł��ˁB
�Q�D��ʑ̂��傫���Ɏʂ��ꍇ�A�œ_�������قȂ��Ă��u�w�i�̃f�B�e�C���v�͕ς��Ȃ��B
���̎��A�]���̕������ΓI�ɔw�i���傫���A�O�i���������Ȃ�B�w�i���{�P�Ă���ꍇ�͌��ʓI�ɔw�i�{�P���傫���A�O�i���{�P�Ă���ꍇ�͑O�i�{�P���������Ȃ�B�u���̂��߁A��ʊE�[�x�ɍ���������B�v
�ǂ������ꍇ�ɂ��̍������ɂȂ邩�͗M�q���Ē�����̏����ꂽ�ʂ�ł��B
��ʊE�[�x�Ƃڂ��̑傫����������������A����������N�����Ă�͎̂����ł����A���҂͂��Ƃ��ƕ\����̂Ȃ̂ł�₱�����B�������r���A�����������܂����B�Ȃ̂ōŌ�ɋ��P�Ƃ��āi�����ċt���I�Ɂj�F
�u��ʊE�[�x�Ƃڂ��̑傫���𐳂����������悤�v
�����ԍ��F13934083
![]() 1�_
1�_
�s���g�ʑO��́u��v�����������͍l�@���Ă���܂���̂ŁA���͈̔͂ŁB
>�uF�l�ƎB�e�{�����ꏏ�ł���A�t�H�[�}�b�g��œ_�����Ɋւ�炸�O��̃{�P�̑傫���͓������v
�u�œ_�����v�̉e���������܂��B��܂����낤���� [13873966] �̎O�Ԗڂ̃O���t�B���ŕ\���� [13932920] �Ɠ����ŁA
y = {m * (f / F)} * {x / (s + x)}
x �������̕ϐ��i�s���g�ʒu�Ɣw�i�Ƃ̋����j�Ay �����̋����ɂ�����w�i�{�P�̑傫���By ���œ_���� f �ɔ�Ⴗ��̂��킩��܂��i�s���g�ʂƂ̋��� s �� f �ŕς�邪�A���̃O���t�� s �̉e�����Ȃ��悤�ɕ��s�ړ����Ă���j�B
>�u�w�i�͊ӏ܃T�C�Y���ی��Ȃ��������Ȃ��Ă����B���̓x�����̓p�[�X���傫���L�p�قnj����B
�����̕����������Ă���Ӗ����킩��܂���B�u�w�i�́g���h�̑傫���͍L�p�قǏ������v�Ȃ�킩��̂ł����B
�����u��ʊE�[�x�v�̒P�ꂪ����܂̕��͂ł����A��͂�u��ʊE�[�x�v�̒P��Ő�������͖̂���������܂��B
�Ƃ肠�����t�H�[�}�b�g�Œ�ōl���āu�B�e�{�� m �v�Ɓu�����Y F�l�v�ɂ���� ��܂����낤���� [13873966] �̎O�Ԗڂ̃O���t�̊������ς��܂��B
y = {m * (f / F)} * {x / (s + x)}
m ���������ƁAF���傫���ƁAy�����Ɉ��k����܂��i�O���t���ォ��M�����Ɖ����Ԃ������j�B
���̂Ƃ��ɏ��߂ċ��e�����~�a �� �̐���
y = ��
�ʼn��Ɉ����܂��B���̐��ƃO���t�̋Ȑ��̌�_�� x���̍��W���u��ʊE�[�x�v�ł���A�œ_���� f ���傫���ق�����ʊE�[�x�́u�K���v�������i�j�Ȃ�܂��B���͂��́u���x�v���ǂ����ł��B
�L�p������ʊE�[�x�ɓ��B�����Ƃ��� x ���A�]�����O���t�ɑ���������̖]�����̃{�P�̑傫�� y �����߂܂��B
y / ��
���̒l���傫����u�]�����̔�ʊE�[�x���v�Ƃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂��i�l���������H�͌l�œ��v�����Α�̏o��Ǝv���j�B
�ŁA�u�t�H�[�}�b�g��ς�����H�v�́u���Z���ׂ����̂͑S�Ă����Z�v����悢�ł��B
>�uF�l�������傫���A�B�e�{�������͈͓̔��Ŕ�r�I�������A��ʑS�̂̊ӏ܃T�C�Y�����͈͓̔��̏ꍇ�̂ݍL�p�w�i�{�P���E�������A�œ_�����ɂ���ă{�P�̑傫�����Ⴄ�悤�Ɍ�����B�܂��ʊE�[�x���قȂ�v
������u��ʊE�[�x�v���g���͖̂���������̂ł��B�����ȈӖ��ł̔�ʊE�[�x�Ȃ�u��ɖ]�����v�ł�����B
�{�P�̂ق��̓{�P�̂ق��Łu��ɖ]�����傫���v�ł����A�w�i�������Ȃ�Ȃ�قǁu�L�p�����A����w�傫���v�Ȃ�A�ŏI�I�ɂ͖������̃{�P�̔�ɋ߂Â��܂��B
��� ���鐯���߂炳�� �� [13921356] �́u���]���́A�w�i�{�P�͑傫�������ɔ�ʊE�[�x���[���v�̏ꍇ�́uF�l��ς����B�e�v�ł��̂ŁA�������Ƃ��Ă͒ʂ�킯�ł��B
�w�i�{�P�Ɋւ��Ă� [13931060] �Łw�]���Ƃ����̂́u�w�i���g�債�Ďʂ��v���̂��x�Ə����܂����B
�L�p�̔w�i�{�P���]���̔w�i�{�P���A�ʂ��Ă���傫�����Ⴄ�����œ������̂ł��B
�u�S���������̂�������A�w�i���L���ʂ��Ă��镪�����L�p�̂ق����g�N�Ȃ�H�v�Ƃ����₢������A�����́u�ہv�B
�]���ŎB�����w�i�̂ق����ʐς��傫�����߁A�g��E�k���ő傫���𑵂����Ƃ��Ɂu�m�C�Y�����Ȃ��v�ł��i�����I�ɂ́j�B
�M�q���Ē����� �� [13933706] �ł����ƂȂ����ꂪ�o�Ă���悤�Ɍ����܂��B
���ƍēx�咣�������̂ł����A�u��ʊE�[�x�v�͓���Ȋ��ɂ͓�����̂����Ȃ��ł��B���̖��̓{�P�̖���
�E�����Y�́i��ʊE���������ւ́j�{��
�E�����Y�̌���
���̓�����ʼn����Ă��܂��܂��B
�u�����Y�̌����v�͂�����Ɠ���̂Łu�����������́v�Ƃ��Ă��܂��A�����Y�̔{���͒����I�ł킩��₷�����̂ł��B�o�Ă��鎮���ϐ�����t�����ē�����Ɍ����邾���B
�u�L�p���]�����w�i�͓������̂Ȃv�Ƃ������Ƃ��A�ł���Β����I�ɗ������Ă��炢�����ł��B
�����ԍ��F13934106
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>�uF�l�ƎB�e�{�����ꏏ�ł���A�t�H�[�}�b�g��œ_�����Ɋւ�炸�O��̃{�P�̑傫���͓������v
�́u�{�P�̑傫���v�́A�u�f�B�e�[���̂Ԃ���v�Ɠǂݑւ��Ă��������B
>�u�w�i�͊ӏ܃T�C�Y���ی��Ȃ��������Ȃ��Ă����B���̓x�����̓p�[�X���傫���L�p�قnj����B
�́u�ӏ܃T�C�Y�v�́u�w�i�́g���h�̑傫���v�Ɠǂݑւ��ĉ������Ă����\�ł��B
�������ȈӖ��ł̔�ʊE�[�x�Ȃ�u��ɖ]�����v
�͈Ⴄ�Ǝv���܂��B
��ʊE�[�x�Ƃ́A�s���g�ʈȊO�̓{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���Ȃ��͈͂ł���A�ӏ܃T�C�Y����f���ɂ���Đ������Ă��邽�ߑ��݂��܂��B
�u�s���g�͖ʂł��������Ă��Ȃ��A����ȊO�͂��ׂă{�P���ŁA���̃f�B�e�[���̕�����̓s���g�ʂ��痣���قǁAF�l���������قǁA�B�e�{�����傫���قǑ傫���B�v
�u��f����������ɑ傫���Ȃ�A������Ɋg��o����A�ǂ̂悤�ȏ����̎B�e�ł��s���g�ʈȊO�{�P�Ă��邱�Ƃ��m�F�ł���B
��P�F�L��ȕ��i���ʂ��ăp���t�H�[�J�X�Ɍ�����摜���A���\���{�ɂ��g�債�Ĉꕔ���������ӏ܂��邱�Ƃ��o����A���L�����ꂽ�ꖇ�̗t�ł���S�̂ɂ̓s���g�������Ă��Ȃ����Ƃ��킩��B
��Q�F�B�e�{�����傫���ꍇ�ł����l�B�����̂�������̗�[13873167]���A������g�債��[13873197]���A�œ_�����Ɋւ�炸�L�A�L�����A���܂Ńs���g�������Ă���悤�Ɍ����邪�A�X�ɍ���f���̃J�����ŎB�e���Ă����Ɗg�債���ꍇ�A�L�Ƌ��̓{�P�Ă��邱�Ƃ��m�F�ł���B�v
���鐯���߂炳�� �� [13921356]�ɂ͈٘_�͂���܂���B
�w�i�{�P�Ɛ[�x�𗼗�������ɂ́A���]���ɂ��Ă�����������܂���B
���]���ŎB�����w�i�̂ق����ʐς��傫�����߁A�g��E�k���ő傫���𑵂����Ƃ��Ɂu�m�C�Y�����Ȃ��v
����͊ԈႢ����܂���B
�܂��A��ʂɁu��f�����傫������ƍ����x�m�C�Y���傫���Ȃ�v�ƌ����܂����A����̓s�N�Z�����{�Ŕ�r����Ό����ł����ӏ܃T�C�Y�𑵂����ꍇ�m�C�Y�̏k�������傫���Ȃ�̂ł��܂�ς��Ȃ���H�Ǝv���܂��B
����͂܂��ʂ̕���ł��ˁB
����̌��A���͈������߂Ďg������������ɓ����悤�ȃX�����Ă��������Ƃ�����܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711068/SortID=7657470/
���������ׂ�Ƃ����ԗ������������肵�Ă����悤�ȋC�����܂��B
�����ԍ��F13934370
![]() 0�_
0�_
�����A����ȊȒP�Șb����Ȃ��B�\����܂���B�������܂��B
>y ���œ_���� f �ɔ�Ⴗ��̂��킩��܂��i�s���g�ʂƂ̋��� s �� f �ŕς�邪�A���̃O���t�� s �̉e�����Ȃ��悤�ɕ��s�ړ����Ă���j�B
������ԈႢ�B�B�e�{�� m �̎����� s �����߂�B
m = f / (s - f)
s = f * {(m + 1) / m}
��y = {m * (f / F)} * {x / (s + x)} = {m * (f / F)} * [mx / {(m + 1)f + mx}]
���Ȃ蕡�G�Ȏ��ŁA�P���Ɂuf �ɔ��v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ł��B
���炭��̕��A
>m ���������ƁAF���傫���ƁAy�����Ɉ��k����܂��i�O���t���ォ��M�����Ɖ����Ԃ������j�B
F �ɂ��Ă͂��̒ʂ�ł����Am �ɂ��Ă͒P���ɂ����͂Ȃ�Ȃ��ł��B
m �� f �ɂ���ăO���t�̌`���ς��̂ŁA�ȒP�ɂ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
������L�p���̔�ʊE�[�x x ��]�����̎��ɑ������
y / ��
�����߂�Ӌ`���o�Ă���Ƃ������܂��im �� f �ɂ���Ă��̃{�P�̑傫���̔�̒l���قȂ� �� �ʐ^�̃{�P����قȂ�j�B
�u�]���͌����ʊE�[�x���v�����͏�ɐ^�ł��im�AF ���̏ꍇ�j�B�ؖ��� [13932920] ���
b2' / b1' = z * {(s1 + Df) / (s2 + Df)}
s1 = f1 * {(m + 1) / m}, s2 = zf1 * {(m + 1) / m}, z > 1
�������A
b2' / b1' > 1
��B
�S�Ă� Df > 0 �ɑ��āA�]���̂ق����{�P���傫������u�]���͌����ʊE�[�x���v�������B
�����ԍ��F13934372
![]() 0�_
0�_
����Ⴂ�ł����B
>�������ȈӖ��ł̔�ʊE�[�x�Ȃ�u��ɖ]�����v
>�͈Ⴄ�Ǝv���܂��B
���
>�u�]���͌����ʊE�[�x���v�����͏�ɐ^
�Ə����܂������A�u�]���ł��p���t�H�[�J�X�i�������̃{�P�T�C�Y�����e�����~�a�ɓ���j�v�̎������͗�O�ł����B���݂܂���B
���Ɓu�]���̔w�i�{�P�ƁA�L�p�̔w�i�{�P�́A���̓m�C�Y�ȊO�͓������̂��v�Ə����܂������A�u�����Y�̉�܌��E�i�������܃{�P�j�v���l����Ɓi��f��������ł��j���҂͈Ⴄ���̂�������܂���B
�ł����A����ׂ͍����b�ł��ˁB
>���������ׂ�Ƃ����ԗ������������肵�Ă����悤�ȋC�����܂��B
���� �M�q���Ē����� ���u�{���v�ɒ��ڂ��Ă����������������ŁA������������ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
���Ȃ蕡�G�Ȏ��ł����A����ꂽ�u�s���g�ʌ������ x �ɂ�����{�P�̑傫���̎��v���ڂ��Ă����܂��i�l�@�͂܂��ł����A���܂ł̍l�@�Ƃ����炭�ς��Ȃ��ł��傤�j�B
y = {m * (f / F)} * [mx / {(m + 1)f + mx}]
������ m = f / (s - f)
�����ԍ��F13934427
![]() 0�_
0�_
���u�w�i�́g���h�̑傫���͍L�p�قǏ������v�Ȃ�킩��̂ł����B
�������Ə�������O�t�H���[���܂����A�Ϗ����𑵂�����ł̑��̑傫���ɂ��Č��y���Ă�̂ŊϏ܃T�C�Y�Ƃ������t���g���Ă�̂ł��傤�B���̋L�q�ɂ��Ă��A�X���傳��̂���܂ł̗����̌o�܂�����A���{�l���������������Ă��邱�Ƃ͕�����܂����A���_�̕������������C������Ƃ���A
�uF�l�����͈͓̔��Ŕ�r�I�傫���A�B�e�{�������͈͓̔��Ŕ�r�I�������A��ʑS�̂̊ӏ܃T�C�Y�����͈͓̔��̏ꍇ�̂݁A�œ_�����ɂ���āA��ʏ�Ō��E�ȏ�̔w�i�ڂ��̐�����͈͂��قȂ�B�܂��ʊE�[�x���قȂ�v
���ȁB
���u��ʊE�[�x�v�͓���Ȋ��ɂ͓�����̂����Ȃ��ł��B���̖��̓{�P�̖���
�X���傳�g�͓I�m�ɃO���t�������Đ�������Ă�킯�ŁA���łɁu��ʊE�[�x�}�X�^�[�v�Ƃ������܂����A�{�P�̖��Ƃ��ĔF���ł��Ă���Ƃ������܂��B
e�����悷���2�ɂȂ邩�H�Ƃ������́A�w�����̖��ƌ����Ă��ǂ����ΐ����̖��ƌ����Ă��ǂ��ł��ˁB�ΐ������Ȑl�̕����������ǁA�܂��A���̒��x�̘b�ł��B
�����ԍ��F13934467
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
�����
>�u�]���͌����ʊE�[�x���v�����͏�ɐ^
�Ə����܂������A�u�]���ł��p���t�H�[�J�X�i�������̃{�P�T�C�Y�����e�����~�a�ɓ���j�v�̎������͗�O
��O�͂��̏ꍇ�����ł͂���܂���B
�ӏ܃T�C�Y�ɔ�r���ăf�B�e�[���̕��ꂪ�傫���ꍇ���Y�����܂��B
[13873546]�ł��Љ���悤�ɁA���{�B�e�Ȃǂ��ǂ���ł��B���̓����̂�������̗�������ł��B
gintaro����
�����܂ŗ��āA�����Ɋւ��Ă͂܂������������Ă���܂���c�B
�B�e�o���Ƃ������痈�鐄���ŏ����Ă��邱�Ƃ������ł��B
�����ԍ��F13934624
![]() 0�_
0�_
[13873546] �ł��A�����ƌv�Z�����͂�]���̂ق��������ʊE�[�x���Ǝv���܂���B
[13934372] �̍Ō�ɏؖ�������܂��B
�ؖ��ŋߎ����g���Ă��镔���́u�����Y�̌����v�ł��B�����͒��ׂĂ܂��B
�����Y�̌����̋ߎ�����F�l�����ɏ������Ȃ�ƌ덷���o���悤�ȁE�E�E�B
���{�}�N���̏ꍇ
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
�����̕������g���� s = t = 2f �ł��B
�܂����Ƃ̓����Y�����͐^��ł͂Ȃ��̂ŁA���H�����Ⴄ���Ă̂͂���ł��傤���B
�����ԍ��F13934679
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
�������ł܂���������[�܂�܂����B
�u��ʊE�[�x�Ƃ́A�s���g�ʈȊO�̓{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���Ȃ��͈́v�͂����ł���ˁH
��ʓI�ɂ́u�s���g�������Ă���Ɗ�����͈́v�Ƃ������܂��B
�ł�����A�m�o�ł��Ȃ������Ȍ덷�܂Ōv�Z���Ă̓_���Ȃ�ł��B
�����͂킩��܂��A�ǂ����Ő������ۂ߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�������s�̂����������̃}�N�������Y���������ł���A���ۂɎ����Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F13934724
![]() 0�_
0�_
>�u��ʊE�[�x�Ƃ́A�s���g�ʈȊO�̓{�P�Ă��邱�ƂɋC�t���Ȃ��͈́v�͂����ł���ˁH
�������F���̈Ⴂ�ł��āB�u�����ȈӖ��ł̔�ʊE�[�x�v��
�u�{�P�����e�����~�a���Ɏ��܂�A�s���g�ʂƔw�i�Ƃ̋����v
�Ǝ��͒�`���Ă��܂��B����͒P�Ȃ鐔���I�Ȓ�`�̘b�ɉ߂��Ȃ��ł��i�����Ɍ����Ă����傤���Ȃ��ꍇ�������j�B
�u�m�o�o���邩�o���Ȃ����v����ɍl����̂ł���A�}�N���ł̃{�P�́u��ʊE�[�x�����v�Ƃ��č\��Ȃ��ł��B
�����ԍ��F13934760
![]() 0�_
0�_
���̊���ƁA
���
>�u�]���͌����ʊE�[�x���v�����͏�ɐ^
�Ə����܂������A�u�]���ł��p���t�H�[�J�X�i�������̃{�P�T�C�Y�����e�����~�a�ɓ���j�v�̎������͗�O
�Ɩ������邱�Ƃ͂Ȃ��ł����H
10km�Ƃ�100km�ł͂Ȃ��A�������N�Ōv�Z�����ꍇ�͂ǂ��ł��傤�B
���������p��̈Ӗ��͂���܂��A�u�����Ȕ�ʊE�[�x�v�̏ꍇ�ł��B
�����ԍ��F13934855
![]() 0�_
0�_
���ʂ́u�ߏœ_�����v���g���܂��B�����~�a���܂݂܂����A�����~�a�����݂₷���ł��B
�����ԍ��F13935089
![]() 0�_
0�_
�������̃{�P�̑傫���� [13921252] �Ŋ��o�ł��B
m * (f / F) �܂��� m * D �i������ D �̓����Y�L���a�j�B
���e�����~�a �� > m * D �̎��A��������Z���œ_�����͑S�Ĕ�ʊE�[�x������ł��B
�����ԍ��F13935239
![]() 0�_
0�_
�b�͂���܂����B
>�������̃{�P�̑傫���� [13921252] �Ŋ��o�ł��B
�ƌ����܂����A�{�P�̑傫���̌����͍���̏ꍇ [13934427] �ł����
y = {m * (f / F)} * [mx / {(m + 1)f + mx}]
������ m = f / (s - f)�Ax �̓s���g�ʌ�������B����ꂽ y ���s���g�ʌ������ x �ɂ���_�����̑��ʂɂ�����{�P�̑傫���B
���]�v�ȕϐ��������ėǂ��ł��傤�B
�������̃{�P�̑傫���́Ax �� �� �Ƃ���� y �� m * (f / F) = m * D �i������ D �̓����Y�L���a�j�ŋ��܂�܂��B
�����ԍ��F13935297
![]() 0�_
0�_
�܂��A�����ɂȂ�Ȃ��ߓ_��悸�l�@������Ǝv���܂��B�������ߓ_�̕������₷���ł��B
���_�E��ʊE�[�x�������ɂȂ��Ă��A�ߓ_�̏ꏊ�͎ʐ^��Ӗ�������܂��B
�ߓ_��1/2��ʑ̋����ɋ߂Â�����A���_���傫���ς��܂����i�[�����Z�ɋ߂��j�A
���̎��A���_�̏ꏊ���ʐ^�ő���͖̂����ł��̂ŁA���p��̈Ӗ����[���ɋ߂��ł��B
�����ԍ��F13935310
![]() 0�_
0�_
>���e�����~�a �� > m * D �̎��A��������Z���œ_�����͑S�Ĕ�ʊE�[�x������ł��B
���Ԃ�킩���Ă����Ȃ��̂ŕ⑫���܂����A����́i���̋��e�����~�a�̒l�ɉ����āj�����ʊE�[�x��������A���Ȃ킿�p���t�H�[�J�X�ł��B
����A�p���t�H�[�J�X�ȊO�̏�ԁix �� ���j�ł́A�����ȈӖ��ɂ����Ắu�]���͔�ʊE�[�x���v�ƂȂ�܂��B
�ŁA���̍��܂ł��Ă����̂́u�����ʊE�[�x�v�ɂ��Ăł��B
�ߏœ_�����Ƃ����̂́As �� �� �ɂ����Ƃ��́u�ߓ_�����isn�j�v�̂��Ƃł��B
http://www.asahi-net.or.jp/~kv5y-aon/DOF/dof.html
s = f * {(m + 1) / m}, m > 0 �Ƃ����As ���L�������͈̔͂̌����ʊE�[�x�ɂ��Ă͌����ł悢�Ǝv���܂��i�ׂ����b������A��܌��E�ɂ��A�w�i�̃{�P�̃f�B�e�B�[������قȂ�Ƃ����b���ł��܂��j�B
�����ԍ��F13935399
![]() 0�_
0�_
�������������Ӗ��͉ߏœ_��������͕ϐ��Ƃ��Ďg���̂ł��B
���e�����~�a��F�l�����̏ꍇ�A�œ_�����̈Ⴄ��{�̃����Y�ɓ������܂����A
�ߏœ_�����̕��������I�Ŏ��p����g���₷�������m��܂���B
�����ԍ��F13935704
![]() 0�_
0�_
�Ⴆ�A��ʑ̋������ߏœ_������0.3�{�̎��Ɂ����Ƃ��B
�r���͂�₱���������m��܂��A���ʂ�������₷���Ȃ邩���m��܂���B
�����ԍ��F13935721
![]() 1�_
1�_
�덷�̘b�ł����A�Ȃ����ɎO���̍����o�āA����9���O���ԍ����x���ƌ����܂���
����͔�ʑ̋����F�ߏœ_�����̔�Ō��߂�ꂽ�̂ł��i�덷�̌덷�͂܂��ڂ������Ă��܂���j�B
�ߏœ_���� �� �œ_�����̕��� ÷ �i���e�����~�a × F�l�j�A�ł����A
F�l�Ƌ��e�����~�a���傫���Ȃ�ꍇ�i�Ⴆ�� ���if/8�A�V���{�C�≖�j�A
�ߏœ_�������������Ȃ�A��ʑ̋����F�ߏœ_������ƁA��ʊE�[�x�̌덷���傫���Ȃ�܂��B
����͏�̌덷�c�_�̐����ɂȂ�Ǝv���܂��i�ǂ�ȏŋc�_���ꂽ���A�Ȃ��Y�������������j�B
�����ԍ��F13936163
![]() 0�_
0�_
�����s�̂�������
���x���Ȃ�܂����B
2011/12/23 13:09�@[13930388]�ł��q�˂���܂����w������������Ȃ��̂Ŋ����������Ă��������x�ɂ��āB
�����̊e���̓����͏Ȃ��܂��B
�܂������Y�̏œ_�������ƎB�e�{��������B�e�����k0�����߂܂��B
�@�@�k0�����i��^2�{�Q���{�P�j�^��
���ŁA���̂Ƃ��̃����Y�O�����i�����Y�����ʑ̂܂ł̋����j��0�ƁA�����Y�㋗���i�����Y���猋���ʂ܂ł̋����j��0�����߂܂��B
�@�@��0���o�k0�{��(�k0^2�|�S�k0��)�p�^�Q
�@�@��0���P�^�i�P�^���|�P�^��0�j�@�@���k0�|��0�ł��ǂ��B
�����āA���x�͔C�ӂ̋����k�ɑ��āA
�@�@���k���k�|�k0
�@�@�@������0�{���k
�@�@�@�����P�^�i�P�^���|�P�^���j
�����߂܂��B
�܂��A���a�c�́A�œ_�������ƌ��a��e����
�@�@�@�c�����^�e
�ƂȂ�܂��B
�����~�̌a����
�@�@�@�����b�c�i��0�|���j�^���b
�ł��B
��������e�����~�̌a�Ő��K������
�@�@���f����÷��
�O���t�͂��f�����k�Ńv���b�g�������̂ł��B
����āA�������[���̓_�͔�ʑ̂̈ʒu���A�v���X���w�i���A�}�C�i�X���J�������������A�c�������K�����ꂽ�����~�̌a�������Ă��܂��B
�����ԍ��F13947911
![]() 0�_
0�_
��܂����낤����@
���̌��� gintaro���� �ɐq�˂��̂ł��B
�{�P�̎��ɂ��Ă͎����œ����܂����B�u�O�{�P�v�̎��͐G��Ă��܂��A���l�ɓ����܂��B
���̃O���t�͂悭�킩��܂���B
�ߏœ_�����Ƃ����͓̂����Ă݂Ėʔ��������ł��B
���鐯���߂炳�� ��
>�ߏœ_���� �� �œ_�����̕��� ÷ �i���e�����~�a × F�l�j
���̎��́A�m���ɂ����Ȃ�܂������A�X�ɒ��ׂĂ݂��
�ߏœ_���� h = f / m�A������ m = f / (s - f) �Ȃ�ł��ˁB
�܂�A�ߏœ_�����Ƃ́u�g�œ_�����h�Ɓg��ʑ̋����h�̓�ϐ����v�ł��B
����̏ꍇ�A�B�e�{�� m ��������l�ł��̂ŁA�œ_�����ɂ���Ĕ�ʑ̋����������I�Ɍ��܂��Ă��܂��܂��B����āA
>��ʑ̋������ߏœ_������0.3�{�̎��Ɂ����Ƃ�
���������l�@�͏o���Ȃ���ł��ˁB
�u�ǂ����������Ŕ�ʊE�[�x�̈Ⴂ�������ł��Ȃ��Ȃ邩�H�v�́A���̌`
Df = (��F * C) / [m^2 - {��FC / (s - f)}]
C = s / (s - f)
�����āA����� m^2 �ɑ� ��FC / (s - f) �������ł��Ȃ��قǑ傫���Ƃ��A���Ȃ킿�u�B�e�{�����������Ƃ��v�A�u���ZF�l���傫���Ƃ��v�A�u���e�����~�a �� ���傫���Ƃ��v�ɐ[�x�̈Ⴂ�������ł��Ȃ��Ȃ�X��������A�ƍl���邵���Ȃ��Ǝv���܂��B
���� C �̓}�N���ɂȂ�ƒl 2 �ɋ߂Â��܂����E�E�E�B�܂芷�ZF�l���傫���Ɩ����ł��Ȃ��Ȃ�܂����B
���Ƃ͂Ƃɂ���������邵���Ȃ��ł��傤�B
�ŁA�X���Ƃ��Ắu�L�p�����p���t�H�[�J�X�ɋ߂��قǏœ_�����̈Ⴂ�ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ�������ł��Ȃ��Ȃ�v�̂ŁA����͂ǂ��炩�ƌ����ƃ{�P�\�����u�p���t�H�[�J�X�B�e�Z�@���_�v�ɋ߂��Ɗ����܂��B
�����ԍ��F13949894
![]() 0�_
0�_
�� ����̏ꍇ�A�B�e�{�� m ��������l�ł��̂ŁA
�� �œ_�����ɂ���Ĕ�ʑ̋����������I�Ɍ��܂��Ă��܂��܂��B
�֘A���̂�����̂ŁA���߂邩���߂��邩�ǂ������o���܂����A
�{�����ߏœ_�����i���F�l�ŗ\�ߊo���Ă����j�Ƃ̊W���l��������
��ʊE�[�x��������₷���Ǝv���܂��B
�{�������ł��ƁA�ߏœ_�����߂��ł̔�ʊE�[�x�ω��͒����Œ͂ݓ�Ǝv���܂��B
������l�ɂ�邩���m��܂����܂Ŋm�������펯�A�K���ł͉ߏœ_�������g���܂��B
�}�N���͔{�����傫���ł����A�ߏœ_�����Ɣ�ׂĔ�ʑ̋������ɂ߂ċ߂��Ɨ������Ă�
�ǂ��ł��傤�B�������̕������ʂ̍l�����Ǝv���܂����ǁB�ʊE�[�x�̌v�Z���A
�������₷�����߂킴�킴�ߏœ_�����iH�j���D��Ŏg���l�������ł���B
�����ԍ��F13949968
![]() 0�_
0�_
�ߏœ_�����͎����͂܂����M������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA������x�l�������Ă݂܂��B���ɂȂ邩�킩��܂��B
���M�������܂����Ă��܂��Ă��݂܂���B
�����ԍ��F13949998
![]() 0�_
0�_
>�ߏœ_���� h = f / m�A������ m = f / (s - f) �Ȃ�ł��ˁB
�����܂���B����������܂��B����̓p���t�H�[�J�X�̏����ł����B
�p���t�H�[�J�X�ł��� s = h + f �Ƃ������Ƃł��B
��ώ��炵�܂����B
�����ԍ��F13950009
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳�� �� [13935721] ������Ă݂܂����B
���_���猾���܂��ƁA����͂ƂĂ��ǂ����@�ł��B
���͍ĎO�ɓn��u��ʊE�[�x�̈Ⴂ�͂��邪�A�ǂ̒��x�Ⴄ���͕ϐ����������Ē���߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ə��������Ă��܂������A�ԈႢ�ł��B�u�ߏœ_�����v���g���Δ�ʊE�[�x�̈Ⴂ�̒��x���A���Ȃ�̐��m���Œ�ʉ��ł��܂��i���鐯���߂炳�� �������������ł��j�B
�s���g�ʌ������ x �ɂ�����{�P�̑傫���̌���
y = {m * (f / F)} * [mx / {(m + 1)f + mx}]
����� m = f / (s - f) ������ x �����߂�ƁA
x = yFs(s - f) / {f^2 - yF(s - f)}�@�E�E�E�i�A�j
�ߏœ_���� h = f^2 / ��F�@���@�� = f^2 / hF�@�i������ �� �͋��e�����~�a�j�B���i�A�j�� y �� ��������� x ���u�����ʊE�[�x�v�ɂȂ�B
�܂��A���i�A�j�� s �� s = nh �����i������ 0 < n < 1 �j�B�L�p���� x �� xW�A�]������ x �� xT �Ƃ��A�Y�[���{���� z �Ƃ��A���i�A�j��ό`�B
xW = nh(nh - f) / {h(1 - n) + f}
xT = znh(nh - f) / {h(z - n) + f}
�� xW / xT = {h(z - n) + f} / z{h(1 - n) + f}
�K���]�����̔�ʊE�[�x���Ȃ�̂ŁAxW > xT �ł���B����������ʊE�[�x�̔䂪10%�Ƃ������Ƃ� xW / xT <= 1.1 �����߁Az = 10 �Ƃ��Đ�������ƁA
10nh <= h + 10f
�E���� h + 10f = f{(f - 10��F) / ��F} �A�����I�ȋ��e�����~�a��ݒ肷��� f >> 10��F �ƂȂ�i�܂��G�c�ɂ͖������Ă悢�j�B�����ő��
n <= 0.1
�ƂȂ邱�Ƃ��킩��B
���鐯���߂炳�� �̌��t�����p�����Ă��������Ȃ�
�u��ʑ̋������ߏœ_������0.1�{���̎��Ɍ����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� 10% �ƂȂ�i�������Y�[���{�� 10�{�j�v�ł��B
���l�� xW / xT <= 1.3 �����߂��
12hn <= 3h + 12f
�ɐF�X�� f �� F ���������
�u��ʑ̋������ߏœ_������0.25�{���̎��Ɍ����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� 30% �ƂȂ�i�������Y�[���{�� 10�{�j�v�ƂȂ�܂��B
�l�̋��߂鏇�����猾���āA���m�ɂ́u��ʑ̋������ߏœ_������0.3�{�̎��ɔ�ʊE�[�x�̈Ⴂ��30%�v�ł͂Ȃ��u��ʊE�[�x�̈Ⴂ��30%�ȓ��ɂ���Ȃ��ʑ̋����͉ߏœ_������0.3�{�ȓ��v�Ƃ����������ł��B
���l�� xW / xT <= 2.0 �����߂��
�u��ʊE�[�x�̈Ⴂ��100%�i2�{�j�ȓ��ɂ���Ȃ��ʑ̋����͉ߏœ_������0.5�{���ȓ��v�ł��B
�܂� xW / xT <= 10 ����
�u��ʊE�[�x�̈Ⴂ��900%�i10�{�j�ȓ��ɂ���Ȃ��ʑ̋����͉ߏœ_������0.9�{���ȓ��v�܂ł͂��܂����B�����܂ł��Ζ@�������ƌ����Ă悢�ł��傤�B
�������S�ċ��e�����~�a �� = 0.03 �Ƃ��Čv�Z���Ă��܂��B
�� �����ɑ傫���Ȃ�� h ���������Ȃ�A���̈�ԉE�̍��A10f �� 13f �������ł��Ȃ��Ȃ�i�ŏ��̎��Ō����Ȃ� f >> 10��F �Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ɓj�A���鐯���߂炳�� �� [13935721] �̖@�����u�������ɂ����v�Ȃ�܂��i�œ_���� f �ɂ���ČX�����ς���Ă��܂��Ƃ�������)�B
�����ԍ��F13953724
![]() 0�_
0�_
�� = 0.03mm �͍��̃e���r�����e���̂ł��ˁB���� 0.01mm (10��m) ���Ó����Ǝv���܂��B
�ߏœ_�����ɋ߂Â����Ƃ́A�p���t�H�[�J�X�ɋ߂Â��A��ʊE�[�x���K���ɋ߂Â����Ƃł��B
�{���Ɋ֘A���������̋����ł����A�l���̏ꍇ��p 30 �{�œ_�����ƌ����܂��B
������ 50/2.2 �Ƃ���ǂ��g���܂����A30 �{�œ_������ 1.5m�A�ߏœ_������ 100m �ȏ�A
f/8 �܂ōi���Ă��A�ߏœ_������ 30m ����܂��i0.03mm �̏ꍇ 1/3 = 10m �ɂȂ�j�B
200�J�L�R�߂��܂ŐL�тāA��i���ɂȂ�錋�_���ł����ł͂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13953803
![]() 0�_
0�_
>�E���� h + 10f = f{(f - 10��F) / ��F} �A �E�E�E
�w�E���� h + 10f ���l�@�B h - 10f = f{(f - 10��F) / ��F} �A�����I�ȋ��e�����~�a��ݒ肷��� f >> 10��F �ƂȂ�i�܂��G�c�ɂ� h �ɑ��� 10f �͖������Ă悢�j�B�x
�킩��Ǝv���܂����������������B
r = xW / xT
�Ƃ����܂�(������ r > 1)�B�Ⴆ�Δ�ʊE�[�x�̔䂪 1.1 �Ȃ� r = 1.1 �ł��B���̃��X�̈�ԏ�ŐG�ꂽ �gh�h �� �g�i���g�Jf�h �̑傫���̈Ⴂ�̈�ʉ������߂܂��i�悤����ɍL�p���̏œ_���� f �������ł��邩�ׂ�j�Br �̎���ό`���A
(rz - 1)hn <= (r - 1)zh + (rz - 1)f = (f / ��F) * {(rz - z)f - (rz - 1)��F}�@�E�E�E�i�C�j
r �� 1 �ɋ߂Â��� f �̉e�����傫���Ȃ�܂��i�@�������������j�B�����I�ɂ� r = 1.1 �Ƃ��Ė@�������Ȃ�悵�Ƃ��Ă悢�ł��傤�ir = 1.01 �͑��v�Ȃ��Ƃ��m���߂��j�B����� r = 1.1 ��
(r - 1)zh + (rz - 1)f >= (f / ��F) * (r - 1) * (f - 11��F)
�킩��ɂ����ł����A��ԉE���� (f - 11��F) �����āA
�uf >> 11��F �ł���Ώœ_�����̉e�������ɖ@�������v
���킩��܂��B
���ۂ� F = 32, �� = 0.03 ��������ƁA 11��F = 10.56 �ł���A����͏œ_�����if = 14mm �Ƃ������肤��j�ɑ��Ĕ��ɑ傫���l�ł��B
���������ۂ� f = 14 �Ōv�Z����Ɓi�������Y�[���{�� z = 100 �Ōv�Z�j�A
F2.0�F n = 0.096
F8.0�F n = 0.109
F16 �F n = 0.126
F32 �F n = 0.160
�������� F32 �܂ōi��� n �̌덷���傫���Ȃ�܂����A����ł����̒l�� 1.6�{�B
�@���u�ߏœ_������ 0.1 �{�̎B�e�����ōL�p�����B�e������A�����B�e�{���Ŗ]�����ŎB�e���Ă���ʊE�[�x�̈Ⴂ�� 10% �����Ȃ��v�͏\����������Ƃ��Ă��悢�ł��傤�B
���i�C�j�ׂ�킩��܂����A���̖@���̓Y�[���{�� z �ɂ͉e�����܂���iz ����ɂ��Ē��ׂ�킩��j�B
�����̎g���L�p���̏œ_�����ƍő�F�l���� f >> 11��F ���������� �� ��I�т�������Ζ@���͐����ł��B
���� f >> 11��F �̏��������A�@���́uF�l�ɂ��ˑ����܂���v�B
�܂�u�L�p���ʼnߏœ_������ 0.1 �{���x�ŎB��A�����B�e�{���ł�����]�����ŎB�낤�Ƃ��A��ʊE�[�x�̈Ⴂ�� 10% ���x�Ɏ��܂�v�̖@������������̂ł��B
�����ԍ��F13954962
![]() 0�_
0�_
�����A�������B
>(r - 1)zh + (rz - 1)f >= (f / ��F) * (r - 1) * (f - 11��F)
������
(r - 1)zh - (rz - 1)f >= (f / ��F) * (r - 1) * (f - 11��F)
�ƈ����Z�ł��B
�킩��Ǝv���܂����A�E���̎��� z �� �� �Ƃ��܂����B
�����ԍ��F13954987
![]() 0�_
0�_
�M�q���Ē�����@�̎w�E�͂������茾���āA�������Ǝv���܂��B����̓e�[�u���̍�������Ζ��炩�ł��ˁB����͐̂��炻�����ƒm���Ă��܂������A���炽�߂čĊm�F���܂����B�ӌ��������̂͂��܂�m���ĂȂ��̂ł��ˁB�ǂ��w�E�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13957666
![]() 1�_
1�_
Macbe����
���������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B
�u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���v�́A�ꕔ������������܂����p�͈͂̑����ɂ����Ă͌��ł���Ǝv���܂��B
�������A�u�]���͔w�i�{�P���傫���v�Ƃ��������ɂ���ʊE�[�x�����낤�Ƃ����C���[�W����s���A�G�����烆�[�U�[�ցA�x�e�������珉�S�҂ցA�Ȃǎ����玟�ւƌ�����F�����`�d���Ă����Ă���̂��Ǝv���܂��B
�J�����̋ƊE�͗��m�I�ł���̂ɁA���ɕs�v�c�Ȍ��ۂł��B
���s�̂�������́A���ȏ�ɂ��̃X���b�h�����y���ݒ�������Ȃ����Ǝv���܂����A�������ł��傤���O�O
gintaro����[13910491]�Œ��ꂽ��^�o�X�̗�ł́A�v�Z��ǂ��Ȃ�܂��ł��傤���H���͌v�Z�̘b��͓r��������Ă����Ă���܂���̂ŁA��낵�����肢���܂��B
���l�t�H�[�T�[�Y�̍��{���Y�[��M.ZD14-150/F4.0-5.6�ő�^�o�X���B��܂��傤�B���Z���{��0.01�Ƃ��āA�����ł��ڂ����~�������͂ǂ�����悢���H
�V���v���ŕ�����₷����ʊE�[�x�s�ϐ_�b��M����Ȃ�u�J��F�l�̏������L�p�[�ŎB��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�łƂ��낪���ۂ́A�L�p�[�ł͊J���ł�40m�`50m��܂Ńs���g�������Ă��܂��A����A�J���e�l�̑傫���]���[�̕��́A����ɍi��Ȃ��ƃo�X1���ʊE�[�x�ɓ���܂���B���ꂪ��������̋A���ł��B
���ꂭ�炢�̔{���ł́A14mm��150mm�̏œ_�����ɂ���ʊE�[�x�̍��́A14mm@�t�H�[�T�[�Y��28mm@�t���T�C�Y�̃t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�ɂ���ʊE�[�x�̈Ⴂ�ɕC�G���܂��ˁB
���鐯���߂炳��͏I�n�咣�ɕω�����܂���ˁB
���̃X���ʼn����V��������������Ηǂ������̂ł����A�������ł����ł��傤���H
�����g�͗���x�̈Ⴂ�͂���܂����A
���u�]���͍L�p�ɔ�ׂĔ�ʊE�[�x���A�{�P���傫���v
�u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���̂Łc�i���j�v
�Ƃ����L�ڂ����������܂��B
������Ď����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���H
�̍ŏ��̖���ɑ��铚���͕ω�����܂���ł����B
�u�����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��v�ł��B
�����ԍ��F13958134
![]() 0�_
0�_
�B�e�{���i����0.01�j�ƌ��a��iF=2.8�A5.6�j�����ɂ����Ƃ��̏œ_�����̕ω��ɑ����ʊE�i�[�x�j�ɂ��Čv�Z���Ă݂܂����B
�����e�����~�̌a��33��m
�w�u�]�������Y�͔�ʊE�[�x���̂Łc�i���j�̍ŏ��̖���ɑ��铚���͕ω�����܂���ł����B�u�����̂ق�̈ꕔ�������Ă͂܂�Ȃ��v�x
�h�i�����ł͂Ȃ����j��萳�����h�����Ƃ���A
�u�]�������Y�́A��ʊE�[�x�����[���ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��A���a��Ɉˑ�����������̒l�Ɏ�������v�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F13958264
![]() 1�_
1�_
�܂����A200�Ŏ��܂�Ȃ��Ȃ��Ă����i�j
�����I���Ȃ����ł���A���̕��̂��ӌ��������Ă݂������ߎ����̋@�ނł���D700�Ɉ����z�����Ǝv���܂��i�����̕��͂�����ł���������������ł����j�B
���s�̂�������
�lj��ł��肢�ł��B���x�͌�������łȂ��O����ʊE�[�x�����킹�Ă��肢���܂��B
��܂����낤����
�V�����O���t���肪�Ƃ��������܂��B
�B�e�{���i����0.01�j�Ƃ������Ƃ́A�t���T�C�Y���ʒu�ŗ������q������ʂ̔������炢���߂Ă���ł��ˁB���Ƃ��肻���Ȋ����ł����A�v�������L�p���Ő[�x���[���ł��ˁBF8�܂ōi���50mm���炢�ł������[���Ȃ肻���ł��傤���H
�܂��A�i����0.001�j�ɂ���ƍL�p�Ɩ]���ł̍��͂ǂ̂��炢�ł��傤���H
�����ԍ��F13958413
![]() 0�_
0�_
�M�q���Ē�����
��ʊE�[�x�̈Ⴂ�ɂ��Ă͌��_���o�܂����B[13953724] ������ł��B
�����ʊE�[�x�̈Ⴂ���u�L�p���̌����ʊE�[�x �^ �]�����̌����ʊE�[�x�v�Ƃ��āA�L�p���̔�ʑ̋������u�L�p���̉ߏœ_�����́��{�v�Ƃ��ĎB�e�B�]�����̎B�e�{���́A���̂Ƃ��̍L�p���̎B�e�{���ɍ��킹��B
�����������B�e�ɂ�����
�u��ʑ̋������ߏœ_������ 0.1�{ �� �����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� 1.1�{�v
�u��ʑ̋������ߏœ_������ 0.25�{ �� �����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� 1.3�{�v
�u��ʑ̋������ߏœ_������ 0.5�{ �� �����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� 3�{�v
�u��ʑ̋������ߏœ_������ 0.9�{ �� �����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� 10�{�v
�u��ʑ̋������ߏœ_������ 1.0�{ �� �����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� �� �i���̊W�͖]�������p���t�H�[�J�X�ɂȂ�܂ő����j�v
���ꂪ����ꂽ�@���ł��B
14mm ���x�̒��L�p�ɂȂ�Ɩ@��������Ă��܂��B
�u��ʑ̋������ߏœ_������ ���{�v�́��̕����� 0.1 �ɂȂ����� 0.16 �ɂȂ�����A�܂��A��r����]�����̏œ_�������L�p���̓�{�i28mm�j���x���Ɓ��̕����� 0.17 �Ƃ� 0.23 �Ƃ��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
���������̖@���̕�����u�����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� ���{�v�́��̕�����傫�����Ă����ƋC�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂��i��̓I�ɂ� 1.3 �Ŕ�ʑ̋����̌덷�� 20% ���x�j�B
�܂��A�u�����ʊE�[�x�̈Ⴂ�� ���{�v�́��̕����� 1.1 �������������x�����߂�ƁA������@��������Ă��܂��B
�������Ή������ʑ̋����̓}�N���̈�ɓ����Ă��Ă���̂ŁA���̗̈�ł́u�ߏœ_�����������o���ׂ��ł͂Ȃ��v�ƌ����ׂ��ł��傤�B
�ӂ��Ɂu�B�e�{�����傫���ƁA�œ_�����ɂ������ʊE�[�x�̈Ⴂ���o�Ȃ��Ȃ�v�ł悢�ł��傤�B
���ƁA[13954962] �̎��i�C�j�̉E�����s�v�ł��̂Œ������Ă����܂��B��������
(rz - 1)hn <= (r - 1)zh + (rz - 1)f�@�E�E�E�i�C�j
�܂��ł���Ԃ̎��n�́u���ZF�l�Ɗ��Z�B�e�{�������Ȃ�A�{�P�������v�ł��傤�ˁB
�����P�ɁA�]�����̓{�P���傫���ʂ�̂Łu�{�P�̉掿�i��܂ƃm�C�Y�j�v�̖ʂŗD��Ă���Ƃ��������̂��Ƃł��B
�s���g�ʑO���̃{�P�̑傫�� �� (-1) * �s���g�ʌ���̃{�P�̑傫��
�ł��B
��̓I�ɂ́E�E�E�B
�s���g�ʌ���̃{�P�̑傫���̎���
y = {m * (f / F)} * [mx / {(m + 1)f + mx}]
������ m = f / (s - f) �B
�܂��A x �̓s���g�ʂ� 0 �̊�ɂ��āA�s���g�ʌ���� + �i�v���X�B x > 0 �̂��Ɓj�ł��B
����āA�s���g�ʑO���̃{�P�̑傫���̎���
y = (-1) * {m * (f / F)} * [mx / {(m + 1)f + mx}]
�������A x �̓s���g�ʂ� 0 �̊�ɂ��āA�s���g�ʑO���� - �i�}�C�i�X�B x < 0 �̂��Ɓj�ł��B
�u�O����ʊE�[�x�v��u�O���̃{�P�i�̓��e�j�v���œ_�����ňقȂ邩�H �̍l�@�͂�������ɍl���邱�ƂɂȂ�܂��B
�܂�����Ă܂��A���̌`�Ȃǂ���u����v�ƌ��ʂ͓����ɂȂ�悤�ȁE�E�E�B
�܂�O����ʊE�[�x�͔�ʑ̋����F�ߏœ_�����̔�Ō��܂�A�{�P�̓��e�͓����A�Ƃ������ʂɂȂ�悤�ȁE�E�E�B
�����ԍ��F13958612
![]() 0�_
0�_
�M�q���Ē�����@���v���Ԃ�ł�
�������ނ��薳�������̂ł����@�܂����������ł����̂�
����₨�肢�ł��܂����H
�œ_�����Ŕ�ʊE�[�x�ς�Ȃ��ƌ������ł����@�t���T�C�Y100mmF2.8�ƃt�H�[�T�[�Y50mmF2.8�œ����g���~���O�ŎB�����Ƃ��@��ʊE�[�x�ς�Ȃ��ƌ������Ƃł��傤���H
�����ԍ��F13958788
![]() 0�_
0�_
���ƃ��{�}�� �Q���� ���v���Ԃ�ł��B
�≖�̖����o�����Ƃ����ʂ̃X���b�h�ł͔��ɎQ�l�ɂ����Ē����܂����B
���肪�Ƃ��������܂��B
�u�����g���~���O�ŎB�����Ƃ��v�̈Ӗ����킩��܂���ł������A���ɔ�ʑ̂���ʏ㓯���傫���Ŏʂ�悤�ɎB�����ꍇ�́A�t�H�[�T�[�Y�̕����B�e�{�����������̂œ��R�Ȃ�܂��B
�����ԍ��F13958846
![]() 0�_
0�_
�ł��ԈႦ���B�[���Ȃ�܂��B
�܂����A���ʂɂP���X�g���Ă��܂����I
�����ԍ��F13958849
![]() 0�_
0�_
���݂܂���B
���p�̂��߂ɐV�X���𗧂Ă�̂��x���Ȃ��Ă��܂��܂����B
������Ɉ��z���܂����̂ŁA�����������ӌ�������Ǝv���܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/SortID=13961246/
�F�l��낵�����肢�v���܂��B
�����ԍ��F13961269
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�f�W�^�����J�����v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 0 | 2025/09/08 4:52:06 | |
| 1 | 2025/09/08 8:02:55 | |
| 1 | 2025/09/08 8:05:42 | |
| 0 | 2025/09/07 22:43:20 | |
| 6 | 2025/09/07 11:48:40 | |
| 8 | 2025/09/08 7:42:42 | |
| 0 | 2025/09/07 3:29:59 | |
| 0 | 2025/09/07 0:39:48 | |
| 0 | 2025/09/06 22:21:27 | |
| 2 | 2025/09/07 5:48:53 |
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z��������VPC
-
�yMy�R���N�V�����zAM5�@128gb
-
�yMy�R���N�V�����zU30
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC
-
�y����E�A�h�o�C�X�z�\�Z25����
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j