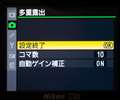D3X �{�f�B
2450����f�t���T�C�YCMOS�Z���T�[/���C�u�r���[/���엦��100%�̃t�@�C���_�[/3.0�^�t�����j�^�[��������f�W�^�����t�J�����B���i�̓I�[�v��
�^�C�v�F���t ��f���F2572����f(����f)/2450��f(�L����f) �B���f�q�F�t���T�C�Y/35.9mm×24mm/CMOS �d�ʁF1220g
![]()

-
- �f�W�^�����J���� -��
- ���t�J���� -��
D3X �{�f�B�j�R��
�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �������F2008�N12��19��
�f�W�^�����J���� > �j�R�� > D3X �{�f�B
D3X�𒆌Âōw�������̂Ńu���O�Ƃ��ɍڂ��������������ǁA�u���O����ĂȂ��̂ł������u���O����ɂ��邱�ƂɌ��߂��B
�ǂ����N�����Ȃ�����A�Ԃ��ʂ�Ȃ����̐^�ő�̎��ɐQ�邩�̂��Ƃ������Ă������Ǝv���B
�܂�100�N�キ�炢�ɊԈႦ�ĒN������Ă��邩���m��Ȃ����ǁI
���肵���͔̂����O���炢�B
�قƂ�ǎC�ꖳ���̔��i��9��8��~�B������90���~�������炵���̂Ŗ�1/10�ɂȂ��Ă��Ƃ������Ƃ��ȁB
���Ă̒��W���J�������g���Ă݂����āA������5���~���炢�̑���̖���D3�������Ǝv���Ă��B�ł�������1,000����f�N���X�͎g�����������ăz���g�ɃI���`���Ƃ����g���Ȃ��B
�i�c�ʒu�ŎB�邱�Ƃ������̂ŁAPC��ʂł͓��{�\���ʼn�ʂ̗��������炸�]�����o�Ă��܂��̂���j
�E�E�E�Ƃ��킯�ŁA2,000����f��D3X���w�������Ƃ�������B
�����ԍ��F24911567
![]() 13�_
13�_
100�N��ǂ��납10���ȓ��ł����I��
D3X�A�ʔ̓X��90����������...
�ŋ߂�D5��D6�Ɣ�ׂ�Ƃ����ԍ��������킯���B
���sD6���܂߂�D�ꌅ�ł͈�ԍ���f�B�܂�24MP�Ȃ̂ō��ł͕��ȉ��̉�f���ł͂������
D3X�AD2Xmode3���g����̂ŋ������肠�肾���ǒe�����̏��Ȃ��̂ƒ��Â����\����...
�Ƃł�12MP��D700�͌����o���o������
�����ԍ��F24911586
![]() 12�_
12�_
���A����100�N�o�����̂��E�E�E�B
100�N�̖��肩��o�܂��Ă���Ă��������Ȃ��B
D700���g���Ă��������������Ȃ��B
�ǂ��}�V���������B
����2,000����f�@��������܂��g���Ă��͂��B
���Ȃ݂�D3�ɂ�F3�̖ʉe������悤�ȋC������B
F3�͂��͂�g�����Ƃ͖������A�i�v�Ɏ��������邾�낤�B
�����悤��D3���A����ɉ����̂��E�E�E�B
�����ԍ��F24911607
![]() 6�_
6�_
D3X�A���������ɐV�i�ōw�����č��ł����L���Ă܂��B
���Ɍ��݂̎g������D850�̃T�u��D800E�̃T�u�Ƃ��������ł����B
D�^�C�v�̃����Y�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ō͒W�̃j�b�R�[���I�ȉ撲�ɂȂ�̂����C�ɓ���BD�ꌅ�Ō�̍���f�@�Ƃ������ƂŁA������Ȃ��܂܍��Ɏ����Ă��܂��B
�����ԍ��F24911624
![]() 4�_
4�_
��X��1���I�͑���
��������d�����Ȃ��p�r��D850��Z 6�����邩�炻�����ŁB
D700��D2Xmode3�̐F���ǂ�����̂ł��̗V�їp�Ƃ��āB���ƃ����[�Y�����J���J�����Čy���ŁA�����͂ނ���D850���D��
D3�Ƃ�D4�̓y���^���̑��`���ǂ��čD��
�q���̍��ȗ��A20�N�ȏ�Ԃ�ɋ≖���悤�ɂȂ��čŋ�F3�A�C���x���Ƃ�FM2�Ƃ��g���悤�ɂȂ������ǁA
�����̑O�AF6�ōs�������Ƃ���܂ōs��������������B
�≖�͂�����������
�����ԍ��F24911633
![]() 2�_
2�_
���[���I�H�\�z�O�Ƀ��X���H
���������āA�ʒm�@�\�Ƃ��H
���肪�Ƃ��������܂��B
���̂Ƃ���{�@�ł̍�Ⴊ�܂����܂薳���̂ŁAD3X�ɑ���z�����J�^���O���ɂ��Ă������Ǝv���I
�����ԍ��F24911638
![]() 4�_
4�_
�������ŃK���X����
2008�N�����̕i�ł������B
���ł��g����̂������ł��ˁB
��ꂽ���ςȂ̂ŁA��ɂ��g�����������B
�܂��A���������Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă�
�f�B�X�v���[�i�Ƃ��ď[���ȑ��݊�������܂��ˁB
�����ԍ��F24911705
![]() 2�_
2�_
�������ŃK���X����
>���[���I�H�\�z�O�Ƀ��X���H
�f�W�^�����J���� > ���ׂā@�Ō��R�~�����C�ɓ���
�o�^���Ă����ƁA�Ђ������ �Ǝv���Ă��肵�Ă������X
�ɃX���̃g�b�v�ɂȂ邵�A���X���t���̂��R��B
���I�ȃu���O������ƌ����Ɨǂ��v��Ȃ��l�B������
�����AD3X�̍��Ƃ��Ă͋K����薳���Ǝv���܂��B
����U�J�e�S���[����ł̓g�b�v�ɏオ�鎖���L��̂ŁA
�{�l���N�����ĂȂ��Ǝv���ăA���o�������A���܂�
�L�v�Ȏ��������܂ܕp�ɂɃ_���_�������Ă�ƋC�ɐG��
�l������Ǝv���܂�����C�����������ǂ����ȂƁB
�قڔ���Ȃ��J�����̃X���b�h������I�ɏオ�邯��
�ǂ��ʐ^������C�ɂȂ�Ȃ����Ńn�[�h���́A�ĊO����
�Ƃ͎v���܂���( �E�ށE)a �撣���ĉ������B
�����ԍ��F24911925
![]() 6�_
6�_
��hattin89����
�}�W�ł����B�䂪�����܂����B
�ȍ~�A���ӂ��܂��B
�����ԍ��F24912129
![]() 0�_
0�_
D3X��4�N��ɔ�������1DX�����C���@�Ɍ���5,000�����x�A����4�N�͎g���|���\��ł��B
2000����f�Ȃ��ł����s���͈����܂���B
�ނ���1200�����x�ɗ}���č����x���K�c�b�Əグ���̂�����Ȃ�~�������炢�B
�����ԍ��F24912166�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���������A����̍w���ɂ��āA�܂Ƃߒ����Ă݂��B
���w���̌o��
�����͍����Ŏ肪�o�Ȃ������J�������A�肪�͂��悤�ɂȂ������A�����Ă݂����Ǝv�����B
����10�N���炢�O���A����Ȋ����Ő̂�500����f�f�W�^�����t�J�����������ɓ��肵�ėV��ł݂����Ƃ��������B����ǂ��f�W�^���J�����Ƃ����͍̂ŏI�I�ɃA�E�g�v�b�g���d�v�B�f�[�^���V���{���ė��p���l���Ⴏ��A���̃J�����͎g��Ȃ��Ȃ�B������A�B�e�s�ׂƂ����͎̂�ԂƋ�J�ƃR�X�g�������B���������B��Ȃ獂�掿�i���Ȃ��Ƃ����p�ɑ���掿�j�ŎB���āA�B�e�̎�Ԃ̌�����肽���Ǝv���B
����ɂ��̌Â��f�W�^���J������1���B�e���邲�ƂɃ������J�[�h�L�^�ɐ��b������A�ƂĂ����p�I�ł͂Ȃ������B���̏�A����~�߃S������1�N�قǂʼn��������ɂ���ăh���h���ɂȂ��Ă��܂��A�G�邱�Ƃ���ł��Ȃ��Ȃ����B
�����č���̘b�ł��邪�AD3�̍w���ɂ͑傢�ɔY�B
���݁A�����̒��ł�1,000����f�J�����͂��łɑޖ������A�Œ�ł�2,000����f���g���Ă���B�m����D3�͍��ł�5���~��Ŏ�ɓ���̂Ŗ��͓I�����A1,000����f�Ƃ����̂��C�ɂ�����B��ɓ���Ă��܂��g��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����ƁB
�������v���p�@�̃��J�ɂ͐G��Ă݂����E�E�E�B
���̂悤�ȓ��X����̎v�l�̖��A�H�蒅�����̂�2,000����f��D3X�B
�uD3��1,000����f�@�v�Ƃ����C���[�W�����������̂ŁAD3X��2,000����f�N���X���Ƃ����̂�Y��Ă���A�H�蒅���܂Ŏ��Ԃ��������Ă��܂����B
D3X�͐V�i���ɖ�90���~���������������̒��ɑ��݂���ꐔ�����Ȃ��悤�ŁA���Âł��o�������Ȃ��B
����Ȓ��ŃI�[�N�V�����Ō��t���ē��D��������������A�V���~��܂ʼn��i���オ��ƕ|�C�Â��ċ��蕉����B�I�����i���m�F����Ɣ�����z�������肷�邪�A���̏�Ō��_���o���ɂ��S�O������z�̓I�[�N�V�����ł͎���o���Â炢�B
���ǂ̂Ƃ���A�l�i�̌Œ肵��9���~��̋ɂ߂Ē��x�̗ǂ��̂����t���A���T�ԃW�b�N���������������ł��w�����ʂ������B�\���o�b�e���[���S�t�����Ă��蔃�������K�v�������ėǂ������B
������
�����ɂƂ��āA����D3X��2,000����f��Ǝ��p�ɂ͑�����̂́A�������Ƀ��C���ƂȂ���̂ł͂Ȃ����߁A���܂�������������Ȃ��Ǝv�����B
���������킯�ŁA���͎g��Ȃ��Ȃ���1,000����f�N���X�̃J���������p���A���ʓI�ɂ��̗��v�����ŃJ�����{�f�B����܂��Ȃ����Ƃ��ł����B
�����Y�ɂ��ẮA�ߋ���Nikon�̈��t���g���Ă����W��AF�����Y�͂R�{����A���߂Ĕ����K�v�����������B�����������Ԏg��Ȃ����������Y�̂��߁A�����Y���ʂɃJ�r��������̂�AF�s���̂��̂��������B�d���Ȃ��̂ŐV�������̂������Ǝv�������̂́A�_�����Ńl�b�g�������Ă݂�Ɠ��Y�����Y�̕�����@���Љ��Ă���A�Ȃ�Ƃ��J�r���|��AF�s�����͉��������B
�Ƃ����킯�ŁA�����D3X�����ɂ�����A���������o���͔������Ă��Ȃ��B
���������J�[�h�̖��
���̃J�����́A���͎g��Ȃ��Ȃ����R���p�N�g�t���b�V���iCF�j�𗘗p����̂ŁA���炽�߂ĕ����ɂ���K���N�^���������Ă݂��Ƃ���A�܂����t�����̂�128MB�BD3X�ɑ������Ă݂�ƁA�u�U�v�ƕ\���ɏo���i14bit RAW�L�^�̏ꍇ�j�B�������ɂU�������B��Ȃ��͍̂���B
�m�����ɂ��ACF�J�[�h�T�C�Y�̃n�[�h�f�B�X�N�u�}�C�N���h���C�u�v�������Ă����͂����ƒT���Ă݂�ƁA����ɂ͂��������A�e�ʂ͂����300MB��B�n�[�h�f�B�X�N�Ȃ̂ɂ��̏��e�ʂɂ͎Q�����B
������V����CF�J�[�h���̂��Ȃ��Ɠ���~�������A�悭�悭�l����ƁA��������PC����CF��ǂݎ�郊�[�_�[�������������ƂɋC���t�����B
���̂܂܂ł�CF�J�[�h�ɉ����ACF���[�_�[��˂Ȃ�Ȃ����A�ǂ����Ȃ��CF�A�_�v�^���Ď莝����SD�J�[�h���g���Ηǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���t�����B���̃A�_�v�^��������AD3X�����̃J�����Ɠ��l��SD�J�[�h�@�Ƃ��ĉ^�p�ł���B
�����ۂ̎g�p
���ۂ�D3X���g���Ă݂�ƁA�\���N�O�̃f�W�^���J�������Ƃ����̂ɁA���ł����h�Ɏ��p�ł���B�������Ƀv���p��������A�������������A�V���b�^�[��������G��X�s�[�h���A���芴�ȂǁA���C���Ŏg���Ă���SONY��7R4�ɗ��Ȃ��B
����ނ���D3X�̂ق����ǂ��Ƃ��낪����B
�܂�AF�\�́B
�~���[���X�J�����̃�7R4�͑��ʈʑ����ł��邪�A�}�ׂ̍��A���Ȃǂ��B�鎞�͔w�i�̂ق��Ƀs���g������������B�V�`���G�[�V�����ɂ���Ă͐�Ɏ�O�Ƀs���g������Ȃ����Ƃ��炠��B������D3X�̂ق��͂������Ɉ��t�̉��҂��������Ĉꔭ�Ŏ�O�̎}�ɃX�p�b�ƃs���g�������B����܂ł̃C���C�������������̂��Ǝv���قǁB
���ꂩ��N�����ԁB
�~���[���X�J�����͂Ƃɂ����X�C�b�`�����Ă���B�e�\�ɂȂ�܂Ő��b�҂������B������D3X�̏ꍇ�A�҂��Ƃ��Ȃ������ɃV���b�^�[�����B
���Q�l
2022�N9�����݂ł̑��ꊴ
���t�I�N����J���AJ-�J�������������������̂�������Ƃ�������B
D3
���얢�m�F�i�F30,000�~
�L�Y�������p�i�F50,000�~
�L�Y���Ȃ����i�F70,000�~
D3S
���얢�m�F�i�F40,000�~
�L�Y�������p�i�F60,000�~
�L�Y���Ȃ����i�F90,000�~
D3X
���얢�m�F�i�F60,000�~
�L�Y�������p�i�F90,000�~
�L�Y���Ȃ����i�F120,000�~
�����ԍ��F24912979
![]() 1�_
1�_
Nikon�̃}�j���A�������Y�͂����ς������Ă�̂ŁA�������D3X�ł��g���Ă݂����Ǝv���Ă���B
����ǂ��A�C�̂�����F3�̃X�N���[�������s���g�̎R�����݂ɂ����悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�Ȃ�Č������A����������ƃX���K���X�I�ȃU���U�������~�����Ƃ������E�E�E�B
�܂����X�}�b�g�ʂŃs���g�����킹��͓̂��ӂł͂Ȃ��̂ŁA�X�v���b�g�`���̋����v���t�������̂��~�����B
�Ƃ͌����Ă��A�����ł͕���}�b�g���������悤�Ȃ̂ŁA�F�X�ƒT�����璆�ؐ��̉��������̂����t�������B���x�����������A�܂��C�������ł�MF�J�����I�ȕ��͋C�������낵�낢�����Ǝv���Ē������Ă݂��B�ςȓ��{��T�C�g�Ȃ̂ŁA�����h�L�h�L���Ă�B
�����ԍ��F24913014
![]() 0�_
0�_
���̋@��ɂ͂Ȃ���������� |
�����Ȃ����̂����B��Ȃ��̂� |
���Ԃ��ĂԂƂ����W���N�X�ő������A�����@�X�^���A�V���[�Y |
��f��������Ⴂ�����Ă���Ȃ��Ƃ��������͂�������D40�g�p |
�����́B
D3X�A������S�N�O���ȁH
�s���t���̃L�^�����̒��Â̒I�ɑ��݊�����p������A�{����D4X���F���悤���Ǝv���Ă���A�������ɗ��������Ă��܂��܂����B
������Nikon�@�̂Ȃ��ŗB�ꉩ�܂Ȃ��ƕ����Ă܂������AISO��400�܂ł����g�����Ƃ͂Ȃ��̂ŁA����ŏ[�����ȂƁB
���G���v���X�`�b�L�[�Ƃ������S���������̂悤�ɃO�j���O�j������D4�ȍ~�̋@��ƈ���āA�K�`�b�Ƃ����d�����H���銴�G�͂܂��ɂƂ������艞�������A�V���b�g���͖�Q���Ƃ����Ă����ǁA���傤�ǃE�H�[�~���O�A�b�v���I��������炢���Ȃƍl���邱�ƂƂ��A���ł���������ɂ��Ă��܂��B
���̍���Nikon�@�́A��f����������Ⴂ�����Ă���Ȃ��Ƃ��������͂�����Ƃ����Ă悭�A���炩�̎���Ŏ�����Ă��܂������̂̍Ăсc�c�Ƃ������������悭�����܂��B
D3���ܘ_�����Ă܂����A�X�ɉ�f�����������炢��D40�����̎�́B
����l����Ƌt��襘H�Ɋׂ�Ƃ��������Ⴖ��n�Ԃ��D200������܂��B
�~���[���X�A���Ƀ\�j�[�͗����オ�肪�x���B
�Ƃ�����Γd�������Ă����炭�̓E���Ƃ��X���Ƃ����킸�A���Ă͗�̓s�s�`���������H�ƕs���ɂ���ꂾ��������A�悤�₭�Ƃ������Ĕz�B
�����łȂ��Ă��\�j�[�@�́A���炭�g��Ȃ��ƃo�b�e���[���J���ɂȂ��ĂĂ����Ƃ��������ɖ��ɗ����Ȃ��B
����D3X�͂Ƃ�����D40�͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���������o�b�e���[�c�ʂ������Ă���x�ł��B
�m���ɒ��ÂŌ������邱�Ƃ͈ȑO���班�Ȃ��A����ł����̂������̉��H
�N�`���b�I�Ƃ����V���b�^�[�������Ƃ��ł����A��ɂ������Ă����Ă��������B
�����ԍ��F24913075�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�j�R���S�ĂŃ\�[�g���Ă�̂�
�p�ɂɖڗ����܂���I
�C���X�^�͂��Ȃ��́H
�����ԍ��F24913117
![]() 1�_
1�_
�����肵��D3X�̃C���[�W�Z���T�[�N���[�j���O�ɂ���
������肵��D3X�̊O�ς͔��i�N���X���������̂́A�e�X�g�B�e���Ă݂�ƁA�C���[�W�Z���T�[���S�~���炯�ŎB�e�Ɏx�Ⴊ�o���Ԃ������B
�Ƃ肠�����u���A�Ő���������Ƃ������ω��������Ȃ��B
Nikon�̃Z���T�[�N���[�j���O�T�[�r�X�̗������m�F����ƁA��3��~����Ƃ̂��ƂŁA��������S�O����B���̋��z���o���̂ł���A�C���[�W�Z���T�[�p�̃N���[�i�[�L�b�g���Ď����ł�����ق��������̂ł͂Ȃ����ƍl�����B
���C�p�[�^�C�v�̂�ƁA�S���_�^�C�v�̂��̂��w���B
���C�p�[�^�C�v�̓t���T�C�Y���̐��@�ō���Ă���A1��@���Ί�������悤�ɂȂ��Ă���B
�~���[���X�J�����̏ꍇ�̓C���[�W�Z���T�[���펞�I�[�v���ɂȂ��Ă���̂ŃN���[�j���O���邽�߂̑���͕K�v�����̂����AD3X�͈��t�̂��߁A�~���[�ƃV���b�^�[�����J���ăC���[�W�Z���T�[���I�[�v���ɂ��鑀�삪�K�v�ɂȂ�B
���j���[��ʂ���u�N���[�j���O�~���[�A�b�v�v��I�Ԃ̂����A�o�b�e���[�d�͂��\���łȂ��ƃO���[�A�E�g������ԂőI�ׂȂ��B���炭�A�N���[�j���O���Ƀo�b�e���[����ĈӐ}�����V���b�^�[���܂鎖�̂�h�����߂��Ǝv����B
��E�E�E�H�Ӑ}�����V���b�^�[���܂�Ƃǂ��Ȃ�H
�C���[�W�Z���T�[���N���[�i�[�_�ł������Ă��鎞�ɃV���b�^�[�����~���ƁA���R�Ȃ���_�ɃV���b�^�[�����Ԃ��邾�낤�B�����悭�Ԃ���ƁA�V���b�^�[���j�����邩���m��Ȃ��B
�҂Ă�A�V���b�^�[���̔j���A�S�����肪����B
�̂̋L�����h���Ă����E�E�E�B
�ȑO�AD600���l�b�g�I�[�N�V�����Ŕ��p�������̂��ƁA���D���肩��u�V���b�^�[�����j�����Ă���v�ƃN���[�������������Ƃ��������B
�u����Ȃ܂����A�����ƃ`�F�b�N�����̂Ɂv�Ǝv���Ȃ����������ԕi���Ă��炢���ׂĂ݂���A�m���ɃV���b�^�[�����ꕔ����ł���A�B�e����ƌ��R��̋O�Ղ��ʂ����B�������O�̃e�X�g�B�e�ł͖��������̂�����A�A�����̖�肩�Ǝv�������Ȃ��A����Ђ˂�Ȃ����Nikon�ɏC���o�����̂��B
���v���AD600�𗎎D�����҂��Z���T�[���N���[�j���O���Ă���r���ŃV���b�^�[���~��Ĕj�����Ă��܂��A���������ĕԕi���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B�����łȂ������Ȕj�����A�����ɋN���邱�Ƃ͍l���ɂ����B����10�N�߂��O�̘b�����A������v���o���Č��ȋC���ɂȂ����B
�b�͖߂邪�AD3X�̃C���[�W�Z���T�[�N���[�j���O�͊ȒP�������B
�Q��ނ̃N���[�i�[�p���悤�Ǝv�����̂����A�ŏ��̃��C�p�[�^�C�v�����ł��Ȃ�S�~����ꂽ�B���������C�p�[�ŃS�~���[�Ɋ�������̂�����Ȃ����̂�����A�S���^�C�v�ł��������Ă��܂����Ƃ��l�������A�قƂ�NjC�t���Ȃ����炢�̃S�~�������̂ō���͂��̂܂܂Ƃ����B
�����ԍ��F24914337
![]() 1�_
1�_
��ppoqq����
���j�R���S�ĂŃ\�[�g���Ă�̂�
���p�ɂɖڗ����܂���I
�}�W�ł����E�E�E�B
�����ԍ��F24914342
![]() 1�_
1�_
D3X��500mm���t���b�N�X�����Y�����ĎB�e���Ă݂��B
���]�������Y�Ȃ̂ŎO�r�K�{�����A���������̃R���p�N�g�T�C�Y�̃��t���b�N�X�����Y�Ȃ̂Ŏ莝���ɒ���B
���̂����Ńt�@�C���_�[���͗h��܂���ŁA�s���g�������Ă邩�ǂ����������Ȃ��B�r���Œ��߂āA�s���{�P�O��̃����O�{�P�ʐ^���B�邱�ƕ��j�]���B
�c�ʒu�ł����肵�ăz�[���f�B���O�ł���̂͂Ȃ��Ȃ��ǂ������B
�u����}�������邽�߂�ISO400�܂ŏグ�����A���̕��摜���e���Ȃ����B
�Ȃ��A���t���b�N�X�����Y�͍\����i�����̉������������₷�����߁j�R���g���X�g���ቺ�������B�d���Ȃ��̂�PC��ŃR���g���X�g���グ�ăV���h�E����߂��B
�����ԍ��F24917340
![]() 0�_
0�_
D700��D600���g���Ă��������玝���Ă������L�p�Y�[�������Y�uSIGMA 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM�v�B
Nikon�̃f�W�^�����t�{�f�B�A��������͂��ׂĎ�����Ă��܂������߁A�{�����Y�̂��Ƃ���������Y��Ă����B
����A����̂��߂ɉ����������͖̂������Ƃ������Ă��Ă��܂��܌��t�����B
12�o�Ƃ������L�p��AF�ł�����̂͑��ɖ����̂ŋM�d�ȑ��݁B
���L�p�����Y�́A�L��Ȍi�F���A���邢�͋����Ƃ�����B�e����̂ɂ͕K�v�Ȃ̂ŁA���������B�e�ł�12mm�ł����g��Ȃ��B���������g��������Ȃ�A�傫�ȃY�[�������Y�ł͂Ȃ�12mm�P�œ_�����Y��������ꂵ���B
�����ԍ��F24917423
![]() 1�_
1�_
�C�̂�����������Ȃ����A����D3X�͔��F�̓R�b�e���n�̂悤�ȋC������B
���Ȃ݂�AF-S Nikkor 24-120mm F3.5-5.6G���g���A�X�g���{�ŏƖ��B
�����ԍ��F24917434
![]() 3�_
3�_
���t�Ȃ̂Ńt�@�C���_�[��`���K�v������A�Ⴂ�ʒu�ŃJ�������\����̂͂Ȃ��Ȃ��炢���̂�����B
�Ⴂ���ɔ�ׂĂ��Ⴊ�ނ̂����ɂȂ����E�E�E�B
�ł����܂��B���Ζ������͑傫���B
���������Ύv���o�������A�B�e���ɎB�e���ʂ�w�ʉt����ʂŊm�F����ƁA�Ȃ��C���[�W�ʂ�̐F���o�ĂȂ��悤�Ɍ����Ă��܂��B����ǂ�����ɋA���Ă���PC��ʂŌ��Ă݂�ƁA�ӊO�ɂ��L���C�ɎB��ĂĔ��q��������B
�����ԍ��F24917438
![]() 3�_
3�_
D3X�������[�g�V���b�^�[�Ŏg�������ȂƎv���Ē��ׂ���AWiFi���t���Ă��Ȃ����ƂɋC�t�����B���ǂ��̃J�����̂悤�Ɏx��Ȃ��g���Ă����̂ŁA�̂̃J�����ł��邱�Ƃ�Y��Ă����B
�ǂ����ԊO���̃��C�����X�����R���������悤�Ȃ̂ŁA�L�����̒��ł���ԃV���v���ȁuMC-30A�v�Ƃ������̂��w���B
���Ȃ݂ɋ����i�uMC-30�v�Ƃ������̂��������炵�����A�R�l�N�^�̒����������ؚ��炵���A�f�����₷���Ƃ̂��ƁB�uMC-30A�v�ʼn��ǂ��ꂽ�Ƃ̂��ƁB
�uMC-30A�v�̉��i�͐V�i��4,500�~�قǁB�@�\�̂��ɍ����ȂƊ������B
��Ɏ����������A���G�͈����Ȃ��B
�Ⴆ��Ȃ�A���j�Ŏg���悤�ȃX�C�b�`�ŁA���쐫�͗ǂ��B���b�N�X�C�b�`���������肵�Ă���A���b�N���O���Ɓu�p�R���v�Ɖ������ăX�C�b�`���߂�B
���g�͂��ƕ��G�ȋ@�\�ɂȂ��Ă���A2���ɂȂ��Ă��邨�����ŃX���[�Y�ȏ㉺�����������Ă���̂��Ɣ[�������B
�����ԍ��F24917674
![]() 2�_
2�_
���X�v���b�g�v���Y���t�@�C���_�[�X�N���[��
�����͐̂�����t�ɂ̓X�v���b�g�v���Y�����邢�̓}�C�N���v���Y�����D��Ŏg���Ă���A�}�b�g�ʂł̃s���g���킹�͋��B
�B��AOLYMPUS OM�V���[�Y�̃}�b�g�ʂ̓U���U�����������ăs���g�̎R���݂͂₷���čD�����������A�����łȂ���D���D��Ń}�b�g�ʂ͎g��Ȃ��B
AF�J�����̎���ɂȂ���Canon EOS630���g���Ă������Ȃǂ������̃X�v���b�g�v���Y���X�N���[�����p�ӂ���Ă����̂ł���Ɍ������Ďg���Ă������̂������B
�Ƃ��낪Nikon D3�n�͊�{�I�Ƀ}�b�g�X�N���[���݂̂����p�ӂ���Ă��炸�A�����ł̓X�v���b�g�v���Y���͗p�ӂ���Ă��Ȃ��B�d���������̂ŁA�����̃V���b�v�T�C�g�uA��iExpress�v����D3�p�̃X�N���[���������B�l�i��4,500�~�B���X���������傤���Ȃ��B�����܂�10���Ԃقǂ��������B
�i��AliExpress�͓��{�ł͌����Ȃ����̂���������̂ł悭���p���Ă���B���ɂ́A����̃J�����p�̃A�Z���u���p�[�c�܂ŏo�Ă���̂ŁA�����������̂͋��炭���{�̃J�������[�J�[�����C�h�C���E�`���C�i�ō�����p�[�c�̗]�蕪������������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƒz������B�܂��Ƃɂ����F�X����B�j
��ʓI�ɃX�v���b�g�v���Y���́A�����W�t�@�C���_�[�̓�d�����v�������v�Ɏ����悤�Ȋ��������A�Â������Y�ł��Ȃ肪�o�Ďg���Ȃ����Ƃ�����B�������Ȃ��疾�邢�����Y�Ŏg���ƃs���g�������Ă邩�����Ă��Ȃ������n�b�L������̂��C�����ǂ��B�������A�X�N���[���̈ʒu�ƃC���[�W�Z���T�[�̈ʒu�������ł���덷���������Ƃ��O��ł͂���B
���ۂɌ�������܂ŁA�{���Ɏg����̂��^�₾�������A���ʂ����Ƃ�����Ɍ덷�͔F�߂��Ȃ������̂ŗǂ������B���������̈��t�Ȃ̂�����A���ケ�̃t�@�C���_�[�X�N���[���ɂ��������D3X���g������ōs�����Ǝv���B
�����ԍ��F24920276
![]() 0�_
0�_
�����x�ʃm�C�Y�̔�r
D3X���掿�I�ɂǂꂭ�炢�̔\�͂������Ă���̂������炩���ߔc�����Ă������ƁA���x�ʂɓ������̂��B�e���A���ꂼ��̃m�C�Y�̏o���ׂĂ݂��B
�����ł́A�u�K���I�o�ŎB�e�������́v�ƁA�u�P�i�A���_�[�I�o�ŎB�e�������̂�PC��łP�i���邭�������́v�̂Q�p�^�[����p�ӂ����B�Ȃ��Ȃ�A�n�C���C�g����Ȃ��悤�ɂ����ăA���_�[�I�o�ŎB��Ƃ������Ƃ͂��蓾�邱�ƁB��������D3X�̔w�ʉt���\������͎B�e���ʂ��ǂ݂ɂ����̂ňӐ}�����A���_�[�I�o�ɂȂ邱�Ƃ��l���APC��ŘI�o�������グ�邱�Ƃ͌����I�ȉ^�p���Ǝv���B
���B�e������
�E�����F�X�g���{�Ɩ�
�E�L�^�����F14bitRAW
�E�����Y�F55mm�}�N��
�ERAW�����\�t�g�FSilkyPix11
�E���x�FISO50�i�g���j�^ISO100�^ISO200�^ISO400�^ISO800�^ISO1600�^ISO3200�i�g���j�^ISO6400�i�g���j�̂W�p�^�[��
�����_��
�摜�{�\���Ō��Ă݂�ƁA��͂�P�i�A���_�[�I�o�ŎB�e����PC��������̂̂ق����A�K���I�o�ŎB�������̂�����m�C�Y�������B
�������玩���Ȃ�Ɍ��_���o���Ƃ���A�K���I�o�ŎB���Ȃ�ISO200�܂ŁAPC���O��Ƃ���Ȃ�ISO100�܂łƂ����̂����x���ȂƎv���B
���Q�l
�Ȃ��A�m�C�Y�̏o���͉��x��RAW�����\�t�g�̎�ނɂ���Ă��ς��̂Ő�ΓI�ȕ]���͂ł��Ȃ����iRAW�����\�t�g�ɂ���Ă�RAW�f�[�^����B�e�J��������ǂݎ���ċ@�킲�Ƃ�NR�̃f�t�H���g�p�����[�^��ς�����̂�����j�A����܂Ŏg���Ă����J���������l�ȃe�X�g�B�e���Ă������Ƃ���A�����B�e�����A�������[�N�t���[�Ō��肳����Ȃ�A���̕]���͉\�ƍl����B
�����ԍ��F24921929
![]() 2�_
2�_
�����d�I�o���p�̃}���`�V���b�g�m�C�Y�ጸ
D3X�̐����������ď��߂āAD3X�ɂ͑��d�I�o�@�\�����邱�Ƃ�m�����B
�u�������v���p�J�����v�Ǝv�������A���ׂĂ݂�v���p�@�����łȂ�Nikon�̈��t�J�����Ƃ����͓̂��R�̂悤�ɑ��d�I�o�ł�����̂炵���B�����͂���܂ŁuD200�v�A�uD700�v�A�uD600�v�Ǝg���Ă��Ă��Ȃ��獡�߂đ��d�I�o�@�\�̑��݂�m��A�傫�ȏՌ���������B
�������f�W�^���摜�ł���APC���ō������H���ł���̂ŃJ�������ő��d�I�o�ł��Ȃ��Ƃ������I�Ȗ��͖����B�ǂ݂̂����d�I�o�Ƃ͌������̂́A���ǂ̂Ƃ��땡�����̉摜���J�������ō������H���Ă��邾���̂��ƁB�܂����C���[�W�Z���T�[��̓d�ׂ�]���������x���I�����ēd�ׂߑ����Ă���킯�ł�����܂��B
���������킯�ł��邩��A���d�I�o���d�˂邱�ƂŖ��邳��~�ς�������A���d�I�o���d�˂Ă��S�̘̂I�o�ʂ��ς��Ȃ��悤�ɂ��s���ǂ��ł���i�Q�C�������j�B
�����l����ƁA���d�I���@�\���g���m�C�Y�ω������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƋC�t�����B
�ŋ߂͑����̃J�����Ń}���`�V���b�g�ɂ���ĉ𑜊����グ����A��f�����̂��̂𑝂₵���肷����̂����邵�ARAW�����\�t�g�ł������J�b�g�����@�\�ɂ�蓯�����Ƃ��ł���BD3X�ł����d�I�o�@�\�œ������Ƃ��ł���Ȃ�A�����x��Ńm�C�Y�����炷���Ƃ��ł������Ɏv���B
�Ȃ����̏ꍇ�A���邳���ώZ����ĘI�o�I�[�o�[�ɂȂ�Ȃ��悤�Q�C���������I���ɂ��Ă����K�v������B
���B�e�̕��@��
D3X�����ȎO�r�ɐݒu���A���FLED�̒����ɂāAISO6400�̊��x�Łu���d�I�������v�E�u���d�I���Q��v�E�u���d�I���T��v�E�u���d�I���X��v�ŎB�����B
��r�p�Ƃ��āAISO100�Łu���d�I�������v�ł��B�e�����B
�i�����d�I���͍ő�10��Z�b�g�ł���悤�����A�Ȃ���9���܂ŎB��Ă�10���ڂ̓V���b�^�[����Ȃ������j
�����ʁ�
���O�̗\�z�ʂ�AISO6400�ł̎B�e�ŁA���d�I�����d�˂閇����������ƃm�C�Y�����邱�Ƃ��m�F�ł����B
ISO100�ő��d�I�������ŎB�e�������̂Ɣ�r���Ă����F�Ȃ��قǂ������B
�������A�O�r�ɃZ�b�g���Ď��Ԃ������đ��d�I�������邭�炢�Ȃ�AISO100�Œ����ԘI�����Ă��������炢�̎�ԂȂ̂ŁA���̃����b�g���������Ȃ��B
�����ԍ��F24924876
![]() 0�_
0�_
���~���[�A�b�v�@�\�ɂ���
D3X�ɂ́A�h���C�u���[�h�̈�Ƃ��ă~���[�A�b�v�@�\���ݒ肳��Ă���B
��ʓI�ɁA���t�J�����ł̓~���[�㏸���̐U���ɂ���Ĕ����ȃu���������N�������Ƃ��m���Ă���B���ɒ��]���B�e����}�N���B�e���Ȃǂ̊g�嗦�̑傫���B�e�ł͂��̉e���������B���̂��߃f���P�[�g�ȎB�e�ł̓~���[�����炩���ߏ㏸�����Ă����ĕʓr�V���b�^�[���Ƃ����A������u�~���[�A�b�v�v���K�v�ƂȂ�B
�̂̃J�����ł̓��J�j�J���ȃ����N�@�\��X�v�����O�`���[�W�̓s����A�~���[�A�b�v���邽�߂ɋ�V���b�^�[���P�x��K�v��������̂�A�~���[�A�b�v���샌�o�[���d�������肷��J���������������A���݂ł̓~���[�̓��[�^�[�ɂ�铮��Ȃ̂ŁA�傫�Ȑ����X�C�b�`��œ��삷��B
���āAD3X�ɂ̓~���[�o�����T�[�Ƃ����V���b�N�z���@�\�����邱�Ƃ���A�~���[�A�b�v�̕K�v���Ȃǂ���̂��^�₾�����B�����ŁAD3X�Ń~���[�A�b�v�̗L�薳���łǂꂭ�炢�ς��̂���m���Ă��������Ǝv�����B
���Ȃ݂�D3X�̃~���[�A�b�v�@�\�͓Ɠ��ŁA�P�x�ڂ̃V���b�^�[�{�^�������Ń~���[�A�b�v��ԂƂȂ�A�Q�x�ڂ̉����ŃV���b�^�[�����B�Ƃ��낪�V���b�^�[���ꂽ��A��U�~���[�����A���Ă��܂��B�܂�A�~���[�͂����Əオ�����܂܌Œ肳���킯�ł͂Ȃ��B�����̓~���[���オ����ςȂ��ŌŒ肳���F3�ȂǂƂ͈قȂ�Ƃ���ŁA�����Y��ʂ����܂œ��荞�ސ̂̋�����Y�Ȃǂ����邽�߂̋@�\�ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
���B�e�i���̂P�j��
�������t�J�����p�Ɏg���Ă����K�b�V�������O�r��p���āA���t���b�N�X���]�������Y������D3X�����S�Œ肵�ĎB���Ă݂��Ƃ���A�~���[�A�b�v�̗L�薳���ŗL�ӂȍ��͔F�߂��Ȃ������B�V���b�^�[�X�s�[�h��1/60�b����1�b�܂ŕς��Ă݂�����������A�Ⴂ���S�����������B
���̂��߂����ł͎ʐ^���f�ڂ��Ȃ��B
���B�e�i���̂Q�j��
�����ɁA�~���[���X�J�������炢�Ɏg���悤�Ȋ��ƃR���p�N�g�ȎO�r��D3X���ڂ��ĎB���Ă݂��BD3X�Ɏg���ɂ͏����A���o�����X���Ƃ������������A�e���̃l�W�͂���������߂��Ă���A���ʂȂ�u������������Ƃ͎v���Ȃ��B
�Ƃ��낪���ۂɎB�e�����Ƃ���A�~���[�A�b�v�B�e�ł̓u�����F�߂��Ȃ��������̂́A�ʏ�̎B�e�ł̓u��������ꂽ�B�R��قǎ��������������ʁB
�V���b�^�[�X�s�[�h��1/50�b�ƒx�߂ł͂��邪�A�~���[�A�b�v�������̂��u���Ă��Ȃ��̂�����A�u���̌����̓~���[����Ƃ����̂�������B���̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�Ƃ������Ƃ́A�~���[�o�����T�[�ł̓u����}�~�ł��Ă��Ȃ��悤���B
����ɂ��āA���߂�D3X�̃J�^���O�ɍڂ��Ă���~���[�o�����T�[�����Ă݂�ƁA�~���[���~���̃V���b�N�͂�����u�j���[�g���̂�肩���i�q���Œ݂邳�ꂽ���������J�`�J�`�Ԃ���I���`���j�v�̌����Ń~���[���̉^���G�l���M�[�������Ă���炵���B����ɑ��A�~���[�㏸���̒��ˏオ��V���b�N�z���@�\�̓����g�v���[�������̂悤���B�Ƃ������Ƃ́A�~���[�o�����T�[�ɂ̓u���}�~���ʂ͖����Ƃ������ƂɂȂ�B�����܂ł��o�����T�[�̖�ڂƂ����̂́A�~���[���~���̃o�^����}�����邱�Ƃɂ����肵���t�@�C���_�[���ƍ����A�ʂ̎����ɂ���Ǝv����B
�����_��
�~���[�A�b�v�Ɋ��҂�����̂Ƃ��ẮA�u���܂�K�b�V���Ƃ����O�r���g���Ȃ��V�[���ł̃u���}�~�v�Ƃ������ƂɂȂ낤���B
���Ȃ��Ƃ��X�^�W�I�B�e�Ŏg���悤�Ȋ��ȎO�r�ŎB�e����Ȃ牽���S�z�������ʂɎB��Ηǂ����A�t�B�[���h�Ōi�F�Ȃǂ��B�e����ۂɎ����^�щ\�Ȍy�ʎO�r�Ńx�X�g�ȕ`�ʂ���������A�~���[�A�b�v�͑�ϗL�����Ǝv����B
���ꂩ��o�����Ƃ��āA�~���[����ɂ��u���Ƃ����̂̓V���b�^�[�X�s�[�h�����r���[�ɒx���Əo�₷���悤�Ɏv���B�܂�A1/2�b�ȂǂƏ\���ɒx����A�I�����Ƀ~���[����̃u�������܂邽�߁A�~���[�A�b�v�����Ƃ��e���͏������Ȃ�B
�܂��A���]�������Y���g���ۂɎO�r�����g�p�����J�����{�̂��O�r�ɐݒu�����ق����d�S�����ėǂ��ꍇ������B�J�����Ƃ����̂́A�d�S�����肵�Ă���ƃO���O�����ău���₷�����́B�d�S�����Ă���ƈ�����ɗ͂�������̂Ńu���ɂ����Ȃ�B������܂�ɋɒ[�ȕ�͋t���ʁB
���Q�l��
���Ȃ݂Ƀ~���[���X���J�����̏ꍇ�͕����ʂ�~���[�����݂��Ȃ��̂ŁA���t�J�����̃~���[�A�b�v�B�e�Ɏ��Ă���Ǝv�����������A���ۂ͈Ⴄ�B
�~���[���X�J�����̃V���b�^�[�̓���v���Z�X�Ƃ��Ă͎��̒ʂ�B
�@�V���b�^�[�����C�u�r���[��~
�A�V���b�^�[���J���ĘI���J�n
�B�V���b�^�[����ĘI���I��
�C�V���b�^�[���J���ă��C�u�r���[�ĊJ
�E�E�E�ƁA�~���[���X�J�����ł̓V���b�^�[�J���Q�����s���邽�߁A���������ƂP�����ڂ̃V���b�^�[�U�����e������\�����L�蓾��B
���̂��߃~���[���X�J�����ł́u�d�q�斋�i�����܂��j�V���b�^�[�v�ƌĂ��@�\������A���̋@�\���g���Ƈ@�A�̃v���Z�X���d�q�I�ɍs���Ď��ۂ̃V���b�^�[�J���P�����ōςށB���������Ӗ��ɂ����ẮA�~���[���X���J�����ł͓d�q�斋�V���b�^�[�@�\���~���[�A�b�v�B�e�ɑ�������Ƃ������Ȃ����Ȃ��B
�����ԍ��F24929377
![]() 5�_
5�_
��AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
���߂Ĉ��t�J�����������A�ŏ��̃����Y�͈�Ԉ���50mmF1.8�����B
����P�{�������������Ă��Ȃ��̂ŁA���݂̂悤�ɂǂ̃����Y���g�������Ɩ������Ƃ��Ȃ��B�l�Ԃ̎���ɋ߂��ƌ����Ă�������A�����s���R�������邱�ƂȂ��A�������̂܂܂��B���Ă����B
����AD3X����肵�ċv���Ԃ�Ɉ��t�J��������ɂ����킯�����A���߂Ĉ��t�J��������ɂ������̎v�����h���Ă����B���ЂƂ�50mmF1.8�����Ďg�������Ǝv�������̂́A���X�����Ă���AF50mmF1.8�͋v���Ԃ�Ɍ���Ǝc�O�Ȃ���J�r�Ă����B
�܂��J�r�Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A�����ۂ��O�ς̃����Y��D3X�����ł͂Ȃ����A���߂ăN���V�b�N�ȊO�ς̍ŐV�^AF50mmF1.8����肵���B
�����͂���܂ōL�p�h���������߁A���ꂩ��50mm�����Y���ǂ̂悤�Ɏg�����������Ă������A���S�ɖ߂��Č������̂܂܂��B�邱�Ƃɂ����B
��������ĎB���Ă��������A�N���}�̎ʐ^���C�����悭�B��邱�ƂɋC���t�����B
���������A���߂�50mm�����Y���g��������̓X�[�p�[�J�[�̎��ゾ�����B�c�ɂł͂܂����Ԃ�ڂɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��������A�����̈��t�J�����ŎB��̂����������Ȃ��E�E�E�Ɖ��������v�����B
���̂������̃����Y�������āA�X�[�p�[�J�[��W�����Ă���Ƃ���ɍs�����Ƃɂ��悤�B
�����ԍ��F24929517
![]() 2�_
2�_
���t�H�[�J�V���O�X�N���[���̈ʒu������
����������A�t�H�[�J�V���O�X�N���[���𒆍����X�v���b�g�v���Y���Ɍ�������MF�ł����K�Ɏg����悤�ɂ������B���̍ہA���Ƀs���g���x�������悤�ɂ͌����Ȃ������B
�Ƃ��낪���߂�50mmf1.8�����Y�ɂĔ�ʊE�[�x�̂��������J��������MF�B�e�����Ă݂��Ƃ���A�ǂ����s���g�������ĂȂ��B����AF�ŎB�e�������͖̂�薳�������Ă���B
�܂�AAF�ō��ł�����Ԃł̓X�N���[����ł͔����Ƀ{�P�Č�����̂ł���BAF�ō��ł�����Ԃ���ߋ������ɃY�����ƃX�N���[����ł͍����Č�����B
���Ƃ���A�X�N���[���̃s���g�ʒu�����������K�v������B
�E�F�u����T���ƁA�T�[�h�p�[�e�B�[���X�N���[�������������Ⴊ�ڂ��Ă���A����ɂ��X�N���[���l�ӂ𐓏グ���邽�߂ɔ����g���n���邱�Ƃ�����Ă����B
�����������悤�ɂ�낤���B
����ǂ��X�N���[���̈ʒu���ǂ��瑤�ɃY���Ă���̂��������I�ɕ�����ɂ����B
�ǂ�����Ă����������_�ɂȂ����̂��A���ƂȂ��Ă͎v���o���Ȃ����A�Ƃɂ����X�N���[���������Ƃ������_�Ɏ������B�܂�A���グ����̂ł͂Ȃ��A�X�N���[�������Ƃ������Ƃ��B
���炭�l�ӂ���邱�ƂŁA�X�N���[����ێ����Ă���g�ɐڂ��镔�����[���Ȃ�̂ł͂Ȃ����ƍl�����B
�����ȃX�N���[�������̂͗E�C���K�v���������A���Ȃ���Ύg���Ȃ��̂ł����邵���Ȃ��B�������ǂ�����ċψ�ɍׂ���邱�Ƃ��ł���̂��낤���H
�����ŁA�J�b�^�[�̐n�𗧂Ăč��E�ɂ������č�邱�Ƃɂ����B��������ΐn���[���H�����ނ��Ƃ��Ȃ��J���i�̂悤�ɍ���Ă������Ƃ��ł���͂��B
�T�d�ɍ���ăJ�����ɑ������Ă݂��Ƃ���A���Ƀs���g�ʂ��ς�����l�q�͖����B
�Ȃ̂ŁA�����悤�ɂQ�`�R��قǍ���Ċm�F���Ă��J��Ԃ����B�������S���ς��Ȃ��B
�����܂ł���Ƃ��������ȃX�N���[���Ȃǂƍl���邱�Ƃ��Ȃ��A�Ƃɂ������܂������B���[��A������Ɖ��P�����悤�ȁA���ĂȂ��悤�ȁH
����Ȃɍ���Ă��ω��������Ƃ����̂́A�Q�̉\��������̂ł͂Ȃ����B
(1)�X�N���[���̈ʒu���߂͎l�ӂł͂Ȃ��ʑS�̂��v���Y���ꕔ�ɓ����邱�ƂŎ������Ă���H
(2)�܂��l�ӂ̍�镝�����������ŁA�������������L����������珉�߂ĕω��������H
����(1)�Ȃ�A���������Ă����_�Ƃ������ƂɂȂ�B
�������A�X�v���b�g�v���Y���Ƃ����̂̓}�b�g�ʂ��班���˂��o�Ă��镔��������A�������v���Y���ꕔ�ɓ������ĕ����Ă���Ƃ������Ƃ�z������ƁA�s���g�ʂ��Y���Ă��邱�Ƃ������I�ɐ����ł��Ă��܂��B
���������܂ŗ������邵���Ȃ��B�������ɖ߂�Ȃ��B
�Ƃ����킯�ŁA���ނ����ɍ���Ă������Ƃ���A����|�C���g����s���g�ʂ������o���A���J��Ԃ����Ƃ���A�悤�₭�s���g�ʂ���v�����悤�Ɏv���B
���������E�E�E�B
�����ԍ��F24932772
![]() 1�_
1�_
�������[�g�R�[�h�uMC-30�v�ƁuMC-30A�v�̔�r
����A�����R���V���b�^�[�uMC-30A�v���w�������̂����A�ʌ��̒T���������邽�߂Ɏ����̃K���N�^���������Ă����Ƃ���A�Ȃ�ƁuMC-30A�v�̋����i�uMC-30�v���o�Ă����B
�����ł͑S���L���ɖ����A�u�Ȃ�����Ȃ��̂��H�v�ƌ˘f�������A���炭D700�����L���Ă������Ɏg���Ă����̂ł͂Ȃ����Ƒz������B�������������������Ă����4,500�~���x�o����K�v�Ȃǖ��������B�N�͎�肽���Ȃ����̂��E�E�E�B
����A�ǂ����Ȃ�ƁuMC-30A�v�ƁuMC-30�v�̔�r�����Ă݂��B
���Ȃ݂ɁA���[�h���tF3�Ŏg���Ă����uMC-12B�v������̂ł���������œo�ꂳ���Ă݂邱�Ƃɂ���B
��ׂĂ݂�ƁA�����̃����R���͑��암�����ʂ̃p�[�c�̂悤�Ɍ�����B�{�^����������������b�N�̊��G�Ȃǂ͑S������B���炭�A�J�����Ɛڑ�������R�l�N�^���Ⴄ�����Ȃ̂��낤�B
�R�l�N�^�̃s�����ɂ��āA�uMC-30A�v�ƁuMC-30�v��10�s���A�uMC-12B�v�͂Q�s���B
�uMC-30�v�ł́A�R�l�N�^�̌�����������Â炭�A�����ɂ͏��X��Ԏ��B���������Ƃ�������ǂ����̂��uMC-30A�v�ŁA�R�l�N�^�̈ʒu�����킹��w�W������A��Ԏ�邱�Ƃ͂Ȃ��B
�����ԍ��F24936966
![]() 0�_
0�_
�{���A�䕗15�����ߕt�����AD3X�̃w�r�[�f���[�e�B�[��������ɂȂ邾�낤�Ƃ������҂������āA�q�K���o�i�ŗL���Ȏ��ɍs���Ă݂��B
�������J�̂������A�|��Ă���Ԃ������������̂́A����ł�30���{������̂ŃL���C�ɍ炢�Ă�����̂�I�Ԃ��Ƃ��ł����B
�����ԍ��F24938279
![]() 0�_
0�_
34���o�x��Ă��܂������A
�����ŃK���X����
> �Ƃ��낪���߂�50mmf1.8�����Y�ɂĔ�ʊE�[�x�̂��������J��������MF�B�e�����Ă݂�
> �Ƃ���A�ǂ����s���g�������ĂȂ��B����AF�ŎB�e�������͖̂�薳�������Ă���B
> �܂�AAF�ō��ł�����Ԃł̓X�N���[����ł͔����Ƀ{�P�Č�����̂ł���B
> AF�ō��ł�����Ԃ���ߋ������ɃY�����ƃX�N���[����ł͍����Č�����B
> ���Ƃ���A�X�N���[���̃s���g�ʒu�����������K�v������B
���Ƃ���A�����ŃK���X����̎��͂ƁA���x��̒����������Ă��Ȃ̂�
���x��������ɒ�������K�v������B
�����ŃK���X����̎��͂ƁA���x��̒����������Ă��Ȃ��ɂ��ւ�炸
�X�N���[�������͎̂ד��B
�f�W�^�����t�̃t�H�[�J�V���O�X�N���[����
���邭���邽�߂ɁA�U�����������ߐ��̕��������̂�
���x����������Ȃ��ƁA�}�j���A���t�H�[�J�X���ł��Ȃ��B
���ɖ��邢�����Y�������Ȃ�B
�����̐l�͓���B
���K�l�ŗ�����������A���x������������
�t�@�C���_�̌����ڂ̃t�H�[�J�X�ʒu��
���ۂ̎ʂ�����킹��K�v��������B
�ƂĂ��ʓ|�������B
�Ⴆ�Ă����Ȃ�A�o�ዾ�Ɠ����B
�l���`������̑o�ዾ�́A�������́i���x�j�̐l�łȂ�����
�����ڕW��������̂ɁA�t�H�[�J�X�������K�v������B
�l�̖ڂ̎��́{�o�ዾ�S�̂��A��̌��w�n�����炾�B
���̂��Ƃ͋≖���ォ��̏펯�B
����䂦�A�S�ʃ}�b�g�X�N���[�����������B
�≖�@�̑S�ʃ}�b�g�X�N���[���͎U���������ɋ���
�{�P�̑傫���������ڒʂ�Ɏʂ�B
���̑���A�t�@�C���_�����ɈÂ��B
�����ԍ��F24959103
![]() 1�_
1�_
��Giftszunge����
�������݂��肪�Ƃ��������܂��B
���w�E�̖��ɂ��Ăł����A�܂����ɁA�����_�Ŗ�肪�������Ă���Ƃ����_���d�v�ł��B
�������̗v�������ł���Ȃ�A�ד����ǂ����Ɋւ�炸��肪��������͂�������܂���B
���āA������������Ă��邩�Ǝv���܂����A�t�@�C���_�[�̃s���g�̌�����ɂ���2�̈Ӗ�������܂��B������čl���˂Ȃ�܂���B
�@�t�@�C���_�[�̃��[�y�̎��x�̖��
�A���e�ʁi�X�N���[���j�̈ʒu�̖��
���̏ꍇ�A�u�ǂ�����Ă��s���g���n�b�L�������Ȃ��̂��v�A���邢�́u�s���g�̃n�b�L��������ʒu���Y���Ă���̂��v�Ƃ����Ⴂ���A���̖��̊̂ł��B
�܂��l���Ă݂܂��傤�B
�J�����̌�����P�������Č����ƁA�����Y��ʂ��������X���K���X�ʂɓ��e�����āA���̑�����Ō���Ƃ����`�ɂȂ�܂��B�唻�J�����Ȃ͂܂��ɂ���ł��B�t�B�����̈ʒu�ɃX���K���X�����ē��e�������Ȃ���s���g�����킹�A�s���g���������瓯���ꏊ�Ƀt�B�����z���_�[�����ĎB�e���܂��B
���������͌����Ă��A��Ō��ăs���g�f����ɂ̓��[�y���g���Ċg�債�Ȃ��Ɠ���ł��B�����듊�e���̓t�B�����Ɏʂ�傫���Ɠ����Ȃ̂Ŕ�r�I�������A�X���K���X�Ƀ��[�y�ĂĒ��ዾ�̂悤�Ƀs���g�������Ă��邩�ǂ���������킯�ł��B���R�A���[�y�̎��x�������Ă��Ȃ��ƃs���g�������Č����܂���B
���t�̏ꍇ�������ŁA���[�y�̓J�����ɓ�������Ă��܂��B���ꂪ�t�@�C���_�[���w�n�ƌĂ�镔���ł��B�̂̓t�@�C���_�[�������ł�����t�J���������������̂ŗ���Ńt�@�C���_�[�X�N���[��������@�������܂������i�E�G�X�g���x���t�@�C���_�[�Ȃǁj�A���̓t�@�C���_�[�����ł��Ȃ����̂����ʂȂ̂ŁA�C���[�W���ɂ��������m��܂���B
������ɂ���A�����Ŏ��x�Ƃ����̂̓��[�y�̖��ƂȂ�܂��B
���R�Ȃ��烋�[�y�̎��x�������Ă��Ȃ��ƁA�g�債�Č��������̓n�b�L�������܂���B�ǂ�Ȃɓ��e�����n�b�L�����Ă��Ă��A������g�傷�郋�[�y�������Ă��Ȃ���n�b�L�������Ȃ��킯�ł��B
�����A���[�y�̎��x�������Ă��Ȃ��̂��A����Ƃ����e���̃s���g�ʂ̂ق��������Ă��Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��Ƃ��܂��B�ǂ�����Ε�����ł��傤���B
����́A�����Y�̃s���g�����ăs���g�������Č�����1�_������A���x�͍����Ă���ƌ����܂��B�t�ɁA�ǂ�ȂɃ����Y�̃s���g�����Ă��n�b�L��������_���ǂ��ɂ������̂ł���A���[�y�̎��x�̖��ƌ������ƂɂȂ�܂��B
���⑫
�Ƃ���ō���A�X�v���b�g�v���Y�������v���g���Ă��܂��B����̓s���g���{�P�Č����邩�ǂ����Ƃ����Ƃ���Ńs���g�����킹��̂ł͂Ȃ��A���̏㉺�̃Y��������ăs���g�����킹��킯�ł��B
�ɒ[�Ȃ��Ƃ������ƁA���[�y�̎��x�����킸��ł̓n�b�L�������Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A�X�v���b�g�v���Y�������v�ɂăY���Č����Ă��Ȃ���s���g�͍����Ă���Ƃ������f���ł��܂��B
�����œY�t�摜�����Ă��������B
�iA�j��̒i�����x�������Ă���ꍇ�̃X�N���[���̌������A�����ĉ��̒i�����x�������Ă��Ȃ��ꍇ�̃X�N���[���̌������ƂȂ�܂��B
�iB�j�����s���g�������Ă���ꍇ�̃X�N���[���̌������A�����ĉE���s���g�������Ă��Ȃ��ꍇ�̃X�N���[���̌������ƂȂ�܂��B
�X�v���b�g�v���Y�������v�ł̓{�P�������̂ł͂Ȃ��A�~���̑��̃Y��������킯�ł�����A�������x�������ĂȂ��iB-1�j�̏ꍇ�ł��A�X�v���b�g�v���Y�������v�̑��̃Y�����Ȃ��ƕ�����̂ł���s���g�����킹�邱�Ƃ��ł��܂��B
�����ԍ��F24959361
![]() 0�_
0�_
�����ŃK���X����
��ϐ\����܂���B
���Ⴂ���Ă��܂����B
�����X�N���[�����_���ŁA�������X�N���[�����_���������B
������A�������X�N���[��������Ă݂��A�ƁB
�����ł͂܂��������Ȃ��̂ł���ˁH
��ώ����\���グ�܂����B
���l�ѐ\���グ�܂��B
�l�����w���̍��A��y��OM-1N, OM-2N�ɂ��������
���̌�AOM-2SP, OM-3, ���[�^�h���C�u2, T32, T8,
50mm F2 MACRO, 90mm F2 MACRO�����Q�b�g���Ă܂����B
ZOOM��Tokina, Sigma�B
�t�H�[�J�V���O�X�N���[�����������p������
�قڑS�ăQ�b�g���Ă܂����B
�S�ʃ}�b�g�����}�b�g�́A�W���̃}�C�N���X�v���b�g�v���Y���}�b�g��
�}�b�g�ʂ����͂邩�ɈÂ������ł��˂��B
���̑���A�g�U�������Q�ł����B
�����ԍ��F24959888
![]() 1�_
1�_
��Giftszunge����
���������A������Ƃ��ĉ����ł��B
�����ł��A�����X�N���[���ł͖��͂���܂���ł����B�������X�N���[���ɖ�肪����܂����B
�Ȃ��������X�N���[���̑f���ɂ��Ăł����ANikonD3�Ȃǂ̃��A�ȋ@��ɑΉ������Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���ꂾ���̂��߂ɃX�N���[�����ꂩ�琻������Ƃ͍l���ɂ����A���炭�����̃X�N���[���i�����������烁�[�J�[���j���x�[�X�ɘg�T�C�Y���H���Ă��邾���ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă��܂��B��������A�P��ނ̃X�N���[�����d�����Α��@��ɑΉ��������i�����邱�ƂɂȂ�܂�����B
���������_����A��p�i�Ɣ�ׂĔ����ȈႢ��������̂����m��܂���B������ɂ���A����̃s���g�ʂ̃Y���͖{���ɋ͂��Ȃ��̂ŁA�}�b�g�ʂł͂قƂ�LjႢ�������炸�A�X�v���b�g�v���Y���ł͔����ɃY���Ă����Ԃł����B�܂�AF�Ŕ��f�������œ_��MF�Ŕ��f�������œ_���ق�̋͂��ɃY�����������킯�ł��B
�I�����p�XOM�ꌅ�@�͊m����MF���₷�������ł��ˁB���^�{�f�B�Ȃ̂œo�R�Ȃǂɂ͏d�܂����B
�I�����p�X�͓���OM-4Ti�̃}���`�X�|�b�g�������D�G�ŁA����܂ł͒P�̘I�o�v�ł����ł��Ȃ������I�o���Z���A�t�@�C���_�[���̃h�b�g�X�P�[���ɂ���ēǂݎ���悤�ɂȂ����͉̂���I�ł����B���S�f�W�^���ڍs���钼�O�܂Ŏg���Ă܂����B
���݂��������E�������L���Ă����悤�ł��ˁi�j�B
�����ԍ��F24960935
![]() 0�_
0�_
���L�͎����I�����i���Y�^�j�B
�����t�`���̃s���g�Ƃ�
���t�`���ł́A�����Y������������͂R�̌o�H�ɕ������B
�@�B���p�C���[�W�Z���T�[�Ɍ������o�H
�A�t�@�C���_�[�Ɍ������o�H�i�~���[�o�R�j
�B�ʑ���AF�Z���T�[�Ɍ������o�H�i�T�u�~���[�o�R�j
�����R�́A�����Y����̋����������łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ǂꂩ�P�ł��������Y���Ă���ΐ������s���g�����킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
����ɑ��A�~���[���X�J�����ł́A�B���p�C���[�W�Z���T�[���R�̖�ڂ����˂Ă��邽�߁A�����I�ɃY�����������邱�Ƃ͂Ȃ��B�~���[���X�J�����̃s���g���x�������ƌ�����̂͂��̂��Ƃɂ��B
�����e���Ƌ��ɂ���
���e���Ƃ́A�����Y����̌��𔒂����Ȃǂɓ��e�������̂��ƂŁA���̑������e�ʂɌ������郌���Y�̃s���g�ʒu�͂P�_�Ɋm��ł���B
���Ƃ́A�����Y����̌���r���œ��e���邱�ƂȂ���ɓ����A�Ԗ��ʂŌ������������̂��Ƃł���B�S�̂̌��w�n�̈ꕔ�Ƃ��Ċ�̃����Y���܂܂�邽�߁A��̃s���g�����@�\�ɂ���Ă�����x�͈̔͂ł̓s���g�������Č�����B�܂�A�����ŏ��̂����͑����s���g���{�P�Č����Ă����Ƃ��Ă��A���̏ꍇ�A�撣���Č���s���g�������Č����Ă��܂���������B����͂܂�A�����Y�̃s���g�ʒu���P�_�Ɍ��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B�ł��邩��A�J�����Ƃ��Ẵs���g�����킹��ɂ́A��������X���K���X��̃t�H�[�J�V���O�X�N���[���ɓ��e���������Ńs���g���m�F����K�v������B
�������Ȃ���A�t�H�[�J�V���O�X�N���[���Ɏg���Ă���X���K���X��̃}�b�g�ʂ͌����U�������邽�߁A�t�@�C���_�[�����Â��Ȃ�Ƃ������_������B�U�����������W�߂邽�߂ɂ̓R���f���T�[�����Y���g���̂���ʓI�����A�J�������R���p�N�g�ɂ����Q�ɂȂ邽�߁A�y���^�v���Y���̉��ʂ������Y��ɂ��ăR���f���T�[�����Y�̖��������˂��@������邵�A�ŋ߂łׂ͍����t���l�������Y���X�N���[�����Ζʂɑ��`���A�X�N���[���P�̂ŏW��������̂���ʓI�B
�܂��~�m���^�̃A�L���[�g�}�b�g��L���m���̃��[�U�[�}�b�g�ł́A�X���K���X��̃}�b�g�ʂ����炩�Ȃ��̂Ƃ��ďW���������߂ăt�@�C���_�[���𖾂邭�������̂����邪�A����͌���������ƃ}�C�N���v���Y�����ׂ����������̂ɋ߂��A�{�P�̍Č����ɖ�肪��������A�����Y�̏œ_�����ɂ�錩�����̈Ⴂ���������肷��B
�Ȃ��A�j�R��F�V���[�Y�ł́A�J��F�l�ɉ������}�C�N���v���Y���t�@�C���_�[�X�N���[��������ޗp�ӂ���Ă����B���ہA�~�X�}�b�`�̃}�C�N���v���Y�����g���ƁA�t�@�C���_�[�����M���M�����ăs���g���킹���ł��Ȃ��Ȃ�B����̓}�C�N���v���Y���̊p�x�̈Ⴂ�ɂ��A�������O��Ċ�ɓ͂��Ȃ��Ȃ邽�߂ł���B�܂�A�t�@�C���_�[���𖾂邭����Ƃ������Ƃ́A���Ɍ�����������̕����ɏW��������Ƃ������Ƃł���A���̏W��������ꏊ����Ⴊ�O��Ă��܂��t�Ɍ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƂɂȂ�B���̓_�A�X���K���X��̃t�@�C���_�[�X�N���[���́A�܂�ׂ�Ȃ������U�������邽�߁A�Â��Ƃ����f�����b�g�͂�����̂́A�������ɕω������܂�Ȃ��B
���̘b�ɖ߂邪�A�ߋ��ɂ͋��̃t�@�C���_�[�������t�����݂����B
�����̓t�@�C���_�[�����Â��Ȃ邱�Ƃ����������߂ŁA���ド�C�J�t���b�N�X��t�H�J�t���b�N�X�Ȃǂ͗L���ł���B���Ƀt�H�J�t���b�N�X�ł̓n�[�t�~���[���Q��ʉ߂�����\���̂��߁A�t�@�C���_�[�̌��ʂ�1/4�ƂȂ��Ă��܂��A���Ƃ�����Ȃ������Ƃ����������B���̘b�ɂ��ẮA�N���V�b�N�J�������No.9�u35mm���t�J�����v�ɏڂ���������Ă���B
�܂�NikonF3�p�t�H�[�J�V���O�X�N���[���ł��A����x�̓V�̎B�e�p�Ƃ��Ă̋��X�N���[���i�����ɂ̓X�N���[���Ƃ͌����Ȃ����j���p�ӂ���Ă����B������͊�����E�ɐU�������A�����̏\�������Y���Ȃ����ǂ����Ńs���g���m�F��������ł���B
�ߔN�ɂȂ��ăf�W�^���J�����ł��AOLYMPUS CAMEDIA C-1400L�̓����Y�Œ莮���t�Ȃ����AF�O��̂��ߋ��Ƃ��Ă���A�t�@�C���_�[�ł̓s���g�̊m�F�͂ł����A�����܂ł��t���[�~���O�̂��߂̃t�@�C���_�[�ł����Ȃ������B
�����ԍ��F24960956
![]() 0�_
0�_
�X�v���b�g�v���Y�������v�B���ӂ̓��F�̓t���l�������Y�ƃ}�b�g�ʂ̊��ɂ����́B |
�L���m���̃j���[�X�v���b�g�v���Y���i�����v���Y���ׂ̍����c�Ŋ��F���o�Ă���j |
���X�v���b�g�v���Y���̂�����
�ŋ߂̓~���[���X���g���Ă������߃f�W�^�����t���g���͖̂�10�N�Ԃ�ŁAD3X���g�����ƂɐV�N���������Ă��鎟��B
���₻�������A�v���d�l�̎g�p���͏��߂Ă̌o���B����20�N�̂����ɂT�`�U�@��̃f�W�^�����t�J�������g���Ă������̂́AD3X�̂悤�ȍ������̍���➑̂Ő�̗ǂ�����������J�������o���������Ƃ͖��������B
����ɂ��Ă��t�@�C���_�[�X�N���[���ɉf�鑜�͈��t�Ȃ�ł́B
���t�̃t�@�C���_�[�X�N���[���́A�t�B��������ɂ͋����v�A�����J�����ɔ�ׂăN���A���Ɍ����邱�Ƃ��f�����b�g�Ƃ��ꂽ�B�������Ȃ���f�W�^������Ƀ��[���X�J�������o�Ă���ƁA�t����ʂɕ\������郉�C�u�r���[�ɔ�ׂ�ƈ��t�̃t�@�C���_�[�X�N���[���̂ق����N���A�Ɍ����Ă���̂�����s�v�c�Șb�B��r�Ώۂ��ς��Ƃ��̕]�����ς��Ƃ����ǂ��Ⴉ�B
�܂����ہA�X�v���b�g�v���Y�����̃X�N���[���ɑւ��Ă݂�ƁA��ʒ����̃v���Y�����͋��̂��ߑ�σN���A�Ɍ����邱�Ƃ͊m���B
���ӕ��̓}�b�g�ʂ̂��߃U���c�L������̂ɑS�̂��N���A�Ɍ����Ă��܂��͕̂s�v�c�Ɏv���邩���m��Ȃ����A����͗Ⴆ��Ȃ�A�l�Ԃ̎���̒��ōł����ׂɌ����镔���u�t�H�x�A�v�݂����Ȃ��̂��ƌ�����B
�l�Ԃ̎���Ƃ����̂́A���������Ȃ���Β��������n�b�L�������A���ӕ��̓{�������Ƃ��������Ȃ��B�������Ȃ��璆�������N���A�Ɍ�����Ȃ�Ύ���S�̂��N���A���ƔF�����Ă��܂��̂��B
D3X�ɂ����āA�X�v���b�g�v���Y���X�N���[���͏����i�Ƃ��Ă͗p�ӂ���Ă��Ȃ����Ƃ͑�ώc�O�B�����~���[���X�S���̂��̎���Ɉ��t�����p����̂ł���A�v�����̉����i�ł͂��낤�Ƃ���x�͎g���Ă݂鉿�l�͂���ƌ�����B
���⑫��
AF�J��������ɓ����Ă���̓t�@�C���_�[�X�N���[���̓{�P��ƃt���[�~���O�̊m�F�����ɂȂ����悤�Ɏv�����AMF����ł̓s���g�����킹�邱�Ƃ��܂����̖ړI�ł������B���̂��߁A��{�\���̓}�b�g�X�N���[���ŁA�����ɗl�X�ȋ����v��g�ݍ���Ń^�C�v�������Ă����B
�����v�̎�Ȃ��̂͂Q����A�N�T�r�^�̃v���Y�����݂��Ⴂ�ɔz�u�����u�X�v���b�g�v���Y���v�ƁA�ׂ����v���Y����~���l�߂��u�}�C�N���v���Y���v������B
�ǂ�����v���Y�����g���ă����Y����̌������݂��Ⴂ�ɃY�������̂����A�����Y��F�l���Â��Ɓi��{�I��F5.6�ȏ�j��������ɓ���Ȃ��Ȃ邽�߂��ȁi�����j���Ă��܂��g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�B
�v���Y���̊p�x����Ζ��͌y������邪�A��������ƃY���̕ω��ʂ����Ȃ��Ȃ邽�߃s���g���x�͒ቺ����B���̂��߃L���m���ł́AAE-1P�̎��ォ��Q�̊p�x�����j���[�X�v���b�g�v���Y�����J�����AF5.6�����Â������Y�ł��Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���B
�Ȃ��A�X�v���b�g�v���Y���͏㉺�̑��̃Y������v����悤�Ƀs���g�����킹�邪�A����͋����v�A�������嗬�����������A�����v�A�����̓�d�����v���^���I�ɍČ����A���t�ւ̈ڍs���X���[�Y�ɂ����邽�߂ł͂Ȃ����Ƒz������B
�����ԍ��F24972285
![]() 0�_
0�_
��D3X�̉摜�͂��܂Ŏ��p�ɑς���H
����ɑ���́A�u���p�ɑς���v�Ƃ����Ӗ��������ǂ��������̂��ɂ���ĕς�邾�낤���A�����ł́u���p�ɑς��遁���̎���̉{�����ŊςĂ��s�s���������v�ƒ�`�������B�ʐ^�Ƃ����̂͊ς邽�߂ɎB��̂ł��邩��A�ς�����]���ɑ傫���ւ��ƍl����͓̂��R�ƌ�����B
������A20�N�ȏ�O�Ƀf�W�^�����t�uCanon EOS-D30�i300����f�j�v�ŎB�����ʐ^�����݂�PC�f�B�X�v���C�œ��{�\��������ƁA��ʒ������ɏ������|�c���ƕ\������邾���B����ł͂ƂĂ����݂̎��p�ɑς���Ƃ͌����܂��B����ł�������PC�ł͉�ʂ��n�~�o���傫���������̂����B
�܂��ߋ��ɎB�����ʐ^�͎���̂����Ǝv���Ĕ[��������Ȃ����A��������EOS-D30�ŐV���ɎB�e����C�͋N���Ȃ��B
�ł́A�u���̎���̉{�����ŊςĂ��s�s���������v�Ƃ����̂́AD3X�̏ꍇ���܂ł̂��Ƃ��B�܂肻�ꂪ�A�`���̎���ɑ���ƂȂ낤�B
2022�N���݁A�ʐ^�����Ƀv�����g����Ƃ��������͖����Ȃ����悤�Ɏv���B
���Ԉ�ʓI�ɂ́A�ʐ^�̓X�}�[�g�t�H���ŎB�e���A�X�}�[�g�t�H���̉�ʂʼn{������B���l�Ƌ��L����ꍇ�ł��v�����g�ʐ^�ł͂Ȃ�SNS���L�ōs���̂����ʁB
���A�[�g�Ƃ��Ă̎ʐ^�B�e�ɂ��Ă��A������������W�p�ɋC�ɓ������������L���Ńv�����g���邱�Ƃ͂��邩���m��Ȃ����A���X���S���P�ʂŎB����̂�S�ăv�����g����Ƃ����̂͌����I�ł͂Ȃ��B�����Ȃǖk�C���ɂP�T�Ԃ̃h���C�u���s�������A�S����5,000�����B���Ă������ƂɎ����Ȃ���������B���̐��ʂł́A�o�ϓI�Ȗʂł��A�����I�Ȗʂł��A���͂⎆�v�����g����Ƃ������z�͖����B�f�W�^���摜�̓f�W�^���̂܂܃t�H���_�̌n�Ő������A�K�v�Ȃ��̂𒀎���ʂŕ\�������ĉ{������̂����R�Ȍ`�B�����W���J���ɂ��Ă��A�߂������̓f�W�^���T�C�l�[�W�Ō����鎞��ɂȂ��Ă���\��������B�܂�A�f�W�^���̓f�W�^���̂܂܂Ŋ���������̂����R�ƌ�����B
�����Ŗ��ɂȂ�̂��A�f�B�X�v���C���ƂȂ�B
�f�B�X�v���C�̋Z�p�I�i���ɂ��ẮA�u���E���ǎ�(CRT)����t����(LCD)�ֈڂ�ς���ċv�����A�ꎞ���v���Y�}�������ꂽ�����݂͏��ŁB����͗L�@EL��������đ���\��������B���邢�͕����Ƃ��ăJ���[�d�q�C���N�������o�邩���m��Ȃ����A����ł̓t���J���[��������A������p�I�ȉ掿�������邩�͖��m���Ƃ������B
�u���E���ǂ̎��ォ��U��Ԃ�ƁA�u���E���ǂ͉�ʂ̃t���b�g�`������A�n�C���]���̃��t���b�V�����[�g���ǂ��t���Ȃ����̃`���������ł������B�����ău���E���ǂ͉��s���̂��闧�̕��̂��߁A�\���ʐς������傫�����邾���ł��e�ςƏd�ʂ����I�ɑ傫���Ȃ��Ă��܂��B
�������������́A���ʃp�l���̑�\�ł���t�����ɑւ���Ă���傫�����P���ꂽ�B
�����̍��̉t���f�B�X�v���C�́A�������x�⎋��p�����ĕ\���F���̖�肪����A���炭�̓u���E���ǂ��x�����邱�����h�������������A�t���̖�������ɉ��P����ău���E���ǂ��쒀���Ă��܂����B
�t�����̗��_�́A��ʃT�C�Y��傫�����Ă�➑̗̂e�ς�����قǕς��Ȃ����߁A���������ł����ʂ�ݒu�ł��邱�Ƃł���B�A�[�����g������ɏȃX�y�[�X�ɂȂ邵�A��낤�Ǝv�����Ė��ƌ��ꂽ�NJ|���e���r�̂悤�ɂ��ł���B
��������ʂ��傫���Ȃ�s�N�Z���̃��b�V�����ׂ������Ȃ���ΐ��ׂ����������߁A�t���p�l�����傫���Ȃ�ɂ�𑜓x��VGA�i640x480�j����SVGA�i800x600�j�AXGA�i1024x768�j�Ƒ����Ă����A�n�C�r�W��������ɓ����HD�i1920x1080�j�A�����č��ł�4K�i3840x2160�j�̎���ƂȂ����B
���ێ����̏ꍇ�A43�C���`��4K�f�C�X�v���C�����Ă��邪�A���̃T�C�Y��4K�łȂ���ΐ��ׂ����s���������낤�Ɗ����Ă���B
����4K�f�B�X�v���C���嗬�ƌ����ėǂ��̂��͕�����Ȃ����A���Ȃ��Ƃ�5���~�����ɓ��錻��ł͂���قǕ~�����������̂Ƃ��v���Ȃ��B���ہA�������w�������̂͂V�N�O�ŁA�U���~���炢�������ƋL�����Ă���B
�Ƃ������m���Ɍ����邱�ƂƂ��āA4K�f�B�X�v���C���ɂāAD3X�ŎB�e�����摜�͕s�s���������{�{���ł��Ă���B�����Ƌ�̓I�Ɍ����A���ʒu�ʐ^�ł͗]�T������A�c�ʒu�ʐ^�ł̓M���M���[�܂��Ă����ԁB���������Ӗ��ł́A2022�N�����_�ł�D3X�͎��p�ɑ���J�����ł���ƌ����ėǂ����낤�B
�ł͍���̘b�ɂ��Ă����A4K�̎��ɍT���Ă���8K�i7680��4320�j�̃f�B�X�v���C��D3X�ŎB�����ʐ^�{�\�������邱�Ƃ�z������ƁA���ʒu�ʐ^�ł͂܂����v�ł͂�����̂́A�c�ʒu�ʐ^�ł͍��E���V���[�g���ė]�����o�Ă��܂��B�����Ȃ�ƁA�������Ɏ��p�I�Ƃ͌�����Ȃ��Ă���B���{�\�����Ă��]��������Ɖ摜�������������Ă��܂��̂ŁA�㉺�X�N���[���ƂȂ����Ƃ��Ă��A�����Ƒ傫���ق����ǂ��B
�Ƃ������Ƃ́AD3X��8K�f�B�X�v���C����ɂ͌������Ƃ������ƂɂȂ�B
�܂�A8K�f�B�X�v���C�����y���鎞���A�`���̋^��̉Ƃ��Ắu���̎���v�Ȃ̂��낤�B
�Ȃ��8K�f�B�X�v���C�͂����y����̂��B
���ݎ�����43�C���`��4K�f�B�X�v���C���g���Ă���ƌ��������A���̐��@�̉�ʂ��{������̂̓M���M���Ƃ�������������B
����ȏ��ʃT�C�Y���傫���Ȃ�ƁA�f����őO�ȂŊςĂ���悤�Ȋ����ŃL�c���Ȃ��Ă���B�����Ȃ�ƁA���̉�ʂ̑傫���̂܂܂ʼn𑜓x��8K�ɂȂ邭�炢���������Ǝv�����A����ȏ�ׂ����Ȃ��Ă����ׂ������サ�Č�����̂��͕�����Ȃ��B���Ȃ��Ƃ�43�C���`�̑傫���ł͑�������Č���̂�4K�𑜓x�ŕs�s�������������Ƃ͖����B
�ȏ�̂��Ƃ��l����ƁA���̐�ϋɓI��8K������K�R���͍l���ɂ����A4K�̎���͍�����܂��܂��������̂Ǝv����B
�Ȃ��A�掿�Ƃ����͉̂�f�������łȂ��m�C�Y�Ȃǂ̗v�f������Ƃ͎v�����A�ȑO�̌��ł�ISO100�Ŏg������D3X�̃m�C�Y�Ŗ��ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��m���߂��B
�����D3X��ISO100�Ŏg������A����������Ǝ��p�ɑς�����̂ƍl����B
�����ԍ��F24977694
![]() 0�_
0�_
��D3x�͈��t�𖡂키�Ō�̋@��
���t�Ƃ����̂̓t�@�C���_�[�`���̈�ł���A�t�B�����J�����ł͍����I�Ȏd�g�݂ł͂�����̂́A�f�W�^���J�����Ƃ��Ă͂��܂荇���I�Ƃ͌����Ȃ��B
�܂����t�̎d�g�݂��ȒP�ɐ�������ƁA�u�����Y��������������J�����ƎB�e�҂����݂Ɏg���t�@�C���_�[�����v�ƌ����\�����Ƃ��ł���B
�t���[�~���O���̓~���[���g���ăt�@�C���_�[���Ɍ����A�B�e���̓~���[�����ŃC���[�W�Z���T�[���ɖ߂��B�B�e�Ɏg�������t�@�C���_�[�Ō��邱�Ƃ��ł���̂ŁA�ǂ�ȃ����Y�����Ă��t�@�C���_�[���ƎB�e���̃Y�����������Ȃ��B�܂�A�����܂܂��ʂ邱�ƂɂȂ�B
���������̕����͂P�̌��̐i�H���ւ�����̂ł��邩��A�ǂ��炩������������悤�Ƃ���A�Е��͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B������B�e�̏u�Ԃ̓t�@�C���_�[���u���b�N�A�E�g���邱�ƂɂȂ�B����͈��t�ő�̌��_�Ƃ���A�t�B��������ɂ͂��̂悤�ȁu�ǂ��炩����Ō��݂Ɂv�Ƃ��������ł͂Ȃ��A�u�������������ē����Ɂv�Ƃ����������o�ꂵ���B
���[�J�[�ɂ���ăn�[�t�~���[���g������A�y���N���~���[�ƌĂ�鍂���q�����������g�ɒ����Ďg���Ȃǂ��ău���b�N�A�E�g�̖������t�����������悤�Ƃ����̂����A�t�@�C���_�[�����Â��Ȃ���肩�I�o���Â��Ȃ��Ă��܂��Ƃ����A�ǂ���ɂ����r���[�Ȃ��̂ƂȂ炴����A���̌�̔��W�ɂ͌q����Ȃ������B
���t�ɂ͂��̂悤�Ɍ���������ł��Ȃ����_������킯�����A����ł����̌�傫�����W�����̂́A�t�B�����J�����ł͈��t�`���������I�ł���������ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�������Ȃ���Ό��ʂ�������Ȃ��t�B�����Ȃ����ɁA�B�e�����Y����ʂ������������t�@�C���_�[��ʂ��Č��邱�Ƃ��ł���̂͏d�v�Ȃ��Ƃ������B
����A�f�W�^���J�����ɂ��āA�����t�����ł̓t�B�����J�����Ŋ��Ɋ������Ă����J�����Z�p�����̂܂ܗ��p��������ō��ꂽ�B���Ƀn�C�G���h�f�W�^���J�����ɂ��ẮA�c��Ȍ��������Y�Q��A�N�Z�T�����g����悤�ɂƁA�����̈��t�`�������p����ăf�W�^���J���������ꂽ�B�Ƃ����̂��A�����̃f�W�^���J�����̓n�C�G���h�J�����ł����Ă��܂��܂��t�B�����̉掿�ɂ͋y���A����ȃf�W�^���J�����ɍœK�����ꂽ�V���ȃV�X�e�����\�z����ɂ̓��X�N���傫���B�����듖���A���[�J�[�e�Ђ͐V�K�i�t�B�����V�X�e���uAPS�v�����s�����L�����V�����A�uAPS�Ŗ{�i�I�ɃV�X�e����g�܂Ȃ��ėǂ������v�ƈ��g���Ă���������������ł���B
�������f�W�^���J�����Ƃ����̂̓r�f�I�J�����Ɠ��l�A�C���[�W�Z���T�[�������Ɍ���^����A�t���t�@�C���_�[����ĊԐړI�ɃJ�����}�����ɂ����������邱�Ƃ��ł���B�K���������t�̂悤�Ƀ~���[�Ő�ւ���K�R���͖����B�����̍��͋Z�p�I�ɓ���Ƃ��A���X�ɖ��͉�������A���ł̓~���[���X�J���������p����Ă���B
�������t�̂悤�ȃ~���[�{�b�N�X��������Ε��G�ȃ��J�j�Y�����Ȃ����Ƃ��ł�����肩�A�����Y�̃o�b�N�t�H�[�J�X�̐����������Ȃ背���Y�v�̎��R�x�������B���ɍL�p�����Y�����^������邱�Ƃ̉��b�͑傫���B����ɉ����A��Ɠx���ł����������ăt�@�C���_�[���𖾂邭�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
���t�̗��Y�ł������L���m���ƃj�R���́A�����̈��t�V�X�e�����Y���c��ł��邱�Ƃ���ȒP�ɐV�����V�X�e�����\�z�ł����A���炭�̊ԃ~���[���X�`���̐V�V�X�e���̓T�u�V�X�e���Ƃ��������ł����Ȃ������B���̂����ŁA�����Ȃ�EOS-M3�������̂̃����Y���������ɋ�J�������A���ǂ͎�������ƂƂȂ����B
�����A���⊮�S�Ƀf�W�^���J�����̎���ł���B�f�W�^���J�����ɍœK�����ꂽ�V�X�e���łȂ�����̐搶���c��͓̂���Ɣ��f�����L���m���ƃj�R���́A���Ђɒx��ă~���[���X�����C���ƈʒu�t���A�V���ȃV�X�e���̍\�z���n�߂��B
����������ł́A�~���[���X�`���ł����L�̂悤�Ȗ��_������B
(1)�t�@�C���_�[�̌�����͉t���̉𑜓x��t���b�V�����[�g�Ȃǂɍ��E����A����͌��w���t�@�C���_�[�ɗ��B
(2)�C���[�W�Z���T�[�������������掿�ʼnt���\��������ɂ̓^�C�����O������B
(3)�B�e���̃u���b�N�A�E�g�����ɂ̓C���[�W�Z���T�[�̂���Ȃ���P���K�v�B
�����̖��ɋ��ʂ��邱�Ƃ́A�Z�p�̌���ɂ����P�����\���������Ƃ������Ƃł���B���������I�ɕs�\�ł���Ȃ�Β��߂邵���Ȃ����A�����Ă����ł͂Ȃ��B�����_�ł��A�R�X�g�̂������Ă��鍂���@�ł͂����̖�肪�y������Ă��邩�炾�B������́A�����ȃ��f�����܂߂��S�Ẵ~���[���X�J�����Ŗ��͊��S�ɉ��������ɈႢ�Ȃ��B�����Ȃ�A���t�͊��S�Ɏp���������ƂɂȂ낤�B
���������͌������̂́A�Z�p���W�������҂��Ă��邾���ł͎B�e�̋@��͎����Ă����B��X�͂��̎���ŗ^����ꂽ�J������K�Ɏg�������A���t�J�����ƃ~���[���X�J������"�ǂ��Ƃ����"�����ĎB�e���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B���������Ӗ��ł́AD3X�ɂ�D3X�łȂ���Γ���B�e�����������B
�����ē����ɁA������͏����Ă������t�Ƃ������̂��A���̂����ɃW�b�N�����키���Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂ������B�����A�q�⑷�����ɁA���t�Ƃ������̂���邱�Ƃ��ł���悤�ɁB
���̂��߂ɁA������D3X����ɓ��ꂽ�̂ł���B
�y�Q�l�F�f�W�^���J�������t�����̋L���z
�f�W�^���J���������ꂽ1990�N����v���Ԃ��ƁA�����͎ʐ^���B��Ƃ������o�ł͂Ȃ��A��������ɃL���v�`������Ƃ������o�������BPC�ɊȒP�ɃC���[�W����荞�ނ��߂̎��Ӌ@��ɉ߂����A�܂�����i���B��悤�Ȃ��̂ɐ������Ă������i���Ƃ́A�������܂߂ē����͒N���v���Ă��Ȃ������B
�J�������[�J�[�ł́A����܂łɂ�APS�t�B�����ȂǂɎQ���������̂̎s�ꂪ�L����ʂ܂ܓP�ނ����ꂢ�L��������B����ɑ����ēo�ꂵ���f�W�^���J�����ł��邩��A���[�J�[�͊��҂ƌx���̓��荬�������ڂŌ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƒz������B
�����ԍ��F24980906
![]() 1�_
1�_
���\���Ƃ��������o�I�Șb�Ȃ��ǁA�����������R�ƌ����Ă�悤��Nikon Z 9��Real View Finder�Ƃ��ł��A����Nikon F6��D850�Ɣ�ׂĔ`�������́u�C�����ǂ��Ȃ��v��ł����
�B���ł͖��Ȃ����ǁA���F�A�}�`���A�Ȃ̂ŁA�n�D�i���ƍl�������ɂ͂���ς����Ɠ����Ă������Ō���������
�����ԍ��F24980909�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�܂��A���ł��ŏ��͂���Ȃ���ł���B
���t���o�Ă������́u�����W�t�@�C���_�[�̂ق����N���A�Ō��₷���v�ƌ����Ă����A
AE���o�Ă������́u�����̃C���[�W�ō��킹�����v�ƌ����Ă����A
AF���o�Ă������́u�����ō��킹�������v���ʂ�ɍ��킹����v�ƌ����Ă����A
�f�W�^���J�������o�Ă������́u�t�B�����̂ق������掿������s�v���v�ƌ����Ă����A
1,000����f���o�Ă������́u����Ȃɂ����ĉ��Ɏg���v�ƌ����Ă����B
�ł������͐V�������̂��Â����̂���Ƃ�������Ă���̂ł��B
���͂܂��ł��B
�����ԍ��F24980926
![]() 0�_
0�_
�����̏ꍇ�͋t���Ȃ�ł���ˁB
�J�����̓���̓~���[���X�A�Ȃ�Ȃ�t�@�C���_�[�̂Ȃ�NEX-3�ł����B����̃�6000�A��6500�A��7III�Ƃ��āA
�������烿700�A��900�A��-7 DIGITAL�AD800�AD850�ƈ��t�ɋt�����A
�������W�t�@�C���_�[Nikon S3�܂ŋt�����Ă܂�
���w�I�ȕ����͂܂��A����Ίm���ɉ��P���Ă镔�����Ǝv���܂����A���o�I�ȕ����͐V��������ǂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂�
�֗��ł��邱�ƂƁA���o�I�ȗǂ������͕ʂł���
�����ԍ��F24981166�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
- �B�e
- ���t
- �s���g
- �X�N���[��
- �t�@�C���_�[
- ���
- �f�W�^��
- �V���b�^�[
- �~���[
- �~���[���X
- �X�v���b�g
- �K�v
- AF
- �~���[�A�b�v
- �ʒu
- �ǂ�
- ��f
- �ʐ^
- �Y��
- �@�\
- ����
- �Z���T�[
- �u��
- MF
- ���
- �\��
- �m�F
- �I�o
- �w��
- �Ⴂ
- ���d�I��
- �m�C�Y
- �t�@�C���_�[�X�N���[��
- �{�P
- �t��
- �g��
- ���d�I�o
- ����
- �
- �K���X
- �摜
- �`��
- ����
- ����
- ����
- ISO100
- �N���A
- �^�C�v
- �t�H�[�J�V���O�X�N���[��
- �v��
�u�j�R�� > D3X �{�f�B�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 9 | 2024/07/02 12:04:51 | |
| 41 | 2022/10/26 9:17:05 | |
| 6 | 2020/01/22 1:31:30 | |
| 12 | 2018/04/13 10:41:14 | |
| 6 | 2017/11/10 9:00:41 | |
| 3 | 2016/03/01 13:15:22 | |
| 16 | 2016/02/12 22:04:04 | |
| 7 | 2017/07/17 10:49:47 | |
| 7 | 2014/11/30 19:08:38 | |
| 3 | 2014/08/27 2:33:05 |
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�������߃��X�g�z���X1440���Q�[������l����
-
�y�������߃��X�g�z���X�X���p
-
�y�~�������̃��X�g�z�V�Z�p�������@�̎���PC
-
�y�~�������̃��X�g�zDDR4�őË��\��
-
�y�~�������̃��X�g�zAM5
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2026�N2���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2026�N1���z

�^�u���b�gPC
- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2026�N2���z

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j